�����{�̌Ó� / �������E�Ñ㓹�H�E�܋E�����E���R��1�E���R��2�E���R��3�E���C��1�E���C��2�u���I�s�v�E�k�����E���R���Ɛ_���E���R�������H�E���q�X���㓹�E�������E���͍��Ó��Ƒ�a�E�֓��̉͐�j
�@
�G�w�̐��E�E��l
�@�@�@


| ���N���s���o�� / ���c���j | |
| ���K������ | |
|
�܌�������ĂЂ����̘b�̒��Ɂu�K�������̂Ă�Ƃ��ȂȂǂ��A�ߑ��a���̖@��ق����Ƃ͌��Ȃ��A���̕������̂��݂ɓV�����J�܂���̂Ȃ�ׂ��A�瑁�ӂ�K�������͋g����A�_�������𐬔s������������A�Ɛ\���܂��Ȃ��̂Ƒ��ւ܂��ĈӖ��̐[���s���ł���B�������Ɠ�����Ƃ��̂����̉Ԃ����͉Ԍ䓰�͂Ȃ݂ǂ��ɂ��₩�������̂ł����āA���͂�͂���Čn���Ђ��������Ƃ��̂��̂ł��������Ɛ��@����B�Ȃ���̘b�̓s���ケ�̔����Ƃ�����������L���˂����Ă����v�Ƃ���B��X�͖��_�������̋�������V�����L���͂��Ă��邪�A�܌����͂܂��Ȃ��Ȃ����̑����\�����Ȃ��B�����Ñ�����̂�����Ƒ����A������̕��̍ޗ������X��o���Ă����B
�܌����͂�����V���Ԃ̉ԂƊƂƂ��������āA�Ƃ͓��{�̉K�������̗p�ɗ��āA�Ԃ͓V���Ă��̕��a��Ԃ����ɕԂ��Ă�낤�Ƃ�����炵�����A����͏��X�ނ������B���̓��Ԃ�_�ɕ����镗�K�͂����ɂ��L���s���Ă��邪�A�K���������Ƃ��Ƃ��Ƃ̓��ɕt���ė��Ă͂��ʁB���ɍF�o�O���M�������傤�낤�܂�҂Ɉ˂�u�]�ˎl�������ɉK�Ԃ��̂͂Ȃ��˂ɝ��͂��މ]�X�v�Ƃ���B���Ȃ��Ƃ����̈ꕔ�ł͊Ƃ�p���Ȃ������̂ł���B�ؑ\�̑��X�ł��Ƃ̌ˌ��ɎR�U�P��܂���ŕt���Ă���̂������͖ڌ������B�ɓߒJ�ł͂������ɕc��Ȃ킵��ɗ��Ă�Ƃ����B�M�c�_�{�l�������̉Ԃ̓��Ƃ��͙��\�Ԃ���Ȃ��������炵���A���B�{�u�Ȃǖ����A�������Ԃ��̈��̎��ƒf�肵�Ă��邪�A����炵���؋����Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�z�K�喾�_�掌�����Ƃ̒��ɏڂ܂т炩�Ɍ����Ă���ԉ�͂Ȃ̂��̎��̔@�����A���������̗����ɕ����ĉE���̓����Ƃ��₭������Ύd�����A�Бm����Ɋ��^�����ɂ�������炸�A���܂������_���ł��������Ƃ�����B���Ȃ킿�܂��ƂȂ��̉Ԃ�p�����Â����ł���B �Ԃ̌A�����̉ԍՂ͂��܂蕨�����Ƃ��Ă��A���O�������{���ÔN���s���Ђ̂��܂��ɂ�������傤�����������˂イ���傤���ɂ��u�l���������U�P�������Ȃ��v�Ƃ�����͂���̂ŁA�������͂ނ��뉽�̂Ɏ߉ޒa���ɉԌ䓰�͂Ȃ݂ǂ������n�߂������l���Č������ʂł���B���K�l���ɂ͒j�R�����A���N�Z���̉Ԃ̓��Ƃ��̎����A�M�c�l�������̗�Ƃ悭���Ă��邱�Ƃ��q�ׁA��҂͟��Ԃ��ɂ��āA�O�҂͉Ē��̋��Ԃ��傤���ɋN��Ɛ����Ă��邪�A�P�Ɋ������l�������ł��邽�߂ɁA���̍��ʂ�F�߂��̂Ȃ�Ό��ł���B�������Бm���Ⴛ���������Â��ċ��ԂƂ��������K�ƂĂ��A�Ȃ�����̓_�܂ŕ��@�̋����Ɋ�Â��Ă��邩���l����K�v������B �㐅���@�N���s���l���\�Z���̏��Ɂu���傤��荕�˂���ǂɂĉĉԂ��Ȃ�E�܂�����]�X�v�Ƃ����āA�ɐ��Ɠ������Ȃ����ǂ���ւ͎O�t�悤���A���̑�Ђ͓�t�悤���A�������t�A���c���t�ȂǂƋL����Ă��邪�A���̉ԓE�̍s��������������̔����ł������Ⴊ�����B�����ЂȂL���Ɉ˂�A�����Ƃ����ȂǂʼnԓE�Ƃ������̂͂��̓��Ԍ䓰�����\���āA���߉ނ����Ⴉ�̓��������u���邱�ƂŁA���̓��܂���b�R���d����������ǂ��̕�����Ԃ����傤���ɁA���l���̏�͓o�q�������ꂴ��҂��Q�w���A�������ɓ���{�I��Ђ����������Ƃ��肳���̏�Ȃ�ԓE�Ђ͂Ȃ݂̂₵��Ɍw����Ƃ���B���������̉ԓE�Ђ����a���ƊW�����������Ƃ͖����m���łȂ��A�ߍ]�`�n�u�������݂悿����Ⴍ��\��̔@���͂��̎Ђ̍Ր_��`����t�̕�Ȃ�ƌ����A���̓��͏��q�����܂œo��q���A�����莵�������܂ň�Ă̊ԉԂ�E�ݕ��ɋ�����̂���ł���Ƃ̂L���Ă���B�Ȃ�قǂ��̓������Ɏ���čł����_����L�O���ׂ����Ȃ�̂ɁA���̓����Ȃ��J�܂��錋�E���������̎ЂɁA�ԓE�̖����N�����̂��Ƃ����������邩�m��ʂ��A�ꂽ�ё��̒n���̎�����r���Č���ƁA�����̕K�����������P���łȂ��������Ƃ��M���m����̂ł���B �z��o�_��̋��������^���イ�낭�����u�o�_��v�Ƃ������ɞH���A���z��̑��X�̕w���A���N�l�������ɂ͐��i���ւ��A�����͑��V�ɐ���̈߂𒅂ċ߂��R�X�ɍs���A���̉Ԗ[����荠�̈�}���̂�҂�Ƃ̕��d�ɋ����B�ĎR�̖�t�֕�����ӂɂē����ݒc�q�����A�Ƃ��x�ނ͌×��̏K�Ȃ�B�����c�������ɐ���ɂ��Ă��邢�͚��ʂ��Ⴕ�̌X����A�x�z�@�Ƃ��͂��ق肯���l�������R�����ւ̖�����A�ǁX�������肵���A�������c��(�O���S���c���厚���c�H)�ɂ��̈╗����A���Â��ē��̉ԗ��͂Ȃ��ĂƂ����ƁB ���̘b�̒��Œ��ӂ��ׂ����Ƃ́A���ɂ͎߉ނƌ��킸���Ė�t�ƌ��������Ƃł���B���̔����͖�t���Γ������ɂ��ɂ͑���Ȃ����A���̗ނ̖�t�͂������Ĕ����Ƃ���������Ղ�n�߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv����e�ׂ�����B��������݂�����ɋ߂����ς��킢��̖�t���A�̐l���ɗ��������̏���P����Ђ߂Ƃ������̌쎝���Ɠ`���A�܂����̓����ȂčՂ���Ȃǂ͂��̒�������ł���(���y�����Z����)�B����݂܂������c�S�L�����厚�㑊���݂����̊ԎR�͂�����ܖ�t�ŁA���N���̓�����O�₹�����Ə̂��鑜��l�����ɂȂ��Ĕw�ɕ����A�Q�O���@���āu��������Z�S�[�v�ƚ��͂₵�đ���ɏ������A�u�������イ����킸�v�ƌ����č����������킸�ɁA��t�����O������Ε���������Ɠ`���鎮������Ȃ�(���쎏�Ƃ�������)�A�גj�����̂��ƊW������炵���Â߂��������K�ŁA�₪�Ă܂���t�̐M����ɋN���������v�킹��B ���ɒ��ӂ��ׂ��͂��̓��R�ɓo��Ƃ������Ƃł���B�K���������R�o��̓��Ƃ���K���͎����čL���s���Ă���炵�����A���̊O�ɂ��R�ɍւ�������L���ȎЂɂ��̓����Փ��Ƃ����͑����B�߂��͕��B�����̎O���_�ЁA��B�����悱�ނ�̐ԏ�_�ЁA�x�͂̈��邠���������_�A�z���̗��R���Ă�܌����A��a�ł͓Z���܂��ނ��̌��t�����傠�Ȃ��ɂ܂��Ђ傤���_�ЁA���k�ł͉H��O�C�����S�̍��������ւ����Б啨���������̂��ݐ_�ЁA���Y���������S���̍r�H�g��͂��_�ЁA�k�H�c�̎����ȂȂ���_�АX�g�_�Г��A�����Ί��̔��R�͂�����_�ЁA�֏邢�킫�q�ΎR�̐����݂��܂�_�ЁA��B�ł͎F�����ؖ�̊��x����ނ肾��(��)�_�ЂȂǁA����������K���������ȂčՓ��Ƃ��Ă���̂ł���B ����ɑ�O�̓_�͕w�l���o��Ƃ������Ƃł��邪�A������e�ׂ̂��낤�Ǝv����́A (�C)�ɂ́A���_���Ղ�Ђ̎l���������Փ��Ƃ��邱�Ƃł���B�Ⴆ�ʈ˕P���܂��Ђ߂��Ղ�Ƃ�������������������S�̓��m��_�A���ވ�䔄�����Ȃ��Ђ߂Ƃ����z�K�����{�Ђ��ł݂̂�₵��A�`瑁X���S�P�P��܂ƂƂƂЂ������Ђ߂��J��Ɠ`�����]��̈�m�{�c���_�ЁA���邢�͘`�P����܂ƂЂ߂݂̂��Ƃ��Ղ����̂��n�߂Ƃ����]�B�������イ�y�R�̓c���_�ЂȂǂ̗ނŁA���̊O�ɂ��V��Ɉ��������Ђ��Ȃ������肻���ł���B (��)�ɂ͐_�֑̂Ȃ�Ƃ������`���̉��X�ɂ��đ����邱�ƂŁA�����ΐ��̕ӂɂ����Ă��̓��̍Ղ��s�����Ƃ�����Ɗ֘A����炵���B�ɐ��鎭�S�̌{���R�͉K�������̓o�R���Ȃĕ��������n�ł���B���ł͐��ω���{���ɂ��Ă��邪�A�����R��ɋ��J�r�Ƃ����������āA�T�������ɑP����������ɂ��イ�����J��̎O�K�����ւ����F�J�����̐_�Ƃ��ċ���Ă���(�O���n�u��\�Z)�B�������ȂĒm���Ă���H�O����̕�����א_�Ђ��Â������Ղ͎l�������ŁA�Ր_�F�ޔV�䍰���������݂̂��܂Ƃ��������͉F��_���Ȃ킿�ٍ˓V�̐M�Ɏn�������̂炵���B ��̍Ղŕ]���̍]�B�}���_�Ђ̔@�����A�Гa��ɗՂ�Œ|���������Ԃ��܂Ɍ����A���͎�_����H�Ð_�����݂��̂��݂Ƃ��Ă��邪�A�ȑO�͎s�n���P�����������܂Ђ߂݂̂��ƂƓ`���Ă���(�ؑ]�H�����}��)�B�Ղ͓����l���̔����Ŕ��l�̓������ʋ����ȂĒ�߈ꌎ�̕������̂��݂����Đ_���Ɏd�����߂��B�O�ɋ������������ύ�̖�t���ɔ������ȂĒr�̐_�̐������ɂ��Ƃ��������`����̂��A���̖�t���Γ������ɂ��Ƃ����l�������ƊW���邱�Ƃ́A�����ɕ���ꂽ������m���ٓ̕V�̐\�����Ȃ钷�҂̖����A�r�ɓ����Ď֑̂ƂȂ����̂��������Ƃ����b(���y�����Z����)�ƌ����킹�Ă�������������B����ɂ܂���B�����̕��n�����˂킽�育��ɂ����Ă��A�֑̎̂ƂȂ����Ƃ������҂̍Ȃ̋��{���A���������̓��ɍs����ł������Ƃ����A�l���Z�����Ȃė�ՂƂ���ߍ]�ɍ��S�̑剹�������Ɛ_�Ђɂ��A��͂�O�@��t���r�̎���ϓx�����ǂ����Ƃ����A���̂����炬���҂̍Ȃ܌Ռ�O�Ƃ炲����̘b(����l���O�O���)�Ƒ�������b����̂����Ă���B �����ɐ����̐Ղ𗯂߂��g���Ƃ�����u��т��ɂ́A���R����є��R�ɓ`���Ă���g�E���̉W���A���Ă͑�a�̋���R�ŌÂ��������̃g������ƁA�N���͊F��ł��낤�Ƃ������͑O�ɂ��łɐ��������A�����͓Ƃ�ނЂ����ɂ���������������܂��邵�܂Ȃǂ̃^���A����ё�ѓ��q�������炵�Ђ��E��ѓ����������炵�Ђ߂Ȃǂ̃^���V�Ƃ�������ŁA�Г��̗����~�^���V�ƌĂԂ��Ƃ��A����Ɗ֘A���Ă���͂��ʂ��Ǝv���Ă���B�L�㍑���̊C��ɂ���P���ɂ���є����������炵�͂��܂�̎Ђ�����B�ȑO�͂�����Ք��������Ƃ�͂��܂�ƌĂ�ł����B�Ղ̓��͎l�������Ǝ��������ƂŁA���̎������������̐_�ɉ��̂�����ł���B �H�c�s�̌Îl���_�Ђ̕t�߂ɂ́A���ƑD�K��Ƃ����n�ɌՃm��Ə̂��鐴�����������B�l�������̍Ղ̓��ɖؔn��炢�����O�̗p�ɂ͗p�����鐅�ł������Ƃ���(�ԉJ�G�M)�B�Ղ̓��ɐ_�`�݂�������̏�Ɍ}���܂��ɂ��Ă��A�O�ɂ�����Əq�ׂĂ��������A������_�`�������͕l����̗�́A�����ɂ��܂葽�������Ă��̏��ɗ��邱�Ƃ��ނ������B�������̒��Ŏ����̒������Ǝv�����̂́A��Ղ̓��̐_���Ƃ͓Ɨ����Ă��̋V���݂̂��s�����́A����Εl����̂��߂̕l������s���n���̂��邱�Ƃł���B���������̂ɂ����̗Ⴊ���������ƋL�����邪�A���������ؐ��ꎁ���畷�������ł́A�֏邢�킫�l�q�l�ɂ����X����_�`���C�݂��l�����ŏo�镗�������āA���̓�����͂�l�������ł������B �����ŗ��߂��Ă��̓����d�v�Ȃ�Ƃ���Ɏ��������R���l���Č���B�M�c�̉Ԃ̓��Ƃ��Ȃǂ́A�����ɗR���Ắu�Ԃ̓��v�Ƃ��u�Ԃ̞�Ƃ��v�Ƃ����܂��܂̎��ĂĂ��邪�A�����z�K�̉ԉ�͂Ȃ��̌Î��ɔ�ׂČ���u�Ԃ̓��Ƃ��v�Ə������Ƃ̐������̂�����B���Ƃ͓��l�܂��͓����̓��ŁA�N�Ԃ̎i�Վ҂��Ӗ�����B�M�c�ɂ������l�㓪�l�قƂ��ɂ�̓�l�������āA���N�l���A�����ȂđI�肹���A���N�̌܌��Z���܂Ő_���������Ď��̓��l�ƌ�サ���B���̓�l�̓��l�͎l���A���̗[���ɗ�{�̊C�ӂɏo�ĉ���(���P���͂炦)�������̂ŁA���̎����Γ��l�l����Ɩ��Â��Ă��������ł���(���B�{�u��)�B ���ꂩ�琄���������ƁA�l�������͌܌��c�A�̋G�߂̍Ղ̂��߂ɂ���֊����̂��݂̎n�߂̓��ł͂Ȃ��������Ǝv���B�_���Ɏ���čł���Ȃ�č���S�̋F���Ɨ\���Ƃ��A�܌��̏�{������[�߂̐ߋ������Ƃ��čs��ꂽ�Ƃ���A�l���̔����͂قڎU�֒v�ւ����������̓����ɍ����̂ŁA���͕K�����������ł͂Ȃ����������m��ʂ̂́A��ɗ�L�����Փ��̊O�ɉK����K�����Â����݂̂��̂Ђƒ�߂��Ђ�����̂Ŏ@������B �w�����c�A�̋V���ɐ[���W�̂��������Ƃ́A���������������Ƃ߂̐����܂����x�x�ɐՂ𗯂߂Ă���B���̒��̈�l��I�肵�ăI�i���Ƃ����A�q���}���`�Ə̂��A���ɐ_�Ɏd�����߂Ă����炵�����Ƃ��ۗw�W�̑����̓c�̂������ɗR���Ď@������B�ޓ������̏����Ƃ��Ēʏ�̐����ƕʂ��ۂɁA�R�ɓ����ĉԂ�E�݁A�C��ɉ����Đg�����߁A�����Ƃ��Ă͗e�ՂȂ�ʋC�Â��킵���ސT���n�߂鎖�́A�Ԃ₩�ɂ��āA�����ɕ�����Ȍ��i�ł��������ƂƎv���B�����̊����傤��������傪�n�܂��Ă��̍�@�̂��o�����ɁA���Ȃ킿���̑����̐��̐_���Ȃ���(�u�s�^���v�A��3����1-91-88)���Ƃ߂�b�͋N�����̂ł��낤�B �o�_��ЂȂǂł͂��̓����Y�����Ȃ܂���݂����Ҏ����܂����̉������鎮��������(��Ўu)�B�͓��̗_�c�������ł��̓��̎�{��ɑ��Ԃ��������d�x������g���̂��A���̏Z�g�Ђł��̓��R�z���������̐_���Ə̂��_�n�������đ��X������̂��A���̏��Ђ̍ՓT�Ƌ��ɁA����ɏd��ɂ��Ă���ɐÏl�Ȃ���p�����傭�̍Ղ̗\���̋V�����甭�B�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���ɂ��̐���̔@���Ƃ���Ȃ�A�����̓��Ɍˌ��ɝ������G�߂̉Ԃ��̒����邵�ƌ���܂łً͈c���Ȃ��A�܌��N���V���Ԃ̓V���Ƃ����ɏd���������ꂽ�_�����́A�����Ȃ��̂��Ƃ������ƂɋA������̂ł���B�@ |
|
| ���T���o�C�~���̓� | |
|
�c�̐_�̍Տ�͈ȑO�́A�c��Ȃ킵��̐^���ł������̂��A��X�����݂Ȃ�������c�̔Ȃ���̈ꕔ�Ɉڂ�A����ɉƂ̒��ʼnP���������݂������̂��A�܂��͏��̊Ԃ�_�I�̏�ł��A�Ղ�����悤�ɂȂ������̂Ǝ��͌��Ă���B�u���v�Ƃ����G���ɏ������u�c���|�Ȃ����݂����̘b�v�́A�s�\���Ȃ��炻���������Ƃ������̂ł������B�����L���̊Ԃɍs�����c�A�ɂ́A�T�Q�Ə̂���c�l���тƂ̓���Ƃ��ǂ肪�A��������g���ďo�ꂷ��B�T�Q�͂����炭���̏�̖��ŁA�T�̖�����T�M�Ƃ��������̂ł��낤���A���݂̓T���o�C�~���̓��ɂȂ��Ă��炱���c�̒��ɗ��Ă邩��A�c���|�Ƃ̊W���s���ɂȂ����B
���n�̓Ȃǂ̎O�c�c�A�ł��A��Ȃ�̈�}�����̎O�c�̕c�̐^���ɝ������āA������A����Ƃ��ɓc�̐_�߂Ԃ����̂��A�܂����̓�̎}��c�̐_�~�Ղ̖ڕW���Ƃ��������������A����܂����łɐA�c�̒��̂��Ƃł����āA�c��ɂ����Ă͂��̕c�������Ɏ戵���Ă�������m�邱�Ƃ��o���Ȃ��B�Ƃ��낪�M�B�Ȃǂ̃^�i���_�A�܂��͓c�̐_���܂̍��|�Ƃ��Ƃ܂�Ƃ������k��Ȃ��̖́A�����c��̑�~���납���̓����痧�ĂĂ����āA�ł��Ƃł͎O�c�̕c���A���̓c�_�_���̂��݂ڂ��̍����Ƃ���̂邱�Ƃɂ��Ă���B�֓��̕c�ڂȂ����Ⴍ�A�Ώ邢�킫�n���̕c���|�A�����蓌�k��тɂ����ẲƁX�̕c���邵�́A��������d���݂܂��ȑO����c��̐^���ɗ��Ă��A�����ړ��ĂɎ���T�����߂ɑ��݂�����̂̔@�������`���Ă��邪�A���������̕c���邵�̍����Ƃɋ߂��c���A���ɑ厖�ȕc���Ǝv���Ă���l�́A����̂����m��ʂ����͂܂��������Ă��Ȃ��B ���ł��Ȃ���b�̂悤�ɏ��Č�邱�ƂŁA�����肪��������C�����Ă��邱�Ƃ́A��̍O�@��t���V���Ă�����A��̕�������Ǝ����Ă����������ɁA��X��ׂɍՂ��Ă�邩��Ƃ��������āA�ςɂ��̎�q�����������͂�̒��ɉB�����������B���̖ڂ��邵�ɗ��Ă�ꂽ�̂��c���邵�̋N�肾�Ƃ������Ƃł���B���̘b�͂��낢��ƌ`�������āA���ł����{�S���ɕ��z���Ă���̂����A�����c���邵�ƈ�ׂƂɌ��ѕt�������̂͏��Ȃ��炵���A���������̓_�����Ȃ�L�͂Ȉ�̈Î��ł������B �ȒP�Ȍ��t�ł͐������킹�Ȃ����A�M�z��т̍L���n��ł́A�t�d�܂�������݂��˂Ɍ����Ă�����X�W�ƌĂ�ł���B�Ƃɓ`���Ă̎�ɂ��n��������A��������̔N�̐��Y�Ɉ��p���ɂ��A���n���Ȍ�̊���̋V���͂������悤�ŁA�Ղ͂��Ȃ킿�c�A�̎n�ߏI��́A�Z���������ȂĊ������邱�Ƃ��o���Ȃ����̂������B���̓_������Q���Y����悤�Ƃ��Ă���̂ł���B�]����S�̂�������̐��̏��������傤����ԂA�����܂Ŏ��������̂ɂ͗��R���������B �����ʼn��߂ď��N�ɐq�˂Č������̂́A�̉F�씎�m�̂������ċV��Ƃ��܂����ꂢ�́A�����Ȃ�������ȂāA���쌧�ł͍s���Ă��邾�낤���Ƃ������Ƃł���B���Ȃǂ̒m���Ă������ł́A���g�̖k���̑��X�ł͎퉺���̓��A�c��̌l�����̓����Ɏ����̎}�𝇂��A�ĕĂ₫���߂ƎG�������Ƃ������ăT���o�C���Ղ����Ⴊ����A�ɗ\��O���̖k�[�̑��ɂ́A��������ɕĈꏡ��N�_�Ƃ����݂ɋ����āA������T���o�C�I���V�Ƃ����K�킵�����������A���̑��̍L���n��͈�ʂɁA���̐_���~���\���̂͏��c�A�A���Ȃ킿���̕ӂŃT�C�P�܂��̓T�C�L�A���̓y�n�ł̓T�I���E�T�r���L�E���T�E�G�Ƃ��������Ɍ����Ă��邩�Ǝv�����ǂ��ł��낤���B�ʂ��Ă��̑z���̔@���Ƃ���A�����ɂ܂���̕s�R�����܂�ė���B���Ȃ킿���̃T���o�C�~�����ȑO�A����ѓc�A�I��̃T���o�C�グ����ɁA�c�ł͂ǂ������_���Ղ������B����ƃT���o�C�l�Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă�����̂ƁA�����͍l���܂��͉������Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�@ |
|
| ���P�����̖ڐ� | |
|
�~�J�����l�̒��҂Ƃ��āA���������傢�ɒm�肽�����Ă��邱�Ƃ́A���\�ꌎ��\�O����̍������ɂ߂���ɁA��t���������ΉP�̖ڂ���Ă��邩���Ƃ����`�����A���݂ǂ͈̔͂ɂ܂��c��`����Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�����̐܂ɔN���Ȃǂ��ӂƌ����o���͂��Ȃ����B���ꂩ����ǂ����C�����Ă��Ă��炢�����B�䏳�m�̒ʂ萠�P���肤������ʔ_���ɕ��y�����̂͂����Â����Ƃł͂Ȃ��B�ΉP�̖ڂ��Ԃ��ƁA�ڂɌ����Ĕ\�����ቺ������̂����A����ɂ͐Ή��̎�����ȓ�����p������A��H�ł͂ǂ����Ȃ�Ȃ��B�����������Ɛl�̒m��ʊԂɁA�����Ɨ��Ėڂ𗧂ĂĎg���₷�����Ă����ĉ������������Ƃ����̂�����A�������Ȃ��炱����M�ł���B
�R��ɍ]�˂Ȃǂł́A�������傤�Ƃ��̏��ߍ��ɂ��ꂪ�͂��A�����̂��낢��̏��Ɍ����Ă���̂��A���ꂩ��S�N�]���ɗ��s�����A�Γ������Ƃ�����n�̕s�v�c�ƈ�ɂ��āA�d���������������w�҂�������(�����̂܂ɂ܂ɁA�V�ی��N�L��)�B�c�ɂ��Ȃ��̕��ł����̑�����t�u�����������������̔ӂ����́A������������̐ΉP�̑����A�|���킪���Ēy���Ēʂ����Ƃ����b���A�������z��̐l�ɒ������悤�Ɏv���B�Â������`���̎��������A�N�Ƌ��ɏ������ς��čs����ł���B ���ԓ`���ł́A�l���̎O���ɁA�X���̗Ⴊ��o�Ă���B���Ìy�̋���Ȃǂł������Ƃ́A�O�@��t�͏\��N�Ɉ�x���N�����̔N�ɑ��������ĝ���������ɖڂ�ł��čs�����B�����ꂢ�Ȉ߂𒅂Ēm��ʊԂɒʂ��Ă��邭����A�N�N�͝����������Ȃ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����������ł���B�����͐ΉP����l�Ă���ꂽ�܂���̕����ł��낤���A����͏Ă����̂�����ڂ��Ƃ������Ƃ͍l���ɂ����B����ł�����̎��┪�̎���t���čs���Ƃ�������A�܂��͓h��V�̏�ɉ~����K���݂قǂ̐Ղ����čs���Ƃ��������肷�邪�A�Ƃɂ�����t�̗�������Ƃł͐g�サ�傤���悭�Ȃ�ƌ����āA���ł��Ђ����ɐS�҂��ɂ��Ă���l������Ƃ����B���������̊����͓�\�O��Ƃ͌��炸�A�H�̖�����Ƃ��A�܂��͏t����H�ւ����āA����Ă�����Ƃ����������ł���(�ȏ�)�B ����͈��{���ɏo�����Ƃ����A�啪�����Ă���l�����Ȃ��Ȃ������������x�f���Ă����B���̖ړI�͐ΉP�����̋�z�͐V�����ɂ������Ȃ����A����͂ǂ������M��Ԃ̉��ɐ��܂�A�ǂꂾ���̋��ɂ܂ŗ��z����Ɏ����������l���Č������̂ł���B�Ȃ��t�L���������Ƃ́A���a���N�̂����Q��̌�ɏo���u���Q������ʂ��܂����߂��̂�����v�Ƃ������ɂ��A�l�Ƃ̐ΉP���m��ʊԂɖڂ�肩���Ă���̂��A�O�@��t�̏��s���催�傤�Ƃ�������������Əq�ׂĂ���B����͂���������̏o�ŕ��ł������B�ΉP�̖ڗ��Ă��ƂƂ��Ă��邭�҂́A�M�B�k�����̑��ɏ������͂������悤�����A����̑S�������ė��Ȃ����������A������đ����ڂׂ̒Ԃꂽ�P�Ȃǂ́A�܂��ƂɎn���̈������̂������B�@ |
|
| ����\�O�铃�@ | |
|
���ՉB���̐�
���邢�͂܂����̕n�����Ƃ̔k���A���͝����肱���̂悤�Ɏw�̂Ȃ��Зւł������B����ł͂��̏��̏��ƂƂ������Ƃ������I�������̂ɁA����~�点�đ��Ղ��B���ĉ����ꂽ�̂��Ƃ����������Ȃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�z��̋����n���Ȃǂł͘b���܂��������肿�����Ă��āA���̑�����\�O���̖�X�ɁA���X�������Ă��邩����t�Ƃ����l�́A�����f���{�ł������Ƃ��`���o�ł������Ƃ������A����Ŏ���̑��Ղ�l�Ɍ����ʂ悤�ɁA����~�点���܂��Ƃ����悤�ɓ`���Ă���B ����͂������ɓ����b�̓�ɕ��ꂽ���̂ł��邪�A���̕����Â�����̂��̂��낤�Ǝv���킯�́A�ՉB���̓`���̑S���Ȃ��y�n�ɂ��A�Ȃ������O��̑�t���܂́A��҂͂���ł������Ƃ��Б��_�����������݂������Ƃ������҂��H�łȂ��̂ł���B�l�͑�t�ƒ����Ƃ܂��O�@��t�̂��ƂƎv���A���ꂩ��O�@���j��߂̗��m�̎p�ŁA���ł��S�������邫�܂���Ă�����悤�Ɍ����҂�����A����R�̕��ł���e���݂����ǂ��̑�t�̂��p���A���N�̂��ߑւ���������ɂ͂�������@�߂̐�������点�Ă�����ȂǂƂ����b���o���Ă��邪�A�����������������܂��܂̘b�����Ȃ�A���̑����O��̗��̐_�����́A�O�@��t�łȂ��ƌ��킸�ɂ͂����ʂ��낤�B ���k�n�����[�X�̕��֍s���ƁA���̑�t�͏������Ƃ����l��������B�f�C�V�R�͕v���Ȃ��A��\�O�l�̎q�����������B���̓������炦�ďグ�銟�����c�q���̑V�ɂ́A������{�̂���Δ��͂��ƁA������{�̏���Ƃ����̂ƁA�K���O�{�Y���邱�ƂɂȂ��Ă���̂����A���������܂莙�̐��������̂ŁA��X�T���֊���ĐH�ׂ����邱�Ƃ��o�����A����ł��̂悤�Ȓ����������p�Ȃ̂��Ƃ������������Ă���B���邢�͂܂���t�͎q���������̂ʼnƂ��n�����A��\�O���̊��ɓ���鉖�������Ȃ��A������ɏo�ēr���Ő���ɑ������ē|�ꂽ�B���������R���ɂ���č��ł����̓��̊������͉������Ȃ��Ƃ����҂�����B ��t�u�̓��ɂ͉����ł������ςċ����A����ɉ������Ȃ����Ƃ͎����ł��邪�A���̓y�n�ł͂܂��n�Ƃ̏����A���̍O�@��t�ɂ��̊��������グ���Ƃ��ɁA�ǂ����ĉ������Ȃ��̂��Ƃ킯�����āA���������ʂ悤�ȕn�R�Ȃ̂ł��Ƃ����ƁA����͍��邾�낤�Ə�̂������ȂĒn�ʂ��h���A�����̗N���o�����������ꂽ�B���̋L�O�̂��߂Ɋ��ɉ������Ȃ��̂��Ɛ������Ă���҂�����̂ł���B����Ȓ���������̘b���A�����ɂ������ɂ��悭�L�������Ă���̂�����A���̏\�ꌎ��\�O�������\�l���ɂ����Ă̈����A��͂�l�����˂ނ炸�ɐ��C�̐����߂�悤�Șb���A�p������ɂ���ӂł��������Ƃ��z�������A�����ɂ��c�ɂ̓~�̏W�肪�A�̂Ȃ��̂��������Ƃ��l������̂ł���B�@ |
|
|
�����������Ă��݂��E�卪�삾������
������������t���A�܂��͍O�@���Ɩ��Â��鏔���̓`���ɂ́A���炩�ɏ\�ꌎ��\�O���̏o�����������Ƃ������̂͊���Ȃ����A�����͑O�ɏo������E���̓�\�O��l�Ƃ����Ԏ��Ă���B�������Ă��̋N��́A�������ɂ܂��O�@��t�̐��܂ꂽ�������Â��̂ł���B���{�S���ɂ͐�ȏ�A�n���ɂ���Ă͑����ɁA�܂��ɂ��̘b�������āA�����ǂ��̂������Ă��͓������Ƃł������B �̈�l�̏������̉��ŋ@�͂���D���Ă���ƁA�����Ȃ��j��߂̌�H�������݂��悤�ȗ��m������ė��āA������t���炢�����Ƃ������B�̂̒n�@�����͕R�Ђ��ł��炾���@�Ɍ���킦�����̂��������A�S�̂₳�������Ȃ̂ł��̔ς킸��킵�����}���Ƃ킸�A�R���قǂ��@���牺��āA�����������݂ɍs���ė��Ĉ��܂����B�ǂ����Ă��̂悤�ɂЂ܂����������̂��Ƃ�����āA�����͐��������R�����A���\�����s���ʂƂ߂��������Ȃ��B���������ŗ�������x���Ȃ�܂����Ɠ�����B����͖������܂Ȃ��Ƃł��낤�B���O�͐S�̑P�����l������A���̖�O�ɐ�������o���Ă�낤�ƁA��Œ��悢�����h���Ƃ����܂��������N�킢���B���ꂪ�������閼���߂������ŁA�ꖼ�������Ƃ����Ă���Ƃ����̂������B ���邢�͂��̋ߏ��ɕs�e�ȏ��������āA���l���������߂�ƁA�����̐���᷂������炢�̐��ł����߂Ƃ������B����ł��̉Ƃ̈�˂͍��ł������Ȃ��D�����Ƃ����悤�ȁA���̘b�̂��Ă���̂�����B�l���̈ꕔ�ł́A���̗��m���Ŗ������������݂傤���Ƃ���肾�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��邪�A�������q�̉��ւ�������ł������āA�����͎������������Ƃ���ł�����A���̂Ƃ��납�����ʼn������ƌ������̂ŁA��������̋ނ��ݐ[���s�����傢�ɏ܂���ꂽ�B��㊂̓��Ȃǂ́A�Ŗ������O�@��t���܂���čs���ʗ�������A��͂肱��ƑS�������b�������āA����͐_�l���p�������āA�l�̐S�����݂�ꂽ���̂̂悤�ɂ����Ă���B �킸��������t�Ƃ����悤�ȏ����Ȃ��ĂȂ��ł��A�u�̐[���҂͐_�̂��b�݂���Ƃ������P�ł������낤�Ǝv�����A����Ɠ����b�͂܂����낢�날��B���Ƃ��Ώ�����ɏo�đ卪�����Ă��鏈�ցA��͂茩���ڂ炵�����m�����đ卪����{�����Ƃ����B���̐�ɂ͐����Ȃ��̂ł܂��܂���Ƃ��������ƁA�������Ƃ����ċ����Ă��܂������A���ꂩ��ȗ��卪����ɂȂ�A��ɂ͂����Ɛ����Ȃ��Ȃ�Ƃ����卪��Ƃ������ꂪ�A��B�Ȃǂɂ͏\������������B �卪�͂��傤�Ǒ����������n�̐���ł���A�܂���\�O��l���Ղ�Α卪���悭�o����Ƃ������M�������̋߂��ɂ�����B�b�q�Ղ��̂��˂܂�̓��ɑ单�����āA�卪����Ɉ�{�����Ə��]�Ȃ��ꂽ�B����͎�l�̕��ł�����グ���܂��A���������͗]���ł����炳���グ�܂��傤�ƁA��҂ӂ��܂��卪�̕Е�������ďグ���B���ꂩ��b�q�̓��ɂ͓�҂̑卪�������āA�单������Ղ�̂��Ƃ����b�����k�ɂ����邩��A���̘b�Ȃǂ͑��������O��̑�t�u�ƊW������A�]���Ă��̔ӂ̖�b�ɂ��Ă������̂ł������낤�B�@ |
|
|
���O�@�@�����ڂ����E���@������Ăʂ���
���̈ȊO�ɂ��Έ���������������ɂ����s���킸�Ȃ��̗ށA���̗��͍d�������ĂƂĂ�����܂��ʂƋ\�����ނ�����A���ꂩ���͋��Ƃ̏o���ʗ��ɂȂ����Ƃ����悤�Șb�́A�����Ă��F��t�̈�b�ƂȂ��Ċe�n�ɕ��z���Ă��邪�A�N�ł��m���Ă���قǐ��������̂�����A�����ڂ����͂����ŏq�ׂȂ��B���ɂ͍O�@�@���Ƃ����āA����͏�����t�̕����������Ǝv���b������B�������͂菗����l�A�ׂǂ����ŋ@��D���Ă���Ƃ���ցA��̗��m�����Ă��̕z�����ڂƂ��A�������癒�����Ă킵�ɂ���Ə��]����B����̂����܂������͂��������͂˂��邪�A���ׂ̗̏��͑m���h���A�ɋC���������Ȃ����͂��݂����ēn���ƁA���ꂪ���ۂ͐l�̐S�̎����������̂ŁA�����y�悵�đ傫�Ȍ�J�����ق��тՂ���B����͉��ł��ʂĂȂ��ɑ����Ƃ����s�v�c�̗͂ł������B���̏����z���@���牵���낵�ĕ������̂����ő���o���ƁA���ڎ���Ă����̐Ղ��܂��c���Ă���B����ł����܂�������ɂȂ��Ă��܂����B �������͂�������đA�܂����Ă��܂�Ȃ��B���X�T���܂���Ă��̗��m�����������ɂЂ��ς��ė��āA����Ƃ�����ʂ̂ɕz�����ڂ��������ēn���ƁA��J���͂���������͂ł������B��������A�܂����ł�����ł����Ă���z���͂��邱�Ƃɂ��悤�ƁA�艱�������Ĉ�˂֍s���A���������ċA��r���A���ׂ��ē]��ł��̐������ڂ�A���ꂪ�܂���U�n�܂����炢���������āA���܂��ɂ͂��̏��̉Ɖ��~�����ɂȂ����B���̏������Ƃ����������ȂƂ����悤�Ȑl���킹��b���A��͂蓯�������`����e�ɂ��Đ��܂ꂽ���̂ł���B ���ꂩ�������A����͍������V�����o�������̂炵�����A���@������Ăʂ����Ƃ����b������B�ނ����S�̔������A��e�����������̎����Č��ɂ������������āA���҂��傤����̉Ƃɕ�������Ă����B��l�̍ȏ��̕�����̂����݂������̂ŁA�����͗����̗]�蕨��H�ׁA�䂪�H�������c���Ă����ė��m�Ɏ{���Ă����B������ӂ��Ɨ����̂��O�@��t�ł��邱�Ƃ�m�炸�A�����ƌ��ǂ������ėp�ӂ̐H���������グ��ƁA���O�͒������P�l�����炱�����낤�ƁA���̕��͌�������O�ڂ���̕z�������������B�������@�ɂ��Ċ��@�ӂ��Ă�����A��O���������ʂ����Ɍ���������ق��Y�킫�ꂢ�ȏ��ɂȂ����B�Ƃ̏��[���т����肵�āA�ǂ������ǂ������Ƃ킯��q�ˁA�}���Ŏ��������m�������ė��āA����ƌ�y���������̂ł܂���@�Ղ���B���������������g����Ȏ{���Ȃ̂ŁA�������Ȃ��čs�������Ȃ��A�����������炪�����Ȃ��ė��āA���܂��ɂ̓q�q���ƚ|���ȂȂ��Ĕ�яo�����ȂǂƂ����ď킹�Ă���B�@ |
|
|
�����Ɛ���
���̘b�̊�ɂȂ������Ǝv���̂��A���k�ɂ��L���s���Ă���A�܂�����̍��̒[�A��㊂̓��ɂ��܂��͂�����ƋL�������Ă���B����͐H����m�Ɏ{�����Ƃ������ɁA�s�v�c�̗��l�Ɉ��̏h��݂����Ƃ������ƂɂȂ��āA��͂�n�����e�؎҂ƁA���~�ȋ����Ƃ̑ΏƂ������Ă���B������\�O���̖�ł͂Ȃ����A���ʂ͐������߂Â����N�̕�ɂƂ����b�������B �����ʗ��̐l�����Ăǂ������߂Ă���Ƃ����̂��A���҂͂����Ȃ��f���Ēǂ��o���悤�ɖ�����߂�B���ׂ̗̕n�R�l�́A���Ƃߐ\�������͎̂R�X�����A���������グ��悤�ȐH�ו����Ȃ��̂ɍ���Ƃ����ƁA���₢��̖T���ɂ����u���Ă����Ȃ�A�т͂킵�������炦�邩��ƁA�傫�ȋ�炩��Ȃׂ��o�����B�܂̒����玨�~�݂݂����Ɉ�ς��قǂ̕����o���āA�������ĉ̏�ɂ�����ƁA�����܂��̂����Ɉ��̐^���ȕĂ̔т��o�����B�������l�v�w�ɂ��H�ׂ����āA���O�����͐��ɗ��h�Ȑl���B���ɗׂ̒��҈ꑰ�����ɂȂ��ĎR�ɓ����Ă��܂�����A���̐Ղɓ����ďZ�ނ��Ƃɂ��Ă�낤�ƌ������B���̗��l�͎��͐_�l�������̂ł���B ���҂͐_��e���ɂ������ŁA�ʂ����ĉ��ɂȂ��Ă��̉Ƃɂ͂����Ȃ��Ȃ�B�����ȕn�R�l�͑��ɂ��̉��~�������ƂɂȂ������A��㊂̘b�ł͂��̉������ݔ߂���ŁA�����R���痈�Ė�̐ɍ������Ěe�Ȃ����B�ǂ�������D���ł��傤���Ƃ܂��_�l�ɉM���������ƁA����Ȃ炻�̐�M���Ă��Ă����Č���Ƃ̂��ƂȂ̂ł�������ƁA�����m�炸�ɗ��č������낵�A�K������Ă��Ĕ�я���ē����čs�����B���ꂩ�獡�ł����̐K�͐Ԃ��A���̎�͐^���ɉ���Ă���̂��Ƃ��A�܂����Ƃ͐����Ƃ���������Ƃ������Ă���B���Ȃ킿�������ʂ��q�������悤�ɁA���b�Ƃ��������̂̌`�ɂ��Ă���̂����A���Ƃ͍���i�Ɛl���M������悤�Ȍ����`���ł��������Ƃ́A�Â������Ƃ̔�r�ɂ���Ă킩���ė���̂ł���B ���̌Â��b�Ƃ������̂̈�́A�L��������т̉u���{�����݂݂̂�Ƃ����_�Ђ̗R���ŁA����͉����N�Ԃ̕��y�L�ɏo�Ă����Ƃ������A���ꂪ�����ł����Ă��O�@��t���͂����ƐV�����B�ނ������̓y�n�ɋ��U���������傤�炢�E�h���������݂傤�炢�Ƃ����Z��̎҂��Z��ł����B���U�͖����߂Ő_���h�킸�A�h���͐������P�l�ł������B�����V�_�ԂƂ��Ă�Ƃ����k���̐_�l���A��C�̔��������_��W�߂Ƃ낤�Ƃ��āA�����Ɉ��̏h�������߂Ȃ��ꂽ�Ƃ��ɁA�O�̘b�Ɠ��l�Ɉ���͂���������݁A���̈���͉������}���\���āA�I�̔т�i�߂��Ƃ������Ă���B �����V�_�͍��̋��s�̔���_�ЁA���ɋ_��������Ƃ����u�a�����т傤�̑�_�������݂ł������Ƃ����B�_����̕����甪�l�̌�q��A��ċA�肽�܂����ɁA������ɂ���ċ��U�͂����܂��ł��łڂ���A�h���̖��͉i���_�̌��Ђ������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��āA���ɍ��ł����X�̓V���ЂĂ�̂�����܂��͋_������̂��Ђ���A��������u�a���悯�̎��D�ɂ́A�h�������q���炻�݂傤�炢�̂�����Ȃ�Ƃ����������A���������̂������̂ł���B���̐l���Ȃǂɂ͕s�R�ȓ_�����邪�A���Ȃ��Ƃ����������炨�o�łɂȂ鑸���_�l���A�^�S���ȂĂ��h����l�X���A�q�����i���ی삹����Ƃ��������`�������͓��{�̂��̂ŁA��������̕�����p���ł���̂��ƁA�������Ƃ܂ł͂���ɂ���ĔF�ߓ�����B�@ |
|
|
���V�_�̂��h
�������Ĉ���ɂ͂܂��L���ȁA�x�m�ƒ}�g���Ƃ����Â��b������̂ł���B����͓ޗǒ�����ɏo�����헤�Ђ������y�L�Ƃ����{�̒��ɏo�Ă���̂ŁA���̎������͂ɂȂ����̂́A�m���ɍO�@��t�̐��܂ꂽ�������O�ł����āA����ɂ͔��s�т������ė���ꂽ���l�́A��c�_�݂��₪�݂ł������Ɩ��炩�ɏ����Ă���B��̂��̑�_���A�x�m�R�̂Ƃ���֗��Ĉꔑ�����߂�ꂽ�̂ɁA�������悢�͐V���ɂ��Ȃ߂̔ӂ�����A�m��ʐl�Ȃǂ͓��ɓ�����Ȃ��ƌ������f�����B����ɑ��Ē}�g�̎R�̕��͕��킩�肪�悭�A�V���͐T���݂̖�ł��邯��ǂ��A���Ȃ�ʓV�_�����h�\���ʖ@�͂Ȃ��ƁA�������}���\���č��˂�ɂ����ĂȂ��������B���̍s���ɂ���Ē}�g�͏������R�����A�ē~��ʂ��đ����h���A���Q��ɗ���l�̐��������A�x�m�͂��̒ʂ�ϐႪ�[���āA�l�̋߂Â����҂̎����ď��Ȃ��̂́A�V�_�Ɍh��s���Ȃ��������߂��Ɛ��������Ă���B �R���V���̍Ղ��c�ނƂ����̂͒��������A����͏��Ȃ��Ƃ����̓�̕����Ɍ�����n���ł́A�ǂ��̉Ƃł��F�×��̍�@�ʂ�ɁA���̈��̍Ղ����ʎ҂��Ȃ��������炻���v�����̂ł��낤�B�������Ă��̘b���������}�g�R�̕����Ђ������Ă���̂́A��̎R�̊ԂƂ͂����Ă��A��Ⓦ�̕��֕��������ɂ����āA���n�߂����̂���������ł��낤�ƁA���͍l���Ă���B �V���͉䍑�ł��Ƃɑ傫�ȏd���Ղł������B�ڂ������Ƃ͎��ɂ����킩��ʂ���ǂ��A��̎��n����������I���Č�ɁA�Ƃ𐴂ߐg�𐴂߂Ă��̍��������A�[���a�䂤�݂��ƒ����a�����݂��ƁA���x�̌�V��_�ɂ����グ��Ղ̂悤�ɒ������Ă���B���݂͑��z��ŏ\�ꌎ�̓�\�O���ɂ��̍Ղ��s�����Ƃɒ�߂��Ă��邪�A�ȑO�͂����ƒx���A�~������ۂNJ����Ȃ��Ă���̍Ղł����āA�����͖k�����ł͑��z����̒[�܂ʼn���A���ꂩ�班�����k�֊҂��ė���Ƃ����A�~���̑O��̎��ł��������Ǝv���B �����ł���������~�����ȍՂ̓��ɂ��Ă��邪�A���m�ł����N���X�}�X�Ƃ����Ă�������A����L���X�g���傤���������ƌÂ����̂������ŁA��̐��w���܂��������m�łȂ���������ɁA�����Ă��낢��Ɨ��A��t���āA������L���X�g�Ƃ����_�̎q�̐��܂ꂽ���ɂ����Ƃ����b�ł���B�ԍ炫���̖��t�Ƃ��������ꂵ���G�߂��A���ꂩ��o�����ċA���ė���Ƃ������ł���̂ɁA�����͋����܂��b�ݐ[���_�̌�q�́A�a���̓��̂悤�ɑz�������̂́A�q���炵����̂̐l�Ƃ��Ă͎��R�Ȃ��Ƃł������B�����Ă����l�̌����҂��A�����čL�߂��ƌ���K�v�͂Ȃ��̂ł���B �V�_�Ƃ��������ł́A�܂���X�ɂ͂͂�����Ƃ��ʂ悤�ł��邪�A���{�ł����̎�X�����L�тčs���t�̗z�C���A�V���ɒa���Ȃ��ꂽ��q�_�݂����݂ƁA�l���邱�Ƃ��o�����̂����m��Ȃ��B��\�O�l������q�̕ꂪ�A����̒��ɉ����ɏo�ē|�ꂽ�Ƃ����̂��A���_��z�����A��Â��Ƃ���͂������炵���A���Ń_�C�V�ƒ����čO�@��t�A�܂��͌��O��t��������p��t�̂�������z�����Ă����̂��A�N��͂�͂葸���_�̌�q�Ƃ������Ƃł����������m��Ȃ��B�����v���킯�͉䍑�ł́A���Ƃ͒��j�������I�I�C�R�Ƃ����A�����ł͏�ɑ�q�Ə����Ă�������ł���B�@ |
|
|
���V���̕���
���̐V���̍ՂƂ��������t�́A�������̂܂܂ł͔_���̒��ɂ͎c���Ă��Ȃ��B����łƂ��̐̂ɏ����Ă��܂����悤�ɁA�{�ŗ��j��ǂސl�͍l���Ă���̂ł���B���ꂪ�������̑����O��A�j�W���E�\(��\�O)�Ƃ������q�u�Ƃ������ƁA�������̂���������ɂ��ꂵ���̂����A�m���ȏ؋��͂������₷�������肻�����Ȃ��B���������ł���ׂČ��邱�Ƃ̏o����̂́A�̂̐V���ł����悢����ł܂ŁA�l���W�܂��ċN���Ă������ƂƁA�j�Ə��Ƃ��ꏈ���قɂ��āA���̈��̕�����������炵�����Ƃł���B����������ɓ`����Ă����Â��̂ɁA �N�����̉��̌˂����ӂ�ɂӂȂ݂ɂ킪�������Ă��͂ӂ��̌˂� �Ƃ����̂�����B�Z�Ƃ����̂͒j�����A�����̕v��j�Z��̂��Ƃł������B���Ȃ킿���͏��ǂ����˂����߂ĉƂ��Ă�����A�j�͂܂��ǂ����ꏈ�ɏW�܂��āA���̔ӂ̎Q�Ă���낤�����Ă����̂ŁA����Ɠ��������A���ł����X�̓�\�O��҂ɂ��Ă��鑺�X�͏��Ȃ��Ȃ��݂̂��A����ɂ܂��M�\�҂�������܂��̔ӂɂ��A����ʂɂ��Ă������K���A�܂��L���s���Ă���̂ł���B�M�\�̓O�邪���̒��A�����̎R���o��̂�q���āA�������������S�����ȂďI�����Ɠ������A��\�O����܂��閾���̏����O�ɁA�R����o�ė��錎�̌��ɐ��ʂ��āA����ōՂ͂��ƎU��U��ɕʂ�ċA�邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A����Ȃǂ̓}�c�Ƃ�������̈Ӗ����A�m��ʊԂɏ��������ׂ��ė������߂ŁA�_�Ƃł͂������ꂩ��Q��l���Ȃ������낤����A���ɖ邷����̍Ղł��������Ƃɕς�͂Ȃ��B ���ꂩ�獡��͘b�̎킪�����A�܂��Â����̂��i���c���āA�������킸�����ʔ�������������C�����Ă��邱�Ƃ��A���̐M�̕ϑJ�ƕ��s���Ă���悤�Ɏv����B�ŏ��͂����V���̖�̐T���݂����d�ŁA��������m��ʐl�������q��������Ă͂Ȃ�ʂƂ����x���ł����āA����ł��H�X�ɂ͐_�l���䎩��K�˂Ă����邱�Ƃ����邩��C�����˂Ȃ�ʂƂ����b�������̂��A��ɂ͐l�Ԃ̎��ߖ����߁A�e�ؕs�e�����߂��Č��邽�߂ɁA�p����������������āA�ƁX��K��Ȃ����Ƃ����悤�Șb�ɂȂ��āA�����K���������̓��ł��邱�Ƃ�v�����A��Ɏ������̐S�̎��������A�������߂��Ɉ��������ꂽ�̂́A�����ɂ���Ă͎Љ���̐i�݂Ƃ������Ƃ��o����B �O�@��t�������N�ȏ�A�n�I������j��߂ł��邫�܂��A�l�̐S�̗��܂ł����Ă�����Ƃ����b�́A���X�͌�H�V�傱�����ڂ����֗̕��ɂ�������ꂽ���m��ʂ��A����ɂ͂��ꂪ�������̐g�̍s�����A�m�炸�����炸�̂����ɂǂ̈ʁA�������߂Ă������m��ʂ̂ł���B��\�O��̖�b�Ƃ������Ƃ��A�߂����܂ő����ɑ����Ă��Ȃ�������A����Șb���������������ɂȂ��Ȃ����ł��낤���A���ۂɂ͂Ȃ����̓�̂��̂̒��ԂƂ������ׂ��b�A���Ȃ킿��\�O���M�\�u�̒��ԂցA���m��ʑ����̐l�������Ă�������Ƃ��A�傫�Ȃ����킹�ɂȂ����Ƃ����b�Ȃǂ��c���Ă���̂ł���B�@ �@ |
|
| ���O�@��t�䂩��̓��Ɣ���̓� �R�����V | |
|
��1
�R�����̉���͖��̂��鏊���ƕ��c�M���A������u�M���̂��������v�ƌĂ�鏊���w�ǂŁA�O�@��t�䂩��̉���͖w�Ǖ����Ȃ��B�Ƃ�����莄�́u�Ȃ��v�Ǝv���Ă����B �����{�����ł͂Ȃ��b�M�z�y�ѓ����{�ɉ����Ă��A�O���ł̈����͂��ߊe�����Ƃɓ_�݂��Ă��邪�A�R���̓��͐M���̃C���[�W�����߂��邹�����O�@��t�̑��݂��܂��������o���Ȃ������B(���̕��s���ɑ��Ȃ�Ȃ����c) �O��̎R�A�Ƃ͈Ⴂ�R���͓������������ɋ߂��A���̉���s�r�̒��ł�����z�[���O���E���h�̂悤�ȃG���A�ł���B ���ۂɂ��̓x�̊��ɉ����Ă��������ɂȂ�͓̂�������݂̂ŁA���̓�͂����ӂ���̂��Ƃ��K��Ă���B��������͂����܂ōO�@��t�Ƃ������_������̂ŁA���܂ŋC���t�����f�ʂ肵�Ă��܂��Ă��������ɏo�����҂�����A�O����萶�����T���ӗ~���X�ɍ��߂Ă���闷�ɂȂ肻���ł���B �R�����́u�R�͂����Ă��R�Ȃ�(��)���A�C�͂Ȃ��Ƃ��L(�b��)�̍��v�Ȃǂƌ�����قǎl�����R�Ɉ͂܂ꂽ�����ʂ�R���ł���B�ꉞ�����n���ɉ������Ă�����̂́A�ꕔ�͓����s�Ɨאڂ��Ă���s�S���������r�I�A�v���[�`���Ղ��B �܂��߂�����ɓ�A���v�X�A�������R��A�����x�ȂǓ��`�O��m���̎R�X�₻�̎��ӂɂ͌��n�I�Ȏ��R�╶���A�܂��������c���Ă���A�C�y�Ɂu�E�s��v���ł���Ƃ����āA��������̓��A��ό����s�ɂ͍œK�ȏꏊ�Ƃ�����B �����s�������������ɏZ��ł���Ƃ������Ƃ�����A���N���Đ��V���C���t������ԑ��̎R���A�Ȃ�ĂȂ��Ƃ���������イ�ŁA�ꎞ�͍�������b���a���炢�܂łɓ_�݂��閼�������z����l�ׂ��ɖK�ꂽ��A�����t�߂������낵�Ă����m�O��̎R�X�ɂ������ς�����o�������Ƃ��������B���ł��������̍b�{�s�����ʓd�Ԃɏ��Ɓu���`�A�܂�����������v�ƌ������ƂɂȂ��Ă��܂��B �����s�S���������q�����͂����Ȃ�R�������Ă���B����Ӗ��A�����w���N�_�Ƃ���ŒZ�Łw�R�x�x�ɓ��B�ł��郉�C���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���B ���̓x�́A���悤�ɔ�r�I�ߏ�ł���ɂ�������炸�A�O���l���Ƃ����s�����B�O��̋��s�R�Ƃ͑�Ⴂ�B�M���̉B������������̗��j�ɖ����ꂽ�O�@��t�̔���A�O�@��t�䂩��̓�������Ƃ��̗��j�Ƌ��Ɏn�܂�������n�����Ղ�B���ɉ����Ɋւ��Ă͈�ʓI�ȍO�@�`���Ƃ͈�����悵�A�܂��ɔ���̗̈�ɓ��ݍ��މ\��������B���̈Ӗ��ō���̗��́A�s�������Ď����ɂƂ��Ắg���m�̎R���h�������D�̋@��Ǝv���B �����Č��ʓI�ɂ��̍��ł͂��̑O�҂Ƃ��āA�������瓒���̖�n�����Ղ�̑O���܂ł�ǂ����ƂƂȂ��Ă��܂����B �{���Ȃ���̍��ł��̍s���͊�������͂��������̂����A�r���o�߂̒��ŗ\��O�̍s����v����P�[�X���o�Ă��܂����̂��B ����͂��̑ʕ���S�苭���ǂ�Œ��������݂̂��ɒm���Ē�����Ǝv���B�@ |
|
|
��2
�R���ґ�2��͍����w����x�m�}���܂łł��B�O�@��t�̔���E�`���ɔ���O�ɕx�m�}�������́A����ꌬ�h�̉���Ɋ�蓹�������܂��B ���݁A�����������w�����\���B�~�ŋ�C������ł��邱�Ƃ�����A�z�[����ł����ɎR�̋�C��������B���x���Ă������ɂƂ��Ă͎����̎��ł���B �L��Ȋ֓�����������������ďI���Ƃ��A�����Đ��܂ꂽ�Ă̏����̎R�B�͎���ɐ����ɐ��͂��L���Ă䂭�B�����ď�������̓����悤�ȒJ���W�����甭�������Z��B�ƌ���藍�ݍ����Ȃ���₪�ĉ������R��Ƃ�������ȎR�Q���`������̂��B �J���W���Ƃ����̂͂����������R�ƕ���̐�ڂɈʒu����ꏊ�ł���A��T�͎R�Y��(�ыƂ�_�Ƃ̈ꕔ�Ȃ�)�Ƌߑ�Y�Ƃ̒��p���Ȃ��g�܂��h�ƂȂ�B ���������s�ł͕����ܓ��s��~�������ŁA��ʌ����Ɣє\�⏬�쒬�ƌ������ƂɂȂ�B����������������̈�ŁA�������ɉ��߂ăO�����ƌ��n���A�����ɂ͂����ɎR�A�����ɂ̓r����x�b�g�^�E�����L�����Ă���B���̈Ӗ��ł͂܂��Ɂw�E�s��x�̏o���_�Ƃ������Ƃ��낾�낤�B �O���l���̍s��������̂�(�����Ŗ��f���Ă͂����Ȃ������̂����c)�ꔑ�ڂ͍O�@��t�Ƃ͓��Ɋւ��̖����Ƃ���Ɋ�蓹���邱�Ƃɂ����B(�ҏW���̊炪�|��)�ځE�O���ڂ̃E�H�[�~���O�A�b�v�Ƃł������ċ����Ă��炨���B ���������s���Ƃ���͌l�I�ɂ�����Ƃ������̂��鉷��h�Ȃ̂��B��R����Ƃ����ꌬ�h�B ���߂ĖK�ꂽ�̂��O�N�O�B�������(�H)����K�C�h�u�b�N���ł͖w�Ǎ̂肠�����Ă��Ȃ����R�~�݂̂ʼnc�Ƃ��Ă���悤�ȏh�ŁA���͋I�s��Ƃ̖���~�l�������̖{�ŏЉ�Ă���̂��ڂɗ��܂�A������������̂���ԍŏ��̔����ł���B���ꂪ���K���Ĉȗ���������C�ɓ����Ă��܂�����Ŋ��Ɍ܉�ڂ𐔂��Ă��܂����B����͋��N�̏\���ȗ��̗��K�ƂȂ�B ���͍���̂��̊�蓹�ɂ͘A�ꂪ����B���̗F�l�̈�l�ɂl���Ƃ����j�����āA�܂������闷���Ԃł���B�������ꂱ��\�ܔN�̕t�������ɂȂ邪�A�Ƃ��ɗ��D���R�D������D���Ƃ������Ƃ�����A�ȗ��l�X�ȎR�₢�œ��T�K�̓��A��ƂȂ����B �P�ƂŎ����̋C�ɓ����������s�������������ŗ�����̂��D���Ȓj�ŁA�����ǂ��炩�ƌ����ƒP�ƕ��Q���D���ȕ��Ȃ̂ŁA�o���̚n�D����v�������ɓ��s�̗F�ƂȂ�悤���B��������T�Ԓ��O�ɔނƈ�t�Ђ����������ɍ���̍O�@��y���̊��̘b����ɂȂ��Ă��܂����B ��R����������x�ނƓ��s�������Ƃ�����A�����������������悤���������A�o�����������ɑS�s���Ƃ����킯�ɂ͂������u��R�͊�蓹�����痈�Ă��C�C���v�Ƃ������ƂɂȂ�������B �b�{�s�����ʓd�Ԃ͔����\�ܕ����B�E�C�[�N�f�C�ɂ�������炸�A�ԓ��͉����̓~�͂�̎R��ڎw���n�C�J�[�ł����ς��B �����͐�m�O��̒�R�������̂ŁA�ď���ނ����C�̐����̎����̂ق����������ăV�[�Y���Ƃ�����B����Ă���A�x�m�R�͂������A������A���v�X�܂Ŗ]�ނ��Ƃ��ł���B�t�ɉď�̓K�X���ēW�]�͂������A�܂��M�R�M�⒎�̏P���ƒ��ǂ����邱�ƂɂȂ�B�܂�������܂����V�����c�B �������璆�p�n�̑匎�܂ł͖�O�\���B�������o�����ʓd�Ԃ͂����ɎR�ԕ��ɓ˓����g���l���̘A���ƂȂ�B���炭���đ��͌��߂���ƁA�������͊ɂ₩�ȎR�����͂ɉ����đ���B���������ꂽ���i������͂�C�C���B �l�������̂Ƃ���Ȃ��Ȃ����̋@��Ɍb�܂ꂸ���������֒f�Ǐ�C���������悤�ň�C�̊J�����𖡂���Ă���l�q�B�����x�R�[�̉����ȉ��A�����̓���A�H�c�̓D���Ȃǂ��ĖK�˂����œ��̘b�Ő���オ��B�Ȃ���T�ԑO�̈��݉��ł̘b���̌J��Ԃ��̂悤�ł����邪�A�����ς��Ƃ܂��y���A�ł���B �o�R�Ƃ̎R���������w�������e�w�o�R�x�Ƃ����悤�Ȗ{���Ă��邭�炢������A�匎�̎�O�̉������߂������ɂ́A�������炢�̃n�C�J�[�q�́A�e�X�̖ړI�̎R��ڎw���č~��Ă������B�匎���͔����l�\�ܕ��B �匎�w�̓��O�n�E�X���̎�̂���w�ɂŎR�̒��̃^�[�~�i���w�̕��i�[���B�w�̗����ɂ͊�a�R���f���ƒ������Ă���B��a�R�͂��Đ퍑�������R�c���̋���ł���v�Q�̒n�Ƃ��Ēy���A���ł����̈�\�����Ȃ�c���Ă���B �W���͌ܕSm���x�̒�R�ł��邪�A�K�x�ɃX�������O�Ȋ�ꂪ����W�]�����炵���̂ŁA�x�m�S�i�ɂ��I��n�C�J�[�ɂ��l�C������B �����o�������Ƃ͂��邪�A�ǂ��炩�ƌ����ƁA������肵����o�����悤�ȎR�e���Ȃɂ�����������Ă���悤�ł����ς牺���璭�߂�ق����D�����B ��������͕x�m�}�s�ɏ�芷���s���s���ʂɌ������B�{���̖ړI�n�A��R����͓s���s�w�̈��̒J�����w���Ŋ��A���Ԃ������U��ɂ͂��������Ȃ̂łƂ肠�����s���s�w�ō~��邱�Ƃɂ���B�l���H���u�s���ɍs���������ǂ�����v�������B�a���O���������̂���ނɊ��҂��A���ʂ����҂ǂ�����ꂽ�P�[�X���ߋ����x�ƂȂ��������̂ŁA�����܂ł���Âɂ��čs�����Ǝv���B �匎�w���o���x�m�}�s�����ʓd�Ԃ́A�x�m�R��ڎw���Ă��x���グ�Ă����B�匎���W���O�S�\��m�ɑ��ďI�_�̉͌��͕W�����S�\��m�B ���\�Z�L���̊ԂŌܕSm���o�邱�ƂɂȂ�A���Ȃ�̌��z�ŁA�i�q�ō��n�_�𑖂邱�ƂŒm���鏬�C���ɂ�����Ƃ����Ȃ��R�x�S���Ƃ�����B�ԑ��ɖڂ��ڂ��Ɠc��ڂ┨�͏������i������A���͂킸���ɉE���オ��ɂȂ��Ă���̂��u�o���Ă���v�Ǝ咣���Ă��邩�̂悤���B�@ |
|
|
��3
�l���̒��ׂ��s���s�̂��ǂɓˌ����܂��B�����ɏZ��ł��鎄�͂�����u�����삤�ǂ�v����D���Ȃ̂ŁA��r����̂��y���݂ł��B �ԑ��̗y����ɐቻ�ς����x�m�R���`���`��������悤�ɂȂ��Ă���ƊԂ��Ȃ��s���s�w�ɓ����B���v���ԏ\�ܕ��B�s���s�͎l�����R�Ɉ͂܂�Ă�����̂́A��w������p�ق��莛�Е��t����Ō��\�����s�s�̕��͋C������B �x�m�}�s�����̒��ɂ����Ă͂��Ȃ�X�̋K�͂͑傫�������낤�B���v������Ə\��������Ɖ߂��B�܂��������̋�C���c���Ă���B ���炭�Ԃ�Ԃ�����Ă���ƁA�ˑR�l�����u�����������v�Ƒi���n�߂��B���I�����w�̃z�[���ʼnw������Ă܂��債�Čo���ĂȂ��̂ɁI�H �ʏ��Ћ߂̔ނ͎d�����̒��H�Ȃǂ͂��܂�H�~���Ȃ��A�{�l�H���u�Ȃɂ�����Ă����܂肤�܂��Ȃ��v���������A��]���ɏo��ƈُ�ɕ��̌���̂������B����ɕ����Ƃǂ����]�n���ʂ̉e���ŁA�ݒ��̒��q�̊������𑣂����𑁂߂�炵���̂��B ���ɕ�����Ղ����������A�܂�������������̗��D�����B �����̍l���Ă����\�����⑁�����܂��������A���ɂ��������̋C������͎̂������B �Ƃ������Ƃł���������̂��ǂ�T�����Ƃɂ���B�l���͂����Ƃ��C���^�[�l�b�g���Ȃɂ��Œ��ׂ��炵���B�莝���̈ē��n�}�����炭���������Ȃ��̂ŁA���Ȃ肤�낤�낷��B�X���̂͂��낢�낶������U�����Ȃ銴�������A���͂��ǂ�ւ̗~�������ׂĂ�ˉ킵�Ă���B �₪�Ă���Ɓu�������A����܂����I�v�Ȃ݂�ƒ��S������͂�◣�ꂽ�A�x�O�Ɉʒu���Ă����B �w�킩�ӂ��x�Ƃ������������A�̂��ɂ́w��ł����ǂ�x�Ƃ���������Ă��Ȃ��B�O�K���Ẵr���̈�K�ɂ������B���ԓI�ɂ��܂��������Ȃ��A�Ƃ��뜜���邪�w�c�ƒ��x�Ƀz�b�Ƃ���B �̂���������ƁA�͂����Ă��q����͈�l�����Ȃ��B�܂����Ԃ����Ԃ����瓖�R���B���V�������\��̂�����(���˂�����H)����l�ł�����Ă���B�X���͓c�ɂ̐H���Ƃ��������B ���݂��Ɂu�܂��̓r�[�����v�Ƃ���Ƀ��j���[���݂�ƁA���ǂ�ȊO�ɂ͂܂ݗނ�������������A�ς��܂��Ƃ����Ƃ��A�v����ɂ��ǂ�̋���p����Ă���悤���B�����ǂ���ُ�Ɉ����B��������������Ƀr�[���Ƃ܂݂��O�i�قǗ��ނƁA�Ί�ʼn����Ă��ꂽ�B���͖��邢�l���Ȃ̂�������Ȃ��B ��l�ŋC���悭����ł���ƁA�ł��Ղ肵���̊i�̒j�����X���Ă����B���܂�C�ɂ����߂��Ɉ���ł���ƁA�j�������������ǂ����̂����ċ������B�����ۂ�M�̂��Ƃ��M�ɂ��ǂ�����\cm���炢�������Ă���B �X�ɂ����������̂́A�j�͂�������̂̌ܕ����炸�őS������Ă��܂����̂��B�����߂��ɍ����Ă����Ƃ������Ƃ����邪�A���ɗՏꊴ������A��l�Ŗڂ��ۂ����Ă��܂����B�����Ă݂���ꂾ���u���܂��v�Ƃ����������ł���̂ŁA�ۂ����ł���X�̂��ǂ�ɑ�����҂͍��܂����悤���B ���炭���āA�ڂ��ڂ����q�������Ă����B���������́A�ǂ����Ă����ߏ��́Z�Z���Ƃ���������B�ǂ����n���̐l�����̊ŔX�I�Ȋ����B �r�[���E�܂݂���ʂ藎���������̂ŁA���������Ă��ǂ�𒍕�����B���������̒n���ł悭�H���u���`�����ǂ�v(�����镐���삤�ǂ�̑㖼��)�Ɠ������j���[���������̂ŁA����ł����Ă݂��B�l�����E�ւȂ炦�B ���ǂ^��Ă����͖̂�O����B����C�̂Ȃ�����Ƀh�o�b�Ɛ����Ă��銴�����������F�̂��ǂn���ɂ����̂ł��邱�Ƃ��B��������H�ׂ��u�ԁu�����I�@���܂����I�v�@�������R�V�ŁA���M���b�Ɗ��ݒ��߂�Ǝ��������Ԃ���銴���B�Ȃ��݂̐[�������삤�ǂ�Ɏ��Ă��邪�Ȃ������ŃR�V���悢�B���`�͔Z���Ȃ��肱�̏o�`�ɁA��قǂ܂݂ŗ������ɔ����X���C�X�����ؓ��������Ă���B�l�����X�ւ��ʂ𗊂ނ܂ł����Ď��Ԃ͂�����Ȃ������B �����삤�ǂ�����������A���ǂ�̕��������t���Ƃ���͕K�����̓y�n��C��̏���(��T�̓}�C�i�X�I��)�����ʂ��Ă���B��ԑ傫�ȋ��ʍ��͕č�ɓK���Ȃ��Ƃ����_�ł���B �Ⴆ�A���̕����삤�ǂ�ɂ��Ă��A���ӂ̓y�n���֓����[���w�ł��邽�ߕې��������A���c�ɂ͌����Ȃ��n�w���������߂ɁA�A���A�q�G�A�����Ƃ��������ނ͔̍|�Ɋ��H�����o�������Ƃ���n�܂��Ă���B�s�����ǂ�ɂ��Ă����l�ŁA�����Ƌ��ɕ��H�������A���̖����Ȃ��ǂ�Ƃ��č����ɑ��Â��Ă���̂��ƌ�����ł��낤�B ���������Ɉ����Ĕ����������B���ꂩ���R����ɍs�����́A�����ƃZ�b�g�ōl���悤�Ǝv���B �������l���o�g�Ȃ̂ŁA�������ɏo�Ă���܂ł͂�����u���ʂ����ǂ�v�����m��܂���ł����B���ǂ����S���e�n�ɂ���ėl�X�ŁA�������������Ɠ����ɑ�ϕ��ɂ��Ȃ�܂����B�@ |
|
|
��4
����͂��̓��̏h���n�A�ꌬ�h�̏�R����ł��B ���͂����ƈȑO����u��x�����ɂ��ď��������ȁv�Ɩ����Ɏv���Ă����̂ŁA�O�@��y��3���ɂ��̕��͂������Ă������͌��\�[�����Ă���܂����B ���ǂ�ŏd���Ȃ�����������������A�Ăѓs���s�̒��S���ɂ��ǂ�B�s���s�w�����R����܂ł̊Ԃ͓s���̎��S�����̉w�Ԃ��炢�����Ȃ��B �s�X�n���A���H�ƕ��s���ė���Ă��鏬���Ȑ�ɉ����������ӂ�ӂ킵���C���ŕ����B�H���ɂ͑~���������Ⴊ�c���Ă��邪�A��͓~����Ŋ����ۂ��ۂ����Ă���B ��͓��ƏZ��̂������𗬂�Ă���A�傫�ȍa�Ƃ������������A��̕�����̐�������������̂��낤�A���\����ł��ꂢ�ȗ��ꂾ�B �~�̓c�ɒ��̋�C�ɂق̂ڂ̂��Ă���ƊԂ��Ȃ��J�����̉w�O�ɒ������B�s���s�w�����菬���������悤�ȉw���[�^���[������A����͈��H�X���O�`�l���Ǝ��]�ԉ����ꌬ�B�s���s�̓�̂͂���̒��Ƃ��������B ���������R����܂ł͓k����Z���B���͂��̘Z���̊Ԃŋ����قǃ��P�[�V�������ς��̂��B�w�̕\���̓��[�^���[����n�܂钬�����A�����͌j��Ƃ����k��������Ă���A���ꂪ�[���J���Ă���B ����ւ͂܂����ݐ�Ő��H���ׂ��A���Ȃ�}�ȉ������k���Ɍ������ĉ���čs���B�����Ƃ����Ԃɐl�Ƃ��r�₦�A�������̓x�Ɏ���̕��i���ς���Ă����̂�������B���X�Ɍk���̉������ɑ傫���Ȃ��Ă������ɏ�R����̂��F�̉����������Ă���B �ŏ��ɖK�ꂽ���͂��̕ω��ɑ������������A�����܉�ڂƂ��Ȃ�Ƃނ���@�g�ω����y���ށh�Ƃ����������B���͉�������悪�j��ɉ˂���苴�ƂȂ�A�ꌬ�h�u��R����v�͋��̎�O�A�j��̔ȂɂЂ�����ƌ����Ă���B ��������ŏh�̔��Α��ɏ����ȍL��̂悤�ȏ�������A���͕K���h�ɓ���O�ɂ����ňꕞ���Ă��܂��B�Ȃɂ��j��ɉ˂��邱�̂苴���悢�_�i�ɂȂ��Ă���A���̏ォ�璭�߂�k�����f���炵���B�L��̘e�̎Ζʂɓ��ł߂�ꂽ�������~���ƁA�����͌��ɂ��ǂ蒅����B �~�̐�������̍����������͂��Ȃ�₽�����A�t����H�ɂ����Ă̌k�����֊��Ԃ́A�nj^�̃��}����C���i�A�j�W�}�X���_���邱�ƂŁA�����̌k���}���œ��키�B �������������������ɂȂ�ƁA�K�����̌k���ɂ������鏊�ɃS�~����������Ă���̂��ڂɕt���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ꕔ�̐S�����Ȃ��҂̎d�Ƃƌ����Ă��܂�����܂ł����A����͒ނ�Ɍ��炸�R�o��E�铒�߂���E�L�����v�����낢��ȕ���ŋ��ʂ��Ă���B �������u�[���ɂȂ�A����ɂ��n��╪�삪����������̂͑f���炵�����Ƃ����A�����Ȃ�ƕK���ƌ����Ă悢�قǃw���ȃ��J�����u�[���ɏ悶�č������Ă���B�ꎞ���b��ɂȂ��Ă��܂����o�R�u�[�����甭�������S�~��������A�����̐��������ɂ�邨�����m�Ԗ��ȂǁA���܂肢��Ȍ������͂������͂Ȃ����A��͂荢�������̂��B �܂��l�X�Ȏv���╮����������Ă��܂������肪�Ȃ��B���̎��͑��X���̔������k�����N�Ԃ�ʂ��Ă��̌i�ς̂܂܂ł��ė~�����Ǝv�������ł���B ����~�l����R����ɂ��ď��������͂ł̖`���͂����ł���B �u�j��ɖʂ�����R����́A�������������I�ŋC�̒u���Ȃ��u�m��l���m��v���h�ł���B�o���ɗ��p����l�A�s�y�A��ɂ��l�A�������y���݂ɂ���l�A�މʂ��ւ��Ĉꗁ���ċA��l�c���܂��܂Ȑl�����̏h��K��Ă���B�v �Ȃ��Ȃ��������Ė��ł���B �n�Ƃ����a�O�\�ܔN�B��オ�{�[�����O���ĒP������A�\�ܓx�̍z����̂��@��ɊJ�����z��h�ŁA�����͓������܂߂ĉ����̂܂܁B�͂����茾���Ă��Ȃ�ÂтĂ���B���ہA��ԍŏ��K�ꂽ���������u�������v���ȃ@�v�Ǝv���Ă��܂����̂������Ă���B������ŕ����Ə�A����A�u�̂̂܂܂ł��ė~�����v�Ƃ����v�]���������Ƃ��������Ă����B�����Ă��킸�����ȁA�C���t�����玄���������肻�̈�l�ɂȂ��Ă��܂��Ă����悤�Ȃ̂ł���B ���ւɓ���A�q���ނ������̋���Ȃǂ��������Ă���t�����g����A�u���߂����[���v���ꔭ�B�����͈ꔭ�ł�����݂̏������o�Ă��Ă��ꂽ�B�u�܂��܂��A��������Ⴂ�I�v�l�������K��Ă���̂ŁA�����Ɗo���Ă���Ă��銴���ł���B �h�͂��̏�������v�w���܂߂��Ƒ��o�c�ŁA�Ƒ������Đ��b�D���ŐS�������l���B���ɏ�������́A�����̏h�ɑ���l�����������ł��������肵�Ă��āA���̏�����������ď�A����ɂȂ��Ă���l�������������B ���ւ��܂ޕꉮ���ؑ���K���ĂŁA��K�͉�����o����L�ԂɂȂ��Ă���B�ꉮ���c�ɑ����Ă��镗���L��������Ă����ƁA�ꉮ���o�����ɁA����ԂƘZ��Ԃ̋q�����\���B���ꂪ�����Ɠ�K���Ă̌����A�v�����ɕ�����Ă��āA�Ώ�Ɖ����̕t�����L���Ō���Ă���B ���ꂼ��̕����Ɍ��ւ����Ă��邩��A����`���Ƃ����Ă������ƌ�����B����ƌ����ƂȂ����̕������܂鍂���h�̂悤�ɕ������邩������Ȃ����A�����Ƃ��Ă�(��������Ӗ��ŁI)���a�O�\�N��̒����Ƃ������Ɍ����Ă��܂��B�������悭���܂�h�̒��ł��A����ȃJ���W�͑��ɂ͂Ȃ��B�����̗v�f���Ɏ����͎䂫�����Ă���̂��낤�Ǝv���B ����߁A�ڂ���A���݂��Ȃǂ̖��̂����ꂼ��̕����ɕt�����Ă��āA����������܂�́u�����傤�v�ɒʂ����B�������܂��f���炵���B���R���ɌÂ����A�����J����Ə����Ȓ������Ōj��̉͌��͂��������ł���B���������ɏo�āA�����ő��ނ���ł��������B �ڂ���O�߁A�ȁ[��ɂ����Ȃ��ґ�Ȏ��Ԃ��y���ށB�Ȃ�ɂ����ĂȂ��悤�ŁA���͂���Ȏ��Ԃɗl�X�ȃC�}�W�����N���Ă����肷�邩��s�v�c���B�]�݂��������b�N�X���Ă���̂������ł��悭������B�Ƃɂ��������̎��Ԃł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B ����������ɑ����������Ƃ�����A���炭�l�����X�����łȂ�ɂ������̂�т�߂����A���낻�땗�C�ցB�����͈�U�ꉮ�֖߂�A�L���̓r���ɂ���B���C�͊���ӂ�Ɏg�����Ђ傤����^�̗���������B�������M���Ă���A�Ђ傤����̔����͍����A���������͒ቷ�Ɠ��ނ̉��x�ɕ�����Ă���B�傫���Ƃ������̊O�͌j��̗���B�Ȃ��Ȃ��̓W�]���C���B�P����ł����������Ă���Ɛg�̂̐c�܂ʼn��܂�B��������Ƃ��Ă̕]�����悭�A���E�}�`�X�A�_�o�ɁA���ɁA�ݒ��a�ȂǂɌ��ʂ�����Ƃ����B�܂�����̗��̃v�����[�O�̓��Ƃ������ƂŁA�����Ɋ��\����B�喞���̓��ł������B�@ |
|
|
��5
��R����̗[�H���ӕ\�������e�ŁA�Ȃ�Ƃ��y�����v���o�ƂȂ�܂����B �������A�{���̈Ӗ��ł����قǁu���a�v��������h�͑��ɂ͂Ȃ������Ǝv���܂��B �ґ�Ȏ��Ԃ͂����Ƃ����Ԃɉ߂��A�[�H�̎��ԁB ���̏h�͉Ƒ��o�c�ł������͗���ɂ�������炸�A���ׂĕ����H�ł���B��U�O�֏o�đ�ςł��낤�B�h������B �܂��A�j��łƂꂽ�V�N�Ȑ싛���Ă����Ăŏo��̂��B�l���Ƃ��ǂ��y���݂ɑ҂B�ނ͗�ɂ���Ē��Ԃ̂��ǂ�͂�������������Ă��܂��A�Ɍ��̋�Ԃ̂悤�ł���B �₪�āA�h�̖����[�H���^��ł����B�⋛�̉��Ă��A�R�̂Ă�Ղ�ȂǁA���ׂďĂ����Ă̗g�����Ăł���B�܂��̓r�[���Ŋ��t����B �Ђ��[����H�ׂĕЂ��[����u���܂��A���܂��I�v�����č����ȗ����ł͂Ȃ����A��i��i�����������J�ŐS���������Ă���B ���炭���āA������͒lj��̕i�������Ă����B�ł����M���B������݂ċ������I�Ȃ�Ƌ���Ȃ��킢���ɂ��A�ۂ��ƈ�t��������Ă���̂��B����ɂ͂l�����ڂ��ۂ������B �������Ȃ��u�R�͂����Ă��R�����v�̏h�Ɂg���Ɂh���c�H���₢��A���͂���ȃ��{�Ȃ��Ƃ͍l���܂��B�f���ɂ�낱�ъ��\���悤�I �����������ɇ����݂�Ƃl���͑�ς��B���͂l���͎���̐l�Ԃ���u���ɂ̓V�G�v�Ƃ��u���ɋU���v�Ƃ�������قǂ̇����ɍD�����ł���B�ނ͔N�Ɉ��k�C���ɗ��s���Ă��邪�A�u�k�C���̂��ɂ�S��H���s�����v�Ƃ������Ă��邭�炢���B���͑����C�����A���O�{���炢�ʼn䖝���Ĕނɏ���C���ƂȂ����B �ނ͎����̕\��Ň����ɇ��ƑΌ����Ă���B�悭�݂�Ɣނ̑O���͂��o�����ł���A���ꂪ�܂��\����A���ɂ̐g���������悭�������Ƃ��̂ɓK���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B �܂��Ȃ�����ȇ����ɇ��́A��������J�������̎p�ɕς���Ă����B�ォ�珗�����畷������u���܂��܁A���̂Ȃ���ł����̂�����������o���Ă݂܂����B�v�Ƃ������Ƃł������B �����A��͈������������B���̊O�̌j�삪�^��ł���S�n�悢��C���ڂ��o�܂�����B�ꉞ�\��ł͍���̍s�����͍D�V�Ɍb�܂��\��B���i�̂����Ȃ����A����ȂɃ��C�Ƃ��v��Ȃ����c�A�܂��������Ȃ��̂��낤���B ��蓹�͂���ňꉞ�I���B�����͂l���ƕʂ�čb�{�o�R�ʼn����������B���̑O����Ƃ��ď[���p�C��{�������肾�B ���������߂ď�R����͖{���ɂ悢�h�ł���B���܉�ڂȂ̂����A�ߏ�Ƃ������Ƃ�����A�܂��C���t������K��Ă��邱�Ƃ��낤�B �ʂ�ہA��������Ƃl�����X��ӂ̇����ɇ��̘b��Ő���オ������A������ς�邱�ƂȂ��撣���Ă��������悤���肢���A��R�������ɂ����B ���N��10���̏I�荠�A���̋L�����ڂ����u�O�@��y���@��3���v�����n�����邽�߁A��������ɏh���\��̓d�b�������Ƃ���A�V���b�L���O�ȕԎ����Ԃ��Ă��Ă��܂��܂����B �u������R����͍��N��10�������ς��������Ĕp�Ƃ��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����c�v �����̘V�����ɔ����A�ό����قƂ��Ă̈��S���ɖ�肪�o�Ă��Ă��܂����B�����ӔC�セ�������ނ�ɂ��ĉc�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��c�B�܂��A�Ռp���̖�蓙���l���Ă��A�����đւ�����͕̂s�\�B �Ƃ��������悤�̂Ȃ����R�������ł��B ���10��29���u�O�@��y���@��3���v�����n�����邽�߂ɖK�ꂽ�̂��A�Ō�̖K��ɂȂ�܂����B �L����ǂ�������ɂ͂����ւ����Ă����������̂��A�����ɂƂ��Ă������₩�Ȋ�тƂȂ��Ă���܂��B ������u�c�O���v�Ƃ��u�Ȃ��H�v�Ƃ���������͂���܂��A�₵���͉B���悤������܂���B �����A���̏������܂��Č��������Ǝv���܂��B ���܂ŁA�f���炵�������ƁA�����̎���(�Ƃ�)�����肪�Ƃ��I�@ |
|
| �@ | |
|
��6
�����4��́u�O�@��y���E4���v�f�ڗ\��ł����u���V���A��n�����Ղ�v�҂ƂȂ�܂��B ����Ǝ���͍Ղ�̑O��Ƃ��āA��������ɃY�[�����܂��B �O���ɂė\��O�̍s�������������ׂɁA���C���ł���͂��̓�������ɂ������n�����Ղ肪�A�{���ɂ��ꍞ��ł��܂����B �܂��͂��̂��Ƃɂ��Đ[�����l�т�\���グ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����A�O��������A���ɓǎ҂̕��X���l�X�Ȋ��z�A��ӌ��A�����������������A���悢(�H)�v���b�V���[�������M������Ă��鎟��ł���B ���āA����Ɓu�{���̈Ӗ��œ�������ɍ~�藧�����v�킯�����A�\��ύX�̃A�I�����Ċ��ɘZ���߂��Ȃ�A�[��ꎞ�����ɏI���Ƃ��������B���藈�銦���ɐg�̂��K���Ŕ������Ă���B �h�ɓ��鎞�Ԃ����Ȃ�x��Ă���A�������Ɠ����Ă��܂��������A�h�̏ꏊ��T�����肪�A���̂܂܉���X���Ԃ�Ԃ炵�Ă��܂��Ă���B ��������܂��U��A�Ƃ����K���Ƃ������A����������s�r�̒��ł����Ă��܂����w���Ȑ��݂����Ȃ��̂ɂ͋t�炦�Ȃ��悤���B �s�X�n�̊X�������ɂ���A�����������炵�炭�����Ă���ƁA�X�����ɂЂ炪�ȂŁw��ނ�x�Ə����Ă���̂��ڂɕt���A����X�̒��S���ɋ߂Â��ė��Ă���̂�������B �₪�ĉ���X�𗬂�鏬���Ȑ�̂قƂ�Ɂw���}�A�������x�Ə����ꂽ�Ԃ��ΐ��̌��ĊŔ�����A���̕ӂ����S�X���ƕ�����B ���̌��ĊŔ̉��ɐ���ׂ������ȐԂ������˂����Ă���A���̐�ɂ́A�s���N�F�̌Âт���K���āB�X�i�b�N�������ł��낤�w�Ԃ����x�Ƃ����������˂����Ă���B ���̎��Ԃł��^���Âł���A�c�ƒ��Ƃ��������ł͂Ȃ��B����ȊO�ł����ɓy�Y���̉��Ȃǂ��Ȃ��A�n���̐l��������Ȃ��悤�Ȉ��݉���H���ɂۂۂ��肪�����Ă���B ������⋷���Ȃ������̐�ɋ�������w�h�̓��x������A��K������A��K�́w��������|�\�Z���^�[�x�ɂȂ��Ă���B��K�̂ق��͌��@�\���Ă��邩�ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A�����炭���|�l����̌����Ȃǂ�����Ă���(����)�̂ł͂Ȃ��낤���H ���̖�̉���X�̕��͋C�̒��ŁA���́A�{���Ŏ��グ���R�A(���Ɍ�����)�̓���������ӂƎv���o�����B���������Ŏ����̂Ȃ��ł������Ɣ�r���邱�Ƃ����������̂����A������͖������L�䂩��̉���n�Ƃ��āA��͍r���𒆐S�ɑN�₩�Ƀ��C�g�A�b�v�����ȂǁA�ό�����Ƃ��Ĕ��ɖ��͓I�Ȑ���������Ă����B �������̔��ʁA�������L�̕���ɕ`���ꂽ����n�̃��A���Y���ɑ���M���b�v���������̂������ł���B �����č��������ĎR���̓�������ɘȂ�ł���ƁA�ނ��떲�����L�ɕ`���ꂽ����n�̃��A���Y���Ƌ��ʂ������̂��A������̕��Ɋ����Ă��܂��Ă���B�u�R�A�̓�����������ꓖ���͂������������������낤�ȁd�v�A�ƁB �w�h�̓��x���琔�\m���炢�̈�т���Ԃ̏h�̖��W�n�т̂悤���B�����ďh�̑O�⌄�Ԃ̋n�ȂǁA�������̏��X�Ńe���g�藇�d���̉��Œn���̐l�B���������Ɖ�����Ƃ����Ă���B �ɂ��₩�Ƀr�[���Ў�ɂƂ�������ł���B��u�Ȃɂ��ȁH�Ǝv�����A�ǂ���痈��ׂ������̍Ղ�̏o�X�̏����̂悤�ł���B �������A�����͂��̈�т��\���l�]��̐l�Ŗ��ߐs������A���̊��������|����M�C���x�z���邱�ƂɂȂ�̂��B���N���N��ŏ����ɋ��ޒn���̐l�B�߂Ȃ���Ȃ�ƂȂ����̏�i��z�����Ă��܂����B ���炭�����Ă����ƁA�o�X�����̃e���g����A����X�����Ȃ艜�܂��Ă����̂��낤�A���X�ɓ����ׂ��Ȃ��Ă���B�����^���Âŕ�����Ȃ����A�����R�Ƃ��������ȎR������X�̌����ނ��Ă���A���͂��̎R�̎n�܂�ɓ˂�������Ɠ����ɍ��ɐ܂�Ȃ���B�����Ă��炭�s���ƎR����O�q����悤�ɉ��V���̎R�傪���ꂽ�B �R��̎���͉���X�̒��S���牜�ɂ͂���Ă���A���Ƃ̓����ۂۂƌ��������B���ɒ�₦���n�߂���̕��i�łЂ�����Â܂�Ԃ��Ă���B �����ŏ������V���̗��j�ɂ��ĐG��Ă݂悤�Ǝv���B �哯�O�N(808)�O�@��t��C��l���������O���~�ς̍s�r�����ꂽ����A���̒n�ɂĖ�n����F�̗쌱���������A���炪�A�Z�����܂�̍���������A���̑������J�Ⴓ�ꂽ�̂��A�J�n(���c�R)�Ƃ����B�ȗ������̋~�������߂�V��j���̎Q�q�̑ΏۂƂȂ����B ���̌�A�V���N(955)����l(�x�O���̍��m)���A�S���V�s�̓r�����̒n�Ɋ���������������쌱�����ɘZ�ڗ]��̖�n�����F�������u���A����ɂ��J��(���c�R�E���V��)����A�ȍ~�A���⓹���ɂ��ċ������ȂǑ����̕ω���s�݂����݂Ɏ����Ă���B �O�@��t�̎�ɂ�鍿���́A���S�Ȕ镧�ł���A���J���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�����A���N�\�O���̌ߌ�\����\�l���̌ߌ�\�܂ł̊Ԃ����A����l�ɂ���n����F���ƍO�@��t�̍�������ƂȂ�A���̓����(�����͈���Ԃ����A��������Ԃɂ킽�邱�ƂɂȂ�)�Ɍ����ʂɌ��J�����B �܂肱�ꂪ�N�Ɉ�x�̖�n�����Ղ�Ȃ̂��B ��n���������̓������͎����J���A�P�j�P���̊肢������A��������������Ă�������B���ꂪ���N�\���l�]�̐l�X�ɂ�薄�ߐs�������͂ƂȂ�̂��낤�B �R���������ƁA�{���܂ł͎R�̎Ζʂɏ]���Ċ���ƒ����Βi�ɂȂ��Ă���B�^���ÂŐl�C(�ЂƂ�)�̂Ȃ��Βi���オ���Ă݂邪�A�Ȃ����Z�����܂���Ă���B �h�ɓ��鎞�Ԃ��C�ɂȂ�����Ԃ����Ƃ�����A�����̑|��(�����炭)���I�������̂��g���̕��炵���l�������̂ŁA������Ƙb���Ă݂����Ȃ��Ă��܂����B�����������������h�ɓ��������������Ǝv���Ă���͓̂��R�����A���������ɂȂ�ƍ��x�͐l�ł������Ԃ��Ă��������^�C�~���O�͂Ȃ��Ȃ�̂ł́H�Ƃ��v�����̂��B ��͂育�Z�E�̂��g���̕��ŁA�����b��ԂŊ����������Ă��Ă���ɂ��S�炸���낢��Ƃ��b�����������B���̒��œ��ɖʔ��������b����B ���̉��V���ɂ́A����Ӗ��{���������ƌ����Ă������̂��������B�m���ɂ������Ƃ��Ă̖{���ɂ͋���l�ɂ���n�����F����������B������ʂɂ͌��J�ł����ɔ镧�Ƃ��āA�Z�E�����m��Ȃ��ꏊ�ɂ��܂����܂�Ă���O�@��t�ɂ�鏬���ȍ������̕����A����Ӗ����̂����̖{���Ƃ��Ă̈Ӗ������c�B �Z�E�̂��g���̕��͂��݂��݂ƌ���Ă��ꂽ�B ���̓�̇��_�����N�Ɉ�x������ɂȂ�̂��B�Ղ�̋K�͂��A�n���̐l�X�̎v�������M�C�����Ȃ�����ł͂Ȃ����c�B�܂��܂������ɑ�����҂����܂��Ă�������ł���B ���Ȃ݂ɁA�����͋���l�ɂ�鍿���̎�̂Ђ�ɍO�@��t�ɂ��镨���̂����邻�����B�͂����ē���Ŋm�F�ł���̂��낤���H���łɂ���ɂ�����(�H)���悤�B ���g���̕��ɂ͂���Ɠ����Ɂu�������܂��Q��܂��v�ƌ����c���A����Ƃ̂��ƂŎ��̑��͍����̏h�w��������x�Ɍ������n�߂��B�@ |
|
|
��7
�O��Ɉ������u�O�@��y���E4���v�f�ڗ\��́u���V���A��n�����Ղ�v�҂̑�2��ł��B ����̓�������Ɠ�������̌���ł��B �ēx���S�X�ֈ��Ԃ��A�h�̈ē��łŏꏊ���m�F����B�����ɒ��������Ԃ��x���������Ƃ����邪�A��}���ł��A�Ƃɂ��������S�̂��m�F�����������̂ŁA�����h�̏ꏊ�܂ňӎ����y��ł��Ȃ������̂ł���B �ē��ł����ɕ����Ă����ƁA�ǂ�ǂ�X������t�߂ɖ߂��Ă��������ʂ̊X�������߂Â��Ă����B�����čŏ��Ɍ�����������a�@�̌������Ƀ�������͌����Ă����B �ȂA�悭�l����Ǝ����͐���f�ʂ肵�Ă����̂��B�Ƃ肠�����z�b�ƈꑧ�B �S�؎O�K���̏�����܂肵���O�ρB������m�قǐ�̓o�X��̂���X���������Ă���Ƃ������Ƃ����邪�A�����鉷�قƂ������A�X���̃r�W�l�X���قƂ������͋C�B�E�[���d�h�̑I��������Ă��܂������d�B���̎��̐����ȋC�����������B �������x��Ă��܂����k���钆�A�N�z�̒�������(�H)�ɉ������Ȃ��������̂悤�ɓ�K�̕����ɒʂ��ꂽ�B�����̑�����O�߂�ƁA��������Ő��ʂɓ�������a�@���f���ƍ\���Ă���B �u�����[�H�̎��Ԃ͉߂��Ă��܂��Ă���܂��̂ŁA�����C�͏o���邾�����������Ă��������ˁA�O�\���キ�炢�ɂ��H�������������܂��B�v ��������͂����̗p�ӂ����Ȃ���D�����ɂ��������ĕ������o���B�����Ă݂�Ίm���ɁA�������v�͎������Ƃ����ɂ܂���Ă���B�Ȃ���������ɖ����Ă��������N�����ꂽ�悤�ŁA�������ɐg�̂��d���Ȃ��Ă����B �U�u���Ɠ����ĔтƂ��悤�B���A�����������̓��͂������������Ȃ̂��B����ς肶������Z���肽���B �ȂǂƔn���v�Ă��Ȃ��痁���ւƌ������B �ꉞ�����͒j���ʂɂ��邪�A�Е��͋@�\���Ă��Ȃ��悤�ŁA�ЂƂ������g���Ă���B(��ꂽ�h�ł悭���|����P�[�X�����d)�O�`�l�l����邭�炢�̏����߂̗����ɖ��F�����̂��ꂢ�ȓ����������B �����̓��Ǝ��āA�A���J�����̏_�炩�������B�����͎l�\�`�l�\��x���炢�Ŋ����M���A�����̂悤�ɁA�ɕ����ē��蕪����悤�ȏK���͂Ȃ��悤���B ��������ȊO�ɉ����Ƒ傫���Ⴄ�_�Ƃ��ẮA�܂����ʂ�������x�m�ۂ���Ă���ƌ����_����������B��������S�̂Ō���͏\������A���̗N�o�ʂ͈ꕪ�Ԃɋ�Z�Z���b�g���ɂȂ�B�܂��A���̐{�쉷��̘Z�烊�b�g����A���Â̎O���Z�烊�b�g���I�قǂł͂Ȃ����A����n�̋K�͂ƏƂ炵���킹��ƁA�o�u���Ȏ{�݂炸�ɐ����Ɍ����z������Ƃ���Ώ\���ȓ��ʂł��낤�B �O���ł͐G��Ȃ��������A���͉����̓��ʂ͂����̏ꏊ�ɑ��Ĕ��ɏ��Ȃ��B���̏�h�̑�Ƃ͎��ƌ���Ȃ̂Ŗ��͂Ȃ����A�����������Ǝg�p���Ă���h�͎��͌����Ă���B ��N�����ɂȂ�����A�̂܂�Ή����̒��ɂ��܂܂�Ă��܂����h���c�O�Ȃ������������͎̂����ł���B ����n�ɂƂ��ē��ʂ͂��̒n�̖��ɓ��������A����ɂ���Ă��̒n�̎��͂�l�C�����E�����̂́A�����������̂Ȃ����Ƃł��낤�B���������͌����Ă���ɂ���Ď����̂��̒n�ɑ���]���∤�������܂邱�Ƃ͂Ȃ��B �ނ��듒�ʂ����Ȃ��Ƃ��A���ʂɍ�����������ׂ��{�݂ŗ��j��ۂ��Ă���Ƃ���ɂ�舤���������邵�A�܂����s�[�g���Ă��܂��B ���͕ʂɉ���]�_�ƂƂ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�̂����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ����A�t�Ɏ��ۂ̓��ʂ����āA���ʂ�臀�q�ʇ���D�悵�������{�݂��Ă��܂��̂����Ȃ̂ł���B �����������h�����ƂȂ��čs�߂����o�c�����̃c�P�𖡂���Ă��錻��ł��邱�Ƃ͈ȑO�ɂ��������B �������ɁA���ƂƂ��āu���W������v�u�������Ă����v�Ƃ����Ӗ��ł̌o�c�ӎ��͑f���������d�v�Ȃ��Ƃ����A���{����A�܂�����ɖ��ɓ����������̂��̂ƁA����Ƃ͕ʂ̖��Ƃ��v����̂ł���B ��������̓��͗������̂͏��������f���������ł������B����łǂ��������������A�Ƃ�ł��Ȃ���K�͂Ȏ{�݂����肵����܂��ς���Ă��܂���������Ȃ��B �����A����n���ێ����A�܂����W�����Ă����ɂ́A�u����������Ȃ��v���Ƃ����蓾�邩������Ȃ��ł��낤�B�����Ă��̕ӂ̓˂����b�͂��̌�A���̏h�̏������炶�����蕷�����ƂɂȂ�B �����̕�������Ƃ� �[�H��A�����ł��낻��Ē��̂�����������т��т��Ȃ���A���������U��Ԃ��Ă����肵�Ă�����ɂ�����O�����܂���Ă����B ��������̌��s���Ε����瓾���O�@��t�������A�����݂̓�������܂ŁA��t�Ɋւ������E�`���A��̐�������̎��Ԃ̒��ŋz�������S�n�悢�d���������Ă��鎞�Ԃł���B(���₢��A�����͂܂��������{�Ԃ���) ��O�������炢�ɂȂ������A�₯�ɗׂ̕��������邳���B�悭�l������A������O�Șb�������͍Ղ�̑O��ł���B���̓��̂��߂ɑS������l�X�Ȑl�B���K��Ă���̂��B����������ǂ̏h����͂ɂ��₩�Ȃ̂ł��낤�B �����������ɁA�g�͔̂��Ă��邪�A���͂ǂ��ɂ��܂��Ⴆ�Ă���ł���B�����̍Ղ��O�ɂ��Đ���オ���Ă���̂͂��������R�ŁA�q�g�Ƃ��ĐS�̒��łł��ӂ߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B �����ň���ł����Ē��Ƃ܂݂������ĂȂ�ƂȂ��������o���B���r�[�ň���ł�낤�Ƃ������@�ł���B ���ւ͊��ɓ��肪�����Ă���A����̑O���Q�Â܂������͋C�B�e���r�ƃe�[�u���A�\�t�@�[�̂��郍�r�[�����ɖ����肪�_���Ă���B�c�ɂ̗��قɋ��ʂ�����̃C���[�W�ł���B���R�N�����Ȃ��B ���炭��l�ň���ł���ƁA����̓��肪�_���ĔN�z�̏����������̂ŁA�v�킸�����������Ă��܂����B�Ȃ�l�q������ȂƂ���ň���ł��肷��ƃw���Ɏv���Ă��܂�(�H)�Ǝv�������炾�B�y�����A���A �u����`�Ղ�̑O��ŁA���ׂ��������オ���Ă�݂����Łd�v �ƁA�����ɂ��錾���݂����Ƃ������ƁA�����͋��������Łu���݂܂���ˁ`�A�ǂ���������������Ă��������ȁv ���͂��̂����Łu���̕��͏������ȁv�ƒ��������B���㏗�j�Ɏ����ǂ����ј\�Ƃ������A���݊���������l���B�b�����̊Ԃɂ��e��ł��Ă��āA��͂肱�̕����������ƕ�����ɂ͂��܂莞�Ԃ͊|����Ȃ������B �ŏ���������̕��͗����b��Ԃ��������A�b������オ���Ă���Ƃ��̊Ԃɂ��\�t�@�[�ɍ����Ă����B���͍���̎�|��b���A���̉���n�ɂ܂��l�X�Șb�̕������D�̃`�����X�Ǝv���A�O�@��y���̑O����n�����Ƌ}���ŕ����ɖ߂����B �O������������ɂ��n����ƁA���Ԃ��Ƃ���ɁA�����̗��j��Ԃ����������ʐ^�W��p�ӂ��Ă���Ă����B �����ċC���t�����珗��������܂��A���ۂݒ��q�̏Ē������������Ɏ���Ă����B �����͗��j�����Â��A�R�����ł͐����Ȃ��O�@��t�`���ɍʂ�ꂽ����n�ł���B�����A������x�̂悤�ɕ������Z�Ȏ��R�i�ς�����킯�ł͂Ȃ��B���ێ����o�X��ɍ~�藧�������A�u����������H�v(����I)�Ǝv�����قǂ��B �������A(�������厖�Ȃ̂���)������Ƃ��Ă̈ʒu�t�������ɒ��r���[�ȏł��邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B�����Ȃǂ͑O���ł��������Ƃ��胊�s�[�g�̓����q�Ɏx�����Ă���v�f���傫���̂��B ���̕ӂ̂��Ƃ���������ɕ����ƁA��͂蓒�����ȑO�͓�������Ƃ��Ă̓`���������Ƃ������肵�Ă����������B�������ɂ������͓̂��ʂ��L�x�ŁA���̌��\������a�@�����邱�Ƃɏؖ������悤�ɔ��ɍ����̂͊ԈႢ�Ȃ��B �����A���������ΒQ���悤�ɂ��炵���̂́A�������\�N�̂������̊e���ق̐Ռp���ɖ�肪�������Ƃ������Ƃł���B�͂����茾���āu�����l���ĂȂ��v�̂��������B�u����͂�����I�ɏグ�Ă���悤�ɂ��Ȃ�܂����d�v�Ƃ�⎩�}���݂ɘb���Ă��ꂽ���̎��������d�B ���̏h�̌��������Ɂw�����z�e���x�Ƃ����傫�ȓS�̏h������B�����̍��̂���l�͗B����ɍ���̓����ɂ��Ĉӎ��I�Ɏ��g��ł���A����ΌnjR������Ԃ������B ����������ƁA�s�X�n�Ƃ������n���t�ɐ������ăr�W�l�X���p�̂��q����ɓ����̗����ʼn��ق̏��T�[�r�X�����B����ɂ�荡�܂łɂȂ��V�����q�w���J�Ă���Ƃ������ł���B �Ȃ�قǃr�W�l�X���p�Ȃ烊�s�[�g���p�ɂ��q����Ղ��B�o���ɂ������ȂǁA���ʂ̃r�W�l�X�z�e���̃��j�b�g�o�X�ɗ�����ł͂Ȃ������V�R����ɐZ���̂��B���������Ă������̕����C�C�ȁA�Ǝv���Ă��܂��B ���������]�X�Ƃ͂�����Ƃ�������Ă��邪�A�f���炵���ڂ̕t�������Ƃ�����ł͂Ȃ����B�������S���Ă��܂����B �����z�e���̂���l�͂��̑��l�X�Ȑ헪�����H���Ă���悤�����A�������܂ŌnjR�����ł���A���̗��ق̐Ռp���B�́A�Â��`���ɏ�������Ă��邾���łȂɂ��l���ĂȂ��̂�����Ƃ������Ƃł���B��������̘b�͂܂��ɔߊ삱�������ł������B �����������Ă��Ă��ꂽ�ʐ^�W������B��������������z��������Ԃł��낢��������Ă����B ������a�@�̂���ꏊ�ɂ́A��l���C�Ƃ����������ꂪ���������ƁB(�a�@�̌����̂Ă���͘Z�p�`�̃f�U�C���ɂȂ��Ă��邪�A����͐�l���C���Â��̂炵��) ������������͈ȑO�͋�قƂ����Â����j�����邱�ƁB(���z���̎ʐ^���o�Ă����A���a��\�N��̂��̂炵��)���̑��l�X�ł���B �ʐ^���݂�Ƃ��̏h���܂߂ĉ��߂Ă��̒n�̗��j�̏d����������B�܂��A���̗��j���p�����Ȃ�����A����̓`���Â���ɐ^���Ɏ��g��ł䂩�˂Ȃ�Ȃ��B��������̘b�̒[�X�ɂ́A���̈ӎ��̋����䂦�A��O�̂悤�Ȃ��̂����_�Ԍ������悤�ȋC������B ���r�[�̎��v������Ƃ����ꎞ�l�\���A�������ɂ��ׂ���̑O��Ղ��I����Ă��邾�낤�B��������ɕt�������Ă�����������\�������A���������Ɍ����Ă���ƏA�Q���邱�Ƃɂ����B�@ |
|
|
��8
���悢���n�����Ղ蓖���̖͗l�ł��B���Ղ�̖͗l��3��ɕʂ��Ă����肵�܂��B �����A��K�̉��̐H���Œ��H���Ă���ƁA���r�[�⌺�ւ̕����疾�邭��������������肪�������Ă���B ���̏h�̑O�ɂ��o�X���\�����A���������ɂ����ẮA����h�������ɋ߂������D�����(�H)�悤���B�ނ�����͉��V���ł���B ��������̘b�ł́A�R�����S��݂̂Ȃ炸�A�^���@�֘A�̂����W�҂��͂��ߑS������Q�q�҂��K��A���̐��͏\���l���z����Ƃ����B���r�[�ňꕞ���Ă���ƌ��ւ̊O�ł͍Q�����n���̐l�B���E���������Ă���B ���̖�n�����Ղ�́A�ό��K�C�h�ȂǁA��ʓI�ɂ́u���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���n�����Ɉ��u����Ă���{���̐Α��n����F�������A���̓�������������J���P�j�P���̊肢������Ă����v�Ƃ���Ă��邪�A����̉��V���̂��g���̕�����̘b�Ȃǂ���ɂ������̉��߂Ƃ��ẮA����l�ɂ���n����F���Ɗ��S�Ȕ镧�ł���O�@��t�̍�������ƂȂ�A����ɂ��P�j�P���̊肢�ɑ��Ď����J���Ă����A�Ɖ��߂��Ă���B ��������ɂ��m�F�����Ƃ��낻��͊ԈႢ�Ȃ��炵���B�����A�Ղ�̐���オ��Ƃ͗����ɂ��̕ӂ̏ڂ��������Ɋւ��ẮA�ĊO�n���̐l�B���悭�������Ă��Ȃ��P�[�X�������������B���̕ӂ͑O�q���������ł̎���ɂ��ʂ��镔���ł���A����������邵���Ȃ��������d�B �h���o��B���ɌߑO�㎞�B��������́A�u�ǂ����[�����炢�܂œ����ɂ����ł���A��i��������܂�����Ă��������ȁv�ƈꌾ�B���͎��R�ɏΊ炪�o�āA�����炭��������|��`�����B�����đ��͍Ăщ���X���S���Ɍ������n�߂��B ����͈Â��Ă悭������Ȃ��������A����ʂ������̗����ɂ͊��ɊJ�X���O�̏o�X���Y�����ƕ���ł���B�Ղ肪�n�܂�̂��\����ŁA���̈ꎞ�ԑO���炢����}���ɐl�������Ă���炵���B �������ɍ��͂܂��n���̐l���������Ƃ������ԑтł���B�����Ă����A�肢�A����d���A�����I�ɂ͏��w�̐_�Ђ̎Q���̕��i�̂悤���B�����A�ǂ�ǂ�����Ă�����ɂ��̃X�P�[���ɋ����B ����X�̃��C���X�g���[�g�݂̂Ȃ炸�A�e���ɂ�����܂ŁA�������̏o�X���B�����炭�S���ȏ゠�邾�낤�B�܂��ɇ��\���l���}������鏀���܂��Ȃ������I���ƌ����������H���X�ɉ���n�S�̗̂���ׂ��M�C���Ђ��Ђ��Ɗ����n�߂�B ��������́u�Q�q�҂������n�߂Ă��狫���ɓ��낤�����燁�Ƃ�ł��Ȃ������ƂɂȂ�v�ƌ���ꂽ�̂��v���o���A���߂ɉ��V�������ɓ��邱�Ƃɂ����B�R��̑O�ɒ����ƁA�x�@�������x��������������Ȃ����A�s�[�N���Ԃ�z�肵�Čx���̗\�s���K�̂悤�Ȃ��Ƃ�����Ă���B���Ȃ�ْ������ʎ����ɂ݂���B ����������͐^���Â������̂ʼn��߂Č���ƁA�܂���������������B�R��̗����̎Ζʂɖ����̐Ε�������A�����Ă��̐Ε����]����悤�ɎΖʂ̒����ɂ́A�O�@��t�����Ȃ�ł���B�����ĉ��߂Ċ������B��͂�A�����������̒��S�ł���A�܂��ے��Ȃ̂��B �R���������Βi���オ��B�����͂܂��A�l�͂܂�ŁA�W�҂炵���l�B�����̂悤���B�������Đ����I �����ɓ���Ɩ{���̉��ɐ����ƌĂ�邨��������A�����ɂ͍O�@��t�̍���������B�����A���̂����͂���(���V��)�ł͂�����w��t���x�Ƃ͌Ă������܂Łw�����x�Ƃ��ł��邻�����B�����Ă��̐����͍Ղ蒆�얀�D�\�����ɂȂ��Ă���B���߂Č���ƁA���������͐\����]�҂Ō��\�l���W�܂��Ă���B ���������s���Ă݂��B���ʂɂ́w�F���얀�D�\�����x�Ƃ���A��t�̂������l�`�ܐl�����]�҂�����Ă���B��������Ɖ����F�̍O�@��t���������̂����ƌ����悤�ɒ������Ă���B �����܂ŗ����玄���d�A�Ƃ��肱���͈�\���������ƌ������ƂɂȂ����B��t�̂�������b���Ȃ���i�߂Ă����B �܂��w��얀�D�F���u�[���x�Ƃ���A���z�ɂ���Ă������o���G�[�V����������B �Z��ʈ��S�F����c�c�c�c���~�ȏ� �Z�ʌ얀�c�c�c�c�c�c�c�c���~�ȏ� �Z��얀�c�c�c�c�c�c�c�c�O��~�ȏ� �Z���ʑ�얀�c�c�c�c�c�c�ܐ�~�ȏ� �Z��얀�J�^�����c�c�c�c���݉~�ȏ� �Z���ʑ�얀�J�^�����c�c���݉~�ȏ� �ƂȂ��Ă���A���ꂼ��Ǝ��̈Ӗ������߂��Ă���悤���B���͂Ƃ肠�������z�̒��g�Ƒ��k(�����I)���āw�ʌ얀�x��I�������B�����~��B ����ƍ��x�́w��x����w�K���F��x�܂œ�\�l�ʂ�̂������ӂ����������������o���ꂽ�B�u���̒�����C�ӂɓ�I��ł��������v�Ƃ̂��Ƃł���B �����Ƃ��ẮA�ߔN�̒������Ƃ��悭����A�܂��O�@��y���̍���̂��Ƃ�����̂ŁA�w�g�̌��S�x�Ɓw�S�萬�A�x�Ƃ����̂�I�B���̎�����́A�q�ϓI�Ȏ�ނ̋C���Ƃ͐藣�ꂽ�S���������̂͌����܂ł��Ȃ��B�@ |
|
|
��9
��n�����Ղ蓖���̖͗l�̑�2��ł��B�{�������M�C�ƌ����A�Î�������肢�����܂��B ��ʂ�̎葱�����ς܂����B��͍Ղ�J�n�Ƌ��Ɏ��ۂɖ{���̑O�Ň�����������Ă��炢�A���̌�{�a(�ڑҏ�)�ɂĂ��D���̂��̂�����������Ƃ̂��Ƃł���B �����������Ă�����Ɏ��Ԃ͏\����������B�Ȃ݂�Ǝ����̍s���̃^�C�~���O���M���M���������̂��H����U������Ɛ\����]�҂����̊Ԃɂ��傫�ȗ�������Ă����B�n���W�҂̐l�B�̍s�������������Q�����Ȃ��Ă����悤���B �����{��(�H)�J�n�܂ł͂܂��Ԏ゠��B���莝�u�^���Ƃ������A���Ԃ����ė]�������ɂȂ��Ă��āA�{���̂܂������낤�낵�Ă���B�{���̌��͓����R�̎R���ɂȂ���R���ɂȂ��Ă���A������Ƒ��������Ă݂邱�Ƃɂ����B �����͒��x�R�傩��n�܂铒���R�̎ΖʂɓW�J���Ă���A�{���̗��͒i�X���̂悤�ɕ�n���L�����Ă���B�{�����O���͂��Ȃ茖�����Ă������A���ɉ��ƉR�̂悤�ɂЂ����肵�Ă���A��C�Ƃ���C�Ƃ����镵�͋C���Y���Ă���B���̐Î₪�\�̌�����������Ă��邩�̂悤���B ��n����ĎR���ւ̎R���ƍ������邠����ɁA���ς��Ȃ��n�����������B���R�̏�ɒn���̎���������Ă���A���̊炪�Ȃ�Ƃ����������g������B���x�A�Ԓ˕s��v�̖���ɏo�Ă���L�����N�^�[�̂悤(�H) �ォ�畷�����b���Ɓu����܂������v�ƌĂꈤ�g�̂����ŁA�n���̏Z���ɂ��e���܂�Ă���悤���B�������̈��g�̂����Ƃ͗����ɗR���́A��ႂ�A�̒ɂ݂ɋꂵ�ސl���F�肵�đn�����Ƃ̂��Ƃł���B�ɂ݂��瓦�ꂽ����S�����̃��[���A�����ɑ������Ƃ���ƁA�Ȃ��t�ɒɁX������ۂ�����B ���̂܂R����o���Ă݂����C�ɂ��Ȃ������A�����͂�������ԂƂ͂����ĕς���ēܓV�͗l�B����t�߂���̓W�]���]�߂������Ȃ����A��ꂱ�ꂩ��Ղ�{�ԂȂ̂��B���ԓI�ɂ����낻����Ԃ��ׂ����Ǝv�������ɖ߂邱�Ƃɂ����B �ߑO�\�ꎞ�B���ƈꎞ�ԂقǂɂȂ����B�����O�͐\����]�҂Œ��ւ̗�ƂȂ��Ă���B�{���O�͊��ɐ\�����I�����l�ƒn���̊W�҂����������Ă������Ԃ��Ă���B �{���̕\�Ɨ��͂܂��ɔM�C�Ɨ�C�ł���B������グ��ƃw���R�v�^�[���������Ă���B �u�b�{�s���݂̂Ȃ���I�{���Ɩ����̓���Ԃɓn���n�����Ղ�ł́A���H�y�ь�ʋ@�֓��A��ύ��G���\�z����܂��I�܂��s�߂����s���͂��ꂮ����T�ނ悤���肢�v���܂��I�v �����炭���x�������̃w���ł��낤�B�Ȃ���_�^�C�K�[�X�D�����̓��ږx��̂悤�ŁA���߂čՂ�̋K�͂Ƃ��̐M�S�̔�����p���[���ĔF����������B�܂��n�܂��Ă��Ȃ��̂Ɂd�B �O�\���O�ɂȂ�A���낻��{���O�ɍs�����Ƃ��āA�ӂƐU��Ԃ�Ɓu��͂�I�Ȃ�قǁI�v�Ǝv�����B �{���O����͓�������X�������낹�邪�A�Ƃɂ������C���X�g���[�g�݂̂Ȃ炸�A�������e���܂łт�����N�����}�̐l�A�l�A�l�A�ł���B�����Ă��̑��Ă��^���̎R��܂ōs��ƂȂ��Ă���B���Ղ���Ǝl���ɕ����ꂽ�}���R��O�ő�����{�̊��ɂȂ��Ď������Ă���A�Ƃł��������瓖�Ă͂܂邾�낤���B�R��O�ň�ɂȂ����s��͂��̂܂ܐΒi���オ�萼���̐\�����܂ő����Ă���B ���ɂ����x���̂�������H�� �u�܂��A�肢���͒����҂ĂA�����҂قǂ�낵�������Ă��炦�����[�ȁ[�A�Ȃ\�ɂȂ�Ȏ�����������̂₩��A������������Ȃ�ڊ肤�Ă����߂₵�ˁ[�d�v �Ȃ�قǁA�����҂ĂΑ҂قǂ����v�͑����A�Ƃ�������̂�������Ȃ��B ���悢��{���O�ɂ��l���Ȃ���W�܂�n�߂��B�������x��Ȃ��悤�ɖ{���̑O�ɍs�����Ƃɂ���B�����\���݂��ς܂��đ����]�T���J�}���Ă������A�������������ł͂Ȃ��Ȃ����悤���B �₪�āA�R��̉��̋{�a�̕�����A���l���炢�̂����釁�g���̐l�����ق�L�𐁂��Ȃ���A�Q���e�̐Βi���オ���ė����B �u�u�D�I�D�[�`���v ��u�A�������O�̌������Î�ɂ����A�M�C����C�ɂ����B ���悢�懁�������J����A���̎��������悤���B �ق�L�ɂ��n�܂�����n�����Ղ�B�얀�������s���Ă���{���֑��ݓ���A�u�o��v�̎����}���܂��B�@ |
|
|
��10
�v��ʒ��҂ɂȂ��Ă��܂����u�R�����V�ҁv������ōŏI��ł��B���ꂩ��̎����̂�����̑�������ɂ��Ȃ肻���ȗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃł����B �g���̐l���{���̑O��ʂ邱��ɂ́A�ق�L�͐Â܂��Ă����B�Î�̒��A��l��l�Â��ɖ{���ɓ����Ă����B���̒��̒N�������邢�́A����t�l�̔镧���g���Ă���̂��H����Ƃ����ɁA�n����F�����̂��Ƃɂ���̂��H����͌����_�ł͕�����Ȃ��B �{���O�͎��̑O�Ɋ��ɏ\�l�قǂ��҂��Ă���A�{���̒��������ƋÎ����Ă���B�����ז��ɂȂ�Ȃ����x�ɏ����g�����o���ڂ��Â炵�Č��Ă݂��B ��͂�I���ɖ{�����ł́A�n����F����O�Ɍ얀�������s���Ă����B ���Â��{���̒��ŁA�ÂɒX���鉊��O�ɒn����F�����������ƏƂ炳��Ă���̂��킩��B�ǂ����肵�Ă����₩�ȕ\��B�����āA���ꂪ�c �����́A���x��̑O������ɂȂ�A�⏕��̏�̏����ȍ��h��̖ؔ��B���ʂ̔��͕����Ă��邪�A���ꂱ��������t�l�̔镧�Ȃ̂ł���B �������Ă�����ɂ��悢��{���O�̈�l��l�ɑ��Ė�����n�܂����B�\��������悤���B���͂��̒��O�ɖ{���̒��ւ̖ڂ���Ă��܂��A��͂Ђ����珇�Ԃ�҂����ł������B ���̔ԂɂȂ�A�O�̐l�ɏK���ė��������i�߂Ĕq�ށB�����{���̒�������]�T�͂Ȃ��B�Ђ�������������߂Ă����B ���̎��̎����̐S�̒��͂��������Ă��Ȃ��B�܂��A�ؔ��̒��ɔ�߂��A����J�n�Ɠ����ɔ����J���ꂽ�ł��낤����t�l�̔镧���̂��̂��A����̖ڂŊm�F����]�T����Ȃ������B �����A����l�ɂ���O�Ɏp���ꂽ�M�́A�J�n�҂ł����C�O�@��t�̔镧������߂Č�������͂��Ȃ̂����A�܂������܂߂��ꂾ���̐l�X���{�\�I�Ɉ������邾���̗��j������̂��B �O�@��y�������ɂ��悭�u���s��l�v�ɂƌ������t���o�Ă���Ǝv���B�l�����\�������ɂ����Ă��A���ʂ��H����́u�����s�v�Ƃ��Ă�A����͎u�������ďC�s���Ă���l�Ƃ����قǂ̈Ӗ����Ǝv����B �������u���s��l�v�ƌ����Ƃ��́A�P�ɒ��Ԃ̕H�Ƃ����悤�ȊW�ł͂Ȃ��B���킸�����ȁA����t�l�A�O�@��t�Ɠ�l�A��Ƃ����Ӗ��ł���B���H����͊F��l��l�����������u���s��l�v�̗������A�����Ĕ��\����̏o�����������̂��Ǝv���B ���V���̖�n�����Ղ�́A���s�́u���v�ł͂Ȃ��A�u�o��v�ł���B����������͂킸����N�Ɉ�x�����������Ȃ��̂��B�����Ă��̈�x����́u�o��v�̒��Ɂu�H�v�̗��ɂ�����Ƃ����Ȃ��M���Ïk�����B �����l����ƁA����������m�ʼn��߂���Ȃ�u�N�Ɉ�x�̓��s��l�v�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��낤���B ���͍��߂ď��߂Ă��̉��V���ɂ������n�����Ղ��̌������B�����ē�������Ɨ��ݍ��������j�̗���Ɠ`�����������������ł̑̌��ł��������A�������g�̂����ۂ��ȒT���S�Ƃ��̂悤�Ȏ��̌����Z������ɂ́A�܂��܂��c������o���ł����Ȃ���������Ȃ��B �������u����v�A�u�H�v�A�����č���̖�n�����Ղ�ɏW���\���l���z����l�X�c�B�����Ă��̈�l��l�̈ӎ���M�S�̗l�X���A���̂悤�Ȑl�Ԃɂ��u�ق�̏��������v�_�Ԍ��ꂽ�悤�ȋC������B ���̌�A�{�a�ɂďo���オ�������D�����炢�A���V������ɂ���B�Ղ�͂��̌�A�����̐��߂܂ő����̂��B ���̑̌��͏I���������A�u�N�Ɉ�x�̓��s��l�v�͂܂��܂��n�܂�������Ȃ̂��낤�B ���͏o�X�Ɛl���݂ł������Ԃ�����X������A���X�o�X�ɂ����ǂ܂�Ȃ���A�����̒��̂��b�ʂ胆������ɗ���������B�����ĖZ�������A���H�ɂ��ł�Ƃ��Ȃ���i�����y���ɂȂ��Ă��܂����B����͎��ނ����B���肪�Ƃ��B��������ɂ͐[������\��������B �������瓒���܂ŁA����E�����Ɣ��ɔZ���Ȏ��Ԃȗ���ł������B�܂��܂����Ȃ�̇�����臁�ȂǂƂ͌����Ȃ���������Ȃ����A�܂��܂��A������X�ɗl�X�Ȃ��Ƃ��z�����Ă������낤�Ǝv���B �ȏ�ŁA�O�@��y����3������4���ɂ����Čf��(4���͖���)���ꂽ�u�O�@��t�䂩��̓��Ɣ���̓��A��R�E�����E�����A�R�����V�v�I�s�͏I���������܂��B�@ �@ |
|
| ������̋S / ���Ɍ��O�g�s�t���� | |
|
�����ЂƂA�`���u����̋S�\�\�̂ȋS�̂���`���\�\�v�ł́A���̂��܂Ⴍ�Ƃ悭�����L�����N�^�[�̋S���Љ���B���̋S���������傱���傢�ł���Ƃ���͂悭���Ă��邪�A�Ō�ɂ͐l�X�̂��߂ɂȂ邱�Ƃ����ēV�ɋ����Ă����B�S�Ƃ������͐_�ɋ߂����i����������B
�b�̓��e�́A�q�R(�܂����)�̗�(�O�g�s�R�쒬�����t��)�𗬂��q�R��̐��ʂ����Ȃ����Ƃ�A�D��(�ӂȂ�)�̗�(�O�g�s�t��������)�ɂ��Ă͎��c(���ł��͂��̈����c)�������������ƁA�q�R���ӂ����Ă͗{�\(�悤����)��I�̖��Y�n�ł��������ƂȂǁA�n��̓������S�̍s���ɂ���Đ������悤�Ƃ�����̂ł���B �S�́A�Â����炵���ΐ��b�ɓo�ꂷ�邪�A���Ƃ��Ε�������ȂnjÂ��i�K�̋S�͐l��߂��ĐH������߂ċ��낵�����݂ł������B���̓`���̂悤�ɐ_�ɋ߂��A�������l�ԓI�ȂЂ傤�������˂��Ȃ������i�̋S�́A���Ȃ�V��������ɍ��ꂽ��ۂ���B�O�g�s�͑����̓��ׂɂ�����̂ŁA����̋S�ɂ����̂��܂Ⴍ�̐��i���e�����Ă���̂�������Ȃ��B ����ƂȂ����́A�d���̑��S�ƒO�g�̕X��S�̋��E�ɂ��т���R�ŁA�X��S���ł͍ō���ł���B���̘b��`���Ă����q�R�̗��͎�����[�ɂ���A���̋S�`���Ƃ͕ʂɍO�@��t(�����ڂ�������)�Ɋւ���`������`�����Ă���B ��́A����R���t�߂̊₪���ɂȂ��Ė�Ȗ�ȓc�����r�炵����č����Ă����Ƃ���A�O�@��t���@��(�ق��肫)�ł�������߂��Ƃ������̂ł���B ������́A�O�@��t�����ɂ���Ă���1�t�̐������߂��Ƃ���A���l�����������Ȃ��������߂ɁA���ꂩ��q�R��̐��ʂ����Ȃ��Ȃ����Ƃ����`���ł���B��҂́A����̋S�̘b�Ƌ��ʂ��A�n��̎��R���������`���ƂȂ��Ă���B ���̎�����×��_���̂���R�ł������B���[�Ɉʒu���鑽��������O��(����)�ɂ́A�Â�����ɒO���喾�_���������Ă����Ƃ����`��������B�������A����Ƃ��喾�_�͖k�[�̒O�g�s�X�㒬�O��(�Ђ��݂��傤�݂͂�)�֔��ł����Ă��܂��A���[�̒O���ւ͑喾�_�ƂƂ��ɂ܂��Ă��������F(����ڂ���)������Ă����Ƃ����B����R��ɒ������Ă����Ƃ����O���喾�_�ƕ����F�Ƃ́A�`����̍��m�ł���@����l(�ق��ǂ�����ɂ�)���J�������@���w���Ă���Ƃ����B �܂��A�喾�_�����ł������Ƃ����O���̓����_��(����������)�ɂ��A��͂�Ր_�͒O���̑�o����(�����̂ڂ肪�݂�)����ڂ��Ă����Ƃ����`�����c����Ă���B���̋S�ɂ́A��������_�Ɋ������Ă����C����(���グ��)�̎p�����e����Ă���Ƃ��l�����Ă���B����̋S�̓`�����A���̂��܂Ⴍ�Ɠ��l�ɁA���������R�ɑ���M��w�i�Ƃ��Ă���悤���B�@ �@ |
|
| ���O�@���߂���I�s | |
|
���a�̎R���̍O�@���
�a�̎R������w�����֕����ƋI�m�삪����Ă���B�����Ë���n��ƍ���R�ւƎ��閃����(������)��(�����X��)�̈ē�������A�|�C���g���ƌ��Ȃ���}���o���Ă����B���̓r���A�u�n�C�^�n���v�̍����ɉ��s5���قǂ̏����ȉ������琅���N�o���Ă����B ����ɓo�����߉꒬�ԏ��c(������)�Ɂu��t�̈�ˁv������B�O�@��t���������]����ƘV�k�������܂ŋ��݂ɍs���̂�ĉ����ɂ��N�o�������A�Ƃ̓`�����c���Ă���B���Ȃ������̍�������킸���ɐ����N�o���Ă����B�������K�̏�ɂ̓T�U���J���炢�Ă����B���̉��ɂ͍����̃R���N���[�g�̊ۂ��䓛���������B �R�Ԃ̎Ζʂɂ���W���͒��̊ȈՐ����̕��y�Ő��ɍ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ������̂́A�����_�Ɨp���ɗ��p����Ă����˂������B ���͉w��������Ė�20���A�q24�����̃o�X��u����ҁv�̘e����k�ɏ������������H�����̌E�n�Ɂu��t�̐��v(���͒�����)������B�I�B�̖���100�I�Ɏw�肳��Ă���B�X�e�����X�̊W�����ꂽ��˂̒���`�����ނƁA�Z�����g���̌a1�����炸�̈�ˌ^��50�����قlj��ɐ�����X���A����ɂ͊ې��~����Ă����B�ē��ɂ��A���̐̋��C�̋������������O�@��t�����˂��Đ^����N�o�����Ĉȗ�����邱�ƂȂ��N���o���Ă���Ƃ����B �œc�w�����֕����ƌ����ɏo��B�����𐼂ւ��炭�s���ƁA�������班���������⓹�Ɂu�o���v�ƌĂ��u�O�@��ˁv(�œc���Ԗ�(����))������B�����ɏ����ȍO�@��t���Ɩ̊W�̂��ꂽ��˂�����B���͒��̍O�@��˂�菭�����Ԃ肾�����͓����ʂ��Ă����B�����ɂ���t������œ˂��ėN�o�������A�Ƃ̓`�����c���Ă���B |
|
|
���l���\�]���̍O�@�䂩��̐�
JR�����w�̃z�[���Ɂu���̓s�����v�̐Δ�Ɛ��ꂪ����B�����s���ɂ́u�����ʂ��v�Ƃ����鎩���������悻200��������B�ΒȎR(�W��1982��)�𐅌��Ƃ�����ΐ�̕��������Z�������n�w�Ƀp�C�v��ł����ނƒn���ŕ��o����B�s�����̋߂��ɂ͂��̑�\�Ƃ��Ċ��������S�I�Ɏw�肳�ꂽ�u�����ʂ��v������B��������Ƃ܂�₩�Ȗ��������B���ʂ邭�������͓̂~�G�ł��N��15���O��̒n�����ł��邽�߂��B �܂�������ːw���̖x���ɊJ�킳�ꂽ�{�w��͌��œ��\�`�̓�����ɁA�����s���������50�I�Ɏw�肳���O�@��������B�����ɂ͍O�@��t����̐�œ˂��Ɛ������N���o�����Ƃ̓`�����c���Ă���B�������Ă݂�ƑS�����C���Ȃ��B�C��̒n�����琴�������̂܂ܗN���o���Ă����B�������łȂ��`��Ɖ��������悤�ɍO�@��t�����������Ă���B JR�ɗ\�O�F�w���琼�֖�15����������(���\�s)�Ɂu�P���t���v�����H�����̌E�n�ɂ���B�����Ȃ����̑O�Ɍa50�p�قǂ̐ΐ��̊ۂ���˘g�ɐ����N���o���A�����ʂ�������ł͏������j���ł����B���̗l�q���炨���̉������H�ƂȂ��Ă���悤���B����o���r�͏��������Ă��邪�R�C���j���ł����B�O�@��t�����˂����ĂĔO����������Ɛ����N�o�����A�Ƃ̓`��������A�P�̌`�̈�˘g����u�P�䐅�v�u�P�r�v�ƌĂ�Ď���Ă����B �ɗ\�S����̎q�w�����֖�30�������Ǝl�\���ԎD�����ю�������B���̎��`�ɂ͍O�@��t�����ɋꂵ�ޑ��l�̂��ĂȂ��Ɋ������Ď���œ˂��Đ���N�o�������Ƃ���A���̈���쐼�ɏ������ꂽ���́u��m���v�ʼn��̉@�ƂȂ����B���������S�I�Ɏw�肳��A��m�������͎��������Ȃǂ݂����s�s�����Ƃ��Ďs���̌e���̏�ɂȂ��Ă���B �r�͎���100�����炸�A���[1���قǂ̒r�ꂩ��d�M��̕��������N�o���鐅�̓u���[�X�J�C�F�Ő���ł���B���̈�p�ɍO�@��t�����������Ă���B�r���痬��o������̓R�C�ƃ}�X���ꏏ�ɉj���A�V�R�L�O���́u�e�C���M(�w���I�I�o�^�l�c�P�o�i�Ƃ����z�N��)�v�������V�[�g�ŕ����ĕی�琬����Ă���B�����̗גn�ɂ́u�S�������S�I�v�̐��ꂪ���邪�A�l���L�ʼn�����ƂȂ��Ă���B�����̕ۑS�̂��߂ɂ͎d�����Ȃ��̂����m��Ȃ��B JR���\��w���������10���قǂ̂Ƃ���Ɂu���\�h��̐����v������B�����̉��ɂ��鐅��́A�J���̗����ۂނ����̐��H�̗����̏�ɏ����Ȓn�����������Ă���B�i�s�V�c�̌���88�l�̌R���炪���q�̕����邱�̐��őh�����Ƃ����`�����c��A�×����Ƃ��đ���Ă����������B���ł�����邱�ƂȂ��N���o�������̂������ŁA����ׂ̗ɂ͑n��200�]�N�ɂȂ�Ƃ����g�R���e�������X���\���Ă���B3���قǕ��������\��ԎD���V�c���ɂ́A�O�@��t�����̐��ʂ������ɗ�C�������č��Ƃ�����{��(�\��ʊϐ�����F)�����u����Ă���B |
|
|
���X��̓ƌ̑�Ɛ_�˂̍O�@���
�ΐ�(������)�w����o�X�ɏ��A���nj������20���������R�[�Ɋ�뎛�╺�Ɋό��S�I�ɂ��w�肳���u�ƌ̑�v������B���̑�͗�����20���ŁA�u�O�@��t����ւ�ގ����邽�߂ɖ����̖@��ł���ƌ��قɓ������ꂽ�v�Ƃ����`�����c���Ă���B�ꂩ��K�i��o��Ɛ�R�s����������B���A�ɍO�@��t��������Ƃ�����s�����������J���Ă���B����Ɍܑ�R�ւ̓o�R���������o�����Ƃ���Ɂu�s��̑�v������B ���ӂ̎R�͒��������E�ɂ�����A���̑�̐��͉��Ð�ւƗ���Ă����B �ΐ��w�����10�������Ɛ���(�݂킩)�����������B���{�C�Ƒ����m�E���˓��C�ɕ����钆�������E�͖{�B�ʼn�����1800��������B���̌����͕W��95���̓��{��Ⴂ���������E�ŁA���̉�����1250���̍œ��[�ɂ���B����͍��J��A������A���Ð���o�Đ��˓��C�ւƒ����B��������͍טH���W�߂č����ƂȂ�A�|�c��A���m�R�s�ŗR�ǐ�ƍ������A���s�{�𗬂���{�C�֒����B�����M�����Ð��R�ǐ���������A�X��n���͂��̒n���I�����𗘗p���Đ��˓��Ɠ��{�C�����Ԓ��p�n�Ƃ��ĉh�����Ƃ����B �{���断�@���n��𗬂�閭�@���쉈�����班���R��ɓ������Z��X�̈�p�ɍO�@�̈�˂�����B���ݐ��ɍ����Ă��鑺�ɍO�@��t�����˂��Ɛ����N���o���Ƃ����`�����c���Ă���B1�~3���̒����`�Ő�˂Ő��̗���͂Ȃ��B3�{�̒������ۂ��������A�u�����������͕������Ĉ���ʼn������v�Ƃ̒��ӏ���������B���ӂ͎R������đ�n�J�����ꂽ�悤�ŁA�y������h�~�̃R���N���[�g�̐�ǂ�����B���̉e���Ő������R�����Ȃ����̂�������Ȃ��B |
|
|
�������̟@�Ɛ�N��
����21���́u�O�@�̓��v�́A�����͘I�X�����юQ�q�҂œ��키�B�����ɂ���u�@�v��4��21���̂ݓ��ʂɌ��J����A�@�v���c�܂��B���̒��ɓ��Ɏ��ꂽ�u脉���v������B�i�q���璆��`���ƈÂ��ĐΊ_�������邾�����B�k��3�����قǗ��ꂽ�_�̒r�ƒʂ��Ă���A�Ƃ����`�����c���˂��B ���R�ɂ����N���͍O�@��t�����������ƂɗR�����Ă���B1218�N�ɑ剾���c�����ہA���̈�p���琴�����N���o�������Ƃ���u��N���v�Ɖ��߂��Ƃ����B���̗��j���鐅�͗��h�ȉ��`�Ɏ���Ă���B���������N���o���Ă���Ƃ������A���̓��͐��̗���͂Ȃ������B���`�̕�C�H�������Ă��邽�߂��낤���B ��N���ɗאڂ������}�@�ɂ͍O�@��t�ƌؐ�������B�{���e�ɍO�@��t�������������������K������B�����K���̊ω������J����ƁA�R�����琅���N���o���Ă���B����˂ƂȂ��Ă���A���͉��[���Ĕ��Â��B������ꂽ�������ۂŐ����d������Ė��������B�����Â������B�u�ԕ�Q�m�̓�������v�ŗL���ȑ�ΗǗY�����̐������Ŋܐ��������Ă��Ƃ����Ă���A14���́u�Q�m���ÂԒ���v�ł��̐����g���������B |
|
|
���I�����̍O�@���
�O�d���𑖂�I�������މw����k����30���قǕ������Ƃ���́A�a�̎R�ʊX�������̊X�p(���C���m�c)�Ɂu���ˁv������B���ɂ͏����Ȃ���������B�ē��ɂ́u�O�@��t�����̒n�֗�����萅�����]���ꂽ�Ƃ��A���̕ւ������ƕ����A��Œn�ʂ��������Ɛ����N���o�����B���������p�ɁA���������͐��̂Ɏg���悤�Ɍ���ꂽ�v�Ƃ���B�召2�̈�˂ɗ��ꍞ�ސ��͉������������Ă���̂��낤�B���̓h�����Ƃ��Ă���B��˂ɂ͑����̃R�C���j���ł���B�������Ă���Ă���R�C�́A����́u�O�@��t�v�Ƃ����邩������Ȃ��B �ׂ̉w�̓Ȍ��w����������B�x��(�킽�炢)���͈ɐ����́u�킽�炢���v�̎Y�n�Œ������L�����Ă���B��������1���Ԃ��炢�Łu�O�@��ˁv(�x��c��)���������B�R���ɂ��邨���̐Ί_�̉�����N���o��������2���~3���A1���~1�D5���̈�˂ɒ����ł���B���̓��͍����炫����A�Ԃт炪���ʂɕ�����ł����B�l�̎p�͂Ȃ��������A�u�~��͒g�����Ă͗₽���A���݂��n��Z���̐�Ɋ��p����Ă���v�Ƃ������Ƃ��B |
|
| �@ | |
|
������(���s�{)�̓��
��a�H��(����)���Ήw����k�֕����Ă����B�ؒÐ�ɉ˂��鋱�m�勴���z���ĉE�܂��A�a����ɉ˂���ؐ؋��̘e�Ɂu���v(���Β��䕽��)������B���̐́A��˂����~�Ɣ��̖��������Ƃ��납��u�~�̈�v�Ɓu���̈�v�ƌĂ�Ă���B ���H���ɂ���u�~�̈�v�͊R������N���o��������3���ɋ��ꂽ��˂ɒ����ł����B���̂����Ă��������ɕ����Ɓu�͈̂��߂��B���͉������������Ă���v�Ƃ������Ƃ��B�����p�ɂɍs�������Ԃ�����A�m���ɐ����͐S�z���B �u�~�̈�v���班�����ɓ������Ƃ���ɢ���̈䣂�����B�����悤�ɊR���̐Ί_����N���o���A�u�~�̈�v��菭����Ԃ��1�~0�D5���A2�~0�D5���A1�~0�D5���̎O���ɋ���A�a����ɒ����ł���B���̐�ŖؒÐ�ƍ������Ă���B���ɂ͍O�@��t������Đ�����Ƃ����`���́u�O�@��t�����ؐؐv�ƍ��ꂽ�Δ肪�����̒��ɒ������Ă���B��˂̓��ԕ\������ƁA����l�Ō�サ�Ȃ���n��Z��������Ă��邱�Ƃ��킩��B |
|
|
���a�̎R�̍O�@��˂ƍO�@��
�I��������w����k�ɕ������Ɩ�30���A�݂���R�Ɉ͂܂ꂽ��p�Ɂu�O�@��ˁv������B�O�@��t����œ˂��ƗN���o�����Ƃ����`�����c���Ă���B�F��Ó������ɂ���A���Ă͌F��w�ł̗��l�����̈�˂ł̂ǂ��������������B���������݁A���͌͂�ʂĂ����Ŏ��ꂽ��˂��Ȃ�ł��邾�����B�c�O�Ȃ��ƂɈē�������Ă����B �݂���R�������������Ƃ���ɁA�t�쉤�q�ՂƂ����t��_�Ђ�����B������Ƃ��u�����t�����Ă���̂ŁA���̖�������v�Ɠ��L�ɋL���Ă���悤�ɁA�C�̂��鐼�ւƂ͋t�����Ă���Ƃ��납��u�t��v�Ăꂽ�Ƃ������Ƃ��B���̐�͍H��̗���ɂ��镝1���قǂ̐삾�B�ē��ɂ́A�u��N�w�g��x�v���߂��A���̒n���ɂ��Ȃ����v�ƋL����Ă����B ���̖����V�R�L�O���Ɏw�肳��Ă��鋴�Y��(���{��)�̋߂��Ɂu�O�@���v(�Í���)������B�O�@��t���̔w��ɂ͂�����苐��Ȋ₪�����肽���Ă���B�O�@���͂��̘e���ɂ���B���ۂ��琔���̊R��ɂ��邽�߂��낤���A�͉����̂Ȃ��P���B�����瑾���m�̊C����]�ނ��Ƃ��ł��鏬���ȗ�����2���菇�Ԃɓ���B���̓������łɑ҂��Ă���l�������B�P�n��̏Z���̌��N���i��}��R�~���j�e�B�[����Ƃ��ė��p����Ă���B(��������l300�~�A���p���E�E�y�E��) �a�ɋꂵ�ޑ��l�����̒��ŁA�_������Ŏw����������N���o���Ă��铒�͖��a����₷�Ƃ̂������������B�ڊo�߂�Ƒ��̊���ڂ��瓒���N���o���Ă����Ƃ����B��������݁A���ɓ���ƕa�����������Ƃ���A���̑����u�O�@��v(�N�c�k�M��)�A������u�O�@���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ����Ɠ`�����Ă���B ���Y��͂��̑�₩��A�����ď\���̋��₪�C�ݐ��ɕ��ї����Ă���B�n���w�I�ɂ͎��͂̓D��ɑ��Čł��ΐ���łł����▬���Z�H���ꂸ�c�������̂����A���̊�ɂ͍O�@��t�̂������낢�`�����c���Ă���B�V�̎S(���܂̂��Ⴍ)���F���K�ꂽ�O�@��t�Ɉ�ӂő哇�܂ŋ����˂��鋣����\�����Ƃ���A�V�̎S�������܂����ɔ�������t�̎ז����������ߋ����̑�₾�����c�����Ƃ����B |
|
|
����R(�ɂ킩���)�O�@�̐�
�L�������R�s�s�X�n����k����5�q���ꂽ�ÔV����������B���̎R�Ԃɉ�R�O�@�̐�������B�R�z�����ԓ����R�r�`�߂��̍������ɉ˂���O�@�勴���z���Ă��炭�����ƁA�Ђ�����ƘȂ�������B�����ɂ͍g�~���炢�Ă����B���͔w��ɂ��т��鍂���R(399��)�̎R������N���o���Ă���B�u��쐅�v�ƍ��ꂽ�������������ĕ��ۂň���ł݂�ƁA�킸���ɊÂ������B �����̋߂��𗬂��J��ɗ��ē��ɂ́u�R�����l���a�����������̒J��Ő�������Ƃ���A���̐������ނƕ��ɂ��������l�X���ꂵ�ނ̂��݂��O�@��t���쐅���o���ċ~�����Ƃ����`��������܂��v�Ƃ������B�ȗ����̐����u�O�@�̐��v�Ƃ����A�݂̕a�C�Ȃǂ̌����Ɨ��p����Ă����B�����đ�X���ӂ̏Z����Łu�⓿��v���������č�����葱���Ă���B���́u�ۑS��v�Ƃ���10���b�g����100�~�����߂邱�ƂɂȂ��Ă���B |
|
|
���F��(���)�̐���
�O�[���Ό��w����命��s���o�X�ɏ���Ė�30���A�u�s��X�v�o�X�₩��k��5�����炢�ŌF��(���)�_�Ђɒ����B��������ɒ߉������{�̎З̂���������_�В��c�̓����ꂪ����A���J(���)�ƌĂꂽ�Ƃ��납��n���̗R���ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B �_�Ђ̊R���Ɋ����̖����S�I�Ɏw�肳��Ă���F��(���)�̐���������B��̕s�������J��ꂽ�����Ȃ��������獧�X�Ɛ����N���o���A�ۑ�������т���2�{�̖ؔ�œ�������Ă���B���a3������[20�����قǂ̓����ʂ�����͐썻���~����āA�R�C���j���ł���B ���̐��͍O�@��t���K�ꂽ�ۤ���s���ŋ�J���Ă����_�������̂��߂ɖ@�͂ŗN�o�������Ɠ`������u�O�@�̗쐅�v�ŁA�ȗ����Ƃ�ɂ�����邱�ƂȂ����p���Ƃ��ĉ��b���Ă����B���͎c�O�Ȃ���A�����@�ɂ�鐅����ɂ͓K�p���Ă��炸�A���p����ɂ͎ϕ����K�v���B�����̎��ӂ͂Ȃ��炩�ȋu�˒n�ŃS���t�ꂪ�����B���̉e�����S�z�����B �ߑO8������ɖK�ꂽ���ɂ́A�ߗׂ̏Z���������̎����|�����Ă����B���N�A����������Ă����̂�����t�M�ɂ��Ƃ��낪�傫���B�a�C�̎�����F��Ȃǂɗ쌱������Ƃ���A�Q�q�҂������B |
|
|
�������_�ЂЂȗ����Ɛ_��
���E������Y�Ɏw�肳��Ă��鉺���_��(��Ό�c�_��)�̌����r�Ŗ��N3��3���Ɂu�Ђȗ����v���J�Â���Ă���B�����r�̑O�ɂ͏\��P(�ЂƂ�)�߂́u���Ђȗl�v�����ԡ�u���Ђȁv�̏\��P��10���Ŗ�15���������邻�����11���߂��Ɏn�܂����_���ɑ����āA�u���Ђȗl�v����琻�̏����Ȃ��M�ɏ�������Ђȗl���q���̐������肢�Ȃ��玟�X�Ƌʐ̕~���̐��[20�����قǂ̌����r�ɗ������B���̂��ɂ��鐣�D�ÕP���J�����ێЌ����_�Ђ̉��̈�˂��琅���N���o���Ă���B���̓��͕������Ő�̗���ɋt����Ă������A���̐��́u��(������)�̐X�v�̒��ɍĐ����ꂽ������ւƗ���Ă����B�P���L����N�m�L�Ȃǂ̗��t�����������̐X�́A����ƍ����̍����n�Ɉʒu���A�u���F(������)�v�Ə̂��ꂽ���Ƃ����̗R���Ƃ����B �����̓쑤�ɂ���_�͊����V�c�����������c�ő�����̘e�ɐ݂������n�ł���B�����ɂ́A�V����(824)�N�Ɋ��œ����̋�C�Ɛ����̎�q���J��̋F����ׂ����A��C���J�Ɛ��̐_�ł���P������(����ɂ��イ����)���C���h���珵�����āA�J���~�点���Ƃ����`�����c���Ă��顂��̑��ɂ����쏬�����J��F����r���ȂljJ��̓`���������c���Ă���B �肢��O���Ȃ���n��Ɗ����Ƃ�����F�̑��ۋ���n��ƁA�����r(�ق����傤��)�̐^���ɑP���������J��ꂽ���������顈���A�u�a�A����A����ɂ���Č܍��L���A�����ɐ��A�q���ɉh�A�������A�����邻����� ���Ă͓�k�l���������(�꒬�͖�109��)�̍L�傾�����_�������̑��c�ŏk�����ꂽ�B���3�����قǗ��ꂽ�����Ŗ��N�����ɍs����u��C�@�v�łͤ�������ށu�䐅���v���s����B�ȑO�͐_�̑P������脉���̐��ۂŎ��t������ŁA�䍁���Ƃ��Ă����������B���ł͓����́u�@脉���v�̐�������ł���B���̈�Ɛ_�̒r���ʂ��Ă��邻�����B������`���ɉ߂��Ȃ��̂����낤������̗������Ȃ����߂��Ȃ�����Ă��� |
|
| �@ | |
|
���V���R������J�ω��k�J����
�R��w�̖k�ɂ��т���̂́A�V��10(1582)�N�ɉH�ďG�g�Ɩ��q���G�R�̍���ŗL���ȓV���R(270�D4��)�ł��顋��s(�R��)�Ƒ��(�ے�)�̋��E�n�Ƃ��Ĥ�×�����R���ƌ�ʂ̗v�ՂƂ��ꂽ����ł�����Ƌ��ދ������n�ɁA��}�ƍݗ����ƐV�������قڕ��s�ɑ����Ă���B�R���ւ̃n�C�L���O�R�[�X�r���̓W�]�䂩��͗��삪�Ղߤ�����ɂ͔~�c�̍��w�r���Q�������顂܂��d���̋����͎m���̂����ώ��A����(�����Ƃ�)�_�ЂȂǂ��_�݂��Ă��� ���J�ω��k�J��(�悤������)�͓V���R�R�����炳��ɖk��3�D5���������B���s���������J�c�����������J�c�Ƃ����B�����ɂ́u�ƌؐ�(����������)�v�����顂����ŋ�C(�O�@��t)���C�s����A�����̊⌊����N�o�������������F������a�����̗쐅�Ƃ���Ă��������17���͉����ŎQ�q�҂��������߁A���̐l�����ݏo���Ă���Ă�������f�͖̊W���Ƃ��Ĉ�˂��狂�ݏo�����A����ł����ʈʂ͕ς��Ȃ�������� �ق��ɂ������ɂ́u�����v������B�������u�_��(�݂̂��)���v�͗���Ă��Ȃ����ʂ����ɐ���Z���Ċ���ʂ����Ƃ����u�ٓV�䐅�v�͐��������Ђ˂�Ɨ��̌����琅�������d�g�݂ƂȂ��Ă��邪����o�Ȃ�� �A��͒����V���{�ɗ�������������ق�Ɣ~���炫�n�߂Ă����B |
|
|
���x�c�ю���������ΐ�A��J�s����
�ߓS�x�c�щw���瓌�֏��������Ƥ�퍑����ɋ������ʉ@�𒆐S�ɍ��ꂽ������������̒��ŗL���Ȃ̂����l�Ώ�I�q�̐��ƂŁA���̏d���Ɏw�肳��Ă��鋌���R�Ƃ���i�q���̉Ɖ����_�݂��钬���݂�����Ă���Ƥ���H�ʂɢ�w���萅�H�գ�ƋL���ꂽ�肪����B�����A�Ɖ��̗���w�������ɔr���H������Ă�����������Αg�݂̍a�����̖ʉe���c���Ă���悤���B �������̓��ɂ́A��N�R�������Ƃ���͓��̐����W�����Ă���ΐ삪����Ă���B��������Ă���Ƥ�T�M��Z�L���C��������������̓��͂��܂��܂������̂��J���Z�~������������������瓌�ɍs���Ƒ�J�s���������28���������ƂȂ��Ă��褂��̓��͏������ŘI�X������A�ˁA�Q�q�҂���������� ��J�s���������͍O�m12(821)�N�ɍO�@��t���J�n�����Ɠ`�����Ă��顋����ɂ́u��������v�����顂��̐��͋������瓌��200�����ꂽ���t�䣂��狂�ݏo���ꂽ���̂�������ȓ��́u��t��v�̘e����|���v�A�b�v����A��ʂɋ��݂����l�����p���Ă��顋����̈ē��ɂ��Τ���̐��͊�a�Ȃǂ̏��a�̕����Ɍ��\������Ƃ��āu�����������v�Ƃ��đ���Ă�����Ƃ���� ����3���قǂ̈�̐������ꗎ����ꂪ���顕s�������������A�u�s��v�̌�����������B�ꂩ�痬��o���Ă��鏬��ɎQ�q�҂�������h�W���E�𗬂��Ă��������́u�g����ǂ��傤�v�Ƃ���꤂���Ŗ�𗬂��Ă��邻�����B ���đ�J�s���͏������ꂽ�ԎR(��������)�ɂ������B���݂����ɂ͕x�c�ъȈՕی��ۗ{�Z���^�[������A�n��1200��������Ƃ���V�R�����顂����̘I�V���C���犋�餋����R�n�̎R���݂��ǂ������顂��̓��̋����R���͂�������Ɛቻ�ς��Ă���� |
|
|
���ɐ��u���E�O�@�̈�˂߂���
�ߓS�d�Ԃƃo�X�𗘗p���Ĉɐ��u���n���ɑ����c��u�O�@�̈�ˁv���߂������ �܂��͒��H�s�ɂ��钆�V���w������10���قǕ��������H4���ڂɂ���u�O�@��ˁv��K�ꂽ�B����͓��H�ʂ����1�D5���Ⴂ�����������r���H�̈�p�ɂ������B�u�O�@��ˁv�ƍ��ꂽ��̉��ɂ����K�̒��ɐΑ������u����A��˂��������B����`�����ނƕǂ̌��Ԃ��琅�����ꍞ��ł�������͑����Ă��Ȃ��̂�����A�����ł͂Ȃ��悤������������̐��Ɣr����������r���H�͈Ë�������Ă���� �O�@��t�����̏ꏊ�ɏ��˂��h���ċ��������Ɛ��������o����悤�ɂȂ����A�Ƃ����`�������顝ۓV�̂Ƃ��ł�����邱�ƂȂ����l�̗p���ƂȂ�������a30�N����܂ň��ݐ�����p���ɂ��g���Ă����������B �C�ӂ̕l�����͋ߓS�L���w����o�X��20�����炸���B���̕l�ɂ��鍂��3���̖h����̓S���̓����Ɂu�O�@�̈�ˁv�����顔���K���Ȃ��O�@��t�䂩��̈�˂Ƃ͑S���킩��Ȃ��B1�~2���قǂ̑傫�Ȉ�˂͊J�ł���g�^�������ŕ����Ă���B�����Ē���`�����ނƁA�Ί_�̕ǂŒ�͋ʐ��~����Ă����B���͏��������Ă���悤������� ���̈�˂Ɏc��O�@��t�`���́A�C�ӂɋ߂��Đ^���̏o���˂����Ȃ��č����Ă������l�ɁA���V�����˂��h���Đ��̏o��ꏊ���������Ƃ���A�@���Ă݂�Ɛ������X�ƗN���o��������̂��V���O�@��t�������A�Ƃ�����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B �ߓS�L�Ï��w���琼��10���قǕ������͌|�����ɍO�@��˂�����B���Ƃ��A�Ȃ鋌�������̌����̒��ɂ���������ɂ͍O�@��t�������u���ꂽ�������顈�˂͊W������Ă���A�W���グ�Ē���`�����ނƐ��͑����Ă���� ��˂̗R���������ꂽ�z�ɂ́A����������O�@��t�ɍ����グ�邽�߂ɐ��炩�Ȑ��������܂ŋ��݂ɍs�������A�Ԑ������o�Ȃ�������˂��琴�炩�Ȑ������ӂ�o��悤�ɂȂ����A�Ƃ����B����Ȍ�u�O�@��ˁv�Ə̂���A�ɐ��X����������l�̂̂ǂ��������Ƃ������Ƃ��B�܂�1960�N�ɒ��c�̏㐅�������܂ł͐����p���Ƃ��ė��p����Ă������A���ł͑S�����p����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B�������ؘg�ň�˂����A��t���J�邨���ɂ͉Ԃ��������Ă���̂�����ƁA�n��ł����������Ă��邱�Ƃ��悭�킩�� |
|
|
���Q����s���̍O�@�̈��
�Q����s���ɂ�4�����̍O�@�̈�˂�����B ���Q����w����k�֕�����5�����炢�̑ŏ�n��Ɂu�ŏ�̍O�@��ˁv�����顓��H�����ɐΑ������u�����������K�̉��ɂ��顂悭���Ȃ��ƌ�������Ă��܂��قǂ��B���͐�����̂悤�����A���Ă͓��Ƃ肪�����Ă�����邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ����B�����ē�����X���̓��[�ɂ���A����R�w�ł�����l��̂̂ǂ��������Ƃ����B �����n��ɂ́u�����̍O�@��ˁv�����顃t�F���X�ň͂܂ꂽ��˂ɂ͂��Ă̒ޕr�̎ԗւ��c���Ă���B���ɂ͏����ȐΑ����J���Ă���B ���𗬂��ŏ�삪��������Q����̐�炩�牺��Ɓu�c��̍O�@��ˁv�����顏c2��90�����A��2���Ŏs���ɂ���O�@��˂ł͍ő�ł���B���̈�˂ɂ͓T�^�I�ȍO�@�`�����c���Ă���B���̒n�ɂ���Ă������V����ɐ��͂Ȃ��ƒf�����Ƃ���A���̂��V����������Ă�Ɛ�������邱�ƂȂ��N���o���A���̂��V���O�@��t�������Ƃ������̂�� �S�n��ɂ́u�������J�O�@��ˁv������B���ɂ͗��h�ȑ�t�����t��������B���̐́A�R������N���o�������͑��l�̋M�d�Ȉ��ݐ�����������݂͒n��̑�\�҂̑g������˂̈ێ��Ǘ����Ă��顃|���v�A�b�v�����n�����̗��p�͒n����̗��p�҂Ɍ��肳��Ă͂�����̂́A�������p�ł���̂͂���������� 300�N�O�ɕt���ւ���ꂽ��a�삪���̕t�߂ŗ���ɍ������Ă��������͐�~�ɂ́A���{���I�ɍŏ��̒�ƋL�����u��c��v�̔肪�c���Ă���B���Ƃ��Ƃ��̕t�߂͒Ꮌ�n�Ŕ×����J��Ԃ��Ă�������ł��Q����͓V��͐�ł��顋}���ȓs�s���Ŕ_�n��R�сA���ߒr���������A�ې��E�����\�͂��ቺ�����B���̂��ߕ��i�͌��������A��J�Ŕ×�����Ɛ������܂�d�g�݂ƂȂ��Ă���V���n���݂����Ă��顂��ꂪ�u�ŏ�쎡���Βn�v��� |
|
|
���`��E�O�@�̐����ƕx�m�{�E��Ԑ_�ЁE�N�ʒr
���c�}���`��w���������5�����炢�̏Z��X�̒��Ɂu�O�@�̐����v�����額��X�ƗN�o���鐅�͗₽����^�I���ŐZ���āA�^�Ă̊���@���ƃq�������Ƃ��ċC�����������B�K���l�͌������Ȃ��������A������Ɛ������ꂽ������݂�ƁA�Z���ɂ���đ�Ɏ���Ă��邱�Ƃ��킩�� �O��ɍ~�����J��������㗬�Œn���ɐZ�����āA�`��~�n�n���ɗ��܂��������u�O�@�̐����v�̂ق��Ɏs���Ŏ������Ă���B�����܂Ƃ߂Ė����S�I�Ɏw�肳��Ă���B �x�m�R����_�̂Ƃ����Ԑ_�Ђɂ́A���̓��ʓV�R�L�O���Ɏw�肳��Ă���N�ʒr������B �x�m�R�̐���������n��ɐZ�����A�_���R�̎R������N�o���������A���_�A���_���J�鐅���_�Ђ̉����瓱������A�����ȓ����������������r�ƂȂ��Ă���B3�D6����/�b�A����13���Ƃ���A���͂��Ȃ蓧���x�������B�J���Ȃǂ̐������X�C�X�C�Ɨ���ƋY��Ă��題×�����x�m���҂͂��̐����Ȓr�Ő��߂Ă���x�m�R�Ɍ��������Ƃ������Ƃ��B ���̒r�̐��͋�������o��Ɛ_�c��(�ꋉ�͐�)�Ƃ��ĕx�m�{�s���𗬂��B�앝3���قǂ������̐������������B�����_�Ђ���N�o���Ă���ʂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ���Ƃ������Ƃ͒r��ȂǗN�ʒr�S�̂���N�o���Ă���Ƃ������Ƃ��낤�B�x�m�R�������炷���̖L�����������Ă���悤��� |
|
| �@ | |
|
���O�@�̒r�Ǝ���
�k���S���ߗ��w����o�X�ɏ��A�������̃o�X��ō~��Ă����A�O�@�̒r������B�Z���тɓ����p�ɁA���a70�����قǂ̊��̂悤�Ȋۂ������琅�����X�ƗN���o���Ă��顕ʖ����������Ƃ�������R��������2�����炸�A���30�g���قǂ̗N�������邻��������̒ꂩ��|���v�A�b�v����A�����琅�����߂�悤�ɂȂ��Ă���B�ߏ��̐l����y�ɂ��������������݂����Ă����B ��O�@��t������̐[���J��萅���^�ԋ�������݁A�����M���̒����œ˂��N���𑣂��ꂽ��ƈē��ɂ��顑�́A���̕ӂ�͋߂��𗬂�����̐쏰�ŁA�������Ă������I�Œꂪ����āA���̂悤���M��(�|�b�g�z�[��)�����R�Ɍ`�����ꂽ������������N���o���d�g�݂͏ڂ����͉𖾂���Ă��Ȃ��B�S�����鏊�ɂ��̂悤�ȍO�@��t�ɂ܂��`�����c���Ă��钆�A���}���������Ă����B�T��ɂ͍O�@��t��������A�₦��������Ă���悤���B �������班���㗬�͎���k�J�Ƃ����A�����ɐ藧�����f�R��ǂ��A�����Ă���B���̒f�R���琅���H�藎����ꂪ����������B���̒��ōő�Ȃ̂��A����32���̖ȃ���ł��顁u�Ȃ����ĕ�������邳�܁v���疼�t����ꂽ�悤�ɁA�x�n�삩�����̒f�R���A�����Ԃ����グ�Ȃ��痎���Ă����B��ʂ͖��̂悤�ɂ�����ł����B ���2702���̔��R�𐅌��Ƃ���̂́A���䌧�𗬂��㓪���줕x�R���𗬂�鏯��A�����Đΐ쌧�𗬂����삾�����͉��ꕽ��������̂Ɠ����ɤ�L�x�Ȑ��Ƌ}���𗘗p���Č�����̐��͔��d�ʂ��ւ��Ă���B �n�������L�x�ȉ����̔��쒬�ɂ́A�u�����͂̐��v�Ƃ����閼��������B����͌l�̊ω��M�ő���ꂽ���̂�����~�̌��֑O�ɂ͢��[��Ə����ꂽ�傫�ț�����A�������K�����顂����Ēn����������ŁA�|�����琅���`�����`�����Ɛ₦�邱�ƂȂ�����o���Ă��顁u���͖��Ȃ�A���͐��Ȃ�v�ƊŔ�����悤�ɁA���̐l�̐M�̐[�����`����Ă��� |
|
|
����������n�N���Q
�k�A���v�X�𐅌��Ƃ��鍕����́A���y��ʏȏ��ǂ̑S���ꋉ�͐�̐��������ł͏�Ƀg�b�v�N���X�̐�����������āA�S��86�����̓��{�L���̋}���͐�ŁA�^���̂��тɐ���ω����Ȃ��牺���ɐ��n���`�����Ă�����]�ˎ���ɂ́u�����l�\�����v�Ƃ�����قǂ̖\��삾��������̔��ʁA�������Œn���ɂ��ݍ��������͍��I�w�ł�߂���A�����̐��n�ɖL���Ȑ��̌b�݂������炵���B�����ł͂��̈�т𖼐��S�I�ɔF�肵�Ă��顂��̑�\�Ƃ����u�����v���߂������B ���P�w�����{�C�߂����ĕ�������40���A���̓V�R�L�O���ɂ��w�肳��Ă���u����̑�X�M�v�ɒ���������a44�N�ɂ�45�������������A�ޏꐮ���Ő��c�ɕς���āA�c����2�D7���������R���ۑS�n��Ƃ��āA�V�R�̑�X�M������Ă��� �Œ���̐����ƊǗ��Ƃ������ƂŁA�ؓ����݂����Ă��顂�����͔��Â���������ɂ͂т�����Ƒۂނ��āA�V�_���ɖ��Ă��顂��̒��ɗN�����N���o���Ă��顉��x�v�ő����Ă݂�ƁA����14���A�C��21���Ŏ��ӂ�肩�Ȃ��������u���n�⊣���n�ɂ͈炿�ɂ����A�엀�Ȏ���C�̂���y�n�ɂ悭��X�M���A���̂悤�ȑ�n�Ɉ�̂́A��ɐ�������Ă���A���̐��ɂ���Ď_�f����������邩�炾�ƍl�����Ă���v�ƃp���t���b�g�ɂ��顖L���ȗN�������̑�X�M����ĂĂ����̂�� ���n���̂߂����ĕ����Ă����r���̌��������ŁA�����̎������������������P�������n��̎�����́A�n��36������n�\3�����������Ă��邻���ŁA���̐��̖L���������������額�������n�N�������ɂ͌Ñ�M���V���̐_�a���̃��j�������g�����顎ԂŒʂ������łɐ��̌b�݂��Ă����l����������� ��������z���Ă��炭����ƁA�u�x�R�p����Ԕ����������钬�v�Ƃ������n��������̒����ɖ��Ƃ̉��~���ɂ������J�̂��܂߂āA18�����̐��������顂��̑����̓X�e�����X���̑��Ő�������A�n��Z�������Ő��|���������Đ���������Ă��顑��ɂ̓X�C�J��y�b�g�{�g���Ȃǂ���₳��Ă������������ł����l����������������āA�q�������̗V�я�ɂ��Ȃ��Ă��� ��O�@�̐�����ƌĂ��̂��O�����������āA���t�l�ւ̐M�����������顃p���t���b�g�ɂ͢�����������Ȃ̂Ɉꃖ���Ƃ��ē����������܂���Ƃ��������A�c�O�Ȃ���A���ɂ͂킩��Ȃ������B�܂��܂��u�����߂���v�s�����낤���B�ł����͂����ς�Ƃ��Ă���� �����ĕs�v�c�Ȃ��ƂɁA�����͊C�݂Ɣ��Ε����ɗ���Ă���B�N���̂��ꂢ�Ȑ��ɂ������܂Ȃ��g�~��������w�ː�ɗ��ꍞ��ł���̂��B���Ă͂��̐�ꂩ����L�x�ȗN����������������� �����s�ɂ͂��̂悤�Ȏ�����600�����邻��������̑����͒n��30���قǂ̔툳���w�̒n�����A�ƒ�̈�˂͂����������R���𐅌��ɂ��Ă���Ƃ�������̈�˂̐��ʂ��ቺ����Ƃ������Ԃ��N�������B1994�N2��28���A������㗬�̏o�����_���ɗ��܂����y���������I�ɗ��������ʁA������͌����݂������w�h���Ŗ��܂���������Đ��ɗ��܂����w�h�����I�w��ڋl�܂肳���āA�����������������߂ƍl�����Ă��� ���{��̍����_�����͂��߂Ƃ��āA������̋}���𗘗p�����d���J���̂��߂Ɏ��X�ƃ_��������ꂽ�B���̌��ʁA�C�ւ̓y���̋���������A�C�݂͂ǂ�ǂ�Z�H����Ă���Ƃ�������a55�N�A���P���g�����̐��[20������40���̊C��ŁA���E�ŌÂƂȂ�ꖜ�N�O�̊C���(���v��)����1�����ɂ킽���Ĕ������ꂽ�B�y���̋����������Đ�����āA�Ñ�̎p���������̂�������Ȃ��B �R���狟������Ă���y����l�Ԃ̓s���Ŏ~�߂��藬�����肷�邽�тɁA���R�͑���ȉe�����A�l�Ԃ̐��������������Ă���̂���@ �@ |
|
| ������� | |
|
�������f��
��l�Z�Z�N�����璆���E���Ƃ̌��Ղ��n�܂�܂��B�ŏ��͕��ɂ̒Âōs���Ă��܂������A���̍`�͉��m�̗��ŗ���ƊC��Ƃ��ɕ�������Ă��܂��܂��B���{�͂��̍`����(���݂̍䋌�`)�Ɉڂ��čĊJ���܂����B�����f�Ղ��ĊJ����Ė��{�̑�s�������̂������̍�̍��������ł����B�ɑ�\�����E���ȏ��l�������u���v���͂��߁A�����̔g�������̂Ƃ���������A�W�A�Ƃ̌��Ղɗ����������Ă����܂����B ���̓����A��`����D�ς݂��ꂽ���ɂ́A�Ζ�̌��ɂȂ闰���A�����A�b�h�A���p�i�Ȃǂ�����܂����B�����āA�����̍��ےʉ݂ł�������������R����^��đD�ς݂��ꂽ�炵���̂ł��B�����̍��u�W�p���O�v�Ƃ����܂����A���ł͂Ȃ����_���ď��O���͓��{��ڎw���Ă����̂ł��ˁB �A���i�ɂ́A�����̌��A����A��A�Ȃǂ̒��ɍ���(�����A���q�A�j��A���̑�)���܂܂�Ă��܂����B�����͏d�v�ȗA���i�̈ꕔ�ł����B �V���N��(1430-1570)�A���̍�����A�W�A�Ɍ���������̍��������́A���ړ���A�W�A�ɏo�������̂ł͂Ȃ��A���͗���(����)�𒆌p�_�Ƃ��Č������Ă����悤�ł��B���̍��A�������瓌��A�W�A�Ɍ����ďo�`�����N���L�^���c���Ă��܂��B ����ɂ��ƁA�V����(�^�C)�Ɍ��������̂͌ܔ��ǁA�o�^�j(�}���C����)�ɏ\�ǁA�}���b�J��Z�ǁA�X�}�g���O�ǁA�W���o�Z�ǂȂǂ��̑��v�S�l��(�N��)���������瓌��A�W�A�Ƃ̌��ՂɌ������Ă��܂����B����炪�䂩�痮���A�������瓌��A�W�A�ւƉ��������Ƃ������Ƃł������ςȂ��Ƃ������Ǝv���܂��B ��܌܋�N�A�����������瓇�Ì��ɑ���ꂽ�i���i�̒��ɃV�����̒���(�^���)�\�҂��܂܂�Ă��܂����B���̍����璾�������d����Ă������Ƃ�������܂��B �@ |
|
|
���u��̌O���E�����v���v�j
��̌O���E�����͂��̂悤�ɌÂ��`�����ւ��Ă��܂��B�������A�����m�̂悤�ɁA��͎O�x�ɋy�ԑ�ɂ��炳��܂����B���ɑ����m�푈�ɂ��D���ɋA�������߁A�֘A���鎑�����قƂ�ǖ����Ȃ��Ă��܂��܂����B�����A�����O�Z�N�܌��A�O�������g��(�g�����l�܌�)�����͂��Ă��낢��Ȏ�������������Ĕ��s�����u��̌O���E�����v���v�j���c���Ă��܂��B���̉��v�j�́A�������ǂ��̎l��ڂ��g�����߂Ă����̂Ő�ЈȑO�ɑa�J���ď�����Ƃ�A���݂����̂Ƃ���ɂ���܂��B������������𗊂�ɏ��������Ă��܂��B ���̉��v�j�́u���������c�g���̏��i����O���̋N���͉��ÁA���ÓV�c�O�N�l���A�����W�H���ɕY��������𓇐l�̎��Č��������c�c�v�Ŏn�܂钆�ɁA�u����A���T�N�ԂɎ����Ă͓��R���Ɖ@���߂č����̖@���𗧂Ă��A������疗y���A�������Ɋ��\����B���Ɏ����ł́A�u��O�Y�E�q��ёv���A�����D�ݎu�여�Ƃ����鍁�����N�����čL�����Ԃɓ`����ꂵ�ȗ��A��h�ɍs��ꂽ��B�����̎��v�ɑ��ẮA�䂪��s�͉��Â��A����A����A�C�v�����ߊO���̖f�ՑD�A�c�Â��t����ɂ��A�����A�����y�э��ށA�G�݂͓����≮�ɉ����āc�����v�Ƃ���܂��B �܂��A�u���\�A�V���̍��A�����̕���̉B�m�A�s���ɏZ�݂����ɂ��V�l�A��ɍ����������A���p�ō�@�E���Ȃǂ̖��m���l�o�Ă�荁�̔�����c���̏��l�ɓ`�����A��X�̍��o�����߂�ꂽ��v�Ƃ�����܂��B���̉��O�ԏє��Ƃ����l�́A�����E�����݂̎O�����u�Ɋ�i�����ɐ������Ă������㐏��̘A�̎t�ł��B�����l�������l�ɍ��̂��Ƃ������Ă����̂ł��ˁB ����ɁA�u�V�ꑼ�A�n���ɂ��炴�肵���̂��c�Â̖��Y�Ƃ��ĊC���ɓ`�d����Ɏ���A�������Ə̂����ނ���ɏ����ґ��p���ŋN����v�Ƒ����܂��B�����Łu�������v�Ƃ������̂��o�Ă��܂����B����ȑO�͓����≮�ō��ނ������Ă����̂ł����A�������͂��߂Ƃ��鍁���E�O������ɏ������l���V���N�ԏ����O����o�Ă��܂��B���ꂪ�u�������v�ł��B���̌�A���ނ͍�`���璷��Ɉڂ��Ă������ƂɂȂ�܂��B ����ɂ��Ắu�����ׂȂ���̂ɂ��f�Ղ̏����͓Ƃ��c�s��̏��l�ɂ��肵���̂ɈˑR�Ƃ��Ē����A���ނ͒������Ə̂��鏤�l����ɒy���Ď��������ɗ�����B��X�̍����A���͌��i��S���ɔ���J�������v�Ƃ���悤�ɁA���̌㒷��ɑD������悤�ɂȂ��Ă��A���ނ͍�̒��������Ɛ肵�Ă������Ƃ�������܂��B �����̗l�q���`���ꂽ����������܂��B�ŏ��͓����ŗʂ蔄������Ă��܂����B �y�������u���k�|���Ɛ��v���z ������͔[���O�Ƃ����鍋���ɂ�錭���f�Ջy�ѓ�ؖf�Ղŋ���Ȍo�ϗ͂������Ă��܂����B�܂��痘�x�̂�ђ����n�߁A���s������O�𐼎������n�߁A�L�������l�������������Ĉ�࣍��ȕ����̉Ԃ��J���܂����B�Ƃ��������Ƃ������̂͌o�ϗ͂�����悤�ł��ˁB ���̓�������I�ɍs���A�����̉���p�ɂɍs���Ă������Ƃł��傤�B���̎��ӂ�����Ƃق̂��ȉ����A�����̍����Y���A���������������ɂ����~�ɏo���肵�ĖZ�������������A�e��O�������鍁�����������ɕY���Ă������낤�Ǝv���܂��B�u���̓��v�ɂ��Ă��u�����v�ɂ��Ă������͋q���}���邽�߂́u�����ĂȂ��̐S�v�ł������ƁA��s�����ٌ��ْ��̐搶�͂���������Ă����܂��B �@ |
|
|
���O�������X
������ɂ��Ắu�V���N�ԁA��h�����哹��폤�A������\�Y�@���Ƃ����l�A���������̖@��`�K��������B��ɂĐ������Ȃ�������䂪���ɂĐ��������̏��߂Ƃ��v�ƁA���v�j�ɋL����Ă��܂��B���̕����ł͍䂪�������˂̒n�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A�ؖ����o���Ă���킯�ł͂���܂���B���A������ɂ��Ă���̐����͒������j�������A���݂܂ő����Ă���̂͊ԈႢ����܂���B ���̗�������ނƂ���鉮�����������u�O�������X�v���A��O�܂ł͏\��`�\�O������܂����B�Ⴆ�A����(�����������q)�A���a(�������a�O�Y)�A���m(�������m��)�A����(�������v���Y)�A����(��������ܘY)�A�ȂǂȂǂł��B���݂͎c�O�Ȃ���ɂȂ��Ă��܂��܂����B���̂����̈ꌬ���A���ǂ����p���u�������v���Y�v�ł��B �����̐����̍����́A�c�{�̒��ɐ����̗��������̂��l�߁A���Ԃ̉��p�Ŗ���߂Ă����Ɛ����������o����Ă����߂��ɏo�Ă��܂��B�����ɂƂ��Ē����߂���Ƃ������̂ł����B���̐��@�͖������̋@�B�ɂȂ閾���̒����܂ōs���Ă��܂����B �y�����˂��u�a�����Ɛ}���v(�a��������)���)�z ���ǂ��̂Ƃ���Ō��݂��g���Ă���u�������v������܂��B����́A�]�˖��������l��ɂ킽���ď����ꂽ���̂ł��B�悭���Ǝ҂̕��ɒ������ȂNJȒP�Ɍ����Ă͂����Ȃ��Ƃ����܂����A���͌��Ă�������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�������ɂ́���~�Ȃǂ�����ł��܂����A����́u�v�Ƃ����L���ł��B�̂̍����E���C���̖��݂�Ȏg���Ă��܂����B�ʐ^�̍��[�Ɂu���A���A�v�Ə�����Ă��܂����A����͐�����\���Ă��܂��B�Ⴆ�A���鐻���Ђł́u�A�L�i�C���K���o�����v���u�A�͈�A�L�͓�A�i�͎O�c�c�v�Ƃ������ɂȂ��Ă���̂ł��B���������Ɠ��̏\�i�K�������Ă��܂��B�u���A���A�v���A������\���Ă��Ă��̐����𑫂��Ȃ���Β������ł��܂���B�킩��Ȃ��ł��傤?�@�Â��������͂��̂悤�ɋL���ɂȂ��Ă��܂�����A�ǂ�ȂɌ����Ă����v�Ȃ̂ł��B ���̂悤�ɁA���݂̍�̐����̗͐̂������������������A���̒����@�����p���Ă���̂œ����̍���Ƌ߂����̂Ɏd�オ���Ă�����̂�����܂��B ���v�j�̍Ō�́u�䂪���ɎY���钆�ɂ��ł����i�Ƃ��ďܗg����ꍡ���A������̏̂���Ȃ�v�Œ��߂������Ă��܂��B��N�u�������v���o�����悤�ł��B �@ |
|
|
�������Ɏc�鍁��̈�b
�V���N�ԏ���(��ܔ��Z�N��)�ɂ͊��Ɂu�������v���Ԃ��������悤�ŁA���۔N��(�ꎵ��Z�N��)�̑g�������ł́A�u���g�D�͋��ۏ\�ܔN�A���s���J�M�Z��̎��A�������͌O���̎�舵�����ƂƂ���҂��\�Z���A��������Z���������Ė��ʂɑg�D���āA���̊ӎD���Ė��N����Ή�������[���A�X�ɔN���ɂ͎�̂��������[���邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă����v�Ƃ���܂��B ������Ƃ����̂͊ӎD���Ƃ邽�߂̐ŋ��̂悤�ȑ��̉��ł��낤�Ǝv���܂��B�������Đ����E��������ʂɐZ�����Ă����܂��B�������A�����Ȃǂ͍����Ȃ��̂ł܂��܂���ʂɂ͓���̓I�̂悤�Ȃ��̂ł����B ���̍�(���۔N��)�́w�̐̕���x�Ɂu�������˂Α�g�͐\���ɋy�����g���Ȃ��v�A�܂��䌴���߂́w�D�F���j�x(���\�N��)�ɂ́u�������ɂ��܂������̂āA���F��������ɂƂǂ߁A�ނ�̂₵�܂Ə����t�������藧������|�������ɂ݂��߁v�Ə�����Ă��܂��B ����(1644-47)���́w���ĕ���x�Ɂu������߂ł����䐢�̂Ƃ����ɁA����̓��Ƃ�\���ׂ��A�����̓��Ƃ�قߐ\����v�ƁA�u���v���u�m�v�ɂ����Đl�ς̓��������ɗႦ����A����Z�N(1678)�ɂ́u�������@���̂₠��@�����̏t�v(�I��)�Ɖ̂�ꂽ�肵�Ă��܂��B �u�����v�Ɋ֘A�����\�������낢�날��܂��B �u�����ŔA�ъG�̒j�v�Ƃ����ƁA����͗ǂ��j�̂��Ƃ������܂����B�u�����ŔA�ъG�̏��v�A�܂�ǂ����Ƃ������Ƃł��B�u�����̉��ʁv�͏㓙�̉��ʁB�u�������v�͑f���炵�����B�u���������l�v�͎��Y�ƁB�u�������Ă��s�����͋�����g���s�����Ȃ�v�͍��Y���g���ʂ����Ƃ������Ƃł��B �g��������̉Ԗ��E�ł́u�j�ɋ��₭���Ƃ́A�������ɂ����Ȃ��\���������v�Ƃ������ƂŁu��������������v�Ƃ������Ɍ����܂����B�u���Ȓj�Ȃ������o���A����ʼn������v�ƌ������Ƃ������Ƃł��B�{���̉�����n���Ă��܂��Ɓu�����Ȑl�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B �u�����̍���Ƃ��̌N���܂͊��x�Ƃ߂Ă��܂��ƂߖO���ʁv�ȂǂƂ����̂����S�Ƃ��Ďc���Ă��܂��B ���̍��́A�����A�������͂��Ȃ�g�p����Ă����悤�ł����A���Ȃ荂���ŒN�ł��������₷���������Ƃ͂ł��܂���ł����B�������̉Ԃł��������Ƃ���A�Ԗ��E�𒆐S�Ƃ��ē����b�ɏo�Ă�����A�֘A����̂����s�����ƍl�����Ă��܂��B �@ |
|
|
���������E�������̋ƊE�g�D
�b��{�ɖ߂��܂����A�̂̉c�Ɛl��(�X�ܐ�)���������̂�����܂��B�V���N�Ԃ��牄���N�Ԃ܂ł͕s���ł����A�����N�Ԃ���͕������Ă��܂��B����͒������E���������킹�Ăł����A��������c��܂łقڐ������ς��܂���B����͊��g�D�Ƃ��Ă�����Ƃ��Ă�������ł��B�����O�ܔN�́A��قǂ��b��������O�������g���̉��v�j�����s���ꂽ�N�ł��B �V���N�Ԃ���c��N�Ԃɂ����āA���l�����͊e�X�̋ƊE�g�D(�����ԑg�D)�ɑ����Ă���̂ŁA�f�l������ɋƊE�ɓ��邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�ƊE�̒��Ԑ��͉��l�A�Ƃقڌ��߂��Ă����悤�ŁA��p�҂����Ȃ����߂ɔp�Ƃ���ꍇ�̂݊����̂ŁA��������n���Ă��炤�Ƃ����ꍇ�����ƊE�Q�����ł��܂����B �ƊE�ɎQ�����鎞�̈�b���c���Ă��܂��B�g���N�s��(�g����)�ƂƂ��ɑ��N�����(���N��Ƃ͍�s�ɂ����铖���̖唴��(���Y��)�ŁA��������̋撷�̂悤�Ȃ���)�ɏo�����A���N��̈��������č��s���֏o�����ĊӎD�����炢�܂��B����ɂ͑����ȋ��i���������悤�ł��B����ɂ��̌�A�ƊE�g�����ɔ�I���Ȃ���Ȃ炸�A���ȉ�����J�����悤�ł��B �����E�O���̏��i���i�ɂ��Ă̋L�^���c���Ă��܂��B ���������˂��Ă��邱�Ƃ��������\���P�ʂɂ́A�u�v���g���Ă��܂��B�����̉��i�͋�̉��i�ł������A�e����̋�̉��i���҂Ɋ��Z���āA�����O�Z�N��̉~�Ɋ��Z���č���Ă��܂��B �����N�Ԃ����Ă݂܂��傤�B��������,���,�Z�Z�Z�c����Ď���,�Z��Z�~�A�O���͓�O,�܌܁Z�҂ʼn��i�͈�Z�l,���܁Z�~�Ƃ������ƂŁA�O���������Ȃ��̂ł��������Ƃ�������܂��B�������A���i����c��ɌO�����ڗ����Č����Ă��܂��B����́A���������ނ��Ă��č���ɑ���S�����ɗ����Ă��邱�Ƃ�\���Ă��܂��B����A�����͏��X�ɐL�тĂ��Ă��܂��B �����̋��ꗼ�̑���������Ƃ��Ďc���Ă��܂��B�⊷�Z�ňꗼ���ܔ���ł����B���̑���͂ǂ�ǂ�ς���Ă��Čc��ɂ͋��܁Z��ł���Ƌ��ꗼ�Ɋ�����ꂽ�̂ł��B�������N�ɂ͋����Z�捷���o���Ȃ��Ƌ��ꗼ����ɓ���Ȃ������̂ł��B���̉��l���オ���Ă���̂������鎑���ɂȂ��Ă��܂��B ���̑��A���̑g�����쐬�����������ɂ͂������낢���ڂ��o�Ă��܂��B�u��s�ݗ��ȑO�A���{��̕��@�v�Ƃ������̂ŁA�������ǂ�����Ď�邩�Ƃ������e�ł��B ��s���ł���O�́u���֏��v�Ƃ������̂������āA�����̋�s�Ƃ����卷�͂Ȃ��Ə�����Ă��܂��B���łɁu��`�v�����ʂ��Ă��āA���̏��������ꂽ�����̍��Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ��قǁA�̂͏��l�Ԃ̐M�p�͏d�������Ƃ������Ƃł��B�ꎞ���������p�ȏꍇ�͎���̂��闼�֏��֍s���ƁA���S�ۂŘZ�������炢�͎������o���Ă���܂����B���̏ꍇ�A��`�̈���𗼑֏��ɂ���Ƃ���܂��B���ꖇ�ł�����݂��Ă��ꂽ�Ƃ������Ƃł��B ���̍��́u�g�������v�ɂ��Ă̋L�q������܂��B ���t�́A�\��ˈȏォ��\�N�̔N������Ƃ��Ă��̕��Z�ƌ_�܂��B���̏ꍇ�A�ۏؐl�������ĕۏ؏������܂��B���t�A��`�A�ԓ��Ə����ʂ͏オ��A�\�܍˂܂ł͑����ł��B�\�Z�˂̏t�ɂ͑O�̐���������荞�݁A���l�O�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�\���˂ɂȂ�ƑO�����藎�Ƃ��܂��B������u�����v�Ƃ����āA��l�O�ɂȂ������Ƃ�\���܂��B�����ĉH�D���p��������܂����B�܂��A�i���͂ǂ̏��Ƃł��֎~���Ă��܂��B���Ԃ���������Ƃ������Ƃ��Ĉ�N�`��N�͋߂邱�ƂɂȂ�܂��B ���̌�A���p�i�A������ʂ�V�����A��˂��\�������A�������o���ēƗ������܂��B������u�v�Ƃ����A��ƂƓ���̉�����t�������܂��B���ꂪ�u�g�������v�ł��B �i�N�ߏグ�A�ʉƂ��������Ă��炤���Ƃ͖��_�Ȃ��Ƃł���A�܂���Ƃɂ����Ă��ʉƂ������邱�Ƃ́A�h�_�Ȃ��ƂƂ��Ċ�Ƃ���܂��B�����̌܁A�Z�N������A���̂悤�Ȕ������Ȃ��Ȃ��Ď₵������ł���A�ƋL����Ă��܂��B �@ |
|
|
���吳����ȍ~�̋ƊE�ƐV���ȍ��蕶���ւ̒���
�₪�āA�吳�A���a�ɓ���������͘Z�܌��ɑ����A������̖����͑S���ɍL�܂��Ă����܂��B �������A�������̑命���͍�s���̋������ʼnc�Ƃ��Ă������߁A�����m�푈�Ő�Ђɑ����A���ׂĂ��D���ɋA���܂����B�Ăї����オ�������Ǝ҂����ς��鎞��̔g�ɂ̂܂�A������f�O�����҂��������A�ꌬ�܂��ꌬ�Ƃ��̉͏����Ă����܂����B���݂͂͂Ȃ͂��c�O�Ȃ���A�c�Ƃ��Ă���̂͏\��ЂɌ������Ă��܂��܂����B �������Ȃ���A�������A�A�ȂƑ����������̗��j���p�����ׂ��A�Ⴂ��p�ҒB�͗����オ��A�Ⴂ�����ł��́u���v�ɒ��킷��p�����Đ��ɗ�������������A�������v���Ă��܂��B �@ �@ |
|
| ���䂪���Ɓu���v�̏o��Ɓu�����v�ɂ��� | |
|
�䂪���Ɓu���v�Ƃ̏o��Ƃ����̂́A�����̂��Ƃł��傤���B�c����Ă��鎑���̒��ł́u�������q�`���v(593-621)�̒��ŁA���ÓV�c�O(�܋��)�N�̕����ɋL�q����Ă��܂��B���̂܂܌��{�𗬗p���܂��ƁA�u�y���̍��̓�̊C�ɑ傢�Ȃ������B�܂��������Ă̔@���B�O�\�����o�ĉĎl���W�H���̓�݂̊ɒ����B���l�w�����x��m�炸�A�d�Ɍ����Ă��܂ǂɏĂ��B���q�A�g�����o���Ă��̖��������ށB�傫����́A�������ڂȂ�B���̍��C�O���鎖�͂Ȃ͂����B���q���đ傢�Ɋ�сA�t���Č����B�w���꒾�����ƂȂ����̂Ȃ�B���̖���~�h���тƂ����B�x�v�Ƃ���܂��B���������w�̐������q�ł��ˁB
���̓V�c�͐��ÓV�c�ŁA���̂��Ƃ͓��{���I�ɂ��u�����W�H���ɕY���A���̑傫����́B���l�A������m�炸���Đd�Ɍ��킵�Ă��܂ǂɏĂ��B���̂�C�����O��B�����قȂ�Ƃ��ĔV��������v�ƋL����Ă��܂��B ���̌�A���̍��͕S�ς̂ɒ������āA�������ڂ̊ω���F������ŋg��̂Ɉ��u����܂���(�u�v)�B���̍��̑�a����́A��Q�[�ɏP���ĂƂĂ��[���ȏ�Ԃ������悤�ł����A�������u�����Ƃ��뎵�����ӈ�����N���A�J����������~���Ă��đ�Q�[�͋~��ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B�@ |
|
|
���u�����ҁv�ɂ���
�����́A���x�⎼�x�Ȃǔ����ȃo�����X�̏�ł������炵�Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B���낢��Ȗ�����܂����A�������ł���悤�Ȗ͂����͂��������݂����A���S�{�Ɉ�{�Ƃ����m���ł��������ł��܂���B����A�W�A�Ȃǂɂ́A���̔�������������E�������̎�ł���\�͂������������܂��B�ނ�͒����̂ł��Ă����������Ɠ�����g���Ď����������č̎悵�܂��B���l����Ă͂����Ȃ��̂œ��R�̂��ƂƂ����܂����A�����ɓ`��钾���̍̎���@�͌��d�Ɏ���A�ނ�ȊO�ɂ͕�����Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����̂���������ēy���ɖ��܂��ĕ����Ă����������������͂��̂܂c��܂��B���̕����͗₽���A�w�r���Ƃ���������ĕ����Ă���̂ł����ړ��Ăɍ̎悷��Ƃ������@���s���Ă����悤�ł��B ���A���I�X�A�x�g�i���A�C���h�l�V�A���Œ��������o���̕c��A�т��Ă��܂��B�L��ȎR�ɉ��\���{�Ƃ�������ĂĂ��܂��B�\�N���炢��Ă��ɏ����Ȍ����J���ăo�N�e���A�B�����A���Z�`�O�Z�N�����Đ��炳����̂ł����Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ������ł��B ���͍�N�A���I�X�̂��鐭�{��������A�x�g�i���Ƃ̍����ɋ߂����R����㗬�̂��镔���ɏЉ�Ă��炢�A���n�̖��т̒��ɓ���܂����B���n�͍��������ŎO�Z��������Ɠ����N���N�����đ̗͂͒��������Ղ��܂��B�q�����ǂ������������̂�����G�܂ŐH�炢���Ă��܂����B�܂��A��Ɏh�����ƃf���O�M�ɂȂ�A���h�����Ɛ����͂Ȃ��Ȃ�炵���̂ł��B����������x�̊o��͂��Ă��܂������A�����͑z����₷��Ƃ���ł����B�������̎��ɏ\�N���̖̂��̎悵�Ă���Ƃ̎v���Ń��I�X���玝���A��܂������A�ڂ�ڂ�̖œ������Ȃɂ����܂���B�����Ƃ͑S���Ⴂ�܂��B���݂ł͒��������O�֏o�����Ƃ͌������K������Ă��܂����A����͓��ʂȌv�炢�ɂ���Ď����o�����Ƃ��ł��܂����B�����������Ƃ��牾���A�����Ƃ������͍̂����Ȃ̂�������O�ŁA�̂̂悤�ɕi���̗ǂ������͂قƂ�ǎ�ɓ���Ȃ��Ȃ��Ă���̂�����ł��B �@ |
|
|
�����厛���q�@�̕u�v
�䂪���Ɍ������鋐��ȉ����Ƃ��ẮA���q�@�ɂ���u�����ҁv������܂��B�ƂĂ��M�d�Ȃ��̂ł����A���������ƂɈꕔ�ɐ���ꂽ����������܂��B����́A�܂������`��������A���͐D�c�M���A�����Ď��ɖ����V�c���ޗǍs�K�̐܂�Ɉꕔ�����Ƃ�ꂽ�Ɓu���q�@�䕨�I�ʖژ^�v�ɋL�ڂ���Ă��܂��B���́u�����ҁv�́A��ʂɂ͉������Ƃ����Ă��܂����{���̂Ƃ���͂ǂ��ł��傤���B �u���q�@�v�̕��ɂ́u�����̒������m���߂邱�Ƃ͑�ϓ���A���������ł͕�����Ȃ��B�g�D�\���ׂĔ�r���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�������̓I�m�ȍޗ����Ȃ��̂Ő��m�Ȕ���͉����ɂ����B���������Ƃ���ł͎����̒������\���Ƃ͌����Ȃ��B�����炭����͂��ł͂Ȃ����H�v�ƕ���Ă��܂��B���n�����V���������őf���炵�����̂ł͂��邪�A�����鉾���Ƃ����Ă�����̂Ƃ͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł��B �����A�O���u����́u��B�ٕ��j�v(�O���I�O��)�Ɂu�����̓x�g�i���ɎY����B�����̎悵�悤�Ƃ��錴�Z���͎R���ō��ƂȂ���|���Đ��N���̂܂܂ɂ��Ă����B�啔���͋����Ă��܂����A�����̕����͎c���Ă���B����𐅒��ɓ����ƒ��ނ��璾���Ƃ����A���܂Ȃ������V���Ƃ����B�v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B��قǂ́u�����ҁv�͐��ɓ���Ē��߂Β���(����)�A���ɕ����ΎV���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����A���������ȂɊȒP�ɐ��ɓ����킯�ɂ͂����܂���B����͂��ڂ�b�Ƃ��Ă��Q�l�܂łɂ��b�����܂����B�@ �@ |
|
| ���V���̍��� | |
|
���V������̍�
�V������̒����Ƃ������̂́A���̂قƂ�ǂ������`���̎��̏@���V��(�č����{�i)�ɕK�v�ȕ��Ƃ��ĉ䂪���ɓ`�����܂����B�u���{���I�v�̍����Ɋւ���L�q�Łu�V�c���N�����A�h���b����ɍ��F�����A�����ĕ��ɗ�q�������v�Ƃ����L�ڂ�����܂��B����Ɂu�V�q�V�c��Z�N�A�������A�A���̑��̍����@�����Ɍ��サ���v���X�Ƃ���A�@���V���Ɏg�p���ꂽ�̂͊m���Ȃ悤�ł��B �V������(�����I)���ɂȂ�ƁA�č����{�̏�łǂ̂悤�Ȏ�ނ̍������g���Ă����������炩�ɂȂ��Ă��܂��B ����͖@�����̍��Y�ژ^�ɋL�ڂ���Ă�����̂ł��B�u���v�Ƃ����̂͂ǂ�ȒP�ʂ������m�ł��傤��?�@�ꗼ�ڂƂ����͎̂l��(��恁�O.���܃O����)�A�܂��܃O�������炢�Ȃ̂ŁA���Ɉ�܃O�����������Ă��炦�Γ����̗ʂ�������܂��B�@ |
|
|
�������̌���
���������Ă��������������Ɏc���Ă��܂��B�E���Ɂu�v�Ƃ������̂�����܂����A����͔��ɒ��d����Ă��鍁���ł��B���̓������߂����āA�����m�ő��D�킪�s��ꂽ�قǂł��B�����ǂ�Ȃ��̂��낤�Ǝd��������Ă݂܂������A���܂�ǂ������ł͂���܂���ł����B���̍��X�ō���̍D�݂Ƃ����͈̂Ⴄ�悤�ł��B �����ŁA�������������̍��������߂ďo�Ă��܂��B�u�l���v�������ł��B�V�R�L�O���ɂȂ��Ă��钆���E�_��Ȃ��l�����̐��B��ł��B�������l�����̃I�X�̃t�F�������ŁA���X���Ăъ邽�߂̂��̂Ŗ�܁Z�L����܂œ͂��Ƃ����Ă��܂��B�����l�����������������ɂƂ��Č������Ȃ����̂ł����A���V���g�����ŕی삳��Ă��ĂȂ��Ȃ���ɓ���邱�Ƃ��ł��܂���B �����́A�V������ɂ͂��낢��ȕ����̏@���V���Ŏg���Ă��܂����B���t�W�ɁA�u�ɂ悵�@�ޗǂ̓s�͍炭�Ԃ́@�������@���@��������Ȃ�v�Ƃ����̂�����܂��B�u�������@���v�Ƃ����̂Œ����̓������낤�Ǝv���邩������܂��A�����ł͂���܂���B����͓V������ɑ厛�@�̐��F�A�ɍʐF�̓���剾���A�܂����ٍ̈�����ӂ�鉹�y�Ɏ����X���A�ٕ����i���Ă����l��\���������̂ł��B���̍��ɂ͂܂�����͕����̂��̂ŁA�������g�̂��߂Ɋy���ނƂ������l�ς͖��������Ǝv���܂��B ���ꂪ���̎���A��������̏����ɂȂ�ƁA�����ς���Ă��܂��B���������̍���Ƃ��Ē������ꂽ������y���ނ悤�ɂȂ��Ă����܂����A�����������F�ł܂����{�l�Ƃ��Ă̍���ł͂���܂���ł����B ����������Ă������̂Ƃ��āA(������)�A���э��A�A���F�A�����Ȃǂ�����܂����B�@ |
|
|
������������Ă���������y���ޕi�X
�A�����ꂽ���̒��Ɂu�����v�Ƃ������̂�����܂��B����͍��F�̈��ŁA���q�@�Ɂu��O�F�v�Ƃ������̂�����܂��B�y���V�����̓��������肪����A�ٍ����������ł��B���`�����Ă��āA�ǂ�Ȃɓ]�����Ă��ǂ�Ȋp�x�ɂȂ��Ă����̍��F�͐�����ۂ悤�ɂł��Ă��܂��B���ō��F���Ă����������ڂ�Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���̂ł��B ���̍����́A�W�̊����Ƃ����l�́u�����G�L�v�ɋL����Ă��āA���������͖̂[���Ƃ����l�̂悤�ł��B�����̂Ƃ����r�̗��E�l���̍��F������Ă��܂����B �g�����ɂ��ẮA���̎���̎��̒��ɁA�u�̂Ƃ�����낵�A�����̓�l�������ƁA�����������ƖD���̂��Ă�������O����v�Ə�����Ă��܂��B���̊Ô��ȓ����ł����Ƃ肵����l��������ނ悤�ȍ��肾���������ł����A���ꂪ����̍����Ƃ������̂ł��B �܂��A��v�́u�V�����L�v�ɓV�q�̐e�ʂ̐l�������{��ɍs���l�q���o�Ă��܂��B�w���q����鋍�Ԃ̋��̈Ƃ⍘�ɑ傫�ȍ��������đ��点����A���ɕt�����������J�c���ɍ�������ꂽ�肵�܂����B���Ԃ����苎��ƍ��̉����_�̂悤�ɂ��Ȃт��đf���炵�����肪�����Ƃ������Ƃł��B�܂��M���q����n���y���ގ����A�������Ƃɕt���đf���炵�������Y�킹���Ƃ���܂��B���̂悤�ɁA���`�̍��F�͏�n�ȂǍ��ɒ݂����ƁA����(聖[)�ŗp���镨�̓��ނ��������悤�ł��B �u���э��v�́A�厖�Ȉߕ��⏑���A�o����ۑ�����h���ړI�Ŏg���܂����B�����ɁA���̍��C���o�����߂ɂ��g�p���ꂽ�Ǝv���܂��B���q�@�ɂ͋��݂��������Ă���A��݂̉����ɂ͓�(���Z��)�N�l����Z���ƋL����Ă��܂��B�����Ȏl�p�̌��̒��ɁA�����A���h�A���q�ȂǁA���̑��Z�퍁�����������̂������Ă��܂��B���ɔ��h�ƒ��q�͍��C�ƂƂ��ɖh���A�h�����ʂ������̂ŁA���̖ړI���ʂ����܂����B�u���э��v�͓����A������A������Ă������A���{�ł����悤�ɂȂ�A��������()�ł́A�u�E�т₩�Ɂ@���т̍��@���ƂȂ����イ����o��v�Ƃ���悤�ɁA�����̕����M���̒��ł͑嗬�s���Ă��܂����B �L�̒��Ɋۖ��̂��̂������Ă��܂����A���ꂪ�u�����v�ł��B�����ł͌ܐ��I��ɍ����̔z������������u�a�����v�Ƃ������̐�发������܂����B�@�̎���ɂ́u�G�����v�Ƃ�����发���������悤�ŁA���̒��ɂ��܂��܂ȍ������ɂ��Ė��A���܂Â�(�Ê��F�Ö����̂ЂƂ�)�������Ċۖ��ɂ��ĒY�ŕ������Ƃ����L�ڂ�����܂��B���ꂪ�����O���ƌ����镨�ł��B�́u�������v�ɂ́u�O���͕��A���A���O�̒��A�h�Ɏn�܂�āu�����v��营���܂Ȃт�����v�Ƃ������ƂŁA����������琻�@���w�悤�ł��B����́A�����A���h�A���q�A�O���A�Ȃǂ����܂Â�A�܂��͖��ŗ���A�ۖ��ɂ��ăJ���ɓ���Ė�ꃖ���y���ɖ��߂č��܂��B�������邱�Ƃł��܂��������������ėǂ������ɂł�������܂��B���ɂ͎���C���K�v�Ŋ������Ă��Ă͂��߂Ȃ̂ł��B ���́u�����v�́A�������̂Ƃ���ł��d���̍��Ԃɍ����������Ă��܂��B���������̍D���ȃG�b�Z���X�����낢�덬���č��A�Ō�Ƀc�{�ɓ���ĕۊǂ��܂��B�O�q�̂悤�Ɋ��������Ă͂����܂���B����������Ɠ��������ł��܂��̂Œʏ�̓��E�Ŗ������Ă��܂��B��قǏo�Ă����u���܂Â�v�͊��̈��ł��̏`���ϋl�߂����̂ŁA�ƂĂ��S���͂�����܂��B�����̉䂪���ł͑�\�I�ȓ����ŁA���̑���ɂ��܂Â�ő�p���Ă��܂����B ���͔��ɋM�d�ŁA�Ӑ^���킴�킴���{�ւ̌���i�̈ꕔ�Ƃ��đD�ɐςƂ����قǂ̂��̂ł����B���ł͂ǂ��ɂł����閨�ł����A�����͖��̎Y�o�@���܂������炸�A�M�d�Ȃ��̂������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B �u���X�v�Ƃ����̂́u�����܁v�̂��Ƃł��B���q�@�ɂ͋��炭���E�ŌÂƂ����鍁�X�����������Ă��܂��B���̍��X�������̓���������Ă������̂ŁA����ɂ��Ă͗L���Ȉ�b���c���Ă��܂��B ���̎��̍c��ł��錺�@�c��́A�k�M�܂ɍ��X��܂����B���̌�u�����̗��v�ŗk�M�܂͎E����ĉ���������܂��B���@�c��͒����ɐV���ɖ������܂������A���̎��ς��ʂĂ��k�M�܂̐g�̂ɂ͗^�������X�����̂܂c���Ă��āA������������@�c��͏I���܂𗬂����Ƃ������Ƃł��B ���̂��b�ɂ͂���Ȑ�������܂��B�␢�̔����k�M�܂͎��͑����ǂş�������Ɛ��ɂ܂œ������ڂ��������ł��B������A�킫���ł��ˁB���ɓ����������̂Ō��@�c��͓��������ɂ�������Ƃ����̂ł��B�k�M�܂́A�̏L�̋������n�C����(�y���V��)�n�̍����������̂�������܂���ˁB �@ |
|
| ���M�̋N���Ɨ��j | |
|
�M�̋N���́A��ςɌÂ��l��ܕS�]�N�O�A���̒����ɉ����Ċ��ɗp�����Ă������Ƃ��A��X�̎j���ɂ��l�@����Ă��܂��B���݂̂悤�ȏb�т�p���č�����M�́A�`�̎���A�֜����R�������������̂ƌ����Ă��܂��B
���{�ɕM���`�������̂́A��a����̏����ŁA���������Ƃ̌𗬂ɂ���ėA������Ă����Ƃ����Ă��܂��B���̌㍵��V�c�̎���(���S�\��N��)�ɁA�m��C(�O�@��t)�����ɓn��M�̐��@���K������A�����A����Ԃɓ`�������̂��A�䂪���ł̕M����̎n�܂�Ɠ`�����Ă��܂��B �ޗǐ��q�@�ɂ���\���{�̓V���M�͎������M�Ə̂���A�^���⏬�K�����̕M(�ʌo�p)�ŁA���̌㕽������A���{�̉����⒲�a�̂ɓK����Ɠ��̉��ǂ��������A���{�̐��M�Z�p�͐i���𐋂��Ă������v���܂��B���̎���̕M�́A�L�c�M�A���c�M�Ƃ��Ă�A���Őc�ɂ���т̍������݁A��ɕʂ̖т�킹�鐻�@�ō]�ˎ��㖖���܂Œ��d����܂����B �]�ˎ��㖖����薾������ɂ����āA������荡�̕M(���M)�̐��@���`�����A�L���̌F��𒆐S�ɋ}���ɔ��W���Ă����܂����B�т̂܂Ƃ܂�ƒe�͂𗘓_�ɂƂ������M����A�n�܂݂悭�A�Z���Ԃō��鐅�M�ɕς���Ă������Ǝv���܂��B�����A���M�����͓̂���(���j��)�݂̂ƂȂ肻�̋Z�p�A���̕M��������ɓ`���čs�������ƍl���Ă��܂��B ���M�̌����̎�ނƓ��� 1.�r�сE�E�E�����Y�̎R�r�̖тł��B�r�т͏_�炩���A�тɔS�肪�����Ėn�܂݂��ǂ��̂������B�ϋv���͔��Q�ɗǂ��ł��B 2.�n�сE�E�E���сA���Ă��݁A�r�сA���Ȃǔn�S�g�̖т��p�����A���ʂɂ��ю����قȂ�܂��B�F���ԁE���E���ƕ�����܂��B�e�͂̂���V���͑��M�ɁA���т͏_�炩���S�肪����̂ŁA�M�̐c��������тɎg���܂��B 3.���сE�E�E�ю��͑�ϒe�͂�����A��ɕM�̍��̕����ɗp�����܂��B�܂��A�т̒����ɂȂ��Ă���A��ϖn�܂݂��ǂ��̂������B 4.�K�сE�E�E�ѐ悪�d���A��ϒe�͂ɕx�ށB��̌������ǂ��̂ŁA���ɗ͂����������Ɏg���܂��B 5.�L�сE�E�E�ѐ�ɏ_�炩���ƔS�肪����A�����M�A�ʑ��M�ɍœK�B 6.�C�^�`�сE�E�E�ёS�̂ɒe�͂����邽�߁A��Ϗd�p����Ă��܂��B ���ɂ��e�сA�R�n�сA���X�тȂǂ�����܂��B �т̎��1 �т̎��2 �т̎��3 ���M�I�т̃|�C���g �M�̎l���ƌĂ��u��v�A�u�āv�A�u�~�v�A�u���v��4�����đI�т܂��B �u��v�Ƃ́A���̕������Ƃ����Ă��邱�ƁB�����Ă��āA�܂Ƃ܂肪����̂���ŁA���ɍוM�͂��ꂪ���߂āB �u�āv�Ƃ́A���S�̂������Ă��邱�ƁB�����̌�������{�̕M�ƂȂ邽�߂Ƀo�����X�悭�z��Ă��邱�ƁB �u�~�v�Ƃ́A��S�̂��������Ƃ����~���`�ɂȂ��Ă��邱�ƁB�n����ꂽ����S�̂��ӂ����炵�āA�s�ϓ��Ȃӂ���݂�˂��ꂪ�N���Ȃ����ƁB �u���v�Ƃ́A���̍��̒e�͂��قǂ悭�A�M�^�т��X���[�Y�ł��邱�ƁB �䂪�ЂŌł߂�ꂽ�M����J���ꂽ�M�܂ł���܂����A��悩�玲�܂ł悭�䗗�ɂȂ��Č��_�̂Ȃ����̂�I�Ԃ̂���ł��B ����ȊO�ɂ��A�M�̑召(���M�E���M�E�וM)�A��̒��Z(����E�Z��)�A��̏_���A�p�r�ɂ����̌`�A�����Ȃǎ�ނ������A���̒����炨�q�l�̈ӂɂ��Ȃ����M�����I�щ������B �@ �@ |
|
| ���u�H�c�Z�S�O�\�O�ω�����L�v | |
|
����\��� �����S��X�� �����R�厜��
�Ï��ɍ��h�̊ω����Ƃ���B���ω��A�啧�t�蒷�̍�B�ނ̏��͙����@���ۂ̗�Ƃ��ӁA����蔪��ؕۘC�H�R�֎Q�w���ׂ��g�F�u�ʐ_�ЁA�o�H��_�̓��g��̉��@�Ƃ��ӁB�a���̎߉ޕ������R�@�������j���B �̂� ��̐��������̋��̓��S�����č��h�̗��B �w�Ï��ɍ��h�̊ω����Ƃ���B����T�t�É@�旧�ꕣ�R�厜�����j���Ƃ���B�E�̌É@�A���C�̐V�݉ƍ��h����J�n�ɖm�����䓰�����B�̍������߂̍��R��X���������đ��Ɛ���A�ސ�������ɂ��ĕ��i�\������B�����l�c�Z�\�����꞊�@��F���m�l�M�\�N�t�O����n�k�A�啗�R���J�y���𗬂��A�������n�����������ߍ^���C���̔@���A��g�R�̔@���B�Ŏ֓ł��N����ɉ_�����ꂸ���āA�l���̔ϑ����c���₽��B���Ɉ˂čL�����ɍ��̊ω������u���B���㐅����ʂ������q�X�Ƃ��ďƂ�A�܂��������֗��ꐅ�F���̔@���ɂ��āA�Ŏ��X�ɐꗬ��鎖�Njv�����A��ɍ����ÒJ�n�ƂȂ�B�ω��̌ÐՖ�B �s��A���o�̌��͙�����ɗ��ʂӁB��ɖm���ۏ��V����Ɉڂ��B��a�̗��ω��A�O���ɗ��A�O�@��t�̌��B���Ɠ��V�q�A���V�q�A�����̓��Ɖ]�ӁA���O�@��t�̌�J���B ���ω��A������X����������ۂ̕������@�Ɏl���ʔV�䓰�A��匚�����B����̎��ꕣ�R�厜���ɓ���B���Ɉ˂č����ɎD��[���B���ە��́A�l�c�l�\�ܑ㐹���V�c��F�V����\��q�N�A���R�ɕ�����F�o���̒n��B��ʂӐՂɌ䙙�c��A�˂ę�������j���B����s���F�A�O�@��t�ʍs�R���A�g��z�Ƃ��ӁB����ؕۘC�H�R�͉H�F�u�ʑ����A���g�쉜�̉@�a���̎߉ޕ���B�����R�@�������j���B���̌�b�A��Ɗ|�A�䙙��(�����Ƃ��]��)�A���̌䙙��q�ƕς��Ƃ���B�}�ۘC�H�R�匠���́A�I�̍����K�S�ۘC�H�R�̘[�����̗��Ɍ������ʂӁB�l�c�l�\�Z��F���V�c�V�����N���єN�����\�ܓ��A�����̗����ۘC�H�R�̒��Ɉڂ����匠�����j���B���~��苗�����̉̂� ��̐��������̋�Ȃ̂Ȃ��S���������č��h�̗��B�x |
|
|
���厜��2
���a2�N(1013)�ɖ������@�Ƃ��đn������܂����B���X�͍��h�ɂ���܂����A���x���ꏊ���ڂ�A�]�ˎ���ɓ���Ɣˎ�ł��鍲�|�����ł��鍲�|���Ƃ̔�̌��A50�̎��̂��A��i���N(1704)�Ɍ��ݒn�Ɉڂ蓌�Ƃ̍��؏��Ƃ��܂����B���Ƃ͓��Ɏ��ӂ̐V�c�J���₻��ɔ������H�≁�A���ߒr�Ȃǎ��Ƃɐs�͂�s�����A19��ڋ`���͂��̒n�ŖS���Ȃ苫���ɂ͕�肪����܂��B�厜���͒����S�����猩��Ɛ�̑Ί݂ɂ���A����A�R��A���O��(�����̉����͏H�c���ł͏��Ȃ�)�ƎO�̖��ʂ��Ė{���ɂ��ǂ蒅���܂��B���ׁ̈A���Ȃ艜�s���̂��镵�͋C������A�{���͈�i�����ꏊ�ɂ���~�n�S�̂����̓I�ɍ\������Ă��܂��B����7�N(1824)�ɂ͐��]�^���������S�̒����̈ב�X����K��Ă���A�����ɂ͑�X���o�g�̃A���r�A���Y�ƌĂꂽ�R�����Y�̈ʔv��������܂��B (����s��X��)�@ |
|
|
����\�l�� ��k�S�Z���������R�{�o��
�{�����ω��A�͓������䎛�̊ω����ʂ��B������h�ߖ{���ɐ���a�É@�旧�ċ����B�{���a��ՁA���X��ɌÉ@�̐Ղ���B�z�K�喾�_�̎Ђ���A�����V�ٌc�̌�瑗L��B�t����A���ƂčL���삠��A�����ɏt���喾�_�̎ЗL��B�����^�ۛԂɎQ�w���ׂ��Ȃ�B�^�ێR�匠���A�哯�N���c�����C�̌䌚���Ƃ��ӁB ��r�̂� ���o�������[�����̐X��߂̂����Ж{�S�̎��B �w���ω��A�͓������䎛�̊ω����ʕ��A�啧�t�蒷��B�Ï��ɞH�A�o�H���R�{�S�^�ۛԂ̒��ɂ����āA�O�@��t�����̌얀���C���ʂӁB���ɓ��V�q�����q�_���Ɏ��营����삵�ʂӁA�R�̖���^�@�\�`�R�Ƃ��ӁB�����o��t�`�����ĕ�R�Ƃ��]�ӁB�O�@��t�̊J���B�c�����R�����̗�n��B���^�ۛԖ�A�厩�݊ω��匠�����j���B�l�c�\��㕽��V�c��F�A�哯�O��q�N�Z������R�Ɋω����䌚����B�ω�����t���喾�_�A����V�A�{���Ƃ̎��_�Ȃ�B�l�c���\�O��x��@�̌�F�����єN�Z���A��a���ޗnjS�A�R�鍑�Ɣn�R��芩�����B�˂ďt����A���ƂčL���삠��B ���ɞH�A�t����͍���і�Ɖ]�ӁA������̖��B���Ƃ͓���艺�A�y��і�̕ӂȂ�B�l�c�S����ԉ��@��F�N���q�N��n�k�A���Ɉ˂ĉ��R���B�ÐՂ͎R�̒��ɍ݂�A�����{�o���D���̊ω���B ���ɞH�A���R�̎��Ɍ��{�����O�R�Ɋω��L��A�����X�ɑJ���ƌ�������B�{�o���É@�����[�ɗL��ƌ�������B���͖��ƂȂ�B�R�Ƃ����ɑ����A����тƉ]�ӁB�����F�쌠���̋{�͕����V�ٌc�̌�����B ���ɞH�A�������{�����ɂ���A�E�ω��������̖k�̎R��B �����A��U�ߖ{���ɐ���g�����É@��旧�ċ����A�������R�{�o�����j���B�g�����A�˂̑m�����V�Ɖ]����A�����ɏZ�����B�������Ȃ�Ƃ��ւ�B�����g���������ɁA���X��̕ӂɈ�������ĘV�m��l�܂��܂��B����݂�͈�g���F�̌�����A�䖼���Ƃւ͓����V�Ɛ�ӁB�g�������o�ĕ��ɋN���A�l���ȂĐq�ˋʂւ͖��Ɉ�킷�B�������ċA�˂����B���Ɉ˂ČÉ@�{�o�����������B�ނ̖���\���ē����R���j���Ƃ���B�l�c��S�l���y���@��F������M���N�\���A�E�ω��X�Ɉ���䓰�������ʂӁA�����B�v��薋�ъω��Ƃ��]�ӁB�{���o�H��a�X�@�ɏZ�����A�˂č��ω����X�ֈڂ��Č䓰���������ӁB�{�o���͖{�����ɂ���A���㕺��̎������ɑJ���B�V���l�����N�̒n�����Ė{�����v���Ƃ��B�{�o���̏Y���{����V�@�����o�S�̒����A�Z�A���A�n��A�����l�U��A������U�A�������B���~��苗�����̉̂� ���o���Ђ�����[�����̐X��߂̐��Ж{�o�̎��B�V�s�\�㐢�̏�l�A�t���̕ʓ������[�A���ЉƑ原��l�����䗷�h�̎���r�́B����߂Ȃ��肹�ΐ��(�}�})(�C)(�s��)�ʒ��Ղɂ�����(�}�})(�C)(��Ƃ�)�t����ɗ��āB�x (��k�S�������Z��) �@ |
|
|
�����\��ԁ@�R�{�S��ꑺ����R
�{���ω��A�啧�t�蒷��B�O�@��t�A���o��t�`���̗�n��B���}�A��L��A�Ėڊ�A�ĎR�A�n���J�A���㕽�B���������ÐՎ旧�A�Ĕ���̖����ɑ��쌴�A���Ր�̗��̏�ɑ剾���𗧂āA�V�������������Ƃ��ӁB �̂� ���݂̂������⎛�̖��̏��ςޔϔY�������čs���Ȃ�B (�\��s��c�䒬) �@ |
|
|
����O�\�ԁ@�R�{�S���ɑ����q�R�ω�
�O�@��t�A�q���Ɋω��̑��t���ӁA�����ω��ɂČ�����ƂȂ�B����̑��䌚���̗�n�Ȃ�B���ω��啧�t�蒷�̍��B �����X�g�R�A���c��ւ��s���Ȃ�B���o��t�ω��̑�����Ĕ[���ӁB�X�g�R�͖�t������B���m�͑劖�a�A���q����Ƃ��ӁB�l�c�l�\�O�㌳���V�c�̌�F�a���N���ɐ������シ�ƂȂ�B ���q��Δ�̌��ق��炩�ɗ���鉹���݂̂�Ȃ���́B �w�̐��ω��A�啧�t�蒷��B�O�@��t�A�q���Ɋω��̑��t�ʂӁA�����ω���B���Δv�ɗ���̊ω��Ƃ��]�ւ�B����̑��h�юl���������ēV�_�����������ɍՂ���B�[�ɂܑ͌呸���Ղ�B�l�c�\�O��~�a�V�c�̌�F�A�V�����N�O�@��t�J��̗�n��B�V�_����A�n�_�ܑ�𐒕��Ƃ��ւ�B����ɂ͓V���厩�ݓV�_���������A�˂Ď����̓V�_���j���B�����X�g�R�A���c��ւ��s��B�X�g�R�͖�t�������̗�n��B���m�͑劖�a�A��������Ɖ]�ӁB�l�c�l�\�O�㌳���V�c�̌�F�A�a���Z�NᡉN�������シ�B�c�ォ�Ԃ͔���������̐��㒃�P�ԁA�c��ԁA�G�X�q�ԂƂėL��B�c��Ԃɂ͎��o��t�ω��̑������Ĕ[�ߋʂӁB�����ɓc���\�㖇�L��A�c�㐅�̒r�L��A�������r�L��B������R�̏�ɂ���B�̂� ���q��Δv�̌���ق��炩�ɂȂ���̉�����@�Ȃ���́B�x (���ʎ� / ���p�s������)�@ |
|
|
����O�\��ԁ@�H�c�S����̏������R
�l�c�\��㍵��V�c�̌�F�A�O�m�����єN�O�@��t���R���J��A�������Ȃđ���@���A����ɔ@���A�厩�݊ω������A����𐴂ߑ�~���̋������A�V���n�v�l�����S���F�鏊��B�O�m�\�O�p�ДN����b�����A�X�g�̐�ƂɎ���č��R�̌䓰�����B �l�c�E�ܑ㕶���V�c�̌�F�V�������N�O���O���A��n�k�ɂČ䓰�A���A���A�V�ɖ��ށB���l�c�E���F���V�c�̌�F�A�����O�M��N�F���V�c�䒺�́A���ɐ����咺���Ɉ˂Č��R�匠���̊z�������A�䒺�̂ɓY�ւďo�H�S�i�ǎ��q����l�i�ǖ[�ɒ������������ӁB ����܂��̌������ɖ���邠��͂�Ƃ������̌��B�������������K�N�Z���\�ܓ��䌚���A��s����l�i�ǖ[�A�����F���V�c�̌䒺�菊�B�䗊�ސl�܂��̊ϐ������Ɛ��Ƌ��Ɍ��ɉk��܂��B �w��O�\��ԁ@�H�c�S��������s������ �s�������镧��A�O�@��t��B�O���q�A�䓰�����Ȃ�B���Ж�t���A�R�̐_�A�F��_�̗��ЁB������s���ꂠ��B�≮�\��ʊω��A�O�@��t�̌��A�{�������B���ω��A�啧�t�蒷��B�}����R�͐l�c�\��㍵��V�c�̌�F�A�O�m�����єN�O�@��t��J��B�������ȑ���@���A����ɔ@���A�厩�݊ω������āA����𐴂ߑ�~���̋��𒒂ēV���n�v�l�����S���F�鏈��B���̉@��R���ɍb�ΗL��B�k�̕��Ɍ�����A�ٓ������A�V�_��A��̏�ɏ��̌ÖA���͂��̖���B�����A��t��A���̕��A�V��̒ދ��A��V���A���V���L��B���@�m�Ə��ӂ钹�L��A�O�������Z�߂�B�O�m�\�O�p�ДN����b������(�ꏑ����)�A�X�g�̐�ƂɎ��肵���������������ʂӂƖ�B�l�c�\�ܑ㕶���V�c�̌�F�A�V�������N�N�O���O����n�k�ɂāA�䓰�A���A���A�����V�ɖ�����B�l�c�\���F���V�c�̌�F�����O�h��N�A���R�֓V�c���䐻�A��������֒����L�Č��R�匠���̊z�������ߋ��ЁA�䐻�̌�̂�Y�ʂЂďo�H�m�S�i�ǎ����̒��q�A����m�l�i�ǖ[���ɐ鉺�L��B �䐻�� �\���̌�������ɖ���邠��͂�Ă点�����̌��B ���������K�N�Z���\�ܓ��䓰�����A��s����m�l�i�ǖ[����B���F���V�c�䒺�菊��B���R�̌`�͑��R�Ɖ]������B���R�̌�͑�R��A���̐l�䌎�R�Ƃ��ӁB���R�匠������A�����R���������A���E�͕��̏��A�Öؑ����B�{�̗т͏��A���A�G�؎R��B��R�̑O������͕s����̗��A�c��Ƃ��ӁB���Â�蓖���̑�瑢�c���ʂӏ���B�l�c�S���㏬���@��F���i�\�єN�ȗ��A�H�c�S������i�Ƒ�X�C�����Ɖ]�ӁB�E�{�Ђ̊X�����̐��A�ʓ��C�������V��c����X�旧����B�l�c�S�\�O�㍡��c��(�쌳�V�c)�̌�F�A�����\��p�q�N���|�Ό����`�[���ċ�������Ƃ��ʂӁB���ɕʓ��E�A�^���@�����R���@�������B��疈�N�l�������A�\�����A�������A�㌎����A�\����A������B���N�@�z�B�ʓ��C���`���@�B�̂� ��ꂽ�̂ސl�������ϐ������Ɛ��Ƌ��Ɍ��ɉk��܂��B�x (�m�Վ� / ���p�s�\�a�c)�@ |
|
|
����O�\�O�ԁ@�H�c�S����̏��ԉ�����{�R�M����
�{����ߊϐ����B�Ï��ɍ��̈�ƗL��B�����o�H���i�̖�����c���Y�M���ċ����A(�C�i�V)�u�˂ĐM�����Ɖ]�ӁB�v������q��ђ藊�̕��B�@�_�A���֏����s�r�̎������ɂď@�_��{�̌�@�̏����߂�����(����)�����Ȃ�݂�(�C�A�����c���)���Ɏc��܂��B�Ɖr������ƂȂ�B�O�\�O���D�Ŕ[�Ȃ�B�O�ޗ͂ɉߋ����݂̍ߏ����ėL��△����̍���̔���B �w�@�_�@�t�����ꌩ�̎������ɂĂ����Ȃ�B��{�̌�@�̏����߂��������Ȃ�݂����Ɏc��܂��B ���檭�̖���A���T��q���Öؖ�B�ԉ�������̌����ƂČÂ��{�A�Öؐ����L��B�����A�̓c�����R���m�ʖ邵�ʂЁA��̉������ʂЊ萬�A�����ƂČ�r�̎v�Ђ���S�̓�����Ȃ�◎�Ƃ͌����ĉ���(�C)(��)�������B ��ɗ���O�\���ꕶ���Y�ւĎD�Ŕ[�ފ�А��A�B�̂� �O��͂ɉߋ����݂�(�C)(��)�ߏ����ėL��△����̍���̔���B�x �w��Z�S�����R�A�ۘC�H�R�A���ԁA��ԔV���A�^���R�A�����{�R�A�����R�A�c��V������̑�������E�����R�͍O�@��t�A���o��t���l�������ӎR��B���ۏ\���p�q��C�g�C�Ó�������ꎜ�o��t�n���j��A�m���n�~�m�g�]�t�B�l�c�\�l��m���鎞��V�m��A���쏬��������B���a�ܔN��ߓ����A���\�l�N���K�N�A����B�R���j�A�\�Z�㐴�a���ϓ�N�M�C�~�m���H�c�S�j���R�j�����ՐԐ_�A���c�����A�����ܔNᡖ��A���A���Z�N�b�\�����\�l�����b�R�O���@���ŃX�g�A�Ԑ_�����V�L���N�B�Ȑ��l���j�A�H�c�j�l�N�����V�ʃt�ԃj�Z�S�ʃq�A�������V�ʃt�i���w�V�B��ϓ�N�������ێOᡈ喘���S���\�l�N��B ��O�@��t�A�m����C�g�]�w���B�H�B���a�R���n�����L�P���g���A�Z�S�n�n���m�̕��N�Ԑ��g�e�����s���g�]���B�����n���X�j��앧�L���s�R�B�A�A���S�����ʃt���������e�����֎��Q�V�^���w�V�B���R�J��g�]�����P�s�R�B �ꐹ�����q�n�l�c�O�\���q�B�V�c��q�A����Nᡖ����������a���A����j�e���ې��O�\�l�㐄�ÓV�c���ꃒ�ʃt�B����\��N�ܓ��I�X�A�l�\��B���ێOᡈ喘��S���O�N��B ��c�����m���R�n�l�c�\�㊺���V�c�V���V�l��B���Εs�m�A��C�A�Ő�(�`����t��)�~�m(���o��t��)�V�����V�l��B�����\�N�h�����ΐ����j�����������A�������������w�V�B�E�h���������ێOᡈ喘��S�l�\�O�N��B ��s���F�n�l�c�l�\�Z��F���V�c�����N�M�Г���X�B���ێOᡈ喘��S��\�l�N��B ��Ő��n�`����A�b�R�������n�n�\�㊺���鉄��N��C��B���ێOᡈ喘��S�\�Z�N��B ���C��������\�O�N�b�\�܌���B�Ő��������N������B���N���ыA����B��C�n�v�����O�N�ڑ哯�������A����B ��\��㍵��V�c�O�m�\�O�N�Z���Ő�����X�B���ێOᡈ喘��S��\��N��B ���C����R���n�n�\��㍵��V�c�O�m���N���\�i���B���ێO�Nᡈ喘��S��\���N��B �ꓯ����n�A�\�l��m���V�c���a��N���K�O��������A���Z�\��B���ێOᡈ喘��S��N��B ��~�m�n���o��t��A�\�l��m���鏳�a�ܔN��ߓ����A���\�l���K�A����B �ꓯ���Ńn�A�\�Z�㐴�a���ϘZ�N�b�\�����\�l���A���s�m�B���ێOᡈ喘���S���\�N��B ���ϔ��N�����Ő��n拎��`����t�A�~�m�n拎����o��t�B ��Z�\����V�c�����\��N�h���\���A��C�n拎��O�@��t�B�E�`���A���o�����\�Z�N�x�V�B �ꎵ�\�O��x��@�����ܔNᡖ��A���`�ƌ���k�������t�A�ƍt���n�X�B���ێOᡈ喘�Z�S�\�O�N��B �ꔪ�\���㒹�H�@�������N�����O�����l���A���Ɖ��C��ŖS�A��������B���ێOᡈ喘�ܕS�\��N��B �ꔪ�\�l�㏇���@�����N�p�\�������ܓ��A��y�@���J�@�R��l���ŃX�B���ێOᡈ喘�ܕS�O�\��N��B ���\���F���@�������N����A��Ֆ@�t���@���J��V���V�s��l�B���ێOᡈ喘�l�S�Z�\��N��B �ꓯ��F�O���ܔN�p�ߏ\���\�O�����@�@�t��X�B���ێOᡈ喘�l�S�Z�\��N��B ��S���㐅���@���a���N���K�܌�������◎��A�G�������Q�A����\�O�B���R�ƍN�����\�l�ΓV���ꓝ�X�B���ێOᡈ喘�S��\��N��B�x (�M���� / ��َs�ԉ���) �@ �@ |
|
| ���^�� | |
|
(�����A����19�N-���2�N(800-860))�@��������O���̐^���@�̑m�B���͏��@�e���I�䉀�B��C�̏\���q�̈�l�ŁA�^���@�ŏ��߂đm���ō��ʂ̑m���ɔC����ꂽ�B�����ɂ��D��A��C�̎������W�߂��w����W�x��ҏW���Ă���B�܂��A�����_�쎛�ɏZ���A���̔��W�ɐs�͂����B���Y�m���E�I�m���E�`�{�m���Ƃ��̂����B
�����U �c�����͊w��E���M�̓��ɗ�ށB�I�����͓ޗǎ���̋I���l�A��������O���̋I���J�Y�Ȃǒ����Ȋw�ҁA���l��y�o���Ă���B �O�m5�N(814)�A15�̂Ƃ��o�Ƃ��ċ�C�̒�q�ƂȂ�B �V�����N(824)�A25�̂Ƃ�������@���`�@��苗��ƂȂ�B��C�ɍ˔\�������܂�ẮA�ٗ�̎Ⴓ�ł̎�@�A�ł���A�����̐l�X�����������Ƃ�����B �V�����N�`���a2�N(835)�A���Y�R��(�_�쎛)�ɘU��12���N�C�s����B�������A�ʐ��ł͏��a3�N����Ƃ���Ă���B �V��3�N(826)11�����痂�N5���܂łƓV��7�N(830)11���`9�N(832)3���A����ɋ�C�����X�̖����̉��`��`�������B�����^�ώ���L�^�������̂��w���Y�����x���Ƃ�����B �V��9�N11���A����ɂ��̂Ƃ���C���獂�Y�R��������B ���a2�N����A����V�c(��c)��12�N�U�R�̋�s��]�����ē�����\�T�t�ɔ��F����B�������A�ʐ��ł͏��a7�N�B ���a2�N����܂łɁw����W�x��Ҏ[����B�����ɂ��A���炪��C�Ɏ����ď������Ȃǂ��ďW�߂������ɁA��C���ݓ����ɂ��Ƃ肵�����̂������A��̑I������10���ɂ܂Ƃ߂��B ���a3�N(836)�A�������v�m�Ƃ��Č����g�D�ɏ�蓂��ڎw���B����ŗ��w�m�̐^�R�����D�B�Ƃ��낪�A���őD����j���A���Ɉڂ�23���ԕY���B30�]�l�̓���҂݂͂ȉ쎀���āA�^�ςƐ^�R��������ՓI�ɐ����c��A��C�̓�(��̓I�ȏꏊ�͕s��)���ɋ~�����ꂽ�B�A����͐_�쎛�̌o�c�ɐs�́B���̂��둽�����A�ܑ動��F��������m���V�c�ɕ\�����F�߂���B ���a4�N(837)7���A�����c�̍c�q�A�������o�Ƃ��Đ_�쎛�ɓ���^�ς̒�q�ƂȂ�(����ɔ��_�T�t�ƍ���)�B ���a7�N(840)12���A���b�ɑ���_�쎛�ʓ��ɔC������B ���a10�N(843)11���A�����t�ɔC������B�܂��A�����҂ƂȂ�(�҂̏���)�B ���a14�N(847)4���A���t�ɔC������B11���A���b�̌���p�������꒷�҂ƂȂ�B �m�����N(851)7���A���m�s�ɔC������B�����V�c�̌����M�C���}���ɏ��i�B �m��3�N(853)4���A�^���@�N���x�҂�V����3�l����6�l�Ƃ��邱�Ƃ�F�߂���B������3�l�͐_�쎛�œ��x�B �m��3�N10���A����m�s�ɔC������B �čt3�N(856)10���A�m���ɔC��������A�t��C�ɑm���ʂ����邱�Ƃ���\���Ď��ށB�Ȍ�A�O�x�ɂ킽��C���Ǝ��ނ��J��Ԃ��B �V�����N(857)10���A�����V�c�A�^�ς̎t���v���S�Ɋ������A��C�ɑ�m���ʂ�Ǒ����A�^�ς�m���Ƃ���B �V��2�N(858)8��23���A�����V�c���ˑR�a�ɓ|���B�^�ς̊ŕa�����A27���A32�ŕ���B�V�c�̋}���Ő��_�̌������ᔻ�𗁂щB������B ���2�N(860)2��25���A�v�B���N61�B ����q ���c2�N(878)11��11���̐^�댾���ɂ��A�^�ς̕t�@��q�͈�l�����Ȃ��B�^�ς̒n�ʂ��炷��ɂ߂ĕs���R�ŁA�����V�c�̋}���ɍۂ��������ᔻ�𗁂щB���������ƂƂ̊֘A���^����B �Ȃ��A�^�ςƎt��W�ɂ��������Ƃ��j���Ɍ�����҂���������B �^�R�c�w���{�O����^�x���2�N2��25�����̐^�ϑ��`�Ɂu��q�^�R�v�Ƃ���B5���{�w�������ҕ�C�x(���X�Q���ޏ]2)�Ɂu�^��m���A�^�ώ�@�v�Ƃ���B ���_�c�w�����{��I�x���a4�N7��22�����ɐ_�쎛�ɓo������������Ƃ������錹���́A�w���ڕ����x�ɂ��Δ��_�B ��斅�c5���{�w�������ҕ�C�x�Ɂu�^�Бm�s�����A�^�ϑm����q�A�@�b�m�����v�Ƃ���B �b�^�c�w�^�������x(���Q���ޏ]28��)�ł͐^�ς̕t�@��q�����A�M�ߐ��ɖR�����B ���`�� ���b���Ƃ̌����� / �����V�c�̑��c�q�E�ҋ��e���Ƒ�l�c�q�E�Ґm�e��(��̐��a�V�c)�̍c�ʌp�������ɂ����ŁA�ҋ����̐^�ςƈҐm���̓V��@�b�������͂������A�^�ς��s�ꂽ���߈Ґm���c���q�ƂȂ����Ƃ������́B�w���ƕ���x�����ɂ͑��o�A�w�]�䕨��x����ɂ͋��n�ő����b���ڂ��Ă���B�Ȃ��w�]�k���x����́A����̐^�낪�Ґm�e���̌쎝�m�ŁA�^�ςƕs���������Ɠ`���Ă���A������͐M�ߐ�������B ����~�ɘf���V��E�S�Ɖ��� / �����V�c�̏���Ő��a�V�c�̕�ł��铡�����q(���a�@)�Ɉ�ڍ��ꂵ���^�ς��A����A���F�������S�A���邢�͓V��Ɖ����Ĕޏ��̂��ƂɌ���Y�܂���B�����Ĕ�b�R�������̑����a���ɑގ������Ƃ����b�B����18�N(918)�`23�N�̊Ԃɏ����ꂽ�Ƃ����w�V���R�����������a���`�x���͂��߁A�w�E�≝���`�x�����̑����`�A�w�Î��k�x���O�A�w�W�x����Ȃǂɍڂ��Ă���B�Ȃ��A�ގ��̐��b�Ɂw���̕���W�x����\�A�掵�b�u���a�m�@�A�דV�{嬈�����v�����邪�A���̘b�ł͍��S(�\��́u�V�{���Ăv�����{���ł͋S)�Ɖ����̂͐^�ςłȂ���a���̋����R�̐��l�ŁA�����a���ɂ��ގ����Ȃ��A�@�͏O�l���̒��A�S�Ə���ɋy�ԂɎ���A�V�c���Ȃ����ׂ��Ȃ������Ƃ�����]�I�����ƂȂ��Ă���B���̐^�ς⑊���a�����o�ꂵ�Ȃ��`�̐��b�̏o�T�́A����17�N�`18�N����O�P���s���������w�P�Ɣ�L�x(�U��)�Ƃ����B�����I�ɑ����a���̓`�L�����Ƃقړ��������A�����炭�́A�w���́x�^�̐��b����ɂ����āA������a���̓`�L�ɑf�ނƂ��Ď�荞�ہA�V��@�ΐ^���@�Ƃ����\�}���������܂�A�^�ς����S�E�V��ɂ��ꂽ�̂ł��낤�B ���J�T�T�M����l�̎p�Ō���� / �V��m�������F���@�c�̒��q�@�ŏC�@���s���Ă����Ƃ���A�^�ς̗삪�J�T�T�M�̎p�Ō����B�����̓J�T�T�M���얀�d�̉ŏĂ����A���̌�A�^�ς̗�͏��l�̖@�t�̎p�Ō����̂��ƂɌ����悤�ɂȂ�A���������|�Ɋׂ��B�����A�����̒�q�ɂ���Đ^�ς̗�͒��������B�w�}�K���L�x����\�O�A����17�N2��3���̍��Ɍ����ݐ����̂��ƂƂ��čڂ��Ă���B�܂��A�����b���w�E�≝���`�x�����̏`�ɂ�����B �����k�����A���� / �����V�c�̎���A�^�ς͉��H�������A��ό��N�A�o�H���u���S�����̎R�[�ɐ��ɂ����āA�����R����������@���J�n�B���N�A���̒n�ɓ��肵���Ƃ����B����@�ɂ͐^�ς̕悪����A���N2��25���ɐ^�ϑm�����@�v���s���Ă���B�@ �@ |
|
| ����C�ƌi�� | |
|
������R�ɐ^��������n��������C
803�N�A��C(�O�@��t)�͍Ő��Ƌ��ɓ������A�i����g�ɂ��A����(���Ɋ����̈ӂŁA�L���X�g���̐���)���A�u�ՏƋ����v�Ƃ������疼���܂����B�u���Ȃ������̌���l�X�̑O�ŋP�����v�Ƃ����A�}�^�C5�F16�̊��ꐹ������Ƃ������̂ł����B �ނ͋A����A����R�ɐ^��������n�����܂��B��C�͐V��������������A�Ő��͋����������A�����Ƃ������Ƃł��B�������A��l�͌��܂��Ă��܂��܂��B �Ő��͓V��@��n�����A��C�͐^���@�����킯�ł����A�ނ̕����͎߉ނ����������n�����Ƃ͎��Ă������ʋ����ŁA�u�i���ƍ������������v�ł����B ����C�ƌi���k�̌i��̏o� �����ŁA�ނ͌i���k�̌i��ɉ�܂��B�ނ́u��`�i�����s������v�̔蕶���������m�ł��B �ނ́A61�ˎ��ɏA�����Ƃ���Ƃ��A�u�߂���ł͂����Ȃ��B�킽���́E�E�E���ӕ�F�̂��Ɏd���邽�߂ɓ���(����)���邪�A 56��7000���N�̂̂��A���ӂƋ��ɍĂђn��Ɍ�����ł��낤�B�v�ƌ����܂����B ���ӂƂ́A�փu����̃��V�A�A�M���V����̃L���X�g�ł���A ���n�����ɂ͂Ȃ������u�L���X�g���ėՂ���Ƃ��ɕ�������v�Ƃ����L���X�g���M�A �i���̐M�Ɠ������̂ł��B �^���@�ł́A�@�v�̍ŏ��ɋ��̑O�ŏ\�����Ƃ��A ����R���̉@��_�O�̓��U�ɏ\���˂����Ă���Ƃ��A�i���̉e�����݂��܂��B �����{�̕����̂����ɂ��銴���̌i���̋��� �P���E�W���Z�t���A�����J�̌i���̋����K�₵���Ƃ��̈�ۋI�ɂ��ƁA���{�̕����̂����ɂ��銴���������Ƃ̂��Ƃł��B�q�t����O���݂ȍՒd�̑O�������ė�q���A�q�t���u�njo�v�̂悤�Ȃ��Ƃ����X�ƍs���A�������Ɠ��̐߂܂킵�œnjo�ƍ��o����قǂ������ł��B �����F����͉��������オ��i���̋��� �܂����F����͉����������A�l�X�͂��̉��������̑̂ɂ�����悤�ɂ��邻���ł��B���ꂪ�j���������炷����ł��B�܂��A�M�҂͎�ɐ���(���U���I)�������Ă��邻���ł��B �����̐���̔��Ď҂́A���̑m�A���^(�ǂ����Ⴍ)(562�`645)�Ƃ����Ă܂����A���̎����ɏ��߂Či�����������̂ł�����A�i���̕��K�ł��������삪�A �����ɂ��Ƃ肢���ꂽ�Ǝv����悤�ł��B �X�ɁA�i���ł́A�낤�����𗧂āA��������Ƃ����܂��B�F��̏��߂�I���ɂ́A�x���̉�����܂��B�Ȃ�ƂȂ������Ɏ��Ă��܂��B ����C�����������́u����@���v ��C�����������́A�u����@���v�ł����B������u�@�g���v�A����ɐ^������������u��g���v�A�����Ď߉ނ̂悤�ȑ��݂��u���g���v�ƁA �����ł́A�قȂ������ł͂��邪���ׂĈ�̂ƍl���A�u��g���O�g�v�u�O�g����v�ƌ����܂��B �L���X�g���ł́A���Ȃ�_�A�L���X�g�A�C�G�X�Ɏ��Ă��܂��B�u����v�̓f�E�X�A�_�̓��{��ƃt�����V�X�R�E�U�r�G���͂������炢�ł��B ���u����͉́v�������u��Ȃ��Ď����v ��C�Ƃ̊W�ŁA�����[���̂́A�ނ̍�Ƃ̑���������A��ʂɂ́A��ҕs���Ƃ���Ă���A�u����͉́v�ł��B�����ɂ��i���̉e�����݂��܂��B����͎������ɕ��ׁA47�����́u���ȁv����ׁA�������[���Ӗ��̂����̉̂ɂ��Ă��邩��ł��B �����ŁA��ԉ��̕����𑱂��ēǂނƁu�Ƃ��Ȃ��Ă����v(�̂̒��Ő����Ƒ����͈�ɂȂ��Ă���)�ƂȂ邱�Ƃ��킩��܂��B�u��Ȃ��Ď����v�Ɠǂ߂܂��B�X�ɁA����A�����A�E���̕����𑱂��ēǂނƁA�u�C�G�X�v�Ɠǂ߂܂��B�߂��Ȃ��Ď��A�̈Ӗ��ł��B����炩��A�u�߂Ȃ��C�G�X���\���ˏ�̎��𐋂����v�Ƃ����A �i���k�������Ă����M�ƊW������̂ł��낤�Ƃ����Ă��Ă���̂ł��B �@ �@ |
|
| ���O�@��t�ƍz�R�T�� | |
|
���C���҂����̈ꕔ�͍z�R�Z�t�Ƃ�����
�R�͖L�����A�Đ��̃V���{���ł���A�V�Ƃ̂Ȃ��肩��_�I�ȗ̈�Ƃ����߂����ƂƂ��ɁA�����͐_�X����̎��蕨�ł�����A��A�S�A���A����ȂǖL���ȋ��������Ă���ꏊ�ł�����܂����B ���̎R�ŏC�s���s���Ă����R���́A�u�R���m�v�Ƃ̊W�̂��錾�t�ł͂Ȃ����Ǝ��͂��˂��ˎv���Ă��܂��B��̖��������т����m���g�Ȃ���C���҂ɕς��ďC�s�Ə̂��ĎR�ɓ���A�B�����ɕ����A���Ȃ͂��R���ƂȂ��āA������͂��ߋM�d�ȋ�����T�����߂ĎR���������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �l���Ă݂�A�z���L�͋����T�����̒��ԓ��m�̘A���ɍD�s���ł��B��(�����E�C���҂Ȃǂ��ߕ���H��Ȃǂ�����Ĕw�������̂�����)�ɂ͋����T���ɕK�v�ȃn���}�[��A���܂��܂Ȍ@�퓹��ނ��B�������Ă����̂�������܂���B�����ł�������(���Ⴍ���傤�B�����S�ׂ̍���œ����ɓS�̗ւ��t���Ă���)�����������T������̈�ł������̂�������܂���B ���B�������̋��R�J���⍲�n�̋��R�Ȃǂ�����܂ł��Ȃ��A�S���e�n�ɋM�d�ȋ����������Ă���\���͔F������Ă����͂��ł��B���������z�R��T�����銈���������ɍs���Ă���̂́A�ނ��듖�R�Ƃ�����ł��傤�B �×��A���������̃C�f�I���M�[�̊�b�Ƃ��Ă������{�ł́A�����₳�܂��܂ȕ����@��ɓ��𑽗p���A�܂�����Ƃ��Ă̓�����b�h�A����ɗǎ��Șa�S(�킸��)��K�v�Ƃ��܂����B���������������Y�o����ꏊ�͌��͎҂ɂƂ��Ă���߂ďd�v�ȏꏊ�Ƃ�����̂ł��B�ł�����z�ƕ���(�ׂ݂�)�Ƃ����������W�c�����āA�ނ炪�z�R�J����B�Z�p���i���Ă����ƍl�����܂��B ����C�ƍz�R�̕s�v�c�ȊW �R�x�����̏C�s�����Ă����Ⴋ���̍O�@��t��C�́A���������z�ƕ��������ƌ𗬂��Ă����\���͍����A�ނ͐�����܂߂��z�������������I�A�o�ϓI�ɂ����Ȃ�d�v���������Ă��邩���\���������Ă����̂ł��傤�B �w�^�������ƌÑ���������x(�����o�ŁA����)�ɂ��ƁA����R��l���H���̎�v�n��́A���z�R�Ɛ���R�̂����߂��ɑ��݂��A�܂�����R���������̂������͋��A��A���A����̕�ɂł���Ƃ������Ƃ��m�F����Ă���Ƃ������Ƃł��B���Ȃ͂��d�v�ȓV�R�����̖����Ă���ꏊ�Ȃ�ꏊ�Ƃ��āA�����Ɏ��@�����������Ƃ��l������̂ł��B�×�����R�����Ȃ�ꏊ�ł���A�����̕�ɂƍl�����Ă����䂦��ł��B ����@���̎x�z����F���ƒ������鎩�R�̐ۗ��A�����Ă��̌��ʐ��܂ꂽ�n���n���w�Ƃ��o���I�Ɍ��т��A��C�̍z�R�ւ̊S�Ɛ����I�A�o�ϓI�Ȍ��ʂւ̊��҂����܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ����A���҂̂ЂƂ�{�鐴�ꎁ�̎w�E�́A�܂��Ɍd��ł��B����ɉ����A�����l�X�̌����I�ȋꂵ�݂���菜���Ƃ��Ă̐����O�̌��ʂɂ���C�͒��ڂ��Ă������̂ł��傤�B �^�������{�R�ł��鍂��R�̓������݂⋞�s�̓���(�����썑��)�̌������������������͂́A��C�̎v�z�ɋ������ނ���芪�������̒�q�A�M�҂Ȃǂ̏�M�������킯�ł����A���̈���ō���V�c�̎x���Ȃ����Ă͎������܂���ł����B���̎x�������t�����w�i�ɁA�z�R�Ƃ����d�v�Ȓn����������邱�Ƃœ����鐭���͂�o�ϗ͂��������Ƃ�����A��C�̗��j�I�ʒu�Â��ɂ́A������̑��ʂ�����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B ��C�́A�C�s���钆�Ő��m�����������z�ƕ�����ɏo��A���������W�c�Ƃ̊W����M�d�z���␅�����ɂ����ƍl�����܂��B �Ő��Ɠ��������g�D�ɏ��A�����Ōb�ʈ�苗�(�������������E������̐^���m�ő�7�c�B��苗��́u�t���v���Ӗ�����T���X�N���b�g��)���疧���̖@����p��8��ڂƂ��ē`���刢苗��ʂ��A�����̌o���▧���@���������ꂽ�Ƃ����܂��B�܂��ʂɑ����̖����@������߂ė����Ƃ��Ƃ������܂��B���̍��͂��z�R�T���ɂ���ē������K�̎����������̂�������܂���B �����A����͐��Ȃǂ̕����ɐ���A�}���K���@��p���āA�t��(���b�L�̋Z�p)���āA����������邽�߂ɕK�v�ȋM�d�Ȃ��̂ł�������A����߂č����ł������ƍl�����܂��B�����ɒ����Ŗ����@����w�����邽�߂ɂ��A���z�ȋ��K��K�v�Ƃ����ł��傤�B�m���Ƃ͂�����C�ɂ͂��������܂�ɋ��K�͌������Ƃ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł������͂��ł��B ��C�͎��R�̗���̒��Łu�ꑦ��A��ؑ���v(��̂��̂͂��ׂĂ̂��́A���ׂĂ̂��̂͂ЂƂ̂���)�����H���Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��C�̈̑傳�������܂��B �z�������Ɣ��p�i�A�H�|�i�͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���܂��B�Ô��p�E�������w��ł����ɂ������āA���ɂ����̐l�X�ɂƂ��čz�������͂ǂ̂悤�ȑ��݂ł���A�ǂ̂悤�Ɏ�ɓ���Ă��������l���鎋�_�͐���Ƃ��K�v�Ȃ��̂Ƃ����܂��B�@ �@ |
|
| �������D�N���m�Ɓu�������c�v�_ | |
|
���s���`(�����܂�)�̐`(�͂�)�����L���X�g���Ɍ��т��Ę_�����ŏ��̐l���́A�����D�Y ���m(1871�|1965)���Ƃ����Ă���B�������́A�L���������s(�͂�����)�̐��܂�ŁA�������w�Z(���݂̑���c��w)�p�ꕶ�w�Ȃ𑲋ƌ�A1893�N(����26�N)�ɓn�āB1896�N(����29�N)�ɋA����A�a���@���w�Z(���݂̖@����w)�Ⓦ�����w�Z�̍u�t���߁A1941�N(���a16�N)�ɒ����i��(�L���X�g���l�X�g���E�X�h)�̌����œ����鍑��w��蕶�w���m�������^���ꂽ�l���ł���B������������w(���݂̒}�g��w)�̊w���ɏA�C���A1947�N(���a22�N)�����9�N�Ԃ͌̋��ł���L���������s�s�̎s�����߂��B
���`�ɂ���ؓ����V�ƌ䍰(�R�m�V�}�j�}�X�A�}�e���~�^�})�_��(�ʏ́u�\�̎Ёv)�ɂ́A���s�O������1�Ƃ���A���{�ŗB��Ƃ����Ă����u�O�������v������B�`���̈ꑰ�́A���_�V�c�̎���(4�`5���I��)�ɒ��N�������n�����Ă����������Ƃ����Ă���B���̐��A����l�Ƃ��A�����l�Ƃ������Ă��邪�A�ނ�́A�{�\�⌦�D���A�y�Ɋւ��č��x�Ȓm���E�Z�p�������Ă������Ƃ��`�����Ă���B�`���̖{�@�Ƃ́A��a�ł͂Ȃ��R�w���R��(��܂���)���̊���(���ǂ�)�S�A�I�ɌS����ՂƂ��Ă������A�Y���V�c�̎���(5���I����)�ɂ͋��s�̑��`�ɒ�Z����悤�ɂȂ����Ƃ����B�ނ�́A���̍��x�Ȏ����Z�p��p���āA���Ƃ��Ƃ͋��Z�ɓK���Ȃ����n�тł��������s���K�͂ɊJ���E�������A794�N(����13�N)�ɂ͕����J�s�������������B�܂��A���̋Z�p���āA��ɐm���V�c�˂̂悤�ȋ��啭��̍\�z�Ɍg���悤�ɂȂ�B�`���͓y���ł���A�ݒn�ł͉B�R���鐨�͂������Ă������A����ł̓N��(�q�A��)���Ǘ����鉺����l�ł������B�]�k�����A�����A�����A���R�A�c���A�сA�����A�H�c�Ȃǂ̐������l�тƂ́A�`���̖���ł���Ƃ����Ă���B �������́A1908�N(����41�N)�ɔ��\�����_���u���`��_���v�ɂ����đ��`�Ɏc��n�����ՂȂǂ������Ƃ��āu�`�������_���l�i���k�v����W�J�����B���̊w���́A�ꕔ�̐l�тƂ���u�������c�v�_(���{�l�̐�c�̓��_���l�ł���A�����ɓo�ꂷ��u����ꂽ�\�x���v�̖��Ⴞ�ȂǂƂ����)���w�p�I�ɍ����Â�����̂Ƃ��đ傢�Ɋ��}���ꂽ�B �����ŁA�������c�_�ɂ��ď������茟�����Ă������B�������c�_���ŏ��ɏ������̂́A���������ɓ��{�ɏZ�݁A���{�l�̗��j�╗���A�K���Ȃǂ��ώ@�����X�R�b�g�����h�l�̖f�Տ��m�D�}�b�N���I�h���ł���A1875�N�Ɋ��s�����w���{�Ñ�j�̏k�}�x�̒��Łu���{�l�̃��[�c�́A�k�����[���V�A�n�̃A�C�k�����A����n�̏��l���A�w�u���C����(���_���l)�ł���v�Ǝ咣����(�����́A1878�N�ɂ́u�ؖ����̓m�A�̎O�j���y�e�̎q���v�Ƃ��咣���Ă���)�B�܂��A���_�����̃��r(���t)�ł���A�w���_���Ɠ��{�@��̌Ñ�j�x(�Y�\��w�o�ŕ��A1975)��w�����ɉB���ꂽ���{�E���_������̌Ñ�j�@����ꂽ10�����̓�x(���ԏ��X�A1999)�̒��҂Ƃ��Ēm����}�[���B���E�g�P�C���[��(1936�|)���A�u�`�������_���l�i���k�v�����x���������A�ނ̏ꍇ�A�`����P�Ƀ��_���l�Ƃ����ɂƂǂ܂炸�A�������R�ł̃A�u���n���ɂ��C�T�N�ɍ���������(�䓪�ՁF����Ƃ�����)���z�K��ЂɌ×��`����Ă��邱�ƁA�C�X���G���̌_��̔��Ɛ_�`(�݂���)�̗ގ����A�C�X���G���̍Վi�̕����Ɛ_�Ђ̐_��̕����̗ގ����A�_��̂��P���̎d���ƌÑ�C�X���G���̕��K�Ƃ̗ގ����A�C�X���G���̖����̍\���Ɛ_�Ђ̍\���̗ގ����A���̑����܂��܂ȃC�X���G���̕��K�Ɠ��{�_���̕��K�Ƃ��ގ����Ă���_���w�E���āA���{�l�̐�c�̓V���N���[�h���o�ēn�������C�X���G���́u����ꂽ�\�x���v�̖��Ⴞ�Ƙ_���Ă���B ���R�u(��ɃC�X���G���Ɖ���)��12�l�̑��q�ɋN�������C�X���G��12�x���̂����A10�x������Ȃ�C�X���G�������́A�A�b�V���A�鍑�ɂ���đO720�N�ɖłڂ��ꂽ�B���̂Ƃ��A�A�b�V���A�ɂ���ĕߗ��Ƃ��ĘA�s���ꂽ10�x���̂��̌�̏����͍����Ɏ���܂ŕs���ł���B �����̒��ł́A�\�x���́u�n���僄�[���F�ɔw���ċ������q�Ɋׂ����C�X���G���̖��v�ł���A���̂��ߔނ�̍��Ƃ͖ŖS�����Ƃ���Ă���B�Ȃ��A������ �u�G���~�����v��u�G�[�L�G�����v�ɂ́A�u����ꂽ�\�x���Ɠ�x���̍��́v���a������Ă���A�u����ꂽ�\�x���������ƏI���̓����߂��v�Ƃ����I���a���Ƃ��֘A�Â����Ă���B �����A���ɁA�`�������N�����o�R�œn���������_���l�i���k�ł������Ƃ��Ă��A�ނ������ꂽ�\�x���Ƃ���̂́A���������邾�낤�B�L���X�g�������܂��700�N�ȏ���O�ɁA���_�������痣��ċ������q���s���ً��k�ƂȂ�s���m�ꂸ�ɂȂ����\�x�����A�V���N���[�h�̃I�A�V�X�E���[�g���o��ԂɁA�l�X�g���E�X�h�̃L���X�g��(�i���k)�ɂȂ��ē��{�Ɍ��ꂽ�Ƃ����c�_�ɐ����͂�����Ƃ͎v���Ȃ��B�����ɂ����āA�u���{�l�̐�c�̓C�X���G���̎���ꂽ�\�x���v�Ƃ�����́A�������W(�{���u���{�q�Õv�v)�̋��V�ʐ^���f�ڂ��ăI�E���_��̉�(��̃I�E���^����)�̐M�Ҋl���ɑ傢�ɍv�������w���̌������u���[�v�ӂ�ɍڂ��Ă���I�J���g�I�l��_�̈��ł���A�^�ʖڂȊw��I�����ɒl����Ƃ͂�����B�t�e�n�A�l�b�V�[�A��j�A�S��ʐ^�A�s���~�b�h�p���[�A���\�́A���肢�A�^���b�g�A�m�X�g���_���X�̑�\���A�f������A�x�m�R�唚���A���[�嗤�ȂǂƓ���Ȃ̂ł���B �Ⴆ�A�u�J�S����̓_�r�f�̐��v���Ƃ����邱�Ƃ�����B�����A�Z䊐����u�_�r�f�̐��v�ƌĂ�ă��_���̃V���{���ƂȂ����̂́A17���I�̃��[���b�p�ɂ����Ăł���B�u�փ��f���{�̈�Ղɂ͋e���l�����܂�Ă���A����́�����ꂽ�\�x�������Ñ���{�ɓn�����čݗ��l�𐪕������Ƃ����c���̃��[�c��\���Ă���v�ȂǂƂ����邱�Ƃ�����B�������A�u�e�̌��v���c���̃V���{���ɂȂ����̂͊��q����ȍ~�̂��Ƃł���B�u���{�l�̐�c�̓C�X���G���̎���ꂽ�\�x���v�Ƃ�����́A�����������j�I�o�܂������Ė������āA�����ڂ̗ގ������瑊�֊W��a���o������z�̎Y���ł���B �u����ꂽ�A�[�N(���C)�͈ɐ��_�{�ɕۑ�����Ă���v�Ƃ��A�u���㌕(�N�T�i�M�m�c���M)�v����сu����������(���T�J�j�m�}�K�^�})�v�ƂƂ��ɁA�{���̌���(�������ǂ���)�ɕ������Ă���A�O��̐_���1�ł���u���@�̋�(���^�m�J�K�~)�v(�{���͈ɐ��_�{�̓��{�Ɉ��u����Ă���A�{���̌����ɂ���̂͂��̕����i)�̗��ʂɁA�o�G�W�v�g�L�̒��őn���傪���[�Z�ɓ����č���������̖��ł���u��͂���Ă�����̂Ȃ�(Ehyeh Asher Ehyeh�F�G�փB�G�E�A�V�F���E�G�w�B�G)�v�Ƃ������t���Ñ�w�u���C�����ō��܂�Ă���Ƃ������\���ꕔ�ł͐M�����Ă���B�������A��̒N���ɐ��_�{�̉��ɂ��������Ɠ����ăA�[�N�̑��݂��m�F�����̂��낤���H�Ñ�w�u���C��̕�����l�Ԃ��u��D��v(�~�t�i�V��)���J�����@�̋�����ɂƂ��ė��Ԃ��Ē��ׂ����Ƃ��������̂��낤���H(��)���̎�̉\�́A�t�e�n�}�j�A�������u�m�`�r�`�̋ɔ鎑���ɂ́A����Ȃ��Ƃ������Ă���v�Ƃ����̂ƕς��Ȃ��B�ǂ����āA����ȋɔ�����ꖯ�Ԑl�ɉ߂��Ȃ��t�e�n�}�j�A�����m���Ă���̂��낤���H��ʐl���e�ՂɃA�N�Z�X�ł���̂ł���A����͋ɔ�ł����ł��Ȃ��B�܂��āA���̏�A�t�e�n�}�j�A���̂����悤�ɕč��̈��S�ۏ�㎀���I�ɏd�v���Ƃ���A�t�e�n�}�j�A�����b�h�`�ɖ���_���邱�Ƃ��Ȃ����������ȓ��퐶���𑗂��Ă�����̂́A��ՂƂ������͂Ȃ��B ������ɂ���A�u�_�`(�݂���)�v�Ɓu�_��̔��v�A�u�R�����z�ɂ��Ă��銕�Ёv�Ɓu�Ñテ�_���l���g�ɂ����A���@�������Ă���r�玆��[�߂����唠(�q�G�N���e�B���[)�v�����Ă���Ƃ��Ă��A�����Ɂu���R�̈�v�v�ȏ�̈Ӗ������o�����Ƃ���̂́A�������ȊO�̉����ł��Ȃ����낤�B�@ |
|
|
�������c�_�́A������`�҂̌R���I�c����`�������Â��邱�Ƃ�����B�������c�_�̕��y�E�Z���ɑ傫�Ȗ������ʂ���1�l�́A���䏟�R��(1873�|1940)�ł���B�ނ́A�R�`�����܂�ŕč����w����A����A�L���X�g���̖q�t�ƂȂ����B���̌�A���R��̏����Ƃ��ăV�I�j�Y���^�������邽�߃p���X�`�i�ɔh������A�G�W�v�g�ɂ����Ȃ�̊��ԑ؍݂����B�A����A���{�̒��Ñ�j�̌����ɖv������悤�ɂȂ�A1931�N�ɂ͎����ɂ��鍑���閾�c����w���Ó��{�̃s���~�b�h�x�����s���āu���{�����s���~�b�h(��\�A�a)���˂̒n�ł���A�G�W�v�g�̃s���~�b�h�����{���������������v�Ƃ������������A�L���������s�ؑ��R���̈����R��2��3000�N�O�ɑ���ꂽ�E�K�������̃s���~�b�h�ł���Ɣ��\�����B�ނ́u��ˍ��R�����V���v�������������A�u���{�����̐�c�́A���E�̍����I�l��(�����_���l)�ł���A���Ñ�ɂ����ē��{�͐��E�̒��S�ł������v�Ƃ����Ɠ��̓������c�_���咣�������ƂŒm���Ă���B���䎁�́A���a10�N����16�N�܂Ō������u�_��V���{�v�����s�������A�S���ʼn�������J������A���R�[�h�܂ŏo�����B���䎁�́A�u�_�r�f���̐����Ȏq���ł�����{�̓V�c�������A����ׂ��~���偁�L���X�g�ɑ��Ȃ�Ȃ��B������L���X�g�̐�N�����Ƃ́A���{�̓V�c�����E���x�z����Ƃ����Ӗ��ł���B�L���X�g�̒n�㉤������������邽�߂ɂ́A�p���X�`�i�̒n�Ƀ��_�����Ƃ���������邱�Ƃ��O��ƂȂ��Ă���B���������āA�c�R(�����{�R)�̓p���X�`�i�ɐi�����āA�V�I�j�X�g�̓Ɨ��������R���ʂ���x�����ׂ��ł���v�Ƃ������咣��W�J�����B
�܂��A���c�d����(1870�|1939)���������c�_�̊��U����Ƃ��Ēm���Ă���B���c�d�����́A���͓��{���\�W�X�g����̓`���҂ł��������A�č��V�J�S�̂c�D���[�f�B�[�����w�@�݊w���ɐ���(�����)�̌b�݂��A�č�����A����1905�N�ɓ��m�鋳��(��Ɂu���m�鋳����{�z�[���l�X����v�Ɖ���)��ݗ����āA���̏���ēɏA�C�����l���ł���B���c���̗��������m�鋳����{�z�[���l�X����́A������`�I�X�������߂�ނ̎w��������H���Η�����1936�N�Ɂu���{������v(���݂́u���{�z�[���l�X���c�v)�Ɓu����ߋ���v(���݂́u��Z��c�v)�Ƃɕ��A���c���͍ėՐM����������u����ߋ���v����ɂ����B���c���́u���{�ɂ́A���ÂɃ��_���l���n�����A�ނ�ƌ��Z���Ƃ̍����ɂ���č����̓��{�l�����܂ꂽ�B�L���X�g�����̐�N�����̂ЂȌ^�Ƃ��ē��{�͍����܂ŘA�ȂƑ����Ă����B����͐_�̐ۗ��ł���B���������āA���{�l�ɂ́A�_�̑I���ł��郆�_���l���x�����A���_���l���Ǝ����𐬂�������ׂ������I�g�����_����^�����Ă���v�Ə������B�����ł��A�r�܃L���X�g����̋v�ۗL����(�����i���g�o�ő�\�A�����i���g����M�A�����i���g�E�~�j�X�g���[��\�@�����Ɠ��{�t�H�[������C�u�t�A���{�������������^�����c���)��葩������(���{����c���������C�q�t�A���{�������������^�����c����فE�����ǒ��A���{����c������V���c��b�l��\�A���{���o�C�o�������]�c��)�Ȃǂ́A�������c�_��W�J���A�u�`���͌i���k�ł���A�`�����n���������{�͕������ł͂Ȃ��A�L���X�g�����ł������v�Ƃ������咣���J��Ԃ��Ă���B ���̂悤�ɁA�ꕔ�ɔM���I�Ȏx���҂����������c�_�ł��邪�A�w�E����͍������́u�`�������_���l�i���k�v���͎���l�Ɋւ��Ĕᔻ�����B�u�C�G�X�ɂ����Đ_���Ɛl���Ƃ͍������Ă��炸�A�������Ă���̂��v�Ɛ����A���̗��ꂩ��}���A���u�_�̕�v�ƌĂԂ��Ƃɔ������l�X�g���E�X�h�Ɋւ��ẮA431�N�̃G�t�F�\�X����c�Łu�ْ[�v�ƒf�߂���A���̌�A�����ɕz���������ڂ������Ƃ��m���Ă���B�l�X�g���E�X�h�̒����`���Ɋւ���ꎟ�����Ƃ��ẮA����������1623�N(�V�[�O�N)�ɐ����Ŕ������ꂽ�Ɠ`������u��`�i�����s������v(�ʏ́u�i����v�A���݂͐����x�O�̋������ɂ���)���m���Ă��邪�A�i����ɂ��A�l�X�g���E�X�h�́A635�N(���9�N)�ɓ������A�����̍c��ł��������@�̌������A��636�N�ɔg�z��(745�N�ɑ�`���Ɖ���)�����������Ƃ���Ă���B���Ȃ킿�A�����Ƀl�X�g���E�X�h�̃L���X�g�����`�������̂�7���I�̂��Ƃł���B�Ƃ��낪�A����ȑO�ɂ��łɐ`���͒��N�����ɏZ��ł���A������4�`5���I���ɂ͓��{�֓n�����Ă��Ă������Ƃ��������Ă���B�����A�`�����i���k�ɉ��@�����Ƃ���A����͓��{�ɓn������200�`300�N�ȏ��̂��ƂƂȂ�A�����I�ɒ��낪����Ȃ��B �������������_�ɂ��ẮA���������F�߂Ă���B�������A�u�`���̓l�X�g���E�X�h�̃L���X�g���k�ł���A�����_���l�ł������v�Ƃ����M�O�͏I���ς��Ȃ������Ɠ`������B�������ǂ��ł���A�������ɂƂ��Ắu�`�����l�X�g���E�X�h�̃��_���l�ł������v�Ƃ������͍��̐^���������̂��낤�B �Ȃ��A1948�N(���a24�N)�ɁA�u�����w�����v���ɂ����āu��a��������������̂́A�����̓��k�n��(�����B)�̏��ԍ]��c�]�̕ӂ�ɏZ��ł������k�A�W�A�n�̋R�n����(�v�]��)�ł���B�ނ�́A1���I������ɖk���嗤����쉺���Ē��N�����ɓ���A�����ō������������A����ɕS�ςȂǔ����암�̎O��(�n�A�C�A�ي�)�������ĒC���������Ă��B���̌�A3���I�����ɂ͉���(����)��{���n�Ƃ��đΔn�A���A�}���ւƏ㗤���ċ�B�𐪕��B�����āA5���I����(���_�V�c�̍�)�A�E���̑�㕽��ɐi�o���đ�a�̍������]���A��a�����������v�Ƃ���u�R�n�������������v���\����������w�̍]��g�v���m�́A�������̒�q�ɓ�����B�]�㎁�́u�R�n�������������v���ɂ��ẮA�ꎞ��ςȃu�[���ƂȂ������A1991�N(����3�N)�Ɋ��s���ꂽ�����^���́w�R�n�����͗��Ȃ������x(�m�g�j�u�b�N�X)���̑����͂��߁A�Ñ���{�j�w��l�Êw�ȂǂɊւ�����{�̊W�w��ɂ����Ắu�l�Êw�I�E�����w�I�ȗ��t���������Ȃ��v�u�ߋ��̎��s����I�����̈�v�Ƃ��Ĕے�I�ł���B�@ |
|
|
(��)���@�̋��ɂ���
���@�̋��ɂ��ẮA�u�����l������v�Ƃ��u���������v�Ƃ����b������B�L���ȂƂ���ł́A�u���㕶����b�̐X�L��͈ɐ��_�{�Ŕ��@�̋��������B�����āA�Ñ�w�u���C�����Ł���͂���Ă�����̂Ȃ聄�Ə�����Ă���Ƃ����閧��R�炵�����߂ɁA�ނ͈ÎE���ꂽ�̂��v�Ƃ����\�b������B���̉\�b�̕ώ�Ƃ��ẮA�u���㕶����b�̐X�L��́A�ɐ��_�{�ɕ������Ă��锪�@�̋��ɌÑ�w�u���C�����Ł���͂���Ă�����̂Ȃ聄�Ə�����Ă��邱�Ƃ�m��A���@�̋������J���悤�Ƃ�������ÎE���ꂽ�̂��v�Ƃ����̂�����B�������A�ڂ����������Ă݂�ƁA���@�̋��ɂ܂�邻���̘b�͂��Ȃ�������Ƃ��킴��Ȃ��B �X�L�炪�ÎE���ꂽ�̂́A�ނ��ɐ��_�{�ɎQ�q�����ۂɁA�C�̂܂ܖ{�a�ɏオ�肱�Ƃ��A�X�e�b�L�Ŗ{�a�̌䒠(�z����)���n�l�グ�Ē���`�����悤�Ƃ����Ƃ����L�����C���X�g����ŐV��(�����d��V��[�V���u���{�v�̑O�g])�ɍڂ�������ł���B�ނ��A�؏�咷��(�X�L��̔鏑�������Ă����l���ŁA�ɐ��_�{�Q�q�ɓ��s���Ĉꕔ�n�I��ڌ����Ă���)���w�썑�j�p�x��l�S�u�X�L��搶���Âтāv�ɏ����Ă���Ƃ���ɂ��A���ۂɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��A�X�L��̓g���u���Ȃ��ɐ��_�{�̎Q�q���I�����̂����A�ނ̋}�i�I�ȋ�����v�ɂ��˂Ă�蔽�����Ă����狌�h�͂��̋L�����L�ۂ݂ɂ��āu������s�h�I�v�ƌ��{���ĈÎE�Ɏ������Ƃ����̂��^���ł���B���������̐�̕s�h�L�����f�ڂ��ꂽ�w�i�ɂ́A�����Ȃ̏��ǂł�������̐��肪�A�����Ȃ̏��ǂɈڂ��āA�����鍑��w�ł�����쐬���邱�ƂɂȂ������Ƃ���������B�]���A��͐_�Ж{���ŏo�ł��đS���Ɏ��^���Ă���A���̎����͐_�{�i���z���̊e�_�������̐��v��̑啔���ɏ[������Ă����̂ŁA�_�Б��Ƃ��Ă͑��肾�����킯�ł���B��������D��ꂽ�_�Б�������v�h�̋}��N�ł������X�L��͑����ɍ��܂�Ă����̂��낤�B�X�L�炪�ɐ��_�{���݂�1887(����20)�N�̒鍑���@���z�̓��̒��ɉi�c���̎���֑O�Ő��앶���Y(�����ȓy�؋ǂɋΖ�����R�����m��)�ɏo�n�(����ɂ͙���)�ŕ������h����A�����̐[��Ɏ��S�����͎̂��������A����̈⏑(�a�@��)�ɂ́A���s�ɋy���R�ɂ��āu(�ɐ�)�_�{�͐_�������̑�_�ł���B��N�O�ɐX���������_�{�ɎQ�q�����܂�A�C�̂܂ܐ_�a�ɏオ��A�X�e�c�L�Ō��(�݂�)���͂ˏグ���邱�ƂȂǕs�h�̋ɂ݁v�]�X�Ƃ������B�܂�A�X�L�炪�ÎE���ꂽ�͔̂��@�̋��Ƃ͖��W�Ȃ̂ł���B �܂��A���c�d������������u����ߋ���v�Ŕ��s����Ă����@�֎��u����߂̗F�v(1948�N5��10���t)�ɁA������̖q�t�ł��鐶�c�ڏr��(�������߁E�����)���́u�_����{�v�Ƒ肷�铊�e���ڂ�A���̒��Łu�R�w�@�̍��ߋ`�J���m�����@�̋��ɌÑ�w�u���C������������Ă���A����͂���Ă�����̂Ȃ聄�ƍ��܂�Ă����̂��m�F�����v�Ƃ����b���Љ��Ă���B���������Ȃ邪�A���p���Ă݂����B�Ȃ��A�����Ɂu���t�v�Ƃ���̂́A���Ɍ̐l�ł��������c�d�����̂��Ƃ��w���Ă���B�@ |
|
| ���t�̖��������̂ʼn��t�Ȃ����ƈ▽����č����܂ł����邵�Ēu�������ő�������ς������A���J���Ă��悢�Ǝv���B�ۍ��������ׂ����ł���ƐM����B(����)���͂ǂ����Ă����{�l�̒��ɂ͉����_��I�Ȃ��̂�����Ɗ�������B��������Ƃ��鎖�ɂ�Ă킪���������̐_�̑I���Ƌ����ׂ��W�ɂ��鎖�����A�����肵�Đ^�̐_�����o���M����҂�����Ƃ���K���ł���B(����)���̓��̉��t�v�l�͏�ɂȂ���(������)���Ɍ��o����ɂ́w������鎖�͕K�����ɂ��M�ɂ��シ�ׂ��炸�x�Ɛ悸�����f���Ęb���o���ꂽ�B���̓����̏�Ƃ��Ă͂���͕K�R�̎��ł���B��b�͎z���ł���B����`�w�@�̂r���m���ˑR�킪�����w�@�ɗ��K����Ĕ��Ɍ����Ȃ鎖�����ꂽ�B�{���̂��Ƃ�ƂȂ����ɁA��(���ɂ���)���_�̂Ƌ��ꋋ�����������B���̋��̗��Ɍ��킳��Ă������̂��͂��߂͖͗l�Ƃ̂���ꂽ������͖͗l�ɂ��炸���ċ����ׂ��A�w�u����ł��鎖�������ɂȂ��B������ό������̋��Ƀw�u���ꂪ���܂�Ă���B�R(��)��Γ��{�ɂ����ăw�u����̌��Ў҂͒N���Ƃ������ɂȂ��B�����őI�ꂽ�̂��`�w�@�̂r���m�ł���B�����䏢�o���ɑ����茵��̗��ɂ��̎ʂ��������ꂽ�B���m�������q������ɁA���Ƀw�u����ɂ��āA�����o���y�O�͈�l�߁u��͗L�č݂�҂Ȃ�v�ƍ��܂�Ă����B���m�͌������ɂ��������(���̂�)�����B���Ƃ��ʐ^�ɎB�鎖���ʂ����Ƃ��A���O��������ʎ��Ȃ�ǁA�䂪���t�̂��˂Ă�胆�_���l���Ɋւ��Ă��̖�������Α��������ĉ��t�ɂ݂̂��̌����Ȃ�閧��ł��J����ꂽ���̂ł����B���t�܂��M�̎q���ł���䓙�ɐe�������̔閧�𖾂����ꂽ�̂ł����B�c�����{�����o���̋F��ׂ̈ɁB�����@���ɂ��������Ȃ�v�����ȂĂ��̊���`�������Ƃł��낤�B��������_��Ȃ邩�Ȋ�Ȃ邩�ȁB�R��ƂČ�l���������ɉ䂪�c���̗��j���w�u���ɂ����̂ڂ��Ƃ���ɂ͂���˂ǂ��A�킪���{���u�����̍��ɂ��炴�鎖�v�����͐M������B�₪�Đ_�̍��̗����͖��������ł��낤�B�s�т��̐_���m�炳��Ĉȗ��M�͂܂��傫���V���ɂ��ꂽ���̂ł���B���̒��̉Ɣq�͏I�n�킪�O��������Ȃ��B���t�̐M�������̂������M���ė����B���Ɉ��ꂽ�_�̐����u��͗L�č݂�҂Ȃ�v�͂܂��Ⴊ�]���ɐ[�����܂ꂽ�̂ł����B(����)(�o���y�O�͈�߁|�\�ܐ�)���ɂ͑������̐_�̐��������܂�Ă����̂ł����B(����)���������_�̐����I�I �w��͗L�č݂�҂Ȃ�x ���{�ɉ��čł����ꂽ�鏊�ɂčł��������̂ɍł��������������܂�Ă����̂ł���B���̍��Ɍ����ȗ����̐_�̐����͔�߂��Ă����̂ł����낤���B�w������m�炸�Ƃ����ǂ�ꖼ���Ȃ���Ɏ�������x(�C�U�����l�\��)�Ƃ͔@���ɂ��̎��ɓK�Ȃ鐹���ł��낤�B�w�G�z�o�͓��Ȃ菂�Ȃ�x�ƎO��N�̐̂킪���{�ƃC�X���G�������ы���������ɐS�����ǂ�B�]�X�@ | |
|
�����Łu�`�w�@�̂r���m�v�Ƃ���̂́A�R�w�@�̍��ߋ`�J���m�̂��Ƃł���B���̓��e���f�ڂ��ꂽ���_�ł́A���ߎ��͊��Ɍ̐l�ł���A�{���ɂ��̂悤�Ȃ��Ƃ��������̂���{�l�Ɋm�F���邱�Ƃ͒N�ɂ��ł��Ȃ������B
���C�R�卲�̌��ˈҏd(���ʂÂ��E���ꂵ��)������Ƃ���1952�N���Ɍ������ꂽ�u���P���b��v(�ږ�ɂ́A�����D�Y��������A�˂Ă���)���A1953�N1��25���Ɂu�ݓ����_������v�̊����ł������~�n�C���E�R�[�K�����̎���ŊJ�������ɂ́A�w�u���C�ꂪ���\�Ȃ��Ƃł��L���ł������c���̎O�}�{�a�����ՐȂ��Ă����B�z�[���l�X����̔��苪��q�t���u���@���v�ɌÑ�w�u���C���������܂�Ă���Ƃ����b���Љ�������Ƃ���A�O�}�{�a�����u�^�������Ă݂悤�v�ƌ�����ƁA���Ȃ��Ă����u�����C�u�j���O�j���[�X(Tokyo Evening News)�v���̎x�ǒ�������(1953�N1��26��)�t�̓����ɃX�b�p�������B�W��́A�gMikasa Will Check the Hebrew Words on the Holy Mirror!�h (�O�}�{�����Ȃ鋾�ɂ���w�u���C����������I)�Ƃ������̂������B�������A�O�}�{�a�������̌㒲���̌��ʂ\�����Ƃ����b�͕����Ȃ��B �w���_���Ɠ��{�@��̌Ñ�j�x(�Y�\��w�o�ŕ��A1975)�ɂ����ă}�[���B���E�g�P�C���[���́A���̌��Ɋւ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�@ |
|
| ���ߎ����O�}�{�ɉ�����Ƃ��A�ɐ��̑�_�{�ɕۑ�����Ă���Ƃ������@���̂�����ɁA�w�u���C��̕�����������Ă���Ƃ������킳�͖{�����ǂ����Ƃ������Ƃ�q�˂Ă݂��B(����)�O�}�{�����̂Ƃ��������̂́A�ގ��g���������V���L���̓��e���悭�m���Ă���Ƃ������Ƃł������B�������A�ɐ��̑�_�{�Ɍ��ݕۑ�����Ă���O��̐_��ɂ��ẮA���Ɍ����閧�̕ǂɎ��͂܂�Ă���A���ɐ_���Ȃ��̂ł���A���ɐ_��I�Ȃ��̂ł���A�O�}�{���g���̔��@�����������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�܂��A�O�}�{�������̖ڂŔ��@�������邱�Ƃ�������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�ނ̌Z�ł���V�c�É����A�܂����@�������ۂɌ������Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������B���ݐ����Ă��邾������A���@�������邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł���Ƃ������Ƃł������B������A���ݐ������Ă���l�Ԃł���A���̋��̂�����ɎO�̃w�u���C�ꂪ������Ă���Ƃ������Ƃ��m�F�ł���͂��͂Ȃ��Ƃ������Ƃł������B�@ | |
|
���āA�����œ��t�ɒ��ڂ��Ăق����B�u�R�w�@�̍��ߋ`�J���m�����@���ɌÑ�w�u���C�����Ő_�̖������܂�Ă��邱�Ƃ��m�F�����v�Ƃ��������Љ�����c�ڏr�����́u�_����{�v�Ƃ������e���u����߂̗F�v���ɍڂ����̂́A1948�N�̂��Ƃ������B���c�ڎ��́A���̘b�𒆓c�d�������畷�����ꂽ�Ƃ����Ă���̂�����A���ߋ`�J�������@���ׂ��̂͒��c�����������̂��ƂłȂ�����������B���c����1939�N�ɂ͖S���Ȃ��Ă���B���������āA�������s��ꂽ�̂Ȃ�A���̎�����1939�N�ȑO�̂͂����B
�Ƃ��낪�A�u�����C�u�j���O�j���[�X�v���ɁA���@���ɍ��܂�Ă���w�u���C�������O�}�{�a������������ƕ�ꂽ�̂́A1953�N�̂��Ƃł���B�������S������Ȃ��B �������A�}�[���B���E�g�P�C���[���ɂ��A�O�}�{�a���́u���ݐ����Ă��邾������A���@�������邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł��v��A�u���ݐ������Ă���l�Ԃł���A���̋��̂�����ɎO�̃w�u���C�ꂪ������Ă���Ƃ������Ƃ��m�F�ł���͂��͂Ȃ��v�Əq�ׂĂ���̂ł���B���@���ɌÑ�w�u���C���������܂�Ă���ƋC�����āA�R�w�@�̍��ߋ`�J�����̂��ߋ{���̌����ɏ������͈̂�̒N�������Ƃ����̂��낤���H���������A��ڌ��āu�����A�Ñ�w�u���C�������I�v�ƕ�����l�Ԃ����{�ɉ��l����̂��낤�B ���c�ڏr���������c�d�������畷�����ꂽ�̂́A�u�������c�v�_�ɐS�����Ă������c���̖ϑz�ł͂Ȃ������̂��낤���H�����āA���c�ڎ��ɂ���čL�߂�ꂽ���c���̖ϑz���u�����C�u�j���O�j���[�X�v���̋L���₻������ɂ����C�O�̕Ȃǂƌ����荇���āA�u�O�}�{�a�����A���@���ɍ��܂�Ă���Ñ�w�u���C�����̂��ƂŐR�w�@�̍��ߋ`�J���m���{���̌����ɒ����̂��߂ɏ����A����͂���Ă�����̂Ȃ聄�Ə�����Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�v�Ƃ����b���ł����������̂ł͂Ȃ����낤���H�@ �@ |
|
| ����t�u�E���q�u | |
|
�\��\�������(����\�ꌎ��\�O������)�́A��N���ł������ł��Z���~���ŁA�����\�O�������\�l���ɂ����ẮA���܂��܂ȍՂ肪�s���܂��B
���̈�ɁA�u��\�O��҂��v�Ƃ������҂��̍s��������܂��B��\�O��͐V�����琔���ē�O�����A�����̌��Ƃ����č��������P���Ă��܂��B���̓��A�l�X�́u��\�O��u�v�Ƃ����W�c�����A����H�ׂ��肵�Ȃ��猎�̏o��҂��܂��B ���̓��́A�u��t�u�v�u���q�u�v�ƌ����āA�ߋE�n�����ł́A�O�@��t(�^���@���J�����m�A��C)�A���O��t(�������㒆���̓V��@�̑m�A�nj�)�A�q�ґ�t(�V��@�������I�ɊJ���������̑m�A�q��)���܂�ƌ����A�܂��������q�Ƃ������̑�Ȑl���������瑺�ւƏ�������āA�l�X�̕�炵���������Ƃ���Ă��܂��B �֓��Ⓦ�k�n���ł́A�u����t�l�v�͈�{���̐_�l���Ƃ����n���������悤�ł��B �܂��A�q�ǂ���吨�A�ꂽ�n�������̐_�l�ł����āA���̂��̓��ɖS���Ȃ����Ƃ����n��������܂��B �܂��A���̓��ɂ́A����t�l�̑��Ղ����������߂ɂ��Ȃ炸�Ⴊ�~��ƌ����A������u�ՉB����v�ȂǂƌĂт܂��B ���k�n���ł͂��̂��댃��������ɂȂ邱�Ƃ��悭����܂����A������u��t�u����v�ƌĂ�ł��܂��B ��������ƉB���̐�A�ł�ډB���̐�A���ƌĂт܂��B ����t�l�͏��������D���Ƃ��Ă��āA���̓��ɖK��Ă��邨��t�l�Ɂu��t���v�A�u�������v�Ƃ��������������A�A��Ă��邽������̎q�ǂ������ɐH�ׂ����邽�߂ɁA���Z�̒���Y���Ă��ĂȂ��܂��B �吨�̎q�ǂ������ɐH�ׂ�����ɂ͂��������V��p�ӂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƌ����āA���ɒc�q���h���ċ����镗�K���A�����{�����łȂ��L�����Ⓡ�����ɂ��L�����Ă��܂��B �������匴�S�ł́A��\��̒������c�q�������A���������̖��X�`�ɂ��ĐH�ׂ܂��B �L�����R���S�̑��q�u�c�q�͏����̖��X�`�ɒc�q����ꂽ���̂������܂��B �������c���ł́A�O�@��t��ᚎ҂̎p�����Đ�̖�ɏh�����߂��A���用����卪�ƃJ�u�𓐂�ŗ��ď`�ɂ��ĐH�ׂ������ł��B ����t�̑��͎w���������߁A���̑��Ղ��B�����߂ɐ���~�点�ė����������ƌ����A��\�O���̑�t�u�ɂ͏����ɑ卪�E�J�u����ꂽ�c�q�`��H�ׂ܂��B �������A���̍s���̑�t�⑾�q�͗��j��Ɏ��݂���l���������̂ł͂���܂���B ���Ƃ��Ƃ́A�c��̈�A�u�I�I�C�S�v�ƌ����闈�K�_(�܂�т�)���~���̂����̎��n�Ղɑ��X��K��A���N�̖L������ƐM�����Ă��܂����B �����āA����������ɂȂ����̂��A�I�I�C�S�ɑ�t�⑾�q�̎������Ă��A�������獬�������܂ꂽ�悤�ł��B �t�A�Y�Ă��A����ȂǎR�œ����l�X�́A�u�R�̐_�v���u�I�I�C�S�v�ƌĂсA�_���R�����킸�L���M����ė��܂����B �^�C�V�_�Ƃ́A�_�̐V���Ȃ镜�����Ӗ����ďo������_�̎q�̎��ł��낤�Ɛ�������Ă��܂��B ���𒆐S�Ƃ���_���ł́A�R�̐_�͏t�ɎR����~��Ă��ēc�̐_�ɂȂ�A�H�̎��n�̂��Ƃł͂܂��R�ɋA��_�ł����A�R���̎R�̐_�́A�����ƎR�ɏZ�݁A�R�������Ă���ƍl�����Ă��܂����B �����āA�Y�Ă��̋Z�p���������̂͐������q�������Ƃ��������`�������������Ƃ���A�R�̐_�A�I�I�C�S�̍Ղ肪�������q��O�@��t�Ȃǂ̖��̂����Ղ�ɕω������悤�ł��B ����ɁA�֓���萼�̒n���ł́A��H�⍶���A�Ή��A�����Ȃǂ̐E�l���A�Â����琹�����q��M���A���q�u��g��ōՂ���s���Ă��܂����B ��������Ɠ��l�A���̌��̎O�̓����t�̓��Ƃ��āA�O�����̑�t�A�\�O���𒆂̑�t�A��\�O�������܂��̑�t���Ƃ����������܂��B ���̑�t�͖������ŁA�s���炵�����͖̂����̂��A���ʂł������ł��B�@ �@ |
|
| ���@���Η�������邽�߁A�O�@��t�͐_���̗Z�a�����݂� | |
|
�����g������A�j���������V���~�Ր_�b
�m�Ђ͂Ȃ����A�^���@�̎����ێ����Ă��鏼�����́A�u���ꂩ��b�����Ƃ́A��펯���Ǝ���邪�v�ƒf��A�u�Î��L�A���{���I�Ō����V��(�Ă�)�~�Ղ̐_�b�́A����͗��j�I�������B���̕���͂��ׂāA���������̈��g�������B�הn�䍑�_�����A���}�^�C�R�N�Ɠǂނ���킩��Ȃ��B���}�h�[���R�N�Ɣ������A��a�̍��̈Ӗ��ɂȂ�v�Əq�ׂ��B �܂��A��a�����̍��J���d���Ă�������(�����)�����A���{�S���ɔ_�k�A�@�D���`�����B�ނ�́A���{�����̊�b�ƂȂ郉�C�t�X�^�C����z�����ꑰ�ŁA���̓`���́A���ł��c���Œ����Ɏp����Ă���v�Ƙb���B �{��̍O�@��t(��C)�̘b�Ɉڂ����B�܂��A��C�������ɂ��āA�u�n�������̐g���̋�C���A�����g�ɑI��邱�ƁB���ł̕s�v�c�ȍs���ƁA20�N�A���Ă͂����Ȃ����w�m�̐g���ɂ�������炸�A2�N���܂�ŋA���������ƁB�A����͉B�ق��Ă������A����V�c�̎���ɂȂ����Ƃ���A�p�������ďo���������Ɓv�Ȃǂ������A�u��C���o�b�N�A�b�v����傫�Ȑ��͂������̂ł͂Ȃ����v�Ɛ��������B �����{�̐_�ƕ��̗Z�a�����݂��O�@��t �������́A�܂��A����R�̂ӂ��Ƃ̓V��~�n�Ɍ������ꂽ�A�O���s�䔄(�ɂイ�Ђ�)�_�ЂƁA����R�����́A���(�݂₵��)�_�Ђ��J���Ă���O�����_�ɒ��ڂ����A�Ƃ����B�u����R�͏��l���Ȃ̂ŁA�O���s�䔄�����u�O�����_�v�Ɛ��ʂ��ڂ������J���Ă���̂��v�B �u�V��~�n��т́A�O�@��t�����������ꑰ�̗̒n�Ǝv���A�O�Ƃ́A����̈Ӗ��ŁA�a�̎R���瓿���ɂ����đ傫�ȍz��������Ă���B����́A�Ñ�A���s���ӂ������߂ɒC��(����)�Ƃ��ďd�ꂽ�v�Ɖ�������݂Ȃ���A�u�O�@��t�͍���R�ŁA�����A�����̐��n�̌����Ƃ������́A���{�̐_�ƕ��̗Z�a�����݂��̂ł͂Ȃ����v�ƃe�[�}��W�J���Ă������B ���O�@��t�ƓV��~�n�̂Ȃ��� (�a�̎R���I�̐�s�߂��ɂ�)�u�������{�Ƃ��������Ȃ���_�Ђ�����B�傫�ȃC�`�C�̖ɃJ�}��ł����݁A�J�}���ɋz�����܂��Ƃ��̊肢�͂��Ȃ��A���Ȃ�Ȃ��J�}�͗�����ƌ����`���̂��鋰�낵���_�Ђ��v�B �u�������Έ䒬�ɁA�卑�喽�̑��q�̌��䖼���_(�^�P�~�i�J�^�m�J�~)�������z�K��Ж{�{(���쌧�z�K��Ђ̖{�{)������B�����ɂ́A���������m�̃J�}��A�������_�Ђɂ����������E�������ΓD�Њ�̔�(������)��������v�ƁA�������̓A���o�C�����̂悤�ɁA�O�@��t�ƓV��~�n�̈ꑰ�Ƃ̂Ȃ�������Ԃ肾���Ă������B �������ł͂Ȃ������O�@��t�̐^���@ ����ɁA�u�O�@��t���J�c�����@���́A�����ł͂Ȃ��B���߉ނ��܂͐�c���q�͔F�߂Ă��Ȃ��B�C���h�ɕ�͂Ȃ��B�։��]��������A�ǂ��ɐ��܂�ς�邩�A�肩�łȂ����炾�B��c���q�͒������ˁB�ƌn���d�̕����������ƃ~�b�N�X�����v�Ƙb���B �u�䂦�ɁA�{�n��瑐�(�ق������Ⴍ�����_���ƕ����𗼗������闝�_)�͉���I�ȍl�����ŁA�C���h�ł́A�o�������A�q���h�D�[�̐_�X���A���@����邽�߂ɕ����ɑg�ݍ���(��䶗�)�B��C�́A���̃V�X�e�����������B�V�Ƒ�_�͑���@����\��ʊω����B����ɗl�͔����l�B��t�@���͐{���T�͑�(�X�T�m�I)�ȂǂɂȂ����B�V�c�́A�_��̃g�b�v�Ȃ̂ŁA�����ł͍���̂��v�B �ł́A�Ȃ��A�O�@��t�͐_���̗Z�a�����݂悤�Ƃ����̂��B�������́u�O�@��t�́A�@���������O���ɂ������̂ł͂Ȃ����v�Ɖ��߂���B ������V�c�ƍO�@��t �u�O�@��t�́A�����ŏ@���Ԃ̑����̖��ʂ�m��A�{�n��瑐����w�̂ł͂Ȃ����B�����āA����V�c�Ɂw����[�߂���@�͖������x�Ƌ������̂ł͂Ȃ��̂��B����V�c�́A���Y�����߂Ĕp�~�����V�c�ł�����v�B ���̂悤�ɏq�ׂāA�������͍O�@��t�́w���g�����`�x����������B�w�w�Z�喳�G(�ނ�)�ɂ��ď���(�䂪)�Ȃ�x�́A�F��������Ă���6�̕����́A��ɓ����n�������Ă���Ƃ����Ӗ����v�Ƙb���A�Z��A�l�ցA�O���̉��߂��q�ׂ��B ����ɁA�u������@��~�ȂǂŐ키�̂ł͂Ȃ��A�����̒����m���߂āA���̒��̂��ׂĂ��̂��A��ɉ��������đ��݂��Ă��邱�Ƃ�m��A�g(�s��)�A��(���t)�A��(�v��)�������Ď��s���Ă����B�����ɁA������Ă�����̂������A���g�������̂��̂��v�Ɛ������B �������̓I�[���}�C�e�B �������́u���{�l�͎G�햯���B�A�C�k�Ɖ����ʂɂ���ADNA�Ӓ肩��͓���̃��[�c�����ǂ�Ȃ��B�ꕶ�A�퐶�A���́A���N�A�J�X�s�A�k���A�|���l�V�A�ȂǁA���ׂĂ̖����̌����������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ��A�@���푈�����Ȃ��������炾�v�Ƃ��q�ׁA�����̗ǂ������̂悤�ɑi�����B �u�����Ƃ̓I�[���}�C�e�B�ȏ@���B�����Ȗ����̋V����������Ă���B���A�^���@�͐M�҂������Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���o���������炾�B���M�@���ł���Ƃ������B�������A���{�̃��[�c�����낢���荞�܂�A�m�E�n�E���l�܂��Ă���@���Ȃ̂ł���v�B�Ō�ɁA�O�@��t�̂��^���u�얳��t�ՏƋ����v���������B�@ �@ |
|
| ���l�����ƍO�@��t | |
|
���l�����\��������� / �O�@��t
4�@���ގR ����� �@����@�� �@�O�@��t �����^���@ �������쒬 5�@���s�R �n���� �@���R�n����F �@�O�@��t �^���@�䎺�h �������쒬 6�@����R ���y�� �@��t�@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ��������� 7�@�����R �\�y�� �@����ɔ@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ���������g�s 8�@�����R �F�J�� �@���ϐ�����F �@�O�@��t ����R�^���@ ���������g�s 9�@���o�R �@�֎� �@���ώ߉ޔ@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ���������g�s 10�@���x�R �ؔ��� �@���ϐ�����F �@�O�@��t ����R�^���@ ���������g�s 11�@�����R ���䎛 �@��t�@�� �@�O�@��t �ՍϏ@���S���h �������g���s 13�@��I�R ����� �@�\��ʊϐ�����F �@�O�@��t �^���@��o���h �����������s 14�@�����R ��y�� �@���ӕ�F �@�O�@��t ����R�^���@ �����������s 16�@���s�R �ω��� �@���ϐ�����F �@�O�@��t ����R�^���@ �����������s 20�@��h�R �ߗю� �@�n����F �@�O�@��t ����R�^���@ ���������Y�� 22�@�����R ������ �@��t�@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ����������s 24�@���ˎR�@�Ō�莛(�y������) �@����F �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m�����ˎs 25�@���R�@�ÏƎ�(�Î�) �@�����n����F �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m�����ˎs 26�@�����R�@��������(�y������) �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m�����ˎs 30�@�S�X�R�@�P�y�� �@����ɔ@�� �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m�����m�s 33�@�����R�@������ �@��t�@�� �@�O�@��t �ՍϏ@���S���h ���m�����m�s 34�@�{���R�@��Ԏ� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m���t�쒬 36�@�ƌ؎R�@���� �@�g�ؕs������ �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m���y���s 38�@�A�ɎR�@�������� �@�O�ʐ��ϐ�����F �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m���y�������s 40�@����R�@�ώ��ݎ� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@��o���h ���Q�����쒬 41�@��R�@������ �@�\��ʊϐ�����F �@�O�@��t �^���@�䎺�h ���Q���F�a���s 42�@��ʎR�@���؎� �@����@�� �@�O�@��t �^���@�䎺�h ���Q���F�a���s 45�@�C�ݎR�@�≮�� �@�s������ �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���Q���v�������� 56�@���֎R�@�R�� �@�n����F �@�O�@��t �^���@���h ���Q�������s 57�@�{���R�@�h���� �@����ɔ@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ���Q�������s 63�@�����R�@�g�ˎ� �@������V �@�O�@��t �����^���@ ���Q�������s 66�@��ꇎR�@�_�ӎ� �@���ϐ�����F �@�O�@��t �^���@�䎺�h �������O�D�s 67�@�������R�@�勻�� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�P�ʎ��h ���쌧�O�L�s 70�@����R�@�{�R�� �@�n���ϐ�����F �@�O�@��t ����R�^���@ ���쌧�O�L�s 72�@��q�t�R�@��䶗��� �@����@�� �@�O�@��t �^���@�P�ʎ��h ���쌧�P�ʎ��s 73�@��q�t�R�@�o�߉ގ� �@�߉ޔ@�� �@�O�@��t �^���@�䎺�h ���쌧�P�ʎ��s 74�@�㉤�R�@�b�R�� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�P�ʎ��h ���쌧�P�ʎ��s 75�@�܊x�R�@�P�ʎ� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�P�ʎ��h ���쌧�P�ʎ��s 81�@�����R�@���� �@���ϐ�����F �@�O�@��t �^���@�䎺�h ���쌧��o�s 82�@��R�@������ �@���ϐ�����F �@�O�@��t�@�q�ؑ�t �V��@ ���쌧�����s 85�@�܌��R�@���I�� �@���ϐ�����F �@�O�@��t �^���@��o���h ���쌧�����s |
|
| ���V�l�����\��������䶗���� / �O�@��t
�l�X�����X�����鐢�E�́A���̂̌��S�ƐS�̈�������߂�ׂ̏C�s�̏�Ƃ���Ă��܂�������āA�l�͙�䶗��̗͂ŁA��芮�����ꂽ���ɋ߂Â����������g�����鎖���o���܂����䶗���ꔪ�\�������͏���҂Ɠ�������ŔY�݁A�l���A��荇�����ŁA����҂���䶗���̓��ł���悤�ɂƍl���A�������N�ɁA�Â����珄��̐��n�Ƃ��Ēm���Ă����l���ɏ��݂������N�̗��j���ւ��\�I�Ù����\���������A�_���̗͂����W����䶗��̐��E�����グ�܂����B���ꂪ�l����䶗����Ȃ̂ł��B �l�����\���������A��������s����_�ɂ��Ď��v���Ŏl�����������̂ɑ��A��䶗����́A��������s���獶���Ɏl�������A���m����͎��˖����o�R�����A���g�r�c�ɓ���g���������āA�������̒������̋��ؑ�(���߉꒬)������̒n�ƂȂ��Ă���B 9�@��_�R�@�ʐ� �@���ؒn����F �@�O�@��t �V��@ ���쌧���ʂ��s 20�@����R�@�����@ �@�߉ޔ@�� �@�O�@��t �^���@�P�� ���쌧�O�L�s 28�@�L���R�@�O���� �@����ɔ@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ���Q���l�������s 42�@�@���R�@�ՏƉ@ �@���ϐ�����F�@��O�@��t �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���Q�������s 46�@�ڗ��R�@���ώ� �@��t�@�� �@�O�@��t ����R�^���@ ���Q�������s 47�@�����R�@�����@ �@����@�� �@�O�V��t �^���@�q�R�h ���Q���u���� 56�@��ڗ��R�@�Ό��� �@��t�@�� �@�O�@��t �^���@�L�R�h ���m���l���\�s 57�@���ʎR�@�ω��� �@���ϐ�����F �@�O�@��t �^���@�q�R�h ���m���{��s 67�@�ݔO�R�@�뎛 �@���ϐ�����F �@�O�@��t �^���@�䎺�h �������O�D�s 70�@�܌��R�@������ �@�s������ �@�O�@��t �^���@�䎺�h �������邬�� 75�@�@�ӎR�@�n���@ �@�ڎ�n����F �@�O�@��t �^���@��o���h �����������s 80�@���`�R�@�n���� �@�n����F �@�O�@��t �^���@��o���h �������������s 87�@���h�R�@������ �@�n����F �@�O�@��t ����R�^���@ �������߉꒬ 88�@�����R�@���ꎛ �@�\��ʊϐ�����F �@�O�@��t ����R�^���@ �������߉꒬ �@ |
|
| ���O�@��t���`�����Y�₫�Z�p | |
|
���E�ł��ō������Ƃ�������{�̖ؒY���A���Ƃ��Ƃ͒�������`����Ă������̂ł����B�������{�ɓ`������l�Ƃ��čl�����Ă���̂��A�O�@��t(��C)�ł��B31�Ō����g�ƂƂ��ɓ��ɓn�����O�@��t�́A�Y�₫�Ȃǂ̕��T�����łȂ����w�I�ȋZ�p�Ƃ��ĒY�₫���ړ������̂ł��B�ȗ��A�O�@��t���Z�ݒ������ꏊ�ɂ́A��������Â��Y�₫�q�̓`�����c���Ă��܂��B
�O�@��t��2�N�Ԃ̓������̂��ƋA�����A�����������ꏊ�ł��錻�݂̕��������ɕ{�s�̈�тł́A�ӂ邢�Y�q�����݂��c���Ă��܂��B�܂��A���N��Ɉڏ�����ꠔ��R(���{)�ߕӂł����{�ōł��Â��ؒY�Y�n�Ƃ��ėL���ł��B�����čO�@��t���J��������R����(�a�̎R��)�ɂ��A��������ɂ͒Y�̎Y�n��������������܂����B�����Y�͍]�ˎ���̌��\�N�Ԃ��̍���R���ӂ��琶�܂�Ă������̂ł��B �O�@��t�ɂ���āA�Z�p�A�����ꂽ�ؒY����Z�p�́A�e�n���̌��̓�����A���ɍ��킹�ĉ��ǂ���A�Y�q���l�X�ȃ^�C�v�����ݏo����Ă����܂����B���݂̓��{�e�n�Ɏc��ؒY�Z�p�́A1500�N�߂��̓`���ƋZ�ɂ���ė��ł�����Ă���̂ł��B�@ �@ |
|
| ���O���s�䔄�`�� | |
| �I���O�����I�A�嗤�͏t�H������}�����B�]��ɂ͉z�ƌ��������A���������тɂ��y�B�O�ܐ��I�A���͉z�ɒǂ�ꂽ�B���̑����̌����k�����������o�����͂邩�`���ɓn�������B������P�ƒt�����P�ł���B���Ȃ₩�ȊC�̕��������̍��ɓ`�d�������B���A�����̎g�p�������A���y�J��т����B��l�̕P�̑z���ł͂₪�ēV�Ƒ�_�ƒO���s�P�_�Ƃ��Č��p���ꂽ�B | |
|
���������b
�_�b�Ɨ��j���Ȃ��ĉ�������݂��m���߂�ꂽ�u�������������ɐ�s�����B���̉��q�ł����������́A���l�̎�����������ɉ��ʂ�����ׂ��������̒n�ɋ���A���g�f�����Č�p���̈ӎu�̂Ȃ����Ƃ��������B �����͎�������ƍ����A���̑����ƌĂꂽ�B�Ȃ��`�͎�������̑����̌���ƐM���Ă����B ���t�H����(BC770�`BC402) ���̌�ɏt�H����ƌĂ�鎞��ƂȂ����B�]��ɂ͉z�ƌ��̋����������A���������тɂ��y�B���͑����A�z���Z�̕c��ʼnč@�鏭�N�̌���Ə̂����B�Ƃ��Ɂu�v�ł��邪�u�v�̌�����̂����B�䂪�`���u�v�ł���B����u�v�̘������A�����B�̎���߂ƓƎ��̕������ɂ��悤�B ���a������������� �g�q�]�̓�A���̌i�F�Ŗ������Y�B�͌��␅����Y����B�t�����́A�]��̌������̖����� �Ƃ��Đ������B�o�����͑�����Ɖ]���B���̒n��ꡂ����̘`���Ɏ��� �����\���� �̐��[�ɓ�����B ����d���_�̌̎��@���nj����v���͉z�������ɔs���B BC473�N�A���͉z�ɖłڂ���ABC334�N�A�z�͑^�ɖłڂ��ꂽ�B�Ȃ��^���͎n�c��̐`�ɖłڂ����B ���z�̈▯�́A�g�q�]�ȓ�̊C�݉����ɍ����\�����B���̗l�ȍ��̗���̒��ŁA�����̎�ɒ������z�l���������ꑰ�����͌������o�����Ղ��A�܂��Ɍ��z���M�őD�o�����A�V�V�n�̘`�����������B���z�͉��Â��`���Ƃ͌𗬂�����A�`���ɂ͋��␅��̍z�����I�o���Ă���A�܂��Z���͉��₩�Ȑl�X�ł��鎖���m���Ă����B ����B�㗤 ���B�ɏ㗤�A�o�̑�����P�͂��̒n�ɔ����ĂƂǂ܂�A��ɓV�Ƒ�_�ƌĂ�鏗�_�̌��^�ƂȂ����B��z���̋�͌�(gu)�ł��邩�B���P�̒t�����P�̓~�Y�K�l�̏��_�Ǝ]�����A���Ȃ킿�O���s�䔄�_�̌��^�ƂȂ����B �t�����P���Ղ����ꑰ�͌F�{�̔���� ���� �̊��Ő���z���������̌@�����B �V����(�O���s�P�_��)�̒O���ǍL���́u�O���_�ЂƒO�����v�ɂ��A�O�����̑����͒}�O�̈ɓs�̒n�Ƃ���Ă���B ���̒n�͎הn�䍑�̈ɓs���ł��邪�����ɂ͐���z���͏o�Ă��Ȃ��B�������I�̍��̎�Ȑ���Y�n�͈ɓs�S���ɂ���A�ɓs������l�Ƌ��ɒn�����^�ꂽ�Ƃ̑z��ł���B �ɓs�����̌��Ⴊ�I�B�O������}�y����̌\�g��ɂȂ���A�啪�L��O�����ɂȂ��Ă������Ƃ̌������J������Ă�����B�ɓs���̎��_�̍����_�Ђ̍Ր_��O���s�P�ƌ��Ă�����B���ɋ���������ł���B�ɓs���̊��͎��x(�ɂ�)�Ɖ]���A����͒O���ɒʂ��邩�B ���啪�ő傫���z�������� �啪 �ő傫���z�����A�P�Ǝ����͈ړ������B���̃T�C�g�ł͒����\���������C�����[�g�ƍl���A�O���s�P�ꑰ�̖���͋I�̍��ɗ������������̂ƌ��Ă���B ���C��n��l���֍s���A�ꕔ�͍L���Ɉړ����� ���_�̌���ɐV���Ɏ��ۓs�䔄�����ꂽ�B�L�� �ֈړ����������͐Ό��E�o�_��d���ւƐi�o�����B ���{�C���ɏo������t�B�͍Ăёc�_�O���s�䔄��ď�� �A�O�� �Ɖ��݂�k�サ�āA ���� �ւƍz�������߂čs�����B ���O���s�䔄�͒����\������i�� �l�� �̊e�n�ōz�����E�̌@���s���ړ������B�l���͋�C�̐��܂ꂽ�y�n�ł�����A����R�^���@���O����_���Ă��i�o���Ă���A��d�\���ɂȂ��Ă���悤���B ���W�H���o�R���a�̎R�� �W�H ���� �I�m�� �ɏ㗤�A�X�ɋI�m��㗬��ڎw�����B�z���̑����I�m��㗬�ɋ��_��݂��A���I�A��I�A�ޗnj��� �g��E�F�� ���ʂɐ��͂�L�����B���ɋI�m�쉺����ɂ͓y�n�̍��J���i�閼���䔄�̂��ƂɌ�q�ł��� ������Ö� �𖹗{�q�ɓ���A�I�m��̎����ł߂��B�I�m�쉺��������z���Ă����\�Җ��̌R�c���O���s�P�̏W�c������A�����䔄���X ���� �����B ���_�Ƃ��č���ɒ��� ���������d�ˁA�O���s�P�ƈꑰ�̌���́A�z�����s�����钆�ŁA�k�n�J��ɂ��]�����A �I�m�여�� �����ł͂Ȃ��A �L�c�� �A�����여��̍̎�Ǝ����ɂƂ߂��B���̂�����ł́A�����̎��荑�y�J��̐_�Ƃ��Ă̒O���s�䔄�����J��_�Ђ������B�z�����s���A�ꕔ�� �d�� �Ɉړ������B |
|
|
����������߂čX�ɓ���
�O���s�䔄�����l�X�́A �O�d �A �� �A ���� �A �É� �A ��t �A �Q�n �ւƍz�������߂Ĉړ����Ă������B ���P�̌���A�_�������ő��Ƃ����n�����@�O�~�˔ȁA�����˔Ȃł��� �����Œ����F�ɔj�ꂽ �_���R �� �I�m�쉺���� �ɓ��������B�����Ő_���̌Z�̌ܐ������͂��A�Ȃ��Ȃ�A �}�R �ɑ���ꂽ�B����A�_���R�͂��̒n�𐧈����ׂ������R�����_�Ƃ��Ă��������˔Ȃ̌R���U�߁A�����˔Ȃ͐_���R�̐V�������S�Z�p�̑O�ɖłы������B �����˔Ȃ̈�͓̂��A���A���Ƃ��ꂼ�ꑒ���A�J��ꂽ�B�_���͋I�������̒n�̎x�z�҂Ƃ��Ďc���A�_���R�͊C�݉����ɓ쉺���A �I��̒n �œ����Ƃ��m�炸�O�~�˔Ȃ��n�����̂ł���B�O���̈З͂̂����܂����͐_���V�c�̌�p�̑���(�V���V�c)�ɐ_�ْ��쎨�̖��ɟْ�(�O��)�Ƃ��Č���A���̓V���V�c�̓V�ْ����i�^�l�ƕq�B�V�c�ْ̟��q����~�ɂ��o�ꂷ�鎖�ŁA���̐_�Ђ������Ă���ƌ����悤�B ���I���̒n��Z�a�� �O���s�䔄���́u�C�v�̕������̏o���ł���B�I���͂��̌Õ�����̔n�h�̏o�y���������悤�Ɂu�n�v�̕������̎����ł���B�I���̑c�͓V�������Ƃ���Ă��邪�A�喼����Ö������̎l���̑��Ƃ��Ă���B���̖��� ���O�{ �����̎Вn�ɑJ�����A �ɑ��V�]�_�� ���R���ɒǂ�������Ƃ����B�y�n�ň��|�I�ȐM�]�Ă��������˔Ȃ̌�Ɏx�z�҂Ƃ��č������I���͖����䔄���J��ƂƂ��ɁA���̑c�_��������Ɛ�`���A�n��Ƃ̗Z�a��}�����̂ł��낤�B ���O���s�䔄���͋L�I�ɂ͏o�Ă��Ȃ��_�ł��� �V�Ƒ�_�ƒO���s�䔄�����o���ł��鎖�͊��ɐ_���R�ɂ͖Y�ꋎ���Ă���A���̌��ʁA�O���s�䔄�ꑰ�����W���Ă��܂����B���̎��ŁA�O���s�䔄�����L�I�ɓo�ꂳ���鎖�͏o�����A�킸���ɒO�~�˔ȂƂ��ēo�ꂷ��̂ł���B ���O���s�䔄���͉��L�̒n����J���Ă��Ȃ� ���B�A�����A�R�A�A���Q�A���A�����{�̑唼�B�V�����̐��́A�������̐��́A�o�_�̐��͂̑傫���n��ɂ͕ʂ̋����̌@�̈ꑰ�������̂ł��낤�B �������{�I�̖����䔄�� ����(�C��)���Ƃ̊W�ł́A�V���R���̌ܐ��̑��̌��l�ږ��̔܂Ƃ��Ē������P�̖����o�Ă���B��ȋM���̘Z�����̖L��C��̖��̍ȂƂ��āA�I�����q���]�̖������P�̖����o�Ă���B �����y�L�̒��̒O���s�䔄�� ���ےÍ����y�L���@�_���c�@���}�����ɍs�K����Ƃ��A�_��̏����ɐ_�X���W�߂��B���̐_�̒��ɔ��z���̐_���܂����Ă��āA�����̏Z�ގR�̐���̂��đD��A���̑D�ɏ���Ă����ƍK��������A�Ƃ̐_�����������B ���d�������y�L���@�_���c�@���V�������ɕ������A�W�܂����_�X�̒��Ɏ��ۓs�䔄��������A������ǂ��J���Ă����Ȃ�ΐԓy��^���悤�ƌ������B���̐ԓy��D�̂Ȃǂɓh���ĐV�����U�������B�A�Ҍ�A�_���c�@�͎��ۓs�䔄�����I�ɍ�����̓���̕��ɒ��ߕ�����B���őD��A�D��ԓy�Ŏ��ƌ����`���́A�̐_�ł��肩��D�O�ɑ��_�Ƃ��āA�_���c�@���d�����J�����Ƃ���Ă���\�Җ���z�N�����߂�B�_���c�@�ƋI�ɂ̍��Ƃ̊W����̐��b�Ȃ̂��A�O���s�䔄���ƌ\�Җ��Ƃ̊W���������b�Ȃ̂��A�����̑����Ƃ���ł���B ���d���ֈړ������� �܂��A�Z�g�_�Ƃ̊֘A�������悤�ł���B�����̒n���A �ɒB�_�� �ƏZ�g��ЂƂ̊֘A������B*1 �u�Z�g��А_��L�v�ɋI�ɍ��ɓs�S�@�O�����V��͒j�E�ӋC���X���E�Z�g��_�Ƃ���B�Z�g��А_��L�͕����O���ȍ~�̋U���Ƃ���Ă��邪�A ���̒��̒O����̐��ɂ͒O���s�䔄������J��������̕�������Ƃ���Ă���B �x�M�������̒n�ł́u�v���Z�g��A�z�����邪�A�ԓy�̒n�Ő���⊌�S�z���o�Ă����悤�ł���B���̒n�œS������Ă����D�؎����d���ֈڂ�ہA�O���s�䔄���l�X���d���֑J���Ď���s�䔄���J��l�X�ƍ��������Ƃ��v����B |
|
|
���O�m���N(816)��C�͍���V�c���獂��R��������
����R�̒n����C���O���s�䔄����������b�͓��ނ���B�O�����_�̓y�n����@��C����n�����߂đ�a���F�q�S�܂ŗ����Ƃ���R�̌����Ȃ��j�ɂ������B��j�̋��͂ő召��C�̍������ē����A�I�ɂƂ̋��̐�ӂňꔑ�����B �����Ɉ�l�̎R���������C���R�֓������B�R�̉��A�O�����_�E�V��{�̐_�ł������B���̋{�̑���ɂ��O�����_�͎����̐_�̂���C�Ɍ������B �ؗp���̐��b1 / �O�@��t�͍��얾�_����\�N�Ԃ̊����t���Ő_�̒n��������A���̌㖧���ɏ\�̏�ɓ_�������Đ�Ƃ����B���얾�_���\�N��Ԋ҂����߂����A������ɉ����Ȃ������Ɖ]���B �ؗp���̐��b2 / ��N�̎ؗp���Ŏ�����A���l�Y�~����̕�����H���j�����̂ŁA�i�v�Ɏ�A�Ԋ҂����Ƃ��ǂ��Ȃ����B�@ �����̌�̒O���s�䔄�����l�X �V�����b��Z�p�̓`�d�A�X�ɐ���z���̌͊�����A�O���_��鑽���̐l�X�͔_���Ƃ��Ė����̒��ɋz������čs�����B����ł���̐��Ő���������l�X�͒O���s�䔄�����J��A�z���̐s���Ȃ����Ƃ⒆�ł���g�����ׂ��F�����̂ł���B����A�O���s�䔄������㦏ۏ��_����ɉJ�t(������)�ւƕϑJ�����J����ꍇ�����������B����R�n�^���@�̐i�o�ɓ������āA�O���_�Ђ̒����n�ɑ_����t���ďo�Ă���ꍇ������B(�d���A�y��) �܂��P�ɐ^���@�����ł͂Ȃ��O���s�䔄�M�Ƃ��ǂ��i�o���Ă���ꍇ������悤���B(���Γ�) ���������Ǝo���@ ������̐��́u�P�v���ł���B���̑����͂��̉Ƃ̏o�ł���P���Ǝv���Ă����B �ޗǎ���̓��{���I�̍u�`���̎���ɁA�c���̐��́u�P�v���ł���ƍu�t�������Ă��� �B�����{�̌Ñ�1�`�l�̓o��(�p�쏑�X) �O���s�䔄�_�� �ł͓V�Ƒ�_�ƒO���s�䔄���͎o���ł���Ƃ̐��������Ă���B�㐢�̕t����m��Ȃ����A�_���c�@���I�ɍ�����̓���̕��ɑ�_����ߕ�������A���̕t�߂͓��ɑ����A���ɒO���삪�����B������A�t�����Ɉ���ŕt����ꂽ���O�Ƃ���A���Ȃ��������̂ł��Ȃ������`���ł���B ��a�𒆐S�Ƃ��āA�����\�����̓��Ɉɐ��_�{�A���ɓ��O�{���������Ă��邪�A���O�{�̍Ր_�̓��O��_�Ƃ͒O���s�䔄����������Ȃ��B������A�o�q�ƂȂ�B���{���L�ɂ��A�B���O�{�̌�_�̂̋��͈ɐ��_�{�̋�����ɏo�������̂ł���B�̂͑o�q�͐�ɐ��܂ꂽ�������Ƃ��ꂽ�B���O�{�̍Ր_��O���s�䔄���Ƃ���A�܂��ɋI�m���̈�{�ɂӂ��킵���B �F�ɂ�g��̋������̎悵���͔̂w�G�ɏZ�ޓn���n�H�l�Ƃ̌���������A�q�m�N�}�łȂ���B �������䔄 �c�a�O���_�Ђ̎Г`�ɂ́A�O���s�䔄���̌�q�̍��얾�_���܂��̖���喼����Ö��Ƃ��Ă���B�a�̎R�ɂ͖�����Ö��Ɩ����䔄�����J��_�Ђ������� ��������B����̌@�Ǝ҂͖��ɗ{�q���}���Ƃ������A���q�͊O�ɏo���̂�����ł������B���ł�����q�����A���̌q����͖��ɑ������B����̓`��(�M���j�Y)�B ���n�́u�C�v�̕����ł���B�����S���_���̒O���_�Ђ̎�_�͒O���s�䔄�_�ł���A�z�_�Ƃ��ĒO���s�F�_���J���Ă���B ���ҌR�c�@�\�Җ��Ɠ��{���� �\�Җ����J��ɑ��V�]�_�Ђ̉��{�͒O���_�Ђł���A�O���s�䔄���ƒO���s��Ö��ɓV�Ƒ�_��z���Ă���B�ɑ��V�]�̎Вn�́A���̓��O�����_�{�̒n�ɂ������B�I�m�쉺����̗v���ł���B �\�Җ����J��_�� �ƒO���_�ЂƂ͍���A�̔�ˁA�Q�n�A�a�̎R�̋I�m��E�L�c��ɒ������A�\�Җ��������Ɉʒu���Ă���B����͎Y���̗A���A�h�q�̓�ʂ���Ó��Ȕz�u�ƌ�����B |
|
|
����B
���ꌧ�@���ÌS�@��쒬�@�O����(���Ɂ@����@����c�@����)�O���_��(�Ր_�@�O���s�䔄��) ���ꌧ�@���ÌS�@���c���@�n�ꉺ(���ɑ呐)�O���_��(�Ր_�@�O���s�Q��) �����́A�O����A���c��̏㗬�Ɉʒu���A���̉����� ���ꌧ�@�n���S�@�L�����@�ӓc�̈�_��(�Ր_�@�V�_�A�\�Җ��A�剮�s�� ����) ���ꌧ�@�n���S�@���Β��n��̍ȎR�_��(�Ր_�@�S�ÕP���A�S�ÕF��) ���ꌧ�@���ÌS�@���NJx�̑��ǛԐ_��(�Ր_�@���X�n���A�\�Җ��A��R�_�� ) �Ȃǂ��������Ă��܂��B ���֓� ��ʌ��@���ʌS�@���̈��ڐ_��(���O����) ��ʌ��@���ʌS�@�_�@�Z����̒O���喾�_ �Q�n���@����S�@���꒬�@3��(�����A���c�A����)�̒O���_�� �Q�n���@����S �S�Β��@2��(�⌴�A��@�����O��)�̒O���_�� �Q�n���@�x���s�@���O���@���Z���c�̒O���_�� �_�����L��̏㗬�ɂ���̂ɑ��āA���̉����ɓ����� �Q�n���@����S�@�g�䒬�@�_�ۂ̐h�Ȑ_��(�Ր_���{���V���A�\�Җ�) �����s�@�����@���c�{�A���׃���ˁA�������̖�V�{�_�ЁA����̒n��_�Г��������Ɉʒu���Ă��܂��B ���ߋE �ޗnj��@�ܞ��s�@�㍇�̑剮��Ð_��(�Ր_�@�剮�F��) ���O���삪�I�m��ɍ������鏊�ɂ���܂��B �a�̎R���̒O���_�Ђƌ\�Җ����J��_�Ђ��قړ��l�Ȉʒu�W�ɓ�����ƌ�����ł��傤�B�\�Җ��͍���Ŕ��������������߂Ă��邪�A�O���s�P�̂ƃ��}���X�ł���Ίy�����b�ł���B�Ȃ��A���{�����ƒO���s�䔄�����J��_�Ђ���r�I�߂��ɒ������Ă���B ���I��̃j�V�L �O�d���I�����т���{�̓�F�ȂǏ���������B������ɂ���A����E�g�삩��F��͒O���s�䔄�̎x�z���ɂ���A�����ŕP�͐�����̂ł���B ���_���Ɖ��_ �����̎�l����_���R�Ƃ��Č�������A�����_��鉞�_�R�ł������\��������B�I���̋R�n�����I�̕��K�A�I�m���ɑ����_���c�@�A���_�V�c�̓`���Ɣ����_�Ђ̐��������������Ă�����̂Ǝv����B �@ �@ |
|
| ���|���X�� / ������^�� | |
|
���Z�g����܂�
�������A�����Ƃ���������̗��j��R�����Ă����ƁA�܂��͓��{���I�ɕ`����Ă����߂��K���o�ꂵ�܂��B ���{���I�����\��A���ÓV�c�̒i�ɕ`����Ă���̂́A �O�N�Ďl���A�����A�Y�����W�H���B�����́B ���ÓV�c3�N(595)�ɁA�W�H���ɒ����̍����Y�����A���l���m�炸�ɐd�Ƌ����}�Ő�������A�ǂ������Y�킹���̂ŁA�s�v�c�Ɏv���Č��サ���A�Ƃ�����b�ł��B���̍��ɂ��ẮA���̌㐹�����q�����̍����畧�������o���ċg��ɔ[�߁A��ɂȂ��Ė@�����ɔ[�߂�ꂽ�Ƃ�����b���c����Ă��܂��B�����Ƃ��������q����点���Ƃ���镧�����A���a�Ɉ��u����Ă�����̂��A���邢�͕ʂ̕������͐F�X�Ə���������悤�ł��B ����Ɋւ�����j��R�����ƁA�܂��͕����Ƃ̊ւ��|�@�����Ɛ������q�̘b�|����n�܂�悤�ł��B���āA�W�H������͂��̓s�܂Œ������^��܂����A���炭�͂��̓��̂�Ɠ��������{�ōŏ��̊����Ƃ�����|���X������������܂��B���̒|���X���́A���{���I�ɂ��ΐ��ÓV�c21�N(613)�ɐ������ꂽ�Ƃ���܂����A�͂��߂Č��@�g��������̂����{���I�ɂ���607�N�A���������@���ł�600�N�A���炭���@�g��h��������A�ԗ���@�̎g�߂Ȃǂ��������߂ɂ����������̂ł��傤���B ����ȑO�̎��ォ��A���݂̏Z�g��Ђ̂���ꏊ���C�̌��ւƂ���Ă����悤�ŁA���N��������̎g�߂Ȃǂ����̓�g�̒n����̓s�������������ł��B�����Ē|���X������������Ă���A���悢�挭�@�g�A�����g�ɂ���ĕ����̕������s�ɉ^��邱�ƂɂȂ�܂����B ���ł������p�����ߗ��Ă��āA�Z�g��Ђ���C��Ղނ͓̂���ł����A���Ă͑����D�̉����œ�����Ă����낤�Ǝv���܂��B������������Ɍ������āA���̍�s�̒��S��������ɊJ���_�Ђ�����܂��B���̊J���_�Ђ͏Z�g�̉��@�Ƃ������A�Г`�ɂ��ΐ_���c�@���A���̒n�ɉ��y�V���_���J��ׂ��Ƃ̒���ɂ���đn�����ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���炭�͐��ÓV�c�̎�������ȑO����Z�g��ЂƊJ���_�Ђ����Ԋ�����������Ă������ƂƎv���܂����A���̊J���_�Ђ��|���X���̐����̋N�_�������ł��B ������^�X���Ƃ͌����Ă��A����͔���̍��̂��ƂŁA���̌�̓ޗǎ���܂ł͗ǂ��Ƃ��āA��������ȍ~�͂��܂艏�������Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����A����ȕ��ɍl���Ă��܂������A�ǂ��������ł��Ȃ��悤�ł��B �|���X���͓s���ޗǂ⋞�s�Ɉڂ�A�퍑����̑�������]�ˎ���ւƎ�����o�Ȃ���A�����Ƃ��Ă̖������I���Ďp��ς��Ă����܂����B�������Ȃ���A���̂��Ă̊X���ɉ����ėl�X�ȕ�����Y�����݂܂Ŏc����Ă��܂��B�ŋ߂ł́A�n��̗��j�̌������Ƌ��ɁA�|���X�����������ł�����������Ă��܂��B�F�X�Ȏj�Ղ⌾����H���Ă����ƁA���X�ɂ��Ă̒|���X����ʂ��āA����̒��ł�������ς��čs������̕��������̊X����ʂ��ėl�X�ȏꏊ�ɉ^��Ă������l�q�����������܂��B ���q����A����܂ł̕�������ɂ͋M���̚n�݂���������̕������A���Ƃ̕����̒��ɏ�������������A��������ɓ���ƋM�������̃��o�C�o�����ۂ̂悤�Ȍ`�ň�ĂɑS���Ɋg�U����Ă����������ł��B�����āA���̎����A��͊����Ȗf�Փs�s�Ƃ��ĉh���A�䂩��S���ɍ�����͂����钆�A��a���|���X����ʂ��ėl�X�ȏꏊ�ɉ^��Ă����܂����B�����ĖL�b�G�g�̎��ォ��ւ������o�č]�ˎ���Ɉڂ�ƁA����܂ł̍���̕����������Ɏp��ς��āA�S���ɍL����悤�ɂȂ�܂��B���̎��ɂ��A��Ɠޗǂ����Ԓ|���X���͏d�v�Ȗ�����S�����ƂɂȂ�܂��B �������j�̒��ŁA�l�X�Ɏp�������āA�������S���ɁA�����čL���Љ�S�̂Ɋg�����Ă�������̕��������̊X����ʂ��Ē��߂Ă��������Ǝv���܂��B�@ |
|
|
���|���X���̍���
�|���X���́A��s���̊J���_�Ђ���m����˂ŗL���ȕS�㒹�R�Õ��Q���āA���䎛�s�ɂ���_�c�����{�̂����T��ʉ߂��đ��q���ɓ���܂��B���̑��q���͌Â�����u�߂v�Ƃ��Ă�Ă��܂����B20�N�قǑO�ɋ߂����ق��J�ق��āA���̖��̂������S���I�ɒm����悤�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ǝv���܂��B�߂̗R���́A�Î��L�ɋL����Ă܂����A��g�̕����猩�Č��݂̓ޗnj��̖��������h���h�A�H�g��s��������h�߂h�Ɩ��t���������ł��B ���̑��q���́A�������q�ɗR�����閼�O�ł����A�������q�̕揊�Ƃ����b������A���ꑼ�ɂ����ÓV�c�˂⌭�@�g�̏��얅�q�̌Õ���悪�c�������j��Y���c�钬�ł��B���ł͐Â��Ȕ_���ł����A�|���X���̂��Ă̎p���悭�c����j�����������܂��B ���R���z����Ɠޗnj��ɓ���܂����A���R�̘[�ɂ͖@�����ƕ��ԌÙ��Œm���铖����������܂��B�����̏W���ɒ��ɂ��钷���_�Ђ��|���X���̓����̏I�_�ɂȂ�A�ޗǖ~�n�𓌐��Ɍ��ԉ���H��i�ނƔցA�k�シ��Ɠޗǎs�X�ɓ���܂��B�ޗǖ~�n�̓쐼�ɓ����̒��������āA�k�ɂ��Ă̓ޗǂ̓s������܂����A���̓r���ɖ@�����ŗL���Ȕ���������A���Đ������q�������\�����{���������ꏊ�ł��B ���{���I�ɂ��A�|���X�����������ꂽ�Ƃ��A�������q�͐��ÓV�c�̐ې��Ƃ��Ċ��Ă��������ɓ���̂ŁA���傤�ǐ������q����̎j�Ղ��X���ɉ����đ�R�c����Ă��܂��B���s���Ő������q�ɉ��̂���j�ՂƂ����A�l�V�������L���ł����A�ޗǂɔ�ׂ�Α��s���s���ɉ��̂���j�Ղ͏��Ȃ��悤�Ɋ����܂��B ��ɋ߂��Ƃ���ł́A�Z�g��Ђ̂����߂��Ɉ�^��������܂��B���Ă͈�т����w�m�ȂǑ����̉��������������킢���ꏊ�������͂��ł����A�����������Ă̖��c�肪�����Ɋ�������Ƃ���ł��B ���̈�^���̉��N�ɂ��A�������q���������āA42�̎����̒n�Ɏ���̖���̈Ӗ������߂Ď������������ē]�@�֎��Ɩ��t�����Ƃ���Ă��܂��B�Z�g�ɂ���R������Ù��Ƃ������ŁA�q�C�̖����F������˂ė��̍��m�����̎��@��K�ꂽ�����ł��B���厛�̍Č��ɖz�������d����A�@�R��l���ꎞ���؍݂��Ă����Ƃ������ꂪ�c����Ă��܂��B �����āA���̎��@�ɂ͂����ЂƂL���m���Ă���Ƃ���ł́A�ԕ�Q�m�̑�Γ������ǗY�A���̎q�̎�x�Nj��A����g�E�q��̎O��̕悪�J���Ă��܂��B�{���̐ԕ�Q�m�̕�͓����̐�x���ɂ���܂����A�Ȃ����̏Z�g�ɂ��J���Ă��邩�Ƃ����ƁA�����̗��R������悤�ł��B ����̕��ꂩ��͏�������Ă��܂������A���s���ɂ͎v�������Ȃ����j��Y���d�Ȃ荇���悤�ɊX���ɗn������ł��܂��B�J�����ڊo�����V��������Z�g��ЁA��a����o�č�ɐi�ނƍ��ł͉�������̎c��Z��n�ɂȂ�܂����A�������ƎU�Ă����ƁA�܂��܂��F�X�Ȃ��̂������肻���ł��B�@ |
|
|
���V������A�Ӑ^�a�����^����
���厛�̐��q�@�ɓ`��闖���҂Ƃ������̖��O��m���Ă���l�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B���q�@�ɓ`����Ă���Ƃ������ŁA�����V�c�̎���ɓ��{�ɓ`������ƌ����Ă��܂����A���ۂɂ�9���I���̂��̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B���̌��͎҂���������A���ɑ����`���A�D�c�M���A�����V�c�̎O�҂ɂ��Ă͐������ꏊ�ɕtⳂŖ��O�����L����Ďc����Ă��܂��B�����̒��ł��ō����̉����ł���Ƃ���Ă��܂��B �����ɂ悵�@�ޗǂ̓s�́@�炭�Ԃ́@�ɂقӂ����Ƃ��@������Ȃ�@����V(���̂̂���) �O�悵�̖�������n�܂邱�̉̂́A���鋞�ɑJ�s���Č��z���b�V���œ�����Ă���s�̗l���������ꂽ��ɕ{�ʼn̂������̂Ƃ��ėǂ��m���Ă��邩�Ǝv���܂��B�X�����ޗǎ���A�����Ƌ��ɗl�X�ȐV�������������{�ɓ͂����܂������A����̕�����������������ɐV���ȓ]�������}���܂��B �Ӑ^�a���́A���{�����ɕ������L�߂邽�߂ɁA���x�����܂��Ȃ�����ŏI�I�ɖK��邱�Ƃ��o�����Ƃ��������R�Ɨ�������Ă��邩�Ǝv���܂��B�������q�̎��ォ��S�N�قnjo������̂��ƂɂȂ�܂��B�Ӑ^�a���͉����̑m�Ƃ��ē����̓����@��Ə̂����悤�ȍ��m�ł������A���̍c��̖��ɋt�炢�Ȃ�����A�m���ƂȂ邽�߂̎���ƁA���d�@�̐ݗ��̂��߂ɑ�ςȋ�J�̖��A�������邱�ƂɂȂ�܂����B ��l�̖ڂ𓐂݂Ȃ���5����n�q�Ɏ��s���A6��ڂ̌����g�D�̋A�H�ɓ��悵�āA�悤�₭���{�ɓ������܂��B�ŏ��Ɏ������̖V�Âɏ㗤���A��ɕ{�A�l�����o�đ��̓�g�Âɓ��`�A��a�삩�痄�������ċ��s�ɓ����Ă���ޗǂɉ����ēs���肵���Ɠ`�����Ă��܂��B�c�O�Ȃ�����ɂ͊Ӑ^�a���̑��Ղ��c�����̂͂���܂��A�r������������Ƃ����l���ɉ�����������܂��B���̌�A����V�c�̒���ɂ��O�@��t�����������Č���Ɏ����Ă���Ɠ`�����Ă���A�l�����\���ӏ���84�Ԗڂ̗��ƂȂ��Ă��܂��B �܂��Ӑ^�a���͈��̒m�����L�x�ŁA�����̒�ɖ�������č͔|���A�����̖⍁���̒����Ȃǂ���{�ɓ`�����Ƃ����Ă��܂��B���݂̂����̒��ɂ͑�R�̊��������������Ă��܂����A�����Ɩ�͌�����H��Γ�������ɂ�����܂��B�܂������̖͌��݂ł��厖�Ɉ�Ă��A���{�ɒ�����w�𐳂��������炵���ŏ��̐l�Ƃ���Ă��܂��B�������ĊӐ^�a���ɂ���ē`����ꂽ�l�X�ȍ����A��̕�������ɓ����ċM���̂����Ȃ݂ƂȂ�A���݂̍����Ɏp����Ă����܂����B�@ |
|
| �@ | |
|
���k�̂ɂقւ鍁����
�ޗǂœV���������₩���������A��������l�X�ȕ����Ƌ��ɁA��R�̍�����Ƃ��Ē��d����A�����Ɏ������܂�܂����B���厛�̐��q�@�ɂ́A�����̉₩�ȗl�q�����ɓ`�����Ă��鎖�͂悭�m���Ă��邩�Ǝv���܂��B ���āA����͕�������Ɉڂ��āA�O�@��t���������̘b�ɂȂ�܂��B�O�@��t�Ƃ����A����Ƃ������얀���C���[�W�����m��܂��A����ɂ܂��b�ł����A����̐ΎR���̍���Ɏw�肳��Ă���u�O����(�ɂ����̂��傤���傤)�v�Ƃ������o������܂��B ���ꌧ�ɂ���ΎR�������̑c�ł���A����E�M���̐M���W�߂��O�����~�S(�����䂤�@890�|953)�̃G�s�\�[�h�ł��B921�N�A�~�S�́A���V�c�̖��ɂ��t�̊ό��m�����A����R�̍O�@��t�_�֎Q������ۂɐ������邱�ƂɂȂ�܂����B���̎��A���肵����t�̕G�ɋ��R�G�ꂽ�~�S�����̎�ɁA���̖F�����ڂ�A���܂ł������邱�ƂȂ��A���̎�ŏ��ʂ��ꂽ�����ɂ����̍��C���ڂ����Ɠ`�����܂��B���̏~�S�M�̐������u�O�����v�ƌĂ�A�ΎR���ł�����ȊO�͌��邱�Ƃ�������܂���ł����B �~�S�́A�������̃��f���̂ЂƂ�Ƃ���A�������^�̑��ɂ�����܂��B ���āA�ޗǎ��ォ�畽������ɂ����āA���ɂ͂ǂ�ȍ��肪�e���܂�Ă������A���t�W�̉̂Ȃǂ���T���Ă݂����Ǝv���܂��B �k�́@�ɂقւ鍁�����@跌����@����̉J�Ɂ@����Ђʂ�ށ@�唺�Ǝ� ���t�W�Ől�C�̍�������Ƃ����A�܂��͋k�̉Ԃ̍���̂悤�Ɏv���܂��B5���ɓ���ƁA���k�n�̔��������ȉԂ��̖X�̒��ɍ炫�n�߂܂��B�͉̂Ă݂����M�q�Ȃǒ��Ō���������������܂������A�X���ł͂Ȃ��Ȃ����鎖���o���Ȃ��Ȃ��Ă����悤�Ɏv���܂��B ���̉Ԃ̍���́A�l�����Ƃ������O�̐����̍���ŃA���}�e���s�[�ȂǂŐl�C�̍���̂ЂƂł��B���t�̎��ォ��Ԃ������̎}���D�܂�Ă����悤�ŁA���̉ԋk�͂قƂƂ����ƑɂȂ��ēo�ꂷ�邱�Ƃ������悤�ł��B �܌��҂@�ԋk�́@���������@�̂̐l�́@���̍�������@�����r�� �k�̉ԂƂ����A������̉̂̕������m���Ă��邩���m��܂���B�@ |
|
|
���~�ƍ��̕���
�ǂ�����Ƃ����A��������łȂ��Ԃ̍���������p����A�厖�Ɉ�܂�Ă�������ł��B���t�W�̎���ɂ͉ԋk�̍���A�V������ɂ͔~�̉Ԃ̍���Ȃǂ�����Ă��܂����B�~�̉Ԃ́A���̉Ԃ���łȂ���������ł�ꂽ�悤�ł��B�ޗǎ���܂ł͉ԂƂ����A�~�̉Ԃ��w�������Ă��܂������A��������ɓ���ƁA����ɉԂ͍����w���悤�ɂȂ�܂��B���̉Ԃ͔~�̂悤�ɍ��荂���Ƃ�����ɂ͂����܂��A��ւ̎R�������J�ɍ炫�ւ�l�́A�m���ɓ��{�̉Ԃ��ے�����悤�Ɏv���܂��B ���������A������������A�~�̉ԁA�喳���ƂāA�t��Y��� ���āA�~�̉Ԃ��������̐l�Ƃ��āA�V���{�Œm���鐛�����^���ɂ��ď������čs�������Ǝv���܂��B���^���̏Z�܂����������s�̖k��V���{���ɕ{�V���{�͂悭�m���Ă��܂����A�X�ɑ�ɕ{�ɍs���r������������Ƃ������s���̑��V���{�������ĎO��V���{�ƌĂ�Ă��܂��B���͓��^���ɂƂ��đ��͔��ɉ��̐[���y�n�ł���A���䎛�s���ɂ��������V���{������܂��B �ߓS���Ɂu�y�t�m���v�Ƃ������O�̉w������A���䎛�s���̓��������ӂ͌Ñ�A�Õ��̑��c�Ȃǂɏ]�����Ă��������A�y�t���̗̒n�Ƃ���A���^���͂��̓y�t���̖���Ƃ����Ă��܂��B�������V���{�͓��^���̏f��̉��~�ՂƂ���A���݂ł��_��Ƃ��ē��^���̈�i���c����Ă��܂��B �y�t���́A�������q�Ƃ̊W���[�������悤�ŁA�|���X���͂��傤�ǂ��̓y�t���̗̒n�̂����߂���ʂ��Ă��܂��B �~�ɑ����āA���ɂ��Č��Ă��������Ǝv���܂��B�~�̈�ۂ��������^���ł����A���Ɋւ��Ă�����̂��c���Ă��܂��B ������ԁA�ʂ���Y��ʕ��Ȃ�A�ӂ����ޕ��ɁA���ƂÂĂ͂��� ��ɕ{���狞�s�̔~���r�L���ȉ̂ƕ���œ`�����Ă��܂��B�Ƃ���ŁA�����r�̂Ƃ����A���s�@�t�̕�������ݐ[����������܂���B ��킭�� �Ԃ̂��Ƃɂ� �t���Ȃ� ���̔@���̖]���̍� ���s�@�t�������r�̂�230��Ƃ���܂����A�����Ƃ��e���܂�Ă���̂͏�L�̉̂ł��傤���B22�̎Ⴓ�ŏo�Ƃ̓���I���s�@�t�́A�����͋��s�̍����Ɣn�R�Ɉ������т܂������A�܂��Ȃ��ޗǂ̋g��R�Ɉڂ�܂��B���������̍��͊��ɍ��̖����Ƃ��ċg��R�͒m���Ă����悤�ŁA���s���o�ƂƂ������͍��̖����Ɏ䂩��ċg��Ɉڂ�Z�̂ł��傤���B ���̌�A��������Q������A����R�ɓ���A���Ȃ荂��ɂȂ��Ă��瓌�厛�Č��̊��i���s�����߂ɉ��B�Ɍ������܂��B �ӔN�́A�x�c�юs���班�����ꂽ�Ƃ���ɂ���O�쎛�Ɉ����A���̒n�ʼn̂ɉr�ʂ�A���̍炭���ɓ��₵�܂����B�O�쎛�͌�̎���ɂȂ��Ă����s�@�t���Â�ő����̕��l��m�������̒n��K�ˁA����厖�ɊǗ����āA���ł����ł͗L���̍��̖����ɐ������Ă��܂��B�@ |
|
|
������̕����̏\���H(�O)
��������̒������߂���ƁA�{�앶�����₩�ɂȂ�Ƌ��ɁA����̕�������w�[�����邱�ƂɂȂ�A���݂̍���̕����̌��^���n���Ă����܂��B �{�앶���̍���Ƃ����A�܂��͌�������ł��傤���B�������A�O�A���{�Ɠo��l�����܂߂č���̕���Ƃ������܂����A���肪�M�l�̚n�݂Ƃ��āA�܂��Ɠ`�̍��肪�X�e�C�^�X�Ƃ��Ă��ꂼ�ꋣ�������Ă��������ǂ�������܂��B ��������͑k��܂����A�ɐ�����ɂ�����ɓZ��镨�ꂪ�U��߂��Ă��܂��B�������ꂪ����̕������ł��₩�ȍ��Ƃ���A���̏����O�̍�����������ƍ���̕������蒅���Ă������������������܂��B�u�܌��܂ԋk�v�̒i�͓����r���̉̂Ƌ��ɁA�L���e���܂�Ă��܂������A�j���̗��₷��Ⴂ�̘b�́A���オ�ς��Ă��S�̏W�܂�e�[�}�Ȃ̂ł��傤���B���̏����߂��������̈�b�ɔ�ׂāA�u���䓛�v�̒i�͂���Ⴂ���猳�ʂ�ɖ߂�b�ŁA�\�́u�䓛�v������t�́u��������ׁv�ȂǁA��̎���ɗl�X�ȉe�����y�ڂ����ƂɂȂ�܂����B �Ƃ���ŁA���̓��䓛�̈�b�́A�ޗǂ̎s�X�����肩��A����R���z���đ��̔����s�����ɂ܂ʼn��x���ʂ����Ƃ���܂����A�|���X�����班���k�ɍs�����Ƃ���ɂȂ�܂��B����ɂ͊����Ƃ��Ă��h���Ă����|���X�����A���̓�g���畽�鋞�Ɍ������Ɖ����ɂȂ�A���̌�͓s�����s�Ɉڂ�ɏ]���Ď�v�ȗ��H���k�ւƈړ����Ă������ƂɂȂ�܂����B �₩�ȕ����̋{�앶���́A���Ȃ��炸��ォ�狞�s�֕������^�ꂽ�Ǝv���܂����A���ɒ|���X���͂��̎�v�ȗ��H�̖�������O��āA�n���X���̂ЂƂƂȂ��Ă��܂��܂��B�������A���̈ɐ����ꂩ���������悤�ɁA���Ӓn��͈ˑR�Ƃ��Ċ����Ȋ��������������͊m�����낤�Ƒz���ł��܂��B �����g�߂Ȃ��̂Ƃ��āA������������G�߂��Ƃɑg���킹����ƁA�����̒��Ŋy���{�앶���̋M�l�̕����̗l�q���悭������܂����A�������ł����A�����̒��ɂ�����̕������Z���������̂ƍl���Ă��܂��B�������㖖���ɂ͖��@�v�z�Ƌ��ɏ�y�M���L���Z�����n�߂܂����A�S���Ɍ��Ă�ꂽ���@�ɂ���āA�����ɍL�����肪�Z�����Ă��������ł��傤�B�@ |
|
| �@ | |
|
������̕����̏\���H(��)
�����M���ɂ�鍁��̕����╧����ʂ��Ă̍���̕����́A���S�N�Ƃ������Ԃ������Ă������Ɠ��{�S���ɐZ�����Ă����܂��B�M���̚n�݂Ƃ��Ĉ�܂�Ă�������̕����́A�����̒��S�����Ƃɕς�����A���ꂪ�S���ɍL���g�U����傫�ȓ]�@�ɍ����|����܂��B ���s�̒�����ς��������m�̗��́A���������헐�⍬������̂悤�Ɍ����Ă��܂����A�����ɋM���̕������p���������m��S���Ɋg�U������������ʂ����܂����B���m�̗��ɂ��敾�������s�̓s�ɑ����āA�L�͏��l�𒆐S�Ƃ������R�s�s��ɑ����̕��m�����A�X�ɓs�ň�܂ꂽ�D��ȕ��������l�Ƌ��ɑS���ɍL�߂Ă������������ƂȂ����悤�ł��B �痘�x�̎t����������Љ����������w�Ƃ����O�𐼎����́A�����̎n�c�Ƃ����قǁA�����Ƃ̊ւ��̐[�������l�ł��B�{���̂�����A��������̎���ɕ����M������������������̒����ȂǁA���̍��ɉ��߂Č�������A���ɓ`��邨���⍁�������܂ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B ��̍���̕����A�]�ˎ��ォ��̐����̗��j�ɂ��ւ��d�v�ȕ��l�Ƃ��āA�A�̎t�̉��O�ԏє�(�ڂ����傤�͂�)�̖��O���������܂��B���O�ԏє��́A���̎O�𐼎����Ɍ�������Ȃǂ̌ÓT���w�сA���ƉԁA������������Q�̘A�̎t�ł����B �є��́A�헐������č�Ɉڂ�A���݂̎O�����u�Ɉ����\���āA���l�B�ɘa�̂�A�̂�`���܂����B�����A��̗L�͏��l�́A���{�̖L���Ȑl�ނ������A���̕������g�����є��𒆐S�ɕ����T�������`������āA��̗��x�Ȃǂɂ�钃�̓��̕����ɂ��傫���e�����y�ڂ��܂����B ���̏є��̎c�����u�O���L�v�ɁA�����ɂ��ď�����Ă��܂��B �u���v�́A���������ƂƂ��āA���̂���(��)�ɂЂ������`�������ҁA�g�o�A���͂ȂǂȂ��������܂��A�u���͂��������́v�́A�~�ԁA�חt�A�V���������Ă͂₵�A�ƁX�ɂ��ǂ݂��������(�@)�����`�āA���������̂ӂ����A���������ƂƂ̂ցE�E�E�B ���m�̗��̌�ɂ́A�����������l��ɂ�蕽���M�������ł����������L���S���Ɋg�U���Ă����܂��B�������������̓`�d���A��̐퍑����̒��̓�������֎p����Ă������Ƃ���Ă��܂��B�@ |
|
|
���b�x��@�F�ɂ̖����q��
���N�̑�̓h���}�u�R�t�����q�v�́A�퍑����̕����ł��鍕�c�����q����l���ł��B�����q�����镑��́A��ɕ��Ɍ��̕P�H�Ɩk��B�A�b�̓W�J�ɂ���Ă͒W�H����l�����ւ���Ă��邩���m��܂��A�����{�S��ő劈��̂ŁA���Ȃ��炸��ɓZ���G�s�\�[�h������o�Ă��邩���m��܂���B ���āA���Ɋ����q�̉��~�ő��q�̏����ۂƋ��ɁA�c������̌㓡�����q���o�ꂵ�Ă��܂����A�ޗnj��̑�F�ɂ̒��O��ɁA���̖����q�Ɉ����̑������܂��B �E���ȍ��c�̉Ɛb�c�̒��ł���ϗǂ��m���A�������珎���ɂ��l�C�����������l�q�ł����A���q�̒����̑�ɂȂ��Ă���͍��c�Ƃ𗣂�āA���̖����n�܂�Ƒ���ɓ��邵�ĖL�b�G���ɕt���]���܂��B�ŏI����̉Ă̐w�ł͌njR�������܂����A�Ō�͈ɒB�̓S�C����ɗ���̒��A���������Ɠ`�����Ă��܂��B ���̗E�҂ȕ��������������q�ɂ́A���̌���������тċ�B�ɓn�����Ƃ���`����A�F�ɂʼnB�ِ����𑗂����Ƃ����`���ȂǁA�e�n�ɗl�X�Ȑ��b���c����Ă��܂��B���̉F�ɂ̖����q�������̈�ŁA���闎��̌�A��F�ɂɐ������тāA���̉��~�ɂ�����������̎���ɖ����q���ƌĂ�Đe���܂�Ă����ƌ����Ă��܂��B��F�ɂ̏W�����班�����ꂽ�c���n�т̒��ɁA�����̖ʉe���c���Ί_�ƙz�Ƃ����Ȃ܂��̍��̘V�������ŁA�ŋ߂͍��̊J�ԂƋ��ɑ吨�̊ό��q���K���悤�ɂȂ�܂����B �����q�Ɍ��炸�A�����ӂɂ͊ւ���������̖��ɂ����Ă̈�b���F�X�Ǝc����Ă��܂��B�Ⴆ�A��̓�@���ɂ́A����ƍN�����~�̐w�Ŗ����q�̑��ŗ��������Ƃ�����b���c���ꂢ�āA�ƍN������Ɠ`�����Ă�������������Ă��܂����A�����Ɗ��͖L�b�ۛ��ȗl�ł��B�@ |
|
|
����Ɛ痘�x(�f��u���x�ɂ����˂�v���J�L�O)
��̗T���ȏ��Ƃɐ��܂�A���̓�(�����̒�)�̊����҂Ƃ��āA�]�ˎ��ォ�疾���ېV���o�āA����ɂ��ʂ��钃���̑㖼���ł���痘�x�B�����ďڂ��������̖��p���Ǝv���܂��B�M������G�g�̎���ɂ����āA�����̓V���O�@���Ə̂���ꂽ����@�v��Óc�@�y���A���͗��x�Ƌ��Ɋ�����O�ł��B ��́A���̓��̐��E�ł͑�ω�������܂����A�����̎Y�n�ł��Ȃ��A������̖������n��ꂽ��ł��Ȃ��A���ƂȂ��Ă͋�X���x��@�v�̐��܂ꂽ�̂��䂾�����Ƃ�����������Ă��Ȃ������m��܂���B �f��̌��ƂȂ��������u���x�ɂ����˂�v�ł́A�����̕���̂قƂ�ǂ͋��s�ɂȂ�܂����A�Ō�̍Ō�ɍ��ɂ������ꂪ�o�ꂵ�܂��B��͂藘�x��퍑�����B������V�[���̑唼�͋��s�Ƃ����C���[�W�ł��傤���B �����������ł́A�I�Ղ̃N���C�}�b�N�X�ŗ��x�̎t�ł��镐��Љ��̌��ɎႫ���x���K�˂��ʂ�����܂��B�Ⴂ��M�I�ȗ��x�ƃ~�X�e���A�X�ȏЉ��Ƃ݂̌��̔��w���킹�܂��B����Љ�����o�g�̍����ŁA���x�̎t�Ƃ��Ę̂ђ���`������B�ł��B ��s���암�̏Z��n�̒��ɓ�@��������܂����A�����ɗ��x�Ƃ��̎q���̋��{���ƏЉ��̋��{��������܂��B���x����ł���̂ŕ�����₷���ł����A���͂��̌Ù��Ɉꏏ�ɎQ�T�����Ɠ`�����Ă��܂��B�܂��M����ƍN�Ƃ������퍑�喼�����̒n��K�˂��Ƃ���Ă��܂��B���ɂ��A2�㏫�R�E�G����3�㏫�R�E�ƌ���2�K�����߂��Ɠ`�����Ă��鍿�_����A�Č����ꂽ���x�D�݂̒����Ƃ����������ȂǁA���낢��ƌ��ǂ���̂��镗�i�̕Y�����@�ł��B ���̂悤�Ɍ��݂̍�s���ɂ��A���x���ÂԎj�Ղ�����c����Ă��܂��B���ɋ��s�̂悤�ɓ����̖ʉe���f���͓̂���Ƃ��������܂����A���������j�Ղ���s�����U�Ȃ���A���x����������̗l�q��z�����Ă݂����Ǝv���܂��B�@ |
|
| �@ | |
|
�����x�̑��Ղ�q�˂ā`��@���`
��@���́A�ߋE��~�ɑ傫�Ȑ��͂����퍑�喼�ł���O�D���c�ɂ���āA���s�̑哿���̍��m��������я@���������đn������܂����B�哿���Ƃ����A���m�̗��ɂ��Ď��̌�A���̈�x�T�t���Z���ɔC�����A�ċ��������͂悭�m���Ă��邩�Ǝv���܂��B���x�ؕ��̌����ɂ��ꂽ�O����A���x���哿���Ɋ��Ă��̂ł��邱�Ƃ͗L�����Ǝv���܂��B ���āA��x�T�t�����Ȃ��炸��ɉ�������܂������A�����哿���͑����`���炪���������R�������p��������[�����̔��M�n�Ƃ������ʂ��������悤�ł��B�̂ђ��̊J�c�Ƃ���A��ɕ���Љ��ɉe����^�������c������A��x�T�t�Ɛe��������T�̐��_���w�Ɠ`�����Ă��܂��B ���������s�̐�[��������ɏ����������I���_�Ƃ��ē�@���͑傫�Ȗ������ʂ������ɂȂ�܂����B ��@���́A�O�D���̕�Ƃ��đn������܂������A���l�Ƃ��Ă��悭�m��ꂽ��я@���̌��ɁA��O���������ĎQ�T���A��������������Љ��◘�x�Ƃ������D�ꂽ���l������Ă����܂����B�������ē�@���͌�̒��̓��̕����ŏd�v�Ȗ������ʂ��Ă����܂������A���ɂ��l�X�ȋ��s�̕�������̒n�ɂ����炵�܂����B �A�̎t�Ƃ��Ēm���鉲�O�ԏє��́A���m�̗��̐�Ђ��1518�ɍ�ɈڏZ���A1527�ɖS���Ȃ�܂ł̊ԁA��̍g�J���Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł��܂����B�є��́A�@�_�ɘA�̂��w�сA�O�𐼎�����ƌ�V���Č��������ɐ�������w�A�Ԃƍ��Ǝ������������Q�̉̐l�Ƃ��Ēm���A��O�Ɍ�������̔�`��`�����Ƃ���Ă��܂��B ���݂̍�������A���̃��[�c�̂ЂƂɏє�����ɓ`�������̔�`���グ���Ă��܂��B�܂��є��ƌ𗬂̂������a�w�҂̎O�𐼎����́A�����̗��e�Ƃ���Ă��܂��B��@���ł́A�T�@�Ƌ��ɋ��s�̍Ő�[�̊w���|�p�������炳��A�����Œ��̓��₨�����䏤�l�B�̊ԂŐV���ȕ����Ƃ��Ĉ�܂�邱�ƂɂȂ�܂����B�@ |
|
|
�����x�ƍ���
�����ł����F�₨���́A�����ĂȂ��̑厖�ȗv�f�ɂȂ��Ă��܂����A���x�������ɍ���̑��w���[���������ƂƎv���܂��B ���F�̎��Y�͍��Ăɂ��ˉΔ� �ʂ荁���ɔ��h������ ���x�S��ɔ[�߂�ꂽ�L���ȉ̂ł����A���x�̍���Ƃ����ƁA�܂��͔��h���v���N������܂��B�����ڂ̏����Ȓ����̒��ŗH���ɍ��锒�h�̍���́A�����̍�����ז������Ɉ����������鍁�肾�����̂��낤�Ǝv���܂��B�����āA�����ɐ�����Ԃ͂Ȃ�ׂ����肪���Ȃ����̂łȂ��ƁA�����̍�����H���Ȕ��h�̍�����e�ɒǂ�����Ă��܂������m��܂���B���炭�A���x�͂����̍�����ז����Ȃ��悤�ɁA�T�d�ɔ����̏���R�@�t�Ƃ��������Ԃ�I�悤�Ɋ����܂��B ����Ƃ����A���x�ƍ��F�ɓZ���b���c����Ă��܂��B�L���ȂƂ���ł́A�u�璹�̍��F�v������܂��B���̗��x�̐璹�̍��F�Ƃ͐��̍��F�ŁA�r��荂�䂪�����O�r�����ɕ����Č����邱�Ƃ���A���̋r�Ɍ����Ăāu�璹�v�Ƃ��������t����ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B����ɂ́A���x�̉�����̏@�����A���̍��F�̋r�̒�������������̂ŒZ������悤�ɗ��x�ɐi�����A���x�����ӂ��Ă킴�킴�r������Ɠ`�����Ă��܂��B ���āA�������̍��F�Łu�璹�v�Ƃ������̍��F���A������p�قɎ�������Ă��܂����A������͕���Љ�����L�b�G�g�ցA�����ē���ƍN�ɓ`����ꂽ�R�����鍁�F�ɂȂ�܂��B���̍��F�͗��x�́u�璹�v�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A���x�����̏Љ������L���Ă������F�R�m���Ă����Ǝv���܂��B ���x�����Ȃő厖�Ɉ����Ă������F�B��@����Љ��̒����ŁA�����ȍ���n��ł��������A���̓���L���ȕ����Ƃ��ĉԊJ�������R�̂ЂƂ����m��܂���B�@ �@ |
|
| �������Ƃ䂩��̗��j��l�� | |
|
����(�`����t)
�Ő�(�`����t)�́A805�N�A��b�R�̌����ꌧ��Îs�̓��g��Ђɓ�(����)��莝���A���������̎��A����B(�w���g�А_���閧�L�x)�m����M���̊ԂŖ�p��V���ɗp����ꂽ���A��ʂɂ͕��y�����A�����g�̔p�~�ɂ��A����ɐ��ނ��Ă����B ����C(�O�@��t) ��C(�O�@��t)�́A806�N�A��(����)��蒃�̎�A�ΉP�������A��A��b�R�ɐA����B(�w�O�@��t�N���x)�m����M���̊ԂŖ�p��V���ɗp����ꂽ���A��ʂɂ͕��y�����A�����g�̔p�~�ɂ��A����ɐ��ނ��Ă����B ���h���T�t(1141�`1215) �킪���̒��A�����̑c�B�ՍϏ@��v(����)����`�����B�����n�̐����@�A�������̂����̂��ĕ������߂Ă킪���ւ����炵���B����ɂ킪���ŏ��̒���发�u�i���{���L�v���B�����̒��̏������u���o�v�����Ƃɒ��̖�����Ɗ֘A�Â��Ȃ���͔|���琻���E�����E���p�E���\�Ɏ���܂Ő��͓I�ɋL�q���Ă���B�u�i���{���L�v�ł́u���͗{���̐��Ȃ�@�����̖��p�Ȃ�v�ƌ��p��͐��B��p�Ƃ��Ă����ɊÊ�����ꂽ��A���I�Őh�������Ă����B����������ł���ƐS����̑��Ȃǂܑ̌��ɂ悭�A�a�C�ɂ�������Ȃ��Ə����c���Ă���B �����b��l(1173�`1232) ���q����̍��m��h���T�t�ƂƂ��ɒ��ƒ����̑c�Ƃ�����B�h���T�t����䂸�肤�������̎���̔�(���s�R��)�ɐA��(�w�̔����b��l�`�x)�A����ɉF���A�ɐ���x�͂̐����A��z���e�n�ɍL�ߍ����̒��Y�Ƃ��`�������B�܂����V����A����F�{�A�����~���A���������Ȃǂ́u���̏\���v���q�ׂ��B �����ꍑ�t(1202�`1280) ���q����̍��m�œ�����(���s)�̊J�R��v(����)����A���̂Ƃ��A���̎��ƕ�����]���������A�����B���̎��͋����ɋ߂��x�͑��E(���É��s���摫�v��)�̒n�ɐA�����Ɠ`�����É����̑c�Ƃ�����B(�w���������x) ���剞���t(��Y�Ж�)(1235�`1308) �v(����)����A���̍ۤ�a�R�����璃��q(���̓��ŗp������I)�ȉ��̒�����ꎮ�ƒ��Ɋւ��鏑��7���������A���Ē����̒��̕�����哿��(���s)�ɓ`�����(�w�{�����m�`�x)�܂��A�����⓬���̏K���������{�Ɏ����A�����Ƃ���Ă���B ���痘�x(1522�`1591) �����̑听�ҁu�痘�x�v�ɂ��A������_�Ă钃���̊�b�������B�u�����v���ݔ�ׂāA�Y�n�����Ă�V�т�����ɍs����B���̍����璃���͓��{�Ɠ��̐��_�����Ƃ��Č���ɐ[�����Â��B ���i�J�@���Y(�@�~) �����s�{�F���c���������J�̏��������̑n�n�ҁu�i�J�@���Y(�@�~)�v�́A�Ă��������ł���̂Ƀq���g�āA�����ĝ��݊��������ǂ̐�����n������B���������ł��낤�B����܂ł͒����̐��@�ł���A���̉�������u���Ċ��������銘�u�萻�@�ł������A�@�~�͏��C�ŏ������t���z�C���̏�ŝ��݂Ȃ��犣�������A�F�E�`�E����Ƃ��ɗD�ꂽ���������܂��� ���R�{�Õ��q(����) ���s�F���̒��t�A�R�{�Õ��q(����)���ʘI�̐��@���l�Ă��A�D�]����B1835�N(�V��6)�ɎR�{�R�̘Z��ڂƂ��ĎR�鍑�v���S���q���̖؉��g���E�q��̉ƂŁA���������ߒ��ŏ����ꂽ�t���������Ƃ���A�ۂ��c�q�ɂȂ����Ƃ��납��u�ʂ̘I�v�Ɩ��t���A���i�����܂����B �������̐̂Ȃ� �L�b�G�g�ƐΓc�O���̗͂��������������I ���������L��Ƃ����L�^�ɂ��Ƒ��}�G�g�����Ē��l���̂Ƃ���������������您���A�I���R����߂���R���Ōe����������߂܂�����₪�č��g�Ƃ������ڏG��Ȃ鏬�V�傪�咃�q�ɂ����Ղ�ʂ邢���������Ăĕ����܂�����G�g�͍��ꕞ�Ə��]����Ƥ���͂��M�����Ĕ����̗ʂ�����܂�����G�g�͂�����݂ɎO�x���]���܂��������ƍŌ�͏����q�ɂ��Ƃ����ʂ�M������ �������i�߂܂�����G�g�͂�������ݤ���m�̍˒m�Ɋ�������a���Ɍ�ĘA��A�褋ߎ��Ƃ��܂�������̏��m����ɓV���ɖ����Ȃ�����ʐl��Γc�O�����̐l�ł�����ݎ�̂��Ƃ��l���Ē�������S����ЂƂ��w�т������̂ł��B�@ �@ |
|
| ������R���ٓV | |
|
������R���ٓV
����R���ɂ͑�\�I�ȕٓV�Ђ����Ђ����āA�ʏ́u���ٓV�v�Ƃ��ĐM����Ă��܂��B�Ƃ��낪���ٓV�Ƃ��ĐM����͂��߂��̂������Ȃ̂��A���m�ɂ͂킩���Ă��܂���B��������A���ٓV�ɂ��Ē��ׂĂ��������ɁA�R���̏���ς������\5�N(1692)�����玵�ٓV�Ƃ��Ċm�����Ă������̂ł͂Ȃ����Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B �×��A���Ƃ��������͐��Ȃ鐔���Ƃ�������ۂ�����A�����_�ɑ�\�����悤�ɁA�������邱�Ƃ��������Ƃ͂悭�m���Ă���Ƃ���ł��B����������R�̎��ٓV�̏ꍇ�A���Ƃ��玵�ٓV�Ƃ��Đ��������̂ł͂Ȃ��A����R�ɂ܂��Ă�����\�I�Ȏ��ٓ̕V�Ђ���肠���āA��Ɏ��ٓV�ƌĂ��悤�ɂȂ������̂ƍl�����܂��B ������R���ٓV�̖��� ����R�ɂ����āA���ٓV�Ƃ������̂���������g���n�߂��̂������Ă݂܂��ƁA�w�I�ɑ����y�L�x�s�l(����)�����\�̊ێR�ٍ��V�Ђ̍��Ɂu���R���ٍ��V�̑��̈�Ȃ�v�Ƃ���܂��B�܂�w�I�ɑ����y�L�x�����������V��10�N(1839)���ɂ́A�x���Ƃ����ٓV�Ƃ��ĐM����Ă������Ƃ����������܂��B����ǂ��A�c��Z�ٓV�̖��̂������Ă͂��܂���̂ŁA���ݓ`�����Ă���ٓV�Ђɑ���������̂��ǂ����Ȃǖ��m�ł͂���܂���B ����Ɂw�I�ɑ����y�L�x�s�l(����)�����\�O�A�ԕٍ��V�Ђ̍��ɂ́A�u�T�ɏ��K���Ђ���@��t���掵�ٍ��V�������������Ƃ��Ӂv�Ƃ���܂��B�����ɋL��������(�ɂ�����)�Ƃ�������A���̏Ƃ�n��A�܂�V����䂪���Ƃ������Ӗ��ɉ��߂���ƁA�O�@��t���V���ɖ��������ٓV��ٓV�x�Ɋ������A���K���Ђ��ƂƂ̂����Ƃ����Ӗ��ɂȂ邩�Ǝv���܂��B���K���ЂƂ����̂����ׂĕٓV�Ђł������ƒf��͂ł��܂��A�����������Ƃ��܂��ƁA���ٓV�̓��̘Z�ٓV�͛ԕٍ��V�Ђ���R���e���ւƈڂ��ꂽ�Ƃ݂邱�Ƃ��ł��܂��B ����A�����w�I�ɑ����y�L�x�ł��w�����̂���ɂ́A�u���ٓV�v�Ƃ̋L�q�͂Ȃ��A�����ěԕٓV�Ђ̖T��ɋ������q�K�ƍr�_�K�����������Ƃ��L����Ă��܂��B�ʍ��u�G�}�ɂ݂鎵�ٍ˓V�Ёv�ɂ��L���܂������A�����A�ԕٓV�Ђ͊w�������x�z���Ă����炵���̂ł����A�]�ˎ���̌�����ɂȂ��čs�l���ւƊǗ������ڂ�A���̍��ɋ������q�K�ƍr�_�K���ێ�����Ȃ��Ȃ����\��������܂��B���K���p�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��ړ]���ꂽ�\��������܂����A������ɂ��Ă������Ȃ������R�͕�����܂���B���ٓV�̘b���s�l���́w�I�ɑ����y�L�x�ɂ̂L�ڂ���Ă���̂Ɖ��炩�̊W������̂����m��܂���B ������R���ٓV�̓`�� ����R�̓`���ł́A�O�@��t������R���̎�v�ȒJ�X�ɐ����i��ٍ˓V������(���傤)�����̂��n�܂�ł���Ƃ���Ă��܂��B�O�@��t�͍���R�̒n�`��\������̂ɁA�����ɗ��������Ă���ƌ`�e����܂����B���̂��Ƃ��痳�̓�����ԕٓV�Ƃ��A�K���̐�[���ɂ�����ꏊ�ɔ���ٓV���܂��Ă���̂��Ƃ����Ă��܂��B����ɗ��̂����ɑ�������ʒu���A������������������ʂւƎ���Q���ł���Ƃ��A���̂��߁A�֕�(�����)���ƌĂꂽ�Ƃ����������܂��B�_�͗��Ɠ����Ӗ��������߂ł��B �������ɁA���̓����ƐK���̐�ɛԕٓV�Ɣ���ٓV�Ђ��܂��Ă���Ƃ������Ƃł͔[���ł��܂��B�������A�c��̌ܕٓV�Ђ𗳂̐g�̂̕����ɔz�����悤�Ƃ���ƁA�����J�A�j���A��r�̊e�ٓV�͗��̂ǂ̕��ʂɑ�������̂��A����ɁA�ێR�ٓV�̏ꍇ�A����ٓV���������ɂ���܂��̂ŁA���̐g�̂���͗���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�ȏ�̂��Ƃ��獂��R���ٓV�Ɋւ��ẮA�����s���ȓ_�◝�����Â炢�_�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B |
|
|
���G�}�ɂ݂鎵�ٓV��
����R���̑S�̂�`�����G�}�́A�]�ˎ���ɏW�����Đ��삳��Ă��܂��B���̗��R�Ƃ��āA����I�Ɍ��V(���{)�ɒ�o����K�v������������ŁA����ɍۂ��ẮA�w�����ƍs�l���������݂��ɗ�������āA�ԈႢ���Ȃ����m�F���Ȃ���s���Ă��܂����B���̂Ƃ����{�����ꂽ�悤�ŁA���{������������R�����@�ɓ`����Ă���A�ߐ��ɂ����鍂��R���̎��@�Ȃǂ�m���ł��M�d�Ȏ����Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B �e�N��̍���R�G�}�ɕ`�����ٓV�Ђ��E���o���Ă݂܂��ƁA���̕\1�̂悤�ɂȂ�܂����B�ԕٓV�A�P��ٓV�A�����J�ٓV�Ȃǂ��K���`����Ă���̂ɑ��āA�j���A��o�ٓV�Ɏ����Ă͕`�����ꍇ���ɒ[�ɏ��Ȃ����Ƃ��킩��܂��B ����V�ɒ�o����G�}�Ɏ�(�₵��)���`����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��v�ȎЂƂ͔F�߂��Ă��Ȃ��������ƂɂȂ�A����Ɍ����Ȃǂ̏C���Ɋւ��Ă��C����s�̊NJ��O�ł��������ƂɂȂ�܂��B�����ŕٍ˓V���G�}�ɕ`����Ȃ��������R�Ƃ��āA���̎������l�����܂��B ���@�ŗL�ٓ̕V�Ђ������\���B ���@�ŗL�̒���Ƃ��Ă܂��Ă����ٓV�Ђ̏ꍇ�A���I�ȊG�}�ɂ͕`����Ȃ������\��������܂��B�����ō]�ˊ��ɂ����鎛�@�ŗL�̒���Ђ̏��w�I�ɑ����y�L�x����E���o���Ă݂܂��ƁA���̕\2�̂悤�ɂȂ�܂����B����Ђ��܂銄���ɂ��ẮA�����̎��@�������A�����ōs�l���A�w�����ƂȂ邱�Ƃ��������܂��B�e���@���ŗL�̒���ЂƂ��ĕٍ˓V���܂�ꍇ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���A�]�ˊ��̍���R���ɂ́A�������ٓ̕V�Ђ����݂������ƂɂȂ�܂��B �������ɂȂ�ƎR���̎��@�́A�p���ʎ߂ɂ��e����o�ϓI�ȗ��R�A�ЂȂǂɂ���Ď��@�̓��p�����i�݂܂��B�����炭�p���⍇�����ꂽ���@�ŗL�̒���ЂȂǁA�ێ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B���̗Ⴊ���@�J����ɓ���@�ԒJ��Z���ɂ܂��Ă����ٓV�Ђł������悤�ł��B �����������A���ٓV�ɔz������Ă����ٓV�ЂɌ����ẮA���@���͔̂p�₵�����̂́A�ٓV�Ђ݂̂��c�����ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B���̌o�܂����ǂ����ٓV�Ђ��A�j���ٓV�Ђł������\��������܂��B ��o�ٓV�Ɋւ��ẮA��x���G�}�ɓo�ꂵ�܂���ł����B��o�ٓV�Ђ͐����ł���Ɋy���̒���ЂƂ��Ă܂��Ă��܂����̂ŁA�w���A�s�l�̗���G�}�ł��鍂��R�G�}�ɂ́A�`����Ȃ������ƍl����ׂ��Ȃ̂����m��܂���B �ԕٓV�ЂɊւ��ẮA�ٓV�Ђ̖T��ɋ������q�K�ƍr�_�K�����������Ƃ��w�I�ɑ����y�L�x�w�����ɋL����Ă��܂��B����ɑ�������̂��A����3�N�A����2�N�A�������N�Ȃǂ̊G�}�ɕ`�����ԕٓV�З��e���K���Ǝv����̂ł����A���\6�N�ȍ~�̊G�}�ɂȂ�ƁA��̓��K���`����Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B����ɏ���2�N�G�}�̛ԕٓV�Ђɂ́A�u�C���s�l�������v�Ƃ���㐢�ɂ��tⳂ������Ă��邱�Ƃ���́A�w�����̎x�z����s�l���ւƊǗ������ڂ����\�����l�����܂��B �Ō�ɊێR�ٓV�Ђł��B�ڂ����͊ێR�ٓV�̕łɋL���܂������A���\6�N(1963)�̊G�}�ɂȂ��āu�@���y�Ё@���˓V�Ж��n�v�Ɩ��L����Ă��邱�Ƃ���A���\6�N�����ێR�ٓV�Ђ̂͂��܂�ł���\��������܂����B���̂��Ƃ́A�ێR�ٓV�́u���R���ٍ��V�̑��̈�Ȃ�v�Ɓw�I�ɑ����y�L�x�ɂ��邱�Ƃɂ���āA����R�̎��ٓV�M�͊ێR�ٓV�Ђ��������ꂽ���\6�N�ȍ~�ł��������Ƃ����Ӗ�������̂ƂȂ�܂��B�@ |
|
|
���ٍ˓V�ɂ���
�ٍ˓V�͐��ɊW�̂���ꏊ�ɂ܂��邱�Ƃ������Ƃ����Ă��܂��B�O�@��t�͍���R���Ђ炭�ɂ������āA���̊m�ۂ���Ƃ��āA��v�ȒJ�ɕٍ˓V(���ٓV)�����������Ƃ��`�����A����R�����Ɍb�܂�Ă���̂́A���������ٍ˓V���܂��Ă��邩�炾�Ƃ������Ă��܂��B �ٍ˓V�����{�̍��ɂ����čL���M�����悤�ɂȂ������Ƃ́A�e�n�ɂ�����n���Ƃ��ĕٓV���A�ٓV�ʂ�Ȃǁu�ٓV�v�̖��O���������t�����Ă��邱�Ƃ�����킩��܂��B���ɕٍ˓V�ٍ͕��V�Ƃ��āA�����_�Ƃ��Ă̎����_�Ɉ�ɑg�ݓ�����邱�Ƃɂ���āA����ɐM���L����܂����B �{���A�ٍ˓V�̋N���͌Ñ�C���h�ɂ܂ł����̂ڂ�A�T���X���@�e�B�[�Ƃ������_�i�������̂��ٍ˓V�ł������Ƃ����܂��B��͂�������̌b�݂��������ɗ^���Ă���܂��B�y�n��c�����������̑��݂́A�_�k�ɂ͌��������Ƃ��ł��܂���B�܂���̂����炬�͖��Ȃ鉹�Ƃ��ĉ��y�ɒʂ��邱�Ƃ���A���i�������Ă���ٍ˓V�ȂƑّ��E��䶗��ɂ݂邱�Ƃ��ł��܂��B�����������Ƃ���ٍ˓V�́A���E���y�E�����Ƃ������l�Ԃɏ����������炷�_�Ƃ��Ă̖����̂��邱�Ƃ��킩��܂��B �ٍ˓V�ɂ��ẮA�����ɂ�����썑�o�̑�\�Ƃ�������w�������o�x�̒��́u��ٓV�_�i�v�ɁA���̂��o����������L�߂��肷��҂ٍ͕˓V�̒q�b�ƕٍ˂������邱�Ƃ��ł��A�������߂�҂ɂ͑������^�����邱�ƂȂǂ�������Ă��܂��B���������q�b�ƍ����̌䗘�v������ٍ˓V�́A���{�ɂ����Ă���������M����A���厛�@�ؓ��ɂ�8���I�̑����ɂȂ�ٍ˓V�������`����Ă��܂��B �ٍ˓V�̏K���_�A�F��_(��������) �����̕�(�{�n)�̊�������̓I�ɕ\�����߂ɁA���{�ŗL�̐_���O�����~�ς���Ƃ���_���K���v�z�́A�X�̕��Ɛ_�Ƃ̊W�m�ɂ��܂����B �ٍ˓V�̏ꍇ�A���ɉF��_�Ƃ̏K��(���イ����)���m���Ă��܂��B���̉F��_�Ƃ́A���{�ŗL�̐_�ł���q���(�����݂̂��܂݂̂���)��ېH�_(���������̂���)�̖��O����A���̉����E�K���ɂɂĂ��邱�Ƃ���A�F��ƂȂ����Ƃ������Ă��܂��B����ɑq����͈�א_�ł���Ƃ������Ă��܂��̂ŁA��א_�ƉF��_�͓��̐_�ł��邱�ƂɂȂ�܂��B���X�C���h�̐_�ł������ٍ˓V�́A�������ĉF��ٍ˓V�ƌĂ��悤�ɂȂ�A�����ł͉F��_�ٍ͕˓V�̕v�ł���A���҂͕v�w�_�ł���Ƃ��������悤�ɂȂ�܂��B �F��ٍ˓V�́A�w�������g�n�]�����~���F��_����F���֎����O�����A�o�x��w�ŏ��썑�F���ړ��@�ӕ��ɗ���o�x�Ȃǂɑ�\����钷�����O�̂��o(���{�ł���ꂽ�U�o)�ɐ�����Ă��܂��B�����̂��o�ɂ́A�n�҂ɑ��鏵�������Ȃǂ��傫�����グ���Ă��邱�Ƃ������Ƃ����A���̐��������́A���悻���q����ł���Ƃ���Ă��܂��B ����ɕٍ˓V�̏K���_�Ƃ������Ƃł́A���̐_�ł���s�����䔄��(���������܂Ђ�)�ƏK�����܂����B�s�����䔄���̉��͌���(��������)�ɒʂ��邱�Ƃ���A�����_�Ђɂٍ͕˓V���܂���悤�ɂȂ����Ƃ���Ă��܂��B���̑��A�ٍ˓V��䶋g��V�Ɠ���_�Ƃ��Ĉ���ꂽ��A�O�\�Ԑ_�ȂǂƂ��K�����A���푽�l�ȓW�J���݂���̂������Ƃ����܂��B�@ |
|
|
���ٍ˓V�̖{��
����R���ٓV�̊e�{���ׂČ��܂��ƁA���̕\�̂悤�ɉF��ٍ��V���������Ƃ��킩��܂��B�����̖{�����A�e�ٓV�Ђ̓������ł��邩�ǂ����͕�����܂��A�������Ă���{�����������A�]�ˊ��������̂ڂ鑜�͖����悤�Ɏv���܂��B �ԕٓV�͍O�@��t�ɂ���āA�V��ٓV�Ђ�芩�����ꂽ���̂Ɠ`�����Ă��܂��B���̂��Ƃ́A�V��ٓV�̖{���ƛԕٓV�̖{���Ƃ͓����ٍ˓V�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B ���݂̓V��ٓV�Ђ̖{���A�ٍ˓V���́A�V��15�N(1587)�̖������锪�]�F��ٍ��V�\�ܓ��q�����Ƃ���Ă��܂��̂ŁA����R���ٓV�̖{���ɉF��ٍ��V�������̂͂����������R�ɂ��̂����m��܂���B ������R���ٓV�̖{��(����) �ٓV�Ж� �@�@�r�̐� �@�{�@�� �ԕٓV�@�@�@ �| �@�@�@�F��_���Ƃ���(���m�F) �P��ٓV �@�@���] �@�@�F��ٍ��V�\�ܓ��q�� �����J�ٓV �@���] �@�@�F��ٍ��V�\�ܓ��q�� �j���ٓV �@�@�| �@�@�@�F��_��(���_) ��o�ٓV �@�@������ �@�镧�ɂ�薢���� ����ٓV �@�@������ �@������ ����ٓV �@�@���] �@�@�ٍ��V�� �ێR�ٓV �@�@���] �@�@�F��ٍ��V�� ���\4�N(1961)�́w�����E�v�W�x�ɂ́A��(�₵��)�̐��@�Ɩ{���̐��@���ꕔ�ł����L�^����Ă��܂��̂ŁA�Q�l�ɋL�ڂ��Ă��������Ǝv���܂��B ���w�����E�v�W�x���\4�N(1691) �ٓV�Ж� �@�@�@�~�n �@�@�@�@�@�� / �{������ �P��ٓV�� �@�@�| �@�@�@�@�@�@�\�s�ڎl���E���s�l�ڎl�� / �l���O�� �����J�ٓV�� �@�\�s��Ԕ����s��� �\�s�l�ړE���s�l�ژZ�� / �ܐ��ꕪ ��o�ٓV�H�ܔV����t�� �| �@�@��ړl���E���l�ڈꐡ / �| �ێR�ٓV �@�@�@�| �@�@�@�@�@�@�| / �{���ܐ������E�\�ܓ��q�O������ �@ |
|
|
���ٍ˓V�̎�X��
�ٍ˓V�̎p�ɂ́A�r�̐������]�E�Z�]�E���]���Ȃǂ������āA���ꂼ��̎�ɂ͊e��̎���������܂��B���]���́w�������o�ŏ����o�x�Ƃ������o�ɁA�e�X�|�E���E���E���E���n�E�S�ցE㮍��Ȃǂ̕���������Ƃ�������Ă��܂��̂ŁA���_�Ƃ��Ă̐��i���L���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���{�ł́A�ޗǎ��ォ��ٍ˓V�ɑ���M������ɂȂ�͂��߂܂��B ���]���́A�w����o�x�Ȃǂ̖����o�T�ɖ����V�Ƃ��Đ�����A���̎p�ّ͑��E��䶗����ɕ`�������i��e���p�̑�����\�ƂȂ�܂��B����̓C���h�ɂ����ĉ��y��ِ�A�w��̐_�Ƃ��ĐM���ꂽ���Ƃɂ��Ƃ���܂��B ���q����ȍ~�ɂȂ�ƁA���]�ٍ̕˓V���F��_�ƏK�����A������������_�Ƃ��āA���̐M���L����܂����B���q�������ɐ��������w�k���E�t�W(������イ�悤���イ)�x�Ƃ��������̒��Ɂu�����V�@�錈�v�Ƃ������̂������āA�����ɂ́A�ٍ˓V�ɂ͖����ٍ˂ƉF��ٍ��Ƃ̗���������ƋL���Ă��܂��B�����ٍ˓V�͒q�b����Ƃ��A�F��ٍ��V�͕�������������ǂ�A���̎p�͔��ւ�̂Ƃ��Ē���ɘV���̌`������ƋL���Ă��܂��B �܂��A�F��ٍ��V�ɂ́A�\��(�\�Z)���q���`���ꂽ��z���ꂽ�肵�Ă���ꍇ������܂��B���{�̍��ł���ꂽ�U�o�A�w�ŏ��썑�F���ړ��@�ӕ��ɗ���o�x�ȂǂɁA�\�ܓ��q�ٍ͕˓V�̎葫�ƂȂ��ē�����ڂ����邱�Ƃ��������悤�ɂȂ��āA����Ɏ��������悤�ɂȂ�܂����B �F��ٍ��V�̑��e�́A�w�������o�ŏ����o�x�ɐ������]������{�Ƃ��āA��א_�̏ے��I�Ȏ������ł��錮�ƕ��ɑւ���Ȃǂ̕ω������A�����ɂ́A�������V�l�Ŏg�̉F��_���ڂ��č����_�Ƃ��Ă��邱�Ƃ������Ƃ����܂��B�\�ܓ��q�͌��A��A�\�Ȃǂ̎������������Ĕz�u����܂��B ���݂̍���R���ٓV�̖{���́A�����ȍ~�̐M���琶�܂ꂽ�F��ٍ��V����{�ƂȂ��Ă��܂��B�����������A�悸���ڂ����̂́A����ٓV�̖{���ł��B����ٓV���܂�@�ԉ@�ɂ́A�u����ٍ��V�v�ƋL���ꂽ�{���̎p���ʂ������D������܂��B�����ɂ͓��]���ŁA�E��ɕ��A����ɑ��ۂ̂悤�Ȃ��̂������A������͔E�҂̂悤�Ɍ���S���Ă���p���`����Ă��܂��B���炩�ɉF��ٍ��V�Ƃ͈قȂ�p�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �܂��A�������]���ł��ێR�ٓV���́A��Ɍ��A����ɕ��������A�����ɂ͒����ƉF��_���̂��Ă��܂��B���̎p�́w�k���E�t�W�x�ɋL����Ă��鎝�����Ɠ����ł��邱�Ƃ��킩��A���̒����͈�א_�A���Ȃ킿䶋g��V�Ƃ̐ړ_���L����ٍ��V���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ����ɛԕٓV�A�j���ٓV�Ђ̂��_�̂́A���������l�Őg�̂��ւł���F��_�ł�(�ԕٓV�̏ꍇ�͖��m�F)�B�U�o�w�������g�n�]�����~���F��_����F���֎����O�����A�o�x�ɂ́A�F��_���܂�ƕn�҂ɂ͕���^���A���̕�͉J�̂悤�ɍ~�蒍���A�������͂��O���ŕ��������Đ��A����Ɛ�����Ă��܂��B�����ٍ˓V�ł��A���ɉF��_�̌䗘�v�����グ���āA�܂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�@ �@ |
|
| ����C�̎����ɓǂޢ�����̒���� | |
|
��1 ���Ƃ�ƕ���
���̖@�͑�����(�Ԃ�)�̐S(����)���̒�(����)�Ȃ�B��(�ӂ�)���͂炢��(������)���������̖���(�܂�)�}(�ڂ�)��E(�܂�)���ꐹ�ɓ���̃L���a(���傯��)�Ȃ�B(����W�@�����) [������] �킽������C���C���������@(����)�̓u�b�_�̋����̖{���ł��肱�̋���������������삷��B�܂��A������Ђ������͂炢�l�тƂ̕����i�����}�v�̂��Ƃ���\�ɂ�����̂ł���B ��C�����̐��U�ɂ����đn�삵���������܂Ƃ߂����̂��w�Տ�(�ւ傤)��������(���傤��傤)�W�x�ł���B�ՏƂƂ͋�C�̟�(���傤)���ł���A���̂��̂����C�Ȃ�m�̌��肪���E��Ղ��Ƃ炷�Ƃ������ꢃr���V���i��̖��B����@���̂��Ƃ��w���B�m�̌��肪�������ꂽ�܂��Ƃ̐S�̎����W�Ƃ����Ӗ��B ���̐���W�̊���܂̢�{���̎g�ɗ^���ċ��ɋA���Ɛ����[��̈�߂ł���B �����ɓn������C�́A���w��N�ڂ̏t�ɒ������Ґ�(�ꂢ����)�ɂ����C���h�m�̔ʎ�O��(�͂�ɂႳ��)�Ɩ���(�ނɂ���)�O������A�܂��A�O����(���{�ɂ����Ƃ��ɁA������͉�b�E���͗͂Ƃ����łɐg�ɕt���A��������̊�{���}�X�^�[���Ă�������A�����ł̓C���h�`���̖��������܂Ȃ������A�C�����邽�߂̞���A���Ȃ킿�T���X�N���b�g)�̎��H��w�͂ƃo�������N�w���w�сA���̏n�B�x��ʂ��āA�������Ɩ{�l�̂����̋H�L�ȏ@���I��ʂ��F�߂��āA�����̌b��(�������F�����掵�c)�a������́A���Ă��珉�H�ɂ����āA�w����o�x�Ɓw�������o�x�o���̋����ƋV�O(����)�̂��ׂĂ�`������邱�ƂɂȂ����B �������āA�Z���Ԃ̂����ɖ����̐����ȑ����҂ɂȂ�����C�́A�H�ɂ́A�������{�ɓ`�����Ă��Ȃ����������̌o�T��Q�H��Y��ēǂ݁A���ʂ��A���̈Ӗ����w�ыL���A�܂��A���E�̖{���������A�ّ��Ƌ����E�̑��䶗���`���A�V���@�����̂��߂̎����Â����Ƃɓ��邱�ƂɂȂ�B �����A�b�ʘa�������̔N�̕��ɁA����������ɋA���āA�����č��Ƃ���A�V���ɗ��z���đ���(���������F���O)�̕�(�����킢)�𑝂���Ƌ�C�Ɉ⌾���ē��ł��Ă��܂����B �b�ʂ̎��ɂ���ăC���h�`���̖����攪�c�ɂȂ�����C�́A�����ɋA���āA�ꍏ�������t���̖�(�߂�)���ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����g����S�����ƂɂȂ����̂��B ���������܂ɁA���܂��ܐV�c�鑦�ʂ̂��j���ɂ���ė������{���̎g�߂������ɓ������B�����ŁA��C�͓�\�N�̗��w���Ԃ�Z�k���ē�N�ŋA���ł���悤�ɐ\�����������Ċ肢�o��B(�������āA��C�͎���悭�A������D�ɏ�邱�ƂɂȂ�[) ���̋A���\�����̕��ʂɁA���������V���@�̈Ӌ`��[�I�ɒԂ�����߂ł���B ���āA���ʂɂ��ƁA��C�̏C�������ŐV�̕��@(����)�ł͢�l�тƂ̕����i������Ƃ������ƂƁA���Ȃ̂����̂��̖��C�Ȃ�m�ɖڊo�߂邱�ƂƂ͓����ł��飂Ɛ����Ă���Ƃ���B �ǂ̂悤�ȗ��R�ł����Ȃ�̂��A���̂��Ƃɂ��Ă̍�����́A�����悻���̂悤�Ȍ������q�ׂ��Ă���B ��킽�����̐S(��̒m)�A�������ďO���̐S(�q�̒m)�A�������Đ�Ύ҂ł��镧�̐S(���ׂĂ̂��̂������܂�Ȃ���ɂ��Ă����C�Ȃ�m�A���Ȃ킿��Βm)�A���̎O�̐S�͂ł��ˁA�{���I�A�{���I�ɁA��ɕ����ł���Ƃ����l�����ł��B�l�Ԃ����������A�܂莩�R�E�S�����܂߂������鑶�݂́A�{���I�ɂ͈�̂ł���A���ׂĂ͑����Ȃ邢�̂��̂����C�Ȃ�m�����ɂ��Ă���Ƃ����l�����B���̍l��������{�ƂȂ��Ģ���g����(�������傤�ԂF���̐g���܂߁A�����Ƃ���������̂Ǝ��R�E�́A���̂܂܂ɂ��Ă��̂������ʂ��Ă����C�Ȃ�m�ɂ���Čq�����Ă���Ƃ��Ƃ邱��)����\�ɂȂ�̂ł��B���̂悤�Ȣ���g������̗��O�ɂ���āA���̐S������Ƃ����̂����@�̖{���ł�����A�Љ�I�Ȋւ��ɂ����āA���ׂĂ̂��̂̕���(�����킢)�𑝂��Ƃ����A���������͂��炫���K���o�Ă��飂ƁB ���̕����̐��_�ɂ��ƂÂ��Љ�Ƃ̋�̓I�ȗႪ�A��C�̍s�Ȃ������Z�r(�܂�̂�����)�̏C�z�ł���A����̋@��ϓ���������������Y��q�@(���グ�����タ����)��Ƃ��������̑�w�̑n�݂ł���Ƃ��B�@ |
|
|
��2 ���ɐ�����m(�ܒq)
��q��C ����(���傤����)������(����)�߂ĊҌ�(����)���v���Ƃ��B�o�H(������)�����m�炸��(���܂�)�ɗ�(�̂�)��Ŋт������B������(������������)����č��̔�����B��(�Ԃ�)�ɗ�(�̂�)��ŐS��(����)���Ԍ�(��������)��q(����)�˂Ƃ��肤�B(����W�@���掵) [������] ��q�ł���킽������C�͎����ɋ�(����)��镧�����͂��܂����ׂĂ̒m�̍����Ɏ��铹��T���Ă����B�������A���̋��߂铹�������o�����ɓ��ɂ������A�ы��������Ƃ��B����Ƃ킽�����̂܂��Ƃ̐S���ʂ��āw����o�x�̌o�T�ɏo������B�������A���̋������w�Ԃɂ͍��x�̞���͂ƋV�O�̏C�����s���ł������̂� �����ɗ��w���邱�Ƃ����ӂ����B ����W�̊��掵�̢�l��(������)�̕��(����)�ɓ̑��䶗���蕶(�������)��̈�߂ł���B�O�͂ŋ�C�̒������w�̂��Ƃ��q�ׂ����A���̗��w�����ӂ������������L�������̂ł���B ���̂悤�ɋ�J���ē��{�Ɏ����A������䶗����`����Ă���\���N���߂��āA���j��A�ʐF�����A�����}���C��Ă����B�����ő����̐l�тƂ̐S�����킹�āA�C�����邱�ƂɂȂ����B ���̊������̊蕶�ł���B (���݂ɁA���̊蕶�̌㔼�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����B��g�������҂��A�G�����҂��A�m�����l��������̂��A�J�͂���������͂��炫���ׂ��A����҂͕M���Ƃ��ĕ`���A����҂͐j���Ƃ��ĕ\������`���A���A�������݁A�H���̗p�ӂ����A�����ƂƂ̂����҂��A���ׂĂ̐l�тƂ��S�����낱�сA������킹�A�F�飂ƁB�����ɁA���C�Ȃ�m�ɂ���ĕ��@�Ɏd���閯�O�̂�����������[) �C�s�̐l ���ׂ��炭�{���𗹂��ׂ��B�����{���𗹂��Ίw�@�ɉv�Ȃ��B������{���Ƃ͎�������̐S�Ȃ�B(��،o�J��) [������] �������ߏC�s����l�͂��Ȃ炸�A�m�̍��{�����߂�ׂ��ł���B�����A�m�̍��{�����߂Ȃ��������w�������Ă����ɗ����Ȃ��B ���̒m�̍��{�Ƃ� ���ׂĂ̂��̂������܂�Ȃ���ɋ�(����)�������C�Ȃ�m�̂��Ƃł���B ��،o�J��̢��،o��Ƃ́A���������o�T�ł��鈢�܌o���͂��߁A���̑��o�T�A����ɗ����Ƙ_���Ƃ����A�c��ȃe�L�X�g���W�߂����T�̑��̂ł���B���������āA�����̕��T���W�ĉ���������̂����J��ƂȂ邪�A���̒��̈�߂ł���B �{���Ƃ����̂́A�{���̂���悤�̂��Ƃł���A��������߂�̂����ł���A���̐^�������߂Ȃ��̂ł���A������w�������Ă�����͉v�̂Ȃ����Ƃ��Ɛ����B�ł́A���̖{���̓����Ƃ͉��Ȃ̂��A���ꂪ��������S(�����傤���傤���傤����)�ł���Ƃ����B �����Ƃ́A�������z���Ă��Ƃ�������Ă���{���̂��Ƃł���A���̖{���͂��Ƃ��Ɛ���Ȃ���̂Ȃ̂ł���ƁB ���ꂪ���C�Ȃ�m�Ȃ̂ł���B �O��(����܂�)�̖@��(�ق��Ԃ�)�͖{(����)���䂪�S(����)�ɋ�(��)�� ���(�ɂ���)�̐^��(����)�͋�(�Ƃ�)�ɐ���Z(���ꂶ�傤���イ)�Ȃ� �b(���イ)����(������)�͊F����@��(�ق�����)�Ȃ�(����W�@����O) [������] ���ׂĂ̂��̂������܂�Ȃ���ɂ��Ă����C�Ȃ�m���킪�S�ɂ���(����)����Ă���悤�ɐ^���̐��E�ƌ����̐��E�͈�ɂȂ��ď�ɑ��݂��Ă���(���̂��ƂƓ����悤��)���b���̎��R�̐��͂��ׂāA���̂��̂����C�Ȃ�m�̌��t�ł���(���̌��t���킪�S�̒��ɂ�����) ����W�̊���O�̢���������̎���̏��̈�߂ł���B�����Ƃ͎l�\�̐ߖڂ��j�������̏K�킵�ł���A��C�͂��̊��z�����̂悤�Ȏ��ɂ��Ċe���ʂɑ����Ă���B ���t���R��@���t�R��ɍ�(��)������@ ����毎n�I�@����(��������)�(����)�n�I������ �l�]�ܔ��@�l(����)�]�ܔ��̍@ ����O���Z�@����ɉ~�Z��O(����)�� ���_���|�o�@���_��(����)��̏���肩�o�Á@ �{����@�{(����)�����炩�ȋ��� �~�k��S��@��S�̎��k����Ɨ~����@ �O�j�N�V���@�O�j�V���ɘN(����)�炩�Ȃ� [������] ���ɐF�Â����t���R��ɎU��ʂĂĂ� ���V��ɂ͎n�܂���Ȃ���ΏI�����Ȃ� �����A�킽�����͎l�\�̍� �H�̖钷�Ɏ����̂Ȃ��~���ŗZ�ʖ��G�Ȃ鎩�R��z�� �����_�͂ǂ����猻��ꂽ�̂� �{���͐��炩�ȋ���Ȃ̂� ���̂킽�����̐S�������Ƃ���� ���ƌ��Ɛ�����������ƋP���A���ݐ����V��̂悤�� �ȏ�̂悤�Ȏ��̏����ɒԂ�ꂽ�̂��A����b���̎��R�̐���Ƃ��̉��ɂ��颂��̂��̂����C�Ȃ�m�̌��t��������߂ł���B �����ɐ����ꂽ���̂��̂����C�Ȃ�m���A�����̐�����ܒq(����)��ł���A���̌ܒq���̂��̂̏ے�������@���ƂȂ�A�@�g(�ق�����)���ƂȂ����B���̖@�g�̐��A���邢�͖@�g�̌��t���@���ł���B ���̌��t���A�{���킪�S�ɂ������Ă��邵�A���b���ɂ������Ă���Ƃ����B �ł́A��ܒq��Ƃ͉����w���̂��A�������C�͈ȉ��̂悤�ɕ��ނ��Đ����B���̕��ނƍ����̉Ȋw�҂̐����A�����w�I�Ȓm�̕��ނ͌���Ȃ��߂��B ��A�@�E�̐��q(�ق������������傤��)�F���̂��̑��݂��̂��̂��i�颐����m� ��A��~���q(�������傤��)�F�����鍪���ƂȂ�ċz�E�����E����i�颐����m� �O�A�������q(�т傤�ǂ����傤��)�F�ߐH�Z�̐��Y�Ƃ����̑��ݕ}�����i�频n���m� �l�A���ώ@�q(�݂傤������)�F���ۂ̊ώ@�E�L���E�ҏW���i�颊w�K�m� �܁A������q(���傤������)�F�p���E�^���E��ƁE����E�V�т��i�颐g�̒m� �ȏ�̌܂̒m���A���̂������܂�Ȃ���ɋ�����C�Ȃ�m�Ȃ̂ł���ƁB �����̒m�������̂����ɐ����邱�Ƃɂ���āA���R�E���ۂ���Ă���B�@ |
|
|
��3 ���ɐ����邢�̂��̂�����(�@�g)
�@�g(�ق�����)��(����)���ɂ��݂鉓���炸���đ����g(����)�Ȃ�B�q��(������)��(����)��䂪�S�ɂ��Đr(�͂Ȃ�)���߂��B(����W�@���掵) [������] ���̂��̂���̂܂܂̂��������ے�����r���V���i�@���͉����ɂ�����̂�����͉����ޕ��ł͂Ȃ��킪�g�̂̒��ɂ�����B���̔@���̎�����邢�̂��̖��C�Ȃ�m�́A�Ȃ�Ƃ킪�S�̒��ɂ���ƂĂ��߂��B ����W�̊��掵�̢����̓��厛�ɂ��ĎO��(����ۂ�)��������蕶��̏��߂̈�߂ł���B �����q�̏C�s�m�Ȃ�ҁA��(���̂��̖��C�Ȃ�m�̂�����)�Ɩ@(���̂��̖��C�Ȃ�m)�Ƒm(���̖��C�Ȃ�m�ɂ��������Đ����邱�Ƃ����H���鋤���̂̐l�т�)�̎O��ɐ[���A�˂��܂���̌�ɂÂ��[ �����ł����@�g�Ƃ͓��厛�̃r���V���i(����F�����ՏƂƖ�)�@�����w���B �r���V���i�@���Ƃ͑���@���̂��Ƃł���A���̏ږ��́A ���Z(���傤���イ)�O��(����)��(���傤�݂傤)�@�g(�ق�����)�@�E�̐��q(�ق������������傤��)��r���V���i����p(������䂤)����Ƃ����B ���Ȃ킿�A�i�v�ɉߋ��E���݁E�����ɂ킽�鑶�݂ł����āA��炩�ɂ��Ė�(����)�Ȃ�@�g�A����͂��̂����̂��̂̑��݂��i�鐶���m�ł���A���̒m�ɂ���Ă��ׂĂ̂��̂��̂���̂܂܂̂��������n��Ɍ����Ă��邪�A���̐�ΓI�Ȃ��̂��̏ے��Ƃ��Ă̑��i���r���V���i�ł���B �܂�A�@�g�Ƃ͢���ׂĂ̂��̂������ɐ����邽�߂ɁA���܂�Ȃ���ɋ�����C�Ȃ�܂̒m(�ܒq)�̂͂��炫��ɂ���Č�����A���̂��̂������ł���B ���̂��������A��C�͢�ܒq����Ȃ颎l��@�g(������ق�����)��Ƃ��Đ����A����́A�����̉Ȋw�҂̐����A�����̕��ޗv�f�Ɏ��Ă���B ��A����(�����傤)�@�g�F��������̂̂��ꎩ�̖̂{���ƂȂ�A���C�Ȃ�m�����邢�̂��̑��݂��̂��́B(���̂��̂������̂悤�Ȃ����������킵�Ă���) ��A��p(����䂤)�@�g�F�̂Ƃ��Ă̂������B �O�A�ω�(�ւ�)�@�g�F��`�̖@���ɂ���ĕω����Ă����̂̂������B �l�A����(�Ƃ���)�@�g�F���l�Ȏ�̂������B �ȏ�̎l��ɂ���āA���̂��͂��ꂼ��̂��܂��܂Ȃ����������������킵�A���ɐ����Ă���B���̂���̂܂܂̂��̂��̑��݂���@�g��Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
��4 �S�Ǝ��R�ƌ��t
����(����)�͌o��(��������)�̔��Ȃ薜��(�傤)�A��_�Ɋ܂ށB(����W�@�����) [������] ���E�͂��̂��̂����C�Ȃ�m�����t�ƂȂ��ĒԂ�{�����ۂƂ����ǂ��A��_�̌��t��A�����o�āA�܂��A�����ɋA���Ă����B ����W�̊����̢�R�ɗV�тĐ��炤��̎��̈�߂ł���B ��C���V�厍�ɑ����đ哹����������̂ł���A���̏����ɂ����āA�����̐��E���w�������ƂƂ��ɁA�����Ԃ̔ς킵����߂��݁A���R�E�ɖ���̎v����������Ƃ����Ƃ���B ���̒��ŁA�����͎R�ɓ����Ď��R�̐����A���̐��Ƃ͂��̂��̂����C�Ȃ�m�̌��t�ł���A���̌��t�ɂ���Đ��E�����ʂ���A�����ɖ��܂����t����ꂽ����A���E�����܂ꂽ�B ���̌��t�A�������͕����̂��ׂẮA��A��̈�_�ɋA���Ă����B �܂�A���t����ɂ������̂ł͂Ȃ��A���̂��̂����C�Ȃ�m����ɂ����Č��t���o�Ă������A���̌��t���̂��̂́A���R�̐��̂Ђт���A��̈�_����n�܂����Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���B �v(��)�ꋫ(���傤)�͐S(����)�ɐ�(������)���ĕς��B�S�C(����)���Α�������(�ɂ�)��B�S�͋���(��)���Ĉڂ�B����(������)�Ȃ�Α����S�N(�ق�)�炩�Ȃ�B�S������(���傤�݂傤��)���ē�����(�͂邩)�ɑ����B(����W�@�����) [������] ���R���Ƃ������̂͐S�ɂ��������ĕς����̂Ȃ̂��B�S������Ă���Ί��͑��邵���̑��������ɐS�͈���������B������(������)�ł���ΐS�͘N�炩�ɂȂ�A����ł���B(���̂悤��)�S�Ǝ��R�������[�����т��Ă��邩�炢�̂��̂����C�Ȃ�m�ƁA���̂͂��炫�ł��铿�Ƃ����݂��邱�ƂɂȂ�B ����W�̊����̢���叟��(������傤�ǂ�)�R�����(��)�Č���(����)���݂����̔裂̏��̈�߂ł���B ������l�̓����J�R�̓o�R�L��m�l���痊�܂�A��C�����M�������̂ł��邪�A���̏o�����ɏ�L�̂悤�Ȗ����Ȋ��_��W�J���Ă���B ���̂悤�Ȏv�z�́A�R�яC�s�҂̐S������ł������܂�Ȃ����̂ł���A��C���g���Ⴋ���ɁA�R�̂�Ԃ��ƂƂ��A�ґz��S�Ƃ��āA�R�тɓ���C�s�����Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ��邩��A�S�Ǝ��R���Ɗւ�����C�͏n�m���Ă����̂��B ������A�{���ɂ����āA�����R�ɂ����鏟����l�̍s����܂�Ō��Ă������̂悤�ɋL�q�ł����B�����ɂ́A��l�Ɠ������ڂƐS�������āA�����������R�ɓ��s���Ă����C�������[�@ |
|
|
��5 ������s��
��(������)�ɓƍ��������̋�(������)�O��(����ۂ�)�̐��꒹(�������傤)�ɕ����꒹������l�S(�ЂƂ�����)���萺�S�_��(��������)��(�Ƃ�)�ɗ��X(��傤��傤)(����W�@����\) [������] ��(������)�ȎR�т̒��̑����ɓ�(�Ђ�)�荿���Ă���ƁA���������̂����܂�j���ĂԂ��ۂ�����(���@�m��)�ƚe���A���̐����������Ă����@���̂悤�ɁA���ł��疳�C�Ȃ�m�̐����Ă���̂�����l�̐S�ɖ��C�Ȃ�m�����݂��Ȃ����Ƃ����邾�낤���@���̐��ƁA�l�̐S�ƁA�������V�n����炪��̉����āA���A�����ɂ���@�����Ɩ@�Ƒm�A������O��Ƃ����B ����W�̊���\�̢���(����)�ɕ��@�m�̒�������B ���������ɑ����ō��T�����Ă���ƁA�Ԃ��ۂ������ƚe�����̐�(�q��)�����B���̒��̐��Ɍ[������āA�R���ɋ��鎩���̐S(���)�ɋC�Â����ꂽ�B���̏u�ԁA��̂Ƌq�͈̂�̂ƂȂ�A�����ɔ��������R(����)���L�������B���̂悤�Ȗ��ĂȐS�����r�������̂ł���B �����̔]�Ȋw�ɂ��A���]�̌����ƑɂȂ�E�]�����́A�s������g�̂Ƃ��̎��͂̋��(��)�Ƃ̈ʒu�W�𗧑̓I�ɔc������@�\���ʂ����Ă���Ƃ����B�Ƃ������Ƃ́A���̉E�]�ɂ���ĔF�����ꂽ��ʂ��܂���ɂ����āA�����ŋN���Ă���o�����ʁE�������������̂��A���]�̌���ƂȂ����̂��B ���̌��ꂪ���B���A�m���ɂ�鐢�E���\�z�����ƁA�l�Ԃ͎����葁���A���̒m�������ɂ���ĕ����̔��f�����A�R�~���j�P�[�V���������悤�ɂȂ����B �����Ȃ�ƁA�E�]�ɂ��g�̂Ƌ�Ԃ���̂��Ƃ��Ƃ̏�ʑ̌��͑a�܂��悤�ɂȂ�A���]���S�̕Ώd�Љ�i�s���邱�ƂɂȂ�B ������A�l�͎��Ƃ��āA�����������܂��ꂽ���_��Ԃ̏�āA�g�̂Ƃ��̐g�̂̒u���ꂽ��Ԃɂ͂��Ɩڊo�߁A����̌��_�ɗ����A��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���T�����Ă���g�̂ƁA���������̋�ԂŚe�����̐��ƁA���̒��̐�(�Ђт�)���`���镧�@�m�̈Ӗ��Ƃ��A�R�т̒��ɁA�͂�����Ƒ��݂��Ă����Ƌ�C�͒Ԃ��Ă���B �����ɂ��Ƃ�̐��E������B�@ |
|
|
�����Ƃ���
���̘_�l�̃e�L�X�g�́A�m�g�j����e���r�̢������̎��㣂ŁA�������N�ɕ��f���ꂽ���C�̐����|�O�@��t�̎�������|��Ƃ�����������(����)����̍u�b�ɂ��B ������������͍���R��w�w�������a�Z�\��N����Z�N�Ԗ��߁A���̌������R�ł̌����������Â����Ă������A������\�O�N�ɎR���~��A�����̎��V�ɋA�����ꂽ�ƕ����B��C�̒��q�ɏڂ����A���ɏ��Ȃ̏ڍׂȓlj��ɂ͒�]������B ���̋�C�����̑��l�҂��A��C���炪�������ɂǂ̂悤�Ȍ��t�������āA�l�тƂɕ��@�������������������̂ł���B ���߂Ă��̍u�b���Ă݂�ƁA��C�̎�������I�m�ɖ����̋������������Ă���A�����̌��t�͑�ϖ��͓I�ł���B�����ŁA���̎������e�L�X�g�Ƃ��āA�킽��������C�̐����Ă݂悤�Ǝv�����B �������āA���̂悤�ȗ������B ��A���@�͂��̖{���ɂ����āA����̂��̂����C�Ȃ�m��ɖڊo�߂鋳���ł��邩��A���̖��C�Ȃ�m�̓����̈�ł��鎩���̌ݏ����_(����)�ɂ���āA�K�������Ƃ����͂��炫���o�Ă���B ��A�l�Ԃ��܂߁A�����鐶�����̂ɂ́A���ɐ����邽�߂̢���̂��̂����C�Ȃ�m������܂�Ȃ���ɋ����Ă���B���̒m�̍��{��ܒq(����)��ɖڊo�߂邱�Ƃ��������߂邱�Ƃł���B �O�A����̂��̂����C�Ȃ�m��ɂ���ċ��ɐ����Ă���A�l�Ԃ��܂߂������鐶�����̂̂���̂܂܂̂�������@�g(�ق�����)��Ƃ����B���̖@�g�ɂ���āA���R�E���ۂ���Ă���B �l�A���R�E�̐��͢���̂��̂����C�Ȃ�m��̌��t�ł���A�l�Ԃ͂��̌��t�����R�̐��̂Ђт���A��̈�_����n�߂邱�Ƃɂ���Č��ꉻ�����B������A���t�ɂ���Đ��E�𗝉����Ă���l�Ԃ̐S�Ǝ��R���Ƃ͂��Ƃ��Ɠ������̂ł���B �܁A������s�ׂ̗v�f�͎O�ł���B�̂Ƃ��Ă̐g�̍s��(�p���Ɠ���Ƌ��)�ƁA���̌̂��R�~���j�P�[�V���������i�Ƃ��ėp���锭��(����)�s�ׂƁA���̐g�̂ƌ���̍s�ׂ������邱�Ƃɂ���āA���̏�ɐ��N���鐸�_�s��(�S�ƈӖ�)�ł���B �Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B �����́A���邪�܂܂ɐ����颐����̒�����̎����ł���Ǝv���B�����̂����̐^���̐��E�ƌ����̐��E�́A��ɂȂ��ď�ɑ��݂��Ă���Ƌ�C�͋�����B �M�d�Ȋw�т̋@����t����^���Ă����������B(���A�����̌�����͕M�҂ɂ��B)�@ �@ |
|
| ������W | |
|
(���傤��傤���イ)�@��C(�O�@��t)�̊������W�B10���B�Ҏ҂͒�q�^�ρB�����N�s�ځB
�������́w�ՏƔ�������W�x(�ւ傤�ق������傤��傤���イ)�B��C�̎��A����A��\���A�[�A�蕶�Ȃǂ��q�̐^��(����)���W���������̂ŁA10������Ȃ�B���m�Ȑ����N�͕s�������A�x���Ƃ���C���v�������a2�N(835�N)�����قlj���Ȃ������܂łɐ��������Ƃ݂��A���{�l�̌l���W�Ƃ��Ă͍ŌÁB10���̂��������`���\��3���͂͂₭�ɎU�킵�A���w����W�x�̊����`���\�ɂ́A����3�N(1079�N)�A�m�a���̍ϝ�����C�̈╶�����W���ĕ҂w���ՏƔ�������W�����x3�����[�Ă��Ă���B�Ȃ��A�ϝ��́w�����x�́A�U�킵�������`���\���̂��̂̕�����}�������̂ł͂Ȃ����A�㐢�̋U��ƍ����ł͔��肳��Ă����i���������܂�ł���B ���Ҏ[ �w����W�x�̏����ɂ��A�^�ς́A�t��C����ؑ��e����炸�A���̏�ŏ����ʂ��Ă����Ȃ����i�������Ă��܂����߁A��C��i���㐢�ɓ`����ׂ��A����T��Ɏ����ď����ʂ��A�����ɂ��Ė�500���ɋy�ԍ�i�����W�����B�����āA����ɓ��̐l�X���t�Ƃ��Ƃ肵����i����G��Ȃ��̂�I��ʼn����A�w����W�x10����҂Ƃ����B��ʓI�ɂ́A�w����W�x�̕Ҏ[�ߒ��́A���̏����̓��e�ɑ����ė�������Ă���B �������Ȃ���A�^�ς�15�ŏo�Ƃ���C�ɒ�q���肵���̂� �O�m5�N(814�N)�Ȃ̂ɁA�������Ȃǂ���ȑO�̍�i���w����W�x�ɑ������^����Ă���B�����ɂ́A�^�ς����ʂ���ȑO�̍�i���ǂ̂悤�Ɏ��W���ꂽ�̂��A��������Ă��Ȃ��B �ѓ�����Y�́A��C������������A�����̕��W�Ҏ[����}���Ď���̍�i�̎ʂ�������Ă����ق��A�X�̍�i�ɕ\���t����10���ɕ҂ލŏI�I�ȕҎ[��Ƃɂ��֗^���Ă����Ɛ��肵�Ă���B���܂̎��^��i�Ɠ������̂��P�̂̊��q�{�Ƃ��ē`������u�z�B�ߓx�g�ɐ��ӂē��O�̌o�������ނ�[�v�u�{���̎g�ɗ^�ւċ��ɋA���Ɛ��ӌ[�v�́A�M�ՂȂǂ����C�^�Ղ̍T���Ɣ���ł��A����ɗ]���ɕt���ꂽ�\�����C�^�ՂƂ݂��A�ŏI�I�ȕҎ[��Ƃɋ�C���֗^���Ă������Ƃ��M����Ƃ����B ��C��24�̂Ƃ��ɒ�����������w�W�ڎw�A�x�̏����ŁA�]���̒����Ɠ��{�̕��w��ɗ�ɔᔻ���A���w�ɂ�����|�p���Ɛ^���̗����𗝑z�Ƃ��Čf���Ă���B�����āA���̕��w���v�̎u�́A�w����W�x����̖`���u�R�ɗV��Ő���ӎ��v�̏��ł��\������Ă���B���w�̉��v�҂����Ƃ��Ă�����C���A����̍�i���㐢�Ɏc�����Ƃ��Ȃ������͂����Ȃ����A���^��i�̑I����z��Ƃ������ŏI�I�ȕҎ[��ƂɁA��C���֗^���Ă����� �\�����\���l�����悤�B ������ �w����W�x�̐^�ϕҎ[���ł��銪�ꂩ�犪���܂ł̂����A�N��̖��炩�ȍ�i�ōł��V�����̂́A�V��5�N(828�N)2��27���́u���@���͎������{�ɕ����ɑ��鎍�v(���O)�ł���B�O�m14�N1��20���̓��t�����u��l������ׂ̈̈⌾�v(���l)���A��l���e�����v�����V��6�N8���̂��̂Ƃ��A����������Ƃ����������B������ɂ���A�w����W�x�͔N�㏇�łȂ���i�̎�ޕʂɕҏW����Ă���̂ŁA����ꂽ�����`���\�ɂ��N��̐V�������̂��������\���͖R�����A�V��5�A6�N�������ƌ�����B���ꂪ�z��ł��鐬���N��̏���ƂȂ�B �����N����߂����Ȑ��͈ȉ��̂Ƃ���B ���V��7�N11���`9�N3���̊� �w����W�x�͐^�ςƋ�C�̋����ҏW�ł���Ƃ̌��n����A���Y�R�Ő^�ς���C���疧���̉��`��������ꂽ(���̋L�^���w���Y�����x�Ƃ�����)�Ɠ`��������ԂɕҎ[���ꂽ�Ƃ�����́B ���V��9�N���珳�a2�N3���̊Ԃŋ�C�ݐ��� �����Ɂu���R�T�O����^�ϐ�v�Ƃ��邱�Ƃ���A�^�ς����Y�R�����R�ɏZ�����V��9�N�ȍ~�Ƃ��A�u�����N�[�����āA�������̐������v�Ƃ��邱�Ƃ���A���ɐ^�ς���C�Ɏt�����Ă����ԁA���Ȃ킿��C�������Ƃ�����́B �����a2�N3���̋�C���Œ��� �����Ɂu�����攪�̐ܕ�����҂͌Ⴊ�t����Ȃ�v�Ƃ���A��C�𖧋��̑攪�c�Ƃ��Ă��邱�ƁA�u��ՏƋ����v�Ƌ�C�̂��Ă��邱�Ƃ���A��C�v��Ƃ�����́B�@ �@ |
|
| ���s�� 1 | |
|
(���傤���^���傤��) �V�q�V�c7�N-�V��21�N(668-749)
���{�̓ޗǎ���̍��m�B677�N4���ɐ��܂ꂽ�Ƃ�����������B�m�������Ƌ@�ւƒ��삪��ߕ����̖��O�ւ̕z���������ւ�������ɁA�ւ�j��E��(�ߋE)�𒆐S�ɖ��O�⍋���w�Ȃǖ�킸�L�����@�̋���������l�X���Ă����h���ꂽ�B�܂��A����⎛�@�𑽂��������������łȂ��A���r15�E�A�a�Ɩx9�A�ˋ�6�����A�����҂̂��߂̕z�{��9�������̐ݗ��Ȃǐ��X�̎Љ�Ƃ��e�n�Ő����������B�������A���삩��͓x�X�e����ֈ����ꂽ���A���O�̈��|�I�Ȏx���Ă��̗͂����W���ċt���˕Ԃ����B���̌�A��m��(�ō��ʂł����m���̈ʂ͍s����{�ōŏ�)�Ƃ��Đ����V�c�ɂ��ޗǂ̑啧(���厛�Ȃ�)�����̎�����̐ӔC�҂Ƃ��ď��ق��ꂽ�B���̌��тɂ�蓌�厛�́u�l���v�̈�l�ɐ������Ă���B ���o�� �����u�˒q�A��I�c�Î��䔄�̒��q�Ƃ��āA�͓���(��̘a��)�咹�S�ɐ��܂��B���Ƃ͌�ɍs��ɂ���ĉƌ����ɉ��߂�ꂽ�ꏊ�Ō��݂̑��{��s�ƌ������ɂ������B �����U �͓����咹�S(���݂̑��{��s�ƌ�����)�ɐ��܂��B682�N(�V���V�c11�N)��15�ŏo�Ƃ��A��(���厛)�Ŗ@���@�Ȃǂ̋��w���w�сA�W�c���`�����ċߋE�n���𒆐S�ɕn���~�ρE�����E�ˋ��Ȃǂ̎Љ�ƂɊ��������B704�N(���4�N)�ɐ��Ƃ��ƌ����Ƃ��Ă����ɋ��Z�����B���̎t�Ƃ���铹���́A�������Č����̋����������ƂŗL���ł���B ���O���������l���ł���ƒ��삩��^��ꂽ���ƁA�܂����̊O�ł̊������m��߂Ɉᔽ����Ƃ��ꂽ���Ƃ���A�{�V���N4��23���ق������ċ��e����Ēe�������B�����A�s��̎w���ɂ�荤�c�J����Љ�Ƃ��i�W�������ƁA�����▯�O��𒆐S�Ƃ������c�̊g���}������Ȃ��������ƁA�s��̊����삪����Ă����u�����{�v�I�ȈӐ}��L�������̂ł͂Ȃ��Ɣ��f�������Ƃ���A731�N(�V��3�N)�e�����ɂ߁A���N�͓����̋��R�r�̒z���ɍs��̋Z�p�͂�_�������̗͗ʂ𗘗p�����B736�N(�V��8�N)�ɁA�C���h�o�g�̑m�E���A�߂��`�����p�����o�g�̑m�E���N�A���̑m�E��璿�ƂƂ��ɗ��������B�ނ�͋�B�̑�ɕ{�ɕ����A�s��Ɍ}�����ĕ��鋞�ɓ�����������ɏZ���A������^�����Ă���B738�N(�V��10�N)�ɒ�����u�s��哿�v��拍���������ꂽ�B(���{�ōŏ��̗��ߖ@�T�u��߁v�̒��ߏ��ȂǂɋL����Ă���B) ���O�̂��߂Ɋ����s���740�N(�V��12�N)����啧�����ɋ��͂���B���̂��߁u�s��]���_�v(���O�̂��ߊ��������s����쑤�̑m���ɂȂ����Ƃ����)�����邪�A��ʓI�ɂ͌��͑����s��̖��O�ɑ���e���͂𗘗p�����̂ł���A�s����͎҂̑��ɂ����̂ł͂Ȃ��ƍl�����Ă���B741�N(�V��13�N)3���ɐ����V�c�����m���x�O�̐@�ōs��Ɖ���A��15�N���厛�̑啧�����c�̊��i�ɋN�p����Ă���B���i�̌��ʂ͑傫���A745�N(�V��17�N)�ɒ����蕧���E�ɂ�����ō��ʂł���u��m���v�̈ʂ���{�ōŏ��ɑ���ꂽ�B(�����{�I) �s��̊����ƍ��Ƃ���̒e���Ɋւ��ẮA�ޗǎ���ɂ����ċ�̓I�ȑm��߈ᔽ�𗝗R�ɏ������ꂽ�͍̂s��݂̂ƌ����Ă���B���̂��߁A���ꂼ��ɑ��āA������̒����ŐȌ����Ă����O�K�����c�̊����Ɠ����̒e���Ƃ̊֘A��e���W���w�E����Ă���B �O����g�@���{�s�����Ɵ�ƂȂǂ��͂��߁A�O�q�̓��厛�啧�����ɂ��ւ���Ă���B�啧���c����749�N(�V��21�N)�A�����(������)��81�œ��ł��A����s�̉����@�ʼnΑ���|�ю��Ɉ⍜����[���ꂽ�B�܂��A�����(������)���牝���@�܂ł̓������s��̒�q���ނ̗`�������ʼn^���������Ƃ���A�����@���ӂ̕�n�n�т͕ʖ��A�`�R�Ƃ��Ă�Ă���B�܂��A�������F��拍����������u�s���F�v�ƌ�����B���̎��ォ��s��́u�����F�̉��g�v�Ƃ������Ă���B�Ȃ��A�s��}�������A�߂�752�N�A�����V�c(749�N�ɑވʂ������́A����V�c)�̖��ɂ��A���厛�啧�J�ዟ�{�̓��t���߂��B ���̑��A�s��͌Î��̓��{�n�}�ł���u�s��}�v���쐬�����Ƃ���A���{�S����������A�����������p���H�Ȃǂ̎����H�����s�����Ƃ���A�S���ɍs��J����Ƃ���鎛�@�Ȃǂ��������݂���B ���s��ɉ��̗L��n �s��͋E���𒆐S�Ƃ����e�n�ŕz���������s���Ă������Ƃ���A�ߋE�n���𒆐S�Ƃ��Ċe�n�ɉ��̒n�Ƃ����y�n�����݂��Ă���B ���ƐՂ͒m�b�̕����F��{���Ƃ��邱�Ƃ��獇�i�F��ŗL���ȉƌ����ƂȂ��Ă���B ���{���Ύs���t�l3���ڕt�߂Ő��܂ꂽ�ƌ�����������A�u�s��a�̒n�v�̐Δ肪���Ă��Ă���B���̐Δ�ɂ́A�u�s��ɘA�Ȃ��H�W�c���玕�������l�Ă����A���̑�H�W�c�͓��얖���܂ŋ��s�䏊�̌�p��H�ƂȂ����A���x�ȑ�H�Z�p����g���č��Βn��̏Z��݂𐿂������Ă����v�ƍ��܂�Ă���B�Ȃ��A�����̌��тɂ��A���̕t�߂��u���v�ƌĂ�Ă���A�s��a�`���̂���n�Ɍ��Ă�ꂽ������ق��u�����(������)�v�ƌĂ�Ă���B �ߓS�ޗljw�O�ɂ́A1969�N�̓��w�n�����̍ۂɍL�ꂪ����A�ԕ��Ă̍s����������ꂽ�B�L��́u�s��L��v�ƌĂ�A�ޗǂł͂悭�m��ꂽ�҂����킹�ꏊ�Ƃ��Ē蒅���Ă���B���̐ԕ��Ă̍s��͌�ɐS�Ȃ��҂̎�ɂ���Ĕj��A���݂�1995�N�ɐ��삳�ꂽ�u�����Y�̑��������Ă���B ���{�ݘa�c�s�̔�����Ղł́A�v�ēc���J�R��(�s�)�O�Ɏ��Ӓn��̂��肪�W������B����́A�v�ēc���̑O�Ɉʒu����v�ēc�r���s��@��w�����A�c���̊J������ӏZ���̐�������֊�^���A���̑��̈⓿����������u�s��Q��v�ƌĂ�Ă���B ���Ɍ��ɒO�s�̍��z�r�����̉����{�݂ɂ͍s��̈̋Ƃ⋹�����ݒu����Ă���B���z�r�̓�쓌1�L���قǂ̏ꏊ�ɍs��̊J������z��������B�s���ɂ͍s�(���傤�����傤)�Ƃ����n��������B�@ |
|
|
���s��J��̎��@�Ɣ��n
��C�b�@����(���{��s��捂�q��) / �����@(���{�����s�ɉ���) / �w���r�@(���{��s���w��) / ���@(���{��s����뎛) / �ƌ���(���{��s����ƌ�����) �� ������(��쎛)(���ꌧ�����S���������41) / �_�P��(���{��s����P�k��) / �ߓc�r�@(���{��s���摐��) / ��쎛�A����@(���{��s����y����) / �[���@���Ԏ�(���{��s����[��) / ����y�@(���{��s��斩�A���{���Ύs) / ������(���{��s������u���������A�����_�Ђ̐_�{���Ƃ��Ă��đ��݂���) / �����@(���{��s�k�摠�O��1578) / �P���@��x�A�P����@(���{���s������) / ��g�x�@�A�����@�A��W���@(���{���s������) / ���c�@(���{���s�Z�g��) / ����@(���{���s�Z�g�撷����) / �������@�A��������@(���{���s�������) / �啟�@��ÁA�啟��@(���{���s�������Î���) �� �v�C���@(���{�����s��t���V��2����) / �E�c�@(���{�����s�ɉ�) / �@(���{�����s���t) / ���R�r�@�A���R�r��@(���{��㋷�R�s) / �Ɋy��(���{���Îs���a��6�Ԓn�t��) / �É@(���{�����s������) / ����y��@(���{���Ύs) / �я���(���{���s�M�B����395) / �R��@(���{�O���S���{��) / �v�ēc�� (���{�ݘa�c�s�r�K��) �� ������(�ޗnj�) / ���n��[(�ޗnj�����s�L����) / �����@�A������@(�ޗnj��ޗǎs��a�c��) / �����������(�ޗnj��ޗǎs������) / ���ɉ@���A���ɓ�@(�ޗnj���a�S�R�s��c��) / �����@(�ޗnj��ޗǎs�D�c��) / �@�T�@�w��(���s�{���s�s������[��) / �͌��@(���s�{���s�s) / ���@(���s�{���s�s�E����) / ��_��(���s�{���s�s�������q) / �g�c�@(���s�{���s�s������g�c�_�y����) / ����@(���s�{���y�S�R�钬�㍝��) / �@�A�z�{�@�A�z�{��@(���s�{���s�s������) / �Ɋy��(���ꌧ�F���s�Ɋy����) / ���ӎ�(���m�����C�s��c��) / �~�ʎ�(���m����{�s���a��) / �≮�ω�(���m���L���s��⒬) / ���ω���(���m���L���s��������) / ���厛(���m���L���s�_�J(���̂�)��) / �D���@�D�A�D����@(���Ɍ��_�ˎs���ɋ�) / �ڗ���(���Ɍ����p��) / �g�É@(���Ɍ���ӌS�����쒬) / ���z�{�@ (���Ɍ��ɒO�s���{) / �吹�� (���R������s�吹��) / �m��R�n���@(���ꌧ�_��s�_�钬�I1688) / ������(�R�`�����͍]�s) �����̑��ɂ��S���e�n�Ɏ��`�⏔���ɍs����J��(�n��)�Ƃ��鎛�@������������B�A�������̒��ɂ͖��s�҂��C�Ɠ��l�ɊJ��ꂽ�`���̎��@�������܂܂��Ɛ��������B�@ |
|
|
���s��@��w�����������r
���z�r(���z�r������)(���Ɍ��ɒO�s) / �v�ēc�r(���{�ݘa�c�s) - �v�ēc���Ɨאڂ���B / ���R�r(��㋷�R�s) - ���{�ŌẪ_���������r(���r)�����C�B ���s��ˋ��w�������� ��(�ؒÐ�) / �R�苴(����) / �s����(���m�[��) ���۔d�ܔ� �ےÂ���d���ɂ����āA�܂̍`(�۔d�ܔ�)�������Ƃ���Ă���B �͐K�� - ���s�_�蒬 / ��֓c�� - �_�ˎs���ɋ�(�_�ˍ`) / ���Z�� - ���Ύs���Z�� / �ؔ� - �P�H�s�I�`�� / ������ - ���̎s��Ò����� ���s��ɂ��J���`�������鉷�� ���{�S���ɂ͍s����������Ƃ���鉷����������B�A���A�����̒��ɂ͊J���`����������ۂɖ��O���g�p���ꂽ�����̉��������Ƃ����B ������� / ���R���� / ���m�q���� / ���É��� / �M�ˉ��� / ��� / �a���� / ���c������ / �R�㉷�� / �R������ / �g�މ��� / �J�É��� / �@�䎛���� / �O�J���� / �ؒÉ��� / ������ / ���]���� / ���������� ���ɂ��m���A�L�b�G�g��ƂƂ��Ɂu�L�n�̎O���l�v�ƌ��p����Ă���B���A�L�n����ⓒ�͌�����Ȃǂɂ��s��ɂ܂��`�����c���Ă���B ���s����� �\���̖{��(�{�뎛��)(���{�L�\�S�\������Ԓ�718)�@ �@ |
|
| ���s�� 2 | |
|
���S�m�E�s��̊���
�����Ő����ƋS�̐^�̊W��m�邽�߂ɁA�����s��ɂ��čl���Ă݂����B �s��͔ӔN�A�����E�̍ō��ʁA��m���ɂ܂ł����̂ۂ邪�A�����A����͔ނ�O��I�ɒe�����Ă����B ����J�s���玵�N��̗{�V���N(���ꎵ)�l���A�s��ɑ���ŏ��̋ֈ����������Ă���B�w�����{�I�x�́A �u���E��݂��D�G�Ȑl�ނ�o�p����̂́A�������������߂ł���A�@��x������̂́A�������֒f���邽�߂��v �Ƃ��������ŁA�m������邽�߂̘b���L�^���Ă���B �u�ߍ��A�S�������͖@���ɔ����A�D������ɓ����ۂߑm���𒅂Ă���B�O���͑m���Ɏ��Ă��邪�A�S�ɓ��l�̋C����������������U��ނ̂ł���A�אS���N����̂ł���B�m��͖{���A���ŐÂ��ɋ���������`������̂��B��H����҂�����Ȃ�ΐ����ȓ͂��o�����܂��������ŁA�ߑO���ɑ���ĐH������B�H���ȊO�͋֎~����v �Ƃ��āA���悢��s��𖼎w���Őӂ߂Ă���B �u�܂��ɂ��܁A�g���m�h�s��ƒ�q�ǂ��́A�J�ɌQ��W�܂�A�݂���Ɉ��ʉ���A�։��]��������A�k�}��g��ŁA�w�ɉ����](�Ђ�)�̔���͂��Ŏʌo���A�Ƃ�K�˂ł���߂Ȑ��@�����Ă͕�����A�U���Đ����Ə̂��ĕS����f�킵�Ă���B���̌��ʁA�m�����O�����ꑛ���A�l�X�͎d�������悤�Ƃ����Ȃ��B�ߑ��̋����ɔ����A����Ŗ@��j���Ă���v �Ƃ����̂ł���B �������A����̋����ɋ�����悤�ȍs��ł͂Ȃ������B�ނ�͏W�c�����t�ɒ�������������͂ւƂ̂��オ���Ă������̂ł���B �V����N(���O�Z)�㌎��\����A����͂��܂肩�˂Ď��̂悤�ɂ����B �u���鋞�̓����̎R�ɑ����̐l�X���W�߂ėd�����Đl�X��f�킷�W�c������B�����Ƃ��ɂ͈ꖜ�l�A���Ȃ��Ƃ��ł�����l������B����͐[���@�Ɉᔽ���Ă���B�������ꂩ��������܂邱�ƂȂ�畏����Ă��Ă͊Q�ƂȂ�ł��낤�B����͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��悤�Ɂv �����Ƃ��ňꖜ�l�A���Ȃ��Ƃ�����l�����鋞�������낷����œk�}��g�ނ��܂͈ٗl�Ȍ��i�ł���B |
|
|
���g���m�h�Ƃ̋�����I�����V�c
���삪�s��̏W�c��e�������̂́A����ɐM�k�̐����ӂ���オ�����Ƃ������R�����ł͂Ȃ��B�s���̏W�c���ޗlj����̍��{�E���ߐ��x��ے肷�邩�̂悤�ȍs�����Ƃ��Ă�������ł������B ���߂����O�̒�Z�A�_�n���k�����Ƃ�O��ɂ����A�ނ���g�ǖ��h�Ə̂��A��蒅����ǖ��̔��S����ӂ邢���Ƃ������Ƃ͂��łɂӂꂽ���A�s���̏W�c�����A�܂��ɗ��߂̐��_�𗠐�l�X�Ȃ̂ł������B �d���ł�J���ɂ������A�܂��ꂵ�݂Ȃ�����ł�s�ɉ^�Ԑl�X�̂��߂ɁA�s��͊e�n�ɋ����˂��z�{���Ƃ���~�쏊������A�z���ɓw�߂��̂ł������B ���R�A���O�̎x���͍��܂�A���ɂ́A�s��̏W�c�́A����ɂƂ��Ė����ł��ʑ��݂ƂȂ��Ă������B���ߍ��Ƃ̋M�d�ȁg�����h�ł���ǖ������́A����ɑm�`(�������傤�^�D�k�ǁq�������r)�ƂȂ�A�_�n���̂ĕY������悤�ɂȂ��Ă���������ł���B ������F�̐����ȑm�ł���A�[�ł̋`���͖Ə�����邪�A���x�m(���ǂ���)�͂��̂�����ł͂Ȃ��A�ނ�̑m�`�ƕY���́A����ɑ��锽�R�Ƃ݂Ȃ���Ă������ƂɂȂ�B�܂�A�ނ�̉^���������ɍL����A���߂̍��{�ǂ��납�A���Ǝ��̂����ł����˂Ȃ��قǂ̏d�厖�������̂ł���B���˂A���������̐l�X�̔����͂����ɋ��߂��邩������Ȃ��B �Ƃ��낪�A���鎞�_��]�@�ɁA����̍s���ɑ���ԓx�́A�t�]���Ă��܂��̂ł���B �w�����{�I�x�V���\�O�N(���l��)�~�\���̏��ɂ́A�ޗǂ̖k���ؒÂɋ����˂���̂ɁA�E���Ə����̗D�k�ǂ��������W���g�������Ƃ���A�����ŁA�ނ玵�S�ܐl�����ׂĐ����ɑm�Ƃ��ĔF�߂悤�A�Ƃ����L�q������B ���̋L�����A�V���\��N�̍L�k�̗��Ɛ����V�c�̊֓��s�K�̗��N�ł��邱�Ƃ͒��ڂɒl���悤�B��������\�����A�����������������������A����܂Œe�����Ă����s���̊������A�t�ɗ��p���悤�Ƃ������Ƃ͖��炩�ł���B ����ɓV���\�ܔN(���l�O)�\���ɂ́A �u�c�鎇���y�{(�����炫�݂̂�)�Ɍ�(����)���܂��āAḎɓ߂̕�������ނ��ׂɎn�߂Ď��̒n���J�����܂ӁB���ɍs��@�t�A��q���𗦂�ďO��(�������)�����ߗU(�݂���)���v �Ƃ����āA�����V�c�́A�啧���������邽�߂Ɏ����y�{�ɓy�n��p�ӂ��A�s��͒�q�����𗦂��āA�l�X�ɂ����ߓ������A�Ƃ����̂ł���B �������̂āA�S��I�����V�c�B �ܐ��I�A�Y���V�c�̓o��ɂ͂��܂����V�c�ƂƁg���m�h�̈ꑰ�̗��j�́A�����I�ɓ������̏o���ɂ���đ傫�ȋȂ���p���}�����B ��}�ƍق�ژ_�ޓ������ɔ��������V�c�Ƃ́A�����ɂ�����g���m�h�̈ꑰ�Ƃ̋�����I���ƂɂȂ�B ���͂��̓]�@���A�g���m�h�̈ꑰ��W�c�ɂ��ω��������炵�Ă������Ƃł������B ��������h�䎁�Ƃ������g���m�h���\����卋�������サ�A��ɉ���������Ă��������Ƃɂ���āg���m�h�̓����͖��O����������ŐV���ȉ^�����͂��܂����ƍl������B�����āA���̉���I�Ȓ���������o�����̂��s������̂ł���B |
|
|
���S�̎R�E����ƓV�c�Ƃ̑Η�
�^���V�c�ƋS�ǂ�������o�����V���Ȓ����B���̐^�ӂ�m�邽�߂̃L�[���[�h�́A�S�̎R�E����ł���B ����ƓV�c�Ƃ̗��j�ɂ͈�̖@���̂悤�Ȃ��̂������āA�ƍَw����e�S�ϐ���A���Ȃ킿�����ɂ������̓��{�������Ă����Њ���̓V�c�ƂƂ͂����Ԃ钇�������A�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�����āA���̂��Ƃ��A�s��Ɛ����̊W�ɑ傫�ȃq���g��^���Ă���B �����ŁA���̊���ƓV�c�Ƃ��߂���@���̗�������������Ă݂悤�B ����͌ܐ��I�ɂ����̂ڂ�B�ƍَw����ڂ������Y���V�c�́A�����̍c�����E���c�ʂ�ӒD���邪�A���̉ߒ��Ŏ��̌��͎ҁE�~��b�q�Ԃ�̂�������)���E�Q���Ă������Ƃ͂��łɂӂꂽ�Ƃ��낾�B�~��b�͑h��n���鎁�ł���A���ɂ���Ƃ��芋��ɒn�Ղ��������ꑰ�ł������B ���̂̂��A�Y���V�c�͊���R�Ƃ͐[�������łȂ����Ă䂭�B ����Ɏ�ɏo�������Y���́A�V�c��s�Ƃ܂�������������ȑ���ɏo���킷�B����₦�A����R�̐_�E�ꌾ��_(�ЂƂ��Ƃʂ��̂���)�ł���Ƃ����B�܂�œV�c�ɑR���邩�̂悤�Ȑ����ɓ{�����Y���́A�_��y���̍��ɗ��(�邴��)����B�g����h���̂͂��܂�ł������B �����I�A�h�䎁�͓V�c�Ƃ��(�Ȃ����낵)��ɂ��A�����ł͍c��ɂ̂����ꂽ�g��佾��(���̂�)���h�����Ē�����h�������B���̔�佾�����̍s�Ȃ�ꂽ�̂��A����R�̍��{�ł������Ƃ���Ă���B�h�䎁�̒n�Ղ͔ł��������A�ނ�͖{�т�����ł������Ǝ咣���Ă���B���̒���A�h������͓V�q�⊙���ɎE�����B�����̗썰������R�����ї������Ƃ����̂��A���R�̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ������炵���B ���Ȃ݂ɁA�h��������ŖS�ɍۂ��A�Ō�܂őh�����邤�Ƃ������ƂŒm���铌��(��܂Ƃ̂���)���́A�p�\�̗��ɍۂ��V���̕��͂Ƃ��Ċ��Ă��邪�A�ނ�͋S�̍�����̏����E����(����)�o�g�ƍl������B�ނ�̖{���n���܂��A�w�G(�Ђ̂���)���犋��ɂ����Ă̒n��ł������B ���āA�V���V�c�͐p�\�̗��̒��O�A�g��ɓ���邪�A�����œV����������S�������p�Ƃ���Ă���B���̓`�����������ǂ����m���߂邷�ׂ͂Ȃ��̂����A������N(�Z�㔪)�Ɉɓ��ɗ�����Ă��܂��������p���A���Ȃ��Ƃ��V���V�c�̎���ɂ́A���삩��F�߂��Ă����炵�����Ƃ́A �u���ߏ��p�A���؎R(���炬�̂��)�ɏZ�݂āA��p���Ȃď�(��)�߂��v �ƁA�w�����{�I�x�ɂ��邱�ƂŖ��炩�ł��낤�B�����p�͎����̓o��ɂ���āA�댯������Ă������\���͍����̂ł���B �����p�Ƃ����C�����̑c���A�����������҂ł������̂��͒���ƂȂ���̂͂Ȃ��B�������A���������Ɋ��Ă������ƁA�y���̉�Ύ��Ƌ����W�Ō���Ă������Ƃ͊m���ł��낤�B���̉�Ύ��́A�啨��_�̖���ŁA�O�֎��Ɠ����A�������̉����ɓ������Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂��B �Ƃ���ŁA�����p�͋S�_�����݂ɑ������S�̐e���ł��������A���̊���̏C�����́A�_���A�����A�����Ȃǂ��ӑR��̂ƂȂ��Đ��������@���ŁA���Ƃ��Ǘ����Ă����킯�ł��Ȃ��A���R�����I�ɎG���̂悤�ȗ͋����Œ����ԓ��{�ɑ���ȉe�����y�ڂ��Ă䂭�̂ł���B����͂܂�ŁA�������ɂ���Ė��E���ꂽ�^�̐_�X�̎̂悤�ŁA���邢�͓����̒z�����Ս��ȗ��ߐ��x�ɑ��閯�O�̉��l�̐����A���̂܂ܐ_�ɏ��ڂ������̂悤�Ȃ��ǂ남�ǂ낵��������������@���ł�����B �s���������̂́A���̊���̍��{���ŁA���������̒n�ŏC�s�A�T�s���Ă����Ƃ���A���邢�͌��h�����̗�������ނ̂�������Ȃ��B���Ȃ݂ɁA����́g���{�h�͑h�䎁����佾���������A�c�_���������ꏊ�ŁA���˂A���{�͊���̋S�̌̋��ł���A���̒n�ōs��C�s����������Ӗ��͑傫���B ���̂悤�ȋS�̏�ŏC�s�����ނ�ɋ��ʂ���̂͋��͂Ȏ�(���グ��)�͂ł���A���̖��͂���g���A�s��͖��O�����A���h�A�����͌��͂ɋ߂Â����Ƃ����B�����Ƃ������͂��ނ���x�������͓̂��R�ł��������A�܂�A����łȂ���ނ�́A���Ɍ��͂���e������A���͂Ɠ����Â����Ƃ������ʓ_������B |
|
|
���S�����͎҂���V�c�Ƃ������
�������Č��Ă���A�g����h�����m�Ȉӎu�������ėY���I�ȓV�c�ƂƑΗ����A�������ƑΛ��������Ƃ���������̂ł���B �����āA�������唲�F�����s��A�S�̎R�E����ŏC�s��ς��ƁA�܂������悤�ɁA��x�͌��͂̍�����������艺�낳�ꂽ�����̖���E������������o�ĕ����������ƂɁA�[���Ӗ����B����Ă����̂ł���B ���O�͍s��̋����ɏ]���A�݂�������Y�����邱�ƂŁA�������ߑ̐��ɔ�����|�����̂ł��낤�B�ނ�̊����́A�₪�Ē����k��������قǂ̗͂������Ă������̂ł���B ����A���������ɔ������������̋S�E�����́A���͒����ɂ����荞�ނ��ƂŁA��]��B�����悤�Ƃ����B�ނ�̎͂́A�₪�ċ{���ʼn؊J���A�����͏̓��V�c�̕a�C���������ƂŐM���A���͂̒��_�ɂ̂ۂ�߂Ă������̂ł������B �������A�s��A���h�A�g���^���Ƃ����S��I��œ��厛���������A���̏̓����������������Ă��̂́A�S�ǂ��̂���グ���������A�����͂Ƃ����傫�Ȓ����𗘗p�����������߂ł��������낤�B�S��i�����悤�Ƃ����F���������鎖���̐^���́A�قۂ��̐}���ʼn𖾂ł���͂��ł���B �������A������̓��̖ژ_�݂�A���h�⓹���Ƃ����������̖���̖�]�́A�����̕ǂ����z���邱�ƂȂ��A���s���ׂ�����B �������A���͂ƑΛ����A�g����邷�ׂ��S�ɋ��߂������̔��z��A����ʼn萶�����V���ȋS�̒����́A���̂̂��̗��j�ɏd��ȉe���𗎂Ƃ��Ă������̂ł͂���܂����B���Ȃ킿�A�i������V�c�Ƃ��A���̋S�������������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^���ł���B �����͓V�c�Ƃ̊O�ʂɂȂ邱�ƂŌ��͂��̂�����A�ނ�ɓV�c�ʂ��˂炤�ӎu�͂Ȃ������ƈ�ʂɂ͍l�����Ă���B�������A�����̎q�E������̓��̖\���́A�ނ�Ɋ�@���������炵���͂��ł���B���ɒ邪�����̎q�ł����Ă��A�������̗͂�������A��͑��̐��͂ɗ��p����Ă������ƁA�V�c���ӎu���������Ƃ��A�����ɂ͎�ɕ����Ȃ��Ȃ��ʂ����肤�邱�Ƃ��A�g�������Ďv���m�炳�ꂽ����ł���B�@ �@ |
|
| �����{�̓`�� / ���c���j�@ | |
|
���Ăѐ��ɑ��錾�t
���{�͓`���̋����قǑ������ł���܂��B�ȑO�͂�����悭�o���Ă��āA�b���Ē������悤�Ƃ���l���ǂ̓y�n�ɂ��A�ܐl���\�l���L��܂����B�����ߍ��͑��ɐF�X�̐V�ɍl���Ȃ���Ȃ�ʂ��Ƃ��n�܂��āA��낱��Ŏz(��)�������b���҂����Ȃ��Ȃ����ׂɁA����Ɏv���o���܂������A�Y�ꂽ��܂��������肵�čs���̂ł���܂��B���͂����ɂނ̗]��A�悸�Ǐ��̂����ȎႢ�l�����ׂ̈ɁA���̖{�������Č��܂����B�`���͎z���������́A����ȕ��ɂ��Đ̂���A�`����ċ������̂Ƃ������Ƃ��A���̖{��ǂ�Ŏn�߂Ēm�����ƁA�����ė��Ă��ꂽ�l�����l������܂��B ���{�ɓ`���̐�����(����)�l�ɑ����̂Ȃ�A�����ƌォ��ォ��ʂȘb���A�����čs������ǂ����Ɗ��߂ĉ������������܂����A���ꂪ���ɂ͒��X�o���Ȃ��̂ł��B�����悤�Ȍ����`�����A������R�ɕ��ׂČ��������ł́A�ʔ����ǂ݂��̂ɂ͂Ȃ�ɂ�����ɁA�킯�������ꂽ�ꍇ�ɂ���ɓ�����p�ӂ��A���ɂ͂܂��ƂƂ̂�ʂ���ł���܂��B��̓`�������{�����A�����ɂ������ɂ��U����ċ��āA�F�����̂Ƃ���ł͖{���ɂ��������̂悤�Ɏv���ċ���Ƃ����̂́A�S���s�v�c�Ȗ��ʔ������ƂŁA������(����)�ɂ͉B�ꂽ���R������̂ł����A���ꂪ���͂܂������ɂȂ��ċ���ʂ̂ł��B���Ɠ��l�ɉ��Ƃ����ĔV(����)��m�낤�Ƃ���l���A�����ĉ��l���o�ė��ĕ����Ȃ���Ȃ�܂���B���̊w���̍D��S��A������ׂɂ́A����ۂǂ���������炵���b����A�f���Ēu���K�v������̂ŁA���������b�肪������Ɠ��ɂ����̂ł���܂��B���ď�(�͂��܂����傤)�̘b�Ƃ����̂��A�����͐������������ċ���܂��B�\�O�˂̓`���������炸�܂Ƃ߂Č������Ǝv���ċ��܂����A�z�������̂��ʂ��ĎႢ�ǎ҂����́A�M�S�ȋ^����U�����Ƃ��o���邩�ǂ����B�Ƃɂ����ɂ��̖{�̒��ɏ������悤�ȒP���ł������F�ʂ̑N���Șb�́A���������͂Ȃ��̂ł���܂��B �ŋ߂Ɏ��́u�`���v�Ƃ��������Ȗ{������܂����B����͎�Ƃ��ė��_�̕��ʂ���A���{�ɓ`���̉h�����������H���l���Č��悤�Ƃ������̂ł����A�](����)�ĎႢ���ɂ��́u���{�̓`���v��ǂ�ŁA�����ł��O���̈�ł��L�����ċ��ĉ�����l�ł�������A�����͋��炭���[�߂�ꂽ���ƂƎv���܂��B����ɂ��Ă����̑��̖{���A�����������Ղɖ��͋����A������ǂސl�̐S�Ɏc���čs�����Ƃ̏o���镶�͂�������悩�낤�ɂƁA�l�����ɂ͋����܂���B����̂ɍ��x�͗F�l�����Ƒ��k�����āA����قǘb������ς��Č��܂����B���{�̕��͂́A��ʂɂ�⎨���Ȃ��ނ��������t�����܂ł͎g���߂����悤�ł���܂��B�`���Ȃǂ̔@���v�����ԁA���̌��t�ł���`����ċ������̂ɂ͂ǂ����Ă��ʂ̏������킵�������p���Ǝv���܂����A���̗p�ӂ��܂����ɂ͌����ċ����̂ł���܂��B�V�ɂ��̖{�����鏔�N�ɁA���̓_�������Ē��ӂ��Ă��������Ȃ���Ȃ�܂���B�@�@�@ ���a�\�ܔN�\�ꌎ�@ |
|
|
���͂�����
�`���Ɛ̘b�Ƃ͂ǂ��Ⴄ���B����ɓ�����Ȃ�A�̘b�͓����̔@���A�`���͐A���̂悤�Ȃ��̂ł���܂��B�̘b�͕��X���т��邭����A�ǂ��ɍs���Ă������p���������邱�Ƃ��o���܂����A�`���͂����̓y�n�ɍ��₵�Ă��āA�������ď�ɐ������čs���̂ł���܂��B����j��(�ق�����)�͊F����������Ă��܂����A�~��ւ͈�{�X�X�Ɏ}�U�肪�ς��Ă���̂ŁA���o��������܂��B�����̘b�̏����́A�����͓`���̐X�A���p(�����ނ�)�̒��ő������܂����A�����ɍ���̍������낢��̓`���̎�q��ԕ����A�����܂ʼn^��ł���̂����ꓙ�ł���܂��B���R��������l�����́A��ɂ��̓�̎�ނ̐̂́A�z���ƒ��a�Ƃ�ʔ�����܂����A�w��͂�����ɕ����āA�l���Č��悤�Ƃ���̂��n�߂ł���܂��B ���N�̑��̍L���w�Z�̒낪�A���͋�n�ɂȂ��āA�Ȃ�̓`���̉Ԃ��炢�Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��A�߂��ނ��Ƃ͕s�K�v�ł���܂��B���Ƃ͂����ɂ��A���܂��܂̂����`�����A��h���Ă������Ƃ�����܂����B�������ē������{�̈�̓��̒��ł��邩��ɂ́A�`�͏���������Ă��A����ς肱��Ɠ�����ނ̐A�������A�����Ă��Ȃ��������Ƃ��������ł���܂��B���͂��̕W�{�̂�����O���A�W�߂ė��ď��N�Ɍ�����̂ł���܂��B �A���ɂ͂����{���đ傫����������͂��A�B��Ă��̍��̓y�Ɛ��ƁA���̌��Ƃ̒��ɂ���̂ł���܂��B���j�͂��傤�ǂ���𗘗p���āA�͔|����_�Ƃ̂悤�Ȃ��̂ł��B���j�̍k�n�����ڂ��čs���A�`���̖�R�̋����Ȃ�̂�����O�ł���܂��B���������{�̉Ƃ̐��͐�ܕS���A�ƁX�͎̐̂O��N�������āA�܂����̕В[�̂ق�̏����������A���j�ɂЂ炩��Ă���̂ł���܂��B����̂ɏt�͖�ɍs���A�M(���)�ɂ͂����āA�̉��̉Ԃ̖���₤�悤�ȐS�����������āA�U����Ă���`�����ׂČ���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �������A�����Ȑl�����́A�����ʔ������b�̂Ƃ��낾����ǂ�ł��u���ɂȂ����炢���ł��傤�B���ꂪ�`���̈�̖̒��ŁA���傤�ǐ̘b�̏��������ĂƂ܂�}�̂悤�Ȃ��̂ł���܂��B���͒n���̓`�����Ȃ邽���L���ɂ��邽�߂ɁA�ڂ����y�n�̖��������Ēu���܂����B�������ĊF����ɍ���x�ǂ�Ō�����悤�ɁA��������̐����������Ēu���܂����B ���a�l�N�̏t�@ |
|
| ���P(����)�̂��Ηl | |
|
�͓̂����ɂ��A��������̒������`��������܂����B���̒��ŁA�F����ɏ����͊W�̂���悤�Ȃ��b�����Ă݂܂��傤�B
�{��(�ق�)�̌��뒬(�͂�ɂ�܂�)�̏،���(���傤����)�Ƃ������̉����ɂ́A��ڂ���̂��k����̐̑��������āA�����Ȑl�������P���o�č��鎞�ɁA���̂��k����ɗ��ނƒ�(����)�Ɏ���Ƃ����܂����B�傫�Ȑ̊}�����Ԃ����܂܁A���Ⴊ��ŗ����̎�Ŋ{(����)���������A�S�����悤�Ȃ��킢������Ăɂ��ł��܂������A�������F�̋����Ă����Ă����̂́A����������ɐl���i�サ�����̂Ǝv���܂��B�q�������́A������P�̂��Ηl�ƌĂ�ł���܂����B �S�N�قǑO�܂ł́A�]�˂ɂ͂܂����X�ɁA���̐̂��Ηl�������������ł���܂��B�z�n(����)�ڂ̈�t�Δn��(���Ȃ��܂̂���)�Ƃ����喼�̒����~�ɂ��A�L���ȊP�̔k�������āA�S���P�Ȃǂœ�V�����鎙���̐e�́A�����Ɩ�Ԃɗ���ŁA���̌䉮�~�̓��ւ��̐�q�݂ɂ͂���܂����B���Ƃ͘V���̌`�ɂ悭������ڗ]��̓V�R�̐������Ƃ������܂����A���̍���肩�A�����ƒ��������̑��ɂȂ��āA�������ꂳ��̑��Ɠ��(����)���Ă��܂����B�k����̕��͊������_�a�ŏ������A�ꂳ��͑傫���ċ��낵��������Ă��������ł����A�����������Ƃɂ́A���l�͐r�����������A����ɒu���ƁA�����Ɩꂳ��̕����|����Ă����Ƃ����āA�������������ĕʁX�ɂ��Ă���܂����B�P�̊�|���ɍs���l�́A�K�������Ŗ�(��������)���u(��)�蕨�����Q���āA��(����)�����Ƌ��ɂ���𗼕��̐̑��ɋ����܂����B�������čł��悭�������ݕ��́A�n�߂ɔk�l�ɊP�������ĉ������ƈ�ʂ藊��ł����āA�����ɖ�l�̂Ƃ���֍s���Ă��������̂������ł��B����������A��������ŊP�̕a�C�̂��Ƃ𗊂�ŗ��܂������A�ǂ����k�ǂ̂̎�ۂł͊o��(���ڂ�)�Ȃ��B������O�l�ɂ���낵���肢�܂��Ƃ����ċA��B��������Ǝ�ɑ����S������Ƃ����]���ł���܂����B(�\�����V���G�L�ܕ�) ���̒��̂悭�Ȃ���k�̐Α��́A��������ɂȂ��āA�b(����)���ǂ��֍s�������s�����s���ɂȂ��Ă��܂������A��ɋ��c(���݂�)�쓌�̋���(��������)�̍O����(�����ӂ���)�ֈ����z���Ă��邱�Ƃ�����܂����B���̎��͈�t�Ƃ̕��(�ڂ�������)�ŁA�z�n�̉��~���Ȃ��Ȃ�������A�����֎����čs�����̂ł������A�������̎��ɂ͌���(����)�Ȃǂ͂��Ȃ��悤�ɂȂ��ē�l���悭����ł��܂����B�������łȂ��P�̔k�l�Ƃ������O���l���Y��Ă��܂��āA�N�������o�������̂��A�����牺(����)�̕a�C�������Ă����Ƃ����āA���݂ɗ���҂������Ȃ��Ă��܂����B�������Ă���ɂ͗������������ė��ďグ��Ƃ悢�Ƃ������ƂŁA���̑O�ɂ͂��낢��̑����Ȃǂ��[�߂Ă����������ł��B(�y���k��) �H�ו���i�サ�Č��̕a�������Ė�����k�l�ɁA��ɂ͑��̕a�C�𗊂݁A����ɗ�������悤�ɂȂ����̂́A�����Ԃ�ʔ����ԈႢ���Ǝv���܂����A�L���s�̋�┪��(���炴��͂��܂�)�Ƃ������Ђ̘e�ɂ��铹�c�_(�����̂���)�̂ق���ɂ́A�q���̊P�̕a������悤�ɁA��|���ɗ���l�������A���̂��������́A��������n�̌B(����)�ł����������ł�(��X(�낭�낭)�G�b)�B���c�_�͓��̐_�܂����s�̐_�ŁA���̏�ɔ��Ɏq���̂����Ȑ_�l�ł���܂����B�̂͑����̎q���́A�F���̐_�̎��q�ł���܂����B�n�ɏ���ĕ��X�̂��Y�̂���Ƃ�K�˂ė��āA���ꂽ�q�̉^�������߂�̂́A���̐_�l���Ƃ����̘b������܂����B���Ȃ킿�q����������ׂɁA�n�̌B�̓���p�ł������_�Ȃ̂ł���܂��B�H��ʂ�l���n�̌B���(��炶)���グ�čs���_�͂ǂ��ɍs���Ă�����܂����A���ł͖��O�����낢��ɂ����A�܂��y�n�ɂ���Ęb������������ċ��܂��B�P�̂��Ηl�Ȃǂ��A����������Ƃ��̓��c�_�̌�e�ނł͂Ȃ����B��������ꂩ��F����Ƌ��Ɏ��͏����l���Č������̂ł���܂��B |
|
|
�P�̂��Ηl�͓̐��������łȂ��A���͑��̌��ɂ����������ɂ���܂����B�Ⴆ�ΐ�z(���킲��)�̍L�ώ�(����������)�Ƃ��������̒��ɂ��A����Ԃ��̐Γ��������āA�P�œ�V������̂ł��Q��ɗ���l����������ɂ����������ł����A���ł͂��̐��ǂꂾ���A�����킩��Ȃ��Ȃ�܂����B����Ԃ��͌Â����t�ŁA�P�̂��Ƃł���܂��B(����(�����)�S���B��ʌ���z�s�쑽��)
�b�B�b���c(�͂���)�Ƃ������ɂ��邵��Ԃ��k�́A��іڂ���̎O�p�ȐŁA����ɂ��u��Ӗ�(����)�Ƃ����Ƃ������āA�����������Ђ������ɋF��܂����B���Ƃ͍s���|��̗��̘V���߂����̐ŁA�₽��ɓ��������M(����)�肪����Ƃ����Ă�����Ă���܂����B(���{�����u�����B�R�����b������(�Ȃ�����)�S�b�S�c(�ЂႭ��)���㔪�c�g) �㑍(������)�̕U�c(����炾)�Ƃ������̉W�_(������)�l�́A�ߍ��ł͎q��_�ЂƂ����ď����Ȃ��{�ɂȂ��Ă��܂����A�����ł����鑸������̓��ꂪ���s���痈�āA�P�̕a�ŖS���Ȃ����̂𑒂����Ƃ���Ƃ����Ă���܂��B���ꂾ����P�̕a�Ɋ�|��������Ύ����Ă����Ƃ������ƂŁA�y�n�̐l�͊Î��������ė��ċ����܂����B�������ė��ނƕK���悭�Ȃ����Ƃ����b�ł���܂��B(�㑍�����e�B��t���N�ÌS�b���C(���Ђ�)���U�c���W�_��) �W�_�͂܂��q��(���₷)�l�Ƃ������āA�ŏ�����q���̂��D���ȘH�T�̐_�l�ł���܂����B���ꂪ����ɕς��ė��āA��ɂ͓����_���J(�܂�)�������̂Ǝv���悤�ɂȂ�A�����������Ă��邤���ɊP�ŋꂵ����A���@���������Ďq�������̕S���P���A���ނƂ����ɋ~���Ă��炤���Ƃ��o����悤�ɁA�M����l�������Ȃ����̂ł���܂��B ����(��������)�̉P��(������)�̒��ł��A����(���날��)���班������ɗ��ꂽ�c�̒��ɁA�����l�Ƃ����̏����Ȃق��炪�����āA�����ɂ͑��̐l���������������Ƃ����Ƃ��グ�āA�P�̏o��a���F���Ă���܂����B�P��̒��̓`���ł́A�����l�͐́b�P��|���(�����������킩�܂�)�Ƃ����c���a�l�̓���ł���܂����B�u�È���(���Â̂��˂���)�Ƃ����҂��P��̏���U�ߗ��������ɁA�����͂�������������N�������ē�(�̂�)�ꂳ���A�����͂��̂�����̏����b��(�����͂�)�̒��ɉB��Ă��܂����B�ǎ�̌R�����������m�炸�ɁA���̑���ʂ�߂��悤�Ƃ����̂ɁA�����ɂ��P���o���̂Ō������āA����̂����͎E����Ă��܂��܂����B���ꂪ���݂̎�ł���䂦�ɁA����Ō�܂ł��P������q��������ƁA�����Ă�炸�ɂ͂����ʂ̂ł��낤�ƁA�y�n�̐l�������l���Ă����悤�ł���܂��B�����������u(��)�蔞���͂����č�������ł����āA�F������䏳�m�̂Ƃ���A�H�ׂ�Ƃ悭�P���o����̂ł���܂��B�����H�ׂč���x�A�P�̏o��ꂵ�����v���o���ĉ������Ƃ�������ł������ƌ����āA�ߍ��ł͏Ă��מ�(�Ƃ����炵)��������l��������Ƃ����b�ł���܂����B���ꂩ�炨����Y����̂́A�������ɂނ������ɒ������ނƁA����ŊP�����܂邩��ł��낤�Ǝv���܂��B(������}�����B��t���b���(�����)�S�P�䒬�P��) �����������Ȃǂ̊P�̂��Ηl�́A�ʂɂ��������������Ȃ��Ă��A��͂藊�ނƎq���̕S���P�������Ă��ꂽ�Ƃ����܂�����A���̓`���͌�ŏo�������̂����m��܂���B�z�n�̈�t�Ƃ̉��~�̊P�̖�k�́A�ȑO�͏��c�����甠���֍s���H�́A����(�����܂�)�Ƃ����Ƃ���̘H�T�ɂ������̂��A�]�˂֎����ė������̂��Ƃ������Ƃł���܂��B���O(�ӂ�����)�Ƃ����m���A��(������)������Ă����ɏZ�݁A��ɏo�čs�����Ɏc���Ēu�����̂ŁA�����������O�̕���̑��ł��낤�Ƃ����܂�����(�����b赎u(������))�A�e�̑����c���ċ���҂��Ȃ��킯�ł�����A��͂肱������̐_�̓�ł������낤���Ǝv���܂��B�R�̓��⋴����(������)�A�܂��͕��Ղ̂悤�ɓ��H�̗�������u�̔������Ƃ���ɂ́A�悭�j���̐̐_���J���Ă���܂����B��������M�C(������)�̕��։z�������(�Ђ���)�̒���Ȃǂɂ��A�����낵����������̑���������āA���̈��腖�(�����)���܁A���̈���O�r��(��������)�̔k�l���Ƃ����܂����B�H���s���l���K�����ɕ��ŁA���ƊJ�������̒��ցA����čs���҂����邻���ł��B�����������ł͂܂��P�̕a���A�F��Ƃ������Ƃ͕����Ă��܂���B |
|
|
�ɂ͍�����l�\�N�قǑO�܂ŁA�W(����)����(�ӂ�)�Ƃ����r���������Ȃ��Ďc���Ă��āA��Ɛ̖��̕���(���̂���)���̘b���A���`�����Ă���܂����B�̊ω��l�����������N�ɉ����āA�S�k�̉Ƃɗ��Ĉ��̏h����A�����m�炸�ɐ̖���̒�(��)�Ō����āA����Ă��킢����l�����E���Ă��܂����̂ŁA�߂��݂̂��܂�ɔk�͂��̒r�ɐg�𓊂��Ď��B�W�����Ƃ����������ꂩ��N�����ȂǂƂ����܂������A���̒r�ł���͂�q���̊P�̕a���A�F��ƕK������ƐM���Ă��������ł���܂��B����͒|�̓��Ɏ������āA�݂̖̎}�Ɋ|���ċ�����ƁA�܂��Ȃ��S�������Ƃ������Ƃł�����A�W�_���A���Ƃ͂�͂�q�����܂����ĉ�����_�ł������̂ł��B(�]�˖����L)
�����K���킯�̂��邱�ƂƎv���܂����A�W�_�͂����Ă����̔�(�قƂ�)���J���Ă���܂����B����ʼnP��̂����l�̂悤�ɁA���̒��Ŏ����̗삪�c���Ă���Ƃ����悤�ɁA��������b�������Ȃ����̂ł���܂��B�É��̎s���班�����A���C���̏�������l�\�Ԗk�ւ͂������Ƃ���ɂ��A�L���Ȉ�̉W���r������܂����B�����ł͗��l���r�݂̊ɗ��āu�W�b�b��(����)�Ȃ��v�Ƒ傫�Ȑ��ŌĂԂƁA��(������)���r�̐����N(��)��������Ƃ����Ă���܂����B�u�b��Ȃ��v�Ƃ����̂́A�����̌��t�ŁA�u���߂��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł���܂��B����ɂ��Ă��낢��̘̐b���`����Ă���悤�ł����A��͂肻�̒��ɂ��P�̕a�̂��Ƃ������҂�����܂��B�x���G�u(����������)�Ƃ��������ɍڂ��Ă���b�́A�̂���Ƃ̓��ꂪ��l�̎q������Ă��̒r�̖T(����)�ɗ������ɁA���̎q�����P�����đ傻���ꂵ����̂ŁA��������ň��܂��悤�Ǝv���āA���ɒu���Ă�����Ɩڂ�����ƁA���̊ԂɎq���͋ꂵ�݂̂��܂�A�]���Ēr�ɗ����Ď���ł��܂����B������e�����ɐ\���킯���Ȃ��āA�����Đg�𓊂��Ď��B���ꂾ����u�W�b��Ȃ��v�Ƃ����Ƃ��₵����A�܂���|��������ƊP������̂��Ƃ����̂ł���܂��B�Ƃ��낪�A���͋��J(���Ȃ�)���҂Ƃ�����Ƃ̓��l(�߂̂�)�ŁA��N�̊P�̕a���Ȃ���悤�ɁA���̉Ƃ̖T�̐̒n���l�ɋF��A�킪�g�𓊂��Ď�l�̒t���̖��ɑ�����A����ł��̎q�̊P�����������肩�A��X���܂ł����̕a�ɂ�����҂��A�~���̂ł���Ƃ����Ă�����̂�����܂��B�`���͂��Ƃ��Ƃ��������ӂ��ɒ������тɏ������b���ς��Ă���̂����ʂł����A�Ƃɂ����ɂ��̒r�̂��ɂ͊P�̉W�_���J���Ă���A���鎞��ɂ͂��ꂪ�̒n���l�ɂȂ��Ă����炵���̂ł���܂��B�������Ēn���l�����̐_�ŁA�܂����Ɏq���̂����Ȍ���ł���܂����B(���{�S���B�É��������s���]�����Ǖ�) �W�_�����Ǝq���l�Ɠ����_�ŁA��Ɏq���̈��S����肽�����_�ł���Ȃ�A�ǂ����Č�X�͊P�̕a������A�����ĉ�����Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��낤���A��������ɂ͎v���Ⴂ���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��A�l���Č��悤�Ƃ����l������܂����B�㑍���̓�̒[�ɊւƂ������������āA�ȑO�����ɂ͍�����ځA���͓�\���ڂ���A�`�͔��p�ŏ�Ɍ��̂���������܂����B��̂��̑��Ɋ֏��̖傪�����āA����͂��̓y��̐ł���Ƃ������ƂŁA�y�n�̐l�͊ւ̂��ΐƌĂ�ł���܂����B���ΐ͌��Ə����̂��悢�Ƃ����҂�����܂������A��͂�ق�Ƃ��͉W�ł������悤�ŁA�������듹�����̂��߂ɓ����̈������菜(��)�����Ƃ��낪�A���ꂩ�瑺���Ɉ������Ƃ��肪�����̂ŁA�܂����̐������ē��̉��̏�ɂ����āA������W�_�Ƃ������J�邱�ƂɂȂ�܂����B���Ƃ̒n�Ɏc���Ă�����̈�̐��A�W���Ǝv���Ă���l�������悤�ł���܂��B�������đ��̒n���ɂ���_�Ɠ��l�ɁA���̕S�N�قǂ̊Ԃɏd�����{�ɂȂ����Ƃ�����������܂����B(�㑍�������B��t���N�ÌS�֑���) �P�̂��Ηl�͎��͊ւ̉W�_�ł������̂��A�����Ƃ����Ƃ��납��l���P�̕a����ɁA�F��悤�ɂȂ����̂ł��낤�Ƃ��������A�s�q�@��(���傤���ق�����)�Ƃ����]�˂̊w�҂��A�����S�N�]����O�ɏq�ׂĂ��܂���(�b�q��b(�������)�Z�\�O)�A���̐l�͏㑍�֑̊��ɁA���ΐ����邱�ƂȂǂ͒m��Ȃ������̂ł���܂��B�ւ̉W�_�͂������A�㑍�ƈ��[(����)�Ƃ̍�(������)����ɂ������̂ł͂���܂���B��ԗL���Ȃ��̂͋��s����ߍ](������)�։z���鈧��(��������)�̊ւɁA�S�Γ�(�����Ƃ��ǂ�)�Ƃ����Ă������̂��W�_�炵���Ƃ����b�ł���܂��B��ɂ͊֎�����(�����ł炱�܂�)�Ƃ����āA���쏬�����N������Ă��炱���ɂ����Ƃ����b������A���̖ؑ��͒Z���ƕM�Ƃ���Ɏ������V���̎p�ɂȂ��Ă��܂����A�ȑO�͂���������Ƃ����낵����������̑��ł���A���̑O�͂����̓V�R�̐ł����������m��܂��ʁB�����͂��Ȃ킿��(��)�����߂�Ӗ��ŁA���c�_�̂������������Ƃ��A�ƍs�q�@��Ȃǂ͂����Ă���܂��B�����ɂ��֓��n���̓��c�_�ɂ́A�ɒj�Ə��̑����������̂������A�W�̕��ɂ����͖�Ɠ�����̂��A���Ƃ͂�������ɂ������̂ł���܂����A�l���k�l������ɂ���悤�ɂȂ��āA��̐͂��������Ȃ�܂����B ����ɂ�腖����܂̐M������ɂȂ�ɂ�āA�O�r�͂̔k�l�̖ؑ�����X�̂����ɍՂ�悤�ɂȂ������Ƃ��A��̌����ł����������m��܂���B�����ł͂��̂��킢��������k�̂��Ƃ��A�D�ߔk(������)�Ƃ����Ă���܂��B�n���̓r���̎O�r�͂Ƃ�����݂̊Ɋւ������āA���̐�����s�������S��(��������)�́A�ߗނ�(��)�����Ƃ����̂ŗL���ɂȂ��Ă���܂��B�����n����F���S�����\���o(�Ԃ����������ڂ��ق�����˂イ�������傤)�Ƃ������{�ł�������o�ɁA���̎����ڂ��������Ă���܂��āA���������ƒD�ߔk�������Č�Ƃł͂Ȃ��̂ł��B���߉�(������)�Ƃ����̂����̖�̕��̖��ł���܂����B �u�k�S�͓��Ƃ��x(���܂�)�߂ė���̎w��܂�A���S�͖��`����(�ɂ�)��œ���(������)���ꏊ�ɕN(����)�ށv�Ƃ������āA���l�͕v�w�̂悤�Ɍ�����̂ł���܂����A�ؑ��͑��k�̕�������Ă���܂����B����ɂ��[���킯������̂ł����A�F����ɂ͂���Șb�͂܂�Ȃ��ł��傤�B |
|
|
�Ƃɂ����ɂ��̒D�ߔk��q�ނ悤�ɂȂ��Ă���A�W�_�͑����͈�l�ɂȂ�A�܂����̊炪����ɂ����낵���Ȃ�܂����B�]�˂Ŋւ̂��Ηl�ɓ��u����グ��悤�ɂȂ���������A�s���̎��ɂ����\�ӏ��̖ؑ��̔k�l���o���A���ł��܂����������Ŗ~�ɂ͂��w(�܂�)�������҂�����܂��B���ꂩ��͂��a�Ȃǂ̐���Ȏ��ɁA���킢��������k�̂͂����ė���̂������Ƃ����悤�Șb���A����ɑ����Ȃ����悤�ł���܂��B�Î�k�Ƃ����āA�Î��͂Ȃ����Ƃ����Ȃ���͂����ė���k���A�u�a�_���ȂǂƂ����Ђ傤����悭�s���܂����B�����q�������e�����́A���������ꍇ�ɂ͋}���łǂ����̔k�_�l�ɂ��w�肵�܂����B�ւ̂����܂��]�˂ł��̂悤�ɕ]���ɂȂ����̂��A���͂����Ǝ�(����)�̈������`�́A�͂�����N�Ȃǂ��n�߂ł������낤�Ǝv���Ă��܂��B
����ɂ��Ă������̂��Ηl�Ƃ����悤�ȁA�Â����O���c���Ă��Ȃ���A�ǂ����Ă���Ȑ̔k�̑��̂Ƃ���ցA�q���̕a�C�𑊒k�ɍs���̂��́A�����킩��Ȃ��Ȃ��Ă����悤�ł���܂��B�O�r�͂̔k�l�̎O�r�͂Ƃ������t�Ȃǂ��A����ς�ւƂ������Ƃł���܂����B�O�r�͂͂ɂ����̂̏\���o�ɂ͑�����(��������)�Ƃ������Ă���܂����A����Ȓn���������̕��ɑO���炠�����킯�łȂ��A���������͓��{��ł����E(������)�Ƃ������Ƃł������̂��A��ɒN��������Ȃނ������������Ă͂߂��̂ł���܂��B�x�m�R���̑��̗�R�̓o����܂��͑傫�Ȃ��ЂɌw��H�ɂ́A���͂��������ꏊ������܂��B���i��(���傤������)�Ə����̂��ł����ʂŁA���ۂ����ɂ͐��̗��ꂪ����A�Q�w(����)�̐l�͂��̐��Őg����(����)�߂��悤�ł����A���ꂪ���߂���̌��t�̈Ӗ����A�\�������̂ł��邩�ǂ����͂܂��m�ł���܂���B�����������_�l�̗̕��̍�(������)�ł��邽�߂ɁA���悢�挵�d�ɐg�����݁A�܂�������_��q�悤�ł���܂��B�̂̊ւ̉W�_�́A���������A�ꍇ�̖�_�Ƌ��ɁA�������J��ꂽ�̐_�ł������낤�ƁA���Ȃǂ͍l���Ă��܂��B������̕��ɓ����Ă����l�������A�����čs���Ēn���ɍs���H�́A�O����(�݂�����)�̋S�k�ɂ����̂ł���܂��B���ꂾ���炱�̐��ɂ��鏔���̂��������ɂ́A�����͒D�ߔk�̑����J���Ă���̂ł���܂��B ���{�{�y�ň�Ԗk�̒[�ɂ���̂́A���B�b�O�암(���ƂȂ��)�̐��Ð�(���傤�Â���)���̉W���ŁA������x���Q����������Ƃ�����܂��B���C���ł͔���(�����)�̔M�c(����)�̒��ɂ���W���́A�Â�����L���Ȃ��̂ł���܂����B����͔M�c�_�{�̐��i��ɉ˂�����W�q(�����)���A�ꖼ����������(������)�ɂ���䓰�ŁA���Ƃ͈��Z�ڂ̒D�ߔk�̖ؑ����u���Ă������ׂɁA�M�c�_�{�͌�{�n(���ق�)腖����{���ȂǂƂ����ꑽ�����Ƃ������҂�������܂�����(�Дb(���傤��)�x�m�����L)�A����͉W�_�̂��Ƃ̂��p���A�Y��Ă��܂����l�̂������Ƃł���܂��B�\���o�͂����̌�o�ł������A����Ɋ�Â��Ēn���̊G����������҂��S���𗷍s���Ă���A���ꂪ�܂��w�l�ł���܂����ׂɁA�킸���ȊԂɕ��X�̌�W�q�l���A����������낵���D�ߔk�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�ȑO�͂����肸���Ƃ₳������ł��������ƂƎv���܂��B�����łȂ���킴�킴�n���������ė��āA�������l�Ԃ̎q���̂��߂ɁA����Ȃɐe�ɐS�z�����Ă����͂��͂Ȃ�����ł���܂��B ���ł��O�r�͂̔k�l�͂��킢������Ȃ���A�q�������̗F�l�ł���܂��B�~�̏\�Z���ɂ��M����̏��N���V�тɗ��܂��B�������łȂ��A�����Ə����Ȏq���ׂ̈ɂ��A���܂��Ɠ��̐S�z�������ȂǂƂ����̂́A�܂������̏����������̂悤�Ɍ����܂����A���ꂪ�������Đ̂���́A�W�_�̖�ڂł������̂ł��B�H��(����)�̋���̐����(������)�̂���́A���ł͎O�r�͂̉W���Ƃ����Ă��܂����A���̏�����e����|��������ƁA�K����������ɏo��悤�ɂȂ�Ƃ����܂��B���̑��͐̐�����̊J�R�b�@�J��l(������傤�ɂ�)�̖��Ɉ�l�̏�������āA���͏��쎛�̕ʓ��т̓���(�ق炠��)�̒��ɁA�����̑��Ƒ���@���̑��Ƃ����Ēu�����B���������ė��čՂ邪�悢�Ƌ����Ă��ꂽ�B���������s���Č���Ƃ��̒ʂ�̓�̑����������̂ŁA�}���ė����Ƃ����`���Ă��܂��B�Y��(������)�̏��쎛��䉖�(���Ⴍ�₭)�̖����ŁA���쏬�����J�����Ƃ�����������܂�����A��������}���ė����ؑ��Ȃ�A���Ƃ������قǂɔ������͂Ȃ��Ă��A�܂����S�����悤�ł͂Ȃ������낤�Ǝv���܂��B(�H�c���ē��B�H�c���b��k(����ڂ�)�S���r��) ����(���傤�Ȃ�)��̓V�����̂��傤�����̉W���A���s���̕w�l���F�肷��Γ��𑝂��Ƃ����āA�����̐M�҂�����܂����B����������ČÂ���̖ؑ��������ł�����A��ɖ��O���������܂������̂ł��낤�Ǝv���܂��B(�O�S�G�L�B�R�`�����c��S�������) ���B�b���t(�݂�)�̑�n�����̓��ɂ���D�ߔk�̑��́A�V�������̂��낤�Ǝv���܂����A�����ł��q���̖����������F��l�������A���̂���ɂ͎q���̑������グ�܂����B�V�Ɋ�|��������҂́A���̑����ꑫ����čs���A����Q��̎��ɂ͂����ɂ��Ĕ[�߂�̂ŁA�����n�����̒��́A�q���̑����ň�t�ł������Ƃ����܂��B(���t����B�É����b�֓c(���킽)�S���t��) ���ꂩ���B�̍���s�ɂ́A��t�Ƃ�����̗�������āA���̕��߂ɂ͍O�@(�����ڂ�)��t�̍�Ə̂���Α��̔k�l������A��������傤�����̔k�Ƃ����Ă���܂����B����ɂ͊P���킸�炤�l���F������āA���邵�������͂蔞�������������ė��ċ������Ƃ������Ƃł���܂��B(����u�B�Q�n������s�ԍ⒬) �z��ł͒����̒������Ƃ������ɁA�Â��\������������腖��l���J���Ă��܂������A�����ł͕Ă��u�蕲�������ĊP�̕a���F��ƁA�����ǂ���ɑS������Ƃ������ƂŁA�P�̏\���Ƃ����ΒN�m��ʎ҂��Ȃ����������ł��B腖��ɕĂ̂��������グ��̂͒������b�ł����A���Ƃɂ��Ƃ��Ƃ͌��t�̒n�����̑����̂悤�ɁA���������Ă������Ƃ̉W�l�̂��������ł����������m��܂���B腖��ƒn���Ƃ͓�����̐_�́A���ʂł���Ƃ������l������܂��B����������������n���͎q���̐��b���ł�����A�킴�킴���킢��������k����ɗ��ޕK�v�͂Ȃ��̂ł����A�ȑO�͂��ꂪ�����̎q���_�ł�������ɁA�����䓰�̒[�̕��ɏo�Ă��āA�Q�w�l�̖ڂɂ��Ղ��Ƃ��납��A�q���₻�̕�e�̊肢���Ƃ́A��͂肻�̔k�l�̎�莟���𗊂ޕ����A�֗��ł��������̂Ǝv���܂��B���ۂ܂��l�Ԃ̕��ł��A�n����腖��̍Ղ�ɉ�������҂́A���߂����܂ő��ĊF�w�l�ł���܂����B���ꂪ�q���W�_�̎O�r�͂̔k�ɂȂ��Č���A�i�����Ă͂₳��Ă�����̌����ł��낤�Ǝv���܂��B�@ |
|
| ����������(���݂�) | |
|
���ꂪ��Ȏ�l�̎q�𐅂̒��ɗ����āA�������\���킯�̂��߂ɐg�𓊂��Ď��Ƃ����b�́A�x��(���邪)�̉W(����)���r�̑��ɂ��܂����X�ɂ���܂��B���ꂾ���Ȃ�ق�Ƃ��ɂ��������Ƃ��Ǝv���܂����A�Ȃ����̊O�ɂ�����ɂ悭�����s�v�c�b������̂ŁA���ꂪ�`���ł��邱�Ƃ��m���̂ł���܂��B
�z��̘@�؎�(���)���̛H(����)����Ƃ����È�˂Ȃǂ����̈�ŁA�����ł��l����˂̖T(����)�ɋ߂���āA�傫�Ȑ��ł��ƌĂԂƁA��(������)����˂̒ꂩ�炵����ɖA(����)������ŗ��āA���傤�ǂ��̐��ɓ�����悤�ł���Ƃ����܂����B��(���邢)�͂�����^���҂��A����ɂ��ɂƌĂсA�܂��͂������ƂƌĂ�Ō��Ă��A�܂�Œm��ʊ�����Ă��������A�������Ȃ������Ƃ������Ƃł���܂��B(���̔V�x(���̂�����)�\�l�B�V�����O���S��Ñ��@�؎������m(�m)�n��) ���Ȃ킿����ł����v�����Ȃ�����܂ŁA�H�̗삪���̒��ɗ�(�Ƃǂ�)���Ă���ƍl��������ꂽ�l�����������̂ł���܂��B�������̑]�n(����)���Ƃ����Ƃ���ɂ́A�܂����܂�Ƃ����̂�����܂����B������T�ɗ����Ă��܂܂�ƌĂԂƁA�����Ɛ��̖ʂɏ��g(�����Ȃ�)���N�����Ƃ����܂��B���܂�͂��̋߂��ɏZ��ł����^(�Ȃɂ���)�Ƃ������m(���ނ炢)�̏��[�ł���܂����B�v�ɑ��܂�āA�E����Ă��̈�˂ɓ������܂ꂽ�䂦�ɁA���܂ł����̂���݂����̒��Ɏc���Ă���̂��Ƃ������Ƃł���܂��B(���؎��̓��{�`���W�B�V�����b���H(�����)�S�b����(�Ȃ��ǂ���)���]�n) ����Ƃ悭�����`���́A��B�ɐ���̋߂��̏��㌴(���������͂�)�Ƃ����Ƃ���ɂ�����܂����B����͈���(����)���r�Ƃ��������Ȓr�������āA���݂̊ɗ����Đl�����܂ƌĂԂƁA�����������ɂ��̐��ɓ����ĉ�����N(��)�����A�u�����ΌĂׂ����Ώo�Áv�Ƃ����Ă���܂��B(�ɐ��蕗�y�L�B�Q�n���b���g(����)�S�b�B�@(�����͂�)����A��) ���܂����܂���܂��H����̂����A���̐����܂��Ƃɋ߂��̂́A�������R�����邱�Ƃ����m��܂���B�x�͂̉W���r�ł��l�����ƌĂׂΗN�����A�W�b��Ȃ��Ƃ������悢�捂���A�𐁂��āA���������Ƃ����b�ł���܂��B�����̗N���o��r���˂ł́A�i�������Ƃ݂Ă���ƖA�����A�܂�����̏_�����y�ނƁA�����������Ƃ����邩�Ǝv���܂����A�����傫�Ȑ��ŌĂԂƌĂʂƂŁA�N������~�����肷�邱�Ƃ�����Ƃ����̂͊�ł��B�������������������]���ɂȂ��Ă��āA�l�����ʂɒ��ӂ��邽�߂ɁA�����������Ƃ��킩�����̂����m��܂���B �����悤�ȕs�v�c�͎��͂܂����X�ɂ���܂����B������������肨�b���Č��܂��傤�B �ے�(������)�L�n(�����)�̉���ɂ́A�l���߂��֊���đ吺�ň����������ƁA�����N�����Ƃ��������ȓ����������āA�������ȓ�(����Ȃ�̂�)�ƌĂ�ł���܂����B����Ȃ�Ƃ������t�͌�Ȃ̂��Ƃł����A��ɏ��̌���(����)�̂��Ƃ������悤�ɂȂ��Ă���́A�ʂɈ���������҂͂Ȃ��Ă��A�Ⴂ���Ȃǂ����������ς����ē��̖T�ɍs���ƁA�����ɓ{���ėN�����Ƃ����]���ɂȂ�A�����i(�˂�)�݂̓��Ƃ����l������܂����B����Ȃǂ͂�قljW���r�̘b�Ǝ��Ă���܂��B(�ےÖ����}��B���Ɍ��L�n�S�L�n��) ��B(�₵�イ)�̓ߐ{�̉���ł��A���Ƃ͓��{����O�����藣��āA���`(���傤�ł�)�n���Ƃ����Ƃ��낪����܂����B�l�������֍s���āA�u���`�b��Ȃ��v�Ƒ傫�Ȑ��łǂȂ�ƁA�����܂����炮��Ɠ����N�����Ƃ����܂��B�̋��`�Ƃ����j�͎R�d(������)���̂�ɍs�����ɁA���т��x���Ȃ��ėF��������ɍs���̂ɕ��𗧂ĂāA��e�ݓ|���ďo�������̂ŁA��(����)���ł��̍������܂ł��A����ȂƂ���ɂ���̂��Ƃ����b������܂����B(���ʕ���B�Ȗ،��ߐ{�S�ߐ{�����{) �ɓ��̔M�C�ɂ͂܂������q�哒(�ւ����������)�Ƃ����̂������āA�u�����q��b��Ȃ��v�Ƃ��炩���Ɠ����N���Ƃ����A���̐l�������ʔ�����̂ŁA���̎q���������K��������āA�Ă��Č������Ƃ������Ƃł���܂��B���ꂪ�������̊ԟ[��(������)�̂��Ƃł��낤�Ǝv���܂����A�O�ɂ͂��̓��ɐ����q�哒�A�ꖼ�b�@�֓�(�ق�������)�Ƃ����̂������āA�����ł��吺�ɔO���������Ďb(����)�����Ă���ƁA���������N�����Ƃ����Ă���܂����B�@�ւ��l�̖��̂悤�ɕ����܂����A���͖@�֔O���Ƃ����x��̔O���̂��ƂŁA���ꂾ����@�֔O����Ƃ��Ă�ł���܂����B�O���łȂ��Ƃ��A�����ɉ������������ΗN���̂��Ƃ������l������܂����A���܂��Č��Ă��Ă����R�ɗN��������̂����m��܂���B(�L�v�����و�ё����B�É����b�c��(������)�S�M�C��) |
|
|
����ł͂Ȃ��Ƃ��A�O����������Ɛ����킭�Ƃ����r�͕��X�ɂ���܂����B���s�̐��̗F�����ł́A�S�����E�q��Ƃ����l�̉��~�̌�ɁA�����͐����Ȃ��āA�݂ɗ����ĔO����\���ƁA�����N���o���Ƃ����r�������āA����ŔO���r�Ƃ����Ă���܂����B�ߍ��͂ǂ��Ȃ������A���͂܂��s���Č������Ƃ�����܂���B(�g�Θ^�B���s�{�b���P(���Ƃ���)�S�V�_�����F��)
���Z(�݂�)�̒J��(���ɂ���)�̔O���r�́A�O�\�O���̊ω��̗��ł���ׂɁA�͂₭����L���ł���܂����B�r�ɂ͏����ȋ����˂����Ă��āA�����O�����Ƃ����A���̉��ɂ͐Γ��������A�����炻�̐Γ��Ɍ����ĔO����������ƁA���ʂɎ�̔@�����X�ƖA�����B�������ɏ�����������ɗ����A�ӂߔO���Ƃ����ċ}���ŏ�����ƁA�A������ɉ����Ă�������ɕ��Ƃ����b�ł���܂��B(�������l�k�B���b�K��(����)�S�J����) ���̌��ɂ͍���A�Ɏ���(������)�̔O���r�Ƃ����̂�����܂����B��͂蓯���`�����������̂��Ǝv���܂��B�����Ö�������Ƃ������炢�ǂ������ŁA�畆�a�̐l�Ȃǂ͂��̐�������œh��ƁA�����Ɏ���Ƃ܂ł����Ă���܂����B(�e�{���Z���B���R���S��Ɏ��Ǒ�) �㑍�̔��d��(�₦�͂�)�Ƃ������ł����w�Z�̗���ɁA�O���r�Ƃ����̂����ł����邻���ł��B����͖A�ł͂Ȃ��r�̔�(�قƂ�)�ɗ����ĔO���������Č��Ă���ƁA���̒ꂩ�獚���������𐁂��o���Ƃ����̂́A��͂萴�����킢�Ă���̂ł���܂��B(�`���p���㑍�̊��B��t���N�ÌS���d����) ����Ƃ��傤�ǐ����̗�́A���O�̊�o�R(����ł��)�̋߂��A���Ƃ���Ƃ�����̘e�ɂ���܂����B�����N������Ēꂩ�獻�𐁂��Ă��܂����A�l�����̑��ɋ߂Â��ē얳����ɕ�(�Ȃނ��݂��Ԃ�)�������Ď��łĂA�b���̊Ԃ͗N����邱�Ƃ��~(��)�ނƂ����̂ł��B���̂�����̖��������̐����ƌĂ�ł���܂����B(���q���L�B�{�錧�b�ʑ�(���܂���)�S��o�R��) �����̐����Ƃ����̂́A���ʂ̒r���Ƃ������āA�l�̂悤�Ȋ��o�����������������Ƃ������Ƃł������悤�ł��B�L��(�Ԃ�)���y�L�Ƃ�����N���܂���O�̏����ɂ��A����Șb�������Ă���܂��B���Ԃ̕ʕ{(�ׂ���)�̉���̋߂��ł���܂��傤���A��{��(���ׂ�)���̈�Ƃ�������́A���������D����ς��ɂȂ��ē��͗���Ȃ����A�l����������Ɠ����̖T�ɋ߂��A�ӂ��ɑ傫�Ȑ����o���ĉ��������ƁA�������ē�䂠�܂���N��������Ƃ����Ă���̂ł���܂��B���ꂪ��ɂȂ�ƔO���̘b���葽���Ȃ����̂́A�܂�O�������ɂ͂��������ł���Ǝv���܂��B���̍��ł��c��̐璬���c(���傤�ނ�)�ɂ́A�������҂̉��~�ՂƂ����Ƃ��낪�����āA�����ɂ͔O�����Ƃ��������Ȓr������܂����B�l�����݂̊ɗ����ē얳����ɕ���������ƁA��������ɉ����ĖA�𗧂āA�ԂԂƂ������Ƃ����b���c���Ă��܂��B(�L�F(�ق�����)�R�L�B�啪���b���(����)�S�ѓc���c��) ���ꂩ�炱�̌��̓��̉��ɂ���P���Ƃ������ł́A���q��(�Ђ傤���݂�)�Ɩ��Â��āA���@�����̋����ɉ����āA�(�قƂ�)�藬���Ƃ��������āA�����P���̎��s�v�c�̈�ɎZ(����)���Ă���܂����B���̓��̐_�l�b�Ԑ�(�����݂�)���_�͕P�_�ł����B���̐����d(��)��Ŏ��������߂ɂȂ낤�Ƃ���Ɛ��̐F���ԎK(��������)�F�ł������̂ŁA�܂������(���͂���݂�)�Ƃ������O������܂����B���Ђ͂��̐�̑O�̊�̏�ɂ���A��_�͕̂M����Ɏ����āA������߂悤�Ƃ��鏗�̌�p(�݂�����)�ł���܂����B�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ͂����蔏�q�ɂ�Đ����N���Ƃ�������łȂ��A�ݒ��̈����l�͂��̐������ނƎ���A�܂��畆�a�ɂ��h��Ύ������Ƃ������Ƃ́A���Z�̈Ɏ��ǂ̔O���r�ȂǂƓ����ł���܂����B(������(�Ђ߂���)�l���B�啪�����b����(���ɂ���)�S�P����) �x�߂ɂ�����Ƃ悭�������X�ɂ����������ŁA�y�n�ɂ���Ă��낢��̖������Ă���܂��B����Ƃ���ł͙��(�Ƃ���)�Ƃ����Ă���܂����B�ǂȂ�ƗN���o�������Ƃ������Ƃł���܂��B����Ƃ���ł͏ΐ�(���傤����)�B�l���������o���Ɛ����}�ɗN�����Ƃ����̂ŁA���Ȃ킿�����̐����������Ӗ��ł���܂��B��q��́A�l������Ɗ��ł킭�����A������(�Ԃ��傤����)�Ƃ������̂́A���łƂ��̐��ɉ����ė����Ƃ����Ӗ��ł���܂����B���{�ł����ДO���������Ȃ���A�N���o���ʂƂ����킯�ł��Ȃ������̂ł���܂��B���n�ɍs���Č��Ȃ��Ɗm�Ȃ��Ƃ͒m��܂��A���͎��͂̓y���_���ŁA�����݂̗͂����ɋ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�헤(�Ђ���)�̐�(�����€)�Ƃ������̋߂��ɂ́A��̓m(����)�Ƃ������Ђ������āA�����̐������l�n�̑������A�N���Ԃ邱�Ǝς����̂悤�ł���Ƃ����A����Ŋ������ƌĂсA�܂��o����(�����݂���)�O��(�݂�)�̌��͂������Ƃ������l������܂����B(�L�v�����و�сB��錧�b�߉�(�Ȃ�)�S���͑���) |
|
|
�b�B�b���v(����)�_�Ђ̎���(�ȂȂ���)�̌���(�݂��炵)�Ƃ��������Ȃǂ��A�l�����̖T��ʂ�Ɛ��������܂��N��������A�ׂ��ȍ�����������āA�����������ł���Ƃ����b�ł���܂��B�����߂��ɍs���������ł����ɗN�����炢�ł�����A�얳����ɕ��Ƃ�������A�W�b��Ȃ��Ƃł����������̂Ȃ�A�������ɗN����邱�ƂƎv���܂����A�����ł͒N������Ȃ��Ƃ����Č��悤�Ƃ͂��Ȃ����������ł���܂��B(�����_�Ў����B�R�����b������(�Ђ��������)�S�x�m�����͓�)
�̂̐l�����͈��ݐ��������邱�Ƃ��A�����������Ɖ���ł���܂����B��˂��@���Ēn�ʂ̒�̐������ݏグ�邱�Ƃ́A�i���Ԓm��Ȃ������̂ł���܂��B���ꂾ����킴�킴���r�ɏo��������A�܂����(������)�Ƃ������̂��˂��āA�������琅�������ė����̂ŁA���܂藣�ꂽ�Ƃ���ɂ͉Ƃ����ĂďZ�ނ��Ƃ��o���܂���ł����B���܂Ɏv�������Ȃ��y�n�ɐ�����o���ƁA���ł����ɐ_�l���J��B���ꂩ�炨�������ɂ��̎��͂ɑ������A�܂����l��������ʂ��čs���܂����B�����Ȃ��̂ň�ԍ������̂͗��̐l�ł���܂����A���̒��ɂ͐��������邱�Ƃ����ʂ̐l�������Ȏ҂������āA�y�n�̗l�q�����Ēn���ɐ��̂��邱�Ƃ��@���A��˂��@�邱�Ƃ��������̂��A�ޓ��ł������낤�Ƃ������Ƃł���܂��B�����̎R�������R�ɂ��邢�Ă����s�r(����)�̑m�A���Ƃɋ���l(�����₵�傤�ɂ�)�Ƃ����l�Ȃǂ��A�����̑��X�ɗǂ���������ĂĎc���čs�����Ƃ������ƂŁA�i���Z���Ɋ��ӂ����Ă���܂��B���͂킪���ɔO���̋������O(�Ђ�)�߂����c�̏�l�ł���܂����B��̐��ɂ��̓���炤�l�����́A���ł����������������ނ��тɁA�K�����̏�l�̖���z���o���܂����B����ɂ̈�Ƃ����Â���˂��e�n�ɑ����̂́A�������̐��̂قƂ�ɂ����āA�����ΔO���̍s���������߂ł��낤�Ǝv���܂��B���h�̔O���͑����̐l���W���ė��āA�x�苶����������O���ł���܂����B�O���r�̕s�v�c���y�n�̐l�ɒ��ӂ�����悤�ɂȂ����̂��A����ɂ͂��ꂾ���̌������������̂ł���܂��B���������ꂾ���̌�������ł́A���̂��낢��ȋ��������A���܂�∢�����r�̓`���͏o�ė��Ȃ������낤�Ǝv���܂��B�O���̑m�������������s�r���Ă��邭�����Ȃ��ȑO����A���̌b�݂��Ɋ����āA�����ɐ_�l���Ղ��Ă��̂��͂��h���Ă������Ƃ��A�ނ���O���̐M���̂ւ�Ɉ��������̂����m��܂���B�������Ă��̐_�l���A��ɉW�_�̖��������Ēm��ꂽ�q���̐_�ł��������Ƃ́A�܂����ꂩ�炨�b���Č��悤�Ǝv�������̓`���ɂ���āA���������ɂ킩���ė���̂ł���܂��B�@ |
|
| ����t�u�̗R�� | |
|
�`���̏�ł́A����l�����Ȃ��O�����{���������邫����āA�����Ƃ�������̐�������A���X�̏Z���̂��߂Ɍ����Ă�������t�l�Ƃ����l������܂����B���̓y�n�ł͂��̌��t�l���A����(������)�̍O�@��t�̂��Ƃ��Ǝv���Ă��܂������A���j�̍O�@��t�͎O�\�O�̍ɁA�x�߂ŕ��@�̏C�Ƃ����ċA���ė��Ă���A�O�\�N�̊Ԃɍ���R���J���A�ނ����������̏������c���A�܂����s�̐l�̂��߂ɑ�Ȃ��낢��̈�(������)�����Ă��āA���������܂ŗ��s�����邱�Ƃ̏o���Ȃ������l�ł���܂��B�����������炢��������A�S���Ȃ����ƌ����Ăق�Ƃ��͂��܂ł����X�������ďC�Ƃ��Ă�����̂ł��낤�Ǝv���Ă����l�������͂Ȃ������̂ŁA����ȓ`�����O���s��ꂽ�̂ł�����܂��傤�B����̑�t���ł́A���N�l����\����̌��(�������)�ւ��ɁA��t���̌䑜�̈߂�ւ��Č���ƁA�������̈�N�̊ԂɈ߂̐�����A�D�ɉ���Ă��܂����B���ꂪ���ł��l�ɒm��ꂸ��������ƁA���̑�t�������̑������邢�Ă�����؋����ȂǂƂ����l������܂����B
�Ƃɂ����ɓ`���̍O�@��t�́A�ǂ�ȓc�ɂ̑��ɂł��悭�o�����܂����B���̋L�O�Ƃ��Ďc���Ă���s�v�c�b�́A�ǂ��������F���Ă��܂����A���ł����̑����͍̂��܂Ő��̂Ȃ������y�n�ɁA�������܂��L�Ȃ鐴����^���čs�����Ƃ����b�ł���܂����B�����{�̕��͑��͍O�@��A�܂��͍O�@�r�ȂǂƂ����A��B�ł͂������t�l���ƌĂ�ł���܂��B���Ƃ͑�t�l�Ƃ��肢���Ă����̂��A��ɑ�t�Ȃ�O�@��t�ł��낤�ƁA�v���҂������Ȃ����̂ł���܂��B����܂蓯���悤�Șb����������ɂ����āA���������ׂČ��Ă��܂�܂���A���͂�����є�тɍ��m���Ă���b�����������Ēu���܂��B�F������N���ɕ����Č䗗�Ȃ����B�����Ƌ߂��̑��ɂ������������`���������āA����ɂ͂��ł������o�Ă��܂��B���̏����ق�Ƃ��͊ւ̉W�l(������)�ł������̂ł���܂��B ���ʂ͈��ݐ��̏\���ɓ����Ȃ��悤�ȓy�n�ɁA���������̘b���������`����Ă��܂��B�l�����܂ł��Y����Ȃ���낱�т̐S���A�N�����ɂ͂����Ȃ���������ł��낤�Ǝv���܂��B�ΐ쌧�̔\��(�̂�)�S�Ȃǂ��A���X�ɍO�@�����������āA���������t�̗����Ȃ������O�̍��́A���̕s���R������Ă���܂��B�Ⴆ�Έ���(�����)���b��(��)�̌�(����)�̍O�@�̒r�́A���̖k�̒[�ɂ��鋤����˂ł���܂����A�̂����ɂ͂܂���̐���Ȃ��������ɁA����V�k���Ă�����������狂(��)��ŗ����Ƃ���ցA���傤�Ǒ�t�l���������āA�A(�̂�)�����������炻�̐������܂���Ƃ����܂����B��Ȑ���ɂ������Ȃ�������悭�����グ�܂��ƁA����Ȃɐ����s���R�Ȃ���˂������悤�Ƃ����āA���̏�(��)��n�ʂɓ˂����Ă�ƁA��(������)���������炢����������o���āA���̒r�ɂȂ����Ƃ����Ă���܂��B���z(�Ƃ肱��)���̊�����(���܂��݂�)�Ƃ��������Ȃǂ��A���r�Ƃ������������̖��ɂȂ�قǁA���ł͗L���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����A���Ƃ͂�͂萅�������Ȃ��āA�킴�킴���(�ĂƂ�)��܂ŋ��݂ɍs���Ă���܂����B�y�n�̋��Ƃ̎��Y���q��Ƃ����l�̐�c�̔k���܂��A�e�ɂ��̐����t�ɐi�߂�����ɁA�Ƃ̑O�ɂ��̒r�������炦�ĉ����ꂽ�̂ł���܂��B���ꂾ���獡�ł��r�݂̊ɂ͑�t�������āA���̉������ӂ��Ă���Ƃ������Ƃł���܂��B�ԍ�(�͂Ȃ���)�Ƃ������ɂ����Ƃ͗ǂ������Ȃ��āA����Ƃ̘V�����������狂��ŗ����̂��A��t�l�Ɉ��܂��܂����B��������Ƃ܂���������āA�������@���Č���Ƃ����čs����܂����B���ꂪ�����̉ԍ�̍O�@�r�ł���܂��B�Ƃ��낪���̋߂��̑ʼnz(��������)�Ƃ������ł́A���ł���˂��Ȃ��Ė����͂����݂ɏo�����܂��B����͂܂��̂��̑��̘V�k���A��t�l�������ق����Ƃ���ꂽ���ɁA������������߂����̔����Ɛ\���܂��B��(�݂Ȃ�)�Ƃ������ɂ��ȑO�͓�܂ōO�@��t�̐����������āA���ł͂��̈�͎���̒�̉��ɂȂ��Ă��܂��܂������A�������t����̂����ŁA�˂��o������ł���Ƃ����Ă���܂����B�Ƃ��낪���ׂ̗�̋g���Ƃ������ɂ́A�����������\�Ȉ�˂��Ȃ�����łȂ��A���ł��g���̐���(��������)�Ƃ����āA���̐l���҈�(�����Ђ�)���͂��ƕa�C�ɂȂ�Ƃ����`���āA�~���Ԃ��r���o���Ă���̂́A��͂肠��W���҈�����Ă��āA��������������ς�����Ƃ���ꂽ�O�@��t�ɁA���̐���ł��|�������炾�Ƃ����Ă���܂��B�ǂ��W�A�����W�̘b�́A�܂�ʼnԍ��A�܂��͐�萝�ȂǂƓ����悤�ł͂���܂��B(�ȏ�݂Ȕ\���S��) |
|
|
���ꂩ��\�o(�̂�)�̕��ł͉H��(�͂���)�Ƃ����C�݂̑��ł́A�̍O�@��t�����̂ւ��ʂ��Đ������߂�ꂽ���ɁA��Ȃ����ɂ���ŏグ�Ȃ��������߁A��t�͕��𗧂ĂĈꑺ�̐������܂�����ł����܂��ɂȂ����Ƃ����āA���ł��ǂ����@���Č��Ă�������C(���Ȃ�)�������Ďg�����Ƃ��o�����A�d���Ȃ��ɐH�ו��ɂ͐�̐�������ŗ���Ƃ����b�ł���܂����B(�\�o�����Վu�B�ΐ쌧�����S�������H��)
�܂��H��(�͂���)�S�̖��g(�����悵)�Ƃ������ł��A����ɂ���ő�t�ɗ^���Ȃ��������߂ɁA���ɗǂ������邱�Ƃ��o���ʂƂ����Ă��܂����A���̋߂��̎u���Y���(�������炤����)�Ƃ��������ł͐e�ɂ����̂ŁA��t�͂��̂���ɂ��̊���w�����ƁA�������̊�̒����琅���N�����Ƃ����Ă��܂��B�����Ė��Y�̎u��N�z(�������炵)�܂��\�o�k(�̂Ƃ�����)�����̐��ŎN(����)���āA���܂ł����̂߂��݂������Ă���Ƃ������Ƃł���܂��B(���y�����O�ҁB�ΐ쌧�H��S�u���Y�����) �ዷ(�킩��)�̊֒J�쌴(�����₪���)�Ƃ������́A�䎡(�Ђ�)��̐�������Ȃ���A�ӂ���͐����Ȃ����đ�J�̎��ɂ���A��ς��ɂȂ��ēn�邱�Ƃ̏o���Ȃ���������ł���܂����B������̂��̑��̘V������l�A��ɏo�Đ��Ă��邨��ɁA�m��C���s�r���ė��Ă̂ǂ����킢���̂ŁA���ł��Ⴂ�����Ƃ��̘V���ɂ���ꂽ�Ƃ��낪�A���̑��ɂ͈��ݐ�������܂���ƁA�����Ȃ��f��܂����B�������ɗ������ď������Ƃ����Ă����̐������Ƃ��Ƃ��n�̉��𗬂�čs�����ƂɂȂ��āA���ł͂Ȃ�̖��ɂ������ʐ�ɂȂ��Ă��܂����̂������ł��B(�ዷ�S���u�B���䌧�b���(������)�S�b��(����)�m(�m)�n��(����)���։�) �ߍ]�̌ΐ��̖k�ɂ��鍡�s(���܂���)�Ƃ������ł��A���ɂ͋����̈�˂�����邾���ŁA���ꂪ�܂�������ėǂ����ł���܂����B������O�@��t������������܂���āA���傤�ǂ��̑��ɗ��Ĉ�l�̎Ⴂ���ɏo�����A�������݂����Ƃ����܂����B����Ɛe�ɉ����Ƃ�����݂ɂ����āA�v�����ԑ�t��҂����܂����̂ŁA��t�����̂킯���ċC�̓łɎv���A�����Ă�����ł�������̊�̊Ԃ�˂����ƁA���Ȃ킿�������N���o���̂����̈�˂ł���Ƃ����܂��B(���y������ҁB���ꌧ�b�ɍ�(����)�S�Љ������s) �ɐ��̐m�c(�ɂ�)���ł͈�ː���(���ǂ���)�̓��Ƃ����āA��͑����Đ���ɂ����g��ꂸ�A���ׂ̗�̈�˂͂܂��Ƃɂ悢���ł���܂����B��͂�V�����鏗����������Ă���Ƃ���ցA�O�@��t�����Đ������߂����ɁA���̐��͈�������Ƃ����āA�킴�킴�����ւ��Ƃ���܂ōs���ċ���ŗ��Ă���܂����̂ŁA��t������͍��邾�낤�Ƃ����āA�������̂����e�̒n�ʂɁ��m�u���v�ł���̏c�_�����ɓ˂������Ă���n(��)���ƁA�������炱�̂悤�Ȑ����N���o���Ƃ����̂ł���܂��B(�ɐ��������B�O�d���b���C(����)�S�b����(����)���m�c) �I�B�͍O�@��t�̉i������ꂽ�������ɁA����̖��������͂��̑�t�̂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B����(�Ђ���)�S����ł��O�@��͓암(�݂Ȃ�)�̓��g�c(�Ђ����悵��)�A��암�̌F���A������(�Ђ��������͂�)�̌��J(�͂炽��)�ɂ�����A�������̒r�c�̑�t���̋߂��ɂ�����܂����B�D��(�ӂȂ�)�̍�{�̍O�@��́A���ł��H�ʂ�l���Ԃ��グ���ΑK(��������)�𓊂��čs���܂��B����(��������)�̐����J(�݂��݂̂���)�ɂ���̂́A�O�@��t���w��Ő�(��)�����Ƃ����Č��\�Ȑ��ł���܂��B�암�̋��F��X���̎R�H�ɁA�������O�@��Ȃǂ́A�e�ȘV�k������ŗ��������A�痢�̕l�܂ŋ��݂ɂ��������̂��Ƃ����b���āA����͂����ւ�Ȃ��Ƃ��Ƃ����āA��t������(���Ⴍ���傤)�̂����ŁA�����ĉ���������˂��Ƃ����Ă���܂��B(�ȏ�݂ȓ�I�y������) �ɓs(����)�S�̖쑺�Ƃ������Ȃǂ́A�O�@��t����œ˂��Ă���O(��)���o�����Ɠ`����āA���ڂقǂ̐�\�܊Ԃ�����݂̏ォ�痎���āA�L�����̓c�n�������Ă��܂��B�b�͎c���Ă��邩�ǂ����m��܂��ʂ��A��������ł��W��Ƃ����̂ł���܂��B��(��)���M(���)�Ƃ������ɂ���t����Ő������Ƃ���������(��������)�̈�˂������āA���̏�𓊂��Ēu���ꂽ��A���ꂪ���������M�ɂȂ����Ƃ����A���̖��܂ł����ꂩ��o�Ă���̂ł���܂��B(�I�ɑ����y�L�B�a�̎R���ɓs�S���쑺���M) ����Șb�͊��ł�����܂�����A��������������ɂ��Ēu���܂��傤�B�l���Ȃǂ͑�t�̔��\���ӏ������邭�炢�ł�����A���̓˂���������ɍ��������āA���������̂��Ƃ�����̐������ł��A������Ȃ��قǂ�������ɂ���A�����k����ƑP���k����Ƃ��A��������t�̐���ɂ����^�������ɂ���āA�Е��͂��܂ł���˂̐����Ԃ��Ĉ��܂ꂸ�A���̕Е��͂���ȗǂ������t�l�ɖ�����Ƃ����`�����A�����̘b�̂悤�ɂȂ��đ����̑��̎q���Ɍ��`�����Ă���܂��B |
|
|
��̐����̘b�̒��ł��A��ɗL���Ȃ��̂́A���g(����)�ł͉�����R(�����Ԃ݂��)�̖���(��Ȃ��݂�)�A���̑��ɂ͂��Ƃ͐����Ȃ������̂��A��t�����̏�Ŋ��˂��A�������琴��������o��悤�ɂȂ�܂����B��͖��̖ŁA�i�����̐�̖T�ɐX�Ɩ��Ă��������ł���܂��B(���B��G�b�B�������b����(�݂傤����)�S������R��)
�ɗ\�ł͍���(������)�̐��ю�(�������)�̏�̕�(�ӂ�)�B���̑��ɂ��̂͐����Ȃ������̂ł����A��t�����ď��n�ɗ��ĂĂ���A���ɂȂ�܂ł̗��h�ȐO���o�����̂������ł��B���������̏�͍��ł͂����Ȃ��̂ŁA�|�ł����������ł��������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B(�ɗ\���̘^�B���Q������S�v�đ�����) �ǂ����ė��̑m���s����X�ɁA��𗧂ĂĂ��邭�̂��Ƃ������Ƃ��A���͂��낢��ɍl���Č��܂������A�r���ƊW�̂Ȃ����Ƃ͂͂Ԃ��Ēu���܂��B��B�̓�̕��ł͐����l(���傤�������傤�ɂ�)�A�z��̎��s�v�c�̘b�ł͐e�a(������)��l�A�b�B�̌��(�݂���)�̎Ђ̋߂��ɂ͓��@��l�Ȃǂ��A�|�̏�𗧂ĂĂ��ꂪ�����������ƂɂȂ��Ă��܂����A�����N���o�����b�ɂ́A�ǂ�����t�l�������悤�ł���܂��B�����̕��߂ł͓���(�����)�S�̎O��Ƃ������ɁA�O�@��t������ꂽ���ɂ́A�C���Ă̂₳�������̏����A�@��D���Ă��������ł���܂��B�����ق����Ƃ�����̂ŁA�@���牺��ĉ����Ƃ���܂ŋ��݂ɍs���܂����B����͒�߂ĕs���R�Ȃ��Ƃł��낤�ƁA����������������ďo��悤�ɂ��ĉ��������Ƃ����������A���ł�����ēy�n�̖��O�ɂ܂łȂ��Ă���܂��B(�V�сb����(�ނ���)���y�L�e�B��ʌ����ԌS����V�䎚�O��) �����@��D���Ă����Ƃ����b���A�������ʂ̂킯�������āA�̂������Ă������Ƃ̂悤�ł���܂��B��t�̈�˂̈�Ԗk�̕��ɂ���̂́A���킩���Ă�����̂ł͎R�`���̋g��Ƃ������ŁA�����܂œ`���̍O�@��t�͍s���Ă�����̂ł���܂��B���̐̑�t�����a�R(��ǂ̂���)���J���ɗ���ꂽ���ɁA�A(�̂�)�������Ă��̑��̂���S���̉Ƃɂ͂����āA�������܂��Ă���Ɛ\����܂��ƁA���[���Ђǂ����ŁA�Ă̖�(��)���`���o���܂����B������t�͂��܂��Ĉ���ōs���ꂽ���A���Ƃŏ��[�̊炪�n�ɂȂ��Ă��܂����B���ꂩ��܂���O�����߂����Ƃ���̂���Ƃł͏��[�͋@��D���Ă��܂����B�����ł������ق����Ƃ����܂��ƁA����Ȋ�������ɋ@���牺��āA�����Ƃ���܂ŋ��݂ɍs���Ă���܂����B��t�͊��ł��̑��ɂ͗ǂ������Ȃ��ƌ�����B��@���Ă�낤�Ƃ����āA��̏�������Ēn�ʂɌ����ق�܂��ƁA����Ƃ��Đ������N���܂����B���ꂪ���������t�̈�˂��Ƃ����̂ł���܂��B(���y������ҁB�R�`�������R�S��y�����g��) �����ł܂��ŏ��ɁA����ꂪ�l���Č��Ȃ���Ȃ�ʂ̂́A���ꂪ�ق�Ƃ��ɍO�@��t�̑m��C�ł������낤���Ƃ������Ƃł���܂��B�L�����{���������̒ʂ�悭�������A�ǂ��ł������悤�ȕs�v�c���c���čs�����Ƃ́A�ƂĂ��l�Ԃ킴�ł͏o���ʘb�ł���܂����A�����_�l���Ƃ��킸�ɁA�Ȃ�ׂ��N���̂̈̂��l�̂������Ƃ̂悤�ɁA�����͍l���Č��悤�Ƃ����̂ł���܂��B����ɂ͍O�@��t���ł����̐l���ƁA�z�����Ղ����������ł͂Ȃ��ł��傤���B����̕��ɂ���Ō@��o�����Ƃ����`���������͂���܂��B��B�̉��ɂ�����(�����)�̉���Ȃǂ��A�̍O�@�l�����Ă��閯�ƂɈꔑ�����Ƃ��ɁA��������Ȃ��̂ō����Ă���ƁA��������������̉Ƃ̓�����ɂ����āA�o���ĉ����ꂽ�̂����̓��ł���Ƃ����`���Ă���܂��B���ꂾ���炱�̉���͋r�C(������)�ɂ悭�����̂��Ɠy�n�̐l�͂����A�܂����̓��̕Иe�ɁA���ł��̏����ȑ�t�l�̑��𗧂ĂāA�q��ł���̂��Ƃ������Ƃł���܂��B(���y������ҁB�Q�n���b����(�Ƃ�)�S��ꑺ��ꓒ��) �Ƃ��낪�ے�(������)�̗L�n(�����)�̓��̎R�ł́A�L�b�G�g����͂��������ĉ�����o�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă���܂��B���}(��������)���L�n�ɗV�тɗ������ɁA�����@(������傤����)�Ƃ��������̖�̑O��ʂ��Ă��傤�����ɏ�������Ēn�ʂ̏��@���A��������������N���悢�B��������Η��Ă͂���̂ɂƂ����܂��ƁA�����܂����̑����Ƃ���A���o���Ƃ����܂��B����ł��̉���̖�����̓��A�ꖼ�肢�̓��Ƃ��Ă�ł���܂������A��ɂ͂��̖�����c���āA����͏o�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B(�ۗz�S�k��) ���}�l�͎v�����Ƃ��Ȃ�ł���(����)�����l������A�����������Ƃ����������m��ʂƁA�l�����҂͂����Ԃ�܂����B���ЂƂ��O�@��t�łȂ��Ă͂Ȃ�ʂƂ����킯�ł��Ȃ������̂ł���܂��B����(�����)�̐��H(������)�Ƃ������ɂ́A���邨���̉����Y��(���ꂢ)�Ȑ����������āA�������t�̌@������˂��ƁA�y�n�̐l�����͂����Ă���܂������A���ꂪ�ŏ�����̂����`���łȂ��������Ƃ͖����ɂȂ�܂����B�l�S�N����O�ɁA����w�҂����̎��ɗ��܂�ď��������͂ɂ́A��́b���{����(��܂Ƃ�����݂̂���)���A�����ɗ��Ď����Ȃ���A���������o���Ȃ��ꂽ�������Ȃ��̂ŁA�|���m�u�|�{���̂���v�n(��͂�)�������Ċ���������ɂȂ�Ɛ����N�����B���ꂪ���̈�˂ł���Ǝ����Ă���܂��B�ߍ��͂��������o�Ȃ��Ȃ�܂������A�ȑO�͑��̎҂����ɑ��h���Ă�����˂ŁA�q(����)��̂�����̂�����������������Ƃ���ƁA��(�ɂ킩)�ɐ��̐F�������Ă��܂��Ƃ܂ŐM���Ă��������ł���܂��B(���B�{�u�B���m���m���S���Y�����H) |
|
|
����Ɠ����悤�ȓ`���́A���̒n���ɐ���������܂��āA�����W�����l�̖�������Ă������ł���܂��B�֓��Ȃǂň�ԑ��������̂́A����(�͂��܂�)���Y�b�`��(�悵����)�ł���܂��B�R(������)�̔�(�Ȃ���)�ɐ��������Ȃ��̂ŁA�_�ɔO���A�|�������Ċ�ɓ˂��A�܂����y�̏�ɂ����ƁA���ꂩ�����Ďm�����Ƃ��Ƃ������(��)�₵���B����Ă����_���Ƃ��Ċ��ӂ̂��ߐ_�̌�Ђ����Ăĉi���J(�܂�)�����Ƃ����āA���̐_�������͔����l�ł���܂��B�������������̗N���ꍇ�ɂ́A���͓y����������Ċ₪����ė��܂��̂ŁA�ꂻ�����ʂ̐l�Ԃ̗͂ł́A���o�����Ƃ��o���Ȃ������悤�ɑz������҂������Ȃ������ƂȂ̂��Ǝv���܂��B���Ȃ킿���̐ΐ���(���킵�݂�)�����̓`���Ȃǂ��A��ɂȂ�قǂ���ɐ��������Ȃ����킯�ł���܂����A���ꂪ���Ђ������Ȃ����̒��⓹�̖T�A�܂��͐l�Ƃ̊Ԃɝp(�͂�)�܂��Ă��܂��ƁA�b�͂ǂ����Ă�����������s�r�̗��m�Ƃ������ցA�����čs����₷�������悤�ł���܂��B
���ꂩ��܂����̂��낢��̓V�R�̕s�v�c���A���������������O�@��t�̎d���̂悤�ɁA��������ӂ�������ɂȂ�܂����B���̒��ł��ł��l�̂悭�m���Ă����ɁA�Έ�(��������)�Ƃ����ėt�͑S�������̔@���A���̍��͍d���ĐH�ׂ邱�Ƃ̏o���Ȃ��A���A�܂��͐H�킸��(�Ȃ�)�Ƃ����āA���������Ȃ����̎��Ȃǂł���܂��B����������̐̈�l�̗��m��������ʂ��āA�����ʂ��Ə��]�����̂��A���ɂ��݂̎�l���R�����āA����͍d���Ă��߂ł��Ƃ��A�܂��͏a���ďグ���܂���Ƃ��������B�������Ƃ����ė��m�͍s���Ă��܂������A��ŕ����Ƃ��ꂪ��t�l�ł������B���̈��܂����͂��ꂩ��Ȍ�d���܂��a���Ȃ��Ă��܂��āA�H�ׂ邱�Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����ȂǂƂ����̂ł���܂��B�`���̍O�@��t�͑S�̂ɏ����{��߂��A�܂���щ߂����悤�ł���܂��B�������ĕ��@�̋����Ƃ͊W�Ȃ��A���������̏�̐����ɂ��āA�P�����������������ɍׂ������b���Ă��Ă��܂��B�Đ����������ĕS���̓�V���~���܂ł͂悢���A�{���Ĉ�˂̐���ԎK(��������)�ɂ��čs������A����ʕ���H�ׂ��ʂ悤�ɂ����Ƃ����Ȃǂ́A���������l�����ɂ͎�����ʎd�Ƃł���܂��B�Ƃ��낪���{�̌Õ��ȍl�����ł́A�l�Ԃ̍K�s�K�͐_�l�ɑ�������̍s���́A���������������Ȃ����ɂ���Ē�܂�悤�Ɏv���Ă��܂����B���̍l�������A���ł��V�������ɂ��āA���肨��͌���ė���̂ł���܂��B�����玄�Ȃǂ́A������O�@��t�̘b�ɂ����̂́A�����̊ԈႢ�ł͂Ȃ��낤���Ǝv���̂ł���܂��B ���̂��Ƃ͍��ɊF�������ōl���Č���Ƃ��āA���������������`���̗�������Ēu���܂��傤�B�Έ��A�H�킸���Ƃ��傤�ǔ��̘b�ɁA�όI�Ă��I�Ƃ����̂����X�̓y�n�ɂ���܂��B��������ł͍O�@��t�̗͂ŁA��U�ς���Ă����肵���I�̎����A�Ăщ�𐁂��ĖɂȂ����Ƃ����āA����Ɏ����Ȃ��Ă���̂ł���܂��B�z��̏�쌴(�����̂͂�)�Ȃǂɂ���Ă��I�́A�e�a��l�̈�b�ɂȂ��Ă��܂����A��͂肠��M�S�̘V���������グ���Ă��I���A���݂ɓy�ɖ��߂āA�������̋�������̐��Ŕɏ�������Ȃ�A���̏Ă��I������o���ł��낤�Ƃ����čs���ꂽ�B��������Ɖʂ��Ă��̌��t�̒ʂ�A���ꂪ�������đ傫�ȌI�тƂȂ�A�������O�x�I�Ƃ����Ĉ�N�ɎO�x���A�������Ԃ悤�ɂȂ����Ƃ����̂ł���܂��B�ǂ����Ă��̂悤�Șb���o�������Ƃ����ƁA���̈��̎ČI�����̂��̂��͂����ƐF�������āA�ɏł����悤�Ɍ����邩��ł���܂����A���s�̓�̕��̂���ݏ��ł́A��͂蓯���b�������āA����͓V���V�c�̌䎖�ւ��Ƃ����̂ł���܂��B�V���V�c���ꎞ�b�F��(�悵��)�̎R�ɂ�����ɂȂ鎞�A���̑��ł��x�݂Ȃ����ƁA�ς��I�����サ�����̂��������B������x�A���ė���悤�ł���A���̎ς��I����𐁂��Ƃ����āA���A���ɂȂ���������ɂȂ��ĉh�����Ƃ������ƂŁA���̎킪�i���`����Ă���܂��B��(���邢)�͂܂��t��(������)�̖��_�����߂đ�a�ɂ��ڂ�ɂȂ����Ƃ��ɁA���t���̐_�傪�όI�̎���d(��)�����Ƃ������҂�����܂��B���������悤�ɘb�͂��ЂƂ��O�@��t�łȂ���Ȃ�ʂƂ����킯�ł��Ȃ������̂ł���܂��B ���ꂩ��܂��Аg�̋��A�Жڂ̕�(�ӂ�)�ȂǂƂ����b������܂��B�Ă��ĐH�ׂ悤�Ƃ��Ă���Ƃ���֑�t������ė��āA��������ɂ���Ƃ����āA��ď��r�֕������B���ꂩ��Ȍセ�̒r�ɂ��镩�́A������������Ă��ł����悤�ɂȂ��Ă���B�܂��͕Жڂ��Ȃ��A�������͕Б����������悤�ɔ����Ȃ��Ă���Ƃ����̂ł��B�����w�̕����猩�āA����ȋ��ނ�������̂Ƃ��v���܂��A�Ƃɂ����ɕЖڂ̋����Z�ނƂ����r�͔��ɑ����A���ꂪ���Ƃ��Ƃ��_�̎ЁA�܂��͌Â��䓰�̖T�ɂ���r�ł���܂��B�r�Ƒ�t�Ƃ́A�܂������������ʂɂ����Ă��W������̂ł���܂��B |
|
|
���͂܂��ߊ|(���ʂ�)����A�H��(�͂����)�̏��Ƃ����`��������܂��B��������̕�(�قƂ�)�ŁA�������`�̊���̂���ꍇ�ɁA�s�v�c�Ȑ_�̈߂��|�����Ă������Ƃ�����Ƃ����̂ŁA���ʂɂ͋C������P�l�Ȃǂ̘b�ɂȂ��Ă���̂ł����A���ꂪ�܂����̊Ԃɂ��A�O�@��t�Ɠ������Ă���Ƃ��������̂ł��B���O�̊C�݂̊Ԍ�(�܂���)�Ƃ����p�̒[�ɂ́A�D�Œʂ�l�̂悭�m���Ă���֊|(����)����Ƃ�����₪����܂��B����Ȃǂ���P(���������Ђ�)�Ƃ����������て�m�u�\�v�́u���v�ɑウ�āu���v�n(���傤�낤)�̒������A����������ŗ��Ĉ����|�������Ƃ��������`��������̂ł����A�y�n�̐l�����́A�܂�����ȕ��ɂ������Ă���B�̑�t���Ԍ��̕����֗��āA�@�߂��������������畨�����̊�(����)��݂��Ă���ʂ��Ƃ���ꂽ�B�Ƃ͂���܂���Ƒ��̎҂������Ȃ��f�����̂ŁA��t���������Ȃ��ɂ��̊�̏�ɁA�ʂꂽ�߂��|���Ă������Ȃ��ꂽ�Ƃ����̂ł���܂��B���������������l�̕s�e�ȏ��́A��Ŕ����������b�ł������낤�Ǝv���܂��B(�W�v(������)�S���B���R���W�v�S�֊|�����J)
���[(����)�̐Ƃ������ɂ́A�O�@��t�̈���˂Ƃ����̂�����܂��B��˂̒�Ɉ��̂悤�ȗt�������A�����A�X�Ɩ��Ă��܂��B�̑�t�����̑��̂���V�k�̉Ƃɗ��āA��������Ȃ����Ə��]�����̂��A�V�k�����ɂ��݂����Ă��̈��͐Έ��ł��ƉR���������B��������ƍ����Ƃ̈����F�̂悤�Ɍ����Ȃ�A�H�ׂ邱�Ƃ��o���ʂ���˂̊O�Ɋ��Ă�ƁA�������琅���N���o���Ă��̈�˂ɂȂ����Ƃ����̂́A�����Ɠ�̘b�̍����ŁA���ł͔��������A��˂͓y�n��Ԃ̐����ł���܂����B�`���͂��������ӂ��ɔ�����������A�܂��p�������Ĉ�ɂȂ����肷����̂ł���܂��B(���[�u�B��t�����[�S���l����) ���(������)�̑剖(��������)�Ƃ������ł͎R�̒��̐������ŁA�߂����܂ł͂�������Ŏςĉ����Ă��܂����B�����������R�ɉ��̈䂪�o��Ƃ����̂́A�y�n�̐l�����ɂ��s�v�c�Ȃ��Ƃł����B����ł�͂�O�@��t������ė��āA�M���p�������Ē����Ă�ʼn����ꂽ�Ƃ����Ă��܂����A����ɂ͂܂��ǂ��������������ĊW�������̂��A���ł͂����Y��Ă��܂����҂������悤�ł���܂��B(�����b�B�������b�떃(���)�S�剖��) �Ƃ��낪���[�̕��ł͐_�](���Ȃ܂�)�̔���(�͂��Ȃ�)�Ƃ��������ɁA��̗��ꂩ�牖�̈�̗N���Ƃ��낪�����āA���ł����̗R����`���Ă��܂��B���̐́b����(���Ȃ܂�)���̉Ɛb�b���Y�g�V��(�������炫���̂��傤)�̌�Ɓb���a��(�݂킶��)�A�{�����D�ݐS�|���̂₳�����w�l�ł���܂����B�哯�O�N�̏\�ꌎ��\�l���ɁA��l�̗��m�����ĐH�����߂��̂ŁA���傤�ǂ����炦�Ă�����������(����������)��^����ƁA���̊��ɂ͉��C���Ȃ�����A���m�͕s�R�Ɏv���܂����B�������n�R�ʼn������Ƃ��o���ʂƂ����̂��āA����͂��C�̓ł��Ɛ�݂̊ɉ���āA��Ɏ������˂������Ďb(����)���F�O���A�₪�Ă�����ƁA���̌����琅���(�قƂ�)���āA���̊�̂Ƃ���܂Ŕ�я��܂����B��(��)�߂Č���Ƃ��ꂪ�^��(�܂���)�ł���A���̑m�͍O�@��t�ł������ƁA�Â��L�^�ɂ������Ă��邻���ł��B(���[�u�B��t�����[�S�L�[���_�]) ������L�^�ɂ͏����Ă����Ă��A���ꂪ���j�łȂ����Ƃ͒N�ɂł��킩��܂��B�O�@�̗��s���������ȑ哯�O�N���ɂ́A�܂����ۉƂ����Y�����Ȃ������̂ł���܂��B��������F����ɂ��b���������Ƃ́A�\�ꌎ��\�l���̑O�̔ӂ́A���ł��֓��n���̑��X�ł���t�u�Ƃ����āA�����̊����ςĂ��Ղ����������Ƃ������Ƃł���܂��B�V��@�̂����Ȃǂł́A���̓������傤�ǓV��b�q��(������)��t�̊����ɓ��邽�߂ɁA���̂���ő�t�u���c��ł��܂����A���̑����̓c�ɂł́A������O�@��t���Ǝv���Ă���̂ł���܂��B�q�ґ�t�͂��̖���q���m�u�M�̂ւ�{�Łv�n(����)�Ƃ����āA�������O�S�l�\�N�قǑO�ɖS���Ȃ����x�߂̍��m�ŁA�����Ă��邤���ɂ͈�x�����{�ւ͗������Ƃ̂Ȃ������l�ł���܂��B�܂��O�@��t�̕��͂��̏\�ꌎ��\�O���̔ӂƁA�������W���Ȃ������l�ł���܂����A�ǂ��̑��ł����̈��Ɍ����āA��t�l���K���Ƃ���Ƃ������Ă��邩���ƐM���āA���̂��Ղ�����Ă����̂ł���܂��B ����ł͏\�ꌎ���̍��́A�������Ȃ芦���Ȃ�܂��B�M�B��z��ł͂��낻��Ⴊ�~��܂����A���̓�\�O���̔ӂ͂��Ƃ������ł��K���~����̂��Ƃ����āA������ł�ډB���̐�Ƃ����܂��B�������Ă���ɂ���͂肨�k����̘b�����Ă���܂����B�M�B�Ȃǂ̕����ł́A�ł�ڂƂ͑��̎w�Ȃ��̂��Ƃł���܂��B�̐M�S�[���ĕn�R�ȘV�����A��������t�l�ɍ����グ������S����A�l�̔��ɂ͂����Ĉ���卪�𓐂�ŗ����B���̔k���ł�ڂł����āA���Ղ��c���ΒN�ɂł�������̂ŁA����܂肩�킢�������Ƃ����āA��t������~�点�ĉB���ĉ��������B���̐Ⴊ���ł��~��̂��Ƃ����҂�����܂�(�����(�݂Ȃ݂�����)�S�����̑�)�B���������̘b�Ȃǂ���ɂȂ��āA��������Ԉ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���_������܂��B�M�B�ł͂��̔ӂɐH���������邨��(�͂�)�́A��(����)�̌s�������ĕK����{�͒����A��{�͒Z����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B������ł�ډB���̋L�O�ł����āA���̔k����͂ł�ڂŊ�(��)����(�����)�ł���������Ƃ����l�����邪�A���ɂ���Ă͑�t�l���g���������ŁA����ł��̔ӑ��X���܂���Ă��邩���̂ɁA�Ⴊ�~��Ƃ��̑��Ղ��B��Ă��傤�ǂ悢�Ɗ���Ƃ����A�u�ł����ł�ڂ̐ՉB���v�Ƃ�����(���Ƃ킴)�����邻���ł�(���J����W)�B�z��̕��ł��Â������t�u�̏������ɂ́A�I�̎}�ł����炦�������Z���̂��������ċ����܂����B���̉����҂����̔������̌��ɓ��Ă�ƁA�悭������ȂǂƂ������܂����B���ꂩ�炱�̔ӐႪ�~��ƐՉB���̐�Ƃ����āA��t�������痢�ւ��邩���䑫�̐Ղ��A�l�Ɍ����ʂ悤�ɉB���̂��Ƃ����`���Ă���܂����B(�z�㕗�����) |
|
|
��������Ƃ���ɑ�t���A�O�@��t�ł��q�ґ�t�ł��Ȃ��������Ƃ��킩���ė��܂��B���ł��R�̐_�l�͕Б��_�ł���悤�ɁA�v���Ă����l�͓��{�ɂ͑����̂ł���܂��B����ő傫�ȑ�����Е����������āA�R�̐_�l�ɏグ�镗�K�Ȃǂ�����܂����B�~�̂ܒ��ɎR���痢�ցA���肨��͉���ė����邱�Ƃ�����Ƃ����āA��͋p(����)���Ă��̑��Ղ����������̂ł���܂����B��ɕ������͂����Ă��炱���M����҂������Ȃ�A�����q�������̂����낵����_�ɂȂ������ɁA����ɂ����Ԃ�Ă������̒��ɎZ������悤�ɂȂ�܂������A���Ƃ̓M���V����X�J���W�i�r���́A�Â������_�X�������悤�ɁA�����̎R�̐_������ŁA�܂����ł������̂ł���܂��B����Ƃ���Ƃ͊W�͂Ȃ������m��܂��A�Ƃɂ����\�ꌎ��\�O���̔ӂɍ����̑��X������A�����̊��������čՂ��Ă����̂́A�����̐l�Ԃ̈̂��l�ł͂Ȃ������̂ł���܂��B����������̌��̌��t�ŁA�����������l�ƌĂ�ł����̂��A������m��l�������O�@��t���Ǝv���������ł���܂��B
�������͂������������Ă�Ȃ�A��q�Ə����̂��������̂ł��낤�Ǝv���܂��B���Ƃ͂������Ƃ����đ傫�Ȏq�A���Ȃ킿���j�Ƃ����Ӗ��ł���܂������A�����̉��ŌĂԂ悤�ɂȂ��Ă���́A����ɐ_�Ƒ������̂��q�l�̑��ɂ͎g��ʂ��ƂɂȂ�A�������ɂ͂������Ƃ����āA�w�ǐ������q����������悤�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���������Â����t���܂��c�ɂɂ͎c���Ă������߂ɁA���ƂȂ������̑�t�ƕ���邱�ƂɂȂ����̂ł����A���Ƃ��Ɛ_�l�̂��q�Ƃ������Ƃł�����A�C�����Č���Ƒ�t�炵���Ȃ��b���葽���̂ł���܂��B�M�B�ł������Ɠ�̕��́A���u(������)���̋Ղ����Ƃ����Ƃ���ɂ́A��o(���傤������)�Ƃ����đ��̈����_�l���J���Ă���܂��B���̌��Ղ��Ԃ̌䏊�A����(��������)�V�c�̌䖅�ł������ȂƂǂ�������������܂����A������܂��������ƉW�̐_�Ƃ��A�q��ł����̂��n�߂̂悤�ł���܂��B���̑�q���H�ő���ɂ߂ē�V���Ȃ��ꂽ�̂ŁA�i���y�n�̎҂̑��̕a�������Ă�낤�Ƌ���ꂽ�Ƃ����āA���ł��M�S�ɂ��w(�܂�)�肷��l������A���̂���ɂ͑���(��炶)��Б������[�߂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�������Ă��̒n���ɂ��A�u����ΎR�̐_�̕Б����܁v�Ƃ����������邻���ł���܂��B(�`���̉��ɓ�(��������)�B���쌧���ɓߌS���u��) ���������V�_�̌�q���A���q�����Ƃ�����{���{(�킩�݂₿���݂̂�)�ȂǂƂ����āA���X���J���Ă����͂�������܂��B�܂���H�Ƃ��ؔ�(���т�)�Ƃ������R�̖ɊW�̂���E�Ƃ̐l���A���ł��䑾�q�l�Ƃ����Ĕq��ł���̂��A���@�̕��̐l�Ȃǂ͐������q�ɂ��߂Ă��܂��Ă���܂����A�ŏ��͂�͂肽���_�l�̌�q�ł������̂����m��܂���B�Â����{�̑傫�Ȃ��Ђł��A����������X�����܂��M���_�l���J���Ă�����̂����X�ɂ���܂����B�������Ă��ł���g���̕w�l���A�K�����̂���(����)�ɕ����Ă�����̂ł���܂��B���ꂩ��l���Č��܂��ƁA�\�ꌎ��\�O���̔ӂ̂��������u�̘V���Ȃǂ��A��ɂ͕n�R����(����)�����Ƃ̎҂̂悤�ɂ����o���܂�������ł��A�ȑO�ɂ͂�����_�̌��A�܂��͌�f��Ƃ����悤�ȁA�Ƃɂ������ʂ̑��̐l���́A�����Ƃ��̂������ɐe���݂̐[�����ł������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���ꂮ�炢�ȕω��͓`���ɂ͒������Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�����̂��Ђ⓰�ɂ͘e��(�킫��)�Ƃ������āA�W�̖ؑ����u���Ă���A�܂��ւ̉W�l�̘b�ɂ�����悤�ɁA���ƉW�Ƃ̗���ꂵ��ɁA��̏�A�r�݂̊��J���Ă���Ƃ����A�`���������Ȃ��̂ł���܂��B ���͎����̎��_�Ƃ��āA�W�̐_��q�ނ悤�ɂȂ����������A��q�����͎��̐_�̂��Ƃł������Ƃ���A����ł悭�킩��Ǝv���Ă��܂��B�W�͂��Ɛ_�̌�q���Ɉ�Ă��̂ɁA�l�Ԃ̕�������[���M�p�����̂ł��낤�Ǝv���܂��B����ɂ��Ă͂܂���O�̏����V�����`��������܂��B�I�B�b��o(�����)���v�(�ق�����)�_�ЂƂ����̂́A�ȑO�͑吼�Ƃ������Ƃ̎x�z�ŁA���D�Ȃǂ���������o���Ă���܂����B���̑吼�ƂŔɂ������N�ɂ́A���������b�������Ă���܂����B����N�\�ꌎ�̓�\�O���̔ӂɁA����(���炪)�̔k���܂���l�K�˂ė��āA���̏h���肽���Ƃ������B�����͕n�R�ʼn����グ����̂��Ȃ��Ƃ����ƁA�H���ɂ͗p���Ȃ��B�������߂ĉ�����悢�Ƃ����āA��ǂ����͘F���̉̑��ɍ����Ă����B��̖������ɐ���������Ŗ���āA����ɕ������ĐÂ��Ɉ��݁A�������ďo�čs�����Ƃ��đ吼�Ƃ̎�l�Ɍ����A���͂��̉Ƃ̐�c�Ɖ��̂���҂��B���܂��������Đe�ɁA�h�����Ă�������̂͂��肪�����Ǝv������A���̂���ɂ͂��ꂩ�炢�܂ł��A�吼�̎q���Ɩ����҂��vጂ��y���A����������悤�Ɏ���Ă�낤�Ƃ����ċA�����B���̐Ղ�������ƁA���傤�Ǎ��̂��Ђ̂���Ƃ���܂ŗ��āA��������(��������݂傤����)�̎p�������čs���m�ꂸ�ɂȂ����Ƃ����Ă���܂��B�퓗�Ƃ������Ƃ̎n�܂�܂ł́A�vጂ͂܂��ƂɎq�������̑�G�ł���܂����B���ꂾ�������vጐ_��������h���Ă����̂ł���܂����A���̘V���͎��͂���ł������炵���̂ł��B���������͂��Ƃ͈��~�̐_�ł����������ł����A���Ƃ���������킪���ł́A���ɏ����̖������Ђ��F���Ă��܂����B����̂ɂ��p����X�����A�����Ĕk���܂Ȃǂɉ����ė�����_�ł͂Ȃ������̂ł��B�������ɂ��Ă��̑吼�Ƃ̐�c�̐l�́A�܂ڂ낵�Ɍ����̂ł���܂��B�O����W�̐_�̌�ɂ͎��̐_�̂��邱�Ƃ��A�m���Ă����ׂł��낤�Ǝv���܂��B(�I�ɑ����y�L�B�a�̎R���߉�S��o�����O) |
|
|
�ɐ��̒O��(�ɂ�)���͌Â����牔�̎Y�n�ł����A�����ɂ͖��̕������z�����܂��B�ߍ��ł͂��낢��̕a�C�̎҂������ɗ���悤�ɂȂ�܂������A�̂͂������̒n���̏��������A���Y�̑O��ɗ��čC��(����)����萶��q�̈��S�����F�肷��Ƃ���ł������ׂɐ�̖����q���̈�Ƃ����A��͂�O�@��t�̉��������Ƃ����`���������Ă��܂����B�퍑����ɂ͂��̓y�n���r��Ă��܂��āA��˂������͖�����A�������������`����Y�ꂽ�l�������Ȃ�A�ߏ��̕S�����������̐��ʂ̈����Ɏg���҂�����܂������A���������Ƃł͂ǂ����a�l�������A���ɂ͎��ɐ₦�Ă��܂����Ƃ����������̂ŁA�����Č��(�݂���)�������Ė��_�l�̐_�ӂ��f���������ł��B���ۂ͐��ɉ��̋C�������āA����ň��ގ҂��Q�����̂����m��܂��A�̂̐l�͂����͎v��Ȃ������̂ł���܂��B����Ō�髂̕\�ɂ́A�q����͎Y�O�Y��̏��̂��߂ɁA�q��Ă�������肽�����ׂ��[���v(����)�������̂����˂�����A������(����)���Đ�������Əo���̂ŁA���ꂩ��͂��悢�悱�����p�̂��߂ɋ��ގ҂��A�M(����)�����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł���܂��B(�O����b�B�O�d�����C�S�O����)
�q���̒r�Ƃ����̂́A�܂������̋߂��ɂ������āA����ɂ��Đ����Ƃ悭�����`���������Ă���܂����B���̒��̐��k�́A���V�q(�����ɂ�����)�̖��T��(�݂傤�Ă�)�Ƃ������̘e�ɂ������̂�����ŁA�̓��@��l�����̒n�����s�r���Ă������A�n�c�ܘY����(���݂��̂��낤�Ƃ��݂�)�Ƃ����喼�̉������A��Y�Ŕ��ɋꂵ��ł��܂����B���@�����ׂ̈Ɉ��Y�̋F������āA��{�̗k�}(�悤��)�������ĉ���������ƁA������������D�ꂽ�鐴�����N���o�����B���̐����d(��)��Ō��������䕄��Ղ�������A���h�Ȓj�̎������ꂽ�Ƃ����āA���̒r�̖T�ɂ���Ö̖��̖́A���@��l�̗k�}��n�Ɂ��m�u���v�ł���̏c�_�����ɓ˂������Ă���n�����̂��A��𐁂��Đ����������̂��Ƃ����`���Ă���܂����B(�V�ѕ������y�L�e�B��ʌ��b�k����(����������)�S���q�����V�q) �`���͎q���̒r�́A�݂̖��̔@���������܂����B�����͎l�S�N���̕��ɑQ(�悤��)���o�����s��ł����A�����ւ��O�@��t�����̊Ԃɂ�����ė��Ă��܂��B�������̌�̒J��(��Ȃ�)�������ɂ́A�����b���(���Ȃ�)�������Ă��Ƃ͗L���Ȑ��������̖T�ɂ������̂ł��B���̐������܂��o�Ȃ������O�ɁA��͂��l�̘V�ꂪ���ɉ�(����)���ڂ��āA�����Ƃ��납�琅���^��ł����Ƃ���ցA��t���������Ă��̐������Ĉ��݂܂����B�N������Ă��疈���������Đ�������ŗ���̂͋ꂵ�����낤�Ƃ����܂��ƁA�������ł͂���܂���A���ɂ͂�������l�̎q�������āA�i�炭�a�C�����Ă���̂ō���܂��Ɠ����܂����B��������Ƒ�t�͎b���l���āA��Ɏ��ƌ�(�Ƃ���)�Ƃ������̂ŁA�����ƒn�ʂ��@��A�����������炱�̐������N���悤�ɂȂ�܂����B���킢�͊ØI�̔@���A�Ă͗₩�ɓ~�͉����ɂ��āA�����Ȃ鉊�V�ɂ���(��)��邱�ƂȂ��Ƃ��������ł���܂����B�W�̎q���̕a�C�͉��a�ł���܂������A���̐��Ő�����瑁���Ɏ���܂����B���ꂩ�瑽���̐l���Ⴂ�ɗ���悤�ɂȂ��āA��(��낸)�̕a�͊F���̐�������ŐΕK���悭�Ȃ�Ƃ����܂����B��ׂ̂��Ђ��A���̎��ɍO�@��t���J���Ēu���ꂽ�Ƃ������ƂŁA���������ɔɏ����č��̂悤�ɒ��������������ė����̂ł���܂��B(�]�˖����L�B�����s�b���J(������)�搴����) ��B�b����(��������)�݂̗{����(�悤����)�̎R�̉��̒r�Ȃǂ́A���a�O�ڂقǂ����Ȃ����r�ł͂���܂����A������O�@��t�̉������Ƃ����`���āA�M�S�[���l����������ōs���Ĉ��ނ����ł��B�̂���w�l����������Ȃ��āA�Ԃ�V������č�����Ă����Ƃ���ցA�����ʗ��m�����Ă��̘b���A���炭�F�O�����Ă����Œn�ʂ�˂��܂��ƁA�������琅���N���o�����̂������ł��B����������ň���ł��悵�A�܂��͓��̂悤�ɂ��ď����Ɋ܂܂��Ă��A�K����v�Ɉ�ł��낤�Ƃ����čs���܂����B���ꂪ�O�@��t�ł������Ƃ������Ƃ́A����������ɗ{�����̐l�������A�����n�߂����Ƃł��낤�Ǝv���܂��B(���y������ҁB�Ȗ،������S�O�a���q) �y�n�̌Â�����̂����`���ƁA������l�̍l���Ƃ��H����������ɂ́A�b�͂��������ӂ��ɂ���Ɩʓ|�ɂȂ�܂��B�����������ɖ��������m�̂��Ƃ��ƂȂ��Ă��܂��ƁA�܂���l�ʂɉW�̑��ցA���炵���᎙��A��ė��Ēu���˂Ȃ�Ȃ������̂ł���܂��B����܂�C���̈����b����������A�ڂ������Ƃ͂���ʂ���ł����A���{�ł悭�����Y��(���Ԃ�)�̗�̘b�Ȃǂ��A���Ƃ͂������̖T���J������Ǝq�̐_�ł���܂����B�p����X�����Ԃ�ڂ̗l�ł��A�_�l�̎q�ł������̂ɕs�v�c�ȗ͂�����܂����B����ʂ�l�Ɍ����ĕ����Ă�������Ă���ƕ�e�������̂ŁA�b�������Ă���Ƃ���ɏd���Ȃ�B���̏d���̂������Ɖ䖝�����Ă����l�́A�K�����Ⴂ�A�܂��͑��(�����肫)��������ꂽ�̂ł���܂��B���ꂪ��ɂ́A�܂������t�ɍs�������āA�p���Ă��̖@�͂������ċ~��ꂽ�Ƃ����b�ɕς��ė��āA�Y���͕��ʂ̐l�̗H��̂��Ƃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�������H�삪�q���Â�ŗ���̂������������Ƃł����A����^����Ƃ����̂��A�܂��܂��������܂���B����ɂ͉������̗��R���������̂ł���܂��B�y�n�ɂ���āA��b�e(��)�����܂��͖�e���ȂǂƂ����āA�^�钆�ɋ�����(������)���̌��ŁA�Ԏq�̚e����������Ƃ����b������܂����A����������낵�����Ƃƍl�����ɁA���ɂ��Y�̂���m�点���ȂǂƂ����y�n������܂��B���͂܂���l�̏��������āA��ɂȂ�ƐԂ�ڂ��e���̂ɍ����āA���̏��̖̉��ɍs���ė����Ă���ƁA�s�r�̑m���ʂ肩�����ĕ����Ă��ꂽ�B�������ď��̏��}���ɂƂ����āA���̌����q���Ɍ�����ƚe���~(��)�B���ꂩ��ケ�̏��̉��ɐ_���J��A�܂���e��������q�̉Ƃł́A���̏��}��܂��ė��ē�(�Ƃ���)�̉ɂ���Ƃ�����������܂��B��B�̉F������(�����͂��܂�)�̕��߂ł́A�O�@��t�Ƃ��킸�ɁA���̑m��l����F(�ɂ����ڂ���)�ƌĂ�ł���܂��B�l����F�͔������F�����ɂ��̗l�Ȏp�����āA���X���������Ȃ����̂��Ƃ����l������܂������A����Ȋ�ȑm�̖�������܂��Ǝv���܂�����A���Ȃǂ͂����l�̕�A���Ȃ킿�l��(�ɂ��)�Ƃ������t���A���̐_�̐M�ɂ��āA�Â��s���Ă������c�ł��낤�Ǝv���Ă��܂��B�q���Ƃ�����Ǝq�Ƃ̐_�́A���ł��֓��n���ɂ͕��X���J���Ă��܂��B�C�����w�l���q��������̑��ł���܂��B�W�Ƃ����̂͂������̐l�̂��Ƃł���܂����B�e�̖����f��Ƃ����̂��A�܂��͌�X�f��ɂȂ�ׂ���Ԃ߈ȉ��̖����A�����̂������炨�Ɠc�ɂł����Ă���̂��A���Ƃ͈�̌��t�ł���܂����B�����V���̂悤�ɍl���o�������߂ɁA���܂��ɂ͎O�r��(��������)�̔k�l�̂悤�ȁA�����낵���̑��ɂȂ����̂ł���܂��B���������{�ɂ͂����ė�����O����A�q���̉W�̐_�͐�����̂قƂ���J���Ă��܂����B�O�@��t�����������Ă����N�̌�܂ł��A�Ȃ��V�Ȃ鐴���͏�ɔ��������A�������t�̈�ˁA���t���̓`���́A���Ȃ킿����ɔ����ė���čs���܂��B�����ē��{�̓c�ɂ����������Ă���҂́A�J(�ނ�)������̌�W�q(�����)�l�ł���܂����B���ꂾ���炱�̐_��H�̖T�A���̏��L����͂���A���l�̊�ы��ސ�̂قƂ�ɂ܂�A�܂��ւ̉W�_�Ƃ��������N�����̂ŁA�M�c�̋���(����������)�̂�������Ȃǂ��A���Ƃ͂��������W�Ǝq���J���Ă�������̖��ł��낤�Ǝv���܂��B�����̉W�q���Â��`���͐l���Y��Ă��܂����A�����Ƃ��̉���̔����ɂ��āA��̕��ꂪ�������̂ł��B�Ȃ��F������C�����Č䗗�Ȃ����A�Â�����̓��{�̘b�ɂ́A�܂��܂����ł����������������������A�W�Ƃꗧ���ďo�ė���̂ł���܂��B�@ |
|
| ���Жڂ̋�(����) | |
|
���̎����ɂ͎q���Ƃ͊W�͂���܂��A�r�̓`���̏�(����)�ɕЖڂ̋��̘b���������Ă݂܂��傤�B�ǂ����ċ��ނɈ������̂Ȃ��̂��o�������̂��B�܂��������ɂ��ق�Ƃ��̂킯�͂悭�킩��܂��A�����������̂���̂͑��͂����̑O�̒r�A�܂��͐_�Ђ̘e�ɂ��鐴���ł��B�����Ɉ�ԋ߂����ł͏㍂���(���݂�������)�̈㉤��(��������)�A�����̖�t�l�ɂ͊�̈����l���悭���Q������ɗ��܂����A���̐܂ɂ͂�������̐싛�������ė��āA�����̑O�ɂ��鏬���Ȓr�ɕ��������ł��B��������Ƃ��̊Ԃɂ��A���̋��͕Жڂ��Ȃ����Ă���Ƃ����܂��B�Ă̍��o���̍ۂȂǂɁA�r�̉����̏����Ȑ�ŁA�Жڂ̋������������Ƃ��܁X����܂����A����Ȏ��ɂ͂���͂���t�l�̋����Ƃ����āA�K���Ăт��̒r�Ɏ����ė��ĕ������Ƃ������Ƃł��B(�L����(�Ƃ悽��)�S���B�����{�L�����S����ˑ��㍂���)
��B�b�]��(����)�̍��_���_(���������݂傤����)�ł́A�Ђ̍���ɐ�������܂����B��(�Ђł�)�ɂ���(��)�ꂸ�A���J(�Ȃ�����)�ɂ����炸�A�꒬���藬��đ��ɗ����܂����A���̊ԂɏZ�މV(���Ȃ�)�����͊F�Жڂł������B���ꂪ��ւ͂���ƁA�܂����ʂ̊��ɂȂ�Ƃ����܂������A����ł����̖��_�̎��q�́A�V�����͌����ĐH�ׂȂ����������ł��B(�R�����L�B�Q�n���b�k�Êy(���������)�S�x�����]��) �b�{�̎s�̖k�ɂ��镐�c�Ɓb�隬(���傤��)�̍�(�ق�)�̓D��(�ǂ��傤)�́A�R�{�����Ɏ��ĊF�Жڂł���Ƃ����܂����B�D�ӂ��Жڂł������łȂ��A�Õ{��(���ӂ��イ)�̉����Ƃ������Ƃ́A���̎R�{�����̎q���ł���̂ɁA��X�Жڂł������Ƃ����b������܂������A���ۂ͂ǂ��ł��������m��܂���B(���Ó��^���̑��B�R�������R���S���쑺) �M�B�ł͌ˉB�_�㎛(�Ƃ��������傤��)�̎��s�v�c�̈�ɁA�ɏZ�ދ��ށA���Ƃ��Ƃ��ЖڂȂ�Ƃ����Ă��܂����B�܂��ԍ�̑ꖾ�_�̒r�̋����A�Жڂ����������A�܂��͒�(��)��Ă��܂����B�_���F��̐l�ɗ쌱(�ꂢ����)�������ׂɁA����������̂��Ƃ����Ă���܂��B(�`���b�p��(��������)�B���쌧�b����(����������)�S�a�鑺) �z��ɂ������b���������܂��B�����̐_�c���ł͐l�Ƃ̖k����ɁA�O�u�r(���������)�Ƃ����r�����Ƃ͂����āA���̐��ɏZ�ދ��(����ׂ�)�͊F�ЖڂŁA�H�ׂ�Ɠł�����Ƃ����ĕ߂�҂��Ȃ������B�Îu(����)�S�{���̈ꉤ(��������)�_�Ђ̓��ɂ́A�X�����ւ��Ăēc�̒��ɏ\�قǂ̏�������A�����̋��ނ��F�Жڂł����������ł��B�̂��̂��Ђ̏t�H�̍Ղ�ɁA���̂��������������������̒r�̐Ղ�����Ƃ����Ă���܂����B�l�\�N�قǑO�ɓc�ɊJ���Ă��܂��āA�������̒r���c���Ă��܂���B���ꂩ��k����(���������ʂ�)�S�̖x�V��(�ق�̂���)�̒��ɂ́A�R�̉��ɌÓޘa��(���Ȃ킴��)�̒r�Ƃ�����r�������āA���̐��������Ē����̗p���ɂ��Ă��܂����A���̒r�̋������Ƃ��Ƃ��Жڂł���Ƃ����܂����B�߂��Ă�����E�����M�肪����A�ƂɎ����ė��Ċ�̓��ɒu���Ă��A���̔ӂ̓��ɒr�ɋA���Ă��܂��Ƃ����b������܂������A���ۂ͎E����(�������傤����)�ŁA�N������Ȃ��Ƃ����݂��҂͂Ȃ������̂ł���܂��B(���̔V�x(���̂�����)�B�V�����k�����S�x�V����) �X���ł͓�Ìy�̉���(���邪)�_�Ђ̂��r�Ȃǂɂ��A���ł��Жڂ̋�������Ƃ������ƂŁA�u�F�݂�Ȃ߂��������v�Ƃ����~�x��̉̂������邻���ł��B���̒m���Ă���̂ł́A���ꂪ��ԓ��{�̖k�̒[�ł���܂����A�������{��������k�ɂ���������ɂ��锤�ł���܂��B(�����B�X���b��Ìy(�݂Ȃ݂���)�S���ꑺ) ���ꂩ�炱����֗���Ƙb�͑����Ȃ����ŁA�ƂĂ��������Ă��邱�Ƃ͏o���܂���A���͂��������ЖڂɂȂ����������A�y�n�̐l�������Ȃ�Ƃ����`���Ă������Ƃ������Ƃ������A�F����ƈꂵ��ɍl���Č��悤�Ǝv���܂��B���̒��ő�������m���Ă����̂́A�ےÂ̍��z�r(����̂���)�̕Жڕ�(�����߂ӂ�)�ŁA����͍s���F(���傤���ڂ���)�Ƃ����ޗǒ�����̖��m�ƊW������A�b�͏�������O�@��t�̏Đ����Ɏ��Ă��܂��B�s��s�r�����Ă��̒r�̂قƂ��ʂ������Ɏ��ɂ������Ă��鉘���a�l���H�ɐQ�Ă��āA����H�ׂ����Ă���Ƃ����܂����B���킢�������Ǝv���āA���F(�Ȃ���)�̕l�ɏo�ċ������߁A�m�ł͂��邪�a�l�ׂ̈����玩���ŗ��������Ċ��߂܂��ƁA��ɐH�ׂČ����Ă���Ƃ����̂ŁA������䖝�����ď����H�ׂČ����܂����B�������Ă��邤���ɂ��̉�����H�͖�t�b�@��(�ɂ�炢)�̎p�������A���͏�l�̍s���������Č���ׂɁA���ɕa�l�ɂȂ��Ă����ɐQ�Ă����̂��Ƃ����āA�L�n�̎R�̕��ցA���F(����)�̌�������Ĕ�ы������Ƃ������Ƃł���܂��B�s��͂��̕s�v�c�ɂт����肵�āA�c��̋��̓������z�r�ɕ����Č���ƁA���̈�ꂸ���F�����������āA���̕Жڂ̕��ɂȂ����B����Ō�ɂ͂��̒r�̋���_���J���āA�s�g(���傤��)���_�Ɩ��Â��Ĕq��ł���Ƃ����̂ł���܂����B����܂莖���炵���Ȃ��b�ł͂���܂����A�y�n�̐l�����͉i�������M���āA�Ԃ��������A�܂��ނ莅�𐂂ꂸ�A���̋���H�ׂ�҂͂�邢�a�ɂȂ�Ƃ����Ă�����Ă��������ł���܂��B(�������l�k���̑��B���Ɍ��b���(�����)�S��쑺���z) |
|
|
�܂�������ł͍s��͎O�\���̔N�ɁA�̋��̘a��(�����݂̂���)�A���ė��܂��ƁA���̎Ⴂ�҂͖@�t�������Č��悤�Ǝv���āA���̂Ȃ܂�������Ēu���āA�ނ�ɂ�����s��ɂ����߂��B�s��͂����H�ׂĂ��܂��āA��ɒr�݂̊ɍs���Ă����f���o���ƁA�Ȃ܂��̓��͊F�����������Đ��̏���j���܂�����B���̋������ł��Z��ł���B�ƌ���(���炶)�̕����r(�ق����傤����)�Ƃ����̂����̒r�ŁA���ꂾ��������r�̕��́A�F�Жڂ��Ƃ����܂����B�������Ȃ܂��ɂȂ��Ă��琶�������������Ȃ�A���ꂪ�ǂ����ĕЖڂɂȂ�̂��́A�ق�Ƃ��͂܂��N�ɂ��������邱�Ƃ��o���܂���B(�a���}��B���{�b��k(����ڂ�)�S���c�����ƌ���)
����ƑS�������b�́A�܂��d�B(�イ)���Ð�(��������)�̋��M���̒r�ɂ�����܂����B���Â̋��M�Ƃ����l�́A�M�S�[���O���҂ł���܂������A��͂�ނ�ɂ����߂�ꂽ�̂ŁA�d���Ȃ��ɋ��̓���H�ׁA��œf���o�����̂������Ԃ��āA�i�����̒r�̕Жڂ̋��ɂȂ����Ƃ����܂����B���ł͂��̋�����l��(���傤�ɂ�)�Ƃ����������ł����A����͐��i��(���傤����)�̂���܂肩�Ǝv���܂��B�������Ă��̒r�����M�̂ق����r���Ƃ����_�́A�s��̍��z�r�̘b�����A���܈�i�Ƃ���t���ɋ߂��̂ł���܂��B(�d����(�͂�܂�����)�B���Ɍ����ÌS���Ð쒬) �����������ЖڂɂȂ������R�ɂ́A�܂����̑��ɂ��F�X�̘b������܂��B �Ⴆ�Ή���(������)��O��(���݂̂���)�̏���(���날��)�̍��̋��́A��b��(�҂�)�c�炸�ڂ���ł���܂����A����͌c����N�̌܌��ɂ��̏邪�U�ߗ����ꂽ���A���b����A�n��(���܂����݂����܂̂���)�̔������P���A�����Ŗڂ�˂��ĊO�x�ɐg�𓊂��Ď��B���̈����ɂ���č��ł����̐��ɂ��鋛���Жڂ��Ƃ����̂ł���܂��B���́u�����v�Ƃ������Ƃ��A�̂̐l�͂悭�����܂�������ǂ��A�ǂ��������Ƃ��Ӗ�����̂��A�܂��m�ɂ͂����ɂ킩��܂���B(���y���؍��B�Ȗ،��͓��S��O�쒬) �����łȂ������̈����̗�������Č���ƁA�����̎s�̋߂��̖���(��̂�)���̕Жڐ����Ƃ����r�ł́A���q���ܘY�b�i��(�����܂�)�����Ŋ�������A���̒r�ɗ��ď��������B���̎���������Đ����ɂ܂������̂ŁA����Œr�ɏZ�ޏ����͂ǂ����������̖ڂ��ׂ�Ă���B�Жڐ����̖��͂��ꂩ��o���Ƃ����܂��B(�M�B�ꓝ�u�B�������b�M�v(���̂�)�S�b�]��(���܂��)����b����(��̂�)) ���q���ܘY�́A�������Y�`�Ƃ̉Ɨ��ł��B�\�Z�̔N�ɉ��B�̌R(������)�ɏo�āA�G�̐���(����)�ɕЕ��̊���˂��Ȃ���A������ʑO�ɓ�(�Ƃ�)�̐�(��)���˕Ԃ��āA���̓G��������Ƃ����E�҂ȕ��m�ł���܂������A���̊�̏��������Ƃ����r�����܂�ɑ����A���̒r�̋����ǂ��ł��Жڂ��Ƃ����Ă��邾���͕s�v�c�ł��B���̈�͉H��̋���Ƃ������̂��闬��A�����ł͌��ܘY�̍����A����ŕЖڂ̋��ɂȂ����Ƃ��������ł��B�����͐̂̌�O�N(������˂�)�̖�(����)�́A����̍�(����)�̂����������Ƃ����܂�����A���肻���Ȃ��Ƃ��Ǝv���l�����������m��܂��A���q���ܘY�i���͒����������l�ŁA�����Ă����֍����c���čs�����͂Ȃ��̂ł���܂����B(���[���B�H�c����k�S����) �����ɎR�`���ł͍ŏ�(������)�̎R���̘[(�ӂ���)�ɁA��̌i�����������Ă����̒��C(�Ƃ�̂���)�̍����(����)���Ƃ����܂����B���ܘY����̏��������r�Ƃ����̂������āA�������Жڂ̋����Z��ł��܂����B�ǂ����Ă��̂������o�����̂��͕���܂��A���߂̑��ł͓c�ɒ����������ɁA���̓������(����)���ۂ�炵�Ē��ǂ�������ƁA��(������)���Q�������Ȃ��Ȃ�Ƃ����Ă���܂����B(�s�r���M�B�R�`�������R�S�R����) �܂�����(���傤�Ȃ�)�̕��c�̖��(�₾�ꂪ��)�Ƃ��������ɂ́A�Â������̎Ђ������āA���̑O�̐�ł����ܘY�����Ėڂ������Ƃ����Ă��܂��B�������Ă��̐�̂������Ƃ������́A����ɂ���ĊF�Жڂł���Ƃ����`��������܂����B(�������k���B�R�`���b�O�C(������)�S�����c���k��) �������ĕ������̕Жڐ����܂ŗ���r���ɂ́A�܂����X�ɖڂ���r���������̂ł����A�����ׂ����Ƃɂ͌��ܘY�i���́A�����M�B�̓�̕��̑��ɗ��āA��͂肻�̖ڂ������Ƃ����b���A�`����Ă���̂ł���܂��B�M�B�b�ѓc(������)���班���͂Ȃꂽ�㋽(���݂���)���̉_�ʎ�(������)�̒�ɁA���̑�̉�����O(��)���Ă��鐴��������ŁA���ׂ̈ɂ����ɂ��邢����͍��̊Ⴊ�ׂ�Ă���Ƃ����܂��B�����̖��͂���݂̒r�A�ǂ���������݂����������͕���܂��A���ܘY�͎b(����)�����̎��ɂ������Ƃ�����Ƃ����̂ł���܂��B(�`���̉��ɓ߁B���쌧���ɓߌS�㋽��) ��������ɂ͎v���Ⴂ�����������ƂƎv���܂����A�܂����������b������܂��B��B�b����(�݂�)�Ƃ������̔��ǂ̒r�́A�����Ȃ鉊�V�ɂ���(��)�����Ƃ̂Ȃ�����(���̂���)���Òr�ŁA�r�ɂ͕Жڂ̉V������Ƃ����܂����B�̈�l�̔n�����n�ɒ��P(���Ⴄ��)���āA�r�̒��ʂ��Ă��Đ��ɗ����Ď��B���̔n���������߂̒j�ł������̂ɁA���ꂪ�V�ɂȂ��āA�܂��Жڂł���Ƃ����b�ł���܂��B���ł��J�̍~����ȂǂɁA�����ƒ����Ă���ƁA�r�̒�Œ��P���Ђ���������ȂǂƂ����܂����B(���쎏�B���R�����c�S�g�쑺����) |
|
|
�z��ɂ͐�(�����€)���̐��r�Ƃ����āA�`���̏�ł́A���Ȃ�L���Ȓr������܂��B���̒r�̐��̐_�͑�ւŁA�܂�܂���������̎p�ɉ����āA�s�֔������ɏo����A���̂����̐������ɗ����肷��Ƃ������̂́A���������X���̂����e�ɂ��̒r���������ׂɁA�������������鉓���̐l�܂ł��]���ɂ��Ă�������A���������b���o�����̂ł��낤�Ǝv���܂��B�́b����(�₷�Â�)�̏�̓a�l�b�ۑ�(������)�Ƃ����l���A�s�ɗV�тɏo�āA���̔������r�̎�������߂܂����B�������ĘA����ĂƂ��Ƃ����̒r�ɂ͂����āA�߂�Ȃ������Ƃ������ƂŁA���̖ۑ��a���A�܂��ڈ�ł������Ƃ��납��A���ɂ��̒r�̋��ނ͈���̖ڂɁA�܂肪����Ƃ����`���Ă���܂��B(�z�㍑�b����(�����Ȃ�)�_�Јē��B�V�����b�����(�Ȃ����т�)�S�b���r(��������)����)
�r�̎�̑�ւ́A���̒��ɂ���Z��ł��āA�ւтƂ��܂�ň���������낵���������ł���܂����B���������������ۂɂ������ǂ����A���ł͂������Ȃ��Ƃ͂����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B�G�Ȃǂɕ`���l�́A��������ւ��������Ƃ̂Ȃ��҂���ŁA�d���Ȃ��ɂ����傫�Ȏւ̂悤�ɕ`���̂ŁA����ɂ����v���l�������Ȃ�܂������A���̑�ւ̕��͐��̒�ɂ��āA���ׂĂ̋��ނ̎�N�̔@���l�����Ă���܂����B�Жڂ̖ۑ��a���r�̎���ۓ�(�ނ���)������āA��������ւɂȂ����Ƃ����A���ނ͂��̈�傾���炾�Ԃ�āA�ڂ���ɂȂ낤�Ƃ��Ă���̂��ƁA�z������l���������킯�ł���܂��B �É��s�̖k�̎R�Ԃɂ���~�̒r�̎�́A������ڂ̐��ł������Ƃ����A�܂��͕Жڂ̑傫�Ȃ܂��狍�ł������Ƃ������܂����A������̂ł�����Ȃ�ɂł��Ȃ邱�Ƃ��o����킯�ł��B�́b�����F(�݂��݂���)���̐���(������)���҂̈�l�����A���R�̒r�̎�ɂ��܂���āA���̒�֘A��čs����悤�Ƃ����̂ŁA���҂͑傢�ɓ{���āA���S�l�̉��j�l�v���w�}���āA���̒r�̒��ւ��܂��̏Ă��𓊂����܂���ƁA�r�̎�͈��������āA�����Č~�̒r�ɂЂ��ڂ��Ă��܂��܂����B���ꂩ��Ȍ�A���̌~�̒r�̋��́A���Ƃ��Ƃ��ЖڂɂȂ����Ƃ����̂́A�Ƃ߂��킭�Ȃ��������ł���܂��B(���{(����)�S���B�É������{�S�b�ˋ@(�����͂�)��) ���A�r�̎�͗̎�̈��n���������̂ŁA�����̒����t(�����̂�)�����ŗ��āA�S���Ƃ����Ēr�̒��֗������Ƃ������܂����A�ǂ���ɂ��Ă����ꂪ���傤�Lj���̊�������A�X�ɋ����Ԉꓯ�̕Жڂ̂��ƂɂȂ����Ƃ����̂́A�������Ǝv���܂��B�Ƃ��낪���������b�́A�܂����ɂ��܂�܂肠��܂��B�������{�S�̋ʐ쑺�A�������Ƃ������̑O�̒r�ł��A�r�̎�̑�ւ����̎q����������̂ŁA�������{���đ����̐𓊂����ނƁA���ꂪ�����đ�ւ͕Жڂ�ׂ��A���ꂩ��͒r�̋����F�ЖڂɂȂ��Ă���Ƃ����܂����B �ւ��ЖڂƂ����`�����A�܂����X�Ɏc���Ă���悤�ł���܂��B�Ⴆ���n�̋��k�R(����ۂ�����)�̈�̒J�ł́A�̏����V�c�����̓��ɂ��o�łɂȂ������A���̎R�H�Ŏւ��䗗�Ȃ���āA����ȓc�ɂł��ւ͂���ς�ڂ�����邩�ƁA�ƌ��ɋ����܂����Ƃ��낪�A���̂����t�ɋ�������āA�Ȍケ�̒J�̎ւ����͂��Ƃ��Ƃ��ЖڂɂȂ�܂����B����ō��ł���։͓�(���ւт�����)�Ƃ����n���ɂȂ��Ă���̂��Ƃ����܂��B����̔��R(�͂�����)�̘[�̑吙�J�̑��ł��A�Ԑ��Ƃ����ꕔ�������́A�����Ȏւ܂ł��F�Жڂł���Ƃ����Ă��܂��B�≮�̊ω����̑O�̐�ɁA�₷�Ȃ���(�ӂ�)�Ƃ����������Ƃ͂����āA���̎�͕Жڂ̑�ւł���������Ƃ������Ƃł���܂��B �̐Ԑ��̑��ɏZ��ł����₷��(��)�Ƃ����҂́A�����߂݂̂ɂ������ł����Ēj�Ɍ��̂Ă��A�����ł��̕��ɐg�𓊂��Ď�ɂȂ����B���ꂪ���܂�쉺�̕��֍~��ė���ƁA�K���V�C���r��A�吅���o��Ƃ����ċ���܂����B�₷���̉Ƃ́A���Ə����̒��́A�{�@��(�ق���)�Ƃ������̖�k�ł������̂ŁA���̎��̕u�ɂ͍��ł��l�ɋC�t���ꂸ�ɁA�₷�����Q�w(����)���Ē���(���傤����)�̂ނ�̒��ɂ܂����Ă���B���ꂾ����~�̑��̒��ł��A���N���̍��ɂ͐����o��̂��Ƃ����A�܂��J���̋�����������ƁA�����͐Ԑ��̂₷�Ȃ��������ȓ����Ƃ������������ł���܂��B(�O�B��k���B�ΐ쌧�b�\��(�̂�)�S�吙�J���Ԑ�) �����߂ɖT�_�n�݂̂ɂ������Ƃ����A�v�Ɍ��̂Ă�ꂽ����݂Ƃ������Ƃ́A�̘b�����Ƃł��낤�Ǝv���܂��B�����b�͗]��ɑ����A�܂����X�̓y�n�ɓ`����Ă���̂ł���܂��B���s�̋߂��ł��F���̑��̂��鎛�Ɉ���ɗ����j������͂��낤�Ƃ���ƁA�Жڂׂ̒�Ĉ�̎ւ����āA�^���ɂȂ��ĕ���̕��֍s���̂����܂����A�Ȃ������낵���Ȃ��āA�ׂ��̂Ăċߏ��̉Ƃɍs���ċx��ł��܂������A���傤�ǂ��̎��ɁA���炭�a�C�ŐQ�Ă������̘a��(�����傤)�����Ƃ����ė��܂����B���̑m���O�ɕЖڂ̓�����̂ĂāA�����Ƃ����ɗ��ĉB��Ă����̂��A�Ƃ��Ƃ��������āA���̗�Ɏ��E���ꂽ�̂��Ƃ����܂����B(�Փc�k�M)�B���͂܂��g���������Ȃ��V�m������ł���A������b�D(�҂�)�̕Жڂ̎ւ��A���̌�̏��̖̉��ɗ��Ă킾���܂��Ă���B���܂�s�v�c�Ȃ̂ŁA���̉����@���Č���ƁA��������̏������������Ė��߂Ă������B����Ɏv�����̂����ĎւɂȂ��ė��Ă����̂ŁA���̘V�m����͂�Жڂł������Ƃ����ނ̘b�A���������͈̂�b�Ƃ������̂ŁA��̘b�����Ƃ͂ǂ��ւł��ʗp���܂����B���ɂ͂킴�킴����������A�l���^��ŗ������̂�����܂������A���ꂪ�����ɂ��ق�Ƃ��炵���ƁA��ɂ͓`���̒��ɉ����A�܂��͍��܂ł̓`���ƌ��ѕt���āA����ɂ����̑��̗��j���A��(�ɂ���)���ɂ����̂ł���܂��B�l������ł���ւɂȂ����B�܂��͋���̊��q���ܘY�̂悤�ɁA�������ɂȂ����Ƃ������Ƃ͐M�����ʂ��Ƃł�����ǂ��A�����Ƃ��ɍ��̊Ⴊ�Ȃ������Ƃ����ƁA�����ꂾ���ł��A�����₻���ł͂Ȃ����Ǝv���l���o����̂ł��B����������Ȃ�ΕʂɊ�ƌ��������Ƃ͂Ȃ��B�܂����Ђ̑O�̒r�̌�V�����Жڂ��Ƃ����킯�͂Ȃ��̂ł���܂��B�����ŏ�����ڂ̓����҂����A�Е������Ȃ����̂������낵���A�܂���Ɏv���킯���������̂ŁA����œ`���̕Жڂ̋��A�Жڂ̎ւ̂����`�����n�܂�A����ɂ��낢��̘̐b���A�ォ�痈�Ă����������̂ł͂Ȃ����B�����������Ƃ��A���������̖��ɂȂ��Ă���̂ł���܂��B |
|
|
���j�̕��ł��ɒB���@(���Ă܂��ނ�)�̂悤�ɁA�Ɗᗳ�Ƃ���ꂽ�̐l�͏�������܂��A�`���ł́A���Ƃɖڈ�̐l�����h�����Ă��܂��B���̒��ł��O�ɂ������R�{�����Ȃǂ́A���c�ƈ�Ԃ̒q�҂ł������悤�ɓ`�����Ă��܂����A���ꂪ�����߂ŁA�܂�����ł���܂����B���q���ܘY�i���̔@�����A�L�^�ɂ͎Ⴍ�ČR�ɏo�Ċ���˂�ꂽ�Ƃ�����葼�ɁA�������c���Ă͂��Ȃ��̂ɁA�������犙�q�̌��̎Ђ��J���Ă��܂����B��B�ł͂܂����X�̔����̂��ЂɁA�i���̗삪�ꂵ��ɂ��܂肵�Ă���̂ł��B
���H�n���̑����̑��̒r�ŁA���ܘY���ڂ̏��������Ƃ����b������̂��A���Ƃ͂�͂����˂�ꂽ�Ƃ������Ƃ��A���h���Ă������߂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��������ƕЖڂ̋��Ƃ����āA���̕��ʂ̋��ƍ��ʂ��Ă����̂��A�K����������Ǝ����悤�Ȃ킯���������̂ŁA���̈�O���́A�r�̎�̂���݂��̂Ƃ����̂́A���傤�ǒr�̕�(�قƂ�)�̎q���_�ɁA�u�W��b��(������)�Ȃ��v�̘b�������ė����Ɠ������ƂŁA��Ɋ���̘̐b���q(��)�����킹�����̂炵���̂ł���܂��B �܂�ȑO�̂����̐_�l�́A�ڂ̈����҂����D���ł������B����O�ɓ�ڂ��������҂����A�ЖڂɂȂ����҂̕����A��i�Ɛ_�ɐe�����A�d���邱�Ƃ��o�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�Жڂ̋����_�̋��ł������Ƃ����킯�́A�����ȒP�ɑz�����Č��邱�Ƃ��o���܂��B�_�ɂ������\�����́A���ΐ�����߂��ė��āA�����ɍ����グ��̂͂����ꑽ������A�����̊ԁA�����_�Ђ̒r�ɕ����Ēu���Ƃ���ƁA����ʂ̂��̂ƍ��ʂ���ׂɂ́A����̊������Ēu���Ƃ������Ƃ��o���邩��ł���܂��B���ۋߍ��̂��Ђ̍Ղ�ɁA����ȗ��\�Ȃ��Ƃ��������ǂ����͒m��܂��A�Жڂ̋���߂��ĐH�ׂʂ��ƁA�H�ׂ�ƈ������Ƃ�����Ƃ��������Ƃ́A���������Â�������̏K�킵������������ł��낤�Ǝv����݂̂Ȃ炸�A�܂��b�ɂ͂��낢��c���Ă���܂��B�Ⴆ�ߍ](������)�̌ΐ��̓�̈�薾�_�ł́A���N�l�������̍Ղ�̑O�̓��ɁA�Ԃ������ē���̕���߂��A��͐_�O�ɋ����A���̈�͕Жʂ̗�(���낱)������Ă��܂��āA����x�ɕ����Ă��ƁA���N�A�l�������ɖԂɂ͂����ė������̂����A��͕K�����̕��ł���Ƃ����܂����B����Ȃ��Ƃ��o���邩�ǂ����^�킵�����A�Ƃɂ����ɖڂ��邵�����Ĉ�N�����Ēu���Ƃ����b�����͂������̂ł��B �܂��V��(�Ă�)�l�͋��̖ڂ��D�����Ƃ����b������܂����B���B�̊C�ɋ߂����n���ł́A�ĂɂȂ�Ɛ��c�̏�ɁA�镪�����̉������Ⴍ��т܂��̂����邱�Ƃ�����B�����V��̖�Ƃڂ��Ƃ����āA�R����V�炪�D�ӂ�߂�ɗ���̂��Ƃ����܂����B���̂��Ƃ������Ă��炵�炭�̊Ԃ́A�a(�݂�)�⏬��̓D�ӂɊ�̂Ȃ��̂��������������ŁA����͓V��l����̋ʂ������čs�����̂��Ƃ����Ă��܂����B����Ɠ����b�͉���̓��ɂ��A�܂������哇(���܂݂�������)�̑��ɂ�����܂����B����ł͂����ނ�Ƃ����̂��R�̐_�ł��邪�A�l�ԂƗF�����ɂȂ��ĊC�ɋ��ނ�ɍs�����Ƃ��D�ށA�����ނ�Ɠ��s���Ēނ������ƁA���ɑ����l��������A����������͂������̊Ⴞ��������āA���͎����čs���ʂ���A�傻���������悢�Ƃ����b������܂����B �܂��{�錧�̋��t�̘b���Ƃ����̂́A���؎R(������)�̉��łƂ�銏��(����)�́A�K�����̊Ⴊ���������A�ׂ�Ă���B����͊�������̕�������؎R�̂��Ђ̓����̉��������ĉj���ŗ��邩��ŁA���t�����͂�������̋��؎R�b�w(�܂�)��Ƃ��������ł���܂��B�K���Ƃ������Ƃ��낪�A��X���ׂČ��邱�Ƃ͏o������̂ł͂���܂���B�l�������v���悤�ɂȂ��������́A��͂�_�l�͕Жڂ����D���Ƃ������Ƃ��A�m���Ă����҂��������؋����Ǝv���܂��B ���ꂩ��܂��A���Ђ̍Ղ�̓��ɁA���̖ڂ�˂��ĕЖڂɂ����Ƃ����b���c���Ă��܂��B����(�Ђイ��)�̓s��(��)�_�Ђ̂��r�A�ԋʐ�(�͂Ȃ��܂���)�̗���ɂ͕Жڂ̕�������B��́A�؉ԊJ��P(���̂͂Ȃ�����Ђ�)�̐_���A���̂��r�݂̊ɗV��ł����łɂȂ������A�_�l�̋ʂ̕R(�Ђ�)�����ɗ����āA�r�̕��̖ڂ��т��A���ꂩ��Ȍ�Жڂ̕�������悤�ɂȂ����B�ʕR���Ə����āA���̎Ђł͂�����ӂȂƓǂ݁A����_�l�̐e�ނƂ����悤�ɂȂ����̂́A�����������R����ł���Ƃ����Ă���܂��B(�}���嗪�L�B�{�茧�b����(����)�S����k����) ����̉��R�̉��(����)�_�Ђɉ�(����)�Ă��A�̂܂��ȑO�̓y�n�ɂ��̂��Ђ����������ɁA�_�l�����̎p�ɂȂ��Č���(�݂��炵)�̐�ŁA�ʔ����V��ł����łɂȂ�ƁA�ɂ킩�ɕ��������Ċ݂̓��̎��������āA���̕��̊�ɂ��������B���ꂩ��s�v�c���N���Ė��̂�����������A�Ђ����̏��ֈڂ��ė��邱�ƂɂȂ����Ƃ��������`��������܂��B�_�̎p�Ƃ����͕̂ςȘb�ł����A���������̋��͌�ɐ_�l�̂��̂̈ꕔ�ɂȂ�̂ł�����A�グ�Ȃ��O���瑸�����̂ƁA�̂̐l�����͍l���Ă����̂ł���܂��B���ꂪ�܂��Жڂ̋����A������ĕ��ʂ̐H�ו��ɂ��Ȃ��������Ƃ̗��R�ł������낤�Ǝv���܂��B(�����_�Ў����B�ΐ쌧�b�͖k(���ق�)�S���������R) |
|
|
�̂̌��t�ł́A�������ċv�����ԁA�_�ɋ��������Ȃǂ��������Ēu�����Ƃ��A�����ɂ��Ƃ����Ă���܂����B�_�l���܂��܂������ݐ[���A�܂����������D�݂ɂȂ�ʂ悤�ɂȂ��āA����(�܂�)���Жڂ̋������Ђ̒r�̒��ɁA�j���V��ł��邱�ƂɂȂ����̂ł���܂����A����Жڂɂ���V�������́A�����ƌ�܂ł��s���Ă����̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv���܂��B��(�܂Ȃ�������)�ȂǂƂ������O�̕����A�܂�܂�͐_�Ђɋ߂��R��݂̊Ɏc���Ă��āA�����ł��������������悤�ɂ����Ă��܂��B����̋����r�Ƃ����r�ł́A���̂قƂ�ɑ傫�Ȑ�������āA����������Ɩ��Â��Ă���܂����B���̒r�̋��ނɂ��Жڂ̂��̂�����Ƃ����A���̐l�͂Ђł�̔N�ɁA�����ɗ��ĉJ��̂��Ղ�����������ł���܂��B(�|�˒ʎu�B�L�����b����(����)�S�_�c�����@)
���g�ł͕����̒J�̑�r�̒��ɁA���͋�\�ځA����̍����\�ڂ���̑�₪�����āA���̒r�ł�����n�߂Ƃ��A�����ȎG��(���Ⴑ)�܂ł��A�c�炸���ł���Ƃ����Ă��܂��B���̊�̖������ł͎ւ̖��ƌĂсA���֕����a(���̂�Ђ傤�Ԃǂ�)�Ƃ������m���A�̂��̊�̏�ɗV��ł�����ւ��˂āA���̊���ˊт��A��Ƃ��Ƃ��Ƃ����������(��)���Ď��ɐ₦���B���̑�ւ̂���݂��i����(�Ƃ�)�܂��āA�r�̋����������ЖڂɂȂ����̂��Ƃ����܂����A������܂���̘b�����э��������̂��낤�Ǝv���܂��B(���y������ҁB�������b�߉�(�Ȃ�)�S�x��������) ��ւƂ������̂́A�ނ�̒r�̎�̂��ƂŁA�Жڂ̌�́A���̍Ղ̂��߂̂����ɂ��ł���܂����B����Ƃ���E�m�����̐_�Ɛ���āA���߂ɏ����A��ɕ������Ƃ����̘b�ƁA�������ĐV�����`�����o�����̂����m��܂���B���������������r�̎�ɂ͌��炸�A�_�X�ɂ���̈�ӂ����Ȃ���������Ƃ������Ƃ́A���ɌÂ����炢���`���Ă�������ł���܂��B�ǂ����Ă���Ȃ��Ƃ��l���o�������͂킩��܂��A�����Ƃ����ꂪ�����ɂ��̊���Ēu�����Ƃ������ƂƁA�[���W�����邱�Ƃ����͂������ł���܂��B���ꂾ����A�܂��ڂ̈���̏������l�A��(���邢)�͂����߂̐l���A���ʂɐ_���爤������悤�Ɏv���҂��������̂ł���܂��B��ւ�����ʂ��Đl�ɗ^�����Ƃ����b�́A�O(�Ђ�)�����X�̘̐b�ɂȂ��čs���Ă���܂��B���̒��ł���O�̉����(����)�̕��߂ɂ�����̂́A���ƂɈ���ł܂������ƊW������܂�����A����������ɏo���Ēu���܂��B�̂��̎R�̘[�̂��鑺�ɁA��l�̎�l(����イ��)���Z��ł��܂������A���̉Ƃ֎Ⴂ�����������łɗ��܂��āA���ꂪ�ق�Ƃ��͑�ւł���܂����B�Ԃ�V������鎞�ɁA�̂����Ă͂����Ȃ��Ƃ������̂ŁA�������ĕs�R�Ɏv���Ă̂����Č��܂��ƁA�����낵����ւ��Ƃ���������āA����q������Ă��܂����B���ꂪ�܂����ɂȂ��ďo�ė��܂��āA�p������ꂽ��������s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�q�����������ɂ͂��̋ʂ���(��)�߂����Ă���ĉ������Ƃ����āA�����ʼnE�̊���Ēu���Ă��R�̏��A���čs���܂����B�����̂悤�ɑ�ɂ��Ă���܂������A���̕]���������Ȃ��ēa�l�Ɏ��グ���Ă��܂��A�Ԃ�V�������������ċ������ĂĂ��A�Ȃ߂����Ă�邱�Ƃ��o���܂���B���܂���Đe�q�̎҂��R�֓o��A���݂̊ɏo�ċ����Ă���ƁA�ɂ킩�ɑ�Q�������ĕЖڂ̑�ւ�����A���킵���b���Ďc�������̕��̊�̋ʂ��Ă���܂��B���ł�������ė��āA�q������ĂĂ��邤���ɁA���̋ʂ��a�l�Ɏ��グ���܂��B�����d�����Ȃ�����g�𓊂��Ď��̂��Ǝv���āA�܂��������ւ���ė��܂��ƁA���x�͖ӂ̑�ւ��o�ė��āA���̘b���Ĕ��ɓ{��܂����B���������Ђǂ����Ƃ�����Ȃ�A�������������Ȃ���Ȃ�ʁB��l�͑����ɂ��ĉ��X�Ƃ������ւ����łȂ����B�����ł͗ǂ�����Ⴄ���Ƃ��o���邩��Ƃ����āA�e�q�̎҂������ɕԂ��܂����B�������Ă��̌�ł����낵�����������āA�R������A�c���C�����܂����̂́A���̖ӂ̑�ւ̎d�Ԃ��ł������Ƃ����̂ł�(�}���얯�(�����݂̂�)�W)�B���B�̗L��(���肽��)���ł́A�V����̑�ւ��ɂ��Đ��ꂽ�q���A��̋ʂ����Ă���������ďo���������b���A�Â����炠�����悤�ł����A������Ƃ������Ƃ́A�����ł͂���Ȃ������Ǝv���܂��B(���]��(�Ƃ��Ƃ��݂̂���)���y�L�`) ���ɂ�����A�ڂ�������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�s�v�c�Ȃ��́A�܂�������ׂ����̂̂��邵�ł���܂����B���B�̕��ł́A��܂Ȃ��A�����ł͈�ڏ��m�ȂǂƂ����āA��̐^���Ɋ�̈���邨�������A�z������悤�ɂȂ����̂����̂��߂ł����A�ŏ����{�ł́A�Жڂ̕��̂悤�ɁA�����ڂ̕Е����ׂꂽ���́A���Ƃɂ킴�킴��̖ڂ��A��ڂɂ����͂̂��Ƃ��A����������A�܂��M(�Ƃ���)�݂����Ă����̂ł���܂��B�����猎�֕������A��ւ̊���ˊт����Ƃ����b�Ȃǂ��A���Ƃɂ��ƕʂɍ���O�̘b�������āA���̌�̗E�m�̂��킴�ɁA�ԈႦ�Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���(�Ђ�)�̔���(�͂����)�̒��̐z�K(����)�_�Ђł́A�����������`��������܂��B������O�S�N�]��ȑO�ɁA���X(���Ȃ���)�Ƃ̉Ɛb�����Z���q��Ƃ����������m(���ނ炢)������ė��āA��l�̖��߂����琥�̎Ђ̂��鏊�ɏ��z���Ƃ����āA��_�̂�ׂ�̑��֑J(����)�����Ƃ����B��������ƁA�_�`(�݂���)���d���Ȃ��ď������������A�܂���̑傫�Ȑ叫���A�Ђ̑O�ɂ킾���܂��āA�Ȃ�Ƃ��Ă��ނ��܂���B�Z���q�傱�̑�(�Ă�)�����đ傢�ɂ����ǂ���A�~�̐܂�}����Ɏ����āA�ւ������Ă��̍��̖ڂ���������A�ւ͉B�ꋎ��A�_�`�͎��̂Ȃ������āA��J�{�����܂��܂����B�Ƃ��낪���̏�̍H���̂܂��I��ʂ����ɁA���ɐ킪�N���āA�Z���q��͏o�čs���ē������������̂ŁA���̐l���������ŏ�̍H�����~�߁A�Ăт��Ђ����Ƃ̓y�n�}���܂����B���ꂩ���́A�܂�܂�Ђ̕��߂ŁA�Жڂ̎ւ�����悤�ɂȂ�A�����͂����z�K�l�̂��g���Ƃ����đ��h�����݂̂Ȃ炸�A���Ɏ���܂ł��̎Ђ̋����ɁA�~�̖͈�{���炽�ʂƐM���Ă��邻���ł���܂��B(�v�c(�܂���)�S���B���v�c�S������) |
|
|
���̘b�Ȃǂ������Z���q�傪����ė���܂ł́A�ւ̖ڂ͓�ŁA�~�̖͊��ł��������Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A�������߂邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���܂��B�����ƑO���炱�̒ʂ�ł������̂�Y��Ă��܂��āA���̎�����n�܂����悤�ɁA�l�����̂����m��܂���B�킴�킴�~�̎}�Ȃǐ܂��āA���������g�҂̎ւ̖ڂ�����������Ƃ������Ƃ́A�C�̒Z���E�m�̍��������A�������Ȃ��Ƃł���܂���B�������łȂ��A�_�l���ڂ�˂��āA���ꂩ�炻�̐A����A���Ȃ��Ȃ����Ƃ����`���́A�ӊO�Ȃقǂ�������܂��B���̌܂Z�������ŋ����Č��܂��ƁA���g�̈��c(���킽)���̊���(���炬)�喾�_�̎Ђł́A�̂��鑸��������A���̊C�݂ɑD������Ȃ��ꂽ�܂�ɁA�Ђ̒r�̕���ނ�ɁA�n�ɏ���Ă��ł����ɂȂ����Ƃ��낪�A���n�̋r�����̖�(��)�ɂ���܂��āA�n���܂������̂ŗ��n�Ȃ���A�j�|(������)�ł��ڂ�˂��Ă��ɂ݂͂͂����������B����̂ɍ��ɂ��̎Ђ̐_�ɂ͊�̕a���F��A���q�̎l�̕����ł́A�r�ɂ͕����Z�܂��A�M(���)�ɂ͒j�|���������A�n��u���ƕK�������肪����Ƃ����܂����B(���̗���B��������S�b�k��(�����Ȃ�)�����c)
���Z�̑��c�ł́A���_�̉��Ό���(�����������ʂ�)�_�Ђ̐_�l���������ɂȂ�Ƃ����āA�܌��̐ߋ�ɂ��A���Ƃ���(���܂�)�����܂���ł����B��́A���Ηl���n�ɏ���āA�킢�ɍs���ꂽ���ɁA�n���痎���Ĕ�(������)�̗t�Ŋ�����˂��Ȃ��ꂽ�B����̂Ɏ��q�͂��̗t������ŁA�p���Ȃ��̂��Ƃ����Ă���܂����B(���y�����l�ҁB�����ΌS���c��) �M�B�ɂ́A���Ƃɂ��̘b�������`�����Ă��܂��B�����S�b����(�Ƃ�����)���̒���́A���߂ċ��s���炨����̎��ɁA�ӉZ(���イ��)�̖��Ɉ����|���Ă����ŁA�Ӗ�(����)�̌s�Ŗڂ����˂��Ȃ��ꂽ�Ƃ������ƂŁA�S�����ɌӖ����͔|���܂���B�������̋ւ�Ƃ��҂�����A�K����̕a�ɂȂ�Ƃ����Ă��܂��B���{�s�̕��߂ł��A�{���̐��ɑ���(��������)�_�Ђ̎��q�́A���~�Ɍ����ČI�̖�A�����A�A���Ă������̖��h����悤�ł�������A���̉Ƃ͔��ɐ����čs���B����͎��_���̂��̒n�ɂ��~��̎��A�����Ŗڂ�˂��ꂽ���炾�Ƃ����̂ł��B�܂�����(���܂���)���̎O�̋{�̎��q�̒��ɂ��A�_�l�����̗t�Ŗڂ�˂��ꂽ����Ƃ����āA�����ɏ��𗧂ĂȂ��Ƃ�����܂��B����(�͂����Ȃ���)������ł��A�����͖叼�̑��ɁA���̖𗧂ĂĂ���܂��B�́b����(�����߂�)�l�Ƃ����̂��Վ҂���ɗ��Ă��āA�叼�Ŗڂ�˂��đ傫�ɓ�V�������B���ꂩ����������ɗ��Ă�悤�ł�������A���̉Ƃ͉Ύ��ɂ������Ƃ������̂ŁA�������Ė��𗧂Ă邱�Ƃɂ����̂������ł��B(����܌S���B���쌧����܌S���ܑ�) ���J�l�ӑ�(�����肵������)�ɂ��A�Ӗ������ʂƂ��������͑����B���_���ڂ����˂��ɂȂ����Ƃ����A�܂��͋����č͔|����҂͊��a��ŁA�˂����悤�ɒɂނƂ������܂����B���y(�Ȃ���)�̕�[�Ƃ������ł͒�������炸�A�܂����݂̖�A���܂���B����͑��̑������̉Ƃ̐�c���A���̖��ɂ܂����āA���݂Ŋ�����������Ƃ����邩�炾�Ƃ����Ă���܂��B(���J����W�B���쌧�k���܌S���y��) ���㑍(�Ђ���������)�̏���(������)�A�������̗������ł́A�̂��猈���đ卪���͔|���ʂ݂̂Ȃ炸�A���܂��ܘH�T(�݂���)�Ɏ�������̂����t���Ă��A�����Č�b�F��(���Ƃ�)�����邭�炢�ł���܂����B���̑��X�ł��A�����̕c���̉Ƃ����́A��l�ɑ卪�����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B������������_���卪�ɂ��܂����āA�]��Œ��̖Ŗڂ�˂��ꂽ�������Ƃ����܂����A����ɂ��Ă͒��̖̕����A�Ȃ�Ƃ�����Ȃ������̂����ł���܂��B(�쑍�V�ۑ�(�Ȃ��̂肼��)�B��t���b��(������)�S�璬������) �����n���ł��A����(�ق���)�̈��(����)���Ȃǂ́A���_�l���|�Ŗڂ�˂��āA�������ׂ��Ȃ��ꂽ����Ƃ����āA���ł������Ē|�͐A���܂���B�|�̓���p������ƎR���z���āA�o�_(������)�̕����甃���ė��邻���ł��B(���y�����l�ҁB���挧����S��ꑺ) �ߍ]�̊}�D(�����ʂ�)�̓V�_�l�́A�n�߂Ă��̑��̖���(��������)�̒��ւ��~��Ȃ��ꂽ���A���Ŗڂ�˂��ĂЂǂ����ɂ݂Ȃ��ꂽ�B����̂ɍs�����킪���q�����҂́A�Y��Ă����͍��ȂƂ������r(���܂�)�߂ŁA���Ɉ�l�Ƃ��Ă���ɂ��ނ��҂͂Ȃ������ł��B(�k�쎏�B���ꌧ�b�I��(���肽)�S�}�D���쌴) �܂�����(������)�S�̐썇(���킢)�Ƃ������ł́A�̂��̒n�̗̎�͈�b�E�ߑ��v(�����䂤)�Ƃ����l���A�ɐ��̓팴(�����͂�)�Ƃ������Ő�(������)�����āA�����̒��œ����ꂽ����Ƃ������R�ŁA���Ƃ͑����Ŗ������͍��Ȃ������Ƃ������Ƃł��B(�����S���B���ꌧ�����S���쑺�썇) �֓��n���ɗ���ƁA����(������)�̏���(���Ȃ�)�Ƃ������ł́A�o(����)���͔|���邱�Ƃ����܂��߂Ă���܂����A���������̐l��(�ЂƂ܂�)�喾�_���A�܂��l�Ԃł��������ɁA������ď����A�����ė��Ă��̑��̋o���̒��ɉB��A���͂̂��ꂽ���A�o�̂���ŕЖڂ��Ԃ��ꂽ�B����̂ɐ_�ɂȂ��Č���A���̍앨�͂��D�݂Ȃ���ʂƂ����̂ł���܂��B(���h(����)�j�B�Ȗ،����h�S���쑺����) |
|
|
���̋߂��̑��X�ɂ́A��ɏo�Ėڂ��˂�ꂽ�E�m�A���̖ڂ��r(����)�����������A���ꂩ��R���̉H�̐�(��)�����炤�b�Ȃǂ����Ƃɑ����̂ł����A���܂蒷���Ȃ邩������~�߂āA���̎����͑��̏Z�����A�_�l�̂������ɕЖڂɂȂ�Ƃ����b���������Č��܂��B�������̓y��(����)�́A��ȎR(�����܂���)�̘[�ɂ���悢����ŁA�O�@��t����𗧂Ă����ȏ��ł����A���ɂ͑��q���������āA�Ⴋ���q�l�̖ؑ����J���Ă���܂��B�̂��̑��̎�l���A����ǂ��|���đ�̉��ɂ͂����čs���ƁA�ӂ��ɑ��ނ�̊Ԃ���A�����čs�������čs���Ƃ����������܂����̂ŁA�����˂Č���Ƃ��̂����ł���܂����B�����Ă��������w�ɕ����ċA���ė��悤�Ƃ��āA�r���ł������̖��ɂ���܂��ē|��A�����͉���������ɁA���q�l�̖ڂ��Ӗ��b�b(����)�œ˂����Ƃ������ƂŁA�����Ă��ؑ��̕Жڂ���A�������ꂽ�悤�Ȃ��Ƃ����邻���ł��B�������Ă��̑��ɐ��ꂽ�l�́A�N�ł���������Жڂ��ׂ��Ƃ����b������܂������A���̍��͂ǂ��Ȃ��������͂܂������Ă��܂���B(�M�B�ꓝ���B�������M�v�S�y����)
��̑傫�������������łȂ��l�́A�v���̊O�������̂ł����A���͒N���Ȃ�Ƃ��v���Ă��Ȃ��̂ł��B���ɂ���Ă͐̒��炳�܂��ׂ�̑��ƁA��������Ėڂ�����Ȃ��ꂽ����Ƃ������Ƃ��A�q�����肪���`���Ă��鏊������܂����A���͂����Â��b��Y��Ă��܂��B����ł��y���̂悤�ɁA���ۂ��������䑜���c���Ă���ꍇ�����́A�ԈႢ�Ȃ�����܂��o���Ă���ꂽ�̂ł���܂��B�O�͂̉��R�Ƃ������ł́A�Y�y�_(���Ԃ��Ȃ���)�̔���(����Ƃ�)�Z�Ђ��܂̌�_�̂��Жڂł���܂����B����̂ɂ��̑��ɂ́A�ǂ����Жڂ̐l�������悤���Ƃ������Ƃł���܂��B(�O�B���R�b�B���m���b��݊y(�݂Ȃ݂�����)�S�b����(�Ȃ�����)������) �Ώ�(���킫)�̑�X�Ƃ������ł́A��n(�ɂ킽��)�_�Ђ̌�{���́A���Ƃ͒n���l�ŁA���ɔ������p�̒n���l�ł������A�ǂ������킯���Жڂ������������Ă���܂����B���ꂾ�����X�̐l�͒N�ł��Жڂ��������ƁA���̒��ł����������Ă��邻���ł��B(������ҁB�������Ώ�S��Y����X) ���ꂩ��܂����S�̂łȂ��Ƃ��A���ʂɊW�̂���A�����Ƃ̎҂������A��X�Жڂł������Ƃ����b�͕��X�ɂ����āA�O�ɂ������b�B�̎R�{�����̉ƂȂǂ͂��̈�ł���܂��B�O�g�̓ƌ؝e�R(�Ƃ����Ȃ����)�̊ω����܂͕Жڂł���܂����B�̂��̎R�̒���̊ω���̏�ŁA�ω����������̎p�ɂȂ��ėV��ł�����̂��A�[�̊`��(�����͂�)���̉����Ƃ����Ƃ̐�c���A�����Ƃ͒m�炸�ɋ|�Ŏ˂��Ƃ��낪�A���̐������傤�ǔ��̊�ɒ�(����)��܂����B���̓H��̐Ղ����čs���ƁA���ꂪ���̌䓰�̉��ɗ��āA�~�܂��Ă����̂ŋ����܂����B���ꂩ�炱�̉Ƃł͎q����X�̎҂����a�݁A���܂��܌Z���|���˂�A�K����̊�ɒ���Ƃ����āA�i���|��̂킴����߂Ă��������ł���܂��B(���O�g����W�B���s�{��K�c�S�b�B�c��(�Ђ�����)���`��) �H��(����)�̒j��(����)�����ł́A�k�Y�̎R��(����̂�)�l�̐_��|���O��̉ƂɁA��c����܂ł̊ԁA��X�Жڂł������Ƃ����`�����c���Ă��܂��B���̉Ƃ̌��c�|����ܘY�͋|��(��݂�)�̒B�l�ł���܂����B���Y���̎唪�Y�������A�~�ɂȂ�ƌˉ�̈�̖ڊ��ɗ��ďZ�����Ƃ���̂��A��ڊ��̕P�_�ɗ��܂�āA�����R(����Ղ�����)�̗�(�݂�)�ɑ҂����������āA�˂Ă��̕Њ���������Ƃ������Ƃł���܂��B��������Ɣ��Y�_�͉_�̒�����A���̐��𓊂��Ԃ��Ė�ܘY�̊�ɂ��������Ƃ������A�܂��͂��̖�̖��Ɍ���āA����̊Ԃ͊���ɂ���ƍ������Ƃ������āA�Ƃɂ����ɖ�ܘY�_��̎q���̉Ƃł́A��l���K�������߂ł����������ł��B(�Y���������B�H�c����H�c�S�k�Y��) ���̒|���_��̉Ƃɂ́A�_�̊���˂��Ƃ������̍����A�ɂ��Ď����`���Ă���܂����B�_�ɓG���������Ƃ��āA�Жڂ��������Ƃ������Ƃ��ԈႢ�łȂ���A���������L�O�i��ۑ����Ă����̂��ςł���܂��B�_���Жڂ̋�������тɂȂ����悤�ɁA�ق�Ƃ��͕Жڂ̐_�傪�A���D���������̂ł͂Ȃ��낤���Ǝv���܂��B ��B(�₵�イ)�썂�����̎����_�ЂȂǂł́A�_���c�Ƃ̐�c���A�r���ʍc�q(�����͂�킯������)�Ƃ������ł������Ƃ����Ă���܂��B���̍c�q�͊֓����䗷�s�̊ԂɁA�a�̂��߂Ɉ���̖ڂ��āA���ꂪ�ׂɓs�ɂ��A��ɂȂ邱�Ƃ�������Ȃ������B����ł��̑��ɗ��܂��āA�_��̉Ƃ������ĂɂȂ����Ƃ����̂ł���܂��B(����_�Љ��v���B�Ȗ،��b�F��(�͂�)�S�R�O���썂��) ���B�̑���(������)���́A���q���ܘY�i�����A��O�N(������˂�)�̖�(����)�̎蕿�ɂ���āA�q�̂����̒n�ł������Ƃ����āA���̌��(����傤)�_�Ђɂ͌i�����J��A���̎q�����Ə̂��鑽�c��Ƃ��A��X�܂ł��Z��ł���܂������A�����ł����ܘY�̊���˂�ꂽ�����������āA���ɐ��ꂽ�҂́A�����������̖ڂ������������߂��Ƃ����Ă��܂����B�����������߂Ƃ����̂́A����̖ڂ����������Ƃł��B�̕������̕��̒����Ȃǂ��A�u�ɐ��̕����͂����߂Ȃ�v�Ƃ����āA��ꂽ�Ƃ����b������܂����A�E�m�ɂ͕Жڂ̂����������l�͊�������܂����B�������Ď��ɂ���Ă͂���������ɂ��Ă����炵���̂ł���܂��B(�����W�B�������b����(������)�S���c�쑺)�@ |
|
| ���@�D���O | |
|
�z��̎R���̑�ؘZ(�������낭)�Ƃ������ɂ́A�����Ő_������Ă����ז�(�ق���)�Ƃ������ȋ��Ƃ������āA���̎�l���܂���X�����߂ł���܂����B�̂��̉Ƃ̐�c�̖�E�q��Ƃ����l���A����Ă̓��ɍ����̎R�֎��ɍs���ĘH�ݖ����A���̊��@(�܂��͂�)�R�ɓo���Ă��܂��܂����B���̎R�͎��ؐ[����������A�߂����܂ł��_�̎R�Ƃ����āA������Đl�̂͂���ʎR�ł���܂������A��E�q��͂��̐[�R�̒��ŁA���ɂ����������P�l�̋@�������Ă���̂����������̂ł���܂��B�����ė����Č���ƁA�������猾�t�������āA�����͐l�Ԃ�����A�邱�Ƃ̏o���ʏ��ł��邪�A���̕��͎d�����҂ŁA�������Ă킪�p�������B����ł��ꂩ�痢�ɉ����āA�i���ꑺ�̒���Ƃ����J(�܂�)���悤�Ǝv���B�}���ł����ĎR���~��čs���A�������ĕK��������Ԃ��Ă͂Ȃ�ʂƂ����܂����B���̒ʂ�ɂ��ċA���ė���r���A�ɔw���Ďv�킸������x�����A����E�Ȃ��Ĕw���̐_�l�����悤�Ƃ��܂��ƁA��(������)�������߂ƂȂ��Ă��܂��āA���ꂩ��Ȍケ�̉Ƃ����j�q�́A��(���Ƃ���)������̖ڂ��ׂ��Ƃ������Ƃł���܂����B���ł������������Ƃ����邩�ǂ����A���͍s���Đq�˂Č������Ǝv���Ă��܂��B(�z���u�Ɖ��̔V�x(���̂�����)�B�V�����b�싛��(�݂Ȃ݂����ʂ�)�S���V������ؘZ)
��ؘZ�ł͂��̕P�_�����@�����ƂƂȂ��āA�������������đ��̒���Ƃ��čՂ��Ă���̂ł���܂����A�y�n�ɂ���Ă͐_�𗢒��ւ��}���\�����Ƃ������A���Ƃ���̏ꏊ�ɂ����炩�炨�Q������āA�q��ł��鑺�������������܂��B��������ƎQ�q���鎞�Ɛl�Ƃ����ꕪ��ɂȂ��āA���Ƃ��炠�����`��������ɕς��ė���̂ł���܂��B����ŎR�̐_�l�����ł������B�����Ȏq��A�ꂽ�W�_(������)�ł������Ƃ������ƂȂǂ��A��ɂ͖Y��Ă��܂����Ƃ��낪�����Ԃ�܂�����ǂ��A�ǂ�������Ƙb�̑�ȋؓr(�����݂�)����A���܂ł�������o���Ă��Ȃ���Ȃ�ʏꍇ������܂����B�Ⴆ�ΐÂ��ȒJ��̕�(�ӂ�)�̒��ŁA�@��D�鞈(��)�̉��������Ƃ����A�܂��͐l���s�����Ƃ��o���ʂ悤�ȕ�̊�ɁA�z���ق����̂�����������Ƃ����Ȃǂ͂���ŁA����������(������)�͒j�����܂���A���ׂ̈ɎR�W�R�P�̂����`���͂Ȃ��i���c��̂ł���܂��B ��ɎR�W�͌����Ƃ���͋��낵������ǂ��A���̐l�ɂ͎����Đe�ł����āA�R�H�ɖ����Ă���Ƒ����Ă����B�܂����肨��͑��ɍ~��ė��āA�@�D�蒗��(����)�݂���`���Ă����Ƃ����b������܂����B�܂��d�����̍D���l�́A�R���ɂ͂����āA�R�W�̒����˂Ƃ��������E�����Ƃ����܂ɂ���B���̎��͂�����g���Ă��s���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ������܂����B�܂��R�W���q����Ă�Ƃ����b���A�����đ����R(����������)�̋����Y����ł͂���܂���B �ȑO�͂ǂ��̍��̎R�ɂ��R�W�������炵���̂ł����A���͂킸�������b���c���Ă���ʂ̂ł���܂��B�������Ă��̎R�W�����Ƃ͐��̒�ɋ@��D��_�ƈ�ł��������Ƃ́A�m���Ă���҂��w�ǂȂ��Ȃ�܂����B����̉��O��(�����݂Ԃ�)�́A���낵���������邩��o�������̖��ŁA�����݂Ƃ͑�ւ̂��Ƃł���܂��B���̎R�̉��ɂ͍������]�������₪�����Ă��āA���̖����R�W�̕z�N(�ʂ̂���)����Ƃ����A���X���̊�̂Ă���ɂ́A�������̂��|�����ĂЂ�߂��Ă��邱�Ƃ�����Ƃ����܂����B(�|�˒ʎu�B�L�����b�o�O(�ӂ���)�S��ؑ����O��) ������(���Ȃ̂���)�̎R���̑��ɂ��A���ɑ�U��(��������)�ȎR�W�̘b������܂����B�I�J(���肽��)�̕z�N���₩��A����ƕ�����(�܂�)�̗��Ċ�A���k(�₾��)�̓�(���)���̎O�̑��ɂ����āA�͎̂R�W���z���Ċ����Ă����Ƃ����܂����B���̊Ԃ����������܂��B�܂����k�̑��̐��ɂ́A�R�W�̊D�`�h(������)���Ɖ]�������ȒJ�������āA��̊Ԃɂ͂����D�`�̐F�������������܂��Ă��܂��B���̐��ł��̎R�W���z���N���Ă����Ƃ����̂ł���܂��B(�����u�B���挧����S���������I�J) ���������b���q���܂ł��A��������Ă����悤�ɂȂ�܂��ƁA����Ɠ`���������炵���Ȃ��ė��āA�R�̕��ꂽ�Ƃ�����R�W�����������Ղ��Ƃ�������A���ւ��������Ƃ��ȂǂƂ����b���o���ė��܂��B�y���̔B��(�ɂ낤)�̎R�̒��Ȃǂł́A��Ɏ��R�̍a(�݂�)���o���Ă���̂��A�̎R�W����������Ă�����(����)�̐Ղ��Ƃ����܂����B(��H�u�B���m���b����(������)�S��B�����b����(��Ȃ���)) �t�ɂȂ�Ǝq�������b��(��)��������̂ɁA�u�R�̐_��������v�Ƃ����Ƃ��������A�܂��u�R��ڕ�������v�Ƃ����Ă���y�n������܂��B���ł͎R�W�͏��N�̒m��l�̂悤�ɁA�Ăт������Ă���̂ł���܂��B����[���ȂǂɎR�̕��������āA�傫�Ȑ��ʼn�����߂��ƁA���ɂ�����ł����܂˂�����̂��A���ʂɂ͂����܂Ƃ����܂����A����͎R�W�����炩���̂��Ǝv���Ă����q��������܂����B�����܂Ƃ����̂��R�̐_�̂��Ƃł�����A���Ƃ͂���������Ƒz�����Ă����̂ł���܂��B �R�W�͏����Ӓn�����B�����q���̂��₪��l�ȁA�ɂ��炵�����������悭����Ƃ����āA���܂Ⴍ�Ƃ������t���A�f���łȂ��q�̂����Ȃ̂悤�ɂȂ����̂��A�ق�Ƃ��͂��̔������n�߂Ȃ̂ł���܂��B�O�ɉW���r�̘b�ł������悤�ɁA���܂�����܂���W�_���܂̂��Ƃł���܂��B�����̂悤�ȎR���牓���y�n�ł��A�̂͗[�Ă����Ă̂��Ƃ��u���܂g(�ׂ�)�v�Ƃ����Ă���܂����B�V�������قǂ��^�ԂɂȂ�̂��A�ǂ����ŎR�̑受���A�g��n�����Ă���̂��Ƃ����Ă���ނꂽ�̂ł���܂��B |
|
|
���̎R�W���@��D�����Ƃ����b���A�܂����낢��̌`�ɕς��ē`����Ă���܂��B���B�̏H�t�̎R���ł́A�R�W���O�l�̎q��ŁA���̎O�l�̎q�����ꂼ��傫�ȎR�̎�ɂȂ��Ă���Ƃ����A���̎R�W���܂����߂��֗��āA���̂قƂ�ŋ@��D���Ă����Ƃ����܂����B�H�t�R�̂��Ђ��班����̕��ɁA�[����˂�����܂��B���̎R�ɂ͂��Ɨǂ��������Ȃ������̂��A��N�]��O�ɐ_�傪�_�ɋF���āA�n�߂Ď���������˂��Ƃ������ƂŁA���̐�̖����@�D�̈�Ƃ����̂́A���̌㉜�R�ɎR�W���v�ǎx(���炫)�R����o�ė��āA���̂������ɏZ��Ő_�l�̈�(����)��D��A��������[���Ă���������A���̖��ɂȂ����̂��Ƃ��������ł��B�������������`���̂����˂́A�܂����̋ߕӂ̑��ɂ�����O������܂��B(�H�t�y�Y�B�É����b���q(���イ��)�S�������b�̉�(��傤��))
�H�t�̎R�̐_�͑��ɎO�ږV���܂Ə�(�Ƃ�)���āA���ł��Γ��h���_�Ƃ��Ĕq��ł���̂́A�����������̋M������A�x�z����_�ł���������ł��낤�Ǝv���܂��B�R�W�Ƃ��̎O�ږV�l�Ƃ́A��ʂ�Ȃ�ʐ[���W���������̂ŁA���̂��߂��R�̉W�����ĐD�����Ƃ����̂��A���ꑊ���ȗ��R�̂��邱�Ƃł����B���B�����̌��̕���(�����܂�)�Ƃ������́A��ɒz�n(����)�֎����ė����P(����)�̉W�̐Α��̂������Ƃ���ł����A���̋߂��ɂ���o�R�H�t��(�����Ƃ�������)�Ƃ������������āA���̍����炩�O�ږV���}�����J���Ă��܂��B���̎��ɂ����ɂ킫�o�����Ƃ�������������A���̒�ɂ͓�̋ʂ��[�߂Ă���Ƃ������āA�J��̍Ղ�������ł��܂����B�O�S�\�N�قǑO�ɁA�����ւ���l�̉W�����ĕz��D�������Ƃ�����̂ŁA��˂̖����@�D��̈�ƌĂт܂����B���̕z�ɌܕS���̋���Y���Ď��ɂ�����A�W�͂�����ւ��s���Ă��܂��܂����B���̑K�͉i�����̎��̕ƂȂ��Ă̂���A�z�͘a��(�����傤)�����ʂƂ��ɒ��čs�����Ƃ������Ƃł���܂��B(�����b赎u(������)�B�_�ސ쌧�b������(�������炵��)�S�b��E(��������)������) ���ł��W�_�͏�ɋ@��D���Ă����邪�A�����l�Ԃ̖ڂɂ͕��ʂ͌��邱�Ƃ��o���ʂ̂��Ƃ����Ƃ��낪����܂��B�M�B�̏��{���߂ł́A�l���a�C�ɂȂ��Đ_�~(���݂���)���Ƃ����҂ɍl���Ă��炤�ƁA���_�̂����肾�Ƃ����ꍇ�����������ł���܂��A���_�l�����̏�ɌܐF�̎���(��)�āA�@��D���ėV��ł�����̂��A�m�炸�ɔ�э���ł��̎�������艘�����肷��ƁA���𗧂ĂĂ�����Ȃ���̂��ƁA�z�����Ă���l���������̂ł���܂��B���ꂪ�ׂɎ��X�͏����ȗ���݂̊ȂǂɁA�䕼(���ւ�)�𗧂ČܐF�̎����čՂ��Ă���̂��A�������邱�Ƃ��������Ƃ����b�ł��B(���y�������) �ˉB�̎R�̘[(�ӂ���)�̐���(������)��݂̊ɂ́A�@�D��Ƃ����傫�Ȋ₪�����āA���̘e�ɂ͞���(�Ђ���)�A⫐�(��������)�A���m�u�w�v�́u���v�ɑウ�āu�v�n��(�����肢��)�ȂǂƁA���낢��@����Ɏ����`�̐�����܂����B�J���~�낤�Ƃ���O�̍��́A���̐̂�����ł��炩��Ƃ�����������̂��A�_�l���@�����D��ɂȂ�Ƃ����������ŁA���̉�����������Ƃǂ�Ȑ��ꂽ�����܂�A��O���̂����ɂ͕K���~��o���Ƃ������̂́A���炭���Ƃ����ʼnJ������Ă�������ł���܂��傤�B(�M�Z��^�B���쌧�b�㐅��(���݂݂̂�)�S�b�S����(���Ȃ�)���≺) �ؑ]�̖�w�r(��Ԃ̂���)�Ƃ����̂��Ђł�̔N�ɁA���̐l���J��ɍs���r�ł���܂����B���̒r�ł͎�����R�W�����̏�ŁA�@��D���Ă���̂������҂�����Ƃ����܂����B���̎R�W�͂��Ƒ匴�Ƃ������̕S���̏��[�ł������̂��A�����t�����p�������āA���܂��ɉƂ��яo���ĎR�W�ɂȂ����Ƃ����܂��B��(���邢)�͂܂��˂��Ă������̏��r�݂̊ɂ����Ēu���āA���̒��ւ͂����Ă��܂����Ƃ����b�������āA���̂�����ɖ��̖���������ɖ��Ă���̂��A�R�W�̏���o���đ傫���Ȃ������̂��Ƃ������Ă��܂����B(�ؑ]�H�����}��B���쌧�b���}��(�ɂ�������)�S���`���{�a) ���̒ꂩ��@��D�鉹���������ė���Ƃ����`���Ȃǂ��A�y�n�ɂ���ď������͘b�������ς��Ă��܂����A�T���Č���Ƃ��������̑傫�Ȑ����ɁA�����悤�Ȃ����`��������܂��B�H��(����)�̓��̑�̔�����ł́A���̐_�l����ɋ@��D���Ă�����̂ŁA�镪���͂��Â��ɂȂ�A���ł����̉������̕��̕����炫������Ƃ����܂����B(��V�O�c���B�H�c���k�H�c�S�b���m��(���ɂ���)��) ���(�Ђ�)�̖�a��(���ǂ킳)��̗��{�����Ƃ����Ƃ���ł́A�̂͗��{�̉��P�̋@�D�鉹���A���т��ѐ��̒ꂩ�炫�����Ă������̂ł������B���ꂪ���鎞��l�̂�������҂������āA�n����(���肪��)�����̕��ւق��荞��ňȗ��A�����肻�̉����������Ƃ��o���Ȃ��Ȃ����Ƃ����܂��B�_��̓V�̊≮�˂̕���ɂ��A���ʂ������̂���b�ł���܂��B(�v�c(�܂���)�S���B���v�c�S�㌴����a��) �̂͑��X�̂��Ղ�ł��A���N�V���ɐ_�l�̈ߕ����Ă������\���Ă����悤�ł���܂��B���ׂ̈ɂ͍ł��q(������)������ŁA�����������l���𗣂ꂽ������̂قƂ�ɁA�@�a(�͂��ǂ�)�Ƃ������̂����ĂĎႢ�������ɁA���̑�ȕz��D�点�Ă������Ǝv���܂��B���̕�������ɂ��ŁA��ɂ͐_�̂������̏��_���A���̖�ڂ��Ȃ���悤�ɍl���ė��܂����B���̂킯�������킩��Ȃ��Ȃ��āA���܂��ɂ͗��{�̉��P�l�ȂǂƂ������ƂɂȂ�܂�������ǂ��A�����ł�������@�̉��͗��{�̂��̂łȂ��A�ŏ�����y�n�̐_�l�̌�p�ł���܂����B���傤�ǕЖڂ̋�����(��)����(�ɂ�)�̂������炨����h��ꂽ�悤�ɁA��X�_�̌�g�ɂ��z�ł���̂ɁA���̋@�̉��̂���Ƃ���ւ́A�����̐l�̕z��D��҂́A�͂����ċ߂��ʂ悤�ɂ��Ă����̂ł���܂��B���܌���ƌ��̊Ԃ́A�����̏��͋@��D���Ă͂Ȃ�ʂƂ������܂��߂�����A�����Ƃ��҂��������������鑺�͍��ł�����܂��B |
|
|
���|(����)�̌���(��������)�Ȃǂ́A���̐_���P�_�ł������ׂ��A�͓̂��̓��ŋ@�𗧂Ă邱�Ƃ���ɋւ����Ă���܂���(�I��[����L)�B�܂��@����������Ă���r�̑���ʂ��������A�����Ď��Ƃ����b�����̑��X�ɑ����̂��A���ׂ̈��Ǝv���܂��B
�ዷ�̍��g�R(���ɂ悵���)�̘[�̋@�D��r�Ȃǂ��A���͂������萅�c�ɂȂ��Ă��܂��܂������A�O�ɂ͐��̒�����@�D�鉹����������Ƃ����܂����B�܂����̒r����r�ł��������A��l�̏����@�̓���������āA�r�̕X�̏��n�낤�Ƃ����Ƃ��낪�A�X������Đ��ɂ͂����Ď��B�@�D�P�_�ЂƂ����̂́A���̏��̗���J�����̂��Ƃ����Ă��܂����A����͑����v���Ⴂ�ŁA���̕P�_�̎Ђ�������̒r������A����ȋ��낵���b���o�����̂ł��낤�Ǝv���܂��B(�ዷ�S���u�B���䌧�b�O��(�݂���)�S�R������K) ��������X�ɕ��������b���A�ߍ]�̔�鍳(�Ђ₵��)�̒r�ɂ���܂��B���Ƃ͂��̒r�ɂ͐��������āA�ǂ�����悢���Ɛ肢�𗧂ĂČ���ƁA��l�̏����Ȃ���r�̒�ɖ��߂āA���̐_���J��Ȃ�A�����Ɛ������Ƃ������Ƃł���܂����B���̎��ɗ̎�̍��X�b�G��(�Ђł���)�̓����鍳��O���A����i��ł��̐l���ɗ����A�����Ă����@�̓���ƂƂ��ɁA���̉��ɖ��߂��܂����B���ꂩ��͉ʂ��Ă��������r��t����̂ŁA���ł���鍳�����_�Ə̂��ĐM�����Ă��܂��B�������Đ^�钆�ɂ��̒r�̘e��ʂ�l�́A�������̒ꂩ��@��D�鉹���������Ƃ������Ƃł���܂��B(�ߍ]�`�n�u��(�����݂悿����Ⴍ)�B���ꌧ��c�S�匴���r��) ���ꂪ�킴�킴�@����������āA�r�̒�ɂ͂����čs�����Ƃ����_�́A����O����̘b�̎c��ł��낤�Ǝv���܂��B��鍳�Ƃ����r�̖����A���Ƃ͂����낵���r�̎傪�����ׂ炵���̂ł����A���Z(�݂�)�̖鍳�r�̕��ł��A��͂肻����ւɉœ��肵�����҂̈���(�܂Ȃނ���)�̖��ł������悤�ɂ����Ă��܂��B�������������`���̘͐b�ɂȂ�Ղ��̂ł��B�̘b�̍ł��ʔ����������A�����ė��Č��т����Ղ��̂ł���܂��B �㑍(������)�̗Y��(����)�̒r�Ȃǂł��A�Ⴂ�ł���(���イ�Ƃ�)�ɂɂ��܂�A�@�̐D������C�ɓ���ʂƂ����Ă����߂�ꂽ�B����ō����Ă��̒r�ɐg�𓊂����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂����A�J�̍~����ɂ͐��̒ꂩ��A���ł����̉�������Ƃ��������͓`���ł���܂��B���Ƃ͂��̘b�͕K�����������r�̗Y�ւƊW���[�������̂��낤�Ǝv���܂��B(�쑍�T�ۑ��B��t���b�R��(�����)�S��a���R��) ���������̘̐b�̕��ł��A�����`���Ƃ������̂��Ȃ�������A�����͖ʔ����͔��W���Ȃ������̂ł���܂��B��̗�������ƁA�y���̒n����(���Ƃ��Ԃ�)��̉����A�s��(�Ȃ߂���)�Ƃ������ɂ͐[�����������āA���݂̊ɂ͈�̑�₪����܂����B�̂���l�����̊�̉��ɂ͂����Č���ƁA���̒�Ɍ��������Ă��̉��̕��ŁA������������(����)��D���Ă���̂������Ƃ����`��������܂��B(�y���B�S�u�B���m���y���S�\�Z���s��) ���̓`���͎�ɍO���S���ɍs���n���Ă���܂����A���͂���ɔ����ċC���̈����A�܂��͖����Șb�����`�����Ă���̂ł���܂��B �H��̏���(���₷)�̕s����(�ӂǂ�����)�̑��ł́A�̂��邫���肪�R�������̕��ɗ����A���ɂ͂����Ă�����������܂���Ă���ƁA�������邢���������ɏo���B��a�������āA���̒��ɂ��Y��(���ꂢ)�ȏ��̐l�����܂����B�R���͂����ɂ���Ƃ����Ă��̒j�ɓn���A��x�ƍĂт���ȂƂ���ւ͗���ȁB�����(���т�)�̐��������Ȃ����B����͎��̕v�̗��_�̐Q�����B���͐��̓a�l�̖������A���_�Ɏ���Ă��������o�����Ƃ��o���ʂƂ������Ƃ����b�B����ɂ͏����@��D���Ă����Ƃ����_���A�����łɗ����Ă���܂��B(��̓`���B�H�c���Y���S����) �Ƃ��낪���̂���������(�肭���イ)����̕��̘b�ł́A���҂̖��͐��̒�Ɉ�l�ŋ@��D���Ă���A��(�Ȃ�)�͂����Ƃ��̋@�̑�ɁA�������|���Ă������Ƃ������ƂŁA�������Ă����̐e�����ɐS�z������ȂƂ����`���������Ƃ����̂ł��B(����(�Ƃ���)����B��茧�b����(�����ւ�)�S������) �X�Ɋ��(���킵��)��{���̒��̋߂����̋@�D��O�̘b�Ȃǂ́A�܂���������ς��Ă��܂��B�̂���l����̗���ɏo�ČL(����)�����Ă��āA����܂��Ă���𐅒��Ɏ�藎�����B����ɂ͂����Ă������܂���Ă��邤���ɁA�Ƃ��Ƃ����{�܂ŗ��Ă��܂��܂����B���{�ł͔��������P�l��������l�A�@��D���Ă����Ƃ����܂��B�v�����҂��Ă����Ƃ���ւ悤���������łƂ����āA�傻���Ȃ��Ƃ莝���ł���܂������A�Ƃ̂��Ƃ��C�ɂȂ�̂ŁA�O���߂ɉɌ�(���Ƃ܂�)�������āA�����ɘH�܂ő����Ă�����āA���Ƃ̑��ɋA���ė��܂����B��������ƎO���Ǝv�����̂�������\�ܔN�ł������B���ꂩ��L�O�ׂ̈ɁA���̋@�D��O�̂��Ђ����Ă��Ƃ����b�ł���܂��B����������ɂ��܂��ʂ̂����`���͂���̂ŁA���͂��̂��Ƃ������ɂ��b���āA���������܂��ɂ��܂��B(�����W�B�������b���B(������)�S����) �@�D��O��D���Ƃ̌��c�̐_�Ƃ��āA�J���Ă���n���͑����̂ł���܂��B���̈�͔\�o�̔\�o�䁦�m�u���{�r�v�n(�̂ƂЂ�)�_�ЁA���̐_�l�͎n�߂Ĕ\�o���Ɍ�Z�̐_�Ƌ��ɂ�����Ȃ���A�_�l�̌�ߕ�������Č�ɁA���̋@������C���ɂ������ɂȂ����̂��A���͐D�(���肮����)�Ƃ������ɂȂ��āA�x�؉Y(�Ƃ��̂���)�̉��ɂ���B���̒n���̐D���Ǝ҂��A�B(�Ђ�)�̊�(����)��D���ɂʂ�̂́A���ƕP�_�l�̂������ł������Ƃ����āA���ł��l����\����̍�ɁA�B�����Ă��������邱�ƂɂȂ��Ă��邻���ł��B(�����_�Ў����B�ΐ쌧�b����(������)�S�\�o����) |
|
|
��B�̓ߐ{�ł͓ߐ{���̌��c�Ƃ��āA���D�r�̂������Ɉ��D�_�Ђ��Ղ��Ă���܂��B��́A�ٖ�(���Ă�)���҂Ƃ����l�����̈��P�ׂ̈ɁA���D�喾�_���}���ɗ����Ƃ����̂��A���̗��j�ł���܂����A���̑O�ɂ͋����悤�Ȉ�̊�k������܂����B���̒r�͍������S�\�N�O�̎R����ɖ��܂��āA�����Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂������A���Ƃ͗L���ȑ�r�ł������B���̍��ɒr�̎傪���������ɉ����āA�s�ɏ���Ă���l�̍ȂƂȂ�A����D���Ēǂ��ǂ��ɉƕx�݁A��ɂ͗��h�Ȓ��҂ɂȂ����B���鎞���̏��[�����Q�����Ă���̂��A�v�����Č���Ƒ傫�Ȃ�w�(����)�ł������B����𑛂����̂ň��̉̂��c���āA�w偂̏��[�͓����ċA�����B�������Ă���ȉ̂��c���čs�����Ƃ����̂ł���܂��B
���������Â˂ė�(����)�ꉺ��(������)�̓ߐ{�̂��Ƃ�̈��D��̂��� ����ŕv���A�Ղ�ǂ��Đq�˂ė��āA�Ăт��̒r�̂قƂ�Ŗʉ���Ƃ����b������܂��B�̂͂��̒n���̉P(����)�Ђ��̂ɂȂ��ĉi���`����Ă����Ƃ����܂�����A������܂��ߐ{�n���̓`���ł������̂ł��B(���앗�y�L�B�Ȗ،��ߐ{�S���H���k�ꎚ�b���J(���Ă�)) ���̉̂����{����(���ׂ̂����߂�)�̕ꂾ�Ƃ�����(����)�̗t�̌ς̘b�ƁA�������̂��Ƃ������Ƃ͒N�ɂ�����܂����A�ߐ{�̕��͎q���̂��Ƃ������Ă���܂���B�Ƃ��낪�A�̂̕���ɂ���ߐ{�̂��Ƃ�Ƃ����̂��A�������̂��Ђ̂�����J(���Ă�)�̂��Ƃł���Ȃ�A�����n���̌��̐_�l�A����P��O�͂��Ƃ͈�ł��낤�Ǝv���܂����A������ɂ͐e�q�̘b������̂ł���܂��B����P�l�͍��̔э�̉���̋߂��A�吴���̑����J���Ă���̂��ł��L���ŁA�y�n�ł͋@�D��O�̋{�Ƃ����Ă���܂��B���낢��̂����`���������āA��������v���܂��A���ł��悭�m���Ă���̂́A�H���R�̐_�l�b�I�q(�͂���)�̉��q�̌��N�ł����āA���q�̂��Ƃ����Ă��̍��ւ�����Ȃ���A�N���\�ɂȂ�܂Ŋe�n�����邢�āA�\��{������D�邱�Ƃ�l���ɋ����A��ɁA���̑吴���̒r�ɐg�𓊂��Ď��Ȃꂽ�Ƃ����̂ł���܂��B����͂Ƃɂ����ɁA�Ђ̑O�ɂ͍��E�̏��r�������Đ������Đ����A�������X�̐l�͌���D��A���̐D�藯�߂����̌�{�Ɍ��[����Ƃ������Ƃł���܂��B(�M�B��S�����B�������b�ɒB(����)�S�э㒬�吴��) ���̏���P�̏���Ƃ�����ɂ́A�����w�l�̋Z�|�Ƃ����Ӗ����A�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A���̏���쑺�̓��ɂ́A�܂��z��Ƃ��������������āA����P�������̐쌴�ɏo�āA����D��Ƃ���̕z���N�����Ƃ������Ă��܂��B���Ȃ킿�z��D��W�̐M�̕����A�p���Ă��̒n���Ɍ��D���̎n�܂���͌Â������悤�ł���܂��B��������Ə���P��I�q���q�̌��Ƃ����n�߂����R���A�����������ɂȂ�܂��B���Ȃ킿���q�̌�ߕ���������Ƃ��āA�������狤�X���J���Ă����̂��A��Ɍ��H�Ƃ�����ɂȂ��āA�Ɨ����Ă��̋@�D��O�������A�q�ނ悤�ɂȂ����Ƃ�������̂ł���܂��B�O�ɐ\������{���̋@�D��O�Ȃǂ��A�̎�̔��R����(�͂�����܂�������)�Ƃ����l���A���̒n�Ɏ���������A�V����~�����D�P�ɏo�����āA�������ď���ۂƂ����q�����ꂽ�B���̏���ۂ̎��̎��ɁA��̐D�P�͍ĂѓV�ɋA��A��ɂ��̎Ђ����ĂāA�J�邱�ƂɂȂ����ƁA�y�n�̐l�����͂����Ă���������(�����W)�A�b�͂܂��ߐ{�̈��D�r�̕��Ƃ��A��������߂��Ȃ��ė���̂ł���܂��B�����������ɍl���ė���ƁA�@��D��P�_�𐴐��̂������ɂ����Ĕq�̂��A���Ƃ͎Ⴂ�j�_�ɁA���N�V�����_�߂������グ�����ׂł����āA�ǂ��܂ōs���Ă���W�q�l�̐M�́A�݂̖��̂悤�Ɉ�̓`���̗���̋��A�����Ɏ����Ă���̂ł���܂��B�@ |
|
| ���䔢(���͂�)���� | |
|
�䔢��n�ʂɂ����Ēu������A����傫���Ȃ��āA��ɂȂ����Ƃ����b�����X�ɂ���܂��B
�����ł͌���(�ނ�������)�̌��(������)�_�Ђ̘e�ɂ��鑊��(��������)�̓�����̈�ŁA���{����l�ڂقǂ̏������(�ӂ��܂�)�ɕ���Ă��܂����A�n�߂͓�{�̖ł��������̂Ǝv���܂��B�Ђ̂����`���ł́A�́A���{����(��܂Ƃ�����݂̂���)�������Œ�k�P(���Ƃ����ȂЂ�)�����Ղ�ɂȂ������A���������ɂ�����̂���������ēy�̏�ɗ��āA����V���ו��Ȃ�A���̔���{�Ƃ���h����Ƌ����܂����B��������Ɖʂ��Ă��̔��ɍ������āA��ɂ͂���ȑ傫�ȖɂȂ����Ƃ����̂ł���܂��B���̓�̎}���l�p�ɂ����������̂��A���ł��Y������l�����������čs�������ł��B����������ɂ��ĐH�������Ă���A�K�����Y���y���ƐM�����l�������A�܂����̖̗t���(����)���Ĉ��ނƁA�u�a���̂����Ƃ������Ă���܂����B(�]�ˎu�ȉ��B�y���k�ꓙ) �܂��̊ω����̌�ɂ���������(���������傤)�́A�������������čs������������A����o���Đ����������̂��Ƃ��������`��������܂����B(����{�V�����؎��B�����s����) �����̂����̖́A����ȊO�ɂ��A�܂��֓��n���ɂ́A���������Ɏc���Ă���܂��B ����(�ނ���)�ł͂܂��y�C(�ǂ�)�̐_���l�̎Ђ̘e�̑吙���A���`�o�̌䔢�ł������Ɛ\���܂��B�`�o�͉ڈΒn(������)�֓n���čs���ȑO�ɁA��x���̑���ʂ��āA�����ɗ��ċx�e�������Ƃ�����̂������ł��A�������ĐÂ��Ȍ���(�݂ʂ�)�̕��i�߂Ȃ��璋�̐H���������Ƃ����̂ł���܂��B���̎��ɔ���n�ɂ����čs�����̂��A����č��̑吙�ɂȂ����Ƃ����Ă���܂��B(����{�V�����؎��B��ʌ��b�k����(����������)�S�b�卻�y(��������)��) �����̓���(�����)�S�ɂ͒֕�(���݂�)�Ƃ���������ӏ�����܂��B���̈�́A�䍑(�݂���)�̒֕��ŁA�����l�ڂ̒˂̏�ɁA�Â��ւ̖���{����܂��B����͐̐V�c�`�傪�A���̒n�ɐw����ĐH�����������ɁA�����Ɏg�����ւ̏��}�������Ēu�����̂��A��ɂ��̗l�ɐ��炵���Ƃ����`���Ă���܂��B(���ԌS���B��ʌ����ԌS�R����) ���܈�͎R���̖k�ׂ�̖k��Ƃ������̒֕��ŁA����͐V�c�b�`��(�悵����)���A�ւ̎}�ɂ��āA�����ŐH���������悤�ɂ����Ă���܂����A���傤�Ǒ����̎R�̒��ɁA�o���������߂��ɂ���̂ł�����A���Ƃ͈�̘b���ɂ킯�Ă����`�������̂ł���܂��B(�����B���S�b����w(���Ă���)���k��) ���ꂩ�炢�܈�O����(���Ƃ�����)�̌��(������)���A�q(��)�̌����R(������)�̓o����ɁA�ѐX���Ƃ�����{�̘V������܂��B����͎q�̐�(�Ђ���)�Ƃ����L���ȏ�l(���傤�ɂ�)���A���߂Ă��̎R�ɓo�������ɁA�����ŋx��ŁA���M(�Ђ邰)�ɗp����������n�ɂ����čs�����Ɠ`���Ă���܂��B���������ӂ��ɐl�͂��낢��ɕς��Ă��A���������̐H���������ꏊ�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂́A�������R�̂��邱�ƂłȂ���Ȃ�܂���B(�V�����؎��B��ʌ������S��쑺�厚��) �b�B�ł́A���R���̏�����(���₵��)�Ƃ������ɁA�܂�����{�����̌䔢���Ƃ���������܂����B����͏����_�Ђ̋����ŁA�F�쌠�����K(�ق���)�̌�ɂ����ł���܂����B���{�����̌��ՂƂ������́A�R�����ɂ͂܂����X�ɂ���܂����A��������ڂ������Ƃ͓`����Ă���܂���B(�b��(����)�����B�R�������R���S������) ��������]�艓���Ȃ����X��(�Ƃǂ낫)���̖�����(�܂�Ղ���)�Ƃ������ɂ��A�e�a(������)��l�̌䔢���Ƃ��������{�����āA����̂ɁA�܂����̌�V�Ƃ��Ă�ł���܂������A��S�N�ȏ���O�̉Ύ��ɁA���̈�{�͏Ă��A�c��̈�{����Ɍ͂�Ă��܂��܂����B�́A�e�a�����̎��ɗ��đ؍݂����悢��A�낤�Ƃ������ɁA�o��(�ł���)�̑V�̔�������āA�䓰�̒�ɂ����܂����B����ɔ@��(���݂��ɂ�炢)�̑厜��߂ɂ́A�͂ꂽ���Ԃ��炭�B�����}�v�����̂��~���ɉk��ʏ؋��́A���̒ʂ�Ƃ����Ă����čs���܂������A�ʂ����邩�ȁA�����������ʂ����ɁA���̔�����ɍ���������𐁂��āA��������Ɩ�G(�Ђ�)�ł��Ƃ����̂ł���܂��B(�a���O�ː}��ȉ��B���R���S���X�͑�) �֓��ł͓��㑍(�Ђ���������)�̕z�{(�ӂ�)�Ƃ������̓��̖T�ɂ��A������������V�̐�����{�����āA���̒n���{���ƌĂ�ł���܂����B����͂܂��A�̌��������A������ʂ��Ĉ��[(����)�̕��֍s�����Ƃ���ۂɁA���̐l�������o�ė��āA���R�ɒ��̔т������߂܂����B���ɂ͐��̏��}��܂��ėp�����̂��A�L�O�ׂ̈ɂ��̐Ղɂ����A���ꂪ�������āA���̑�ƂȂ����Ƃ����āA�������V�c�`��̒֕��Ɠ��l�ɁA�������˂ɂȂ��Ă����Ɛ\���܂��B(�[���u���B��t���b��(������)�S�z�{��) �Ȃ����ꂩ��l�����萼�ɓ����āA�s���S�̕���(�ւ�����)�Ƃ������̓�{���ɂ��A���������������䔢�������čs���ꂽ�Ƃ����`�����c���Ă���܂����B���������ł���A�܂����ł��邱�Ƃ́A��قǒ������b�Ƃ���˂Ȃ�܂���B(�[���u�����ҁB��t���s���S�b���O(�ւ�����)��) |
|
|
�㑍�ł́A�܂��������̌䔢�́A��(������)�̌s�������č��A�H���̌�ɂ���������Ēu����������̂ŁA���ł��Z����\�����̐V��(�ɂ���)�Ƃ����Ղ���ɂ́A����܂��Ĕ��ɂ���Ƃ����`���Ă��鑺������܂��B(�쑍�V�ۑ��B��t���b����(���傤����)�S�����{�����{��)
�z��Ȃǂł́A������\��������̓��Ɩ��Â��āA�K����(��������)�̕��ɐ��āA���̓��̒��̐H�������鑺���������������ł��B���̂����́A�̐쒆������̎��ɁA�㐙���M���z�K���_(����݂傤����)�ɋF���āA���^�v���̒ʂ�ł������̂ɁA���̌�i���z�K�̑�Ղ�̎�����\�����̒������́A�_�̂���тȂ���銞�̕���A���ɗp���邱�Ƃɂ����̂��Ƃ����Ă���̂ł���܂��B(���̔V�x����\) ��(���邢)�͂܂���������(�悵)��܂��āA���ɗp�����Ƃ��`���Ă���܂��B�㑍�̏r�́A���i���ɋ߂���r�ł���܂����A��{���тƂ������̂������܂���B����̗͐��������A���̒r�݂̊Œ��ٓ̕����g���A�т�܂��Ĕ��ɂ����Ƃ��낪�A����܂��ĐO�������܂����B����ŕ��𗧂Ă��т̔���r�ɓ������̂ŁA���ł����̒r�ɂ��т��炽�ʂ̂��Ƃ����Ă���܂��B(�㑍�����e�B��t���N�ÌS���쑺) ����(��������)�ł́A���(�����)�S�b�V��(�ɂ��ς�)�̈�(����)����(����)�Ƃ������ɁA����͗����̌�Ɛl(�����ɂ�)�ł�������t����(���̂����˂���)�̔����A���������Ƃ�������������܂��B��͂肱�̒r��ʍs���Ē��̐H��������̂ɁA����܂��Ĕ��Ɏg���A��ł����n�ʂɂ����čs���ƁA���̔��ɍ����āA�ǁX�ɖ����Ƃ����A�����������獡�ł��K����{������Ő�����̂��Ɠ`���Ă���܂����B(��S���B��t����S�x�����V��) ���[�̏F��(���̂���)�̗{�V���Ƃ������̒�ɂ́A��͂藊�����̒��т̔������������Ə̂��āA�����̖T�ɔ��̊�������܂����A����͑O�̘b�Ƃ͔��ɁA���N������{���������s�������ʂ̂ŁA��{���̖��������Ēm���Ă���܂����B���Ԃ͕��ʂɂ͉��{���ꂵ��ɏo�܂�����A�������ʂ̗��R���Ȃ��Ă͂Ȃ�ʂƂ����ӂ��ɁA�l�����Ă������̂Ǝv���܂��B(���[�u�B��t�����[�S������) ���Ɣ��̔��̘b�́A�������̑��ɂ͕����Ă���܂���B���k�n���ł́A��������ڂ̊}��(�����܂�)������܂��B����K���牡��ɍs���S���̋߂��ŁA�D�Ԃ̒�����悭�����鏼�ł��B����͐e�a��l�̌��q�̐M�H(�̂Ԃ���)�Ƃ����l���A��͂�b�B�̖������̘b�Ɠ����l�ɁA���@�̂����Ƃ����Ƃ�y�n�̐l�����Ɏ������߂ɁA�H���̔��Ɏg�������̏��}���{�A�n�ʂɂ����čs�����̂��傫���Ȃ����̂��Ƃ����Ă���܂��B(�V�����؎��B��茧�a��S����ڑ�) ���ꂩ��܂��A�z��ɗ��āA�k����(���������)�S�b���c(�Ԃ�)���̓s�k(��)�̏����A����܂��e�a��l�̒��т̔��ł���܂����B���̏��͏��̎p�ɂȂ��ċ��s�ɍs���A�����Ɩ�����Ė{�莛�̕����̎�`���������Ƃ����̂ŁA���ɗL���ɂȂ��Ă��鏼�ł���܂��B(���y������ҁB�V�����k�����S���c��) �\�o�̏��(������)�̍��Ǝ�(�������傤��)�Ƃ������̑O�ɁA�Â��͔\�o�̈�{�Ƃ�����ꂽ��̐�������܂����B����͔��S�N�������������Ƃ����ዷ�̔���u��(����т���)�́A���M�̔��ł���܂����B����u��́A���鎞��̕a�ɂ������āA���̎��̖�t�b�@��(�ɂ�炢)�ɁA�S���̊Ԋ肩�������܂����B�������ĐM�S�̂��邵�ɁA���̔���n�ɗ��Ă��Ƃ������Ă���܂��B���̓�͔�����łȂ��A�������߂����ď�(��)��ւ̏��}�������A���ꂪ�F���͑�ɂȂ��Ă���̂ł���܂��B(�\�o�����Վu�ȉ��B�ΐ쌧�b��F(����)�S��ˑ�����) ����ł͔��R(�͂�����)�̘[(�ӂ���)�̑哹�J(�����ǂ�����)�̓��̒���ɁA�܂���{���ƌĂ���������āA����͗L���Ȃ�א�(�������傤)��t���A���тɗp��������n�ɂ������Ƃ����Ă���܂��B�����͂��傤�ljz�O�Ɖ���Ƃ̍����ŁA���̌����͉z�O�̖k�J�A���̕ӂɂ��F�X�Ƒא���t�̌̐Ղ�����܂��B(�\��(�̂�)�S���B�ΐ쌧�\���S������) �z�O�ł͒O��(�ɂ�)�S�̉z�m�R(��������)�Ƃ����̂��A�א���t�̊J�������R�̈�ł���܂��B�א��͂��̎R�ɏZ��ŁA�H�ו��̂Ȃ��Ȃ������ɁA����n��ɂ������̂����������Ƃ����āA�傫�Ȟw(�Ђ̂�)�����ł���{����܂��B���킵���b�͂킩��܂��ʂ��A������M�S�̗͂ŁA�₪�ĐH�ו�������ꂽ�Ƃ����̂ł��낤�Ǝv���܂��B(���y�������) �ߍ]���ł́A�������q���S�ώ�(�����炶)�������ĂȂ��ꂽ���ɁA���̎������i��ɔɏ����ׂ����̔��������āA�t�H�̔ފ݂ɉԍ炯��Əj���āA�������Ȃ��ꂽ�Ƃ�������(����)�̌䔢���A�ɂȂ��ē�{�Ƃ��c���Ă���܂��B�y�n�̖����ԑ�A�k�ԑ�A���̖��Ԃ̖Ƃ����Ă���܂��B��(������)�̈��ł����A�Ԃ��������A�܂��]�肽������ɂ͂Ȃ��Ȃ̂ŁA���̍��͔��ɒ��ӂ�����悤�ɂȂ�܂����B���������Z�O�͂̎R���Ȃǂɂ��A���܂ɑ���������邱�Ƃ������āA���͂���Ƃ��Ƃ����l���A���𗧂Ă��Ƃ����`�����Ă��邻���ł���܂��B(�ߍ]���`�n�����ȉ��B���ꌧ�b���m(����)�S��������) ���̒n���ł͍���A�X�ɋ����ׂ��䔢�̐����A����(���ʂ���)�S�̐���Ƃ������ɂ���܂��B��́b�V�Ƒ�_(���܂Ă炷�����݂���)���A����(����)�_�Ђ̒n�Ɍ�~��Ȃ��ꂽ���ɁA���̔��������Ē��т��������A����������ĂȂ��ꂽ�̂��h�����Ɠ`���āA���̎R�ɑ�ɂȂ��č��ł�����܂��B(�V�����؎��B���ꌧ����S�e��������) |
|
|
�������q�̌䔢�̖́A���ɂ����Ƃ͈�{����܂����B�ʑ�(���܂���)�̈��(���Ȃ�)�_�Ђ̒n���I��(���肨��)�R�A�܂��͌I�R�Ƃ����Ă̂́A���̓`�����������ׂŁA�����ł͌I�̖��������������ł������Ƃ����Ă���܂��B���q�������牮(���ׂ̂̂̂����)�Ƃ��킢�Ȃ��ꂽ���ɁA���̂����������ׂ��Ȃ�A���̌I�̖A����̂����Ɏ}�t�b�o(��)���ׂ��Ƃ����āA�������Ȃ��ꂽ���H���̔����A�ʂ��ė����͖����ɂȂ��Ă����Ɠ`�����܂��B������ʂɂ͂��蓾�Ȃ����Ƃ���ł����A���ꂾ���瑾�q�̌䏟���́A�l�Ԃ̗͂łȂ������Ƃ����ӂ��ɁA�ȑO�̐l�͉��߂��Ă����̂ł���܂��B(�����D(�����킯�Ԃ�)�B�����_�Ў���)
����(�݂܂���)��䑑�̓���̓`���Ȃǂ́A�����ċ߂����̏o�����̂悤�ɐM�����Ă���܂����B���鎞�b�o�_��(�������̂���)�����l�̏��炪����ė��āA�����̊ω����ɎQ�w�����āA�H�̂������ŐH�������܂����B���̒j�͑���ɂ߂Ă����̂ŁA���ꂩ���̉i�����s�������ɑ����čs����邩�ǂ����A���ɐS�ׂ��v���܂��āA���Ɏg�������̏��}��n��ɂ����āA�������S���ω��ɋF��܂����B�������ė������Ă��邤���ɁA����Ƒ��̕a�C���悭�Ȃ�A�����̏��q���c�鏊���Ȃ����܂��܂����B���N����̏t�̕��ɁA�Ăт��̐�̂قƂ��ʂ��ċC�����Č���ƁA�ȑO�����Ēu�������̏��}�́A���ɐ������ĐX�����{�̖��ƂȂ��Ă��܂����B�����œ���Ƃ����n�����n�܂����Ɠ`���Ă���܂��B��S�N�O�̑吅�ɂ��̖��͗���āA��ɑ��̖�A�������Ƃ����̂��A������܂���ɂȂ��Ă����Ƃ������Ƃł���܂��B(��z���B���R���b�v��(����)�S�b��`(��܂�)�������) �l���œ���邨�����̓`�������́A���������ł͒��̐H���Ƃ������Ƃ������Ă���܂���B���̈�͈��g�̎ő��̕s���̐_��(���݂���)�Ƃ������́A��{�̑���n�ʂ�����قǂ̏��ŁA�O�Ԏl��������傫�Ȋސ��x���Ă���܂��B�̍O�@��t���A���̒n��ʂ��āA�傫�Ȋ�̗����������Ă���̂����āA����͂��ԂȂ��Ƃ����āA��{�̐����𗧂Ăċ������B���ꂪ����ӂ��������āA���v�ȑ傫�Ȏ��ɂȂ����̂��Ɠ`���Ă���܂��B(�������V�����؎��B�������b�C��(������)�S�쐼����) �ɗ\�̔щ����̉����X��(���������肶)�ɂ�����̂Ɏ����ẮA�Ȃ�l(�т�)�̔��ł��������Ƃ������Ƃ��s���ɂȂ�܂������A����ł����̖̖��͐^�������A�܂Ȃ��Ƃ͌䔢�̂��Ƃł���܂��B���\�N�]��O�ɁA���̖�(��)���Ă��܂����Ƃ��낪�A���ɐF�X�̈������Ƃ������܂����B���͐^�������������߂ł͂Ȃ��낤���Ƃ����āA�V���ɍ������A���āA�Â����𑊑������A�����̐_�Ƃ��đ��h���Ă���܂��B(�V�����؎��B���Q���b�V��(�ɂ�)�S�щ���) ��B�ɂ́A�܂�����Ȑ̘b�̂悤�ȓ`�����c���Ă���܂��B�̔�O�̏��Y�̂ƈɖ���(���܂�)�̂ƁA�̕��������߂悤�Ƃ������ɁA���Y�̔g���O�͎�(�͂��݂���̂���)�́A�ɖ����b������v(�Ђ傤�Ԃ��䂤)�Ɩ��āA�o������閾���̌{�̐��������Ĕn�����o���A�r���s������������̕��̍�ɗ��Ă悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�Ƃ��낪���̖�A�ݛ�(��������)�̌{�������������̂ŁA���Y�̎g�҂͑����o�����A�ׂ�̗̂̔���(�����)�Ȃ���(����)�Ƃ������ɗ��āA�n�߂Ĉɖ����̎g�҂ɍs�������܂����B����ł͂��܂�ɕЕ��֊��߂���Ƃ����̂ŁA�ɖ��������痊��ŁA�\�O�˂Ƃ������܂ň��������Ă�����āA���̖쌴�Ŕn���牺��āA��H�������܂����B���̎��p�����̂͌I�̖̔��ł������A������L�O�̂��߂ɁA���̏ꏊ�Ɂ��m�u���v�ł���̏c�_�����ɓ˂������Ă���n(��)���ċA���ė��܂��ƁA��ɔ��������o���āA�����ɌI�̖���܂����B�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ͖��N�Ԃ��炭����ŁA���͂Ȃ�Ȃ������Ƃ����`���Ă���܂��B(���Y�̊�) ����Ɠ����l�Șb�͋C�����Ă���ƁA�܂�������ł��m���Ă���l���o�ė��܂��B�ȑO�͂ق�Ƃ��ɂ���Ȃ��Ƃ��������Ǝv���Ă����҂����������̂ŁA�i���ԊF���o���Ă����̂ł���܂��B���ł��R�̒��ł����̋��ł��A�_�̂��Ղ�������ȏꏊ�ɂ́A�K�������ς���������c���Ă���܂����B���ꂪ�ߍ]�̉Ԃ̖̔@���A��ނ̔��ɒ��������̂�����A�܂������̑����̏�(����)�̂悤�ɁA�}�U��⊲�̌`�̖ڂɂ����̂�����܂������A�ł����ʂɂ́A�����N��̓������{�������ׂĎc�����̂ł���܂��B�������Ēu���A�����ɋ��R�̂��̂łȂ����Ƃ���̐l�ɂ��킩�����̂ł���܂��B �������Ĉ���ɂ͂��Ղ�̐܂�Ɍ����āA�̋�(����)�܂��͖̎}��y�ɂ����K��������܂����B�����ɂ܂��V���������������āA�Ղ�̐H����_�Ƌ��ɂ���K��������܂����B���͌����Đ������đ�ƂȂ邱�Ƃ̏o������̂ł͂���܂��A��̂Ȃ�A�܂��_�l�̗͂Ȃ�A����Ȃ��Ƃ������Ă��s�v�c�łȂ��Ǝv�����̂ł��B����������̐l�ɂ́A�Ƃ��Ă��]�܂�ʂ��Ƃł���̂ɁA���čł��D�ꂽ�l�̗����ꍇ�A�������͔��̑厖���ɔ����āA���������o�������������悤�ɁA�z������҂������Ȃ�܂����B���������ۂ͂�������Ȃ��ȑO����A��͂肱��͑�̘̂b�Ƃ��āA���`���Ă������̂ł������낤�Ǝv���܂��B�@ |
|
| ���s����(�䂫��������) | |
|
���́A�ŏ��_�X�����߂ɂȂ����悤�ɁA�l���Ă����l�����������̂ł���܂��B�l�͂��܂ł����𑈂����Ƃ��܂����A�_�l�ɂ͑������o���Ă��āA���̂��邵�ɂ͂����Ă����̖A�܂��͑傫�Ȋ₪����܂����B��a�ƈɐ��̋��ɂ��鍂���R�̎��͂ł́A�ޗǂ̏t��(������)�l�ƈɐ��̑�_�{�l�Ƃ��A�䑊�k�̏�ō����������߂Ȃ��ꂽ�Ƃ����Ă���܂��B�t���l�͗]���a�̗̕��������̂ŁA�������A�������Ƃ̂��܂�ĉʂĂ����Ȃ��B�������̂��Əo�����ٖ�(�����߂�)�Ƃ��āA�������������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�ٖʂ͂����߁A���Ȃ킿��̂��ƂŁA�o������i��ŗ��āA�o�������������ɂ��悤�Ƃ����킯�ł���܂��B�����ŏt���̐_�l�͎��ɏ���Ă������ɂȂ�B�ɐ��͕K����_�n(�������)�ɏ���āA�����ė�����ɑ���Ȃ�����A����͂Ȃ�ł���قǑ����o�����ʂƕ�����Ƃ����āA��̖����ʂ����ɏo���Ȃ���܂����B���̂��߂ɋp���ďt���l�̕��������ɐ��̂ɂ͂����āA�{�O(�݂�̂܂�)���̂߂��炵���̏�ŁA�ɐ��̐_�l�Ƃ��o�����ɂȂ�܂����B�����t���͂����Ɛ����������ɂȂ����̂ɁA�߂��炵���Ƃ������O���o���܂����B�����������ɂ��Ă͗]��Ɉɐ��̕��������Ȃ�̂ŁA���x�͑�_�{�l�̕����炨���݂�����A���M������Đ��ɕ����ׂāA���̏M�̂����������ɂ��悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
���̍��͂܂����̕ӂ͈�ʂ̐��ŁA���̐����Â��ŁA���M�͏���������܂���B����ňɐ��̐_�l�͈�̐�����āA����͒j�Ƃ����Đ��̒��ɓ������܂�܂��ƁA�M�͂����悤�č��̏M��(�ӂȂ�)���ɂƂ܂�A���͍����̗���߂��đ�a�̕��֏�������܂����B��������Ĉɐ��̑�_���A�M�͏M�ˁA���͉߂����ɂƋ���ꂽ�̂ŁA�ɐ��̑��ɂ͏M�ˑ�������A��a�̕��ɂ͐��J�̑�������܂��B���ɐ_�l�̂��t���ɂȂ����Â������Ƃ����Ă���܂��B���̒j�͍����߂��炵���̎R���ɂ����āA�V����ʂ��Ă���������悭�����܂��B���̉ƂɎq���̐���悤�Ƃ���҂��A���ł����̐�ڂ����ď���ł����āA�����q���j�������Ɛ肢�܂��B�j������鎞�ɂ́A�K�����̏����j�ɓ���Ƃ����Ă���܂��B�O�\�N�قǑO�܂ł́A���̒j�̋߂��ɁA�Â��傫�ȍ�(������)�̖��A�_���J(�܂�)���Ă���܂����B�ɐ��̐_�l���_�n�ɏ��A��̎}���(�ނ�)�ɂ��Ă����łɂȂ����̂��A������ƒn�Ɂ��m�u���v�ł���̏c�_�����ɓ˂������Ă���n(��)���Ēu���ꂽ���̂��A���̂܂ܐ������đ�ɂȂ����B����̂Ɏ}�͂��Ƃ��Ƃ����̕��������ĐL�тĂ���Ƃ����܂����B���̖��������Ƃ����̂��A�t�̈Ӗ��ŁA�������n�܂�ł������Ɠy�n�̐l�͂����Ă���܂��B(���y������ҁB�O�d���b�ѓ�(�͂�Ȃ�)�S�{�O��) ��a�ƌF��Ƃ̋��ɂ����Ă��A����Ƌ߂��b���`����Ă��邻���ł���܂��B�t���l�́A�F��̐_�l�Ɩ����āA��͂��O�̏��Y�l�Ɠ����悤�ɁA�s�������ٖʂƂ��ė̕��������߂悤�Ƃ����܂����B�F��͉G�ɏ���Ĉ��тɔ��ŗ����邩��A�������Ȃ��Ă͕�����Ǝv���āA�܂���̖����ʂ����ɏt���l�́A���ɏ���ċ}���ł��ł����ɂȂ�ƁA�F��̐_�l�̕��ł͖��f�����āA�܂��Ƃ̓��ɋx��ł����܂����B�ʂ�ɂ���ƁA���̉��܂ő�a�̗̕��ɂ��Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł����A����ł͍���̂Ŗ����ɏt���l�ɗ���ŁA�F��̉G�̈��ѕ������A�n�ʂ�Ԃ��Ă��Ⴂ�ɂȂ�܂����B����̂ɁA���ł��ޗnj��͓�̕��֍L���A�F��͍�܂ł������߂��̂��Ƃ����܂��̂́A�܂�œe�ƋT�Ƃ̘̐b�̂悤�ł���܂��B ����Ƃ悭���������`�����A�܂��M�B�ɂ�����܂����B�M�B�ł́A�z�K�喾�_��������䂫�߂Ȃ���邽�߂ɁA����(������)�S��ʂ��ĉz��̋�����(���킵�݂�)�Ƃ������܂ōs����܂��ƁA�����։z��̖�F(��Ђ�)���������o�����ɂȂ��āA�����܂ŐM�Z�ɂ͂����ẮA���܂�z�オ�����Ȃ邩��A��������̕�����ɂ��悤�Ƃ����䑊�k�ɂȂ�A���r(���炢��)�Ƃ������܂ł��ǂ��č�𗧂Ă��܂����B���ꂩ�琼�։���ĉz���̗��R(���Ă��)�����A����̔��R(�͂�����)�����Ƃ����o�����Ȃ���āA�����O�ӏ��̋������܂�A���ꂩ���͎��N�Ɉ�x���A�z�K�������(�Ȃ�����)�Ƃ������̂����āA��ڂɂ��邵�𗧂Ă��Ƃ������Ƃł���܂��B(�M�{���L) �����b���A�܂����̂悤�ɘb���Ă���l������܂��B�̍������߂鎞�ɁA�z�K�l�͋��ɏ��A�z��l�͔n�ɏ���āA�r���䂫�������������ɂ��悤�Ƃ����������܂��āA�z��l�͔n�̑��͑�������A���܂�s���߂��Ă����炾�Ǝv���āA�邪�����Č�ɂ������Ƃ��o�����ɂȂ�B�z�K�l�̕��ł́A���͓݂�����ƁA�钆�ɂ����đ�}���ł���ė���ꂽ�̂ŁA��ɉz�㕪�̍�(����)�̐_�Ƃ������܂ŗ��āA�����ł���Ɖz��l�̔n�Əo����ꂽ�B����͗��߂����킢�ƁA���������Ԃ��ďo�����čs���ꂽ�Ƃ��������A�z�K�̕��Ƃ����̂������ł���܂��B(���J����W�B�V�����b�����(�ɂ����т�)�S���m��) �̂͂��������ӂ��ɁA���̋��������Ƌ߂��ƁA�ɂ��߂Ēu���K�����������炵���̂ł���܂��B��������Ȃ�قnj���(����)�����邱�Ƃ��A�����čς킯�ł���܂��B�L��(�Ԃ�)�Ɠ���(�Ђイ��)�Ƃ̋��̎R�H�Ȃǂł��A�䂩�班�������āA�o���ɑ傫�Ȃ��邵�̐��̖�����܂����B�������ĖL��̂Ɋ������������̖A����Ɣ��ɓ����̑��ɂ�����̐����A�L��̖Ƃ����Ă���܂����B�S�N�قǑO�ɂ��̖L��̖��͂ꂽ�̂ŁA�����Č��܂��ƁA���������炽������̎K(��)�т��V(�₶��)���o�܂����B����͖(�₽��)�̐��Ƃ������āA�ȑO�͂��̉���ʂ�l�X���A���̖Ɍ����Đ�(��)���˂��ނ��Ƃ��A���̐_���Ղ��@�Ƃ��Ă����̂ł���܂��B�����̊֎R�ɂ��b�B�̍��q(������)���ɂ��A���Ƃ͑傫�Ȗ���̖��������̂ł��B�M�B�̐z�K�̓����Ƃ����̂��A���̐��̑��ɓS�̊����A�_�̊��ɑł������̂Ǝv���܂��B�ߍ��ɂȂ��Ă��A���ɋ߂���̊�����A�������`�������Ê����܂�܂�o�܂����B�������Ă���Ɠ��������A�z�K�ł͍������Ղ�ɗp������̂ŁA�㊙(�Ȃ�����)�Ə��������������悤�ł���܂��B���ɂ���z�K�̖��_���A��������߂ɂȂ����Ƃ����`���́A����ł����ސ_�����邽�߂ɁA�o�������̂ɑ��Ⴀ��܂��ʂ��A���̘b�̕��͂��������ɕς��čs���̂ł���܂��B�Ⴆ�Ήz��̐_�l�́A�z�K�̐_�̕�N�ŁA��q�̗l�q�����������āA�z�ォ��킴�킴���o�łɂȂ�H�ŁA���傤�Ǎ����̏��ŁA�z�K�̐_�l�Ƃ��o�����Ȃ���A�z�K�l������(������)�A����(���Ƃ�)�̐_�ɍ~�Q�Ȃ��ꂽ���Ƃ������āA���]���Ă�������ʂ�āA�z��ւ��A��ɂȂ����ȂǂƂ����̂́A��ɗ��j�̖{��ǂl�̍l�������ƂŁA���[(����)��㑍�ŁA�������̗��s�̂��Ƃ��A�����������̂Ɠ����l�ȑz���ł��낤�Ǝv���܂��B |
|
|
���(�Ђ�)�̎R���̋o���J(���т�����)�Ƃ������Ȃǂ́A�̐쉺�̈����싽(�����̂���)�Ƃ̋����s���Ȃ̂ŁA�����������č����Ă������ɁA�o���̑��̐l���𗧂āA�o���J�ł͋o���a�A������͑吼�a�Ƃ����l�𗊂݁A���ɏ���ė���������݊���āA�s������������̕��̋��Ƃ��邱�Ƃɂ��܂����B����(����)����(�ق�)�̋���ŁA���̓�̋������傤�Ǐo�����A����Ȍ�͂����ɒ�߂��Ƃ����Ă���܂��B���̋o���a���吼�a���A���ɖؑ]���痎���ė����B���̕��m(���ނ炢)�ł������Ƃ����܂����A�b�͂܂������t���ƌF��A�������͐z�K�Ɩ�F�́A�o�����ٖʂ̓`���Ɠ������̂ł���܂��B(��ˍ����ē��B���b�v�c(�܂���)�S������)
���Z�̕��V(�ނ�)�S�̊`��(������)�Ƃ������ƁA�R���S�k�R�Ƃ������Ƃ̋��ɂ́A���ɂ̂����Ƃ������������āA�����Ɋ`��̎��_�l�ƁA�k�R�̒���l�Ƃ��A�ʂ�̔u(��������)���Ȃ��ꂽ�Ƃ����`���Ă���܂��B���̔u�Ɖ����̌{�Ƃ��A���̒n�֖��߂čs���ꂽ�̂ŁA���ł����������̒��́A���̉����̌{���o�Ė��Ƃ����Ă���܂��B(�e�{���Z�u�B�����V�S�b��(���ʂ�)��) ��̓y�n�̐_�l���A�������ɓ����ꏊ�ŁA���Ղ�\����͕��X�ɂ���܂����B��������Ηׂ蓯�m�����ǂ��A���̑����͏o���Ȃ��Ȃ�ɂ��܂��Ă��܂��B�n�}���L�^���Ȃ������̂̐��̐l�����́A�������ł���ɂނ�Ȃ��Ƃ������ɁA�悻�̐l�ƌ��ۂ��邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ�܂����B������ǂ��̑��ł��`����厖�ɂ��Ă����̂ŁA�����`������������ς����肷��A���Ղ�̂��Ƃ̈Ӗ����킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���܂��B �s�������Ղ�����邨�Ђ́A�ʂɂȂ�Ƃ����_�l�Ɍ���Ƃ������Ƃ͂Ȃ������̂ł���܂��B�M�B�ł͉J�{(���߂݂�)�̎R��(����̂�)�l�ƁA����(�₵��)�̎R���l�Ɠ����O���b�\(����)�̓��̐\�̍��ɁA���̋��̋��̏�ɓ�̐_�`(�݂���)���W���āA�����̐_��������܂����B���̋��̖���l���̋��Ƃ����Ă���܂��B�����̋߂��ł́A�k�Ɠ�̕i��̓V���l�̐_�`���A��̏h�̋��ɉ˂������̏�ŏo�����A���̗�������(������)�̂������ł��Ղ�����܂����B�������Ă��̋����s�������̋��Ƃ����̂ł���܂��B�����p���̏��X�̊C�݂ɂ́A�܂���ł�����Ɠ������Ղ肪����܂����A���Ƃ͋����߂�̂��ړI�ł��������Ƃ��A�����Y��Ă���l�������悤�ł���܂��B�������Ĉ�����P�_�ł���ꍇ�Ȃǂ́A�����_�l�̌䍥�炩�Ǝv���҂������Ȃ����̂ł���܂��B�@ |
|
| ���Ԑ�(�����Ƃ���) | |
|
�́b����(�т�)�̉��R��(������܂���)���ɁA���Y���q��Ƃ����M�S�[���S���������āA���N�����������|(����)�̋{������֎Q�w(����)���Ă���܂����B����N�_�O�ɔq�݂��������āA���������N���Ƃ��Ă��܂��܂����B���Q������ꂪ�I��ł�����܂��傤�A�Ƃ����ċA���ė��܂��ƁA�D�̒����Ԃɏ����Ȑ���A�͂����Ă���̂ɐS�t���܂����B�N����荇���̐l������������������̂ł��낤�Ǝv���āA���̐��C�֎̂ĂĐQ�Ă��܂��܂����B�����ڂ��o�߂Č���ƁA���������܂��Ԃ̒��ɂ���܂��B���܂�s�v�c�Ɏv���đ�ɂ��đ��֎����ċA��A�ߏ��̐l�ɂ��̘b�����܂����Ƃ��낪�A����͕K���_�l���炽�܂�����ł��낤�B�J(�܂�)��Ȃ���Ȃ�܂��Ƃ����āA�����Ȃق�������ĂĂ��̐���ɔ[�߁A�����喾�_(�������܂����݂傤����)�Ə�(�Ƃ�)���Ă����߂Ă���܂����B���̐���ɂ���Ƒ傫���Ȃ����Ƃ������ƂŁA���̘b�������l�̌������ɂ́A��������ڔ�������A���肪��ړ�O�������������Ɛ\���܂��B���ꂩ��ǂ��������킩��܂��A�������ł��܂�����Ȃ�A�܂���قǑ傫���Ȃ��Ă���킯�ł���܂��B(�|�ˎu���B�L�����b�b�i(��������)�S�b�X�R(�ނׂ��)��)
�M�B�̏����ɂ́A�x�m�Ƃ����傫�Ȋ₪����܂��B����͐̂��̑��̔_�����x�m�ɓo���āA���R����E���ė������ł���܂����B�Ƃ̋߂��܂ŋA�������A�Ԃ̚�(����)�����Ƃ��āA����ɂ܂���Ă����֗������̂��A���̊Ԃɂ����̂悤�ɐ����������̂��Ƃ����Ă���܂��B(�`���̉��ɓ�(��������)�B���쌧���ɓߌS�q����) �܂������n���̍��c�̑��ɋ߂����_�̎Ђɂ́A�����Ƃ����傫�Ȋ₪����܂��B����͐̂��鏗���A�V����̐쌴�Ŕ��������������A�E�����Ԃɓ���Ă����܂ŗ��邤���ɁA�Ԃ��d���Ȃ����̂ŋC�����Č���ƁA���̏��������傫���Ȃ��Ă��܂����B�������Ď������܂̐�œ˂����������r(����)���Ƌ��ɑ傫���Ȃ��Ă���̂ŁA�т����肵�Ă��̐��_�l�̑O�֓����o���܂����B���ꂪ�X�ɐ������āA���܂��ɂ͂��̂悤�Ȋ�(���킨)�ƂȂ����̂��Ƃ����`���Ă���܂��B(�`���̉��ɓ߁B���쌧���ɓߌS���]��) �F��̑��J�Ƃ������ł��A�J��̒����ɂ���傫�ȉ~�`�̊�A������Ԕ��Ɏ��肪���Ԃ������āA��ɂ͂��낢��̖�̖��Ă���̂��A�����ԐƂ����Ăق�������Ă��J���Ă���܂����B������܂������Ƃ������Ă��܂������A���̂킯�͂����`����Ă���܂���B(�I�ɍ��G���y�L�B�O�d���b�어�K(�݂Ȃ݂ނ�)�S�܋���) �ɐ��̎R�c�̑D�](�ӂȂ�)���ɂ��A�����v(���炾�䂤)���ԐƂ����������܂��B�����͌ڂ���A����Ɋ_�����đ�ɂ��Ă���܂����A����͐́b����(����)���}��(����)�ɗ����ꂽ���A�x��t�F(�킽�炢�̂͂�Ђ�)�Ƃ����l�������čs���āA�A��ɔd�B(�イ)�̑��̉Y�Ƃ������ŁA�E���ė���������ł���܂����B���ꂪ�N�X�傫���Ȃ��āA�I(��)�ɂ��̒ʂ�̑�ƂȂ����̂ŁA���̖T�ɐ����̗���J�邱�ƂɂȂ����Ƃ����`���āA���ł������ɂ͐����Ђ�����܂��B(�_�s�������B�O�d���F���R�c�s�D�]��) �y���̒Ñ�(����)���ƈɗ\�̖ڍ����Ƃ̋��̎R�ɁA�����ԐƂ���������Ԕ��A����܊Ԃقǂ̑傫�Ȑ�����܂����B����͐̑]��̏\�Y�ܘY�Z��̕ꂪ�A�֓����痎���ė��鎞�ɁA�Ԃɓ���Ď����ė������̂Ƃ����`���Ă���܂��B���̒n���̎R�̒��̑��ɂ́A�]��̌ܘY���J��Ƃ����Ђ����X�ɂ���A�܂����̉Ɨ��̋S���c�O�Y(���ɂ������Ԃ낤)�̌Z�킪�Z��ł����Ƃ����̐ՂȂǂ������ɂ���܂��B�]��̕ꂪ���l(�����イ��)�ɂȂ��ė��Ă����Ƃ������Ƃ��A���̕ӂł͂悭�����b�Ȃ̂ł���܂��B(��C�W�B���m���b����(�͂�)�S�Ñ呺) ���̊���(�Ȃ߂���)���ɂ́A���Ƃ��������F�̊₪�A���Ƃ͓���C�̐��̒�Ɍ����Ă���܂������A���ߗ��Ă̓c���o���Ă���A�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���̐͐_��(����)�c�@���O�ؐ����̂��A��ɁA�Ԃɓ���Ă������ɂȂ��������A�傫���Ȃ����̂��Ƃ����Ă���܂����B(��㍑�u�B�F�{���ʖ��S���Α�) ��B�̊C�݂ɂ͐_���c�@�̌�㗤�Ȃ��ꂽ�Ƃ����`�����ꏊ���A�܂����̑��ɂ������ƂȂ�����܂��B�������ċL�O���Ԑ��ɂ��Ă����Ƃ�����A���X�ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��ԌÂ�����L���ɂȂ��Ă����̂́A�}�O�b�[�](�ӂ���)�̎q����(�����̂͂�)�Ƃ����Ƃ���ɂ�������̍c�q(�݂�)�Y�ݐł���܂��B����͂����̒��Ɂ��m�u���v�ł���̏c�_�����ɓ˂������Ă���n(�͂�)��ł��A��ɂȂ����Ƃ������ł����A���t�W�╗�y�L�̏o�������ɂ́A������ڈȏ�̏d���ɂȂ��Ă���܂����B���̌`�������������ł����������ł��B��ɂ͂ǂ��ֈڂ����̂��A�m���Ă���l���Ȃ��Ȃ�܂����B�y�n�̔���(�͂��܂�)�_�Ђ̌�_�̂ɂȂ��Ă���Ƃ������l������A�C�݂̉��̏�ɍ��ł������āA�����O�ڗ]��ɂȂ��Ă���Ƃ����l������܂����B(����(������)�Ǔ��u�B�����������S�[�]��) �傫���Ȃ����Ƃ����̂́A���͉�������l���^��ŗ������ŁA�n�߂��炻������̂����̐Ƃ͈���Ă���܂����B�����̈��(�����)���̋߂��A���c���̋{�Ԗ^�Ƃ����l�̉Ƃł́A���~�ɐΐ_�l�̂ق�������ĂāA�ڗ]��̒������`�̐��J���Ă��܂����B�ނ������̉Ƃ̑O�̎�l���A�I�B�F��֎Q�w�̘H�ŁA����(��炶)�̊Ԃɝp(�͂�)�܂�����������Č��܂��Ǝ��Ɋ�Ȋ��D�����Ă��܂����B���܂蒿�����̂�����(�Ђ����Ԃ���)�̒��ɓ���Ď����ċA��܂��ƁA�����r�����炻�낻��傫���Ȃ�n�߂��Ƃ����Ă���܂��B(��k�G�j�B��t����S������) |
|
|
�܂���t�S�b��юR��(���݂͂���)�̗тƂ����Ƃł��A���̐�����������_���J���Ă��܂����B����͂����ƈȑO�Ɏ�l���ɐ��Q������āA���ꂩ���a���߂����ēr���Ŏ�ɓ��ꂽ���ŁA�В�(���Ⴍ)�ɓ���ė����̂ɁA���̖����В��ƌĂ�ł��܂����B(�����B������t�S��{��)
�y���̍��⑺�̂��͗L���Ȃ��̂ł���܂����B�_���J���đ�ΐ_�A�܂����ɐ��_�Ə�(�Ƃ�)���Ă���܂��B����������Ɛ̂���l���A�ɐ�����В��ɓ���Ď����ė��Ă����ɒu�����̂��A�I�ɂ��̌��グ��悤�ȑ��ɂȂ����̂��Ƃ����Ă���܂��B(��H�u�b����(���̂�)�B���m�������S���⑺) �}��ɂ���Α��̑�ΐ_�ЂƂ����āA���̖��ɂȂ������̐_�̐�����܂��B�̑�Ήz�O��Ƃ����l���A�ɐ������炱�̐����ɓ���ĎQ��܂��āA������ɐ���_�{�Ɛ�(����)�߂��Ƃ������A��(���邢)�͈�l�̘V������A�����Ԃɓ���Ă��̒n�܂Ŏ����ė����̂��A����ɑ傫���Ȃ����Ƃ������Ă���܂��B������O�S�N�O�ɁA������ڎO���قǂɂȂ��Ă���܂����B�������ĕʂɍ���O�ڂقǂ̐������āA���̐l�͂�������ɐ���O�Ə̂��āA�Ђ����ĂĔ[�߂Ă���܂����B���̎Гa�����x������ւ����̂́A����傫���Ȃ��āA�͂���Ȃ��Ȃ��ė������炾�Ƃ����Ă���܂��B(�Z���}��u�B�������b�O��(�݂���)�S�b����(�Ƃ肩��)��) ���̑�Α��̂��Ђɂ́A���Y�̊�|��������l���������������ł��B�̂悤�Ɍ�����v�Ȏq���A���܂��ɒm��ʊԂɑ傫���Ȃ�Ƃ����q�����A�e�Ƃ��Ă͖]��ł�������ł���܂��傤�B�F�삩�痈���Ƃ����̒��ɂ́A�����������邾���łȂ��A�e�Ƃ悭�����q���Y�Ƃ����`��������܂����B�Ⴆ��B�̓�̎�q��(���˂�����)�̌F��Y�A�F�쌠���̐_�Ȃǂ�����ł���܂����B���̂��Ђ͐̂��̓��̎�A��q���b���ߏ���(������̂��傤����)�Ƃ����l���F���M���āA�������̒n��菬���Ȑ���A�����ɓ���Č}���ė��܂����Ƃ��낪�A���ꂪ�N�X�ɑ傫���Ȃ��āA��ɂ͍����l�ڎ����ȏ�A����͈��O�ڗ]�A���E�Ɏq���Ă��̎q���܂��������������A�F���`���F��Ɠ����ł������Ɛ\���܂��B(�O�������}��B���������F�ьS����q�����v) ����Ƃ悭�����b���܂����{�̖k�̓c�ɁA�H�O(������)�̒������̌F��_�Ђɂ�����܂����B������l�S�N�قǑO�ɂ��̑��̐l���A�F��֎��x�w��������҂��A�L�O�ׂ̈ɓߒq�̕l����A�����Ȑ��E���ċA��܂����B���ꂪ���\�N����̊Ԃɂ���Ƒ傫���Ȃ��āA��ɂ͈�����ɗ]��قǂɂȂ�܂����B�`�����Ɏ��Ă���̂ʼnW��(������)�Ƃ����������܂����B���ꂪ�N�X�ɓ��]��̎q����ŁA�召��������`�͗��̔@���A���Y�Ύ��Y�A���ȂǂƌĂ�ł����Ƃ����̂́A���Ȃ��҂ɂ͂ق�Ƃ��Ƃ��v���ʒ��̘b�ł����A��������̓y�n�ł͍��F��Ƃ����āA�q��ł��������ł���܂��B(���K�B�R�`���k���R�S�{����) �y���ł͍���B����(������)�S�b�R�k(��܂���)�̎Ђ��J��_���A�̂��̑��̐l�����̋g�c�_�ЂɎQ�w���āA�_�y��(�����炨��)�̐�Ղ��ċA���ė����̂��A���������ɐ��������̂��Ƃ����Ă���܂��B(�y���C���ҁB���m�������S�R�k��) �ɐ��ł͉ԉ����̑P�o��(������)�Ƃ������́A�{���̓y�����������ł����B����ׂ͗�̏��Ƃ��������̐l���A�����b�M�c(����)�̎Ђ��玝���ė��Ēu�������̂ŁA���̐l�͂��ƔM�c�̔H�X(�˂�)�ł������̂��A���̕����̐l�ƌ����������߂ɁA�M�c�ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă����֗��ďZ�Ƃ����āA�����ɂ͍��ł��z��(��������)���̔M�c���̂Ƃ����c��(�݂傤��)�̉Ƃ�����܂��B(�|�t���B�O�d���b�ѓ�(�͂�Ȃ�)�S�b�˘a(������)��) ���̓���̐ΐ_��(�������݂₵��)�̐��A���Ƃ͉F�������̐_���b����(���Ƃ���)�����A���̂��Ђ̐_�O���玝���ė����J�����̂ŁA���ꂩ��N�X����悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���܂��B(��㍑�u�B�F�{���b�O��(�ق�����)�S���葺) ���̒ʂ�A�傫���Ȃ�̂ɋ����Đl���q�ނ悤�ɂȂ����Ƃ��������A�n�߂��瑸���Ƃ��ĐM�S�����Ă��邤���ɁA����Ƒ傫���Ȃ����Ƃ������������̂ł���܂��B�����炻�̐��ǂ����痈�����Ƃ������Ƃ��A���������b���Ȃ���Ȃ�ʂ̂ł���܂����A���|�̒���Ƃ������ł́A�����̓�������c��(�����)�̒��̑傫�Ȋ���A�o�_��(����������)�Ƃ����Ă���܂����B������܂����ł����������ɁA�l���o�_�����玝���ė��āA�����ɒu�����̂��傫���Ȃ����Ƃ����Ă���܂��B(�|�˒ʎu�B�L�����L�c�S���㑺) ���̏o�_���ł͔ѐ�(������)�_�Ђ̌�ɂ���傫�Ȑ��A��͂�̂��瑱���đ傫���Ȃ��Ă���܂����B�̌`���т����l������Ƃ������A���͔��(�͂�)�̒��ɂ͂������܂܂ŁA�V����~���ė���������Ƃ������Ă���܂��B(�o�_�����Ѝl�ȉ��B�������ѐΌS�ѐΑ�) |
|
|
�ǂ����Ă��̐̑傫���Ȃ����̂��킩�邩�Ƃ����܂��ƁA���̎���̍r�_����肩����x���ɁA�������ȑO�̐��@���A���ׂȂ���Δ[�܂�ʂ���Ƃ����Ă���܂��B�L�O(�Ԃ���)�̌���(���Ƃ܂�)�Ƃ������̒O�g�喾�_�Ȃǂ��A�l�x�����Ђ����ւ��āA����ɐ_�a��傫�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����Ă���܂����B�̒O�g�������l�̓A������Ŏ����ė��āA���̑��ɗ��ĖS���Ȃ�܂����B���̏����傫���Ȃ�̂ł��̂ق���̒����J��A�O�g�l�ƌĂԂ悤�ɂȂ����̂������ł���܂��B(�L�O�u)
�Ό�(�����)�̋g��(�悵��)�̒��A��(���߂���)�Ƃ������ł́A���̐���������������(����������)�Ƃ����Ă���܂��B����͐̎l���𗷍s�����҂��A�ӂƂ���ɓ���Ď����ċA�������Ɛ\���Ă��܂��B(�g��L�B�������b����(���̂���)�S���q��) �x�m�Ƃ������܂���A���](�Ƃ��Ƃ���)�̐ΐ_���ɂ�����܂����B���̎R�̐�ʂ��̂Ƃ���ɂ����āA������N�X�傫���Ȃ�̂ŁA�ΐ_��_�Ƃ����J���Ă���܂����B�����x�m�R���玝���ė������ł������ƁA�y�n�̐l�����͎v���Ă������Ƃł���܂��傤�B(���]�����y�L�`�B�É����b�֓c(���킽)�S�㈢���Ñ�) �֓��n���ł͒���(������)�̏�����(������)�̏h�ɁA�M�Z�Ƃ������炵���`�̐�����܂����B�傫���͈��l�����炢�A�܂Ɉ�ڂقǂ̌�������܂����B���̌��Ɏ��ĂĂ���ƁA�l�̕�����������������Ƃ������܂����B����͐̂��̓y�n�̔n�����M�B�ɍs�����A��ɁA�n�̉ו��̕Ј�����y���̂ŁA����ɂ��邽�߂ɁA�H�ŏE���ĝp��ŗ��������A����ȑ傫�Ȃ��̂ɂȂ����Ƃ����̂ł���܂��B(�V�ҕ������y�L�e�B��ʌ������S�����쒬) ���̐M�B�̕��ɂ͂܂����q�Ƃ����̂�����܂����B���v(����)�̈��{��(����悤��)�Ƃ������̒�ɂ����āA�n�߂Ċ��q���玝���ė������ɂ́A�ق�̈ꈬ��̏��ł��������̂��A�������Ďl�ڂ���ɂ��Ȃ����̂ŁA��̌È�˂̊W�ɂ��Ēu���܂��ƁA����ɂ����܂킸�ɁA��ɂ͈��ȏ�̑��ɂȂ��Ă��܂��܂����B�����炷���Ԃ���̂����Č���ƁA��̉��ɍ��ł���̌`������������Ƃ����܂����B(�M�Z��^�B���쌧�b�k���v(��������)�S�O�䑺) �������Ă킴�킴�����Ƃ��납��A�l���^��ŗ���قǂ̏��Ȃ�A�����悭�悭�̈���������A�܂��s�v�c�̗͂�������̂ƁA�̂̐l�����͍l���Ă����炵���̂ł���܂����A���ɂ͂܂������ƊȒP�ȕ��@�ŁA�傫���Ȃ����悤�ɂ����Ă���Ƃ��������܂��B��B�̈��h(����)�n���Ȃǂł́A�ǂ�ȏ��ł��E���ċA���āA���̉����ǂ����ɓ�(����)���Ēu���ƁA�����Ƒ傫���Ȃ��Ă���悤�ɐM���Ă��܂����B�₽��ɊO���珬�������ė��邱�Ƃ������Ă���Ƃ͍��ł����X�ɂ���܂��B�쌴����Ԃ��������ė���Ɖɂ�����Ƃ�������A�����̂͂���������e����Ƃ����āA������Ƃɓ����Ɛe���a�C�ɂȂ�ȂǂƂ������̂��A�܂�q���Ȃǂ̂�����ɂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��҂��A�J������q�肷��l�̐^�������邱�Ƃ����߂�ׂɂ������������̂��Ǝv���܂��B ������l�͖ő��ɐ��ƂɎ����ė��悤�Ƃ��Ȃ������̂ł����A�����킯�������Ď����ė���悤�Ȑ́A���͕s�v�c�����ꂽ�Ƃ����`���Ă���܂��B���B�b�O�암(���ƂȂ��)�̏�����Ƃ����C�݂ł́A�C�l(�Ȃ܂�)�����Ԃ̒��ɁA������͂����Ă����̂ŁA�����ΐ_�Ɩ��Â����J���Ēu���ƁA����Ƒ傫���Ȃ����Ƃ����āA���グ��悤�ȍ����ΐ_�̊₪���̋߂��ɂ���܂����B(�^���V���L�B�X�����k�S�e��b���z��(�������Ƃ܂�)) �B��(�����̂���)�̓����Ƃ������ł́A�̂��̕l�̐l���ނ�����Ă���ƁA���͒ނꂸ�Ɉ��茝�قǂ̐���ނ�グ�܂����B���܂�s�v�c�Ȃ̂ŁA�����ȋ{���Ĕ[�߂Ēu���܂��ƁA�������Ď����N�̌�ɂ́A���E�̔������j��܂����B����ō��x�͎Ђ�傫�����Ē����ƁA�܂����̊Ԃɂ�����������j�����Ƃ����āA��ɂ͂�قǗ��h�Ȃ��{�ɂȂ��Ă��������ł��B(�B�B�������L�B�������b���g(����)�S������) ���g�̈ɓ��Ƃ������ł��A�Ԃ��Ђ��Ă��܂��ƁA�f(�܂�)�̌`�����������Ԃɂ͂����ď��܂����B������̂Ă�Ƃ܂��������͂���܂��B����Ȃ��Ƃ��O�������āA�O���߂͎�ɑ務�ł������̂ŁA���̐�g�q(���т�)�喾�_�Ƃ����J��܂����B���ꂩ��ꂻ���y�n�̋��Ƃ��h���A�����܂��ق���̒��ő傫���Ȃ��āA�ܘZ�N�̂����ɂ͂ق��炪���肳���Ă��܂��̂ŁA�O�x�߂ɂ͂�قǑ傫�����Ē����������ł��B(�����^�B�������߉�S�ɓ�) ����������͂����C�݂ɑ��������悤�ł���܂��B�������p�̓�̒[�A�R��̍`�̋߂��ł��A�̂��̕ӂ̔_�v�����J��̓��ɒ�������(��)�݂ɍs���܂��ƁA���̊�̒��ɔ����������Ȑ��͂����Ă���܂����B�O�x�����݂����܂������A�O�x�Ƃ��������͂����ė���̂ŁA�s�v�c�Ɋ����Ď����ċA��܂����Ƃ��낪�A���ꂪ�������傫���Ȃ�܂����B�����Ă��{�����Ă��J�����Ƃ����`���āA�������{�����_�ЂƂ����Ă���܂��B�������Č�_�̂͂��Ƃ͂��̏��ł���܂����B(�F����(�������ɂ�)�n���b�[�l(����)�B���������b�K�h(���Ԃ���)�S�R�쑺����) |
|
|
���ꌧ�Ȃǂō������X�̋��Ƃő�ɂ��Ă���́A�����͊C���������ł���܂��B�ʂɂ��̌`��F�ɕς����Ƃ��낪�Ȃ��̂����܂��ƁA����������E���グ�����ɁA�s�v�c�Ȃ��Ƃ��������̂ł��낤�Ǝv���܂��B�F��(����)�ɂ͐ΐ_���Ƃ����m���̉Ƃ����X�ɂ���܂����A��������R�c�Ƃ������̐ΐ_�_�Ђ��A�Ƃ̎��_�Ƃ��Ĕq��ł���܂����B���̂��Ђ̌�_�̂��A�����F�������傫�Ȍ�e(�݂���)�̗l�Ȑł���܂����B�̐�c�̐ΐ_�d���Ƃ����l���A�n�߂Ă��̍��֗��鎞�ɓ��ŏE�����Ƃ������A���͒��N�����̎��ɓ����Ŋ��������Ƃ������A����������̋{�Ԏ��̐̔@���A���܂̊Ԃɝp�܂��ĉ��x�̂ĂĂ��܂��͂����Ă�������A�E���ė����Ƃ����b������܂����B�����������ł͉^�����邱�Ƃ��o���Ȃ����̑�ł�����A�������͂�i���Ԃɂ͐��������̂ł���܂��B(�O�������}��B���������F���S�i�����R�c)
�ɐ_�l�̂��͂������ƁA�̂̐l�͐M���Ă����̂ŁA�n�߂����_�Ƃ����J�����̂ł͂Ȃ��̂ł����A�_�̖���m�邱�Ƃ��o���ʂƂ��ɂ́A�����ΐ_�l�Ƃ����Ĕq��ł����悤�ł���܂��B���ꂾ����y�n�ɂ���āA�̂��邨�Ђ̖������낢��ɂȂ��Ă���܂��B����(�т�)�̉����̐ΐ_�ЂȂǂ́A���̐l�����͉��c�F(���邽�Ђ�)��_���Ǝv���Ă���܂����B���̐Ȃǂ����������ɐ�������Ƃ����āA��ɂ͏c�����Ɉ��ȏ�ɂ��Ȃ��Ă��܂����B���ʂɂ͐ΐ_�͘H�̂������ɑ����A���c�F���܂����H�����_�ł������ׂɁA���R�ɂ����M����悤�ɂȂ����̂ł���܂��B(�|�˒ʎu�B�L�����b��k(�Ђ�)�S�b���z��(���ʂ�)������) �헤(�Ђ���)�̑�a�c���ł́A��ɂ͎R�̐_�Ƃ����J���Ă���܂����B����͒n�ʂ̒�����@��o�����Ɠ`���Ă���܂��B�n�߂��Ԃ̒��ɓ����قǂ̏��ł������̂��A�������傫���Ȃ�̂ŁA�����Ƃ���֎����ė��Ēu���ƁA���ꂪ���悢�搬�����܂����B����Ŏ��(�ʂ�����)�喾�_�Ə����Ă����Ƃ����`���Ă���܂��B(�V�ҏ헤���u�B��錧�����S�b�b(�Ƃ���)����a�c) �ɂ͌������O�Ȃǂ͂Ȃ��̂����ʂł����A�����������Ƃ��炾��ɖ����o����悤�ɂȂ�܂����B�ɐ��A�F����ɐ��̐_�A�F�쌠���̂��Ђɂ���悤�ɁA�o�_�A�g�c�A�x�m�A�F���Ȃǂ��A���Ƃ��Ƃ��ꂼ��̐_���J��l�������A��ɂ��Ă����ł���܂����B���q���������q�̔����l�́A���͂Ő����������̂ƍl���Ă����̂��낤�Ǝv���܂��B�������ǂ����ė��������悭����ʐɂ́A�l���܂��В��Ƃ��ԐƂ����悤�ȁA�ȒP�Ȗ����Ēu�����̂ł���܂��B �H��̐�k(����ڂ�)�̈��̑�̕s�����ɂ́A�N�X�傫���Ȃ�Ƃ����ڂقǂ̊₪�����āA�����������ƌĂ�ł���܂����B������Ƃ����̂͂��̒n���ŁA�傫���Ȃ�Ƃ����Ӗ��̕����ł���܂��B(���V�o�H�H�B�H�c����k�S��쐼����) ����̎R���̓c�ɂɂ͂܂��Ԏq�Ƃ����̂�����܂����B����͎͐̂O�ڂ���ł������̂��A��ɂ͐������Ĉ��l�ڂɂ��Ȃ��Ă�������ŁA����Ȃɑ傫���Ȃ��Ă��Ȃ��Ԏq�Ƃ����āA���Ƃ�Y��Ȃ������̂ł���܂��B(�|�˒ʎu�B�L������k�S��a���Í�) ��˂̐��ˑ��ɂ́A����Ƃ�����₪����܂����B�C��(��)�Ƃ����L�Ɍ`�����Ă��邩��Ƃ��\���܂������A�n�}�ɂ͔{��Ə����Ă���܂��B����������������Ƃ������傫�����{�ɂ��Ȃ����Ƃ����̂ŁA�{��Ƃ����n�߂����̂��낤�Ǝv���܂��B(�㑾�㕗�y�L�B���v�c�S����������) �d�B�ɂ͐��{�Ƃ������������������X�ɂ���܂��B���Ƃ��Ή���(����)�S�̖���̓����Ȃǂ��A�y�n�̐l�͂܂����{�Ɛ\���܂����B���傤�Nj����̗т̒��ɂۂ�ƈ�����āA�������l�ځA�����O�ځA�f�̗l�Ȍ`�ł����������ł�����A�O�ɂ͏����������̂��������L�тđ傫���Ȃ����ƁA�����`���Ă������̂Ǝv���܂��B�����Ƃ������O�͕��X�ɂ���܂����A�ǂ��������傫�Ȋ�ŁA�ƂĂ��l�Ԃ̗͂ł͓�����ꂻ�����Ȃ����̂���ł���܂��B(�d����(�͂�܂�����)�B���Ɍ����ÌS������㌳) �����Ԑ́A�l�����ӂ����n�߂����ɂ́A�����]���傫���Ȃ��Ă����悤�ł���܂��B�������ēy�n�ŕ]���������Ȃ��Ă����́A�ق�Ƃ��͂��܂�傫���͂Ȃ�܂���ł����B�O�ɂ��b�����������̌F��Ȃǂ��A�F�삩��E���ė����������܂̒��ŁA�����傫���Ȃ��Ă����Ƃ������炢�ł���܂������A��ɂ͂���Ɛ������ڂɗ����Ȃ��Ȃ�܂����B��\�N�O�ɔ�ׂ�ƁA�ꐡ�͑傫���Ȃ����Ƃ����l������A���N�Ĉꗱ���͑傫���Ȃ��Ă���̂��Ƃ����l������܂������A����͂��������v���Č����Ƃ��������ŁA��x���̐��@�𑪂��Č��悤�Ƃ����҂́A���ۂ͂Ȃ������̂ł���܂��B���͏o�_�̔ѐΐ_�Ђ̐_�̂悤�ɁA���Ƃ͂��Ђ̒����J���Ă������Ƃ����A�܂��͒}��̑�ΐ_�Ђ̔@���A�ȑO�̂��{�͍��̂����A�����Ə����������Ƃ����b�͕��X�ɂ���܂����A����͉����̂̂��Ƃł����āA�̑傫���Ȃ��čs���Ƃ�����A���Ă���Ƃ������Ƃ͒N�ɂ��o���܂���B�(�����̂�)�̂悤�ɑ�������������̂ł��A��͂�l�̒m��ʂ����ɑ傫���Ȃ�܂��B�܂��Ă�͌N����̍��̂ɂ�����ʂ�A������̊�(���킨)�ƂȂ閘(�܂�)�ɂ́A���ɉi���N���̂�������̂ƍl�����Ă����̂ł���܂��B�܂�͈�̓y�n�ɏZ�ޑ����̐l���A�Â����狤�����āA�͐���������̂��Ǝv���Ă����ׂɁA���������b���ĐM�p�����l�����������Ƃ��������ł���܂��B�@ |
|
| ���R�̔w����� | |
|
���o���ʂ��ɑ傫���Ȃ낤�Ƃ��āA���s�����Ƃ����b���c���Ă���܂��B�Ⴆ�Ώ헤(�Ђ���)�̐Γߍ�(�����Ȃ���)�̓��̐́A�����X�X�L�тēV�܂œ͂����Ƃ��Ă����̂��A��(����)�̖��_�������݂ɂȂ��āA�S�̌B(����)���͂��Ă��R(��)����Ȃ��ꂽ�B��������Ɛ̓�����ɍӂ��A��͔��ō��̉͌��q(����炲)�̑��ɁA��͐ΐ_�̑��ɗ����āA����������̓y�n�ł͂ق�����J(�܂�)���Ă����Ƃ����b������܂��B����ɂ́A�V�̐_�l�̌䖽�߂ŁA�������ďR������Ƃ������āA�Γߍ�ł͂��̎c�����̍����A���_�ƌĂ�ł���܂����B�����͌���肵������܂��A����͎R��t�ɍ����āA�Ȃ�قǂ������̂܂܂Ő���������A��ςł������낤�Ǝv���悤�ȑ��ł���܂����B(�×w�W�����B��錧�b�v��(����)�S��{���Ζ���)
�����b���R�c(����܂�)���̂͂���Ƃ����Ђ̎��͂ɂ��A�傫�Ȑ̒��̒Z���܂ꂽ�悤�Ȃ��̂��A�����ɓ]�����Ă���܂������A�������̂̐_��(���݂�)�ɐ��������āA���̒��ɓV��˂��������Ƃ��Ă����̂��A�_�l�ɏR�����āA���̂悤�ɏ������܂ꂽ�̂��Ƃ����Ă���܂����B(�a��B�ѓ�S�u�B��茧�a��S���R�c��) ����(�݂Ȃ݂�����)�̐X�ˑ��ɂ́A�X�˂̗���Ƃ����傫�Ȋ�R������܂��B�̂��̎R���傫���Ȃ낤�Ƃ��Ă������ɁA��͂肠��_�l�����āA���̓����R�܂�ꂽ�Ƃ����Ă���܂��B�������Ă��̂�����������ė��āA�t���ɒu�����̂����ꂾ�Ƃ����āA�ׂ�̊≺�̕����ɂ͋t��Ƃ�����������A����l�\���قǂ̑傫�Ȋ₪���ł�����܂��B(���ÌS�ē����B���������ÌS�b�ي�(���Ă���)���X��) �R��Ȃǂ̂悤�ɏ��X�ɑ傫���Ȃ������̂ƁA�v���Ă����l�����Ƃ͂������̂����m��܂���B�x�m�R�Ȃǂ���́b�ߍ]��(�����݂̂���)������ŗ������̂ŁA���̐Ղ����i(�т�)�ɂȂ����̂��Ƃ����b������܂����B���B�̒Ìy�ł́A��؎R�̂��Ƃ�Ìy�x�m�Ƃ����Ă���܂��B�̂��̎R�����̂����ɑ傫���Ȃ낤�Ƃ��Ă��鎞�ɁA����Ƃ̂��k���钆�ɊO�֏o�Ă�����������̂ŁA�������������L�т邱�Ƃ��~(��)�߂Ă��܂����B�N�������ɂ�����A�����ƍ����Ȃ��Ă��锤�ł������Ƃ����b�ł���܂��B�֏�(���킫)�̌��J(���ʂ�)���̌��J�x�m�́A�x�m�Ƃ͂����Ă���S���[�g���قǂ̎R�ł����A��������傤�ǒn����N(��)���o�������ɁA����w�l����������āA�R�������Ȃ�Ƒ傫�Ȑ��ł������̂ŁA�����Ȃ邱�Ƃ��~�߂Ă��܂��܂����B������������Ȃ��Ƃ�����Ȃ�������A�V�ɂƂǂ��������m��ʂƁA�y�n�̐l�����͂����Ă���܂��B(���y������ҁB�������b���(���킫)�S���쑺���J) �x��(���邪)�̑����R(�����������)�́A��́b���z(���낱��)�Ƃ���������A�x�m�Ɣw����ׂ����ɓn���ė����R���Ƃ����b������܂��B���C�����D�ԂŒʂ鎞�ɁA���傤�Ǖx�m�R�̑O�Ɍ�����R�ŁA�������������Ē��X�傫�ȎR�ł����R�̓�������܂���B����͑���(��������)�R�̖��_�����ӋC�ȎR���Ƃ����āA���������ďR�������ꂽ�̂ŁA����ő����͒Ⴍ�Ȃ����̂��Ƃ����Ă���܂��B���̎R�̂����炪�C�̒��ɎU����Ă����̂��A����W�߂ĊC�݂ɁA��������̗��n�������炦�܂����B���ꂪ�����������ŁA���������S�����ʂ��ċ��܂����A�ȑO�̓��H�͏\����(���イ�肬)�Ƃ��������z���āA�x�m�Ƃ��̑����R�Ƃ̊Ԃ�ʂ��Ă���܂����B�������ĉE�ƍ��ɓ�̎R��������ׂāA�̗̂��l�͂���Șb�����Ă����̂ł���܂��B(���{���q�B�É����b�x��(����Ƃ�)�S�{�R��) ����(�ق���)�̑�R(��������)�̌�ɂ͊؎R(������)�Ƃ�������R������܂��B�������R�Ɣw����ׂ����邽�߂ɁA�킴�킴��(����)����n���ė����R������A����Ŋ؎R�Ƃ����̂��Ƃ����`���Ă���܂��B���ꂪ���������R�������������̂ŁA��R�͕��𗧂ĂāA�ؗ�(�ڂ���)���͂����܂܂Ŋ؎R�̓����R������Ƃ����܂��B�����獡�ł����̎R�̓��͌����Ă���A�܂���R���͑啪�Ⴂ�̂��Ƃ������Ƃł���܂��B(���y������ҁB���挧�b����(�����͂�)�S��R��) ��B�ł́A���h�R�̓���ɁA�L�x(�˂�����)�Ƃ����������`�̎R������܂��B���̎R���������h�Ə䋣(��������)�ׂ����悤�Ƃ��Ă��܂����B���h�R���{���Ă���|�̏�������āA�n�I�L�x�̓���ł��Ă����̂ŁA���������ēʉ�(�ł��ڂ�)�ɂȂ�A�܂����̂悤�ɒႭ�Ȃ����̂��Ƃ����܂��B(�}����b���(�݂�)�W�����B�F�{�����h�S�b����(�͂�����)��) �R���w����ׂ������Ƃ����`���́A�����Ԃ�L���s���Ă���܂��B�Ⴆ�Α�p�̉��n�ɏZ�ސl���̒��ł��A�����R(�ނƂ�����)�Ƒ啐�R(�����Ԃ���)�Ƃ̌Z��̎R���������āA��̑啐�R���Z�̖����R�����܂��Ĉ�l�ł��邷��Ƒ傫���Ȃ����Ƃ����b������܂��B���ꂾ����啐�R�́A�Z���������̂��Ƃ����Ă���܂��B(����(������)�`���W�B�p�C�������}�V�N�W��) ���ꂩ��܂��Â�����ɂ��A�����`�����������̂ł���܂��B�ߍ]���ł́A���̉����_���R(���Ԃ����)�ƍ�������ׂ��������ɁA���̉��͒_���R�̖�(�߂�)�ł���܂������A���̒��ɐL�тāA�f������ɏ��Ƃ��Ƃ��܂����B�_���R�̑��X���F(�����݂Ђ�)�͑傢�ɓ{���āA�����Đ��P����(����)���܂��ƁA���ꂪ�ΐ��̒��֔��ōs���ē��ɂȂ����B���̒|����(�����Ԃ���)�́A���̎�����o�����Ƃ������Ƃ��A������N���O�̐l�������`���Ă���܂����B(�Õ��y�L�핶�l�B���ꌧ�����S�|����) |
|
|
��a�ł͓V���v�R(���܂̂������)�Ǝ����R(�݂݂Ȃ����)�Ƃ��A���T�R(���˂т��)�̂��߂Ɍ���(����)�������b���A�Â��ޗǒ��̍��̉̂Ɏc���Ă���܂��B����Ƃ悭�����`���́A���B�̖k���̏㗬�ɂ�����܂��āA���R�Ƒ��n���R(�͂₿�˂���)�Ƃ́A���ł������D���Ȃ��悤�ɂ����Ă���܂��B�D�ԂŒʂ��Č��܂��Ɠ�̂��R�̊ԂɁA�P�_�R�Ƃ����������ǎR�������܂��B�����͂��̕P�_�R�̎�荇���ł������Ƃ������A���͂��̔��Ɋ��R�͕P�_���ɂ���ŁA����R�Ƃ����R�ɂ������āA�����֑��点�悤�Ƃ����̂ɁA����R�͂��̖�ڂ��͂����Ȃ������̂ŁA�{���Č����Ă�������������B���ꂪ���ł����R�̉E�̘e�ɍڂ��Ă��鏬�R���Ƃ������܂����B(���؎��̓��{�`���W�B��茧���S���)
���{�l�͉i���N���̊ԂɁA����Ɖ���������ڏZ���ė��������ł��B�̈�x���������b�������Ƃ̂���҂̎q�⑷���A�����O�̂��Ƃ͖Y�ꂩ���������ɁA�m�炸���炸�����悤�ȑz���������Ƃ��������ŁA�킴�Ƃ悻�̓y�n�̓`����^���悤�Ƃ����̂ł͂���܂��܂����A�R���E���ɍ������т��āA���������ł����Ă���悤�Ɏv����ꍇ���A�s����X�̑����̌i�F�ɂ͂���̂ŁA����������ƒ��߂Ă��āA���x�ł�����Ȑ̘b�����o�������̂ƌ����܂��B �X�̎s�̓��ɂ��铌��(�����܂���)�Ȃǂ��A�́b���b�c�R(�͂�����������)�ƌ��܂����Ďa���Ĕ�Ƃ����āA������̂悤�ȎR�ł���܂��B�����������Ŋ�؎R�̏�ɗ����A��؎R�̌��ɂ��(����)�݂����ȏ��R������Ă���̂��A���̓��Ԃ���ł������Ƃ����l������܂��B�Ìy����̓y�n���삦�Ă���̂́A���̎��̌������ڂ�Ă��邩�炾�Ƃ������܂��B�������Ċ�؎R�Ɣ��b�c�R�Ƃ́A���ł������D���Ȃ��Ƃ����b������܂��B(���؎��̓��{�`���W�B�X�����Ìy�S���ԑ�) �o�H�̒��C�R(���傤��������)�́A���Ɠ��{�ň�ԍ����R���Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪�l�����āA�x�m�R�̕����Ȃ������Ƃ������̂ŁA����(����)�����ĕ��𗧂ĂāA���Ă������Ă�����ꂸ�A�����������C�̌����֔��ōs�����B���ꂪ�����̔�(�Ƃт���)�ł���Ƃ����܂��B�͊C�݂����\�}�C�������ꂽ�C�̒��ɂ��铇�ł����A���ł����C�R�Ɠ����_�l���J���Ă���܂��B����ɂ͕K���[���킯�̂��邱�ƂƎv���܂�����ǂ��A���������ς����̘b��葼�ɂ́A�����̂̂��Ƃ͉�����`����Ă���܂���B(���y�����O�ҁB�R�`���b�O�C(������)�S��) �����邱�Ƃ̌����Ȏ҂́A�����ĎR����ł͂���܂���ł����B�S�̂ɓ��{�ł́A�y�X�����l�̗D�������͈̂������ƂƂ��Ă���܂������A��ʂ�����J���ė���ƁA�ǂ����Ă����������]�������Ȃ���Ȃ�ʏꍇ�������A������܂���ւ�ɋC�ɂ���Õ��ȍl�����A�_�ɂ��l�Ԃɂ������Ȃ������悤�ł���܂��B���g�̊C����(�����ӂ���)�̐����ɂ́A��(�Ƃǂ�)���̑�A�ꖼ�����]��(���ꂢ)�̑�Ƃ����傫�ȑꂪ�����āA�R�̒��ɉ��]�����_�Ƃ����Ђ�����܂����B���̑�̋߂��ɗ��āA�I�B�F��̓ߒq�̑�̘b�����邱�Ƃ͋֕��ł���܂����B�ߒq�̑�Ƃǂ��炪�傫�����낤�Ƃ�������A�܂��͂��̑�̍����𑪂��Č��悤�Ƃ����肷��ƁA�K���_�̂����肪�������Ƃ����̂́A�������̕����ߒq���������������������߂ł��낤�Ǝv���܂��B(�����^�B�������C���S��㑺����) ���Ȃǂ́A��ɉ����̐l�������ʍs����̂ŁA���x���̓y�n�̋��̉\(���킳)�����Ƃ��������낤�Ǝv���܂����A�������Ɍ����Ƃ����b�������̂ł���܂��B���̐_�́A�����Ă˂��ݐ[�����̐_�l�ł���Ƃ����Ă���܂����B �b�{�̋߂��ɂ��鍑��(���ɂ���)�̑勴�Ȃǂ́A���̒������A���Ƃ͕S���\�Ԃ������āA�b�㍑(�����̂���)�ł́A��ԑ傫�ȁA�܂��Â����ł���܂������A���̋���n��Ԃɉ���(����͂�)�̂��킳�����邱�ƂƁA��{(�݂̂̂�)�Ƃ��������������������ƂƂ��֕��ŁA���̉��߂�j��ƁA�K�������낵�����Ƃ��������Ƃ����܂����B���ł��y�n�̐l�����́A�����Ă����������Ƃ͂��ʂł��낤�Ǝv���܂��B�����͏���������ǂ��A���{�ɂ��������Ƃ��������ȋ��ł���܂�����A����Ɣ�ׂ��邱�Ƃ��A���̑勴���D�܂Ȃ������̂ł���܂��B�������Ė�{�́A���̂˂��݂���������ł���܂����B(�R�����������B�R�������R���S����������) ��B�̓�̒[�A�F���̊J���x(��������)�̘[(�ӂ���)�ɂ́A�r�c�Ƃ����������ΎR������܂��B�ق�̋͂ȗ��n�ɂ���ĊC�Ɗu�Ă��A���������ɗ��ĂA�C�ƌΐ��Ƃ���x�ɒ��߂邱�Ƃ��o���邭�炢�ł����A��m�Ɣ�ׂ��邱�Ƃ��A�r�c�̐_�͔��ɂ��炢�܂����B�������Čΐ��̋߂��ɗ��āA�C�̘b��A�M�̘b������҂�����ƁA�����ɑ啗�A���Q�������āA���������i�F�ɂȂ����Ƃ������Ƃł���܂��B(�O�������}��B���������b�K�h(���Ԃ���)�S�w�h��) �ΐ���r���̐_�́A�����͏����ł���܂�������A��(�ЂƂ�)�B��Đ��̒��̂˂��݂��m�炸�ɁA�Â��ɔN���𑗂邱�Ƃ��o���܂����B�R�͂���Ƃ������āA�����̐l�ɏ�ɉ������猩���Ă��܂����߂ɁA�ǂ����Ă�����Ȃ���Ȃ�ʏꍇ�����������悤�ł���܂��B �L��̗R�z��(��ӂ���)�́A��B�ł������R�̈�ŁA�R�̎p���Y�X���������������̂ɁA�y�n�ł͖L��x�m�Ƃ������Ă���܂��B�́b���s(�������傤)�@�t������Ă��āA�b(����)���[�̓V��(���܂�)�Ƃ������ɂ������ɁA���̎R�߂Ĉ��̉̂��r�݂܂����B �L��(�Ƃ悭��)�̗R�z�̍����͕x�m�Ɏ��ĉ_�������݂��킩�ʂȂ肯�� ��������Ƃ����܂����̎R�������āA����ɕ������n�߂��̂ŁA����͂����������������ƐS�Â��āA �x�͂Ȃ�x�m�̍����͗R�z�Ɏ��ĉ_����(������)���킩�ʂȂ肯�� �Ɖr�ݒ������Ƃ��낪�A�قǂȂ��R�̏Ă���̂������܂����Ƃ����b�ł���܂��B���s�@�t�Ƃ����̂͊ԈႢ���낤�Ǝv���܂����A�Ƃɂ����Â����炱�������b���`����Ă���܂����B(���y������ҁB�啪���b����(�͂��)�S��[���V��) |
|
|
���Ƃ͂ق�Ƃ��ɂ��������Ƃ̂悤�Ɏv���Ă����l���������̂����m��܂���B�����łȂ��Ƃ��A�悻�̎R�̍����Ƃ����\������Ƃ������Ƃ́A�Ȃ邽���Ђ�����悤�ɂ��Ă����炵���̂ł���܂��B�����̘̐b�͂��ꂩ�琶��A�܂����Ƃ��Ă�����܂��Ȃ��ɗ��p����҂�����܂����B�Ⴆ�ΐ́b������(�Ђイ���̂���)�̐l�́A�(�悤)�Ƃ����ł����̂̏o�������ɁA�f�Z��(�Ƃ݂̂̂�)�Ƃ����R�Ɍ����Ă����������t�������Ĕq�����ł���܂��B���͏�ɂ��Ȃ��������Ǝv���Ă��܂������A���̂ł��������ł͂ȂȂ����������Ȃ�܂����B�������������Ȃ�A�������̂ł����̂��������܂��ĉ������Ƃ����āA�������x���n(����)�̂��������̂��ł��ɓ��Ă�ƁA�O���߂ɂ͕K������Ƃ����Ă���܂����B������R�̐_��������荂���Ȃ낤�Ƃ���҂��ɂ���ŁA�}���ł��̋n�������Ă�����������悤�ɁA������������������(�������)�����������̂��Ǝv���܂��B(�o���B�{�茧�b����(����)�S�s�_��)
�R���w����ׂ������Ƃ����Â������`���Ȃǂ��A��ɂ͎������肪���Ă����̘b�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������Ă���ɘb���ʔ����Ȃ�܂����B���̔ѓc�R(����������)�͌F�{�̎s����A���֎O�l���قǂ�����Ă���R�ł����A�s�̐��ɋ߂������R(����Ղ���)�Ƃ����R�ƁA�����̎������猖�܂������Ƃ����Ă���܂��B���܂ő����Č��Ă����������ʂ̂ŁA�����̎R�̒���ɔ�(�Ƃ�)�������n���āA���𗬂��Č��悤�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B��������Ɛ����ѓc�R�̕��֗���āA���̎R�̕����Ⴂ�Ƃ������Ƃ������ɂȂ�܂����B���̎��̐�����(����)�����̂��Ƃ����āA�R�̏�ɂ͍��ł���̒r�����邻���ł��B����ɂ͕������āA���������炻��Ȃ��Ƃ́u�����o����v�Ƃ������̂ɁA�R�̖�������������Ƃ����悤�ɂȂ����Ƃ��\���܂��B(���؎��̓��{�`���W�B�F�{���b��v��(���݂܂���)�S�і쑺) �������x�m�Ƃ����R�́A�������̖k�̋��A����(���邩)�̒r�̋߂��ɂ��鏬�R�ł����A�R�̎p���x�m�R�Ƃ悭���Ă���̂ŁA�y�n�̐l�����ɑ��h�����Ă��܂��B���ꂪ���ׂ�̖{�{�R(�ق�����)�Ƃ����R�ƍ�����ׂ����āA��͂����|������ʂ��Č����Ƃ����b���`����Ă���܂��B�������Č������ʂ��A���x�m�̕��̕����ɂȂ�܂����B���N�Z������̂��Ղ�̓��ɁA�[�̑��̎҂����Ђ��Ă��̎R�ɓo�邱�ƂɂȂ����̂́A�����ł����R�̍����Ȃ邱�Ƃ��A�R�̐_�l�����邩�炾�Ƃ����b�ł���܂��B(���{�����u�B���m���b�O�H(�ɂ�)�S�r�쑺) ����Ɠ����悤�ȓ`���́A�܂�����̔��R(�͂�����)�ɂ�����܂����B���R�͕x�m�̎R�ƍ������ׂ����āA���������邽�ߔ��n���Đ���ʂ��܂��ƁA���R�������Ⴂ�̂ŁA���͉���̕��֗���悤�Ƃ��܂����B��������Ă������R���̐l���A�}���Ŏ����̑���(��炶)���ʂ��ŁA������̒[�ɂ��Ă������Ƃ��낪�A����ł��傤�Ǒo�������ɂȂ����B����̂ɍ��ł����R�ɓo��҂͕K���Е��̑��܂��R�̏�ɁA�ʂ��Œu���ċA��˂Ȃ�ʂ̂������ł��B(��̓`���B�ΐ쌧�\���S������) ����|�����Ƃ������Ƃ͂܂������܂��A�z���̗��R�����R�Ɣw���ׂ������Ƃ����b������܂��B�Ƃ��낪���R�̕����A���傤�Ǒ��܂̈ꑫ�������Ⴉ�����̂ŁA���ɂ�����c�O����܂����B���ꂩ���́A���R�ɎQ�w(����)����l���A���܂������ēo��A���ɑ傫�Ȍ䗘�v(����₭)�������邱�Ƃɂ����Ƃ����Ă���܂��B(���y������ҁB�x�R���b��V��(���݂ɂ�����)�S) ���ꂩ��z�O�̔э~�R(���Ԃ���)�A����͓��ׂ̍r���R(���炵�܂��)�Ɣw����ׂ����āA�n�̌B(����)�̔��������Ⴂ���Ƃ��킩���������ł���܂��B����̂ɂ��̎R�ł��A�������ēo��҂ɂ́A������͊肢���Ƃ����Ȃ��Ƃ����āA���N�܌��ܓ��̎R�o��̓��ɂ́A�K���������čs�����ƂɂȂ��Ă���܂��B(����B���䌧���S��쒬)�B �O�̖͂{�{�R�ƁA�Ί��R(�����܂����)�Ƃ́A�L��(�Ƃ悩��)�̗�����u�ĂĐ����ɁA���ł���̈ȗ��̏䂭��ׂ𑱂��Ă��܂����A���̓�̕��́A�����������̍����Ȃ��Ƃ������Ƃł���܂��B����ŗ����Ƃ��ɐ���Ɏ����ēo��Ώ���������(������)��Ȃ����A����Ɣ��ɏ��Έ�ł������č~��ƁA�Q�w�͂ނ��ɂȂ�A�_�����K������Ƃ����܂��B�܂�Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ���Ɍ����̂ł���܂��B(��̓`���B���m���b����(���)�S�Ί���) �L���ȑ����̎R�X�ł́A�݂�Ȃ��w����ׂ̂��߂ł͂Ȃ����������m��܂��A���ɓy����ɂ��āA����������čs�����Ƃ����₪��܂����B�R�ɑ��܂��c���ė���K���́A���ł��܂����X�ɍs���Ă���܂��B���R�◧�R�ɂ͂���Ȑ̘b������܂����A���Ԃɂ͂����Ɛ^�ʖڂɁA���̗��R���l���Ă����҂����������̂ł���܂��B�Ⴆ�Ή��B�b���؎R(������)�̌����́A�R�Ɠy�����܂ɂ��āA������O�֏o�邱�Ƃ�ɂ��܂��Ƃ������ƂŁA�Q�w�����҂́A�K��������ʂ��̂ĂĂ���D�ɏ��܂����B(�������M�B�{�錧�b����(������)�S���쑺) �x�m�R�̂悤�ȑ傫�ȎR�ł��A��͂�R�̓y�������֎����čs����ʂ悤�ɁA�[�ɍ��U���Ƃ������������āA�ȑO�́A�K�������ŌÂ����܂��ʂ������܂����B�������ēo�R�҂��A���ݍ~�����{����(�����肮��)�̍��́A���̖�̂����ɍĂюR�̏�A���čs���Ƃ������܂����B ���˂̑�R�ł��A�R�̉��̍����A��������ƕ��ɏ��A���͂܂��[�ɉ���Ƃ����Ă���܂��B�R������܂��A�R�̗͂�M���Ă����l�����ɂ́A���ꂭ�炢�̂��Ƃ͓���O�ł����������m��܂��A����ł��o���邾���F�Œ��ӂ����āA�����ł��R��Ⴍ���ʂ悤�ɓw�߂Ă����̂ł���܂��B�x�m�̍s��(���傤����)�͎R�ɓo�鎞�ɓ��ɕ��݂�����ŐȂǂݗ����ʂ悤�ɂ��Ă��������ł����A�܂��ߍ]���̓y�������ė��āA���R�ɔ[�߂�҂������������ł���܂��B�x�m�͊F�l���䑶���̒ʂ�A��̋ߍ]�̓y�����ŁA���ɏo�����R���Ƃ����`���Ă��܂��̂ŁA����������Ƃ̍��̓y�������āA�����p���������Ƃ����̂ł���܂��B�@ |
|
| ���_������ | |
|
���{��̕x�m�̎R�ł��A�͕̂��X�ɋ����҂�����܂����B�l�������X�X�̓y�n�̎R���A���܂�ɔM�S�Ɉ�����ׂɁA�R�����������ɂ͂����Ȃ������̂��Ǝv���܂��B�Â��Ƃ���ł́A�헤�̒}�g�R(������)���A�Ⴂ����ǂ��x�m�����D���R���Ƃ����āA���̂��������`���Ă���܂����B��́b��c�_(�݂��₪��)�����X��������Ȃ���āA���̕��ɕx�m�ɍs���Ĉ��̏h�������߂Ȃ��ꂽ���ɁA�����͐V��(�ɂ��Ȃ�)�̍Ղ�ʼnƒ��������݂����Ă��܂�����A���h�͏o���܂��ʂƂ����Ēf��܂����B�}�g�̕��ł͂���Ɣ��ɁA����͐V���ł�����ǂ��\���܂���B�������������艺�����Ƃ��������Ȍ�y�������܂����B�_�l�͔��Ɍ��тŁA���̎R�i���h���l��ɗ�(����)��V�сA���H�̕����鎞���Ȃ��悤�ɂƁA�߂ł��������̏j�������A�̂ɉr��ʼn�����܂����B�}�g���t���H���X�Ɩ��āA�j���̊y�����R�ƂȂ����̂͂��ׂ̈ŁA�x�m������葽���A�o��l�������A�����H���ɕs���R������̂́A�V���̑O�̔ӂɑ�Ȃ��q�l���A�A���Ă��܂��������Ƃ����Ă���܂����A����͋^�����Ȃ��}�g�̎R�ŁA�y�����V��ł����l���肪�A���`���Ă����̘b�Ȃ̂ł���܂��B(�헤�����y�L�B��錧�}�g�S)
�x�m�Ɛ�ԎR�����肭��ׂ������Ƃ����b���A�����Ԃ�Â����炠�����l�ł����A����͂����c���Ă���܂���B�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ͕x�m�̎R���J(�܂�)��_���A�ȑO�����ԑ�_�Ə�(�Ƃ�)���Ă���܂����B�x�m�̋����҂̒}�g�R�̒���ɂ��A�ǂ������킯�ł����(����)�l���J���Ă���܂��B���ꂩ��ɓ������̓�̒[�A�_��(������)�̌�ԎR(�݂������)�ɂ���Ԃ̎ЂƂ����̂�����܂��āA���̎R���x�m�Ɣ��ɒ��������Ƃ����b�ł���܂����B���̍����炢���n�߂����̂��A�x�m�R�̐_�͖؉ԊJ��Q(���̂͂Ȃ�����Ђ�)�A���̎R�̐_�͂��̌�o�̔֒��Q(����Ȃ��Ђ�)�ŁA�o�_�͎p���X�������̂ɐ_�l�ł���͂��b��(�˂�)�݂��[���A����ł��̎R�ɓo���ĕx�m�̂��킳�����邱�Ƃ��A�o���Ȃ������Ƃ����̂ł���܂��B(�ɓ��u�����B�É�����ΌS�b���(���킵��)���_��) �Ƃ��낪���ꂩ��͓��܂藣��āA���c(������)�̒��̌�ɂ́A���c�x�m�Ƃ������R�������āA����͏x�͂̕x�m�̖��_���Ƃ����Ă���܂��B�������Ďo�l�����X�ɔ����������̂ŁA�����������̂��}(����)�ŁA�ԂɓV��R(���܂�����)��(�т傤��)�̂悤�ɂ����ĂɂȂ����B���ꂾ���牜�ɓ��͂ǂ�������x�m�R���������A�܂����l������Ȃ��ƁA�y�n�̐l�͂��������ł���܂��B�����������ƈ�̘b���A��ɂ����������ɕς��ė������̂��낤�Ǝv���܂��B(���y������ҁB�������S���c��) �z���b�M�q�R(�ӂ˂̂�����)�̐_�͎o�q�Q(���˂���Ђ�)�Ƃ����āA���Ɣ\�o�̐Γ��R(�����ǂ�����)�̈ɐ{����F(�����邬�Ђ�)�̉����ł����������ł��B���̈ɐ{����F����ɔ\�o�̞[�؎R(���܂����)�̐_�A�\�o�Q���ȂɂȂ��ꂽ�̂ŁA��̎R�̊ԂɎ��i(������)�̑������������Ɛ\���܂��B�z�q�R(�ʂ̂�����)�̕z�q�Q�͎o�q�Q�ɉ������A�b�R(���ԂƂ��)�̉��v���F(���ԂƂЂ�)�͔\�o�Q�������āA�傫�Ȑ_��(���݂�����)�ƂȂ����̂��A�����̐_�X���W���Ē��ق��Ȃ��ꂽ�Ɠ`���Ă���܂��B����ɂ͖��N�\���\����̍Ղ�̓��ɂ́A�M�q�ƐΓ��R�Ɛ��킪����A�M�q�̌������I(�Ԃ�)��ł��������̂ɁA���̎R�̘[(�ӂ���)�̖�ɂ͏����Ȃ��̂��Ƃ������Ă���܂����B(�m�\��B�^���B�x�R����V��S�D�葺�M�q) ����Ɣ��ɁA���g�̊�q�R�͊�̑����R�ł���܂����B����͑�̂��̍��̑��R�ƁA���z(������)�R�Ƃ̊Ԃɐ푈�����������A�o�����瓊�����������ɗ���������Ƃ����Ă���܂��B�������č��ł����̓�̎R�ɐ������̂́A�݂ɂ킪�R�̐𓊂��s�������炾�Ƃ������Ƃł���܂��B(���n(�݂�)�S���y���B���������n�S��q��) ��������X�ɗL���Ȉ�̓`���́A��B(�₵�イ)�̓����R�Ə�B�̐ԏ�R�Ƃ̐_��ł���܂����B�Â���r(�ӂ���)�_�Ђ̋L�^�ɁA���킵�����̍���̂���l�������Ă���܂����A�ԏ�R�͂ނ��ł̌`�������ĉ_�ɏ���čU�߂ė���ƁA�����̐_�͑�ւɂȂ��ďo�łĂ����������Ƃ������Ƃł���܂��B�������đ�ւ͂ނ��łɂ͂��Ȃ�ʂ̂ŁA�����̕������������ɂȂ��Ă������ɁA���ۑ��v�Ƃ����|�̏��ȐN�������āA�_�ɗ��܂�ĉ��������āA���܂��ɐԏ�̐_�������ނ����B���̐�������L����ꂪ���Ƃ����A���͗���Đԏ��ƂȂ����Ƃ������Ă���܂��B�N�������Ă��A�ق�Ƃ��Ƃ͎v���Ȃ��b�ł����A�ȑO�͓����̕��ł͂����M���Ă����ƌ����āA�㐢�ɂȂ�܂ŁA���N�����̎l���̓��ɁA����(�Ԃ���)�Ղ�Ə̂��Đ_�傪�R�ɓo��ԏ�R�̕��Ɍ����Ė���˕��V��������܂����B���̖�ԏ�R�ɓ͂��Ė��_�̎Ђ̔��ɗ��ƁA���q�����͖���̖݂Ƃ����̂������āA���̖���Ă��Ղ�����邻�����ȂǂƂ����Ă���܂������A�ʂ��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ����������̂��ǂ����B�ԏ�̕��̘b�͂܂��킩��܂���B(��r�R�_�`�B�����R���Վu��) �����������Ƃ��ԏ�R�̎��͂ɂ����Ă��A���̎R�������ƒ��������������ƁA���ꂩ���̐_�킪�����āA�ԏ�R�������ĉ�����Ȃ��ꂽ���ƂȂǂ������`���Ă���܂��B�����S�b�V�_(��������)�̉���Ȃǂ��A���ł͘V�_�Ƃ������������Ă��܂����A���Ƃ͐ԏ�̐_������ɕ����āA�����Ă����܂ŗ���ꂽ�̂ɁA�ǐ_�Ƃ������ƂɂȂ����Ƃ������܂����B(���(��������)�u�B�Q�n�������S�����V�_) |
|
|
���ꂩ��܂��ԏ閾�_�̎��q�����́A�����ē����ɂ͌w(�܂�)��Ȃ����������ł���܂��B�ԏ�̐l���o���ė���ƕK���R���r���ƁA�����ł͂����Ă���܂����B�����ł�����(��������)�͂��Ə�B�̐l�̊J�����y�n�ŁA�����ɂ͐ԏ�R�̐_���J�����Â�����̐ԏ�_�Ђ�����܂����B���̋����ɂ͓��쎁�̕��m���������̋߂��ɏZ��ŁA�ԏ�l�̎��q�ɂȂ��Ă��܂������A���̐l�����͓����Ɍw�邱�Ƃ��o���Ȃ����������ł���܂��B����������ڂ������āA���Ѝs���Ȃ���Ȃ�ʎ��ɂ́A���̑O�Ɏ��_�ɗ��R�������āA���̊Ԃ����͎��q�𗣂�A�z�y(����)�̔������̎s�J(��������)�̔������̂́A���̎��q�ɂȂ��Ă���o�������Ƃ������Ƃł���܂��B(�\�����V���G�L)
���B�Ìy�̊�؎R�̐_�l�́A�O�㍑�̐l�����ɂ��������Ƃ������ƂŁA�m�炸�ɗ����ꍇ�ł��K���Ђ�����܂����B�̂͊C���r�ꂽ�舫���z�C�̑������ɂ́A������O��̎҂����荞��ł͂��Ȃ����ƁA�h����`�̑D��В[���炵��ׂ������ł���܂��B����͂��̎R�̐_���܂��l�Ԃ̔��������P�l�ł��������ɁA�O��̗R��(���)�Ƃ������łЂǂ��߂ɂ��������Ƃ�����������A���̂��{���[���̂��Ƃ����Ă���܂����B(���V�G�L���̑�) �M�B���{�̐[�u(�ӂ���)�̓V�_�l�̎��q�����́A�������̐l�Ɖ��g�݂����邱�Ƃ�����܂����B����͓V�_�͐������^(�������݂̂�����)�ł���A�������̎��_�b��(����)�̋{�́A���̋����҂̓����b����(�Ƃ��Ђ�)���J���Ă��邩�炾�Ƃ������ƂŁA�Ŗ�����łȂ��A����ɗ����҂ł��A���̑��̎҂͉i�炭���邱�Ƃ��o���Ȃ����������ł���܂��B(���y������ҁB���쌧�b���}��(�Ђ���������)�S������) ������_���J�����Ƃ������Ђ́A�܂�����(������)�̌Í](�ӂ邦)���ɂ�����܂����B������ׂ�̍���(�������)�Ƃ������ɁA����(����)���J��������̎Ђ������āA�O���炻�̑��ƒ������������䂦�ɁA���������z���������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̓�̑��ł́A�j���̉������ԂƁA�K�������悭�Ȃ��Ƃ����Ă����݂̂Ȃ炸�B�Í]�̕��ł͒�ɔ~�̖�A�����A�܂���(�ӂ���)����(�т傤��)�̊G�ɔ~��`�������A�ߕ��̖�l�ɂ����߂Ȃ������Ƃ������Ƃł���܂��B(���h(����)�j�B�Ȗ،����h�S�b����(���ʂԂ�)������) �����̎��X��(������)��a�c�Ƃ���������ł��A��قǍL�����ɂ킽���āA���Ƃ͈�ӏ����V���{���J���Ă��܂���ł����B���̗��R�͒���̎Ђ����������ŁA�V�_�̓G�ł��邩�炾�Ƃ����܂������A�ǂ����Ď�����b���J��悤�ɂȂ������́A�܂����������Ă͂���܂���B(�Ñ����b杊C(����)�B��t���b���(�����)�S���X�䒬) �O�g�̍����Ƃ������́A���Ǝ������̗̕��ł����āA�����ɂ͎������~(���ւ��₵��)������A���̎q���̎҂��Z��ł������Ƃ�����Ƃ����Ă��܂����B����͂������Șb�ł��Ȃ������悤�ł����A���̑��ł��V�_���J�邱�Ƃ��o�����A���܂��܉摜(������)�������ė���҂�����ƁA�K������(�ނ�����)���N���Ă��̉摜����Ɋ����グ�A�ǂ��ւ��s���Ă��܂��Ƃ����`���Ă���܂����B(�L�v�����و�сB���Ɍ��b���I(����)�S��k��) �����̂���A�V�_�l���J�邱�Ƃ̏o���Ȃ��킯�������āA���ꂪ�����s���ɂȂ��Ă���̂ł���܂��B���ꂾ���瑺�ɎЂ�����Γ��������̂悤�ɁA���O�������^�ƒ������������l�́A�Ђł���悤�ɑz���������̂��Ǝv���܂��B����s�̋߂��ɂ��V�_���J��ʑ�������܂������A�����ɂ͈�̌Ò˂������āA������������̕悾�Ƃ����Ă���܂����B����ȏ��ɕ悪����͂��͂Ȃ�����A��͂��ɂȂ��ĒN�����l���o�����̂ł���܂��B(���Ɍ��L�B���挧����S) �������V�_�ƒ����P���Ȃ��Ƃ������Ђ͑��ɂ�����܂����B�Ⴆ���s�ł͕���(�ӂ���)�̈��(���Ȃ�)�́A�k��̓V�_�ƒ��������A�k��ɎQ�����Ɠ������ɁA��ׂ̎ЂɎQ�w���Ă͂Ȃ�ʂƂ����Ă��������ł���܂��B���̗��R�Ƃ��Đ��������Ă����̂́A�������Ƃ��������悤�Ȑ̘b�ł���܂����B�͎̂O�\�Ԑ_�Ƃ����ċ��̎��͂̐_�X���A�����������߂ċ֒��̎������Ă���ꂽ�B�������^�̗삪��(�炢)�ɂȂ��āA�䏊�̋߂��ɗ��Ă��ꂽ���́A���傤�Lj�ב喾�_�����Ԃł����āA�_�ɏ���Č���Ă����h���A�\���ɂ��̈З͂�U�킹�Ȃ������B����䂦�ɐ_���J���Č�܂ŁA�܂��k��̓V�_�͈�Ђɑ��āA�{���Ă�����̂��Ƃ����̂ł���܂����A�������������̐l�������n�߂����Ƃɑ��Ⴀ��܂���B(�k���E�t�W�B�ډ��L��) ��(���邢)�͂܂��V�_�l�ƌ��t�l�Ƃ́A���������Ƃ����b������܂����B��t�̉����ɉJ���~��A�V�_���J��̓��͓V�C���悢�B��\������������V�Ȃ�A��\�ܓ��͕K���J�V�ŁA�ǂ��炩�ɏ�������������Ƃ������Ƃ��A���ł����̓c�ɂł��悭�����Ă���܂��B�����ł͌Ղ̖�̋������l(����҂炳��)�ƁA�y�k��(�������炿�傤)�̐��V�{(�����Ă�)�l�Ƃ������҂ŁA����̉��������V�C�Ȃ瑼�̈���͑��J���~��Ƃ����܂����A���Ƃ�����Ȃ͂��͂Ȃ��Ă��A�Ȃ����������C������̂́A�����ׂ͗蓯�m�̓�ӏ��̎Ђ��A�݂ɑ���ɂ��܂킸�ɂ́A��(�ЂƂ�)�Ŕɏ����邱�Ƃ��o���ʂ悤�ɁA�l�����Ă������ʂł��낤�Ǝv���܂��B |
|
|
������̂̐l�͎��_�Ƃ����āA��Ɏ����̓y�n�̐_�l���ɂ��Ă���܂����B�l���������ꂽ�Ƃ���܂ŁA���Q�������悤�ɂȂ��Ă��A�M�S������_���͓y�n�ɂ���Ē�܂�A�ǂ��֍s���Ĕq��ł��悢�Ƃ����킯�ɂ͍s���Ȃ������悤�ł���܂��B������̐_�l�ł����Ă��A����ł͉h�����̈���ł͐����邱�Ƃ��������̂́A�܂�͔q�ސl�����̋����ł���܂��B���s�ł͈Ɣn(�����)�̔�����l(�т������)�֎Q��H�ɁA����쒆���̔����哰�������āA���Ƃ͂���ɂ��݂̔�����ȂǂƂ����Ă���܂����B���������Ɣn�Ɍw���Ď������ė��������A�ɂ���ŒD���Ԃ����Ƃ����āA�Ɣn�Q�w�̐l�͂��̓���q�܂ʂ݂̂��A�킴�Ɣ����ē��̕��̘e�H��ʂ�悤�ɂ��Ă����Ƃ����܂��B�������̐_�ł��J���Ă���ꏊ���������ƁA���������w�邱�Ƃ͏o���Ȃ������̂�����ƁA���̑P���Ȃ��̂͐_�l�ł͂Ȃ��āA��͂�R�ƎR�Ƃ̔w���ׂ̂悤�ɁA�y�n��������l�����̕������������ł���܂����B�����̂��ЂȂǂ������ɌF��������āA�����ɌF��̐_�l�����~��Ȃ��ꂽ�Ƃ����b������A�ȑO�͂��̂��Ղ�����Ă������Ǝv���ɂ��S(������)�炸�A�����̎��q�͋I�B�̌F��֎Q���Ă͂Ȃ�ʂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂����B���ꂩ��F��̐l���������ď����ւ͎Q���ė��Ȃ����������ŁA���̂��܂��߂�j��ƕK�������肪����܂����B����Ȃǂ������o���̐M�����Ă������߂ɁA�������ē�S�܂�邱�ƂɂȂ������̂ł��낤�Ǝv���܂��B(�s�����}��E��B����(�ЂȂ�)�L��)
�ǂ����Đ_�l�ɒ��������Ƃ����悤�Șb������A���Q�肷����������Ƃ����҂��o�����̂��B���ꂪ����킩��Ȃ��Ȃ��āA�l�͗��j�������Ă��̗��R��������悤�Ƃ���悤�ɂȂ�܂����B�Ⴆ�Ή��R�Ƃ����c���̐l�́A�헤�̋����R(���Ȃ����)�ɓo�邱�Ƃ��o���Ȃ��B����͐̍��|���̐�c�����̎R���ď�(�낤���傤)���Ă������ɁA�����̉��R�}�̐l�������U�߂ė��āA��̎傪�v�����邱�ƂɂȂ������炾�Ƃ����Ă��܂����A���̎��Ɋ��q���R�̖��������āA�]�R�������m�͂�������܂����B���R�����肪���܂ł��ɂ��܂��킯�͂Ȃ�����A����ɂ͉������̌������������̂ł���܂��B(�����G�L�B��錧�b�v��(����)�S������) �����ł͐_�c(����)���_�̂��Ղ�ɁA���쎁�̎҂��o�ė���ƕK���킴�킢���������Ƃ����܂����B�_�c���_�ł͕�����(������̂܂�����)�̗���J��A����͂��̏�����U�߂ق�ڂ����U�����G��(�����Ƃ����Ђł���)�̌���(��������)������Ƃ����̂ł���܂��B�������c(���������Ȃ肽)�̕s���l�́A�G���̎�蕧�ł������Ƃ����b�ł���܂����A�����̋߂��̔���(�����킬)�Ƃ������̎҂́A�������Đ��c�ɂ͎Q�w���Ȃ����������ł���܂��B����͔��̎��_�b�Z(��낢)�喾�_���A��͂蕽����̊Z����_�̂Ƃ��Ă���Ƃ��������`��������������ł���܂��B(���Ó��^�B�����{�b�L����(�Ƃ悽��)�S����������) �M�B�ł͐z�K�̕��߂ɁA�牮�Ƃ����c���̉Ƃ���������ɂ���܂����A���̉Ƃ̎҂͑P�����ɂ��w�肵�Ă͂����Ȃ��Ƃ����Ă���܂����B�����ĎQ�w����ƍГ����ȂǂƂ������܂����B����͂��̉Ƃ������牮�A(���ׂ̂̂̂����̂ނ炶)�̎q���ł����āA�P�����̌�{�����g(�Ȃɂ�)�x�]�ɗ����̂Ă����������l(�ق��Ƃ��ɂ�)������Ƃ����̂ł���܂����A��������炭�͌�ɂȂ��đz���������ƂŁA�牮���͂��Ɛz�K�̖��_�Ɏd���Ă����Ƃł���䂦�ɁA���̐_����M�S���Ȃ������܂łł��낤�Ǝv���܂��B(�����M�L�\�B���쌧����s) �V�_�̂��ЂƋ��������ׂ�̑��̎��_���A�����������J��Ƃ������͖̂��ȊԈႢ�ł����A����Ƃ悭������͂܂��R�X�̔w����ׂ̘b�ɂ�����܂����B�x�m�ƒ��̈����ɓ��̉_���̎R�̐_���A�֒��Q�ł��낤�Ƃ����l������ƁA����x�m�̕��ł͂��̌䖅�́A�؉ԊJ��Q���J��Ƃ������ƂɂȂ�܂����B�ǂ��炪���������n�߂����͂킩��܂��A�Ƃɂ����ɂ��̓�l�̕P�_�͎o���ŁA����͔���������݂͂ɂ����A���݂��炨�������������悤�ɁA�Â����j�ɂ͏����Ă���̂ŁA���������z�����N�����̂ł���܂��B�ɐ��Ƒ�a�̍����̍����R�Ƃ��������R�́A�g���̐쉺�̕����猩��ƁA������(�Ƃ��݂̂�)�Ƃ����R�Ɣw����ׂ����Ă���悤�Ɍ����܂����A���̑�����ɂ͐̂���A��������(�ӂ����̂��܂���)���J���Ă���܂��䂦�ɁA�����R�̕��ɂ͑h�����(�����̂��邩)���J���Ă���Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B���������̂悤�ȎR�̒��ɁA�J���Ēu���͂��͂Ȃ��̂ł����A���̎R�ɓo��l�����͑�����̘b�����邱�Ƃ��o���Ȃ���������łȂ��A�����̂��Ƃ��v���o������Ƃ����āA���������ēo�邱�Ƃ��������܂��߂��Ă���܂����B���̂��܂��߂�j���Ċ��������čs���ƁA�K�����������Ƃ����A�܂��͎R�肪����Ƃ����Ă���܂����B(�����l�B�ޗnj��g��S������) |
|
|
���̍����R�̘[��ʂ��āA�ɐ��̕��։z���čs�����H�̘e�ɁA�������邩�Ǝv����₪�����܂����A�y�n�̐l�̘b�ł́A�̂��̎R��������ƌ��܂����ĕ��������ɁA�R�̓������ł����ɗ������̂��Ƃ����Ă���܂��B�������Č���Ƒh��������J������O����A�����R�ƎR�Ƃ̑����͂������̂ŁA���̑����ɕ��������̎R�̓����A��Ƃ����_���H��(����)�̔�(�Ƃт���)�A���͏헤�̐Γߍ�̎R�̊�ȂǂƁA���l�ł������̂ł���܂��B�ǂ����Ă���ȓ`���������ɂ������ɂ�����̂��B���̂킯�͂܂����킵���������邱�Ƃ��o���܂��A���Ƃɂ��ƕ�����ɂ͕���������ǂ��A����͕����V�ٌc������ۂ����ɍ~�Q�����悤�Ȃ��̂ŁA���������������ĕ��}�ȎR�ł͂Ȃ������ƁA�l���Ă����l�����������ׂ����m��܂���B�Ƃ��������R�ƎR�Ƃ̔w����ׂ́A���ł������čۂǂ����������ł���܂����B���ꂾ����l�͓ɂȂ����R�����y��(�����ׂ�)���Ȃ������̂ł���܂��B����(�Ђイ��)�̔і싽�Ƃ����Ƃ���ł́A�����܁b�q(�Ђ�)�قǂ̊₪�쌴�̐^���ɂ����āA����𗧐�(���Ă���)�����Ɩ��Â��Ĕq��ł���܂����B�������牓���Ɍ�����痯���R(���邻����)�̐Ⓒ�ɁA���s�k(���Ƃ�)�A�ω��Ƃ�����̑�₪����ł��āA�̂͂��̍�������S�������ł������̂��A��Ɋω����܂�āA�_�͂������Ĕ��ł��̖�ɗ��ė������B����̂ɍ��ł͒Ⴍ�Ȃ�܂�������ǂ��A�l�͂������Ă��̊ω��̓���q��ł���̂ł���܂��B(�O�������}��B�{�茧���b����(���납��)�S�і쑺���c)
���̎R��(��܂�)�ł͉��{�̕F��(�Ђ�����)�����̎R�ƁA����(������)�̕s����Ƃ͌Z��ł������Ƃ����Ă���܂��B�����͌p�q(�܂܂�)�ŕꂪ�哤����H�ׂ����A�s���͎��q�����珬����H�ׂ����Ă��܂����B��ɂ��̌Z��̎R���j����Ɋ|���Ď�������������ɁA�����R�͑哤��H�ׂĂ����̂ŗ͂������A�����ŗ{��ꂽ�s����͕����Ă��܂��āA����Ђ����ċv��(����)�Ƃ������ɂ��̎������Ƃ����āA���ł������ɂ͎��Ƃ����₪�����Ă��܂��B�h(���)����(����)�Ƃ�����͂��̂܂ɗ����Ă��āA��Ђ��̍j�Ɉ����|�����Ă�邢������h�ԁA�R�ɓ�̂��ڂƂ��낪�����āA�����������̐����Ȃ��̂��A�j�ł���ꂽ��(����)���Ƃ����A��������H�ׂĂ����Ƃ����s���̎��̋߂��ł́A���ł����̂��߂ɓy�̐F���Ԃ��̂��Ƃ��������ł���܂��B(��㍑�u���B�F�{���b���{(������)�S�O�ʑ�)�@ |
|
| ���`���Ǝ��� | |
|
���N�̉Ƃ̂܂��A�������邢�Ă��铹�H�̂������ɂ��A���Ƃ͂���������Ɩʔ����`�����A������Ƃ��Ȃ��c���Ă����̂ł���܂��B�w�Z�ɍs���l�����������������Ȃ��āA�b(����)�����܂킸�ɒu�������ɁA�����o���Ă��Ęb���Ă����l�����Ȃ��Ȃ�܂����B���ꂩ������������c�ɂȂ�A�����ȑ���͂�ĕЕt�����Ă��܂��ƁA�����͂��̂��킳�����邱�Ƃ��������đ�������ǂ��A��ɐ��ꂽ�҂ɂ͊����������̂ŁA���������ɖY��čs���悤�ɂȂ�̂ł���܂��B���Ȃǂ͂��̂��߂ɑ啪���т����Ȃ�܂����B
�`���́A���܂ł��Ȃ�v�����ԁA�q�������������ɂ��Ęb����Ă���܂����B��(������)����l���e�ɂ��Ă����Ă͂���̂ł����A���͂����炢�����邨�肪�Ȃ����߂ɁA�q���̂悤�ɉi���L�����āA�����ƌ�ɂȂ��Ă���A�܂����̐l�ɘb���Ă����ɁA�M�S�ɂ͂Ȃ�Ȃ������̂ł���܂��B�q���̂����炢�́A���̖̉��ŗV�сA�܂��݂͂�ȂƘA�ꂾ���āA���̊�̑O�╣(�ӂ�)�̏�A�r�̒�������ʂ��čs�����Ƃł���܂����B�b�͕s���肾����N�����킵���͘b���܂��A���̓x���Ɉꓯ�͑O�ɂ��������Ƃ�z���o���āA�b���͓����悤�ȐS�����ɂȂ��āA�݂Ɋ���������̂ł���܂��B�l���N������Ęb�����邱�Ƃ��D���ɂȂ�A�܂����ɂȂ��Č�ɁA�̂̂��Ƃ��Ƃ����Ă�������b�́A����́A�����������N�̍��ɁA�o�����b�����ł���܂����B������ǂ�ȘV�l�̋����Ă����`���ɂ��A�K�����鎞��̎������W���Ă���܂��B�������Ă����������W�����Ȃ�������A���{�̓`���͂����Ƒ����Ȃ��Ȃ邩�A�܂��͖ʔ����Ȃ����̂��葽���Ȃ��Ă����ɈႢ�Ȃ��̂ł���܂��B ������F���Ⴂ�����ɁA�����Ēu���b�������Ȃ�A�܂�������o���Ă��邱�Ƃ�����ɂނ������Ȃ�ƁA���������̔N��肽���̑��ɁA���ނ��O�͂Ȃ��̂ł���܂��B�����ɂ͑�l�ɂ�������悤�Șb�A��l����������悤�Șb�������̂ł���܂����A���ł͂��̒�����łȂ��ƁA�̂̎����̐S�������A�m�邱�Ƃ͏o���ʂ悤�ɂȂ�܂����B�����S�̂ɂ܂��N���Ⴍ�A�N�ł����N�̔@�����������Ƃ��������������āA�V�n�����߂Ă������オ�A���Ĉ�x�͏��N�̊Ԃɂ���A�����Ă������Ƃ�����܂����B�����͉�����Ă�������A�Ăя��N�Ɍ�낤�Ƃ��Ă���̂ł���܂��B ���Ƃ͏����Ȑl�����͊G����̖{��ǂނ悤�ɁA�ڂɂ��낢��̕��̎p�����Ȃ���A�Â�����̂����`������������v���o�����肵�Ă����̂ł���܂��B�_���̖ɗ��鑽���̏����́A���̚e(��)�����̂�������������Ă���ԁA����������т܂���Ęb�̋���Y���܂����B�H�̂قƂ�̂��܂��܂̐Ε��Ȃǂ��A�̘b��m���Ă���q�����ɂ́A���Ȃ����悤�ɂ����قق��ނ悤�ɂ��������̂ł���܂��B��(����)���ł��N���Ƃ��Ă����ɂ��̍��̂��Ƃ��l����҂ɁA��ԉ������������̂͒n���l�ł���܂����B�傫�������͏\���̎q�����炢�ŁA��͕����܂Ƃ��������A�l�Ԃ̒N���Ɏ��Ă���̂Ō��o��������܂����B�������Ă܂������̓`���̊Ǘ��҂������̂ł���܂��B �����ɕʂ̘b�A���̖��O�������Ă����̂��A�Βn���ɍł����������悤�ł���܂��B�������������̉i�N�̗F�������A���̊Ԃɂ����Ȃ��Ȃ肻���ł�����A�����ɂ͕S�N�O�̎q�����ɑ���āA�����Ɏc���Ă���O�l�̘b�����Ă݂܂��傤�B�Â�����L���ł������̂́A��(��)��(��)���n���ɐg���n���A�M�S������҂̐g���ɂȂ��āA��Ɍ���Ɣw���ɓG�̖�����Ă����ȂǂƂ����n���ł����A����͂܂����̐l�����̕s�v�c�ł���܂��B�y�n�ɉ��̐[���n���l�ɂȂ�ƁA���ɗ��܂��Ƃ����̂��߂ɓ����ĉ�����Ƃ����āA�ނ���ӊO�ȏo�����������Ă����ɁA�q�݂ɗ���҂��������đ����Ȃ�̂ŁA���̒��ł��A���Ƃɒn���́A�_�Ƃɑ��ē�������Ƃ������Ƃ��A�ꓯ�̊��ӂ���Ƃ���ł���܂����B����킸�̒n���Ƃ����̂́A���X�S���̎p�ɂȂ��āA�������������Ɏ�`���ɗ��ĉ�����B�������n���͓c�̐��̑���Ȃ����ɁA�����ƍa(�݂�)����Ă�����̓c�����ɐ��������A���̂��߂ɗׂ�̑����炤��܂��悤�Ȃ��Ƃ�����܂������A���ꂪ�n���̎d�Ƃ��Ƃ킩��ƁA�{��҂͂Ȃ��Ȃ��āA�������S�������ł���܂����B �@��(�͂ȂƂ�)�n���Ƃ����̂��܂��_���̓���҂ŁA�����{�ł͑����̑����J(�܂�)���Ă���܂��B���̍�����Ƃ����ԋ߂��̂́A��쉄(���݂����̂�)�̉�����(����߂���)�̕@��n���A�r��n�����ƂȂ���������̂��䐾��ŁA�k�͉��B�암�̕ӂ܂ł��A���ɕ������n���ł���܂����B�̂��̑��̓c�A���̓��ɁA����̉Ƃ̔n���r��č����Ă���ƁA�����ʏ��m��������l���āA���̌�������Ă��ꂽ�炷���ɐÂ��ɂȂ����B�����̓��A���̘a��(�����傤)�����o��ǂ����Ƃ��čs���Č���ƁA�䑜�̑��ɓD�����Ă���B����ō���̏��m���n���l�ł��������Ƃ��m��āA��]���ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B(�V�ҕ������y�L�e�B�_�ސ쌧�b�k��(������)�S���u����쉄) |
|
|
�Ƃ��낪�܂������q�̋Ɋy��(�����炭��)�Ƃ������ł��A����͒n���ł͂Ȃ����A�{���̈���ɗl(���݂�����)���A�@��b�@��(�ɂ�炢)�ƌĂ�ł���܂����B�̂��̋ߏ��ɂ��������̓c���A�S�����Ȃ܂��čk���Ă���ʂ̂ō����Ă���ƁA��������m������āA�n�̕@���Ƃ��ď������Ƃ����Ă���܂��B�ǂ������킯�ł����̈���ɔ@���́A�O���J�����������āA������ƒ�������̕��l�ł���̂ŁA�ꖼ�����ӂ����Ƃ���(�Ƃ�)���������ł���܂��B(����B�����{�����q�s�b�q��(���₷))
�x�͂̉F�s�J(���̂�)���̉��ɂ���n�����́A�������q�̌�삾�Ƃ����̂ɁA������@��n���Ƃ����ٖ�������܂����B���ĐY��(�͂���)�S�̔_�Ƃŋ��̕@�Ƃ�����Ď�`���Ă����ꂽ�Ƃ������ƂŁA�肢���Ƃ̂���҂́A���������ė��Č��[�����Ƃ����̂́A�_�Ƃ����D�����Ǝv���Ă�������ł���܂��傤�B���鎞�͂܂������R�̂����̐H��(������)�߂̎��֏o�����āA����ɍ��p(�����߂�)��H�ׂ��Ƃ����āA���p�n���Ƃ������O�������Ă���ꂽ�����ł��B(�x��(����)�G�u�B�É����b���{(����)�S���c���F�s�J) �@���Ƃ����̂́A�Z�ڂ���̖_�ł���܂��B���n���g���ēc�����Ȃ����ɁA���̖_�����̏��Ɍ��킦�Ĉ������̂ł��B���ł͂����p����_�Ƃ��A���k�̕��ł��A�����Ȃ�܂������A�c�A���̑O�̔��ɖZ���������ɁA���Ƃ͂��̕@�Ƃ�ɕʂ̐l�肪������̂ŁA�d���Ȃ��ɑ����͏��N�����̖��Ɏg���A���܂��o���Ȃ��̂ł悭�����Ă��܂����B�n������`���ɗ��Ă킴�킴����������(������)�����ĉ�����Ƃ������̂́A�܂��Ƃɏ��N�炵�����ł���܂��B���Ƃ͂������������̖_���Ȃ��ɁA���ڂɋ���n�̕@�̍j���Ƃ�܂�������A���ꓙ�ɂ͂��Ȃ�炢���ł���܂������A���Ƃ��Ƌ��n��c�Ɏg���Ƃ������Ƃ��A���̕��ł͂����Â�����ł͂���܂���B�����炱��Ȃǂ��V�����o�����`���ł���܂��B�Ώ�(���킫)�̒��F(�Ȃ��Ƃ�)�̒�����(���傤��イ��)�̕@��n���Ȃǂ́A����_�v����~(���납)���̎��ɁA�Ђǂ��@�Ƃ�̏��N�������Ă���ƁA�ǂ�����Ƃ��Ȃ��ʂ̎q��������ė��āA���̑������Ă���āA����͔_�v�̋C�ɓ���܂����B��ŗ�����悤�Ǝv���Ă������Ă݂��������Ȃ��B���̒n�����̏��̔ɁA�����ȓD���̐Ղ����Ă���܂��B���Ă͒n�������N�̎�����̂����킢�����Ɏv���āA����ĕ@�Ƃ���Ƃ߂ĉ��������̂��ƁA��ɂ킩���Ă��������Ƃ����b�ł���܂��B���̒n���͈�����(����Ȃ�)�Ƃ��̖���ŁA���ł͍���ɂȂ��Ă����Ȃ����ł���܂��B(���y������ҁB�������Ώ�S��Y�����F) �܂������̒��̋߂��ŁA���l(�����̂͂�)�̓V���{�ׂ̗�ɂ���n���ɂ������b�������āA�����̖���@����Ƃ����Ă���܂����B������q���ɉ����ēc�̐��������A�n�̕@���Ƃ��Ĉ����Ď�`���܂����B���т̎��ɘA��ė��Č�y�����������ŁA�c���炠�����ĕ��X��q�˂��������Ȃ��B�q�˂܂���Ă����̒��ɂ͂����Č���ƁA�n���̑��ɓc�̓D�����Ă����Ƃ����̂ł���܂��B(�M�B�ꓝ�u�B�����������s���m(�m)�n�l) �o��(�Ƃ��)�̐V��c(���炢��)�Ƃ��������ł́A�ׂ̗�̌S���番�Ƃ����ė����҂��A���ω��ƒn���Ƃ���_�Ƃ��Ď����ė��āA���~�ɓ������ĂĂĂ��˂����J���Ă���܂����B���̐l���������Q������Ĕq��ł��܂������A�_���Z�������ɂ́A���X�������Ƃ̂Ȃ��q��������ė��āA���X�̉Ƃ̕@�Ƃ�̉��������Ă���邱�Ƃ������āA���ꂪ���̒n���l���ƊF�v���Ă��������ŁA��~�n���Ə̂��č��ł��q��ł��܂��B(�o�ČS�j�B�{�錧�o�ČS��]���V��c) ���ꂩ�����(������)�S�̓�R(�Ȃׂ��)�̒n���l���A�悭�_�Ƃ̎���������ĉ�����Ƃ����b�������āA�킴�킴���̑����J������ۂɁA�ׂ�̖�c�R����}���ė����̂������ł��B(�����W) |
|
|
�n����F�쌱�L(�������ڂ��ꂢ����)�Ƃ�����������̏����ɂ��A���������b�͂��낢��Əo�Ă���܂��B�o�_�̑�Ђ̔_�v���M�S���Ă����n���l�́A�\�����̐N�ɉ����āA���̔_�v���a�C�̎��ɁA���ɏo�ė��āA���Ђ̓c�œ������Ƃ������Ƃł��B���܂�悭�����̂ŕ�s�����S���āA�H���̎��ɔu(��������)������܂����B���Ŏ�������ŁA���̔u�̏�ɂ��Ԃ�A��ɂǂ��ւ��A���čs���܂����B�����ɂȂ��āA�_�v�����̂��Ƃ������A������Ǝv���Đ~�q(����)�̌˂��J���Č���ƁA�ʂ��Ēn���l���u�����Ԃ��āA���͓D���炯�ɂȂ��ė����Ă���ꂽ�Ƃ����܂��B�ߍ]�̐��R���̍��g�Ƃ����S���́A�a�C�œc�̑����Ƃ邱�Ƃ��o�����ɂ���ƁA�����M�S�̖ؖ{(���̂���)�̒n�����A���̊Ԃɂ����āA�������葐���Ƃ��ĉ��������B���̂����Q�w(����)�̘H�Ō������ɂ́A����قǐ������Ăǂ����悤���Ǝv�����c�̑����A�A��Ɍ���Ƃ�������c�炸�Ƃ��Ă���B�ǂ��������Ƃ��Ǝv���ċ߂��ɂ����҂ɐq�˂�ƁA���̂������\����̘V�m���A�c�̔�(����)����܂�肠�邢�Ă�����̂��������ɂ́A�N�������l�͂Ȃ��Ƃ����̂ŁA����ł͒n���̌���ւŏ����ĉ����������̂ł��낤�ƁA�����Ԃ��Ă����֍s���Č���ƁA�����炠���肪��ʂɓD���̐ՂŁA���ꂪ���~�q�̒��܂ł������Ă����Ə����Ă���܂��B
��(���邢)�͂܂��A�c�A���̍��ɐ�����(�݂�����)�������āA��l�̔_�v����������ĐQ�Ă���ƁA��̊Ԃɏ��m�����āA���̒j�̓c�ɐ������Ă���B������ɂ��ގ҂��ォ���(��)���˂�����ƁA�����Ăǂ����ւ����Ă��܂����B��ɂ��̉Ƃ̒n���l��q�����Ƃ��Č���ƁA�w���ɐ��������āA�c�̓D�����ɂ��Ă����B�������������n���̘b���Â����炠��܂����B�܂��}�㍑�̓c�ɂł́A���u�̕Ă����c�֖�ɂȂ�Ɛ��������҂�����B���̐l���吨�o�Č���ƁA�Ⴂ�@�t����(��)�������ēc�̐����ɗ����A�a(�݂�)�̐��������܂킵�Ă���̂��A���̌��ł悭�����܂����B��𗬂�ɓ���đ~���悤�ɂ���A�ׂ��a�삪�g��ł��āA�ǂ��ǂ��Ə��֗���A���͂��Ƃ��Ƃ����̓c�ɂ͂���܂����B����������˂��Č�Ō���ƁA�n���̔w���ɗ����Ă����Ƃ����܂����A���̐����R���̉H�������Ă͂��ł������Ƃ����̂́A�O�ɐ\���������̕Жڐ����Ǝ��Ă��܂��B���̕s�v�c�ɋ�������āA���̓c����i���Ă��������āA������c��(�₾�ł�)�Ɩ��Â����Ƃ������Ƃł���܂��B ���������b�́A�n���l�łȂ��Ă��A���͏㑍(������)�̒���(���傤�Ȃ�)�̑���b�m��(�ɂ���)���́A�x�̖͂��ʎ�(�ނ�傤��)�̑�����(�����Ƃ�)�̖��(�݂�)���́A�����̖��(�̂���)�̓D���̖�ɂ��̂Ƃ����̂��A���������̑��ɂ͂������̂ł����A���̒��ł���Ԃɐl�Ԃ炵���A�܂��q���炵�����Ƃ��Ȃ��ꂽ�̂��n���ł���܂����B�����̕��ł��A�n�����͐l���~�����߂ɁA�ǂ��ւ��s���N�Ƃł������������Ȃ���Ƃ����āA�܂�ʗ��m�̎p�ŏ�������āA�n�I���邢�Ă�����悤�ɍl���Ă��܂����A���{�̘b�͂��ꂾ���ł͂Ȃ��悤�ł���܂��B���B�̎R�̒��̂��鑺�ł́A�S��������(�������)�̖�Ԃ�����̂ɍ����āA�������̔��̔Ԃ����āA�����ɐH�킳�ʂ悤�ɂ��ĉ�����A��Ɉ��̖݂������炦�ďグ�܂��傤�ƁA�Βn���Ɍ����Ă����܂����B�������Ēu���Ă�������Y��Ă���ƁA�n�����傻�����𗧂ĂāA���̒j�͕a�C�ɂȂ�܂����B�C�����ċ����Ĉ��̖݂������čs������A�����ɑS�������Ƃ����b������܂��B�����̋{�n���Y�Ƃ������m(���ނ炢)���Ԍ������Ă���ƁA�R�̒n���l���R���ɉ����ė��Ă̂����܂����B�������Ă�э��܂�ĉ̂���݁A�G�X�q(���ڂ�)�����Ԃ�ۂ�ł��āA�����q(����)�����Ƃ����b������܂��B �܂����鏊�ł́A�M�S�[���V�l�������āA�����閾���O�ɖ���ɏo�āA�n���l�̑�������Ă��邩��邨�p�����悤�Ƃ��Ă��܂����B�Ȃ�N���������Ă��邤���ɁA�Ƃ��Ƃ��n���l��q�Ƃ������Ƃł���܂��B���̗l�q���܂�Ől�ԂƏ�����������Ȃ������Ƃ����Ă���܂��B�n���̖�V�тƂ������Ƃ́A�����̑��ł����b�ł���܂����B�Ⴆ��ʌ��̖쓇(�̂���)�̏�R��(���傤����)�̕Жڒn���Ȃǂ́A���܂�悭�o�čs�����̂ŁA�Z�E���S�z���āA�w���ɓB(����)��ł��č��łȂ��Œu���ƁA�����܂����������Ĉ����a�ɂ������Ď��Ƃ����܂��B���ꂩ��͎��R�ɖ�V�т������Ă����Ƃ��낪�A���鎞�����ɂ͂����Ē��̖Ŗڂ�˂����Ƃ����āA���ł����̖ؑ��͕Жڂł���܂��B�܂����̖ڂ̏����O�̒r�̐��Ő�����Ƃ����āA���ł����̒r�ɏZ�ދ��́A��(���Ƃ���)���Жڂł��邻���ł��B(�\�����V���G�L�B��ʌ����ʌS�������쓇) �����ł����J����(�����₩�Ȃ���)�̐��O��(�����˂�)�ɁA���(�߂��炢)�n���Ƃ����̂�����܂����B���ꂩ��@��(�͂Ȃ���)�n�����̉���(�����Ȃ�)�n�����̂ƁA�ʔ������O����������܂����B��X�n���A�x�n���A�������n���ȂǂƂ����̂�����܂����A�`���͂��������͎c���Ă���܂���B�܂����X�͘H�T�̒n���ŁA������������ė��l�����点���Ƃ����b������܂��B���B(�������イ)���ɂ͉����n���A�ꖼ�b�U����(��������)�n���Ƃ����̂����Ƃ͂���܂����B�ɓ��̐m�c(�ɂ���)�̎薳���Ƃ����̂��Βn���ł����āA���ӋS���ɉ����Ēʍs�̎҂����ǂ��Ă��邤���ɁA���鎞�����᎘�ɏo�����āA����a���ėт̒��֓������݂܂����B�����s���Č���ƁA�n���̎肪�c�̔Ȃɗ����Ă����Ƃ����̂��������Șb�ł���܂��B(�ɓ��u�B�É����b�c��(������)�S�b����(����Ȃ�)���m�c) |
|
|
�����n���Ƃ����̂ɂ͂��낢�날���āA���s�̐p����(�݂Ԃł�)�̓�ڒn���Ȃǂ́A��͐g���n���ł���܂����B�����̏Z�l�b�����V���q��(�����킵������)�A���̎��ɂ�����Ēǎ���A���Ɋ낢�Ƃ����{���̒n��������ĉ�����āA�����ė��Ă���悭����ƁA�n�����ł������Ƃ����̂́A�������������b�ł���܂��B�������Ǝv���ƕi��̊�s��(���傤��)�̂���n���Ȃǂ́A�肢���Ƃ�����҂��������āA��ŏォ���ւƂ���܂����B�������N�Ɉ�x�\��̔ӂɁA���̏Z�E����������قǂ��Ēu���ƁA�����̓�����܂�����n�߂�̂ł���܂����B(��|�d��L�B�����{�b�`��(����)�S�i�쒬��i��h)
���Ƃ͂���Ȃǂ͓�����̂ŁA�������̂ł͂Ȃ��悤�ł���܂��B���ł��_�Ƃ������̌˂̋��ԂƂ��ɁA����⎅�R(���ƂЂ�)�����т��邱�Ƃ��悭�����āA�������Đl�Ɛ_�l�Ƃ̊ԂɁA�A�������悤�Ƃ����炵���̂ł���܂��B�O�ɕ@��n���̘b��������쉄�̑��Ȃǂɂ��A���菼�A�ꖼ�b����(�Ђ���܂�)�Ƃ���������Ƃ͂����āA��|��������l�͓�������ė��āA���̏�������܂����B�������Ċ肢���Ƃ����Ȃ��ƁA����ɎQ���Ă��̓���������̂ł���܂��B����Ƃ������߂ɁA�����������Ƃł������悤�ɍl���āA���낢��̘b���n�܂�܂����B�T��˂̓V�_�̋����ɂ́A�ڋ{�_(�Ƃ�����)�Ƃ������{�������āA���̒��ɂ͖�Ɣk�Ƃ̖ؑ����u���Ă���܂����B���̌�ɂ͐ԓ�S����������ė����Ă��܂��B�ڋ{�_�Ƃ����̂͂��̖�l�̂��ƂŁA�̐������}���ɗ����ꂽ���ɁA�k�͐e�ł��������A��̕��͂܂��Ƃɂ炭����܂����B����ō��ł����Q�������l�́B�킴�킴�S�̎����Ă����Ŗ�̑̂������t���ēV�_�Ɋ�|��������B�������Ď����ڂɂ��̓�������̂��Ƃ����Ă���܂��B(��|�d��L�B�����{��b����(������)�S�T�˒�) �J��̋F��(���Ƃ�)�ɂ��A�悭�Βn���͂����܂����B�H��̉Ԋ�(�͂Ȃ���)�̑�{���_�͐��̐_�ŁA��_�̂͐̂͐̒n���ł���܂����B�����y�n�̐l�͉J�n���A�܂��͉J���n���Ƃ��̂��āA��(�Ђł�)�̍ɂ͒����j��������āA�Α����^������(�����ӂ����Ԃ�)�ɒ��߂Ēu���ƁA�K�����ꂪ�J��ɂȂ��ĉJ���~��Ƃ����܂����B(���V�o�H�H�B�H�c���b��k(����ڂ�)�S�Ԋّ�) ���ɂ���ẮA�����J��n���̊J�������������ŁA�J���~����̂ƐM���Ă�����������܂����A�Ȃ��Ȃ����ꂾ���ł͍~��ʂ̂ŁA���肨��͂����Ƃ������Ƃ������̂ł���܂��B�F��̖F�{��(�͂�ނ�)�̂ǂ�{�̒n�����Ȃǂ́A�䑜����̍��܂Ő�̐��ɐZ���ĉJ������܂����B(���y������ҁB�a�̎R���b�����K(�ɂ��ނ�)�S���F�{��) �d�B(�イ)�D��R�̐��|�n���́A���̘e�ɂ���È�̐�����(��)��ŁA���̒��Œn�����s�������A��ł��̐���M�S�̐l�����݂܂����B���ł͉J��Ƃ͊W���Ȃ��悤�ł����A���̈�˂������Ȃ�Ђł�ł���(��)��邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����Ă���܂��B(�ԕ�(������)�S���B���Ɍ��ԕ�S�D�㑺���R) ��O�̓c��(���т�)���̊������Ȃǂł́A�Ђł�̎��ɂ͓y�n�̐l���W���ė��āA�ꂵ�傤�����ɂȂ��ĕ��̐������ݏo���܂��B�[������������ɂ�����ƁA���̒��ɐ̓��������ė���̂��A�n����F�̌��(�݂���)�Ƃ����Ă��܂��āA����܂őւ��ق��ė���ƁA�����Ă��J���~�����Ƃ������Ƃł��B(�b�q��b(�������)�B���茧�k���Y�S�c����) ���������J��̂����́A�����Ɛ̂�����{�ɂ͂������̂ŁA�n���͂����O������͂����ė��āA��ɂ��̖�ڂ������p��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �}��̎R�쑺�̑�̕��Ƃ������ł́A�̕��ƕ��̂����l�̕P�N���A����(���シ��)���Ă��̕��̎�ƂȂ�A���ł��Z��ł�����B����͋����悤�ȑ���(�����Ȃ܂�)���ȂǂƂ����Ă���܂����A�݂ɂ͎���ЂƂ����ق�������ĂĕP�̖ؑ����J���Ă���܂��B�Ђł�̏ꍇ�ɂ͂��̑������o���A���̐����ɓ���Ēu���̂��A���̓y�n�̉J��̕��@�ł���܂����B(��n�䍑(��܂�������)�T���L�B�������b�R��(��܂�)�S�R�쑺) ��a�̒O���J(�ɂ�����)�̑�m��(�����ɂ�)�_�Ђ́A���Ɍ�O������Ƃ����Đ��̐_�ŁA�܂��P�_�ł���܂��B�����ł��J��ɂ͌�_�̂𐅂̒��ɒ��߂āA�����҂��Ă���ƕK���J���~��Ƃ������Ƃł���܂����B(���s(��������)�S�u���B�ޗnj����s�S�M�q���O���J) �����̔��(�Ђ�)�̔ѓc(������)�̐ΑD(����Ԃ�)�����Ƃ����̂́A�ȑO�͑D�̌`��������ڌܐ�����̐���_�̂ł���܂����B�Ђ̑O�ɂ������(�݂��炵)�̒r�ɁA���̐�Z���ĉJ���F��A�K����(���邵)������ƐM���Ă��܂������A�ǂ��������̂���ɂ͌䕼����ɂȂ��āA�������̐͌����Ȃ��Ȃ����Ƃ����܂��B(�V�ҕ������y�L�e�B��ʌ����S��͑��ѓc) |
|
|
���ꂩ��Βn���ɁA���낢��̕���h����邱�ƁA��������@�������ė��������ł͂Ȃ������悤�ł���܂��B�J��̂��߂ɂ����́A�H��̒j��(����)�����Ɉ����܂��B����(�͂Ƃ���)�̊C�݂ɋ߂��Q�n���Ƃ����Ă����̂́A��������(�ڂ�)�������̐Δ�ł���܂������A��ɂ͉��ɂ��Ă����āA�J��̎���������𗧂ĂāA�ɓc�̓D����ʂɓh��܂��B��������Ƃ����ƍ~��Ƃ����Ă���܂����B(�^���V���L�B�H�c����H�c�S�k�Y���쑺)
����͋��炭�D�ʼn����ƁA���Ȃ���Ȃ�ʂ���J���~��̂��ƁA�v���Ă����̂ł���܂��傤���A�����łȂ��Ă��n���ɂ͓D��h��܂����B��a�̓�K���̓D�|�n���Ȃǂ͖�����\�l���̌䉏���ɁA���ł����̂ɓD���|���Ă��Ղ�����Ă��܂��B(��a�N���s���ꗗ�B�ޗnj��b�R��(��܂�)�S��K����) ���|�n���Ƃ����āA�Q�w�̐l�������|���Ĕq�ޒn��������܂����B���̋߂��̖쒆�̊ω����̘e�ɂ́A�n�|�n���Ƃ����^���Ȓn��������܂����B�肢���Ƃ̂��̂����l���A�K���n�`�������ė��Ċ|�����̂������ł��B(�Q��(�Ȃɂ�)�S���k) �H�O�b���(���肩��)�̗�⎛(�ꂢ����)�̑O�ɂ́A�јC��(�����)�n���Ƃ����̂�����܂����B�ȑO���ʂ̉Ƃł����邱�Ƃ��o�������ɁA���̋ߏ��̎҂́A����݂Ƃ����Ď��ɂȂ肩���̕Ă̏`���A�悸��t��������ŗ��āA�n���̓����痁����B���ꂪ����ƕ����ĘH��ʂ�҂��@���܂ޒ��L����������ǂ��A�N��l�Ƃ��Ă������߂�҂��Ȃ����������ł��B�̂���_�v�����܂肫���Ȃ��n���l���Ƃ����āA����������������ďグ���Ƃ��낪�A�����܂��������Ĉ�Ɠ��u�a�ɂ�����A�傫�ȓ�V�������Ƃ����b������A������Ď������҂��Ȃ������̂ł���܂��B(���y������ҁB�R�`�����c��S��쑺) ���ꂩ��܂��A���|�n���Ƃ����̂���������܂��B�ɗ\�̓���̉���ɂ�����̂́A�Q�w�̐l������(�����낢)�������ė��Ăӂ肩���܂����B���̖����n���Ƃ����A�ق�Ƃ��͎q�D���n�����낤�Ƃ�����������܂������A�������Ȃ��Ƃ͂ǂ����킩��܂���B(���{���V��k�B���Q������S���㓒�V��) �x�̗͂��̋߂��ɂ��A���m�ɉ������Ƃ����̂ŗL���ȐΒn��������܂������A��������Ղ�̎��ɔ�����h���ĉ��ς����܂����B(�c�q�V�Ó��B�É����x�m�S���g����) ����(������)�̍O����(����������)���̉��ϒn���A�������|��������l��������A�ӕ�(���ӂ�)��n���̂���ɓh���Ĕq�݂܂����B(�V�ґ��͕��y�L�B�_�ސ쌧�b������(�������炩��)�S�쑫�����O����) �ߍ]�̌ΐ��̖k�̑剹(������)���̕��|�n���́A���̂ւ�̍H��Ŏ��Ƃ�����閺�������A�肪�r�ꂽ���ɂ́A�Ă����̕�������ݎ����ė��āA���̒n���ɐU��|����ƁA���������悭�Ȃ�Ƃ����Ă���܂��B(���y�����l�ҁB���ꌧ�b�ɍ�(����)�S�ɍ���剹) ���|(����)�̕�����(�ӂ����傤��)�̋���(����������)�̌䑜�ɂ́A���߂̔_������ɔ��̕���A�Ă̕��������ė��ċ����܂����B����͂��̕��̌䖼���u�����v�Ƃ����̂��Ǝv���āA����Ȃ�Ε����グ������邾�낤�Ƃ������ƂɂȂ����Ƃ̘b������܂���(��X�G�b)�A����ƂĂ��͂₭���畲���|���Ă������߂ɁA�ꂻ������Ȑ������M���Ղ��Ȃ����̂����m��܂���B�Ƃɂ����ɋ��́A�n���ɑ��錾�t�ŁA���Ƃ͌Z��̂悤�Ȓ��ł������̂ł����A�y�ɉ��̐[���n�����������A���ʂɔ_���̐l�C���W�߂邱�ƂɂȂ����̂ŁA����ɂ͏��N�̂��Ƃ��Ⴂ�l�������A���ł��Ђ��������Ă������Ƃ��傢�Ȃ�͂ł���܂����B ���s�ł͂����Â�������A���N�����̓�\�l���ɂ͘Z�n���w��Ƃ����āA�����̐l���ߍ݂̑�������Ă��邫�܂����B���̕��ł͋x�ݏ��������Ă������o���A�q���͘H�̖T(�͂�)�̐Ε�������ɏW�߂ė��܂����B�������Ă��̊�𔒂��h���Ă��ׂĂ����n���Ɩ��Â��A�Ԃ𗧂ĂĐH�ו��������āA�����痈���l�ɔq�܂��܂���(�R��(��܂���)�l�G����)�B���Ȃǂ̓c�ɂł��A�Ă̗[���̒n���Ղ�́A���̎q�̍ł��y�������ŁA�O�p�Ɍ������т̖��́A�N���Ƃ�܂ŒN�ł��F�悭�o���Ă��܂��B �y�n�ɂ���Ă͊����~�̂Ȃ��ɁA�n���̍Ղ��������������܂��B���ˍ�(�ق����̂���)�̂��鑺�ł́A������t�u�Ƃ����āA�\�ꌎ��\�l���̖�̖����ʑO�ɁA���̒c�q�������ĘH�̒҂ɍs���A�����Z�n���̐̑��ɓh����܂����B��ԑ����h���ė����҂́A�傫���Ȃ��Ă���������ł����炢�A�D���j�𖹂Ɏ��Ƃ����Ă���܂����B(��(������)���g�������B���挧����S����) ���V�����̒n���Ղ�́A�ȑO�ɂ͋��̏\�ꌎ�̏\�Z���ł���܂����B���̒������q�������́A�Ă̕��������ė��Ēn���̂���ɓh��A���̗[���ɂ͂܂��m��(����)��(��)���āA�^���ɂ��Ԃ��܂����B�������āu���N�́A���N�́v�Ƃ͂₵�āA���ʂ�̗x���x�����Ƃ������Ƃł���܂��B(�Q�ؕS���k) �l�ɂ���ẮA�������_(�ǂ��낭����)�̍Ղ�Ƃ������܂����B����_�͓��c�_(�����̂���)�̂��Ƃł���܂����A��������N�Ɣ��ɒ��̍D���҂̐_�ŁA���Ƃ͒n���ƈ�̐_�ł������̂ł�����A���������Ă������ĊԈႢ�ł͂���܂���B���c�_�͂����Ă��̏��ł́A�����\�ܓ��ɂ��̂��Ղ�����܂����B�ō�����ꍇ�ɂł��A��͂�q�����͔������̂�h��܂����B�������琼�Ɍ�����R�̒��̑��Ȃǂł́A���̓��̂ǂ�ǏĂ��̉̒��ցA�̓��c�_�����č������Ԃ��܂����B�M�B�쒆���̑��X�ł́A�̔��������Ղ�̓��ł���܂����A���̒��͖݂�(��)���āA�����m���̔n�ɕ��킹�A����_�̑O�܂łЂ��čs���A���̖݂�_�l�̐Α��ɏ����킸�h����邻���ł���܂��B |
|
|
���̎������߂����܂ŁA�u�e�⓹��_�v�Ə����āA���̖�Ȃǂɂ͗V��ł��܂����B���k�̓c�ɂł͎O�\�N���炢�O�܂ŁA�n���V�тƂ����������V�Y������܂����B��l�̎q���ɓ�V�̖̎}���������A�e�w���B���Ď�����点�B���̎q���Ƃ芪���đ��̑����̎q�����A�������߂������߂̂悤�ɂ��邮��Ɖ���āA�u�����Ⴀ��n���l�v�ƁA�Ȃ�ׂ�������Ă���ƁA����ɂ��̎q���n���l�ɂȂ�܂��B
�@�@�������ɂ����������n������ �@�@�V�тɂ����������n������ �Ƃ����āA�F���ʔ����̂�����x�����肵�܂������A���Ƃ͕������Ȃǂ̂��鎞�ɂ��A���̎q���̒n���̂������Ƃ��������Ƃ��܂����B�܂����鑺�ł́A�V�ђn���Ƃ����āA�����n�����܂̑���肠���āA�n���͂ǂ����֏o�����Ă���Ƃ�����������܂����B���������̂́A�Ⴂ�O���҂̍L��֎����o���āA�͎����̗͐ɂ��Ă���̂ł��B�œ�����(�ނ�)����j���̂��鎞�ɂ��A��͂�Βn���͎Ⴂ�O�ɂ�����āA���̉Ƃ̖���֗V�тɗ��܂����B�n���u�̒n���ɂ́A���n���Ƃ����āA�������玟���ƒ��Ԃ̉ƂɁA�ꌎ���V��ōs���̂�����܂����B �q�����S���Ȃ�ƁA�߂��ސe�����͕��|�⓪�ЁA�����Ȃǂ������炦�āA�҂̒n�����ɏグ�܂����B����Œn�����悭�q���̂悤�ȕ������Ă��܂��B�������Ďq�������ƗV�Ԃ̂��D���ŁA������ז�����Ɛ܂�܂蕠�𗧂Ă܂����B��ň�����������A���̏�ɓ]�����Ĕn���ɏ���Ă����肷��̂��A����Ȃ��������Ȃ����Ƃ�����ȂƎ����āA���ꂢ�ɐ���Ă��Ƃ̑���ɖ߂��Ēu���ƁA���ɂ��̐l�̂Ƃ���֗��āA���炭�n�����{�����ȂǂƂ����b������܂��B���������������҂Ɩʔ����V��ł����̂ɁA�Ȃ�ł��O�͒m������Ȃ��ŁA���������ĘA��Ă��ǂ������ƁA�U�X�Ɏ���ꂽ�̂ŁA�����Ă��Ƃ̒ʂ�Ɏq���ƗV���Ēu���Ƃ����n��������܂����B �Ȃ�قǐe�����͉����m��Ȃ������̂ł�����ǂ��A�q�������ƂĂ��A�܂���͂�m��Ȃ��̂ł���܂��B�����V�K�ɂ���Ȃ��Ƃ��n�߂���A�n���l�͕K���܂����𗧂Ă�ł��傤���A���̐�����Ƃ��Ȃ���X�̎������A�������ċ��X�ɗV��ł�����̂ɂ́A�������ꂾ���̗��R���������̂ł���܂��B���B�b����(���ɂ₷)���̐Βn���Ȃǂ́A���̏����Ȏq�����������ė��āA�@���Č����@�肭�ڂ߂ėV�Ԃ̂ŁA�Ȃ�x�V���������Ă��A�����ɂ����Ă��܂��܂����B�����ɂ����Ǝv���ď���(������)���������Ƃ��낪�A���̐l�͋p(����)���Ēn���̂���������Ƃ������Ƃł��B(���{�ꋽ���G�L�B�É����b���}(������)�S���l������) ���̂悤�Ȃ܂�ʏ����ȗV�ѕ��ł������A�Ȃ��n�����܂̑����͂����ƑO���炠�����̂ł���܂��B�̂Ƃ������̂̒��ɂ́A��������Ȃ��قǑ����̕s�v�c���������Ă��܂��B��������킵���m�邽�߂ɂ́A�傫���Ȃ��Ċw������Ȃ���Ȃ�܂��A�Ƃɂ����ɑ�l�̂����Y��悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A�q���͂킯��m��ʂ��߂ɁA�p���Ċo���Ă����ꍇ�����������̂ł���܂��B�ؑ]�̐{��(���͂�)�ɂ́A�ˎ�(����)�̖�ɓ��Ƃ����̂�����܂����B���Ƃ͏t�̔ފ݂̂������ɁA���̏h�̒j�̎q���W���ė��āA�₳�����Ƃ����ď��|�������āA����ɂ̖ؑ����˂āA��������ċA��̂����Ղ�ł����������ł��B(�ؑ]�Ó��L�B���쌧���}���S��K���{��) �������˂�Ƃ������Ƃ́A��ւ�Ȃ��Ƃł����A����ɂ��_�l���ڂ����˂��ɂȂ����Ƃ����ނ́A�Â��`�����������̂����m��܂���B�z��̐e�s�m(���₵�炸)�̊C�݂ɋ߂��؍�̕s���l�́A�z��M�B�����̕��̐l�́A�s���l�Ƃ����Ĕq�݁A�z�����琼�̐l�́A����l�Ə̂��ĐM�S���Ă��܂����B�����ł͍�����l�S�N�قǑO�ɁA��{����Y�Ƃ����l���C����E���グ�����l���Ƃ����܂����A�y�n�̐l�́A���Ƃ��炱�̉��̏����ȓ��ɁA�q�Y�ݓa�Ƃ������J���Ă������_�l���Ǝv���Ă��܂��āA����m��ʐl�̂����������ǂ����������悤�ł���܂��B�Ƃ����킯�́A���̂����ւ́A��ɂȂ��ē��̑���Ȃ����̐l���A�������Q������ė����̂ł���܂����B�������Ă���ɂ͏����Ȃ���Ƃ����āA�Ԃ�V�����Ēu���m���̉�(����)�̂悤�ȕ��������ė��āA���̑�(�������)�̐̎}�ɂԂ牺���܂������̐��͂������S�Ƃ��m��ʂقǂ���Ƃ����܂��B���̐_�l���n���Ɠ����悤�ɁA���Ɏq�������D���ł���Ƃ������ƂŁA�����Ƃ������ɂ́A���X���瑽���̎������W���ė����Ƃ������Ƃł��B����Ȃ��킢��������s���l�ł��A�W�_(������)�ƈꂵ��ɏZ�߂���̎q�̕ی�҂ł���܂����B���~�ɂȂ�Ə��N��腖���(����܂ǂ�)�Ɍw��̂��A��͂肠�̕ςȔk�����邩��ł����B(���(���т�)�O�S�j���B�V���������S������) ���{�͐̂���A�������_�Ɉ������鍑�ł���܂����B���c���n�������̍��ɓn���ė��Ă���A���������ɏ��N�̗F�ƂȂ����̂́A�܂����������̍����ɂ��Ԃꂽ�̂ł���܂��B�q���P�_�̔������M�����Ƃ̂��͂��Ȃ�������A��X�̎����������ɐ������āA�W���Ă��̍���傫�����邱�Ƃ��o���Ȃ������@���A�������y����ő����̓`�����o���Ă��Ă���Ȃ�������A�l�ƍ��y�Ƃ̈����́A�������(�͂�)���ɔ������������m��܂���B���̑傫�Ȍ��J�ɔ�ׂ�Ƃ��́A���̂��̈���̖{�͂܂����܂�ɏ������B���ɏo�ė�����{�̓`���W�͂����Ɩʔ����A�܂����܂ł��Y��邱�Ƃ̏o���ʂ悤�ȁA�����Ɨ��h�Ȋw��̏��łȂ���Ȃ�܂���B�@ |
|
| ���`�����z�\ | |
| ���̖{�ɏo�Ă���`���̒��ŁA�����̖��̒m��Ă��镪���A�\�ɂ��ĂȂ�ׂĂ݂܂����B���̈ȊO�̌��S�����ł��A���������m��Ȃ������Ƃ��������ŁA�ނ��q�˂Ă݂�����ł��A�����悤�ȓ`�������邱�ƂƎv���܂��B���̐����̓y�[�W���ł��B�����̑��̘b���o�Ă��܂�����A�܂������̂Ƃ��납��ǂ�Ō䗗�Ȃ����B | |
|
���X��
�R�̑���(���Ìy�S���ԑ�) / �Жڂ̋�(��Ìy�S���ꑺ) / �ΐ_��(���k�S�e����z��) ����茧 ����R(���S���) / �͂���̐_��(�a��S���R�c��) / �}���̗R��(������ڑ�) / ����̕�(���ɌS������) ���{�錧 �����̐���(�ʑ��S��o�R��) / ��~�n��(�o�ČS��]���V��c) / ���؎R�̓y(�����S���쑺) ���H�c�� �Жڂ̐_��(��H�c�S�k�Y��) / �Q�n��(�����쑺) / �s����̏�(�Y���S����) / ����̋@(�k�H�c�S���m�������̑�) / �Жڂ̋�(��k�S����) / �O�r�͂̉W(�����r��) / �J���n��(���Ԋّ�) / �������(����쐼����) ���R�`�� �i����(�����R�S�R����) / ��t�̈��(�����R�S��y�����g��) / �F��̉W��(�k���R�S�{����) / ���̋�(�O�C�S�����c���k��) / ���C�R�̎�(����) / �јC���n��(���c��S��쑺) / ���傤�����̉W(���c��S�������) �������� �@���(�����s��(�m)�l) / �Жڐ���(�M�v�S�]�ڑ������) / �Жڂ̑��q(���y����) / ����P�̎�(�ɒB�S�э㒬�吴��) / �@�D��O(���B�S����) / ���q�̕Ж�(���όS���c�쑺) / ����(���ÌS�ي⑺�X��) / ��t�̉��̈�(�떃�S�剖��) / ���J�x�m(�Ώ�S���쑺���J) / �����ߒn��(����Y����X) / �@��n��(�������F) |
|
|
���Ȗ،�
�Жڂ̕P(�͓��S��O�쒬) / �Жڂ̍c�q(�F��S�R�O���썂��) / ���D�r(�ߐ{�S���H���k��) / ���`�n��(���ߐ{�����{) / �V�_�̓G(���h�S����������) / �l�ۑ喾�_(�����쑺����) / ��t�̉�����(�����S�O�a���q) ���Q�n�� �k��(����s�ԍ⒬) / �Жڂ̉V(�k�Êy�S�x�����]��) / �_�̐�(�����S�����V�_) / ��t�̓�(����ꑺ��ꓒ��) / �������r(���g�S�B�@����A��) ����錧 ��̓m(�߉όS���͑���) / ���_��(�v���S��{���Ζ���) / ���R���炢(��������) / ��Α喾�_(�����S�b����a�c) / �}�g�R�̗R��(�}�g�S�}�g��) ����ʌ� ����Ԃ��k�Γ�(��z�s�쑽��) / �q���r(�k�����S���q�����V�q) / �_���̑吙(���卻�y���y�C) / �O��(���ԌS����V��) / �֕�(������w���k��) / �֕�(���R�����䍑) / �ΑD����(���S��͑��ѓc) / �M�Z��(�����S�����쒬) / �ѐX��(����쑺�厚��) / �Жڒn��(���ʌS�������쓇) ����t�� �В���(��t�S��{����юR��) / ��{��(�s���S���O������) / �����l���K(��S�P�䒬�P��) / ���̈����_�l(�����X�䒬) / ������(���x�����V��) / �ΐ_�l(�����������c) / �V���ߋ�(�����S�����{�����{��) / �Y�ւ̒r'�R���S��a���R��) / �r(�N�ÌS���쑺) / �W�_�l(�����C���U�c���W�_��) / �O���r(�N�ÌS���d����) / �ւ̂��ΐ�(���֑��厚��) / �卪�͂���(���S�璬������) / ��{��(���z�{��) / ��{��(���[�S�������F��) / ��t�̉���(���L�[���_�]) / �����(�����l����) �������{ �����(�����s�����) / �������(�����J��J��������) / ����n��(�`���S�i�쒬��i��h) / �Z�喾�_(�L�����S����������) / ��t�̋�(������ˑ��㍂���) / �ڋ{�_(�슋���S�T�˒�) / ������(�����q�s�q��) ���_�ސ쌧 �@��n��(�k���S���u����쉄) / ���ϒn��(������S�쑫�����O����) / �@�D�̈�(�������S��E������) |
|
|
���R����
�䔢��(���R���S�����������ܑg) / �e�a��l�̔�(�����X�͑�) / �Жڂ̓D��(���R���S���쑺) / ���ʂ̑勴(������������) / �����̌���(������S�x�m�����͓��g) / ����Ԃ��k�̐�(�������S�S�c���㔪�c�g) ���É��� �W�b��Ȃ�(�����s���]�����Ǖ�) / ���c�x�m(��ΌS���c��) / �x�m�̎o�_(����ȑ��_��) / �����q�哒(�c���S�M�C��) / �薳��(�����쑺�m�c) / �R�̔w�����(�x���S�{�R��) / �����n��(�x�m�S���g����) / �@��n��(���p�n��)(���{�S���c���F�s�J) / �~�̒r(���ˋ@��) / �q���ƒn��(���}�S���l������) / �@�D�̈�(���q�S�������̉�) / �W�Ƒ���(�֓c�S���t��) / �x�m��(���㈢���Ñ��ΐ_) �����쌧 �P�����Ɛz�K(����s) / ���q��(�k���v�S�O�䑺) / �ꖾ�_�̋�(�����S�a�鑺�ԍ�) / ���݂̒r(���ɓߌS�㋽��) / �Ԃ̌䏊(�����u��) / ���{�ނ̊���(�����]�����c) / �x�m��(���q���������) / ���̈����_�l(���}���S������) / ��w�̒r(���}���S���`���{�a) / ������s��(����K���{��) / �叼���Ă�(����܌S���ܑ�) / ����炸(�k���܌S���y��) / �����m�u�w�v�́u���v�ɑウ�āu�v�n��(�㐅���S�S�������≺) ���V���� �O�u�r(�����s�_�c��) / �s�k�̏�(�k�����S���c�����c) / �H����(�O���S��Ñ��@�؎�) / �Óޘa��r(�k�����S�x�V�����x�V��) / ���@����(�싛���S���V������ؘZ) / ���܂�(���H�S���ʑ��]�n) / �Жڂ���(�����S���r����) / ����_�Ƃ���(�����S�������؍�) / �z�K�̓㊙(�����m��) �����m�� �������x�m(�O�H�S�r�쑺) / �|�̐���(�m���S���Y�����H) / ���q�Ж�(��݊y�S��������) / �R�̔w�����(�����S�Ί���) ���� �O����(�K��S�J����) / �O���r(�R���S��Ɏ��Ǒ�) / �����̌{(���V�S�����`��) / �ڂ�˂����_(���ΌS���c��) / �ւƔ~�̎}(�v�c�S������) / ���{����(���㌴����a��) / ����(������������) / ����̋�(���������o���J) ���ΐ쌧 ���R�ƕx�m(�\���S������) / ��{��(������) / �₷������(���吙�J���Ԑ�) / �Жڂ̋�(�͖k�S���������R) / ��t��(�H��S�u���Y�����) / �@�D�ƕB�̊�(�����S�\�o����) / �������̗R��(���������H��) / �\�o�̈�{��(��F�S��ˑ�����) ���x�R�� ���R�Ɣ��R(��V��S) / �R�̂�����(���D�葺�M�q) �����䌧 �R�̔w�����(���S��쒬) / �@�D�r(�O���S�R������K) / ������(��ьS��(�m)�����։�) |
|
|
���O�d��
�����v���Ԑ�(�F���R�c�s�D�]��) / �߂��炵��(�ѓ�S�{�O��) / ���������(���˘a��) / ���(���C�S���ޑ��m�c) / �q���̈�(���O����) / �Ԑ�(�어�K�S�܋������J) ���ޗnj� �D�|�n��(�R�ӌS��K����) / �J��ƒn��(���s�S�M�q���O���J) / �������J��R(�g��S���������J) ���a�̎R�� �vጐ_��(�߉�S��o�����O) / ����M(�ɓs�S���쑺���M) / �J��n��(�����K�S���F�{��) �����ꌧ ��������(�����S���쑺�썇) / ����炸(�I���S�}�D���쌴) / �Ԃ̖�(���m�S����������ԑ�) / �䔢�̐�(����S�e�������厚��) / ��鍳�̒r(��c�S�匴���r��) / �|�����̗R��(�����S�|����) / ���|�n��(�ɍ��S�ɍ���剹) / ��t��(���Љ������s) �����s�{ �O���r(���P�S�V�_�����F��) / �Жڊω�(��K�c�S�B�c�쑺�`��) �����{ �����r(��k�S���c�����ƌ���) �����Ɍ� �s�g���_(��ӌS��쑺���z) / ����Ȃ蓒(�L�n�S�L�n��) / ��l��(���ÌS���Ð쒬) / ���{��(��������㌳) / ���|�n��(�ԕ�S�D�㑺���R) / �������~(���I�S��k������) |
|
|
�����R��
�֊|��(�W�v�S�֊|�����J) / ���ǂ̒r(���c�S�g�쑺����) / ���(�v�ČS��`���厚�����) ���L���� �o�_��(�L�c�S���㑺����) / �����r(�����S�_�c�����@) / �������Ԑ�(�b�i�S�X�R�����R��) / �z�N��(�o�O�S��ؑ����O��) / �ΐ_��(��k�S���z������) / �Ԏq��(����a���Í�) �����挧 �z�N��(����S���������I�J) / �������̕�(���S) / �؎R�̔w�����(�����S��R��) / �|�͂���(����S��ꑺ) / ��t�u�ƒn��(������) �������� ���������(�ѐΌS�ѐΑ�) / ������(�����S���q�����A��) / �ޏグ����(�B����g�S������) |
|
|
�����Q��
�����n��(����S���㓒�V��) / ��̕�(���v�đ�����) / �^������(�V���S�щ���) �������� �ւ̖�(�߉�S�x��������) / �g�q�_�̐�(���ɓ�) / �s���̐_��(�C���S�쐼����) / �����̑�(����㑺����) / ����(�����S������R��) / �ڂ�˂��_(��S�k�呺���c) / �R�̐�(���n�S��q����q�R) �����m�� ����D��P(�y���S�\�Z���s��) / �g�c�̐_��(�����S�R�k��) / �R�W�̔����(����B��������) / ���ɐ��_(�����S���⑺) / �����Ԑ�(�����S�Ñ呺) |
|
|
��������
������(�����S�[�]��) / ��ΐ_��(�O�k�S���������) / ����Ђ̕P�_(�R��S�R�쑺) �����ꌧ �\�O�˂̌I��(�����Y�S��쑺) ���啪�� ���q��(�������S�P����) / �R�z��(�����S��[���V��) / �O����(���S�ѓc���c��) �����茧 ������(�k���Y�S�c����) ���F�{�� �ΐ_�̐�(�O���S���葺) / ���̗R��(�ʖ��S���Α�) / �R�̎��(���{�S�O�ʑ�) / �L�x(���h�S������) / �ѓc�R(��v��S�і쑺) ���{�茧 �ω��̓�(�������S�і쑺���c) / �s���̐_�r(�����S����k����) / �R�Ǝ(���s�_��) ���������� ��{�����̐�(�K�h�S�R�쑺����) / �r�c�̉ΎR��(���w�h��) / �ΐ_���̐_(�F���S�i�����R�c) / �F���(�F�ьS����q�����v)�@ |
|
| �@ | |
| ����C�̑z�� | |
|
�����������x������C�̓���
�ޗǎ�����I�����}���悤�Ƃ��Ă��������I�㔼�A�����V�c�����ʂ��ꂽ����A�s�͕��鋞���狞�s�̒������֑J�s����܂����B��s�������͂̔�剻�������������V�c�́A�G���鐨�͂̕s���ȓ���������邽�߁A�����̒��������f���Ƃ����������̑��c�����ӂ����̂ł��B�����đJ�s���邱�Ƃɂ��A�V�c�Ƃ̌����Ƃ��Ă͎ア����ɂ���������̋��������łȂ��̂ɂ��A���̏�ŕ��鋞�̒n���I��_���A�V�����s�̒n�ɂč������悤�Ƃ��܂����B�Ƃ��낪784�N�A�s���������֑J�s����Ă���Ƃ������́A�����͍Г�����܂����B�v�������ʋQ�[�̓����A�͐�̔×��A�u�a�̗��s�����łȂ��A�����V�c�̐g���ɂ��a���������̂ł��B�����͕s�K�ȉ^���𐋂������ǐe�����M��ł���ƉA�z�t���肤�قǁA���Ԃ͐[���ł����B ����������@�ɒ��ʂ��A�����V�c�ւ̐M�C����炬�͂��߂�����A��������N��\�ɂ��Č䑠���Ō����J���A�o�Ƃ����̂���C�ł��B������͂��߂Ƃ���A�W�A�e���̌��t�Ƒ嗤�����ɑ��w���[���A���w�ȏ@���Ƃ̑����y�o���Ă����������̏o���ł�����A���A�W�A�̕�������{�ƃC�X���G���Ƃ̊ւ�肾���łȂ��A�w�u���C��ɂ��Ă��[���m���Ă����ƍl�������C�́A���̔w�i���炵�ēn���n�̐l�X�Ƃ������̐ړ_���������悤�ł��B�����Ĕ����ł��鈢���呫��ʂ��Ē���A����ѓV�c�ƂƂ̖ʎ��������ƂƂȂ�A�����{��ɂđ傫�ȉe���͂������A���_�����[�c�̉\���₦�Ȃ��`���Ƃ��𗬂����������Ƃł��傤�B�������ċ�C�́A�����������ɐ[���ւ���Ă������ƂɂȂ�܂��B ������������������������@���F�苁�߂Ă���������A��C�͐V�����s���C�X���G���̎�s�G���T�����ɂȂ���đ��c����K�v���ɖڊo�߁A�n���w�̓V�ˁA�y�؍H���̒B�l�ł���A���܂��܂ȋ������z���čŏI�I�ɂ͓V�c�̑��߂ƂȂ����a�C�����C�Ƒz�����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�a�C�����C�͌Ñ�̂��܂��܂ȑ��ʋZ�p����g���āA���̓s�����c�����ׂ��ꏊ���s���|�C���g�Ō������邱�Ƃ��ł��܂����B���̐��n�������V�c�ɏ������R�̏ォ�炲��I�����w�i�ɂ́A�����C�Ɛ`����̖��ڂȃR���{���[�V�������������ƍl�����܂��B�����ė]���𐔂���N���ł����������C�́A������c�������Ƃ̑������Ⴍ���Ĕ��w�ł�������C�ɑ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ނ�̔M�ӂƋ��ٓI�ȓ��@�͂Ɋ�Â��挩�̖ڂ��m�M���������V�c�́A�`���ɉ����Ęa�C�����C�Ƌ�C�Ƃ������������̌㉟�����āA�ēx�A�J�s�����s���錈�f�����܂��B ���̐V�����s�̖��O�͐`����̒ɂ��A�C�X���G���̓s���w�u���C��Łu�����̓s�v���Ӗ�����G���T�����ł��邱�ƂɂȂ��炦�A�u�������v�ƓV�c�ɒ���܂��B�������̓����ɂ́A�G���T�����Ɠ����悤�ɑ傫�Ȕ��i�����݂��܂����A�L���Ȑ����𓌕��ɔ������Ƃ��A�V�����s���j������邽�߂̈��v�f�ƍl����ꂽ�̂ł��B�G���T�����̖k���ɂ̓K�����������݂��A�w�u���C���(��)�u�����E�L�l���b�g�v�@�ƌĂ�Ă��܂��B�u�L�l���b�g�v�̌ꌹ�́u�Ձv���Ӗ�����(��)�u�L�m���v�ł��邽�߁A�K�������́u�Ղ̐�v�̈ӂƂȂ�܂��B�����ĕ������̓�������k���ɂ����čL���������G��(���i)�̌`���������{�ő�̌��A���i�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B����͌����ċ��R�ł͂Ȃ��A�K�������ɔ�肳�ꂽ�����炱���A�������̓��ɂ���͔��i�Ɩ������ꂽ�̂ł��B�@ |
|
|
���l�����R�ɂ��֘A���镽�����̈ʒu�Â�
����ł͕������̈ʒu���ǂ̂悤�ɂ��Č��ɂ߂�ꂽ�̂��A���̕��@�_�ɂ��čl�@���Ă݂܂��傤�B�C�X���G���̎�s�G���T�����́A�C�ݐ�����60�q�����̖~�n�ɂ���܂��B�������ւ̑J�s�ȑO�A����܂œs���ʒu���Ă��������������l�ɁA���p�Ɠ��{�C���̎ዷ�p�A�o������60�q�قǓ����ŁA�O�����R�X�Ɉ͂܂ꂽ�~�n�Ɉʒu���Ă��܂����B�Ƃ��낪�������́A�{������ׂ��s�̒n��������ɂ���Ă��邾���łȂ��A���n�ɑ�ȓ����̐����������Ă����̂ł��B�܂���ƂȂ钆�S���́A�ɐ��_�{����_�Ƃ��ēޗǂ̐Ώ�_�{�����Ԑ��ł���A�Ñ�Љ�ɂ����ďd�v�x�̋ɂ߂č����Q�̐_�Ђ̉�������ɂ́A��ɋ�C�̑�ȋ��_�ƂȂ�_�˂̍ēx�R�A����јa�C�����C�����������嗳��������܂��B���̒��S���̓쑤�ɁA�ɐ��_�{���猕�R�ւƐ��������A����ƑΏ̂�����𒆐S���̋t���ɁA�ɐ��_�{����k���̕����Ɉ����ƁA���傤�Ǎ��̕����_�{���Ƃ���܂��B���̑Ώ̐���ɓs�����邱�Ƃ��A���͏d�v�ł������̂ł����A�������͂��̈ʒu���炸�ꂽ�ꏊ�ɑ��c����Ă����̂ł��B ��C�́A�a�C�����C�Ƌ��ɁA�l���̎R���ɂ������ƍl������Ñテ�_���̏W����A�C�X���G���̔�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�̐₦�Ȃ����R�A�����Đ_��Ɋւ���L�q���j���ɂ�����������ɐ��_�{�A����ѐΏ�_�{�̒n���I�Ȉʒu�W���A�w�I�v���������Č���Ă��邱�Ƃ𗝉����Ă��܂����B���̂��߁A���z���Ƃ��Ă̓s�̈ʒu�́A�ɐ��_�{�ƌ��R�����Ԑ��Ƃ͑Ώ̓I�Ȑ���Ɉʒu���A�������R�X�Ɉ͂܂ꂽ�n�ł���A����ɃG���T�����Ɠ��l�ɖk���Ɍ����݂���ꏊ�ł���ׂ����Ƃ����߂��̂ł��B�a�C�����C�͒���������k���ɂ��悻12�q���ꂽ�ꏊ�ɁA�����̏������������n�����o���A�V�����s�A�u�������v�ƂȂ�ׂ��n�Ƃ��Č���߂܂����B�����ċ�C�����̏��������\���ɗ������Ă������炱���A��ɂ��̈ɐ��_�{�ƌ��R�����Ԑ�����ɁA�������Ƃ͂��傤�ǑΏ̂ƂȂ����ŁA�������ɐ��_�{���畽�����܂ł̋����Ɗ����Ȃ܂łɈ�v�����ʒu�ɁA����̐l����S�����邽�߂̐��U�̋��_�ł��鍂��R�肠�����̂ł��B �������āA������������Z���Ԃʼn�����邽�߂̎{���S���Ă�����C�́A�V�c�̂���Ȃ�M���M�]���邱�ƂƂȂ�A���߂Ƃ��Ċ��邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ęa�C�����C�͕������̑��c�ɁA��C�͉���̎�������̉���Ɛ_��̎�舵���ɂ��Đ�O���A���X�����ӂƂ��镪��ɂ����č��ƂƓV�c�Ƃ̈��ׂ�S����肢�A�S�g�S���s�����Ċ����V�c�ɂ��d�������̂ł��B�@ |
|
|
���Ⴋ���̋�C�̋�Y�ƐM�O
���{�̗��j�Ɏc��̑�Ȋ�ƉƂ̈�l�ɁA�O�䕨�Y�𑍍����Ђɂ܂ň�ďグ���v�c�F�̖��O���������܂��B1848�N�A�V�����̍��n�ɐ��܂�A�c���������w�ɑ�z�����˔\�������v�c���́A12�ɂ��ē��������̖��z�P�����ɂ������A�����J���g�قɋΖ����邱�ƂɂȂ�܂����B14�̎��ɂ͌����g�ߒc�ɉ����@��^�����A�����ېV�̒���A�A�����J�̑�菤�Ђɓ��ЁB�����ĉv�c�F�̊���Ԃ�́A���������]�̖ڂɗ��܂�A23�ɂ��đ呠�ȂɊ����Ƃ��ē��Ȃ����̂ł��B���̌�A�����̌��т��O��Ƃɍ����]������A1876�N�A�㊥27�ŎO�䕨�Y�̎В��ɏA�C���܂��B �������̂̕����N��ɂ�����邱�ƂȂ��A�{�l�̎��͎���ŗ��g�o���ł���`�����X�Ɍb�܂�Ă������Ƃł��傤�B���ɉv�c�F�́A��w����Z�Ƃ����O���̒m���ɒ����Ă������߁A���̌o���ƃX�L�����������{�ɂƂ��ďd�ꂽ�̂ł��B�S�N�O�ł��N��̕ǂ��z���Đ��E�A���E�Ŋ���@�20���������̐N�ɗ^����ꂽ�̂ł�����A����ɐ�N�ȏ���̂ƂȂ�A�o���̉\���͖����傾�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����́A�������㏉���̓V�c�����̉��ŁA��ނȂ��˔\����������C��20��O�ɐ��{�����ւ̓�����ݎn�߂����Ƃ́A�z���ɓ����܂���B ��t�a�]�ɂ����āu��Ύ��̂��̎��ɏO���̂��߂ɐg���̂Ăāv�Ə^������C�́A15�ɂ��Ę_���F�o���K���A18�̎��ɂ͓����B��̓s�̑�w�ɓ��w���Ė��o�����U���A��w���}�X�^�[���܂����B�����ċ�C�̖����͐e���ł��鈢��������@���@�̑m�������āA�����V�c�ɂ��m��n��A�����呫�̓�����ʂ��čc���̑��߂Ƃ��Ă����͂��߂܂��B�u�O�@��t�����A���E�Ɍւ蓾����{�̉p�Y�ł��萹�҂ł���v�ƁA����G�����m�͂������Ⴂ�܂������A�܂��ɂ��̂Ƃ���ł��B �Ƃ��낪�s�̌����ڂ̓�����ɂ�����C�́A���̉h�ƕ����k�̐����I���ނ��뜜���A19�ő�w��ފw���Ă��܂��܂��B��C�����M�����u�O���w�A�v�ɂ́A�u���s�̉h�ؔO�X�ɂ�����}���A���M(����)�̉����A���[�ɂ�����˂����v�Ə�����Ă���A��C���ǂ�قǓs�̋��h�Ə@���̍r�p�Ɍ��C�������Ă��������@���邱�Ƃ��ł��܂��B��C�̖ڂɏĂ������s�̎p�Ƃ́A�n���ɔY�ޏ����ƕa�l�Ɉ�ꂽ��Y�̐��E�ł���A������v�����тɋ�C�͊w��̒Njy�����A�ނ���^�̓�������Đl�X�̍����~�����Ƃ�������̂ł��B�����Ēǂ��ł���������悤�ɓs�̊�@���K��A��C����w�����鎞���𑁂߂錋�ʂƂȂ�܂����B�����������ǐe�����M����͂��߁A�n���I�v�f�ɗ��ނ��܂��܂ȓV�ϒn�قɂ���@�Ɋׂ����ہA��s�Z�@�̕������͂Ƃ̐ڐG�������Ă��������V�c�́A�����̖����������鎅�������ނ��߂ɁA�@���A�h�o�C�U�[��K�v�Ƃ��Ă����̂ł��B�����ŏ��W���ꂽ�̂��A�ޗǂŕw�ɗ�݁A�����A�ޗǕ����E�ɂ����Ă���Ԑ��͂������Ă����@���@�̑m����Ɖ��̊W�������Ă�����C�ł͂Ȃ����Ɛ������܂��B��������C�͑嗤�ʂł���A����⒆����Ȃǂ̊O���ꂾ���łȂ��A�����v�z����{�×��̏@���ɂ��Ă��n�m���Ă��܂����B�����ďo�g�͎]��A�����̍��쌧�ł���A�����͌��R�̂��G���ł��邾���ɁA�����V�c�ɂƂ��Ă͊���Ă��Ȃ��l�ނ������̂ł��B �V�c�̔Y�݂�m��₢�Ȃ�A��C�͂��̓������F�苁�߂邽�߂ɑ�w������A�v����y���ēޗǂ̎��@��K�˂ĕ������A���̌����R�A����R�A�ɗ\�̐ΒȎR�A���g�̑�ꃖ�ԂȂǂŏC�s���d�˂܂��B��C���g���̂Ƃ��̎���̂��肳�܂��A�����̗a���҂��霂�����u������v�ƌĂсA�O���w�A�ɂ́u�r���тƂ��āA�ڂ�ڂ�̈߂�Z������C�̊�͂��A�����r���������āA�r�̔Ȃ̍�̋r�̂悤�ɂȂ����v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B�����̋L�q������A��C������ɉۂ����ߍ��ȋ�s���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł��܂��B������794�N�A��C�͓y���̎��˖��A��~�l�A(�݂����)�ɂČ����J���܂��B��̓I�ɂ͐����ɂ��ގ������y���e�R�X�e�̋L�ڂ�����悤�ɁA�V��E���琹�Ȃ�삪��C�ɉ���A���̐���̗͂ɂ���Đ�ɉ������悤�ɖ��m�̍��̌��t�A���Ȃ킿�ٌ���������̂ł��B��C�͏C�s�̖��A���̐����g�ɗ��тė�̐��E�ɖڊo�߁A��Ɍ����g�Ƃ��Ē����Ɍ��������ۂɂ͌i�����w�сA�����̌��t���炻�̈Ӗ���m�邱�ƂɂȂ�܂��B ��C���C�s�̍ۂɎ����߂���������R���A���́A����R�Ɠ��l�ɌŗL�̎R���w�����̂ł͂Ȃ��A�g��R����F��֑����R�x�n����Ӗ����Ă��܂��B���x���̒��S�ɎR��x�����т������A����ɂ͏C�����̍��{����ƂȂ����g����R���h������܂��B���̑���R������R�Ɠ��l�A�l�����R�ƈɐ��_�{�����꒼����ɑ��݂��A���ォ��́A���Ɉɐ��_�{�A���ɂ͍���R�����n�����Ƃ��ł��܂��B�����Ă����̐��n�ƍ���R�A�Ώ�_�{�Ƃ̒n���I�q����ɒ��ڂ�����C�́A�ɐ��_�{�ƐΏ�_�{�����Ԑ��𒆐S�ɁA���R�ւ̐��Ƃ͑Ώ̂ƂȂ����ɕ����̓s�ɑ����������n�����邱�ƂɋC���t�����̂ł��B������794�N3���A�V�c�͑J�s�̒n��a�C�����C�Ƌ��ɏ�������A���̌�A���c���}�s�b�`�Ői�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B���}�ɑJ�s���������Ȃ���Ȃ�Ȃ������w�i�ɂ́A����̖�肪����A�����̐l�X�ɂƂ��āA���ɓV�c�ƈꑰ�ɂƂ��Ă���͂܂��ɁA������肾�����̂ł��B�@ |
|
| �@ | |
|
��������������킷����̑���
�Z���Ԃɓ�x�ɂ킽��J�s���J��Ԃ��ꂽ���j�̔w�i�ɂ́A���삩��̉���Ƃ�����肪����ł��܂����B�����������鋞���璷�����ɑJ�s�������̂́A���ォ�牅��̉\���₦���A������V�ϒn�فA�g�̉��̂��܂��܂ȕs�K�Ɋ����V�c�͔Y�݁A��������X���߂����Ă��܂����B���̂��߁A�ēx�A�s�̑��c���ژ_�܂�A�J�s�ɂӂ��킵���V�V�n�����߂����ʁA�������̒n���a�C�����C�ɂ����ꂽ�̂ł��B�܂�A�������J�s�̈��e�[�}�́A������M�肩��̉���������̂ł��B�����ēV�c�̖��ɂ��A�������i��p���ĕ���������삷��p���s������܂����B �܂��J�s�̗��n�����ɂ����ẮA�����×��̋����ł���u�l�_�����v�Ɋ�Â��A������k���l�_�ɂ���Ď�삳��A�`���̒n�𐬂����̂Ƃ��܂����B�O�q�����Ƃ���A�l�����R�ƈɐ��_�{�A����ɐΏ�_�{�����Ԑ��A�����č���R�Ƃ̒n���I�֘A�����l������A���݂��̋����W���d������܂����B���̌��ʁA���肳�ꂽ�������̒n�́A����̐������u���v(������イ)�̏ے��Ƃ��ē��ɑ��݂��A�s�̎C���R�A�����u���Ձv(�т����)�̏ے��Ƃ��Đ��ɁA�܂���ɂ͐삪�������ދ����r�́u�鐝�v(������)�A�k�ɂ́u�����v(�����)�ƌĂ��T�Ǝւ����̂������_�����D���R�̋u�˂ƁA�u�l�_�����v�̗��z�I���ł������̂ł��B �܂��A�s����삵�ĉ���̎d�Ƃł���V�ϒn�ق�s�K����g����邽�߂ɂ́A�s�̎l�������ЂŎ�邱�Ƃ��d�v�ł����B�����Ŋ����V�c�́A�s�̓�����k�ɑ叫�R�_�Ђ��������A�_�X�̒��ł�����ȗ͂����q����Ă����X�T�m�I�m�~�R�g���J�邱�Ƃɂ���Ė�������A����������삷��b�Ƃ��܂����B�����ČÑ��萒�q����ė����֑q�̋����A�s�̓����ł͊Ϗ����Ƌ������A��k�ł͖����@�s�����ƎR�Z�_�Ђ��J�邱�Ƃɂ��A�s�S�̂�叫�R�Ɗ�̐_�ɂ���ē�d�ɉ��삷�邱�Ƃ�ژ_�݂܂����B����ɓ����k�O�����R�Ɉ͂܂ꂽ�������̓쑤����銯�ݎ��@�Ƃ��āA796�N�ɂ͓������n�����ꂽ�̂ł��B���̓��������A823�N�ɍ���V�c����C�ɉ�������A�d�����������ꂽ�A��̐^�������̍��{����ł��B �Ō�ɓ��M���ׂ��͋S�����鉄��̑��݂ł��B�J�s���O��788�N�A�Ő����J�������~�ω@���N���Ƃ��đn�����ꂽ����́A�A�z���̋S��ɂ�����s�̓��k���Ɉʒu���܂��B�S���o���肷��ƍl����ꂽ�S������ꂽ�����V�c�́A���������鎛�Ђ̒��ł�������ŏd�v�����A�����ŕp�ɂɉ����F��������s���܂����B�ޗǂ̓�s�������͂�đJ�s�����f���������V�c�����ɁA�_�̂���������߂�ɂ��Ă��A�ޗǕ����̗v�f���ɗ͔r�����悤�Ƃ������Ƃ͑z������ɓ������܂���B������������邽�߂ɂ́A�֑q�Ƒ叫�R�_�ЁA����щ���̉����F�������ł͑���Ȃ��ƍl�����̂ł��傤���A��O�[�u�Ƃ��Ď��_�̏ے��ł��������V���A�s�̖k�͈Ɣn���ɁA��͗����ɂ��u���܂����B�������āA�������͑��c�������瑽���̐_�X�ɂ���Ď�삳���悤�ɂȂ����̂ł��B�@ |
|
|
������ގ��Ɛ_��̏�����C����ꂽ��C
�u���삩��̉���v�Ƃ����V�c�̐Ȃ�肢�������āA�J�s���������邽�߂Ƀ}�X�^�[�}�C���h�Ƃ��Ĕw��Ŋ����̂��`���A�a�C�����C�Ƌ�C�ł��B�`���́A�o�ϓI�Ȏx����ɂ��܂����A�J�s��Z���ԂŎ������邽�߂̌����͂ƂȂ�܂����B���_���Ƀ��[�c�����ƌ�����`���ɂƂ��āA����̉e���͉��ł���R�w������S���ӂɑJ�s�����������邱�Ƃ͒��N�̖��ł�����A�ƂĂ��d�v�ł����B�`���̖������o�ϓI�x���Ƃ���Ȃ�A�a�C�����C�ɂ͌��z�y�؋Z�p�ɂ����銈���߂��܂����B���{�̍��y�����܂Ȃ��������Ȃ���|���Ă����a�C�����C�̒n�����ƁA�����̟��H����_�Е��t�̑��c�H���Ɍg���Ȃ���̓������y�،��z�Z�p�̌o�����ɂ����āA�����ނ̉E�ɏo����̂͒N�����܂���ł����B����́A�a�C�����C�ɂ͕������̑��c�����ɔC���ꂽ�̂ł��B�����Ċ����V�c���ł����ꂽ�������菜�����߂̏@���A�h�o�C�U�[�Ƃ��āA�����A�@���S�ƌ�w�́A���O�������̒m���ɂ����Ĕ�ނȂ������Ă�����C�����߂Ƃ��ď�����A�J�s�n�̐��ʂƐ_��̏����ɂ��ĔC���ꂽ�̂ł��B�������āA�`���A�a�C�����C�A��C�̎O���ɂ��R���{���[�V�����ɂ��A�������̑��c���}篁A��������^�тƂȂ�܂����B �������̑J�s��������������A��C�͐����ɑm���ƂȂ邱�Ƃ��肢�A�䔯���x�̎����邽�߈�U�A�ޗǂɖ߂�A�����̋K��ɏ]���č��Ǝ������܂����B�ޗǕ����Ɏ��]���A��w�𒆑ނ��Ă܂ŏC�s��ς݁A�����J������C���A���̂�����Ăѓޗǂɖ߂邱�ƂɂȂ����̂ł��B��C�͂��̌�2�N�ԁA�ޗǑ�����̏Z�m�Ƃ��āA��s�Z�@�̌o�T�Ȃǂ̌����ɓO���܂����A���̊ԁA�_��̗��j�Ƃ��̏��݂ɂ��āA���܂��܂Ȏ��������������ɈႢ����܂���B������796�N�A22�ɂ��ē���藈�����Ă����אM�a��������������܂����A�����̋~�ς�Y��Ė��v�ȏ@���N�w�◧�g�o����ڎw�����ƂɏI�n�����s�Z�@����C�͌����A�u������m��͓������ė~���炸�v�ƁA�ɗ�ɔᔻ���������̂ł��B ������A�F�苁�߂Ă�����C�͌䕧�̌[���ɂ��A�u�v�Ăɍs���ׂ��v�Ƃ̌[�����܂��B���̂Ƃ���ɓ�����K�˂Ă݂�ƁA�����Ŏv������炸�C���h���������[�c�Ɏ��u����o�v�̌o�T���������܂��B���̌o�T�ɂ́A���Ɖ䂪��̂ƂȂ鑦�g�����Ɏ�����̋������L����Ă��܂����B�吨�̏������~�������A������M�肩��V�c���͂��ߑ����̐l�X��������邱�Ƃ�V���Ƃ�����C�ɂƂ��āA�܂��Ɂu�����̏@���v�̊�ƂȂ�ׂ��o�T����ɂ����̂ł��B���̒���797�N�A����23�̋�C�́A�˔@�Ƃ��Đ������������₿�܂��B������804�N�A�����g�Ƃ��Ē����ɓn��܂ł�7�N�ԁA��C�͗��j����p���������ƂɂȂ�܂��B�@ |
|
|
����C�̒m��ꂴ�鎵�N�Ԃ̈Ӗ�
��\�O�ɂ��đ���o�̌o�T����ɂ��A�����̉��`�ɐG�ꂽ��C�́A���ꂩ�猭���g�Ƃ��ē��ɗ����܂ł̎��N�ԁA�������Ă����̂ł��傤���B���̋̊��Ԃɂ��Ă͋�C�̓`�L�ɂ���؋L�ڂ��������߁A�����̑�t�`�ł��m��ꂴ�鎵�N�ԂƂ��ďȗ�����Ă��܂��B�܂��A�Ⴆ�������������ɂ��Ă��A����o�̌o�T����肵����A���̏K���̂��߂ɎR���ɂ��������Ƃ��A�������͓��{�����𗷂��Ȃ���A�����g�Ƃ��ē������鏀�������邽�߂Ɋw����w�ɐ�O���Ă����Ƃ̂ł͂Ȃ����Ɛ�������Ă���ɂ����܂���B���̑O��C�̒Ⴂ�g���ł���A���ɓn�邽�߂̎��Ȏ�����~���邽�߁A�����̋�J���d�˂Ċe�n�𗷂��Ȃ��炨�z�{����A�܂��A�A�������m��������b���Ċw�ł��낤�ƍl�����Ă��܂��B�܂���̐V�đm���Ƃ��āA��C�͓������邽�߂̏����ɗ��ł����Ƃ����̂�����ł����A�ʂ����Ă����ł��傤��? �^��_�́A�܂��A�n�����ƌ���ꂽ��C���A���͑��z�̋��K���g���ē������Ă��邱�Ƃł��B��C�́A�����\�肳��Ă�����\�N�ɓn��؍݊��ԂɕK�v�Ȏ������\���Ɍg���Ă��������łȂ��A���炪�~���鏑�Ђ͉��ł���ɓ���邱�Ƃ��ł����قǁA��Ƃ肪�������悤�ł��B���ہA��C�͌o�T�l�S�Z�\���◼�E��䶗������łȂ��A���X�̕���܂Ŕ������߁A���̃R���N�V�����̎��̍������Ő��̎��ɓ���A�A����A�Ő��̐\������ɉ����āu�،��o�v�Ȃǂ�݂��o���Ă��܂��B���_�A�b�ʘa������������̏��Ђ��������A���w���Z���ԂɏI������ڈ����t�������Ƃ���]�莑�������܂ꂽ�Ƃ����������ł��܂����A������ɂ��Ă��n�������w���̍s���Ƃ͎v���܂���B �܂��A���������O��797�N�ɋ�C������킵���u�O���w�A�v�ɂ́A��C����w�𗣂�ĎR���ŏC�s��ς��Ƃ�������Ă��܂��B������20�ɂ��Ď��˖��ŋ������@�𐬏A���A�����J������A�R�x�@���̍s�҂ƂȂ��āA�������̍s�����ɂ��[���S������Ă����͂��̋�C�����ɁA�������J�s�Ɋւ�鉅���肪���R�Ɨ��z����鍑�Ƃ̈�厖�̎��ƒm��Ȃ���A���z�{�W�߂̂��߂ɍ������s�r����悤�Ȏ���̗����̂��߂̍s�����Ƃ�Ƃ͍l�����܂���B��������C�قǂ̐l���ł�����A�����𗷂����Ȃ�A�K�����̒n��ɉ��炩�̋O�Ղ��c����Ă���͂��ł��B�������A7�N�ԉ����C�Ɋւ������݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�Ⴆ�������Ă����Ƃ��Ă��A���ɂ͂ł��Ȃ����R������������ł͂Ȃ��ł��傤���B�܂��A����Ȃ�C�s���N���������ĐςނƂ��l���h���A����o���w�Ԃɂ��Ă��A��C�̍˔\���炵�Ď��N�Ƃ������Ԃ͗]��ɒ������܂��B �����g�Ƃ��ē��Ɍ�������804�N�A��C�͒ʖ�҂�K�v�Ƃ��Ȃ��قǁA������𗬒��ɘb�������Ƃ���A��C�͓n���l�Ƃ��ϋɓI�ȌW��������O���玝���Ă����Ɛ�������A���̐l���͕��L�����̂ł������ɈႢ����܂���B�@����ɋ�C�������g�ƂȂ����w�i�ɂ́A���炩�ɒ���A����ѐ`���̉���Ǝ���������������������łȂ��A�����Ɏ���܂ł̊ԁA���N�ɓn��A��C�͖����ɓV�c�Ɏd���Ă����ƍl������̂ł��B�����ĉ����ɍv�����A�_��̏����ɂ��Ă��ӔC�����đΉ��ł�����͎҂ł��������䂦�ɁA�����V�c�̓Ă��M�C���邱�ƂƂȂ�A���̌�A����̏@���s���Ɋւ���d��ȃv���W�F�N�g�̐ӔC��C�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B 794�N�ɕ������J�s���������܂������A�����鉅��Ƃ�ꂽ�ɂ��ւ�炸�A���͉������邱�Ƃ͂Ȃ��ˑR�Ƃ��Ċ����V�c��Y�܂������Ă��܂����B�����Ċ��Ɍ����J���Ă�����C�́A�J�s����������������A��s�Z�@�̖{���n�ޗǂœ�N�ԁA�w�т̂Ƃ��������Ȃ��璲���Ɏ��Ԃ��₵�܂��B�s�̍s�����ɂ��Ă��[���S������Ă����ł��낤�ƍl�����邾���ɁA����̎��ӂɕs�K�ƍГ�A�����ċN���Ă������797�N�A��C�͉��炩�̏d�v�Ȗ�ڂ삩�������A���ꂩ��7�N�ԁA�S�g�S��������Ď��g�ނ��ƂɂȂ������Ƃ�����j���獚�R�Ǝp�������Ă��܂����Ƃ͍l�����Ȃ��ł��傤���B���������̃v���W�F�N�g�͋ɔ�ł��������߁A���ɂ��邱�Ƃ��ł����A�L�^�ɂ��c��Ȃ��قǖ�����7�N�̎����߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B�����Ė����̌o�T������797�N����������܂ł̎��N�ԁA��C�͏�����₿�܂��B ���傤�ǂ��̓����A�����Ŗ�N�ɂȂ��Ă�������ɂ����āA�N���Ώ��ł����ɕ��u����Ă�������肪����܂����B���ꂪ�A�����̐�D�Ƃ�������u�_��̈ڐ݁v�ł��B�V�c�Ɠs����삵�A���Ƃ̈��ׂ��������邽�߂ɁA�V�s�ɐ_����ڐ݂��邱�Ƃ��s���ł������A�����A����ɂ͂�������s�ł���҂����Ȃ������̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A���Â̎��ォ��N�����M���|��邠�܂�A������ł����_���G�邱�Ƃ͂��납�A�T�����茩�邱�Ƃ��������܂�A�����ɂǂ�Ȑ_�鑠����Ă���̂�������������Ȃ��ɂ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �������̌��^�ł���ƍl������C�X���G���̃G���T�����_�a�ł́A�_�a�����z���ꂽ����ɁA���̖��ɂ���Đ_�a�Ɂu��̌_��̔��v�Ɓu�_�̐��Ȃ�Ջ�v���^�т��܂�܂���(��㎏��22��)�B���l�ɁA�������ɂ����Ă��_��̈ڐ݂������]�܂�A���ꂪ�����̒��ł���ԁA��ȃ|�C���g�������̂ł��B��C�̏������r�₦���̂��������̑J�s����Ƃ������Ƃ�����A���삪�����Ɏ��g��ł���^�Œ��Ƃ����^�C�~���O����@���Ă��A��7�N�Ԃ͐_��ɊW���Ă���\���������ƍl����̂��Ó��ł��B�������̉ƌn����y�o���ꂽ�L�\�ȏ@���Ƃł����������ɁA��C�ɂƂ��ăC�X���G���̐_���T�����邱�Ƃ͌����Đl���Ƃł͂Ȃ������͂��ł��B�܂��Ă�A�̋��̎l���ɂ����ẮA���R�̎��ӂɃC�X���G���̏W�������݂��A�����ɂ͐_�鑠����Ă���Ƃ��������`�����Â�����c����Ă��������ɁA��C���[���S�������Ă����ɈႢ����܂���B ����ɋ�C�̕���ł��鈢�����̃��[�c��k���Ă����ƁA�P�ɐ`����Ƌ��ɃC�X���G���̋N���Ōq�����Ă��邾���łȂ��A�������ƌĂ��ꑰ���̂��̂��A�_��̎�舵���Ɛ[���ւ���҂Ƃ������j�����݂��Ă����̂ł��B����䂦�A��C���������̉ƌn�ɑ�����҂Ƃ��āA�_��̎�舵���ɋ����������Ă��������łȂ��A���ۂɑ�X����`������Ă��������`�����܂߂āA���܂��܂Ȓm�������ɓ��Ă����\���������̂ł��B�������ċ�C�́A�_������������邽�߂̑��l�҂Ƃ��āA�����菢���ꂽ�ƍl�����܂��B �����̔w�i����A��C�̒m��ꂴ��7�N�Ԃ��𖾂��邽�߂ɂ́A�P�ɋ�C�̕����������邾���łȂ��A��C���Ƃ�܂������Ə@���̊����������Ȃ���A�����𗬂̗��ɐ��ތ��͓�����A�����Ɏ��g�ޏ@���Ƃ�̓����A�܂��m���K���̐l���Ƒ��݊W�Ȃǂɂ��ڂ𗯂߁A����炪�ǂ̂悤�ɋ�C�̐��U�ɉe����^��������T��K�v������܂��B�����ĕ��������̎���ɂ����āA�_���N���A�ǂ̂悤�ɊǗ�������̂ł��������A�Ƃ������Ƃ��܂���������K�v������܂��B�����āA�����̐��܂������͓����Ɖ�����Ŏ~�߂���C������@�����V�����ǂ������A�ǂ̂悤�ɍs�������ł��낤���Ɛ�������̂ł��B�����ċ�C���������O�ƁA���̌�A�ēx�p�������������r���A�����̋��ʓ_�����C�����Ǝv����O�Ղ�H��Ȃ���A�ǂ��ʼn������Ă������A�ǂ������l�X�Ɩʎ������������Ƃ������Ƃ����ɂ߂邱�Ƃ��厖�ł��B����ƁA�����ɂ́A��C�Ɠn���l�A���Ɉ������Ƃ̊ւ���A���삩��̉���A�����Đ_��̍s���Ȃǂ̃e�[�}�������B�ꂷ�邱�Ƃ��킩��܂��B�������ЂƂЂƂ����邱�Ƃɂ��A����ꂽ���N�Ԃ̐^���������Ă��܂��B�@ |
|
| �@ | |
|
���n���l���劈��Ñ�Љ�
3���I�ȍ~�A�n���l�̗��ꂪ��ς��A�˔@�Ƃ��đ吨�̖������N��������C��n��A�V���N���[�h�̍ŏI�n�_�ƂȂ������{�ɈڏZ���Ă��܂����B����܂ł��n���l�̗���͗ɂނ��ĉ��S�N�������Ă��܂������A���̗��ꂪ��C�ɉ��������̂ł��B�����Ė퐶����������A�ޗǎ���ɂ����āA���ɌÑ�Љ�̃����e�B���O�E�|�b�g�ƂȂ����ޗǖ~�n�̎��ӂɂ͑����̒m���K���w�̓n���l�����Z����悤�ɂȂ�A�嗤�����̗����ƂƂ��ɉh���܂����B�����̌Ñ�Љ�ɂ����Đ�����@���A���w�A�_�ƂȂǁA���{�̎Љ�S�ʂɑ���ȉe����^���A���{�����̊�b��|�������͂ƂȂ����̂́A�n���l�ɂق��Ȃ�܂���B ���̌�A�n���l�͗̕����ɓ������A�����N���������ē��{�Ǝ��̕��������グ�Ă������Ƃɍv�����܂����A�������Ȃ���A�L�͎҂̏o���̂قƂ�ǂ��嗤�n�ł��邱�Ƃɕς��Ȃ��A���̖������Ɠ��ِ��ɂ��ẮA�V�V�n�ł�����{�̒n�ɂ����Ă����N�A��������A���̎����͗��j�ɖ����c�����ƂƂȂ�܂��B�Ⴆ�Β�����(�����s�{)�̎��ӂɋ��Z���Ă����`���A��⎁�A�����A�o�_���Ȃǂ̑����́A�n���n�ł��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�����̗L�͎҂̌o�ϗ͂ƍ������{�̃��x���͓n���l�Ȃ�ł͂̂��̂ł���A���̖��O�̑������w�u���C��̈Ӗ��������Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A�n���n�̒��ɂ͒P�ɒ����⒩�N�����Ƃ̌q���肾���łȂ��A�C�X���G���n�̖����������݂��Ă����Ǝv���܂��B���ł��R�w���Ŏ���������A�������J�s�̗����҂Ƃ��Ċ����`���ƃC�X���G���̊W�ɂ��Ẳ\�͐₦�܂���B�`���͂��̍��͂Ƒ嗤�����Ɍq����l���̂ɁA�������J�s�̍ۂɂ͏��L������Y��s���Y�����サ�A�����V�c�̐M�C�Ȃ��璩��ɂƂ��đ傫�Ȍo�ϓI�x���ƂȂ�܂����B�܂��A����ȑO�A���鋞���璷�����ւ̑J�s�ɂ����Ă��A������w������������p�̕�e���`���ł���A��A�̑J�s�̔w�i�ɂ͓������瑽���̐`���̉e��������������Ă����ƍl�����܂��B �`���̂ق��ɂ��ޗǎ��������畽�������ɂ����āA���ڂ��ׂ��n���n�l���A���������яオ���Ă��܂��B�܂������V�c�̕�e�́A�����V�c�́u�䂩��v�����ɂ��������悤�ɁA����V�}�Ƃ����S�ς̏o�ł���A�����̘a���͕��鉤�R���̕S�ω����ł��B�܂��A������������A�����V�c�Ɏd�����Ő��́A�㊿�̍F����̎q����c��Ƃ���O�Î��(�݂̂���)�̉ƕ��ł���A�����n�̓n���l�̎q���ł��B�����ċ�C���A����̈��������A���l�ł��B�����ċ�C�̔����ɂ����鈢���呫(���Ƃ̂�������)�́A���̗D�ꂽ���{�ƒm��������ł������]������A�����V�c�̍c�q�A�ɗ\�e���̎��u���߂Ă����قǂł����B���̈����呫�������炭�����Ŋw�ƍl������_��A�F�o�A�j�`�𒆐S�Ƃ��������̒m�����A�c����C�Ɏ���������̂ł��B�������ČÑ�Љ�ɂ����ẮA����Ƃ���œn���n�̐l��������ɑ傫�ȉe���͂�^���A���{�̕����̑b�����傫�Ȍ����͂ƂȂ��Ă����̂ł��B�@ |
|
|
�����������D�ꂽ�@���Ƃł��闝�R
��C�̕���ɂ����鈢�����̏o�����n���l�ł���A�C�X���G���̖���ł���\���������A�Ƃ������Ƃ�m��Ƌ������������Ȃ��Ȃ��͂��ł��B�������Ñ�Љ�ɂ����Ĕ��w�ł��邱�Ǝ��́A�n���l�Ƃ̌��т��Ȃ��Ă͐������邱�Ƃ�����̂ł��B��C�́A������n���l�ł��邪�䂦�ɁA���̔����ɂ����鈢���呫���班�N����ɑ����̋��{���w�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�܂��A���E�j��A���_���l����̑�Ȑl���������y�o����Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A���{���ւ�̑�ȏ@���w���҂ł����C���A���̌������p���ł���̂ł���A�ނ���ւ�Ɏv���ׂ��ł��傤�B�������̉ƌn�͑����̗D�ꂽ�@���Ƃ�y�o���Ă���A�@���@�������ł������R�������ɂ���悤�ł��B����������������𗝉����A�����ꑰ�ł����C�Ƃ̐ړ_�����o�����Ƃ��A��C�̐������������łȂ��A���̎u������S���s�r�̓��@�A�����ė��j�̋ƂȂ��Ă����C�̒m��ꂴ�鎵�N�Ԃ𗝉����邽�߂̑�Ȍ��ƂȂ�܂��B �܂��A��C�̊���Ɠ������A�ޗǎ��������畽�������ɂ����Ė@���@�𗲐��ɓ������@���Z�c�̑m���̈�l�A��a���o�g�̑P��ɒ��ڂł��B�����I�̏I���A��s�Z�@�ł͌o�T���u�������̉��߂��ɂ߂邱�Ƃ��d�v������A���̌��ʁA�o�T�̎ߋ`�ɒ����Ă����@���@�����@�����|����悤�ɂȂ�܂����B�����A�@���@�̃��[�_�[�i�ł������P��́A����Ƃ��[���ւ��������A�c���q���a�e���̌����M�����Ă��������łȂ��A�}���������ǐe���Ƃ��𗬂�����܂����B�܂��A�H�����J��A�����ł͌㐢�ɂ����Ė@���@�Ɛ^���@�����w����邱�ƂɂȂ�܂��B ���̑P�삱���A�@���@�@���̒��_�ɗ��������т̈���q�ł���A���������т���g���߂������{�q�Ƃ̊Ԃɂł����q�Ƃ������Ă��܂��B�����đP��̑��`�ɂ́u�@�t�������s�h�H�v�A���т��u���ѐ��������v�Ə����Ă��邱�Ƃ���A�Ƃ��Ɉ������̏o�ł��邱�Ƃ��f���܂��B����Ɂu���厛�v�^�v���Q�Ƃ���ƁA���т̎t�ł���`��(������)���������Ȃ̂ł��B�܂�`�����猺�сA�����đP��ƈ����p����Ă����@���@�̖@���́A�܂�����Ȃ��������ɂ���Čp������A�ޗǂ��畽�����㏉���ɂ����āA���̏@�������͂͒��_���ɂ߂܂����B ���������A���삪�Y�܂��ꂽ���ǐe���̉�����ɂ��Ă��@���@�͐ϋɓI�Ɋւ��A���ɑP��́A���ǐe���̢���죂���邾���łȂ��A��͂������Ē��߂邱�Ƃ��ł������߁A�V�c�̌����M�C�܂����B��s�Z�@�̉e�������瓦��邽�߂ɑJ�s�ɓ��ݐ����o�܂��炵�āA����܂ňꌩ�A�Η��W�ɂ������Ǝv���Ă�������Ɠ�s�Z�@�Ƃ̊W�ł����A���ۂɂ͒���Ɩ@���@�̃��[�_�[�ٖ͋��ȊW��ۂ��Ă����̂ł��B����͉��������邠�܂�A�m�����͂ގv���ŗ�͂�L����҂ł�����S�O�����o�p���Ă���A�Ő���n���Ŋ���@���Ƃ����łȂ��A�ޗǂ����_�Ƃ���P���ɂ������|�����܂����B�������đ����̗D�ꂽ�@���w�҂�y�o�����@���@�́A��͂������Ē���Ɏd���A���J������S���l�ނɂ��b�܂�Ă����̂ł��B ���̖@���@�̗�������ފw�҂̈�l���A��C�̕���̔����ł���A�����呫�ł��B�ނ͒���ɂ����Ċ����V�c�̎q�ł���ɗ\�e���̎��u���߂������łȂ��A��C�ɂ������Ă��܂����B�܂�ɗ\�e�������łȂ��A��C�������呫��ʂ��Ė@���@�̑m����Ɛe����[�߂�@��������ƍl�����܂��B����䂦�A��C�͓�s�Z�@�̂��肩����ᔻ���邱�Ƃ͂����Ă��A�F�D�I�ȊW��ۂ������A��ɍ���R���J�����ۂ��A���₩�ɐ��n���\���邱�Ƃ��ł����̂ł��B�����A�@���E�ɂ����Ă͈��|�I�Ȑ��͂��ւ鈢�����̏o�ł���A�V�c���͂��߂Ƃ��钩��ƁA��s�Z�@�ň�Ԃ̐��͂����@���@�A�o���̐l���Ɍb�܂ꂽ��C�́A���Ƃ̕��a�ƍc���̑�����肢�A���痧���オ��܂��B�����ēV�c�̓Ă��M�C�āA����܂ŒN���肪���邱�Ƃ��ł��Ȃ���������v���W�F�N�g���莒�邱�ƂɂȂ�܂��B �������������ɂ��āA����قǂ܂ł̏@�������͂����Ɏ������̂��A���̔w�i�����ɂ߂邽�߂ɁA���������n���n�ƌ����Ă���䂦��ɂ��Č����Ă݂܂����B�������͈��l���Ƃ������A�������̌n��̎����ł��B�����J�s�̍ۂɁA�������̑c�_�͉͓����a��Q(�����̓����ߕ�)���J������A���s�s�E���捵���̈����_�Ђ��J���܂����B����3�N�Ɋ��������_���I�^(�����낭)�ɂ��ƁA���̑c�_�Ƃ͈����h�H�c�_(���Ƃ̂����˂��₪��)�ł���A�V�Ƒ�_(�A�}�e���X�I�I�~�J�~)����_���������A�_�������ɐ旧���ĉ͓����ɓV�������`������(�j�M�n���q�m�~�R�g)�̑��A���`�c��(�A�W�j�M�^�m�~�R�g)�̎q���ɂ�����܂��B���������ɕҎ[(�ւ�)���ꂽ�V����^�ɂ������h�H���`�������̑��ł��閡�`�c���̌���ł���Ƃ����L�q������A�������ɏ����ꂽ�u��㋌���{�I�v��10���A�u�����{�I�v�ɂ��`�������̌ܐ����ɂ�����刢�l����(�������Ƃ̂����ˁA�����h�H)���������������Ə�����Ă��܂��B�Õ����̉��߂͕s�����ȕ����������A�u��㋌���{�I�v�Ȃǂ́A���̏����̓��e���炵�ċU���Ƃ݂Ȃ���邱�Ƃ�����܂����A�������̑c�_�ł����`�������Ɋւ���L�q�ɂ��Ă͐M�ߐ��������ƍl�����܂��B���̌��ʁA����15�N����A���s�{�ɂ��Ҏ[���ꂽ�_�Ж��ג��ɂ́A�����h�H�c���`�c���������_�Ђ̍Ր_�ł���ƋL�ڂ���邱�ƂɂȂ�܂����B�������̏o�����A�����݂ɒ��ڐ[������������`�������̒��n�ł��邱�Ƃ́A��Ϗd�v�ȈӖ��������܂��B ����Ɂu��㋌���{�I�v�ɂ́A�`�������Ɛ_��Ƃ̊ւ��ɂ��Ă������̋L�q���܂܂�Ă��邱�Ƃɒ��ڂł��B���̓��e����{���I�A�Î��L�ƏƂ炵���킹�ēǂނ��Ƃɂ��A�`�������̖�ڂ���薾�m�ɂȂ�܂��B�܂����{���L�ɂ��ƁA�V�Ƒ�_���瓝�����̏Ƃ��Đ_������������`�������́A��������n��(�j�j�M�m�~�R�g)�������̍�����ɍ~�Ղ���O�ɁA�D�ʼn͓����ɓV����A���̌�A��a�Ɉڂ����Ƃ���Ă��܂��B�u��㋌���{�I�v�ɂ��ƁA���̐_��͓V�_��c(�A�}�c�J�~�~�I��)���������ꂽ2��̋��A1��̌��A4��̋ʁA������3��̔��ł���A�u����\��(�~�Y�m�^�J���g�N�T)�v�ł���Ƌ�̓I�ɋL����Ă��܂��B���̌�A�_���V�c�����ʂ���ہA�`�������͐���\������n���A�V�c�̐b���Ƃ��đ��ʂ̋V��������s���A�V�c�ƂɊւ��e��̒�߂����߂邱�Ƃɍv�����܂����B �܂��A�Î��L�ɂ͐_���V�c�̓����ɗ����`�������Ɋւ���L�q������܂��B��a�̍��i�o�����`�������́A���̒n����x�z���Ă��������̒����F(�i�K�X�l�q�R)����U�͕��]�����A�����F�̖����Ȃɂ��܂��B���̌�A�����n���̑��ɂ������̐_���V�c(�J�����}�g�C�����q�R)���������Ē����F��ł��j�����ۂɁA�V�c���V�Ƒ�_�̎q���ł��邱�Ƃ�m��A�`�������͐_���V�c�ɋA�����A���ꂩ��͍��J�̖�ڂ���ɒS�����ƂɂȂ�܂��B�܂�A�V�Ƒ�_�̑��ł����`�������́A�V�_��c�̒��߂������Đ_����Ǘ����A���J�̖�ڂ�S���A�����߂��x���邽�߂ɐs�͂�����Վi�������̂ł��B�����Z��ł��Z���`�������͏@���V�����i��ƌn�̗�������ވꑰ�ƂȂ�A��������n���́A�c���̌��_�ƂȂ�_���V�c���͂��߂Ƃ���c����y�o����ꑰ�̗���ƂȂ�A���ꂼ�ꂪ�ʌn���̌����p���ł������ƂɂȂ�܂��B �����V���~�ՂɊւ���Õ����̋L�q�́A�O�q�����Ƃ���A�C�X���G���̖������A�W�A������{�ɈڏZ���A���̐V�V�n�ɂ����đ��������o�������A�j���Ɋ�Â��Ȃ���_�b���������̂ł���ƍl�����܂��B����䂦�A�����̐_�b�ɂ͂��悻���ׂāA���̃��f���ƂȂ����l�������݂����̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�ł��܂��B���ł��A�Վi�̖�ڂ����킳�ꂽ�����́A�����̊��s�ǂ���A�C�X���G���̃��r�l�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�C�X���G�������s���ē��{�ɓ������Ă��������́A�a���҃C�U���Ƃ��̍ȁA�q���A����ѐ_��̎�舵����C���ꂽ���r���̃��[�_�[�����ł����B�C�U�����g�̓��_���ɑ�������̂ł����A�Ȃ̒��ɂ̓��r���ɑ����鏗�������݂����\��������A�܂��A���̎q���̒��ɂ̓��r���ƍ����W�����҂����������Ƃł��傤�B�܂��A���A�W�A���瓯�s���Ă������l�̒��ɂ́A���n�ꑰ�̎q���������\��������܂��B������ɂ��Ă��A���l���Œ��������Ȃ���A�̓��X�Ɍ������Œ��A�C�U���̐S���ɂ͉��n���_���̌����ƁA�_�����舵���Վi���r���̌����́A�Ƃ��ɐ�ɐ�₵�Ă͂����Ȃ��Ƃ����v�����������̂ł��B���̌��ʁA���_���ł���C�U���̉ƌn����́A���n�_�r�f�̌������p���҂����łȂ��A���r���̌����̗�������ގq�������܂ꂽ�ƍl�����܂��B���̃��r���̌������p�����������ƂƂȂ��l���`�������ł��B�����āA���̖���Ƃ��āA���������o�ꂷ�邱�ƂɂȂ�܂��B �O�q�̂Ƃ���A�������̑c�_���`������(�ɂ��͂�Ђ݂̂���)����ł��鈢���h�H�c�_(���Ƃ̂����˂��₪��)�ł���A�u��㋌���{�I�v�ɂ��A�`�������Ɛ_��Ƃ̊ւ��ɂ��ďڍׂ̋L�ڂ�����܂��B�܂��u�V����^�v�ɂ��A�`�������͍��V���̏o���ł��邱�Ƃ��L����Ă��܂��B���̍��V���Ƃ́A�C�X���G���̖��̑c��u�A�u���n���v�̐��܂�̋��ł���A���Ƃ���������ɑ嗤�����f����r���A�C�U����s���؍݂����ꏊ�Ƃ��l�����Ă��܂��B�܂��A���V���Ƃ͓��{�Ƒ����āA���A�W�A�̃^�K�[�}�B�n�����A���Ȃ킿���V���ɒn�����̑嗤�̈ꕔ���w���Ă���Ƃ��l�����܂��B���̏ꍇ�́A���A�W�A�ł������m�݂⒩�N�����ł��A���V���ƌĂԂ��Ƃ��ł���ł��傤�B������ɂ��Ă��A��s�̗��̓r���ɂ��鍂�V���ŏo�������̂��`�������ł��B�嗤�Ő��܂�A��ɐ������ĐN�ƂȂ����`�������́A���{���ӂɓ���������A��������n��������s���ĊC��n��A�̗��n��ڎw���Đi�݂܂����B���V���̏ꏊ�����m�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A�������̃��[�c�����������`���������獂�V���܂ł����̂ڂ邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ǝ��́A�������͑嗤�n�ł���A�������C�X���G���Ɛ[���q�����Ă����\���������ƌ����܂��B�@ |
|
|
�����������鈢�����̏o��
���̈������Ɛ_�����舵���Վi�̓����Ƃ̌q����ɂ��ẮA�����̋L�q��������o�����Ƃ��ł��܂��B���̔w�i�ɂ���C�X���G��12�����̗��j�A���Ƀ��r���ƃC�X���G���̐_��Ƃ̊ւ��ƁA���_���̖����ɒ��ڂ��Ă݂܂����B�C�X���G���Ƃ������O�́A�����̕��ł��郄�R�u�̕ʖ��ł���A���R�u�ɂ�12�l�̎q�������܂����B�ꎞ�̓z�ꎞ����o�ăG�W�v�g��E�o���̒n�J�i���Ɍ������r���A�C�X���G���̎q�������͐_�̖��ɂ���Ď������ƂɌːГo�^���s���A��������C�X���G��12�������n�܂�܂��B���̌�A�̒n�ɂ����č��Ƃ��������܂����A����A����C�X���G�������͕��A�k�����C�X���G����10�����Ɠ쉤���̃��_���ƃx�j���~������2�����ɕ�����Ă��܂��܂��B�܂��A���Z�t�̑���ɔނ̎q���ł���G�t���C���ƃ}�i�Z�����R�u�̗{�q�Ƃ��Ėk�C�X���G��10�����̓���2�����ƂȂ�܂����B���̂��߁A����12�l�̒��Ɋ܂܂�Ă������r�������O����Ă��܂����̂ł��B���̂ł��傤���B �����͐����́u�����L�v�ɖ��L����Ă��܂��B���r���ɂ́A�_����u�����Ƃ��ׂĂ̍Ջ�̉^���ƊǗ���������v�Ƃ�������ȔC�����^����ꂽ���߁A�ːГo�^�̑ΏۊO�ƂȂ�A�C�X���G���̕����Ƃ��ēy�n�����L���邱�Ƃ�������Ȃ������̂ł��B�����Ō���Ă��開���Ƃ́A�C�X���G���̖����_�̏Z�܂��鐹�Ȃ�ꏊ�Ƃ��Đ��߂��ړ����e���g�^�̐_�a�̂��Ƃł��B�����ă��r���͐_�a�̎��͂ɋ��Z���Ȃ���A�Ђ�����_�Ɏd����Վi�ƂȂ�܂����B����䂦�A�G���T�����ɃC�X���G���_�a�����z���ꂽ����A���r���͐_�a�̎��͂ɋ��Z���A�ق��̕����̂悤�ɓy�n�����蓖�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ��A�ƒ{�̕��q�n�݂̂��^�����܂����B�܂背�r���͐_�Ɏd�����D�G�Ȗ��ł���Ȃ���A�_�����舵�����E�Ƃ�������ɒu���ꂽ���ߎ��Y�����ĂȂ������̂ł��B�����Ɉ������̉ƌn�Ƃ̋��ʓ_������悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B ���āA���̃��r���̉ƒ��ł��郌�r�ɂ́A�Q���V�����A�P�n�g�A��������3�l�̎q��������A���ꂼ��ɖ����̋߂��������܂���(�����L3��)�B���ł��P�n�g���̖�ڂ́u�������x��v���A�u�_��̔��A�������̊��A�C��A�Ւd�A�����ɗp�����鐹�Ȃ�Ջ�A���A����т����ɂ������d���v�ɐ�O����Ƃ����d�v�Ȃ��̂ł����B���̏�A�P�n�g���ȊO�́A�����Ă����̐_��ɐG�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����|����߂��A�_�́u�P�n�g�̏����������r�l�̒�����f�₵�Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƍ����܂����B����āA�C�X���G���̖��̒��ŗB��A�_�����舵�����Ƃ�������Ă��郌�r���A���ł��P�n�g���́A�C�X���G���̍��Ƃɕs���ȑ��݂ƂȂ����̂ł��B���̃P�n�g���̏o�������[�Z�ƃA�����ł���A���r����26��ڂ̃��U�_�N(�I���O586�N����)�܂ł��̉ƌn�����m�ɐ����ɋL����Ă��܂��B �Ƃ��낪�A�_�a�Ɛ_��̊Ǘ���C���ꂽ�͂��̃��r���̂قƂ�ǂ����j����p�������Ă��܂����̂ł��B����C�X���G�����Ƃ�������A�I���O721�N�ɂ͖k�����C�X���G�����A�����ċI���O586�N�ɂ͓쉤�����_���ŖS���܂����B���Ƃ̕����A�k������10�����͗��U���čs�����킩��Ȃ��Ȃ�A�쉤���̃��_�́A�ߎ��̖��Ƃ��ăo�r�����ɘA��Ă�����A���ꂩ�炨�悻50�N��̋I���O538�N�A�y���V�����̖��߂ɂ�胆�_�̕ߎ��̖��͑c���̒n�ɋA�҂��邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�G�Y����2��40�߂ɂ��ƁA�A�҂����쉤�����_�̖��̐��͕����A�����Ƃɐ��S�l���琔��l�̋K�͂ł������̂ɑ��A���r����74�l�A�r���҂�128�l�A�����Ė�q��139�l�������Ȃ������̂ł��B��㎏��9�͂ɂ��ƁA�r���҂Ɩ�q�����r���ł���A���ɖ�q�́u�_�a�̍Վi���ƁA�ɂ̐ӔC�v�Ƃ����d�ӂ�w���킳�ꂽ���߁A�_�a�����݂��ꂽ�ۂɂ�4,000�l���C�����ꂽ�Ƃ���܂��B �Ƃ��낪�ߎ���ɋA�҂������r�l�̐���139�l�Ǝv���̂ق����Ȃ��A���r���S�̂ł�341�l�������܂���ł����B���̗��R�ɂ��āA��ʓI�ɂ͑c���ɂ����郌�r���̎Љ�I�ҋ����ǂ��Ȃ���������ƌ����Ă��܂����A�{���̗��R�͈Ⴂ�܂��B�����܂ł��Ȃ��A���r���̑唼�͍��Ƃ������ہA�_��̔��ƂƂ��ɁA�V�V�n�����߃A�W�A�嗤�����f�����s�Ɠ��̓��X��ڎw�����ɏo���̂ł��B�_���ȍՋ�ɐG��邱�Ƃ������ꂽ�̂̓��r�������ł��������߁A�a���҃C�U���̌��t��M���嗤�����f�����吨�̖��Ƌ��ɁA�_��̔���_���ȍՋ���^�������ڂ��ʂ������߂ɁA�����̃��r�������s�����̂ł��B ���̃��r���̒��ɁA�w�u���C���(��)(�A�^�AAter)�Ə����A�e���������܂���(�G�Y��2��42��)�B�A�e�����̓o�r�����ߎ���ɑc���A�҂���ہA�l�w�~����ƂƂ��Ɏ�̌_��ɒ����_�̂������1�l�ł���(�l�w10:17)�A���ۂɑc���̒n�ɋA�҂����A�e�����͐��\�l�ɂ������Ȃ������悤�ł��B�܂�A����ȑO�Ɋ��ɑ嗤�𓌂ւƗ��������l�X�̒��ɑ吨�̃A�e�������܂܂�Ă����ƍl�����܂��B�w�u���C��ŃA�e��(��)�̔����́A���{��́u�A�g�v�Ƃ��������邽�߁A�������̃��[�c�������ɔ�߂��Ă���\��������܂��B �����̔w�i���炵�Ă��A����������͏@���w�҂������y�o����A���w�ł������ɂ��ւ�炸�A�o�ϓI�ɂ͂��قnjb�܂�邱�Ƃ��Ȃ��������R�������Ă��܂��B���r���̏o���ł���A�P�n�g������ł��鈢�����̑c��́A�����A�y�n����Y�����L���邱�Ƃ�������Ă��炸�A�_�a�̋߂��ɏZ�܂��A�_�a�Ɛ_����Ǘ������ڂ��������Ă����̂ł��傤�B���̂��߈������̐�c�ł����`�������́A�u��㋌���{�I�v�ɋL�ڂ���Ă���Ƃ���A�A�}�e���X���10��̐_��A�u����\��(�݂��̂�����Ƃ���)�v��������A�_�Ɏd���邱�Ƃ�E���Ƃ��Ă܂��Ƃ������ƍl�����܂��B�܂��`�������́A�C�X���G���̃��r���̏o�Ƃ��āA�_�a�̕ɂ��Ǘ�����ӔC��S���A���̐Ӗ��̓C�X���G�����牓�����ꂽ���{�̒n�ɂ����Ă��������Ɍp������A�����ĕ��������ɂ����Ă͋�C�ւƈ����p����Ă������ƍl�����܂��B�����Ă�������C�̐S�̉��ɂ́A�C�X���G���̗��j�ɓ��݂���_��ւ̋������h�̑z���Ɠ��ꂪ�����オ���Ă����̂ł��傤�B���������~���A�����V�c�������邽�߁A�����Đ_����̏j�������ׂĂ̖������邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�������ł����e������C�́A�Վi�̔C����^����ꂽ���r�l�̌��������ސ_�̖��A�C�X���G���̖���Ƃ��āA��Վi�̓����𐬂������Ă������ƂɂȂ�܂��B�@ �@ |
|
| �����R�Ƌ�C | |
|
�����R�ւ̋�C�̑z��
�u�����߂����߁v���w�u���C��Ŗ|��ƁA���̉̎��̓C�X���G���̐_��ɂ��Ă̎�舵���ƁA���̍s���ɂ��Č��y���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B���̉̎��̉𖾂����������Ƃ��āA�M�҂͕��Ɍ��̐V�_�ˉw�A�k���ɂ���ēx�R�̑��݂�m�邱�ƂƂȂ�A��C�������g�Ƃ��Ē�����K�˂��O���2��ɓo�������̎R���A���́A�d�v�ł��������Ƃ������R���l���������邱�ƂɂȂ�܂����B�ēx�R�͒n�}��ŁA�ɐ��_�{�ƐΏ�_�{�Ƃ����j���ɂ��L����Ă��閼����2�̐_�Ђ����Ԓ����̉�������ɂ����邱�Ƃ��炵�Ă��A�ɂ߂ďd�v�Ȉʒu�ɂ��邱�Ƃ��킩��܂��B�������A���̍ēx�R���獡�x�͓쐼�����ɂ���W�H���̈ɜQ���_�{�Ɍ����Đ��������ƁA���̉�������Ɍ��R�̒��オ���݂���̂ł��B �ɜQ���_�{�́A���̋����ɐݒu���ꂽ�傫�Ȓn�}�ɕ`����Ă���Ƃ���A�O�q�����ɐ��_�{�ƑΔn�̊C�_�_�ЂƂ܂����������ܓx�Ɍ�������Ă��邾���łȂ��A��������Ď��A�~�����w��30�x���������ƁA�o�_��ЁA�z�K��ЁA�F���ЁA�����ċ�B�̍����ɂ����� �܂��B�ɜQ���_�{�͏��X�̒����ȗ�R��n�A�_�Ђ̒��S�I���݂Ƃ��ČÂ�����m���Ă��������łȂ��A���ۂɒn���I�ɂ�����琹�n�̒��S�n�ƂȂ�ꏊ�Ɍ�������Ă����̂ł��B�ɐ��_�{�ƐΏ�_�{�A�ēx�R�ƌ��R���n���I�ɈɜQ���_�{�𒆐S�Ƃ��Č��т��Ă��邾���łȂ��A����R�╽�����Ƃ��W���Ă��邱�Ƃ́A�����̈ʒu��n�}��Ŋm�F����Έ�ڗđR�ł��B�������ĈɜQ���_�{���A�m���ɌÑ���{�ɂ����Đ_�Ђ̒��S�ł���A���̐_�{������W�H�������A�j�����L���Ƃ��荑���݂ɂ�����ŏ��̓��ł��邱�Ƃ��킩��܂��B ���āA���̌��R�ɂ͐̂��烆�_�����[�c�̉\������A��̂ɃC�X���G���́u�_��̔��v��_���R�̎R�����ӂɉB���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����b�����Ƃ�����܂��B�S���e�n�ŊJ�Â������{�̍Ղ�̏ے��ł�����_�`�́A���̌`�Ԃ��������Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A�C�X���G���̌_��̔������f���Ƃ��Đ_�`���f�U�C�����ꂽ�\��������܂��B�_��̔������ۂɓ��{�Ɏ������܂�āA���̃��v���J���S���e�n�ō���A�Ղ�̍ۂɒS�����悤�ɂȂ����ƍl����A���̃��[�c�������ł��邾���Ȃ��A���c�ƂȂ�_��̔����́A���ł����{�̂ǂ����ɔ鑠����Ă���\�����c����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���������̏ꏊ����肷�邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��悤�ł��B�Ƃ��낪�A�w�u���C���[�c�����Ǝv����u�����߂����߁v�̈Ӗ������������������ʁA�����ɂ͓��{�����ɐ��ރ��_�����[�c�̍��Ղ��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��邾���łȂ��A���R�����́A�Ñ���_��������Ă����̂��A���̏d�v���𗝉����錮����߂��Ă����̂ł��B�l���̗�R�Ƃ��Ė��������R�́A�����{�ŐΒȎR�Ɏ�����2�Ԗڂ̕W�����ւ�R�ł���A�W�H����������邱�Ƃ̂ł����R�ł����A��C���g�͂͂����Ăǂꂾ���̑z�������R�ɊĂ����̂ł��傤���B�@ |
|
|
�����R���͂ގl�����\�������̈Ӗ�
�l����������Ȃ����C������̑��ŕ�������A�K�˂����̂�����ǂ�Ȃ���88�����̎��@�����1200�q�ɂ��B����H�́A�u�l�����\�������v�ƌĂ�A���܂�ɗL���ł��B���̕H�̒��S���ނ����̂����R�ł����A�H����͂��̒�������邱�Ƃ��قƂ�ǂł��܂���B���Ԃ̎D���ł����R���͎l���̖k���Ɉʒu�����̋ߍx�ɂ���܂��B�������炨�悻���R�ȓ����\�Ԃ̐ؔ����܂ŕ��������A���̍���ɂ��鉜�̉@�܂ŊK�i��o��߂āA���̍��䂩��͉���������ɁA���R�̒��オ�R�X�̂��Ȃ��ɂق�̂킸���A�˂��o���Č����邾���ł��B�����Ď��̑�\��ԓ��䎛���猕�R�̕��p�ɂ����\��ԎD���̏ĎR���ւ̎R���͑�ό������A���r�������Ă���1�������Ă���Ƃ��ǂ蒅���邩�Ƃ����قǁA�r���ɂ͋}�Ζʂ������܂��B�~��Ȃ��U���ɖ����Γ������o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��������������ɁA�H������l���A������ł��悢�Ƃ����S�\���̕\��Ƃ��Ĕ����߂𒅂�悤�ɂȂ������̗��R���A�킩��悤�ȋC�����܂��B �Ƃ��낪�����������R�̕����ɒ����Ԃ����ĕH�����ł��Ă��A���������������J�̕ǂɗ����ӂ�����ē쉺�ł��Ȃ��Ȃ�A�������ɂ���͂��̌��R�����邱�Ƃ����ł��Ȃ��Ȃ�̂ł��B�厩�R�̕ǂɑj�܂�A�l�Ԃ̗͂ł͐_�̐��n�ɂ͂��ǂ蒅�����Ƃ͂ł��Ȃ����̂��A�ƌ��R�ւ̓���f�O����Ƃ���ɘȂނ̂���\��Ԃ̏ĎR���ł��B�����Ă��̂������Ō�ɕH�̗��H�͌��R��w�ɂ��ē������ւƌ������A��\�O�ԎD���ȍ~����l���̊C�ݐ��܂œ��B���A�������瓇�̎��ӂ�������āA�ŏI�I��88�����̐_�Ђ����̂ł��B�����ɋ�C�́u�_�B���v�̑z���A���Ȃ킿���\���Ƃ����u���v���d�Ȃ鐔�����Ӗ�����u���d�v�A�w�u���C��ł́u���[�E�F�[�̐_�v�ɂ��Ȃ��t�ɁA�u�B���v���Ӗ�����u������v���܂݂��āu���d���v�Ƃ������t��n�삵���z���������Ȃ��ł͂����܂���B�_�������Ă���悤�Ō������A���₷�����݊�邱�Ƃ��ł����A���n�Ƃ͐l���ߊ���s�v�c�ȏꏊ�ł��邪�䂦�A�H�Ƃ͂�����ے����邩�̂��Ƃ��A���n�̎�����Ƃ��Ƃ�������葱���Ă��Ȃ��Ȃ����B�ł��Ȃ��悤�Ɏd�g�܂�Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����Ă��̐��n�����A��C�������Ă�܂Ȃ��������R�������̂ł��B�@ |
|
|
����������ꂽ�؋�
�u�I���̓��ɁA��̐_�a�̎R�͎R�X�̓��Ƃ��čd�������A�ǂ̕�����������т���v�Ƃ����L�q�������̃C�U�����ɂ���܂��B�W�H����l���ؔ����̍����艓���ɖ]�߂錕�R�͂��̐����̌��t�ɂӂ��킵���A���̒���͂ق��̎R�X�̕��荂���ނ������Ă��܂��B�Ñ���{�ɂāA�C�U���ɓ����ꂽ�C�X���G������̓n���҂����{��K�ꂽ�Ƃ���Ȃ�A�C�U�����̋����ɏ]���ĕW���̍����_�̎R�����߁A�����n�Ƃ����ɈႢ����܂���B��s���ė�K�ꂽ�C�X���G���̖��́A�j���̋L�q���݂�ƁA�̒��S�ƂȂ��_��W�H���ƒ�߁A�����������݂̌��_�Ƃ����悤�ł��B�����Ă���������ӂ̓��X�����܂Ȃ��M�ŏ���n��A��A�́u�����݁v�Ƃ��铇�T���Ƃ��̖����Ƃ����^�X�N�̒��ŁA�̓��X����肵�Ă������ƂɂȂ�܂��B ���̋N�_�ƂȂ�W�H������ڂɂ��邱�Ƃ��ł����ԍ����R���A�l���̌��R�ł��B���������̌��i�́A�u��̐_�a�̎R�͎R�X�̓��Ƃ��čd�������v�Ƃ����C�U�����ɋL�ڂ���Ă���Ƃ���A�����̎R�X�̒��������ɒ��߂钆�ŁA���R�̓����ЂƂ�����łĂ���̂ł��B�Ñ�C�X���G���̓n���҂̖ڂɂ́A���̌��R�����Ȃ�R�Ƃ��ĉf�����ɈႢ�Ȃ��A���̂��悻���S�Ɉʒu���A�����ɓ��B���邽�߂ɂ͋ɂ߂č���ȎR����ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��炵�Ă��A�܂��ɐ��Ȃ�_�a��z���グ��ɍł��ӂ��킵���R�ł���ƍl�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ��R�Ƃ��Ė��������R�̂���l���ł́A�×���茕�R�ɂ܂�邳�܂��܂ȓ`�����c����Ă��Ă��܂��B���ł����R�ɂ̓C�X���G���́u�_��̔��v�ƁA����ɓZ���_���߂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�͍������n���Ō��p����Ă��Ă���A�����A����ŊǗ�����Ă���ό��ē��̃p���t���b�g�ɂ��A�����̓`���ɂ��Ă̋L�q�������܂��B�����ŁA�_��̉\�ɂ��āA����܂Ś�����Ă������e���ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B �܂��A�l���̑c�J���ӂɂ���n���̒n��ł́A�̂�������V�c�̌����B����Ă���Ƃ��������`��������A�܂��\���������̔���R�ɖ�������Ă���Ƃ����`���ɂ����ڂł��B�̂Ȃ����ɉ��͂������Ƃ������Ƃ��炵�Ă��A�����A�o���ƂȂ�v�������肻���ł��B���R�͎R�x�M�̗��Ƃ��Ė������ł����A�����a�̏��߂܂ł́A�������߂Â����Ƃ���������Ȃ����l���̗�R�������̂ł��B�܂��A���R���ӂɂ̓C�X���G���̖������Z���Ă����ƍl�����鍪�������낢�둶�݂��܂��B�Ⴆ�Ό��R���ӂɌÂ�����`������Ă������t�̒��ɂ́A�w�u���C��ŗ����ł�����̂��܂܂�Ă��邱�Ƃ�A��N7���ɍs���錕�R�Ղ�ŁA�_��̔��ɍ������Ă���_�`�������Ȃ��猕�R����܂œo�镗�K�́A�C�X���G�������̖��c�ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B �܂��A�l���̍��n�ɂ͒����r�Ǝv���鐅���������ɑ��݂��A���R���ӂ���O�ł͂���܂���B�R�̒�����ӂ���[�Ɏ���܂ŁA�����ɐ����N���o�Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A�����Ɍb�܂�Ă��邱�Ƃ͈�ڗđR�ł��B�����Ē��ɂ͐l�H�r�������܂܂�Ă���ƍl�����܂��B ����قǂ܂łɏ\���ȗʂ̐������m�ۂ��Ă������R�́A�×��A�R�X�̏�ɂ͑吨�̐l�����Z����悤�ȏW��������������ł͂Ȃ��ł��傤���B�����čՒd��_�a�̎��ӂɂ͂��܂��܂Ȑ��߂̋V��������s�����߂ɏ\���Ȑ�����������K�v������A�F�X�ȍH�v���{����Đ������v���Ɋm�ۂ��ꂽ�ƍl�����܂��B���̌��ʁA���R���ӂɂ͐������m�ۂ���A���̌��ʁA�����ł��R�̐��������ɐ�������o�Ă���A�L�x�Ȑ��ʂ���������Ă��邱�Ƃ��f���܂��B ���ہA�l����R�A�A�R�z�n���Ȃǂɂ͍��n���W�����L�͈͂ɑ��݂��Ă������Ƃ��m���Ă��܂��B���Ɍ��R�̎��ӂł́A�����ɂ͑c�J�A���c�J����A���̓��k���͖؉�������ĎR�����ӂ̐_�R�Ɏ���܂ōL�͈͂ɍ��n���W�������݂��Ă����Ƃ݂��܂��B�����̏W���ł͍������ōՒd������A�_�𐒂ߕ��Ƃ������K�������̂��炠�����Ɛ��肳��邾���ɁA�߂����ނ����ō���̕W�����ւ錕�R�Ƃ��ւ�肪�������ɈႢ����܂���B �܂��A���R���̉��c�J���ӂ̎R�X�ɂ́A��������܂ő�K�͂Ȗq�ꂪ�R�̍���ɑ��݂��Ă��܂����B���̌�A�q����Ǘ�������̐l�X���s�s���֗��o���A�����肪�s�����Čo�c�����藧���Ȃ��Ȃ������Ƃ��琊�ނ𑱂��A�ŏI�I�ɂ͂����̖q��̐Ւn�ɍ��̐���ɂ��A���̐A�т�����ɍs����悤�ɂȂ����̂ł��B�����ďu���ԂɁA�����̌Ñ�W����q��̐Ւn�ɐ��̖��炿�͂��߁A�������q��̎p�́A�Ռ`���Ȃ����������Ă����܂����B�����̏��ł����q��̔w�i�ɂ́A���n���W�������݂��Ă����͂��ł��B���̂Ȃ�A���n���W���͗V�q�����̖��c�ł�����A�����A�A�W�A�嗤���K�ꂽ�n���l�ɂ���č\�z����Ă����ƍl�����邩��ł��B�����̂��Ƃ���A�l���ł͐��A�т̏ꏊ�����ɂ߂邱�Ƃɂ��A�q��⍂�n���W�������݂��Ă����\���̂���ꏊ��m�邱�Ƃ��ł��܂��B�����Đ��A�т͌��R�𒆐S�ɁA���̐����͎O�D�s������n�S�A�����ē����͏ĎR�����̐_�R���珟�Y�S�ɋy�Ԃ܂ōL�͈͂ɍL�����Ă����̂ł��B �܂��A���R�͐l�H�̎R�ł���Ƃ����w�������݂��邱�Ƃ����ڂɒl���܂��B���a�����ɂ́A���R�̌����ł������Ȏl�����R������̌̍����������ɂ��A���R�ɂ����Ĕ��@��Ƃ��s���܂����B�������̏،��ɂ��ƁA�����A�n��147���[�g���܂Ŕ��@��Ƃ��s���A�������甭�@���ꂽ��̏ڍׂ��������邱�Ƃɂ��A���R�̒���́u�O���O���A�l�H�̊m�ł������v�Ƃ������_�����\����Ă��܂��B�܂����R�̒���͔n�̔w�̂悤�ȕ���ȑ����ƂȂ��Ă���A���̒n�`�Ⓒ����ӂɐ����Ă���A���̎�ނ����Ă��A�W��1900���[�g���̎R�̒���Ɏ��R�ɉ萶�������̂Ƃ͍l���Â炢�̂ł��B����ɖL�x�Ȑ��������邱�Ƃ��炵�Ă��A���R�̎R���͐l���ł͂Ȃ����Ɛ����́A���̗]�n���c����Ă��܂��B �Ō�Ɍ��ߎ�ƂȂ�̂��A���R�̔閧�ɂ��Č��y�����ƍl������u�����߂����߁v�̉̎��ł��B�×����̂��Ă������e�����̔����ǂ���Ƀw�u���C��ɂ���ĉ��߂���ƁA���{��ł͂��悻�s���ȉ̎��������Ӗ������m�ɂȂ�A�̎��S�̂̎�|���킩��܂��B�u�����߂����߁v�̉̎��́A�u�����v�ƌĂꂽ�_�̔��ɂ��ĉ̂��Ă����̂ł��B���͂̕���������ւ����A�l�C�̂Ȃ��₵���ꏊ�ɂĐ���������A���̎R�ɖ������ꂽ���Ƃ��f���܂��B�̂ɓo�ꂷ��u�߂ƋT�v�����A�u�ߋT�R(�邫����)�v�Ƃ��\�L����錕�R�̏ے��ł���\��������A���ہA�R�̒���ߕӂɂ́A���R�ő���ꂽ�߂ƋT�̃I�u�W�F���u����Ă��܂��B�����u�����߂����߁v�����R�ɗ���ʼn̂��Ă���Ƃ���Ȃ�A�_��A�������͂��̃��v���J�Ƃ�������U���̂ǂ��炪���R�ɖ�������Ă��邩�A�̎�����͂͂�����Ƃ͗������邱�Ƃ��ł��܂���B��������q����悤�ɁA�n���҂̗��j�Ɛ_��Ɋւ���j���̋L�q��A�̂̕������������A�����炭�^�̐_��͌��R�����o����A�ʂ̏ꏊ�ɉB������邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɖ��߂ł��܂��B ���{��ƃw�u���C����u�����h���ĕ҂ݏo���ꂽ�u�����߂����߁v�̍�҂́A���̓��e�Ǝ���w�i����@����ɁA��C�̉\���������ƍl�����܂��B2�̌���������ɗ��߂Ȃ���A�N�̐S�ɂ��c����{�̓��w�Ƃ��ď����ɒ蒅�����A���������̓��e�̓w�u���C��ɂ����Ă̓C�X���G���̐_��ɂ��Č���Ă���A�Ƃ����悤�Ȑ_�ƓI�ȍ쎌���ł���\�͂����l�Ԃ́A��C�ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��ł��傤�B�܂��A��C�̏o�g�n�͎l���̎]��ł���A���̌̋��̒n���猕�R�����������Ƃ��炵�Ă��A���R�͋�C�̐S�Ɏc�鐹�n�ł������ɈႢ����܂���B��������C���g�͊��Ƃ̖��l�ł���A�R��ɂł��������������m�E�n�E�������Ă��܂����B�����Ă��̌��R�ɌÂ�����_�B����Ă������Ƃ��m�F������C�́A���R���͂ނ悤�ɍs�r����H���߁A�Ƃ��肷����ɗ�q���Ƃ��Ă̎D����I�ʂ��A���̐���_�B���̏ے��ł��鐔���̔��\���Ƃ����̂ł��B�����Ă������吨�̐l�X�����̋��n�ɏ����ł��߂Â����ƁA���R�𒆐S�Ƃ���H����C�̋����ɏ]���ď�������Ȃ���A�S�𐴂߂���z���ɐZ�����̂ł��B�͂����Č��R�ɐ_���ł���������Ă��邩�́A����A���炩�ɂ���邱�ƂɂȂ�ł��傤�B�@ |
|
|
�����R�̐��ɐ��ދ~���̃��b�Z�[�W
���R�ɂ܂��w�u���C���[�c�Ƌ�C�Ƃ̊֘A��T�邽�߁A���R���ӂ̗��j�I�w�i�ׁA���ɒn����Â����猾���`�����Ă��錾�t�ɒ��ڂ��Ă݂܂����B�܂��A���R�Ƃ������t�ł����A�w�u���C���(��)(tsuru�A�c��)�͊���Ӗ����A(��)(ki�A�L)�́u�ǁv�ł�����A�u�c���L�v�́u�ǂ̊�v�̈ӂƂȂ�܂��B����́u�V�̊�ˁv�����łȂ��A�C�X���G���̃G���T�����{�a�̐^���ɂɂ���u�Q���̕ǁv�����A�z�����錾�t�ł͂Ȃ��ł��傤���B�_�鑠����鐹���̎��ӂ͊�ň͂܂�邱�Ƃ���Ƃ��Ă������Ƃ���A�_��Ɋւ��d��ȗ�R�ƂȂ������R�ɂ́A�u�ǂ̊�v�Ƃ����Ӗ��������̂��^����ꂽ�̂ł��傤�B ���̌��R�̘[�ɂ́A���{�O��鋫�̂ЂƂł���c�J�R��(�����܂���)������܂��B���̒n���͂����炭���Ď��ł���A���̃��[�c�̓C�X���G���ƃ��[�E�F�[�_�̓��������Ƃ������̂��A�������̓C�U���́u�U�v���������ȗ�����A�u�C���v�ɂȂ����ƍl�����܂��B�ǂ���ɂ��Ă��A���̌��t�̈Ӗ��́u�_�̋~���v�ƂȂ�܂��B�c�J�ɂ͗̌k�J�ɉ˂���ꂽ�u�����狴�v������܂��B�������㖖���A���Ƃ��c�J�܂ŗ������сA�������猕�R�������ۂɁA�ǎ肪�����炢�ł��藎�Ƃ���悤�ɂ����̂����́u�����狴�v�ł���Ɠ`�����Ă��܂��B���́u������v�Ƃ������t�̌ꌹ�́A��ʓI�ɁA�鐫�A���́h�V���N�`�J�Y���g��҂�ō���Ă��邱�Ƃ���A�����Ă�Ă���ƍl�����Ă��܂��B�������A���ꂾ���ł́u������v�̌ꌹ���𖾂���ɂ͎���܂���B�{���̈Ӗ��́A�u��v�A����飂��Ӗ�����w�u���C���(��)(gazrah�A�K�Y��)�Ǝv���܂��B�鐫�A����҂�ō�����j��p���ĉ˂���ꂽ���́A�����������߂ƂȂ��Ă������߁A���̐A�����̂��w�u���C�ꃋ�[�c�́u�K�Y���v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A���̂��҂�łł��オ�������́u�����狴�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂ł��傤�B�����ɂ����_���̃��[�c����߂��Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B �������A���̂ɕ��Ƃ͑c�J�܂œ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��傤��?�@���ƕ���ɂ��ƁA�d�m�Y�̐킢�ň����V�c�͎O��̐_��ƂƂ��ɓ��������Ƃ���Ă��܂��B�������A�����V�c�͖����Ɏl���ɗ������сA�����ŕa�ɓ|��钼�O�A���Ƃ̍ċ����F�肵�A�����R���ɕ�[�������Ƃ���u���R�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����p����Ă��܂��B�����V�c�ƃ��_���̔��̊֘A���͒肩�ł͂���܂��A������ɂ��Ă��A�×���茕�炵������R�ɉB����Ă����\�����A���ƕ���ɂ��֘A���Ďf�����Ƃ��ł��܂��B �O��̐_��Ɋւ�錕�Ɋւ��ẮA�\��_��̒��̔�������㌕�Ȃǂ��j���ɋL�ڂ���Ă��܂��B�܂��A�z�K��Ђ̂悤�ɂ��̑O�{�{�a�̂��_�̂ł��闠�R�̎牮�R�ɗ���ŁA�_��̌���ۊǂ��Ă����Ƃ����悤�ȓ`�����c����Ă���悤�Ȑ_�Ђ�����܂��B�_��̌��Ƃ́A�_�Ђ̗��j�ɂ����đ�Ϗd�v�ȑ��݂ł���A���̏��L�����łȂ��A�ŏI�I�ȕۊǏꏊ����ɍl�����Ă������Ƃ��킩��܂��B�����Ă��̐_��̌��Ɋւ��āA�l���̌��R�͂��̎R�̖��̂�����킩��Ƃ���A���炩�̌`�Ŋ֗^���Ă���ƍl�����܂��B ���̌��R���痬��o�鐅�͑c�J��ƂȂ�A�l���R�n�����݁A���{�L���̑�͂ł���g���ɒ������܂�Ă��܂��B�g���́A�w�u���C��Łu�_�̋~���̐�v�̈Ӗ��ł��B�w�u���C��Łu�_�̋~���v�́u���V���A�v(Yehoshua)�́u���V���v�ƁA�u��v���Ӗ�����(��)(nahar�A�i�n�[)�Ƃ������t�����킳��u���V���i�n�[�v�ƂȂ�A���ꂪ�a���āu�悵�̂���v�Ɣ��������悤�ɂȂ����ƍl�����܂��B�����ēV�c��s�����̋g����n��ۂɁA���̑���ɌI�̖��˂��Đ��n��ꂽ���Ƃ���A���̏ꏊ�́A�I�}�n(�N���V�g)�ƌĂ��悤�ɂȂ������Ƃł��傤�B���̌��R�̘[�A���c�J���ɂ͒����̂Ȃ��I�}�n(�N���V�g)�_�Ђ�����A���_�Ђ̋L�^�ɂ��ƌ��R���Q�q����҂͉����̂���I�}�n�_�Ђ��Q�q���邱�ƂɂȂ��Ă����Ɩ��L����Ă��܂��B�I�}�n�_�Ђ̖��O�́u�L���X�g�v�̔����ɍ������Ă��邱�Ƃɒ��ڂł��B ���R����v���������Ñ���{�̃��}�����h���Ă��܂����B�l�����ނ��т������R�̂ǂ����ɐ_��[����Ă������Ƃ�����A�������痬��o��b�݂̐����u�_�̋~���v���Ӗ�����c�J�삩��g���ւƒ�����A���́u�_�̋~���̐�v���I�}�n(�N���V�g)�A���Ȃ킿�u�L���X�g�v�ƂƂ��ɓn��A�~���ɂ�������Ƃ����s�ς̃��b�Z�[�W�������ɏW��Ă����̂ł��B���̌b�݂̃��b�Z�[�W�́A���܂��܂ȓ`���̒��ɁA�����B�ꂷ��w�u���C��̃J�[�e�����ɉB����Ȃ���A�㐢�ɓ`������ׂ��A�����܂Ŏ���Ă����̂ł��B�@ |
|
|
��2�̋g���̔閧�Ƃ�
���������I�قǑO�ɂȂ�ł��傤���A�����A���w�̕������Ă����M�҂͓��{�n���̎R���Ȃǂ̒n�����ۈËL���Ă��܂����B�����Ă�����A�����Ő�̖��O�����������Ă��܂��܂����B�ł��A�Ȃ��Ԉ�����̂��킩�炸�A�s�v�c�Ɏv�������Ƃ����ł��o���Ă��܂��B�l���̐�ƋL�����Ă����g��삪�A���͋ߋE�n���ɂ����݂��邱�ƂɋC�Â��Ȃ������̂ł��B�l���̋g���́A���R�̘[���o�āA�I�ɐ����ɗ���o��l���O�Y�ٖ̈������Y��Ŕ����������ł����A���͓����̐삪�A�ޗnj�������悤�ɍ���R�̖k���𗬂�Ă��܂��B���̐�́A�a�̎R�����ɂ����Ắh�I�m��g�ƌĂ�Ă��܂����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɍ���R�����ڂƂ��āA�ޗnj����̏㗬�������h�g���g�ƌĂԂ̂ł��B ���̐�̖��O�̓w�u���C��Łu�_�̋~���̐�v���Ӗ����邽�߁A�l�����R�̘[�𗬂��g��삾���łȂ��A����R�����̐����C�ɂ���Ė������ꂽ�ƍl����̂��Ó��ł��傤�B�l���̋g���͋�C�̌̋��A�]��̓���𗬂�A�a�̎R�̋g���͋�C�̑��{�R�ƂȂ鍂��R�̘[�𗬂�Ă��܂��B���̂ӂ��̋g�����q���g�ɁA���R�ƍ���R�̌q���肾���łȂ��A���̔w�i�ɐ��ޑs��ȋ�C�̃��C�t�v���W�F�N�g�������яオ���Ă��܂��B ����R��819�N����A��C���J�����u�I�ɎR�n�̗��ƎQ�w���v�Ƃ��Ă��܂�ɗL���ł���A���E��Y�ɂ��w�肳��Ă��܂��B�Ƃ��낪���ۂɍ���R�Ƃ����R�͑��݂��܂���B�a�̎R���̖k�����Ɉʒu���鍂��R�́A�R�̌ŗL���̂ł͂Ȃ��A�W��900���[�g�����ւ锪�̕�X�Ɉ͂܂ꂽ��т��w���Ă���̂ł��B��C������R�������āA�����Ɏ������������Ǝv��ꂪ���ł����A���ۂ́A���n�Ƃ���ׂ��R�X�����o������C���A���̒n�������R�Ɩ��Â����ɂ����Ȃ��̂ł��B �R�E���̓w�u���C���(��)(kolya�A�R�[��)�A��������(��)(koakhya�A�R�b��)�Ə������Ƃ��ł��܂��B�O�҂́u�C�X���G���̐��v���Ӗ�����(��)(�R�[�C�X���G��)�́u���v���Ӗ�����u�R�[�v�Ƃ������t�Ɂu���v�������āu�R�[���v�A�܂�u�_�̐��v�ƂȂ�܂��B��҂̏ꍇ�u���ƍ����́v�u�D���v���Ӗ�����(��)(�R�b�G������)�Ƃ����w�u���C��Ɋ܂܂��_�̖��A�u�G�������v���u���v�ɒu���ւ��āA�u�R�b���v�܂�u�_�̗́v�ƂȂ�܂��B�G�������ɂ́u���ƍ����v�Ƃ����Ӗ������邱�Ƃ���A�u����v�Ƃ������������Ă��̂�������܂���B�_�̐��������n��R�A�����Đ_�̗͂Ɋ������ɂ͂����Ȃ��s��ȑ厩�R�Ɉ͂܂ꂽ���n������R�Ȃ̂ł��B��C�̔M���v�����A���̖��O�ɍ��߂��Ă��܂��B �������A����قǎl���̌��R�Ƌg���������A88�ӏ��̏��珊�܂őn�݂�����C���A�Ȃ�����̏@���N�w�̏W�听�Ƃ��������{�R���l���ɑ��炸�A�I�ɂ̎R�X��I�сA������V���Ȃ�M�̐��n�Ƃ����̂ł��傤���B���̓���������́A�����߂����߂̉̂̃w�u���C���(�y�u�����߂����߁v�̐^���ɔ���z�͎̏Q��)���K�C�h���C���Ƃ��āA2�̋g��쉈�����ނ������R�ƍ���R�A�����Ĉɐ��_�{�ƓV�c���Z�܂��鋞�s�䏊�̈ʒu�W�𗝉����邱�Ƃɂ���܂��B�����āA��C���`��������R�̒n���I�ʒu�Â��ɒ��ڂ��邱�Ƃ��s���ł��B ���R�ƈɐ��_�{���Ō��ԂƁA���̐���ɍ���R�����݂��܂����A�������ƂɁA�ɐ��_�{���狞�s�䏊�ƍ���R�܂ł̋�����n�}�ő��肷��ƁA�Ƃ���108.5�q�ƂȂ�A�����Ȃ܂łɈ�v���Ă���̂ł��B����͋��R�̈�v�ł͂Ȃ��A���ׂČv�Z�����߂Ō��I���ꂽ�����̈ʒu�Â��̌��ʂƌ����܂��B�Ñ�Љ�ɂ����Ă͐��Ȃ�R�ƊC�݉����̃����h�}�[�N�����т��Ȃ���A���ꂼ��̃N���X�|�C���g�ɐ��n�ƂȂ�ׂ��n�����o���Ă������̂ł��B��C�͂��̃}�X�^�[�}�C���h�̈�l�ł����B �l���̌��R�Ƌg���������邠�܂�A��C�͎��炪��߂�����R�ƌĂ�鐹�n�̂��𗬂�����A�u�_�̋~���̐�v���Ӗ�����g���Ɩ������܂����B�����ĐV�����J�s���ꂽ�������̌b�݂ɗ͂�Y����ׂ��A�Ώ�_�{�ւ̃��C���𒆐S���Ƃ��ĕ������Ƃ͑Ώ̂ƂȂ�ʒu�ł������A�ɐ��_�{����͓������ł���A�������ɐ��_�{�ƌ��R�����Ԑ���ɍ���R���ʒu�Â����̂ł��B�������č���R�͉i���̃p���[�X�|�b�g�Ƃ��āA���R�ƈɐ��_�{�ɋ��܂�邾���łȂ��A�����������n���Ȃ���Ώ�_�{��ēx�R�Ƃ��n����̃����N��ۂ��Ȃ���A�i�v�ɐ_��������A���Ƃ̕������F�邽�߂̐��n�ƂȂ�ׂ������܂Ŏ����Ă��܂��B�@ �@ |
|
| ���̉͌� | |
|
�c�����āA�e���������S���Ȃ����q�ǂ����s���A���I���Ƃ��Ȃ���ςݑ�����Ƃ��������A�O�r�̐�̉͌����g�̉͌��h�Ƃ����܂��B�����Ɨ����̋��E�ɂ���Ƃ��A���y�̎�O�ɂ���Ƃ����Ă��܂��B�ϔO��̒n���̈�ł����A����������Ɍ��o�������ꏊ�ł�����܂��B��������̑m�E���ɂ�鐼�@�͌��n���a�]�́u��d�g(��)��ł͕��̂��߁A��d�g(��)��ł͕�̂��ߣ�Ƃ����������������܂�U���A�����͎q�ǂ��̗삪���V�����n�Ƃ����C���[�W������܂��B
�����ȍ~�A�����̏������������̏ꏊ�ō��͖S���q�ǂ��̖������F��A�߈����ɐӂ߂����Ȃ܂�Ă��鎩�����Ԃ߂Ă��܂����B ���ꂩ���̉͌��̗��j��Ӗ������Љ�Ă܂���܂��B������Ȃ����t�������o�ė��Ă킩��ɂ�����������܂��A�Ō�܂ł��t���������������B �Ȃ��A���͐��Ƃł͂���܂���B����s����ԈႢ�����X���邩�Ǝv���܂��B�ǂ������e�͂̏ゲ�������������B �� ���āA����܂łɔ�������Ă���Ñォ��ߐ��̎j���ɂ́A�̉͌��̐����ߒ������������͔̂�������Ă��܂���B�����������w�A���j�w���̌����ɂ���đ����̂��Ƃ��킩���Ă��܂��B���Ƃ��A��̘a�]�͋��(������)�̍�ł͂Ȃ��Ƃ����̂͂��͂�펯�ł��B�^�玁�͌��\9(1696)�N�`����2(1742)�N�ɑn�삳�ꂽ�Ǝ咣���A�X�R���͐^��������������Â��Ǝ咣���Ă����܂��B���͖��ԏ�y���̑c�Ƃ���A���O����s��(�����̂Ђ���)�A����ɐ��Ƃ����ď����ɕ��ꂽ���m�ł��B���̂悤�Ȑl���̍�Ƃ��邱�ƂŁA�a�]�̉��l����ʂ����߂悤�Ƃ����̂��ƌ����Ă��܂��B ��q����悤�ɁA�̉͌��͓��{���܂ꖯ�Ԃɓ`�����ꂽ�v�z�ł��邽�ߊ���������܂���B�����Ő��@�͌��A���̉͌��A����͌��A�lj͌��ȂǗl�X�Ȏ������Ă��A����炵�������`���Ƌ��ɓ`����Ă��܂��B �� �̉͌��̋N���́A�����A���A�l�҂Ȃǂ́g���E�h�ɓ��c�_[��(����)�̐_]���J���ĎĂ�܂������u����(�ς��)�A���s��a�ȂǍЂ��̐N������(����)���낤�Ƃ������c�_�M�ɂ���Ƃ����Ă��܂��B���c�_�M�͕��������{�ɓ`������ȑO������{�ɂ��������ԐM�ł��B����ɒn���M�A�������K�����Ċ������܂����B���̂悤���̉͌��̌��^�͌Ñォ�炠�����̂ł����A�g�����̂����h�����߂ĕ����ɂ������͎̂�������̌䉾(���Ƃ�)���q�w�x�m�̐l�����q�x�ł��B�x�m�̐l����T�����ėl�X�Ȓn���ɏo������������A�A���Ă��炱���l�ɘb�����Ƃ��뎀��ł��܂��Ƃ����b�ł��B �܂��A�G��(�n���G�})�ɕ`�����̂��������オ���o�ł��B �`���́g�c�����āh�Ƃ͉����炢�܂ł������̂ł��傤�B��q�́w�x�m�̐l�����q�x�ł��A�M�ŏ����ʂ����{(�]�ˏ���)�ɂ�7�`8�Ƃ���A�ʼn���肵���{(�]�ˏ���)�ł�12�`13�ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A���@�͌��n���a�]�ɂ́g�\�ɂ�����ʂ݂ǂ�q(�d��)���h�ƕ\������Ă��܂��B�g�\��艺�́h�Ƃ���Ă�����̂�����܂��B������ɂ��Ă��\�ł��邱�Ƃɂ���肠��܂���B ��������̖����A�x�͍�(�É�)�ł�15�Έȏ�̎҂̏������K�肳��Ă��܂����B����30�N��̍b�㍑(�R��)�ł́A13�ΈȌ�̎҂��E�l��Ƃ����ꍇ�͍߂�Ƃ�Ȃ��Ƃ���Ă��������ł��B�]�ˎ���ɖ��{�́A10�܂ł�c���Ƃ��č߂���Ȃ��Ƃ��Ă��܂����B�����������N�@�̐��_�Ɋ�b��u���Đ��@�͌��n���a�]�͑n�삳�ꂽ�A�Ɛ^�玁�͏����Ă��܂��B�܂��A�g�݂ǂ�q�h�Ƃ������t�ɂ́A��ςݑ�����悤�ȋ������Ǝv��Ȃ��悤�ȗc�����\������Ă���Ǝv���܂��B �܂������W����܂��A�S���w�I��9�͏d�v�ȈӖ��������Ă��܂��B�g9�̕ǁh�Ƃ����܂��B9�`12�͋�̓I�v�l���璊�ۓI�v�l�Ɉڍs���鎞���ł��B�g���Ƃ��b�h�ŕ����𗝉��ł���悤�ɂȂ�킯�ł��B�܂��A9�`15�̊Ԃɕ������l�����܂��B���̍��̐l�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B9�Έȏ�̔N��ɂȂ�Ɛ��ӋC�Ȍ��𗘂��悤�ɂȂ�����A�C�W���⎩�E���N�����肵�܂��B�܂��A�C�O�ւ̓K�����c������������ɂȂ�܂��B �� �@�،o�̕��֕i�Ɏ��̂悤�Ȃ��Ƃ�������Ă��܂��B���̂��߂ɓ����_�Ȃǂ����������l�́A���͂�N���������𐬏A����(����)���ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�q�ǂ��ł����Ă������ł��B���Ƃ��A�q�ǂ����������W�߂ĕ��������Ȃ�A���ꂪ�V�тł����Ă��A���͂₱�̎q�͕����𐬏A�������ƂɂȂ�܂��B���́u�T�����q�Y �ڍ��טœ� �@�����l�� �F�ߐ��œ��v�Ƃ�����߂��̉͌��̍������Ƃ�����������܂��B�@�،o���̉͌��̐����Ɣ��W�ɗ^�����e���͏d��ł����A�]�ˎ���ɏo���ꂽ���̐��͔ے肳��Ă��܂��B�@�،o�Ő�ςނ̂͐����Ă���q�ǂ��ł����āA�S���Ȃ����q�ǂ��ł͂���܂���B�܂��A���̈�߂͐�ςނ��Ƃ̍����ɂ͂Ȃ邩������Ȃ����A�̉͌����n�����ꂽ�����ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B���������ᔻ�����܂��āA�̉͌��͕����o�T�Ɋ�Â����M�ł͂Ȃ�(�o�T�ɂ͏�����Ă��Ȃ�)�A�������(��������)�ɓ��{�őn�����ꂽ�n�����Ƃ�������蒅���Ă��܂��B �g���܂ł͐_�̂����h�Ƃ������t������܂��B���̔N��܂ł͐l�Ԃ����_�ɋ߂����݂ł����āA����ł����܂�ς��Ƃ����v�z�ł��B�ł�����q�ǂ����S���Ȃ��Ă��A���̑��V�͑�l�����ȗ��ɁA��������l�Ƃ͈قȂ�ꏊ�ɖ�������܂����B���ꂪ��������ɂȂ��đ����V��(���V�A��c���{)����ĕ��������������ɐZ�����Ă���ƁA��̌`�Ԃ��ω�������A�q�ǂ��̈ʔv�����悤�ɂȂ�Ȃǂ̕ω����݂���悤�ɂȂ�܂��B�܂��A�q�ǂ��̏ё��悪�`���ꂽ��A�q�ǂ��ւ̌Y������߂�ꂽ�肵�܂����B�q�ǂ��ւ̊S�̍��܂肪�݂���̂ł��B�����������Ƃ�w�i�ɂ��āA���{�ŏ��߂āg�q�ǂ���Ώۂɂ����h�g�q�ǂ��̑�(��)����h�n���Ƃ����̉͌����n�����ꂽ�̂ł��B �����������ߐ��ɂ����āA�����͌��̃P�K��������̂Ō��̒r�n���ɑ���A�Ƃ����v�z���e�n�ɂЂ�܂�܂��B�o�Y���Ɏ��S�������������̒n���ɑ���Ƃ���܂����B����͕����̏������ʎv�z�����{�ɂ���܂��B�����̌��̓P�K���Ă���Ƃ����l�����́A�Ñ�́A���Ȃ��Ƃ������`���ȑO�̓��{�l�ɂ͂Ȃ������ϔO�̂悤�ł��B �܂��A�q�ǂ����Y�߂Ȃ������^�Y�܂Ȃ����������͐Ώ�(���܂��߁B�s�Y��)�n���ɑ��܂��B�����ŏ��������́A���J�I�ŁA���������Ӗ��ŕs�\�ȍ�Ƃ��i���ɂ������܂��B �l�X(���ɏ���)�͋~��ꂽ���A�����������A�^�^�����|���Ƃ����S�ӂ���A�아(����)���Đg�ɂ�����A�ω���n���ɋF�����肵���̂ł��B �� ��������ɓ��{�Œa�������n��(�̉͌��A���̒r�A�Ώ��Ȃ�)�́A���́A���Ɍ����I�ȗ��R�����דI�ɍ��ꂽ���̂������̂�������܂���B���̒r�n�������̎���ɕ��y�����w�i�ɂ��āA���B�����������낢���Ƃ������Ă��܂��B�v�|�������܂��B ��������A�����o�ς����ނ��ċ��������炨�����W�߂邱�Ƃ�����ɂȂ��Ă����B�����ŏ���������������W�߂邽�߁A�����ɂ��킩��₷���n����n��o���A�G��ɕ`���A�����ɂ���čL�߂Ă��������Ƃ��z�肳���B�����ɂ��Ă��A�a�]�ɂ��Ă��A�u���Ƃ��߂āA���Ƃ��߂āA�~���v���̂������B ���̒r���̉͌��̓Z�b�g�ōl���Ă����ׂ��n���ł�����A���̒r�����łȂ��̉͌����A���̂悤�ȗ��R�������đn�����ꂽ�̂�������܂���B �V�������ꂳ��Đ헐�����܂����]�ˎ���A���{�͕����̐��̗��Ē������͂��邽�ߎm�_�H���̐g�����x�����܂��B�q�ǂ�����(�ƓA�ƋƁA�ƍ��A��c���{��)���p���d�g�݂��m�����܂��B�Ƃ��X�ێ��p�����Ă������߂ɂ͐Ռp�����d�v�ł��B����āA����܂ňȏ�Ɏq�ǂ��͏d���݂���悤�ɂȂ�A�����͎q�ǂ�(���ɒj�̎q)���Y�݈�Ă邱�Ƃ��K�v�ɂ��ď\���Ȗ������Ƃ���܂��B�c���Ƃ��ɂ͐e�ɏ]���A�ł�����v�ɏ]���A�q���Y�݈�āA�V������q�ɏ]���Ȃ����Ƃ������Ƃł��B�������ď����̐S���A�����ƒn�ʂ͒�����������ɗ}�����ꂽ���̂ɂȂ�܂��B�g�����x�ƒj�����ڂ��͂��߁A�u�a�A�n���A���ɖK���Q��Ƃ������ꂵ�݂��~���Ă����̂����n���l���A�Ɛl�X�݂͂Ȃ��Ă��܂����B ����ȏ����̖����ł��邨�n���l�𐭎������p���܂��B�]�˖��{�͐l�S���������A�̐����ێ����Ă������߂Ɏ��@�ɒ��ڂ��܂��B�m����ʂ��āA�Εׂ�(���F��)�F�����(���e�F�s)���Ƃ������ɓO�ꂵ�A�Ђ��ẮA�d����ً��M��j�~���܂����B���{�͒h��(����)�Ƃ����d�g�݂������āA���@��ʂ����ԐړI�Ȗ��O�x�z���s�����̂ł��B ���@�͌��n���a�]���n�삳�ꂽ�̂́A����Ȏ���ł����B����������̉͌�(�̊G��╨��)�ɂ͋S�͕K�{�ł͂���܂���ł������A���@�͌��n���a�]�ł͕K���o�Ă���K�{�A�C�e���ɂȂ�܂��B�a�]�̕`�����E�����낵������낵���قǁA�߂�����Δ߂����قǁA�����͂��n���l�Ǝ��@�ւ̐M��Ă����܂����B�Ђ��Ă͂��ꂪ���̑̐��̈���Ɋ�^���邱�ƂɂȂ�܂��B���ۓI�ɂ����ƁA�̉͌��͕���ł���A���@�͌��n���a�]�͕���ʼn������鉉�ڂł������Ǝv���̂ł��B �V���������s(���E�Ȕ��s)�ł͈ꎞ�r�₦�Ă����͌��ł̐ΐς݂��������Ă��܂��B���̂悤�ȍs���͍]�ˎ���ɏ����̊Ԃɂ��~(᱗��~��)�����y�������ʁA��c�����{����ړI�ōs����悤�ɂȂ������̂ł��B�u�n���M��᱗��~�ɕt�����A�n���o���琶�܂ꂽ�c�拟�{�̍s���̂ЂƂł������v(�Γc)�Ƃ������Ƃł��B �� �̉͌��ɂ��n���l(�n����F)������̂͂Ȃ��Ȃ̂ł��傤�B ���ł����n���l�͎q�ǂ��̎��_���Ƃ����܂��B�܂��A���c�_���q�ǂ����NJ�(�Ǘ�)����_���Ƃ����Ă��āA�n����F�͓��c�_���p�������Ƃ��A���c�_�́g�{�n�h�ł���Ƃ����܂��B����͍]�ˎ���ɏo�Ă������ł��B����A��������̏\���M�ł͒n����腖�(�����)�Ɠ��̂��Ƃ��A腖��́g�{�n�h�ł���Ƃ����܂��B腖��l�͒n���̎x�z�҂ł��B��Ɏ��������ŁA�S�҂����O�ɍs�������ׂĂ̏��Ƃ��f���čْf���������_�ł��B���n���l�͂����n���ɑ����S�҂��~�����肩�A��������(����)�ƌ������v�������炵�Ă���镧���Ƃ݂Ȃ���Ă��܂����B �Ȃ��A�������v�Ƃ͕a�C�ގU�ƉA���a���ЂȂǂ��̐��ł̗��v��]�ނ��Ƃł��B �ϐ�����F�A���ӕ�F�ȂǁA��F�ɂ����l�����܂����A�g��F�h�Ƃ͕�(�@��)�ɂȂ낤�ƏC�s���̑��݂ł��B�n����F�͕��ƂȂ��ė���(��y)�ɏ�Z�����A�����ƌ������s�����藈���肵�Ȃ���A�n����l�ԊE�Ȃǂ����鐢�E(�Z��)�ɂ���l�X�̖�����ꂵ�݂��~�����Ɛ��������Ă܂��B�����ƌ����̋��ŋ���Ă���q�ǂ����~���ɂ́A���傤�ǂ悢�̂�������܂���B�O���͐l�ɋ߂��A�C�s�m�̊i�D�����Ă��Đe���݂₷�����݂ł����A�n����F�̌����͂ق��̕�F�����D��Ă���Ƃ���Ă��܂����B �̉͌��ɏo�Ă���S�͕������킯�ł����A����͎q�ǂ��̕������A���ז����邱�ƂɂȂ�܂��B�����A����ȏ�ɁA�@�،o�̐��_���ז�����u���v���Ƃ����܂��B�n����F�͂���Ȉ��S�ł���E������A�ł��̂߂����肵�܂���B���ꂾ���n����F�́g�傫���h����������A�l�X�̐M�����W�߂��̂ł��傤�B���̂悤�Ȃ��Ƃ���n����F�́A�̉͌��̋~�ώ҂Ƃ��čœK�ȑ��݂ł������̂ł��B �ȏ�̒n����F�̗��v�ɂ��Ă̐����́A�n���o�T���͂��߉��N�E���b�Ȃǂɏ�����Ă��邱�Ƃł��B �n���M�̓C���h�Œa�����A�������o�R���āA���{�ɂ͓ޗǎ���ɒn���o�T���`�����܂����B���n���l�͓`�������珎���̕��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�͂��߂͑m�ցA��������ɋM���ɐM����܂����B���̌�ɕ��m�⏎���ɓ`���A��������ɓ�����̉͌����n�������Ȃǂ��ď����ɒ蒅���܂��B�ߐ��̒n���M�͐g����n���A�q���n���Ȃǂ̐M�@�ɔ��W���܂��B���������Ε�������Ɍ�������M����܂����B���̂悤�ɒn���M�̎��_����݂��̉͌��́A�n�������O�Љ�ɒ蒅�����W���Ă������ł̈�ߒ��ł���A�Ƒ������Ă���悤�ł��B �� �c�O�Ȃ���A���́A�̉͌��̐���S���W�v�����������������Ƃ�����܂���B�{��l�b�g���̉͌���T�����Ƃ���A�k�͍��㓇�����͋�B�܂�100�����ȏ�������邱�Ƃ��ł��܂����B����͕s���ł��B���������邱�Ƃ��ł��Ȃ�������A�P������Ă�����A�n���̘V�l���m��݂̂ł܂���������Ă��Ȃ��ꏊ�Ȃǂ�����ł��傤�B�ł�����̂͂��̐��{�͂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �ł͂ǂ�ȏꏊ�ɂ���̂ł��傤���B��̓I�ɂ͎R(�M�̎R�A�ΎR�A����N�o�n)�A����(�C�݁A���A��݁A����̕�)�A�����A��n�A���@�A�_�Ђ̂����A�ЂƂȏ�̗v���ɍ��v����ꏊ�ɂ���悤�ł��B ��ɏ������悤�ɁA�̉͌��̋N���͓��c�_�ɂ����āA���A�l�҂ȂǂɌ��Ă�ꂽ�Ƃ����܂��B�������l�b�g��{�ɏ����ꂽ�̉͌����ꗗ�ɂ��Ă݂�ƁA����l�҂Ƃ����ꏊ�ɂ͂قƂ�ǂ���܂���B���ł�ړ����l���ɓ���Ă��A���Ȃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̓_�͂����Ƃ悭��������K�v������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �̉͌��Ƃ����ƌ��������L���ł��B����(���ݒn)�Ɉړ]�����O�͐��i�r�̂قƂ�ɂ����āA���q����ɒn�����Ƃ��ꂽ�ꏊ�ł����B�u���Ĕ����͒n���������v�Ƃ����܂����A�����A�n��A�M���Ƃ��������i�������̐l�X�͒n���Ƃ݂��̂ł��B���ۂɁA�����ɂ͑�n��(��O�J)�A���n��(���O�J)�ȂǂƂ�����ꏊ������܂����B �n�����v�킹��悤�ȏꏊ�A�C�݉�����R���ŏC���҂͎��R�ƈ�̂ɂȂ�Ȃ���C�s���A���悤�Ƃ��܂����B�����āA�C���҂͊e�n�Œn���M���Ђ�߂A�l�X���~�ς��܂��B���������ƌ������v�̗v���ɉ����Ă������킯�ł��B�����������]�ˏ��E�����ɂ����āA�C���҂������̉͌��c������A�܂��́A���Â��Ă����܂����B ���̂悤�ɁA�̉͌��̏��݂���ꏊ�ɂ͖@��������܂��B���̖������Ȃ������ɑ��݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��A���Ӓn��̐M�f���Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�߂��ɒn���G�}���`�����Ă�����A�n�����y�Ƃ��������̂����R�E��E�n������������A�C��(�V��E�^��)�̎��@����������A�O�@��t������p(����̂��Â�)�̓`�����c���Ă����肵�܂��B(�O�@��t��C�͌��@�̑c�ł���A�����p(�܂��͖��s��)�͏C�����̑c�Ƃ���Ă��܂��B)�Ȃ��A���Ӓn��Ƃ����ꍇ�A�����Ƃ��S�s�����Ƃ������͈͂ł͂Ȃ��A�����ƍL���n��ŗ��������ق����悢�悤�ł��B(�k�M�B�A���k�A�[���Ƃ���������) �� �ߔN�A���@�����ɐ��q���{��ړI�Ƃ����̉͌������c����Ă��܂��B���q�̍l�����͒����ɂ��������悤�ł����A��������{���悤�Ƃ���l�������o�Ă����̂͋ߐ�(�����炭�]�ˏ���)�ɓ����Ă���ł��B�������A�{�i�I�ɂȂ����̂́A���a40�N��ȍ~�̂��Ƃł��B ���@�͌��n���a�]�ł́A�ǑP���{��ӂ��Đe���Q���Ă��肢�邩��q�ǂ��͋����̂��A�Ƃ������܂��B�܂��A�̉͌��Ɍ��ꂽ���n���l�́A�������Ԏq�ǂ����߂ʼnB���Ď���Ă���܂����A�S��ǂ��������������āA�q�ǂ�����ς݂₷���悤�ɂ͂��Ă���܂���B����ɂ��Đ��i���́A���ꂱ�����̉͌��̂��n���l�̎��߂Ȃ̂��Ƃ��āA���̂悤�Ȑ��������Ă��܂��B�q�ǂ��ɂӂ肩����������e���l����菜���Ă��̂ł͂Ȃ��A���ɗ�����������E�C�ƔE�ϗ͂����q�ǂ��Ɉ��(���炵)�Ȃ����B�����ɂ��q�ǂ��ɂ���J�������Ȃ�(���S��ǂ�����)�悤�ɂ���l����������ǂ��A���ꂪ�K���ł͂���܂����B ����Љ�ɂ́g�Ɋy�h�͂����Ă��g�n���h������܂���B�Ȃ��Ƃ��������ے肷��Љ�Ƃ������炢����������܂���B�n���Ƃ͋����m��A����̌��E�ɋC�Â��ꏊ���Ǝ��͎v���܂��B�C�P�C�P�h���h���̐��̒��ŁA�����g�̂قǂ�m���đނ����Ƃ����Ȃ��̂ŁA�E���҂��o����A���_�I�Ȏ�����悷�l���o�Ă���̂ł��B�ł�����A�g�n���h�����Ӗ��͌���ł������Ă��Ȃ��Ǝv���܂����A�q��Ăɂ������̉͌����S���Ă�������������Ă͂��Ȃ��Ǝv���܂��B �� [�NjL] �V�����ƒ��쌧�̌����̎R�ԂɁA���Ƃ̗��l�`�����`���H�R���Ƃ����n�悪����܂��B�����ł́g�̉͌��h�Ƃ����R�g�o����ʖ����Ƃ��Ďg���Ă��܂��B��J�ŎΖʂ�����r�ꂽ�ꏊ���w���āA�u�܂���̉͌��݂����ɂȂ����v�Ƃ��������ł��B���ɂ����Ȃ��ꏊ�Ƃ����Ӗ��ł��B�����܂ł��Ȃ���ς�M�̑Ώۂł͂���܂���B����̐l���g�����t�̂悤�ł��B���p�ł���y�n�������Ă��邱�Ƃ��琶�܂ꂽ�A���t�̎g�����Ȃ̂�������܂���B |
|
|
�����K���̉͌� / �k�C�����K�S���K�����
�C��]���ҁA�c�����S�҂Ȃǂ̈ԗ�̒n�B ���K���̉͌��͉��K���̖k�[�A���n��̍r���Ƃ����C�݉����ɂ���B �����̉͌���15���I�ɗ��ƂȂ�A����20�N8���ɂ͒n�������J��ꂽ�B��6�w�N�^�[���ɂ���ԕ~�n�ɐΐς݂����сA�C����҂̉Ƒ��≜�K���o�g�҂��A������Ƃ��Q��ɗ����Ƃ����B ���̕��a�Ȉԗ�̒n�́A1993�N7��12���ɔ��������k�C���쐼���n�k�ɂ���ĉ�œI�Ȕ�Q�����B�k�x6�̗�k�ɉ����A�W��4�`7m�̈��n��ɍő卂��9.1m�̒Ôg���������B���̂��ߒn������ׂĂ̏Z��E���w�Z�͑S������܂މ��炩�̔�Q���A���ҁE�s���s���҂�16���𐔂����B �̉͌������̒n�k�ɂ���Ă��ׂĂ��j�ꂽ�B�ΐς݂͂������A�n����������Ă��܂����B�ꕔ�̒n�U�͂��̌�ɔ�������A�n�����Ɉ��u���ꂽ�B���̒n�����͔����B3���̔��X���g�p�s�\�ɂȂ����B ���̒n�k�̌�A���̈�т͌����Ƃ��Đ�������A�n�������Č����ꂽ�B�����āA�n�k�ɂ���ĖS���Ȃ�ꂽ���n��Z���̈ԗ�肪�������ꂽ�B �n�k��A�̉͌���K���l�͌����Ă��܂����Ƃ����B����ł��A�Q�q�҂ɂ���Đςݏグ���̓��́A�������C�̈��S�ƖS���c�Ȏq�̒����̂��߁A�C�����Ȃ���Ђ�����Ɨ����Ă���B ���N6��22���A23���ɐ���ȗ�Ղ��c�܂�Ă���B�n��3�W������N���ŏ����^�c���Ă���B�n�k�Ȍ�ɂ́A�C��]���҈ԗ�A����M���҈ԗ�A�c�����S�҈ԗ�̂ق��ɖk�C���쐼���n�k��Q�҈ԗ�Ƃ����ړI��lj����āA�n�k������N�邱�ƂȂ������Ă���B�}���A����A�njo�ⓔ�U�����Ȃǂ̏@���s���̂ق��A�|�\���\��\�t�g�{�[�����Ȃǂ̌�y�s��������ɍs���Ă���B �Ō�ɁA�w���Ɠ`���x�ɏo�Ă������Ƃ��܂Ƃ߂Ă����B ���K���J���������̎��ӂ͓�j�D�̎c�[���ݐς��Ă���A���̒��ɒn�������������B�����̉Éi4(1851)�N�ɏ��߂ċ��{���s�Ȃ�ꂽ�B���̌�A����20(1887)�N�ɑ�{��S���s�Ȃ�ꂽ���A���̂����S�삪��������W�܂��Ă��āA�Ւd���|�Ȃ�ɋȂ������B���̔N�ȍ~�A���N�̂悤�ɋ��{������悤�ɂȂ����B �u�̉͌��v/ ��Z�w�N�^�[���ɋy�Ԑΐψ�т��C��]���ҁA����M���҂��邢�͗c�����S�҈ԗ�̒n�ƂȂ��Ă���B���̗��́A��܁Z�Z�N�O�A���O�˂̎n�c���c�M�L���ꑰ�𗦂��ēn���̓r���C�㕗�g�ɑ������Ė{���ɔ����܁A���R�̉͌��̏��݂�m���č���ɖ@�v���ꂽ�Ɖ]���B������\�N�����A���l�����F���������Ēn���������J���Ĉȗ��A��N�Z����\��A��\�O���ɐ���Ȗ@�v���c�܂�Ă���B�@ |
|
|
���ϒO�������̉͌� / �k�C���ÉF�S�_�b�����X��
�ϒO�����̐����A�W���E�{�E���̕t�����ɂ�����ʒu�ɐ��̉͌�������B�_��I�ȂƂ���Ƃ����Ă���A�܂��A��n�Ƃ���Ă��邪�A��ʕs�ւȒn�ɂ��邽�ߖK���l�͏��Ȃ��B�n���̐l�X�ɂ���ĐM����A����Ă���B �܂��A������1952�N�Ɍ�u�\�i�̂ЂƂɎw�肳��Ă���B���݂͂��̂悤�ȍL��͂���Ă��Ȃ��悤�����A�[�������ތi�F�͂������Y��Ȃ��Ƃ��낤�B ���̉͌��g���l���Ƒ�V��g���l���ɋ��܂ꂽ���������ɁA�g�C����L���钓�ԏꂪ����B�����ɎԂ�u���A�ݒu����Ă���Ŕ��������ƁA�����n�߂�B�����̉���������A�C�����̎R�̎Ζʂɐ�J�炩�ꂽ�V������20�`25���i�ށB ����8�N10���܂ł͂�����K���ɂ͑D�������@���Ȃ������B�ϒO���������鍑�����������A���ԏꂩ�琼�̉͌��܂ő����V��������������āA�悤�₭��y�ɍs�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�Ƃ͂����A�M�̒��̗V�����Ȃ̂ŁA�������ӂ���ƂƂĂ������铹�ł͂Ȃ��B���͓r������C�݂ɍ~��āA�g���Ԃ��̂����������z���Ȃ���i�B�����Ȃꂽ�^���C�𗚂��A�F�悯�̗��炵�A���肪�g����悤�Ƀ����b�N��w�����čs�����̂��K���������B���������ꏊ�͉����N���邩�킩��Ȃ��̂ŁA���S�̎x�x���K�v���B �ϒO�����͑D�̓�ł���A�����̐l��������B�]���҂̗���Ԃ߂邽�߂ɒn�����J����悤�ɂȂ�A�n�����̑O�ɂ͕l�̐��ςݏd�˂��Ă���B�߂��ɂ͒n�����A�Ɋy���A���̒r�ƌĂ��Ƃ��������A�������Ƃ������l�͂��̉��ɗ�����Ƃ����Ă���B �ȉ��A�Q�l�����ɋL����Ă��邱�Ƃ������Ă����B �_�b�����ɂ͂��ׂĂ̒����ɒn�����J���Ă���B���̉͌��̒n���͖̍���l�^�ɒ��������̂����A�S���̋~�ρA�C��ҋ��{�A�Ɠ����S�A�C����S�A�務�F��ȂǕ��L�����v������Ƃ���Ă���B���ɁA�C��]���ҋ��{�̐F�ʂ������B�n�����ɂ͐̒n����30�̂قǂ���B �]�ˎ��㖖���A����3(1856)�N���Y���l�Y�̓����Ɂu�a�l���@�쌴�Ƃ����B�M�����ɏ���ϒu����B(����)�]�͕���[�O���O�N]�̔N�����Ɉ�h�������A���v�̘b�ƂāA���𒋕����Ēu���́A��̊ԂɑO���̔@���ς���ƌ��ɁA�]����������ǂ��A�l�̐M�����܂����̋L�����B�v(�ꕔ�����ɏC���B�O���O�N��1846�N))�Ƃ���A���̎���ɂ͂��̏ꏊ�Őΐς݂��s���Ă������Ƃ��킩���Ă���B ���a30�N��܂ł�1���A6���̔N2�M���Ɛ��̉͌������ɒn���u���s���Ă����Ƃ����B���̌��6��23�`24���̂ݎ���s��ꂽ�B���a61(1986)�N�`����10(1998)�N�܂�6���ɐ��̉͌��Ɋy�܂���J�Â��Ă������A13��ڂŏI�����Ă���B(���̌�̒n���u�̊J�Ï͂킩��Ȃ��B) �����̒n���̌����`���ɂ͎��̂悤�Ȃ��̂�����B��D�ōȎq��S�������j�����ȂƎq�ǂ���ɒ������J�������ƂɎn�܂�B�l�ɕY�����������j�V����(����)����邽�߂̐d�ɂ������R�����A�C�ɗ����Ă��l�ɑł��グ����̂Œn���ɂ����B �u��ꐼ�̉͌��v/ ���ݒn����k���Ŗ�30���̈ʒu�ɂ���B���̉͌��Ƃ́A�A�C�k��ŃJ���C�~���^���Ƃ����u�_�̗V�т����v�Ƃ����Ӗ��ŁA����ʂ�D�傽���͖k�C���O��(�ΒÑ����A�Y�~���A�_�Ж�)�̂ЂƂɐ������A�u�n�����̉͌��v�ƌĂ�Ă����B�܂��A�͌���тɐςݐ������_�݂��Ă���A����ɂ́A�߂��ɒn�����A�Ɋy���A���̒r�Ȃǂ�����ׂɈٗl�ȕ��͋C���������A�����Ă�ė������̂ł��傤�B���Y���l�Y�������O�N(1856�N)�ɉڈΒn�������܂Ƃ߂��u�ڈΓ����v�̒��ɂ��A�u���@�̉͌��Ƙa�l���ĂԒn�L��v�ƋL�q����Ă���B�����ɂ́A�n����������D�ő�����l�X�̗�����{���邽�߂̒n���l���Ղ��Ă���B�̂���A���̒n���l��O�l�ɂ���ςݐɂ͗l�X�ȓ`��������A�_�邳�𑝂��Ă���B�@ |
|
|
���b�R�̉͌� / �k�C�����َs���쒬
���b�R�͔��َs(���E�b�R��)�̃V���{���B���ԏꂩ���̉͌��܂ł͗V�������̂тĂ���A�Ƃ���ǂ���̒n���߂Ȃ��炻��������B�_�݂���n���ɂ͈�ЂƂԍ����ӂ��Ă���B���̂ق��A�l����i�����Ǝv���閼����̊ω��l�������Ă���B �u�C����S�̔�v/ ���c���Õ��q�̓J���t�g�Ɩy���ւ̍q�C�̓r���A�b�R�������ɂ����Ĕ���j���A��ɔ��قɋA�蕶��6�N(1809�N)1�����̒n�ɔ���������ĊC��̈��S���F�肵���B���a11�N(1936�N)3��21����\���̂��߂ɕ��̂��]�|���ē�ɐ܂�Ă��܂����̂ŁA���̂Ɗ�b���C�������B�@ |
|
|
�����R�̉͌� / �X���ނs�c�������F�\���R
���R(�F�\���R)�͐���862�N�Ɏ��o(������)��t�~�m���J蓂��A�����R�����O���Ə̂����B���̍��͓V�䖧���̎��ł������B�a��(��������)�̗��Ŏ��͔j��(1457�N)����Đ��ނ������A1530�N���ڊo(���ォ��)�ɂ���čċ����ꂽ�B�����@�ɉ��@����A����R��Ə̂��ĉ~�ʎ�(�ނs)���ʓ����Ƃ߂��B�Ȃ��A�ڊo�͉~�ʎ��̊J�R(�J�c)�ł���B �̉͌���������݂����̂��͂킩���Ă��Ȃ��B����2�_�̎����ɂ��̑��݂��m�F�ł���B1�_�ڂ́w���R�{�V�~�ʎ����x�ł���B����5�N(1793�N)8���t���̊o�Ɂg���@�m�͌� �Ε��m�n�����h�Ƃ̋L�q������B2�_�ڂ͐��]�^���̓��L�ł���B����5�N6��23���t���̕����Ɂg�����̉͌��h�Ƃ̋L�q������B���]�̂ق����~�ʎ����������\���Â��L�q�ł���B�����2�_�����Â��L�q�͌������Ă��Ȃ��B �̉͌��̐Α�����ɔ@�������̑���ɁA����4�N(1857)�̓��t�ƂƂ��ɁA�o�Y���Ɏ��S��������(���N25)�̋��{�̂��߂̌��~�o�����܂�Ă���B ���R�̍L��ȕ~�n�ɂ�4�̉���(���Ă�5����)�A�n�����A�C�^�R�������{�s���錚���Ȃǂ��_�݂��Ă���B�~�n���͉ΎR�₪�R�ς݂ɂȂ��Ă���A�����_�K�X���u�N�u�N�A�W�����[�Ƃ����������ĂȂ���N�o���L�C������Ă���B���̂悤�ȏꏊ�͓q���n���A���̒r�n���ȂǂƖ��Â����A108�̒n��(���Ă�136�n��)�Ƃ��ꂽ�B�����ĉF�\���̌ΔȂ��̉͌�������B ���R�͂��Ƃ��ƖL��E�務�A�q�s���S�Ȃnj������v���F�肷�閯�ԐM�̒n�ł������B18���I�ȍ~�A�����o�T�Ɋ�Â��n���M���K�����A���X�Ɏ��ҁ���c�����{����M����������B�������]�ˎ���͂܂��������v���F�肷��n�Ƃ��Ă̋@�\�̂ق����傫�������B(�ڈΒn�ƌ��Ղ���C�������R��M�����B�����̊�i�����c����Ă���B)���҂̍��͂��R�ɓo��Ƃ����R�����E�ς͍]�ˎ���ɂ��������B�Ă̑�Ղł͋��R�ɓo�q�����{���s��ꂽ�B���̂悤�ȊϔO�͒n��̏��������ɂ��g�n���u�h�ɂ���Ďx�����Ă����B ���݂̂悤�ȃC���[�W���Œ�����̂͑����m�푈��̂��Ƃł���B�푈�ʼnƑ���S�������l�X�����R�o�q���Ď��҂����{���A�C�^�R�̌��ɂ���Ė����ꂽ�̂ł���B���̌�e���r�����y���ċ��R�ƃC�^�R�̑��݂��f���ɂ���Ēm�炳�ꂽ���ƂŎQ�q�҂��������A���̃C���[�W�����łȂ��̂ƂȂ��Ă������̂ł���B ���R�Ƃ����ƃC�^�R�̌����L�����B�����K�ꂽ�Ƃ��ɂ��A�����ł������ɂ�������炸�A�����s���Ă���p���݂邱�Ƃ��ł����B��Ղ̓��ɂ͂�����������Ƃ��낤�B�Ƃ͂����A�吨�̃C�^�R���W�܂�悤�ɂȂ����̂͐��̂��Ƃł���A��O�ɂ͂킸��2�`3�����{�s����ɂ����Ȃ������̂��Ƃ����B ���R�ɂ͌����`���������B���ɐl���S���Ȃ�O��ɋ��R�Ŏp�����������Ƃ����b�������B���k�n���ł͐l���S���Ȃ�Ƌ��R�ɏ���Ă����Ƃ��A���R�͎��҂̗�̏W�܂�Ƃ���Ƃ���ꂽ���ƂɗR�����Ă���B �ق��ɁA��Ղɂ͒n���̊����J���̂ł�������A������A�q���̗삪�̉͌��ɂ���Ă��ėV�ԁB�钆�ɂ��̒n��K���Ǝq�������̋��������������������Ƃ��������`��������B �w�n���̐Ӌ�����ɎāA�����ɖ����l�Ԃ������A���E�̓V�l��x���x/ ���̒n����F�̐��肪�������A�[�R�̗�������Ԓn���J����Έ��y�̑�n�ł���A�u�n���Ƌ��ɂ��킷�̂ɏ�y�Ȃ�v�ƁA�����̐��@�����炳��Ă���̂ł���B ���͖S�����e�̕����Ƃނ炤���� �̐l�̗�Ƃ��݂��݂ƌ�荇���������� �����̐M�S������w�[�߂������� ���N�̉i���ɘj��A�u�l�����˂��R(���R)�ɍs���v�Ƃ����f�p�ȏ����S��̉��A���܂��܂ȋF��̎p���J��L�����Ă���̂ł���B�@ |
|
|
�������̉͌� / �X���k�Ìy�S����������
�V�W�~�L�ŗL���ȏ\�O��]�ލ���ɁA��]�ނ悤�ɍ����̉͌�������B�{�����͂���ŁA(���O��)�傫�Ȓn����2�́A�����Ȓn����33�̕���ł���B���ׂĂ̒n�������킢�炵���X�q�ƕ��𒅂��Ă�����Ă���B �����̉͌��́A�u���{�ŌẪC�^�R���˒n�v�u��q�̉͌�(��q�n����)���˒n�v�ƌ����`�����Ă���B �����̉͌��ł́A�c�拟�{�ƕ����{��ړI�Ƃ�����Ղ����N6��23���ɐ���ɊJ�Â���Ă���B�C�^�R�̌��A�̗w�V���[��J���I�P���̂ق��A���w���ɂ��ۓJ���̉��t�Ȃǂ����葽���̗���҂ő�ςɓ��키�B���̓��ȊO�͂��Q�肷��l�͏��Ȃ��A�Ђ�����Ƃ��Ă���B(�ߏ��̐l�̘b) �����̉͌��͓�k������̑�Ôg�⎺������̐헐�ŖS���Ȃ����l�����{�����̂��n�܂�ł���A���������ɖؑ��̒n�������o�y�������Ƃ��炱�̒n�ɕ��������̂��Ƃ����B�@ |
|
|
����q�̉͌� / �X�����쌴�s���ؒ���q���[��
��q�̉͌��n�����ɂ́A�����̒j���̗삪�����K����ɒB����Ɛ_�l���v�w�Ƃ��Č��т��Ă����Ƃ����`��������B��������쌋���������͖����Ƃ����B�����ɂ͑召��2000�̂̒n�����J���Ă���B�{���������ɔ��X������A1���`1��5000�~���x�̉ԉŐl�`��v�w�l�`�������Ă���B�Q�q�҂�������w�����A�q�ǂ��̖��O�Ɣz��҂̋�z��̖��O���L���Đl�`���ɂ���������̂��Ƃ����B�Ǘ��������̐l�́A�u����Ă܂���v�ƌ����Ă����B�Ìy�n���͂�������_�n������K���l������Ƃ����B �Ȃ��A����̒����ƍl�@�ɂ��A�Ìy�n������L���������̏K���̗��j��1950�N�ȑO�ɂ͑k��Ȃ��A�Ƃ̂��Ƃł���B ���̒n�����̏@�h�͓V��@�B���k���{�R�͕������B��q�̒n�����͒Ìy�n���̒n���M�̒��S�Ƃ����Ă���B 2007�N8���̗��Ղɍs���Ă����B�V��j���ł�������������Ă����B��O�X�e�[�W�ł͖��w���̏o�������������A�����ɂ͐H�ו��₨������̓X���o�Ă����B�������O�̐Βn���ɂ͐V���������������A���ϒ��������Y��Ȋ�����Ă����B���X�ő����������Ă����̂ŕ����Ă݂�ƁA����S�����܂ł͑��������������A����ȍ~�͕��ʂ̌C�ł悢�Ƃ̂��ƁB�n�������ɂ͂�������̑������������Ă����B���̂ق��A�Q�w�҂͎�ʂ����A��������܁A�َq�A�ߗނȂǂ�������B�n�������̒��ɂ͂��V�����l���āA���{�̎t�������Ă���B�n����������̓C�^�R�}�`���B�e���g�̉��ɏ��������A4�Ɏd���Ă���B������4�l�̏��������������̑��k�ɉ����Ă���B���������̂܂��ɂ́A���ꂼ��\�l���炢�̒j��������A�����̘b���Ă����B �w���k���������W�x(1979)�ɂ��A�����̉͌��͕����N��(1818�`1830)�����q�ΐ쌴�u�����Ǘ����Ă����B�ˎ傪�u���ƂȂ萢�P���ŁA�s���̏�����^�c���s�����B6���̍�A�t�H�̔ފ݂ɂ̓C�^�R�̌���(�z�g�P���낵)���s����B����(1993)�ɂ��A���Ȃ��Ƃ����q����ȑO����C�^�R�����̏ꏊ�Ō����s���Ă����B 1965�N�ɂ�60�l�̃C�^�R���n���ՂɏW�܂����B���̌�C�^�R�͌������A1985�N������͊�؎R�ŏC�s�����J�~�T�}(�J�~�T��)�������ɏW�܂�悤�ɂȂ����B�C�^�R�̓z�g�P���̂��̂Ɍ�点��u���v���s���̂ɑ��A�J�~�T�}�͐_���߈˂����đ��邷��Ƃ�����ʂ�����Ƃ������A�����ɏW�܂�J�~�T�}�͌��I�Ȃ��Ƃ�����̂��Ƃ����B ���݂͋������牺��⓹���̉͌��Ƃ��Ă��邪�A�ȑO�͕ʂ̏ꏊ�������B�⓹�����肫�����Ƃ���ɓ��}���r(�����)������B���̒r�ɂ����鈰��勴�̉��̐���̐_��Ƃ����A���̉͌����̉͌��ƌ����Ă����B�]�ˎ���ȑO���̋��͋��ؑ��Ɛ�q���̑����������A�ƒn�������狳���Ă�������B �{�ɏo�Ă��������`���������Ă����B �Â��Ȃ��Ă��琅�ӂ�ʂ�ƈł̒��Ŏq�ǂ��̐�������������A�J�オ��̒��ɐ��ۂɏ����ȑ��Ղ����Ă��邱�Ƃ�����B �S���Ȃ����q���̒�������n�����Ɉ��u���A���N���������ւ���B�g���ŕa�C���o�����ɂ́A���̒�������Ă��ĕa�l�ɒ�����Ƒ�������B�n���ɂ��Q�肷��ƕa�C������B�z�Œn�����ȂłāA���̕z�Ŏ����̈����Ƃ����������ƕa�C������B�a�C���d���Ƃ��͒n�����ƂɘA��čs���A�n���ƕa�l������邪���ȂłċF��B�Ԃ���M���o�n��������A�n�����������ƔM��������B ���̒n���Ől���S���Ȃ���̉͌��ɍ����s���B (�̂̌����`��)�̉͌��Őς܂�Ă���͖S���Ȃ����q�����ςނ��A���Ղ�23�������͋S���o�Ă��Ȃ��B���̓��͎q�������łȂ����̐e���ꏏ�ɐ�ςށB �̉͌��ł͖S���Ȃ����q�����������܂���Ă��āA�����Ɍ����@��Ƃ��̒�����q�������̏����⋃��������������B�J�̓��Ȃǂɂ͎q�������̐����K���K���ƕ������Ă���B ���a31�N8��20���A��J�y���Y�Ƃ����l���d�����Ƀi�^������č��Ђ��ɂ��������B�Ƃ��낪�n�Ղ͂��邪��Ă͂��Ȃ��B���ꂩ��n�����ɂ��Q��ɂ������Ƃ���A�n���̍��Ђ��̂Ƃ��낪��Ă����B�̉͌��g���艄���n�����Ɏ��ۂɂ������b�Ƃ��ē`����Ă���B �����[�������`���������ďI���ɂ������B �u�܂��A�ȑO�͎O�N�Ɉ�x�͋Q�[������A���̎��Ɏq�ǂ����̂Ă��R�A�q�̂ĎR���A�ΐ쌴�ƂȂ��Ă���B�ΐ쌴�ɂ͊I�����邪�A��q�ł͐ԃ��V�̂��Ƃ��J�j�Ƃ����A�ΐ쌴�ɍs���J�j������Ƃ������Ƃ������Ă���v(�w�����W�x) �u�̉͌��ɂ̓K�j(�^)�����āA�J�̍~�肻���ȓ��̔ӂɂȂ�ƐԎq�̖���������v(�w�n���̐��E�x) �u��q�Ζ�쌴�n�����v/ ������q���Ζ�쌴�͎��o��t�̊J�n�Ɠ`������_�͉��k�̋��R�Ɠ��l�ł��邪�A�V�炨�������~��A�@��ƈ�̂̒n�������o�y�A��������u�����̂����̎n�܂�Ƃ������B�����A�����̍�����Q�w�l���������Ƃ������Ƃ���A���悻170�N���O���疯�ԐM�̃��b�J�Ƃ��Ďx�����A����(�����6��22�����24���܂�)�ɂ͑����̎Q�q�҂œ��키�B���Ɋ��q����ȑO���炢���Ƃ����ޏ�(�C�^�R)�̌���(��})���s����ꏊ�ƂȂ��Ă���B�@ |
|
|
������̉͌� / �X�����Ìy�S�[�Y���X�R
�X���[�Y��(���E��葺)�̊C�݂ɓ˂��o�������̉͌�������B���N�O�ɖ^�h���}�̎B�e�ɂ��g��ꂽ�B �̉͌��́A�`�������p����Ă���_��̓��A�g�K���K�����h�̏�ɂ���A�̂����n�Ƃ���Ă����Ƃ���ł���B�n�����ɂ��ƁA�����ȑO���炱�̒n�ɂ���̂��Ƃ����B �u�̉͌��ɐς𓊂���ƊC���r���v�u8��7���̖�͖K��Ă͂����Ȃ��v�Ƃ��������`��������B ���N8��23�A24�̗�����Ղ��s���A���{�����B�Q�q�҂ɂ����1�N�Ԃɋ�����ꂽ�����A���̑�ՂŐ�������̂��Ƃ����B�m���ɁA�������������N�����̂܂܂ɂ��Ă����킯�ɂ������Ȃ��̂ŁA��Ղ����������ɐ�������Ƃ����͍̂����I�Ȃ��Ƃ��B ���Ղ�Ƃ������ƂŃC�^�R�̌��A�o�X�A�������N���̃T�[�r�X�A�̗w�V���[�Ȃǂ��s���ē��키�B�������A����ȊO�͖K���l�͏��Ȃ��̂��Ƃ����B �����ɋL�ڂ���Ă��錾���`���������Ă����B �̉͌��͎�Ɏq����S��������e���ςށB�q�������łȂ��A�Ԃ��炩�Ȃ������l���S���Ȃ������̉͌��ɍs���B�ς܂ꂽ������Ă����̓��ɂ͌��ʂ�ɂȂ��Ă���B��e����ςݏd�˂Ă���Ƃ��ɐ��������C�ɗ��Ƃ����肷��ƁA�C���r�ꂽ��䕗�������肷��B�������ɍs���ƁA���Ɍ������Ă�����̂�����B�q���̎�̔炪�ނ��Č����o�邽�߂ł���B�K���K�����̓V�䂩�痎���鐅�́A�̉͌��̎q�������������Ă���܂ł���B �u�����n�� �̉͌��̗R���v/ ������S�N�]��̐̂̎����̃K���K�����ɂ͊C�����Z�݁A���Ƃ̐l�����͋ߊ�鎖���ł��܂���ł����B�����ʼn��k�̋��R����̐�q�n���̒n�Ɏ�����������o��t�����̐X�R�̉͌��ɂ���������܂����B�_�̋����A���̋������O�@��t�l�̋����ɂ��A�̉͌��̒n�Ƃ��ĊJ�����ɂȂ�܂����B�����n���Ƃ͋S�ɐӂ߂�ꋃ���q���B�̉��ɉB���Ă����n���l�ł��B�q�������Ă���e�ɂ͂Ƃ��ɉ��̐[�����l�ƌ����Ă���܂��B�@ |
|
|
����y���l�̉͌� / ��茧�{�Îs�L�P��
��茧�{�Îs�́g��y���l�h�́A�V�a�N��(���b����20�N�قǑO)�A�{�Ï���������싾���Θa�������Â����Ƃ����閼���ł���A�����C�ݍ��������̒��S�ł���B ��y���l�ɂ͐����瓌�Ɍ����čׂ����}��̍ג�������������B���͂��̏����Ȕ����̊O�C��n���A���p���Ɋy�Ɍ����Ă��Ƃ����B�����̓˒[���g���̒r�h�Ə̂��A���p�ɏ����������C�݉����̏����ȕl���g�̉͌��h�Ə̂��Ă���B��������o�����Ƃ���ɁA�������u�����Ɠ`�������̉͌��q���n�����J���Ă���B �̉͌��Ǝq���n���ɕ����čs�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�ό��D���߂Â��Ȃ��B�݂��{�[�g����āA���瑆���ł��������Ȃ��B�������̎��������܂ł��Č��n�ɍs���Ȃ������̂ŁA�ΐς݂̗L�����ɂ��Ă̗l�q�͕s���ł���B ���n�̐l�̐����ł́A(��q�̂悤��)�C�݉����̏����ȕl���̉͌��Ə̂��Ă���Ƃ����B����A�Â��n�}�ł͔����̒��������̉͌��Ƃ���Ă���A�����Ɏq���n�����J���Ă���B�n���ƋɊy(�O�p�Ɠ��p)�̋��Ɉʒu���Ă���Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B���݂̏ꏊ���̉͌��Ə̂���悤�ɂȂ����̂́A�������������̂��ƂȂ̂ł��낤���H �J���Ă���q���n��(����)�͋��Ɏq��������Ă���A�ڂ��傫���B�܂��A�Z��n�����O��?����A���ꂼ��ʂ̎��@���Ɉ��u����Ă���B�����͂��ׂė��̍�Ɠ`�����Ă���B�@ |
|
|
���ܗt�R�̉͌� / ��茧��D�n�s�����s��
�ܗt�R(���悤����B1341.3m)�͊�茧�̊C�����A���Ύs�A��D�n�s�A�Z�c���ɂ܂�����B���A�����L�x�B���͏W�c�����̖k���Ƃ���Ă���ق��A�N�}���Z�ށB�ނ����͐��˂ɍޖ����������p�̎R�ł������B�ǎ��ȃq�m�L��͉Γ�e�̒��ɗp����ꂽ�B �܂��ܗt�R�́A�×����M�̎R�Ƃ���Ă����B�V�䖧���A�F��M�Ȃǐ_�������ł���A�R���̏C������ł������B3�s���ɂ͎R���܂�_�Ђ������B�������߂܂Ōܗt�R�͏��l���ł������B �W��712m�̐ԍ⓻(��D�n�s)�ɎԂ�u���A�o�邱��25���B3����(930m)�g�̉͌��h�ɒ����B����܂ł̐A���������̂悤�ɁA�����������y�Ɗ�̐��E�ł���B��k90m�A����120m�ɋy�ԂƂ�������A�����h�[��������������x�̍L�����B���̏ꏊ�������A�����Ȃ��R�����ނ��o���ł��邱�Ƃ�A�k���̕ΐ����̒ʂ蓹�ł��邱�ƂȂǂ���A���̐��Ƃ��̐��̋���A�z���̉͌��Ɩ��Â���ꂽ�̂ł��낤���B�ɂ�������炸�̉͌��ɂ́A�n���͂������A�ق��̂ǂ̂悤�ȐM�̑Ώۂ��J���Ă��Ȃ��B�@ |
|
|
�����؎R�̉͌� / �{�錧�Ί��s����l(���؎R)
�{�錧��������(���E������)�̉�1Km�ɕ����ԗ쓇���؎R�B���݂̓��ɂ͐l�����쐶�̎��≎�������Z��ł���B �����ł͂Ȃ������ɏ�y���݂Ă����Ñ�̓��{�l�́A���؎R���܂��ɉ����̂��ӂ�铌����y�Ƃ݂Ȃ��Ă����B�Ñ㖖�����璆���ɂ����ẮA�^���n�C���҂����̓��������o�y�n�Ɛ�`���Ă����Ƃ����B ���̓��݂̒f�R��ǂ��̉͌�������B �����̉͌��ɍs���ɂ͐Ί��s�X���玩���Ԃ�50���A����D��25���A���؎R�R���o�R�œk��2����25��(�A���3����)��v����B�x�e���Ԃ͊܂܂Ȃ��B��{�I�ɓ����͓k���ȊO�Ɍ�ʎ�i�͂Ȃ��B �����R�_�ЎЖ������琅�_�Ќo�R�ŎR��(�C��444.9m)�܂ł͈�{���Ȃ̂œ��ɖ������Ƃ͂Ȃ��B����A�R�����瓌���͓��ɖ����₷���Ƃ����B�A���Ă��Ȃ��o�R�q������ƁA��A�Ж����E�����T���ɏo�邱�Ƃ�����Ƃ̂��ƁB���ہA2005�N5���Ɏ����K�ꂽ�Ƃ��A�唟��Ɏ���Ō�̖�1km�͓����قƂ�ǂȂ���Ԃł������B�s���͖��Ȃ��������A�A��͓��ɖ����Ă��܂����B����Ő��_�I�ɂ��Ȃ��J�����B�Â������ɁA���O�����������ɂ��Ă����K�v������B�Ȃ��ē��}�ɂ��ƁA�n�C�L���O�R�[�X�͑唟��ōs���~�܂�ł���B�����聕�̉͌��ɂ͍s���Ă͂����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B �唟�肩�玭�̕����~���߂�ꂽ���n��������̉͌�������B�l�X�ȑ傫���̉ԛ���̉ςݏd�Ȃ��Ă���B������150m�B������ړI�Ƃ��Đςݏグ��ꂽ�Ǝv����悤�ȁg�ΐς݁h�͂Ȃ��B ���̏ꏊ��2�̂̕��̂��݂邱�Ƃ��ł���B 1�͍̂���350mm�œ�������������ė����Ă���B���̉��ɗ��e�ɂ������̕������ߍ��܂�Ă���B����1�̂̏ڍׂ͕s���ł���B�������܂�Ă���A�n����F�����͊C��������悤�ɖk�������ɉ��ɐQ�������Ă����B �����ɋL����Ă��邱�Ƃ������Ă����B �Éi�N�ԁA�����L�ׂ́w���؎R�I�s�x�Ɂu�唠�A��������z������̉͌�������E�E�E�v�ƋL����Ă���B�����G�t������48�V���������A���ׂĂ��V��n���Ƃ����Ă���B���̓��ł̏C�s�̈�Ƃ����̉͌��ɂ��C���҂����Q��ɂ����B�������߂܂ŁA�����͐_�Ђ̒����܂ł����s�����Ƃ��ł��Ȃ����l���̓��ł������B���ɏ㗤���鎞�ƋA�����鎞�ɕK�������𗚂��ւ��镗�K���������B �q����S�������e���s���Ǝq���̐����������A�e�����l��S�������l���s���Ƃ��̐l�̐�����������B�@ |
|
|
���x�̉͌� / �{�錧���s���
�x�͑D�`�ΎR�Q�̍Ō�Ɍ`�����ꂽ����ΎR�ł���B(�Ȃ�̂�������H)�̉͌��͂��̎R�̂����Ƃ���ʓI�ȓo�R���[�g�̓r���ɂ���A(�����炭)8�`9���ڂɂ�����B�R�̐���ΖʂɈʒu���Ă���A���̏ꏊ���瑠���A������]�ނ��Ƃ��ł���B �咓�ԏ�ɎԂ�u���A�x���N���R�̉�(�W��583m)��ʂ��Đ��_(825m)�Ɍ����B���(1000m)���߂�����̉͌��ł���B���̑��Œ��ԏꂩ��1����35���ł������B�������炳���10���قǂŎR��(1172.1m)�Ɏ���B���w�Z1�N�������C��t�œo���Ă����B �̉͌��ɓ��B����ƁA�g���@�h�̉��Ŕ���B������ɒn����F�Ǝv����Ε�����B�Ε��̉����͌͂ꑐ�Ɛŕ����Ă���A�����Ȃ̂������Ȃ̂��m���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�ώ@��������ł͍����ł��낤�B �n���͎�����������A����͑T���(���T�̂Ƃ��̎�̂�����)���ނ��сA���(�ۂ���)������Ă���B�吳�O�N�������Z���̓��t�Ɣ��N�l�Ƃ���(�����炭)����16���̖��O�����܂�Ă���B�g�����炭�h�Ə������̂́A�͂ꑐ�Ɛŕ������B��Č����Ȃ��������߂ł���B ���̏ꏊ�̓e�j�X�R�[�g2�ʂ��炢�̍L��������B���n�ŁA���S���S�����Ă���B���̏�ɁA����ɍL�����n���L�����Ă���B�g�����̉͌��h�̉��Ŕ�����B���n�����ׂĂ��킹��Ɩ싅��̔������炢�̍L��������̂ł͂Ȃ����낤���B �R���ɂ͎O�g�喾�_���J�鏬���Ȃ���������B�����N��(1818-1829)�ɕ�[���ꂽ���̂��Ƃ����B�܂��A�R���̓��Ζʂɂ͖�t�@�����J�鏬���Ȃ���������Ƃ����B���k�c�여��̐l�X���J��A���u�ގU���F�肵���B�@ |
|
|
�������h�̉͌� / �{�錧���c�S�����h�����J�n�R
�����h���͕������ƎR�`���ɐڂ��Ă���B�ɒB���@���đ�ƕ������������邽�߂ɂ��̒n�ɓ����J���ꂽ�B�]�ˎ���ɂ͉��H�X��(�H�B�X��)�Ƃ��ď�����H�c�Ȃǂ̑喼�̎Q�Ό�����Ă̗����ɗ��p���ꂽ�B���Ƃ͎R���u�ĂĂ��邽�߁A�ɒB�Ƃ̖ڂ̓͂��ɂ����X���������̂��B�h��͑傢�ɓ�������Ƃ����B �ꗢ���ƂɎ��̏h�ꂪ���������Ƃ��玵���h�̖��������B ���̒��𗬂�鉡��Ɣ��ΐ�̍������邠����̉͌����̉͌��Ƃ������B�R���R�A�X��X(������������)�Ƃ����R�����C�s�����R�̘[���B���Ă��̏ꏊ�֑͊�(�h��)�̊O��ŁA���т����Ƃ��낾�����B����̒��������̎��ӂ��̉͌����Ƃ����F���͂���Ƃ����B�������A�͌��ɂ��̉͌����v�킹�鉽���Ȃ��B�����A�֏Z���^�[(������)�߂��̂s���H�ɎO�̂̒n�������u����Ă���A�̉͌��̒n���Ƃ����Ă���B���H�̘H�ʂł͂Ȃ��ڐ��̍����̈ʒu�ɒu����Ă���B�����ɊK�i�͂Ȃ�����(�Ζ�)�͑��ŕ����Ă����B ���̒n���ɂ��Փ�������A��O�ɂ́A�Փ��ɂȂ�ƌX��X�̎R���ň��ݐH������K�����������B���݁A���ƏZ���ɂ��s���Ƃ��Ă̋��{�͍s���Ă��Ȃ��B�l�I�Ɏ���ŋ��{���Ă���l�͂��邩������Ȃ����A�m�F�ł��Ă��Ȃ��B �����J���Ă���n���̂�����͍̂�����50�Z���`�Ə��Ԃ肾�B�R�c���H�q(���Ƃ킱)����̊G���L(1845�N)�̑}�G�ɕ`���ꂽ�̉͌��̒n���͂�����傫���悤�Ɍ�����B�܂��A�]�ˊ��ɂ͒n���͈�݂̂̂����A���݂͎O�̂��B���̌o�܂͕s���ł���B ���a9(1772)�N�̕������y�L�A���i�N��(1772�`81�N)�̕��y�L��p���o�ɂ݂���L�q�͎��̂Ƃ���B ����Ɠ��삪��������Ƃ����y�n�̐l�X���̉͌��ƌ����Ă���B�͌��̏��X�ɏ����d�Ă���A�Α��̒n�����������Ɉ�̗����Ă���B�����͂Ȃ��B�n���̍�҂͕s�������A���a2(1765)�N9��29���Ɋ̘a�����ċ������B�ʓ��͊B�Փ���9��29���B �����`���B�l�����ʂƉ���̉͌���ʂ��Ă����B���̑��Ղ��c�����B���̂Ƃ������Ŕ߂����v���������҂͋����A�K���������҂͏��B��ނ�ɍs���Ă��̐�(�������A����)�����Ƃ��������B �́A�H�c�Ɏq�ǂ������X�ƖS�������a�l�������B�Ɨ����]�˂Ɍ����r���A3�`4�l�̎q�ǂ������̉͌��𑖂��ė��āA���m���Ԃɂ�������u���������Ɂv�ƌ������B��ɁA���m�͂��̉͌��ɒn�������āA�q�ǂ����������{�����B�������Ă����ɒn���̈߂Ɏq�ǂ��������������������Ă���̂͂��̂��߂��Ƃ����B �̉͌��̖��b������B�n�����c�q��ǂ��Č��ɗ������Ƃ�����S�ɕ߂܂��Ă��܂��B�����A�S�����Ȃ��Ȃ����Ƃ���ŁA�S���W�߂���n������ɓ���āA�����Ă���l�ɔz���Ă܂�����B �{�錧�S�Ȏ��T�́g�̉͌��h�̍��ɁA�u���҂��ʂ铹(�����h����)�v�Ƃ��Ďʐ^���f�ڂ���Ă���B����͊ւ̓��싴�t�߂���B�e�������̂��Ƃ����B �ʌ������A���������Ă����B ���������h��K�ꂽ2007�N8�����݁A�����A���c�A���쓙�̏W���ł͑����s�s���Ă���B10�N�قǑO�܂ł͊ւł��s���Ă������A�����̌�ʗʂ������댯�Ȃ̂Ŏ���߂�悤�Ɏw���������āA���̌�͍s���Ă��Ȃ��B�����̍ۂɏ��������ŔO����������K���͍��������Ă���B�q�ǂ����S���Ȃ������̑��V�͊ȗ�(�������ʂ��Ȃ�)�ɂ���K��������B�@ |
|
|
�����̉͌� / �R�`����c�s��
�R�`���B��̗L�l�����ł���͎���10.2km�A�ʐ�2.32����km�̏����ȓ��ł���B�R�`�ł��k�Ɉʒu���Ă��邪�A�Δn�C���̗��H�ɂ��邽�ߔN�ԋC��12�x�Ɣ��ɉ��g�ł���B�t�E�H�ɂ͓n�蒹�̕�ɂƂȂ�A�܂��A�g�n�n�A���n�n�̐A����500��ދ߂�����B2005�N6�������݁A�l��312�l�A147���сB�������60���߂��B �́A�͉����q�H�̒��p�n�Ƃ��ċ@�\���Ă����B1672�N�ɐ����q�H���J�����c���Ă̏W�U�n�ƂȂ��Ă���́A��c�`�̕⏕�܂��͔��`�Ƃ��Ă��@�\�����B�����ɂ͍��ʂɏh���������Ƃ����B�����͎̔��������̓��ł��������A���������D�̂��߂ɓ����͋M�d�ȐH���E�����^�����B �D����j����ƁA�t�ɂ͓쓌�̕��ɂ̂��đD�ׁA�c�[�A���̂��C�݂ɑł��グ��ꂽ�B�����̊��̕l�͎��l��(���тƂ��)�Ƃ���ꂽ���A���Y�̏����l(�C������ɂȂ��Ă���)�ɂ��オ�����B �]�k�����A�����m���͑�m�Ɏ��̂�������Ă��܂��Ɨ��ɂ͏オ��Ȃ��B�������A���{�C���͒��̗���A����������~�������\���������������A���̂��C�݂ɑł��グ����\�����傫�������B�����m���ɔ�ׂē��{�C�̊C�݉������̉͌��������̂́A�����������Ƃ��W���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B ���̐������̌�ϓ�(�����Ⴍ����)�͓����ɂƂ��čő�̐M�̒n�ł���B���l���̗쓇�Ƃ���Ă����B��R�ł���l�͏㗤�ł��Ȃ��B ���̓��ɂ͑傫�ȓ��A������B�����̕ǖʂ͉��F�̂��낱��ŁA���_�A�����j�A�̉e���Ńs�J�s�J�ƌ����Ă���B�̂̐l�͂�������āg�C�̐_�l���h�ƐM���Ă����B���̓��A�������ĉ����(������)�_�Ђ̖{�a�Ƃ���A���݂Ɏ����Ă���B ��ϓ��̓�ɉG�X�q(���ڂ�)�Q��������B������łł����召�̓����_�݂��Ă���B�����͉�����_�Ђ̋����ɂ��Ƃ���ꂽ�B �̉͌��͑�2�̐M�̒n�ł���B���Y�̊C�����ꂩ��V������������C�ӂɂ���B���������͕s���ł��邪�A�������N(1804)�߉��̔ˎm�ɂ��I�s�����c����Ă���B �G�X�q�Q�������̉͌����ӂ܂ł͊C��(�C��̑�n)���Ȃ��Ă���A���ӂ��ꂽ������͒��̗���ɏ���ĊC���]����A�p���Ƃ�Ċۂ����ƂȂ��ĕl�ɏオ�����B�̉͌��ɂ͂��ꂪ��R�ɂ��c�q�ς݂���Ă���B�����ɓ������̉͌��̉������ɔg�����u���b�N�ݒu���ꂽ���߁A���̒��̗���͐��f����A���l�ɗ���ė��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B����ɁA�l�ɂ������͂��̐����ɗ�����ĊC���ɖ߂���Ă��܂����B(���ہA���͊C�݂ɂ������͂��̑����̐��C���ɒ���ł����B)���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�͕̂l�����ς��ɂ������̉͌��̐ΐς݂́A���ł͂������茸���Ă��܂����̂��Ƃ����B �����̉͌��ɂ�3�̂̐Ε�����ϓ���w�ɂ��ė����Ă���B��쐼�����B���̐Ε��ɂ��Ắw�H��}���x�ɏڂ����B �̉͌��̖k�ɖ��_�Ђ���ϓ��������Č����Ă���B�n���N��͕s���B�̉͌��̎��_�l�ł���B �����ȑO�A���̐_�Ђ͊O�Y�ω��A�喾�_�ȂǂƌĂ�A������_(���_)�A�������_��(���_)���J���Ă����B����9�N�ɉ�����_�ЂƉ��̂��A���Y�̉�����_��(�q�a)�̐ێЂƈʒu�Â����A��C�Ì���(�C�_)�ق����J�����B���݁A������_�Ђ̐ێЂ������Ȗ��́E�n�ʂł��邪�A���ɖ��_�ЂƂ����_�̎ЂƌĂ�Ă���B������_��(�q�a)�ƌ�ϓ��͑�C�Ì����ق����J���Ă��邪�A���_�Ђ͏������_�Ђ��J���Ă���B���ɂ킩��ɂ������A�������j�̒��Ŗ|�M����Ă����_�ЂȂ̂��낤�B �����̉͌��ɂ͏�������Ȃ��قǑ����̓`��������B �̐l�����łȂ����l�͕K���̉͌���K���B�̉͌��͎��҂������Ƃ���ŁA�L���̎҂��w��Ƃ���ł͂Ȃ��B ���Ŏ��҂���Ƃ��́A�͌��Ɍ����ĕ������������Ƃ��ł���B ���̉͌��̐������Ē���D�ɏ��ƑD���̏Ⴗ��B����ɂ��ē��ݏZ�̒��N�j���͌����B�u�M������Ȃɂ��A�����`���ł�����˂��B���̐l�͊F�����l���Ă��܂��B�v�@ |
|
|
���U���ێR�̉͌� / �Q�n���݂ǂ�s
����ƁE����x�O����̔��p�قŗL���ȁA�݂ǂ�s(���E����)�ɌU���ێR(�����܂���)�Ƃ����R������B ���̎R�̒��͑傫��2����A��k�ɓ�҂ƂȂ��Ă���B�k�����U���ێR(1908m)�A����O�U���ێR(1787m)�Ƃ����B�O�U���ێR�̓쓌�̗Ő��A�W��1550m�قǂ̂Ƃ�����̉͌�������B���̒n�ւ̍ŒZ���[�g�͍���122��������ѓ����Ԃł����݁A�ܗ��o�R������o��|�̎�R�[�X�ł���B��1���Ԃœ�������B�Ƒ��A��ł��\�ȓ��������z���}�ő̂������B�����ЂƂ̃��[�g�͓��m��o�R������o��A�Q�߉�(�Α��߉ޟ��ϑ�)���o�R�����̉͌��Ɏ��铃�m�[�g�ł���B�O�U���ێR�̎R���ɂ��̉͌����炳���2���Ԉȏ�̋���������B �U���ێR�͐ԏ�A�Y���ȂǂƓ����V�����4�I�̉ΎR�̂ЂƂł���B�O�U���ێR�͎R���t�߂��畬�o�����ΎR��(���P�Έ��R��ƃJ��������)���琬���Ă���A�R�����甼�a2km�͈̔͂Ŋg�����Ă���B �̉͌��̐ΐς݂����̉ΎR��ł���B�܂��A���̒n�͗��n�Ŗ������Ă��Ȃ����A���͂ɂ̓c�c�W���炭�B �ԏ���ӂɂ́g���҂̍��͐ԏ�ɂ̂ڂ�h�g��4��8���ɐԏ�R�ɓo��Ǝ��҂ɉ��h�Ƃ��������`�����������B�U���ێR�ɂ��g���̔N�Ɏq�ǂ���S�������l���̉͌��ɍs���Ǝ��҂ɉ��h�Ƃ��������`��������A�Q�߉ނɎQ�q��������̉͌��ɓo���Đ�ςƂ����B�Ƃ��ɋ���4��8���͐Q�߉ނ̍Փ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�n���̑m���Q�߉ނɍs���F�����s�����B(�ԏ�R�Ɠ��l��)���̓��ɓo��Ǝ��҂ɉ��Ƃ������ƂŁA���̓��ɓo��l�����������B��O�͑��l�⓺�R�W�҂��w�łĂɂ���������A���͂�����Ă������B �Q�߉ށA���͂��߂Ƃ��āA�R���ɂ͏@���I�Ȓn���▼�̂��������݂���B�n���̏C���҂��R�ŏC�s���s�����Ƃ��`�����Ă���B���������݂͐M�̑ΏۂƂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B ���̐́A�O�@��t�����̕t�߂ɗ����Ƃ��A�������Ė�ɂȂ����B�q�������̋���������������̂ł��̕�������ƁA�S�������A�吨�̎q�����W�܂��Đ�ςݏd�˂Ă���ƁA�S���ԋS�S�ƂȂ����̂ŊF������߂��Ă����B�����ōO�@��t�͎q�������̐Ӌ���~�����ߎO��Ōo(����)���ϓx(������)�����Ƃ����A���ł��q���̐V�����o�����l�������Ő�ςނƎq���ɉ��Ƃ����Ă���B�@ |
|
|
�����É��̉͌� / �Q�n����ȌS���Ò��厚����
�g���Â悢�Ƃ���x�͂����Ł`�h�Ƒ��Ð߂ɉ̂��鑐�É���́A�L�n�A���C�ƕ��ѓ��{�O�����̂ЂƂɐ������Ă���B�J���̓`���ɂ͓��{�����ł���Ƃ��A�ޗǎ���̑m�E�s��ł���Ƃ��A�����������ɗ��ĉƗ������������Ƃ���������B�����R��M����C����(�R��)���������čL���Љ�Ă������Ƃ����̂��j�����낤�B���łɉ���3(1491)�N�̋L�^�ɑ��ÁA�L�n�A�����������{�̗쓒�̍ł�����̂ƏЉ�Ă���B �����R�͏C���̎R�ł��菗�l���̗�R�ł������B���̘[�Ɉʒu���鑐�Â͔����R�C���̍����n���B���Âɒ������锒���_�Ђ͔����R��M�̑Ώۂɂ��Ă���B���݂̖{�����R(���Ô����R)���M�̑Ώۂ��������A��ɑ��Ô����R��������ꂽ�B���Ô����R�͔������_�A�{�����R�͌Ô������_���J���Ă���B ����6�N�Ɍ��ݒn�Ɉڂ����܂ł̔����_�Ђ͉^�������������̍c��_�Ђ̎��ӂɂ������B���̒n�_�͉���X����߂��A�]�˓��Ƒ�n���̕���_�ł���A�X���̍ł������ʒu�Ƃ����d�v�Ȓn�_�ł���B�߂��̋F���d����͐M�̎R�X(�����R�A�Y���R�A��ԎR)��y�q���邱�Ƃ��ł���Ƃ����B �����̉͌��Ƃ����ΐ��̉͌������̂��Ƃł��邪�A�̂͒n���̓��ɂ��������B�n���������痬��o�����ׂ�����Ă���Ƃ�����̉͌��Ƃ������B�����ɂ͒n�����A�s�����A������Ȃǂ��������B���������̍�(19���I����)�����͑��Â̐����Ƃ���ꂽ�悤�ɁA���オ����ɂ�ĊJ�����i�݁A�������ꉺ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�������̉͌��ł��邱�Ƃ͐l�X�̋L����������Ă������B���݁A����͋��������ߗׂ̏h���{�݂ɔz�������ƂƂ��ɁA�������o���Ė����̋�ԂɂȂ��Ă���B �n���̓����n�������ז쎁�����L���Ă����B���̂����͏�y�@�Ƃ����A�R���͑��ÎR�B�ז쎁�͏C���҂ŁA���Â𐭎��I�Ɏx�z�������{���̌n�B�n�������ɂ͍���25cm�̒n�����{���Ƃ����J���Ă���ق��A�ז쎁�̈ʔv�������ׂ��Ă���B�s���Ȃ̂ŗ��R�͕s�������A��y�@�͕���12�N(1829)�ɎR�������ɏ����Ă���B�]�ˎ���ɕ`���ꂽ�G�}���݂�ƁA�����傫���`����A����A��y�@�͂܂������`����Ă��Ȃ��B���̉e���͂̑傫���A�l�X�̐M�̑傫�������������m�邱�Ƃ��ł��悤�B ���̉͌��������ӂ͂������ʂ̎���Ƃ��납�牷�N���o���Ă���A���͐������A�L�C���Y���Ă���B���Ȃ��物��̍����v�킹��i�F����g�S�̐h�Ƃ����A �K���l�͋H�ł������B���̍����s�������A���̒n�ɂ͋S�̓`���������`�����Ă���B ���āA���n�́u���̉͌��v�́g���h�́A�g�����h�ł͂Ȃ��g�ɂ��h�Ɠǂނ̂��������ƒn���̐l�������Ă��ꂽ�B���Âɂ͑傫���킯��3�̉͌��A���Ȃ킿���̉͌��A��(�ɂ�)�̉͌��A�n�U�̉͌�(���̉͌�)������A���̂������ƒn�U���̉͌����Ƃ����B�]�ˎ���̐��M��G�}�Œ��ׂĂ݂��B�ǂ���g�S��(��)�h�g�h�g�����̐쌴(�͌�)�h�ƂȂ��Ă���B�g�ɂ��̂����h�Ɩ��m�ɂ킩����̂͌������Ȃ������B����ł��ØV�́A�g�ɂ��̂����h���������ƌ����B ���a30�N���Ô����R�̓������痰�����̌@���ɁA�n����������k(�`�o)���o�y�����B�����������̑啬�Β���(����̐�)��������15���I�O��(���}�̐�)�̂��̂��B�����k�ɂ͌��~�o�̌o���炵���������L����Ă���B�C���҂������R(�ΎR)�̒���Ə��l�~�ς�ړI�Ɍo���������A�F�����Ȃ��瓒���Ɍ����ē������B���������ꂪ�����ɓ��炸�A�����w�̉��ŕ��炸�Ɏc�������̂��B���E�L���̎_�x���ւ铒�������ɁA���̒��ɓ�������Ă���Ηn���Ĕ��@����邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�B����甭�@���ꂽ�����k�̂����̐����͑��É����قɓW������A�u12���I�����[���ꂽ�v�Ɖ�������Y�����Ă���B�@ |
|
|
���V�ʐ��@�̉͌� / ��t������s�V��
�[�������A����s�̒��S�����獑��128���������炭�������V��(���܂�)�W���̂͂�����̉͌�������B�n���̐l�X�͐��@�̉͌��ƌ����Ă���B 2008�N�Ăɂ�����K��A�������̏Z�E���炢�낢��ƕ������Ƃ��ł����B ���݂����͖[�������B����̉͌����B���\�N�O�܂ł����ɐΕ��͐��\�̂����邾���������B�����鐅�q�u�[���̉e��������A�@�|�ɊW�Ȃ��Ε���u�����Ƃ������Ă������Ƃ���`���āA�Ε���ʐ^�Ȃǂ̕�[�����������A���݂̂悤�Ȗ��t��ԂƂȂ����B���̂��ߌ��݂͐Ε���V�K�ɒu���̂�f���Ă���Ƃ����B ���q�Ɍ��炸�A�����ɂ͗l�X�ȔN��̐l�����̋��{�̂��߂ɐΕ�����[����Ă���B����24���̉����Ɍ��炸�A�n�����͂��Ƃ����A�Q�n�A��ʂƂ���������������Ƒ��A�v�w�A�܂��͌l�ȂǗl�X�Ȓj�������Q��ɖK��Ă���B �������A���̒n�����߂Ă�����Δ�(�������s���)�̔ˎm���V�ʂɂ���Ă��ĖC������������B�ˎm�͂��̎��̓��L�ɁA�C��̍����ɃT�C�m�J�����̐ΐς݂�����ƋL���Ă���B ���݂܂łɐ��@�̉͌���3��̈ړ]���J��Ԃ��Ă����B�����͑��C���w�Z���͂����Α��ɂ������B���ꂪ���ݒn���Ɉړ]���A���a�̏��ߍ��Ɍ��ݒn(�����e)�Ɉڐ݂��ꂽ�B�R���N���[�g���̌��������Ă��͍̂�����20�N�قǑO�̂��ƂŁA�R����y���������Ă��Ċ댯�Ȃ��߂��Ƃ����B ����128�������ł���܂ł́A�����̂ނ�������͊C�݂Ő��S���S�����Ă����B���̐��Ђ���Ă��Đ��@�̉͌��ɐς�ł����B�������A���̊C�݂ɍ������ł��Ă���͐��E���Ă��邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�A�ΐς݂͓r�₦���B ���@�̉͌��̊Ǘ��͓����V�ʏW���ōs���Ă������Ǘ�������Ȃ��Ȃ�A�u�Ɉς˂��������ł��Ǘ�������Ȃ��Ȃ��āA�n���̐������Ɉڊǂ��ꂽ�B���݁A�Z�E�v�Ȃ��������Ő��@�̉͌��ɋl�߂Ă���Ƃ����B�����K�ꂽ�Ƃ��ɂ��A���傤�ǏZ�E������Ă��āA�����ӂ�܂��Ă����������B �����w�ł́A�[�������͗��搧(���ߕ�ƌw���)�ŗL�����B�V�ʂł̓I�R�c�A�Q(�����グ)�Ƃ���������K�������M���ꂽ�B�����Z�E�ɐ��@�̉͌��Ɨ��搧�Ƃ̊W��q�˂��Ƃ���A�u�W�Ȃ��v�Ƒ������ꂽ�B�V�ʏW����3�n�悠��A���@�̉͌��̂���n��͑��n�悩��͊O�ꂽ�ʒu�ɂ���B���n��ɏZ��ł����l�������A�ЊQ�Ȃǂ��߂Ɍ��ݒn�Ɉړ]���Ă��ďo�����n��Ȃ̂��Ƃ����B���̒n��́A�����V�ʏW���ł������I�ɂ͈قȂ��Ă���Ƃ̂��Ƃł���B �Z�E�ɂ��A�̉͌��͑S���ɑ������邪�u���@�̉͌��v�Ə����Ƃ���͂قƂ�ǂȂ��A���̂悤�Ȏ������Ă��̉͌��ɂ́g���邳������h�̂��������B���̖��邳�Ƃ͂ǂ����������ƂȂ̂��A���ɂ͂悭�킩��Ȃ������B�����A���R����ė����n���̘V���ƏZ�E�Ǝ��Řb���e�݁A�傢�ɏ��Ă��̏����ɂ��邱�Ƃ��ł����B��������@�̉͌��́g���邳�h�Ƃ������̂��낤���B �Ō�Ɍ����`���������Ă����B �������Ă��Ȃ��j��(�q�����c�����Ɏ��j��)�͉��ɂȂ��Ă����@�̉͌��ɍs���B�S���Ȃ����q�ǂ��̗�͐��@�̉͌��ɏW�܂��Ă���B���@�̉͌��̑O��ʂ肩��������q�ǂ����o�Ă��Ēʂ��Ȃ������B������(��������(�����Ɏq�ǂ�)���������v��)���ł��肢�����Ȃ��Ă����B�@ |
|
|
���S���} / ��t���R���S���Ō�������,�L�ώ�
��t���k�����A��\�㗢�l�ɖʂ������A���Ō����̒���(�ނ��傤)�Ƃ��������ȏW���ɍL�ώ��Ƃ����^���@(���Ă͏�y�@)�̎�������B�{���͒n����F�B���̎��ɂ�(���N�ɂ���)���q���ォ��S���}(���炢����)�������͋S�����Ƃ�����@�����ʌ����`����Ă���B1976�N�ɍ��̏d�v���`�����������Ɏw�肳��Ă���B ���N8��16���ɖ{���ōs����{��S(������)���{�̌�A�{���e�̉��ݕ���Œ����W���̐l�X�ɂ���ĉ������Ă���B��x�ł��x�ނƗ��Ɉ����a�����s��Ƃ��������`��������A�펞�����x�ނ��ƂȂ��������Ă����B�����K�ꂽ2008�N�͒����ɖҗ�ȑ�J���~��������ǂ��A�㉉���Ԃ��߂Â����炨�V���l��������āA�����̏��������̒��Ŗ����ɏ㉉���ꂽ�B�����W���̐l�X���������炷�ׂčs���Ă���Ƃ�������A���̂���J�ɂ͖{���ɓ���������B �S���}�͒n���̗l����`�����n�����ł���B�g�变�h�g�̉͌��h�g������h�g���o�̎R�h�̎l�i�ɂ킯���ĉ�������B�ԋS�A���S�A�S�k(�D�ߔk)�A�S��(��l�A�q�ǂ�)�A腖��A�䐶�_�A��F(�ω��A�n��)�����o���҂��B���̌��͉����̐l�X�ɂƂ��Č�y�ł���Ɠ����ɁA���ʉ���ƕ�F�ւ̋A�˂��O���ɂ킩��₷�����������������Ă���B �g�̉͌��h�̒i�̓��e�͎��̂Ƃ���B �S��(��l)�ɐ擱���ꂽ���l�̎q�ǂ��̖S��(�ȉ��A�u�q�ǂ��v�Ƃ����B)�������̉͌��ɂ���Ă���B�q�ǂ������́u����O��l�\��艺�̗c�q���`�v�Ƃ������Ȃ����ςށB�����ɐԋS�E���S��������A�u���畃��͛O�k�ɂ���B���[�A�����A�ނ�������∤����Ǝv��������ɂāA�ǑP���{�̐S�͂Ȃ��B�F�A����̍߂ƂȂ�B�������ނ��ƂȂ���v�ƌ����Ȃ���A�����f���q�ǂ�������ǂ�������B�����ɒn����F���������ƁA�q�ǂ������͂��̔w�ɉB���B�n���͋S��ǂ������A�q�ǂ��̂ЂƂ������グ��ƁA�ق��̎q�ǂ��������]���Ă������Ƒޏꂷ��B���̊ԁA�a�]���r������B �S���}�͊��q������ɂ��Ă͂��邪�A���̐����͎����O���ł���B���̍��ɂ��̉͌��͂܂��a�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂�����Ȃ̂ŁA�S���}�̐�����������g�̉͌��g�̒i���������Ƃ͍l���ɂ����B�����āA�g�̉͌��h�̒i�����Ɏq�ǂ����o�Ă���̂͂Ȃ����A���̒i���g�变�h�Ɓg������h�̒i�ɂ����͂��܂�ĉ������Ă���̂͂Ȃ����Ƃ����^����������B�܂��A�����ʼnr������n�U�a�]�̐����͍]�ˎ���ł���B�����̂��Ƃ���g�̉͌��h�̒i�͋S���}�̐��������炠�����Ƃ͎v���Ȃ��B�������������Ă���悤�ɁA���̒i���܂Ƃ܂����͍̂]�ˎ���Ƃ݂�̂��������Ǝv���B�����N���̂����ɗl�X�ȍH�v���lj����ꂽ��A�͂Ԃ��ꂽ�肵�Ȃ��猻�݂̋S���}�ɂȂ����̂��B �㉉�̖��ԂɁg�������h���s����B�S�k(�D�ߔk)�ɐԂ���������Ă��炤�ƌ��N�Ɉ�Ƃ��������`�������邱�Ƃ���A�����̐Ԃ���e�̊肢�̋]��(�H)�ɂȂ�B�S�k�������吺��������ƁA�勃������q�A���C�Ȏq�A�Q�Ă���q�ȂǗl�X���B����Ȕ����ɉ�ꂩ�犽����������B�䂪�q�����N�Őe�F�s�Ȏq�Ɉ���ė~�����Ɗ肢�S���}�^�����������ɗ��������̏��������ɂ́A�悢�������ɂȂ������낤���A����ɐM��[�߂邫�������ɂ��Ȃ������Ƃ��낤�B �̉͌��̐M�͎��ۂ̏ꏊ�Ƃ��Ă��̉͌������łȂ��A�������A�`��(�̘b��`��)�A�a�]�A���w�A�G��ƊG�����ȂǗl�X�Ȏ�i��p�����Ė��O�ɐZ�������B�@ |
|
|
���������̉͌� / �_�ސ쌧�������S������������
���m�̌ΔȁA�����_�Ђ̑咹���̑������̉͌��Ƃ�����ꏊ������B�c�O�Ȃ��炱�����̉͌��Ƃ͖�����B�Ε������ꂢ�ɕ��ׂĂ��邾���ŁA�܂��������͋C���Ȃ��B �����̉͌��������������̂��s���ł��邪�A1658�N�́w���C�������L�x�Ɂg���m�ΔȂ��̉͌�������h�ƋL����Ă���B���̌�1841�N�́w�V�ґ��͍����y�L�e�x�Ȃǂɂ��A���m�Ό̐��ۂ�130���܂�̐Γ��E�Ε��E�������݁X�ƕ��сA�R���ɂ̓J�������̒n������5����ł����Ƃ����B�����ېV�̐_�������߂ɔ������̉͌��͔����_�Ђ̊NJ����痣��A�܂��A���߂ɂ��p���ʎ߉^���̍��܂�ɔ����Γ����̑��������p���̗J���ڂɂ������B���̌�2�x�̈ړ]�A�����A�������J��Ԃ����݂̎p�ƂȂ����B �Ε��̂����̑����́g�R�̎��h�ɕ��ׂ��Ă��邪�A�������ɗ����Ă�����̂͂Ȃ��B �]�ˎ���A�����ɂ͈��m�̂ق��A�Z���̒�(���i�r�t��)�A�W�q�ɂ��̉͌����������Ƃ����B �Z���̒҂�K��Ă݂����A���m���������ƕ��͋C������B�������A�g�̉͌��h�Ƃ�������̏ꏊ���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���i�r�̌ΔȂ�Ε��Q�߂Ȃ���U������Ƃ悢�B �u�̉͌��v/ ���̒n�͒n���M�̗�n�Ƃ��āA�]�ˎ��㓌�C���𗷂���l�X�̐M���W�߂��Ƃ���ł��B���̋K�͂͑傫���A�����̐Ε��A�Γ����ΔȂɕ���ł��܂����B�������A��������ɓ���ƁA�����̔r�˂��瑽���̐Ε��������A�܂����m�ΔȂ̊ό��J���̒��ł���Ƃ��̋K�͂��k�������݂̂悤�ɂȂ�܂����B��������Ε��A�Γ��̒��ɂ����q����Ɛ��肳����z�����n�ߋM�d�Ȃ��̂�����܂��B�@ |
|
|
�����n����̉͌� / �V�������n�s��
���n�J�[�t�F���[�����ꂩ��Ԃ�1���ԁB�O�C�{�̖k�[�Ɋ�W��������(�����h�����)�B���ԏ�ɎԂ�u���A���Ă͐������H�������Ƃ����Ώ�̎��R�V����������B700�`800���قǐi�Ƃ���ɁA�s������Ղ�悤�ɑ傫�Ȋ₪�������B���̐�͌����Ȃ��B���̊�̒��S������т���Ă���A������ʂ蔲����ƓˑR�Ɉً�Ԃ��Ђ낪��B�̉͌����B���̏ꏊ�����c�T���ԋ߂Ɍ����邪�A��c�T���߂����̉͌������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�ォ������E��������p�ɂȂ����ꏊ���̉͌��͂���̂��B���ɐ▭�ȏꏊ���Ɗ��S����B ���̏ꏊ�͒n�ςł͘h��ł��邪�A����̉͌��Ƃ���Ă���B�Â������W���̐l�X���Ǘ����Ă����B �̉͌��͊C�H����(����������5��)�̒��ɂ���B�����ɑ召�l�X�Ȓn�����������u����Ă���B��������(������)�����̂��ڂ݂́u���̒r�v�Ɠ`�����Ă���B ���̍����炱�����̉͌������݂���̂��낤�B1736�`1741�N���ɏ����ꂽ���n�����L�Ɂu�������̉͌��Ƃ����Ƃ��날��v�ƋL����Ă��邱�Ƃ����͒��ׂ�ꂽ�B������̂̂��Ƃ͕s�����B �ߑォ�猻��̏ɂ��Ă����炩�L���Ă������B �����w�Җ��c���j�����n��K�ꂽ�吳���ɂ́A�����ɒn�������������B�{�{�̒����ɂ͒n�������i�̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B�^�X��̑��l�͎O��H(����H�Ƃ��B���E�Ԕ�����)����A��ƊC�{�H�����K��������A���̈ꔑ�ڂ����̒n�����ł������Ƃ����B�̉͌��͎��@�ł͂Ȃ����߁A���n�ɓ`��镡���̕H�̐����ȎD���ł͂Ȃ����A�����������ď��q����Ă����B�Ȃ����݁A���F�͑��݂��Ȃ��B �̉͌��̑O��ʂ�V�����́A����45���������������܂Œn���̐������H�ł������B�n���ʂ����B����\�N�O���̉͌��́g���������Ƃ����ꏊ�ŁA�q�ǂ��ЂƂ�ł͕|���Ēʂ�Ȃ������h�ƒn���̏����͌����B 1996�N8���ɂ�����K�ꂽ�Ƃ��A����10cm�قǂ̐��q�n�U�������炱����ɖ����ɒu����Ă����B2009�N�ɍĖK�����炻�̐��͌������Ă����B���N�O�ɍ��g�������Ĕg�ɂ����ꂽ�̂ŁA�ł��邾���E���W�߂������������̂��Ƃ����B�Ȃ��A���̑�ʂ̐��q�n�U�́A�ނ����A�ω����̏Z�E�������Ă��Ċ�ɐڒ��������̂Ƃ̂��ƁB ���݁A�Z���̌����ƍ���ŊǗ��͂܂܂Ȃ�Ȃ��悤���B�C�ݕY���S�~�̐��|�A�����̑|���A�ΑK�D�_��Ȃǖ����͑����d���B���̏W���ɂ͂ق��ɂ��_�Ђ�ω���������B�ߔN�̓J���]�E�̕ی쑝�B�ɂ��͂����Ă���B��邱�Ƃ������ς����B �����̐M�҂ɘa�̎R�̐l�����āA��]�҂���A��B(����)�ɂȂ��ĔN�������ė��Ă͐��|���A���Ԃ��������Ă����Ƃ����B����Ȑl�����Ȃ��ƈێ�����ς��B���s�҂̓S�~��u���Ă��Ȃ��悤�C���������B ���N7�����ɍՂ肪�J�����B2009�N�͂����ɂ��̉J�͗l�ł������B����ł�����҂𒆐S�ɐM�҂��W���Ă����B�����ɕ��Ԓn���̒����玩���̒n���������o��(�n���ɂ͔ԍ����U���Ă���)�A�َq�Ȃǂ������Ă͎�����킹�Ă����B����̎��ԂɂȂ�Ƒm�����njo����ƂƂ��ɁA�M�҂̏Z���Ǝ����������ċ��{���Ă����B���̒n���ɂ͓��������łȂ��k�C���Ⓦ�����������B �Ȃ��A���n�̊ό��p���t��K�C�h�u�b�N�ɂ��̍Ղ�͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B�ό��s���ł͂Ȃ��M�҂̂��߂̋��{�̏�Ƃ������Ƃ��B �n���ł͊��O��(2��)�ɂ͕K�����Q�肷�邵�A�Ƒ����S���Ȃ��3�N�Ԃ͖��N���Q��ɍs���B�����e�n����q�ǂ���S�������e�����Q��ɗ��邱�Ƃ������Ƃ����B ���ɁA�����ɓ`���`���������B ������S�������҂̑D���̉͌��̉�������ʉ߂���Ƃ��ɂ́A�D�̔���������B �ΐς݂����Ă���q��������Đ𗎂Ƃ��Ă��܂��Ă��A�����ɂ͕K�����ʂ�ɂȂ��Ă���B�����Őΐς݂�����̂�10�Έȉ��̎q���̗�ł����āA�q�����S���Ȃ邽�тɐ̐���������B�����̒n���������Ă���ƁA��ɂȂ�ƉƂ̒����g���₪��h����B �����̉͌��ɂ�����͉̂��ЂƂ����Ă��Ă͂����Ȃ��A�ƒn���̐l�͌����B���a����Ɂg�{���ɂ������b�h�����̂ōŌ�ɏ����Ă����B �����ɏZ�މƑ����������̉͌��𗷍s�����B���̌ケ�̉ƂɍЂ����������B�@���҂��ĂƂ���A�u�̉͌����牽�������Ă��Ă��Ȃ����v�ƕ����B�v�w�ɂ͐g�Ɋo�����Ȃ��B�q�ǂ���₢�l�߂��Ƃ���A�u���܂�ɂ��킢����������A�n�U���ЂƂ|�P�b�g�ɓ���Ď����Ă����v�Ƃ����B�@���҂���u�Ԃ��Ă��Ȃ����v�ƃA�h�o�C�X���A�Ƒ��͂����ɍĖK���Ēn�U�����ɕԂ����B����ƍЉЂ͎~�B ���Y���l�Y�������ɍ��n�𗷂����L�^�̒��ɁA��q���ɐ��@�쌴����Ƃ̋L�q���݂����B��q�͊肩��15�`16km�쉺�����C�݉����̒n�����B�ΐς݁A�n����������������Ƃ����B �̉͌��͌����Ɩ��y�Ƃ̊Ԃɂ���O�r�̉͂̉͌��ɂ���A�e�ɐ旧�s�K�ȗc�����������e����鍡�̗{��{�݂ł��낤���B�c���̎d���́u��ς�ł͕��̂��߁A��ς�ł͕�̂��߁E�E�E�v�ƕs�K��l�тȂ��珬��ςނ̂Ŗ����̏��̓����o����B�������[���ɂȂ�ƒn���̋S�ǂ��ɓ��݂�������A�c���B�͋~�������߂ċ������ѓ������B������u���y�̕���͂��Ȃ邼�v�ƌ���Ė@�߂ɕ�ނ̂͒n����F�ł���B�S�ǂ��̗�������Ɨc���B�͏��ΐς݂ɂ͂��ݗ����܂łɗ��h�ȓ���ςݏI��Ƃ����B�c�����Đ����������q���B�̖������肤�䕧�̗��ł���B�@ |
|
|
�����_�̉͌� / �V���������s����(���])
�V�����̉͌��Ƃ����ƍ��n���L�������A���E���_���̗��ܓ��R(��������)�̘[�A�o��(�ł�)����߂��ɂ��̉͌�������B �����R�͍O�@��t��C���J�����Ɠ`�����Ă���B�܂̒�������A���ꂼ��ɐΕ����J���Ă���B���̎R�̘[�Ɉ���ɔ@���M�̗�n�Ƃ�����ؕ�(���ق���)���Ɋy�A�̉͌���n���A�����đ�r��̉����ɂ���D�k��(������)���O�r�̐�ɂ݂��ĂĐM���Ă����B�ؕ𒆐S�Ƃ��Ď��͂ɂ͘@���A�o��A���̒r�A�n���J�A���k�ˎR�Ȃǂ̒n�����������Ƃ���A�@����o��o�y�����������̈���ɔ@���Ȃǂ̐Α����͌����ő勉�Ƃ̂��Ƃł���B�܂��A�ؕ̋����ɂ́A�O�@��t�䂩��̉���(����A)������A��������Ƃ��Ĉ��������ŊJ������Ă���B �̉͌��̂���ꏊ�́A�ނ����A��r��̍L���͌��ŁA�召�̐��S���S�����Ă����B�������������Ƃ��Ă����B�l�ʂ肪�Ȃ��₵���A���邢�͕|���ꏊ�ł������B�����āA�x�d�Ȃ��r��̔×��B���a42�N8���̉H�z���J�ł́A8��29����360m�̏W�����J�ɂ���r��̓y�Η����R�Ôg������A9��13���ɂ́u�Ή͌����A�z���v�Ƃ��L����Ă���B�����Ă��̌�̑�r��̃R���N���[�g��ݍH���B�܂����a30�N��̍����H���ɂ���̉͌��o�˂̏��ŁB �̉͌������̏Z����(�s�̌������ł�)�u�����s���]471-1�v�Ƃ���Ă���B����A�s�̕������w�胊�X�g�ł́u�����s�����n�� �m�͌��Α����Q ����9�N10��22���v�Ƃ���B�s�̐E���ɕ������Ƃ���A���A�����Əo����蕪���Ĕ��]���������̂ł���A���]�ł������ł��ǂ�����������Ƃ̂��Ƃł������B�����ɂ��A���A���]�ɂ͓��A�҂̊J�����ł����̂��Ƃ����B �Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ����������Ƃ����ƁA���̊J��A�ЊQ�A�H���̂��߂ɁA�̉͌��̕��i�͈�ς��A�M�̒n�Ƃ������͋C����قlj������̂ɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ𗝉����Ă������������Ǝv��������ł���B �������̉͌��́A�ؕ̊J�c�����c�������̂��Ƃ����B �ܓ��R�Ɠ��l�ɉؕ�806�N�ɍO�@��t���J�����Ɠ`�����Ă���B�����܂ł��Ȃ��j���ł͂Ȃ��B�̉͌��Ɖؕ��W���Ă����炵�����A��m���N(1238�N)�̑�ŏo��36�V���Ď����Ă���A�����͎c����Ă��Ȃ��B ���y�n���@�̒n�}���̉͌��͑�r��̏㗬�ɂȂ��Ă��邪�A���݁A�̉͌��n�����͉����̍��������Ɉ��u����Ă���B�����͎s�̌����Ƃ��Đ�������Ă���B�I�V�ɐ��̂̒n���A�蓙�����ׂĐ������ɕ���ł���B���̔z�u�ł́A�l�́A�����R�Ɍ����ċF�邱�ƂɂȂ�B�ő�̒n���͍����ŁA����1m�A��70cm�B �������ɑ傫�Ȓn����������B�̊Ԃ�4�����͂���̂ł͂Ȃ����B���̉��ɏ�����������ς܂�Ă���B�n�����̉���2�̂̒n�����������Ă���B�ǂ�������k���������Ă���B�傫���ق��͑�����܂߂�����1m85cm�A����80cm�Ƒ傫���B����2�̂̒n���ƕ���ŁA�ƒ납���[���ꂽ�l�`�����ׂ��Ă���B���������Ƃ���ɒu���Ă��鐼�m�l�`�͂Ȃ��Ȃ����͂�����B(���C�������Ƃ����Ӗ��ł��B) ���̌����̋A�肪���A200m�قǗ��ꂽ��������(�{�{��O)�ɒn���Ȃǂ����̕���ł���̂����������B�������ׂɐ^�V����(����15�N6�����c��)�����������Ă���B�����ɓ����Ăт�����B�m���A�n���A�S�A�Ԃ��悾�ꂩ�������������̎q�������̓y�l�`�������Ă���B �ނ����A���̏ꏊ���̉͌��ł��������ǂ����͕s���ł���B���������Ȃ��Ƃ��A�����������̐���Ȓn��ł��������ƁA�e���ɐΕ����_�݂��Ă������Ƃ����������m��̂ɏ\���ł���B ���c���j�́A�����̉͌��ɂ��Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B ���N4�A5���͗��l����������W�܂��Ă���B�����ł͐��{��S���s���B�ǑP���{�Ƃ��Ď��ł͏����k�𑽂�����A�M�k�͂����[�߂��B�ǂ������킯�Ő�ςނ̂����O���m�����m��Ȃ��̂����A���Ԉ��K�̋����͂Ŗ��N���������ɍs���Ă����B �Ō�ɁA�g���새�X�~����(���_��)�����̘b�u�̉͌��v�̊T�v���Љ�����B �_���i�l�̉Ƃ̒j�̎q���S���Ȃ�܂����B�q�ǂ����ɂ��邠�܂�A����������Ɉ�ĂĂ�������_�l���������Ă��̂��A�Ƒ��l�͂����₫�܂��B��e�͔߂���ŋ��������ނ��肽���قǂł����B��e�͘a������ɑ��k�ɍs���܂��B�u�e�̐ς͋S�������Ȃ��Ƃ����B���܂�������̉͌��ɂ����Đ�ςނƂ����B�v��e�͖����̉͌��ɍs����ς݂܂����B���̌�A��e�͏��̎q���Y�݂܂��B���̎q�ɂ͂��܂�킪�܂܂������Ȃ��ň�Ă��̂ŁA�����q�Ɉ炿�܂����B�@ |
|
|
���Ȕ��̉͌��ΐςݍs�� / �V���������s, ���E�Ȕ��s
�n���̊����x�ނƂ���8��7���́u�����~�v�Ƃ����Ă���B���̓�����͎q�������̗���ΐς݂��x�ނƂ����B���̓��̑����A���̐��̐l�Ԃ��q���̗�ɑ����Đ�ς݁A������͂₭�삪�Ɋy��y�ɍs�����Ƃ��ł���悤�Ɋ���čs���邨�~�̍s���ł���B ���̓������̍s���ł���̂ŁA�P�v�I�ɐΐς݂����݂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B����5�����납��O�X�܁X�ɐΐς݂��s���A����1���Ԓ��x�ŏI������B ���̍s������������s���Ă������͕s���ł��邪�A�]�ˎ���ɂ͍s���Ă����Ƃ����B�Ȕ��ł͏��a30�N����Ō�ɐ��ނ������A�n���Z���ɂ���Ăق��ڂ��Ƒ������Ă����B����4�N�ɕ����̓���������A����15�N����͊ό��s���Ƃ��Ďs�����͂��A���킹�āA�s�̕���������͂��Ċ��J�c�싴�̎��ӂŎ{��S(������)���{���s����Ɏ���B ���̍s���͓Ȕ������łȂ������A���c�ł��݂�ꂽ�Ƃ������A���ނ��Ă���B �Ō�ɁA�Ȕ��s�j(1972�`1978�N���s)�ɋL����Ă��邱�Ƃ��܂Ƃ߂Ă������B ���̐ΐς݂�8��7���̑���(���H�Oor���̏o�O)�Ɏq�����߂��̐�ɍs���ΐς݂��s���B(�s�j�ɏ��a20�N��㔼�`30�N�㏉���ɎB�e���ꂽ�Ǝv����ʐ^���o�Ă������A��l�͐����Ȃ��A�q�����v���v���ɍ������ɐς�ł����B)���݂͊��J�c�삪���ɂȂ��Ă��邪�A���ޑO�͎q�������̒n���̐�Ő�ςނ��̂������B�̐ςݕ��́A�����̔N�̐������ς߂悢�A��������Ȃ��悤�ɂ�������ςق����悢�A3�d�˂�ΐς��ƂɂȂ�ȂǁA�����ɂ���Ă��낢��ł���B �܂��A��ɖ���Ă���̂Ő�Ŋ��Ƃ悢�A�͌��̐������ꂢ�Ȏ��ɔ���Ƃ悢(�܂߂ɂȂ�)�A��Ő�������ƒ����H��Ȃ��Ȃǂ̌����`��������B���̓��ɕ�|�������钬��������B�@ |
|
|
�������R�̉͌� / ���쌧�юR�s�厚����
�юR�s�̖����ɏ����R������B��������ɖ����p(���s��)���J�R�����C���̎R���B�����p�͏�������(�������_�^�n���ω��B�V��@)����_�Ƃ��āA�ˉB�A�F��A����A���R�A���R�A�R���A�����̎��_�����������J�����B�����珬�������͔��������ƌĂꂽ�B����������͂����܂œ`���ł���A�����ɂ͕�������ɊJ���ꂽ�悤���B ���ǎR�̒����ɏ������Ƃ���ꂽ�W��������B�����_�Ђ̗��ЂȂǂ�����B�n�������͊w��m����߂Ă������A���̌�C����(���m��)�����𑝂��Ă������B���������ɂ͔эj�A�ˉB�A�����͉��M�Z�O�R�Ƃ��k�M�Z�O����Ƃ���ꂽ�B�������͒������ɗ������ɂ߁A�����̎��@���u����A�m���Ȃǂ�300�l�ȏ�������Ƃ����B�쒆������̉e���ʼn��Ђ������ĎR���Ď�����Ƃ����ߌ������������A�]�ˊ��ɍČ����ꂽ�B�����ɓ����Đ_�������̉e�����āA����33�N�ɏ����_�ЂƉ��߂�ꂽ�B �R�[�̈�̒�������m���傻���ĉ��Ђ͈�{�̓��Ō���Ă���B���̓����疭���R�𐳖ʂɁA��Ȑ���ቺ�ɖ]�ނ��Ƃ��ł���B�����R�͐M���E���v��I�ɔz�u�E�`���������@���n�悾�����̂��B �����W�����珬���_�Љ��Ђ܂ŎQ����o�����B�C���̓����B����1500���[�g�����v1���ԁB�Q���̂͂��߂͎���300�N�Ƃ���180�{�̐�����600�`700m�قǑ����Ă���B���̊Ԃ͗]�T���B�����������ꂽ�Ƃ��납��{�i�I�ɎR��o��B���������A�Ƃ�ł��Ȃ�����ǂ������B �̉͌��͉��Ђ܂Ŏc��400���[�g�����̒n�_�ɂ���B���ЂɌ����āA�Q���E���͊R�ɂȂ��Ă���A�ΐς݂�����B�Q�������͎R�ŁA�����琔���[�g�������n�_�ɒn�����(����90cm�̗���)���J���Ă���B�̂̔����͌͗t�Ŗ�����Ă����B�n���̖ڂ́A������ʂ�l�X���₳����������Ă���悤�Ȋ����ł������B ���Ђ̗��ɑ�ƒr������B���̐��������̂��_�̂��Ƃ����B�����M�Ƃ����B ��k�����̊G�}�ɒn���J�ƌĂ��n��������B���݁A�ω����O�ɘZ�n�����J���A�n���Ɋy�G�}(�]�ˎ���)���`���A�S�̓`���������`�����Ă���B�Q���̌���Ɩ��Â���ꂽ���ɂ́A�����p�^�O�@��t���x�������Ƃ����`��������B������ɂ͈����������A�s����ɂ͕s���������J���Ă���B�̉͌��ɂ��ẮA�g�������������Őςݏグ��ƁA�������Ƃ��E�E�E�h�ƃK�C�h�}�b�v�ɋL����Ă���B����ɂ��Ē��ׂĂ݂����A����(����)�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B �̉͌��Ƃ����ƒn���a�]�̔߂����C���[�W����ʓI�����A�����R�̏ꍇ�͂���Ȉ�ۂ͂܂�łȂ��B�Q���ɂ���������`���I�Ȑ̂ЂƂƂ����ʒu�Â������������Ȃ������B �����R�ɂ��`��钌���_���Ɠ��l�̐_���������_�Ђɓ`����Ă���B�����ē�(�ē�)�_���Ƃ����āA7���I���瑱���Ă���B���Ă͏C���҂��s���Ă����B���݂�3�N��1��A�W���̏Z���ɂ���čs���Ă���Ղ肾�B���Ђł͂Ȃ������W�����ŊJ�Â���Ă���B�@ |
|
|
�����O���̉͌� / ���쌧����s�ԕ�29, ���O��
��M�B����̋F����Ƃ��Ēm�����ώR���O���B�J���860�N�B�@�h�͓V��@(�o�T�͖��@�@�،o�A���{�R�͔�b�R���)�B���̌Ù��̈�p���̉͌�������B���o�����̂��A�N�����肵���̂��s���ł���B ����1.38m�̐e�n���͍]�ˎ��㒆���̐H�F�牮�厡�̍�ɂȂ�Ɠ`�����Ă���B(���O���ɂ͒厡�̍�ƂȂ�Ε������̂ق��ɂ����̂���B)���̐e�n���̎��͂ɐ��\�̂̎q�n����ω���������ł���B�S����60�̂قǂ����邾�낤���B���ɂ́A�����҂⓶�q�E���̖��������̂�����B���a�A�����̂��̂�����B 2�Ύ��̖��Ɛ��q(�݂���)������ō��܂ꂽ��̂̒n�����������B���̂ŖS���Ȃ������̂ł��낤���H���Ƃ������Ȃ��C�����ɂȂ�A���炭�������Ƃ��ł��Ȃ������B �����̒n���Ȃǂ́A�قڂ��ׂĂ����悻���̕��p�������Č����Ă���B���d�͐���w�ɂ��Ĕz�u����̂��悢�Ƃ���Ă���Ƃ������A�����n�������l�̎�|�ł̔z�u����Ă���̂��낤�B�@ �@ |
|
| ���F��O�R�ƐM�� | |
| ���͂��߂Ɂ@ | |
|
�I�B�F��̌F��{�{�A�V�{�A�ߒq�̌F��O�R�͌×����M�a�O���̐M���W�߁A���q���ɂ͊�i���ꂽ�����͊֓��A���C�A�ɐ��A�ےÁA�d���A���O���A19������31���ƂȂ�傢�ɗ��������B�������A�����������퍑����ɂ����Ċe�n�̑����͍ݒn�y���̎x�z���ɓ���A�o�ϓI��Ղ��s����Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B�헐�ƎЉ�̍����ɂ��A�P��I�ȍ����Ǝv��ꂽ���З̑����̌o�c�������s���Ȃ��Ȃ�A���ɂ̈ێ��E�C�U�͍���Ȃ��̂ƂȂ�B����Ȏ��A�O�R�̎������ɑ��݂��Ă������E�R���炪�������߂��芈���Ȋ��i�������s���A���̎�r���O�k(1)�ɔF�߂��ĎГa�����̌����E�ċ��E�C�U��S���悤�ɂȂ����B�����d�ˑg�D�����ꂽ�ނ�́A���ɓߒq�R�ł͎R���̖{�Ћ߂��ɖV��=�{�莛�@���\����悤�ɂȂ��Ă����B
���̂悤�ȌF��O�R�̖{��g�D�̌`���ɂ��āA����́u��ɗ��n�C�j�v�Łu���̔N������肷��ɂ́A�Ȃ��j���̏N�W�ƐT�d�ȋc�_��ςݏd�˂�K�v������v(2)�Ƃ��A�l���P�ƂŊ������Ă����Ɛ��������13���I�ȍ~�̎j�����Љ��Ă���B�����ŁA�F�슩�i�����̎j�����m�F���Ă݂悤�B �@ |
|
|
���u�����L�v(3)
���m���N(1201)10��15���� �F��{�{�̐_��̓�����ł���A���S�剤�q�Ђ̔�u��u�얳�[�v �ߎ��������S��h��얳�[�� ���u�F��w���L�v(4) ���i34�N(1427)10��1���� / �ߒq�̔�u��u�����i�̓�v �����ɓߒq�̌�t�̖V����A����ɂĂ��������������A����̌�₩�Č䂽���A���{�ɂĂ͂��߂������X�A��X�߂���A�����ɋ����i�̓�̐S����(�u)�ӂ�������A������薲�̍��Ƃ��₠��ċ����鈢��ɂ̖�������������A�l�M�S���������Ă�����(�q��)���Ă܂�(��)��n�A�����̘Z���̒����A��ɗ��̗O���Ă܂��܂��悵�A���̔N���\���ւ�A���̂���(�x)�����������(�q��)���Ă܂�(���)�ɁA���ɂ������(�A��)�̂���(�@)���A����(��)�����̂́A���R�Ƃ��Ă��܂�(����)�o������A�������܂ɂ��ӂ���(�s�v�c)�̎��A����₤���镨����A��ɓ��Č�A�ߒq�̌�R�ɒ��܂��܂��A ���u�䓒�a����L�v(5) ����14�N(1482)4��17���� / �͂��A�Ƃ��厛���A���܂̂̌�ق���(���)�̎��\�����B�䂽��(����)���ЂĂ��������B ����16�N(1484)9��5���� / ���܂̂̂ق�(�{�{)�̌�ق���(���)�̎��A����낵(�ØI��)�\����āA�䂽�����������B ����3�N(1491)6��9���� / ���܂̂̌�ق���(���)�̎��A�\�����̐\�ƂāA�Ȃ��͂�(����)�Ƃ��\���B���]��[���ɂ��������āA�䂽�����ЂĂ��������B �V�����N(1532)8��10���� / ���܂̂̂Ȃ�(�ߒq)�̂����(���c)�ȂƂ�����\�����A���₤�Ƃ�(�s��)�F�X����ɂ��āA��l����(��)�̎��\�悵�B�܂Ă̂�����(�������H)�\�����B �O��4�N(1558)1��23���� / �����(���C)�����[�����A���܂̂̂�������l�����̎��\�A��S����悵��Ԏ�����B ���u�����@���L�v(6) �V��11�N(1542)3��5���� / �F����q�����������L�A��x��x ���N3��6���� / �q����A�L�A���܂̂̂�����(�F��̍���)�A��쏯�ޖؒ� ���N�[3��19���� / �F��\���C������ ���u���p���L�v(7) �O�g�������S��l��ɗ��A�F�싍�ʓA���ߒq�单����A�����܁A�M���\�D�������A��������A����l���V���]�V�R�\�A�������]�X�B�@ |
|
|
��u��E�얳�[�A�����i�̓�A�\�����A�F��̍����E�q���A�F��\���E�C���A���E���S��l���A�����P�Ƃ̊��i���W�܂�g�D�����ꂽ�����ɂ��āA����́u�ނ�̑g�D�Ƃ��Ă̑��݂͌c���N��(1596�`1615)���납��j����ɂ݂��͂��߂邱�ƂɂȂ�A���������ČF��O�R�̖{��g�D���ꊇ���Đ����̂�16���I��������17���I�����ł������ƁA�ꉞ�̌��ʂ������āE�E�E�v(8)�Ƃ���Ă���B�R�{�B�����́u�F��{�菊�́A���������E������I�E�L�͈͂ɍs���Ƃ���̎O�R���̑g�D�̂Ƃ��āA15���I��������A�V�s�E�̊��i�炪�g�D������A�ނ�̊��i�E���c�̎��тƊ���������Ղɐ����E���W�����̂ł��낤�B�v(9)�Ƃ���Ă���B
�����̐������킹�l����A�F��E�ߒq�̖{���13�`14���I�ɂ͌X�̊����ł��������̂�15���I�����ɂ͂��̏W�܂肪�g�D������A16���I������17���I�͂��߂ɌF��O�R�{�菊�Ƃ��Đ��������Ƃ����邾�낤�B �O�R�e�Ђ̋ߖT�ɏZ���A������������i���s�����ҒB�́u�C���ҁv�u�R���v�u���v�u�����v�u�\���v�u��u��v�u�����i�v���ƌď̂���邪�A��������́A�ނ�̐M�`���ߒ��Ŏ������ꂽ�ł��낤�A�����̏@�h�F�Ƃ������ׂ����̂��������Ȃ��B��́A�ނ�͌����̂ǂ̏@�h�ƊW���A���̉e�����Ă���̂��낤���B�܂��A�{����͂邩�ȑO�A�F��E�ߒq�̊J�n���ɂ��̐M���`������ߒ��Ō��������������Ɋւ�����̂��A�F�쌠���ƎR�сE���ďC�s�̐��n�ɂǂ̂悤�ȏ@���҂��W�����̂��A�Ƃ����̂��C�ɂȂ�Ƃ��낾�B �u�F��ʓ���X����v���ɂ��A�{�{�E�V�{�E�ߒq�̎O�R�������F��ʓ��̊������L�^����Ă���̂�10���I����14���I�ɂ����Ă����A���݂̂Ƃ���A�ʓ�����Z�������@�̑��݂͕s���ŁA�V��E�^�����̎��А��͂ƂȂ��鎛�@���Ȃ������悤���B(10)�F��ʓ����������Ă�������̌F��O�R�ɂ��āA�ܗ��d���́A�u���̂悤�ȌF��ʓ��ƌF���O�͌F��C�������c���`�����Ă����̂ł��邪�A�����ɎO�R�M�̓��ِ�������Ƃ�����B���Ȃ킿�O�R�M�͐_���ł��Ȃ���Ε����ł��Ȃ���O�̏@���������̂ł���B��������b�R�⍂��R�Ƃ͂����������c�g�D�������A�ȑѐ��P�̔��m�����̕ʓ��ƂɂЂ�����ꂽ�R���̍��ߕ��m�c�ƁA�S���I�ȎU�ݎR���̊��i�g�D���琬���Ă����Ƃ����悤�B���Ȃ킿�ʓ��͌R���I�ɂ͕��m�c�̓����ł���A�@���I�ɂ͌F�쌠���̖��ɂ����ĎR��������F��C�����̊ǒ��ł������킯�ł���B�������o�ϓI�ɂ͐_�̑������x�z���A����ȋM���̊�i�{���������[����̂ł��邩��A���[���b�p�����̖@���̂悤�ɋ����Ƒ��������킹���匠�҂ł������B�v(11)�Ɖ������Ă���B���̂悤�Ȍܗ����̎w�E�́A�F�쌠���𒆐S�Ƃ����M�`�ԂƑg�D�̓Ǝ����܂��Ă̂��̂��낤���A�����������m�F����ƁA���̐M�̓����́A��͂�A���������̋����𑽕��ɐۂ����Đ����������̂ł͂Ȃ������낤���B �F��E�ߒq�̐M�����̂Ɍ������Ȃ��u�C�����v�ɂ��āA�a�c���́A�u�C�����Ƃ́A���{�×��̎R�x�M�ɁA�����⓹���I�M�������A����Ɍ�ɂ͉A�z���̉e�������āA10���I�㔼����11���I��ɐ��������@���ł���B�R�т�R�x�ŏC�s���邱�Ƃɂ��A�_��I�Ŏ�p�I�Ȕ\�͂�g�ɂ���̂��C���ł���A�����B�������l���C���҂ł���B�����ȍ~�ɎR���̌ď̂����܂�邪�A����ȑO�͌��҂Ƃ�ꂽ�B�`�����`10���I�㔼����11���I�ɏC��������������B���������̓����̌��҂����͎R�x�ŏC�s���A���͂��m���ł��������Ƃɒ��ڂ��Ă��������B�ޗǎ���ɂ́A�R�тŏC�s����D�k�ǂ������B�������������E����̎j���ɂ݂���̂͂��ׂđm�ł���B�v(12)�Ƌ�������Ă���B ���䓿���Y���́A�u���n�I�ȎR�x�M����Ղɗ쌱�����߂閧���Ƃ̏K���ɂ����Đ��������C�����v(13)�Ƃ���Ă���B �{�Ə����́A�u�Ƃ���ʼn䂪���̌×��̏@���ł́A�R�x��C(�C��̓�)�Ȃǂ̐��n�𗢂���q���āA�����ɂ���_��̉�����F��`�Ԃ��Ƃ��Ă����B���̂��Ƃ́A�����������n��q������ꏊ�ɍ��J��Ղ�ÎЂȂǂ����邱�Ƃ���������炩�ł���B�����Ă��̐��n�̐_���R�[�̎Ђɏ������J�邱�Ƃɏd�_���������@����_���ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���B����ɑ��ďC�����́A�ϋɓI�ɐ��n�ɓ����ďC�s���A�����̐_��̗͂�g�ɂ��Ċ�������@���҂𒆐S�Ƃ��Ă���B��������A�䂪���×��̐��n�M�̂����A�R�[���琹�n��q����Ƃ����`�ԂɓW�J�����̂��_���ŁA�ϋɓI�ɐ��n�ɓ����Ă��̐_��̗͂��l�����āA��������ƂɊ�������̂��A�����̌��҂�C���҂ł���Ƃ������Ƃ��ł���̂ł���v(14)�A�u�ꌾ�ł����ΏC�����͋ߐ����܂Ő��x�I�ɂ͕����ɂȂ��Ί���`�œW�J���Ă����ƍl������̂ł���v(15)�Ƌ�������Ă���B �e���̋����܂���A���{�×��̐��n�M�Ƃ��̐��n�ɓ���쌱�����߂閧���Ƃ̏K���ɂ�萶�܂ꂽ��O�̏@�����A�F��݂̂Ȃ炸�e�n�̏C�����ł������B���̌`���ƓW�J�ɂ͌����������傫����������Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ邾�낤���B �����ŋC�ɂȂ�̂��A�C�����`���̑傫�ȕ������߂Ă���u�����v�̑̌��ҁA�`���҂͒N�������̂��B�R�x�ŏC�s���A���͂������̑m���Ƃ͒N�������̂��B�܂��A�ߒq�R�ɖ{�肪��������͂邩�ȑO�́A��������̓ߒq�R�ɏZ���A�F��ʓ��̓����Ƃ͈�����悵�Ȃ���ߒq��̏C�s�𒆐S�ɓƎ��F��ۂ��A���R�̊Ǘ��E�^�c�ɂ��������O�k�̏@���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��A�Ƃ������Ƃ��B�{��ɂ��Ă��A�O�ɏ������悤�ɐ������̏@���͂ǂ��������낤���B �����܂ŕM�҂̈ӂ̂����ނ��܂܂ɏ����Ă��܂��A�킩��Â炢���͂ƂȂ��Ă��܂����̂ŁA���߂āu�m�肽�����Ɓv�����Ă������B �E�F��E�ߒq�̊J�n���ɂ����錰�������̊ւ��B �E���̎���A�ǂ̂悤�ȏ@���҂��K��C�s�����̂��B �E�R�x�ŏC�s�����͂��m���Ƃ͒N���B �E�C�����̌`���ɏ��Ȃ���ʖ������͂����������̑̌��ҁA�`���҂͒N���B �E�ߒq�R�̏O�k�̏@���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B �E�{��g�D�̎�̂ƂȂ�u�C���ҁv�u���v�u�����v�u�\���v��̐M�`�����Ȃ����@���B �C�����̐����͂����悻10���I�㔼����11���I�Ƃ���Ă��邪�A��������͏��������L���āA�������犙�q�̓�̎����w�i�Ƃ��A�F��E�ߒq�ɂ�����@���҂ƏO�k�E�{��̏@����m��肪��������߂āA�e�핶���ɂ�����Ȃ�����j�������̂ڂ��ĊT�ς��Ă݂悤�B |
|
| ��1�@�u�F�쌠���䐂瑉��N�v�Ɓu�F�쌠������������a�������L�v�@ | |
| �F��̎�_�ƎO�R�̋N����m�镶���Ƃ��āA��������̒����N��(1163�`1164)�ɍ쐬���ꂽ�u���������v�̕����Ɉ��p�����u�F�쌠���䐂瑉��N�v������B �@ | |
|
��(1)�@�F�쌠���䐂瑉��N
�F�쌠���䐂瑉��N�]�B ���̍b�ДN���T�V��R�T���q�M�p�Ֆ�(1)�B���{���������q�T�R��J�~���B���[���p�ޗ������T�B�����O�ژZ���ޗ��m�V�B�V�����z�B���܃��N���o�V�B��ߔN�ɗ\���T�ΒȔT���m�n���B���Z�N���o�V�B�b�q�N�W�H���T�V�߉H�T���m�n���B���Z�ӔN�߁B�M�ߔN�O�����O���I�ɍ����R�S�ؕ��R�T���T�C�T�k�T�ݔT�ʓߖؔT���_��T���ؖ{�n���B���\���N���߁B�M�ߔN�O�����O���F��V�{�T��_�_����~���B���Z�\��N�M�ߔN�V�{�T���_���{��T�ДT�k�Ε��T�J�m����Õ�×��B�n���ʉƒÔ���q�o�\�B��F�Ж�B���\�O�N���ߜV�B�p�ߔN�{�{�哒����ʖB�O�{�T���O���B���`�m�V�V�~���B���ӔN���o�B�M�Д_�N�Α��͔T��͓��T�Z�l�F�암��^��y�]�����B�������ړޗ��ˁB�Ւǐq�V�Α��͉���s�B�����T�Չ����V�s�m�B�哒���s�V�B�����T��ʔ_�ؔT�{�m�������a�B������V�H�B���؉��m��h���o�V�B�ؔ_���������t�V�B��\��B���������V�ؔT���m�g�䍿�~�\�m�B�������m���]�B����g�F��O�������~���\�B��Ќ��ؐ����F�y�\�B�������җ��������y�ޖ��\���z�]�X�B (�Ӗ�) �͂邩�̂̍b�Ђ̔N�A���̓V��R�̒n��_�E���q�M(�W)�����A����(��B)�̓��q�T�R���F�R(�p�F�R�E�������A�啪��)�ɓV�~�����B���͔̑̂��p�`�̐����̐ŁA�����͎O�ژZ���ł���B �ܔN��̕�߂̔N�A�ɗ\���̐ΒȎR(���Q�������s�A�v��������)�Ɉڂ�ꂽ�B�Z�N���o�����b�q�̔N�ɂ́A�W�H���̗V�߉H(�@�߉H�R�E���Ɍ��삠�킶�s)�̕�ɓn��ꂽ�B���ꂩ��Z�N���߂����M�߂̔N�ɁA�I�ɍ����K�S�ؕ��R�̐��̊C�̖k�̋ʓߖ̕��̏�̏��ؖ{�ւƓn��ꂽ�B�\���N��A�M�߂̔N�̎O����\�O���A�F��V�{�̓�ɂ���_�q�R�ɍ~��ꂽ�B ����ɘZ�\��N���o�����M�߂̔N�A�V�{�̓��A���{��Ђ̖k�ɂ���Ε��J�Ɋ��������A�������ʉƒÔ���q�Ɛ\����A��F�̎Ђ��J��ꂽ�B�\�O�N���߂����p�߂̔N�A�F���㗬�E�{�{�̑��(������̂͂�)�̎O�{�̟J(������)�̖̏��ɁA�O�̌��̎p�����ēV�~�����B���ꂩ�甪�N��A�M�Ђ̔N�A�Α��͂̓�͓��̌F�암��^��Ƃ��������̗t�����ڂ̑咖��ǂ��ĐΑ��͂�k��A�{�{�̂������ɍs���������B�ǂ����߂����͟J�̖̉��œ|��Ă���A���Ɏ���ł����B�t�͒���H�ׂ���A���̂܂ܑ���̟J�̖̉��ň����߂����Ă����B���̔ӁA�̏��Ɍ����������Ă���̂��������̂ŁA�u�ǂ����Č������藣��Ė̏��ɂ���̂��v�Ɨt�͖₢�q�˂��B���́u��͌F��O�������ł���A��Ђ͏ؐ����F�Ƃ����A�̌��͗��������ł���v�Ɠ�����ꂽ�Ƃ����B �v���N��(1145�`1151)�A�b���E���������͌F�쌠���̗쌱�����������Ƃ��āA����̋��ČF��{�{�ɔ��㑑����i�B���̌F��ʓ��E�X���́A���㑑���F��{�{�̑����ł��邱�Ƃ�����牓��(�ڂ���)�𗧂Ă��B�Ƃ��낪�A����2�N(1162)�ɍb���ƂȂ����������d�́A�O��̎�茈�߂�����I�ɖ�������s���ɏo��B���d�͖ڑ�̒������O�����n�ɔh���B�b��̍��̊��l�E�O�}�琭��ƍ����������O�́A�R���𗦂��āu�����v�ɏ�荞��牓����P���B�����I�ȔN�v�̎旧�āA�u�����v�̐l�X��_�l�ւ̖\�s���d�˂��Ƃ����B ���̎��Ԃɑ��A�{�{���͒���ɑi���o��B�������N1163)�A�ْ�𖽂���ꂽ���@���m�̒����Ɨς́A���Ƃ̌o�܂Ɓu�F�쌠���䐂瑉��N�v�����ƂɁA�ɐ��̐_�̂Ɠ��̂ł���F�쌠����N�Ƃ������Ƃ͍߂ɂȂ�Ƃ��āA�i�Y�Ƃ���悤���\(��)�����B���́A�ɐ��ƌF�삪���̂ł���A�Ƃ������Ƃɂ��Ă͓����͌���A�L���҂̈ӌ��\�q���������A���ʁA�������d�͈ɗ\�ɔz���A�������O�͓�������Ă���B ���́u�I�ɌF��_�ЎЗ̔��㑑��p�����v�̉ߒ��ŁA�ْ�̂��߂ɒ����ꂽ�������W�������̂��̂��u���������v�ƌĂ�Ă���B�u�F�쌠���䐂瑉��N�v�́A����Ώd�v�����ƂȂ邾�낤���B�@ |
|
|
��(2)�@�I�ɍ��E�F��ƖL�O���E�F�R
�u�F�쌠���䐂瑉��N�v�ł͖`���A�V��R�̉��q�M(�W)���������̓��q�T�R(�F�R)�ɓV�~�����Ƃ��邪�A��������A�×�����̗��ł���F�R(���݂̉p�F�R)�̉��N�ƌF��̉��N�Ƃ̊W���w�E����Ă���B�F�R�͍]�ˎ���ɂ͖V��800��3000�l�̏O�k��i���A��F�R�O�甪�S�V��Ƃ���ꂽ�Ɠ`������B �ܗ��d���́A�u�����炭�w���������x�́w�F�쌠���䐂瑉��N�x�͕F�R�̉��N�����Ƃɂ���ꂽ�̂�������Ȃ��B����12���I�̓`���͌F��ƕF�R�̓��[��������́A�F�R�̕����F����Â����Ƃ��咣�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B����������͕F�R���F��̎P���ɓ����Ă���̂��̂ł��邩��A����ɂ���āA�F��̎x�z����ʂ��o�����Ƃ������̂Ƃ������B�v(2)�Ƃ���A�{�Ə������u�F�R���F��̓V��C���̉e�����ɂ��������Ƃ����������B�v(3)�Ǝw�E����Ă���B �ł́A�F�R�͂��A�F��́u�P���ɓ��v��A�u�e���v����悤�ɂȂ����̂��낤���B�ܗ����́u�F��R�ʓ���X�L�v��7��ʓ��E���c(�N��2�N�m965�n�ʓ���މB�����Ƃ����)�ƕF�R11���`�����B�E���c(���O3�N�m1006�n�v)�����ԓI�ɐڍ����邱�Ƃ��瓯��l�̉\��������Ƃ��āA�F��ʓ��̑��c�͕F�R���F��̎x�z���ɂ������Ƃ�ړI�Ƃ��ĕF�R�ֈڂ����Ɛ�������Ă���B�����A�u�F��ʓ���X����v(4)�͌㐢�ɕҎ[���ꂽ���̂ŁA�ʓ��̋N�����Â������邽�߂̍�ד����w�E����Ă��Ďj���Ƃ��Ă̐M�p���ɖ�肪����(5)�A���c���F�R�ɈڏZ�����Ƃ̐��́A���i�K�ł͐��_�̈�ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ����B �F�R���F��̎P���ɓ����������ɂ��āA���j�j�����痠�t��������Ƃ��Ă͋{�Ǝ�����������悤��(6)�A�㔒�͏�c(1127�`1192)���������E�d�����q�ɖ����ċ��s���R�̖@�Z���a�ɒ���Ђc�����A�i��N(1160)�ɌF�쌠�������������V�F��Ђ��n������Ă���̂��ƂɂȂ邾�낤�B���̎��A�F�R���܂ޏ����̑���28�������V�F��ЂɊ�i����Ă���B���̐V�F��Ђ̏��㌟�Z�ɔC����ꂽ�̂�4��F��O�R���Z�̊o�]���B�ނ͐m��2�N(1152)���玡��4�N(1180)�܂ŎO�R���Z�̔C�ɂ��Ă��邪�A���Z�̊o�^�Ȃ珔���̗�R�̉��N��m�闧�ꂾ�B�̂Ɍܗ����́A�u�����炭�w���������x�́w�F�쌠���䐂瑉��N�x�͕F�R�̉��N�����Ƃɂ���ꂽ�̂�������Ȃ��v�Ƃ̐��͐��������̂��Ǝv���B �����A�ܗ����́u�F�쌠���䐂瑉��N�v�́A�F�R���F��̎x�z���甲���o��ׂ��쐬�����A�Ɛ������Ă���悤���B����ɂ��ẮA����2�N(1162)�ɔ��������b�㍑���㑑�̎������A�V�F��Ќ��Z�ɔC����ꂽ�o�^�������m��Ƃ���ƂȂ����F�R�̉��N��������āu�F�쌠���䐂瑉��N�v������A�F��ʓ��E�X����i�삵���Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B �F��ƕF�R�̊ւ��ɂ��ẮA�ܗ����Ɠ��l�A�V��ʎ����w�E����Ă��āA���̍l�@�͑����́u�F��w�v����҂��[��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B(7) �V�쎁�̐���⋭����Ӗ��ň�_��������A�u�F�R���L�v�̉����ɂ́u���ی��N(1213)ᡓю��������v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���A�����͊��q����̎ʖ{�ł��邱�Ƃ���������A�W�̍l�@�ł����l�ɏЉ��Ă���B(8) ���q����̋敪�Ƃ��Ă͎��i4�N�E����2�N(1185)������Ƃ���邱�Ƃ���A�u���������̒������N(1163)���A���ɏo���w�F�쌠���䐂瑉��N�x�̕�����ł���o�^�̖ڂɁw�F�R���L�x�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�ނ���w�F�R���L�x�̕����w�F�쌠���䐂瑉��N�x�������ꂽ�̂ł͂Ȃ����v�Ƃ̋^�₪�悳��邩������Ȃ��B �������Ȃ���A�u�ォ����ƂȂ��������ł����̍��ɏ����ꂽ�Ɛ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͗e�ՂɎ�m�ł��邱�Ƃł���A�u�F�쌠���䐂瑉��N�v�Ɓu�F�R���L�v�͂ǂ��炪��Ōォ�Ƃ������͕�������ׂ������ł́u�f��v�ł�����̂ł͂Ȃ��A���̏ꍇ�A�O��̏��܂��Đ������ׂ����Ǝv���B������x�A�v�_���܂Ƃ߂Ă݂悤�B �E�v���N��(1145�`1151)�A���������͒���̋��ČF��{�{�ɍb�㍑�̔��㑑����i�B �E�F��ʓ��E�X���͔��㑑�ɑ����ł��邱�Ƃ�����牓���𗧂Ă�B �E�m��2�N(1152)�A�F��O�R�E4�㌟�Z�Ɋo�^����C�����B �E�i��N(1160)�ɐV�F��Ђ��n���B �E�F�R���܂ޑ���28�������V�F��ЂɊ�i�����B �E����2�N(1162)�A�I�ɌF��_�ЎЗ̔��㑑��p�������u���B �E�{�{���͒���ɑi���o��B �E�������N(1163)�A�����Ɨς́A���Ƃ̌o�܂Ɓu�F�쌠���䐂瑉��N�v�����ƂɊ��\����B �E�L���҂̈ӌ��\�q���������A�{�{������i����ꂽ�������d�͈ɗ\�ɔz���A�������O�����������B �E����4�N(1180)�A�o�^�͌F��O�R���Z��ޔC �E���q����(1185�N��)�A�u�F�R���L�v�����ʂ����B �u�F�R���L�v �v�����A�̎ҝe�����V�����A�n����V���ዋ���A�y�u���y�����A�~�m��瑘a���V��A�����d�����܌��V��A�b�Ѝΐk�U���V��R���q�W���Փ��Q�A��Ӑ[�����V�V���g�𓌓y�V�_���A����D�u�e�ݖL�O���c�͌S�L��×W������M����B���ݔV�������t���_�؏h�A�n�喾�_�̋����V�R�s��؏h�Aৌ����������A���ꖜ�\���������q�A�ލ��t�Ԏ��ؗ߉g��A��䢎}����莀�ΘI�`�A�����������o�F�R�V���A�n��_�k�R�O��O��Z����������V�ԁA�b���R�V���w�������A�I�ڋ���R�I�A�������N���\�Εq�B�V�c��F��B ����瑔V�n�A�攪�p�������[�O�ژZ���`�A�ʎ�A��J�~���������V��ꌕ���A�㌩�t�����A�l�\��ӌA�e�䐳�[����������V������u�V�A���ꖜ�\���������q����B ৎO�������Җ@�[���[���[��A����瑎O�ԋ��~���ގO����s�v�c��B �`�ȉ��A�{�����` �F�R���L��|�@���A�ό����L�A�זڈ���V�]�X �{�]���ی��N(����O)ᡓю������� ���R�V���n �������N�h��q�ґ�t��a�������P�Y���o�Җ� ��B��O������S�����R�_�{�� �@��m�s�J���V�c�w�@��(9) ���Ƃ̌o�܂���Ղ���A�{�{���̏��i�Ɂu�F�쌠���䐂瑉��N�v�����Ȃ���ʖ������ʂ����Ă���Ƃ����A����ȑO�̕����ނɁu�F�쌠���䐂瑉��N�v�����p���ꂽ��A�F��J�n杂����`����Ă���`�Ղ��Ȃ����Ƃ���A�u�F�쌠���䐂瑉��N�v�͔��㑑��p�������đn�삳�ꂽ�Ƃ̐��������藧�Ǝv���B �ł́A�������Ƃɍ��ꂽ�̂��Ƃ����A�ގ��̕����Ƃ��ẮA �u���̍b�ДN���T�V��R�T���q�M�p��(�F��)�v�u�b�Ѝΐk�U���V��R���q�W���Փ��Q(�F�R)�v �u���{���������q�T�R��J�~��(�F��)�v�u�����������o�F�R�V��(�F�R)�v �u���[���p�ޗ������T�B�����O�ژZ���ޗ��m�V(�F��)�v�u����瑔V�n�A�攪�p�������[�O�ژZ���`(�F�R)�v ���A����狤�ʂ̃L�[���[�h�����u�F�R���L�v���������A���l�̂��̂́A�ق��ɂ͌�������Ȃ��B�̂Ɂu�F�쌠���䐂瑉��N�v�́A�V�F��Ђ̑����Ƃ��ĕF�R����i����A���̊J�n杂�m�����F��O�R���Z�炪�����������A�i�ב�Ƃ����L���Ȃ��Ƃ��瓱�����A�F��̊J�n杂Ƃ��Đ����������\���������A�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�������u�F�암��^��v�Ɍ�����t�̘b�����A�ݒn�ɓ`���`�����������Ȃ���쐬�����Ǝv����B�����āA�O�R���Z�炪�m��Ƃ���ƂȂ����F�R�̌Â�����̓`���͊��q�����ɖ��������ꂽ�A�ƍl���Ă���B�@ |
|
|
��(3)�@�F�쌠������������a�������L
�ߒq�R�̊J�n�́u�F�쌠������������a�������L�v�ɁA���̓`�����L�q����Ă���B �u�F�쌠������������a�������L�v �F���V�c��F�A�V�c���q�B��T�O�\�l�h�K�A�����\�O�N�A��N�S��\�B��a���t��r�S�{�䍿�B���䎞�A�V�{�F��A���F�O�D���B�t���^�~�ˌF�ǁA�����k�R�Ώ㌻�O�����B���V���A���^��(�܂�)�̋|���Bৗ��`���l�o���A�O�����㑢���ƁB�F���V�c�䎞�A��ߍA�ߒq�ꌰ�����ω��B�㌎����A�R��A���`���l��j�\�����B �F���V�c�h�K��(�I���O450)�A�F��V�{�ɎO�C�̌F������t�̐��^���ǂ��ƁA���k�̊��ŎO�̋��ƂȂ����B�����ɃC���h���n���������`���l�����āA���^�Ƌ����K�����A�����J�����̂��n�܂肾�Ƃ����B�u���L�v�v�ɂ́A�����Ă�����̘b���ڂ����Ă���A�F���V�c��ߍ�(�I���O423)�A�ߒq��ɐ��ω������ꂽ�B�����N��9��9���A���`���l���R��ŌF��\��������J�A���ꂪ�ߒq�R�̋N���Ɠ`�����Ă���B �ߒq�̔@�ӗ֓��A���݂̐ݓn���̑n���ɂ��Ă��A���`�ł͗��`���o�ꂷ��B���`���l����C�s�����Ă����Ƃ���A�����腕��h�����������̔@�ӗ֊ω����������B���`�͊ω����𑐈��Ɉ��u���āA���[�̋s��ӂ�Ȃ������B���`�̎����A��a�̐�����l�����قǂ̔@�ӗ֊ω������݁A�ٓ��ɗ��`�����̋��������A���F�����Ă��Ƃ����B�@ |
|
| ��2�@�u�V���i�������v���ځE�哯���N�̑��������Ɓu���쎮�_�����v�@ | |
|
��(1)�@�V���i������
�V���_��2�N(766)�A�F�어�{���_�Ƒ��ʐ_(�V�{)�Ɋe�l�˂̕��˂��^����ꂽ���Ƃ��A�u�V���i�������v�Ɏ��ڂ��ꂽ�哯���N(806)�̑��������ɋL�^����Ă��āA���ꂪ�F��̎�_�Ɋւ���ŌÂ̎����Ƃ����B �F�어�{���_�@�@�l�ˋI�Ɂ@�@�V���_���N��[ ���ʐ_�@�@�@�@�@�@ �l�ˋI�Ɂ@�@�_���N�㌎���l����[ ���ʐ_�͐V�{�����A�F�어�{���_�͖{�{�E�ߒq�̂ǂ�����w���̂����͂����肵�Ȃ��B�������A��ɓߒq�̎�_�͌F�어�{���_�Ƃ���Ă���B����ɂ��ẮA(3)�Ō���u���쎮�_�����v�ɂ͓ߒq���Ȃ����Ƃ���A���R�������͑�v�A���̂悤�Ɏw�E����Ă���B�u���̎��́w�F�어�{���_�x�͖{�{�̐_�̌Ö��ł���A���ꂪ�������Y�����9���I���ɂ́w�F�썿�_�x�Ə̂��A��������ɓߒq�����ڂ����ɋy��ŁA��U�͔p���ꂽ�w���{���_�x���ߒq�̐_�i��\�����̂Ƃ��čė��p�����ɂ��������B�v(1) ����A�{�Ə����́u���̓�_�͌��݂̐V�{�ɔ�肳��A�F��_�W(�V�{�s)�ɓ�Ђ��ꏏ�ɂ܂��Ă����Ɛ��肳���v(2)�Ƃ��Ă���B ���Ƃ��ẮA����5�N(927)�́u���쎮�_�����v�ɌF�썿�_��(�{�{)�A�F�쑁�ʐ_��(�V�{)�̓�Ђ��L����Ă���̂ŁA100�N�ȏ�O�̓V���_��2�N(766)�̎��_�Ŗ{�{�ƐV�{�̌��^�ƂȂ��Ђ����݂����A�Ƃ��Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�哯���N���������̌F�어�{���_�́A�{�{�̐_�ł͂Ȃ����Ɛ������Ă���B�@ |
|
|
��(2)�@�F�쑁�ʐ_�ƌF�썿�_�̏��i
���������ɂ��ƁA�V��3�N(859�A��4��25���ɒ�ςɉ���)1��27���A�F�쑁�ʐ_�ЂƌF�썿�_�͏]�܈ʉ�����]�܈ʏ�ցB5��26���A��Ђ͏]��ʂɐi�ށB���5�N(863)3��2���A�F�쑁�ʐ_�͐���ʂɁB����7�N(907)10��2���A�F�쑁�ʐ_�͏]��ʁA�F�썿�_�͐���ʂƂȂ�B�V�c3�N(940)2��1���A�F�쑁�ʐ_�ƌF�썿�_�͋��ɐ���ʂɐi��ł���B �������� �V���O�N�����������b�ЁB�I�ɍ��]�܈ʉ��F�쑁�ʐ_�ЁB�F�썿�_�B���]�܈ʏ�B ��ό��N�܌����Z���h���B�]�܈ʏ�F�쑁�ʐ_�B�F�썿�_�B���]��ʁB ���ܔN�O������b�q�B�]��ʌF�쑁�ʐ_������ʁB ���쎵�N�\��������߁B������ʌF�쑁�ʐ_�]��ʁB���]��ʌF�썿�_������ʁB �V�c�O�N������сB���_�ʋL���B�F�쑬�ʐ_�B�F�썿�_�B��������ʁB�@ |
|
|
��(3)�@���쎮�_����
����5�N(905)�A���V�c(885�`930)�̖�����������(871�`909)��ɂ��Ҏ[���n�߂�ꂽ�u���쎮�v�͉���5�N(927)�Ɋ����B���̓��̊���Ə\�́u���쎮�_�����v�ƌĂ�邪�A�����ɂ͕������㒆���̑S���̎�v�Ȑ_��(������)2861�ЁA��������_3132�����L�ڂ���Ă���B�F��ɂ����ẮA���\�́u�I�ɂ̍�������@��\�O���@���\�����v�́u���K�S�Z���@�����@���l���v�ɁA�{�{�́u�F�썿�_�Ёv�A�V�{�́u�F�쑁�ʐ_�Ёv�Ƃ��ċL�ڂ���Ă���ߒq�̖��͌����Ȃ��B�@ |
|
| ��3�@�u���{��ًL�v�@ | |
|
�ޗǎ��ォ�畽�������ɂ����āA�����m���A���̖������݂܂œ`������قǂ̉����Ȋ�����W�J���A�C�s�E�`���Ƌ��ɏ����̗����J�n���Ă���B
�E���ォ��ޗǎ���ɂ����āA��a�̊���R��тŊ���������p�҂ŁA�������̎R�яC�s�E�R�x�M�̗����ɂ��C�����̊J�c�ɉ������ꂽ�����p(���s�ҁE���v�N�s��)�B �E���O�����ƎЉ�Ƃ�W�J���A���厛�啧���c�̊��i�����������A���{���̑�m���ƂȂ����s��(668�`749)�B �E���R���J�R���A�e�n�ɕ�����`�d�������z�O�̑א�(682�`767)�B �E���x�_�{����n�����A�����_�{���̑n�����`�����A�����O�����������������Ƃ�������(���v�N�s��)�B �E�`���̑�����㔪��S�̔�u��E�ɗ���F(���v�N�s��)�B �E���E����E�����Ŗ��O��������������(���v�N�s��)�ƈ��B �E�R�яC�s���s���A�����R���J�R��������(735�`817)�B �E�헤�����Âɂ����āA���̊����Ǝ��@�̊J�n���`�����铿��(�H�`824)�B �ނ�Ɠ�������A�ݒn�ŕ����^�����s������l�Ƃ��ĉi��(���v�N�s��)�̖����������B�i���̑����͈����N�̎��A�܂��s���̎��Ƃ������A�ےÍ��蓈�S�̕S�όn�����̉Ƃɐ��܂ꋻ�����̑m�ƂȂ����B�V����F2�N(758)�A�O�j��ǂ̏���E�ƂȂ������I�ɍ����K�S�F�쑺�ɈڏZ���A�R�x�C�s���s�����B�@�،o���u���d�ˁA���l�������i���͌F��̊C�ӂŕa�҂��ŕa���A�l�X�����������B�y�n�̐l�X�͉i���̍s�����ق߂������ĉi����F�A�܂��͌F�삪���鋞�암�Ɉʒu���邱�Ƃ�����F�ƌĂсA�̎^�����Ƃ����B(1) ��T���N(770)�A�i���͑�4��̓��厛�ʓ��ɕ�C����A��T3�N(772)3��3���̏قɂ��A�V�c�̐g�̂��쎝����\�T�t�̈�l�ɑI��Ă���B(2)�F��ɂ�����i���̊����ɂ��ẮA�u���{��ًL�v�ɖ@�،o�̗쌱杂Ƃ��ďЉ��Ă���B(3) �u�@�Ԍo�����������҂̐�A���肽���鐂̒��ɒ����ċ��������肵���@���v (�Ӗ�) ������A�i���̂Ƃ���Ɉ�l�̑T�t���K�ꂽ�B�������́A�@�،o�ꕔ�Ɣ����̐��r��A�ꏰ�ꑫ(���҂ݒ������֎q)�����������B�T�t�͉i���̂��ƂŖ@�،o�̓��u�ɐ�O���A��N���܂�o�Ɓu������R�ɓ��낤�Ǝv���B�ɐ��̍��Ɍ������܂��v�ƌ����A�i���Ɍh�炵��̈֎q���c���ďo�������B�i���͂����Ă̊��т����ĕ��ɂ������̓�l����T�t�Ɏ{���A�r���܂ł̈ē��Ƃ��ėD�k�Ǔ�l�����ē��s�������B ����������Ƃ���ŁA�T�t�͖@�،o�Ƃ��킹�Ĕ��A���т̕�����D�k�ǂɗ^���ċA�点���B����́A�������̓��\�q�Ɛ��r�����ɂ��Ă��邾���������B ���ꂩ���N���肽�������A�F�쑺�̐l���F���̏㗬�̎R�ɓ���A���đD������Ă����B��������������̂Ŏ��܂��ƁA����͖@�،o���u���鐺�ł������B�������d�˂Ă��A���̐��͂�ނ��Ƃ͂Ȃ��B���l�͖@�،o���u�̐��ɔ��S���A���̎�Ԃׂ������̐H��������悤�ƒT�����߂����A���Ɍ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�R���̏����ɋA���Ă��A�o��ǂސ��͕������������B���ꂩ�甼�N���ւāA���l�͑D�������o�����߂ɍĂюR�ɓ������B���̎����A�N�����Ȃ��R���ɖ@�،o���������A�s�R�Ɏv�������l�͉i���ɓ`�����B �i�����R���ɓ������Ƃ���A�܂��Ƃɖ@�،o��ǂސ�����������B���X�������ˌ����Ƃ���A��̂̎��[���������B���̂́A���̓���̑��ɂȂ��ŊR�ɂ������Ă���A�R���g�𓊂��Ď��悤��(�M�ҁE�̐g�s��)�B���̖̂T�ɂ͐��r������A����������i���́A���Ƃ̎����m��Ƃ���ƂȂ����B �R���g��݂邵�Ă����҂́A���N�O�ɕʂꂽ�T�t�ł������̂��B�i���͔߂��݂ɂނ��сA�����Ȃ���F��̑��ɖ߂��Ă������B���ꂩ��O�N���o�߂������鎞�A���肪�i���̂Ƃ���ɗ��āA�u�@�،o��ǂސ��͏�̂��Ƃ��A��ނ��Ƃ�����܂���v�ƍ������B�ĂюR�Ɍ��������i�����T�t�̍�����낤�Ƃ����鐂��ԋ߂Ɍ���ƁA�O�N���o���Ă���̂ɑT�t�̐�͕��炸�A�����Ă���l�̂悤�Ȃ��̂ł������B�܂��Ƃɒm��ׂ��ł���B����͖@�،o�̕s�v�c�Ȃ�͂ł����āA�o��ǂ݁A����ς����ł���Ƃ������Ƃ��B �������u���{��ًL�v�́u�@�@�Ɏʂ���肵�@�،o�̉ɏĂ����肵���@��\�v�ɂ��A�@�،o�̗쌱杂��L����Ă���B�I�ɍ������S�r�c��(�a�̎R���L�c�S�L�c�쒬)�ɏZ�ގ��x�m�E���K����(�����E�|�{��)�́A�Z�����ɂ킽�萴��̐g�Ŗ@�،o�̏��ʂ��Ȃ����B�������A����Ύ��ɂȂ�S�Ă��Ď����Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�o�������͏ł��������Ă��c���Ă��āA���̌o�T�������ł������B����́A���K���킪�[���M�S�̌�����ςݖ@�،o���ʂ������Ƃɂ����̂ŁA��@�_�̎�肪�Ђɍۂ��ė쌱�����킵�����̂Ȃ̂ł���B�s�M�҂̐S�����߂�̂ɑP���b�ł���A���̐l�̈����~�߂�̂ɂ����ꂽ�t���Ȃ̂ł���A�Ƃ����B |
|
| ��4�@���m���K杁@ | |
|
��(1)�@��C�A�`�^�A�~�m�A�nj�
�u�F��N��L�v�́A�u�~�a(�V�c)�@�V���l(�N)�@�����@�A��C���F��B�v�ƓV��4�N(827)�ɋ�C(774�`835)���F���K�ꂽ�Ɠ`���Ă���B �u�i����N(��l�O�Z)�������{�v�Ɖ����ɂ���A�����O�L�ɏ��ʂ��ꂽ�u�F��R���L�v�ɂ́A�u��K�������q�@�s��㮍��@���o��t�����v�u�ؖڋ������q�@�`�^�a�������@�\��ʊω��v(1)�Ə�����Ă���B�F��w�ł�����ɂȂ���12���I����13���I�ɂ����A�Q�w�H�ł������I�ɘH�A���ӘH�ɂ͑����̉��q�Ђ����Ă���\�㉤�q�ƌĂꂽ�B���̂����̈�A�F��X�����ӘH�����ɂ����K���q�̖{�n�E�s��㮍���F�ɂ��ẮA���o��t�~�m(794�`864)�����������̂��Ƃ����B�܂��I�ɘH�̐ؖډ��q�̖{�n�E�\��ʊω��́A����V�����̋`�^(781�`833)�����������̂Ƃ���Ă����B �������u�F��R���L�v�ɂ́A�u������t���N��ċ�{�s�@低��@�����ʏ�����v(2)�Ƃ���A�V��̎��b��t�nj�(912�`985)�͖��N�āA�ߒq�R�̈������Ă�s�@���Ȃ����B�ߒq��̉��A����̏��ʏ����R���̒n�ł���Ƃ��Ă���B�������A�u������t�v�́u���o��t�v�Ƃ��������̂���ʂ��ꂽ�\�������邩������Ȃ��B ����疼�����鍂�m�̌F�었�K�ɂ��ẮA�Ⴆ�A�ɓ����E�����R�ɍO�m10�N(819)�A��C���R�̓`��������̂Ɠ������A�����̗��E���n�ɂ͂����̂́u���m���K杁v�̈�ł͂Ȃ����낤���B�c�t�Ɠ�����̎j���ɂ͌����Ȃ����т��A�㐢�A�c�t�E���l�̓`�L�����ʂ����ߒ��ŏ���������ꂽ��A���̒n��K�ꂽ�@�n�̐��炪�����`���āA�㐢�ɓ`�����ꂽ���̂͐��m�ꂸ����Ǝv���B ���A�u�F��R���L�v�͉����́u�i����N(1430)�v���n�܂�Ƃ��āA�]�ˑO���܂œߒq�̐���čs�҂ɓ`����ꂽ�Ɛ��肳��Ă���(3)�A�M�҂Ƃ��Ă͌p���̉ߒ��ŏ����������邱�Ƃ��������Ǝv���B�@ |
|
|
��(2)�@�~��
�u�����ߏ��v���O�E�~��(814�`891)�̍��ł́A�u���w�I�B�F��A�K���J�A���B�����H�A��咹�בO���B�ߎ����K�A�ߏ�V���s硉��A�֍u�@�A�_�r�a�ˁB�����F�R��攪�u�A嫐��V�u���u�t�����A�Ȉ��B�v�ƁA�~���̌F��w�łƖ@�ؔ��u�̗R����`���Ă���B �~���͋I�B�F��֎Q�w�Ɍ����������A�r���A���������J�ƂȂ蓹�ɖ����Ă��܂����B����Ȏ��A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��傫�ȃJ���X�����������܂܂ɐi�ނƁA�K�̑O�ɂƎ������B����́u�̂��邱�Ƃ��v�Ǝv�����~���͈߂̏�̔G�ꂽ�����������Ƃ��Ȃ��A�����ɖ@�،o���u���Ă����B����ƁA�K�̌˂������J���Đ_�����ꂽ�B�~���͂������������A�������A�F��R�ł̖@�ؔ��u�̏�ł́A���V�ł�����u���Ă����ɍu�t������A�@����c�ނ��ƂɂȂ����Ƃ����B �u�F��R���L�v�ɂ��u��a���������q(���d����������q)�@�{�n���ӕ�F�@�q�ؑ�t�����v(4)�Ƃ���A�F��̐_�̈�ł����a���������q(���d����������q)�̖{�n�E���ӕ�F�͉~�������������̂Ɠ`�����Ă����B ���鎛�̎��`�ł��A�ĎR���I����ĊԂ��Ȃ��̏��a12�N(845)�A�~���͑���E����E�F��O�R��l�M�C�s�����Ɠ`���Ă���B �~���̑O�ɐ_�����ꂽ�̂͐��l�쌱杂̈�Ɠǂ߂邪�A�~�����F��ɎQ�w�����L�q�͂ǂ����낤�B�͂����Ďj���Ɋ�Â����̂Ȃ̂��낤���B ���������̌����E���w�҂̎O�P���s(847�`919�A��ɂ݂�̕�)�͉���2�N(902)10���A����������~���̎��т��Ă���B���̌��{�͌������Ȃ����A�Ï�3�N(1108)4��21���A��R��̏��c���R���Ǝv���鏊�ŁA�������m�Ɛ������萟���u�g�˖[�{�v���Ȃď��ʂ��A�d���@�t�ۂ��Z���������̂����厛�^���@�̑m�E�o���̎�ɓn��A�u�V��@������咿�a���`�v(����)�Ƃ��Ď��ꌧ��Îs�̐ΎR���ɓ`�����Ă���B (���\���[���O��)�@�q�ؑ�t�`�@�m�o���V�{ (����)�@ �V��@������咿�a���` (����)�@ �Ï��O�N�l������������c���ȋg�˖[�{ �@�@�@�@�@�@�@�@���ʗ��@�@�M�t�萟 �@�@�@�@�@�@�@�@�u��Z���d���@�t�ۖ�v(5) �u�V��@������咿�a���`�v�ł́A�~���̏o���A����ŕ�F�������12�N���ĎR���s�������ƁA6�N�Ԃ̓������@�̗��A�o�T�����ƋA����̊����A��q�ւ̕t�@�Ɠ���܂ł��L�q���Ă��邪�A�F��E�ߒq�Ɋւ�����̂͌����Ȃ��B�܂��A�����L�������u�V��@������咿�a���`�v�����u���������������̂ł���Ƃ݂Ȃ����Ƃ��s�\�ł͂Ȃ��v(6)�Ɠ��e���ڍׂɌ������ꂽ�A�u���{���m�`�v�����v���ڂ́u�q�ؑ�t�`�v�Ɓu�������N�W�v�t�ڂ́u�~���a���`�v�̓�̕����ɂ��F��W�̋L���͌�������Ȃ��B ����A�����ɂ͊O��Ɂu�~���a���`�@�˗ъw�m�P�s��v�A����Ɂu�q�ؑ�t�`�v�ƋL�����Îʖ{���`���A�����ł͖{���̌�Ɂu�ߏ�܉ӏ�s�ڍL����`�U�ݏ��������W����v�ƋL����A�u�L����`�v�ɍڂ���ꂸ�U�݂��鏔���������W�߂��܉ӏ������^����Ă���B ���̈�ɂ́u��t�Q�w�F���Љ��O��������őO�ΏC�A�@�ؔ��u���O�������s���@���J�œa�����A�M�l�`���ߕ����[�ؐ���p�H�����������A�|�Ќ�����痘�v���������O���C�ӎ��ݎҁA�R�җL����]����t���H�����ʁ��O�S�A�ٌ�����]�A�쎝�䕧�@�p�������������A�����ĎO���l�����s�����]�X�B���`�]�̌F���œa���НّO�q�a�����A���u��t�Q�w���J�V�����ᒅ���}�߁A�ΏC���u���̈ˍ��ᎊ�����҉��q�a�V�A���J�~�s�~�s�]�o�����ᒅ���}�����A�Җ�]�X�v(7)�Ƃ����āA�F��ɂ�����~���̎��Ղ�`������̂ƂȂ��Ă���B ���̓����{�́A�������N(1185)8��27���A���b���ʼn��鎛�̑m�E�Œ����u���{�䏊�����@��{�v�����ʂ������̂ŁA���������2�N(1212)4��23���A����^���ʂ��A���x�́u�����S�@��{�v�ƂȂ������̂�����2�N(1357)4��18���A�������@�m�V�Ō����ʂ��Ă���B �������N���������������b�����{�䏊�����@��{���ʗ������������@�@��菑��]�X�@�Œ��L �@��ҍs���@���[���������b�o�葧��A�{��m���s�[�t�@��㔒��@�t�� �����N�l�����O���Ȓ��[�����t�Œ��V�{ �@�@�@�@�@�@�@�@���ʗ��@�@����ݔ� ������N���юl���\�������������@�m�V�����S�@��{�ʗ��� �������w����@������ �����ܓ���_��(8) �ΎR���{�́u�Ï��O�N(1108)�l����\����v�̊萟���ʂŁA�����{�́u�������N(1185)������\�����v�̍Œ����ʂ��͂��܂�Ƃ��A��������̂܂ܐM�p����A��̕����ɂ�77�N�قǂ̊u���肵���Ȃ����A�����͂�͂�A�����{�̌F��K��́u�U�ݏ��������W����v�Ƃ��ꂽ�u�܉ӏ��v�̒��Ō������̂ł��邱�Ƃɒ��ӂ��ׂ����Ǝv���B �F��E�ߒq�̖����s�Œm���Ă��鎞�����m�F�����j���Ƃ��ẮA�i��2�N(984)�A����(�H�`1011)���쐬�����u�O��G�v������A���̎��ɂ͊��Ɂu�F�씪�u��v�����`����Ă������Ƃ�����������B�����Ċ���4�N(1090)�A���͏�c�����߂ČF��ɎQ�w���A���̎��A��B�߂����鎛�̑��_(1032�`1116)���F��O�R���Z�ɕ�C����Ă���B����͂���ȑO�ɁA�V��A�Ƃ��Ɏ���n�̑m���F��ւ̉������d�˂Ă������Ƃ��Ӗ�������̂����A�~������(����3�N�E891)100�N�߂�����200�N�ɂ����āA�V�䎛��n�ƌF��̊W���[�܂����Ƃ��납�甭�������u���l�E�c�t�`���v�̈���A�u�~���F�었�K杁v�ł͂Ȃ����낤���B �~���̖@�n�B���F�쉝���E�C�s���d�˂钆�őc�t���K杂����܂�A�U�݂��Ă��������̈�ɏ�����Ă������̂��u�~���a���`�v�Ҏ[�����̈�Ƃ��Ď��W����u�܉ӏ��̈�v�Ƃ��ď����Ƃǂ߂��A�������N(1185)�Ɏ����čŒ��ɂ�菑�ʂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����L�����͌܉ӏ����u�`���܃����̋L�ځv(9)�Ƃ��A�u�~���`����m��̂ɉ��l������L�ڂł���Ƃ������Ƃ��ł���B�v(10)�ƁA�u�`���v�Ƃ̌�����������Ă���B���������~���̎��Ղ̏ڍׂ��L�q���ꂽ�u�~���v(11)�ł��A�F��Ɋւ��Ă͐G����Ă��Ȃ��B�@ |
|
|
��(3)�@����
�F��Ƒc�t�`���Ƃ����A��ɓ��R�h(�^��)�̑c�Ɛ��߂���悤�ɂȂ����^���m�̐���(832�`909)�����ڂ��ׂ��l�����B �u�F��N��L�v�ɂ��ƁA���c5�N(881)8���A����͐V�{�̐_�q�R�ŏC�s�B�܂��A����5�N(893)�A�F��ɎQ�w�������ɂ́A����s��������R�ɕ����Ă���B����2�N(902)�A����͌F��̉��n�ɓ���A�ւ��a��r���J���Ă���B�܂��_�q�R���ĎR�C�s�����Ƃ����B �u�F��N��L�v �z��(�V�c)�@���c��(�N)�@�h�N�@�����A����A�_�q���F�x�A���ꎵ���`��C�@��s�B �F��(�V�c)�@������(�N)�@ᡉN�@����A�F��Q�w�����s������������R�A�˒���]�X�B������Z�\��B ���(�V�c)�@�����(�N)�@�p���@�����l�A�F�쉜�ɓ���A�ւ��a��r���Ղ�B��l�בm���B�_�q���āA�O����B �u�N��L�v�̋L�q�̂����A�u����s�����`�v�́A���������F��ɖ{�菊�������̂�15���I�ȍ~�̂��ƂȂ̂ŁA���̎���ɂ͈��厩�̂����݂��Ȃ��B�㐢�A�ЉƂƖ{�肪�Η�����悤�ɂȂ�������A�{�肪�Â����瑶�݂��Ă������Ƃ������A�����j��̐��l�ƊW�����������Ƃ������������̂ŁA�ЉƂɑ���{��̗����ʒu��D�ʂȂ��̂ɂ��邽�߂̍�דI�ȋL�q���Ǝv���B���u�ւ��a�v�����Ƃ̋L�q���A����2�N(1325)���A�h�C(1278�`1347)����q�����u�^���`�v���́u����̓`�v�ɂ���u���A����͖��s�ҁA��n���s�Ќ���������A�Ŏ֑����������ӂ����ĎQ�w����l�Ȃ��B�R���(����)�m���A�Ŏւ���(���肼)���ĎR����J���B������ȗ��l�M(�Ƃ���)�̍s�ґ����Đ�鎖�����v�Ƃ�������ł̑�ցA�Ŏ֑ގ��̓`�������Q�l�ɂ������̂ł͂Ȃ����B �����u�`���v�͏����Ƃ��Ă��A���F���K�ꂽ�A�Ƃ������ƂɊւ��Ă͂ǂ����낤���B�{�莛�@�������̑��h���W�߂鐹�l�Ƃ̂Ȃ�������������̗R����n�낤�Ƃ����A�ƌ��_�t����O�ɁA�j���̉\����T���Ă݂����Ǝv���B�܂��́A����̎��Ղ��m�F���Ă݂悤�B �E���a14�N(847)�A����͋�C�̎���E�^��(801�`879)�ɐ����o�Ƃ���B ���������ւ̒T���S�������ŁA�������̊��(�H�`874)�Ɖ~�@����O�_���w�сA���厛�̕��m����@���A���������厛�̌��i����،��A�^������͗����w��ł���B �E���13�N(871)�A�^���薳�ʎ��@����w�B �E���16�N(874)�A�}��R(���R)�R���ɑ������\����B �E���18�N(876)�A�}��R�R���ɏy�����āA�@�ӗ֊ω��Əy��ω����B��펛�̑b������B �E���c4�N(880)�A��C�̒�q�ɂ��āA�^�납��ّ��E�����̟����^�R(�H�`891)���A�ّ��E�������E�̑�@����B �E���c5�N(881)�āA�^�R�̂��ƂŏC�s�B���̎��A��C����^��A�^�R�ւƓ`������u�ّ�����O����v�����^����Ă���B �E���c8�N(884)�A���N�A�����̓�̒��҂ƂȂ錹�m(818�`887)�̂��ƂŁA�`�@����B �E����7�N(895)�A�����̓�̒��҂ɕ�C�����B �����L�����́u��펛�v���v�Ɍf����A����13�N(913)10��25���t���̑��������Ɉ��p�����ό�(12)�̑t��ɂ���A�u��t(����̂���)�A�́A���(�Ђ��Ⴍ)��U���āA�Ղ����R�ɗV�сA����(�������)�A�߂𐁂��āA����̊ނ܂��A���_�A���(����)�߂āA����̛�(����)��T�炴��͂Ȃ��B�R��Α����k(����)�A�ِ��A�����̐Ղ�(����)�߂�Ƃ��v�����ƂɁA����������̂͋g��̎R�X�ł���A������(��h�R��=���݂̐�����)�ɓ��R�������Ƃ͊m���ł���Ƃ��A���̍������������Ă���B(13) �E����͋�C�̎���ł���^��̂��Ƃŏo�Ƃ������Ƃ���A��C�������Ă������������@�̍s�@�̗���̒��ɂ������B �E����̎O�_���w�̎t�E��ł͋Α�(754�`827)�̖��ŁA����(�H�`744)�ȗ��́A���������@�̓`�������ɂ����B �E��ł͌������̎O�_���w�����ł͂Ȃ��A�@���@�B���ɂ��ʂ���w�m�ŁA�@���@�̊w�n�ɂ͌������ł̎R�яC�s�̓`�����������B �E�u��퍪�{�m�����`�v(14)�́A���������ŏ�Z�̖��ӕ�F���ƈ��̒n����F���������Ɠ`���Ă��邱�Ƃ���A����ƌ������ɖ��ڂȊW���������ƍl������B ����͂܂��A�����R�Ƃ̊ւ��������`�����Ă��邪�A�������͐M�ߐ�������̂́u��퍪�{�m�����`�v�́u�����R�ɓ������āA���тɋ����Z�ڂ̋��F�@�ӗ֊ω��A���тɍʐF���̑���V���A����������F����B�E�E�E�E�����R�̗v�H�A�g��͂̕ӂɑD��݂��A�n�q(�Ƃ�)�A傜��(�悤�Ă�)�Z�l��\���u����v�ł���Ƃ��A����ȊO�̏������`����̂͂��ׂē`���ł��邱�Ƃ��w�E�B����a�Y���̒���u������t�v�����p���Ȃ���A�������R�ɓ��ɂ����āA������A�����R�ւ̗v�H�ł���g���̓n�D�̐ݒu�ƑD���E�l�v��z�������̂́A�Ⴋ���̓�s�C�w����ł͂Ȃ��A�ނ̏@���I���������Ȃ�n���Ă��������̂��Ƃł���A�Ƃ���Ă���B(15) �������̋����̂����A���Ɋό����u��t�͐́A�������ɂ��āA�Ղ����R��V�s���A�̎R�̋C���߂����A������̑傫�Ȋ�܂Ȃ����Ƃ��Ȃ��A�����_�����������߂āA������̎R�̓��A��T��Ȃ����Ƃ͂Ȃ������B�������Ă����A�R�тɉB������������ꏊ���߂悤�Ƃ����v�ƋL�q���Ă��邱�Ƃ��炷��A���e�n�̎R�x����K�˕������ŁA�F���K�ꂽ���Ƃ��l�����邾�낤�B�܂��A�u���{��ًL�v�̉i�������厛�ʓ��ɕ�C����A�\�T�t�̈�l�ɑI���ȑO�ɁA�I�ɍ��F�쑺�ŏC�s���Ă��邱�Ƃ��A��́u���v�ɂ͂Ȃ�B�������A�����_�ł́u�\��������v�Ƃ�����Ȃ̂ŁA����̌F�었�R�͎Q�l�Ƃ���ɂƂǂ߂�ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���B ���A����֑̎ގ��`����`����n���A�g��ƌF������ԏC���̓��ł���u������퓹�v�ɑ��݂��Ă���A�ܗ��d���͎R���̋����[���b���Љ��Ă���B �u���傤�ǂl(�M�҂��C�j�V�����ɕύX)���B�ƈꏏ�ɂ��邢�Ă����̂ŁA���̗R�����������Ƃ��ł������A�R���`���ł͗�����t(����)�̑�����풆���͑�ւ�ގ����ē����J�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B���̑�ւ����i�ɐ��Ă��Ă��̂����r���Ƃ����v(16) ���퓹�ɂ͑����̏C�s�ꂪ����A���̏���r(�Ȃт�)�ƌĂ�邪�A�g�쑤�̑���R������ߒq�R�A�F��{�{�Ɏ���܂łɂ́A���\�܂��r������Ƃ����B���̂����A��\��̎��j�x�Ƒ�Z�\�̒t�����̒��Ԃɂ���A���r�ƌĂ��Ƃ��낪�A���ւ�ގ������Ƃ����`���̒n�̂悤���B ���̂悤�Ȑ��l�A�C���҂������ւ�ގ������Ƃ̓`���ɂ��āA�{�Ə����͎��̂悤�ɉ������Ă���B �u�R�x���̗�n�ɂ�����E��E��Ȃǂ́A�C���҂��R���ɓ���ȑO����_�삪�Z����Ƃ��Đl�X�ɂ���Đ��߂��Ă����B���ɂ����ꂽ��n�̐_��E�R�̐_�E�����_�Ȃǂ͂Ƃ�킯�傫�ȗ�͂����Ƃ���Ă����B�ցE�T�E�ρE�F�Ȃǂ̓��������������_�̂�����Ƃ��Ă�������Ă������B�Ȃ��ł�����ւ͊e�n�̎R�x�Ő����_�̑̌��Ƃ���Ă���B���R�h�C���̊J�c�ɉ������ꂽ�����R�ő�ւ�ގ������Ƃ̓`���Ɍ�����悤�ɁA�R�x�ɓ������C���҂�����ގ������Ƃ̓`���́A�C���҂��R�x�̎�Ƃ������鐅���_�����Ȃ̓��䉺�ɂ��������Ƃ���Ă���Ƃ����悤�v(17)�@ |
|
| ��5�@�O��G���ɂ݂���F��@ | |
|
�������̎�����j���u�}�K���L�v�ł́A����7�N(907)10���A�F����c(867�`931)���F��ɎQ�w�����Ɠ`���Ă���B
����3�N(992)�ɉԎR�@�c(968�`1008)���ߒq���Ă��s�����Ɠ`��邱�Ƃɂ��āA�u�F��N��L�v�́A�u���(�V�c)�@����O�p�C�@�@�c�F��s�K�ߒq�R��{�{�����i�A�{�{�@�،o�ꕔ�[�A�V�{���ߑ��[�A������ɊҌ����𖭖@�R�ɔ[�ꐡ�����̋�����ߔ[�B�v�ƁA�ԎR�@�c�͓ߒq�R��{�ɖ{������i���A�{�{�֖@�،o�ꕔ��[�߁A�V�{�ɂ͎�ߑ������[�B8����{�ɂ͓s�ɖ߂�A�@�c�̗߂ɂ�薭�@�R�Ɉꐡ�����̋�����[�߂��Ƃ��Ă���B ���q����̌R�L����u���������L�v�ł́A�u�ԎR�@�c��Q�w�A��{�ɎO�N����̍s���n�ߒu�������ւ�B���̐��܂ŘZ�\�l�̎R�U�ƂāA�s翂̏C�s�ҏW��āA��s��s����Ƃ���B�v�ƁA�ԎR�@�c�͓ߒq�Ő���̑��Ă��s���A�ȗ��A60�l�̏C�s�҂��R�Ă���s��s�����ƋL���Ă���B�܂��A�u���_�v������āu�@�ӕ����������̔O���A�A�㌊���z�L����v�����B�@�c�́u�����{���߂���āA����s�҂ׂ̈ɂƂāA�����Ί≮�̒��ɔ[�߂��A�O����ΐ�蓰�̂ւ�ɔ[�߁v�āA�u�z���Έ�̑��ɕ����u���ꂽ�v�Ƃ��Ă���B �u�F��R���L�v�����l�ɎQ�Ď��̗쌱杂��L���Ă��āA�u�ԎR�@�c��Q�Ď��A�O�d��j�{�n���@�ӗ֔n���g����X�v(1)�ƁA�ԎR�@�c�̓ߒq���Ē��ɖ{�n�E���ω��A�@�ӗ֊ω�������A�u�ԎR�@�c����N���A���ÎO���N�V�Q�āA���ڐ���V�����A��A�Z�\�l�V�T�k�A���s冣��V��@�A�����m�f���≌�V���v(2)�ƁA�@�c�̓ߒq���Ă͐���̒����ɂ킽��A�ȗ��A�Z�\�l�̏C�s�҂��A�Ȃ����Ƃ��Ă���B �ԎR�@�c�̓ߒq���ẮA���q���̒m���w�ɂ͍L���m���Ă����悤�ŁA������(1147�`1199)���t�Ƌ����ɓ��̍������R�̏Z���E����[�ǝ�(��傤����)���A�F�J�����̓ˑR�̏o�Ƃ��Ђ߂��莆�ɂ����p����Ă���B����́u��ȋ��v���v3�N(1192)12��11���Ɂu�ԎR�@�c�̖P���������A�F��R�ɗՂށB�܂��A�c�c�̕����~�͂�ׂɁA�ߒq�̉_�ɎO����Q�Ă����ށB����F�A�q���E�̗���\���̌̂��B�v�ƋL����Ă��āA�@�c�̑��ẮA�c�c�̕������߂̂��̂ł���A�q���E�̗���\�����̂ł������Ƃ����B����͓����ɁA���q���ɓߒq�Q�Ă������s�ҒB�̐S���ɁA�ʂ�����̂��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �u�M�l�C�s杁v�Ƃ������ׂ����A�F��E�ߒq�ɗl�X�ȗ쌱杂����ԎR�@�c�����A���̉ԎR�@���V�c�ɑ��ʂ����i��2�N(984)�̓~�A������z������̊G������������B����́u�O��G�v�Ƒ肳��A���������̊��l�ŕ��w�҂̌���(�H�`1011)���A���V�c(950�`1011)�̑��c���ł��鑸�q���e��(966�`985)�̂��߂ɍ쐬�������̂������B���̌�A�G�͈�S���Ď������c��A���ꂪ�������b�W�u�O��G���E�O���v�Ƃ��ē`�����Ă���B �u�O��G���v�ɂ͌F��́u�@�ؔ��u�v���L�q����A�����́u�F��̐_�̐��E�v�ɂ�����u�����̐F�ʁv��`����j���ƂȂ��Ă���B �u�O��G���E�����v�@�\�ꌎ �F�씪�u�� �I�ɍ����K�S�ɐ_���܂��B�F�염���A�ؐ��ꏊ�Ɩ��Â�����B�����͕�Ɩ��Ɩ�B�����ʂƐ\���B�ꏊ�͂��ւ�Ж�B���̎R�̖{�_�Ɛ\���B�V�{�A�{�{�ɊF���u���s���B�I�ɍ��͓�C�̂��́A�F��̋��͉��̌S�̑���B�R�d�Ȃ�A�͑������āA�s�����y���Ȃ�B�t�䂫�H����āA����l�܂��B�R�̘[�ɂ���҂́A�̎����E���Ė����p���B�C�̂قƂ�ɏZ�ގ҂́A�����Ȏ��č߂����ԁB�������̎Ђ��܂����肹�A���u�����s�͂���܂��B���̔��u�Ȃ���܂����A�O������m�炴��܂��B�\�l�܂ł����`�֓��ׂ�ὁX(�ׂ��ׂ�)���鏊�ɁA���@���L�ߕ������ߋ��ւ�́A��F�̐Ղ𐂂ꂽ��ƌ��ӂׂ��B�l���̒h�z�A���s�́A�����������l�̊��ނ�ɏ]���B�����̍u�t�A���O�́A�W�܂��m�̖��ނ�ɔC������B�m���͔��q�����݂����B�̍b�ɎA�ё܂ɓ���B�u���͏U���ւ��B����̈߂𒅁A���Ђ�������B�M�G�̂��Ȃ����I���A�V��������߂��B �`���Łu�I�ɍ����K�S�ɐ_���܂��v�Ƃ��A���̌F��̐_�q���e���ɋ�������̂Ɂu�F�씪�u��v���ނɂ����Ƃ������Ƃ́A�F��ɂ�����@�ؔ��u�����̋M���E�m���w�ɍL���m���A�S��������Ă������Ƃ��Ӗ�������̂��Ǝv���B���������ł́A�u�R�K��(������)���ω�v�u��t���ŏ���v�u���Y(�_�쎛)�@�ԉ�v�u�@�Ԏ�(��a���̑�������)�Ԍ���v�u��b��{���w��v�u��t��������v�u��b�ɗ���v�u�������ʎ��v�u��b����v�u���J��F���v�u���厛��ԉ�v�u��b�s�f�O���v�u����������v�u��b�v�u�R�K��(������)�ۖ���v�u��b������v���X�A�������@�̖@��̗R���A���N�A�쌱杂ƕ���ŁA�R�͗y���ȌF��̒n�ɂ�����@�ؔ��u�̑ԗl���L����Ă���B ���������u�O��G�v�쐬�̔��[���A�Ⴍ���ē����������q���e���̕��������ɂ��������Ƃ��炷��A10���I�̋M���E�m���w�̕�������ɂ͑�a�E���̗L�����@�̐M�Ƌ��ɁA�F��M�̗������K�v�Ƃ���Ă������Ƃ��ǂݎ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B��Ɍ���F��̋I�s���A�u���قʂ��v�̍�҂ł��鑝��@�t(���v�N�s��)���F��{�{�Ɍw�ł��̂��A�@�ؔ��u�ɎQ�邽�߂ł������Ǝv���A�����Ɂu�����̌䔪�u�ɂȂ�ʁB���̗L��l��Ȃ炸�����ɑ����v�ƋL���Ă��邱�Ƃ́A�����̕��l�E���{�w���F��ɊS�������A�S���Ă������Ƃ��������̂��낤�B �u�O��G���v�ɏ����ꂽ�F��̎Гa�A���������̓`������Ƃ���ł́A�F��̍Փa�̈�Ђ́u�F�염���v�ŁA������Ђ́u�ؐ��ꏊ�v�Ɩ��Â����Ă����B�㕶�ɂ��ƁA�F�염���Ƃ͌�(�ނ���)�Ƒ���(�͂₽��)�̗����ł���A��_����Ђ��J���Ă����B�����̌��̐_(�F�어�{���_)�Ƒ��ʂ̐_(���ʐ_)�̓�_�́A��Ɩ��̊W���Ƃ����B�u�ꏊ�͂��ւ�Ж�v�Ƃ́A�ؐ��ꏊ�ƌF�염��(���E�F�어�{���_�Ƒ��ʁE���ʐ_)�݂͌��Ɋ��Y���_�ł���Ƃ������ƁA����͎O�_��̂��Ӗ�������̂��낤�B�����āA�u���̎R�̖{�_�Ɛ\���v�ƁA�ؐ��ꏊ�͌F��̎R�̖{�_�ł���ƈʒu�t�����Ă���B �u�F�염���v���u��(�F�어�{���_)����(���ʐ_)�Ɛ\���v�ƋL����Ă���Ƃ��납��A�u���̎R�̖{�_�v�ł���u�ؐ��ꏊ�v�͉Ɠs����q�_�Ɨ����ł��邪�A�����ɏ����ꂽ�u�ؐ��v�Ƃ͉����Ӗ�����̂��낤���B ����ɂ��ĎR�c�F�Y���́u�����ɂ��ӂ͈���Ɍo�ɋɊy�̑����ƈ���ɕ��̌����Ƃ�����A���A��A���A�k�A��A���A�\���̏������e���L����o���āA���̐������Ȃ邱�Ƃ��ؖ�����Ƃ��ӂ��ƂɊ�Â��Ă��̐�瑂��ؐ����F�Ƃ��ւ�Ȃ�B�v(3)�Ɖ������Ă���B �ؐ����͕̂���Łu���̎��̐^���E���ł��邱�Ƃ��ؖ�����Ƃ̈Ӂv�����A�nj��ɂ��A�u�O��G�v���d�オ�����i��2�N(984)�����A��́u���H�L�v(����3�N�E1134)�̂悤�ɉƓs����q�_�̖{�n������ɔ@���Ɩ������������͌�������Ȃ��B�����A�u�O��G���v�ɖ@�ؔ��u�̖͗l���L����Ă���悤�ɁA�����̌F��ɂ͕����m(�V�䂾�낤)���@���蒅�����Ă����B�Ƃ������Ƃ́u���̂̌����E�l�����v���ڐA���āA�u�{�n��瑐��v����������Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����^�₪������B �u�O��G�v�ȊO�ɖڂ�]����ƁA���a2�N(962)�̉��������u����������@�������N�v�ł͔����_�̖{�n���߉ގO���Ƃ���l�����ǂݎ��A���a���N(985)�ɂ͌��M(942�`1017)���u�����v�W�v���A�������a�N��(985�`987)���Ɍc���ۈ�(933�`1002)���u���{�����Ɋy�L�v��Ҏ[���Ă��āA�i��7�N(1052)�̖��@���肪����ɓ��������̋M���A�m���l�ɓV���y�����L�܂��Ă���B�܂��A���ɌF��̐M�͍ݒn�ɖ����ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�s�̋��{�l�ɂ͍L���m����Ƃ���ƂȂ��Ă����B ���������Ă���ƁA���̎��́u�ؐ��v�́u�w���̎R�̖{�_�x�Ɨ��v�ɂ��Ă��̐^���E�����ؖ�������́v�Ȃ̂��A�܂��́u�w����ɔ@���x��������O�����~���Ɋy��y�։��������邱�Ƃ𐽂ɏ�(����)�����́v�Ƃ����ӂȂ̂��A���f�ɖ����Ƃ��낾�B ����ɒǂ��ł�����������̂��A�㕶�ɂ��A�ǂ̂悤�ȕ�F�Ƃ��Đ�瑂����̂��L�q����Ă��Ȃ����̂́A�u��F�̐Ղ𐂂ꂽ��v�Ƃ����Đ�瑂̎v�z���ǂݎ��邱�Ƃ��B�u��F�̐Ղ𐂂ꂽ��v�ɂ��Ă��A��ʂ�̂��Ƃ��l�����A�ǂ�������ׂ������f�ɖ����Ă��܂��B��́A�u�O��G���v�̉i��2�N(984)�ɂ͌F��ɖ{�n��瑐�����������Ă������Ƃ��������̂ł���A�Ƃ������́B��������A���́u���w��v�ɎQ�����������̊w���̔��e�̂��ƂŁA�ނ̊ϔO���E�ɕ�����Ă�����瑎v�z���F��ɓ��Ă͂߂Ă����\���������̂ł���A���n�ɓ�������Ă����킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ������̂ŁA�͂����đO�ҁA��҂̂ǂ���ɂ��ׂ��Ȃ̂��낤���B �Q�l�ɁA�����̐_�Ђւ́u�{�n��瑐��v�����̎����ɂ��Ă݂�ƁA9���I�̔�����10���I�ɂ����ĕ���F�̉��̎p�Ƃ��Ă̓��{�̐_�Ƃ����ϔO������A11���I����12���I�ɂ����Ċe�n�̐_�ɖ{�n�����ݒ肳��Ă���B�ł́A�F��́A�ƂȂ���̎�����m���j���A�����m�ɏ����ꂽ�����́u���H�L�v�ŁA�u�O��G���v����100�N�ȏ���o�߂�������3�N(1134)�̂��ƂɂȂ�B �u�ؐ��v�̈Ӗ�����Ƃ���A�u�O��G���v�������̉i��2�N(984)�ł̌F��ւ̖{�n��瑐������̗L���A�Ƃ�����̖₢�ɂ��ẮA�����_�ł́A�e��̉̂ǂ���Ƃ������Ȃ��B���́A�u�O��G���v�ɖ{�n���Ƃ��Ă̈���ɔ@������������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�i��2�N(984)�ɁA�{�n��瑐����F��Ɏ�������Ă����\��������B�܂��́A�F��O�R�̐_�X�̖{�n�����ݒ肳���悤�ɂȂ�G�肪�����Ɍ�����A�Ƃ��Ă������B �{���ɖڂ�߂��ƁA�{�{�ƐV�{�ł͖@�،o�����[�œ���A�l���ԂŔ������u������u�@�ؔ��u�v���s���Ă���Ƃ���B�I�ɍ��̓�C�̒[�A�X�Ȃ鉜�n�̌F��͎R�ɎR���d�Ȃ�A��������A���y���Ȃ�n�ł���B�R�[�̖��͖̎���H���A�C�ӂ̖��͋���H�ׂĂ͍߂������Ă���Ƃ����B���̂悤�ȕӋ��̒n�ł͌\�W�]���Č��`���邱�Ƃ͓���A�Гa�ʼnc�܂��@�ؔ��u�ɂ���Ė��͎O���m�邱�Ƃ��ł���̂ł���A���@���L�܂薯�̎��ɓ͂��͕̂�F���O�����ϓx���ׂ��F��ɐ�瑂��ꂽ����Ȃ̂ł���A�Ƃ����B���̉ӏ��ɂ��Ă͐_�̈Ќ��Ƃ��������A�����̏O���ϓx���̂��̂̐M���E���L�q����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�ؔ��u�̎l���Ԃ̎{��(�h�z)�⏔�����s����m(���s)�́A��߂Ƃ������̂͂Ȃ��W�������̊��߂ɂ��������C�ɓ�����B�����̍u�t�A���O����߂͂Ȃ��A�Q�W����m�̋߂�ɔC����Ƃ������̂ŁA�Q���҂���C�ӂɍu�t�A���O��I��ł����悤���B�����đm�̐H���ł͔���o��p�����̍b�ŎA���ɒ������я�̑܂ɓ��ꂽ�Ƃ����B�u���̑m�́A�m�E�ɂ���҂��g�ɂ���U�����𒅗p���Ĉߑ��𐮂��邱�Ƃ������A����̈߂ɋr�J�𒅂��Ă����B�����ł͋M�G���Ȃ���ΘV�����Ȃ������Ƃ����B ���̕��Ɓu���قʂ��v�̋L�q�ɂ��A�{�{�E�V�{�̖@�ؔ��u�́A�a�₩�őf�p�ȕ��͋C�ł���Ȃ�����A�h�i�̔O�[�����̂ł������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�@ |
|
| ��6�@�F��Ƒ���̓l�M�@�u�@�،��L�v�u���R���N�v�@ | |
|
��(1)�@�@�،��L
�������㒆���̒��v�N��(1040�`1044)�A��b�R�E���@�̒���(���v�N�s��)������u����{���@�،��L�v(�@�،��L)�ɂ́A�@�،o�ƌF��ɂ܂��쌱杂������L����Ă���B(�e���Ƃ��ɈӖ�) �u����E���@�ޒq�R�̉��Ɩ@�t�v �F��ޒq�R(�ߒq�R)�̏Z�m�E���Ƃ́A�@�،o���u�����̋ƂƂ��Ă����B���Ƃ͐l�Ԃƌ��G���邱�ƂȂ��R�ю������Z�݂��Ƃ��A�����ɐ��i�A��ӂ��邱�Ƃ��Ȃ������B�@�،o��]�u���鎞�A�i�Ɏ���x�ɍ����ɖ����̒_�ɓO���āA�쌩��F���g���Ă��A�I��R�₵�����Ƃ���琏�삵���B�ނ͐��ɔO����A��F�̔@���g���Ă��ď��X�̕��ɋ��{���悤�Ǝv���������B���Ƃ͍���f���A���𗣂�ĊÖ���H�����A���t��V�Ƃ��������A���O�̕s��𐴂߂ďĐg�̕��ւƂ����B���̎��ɗՂ�ŐV�������̖@���𒅂��A��ɂ͍��F������A�d�̏�Ɍ���������Đ����Ɍ��������������������肵�Č������B �u��͂��̐g�S�������Ė@�،o�ɋ��{���A�����������ď���̏��������{���A���������ĉ����̐����ɕ���B�w�͓����̔�����(�L���E���̒ʍ�)�[���܂ցB�O�͐����̐��Ւm(���̏\���̈��)���������܂ցB�T�����������Ď߉ޑ�t�ɋ��{���A���E�̘e�������đ����Ɏ{���A��A�������Ĉ���ɔ@���ɕ�シ��B�T���ܑ��͌ܒq�@��(����@���A��閦�@���A�@���A�ώ��݉�[�����]�@���A�s�A�@��)�ɋ��{���A�Z�{�������ĘZ���̏O���Ɏ{�^����v ���Ƃ͒������ь��ɖ��@���u���A�S�ɎO���M���Β肵���B�g�̂͊D�ƂȂ��Ă��@�،o���u���鐺�͐₦���A�̂��U�����邱�Ƃ��Ȃ������B����������A�]�����c�苕��ɏƗj���ĎR�J�͖��N�ł������B�������Ƃ��Ȃ���Ȓ������S���W�܂�A��̐��̔@���ɘa��V���Ă����B����͓��{���ŏ��̏Đg�ł���A�����l�A�`���������l�͊F�A���삵���Ƃ����B �ߒq�R�̈�p�A���@�R�̈���Ɏ��ɉ��Ɩ@�t�̉Β�O���Ղ�����B���`�ł́A�����n�������m�E�@�₪���̒n�Ŗ@�؎O�����C���āA�R���ɖ@�،o�o�A�߉ޔ@�������u�����̂��n�܂�Ƃ���Ă���B���@�R�̖V�ɂ͎߉ޔ@������{���Ƃ��Ă������A�O��3�N(1280)�ɐ^���ƔO�������C����ՍϏ@�̑m�E�S�n�o�S(1207�`1298)�ɂ��ċ�����(1)�A����ɔ@����{���Ƃ����y�M�̎��ɂȂ����Ƃ����B �ȗ��A���@�R�͔[���ƁA���҂����{������Ƃ��Ă̊ϔO���ݒn�ɒ蒅�����B�R�[�Ől���S���Ȃ�ƁA���т��������ԂɖS�҂̗썰�������̞���������@�R�ɓo��A����Ɏ��̖��Ԃ̏���ł��炷�Ƃ���A����́u�S�҂̌F��Q��v�Ƃ��ē`������Ă���B���@�R�ւ̔[���A�[���Ǝ��ҋ��{�͍����܂ő����Ă���A�u����A���̂��痣�ꂽ�썰�E�r���͎q���E�⑰�����{���邱�Ƃɂ���Đ���Ȃ��̂ƂȂ�A�R�̍��݂ɓo��B�R���͐��߂�ꂽ���҂̗썰���W�܂鐢�E(���E)�ɂȂ�v�Ƃ����u�R�����E�v(2)�̊ϔO�ɂ��c�搒�q�A���ҋ��{�̏K���̗��Ƃ��āA�F��̈�ʂł���u���҂̍��E�F��v���ے�����n�ƂȂ��Ă���B �u����E��\��@�g�쉜�R�̎��o�Җ^�v ���R�����s�����@���C�s���Ă�������E�`�͂́A�F��R�������ʂ�g��̋���R�ւƌ������B�������[�R�H�J�œ��ɖ����Ă��܂��A���܂悤���Ə\�����ɋy�B���̊ԁA�{�����F�O���O��炵�āA�悤�₭�����Ƃ����тɒ����B �����ɂ͐V���̏Ȃ�m�[������A�T���ł͓�\�Έʂ̐��l���@�،o���u���A���q�����d�����Ă����B�`�̖͂₢�ɁA�u���͔�b�R�����̎O������(�N�ی��N[964]�ɑ�17��V�����ƂȂ�����c)�̒�q�ł��������A��������Ă��܂��e�n�𗬘Q���Ă����B�V���ɓ����Ă���͂��̒n�ɋ����߂Ĕ��\�]�N�A�@�،o��ǂ݁A���������Ă���v�Ɛ��l�͂����B�X�ɓ��q�����d�����Ă��邱�Ƃ́u���y�s�i��\�l�v�́u�V�����q�@�Ȉ��g�v�̂Ƃ���ł���A��N�̂��Ƃ��́u��F�{���i���\�O�v�́u�������o�B�a�����ŁB�s�V�s���v���ό�ł͂Ȃ��^���ł��邩�炾�Ƃ����B���̔ӁA�m�[�ɔ��܂����`�͂́A�ٗޏO�`�̋S�_�E�b������W��A���l���@�،o��ǂނƂ����ڌ�����B�@�@�@�@ �����A�u��ي�L�̈ٗނ̐�`�͂�������藈���̂��v�Ƃ����˂�`�͂ɁA���l�́u�@�t�i��\�v�́u��l��Ձ@�䌭�V�����@�鍳�S�_���@�쒮�@�O�v�͂����̔@���ł���A�ƍ�����B���̌�A�`�͂͐��r�̓����ŎR���Ɏ���A���ɏo�邱�Ƃ��ł����B�`�͂͐[�R�̎��o�ҁE���l�̍�@���s��`�����A�����l�͐��삵�ė܂𗬂������̎҂����S�����Ƃ����B �u����E��\�O�@�I�ɍ����w�R�ɖ@�،o���u���鎀�[�v ���N�ɂ킽��@�،o�����Ă������͂́A�F������������A���w�R(�����w���E�a�̎R�������S�ƗL�c�S�̋�)�ňꔑ�����B�锼�A�@�،o���u�̐��������Ă������A������@�،o���u���O����q�A�߂���������B ���ɂȂ���͂�����Ǝ��[�̍�������A�ゾ�����Ԃ��N�₩�ł������B���x�������͂͂��̔ӂ��@�،o���u���A�������A�[���ƌ�荇���B���[�͔�b�R�����̏Z�m�E�~�P�ŁA�Z�����̖@�ؓ]�ǂ��u�����������قǂŎ���ł��܂��A���O�̗�����ʂ������߂ɂ��̒n�Ŗ@�،o�����������Ă����B���A�肢�͊��ɖ����A�c��̌o�͊�قǂ̂��̂ł��Ȃ��B���N�͂����ɏZ���A���̌�͓s���̓��@�ɐ��܂���ӕ�F�ɒl�����Ĉ��ۂ�ւ肽���A�Ƃ����B �����I��������͂͊[���ɗ�q���A�F��ɎQ�w�����B��N�A�[���������˂����ǂ��ɂ��������A���͂͐���̗܂𗬂����B �u����E��\�l�@�u�����̊⓴�ɏh���_��@�t�v �_��͏����S�̎������@�،o�������A��ɐ��̖��߂��}���A�ÊՂ̏������ߏC�s���鍹�傾�����B���鎞�A�쌱���ɏ��炷�邱�Ƃ��v�������F��ւƌ��������B�u���̍����߂��A�l�Ƃ��Ȃ��Ȃ�C�݂Ɏ������Ƃ���ŁA�⓴�ɔ��܂����B�⓴�̏�ɂ͎���������A�R�͊C�ɐꗎ���A��襂ɂ��ėH�A�Ƃ������ׂ��Ƃ���ł���B�܂��Ă�⓴���ɂ͈ٗl�Ȑ��L�����������߁A���|������A�g���S���x�܂邱�Ƃ��Ȃ������B�_��͈�S�ɖ@�،o���u���A�����邪�����Ȃ����̂��Ƒ҂��]�B �[��A��ςȕ��J�ƂȂ�A���������L�����̂��g�ɔ����Ă����B�C�����ƁA�傫�ȓŎւ������J���A���܂��ɉ_������ݍ������Ƃ��Ă���B�ނ͂����ɂ����Ď����߁A���悢��̐M�S���Ė@�،o����u�����B��킭�͌o�̗͂ɂ���Ė��I���肵�A��y�ɉ������Ĉ���ɑ��Ȃ����Ƃ��A�ƁB���������ւ́A������ł����߂Ă����܂��ɂ��Ď��߂̐S���N�����A�Q�������邱�ƂȂ������Ă������B���̎��A�\�J�ƂȂ��ė������̌��̂悤�ɋP���A�R�̐��͂��ӂ��������قǂ������B�v�������ĉJ�͂�B�����ɒ����̐l������A�_����h�������݂���ŗ�����Č������B �u���͊⓴�̎�ł��B�\���̐g���ďO�����Q���A�l�X�����������Ɛ����ƂȂ�܂��B���A���l�̖@�،o���u���鐺���A���Ɠ]�ł��đP�S����O�̂��̂ƂȂ�܂����B�����̑�J�͎��̉J�ł͂���܂���B���̗����藬��o�Â�܂Ȃ̂ł��B���Ƃ�ł������̂ɁA���I�̗܂𗬂��܂����B�����Ȍ�́A���S�������邱�Ƃ͂���܂���B(�㗪)�v�ƁA�����I������l�́A���������ւƋ����Ă��܂����B �_��@�t�͑�ւ̊Q�ł�Ƃ�Ċ���̔O���A�܂��܂����S���āA�O��@�،o�ɂȂ��A�x�����邱�ƂȂ��C�s�ɗ�Ƃ����B�Ŏւ���@�،o���āA�P�S�N�����̂ł���B��̐l���@�،o�őP�S���N�����Ȃ��Ƃ������Ƃ����낤���B �u�����E��Z�\�@�@���@�t�v ����@���͈�S�ɖ��@�،o���u���A��ӂȂ����i���d�˂�@�t�ł������B�т������̂͟����̎������B���ɂȂ薍��p���Đ��������邱�ƂȂ��A�ЂƂ��ɋN���č�����݂̂������B�njo�̎��́A�S�͗E�҂ɂ��đӂ�v���Ȃ��A��ɖ��@�،o���u�������A��ӂ̐S�����������͋x���������B����ȊO�͏�ɁA�o��ǂݑ������̂ł���B �@���͋���A�F�쓙�̏��X�̖��R�A�u��(�u�ꎛ��������)�A���J���̗쌱���ɎQ�w�B��X�̗쌱���R�ɏZ���ẮA�畔�̖��@�o����u�����B���{�����̈�̗쌱���ɏ��炵�āA�畔�̖@�،o����u�����̂ł���B �u�����E���\��@���~�@�t�v �V��̎R�m�E���~�͖@�،o����u�A�s�������ɕ�d���A�C�s�����d�ˌ��͂͌��R������̂��������B���鎞�A���~�͌F��R������ɓ������R�ւƌ��������A�[�R�̓��ɖ����O��s���̏�ԂƂȂ��Ă��܂����B��S�ɖ��@���u�����Ƃ���A���Ɉ�l�̓��q��������u�V�����q�@�Ȉ��g�@�ܓ��J�D�@�������H�v�ƍ�������B������o�߂����~�͐��������āA����R�Ɍw�ł邱�Ƃ��ł����B �u�����E���@�I�ɍ����ޔ{�S�̓��c�_�v �@�،o���u�̏C�s�m�E�V�����̓����͏�ɌF��ɎQ�w���A�������߂Ă����B�F�삩��̋A�蓹�A���ޔ{�̋�(�a�̎R�������S�݂Ȃג�)�̊C�ӂ̑�̂��Ƃɔ��܂����B �锼�A�n�ɏ�����l����A�O�\�R�قnj���āA�̉��ɏW�܂��Ă����B��l���u�̉��̉����낤���v�Ɩ₤�ƁA�������u���ł���v�Ɠ������������B�u���₩�ɏo�Ă��ċ�������v�Ƃ̌Ăт����ɁA���̐��́u�ו����n�̑����܂ꑹ���ď�邱�Ƃ��ł����A���ɗ����Ȃ��B�����ɂ͎��Â��邩�A���̔n�B���邩���ċ��ɎQ�낤�B���͘V���ƂȂ葫���������Ă��āA�ƂĂ������Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����B���������n�̐l�X�͕��U���Ă������B �����A�钆�̂ł����Ƃ�������������̉����߂��茩��ƁA���c�_�̑�������B���͌Â������Ă���A���N�����o�Ă���悤���B�j�̌`�͂����������̌`�͂Ȃ��B���̑O�ɂ͔̊G�n�����������O�����j�����Ă���A��������������͎��ŒԂ�₢���Ƃ̏��ɒu�����B�ނ͂��Ƃ̉���m�邽�߂ɁA���̖����̉��ɏh�����B��͂�锼�ɂȂ�Ƒ����̔n���W�܂�A���x�͉��͔n�ɏ��A���������ւƏo�Ă������B �������A�����A���Ă��ē����Ɍ������Č����B �u���\�̔n�͍s�u�_�ŁA���͓��c�_�ł��B���̓������鎞�́A�K��������G�̖��߂܂��B�������Ȃ����⚂őł��U�߂��A���t�Ŕl�i����܂��B��l���n�̑��������Ă��ꂽ�̂ŁA���̌����߂邱�Ƃ��ł��܂����B�@ ���A���͉���Ȃ�_�̌`���̂ĂāA��i�̌����̐g�悤�Ǝv���B�䂪�g�Ɏ�ꂵ�݂͖��ʖ��ӂł���A���l�̗͂ɂ���Đ��A���Ă������������v �����́u���̂悤�Ȃ��Ƃ͎��̗͂̋y�ԂƂ���ł͂Ȃ��v�Ɠ��������A���c�_�́u���̖̉��ŎO���O��A�@�،o��ǂ�ł��������B������A�o�̈З͂ɂ���ĉ䂪�g�̋��]���āA�̐g���邱�Ƃ��ł���ł��傤�v�ƌ������B �����œ����͌���ꂽ�Ƃ���ɎO���O��A��S�ɖ��@�،o����u�����B�l���ڂɓ��c�_������A���o�҂��q���Č����B �u���l�̎��߂ɂ���č��A���̔ڑG���̐g��Ƃ�A��������̌����̐g�āA��ɗ����E�ɉ������ω����ő��ƂȂ��ĕ�F�̈ʂɏ��낤�B����͖��@�������_�͂ł��B���Ƃ̋�����m�낤�Ǝv���Ȃ�A���̎}�ŎĂ̑D�莄�̖ؑ����悹�ĊC��ɕ����A���̍�@�����Ă݂Ȃ����v �����œ����͎Ă̑D��A���c�_�̑����悹�ĊC��ɕ��������ׂ��B���̎��͕����Ȃ��g���Ȃ������̂ɁA�D�͓���̐��E��ڎw�����X�ɑ��苎���Ă������B�܂��A���ޔ{�̋��̘V�l�������݂��B��̉��̓��c�_�����F�̕�F�`�ƂȂ�A��������Ƃ炵�P�����A���y��t�ŕ����Ȃ������̐��E��ڎw���A�͂邩�ɔ�я���Ă������B �����͂��̘b��M�A�V�����ɋA���Č��`�����B�����҂͐��삵�āA�F���S�����Ƃ����B �u�@�،��L�v�ł͑��ɁA�@�،o���o�҂��F����͂��ߊe�n�̗��Ő_�������b�Ƃ��Ė@�����ɏZ�������@�u�����E�攪�\�@�����̎��o�Җ��@�@�t�v�A�F��ɎQ�w�������o�҂����l�ς����ŎւɏP������@�،o�̌����ɂ��V�ɏ���Ƃ����u�����E�����@�I�ɍ��S���K�S�̈��������v���Љ��Ă���B �����u�@�،��L�v�́u����v����́A�����̖@�؎��o�҂��F��Ɍ������Ă������Ƃ��m�F�����B����E�`�͂Əo�������b�R�O������̒�q�ł���Ⴋ���l�ƁA���[�ƂȂ��Ė@�،o����u����������b�R�����̏Z�m�E�~�P�A�V��̎R�m�E���~�̘b������́A�����ɓV��m���������Ƃ��킩��B�܂��A����E�`�́A�Ⴋ���l�A���~�̘b����́u�@�،��L�v��������镽�������̒��v�N��(1040�`1044)�ȑO����A�F��Ƒ�������ԎR�ѓl�M���s���Ă������Ƃ��ǂݎ���Ǝv���B�@ |
|
|
��(2)�@��
���������̌����E�O�P���s�̎q�ł����(891�`964)���A�F��Ƒ���ɉ�����V��m�̈�l���B �u��@�t�`�v�ɂ��ƁA��12�ŌF��E�������̏����̗��ŏC�s��ς݁A16�Ŕ�b�R�̌��ƈ�苗��������E�E�ّ��E�E�h���n�̎O���̑�@��`������A18�ɂȂ�Ƒ�d�@�t�ɐ����Ď��܂��w�B19�̎��ɂ͔�b�R����̑ۓ����Ă�A�Z����։�O���̔���^�y�̂��ߖ����A�@�،o�Z������u�B脉����������Ė���A�Z�甽��q���s�����B23�A��l�ő���ɓ���B24�̎��A����R�E�����R�ŏC�s���A���s�҂䂩��̌A�ŕs�������������B����15�N(915)�A25�̎��ɓߒq�R�ɓ���A�ߒq��̑����œ���A�@�،o�Z�����u����@���g���E�\������͂��l�������Ƃ����B �u��@�t�`�v�ɂ��Ă͈̐l�`�I�Șb����쌱杂������A���̓_�ɂ��Ă̎�e�ɂ͐T�d�ɂȂ炴������Ȃ����A�V��m�̏��F����͂��ߏ����̗����߂���C�s���Ă����A�Ƃ�������Ƃ��Ă͈��p�ł���Ǝv���B (�̌F��E�ߒq�C�s�ɂ��ẮA�u14�@���n�Ɍ����������ҁv�̍��ł���Ɍ�������) �u��@�t�`�v����E�F��W�� �E�\��E�E�E�E�w�F�����������n�A���C��߁B �E���\�Z�����ƎE�O���V��@�B �E�\���ΐ���d��@�t�A�ܑ�@���R�a�������V��q��A�K�w���܁B �E�\��ΐ����O�ӔN�A孋�����ۓ��A�טZ��Q�ޔ���^�y�A�����u�@�Ԍo�Z���A�O���C�s�@�A�Z����脉��A��s�Z�甽��q�B �E���O�ΓƓ����A�S���Ɣ��O���B �E���l�ΐ��������������؎R�A�ȌI�ב��Ɩ�B�A�������R��J�B�E�E�E�E�O���\�O���������A�A���A�̖��s�ҔV���Z��B���������鐋�ȕs������S�u��A�������V�e���B �E���܍ΉB���ߒq�R�A�����O�N�A���뉺��佈ȉʑ�萋�A�����ǘ@�o�Z���A�Z���C�s�@�A���ȓ�g��A����������A���^�������Ջ��A���t�אH�A���������V���A�ӑۈ߁A�g���h���V�v�A�@����s�s�̌v��B���N�����A�{�t���������H�A��������S���s�ÁA�a�}屢�N�P�b�s����Aॐ���ʖ쎝��E�E�E�E���㗥�t�����Y�C��A��R�O�N�^�߈ȏo���B�@ |
|
|
��(3)�@���R���N
�u�@�،��L�v�Ɍ�����R�ѓl�M�Ɋ֘A���镶���Ƃ��āA�u���R���N�v������B�����ɂ��Ε�������A�F��ŏC�s���ĎR�т�l�M�A�������R�яC�s�̐��n�E�g��̑���R��ڎw���C�s�҂��������Ƃ�����������B�����́u������쓹�v�̊J����Ƃ����邾�낤���B���A��̖{�R�h(���鎛�n����@)�Ɠ��R�h(��펛�O��@)�̎���ɂȂ�ƁA�F��{�{����g��Ɍ������̂������A�g�삩��F��{�{�ւ͋t���ƌĂ��悤�ɂȂ�A�����͖{�R�h�A�t���͓��R�h���哱�����B �u���R���N�v ���P�̔N�A�T���n�߂ČF�쌠���̌��O�ɎQ���āA�s�ӎ����ɕL��ʁB����ɓ�����Ă�B�\��N�̏t�A�ّ��E�̌����o�łāA���\�O�N�̍M�Ђ̔N�ɁA�����������E�̏���ɓ���B�����̈ʑ��������F埵�̈ʁA�������͂ꋋ�ӁB����F���̐����(�܂���)���B�����̍s�҂̂��ߏ��X�Ɏ����L���B����F�̛Ԃ̏Z���Ȃ�B�m�@�m�邱�ƓƂ�Ȃ�B��q�ɌZ�͒m�炸�B�ނ���ɏ��������{�����ׂ��A��F�̈ʂ����O���ׂ��B��X�̗쏊�A���V���l�̏Z�ޏh���A�F����A�Ɖ]�X�B ���ꂪ���͂ǂ���A���N���̈���P����ŁA7���I�̂��ƂƂ���ɂ͖���������悤���B�u�F�쌠���̌��O�v�Ƃ��邪�A�����ƌď̂����̂́A��ɂ݂�u�F��{�{�ʓ��O�j��O�����v�Ɂu�O�������̌쎝�v�Ƃ���i��3�N(1083)�̍��Ȃ̂ŁA7���I�Ɍ����ƌĂԂ��Ƃ͂܂��͂Ȃ��B�F�쌠���ɎQ�w�����T���Ƃ����l���ɂ��āA�u���{�v�z��n��\�@���R���N�v�́u�⒍�v�ł́A�u�F��ʓ�����Ƃ���邪�A�ړ`�͕s���v�Ƃ��Ă���B�㔼�ɏo�Ă���A�u�m�@�̓`�L�����炩�łȂ��v�Ƃ���B �g��ƌF������ԑ�����쓹�́A�߉ރ��x���k�ɍE���x�������r���̊��Ɂu���������v�ƌĂ��Ƃ��낪����A�g�쑤�������E�A�F�쑤��ّ��E�Ƃ��Ė����̙�䶗����E�Ɍ����ĂĂ���B�����́u�ّ��E�̌����o�łāv�u�����E�̏���v�Ƃ����̂�����ɂ�����̂��낤�B�ȉ��A�{���́u���g�����@���@���ӂ̏h������̓��A�l������B�ꏊ�͍ːg�Ȃ�B����ɓ���B�̒��Ɉꏊ����v���A���ۂ̎R�X�������E�ّ����E�̙�䶗��ɓ��Ă͂߂ċ�̓I�ɉ�����Ă���B �u���R���N�v�̕����ɂ́A �u�ߏ�A�{�̔@���ʂ�����ʁB�c���{�Ȃ�B�ߏ�A�s�@��(�����[���^���̑��Ȃ�)���ȂĂ�������ʂ����ߗ���ʁB�A�������̖ނ��s�R�Ȃ�́A���ׂ��炭���{�𐿂ЂĂ�����������ׂ��̂c���{�Ȃ�v�Ƃ���B ���䓿���Y���́A�u�����N�����m�肷��̂͂ނ���������ǂ��A�����Ɍc��(���njo�̒j�A1189�`1268)�̉���������A�܂��{�����Ɍ��v3�N(1192)�̔N����A�F��ʓ��X��(����4�N[1174]��)�E�X��(���i�܂��͕����̍��ʓ��ƂȂ�)�̖����݂���̂ŁA�����������̂��Ƃ��c���̏����ł��邱�Ƃ��m���Ȃ�A���q����������ȑO�ɕҏW���ꂽ�Ƃ݂Ă悢�v(3)�Ɛ����N���𐄒肳��Ă���B�������ɁA�u�F�쌠���̌��O�v�Ƃ̖{�n��瑐������ȍ~�̕\���ƁA�g��ƌF������ԑ������̎R�X�������E�E�ّ��E��䶗��ɓ��Ă͂߂Ă��邱�Ƃ��炷��A���������犙�q�����̕Ҏ[�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���B ��Ɍ����悤�ɁA�F��̉i���T�t�̂��ƂŏC�s���A�R���Ŏ̐g�s���Ȃ����@�،o���o�҂�`�����u���{��ًL�v�̐����̎��A�O�m�N��(810�`824)�ɂ́A�R�ѓl�M�Ɖߍ��ȏC�s���F��Ǝ��ӂ̐[�R�ōs���Ă������Ƃ�����������B���Ɍ����u�@�،��L�v����́A���������ɂ͌F��Ƒ���Ƃ�����̐��n�����ԎR�x�H���J����A�@�،o�̎��o�҂��������Ă������Ƃ��m�F�����B�����āu���R���N�v�ɂ��A���������ɂ́A���̓����͏ڍׂȏ@���I�Ӌ`�t�����Ȃ���A���n�������̂��@���I�ɐ��Ȃ�C�s�ƍ��߂��Ă������Ƃ����������B�@ |
|
| ��7�@����@�t�̋I�s���u���قʂ��E�F��I�s�v�@ | |
|
����@�t�́u����āA�S�̂܂܂ɂ���ށv�Ǝv���A�u���̒��ɕ����ƕ������X�A���������v�������˂āA�܂��u�������ǂ���q�ݕ��A�킪�g�̍߂����łڂ��ށv�Ƃ��āA�����̖����E���Ղ������˕������B�ނ͂���N�̓~�A��l�̓��q���ČF��ɎQ�w���A���̖͗l���̏W�ł���I�s���ł�����u���قʂ��v(������L)�́u�F��I�s�v�ɋL���Ă���B�@�@�@
�u���قʂ��v(1)��11���I�����ɂ͐������Ă��āA��������̌F���m�邱�Ƃ̂ł���j���̈���B����ɂ��ƁA�{�{�ɂ͈�����200����300������A�~�Z����C�s�҂͗瓰�ɏo�d���ė��@�̋s���s���A�z�����Ȃ���ɗ�����u���Ă����B�����ɂ͓V��̖@�ؔ��u���s���Ă����Ƃ����B �u���قʂ��E�F��I�s�v�̌F��Q�w�� ������O���Ƃ������A��R�ɒ����ʁB��������������Č���A�����ǂ���A�O�S������̂��A�v���v���ɂ�����l�����Ƃ������B�e�����m�肽��l�̂��Ƃɍs������A����������(�ӂ���)�̂悤�Ɉ��������āA�ɞZ(�ق������E�R���c������)�Ƃ������̂ɂ��āA�܂�˂ɐQ(����Q)����B���ƌ����A�����āA�Ƃ����苋���ƌ����ē���A���ق邶����ƂāA����(���������E��̓������)�̑傫���Ȃ���̓������o���ďĂ����B���ꂼ���̕�ƌ����A���͓��̊Â��₠���ƌ����A�l�̎q�ɂ����H�킹�߂ƌ����āA�����߂�����A���ď��łĂΌ䓰�֎Q��ʁB��������݂āA���������A�����������ɐ��m�炸�w�ŏW�܂�āA��ʂĂĂ܂���o��ɁA���͑m���̌�O�Ɏ~�܂������B�瓰�̒��̒��̂��ƂɁA���������E�т₩�Ɋ����������������B�z�Â��ɗ���ǂނ�����B�l�X�ɕ����ɂ����A����͂ɂ��ƕ���������B�����Ă��Ԃ炤�قǂɁA�����̌䔪�u�ɂȂ�ʁB���̗L��l��Ȃ炸�����ɑ����B���u�ʂĂĂ̖����ɁA����l������������������B ���납�Ȃ�S�̈Âɂ܂ǂ��@�����ɂ߂����g�炵�� ���قʂ������̎���^�S�ɂ����S�̂��Ƃ��Ǝv���B �����̌��܂��o�ďƂ炳�Ȃށ@�����Ȃ�R�̉�(����)�ɂ���Ƃ� �܂��N����Ƃɐs�����邱�Ƃ������� �ʂ̏������ԐS�̂�����Ȃ��@�łƂ��Ă̂݉߂����邩�� ���Ă��Ԃ炤�قǂɁA���������̂قǂ̖����܂��o�Ȃ�ƂāA�����͂̂�ɗV�ׂA�l�b�����Ԃ炢���������B�_�������������킶�Ȃnj����قǂɁA�������날��āA �R���炷��������������ɂ���@�䂪�A��ׂ����◈�ʂ�� ���Đl�̎�(�ނ�)�ɍs������A�w��l�̕������A�͂���͂��߂����Ƃ�Ď���A���̎�A���̎R�͞ɞZ(�ق�����)������āA�͂��͂��Ƃ��\���ƌ����A�������Ȃ��ƌ����Ĕ����ʁB (�Ӗ�) �x���n�Łu����̐_�Ƃ���������̐_�ɂ����������A�[���F�O��������ɂ́@�肤���͎������A����ł��낤�v�Ɖr��ł���O����A�F��̖{�{�ɒ������B�����炱����Ə����Č���A��������A�O�Z�Z����A�v���v���Ɍ��Ă��Ă���l�͎��Ɏ�[�����̂�����B�e�����m�肠���̂��Ƃɍs���Ă݂�ƁA�������ɖ��(��)�̂悤�ɂ����āA�R���c�����؍�(�ɞZ)�ɂ��āA����Q�����Ă���B���A����Ƌ����N���āA�u�ǂ���������Ȃ����v�ƌ����A���ɏ����ꂽ�B�����̎�͂��ĂȂ����ƁA��Γ���(����)�قǂ̑傫���̈��̓������o���āA��q�ɏĂ����Ă����B�F�ň���H�ׂĂ���ƁA�m�l���u���ꂱ�����̕�ł͂Ȃ����v�ƌ����̂ŁA�����u���Ă͓��̊Â����낤���v�Ɖ�����ƁA�m�l�́u�Ȃ�Ύq���ɂ����H�킹�������̂��v�ƕԂ����肵�āA�a�₩�ɒk���Ă����B���̂����ɏ����ł��炳�ꂽ�̂ŁA�F�Ō䓰�ւƌ��������B �䓰�ɂ́A�����U���Ȃǂň�����ݖ��𒅂��������A�����������ɂƐ��m�ꂸ�W�܂��Ă���B�荏�̋s(�)���I���ޏo�ƂȂ������A����҂͑m��(�F��ʓ��̂��Ƃ�)�̌�O�ɂƂǂ܂�A����҂͏ؐ��a�̗瓰�̒��̂��ƂŁA���𒅂��܂ܔE�т₩�Ɋ���U���ȂǂɈ�������Ă���B�܂��z�Â��đɗ����ǂ�ł���҂�����B�njo�̐��͗l�X�ł��蕷���Ƃ�Ȃ��قǂ̌����ŁA�u�����傫������v�Ƃ̍r�������������Ă���B �䓰�Q����d�˂Ă��邤���ɁA�\�ꌎ�̖@�ؔ��u�̓��ƂȂ����B���̗L��l�͏�̂��̂ł͂Ȃ��A���ɂ��肪�����������̂ł���B�@�ؔ��u���I����������A����l�������r��ꂽ�B �u�����Ȃ�S�̈Â��ɖ����Ȃ���@���������߂���䂪�g�̐h�����Ƃ�v ���قʂ�(����@�t)�����̉̂Ɋ������āA�����Ɉ�r�Ȑ^�S�������̂��Ƃ��ł���Ǝv���B �u�������Ȃ錎�͂܂�����Ƃ炷�ł��낤�@�d�Ȃ�R�̉����֓��낤�Ƃ��v �܂��A�N���A�o�Ƃ����ɂ������Ƃ������� �u�ʂ̏������Ԃ悤�ɐS���ł߂Ă����̂Ɂ@�����̂��Ƃɂǂꂾ���̎����߂����Ă��܂����̂��낤�v ���āA���̂悤�ȓ��X���߂��������ɁA�\�ꌎ��\�����ɂ͏o�����悤�Ǝv���A������̊ݕӂł̂�т肵�Ă���ƁA����l����u�����b����������Ⴂ�B���A�o���Ȃ���̂́A�F��̐_�������Ȃ����Ƃł��傤�v�ƌ���ꂽ���A���̎��A���̔����G�����ł���̂��������B �u�R���炷�̓��������Ȃ����悤���@�䂪�̋��A��ׂ����������̂ł��낤�v �������āA����l�̈����ւƍs���Ă݂��Ƃ���A�w(�Ђ̂�)���Ă���̂ł��낤�A�̕����͂���̂����Ă���ƁA�����̎傪�u�F��̎R�ł͔R���c��̖؍�(�ɞZ)�Ɍ�������A�w�͂��͂��x�Ƃ����̂��v�Ƃ����B���قʂ��́u�d���R���鐺�Ȃ̂ł��傤�v�Ɠ����A�F������B �ȏ�A�u���قʂ��v�̈ꕔ�������̈��p�����A�����̖{�{�̕��i�ƂƂ��ɑ���@�t�̐S�����`���o���ꂽ�悤�Ȗ��킢�[���I�s�����Ǝv���B���A��������ɂ͖{�{�E�V�{�E�ߒq�̊e�R�ɏ�Z����m(��O�E�O�k)�̒��ɎO���m�����āA�@�؎O���ɏ]�����Ă������Ƃ���������m�F�����B �u�{�����I�v�m��3�N(1153)3��5����(2) �m���@�@��F��w�� �{�{ ����m�s�L�ρ@��،o���{�䓱�t �@���X���@�ʓ��X���� �����t�s���@���B �����@�����@�y��C���� �V�{ �@���͒q�@���ʓ��s�͏� �ߒq �@�����_�@�O�����C���� ��苗����ρ@�q�m �u��L�v�m���O�N(���O)�����\�ܓ���(3) �E�E�E�E�F��V���O�����̎��E�E�E�E �u�㒹�H�@�������v�����N(�����)��(4) �E�E�E�E�V�{���E�͔I�X���A�{�{��E�͎O���m���A�ߒq��E�͎Вd���d�����E�E�E�E �F��E�ߒq�̊e�R�ɂ́A��Z�m�ȊO�ɂ��������s�r���鑽���̋q�m��������Ă��āA�{�{�ƐV�{�ł́A�Гa�O�̗�a(����)�ɏo�d���Ė@����s���Ă������Ƃ��璷���O�ƌĂꂽ�B�����O�͏������܂��F�쌠���̗쌱������A�����̏C���҂����Ă����B��Ɍ���A���q����̈�Ղ̌F�쐬����`�ʂ����u��Ր��G�v�ɂ́A�u�{�{�ؐ��a�̌�O�ɂ��āA��ӂ��F�����A�ڂ���Ė�������(�܂ǂ�)�܂���ɁA��a�̌�˂������J���āA�����Ȃ�R��̒����Њ|���ďo�ŋ��ӁB�����ɂ́A�R��O�S�l����A���n�ɂ��ė�h�����B�v�ƁA�����O���o�ꂷ��B �ȏケ��܂Ō��Ă����u���{��ًL�v�u�O��G���v�u�@�،��L�v�u��@�t�`�v�u���قʂ��v������́A�F��̗���K���@�،o�̎��o�҂͓ޗǎ��ォ�炠��A����͕������ɓ��芈�����������ƁB�F��E�ߒq�́A�Â��@�،o�M�L���̒n�ƂȂ��Ă������ƁB�F��E�ߒq�ł́A�V��m�ɂ�苳���ʂ��ڐA����Ă������Ɠ����ǂݎ���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B |
|
| ��8�@�M�a�O���̎Q�w�@ | |
|
��(1)�@��c�E���Ƃ̎Q�w
�F��O�R�ɂ͔��͏�c(1053�`1129)��9��A���H��c(1103�`1156)21��A������c(1119�`1164)1��A�㔒�͏�c(1127�`1192)34��A�㒹�H��c(1180�`1239)28��A�y����c(1196�`1231)2��A�㍵���c(1220�`1272)3��A�T�R��c(1249�`1305)��1��ƁA����c���͂��ߋM���̎Q�w���������B�P�s���d�˂�قǂɌF��O�������̌����������Ƃ����A�u������P�����M�v����c��̌F��w�ł̉ɕ\��Ă���悤���B���ɌF���34��Q�w�����A�㔒�͏�c������̗w�W�u���o�鏴�v(�����N��[1177�`1181]����)�ł́A�F��Ɋւ���̂������ڂ����Ă���B �u����@�l��_�́@�_���v �_�̉Ƃ̏����B�́A�����̎�{�A�F��̎ቤ�q�q���O ��b�ɂ͎R���\�T�t�A��ɂ͕Љ��M�D�̑喾�_ �F��֎Q��ɂ́A�I�H�ƈɐ��H�̉���߂��A�ǂꉓ���A �L�厜�߂̓��Ȃ�A�I�H���ɐ��H�������炸 �F��֎Q��ɂ́A�����ꂵ���@�C�s�҂�A �����P���ܗt���A�痢�̕l �F��֎Q��ނƎv�ւǂ��A�k�����Q��Γ������A������ĎR�s(����)���B �n�ɂĎQ���s�Ȃ炸�A����Q��ށ@�H��(�͂˂�)�ቤ�q �F��̌����́A�����̕l�ɂ����~�苋�ցA �a�̂̉Y�ɂ��܂��܂��A�N�͂䂯�ǂ��ቤ�q �Ԃ̓s��U�肷�ĂāA���ꂭ��Q��͞O(���ڂ�)�����A ���͌����䗗����A�@�̊��N���� �u����@�l��_�́@�m�́v ���̏Z���͉����ǂ����A���ʂ揟����B�d���Ȃ�A���ʂ̎R�A �o�_�́B�k����B���̌��A��́B�F��́B�ߒq�Ƃ��� ���̏Z���͉����ǂ����A���̒ƁA ���ʂ揟����@�d���̏��ʂ̎R�A��͌F��̓ߒq�V�{ ����ʂ�ɂ́A���@�C�s����m���A�B��l�A ���q��͓��ŋ��ЁA���哶�q�͐g����� �u����@�G�@���\�Z��v ����đ������A�W(�͂�����)��(�͂�Ԃ�)��Ȃ��A ��̐��A�R��藎������ĎԁA�O�����ɐ\���� �F��̌����́A�����̕l�ɂ��~�苋�ӁA �C�l(����)�̏��M�ɏ�苋�Ё@���߂̑��������ꋋ�ӁA �u����@�l��_�́@�_�Љ́@�F����v �I�̍��▴�K�̌S�ɍ�(����)���܂� �F�염���͌��ԑ��� �F��o�łĐؖڂ̎R�̞�(�Ȃ�)�̗t�� ��(��낸)�̐l�̏��(���͂�)�Ȃ肯�� �Q�w�҂͌��ւ̌�A�������k���Ē��B�ɂ���{�{(1)�ւƌ������B����́A�u�F��w���L�v�Ɂu������ʂ���B�̓������Ɛ\���v�Ƃ���悤�ɁA�u�ʂ��炶�̓����v�Ƃ���ꂽ�B�ؐ��a�ʼnƓs����q�_��q���A�E�o���{���s������҂͌��������A�㐶�P���A����҂͋Ɋy������������B�{�{�̌�͌F����D�ʼn����ĐV�{�ցA�����ēߒq�ɎQ�w�A�O���̋ߖT���J��ꂽ�_�X�����q�����B ���ɗ���c�̎Q�w�ł́A�R���̑m�����W�߂Čo���{���t�̂��ƌo�T��]�ǂ����߂Ĉ�،o�A���D��ʎ�o�A�ܕ����o�A���D��،o���̋��{���s���A�X�Ɏʌo�̕�[�A��m���{���s���Ă��āA�u���قʂ��v�̋L���ƍ��킹����ƁA���̑ԗl�͕������ł������Ƃ�����Ǝv���B�@ |
|
|
��(2)�@�{�n���̐ݒ�
���������̕��l�E��w�҂ł���c���ۈ�(�悵�����̂₷����)�́A���a�N��(985�`987)�Ɂu���{�����Ɋy�L�v��Ҏ[�B���̖`���ɂ́A���̂悤�ɂ���B �\(���)����������ɕ���O���A�s�N�l�\���ȍ~(���̂���)�A���̎u���悢�挀(��������)���B���ɖ��������ցA�S�ɑ��D���ς���B�s�Z����b�����Y�ꂸ�A����顚��(�������Ă�͂�)�K������ɂ����Ă���B���ꓰ�ɓ��_�ɁA��ɂ̑�����A��y�̐}������A�h�点���邱�ƂȂ��B�����j���́A�Ɋy�Ɏu����A��������ӂ��Ƃ���҂ɂ́A���������邱�ƂȂ��B�o�_�`�L�ɁA���̌���������A���̈������q�Ԃ���̂��A��{�����邱�ƂȂ��B �ۈ��̈���ɕ��ւ̌����M���`����Ă���L�q�����A������20�N���O�̉��a4�N(964)�A�ނ͑�w���I�`���̊w���A�V��m�Ƌ��ɁA�O�����ЂƂ������ׂ��u���w��v���n�߂Ă���B�����ōs��ꂽ�̂́A�ۈ��̋L���Ƃ���ł́A�u�����A��؏O�������ď����m���ɓ��炵�ނ�́A�@�،o����Ȃ�͂Ȃ��B�̂ɐS���N���������āA���̋����u���B���ʂ̍ߏ��ł��ċɊy���E�ɐ�����́A��ɕ��ɏ�����̂Ȃ��B�̂Ɍ����J������g���āA���̖��������Ӂv(2)�Ƃ������̂ŁA�V���y���̖@�ƔO���̕��C�M�ł������B �u�@�،o��������؏O���������m���ɓ��炵�߁A�O���ɂ��Ɋy���E�ɐ�����v�Ƃ̐M�́A�u���E��ځA�[�E�O���v�Ƃ������t�Ɏ������悤�ɁA�����̋M���A�m���w�ɍL�܂��Ă����B���̂悤�ȁA�@�،o�ɂ�茻���̒m�b�A�����������Ĉ���ɐM�ɗ�Ɋy��y�ւ̓����������҂����H�E��H���z���ČF��Ɍw�ł�A�����ł͎���̐M�����e����悤���A�܂�����鑤�����́u�肢�v�Ɓu���߁v�ɉ��������̂�p�ӂ��邱�ƂɂȂ�B �i��2�N(984)�~�ɐ��������u�O��G���v�ł́A�u���̎R�̖{�_�v�ł���Ɠs����q�_�́u�ؐ��ꏊ�Ɩ��Â��v���A�F��̐_�X�ɖ{�n�����ݒ肳���G�肪�݂�ꂽ�B �u�}�K���L�v�i��2�N(1082)10��17�����ɂ́A�u�\�����b�q�B�F��R�Ɨ���O�O�S�]�l�B�ו��V�{�ߒq���[��`�B���W���c�R�B�b����`�����R���B��O�Q������B�i�������ِl�E��O���V���B�v�Ƃ���A�F���O���V�{�E�ߒq�̐_�`��ď㗌�������Ƃ��L����Ă���B���̋L�q�́u�ߒq�v�̎j����̏����Ƃ���A���i�Ő_�`����������(3)�Ƃ������B �F��ʓ����_�̂̉��̂�i�����i��3�N(1083)9��4���́u�F��{�{�ʓ��O�j��O�����v�ɂ́u�O�������̌쎝�v�Ƃ����āA���̍��ɂ́A�O�R�����ʂ��Č������Ղ�u�F��O�������v���������Ă����ƍl������B�܂��A�u�����v�Ƃ��邱�Ƃ���A�i�۔N�Ԃɂ͌F��̒n�͐_�����K�����A�{�n��瑐��ɂ��_������Ă������Ƃ����������B ���H��c�̌F���K������d�˂鍠�ɂ͌F��O�R�̐_�X�̖{�n������܂�A�u���H�L�v����3�N(1134)2��1�����ɂ́A�u�F��\�����v�̖{�n���������߂��Ă���B���H��c�ƑҌ���@���q(1101�`1145)�̌F��Q�w�ɓ��s�������t��(1077�`1136)�́A�F��O�������̖{�n�����B�ɖ₢�A���̓����Ƃ��āu�告(�ؐ��a�E�{�{)�̘a���ƒÉ��q�v�́u����ɕ��v�A�u���{(�V�{)�̑��ʖ��_�v�́u��t�@���v�A�u���{(�ߒq)�̌��{�v�́u���ω��v�Ɖ���Ă���B �u���H�L�v ����A�ȕX�t���]�A���H�䓰�p�؊��@���A�]�A�R�ҁA����B�A�Ԍ얾�{�n�A �告�A�@�a���ƒÉ��q�A�@�@�`����ɕ� �����A�@���{���{�A���`�A�@�{�n���ω� ���{�A�@���ʖ��_�A���`�A�@�{�n��t�@�� �ߏ�O�� ��{�A���`�A�@�{�n�\��� �T�t�{�A���`�A�@�{�n�n����F ���{�A�@�`�A�@�{�n������F ���{�A�@�{�n�@�ӗ֊ω� �q��A�@���ω� �ߏ�����q �ꖜ�����A�\������A�����\���A�߉ށA��s�鍳�A�s�����A�Ď��������q�A毗����V�A��a���������q�E�E�E��A ��������ɂ́A�F��̐_�X�͖{�n�������̎p���Ƃ茻�ꂽ���́A�����{�n��瑐��Ō����悤�ɂȂ�A�{�{�͈���ɔ@���̐�����y�A�V�{�͖�t�@���̓����ڗ���y�A�ߒq�͊ω���F�̕�ɗ���y�Ƃ���A�F��̒n�́u�R�����E�v�ł���Ɠ����ɁA���E��F�̏�y�ƊϔO�����悤�ɂȂ��Ă����B���̐M�́A������d�˂邲�Ƃɋ��܂�A�������́u�F��R���L�v(�i��2�N�E1430)�ɂ��u�ؐ����F�ƒÔ����ҁA�{�n���ʎ�����瑖�v�u����O�@���{�ҁA�{�n�����ώ��ݑ���瑖�v�u���������ʂ̋{�ҁA�{�n��t�@����瑖�v(4)�ƋL����Ă���B �{�n������߂�ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�Гa�ɂ��̑����������ꂽ�Ƃ������Ƃł�����B�a�̎R����o�s�̐^���@�L�R�h�E�ՏƎ��ɂ͖ؑ��O�@��t����������A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B�����̑ٓ��w�ʂ��甭�����ꂽ�n�����ɂ́u�F��O��R�啧�t�lj~�@�i�m��N�b�ߏ\���O���@�i�V���߁v�Ə�����Ă��āA�i�m2�N(1294)���A�F��O�R�̕��������Ă������t�̑��݂��m�F�����B(5)�@ |
|
|
��(3)�@�F��M�̐S
�����ŁA�F��ɎQ�w�����Â̐l�X�̐S�Ɏv�����͂��Ă݂悤�B 11���I�����ɂ͐ݗ������u���قʂ��v�̒��ҁE����@�t�́A�F��ւƌ������ɂ��������S�����̐l�炵���L���Ă���B �u������̂��Ƃɂ����肯�ށB����āA�S�̂܂܂ɂ���ނƎv�ЂāA���̒��ɕ����ƕ������X�A����������q�˂ĐS�����A���͑������ǂ���q�ݕ��A�킪�g�̍߂����łڂ��ނƂ���l�L�肯��B���قʂ��Ƃ����Ђ���B�v �����𗣂ꎩ��̐S�̂܂܂ɂ��낤�Ǝv���A���̒��ɓ`�����閼���A��̂��鏊�������˂ĉ䂪�S�����������Ԃ߁A�܂����n�E�����߂���q���Ă킪�g�̍ߏ��ŋp�����悤�A�Ƃ�����������˂��̂��F�삾�����B�����ɓ����̐l�X���F��ւƌ��������u�v���v�Ɓu�肢�v�̈�[���\������Ă���Ǝv���A����́u�S�̉���E�Ԃ߁v�ł���A�u�ō߂Ɛ��P�v�ł͂Ȃ������낤���B �V�m2�N(1109)10��26���A�{�{�E�ؐ��a�ɎQ�q���������@��(1162�`1241)�́u�����A�K���ɂ��ĎQ�w�̑�]�𐋂��A�ؐ��a�̌�O�ɎQ��B���ܗ}����A���슴�x����B�����̔@�����A��߂ďh���L�邩�B�O��̑�萬�A�����m��B�v�Ɠ��L�ɋL���Ă���(���E�L)�B ���m���N(1202)�A�������(1162�`1241)�͌㒹�H��c�̌F��Q�w�ɋ��A���̖͗l����L(�F�쓹�V�ԋ��L)�ɋL�^���Ă���B10��16���A�u�R��痢���߂��A���ɕ�O�ɕ�q�B���܋ւ���v�Ɗ����̒��Ŗ{�{�E�ؐ��a�ɎQ�q�B17���ɂ́A�u�F��Ƃ���͂����A�������o�����A�ՏI�̐��O�Ȃ�v�Ə����Ă���B (�F�쓹�V�ԋ��L[���͌㒹�H�@�F���K�L�Ƃ�]�͒�Ƃ̓��L�u�����L�v����̔���) �u���ƕ���v�ɂ���A���ې�(1158�`1184)���F��̊C�œ�������O�ɎO�R���w�ł����̕`�ʂ́A�����������������q���ɂ�����u�F��M�̐S�v��L���ɕ\�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �u�ؐ��a�̌�܂ւɂ������ЂA���炭�@�{�Q�点�āA��R�̂₤���������ӂɁA�S����������ꂸ�B��ߗi��̉��͌F��R�ɂ��Ȃт��A�쌱���o�̐_���́A�����͂ɐՂ�����B���C�s�݂̊ɂ͊����̌����܂��Ȃ��A�Z�������̒�ɂ́A�ϑz�̘I���ނ����B���Â�����Â�����̂������炸�Ƃ��ӎ��Ȃ��B�v �u���R����(�{�{�E�ؐ��a)�͖{�n����ɔ@���ɂĂ܂��܂��B�ێ�s�̖̂{�肠��܂����A��y�ֈ��������ցv �u�ߒm�̌�R�ɎQ�苋�ӁB�O�d�ɟ��肨���̐��A�����܂ł���̂ڂ�A�ω��̗쑜�͊�̏�ɂ���͂�āA��ɗ��R�������ׂ��B���̒�ɂ͖@�ԓ��u�̐�������A��h�R�Ƃ��\���ׂ��v ���v�̗�(���v3�N�E1221)�̍�����́A�k�ɐ��̓������d(���v�N�s��)�́u��P���L�v�Ɍ�����悤�ɁA�n�����m�ɌF��M���Ђ�܂葽�����Q�w�����B�i�m4�N(1296)���ɐ��������̗w�W�A�u���ȏ��v��́u�F��Q�w�v�ɂ́A���H�y�X��H���z���āA�悤�₭�̎v���Ŗ{�{�̒n�Ɍw�ł��l�X�̊�т��A�����L���ɂÂ��Ă���B �u�R���ɏ��]�߂A���؎}��A�ˁA����(�܂�����)��(�݂ǂ�)�A(����)��(����)���A���͔�(�Â�)�ɐ܂�A��(����)�͛�(�Ă�)�ɒʂ��ċt��(�����̂�)��B�o��o��Ă͎b���x�݁A�Ί�̕�(�قƂ�)�s�X(�䂫�䂫)�ẮA�Ȃ����A�H�X(�䂤�䂤)����Ƃ���B���̉_�ɖ�(����)�ޕ��Ȃ�A���ɍ���(�����͂�)�̖����݁B��(��)��~���⍪�͑��́A���q���߂��čs���O(����)���A�͂�ߘI�ɂ��ʂ��B�O�]��(�Ђ��͂�)������̉��ɁA�͌͂ꊦ����U��A�Ԃ��ƕ�(�܂�)�ӌp��(��������)�B��_�E���̉͂͂��ƁA��`���z���ĖT�`(���Â�)�ЁA�ՒJ(����)�l�A�H(�܂�)�Ȃ�B���̈ꐺ�A��(�Ȃ���)�̕X�A���̐�A�����ƂɎ₵���F�Ȃ��B ���������Ȃ�����āA��(����)�����S�́A��ƕ����A����肢�ƂǑ���Ȃ��B�S�̓��̐��݂̂��A���ɐ��܂���Ēꐴ���A������߂��P���a�B��O�̐�͉����́A�Q(�Ȃ�)�Â��Ȃ闬��Ȃ����B�v �������犙�q�A��k���A�����Ď�������Ɏ���܂ŁA�����̋M�a�O�����F��E�ߒq�ɎQ�q�������́A�_��q���Ȃ��������O����S�����������̂ł͂Ȃ����낤���B��������́u�F��w���L�v(���i34�N�E1427)�ł́A�F��{�{���ȉ��̂悤�ɕ`�ʂ��Ă���B �u��Ђ��[���炭������(�q)�݂��Ă܂�(��)��ɁA���܂���S������(��)�t�ɂ���n��(�y��)�A���̓y�n����ԑ��̐��E�Ȃ�A�ؐ����F�̌�{�ɂ���(��)��ʂ�́A���݂₩�ɋ�i�̂��Ă�(��)�ɂ�(��)�܂ꂽ��A�\�����y���ق��ɋ��ւ��炷�A�\�̌�{�n�e�X�̐��������(�v)�ӂɁA��������̂������炷�Ƃ��ӎ��Ȃ��B�v �F��{�{�̗l�͐S�����t�������ʂ��̂ŁA����́u�ԑ��̐��E�v��������ɕ��̂܂��܂��@�ؑ����E�ł����y���̂��̂ł������B�{�{�ŏؐ����F��q������݂₩�ɉ������A��i�̘@�̗t�̑�ɐ��܂��̂ł���A�\�����y�𑼏��ɋ��߂Ă͂����Ȃ��B�F��\�����̖{�n�̐���͂�����������������̂ł���A�Ƃ��Ă���B�K���l�ɂƂ��āA�s�̂��Ȃ��ɂ���F��{�{�́A�����̋Ɋy��y�ł������B�@ |
|
|
��(4)�@�\�Z�����疜�N�̖���
�M�a�O�����g�ɂ��Čw�ł��F��E�ߒq�͂܂��A���o�̐��n�ł��������B�u�ߒq�R��{���o��(��������)���N�v�́u�厡�ܔN(1130)�㌎�Z���@����s�_�v�̉����������A����������ʂ����ʖ{���A�ߒq�R��{�̖�E�����ł��������呠�V�̉ƌn�ɓ`�����Ă���B�ʖ{�ɂ͔N�I�Ƃ��āA�u�����N(1656)�@���\�@�ጎ�Z�����ʁ@�ߒq�R��{�O���v�ƋL����Ă���B �u�ߒq�R��{���o�剏�N�v�͍���E�s�_���쐬�������̂ŁA����ɂ��ƁA��b�R�E�ю��ŏo�Ƃ�������E�s�_�͏������������ďC�s���d�ˁA��30�̔N�̑厡2�N(1127)�A�ߒq�R�ɎQ�āB���D��ʎ�o�E�@�،o�E�ŏ����o�E��ɗ������ʌ��u���A�㐢�ɓ`���邱�Ƃ肷��B��C�O���s�E�퍿�O���s�E�O����@�����C���x�X�A�얲�������Ă���B���鎞�A����������䋖�̔~�}���������_�l�����Ă��̉�����đ��ɐ^�����Ƃ����B �i�_�E�O�o��A���@�m���̏����ŌF��O�������̌䐳�́A�����E�O�\�����A�����{��𒒑��B������6��9��l�̌����҂���A�@�،o�A���D��ʎ�o�A�ŏ����o�A��ɗ���A�m���o�����S���\�������ʂ��A�厡5�N(1130)9��26���A�ߒq��{�̊�A���ɕ�[�����Ƃ����B�u���N�v�ɋL���ꂽ�ژ^�̖��́E���@�ƁA�o�˂���o�y�����╨�̂����Z������@���A�ܐ��l���E�l��F�����ƍ�����Ă���B �ߒq�l�\����ƌĂ�60�]�̑ꂪ����ߒq�R�́A�����p���u���̗��ƒ�߁v����s�𐋂��A�ޗǎ�����ꕔ�m���A�D�k�ǂ̎R�яC�s�A���čs�̏�ł������Ɠ`������Ă���B�ߒq��̘[�A���o��ƌĂ����ӂł͑吳7�N(1918)��3��A���a5�N(1930)��2��ɂ킽���Čo�ˈ╨��������������A���̓��e�������A�����A�����A���̙�䶗��d�̕i�A����A�o���A���A����A���q�A���A�ÑK�A�������A���ʂȂ��̂ŁA��S���\�_�ɒB���Ă���B�����͊ω����Ɩڂ������̂������A��������̑����唼�����A����̌��w�c���A���P����̊ω����A�\��ʊω����A���ӕ�F���A�ޗǎ���̐��ω����A��t���A�ω����A�Əo���A���o��t��������B���̂��Ƃ���A��Ɍ����u���{��ًL�v�̖@�،o�̎��o�҂��A�F��̒n�ŎR�яC�s�A���O�����A�a�ҋ~�ς̊�����8���I����s���Ă������Ƃ܂��āA�ߒq��ł͓ޗǎ��ォ�畧�����[���Ă����A�Ƃ̎w�E������B �����A����ɂ��Ă͊��O4�N(1007)�A��������(966�`1028)���g��̋����R�Ɏ���̍������D�̌o�����o���ɔ[�߂Ė��[�����̂��A��������ɂ�����A�����ł̌o�ˑ��c�̂͂��܂�Ƃ���Ă���A�ߒq�o�˂̔E���P�E�ޗǎ���̕����������̎���ȍ~�A�ߒq�ł̖��o������ɂȂ钆�Ŏ������܂ꂽ���̂ł͂Ȃ����낤���B�Ƃ��ɓߒq�R�́A�ω���F�̂��܂���ɗ���y�ƌ��`���ꂽ���Ƃ��瑽���̓������ߒq��{�Ɋω���F�[���A�����̏����ł̖��o�҂������ł������悤�ɁA�߉ޖŌ�\�Z�����疜�N��̖��ӕ�F�̏o���܂œ`����ׂ��A�o�T�̖��[���s���A���������Ɏv�����͂����̂��낤�B �s�_�ɑ����A�ی����N(1156)�ɂ́A�m�E�萼���M�Z���A���Z���̐M�҂ɔ@�@�o���������ʂ����āA�ߒq�R�̑�{�ɂ����߂Ă���B�@ |
|
|
��(5)�@��C�̂��Ȃ���
�F��E�ߒq�̒n�ɕ����E�o�T�߂Ȃ��疢���֑���������A�ߒq�̕l�ł͓�x�Ɩ߂�Ȃ���C�ւ̑D�o������l�������B��ɗ��n�C�ł���B �u��ȋ��v�V�����N(1233)5��27�����ɂ́A���N3��7���A����@�،o����u���Ă����q��V���A�ߒq�̕l����ɗ��R�Ɍ����ēn�C�������Ƃ��ڂ��Ă���B ���B�䏊�ɎQ�苋���B�ꕕ�̏��т���O�ɔ◗�����B �\�����ߋ����ĞH���A����O�������A�F��ߒq�Y���A��ɗ��R�ɓn��җL��B�q��[�ƍ����B���ꉺ�͕ӘZ�Y�s�G�@�t�Ȃ�B�̉E�叫�Ɖ���̍��ߐ{��̌��̎��A�厭�ꓪ���q�̓��ɉ炷�B������Ȃ�ˎ���сA�s�G�����o���Ď˂���̗R�����B�����Č����ɏ]�ӂ�嫂��A���̐���(����)�炸�A�����q�̊O�ɑ���o�ÁB���R�l�Y���q��ђ����ˎ��L��ʁB�����Ď��ɉ����ďo�Ƃ𐋂��Ē��d���A�s����m�炸�B�ߔN�F��R�ɍ݂�āA����@�،o����u����̗R�A�`�֕����̏��A���卟�̊�Ăɋy�ԁB����މ����Ȃ�Ɖ]�X�B ����ɍ��A�◗�����ߋ��ӂ̏�́A�q��A���@�ɑ����āA���B�ɑ���i�����̎|�\���u���B�I�ɂ̍����䏯���V������i���āA�����������B�ݑ��̎����o�Ɠِ��Ȍ�̎��A�����V���ڂ��B���h�O�i�e���V��ǂݐ\���B�ܐߋ_��̒j���A�V���Ċ��܂��~���B���B�͐̋|�n�̗F����̗R�A���\����Ɖ]�X�B�ނ̏�D�́A���`�ɓ���̌�A�O���B���ȂĊF�ł��t���A����������A�����̌����ς���\�킸�B�������ɜ�(��)����B�O�\�ӓ��̒��̐H�����тɖ����A�͂��ɗp�ӂ��Ɖ]�X�B (�Ӗ�) �V�����N5���A�k���(1183�`1242)�̂��ƂɋI�ɍ����䑑����ʂ̏��͂��A���͏��R�E�������o(1218�`1256)�̑O�Ŏ��h�O�i�e���ɓǂݏグ�������B 3��7���A�F��ߒq�̕l����ɗ��R�Ɍ����n�C�����q��[�́A���Ƃ͉��͕ӘZ�Y�s�G�Ƃ�����Ɛl�ł������B���ĉ��썑�E�ߐ{��ōs��ꂽ���̍ہA���������A���q�Ɏ��͂܂ꂽ�ꓪ�̑厭���˂Ƃ߂�悤�������ꂽ�B�������A�s�G����������͖��������厭�͐��q�̊O�ɑ���o���Ă��܂��A�����ď��R�l�Y���q��ђ����̖�œ�����邱�Ƃ��ł����B�����̑O�Ŏ��Ԃ��������s�G�͂��̏�ŏo�Ƃ��A���d�B�Ȍ�A�s���s���ƂȂ����B�ߔN�A�s�G�͒q��V�Ɩ����A�F��R�œ���A�@�،o����u���Ă��邱�Ƃ��Ă������A���ǂ͕�ɗ��R�ւ̓n�C�ɋy�Ƃ����B�܂��Ƃɗ���ނׂ����Ƃł���B ���̏���͓n�C�O�̒q��V�����ɑ���͂���悤���@�ɑ��������̂ŁA�I�ɂ̍����䏯��荡���A�͂������̂ł���B�����ɂ͍ݑ��̎����o�Ɠِ��Ȍ�̂��Ƃ��A���ׂ����L����Ă����B���h�O�i�e�����ǂݏグ��ƁA���͂̐l�X�͊��܂��A���͐́A�s�G�Ƃ͋|�n�̗F�ł������ƌ�����Ƃ����B �q��V�̏�D�͉��`�ɓ�������A�O����B��ł������Ĉ�̔����������̂������B�����ɂ͓����̌������邱�Ƃ��Ȃ��A�����A�������𗊂�Ƃ����B�O�\�����̐H���Ƃ킸������̖���ς�ł����Ƃ����B �u�F��N��L�v�ɂ́A�u���a(�V�c)�@��Ϗ\(�N)�@��q�@�\�ꌎ�O���A�c����l��ɗ��ɓ��v�Ƃ���A���10�N(868)�ȍ~�A�ߒq�̊C�݂����ɗ���y��ڎw���ĊC�֏o���ɗ��n�C���n�܂��Ă���悤�����A�������犙�q����ɂ����ẮA�F��E�ߒq�ɂ�����@�،o�M�Ǝ��H�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��B����ɑ��Č㐢�ɂ܂ő傫�ȃC���p�N�g��^�����̉Ƃ��āA�ōߌo�T�Ƃ��Đs���߂��Ƃ���̋��ɂ̍s�ׁA�̐g�s�ւƌ����킹����̂ł������Ƃ������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����낤���B���̎��Ⴊ�i���̂��Ƃ�K�ꂽ�@�،o���u�m�̎̐g�ł���A�ߒq�R�E���Ƃ̊쌩��F�̂��Ƃ��Β�ƁA�ω���F�̕�ɗ���y��ڎw�����q��V��̓n�C���Ǝv���B�@ |
|
|
��(6)�@�O�R�̑g�D
���͏�c�̌F��w�łɂ͂��܂�Q�w�҂̑����ɔ����A�����������犙�q����ɂ����āA�F��O�R�̉^�c�Ɋւ���g�D����������Ă���B�Õ������m�F������E�������m�F���Ă������B �{�{ �F���K���L�E�F��{�{�ʓ��O�j��O�����@�@�i��3�N(1083)9��4�� �ʖڑ�A�s�ۓ߁A����A�ݒ��A�y�ڑ�A����A���Z�A�C���ʓ��A�ʓ��A �F��R���������@�@����2�N(1200)5�� �O���ʓ��A�����ʓ��A�ʖڑ�A��������A��������A�C��������[ �V�{ ���E�L�@�@�V�m2�N(1109)10��26���� �����ݒ� �\��@�@����3�N(1290)7�� �{�� �ߒq�R ���E�L�@�@���i���N(1118)10��15���� ���d�`������苗������߂� �m�j��C�@�@�V�����N(1131) �ʓ��`���͂���C����Ă��� ���Ᏼ�E�ߒq�R�m�j��@�@�m��3�N(1153)2��16���� ��a���`�ߒq�R��Z�̈�a����苗��×_���@���ɏ������ ���Ᏼ�@�@���v���N(1204) �ߒq�R���Z�`�����̂��߂ɐ݂����� (12���I������n�܂�ߒq�R���s���A13���I�������{���s�Ƌ��Ɉ�R������悤�ɂȂ�) ��{���s���Ϗ���ā@�@���v���N(1219)10��18�� ��{���s�`���̓��́u��{���s���Ϗ���āv����{���s�̏��o �����m�s���o������@�@�i�m6�N(1298)5��1�� ���̓��́u�����m�s���o������v�ɂ͎��s�@��o���A��{���s�@��K�ӁA�@��l�l�A�����m�s��l�A�����t�l�l�A�ݒ��@��S���A�ݒ������t���_������ �u�ߒq�R��{���v(�i��2�N[1430]�̉���)�ɂ��A�ߒq�R�͑�R�Q�ďO�A�ɗ���O�A�{�R�ďO���琬���Ă���A��R�Q�ďO�̍s�@�͗��`��l�A�����p�A�`����t�A�O�@��t�A�q�ؑ�t�A�b���A�͏r�Ƃ������ߒq���擿���`����ꂽ���́A�Ƃ���Ă����B ���q���ォ��͍c���E�M���ȊO�ɂ��e�n�̕��m��̌F��O�R�Q�w�������A���̈ē���h�����̑��̐��b���s���҂��B�ƌĂԂ悤�ɂȂ�A�Q�w�ҋy�ь��n�ɍs������B�ɋ��{������l�͒h�߂ƌĂꂽ�B����A�F��̒n�Ő�B�A�h�߂��}���A�F���E�ē��E�h���̐��b������҂͌�t�Ƃ������B��t�Ɛ�B�E�h�߂͎t�h�W�������̂Ƃ��ꂽ���A����͓����Ɍ�t�̌o�ϓI��ՂƂȂ邱�Ƃ��Ӗ����A���q�E����������퍑���ɂ����Ă͐�B�P�ʁA�ꑰ�E���P�ʁA���E�S�E���P�ʂŏ��n�A�����A�S�ۂ̑ΏۂƂ���Č�t�ԂŎ������Ă���B �U�ߏ��� (�[����)�u���[����v �i���n�|���� �ؓ��[�� ��A�@�O�͍���B���h�ߕ������ʓ��O�g�m�s��o�L�O�ʑ�m�s�����h�ߓ��E��ˈꑰ�� ��A�@�헤����B���h�߁E���~����̏��m�s���h�ߓ� ��A�@�O�㍑��B���h�ߓ� �E����B���h�ߓ��ҁA�@�T�d�㑊�`�|��A���ؓ��[�m�i�����n��A�S�s�L���l�W�Җ�A������T������@�� �ω��Ɛh�K�N(1351)�\�\�O�� ��苗��S�@�@�ԉ� ���M�S���@�ԉ� �����m�s�@�@�T�@�ԉ�(6) ��������ɂ́A���m�E�����̎Q�w���u�a�̌F��w�Łv�Ə̂����قǂɊ����Ȃ��̂ƂȂ����A�헐�A�Q�[�A�^���A��n�k�̓x�Ɋe�R���Ɍo�c�ɋ����邱�ƂƂȂ����B�ߒq�R�ł́A�����̖V���敾���h�߂�������A�L�V�V�E�ԑ��@�E����@�̎O�@�������̒h�߂����A���ł�����@���傫�Ȑ��͂ƂȂ��Ă������B �U�ߔ��� �i����n�\�U�ߔV�� �����Ɗѕ��ҁA �E���V��U�ߎ��ҁA�I�ɍ��c�Ӄ~�ȂƂ̋�Y���q����n�\�|����A������肢���ꌾ��n�o�A��{�V���Z�q���݂����\��A��������肯���@�� �����O�N(��l�l)�����\��� ����ʂ���{���Z�@�ԉ� �����ʂ��ߒq�R����@(7) �@ |
|
| ��9�@�{�n��瑐��@ | |
| �����ł͌F��O�R����ڂ�]���A�������������̂ɂ����Ēʂ�Ȃ��{�n��瑐��̐��藧���ɂ��āA�ЂƂƂ���T�ς��Ă������B�@ | |
|
��(1)�@����F�̉��̎p�Ƃ��Ă̓��{�̐_
眓��o�T���̋���(1)�ɂ��ƁA�{�n��瑐��͈ꋓ�ɂ܂Ƃ܂��Č��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A��ɐ�瑎v�z������Ă���Ƃ����B ������̏����́A�u���{�O����^�v�̒�ό��N(859)������\�����h����A�u�ˏ\�T�t�`����@�t�ʌb���\���B�n�u����N���x�ғ�l�B����l��ΐ_�B������y�o�B�����@�،o�������o�B��l�t���_�B���ۖ��l�����o�B�����@�،o�������o�B�\�H�B�b�����B�c�o�����B���������B��m��瑁B�������_�B�v�ɂȂ�悤���B ����͒�ό��N8��28���A����̌b��(812�`860)����ΐ_�Ət���_�̂��߂ɔ�b�R�ɔN���x�ғ�l��u�����Ƃ�\���������ŁA��ΐ_���̈�l�͑���y�o���C���A�����Ė@�،o�A�������o���C����B�t���_���̈�l�͈ۖ��o���C���A�����Ė@�،o�A�������o���C���邱�Ƃɂ��Ă���B�����Ắu�c�o�̕����͊��͎��A���͌��B��m��瑂𐂂��́A���͉��A���͐_�v(�c�o=�@�������������̂ɂ͎�[�̎p]������Ό�[���̎p]������A��m[��F]�����̎p�ƌ����̂ɂ́A���邢�͉��ƂȂ�A���邢�͐_�ƂȂ�)����瑎v�z�̚���Ƃ����Ƃ��낾�B ���ɁA����7�N(937)10��4���A��ɕ{����⦍�{�ɏo���ꂽ�����ɁA�u�ދ{���{嫑��n�فA������F��瑗P���B�v(�ދ{[�F���{]�E���{[⦍�{]���̒n�قȂ��嫂��A������F��瑗P�����B�ΐ����_�Е����E��)�Ƃ���B�@�،o��[�߂�@���F�����ӎ�(�啪���F���s�E�F���_�{�̋����ɂ������_�{��)�ɗ\�肳��Ă����̂��A⦍�_�{��(�����������s�����⦍�{�ɂ�����)�ɕύX���ꂽ���Ƃɂ��āA�u�F���̋{��⦍�̋{�ł͓y�n�͈قȂ邪�A������F(�������F)����瑂���邱�Ƃ͓����ł���v�Ƃ��Ă���B �����ẮA�u����������@�������N�v(���a��N�E962)�̉����ŁA����ɂ��ƁA������̑m�E�s��(���v�N�s��)�͓����A���̍ہA�L�O���̉F�������{�Ɉ�ċ�{�̊ԎQ�Ă���B�Q�Ē��A�߂̑���Ɏ߉ގO�����������Ă���A����͔����_�̖{�n���߉ގO���Ƃ���l�����������Ă������Ƃ��Ӗ�������̂Ƃ����B �ȏ�̌b���\�����A�ΐ����_�Е����A����������@�������N���A9���I�̔�����10���I�ɂ����āA����F�̉��̎p�Ƃ��Ă̓��{�̐_�Ƃ����ϔO������Ă��邱�Ƃ��ǂݎ���B11���I����12���I�ɂ����ẮA�×�����̊e�n�̐_�ɖ{�n�����ݒ肳��A�{�n��瑐����������鎞��ƂȂ�B�@ |
|
|
��(2)�@�e�Ђ̖{�n��
��1�@�����_�� ����2�N(1164)9���A������(1118�`1181)�͈��̔ɉh�����ӂ������̖��ʂ��肢�A�@�،o�O�\���E����Ɍo�ꊪ�E�ʎ�S�o�ꊪ�E�蕶�ꊪ�������Ђɕ�[(���Ɣ[�o)�B���̊蕶�ɂ́u���`�]�A���А��ω���F�V������B�v�Ƃ���A�ω���F�̉����������Ђ̐_�E�ɓs���_�ł���Ƃ���Ă����B �u���������L�v����\�O�́u�����M��������瑎��v�ł́A�����Ђ̖{�n���L�q���Ă���B �{�n��\���A��{�͐������A��ɁA�����A���ӁB���{�͏\��ʊω��B�q�l�{�͕��@�쎝����V�A�ő��_���A�߉ށA��t�A�s���A�n����B�y�����ʋ{�Ƃ��\����B �����Ђ̖{�n杂��L�����u������{�n�v�ɂ��A�ȉ��̂悤�ɂ���B �}�X�����喾�_�Ɛ\�����́B�䂪�����ÓV�c�̌䎞�B���₤�ܔN�b�\(���̂�����)�\�\�O���ɁB ���{�H�Ó��R�z�����|�̍��������̌S�Ƃ������ɁB�O���ϓx�̂��߂ɐՂ𐂂�ʂӁB���̑喾�_�̌�{�n���ς������Â˂��Ă܂�ɁB�̓V���ɏ\�Z�̑卑����B (����) �������̓����݂��B�����������Ƌ�����ɂ�āB�����Ƃ͂�����\���n�܂肯��B�����ɂ��B�܂Â���ǂ̂��͂��߂Ƃ��āB�܂Ñ傲��Ɛ\���Ȃ�B�����т��݂̂�̌䎖��B��{�n�ّ͑��E�̑���Ȃ�B�܂����Ƃ��P�����̌䎖�́B ���Â˂������ЂĂ��点���ւB�q�l�Ɏv���B�܂낤��(�q�l)�̌�O�Ƃ͐\���Ȃ�B��{�n�͔�����V�ɂĂ��͂��܂��B����(��)�̌�O�́B����т�����̌䉤�q�̌䎖�Ȃ�B��{�n�͐��ω��ɂĂ��͂��܂��B�Ђ���(��)�̌�O�Ɛ\���́B���т�(��毗��)���̏�l�ɂĂ��͂��܂��B�{�n�͕s�������ɂĂ��͂��܂��B���炦�т��Ɛ\���́B���̌�ē��\������Ђ��葠�{�Ȃ�B ��2�@���g��� �Ő��ȗ��̓��{�V��Ɠ��}�R(��b�R)�̎R�x�M�A�_�����Z�������R���_���ł��R������(���g�����܂��͓��g�R�������Ƃ�)�̖{�n��ݒ肵�Ă���B����ɂ��ƁA��{�E���b(���{�{)�͎߉ޔ@���A��{�E����b(���{�{)�͖�t�@���A�ێЂł��鐹�^�q(�F���{)�͈���ɔ@���A�����q(�����_��)�͐��ω��A�q�l(���R�P�_��)�͏\��ʊω��A�\�T�t(�����_��)�͒n����F�A�O�{(�O�{�_��)�͕�����F�Ƃ���Ă���B �u���������L�v����l�́u�R����瑂̎��v�ɂ́A��b�R�E���@�̌c�����R���̖{�n���ߑ��ƒm��A���܂����͗l���L����Ă���B �}���R�������Ɛ\���́A��铇���h�{���ʌ��N�A��a�����S��O�_�ƓV�~�苋�Ђ����A��Ë{���ʌ��N�ɁA���`�V����铂ɂāA���b�喾�_�ƌ��ꋋ�ւ�B���@�̍���c���A�R���̖{�n���F��\���ꂯ��ɁA�����ɉ]�͂��A���ɂ��Ė��ʍΕ��ʂ������A���ɂ��Ė��ʍΌQ���𗘂��Ƌ�����A����A��k�i�̉䌩�߉ޔ@���A�����ʍ��A��s��s�A�ό��ݓ��A����F�����\�~���A�ώO���琢�E�A�T�����L�@�H�q����A����F�̐g�����Ɖ]�ӕ��Ɏv�Ѝ��͂��āA��{�����́A�͂�A�ߑ��̎����Ȃ肯��B����A�䂪�œx��A�����@���A���喾�_�A�L�x�O���Ƃ������A��ܚe���A��腕���A�����Ґ����喾�_�Ƃ��Ԃߋ��Ђ���́A���{�b�x�̘[�ɁA���g�̑喾�_�Ɛ��Ղ����ӂׂ�����������Ђ���ɂ����ƁA���܂��������ꂯ��B ��3�@�t���� �u�t���ЌËL�v�̏����ܔN(1175)�O��������ł́A��{����l�{�A�X�Ɏ�{�̍Ր_�̖{�n�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɋL���Ă���B ��{�@�Ր_�E���P�Ɩ����{�n�E�s��㮍��ω� (�u�t���ЌÎЋL�v�u�t���Ў��L�v�́A�u���邢�͎߉ޔ@���v�ƒNjL) ��{�@�Ր_�E�o�Î喽���{�n�E��t�@�� (�u�t���ЌÎЋL�v�́u���邢�͖��ӕ�F�v�ƒNjL) �O�{�@�Ր_�E�V�����������{�n�E�n����F �l�{�@�Ր_�E�䔄�_���\��ʊω� (�u�t���ЌÎЋL�v�͑���@���A�u�t���Ў��L�v�͋~���ω���NjL) ��{�@�Ր_�E�V���_����������t����F (�u�t���Ў��L�v�́u���邢�͏\��ʊω��v�ƒNjL) ��4�@�_���O������ ����3�N(1179)4���A����ϊC�͋_���O������(���s�E����_��)�̋����O�ڂ̕���F���O�̑����ƁA�O�ڂ̉~���O�ʍ쐬��B�{����菕�����Ăт��������i������������̊����W�ł���u���ܕ��W�v�ɍڂ����Ă���B����ɂ��ƁA�_���O�������̖{�n�͖�t�@���A����t����F�A�\��ʊω��Ƃ��Ă���B ��5�@�Î��k ������(1160�`1215)���A����2�N(1212)���猚��3�N(1215)�̊ԂɕҎ[�������b�W�u�Î��k�v�ł��A�_�̖{�n���ɂ܂��b���Љ�Ă���B �����͌�(1107�`1165)�͋��s�E��ΎЂɎQ�w���邽�сA�ʎ�S�o��������[���Ă����B������A�u�喾�_�̌�{�n�͉��ɂČ䍿(���͂���)�����ށv�ƋF���B���̌�A���̒��ɏ���������A�{�n��₤�Ƙ@�������g�̐��ω��ɕς��A�g���Ă��đ���̎p���������B�ڂ��o�߂��͌��͓��g�̐��ω������A���R���Ɉ��u�����Ƃ����B(��ܐ_�Е����E�\�l)�B ������������R�ɑ哃�����Ă�ׂ�������ޖ�������Ƃ��Ă������A�����̑m������A�u���{���̑���@���́A�ɐ���_�{�ƈ��|�̌����Ȃ�B��_�{�͂��܂�H���Ȃ�B��K(���܂���)���i�ƈׂ�B���������ɕ�d���ׂ��B�v�ƍ�����ꂽ�B�������m�̖���₤�Ɓu���@�̈�苗��ƂȂސ\��(��C���Ӗ�����)�v�Ɠ����A�����������Ƃ���(��ܐ_�Е����E�O�\�O)�B |
|
|
��6�@���_�{���W
�{�莛3���E�o�@(1271�`1351)�̒��q�ŁA�e�a(1173�`1262)���5��ڂɂ����鑶�o(1290�`1373)�͓��厛�ŏo�Ǝ����A�������A����Ŋw�сA�^�@�̕z���������ɍs�����B����4�N(1324)�A���o�͗���(1295�`1336)�̋��߂ɉ����A�u��y�^�v��v�u������v�u���_�{���W�v�̎O���킵�t�^���Ă���B���̂����u���_�{���W�v�́A���q�V�����̐_���_���\������́A�ƕ]������Ă���B ���Ƃ���Ƃ���́A�u���_�̖{���𖾂����āA���@���s���A�O�����C���ׂ��v����m�炵�߂�Ǝv���v(�����`��)�A���������̊e�Ђ��J����_�̖{�ӂ́A�O�������ĔO���ɋA�������邱�Ƃɂ���Ƃ������̂����A�����A�����A�F��A�O���A�����A���R�A�M�c���A�傾�����_�Ђ̖{�n�����L�q����Ă��āA�����[�����e���B���ɌF��\�����Ɋւ��ẮA�u��ɓ��{���̗�ЂƐ��߂�ꋋ���v�Ƃ��ĊJ�n杂����p���Ă̒����̉���ƂȂ��Ă���A�����A�F��M�������Ɍ��`����Ă�����������������j���ƂȂ��Ă���B�@�s�@�{������(�@)�͕M�҂��L���B�܂��K�X���s�����@�t �Ԗ��V�c�̌䎞�A���@�͂��߂čL�܂肵��肱�̂����A�_���h�����ȂāA���̐�(�܂育��)�Ƃ��A���ɋA������ȂāA���̉c�݂Ƃ��B����ɂ��āA���̊����������ɗD��A���̈А����ْ��ɒ�������B���ꂵ�����Ȃ���A���ɂ̗i��A�܂��_���̈З͂Ȃ�B�������ȂāA���{�Z�\�Z�Ӎ��̊ԂɁA�_�Ђ𐒂ނ邱�ƁA�ꖜ�O�玵�S�]�ЂȂ�B����̐_�����ɍڂ���Ƃ���A�O���S�O�\��ЂȂ�B �����������{�䂪���́A�V�_����A�n�_�ܑ�A�l���S��Ȃ�B���̓��A�V�_�̑掵����A�ɜQ��(�����Ȃ�)�E�ɜQ�f(�����Ȃ�)�Ɛ\�����B�ɜQ���̑��͒j�_�Ȃ�B���̎����̑喾�_(�����_�{)�Ȃ�B�ɜQ�f�̑��͔ܐ_�Ȃ�B���̍���̑喾�_(����_�{)�Ȃ�B (����) �����̑喾�_�́A�{�n�\��ʊω��Ȃ�B�a�������̂����Ղ��A��V���Ƃ炵�A�����ϓx�̌b�݁A�����l�C�ɖւ炵�߂���B���̌̂ɁA���݂�������l�́A�����̎��n�𐬂��A�S���������y(�Ƃ�����)�́A�S���̏���B���̌�O(�����Ђ̐ێЂ̕M���E���{)�́A�{�n�s��㮍��Ȃ�B���E�̔����_(�����Ђ̐ێ�)�́A�s��������Ȃ�B�����e�X���݂���B�ϓx�F�ނȂ����炸�B ���̖��_�́A�ޗǂ̋��ɂ��Ă͏t���̑喾�_(�t�����)�ƌ����A��g�̋��ɂ��Ă͏Z�g�̑喾�_(���s�̏Z�g���)�ƌ���A������̋��ɂ��ẮA�����͑匴��̑喾�_(���s�̑�쌴�_��)�Ɛ��߂��A�����͋g�c�̑喾�_(���s�̋g�c�_��)�Ǝ��������B���X�ɗ��v�𐂂�A��X�ɗ쌱���{�������B�{�ЁE���ЁE�����F�߂ł����A�����E���O�A�ϓx���ƂɗD�ꂽ�܂���B �q��̌�O(�F��̎q��{��)�́A�����ɂĂ͉��̌�O�ƌ���A�t���ɂĂ͌��̋{(�s��)�Ǝ��������B�V�Ƒ�_�͓��V�q�A�ω��̐�瑁A�f���j��(�����̂��݂̂���)�͌��V�q�A�����̐�瑂Ȃ�B���̓��F�́A��ɔ@���̔ߒq�̓��Ȃ�A���̗��Ђ��͂��ɔ@���̕��g�Ȃ�B���̗��Ђ��łɑR�Ȃ�B�ȉ��̏��ЁA�܂���ɂ̑P�I���ւɔƂ������Ƃ���ׂ��炸�B �F��̌����Ƃ����́A���͐��V���d�ɍ��̑剤�A���ߑ匫���Ȃ�B������ɖ{�������������Ƃ���āA���@�_�V�c���ʌ��N�H�����ɁA�y���ɐ��V���܂��݂𓌂ɓ����āA�u�䂪�L���̒n�Ɏ~(�Ƃ�)�܂�ׂ��v�Ɛ����������ɁA��͋I�ɂ̍����K�̌S(�F��O�R)�Ɏ~�܂�A��͉���̍������R(�j�̎R�A��r�R�_��)�Ɏ~�܂�A��͏o�H�̍��Ώ�̌S(�o�H�O�R)�Ɏ~�܂�A��͒W�H�̍��@�߉H�̕�(�W�H���̗@�߉H�R)�Ɏ~�܂�A��͖L��̍��F�̎R(��B�̉p�F�R)�Ɏ~�܂�B���̕F�̎R�ɓV�~�苋�������́A���̌`���p�̐����Ȃ�B���̏�(����)�O�ژZ���Ȃ�B�쌱��B�ɕՂ��A���l���݂��^���Ƃ������ƂȂ��B ���������A�F�쌠���ƌ��ꋋ�����Ƃ́A�I�ɂ̍���c�͂̕�(�قƂ�)�ɁA��l�̗t����B���̖��������̐琢(���Ƃ̂���)�Ƃ����B�R�ɓ���āA��肵����ɁA��̌F���˂��肯��B���������ˁA�Ղ����߂čs���قǂɁA��̓�̂��ƂɎ����B���̎��A����肯�錢�A��(������)�����グ�ĕp(����)��ɖi������A�琢�A�̏������ɁA���̖̎}�ɎO�̌��ւ���B�琢�A�����݂��Ȃ��āA�₤�Č����l�A�u���A���̌̂ɂ��A��𗣂�ď��ɂ�������B���A�܂������O�L���B�V�ς��A�����̂��A�r(�͂Ȃ�)���o��(���ڂ�)�Ȃ��v�ƌ����B���̎��A�������邵�Ă̋�������́A�u��͓V�ςɔB�����̂ɔB���y�̏O�����~����߂ɁA���V���������y���ɂ��̒��ɗ������B�����A�F��O�������ƌ����Ǝv���B�𑬂₩�ɎВd��āA��𐒂ނׂ��v�Ǝ�����������A�琢�����܂��Ɋ���(������)�̎v�����Ȃ��A���ƂɋA�˂̐S���������āA�������a��āA��������肯��B�����肱�̕��A�������˂������A����𐒂߂���͂Ȃ��A�����̂��ߌ㐶�̂��߁A����Ɍw�ł���l�Ȃ��B �܂��ؐ��a(�F��{�{)�͈���ɔ@���̐�瑂Ȃ�B�����̔ߊ�(����ɔ@���̖{��E�l�\����)�ܑ͌��̏O�����~���A�ێ�̌���(����ɔ@���̎��߂̌���)�͐�O�̍s�҂��Ƃ炷�B ��������(�V�{�Ɠߒq)�Ƃ����́A���̌�O(�ߒq�̑�l�a���J��ꂽ�v�{���_�𐼋{�Ƃ�����)�͐��ω��Ȃ�B��S�̖��̕��̂����ɂ́A���V�a���̍C�o(������)���͂炢�A�ꎞ��q�̌��̑O�ɂ́A�S�疜���̊�]�B ���̌�O(�V�{�͒��{�A����O�Ƃ�����)�͖�t�@���Ȃ�B�\��ُ�̐���(��t�@�����ߋ����ɗ��Ă��\��̑��)���N���āA���]�̌Q�G(��؏O��)�������A�o����E�̗ǖ��^���āA�ٖ�(�ނ݂傤)�̏d�a����₷�B �����̔@���A�O��������ׁA�_������тĐՂ𐂂ꋋ���B���x�̕���(�O�����~������)�A�(����)���낻���Ȃ邱�Ƃ�����B ���Ɍ��̉��q(�F��\�����̓��̌ܐ_�ŁA��{[��ꉤ�q]�A�T���{�A���{�A���{�A�q��{�������q�Ƃ���)�Ƃ����́A�ቤ�q(��{�E��ꉤ�q)�͏\��ʊω��Ȃ�B�����O���̗͂��ȂāA�Z���̏O���������A��ɂ̑�߂��i(������)��āA�O�L(�O�E)�̏O�ނ��~�������B �T�t�̋{(�T���{)�͒n����F�Ȃ�B�厜��߂̗������Ƃɗ��������A�����㐢�̈������A�Ƃ������B���̋{(���{)�͗�����F�Ȃ�B�畔�̘_�������āA�L��(����)�̎�(������L�Ƃ݂�A�܂��͖��Ƃ݂�l���B�������炷��Ύ��ƂȂ�)��j���A�ُ�̑����ׂāA���y�̉��������ߋ�����B ���̋{(���{)�͔@�ӗ֊ω��A�q��̋{(�q��{)�͐��ω��Ȃ�B���̌`�A���������قȂ�ǂ��A���Ɋω��̈��[�Ȃ�B���̖����炭�ς��ǂ��A���тɖ�ɂ̕��g�Ȃ�B�ϓx���тȂ��A���v���Ƃ��Ղ��B ���Ɉꖜ�̋{(�l�����_�̓��̈ꖜ�\���̂��ƁB�l�����_=�F��\�����̓��̎l�_�ŁA�ꖜ�\���A�Ď������A��s�鍳�A�����\��������)�́A�吹����t����F�Ȃ�B�O���̏����̊o��ߑ����̑c�t�Ȃ�B���Ƃ͋��F���E(�����F�̏�y)�ɂ܂��܂���嫂��A��ɐ����R(�����ܑ̌�R�ُ̈́A�����F�̎����̒n)�ɏZ���A�|�т̐���(�@�Ƃ����Ă��O������̒|�ю�)�������āA���̕ЏB�Ɍ�����������B�@�@�@ �\���̋{(�ꖜ�\��)�͕�����F�Ȃ�B�\��̏�����N���ẮA���{(�Ɋy)�̉��������߁A�����̖��@�������ẮA�ō߂̋��v�������B�����\���́A��㋳��߉ޔ@���Ȃ�B�O�k�����̋���Ƃ��āA�O���𐼕��ɑ���A���ꖼ���̗v�@������ɕt�����āA�}�v�̉��������������B��s�鍳�͕s�������Ȃ�B�m�b�̗��݂�U�邢�āA�����̖��R�𝔔j���B�Ď��������q�͔�����V���Ȃ�B�����̍b�h��т��āA�ϔY�̉��G���~�����B �����悻���̌����́A�Ɉʂ̔@���A�n��̕�F�Ȃ�B�A��(�Ȃ���)�ɏؐ��a�́A�����ɖ�ɂ̐�瑂ɂĂ܂��܂����̂ɁA��ɓ��{���̗�ЂƐ��߂�ꋋ���B�O�k�E�̗��v�A�ٗʍ���������o(����)�ނ��ƂȂ��A�䂪���̉����A���ɐ���N�ɋy�тāA�v�X����Ȃ�B �O���̑喾�_(�����A�ɓ��R�A�O���̊e��)�Ƃ����́A�唠��(�����_��)�͎O�������Ȃ�B�@�[�͎O���o��̕���t���A���[�͓���(����)���t�̖��ӎ����A���[�͎{�و؎�(���S�ƗE�C��^����ҁE�ϐ�����F�ُ̈�)�ω��F埵�Ȃ�B �O���̑喾�_(�O�����)�͏\��艤�㉤�P��(�����������E��t�@���ُ̈�)�Ȃ�B �����O��(�����{�̍Ր_�E�������F�A��ѕP���A�䔄��_)�́A�Ȃ��͔������F�A����ɔ@���A���͂������炵�Ђ�(��ѕP��)�A�{�n�ω��Ȃ�B�E�͂Ђߑ�_(�䔄��_)�A�吨����F�Ȃ�B��{�l��(�����{�̐ێЁB��{�A��P�A�F��A�v��)�Ƃ����́A�{�n�\��ʊω��Ȃ�B��P�͐�����F�Ȃ�B�F��͕���A�K��͕����Ȃ�B����F�A���_�V�c�̌�q�Ȃ�B���ɒ|���̑�b(�����{�̐ێЁE�����h�H���J��)�́A�{�n����ɔ@���A���ꓯ�����V�c�̐b���Ȃ�B�ւ��ǂ�(�����{�̐ێ�)�͕�����F�A�������V�c�̛H��(����)�Ȃ�B ���g(���g���)�͎O�@���̐�瑁A�l��F�̉���Ȃ�B�������{�͎߉ޔ@���A�n�匠���͖�t�@���A���^�q�͈���ɔ@���A�����q�͐��ω��A�q�l�͏\��ʊω��A�\�T�t�͒n����F�A�O�̋{�͕�����F�Ȃ�B ���̂ق��A�_��(���s�E����_��)�͏�ڗ����E��t�@���̐�瑁A���(���s�E��א_��)�͐��@�ӗ֊ω����ݑ��̉����Ȃ�B���R(�ΐ쌧���R�s�̔��R����[�����܂Ђ�]�_��)�͖��������A����\��ʊω��̉����A�M�c(���É��s�E�M�c�_�{)�͔��ݑ��F�A����s�������̉�瑂Ȃ�B�@ |
|
|
��(3)�@�����_�̖{�n�̕ϑJ
���a2�N(962)�̉��������u����������@�������N�v����́A�����_�̖{�n���߉ގO���Ƃ���l�����A�����̉F���n���ł͐������Ă������̂Ɨ������ꂽ�B���ꂩ��140�N��A��]���[(1041�`1111)���Ҏ[�����u���{�������`�\�Z�E�^����l�`�v(2)�ł́A���g�̕��͔����_�ł���A���̖{�o�́u�������ʎ��@���Ȃ�v(����ɔ@���̕ʖ������ʎ��@��)�Ƃ��A�����_�̖{�n�͈���ɔ@���Ƃ���l�����蒅���Ă������Ƃ������Ă���B �^����l�́A������R�̌��֎��ɏZ����B��ɐ�����N�ĂĞH���A�@�Ԍo�̕��ɏ�ݗ�h�R�A�y�]���Z���Ƃ��ӁB���{���͂��ɓ��炴��]�̏��Ȃ�ނ�B�R��Ζ�(�܂̂���)��ɐ��g�̕��������ނƂ��ւ�B���̊���[���ނ����߂ɁA���ɖ@�Ԍo���u����B�����Ƃɗ�q���C���邱�ƎQ�x�B脉������ӂ邱�ƈ�O�Ȃ�B��⑽�N����đQ���Ɉꕔ��s����B���ւĎ����Ƃ���Ȃ��B�攪���̓���ɓ���āA�s�ƛ߂ɖ��Ă�B���̖�̖��ɞH���A�ΐ����ɎQ��ׂ��A�]�X�Ƃ��ӁB���̋{�ɖ����Ɍ�a�̌˂��J���҂��{��ƈ��ӁB�����ɋq�m�̌䒠�̑O�ɂ�������āA�傫�ɋ����ĒNjp���ނƂ�~���B���̊Ԃɐΐ����ʓ��g�������āA�{��̑m�ɍ����ĞH���A�_�a�̒��ɒ�߂ċq�m����ށB���E(�Ƃɂ���)�ɂ��ׂ��炸�B���ꍡ��̖��̒��ɗ����ւ邪�̂Ȃ�A�]�X�Ƃ��ւ�B�����ɒm��ʁA���g�̕��́A�������ꔪ�����F�Ȃ邱�Ƃ��B���̖{�o�����͂A�������ʎ��@���Ȃ�B�^���߂ɐ��g�̕���������B���ɉ����̐l�ɂ��炸��B ���a���N(985)�A��b�R����E�b�S�@�̌��M���u�����v�W�v���A�O��������������A�P�ƁA���̗D�ꂽ�鏊�Ȃ�����A��y�����ւ̓������������̂Ǝ��������āA�c���ۈ����u���{�����Ɋy�L�v��Ҏ[(985�`987)�B�V���y���̓W�J�A�Ɋy��y�ւ̐M�Ɨ����ɂ��A�����_�̖{�n�͎߉ގO�����爢��ɔ@���ւƕω����A�L�������킽��蒅���Ă������B�@ |
|
|
��(4)�@�{�n��瑐������̔w�i
�������ɂ�����{�n��瑐������̔w�i�ɂ́A�l�X�Ȍ������悳��Ă���B�����ł͍����O�v���A�R���u��Y���A眓��o�T���̌��������グ�A���̓��e���m�F���Ă݂����B(���p�͎��) �����O�v���́u�_�����{�v(3)�ŁA�u��������ɖ{�n��瑐��������o����A�܂������Ԃɗ�Ȋ����邱�ƂɂȂ��������͉��������̂��낤���B���̔w�i�ɂ́A10���I���납��}���ɐi�W����ފݕ\�ۂ̔�剻�Ə�y�M�̗��s���������B�v�Ƃ��A���E��y�\���y�̓�d�\�����������I�Ȑ��E�ς̊����ɂ�舢��ɕ��̂���Ɋy��y�ւ̉�����]�A�܂��ω���F�̕�ɗ���y�A���ӕ�F�̊�����y�A��t���̏�ڗ����E�A�߉ޕ��̗�R��y���A���ʂȏ�y�ւ̓��ꂪ�����A�������疖�@�ӓy�̋~�ώ�Ƃ��Ă̐�瑂��N���[�Y�A�b�v�����悤�ɂȂ����B��瑂̂����n�E���ɑ����^�ыA�ˁA�������邱�Ƃ������ւ̂Ȃɂ��̋ߓ��ƍl������悤�ɂȂ����A�Ƃ���Ă���B �R���u��Y���́u���@���`�l�v(4)�ŁA�u���́w�{�n��瑐��x�́A�����́A�Ñ�̐_�_�M���ɓ�������ߒ��ŁA�p����ꂽ���̂ł��������A�����ɂȂ�ƌ��̈Ӑ}�𗣂�āA�_���̑�����ϋɓI�ɗ��p�����悤�ɂȂ����B�v�Ƃ���B�����ɂ́u�o�ϓI�Ȕw�i���M����v�Ƃ��āA�ݒn���̋����_�Ђ́A���_���q�Ƃ��ē���n��̎����Ƃ̂��т��Ă������A�����o�c�Ŋw�_�������́A����̎Ђ��O�Ɍ������Ĕ��W�����邽�߂ɂ͑����̐M�҂��K�v�ł���A�ݒn���̐������蕥���ׂ����ƂɋC�t���B�����ŕ�������������A�_�Ђ̗��_���𐄂��i�ߒ����_�����`������Ă����A�Ƃ����B 眓��o�T���́u�����_�Ɛ_���K���v(5)�ŁA�u�{�n���̐ݒ�E�{�n���̑������u�́A�{�n��瑐�����̓I�ɐ���������̂Ƃ��āA���̐������y�����Ō��ʓI�ł������B���ɖ{�n��������������u�����ƁA���ܔq���Ă���_�̖{�n�̎p���`�ƂȂ��Ċ�O�Ɏ��������̂ł��邩��A�M��̌��ʂ͂���߂č����Ƃ����悤�B�������ł͂Ȃ��B�{�n��瑐��ɂ͒P�ɏK���̗��_���Ƃ����ʂ����łȂ��A�ʂ̖ʂł��傫�ȈӖ����������B�v�Ƃ��A���_�I�Ȓn�搫(�n��I����)�����_�_���{�n���������ƂŁA����܂ł̒n��Ƃ����g������ʓI�Ȃ��̂ƂȂ�M���L�܂�B�X�̐_�_�̗��v���{�n���������ƂŐV���ȓ����������A�F��E�F���E������������ȏK���I�@���V������Ƃ���A��O�̐M���������邱�ƂɂȂ����B�Ր_�̕��_�A��_�A�q�_�Ƃ����Ƒ��I�W���A�{�n���̐ݒ�ɂ��e���A�ő��A��@�_���̊ϔO�ɒu���������āA�����̍��J�A�z�J�A�ێЁA���Ђ̐_�X�����o����A�Ր_�̍ו����A�������ɂ��Q�w�҂̑��l�ȋF����e�ɑΉ��ł���悤�ɂȂ����B�{�n��瑐��͐_�_���A�������o���ɁA�����̐M���W�߂��ł���߂ėL���Ȏ�i�ƂȂ肦���A�Ƃ���Ă���B �ȏ�̊e���̋����܂��āA�{�n��瑐������̔w�i���܂Ƃ߂Ă݂悤�B 10���I���납��}���ɐi�W����ފݕ\�ۂ̔�剻�Ə�y�M�̗��s��w�i�Ƃ��A�_�Б�������܂ł̍ݒn���Ƃ����������蕥���A������������_�̖{�n����ݒ肷��B�����ɂ͕���������̓��������A�������s�r���錰���̓`���ҁE����A���ɑ䖧�E�����ɂ�鋳���̓`�����Ȃ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���䓿���Y���́u���̐�(�{�n��瑐�)�����_�I�ɍ\�z�����ɂ������ė͂𒍂����̂́A�V��E�^���̗��@�ł����āA�R������_��(�V��)����ї����K���_��(�^��)�̐������d�v�Ȕw�i���Ȃ��Ă���B���������Đ�瑉��N�̑����͗��n��̋������琶�ݏo����Ă���v(6)�Ǝw�E����Ă���B �����āA�{�n�����A���u���邱�Ƃɂ���ċM�a�O���̎Q�w�𑣂��A�_�̖{�n�̎p����O�Ƃ����F��҂̐M�͂�苭�łɂȂ�A���ꂪ���`����邱�ƂŐM�͍L�܂�Q�w�҂̑w�������ł����̂ƂȂ�B���̉ߒ��ŌX�̐_�_�̗��v����������A���ꂼ��̋��߂ɉ������F��E�F���E�������s���A���s���Ē����_�����_�̌`���A�e�ЂƐM�҂̑g�D����������邱�ƂɂȂ�B���ʁA��O�ɁA��瑂̂����n�E���ɑ����^�ыA�ˁE�������邱�Ƃɂ��~�ς���A�����������Ƃ̍l�����蒅���Ă������A�Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���B �����Œ��ӂ������̂��A�������A�_�����ɂ��{�n��瑂̐ݒ�A���_�������ł͂Ȃ��A�������`�ȊO�ɖ����Ȃ��n���l�ɂ���ē��{�̓y���̒��ɓ`����ꂽ���̋��������ƂɊ��K�I�A���R�I�Ȑ_���K�������O�̊Ԃɏ�������Ă����Ƃ����ϓ_���B�u�A�W�A�����j���{�҇U�E��������<�M���ƕ���>�v(7)�ł́A�u���������܂ł̐_�{���������̊���ЂłȂ���������n���̐_�Ђł��邱�Ƃ��l����ƁA�n�����O�̖����o�I�Ȑ_���K���v�����y��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����v�Ǝw�E����Ă���B�@ |
|
|
��(5)�@�{�n��瑐��ƈꕧ�M�̗��_��
���̂悤�Ȗ{�n��瑐��̒蒅�ɂ�蕧�Ɛ_�͏c�Ɍ����B���̕����̕��E��F�͖@�g���ւƗn�Z����̂�����A�e�n�̐_�͌������ǂ�Γ����ł���A�F�����ňꕧ�ɋA������A�Ƃ������ƂɂȂ�B���鎛�����̌���(1110�`1193)������R�̐��E�P����ɕ��ɐ_���̊W�ɂ��ċ��������b���A���Z(1227�`1312)�̒��������b�W�u���ΏW�v(8)�ɍڂ����Ă���B(9) ���̌̂́A�吹�̕��ցA���ɂ��A�@�ɐ��ЂĒ��鏀(�̂�)�Ȃ��B�u���l�͏�̐S�Ȃ��B���l�̐S���ȂĐS�Ƃ��v�ƁA���ӂ��@���A�@�g�͒���g�Ȃ��B�����̐g���ȂĐg�Ƃ��B�R��A�����@�g����̏\�E�A�F��m��Ḃ̑S铂Ȃ�B�V��̐S�Ȃ�A����̎O��\�E�̈ː��A�F�@�g����̖����Ȃ�A�����̏\�E���C���ɂ���͂��āA�����F�g�̐����ȂāA��E�̖����x���B�������̐S�Ȃ�A�l�d�֒����́A�@�g����̏\�E��B���؎�����̖{���������āA�O�p��߂̗��v�𐂂�B�����̈ӂɂ��Ă͂���m�ʁB�@�g���\�E�̐g�������āA�O���𗘉v���B��铂̏�̖��p�Ȃ�A�������ʔg�̔@���B�^�@�͂Ȃꂽ�鉏�N�Ȃ��B�R��A���V���̋@�ɂ́A����F�̌`�������āA�����x���B �䍑�͈��U�Ӓn��B�����̏O�����ʂ�m�炸�B���@��M���ʗނɂ́A��铖����̎��߂ɂ��āA�����@�g�̉��p�𐂂�A���S�א_�̌`�������A�Ŏ֖ҏb�̐g�������A�\���̑������āA�����ɓ��ꋋ�ӁB����Α����L���̐g���̂ݏd���āA�{�������̌`�����y���ނׂ��炸�B�䒩�͐_���Ƃ��đ匠���Ƃ𐂂ꋋ�ӁB���A�䓙�݂Ȕނ̑����B�C��������������炸�B���̊O�̖{����q�˂A�҂Ċ����ւ�����ʂׂ��B���ċ@�������̘a���̕��ւ��āA�o�������̗v�����F��\����ɂ͂������B �����̐_�X���c�Ɉꕧ�ɋA������Ƃ������Ƃ́A��瑂̐_��M���邱�Ƃ̗��_��⋭���邱�ƂɂȂ邪�A����ł́A���̈ꕧ��M��������鐂瑂̐_���𐒂߂�Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�A�ꕧ�M�̗��_�����Ȃ���邱�ƂɂȂ�B��Ɍ����u���_�{���W�v�̖`���Ǝ��̐�瑂̐_������̖����A�X�ɕ����́A��y���̐M�̍������Ȃ�����Ɉꕧ�ւ̋A�˂Ƃ����_�ɂ����āA���̂��Ƃ�[�I�Ɍ����\���Ă�����̂ł͂Ȃ����낤���B �u�{���W�v�̖`�� ���ꕧ�ɂ͐_���̖{�n�A�_���͕��ɂ̐�瑂Ȃ�B�{�ɔ��瑂𐂂�邱�ƂȂ��A瑂ɔ�Ζ{���������ƂȂ��B�_���Ƃ������ɂƂ����A�\�ƂȂ藠�ƂȂ�āA�݂��ɗ��v���{���A��瑂Ƃ����{�n�Ƃ����A���ƂȂ���ƂȂ�āA���ɍϓx���������B�������[���{�n�𐒂߂���̂́A�K����瑂ɋA���闝(���Ƃ��)����B�{��萂���瑂Ȃ邪�̂Ȃ�B�ЂƂ��ɐ�瑂Ԃ��̂́A���܂��K�������{�n�ɋA���邢���Ȃ��B瑂��{�𐂂ꂴ�邪�̂Ȃ�B���̌̂ɁA��瑂̐_���ɋA����Ǝv��A�����{�n�̕��ɂɋA���ׂ��Ȃ�B ��瑂̐_������̖��� ����(�����A����A�F��A�O���A���g�A���R���̏����̊e�Ђ�)�F�A���̖{�n�������ʂ�A�ɉʂ̔@���A�[�ʂ̑�m�Ȃ�B�������@�̖{���ɂ��您����A���v�O���̔ߊ�ɏZ���āA���ɐ_���̌`������������B����̏H�̌��A�����H�Ó��̔g�ɏh���A��g�̏t�̉ԁA������L�����̕��Ɏ{���B���͊F�A�����̖@�g�A�{�n�͎�����g�̑S�[�Ȃ�B���̖{�n�A�l�X�ɈقȂ�ǂ��A�F��Ɉꕧ�̒m�b�Ɏ��܂炸�Ƃ������ƂȂ��B���邪�̂ɁA��ɂɋA�����A���X�̕���F�ɋA����闝(���Ƃ��)����B���̗����邪�̂ɁA���̐�瑂���_���ɂ́A�ʂ��Ďd���܂�˂ǂ��A�������琥�ɋA���铹������Ȃ�B ���� ���s�����������ĔO���ɋA����́A��s�����̂ĂĈՍs���Ɉڂ�Ȃ�B���㑊���̖@�Ȃ�ɂ��āA���艝���̉v�ׂ����̂Ȃ�B��瑂ɂƂǂ܂炸���āA�{�n�����́A�_���̖{���������ˁA�����̖{�ӂ�M����Ȃ�B�_���̂܂��Ƃ̌�S�́A��瑂𐒂߂���Ƃɂ͔B�O�������ĕ����ɓ��ꂵ�߂�Ǝv���������̂Ȃ�B�{�n�̕���F�́A������Ɉꕧ�̒q�d�Ȃ�A��ɂ̖������̂���ɁA�\���O���̏������̂�����O����ꋋ���B������F�A�O�����邢��ꂠ��A���̐�瑂��鏔�_�݂ȁA�܂��M�����邱�ƁA���̗��K�R�Ȃ�B����ΔO���̍s�҂ɂ́A���V�E�P�_�����̔@���ɐ����āA�������苋���̂ɁA��̍ЏᎩ�R�ɏ��ł��A���X�̕��S���߂���Ɏ������痈����B���������ɂ��āA�㐶�ɂ͕K����y�Ɏ���A�����i���ɝوׂ̖@�y���B���킵�āA�K������Ȃ�B�܂��Ƃɂ���ٖ��̍���闘�݁A�ϔY�̕a��������ǖ�Ȃ�B�ߑ��͂��ꂪ���߂Ɍ��t���͂��Ď]�Q���A�����͂��̌̂ɐ����ׂďؐ�(���傤���傤)��������B���ɂ̗i��ɂ�������A�_���̌�S�Ɋ����Ǝv���ɂ��A������(�˂�)��Ɍ㐶�����肢�āA����ɖ�ɂ̖������̂��ׂ����̂Ȃ�B�@ |
|
|
��(6)�@�߉ވꕧ�ց@���@�̏ꍇ
�u���_�{���W�v�ł́u�{�n�̕���F�́A������Ɉꕧ�̒q�d�v�Ƃ��āA����ɔ@���ւ̋A�˂���������A���̈ꕧ���߉ނƂ��āA�u��ؐ��Ԃ̍��X�̎�Ƃ���l���ꂩ����ߑ��Ȃ炴��B�V�Ƒ��_�E�������F�����̖{�n�͋���ߑ��Ȃ�v�Ɛ��������̂��@�،o�̍s�ҁE���@(1222�`1282)�������B ���������犙�q���ɂ����A�����_�̖{�n�͈���ɔ@���Ƃ��čL���M���ꂽ����A�a�����N(708)�����Ƃ�����������{(�������_��)�ł�11���I�ȍ~�A�����_�𐳔����Ƃ��A�{�n�͎߉ޔ@���Ƃ��āA�F�������{�Ƃ͖{�Ƒ��������Ă����B����̐������M��͏����h�ł͂������낤���A���@�͐�������p���Ė{�n�E�߉ނ������A�����Ƃ��ēW�J���Ă���B(10) �O��2�N(1279)2��2���u���Ꮧ�߉ޕ����{���v(�^�֑]��) �@�،o�̎��ʕi�ɉ]�͂��u���͌Ȑg��������͑��g������v���]�]�B�����̑P�����E�����̑���@���E�\���̏����E�ߋ��̎����E�O���̏����A��s��F���A����t���E�ɗ������A�垐�V���E��Z�V�̖����E�ߒ����E���V�E���V�E�����V�E�k�l�����E��\���h�E�ܐ��E�����E�����l��̖��ʂ̏����A���C�����E�V�_�E�n�_�E�R�_�E�C�_�E��_�E���_�E��ؐ��Ԃ̍��X�̎�Ƃ���l���ꂩ����ߑ��Ȃ炴��B�V�Ƒ��_�E�������F�����̖{�n�͋���ߑ��Ȃ�B (�u���a��{�@���@���l�╶�v�ȉ��A�u��v�ƕ\�L�@p.1623) �O��3�N(1280)12��18���u�q���[��Ԏ��v(�^��) ���Ԃ̐l�X�͔������F���Έ���ɕ��̉��g�Ɛ\�����B��������Â̐l�X�̌䌾�Ȃ������B�A������̐������̖̐��ɂ́A����ɂ͔����Ɛ\���A����ɂ͐̂���h�R�ɍ݂Ė��@�،o����č����{�̒��ɍ݂đ��F�Ǝ��������]�]�B�����ɂĂ͎ߑ��ƌ��͂�Ė@�،o��������ЁA���{���ɂ��Ă͔������F�Ǝ������Đ����̓���ɗ��ċ��ӁB����ߑ��͏Z�����̌��A�l���S�̎��A�l�������b�Ђ̓����A�V���ɐ��ꋋ�ЁA���\�N���o�āA�\�ܓ��p�\�̓�����łȂ苋�ӁB�������F�͓��{����\�Z�㉞�_�V�c�A�l�������b�Ђ̓����ꂳ�����ЂāA��N���\�̓̏\�ܓ��p�\�ɉB�ꂳ�����ӁB�߉ޕ��̉��g�Ɛ\�����͂���̐l�����炻�����Ȃ��ׂ��B ������ɍ����{���̎l�\�܉��������Z�S�\��l�̈�؏O���A�P���E�d�S�E�i�ρE�@�R���̑�V���ɂ��ڂ炩����āA�ߑ����Ȃ����ĂĈ���ɕ���{���Ƃ��B���܂�̕��̂���킵���ɁA�\�ܓ���D�Ў�Ĉ���ɕ��̓��ƂȂ��B�������܂��炩���Ė�t���̓��Ɖ]�]�B���܂�ɐe���ɂ��܂�ƂāA�������F���Έ���ɕ��̉��g�Ɖ]�]�B���F�����ĂȂ��₤�Ȃ�ǂ��A�����̌䂩�����Ȃ�B�m�炸�킳(��)�ł�����ׂ��ɁA���@����\���N���ԁA�����O�E�̕������č��̖��Ђ����߂��A�M�������Ă����L��ׂ��ɁA��(��)�A��(��)�A���낵�A�Ȃ����A����(��)��ւɁA�������F����₢�Ă����V�ւ͂̂ڂ苋�Ђʂ�߁B���@�����ւČ��������_���Ȃ�B(��@p.1826) �O���O�N�\�u�ЋŔ������v(�^��) ����̐������{�̐̕��ɉ]���u�̗�h�R�ɍ݂Ė��@�،o����������{�̒��ɍ݂đ��F�Ǝ������v���]�]�B�@�،o�ɉ]���u�����O�E�v���]�]�B���u��ɗ�h�R�ɍ݂�v���]�]�B�����͎O���琢�E�̈�؏O���͎߉ޔ@���̎q��B�߂��͓��{���l�\�㉭�㖜�l�甪�S��\���l�͔������F�̎q��B�����{���̈�؏O���͔��������̂ݕ��₤�ɂ��ĂȂ��A�߉ޕ������ĕ��́A�e������܂�骵�����ȂÂ�B�q�Ɍ��Đe���̂�(�l)�����Ƃ��B�{�n�͎߉ޔ@���ɂ��Č������ɏo�łĂ͐����̕��ւ̖@�،o��������ЁA��瑂͓��{���ɐ���Ă͐����̒��ɂ����ӁB(��@p.1848) �@ |
|
| ��10�@�u���ƕ���v�Ɍ�����F��M�@ | |
| ���q����ɐ��������Ƃ����u���ƕ���v�ɂ́A�F��M�S�����̗l�����ĂƂ��悤�ȕ`�ʂ���������B�����ƂȂ��Ă��܂����A�u���ƕ���v�̌F��W�̋L�q�����Ă݂悤�B�s�K�X���s�����t | |
|
�u�����E��(������)�v
���Ƃ��₤�ɔɏ�����ꂯ����A�F�쌠���̌䗘���Ƃ����������B���̌̂́A��(���ɂ���)�A�������A���܂����|�炽�肵���A�ɐ��̊C���D�ɂČF��֎Q��ꂯ��ɁA�傫�Ȃ���̑D�ɓ��肽�肯����A��B�\������́A�u����(�F��)�����̌䗘���Ȃ�B�������Q��ׂ��v�Ɛ\������A������(�̂���)�Ђ���́A�u�́A���̕����̑D�ɂ����A�����͗x����肽�肯��Ȃ�B���A�g���Ȃ�v�ƂāA������\�����������A���i���ւ̓��Ȃ�ǂ��A�������āA�Ǝq�����ɐH�͂���ꂯ��B���̌̂ɂ�A�g���݂̂����Â��āA������b�܂ł��͂ߋ��ւ�B�q���̊��r(������)���A���̉_�ɏ�����́A�P���݂₩�ɂ�B���̐��F(���傤)���������ӂ����ڏo������B (�Ӗ�) ���Ƃ����悤�ɔɏ������̂��F�쌠���̌䗘�v�ł���A�Ə����ɕ������Ă���B���̌̂́A������(1118�`1181)���܂����|��ł��������A�ɐ��̊C���D�ŌF��֎Q�w�������A�ˑR�A�傫���炪�D�ɖ�荞��ł����B�����������B�́u����͌F�쌠���̌䗘�v�ł��B�}���ŐH�ׂ܂��傤�v�ƌ����A�����́u���̐́A���̕����̑D�ɔ�������荞�Ƃ������A����������g���ł���v�Ƃ��āA�ł��\�����������Đ��i���ւ����Ă��������ł͂��������A������ĉƂ̎q�A���B�ɐH�ׂ������̂ł���B���̌̂ł��낤���A�����ɂ͋g���݂̂������āA������b�܂ŏ���߂Ă���B�����̎q���̊��ʂ��A�����_�ɏ�������A�Ȃ��������̂ł������B��c�E���̐����z����ꂽ�̂͂߂ł������Ƃł���B |
|
|
�u�����@��[�����߁v
����3�N(1177)6���A�㔒�͉@��i����ߐb�����Ƒœ|����Ă��Ƃ����u���P�J(����������)�����v�ł́A�����ɂ�肱�Ƃ����O�ɘI���B��d�҂Ƃ��ꂽ��[���E�������e(1138�`1177)�͗��߂ƂȂ�B���Č㔒�͉@�̌F��Q�w�ɐ��������e���A���Ɉ͂܂�đD�ɏ�荞�ތ��i��`�������͂́A���̎���ɂ�����F��w�ł̖͗l���M������̂ƂȂ��Ă���B����ɂ��ƁA�u�F���V�����ɎQ�w���鎞�́A����A�O���̗��h�Ȍ���D�ɏ��A�������D�͓�A�O�\�z�قǑ����A�˂Ă����v�Ƃ�������Ȃ��̂������B �F��w�A�V�����w�Ȃ�ǂɂ́A����͂�̎O���ɂ�������M�ɏ��A���̏M��O�\�z�����Â��Ă������肵�ɁA���͂������邩������`�M�ɑ喋�Ђ����A�����Ȃ�ʕ����ɂ������āA������������ɓs���o�łāA�Q�H�͂邩�ɂ����ނ��ꂯ��S�̂����A�����͂����Ĉ���Ȃ�B ������@�N���j��� �u���P�J�����v�̎�d�҂Ƃ���铡�����e�͔��O���֗��߁B����(�H�`1177)�͎a��A���e�̎q�E���o(1156�`1202)���������֗�����A��ɕ��N��(���v�N�s��)�A�^���m�̏r��(1143�`1179)�Ƌ��ɎF�����S�E�P���֔z�������B�������o�A���N���̓�l�͋S�E�P���̊e�����F��O�R�Ɍ����āA���ߎ͖Ƃ��F�肵�Ă���B ������ɁA�S�E�����̗��l���A�I�̖����t�̂���ɂ������āA�ɂ��ނׂ��Ƃɂ͂���˂ǂ��A�O�g�����̂����ƁA���ɑ��̗́A��O�����������A�ߐH����ɑ���ꂯ��A����ɂĂ��A�r���m�s���N�����A���������ĉ߂�����B �N���͂Ȃ����ꂯ�鎞�A���h�̎��ςɂāA�o�Ƃ��Ă�A�@���͐��ƂƂ��������肯��B�o�Ƃ͂��Ƃ��̖]�Ȃ肯��A �Ђɂ������ނ��͂Ă��鐢�Ԃ��A�Ƃ��̂Ă��肵���Ƃ����₵�� �O�g�����A�N�������́A���Ƃ��F��M���̐l�X�Ȃ�A�u�����ɂ����āA�����̂����ɁA�F��̎O������������������āA�A���̎����F��\����v�Ɖ]�ӂɁA�r���m�s�́A�V���s�M���̐l�ɂāA����p�����B��l�͓����S�ɁA�����F��Ɏ����鏊�₠��ƁA���̂�����q�˂܂͂�ɁA���͗ѓ��̖��Ȃ邠��A�g�яJ�̏ς��Ȃ��ȂɁA���͉_��̂��₵������A�ɗ����̐F��ɂ��炸�B�R�̂������A�̂������Ɏ���܂ŁA�O�����Ȃُ��ꂽ��B���]�߂A�C���X�Ƃ��āA�_�̔g���̘Q�ӂ����A�k�����ւ茩��A���R�x�̉�X������A�S�ڂ̑ꐅ���藎������B��̉����Ƃɂ����܂����A�����_���т���Z�ЁA��ꌠ���̂��͂��܂��A�ߒq�̂��R�ɂ������肯��B ���Ă����₪�Ă������A�ߒq�̂��R�Ƃ͖��Â�����B����͖{�{�A����͐V�{�A���͂�����₤�����q�A�މ��q�Ȃ�ǁA���q���q�̖���\���āA�N��������B�ɂāA�O�g�����������A�����ƂɌF��܂��ł̂܂˂����āA�A���̎������F����B�u�얳�����������q�A�˂��͂��͗������ꂳ�����͂��܂��āA�Ë��ւ��ւ����ꂳ�����ЂāA�Ȏq��������x�݂����ցv�Ƃ��F�肯��B ��������Ă������ӂׂ���߂��Ȃ���A���̈߂�g�ɂ܂ƂЁA��ӂ̐�������ɂ����ẮA��c�͂̂��悫���Ƃ����Ђ��A�������ɂ̂ڂ��ẮA���S��Ƃ��ς�����B�Q�邽�т��Ƃɂ́A�N�������j����\���ɁA�䕼�����Ȃ���A�Ԃ���܂�Ă������A�ۂ������Ύ��A�������N���сA���̂Ȃ�я\���A���̐��O�S�\�]�P���A�g���ǒC�����ŁA�����܂����z���A���{����̌��A�F��O�������A����F埵�̋��߁A�F���̍L�O�ɂ��āA�M�S�̑�{��A�H�ѓ������o�A��ɍ��퐫�ƁA��S����̐���v���A�O�Ƒ����̎u�𒊂łāA�ނł����Čh���B �v�ؐ����F�́A�ϓx��C�̋���A�O�g�~���̊o����B���͓�����ڗ��㉤�̎�A�O�a�����̔@����B���͓����ɗ��\���̎�A���d����̑�m�B�ቤ�q�͛O�k���E�̖{��A�{���؎҂̑�m�A����̕��ʂ������āA�O���̏�����݂ċ��ւ�B���ɂ���āA���݈�l���A���������Ɏ���܂ŁA���͌��������̂��߁A���͌㐶�P���̂��߂ɁA���ɂ͏�����ŁA�ϔY�̍C���������A�[�ɂ͐[�R�Ɍ����āA�����ӂ�ɁA�����������鎖�Ȃ��B��X�����̂��������A�_���̂������ɚg�ցA�ӁX����J�̂ӂ������A�O���̂ӂ����ɏy�ւāA�_���Ă̂ڂ�A�I�����̂��ʼn���Bূɗ��v�̒n�����̂܂��ނA��������ӓ�̘H�ɂ͂���B�����̓������ӂ�����A�����K�������H���̋��ɂ܂��܂��ށB�����ďؐ��匠���A����F埵�A�@���߂��Ƃ𑊂Ȃ�ׁA��������(������)�̌䎨���ӂ肽�ĂāA�䓙������̒O����m�����āA��X�̍��u��[���ցB�R��Α����A�����ʂ̗��������A���̂��̋@�ɐ����āA�L���̏O�����݂��т��A�����̌Q�ނ������͂��߂ɁA�����̂��݂������ĂāA�����l��̌���a���A�Z���O�L�̐o�ɓ������ւ�B�̂ɒ�Ɩ��\�]�A�������������̗�q�A������ˁA������������鎖�Ђ܂Ȃ��B�E�J�̈߂��d�ˁA�o���̉Ԃ�����āA�_�a�̏������A�M�S�̐������܂��āA�����̒r��X�ւ���B�_���[���͂A����Ȃ��A�������B����͂��́A�\�����A������������ׂāA�y���ɋ�C�̋�ɂ�����A���J�̏D���₷�߂āA�A���̖{�����Ƃ����ߋ��ցB�Ĕq�B�Ƃ��A�N���j�����ΐ\������B (�Ӗ�) ���āA�S�E�����̗��l�B�́A�I�����̗t�̖��ɂ������Ă���悤�ɁA�ɂ���ł���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�O�g����(�������o)���n�E��e�ɑ�(������)�̗̒n�E��O������������A�ߐH����ɑ���ꂽ�̂ŁA����ŏr���m�s�����N���������Ȃ��߂����Ă����B���N���͗����ꂽ���A���h�̎��ςŏo�Ƃ��āA�@���͐��ƂƂ��Ă����B�o�Ƃ͂��Ƃ��̖]�݂������̂ŁA���ɂ͂����̂ĂĂ��܂������̒����A�����Ɏ̂ĂȂ������͉̂��������Ƃł���Ǝ���̐S���f�I���ꂽ�B �O�g�������o�ƍN�������͌��X�A�F��M�̐l�Ȃ̂ŁA�u�Ȃ�Ƃ����āA���̓��̓��ɌF��O������������������āA�A���̎����F��\���������̂��v�ƌ��������A�r���m�s�͓V���̕s�M���̐l�ł���A���o�ƍN���̂������Ƃ�p���Ȃ��B��l�͓��S���āA������F��Ɏ����������邩������Ȃ��ƁA���̒���q�˂܂��ƁA���邢�͗т̒炪����A�g��т̎h�J�̂悤�ɔ�������������B���邢�́A�_�̂��������R�X������A�����F�ł͂Ȃ��ω����Ă���B�R�̌i�F��ؗ����̗l�܂ł����̏������������A���ɖ��Ȃ�i���̒n�ł���B���]�߂ΊC�͍L����A�g�͉_�≌�̂悤�Ɍ����A�k�U��Ԃ�ƎR�X�̌������Ƃ�����A�S�ڂ̑�̐������������Ă���B��̉��͂��Ƃɐ��܂����A�����������_�X�����Âт��Ƃ���́A��ꌠ���̂܂��܂��ߒq�̂��R�ɂ悭���Ă���B�����ŁA���̒n��ߒq�̂��R�Ɩ��t�����B ���̕�͖{�{�A���̒n�͐V�{�A����͉��X���q�A���̉��q�A���̉��q�ƁA���q�̖��������Ȃ���N���������B�Ƃ��āA�O�g�������o���������āA�����ɌF��w�ł̐^�������ċA���̎����F���Ă����B �u�얳�����A�������q�A��킭�͗���݂𐂂�A�̋��A�����֓��ꂳ�������B�Ȏq�ɂ��A����x�A��킹�����v�Ɠ�l�͋F�����B �����o���A���ւ���ׂ���߂��Ȃ��̂ŁA���̈߂�g�ɂ܂Ƃ��āA��ӂ̐���g�̍C�𗎂Ƃ����߂ɋ���ł́A��c�͂̐�������Ǝv���A�������ɓo���ẮA�����S��Ƃ��Ă����B�Q�w�̓x���ɍN���������j��(�̂��)��\�������A�䕼�̎��������̂ŁA�Ԃ���܂肵�Ă͕����Ă������B �N�͂��ꎡ�����N(1177)����(�Ђ̂ƂƂ�)�A���̂Ȃ�т͏\���A���̐��͎O�S�\�]���ƂȂ�B�g���A�ǂ�����I��ŁA�\���グ����z�����A���{���̑�쌱�A�F��O�������A���ω��̐�瑂Ŝ|�{�g�ł�������F�̋����ɗ�����O�ɂ����āA�M�S�̑�{��A�E�߉q�����E�������o�A���тɍ���E����(�N������)�A��S����̐�������āA�g���ӂ̎O�Ƃ����������u�������āA�ނ�Ōh���Đ\���܂��B ����ؐ����F(�{�{)�́A�O������C����~���ފ݂֓n������ł���A�@�̎O�g���~�����ꂽ���ł���܂��B ���邢�͑��ʋ{(�V�{)�̖{�n�E��t�@���͓�����ڗ����E�̎�ł���A�O����a���~����@���ł���܂��B ���邢�͌��{(�ߒq)�̖{�n�E���ω���F�͓����ɗ���V�s�\���̎�ł���A���o�̕�F�ł���܂��B �ቤ�q�͛O�k���E�̖{��ŁA�ϐ�����F(�{���؎�)�ł���A����̕��ʂ������ďO���̏���������Ă��������܂����B ����ɂ���āA���l���A�������Ɏ���܂ŁA���邢�͌��������̂��߁A���邢�͌㐶�P���̂��߂ɁA���ɂ͏�����ŔϔY�̍C���������A�[�ׂɂ͐[�R�Ɍ����ĕ��̖���������ƁA�����ӂ鎖�͂���܂���B ��X�����̍�����_���̂�������栂��A�������J���[���̂��O���ϓx�̐����[���ɂȂ��炦�āA�_���Ă͓o��A�I�����̂��ł͉����Ă��܂��B�����ɏO���ϓx�̕���F�̗��v�𗊂݂Ƃ��Ȃ���A�����ɂ��Č���̘H����ނ��Ƃ��ł���ł��傤���B�����̓������Ȃ���A�ǂ����Ă��̂悤�ȗH���̋��ɂ��킵�܂����Ƃ�����ł��傤���B�䂦�ɏؐ��匠���A�����F��A�@���߂̊����ׁA������(��������)�̂悤�Ȍ䎨���ӂ肽�ĂāA�䓙������̐^�S��m������A���̍���Ȃ�u��[�ꋋ���B �R����Ȃ킿�A���E���ʂ̗��������́A�e�X�̋@�ɐ����āA�L���̏O�����A�������O�����~����߂ɁA�����̂��݂����̂ĂāA�����l��̌���a�����E�ւƂ�����A�Z���O�E�̔ϔY�̐o�ɓ������Ă���܂��B�̂ɒ�Ɩ��\�](�@�ؕ���L)�A������������(��t�{������o)���肢��q����҂�����A�ˁA����(�_�ɕ����镨)�A���(�_���ɋ����鋟��)������邱�Ƃ͓r��邱�Ƃ�����܂���B�E�J�̈߂𒅂āA���ւ̉Ԃ�����āA�_�a�̏������قNjF�肵�A�M�S�̐��܂��āA�������v�̒r�͖����Ă��܂��B�_�l���[�Ă�������Ȃ�A�肢���ǂ����Đ��A���Ȃ��Ƃ������Ƃ�����ł��傤���B����킭�Ώ\������A�����̗�����ׂėy���ɉ��̂��̋ꂵ�݂̊C�A��ɔ��ł��āA���J�̔߂��݂��Ȃ����A���̖{���𐋂����������B�Ĕq�B �ƍN�������͏j����ǂݏグ���B (������2�N[1178]�A�������̎����E���q[1155�`1213]�̈��Y�F��̑�͂��o����A�������o�ƕ��N���͎͂���ċA���B�r���͓��ŖS���Ȃ���) |
|
|
�u����O�@飈(������)�
���܌��\����ߙ�(���܂̂���)����A�����ɂ͒ҕ����т������������āA�l�����ق�顚�|���B���͒���勞�ɂ�肨�����āA���\(�Ђ�����)�̕������čs���ɁA���啽��𐁂��ʂ��āA�l�ܒ��\���������Ă䂫�A�����A�Ȃ����A���Ȃ�ǂ́A����ɎU�݂��B�w��A�ӂ��̂����ЁA�~�̖ؗt�̕��ɗ���邪�@���B���т��������Ȃ�ǂ�މ��A�ޒn���̋ƕ��Ȃ�Ƃ��A����ɂ͉߂����Ƃ��݂����B�����ɉ��̔j������݂̂Ȃ炸�A�������Ӑl�������B���n�̂����ЁA����s�����đł����낳��B���������ɂ��炸�A��肠��ׂ��ƂāA�_�_���ɂ��Č�肠��B �u���S���̂����ɁA�\���������b�̐T�A�ʂ��Ă͓V���̑厖�A���тɁA���@���@���ɌX���āA���v�������ׂ��v�Ƃ��A�_�_���A�z���A���ɂ���ȂА\������B (�Ӗ�) ���N(����3�N�E1179)5��12���̐��ߍ��A�����ɒҕ��������r��A�����̐l�Ƃ��|���B���͒�����H�Ƌ��ɑ�H�̌������邠���肩��N����A�쐼�̕������Ă����A��(�ނ�)�̂����A����(�Ђ炩��)�𐁂�����āA�l�A�ܒ��A�\���������Ă����A���A����(�Ȃ���)�A�����͋�ɕ����������Ă��܂����B�����̞w��(�Ђ킾)�A����(�ӂ�����)�̗ނ́A�~�̖̗t�����ɗ����悤�Ȃ��̂��B���̉��͂��т���������ǂ�߂��āA�ނ̒n���̋ƕ��ł��A����قǂł͂���܂��Ǝv����B�����A�Ɖ����j��邾���ł͂Ȃ��A�����̐l�������������B���n�̗ނ��́A������Ȃ��ł��E����Ă���B���̂悤�ȎS���͂������ł͂Ȃ��B���(�݂���)���s���ׂ����Ƃ��āA�_�_���Ō�肪�s��ꂽ�B �����ł́u�����S���̓��ɁA���\�̑�b���ސT���邱�ƂƂȂ�A�Ƃ��ɓV���̑厖���N���A�����ɕ��@�E���@���ɐ����Đ헐�������������ԂƂȂ�ł��傤�v�ƁA�_�_���E�A�z�����ɐ肢�\���ꂽ�B |
|
|
�����O�@��t�ⓚ�
�����̂��Ƃǂ��l�̎��������ЂāA���ÐS�ڂ�����v�͂ꂯ��A����F��Q�w�̎����肯��B�{�{�ؐ��a�̌�O�ɂāA���������h������ꂯ��́A�u�e�����������̑̂��݂�ɁA���t�����ɂ��āA��������ΌN���Ȃ�܂����B�d�����q�Ƃ��āA�p����|���������Ƃ��ւǂ��A�g�s�т̊ԁA��������ĕ��^�����B���̂ӂ�܂Ђ��݂�ɁA����̉h�ԗP����ӂ��B�}�t�A�����āA�e�������A����g���������B�����ɓ����āA�d�����₵�����v�ւ�B�Ȃ܂��ЂɗāA���ɕ������A���ւėǐb�F�q�̖@�ɂ��炸�B�������A����g��ނ��āA�����̖��]��e�āA�����̕������߂�ɂ́B�A���}�v���n�A����ɂ܂ǂւ邪�̂ɁA�P�S������(�ق����܂�)�ɂ����B�얳�����������q�A��͂��͎q���ɉh���������āA�d�ւĒ���ɂ܂��͂�ׂ��́A�����̈��S��a���āA�V���̈��S���ߋ��ցB�h�s��������������āA�㍬(��������)�p�ɋy�Ԃׂ��́A�d�����^�����Â߂āA�����̋�ւ��������ցB���P�̋���A�ЂƂւɖ��������v�ƁA�̒_�𝔂��ċF�O����ꂯ��ɁA���Ẳ̂₤�Ȃ镨�́A���Ƃǂ̌�g���o�łāA�ς��Ə���邪���Ƃ����Ď����ɂ���B�l���܂�����肯��ǂ��A����Đ���\�����B �������̎��A��c���n��ꂯ��ɁA���q(���Ⴍ��)����(����̂���)�����ې�(�������)�ȉ��̌��B(����)�A��߂̂����ɔ��F�̂��ʂ𒅂āA�Ă̎��Ȃ�A�ȂɂƂȂ��͂̐��ɋY(�����)�ꋋ�Ӓ��ɁA��߂̂ʂ�Ă��ʂɂ������邪�A�ɐF�̂��Ƃ��Ɍ�������A�}����\(�����悵)�A��������Ƃ��߂āA�u���ƌ����A���̌��߂́A��ɂ��܂͂����₤�Ɍ����������͂��܂���B�������ւ��ׂ������v�Ɛ\������A���ƂǁA�u�킪������ɐ��A���ɂ���B����ߊ��ւĂ��炽�ނׂ��炸�v�ƂāA�ʂ��Ċ�c����F��ցA�x(��낱��)�̕�(�ق��ւ�)�������Ă�ꂯ��B�l���₵�Ǝv�Ђ���ǂ��A���S�������B������ɍ����B�A���Ȃ��܂��Ƃ̐F�𒅋��Ђ��邱���ӂ����Ȃ�B�����̌�A�������̓������o�����āA�a�t�����ӁB�������łɌ�[��ɂ����ƂāA�Î��������͂��A�F�������������ꂸ�B (�Ӗ�) ����b�E�d��(�����̑�b�E���d���A1138�`1179)�́A5��12���ɋ����������r��A�r��Ȕ�Q�������炵�����Ƃ���āA�����ɂ��S�ׂ��v��ꂽ�̂ł��낤�B���̍��A�F��ɎQ�w���ꂽ���Ƃ��������B�{�{�E�ؐ��a�̌�O�ɂāA��ʂ����ꂽ���Ƃ́A �u���E��������(������)�̐U�镑�������܂��ƁA���t�����ɂ��āA��������ΌN(�㔒�͖@�c)��Y�܂�����Ă��܂��B�d���͒��j�Ƃ��ĕp����|�߂Ă���܂����A�s�т̐g�ł�����́A���͕�������Ă���܂���B���̂܂܂ł́A���̉h�ł������낤�����̂�����܂��B���̐�A�q�����ɉh���āA�e�̖������߂邱�Ƃ͓�����Ƃł��傤�B���̂悤�Ȏ��ɂ�����A�d���͕s�����Ȃ�����v���܂��B�Ȃ܂��d�b�ɗāA���̕������݂ɐg��C���邱�Ƃ́A�ƂĂ��ǐb�F�q�̍s���Ƃ͂����܂���B�����̂Đg��ނ��āA�����̖������Ȃ������ė����̕������߂�ɂ��������Ƃ͂���܂���B�������A�ϔY�ɂ܂݂ꂽ�}�v�Ő���ɖ������̂ɁA�Ȃ��A�o�Ƃ̎u�𐋂���ꂸ�ɂ��܂��B�얳�����������q�A��킭�A�q���̔ɉh���₦���A����Ɏd���Đl�X�Ɍ�����Ȃ�A�����̈��S��a�炰�āA�V���̈��S���������B����Ƃ��h��������ŁA�q���ɂ܂Œp���y�Ԃ̂Ȃ�A�d���̉^���͂���܂łƂ��A�����܂ŌJ��Ԃ����ꂵ�݂�菕�������B���̓�̊肢�������āA�_�̏����������̂ł��v �ƁA�S��s�����Đ[���F�O�����Ƃ���A���Ẳ̂悤�Ȃ��̂��d���̐g���o�āA�ς��Ə�����悤�ɂ��ĂȂ��Ȃ����B�����̐l�����̕s�v�c�ȗl�����Ă������A�F�A����Č��ɂ���l�͂��Ȃ������B �܂��A�A��Ɋ�c���n���Ă����Ƃ���A�d���̒��j�E�ې�(1158�`1184)�ȉ��̌��B���A��߂̉��ɔ��ĐF�̈߂𒅂āA�Ă̂��Ƃł���A�Ȃ�Ƃ͂Ȃ��ɐ�̐��ŋY�ꂽ�̂����A��߂��G��ĉ��̈߂��������̂��A�����������n�F�̑r���Ɍ������̂ŁA�}����\����������Ƃ��߂āA�u���Ƃ������Ƃł��傤�B���̌��߂͊��܂킵�����̂Ɍ����܂��B�����ւ����ق�����낵���ł��傤�v�Ɛ\���グ���Ƃ���A�d���́u�����肤�Ƃ���͊��ɐ��A�����̂��B���̏�߂͂����Ē��ւ���ׂ��ł͂Ȃ��v�ƌ����A���ʂɊ�c����F��ցA���̕g�����킳�ꂽ�B ���͂̐l�͏d���̐S�������炸�A�������Ȃ��Ƃ��Ǝv�����B������ɁA���̌��B���A���Ȃ����Ă܂��Ƃ̑r���𒅂�悤�Ȃ��ƂɂȂ����͎̂��ɕs�v�c�Ȃ��Ƃł���B�F����A��ꂽ��A�����������Ȃ������ɕa�C�ɂȂ��Ă��܂����B�d���́u�F�쌠�������ɉ䂪�肢����[�ꂽ�̂��v�Ƃ��Ď��Â����ꂸ�A�F�������邱�Ƃ��Ȃ������B (����3�N[1179]�[7��29���A���d���͕a�v����) |
|
|
�u����l�@�������v
����4�N(1180)4���A�Ȑm��(1151�`1180)�������Ǔ��̗ߎ|��S���̌����Ǝ��ЂɌ����Ĕ����A���s��(�V�{�\�Y�@�H�`1186)�������Ɍ������B��5���A���̓�����m�����F��ʓ��Ƃ̒X��(1130�`1198)�͕��ƕ��ɗ^���A�{�{�Ɠc�ӂ̐��͂𗦂��Č������̐V�{���A�ߒq���Ɛ키���s�k����B�������A�������̋�����͌F��O�R�̗Z�a�ɓ����A���i3�N(1184)��21��F��ʓ��ɕ�C����Ă���͌������ɉ����B���i4�N(1185)3���A�F�쐅�R�𗦂����X���͌����R�Ƌ��ɕ��Ƒ���ɐ킢�A�u�d�̉Y�̐킢�v�̏����ɍv�������B ���A�ܗ��d���̋����ɂ���(1)�A�X���͍���R�����@�J�ɎO�Ԏl���̏Z�[�������Ă���A����5�N(1175)5���A����[�S�o(1117�`�H)�ɏ���n���Ă���B�S�o�̈ڏZ�ɂ���ďZ�[�͕Տƌ��@�ƂȂ����B��s���厛�n�̔O��������R�ɓ��������̂��S�o�ł������Ƃ����B �����@���̍c�q�A�Ȑm�̉��Ɛ\�����́A�������[���G�����̌䖺�Ȃ�B�O�����q�ɂ܂��܂�����A���q�̋{�Ƃ��\����B���i�����N�\�\�Z���A��N�\�܂ɂāA�E�т߉q�͌��̑�{�̌䏊�ɂāA�䌳�����肯��B���Ղ��������������A��ˊw������Ă܂��܂�����A�ʂɂ��������ӂׂ��ɁA�̌��t��@�̌䂻�˂݂ɂāA�������߂�ꂳ�����ЂA�Ԃ̂��Ƃ̏t�̗V�ɂ́A���|���ӂ���Ď�Â�����������A���̑O�̏H�̉��ɂ́A�ʓJ���ӂ��Đg�Â���뉹������苋�ӁB�������Ă��������炵���ӂقǂɁA�����l�N�ɂ́A��N���ɂ��Ȃ点�܂��܂�����B����߉q�͌��Ɍ�Ђ��錹�O�ʓ��������A����Ђ����ɍ��{�̌䏊�ɎQ���Đ\�����邱�Ƃ��������낵����B �u�N�͓V�Ƒ�_�l�\�����̌䖖�A�_���V�c��莵�\����ɂ����点���ӁB���q�ɂ������A�ʂɂ��������ӂׂ��ɁA���܂ŋ{�ɂĂ킽�点���ӌ䎖���A�S�����Ƃ͂��ڂ��߂�����B�����̂Ă�����ɁA���ւɂ͂������Ђ���l�Ȃ�ǂ��A���X�͕��Ƃ����˂܂ʎ҂��B��d�������������ЂāA���Ƃ��ق�ڂ��A�@�c�̂��ƂȂ����H�a�ɂ������߂��Ă킽�点���ӌ�S�����A�₷�ߎQ�点�A�N���ʂɂ������ӂׂ��B�����F�s�̂�����ɂĂ�����͂�B�������ڂ��߂����������ЂāA�ߎ|�����������ӕ��Ȃ�A�x���Ȃ��ĎQ��ނ��錹���ǂ��������ق���ցv�ƂĐ\���Â��B �u�܂Ë��s�ɂ́A�o�H�O�i���M���q���A�ɉ�����A�o�H���������A�o�H���l���d�A�o�H���Ҍ��\�A�F��ɂ́A�̘Z���`�����q�A�\�Y�`���ƂĂ�����Č�B�ےÍ��ɂ͑��c���l�s�j������ւǂ��A�V��[�����e���̖d���̎��A���S���Ȃ��炩�ւ蒉������s���l�Ō�ւA�\���ɋy���B ����Ȃ��瑴��A���c��Y�����A�蓇�̊��ҍ����A���c���Y����A�͓����ɂ́A������������`��A�q���Ή͔�����`���A��a���ɂ́A�F�쎵�Y�e�����q���A���Y�L���A��Y�����A�O�Y�����A�l�Y�`���A�ߍ]���ɂ́A�R�{�A���A�ь×��A���Z�A�����ɂ́A�R�c���Y�d�L�A�͕ӑ��Y�d���A�Y�d���A�Y��l�Y�d���A���H���Y�d���A���q���Y�d���A�ؑ��O�Y�d���A�J�c������d���A��搶�d���A���q���Y�d�s�A�b�㍑�ɂ́A�팩���ҋ`���A���q���Y�����A���c���Y�M�`�A���ꌩ��Y�����A�������Y�����A������Y�����A�_�O�Y���M�A�팩���q�L�`�A���c�ܘY�M���A���c�O�Y�`��A�M�Z���ɂ́A������Y�ۋ`�A���c���Ґe�`�A���ꊥ�Ґ��`�A���q�l�Y�`�M�A�̑ѓ��搶�`�������j�A�ؑ\���ҋ`���A�ɓ����ɂ́A���l�O�E���q�������A�헤���ɂ́A�M���O�Y�搶�`���A���|���Ґ��`�A���q���Y���`�A���O�Y�`�@�A�l�Y���`�A�ܘY�`�G�A�������ɂ́A�̍��n���`�������q�A��Y���ҋ`�o�A����݂ȘZ�����̕c��A���c�V������������Ȃ�B ���G�������Ђ炰�A�h�]���Ƃ������́A�������Âꏟ��Ȃ��肵���ǂ��A���͉_�D�܂��͂���ւ��ĂāA��]�̗�ɂ��Ȃق��Ƃ��B���ɂ͍��i�ɂ������ЁA���ɂ͗a���ɂ��͂�A�����G���ɂ��肽�Ă��āA�₷���v�Ђ���͂��B��������S��������B�N�������ڂ��߂����������ЂāA�ߎ|�������Â���̂Ȃ�A�����ɂ��Œy���̂ڂ�A���Ƃ��ق�ڂ��A�������߂��炷�ׂ��炸�B�������N��������Č�Ƃ��A�q���Ђ���ĎQ���ׂ��v�Ƃ��\������B �{�͍�������������ׂ����ƂāA�����͌䏳�����Ȃ��肯�邪�A���Êۑ�[���@�ʋ��̑��A����O�i�G�ʂ��q�A���[���ɒ��Ɛ\����A���ꂽ�鑊�l�Ȃ肯��A���̐l�����[���Ƃ��\������B���l�����{�����Q�点�āA�u�ʂɑ��������ӂׂ����܂��܂��B�V���̎��v�H���͂Ȃ������ӂׂ��炸�v�Ɛ\�����邤�ցA���O�ʓ������A���₤�ɐ\���ꂯ��A�u���Ă͂�����ׂ��A�V�Ƒ�_�̌䍐����v�ƂāA�Ђ��Ђ��Ƃ��ڂ��߂����������Ђ���B�F��Ɍ�\�Y�`���������āA���l�ɂȂ���B�s�ƂƉ������āA�ߎ|�̌�g�ɓ����ւ����肯��B ���l���������A�s�������ċߍ]�����͂��߂āA���Z�A�����̌������Ɏ���ɂӂ�Ă䂭�قǂɁA�܌��\���A�ɓ��̖k���ɂ�������A���l�O���q���a�ɗߎ|���A�M���O�Y�搶�`���́A�Z�Ȃ�Ƃ点��ƂāA�헤���M�������ւ�����B�ؑ\���ҋ`���́A���Ȃ����ƂāA���R���ւ������ނ�����B ����̌F��ʓ��X���́A���ƂɐS�����ӂ����肯�邪�A���Ƃ��Ă����ꂫ�����肯��A�u�V�{�\�Y�`���������q�{�̗ߎ|���͂��āA���Z�A�����̌����ǂ��A�ӂ����ق��A���ɖd�����������Ȃ�B�ߒq�V�{�̎ҋ��́A�����߂Č����̕��l���������B�X���́A���Ƃ̌䉶��V�R�Ƃ����ނ�����A�����ł��w�����ׂ��B�ߒq�V�{�̎ҋ��ɁA���˂����āA���Ƃ֎q�ׂ�\����v�ƂāA�Ђ��b���l�A�V�{�̖��֔������B �V�{�ɂ́A����̖@��A���V�̖@��A���ɂ́A�F��A��A�����A�T�b�A�ߒm�ɂ́A���s�@��ȉ��A�s���������]�l�Ȃ�B���������āA�����̕��ɂ͂Ƃ����˂�A���Ƃ̕��ɂ͂��������˂�ƂāA����т̐��̑ޓ]���Ȃ��A�L�Ȃ��ނЂ܂��Ȃ��A�O�����قǂ���������������B�F��ʓ��X���A�Ǝq�Y�����ق��������A��g�肨�ЁA���炫���������A�{�{�ւ����ɂ��̂ڂ肯��B (�Ӗ�) ���̍��A�㔒�͉@�̑�q�E�Ȑm���Ɛ\�����́A��ꂪ�����[���G�����̌䖺�ł���B�O�����q�ɏZ�܂�ꂽ�̂ŁA���q�̋{�Ɛ\���ꂽ�B ����i�����N(1165)12��16���A��N15�ɂ��āA�l�ڂ�E�Ԃ悤�ɋ߉q�͌��̑�{�̌䏊�ɂāA�䌳�����ꂽ�B�B�M�ŏ���������F�߁A�w��ɂ��D��Ă��āA�ʂɂ������ɂȂ�ׂ��ł��������A�̌��t��@�̓i�݂̂��߂ɉ������߂��߂�����Ă����B�Ԃ̂��Ƃ̏t�̗V�тɂ͕M���ӂ���Ď���̎��̂������A���̑O�̏H�̉��ł͎���ʓJ�𐁂���ĉ�ȉ���t�ł���B���̂悤�ɖ�������炵�Ă��邤���ɁA�����͉߂��A����4�N(1180)�ɂ͌�N30�ɂȂ��Ă����B ���̍��A�߉q�͌��ɏZ��ł������O�ʓ�������(1104���`1180)���A�����A�邩�ɍ��q�{�̌䏊�ɎQ��\���ꂽ���Ƃ́A��ςɏd��Ȃ��Ƃł������B �u�N(���q�{)�͓V�Ƒ�_�ȗ�48���̌䖖�ł����A�_���V�c���78��ɂ������Ă���܂��B���q�Ƃ��Ȃ�A�c�ʂɂ������ׂ����A30�܂ŋ{�̂܂܂ʼn߂����ꂽ���Ƃ͎c�O�Ȃ��Ƃł͂���܂��B���̐��̗L��l�����܂��ƁA����ׂł͕��Ƃɏ]���Ă���悤�ł��āA���S�ł͕��Ƃ܂Ȃ��҂�����ł��傤���B��d�����N������āA���Ƃ�łڂ��A�@�c�������܂łƐ���������ɁA���H�a�ɉ������߂��Ă����S�����߂܂��点�āA�N(���q�{)���c�ʂɂ����ׂ��ł��B����A��F�s�̂�����Ƃ������̂ł���܂��傤�B�����A���̐\���グ�����Ƃ����S�ɂ��Ȃ������オ���A�ߎ|������������������A��ђy���Q���錹���͑�������ł���܂��傤�v�Ƃ����A�b���������B �u�܂����s�ɂ́A�o�H�O�i���M�̎q�E�ɉ�����A�o�H���������A�o�H���l���d�A�o�H���Ҍ��\�����܂��B�F��ɂ́A�̘Z���`�̖��̎q���A�\�Y�`���Ƃ����ĉB���炵�Ă��܂��B�ےÍ��ɂ́A���c���l�s�j�����܂����A�V��[�����e���̖d���̎��A��U�͓��S���Ȃ���Ԃ蒉���ĕ��Ƃɖ����A�������l���ł�����A�\���܂ł̂��Ƃ͂���܂���B�ł����A���̒�A���c��Y�����A�蓇�̊��ҍ����A���c���Y������܂��B �͓����ɂ́A������������`��A�q���Ή͔�����`���A��a���ɂ́A�F�쎵�Y�e���̎q�E���Y�L���A��Y�����A�O�Y�����A�l�Y�`���A�ߍ]���ɂ́A�R�{�A���A�ь×��A���Z�E�����ɂ́A�R�c���Y�d�L�A�͕ӑ��Y�d���A�Y�d���A�Y��l�Y�d���A���H���Y�d���A���̎q�̑��Y�d���A�ؑ��O�Y�d���A�J�c������d���A��搶�d���A���̎q�̑��Y�d�s�A�b�㍑�ɂ́A�팩���ҋ`���A���̎q�̑��Y�����A���c���Y�M�`�A���ꌩ��Y�����A�����������Y�����A������Y�����A�_�O�Y���M�A�팩���q�L�`�A���c�ܘY�M���A���c�O�Y�`��A�M�Z���ɂ́A������Y�ۋ`�A���c���Ґe�`�A���ꊥ�Ґ��`�A���̎q�̎l�Y�`�M�A�̑ѓ��搶�`���̎��j�A�ؑ\���ҋ`���A�ɓ����ɂ́A���l�̑O�E���q�������A�헤���ɂ́A�M���O�Y�搶�`���A���|���Ґ��`�A���̎q�̑��Y���`�A�������O�Y�`�@�A�l�Y���`�A�ܘY�`�G�A�������ɂ́A�̍��n���`���̖��̎q�E��Y���ҋ`�o�����܂��B �����͊F�A�Z�����o��̎q���A���c�V�������̎q���ł��B���G�炰�A�h�]�𐋂������Ƃ͌���������Ƃ�����͂Ȃ������̂ł����A���͉_�D�̍��ƂȂ����邱�Ƃ�����܂���B��]�̊W���������J���Ă���قǂł��B���ł͍��i�ɏ]���A�����ɂ����Ă͗a�菊�Ɏg���Č����G���ɋ�藧�Ă��A�S���炮��������܂���B�e�n�̌����̖��O���́A��������ł���܂��傤�B�N�������A������ėߎ|���������Ȃ�A�����̌R���͖����ɂ��ŋ��ւƒy���̂ڂ�A���Ƃ�łڂ��̂ɓ����͗v���܂���B����(������)���N���Ƃ��Ă͂��܂����A�䂪�q���X�A�y���Q���܂��傤�v�Ɛ\�����B���q�{�́A���̎��͂ǂ��������̂��낤���ƁA�����A���m����邱�Ƃ͂Ȃ������B ����Ȏ��A���Êۑ�[���@�ʋ��̑��ŁA����O�i�G�ʂ̎q�A���[���ɒ��Ɛ\���҂������B�ނ͏��ꂽ�l�����ŁA�����̐l�X�͑����[���ƌĂԂقǂł������B���̐l�����q�{�����āA�u�c�ʂɂ����ׂ��l���ł����܂��B�V���̎��ւ̎v������������ׂ��ł͂���܂���v�Ɛ\������A���O�ʓ������������Ƃ�\�����̂ŁA�u���ẮA�R��ׂ����ƂȂ̂ł��낤�B����͓V�Ƒ�_�̌䍐�ł��낤���v�Ǝv���A�œ|���Ƃ����f�����B���q�{�́A���Â���Ȃ��悤�ɁA���ʉ��Ōv������ꂽ�̂ł���B �܂��A�F��ɉB��Ă����\�Y�`�����ĂъāA�����@�̑��l�ɕ�C���ꂽ�B�`���͍s�ƂƉ������A�ߎ|�̌�g�Ƃ��ē����ւƉ����Ă������B ���N(����4�N�E1180)4��28���A�s�Ƃ͓s���ċߍ]�����n�߁A���Z�A�����̌������Ɏ���ɐG��Ă��������ɁA5��10���A�ɓ��̖k���ɉ��蒅���A���l�Ƃ��ĕ�炵�Ă����O���q���a(������)�ɗߎ|�������������B�@�@ ���ꂩ��A�M���O�Y�搶�`��(�H�`1184)�͌Z�ł��邩��Ƃ������ƂŁA�헤���M�������ւƉ������B�����āA�ؑ\���ҋ`��(1154�`1184)�͉��Ȃ̂ŗߎ|��^���悤�ƁA���R���ւƕ������B ���̍��A�F��ʓ��Ƃ̒X���͕��ƂɐS��[���Ă����̂����A�ǂ̂悤�ɂ��ĕ����y���̂��낤���B �u�V�{�\�Y�`��(�s��)�͍��q�{�̗ߎ|�������āA���Z�A�����̌������ɐG��A���ɖd�����N�������悤���B�ߒq�E�V�{�̑�O�́A�K���⌹���̖��������邱�Ƃ��낤�B�X���͕��Ƃ̌䉶�������ނ邱�ƁA�V�����A�R�قǂł���A�ǂ����Ĕw�����Ƃ��ł��邾�낤���B�ߒq�E�V�{�̎ҋ��ɖ�̈�ł��˂����āA�d���̏ڍׂƂւ��`�����悤�v�Ƃ����āA�Z��g�ɂ܂Ƃ������l���V�{�̖������o�w�����B �V�{�ɂ͒���̖@��A���V�̖@��A���ł́A�F��A��A�����A�T�b�B�ߒm�ɂ͎��s�@��ȉ��̑�O�ŁA�R���͍��킹�ē��]�l�ƂȂ�B騂�����A��킹�����āA�����̕��ł͂����˂�A���Ƃ̕��ł͂����˂�Ƃ����āA��т̐��������邱�Ƃ��Ȃ��A�L���~�މɂ��Ȃ��A3������������̂ł���B���ʁA�F��ʓ��X�����͉Ǝq�E�Y��������������A�X���������A�Ȃ�Ƃ����E�������Ė{�{�ւƓ����A�����B |
|
|
�u����\�@�F��Q�w�v
���i3�N(1184)2���A��m�J�̐킢�O��ɓ��S�������ې�(������̂������E�������̒����A���d���̒��j)�͍���R�ŏo�Ƃ�����A�F��O�R�ɎQ�w�B���̖͗l���A�u���ƕ���v�͎��̂悤�ɕ`�ʂ��Ă���B �₤�₤�������Ӓ��ɁA�����ӂ�Ί�c�͂ɂ������苋�Ђ���B�u���̗͂������x���킽��҂́A���ƔϔY�A���n�̍ߏ����Ȃ镨���v�ƁA���̂����������ڂ�����B�{�{�ɎQ����A�ؐ��a�̌�܂ւɂ������ЂA���炭�@�{�Q�点�āA��R�̂₤���������ӂɁA�S����������ꂸ�B��ߗi��̉��͌F��R�ɂ��Ȃт��A�쌱���o�̐_���́A�����͂ɐՂ�����B���C�s�݂̊ɂ͊����̌����܂��Ȃ��A�Z�������̒�ɂ́A�ϑz�̘I���ނ����B���Â�����Â�����̂������炸�Ƃ��ӎ��Ȃ��B ��X���l���Â܂��āA�[�������ӂɁA���̂��Ƃǂ̍���O�ɂāA�u���������Č㐢�����������ցv�Ɛ\���ꂯ�鎖�܂ł��A�v�H���o�łĈ���Ȃ�B�u���R�����͖{�n����ɔ@���ɂĂ܂��܂��B�ێ�s�̖̂{�肠��܂����A��y�ֈ��������ցv�Ɛ\���ꂯ�钆�ɂ��u�ӂ鋽�ɂƂǂ߂������Ȏq�����Ɂv�Ƃ��̂�ꂯ�邱�����Ȃ�����B���������}�ЁA�܂��Ƃ̓��ɓ��苋�ւǂ��A�ώ��͂Ȃق����Ɗo���āA����Ȃ肵�����Ȃ�B �����ʂ�A�{�{���D�ɏ��A�V�{�ւ��Q��ꂯ��B�_�����������ӂɁA�ޏ����������т��āA���ϑz�̖���j��A�������悭�Ȃ���āA�Q�o���̍C����������ނƂ��o������B �����Ђӂ������݁A����̏��������߂��āA�ߒm�̌�R�ɎQ�苋�ӁB�O�d�ɟ��肨���̐��A�����܂ł���̂ڂ�A�ω��̗쑜�͊�̏�ɂ���͂�āA��ɗ��R�������ׂ��B���̒�ɂ͖@�ԓ��u�̐�������A��h�R�Ƃ��\���ׂ��B�}�������R�ɐՂ𐂂ꂳ���܂��܂��Ă��ȗ��A�䒩�̋M�G�㉺�����͂��сA�����ׂ������ނ��A�������͂��āA�����ɂ��Â��炸�Ƃ��ӎ��Ȃ��B�m��������O���Ȃ�ׁA����������˂���B���a�̉Ă̔�A�ԎR�̖@�c�\�P�̒�ʂ��̂��ꂳ�����ЂāA��i�̏������Ȃ͂����Ђ���A������̋��Ղɂ́A�̂����̂ԂƂ��ڂ����āA�V�̍����炫�ɂ���B �ߒq�Ă̑m���̒��ɁA���O�ʒ������悭�悭���m��������Ƃ��ڂ����āA���s�ɂ����肯��́A �u�����Ȃ�C�s�҂������Ȃ�l���ނƎv�Ђ���A�����̑�b�a�̌䒄�q�A�O�ʒ����a�ɂĂ��͂����邼��B���̓a�̖����l�ʏ����ƕ������Ђ������̏t�̔�A�@�Z���a�ɂČ\�̌��̂��肵�ɁA�������a�͓���b�̍��叫�ɂĂ܂��܂��B�����@�����͑�[���̉E�叫�ɂāA�K���ɒ�������ꂽ��B���O�O�ʒ����m���A�������d�t�ȉ����̐l�X�A�����𐰂ƂƂ��߂����ЂāA�_��ɗ������Ђ������A���O�ʒ����A���̉Ԃ��������ĐC�g���ďo�ł�ꂽ�肵���A�I�ɛZ�т���Ԃ̌�p�A���ɖ|�镑�̑��A�n���Ă炵�V�������₭����Ȃ�B���@���֔��a����g�ɂČ�߂�������ꂵ���A���̑�b���𗧂��A�������͂��ĉE�̌��ɂ����A�@��q����苋�ӁB�ʖڂ����Ђ����Ȃ����������B�����ւ̓a��l�A�������肤���܂����v�͂ꂯ�ށB�����̏��[�B�̒��ɂ́A�w�[�R�̂Ȃ��̍��~�Ƃ������ڂ��x�Ȃ�ǂ��͂ꋋ�Ђ��l�������B�B����b�̑叫�҂��������ւ�l�Ƃ�������肵�ɁA�����͂������͂ċ��ւ��L�l�A���˂Ă͎v�Ђ���炴��������B������͂鐢�̂Ȃ�ЂƂ͂��ЂȂ���A����Ȃ�䎖�Ɓv �ƂāA�������قɂ������ĂāA���߂��߂Ƌ�������A��������Ȃ݂�肯��ߒm�Ă̑m�����A�݂ȑň߂̑������ʂ炵����B (�Ӗ�) �ې���s�͕��݂�i�߂邤���ɓ������d�Ȃ�A��c�͂ւƂ������������B ��̗�������Ă���ƁA�u���̐�̗������x�ł��n��҂́A���ƁE�ϔY�A���n�ȗ��̍ߏႪ������̂ł��낤�v�ƁA���������v����B ��s�͖{�{�ɎQ�w���A�ؐ��a�̌�O�Œ[�����Ē����njo������A���R�̗l�߂Ă���ƁA�S�ɂ����t�ɂ��s�����ʗL�肪�������̂Ɋ�����ꂽ�B�_���̏O���i��̑厜�߂͉��̂悤�ɌF��R�ɂ��Ȃт��A���Ԃ��ƂȂ��쌱���炽���Ȑ_���͉����͂̋{�ɐ�瑂���Ă���B�@�،o���C�s���邱�̒n�ł͐_���̊����͌��̋P���̂悤�ɕՂ��A�Z�����N����߂�������邱�̒�ł͖ϑz���I�قǂ������Ȃ��B�ؐ��a�ŋF�O�����邤���ɏ�y�ւ̉����͊m���Ȃ��̂ƂȂ�A�ǂ����ė��������Ȃ��Ƃ������Ƃ����낤���B �邪�X���Đl���Q�Â܂钆�A�ې��͈�l�_���ɐ\���グ�Ă��邤���ɁA���̏d�������̌�O�ɂāA�u���������Č㐢�����������������v�Ɛ\���ꂽ���Ƃ��v���o���Ċ����ʂł������B�u�F��{�{�̌����́A�{�n�E����ɔ@���ł���������B�O���̊肢������āA��y�ւ�������������Ƃ����{��͌���Ƃ͂Ȃ��B�ǂ��������y�ւƓ������������v�Ɛ\����钆�ł��A�u�̋��Ɏc���Ă����Ȏq�������ł���܂��悤�Ɂv�ƋF�����͔̂߂������Ƃł���B�������}�����̓��ɓ����Ă��A�Ȏq���v�������͐s���Ȃ��悤�ŁA����Ȃ��Ƃł������B �邪�����āA�{�{����D�ɏ��V�{�ɎQ�w�����B�_�����Q�q����ƁA��̏�ɍ����������������т��Ă���A�������́A�͂��Ȃ�������������A�����͐����A�g������͛O�k�̐o�A�ق���̍C���������ł���悤���B �ې���͖�����(�_��)���q�݁A����̏�����ʂ��ēߒm�̂��R�ɎQ�w���ꂽ�B�O�d�ɟ��藎�����̐��͐����̍����܂ł悶�o���Ă���悤�A�ω��̗쑜�͎R�̊�̏�Ɍ���A��ɗ��R�Ƃ������Ƃ���B�������Ȃт�����͖@�،o���u�̐����������A�ߒq�R�͎߉ޔ@���̂������h�R�Ƃ������ׂ��ł���B ���������������ߒq�R�ɐՂ𐂂��������Ă��A�䂪���̋M�G�㉺�͑����^�сA��q�E�������āA���v�ɂ�������Ȃ��l�͂��Ȃ������B�̂ɑm���͑����̖V�ɂ����āA�o�Ƃ��݉Ƃ�����A�˂�悤�ɎQ�w�����B ���a2�N(986)�̉Ă̍��A�ԎR�@�c�͓V�q�̈ʂ������ďo�ƁB�ߒq�ɗ����āA��i�̏�y�ւ̉���������C�s����Ă���B�@�c�̌�����̋��Ղɂ́A�̂��ÂԂ悤�ɘV�̍����炢�Ă���B �ߒq�ɎQ�Ă���m�̒��ɂ́A�O�ʒ���(���ې�)���悭���m���Ă���҂�����悤�ŁA���s�҂Ɍ��ɂ́A �u�����ɂ���������C�s�҂͂ǂ̂悤�Ȃ������낤���Ǝv���A�����̑�b�a(���d��)�̌䒄�q�A�O�ʒ����a�ł���܂��B���̓a���A�܂��l�ʏ�������������2�N(1176)�̏t�̍��A�@�Z���a�Ō㔒�͉@�̌\�̌�ꂪ�s��ꂽ���A���̏����a�͓���b�����叫�ł���ꂽ�B�f���̏@�����͑�[�����E�叫�ŁA�K���ɒ�������Ă����B���̂ق��ɁA�O�ʒ����m���A�������d�t�ȉ��A���ƈ��̐l�X�͍�������Ɛ���₩�ŁA�_��ɗ����Ă���ꂽ�B ���̒����A���̎O�ʒ������A���̉Ԃɂ������ĐC�g���Ȃ���o�Ă����A�I�ɛZ�т��Ԃ̂悤�Ȍ�p�Ƃ����A�������Ƃɑ������ɖ|��l�Ƃ����A���̎p�͒n���Ƃ炵�V���P������ł������B ���@���A�֔��a����g�ɂ��Č�߂��������̂ŁA���̑�b�����𗧂��A�߂Ղ��ĉE�̌��ɂ����A�㔒�͉@��q�����B���͂̎҂́A���̏���Ȃ��ʖڂł��낤�ƌ��Ă��āA�T��ɂ����a��l�͂�������A�܂����v�������Ƃ��낤���B �����̏��[�B�̒��ɂ́A�w���̕����̔������́A�[�R�̒��̍��~���݂�悤�ł��x�Ƃ܂Ō���ꂽ�l���B�������ɂł��A��b�����叫�̈ʂɂ����l���Ɣq������Ă����̂ɁA�����̂����͂Ă����p�A�̂�m��l�ɂ͎v�������Ȃ��B�ڂ�Ες�鐢�̏K���Ƃ͂����Ȃ���A����Ȃ��Ƃł͂Ȃ����v�ƌ����A������ɉ������ĂāA���߂��߂Ƌ������̂ŁA���͂̑����̓ߒm�Q�đm�B���A�F�A�߂̑���܂ŔG�炵�Ă����B |
|
|
�ȏ�A���ƕ���S�̂��炷������ꕔ�̈��p�����A����ł��������̂ƂȂ��Ă��܂����B
�{�{�̊�c�͂́u��x�ł��n��҂͈��ƁE�ϔY�A���n�ȗ��̍ߏႪ������v�ƐM�����A�{�{�E�ؐ��a�ɂ͈���ɔ@������瑂��A�����ŋF�O����҂͐_���̏O���i��̑厜�߂ɕ�܂��B�@�،o���C�s����{�{�ł́A�_���̊����͌����Ղ��̔@���A�Z�������ɂ��ϑz�͏��ł���B�Q�w����l�ɂ́A�ؐ��a�͋Ɋy��y�ւ̓�����ł������B �V�{�͖�t�@���̗ڗ�����y�ŁA�߂��̐_���ɐ������͖ϑz�̖��𐁂������A���̗���ɛO�k�̐o�A�ق���̍C�͂��������B �F�어�{���_(�{�n�E���ω�)����_�Ƃ��@�ӗ֊ω����J��ߒq�R�́A�ω���F�̕�ɗ���y�ł���@�،o���u�̐����������A���Ȃ����h�R�̂悤�B�����ɂ͋M�a�O���A�m���A�g�����킸�ɑ����̎Q�w�҂�����A�R�ɂ͑m�V���A�Ȃ��Ă���B���̂悤�ȕ��ƕ���̋L�q�́A��������̌F��O�R�̏@���I�ʒu�t���ƁA���ꂪ�����Ɍ��`����Ă�������[�I�Ɏ������̂ł͂Ȃ����낤���B�@ |
|
| ��11�@���n�̕����ҁ@ | |
| �@�،o�̗�o杂ɖ������F��E�ߒq�̒n�����A�������A�@�؈�o�̏C�s�҂����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��A�ՍϏ@�@���h�͌F��O�R���ӂɕz���W�J���A�^���A�O���̍s�҂����̒n�ŏC�����_���̌[�����Ă���B�@ | |
|
��(1)�@�ՍϏ@�@���h�̓ߒq�ЁE���̉@(�ꌩ��)
�ߒq�R�̎ЉƂ̕�ł������ꌩ���ɂ��ẮA����́u��ɗ��n�C�j�v(1)�ŏڐ�����Ă���B���䎁�̋����ɂ��ƁA�_����̑ꌩ���͓ߒq�Ђ̉��̉@�ŁA�{�n�ω�����Ƃ��Ă�Ă����B�I�ɍ��E�R�Ǒ��ɂ��鋻�����̊J�R�ɂ��āA�ՍϏ@�@���h�̑c�E�S�n�o�S(1207�`1298)���ꌩ���̊J��Ɠ`������B�u�V�{�{�����~�{�ƕ����v�ɕ��2�N(1752)�̗R�Nj������̏��グ���ڂ����Ă���A�����ɂ́u�ߒq�R�V�m�������V�@���ɒv�A���Â��ōߎ��s���\��A���V�@�����͍O���O�M�C�A������N�Ɏ��Ďl�S���E�O�N�Ɏ������v�Ƃ����āA���̉@(�ꌩ��)�͍O��3�N(1280)�ɑn�����ꂽ�Ƃ����B�ꌩ���ɂ͖@�����t(�S�n�o�S)�̑����`��������A�V��9�N(1581)�̕��ŏĎ����A�c��10�N(1605)�A���s���t�E�N���ɂ��V��������Ă���B �^���m�E�萫���R�Ǒ��̐�����(��̗ՍϏ@�@���h�{�R�E������)�ɐS�n�o�S���}���A�J�R�Ƃ����̂�����2�N(1258)������A�ߒq�E���̉@�̑n�������ۂɍO��3�N�ł��������ǂ����͂Ƃ������A���̌�̖@���h�̕z���W�J�ɂ��A�ߒq�Ђ̐_����ɉ��̉@�����Ă邱�Ƃ͂������Ǝv���B�ꌩ��(���̉@)�̖@�����t���̓`�����A�@���h�ɂ��n�������̂��낤�B �����ɂ͊J�n�ȗ��A�ՍϏ@�@���h�̑m���Z���Ă����̂ł͂Ȃ����B��������p(2)�����A����12�N(1727)�u�{��o��暐Օ��ʕʒ��ʁv�̓�Ɏ��^���ꂽ�u�؎x�O������v�Ɂu�R�Nj����������@���@�@�c���v�Ƃ���̂��T�ɂȂ邾�낤�B ���A�������ɓ`������u�I�B�R�ǘh��J�R�@���~�����t�V���N�v�̊o�S���\�l�Ώ��ɁA�u�ߒq�_�{��ɗ��s�|�L�v�Ƃ������������p����A�����ɐS�n�o�S�̓ߒq�ł̏C�s�Ɖ��̉@�����Ă����Ƃ��`�����Ă���B�S�n�o�S�͏������N(1207)�ɐ��܂�A�i�m6�N(1298)�ɖv���Ă���B�ނ�74�Ƃ����ƍO����(1278�`1288)�ɂȂ��Ă��邩��A���̉@�n���̎��Ƃ����O��3�N(1280)�Ƃ͕������Ă���B���n������킹�����l�C�s杂Ƃ������邵�A�̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ��Ƃ��v���A���́u���̉@(�ꌩ��)�̑n�����S�n�o�S�������ɂ܂ők���\��������v�Ƃ������ƁA�܂��u13���I�ɂ͐S�n�o�S�̈�傪�F���~�ɕz�����A�ߒq�ɂ͖V�ɂ����Ă�܂łɓW�J�����v�Ƃ̗����ɗ��߂Ă��������Ǝv���B�@ |
|
|
��(2)�@�V���y�L�̐^���t�E���Y
���������̊w�ҁE�������t(�H�`1066)�́u�V���y�L�v�ɂ́A�ꐶ�s�Ƃ��т����匱�ҁE�^���t�ł��鎟�Y���C�s�����n�Ƃ��āA�u���A���A�F��A����A�z�����R�A�ɓ��������{�����A���ˑ�R�A�x�m��R�A�z�O���R�A����A���́A�����A���쓙�v�������Ă���B ���Y�́A�ꐶ�s�Ƃ̑匱�ҁA�O�Ƒ����̐^���t�Ȃ�B�v�C���s�N�[���A�������i���ς��B���E���������A�ʑ��ʂ�B�ܕ��̐^���_����āA�O���̊ύs����(�ق��炩)�Ȃ�B���ꎻ�ܐ�a(���炩)�ɂ��āA��������w�](����)�₩�Ȃ�B����E����֑�Ȃ��A�C�@�ɊH�q�Ă��Ɍ�����B�얀�E�V���ɂ͈�苗�����B���ɂ͒�q����B�}���^���̓�������߁A��s�̌��T�ɔ�������B�\�����𐋂��A�ꗎ���邱�Ɠx�X�Ȃ�B���E����ʂ�A�ӓ��ނ��ƔN�X�Ȃ�B�F��E����E�z���̗��R�E�ɓ��̑����E���{�����E���˂̑�R�E�x�m�̌�R�E�z�O�̔��R�E����E���́E�����E���쓙�̊ԂɁA�s�����Ќ��܂��邱�ƂȂ��B�R��C�s�҂́A�̖̂��s�ҁE�M���Ƃ��ւǂ��A������ɗ���̌��҂Ȃ�B���̉E�q��т̎��Y�N�ɉ����ẮA���łɒq�s��̐����Ȃ�B�@ |
|
|
��(3)�@�^���m�E�͏r
���ی��N(1074)10���A�^��(����)�m�E�͏r(1038�`1112)�͓ߒq�ő��Ă���n�߂��B�����@���C���A�d��ɔ@�ӕ����o���������Ƃ����B�Ï����N(1106)�A�͏r�͓������҂ɕ�C����Ă���B���A�͏r�͉i��2�N(1082)�ɐ��J�o�@���C���ė쌱�����������̂́A�`��(1023�`1088)�̖W���ɂ��ʖڂ������ߒq���Ă����Ƃ����������邪�A�u���O���l�������v�Ŕے肳��Ă���B �u�F��R���L�v �͏r�m�����S�O���A��C�s�f�����@�V���A�s�f���O���Ύɓ��d��o���V�A�@�ӕ��ݔV�A(3) �u���O���l�������v(4) (�͏r��)�ߒq�R�ɎQ�Ă��A����̍s���n�߁A�������̖@���s���E�E�E�E ���L�����ɉ]�A���ώ��ɉ]�A�͏r�ߒq�R���Ă鎖�͏��ی��N(1074)�\���\�ܓ��Ȃ�A�A���͓��O�N(1076)�\��{��B���J�o�̖@���C���鎖�͉i�ۓ�N(1082)�����\�Z����B���ێO�N����i�ۓ�N�Ɏ��Ď����N���u�ĂČ�A�C�@�Ύd����ΐ��J�o�̖@�Ɉ˂Ėʖڂ������ɓߒq�R���Ă�Ɖ]���Ǝ���B(5) �u�^���`����Z�v�T��(1184�`1255)�� ���m���͏r�n�A�����m�s�m�t�@�B����@���m������B��O���@���v�O�N(1071)�����\�l���A��䶗����j�V�e����B���ی��N(1074)�\�������A�ߒq�R�j�Q�ăX�B(6)�@ |
|
|
��(4)�@�щ��ƒ��Z�哿
13���I�ɐ��������Ƃ������b�W�u��W���v(7)�̊��Z�A��O�u�щ��m�s���S�V���v�ɂ́A���̖���������ďo�Ƃ��A�̂��ɎR�K��(�������̋���)�̊ю�ƂȂ������@�̑m�s�E�щ�(951�`1025)�̎Ⴋ���̓ߒq��ł̏C�s�̌����ڂ����Ă���B����ɂ��ƁA�щ��͒��Z�哿�ƂƂ��ɓߒq��ŏC�s�B���Z���ʎ�S�o���u�����Ƃ���A�ꂪ�t������̏�ɐ��g�̐��ω������ꂽ�Ƃ����B ���Ă��A���l(�щ��̂���)�Ⴍ�܂��܂�����Ƃ��A���Z�哿�ɂƂ��ȂЂāA�F��֎Q�苋�Ђ���ɁA�ߒq�̑�ɂāA���Z�哿�u�S�o�v���M������Ђ���A�낳�����܂ɗ���āA��̏�ɐ��g�̐��ω��̌��ꂢ�܂����肯����A�܂̂�����q���Ђ���ƂȂ�B���Z�̓��s�͂��鎖�ɂāA�������ւ�ԉ����肪�������ɂȂ�A���̂���\���肯��Ƃ��B�@ |
|
|
��(5)�@�^���m�E���o�̏C�s
����ƕ��ꣂɂ́A�������̐^���m�E���o(1139�`1203)���ߒq��ŕs�������̎��~��(��������)�������A��s�����A�����s�����Ƃ����s���������ő��ł�����㹗����q(����ǂ���)�Ɛ�吒�ޓ��q(���������ǂ���)�ɏ�����ꂽ�b���ڂ��Ă��āA���̖͗l�́u�ߒq�Q�w��䶗��v�ɂ��`����Ă���B���o���ĎR�s����𐬂��������Ƃ����B �u���ƕ���E����܁@���o�r�s�v �}���̗����Ɛ\���́A���镽�����N�\�A�������n���`�����d���ɂ���āA�N�\�l�Ɛ\�����i��N�O�������A�ɓ����g���ւȂ�����āA���]�N�̏t�H��������ނ��ӁB�N���������������肯�߁A���N�����Ȃ�S�ɂĖd�����������ꂯ�邼�Ƃ��ӂɁA���Y�̕��o��l�̐\�������߂�ꂽ�肯��Ƃ���B �ޕ��o�Ɛ\���́A���Ƃ͓n�ӂ̉������ߏ��ĖΉ����q�A�������Ґ����ƂāA�㐼��@�̏O��B�\��̍A���S�������o�Ƃ��āA�C�s�ɂ��ł�Ƃ����邪�A�u�C�s�Ƃ��ӂ͂����قǂ̑厖����A���߂��Č���v�ƂāA�Z���̓��̑�����邪���Ă�����ɁA�ЎR�̂�Ԃ̂Ȃ��ɂ͂���A���ӂ̂��ɂӂ��A�����Ⴜ�I�a�Ȃ�ǂ��ӓŒ��ǂ����g�ɂЂ��ƂƂ���āA�������ЂȂ�ǂ�����ǂ��A�����Ƃ��g�����͂��炩�����A�����܂ł͂��������炸�A�����Ƃ��ӂɂ����������āA�u�C�s�Ƃ��ӂ͂�����̑厖���v�Ɛl�ɖ�ւA�u������Ȃ��ɂ́A�����ł����������ׂ��v�Ƃ��ӂ��Ђ��A�u���Ă͂���ׂ�������Ȃ�v�ƂāA�C�s�ɂ����łɂ���B �F��֎Q��ߒq�����肹��Ƃ�����s�̐S�݂ɁA��������ɂ��炭������Ă݂�ƂāA����Ƃւ��Q�肯��B��͏\�\�����܂�̎��Ȃ�A��ӂ�������āA�J�̏��͂����������B��̗��ӂ����ق��̔������X�ƂȂ�A�݂Ȕ����ɂ����ȂׂāA�l���̏��������킩���B������ɕ��o�A��ڂɂ���Ђ���A�͂����Ď��~�̎���݂Ă��邪�A��O���������肯��A�l�ܓ��ɂ��Ȃ肯��A����ւ����āA���o����������ɂ���B�����݂Ȃ��肨���Ȃ�A�Ȃ����͂��܂�ׂ��B�����Ƃ������Ƃ���āA�����Ȃ̐n�̂��Ƃ��ɁA���������т����₩�ǂ̂Ȃ����A�����ʂ��Â݂ʁA�ܘZ�������Ȃ��ꂽ��B���ɂ��������Ȃ银�q��l�����āA���o�����E�̎���Ƃ��ĂЂ��������ӁB�l�A����̎v���Ȃ��A���������Ԃ�Ȃ�ǂ�����A��ƂȂ�ʖ��ł͂���A�قǂȂ��������łɂ���B ���o�������l�S�n���ł��āA��̂܂Ȃ����������炩���A�u��ꍟ��ɎO����������āA���~�̎O�������݂Ă��ǎv�ӑ�肠��B�����͂�Â��Ɍܓ��ɂȂ�B�������ɂ��߂�����ɁA�ȂɎ҂������ւ͂Ƃ��Ă����邼�v�Ƃ��Ђ���A����l�g�̖т悾���Ă��̂��͂��B����ڂɂ��ւ肽���Ă����ꂯ��B �����Ƃ��ӂɁA���l�̓��q�����āA�Ђ�������Ƃ����ւǂ��A����ɂ��݂����Ă����炸�B�O���Ƃ��ӂɁA���o�Ђɂ͂��Ȃ��Ȃ�ɂ���B��ڂ����������Ƃ�A�݂Â猋������V����l�A��̂��ւ�肨�肭����A���o��������A�葫�̂܂����A���Ȃ���ɂ�����܂ŁA��ɂ��������ɂ����������������āA�Ȃł��������ӂƂ��ڂ�����A���̐S�n���Ă������łʁB �u�}�����Ȃ�l�ɂĂ܂��܂��A�����͂��͂���ӂ��v�Ɩ�Е��B�u���͂���吹�s�������̌�g�ɁA����(��㹗�)�E��������(��吒��)�Ƃ��ӓq�Ȃ�B�w���o����̊���������āA�E�҂̍s�����͂��B�䂢�ė͂����͂��ׂ��x�Ɩ����̒��ɂ���ė����Ȃ�v�Ƃ������ӁB���o���������炩���āA�u���āA�����͂��Â��ɂ܂��܂����v�B�u�s���V�Ɂv�Ƃ����ւāA�_��͂邩�ɂ����苋�ЂʁB���Ȃ���������͂��Ă����q�����B ����킪�s���A�吹�s�������܂ł��A���낵�߂��ꂽ��ɂ����Ƃ��̂��������ڂ��āA�P��ڂɂ��ւ肽���Ă����ꂯ��B�܂��Ƃɂ߂ł��������ǂ����肯��A�������镗���g�ɂ��܂��A�������鐅�����̂��Ƃ��B�����ĎO�����̑��ЂɂƂ��ɂ���A�ߒq�ɐ��������A���O�x�A�����x�A����A���́A����R�A���R�A���R�A�x�m�̐��A�ɓ��A�����A�M�Z�ˉB�A�o�H�H���A���ׂē��{���̂��鏊�Ȃ��A�����ȂЂ܂͂��āA���������ӂ闢��������肯��A�s�ւ̂ڂ肽�肯��A�}���ƂԒ����F�肨�Ƃ����̂₢�̌��҂Ƃ����������B (�Ӗ�) ���������A���̗����Ɛ\���̂́A���镽�����N(1159)12���A���̍��n���`��(1123�`1160)�̖d���ɂ���āA�N��14�Ɛ\�����i��N(1160)3��20���A�ɓ����̕g���֗�����āA20�]�N�̏t�H�𑗂�}���Ă����B���N�A���l�Ƃ��Ă��ƂȂ������Ă������炱���A�����ɉ߂��������̂��낤�B���ꂪ�A���N�ɂȂ��āA�ǂ̂悤�ȐS���̕ω��Ŗd�����N�����ꂽ�̂��Ƃ����ƁA���Y�̕��o��l�̐\���i�߂��Ƃ������Ƃ��B ���̕��o�Ƃ����l�́A���͓n�ӓ}�̉������ߏ��ĖΉ��̎q�A�������Ґ����Ƃ����āA�㐼��@�Ɏd����O�ł������B19�̔N�ɓ��S���N�����ďo�ƁA�C�s�ɏo�悤�Ƃ������A�u�C�s�Ƃ����̂͂����قǂ̑厖�ł��낤���A�܂��͎����Ă݂悤�v�Ƃ��āA6���̑��z���Ƃ�������ő����h�邪�Ȃ��悤�ȓ��ɁA�Ӌ��̎R�́A�M�̒��ɓ���A�����ɐQ�]�������B���A��A�I�A�a�Ƃ����Œ������g�ɂ����Ԃ��Ȃ��Ƃ���āA�h������A���肵���̂����A�������g�������邱�Ƃ͂Ȃ������B���o��7���܂ł͋N���オ�炸�A8���ڂɋN���オ���āu�C�s�Ƃ����̂́A������̑厖���v�Ɛl�ɖ₤���Ƃ���A�u������ł́A�ǂ����Ė��������Ƃ����낤���v�ƌ���ꂽ�̂ŁA�u����ł́A���₷�����Ƃ��ȁv�Ƃ����āA�C�s�ɏo�������̂ł������B �F��֎Q��ߒq�Ă�����悤�Ƃ������A�܂��͎����ɂƁA�������ߒq�̑�Ɏb���ł���Ă݂悤�A�Ƒ�̂��ƂւƎQ�����B�^�~��12��10���̂��Ƃ�����A�Ⴊ�~��ς����ĕX���ƂȂ�A�J�̏���̉����������Ȃ��B��X���킽�镗�͐����ǂ�����A��̔���������X�ƂȂ��Ă���B�S�Ă��������Ȃ鐢�E�A�l���̏������������Ȃ��قǂ��B ����Ȓ��A���o�͑��ւƍ~�艺���đ̂��Ђ����A��܂Ő��ɐZ�����Ď��~�̎�(�s�������̑ɗ���)�������Ă����B2�A3���͎��������������̂́A4�A5�����o�߂����犬���ꂸ�A���o�͕����オ���Ă��܂����B���������藎����ꂾ����A�ꃖ���ɂƂǂ܂��Ă�����킯���Ȃ��B�����Ƃ����Ԃɉ������Ƃ���āA���̐n�̂��Ƃ��A��������p�̊Ԃ����݂��Ȃ���A�܁A�Z����������Ă��܂����B���̎��A����̓��q����l�������āA���o�̍��E�̎���������グ��ꂽ�B��������Ă����l�X�͕s�v�c�Ȏv���ƂȂ�A�����߂��肵�Ă��ꂽ�̂ŁA�܂������̎��ł͂Ȃ����Ƃ�����A���Ȃ����đ��𐁂��Ԃ����B ���o�́A�������ė����������l�q�ƂȂ������A�傫�Ȋ�����J���āu��͂��̑�ɎO����(21��)�ł���āA���~�̎O����(�O�\���Ղ̎��~��)�������Ƃ������𗧂ĂĂ���B�����͂킸��5���ڂɂ����Ȃ��B7�����߂��Ă����Ȃ��̂ɁA���҂������֘A��Ă����̂��v�ƌ������̂ŁA���q���������l�q�����Ēm���Ă���l�X�͐g�̖т��悾���A���̂������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B ���o�͍Ăё��ւƖ߂�A���ɑł��ꑱ�����B���ꂩ��2���ڂƂ������ɁA���l�̓��q���������Ĉ����グ�悤�Ƃ��ꂽ�̂����A�݂͂����ƂȂ�������A���o�͏オ��Ȃ������B3���ځA���o�́A�͂��Ȃ������₦�Ă��܂����B���������܂��Ƃ����̂��A�p��(�݂���)���������V�̓��q����l�A��̏���~�艺���Ă����B���҂ƂȂ������o�̓�����A�葫�̂ܐ�A���̗��ɂ�����܂ŁA��ɂ����������������������ĕ��ʼn�����Ă����Ǝv������A���̐S�n�����čĂѐ����Ԃ����B �u��������������ʼn����邠�Ȃ��l�́A�ǂ̂悤�Ȑl�ł�����̂ł��傤���v�ƕ��o���₢���ƁA�u��͑吹�s�������̌�g�ɂ��āA��㹗�(����)�E��吒��(��������)�Ƃ����q�ł��B�w���o�͖���̊肢���N�����A�E�҂̍s����ĂĂ���B�����ɍs���͂������Ȃ����x�Ƃ̕s�������̒��ɂ��A���̒n�ɗ����̂ł��v�Ɠ�����ꂽ�B���o�͗͂��鐺�ŁA�u���āA�s�������͂������ɂ�����̂��v�Ƃ����ˁA�q�́u�s���V�ɂ�������Ⴂ�܂��v�Ɠ����āA���_�̏�ւƏオ���Ă����ꂽ�B ���o�͏��������āA���̌��i��q������Ă����B�u�Ƃ������Ƃ́A�䂪�s��吹�s�������܂ł����䑶�m�Ȃ̂��v�Ɨ��������v���Ă��āA�P�����ւƖ߂萅�ɑł��ꑱ�����B�܂��Ƃɂ߂ł����������������̂ŁA�������銦�����g�ɓ��݂邱�ƂȂ��A�����Ă���␅�����̂��Ƃ��ł������B�������āA21���ԑ�ɑł���Ď��~�̎O���������Ƃ�����肪������ꂽ�̂ŁA���o�͓ߒq�ɐ���Q�Ă��A�g��̑��ɂ͎O�x�A����R�ɓ�x�A���ɍ���A���́A����R�A���R�A���R�A�x�m�R�A�ɓ��A�����A�M�Z���̌ˉB�A�o�H���̉H���R�ƁA���{���̗����c�����ƂȂ��C�s���Ă܂�����B���̌�A�������Ɍ̋����������Ȃ����̂��낤���A�s�֏���ė������ɂ́A���悻��Ԓ����F�藎�Ƃ����́A�n�̂��Ƃ����҂ł���ƁA���̖��͍������̂ł���B �u�F��N��L�v���������N(1163)�A���o���F��Ő�H�̍r�s���s�������Ƃ��L���Ă���B ���(�V�c)�@�������N�@ᡖ��@���o�F��ɓ���A�O�R�Ɏ�������H�B �܂��ƂɗE�܂����r�X��������̕��o�̏C�s�����A��C�s�̗쌱杂Ȃǂ́u���ƕ���v�ɂ���Ă���ꂽ���̂Ƃ��Ă��A���ۂ̂Ƃ���͂ǂ����낤�B�ނ͌F���K��Ă����̂��낤���B �s�N���ɐ_�쎛�̍ċ��𐬂������A�������������o�̔�҂͌㔒�͖@�c�ŁA���̖@�c��34����̌F��w�ł��s���Ă���B�F��{�{�ɂ́u�����ǂ���A�O�S����v(���قʂ�)�Ƒ����̏C�s�҂��W��200�ȏ�̈���������A�F��O�������̐_�Ђ��u���{����̌��v(���ƕ���)�Ƃ������̂��B�����ŏC�s�ɑł����ސN���o�̎p��z�����Ă��A���Ȃ����ԈႢ�ł͂Ȃ��Ǝv���B ���o�̌F��C�s�ɂ��ẮA�R�c���S�����u���o�v(8)�ɏڂ����܂Ƃ߂��Ă���̂ŁA�ȉ��A�v�_��������B ���㐼��@�O=��@�x��̕��m�ł������������Ґ����́A�������N(1159)�N���璷�����N(1163)�N���܂łɂ͏o�Ƃ��A���o�ƍ����Ă���B �����o�̌�N�̊���Ԃ肩�炷��A�^���m�ł������Ƃ�����B�������A�^���̌����n���ɂ͕��o�̖�����������Ȃ��B�킸���Ɂu�`���A�^�㊪�v���u���C�������@�w�u���R�`�v�ɁA���R�̕t�@�l�l�ɍs���A���فA�h�R�A���o������A�����ɕ��o�̖��������邾���ł���B�u�`���A�^�㊪�v���A���R�t�@���l�l�Ƃ��������͕s���B���o�����R�̕t�@�����̂́A50�̍��Ɛ��������B �����o�ɂ͕��o�ȊO�̌Ăі��͂Ȃ��A�@���炵�����̂��������A�����n���ɍڂ炸�A��q�Ɏ��������Ă��Ȃ����Ƃ���A���K�̉����������Ȃ����x�m�ł������Ɛ��������B���o�͎��̂Ǝv����B ���u���Ǐ��v���Z�ɂ́A�u���o�͍s�͂���NJw�͂Ȃ���l�Ȃ�v�Ƃ���A�ނ̎��ӂ���͊w��炵�����̂͌����Ă��Ȃ��B �����o���F��ōr�s�������ł��낤���Ƃ͏؋����琄���ł���B �E���o���㔒�͉@�ɒ�o�����u���o�l�\�܉ӏ��N�����v(�m���o�N����)�ɔނ̗������������܂�Ă���A����ɂ��ƁA�ɓ��z���̎��A30���Ԃ̒f�H�����Ă���B ���i���N(1182)4��5���A�������̐폟���F�肵�āA�]�m���ő�ٍ˓V�@���C���A21���Ԃ̒f�H�����Ă���B�����ł̒f�H�͏C���҂̍s�@�������Ƃ݂���B �E�u�F��N��L�v�̎j�����l�́u�m���o�N�����v��u��ȋ��v���͒Ⴂ���̂́A�������N(1163)�A�F��ł̕��o�̒f�H��`����O��́A�㔒�͉@�̌F���K�̋L�^�͂قڎj���ƍ����Ă���A���o�Ɋւ���L�q�͖����ł��Ȃ��B �E���s�ƕ��o�͌𗬂������Ă��āA���s�́u�R�ƏW�v�ɌF��Ƒ肷��̂�����B ���炽�Ȃ�F��܂��ł̂��邵���ΕX�̍C���ɓ��ׂ��Ȃ肯�� ���̉̂�����A�~�G�A�F��Ő��C�����Ƃ�r�s���s���Ă������Ƃ�����������B �E���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�o�Ƃ������o���ڎw�����̂͏C���̍s�l�̓��������ƍl������B�@ |
|
|
��(6)�@��Ղ̌F�쐬��
������V�s���ĔO���D�Z(�z��)�A�x��O����������ď�����O�ɔO�������߂����@�̊J�c�E���(恁E�q�^�@1239�`1289)�́A���i11�N(1274)�āA�F��ɎQ�w���F�쌠�����_�������B���̖͗l�͈�Ղ̏\�N���ɂ����鐳�����N(1299)�A��q�̐�����ɂ��쐬���ꂽ�u��Ր��G�v(��Տ�l�G�`)�ɏڂ����B �q�^�͕��i8�N(1271)�A32�̎��ɓ�x�ڂ̏o�Ƃ����A�������߂��蕶�i11�N(1274)�āA����R���o�R���ČF��{�{�Ɍw�ł�B���s���l�ɔO���D��z��Ȃ�������q�^�́A�F��̎R���ŘV�m�Əo��B�O���D�����߂�ꂽ�V�m�́A��O�̐M�������Ƃ𗝗R�Ɏ������ہB����ł��q�^�͘V�m�ɑ��A������M����S�̗L���A�s��̗��R��₢�A�V�m�͐M�S�̋N����Ȃ����Ƃ͂�����Ƃ�����|��ԓ��B����Ȗⓚ�����Ă���Ƃ���ɁA���s���l�X���W�܂肾���A�q�^�͘V�m���O���D�����Ȃ���ΊF���Ȃ��ƍl���A�{�ӂł͂Ȃ����̘̂V�m�ɎD��n���A����������l�X���D��������B�Ƃ��낪�A���̘V�m�͎p�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B �O���D�̕��Z�����߂邱�Ƃɂ��A�v���Y�q�^���F��{�{�E�ؐ��a�ŋF�O���Ă���ƁA�����̎R���p�̉��g�����ꂽ�B�u��[�̊��߂ɂ���؏O������������̂ł͂Ȃ��A����ɕ��̏\�����o�ɂ���؏O���̉����͕K��Ȃ̂ł���B�M�s�M��I���A��s������킸�A���̎D��z��ׂ��v�ƍ�������B�܂��A12�A3�̓��q��100�l�قǏW�܂�A�������ĔO���D�����A�O���������Ȃ��牽���Ƃ��Ȃ������Ă��܂��B ���̌F�쌠���̌[���̌�A�ނ͈�ՂƏ̂��A����܂ł̓얳����ɕ��̔O���D�Ɂu���艝���Z�\���l�v�Ə���������悤�ɂȂ�A���������܂Ȃ��V�s���Ă���B�F�쌠���̐_���ɂ��ẮA�]�ˎ���ɕҎ[���ꂽ�u��Տ�l��^�v�ł́u��@��͌F�쌠�����z�̌��`��v�Ƃ��A���@�ł́u�F�쐬���v�Ƃ���Ă���B �u��Ր��G�v(��Տ�l�G�`)�̎����ߕ��E�F�쐬���̕��� ����O�@���i ���i�\��N�̉āA����R���߂��ČF��֎Q�w�����ӁB�R�C��d�̉_�H�𗽂��āA��c�̗͂���Ɉ߂̑���A���q�����̗�q��v���āA���S��̐��ۂɁA�S�̍�(�Ƃ�)�����J�����ӁB������̑p�K�ɂ́A��瑂̘I�A�ʂ��A�{�{�V�{�̎Вd�ɂ́A�a���̌������|������B�Ê��V���̉e�X�ւ���u���̔g��������A�ыJ�ʍc�̏����Y�ւ��鍿�R�̉_�A�F���ڂ��B�A���A����̎߉ނ́A�~���̖����Ƌ��ɓ��ɏo�ŁA���}�̖�ɂ͈��ڂ̎F埵�ЂāA���Ɍ��͂ꋋ�ւ�B �����Ɉ�l�̑m����A�����߂Ă̋��͂��A�u��O�̐M���N�����ē얳����ɕ��Ə��ւāA���̎D�����ӂׂ��v�ƁA�m�]���A�u����O�̐M�S�N���莘�炸�A�Ζό�Ȃ�ׂ��v�ƂĎ��B���̋��͂��A�u������M����S�䍿(���킵)�܂�����A�Ȃǂ����͂���ׂ��v�m�]���A�u�o�����^�͂���嫂��A�M�S�̋N���炴�鎖�́A�͋y���鎖�Ȃ�v�ƁB���Ɏ(������)�̓��ҏW�܂��B���̑m�������A�F�܂����ɂĎ��肯��A�{�ӂɔȂ���A�u�M�S�N���炸�Ƃ����ցv�ƂāA�m�ɎD��n�����Ђ���B��������ē��ҊF��������ʁB�m�͍s������m�炸�B ���̎��v�҂���ɁA�̖����ɔA���i�̎�������ׂ��Ǝv�Ћ��ЂāA�{�{�ؐ��a�̌�O�ɂ��āA��ӂ��F�����A�ڂ���Ė�������(�܂ǂ�)�܂���ɁA��a�̌�˂������J���āA�����Ȃ�R��̒����Њ|���ďo�ŋ��ӁB�����ɂ́A�R��O�S�l����A���n�ɂ��ė�h�����B���̎��A�����ɂČ䍿���܂������Ǝv�Ћ��ЂāA�M������Č䍿������ɁA�ނ̎R�琹�̑O�ɕ��݊�苋�ЂĂ̋��͂��A �u�Z�ʔO�����ނ鐹�A�����ɔO�����Έ��������߂��邼�B��[�̊��߂ɂ��āA��؏O�����߂ĉ������ׂ��ɔB����ɕ��̏\�����o�ɁA��؏O���̉����͓얳����ɕ��ƌ��肷�鏊��B�M�s�M��I���A��s������͂��A���̎D��z��ׂ��v �Ǝ������ӁB��ɖڂ��J���Č����Ђ���A�\��A�O��(��)��Ȃ银�q�A�S�l���藈��āA�������āA�u���̔O���ށv�Ɖ]�ЂāA�D�����āu�얳����ɕ��v�Ɛ\���āA�����Ƃ���������ɂ���B �}���Z�ʔO���́A�匴�̗ǔE��l�A����̒��Ɉ���ɕ��̋��������ЂāA�V�����N(1124)�b�C(���̂�����)�Z��������ߍs�Ћ��ӎ��ɁA�Ɣn��������V�������ߕ��āA���V��ߓ������ɖ������͂��ē��苋�Ђ���B ���̓��q�����q�B�̎��Ђ���ɂ�A�Ǝv�Ѝ��͂������������ׂ��B�匠���̐_���������肵��A�u���悢�摼�͖{��̐[�ӂ�̉�����v�ƌ�苋�Ђ��B�@ |
|
| ��12�@�F��O�R���Z�̊����Ɩ{�R�h�E���R�h�̐����@ | |
|
��(1)�@����@�E����
�O�k(�Љ�)��{��̏@�����l����̂ɁA�������Ȃ��̂����͏�c�̌F��Q�w�ȗ��A�F��O�R�ɒu���ꂽ���Z�E�ƍݒn�Ƃ̊ւ�肾�낤�B ����4�N(1090)�A�F��ɎQ�w�������͏�c����B�߂����_(1032�`1116)(1)���F��O�R���Z�ɕ�C���Ĉȗ��A�O�R���Z�ɂ�6��E�o���܂œV�䎛��n�̑m����C����Ă���B���̌�A�㒹�H��c�̐M�C���m�a���o�g�̒���(1152�`1228)���^���m�Ƃ��Ă͏��߂āA7��̌F��O�R���Z�ƂȂ�A����7�N�E���v���N(1219)���珳�v3�N(1221)�܂ōݐE���Ă���B8�㌟�Z�ɂ͓����o�g�Œ߉������{���ʓ��̒荋(1152�`1238)����C����A���v3�N(1221)����Ò�4�N�E��m���N(1238)�܂Ŗ��߂Ă���B9��̗Ǒ�����͍ĂѓV�䎛��n�ƂȂ�A21��̖��ӂ̍��ɂ͓V�䎛��n�E����@��Ղ̏d��E�ƂȂ��Ă���B �����Œ��ڂ������̂��A22�㌟�Z�ƂȂ�������(1430�`1527)�̎��Ղ��B�����͉i��2�N(1430)�A����b�E�߉q�[�k(1402�`1488)�̓�j�Ƃ��Đ��܂�A�c�����ɏo�Ƃ��A�䖧���w���w��ł���B���E�[�k�͕���2�N(1445)�֔��ƂȂ�A����2�N(1461)������b�ɔC�����Ă���B�����Ă���̓����͐���@��Ղ̑�24���ɂȂ�A���鎛�����A�F��O�R���Z�A�V�F��Ќ��Z�߂Ă���B �����̎O�R���Z�͊���6�N(1465)���疾��10�N�E���T���N(1501)�̒����ɂ킽�邪�A�ނ͌��Z�ƂȂ������N�̕������N(1466)7��22���A�E��������Z�A�����A�ɐ��A�I�ɁA�X�Ɏዷ�A�O��A���O�A�����A����A���|�ւƎ��������s���A9��21���ɋA���B��10���ɂ͒O�g�E�d���ɏ��炵�A������11��8���ɂ͓ߒq�������Q�ďC�s���͂��߂Ă���B���m���N(1467)5���A���s�ł̐킪�{�i��(���m�̗�)������Q�Ă𑱂��A���m2�N(1468)7����3�N�Ԃ̎Q�Ă��I���ċA���B8��6���ɂ͐���@�����ɂ��Ă��A�����͈ɐ��Ɍ������B�F���̎O���ˎ��ɑ؍݂�����A���k�̊�q�Ɉڂ��ꂽ����@�ɏZ���Ă���B �����͎������{��8�㏫�R�E�����`��(1436�`1490)�̌쎝�m�ŁA����̌���肪����A�`���E�`��(1465�`1489)���q�ɉ̂��Ȃ���A����18�N(1486)6��16���A��������ɗ��������B���̎��ɉr�a�́E�����E�o�~�̂ƋI�s�����u�G�L�v�Ƃ��ē`����Ă���B ����ɂ�藷�̍s��������ƁA�R��A�ߍ]�A�ዷ�A�z�O�A����A�\�o�A�z���A�z��A���A�����A�����A�㑍�A���[�A���́A����A�헤���O�����ʼn��A�H�ɂ͍Ăщ����A�����A���͂��߂���ɓ��A�x�͂ւƑ����̂��A���͂��畐���Ɏ���͉z(��z)�E��˂̏\�ʖV�ʼnz�N�B������19�N(1487)2���ɂ͍b��Ɍ������A�����ɕ����ɖ߂�A3����{�ɏ��A���삩��k�サ�ĉ��{�ɂ͗����̋{���A�����A�����̉Y�ւƎ����Ă���B�A�H�̖����ʼn̂��r�Ƃ���Łu�G�L�v�̋L�q�͏I���A5��19���ɋA�����Ă���B�ނ�������I���ēs�ɖ߂����̂́A���N4���̐���@�Ď��Ƃ������Ԃ��Ă̂��ƂƎv���邪�A�������̂悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ���A���R�E���R�E�������T���E�}�g�R�E���q�̎Ў��E���͂̑�R���E���[�̐��������A���Ў��̏��q���d�˂����݂��炵�āA����̏�y��ڎw���Ă������̂��낤���B����2�N(1493)8��13���A���x�͐���������s�r���A���O��������]��ɓ���z�N�B������3�N(1494)6���ɋA�����Ă���B ���̂悤�ȓ����̏�������́A����A����A�F��O�R�ɘA�Ȃ�C���҂��A����@�𒆐S�Ƃ���{�R�h�Ƃ��Č`������Ă����ߒ��ł̏�����Ƃł���A�g�D���ł������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B ���m���N(1467)10�����{�A�ߒq�Q�Ē��̓����́A�t�H��G�ɓ��R����C�s�҂J�����邽�߁A�ߒq��̐Ⓒ�Ɉ�F�����Ă�B���ɂ͑ꓪ�(�낤�Ƃ�����)�ƍ����ꂽ�B�����͎肸����s�������̑����𓏎D�Ɏʂ��āA�ꓪ꜂̒d��Ɉ��u�B�����Ԃɂ킽��̒_�𝔂��A�v�����Â炵�č���ɊJ�ዟ�{���s�����B�����ɂ͓ߒq�R�̑�{���s�E�@�C���A�Ȃ�A�������ߒq�R���s�̎��̂��Ƃ������B���m2�N(1468)4���ɂ́A�����͖@�،o�E�ʎ�S�o�E����Ɍo�E����o����ߒq�ꎵ�����̔鐅�ŏ��ʂ�(���@�،o)�A���i33�N(1426)�ɓߒq�̎Гa��薭�@�R�֏オ�����Ƃ���Ɍ��Ă��Ă����u�ߒq�R�@���@�@���v�̖{���Ƃ��ĕ�[�B�L���E�����̏O�������o�̌��͂ɂ��A���ɕ��Ɏ���̂ł���Ƃ��Ă���(�a�̎R���C��s�E���ێ���)�B ����瓹���̊����́A�u�F��ʓ��v�̖��̂����j�̕\���䂩�������100�N���o�߂��Ă���̂��Ƃł���(2)�A�F��O�R���Z�����̌`���I�ȗ��ꂩ�璼�ځA�ߒq���̍ݒn�Ɋւ��悤�ɂȂ������Ƃ��������Ƃ�������̂��낤�B �R��s�������D�{�� �R��s�������D�{�������V�ʔ@�� �����A�㎷�s�@�� ��G�R���V���A��q�˕��J�A����ȗ��A�s�� �v�V�B���݈�F�����A���H�듪��꜁B������ �����s�������@�@�@�@�@�@���Ⓒ��B�R�\�莩�̕s�����������A�� �ȍ������D�@�@�@�@�@�@�u�ގ����d��B���������ցA�Í��O�A��J �ዟ�{�B����{���s�@�C�A���������{�V ���L�B�b�吹�Г{�����j���E���A������ �v�A�ߐ��i�싋��B�@�@�@�@�@�@�@�@��B�x�@�����[�d�C �����[�L�V �������m�����\�����{�A������s�l�A����@�y�O�{�����䔻(���s�وׁA�錣) ����{����S�C�V�a���A�����n�V���L�B(3) ���݁A���D�̑��݂͊m�F����Ă��Ȃ����A����4�N(1807)�A���̌F��O�R���Z�E��i�@�e�����ꓪ꜂��C�����A���̍ۂɕs�����������Ĉ��u�B���̑��͐ݓn���ɓ`�����Ă��邱�Ƃ��A�u�a�̎R���̕������v��O��(4)�ŏЉ��Ă���B�����ɂ͓��D�̕�������A�����ł͕����́u����{����S�C�V�a�������n�V���L�v�͂Ȃ��A����ɂ��đ��c���V���́u������{�葤�̋U��Ɣ��f�ł��悤�v�Ǝw�E����Ă���B(5) ��͓��q�K���́A�����̎���E�߉q����(1444�`1505)�̓��L�u��@���@�L�v�����p���A�������ߒq�ŎQ�Ă������Ƃ�������Ă���B(6) �����ŁA��͓������Љ�ꂽ�u��@���@�L�v���m�F���Ă݂悤�B ���������N(1466)11��2���A���Ɠ@����@(����)�A�����@�A���r�@�炪���Ƃ��ꍧ�k�B�����ł́A������7�����ߒq�֎Q�Ă��邽��3�N�Ԃ͉�Ȃ����ƁB�܂����r�@��6�������s���n�߂邱�Ƃ�������ꂽ�B���̌�A���䏊�������[��܂ň��H���Ă���B3�����A�����Ǝ����@���A��A���߂��Ɏ��r�@���A��A���䏊�Ɛ��Ƃ͈ꏏ�ɏR�f�������悤�ŁA�[���ɉ��䏊���A��Ă���B8���A�������̉J�̒��A�����͓ߒq�Ɍ����������A���Ƃ�3�N�̕ʂ��ɂ���ł���B �������N�\�ꌎ��� �M�߁@���A�s��A���X���J��A����@�A�����@�A���r�@���ߗ����A���厩�������ߒq�Q�Ė�A�O���N�V�ԕs�L����ԁA�e��Q��|��A���r�@�������Z����n���s�]�X�A����e�䐀���A�I��L����A���䏊�ߗ����A �O�� �h���@���A����@�A�����@�����ߋA���A���r�@�������ߋA���A�L�R�f���A�y�������䏊��A�A ���� ���q�@�J����~�A�����@�ߗ����A���I�������A�O铍u�ږ�A��Ǎ��`�A�r��e�����A�藈�\�Z���V��A�ω͌����S�A���� ������b���A�Ԑi�b�뚤����S�ڋ{�w�����A���卡���ߒq�i���]�X�A�O�N�V�ԍ�����k�V�u����ސ[�Ҍ��A �����m2�N(1468)7��4���A�ߒq�Q�Ă��I���������͋��s�ɖ߂萭�Ƃ������ˁA�����ʂ��������Ƃ���т����Ă���B�A�����̓����̎p�́u�R�ȉƗ�L�v���m��N�����Z�����Ɂu�������@��Q�A������̖�A�䔯�A���C(��)�A�g�L��(����)�A�X�Y�J�P(��)�A�L(��)�i���q�^�^��(����)�A����A�J�C�m���g��v�Ƃ���悤�ɁA�R�т�l�M����R���p�ł������B ���m��N�����l�� �p���@���A�ߍ�������@��Q�a����A��������s�㗌�]�X�A�]���y�ȊO�V�ԕs�Q��A����������ߗ��������A�����������]�A���ꎖ���ᗐ�퐋���ߔV�ԁA��g��c�s�ߔV�A�O�N���i����������A �����m2�N�[10��7���A�������ߒq�Q��3�N�̊Ԃɏ��ʂ�������ʎ�o���������Ƃ́A���ꓹ�f�A��̎���Ƌ����A��s�Ɏ������S�\�]�̏����ȕ����ł́A�V��ɂ͌��������a����Ȃ�悤�ŁA�}���̋y�Ȃ��Ƃ���ł���A�ƋL���Ă���B ���m��N�[�\������ ᡈ�@���A�Q�����@��e��O�A ����@�O���N�V�ԉ��ߒq�莩�폑�ʑ�ʎ�A�����팩�V�A���ꓹ�f��V����A�Ꭾ������s�����S�\�]����A�V��s���V�A���@���a�A�}���ޓ�y�A�ꕔ���I�]�X�A �ȏ�A�u��@���@�L�v�̋L�q�ɂ��A�ߒq��̎R��s�������D�ɋL���ꂽ�u���m����(1467)10�����{�v�A�����͓ߒq�ɎQ�Ē��ł��������Ƃ��m�F�����B���D�����́u����{����S�C�V�a���A�����n�V���L�v�ɂ��ẮA�㐢�́A�{��̑�{���傪�N����k�点�Ă��̑��݂��������߂Ɍォ�珑�����������́A�Ƃ̗����ł����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�@ |
|
|
��(2)�@�{�R�h�Ɠ��R�h
�����̐��U��ʂ��Ă̊����ȏ���ƏC�s�����̈�Ƃ��A���̌F��O�R���Z��̓����ɂ��`�����ꂽ�̂��V��n�̏C�����E�{�R�h���B��ɐ^���n�E���R��(�h)�Ƃ̑��_���N�������ƂɂȂ邪�A���h�̌`���ƓW�J���A���^�K�q���́u�C�������c�����j�v�ł̋��������ƂɊT�ς��Ă݂悤�B(7) �{�R�h�`���̕����Ƃ��ẮA���͏�c�̎����͂��߂Ƃ��āA����c�̌F���B��V�䎛��h�̍��m���S���Ă������Ƃ���������B14���I�㔼����15���I�ɂ����āA����@��ՁE�F��O�R���Z�͊e�n�̌F���B�E�R������܂��A�F��E����ŏC�s����V��n�C���҂̓�����}���Ă���B�����ĕ���18�N(1486)�A�����͉�����s���ČF���B�̏����ƏC���҂̑g�D���ɓw�߁A����@��Ղ��p��������(1508�`1571)�͈��g�E���𑽂������A����́u�C�������c�v�Ƃ������ׂ��{�R�h�̌`���ւƂȂ����Ă������B ���q��������k������ɂ����A���������͂��߂Ƃ����s���厛���O�́A���������ƏC�����̏C�s�̂��߂ɎR�ѓl�M���s�������A���̊����͑�a�����ӎ��@�Ɏ~�Z����^���n�C���҂����W����悤�ɂȂ�A�ނ炪���R���̑O�g�ƂȂ����B�^���n�C���ҏW�c�͐����l�M�̑��l�ҁE���{�Ƃ��ė��c�Ƌ��A�������̍�Ɛ��������u������R�{����������������B�L�^�v�ł́A����̑�֍~���̌��ƕ����̔鎖�𑊏����鋻�����������������ł���Ƃ��Ă���B ��k�����㖖�A��s���厛���O���C���ҏW�c�̎w���I���ꂩ��ޓ]����B���厛�@�̓������������ނ�͐�B�O�𒆐��Ƃ��鎩���g�D�ƂȂ�A�u���R��B�O���v�u����B�v�u���R����B���v�Ǝ��̂�����B�O�́A�z���̏C���҂𗦂��Ċ�������(��B�O�͌�Ɂu�O�\�Z�����B�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�)�B ����M�Ƃ����Ǝ����������R���ƁA�V��n�C���҂��j�Ƃ���{�R�h�͊m����[�߁A���Ђ̌�돂�̂Ȃ����R���͈��y���R����ȍ~�A����̑n��������펛�E�O��@��ՂƊւ��������A�c���N�ԂɂȂ�Ƒ�펛����E�O��@��Ղ̋`��(1558�`1626)�R���̓����Ƌ��悤�ɂȂ�B �c��7�N(1602)6���A�O��@��Ղ����R���R���̍��n����s�@�ƒq���@�ɋ��E�n���U���̒��p��������ƁA���c��8�N(1603)7���A���������{�R�h�̎R���E�����V��ɂ���s�@�ł����莖���������B�ȍ~�A�{�E���̑��_�������A���N10��8���A����ƍN�ɂ��u���R�E�{�R�e�ʁv�ً̍����������B�����A�{�E���̑Η��͂����܂炸�A�c��14�N(1609)�ɏC�����E�����R�C���҂ɑ���@�x��������ꂽ��A����@��Ղ͕������̏����@�ɔN�s���E�̕�C�E���g�������A�֓��^���@�Ɠ��R�h�ɖ�K�ۂ��Ă���B �c��16�N(1611)�A�W�H���Ŗ{�R�h�̑�P�@�����R�h�̃i�J�V��ʼnʂ��A�����̏C���҂�{�R�h�ɕғ������Ă��܂��B���N8���ɂ́A���R�h���{�R�h�̓����W�Q����āA���܍����ƂȂ�B11���A���R�h����B�͏x�{�ɉ������A���㏑���o�B���ʂł͎�����u���{�V�^���@�́A�ܘ_���R�V�嗬�v�ƈʒu�t�����R�h�̗R�����L���A���R�h�Ɗ֓��^���@�ɑ���{�R�h�̔�i���Ă���B���c��17�N(1612)4���A���R�h�̎咣�������ꂽ�ْ肪�������B �c��18�N(1613)�ɂ͖��{���C�����@�x���������A�C�����͓��R�h�Ɩ{�R�h�̓�ƂȂ�A�����̏C���҂͂ǂ��炩�ɑ����邱�ƂƂ��ꂽ�B�w�i�Ƃ��ẮA�c�����N���猳�a�N�Ԃɖ��{�̎��@�������������ꂽ���ƁA�{�R�h�̐���@��Ղ���k�����A�L�b���狌���͂Ƃ̊W���[���������ƁA�{�R�h�ɓ��R�h�����������邱�Ƃɂ��݂������������悤�Ƃ������Ɠ����w�E�����B�O��@��Ղ͋`���̎��̊o��A���̌�p�̍����̑ォ��C�����@�x�����菊�Ƃ��A��B�̌U���ɘA�Ȃ�C���҂́A���ڎx�z���n�߂�悤�ɂȂ��Ă����B |
|
| ��13�@�F��O�R�{�菊�@ | |
|
�`���ɋL�����悤�ɁA15���I���ȍ~�A�F��R���E�F���u���͏������߂���F��O�R(�F��{�{�A�F��V�{[����]�A�F��ߒq)�̎Гa�E�����E�R���{�݂̌����A�ċ��A�C���̂��߂̊��i�������s�����B���i��u��ɂ���ĊG����������A�����̏������F��O�R�̐M�ւƗU�����u�F��ϐS�\�E��䶗��v���e�n�ɓ`���50���{���������Ă���̂��A���N�̊����Ԃ�����̂��낤�B(1)
�F��R���E��u��𑗂�o�����̂��F��O�R�{�菊�ŁA���̋K�͂͑傫���A�{�{�E�V�{�E�ߒq�̊e�R���Ƃɖ{�菊������A���ɓߒq�R�͎��̖{�莛�@����\�����ꎵ�{��A���c�����ƌĂꂽ�B(2)�{�莛�@�ɂ́A���t���̎R���E��u���Z���A���������i�s�r�����R���E��u��͊�E�ƌĂ�A�g�D������Ă����B �ߒq�R�̖{�莛�@�̏@�|��m�鎑���͍]�ˎ���̂��́A���\16(1703)�N�Ƌ���12�N(1727)�ɍ쐬���ꂽ�u�؎x�O������v(3)�ƂȂ邪�A�V��Ɛ^���ō\������Ă���B �������Ђ����̂��܂̖V�ɂ̔z�u�ŁA�u�ߒq�R�ÊG�}�v(4)�ɂ��Ό�O����(�V��)�A�����(�^��)�A�ߒq����(�^��)�A�t�T�V(�V��)�A�����@(�^��)�͓ߒq�{�Дq�a�̋߂��Ɍ��Ă��Ă���B�{�莛�@�̑��̓�A����Ɏ�(�^��)�͓ߒq�R�ɗאڂ��閭�@�R���ɁA��ɗ��R��(�V��)�͓ߒq�̊C�߂��Ɉʒu���Ă���B�@ |
|
|
��(1)�@�ߒq�R�E���̖{�莛�@
�����荪��́u��ɗ��n�C�j�v�ƁA���c���V���́u�����̎Ў��ƐM�@���i�Ɗ��i���̎���v�̋����ɓ�����Ȃ���A��Ɂu�F��ߒq��Е����v(5)�Ɓu�F��{�菊�j���v(6)���߂���A�F��O�R�{��̐����ƓW�J���T�ς��Ă݂悤�B (�����̒���̊Y���łɂ��Ă͈ȉ��A�u���䎁�v�u���c���v�ƕ\�L) |
|
|
��1�@��O����E�V��@
�{�Дq�a�߂��A�t�T�V(��T�@)����ɋߐڂ��Ă����B���݂͍֊ق����B�R���̏ؐ��a�A��{���̎�v�Гa�A��m�����A�U�������A���������A��\�������NJ����Ă����B��O���傪�m�F�����Â������́A�i��11�N(1439)3���A���t�́u�ؑK��v�Ƃ����B �\���肹�ɂ̎� ���E�ѕ��ҁA �E���̌�p�r�n�˗L����\������A�A�A���̌�p�r�n�A���ʃj�S���j�ܕ����̗���������āA���\�������j�����\��ւ���A�䂵���Ƀn�m�����̂�������̓������\����A�����₭�����̌���������n�R�A���ւ���̂߂��Ƃ��\��n�鎞�j�A�ꌾ�̎q�א\���܂�����A������ؕ��V��@���A �i���E��N�O���A���@低�p�S �ԉ� ��Y�@�ԉ� ���ݒ��@���C�@�ԉ� �@�@�@�@�@�@�@�@���Z�@�ԉ�(7) �i��11�N(1439)3�������A低�p�S�ƒ�Y�͏\�ѕ�����A�ߒq�R�̐m�����֑̊K�����Ƃ����B����A�u�{��o���ؐՕ��ʕʒ��ʁE��v�Ɏ��ڂ���u�{�蒆�N���s���V����v�ɂ́A��O���傪�u�m����v���NJ����Ă������Ƃ��L����Ă���A�m�����֑̊K�����ɂł���u�ؑK��v�́u低�v�Ƃ́A��O����ł���Ɛ��肳���B���N��9��28���ɂ��A低�p�S�ƒ�Y�͏\�ѕ�����Ă���B �\������肹�ɂ̎� ���E�ѕ��ҁA �E�������n�A���ʃj�S���j�ܕ����V�����������āA�\�����̓��j�����\��A�A�A��^(��)�j�n�m�����V���V�֑K�����u�\��A������������n�A���������\�ւ���A�������n�V�{�ƗL�n�^�|��V���A���ƔV���߃j��\��A�������@���A �i���\��N�㌎�������@�@���ݒ��@���P�V���V�@�ԉ� �@�@�@�@�@�@�@�@����[���݁@�ԉ� �@�@�@�@�@�@�@�@��㊯��Y�@�ԉ� 低�p�S �ԉ�(8) ���ɂ��̊����̂���������̂��A�u�F��ߒq�R�{�蒆�o���ؐՋL�^�v(9)�́u�{�蒆�o���ؐՔV�ʕʒ��E��v�ɂ��銩�i���̏����ƂȂ�B �\�{�a�ċ����i�� ���i����@�h�� ����諗�M�e���˕��Z�\���ɎD�@���]�f�����ċ��\�{�a�� �`���͗��` �O���O�N�Ɍ��g�� �F��ߒq�R�\�����䑢�c���i�� �{���O����V�@�nj��@�ԉ� ��q�呠�V�@���S�@�ԉ�(10) �O���O�N(��܌�)�\�A��O����̗nj��ƒ�q�̌��S�́A�Z�\�����̎D�����ēߒq�R�\��Ќ����̍ċ����i���s���Ă����B����͈�Ղ��F�쌠���̌[��������A�u�얳����ɕ��@���艝���Z�\���l�v�̎D�Z���ď�����V�s�������Ƃ�f�i�Ƃ�������̂ŁA��Ղ̌F�쐬���Ə@���I���H���v��O�Z�Z�N�߂��ɍs��ꂽ���i�����̂��ǂ���ƂȂ��Ă������Ƃ�����������B ���\�\�Z�N(�ꎵ�Z�O)�́u�؎x�O������v�ł́A��O����ɒj�����l���Z������A�Z�E�́u���Z�v�ƂȂ��Ă���B���ۏ\��N(�ꎵ��)�ɂ͏Z�E�����āA�j���Z�l���Z���Ă���B |
|
|
��2�@�����E�^��
��O����̓�A������̓��Ɉʒu���Ă����B�c���N��(1596�`1615)�ɂ́A���A�@�ƌĂ�A�����ɏ\�����~���������B�ߒq��E�R��s�����̉��m���N(1467)�́u�R��s�������D�v�ɂ́A�u��{����S�C�V�a���v(�R��s�������D�{��)�Ƃ��邪�A�O�Ɍ����悤�Ɍ�ɏ������������̂Ɛ��肳���B �����̏Z���Ƃ��āA�c���N�ԂɍL������������u��E�����͉B�����A��Z�ɗ������w�������B�����͂��Ɛ��@�̑�s�҂�34�N�Ԃ̑�{�C�s�������Ȃ��A�얀���ƎR�㓰�������B�@�،o�ꕔ���u�́A�@�،o�̎��o�҂ł��������B ��䑢�c�o���� �������Z������m�s�@����a�� G���Ӄm�t�� �����F�B���q�R ��{�R�ę��l�N���{�얀���E���R�㓰�E����厛�����m�m�� �����@�؈�s(��)���u�@���E���˃j�e���@���@�����A ���i�O(1626)���Ѓm�\�l��(11) ���\16(1703)�N�́u�؎x�O������v�ł́A�Z�E�́u��݁v�Œj��22�l���Z���Ă���B����12�N(1727)�ɂ͒j��25�l���Z������A�Z�E�́u���Z�v�ƂȂ��Ă���B |
|
|
��3�@�ߒq����E�^��
�ߒq��ЁE�@�ӗ֓�(���݂̐ݓn��)�O��艺���������B�����̖k�Ɉʒu�B�����ɂ͉��V�V�ƌĂ��B ���s�E�������̐��k���P(1392�`1473)�̓��L�A�u��_�����^�v�̋������N(1452)������\�Z�����ɂ���u�@�ӈ���v���ߒq����m�Ɛ����������A���̖{��Ƃ��Ă̊����͖��炩�ł͂Ȃ��悤���B ���T3�N(1503)2���g���́u�i�㔄�n�\�~�V���v�ɂ́A�����@���L�̉��~��@�ӗ֓��̖{�肪�u�U�ߔV���~�j�d�Ƃď��]�v���A������u�O�ѕ��v�Łu���吳�|�v�ɔ���n�����Ƃ��L����Ă��āA�@�ӗ֓��̖{��ł��鐳�|���ߒq����Ɛ��������B���A�U�߂Ƃ͏C�s�m�E�Q�w�҂�ڑ҂��A�ނ炪�h������{�݂̌ď̂ŁA�e�n�̗��ւ̎Q�w�H�����ɐ݂���ꂽ�B ���~���� �i�㔄�n�\�~�V�� ���O�ѕ� �E���V���~�ҁA�ݏ��n���V�@�T���[���n�ɂČ���A�˗L�p�v�A�����@�ɔ����d����A�@�ӗ֓��{��U�ߔV���~�j�d�Ƃď��]��ԁA�ߕ��n�j�Č���A�P���j�Č�ԁA�i�㔄�n�\��A���������߃n���n�����̖ؒ��Α���������A���n���o�@�ː�������A���ґ哹��������A���Ѓn��K����������A��A�މ��~�������ᗐ�o����ҁA����Ƃ��ē����\��A����������V��@���A ���T�O�N�@�~�̂Ƃ̈�@�ƌ��g�� �����@�@����d�ρ@�ԉ� �����|(12) �i��12�N(1515)�A�d���́u�c�n�����v�̈����ɂ́u�@�ӖV�ߒq����v�Ƃ���B �c�n���� �i�㔄�n�\�n�V�� ���ܕS���ҁA �E���n�ҁA����V����@�[���`�ɂČ���A�˗L�p�v�A�ߒq����ɉi�㔄�n�\�|����A��A�������ᗐ�o����ҁA��@�V�Ƃ��ē����\��A�������@���A �i���\��N�[������ �d���@�ԉ� �@�ӖV�ߒq����(13) ��i2�N(1522)�A���V�V���ߒq�R�@�ӗ֓����{�̒Ǝn�߂̋V���s���Ă���B �ߒq����ɂ͉ԎR�@�c�ɗR������u�����O�\�O�������v�ꕝ�A�u�䉏�N�v�ꔠ�A�u���牏�N�v�ꔠ�A�u�ԎR�@�c�����O�E�O���䏇�K�ȗ��䌌���ߋ����v������`�����Ă����Ƃ����A���\�N��(1688�`1704)�ɂ͔@�ӗ֓��̌���a����Ǘ����s���Ă��āA�����O�\�O���ω�������NJ�����{�莛�@�Ƃ��Ă̋@�\��L���Ă����B �ԎR�@��╨ �����O�\�O�������@�@�@�@�@�땝 �䉏�N�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �딠 �E�V��{���Ŋ��l��M�A��Ԃ��O�\�O�ԔV�䏑 �t�҉ԎR�@�䛂�M�V�R�A�E�V��{���s�ҋ��{�V��{����A �ލs�Ғ��Ԉ��d�V���]�a��\��E�E�E�E ��@���牏�N�@�@�딠�@�@���L�ژ^�E�E�E�E ��@�ԎR�@�c�����O�E�O���䏇�K�ȗ��䌌���ߋ���(14) �ߒq�ő��Ă���s�����Ƃ����A�ԎR�@�c���n�߂��Ɠ`�������̂������O�\�O�����̏���ŁA���̈�ɓߒq�̔@�ӗ֓����g�ݍ��܂�Ă����B��k�����㍠�Ɉɐ��_�{�ւ̎Q�w������ɂȂ�ƁA�@�ӗ֓��������O�\�O���̈�ԗ��A�D���Ƃ��ꂽ�B����ɂ��A�ߒq�R�ւ̏���҂������������Ƃ��ߒq���{��̑g�D���𑣂��A���i���Ƃ̊������ւƂȂ����Ă����B ���\16(1703)�N�́u�؎x�O������v�ł͏Z�E�́u�����v�A�j��20�l���Z����B����12�N(1727)�͒j��13�l���Z���Ă���B |
|
|
��4�@�t�T�V�E�V��
��O����̖k���Ɉʒu�B17���I�������́A��T�@�ƌĂ��悤�ɂȂ�B �u�F��N��L�v ������(1659)�Ȉ�@�ߒq�R�t�P�V�䎺�̋{����T�@�Ɖ̗ߎ|�A������o�A�搴�V���A������T�@�Ɖ]�B �c��4�N(1599)�A�u�c�y�ċ����L�v�ɂ͓ߒq�c�y�ċ��̑����E�������i�����A�u��O����A�ߒq���~�A�����A��ɗ��������A�t�T�@�������v���L�ڂ����B �c�y�ċ����L�� �ߒq�R�c�y�L�V�ꗐ�������N�����Ă�d�A�L���A���v�����[�t�A��V�~���ہE���ܘY���ہE���������q�E�����V���E��E�����ہE���u��E�q��E��������i�e�d�A�c���l�N���c�y���Ƃ�\��A��������i�V���A �ܐl�O���@����@ ��l�O���@��O���� ��l�O���@�ߒq���~ ��l�O���@����� ��l�O���@�t�T�@������ ��l�O���@�v�S ������ꂤ������ ��ɗ������� �����̂��i�O ��c���@�_�{�����_�O�Y ��c���@�����̐쏯��^�O�Y ��c���@�V�������^���q�� ��c���@�������쏕 �E��i��A ��R�m�փj�A ���R���s�@����@���� ���V�O�k�O�m���@�V���[ �`�@�o�P�[ �\�@�[�@��P�[ ��t�[�@�P���[ �����[�@��@�[ �t���[�@��y�[ ��[���@�����V ��{�O �����[�@����[ ���[ �����H�l�� �쉁�@���V�� ��(�O��)��@�Ҋ��V�� ���@�l�㏕ ���V���@���B�[ ��(������J)��֘L �A���҃j�č����o���\��A �c���l�Ȉ�N�Z���g�� ���`�@�� ���\16�N(1703)�́u�؎x�O������v�ł́A�Z�E�́u��Ӂv�Œj��20�l���Z���Ă���B����12�N(1727)�ɂ͒j��18�l���Z����B |
|
|
��5�@�����@�E�^��
�Â��͍s���V�ƍ�����(���i10�N�E1633�A�Г������w�})�B�t�T�V�̓�A������̐����Ɉʒu�B ���i�\ᡓюO�����O���Г������w�}�@�ꊪ �E���Y���O�@���V �����@�@���r ��j�ā@����@���@�@�L�V�V�@�d�B �@�@�@�@�@���f�@��R�y���@�y�Аl�� �ߒq����@���� ��O����@���� �����@�@�@G ��j�ā@��T�@���@�@�t�T�V�@�@ �敟 ��j�ā@�����@���@�@�s���V�@�@ �S�� ���@�R�@�@����Ɏ��@�C�� �_�V�{�@�@��ɗ����@���_ �e����(15) �c��18�N(1613)�A�Бm�E�L�V�V���Ắu�ߒq�R��m����\���v�̏����ɁA�u�s��(��)�v�Ƃ���B ���\16(1703)�N�́u�؎x�O������v�ł́A�Z�E�́u�c�Ӂv�Œj��7�l���Z����B����12�N(1727)�ɂ͏Z�E�́u���Z�v�ƂȂ�A�j��7�l���Z���Ă���B |
|
|
��6�@��ɗ��R���E�V��
�ߒq�̊C�߂��Ɉʒu�B�ω���F�̂����y�����ɗ���ڎw���A���D�ɂ̂��C�ɐg����������̐g�s����ɗ��n�C�ƌĂ�A�������ォ��]�ˎ���ɂ����čs��ꂽ�B��ɗ��R���͕�ɗ��n�C�������m��̋��_�ƂȂ����B���s�E�@�@��12���I����15���I�ɂ����Ă̋L�^���W�听�����u��t�L�v�ɂ́A�����@�����ژ^(���a���N[961]6��5���t��)���ڂ����Ă��āA�����Ɂu��ɗ����́v�Ƃ���̂������Ƃ����B ���\16(1703)�N�́u�؎x�O������v�ł́A�Z�E�́u����v�Œj��4�l���Z����B����12�N(1727)�ɂ͏Z�E�́u���Z�v�ƂȂ�A�j���͓�����4�l���Z���Ă���B |
|
|
��7�@���@�R����Ɏ��E�^��
�ߒq�R���쐼�ɘA�Ȃ�@�R�̒����ɂ���B���`�ɂ��ẮA�u�@�،��L�v�́u����E���@�ޒq�R�̉��Ɩ@�t�v�̍��ł݂��Ƃ��肾�B���A�u�I�ɑ����y�L�v(�����O�N�L)�ł́u�O�@��t��C�̊J�n�v�Ƃ��A�[���A�����k���{�A�Γ������́u�����~���V����v�Ƃ���A���l����ƌĂꂽ�Ƃ����B�����͒����A���쐹���s�r���đ�t�M���Ђ�߁A����R�ւ̔[���Q�w�����߂����ƂƋO����ɂ��Ă���悤�Ɏv���A��C�J�n�`���Ƃ��킹�^���̓`���҂ɂ�銈�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B ���\16(1703)�N�́u�؎x�O������v�ł́A�Z�E�́u�o���v�Œj��14�l���Z����B����12�N(1727)�ɂ͒j��4�l���Z���Ă���B�@ |
|
|
��(2)�@�ߒq�R�̎Љ�
�R���A��u��炪�e�n�Ŋ��i�������A�ߒq�R�̎Гa�E�����������A�C�������ߒq���{��̐�����15���I��������Ƃ���邪�A�Â�����ߒq�R�������E�^�c���Ă����͍̂ݒn�̎�w���o���Ƃ���O�k��ŁA�ނ�͖{�肪��������ɋy��Ŏ���ЉƂƏ̂���悤�ɂȂ����B�ߒq�R�̋��Z�l���̑唼�ȏ���߁A�R���̕����A�_�������d���Ă����ЉƂ̎��@(16)�ɂ��Ă��A�u�؎x�O������v�ɂ��Ή��V�@�̗ՍϏ@�ȊO�͓V��Ɛ^���ō\������Ă���B
���\16(1703)�N�@�u�؎x�O������v(�{�莛�@���܂�) �����@�E�V��@�����s�V��@�g�� ��V�V�E�V�� ��t�V�E�^�� �����@�E�^�� �����@�E�V�� ����@�E�V��@�����s�V��@�g�� ��@�V�E�V�� ���V�V�E�^�� ����V�E�V�� �����@�E�V��@�V��g�� ���ܖV�E�V�� �����E�^�� ���@�R(����Ɏ�)�E�^�� �嗴�@�E�^���@�^���g�� �呠�V�E�V�� ���V�E�V�� �����V�E�V�� ���y�V�E�V��@�V��g�� �ߒq����E�^�� ����E�V�� ��T�@�E�V�� ��O����E�V�� �_���V�E�V��@�V��g�� ��ɗ����E�V�� �V�E�V�� �t���V�E�V�� ���o�V�E�V�� ����12�N(1727)�@�u�؎x�O������v(�{�莛�@���܂�) �����@�E�V��@�����s�V��@�g�� �V�E�V�� ��V�V�E�^��(�O�͓V�䂾����) ��t�V�E�^�� �����@�E�^�� ����@�E�V��@�����s�V��@�g�� ��@�V�E�V�� �o���V�E�^�� �呠�V�E�V�� �^�o�V�E�V�� ���y�V�E�V��@�V��g�� �ߒq����E�^�� �@�@����E�V�� ��T�@�E�V�� ��O����E�V�� �����@�E�V��@�V��g�� ���ܖV�E�V�� �����E�^�� ���@�R(����Ɏ�)�E�^�� �嗴�@�E�^���@�^���g�� ����V�E�V�� �~�C�@�E�V�� ���V�E�V�� �����V�E�V�� ����V�E�V�� �_���V�E�V��@�V��g�� ��ɗ����E�V�� �V�E�V�� �����V�E? �t���V�E�V�� ���V�@�E�Ս� �×����F��O�R���^�c���Ă����ݒn�̗L�͎҂ɂ��āA�{�n���ꎁ�͘_�l�u�F��_�ЂƌF��R�v(17)�ɂāA���̂悤�ɉ������Ă���B �u�������S�R���ʓ��Ƃ̓����̉��ɑm���̐��͌��ɋA���������́A���̉F��E��؎��̔@���×��̖������A�吨�̂܂ɂ܂ɎБm�ɍ����Ė������q���̊O�Ȃ��肵�Ȃ��B�O�R�̒�������Ñ�̐����̔�r�I�悭�ۑ�����ꂵ�́A���ɐV�{�ɂ��āA�����Ɍ���H�X�E�{�哙�̐_�E�̎c���́A��ɔޓ��ׂ̈߂ɂ���ꂵ���̂Ȃ�ׂ��B(�����y�L���\�O)����ǖ{�{�ɂ���ẮA�w�lj��Â̎АE����|���s���Ă��̐Ղ𗯂߂��A�ߑ�Ɏ���_���Ƃ��ĕ�d�����́A������a�̉��Ȃ�ʒu�R(�{�{���@�Ə̂�)���ڂ肵���̂Ȃ�Ƃ����B(�����y�L���\�Z)���ɓߒq�͑m���̎�ɑn�߂�ꂵ���ȂāA�ŏ����_�E��u�����A�����ɔV��݂���Ɏ��炴�肫�B�v �������ݒn�̗L�͎҂ɂ��A�ܗ��d���͎��̂悤�ɉ�������B �u�F��ʓ��̐����͂ǂ����͂����肵�Ȃ��̂ł��邪�A�F��O�R�̎i�Ր_�E���F��C�����̐����ƂƂ��ɎR�����������̂ł��낤�B�Ƃ��ɐV�{�ɂ͉F��A��A�|�{�̐_�E�Ƃ�����A�ߒq�ł͕ėǁA����̐_�E�Ƃ����������A��������F��~���V�A��ؑ��V�A�|�{��~�V�A�ėǎ���@�A���葸���@�Ȃǂ̖��ŏC�������Ă���B�v(18) �u�V�{�͖{�{�A�ߒq�Ƃ������Đ_�������ŏC�����Ȃ������Ƃ�����B�����������Ȃ��Ƃ��_�q���͏C���ł������B�V�{��Ђ̕��ɂ��O�k�ƎБm���������̂́A��͂�C���ł����āA�O�k�̈��d�𑍌��Z�Ƃ����A�Бm�̈��d����a���Ƃ������̂͂��������킵�Ă���B�����������͉|�{�A�F��A��Ȃǂ̐��������Ă����̂ŁA�̂��ɕ��m������̂ł���B�v(19) �������Đ퍑����̓ߒq�R������ƁA�R���͓����Ɛ������琬�藧���Ă����B�����͒��葸���@�ȉ��V��@�̘Z�Ƃ���Ȃ��{���s���o���A�����͐����@�ȉ��^���@�̘Z�Ƃœߒq�R���s���o���Ă����B���̍��͓ߒq�R���s�Ƒ�{���s�̗������ߒq�R�����Ă���B �Бm�ɂ��ẮA�h�V10�l�A�u�u12�l�A�O�k75�l�A��O66�l�A��l12�l�A�s�l85�l�A����7�l�������B���s�E�o���҂��h�V�ƂȂ�A�O�k�͎R���̍�E�@����s���A�����͓��F�̏C���A������S���A��O�E�s�l�͑�{���s�̔z���ɂ������B���ɖ{��Ɛ��|���s�����@�t��(�n���l)�������B�@ |
|
|
��(3)�@�V�{�̖{�菊�E�V�{����
�F��V�{�̖{�菊�ł���V�{����̋N���͏]���A�O��8�N(1285)5���Ɂu�_�_����]��ʁv���V�{�_��̓������A�u�ʓ���{�菊��O�k�����v�ɓ`���������u�_�_���_������v�ł���Ƃ���Ă����B �_�_���_������� (�[����) �u�ʂ��v ��\�@�F��V�{�_������ �㌎�\�ܓ����\�Z���@���\ �E�p�ߔN�C�_������ �V��@�� �O�������ь܌��� �_�_����]��� �ʓ���{�菊��O�k���� �ݒ����l��_���I�� ���@��������(20) �u�_�_���_������v�ɂ��ẮA���c���V���ɂ��u�_�_����v�Ƃ͋g�c�_���̋g�c��俱(1435�`1511)���_�_�E�̒�����ׂ����̂��A�ȍ~�A�g�c�Ɠ��傪����̂������̂ŁA13���I�ɂ͑��݂��Ȃ��ď̂ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���(21)�B���A�g�c��俱�͐_������Ɩ����A���ɐ_�_�Ǘ̒���幷��������Ə̂��Ă���B 15���I�����A�א쏟���͏㐙�����Ɛ������l���Ɏ莆�𑗂�A�u�F��V�{���c���i�ׁ̈A�\��(��)�m�o���������v���邱�ƂƏ������˗����Ă���A���̍��ɂ͐V�{���c�̊��i�̂��߁A�����Ɍ��������i���̑��݂������Ƃ��m�F�����B ����7�N(1374)�́u�x�����[�玁�P����v�ɂ݂���A�u������ܓN��l��[�v�̗�����͐V�{�{��̌Â��V���Ƃ���A�c�����N(1603)������\�����t���́u���Ҋ�i���v�ɂ��u�V�{���������@�s�t�v�Ƃ���B �u�F��N��L�v�ɂ́u�F��{��フ���̓��{�菊�ҁA�V�{����A�O�R�̖@����v�Ƃ���A�V�{����͌F��O�R�{�菊������u�@���v�Ƃ��Ċe��̖Ƌ����A������L���Ă����B�c���N��(1596�`1615)�ɑN���������C�����E���R�h(�^���E��펛�O��@)�Ɩ{�R�h(�V��E����@)�̑Η��͐V�{����ɂ��y��ł���B �����a8�N(1622)3���A�V�{����E�Z���̍s���͓V��R��̓V�C���A����@���E�Ƃ��āu�����@�v���C�����B ��b�R����@���E�����@��C�� (��E�n���A�ܕ�) �u��C�@�@�����@�v (�[���\��) �u�͕��v ��C ��b�R����@���E�� �F��R�_�{低� ��C�����@ �E�ȁ@����V�|�A���� ��A�鏳�m�Җ� ���a���N�O���@�ӎ�H �R��T���m���V�C��(22) �����i18�N(1637)�A�ѓ����~�{�@�̍s筭���V�{����ɓ����A���т���B�ߍ]���b��ɂ���ѓ����̔~�{�@�Ɗ�{�@�͓��R�O�\�Z�����B�O���\�����Ă���A�����̏C�����E���R�h�R���������A����Ȑ��͂�i���Ă����B�ȍ~�A�V�{����͔~�{����Ƃ��Ă��悤�ɂȂ�B ���c��4�N(1651)�A�ѓ����̍s�Ƃ��V�{����̖@�����p���B ������6�N(1666)�A�s�Ƃ͑�펛�O��@�̖��ɂ��A���s�҂Ɨ�����t����̌䋟�������̂��ߏ��������s����B����ɂ��ẮA�O��@�ɂ��C�����E���R�h�x�z�̈�Ƃ��Ă݂邱�Ƃ��ł���B �F��N��L ���ܔN�����Ɍ��Z���A�O��@�a������˗��A(��)�s�ҕ����t�䋟�������R����l�O�ꃖ�����o�V�A���R�����B�ѓ����~�{�@�s�Ɩ@���� �����\15�N(1702)�A�~�{�@�ƌ��т����V�{����̏Z���͍s�Ƃ��s���A�����Ƒ����Ă������A���̔N�A�����̌�Z��q�̍s�ق��s�@�@(�ڍׂ͕s��)�ɂ�芨������A�ȍ~�A�~�{�@�Ƃ̌��т͓r�₦�A�V��m�ɑւ���邱�ƂɂȂ�B ������10�N(1725)�A�V�{����E�Z���̗Ǐ��͔�b�R�������s�T�肩��m�j�E�ɕ�C�����B�ȍ~�A�V�{����͔�b�R������ƂȂ�B �V�{�̐���ɂ���_�q�R�́A�F��̐_���~�Ղ����Ƃ�����R���B�����A�_�q�R�̃S�g�r�L���_�̂Ƃ���_�q�Ђɂ��A���S����{�蓪�Ƃ��ĉ،��@�A��ω@�A�O�w�@�Ƃ����{�莛�@���������B���S���́u���̒n���{��v�A�،��@�́u���̖{��v�A��ω@�́u���̖{��v�A�O�w�@�́u��䶗����̖{��v�Ƃ��āA�_�q���͎Q�w�҂��狴�K�A�ʍs�œ����B�������ɓ��F�̐����A�Q���A���̈ێ��Ǘ���S�����B �u�F��N��L�v�ɂ��ƁA��i�N��(1521�`1528)��苝�\4�N(1531)�ɂ����Ă̖�10�N�ԁA�_�q�{��̖�����ƒ�q�E�S�����ɍċ��̂��߂̊��i�E������s���A������(1532)�ɖ��S�������āA����ɂ��{�荆��Ƌ�����Ă���B �F��N��L ���\�l�@�h�K�@��i�N����荡�N�������_�q���i����ċ��B�_�q�{�薭�����A��q�S���� �������@�p�C�@���N���S���֊��i���˔V�Ƌ��{�荆�@ |
|
|
��(4)�@�{�{�̖{��
�퍑���Ɛ��������u�y�葠�l���L����v(�N���s���A�K���\�����t��)�Ɂu�{�{����V�v�Ƃ���(�F��{�菊�j��)�B�c��8�N(1603)�́u�F��ߒq�R��J�{�V���v�ɂ́u�{�{����v�Ƃ���B�u�F��N��L�v����3�N(1654)���Ɂu�Z���o���㓏�A����얀���U�A�{�{����s����v�Ƃ���A�{�{�̈���E�s���̖����݂���B ����8�N(1668)�A��펛�O��@�̖�l�E�ѓc����ƒ����������Е�s�ɒ�o�����u����V�o�v�ɁA�u�{�{�V����A���R�������v�A�{�{�V�Ж𑊋ΐ\�v(��a����������)�ƋL����A�{�{�̖{��͓��R�h(��펛�O��@)���������Ă������Ƃ��m�F�����B���ꂩ��19�N��A�勝4�N(1687)4���́u�F��O�R�{�菊�ブ���Ж��s���V�o�E�{�{����Ж��v�ɂ́A�u�{�{����V��@���m�A�B���Җ��Z�v(23)�Ƃ���B�킸��19�N�̊Ԃɖ{�{����͓��R(�^��)����V��(�{�R)�ւƕς��A���������ނ��Ė��Z�ƂȂ��Ă���B ����當���́A�×�����̐��n�ł���F��̒n���A�{�E�����h�̐��͊g��̎啑��ƂȂ��Ă������Ƃ������j���Ƃ����邾�낤�B�{�{�����17���I�����ɂ͑ޓ]���Ă������A�P���ɂ������Ɛ��������ߖT�̐������ł͌F���u��炪�N�Ă肵�A�N�n�ɂȂ�Ƌ��ʕ�������A�����֊��i�ɏo�����Ă����Ƃ����B�@ |
|
|
��(5)�@�{��̐���
�F��O�R�̗����ɑ���Ȃ�v���������{��͒蒅�����A����܂ŏO�k�E�ЉƂ��S���Ă������s���Ɋւ��A�F�����s���悤�ɂȂ����B�勝4�N(1687)4���A�F��O�R�ブ���y��̓ߒq����A��T�@�ƐV�{�����E�ꉹ�[���I�B�˕�s��(���Е�s)�ɒ�o�����u�F��O�R�{�菊�ブ���Ж��s���V�o�v�ɂ͈ȉ��̂悤�ɋL����Ă���B �u�V�{����Ж��v �������U��莵���V���A��{�n���얀�A��ʎ�o�]�ǁA���ʉ����v�C�@�A�V���ו��E���y�����V��F��A�鉗��_�O�A���ԁE�����A��断�T���u�d�A�����@���s����ӁA���܋㌎�V�Γ��f�A���O�@�䍑����A����E���d�ߌ�F�����A�㌎�\�ܓ��Z����_����A�_�n�E�_�`�E�ɐl�E�x�Ől���ȉ��o���A��_�n��X�}���d�A�_�`�C���D�ȉ����U�d��E�E�E�E �u�ߒq�R���ӎ��Ж��s���v �ߒq�R��O����E�����E���@�R�E��ɗ����E�ߒq����E��T�@�E�����@�A�E�V�������ҁA��断�T�v���u�A�\�����V�����@���A����_�O����V���ו��E���n������F�d�s����ӁA���O�A�䍑�������E���h�ߌ�F�����ΐ\��A ��_�O����@�ӗ֓��A���O���Џ����s�c�C���A�����E���ԁA��J�{�����ΐ\��A�G�p�d�d��A��{�Г��s�c�C�������E�E�E�E(24) �{�{����ɂ��Ă͑O�Ɍ����悤�Ɂu�V��@���m�A�B���Җ��Z�v�ƂȂ��Ă��āA�勝4�N(1687)�̎��_�ł͖{��Ƃ��Ă̋@�\�͎����Ă����B �V�{��ߒq�̂悤�ɐ_���A��A�F�����̖{��̐E���������Ă��̑��݂��傫�Ȃ��̂ƂȂ�A�O�k�E�ЉƂ̐E���Əd�����A�₪�ė��҂ɂ��a瀂����܂��悤�ɂȂ�B����3�N(1675)2���A�{�莛�@�͖��{�̎��Е�s������{��E�ƏC���E�̌��т��֎~����Ă��܂��A�C����p���{��E�ɐ�O���邱�Ƃ��߂��Ă��܂��B ���Е�s�{�菊�Z�E�菑 �@�@�@�o ��@�F��O�R�{�菊�Z�E�V�y�A�@�O�X�ΉΊ�E�A�s���C������ ��@�~�C�����A�Ί�E�ʁX���ߓ����ҁA�ȏ��V�U���؉��s�V�A�{�R�E���R�s������ ��@�{�菊��Z�V�V�ҁA�菊�ブ���ȑ��k���莖 �E���X�������V�A�s�Ꮈ�Җ� ����O�N���K��� �{�@�@����� �ˁ@�@�ɉ�� ���@�@�R��� �F��{�菊 �ブ��(25) �܂��u�ߒq�R�a�k�ؕ��ʁv�ɂ��A����5�N(1677)�A�ߒq���{��͎ЉƂ̌Ö@�ɏ������Ă���B�{�萨�͂͐��ނ̈�r�����ǂ�A���\15�N(1702)��16�N(1703)�A��O����͖��Z�ƂȂ�A�ꎞ�I�ɑޓ]���Ă���B�����Đ���3�N(1713)�ɗ����@�����Z�ɁB����11�N(1726)�ɑ����A16�N(1731)�ɕ�ɗ��R�������Z�ƂȂ��Ă���B ����6�N(1721)�A�ЉƂ��C���̉�ɓ���Ȃ��Ƃ��ꂽ�{��͖��{���Е�s�ɑi���A���{�͖{�����ɓ����悤�ْ肵�Ă���B �I�B�Ɛ\�n��� ���ۘZ�N�V�N�Љƍ����a�k�V�߁A�����Љƃj���Ќ�l�j�I�B�������荒���]��n��䏑�t�ʂ� �F��{�苤 ���l���A���d�� ���V���Е�s�O�����Δn��a���폢�Č�߁A�Δn��a�]��ɗ����菑�o�V���A�s�͔V�R�j���ЉƎБm�C����]�{�苤�����s�\��t�A�E��j����l�j�d�x�|�ĉ��\�o��A���]�˕\�Δn��a�]�B���������@���֔V������R��o��i�A�s���@�V�V��A����E�荷�o�V��߁A�����]���s���B�A���ώd��i�ӕs�̓j��A��R��\�N����C����j�ҁA�ЉƎБm���Ƒ�X�]�˕\�]�Α��l�j�ҁA��C�����V���j�ғ���L��V�����i�ސ��y�o���n��C�����s���V���j�Ή����j����A�{�苤�V�V����]���A�������k�d��A���O�V����L�V��n�n�A�C�����ό�ߌ㑊�B�\��A���ߌ�ᖡ�L�V�|�A�����Ё��Бm���]���]�ː\����|�A�ύה����V�j��A�����x�V�`�n�a�k�V���j���v���k��A�������֔V�l�j���S���s�\�A�����ЉƋ��֑��������k�d�����j�v�S�|�\��ԁA�{�苤�V���ʁA���������k�d��A�ᑶ�O���L�V��n�A�C�����ό��A���B�\��A�����j���L��(26) �������N(1736)�A���{���F��O�R�֊�t������A��������Ƃɔ˂ƎЉƂ��ݕt�����^�p���C���A���c��d�����ƂɂȂ�B �{�{�|�V�呠���� �@�@�o �َҋV�A���t�]�˕\�֔�z�A������N�瑊�Ή�A�V���A�䑤�O�哈�ߍ]��a�����`��ɉߌb�����d�|�A�������莆�Q���A�ߍ]��a���C�����䑊�k�j�y�\��A���V�����j�됬�\��A ��]�@���`�A�F��O�R��C�������Ɛ痼���חV��|�A���C�m�O�����Z���A�ʎ��䏑�t�V�ʏ����I�Ɏ�l��n�A�E��������A��`�j���V���l�l���V�䗠�����ȁA���l���\����j�������A���I�B�l�䉮�~�֑��[�\��A�E��j�t�A�ߒq�В��V���n�����@�A�V�{�n�i�c��V�]�ˌ��푊�Ό�A�{�{�n��B���呠�Ό�̑y��s����A�E�]���V�o��䏑�t�ʚ�ʐi�V��A��{���n�{�{�j�a��[�u�\�A���l�j����S�퐬��A �������N�C�m�Z���@�@�@�@�@�@�@�@�{�{�@�|�V�呠�@�� �@�@�@�@�@�@�ߒq�R�В���y��@�����@�� �`�ȉ����`�@(27) �������N(1744)4���A�u���Е�s�O�Ж@�\�n��v���o����Ė{�萨�͔s�i����(�����ً̍�) �B�����ł́A�{��͎ЉƂ�艺�ʂƂ���A�В��Ƃ͎ЉƂł���A�{��͎ЉƂ̎x�z����B�X�ɋ���21�N�E�������N(1736)�ɖ��{��艺�����ꂽ��t�����^�p���đ��c�ɂ�����A����͎ЉƂ̖�ڂł���Ƃ��ꂽ�B�Ж��A�Ж@�A���c����O���ꂽ�{��́A���̑��݊�Ղ��������ƂɂȂ��Ă��܂����B ���Е�s�O�Ж@�\�n�� �I�B�ߒq�R�ЉƁE�{��A�A�Ж��y���_�A�ᖡ�V��o���]�\�n���X ��@�ЉƁE�{�藼�ւ̂��Ƃ��Ж𑊖��V�|�{��i�� �ЉƎҐ��X�V�@�d�|�E�䋳�����`�A����R�АE�V�d���ܘ_�ɗL�V�A�{��җ��[�Ж����j�y�A���i�V��АE���A���㗼�֓��l�j�s���S����A ��@�{����В��ɘU�V�|�i�� ��R�Z���V�y�����ւĎВ��Ɛ\�V�n���Јꓯ�V����A嫑R�×����O�V�R�ɂ���ăn�A�ЉƂ������ĎВ��Ə̂�����A�t���n���킩�ꕴ�����y���_�Ƃ��ւƂ��A�����{��n�N����АE�Εʒi�ɂāA���ɖ{��ƍ�����ʖ��L�V�A����O�N��s�����V�|���j���A�C�������~�A�Ɋ�E�����V�|�L�V�A�ЉƂƃn�ʒi�V�V��ԁA������Ȋ�E��𑊖��A�Љƍ]�s������A ��@�Љƈ��d�V�x�z��s���V�|�{��i�� �ЉƔV�������d�ɂ����ނ��̃n�A��R��ߎx�z�A�R���㉺�����w�������ؖ��^�A�����{��Έ��d�V���x�z�A�ݒ[���w���ܘ_�A�Ж����G�L�V�ԕ�A ��@�{��F�ߔV�� �O�i���V�j�t�A���x�ブ���V�{��F�ߗߒ�~�V���A���|�𑊐S���s�v���p��A �A�A��O����F�ߒv���p��V�A緃�w�Ö@�Ƃ��ӂƂ��A���b�R��]���s���B�A�ЉƋ��w����i����V����A�����R���V�@����Ƃ��A�����V���L�V�ԕ�A �`�����` ��@�{�ЏC���V�V�Җ{��V�������ɂ�āA�j���L�V�߂͖{�����o�x�V�|�i�� ���ۓ�\��C�N�] ���V����L�V�Љƍ]��@�n�A�����I�ɓa��l�a�V�A�j���V�ߎҎЉƂ�葊�B�A����C��V��ҁA�ЉƂ����ĕs���S��A�{��җP�ȕs���Y�V��A�˔V��V��s�y������A �`�����` ��@���x�ЉƋ����o��ߒq�R���[�菑��Ж@�i�����ߓ_���V��A�e�����n�V���A�R���i���|�������A �`�㗪�`�@(28) ���N�ɂ́A��O�����y��Ƃ��đ����A��T�@�A�����@�A����Ɏ������Z�ł��������Ƃ��m�F�����(��O����l��)�B��ɗ��R������O����̌��тƂȂ�A�����ً̍��ȍ~�A�ߒq���{��͌�O����E��ɗ��R��������������ۂ�ԂƂȂ��Ă��܂����B ��O����l�� �`�{�����` �������b�q�N�����@�{�蒆�y��@��O����@�� �䎷�s�� ���S�@�� �E�{��V���A�ߒq����ҍݍ]�ˁA�܃����n���Z�A��ɗ����ّm���ь̒v�ꔻ�\��A�ȏ�A ��O����(29)�@ |
|
| ��14�@���n��n�镧���ҁ@�@�`�@�h���z�����F��M�`�@ | |
|
��Ɍ����u�O��G���v�u���قʂ��v���琄������ƁA���������ɌF��E�ߒq�́u�M�̋����ʁv���������͓̂V��m�ł͂Ȃ����Ǝv����B
11���I�����܂łɐ��������u���قʂ��v����́A��������̌F��{�{�ɂ�2�A300�̈������������сA�瓰�ł͑m���̂��Ɨ��@�̋s���s���A��O���F��������l�͌����ɕ�܂ꂽ���́A�����ɂ͓V��̖@�ؔ��u���s���Ă������Ƃ��m�F���ꂽ�B�������F��ɂ��āA���̑ԗl���ڏq���Ă���u�O��G���v�͉i��2�N(984)�ɐ������Ă���B ������������10���I����11���I�ɂ����ẮA�V�䐹���������߂���ݒn�̎Г����ċ����Ă͐��l�`��������A�R��������̂ɂ��邱�Ƃ����������Ă������ゾ�B(1)�u���o��t�~�m�ɂ��n���E�ċ��v��`���鎛�@�͐��S�ɂ̂ڂ邱�Ƃ���V�䐹�̊����͍L�͈͂Ȃ��̂ł������Ǝv���A�Ⴆ�Γ��k�̋��R�A����E�������A�R���E���Ύ��A�����E���ގ��A�����̑�A�������~�m�ɂ��J�R�E�ċ����ꂽ�Ɠ`������B�܂����[���ɂ͕�������̖�t�@�����������A��t���Ō���ƌ����S�@�����̂�����t�@�����̐�߂銄����33.3���ł��邱�Ƃ���(2)�A�V�䐹�̊����ȓ`������������A���@���w�������̕s�v�c�@�t�J�n�E�~�m�ċ��Ƃ̏��`���V�䐹�̊�����`������̂��낤�B �����ČF��ɂ������̓V�䐹�����Ƃ���Ă����B�ނ炪�F��Ɍ����������Ƃ��m�F�����j���Ƃ��ẮA���v�N��(1040�`1044)�ɐ��������u�@�،��L�v����������B �E�F��������R�Ɍ����A�R����l�M���Ă�������E�`�͂��R���ŏo������A20�Έʂ̐��l(��17��V�����E��c�̒�q)�B �E�@�،o�̎��o�ҁE���͂����w�R�ŏo������A�@�،o����u���������b�R�����̏Z�m�E�~�P�̎��[�B �E�F�삩�����̎R���ŁA���̒��Ɍ��ꂽ���q�̓����ɂ��A�����Ƃꂽ�V��̎R�m�E���~�B �@�،o�M���ې����邽�߂̋r�F�E�쌱杂͍��������Ƃ��Ă��A���̂悤�Șb�́u�@�،��L�v�����ȑO����́A�V��m�̎R���l�M�A�F��Ƃ̉����������Ă͂��߂Đ��܂����̂ł͂Ȃ����낤���B �ق��ɂ͕��������̌����E�O�P���s�̎q�ŁA��b�R�ŏo�Ƃ�����(891�`964)������A�u��@�t�`�v�ɂ���25�̎��ɓߒq��̑����œ���A�@�،o�Z�����u���Č��͂��l�������Ƃ����B�̌��͉]�X�͂Ƃ������A�ނ��F��E�ߒq�ŏC�s�������Ƃ��j���ł��邩�ۂ��ɂ��ẮA�`�L���ɓ�x�ɂ킽�肻�̒n�����o�Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ����Ǝv���B����̌��̗͂��t���Ƃ��Ă̗��C�s杂ł���Ȃ�A�u�V���y�L�v�̎��Y���C�s�����n�Ƃ��āu���A���A�F��A����A�z�����R�A�ɓ��������{�����A���ˑ�R�A�x�m��R�A�z�O���R�A����A���́A�����A����v�̖���������@���A��x���̒n�����L���Ύ������̂ł���A��x�ڂ�12�ŌF��C�s�͍l�����Ȃ��ɂ��Ă��A��25�̐N���Ȃ�Ώ\�����蓾��b�ł͂Ȃ����낤���B �܂��A�V���_��2�N(766)�A�F�어�{���_�Ƒ��ʐ_�Ɋe�l�˂̕��˂��^�����A�V��3�N(859)�ȍ~�A�����ČF�쑁�ʐ_�ƌF�썿�_�����i���A����5�N(927)�ɐ��������u���쎮�v�́u�_�����v�Ɂu�F�썿�_�Ёv�Ɓu�F�쑁�ʐ_�Ёv���ڂ����Ă��邱�Ƃ���A10���I�����ɂ͌F��M�͓s�ōL���m������̂ƂȂ��Ă������Ƃ��M���A��ɂ��̌��͂��`������قǂ̐l���ł���A�ӗ~�����ȐN���쌱���炽���Ȃ鐹�n�֏C�s�ɕ����p��z�����Ă��A�ԈႢ�ł͂Ȃ��Ǝv���B ������12���I�̓V��m�A�s�_�̓ߒq�R�Ăƌ��n�ł̕������̒����A�o�T���ʂƕ�[�́A�O�ォ��̓V��m�ɂ��F�쉝���A�Q�āA�C�s�̒��Ɉʒu�t���Ă悢���̂��낤�B ���̂悤�ȓV�䐹�F�었�K�̔w�i�Ƃ��ẮA�F��E�ߒq�͌Ñ���R�����E�̑c�搒�q�A���ҋ��{�̏K����`���A����̍��E�퐢���ɘA�Ȃ�n�A�_����Ă���Ƃ��Ă̊ϔO������A�V�䐹�E�C�s�҂炪�쌱�E�@���I�̌������߁A�܂����炪���������v�z��Z��������̂Ɋ��D�̒n�Ƃ������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B�ނ�̊����ɂ�蓱�����ꂽ�̂��A�u�O��G���v�u���قʂ��v�ɕ`�ʂ��ꂽ�V��E�����̖@��A��@�ł͂Ȃ����B����4�N(1090)�́A���͏�c�F���K�̐�B��w�߂��̂����鎛�̑��_�ł��邱�Ƃ��A����ȑO�ɓV��A�Ȃ�������n�̑m���F��ւ̉������d�˂Ă������Ƃ���Ă���A���̎�����u�O��G���v�u���قʂ��v�̐������Əd�Ȃ��Ă���B �u�����ߏ��v�ɂ���~���̌F��w�ł̏��`�ƁA��a���������q(���d����������q)�̖{�n�E���ӕ�F���~�����������Ƃ����̂́A���̌n���ɘA�Ȃ�V��m(����n)�̊����ɂ����̂��낤���A��K���q�Ђ̖{�n�E�s��㮍���F���~�m�������A�ؖډ��q�Ђ̖{�n�E�\��ʊω����`�^���������Ƃ̏��`���A�@�n�̓V��m(�R��n)�ɂ�����ꂽ���̂��낤�B����A�nj������N�A�ߒq�ň�ċ�{�s�@���Ȃ����Ƃ́u�F��R���L�v�̋L�q�ɂ��ẮA�N��3�N(966)�ɓV�����ɏA�C����ȑO�́A40��̍��܂łȂ�L�蓾��b�����A�A�m���Ȏj���̌�������Ȃ����i�K�ł́A���̉\��������A�Ƃ������e�ɗ��߂Ă����ׂ����Ǝv���B �Â����_�_�ւ̐M���W�߂Ă����e�n�̗��ł́A��������ɂ͖{�n��瑐��ɂ��_�̖{�n�Ƃ��Ă̕��E��F�������悤�ɂȂ�A�_���K���v�z����i�ƐZ�����Ă����̂����A����͐_�̕������_�ɂ��ʒu�t���ƐM�̓W�J�ƂȂ�Q�w�҂͑������A���Ђ̋����������炵�A�ݒn�̎v���ƍ��v������̂ł��������B�{�n����n��A�{�n��瑐���`�d���������҂��V��E�^���̑m�ł���A�u���l�M�v�͂��Ƃ��u�{�n��瑁v�����z�̈ꗃ��S�����V��m�ł���A�����A�M�����珎���E��O�ɂ܂ōL�܂��Ă�����y���Ɩ����̉����E�F���A�X�ɖ{�n���̊T�O���F��̒n�ɈڐA���A�n�삷�邱�Ƃ͗e�Ղɍl�����邱�Ƃ��낤�B�ނ�ɂ��A�u�{�{�E�ؐ��a�̐_�̖{�n�͈���ɔ@���ł��肻�̒n�͐�����y�B�V�{�̐_�͖�t�@���ł��蓌���ڗ���y�B�ߒq�̐_�͐��ω����{�n�ł���ߒq�R�͔@�ӗ֊ω����J��ω���F�̕�ɗ���y�v�Ƃ���A���`�����悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B�Љ�̊e�w�ƂȂ���������������������鐹�ł���A���̖��Ɩ@���A���̗��v��`���Z��������̂Ɏ��Ԃ�v������̂ł͂Ȃ������낤�B ������̊J�n���ƌ����ׂ����A����Ƃ��ċ����Ƃ����ׂ����A������ɂ��Ă��u���ɖ����m����悤�ɂȂ������v�̌F��O�R�̐M�͖@�،o�Ƃ̉��A�[���ł������Ƃ�����Ǝv���B �܂��A��ɓ������҂ƂȂ�͏r�����ی��N(1074)���3�N�ԁA�ߒq�ŏC�s���s�������ƁB�_�쎛�̒����̑c�Ƃ���镶�o(1139�`1203)�̑�C�s����́A���̓�l�����ł͂Ȃ��A���Ȃ���ʐ^���m���F��E�ߒq��K��Ă����Ɠǂݎ���̂ł͂Ȃ����낤���B ���o�����R���t�@���ꂽ�̂�50�̍������A�ނ͕ۉ�5�N(1139)�ɐ��܂�A�F��ŏC�s�����̂��������N(1163)��20�㔼���B���ꂩ��5�N��̐m��3�N(1168)�H�̍��A�͂��߂Đ_�쎛�ɎQ�w���A���̍r�p��Q���ĕ����̑���������(�m���o�N����)�A�������\���Ă���B�ނ̐M�p���́u�M��ȑ�t�M�ɗR������^���Ȑ^���̍s�l�v(3)�Ƃ������̂ŁA�o�ƌ�̐M���ǂ��ɂ��������A����͏C���̍s�l�̓��ł���^���������Ƃ����邾�낤�B ���������A�匱�ҁE�^���t�ł��鎟�Y���F��ŏC�s�����Ƃ����u�V���y�L�v�̋L�q���A���Y���l�̌F��C�s���j�����ǂ����͂Ƃ������A���ɖ�����������匱�ҁE�^���t�̏C�s�̒n�Ƃ��āA�F�삪�������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ������B�u���A���A�F��A����A�z�����R�A�ɓ��������{�����A���ˑ�R�A�x�m��R�A�z�O���R�A����A���́A�����A����v���ł̏C�s������(���ۂɂ͂��ׂĂ̒n�Ɍ������͖̂����Ƃ��Ă�)�A�^���t���匱�҂ƂȂ�A�u�q�s��̐����v�Ə̂����O�����A�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B �X�ɁA���q���������k�����̐����Ɛ��肳���u���������L�v�̉ԎR�@�c�̓ߒq���Ă��`���銪�O�́u(�㔒��)�@�c�F��R�ߒq�R��Q�w���v�ɂ́A�u���̐��܂ŘZ�\�l�̎R�U�ƂāA�s�(�Ƃ�)�̏C�s�ҏW��āA��s��s����Ƃ���v�Ƃ���A�u���̐��܂Łv�����u���������L�v��������鎞��܂ŁA�u�s翂̏C�s�ҁv�s�Ƃ��̎��ӂ̏C�s�҂̑������ߒq�ɏW�܂�A���Ă�������Ƃ������Ƃ́A�����ɓV��E�^���̍s�҂��W�����Ɠlj����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����B�u�F��R���L�v�ɂ��u�ԎR�@�c����N���A���ÎO���N�V�Q�āA���ڐ���V�����A��A�Z�\�l�V�T�k�v�ƁA�Z�\�l�̑T�k���m���A�Ȃ����Ƃ���B �͏r�ƕ��o�̎���A�����đ匱�ҁE�^���t�̏C�s�̒n�Ƃ��ČF��E�ߒq���������Ă��邱�Ƃ���A10���I�ɂ͑����̓V��m���K��C�s���A�n��グ��(�Ƃ��Ă��悢���낤)�F��E�ߒq�R�ɁA11�`12���I�ɂ͐^���m�������Ă����̂ł���A���������ɂ͓V��E�^���̑m���F��E�ߒq�R�ŋ��ɏZ�����A�Ƃ������ƂɂȂ�B ���͏�c�̎Q�w�ɂ��F��M������ɂȂ�ȑO�́A�����O���ɑk�邪�A�u�V��Ɛ^�������ɍ݂�v�Ƃ������Ƃɂ��āA�����͗��҂̊_���͒Ⴉ�������Ƃ��m�F�ł���j��������B�����L�����́u����v�ł͎��̎�����Љ��Ă���B(4) �E�u���G���L�v�����ɁA�u��Ϗ\���N�A����̏����̋��{�̓��t�́A�ՏƑm���Ȃ�v�ƋL����Ă���B���18�N(876)�A�^���m�E���@�ӗ֊ω��Əy��ω������A�}��R�R���Ɉ��u�̓������Ă��ہA�������{�̓��t�͓V��̕Տ�(816�`890)�����߂��Ƃ����B�Տ��͉~�m�A�~���Ɋw�ѓ`�@��苗��ʂ��������A���10�N(868)�Ɋ}��R�����6�L���̂Ƃ���ɉԎR�������ďZ���Ă���B �E���16�N(874)11���ƌ��c6�N(882)10���̓��A��ώ�(���ċ��s�ɂ������^�����@)�̏���m�E���N(���E���v�N�s��)�́A�~�������@������������E�̟��Ă��āA�����A�^���@�ƓV��@�̑m���̂������ɂ킾���܂�̂Ȃ��𗬂��������A�Ƃ����B �������́u�~���v(5)�ł��A�^���m�̏@�b(809�`884)���~����藼���̑�@�������Ƃ��Љ��Ă���B�T�ю��m���E�@�b�͎��ɑ��ʂȊ�Ԃꂩ�狳������Ă���悤���B��b�R�ŏo�Ƃ��ďC�w������A�������Ŗ@�����w���A����R�̊J�n�ɐs�͂������b����͐^���������w�сA��C�̒�q�E�^�Ђ��J����T�ю��Ő^�Ђ����Ă���B���4�N(862)1�����ɂ́A���鎛�ʼn~�����ّ��h���n�̑�@�����@����Ă���B���4�N7���A�^�@�e����Ƌ��ɓ������A�A����͓��厛�ʓ��A�������҂��Ƃ߂��B ���q����ɂ��A�E�c�N�������_�l�u���[�����R�������@�s�҂̌n���@�\�@�������@�|�čl�@�\�v(6)�ŏЉ�ꂽ�悤�ɁA�䖧�E�������n�̖@���ɘA�Ȃ�������(�H�`���1358)�̂悤�Ȑl��������B����͓����̐^�����O�����`���A�䖧�̘@�؉@���A�������A�O�����𑊓`���Ă���B�������ł́A�������@���O�x�C��(�ؒ��v���E�^��������������)�A1330�`1340�N��̊ԂɁA�����ɂ����ğ������Ă���B ���A�ꏊ�A�l�����m�̊W���ɂ��A�V��E�^���̊_���͒Ⴉ�������̂��B���̂悤�Ȏ���͂ق��ɂ����邱�Ƃ��낤�B ���q�������ɁA�ߒq�ɉ��̉@(�ꌩ��)�Ƃ����R�ǁE�������̖����ƂȂ鑊���̖V�ɂ��\�����ł��낤�ՍϏ@�@���h�̑m�͕ʂƂ��āA�������犙�q���A���̒n��K�ꂽ�V��E�^���̐��E�s�ҒB�́A���Z���Ԃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂������낤���B�F��E�ߒq��K��鐹�E�C�s�҂͓`���ƎR�ѓl�M�A���āA�����ČF��O�������Q�w����ړI�������낤����A�ނ�͈����Ԃ̋��Z�ɑς�����ȈՂȈ��������Ԓ��x�ŁA�{�i�I�ȖV�ɂ邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���B ����@�t�́u���قʂ��v�ł́A�{�{�ɂ͈�����200�`300���������Ƃ��L���Ă��邪�A�����ł͍s�ҒB�͖��������A�؍ނɂ���Q���āA����H���Ă���A�ނ�̐����Ԃ肩�炷��Ύ��@���z�ł͂Ȃ��ȑf�ȑ���Ɨ����ł�����̂ŁA�F��E�ߒq�ɑ؍݂������E�C�s�҂̋��Z�̑ԗl��m��̂ɎQ�l�ɂȂ�Ǝv���B ��������点�āu�F��R���L�v(7)������ƁA�u�ޓߒq�R�ҁA�O�S�]�[�F����A�����j�����Z�V�`�A�{�E�V���R�ҁA��低��O�ݒj�������V�V�Ɍ̖�v(8)�Ƃ����āA�{�{�ƐV�{�̖V�ɂ͒j�������Z���Ă����̂ɑ��āA�ߒq�R�͒j�������Z���邱�ƂȂ�300�]�̖V�ɂ��F�������Ƃ��Ă���B����ɂ��Ă��A��������̓ߒq�R�̖V�ɂ̐����������̖{�{��2�A300���A300�]���������Ƃ����̂ɂ͋��������B�������A�����ł��邩�ǂ����͂Ƃ������A�����ɑ����̏C�s�҂��ω���F�̏�y�A���Ă̐��n�������˂Ă�������鐔���Ȃ̂��낤���A�����R�Ԃ̒n�ł���́A���̖V�ɂƂ������̂��A�ȑf�Ȉ������x�̂��̂������Ǝv���B�����ėy�X�A�F��{�{�ɎQ�w��������@�t���u�e�����m�肽��l�̂��Ƃɍs�v�����悤�ɁA�ړI�n�ɒ������C�s�ҒB�͖@�n�A�@�F�̂��鑐���ւƌ��������̂��낤�B �����܂ŌF��E�ߒq�ɂ�����V��Ɛ^���ɓI���i���Ă݂Ă������A���m�ɂ́A�ߒq�ɉ��̉@(�ꌩ��)���n������ՍϏ@�@���h�̑m���Z���Ă���\���������̂ŁA���@�����Ă�ꂽ13�`14���I�ɂ́A��R���ɓV��E�^���E�T�̎O�҂����Z�����Ƃ������ƂɂȂ�B����ɕ��i11�N(1274)�Ă̈�Ղ̌F�쐬���ɕ킢�A�F��E�ߒq�ŎQ�Ă���O���m���������낤����A���̏ꍇ�A�V��E�^���E�T�E�O���̎l�҂ƂȂ�B�����Ƃ��A���t��������3�N(1134)2��1���Ɂu�告(�ؐ��a�E�{�{)�̘a���ƒÉ��q�v�̖{�n�́u����ɕ��v�Ə�����(���H�L)������́A�����ɂ��̖����`������ƍl�����A��ՈȑO�ɌF��ɎQ�Ă����O���m�����ɂ��āA���̌n���Ɉ�Ղ��A�Ȃ����\��������Ǝv���B ����ƌ��c���r���̋����ł́A�T���m��̌F��Q�w�������ŁA�S�n�o�S�̒�q�E���S(�a�̎R�E���쎛���V)���������s�r���镧���ҁA�F��Q�w�����҂̐ڑҏ���݂��A����2�N(1330)�ɐڑҏ����c����i���Ă���(9)�B���̂悤�ȎQ�w�̑T�m�A���m���O�R�ŎR�Ă����̂��\���l������Ƃ���ŁA14���I�ɂ́A�F��E�ߒq�ɓV��E�^���E�T�E���E�O���Ƃ����A�����̎�v�@�h�����ɏZ�����Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B ����܂ł݂Ă����o�܂��܂Ƃ߂Ă݂悤�B |
|
|
�F��E�ߒq�ɂ�����ݒn�̏O�k(�Љ�)�̏@���́A�������ɓV�䐹��ɂ��u�����v���������܂�A�����ɐ_���̂��鐢�E�֕�������R����Ɠl�M�́u�s�v���`�����A�ݒn���͂͂����ێ悵���B���ꂪ�×����́A�R�x�Ȃǂ̎��R�𐒔q���Đ_��̉�����F��M�ƌ��т��A�ݒn�F�̔Z���F��E�ߒq�C�����c�Ƃ����ׂ����̂ƂȂ����B�������Ɏ���A�������͂��߂Ƃ���F��O�R���Z�̒��ڎx�z���y�Ԃ悤�ɂȂ�ƓV�䎛��̉e���͂������A�F��E�ߒq�͂�����z�����Ȃ�����A���呤�������ɐێ悷����̂��������A����Γs�ƍݒn�ő��݂ɉe�����������Ƃɂ��F��M�̗��������}�����̂ł͂Ȃ����B���ɖ{�R�h(�V��E����@)�Ɠ��R�h(�^���E��펛�O��@)�̐��͊g��ɂ��A�O�k(�Љ�)�ƌ�ɑ䓪���Ă����{�萨�͖{�E���̂ǂ��炩�ɘA�Ȃ���̂ƂȂ����B���h�̊����͉����Ȃ��̂ŁA��̎��@���Z���N���̂����ɓV��A�^�����ڂ�ς�邱�Ƃ��������A�Ƃ��������ɂȂ邾�낤���B
������ɂ��Ă��A�F��V�{�̐V�{����A�ߒq�R�̎ЉƁE�{�莛�@�Ɍ�����悤�ɁA���\16�N(1703)�Ƌ���12�N(1727)�́u�؎x�O������v�ɏ@�h�������������܂ł́A�����̕ϑJ���o���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �ȏ�A��ςɒ������͂ƂȂ��Ă��܂������A�������犙�q�A�����č]�ˎ���ɂ����āA�F��E�ߒq�̒n�ɂ͎傾�����@�h�������Ă���A�F��O�������̐_�Ђƈ���ɔ@���̐�����y�A��t�@���̓����ڗ���y�A�ω���F�̕�ɗ���y�Ƃ����u�F��M�v�́A�e�@�E�e�h���܂�����̐[�����̂ł���A�قȂ�@���҂������킹��͂ɖ��������̂������Ƃ����邾�낤�B�������A�u�F��̐_�Ёv�u�F��M�̐���̍L���v�Ƃ����Ă��l�Ԃ��n��o�������̂ł���A���̑n��ꂽ�A�ڂɌ����Ȃ��_���ւ̐M���܂��V���Ȃ�l���Ə@���ҁA�����ĉ��l�ݏo���A���ꂪ�O���̐S�c���k�����ƂɂȂ�̂�����A�����Ɂu�@���̖����v�Ƃ������ׂ����̂�����悤�Ɏv���B���̂悤�Ȋϓ_����A�M�҂́u�@���Ƃ͏I��邱�Ƃ̂Ȃ��l�Ԑ��_�̑n���������i���̑n���ł͂Ȃ����v�Ɨ������Ă���B�@ |
|
| ����v�Q�l�����@�@�{���s���t�\�L�ȊO�@ | |
|
�u�F��O�R�M���T�v�@�������v���E�ҁ@1998�N�@�^���ˏo��
�u���̍��E�F��v�@�L���C���@�@1992�N�@�u�k�� �u�F���Ёv�@���l�Y���@1969�N�@�w���� �u�ߒq�o�ˈ��v�@�������������فE�ҁ@1985�N�@�������������� �u���{�v�z��n�Z�@���M�v�@�Γc�������E�Z���@1970�N�@��g���X �u���{�v�z��n ���@�����`�@�@�،��L�v�@�����厁�A��\���͉�E�Z���@1974�N�@��g���X �u���{�v�z��n�\�܁@���q�������v�@���c�ΗY���A�c���v�v���E�Z���@1971�N�@��g���X �u���{�v�z��n �\��@�����_���_�v�@����a�Y���E�Z���@1977�N�@��g���X �u�V�ҁ@���{�ÓT���w�S�W�\�@���{��ًL�v�@���c�j�v���@�Z���E��@1995�N�@���w�� �u�V�ҁ@���{�ÓT���w�S�W�l�\�܁E�l�\�Z�@���ƕ���v�@�s�Ò原���@�Z���E��@1994�N�@���w�� �u�F���{�v�@���씦�\���@1985�N�@�g��O���� �u�����̐_���ƌÓ��v�@�˓c�F�����@2010�N�@�g��O���� �u�^�����P�{�p���@��\���@�L�^���O�@�F�����������N�W(�F�쌠������������a�������L)�v�@�����w���������فE�ҁ@1998�N�@�Ր쏑�X �u����@�j���听(��L)�v���\�l���@����u�j���听�v���s��E�ҁ@1974�N�@�Ր쏑�X �u����@�j���听(���H�L)�v��\�����@����u�j���听�v���s��E�ҁ@1965�N�@�Ր쏑�X �u�_����n�@���w�Ҍ܁@�Q�w�L(�F��w���L)�v�@�_����n�Ҏ[��E�ҁ@�V���O���E�Z���@1984�N�@�_����n�Ҏ[�� �u�V�@���{�ÓT���w��n�@��\���@�{�������v�@��\���͉�A���������A�㓡���Y���E�Z���@1992�N�@��g���X �u�V�@���{�ÓT���w��n�@�O�\��@�O��G�@���D�I�v�@�n���a�v���A����O���A���쉓���E�Z���@1997�N�@��g���X �u�V�@���{�ÓT���w��n�@�l�\��@�Î��k�@���Î��k�v�@��[�P�����A�r�؍_���E�Z���@2005�N�@��g���X �u�V�@���{�ÓT���w��n�@�\�Z�@���o�鏴�@�Ջ�W�@�����̗w�v�@���іF�K���A���Ώ��v���A�y��m�ꎁ�A�^�珹�O���A���{�������E�Z���@1993�N�@��g���X �u���{�ÓT���w��n�@���\�܁@���ΏW�v�@�n粍j�玁�E�Z���@1966�N ��g���X �u���j��n�@��㊪�@�{�����I��@���������E�ҏS�@2007�N�@�g��O���� �u���j��n�@��\�@�}�K���L�@�鉤�ҔN�L�v�@���������E�ҏS�@1999�N�@�g��O���� �u���j��n�@���\�����@�V���i�������@�@���ޗс@���ڕ��鏴�@�����叴�@���ڕ��鏴�v�@���������E�ҏS�@1999�N�@�g��O���� �u���j��n�@��O�\�ꊪ�@���{���m�`�v�����@�����ߏ��v�@�K�������E�ҏS�@2000�N�@�g��O���� �u�Q���ޏ]�E��\���S�@���L���@�I�s��(���قʂ�)(�G�L)�v�@���یȈꎁ�E�Ҏ[�@1977�N�@���Q���ޏ]������ �u���Q���ޏ]�E��\��S��@���M��(���ܕ��W)�v�@���یȈꎁ�E�Ҏ[�A��E���c���l�Y���@1971�N�@���Q���ޏ]������ �u���Q���ޏ]�E��O�S���@�_�_��(������{�n�A�F�쌠������������a�������L�A�F��{�{�ʓ��O�j��O����)�v�@���یȈꎁ�E�Ҏ[�A��E���c���l�Y���@1976�N�@���Q���ޏ]������ �u���Q���ޏ]�E��\��S���@�V�Y���E���H��(���ȏ�)�v�@���یȈꎁ�E�Ҏ[�A��E���c���l�Y���@1974�N�@���Q���ޏ]������ �u���X�Q���ޏ]�E��O�@�j�`��(��@�t�`)�v�@�������s��E�Ҏ[�@1978�N�@���Q���ޏ]������ �u���Q���ޏ]�E���O�@�����a�̏�̓��L(��)(��)(�l)(�Z)�v�@���یȈꎁ�E�Ҏ[�A��E���c���l�Y���@1975�N�@���Q���ޏ]������ �u��W���v�@�������ꎁ�E�Z���@1970�N�@��g���X �u���{�G���听�@�ʊ��@��Տ�l�G�`�v�@�����Δ����E�ҁ@�����Δ����A���d�J���A�ÒJ�����E���M�@1979�N�@�������_�� �u��Ր��G�v�@�勴�r�Y���E�Z���@2000�N�@��g���X �u�q�ؑ�t�~���v�@���ї������@1990�N�@�����o�� �u�����p���@���\��E��\�O�����S(�F��N��L)�v�@2008�N�@�����w�����w������ �u�C���ƔO���v�@��c�����q���@2005�N�@���}�� �u�m��=�F��Ɩ\�̗͂́v�@�ߐ�m���@2010�N�@�u�k�� �u�F��C���̐X�@����R�����킯�L�v�@�F�]�q�����@1999�N�@��g���X �u���������̌��`�ƓW�J�v�e�n������@2007�N�@�g��O���� �u���������@�v�z�E�M�E�����v�@�������v���A�ؑ��G�����A����\�玁�A��ːL�v���E�ҁ@2013�N�@�t�H�� �u���a��{�@���@���l�╶�v�@������w���@���w�������E�ҁ@1959�N�@�g���R�v���� �u�C�������j�����_�W1�@�C�����c�̌`���ƓW�J�v�@��؏��p���@2003�N�@�@���� �u�F��@�_�ƕ��v�@�A���[�i���A��S�Ɨ����A�c�����T���@2009�N�@�����[ �u���j���听(��@���@�L)�v��܊��@�|�����O���E�ҁ@1994�N�@�Ր쏑�X �u�G�L�̌����v�@�����ǗY���@1987�N�@�����쏑�@ �u�F��M�̐��E�@�\���̗��j�ƕ����\�v�@�L���C���@2013�N�@�c�F�Ё@ �@ |
|
| �����Ԃ̗��j | |
| �����Ԃ̗��j�@ | |
|
���Ñ�̍���
�u�����{�I�v�ɁA�u�ΎQ�v�Ƃ����������o�Ă��܂��B���܂ŕ������̍��{�ɍs���ɂ͓��R���̏�썑��ʂ��čs���Ă������s�ւȂ̂ŁA���C���ɂ��炽�߁A�ΎQ����̓��ɂ�����ǂ����Ƃ����t�オ����A�����ꂽ�Ƃ������̂ł��B ���̈ΎQ�͂̂��u�a�����v�ɏo�Ă���u�ɎQ�v�ł��낤�Ƃ���A��썑�ɓ����̒n������A�C�T�}�ƌP������̂ŁA���͍��̈ΎQ���C�T�}�Ɠǂ݁A�C�T�}�́u�C�v���E�����āu�U�}�v�ɂȂ����Ƃ����̂ł��B ���Ԃ̌ꌹ�ɂ��Ă͕ʂɂӂ�܂����A���Ԃ͗N���������A�ꕶ����̈�Ղ̑����Ƃ���ł��B�������A�퐶����ɂ��Ă͂قƂ�lj�����Ղ炵�����̂��Ȃ��A�����͕č�ɂ͌����Ȃ������n�ł��������炩���m��܂���B�@ �Õ�����Ɏ����āA�u�̒����ɉ����Õ�������������悤�ɂȂ�A���ݔ������������ł�30�����܂��B���Ƃ��Ɛ��̑��������y�n�ł�����A�J��ɂ���ēc�����L�����Ă����̂ł��傤�B �ב������{�⍑�����̏��ݒn�������C�V���ŁA�C�V���ɂ͔Ǔc����̖��c����Ƃǂ߂�c��ڂ��L�����Ă��܂�����A���Ԃ��e�����Ȃ������͂��͂���܂���B�@ |
|
|
���ΎQ�w�@
�u�ΎQ�v�́u�����܁v�ƓǂނƂ����̂����������̍l���ł����A���m�ɂ͂ǂ��ǂ̂��킩��܂���B�����Ƃ��Ă��̖����o�Ă���̂́w�����{�I�x�Ƃ����j���̕�T��N(������)�ŁA�������{(���{���s)�͓��R���ɑ����Ă��邪���C���̈ΎQ����̓����Ƃ�A���C���ɑg�ݓ��ꂽ�ق����֗��ł���Ƃ���Ƃ���ł��B ���������t���炭�A�u�������͎R���ɑ�����Ƃ��ւǂ��A���˂ĊC���������A���g�ɑ��ɂ��āA�q�����ւ������A���̓��R�̉w�H�́A��썑�V�c�w���A���썑�����w�ɒB���A���֓̕������A��썑�W�y�S���܂��Č܃��w���o�ĕ������ɓ���A��������ċ�����A�������������ĉ��썑�Ɍ������A�����C���́A���͍��ΎQ(������)�w��艺�����ɒB���B���Ԏl�w�ɂ��ĉ��ҕ߂��B������ɂ��������ނɏA�����Ƒ��Q�ɂ߂đ����B�b�珤�ʂ���ɁA���R�������߂ē��C���ɑ����Ό������āA�l�n�����邱�ƗL��ށv�ƁB�t���B���@(�w�����s�j1�x�����ҁE�����s) ���̈ΎQ�͖�90�N�̂��ɒ����ꂽ�w�a�����x�́u�ɎQ�v(�����S)�ł��낤�Ƃ������ƂɂȂ�A����Ȃ瓯���̏�썑�̈ɎQ�Ɂu�����܁v�ƃ��r������̂ŁA������u�����܁v�Ɠǂ݁A��āu�ΎQ�v���u�����܁v�ƓǂނƂ���Ă��܂��B�����٘_������Ƃ���ł����A���͂��̐��ɂ��������Ă����܂��B���̈ɎQ����u���v���E�����āu���܁v�A�u���܁v�ƂȂ����Ƃ��A�ΎQ�E�ɎQ�͍��Ԃ̌̒n�Ƃ���Ă���̂ŁA���܂́u�����܁v�Ɩ��t���������܂Ŕ�������Ă��܂��B �ΎQ�w�́u�w�v�́u���܂�v�Ɠǂނ��ƂɂȂ��Ă��܂��B�Ñ�̊X���ł͂Ƃ���ǂ���ɉw�������A�n��l�v������āA���l�̋��߂ɉ����ĉw����w�p�����Ă����Ă��������ł��B �������w��(���܂�Ɠǂ�)�A�w��(���܂₽��)�Ƃ����A�l�n�������ق��A���ق����ˁA�Ǘ��҂Ƃ��ĉw��(���܂�̂���)�����Ă��Ƃɓ������Ă����Ƃ����܂��B�����Ă���͗��ߐ��Ɍ��߂�ꂽ���x�ł����B �����A�ً��ɗ�������Ƃ������Ƃ͂����ւ�Ȃ��ƂŁA���ĂƂ����X�Ȃǂ͂���܂��痷�l�͐H�Ƃ��������g�s���Ȃ���Ȃ炸�A��h��R��ł̎ϐ������ӂ��������ł��傤�B �g�s����Ƃ����Ă��A�K�Ȃǂ̕��y���Ȃ���������(�̂����{�͑K��܂ɓ���Čg�s����Ƃ����t���������Ă��܂���)�ł�����A��ؕ���������������܂���B������������ɗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ����������������킯�ł͂Ȃ��ł��傤���A�����ɂƂ��Ăǂ����Ă�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ���������܂����B�����ł����Αd�łƂ��Ē�������镨�������܂ʼn^�˂Ȃ�Ȃ��������ƁA������ꂽ�J���ɂ����������߂ɁA��͂苞�܂ŏo�����˂Ȃ�Ȃ��������ƁA�h�l(��������E���m)�Ƃ��ď��W�ɉ����čs���˂Ȃ�Ȃ��������ƂȂǂł��B ����N�̖��������݁@�ȕʂ�@�߂����͂���ǁ@��v�́@��U�肨�����@�Ƃ葕�Ё@��o������@���炿�˂́@�ꂩ���ȂŁ@�ᑐ�́@�Ȏ��t���@�ނ��т@���ꂷ��@�Q���̏o�ŗ������Ăɑ�@�ڂ݂��@���≓�Ɂ@���𗈗���@���⍂�Ɂ@�R���z���߂��@�����U��@��g�ɗ����(��)���@(�w���t�W�x���X�ؐM�j�ҁE��g����) ����͓������牞�����A��g(���)����D�ɏ���ċ�B�̖h�l�ƂȂ������m�̏���̂������̂ł��B ���͕��̏������������Y�ꗈ�閅�����ĂтČ���˂������� �����炭���͂̎�҂̑��������Ȃƕʂ�đ����R���z���čs�����ł��傤�B �Ƃ�ɂ͈��Ε����ǂ��Z�ݍD����}���ɓ���ė��������͂� ����͋k���S(���s)�ɏZ�Ȃ̉̂Ƃ����܂��B �w�����{�I�x�̗�T��N(����Z)�̓V�c�̏قɁA ����(�łƂ��Ă̖��z�Ȃ�)���^�Ԑl�v�����ɂ͂������ߕ��͂���j��Ċ�F�͐̂悤�Ȃ��̂������A�ɂ��S�炸���̒���ɂ͂����U��������ǂ��悤�Ɍ��������āA����ɑ���]��悤�Ƃ��Ă���B���i�A�S�i�����̂悤�ł���Β��͉����ς˂邱�Ƃ��ł��悤�����@(�w�����{�I�x�F���J�ЁE�u�k�ЁE�ȉ�����) �Ƃ���܂��B�����̎�������߂����̂ł��傤�B �Ƃ���ŁA���ߐ����̉w���́A�����O�\�����ƂɈ�w��u���A�w�n������������Ƃ����A���͍��̉w�͐������{�A�����A���ցA�ΎQ�Ƒ����A��T��N(������)�̑��������ȍ~�ΎQ�w���畐�����̎l�w(�X���E�����E���E�L��)���o�ĉ������Ɏ��邱�ƂƂȂ����Ƃ������Ƃł��B �����̓��C���͑��͍��O�Y�������猻�����p�̑����̊C���㑍���֓n�郋�[�g���Ƃ��Ă��������ł����A��K�͉͐�̒ʉ߂�����ɉ\�ɂȂ��Ă��āA�댯�ȊC�H������A���C�������H�ɂȂ����炵���̂ł��B��{�A�����A���ւȂǂ̉w���͑��͂ł͖k���̎R���ɂ�����A�V�R�ЊQ�̏��Ȃ����������ł��傤�B�@�w��I�肷��ɂ������ẮA����N(���Z��)�A���߂ċI�ɍ����(����)�̉w��݂������Ƃ��L�^����Ă��܂����A�������W�H�ɓn��`�ł���������Ƃ������Ƃł����B�ΎQ�̏ꍇ�͑��͐��n��v�H�ł��������Ƃ��l�����܂��B �邪���̑��n�w�Ƃ݈̂�̐������܂ւȖ�������� �w�ɂ͗��l�̂��߂ɐ��ꂪ����A�n�ɂ͗邪�����Ă����悤�ł��B���̊Ǘ����ɂ��Ă邽�߉w�c�Ƃ������̂������āA�����̎��n����w�N��Ƃ����A���̑ݕt���Ōo�c�����悤�ł��B�@���Ԃ̂m�s�s�ǂ̒n���甭�@���ꂽ���(�c����ՂƂ���)�͂��悻���̎���̏Z���ՂƂ����A�{�b��E�y�t��E�D�֓���E�n���y��Ȃǂ��o�y���܂������A�o�y�i�̂Ȃ��ɓy�������������Ƃ����ڂ���܂��B���̂���A���̂�����ɋ߂����J�̂ł���삪�������̂ł��B���邢�͓c����Ղ̒n�͉w�c�ł����������m�ꂸ�A�߂��́u�`���v�Ƃ����n���́u���v�͔n��(�n��)�������u�q�v�ł����������m��܂���B�����炭���̂����肪��n��ɍD�����ł����āA�N���ɂ��b�܂�A��ʂ̗v�n�ł��������ƍl�����܂��B ���́A���̖؍₠����ɉ����悪��������܂����A����Ƃ��Ă͂��悻��������̂��̂ŁA�w��(��������)��`�w��(���܂�ׁE�w�ƈێ��̂��ߎd�����)�̕揊�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B �w�Ƃł͒P�ɏh�ɂƂ��Ă̋@�\�����ł͂Ȃ��A�V����N(���O�Z)�đ��ɑ�đ唺�S�オ�a�Ƃ��V�c�͎g�����Č������������ŁA�K���a�����Ďg�����A������Ƃ��A�S�ソ����������������āA �����ɈΎ�̉w�Ƃɓ���A�ւ����݂ĕʂ�߂��݁c�� �Ƃ���悤�ɂ����ς���邱�Ƃ��ł����炵���̂ł��B���̐Ȃɂ͕S��̎q�Ǝ������Ȃ��Ă��܂����B(�w���t�W�x���O)�@�������A�w�Ƃ͌��p�̂��̂ł�������A��ʏ������C�y�ɗ��p�͂ł��Ȃ������悤�ŁA�܂��A�����₯�̎g�҂���p�ŗ��p�������ꂽ�l�̏ꍇ�A�ق��̓���ʂ��Ă͈��H�h�ɂ̒͂Ȃ��̂ŁA���߂�ꂽ���Ɖw�����ǂ�ق��͂Ȃ������Ǝv���܂��B�����������ƂŁA�������{�ւ̓��������̈����ɂȂ����܂܂������̂ł��傤�B ���Ԃ̌Â������ɂ͘U�n(�����܁E�낤��)�Ƃ������n�ɂ܂����̂�����܂��B�E�����E�ޗǂƂ������Ñ�ɂ́A���ł͍l���y�Ȃ��ӎ��Œ�������݂��Ă����ł��傤�B �ΎQ�������ւ̊X���̏h�w�ł���A���{����ʂ��ē��R���ւ��ʂ��邱�Ƃ��v���A�����̍���������l���܂��ƁA�ۉ��Ȃ����_�͓��k�o�c�̗v�ՂƂ������ƂɒH�蒅���܂��B���͎炾���������h�H�����A�唺�h�H�Ǝ��͑������ŏ㑍��≺��������ˁA�̂��A�������։������Ă��܂��B�����ƈΎQ�܂���ԂɏW���������R���������āA�ɂ��ɂ������݂��̂��֏o�������ɈႢ����܂���B ���̂悤�ɍl���Ă���ƁA�u�ΎQ�v�Ƃ����������Ȃ��Ӗ��[�Ɍ����܂��B�ΎQ�́u�v�́u���т��v�Ƃ��ǂ݁A�������牓������āu�܂��ʖ��v�̂��ƂŁA���Ȃ킿�A����(�݂��̂�)���Ӗ����܂��B�u�Q�v�́u�܂���v�ł����Q��Ȃǂ́u���܂�v�Ƃ������Ƃł��B�Q��ɂ́u�s���A����v�̈Ӗ�������܂��B ��T��N(������)�A�������{�����C���ɑ������ƂɂȂ��Ĉȍ~�A���k�o�c���ɂ킩�ɑ��������Ȃ������Ƃ͗��j�̎����Ƃ���ŁA��T�ܔN(�����l)�ɂ͑唺�x�͖��C�������Ɍ������A��T���N�ɂ͗����E�o�H�̌R���ڈΌR�ɔs��A��T�\��N�ɂ͔����ŋI�L�������ɂ܂����B�V�����N(������)�����������C���ڈ𐪓��A���N(����N)�ɂ͑唺�Ǝ�����������{���R�ƂȂ��Đ����ɕ����A�����N�ɂ͓��C�E���R���ق��֓�����������R5���]�l�����đ�������点�Ă��܂��B���\�O�N�ɂ͑唺�햃�C�̓���������A����ł��������Ȃ������̂��A����\�N�ɂ͍��c�����C�������ɕ����A���N�A����Ɖڈ̎A�e���C���~�������Ă��܂��B�����o�H�����̋L���̏I���͍O�m��N(�����)�̐��Ώ��R�����Ȗ��C�̐폟�������ĈȌ�̂��ƂɂȂ�܂��B ���̊ԁA�ΎQ�͐����R�̊�n�Ƃ��đ����̕��n�̖�c�����������Ƃł��傤�B�Ĕn(�����܁E�낤��)�͂��̖��c�肩������܂���B�@ |
|
| �����X�؈ꑰ�@ | |
|
�����ԋ��ƍ��X�؎�
���Ԃɉ߂������́A�ƌ����Ύ����邾�낤���Ø\�O�N�̐��J���̞���������B���X�ؐM�j����i�������̂Ƃ������w��̏d�v�������ł���B���Ԏs�̕������ō��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă�����̂͂��ꂾ��������A�����ƊS�������Ă悢�Ǝv���̂����A���ł���Ȟ����������ɂ���̂��ɂ��Đ^���ȒNjy���Ȃ��ꂽ���Ƃ����܂蕷���Ȃ��B ���̖����͗z���Ŏ��̂��Ƃ��Ȃ��Ă���B �@�@�@���B�@���J�� �@�@�@�@����� �@�@�@�Ø\�O�N����Ύ���������� �@�@�@�助�i�����Ŏq�@�G�| �@�@�@��h�z����@���� �@�@�@��h�߁@�����b�@�M�j �@�@�@�@�@�@�@��H���g�� �@�@�@�@�@�@�@���i������q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�� ��h�߂̌����b�M�j�ɂ��ẮA�������̓c�㊥�ҐM�j�Ƃ����l�������āA���Ɠ����̋`�o�ɏ]���ČR�������ĂĂ��邪�A���オ����Ȃ����Ƃƌ����b�̏̂��ߍ]���������ɂӂ��킵�����ƂȂǂ���A���X�ؐM�j�Ƃ��Č��Ȃ����̂Ƃ���Ă���B ���X�؎��͉F���������̂��A�ߍ]�̍��X�ؑ���`�̂��ďG�`�Ɏ������B�G�`�\�O�̎����`�̗P�q�ƂȂ�A��A�`���ɏ]���ĕ����Ɛ����(�����̗�)�B�킢�ɔs�ꂽ�G�`�͗̒n�������A�q����𗦂��ē����G�t(�G�`�H��v��Ɓw��ȋ��x�͋L��)�����̂݉��B�ɕ������Ƃ������A���͍��Ɏ����ďa�J�d�����G�`�̗E�����ɍ��ꂱ��Ŏ��̂ɗ��ߒu�����Ɓw��ȋ��x�ɂ͂���B �a�J���͊��������ő��͍��a�J�����N��a�J�����̂����Ƃ����B���ߏa�J�d���͗����̗U���ɏ]��Ȃ��������A���X�؏G�`�Ƃ��̎q������(��j�E�o���E���j�E���j�E�`���̌܌Z��A�����ܘY�`���͏d���̖��ƏG�`�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ)�͗����̋����ɉ����ĎR�،����ُP���̍őO�ɒy���Q�����B���̎��G�`�͎��\�O�A�G���͂��̘V����R������Ă߁A�G�`�͘V���̂��ߑs��Ȑ펀���Ƃ����Ƃ����B�u�֓������M���ɒ�߂��䊴�̗]��v��̏܂ɗa����v�Ɓw�����ƌn�厫�T�x(���c��)�ɂ͂���B �₪�ďa�J�d���������̌R�ɉ����A�u���ɔe�{�̌��V�ƈׂ��v(�w�n���u���x)���Ƃ��Ȃ������A���X�،Z�킪���Ɠ����ɉX����������������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���A���̌��тɂ����ďa�J��������̂��������悤���B ����܂ō��X�؈ꑰ�͏a�J�̏��̂̈ꕔ��a����A���̌o�c�������Ă����悤�����A���̒n�������ł��������ɂ��Ă͊m���Ȃ��B�a�J���͓������R�}�̈ꑰ�Ƃ��Ęa�c����ł͘a�c���ɉ��S���Ĕs�k�A���̏��̂��������ƂƂȂ����B��N(��N�����l�����Ƃ���)�a�J�����F���Ɉڂ����Ɏ������ꑰ�ɂ͑��쎟�Y���d�A�g���O�Y�d�ہA��J�l�Y�d�A���i�ܘY��S�A�����Z�Y�d��Ƃ���A����A�g���ق��̒n���a�J���̖{�тł������Ǝv����B�����̒n�������Ă̏a�J���A���Ȃ킿���ԋ��̒n�����X�؏��ǂƂ��ꂽ�̂ł͂Ȃ����B���ԋ��͂��̂悤�ɂ��Əa�J������o�c���ϑ�����Ă������̂ŁA�a�c����㐳���ɍ��X�̏��̂ƂȂ������̂Ƒz�������̂ł���B �a�c����(����O�N������O���܌�����E�O��)�ł͘a�c�`���ɉ����������m�̖w�ǂ����R�}�𒆐S�Ƃ������́E�����̑�A�����A��Ɛl�ŁA�a�J�d���̒��q���d(�w��ȋ��x�ɂ͎��Y���d�A���R����d���ۂƂ���)�����̒��Ɍ�����B������X�ł͖k�𑤂ɂ��đ�q�ŕ��킵�����X�؋`���̖�������B ��㒼���Ɏ��̂悤�ȕ������k���`���E��]�L���̘A���ŏo����Ă���B �a�c���q��ы`���A�y����w���`���A���R�E�n���B���ւđ��͂̎҂Ƃ��A�d�����������Ƃ��ւƂ��A�`���m���L�B�䏊���ʂ̌䎖�Ȃ��A�u��Ƃ��A�e�ޑ������ցA���������肿��ɐ��悵�������߂��B�C��萼�C�ւ����s��ʂ��B�L�́B�L�j���̂��̂��Ȃ����܂̌�Ɛl���ɁB���̌�ӂ݂̈Ă��߂��炵�āB���܂˂����Ђӂ�āB�p�ӂ��������āB�����Ƃ�Ă܂��炷�ւ���B �@�@�@�@�܌��O���@�э��@�@�@�@��V��v �@�@�@�@���X�؍��q��ѓa ���t�͐헐���������S�Ɏ������ꂽ�Ǝv���ʓ��̗[���̂��̂ł���B����́u���s���킵���v(�w��ȋ��x)�Ƃ���̂ŁA���X�ؑ��̂̍L�j�͓����ߍ]�ɂ����Đ퓬�ɂ͎Q�����Ȃ��������悤�����A���ԋ��͂��̈��A���邢�͒�̎l�Y�M�j�ɔC���Ă�����������Ȃ��B�����͉��R�}�̑ޘH��n���߂Ă����̂ŁA�Ɛl�ɖ����Ďc�}�̓��S��j�~����Ɩ������킯�ł��낤�B �������Ĕ݂�݂��ĕꉮ���������a�J�����猩���X�������X�ŁA�̂̉��őj(�M�j�O�j)���a�J����喼�ł���ƌ������̂ɑ��A�a�J���d(���d�̎q��)�͂���J�Ǝ���Č��_�ƂȂ������Ƃ��w��ȋ��x�ɂ���B ���ԋ��ɂ����鍲�X�؎��̋��ق͂����炭���ݐ��J���̏��݂��鍂��ł������Ǝv���A��n�ɉ������J�˂��ߍ]�J�˂Ƃ����A�ߍ]�v�ۂƂ��������Ƃ����`��������B���̒n�����F�̔Z���y�n�ł��邱�Ƃ́w���B���J���Ø\�N�I�����Ɋւ���Q�l�����x(���Ԏs�������ی�ψ����)�ɂ��q�ׂ��Ă���Ƃ���ł���B���J���ɐM�j��i�̞��������邱�Ƃ͍��ԋ������X�̏��̂ł����āA���̋��ق͂���ɋ߂��n�ł��������Ƃ��ؖ�����Ǝv���B�@���̂̈ꕔ�����Ɋ�i���A���ق��߂��ɏ��݂�����͐��s�̍��q�̏@�O���ɂ�����B���̎��͂��Ə������Ƃ����A�t�߂͍��X�؍��j�̏��̂ł������Ƃ����B���j�͖ؑ]�`�������̉F�����w�Ŗ��𐬂��������ŐM�j�̏f���ɂ�����B�M�j�����Ƒœ|�ŋ`�o�ɏ]���ċ��֍U�߂̂ڂ�A�f���ɂȂ���ĉF����̐�w��w�߂����Ƃ͍X�ɗL���ł���B���j�͏��̂̂������q��ӑ�����t���ď�����������̕�Ƃ����Ƃ����B���̎��ɂ͐M�j�̎q�j��i�ɂȂ鞐�����������B �w�V�ґ��͕��y�L�e�x��w�c���n���c�e�x�ɂ��ƁA���Ԃ̒n�͂ނ����u�a�J�����ԋ����ԑ��v�Ƃ����悤�ɂ����Ă������A�u�a�J�����ԋ��v�͌��݂̍��Ԏs����k�����͌��̐V�ˁE�镔�E�c���E�����E�a�E�����E��Ȃǂ܂ł̍L���͈͂ƂȂ��Ă���B���Y���͒Ⴂ���L��Ȓn���a�J���A���̗̂������p�������X�؎��͐�߂Ă����킯�ł���B ���̂ɍݒn�̑㊯��u���čٗʂ��������Ƃ́A���j���k���S���R���̗̒n���u�\�]���l���̊ق����܂ցA�l�ʂ@���߂��炵�ėv�Q�Ƃ��A�ꑰ�A�Z�p���Y�A���R���q��𗼖ڑ�Ƃ��A���쏯�i���ɐl�Ƃ��Ă����ɂƂǂ߂����A���̐g�͊��q�ɂ���ċΎd����v(�w�����ƌn�厫�T�x)���Q�l�ɂȂ낤�B�@ |
|
|
�����v�̕ςƍ��X�؈ꑰ
�w�����ƌn�厫�T�x�ɂ́A�u�G�`�̌��ɂ��A�����̎q�ܐl�A��������q�{�n�ƂɌ����肵�ɂ��A�G�`���q��j�͋ߍ]�A����A�Ό��A�B��l�����̎��A���j�o���͒W�H�A���g�A�y�����̎��A�l�Y���j�͔��O�A���|�A���h�A�����A���ˁA�����A�o�_���̎��A�O�Y���j�͏��A�]��A�ɗ\�A�ܘY�`���͉B��A���ˁA�o�_���̎������ˁA�ꑰ�\�����ɘj���ɋߍ]�Ȑ��A�����A�l���ɉh������v�Ƃ���B���̂悤�ɈА����݂łȂ��������X�؎��͏��v�̗�(���v�O�N�E�����)�Ɏ����Ă��̌��Ƃ̑啔���������H�ڂɂȂ����B���̍L�j���͂��ߎq�̈ҍj�A�j�A�L�j�̏f���o���Ǝq�̍��d�ȂLjꑰ�̑������@���ɎQ�����Ĕs�������̂ł���B �������A���v��N�ɂ͒�j�E�L�j�e�q���F���E�B��ɗ�����鎖��������(��͖�)�A������N(���Z�Z)�ɂ͌o�������g�E�W�H�E�y���̎��E��D����Ƃ����������������B�ނ�ɂ͑��O������A�����Ɋ��q�Ɍ����Ȃ��A�����̖k���ɉ��`�͊������A�㒹�H��c�̗U���ɏ���Ċ��R�ƂȂ������̂Ǝv����B ��l�M�j�͑��͂ɂ����āA���ɏ]���Ċ��q���ɎQ������(�k���R�ɍ��X�ؐM���m���j�̎q�n�̖��������邪�E��̋L�^���Ȃ�)�B�������ĉF����ł͈ꑰ�G�����ƂȂ��Đ키���ƂɂȂ����B�w���v�R����x(�w�Q���ޏ]�x���핔��)�ɂ́A ���������ւ͂������̒��[������܂����A���Ђ̂������₤�����̂肵��(�͋`)�A�������̂����Ƃ���(�L�j)�A���������Y������� �ȂǂƂ���A�M�j�͑��q�̏d�j�ƂƂ��ɐ�w����ČZ�≙�̊��R��j�����̂ł���B �M�j�ɂ͊��q�̌�Ɛl�ł��������Ƃ̂ق��ɁA���̎������̖��ł������Ƃ���������������낤�B�q�̑j�̕ꂪ���̖��Ɓw�����ƌn�厫�T�x�ɂ��邩��ł���B�@���̐�ƒNjy�͌����������B�M�j�̏f�����X�؎��Y�o���͕������Ęh���̎��@�ɂ����Ƃ���A���́u�o���ǂ̂͂��̂��ђ����ɂ���ċ����ɑ����ꂽ���A�����l�N�̎R�؍���ȗ��̊��q�̌��b�Ȃ�Ύ��E�����Ă͂Ȃ�ʁv�Ɛ\���ꂽ�B����ɂ͐M�j�͂��ߏa�J�O�Y�A��������A���X�ؖ����Y�A��ѕ��O�������玩���̌��ɂ����Ă̏����Q�肪�Ȃ���Ă����B�o���͂����p���Đؕ����ĉʂĂ��Ƃ���(�w�V�ߌ�ȋ��x����)�B�Q��҂����Ԃɋ߂��l�X�ł��邱�Ƃ����ڂ����B�M�j�͖��ɂ���ČZ�̎R���L�j���a��B����Ɉ���ł������͍̂L�j�̎q�������ۂŁA���́u�L�j�̉Ȃ͏d�����ʂȂ珕���������Ƃ͏o���Ȃ����A���݂͂ȕ��̖��Ƃ��ċv�������A�܂��\�̌ǎ��̂��Ƃ����爫�����Ƃ͂��܂��v�ƕ�̊肢������A�����̂���Őg����M�j�ɗa�����B�Ƃ��낪�M�j�́A�Z�L�j�̒��q�ҍj�A���q�j�����X�߂炦���Ďa��ꂽ�̂ŁA�������ۂ�������ʖ��Ǝv���A�l�̎�ɂ�������͂ƈ��ʂ��܂߂Ď���̎�Ŏ���͂˂��̂ł���(�w�V�ߌ�ȋ��x��)�B ���J���̞����̉Ø\�O�N(����)�͂��̐��N��ɂ�����B���̎��Ԏ��E�A�Ø\���N�̑�]�L���E���q�̎����A�Ø\��N�̎g�߂Ƃ��Ă̏㋞���l����ƁA���������̑��Z�̒��ɁA���X�ƞ����̒����A���̕������������Ă������ƂɂȂ�A����̏h���Ƃ͂����Ȃ���A�s�^�ɎU��A���������������ߐe�҂̕����A������������S���͗����o����C������B��A�ِ��o�Ƃ��ċ������Ə̂��A�m���O�N(���l��)�A�Z�\��ő�����(�@���o��)�B�@ |
|
|
�����퐼��ƈ˒m
�M�j�̖����āA�����̒�����J���̑��c��i�߂��̂͐���ł����āA�葫�ƂȂ��ē������̂����i������q�G�͂ł������낤�Ɩ�������ǂݎ���B ����ɂ��Ă͑O�L�w���B���J���Ø\�N�I�����Ɋւ���Q�l�����x�ł��A�w���Ԃނ����ނ������W�x�́u���J���G�L�v(�ѓ����Y)�ł��w��ȋ��x�ɓ�x������ق��͕s���Ƃ��Ă���B����̖����狽�y�j�Ɣѓ����Y�����u���X�ɊW�̂���l���v�Ɛ��������̂͂������ł���B ����l���Ƃ����m�͂Ȃ����A����Ƃ����@�������l���͂��̈ꑰ�ɂ���B���X�،n�̕��䎁�ŁA�w�����ƌn�厫�T�x�ɂ͍��X�،n�}�̈��q�l�Y���v�ƍs�̎q�Ǝ�(���䌠��A�]�܈ʉ��A�@���}��)�ɓ�l�̎q������A���j�N�Ƃ͕��䎵�Y�A�@������Ƃ���B �Ƃ���ŁA�����Œ��ڂ����̂́A���䎁�����Ƃ͈��q���ł��������ƂŁA����͋ߍ]�����q�S����W����N����Ƃ����B���q�̓G�`�Ɠǂ݁A���m�Ƃ��A�˒m�A�˒q�A�ߒm�Ƃ������B�˒m�A�˒q�͍��Ԃɂ͌������݂ɂ�����n���ł���B���X�͓����̈��q(�˒m)�������đΊ݂̒n���Ǐ��������̂ł͂���܂����B���̌ケ�̈�т͊C�V�����n�̖{�Ԏ��̏��̂ƂȂ������A�˒m����o�ĉz�q�𖼏�鑰������B�߂��̎O�c�ɐ����@�Ƃ������������āA�����͂��Ɖz�q�e�����̋��قŁA�V���N�ԉz�q�o�_���i�̖�t���{���ƂȂ��Ă���B���̉z�q���́u���͈��b�S�˒q���N��A�˒q���z�q���a�肵�Ȃ��v�Ɓw�����ƌn�厫�T�x�ɂ��邩��A���X�،����̈ꑰ�ł��邩���m��Ȃ��B�����@�ɂ��Ă͍��Ԃ̗����@�����̖����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��������Ђ�(�o���Ɍ��̎�������̂͋��R��)�B ���ł����A�˒m(��)�ɕ���ƂƂ������Ƃ�����A��͂���Ƃ͍��X�؎��������Ƃ����`��������B�Ɩ���l�ڌ����ł���B�˒m�ŕ���Ȃ炻�̂܂܋ߍ]�̈��q�S���䑺�����A���̉Ƃ̐�c�͐ےÑ��c���A���䑑��̂������ŁA�V���N�Ԕ����q���炱�̒n�Ɉڂ�Z�Ƃ���(�w�_�ސ쌧�����ƌn�厫�T�x�p���)�B�ߍ]�̕��䎁���]�o���Ċe�n�ɕ���̖����L�߂����Ƃ́A�����ߍ]�̍����S�ɂ����q�S���䑺�̑����J�������䂪���邱�Ƃ�����m���B����ɂ��Ă��˒m�̒n��I��ŊJ����s�����Ƃ́A���R�ɂ��Ă͏o���߂��Ă��͂��܂����B��c�����q�̕���ł��邱�Ƃ��L������Ă��āA���邢�͓������c���k���̉Ɛb�Ƃ��ĉz�q���Ɩʎ�������A�z�q�������̒n�ɗU�������̂��B ���肪���q�Ŋ����N(��O�O�Z)�ޓa�ω����́u���b���n�v�̊��i���߂����Ƃ́w��ȋ��x�ɂ��邪�A���ɂ͂��̐l����������u�ω����Ⓦ�O�\�O�D���v�̐����ɂ��Ȃ�̊֗^�������悤�Ɏv����B�Ƃ����̂́A��ԎD���̐��{���ɑ����Ă��̊ޓa�ω���(��a��)����ԂƂȂ��Ă���B���{���Ɗޓa�ω����ɗ������Q�w�������Ƃ�����̂ŁA�Ⓦ�O�\�O�D�����肪���q�{����o�����̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��낤�B�O�Ԃ̈��{�@�͓c�㎛�Ƃ������A���̓c��M�j�����u�������ω����܂�Ƃ����B���J���̐M�j�Ɩ�������悤�����A�c�㎛�̏���̂́u�͖ɂ��ԍ炭�����Гc�㎛�@�����̂ԍj�̐Ղ��v�����v�ŁA�M�j�̐���炤�ӂƂȂ��Ă���B�c�����Ĉꑰ�̑��̂Ɏv�����͂����A�ƌ����Ȃ����Ȃ��̂ł���B���J�������𒒂��Ƃ����юR�ɂ͎��Ԃ̎D�����J��(�юR�ω�)������A�����Ŏ���̖��������������̂��鐯�J���ԎD���Ƃ����B������ʒn(�C�V���s����)�ɍ��w�蕶�����Ƃ����i���������ω���[�߂�������(����)������A�������J��Ɠ`���邱�̎��������ĂȂ����Ԃ̐��J���Ȃ̂ł��낤�A�Ǝv���Ɛ���̖���������ł���̂ł���B���J���̍Č��ɁA��ԎD�����{���Ɠ������Ў��̖{���̐��̖ւ̔��`��������B�����܂ł���Ɛ��J���̍Č��͍��X�؎��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���邪�ǂ����낤�B�@ |
|
|
����H���g���ƍ��X��
���̏������܂�o���̗ǂ��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A���y�j�����Ɣѓ����Y���̎w�E������A�w�Âꑐ�x20�����v)�B�x�R���͒����̐��ƂŁA���J�������ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��Ă���B �����g���������̈ꑰ�Ƌ��ɔюR�̒n�ł͎n�߂Ă̞����̐������s�������̂Ǝv����B�n�Ƃ̋�J�͑�ςȂ��̂ł������Ƒz���o����B�]���Đ��J���̞���������߂Ċ�Â̎�@�ɂȂ���̂ŁA���̏��g�͌��a�ɑ��Ē����������A���̎w���͈�l���E���ƂȂ��Ă���B��ʂ̏��ł͈�O�܈ʂ̐��l�������Ă���B����ɏ��g�̊O�Ȑ��͂���߂Ă�邭�A�قƂ�ǒ����ɋ߂����ɋ߂��O�ς�悵�Ă���B�����͒ʏ�O��ɂ��邪�A���̏��ɂ͈���ɂ����Ȃ��B�����̏o�����Ƃ��Ă����Ĕѓ��搶�������Ă����l�ɗǂ��o�����ł͂Ȃ��B���̒��������ɉ~���ɉ����đ傫���r�������Ă��邪�A���͂���́u�����v�ƌ��Ă���B�����Ƃ͒����̂Ȃ��Ɏ_�������o���Ĉ�̂̒����ƂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ������B�v���ɗo��\�͂����̏�����̗e�ʂ��Ȃ��āA���̘F���x�����ėo����Ƃ����āA���̒�������x�ɕ����čs�������̂ł͂Ȃ��炤���A��r�I�ɗo�����x�̒Ⴂ�������ł���̂ŏ����ł肩�������̏�ɐV�������x�̍����������������̔M�ŋ����o���Ĉ�̂ƂȂ邱�Ƃ͍l�����邪�A���̈ꕔ�����܂��o�����Ȃ������r�Ƒz�����Ă���B��ʏ펯���猾���Ζ����ɕs���i�i�ł��邪�A���Z�Z�N�O�ɏ��߂Ă̍�i�Ǝv���Ƃ悭������Ǝv���B�� ���́A���̂悤�ɏ����I�ł͂��邪�A�֓��ł͍ŏ��Ǝv������̒������s�킹���M�j�́A�����t�g������ߍ]����Ăъ��Ɛ�������B���ۂɒ��������ꏊ���юR�ł��������ǂ����͕s�������A���b�̔юR���牬��ɂ����Ăł��낤���A���X�̎�̎҂ł������ł��낤���Ƃ́A�O�L���̏@�O��(������)�̞�������͂茹���̑�H�L��Ŋ�i�҂͐M�j�̎O�j�j�ł��邩��ł���B�@�܂��A�o���h���͂Ƃ������A�֓��ōŏ��Ƃ����Ă������������f����ɂ��ẮA���ꂾ���̋K�͂̎��ł���˂Ȃ�ʂ͂��ŁA���J���͂��̍��Č��Ȃ����ڒz���ꂽ���Ƃ����ɂ͍l����ꂽ�̂ł���B ���X�؎��̖{�т̒n�ߍ]�͒����̓��ӂȏꏊ�ł������炵���A�w�n���̌����x�Ŗ��c���j�́u�ߍ]�ɂȂ��������t�ɉ��[���A�I���S�ɂ����m�S�ɂ������̌̐Ղ�����v�Əq�ׂĂ���B���͍ŋߎl�b�J�����Ƃ̌̒n�A���̊֎s�ׂ���(�֎s�͗�̊ւ̑��Z�����߂Ƃ����S���L���̓����̒��ł�����)�A���s�����t���̓V�����͘Z�p�Ǘ̍��X�؎����̊�i�ɂȂ鎛�Ƃ����ċ������B���Ԃ̍��X�����y�ߍ]����b��t���Ă炵���A���h�̈�тɂ͒b�艮�����������B�~�����ɂ͍��X�؊|���Ə̂��铨������A�s�w��̏d�v�������ƂȂ��Ă���B�w���Ԏs�d�v�������ē��x(�s�������ی�ψ���ҏp)�̉���ɂ��ƁA �����́A���E�I�ɂ݂āA�Í���ʂ��A�݂�`�ł��邪�A���{�ł́A�Õ����㖖����Ǝ��̔��B���͂��߁A�������㖖�ɂ͑�����S�̂��|������̂ƂȂ����B���ɁA�{�i�̂悤�ɍ��X�؊|���Ə̂�������̂́A�ł���`�ɔ��B�������̂ł��邪�A�ߍ]��(���ꌧ)�ł͍��X�ؗ̓��ō���A����|���Ƃ��Ă�遄 �Ƃ���B���`�ł͓��@��l�����̌�����˒m�̖{�ԓ@�쑗�����Ƃ�����Ă����n�̓��Ƃ������A����N��͂����Ɖ������Ď�������ƌ����Ă���B���`�͓��@�����̎��ɋx�������Ƃ����`���ɍ��킹�����̂��낤���A���̊J��͗�Ƃ����b��ł���������A���̂悤�ȓ��������Ő��삳��Ă������Ƃ��ؖ�����̂����m��Ȃ��B���h����ߍ]�v�ۂɂ����Ē����t�����Z�������Ƃ͗鎭(�w���Ԃނ����ނ����x���W)���Ƃ������đz���o����B���Ƃɒb��͌������Ƃ̏o���Ȃ����̂ł��邵�A���̕ӂ�̒i�u���͊e���ɒb��ɕK�v�ȗN���������N���A���Ԏs�̌ւ�ƂȂ��Ă���̂ł���B�@ |
|
|
�����q�Ó��Ɠ��@��
�������Ȃ��㗢�̓� ���Ԃł͂���������Ó��������āA���J���e��ʂ��ē���E���q�ɒʂ����q�Ó��̖�������B���͐썶�ݒi�u�̏���ׂ����������ʉe���Ƃǂ߂Ă���̂ł��邪�A�M�j��L�j�����q�ɒy����ɂ͂��̓������Ȃ��A�����㍲�X�ؓ��ƌĂ�ŗǂ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�a�J���̂�������A����ɂ��ʂ��A�w���������L�x�ɂ����u�̍��n���̗P�q�ɁA�ߍ]���̏Z�l���X�،��O�G�`���q���A�����̗��̌�͍����ނ����ɂ����܂苏����A���Y��j�͉���F�s�{�ɂ���A���Y�o���͑��͂̔g����ɂ���A�O�Y���j�͓����a��ɂ���A�l�Y���j�͓s�ɂ���A�ܘY�`���͑�ꂪ�O�Y�̖��ۂɂđ��͂ɂ���]�X�v�̐��j��`���̊ق��r���ɂ��������Ƃł��낤�B ���̓��͑O�L���@���{�Ԏ��̊قɑ���ꂽ���ł������āA�C�V�����̎��Վ��ւ̋Ȃ���p�ɐ̓��W������A �@�@�@�E�@���ԋx���R �@�@�@��˒m������ �ƒ����Ă���B ���Վ��͓��@�@�����A�����J��͍��X�؍��j����������T�؎��Ղł���B�ނ͐�c�̌̒n���������ݗ������Ă��̖��ƗD��Ȟ���(����O�N����Z���܁���)���c���Ă���B�x���R�͉~�����̎R���ŁA���@�����̒n�ɂ������b�艮�~��ؑ�ŋx�������Ƃ����Î��ɂ��Ȃ�ł̎R���ł���B���ԕt�߂̓`���ł́A�x���������@�̈�s�͎l�b�J��̊O�L�͌�����˒m�֓n�����Ƃ������A����ł͍s�����s���R�ł���B�u��˒m�������v�̐����͓��@���@�y�����琯�����������Ƃ�����(���`��)�̓`���ɂ�閼�����A��˒m�ւ͓���(���͓c��)�̓n�����D�ւ̂͂��A�����炭�b�艮�~�܂ŗ��ē����n�����g���Ȃ�(�o���ŏM������ꂽ��)�����̂ł��낤�B��ނȂ�����߂�悤�ɒH���ĊO�L�̓n���ɏo�����̂Ǝv���B���Ɠn���̑D�������Ă����Ƃ������Ƃɂ̓{���{�������������@�̏������������������������B�@ |
|
|
�����̌�̑��͂ƍ��X��
�M�j�͞����̋I�N�Ɠ��N�ɋߍ]���̒n���A�����Č����g�ɕ₳��A����O�N(���O��)�ɂ͋ߍ]��ƂȂ��Ă���B���̍����X�ؑ��̂��p���ߍ]�ɕ������Ǝv����̂ŁA���ԋ�����͂��������Ȃ����������ƂɂȂ�B���ꂪ���ԋ��ɍ��X�̖��𑽂��Ƃǂ߂ʌ����ɂȂ����̂ł��낤�B �w���ԌÐ��x�Ɂu����N(��ꔪ�l)���q���V���A��n���~�Ƃ��ӂɒ��h�ƌ������o���v�Ƃ��邪�A�����I�ɂ���͍��X�؊֗^�̒����Ǝv����B��������o���Ƃ������݂̒��h�t�߂Ɏl�ڌ������Ɩ�Ƃ��Ă���Ƃ���A�O����B�����h���w�߂ɂ���č��ꂽ�����ł��������Ƃ́A�u���c��N���q�ق�ԁA���h�̎Ғ���V�k�����ʂ�]���v�Ɓw���ԌÐ��x�ɂ���ʂ�A���q�{�̖ŖS�Ɠ����ɒ��������U���Ă��邱�Ƃ�����m���B �M�j�Ȍ�����ԋ������X�؏��̂ł��������Ƃ́A���ԋ�������(���͌��s�V��)�ɂ��Ă����X�؍��G�̕����ɂ���Ă킩��B���̕����́u���ԁv�Ə����ꂽ�����ŌÂ̕����ƌ����A���a�O�N(��O�l)���̂��̂Ɛ��肳��Ă���B���G�͖k���̐b�ŁA�쒩�Ɛ���Ė�����N(��O���)�ɐ펀�������ɍ��G�ɔ�肳��A���̂Ƃ��Z�\�l�ł������B���ɉƂ͐M�j����ł���B ���̒������ɋ߂��A�ߍ]���ʂ�Ƃ��ߍ]�����̖����c��̂͋����̂���Ƃ���ŁA�ߍ]���ʂ���s���Α��͐�ɏo�āA�Ί݂͈˒m�ł���B�˒m�͔w�ɓΔ��R(��O�܂�)���Ă��邪�A�u�g�r�I�v�́u�I�v�́u�z(��)�v�ŁA�Δ��́u��щv�A���Ȃ킿�u�̂낵��v�ł��������Ƃ��l������B���Đ��J�������ɕ����O��R(���ろ)�����Ԃł͍ł������A�Δ��R�Ƃ̈ʒu���炢���Ă��u�̂낵��v�Ɋi�D�ŁA�����Ε����̐_���Ղ��Ă���B�l���Ă݂�ƁA�����Ƃ����̂��펞�ɂ͓`�B�̎�i�ł��������B ���@��{�ԉ��~�Ɍ�q�����{�ԏd�A�̒풼�d�́w���؎s�j�j���W2�x(���~�R���~�@���`��)�ɂ��ƁA �����i���N�㌎�\�O���A�d�A�̒�O�Y���q�咼�d�@�c���@�𗳂̌���蓖���ɔ��З���d�A���@���ω����ɋ����ށA��������^�ɂ�����A�A���d���d�A�̘Y���z�q���ƋL���聄 �Ƃ���A���d�͍��X�؈ꑰ�̈˒m(�z�q)���ł������\��������B�˒m�ɂ͍��{�Ƃ̗�̂悤�Ɏl�ڌ������`���鋌�Ƃ�����B �܂��A�����̒����t�����Z���A���J�������𒒂��Ƃ����юR���ɂ��A�V���O�N(��O�l)�v�̍��X�؉��삪���������S���̈�ƂƂ��Ė����Ƃǂ߂Ă���B����̗��ɂ͌������Ƃ������͌��Ƃ������䂩��̖����c�邪�A��������X�،����ł������\�����̂Ă���Ȃ��̂ł���B�@ |
|
|
������
��1�@���ԋ������X�؎��̏��ǂƂ���l���͑����A�Ⴆ�Ό��̗��j�Ɩk�����ꎁ���w�����G�j���x�ŁA�u���Ԃɂ͍��X�ؐM�j�����J�����[�����ޏ�������B���̓����G�`�̑��̐M�j�ɍ��ԋ��^���Ă����̂ł���v�Əq�ׂĂ���B ��2�@���B�͍葑�������������Ɂu��h�ߑT���u�\�����]�܈ʏ�s���猹���b�j�@�助�i�m���r�@�O���O�Nᡓ����@�����@��m�@���c�@�����t�@���L��v�Ƃ������Ƃ����B(�w�V�ҕ��������y�L�e�x) ��3�@�����@�͂��ƓV��@�ł������̂Ŗ{����t�ƂȂ��Ă���B�Ëg�O�N(��l�l�O)�ɑ����@�ɉ��@�����Ǝ��`�ɂ���B�����@�̔����i�_�瑶�����ԗ����@�̊J�R�ƂȂ����B���̑m�͑��ɂ������̊J�R�ƂȂ��Ă���B ��4�@�˒m�ƍ��Ԃ̈��ʊW�͑����A���̕��䎁�Ɖ��̂���Ƃ����Ԃɏ��Ȃ��Ȃ��B�V�c�h�z�K���_�Ђ̐V�c�Ƃɂ͕���Ƃ��炫���ȏ��u�V�c�������_�品���v�̕悪����B�吳��N�v�A��\��ƒ����ł��������̐l�̖����͌��h�̗�؉p�v�搶�̂��ꂳ��炵���B�܂����͌��́w�Âꑐ�x����A�V�c���b�q����̂��ꂳ�������Ƃ̏o�������ł���B ��5�@���J���͂��Ɩk���l�ܒ��̎��{���ɂ����āA���̍����Ђɑ��������A�{���͎���������Ĉ�{���ɂƂǂ܂����Ƃ����B���߂ɁA���̖ɋ߂����ݒn�ɍČ����ꂽ�Ɠ`����B ��6�@��j�E�L�j�͓����̖��{�̈ӌ��ɂ��������Ĕ�b�����B�Ƃ��낪���{�̕��j�ύX�ŋt�ɗ��߂ƂȂ�A�㋖����ď��̂������B�Ԃ��Ȃ��b�R��\���A�Ăѓ����̖����������B���̍��Ōo���ɏ]�������j�̒��q�d�j���펀���Ă���B ��7�@�w���ڕ����x�ł͉͍�d�̖��Ƃ���B ��8�@���̓����J�����r�g�̂��߂ɏM�͍��ɂ��͒��ɓ]���������ɂȂ������Ƃ��`���ɂ���B���@�̖@�y�ɂ���Ď��Ȃ����Ƃ����B ��9�@���c��N(��O�O�O)�̐��c�͖k���̔N���ŁA���G�̍s���ƕ�������B�܂��A���̋I�N���̔肪�{���R�̉����H�j�Ƃ̕�n�ɂ���A�������Ԃ��k���̊NJ��ł��������Ƃ��킩��B�@ |
|
| ���������ƍ��ԋ��@ | |
|
�����������R
�����Ɏc�鍲�X�؈ꑰ�̏��̂ɏ����̂�����B�w��ȋ��x�������N(���O��)�\�l���̏��ɁA �����������������R���r��J�����c�V�R�B���v�ёj�B���@�Ƃ���B���������������R�͍��̉��l�s�`�k�撹�R���t�߂������B���������k����ŁA���̒n�̐��c�J�����v�ёj(���X�ؑj)�ɖ������Ƃ������̂ł���B���̒n�͌����������X�؍��j(�ؑ]�`���Ǔ��̉F�����w�Ŗ�����)�ɔn�����Ƃ��Ď���������(�w�������y�L�e�x)�ŁA�w�����ƌn�厫�T�x(���c��)�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B ���`���k���S���R���ɍ��X�؍��j�ِ̊Ղ���B�u�����{�̐��Ȃ�A���͗��c�ƂȂ�B�ω����N�ɂ��Ɂu���j�����y�ыߗׂ�̂������A���̒n�֏\�]���l���̊ق����܂֎l�ʂɖx���߂��炵�ėv�Q�Ƃ��A�ꑰ�Z�p���Y�A���R���q��𗼖ڑ�Ƃ��A���쏯�i���ɐl�Ƃ���ূɂƂǂ߂��A���̐g�͊��q�ɂ���ċΎd����v�� ���R�ɂ͏����N��(��ꎵ��`���l)�A�����̖{��ɂ�荂�j�̕�s�Ō������ꂽ�Ƃ����O�������B���l�������w����1�L�����炸�̏ꏊ�����A���ݒn�͓����̉ӏ�����ڂ��ꂽ�悤�ŁA���C�Ƃ����m���u�������N(��O�ܘZ)���ݒn�Ɉڂ��Ē����v�ƌ��`�ɂ���B���͎��n��Ƃ���ꂽ�ꏊ�ŁA�����~�ƌĂԏ����߂��ɂ������Ƃ����B����R�^���@�ŁA��N���j������R�ɓِ��������Ƃƕ�������B �����{����������̂ő{���ĕ��������A��������܂������R�ŋ�`���_�Ƃ����K�ɏo�������B�ē��Ɂu���j�̔n�u���Â��v�𑒂����Ƃ���B���j���F�����w�̂Ƃ��R�悵�Ă������n�ł���B�����ɂ́u���Â��v�u���n�v�Ƃ���2���̖��n���������B���ł��u���Â��v�͔��Q�������炵���B���ߊ����i�G���o�w�ɂ����肱������]�������A�����́A����͎����̏�n������Ƒウ�āu���n�v��^�����B���̂��ƍ��j�����]�ɗ��āA �����q�a�A�������v�������ꂯ��A�u���]�̎҂͊������肯��ǂ��A���̎|���m����v�ƂāA���H(����(�w���ƕ���x) �ƁA���Ǎ��j�������߂Ă��܂����B����ō��j�͌i�G�Ɛ�w�𑈂��A��ԏ����ʂ������̂ł���B �����{�͋u�̒����ɂ����āA���̐��ł͋u�̏�ɏo�Ă��܂��A���̐藧�����ꏊ�Ɋق͍\�����܂��Ǝv�����B��`���_�͋u�̓�Ζʉ��ɓ����邪�A�t�߂͊J���ĕ���ł���B��`���_�����邩��ɂ͔n��͂��̂�����ł͂���܂����B���c�삪����Ă��āA�l�ʂɖx���߂��炷���Ƃ��\�ł���B �u�ꑰ�Z�p���Y�A���R���q��𗼖ڑ�Ƃ��A���쏯�i���ɐl�Ƃ�(�j�l�j�̕�j�����R�����̂��Ă���)�E����(���R�̌�L�炵��)�̂�������n���Ƃ��ĕt�߂Ɏc����Ă���B �w�����ƌn�厫�T�x��������^���Ă���B���j�͑j�̕��M�j�̏f��(�j�ɂ͑�f���ɓ�����)�ł���B�j�Ȍ�̖��̘Z�p�ł͂��������Ƃ����킯���B���A�Z�p���̐��R�_�Љ��N�ɂ��ƁA���̒n�ŋx�e���ꂽ���{�������Z�p�̔�(��ɋ��Ƃ���)�����������Ƃ���Ƃ����A���Ȃ�Â����납��̌Ăі��Ƃ��l������B �������ɂ͊ق̂��������R�݂̂Ȃ炸�A�����E�{���E�����E���R(���Ɖ��R�̈ꕔ)�ɉ����A�Ί݂̐���E�ܖ{�E��F(���X�̏�(���l�s�s�z��\�Ó�̊�����ł͂Ȃ�)���܂܂��B�@ |
|
|
���O�̏�
�X�ɘZ�p������쉺����ΏF�薾�_�Ђ̂���ؒ��Ɏ���B���̖��_�Ђɂ͐��J���̞����Ɠ����юR�̌����̒����ɂȂ鞐�����������B�w�������y�L�e�x�ɂ́A�u�����̐_�ސ�h�{�m���v�Ƃ���A���́A ����{��@���큠�C�@�@����@�T���@�@����@����i���@�@����@�F�j������r�@�@�菠�@���B�юR�@�����O�� �����Ő_�ސ�h���u�����́v�ł��邱�Ƃ����ڂ����B�����̂Ƃ͍��X�ؗ̂Ƃ������ƂȂ̂ł���B ���̏@�O��(���Ə�����)�̞����ɂ́A ����h�ߑT���u�\���@���]�܈ʏ�s���猹���b�j�@�助�i�m���r�@�O���O�Nᡓ����@�����@��m���c�@�����t�@���L�偄�@�Ƃ������Ƃ����B���J�ω��̞����́A ���c��h�߁@�����b�@�M�j�@�@��H�@���g���� �Əƍ����ĎO�̏����݂ȍ��X�̑��̂��������юR�̌����̒����t�ɂ���Ă��邱�Ƃ����ڂ���A 1�@������ 2�@���X�̑��̂��������юR�̌����̒����t �͑��݂ɍ��X�؏��̂ł��邱�Ƃ�⊮������̂ł���A����͂܂����ԋ������X�؏��̂ł��������Ƃ��ؖ�����L�͂ȕ��ł�����B�@���Ƃ��������Ƃ����A����������j�̌�ɑj�̖��������邪�A���j�͉��̂��������̂����Ŏl�j�̐M�j(�j�̕�)�Ɍ����ꂵ�Ă���悤���B���j���F����Ő�w�̂Ƃ��A���Z��j����^����ꂽ�Ɠ`���́u�ʉe�v�Ƃ��������Ő�̒��ɒ���߂��点���������B���v�̗��ł́A���j�͂��̖�����M�j�ɗ^���A���x�͐M�j�������悤�ɉF����̐�w���ʂ������B���j�͌Z�o����̉Ƃ̉��L�j(�M�j�̒��Z)��G�ɁA���q��(�M�j��)�̍s�����Ƃ��Ă���̂ł���B���̉Ƃ����s�ŖŖS���ĐM�j�����̉Ƃ��k�����ƂɂȂ������A�j�͎������̊O���ł�����A���������ɏ��̂����j�̌��j�ɂ������ƍl������B�@ |
|
|
���������̍��Ԏ�
�w��ȋ��x�ɂ́u���������R���r��v�Ƃ���A�J��͒��R�����ł͂Ȃ��A�ߌ���Ί݂��܂߂����X�؏���(������)�̍r�삾�����̂ł��낤�B �Ƃ���ō��Ԏs���̈�l�Ƃ��ẮA���̏������̈ꕔ�ɌÂ�������Ԑ��̏Z�����������Ƃɖڂ������B �i�\��N(��܌܋�)�k�����N����点���w���c���O���̖x�ɂ��K���ԁu�E�ѓ�S���A����������v�L�A�K���ԐV���q��u�E�ѕ��A�����ܖ{�v�L�Ƃ݂��A�r�ӑ��ł͉i�\�l�N(��ܘZ��)�A���Ԗ�O�Y�Ɉ��Ă��{�썶�ߏ���(���B�Õ���)�Ɂu�䓙�m�s�r�ӔV���v�Ȃ镔��������Ƃ����A�܂����̍��̌Õ����ɍ��ԖL���E���Ԗ�O�Y�̖�������Ƃ����B�u������v�u�ܖ{�v�u�r�Ӂv�̂�����̗̎傪���Ԏ��ł������炵���̂ł���B ���Ԑ������Ԏs�ɂȂ��A���͌��s�≡�l�s�r�Ӓ��A�܂��͉����M�B����Z�Ɍ����邱�Ƃɂ��Ă͊��ɗ�ؖF�v�����q�ׂ��Ă���(�w���Ԃނ����ނ����x��O�W)�B���̒��Ŏ��́A���ɐܖ{�̗̎���ԐV���q��ɒ��ڂ���Ă���B�V�c�h�ɐܖ{�Ƃ����������݂���̂ŁA����͐V���q�傪���ԏo�g�҂ł��邱�Ƃ��ؖ�������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂ł���B���Ԑ��̎҂����ԏo�g�ł��邱�Ƃɂ́w�����ƌn�厫�T�x�ł��q�ׂ��Ă���Ƃ���ł���A���������l�����Ƃ�B���A���ԋ������X�؎��̑��͂ɂ�����ŏ��̗̕��ł��������Ƃ��l����A�j�����R���̊J��Ɏ��|����Ƃ��A���Ԃ̏��̂���x���̐l�ށE�J�͂�h�������ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ����B�@���͍��Ԏ��Ƃ����͍̂��X�؈ꑰ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����l���Ă���B���X�؎嗬�͓Ɨ����������A�������o���̒n���𖼏���Ă���B���X�Ə̂�����̂ɂ͂ނ��떖���������̂ł���B �������̂����A���ݍ��Ԑ����ł������̂͒r�Ӓ�(���l�s�s�z��)�ŁA�d�b���Ō���Ɖ��l�s���ɍ��Ԑ���Z��A�����s�z��O��A���̖w�ǂ��r�Ӓ��ł���(�ق��j������l�A�����͈�)�B���ɂ͐��J�ƌĂ�鎚��������B �r�Ӓ��͒ߌ��������ŏ����̑Ί݂ɂ�����A���͂m�d�b�Ȃǂ̍H�ƒc�n�ƂȂ��Ă��邪�A���Ƃ͍L��Ȑ��c�n�т������悤���B�ߌ��삪�ɂ₩�ɘp�Ȃ��A�����̌Q�ꂪ�����P���Ă����B���̉��������낷�ƁA���ɂ͑傫�Ȍ�j���ł������A��Ȃ����ƂɌ�͉����̚��ɂ܂݂�Ă����B�y���Ɍ�����u�܂ŕ����Ɛ��ʂɊω���������B�����O�\�O�ω��\���ԎD���A����R�^���@�ŁA�n���N��͕s���������R�̎O��̖����ł������B�r�ӂ������̂ł��邱�Ƃ��������̂ł��낤�B���͎��ăg�^�������́A�ꌩ���Ƃ̂悤�ł���B��n�ɂ͍��Ԑ��̂��̂͂Ȃ��A�����E�g�c�E�p�c�E�O���Ȃǂ�����B�������͍��Ԃɂ����邪�����̉Ɩ�͍����B���̗{�q�ɕ������������Ƃ��킩�����B�߂��ɒ������Ƃ�����������A����R�^���@�ŁA��������ƎO����ł������Ƃ����B�����ɍ��Ԑ��̕�1���A�Ɩ�͊ۂɑ�̉H�A�䂪�ƂƓ����ł���B1�L����������ȒÉ@�Ƃ��������Ȏ��Ɏ���B�����ɂ͂��Ȃ苌�ƂƎv������Ԑ���n�ɁA�勝�l�N�̈���ɔ@���̐Γ��Ȃǂ��������B�������̉H��(�t�߂ɂ͉��̂���̉H�䂪�����B�������傾�����Ƃ������c�s�j����̉H�䂾�����悤��)�B�ȒÉ@�͑����@�ŁA���Ə����̉_���@���Ƃ����B�@ |
|
|
����k�����Ə�����
�_���@�����������̂͏��c���k���̉Ɛb�}���M�ׂŁA�������ł������B��ؖF�v�����u�M�B���{�s�̍��Ԏ������c�̉Ɛb�������Ƃ����̂́A�k�����G�����c�̐l���ɂȂ������Ƃ�����̂ł���ɕt���Y���čs�������Ԃ̕����ł��������v�Ɛ�������Ă���(���ݏ��{�s�ɂ͓�\������̍��ԉƂ�����)�B���G�������̏��ł��������Ƃ��l����ƁA���炭�͏����̂���̍��Ԏ��Ȃ̂ł��낤�B�����Ƃ��A���G���l���ɂȂ����͎̂O�A�l�̂���Ƃ�������A�������łɏ����̏��ł������Ƃ͍l���ɂ����Ƃ������������B���A���G�̊x���ɓ����錶�����c���̂���ɏ��̂Ă���̂ŁA���ڂ͏�傾�����̂����m��Ȃ��B��N�j��ƂȂ��ċA��(�i�\�\�N����ܘZ��)���A���߂ď��Ƃ��ē��邵�Ă��邪�A����ȑO�ɍ��ꂽ�w���c���O���̖x(�i�\��N)�ɂ́A�������ӂ̖{�����E�������E���R���Ȃǂ��O�Y�a(���G)�̏��̂Ƃ��ċL�ڂ���Ă���B�l���ŕs�݂Ȃ̂ɁA�ł���B���̎O�Y�a�͋C�̓łȐl�ŁA���T���N(����Z)�ɍ��x�͏㐙���M�̂��Ƃɐl���ɂ��ꂽ�B���M�͔ނ��������ĐՎ��ɂ��悤�Ƃ��Ă���(�����̗c���u�i�Ձv��^����)�B�Ƃ��낪���M�̋}���ŏ㐙�n�݂̌i���Ƃ̑����ɂȂ�A�O�Y�a�͓�\���A���Ŏ��n���ĉʂĂ��B���j�ő�����݂ł������Ƃ������Ƃł���B ���̂悤�ɕ��ƂƂ��Ă̍��Ԑ��͏������ӂɋ������f����Ă���B�@ |
|
|
�����ԋ��̍��X�؎�
���ԋ��������̍��X�͒�j�ł��낤�B��(�G�`)�ɂ��������ďa�J�ɗ��������A�����炭���N���������j�̔ނ����l���āA�a�J�d���͈�傩��ł����������Ǝv���B�n�N�Ŏl�l���q�̂���G�`�ɂ����������Ă����Ă���̂ł���B����̒��j������Ă����͂��͂Ȃ��B���̖��ł���Ώ��̂̋�(���ԋ��͂��̂悤�Ȉʒu)��C���Ă悩�����̂��B�a�c�`���̔�����̉��܂ɍ��X�ƍ��ԋ��̖��������Ȃ��̂́A���łɍ��ԋ��������I�ɂ͍��X�ł��������Ƃ������Ǝv���B�a�J�����ԋ��ƌĂԂ̂͂��̊Ԃ̎�����������̂ł��낤�B ���ԂƂ������_�������͂Ƃ������Ԏs���ɂ������A���Ԃ̖��̋N����͑��̍����_�Ђ������ł���悤�Ɂu�������聁��̌ぁ�N���̖��v�ŁA�鎭�_�ЎВn�������A�鎭���_�Ђ��{���͍��Ԗ��_�ЂƌĂ�Ă悢���̂ł������Ǝv��(�u�鎭�v�́u���v���B����������Ӗ����A���̖��̐�͈ɐ����╽�˂ȂǂɗႪ����)�B���X���u�������聁���ԁv�Ɋق�u���č��ԋ������z�����̂ŁA���ԋ��̓�\�������̒��炪�鎭���_�ɂȂ����̂ł���(�u���ԁv�Ƃ������͑����ނ��닽�̖��ł������Ǝv����)�B ���\�O�N�̗鎭���_�̞����ɍ����ꂽ�����ɂ͍��ԋ���\�������̖����S�Ă���B �@�@�@���ԓ��J���@�@���ԏh���@�@�V�c�h�� �@�@�@�l�b�J���@�@�@�V�ˑ��@�@�@�@�镔�� �@�@�@����@�@�@���@�@������ �@�@�@���{���@�@�@�@���R���@�@�@�@�����q�V�c�� �@�@�@����@�@�@�@���m�ӑ��@�@�@���a�� �@�@�@��a���@�@�@�@�������@�@�@�@�c���� �@�@�@�哇���@�@�@�@��ߊԑ��@�@ ���ߊԑ� �@�@�@�����J���@�@�@�I�����@�@�@�@�㍡�� �@�@�@�����@�@�@��V�c���@�L�m�X�� ���Ԃ͏��̒n(���ԋ�)�̖��ŁA�Z�������ɂ͓���݂̂Ȃ����̂ł��������A�Â��͑��Ƃ��Ďg�p���ꂽ�`�Ղ��Ȃ��B�ߐ��O���̈╨�ɂ͍��ԋ����ԓ��J���Ƃ����ԏh���Ƃ����č��ԑ��͂Ȃ��̂ł���(����Ɏ����č��ԏh���ɑ����č��ԑ��Ƃ�����悤�ɂȂ�����)�B ���X�؎��̐��i���݂�ƁA�n�ƒb��A�����Đ_�Ђ�����B���X�͖{���_���̏o�ł���炵��(���X�����X�M�͌�˂̈ӂŁA��˂���鐢�E�Ƃ���)�A�_�Ђɍ��X�؎��̖��������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B���͂ǂ��Ȃ������A�߂��͑�R�J�~�_�Ђ̐_������X�؎��ł������B �ق̋߂��ɔn��Ǝ��Ɛ_�Ђ�݂���B�܂������t���ĂԁB���ꂪ�ނ�̂�肩���ł���B���Ԃł����J�𒆐S�ɂ���炪�S�đ��݂���(�n��ɂ��Ă͑O���L���̐��₪�n���Ƃ������Ă����Ƃ������ƂŒm����)�B �����ŁA���ɋL���ꂽ�����ɍ��܂܂�Ă��邱�Ƃɍ��_�̂������Ƃ�����B�������ɓ������_�ЂƂ��������ȎЂ����邪�A���̎Ђ̌Â����D�ɁA�u�������N(�����)�u��L�j�c�c�v�Ƃ������Ƃ���(�w�V�ґ��͕��y�L�e�x)�B���ォ�炢���čL�j�͍��X�؍L�j�ł��낤�B�Ƃ��낪�t�߂̉Ƃ̕\�D������ƒ����݂͂ȍ���(�C�V���s)�ɂȂ��Ă���B���R�C�V�������̂̂͂��H�@�Ƌ^�����̂ł���B���ƂŒn�}���悭����ƁA���݁A������l�Z���������f���Ă��邪�A���̞��`�̂킸���Ȉ�p������������Ȃ̂ł���B�������ԋ��Ȃ獲�X�؍L�j�ł����̂��B�@ |
|
|
����������̍��ԋ�
��������(��������)�u����v�̍��X�ؓ��_�����ɉƂɌ���ĈА����ӂ�������A�q�̍��G�A���̍��F�Ɏ����Ă������������B�������ĊԂ��Ȃ����m�̑嗐���n�܂�B���X�؎嗬�͋��ɁA�Z�p�������ɕ�����đ����A�܂��܂����͂��������ƂɂȂ����B ���ԋ��̏������X�؍��G�̕���(���a�O�N����O�l���Ƃ�����)���A�V�˂̒������Ɏc��A���Ԑ������a�ɑ����Ƃ����̂͐��c�J��Ŏx�z�̒��S���k�ֈڂ����̂ł��낤�B�����̍��̍��Ԓ�n�͐��c�J���̉\�ȏ�Ԃł͂Ȃ������炵���B ���i�O�N(��O��Z)�ɑ�������(�֓��Ǘ�)���������ɗ^�������g��͍��ԋ��������̏����ɓ��������Ƃ��������̂ŁA���̂��덲�X�͍��ԋ����������̂��낤�B �����i�t����Ƃ̗��㐙���ɖd�����Đ�����Ƃ��A���̍���ƂȂ����̂�������ł������B���̂Ƃ��i�t���͈镔(���͌��s)�ɏ��z���������c����̍U���ɑ����ė��邵���Ɠ`�����Ă���B�镔�͉��a�Ɏ��߂ŁA���a�Ə����̗����Ԏ����ĉ����Đ�����̂��낤���B�镔��Ղɂ��āw�V�ґ��͕��y�L�e�x�ɂ͎��̂悤�ɂ���B�@�������n���ڂɂ���(���̐���̕��Ɍ@�V���A��d�@���̏�������A�����Ղ̈▼�Ȃ�ׂ��Ɖ]��)�������R���㐙���̘V�b�����i�t�d�����N���A�㐙���Ɨ\���ɋy��������ɌR�����Ēu�A�����̏��X�ɂč���ɋy�ѕ����\�N(��l����)�O���i�t�ŕ����ē��鐋�ɗ����ɋy�т��Ȃ聄 ���̕����̂���(��l�Z��`���Z)�̍��ԋ��̒n���E����D�����[�̊ق��S�⎛�̒n�ɂ������B��������̓����̒��S�����ݓ��J�̗鎭�E���̒J�ɂ��������Ƃ��������̂����A���̔��䎁�ɂ��Ă͍���ڂ炩�łȂ��B���a����c���ɂ����Ă����Ƃ����邪�A���X�ł͏d�j(�M�j�̒��j)�̌���ɔ��䎁�̖�������(�ւ���Ɍ��˂��g���B�S�⎛�̎���͌O��)�B����������̓y������A�֎R���͈�ՂƓ����ňɗ\�͖̉쎁�̏o�Ƃ����B�ɗ\�̎�삪���X�ؐ��j�ł��������Ƃ͋��R�ł��낤���B�@ |
|
|
�����j�̓}
�j���̒������֍s�����̂́A�Z�E�����X�ؐ��Œh�Ƃ̑���ɍ��Ԑ�����l������ꂽ(�w�S�����@�����x)����ł���B�s���Ă݂�Ɩ�O�𓌉����������Ă��āA���ւ͌א�����n��˂Ȃ�Ȃ��B���`�ɂ��ƁA���̏Z�E�̑c��͍j���\���R�̈�l�A������T�Ƃ����āA�̂����X�ɉ������A�o�Ƃ��Ď��̊J�R�ƂȂ����Ƃ����B�V���N��(����O�`���)�̑n�����������B�����Ŏv���o���͔̂��O�̎����ŁA����͕��ƒǓ��̐킢�ō��X�ؐ��j(���j�̌Z)���n�ŊC��n���đ�������āA��������u�̂��A�n�ɂĉ͂�n���������Ƃ��ւǂ��n�ɂĊC��n�����A�V���k�U�͒m�炸�A�䂪���ɂ͊��̗�Ȃ�v�Ɛ��j�Ɏ������y�n�ł���(�w���ƕ���x)�A�������͍��X�؎x���Ƃ��Ďl�ږ��p���Ă���B�j���̎������͓V���̂���A���O���獲�X�̌̒n�𗊂��ė����ꑰ�ł��낤���B ��Ɍ���u���Ԏ��v�́A�勝���납��̂��̂ŁA��n���̈�p���߂Ă��ėL�͎҂ł��������Ƃ��킩��B�ۂɌ��O����ł���B���ԂłȂ����ԁE���Ԃƍ��ނ��̂�����A�Z�g���E�������Ɖ����̂�����̂�����B���̂��鏤�Ƃ������̂ł��낤�B���������ԋ��Ɍ��т�������̂͂Ȃ��B �����Ŕ��Z�̍��Ԏ��ɐG��Ă��������B ���Z(��)�̍��Ԏ��͐�Ӓ��ɑ���(��\����)�B������̒��j�҂��ɖ₢���킹���Ƃ���A 1�@���Ԃ́u���܁v�łȂ��u����܁v�ƌĂԁB 2�@�R���͂悭�킩��Ȃ����A�c��͐�(���R���H)�̂����肩��ߍ]���o�ĈڏZ�����炵���B 3�@�Ɩ�͊ۂɋk�B �Ƃ������Ƃł������B 1�@�ɂ��Ă͗�ؖF�v�����w���Ԃނ����ނ����x��O�W�ɏ�����Ă���ʂ�ł���B�ʂɍ��n�Ə�����������B�n����n���ɂ��ƂÂ����̊����\�L�́A���ʂƂ����ĉ��ɏ]���Ď��������ĕ\�L�����u���ԁv���u��������v�̕\�L������ł���B���Ԃ��u����܁v�Ɠǂ݁A���邢�́u����܁v(���l�Ɉ�Ⴊ����)�ƓǂނƂ��Ă��A���Ƃ͍��ԁ��u���܁v�Ǝv���B 2�@�ɂ��Ă͋����̂���Ƃ���ŁA���X�؎��ɂ͋ߍ]��ƂƂ��ɔ�������̂���҂������B�܂����O�ɂ͑O�L�������̎���������B(���X��)���������ł������悤�ɁA���X�ɏ]���Ď����ɂ��������Ԏ������X�ɏ]���ċߍ]�ɋA��A�₪�Ĕ��Z�ɏZ�ݒ������̂ł͂���܂����B���Z�����X�̐F�̔Z���y�n�Ȃ̂ł���B 3�@�Ɩ�ɂ͎�|����͔F�߂��Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���ԋ����O�ɏo�����Ԑ��ʼnƖ���قɂ��鑰�́A���ꂼ�ꂩ�Ȃ�Â�����ɕ����ꂽ���̂��Ǝv�킹��B �@ |
|
|
�����a�̍��Ԏ�
���a�ɂ͐�����(�����@)�������đ����̍��Ԑ��̕������B���y�j�Ƃ̍��Ԕ��s�����̕�������ɂ���A�����ɂ͎����B�M�ŏ������Δ������B���Ԑ��̕�̉Ɩ�͂�������ۂɖ؉Z�ł���B���{��̐Γ��ɁA ���ÊՂ̋��J�˂ɖ���c��̉i���̉�����F�O�����̔�ɍ��ݕ�{�ƂȂ��� �Ƃ���A���؎s�����̍��Ԗ^�̖�������̂ŁA���؎s�̍��Ԏ��͉��a����̈ڏZ�ƒm���B���`�ɂ��Ɠ����͌c�����N(��܋�Z)�ɓV���@�����Z�E�V�R���_�̑n���ɂȂ�Ƃ����B�t�߂ɔ����{�ƁA���̂��ɕs����������B�s�����͑��͌��s�̏d�v�������ŁA�����{�̕ʓ�����@�̖{���ł��������A����ɂ͍��ԑ��̑�V�ƐV�c���̎����@(�z�K���_�Ђ̕ʓ�)�̏Љ�Ŋ��q�̌㓡���߂����ۋ�N�ɐ��삵�����Ƃ��ٓ��ɏ�����Ă���Ƃ����B���ԓ��J���ƐV�c�h�����O(���a)����͍��ԑ��E�V�c���ƌĂ�Ă������Ƃ��킩��B�@�V���@�͌������w���Ԃ������a�ɂȂ�B�w�S�����@���Ӂx�ɂ��Ɩ����O�N(��l��l)�A������j�̏��R���吆�オ�J����Ƃ����B���쎁�͓����G���n�Ƃ������A�F�s�{���ƂƂ��ɗ��j�ɉB���ꂽ����������炵��(������j�����̂Ƃ������Ƃ�����)�B�R��������ӂꂽ���Ɍ����邪�w�����ƌn�厫�T�x�ɂ͒�j���j����͎R�����c�Ƃ���B���̎��͖k�����Ƃ̖���S�������ɍċ��������̂Ƃ����A��S�̕����n�ɂ���B���͎����S�ɍl���邩��u��S�����̌ܐ���A�ɋA�˂��čċ������v�Ɠ`���Ă���(�w�S�����@���Ӂx)���A���Ƃ̖��Ȃ��͑�Β�v�̖��ł��낤�B��N���Ԏs�̗��j���D�̃T�[�N���u���j�U���̉�v�Ŕ����q�s��K�˂��Ƃ��A��Ύ��ِ̊Ղ������Ƃ����i�ю��ɗ���������B��v�̕�Ŕb����m�F�������A���b���̑�Ɠ����ł���B�b��̑�͂�͂�G���n�Ƃ����̂ō��쎁�Ƃ̂Ȃ��肪����̂��낤��(�ߍ]�ɂ��I���S��ɕ������X�؏����̑������A���͋j�[�A�ւ���Ɏl�ڂ��g��)�B �����ɂ��\��ȏ�̍��Ԏ��̕悪����A�Ɩ�͊ۂɖ؉Z�ł���B���ӂɂ����Ԃ̕\�D���ڂɂ��������Ă����Ε��ƓI�Ȃ��̂͊������Ȃ������B |
|
|
�����Ԃƍ��Ԏs��
�鎭���_�Ђ̍O����N(��܌ܘZ)�̍Č����D�ɂ͑��B�c�q�S�a�J�����ԋ��Ə�����Ă���B�c�q�S�͍����S�ŁA�a�J���͏a�J���̐��͌����������Ƃ��������̂ł��낤�B���ԋ��͂��̒��ł̍��X�؏��̂ł��������A�a�J���͑��͐썶�݂����ł͂Ȃ��A�Ëv��܂ł̉E�݂��a�J���ł������B�a�c�̗���̏a�J�������ꂾ���͈̔͂�ۂĂ�͂��͂Ȃ��A���X�̐��͂��E�݂ɂ��y�ƍl����̂����R�ł���B���������Ă̈˒m(���q���ߍ])�ł���A�юR�̌��������t�ł��낤�B ���a��\�O�N�A�Z���̖҉^���ɂ���č��Ԃ͑��͌�������Ɨ��������A�������ė��j�����ǂ��Ă݂�Ƃ݂݂��������Ƃł͂Ȃ��������Ǝv���B�����������j�𗝉�����҂�������A�ނ��둊�͌����܂߂āu���Ԓ��v�ɉ��̂���^�����N�����������ł������B���͈͍̔͂��ԋ��ł���A���Ђ͗鎭�ɑ��݂���̂ł���B���́A�鎭�̒n�����Ԃ̖��̋N����ł��������Ƃ��Y����A�S�⎛���u���ԎR�v�Ƃ��邱�Ƃɂ����A���ł���ȏ�(���J�������͗鎭)�ɂ���̂ɍ��ԂȂ̂��ƕs�v�c����҂������̂��s�v�c�ł���B�@ |
|
| �����ԋ������L�@�@ | |
|
���N(���l��)�Z���ܓ��A�����k�������͎O�Y�ב��E�����Ƃ��̈ꑰ��łڂ����B���̂Ƃ���]�L���̎O�j�ŁA���b�S�ї���(���؎s)��̂��Ă����G���́A�Ȃ̎��Ƃ��O�Y���ł����������A�L���ȗ��ǍD�ȊW�ɂ������k�����̗U����U����ĎO�Y���ɉ�������B
�L���̎��j���L�͗����̉��B�����ɏ]���Č�����A�H�O�����䋽�������Ē��䍶�q��Ƃ����A�q���͒��䎁���̂��đ�X�֓��]��O�̏d�E�ɂ������B���̕���̂���͎q�̑G�E�d�̎���ŁA�ޓ��͓��R�k�𑤂ɂ��ĎQ�w�����B ����d���萨��A��ĉ��~���o�Č䏊���������r���A�f���ї�����(�G��)�̌R�Əo���킵���B�������A�ї��͎O�Y�̐w�֒y�������l�q�����āA�d�͌��t��������̂��~�߂Č䏊���������Ƃ���(�w�V�ґ��͕��y�L�e�x���q�����l)�B �O�Y�͔s��A�G���Ƃ��̎q�O�l�͎��Q���ĉʂāA���̖ї��͐₦���B���̂Ƃ��A�z��̍������ɂ������q�̌o���ɂ���Đh�����Ėї��̖��͎c��A���ꂩ����|�̖ї���������āA���m�g�j��̓h���}�ɂȂ��ĕ��f���̌��A�Ɏ���̂ł���B �ї������L���ɂȂ��āA��]�L���̌n���͂�����ɒ��ڂ��������A�L���̌���p���ŗv�E�ɂ������̂͂ނ��뒷�䎁�̕��ł������B���L�����߁A�G�E���G�E�@�G�Ƒ�X���֓��]��O�ł��������A�O�o�̑d(�G�̒�)���Z�g���]��O�߂Ă���B �`�����璷������������ɏo�����̂ɂ͗��R�������āA���ԋ��̖��̏��o�Ƃ�����A�V�˂̒������ɂ��Ă������̍��G�Ɂu����v�ƌ��̒NjL�����邱�Ƃɂ��B�܂��A����ɂ́u�����O�N�v(��O�O�Z)�Ƃ����NjL������(�w���Ԃނ����ނ����x��O�W�ł͍����s���Ƃ��Ă���)�B �����͎��̒ʂ�ł���B �@�@�@���ԋ������������@���㏊��\�t��@�틻�s���� �@�@�@����v�V�����S�V���@���K���c����V��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X�ތ� �@�@�@�@�@�u������v�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u����v �@�@�@�@�@�Z������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���G(�ԉ�) �@�@�@������������T�t ���Ԏs�ŏ����ꂽ�����A���Ƃ��u���B���J���Ø\�N�I�����Ɋւ���Q�l�����v(���Ԏs�ی�ψ���E�r41)�ł͍��G�����X�؎��Ƃ��Ă��邪�A�w�_�ސ쌧�j�x(�ʎj��1)�ɂ��ƍ��ԋ��̏��̈��g�䍂�G�Ƃ��Ă���B���j�ł͒NjL�̕������̂܂܂ɍ̗p�����炵���A�N����������N(���̔N���͂Ȃ��B�����炭�NjL�̌�������L������)�Ƃ��Ă���B ���G�͍��X�؎��ł���̂����䎁�ł���̂��H�@ �NjL�̔N��͐M���ł���̂��낤���H �u������v�̍����́H ���̕����̔N��͂�����ɔ�肷�ׂ����H(�w���Ԃނ����ނ����x��O�W�ł͈�O�l�N���Ɛ��肷��)�B �N��̎�|����ɂ͌������́u������T�t�v�ł��낤�B�O�L�u���B���J���Ø\�N�I�����Ɋւ���Q�l�����v�ł́A ��������������T�t(35���Z�E�f��)�Ƃ̊֘A�ɂ����ĉ����ܔN(�\�������f������O�Z�Z)���邱�Ƃ͂قڊm���� �Ƃ���B�Ƃ��낪�w���q�s�j�x(�Ў���)�ɂ͌������̗��m�͓�\�O��܂ł����L�ڂ��Ȃ������B��������߂āA�����ɍڂ����Ă��������ɁA������T����������͂��Ȃ����߂����Ă݂��B�T�����͎��̑O���̋u�ɂ����āA����Z���Ƃ��Ă��������ł���(�����⑰�̕����Z��ł�����)�B�L�ڂ������āA����͓�\���ِ����̓����Ƃ������B �����ŋC�t�����̂́A�������Ɍ������鎁���̌Õ����ł���B�������������Ȃ�Ƃ����̖����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�������Ă����Ǝv���B�K�����Q�����m�[�g�Ɏʂ����������̂ŁA�����m���߂邱�Ƃ��ł����B �@�@�@�@�@�@�@��i�E�� �@�@�@�������������������� �@�@�@���͍����ԋ����c������ �@�@�@�@�@���� �@�@�@�@�@�L�ʏ��@�@�@�� �@�@�@�E�ד����̔@����v�����V�� �@�@�@�@�� �@�@�@�@�@���i�O�N�\�\���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q�����b�@(�ԉ�) ���̕����͑��͌��s�Ɍ�������ŌÂ̕����Ƃ��Ďs�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă�����̂ł���B���́u�����v�Ƃ͂ǂ��������Ȃ̂��B���ǂ��Ă݂�Ǝ��̂悤�ł������B �������f���̓����B�f���͒�a���N(��O�l��)�Ɏ��₵�Ă��邪�A�c�c�� �����ɑf���̖�������āA�����������ƒ������̊W���������B���A���Ԏs�̎����Ƃ͖v�N������Ă���B����ł����Ɓw���Ԃނ����ނ����x��O�W�̍��G�����̎��㐄��͌��Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��A���G�������f���̎��̓�A�O�N�O�Ƃ��Ă݂�ƁA�×��N(��O��)�ɐ��܂ꂽ�Ƃ������X�؍��G�͏\�܍��炢�ɂȂ�B�����Ƃ��NjL�ɂ���悤�Ɍ�����A�O�N�ł͎O�A�l�ŁA���̂悤�ȉԉ��͖������낤����NjL�̔N��ł͕ʐl�Ƃ��������Ȃ��B�Ȃ��A�f���̖v�N���猳����A�O�N�ւ����̂ڂ�Ə\�l�A�ܔN�ƂȂ�A�����܂ł����̂ڂ��đf��������ɂ����Ƃ͍l����B�����O�N������\�N�ɎO�\�ܑ�ł���B���ς���ƁA���O�N�ɖ����Ȃ�����E�����̔N���łُ͈�ɒ����͂Ȃ����낤���B���������̊ԁA���q�͖��{�̖ŖS�⒆���̗��Ƃ��������̂��Ȃ��ɂ������̂ł���B ���ɁA���䍂�G�Ƃ����l���̎��݂�T���Ă݂�B�w�����ƌn�厫�T�x�ɂ��w���ڕ����x�ɂ����䐩�ɍ��G�̖��͌����Ȃ��B�w�����L�x�ɂ�����𖼏��l���͂��т��яo�Ă��邪�A���䍂�G�Ƃ����l���̓o��͂Ȃ������B�Ƃ��낪�A�{���łȂ��ċr���̕��ł��ꂪ���������B�{���͊��\�O�ŁA�����k�����s�̗��ŋ�킵�Ă��鑫�����`�������邽�߁A������҂��������������։����đ��͐�Ŏ��s�R�ƑΛ������ʂł���B �����ߏH�̋}�J��ʂ肵�āA�͐��݂�N������A����(�����R)����n���͌��炶�ƁA����(�k���R)�������f���āA�蕉���������n���x�߂āA�s�R�̎m���W�߂�Ƃ����鏈�ɁA��ɓ���č��z���(���t��)���]�R�ɂď�̐���n���A�ԏ��}����͂͒��̐���n���A���X�؍��n�������_�ƁA���䎡������́A���̐���n���āA���Ƃ̐l�̌�։��A�����ɕ�����āA�����Ɏ����ǂ��ƍ�遄 ���X�؍��n�������_(����)�͗�̂���喼�ŁA���X�؍��G�̕��ł���B���䎡������ɂ��ċr���ł́A ���i�䎡�����㍂�G���B�u�������㍂�G�����V��A���l������Ɓv�]�X(�匰����A�������A�\��A����)�� �Ƃ���B��ɂ����䎡������A�i�䎡�����オ�o�Ă��邪�A�{���ł͍��G�Ƃ͂Ȃ��A�匰�������i�䎡�����㍂�G�Ɩ��O�܂ŏ����Ă���B����̔N�ォ�炢���āA���G�����̒NjL�͂��̍��G���w�������̂Ƃ��Ă悩�낤�B ���X�؍��G�ɂ��ẮA�w�����ƌn�厫�T�x�̋��ɗ������ɁA�@���\�㍂�G�A�����O�j�A���ɌܘY�A���q��сA��������A�\�o��A���t���l�A�����ʓ��A�]���s�A��V��v�A�]�܈ʉ��A�@���������쓱�B������N(��O���)�����\������c�펀�A�Z�\�A��ю��� ��A��I�@���̍��G����������ł��������B�Z�\�l�ΐ������邪�����ł͘Z�\�Ƃ��Ă���B����ł����đf���̎����a���N�Ƃ�����G�͏\�l���炢�ɂȂ��Ă��܂��B��͂荂�G�����X�Ƃ���ɂ́A�f���̖v�N��(�u���B���J���Ø\�N�I�����Ɋւ���Q�l�����v�̂悤��)�����ܔN(��O�Z�Z)�����ɂ����Ă����Ȃ��Ɩ����̂悤�ŁA����Ȃ獂�G�͎O�\���炢�ɂȂ�B���̉����ܔN�͂ǂ�Ȏ����ɂ�����̂ł��낤���B �Ƃ���ŁA�����J�ˎR�����R���̈ē��ɁA�u���̂�����ԋ��Ə������(���������E���|�̎q�����G�̕���)�v�Ƃ���̂������B����������������̒��قǂ�����ł���B�����̎q���Ɏ��|�����G���w�����ƌn�厫�T�x�w���ڕ����x�Ɍ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�u���ԋ��Ə������v�Ƃ������Ƃ����ԋ��̏����Ƃ������ƂȂ�A�O�L�������̎�������ɂ��łɁu���͍����ԋ��v�Ə�����Ă���̂�����A�����̎q���ł͖��ɂȂ�Ȃ��B �����̗��Ƃ����̂́A���c��N(��O�O�O)�܌��A�V�c�`��R�ɍU������č����ȉ��̖k����傪���c���Ŏ��E�����Ƃ��A�Ђ����ɐM�Z�ɓ���Ă��������̎��j���s���A������N(��O�O��)�����A�z�K���d��ɗi����ĕ����ɍU�ߓ���A�������`�R��s���Ċ��q�ɓ������킢�������B���̂Ƃ��A���`�݂͂�����o�w�A���ԋ��̈�т͐�ɂ܂݂ꂽ�B���`�͒��c�s�̐����_�Ђ̒n�Ŏ��s�R�Ɛ���Ĕs��A���q�ɑނ��ē����Ƃ��A���`�z���ɂ���������Ӌ`���́A���`�̖��Ō�ǐe�����h�E�����B���s�͓�\�ܓ����q�ɓ���A�u�֓��̎����тɍݍ��̔y�݂͂Ȏ��s�ɂ��������A�V���͂ӂ����т������������̂悤�ł������v�Ƃ����B���̑����͒��`�������Ď��s���ߐ��Α叫�R���Ǖߎg�ɔC������邱�Ƃ�]�������ꂸ�B�����͒������܂������s���o���A���������Ɏ��]���Ă������m����������ɏ]���A��R�ƂȂ��������R�͎O�̖͂�Œ��`�R�ƍ����A���x�̐킢�Ŏ��s��j��A�����\����A���q�֍U�ߓ������B���s�̊��q���e�͂킸����\�����܂�ŏI������B����Ӌ`���͎O�͂̐킢�Œ��`�̐g����ƂȂ��ē����ɂ����Ƃ����B �����͏���֓��Ǘ̊�̎q�ŁA����S���Ȃ��Ă܂������ۂƂ����Ă����������Ǘ̐E�ɂ����邽�߁A�厡�Z�N(��O�Z��)�܌��A���X�؍���(���_)���g�҂Ƃ��Ċ��q�ɉ������B������O�A���a�O�N(��O�l)�ɂ́A���X�؍����͑��͏㑍�����ߍ]���̏��̈��g���Ă���̂ŁA���X�؎����܂����͂ɏ��̂�ێ����Ă������Ƃ��킩��B�����͌��C�̒j�ŁA���̈ꐶ�͐헐�ɖ�����ꂽ�ꐶ�������B����Ɏ��M�����������́A���s���y������悤�ɂȂ�A�N���N(��O���Z)�ɂ͊֓��̌R�������ċ��s�ƌ����o���n���ŁA�����㐙���t��������|�߂Ď��E����Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ��������B �w�_�ސ쌧�j�֖����V�R�L�O���������x�掵�S�ɂ��ƁA�u�N��N(��O����)�\��\�����A�����_�ސ�A�i�쏔�Ïo���D�̔��ʑK�����q�œ������c���g�X�v�u�i����N(��O����)�����Z���A�����F�����g�V�e�k�S�����ۃm荒n���߉������{�Ɋ�X�v�u���i�O�N(��O��Z)�\�\�����A�������͒��������V�e�����̓������ԋ��̒n�����g�Z�V���v�Ȃǂ�������B�����͂���������X�؏��̂܂��͏����Ƃ��Ă̊֘A�̍l������n�ŁA�����̑O�ɍ��X�؏��݂̂͂Ȏ���ꂽ���̂Ǝv����B�����͉��i�ܔN(��O�㔪)�\�ꌎ�l���A�N�l�\��Ŗv�����B�@ �@ |
|
| �������J�R�E���叟���̐l���� | |
| ����@�͂��߂Ɂ@ | |
|
�����́A�ޗǖ��E���������ɉ��썑��ɗ��R(���E�Ȗ،������j�̎R�B�����R�Ɨ���)���J�����Ƃ��Ė������m���ł���B�����F��S�ɐ��܂ꂽ�����́A�����R�ւ̓o�������݁A�O�x�ڂɂ��Ă悤�₭�����A����ɎR�[�̓��(���E���T����)�̔Ȃɐ_�{�������ĂďC�s�����Ƃ����B���̌�A��썑�̍u�t�ɔC�������ƂƂ��ɁA���썑�s��S�ɂ͐��ɂ��������ė����O�����A�܂���鯂ɍۂ��Ă͓����R�ɓo���ċF�J�������ƂȂǂ��`�����Ă���B
�����Ɋւ���j���͏��Ȃ��B���g�̒���͌��������A�܂����炩�̒�����Ȃ����Ƃ̓`�����Ȃ��B������̎j���Ƃ��ẮA�w�ՏƔ�������W�x�Ɏ��^�́u���叟���R������Č�����������тɏ��v(�ȉ��A�w�����蕶�x�Ɨ���)������B����͍O�m�ܔN(814)�A�O�@��t��C(774-835)�̍�ŁA�����R�̏����Ə����̎��т��������蕶����я��ł���B�܂��㐢�̎j���Ƃ��ẮA������(1062-1144)�́w���T�����L�x�A�����̒�q�Ƃ����m���E�����E���߁E���Ԃ́w��ɗ��R�����C�s���L�x(�w�C�s���L�x�Ɨ���)�A�����́w�����R����������n���L�x(�w���n���L�x�Ɨ���)��������A�m�`�Ƃ��Ă͌Պ֎t�B(1278-1346)�́w�����ߏ��x�A����潡(1633-1695)�́w�������m�`�x�A���t��(1626- 1710 )�́w�{�����m�`�x�ɂ��ꂼ�ꗪ�`���L����Ă���B �����Ɋւ����s�����́A���łɒ~�ς�����B�����Ɉ˂�ƁA�����̐l�����́A���悻���̎O�̊ϓ_����������Ă���B��ɂ́A���엝��Y���╟��N�����ɑ�\�����悤�ɁA�����J�R�҂Ƃ��Ă̏����ɑ���c�]�E�M��O�ʂɏo�������_�ł���B�w�����蕶�x�ɉ����A�����̐����Ƃ����w�C�s���L�x�w���n���L�x����{�Ƃ��A����ɂ͊e�n�Ɏc�鏟���`��������C���̌����Ȃǂ�����荞�݁A���̂قƂ�ǂ��j���Ƃ��āA�����̐��U��`���Ă���B���悻���S�N�ɂ킽������R�Ə����Ɋւ���M�̏W�听�Ƃ����Ӗ��ł́A���ɑf���炵�����ʂƌ����悤�B�������A�j���ƌ㐢�̋r�F�Ƃ̔��ʂ͑S���Ȃ���Ă͂��炸�A���������̂܂����̎����ƌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B ��ɂ́A��Ƃ͑S���t�̎��_�ŁA�^�킵���́A���ׂč̗p���Ȃ��Ƃ������̂ł���B���o���o���Ȃǂ�12�A�w�C�s���L�x�w���n���L�x�͌����ɋy���A�w�����蕶�x�ł����A�S���M����ɑ���Ȃ��Ƃ���B���ǂ̂Ƃ��돟���ɂ��ẮA�u���Ԃ̕����I�@���ҁA����Ύ��x�m�I�Ȃ��́v�Ƃ������ƈȊO�͉������������A�u�����R�͏����ɂ���ď��߂ĊJ���ꂽ�ƁA�����ł͂��łɕ�����������M�����Ă����v�Ƃ������Ƃ̂ݐM���ėǂ��Ƃ����B�m���Ɂw�����蕶�x�͋�C�̍�ł���A�����R�Ə������c�]����Ӑ}�����������ł��邩��A�����Ɍ����A���łɓ������r�F�����������Ƃ͊m���ł��낤�B�������A�����̕����҂̓������炵�āA������P���Ɏ��x�m�ƌ��ėǂ��̂��낤���B����Ƃ̐��������m���߂Ȃ���A�w�����蕶�x�ɋL����鏟�����⏔����₤���Ƃ́A�����̏@���E�����̂�������l�@���鑫������Ƃ��Ȃ�ł��낤�B �O�ɂ́A�����ɂ������R�J�R���A�����̓����̎���I�E�n���I�w�i�ƌ��т��鎋�_�ł���B�܂��a�v�k�����⋴�{���N���́A�����̓����R�J�R���A�ڈΖ��̏I���Ƃ������ƓI�g����w���������l�Ƃ��Ă̎��Ƃƈʒu�Â��Ă���B�������A����������R�ƁA�ڈΖ������т��钼�ړI�Ȏj���͎�����Ă͂��炸�A���_���}���Ă��銴���ۂ߂Ȃ��B�ʂ����ď����̓����R�J�R�́A���ɉڈΖ��ƌ��т��ė������ׂ����̂ł��낤���B���̐��U�E�ړI�ӎ��̑S�̂܂��A�o���̈Ӌ`���l����K�v�����邾�낤�B �ȏ�̂悤�ɏ����́A�_�҂̎��_�ɂ���āA�̑�ȓ����C���̑c�t�Ƃ��A�����̖��ԏ@���҂Ƃ��A�ڈΖ��̏I�����F�銯�m�Ƃ��q�ׂ��Ă���A���̌����ɑ傫�ȍ�������B�����āA���̂���������A�čl�̗]�n���c�������̂ł���Ǝv���B �����ɂ́A���̐��U���L����������̎j�����`�����A�܂�����𗠕t����R����Ղ����@����Ă���B�����̎R�яC�s�҂̒��ŁA�����ƕ��̗��ʂ���A���̓������l�@�ł��鎖��͋ɂ߂Ă܂�ł���A���̈Ӗ��ł������͏\���Ɍ������ׂ��l���ł���B�M�҂͖{�_���ɂ����āA�l�Êw�̐��ʂ��Q�Ƃ��A�ł���{�Ƃ��ׂ��w�����蕶�x���ēx�������A�֘A���鏔���ɂ��Ď�̍l�@�������Ȃ���A�����̐l���������߂čl���Ă݂����B�@ |
|
| ����@���̐��U�@ | |
|
�܂��́A�w�����蕶�x�ɋL����鏟���̐��U���T���������B���̍ہA���ڂ������ѓ��́A�q���ʁr�Ƃ��āw�C�s���L�x�̋L�q���Q�l�Ƃ��ĕt�L����B
�����́A�q�V�����N(735)�r�A���썑�F��S�ɐ��܂�A�����͎�c���Ƃ����B�Ⴍ���Ĕ�}���������������́A���Ƃ�ς��ĕ������u���A�W���̌������}���ѐ�̐Î�������Ƃ����B�q�Ƃ��o�������́A�ɓ�����匕��ɂďC�s���A�ݒu���ꂽ����̉����t�����d�ɂč�����E��������Ƃ����B�r �_��i�_���N(767)�l����{�A���B�̓����R�֍ŏ��̓o�������݂�����s���A�����Ɋ҂��ĎO�����ԏZ���ċA�����B �q���̌�A�l�{����(���E�����R�։���)�����_�ɁA���ߑe�H�ɂč��T�njo�ɐ��i���A�r�\�l�N��̓V�����N(781)�l����{�ɍĂѓo������s�A���N�V����N(782)�O���A�O�x�ڂ̎��݂ɂ��Ă悤�₭���̒��ɓ������Ƃ����B���̎O�x�ڂ̓o���ɍۂ��ẮA�܂��R�[�ɂ����Ĉꎵ���ԁA�njo�畧���A�u�䂪�}�ʂ��鏊�̌o�y�ё����A���ɎR���Ɏ���āA�_�ׂ̈ɋ��{���A�ȂĐ_�Ђ𐒂߁A�Q���̕����`�ɂ��ׂ��v�Ƃ̐���Ăēo�������s���A�O���Ԃ����Đ��ɂ��̒��ɒB�����B����̐���̋��Ɉ������сA�O�����ԏZ���ė�����A�̋��ɋA�����Ƃ����B ��N��̉���O�N(784)�O�����{�ɍĂѓo��A�ܓ��Ԃ�v���ē�̕ӂɓ���Ƃ����B��A�O�l�̒�q�Ƌ��ɓ�E���E�k��V�����A��̏��n�ɉ��������ĂĐ_�{���Ɩ��t�����B�����ɐ��N�Ԏ~�Z���C�s�����Ƃ����B ���̌�A����N��(782-805)�ɂ́A��썑�u�t�ɔC�����A�܂��s��S��R�ɂ͉،����ɂ��������āA�����ɂė����E�O�������Ƃ����B�哯��N(807)�̝�鯂ɍۂ��ẮA���i�̗v���ɂ������R�ɓo��F�����A�������������Ƃ����B�����͔ӔN�A�����R�̏��i���L����Ă��Ȃ����Ƃ�V���A���썑�ɉ������Ă����ɔ��m��ʂ��āA��C�ɂ��̕��͂��˗������B������ċ�C�͍O�m�ܔN(814)�Ɂw�����蕶�x���쐬���Ă���B���̎����łɏ����͎��\�Ɏ���A�̒�������Ĕ\�����I�����Ƃ����B�q���邢�͍O�m���N(817)�A�l�{�����k�̊�A�ɂē��ŁA�s�N���\�O�ł������Ƃ����B�r ���̐��U�𐫊i�̈Ⴂ���番�ނ���Ȃ�A�T�����R�o�������݂�܂ł̐��N���A�U�����R�R�����߂������o�����A�V��ΔȂɐ_�{�������ĂďZ�����C�s���A�W���̌�̗����O�����A�̎l�ɕ������悤�B�ȉ��A���̎l�̎����ɏ]���āA�������̖��_���l�@���Ȃ���A�����̎��ՁE�l�������ڂ������Ă��������B �@ |
|
| ���O�@�����̐l�����Ə����@ | |
| ���T�����R�o�������݂�܂ł̐��N���@ | |
|
��(1)�����̏o��
�����̏o���ɂ��āA�w�����蕶�x�́A�L���叟���ҁA����F��l��B������c���B�Ɠ`����B�u����F��v�͌��݂̓Ȗ،��쓌���̖F��n���ɂ�����B�܂��u��c���v�ɂ��āA�w�C�s���L�x�́A���m�V�c�̑��c�q�ŁA�����ɕ������і썑���̔����Ɏ~�Z�����������̎q���Ƃ��A�w�����s�j�x�́A��썑�Љ��S��c������o�āA�̂����ֈڂ����ꑰ�Ƃ���B�Ȃ��w�C�s���L�x�Ɉ˂�A���͉����̎�c�����A��͋g�c���̏��ŁA��l�͎q��Ɍb�܂ꂸ�ɂ������A�ɓ���(���E�Ȗ؎s�o����)�̐��ω��ɋF�����Ƃ�����D���A�V�����N(735)����l��������ɏ���(�����E����)�����������Ƃ����B�܂��A���ɓ`���`���ł́A���̉Ƃ͎�c���{�т̉��썑�s��S��R�ɂ��������A����̎��Ƃł���F��S�ɂďo�������Ƃ����B����������̂́A�����_�ŏ����̏o���̎��ۂ�F�����邱�Ƃ͓���B �c�����̏����ɂ��āA�w�����蕶�x�͉������Ȃ����A�w�C�s���L�x�͋�̓I�ȃG�s�\�[�h��`����B��͐Γ��⍻�����Đ_����q���ƁA��͕���F������Əo��A�O�A�˂�l�O����������������Ƃł���B�������������́A���m�̓`�ɂ��肪���Ȍ㐢�̕t��Ƃ��ĂقƂ�ǒ��ڂ���Ȃ����A�Ⴆ�Γ�����̕������b�W�w���{��ًL�x�ɂ́A�`��(���E�a�̎R���C��s���Ò�����)�̎q���������Y��āA������ŕ����Ƃ��A��ς�ŕ����Ƃ��A���{�̂܂˂��Ƃ����ėV�ԏ�ʂ��L����Ă���B����Ɠ��l�ɁA�����������I�ȏK���̓y��Ɉ�����\���͂��邾�낤�B�@ |
|
|
��(2)����E��u�Ƃ��Ă̏���
�����̐N���ɂ��ẮA�w�����蕶�x�ɁA�_邈�~�a�VꔁA�Ӑ���囊�VꏁB�~�g�l���V�����A���Q�O���V�ŋƁB�}�ڗ��V�����A�ѐ�VᩑR�B�Ƃ���B�C���ɖ����Ă͂��邪�A��ӂƂ��ẮA�Ⴍ���Ĕ�}�E����ł���A�������}���������u�����Ƃ������Ƃł���B���Ȃ킿�A�u�~�a�̗�v�܂荹��(�ʏ�A�������\�܂�)�ł�����������A���łɔ�}�Ȑ��_�������A�u�ɔX�̎��v�܂��u(�ʏ�A��\�Έȏ�)�ƂȂ�����ɂ́A����Ȃ�S�ӂɒB�����Ƃ����B�܂��u�l���̐����v�܂�m�_�H���Ƃ��������̐��Ƃ�ς킵�����g�Ɗ����āA�u�O���̖ŋƁv�܂���̎O���ɂ�镧���C�s���u���A�W���̌������}���A�R����ѐ���������Ƃ��m����B �Ȃ��A�u�~�a�v�Ɓu�ɔX�v�ɂ��āA�]���̌����ł́A�����P�Ȃ�N��̔�g�ƌ��āA�u(����ƂȂ�)�\�܁A�Z�̍��v�u(��u�ƂȂ�)��\�̍��v�Ƃ��邪�A�q�ω@�掵���^��(1614- 1693)�́w����W�֖ցx�́A�[�I�Ɂu����ł��������v�u��u�ƂȂ�����v�Ɖ����Ă���B�ߔN�̌������A�����P�ɔN��̔�g�ƌ��āA���ۂɏ������o�Ɠ��x���č���ƂȂ�A������Ĕ�u(�m���E����)�ƂȂ����Ɠǂ܂Ȃ��̂́A�����͒n�����Ԃ̏@���ҁE���x�m�ł������Ƃ����Öق̑O��Ɉ˂邩��ł���B�Ⴆ�Ή��o���o���́A�u(������)�����Ɍq����̂��銯�m�E�ɑ��������Ƃ̂Ȃ����Ԃ̕����I�@���ҁA�q�����r���ɂȂ�ɂ��������Ċ��m�Љ�̖����m�I�ȍs�ґ��Ƃ��āA���Z���ɏC������Ă��������̂Ǝv���B�܂�A�������������̏������́A�㐢�̍�ׂƂ��ėǂ��Ƃ������Ƃł���v�Ƃ��āA�������N���ɍ���E��u�ƂȂ��Ă������Ƃ͂��Ƃ��A����ȍ~�̎��т̂قƂ�ǂ�F�߂Ȃ��B�����A���̘_���͉��玦����Ă͂��炸�A�������ɂ������_�Â����Ă���ɂ����Ȃ��B ���̎����̏����ɂ��āA�w�C�s���L�x�͎��̂悤�ɓ`����B�����͓V������Z�N(754)�A��\�ɂ��ďZ���𗣂�A�ɓ�����匕��Ȃǂ̎R�X�ɓ���A���ω������O���ĎO�A�l�O���u�����Ƃ����B����ɓV���ܔN(761)�ɂ́A�����t���ɉ��d���݂���ꂽ�Ƃ̒m�点���A�����͂�����x��Ŗ�t���ɕ����A�Ӑ^�̒�q�̔@�ӂ�b�_�ɐ����A��\���ɂ��č�������A���Z�N(762)�ɂ͋�����A�ܔN�Ԏ~�Z���ċ������@���C���A�w�،��o�x�w�@�،o�x�w�������ŏ����o�x�w���B���_�x�Ȃǐ����̌o�_����u�����Ƃ����B ���������`���́A�܂��ɉ��o�����㐢�̍�ׂƂ���Ƃ���ŁA�S���̏C���ł���Ƃ��č̗p����Ȃ��B�������Ⴆ�A���x�����߂�D�k�ǁE�D�k��(�݉ƕ�����)�𐭕{�ɐi�߂鎞�̕����A������w�D�k�Ǎv�i���x�Ɉ˂�A�w�C�s���L�x�̋L�ڂ͕K�������s�����Ƃ͌����Ȃ��B�܂�w�D�k�Ǎv�i���x�ɂ́A�D�k�ǁE�D�k�̑����A���u�ł���o��A��s�N���A�t��m���Ȃǂ��L�ڂ���Ă��邪�A�L�^�̎c��V���l�N(732)����\���N(745)�܂ł̎l�\�O�l�Ɋւ���A���̓njo�o�T�Ƃ��Ă͒��ɂ���ċK�肳��Ă����w�@�،o�x�w�������ŏ����o�x����ł���A�u�o�o�T�Ƃ��āw�ω��o�x�Ƌ��Ɂw��t�o�x�w����o�x�������B�������u���ɗ���Ƃ��Ắu���ɗ���v���ł������A�u�����ɗ���v�u�\��ʑɗ���v�u�s��㮍��ɗ���v�Ƒ����A��l���̎O�̗D�k�ǂ���A�O��̑ɗ�����Ă��邱�Ƃ��m����B�܂��w���{��ًL�x�ɂ́A�_��i�_�O�N(769)�ȑO�ɁA���̏��쒩�b�떛�Ȃ�҂��D�k�ǂƂȂ�A���ω��̎���u�����ĉ���S�̎R��W�]���ďC�s�����Ƃ̐��b������B���������܂���A�������W���̌���������A�܂��͗D�k�ǂƂȂ��ĎR�тɓ���A���ω�������O���ď��R��]�X�Ƃ����\���͏\���ɂ��蓾�邾�낤�B �܂��V����N(758)�ɒ���́A�����̎R�тɉB��ď\�N�ȏ�̐��s��ς�m(�D�k��)�ɁA���x��F�߂Ă���B����Ɏ���͉��邪�A���a�\�ܔN(848 )�ɂ́A���o�⎝��ɗD�ꂽ�҂̎����������Ƃ���A����w������������̐��S�l�����X���W�܂�A�������\�l���܂�Ɋ��x���F�߂�ꂽ�B�������������̗D�k�ǂƓ��l�ɁA�ɓ����Ȃǂ̎R�тŏC�s���Ă����������A�����t���̉��d�ݒu���x��Œy���Q���A���x�E����������ꂽ�\�����l������B ����ɐ�s�����ɂĎ������悤�ɁA�ޗNJ��̕����͎R�яC�s�Ɩ��ڂɊւ���Ă����B�o�Ƃ��u���D�k�ǂ͂������̂��ƁA���x�E�����̍�����u�ł����Ă��A�ϋɓI�ɎR�тɓ��ݓ���A�C�s��ς��Ⴊ�w�E����Ă���B�܂������̍�������L�͂Ȏ����ł́A�ߐڂ���R�n�ɎR�����c�܂��ꍇ������A�m�������̏C�s�̏�ƂȂ��Ă����Ƃ����B ����瓖���̏ƏƂ炵���킹��A�ɓ����ł̎R�яC�s�A�����t���ł̎���E�C�s�ȂǁA�w�C�s���L�x���`���鏟���̐N���̎��т́A��Ƃ��Ă����F�߂Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ��낤���B��q����悤�ɁA�����R�R������͓ޗǂ��畽�������Ƃ���鋾�ӂ�@������o�y���Ă��邪�A����͏����������̖��ԏ@���҂Ƃ������A�L�͂Ȏx���҂������҂ł��������Ƃ��������Ă���B�܂���C�́w�����蕶�x�ɂāA�������u����v�Ə̂��Ă��邪�A�u����v�Ƃ͓����̓��{�ɂ����āA��u�E�m���Ɠ����Ӗ��Ŏg���Ă���B����ɏ������ӔN�Ɂu�u�t�v�ɔC������A�u�@�t�ʁv�ɂ����č��i�̗v���ɂ��J���F���Ă��邱�Ƃ���A���������I�ɔF�߂�ꂽ�m���ł��������Ƃ͋^�����Ȃ��B�ł͂������������A�����͎���������ƌ����A��C���N���̏����ɂ��āA�u�~�a�v�u�ɔX�v�Ƃ�������E��u���w����������g�p���Ă���ȏ�A�����R�o���ȑO�ɂ͓��x�E������āA���łɍ���E��u�ƂȂ��Ă����ƍl���������Ó��ł��낤�B�@ |
|
|
��(3)�����̏@���F�V��Ɖ،��̉\��
�Ȃ��A�`���̒ʂ�ɏ����������t���ɂĎ�����A�����Ɏ~�Z�����m���ł������Ƃ���A���̏@����@���ɍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤���B����͐�́w�����蕶�x�Ɍ����u�O���̖ŋƁv���Q�l�ƂȂ낤�B�]���̌����ł͓��ɒ��ڂ���Ȃ����A���ꂪ���̎O��������@�̒q�ґ�t�q��(538-597)�̖嗬�A���Ȃ킿�u�V��v�̔�g�ł��邱�Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B���łɓc���W�S�����w�E���Ă���悤�ɁA�����̕����A���ɉ���E��염���̕����́A�V��Ƃ̊ւ�肪�[���Ƃ����B�܂�`����t�Ő�(767-822)�̈�،o�ʌo�Ⓦ�������Ƃ����������ɐϋɓI�ɉ��������A�܂�������葽���̎҂��Ő��ɒ�q���肵�āA�~��(771-836)�A�~�m(794- 864)�A���d(795-868)���V�����ɏ���ȂǁA�����̓��{�V��@�̔��W�ɁA���������͏d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ����B�c�����́A���̕�̂Ƃ��āu�����V�䋳�c���������c�v�̑��݂𐄑����Ă���B�܂���{�ɗ���`�����Ӑ^��a��(688- 763)�́A���ƂƂ��ɓV��ɐ��ʂ��Ă������A�V���ܔN(761)�ɉ����t���̉��d���ݒu���ꂽ�����A�������Ə̎^���ꂽ��q�̓���(���v�N����)���h������A�����ɊӐ^�̖嗬���L�܂����Ƃ��Ă���B ���̂悤�ɉ����t�������_�ɊӐ^�̖嗬���������Ă����Ƃ���Ȃ�A�u�O���̖ŋƂɒ��Q����v�Ƃ́A�܂��Ɂu�V��v�̋������u�������Ɖ��߂ł���̂ł͂Ȃ��낤���B�㐢�ɂȂ��āA�����R�ɂēV��@������ƂȂ鉓���́A���łɏ����ɂ������\��������B�Ȃ��w�C�s���L�x�ɂď����̎t�Ƃ����u�@�Ӂv�u�b�_�v�Ƃ́A�Ӑ^�剺�̓n���m�E�@��(?-815)�ƌd�_(?-810)�̂��ƂƎv����B���҂͂Ƃ��ɊӐ^��笏����ė������A���̐�g�ɗ�݁A�ӔN�͑m�j�ɂ��C����ꂽ�l���ł���B���Ȃ��Ƃ��㐢�ɂ́A�������@���d�_��ʂ��āA�Ӑ^�̖嗬�ɘA�Ȃ��Ă����Ƃ̓`�������������Ƃ͊m���ł���B �����Ƃ��w�����蕶�x�ɂ́A�������ӔN�Ɂu�،����ɂ�s��S��R�Ɍ������v���Ƃ���B�܂��w�C�s���L�x���A���������u�����o�T�Ƃ��āA�D�k�ǂ��x��������Ƃ��ĉۂ����Ă����w�@�،o�x�w�������ŏ����o�x�ɉ����A�w�،��o�x����u�����Ɠ`���Ă���B�����́u�،��v�ɂ��ʂ��Ă������A���邢�͑P�����q�̕�ɗ��R�V�s������w�،��o�x�ɐM���Ă����̂�������Ȃ��B�����̓����ɂ�����،��̍O�ʏɂ��ẮA���łɒ��N��������̋A���l�����������Ɉڂ�Z��ł��邱�Ƃ���A���N�����ɂĐ���ł������،����A�A���l��ʂ��ē����ɏ����ꂽ�Ƃ̌���������B ������ɂ���A�����̏@���𐄑�����Ȃ�A�u�V��v�u�،��v�Ȃǂ̈ꕧ�悪�A�ЂƂ̉\���Ƃ��Ďw�E�����邾�낤�B�܂��A���������₵����ł͂��邪�A�O�m���N(817)�ɍŐ���������K��Ĉȍ~�A�헤�E���������_�Ƃ����@���̓���(750��-840��)�ƁA���E��������_�Ƃ����������c����ɂ͉b�R�̍Ő��Ƃ̊ԂŁA������u�O�ꌠ���_���v���W�J���ꂽ�B�����܂Ő����̈�͏o�Ȃ����A���N��������̋A���l�A���邢�͊Ӑ^�̒�q�̓�����ʂ��āA�����A���ɉ���E���ɂ́A���`�̏�œ�s�̕����Ƃ͈�����悷�ꕧ��̏@�������t���Ă����̂ł��낤�B �w�����蕶�x�ɋL���ꂽ�͂��ȍ��Ղ́A�����ɂ����̌X�������������Ƃ�����������̂ł���B�@ |
|
| ���U�����R�R�����߂������o�����@ | |
|
��(1)�K���栂���ꂽ�����R
�������n�߂ē����R�ւ̓o�������݂��̂́A�_��i�_���N(767)�A���悻��\����O�\��̍��ł������B�Ȗ،��̖k���Ɉʒu��������j�̎R�́A�W����l���Z���[�g���A�֓��n�����w�̖��R�ł���B���w�ΎR�ɂ��~���`�̎R�e���������B���̎R�ɂ��āw�����蕶�x�͎��̂悤�ɋL���B��L���B��ɗ��R�B�� ��}�⊿�A�����Օɗ��B磤������鼉��A�ĖP�����r�p�B鳖�㥒ʁA�l�����B�ؖ�U�ÁA���L���R�ҁB �]���̌����Ɠ��l�ɁA�^�Ƃ́w����W�֖ցx�ɏ]���A���̉ӏ��͓����R�́u�����v���g�I�ɏq�ׂĂ���Ɖ��߂ł���B�܂�A���̍����ނ���R�e�́A�Ăɂ͐��䂪�V�̐��˂��h�����A�~�ɂ͔���������ɓ˂���������ł���A����ɂ͗��ł����Ă��R���ō������A�P���ł����R�[�Ŕ��Ă�����ł���B����́A鳖����ʂ邱�Ƃ͂܂�ŁA�܂��Đl�Ԃł͈ȑO�ɓo�����҂ȂǒN�����Ȃ��Ƃ���B �����A�����������߂ɉ����āA�ʂ̈Úg��ǂݎ�邱�Ƃ��ł��悤�B�܂��u�K��v�Ƃ́A��̓I�ȎR���Ƃ��ẮA���݂̒����V�d�̐��암�Ɉʒu����p�~�[���R�n���Ӗ�����B�w�����x�u����`�v�Ɂu���͑�������ɔK����ȂĂ��v�Ƃ���悤�ɁA�����̒n���F�����炷��A�u�K��v�Ƃ͐���̍Ő��[���Ӗ����Ă����B���̔F���͌㐢�̓��{�ɂ��`������A�w���ƕ���x�ɂ��u�V���A�k�U�̋��ɁA�����A�K��Ƃ��ӛӓ��B�n�����ĉz������Ȃ�v�ƋL�������ł���B �܂��u�K��v�́A�����̎R�ł���Ɠ����ɁA�V���ւƒʂ��鋁�@�̎R�ł��������B�Ⴆ�A���H�ɂĐ����i�ݓV���ւƓ��������v�̉���������ܖ��(-420��-)�̑m�`�ɁA�u�K���o��Đ�R��x��v�ƋL�����悤�ɁA���đ����̋��@�҂����́A�u�K��v���z���ē��������݂Ă���B�����ē��W�̕��z����@��(337��-422 ��)�̓`�Ɂu�K��Ɏ���B��A�~�ĂɐϐႵ�A�����L��ēŕ���f���A���I���J�ӂ炷�v�Ƃ���悤�ɁA���̎R�H�͂܂��ɖ������̍���Ȃ��̂ł������B�����A���@�҂̑������A�����Ŗ��𗎂Ƃ����Ƃ����B�����炭�u�K��v�Ƃ́A�����҂ɂƂ��ē��ʂȊ��S���������R���ł������̂ł͂Ȃ��낤���B��C�́A�����R���u�K��v��栂��邱�ƂŁA�����R����a���牓�����ꂽ�R�ł���A�����ݓ��邱�Ƃ�����ȎR�ł���Ƃ̔F�����Âɕ\���Ă���ƍl������B ����́u鼉��v�Ɓu�r�p�v�̔�g������ǂݎ���B�����́u���v�Ɓu���ނ��������v���Ӗ����Ă���A�]���̂悤�ɎR�̍�����\���Ɖ��߂���ɂ͋^�₪����B�ނ��낱�̎R�̎��R�̌������A����ɂ͓��ݓ��邱�Ƃ̊댯����\�����Ă���̂ł��낤�B�傫�ȗ����N����A�R���ł�鼉���Ⴆ��@�����܂藋�������Ă���B�P�������Ă��邱�ƂŁA�R�[�ł͋����������r�̊p�̔@���ɉQ�����Ă���B����������ڂ̓o���Ɏ��s�������R���A�[��A��ǁA�_���A���ȂǁA���R�I�ȏ��ł������B�����͂��������ߊ��҂��Њd���邩�̂悤�ɗ����͂�����B�����炭��C�́A�����R�ɝ����o�����������A����̌������R�X���z�������@�m�ɏd�ˍ��킹�Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�@ |
|
|
��(2)�����R�R����Ղ̉���
�Ȃ��A�����Ŗ��Ƃ��ׂ��́A�����R�̎R����Ղ̂��Ƃł���B���̈�Ղ͎R�����̋���𒆐S�ɉc�܂�A�Õ�������]�ˊ��ɂ����Ă̈╨�A��Z��_���o�y���Ă���B���ゲ�ƂɈ╨�̕ϑJ�͂��邪�A�傫�ȓ]�@�͕������E���q�����ł���A���̎��������ɑO���̎�v�Ȉ╨�ł��������ӗނ��p�������A���o�i�E����E�n��E�C�����W�i���o�y����悤�ɂȂ�Ƃ����B���E�ʂƂ��ɁA����قǂ̈╨���R������o�y����̂͑S���I�Ɍ��Ă��܂�ŁA�ޗ�Ƃ��Ă͓ޗnj��R�ブ�x�A�������R������݂̂Ƃ����B �Õ����̈╨�Ƃ��ẮA���ʁE�؎q�ʁE��s�y��E��_��b��������A�ޗNJ�������ȑO�Ƃ����╨�ɓS�����A�ޗNJ��Ƃ����╨�ɔg���ђ��b���A�C�b�������A�Ԏ}���A�f���p�������A�����P�n���Ȃǂ̓����A�������E�|�{�^�O�؋n�E�y��E�S���n�`�i�Ȃǂ�����B�����O���̈╨�Ƃ��ẮA�ޗNJ��������p���A�����@��E�È�E���`���q�Ȃǂ�������Ƃ����B ���̂������ɓZ�܂�����Ղ��\�������̂́A�ޗNJ����畽�������ɂ����Ăł���A�R���̐����̒f�R�ɐڂ���t�߁A���݂̑��Y�R�_���K�a�̐����ɂ���I��ɋ��܂ꂽ���n����A���ӁE���E�@��Ȃǂ��o�y���Ă���B����ɂ��A�l�Êw�I�Ȏ��_������A���̎����̕����҂ɂ��o���͔ے肷��]�n���Ȃ��Ƃ����B �Ȃ��A���̈�\�̏ꏊ���u�R���̐����̊�̌E�n�v�ł��������Ƃ́A���ɒ��ڂ��ׂ��ł���B��q����悤�Ɂw�،��o�x�́A�ω���F�̏Z�����ɗ��R�R��́u�����v�u���ʊޒJ�v�Ƃ���B�܂��w�����蕶�x�́A�������o�����ĎO�����̗�����C�����̂́A�R���́u���p(�쐼�̊p)�v�ł������Ƃ���B�o�T�̋L�q�ƁA�C�s�҂̓����A�����Ĉ�\�̏ꏊ�����悻���v���Ă���B�����R�R����Ղ̈�̉��߂Ƃ��āA�����͂��̏ꏊ���ω���F�����킷�u���̊�̌E�n�v�ƌ��Ȃ��A�����ŎO�����̗�����s�����ƍl���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�������ꂪ�������Ƃ���A���̎R����Ղ́A�����̎��ݐ��A�w�����蕶�x�̐��m���𗠕t���镨�ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B ������_�A���ƂȂ�̂́A�����ȑO�Ɩڂ����╨���A�͂��Ȃ�����o�y���Ă��邱�Ƃł���B����͐�ɋ������u鳖��A�ʂӂ���㥂ɂ��āA�l���A�₦����B�U�Â��ؖ₷��ɁA���������R��҂��炸�v�Ƃ�����C�̔F���ƈقȂ鎖���ł���B����̌����ł́A�Õ����̈╨�͐���N�����ɁA���R�̔����i��`���i�������҂ɂ��R���֔[�߂�ꂽ�Ƃ��A�܂��ޗNJ�������ȑO�Ƃ���镧��Ɋւ��ẮA���łɏ����ȑO�ɕ����҂��o���������߂Ƃ���Ă���B ����ɑ��đ�a�v���́A�ߔN�S���e�n�̎R��������A�Õ����Ƃ����╨����������Ă��邱�Ƃ���A���łɌÕ����ɂ͓o�����s���Ă����Ƃ���B�܂��A�������J�̋�ɗp����̂́A�䂪���̒��Ɏ��������Ղ�̕��@�ł���Ƃ��A���̏K���ɏ]���ČÕ����ɎR���ł����J���s���A��ɕ����҂�����������p�����Ƃ̌����������Ă���B�����Ƃ��A���͓����ł��d������A���m�����R����ۂ́A���S��鳖���������Ӗ��ŁA�����g�т��邱�Ƃ���Ƃ��Ă����B�����̋��ӂ̏o�y���A�����I�M�̉e��������ɓ����K�v�����邾�낤�B���̕�����{�Ɏ��������M�Ƃ��邱�Ƃɂ͋^�₪����Ƃ��Ă��A�Ⴆ�Γ����Ȃlj��炩�̐M���������҂��A�����҈ȑO�ɓo�������\���͍l�����Ă����K�v�����邾�낤�B �������A�����͓����R�ւ̓o�����x���s���A�������\�ܔN�����ĎO�x�ڂ̎��s�ɂ���Đ��ɐ������Ă���B�����炭�o�R���Ȃǂ͖����m�����Ă��炸�A�ɂ߂č���ȏł������Ǝv����B�܂��A�����R�R����Ղ̍ŏ��̌`�������ޗNJ����畽�������ł��邱�Ƃ��l������A����ȑO����p�ɂɓo�����Ȃ���Ă����Ƃ͍l���ɂ����B��̐��҂������\���͂��邪�A�{�i�I�ȊJ�R�́A�ޗNJ��̕����҂Ɉ˂���̂Ƃ��ėǂ����낤�B�܂��A���̒��S�l����������Ƃ���A��͂菟���ƌ���̂��Ó��ł��낤�B�@ |
|
|
��(3)�ڈΖ����߂�����
�Ƃ���ŁA�����R�R����Ղ̈╨���A�ʁE���Ƃ��ɗD��Ă��邱�Ƃ���A��a�v���Ȃǂ́A���ƃ��x���ł̎x����z�肵�Ă���B����ɂ��̔w�i�Ƃ��āA�ڈ̔����ɂ�鍑�ƓI��@�������A�����̓����R�o�����A�P�Ȃ�@���I��M�ɂ��s�ׂł͂Ȃ��A���썑�ƓI�E�������J�I�Ȑ��i�𑽕��ɑтт����̂Ƃ��Ă���B�܂��T�ܔN(774)�̓�����N������A���\��N(780)�̑����ח��܂ł́A������ڈ̔������Ɍĉ����āA�����͍��ƓI�g����w�����ēo�������݂��Ƃ����B �m���ɂ��̎�������A�����\�N(801)���Α叫�R���c�����C(758- 811)�̐����ɂ��吨�������A�����o�H�@�g���Ώ��R�����Ȗ��C(765-823)�̒����ɂ���đg�D�I�Ȑ�������~�����O�m��N(811)�܂ł́A������O�\���N�푈�ƌĂ�A�ڈΖ��͍��ƂɂƂ��đ傫�ȉۑ�ł������B�܂���a�v�����w�E����悤�ɁA���썑�͒}�����Ƒ������āA�����Ƃ����ʒu�Â����Ȃ���Ă����ƌ����邾�낤�B�����ɂ�������d�@�̐ݒu�A�Ő��ɂ��Z���̑����A�j�̎R�ƕR�̎R����ՂȂǂ́A���̐����𗠕t����B�������A�����������āA�������邢�͓����R�ƁA�ڈΖ������ՂɌ��т���̂́A���_���}���Ă��銴������B�m���鍪���͉�������Ă͂��Ȃ��B�����������������߂ēo�������݂��̂͐_��i�_���N(767)�A�ڈ̔����ȑO�̂��Ƃł���B��a�v���͂���ɂ��āA����ڂ͎R�ѕ��k�Ƃ��Ă̌l�I�ȏC�s�A���ڈȍ~�͒��썑�Ƃ̎g���������l�Ƃ��Ă̍s���ƁA�S���s�ʂ��Ă��邪�A���_���肫�̍l�@�ł͂Ȃ��낤���B �����̓��ڈȍ~�̓o�����s�́A�܂��Ɋ������ɂ����邪�A�����V�c���x�������R���Ƃ��āA��a�̎q���R���Ƌߍ]�̞��ߎ����m����B�O�҂͉���l�N(785)�ɎR�яC�s�m�E��( 718��-795)�������V�c�̌�a�������F�������тɂ����́A��҂͍��Ƃ̈��J���肢�R�яC�s�̓���Ƃ��ē��ܔN(786)�ȍ~�ɑ��c���ꂽ���̂ł���B���������R�ւ̓o���E�R���̑��c���A�ڈΖ��Ɗ֘A�������ƓI���Ƃł���Ȃ�����A�����R�̎��ЂɊւ���n����o�c�A���邢�͎R��ł̏C�@���ɂ��āA������̎j���ɋ͂��ȍ��Ղł��c����ėǂ������ł��邪�A����͍��̂Ƃ���S����������Ȃ��B �܂��A�����R�ɊW����ł��낤�u��r�R�_�Ёv�́A���썑�̎����ЂƂ��Ă͗B��̖��_��Ђł��邪�A���̏��ݒn�́w���쎮�x�Ɂu�͓��S�v(���E�F�s�{�s)�Ƃ���A�n���I�ɍ��v�����s���ȓ_�������B�u��r�R�_�Ёv�̏��݂������R�ォ�A���邢�͉͓��S���肩�ł͂Ȃ����A������ɂ���A���̏��o�́w�����{��I�x�u���a�O�N(836)�\�������v�́u���썑�]�܈ʉ��M�l����r�_�ɐ��܈ʉ����������v�Ƃ̋L���ł���B���Ȃ��Ƃ����̎��ɂ́A�u�]�܈ʉ��M�l���v�ɏ�����Ă���Ƃ͂����A�ڈΖ�肪�ꉞ�̏I���������O�m��N(811)����͑啪�u���肪����B�Ȃ��������ɓ����ł́A����������S�̏]�O�ʈɔg��喽������ʂɁA�헤�������S�̏]��ʙ��ꓙ����ꓤ�q��������ʂɏ��i���Ă���A���ƓI�ɂ́u��r�_�v�̒n�ʂ͍���E�����̗��_�ɔ�ׂ�ƁA�K�����������͂Ȃ��B �����������{�Ñ�ɂ����āA�폟��_���ɋF�肷���͂������������Ȃ��B�V�c�̕s����V��̕s���ɍۂ��āA����قǕp�ɂɐ_���E���������s���ꂽ���Ƃɔ�ׂđΏƓI�ƌ�����B�ڈΖ��Ɋ֘A�����Ƃ���ł́A��T�\��N(780)�ɗ������畛���R�S�ω��r�N(?-795)���u�ڈΌR�ɕ�͂��ꂽ���A(������)�����E���͗��S�̐_�\��ЂɋF�����Ƃ���͂���j�����B���̏\��ЂЂɗ邱�Ƃ𐿂��v�Ƃ̑t�オ����A������������Ƃ̋L�^�ƁA����N(782)�ɗ��������u(���������݂�)�����_�ɉڈΓ������F�����Ƃ���A�_�����������B�ʕ������Ƃ��v�Ƃ̑t�オ����A�M�ܓ��ƕ���˂��������Ƃ̋L�^��������B����ɂ��A�ڈΓ����̑O���ɂ��������R�⍑�i���A�ݒn�̐_�ɐ폟���F�肵����ɂ��ẮA�͂��ɒm�邱�Ƃ��ł���B�����A�ʂ����č��Ǝ哱�ɂāu��r�_�v�ւ̋F�肪�s��ꂽ�ł��낤���B��L�̗l�X�ȏ܂���ƁA�����̓����R�o���̔w�i�Ƃ��āA�ڈΖ��ɂ�鍑�Ƃ̎x����z�肷��ɂ͍����ɖR�����A���̉\����ϋɓI�ɘ_����ɂ͓���邾�낤�B �������A�����R�R������D�i���o�y���Ă��邱�Ƃ��炵�āA������̓����R�J�R���x�������L�͎҂����������Ƃ͑z�肵����B���������߂ē����R�R���ɓ������̂��V����N(782)�A���X�N�̉���O�N(784)�ɂ͌ΔȂɐ_�{�������ĂďC�s���Ă���B�����̎R���Ɋւ��鐭�������ƁA���N����l�N(785)�ɂ́A�m�E��E�D�k�ǁE�D�k������Ɉ˂炸���āA�R�ю��@�ɂđɗ����ǂ݁A�d�@���s���邱�Ƃ��ւ����Ă���B�܂�����\���N(799)�ɂ́A�{���������ĎR�тɉB�Z���A�l�̏������Ďז@���s�����傪���X�ɂ��Ă��邽�߁A�R�т̐��ɂƂ����ɏZ�ޑm�E��E�D�k�ǁE�D�k�����Ƃ̒��ꂪ�o����Ă���B����炪���ʂ��ċւ��Ă���̂́A�C�s�҂����I�Ȓh�z�ĎR���ɏZ�݁A�h�z�ɗL����(���Ƃɕs����)�C�@���s�����Ƃł������B�ޗNJ���ʂ��āA�������̕�(729)�A�b�������̗�(764)�A������p�ˎE����(785)�Ȃǂ̉A�d�����̒���ɂ́A�R�ю��@�ł̊����𐧌����钺�ꂪ�o����Ă��邱�Ƃ��炵�āA���͑����Ɋւ��s���ȓ����������܂�Ӗ��������āA�R�тɂ����閳���̊������ւ����Ă����ƍl������B����́A�R�яC�s�҂̌��͂���Ɉӎ����Ă���A������O�삷��̂͊�{�I�ɂ͓V�c�ł���Ƃ̌�����L���Ă����B�����A������������̎v�f�Ƃ͗����ɁA�l�X�͎��I�ɎR�яC�s�҂��x�����A�C�s�҂͂��̈˗��ɉ����Ď�X�Ȃ�V����s���Ă����B�x�d�Ȃ�R�яC�@�̋�������𗠕t���Ă���B �����Ƃ��A�����̏ꍇ�A���������x���҂����������N�ŁA�����ɂǂ̂悤�ȈӐ}�����������̂���f�肷�邱�Ƃ͓���B�B��A�w�����蕶�x�ɋ�������̂́A�哯��N(807)�̝�鯂ɍۂ��āA���i�̗v���ɂ��A�J���F�����Ƃ������Ⴞ���ł���B���邢�͖��L����Ȃ��Ƃ��A�ڈΓ����̎g����ттĉ����������R�⍑�i�A�o�������ݒn�̍����Ȃǂ̈˗��ɂ��A�������ڈΖ��̏I�����F�������Ƃ���������������Ȃ��B�������A���̉\����ϋɓI�Ɏx�����鍪���͖R�����B �܂��A���Ƃ��������ڈΖ��̏I�����F�����Ƃ��Ă��A����͌�q����悤�ȁA���������~�����߂����������̐��U�E�ړI�ӎ����炷��ƁA���̈ꕔ�A�܂藘���s�̈�Ɨ������ׂ��s�ׂł���A�K���������ꂪ�S�ĂƂ�����ł͂Ȃ��B�����̓����R�o���̗��R�Ƃ��āA�ڈΖ��݂̂���������̂́A�K���ł͂Ȃ��Ǝv����B�@ |
|
|
��(4)��ɗ��R�Ɠ�r�R
���������������o�������݂������R�́A�w�����蕶�x�ł́u��ɗ��R�v�ƌĂ�Ă����B�u��ɗ��v�Ƃ́A����Potalaka �̉��ʂŁA�ω���F���Z�ނƂ����R�̂��Ƃł���B���W�̓V���O��������ɗ�(359-429)�̋���w�،��o�x�u���@�E�i�v�ł́A�u�����R�v�Ɗ���A�P�����q���V�s���ĎR��ɓ���A�����ɂĊϐ�����F�Ɍ��܂݂����Ɠ`����B���̏�i�́u�����ɊF�ȗ��r�L��B�і؉T���A�n���_��Ȃ�v�ƕ`�ʂ����B�܂����̘�闐���O���������(652- 710)�̐V�� �w�،��o�x�ł́A������ʂŁu�✅���ށv�Ɖ��ʂ���A�P�����q�͂��̎R�̐��ʂ̊ޒJ�̒��ŁA�ώ��ݕ�F�Ɍ��܂݂����Ƃ���B���̏�i���u��縈�f���A������T���A�����_��Ȃ�v�Ƃ���̂����l�ł���B �ω���F�͎R��̐��̊ޒJ�ɍ����A���̏�i�Ƃ��ẮA��E���E��������Ƃ��Ă���B ����ɓ��̎O���@�t����(602-664)�́w�哂����L�x�ł́A��C���h�B����䶍��̓�A�a�h��R(�}�����R)�̓��Ɉʒu����Ƃ���A�u�z呾���ގR�v�Ɖ��ʂ����B�R�a�͊댯�ŁA�ޒJ�͌X���A�R���ɒr���L��B���̐��͋��̂悤�ɐ��݁A��͂𗬏o����Ƃ����B�ώ��ݕ�F�Ɍ��܂݂��邱�Ƃ��肤�҂́A�g�����ڂ݂��A����n��R��o����A�����ɓ��B�ł���҂͋ɂ߂ď��Ȃ��Ɠ`����B �ω��M�̗����ƂƂ��ɁA��ɗ��͊ω��̏�y�Ƃ��āA�C���h�ȊO�ł�������悤�ɂȂ�B�������]�Ȃ̕��ɎR�A���邢�̓`�x�b�g�̃|�^���{�Ȃǂ͗L���ł���B���{�ł��A�F��ߒq�R�≺������R����ɗ��ƌ��Ȃ���Ă����B ���Ė��́A�Ȃ������R���ω���y�E��ɗ��ƌ��Ȃ���A�����ď̂����悤�ɂȂ����̂��ł���B�������邪�A���悻���̓���ɏW��ł���B��͓����R�̎R�e����ɗ��̃C���[�W�ɍ��v���Ă�������A�Ƃ������̂ł���B�܂菟���Ȃǂ̕����҂����߂Ă��̎R�ɓo��A�R�����f���鏟�i��ڂ̓�����ɂ��āA�܂�������ɗ��ł���Ɗ�����������Ƃ������R�ł���B�����Ă��̎R�̌ď̂��A��ɗ�(�t�_���N)�����r(�t�^���܂��̓t�^�A��)�A�����ē�r(�j�R�E)�A����ɓ���(�j�b�R�E)�ւƕω������ƌ����Ă���B ����̐��ł́A���Ƃ��Ƃ��̎R�͓�r(�t�^���܂��̓t�^�A��)�ƌĂ��×�����̐M�̎R�ł���A�ď̂��ʂ��邱�Ƃ���A�����҂ɂ���Č�ɕ�ɗ��Ƃ��Ă��悤�ɂȂ����Ƃ���B���̏ꍇ�A�{���̎R���Ƃ����u��r�v�̉��߂��A�j�́E����̓�̍r�R�A���邢�͒j�́E����̓�_�������Ƃ������ȂǗl�X�ł��邪�A������ɂ���A�����M�ȑO����̌ď̂ɗR������Ƃ̐��ł���B �������������R�́A�ޗNJ��̕����҂ɂ���āu��ɗ��R�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����̂��A���邢�͂���ȑO����u��r�R�v�ƌĂ��M�̎R�ł������̂��낤���B������Ō����A�u��ɗ��R�v�̏����͍O�m�ܔN(814)�A��C�́w�����蕶�x�ł���A�u��r�v�̏����͐�ɋ������w�����{��I�x�u���a�O�N(836)�\�������v�ł���B�������́u��r�_�v�Ƃ́A�w���쎮�x�ɋL�ڂ͓̉��S(���E�F�s�{�s)��r�R�_�Ђ̂��ƂƂ��l�����A�n���I�ɍ��v�����s���ȓ_�������B�܂��A�Ⴆ�Γ����������̗�R�ł���헤���̒}�g�R���A�w���t�W�x�w���y�L�x�w�����{�I�x�Ȃǂɕp�ɂɓo�ꂷ��̂Ɣ�ׂ�ƁA�u��r�R�v�ɂ��Ă͑S���L�ڂ��Ȃ��A���a�O�N(836)�ȍ~�A�u��r�_�v�ɈʊK��������ꂽ�Ƃ���L�������j�Ɍ�����݂̂ł���B���̂悤�ɕ����I�Ȏ��_���炷��A�ޗNJ��ȑO�̓�r�R�M�ɂ��āA�ϋɓI�ɘ_���邱�Ƃ͐T�d�ɂȂ炴��Ȃ��B �������A�R���̈�Ղ���A�Õ����̂��̂Ƃ����╨���͂��ɏo�y���Ă��邱�Ƃ��ǂ����邩�B������_�҂ɂ���ĉ��߂ɍ�������A�Õ�������̐M�̎R�ł��������Ƃ̏؋��ƌ��邩�A���邢�͕����҂̊J�R�ȍ~�ɕ�[���ꂽ�Εi�̈ꕔ�ƌ��邩�A�����͗l�X�ł���B������ɂ���A���̎R�̌×��̖��̂�M�̂�����ɂ��ẮA�ǂ������I�ȍ����͖R�����A�[�I�Ɍ����A�_�҂̏d������ϓ_�ɂ���Č��_���قȂ銴������B�����ł́A�ǂ�����\��������Ƃ̔F���ɗ��߂Ă��������B��������d�v�Ȃ��Ƃ́A�ޗNJ��ɂȂ��ĕ����҂����̎R�ɓ���A������u��ɗ��v�ƌ��Ȃ����Ƃ��������ł���B�@ |
|
|
��(5)�R�_�ւ̈ؕ|�Ɠ��R�̍�@
���āA�w�����蕶�x�Ɉ˂�A�������n�߂ēo�������݂��̂́A�_��i�_���N(767)�l����{�A�����ē�x�ڂ� �V�����N(781)�l����{�ł������B����ڂɂ͐[��Ɗ�ǁA�_���Ɨ��ɂ��r���ň����Ԃ��A�����ɎO����(��\���)�ԏZ���ċA�����Ƃ����B����ڂ����l�ɓo���ł��Ȃ������Ƃ����B�����ė��V����N(782)�A�O�x�ڂ̎��݂ŏ��߂ēo���ɐ��������Ɠ`����B���̎��̗l�q���ڂ������Ă݂悤�B ��N�O�����A��ਏ��_�_�A���S���ŁA����呫�A�P���}���B�y���S���A�����R�[�B��S��ŁA�ꎵ����B�u�O���v�̒��{�A�܂��͏��X�́u�_�_�v�̂��߂ɁA�o�T�����ʂ��A������}�悵����ŁA������w�����ĎR�[�ɓ���A�u�����v�̊ԁA�njo�E�畧�����Ƃ����B �o���ȑO�̂���������@����A�z�����̂́A�����̓��R���@�ł���B���������Ȃ邪�A���W�̓��ƁE���^(284- 363)�̒��Ƃ����w���p�q�x���шꎵ�u�o�v�����p�������B�u�R�A�召�Ɩ����A�F�A�_��L��B�R�A��Ȃ�A�����_����A�R�A���Ȃ�A�����_�����Ȃ�B�R�ɓ���ďp������A�K�����Q����B�q�����r�y���ĎR�ɓ���ׂ��炸�B���ɎO���E�㌎���ȂĂ��ׂ��B���͎R�J�̌��Ȃ�B�܂����ɑ��̌��̒��A�g���E��������Ԃׂ��B�������v�������āA�����ɍ��̌���҂��Ɠ�����A���������̂ݑI�Ԃׂ��B�}���l�A�R�ɓ���ɂ́A�F�A���ɐ悸�V�����邱�Ǝ����ɂ��āA���q���o���āA���R����ттĖ���o�ŁA���g�O�ܖ@���삷�ׂ��v�Ƃ���B�R�͑召�Ɋւ�炸�A�_�삪������B���R�̕��@�ɑ����Ȃ���A���̓{��ɐG��Ċ��Q��ւ�Ƃ��A�ł���{�I�ȕ��@�Ƃ��āA�O���E�㌎�̑���A�����Ԃ̌��ցA�����Č아�ƏC�@���Љ��Ă���B �������o���Ɏ��s�������ځA���ڂ͎l���ł���A���������O��ڂ͎O���̂��Ƃł������B�܂���E���ڂ͓���ɂ������Ă̍�@�͉����L����Ă��Ȃ����A�O��ڂ͓���O�Ɏ����ԓnjo�畧���A����ɂ͌�ɏq�ׂ�悤�ɐ_���ɑ��Č�������𗧂ĂĂ���B�����͒P�Ȃ���R�ł��낤���B���邢�͉�������̓���̍�@�ɑ��������̂ł��������B���邢�͋�C�̋r�F�ł��낤���B��������\���Ƃ��Ă͂��邾�낤�B�����A�����炭�Â��͓����Ɍ�����悤�ȁu�R�̐_��ɑ���ؕ|�v�Ɓu����ɂ������Ă̍�@�v�Ƃ����v���́A����������C�s���u�������̕����k�ɂ���������A���̈ӎ��ƕ��@�́A���{�̎R�яC�s�҂ɂ��p����Ă������̂ł͂Ȃ��낤���B�R�тɓ��ݓ����ďC�s����҂ɂƂ��āA���̎R�ɂ��킷�_��̑��݂́A�����ł��Ȃ��������ł���B���݂ɂ����Ă��A�����҂�C���҂ɂ�����C�s�̑O�ɂ́A�g����߂邱�Ƃ���Ƃ��Ă���B�܂��ē����̓����R�́A鳖������݂�Ƃ����댯�Ȑ[�R�ƌ��Ȃ���A���ۂɏ����͊��x���o���Ɏ��s���Ă����B���̑O�r�ɗ����͂�����[��○�Ȃǂ̏����A�����������R�̐_��̎d�Ƃƍl�����Ƃ��Ă����������͂Ȃ��B �O�x�ڂ̎��s�ŁA�����͎R�[�ɂĈꎵ���Ԃ̓njo�畧�̂̂��A���̂悤�ɐ���𗧂Ă邪�A�����ɂ͓����R�̐_��ɑ���Ȃ�z����ǂݎ�邱�Ƃ��ł���B��ᢐ��H�A��g�_���L�m�A��@��S�B�䏊�����S�y�����A�c���R��ਐ_���{�A�Ȑ��_�ЁA�`�Q�����B��P�_���ЁA�ŗ������A�R���O���A���ʉ��B���s���R���A���s�����B �����́A���̓������Ė��Ӗ��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�܂��͐_�_�̂��߂̍s�ׂł��邱�Ƃ���������B���������ʂ����o�T�A�}�悵�������A�����ď������g�A�����Ȃ�Ε��@�m�̎O����R���ɕ����邱�ƂŁA�_�_�����{�������Ƃ����̂ł���B�܂�A�O��̌����ɂ���āA�_�_�̈З͂���w���߁A�Ђ��Ă͐l�X�ւ̍K���������ė~�����Ƃ̊肢�ł������B���ꂪ���A���邽�߂ɂ��A�P�_�E�ŗ��E�R���ȂǁA�����R�̏��X�̐_��̉��삪�K�v�ł���A���̓o�����������Ȃ���A���g�̕������蓾�Ȃ��Ƃ̌��ӂ�\�����Ă���̂��B����ɂ��A�����̓����R����ɂƂ��āA�_�_�ւ̋��{�͌��������Ƃ̂ł��Ȃ��v���ł��������Ƃ��m����B����͓����ɁA�O���̍K�����肤���̂ł���A���������g�̕��ɂƂ��Ă��s���ȏ@���I�s�ׂł������ƌ���ׂ����낤�B�@ |
|
|
��(6)�R���ɂ�����O�����̗��
���āA���̐���̍b�゠���Ă��A����Ώ����͐_�_�̉���āA���ɓo���ɐ�������B�w�����蕶�x�͂��̏����̂悤�ɋL���B �@��ᢊ��^�A�ה���V�᫁A���Ηt�V璀璨�B�r���ꔼ�A�g���⑁B�e���M�h�A�I�������B怳��怳���A���������B�s�������A�����_���A�s�R���Z�A�����_�A�B����߁A�S����B�R�Vਏ��B������卧�A��]���ɁA��k�����A�����L���B�w������ਙQ�A��������сB�t�ЗP�ځA�A崐���V����B���o�斾�A�����ӓ��B�s��V��A�ݗ��ڑO�B���X�捔�A���_�����B��ʋщԁA���@��D�B�S��앨�A�N�l����B�k�]���L�B��v��S���B�����ÁA��k���B���ږ��L�ꏬ�B���L��\�P���Bᾍ��X�L���B㰌v����P���B�����s舁A��k�����B�l�ʍ����A�|�e�����B�S��ّ��A�ؐΎ��L�B���~�n�A����ᢎ}�B�r�������A���F�N���B�R�����f�A��Ő⒰�B�ۘȖ��O�A����趂�l�B�䌋�佘������p�A�Z�V������S�O�����B�ߐ��z��A�֟d�̋��B ���Ⴊ�ς���A������}�s���o��A�u�M�h�v�܂�̍s���ɂāA���ɂ��̒��ɓ��B�����B�܂��Ɂu怳���Ƃ��āv�u�S��������v�A���������V�ɂ��������悤�ȁA���邢�͐勫�ɓ������悤�ȐS���ł������Ƃ����B �܂��R�����猩������R�̏�i�́A�u�����v(�{��R)�������ނ������A�O���Ɂu�֓S�v(�S�͎R)���A�Ȃ邪�@���́A�f���炵������ł���A���̖��R�ł���u�t�Ёv(��x�t�R�E���x�R)���́u�����v(���ĎR�E�����R)�ł���A����y�Ȃ��Ə^����Ă���B�����ĎR���̖k�E���E���쑤�ɂ́A�召�̌�����A���̔@���Ζʂɂ͎l���̍���̉e���f��A����ɌΖʂɔ��˂��������ɏƂ炳��ĎR�̐��}����w�P���𑝂��Ă���B�����́A�R�ƌ��D��Ȃ��u�R�����f�v�̏�i�ɁA�u�R�a�댯�ɂ��āA�ޒJ敧�X���B�R���ɒr�L��āA���̐��̐��߂邱�Ƌ��̔@���v�Ƃ����u��ɗ��v��z�N�����̂ł͂Ȃ��낤���B �����͎b���͂��̐�i�ɘȂ�ł������A�������R���̓쐼�̋��ɑ��������сA�{���̊�𐋂��Ă��牺�R���邱�ƂƂȂ�B���̊�Ƃ͂܂�_�_���{�̂��Ƃł���A����͎O����(��\���)�̗���Ɉ˂���̂ł������B �ȉ��A���́u�O�����̗���v�̓��e�ɂ��Đ������Ă݂����B������������Ƃ́A�O����q���A�����̍߂�������邱�Ƃł���B����Ɏ�p�I�ȈӖ��������A���ɒ����̓�k������ȍ~�A�@���v��ɘj���āA��X�̗��v���肤�V��Ƃ��Ă̜�@�E���ߖ@���쐻���ꂽ�B�����͓��{�ւ��`�����A�ޗNJ��ɂ͋g�ˉ��߁E��t���߁E�\��ʉ��߁E�����߁E����ɉ��߂Ȃǂ�����ɍs���A�܂��������Ȍ�͖@�؎O���𒆐S�ɗl�X�Ȝ�@���s����悤�ɂȂ����Ƃ����B ���{�̌Ñ�ɂ����āA���߉�͑厛�@�݂̂łȂ��A�R�тł��s���Ă����B�V���\���N(745)�ɂ͐����V�c�̕s���ɍۂ��A���t�E���̏����y�я����R�̏ɂĖ�t���߂��s��ꂽ�B�܂��V�����N(764)�ɂ́A���t�̓k���R�ю��@�ɑm���W�߂ēnjo�E���߂��邱�Ƃ��ւ����A����ɉ���l�N(785)�ɂ́A�����V�c�ƍc�@�̊�i�ɂ��A��a���s�S�̎q���R���ɕ��a����������\��ʉ��߂��s���Ă���B�����炭�����̍��ɂ́A���Ƃ̎哱�A���邢�͎��I�Ȋ�Ăɂ��A��X�̗��v������ĎR�тɂėl�X�ȉ��߉�C����Ă����ƍl������B�R�тɂ������p��C�s�Ƃ����ƁA�����I�v�f��A�z�������ł��邪�A���߉�E��@�ɂ��Ă��l������K�v�����邾�낤�B �����������R�R���ɂčs��������Ƃ��āA�܂��\���������̂́A�����p�ɂɍs���Ă������߉�ł���B�����R���ω���y�E��ɗ��ƌ��Ȃ��ꂽ���Ƃ��炷��A�\��ʉ��߁E�����߂ȂǁA�ω��ω��n���̉��߉��������B�������q���Ɉ˂�A���ߖ@�v�͂��̖{���Ɋւ�炸�A��{�\���͓��̐�����������q��(-730-)��w�W���o����V�x��͂Ƃ��A�������̋��{�����A�W�J���̎��A�啔�̖̏����߁E����A��u���̑�����E���蓙�A�����ďI�����̍s���E���������Ȃ�Ƃ����B�{���̑���́A�{�����]�Q���Ȃ����q�s�ɂ���čߏ�����̐S�ӂ�\���u�̖����߁v�Ɍ����A�\��ʉ��߂͓��̎O���@�t����(602-664)��w�\��ʐ_���S�o�x�A�����߂͓��̐��V�����剾���B��(���v�N����)��w�����ώ��ݕ�F�L��~�����V��ߐS�ɗ����o�x�Ɉ˂�Ƃ����B �܂������R�R����Ղ���́A�ޗǖ����畽���O���̍쐻�Ƃ����S���O���^����A�����O���^�܌����o�y���Ă���B�u�^�v�͓ޗNJ��̖@��Ɏg�p�����Ƃ����y��ł���B�������ȍ~�A�����ł͒ʏ�u��v��p����B�u��v�͗�g���J���ē��ɐオ������̂ɑ��A�u�^�v�͗�g���������Ɋۂ������Ă���B���厛���̏C���(�������E�\��ʉ���)�ł́A���݂ł��O���^���g�p����Ă��邱�Ƃ���A�ޗNJ��̉��߉�ł��O���^���g�p����Ă����\���͍����B�����R�R����Տo�y�̎O���^�́A�������R���ɂďC�����O�����̗�����A���߉�ł��������Ƃ���������B �������߉�́A�ʏ�u�ꎵ���v�������Ƃ��ďC�����ꍇ�������B�����Ƃ����݂̓��厛�C���(�\��ʉ���)�́u���v�ł��邩��A�������R���ɂāu�O�����v�̊ԁA���߉���C�����Ƃ��Ă��s�����ł͂Ȃ��B�������������u�O�����v�Ɩ�������A����ɑ���ڂ̓o�����s�̍ۂ��A�����ɂāu�O�����v�Z���ċA�����Ƃ���邱�Ƃ���A�u�O�����v�Ƃ��������ɂ́A�����Ӗ������肻���ł���B ���̓����ɒ��ڂ��āA�����̖@���l���Ă݂�ƁA�@�̒q�ґ�t�q��(538-597)�ɂ��u�@�؎O�����V�v��u���ϐ�����@�v�Ȃǂ��z�N�����B�܂��u�@�؎O�����V�v�́w�@�،o�x�Ɓw�ϕ����o�x�Ɋ�Â���@�ŁA�w���d�~�ρx�ɐ����l��O���̂����A��O�̔��s�����O���ɔz�������B�Ő��͂��̍s�@��V��w���̎~�ϋƂ̉Ȗڂɉ����A����ɉ~�m���O�߂����ƂŁA�Ȍ�V��@�ɂĐ��s���A���݂ł��ł���ʓI�ȏ�p�@�V�Ƃ����B���̜�@�́u�O�����v�������Ƃ��āA�����̎��͂�����s���ƍ��T�Ƃ����˂ďC���A���̊Ԃɗ畧�E�����E�u�o�Ȃǂ��s����B�܂��O���ւƂ��āA���s�҂����C�ɐ悾���čs���ׂ��ꎵ���̍s�@��������Ă���B��Ɍ����悤�ɁA����������̑O�ɁA�R�[�ɂĈꎵ���̓njo�E�畧���s���A��������̂́A�R���ł̗���̑O���ւƂ̈ʒu�Â��ł��낤���B�����A�u�@�؎O�����V�v�͖{������F�Ƃ��Ă���A��ɗ��R�̊ω���F�Ƃ͈�v���Ă��Ȃ��B �Ƃ���A�������q��ɂ��u���ϐ�����@�v���Ó��ł��낤���B����͓��W�̓V�����m�����(419-?)��w���ϐ�����F�����ŊQ�ɗ����o�x�Ɋ�Â��A�q�쐻�������̂ŁA�q��̒�q�̊���(561-632)���Ҏ[�����w�����S�^�x�Ɏ��^�����B�w���d�~�ρx�ɐ����l��O���ł́A��l�̔�s�O���ɑ�������B���̜�@�́A�ω���F��{���Ƃ��A�s�ҏ\�l�ɂāA�畧�E���T�E�u��E�����E�s���E�njo�Ȃǂ��s���A�u�O�����v���邢�́u�������v�������Ƃ��ďC�����B���̎���𗪏q����A�܂�����𑑌����A�����������A�ω����𓌌����ɒu���B�s�҂͐��Ɍ������č����A�ܑ̓��n���A�߉ޕ��E���ʎ����͂��ߕ���F����A�č��E�U�Ԃ��ď��������{����B����ɍ��T�E�O��������A�߉ޕ�����A�k�}�E�ɂċ��{����B�����ĎO��y�ъω��̖����̂��A�w���ω��o�x�ɐ����������ŊQ��E�j���Ə�ɗ����E�Z���͋����u���B�������Ƃ����������ɍs�����A��l�������ɓo���āw���ω��o�x����u����̂ł���B�w�����蕶�x�̖����ɂ��A�����́u�ω��ɋA�˂��߉ނ��q���v�Ƃ��邩��A�������R���ɂďC�s�����u�O�����̗���v��z�肷��Ƃ���A������̉\���Ƃ��āu���ϐ�����@�v����������B �������A�u���ϐ�����@�v�͍Ő��̐����ژ^�w��B�^�x�Ɂu���ω��O���s�@�ꊪ�A���~�ϛ�V�䍑���S�^���v�Ƃ���̂������Ƃ��A����ȑO�ɏC���ꂽ�Ƃ̋L�^�͌����Ȃ��B�����u�@�؎O�����V�v�ɂ��ẮA�w����a�㓌���`�x�ɊӐ^�̏����Ƃ��āu�s�@��@�ꊪ�v���������A����ɒ�q�̓n���m�@�i(709- 778)�͂�������ʂ��Ă���B�Ƃ���A���łɊӐ^�剺�ɂāu�@�؎O�����V�v���C����Ă����Ƃ��Ă��s�����ł͂Ȃ��B��ɂ��m�F�����悤�ɁA�����͉����t���̑m�ł������ƍl�����A�܂��w�C�s���L�x�ɂď����̎t���Ƃ����d�_�́A�@�i�̒�q�ł������B�����������ɍO�܂����Ӑ^�̖嗬�A�܂�u�V��v�ɐG��Ă����\�����l������A�R���ł̗�����A�V��ɂďC����鉽������̜�@�Ɉ˂��Ă����\��������̂ł͂Ȃ��낤���B�Ő��ȑO�̓����ɂ�����V��̍O�ʏƂ������_�ɂƂ��Ă��A�����[�����ł���B ����A�w�C�s���L�x���`����ɂ́A�V������Z�N(754)��\�̏����́A�Ƃ��o�āu���ω������O���v�Ƃ����B�����̗D�k�ǂ�m���ɗ�������u���Ă������Ƃ͖��炩�ŁA���Ɂu���ɗ���v�͍L�����z���Ă����B����ɂ��̓T���ł��铂�̐��V�����剾���B��(���v�N����)��w�����ϐ�����F�L��~�����V��ߐS�ɗ���o�x�́A�ޗNJ��ɍł��ʌo���ꂽ�G���o�T�Ƃ����B���ɓV�����N(735)�ɋA����������(?-746)�́A�V���\���N(745)��᱗��~��̓��ɁA�V���V�c�E��������V�c�E�����c�@�̐��������A�O�����ɑ����O���̋~�ς��F��A�{�o��犪�̎ʌo�肵�Ă���B�`���ʂ�A���������ω������O�����Ƃ���A�R���ł̗���ɂ��Ă��A���ω��n�̎G���o�T�ɐ������V���F������K�v�����邾�낤�B �܂��w�����ϐ�����F�L��~�����V��ߐS�ɗ���o�x�́A�߉ޖ����u��ɗ����R�v�̊ϐ����̓���ɂ������A�ϐ�����F�����̋����āA�u�L��~�����G��ߐS�ɗ���(���ɗ���)�v������Ƃ̓��e�ł���B���̌����Ƃ��āA�a�C�∫�Əd�߂̖ŏ��ȂǗl�X�ȗ��v��������A����ɂ��̂��߂̍�@�E�d�@��������Ă���B���̈�߂ɁA�u�Ⴕ���̏O���A�����Ɋ�����߂�҂́A�O�����ɉ��ď։��������āA���̑ɗ�����u����A�K��������ʂ�����B�����̍ۂ�萶���̍ۂɎ���܂ł̈�̈��ƁA���тɊF�ȖŐs����v�Ƃ���̂����ڂ����B�O�����Ԃ̍։��ƁA�ɗ�����u��ɂ��A��̈��Ƃ��ł����A���肪�ʂ������Ƃ����B����͑ɗ���ɂ��ō߂ł���A�L���Ӗ��Ŝ����̖@�Ɋ܂܂����̂��낤�B �܂��A�ʌn���̐��ω��o�Ƃ��āA���̑���������q��(-653-)��w�����]�ϐ�����F�ɗ���_��o�x �A�y�т��ٖ̈�ł��铂�̓V���O����u(572-727)��w�����ϐ�����F�W�ɗ���g�o�x�ɐG�ꂽ���B�{�o�����łɓޗNJ��ɂ͏��ʂ���Ă���A���ʔN�オ�m�F�ł���Ƃ���ł́A�q�ʖV����N(737)�A��u��͓V�����N(735)�ł���B�{�o�́A�ϐ�����F�����ɉW�ɗ����������Ƃ�������A�ɗ���Ƃ��̌��������������B����ɓ�\��̈��Ƃ��̌�����������A�����đ�\���̌�ɂ́u�֝[���d�@(�q�ʖ�)�v�u��d�@(��u��)�v���������B�����ł́A�����ω���{���Ƃ���֝[���̉�d��@��������A�u���ɓ��ʎO���ɑ��̑O�ɍ߉߂�������ĎO��������ׂ��B���̐����̑��̏�ɔT�����������B�q�����r���̎��@�̎t�Ɖ揠�̐l���Ƌy�я��̏O���A���̌��ɋ����҂́A�ɑ�Ȃ�d�߂ɂĂ��ꎞ�ɏ��ł��ę�������Ȃ邱�Ƃ�(��u��)�v�Ƃ���B�֝[�����悫�A��X�̋���������Đ��ω������{���A�O�����̊ԁA�������邱�ƂŁA�C�s�ҁE��t�E�O���A���ׂĂ̍ߋƂ����ł���Ƃ����B�܂�������C���ꏊ���A�u���͎R�̊ՐÂ̏��ɋ����B�R�̒���ɍ݂�āA�`�����鏈(�q�ʖ�)�v�u�����A�����͎R�ԂɌ����A�����͟Ր�A�ѕ�(��u��)�v�Ƃ����B�����������R�o���̒��O�ɕ������悢�Ă��邪�A���邢�͂��̒d�@�Ɋ�Â����̂ł��낤���B�����Ƃ��A���̒d�@�͓�\�܈�Ƃ̊ւ�肪�R�����A���˂ɐ�����邱�Ƃ���A���̑}���ƌ����Ă���B�������A����͕�u��E�q�ʖ�Ƃ��Ɏ��^����A���e�E�\�����Ɏ�̑��Ⴊ�����邱�Ƃ���A�}���Ƃ��Ă����{�`���ȑO�ƍl�����A���łɓޗNJ��̕����҂����̒d�@��m�蓾���\���͏\���ɂ���B ��ɂ����������A����l�N(785)�ɂ́A�m�E��E�D�k�ǁE�D�k������Ɉ˂炸���āA�R�ю��@�ɂđɗ����ǂ݁A�d�@���s���邱�Ƃ��ւ����Ă���B�����Ɂu�ɗ���v�u�d�@�v�Ƃ��邱�Ƃɒ��ڂ���A�����̎O�����̗���Ƃ��āA��ɋ��������ω��ɗ�����u��A���邢�͐��ω���d�@�ȂǁA���ω��n���̎G���o�T�ɐ������V��ł������\�����A���Ȃ����ے�ł��Ȃ��B �ȏ�A�������R���ɂďC�����O�����̗����z�肵�Ă݂��B�����Ƃ��A�����̋V��Ɂu�畧�v�u�����v�̗v�f�����邱�Ƃ͂ނ��듖�R�ł���A�܂��V��̊������o�O�̋L�ڂƁA���̎��C�̏�ʂł́A��v���Ȃ��ꍇ�����邾�낤�B�]���āu�O�����̗���v����肷�邱�Ƃ͍���ł͂��邪�A�����̕����̍O�ʏE�����̎��сE�R����Ղ̈╨�����A�����Đ�������A�ޗNJ��ɕp�ɂɍs���Ă����u�\��ʉ��߁v�u�����߁v���̉��߉�A�V��ɂďC�����u�@�؎O�����V�v�u���ω���@�v�Ȃǂ̜�@�A�����Đ��ω��n���̎G���o�T�Ɋ�Â��ɗ���@��d�@�Ȃǂ����Ƃ��ċ�������B����������ɁA�����̑��̎R�яC�s�҂̎�����l�����A�ڍׂɂ��Ă͍���̉ۑ�Ƃ������B�@ |
|
|
��(7)����ɂ��_�_���{
�����͐_�_�����{���邽�߂ɁA�o����w�����ĎR���֓o�����B�����ĎR���ɂāA�O�����̊ԁA��������̗�����s������ł���B�Ƃ���A���̗畧�E�����̋V��Ƃ́A�܂��ɐ_�_�̂��߂ɏC���ꂽ�Ƃ������邾�낤�B�����őz�N�����̂��A�ޗNJ��Ɋe�n�Ɍ������ꂽ�_�{���̖��A���ɂ́u�_�g���E�̐_�v�̂��Ƃł���B ���ĒґP�V�����́A�ޗǑO�����A�_�_�͕��@���x�їi�삵�A�܂����@�ɂ���Y��E���Ƃ����v�z�̌���Ƃ��āA�_�{�������E�_�O�njo�E�א_���x�Ȃǂ��s���A��������̉���N��(901- 923)�O��ɖ{�n��瑐����萶���A���q���ɓ��肻�̋����I�g�D���听���ꂽ�Ƃ����B�Ҏ��͕K�������A�u���@���x�Ԑ_�_�v����u���@�ɂ���Y��E����Ƃ���_�_�v�ւƂ����_�i�̓W�J���咣�����̂ł͂Ȃ����A�̂��ɓc���������͂��̗��҂��n��E���i���قɂ���ʁX�̐_�i�Ƒ������B�O�҂ɂ����钆���̐_�́A�Ñ㍑�ƂƖ��ڂȊW�ɂ���A�K�������_�ł��邱�Ƃ̋�Y��\�������A���@���x�ю�삷��_�ł���̂ɑ��A��҂ɂ�����n���̐_�́A��Y����O���̂ЂƂƌ��Ȃ���A�����̔_���ɕp�������u�a��Јق�Ƃ�邽�߁A�_�g�𗣒E���ĎO��ɋA�˂���͂̉��肤�_�ł������Ƃ����B������u��@�P�_�v�Ɓu�_�g���E�̐_�v���A���Ƃƒn���̈Ⴂ�Ƃ��ė��������̂ł������B ����Ɂu�_�g���E�̐_�v�̔w�i�ɂ��Đ�s������Z�߂�ƁA�@��Y����n���Љ�(��Y����_�_)���I��p�ɂ��~�ς��悤�Ƃ��镧���҂ƕx���w�̈Ӑ}�A�A�����̐_�_�M��V���̕����Ɏ�荞�����Ƃ��镧���҂̈Ӑ}�Ƃ�����_�ɗv��ł���B�����Ēn���̐_���K���Ɋւ���������҂́A��Y����Љ�(�_�_)���~�������s�҂Ƃ��āA�������͕������L�߂�z���҂Ƃ��đ������A���̗����I�ȈӐ}���_�{���o���̌����͂Ƃ���Ă���B �����A�w�����蕶�x�ɋL����鏟���̎��Ⴉ�炷��ƁA���̐_�_�ς͏�L�̉��߂ɂ͝��܂�Ȃ���������B��ɂ��������悤�ɁA�����͓���ɍۂ��āA��ᢐ��H�A��g�_���L�m�A��@��S�B�䏊�����S�y�����A�c���R��ਐ_���{�A�Ȑ��_�ЁA�`�Q�����B��P�_���ЁA�ŗ������A�R���O���A���ʉ��B���s���R���A���s�����B�Ƃ̐���𗧂Ă��B���̗v�_�́A�@�O����R���ɕ����A�_�_�����{���A�_�Ђ����߁A�O���̍K�����肤�A�A�P�_�E�ŗ��E�R���ɁA�o�����鏟���̉������肤�A�B�������g�̕����肤�A�Ƃ̎O�_�ɓZ�߂��邾�낤�B ���̂����@�ɂ��āA�����R�̐_�_�͒��ړI�ɂ́u�_�g���E�v��\�����Ă͂��Ȃ����̂́A�O��ɂ���ċ��{����邱�ƂŁA�_�Ђ����܂�A�O���ւ̍K�������҂���Ă���B�c�����̕��ނ��炷��A�u�_���ɕp�������u�a��Јق�Ƃ�邽�߁A�_�g�𗣒E���ĎO��ɋA�˂���͂̉��肤�_�v�ƍ\���I�ɂ͈�v���Ă���B�R���ł̎O�����̗���ɂ́A�O���Ƃ��Ă̓����R�̐_�_�̍߂��������Ƃ����Ӗ����������������̂Ɛ��������B�����ɁA��Y����n���Љ�(��Y����_�_)���I��p�ɂ��~�ς��悤�Ƃ��镧���҂ƕx���w�̈Ӑ}��z�肷�邱�Ƃ��s�\�ł͂Ȃ��B�����A�A�̏C�s�҂���������P�_�E�ŗ��E�R���Ƃ������T�O�A���邢�͇B�̏C�s�҂̕��E�����s�Ƃ������v�_�́A���܂܂ŏ����̐_���K����_����ہA���߂�����Ă�����������B �܂��A�ł́A�P�_�͈З͂𑝂��ďC�s�҂����삵�A�ŗ��͖����A�R���͐擱���āA�����̓o�����ʂ������悤����������Ă���B�����őP�_�ɉ����āA�ŗ���R���ɑ��Ă��A�C�s�҂̎x��������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��ׂ��ł���B�����K�������P�_�ł͂Ȃ����݂ɂ��āA�@���ɗ���������ǂ����낤���B����ɂ́w�����蕶�x�̖`���̔�g���Q�l�ƂȂ낤�B�h�ژh�ԁA�ِl���s�B�B�������A�앨�z�݁B���Ȉِl�m��A���ȗ앨���Y�B毓k�R���B�����_�V�B �u�h�ځv(�{��R)��u�h�ԁv(��h�R)�ɂ́A�u�ِl�v���s���A�u�B���v(���ߔk�B���r)��u�����v(�����r)�ɂ́A�u�앨�v���݂�B�����ł̓C���h�̗�R��쐅�������āA�����Ɂu�ِl�v���Z�݁A�u�앨�v���h���Ă��邱�Ƃ������Ă���B�ʏ�A�����I�ȉ��߂ł���A�u�ِl�v�Ƃ͕���F���A�u�앨�v�Ƃ͌�@�̗����Ȃǂ��w���B�����A���̈ꕶ�͎R�����f���鏟�n�ł�������R���g�I�ɐ������Ă���ƍl�����A�ʏ�̈Ӗ��ɉ����āA�u�ِl�v�Ƃ͓����R�̐_�����A�u�앨�v�Ƃ͓ŗ���R���ȂǓ����R�ɏZ�މ��������Úg���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�����R�ɂ́A�R�̐_���⏔�X�̗앨���Z��ł���B�����͓o���ɍۂ��A����炪��Q�������邱�ƂȂ��A�t�Ɍ�蓱���ė~�����Ɗ���Ă���̂��낤�B �ŗ���R�����A�Ȃ��C�s�҂��x�������邩�ƌ����A�����炭����̇@�ɋ������A�_�_���{�Ɗւ�肪���邾�낤�B�����́A���@�ɂ��_�_�̋��{��\�����Ă��邪�A���̐_�_�ɂ́A�����R�̐_���͂��Ƃ��A�ŗ���R���Ȃǂ̗앨���܂܂��̂ł͂Ȃ����낤���B�܂�_��͋�Y����O���̂ЂƂƌ��Ȃ���A�C�s�҂������̖@�ɂ���Ă��̍߂�ł��A�_������̏o���Ɛ_�Ђ̑������肤���ƂŁA�_��͂�����x�сA�C�s�҂����삷�鑶�݂ƂȂ蓾��ƍl����ꂽ�̂��낤�B���������{����_�ƁA��������蓱���_�Ƃ́A�����̐_�������̂ł����āA�_�͏C�s�҂̋��{����Ƃ��ɁA�C�s�҂����삷����̂Ɨ��������B �����ł���A�c�����̂悤�Ɂu��@�P�_�v�Ɓu�_�g���E�̐_�v�𑊗e��Ȃ��_�i�Ƃ��錩���ɂ͋^�₪������B�����͕K���������Ƃƒn���Ƃ������_�œ����_�i�ł͂Ȃ��A�_�̗����ʂƍl���������Ó��ł͂Ȃ����낤���B�_(�ŗ���R�����܂܂�邾�낤)�͐_��(�Z���̂����̓V��)�Ɋׂ����O���ł��邩��A����@�ɂ���ċ~���Ƃ����l�����ƁA���Ƃ��_���ɂ������Ƃ��Ă��A�l�����͏��ꂽ�З͂�L���Ă��邩��A���@�ɂ���Ă��̈З͂𑝂��ĉ�����肤�Ƃ����l�����́A����������_�ϔO�ł��낤�B���݂ł��A�Ⴆ�ΐ^�������̏C�@�̂����A�_�_�ɖ@���^����u�_���v�Ȃǂł́A�_�_�́u���Ɠ����v�Ɓu�Ќ��{���v���F�邱�Ƃ�v�_�Ƃ��Ă���A���̓�ʂ̐_�ϔO�́A���݂܂Ōp������Ă�����̂ƌ����悤�B �܂��B�ł́A�u���Ⴕ�R���ɓ��炸�A�������ɂ͎���܂��v�Ƃ��āA�o���͏����̕��ɂƂ��āA�K�v�s���ȏC�s�ł��������Ƃ��m����B���̈ꕶ�ɂ��A�����̓o���́A���ɓI�ɂ͎��g�̕����߂������s�ׂł������Ɨ����ł���B���Ȃ��Ƃ��A��C�͏����̓����R�o���������������Ă����B��C�́w�����蕶�x�̔蕶�ɂāA�����̓����R�����]���āA�}���l�M�A��������B������巘�A�P���S�߁B�_���Ќ�A�𗗎R�́B�Əq�ׂĂ���B�u�l�����Ē����ɍ���ɓ���v�Ƃ́A�����R�ɓ��ݓ����āA���̎R���ɓ��邱�Ƃ������B��C�͓������w����W�x�����́u�R�ɓ��鋻�v�ɂāA�u�l�����đ����@�g�̗��ɓ���v�Ɨ@���Ă���A�R�тɓ��ݓ��邱�Ƃ́A���ɒʂ�����̂ƍl���Ă����悤���B���������̓���́A�u�_���̈Ќ�v�ɂ��Ƃ̔F���ł���B �ޗNJ��̐_�{���o���̌����͂Ƃ��āA�����҂̗����I�ȈӐ}�݂̂��w�E����Ă��邪�A�����ɂ͓��R�A�R�тɓ��ݓ������C�s�҂̎����I�ȈӐ}���ʼn߂��ׂ��ł͂Ȃ����낤�B�C�s�҂��R�тɓ��ݓ������傫�ȗ��R�̈�́A�����C�s�̂��߂ł������B�Ⴆ�Βq��́w�V�䏬�~�ρx�ɁA�T����C���̂ɓK����ꏊ�Ƃ��āu��ɂ͐[�R�ɂ��āA�l��₷��̏��Ȃ�v�Ƃ���悤�ɁA�[�R�́u�Ջ��v�̑��Ƃ���A�����҂͏C�s�̏ꏊ��[�R�ɋ��߂��B���邢�͏����̏ꍇ�A�w�،��o�x�u���@�E�i�v�ɐ������P�����q�̗V�s���ɖ͂��A��ɗ��R��̊ω���F�Ɍ��܂݂���Ƃ̔O����������̂�������Ȃ��B�ł͂Ȃ������Ċ댯��`���Ă܂ŁA�[�R�ŏC�s������A�R��̕�F�։y�����悤�Ƃ���̂��ƌ����A���ɓI�ɂ͕����C�s�̂߂����Ƃ���A���Ȃ킿�������߂Ă�������ł��낤�B �������߂ĎR�ɓ��ݓ���C�s�҂́A�Â��͓����ɂ�������悤�ɁA�R�̐_��ɑ���ؕ|�̔O������Ă������ł���B�R�̐_�삪�C�s�҂Ɋ�Q�������邱�ƂȂ��A�t�Ɏx�����鑶�݂ƂȂ邽�߂ɂ��A�_�_���{�͕s���ł������B�����͓����R�o���ɍۂ��A�܂��͎R�[�ɂĈꎵ���̓njo�畧���s���A�R���ɓ����ĎO�����̗�����C���A�����R�̐_�_�����{���Ă���B���̈Ӑ}�́A�_���Ɋׂ��Ă���_�̍߂�������A�_������̏o���ƁA�_�Ђ̑������肢�A�L���͏O���̍K�����A���ɂ͎R�тɓ��ݓ���C�s�҂ւ̉�������҂��Ă������̂ƍl������B�@ |
|
| ���V��ΔȂɐ_�{�������ďZ�����C�s���@ | |
|
��(1)�C�s�̏��n�Ƃ��Ă̎R����y
�����́A���̓o�������N��̉���O�N(784)�A�Ăѓ����R�ւƓo�����B�O��́A�R���ɂĎO�����Ԃ̂ݗ�����Ă����ɉ��R�����̂ɑ��A�l�x�ڂ̓���͒����ɋy��ł���B�w�����蕶�x�ɂ́A������O�N�O�����{�A�X���S�܉ӓ��A���ޓ��粁B�l����{�����ꏬ�D�B�����A�O�ځB���^��O�q�A���ΗV���B�Ւ��l�ǁA�_��쑽�B���Ő��ŁA�ė�����B���鋻�P�A������F�B���F�������O�\���P�A�����O�\���P�B���F�V���A���ԕx���B���X�����B�����Ώ\�܋����B�����k����ΎO�\�����B���ᶔ��A揔�s�@��B�q�����r�������n�A�������A���H�_�{���B�Z���C���A�`䒎l�J�B�Ƃ���B�����͎O�����{�ɓ��A�ܓ��Ԃ����ē�̔Ȃɓ������B�l����{�ɂ͈��z�̏��D��A��E�O�l�̒�q�Ƌ��ɌΏ��V�����Ă���B����ɐ��A���A�k�����ĉ������A�ł����ꂽ���(���E���T����)�Ȃ̏��n�ɐ_�{�����������A�����Ɏl�N�Ԏ~�Z���ďC�s�����Ƃ����B �O��̓o�����A�܂��͓��������ĎR�̐_�_�����{����ƂƂ��ɁA�R�̏�i����T�ς���̂��傽��ړI�ƌ�����̂ɑ��A����̓o���́A���{�i�I�ɏC�s����̂ɓK�ȏꏊ�����đI�肵�A�����ɂ킽��C�s���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����ƌ����悤�B �����ł܂����Ƃ������̂́A�C�s����̂ɓK�ȏ��n�̏����ł���B���̏�i�ɂ��āw�����蕶�x�́A����Α��ɐ������A�[�s���B��N�����A�Ր����X�ΊW�B�S���w���A␛�������B�܍ʔV�ԁA�ꊔ���G�F�B�Z���V���A���������X�B���ߕ���A����Y���A�U���@��A�f���ʋ��B�������ՁA坻�Q���ہA�܉����t�V�C�A�����W�W�����B�����_���A������ɔV㰗��B�����d�x�A�ɝɕ����V�c���B���r�������A�m�����V���q�B�d���A�S�Ւq�V�݉�B�������n�A�������A���H�_�{���B�Z���C���A�`䒎l�J�B�Ɠ`����B���̉ӏ��͎l�Z�w�U�̂ɂ��C����傪�����B�����́A��ΔȂ̏��i���������邽�߂̋Z�I�ł���Ƃ̉��߂���ʓI�ł���B�m���Ɍ֒����ꂽ�\���͑����ł��낤���A�P�Ɂu���R�̕������Z���v���������Ă��邾���ł͂Ȃ������ł���B �܂�A���鎩�R���Ɂq�����r���ς��Ă����悤�ȁA���邢�͎��R������q�����r����������Ă���悤�ȁA���������\�����Ȃ���Ă���B�Ⴆ�A�u��N�̏����v���u�ΊW�v�A�u�S�̞͂w���v���u���O�v�A�u���߁E����v���u��̉��E�ʂ̋��v�A�u�����E�u�Q�v���u�ՁE�ہv���u�܉��E�����v�Ȃǂ́A���R������āA�����Ɂu��y�̏����v��\���Ă�����̂ƍl������B�Ⴆ�ΛL�`�̋T䢎O���������Y(350-409��)��w����Ɍo�x�ɐ�����y�̏�����v��Ǝ��̔@���ł���B�u���琬��s���◅�Ԃ��߂���A��������������������r���L����B�����ɂ͎���ɑ������ꂽ�O�t�������A����̘Z���ə֑ɗ����~�肻�����B�����Ď�X�̊��������Ȑ��ł�������A�s���◅�Ԃ̎���̋ʂ͕��ɗh��Ė��Ȃ鉹��t�ł�B�v�����́A��ΔȂɁu��y�v���ς��Ă����̂ł͂���܂����B�����炭��C�͂��̂悤�ɗ����������ł���B ���ɓ����R�́A����̂ɋɂ߂č���ŁA�R�ƌ��D��Ȃ���i�ɏ��ꂽ�u�R�����f�v�̒n�ł������B�����ȂǓ����R�ɓo���������҂́A���̏��Ԃ��Ɋώ@���A�܂��ɂ��̎R���u�R�a�댯�ɂ��āA�ޒJ敧�X���B�R���ɒr�L��āA���̐��̐��߂邱�Ƌ��̔@���v�u�؉ʎ��сA�F�ȕՖ����A�r���A���������v�ȂǂƂ����u�ω���y�E��ɗ��v���̂��̂Ɗ��������̂ł��낤�B �܂��u���E�_�v���u���E���v���u��Ɂv(��ɗ���)�A�u���E�d�v���u���E�x�v���u�����v(����F�̉����E�����V�q)�Ȃǂ́A���R������Đl�m���z�����u�����v����������邩�̔@���ł���B�Ȃ��u��ɗ����v�͎����R�ȂǂɌ����间���M���A�܂��u�����V�q�v�͋�C���C��������F�������@��z�N������B���邢�͏����ɂ��A����������s�̎R�яC�s�҂Ɠ��l�A�u�����v��u�������@�v�̐M���������̂�������Ȃ��B�܂��㐢�́w�C�s���L�x��w���n���L�x�ɂȂ�ƁA���ꂼ��u�����E�l�{�����E�[���剤�v�u�������@�E�����V�q�v�ȂǁA�u���v�Ɓu���v���߂����̓I�ȕ���ւƓW�J���A�����͒�q�����Ɂu�A�ł����̗��_(�[���剤�E�����V�q)�ɋA�˂��ׂ��v�Ƃ������킵�߂Ă���B���̖G��͂��łɁA��C�́w�����蕶�x�Ɏ�����A���邢�͏����܂ł����̂ڂ�\����������A�����ɂ�����J�R�`����l�i�_�̌������b���A�㐢�̍r�����m�ȕt��Ƃ����������ɂ͂����Ȃ��̂ł���B ����Ɂu�r���̉~���v���u�����̋��q�v�A�u�̌d���v���u�Ւq�̍݉�v�Ȃǂ́A���R���̒��Ɂu�����̋����v��\���Ă���悤�ł���B��ɋ������w����Ɍo�x�ł́A��y�̒��͂��̉�Ȗ����ɂ���āA�܍��E�ܗ́E����E���������Ȃǂ̖@���������A����͕��ɗh��āA���̖��Ȃ鉹���҂͎��R�ɔO���E�O�@�E�O�m�̐S����Ƃ����B����Ɠ��l�̍\�}�������Ɍ��邱�Ƃ��ł��悤�B �����Ƃ��A�Ō�̋����Ȃǂ́A������F�̏���S�����@���̈�ؒq�q�Ƃ�������C���咣���閧�������Ɉ����Ă���A���̂܂����̐S�ۂƂ��邱�Ƃ͓�����낤�B�����A�����̕\���́A���������n�Ƃ�����̔Ȃ��A�P�ɕ������Z�Ȍi���ł���Ƃ��������ł͂Ȃ��A����������i����@���I�ȊϔO��z�N������ɑ��������ꏊ�A�����Ȃ�u�R���̏�y�v�ł��������Ƃ��������Ă�����̂Ǝv����B ����ɕt��������Ȃ�A���̏��n�͒P�ɕ����I�ȕ\���݂̂ɂ���ċL�q����Ă���̂ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�u������R�߂����Đ_�A�����邱�Ƃ���v�u���m�炸���ɂ�����B�_�l�霂Ƃ��đ����邪�@���v�Ȃǂ́A�R���⏟�n�̗l�q���A�����ł����_�勫�Ɍ����Ă��邵�A���邢�́A�u�m�͎R�Ɉ˂�A�q�͐��ɑ����v�u���i�������i���Ċy���ݒ��ɑ���v�Ȃǂ́A�w�_��x�ɐ������l�̂���������p���Đ������Ă���B�����͒����ɗR������u�_��v�z�v��u�R���v�z�v����̉e���𑽕��Ɏ����̂ł��낤�B�����̕����҂́A�ϋɓI�ɎR���ɏC�s�̏�����߂Ă��������A����ɓK����ꏊ�Ƃ́A�P�ɕ������Z�Ȍi���Ƃ��������łȂ��A�����I�ȏ�y��z�N������ꏊ�A����ɂ͒����v�z�ɐ�����闝�z�������܂A�L���Ӗ��ł̏��n�ł������ƌ���ׂ����낤�B�@ |
|
|
��(2)�_�{���̋@�\
���āA�����͂����������n�ɉ��������ĂďC�s�ɗ�B�O��͒Z���Ԃ̓o���ł������̂ɑ��A��N��̍���̓���͒����Ԃɋy�B�R�e�����A���n�ɉ������������A���N�Ԃ����Ɏ~�Z���ďC�s���Ă���B�����炭�͎x���҂āA�������܂߂��l���A���邢�͎������A����Ȃ�̏�����������ł̎��Ƃł������̂��낤�B���̉������u�_�{���v�Ɩ��t����ꂽ���Ƃ́A�ޗNJ��ɑ����������ꂽ�e�n�̐_�{���Ƃ̊֘A�ŁA�����[�����ł���B �u�_�{���v�Ƃ����ƁA�_�_(�n���Љ�)�̋�Y�@�ɂ���ċ~�����߂̎��@�A�_�_�Ɏd���邽�߂̎��@�ȂǁA����Η����I�ȈӖ������ŗ��������ꍇ�������B���������̏ꍇ�A��������āA�[�R�̏��n�ɂďC�s���邽�߂̎��@�Ƃ��������I�ȈӖ������������ł���B��q�����悤�ɁA�����͓����R�ɓo�����A���@�ɂ���ĎR�̐_�_�����{���邱�ƂŁA�_���Ɋׂ����_�̍߂�������A�_������̏o���ƁA�_�Ђ̑���������Ă����B����ɂ��A�O���̍K���Ɠ���C�s�҂ւ̉�������҂��Ă����̂ł���B�������������̐��肩�猩�Ă��A�����͎R���Ɂu�_�{���v�����āA�R�̐_�_�����{���A�_�_�̉���̂��ƂɏC�s�ɗ�ƍl������̂ł͂Ȃ��낤���B ����܂���ƁA���������Ă��u�_�{���v�ɂ́A���Ȃ��Ƃ���ʂ̋@�\���z�肳���B��ɂ͐_�_�����{���A�_�_�̓����ƏO���̍K�����F�肷��Ƃ��������I�ȑ��ʁA��ɂ͐_�_�̉���̂��ƁA���g�̕������߂ďC�s����Ƃ��������I�ȑ��ʂł���B��敧���ɂ����ẮA���������~�����|�Ƃ��Ă���A�_�{���̋@�\�Ƃ��āA�����ʂ͂ǂ�����s���ł���A�݂��Ɍ��т��Ă��邾�낤�B�����ōs��ꂽ�C�s�̓��e�ɂ��ẮA��̓I�ɂ͖��ڂł��邪�A�w�����蕶�x�Ɂu�]���E���t�v�ɂĊ���������A�u�E���v��H���A�u�ԑ��E�����v���ϔO����Ƃ��邱�Ƃ���A�����炭�͑����E���߁E�e�H�ɂāA�C�T�E�C�w�ɗ���̂Ǝv����B���̈Ӑ}�́A�_�_�̓����̂��߁A�O���̍K���̂��߁A�Ђ��Ă͎��g�̕��̂��߂́A���������~�����߂��������C�s�ł������ƌ����邾�낤�B�@ �E�L�̐����́A�ЂƂ菟�������łȂ��A������̊e�n�̐_�_���{�̎���ɂ����Ă͂܂邾�낤�B�����ł́A�ɐ���_�̂��߂ɑ�ʎ�o�̏��ʂ��s�������퓹�s(���v�N����)�ƁA�w���{��ًL�x�ɓo�ꂷ����������b��(���v�N����)�̎�������������B�܂����퓹�s�́A�V�������N(757)�A�����ɋA�˂��Đ������̂āA�R�x�ɓ����ĊՋ����Ă����Ƃ��뗋�d�ɑł����B�����V���ƌ��āA�_�̂��߂ɑ�ʎ�o���ʂ����Ƃ𐾂��ƁA���d���Â܂萳�C�����߂����Ƃ����B�m�������U���ď��ʂ��ꂽ��ʎ�o�̉����ɂ́A�u����킭�́A�_�Ј��B�A���d���n�A���얳���A�l���J��ׂ̈ɁA�h���đ�ʎ�o�Z�S�����ʂ�����Ɨ~���B�q�����r�����Ċ�킭�́A����_�ЁA�g��̈Ќ�����A�����吹�̕i�ɓo���v�Ƃ���B �܂�����b���́A��T�N��(770-780)�A�ߍ]����B�S�̌��Ԃ̐_��(���E���ꌧ��F�s�O��R)�̑��̓��ɂďC�s���Ă������A�ߋƂɂ���ĉ��̐g���Č��_�Ђ̐_�ƂȂ����ɉ�_���A�u���̐g��E��ׂɁA���̓��ɋ��Z���ĉ䂪�ׂɖ@�،o��ǂ߁v�Ƃ̐_����B���̌��t���R�K���̒h�z�E���a��@�t�ɍ��������A���̌��t�Ƃ��ĐM�Ȃ������B����Ɩ��a��@�t�̒m�����Z������ǂލ݂ɉ�������A�哰�╧���E�m�V�����Ƃ��Ƃ��j�ꂽ�B���a�ƌb���͐_����M���A�ɉ�_�̂��߂ɓ����ĘZ������ǂނƁA�_��͐��A����A���͖����Ȃ����Ƃ����B �ނ�͂�������A�_��ɂďC�s�����Ă����ہA���≎�̏��ɋ����B�����_�̓{��ƎƂ߁A�ʌo�E�����E�njo�ȂǕ��@�ɂ��_�_�ւ̋��{���s���Ă���̂��B���̈Ӑ}�́A�u�_�g��E��v�u�吹�̕i(����)�ɓo��v���ƁA���Ȃ킿�_�_�̗��Ɠ����ɂ���A�Ђ��Ắu���얳���v�u�l���J��v�ȂǁA�����O���̍K����������Ă����B����ɂ��A�_�̓{��͒��܂�A�_��ł̏C�s�����������\�ƂȂ��Ă���B�����Ȃ�A�_��ł̕����C�s�ɐ_�̏��F����ł���B�E�L�̓��́A�ʌo�E�����E�njo�ł����āA�_�{���̌����ƌ�����ł͂Ȃ����A���@�ɂ��_�_�ւ̋��{�ɂ��A�_�_�̓����E�O���̍K����������A�Ђ��Ă͕����҂̏C�s���ۏႳ��Ă���A�\�}�Ƃ��Ă͋��ʂ������̂ł��낤�B ���ɂ������͊e�n�ɂāA�_�{�������E�_�O�njo�E�א_���x�ȂǁA�l�X�ȕ��@�ŁA���@�ɂ��_�_�ւ̋��{���s���Ă����B���̈�X�̌����͑����������������A�����̌��Ă��_�{���Ɍ�����@�\�́A���̍ۂɏ��Ȃ��炸������^������̂Ǝv����B�@ |
|
| ���W���̌�̗����O�����@ | |
|
��(1)�����̎w���ҁE�z���ҁE���҂Ƃ��Ă̏���
�����́A�����R��ΔȂ̐_�{���ɂāA���Ȃ��Ƃ��l�N�ȏ�(���邢�͏\��N�ȏ�)�C�s������A�R���~��ė����O���ɗ�Ƃ����B�w�����蕶�x�ɂ́A��H���߁A�ՒB���V�B������N���A�����c�長�V�A�֔C��욠�u�t�B�����L���A���S�����B�������Ԛ����ɁA���s��S��R�B�A�����ށA�����O���B���哯��N�A���L�z��B�B�i�ߖ@�t�F�J�A�t�����ɗ��R�F禱�B�䎞�ÉJ霶輁A�S���L�o�B���L�ŋƁA�s�\�~���B�Ƃ���A��썑�u�t�ɔC�����ꂽ���ƁA�s��S��R�ɐ��ɂ��������ė����E�O���������ƁA��鯂ɍۂ��č��i�̗v���ɂ������R�ɂĉJ���F�������Ƃ��`�����Ă���B �u�u�t�v�Ƃ́A�͂��߂͍��t�ƌĂ�A�o�_�̍u���A�����̏����A�����̊ēȂǂɂ��������m�ł��� �B������(697-707)�ȍ~�A�����ɍ��t���u���ꂽ���A�����N(783)�ɂ͒������������A��E�㍑�͑卑�t��l�Ə����t��l�A���E�����͍��t��l�ƂȂ�A���O�N(784)�ɂ͔N����Z�N�ƒ�߂��B����ɓ��\�l�N(795)�ɂ͌ď̂��u�t�Ɖ��߁A�u���̍˂���҂��N�p���A������l�̏I�g�̔C�ƂȂ����B���\�Z�N(797)�ɂ͍u�t�������̏��������ˁA����\�N(804)�ɂ́A�u�q�s�̂����A�l�̎t�ׂ�Ɋ�������ҁv���I��A�C�s�҂ւ̋��������d�����ꂽ�B����ɓ���\�l�N(805)�ɂ͍ĂєC����Z�N�Ƃ��A�l�\�܍Έȏ�́u�S�s�߂ɒ�܂����v�҂�₵�āA�����̏��������i�Ƌ��Ɍ��Z���邱�ƂƂȂ����B���m���ȍ~�A���Ɋ������ɂ́A���@��m��̎�p���ւ̊��҂ƈؕ|��w�i�Ƃ��āA�m��̍˓������߂A���Ƃ̐��͂���������{�Ƃ�ꂽ�B���̎����ɔN���x�҂�u�t�̐��x�����s���낵�Đ������Ă䂭�̂��A���̈�ł���B�R�яC�s�ɗ�����̖����͒���܂ŒB���A��썑�u�t�ɕ▽���ꂽ�Ƃ����B���ꂪ�������Ƃ���A�����͎R�яC�s�݂̂Ȃ炸�A�o�_�̍u���ɂ����ꂽ�u�q�s�v����̑m�ł��������Ƃ����������B�����Ă��̔C���̎����́A����\�l�N(795)�ȍ~�A�~�Z�����̂͏�썑�����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��A��썑�����̖k�����ނ���ԏ�R�́A�������J�R�����Ƃ̓`�����c��B�ԏ�R�͏�썑�̏ے��Ƃ������ׂ��R�ŁA���̎R�[�𒆐S�ɐ����╶�����W�J���A����ȌÕ��⊯�ɁA���@���������ꂽ�B�R�[���ӂɂ͏����䂩��̎��@�����_�݂��Ă���A�����ɂ͏�썑�Ƃ̊W���������\�����������Ă���B �܂��A�s��S��R�ɉ،����ɂ��������A��������_�ɗ����E�O���ɖ��߂��Ƃ����B���̋�̓I�Ȋ����͒肩�ł͂Ȃ����A���ēs��S�ł������Ȗ،����������R�n�̓��[�ɂ́A�����J��Ƃ���鎛�@���_�݂��Ă���B���ł��s��S�s�꒬�̒��j�Ձu�،����v�́A�w�����蕶�x�̓`����u�،����Ɂv�ɔ�肳���B�m�͓����Ȃ����A�����͓����R�ł̏C�s���I�����̂��A�����R�n���[�̎����s�A�������A�s�꒬�ȂǁA���s��S�𒆐S�ɁA�h�z�̎x���ď����ɂĊ����������̂Ɨ\�������B����ɁA�哯��N(807)�ɂ͉��썑�ɝ�鯂�����A�����͍��i�̗v���ɂ���ē����R�ɂċF�����A�������������Ƃ����B����ɂ��A���������炩�̕��@�ʼnJ���F�������Ƃ����������B�w�����蕶�x�ɂ́u���̒��A�_�̖��A������ɂ�㰗�����Ȃ�v�Ƃ�����߂����邪 �A��ɂƂ͐��_�ł����ɗ������Ӗ�����B������ɓ�s�m�͑�a���̎����R���ɂāA�J���F���Ă���A�����ɂ������������܂����l�ɁA�����R�ɂĉJ���F�����\���͏\���ɂ���B�܂������R�̎R����Ղ���́A�������|�{�^�O�؋n�ȂǓޗNJ��̖����@��ƌ����镧��o�y���Ă���A��������̖����n�̏C�@���s��ꂽ���Ƃ��������ꂤ��B�Ȃ��A�����ŏ����́u�@�t�v�ƕ\������Ă��邱�Ƃ���A�x���Ƃ����̎��܂łɂ́u�@�t�ʁv�ɏ����Ă����ƍl������B ���āA���������R����������́A�����̎w���ҁA�z���ҁA�����Č��҂Ƃ��Ă̏������ɂ��āA���o���Ȃǂ́u���m�Љ�̖����m�I�ȍs�ґ��Ƃ��āA���Z���ɏC������ĕ`����Ă���v�Ƃ��āA�S����舵�����Ƃ��Ȃ��B����������́A�����̕����ɂ��āA�����E���߁E���m�E�厛�@�E�w��Ƃ���������ƁA�n���E�����߁E���x�m�E�R�ю��@�E��p�Ƃ�����������A�Η��I�ȗ���Ƃ��Č���邱�ƂȂ��A���s���ēW�J���Ă����Ƃ��������T�O��O��Ƃ��邩��ł���B�����͖������Ɍ�҂ƌ��Ȃ���A�O�҂Ɋւ�鎖�т͌㐢�̕t��Ɨ������ꂽ�̂ł���B �������A�����̕����ɂ��ẮA���ۂɂ͐�̓Η��I�Ȍ����Ŕc���ł��Ȃ�����������A���łɋ^�⎋����ċv�����B�m���̎R�яC�s�Ɋւ���A���������m(705-793)��C�~(771-835)��ɂ�鎺���R�������ƏC�s��C�@�A�������얽(750-834)�������Α�(754-827)�ɂ���h�R�ł̋������@�C�@�Ȃǂ͗ǂ��m����B���邢�͕�T�O�N(772)�̏\�T�t�ݒu�A�����V�c�ɂ���(718��-795)�ւ̉����A����V�c�ɂ�錺�o(738��-818 )�⒮��(���v�N����)�ւ̎���Ȃǂ́A�R�яC�s�҂̖���������ɒB���A�^�E�x������ł���B ���̂悤�ɁA�����̑m���ɂ́A�ϋɓI�ɎR�тɓ��ݓ���A��������ĂďC�s��C�@���s���҂������B���Ɏ������łɂ��ď��ꂽ�R�яC�s�҂ɂ́A���̎����I�ȁu�o���Ԑ��v�Ɨ����I�ȁu��p���v�Ɍh�ӂƊ��҂����A�א��҂�������ւ�A�l�X���u��F�v�Ə̂��ꂽ�̂ł���B �����̏ꍇ���A�������������t���ɂĎ�������m�ł������\���͍����A����Ȃ�C�s�̏������R�ɋ��߂āA�_�{�������Ă��ƍl������B�u��H�̒ߐ��A�V�ɒB���Ղ��v�Ƃ���悤�ɁA���̓��s���F�߂��āA������u�t�ɔC������A���邢�͒h�z�Ď��@���������A����ɂ͗v�����ċF�����s�����Ƃ��Ă��A����s�����ȂƂ���͂Ȃ��B���N�ɂ킽��R�яC�s���������сA�����L�͎҂ɂ���w�̏^�E�x����w�i�Ƃ��āA�u�t�E���@�����E�z���E�C�@�Ƃ����������̊������W�J���ꂽ�\���͏\���ɍl������B������P���ɔ����ߓI�Ȏ��x�m�ƌ��Ȃ����Ƃ͑Ó��ł͂Ȃ����낤�B�����R�R����Ղ��o�y�����╨�́A�������L�͂Ȏx���҂������҂ł��������Ƃ��������Ă���B �܂�����\��N(792)�A�`����@�t�ʎ{��(?-804)������ɎR�яC�s�҂ւ̎x�����肢�o���t��ɂ́A�R�яC�s�Ƃ͒P�Ȃ鎩���s�ł͂Ȃ��A�썑���l�Ƃ��������s�������������̂ł���Ƃ̌�����������Ă����B��C�́u�l�����ē��ɏ}���A�Y�R�Ƃ��ēƍ����A���ؔ\�������x���A�O�f����Ⴊ�߂Ȃ�B�C����Ƃ���̌����A�Ȃč����ɏV���v�Ƃ̔F�������l�ł���B�������g�̐S�ۂ͒肩�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A�u�����Ɏ��L��v�Ƃ����悤�ɁA�����R�ł̏C�s�́A���ʂƂ��ė����s�ɒʂ�����̂ł������B�������}���R�тɓ��ݓ����������́A���N�̎R�яC�s�̌����āA�Ăѐ����ւƗ����Ԃ����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł��悤�B�@ |
|
|
��(2)�����̎���
�Ȃ��ŔӔN�̏����ɂ��āA�w�����蕶�x�́A���A���ԓ�A�l�Ԉ՝́B�n�S�����A�l��㾁B���U�����A�\���L��B�O����ɔ��m���A�o�@�t�P�B���ޓ����B�����@�t�A�V�����V���L�A�v�������]�M�B�Ɍ��^�]�́A�Ŏ��s�ƁB�ۋ����|�B�Ɠ`����B�����ɏ����̌�F�W�̈�[��������B�܂�O�̉��썑�̔��m�ł������Ɍ��Ƃ̌𗬂ł���B��T�\�N(779)�̉���ɂ��A�����̔��m�́A��{�I�ɍ����Ɉ�l�u����A�C���͘Z�N�Ƃ��ꂽ�B�ɔ��m�ɂ��Ă͖��ڂł��邪�A���m�Ƃ��ĉ��썑�ɉ������Ă������A�����Ƃ̐e�����𗬂����������Ƃ��m����B�����͓����R�̏��i���L�������͂��������Ƃ�V���Ă����B�ɔ��m��ʂ��A��C�������ɏ���Ă��邱�Ƃ�m�����̂ł��낤���B�C���������ċA������ɔ��m����āA��C�ɂ��̎��M���˗����Ă���B�ɔ��m�Ƌ�C���A���m�̊ԕ��ł������Ƃ����B��C�͂�����Ŏ�������Ƃꂸ�A�w�����蕶�x���쐻�����B�n���̑m���A�����ɕ��C���銯�l�A�����Ē����̑m���Ƃ́A�l�I�𗬂̈�[���_�Ԍ��邱�Ƃ��ł���B �����͏���A���������Ɂu�]�S�v�܂莵�\�Ɏ���A�u�l�ցv�܂�l�傩��Ȃ�g�̂��������������B�O����ێ�U�����鎄���s�߁A�Ȃ��ׂ����͂��ׂĉʂ����I������Ƃ����B��C��������L�����̂́u�O�m�V�֏˔V�v�A�܂�O�m�ܔN(814)�ł������B�u�\���L��ʁv�Ƃ��邩��A�����炭�����菭���O�ɁA�����͂��̐��U��������̂Ǝv����B���Ɏ�����O�m�ܔN(814)���\�Ƃ���A���̐��N�͒x���Ƃ��V���\���N(745)�ƂȂ�A���₪�����葁���A���\���z���Ă����Ƃ���A���N�͏\�N�قǂ����̂ڂ邱�Ƃ����肤��B�Ȃ��w�C�s���L�x�́A�����̎�����O�m���N(817)���\�O�Ɠ`���A����ɏ]���ΐ��N�͓V�����N(735 )�ƂȂ�B �����̐��v�N��f�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��܂ł��A���悻�V����(735)����\���N(745)�̐���ŁA�O�m�ܔN(814)���ɁA���E���\�̒�����S�������ƌ��ėǂ����낤�B������t�Z����ƁA���߂ē����R�ւ̓o�������݂��̂���E�O�\��̍��A�o���ɐ��������̂��O�\��㔼����l�\��㔼�A�R�яC�s�̋@���n���ču�t�ɔC�����ꂽ�̂��܁E�Z�\�̍��A�����R�ʼnJ���F�����̂͘Z�E���\�̍��ƂȂ�B�@ |
|
| ���l�@�����Ɂ@ | |
|
���썑�F��S�ɐ��܂ꂽ�����́A�Ⴍ���Đ������}�����������u�������B�����炭�͓����o���R�Ȃǂ̎R�тɐg���A�D�k�ǂƂ��ďC�s�ɗ���̂Ɛ��@�����B�₪�ĐV�݂��ꂽ�����t���̉��d�ɂĎ�����A����E��u�ƂȂ����\���͍����B�����̓����ɂ͊Ӑ^�̖嗬�ł��铹���̓V�䋳�c������A����ɂ͒��N��������̋A���l��ʂ��ĉ،��������ꂽ�Ƃ̌���������A�������u�V��v�u�،��v�Ȃǂ̈ꕧ��ɐG��Ă����\�����l������B
���썑���ނ�������R�̎R������́A��ʂ̈╨���o�y���Ă���B���ɓޗǂ��畽�������ɂ́u�R���̐����̊�̌E�n�v�ɓZ�܂�����\���`�������B����́w�،��o�x�ɐ����ω���F�̏Z���A�w�����蕶�x�ɋL�������̏C�s�n�ƍ��v����ꏊ�ł���A�����̎��ݐ��A�w�����蕶�x�̐��m���𗠕t���镨�ƌ��邱�Ƃ��ł���B�܂��Õ����ɔ�肳���╨���͂��ɏo�y���Ă���A�����ȑO�Ɏ�̐��҂������\�����l������B�����������̓o���͍�����ɂ߂邱�Ƃ���A�{�i�I�ȊJ�R�͓ޗNJ��ȍ~�̏����𒆐S�Ƃ��������҂Ɉ˂���̂ƌ��ėǂ����낤�B�܂��R����Ղ��ʎ��Ƃ��ɏ���Ă��邱�Ƃ���A�����̓����R�o���̔w�i�Ƃ��āA�ڈΖ��ɂ�鍑�Ƃ̎x����z�肷�錩��������B�����������ɖR�����A���̉\���݂̂���������̂́A�K���ł͂Ȃ��Ǝv����B �Ƃ���ŁA�����R�̌ď̂ɂ��āA�ޗNJ��̕����҂ɂ���ď��߂āu��ɗ��R�v�Ə̂��ꂽ�Ƃ�����ƁA�×����u��r�R�v�ƌĂ��M�̎R�ł������Ƃ����������B����������Ƃ�����I�ȍ����͖R�����A�ǂ�����\��������Ƃ̔F���ɗ��߂Ă��������B������ɂ���A�����R���u��ɗ��v�Ə̂��ꂽ���Ƃ͈Ӌ`�[���B�u��ɗ��v�Ƃ́A����Potalaka �̉��ʂŁA�ω���F���Z�ނƂ����R�ł���B�w�哂����L�x�ɂ́A�ώ��ݕ�F�Ɍ��܂݂��邱�Ƃ��肤�҂́A�g�����ڂ݂����ݓ�����A�����ɓ��B�ł���҂͋ɂ߂ď��Ȃ��Ɠ`����B�����̓����R�o���̈Ӑ}�Ƃ��āA�[�R�ł̏C�s�ɉ����A�R��̊ω���F�ւ̉y���Ƃ̔O�肪�������̂�������Ȃ��B ���������̓o���́A������ɂ߂��B��C�́A�댯��`���ē����R�ɝ����o�����������A����̌������R�X���z�������@�m�ɏd�ˍ��킹�Ă���B�����̑O�r�ɂ́A�[����ǁA�_���○�Ƃ��������R�I�������͂��������B�����炭�����͂������A�����R�̐_�_�̎d�Ƃƌ����̂ł͂���܂����B����͌Â��͓����ɂ�������A�R�̐_��ɑ���ؕ|�̔O�Ɉ˂���̂Ǝv����B�������߂ĎR�ɓ��ݓ���C�s�҂́A���̎R�ɏZ�ݏh��_��̂��Ƃ��C�Ɋ|���Ă������ł���B ���̂��Ƃ́A�������O�x�ڂ̎��s�ɍۂ��A�����R�̏��X�̐_�_�Ɍ����Ĕ���������ɂ��M����B����͓����R�ւ̓��A�����Ė��Ӗ��ȍs�ׂł͂Ȃ��A�_�_�����{���邽�߂̂��̂ł���Ƃ̕\���ł������B�܂�O��̌����ɂ���āA�_���Ɋׂ��Ă���_�̍߂�������A�_������̏o���ƁA�_�Ђ̑������肢�A�L���͏O���̍K�����A���ɂ͎R�яC�s�҂ւ̉�������҂������̂ł������B �����Ȃ�ΐ_�_�̉���āA�����͐��ɎR���ɓ���B�R�ƌ̐D��Ȃ���i�ɂ����S��D������A�R���ɂāu�O�����̗���v�݂̂��s���Č̋��ɋA�����B���̗���������Đ�������Ȃ�A�ޗNJ��ɍs���Ă������߉�A�V��ɂďC������@�A�G���o�T�ɐ������ɗ���@�E�d�@�Ȃǂ��A���Ƃ��ċ������邾�낤�B ���̓�N��A�����͍Ăѓ����R�ւƓo�����B�O��͒Z���Ԃ̓o���ł��������A����̓���ł́A�R�e�̒����A�����̌������Ȃ���A�R�����Ă̏C�s�́A���Ȃ��Ƃ��l�N�A���邢�͏\��N�ȏ�Ƃ��������Ԃɋy�B�����炭�͎x���҂āA�������܂߂��l���A���邢�͎������A����Ȃ�̏�����������ł̎��Ƃł������̂��낤�B�������C�s�̂��߂ɑI���n�Ƃ́A�P�ɕ������Z�Ȍi���Ƃ��������łȂ��A�����I�ȏ�y��z�N������ꏊ�A����ɂ͒����v�z�ɐ�����闝�z�������܂A�L���Ӗ��ł̏��n�ł������ƌ���ׂ����낤�B�u�R�����f�v���邻�̏��n���A�����͂܂��Ɋω���y�E��ɗ��Ɗ��������̂ł͂Ȃ��낤���B �����́A����ΎR����y�ɉ��������āA������u�_�{���v�Ɩ��t�����B���̋@�\�Ƃ��čl������̂́A��ɂ͐_�_�����{���A�_�_�̓����ƏO���̍K�����F�肷��Ƃ��������I�ȑ��ʁA��ɂ͐_�_�̉���̂��ƂɁA���g�̕������߂ďC�s����Ƃ��������I�ȑ��ʂł���B�����ōs��ꂽ�C�s�̓��e�͖��ڂł��邪�A�Ӑ}�Ƃ��ẮA�_�_�̓����̂��߁A�O���̍K���̂��߁A�Ђ��Ă͎��g�̕��̂��߂́A���������~�����߂��������C�s�ł��������̂Ɛ��������B �R�яC�s�̋@���n���A�����͎R�����肽�B�����L�͎҂ɂ��^�E�x����w�i�Ƃ��āA����E��썑�ɂāA�u�t�E���@�����E�z���E�C�@�Ƃ����������̊������W�J���ꂽ�\���͍����B���ɍu�t�ɔC������Ă��邱�Ƃ���A�����͎R�яC�s�݂̂Ȃ炸�A�o�_�̍u���ɂ����ꂽ�q�s����̑m�ł��������Ƃ����������B�����̎w���ҁA�z���ҁA�����Č��҂Ƃ��Ă̊����́A�����Ȃ�ΎR�яC�s�̌����Ă̗����s�ł������Ɖ��߂ł��邾�낤�B �� �ȏ�A�w�����蕶�x�����ƂɁA�����̎���ƏƂ炵���킹�Ȃ���A�����̐��U���T�ς��Ă����B���̗v�_�́A���̎l�_�ɓZ�߂邱�Ƃ��ł��悤�B �@����(����)���}�����āA�R��(����)���u������B�y�o���ԁz �A�R�тɓ���ɂ�����A�R�т̐_�_�����{����B�y�_�_���{�z �@�@���_�_�̗��Ɠ����E�Ќ��{���A�O���̍K���A�C�s�҂ւ̉�����肤�B �B�R�т̐_�_�̉���āA���n�ɐ_�{�������ĂďC�s�ɗ�ށB�y�_�{���E�R�яC�s�z �C�C�s�̌����āA�Ăѐ����ɗ����Ԃ�A�����s�ɗ�ށB�y�����s�z �����[�I�Ɍ����A�����𗣂�ĎR�тցA�����ĎR�т��Ăѐ����ւƂ������U�ł���B�����R�R�����߂������O�����́A��Ɏ����I�ȏC�s�̎����ł���A�@���n���ĉ��R�������̎w���ҁE�z���ҁE���҂Ƃ��Ċ����㔼���́A��ɗ����s�̎����ł������B�����R�ւ̓���C�s�́A�܂��ɂ��̐��U�̓]�@�Ɉʒu�Â����Ă���B �܂����̎R�яC�s�ɂ��A���������̈Ӗ����������߂��Ă����B����͐������痣��ĎR���̏�y�ɓ���A���g�̕������߂�Ƃ��������̑��ʂƁA�R�т̐_�_�����{���ďO���̍K�����肢�A�Ăѐ����ɗ����Ԃ�Ƃ��������̑��ʂł���B�����̎R�яC�s�́A���������~�����߂������@���I�s�ׂł������Ɨ������ꂤ��B���̐l�����́A�܂��Ɂu�㋁���v�u�����O���v�����H���������ҁE��F�m�ƌĂԂɑ����������̂ƌ����悤�B �� �Ƃ���ŁA�E�L�̂悤�ȏ����̐��U�E�R�яC�s�̖ړI�ӎ��E�l�����́A�����ʂ茀�I�ł���B����������C�́w�����蕶�x�́A�ɔ��m�̓`���ɂ��A�����R�Ə������c�]����Ӑ}�ŋL���ꂽ���̂ł������B�{�_���ɂĊm�F�����悤�ɁA���̓��e�͓����̎�����炵�āA��Ƃ��ď��F�ł���Ƃ��Ă��A�w�����蕶�x�ɕ`�ʂ��ꂽ�����ƁA���̎����Ƃɂ́A������x�̊r����������̂Ǝv����B�܂茵���Ɍ����A���������m�蓾�鏟���Ƃ́A��C��ʂ��Ă̏����ł������蓾�Ȃ��B �������t�ɁA��C���C���[�W�����q���叟���r�Ƃ����l�����́A���m�ɂ���Ƃ������悤�B���̎��сE�l�����́u���L�̕��Ɓv�u���f�̉�v�v�Ə̎^�������肩�A��C�Ɓu�u�������āv�u�ӂ��ʂ��v�A�����������F�̔@���e���݂����߂āu�X�W�̋��Ȃ�v�Ƃ��������Ă���B�܂�A��ɋ��������I�ȁq���叟���r�̐��U�E�ړI�ӎ��E�l�����́A�܂��Ɂq�����C�r�̕��������z�I�ȍ���(�o�ƎҁE�m��)�̂�����ƁA�O����ɂ���ƌ�����̂ł͂Ȃ��낤���B����͓����̍��傽���̎���ӎ��A���邢�͌Ñ�Љ�ɂ����镧���̈Ӗ����l�@����ہA��̎�����^������̂ł��낤�B �Ȃ��{�_���ł́A�����̎��т�ʂ��āA�������̖��_���l�@�����B���ɁA����E��u�Ƃ��Ă̏����A�����̏@���A�R���ł̎O�����̗���A�C�s�̏��n�Ƃ��Ă̎R����y�A�_�{���̋@�\�Ȃǂ́A�����̕����҂ɂ��R�яC�s�E�_�_�M�Ɋւ��d�v�Ȗ��ł������B�����ȊO�̎���ƍ��킹�āA��������߂čl�@���Ă݂����B�@ �@ |
|
| ����r�R | |
|
��r�R�_�Ђ̍Ր_�͌��݁A��ȋM���E�c�S�P�E���э��F���ƂȂ��Ă���B����́A����������������q�����ɐ��������ł��낤�Ɖ]����u���썑��r�R���ΐ��{������`�L�v�ɂ����̂炵���B����������́u��ɗ��R�C�s���L�v�ɓo�ꂵ�Ă���_�炵�����݂��̒ʂ����_�ɒu�������������̂悤�ł���B
�u��ɗ��R�C�s���L�v�ɓo�ꂷ��_�̂��̈�́u���p�@�鍳�A�����߁A����ڍ��E�茞�ցv�Ƃ��������߂𗈂��_�̂悤�ł������B�܂��ʂɁA���ւ��o�ꂵ�A�����āu��l�V���A���p�ԗ�A����O�\�]�v�Ɓu��l���єc┐��ߊ��A�ЋV�V���A���Ό\�L�]�A����������v���o�ꂵ�Ă���B����͎��ێl���̐_�ł�����̂����A���̂������ւ́u���_�K�Ք��֔V�_�A�������T���v�ƁA�P�ɒ��T�����J�����Ƃ����B�܂�ŏ��ɓo�ꂵ���֑̂̐_�����э��F���ƂȂ��āA�V���炵�����c�S�P�A�Ќ��̂���_����ȋM���Ƃ��ꂽ�̂��낤�B �u�����R����������n���L�v�́A���q����ɐ����������w��̏d�v�������ł��邪�A����ɋL����Ă�����e�ɒ��ڂ������B�u����ďO�R�����ʏ����o�V�A�o�H�����Ԏ������y�O�\�]�N�v�r���͗��������܂�A���̎ʖ{�͑���ʏ��ɓ`������������ɑ����A�o�H�����Ԏ��Ɏ�������ꂽ���A�Ăё���ЂɕԊ҂��ꂽ�Ƃ������e���B���Ԏ��Ƃ́A���݂̎R�`���̗��Ύ��ƂȂ�B���̗��Ύ��͎��o��t�~�m���J�c�ƂȂ��Ă��邪�A���̂ɓ����͗��Ԏ�(�肤���Ⴍ��)�ƍ������̂��킩���Ă��Ȃ��B�����A�Ԃ����őz�N�����̂́A�u��ɗ��R�C�s���L�v�̓����ɓo�ꂵ���_�ł���B�L����Ă���u����ڍ��E�茞�ցv�Ƃ����p��ǂ�Ŏv���o���̂��ʋ����ł���B�ʋ����̎p�́u���{�Ε����T�v�ɂ��u���ɓ��Ԏւ�Z���B���r�r��ɖ���Ԏւ�Z���v�Ƃ���A�܂��Ɂu��ɗ��R�C�s���L�v�ɓo�ꂵ���_�ɋߎ����Ă���B��r�R�ɓo�ꂵ���_�̎p���w�҂͈�ɕt�����A�ʋ����Ƃ��čl����Ȃ���ʂ�̂��Ǝv���B���R�A�R�`���̗��Ύ��̓����̗��Ԏ��Ƃ́A�ʋ������Ӗ����č����ꂽ�����ł͂Ȃ��낤���B �u�ʋ����v�́A�����Ɋm�����ꂽ�悤���B�Ñ�ɂ����Ă͍̐��Ɠ����ł��������A���̒����̍��ɂ́u�v�Ƃ������̂́u���v���Ӗ�����F�Ƃ��ĔF�����ꂽ�ׁA���炭�u�ʋ����v�́u�ʁv�͐����Ӗ�����̂��낤�B�u�����v�́A�k�l�������Ӗ����鎖����A���Ɩk�l���������т��鑶�݂��A���́u�ʋ����v�̖{���̈Ӗ����낤�ƍl����̂��B�����ē��R�A����͐��_�ł����閭���M�Ɍq����B �܂��A��͂��r�R�ɓ`���u���n���L�v�ɓ�r�R���w���āu���ԗL���̗�_�v�Ƃ��鎖�ƁA��́u�u��ɗ��R�C�s���L�v�v�ɂ����Ă��u��͖��������A��t�̐����ɂ�茻�ꂽ�B���̕�͏��̂̐_�̋����鏊������A���̐_�����J��\���B��̐��Ƃ͒��T���ł���B�v��������A��r�R�̐_�Ƃ͏��_�ł���A�����_�ł��鎖���킩��B���炭�u���썑��r�R���ΐ��{������`�L�v�ł́A�����A�R�̒j�̎R�Ə���R���Ĕ����J�����̂��A�F��C���̏C�@���r�R�Ɏ���������C���𐬗����������S�̎���ɋN��������̂Ǝv����B�F��̎O���������O���ƌ��ѕt���A���������A�R�ɏd�˂����̂ł��낤�B����āA��ȋM���E�c�S�P�E���э��F���͌㐢�̍Ր_�ł���A�{���J���Ă����_�Ƃ͓S�̎ւł���A���n�o�L�_�ɑ��Ȃ�Ȃ����낤�B ��r�R�ł��錻�݂̒j�̎R���J����_�Ƃ́A����_�Ђ̐_�ł���̂��킩�����B���̑���_�Ђ̎Q���ɂ́A�����̒j�����ۂ��������J���Ă����Ƃ����B�����������B�Ɋւ���M�����_�Ƃ͎R�_�ł���A���̒j�����ۂ������m�A�ʂɃR���Z�C�T�}�M�ƌĂ����͓̂ꕶ����܂ő������̂ł���B ��r�R�̑O�R�Ƃ��ꂽ���鑾���R�̎O���M�ł́A�����R�匠��(��)�E�F��匠��(��)�E�����匠��(��)�ƂȂ��Ă��邪�A�����w�j�����J�鑾���R�����Ȃ̂͗����ł���B�܂��A���@�G�̌F����܂����z�ł���̂������ł���B�Ƃ��낪�����匠�������̌��Ȃ̂��͐����ł��Ȃ��B�A�z�܍s�ł̉A�Ƃ͏��ł��茎�ł���A�����Ӗ����邩�炾�B�Ñ�̍��J�̊�{�́A�F�_�ƕP�_�Ƃ����A�z�̘a���Ő��藧���Ă���B�����A�e���y�L�ɂ�����R�ɂ����āA�F�_�ƕP�_�����������Ԃ��Ă���̂́A���̂܂��[�M�Ɍ��ѕt�����A�V�̐삪�F�_�ƕP�_���u�Ă��Ƃ���Ñ㒆������̓`��������Ȃ�����ꂽ�Ƃ��A�����������{�̓`�����l���ɓ��ꂽ���̂Ǝv����B ��і�@���h�̂ܖ��ނ�@���������@�Q��ǖO���ʂ��@���ǂ��䂪���� ��L�́u���t�W3404�v�̉̂ł��邪�A���h�͓Ȗ،��̈��h�S�������̂����A�Ñ�ł͌��݂̌Q�n�����܂ޒn�ł������悤���B���̈��h�S�́A���̖��Y�n�ŗ{�\������ł������炵���B�{�\�͌��݂ł��Q�n���ɐ����A�L���Ȃ̂͋ː��s���B�ː��s�ɂ͗L���Ȕ���P�̓`��������B�Ñ�ɂ����Ă��֓���~�ɗ{�\�����́A���Ȃ�̍L������������B���̒��ɘ`�����̐i�o���������̂��낤�B����̂ɁA�Ð_�Ђ���P�`���_�Ђ��A���̘`�����̉e��������B ���̘`���_�Ђ����A����ɂ��`���_�Ђ�����A�Ր_�͉摜�̒ʂ�A�V�Ƒ�_�Ɖ��ƕP�ɐ��D�Ô����ƂȂ��Ă���B���炭����͎O���M���Ӗ�����Ր_�ł���A���z�͓V�Ƒ�_�ł���A���ƕP�́u�V�i�e���v�Ɓu�V�^�e���v�����`�ł���u�V�i�e���v�͌��������Ɍ���ӂƂȂ�̂Ō��B�����ċ��炭���D�Ô����́A���P�`���_�Ђ�Ð_�Ђ����Ă������w�j���̂��̂����_�ł���A����͎_�ł��鎖����A���_�Ƃ��Ă̐��D�Ô����Ƃ��������낤�B�܂�A�����w�j=���D�Ô����ł��鎖���Ӗ����Ă̍Ր_�ł���Ǝv����B ���D�Ô����́A�y���̋Ք��ɔ���ƌĂ��ꂪ����A�������J��ꂽ�_�����D�Ô����ł������B���ꂪ��������ƂȂ�A�y���ܓ��s�̘`���_�Ђɍ��J���ꂽ�̂����A����P�Ƙ`���_�̊W���l���Ă݂����B�`�����͏��߂ē��{�Ɏ��[�Ɋւ���`����g�ݓ��ꂽ�����ł���A���ꂪ�ȑO�ɏЉ���ΐU�̂Ɍq����̂��Ǝv���邩�炾�B�@ �@ |
|
| �������C���ƋU���̐��� | |
|
�ό��n�Ƃ��ē��O�ɒm��������́A�Ñォ��̐M�̎R�ł���j�̎R�̎R�x�M����Ղɔ��W���Ă������̂ŁA�����M�̗��j�������A��R�͐������d�˂č����Ɏ������B�j�̎R�͕����n���ȑO����M�̎R�ł���A�ޗǎ���ɂ͕�ɗ��ω���y�ɋ[�����ĕ�ɗ��R�ƌĂ�Ă����B�u���쎮�v�u�_�_�\�E�_�����v�ɂ͓�r�R�A�u�G�L�v�ɂ͍����R�Ƃ���B�W��2�A484.4�J�̐��w�ΎR�ŁA�����R�n�̎��ł���B�Ñ�ɂ͉���ꍑ��\�ۂ���R�ł���A���̎R��_�̎R�Ƃ��ċL�邱�r�R�_�Ђ͉��썑�B��̎�����ЂƂ��Ċт̐i�K���M�����B�j�̎R�͓����L���̗�R�Ƃ��Č����M����A�֓�����̎R�Ƃ��Ċ��q���{�E�]�˖��{���瑸�������B�����̒n�ɓ���ƍN�̗�_�ł��铌�Ƌ{�����c���ꂽ�̂��A����Ȃ����ӂ���낤�Ƃ����ƍN�̈⌾�ɂ����̂Ƃ����B�����̗��j�͒j�̎R�Ɏn��Ƃ����Ă������ĉߌ��ł͂Ȃ��B
�����R�̉��N�ɂ��Ă͌㐢�ɍ��ꂽ�u�����R�����Љ��N�v�����邪�A����͊e�R�e�Ђ̉��N���Ɠ��������̂܂܂ł͗��j�̎j���ɂȂ�Ȃ������ŁA�ʓr�̌������K�v�ł���B����Ƃ͕ʂɑ����͉��N�Ƒ肳��Ă��Ȃ����A���N���Ƃ݂Ȃ��Ă悢����̈ݑ炪����B�啔������������O���̔N�L�������A��q�҂̖������炩�ł���B����Ɓu�ՏƔ�������W�v�́u���叟�����R���M�������裁A�u��ɗ��R�����C�s���L�v�A�u����Ill�d�T�������n���L�v�A�u�~�m�a�������R�L�v�A�u��r�R�畔��N�v�A�u���莛�O������L�v�A�u���T�����L�v�A�u�O����N�v��8�҂ł���B�ȏ�̂����u���T�����L�v�͕����������̍�A�u�O����N�v�͔N�L���Ȃ��B8�҂̂Ȃ��Ő^��́u���叟�����R���M�����v�Ɓu���T�����L�v��2�҂݂̂ŁA����6�҂͋U��Ƃ���A�U���̐����͊��q����Ȍ�ƍl�����Ă���B �Ñォ��̎R�x�M�̗�R�ɂ͓ޗǎ���̎R�ѕ��k�̌n���������C�s�҂��Z���A�ނ�͂̂��ɏC�����ɑg�D���ꂽ�B�C�����͉䂪���×��̎R�x�M�ƕ����E�������̑��嗤�n���̐M��v�z�Ƃ��K�������R�x�@���ł����āA�����Ɉˋ������`�Ԃ�����ɓ��{�Ǝ��̏@���Ƃ���Ă���B�e�n�ɂ͗�R�������A�����͒n���C���Ƃ��Ď���ɑg�D����Ă䂭�B�����̏ꍇ����O�łȂ��A�����C���͒j�̎R�M����Ղɂ��Ċ��q����ɋ��c�̑g�D�������������̂ł���B �C���͎R���C�s�ɂ���đ̓����ꂽ���ɂ�薯�O���~�ς��錻�����v�ɖ{�|������A���c���������Ă���́A�R���̏C�s�͏W�c�Ŏ��{�����1�悤�ɂȂ���������.�m��X��ȂǂƂ����A�n���ɂ���ĈقȂ邪�����I�ɂ͏t�ďH�~�̎l�G�̓��������B�ߍ��ȕ����C�s��̓��������̂łȂ���ΏC���҂̎��i�͂�������ꂸ�A���ׂ̈ɂ��A�܂��ΊO�I�ɂ��C�s�̗R��������K�v����������㐢�̍�ł��邪�u�O�Z���u�����閧�`�v�u�C����L�����v�s�����i�L�v���X�C�����̋��`���E�j�`���ɂ́A�c�Ƃ��������p�̎��ւ��֒��C�����ď�����Ă���B�����C�����܂���s�̑c��j�̎R�J�R�̏����ɋ[���A���q�̉��N���̂����u��ɗ��R�����C�s���L�v�Ɉˋ����ē���̑�@�����ꂽ�B ��q�̒ʂ肱�̓��L�͏����̓�����j���ł͂Ȃ��A���q����ɏ����ꂽ�U���ł���A�Ñ�j�̎j���Ƃ��Ă͉��l���Ȃ��B�U��ł��邱�Ƃ̘_�ɂ��Ă͐�w�̋Ɛт�����A���߂ĐG���K�v�͂Ȃ��B�U���͋U���Ƃ��āA�{�e�ł͓�����R�ŋU��Ȃ��K�v�ł������̂��A���L�U��̎����͂����悻�����납�A�܂����ꂩ��h������l�G�̕�s�̐��������͂ǂ��Ȃ邩�A�Ƃ������U���̐����ɂ�����邢�����̖����A�^��̎j���Ƃ̔�r�ƎR�x�M�ɊW�����ՁE�╨�̌�����ʂ��čl�@���Ă݂悤�Ǝv���B�@ |
|
|
���j�̎R�̌Ñ�ɂ�����镶��
�ω���y�̐��n�ƍl������ɗ��R�Ƃ�ꂽ�j�̎R�́A����v�z�ɂ���ĎR�_�ł����r�R�_�̖{�n���\��ʊω��A����͑喤�M���Ƃ��ꂽ�B�_�Ђ͖��_�Ղɗ��ЂŁu���{�O����^�v���11�N(869)2��28���̏��ɁA����ʌM�l���̐_�K���L����Ă���B�M�ʂ͉��썑�̖��̉ڈΐ����ɂ�����ꓬ�E�M���ɑ��āA�ꍑ�̐_�Ƃ��ď��M���ꂽ���̂ƍl�����Ă���B�j�̎R�J�R�̍��叟�����J����Ɠ`���鎛�͖��̂��ϓ]���A����ɂ���Ė{�V�̈ړ����݂����A�����R�։����Ƃ��č����܂Ŗ@����`���Ă���B�����͉،��@�̑m�Ƃ������������邪�A���m�Ȃ��Ƃ͕���Ȃ��B ��s�Z�@�̂����ꂩ�ɑ����Ă������̂ł��낤���A�ނ̎��セ���Ԃ��������V��@�ɕς�A�����܂œV��@�̎��@�ł��葱���Ă����B ����������R�̗��j�́A���썑�F��S�̐l���叟���̒j�̎R�J�R�ɂ���Ė����J�����B�^��U��̖��͑[���āA�܂��O�L����8�҂̓��e�����������E��ŏЉ�Ă��������B ��1�D�u���叟�����R���M�����䏘�v(�ȉ��u��r�R��v�E�u�R��v�Ɨ���) �R�яC�s�҂ł������������ꓬ�̖��A�V��2�N(782)�ɒj�̎R�̓o���ɐ������A�����ɂ��钆�T���̂قƂ�ɐ_�{�����������ĎR���̓���Ƃ����B���ɂ��ނ͏�썑�u�t�ɕ�C����A�O�m5�N(814)���v�����B���O���썑�w�̎t�ɔ��m��ʂ��ċ�C�ɊJ�R�̔蕶�̐���˗����Ă���A��C�������������Ĕ蕶���q�����B�l�Z�̂̂����Ԃ����Ȏ����ŁA�C�����������ߖ������̂܂܌㐢�Ɍ�p���ꂽ�������Ȃ肠��B�O�m5�N8��30����C��B ��2�u��ɗ��R�����C�s���L�v(�ȉ��u��ɗ��R���L�v�E�u���L�v�Ɨ���) �����̒�q�Ƃ����m����4�l���A�t�̓`�L���܂Ƃ߂��Ƃ����`�̂��̂ŁA�����̈�����̍O�m9�N(818)�Ɋ����������Ɖ����ɂ���B���q����ɉ���U��ŁA�m���ȉ�4���̒�q�̖��́u��r�R��v�ɂȂ��A�����̖v�N������Ă���B�{�e�Ɏ��グ��̂͂��̏��ŁA�u��r�R��v�ƑΔ���s���B�O�m9�N2���m���E�����E����E���Ԑ�B ��3.�u�����R����������n���L�v(�ȉ��u������L�v�Ɨ���) ��������蕶��q�̈˗�������C���A�O�m11�N(820)�ɓ����֗��R���ď����̎��ւ�K�ˁA�����ɎГa�E������������b���ŁA����ł͖����̌����ɂ����A�������L��B�u��ɗ��R���L�v�̑��҂ŋ�C�����̎j���Ƃ���邪�A���q����Ȍ�̋U��ł���B�V��2�N(825)4��3��������B ��4�D�u��r�R�畔��N�v(�ȉ��u�畔��N�v�Ɨ���) �����R�̐畔������̒�q���T�E�����E���@�E�m����ɂ���Ďn�߂�ꂽ���Ƃ��q�ׂ邪�A���T�Ȃǂ̍��匾�����s���ŁA�U��Ƃ���Ă���B����͌㐢�ɉ���B�V��5�N(828)4���B ��5.�u�~�m�a�������R�L�v(�ȉ��u�~�m���R�L�v�Ɨ���) �̂��ɔ�b�R�̑�3�����ƂȂ����~�m�������֗��R���āA�R���⒆�T���ΔȂɕ������������A�������L�����Ƃ���L�^�ł���B���̏��̏d�_�͂����ɂ���̂ł͂Ȃ��A�~�m�������E��C�̖嗬���W�߂ēV��̖嗬�ɋA�����߂��Ƃ��������ɂ���B�����Ƃ��̒�q�B�͓�s�̖@���ɑ����Ă������̂Ǝv���邪�A�����������ɂ͊m���ɓV��@�ƂȂ��Ă���B�����͋��h�����̐l�A�u��r�R��v��̋�C�͐^���@�̊J�c�ł��邽�߁A�V��@�ւ̋A������������K�v����A���썑�o�g�̉~�m�ɉ����������̂Ǝv����B�b���̏�������́u�畔��N�v�Ɍ�s���邪�A���q����Ȍ�̋U��Ƃ���Ă���B�čt2�N(855)����������B ��6.�u���莛�O������L�v(�ȉ��u�O������L�v�Ɨ���) ���������������Ɓu��ɗ��R���L�v�ɂ���l�{�����Ŏ��s�����O����@��̉��N���q�ׂ����̂ŁA�����Ɂu��q�̕ρv�̕��ŋF��ɑ���̂�������������������ʌM�ꓙ�̋Ɉʂɏ����ꂽ���ƁA�����̏��i������\����q�������ƂȂǁA�ˋ�̎��ւ��q�ׂĂ���B�㐢�̋U��ł���B�V�����N(857)�[6�����@��B ��7.�u���T�����L�v(�ȉ��u���L�v�Ɨ���) ������㓡�����̐�ɂȂ�����R�̉��N���ŁA��R�̈˗��ɂ���q�������̂ƍl�����Ă���B���ɂ͉��ꍑ���R�̏O�k���˗������J�R�א��̓`�u���R��l���N�v������A�����N�Ƃ����R���瑗��ꂽ�����ɂ���Đ�ۂ��ꂽ�B�������ɂ�镲���͂܂ʂ��ꂪ�����A�����ɂ͎����ƍl�����Ȃ��ӂ������邪�A���̉��N���́u��r�R��v�ƂƂ��ɓ����̌Ñ��m�鍪�{�j���ł���B�ۉ�7�N(1141)7��3����������B ��8�D�u�O����N�v ���̉��N���͏������j�̎R�̏��o�������݂Ď��s�����_��i�_���N(767)���N�_�Ƃ��A369�N�]�̂��Ɛ�������ƂɂȂ��Ă���B�����������㖖�̐����Ƃ������ƂɂȂ邪�A�m�͂Ȃ��B�㐢�̍�i�ł��邩������Ȃ��B�����̓o�����O����̕����Ƃ���̂ł��낤���A�u�O������L�v�ł͖@��̋N�_���O�m12�N(821)�Ƃ��Ă���A�H���Ⴂ���݂��Ă���B�N�L�E��҂Ȃ��B �{�e�����グ��U��́u��ɗ��R���L�v�́A�������U��́u������L�v�E�u�~�m���R�L�v��2�҂Ɍp�����֘A���Ă䂭���N���ŁA�ЂƂ̃Z�b�g�Ƃ݂�悢�ł��낤�B�U��O����Ƃ�ׂ邩������Ȃ��B�u��ɗ��R���L�v�ɂ͎����Ƃ͂Ƃ��Ă��l�����Ȃ����m�ȋL���������A�����Ȍ�肪�����āA���w�Ȏ҂̈��M�Ƃ������]�����邪�A�����������Ƃ͌㐢�̉��N���Ɍ�����ʗL�̎����ŁA���ꎩ�̂͂��܂ŋC�ɂ��邱�Ƃł͂Ȃ��B ��ʂɋU���E�U�����Ƃ����Ƃ��ꂾ���Ŏj�����l�͖����A���j�̏��q���珜�O���ׂ������̂��̂Ƃ����B�������l���悤�ɂ���ẮA�U���E�U������K�v�Ƃ��鐢�E�������ɂ���A�^��łȂ��ɂ�������炸�������������������Ă��邱�Ƃ��܂��ʼn߂ł��Ȃ��B�U��ł��낤�Ɩ����낤�ƁA����͂ЂƂ̗��j�����ł���A���j�����̑ΏۂɈႢ�Ȃ��B�@ |
|
|
�������R�n�̒n�`
�C���͎R���C�s�����{�ł���A�R���C�s�������C���͂��肦�Ȃ��B�����C��������Ƃ��������R�n�͂ǂ̂悤�Ȓn�`�ł���A�R�n�̂ǂ̕����ŏC�s���s��ꂽ���A�܂��R�n�̗l�q���ς��Ă��������B �����R�n�̒n�`���q�ׂ�ɂ͎�X�̎d�������邪�A�{�e�̂悤�ɎR�x�M�j�����Ƃ���ꍇ�ɂ́A�n���ɏ]�������R�n�̒��S�ɂ��钆�T�����܂ɂ��ĎR��̔z�u���q�ׂ�̂��K���ł���A�������₷���Ǝv���B �}�͒��T���𒆐S�Ƃ����R��������Ă���B�����R�n�Ǒ��̂���R�X�ŁA�����ɂ��钆�T���͖ʐς�11.49�������A�Ζʂ̕W���͖�1�A200�����₪����A�^�ϐ����̒j�̎R���ő�J�삪���~�߂��Đ��ꂽ���~�ߌł���B�����ɍג����s���`�ŁA���݂�����3���͎R���Ί݂ɂ��܂�A���l�̕����������ŊJ���͐i��ł��Ȃ��B���{���E���T������������A�������W�������̂͌̓����ŁA�u���T�����L�v�ɂ݂鐷���͒��{�n��̂����Ă̔ɉh����Ă���B �̖k���ɒj�̎R�𒆐S�ɂ��ē����ɕ��Ԍʏ�̎R����B���ꂪ�\�����ƒʏ̂��������ΎR�Q�ŁA�^�ϐ��ɕ��o���A�j�̎R�Ɛԓ�E����R�����w�ΎR�A���̎R�X�͉Ό����s���̗n��~���u�ł���B�R��̓��[�͕W��2�A010.3�C�̐ԓ�R�A���[��2�A577.6�C�̔����R�ŁA�����R���ΎR�Q���̍ō���ƂȂ��Ă���B�R�̂��ł��傫���A�ΎR�炵�������Ȏp���݂���̂��W��2�A484.4�C�̒j�̎R�ŁA�R���֓ˏo���A���암����̗e��]�����邱�Ƃ��ł���B����ΎR�̂̐ԓ�R�Ə���R�͕ʂƂ��āA���̑��̎R�X�͓Ɨ������Ǖ�̊��������A2�A000����z���������Ă���B���T���Γ�݂ɕ��ԎR��͎R�̂̌`�����k���̎R�����Â��A2�A000�C���z����R�͎��P�x�����ŁA���Ɍ����ĕW��������ɉ���B�R��̓��[�͖��R�A���[�͔����R�̓�X���Ɉʒu������P�x�ŁA��̓������ꒃ�̖ؕ�������R�̊Ԃ́A�����R�n���Â�����Ɍ`�����ꂽ�����R�n�̎R�X�ł���B�Ǖ�Ƃ�ׂ�͎̂��P�x�Ɨׂ�̏h���V�R���炢�ŁA���̑��͓ˏo�����R�łȂ������ʂ�̍��܂�ɉ߂��Ȃ��B�ÎЂ̓�r�R�_�Ђ��_�̎R�Ƃ��ċL��R�͒j�̎R�̂ق��A�ԓ�R�E����R�B ���^���q�R�E��^���q�R�E���Y�R�E�����R�E�O�����R�E�����R��8��ŁA����݂͂Ȗk���̎R��ɑ����A�쑤�̎R��ɂ͐_�̎R���Ȃ��B�܂��O�R�M�ɂ���ċI��ꂽ�R�͒j�̎R�E���Y�R�E����R��3�R�ŁA������k���̎R��̎R�ł���B �����R�n�̎��͒j�̎R�ł���B�R�̂̋K�͂����R�������đ傫���A�\�����̑O�ʂɈʒu���ĒႢ�����R�n��O�R�ɂ��邽�߁A���삩��̒��]�Ɍb�܂�Ă���B����̕�������݂�R�`�́A�×�����̐M�̎R�ɑ����_�ޔ��^��悵�A�Ⴂ�R�ł͂��邪���`�̒}�g�R�ƂƂ��ɁA�֓�����̓����Ɉʒu�����R�Ƃ��āA�Ñォ�疯�O�̐M���W�߂Ă����B �@ |
|
| ���~�m�Ɖ��썑�̕������� | |
|
�u���o��t�~�m�v�J��Ɠ`��鎛�@���������k�n���ɐ��܂ꂽ���Ƃ��ẮA�����ɂ��čl����Ƃ��A�ǂ����Ă����̈̐l���ӎ�������܂���B�~�m�́A�����炩�ɍŐ����C�����g�߂Ɋ����鍂�m�ŁA���ꂪ�ڈ̍��ɂƂ��ėL�����݂ł��������ۂ��͂킩��܂��A���Ȃ��Ƃ��n���ɂ����āu�~�m����v�ƌĂꑱ���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ����܂���B
�~�m���u���썑�\�\���F�Ȗ،��\�\�v�ɐ��܂ꂽ�̂́A�����J�s�̔N�A���Ȃ킿����\�O(794)�N�̂��Ƃł����B�ނ́A��ɂ��āu�������c�v�ƌĂ�鋳�c�̑m�u�L�q�v�̉��ŕ��@���w��ł���܂��B ���́u�������c�v�̃��[�_�[�u�����v�́A���́u�Ӑ^�v�̍���ł��B�Ӑ^�ɂ��Ă͂��炽�߂Č����܂ł��Ȃ���������܂��A�O�̂��ߐG��Ă����܂��ƁA���{�l�ɉ������ĔF�������邽�߂ɖ��������ė����������̊w�m�ł��B�u���厛�v�ɓ��{���̉��d��݂����̂��A��������Ƃ��Ắu�����v�����������̂����̑m�ł��B �����͂��̈̑�ȊӐ^�̒�q�̒��ł��u��������q��v�\�\�w�b�R��t�`�x�\�\��搂�ꂽ�قǂ̍���ł������悤�ł��B �Ӌ��ɐ��܂ꂽ�~�m������قǂ̑m�̐g�߂ɑ��݂������̂́A�ނ̌̋����썑�Ɂu���厛�v�u�}���ϐ������v�ƕ��ԁu�O���d�v�̂ЂƂu�����t���v�����݂��Ă�������ł��傤�B���̎��͎����I���ɒn�������̉��і쎁�ɂ���đn�����ꂽ�̂ł����A���̌�A���̂����ƌo�c�̊����Ƃ��Đ������ꂽ�̂ł��B��͂�A�u���і쎁�v�̑c���铌�����w�̌Ñ㎁���u�і쎁�v�̈Ќ��ɂ��̗��R�����߂Ă����ׂ��Ȃ̂ł��傤���E�E�E�B �����t���̑��݂́A�V��@��M���ɓ����ɑ����̍��m��y�o���܂����B ���݁A���E��Y�ł��铿��ƍN�̗�_�u���Ƌ{�v�̐F���������������A���̓������J�R�����Ƃ����u������l�v���A�V����(761)�N�A�����t���ɂĎ�����x���Ă���܂��B���ЂƂ�ɕ�܂ꂽ������l�ł͂���܂����A�u�j�r�R��(�ӂ��炳���)�v�ɂ���ď��Ȃ��Ƃ���C�Ƃ̊ԂɂȂ�炩�̌𗬂����������Ƃ͊m���ŁA�܂����̓�߂�����ɂ����ċ�C�͔ނ̎��т��]���Ă���܂��B��������C�̎^���ɂ͂��悻�ؔ��ȑ����������̂������ł�����̂ŁA�S�Ă�{���Ƃ��đ����邱�Ƃ͊댯�ł����A����Ӗ��ō��r���������ė����Ă�����C�ɂ��ꂾ���̂��Ƃ����������Ƃ������̈ꎖ�����ł������Ȑl���ł��������Ƃ��M���m���Ƃ������̂ł��傤�B �܂��A�����t���ƌ����A�O�ɐG�ꂽ�Ƃ���A��T��(770)�N�A�u�F�������_�������v���o�āu�̓�����v�����䂵����A��҂��������u�|�퓹���v���ʓ��Ƃ��Ĕz�����ꂽ���ł�����܂��B ���̂悤�ɉ��썑�ɂ����镧���G�s�\�[�h�����{�j���̐l�����������ނقǂ̂��̂ł��邱�Ƃ͒��ڂ��ׂ��ƍl���Ă���܂��B ����͂Ƃ������A�����͂����炭�A������������l���Ƃ��ĉ����t���ɔh������A���̂܂܉��썑�́u�厜���v�A��썑�\�\���F�Q�n���\�\�́u���쎛�\�\��y�@�\�\�v�A�u�������\�\���F��ʌ��\�\�̎������v���J��A��K�͂ȋ��c��g�D�����悤�ł��B ��썑���쎛�ɂ́A���̓����̒�q�Ō�̓V��j�����́u�~���v������܂������A�c���~�m�͂��̉~���̌Z���q�ł����鉺�썑�厜���̍L�q�Ɋw��ł����̂ł��B �ނ�ƍŐ��Ƃ̉��́A����\��(798)�N�A���������ɕ�F����^���Ă����~���ɔ�b�R��o�R���������ƂɎn�܂�܂����B �哯�O(808)�N�A���邢�͈���ɑ哯��(810)�N�ɂ́A�����̌�p�҂ƂȂ��Ă����L�q���~�m���Ĕ�b�R�ɓo��A����ȍ~�A�~�m�͍Ő��̒�q�ƂȂ�܂��B ����ɂ��Ă��������c�͉��̔�b�R�ɗL�\�Ȑl�ނ𑗂�A�Ő��ɐڋ߂����̂ł��傤���B���ɑz������Ȃ�A�P�Ɋ��������ɂ����˂������Ƃ��l�����܂��B ���������̑z���́A����N�Ԃ̉~���̉b�R�o�R�̎����ł���������藧���̂ł��B���Ɋ����邪���䂵�A����̕����̐��ł���哯�O�N�Ȃ����ܔN�ƂȂ�ƁA�Ő��̗��ꂪ�K�������m�ł�����̂ɂ͎v���܂���B ����ł��A�����̎t�ł���Ӑ^���̐l���A���������V��@�̎l�c�Ƃ���Ă������ƁA�y�сA���{�ɓV��o�T�������l���ł���ȏ�A�������{�̓V��@��w�����Ă���Ő��Ɩ��ɂ��Ă������Ƃ́A�K�R�ł���A�Ӗ��ł����������Ƃł��傤�B �Ȃɂ���A���̎����ɉ����N���Ă����̂����l����ƁA����ȑz���Ȃ���A���ʉ��ŌՎ�ἁX�ƕ�����_�������́A���Ȃ킿��s�Z�@�̉e�������B�ꂷ��̂ł��B �ӂƁA�����I�E�n���I�ɁA����l�������ɕ�����ł��܂��B ��Ẩ��m�u����v�ł��B �ނ́A�헤�̒}�g�R���Â̔֒�R�Ƃ������Ӌ��ɂ���Ȃ���A��s�Z�@�̖@���@�̑m�Ƃ��Ė{��ޗǂ̒N�����_���ɂ߂Ă����l���ł����B �����x�Y����͎��̂悤�Ɍ���Ă���܂��B ���p �w����ƍŐ��@�����ЂƂ̐��������x �哯���N����A�����ɉ������͂��̓���́A���������܂��ǂ��ɉ���A�{�����ǂ��ɒ�߂��̂ł��낤���B�����ɂ����铿��̋��_�͓�����āA���̈�͏헤�}�g�R�A���̃j�����B��Ìb�����ł��邱�Ƃ́A�����܂ł��Ȃ��B �`�����` ���������̖��͂���قǎ����ł͂Ȃ��B�����̓���`�ɂ��A�}�g�����Âւł͂Ȃ��ɁA��Â���}�g�ւ̓��������Ă�����̂����邩��ł���B�����͂������ᔻ�I�Ɏj�������Ȃ���A����s�N�Z�\��A���N���a��N(���l��)�A���N�V�����N(������)�Ƃ�������N��L�𐄒蕜�������B�������̍l�������ɗ��Ȃ�A�O�m�Z�A���N(����܁A�Z)�N����ɂ͂��łɉ�Â̊w�m�Ƃ��čL�����ɒm���Ă��铿�ꂪ�A����ȑO�A�헤�Œ����ɂ킽�鋳���̎d�����I���Ă�����ÂɈڂ�Z��ł�����̂Ƃ́A�Ƃ��Ă��l�����Ȃ��̂ł���B �܂���ÂցB�R��̂���Â���}�g�ցB��������`�́A�������������ɂȂ�B �ЂƂ܂���Â��悩�}�g���悩�͂ǂ��ł������̂ł����A���ڂ��ׂ��͂��̎����̓��ꂪ������ɐ��͂��g�債�Ă����Ƃ������Ƃł��B�n�}��ōl����ƁA���̐��͐}�͂����炩�ɉ��썑���͂�����܂��B �܂�A�����炭�������c�́A����̋��Ђ���g����邽�߂ɍŐ��ɋ߂Â����̂ł��傤�B�Ȃɂ��듿��́A��s�Z�@�̑m�Ԃ���������ł�����Ȃ������Ő��Ƃ�������l�őΓ��ɓn�肠��������Ȃ̂ł��B ���̂悤�Ȏ���Q�������A�~�m�͔�b�R�ɓo��A�Ő��̒�q�ɂȂ����̂ł����B ���������銺���V�c����A�������̋S�����삷�ׂ��u�`����t�Ő��v�Ɉς˂�ꂽ�u��b�R����v�́A���́g�`����t�h�̖��������Ƃ���A��ɑ����̗D�ꂽ���m�𐢂ɔy�o������A�J�f�~�[�̗l����悵�Ă����܂��B�������͌��X�Ő��̎u�����Ă������̂ł���܂����A���ɍŐ������̑O���Ɍ����c�������t�ɂ���Ċm�ł�����̂ɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă���܂��B �Ő��́A�V��@�؏@�Ɋ��蓖�Ă�ꂽ�u�N���x�ҁv�̓�l�ɂ��āA�\��N�Ԕ�b�R����o�邱�Ƃ������Ȃ��Ƃ����������C�s���`���t���邱�Ƃ�錾���܂����B �u�N���x�ҁ\�\�N�����x�ҁ\�\�v�Ƃ́A���x�m�̒���̂��Ƃł��B�����V�c�\(698)�N����n�܂����Ƃ����N���x�҂̐��x�́A���ƂƂ��Ė��N��萔�̑m���u���x�v������Ƃ������̂ł����B �u���x�v�Ƃ́A�u�o�Ɓv�̂��ƂƑ����Ă����č����x���Ȃ��Ǝv���܂��B ����ɂ��Ă��A�{���o�ƂƂ͑����̈���痣��邱�Ƃł���A�����o�Ƃ�����Ƃ����̂͂ǂ��ɂ���a��������܂��B�������A�Ñ�ɂ�������{�̕��@�Ƃ͂����������̂ł������悤�ł��B�����Ƃ��Čl�̏o�Ƃ͋ւ����Ă���܂����B�������M�S�Ƃ������̂́A���̌l�ɂƂ��č��ƂƂ����g�g�݂�����ʂɂ���A���������}���ł�����̂ł͂���܂���B��͂�ǂ����Ă����ƂƖ��W�ɕ��@�ɋA�˂���҂�����܂����B�����������l���́u���x�m�v�ƌĂ�A�g�ƍߎҁh�ɂ�����܂����A���@�̖{���I�ȈӖ����炷��Ζ{���]�|�ƌ����ׂ��ł��傤�B �b��߂��܂��B �����V�c���㗈�̔N���x�҂́A�ޗǎ����ʂ��āg����\���h�ƒ�߂��Ă���܂����B���R�Ȃ��炻�̏\���͓�s�Z�@�̐l�ނ���e�X�u�،��v�u���v�u�O�_�v�u�����v�u�@���v�u俱�Ɂv���U���������I��܂��B �����̐M���Ɗ��҂���g�ɎĂ����Ő��́A�����ɓV��@�����荞�܂��܂����B���̐l�Ő��́A�����ɓV��@�̃j���������������\�̘g���Ă��A�����m�ԂɔF�߂������̂ł��B�V��@���S����U�Ȗڂ́u�ՓߋƁv�Ɓu�~�ϋƁv�̘g�ł����B�u�ՓߋƁv�Ƃ́A�u����o�v�A���Ȃ킿�g�����h�ł��B �ȑO�A���k���j�����ق̊��W�Ŕq�������Ő����M�́w�V��@�؏@�N���x�w�������x�\�\��������\�\�ɂ́A�u�m���C�`�Փߌo�Ɓv�Ƃ���A����ɑ����āu�m���m�`�~�ϋƁv�Ƃ���܂����B�����ɂ͎鏑���Łu�ȓ�l�O�m�ܔN�����x�ҁv�ƍZ�����������Ă���܂����B �܂�A�O�m��(814)�N�����x�҂ƂȂ����~�m�́A�I�肷����̔N���x�҂̈�l�ł͂��������̂́A���́A���̎��_�Łu�����\�\�ՓߋƁ\�\�v���U���Ă����͉̂~�m�ł͂Ȃ��A�����́u�~�C�v�ł������̂ł��B��ɖ���������ēV��@���~���~�m�̐�U�́A���̎��_�ł͖����ł͂Ȃ������̂ł��B ���̍��A�Ő��̓V��@�͑傫�ȔY�݂�����Ă���܂����B �Ő������������m�ۂ����N���x�҂̘g�ł���܂������A�̐S�̓��x�҂̗��o�������������̂ł��B���ɎՓߋƂ̊w���ɂ����Ă���͌����ł����B�~�m�̓����ŎՓߋƂ�S�����~�C�����̗�ɘR��܂���ł����B�����ɂ͖��m�ȗ��R������܂��B����������C�̉e���ł��B�@ �@ |
|
| ��������l�u�����o�R�L�v�Ƌ�C | |
|
���R�Ɛl�Ԃ̂�����̊ւ��ɂ��ċ�C�́u���������A���͂�����ɂ��������ĕς����̂ł���B�����낪����Ă���Ί��͑��邵�A���̊��ɂ���Ă܂��A��������ڂ�s�����ƂɂȂ�B�Â��Ȋ��ɓ���A�����ɐg��u������������炩�ł���B�����āA������Ɗ������v���A�݂������S�ɂЂт��������Ƃ��ł���A�����̍����ƂȂ�"���R�̓���"�Ƃ��̂͂��炫�ł���"�m"�������Ɣ��������B�����Ɍ�肪����v�Ɛ����B
��C�ɐ�āA���̐Â��Ȋ��A���[���R�ɕ�������A�����ŏC�s���邱�Ƃɂ���Č����s�҂��A������l(���傤�ǂ����傤�ɂ�)�ł���B���썑�F��(�������̂��ɁA�͂��F���̓Ȗ،��^���s)�̐l�ł������B ��l�͏��N�̍�����a�̂��̂��ł���E�����Ȃ������B�N�ɂȂ��Ă�����P���̉��������A������͐��炩�ł������B���Ԃ̐������ɂ�����炸�A�����̋�(����)�̋������w�сA�X�̌����������A���R�̐��炩�������āA�R�тł̏C�s�ɂЂ������B ���̐N��48�ɂȂ��āA�����R(�j�̎R)�o���ɐ������A�J�R�̑c�ƂȂ����B ��l�́A817�N��83�ŖS���Ȃ��邪�A����3�N�O�ɁA�l����āA�����̒n�A�����̋L�q����C�Ɉ˗������B����҂Ƌ�C�͐̂���̒m�荇���������̂ŁA����������邱�ƂɂȂ�B��C�A41�̂Ƃ��ł���B �ȉ��́A���̋�C���M�ɂ��u���叟���A�R�����(��)�Č������(�݂�)��(�����ɂ߂�)�̔�v����́A�䂪���ŏ��́u�o�R�L�v�Ɠ����R�ł̏�l�̌��̏�ʂ���������̂ł���B �����Z���N�l����{ (��l�A)�����j�̎R�̓o�������݂�B�������A��͐[���A�R�͂��킵���A�s������_�Ɩ��ɕ�����A���ɂ����A�f�O����B�����܂ň����Ԃ��A�����ɓ�\����ԑ؍݂����̂��A���R����B ��������N�l����{ �ēx�A�o�������݂邪���s����B ��������N�O�����{ ����́A�o������܂ł͐�ɂ�����߂Ȃ��Ƃ̊o������߁A�����ɏ��������A�R�[�ɒ������B�����Ɉ�T�ԑ؍݂��A����̓o���F����s�Ȃ����B �u�킽�������o�����߂����̂́A���ׂĂ̐������̍K�����肤���߂ł��B���̏Ƃ��āA�킽�������s��̂�����̎�����łȂ����Ƃ������o���ƕ��̊G�p�}�����炵�����߂܂����B������A�R���ɒH�蒅�����Ƃ��ł���ΐ_�X�ɕ����܂��B�ǂ����A�P���_�X��A���̂�����������A�Ђ��ƂȂ閶���������߂������܂��A�R�̐��삽����A�킽������擱���邽�߂ɂ��̎�����݂����������B���̊肢�A������������Ȃ��������x�Ɠo�������݂܂���B�����āA���͂���邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�v�B ���̂悤�Ɋ肢�����Ă����ƁA��̔��������Ƃ�����z���A�̃n�G�}�c�̂���߂��R���悶�o�����B�R�̏ォ�璸��܂ł͎c�蔼���̋����ł��������A���炾�͔��ʂāA�̗͂����Ղ��Ă��܂����̂ŁA���̏�ɓ��āA�̗͂����A�����āA�Ƃ��Ƃ�����ɗ������B (���A���̏�ɂ��邱�Ƃ�)���̂悤�ł���A�ł������ł��邱�Ƃ��������Ȃ��炤���Ƃ肵�Ă���ƁA�V����Ԕ�(������)�ɏ��Ȃ��Ă��A�����܂��̂����ɋ�̗͂���ɕ�����ł���悤�����A����(���o��)���r�߂Ă��Ȃ��̂ɁA���R�̐_�̏Z�ނƂ����≮��K��Ă���C������B���������A��тɗ܂��A������͕��Âł͂����Ȃ������B ���̎R�̂������́A�����͗������Ԃ��ɐQ���w���̂悤�ł���A���̒��]�͌���Ȃ��A��k�͌Ղ��������܂����悤�ł���A�܂�ŁA����ȌՂ��������Ă���悤�ł���B ���̎R�́A���E��n��_�̏Z�ގR�A�{��R(����݂���)�̒��Ԃ̂悤�ł���A���͂̎R�X���{��R���ׂ�O�C����芪���Ă���Ƃ����S�͎R(�Ă�����)�̂悤�ł���B �����܊x�ɐ�������t�R(��������)�E�R(��������)�����������Ⴍ�A�����̓`���̎R�A��l�̏Z�ނƂ������ĎR(������)��A�悢����̂����悤�Ƃ����C���h�̍����R(������������)�ɂ������Ă���ƁA���̎R�͏��Ă���悤���B ���̒����́A��������Ƃ܂���ɖ��邭�Ȃ�A��������Ƃ����Ƃ��x�����ށB�������炾�Ɛ_�ʗ͂����ڂ��Ȃ��Ă��A�����̔ޕ��܂ł��ڂ̂܂��ɂ���A�ꋓ�ɐ痢���ԂƂ����_�b�̒���������Ȃ��B�����_�C�͂킽�����̑��̉��ɂ���̂��B �L����F�Ƃ�ǂ�̌i�F�́A�@(�͂�)���Ȃ��̂ɔ������т�D��Ȃ��A�����ȍ��R�A���͈�́A�N��������̂��낤�B �k���߂�ƌ�(���̐얓�̕����ɂ�����)������A���̍L���͂����ƌv�Z����Έ�S��(�����F�����n�ς̒P�ʁB�ꍠ�͕S��)�B�����͋����A��k�͒����B �������ӂ�Ԃ�ƁA��͂��̌�(���̌�)������A��\�]���̍L���͂��肻�����B ������ɖڂ�������ƁA����ɑ傫�Ȍ�(���T����)������A�L���͐�]��(�꒬���S��)�����肻�����B��k�͍L���Ȃ����A�����͒����L�тĂ���B�Ζʂɂ͂܂����Ƃ�܂��R�X�̍������̉e���t���ɗ��Ƃ��A���̎R���ɂ͂����ȕς��������₪����D��Ȃ��A���[���F����������A����̎c��̂���Ƃ��납��͑��t�̉Ԃ��炫�A���F�ɋP���Ă���B�����̂��ׂĂ̐F���]���Ƃ���Ȃ����̂悤�Ȑ��ʂɉf���o����Ă���B �R�Ɛ��݂͌��ɂЂт��P���A���̐�i���킽�������܂�����B�l���߁A�������݁A���O���邱�Ƃ��Ȃ��B�������A�ˑR�̐�܂���̕��������̌i�F��ł������Ă��܂��[ �킽���������͏����Ȉ��𐼓�(���T���Α�)�̋��Ɍ��сA�o���F��̖�_�X�ɉʂ������߁A�����ɓ�\����ԑ؍݂��A�߂��s�Ȃ��A���̂̂��A���R�����B �������l�N�O�����{ ���߂�(���x�͒��T���Ƃ��̎��ӂ�T�����邽�߂�)�����R�ɓ������B�ܓ��Ԃ������Č̂قƂ�ɒ������Ƃ��ɂ͎l���ɂȂ��Ă����B �قƂ�ň��z�̏��M��グ���B�����͓��(���͏\��)�A�Ђ͎O��(��ڂ͖�O�\�Z���`)�B���������A�킽�����Ɠ�A�O�l�����A�ɞ��������A�V�������B �Ώ�����͂̐�ǂ����ƁA�_��I�Ŕ������i�F���L�����Ă���B���߁A���߁A�M�̏㉺�̗h��ɂ��킹�ċC�������͂��ށ[ �܂��܂������炱�����V���������������A�����ɂ͓�̒��F�ɏM�𒅂����B���̒��F�͗�����O�S�䑫�炸����Ă��āA�L���̓^�e���R�O�\��]�肠��A�����̒��F�̂����ł�����Ĕ������i�ς������Ă����B ���̓�����͌̐��݂ɏオ��A����(���̌�)�ɏo������B���T������͏\�ܗ�(��������A�ꗢ�͖�ܕS���[�g��)���藣�ꂽ�Ƃ���ɂ���B�܂��A�k��(���̌�)�����ɍs�����B�����͒��T������O�\�����藣�ꂽ�Ƃ���ɂ���B��������������ł��邪�A���T���̔������ɂ͂Ƃ��Ă��y�Ȃ��B ���̒��T���݂͂ǂ�F�̐������̂悤�ɐ��݂킽��A���[�͑���m��Ȃ��B �����N�̏��┐�̏�̎}�����ʂɐ���A��̏�ɂ͍��F�̘O�t�̂悤�ȋ���Ȟw�␙���˂������Ă���B ���������̌ܐF�̉Ԃ͓������ɍ����肠���č炫�A���E���E�[�E�ӁE�[��E�������ɂ��ꂼ��ɖ����́A������������ɕ������Ă��A���ꂼ��Ɏ�ނ̂��������Ȃ̂��B �����߂͉H���Ђ낰�ĂȂ����ɕ����A�������͌ΖʂɋY��Ă���B�����̒��̉H�����͕��ɗh����̂悤�B���̖����͖����ꂽ�ʂ̋����̂悤�B �����͋ՂƂȂ��ĉ��F��t�ŁA�݂Ɋ�g�͌ۂƂȂ��Ē��ׂ�łB �����̎��R�̔����鋿�������킳���ēV�̒��ׂƂȂ�A�ΐ��͊Â��E�₽���E��炩���E�y���E�����E�L���Ȃ��E�̂ǂ����悭�E����������̂��܂܂��A�����₩�ɂ������ƒ������Ă���B (�N������)����_�́A���̐_������������������킴�ł���A���̂܂������ƈ���́A�V��̐_�A�������������̎������ɓ���A�������������Ƃ��邩��ł���B ���A"�ΐ��ɉf�閞�������ẮA���邪�܂܂ɖ��S�ɐ�����Ƃ������Ƃ�m��A�ɋP�����ւ����ẮA���ׂĂ̂��̂����z���̌b�݂ɂ���ċ��ɐ�������Ă��āA���̎��R�̂����炷�p�m�Ƃ킽������������̂̂��̂ł���"�ƌ��B �\���̂̂��A���̌��̒n�ɂ����₩�Ȃ��������āA�_�{���Ɩ��Â����B�����ɏZ��Ŏ��R�̓����Ƃ��̂͂��炫�ɐg������A���̂܂l�N�̍Ό����߂����B ���������N�l�� ����ɖk�̒[�ɏZ�܂����ڂ��B���̒n�̎l���̒��]�͌���Ȃ��A���l�͍D�܂����B���܂��܂ȐF�̉Ԃ͂��̖���������Ȃ��s�v�c�Ȃ��̂���ł���A�ǂ�����Ƃ��Ȃ��Y���A�k�������Ƃ̂Ȃ��F���ȍ��肪�킽�����̋C������a�܂��Ă����B �����ɏZ��ł����ɂ������Ȃ���l�͂ǂ��ɋ������̂�������Ȃ����A���R�̐_�X���m���ɂ����ɂ͂���B ���̔������n���A�����̕��l�A������͂��̒��w�C���\�F�L�x�̖����̒n�̈�Ƃ��āA�ǂ����ċL���Ȃ������̂��낤�B�R�������ł�M�������͂ǂ����Ă����ɏW���A�M���ׂėV�Ȃ��̂��낤�B (�u�b�_�͋�s�̎���A�Q�����Ղɐg�����{���A���̉a�H�ƂȂ����Ƃ̘b�����邪)���̌Ղɏo�������Ƃ��Ȃ��A(�s�V�s���̐�l)�q�������łɗ������������ƁB���̂悤�Ȑ��Ȃ�n�̐��݂������L���ΐ�����͋��̂悤�Ȃ�������w�сA�����R����͎��R�E��n�肾���Ă��閳�C�Ȃ�d�g�݂�m��B �~�͖�c�^�Ɋ������������� �Ă͂������t�A�ɏ����������B �ؐH�����A�������ނ����ł̐����ł�������͊y���� ����Ƃ��͏o�����A����Ƃ��͎~�܂� ���E�𗣂�āA�Ђ�����C�s���Ă���킽���������������ɂ���B ����l�N�����O�\����C�L���B �� ������l�������j�̎R�ɏ��o��(782�N)�����Ƃ��A��C�͐^��(�܂�)�ƌĂ��A�܂�8�̏��N�ł������B���̏��N���Ⴍ���Ă�����w��ɒʂ��Ȃ�����A20�Ή߂��ɂ͓s�̑�w������A�R�̂�Ԃ��ƂƂ��A�ґz��������Ƃ��āA�R�тɓ���C�s�����B ���̍��̂��Ƃ��A��C�͈�҂̎��ɒԂ��Ă���B �\�O�����\ �J��̐���t�ŁA���͂��̂����Ȃ� �R�����z�����݁A�[�ɂ͉p�C��{���B (�R�̏Z�܂���)���ꂳ�������c�����ƍג������̗t�ŏ[�� �C�o���̗t�␙�̔炪�~�����オ�A�킽�����̐Q���B (���ꂽ����)�b�݂̓V���ƂȂ��čL���� (�J�̓���)���̐��������Ƃ����˂Ď��R���₳�����������B (�킽�����̏Z�܂��ɂ�)�R�������������ė��āA�̂��������� �R����(�ڂ̑O��)�y�₩�ɂ͂˂āA���̌����Ȍ|���I����B (�G�߂������)�t�̉Ԃ�H�̋e�����݂��� �������̌���A���̕��́A�킽�����̂�����𐴁X����������B (���̎R����)�����ɋ���A���炾�ƌ��t�Ǝv�l�̂��ׂĂ̂͂��炫�� ���炩��"���R�̓���"�ƈ�̂ɂȂ��đ��݂��Ă���ƒm��B ���A�����A�ЂƂ����̂��ނ������ �o(�^���̌��t)������Ԃ₭�� �킽�����̂�����́A���ꂾ���̂��Ƃŏ[�������B �����ɖ��C�Ȃ鐶�����̌�肪����B �\�㕶���\�@��C���W�u�R���ɉ��̊y(���̂���)���L��v��� �����A��C���܂��A���R�Ɛl�Ԃ̂�����̊ւ����悭�������A��������A����C�s�����Ă����B������A�����R�ɂ����鏟����l�̍s����܂�Ō��Ă������̂悤�ɋL�q�ł����̂��B���̋L�q�ɖڂ�ʂ��A��l�͖����������ƂƎv���B�����ɂ́A��l�Ɠ������ڂƂ���������A��C�Ƃ����l�������B�@ �@ |
|
| ��������l | |
|
�T�v / (�܂�)�@�ޗǎ���̑m�Ƃ����B������l�A�݊���l�A����ȂǂƂ��Ă��B�C�����ɂ����ʂ��A�����R�Ŕ����O�����������������B
⦍��R���N�ɂ��A�{�V�N�Ԃɋ��s�̍���q�m�ɐ��܂ꂽ�j�q�ł���A20�Ŏ��䔯(�o��)���A�ꖜ���ɂ��y�Ԍo�T���Ă̂Ŗ���(�݊�)�Ə̂���A���{�S���̗������s�����B �V�����N(757�N)����̖����āA�����R�̎R�x�M�𑩂˂�ړI�Ŕ����R�ɓ��R���A���͍��呁�͏�Βr���ӂœ�s��s�̌��ŎO������(�@�[�E���[�E���[)�����������B���ꂪ�����O�������̗R���ł���B�܂��A���m�ɏZ��9�̓������ŗ�(�㓪��)���r�ꋶ���đ������ꂵ�߂Ă����̂�@�͂Œ��������B�������ꂽ�㓪���͜������ĕ��E����E���r�������Ė�����l�ɋA�˂����̂ŁA�̎�E���_(�㓪������)�Ƃ����J�����B �V�����N(749�N)�����S��̒��b�A�瓿�A���{�i���b�����A��@�ƂƂ��Ɏ����_�{���̌����������B�܂��A�V����7�N(763�N)���x�����̐_���ő��x�_�{�������������B �������甠���Ɍ������r���A�C�ɉ����オ�苛������ŋ�������Y���Ă���̂�ڌ������̂œnjo������ƁA��t�@���������Ė@�͂ʼn�����C����R�Ɉڂ��悤�ɋ��������̂ŁA37���Ԃ̒f�H�F���Ŏ��������B���ꂪ�M�C����̗R���Ƃ��`������Ă���B�@ |
|
|
�� ���́A�����ŕ������w�ыA�����A���̌�̕������E�ς�h��ւ��Ă��܂����Ő��E��C�ȑO�̕�������ȑO�̕����ƎR�x�@���Ɏ䂩���҂ł���B�Ȃ��Ȃ�ꕶ����̑��Â�艽���N�����{�l����܂ꂽ�@���ρE���E�ς��@���Ȃ���̂��������A���̎�����������悤�Ȋ��҂����邩��ł���B���̈Ӗ��ŁA�_�������̏W�听�ҁE������l�̎c�e��ǂ����Ƃ̖{�ӂ������@�������������B ���āA������l�̊w�����́A��s�Z�@�Ƃ����B�u��s�Z�@�v�Ƃ́A�ޗǎ���̘Z�̏@�h�A�O�_�@�E�����@�E�@���@�E��ɏ@�E���@�E�،��@�������B�܂�A�����E����ρA�����F�ւƕώ������Ă��܂����V��@�E�^���@�̎Y���͌㐢�̂��ƂƂȂ�B ���{�ɂ͂��߂ĕ������`�������̂͘Z���I�̋Ԗ��V�c�̎���ł��邪�A�������q�̎���Ɏ����Ė{�i�I�ɏ������ꂽ�B(������Ȉӌ��Ƃ��Ē��N�����⒆���嗤����̒f�ГI���I�𗬂̓n���m�ɂ��Z���I�ȑO���畧���`���������邪�A�����ł͊�������) �������q�́A�����v�z�����ƂƂ������ƎЉ�̍\�z��ڎw���A����15�N(607)�A�ŏ��̌��@�g�Ƃ��ď��얅�q��h�������̂��͂��߂Ƃ��A���̌���A�����̗��w���◯�w�m���@�ɔh�����āA�ϋɓI�ɑ嗤�����̐ێ�ɓw�߂��B����ɑ��q������l�V�������������A�h�c�E�ߓc�E�{��E�É@�̎l�@��ݒu���ĕn���~�ώ��Ƃ������A���E���{���E�@���������������ĕ����v�z�ɂ��ƂÂ��������s���A����̔ɉh��z�����B�@ |
|
|
�� �������q�v��A�܂��Ȃ��O�_�@���`���A�����Ŗ@���@���`������B���̗��@�ɕt�����Đ����@�E��ɏ@���`����ꂽ���A��@�͎O�_�E�@���̗����w���w�Ԃ��߂̕⏕�I�Ȋw��@�h�ɂ����Ȃ������B�ޗǎ���ɂȂ��ĉ،��@�Ɨ��@���`����ꂽ�B ������s�Z�@�͓Ǝ��ɏ@�h���`���������̂ł͂Ȃ��A���@�������I�ɂ͊����ł���A���Ƃ̔�̂��ƁA���썑�Ƃ̋F�菊�Ƃ��Ă̖�����S���Ɠ����ɁA������������������ꏊ�ł��������B������l�̖{���́u����v�A���܂�͋��s�A���͏C�s�m�ł���c����蕧���Ɏ��ڂ�ڂ����������B�w⦍��R���N�x�ɂ��A��\�ɂȂ�A���䔯�����Ƃ��邪�A�s�̍������ɐ����ɑm�ƂȂ�����`����ꂽ���̂Ƃ���A����ȑO����C�s�m�ł��镃�̔w�������Ĉ炿����k�̑f�{�͏\�ł��Ă����B �����Ƃ���Ő�[�̕����������w�ԍ�����(���Ō���������w)�ɓ��債������͐������̔@���w��ɖv�����A�����̒m���~�ɂ��o�T�E�ɗ����������Â�悤�ɓǂݑ����A�₪�Ė����Ə̂�����悤�ɂȂ�ȂǑS���̍������̑m�B�𗽉킷�鋳�w��g�ɕt���Ă���B���̌�A�s�̍��m�ɖʎ���������ƂƂ��ɁA�X�ɕ��@�̉��`�����߂悤�ƁA�C�s�m�ƂȂ��ď������̗��ɏo��B ���m���L��s�c���c�K�ɖ����������ďZ�E�ƂȂ��Ă���B�Ȃ̎�����݂�����͓̂����Ƃ��ċɋ͂��ȍ��m�A�����������̖��O���g��������݂��邱�Ƃ͈ٗᒆ�̈ٗ�ł���A�@���ɖ�����l�ɑ��鐢�ԕ]���̍������Â�鎖��ł���B�c�O�Ȃ��瓯���͖앐�m�̕��ɂ��S�Ă��c����Ă��Ȃ����A�n���̐l�X�ɂ��w�܂��x�Ƃ��A�߂��̋��́w�܂����x�ƌĂ�L������Ă���B �����V�c�́A���Ƃ̈��N�ƌ܍��L�����F�邽�ߑS���ɍ�����(�������l�V���썑�V��)�E������(�@�ؖōߔV��)���������A����ɂ��������鑍�������Ƃ��ē��厛�����������B�܂��A�S���I�ɗ��ߑ̐����m�������ɔ����m��ߓ����z����A���������̓����@�\�̒��ɑg�ݓ�����Ă������B �O���Ɉɓ��������A�������������ꂽ�̂������I�����ł������B�܂薜����l�������ɗ��������ɂ͊��ɎO���ɍ��ƓI�厛�@�����݂��Ă������ƂɂȂ�B������l���ʓǂ����o�T�͓�s�Z�@�F�O�_�@�E�����@�E�@���@�E��ɏ@�E���@�E�،��@�̌o�T�ɍi����B�����āA�ޗǂ̓s�̍��m�Ɋw�є�b�R�̎R���ł̍r�s�ɑł����ݐS�_���ƂƂ��Ɍ����I�C������B�Ƃ̐ڐG���d�˂čs���A�C�����ɂ����ʂ���B �V�����N(749�N)�����������Đ_�ɕ�d���鎭���_�{����n������ʎ�o600���̎ʌo����,������`���Ă���B�b�͔�Ԃ��A���̏헤�̎����_�{�ɋ߂镨��(���̂���)�A�֏�(������)�����݂����B�@���̛ޏ������́A�ɐ��_�{�̍։�(�����݂̂�)�̂悤�ɏI�����������ɉ߂������ޏ������݂��Ă��邱�Ƃ̋��ɒu���Ă��Ă��炢�����B ���āA�����E�C�����ɐ��ʂ��閜����l�͓V�����N(757�N)����̖����āA�����R�̎R�x�M�𑩂˂�ړI�Ŕ����R�ɓ��R���邪�A���Ƃ��Ɣ����R�����{����Ƃ���C������B�̃v���C�h�ƕ����ւ̕��芴����`���ĎႢ�V�Q��(���m)�ւ̋��͂Ȕ�����R���������ɈႢ�Ȃ��B���ɏC�������֎~���ꂽ�蕧�������v�����悤�ɂȂ����炱��܂Œz���ė��������̗ƂƓy�������������邩�炾�B ���ꂪ�A���͍��呁�͏�Βr���ӂœ�s��s�̌��ŎO������(�@�[�E���[�E���[)�����������o�܂łȂ��������Ǝv���B���͍��呁�͏�Βr�����݂̒n�}�ɂ��Ăǂ̕ӂ���w���̂������̂��鎑���ɐڂ����Ȃ����A������l�͔����R�ւ̓o����t�߂̑��͍�(�_�ސ쌧���c���s����)�ɒ�q�B���̑��]�ҒB�ƂƂ��ɉ��h���\���A������l�͌ΖʂɌ������ē�s��s�̖��A�R���B��������O�����������������B �����A�O�������͖�����l���z�N�҂łȂ����Ƃɒ��ӂ�v����B������l���a������2�N�O��717�N�ɉz�̑哿�E�_�Z�T�t�A�א�(�z�O�������Ð��܂�)36�͔��R(�W��2702m)��q2�l�ƂƂ��ɊJ���B���R�ɂ́A�O�_�����āA�O�������ƌĂ��B���R���������E��s�������E��������̎O�_���`�����Ă���B�×����C�����̃��b�J�Ə̂���锒�R�M�̊J�c�E�א��Ƃ������B���O�������Ɩ{�n��瑂������Ă��邩��ł���B�א��Ɩ�����l�Ƃ̐ړ_�͎���̔g�ɓۂݍ��܂�ĕ���Ȃ��Ȃ��Ă�����̂́A�O�_�E�O�������Ə̂��Ƃ��낪���ʂ���Ƃ��납�疜����l�͎O���������n�m�C�����Ă����ƌ���̂����R�ł���B ����A�㓪�������������̂��C�������B�ҁE�א��Ȃ̂ł���B�א��́A�{�V���N(717)�A36�̎��ɔ��R(��O��)�֓o��A���R�̎R���ɂ���Εɒr(�����r)�Ŕ��R�������������������Ƃ����B���R���������́A�㓪�������Ƃ�����̓��������_�̎p�ŏo�������B�@�����A�א��́A���̎p�ɖ��������A����ɋF�O����ƁA�₪�Đ^�̎p�ł���\��ʊω��ɕϐg�����Ƃ����B���ɖ�����l�͑א���t�̋���������q�̔@�������ɐ��i���W�听���Ă���̂ł���B�������a�������N�A�C�s�m�̕���25�Ɛ���A�א���38�ł���B���̎O�����ǂ��q�����Ă������͌ܗ������ł͂��邪�A������l�̎c�e��ǂ��ɂ�A�����������l�Ƒא���t�Ƃ��Z��ɍ������Ă��鎖���������ė���B�����ĈႢ��\���A�א���t���ω��M���厲�ɂ����̂ɑ��A������l�͖�t�M���厲�ɒu����Ă������炢�ł���B �����R�Ɣ��R�����Ƃ̈����͓ޗǎ���ɑk��B���R�_�Ђ͍]�ˎ���܂ł͔��R�����ƌĂ�Ă����B�V���N��(729-748�N)�Ɋ֓��ɔ��(�ق�����)���嗬�s��������ɁA���ꔒ�R���̊J�c�א�����h�����ꂽ��q�E���(���悳��)�s�҂��A�V��10�N(738�N)�����ɔ��R�����Ђ����āA�\��ʊω��y�V��8�N(736�N)�A�����A���̌��т����ɏ\��ʌo�����ꂽ����z���J�����Ƃ���R�����N���o���A�a���������Ƃ����`�����c����Ă���B���ꂪ�������{����̋N����Ƃ���Ă���B�܂薜����l�������ɓ��R����19�N�O�ɓ��{�̉���(�]�ˎ��㒆����܂ŏh���{�ݖ�������(���)�ƌĂ�Ă���)�Ɣ��R�����Ђ͑��݂��Ă������ƂɂȂ�B�������݂̉���X�Ƃ͈���Ċ����̒��̌����Ђł��������ł��邪�A���ꂾ���ɓ��Ђ��o�R��������̓��W�ɂȂ��Ă������Ƃ͊ԈႢ�������ƂƎv����B�@ |
|
|
�� �א��̎咣�́A�㓪���̖{�n�͏\��ʊω��Ƃ����B���m�ɋ㓪���_�Ђ��J����\��N�O�ɔ������{�ɏ\��ʊω����J���Ă����̂ł���B�܂��ɑא��̋F�O�͓K�����A�������{�̖{�n�͔����R���̈��m�ɖ�����l�ɂ��J�J����A�㓪���_�ЂƂ����J���A�����Ȃ��l�X�̐M���W�߂Ă���B �Ƃ�킯�A�א���t�ɂƂ��Ė�����l�̂�邱�ƂȂ����Ƃ͐�^�̈�ɂ��������Ƃ͊ԈႢ����܂��B 757�N�����A������l�Ɣ��R�����̏C���҂Ƃ̐ڐG�̗L���͏؋����c����Ă��Ȃ����̂́A���͔���K���̐V�����Ղ̖k�����ɔ��R�_�Ђ��J��ꓯ���Ղ̓쐼���ɌF��_�Ђ��J���Ă��邱�Ƃɒ��ڂ����B �O�������E�{�n��瑁E�����E���R�_�ЁE�F��_�ЂȂlj����Ƌ��ʍ�������A������l�̔����O�������Ɣ��R�O�������ƌF��O�������Ƃ̐�ʈ������_�Ԍ����Ă���B �X�ɐ[�ǂ݂���Ȃ�A������l�����͍��呁�͏�Βr���ӂœ�s��s�̌��ŎO����������������ȑO�ɁA���ɕ����ƏC���҂Ƃ̗Z���ɐ������Ă��锒�R�����̑א��E����B�ƌF�쌠���̏C������B�҂Ƃ̎����Ȃ邨�V���Ă����O�ɂȂ���Ă����\�����l������B����͖�����l���݂̗̂v���������Ƃ��v���Ȃ��B���R�������тɌF�쌠�����Ƃ��Ă��A����̒��߂Ƃ��Ė�����l�������R�Ɍ������Ƃ���ΗR�X�������ԂƂ��č�����R�Ɍ����킹�����Ƃ��l�����邩�炾�B �Ȃ��Ȃ�A���R�ɂ���F��ɂ���A�V���̌��Ə̂���锠���͒n���̗��Ƃ���d�v�Ȉʒu�t�����ꂽ�C�����ɂƂ��ďd�v�ȏꏊ�A���̏ꏊ�֒��쒺�߂Ƃ��Ė�����l�����R����ƕ�������ق��Ƃ��Ēu����Ȃ��B�����ƑS���̏C�����̐�B�B���W�������ɈႢ�Ȃ��B���̊ԁA�����̐_�X��������O��������n�o���邱�Ƃ���l�ɑ������ƂƂ��ɈÂɏC���������̋㓪���_�̋��{�������ϑ����ꂽ�B�@ |
|
|
���א���t
(�������傤�������E691�|767)�@�א���t�͔���(7���I��)�A691�N�A�z�O��������(�� ����s�O�\���В� �א���)�ɐ��܂ꂽ�B �_���Ƃ���ꂽ��t��11�˂̎��A���̂������ʼnz�m�R��J���ɓo��A��s��s�̌�A���ɕ��̋�����������Ɠ`������B �א���t�̖����͓s�܂œ͂��A21�̎��A����͒��썑�Ɩ@�t�ɔC�����B ���̌�A36�˂̎��A2�l�̒�q�E��(�ӂ���)�s�҂Ə��(���悳��)�s�҂Ƌ���717�N�ɗ�����R���J�����Ƃ���Ă���B �{�V7�N(722�N)�A�����V�c�̂��a�C���F���ɂ���ĕ����������Ƃɂ��A�_�Z�T�t�̍��������B �_�T2�N(724�N)�A�s����R��K�˖{�n��瑂̗R����₤�����Ƃ��_���K�����̑c�ƌĂ�Ă���B �V��2�N(730�N)�A��،o���ʌo���@�����ɔ[�߂��B����́A�{�����}�����Ɍ������Ă���B �V��8�N(736�N)�A�����A���̌��т����ɏ\��ʌo�������B �V��9�N(737�N)�A�S�����vጂ����s���A�����ɂ��F����s���u�a���I���������Ɠ`������B ���̂Ƃ��A�V�c�����a���ʂ��������A�u�א��v�̑��̂������B �א���t�̖����́A�s�݂̂Ȃ炸�S���I�ɕs���̂��̂ƂȂ�A�������v�̊肢��������F���͂��M�������w�̑A�]�̓I�ɂȂ�A���R�M�͔��R�C���ҏW�c�ɂ��S���I�ɍL�����čs�����B ������l�������ɓ�����10�N��A�_��i�_���N(767�N)�A�z�m�R��J���ɖ߂����א���t�́A�߉ޓ��̐�A�ɍ��T��g�܂ꂽ�܂�86�őJ�����Ă���B �������K���鍑�w�蕶�����̋�d�̐Γ��͑א���t�̂���Ɠ`�����Ă���B�@ |
|
|
�� �א���t������������ �J�������͐_����̂̎��@�������B �����Ő����ɂ� 48�̎Ђ� 36�̓� 6000�V�@(�C�s�m��C���҂̏Z��)���������Ɠ`�����Ă���B �O�̒����̎�O�̔q�a�̕��͎O�\�O�Ԃ��������̂Ƃ���A�����ɂ����ẮA���̒ǐ��������ʏ@���I���͂��M����B �Ȃ��A���E�ɕ��ԏ����Ȍ�����6000�V�Ə̂����C�s�m�̏Z���ł���A�S�����א���t�̋����������낤�Ƃ����C�s�m���������݂������Ƃ�Y�قɕ�����Ă���B ���X�ɌÊG�}���Q�l�ɔ��@����������Ă���悤�����A���݂̏��A�ÊG�}�ɍ��v����ʒu����@���s�s�𗠕t�������悤�Ȉ�\���o�y���Ă���悤�ł���A�S�e���𖾂���邱�Ƃ����҂���Ă���B ������l�▜����l�̕��e�����R���ɑ����^���ۂ��A�����������Ȃ��������͗��j�̈łɏ����ĕ���Ȃ����̂́A���݉s�Ӓǒ����ł���B ���@�����Ȃǂɂ���āA15�`16���I���̕������̗l�q���킩��͂��߂Ă���B ���Ă̋����͓�����1.2�q�A��k1�q�͈̔͂ɍL����A�����̖k���Ɠ����ɂ́A�O���R����̂т�������������A�쑤�ɂ͏��_�쉈���ɊR�������Ă���B �����̒��S�����́A���������̍ג���������ɂ����āA�Гa�⓰������������ł����B���������k�����̒J(��J�Ɩk�J)�ɂ͑����̖V�@���W�����Ă����B�����̕��́A�܂��ɒ����́u�@���s�s�v�Ƃ�ׂ鐫�i������Ă������Ƃ�����������B �V�@�Q�̒��𑖂铹�H�͐Ε~���ő��a�������A�V�@�~�n�̏o���������Ԋu�ɔz�u�����ȂǁA���Ȃ�v��I�Ȑ������Ȃ���Ă����B �V�@�Ղ���݂������╨�̑����͐����p�i�ł���A�V�@�͏@���I�Ȏ{�݂ł���Ɠ����ɁA�m���̓���I�Ȑ�����Ԃł��������Ƃ��悭������Ă��܂��B �H��ނɂ́A���ˁE���Z�Ă����̂��ő����̒����������킪�p�����Ă����悤���B �܂��A���[��⒃����A���ԋ�Ȃǂ���������o�y���Ă���A������ʂ��đm�������̐����╶���̗l��������������B�@ |
|
|
�� ������l�̏�����O�������Ƃ͑א���t�̏�����O�������̉��p�Ƃ���@�[(�m)�E���[(�݉�)�E���[(�ޏ�)�̎O�̂̐_(����)���J�邱�Ƃł���A�����O�������͒j������m�����z���A�����ƏC�����Ƃ��K��������O�̂̐_�����J��Ƃ���������l�̃��b�Z�[�W�ł������B�C���ґ����炷��ƒ��삪�S���ɍ������⍑�������āA�{�C�œ��{���ɕ������L�߂��邱�Ƃ͎@�m���Ă���A�C�����̍s�����������Ƃ�����Ôg�Ɉ��ݍ��܂�Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����傫�ȕs�������������ŁA���삩�猭�킳�ꂽ���m�Ƃ̖ʉ���A������̏ꍇ�����Ⴆ�̊o��ő҂��\���Ă����ɈႢ�Ȃ��B �C���ҒB�͖�����l�̔����R�ӂ��Ƃł̓��Â��������猩���ώ@�����B�s�炿�̂��ȃC���e���m�ł͂Ȃ��A�����B�Ɠ����悤�ɑ厩�R�Ɍ������ē�s��s��ςF�����s�����l�ł��邱�Ƃ��@�m����悤�ɂȂ�A�E�C���旧�S�������x�͘b������������̂��ǂ������m��Ȃ��ƁA��O�̐S�����ς���������m��Ȃ��B������s����C�萬�ɔ����R���Ɍ��������Ȃ�Ζⓚ���p�Ɩ��𗎂Ƃ��Ă����\�����������B ���m�ɏZ��9�̓������ŗ�(�㓪��)���r�ꋶ���đ������ꂵ�߂Ă����̂�@�͂Œ��������B�������ꂽ�㓪���͜������ĕ��E����E���r�������Ė�����l�ɋA�˂����̂ŁA�̎�E���_(�㓪������)�Ƃ����J�����Ƃ̓`���͍J�ɗ�����Ă���B���炭�A������l�v��100�N200�N��ɖ�����l�̈̑�ȋF���͂��㐢�ɓ`���悤�Ƃ���J�̌�葐�������ɋy���̂Ǝv����B �㓪�������E����E���r�������ċA�˂����Ƃ���B���E����E���r�͏C���҂̓�����w���B��̓��Ƃ͔����R����ƈʒu�t����S���̏C���ҏ��h��9�l�̓�(������)���������A�㓪���_�Ђ̑n�݂͖�����l�ƏC���ҏW�c�Ƃ̘a�r���Î����Ă���B�㓪�������ƃf�t�H�������ꂽ�`��������Ă��邪�A�����I�ɂ͎��s�̋�����Ȃ��V�����@���ƌÂ��@���Ƃ̖������̌��ł���A���ꂱ����������a�r�������ɈႢ�Ȃ��B ���̂ɐ�~�����ׂ��łȂ������h�̎咣�ɑ��A�C���ҒB���R�����Ȃ��������ł���B����́A������l�̒������[�̏��F���傫���B�݉Əo�Ƃ��唼���߂�C���҂ɂƂ��ċ�̓I�ɒ��쑤�̔F�߂���l�̑��[���F�̋�̈Ăɑ��A����ȏ�̒��쑤�ւ̔��t�͕s�v�ɂȂ�Ɣ��f���A�C�����ɐ��ʂ��_���K���������閜����l�̎O�������̕\���ɑ��A�C���ҒB�͖{�C�Ŗ������悤�Ƃ̕������߂��B���̐��ʉ��ł̋��͎҂͔��R�C���ҒB�������C�z�������R���ӂɕY���Ă���̂��B���R�O�������͔����O�������̐�y�i�ł���A�א���t���C���҂𑩂˂�{�n��瑂̗��ɓK���Ă��邩��ł���B ������d�v�Ȃ̂͏��[�̑��݂ł���B������l�͑�a�̍��͑��Â�菗�����_=�ނł���A�_���ƍՂ�͏������{���S���ė����j����m���Ă����B�C�������ٓ�����Ƃ��Đ��܂�ς��̍s���d�v�����Ă���B�C�����ɕ����F���Z���Ȃ��čs������ɂȂ��čs���ɂꏗ�l���Ƃ���R�������������A������l�͓�����菔�X�̋�����Ă��炸�A���̌�ɂȂ��Ă����l�����Ƃ��Ă��Ȃ��B�����́A�l�Ԃ����ʂƒj���̋�ʂȂ��A���҂̗썰�������R�ɋz������ƐM�����Ă������Ƃ�����B�w�V�ґ��͍����y�L�e�x�̌������̍r����`�����̍��ɂ́u���Ô����̒n�A�����h�C����u�A�}���Z�S���]�Z���������A�ޔyꡔq�ׁ̈A�n���`���������������Ɠ`�Ӂv�Ƃ���A�����ɂ́u�����h�C����u��v�Ƃ����鏗���@���҂������������Ƃ��`����ꂢ��B�ޏ������͎��삪�W�܂锠���Ŏ��҂̗�������A�Ԃ߂��\�҂ł������ƍl����Ă���B�����h�C����u��̂��̌�̑S���ւ̍L������L�^���镶���͋ɂ߂ĖR�����B ������l�́A�u�����v�u�C�����v�Ƃ����^�����������_��ɔ����Ă���B�_����m���ɂ��_��������Ă���B�Â���̒n�����R�_�ƕ��Ƃ̖{�n��瑂ւƘ_�_�����[�v�����Ă���B�u�����R�̐_�ł���v�Ǝ��疼���O�̂̐_�X����l���������āA�@�[�E���[�E���[�̎O��������O�ʂɉ����o���A�C���ҒB�̎R�x�@���̐_�Ɠ����̐_�������J�邱�Ƃ��O��ɒu�����b�Z�[�W�ɉ��甽���̗]�n�͖��������B ���[�E���[�̂��n�t�����A����̏C���҂�ޏ��̐�����Ղ�ۏ�������̂Ɨ������ꂽ�B����ɉ����Ė@�[�͎O���o��̕����F�̐�瑁A���[�͓������t�̖��ӕ�F�̐�瑁A���[�͎{���؎҂̊ϐ�����F�̐�瑂Ƃ���钴�ꗬ�̖�����l�̏�����{�n��瑂̗��O�܂ŋ�������A�����ƏC�������W������čs�������C�����̒[���ƂȂ����B������l�ƏC���ґ�\�Ƃ̘b�������͈�{�̒ʂ������̂ŋ��������������̂ł���B�������̈�苗������R�x�C�s��ςޏC�s�m������鎞�オ�m���ɂ������̂ł���B ������H���������Ƃ������A�C���ҒB�̐��q�����R�ɏh���_�X��̂ނ��Ƃ������A�_���K���E�{�n��瑂̗��ɗ��ł����ꂽ�����O���������C���ҒB�Ɏ��R�ɖ����Ȃ�������A���������삩��h�����ꂽ���m�̗i�쉺�ɒu�����S�������C���ҒB�ɗ^���Ă����\���͍����B���m�ΌΔȂɋ������@���������������ꂽ����ł͂Ȃ��B���̌ΔȂɂ͋㓪���_�ЁE�ٍ��V���J��ꖈ�N�Ղ�����s����Ă���B�����_�Ђ͐_�������߂ɒ�G���Ȃ��������Ƃ��K�����A�̂Ȃ���̍ՓT���A�ȂƎ���s���Ă���B ����6�N�A�����V�c�̏��s�ɍۂ��A���n���͏��O�J�ɑ�n���͑�O�J�Ɩ��̂��ύX���ꂽ���A�̉͌��Ȃǂ̒n���ɊW���閼�̂����ł������R�ɑ����c����Ă���B�S���̏C���ҏ��h�͔����R=�n���ƈʒu�t������A�n���̗��Ƃ���S���̏C���ҏ��h�̋��L���ƂȂ��Ă����B�����ł������W�́E��`�͂�L���Ă����̂͏C���ҏW�c�Ƃ���A���������Ĕ�������������Ƃ������Ƃ͌���Ō����Βn���V���ЁE���[�J�������ǂ��蒆�ɂ������ƂɂȂ�A�����̒���̐^�̑_���͏��̑S���l�b�g���[�N�̍\�z�ɂ������Ǝv����B �������̓w�łƊ��q�ւ̐�����̖h��ǁB����ƍN�̔����R�����]�˂̏d�v�̖h��ǂƂ������Ƃɒʂ��锠���R�̒n���I�E�R���I�������]�ˎ���܂ŏd������ė����B�ޗǎ���ɂ����Ă͓��厛���S���̍������̒��S�ɒu����m�B�������B�����ł͂��邪�A����̕����̎�荞�݂Ƃ̑Η����ɂ������R�x�@���Ƃ�킯�S���̏C���ҒB�̊��W�܂锠���ɖ�����l����R�����������@��������n�������A�S����������̏����W�Ə��̏d�v��n�Ƃ��A����Ŏ���̐��E�ŕ��@�̉ʂ��������𐢂Ɏ����B�����ɂ�鍑�ƈ��N���肤����̏d�v�Ȑ����I�A�v���[�`���u������������v�̔w�i�ɂ��������̂Ǝv����B �������Ε��E�Γ��Q�ɂ���������悤�ɁA�����̔����͎��҂̗썰���W�܂�n���M�̐��n�������B�܂��A�����ɂ́u�����h�C����u��v�Ƃ����鏗���@���҂������������Ƃ��`�����Ă���B�ޏ������͎��삪�W�܂锠���Ŏ��҂̗�������A�⑰�E�Y�߂鏎�����Ԃ߂��\�҂ł������ƍl�����Ă���B�O���s�̈�苗����H�Ɏc�����s�q���A���̎���w�i�̗�������ނ��̂��W�������̂���肪�c����Ă���B ��ɏq�ׂ��헤�̎����_�{�̛ޏ��̂悤�ɔ����̏C����u������l�ɉ��̂�������l�̕����ꂽ��ɂ͛ޏ�(�݂�)���t���ĉ��A�����ʂ����������������A�j�������莋���Ȃ�������l�͌㐢�ɂ�����ޏ��̎����I�Ȑ��݂̐e���Ǝv�킴��Ȃ��B�ٍ��V���J���Ă��邱�Ƃ��ʼn߂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B �����_�Ђ͉��������u���Ă��㓪���_�Ђ̍ՓT�͑��Ɏ��p�����ė����B������l�����͂�s�����ĒB�ς����O�������̎O�̂̐_�Ƌ㓪���ƕٍ��V�Ȃǂ͊F�����ł��邱�Ƃ����{�����ł���B������l�ȍ~�͍Ղ�̎�Î҂ł��锠�������͋㓪���_�Ђƕٍ��V�̍Ղ�͑��`�̌������ʍs���Ȃ̂ł���B ���āA������l�͓O�ꂵ���_���K���_�҂ł���B���̎v�z�͖����̐_�������߂��������܂őS���̐_�Е��t�ɂ����ĘA�ȂƑ����Ă���B�{�n��瑂Ƃ��Đ_�ƕ���Z�������J���Ă���B���āA������l�̎c�e��ǂ��Ɠ���l�����ɐM�Ă������͖�t�@�����������Ƃ��ǂݎ���B������l�̒�q�B���A��t�̂��Ƃ͎��m���Ă���A��������(11���I����)����V�����̖{���Ƃ��Ė�t�@���������J���Ă���B �����܂œǂ܂ꂽ�l�Ȃ�A�����_�ЂƔ��������̓�w�\������������锤�ł���B�����_�Ђ͖������N�̐_�������߂̒��������V���Ȑ_�Ђł���A��Ր_�������n��(�Ʒ��к�)�A�F�ΉΏo����(˺������к�)�A �؉ԍ��P��(���Ż�����к�)�A�ƂȂ��Ă���V�c�n�̐_�X���J���Ă���B�@ |
|
|
�� ���Ɛ_���̖��̉��ɐ_���K���̐_�X�͕\�ʏ㖕�E����V�c�̖��ɂ��n�����ꂽ�������@�������̕��t�͎���A�ʓ���m�B�͖����̐����p���V���Ȑ_�А_���̑I����]�V�Ȃ�����Ă���B�߂������j�̒��ɂ����ċ�a�̑I����]�V�Ȃ����ꂽ�l�X�́A����ł����Â̓`������葱��1200�N�������ė���������l�̐��_��[���������A�����Ղ��s���͌�������Ă��舰�m�ΔȂ̐_�X�͑���J���Ă���B �ޗǎ���̓V�c�̖��ɂ��n�����ꂽ���@�̕��t�╧�����ꂽ�B�����ɓ�����j�ɖ��m�֖��Ȑ푈���ɂ�����ꂽ���O�ɂ��S���ő����̋M�d�ȗ��j������Y���j������Ă���B ����ΌÂ̓V�c�ɑ���d���s�ׂł���ƒf���ł���B ���������_�ЂɌw�ł�@�����Ȃ�A�܂��^����ɔq�݂����͔̂����R��k���Ƃ����P����(�q���V����)�̏��тł���B�����̂��̂�芲���Ԃ��̂������ł��芲�����炩�Ŕ������B���̕P�����́A �����O�֎R�̈�p�u�Ɗ|�R�v�쐼�Ζʂ̕W��600m�`800m�́A�]�ˎ��ォ��֔��тƂ��ĕی삳��Ă����A�J�K�V�A�u�i�A�q���V�����Ȃǂ̗тɍL����B������l�̕�E�V�����̂��鏬⦍��K���̕����Ɏ������Ă���B������É����c���S���쒬�̒��Ɏw�肳��Ă���B���͋������@�������̊J�c�ł��閜����l�̕�(���Ï�)�̋߂��ɂ���P�����̏��т��C�ɂȂ��Ă��傤���Ȃ��B������l�ƕP�����̊W���C�ɂȂ�̂��B�������@�������Ղ̑b������߂��̕P�����̏��т����Â��ÂԗB��c���ꂽ�p�Ǝv����̂ł���B�@ |
|
|
���P����
�q���V����(�C�M���X�ł́A�X�̏����ƌĂ�Ă���)�@�������\������̈�ŁA�����m���̎R�n�ł͔������k���ɂ�����B�����_�Ў��ӂɂ̓q���V�����̏��т�����A���̐��͕S�{�ȏ�Ƃ����B�a���u�P�����v�̃V�����́A�C���h�Y�̍����o��(�T���\�E�W��)�̂��ƂŁA�̂̐l���i�c�c�o�L�̂��Ƃ������Ă̂��Ƃ����B ������l���������@��������n���������A���ɐl�H�̌������͙R���p�����������@�̌��̍����o���̏��т͉i���ɕ��@�̍��Ղ��c���ɈႢ�Ȃ��ƁA���삩��̒���(���@�ɂ��R�x�@���E�̓���)�����炷��C�����߂ē������ӂɕP�����̕����F�̔Z���P�����т������\���͍����B �Ȃ��ɕP�����������R���k���Ȃ̂�?�A��������悤�������͖�����l�̐_�ʗ͂Ƃ����ł͓����Ă������V��A�R�ɑ������O�Y�x�ւ̎R���ɔɖ���P�������͂��߂Ƃ��鋐�،Q�͈ɓ������̐^�̕�Ǝv����B ���Ȃ݂Ƀq���V�����ƃi�c�c�o�L�̉Ԃ͂悭���Ă��āA2cm�قǂ̔����Ԃ�����B���̖́A����ɓ���������A�F�͒W�Ԋ��F�A�G���ƃq�����Ɨ₽���A���̖̔��Ɣ�r����Ƃ��ɗǂ����ނɂȂ�B�₽���̂́A����̂����������A�����z���グ�铱�ǂ��ʂ��Ă��邩��Ƃ����B�ؔ����������̂ŁA�Ɖ��̏����Ƃ��Ē��d����Ă���B���炪�����ꗎ�������Ƃɂ́A�D���F�̔��䂪�ł���B �Ԋ���6���`8�������A���Ȃ̂ʼnԂ�ꡂ���A�߂��Ō���`�����X�͏��Ȃ��B 9�����A�ʎ����n���B�ʎ���1.5cm�قǂ̗��`�A�����т��������؎��Ō����B ���̐��N�ԁA�ΐK�����O�J�Ɏ��鎩�R�T���H�̃q���V�������A�}�ɂ��ԗl�̂ӂ���݂������Ă���B�����ԂƂ͖��炩�ɈႤ�B�a�C���낤���B �q���V�����Ǝ��Ă���q�R�T���q���V�����́A�ؔ��ɗւ̂悤�ȋ����邱�ƁA�}�Ԃ肪�r�����ƁA�Ȃǂŋ�ʂ���B��q�̓q���V�������傫���B�����ɑ����������Ă���B �u�����o��(���炻������)�v�ƌĂ�邱�Ƃ����邪�A���߉�(���Ⴉ)�l���S���Ȃ����Ƃ��� �߂��ɐ����Ă������ƂŗL���ȁu�����o���v�́A �S���ʂ̔M�ю��̂��ƁB �u�����o���v�͓��{�̕��y�ł͈炽�Ȃ��B �ł́A�Ȃ��Ēւ����́u�����o���v�� �Ԉ��ꂽ���E�E�E�B �́A����m�����A�����ɂ䂩��̂��鍹���o���̎��͓��{�ɂ������Ƃ���͂��A�ƎR�ɓ����Ă��낢�� �T�����Ƃ���A�Ēւ̖����� �u���ꂪ�����o������v�Ǝv�����݁A������L�߂����߁A�Ƃ̐�������B�@ |
|
|
�� �V����7(763)�N��,�ɐ���(�O�d��)�K���S�̑��x�_�Ћ߂��̓���ɏZ��,��Z�̈���ɕ��̑��������Ƃ���,���R�Ɛl�������,�u�d���ߋƂ��s���Ă�������,�Ƃ��Đ_�̒n��(�_�̐g�ƂȂ���)���Ă���,�i�v�ɐ_�̐g�𗣂�邽�߂�,���@�ɋA�˂������v�Ƒ��x�_�̑�����������B����͎R���J����,����������,�܂����x�_�̐_����,���x�_�ɕ�F����,���x���F�Ɩ��Â���,���̑��x�_�{���Ɉ��u�����B���ꂪ�����Ɍ��ꂽ�ŏ��̐_������ł���B ���q�R��{�@ ���@��(���傤�ڂ���)�́A���m���L��s�ԍ⒬�ɂ���^�@��J�h�̎��@�ł���B�R���͑��q�R�B�@���͏�{�@�B�{���͈���ɔ@���B �������q���O�͒n���K�ꂽ�ہA�ԍ��{�Ƃ������ɑ��q���J�铰�F(���q��)�����Ă����Ƃ��n���̐��|���ł���Ƃ����B����V�c�̎���(809�N - 823�N)�ɁA������l�������_�ЍČ��̒����邽�ߏ㋞�������A���̋A�r�ɕa�đ��q���ɂė×{���A�O�m7�N(816�N)10��2���Ɏ��������B��l�̒�q��́A���q�������z���ď�l���J��Ƃ����B �Ó`���̈�ɍ���V�c��������l�̗�_��n��悤�ɂƒ����������ꂽ���̂Ɠ`�����Ă��邪�A���ꂪ���q���Ȃ̂���⦍��R�V�����������̂���̓I��_�̏ꏊ�ƌ������Ȃǂ����L���ꂽ�Õ����ɐڂ��邱�Ƃ��o���Ȃ��B�V�����͎��������̑傫�Ȏ��@�ł������悤�œ����̔��������͖�����l������V�c�ɔ��������Ђ̍ċ��Č�����t���Ă���o�܂����蔠�������ЂɎ���������n����������I�]�͖͂��������ƌ����A�܂���q�B�����q����������Ŏ����I�]�T�͖��������Ɛ��@�����B ���Ƃ���Ȃ�A���E��̗��N�ɑ���ꂽ�V�����̎��������͍���V�c�̒��߂ɂ�薜����l�̗�_�Ƃ��đ���ꂽ�\�����������ɂȂ邪�A����V�c�ƐV�����̈��ʊW�̊m��Ɏ����Ă��Ȃ��B �m�͓����Ă��Ȃ����̂́A�Г`�ɂ��Α�\��㍵��V�c�͍O�m���N(817)���ɂ��x����(�����I�ɂ͏��c���˗̂Ƃ��̎���)�̎O�B����i�����Ɠ`����ꖜ����l�����E�������N817�N��⦍��R�E�V�������������ꂽ�N�Ɗ�����������Ă���A�m�M�͖������̂̎O�B��i�ƐV���������Ƃ̈��ʊW���ǂ߂����ȋC�����ė����B ��N�Ƃ͂Ȃ邪��Z�\�ܑ�ԎR�V�c�̎��ɂ́A�c�q�L�o������\�ܑ����E�ɒ��C�A�V�c�̍c�q��d����ł��ꑊ���̌o�ϓI��Ղ���������蓾�ʂ��ƂƎv��ꔠ�������͒�x���o����o�ϊ�Ղ�L���Ă����ƌ�����B�܂����H��c�͔��������𐒌h���A������l�\��������i���Ă���A���������͑n������薜����l���n�̌����ЂƓ������Ƃ���̂𐬂��Ă���A�����F�������������ߎ��O�ЂƂ���Ă������A����̐M�Ă��A�֓�����̕ʊi��ЂƂ��Đ��߂��Ă����B �b�͔�Ԃ�������l�����O���̔����R�̉ΎR�͑傫�ȕ��͖������N��Ԃ�ۂ��Ă����B�x�m�ΎR�̉����(800�`802�N)�́C���{��I�́u�D���J�̂悤�ɍ~��C�R���͍g�ɐ��܂����v�u�Ӑ������ǂ������߁C�����H��p���Ĕ����H���J�����v���̋L�q���e����C�����n�◬�𗬂�����ϕ���(864�N)���i����(1707�N)�ƂȂ�ԕx�m�ΎR�̗��j�����3�啬�Ƃ݂Ȃ���Ă����B �Ƃ��낪�ŋ߂̒��ׂ��瑫���H�߂������͂��̕��Α͐ϕ��͋ɂ߂Ĕ������Ƃ��������A�����I�ɕx�m�g�c�����n�悪�n��ɂ�薄�ߐs������x�m�R�k�Ζʂ�ʂ��Ă�����ԌÂ����C���������s�ʂƂȂ�A1�N��ɂ͑������J�ʂ����Ƃ����̂͏��Â̍����X���Ɍq����x�m�R�쑤���[�g�̋����C���̐芷�������̂��Ƃ������B�����A�Z���ԂƂ͌����A���������z���铌�C���̑����͋i�ق̉ۑ�Ƃ���A���̒n�����锠�������ւ̒��삩��̒��߂����������̂Ɛ��@����A������l�̒�q�B���C���҂�n���_���Ȃǂ̋��͂����Z�ߏ��c���ƎO�����q���V���ȓ��C���������̂Ǝv����B �������N�_�������߂ɂ���Ĕ�����������������p�~���A�����_�ЂƉ��̂����ۂɁA�������@�������͔p���ƂȂ�A���������͑ł��ꂽ���A�������@�̖{������ɔ@���Ɛe�a���l�M�Ɠ`������\�������ƂƂ��ɁA�e�a���l���͔������ݕ����Ɉڂ�����Ă���B�����ɂȂ�O�͔����O������(�����匠��)�Ə̂��ꖜ����l�����Ă��������@���������������ɂȂ��Ă������A�O�������E�㓪���_�ЁE�ٍ��V�������匠���̍ł���Ȓ��ł��������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@ |
|
|
�� �Ō�ɂȂ邪�A���ڂ��ׂ���̂̐_���������_�Ђ̑q�̉����猩���������Ƃł���B�ޗǎ���̐_�̑��ȂǑS���I�ɑO�㖢���̂��Ƃł͂��邪�A���[�E���[�ƌ����郆�j�[�N�ȑ����m�F���ꂽ�̂ł���B�c���ꂽ�m�[�͖�����l�����ł���v�O�̂ƂȂ茾���`���ƕ�������B������l�����͖�����l��`�ʂ����l�����ł͖����m�[�̂��_�̂Ɨ������������O�������̗R�����玩�R�ł���B����N��͖�����l�������Ă���������A�����ƌ�̎��ƊӒ肳�ꂽ���A���삳�ꂽ�͕̂�������ł����q����ɓ����Ă���ł��\��Ȃ��B�v�́A������l���R��̐_�X�����`�[�t�ɐV���Ȑ_�X�����グ�A������l�̏�������̂̐_���ƌȂ̑����㐢�̒�q���ؑ����肵�ʐF���A���݂̕����̎���֎O�̎c�����n���I�Ŏ��R舒B�Ȍ����̎Е����A�����Ȃ����m�ΔȂɐ����n���Ă���悤�Ɋ������B ���ɍ��d�v�������Ɏw�肳��Ă���u�ؑ��݊���l�����v�ɉ����A���̓��[�̐_�������d�v��������2012�N4��21���w�肳�ꂽ���Ƃ��u��������V���v���Ă���B�@ |
|
|
��������l 719�N�`816�N�B�{���͖���B���������������㋻������l�B �����̖��̗R���͌o���ꖜ����ǔj�������Ƃɂ��B�헤�̎����ɐ_�{�������Ă���A�����ɗ��ē��������ċ����A���ꂪ���������������㋻�������ƂɂȂ�B���m�Β��ɏZ�݁A�t�߂̏Z�������ꂳ���Ă����ŗ����F��ɂ����߁A�㓪���_�Ƃ��ĉ��S�������̂�������l�̌��тƌ�����B97�˂̒�����S������܂ŕ����̕��y�ɐs���������m�ŁA���̈�e�͔����_�Ђ̕a���J���Ă���B ���݂̔��쒬�K�����܂ޖk������~�͏�⦍��ƌĂ�A���������⦍�����(�����A����)�̐_�̂ƂȂ�A�V�����N(757)��⦍��������J�����݊���l�̕�E��⦍��R�V����(�p��)���������B��l������������ɁA��q��������l�̈������K���̒n(��⦍�)�Ɏ��������̑厛�����Ă����̂ł���B ��P�x�R���̌��{���疜����l�����m�ΌΔȂɌ��݂̔����_�Ђ̏ꏊ�ɔ����O�������Ƌ������@��������n�������Ƃ͌����A�W�����������m���琁�������Ԋ��C���������A�~��ł͕X�_���ƂȂ茵�����C�s���������ɈႢ�Ȃ��B������l�͎R�x�@����M��C���Ғc�̂̎��܂Ƃߖ��Ƃ��Ē��삩�甠���R�֔h������A������������_�������̍r�C�s���d�˂Ă������̂́A���d�˂邲�Ƃɒ�q�����̊��߂�����A�����̔����R���m�ΔȂɔ䂵�A�����̓�̒�n�Ɉʒu���鏬⦍�(����K��)�͐��i�g����(�N�ԕ��ϋC��16�����O)�A���������̐_�̂ł����������R�֑����^�Ԃ��Ƃ������Ȃ����Ǝv����B �ΔZ�����R�Ɉ͂܂�A������̗��ꉺ��J�ԂɊ����̔_�Ƃ��U�݂��A���X�̘V��j���Ƃ������݂ƂȂ���������l�͎���ɊՐÂȓ��n�֒ʂ����Ƃ������Ȃ��čs���A���ɂ͐Ԏq��w������q�̎p���ς��āA��l���N���ɗ��ʂ�����e���v�炵�������m��Ȃ��B�r�Ԃ�R�x�C�s�̖��̊J��A�R�x���ɂ͕s�\�ȓc�����k���A�y�ɑ����t������炵�̉��[���A������l���Ō�Ɍ��߂���⦍��̗��R�̕��a�Ȏp�����������m��Ȃ��B ��q��������l����⦍���[��������Ă��邱�Ƃ��n�m���Ă���A�����Ƃ��Ă͋��ٓI�N���97�˂ő剝��������l�̐S������������A�K���̒n�Ɏ��������̑厛���������A���̌�s�̈ꗬ���t�ɕ�������点������l�̒�q�����ɂ��i�����{��������ꂽ�B�������̏C���ҒB�̎Q�q�����ł����R�����������B �p���ƂȂ������R�⎞���͖��炩�ł͖������A�����̏�Ԃ���r�I�ǍD�ł��邱�Ƃ���A�Ђ�n�k�ɂ��{����|��ł͖����A�V��������I�ϑJ���ɂ��p����]�V�Ȃ����ꂽ�Ǝv����B����������ɂ����t��(�K���n��̏Z�����ێ��Ǘ����ė���)�̓������痈���쉈���ɖk��300���قǗ��ꂽ���c�̒��ɑb���c����Ă���B������ɂ���A������l�����O��⦍����������悤�ɒn���Z�l����l�ւ̑����Ɛ����̔O�������A�V�����̔p����A�N�Ƃ������ɖ����R�ɕ����̈��u�ێ��Ǘ��ƕ�d�ɓw�߂ė����̂ł���B �쓌��300m�ɂ��钷��������Ɉʒu����K����t���̒��ɕ��������u���A��Ȃǖ�������z�������Q(�S24��)���Ɏ�蔲���ė����K���n��̏Z�l�̋����M�S�Ɍh�ӂ��������Ȃ��B ���̂������Ő��ɂ͕����͌��d�v�������Ȃǂ̈�Y�o�^���Ȃ���A2012�N4���ɂ́u����Ȃݕ��̗����p�فv�������A������l�v��A���ɖ�1200�N�Ȃ��Ƃ���O�ɐV�����̕����͍���Ƃ��č����̈ϑ��ɉ�����ׂ��ۑ��ɑ����������u�ꏊ�ւ��߂�ɂȂ����̂ł���B����܂ł̌K���̐�l�B�̌��J�ɓ������������B �����炭����V�����n�݂��ꂽ�u����Ȃݕ��̗����p�فv�ɐl�X�̒��ڂ̓I���W�܂�Ɨ\������邪�A���͑S�����������ɂ��A�X�ɔ���K���̗��j��Njy�������ƍl���Ă���B�@ |
|
|
��������l
������l���������ޗǎ���́A�����������u�炭�Ԃ́A�ɂ��������Ƃ��v�ޗǂ̓s�ł��������A�n���ɋN�������V�@��-�_���K�����t�ɂ��̓s(����)�Ɏ������܂ꂽ�B �����Ă��̐_���K���̊@�ƂȂ����̂�������l�ł���A�_�{���̌����⌠���M��(�v�z)�̊m���Ɏ�����ʂ����ꂽ�̂ł���B�܂��ɓ���̏@���I�V�˂�搂�ꂽ�^���@�̋�C��A�V��@�̍Ő��ƕ����i��������̈̑�ȏ@���Ƃł��������Ƃ��M����B ������l�͋��s�̐��܂�ŁA���͒q�m�Ƃ����A�u����v�ƌĂ��C�s�m�ł������B ��l�́A�q���̍����痘���ŕ��o�����悭�����悭����ΕƂł������B���������L�����̂�H�ׂ��ؚ��������A�������D�܂ʐ��m�̂悤�Ȓn���Ȑl���������B���̒q�m�́A�q���ɂ��Ă͒����������̂ŁA���Ɂu��Ȃ�v�Ƃ��ĕ���ɓ���邱�Ƃɂ����B �w⦍��R���N�x�ɂ��ƌ����V�c�{�V�N���A���W�ɍ���q�m����B������m�炸�B��j�q���B������̍ہA�������H�������A���ɋяJ�������B�����ɔV����Ƃ���B�G���킫�܂��Ďߖ�ɓ���A��\�ɂȂ�A���䔯���āA���ہA���L�o���ʼn{���邱�ƈꖜ���B�̂��݊��Ə̂��B���B�̗������������B ����ɓ����Ă���́A���ۂƂ��ĕ��T����u���A���ɖ����̌o��ǔj�����̂Ől�ǂ�Łu�݊��v�Ə̂���悤�ɂȂ����B�����čX�ɕ����̉��`�����߂悤�ƁA�C�s�m�ƂȂ��ď������̗��ɏo��̂ł��邪�A�ޗǂ̓s�ɏo�č��m�w�Ɋw�сA��b�R�ɓo�����̂����̍��̂��Ƃł������B���̍��̔�b�R�͐�炱�������C�s�m�̏C���̗��ł������̂����A��C��Ő�������C�������̂́A���ꂩ��܂������ƌ�N�̂��Ƃ������B �V�����N(749�N)�����S��̒��b�A�瓿�A���{�i���b�����A��@�ƂƂ��Ɏ����_�{���̌����������B �V�����N(757�N)����̖����āA�����R�̎R�x�M�𑩂˂�ړI�Ŕ����R�ɓ��R���A���͍��呁�͏�Βr���ӂœ�s��s�̌��ŎO������(�@�[�E���[�E���[)�����������B���ꂪ�����O�������̗R���ł���B�܂��A���m�ɏZ��9�̓������ŗ�(�㓪��)���r�ꋶ���đ������ꂵ�߂Ă����̂�@�͂Œ��������B�������ꂽ�㓪���͜������ĕ��E����E���r�������Ė�����l�ɋA�˂����̂ŁA�̎�E���_(�㓪������)�Ƃ����J�����B �܂��A�V����7�N(763�N)���x�����̐_���ő��x�_�{�������������B �������甠���Ɍ������r���A�C�ɉ����オ�苛������ŋ�������Y���Ă���̂�ڌ������̂œnjo������ƁA��t�@���������Ė@�͂ʼn�����C����R�Ɉڂ��悤�ɋ��������̂ŁA37���Ԃ̒f�H�F���Ŏ��������B���ꂪ�M�C����̗R���Ƃ��`������Ă���B�@ |
|
|
���c���ꂽ�����S�Ă���V�����̗��j��ǂ݉���
������l���S���Ȃ�ꂽ���N�E�O�m���N(817�N)�ɏ�l�̕�Ƃ��ď�⦍��R�E�V����(��������)���n�����ꂽ�B���z�l���́A�ޗǎ���̌���ɓޗǂ̓s�ɂ����Č��݂��ꂽ���������̗l���ɕ�������̂Ɛ��@�����B���Ԃ�A�ޗǂ̓s����r�̗���H�����ȉ��E�l���Ăꂽ�ɈႢ�Ȃ��B �n�������ɂ͕����͈��u����Ă��Ȃ��B�����͑S���I�ɕ������̋������q�͕K�������Z�����Ă��炸�A�_�������̎R�x�@���ɂ����ẮA�������q���͎R�E�E�E�₻�̂��̂ɐ_�삪�h��Ƃ̎��R���q�̔O�������A�_�������v�z�̑��B�E������l�̒����̒�q�B�ɂƂ��ĕ������u�̕K�R���͓��̋��ɂ����������Ǝv����B�܂�A��t�@�����������u�����܂ł̒������ԕ����͐V�����ɖ����������ƂɂȂ�B ���āA�V�����̖{���Ƃ�����t�@������(�É����w��L�`������)�̐���N��͐��Ƃ̐�������Ƃ���ł́A�������㒆��(11���I����)���Ƃ���A��ؒ���̕������S���I�ɍL�܂鎞��ɓ����ĕ������q���Ƃ��A�����̎��ɕ��������u����͓̂�����O�Ƃ��镽�����̏Z�E����z�������̂Ɛ��@�����B ���ɏ\��_�������̐���N��́A��������3�́E���q����E��k�����㖖�`�������㏉���E�]�ˎ���ɕ��������Ă���B�{���̖�t�@�������\��_���͏\��̑����Ă����̖��̂ł��邩��ɂ��ĕ������㑢��ꂽ�\��_���������c����Ă��邱�Ƃ���A����������ɏ\��̑S�Ă������Ă������ł���B�@ �������A�Ό����d�˂钆�ɂ����ĉ��炩�̍ЉЂɂ����đ���_����������A���q�����蕽������̐_���𒉎��ɖ͂����_�����������A��k���E������������l�ȍ�蒼�����Ȃ���A�]�ˎ���Ɏ���܂ŗ��̏Z�E�̌v�炢�ŏ\��̂̐_�������S�Ă��ێ�����ė������Ƃ���Ă���B �]�ˎ���̉������܂ŐV�����������������́A��ԐV���������̐���N�オ���肳���K�v������B �����āA�K����t���̒��H�����̓�����K�v���낤�B�V�����̔p�������ƌK����t���̑n���������d�Ȃ�Ƃ͌���Ȃ����A�V�����Ɋւ��鎑����������Ȃ�����A�c���ꂽ�����Q�⌚��������ǂ݉����������r�������̂�����ł���B�b�̈�Ք��@���K�v�ƂȂ邩���m��Ȃ��B ������ɂ���A�c���ꂽ24�̂̕������V�����Ɉ��u����Ă������̂Ƃ������Ƃ�O��ɒu���Ȃ�A�V������817�N�ɑn������A�����A�����A���q�A��k���A�����A�]�ˎ���܂ő������Ă������Ƃ���������ǂݎ����ł���A�V�����͒����Ԃɘj�蔟��K��(��⦍�)�ɑ������Ă������ƂɂȂ�B �܂��A�V�����̌��ݎd�l�Ɋւ��ẮA�V�������n�����ꂽ817�N�ȑO�ɍ��ꂽ���������`���̎��@�l������������Ƃ��ĐV�����Ղ̒n���◈����Ƃ̈ʒu�W���̏�A�R���s���[�^��ŎO�������f�����쐬���邱�Ƃ���n�߂�̂��V�����T�v�̌����o�ϓI�Ȗ͍����@�Ǝv����B�@ �@ |
|
| ���b�㍑�ΐ��`���̐����ɂ��� | |
|
���͂��߂�
�u�×��b�㍑�͌ł��������A��ɘA�Ȃ�R�X���J���Č̐���x�m��ɗ��������ʁA�엀�ȍk�n�����ݏo���ꂽ�B�v����́A�b�㍑�̐�����鍑���ݓ`���Ƃ��ē`������Ă����b�㍑�ΐ��`��(�ȉ��u�ΐ��`���v�Ƃ���)�́A��ʂɒm��ꂽ���炷���ł���B���j�ȎR�x�n�悩��~�n��J�ɗ��ꍞ�ފ���̋}���̉͐�ɂ��A���Q���₷���R���̒n�`�I�������A�ΐ��`���̔w�i�ɂȂ����Ɨ�������Ă���B ���̂悤�ȎR�������ΏۂƂ��������E�����j�����ł́A��������ߐ��ɂ����Ď��{���ꂽ��h�H���Ƃ���ɑΉ������n��Љ�̓����A�܂����͐여�H�̕����⎡���E�����Z�p�̕ϑJ�ȂǂɊւ��錤�����A����܂ŐϋɓI�ɍs���Ă����B ���̈���A���Ɋւ��M��`�����A�n��Љ�̒��łǂ̂悤�Ɍ`���E�p������Ă����̂����ۑ�Ƃ��������́A����܂ňꕔ�̍�������قƂ�Ǎs���Ă��炸�A�����E�����̓W�J��͐�̗��H�ϑJ�ȂǂɂƂ��Ȃ��n��Љ�̍ĕҐ����A�M��`���Ƃ������l�X�̐��ɑ���S�ە\���ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ����̂��́A�\���ɖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �����Ŗ{�e�ł́A�`���ŏЉ���ΐ��`��������ɁA���̓`�����ǂ̂悤�ɂ��Č`���E�p������Ă����̂����l�@����B �ΐ��`���͕����̓��e���`�����Ă��邪�A���̂��������ϒn���ɂ��J���`����ΐ��`�����߂����ẮA���ɍ��B�ޏ������������ϒn���̉��N�ł���u����n���R���L�v����сu���n�����F�����N�v���j���Љ�A���̋L�q���e�̕��͂��s���Ă���B ���̈���A�c�~�R(�B��s)��Ƃ��ē`������Ă���������̌ΐ��`���ɂ��ẮA�B��s����ψ���ɂ�葍���w�p�����������s����Ă���A�l�ÁE�����E���p�E���z�E�����Ƃ����w�ۓI�ȕ��삩��c�~�R�̐M�ƈ�ՁE�╨�������I�Ɍ�������Ă���B���ł��A�R�{�`�F���́A�_�����K�������c�~�R�̐M���u�{���v�l���Ƃ��Ĉʒu�t����ƂƂ��ɁA�P���O�R�̎R�x�M�ƘA�g�������̂Ǝw�E���A�܂��ΐ��`���ɂ��āA��n�Ɍb�݂������炷���y�̕�_�M����Ղɂ��āA�b�{�~�n�̊J���ɂ����čő�̓�G�ł������䒺�g��Ɗ�����̐�����߂�M�ƁA�c�~�R���܂P���O�R���ӂ̎R�x�M�̒��ŏ������ꂽ�R�̒n����F�̐M���d�Ȃ荇���`�����ꂽ���Ƃ�_���Ă���B �{�e�ł́A�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����A��̌ΐ��`�����Ƃ肠���A�����̊W���ɂ��čl����B�@ |
|
|
����@�c�~�R�̕����ƌΐ��`��
�{�͂ł́A�c�~�R�ɊW����ΐ��`���ɂ��čl�@����B�c�~�R�͍b�{�~�n�̐����A�䒺�g����n�̐���k���ɂ��т���W�����Z�Z�Z���[�g�����̎R�n�ł���A�ԐΎR��(��A���v�X)�ɑ�����P���O�R(�ω��x�E��t�x�E�n���x)����ҎR�E�瓪���R�E�×��R�ւƑ��������̐�[�Ɉʒu����B �c�~�R�̎R���t�߂́A�䌩�_�Љ��{�̋����ƂȂ��Ă���A�������㏉���܂ł͐^���@���@�̕����䌩�_�Ђ̕ʓ��߁A���݂̉��{�{�a�͋����ƌĂ�Ă����B�܂��A�R���t�߂���͌Ñ�̒G�������Ղ��o�y���Ă���ق��A���{�쑤�ɂ͉�����N(��O�Z��)���̔N�L������Α������m�F����Ă���A�Ñ�E��������c�~�R�̐M���p����Ă������Ƃ�����������B ���݂̉��{�́A�{�a�E���a�E�q�a���ڑ����Ĉ�̂ƂȂ��������ƂȂ��Ă���A�������N(�ꎵ�O�Z)�����̎Гa����{�Ƃ��A�����O�\�Z�N(���Z�O)����я��a��\���N(���O)�ɑ�C�����{�����ƍl�����Ă���B���̂����{�a�̐g�ɂ́A���s�O�ԂŒ����ƍ��E�̎O�̊Ԃɕ�����Ă��邪�A�E�̊Ԃɂ́A�ߔN�Ɏ���܂Ŗؑ������`�������J���Ă���(�����}��1)�B���̑����͈��܁E��Z���`���[�g������A�����̌��ʁA���q����(�\�O���I)�̐���ƍl�����Ă���B �w�b�㍑���L�x�Ɏ��^����Ă���u���R�����v�ɂ́A�䌩�_�Ђ̖{�a�ȉ��̎Гa����ы���F���E�����V�q���E�s�����������͂��߂Ƃ��镧���������グ���Ă��邪�A���̂����{���́A�R�����Ɍ�����ؑ��̕s���������ɊY������Ɣ��f����Ă���A�܂��A�������O�ɘr���Z�{����O�ʘZ�]�̎p�����Ă��邱�Ƃ���A�{�����}�̐_�A�R�_�Ƃ����J��ꂽ�O��r�_��\���Ă���ƍl�����Ă���B ����A�w�b�㍑�u�x�́u�c�~�R���v���ɂ́A�u�����E���q�a�@�O�ԁE�Z�ԁA�O�����n�{�n���A�E�n�����喾�_�A���n�R�㉤�q�����v�ƋL����Ă���A�����̋����ɂ͎O�̔�������A����F�����̔��A�����喾�_���E�̔��A�R�㉤�q���������̔����J���Ă����Ɠ`����Ă���B ��q�����悤�ɁA�{���͉��{�{�a�̉E�̊Ԃ��J���Ă������Ƃ���A�w�b�㍑�u�x�̋L�q�ɂ��������ƁA�{���͉E�̔����J��ꂽ�����喾�_�̑��ɊY������ƍl������B �����喾�_�ɂ��āA�w�b�㍑�u�x�́u�c�~�R���v���ɂ͎��̂悤�ɋL����Ă���B �y�j��1�z �̃V�^���m���A�P���R�m�쉺�j��A�A���A�_�u�g�]�t�A�Z�x��l�g�]�t�ҏZ�����A�R�����_�g�̓��C�Z��R���w���^�����R�V�d�B�m�n���J�L�����ŗ��샊�e�܍��m�탒�{�Z���A�̃j�R���c�~�g���X�A(�ȗ�)�Z�x��l�n�R��m���j�Z�V�R�㉤�q�m�����ʕP���W���e�O�j�ꏗ�������A�������Չ��q�g�]�q�A���n���ԉ��q�E�J�{���q�E�����P�i���A�n�����L�e�l�S�g�i�V�A���Ճ������j���W�A���ԃ��R���j���W�A�J�{������j���W�A�������s���j���W�e���j���j�ރL�e�_�g�i���A�������_�Ȍ�l�q���e�X�_�g�i���A����������E�R�����_�E���㌠���E�z�����_�A�����i���g�]�w���A �j��1�ɂ��ƁA�����喾�_�́A�R�����_�ƂƂ��ɍb�{�~�n�암�̎R���J���A���𗬂��Ĕ엀�ȓy�n�ɕς��A�b�㍑�l�S��n�݂����Ƃ����Z�x��l���_�ƂȂ������݂Ƃ���Ă���B���Ȃ킿�A�����喾�_(�Z�x��l)�ł���ƍl������{���́A�ΐ��`���̎���ɊY�����镧���ł���ƈʒu�t������B ���̈���A�w�b�㍑�u�x�́u�c�~�R���v���ɂ����āA�u�{�n���v�u�����喾�_�v�ƂƂ��ɋ������J���A�����̍��̔��ɔz�u����Ă����u�R�㉤�q�����v�̏����͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂��B �w�b�㍑���L�x�́u���R�����v�ɂ́A�䌩�_�Ђ��J��ꂽ�����̂������j���Ȃ����Ƃ��āA�u����F�@�ؑ��v�u�s�������@�ؑ��v�ƂƂ��ɁA�u�����V�q�@�����v���L�ڂ���Ă��邪�A���̂��������V�q�������̖{���ł������@�P��(��A���v�X�s)�ɓ`�����铺���̋���F����(�����}��2)�ɊY������ƍl�����Ă���B �{���́A������Z�E�Z�Z���`���[�g������A���q����(�\�O���I)�̐���ƍl�����A�{���͋����t�����䐳�̖̂{���ł������B�������㏉���̐_����������ɂ������p���ƂȂ����ہA�{���͖{�n���ł���������F���ƂƂ��ɓ����̖{���ł���@�P���Ɉڂ��ꂽ���A�����l�N(�ꔪ����)�܌��O���̖@�P���̉Ђɂ��A�{�n���̋���F�����Ď����A�{���݂̂���������Ɏ������ƍl�����Ă���B ��q�����悤�ɁA����(���{�{�a)�̉E�̔����J��ꂽ�����喾�_�������`�����ɊY�����邱�Ƃ��画�f����ƁA�{���́A���̔����J��ꂽ�R�㉤�q�����ɊY������ƍl������B�R�㉤�q�͍����喾�_(�Z�x��l)�̍ȂƂȂ������ʕP�̕��ł���A�w�b�㍑�u�x�́u�c�~�R�����v���ɂ́u��Í����m�_��R�����w�V�e�ΐ� �����V���S���n�g�i���V���R�㉤�q��c���~�L�{�V�e���j���p�m���������v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���A�R�㉤�q�����́A�����̐_�ł��鍑���喾�_�ƂƂ��ɔ_�k�_�Ƃ��Đ��q���ꂽ���Ƃ��킩��B ����ł́A�c�~�R�ɓ`������ΐ��`���́A��������m�F�����̂ł��낤���B���Ɋւ��ߐ��O����k��R�����╶���ނ����݂��Ă��Ȃ����߁A�c�~�R�ɊW����ΐ��`���̔��ˎ����͒肩�ł͂Ȃ����A���ۏ\���N(�ꎵ�O��)�ɐ��������w�b�B���x�ɂ́A�u�����S�×��̐��̕��ɕc�~�R�Ɖ]�L�A���R��ɗ����ʂӋ���F�́A���ߚ����̐����b�ֈ�̕c���o���ӂƂāA�ꚠ�̕S�����N�����\�O���ɑ��N�̐V�Ă����������U�ɝn�֎��Q�v���悵�A�×����̌��B�����R�\�V�v�Ƃ���A�\�����I�O���i�K�ɂ����āA���Ɍ×����̌��`�Ƃ��Čp������Ă������Ƃ��킩��B�@ |
|
|
����@�����ϒn���ƌΐ��`��
�O�͂ł́A�c�~�R�ɊW����ΐ��`���ɂ��čl�@�������A�ΐ��`���ɂ͂�����ʂ̃X�g�[���[�����݂���B����́A�b�{�R�ɗ�ՍϏ@�̌Ù�������(�b�{�s)�̓����ł������@�鎛���J���Ă����u�����ϒn���v�ƌĂ��n����F��(�����}��3)�Ɋւ���`���ł���B �����ϒn���Ɋւ���ŌÂ̕����Ƃ��Ē��ڂ����̂́A�\�ꐢ�I�ɐ������A�\�ܐ��I�ȍ~�ɏ��ʁA�NjL���ꂽ�w�n����F�쌱�L�x�Ɍf�ڂ���Ă��鎟�̂悤�ȓ`���ł���B �y�j��2�z �����̓g�]��͓����j���^���B�މ̓m��j�A�l����S�]���o�J���m�D������i�������m�͌��A���B���j�Y�g�j�Z�J���e�����N���P���n�A�l�A�����͌��g���t�P���B�ރm�����j�A�����䓰�g���V�e�A�Α��v�L�Î���F�A���B�{���n�n����F�A�Z�ڎO���m�����A�؋�m�ʐF�j�e�}�V�}�X�B�C�����y�\�]�N�g�]���V�B(�ȗ�)�~�a�V�c�m��F�j�A���J�p�j�V�e�A�^���R�����V�����j�P���o�A�ރm���n�A���Ð��R�����x�m�[�j�A�����m�Ӄj���ʉ@�g���V�e�A���R�j�[�N���ʃt�B�s���F�m�䌚���A�ϓx�r�[�m����^���B�{���n�n���j�e�݃X�B�R�[�l�������V�e�A�����m�փ��R�N���v���P���A�ރm�����^���m�׃j�������e�A�y�j�ރm�͌��j�ڃe���ʃw�o�A���l�������䓰�g���X�i���B �j��2�ɂ́A�O�͍���l(���m���ɓ�s)�ɏZ�ݒn����F�𐒔q�����@�t���A�M�Z��(���쌧)�̑P�������Q�w���闷���A�x�͍�(�É���)�̕x�m�R�[�Łu�b�B����m�����͌��j���ʃt�n�����v�̑��݂�m��A�����̓r���ŗ���������ۂ̌������L����Ă���B ���Ȃ킿�A�u�����́v(������)�������ɗ����u�b�B����m�����͌��v�Ɂu�����䓰�v�ƌĂ��n����������A�Z�ڎO��(��ꔪ��Z���`���[�g��)�̍ʐF���ꂽ�ؑ��̒n����F�������u����Ă������A���̓��͖{���A�u�����v(�{���A��A���v�X�s)�͔̉Ȃɂ������s����Ɠ`�����ʉ@�̖{���ł���A��������̏~�a�V�c�̎���(�݈ʊ��ԁ@�O�m�\�l�N�m����O�n〜�V���\�N�m���O�O�n)�ɍ^���ɑ����ė����ꂽ�Ƃ����B �܂��A�\�ܐ��I�ȍ~�ɏ��ʂ���A�w�n����F�쌱�L�x�ƈꊇ����ċߐ��ɗ��z�����w�n����F�O���쌱�L�x�ɂ́A�s��b�㍑�́u���R�v(�b��s)�Ƃ��������\�]��A���������A��k�\���̎R����Ƃ��A���̒n�Œn����F�̉��g�Əo��������A�����́A���R�̖k���ɑ�͂������ɗ���A���̐쉺�͐���Ɍ������Ă������Ƃ��L�ڂ���Ă���B �����āA�s��́A�n����F�̎p��̕����ɍ��݁A�{�V��N(���ꔪ)�O����\�l���Ɉ�Ԏl���̑������������A������{���Ƃ����J�����B����ȗ��A�u�ΐ��������k�A�ރm���̃g���P�A�\���������L�j�V�e�A�t�n�J�}�h���j�M�n�C�A�H�n�C�l���c�~�P���o�A�l�āw��ρx�g�n�\�V�P���v�Ƃ���悤�ɁA���̕������u��ϒn���v�ƌĂ�L��������炷���Ƃ��Đ��q���ꂽ���Ƃ��L����Ă���B �Ȃ��A�{���ɂ��ƁA�s��͑����̖��̂���֓��Ɩ��t�������A���̌�̌o�܂ɂ��Ď��̂悤�ɋL����Ă���B �y�j��3�z ����A�~�a�V�c�m��F�j�A�ރm���^���×��V�e�A�����j���g�X�B�̃j�A���V�R���t���X�B�˃e�A�V���\�N�\�����A�O�@��t�j���V�e�A�w���֖@���V���x�g�z���i�V�A���_���ՃP���o�A���l�J�j�����A�g�p���z�j�V�d�}���P���B�T���o�@�����g�n�A���m�S�A�������y�g���g�]�t�R�R���i���B����A���a�V�c�m��F�j�A������a�m�@�m��̃i���o�A�䑒��@�����@�m�����j�e�A���x�L�R���鉺�A���B���A���z�������n���B �j��3�ɂ��ƁA�~�a�V�c�̎���ɍ^�������葐�����r�p�������߁A�V���\�N(���O�O)�\�����A�u���֖@���V���v�Ƒ����̎������߂Đ��_���J�����Ƃ���A�^�������܂����B����ɁA���a�V�c�̎���(�݈ʊ��ԁ@�V����N�m���ܔ��n〜��Ϗ\���N�m�����Z�n)�A�u�@�����v���A�V�c�̕�ł���u������a�m�@�v(�������q)�̏��̓��ɂ��������߁A�@�䂩��̖@�����@(���s�s�E����)�̖����ƂȂ����Ƃ����B ���ł��A�����ϒn�����J���Ă����u�@�����v�ɐ��_�����킹���J�����Ƃ���A�^�������܂����Ƃ̋L�q����A�\�ܐ��I�i�K�ō����ϒn���Ɛ��_�ւ̐M����̉����Čp�����ꂽ���Ƃ����������ڂ����B �Ȃ��A�j��2�́w�n����F�쌱�L�x�ł́u�b�B����m�����͌��v�ɂ������u�����䓰�v�A�܂��j��3�́w�n����F�O���쌱�L�x�ł́u���R�v�́u���֓��v�ƁA���҂̐��b�̓��e�ɂ͍��ق��m�F����邪�A�����ɗ������(�u�����́v)�̔Ȃɒn�������J�������ɂ����݂���_��A�~�a�V�c�̎���ɍ^���̔�Q�������Ƃ��`����Ă���_����A���҂͋��ʂ̓`�����甭���������b�ł���Ɣ��f�����B �����āA�����̐��b�̓��e��w�i�Ƃ��A�����ϒn���ƌΐ��`���Ƃ̊W����̓I�ɋL����Ă���̂��A�\�Z���I�㔼�̐퍑����ɐ��������w�b�z�R�Ӂx�Ɍ����鎟�̋L�q�ł���B �y�j��4�z �ق����悤���n�A�b�㍑�A�ƂƂނ����n�����~�Ȃ�A�Ƃ����B���~�ł��n���ڂ��̌䂿���ЂɂāA��̎R������āA�ꍑ�̐��A���Ƃ����ӂ���ւ���ɂ��A�b�B�������n�ƂȂ�āA�������̂��Ƃ��Ȃ�B����ɂ��āA���~�ł��n�����ƃn�\���ǂ��A�������o�A�u�@�鎛�v�Ɛ\�B���̕����́A�u�����ēy�Ɛ��v�Ɖ]���ƃn���B�ق����₤����Ԃ�o�A�b�B�n�����тȂ�B���㖘���b�B�����n�A�������~�ł��@�鎛����������ׂ��B �j��4�ɂ��ƁA�b�㍑�����Čł���������ɁA�@�鎛�̏��n����F(�����ϒn��)�̐����ɂ���čb�㍑�̓���̎R�n���J���A�ꍑ�̐��������x�m��ɗ��������߂ɁA���������n�ɂȂ����Ƃ����B ���̂悤�ȍ����ϒn���ɊW����ΐ��`���ɂ��āA�����`������Ă�����e�ɗގ����錴�^���`���̂́w�b�z�R�Ӂx�������Ƃ��Ă���A���������M���ꂽ�\�Z���I�i�K�ɑk�邱�Ƃ�����������B �܂��j��4����́A�b�㍑�̓����҂����������ϒn�����J��@�鎛��ی삵�Ȃ���Γ�������������ƁA�\�Z���I�̍b�㍑�ɐ������l�X�̊ԂŔF������Ă������Ƃ��킩��B ���̌�A�ߐ��ɓ���A�ΐ��`���ɂ��ďڍׂ��L�����j���Ƃ��āw�b�㍑�u�x�̋L�q�����ڂ����B �y�j��5�z ��ύ���n���m���L�j�]�t�A�{�V���s���F�{�B�j���^����R�����L�^���������V���A�n����m�m�������V�f���m���j�Ճ��@�鎛�g���X�A����z���O�Y���m�n�w�ڃV�i�\���M���Õ{�w�ڃV�A�㖔�_�m���������j�ڃV�e���j���݃Z���A(�ȗ�)�b�B�L�lj��j�s���F�j�n����m�m�������~���m���j���u�Z�V�K�^���j�Y�q���S�㍂���m��j�~�}���V���A���l�惊�A�Q�e�V���䓰�g���X�A��j�O�@��t��ڗ]�m���j�͍�V�m�������o���m���j�������S�Ï���j�J�V�u�L���֖@�鎛�g���z���\�V���V����m�@�����@�m�����g�i�X�A�~�a��V���\�N�m����g�A���A �j��5�ɂ��ƁA�@�鎛�́A�{�V�N��(���ꎵ〜����l)�ɍs������ϒn���������āu�����v���J�������Ƃ��n�܂�ł���A����N��(��Z�Z��〜��Z�Z��)�ɂ͌��`��(�V���O�Y)���u���ꋽ�v�ɁA�܂��i�\�N��(��܌ܔ�〜����Z)�ɂ͕��c�M�����u�Õ{�v(�b�{)�ɓ������ڂ��A����ɁA�������Ɉړ]���Č���(�w�b�㍑�u�x���Ҏ[���ꂽ�\�㐢�I����)�Ɏ������Ƃ����B �܂��A�s��������������́A�^���ɂ���āu�����v����㍂��(��A���v�X�s)���ӂɗ�����A�n���̏Z�����u���䓰�v���J�������A�O�@��t(��C)���A�V���\�N(���O�O)�ɂ��̑���͂��Ĉ�ڗ](��O�Z�Z���`���[�g��)�̕�����A�{���̑������̓����ɔ[�߁u���S�Ï���v(�b�{�s)�Ɉڂ����Ƃ����`�����`����Ă���B �j��5���j��2�A3�A4�̋L�q�Ɣ�r����ƁA�w�b�㍑�u�x�̍����ϒn���Ɋւ���L�q�́A�w�n����F�쌱�L�x�w�n����F�O���쌱�L�x�w�b�z�R�Ӂx�̓��e��Z�������A�܂����ꂼ��̋L�q���e�̐��������Ƃ��悤�ɒ������Đ������Ă��邱�Ƃ��킩��B ���̈���A�����ϒn�����́A�w�n����F�쌱�L�x�w�n����F�O���쌱�L�x�Ɍ�����s��E��C�Ƃ��������m�ɉ����āA���`���E���c�M���Ƃ������b�㌹���̈ꑰ�䂩��̕����Ƃ��āA�ړ]���J��Ԃ��Ȃ���`�����Ă������Ƃ�A�s��R���J�������ƂȂǁA����܂ł̓`�����ϗe���Ď`����ꂽ���Ƃ��m�F�ł���B �Ȃ��A�w�b�z���L�x��i���N(��ܓ�)���ɂ́A�u�������ܐh��A����m�n�����旧�g�e�A��{�m���m�n�`���������v�Ƃ���A�u����m�n�����v(�@�鎛)�̍b�{�ړ]�̏��L����Ă���B����́A��q�����j��4�ɋL����Ă���悤�ɁA�b�㍑�̓����҂͖@�鎛��ی삵�Ȃ���A��������������ƔF������Ă������Ƃ�w�i�Ƃ��āA�����b�㍑�����Ă������c�M�Ղ��A�b�㍑�̍���Ƃ��Ė@�鎛�̕ی�����s�������Ƃ�\���Ă���B ���̂悤�ɁA�����ϒn���Ɋւ���ΐ��`���́A�n���M�ƍb�㍑�̐��Q�Ɋւ���`�����\�ܐ��I�܂łɕ����������Ă������ŁA�\�Z���I�Ɍΐ��`���Ƃ��Ă��̌��^���������A����ɋߐ����Ƃ����Ă����̓`�����Z���E�ϗe���A�\�㐢�I�����܂łɂ͍����`������Ă�����e�Ɋm�肵���ƍl������B�@ |
|
|
���O�@���т���̌ΐ��`��
�ȏ�A�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����ΐ��`���ɂ��čl�@�����B�{�͂ł́A��̌ΐ��`���͑��݂ɓƎ��ɔ��˂������̂Ȃ̂��A����Ƃ����ʂ̌��^��L����`���Ȃ̂�����������B ���͂ōl�@�����悤�ɁA�w�n����F�쌱�L�x�ɂ��ƁA�u�����́v(������)�������ɗ����u�b�B����m�����͌��v�ɂ������n����F�����J��u�����䓰�v�́A�{���A�u�����v(�{���)�͔̉Ȃɂ��������ʉ@�̖{���ł������Ƃ����B�܂��w�n����F�O���쌱�L�x�ɂ��ƁA�����ϒn�������J�����u�@�����v(���֓�)�́A�u���R�v�ɏ��݂����Ƃ����B�����āA�w�b�z�R�Ӂx�ł́A�����ϒn�������u���~�ł��n���ڂ��v�ƌď̂��Ă���悤�ɁA�{���͌Ï�����J���Ă������Ƃ��������Ă���B �@�@�@�}1�@�b�㍑�ΐ��`���W�n�} �����̎j���ɋL�ڂ��ꂽ�b�{�ړ]�ȑO�ɂ����鍑���ϒn�����̏��ݒn���܂Ƃ߂�ƁA1�{���A2�����A3���A4�Ï���A5����Ƃ����悤�ɂȂ�B����1����5�܂ł̒n��́A�}1�̂Ƃ���A��������䒺�g�삨��ѓ���ƍ������銘����̋������H�����ɓW�J���Ă��邱�Ƃ��킩��B���ۂɁw�n����F�쌱�L�x�ɂ́A�u�b�B����m�����͌��v�̏��ݒn���u�����́v(������)�������ɗ����ꏊ�ƋL���Ă���B�܂��A�w�n����F�O���쌱�L�x�ɂ́A�u���R�v�̖k���ɑ�͂������ɗ���A���̐쉺�͐���Ɍ������Ă������Ƃ��L�ڂ���Ă���B �����쓌���H�́A����(�b��s)���瓌�̕��p�Ɍ����A�r��ƍ���������A�쐼�̕��p�ɗ����ς��ė���(�b�{�s)�t�߂œJ����ƍ������Ă���A�i�\�O�N(��ܘZ�Z)�ȑO�ɗ����M���炪�z������ė��H���ߐ���܂ő������Ă����ƍl�����Ă���B�w�n����F�쌱�L�x�w�n����F�O���쌱�L�x�Ɍ�����͐�̐����́A�܂����������쓌���H��\�����Ă���ƍl���ĊԈႢ�Ȃ����낤�B �����āA1�͕c�~�R�̓쐼�R�[�𗬂�䒺�g��ƍ������Ă��邱�Ƃ���A�����ϒn���̐M�́A�c�~�R�[�̐{��삩��䒺�g����o�Ċ�����Ɏ��銘���쐅�n����ɓW�J���Ă���A�c�~�R�̐M�Ƃ̐ړ_���m�F�����B �j����ɂ����Ă��A�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����ΐ��`���ɂ͐ړ_������������B���Ȃ킿�A���ۏ\���N(�ꎵ�O��)���ɐ��������w�b�B���x���V��ɂ́A�����ϒn���Ɋւ���ΐ��`���ƕ��L���āA�c�~�R�Ɋւ���ΐ��`�����L�ڂ���Ă���B�܂��A�Éi�l�N(�ꔪ�܈�)�ɕҎ[���ꂽ�w�b��p�L�x�ɂ́A�}2�̂悤�ȕc�~�R�ƌ䒺�g�삪��̂Ƃ��ĕ`���ꂽ�}�}�ƂƂ��ɁA���̂悤�ɋL����Ă���B �y�j��6�z �c�~�R�@�㞊�슄���@���ɎЂ���B����n���@�����Ƃ��]���a���Ȃ�@�ƚ����_�Ƃ�z�J����Ƃ��ւ鎛����āA���J���B���̎��Η]����B�Â��B�ɚ����_�A�s���F�Ɨ͂�C�ē�R��r�w���A�ΐ����Ě���蓂��A��c��B�n���̂ɍ��R��c�~�ƍ��Ƃ��B �j��6�ɂ��ƁA�c�~�R�̎R���̎ЂɁu����n���v�Ɓu�����_�v���J���Ă���A�u�����_�v�͍s��ƂƂ��ɓ���̎R�n���J���Čΐ��𗬂��A�b��̍��y���J�����Ƃ����B�����ł͕c�~�R�̓`���̒��ɍ����ϒn�����o�ꂵ�A�c�~�R�̖{�n���ł��鋕��F�ƈ�̂̂��̂Ƃ��ē`������Ă������Ƃ��킩��B�܂��A�}�}(�}2)������A�c�~�R�ƍ����ϒn���䂩��̌䒺�g�����̂̒n��Ƃ���F�������݂��Ă������Ƃ�����������B ����A��i��N(�ꎵ�Z��)�ɏ��ʂ��ꂽ�Ɠ`���u����n���R���L�v�ɂ́u�����J蓔V�_�����喾�_�g�V���A�{�n�����Z�n�n����F�j�e�}�V�}�X�v�ƋL����Ă���ق��A�\�����I�㔼�ɋL���ꂽ�ƍl�����Ă���u���n�����F�����N�v�ɂ��u��Ԃɕc�~��l�Ƃ��ւ鉥����āA�Ȃ�����m�̕��M�ƂȂ���Ǝn�Ēn�Ɍ܍��̎�q��d���ʂӁA�c�~�R�Ɉ������ʂӋ���F����A�������̐l���̐_�Ƃ����ށv�Ƃ���A�����ϒn���̉��N���ɂ��A�c�~�R�䂩��̐_�����o�ꂷ��B �@�@�@�}2�w �b��p�L�x�O�S�l�u�c�~�R�v�� �}�}(�R�����������ّ�) �Ƃ���ŁA����F�͓V�ׂ�_�Ƃ��Ēn����F�ƈ�ƂȂ��ĐM����Ă������Ƃ�A����F�������E����A�n����F��ّ��E����Ƃ��ē��̂Ƃ���������݂��邱�ƁA�܂����q���ȍ~�A��y�v�z�̒��ŋ���F���V���Ɋy�ւ̓��ҁA�n����F���n���n������̋~�ώ҂Ƃ����ϔO���L�܂������Ƃ��w�E����Ă���B ���̎w�E���ӂ܂���ƁA�����ϒn���ƕc�~�R�̖{�n������F�́A�{����E��̂̂��̂Ƃ��ĐM����Ă���A���ꂪ�����ł���c�~�R��Ƃ��̎R�[�A����Ɋ����쐅�n����ɂ킽���āA���_�M�ƌ����A�ΐ��`���Ƃ��Čp������Ă����ƍl������B �Ȃ��A�����ϒn�����J�������@���u�@�鎛�v�ł������A�c�~�R�̕ʓ����@�́u���v�ł���B���̎����̓ǂ݂͗ގ����Ă���A�����͍����ϒn������і{�n������F���J��{������̎��@�ł������\��������B ���̂悤�ɁA�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����ΐ��`���́A�{���c�~�R���炻�̎R�[�𗬂��{���E�䒺�g��E�����여��ɂ����ē`������Ă������ʂ̍b�㍑�̍����ݓ`�����N���Ƃ����ƍl������B���ꂪ�A�������쓌���H�̏��łɑ�\�����悤�ȉ͐�̗��H�ϑJ�ɂƂ��Ȃ��n��Љ�̍ĕҐ��ɂ���āA���̕c�~�R���ӂƐ쉺�̊����쐅�n����ɂ��ꂼ�ꕪ�����Č��`����Ă����̂��A�����ɓ`�������̌ΐ��`���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B�@ |
|
|
��������
�ȏ�A�{�e�ł́A�c�~�R���J��ꂽ�����ɂ��čl�@���A�c�~�R�̐M����ьΐ��`���Ƃ̊W�ɂ��Ę_�����B�܂��A�����ϒn���Ɋւ���ΐ��`���̓��e������ƂƂ��ɁA�c�~�R�̐M��`���Ƃ̊W�ɂ��čl�@�����B ���̌��ʁA�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����ΐ��`���́A�{���A�c�~�R�̖{�n���ł��鋕��F�ƍ����ϒn�������킹�ĐM�̑ΏۂƂ��A�c�~�R���炻�̎R�[�𗬂��{���E�䒺�g��E�����여��ɂ����čL�܂������ʂ̍����ݓ`�����N���Ƃ��Ēa�������ƍl�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B ���ꂪ�A�w�n����F�쌱�L�x�w�n����F�O���쌱�L�x�����������\�ܐ��I�ȍ~�A����F���J����̕c�~�R���ӂƍ����ϒn����M����쉺�̊����쐅�n����ɏ��X�ɕ������āA��̌ΐ��`���Ƃ��đ̌n�����p�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B �Ƃ���ŁA���B���́A�c�~�R�ƍ����ϒn���ɂ��ꂼ��W����ΐ��`���ɂ��āA�{���͕ʌn�̎����`���ł������������_�̓`�����A�����ϒn���̉��N�Ɏ�荞�܂�A����ɂ���ĕc�~��l�`���ƈ�ϒn���`���������������Ƃ��w�E���Ă��B�܂��A�R�{���́A��n�Ɍb�݂������炷���y�̕�_�M����Ղɂ��āA�b�{�~�n�̊J���ɂ�����ő�̓�G�ł������䒺�g��Ɗ�����̐�����߂�M�ƁA�c�~�R���܂P���O�R���ӂ̎R�x�M�̒��ŏ������ꂽ�R�̒n����F�M���d�Ȃ荇���A�u�����䓰�v�⍑���ϒn�����ւ̐M���`�����ꂽ���Ƃ��w�E���Ă���B ���̂悤�ɁA���B�E�R�{�����Ƃ��ɁA��̌ΐ��`���́A�{���ʌn���ł������M�����݂ɓ����E�e�������������̂Ƃ��Ĉʒu�t���Ă��邪�A�{�e�ōl�@�����悤�ɁA�ΐ��`���́A���̕c�~�R���ӂƐ쉺�̊����쐅�n����Ƃ�����̐����������n��ɂ����Đ�����������̓`�����N���Ƃ��A�\�ܐ��I�ȍ~�A���҂����ꂼ��Ɨ������`���Ƃ��Čp������Ă����ƍl������B �{�e�̌������ʂɂ��ẮA�c�~�R����э����ϒn���̐M���̕ϑJ��A�W�n����ɓ`���R���E���N�Ƃ̔�r�Ȃljۑ肪�c����Ă���B����́A�����̉ۑ�������E�����j�����Ɨ��߂Ȃ���l�@���Ă����K�v�����낤�B �@ |
|
| ����C�Ɩ����z�� | |
|
����C�@��������
�����������w�Ԃ��߂ɋ�C�͉���23�N(804)8���ɓ������Ă̂��A�����̐����b�ʘa���Ɏt�������B����24�N5��(805)�̂��Ƃł������B���������掵��c�̌b�ʘa���͋�C�̔�}�ȍ˔\��F�߂āA��������{�ɕ��y�����������C�ɑ����邱�Ƃɂ��āA��C�ɒ��������̂��ׂĂ�^�����B��C�͂悭����ɉ����āA�Z���Ԃ̕w�ŁA��ߑّ��̊w�@�Ƌ����E�̟ƂŁA����@���Ƃ̌������B����ɁA��苗��ʂ̟��āA�u�ՏƋ����v�̟������������B�u���̐��̈��Ղ��Ƃ炷�ŏ�̎ҁv�̈Ӗ��������ł���B �b�ʘa�������₵���̂ŁA��C�͑S��q���\���Ė@�v���ς܂��蕶��������B����25�N(806)3���A��������ɂ��ĉz�B�ցB4�����؍݂��ēy�؋Z�p�E��w�̑��������A�����g�������K�B���̋A���D�ɕ֏�A���N8���A���B���o�����ċA���̓r�ցB�r���\���J�ɑ����A�ܓ����]���ʉY(���܂̂���)���Ɋ�`�B�����āA�^�������̌o�T�E�����@����g���đ�ɕ{�ɑ哯���N(806)10�������B�����ɓ������������܂Œ����ԑ؍݂����B20�N���w�\��̊���w�m�����X�ƋA���������ƂɁA�w�ƕ����̋^����������ꂽ�̂ŁA�����̋����͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B���̂Ƃ������V�c�͕��䂵�Ă����B ���������k����m�V�c�̎��̘b������B���m�V�c�̌�p�҂ɂȂ邱�Ƃ�ژ_��ŁA�R���e��(�����V�c)�͓�������Ƃ̌�돂�������Ȃ����]�Z�푼��(������)�e���Ƃ��̕�����e���Ƃ��I���ɖd�E�����B�����V�c�̑����ːe���͓V�c�̗L�͌��҂ł���B�d���͕�T3�N(772)�̂��Ƃ������B��������V�c���҂��������R���e���͗���T4�N�ɍc���q�ɂȂ�A�V�����N(781)�Ɋ�]�̂Ƃ���V�c�ƂȂ����B�����m�V�c�͓����ɓ���푁�ǐe�����s���厛����ґ������čc���q�Ƃ����B �����V�c�͓����S��E�����njp(����)�Ƒg��ŁA�唺�ꑰ���������āA�c���Ƃ��Ă̒n�ʂ�z�������Ă������B�V�c�ɂȂ��Ă���A��a����̕��Ђ�U���A������i�߂āA����̎x�z�n�𑝂₵�Ă������B��s�ł��J�育�Ƃ̝y�I��������āA�ꐧ�N��𑱂���V�c�͓ޗǂ̖k���R��ւ̑J�s�������Ɍv�悵���B�����钷�����J�s�ł���B �J�s�͉���3�N(784)�����ɂ����Ȃ�ꂽ�B���N�A�������g�b������p�����c�w�������钆�ŏP���E���ꂽ�̂ŁA�{���������V�c�͑J�s���Δh�唺�ꑰ�瑽�����E�C�A������i����푁��(�����)�c���q��l�߂ŎE�����B���Ǎc���q�����P���ɕ����߂āA��H�ōR�c����c���q����x�����ׂ邱�Ƃ������ɁA�W�H�ɗ����ƋU���āA�����͓��ŋ��E���Ă��܂����B��s�̓��厛����ґ��܂ł���������E�������V�c�̎c�s�s�ׂ͂ǂ��ߖ����Ă��A�߂͖Ƃ�Ȃ����̂ł������B�V�����c���q�͊����V�c�̑��c�q���a(����)�e���ɂȂ����B��̕���(�ւ�����)�V�c�ł���B ���ꂩ��V�c�ƍc���q�̎���ŋN����ЊQ�ƃs���|�C���g�I�ȓ��e�ˑR���̘A���Ɋ����V�c�͂��т������ĕ�炵�Ă����B����25�N(806)�������Őꐧ�������V�c�͎����B�@ |
|
|
������V�c����
�����V�c�̒��j����(�ւ�����)�c�q�͓V�c�ɑ��ʁA�����Ē퍵��c�q�͍c���q�ɁB���̕���V�c���������V�c��^���āA���ʂ̗��N�Ɉٕ��ɗ\�e�����E���Ă����B����V�c���A�����������āA���ʂ���3�N�őވʂ�����Ȃ������B���������Ƃ̓V�c�h���������Đ��i�I�ɐƎ�ȓV�c�͐��_�a��a��ŁA����ވʂ����̂ł���B����V�c�͈ٕ��ɗ\�e�����M�������Ă����Ƃ�����B �哯4�N(809)4���A����V�c�͔��a�őވʂ���c�ɂȂ����B�����ɍ���V�c���ʁB�V���������c�̎O�j���x(��������)�e�����c���q�ɂȂ����B���̂�����܂ł͐����̈ړ��͏����ɐ��ڂ������ɂ݂����B �����A���N�����������c�͑哯4�N12���A�ˑR���鋞�Ɉړ����āA���N9���ɏق��A�u�s�鋞�ɖ߂��v�Ɛ錾�����B����V�c�͂���Ɉ�U�͏]�����ӂ����A���c�����C�A�����~�k�A�I�c���{���{�g�Ƃ��āA�ޗǂɂ����肱�ށB����V�c�͐��Α叫�R���c�����C�A�����Ȗ��C��߉q�{���l���������Ă����̂ŁA��c�̐錾�œ��h�����M���A��l��}���邱�Ƃ��ł����B�哯5�N10���A����V�c�͍���b��������(���ƁA��q�̌Z)�𑨂��č~�i�A�����c�̓���������q(������)�A���͏�c�̈��l�������Ƃ��čĂь������ӂ���Ă����̂ŁA����V�c�͖�q�����ɒǕ��Ƃ����B ����ǂ��A�����͂���Ŏ��܂�Ȃ������B�����c�͓�����q���A�ޗǂ�E�o���āA�����ŕ���������s���ɏo���B����V�c�͐v���ɓ����A��c�̒E�o�������̂ŁA��c�͂�ނȂ������Ԃ��A�o�ƉB�����邱�Ƃɂ����B���l��q�͖�����Ŏ��E�����B������ꂽ���������͎ˎE���ꂽ�B����ŁA�V���͏��������捂ɂȂ����B��������������q�̑f���͂Ȃɂ��B������p�̏�(�ނ���)�A���[���������v�l�Ƃ��ĎO�j���Y��ł���B���������a�e���̋{���Ƃ��ē��{�ɍ����o���Ă���A���a(����)�c���q�Ƃ悢���ɂȂ��Ă����B���������C�ƒʂ��Ă������̂ŁA���܂�̏X�ԂɁA�����V�c���瓌�{��Ǖ�����Ă��������ȏ��ł���B���a(����)�c���q���V�c�ɂȂ������A�ӂ����ы{��ɖ߂�A�v����������B��ɕ{���Ƃ��āA���s���牓������Ƃ����X�s�����Ă���B �e���X������ʊ����V�c�̕s�l�C�Ԃ�͂Ђǂ����̂ŁA���㑒�銺���˂��V�c�̈ӎv�ʂ�ƂȂ炸�A����s������i�ƍ��܂��Ă����B�呛���̖��ɑ���ꂽ���s�����̌�˂͏G�g�̕����z��ʼn�āA���݂Ɏ���܂ŏꏊ������ł��Ă��Ȃ��B�\�s�I�V�c�̖��H�͈���ł���B����ʂĂ��������{�͕����J�s��N���L�O���Č������������_�{�ɓV�c���J�����B�����_�{�Ɋ����V�c�����܂��ƔF�߂�l�͏��Ȃ��B �����Ŗ\�͓I����v�����������V�q�V�c�̖��Ⴝ���͑����Đ��i����낵���Ȃ������B�V�q�V�c�̂����������s�䓙�̈ꑰ��������������A�V�c�Ƃ̌p���ɍ����������炵�Ă����B�Ƃ��낪�A�����c�̒퍵��V�c�͓V�q�V�c�n�̐l���ł���A�ʊ��ȂƂ�������邪�A���ƌZ�Ƃʋ��t�Ƃ��āA�s�҂�ڑł��Ƃ͂��Ȃ������B�c���̓����͎���ɍs���͂������̂ɂȂ��Ă����B�Ր��ɂق���т������Ȃ��Ƃ��낪�A����V�c�̗͗ʂł������B�@ |
|
|
������V�c�Ƌ�C
����V�c�������ɖz�����Ă��鎞�A��C�͘a�ݘa�c�������R�́u�{�����v�ɑ؍݂��Ă����B�R�̒��̂��̎��͎Ⴂ��C���������̑�w��ލZ���R�x�C�s�ɓ������C����ł������B��C�͖��������U���Ă����������̕��ɂ������炸�ɁA���̎R���Œ䔯���ĕ����E���������Ă����B������w�҂ɂȂ邱�Ƃ����߂āA�����̐��E�ɓ��낤�Ƌ�C�͎�҂炵�����x�m�Ƃ��ďC�s�ɓ����Ă����B����12�N(793)�A20�̋�C���Α�(����)�t�Ƃ��Ē䔯�����䓰���������Ă���B �������w���I���āA�A��������C�͑�ɕ{�ɂ��炭�ؗ��A�����đ哯4�N(809)�ɘa�����R�u�{�����v�̋Α��̂��Ƃɐg���Ă����B�Ⴂ��C�͓����ɑ؍݂��Ă���Ԃ��A�������y�����ɗ]�O���Ȃ������B �����R���������15�L���قǖk���ɉ͓�����s�ƎO������������B�O���������炳��ɓ��֒�����10�L���قǂ̂Ƃ���Ɋ���R(553�b)������B���̎R�[�ɐ瑁�ԍ⑺���������B����R�̓�ɂ͕��`���ɋ����R(1125�b)���ނ��Ă���B����R���ł����Ƃ��������R���C���[�W���Ă�����Ă������B�瑁�ԍ⑺�Ɏ���ɂ́A�O���������瓌��5�L���قǕ����̂ł��낤���B�����ɞw���R(�Ђ̂�������)�ϐS��������B�ϐS���͌Â��́u�_�S���v�Ƃ��A8���I�̏��߂���A�R�x�C�����̑c�u�����p�v(����̂��Â�)�������R�𒆐S�Ɏ��͂̎R�ɏC��������J���Ă����B�_�S�������̂ЂƂƂ���Ă���B�_�S���͓�ʂɐ_���u(�R��)�ƌĂ�鍂������������A�ϐS���͏C����ɂӂ��킵���k�J�̂Ȃ��ɂ���B�����͍���Ɏw�肳��Ă���B �哯4�N(809)�A��C�͂��̉_�S���ɓ���A�����̔鎖����(�ق���)���s�����B�����Ƃ͖k�l�������Ղ�s���ł���B�V���ł́A7�{�̛�𗧂āA���̑O�ɞ�(�Ȃ�)�ƒ��������A�肤�ЂƂ̑��ЁA���v�A�������F��V���ł���B�l�Ԃ͒a���̏u�ԂɁA�{�����Ɩk�l����(����)�����߂��A���̓�̐������U�̉^�������E����Ƃ���ꂽ�B��C�͋�����7�̐��˂��߁A���T��g�B���A��e�����c���Ă���B�ϐS���̊J�c�́A��C�̒�q������t���b(����)�ƂȂ��Ă���B���̎��@�͋�C��������ꂽ�����Ȃ̂ł���B ��C�͑哯4�N(809)7���ɑ���������҂��ē����A�a�C���̎������s���Y�R��(��̐_�쎛)�ɓ������B�����ɂ��ẮA�ォ��A�������Ő��̐s�͂Ǝx�����������B��C�ɂ͎x���ҍ���V�c�������B�����V�c�̑��c�q����V�c���Z�����c���u��q(������)�̕ρv�ŒǕ����āA�V�c�̒n�ʂ�Ȃ��̂ɂ��Ă����B�J���X�}�����鍵��V�c�̋����w���͂Ɛ����͂ŁA�c���̐������s���Ă����B�����c�̏o�ƂƏ�c�̎q���x(��������)�c���q�̔p���A�ٕ��唺�c�q(��̏~�a�V�c)���c���q�ɗ��ĂāA���������̈��肪�i�߂��Ă����B�O�m9�N(818)�̍O�m�i�̔��\�ŁA����̎��Y���x�p�~�����߂�ꂽ�B����V�c�̉p�f�ł������B �������āA�V�����^�������y�����悤�ƁA����V�c�͋�C�Ƒ��g���čՐ��̋������Ƃ��H�v���Ă����B����V�c�͂܂��A��C�����P(���Ƃ���)���̕ʓ��ɔC�����B�O�m2�N(811)�̂��Ƃł���B���P���͐������q���������������ōł��Â����ł��邪�A�����^���������@�Ƃ��邱�ƂɂȂ����̂ł���B����V�c�͉��P���ɍs�K���ċ�C�ƌ��t�����킵�Ă���B��l�͂��݂��ɔF�ߍ����\���Ƃł������B�Ő������̎���K�˂Ė����ɂ��ď@�_���������킹�Ă����B��C�͍O�m3�N(812)11���ɂ́A���̉��P�����獂�Y�R���ɖ߂��Ă���B��C�͍��Y�R����^���������@�A����Ƃ����B�Ő��͂����ş��������Ă���B �܂��A�u��q�̕ρv(809)�̌�A�ޗǂ̓��厛�ȂǓ�s���@�Ƃ̊W�C���╽�鋞����Î��@�̞��������ꂪ�ۑ�ƂȂ��Ă����B����V�c�͓��厛�Ɂu�^�����v���������A��C�����Z�ɂ��āA�o�Ƃ��Ă����������c�ɟ��{���Đg�������肳���Ă����B����ɍ��x�e������C�̒�q�Ƃ����A���e���̐����铹�����߂����Ă����B ����V�c�ɂ͂Ȃ��Ȃ��e�����a�����Ȃ������B�v�l�k�Òq�q(�����Ȃ̂�����)�����q�a��������āA�哯4�N(809)�A�R�鍑���y�S(������̂�����)�̖�T�̑P�����Ɂu�@�v�������B�A�����ē�����������̋�C�ɓ���������B��C�͖@�،o��䶗��ɂ��镁����F��{���Ƃ��邱�Ƃɂ��āA�o�̎q�q��(������)�ƂƂ��ɑ����Ɏ��|����B���t�͒ֈ�(��)�o�@��B�q�����`�����Ă����Ƃ���A�]��ɂ����q��̕ꂪ�ˑR����āA�����������`�����B���̎肾��ɕ��t���������Ƃ����B�ʊ�͒q���ꂽ�B�q��̎��̍b�゠���āA���O�m���N(810)�ɍc�q���a�������B���̍c�q�͌�̐m��(�ɂ�݂傤)�V�c�ł���B��C�ɑ��鍵��V�c�̐M���������A�q��̕]�������܂����Ƃ�����B�Ȃ��A���͌�N�A�߂��́u��D���v�ƕ�����ꂽ�̂ŁA�@����������Ɏc���Ă���B�@ |
|
|
���\�s�Ȋ����V�c
�������艓���ɂȂ邪�A����V�c�̕������V�c�̐e���ɂ��ĐG��Ă������ق����s�̐�����𗝉�����̂ɕ֗����Ǝv���̂ŁA�Ƃ肠�����A�����V�c�̋ƐтƑ��Ղ�ǂ��Ă݂邱�Ƃɂ���B ���鋞���璷�����ցA����ɒ��������畽�����֑J�s�����̂͊����V�c���B10�N�����o���Ă��Ȃ���������u���ĕ������֑J�s����Ƃ����ꐧ�����������ʂ����\�s�I�V�c�B���͌��m�V�c(�V�q�V�c���c�q)�A��͍���V�}(�����̂̂ɂ�����)�B����͋A���S�ϐl�ł���B�`���𖼏��ꑰ�ŁA�S�ύ������̌n��Ƃ�����B�`���͎R�鍑�������Ȃnjj��Ȑ��̈��K�n�����L���A�_�Ƃ̊J����i�߂Ă����B�����̈�א_�Ђɂ͐`���̎����_���J���Ă���B���̐_�l�ł���B�����V�c���j��Ȑ��̒n��V�s�Ƃ��đI�̂́A�������R�Ȃ��Ƃł������B ���鋞�͑�삩�牓���āA���^���肩�A���s���ŔY�s�s�ł������B�l���\���l�قǂ���������X���������ɍ���A��������r�����̎̂ď�ɍ�������q���I�ȏ�Ԃł������B�X�S�̂���q���I�Ȋ���80�N����������A�����Ă��̏Z���͊X���o�������Ǝv���͓̂��R�̂��Ƃł���B �n�������Ƒg��ʼn����Ɩ����N�����������E���鋞�̓V���V�c�n�̍c���B�c�Ђɓ��荞��������M�������͒��슯���Ƒg��ŁA���ߐ��x�̐����̂����Ɏ��̉��E��������i�߂��B���@�����ƈ��J���肤����ƌ���Ŋ������������n���A�����V�c������ɍ������ƍ������������Ēn���̖��̕��S���d�����̂ɂ��Ă����B �悤�₭�A�����V�c�n�̌��͂̉e�����ꂽ�̂ŁA����������(������)�̎����œV�q�V�c�n�̌��m�V�c���o�����Ă����B���m�V�c�͐g�̈��S���l���A��Z��̐����𑗂�}�f�ȍc���������Ă������V�I���݁B�n�R�Ȃ����ɁA������M���̖������l������鏗�ɂ��炵�̂Ȃ��j���m�V�c�B �����V�c�͈ɐ��_�{�̍{�P�߂Ă����x�ꂽ�Q���(���̂�)���e�������̌��m�e���ɉ����t���Ă����B�����e���͎�l���e���Ƒ���(������)�c�q���Y�B���m�����ݐe���̖�(���e��)�ɂ���ꂽ���O�͔���ɕ�������B�����āA�V���V�c�n��������ːe���͗L�͂ȉ��ʌp�����i����c�q�ł������B��������Ƃ̌�돂�����邤���́A���ˍc�q�͏��]���ꂽ�c�q�ł������B��T2�N(771)1���A����(������)�c�q�͍c���q�ɂȂ����B �����V�c�̖������e���ɂ��Ă͐������̓`��������炵���B�v���m�V�c�Ƃ̕s�����A����o�Y�̋^�₪������e���ƍc�q�̒a���A���s�j���e���̕v�X�㉖�ĉ�(�V���V�c�c��)�́u���������C�̗��v�A���A����ϐe���̉����A���m�V�c���f���w���A�V�c�o��g���e�����f���w���A�V�c�̐���̎����̎��A��p�������Ă����\�𗬂��ꂽ�B�{�P�����������V�c�������鋰��Ǝ��݂��A�����e���̐g�ӂɉQ�����Ă����B �����e���͕�T3�N(772)�A���m�V�c���������t�e�^�ōc�@��p���ꂽ�B���N5���A���ˍc�q�͍c���q�̒n�ʂ��O���ꂽ�B�����ĕ�T4�N(773)11���A�����e�����A���m�V�c�o��g���e�����E�����Ƃ��āA���ːe���ƂƂ��ɏ��l�Ƃ���A��a���F��S(���s)�ɗH���ꂽ�B���͋I�m��㗬�A��x�R��������ɓ��s������翂ȂƂ���ł���B�ߐl�Ƃ��āA�g��ɑ��荞�܂ꂽ�������ł���B�c�q�����u���ˁv�Ƃ͕s�v�c�Ȗ��Ǝ��͍l�����̂����A����Ŕ[�����������B���ӂ̂��铖�Ď��ł���B�u�����ׁv�̎��͕ʂȕ������[�Ă��Ă����͂��ł���B��T6�N4���A�e���͗H��ŕ�ƂƂ��ɋ}������B�������Ƃ���d�E�̎肪��������̂Ƃ݂���B�V���V�c�n�̍c���͂������āA���X�Ə�����Ă������B �����V�����ʂ������͍��Ƃ̍�����@���\�ʉ����Ă����B�܂�A�l�\�ܑ㐹��(���傤��)�V�c�����Ǝ��Ƃ̒��S�ɕ����𐘂��āA�Ր���v���z��ڎw���������p���̉e���傫�������V�c�̐������䂪�߂Ă����B���Ƃ��A40�N�ɋy�ԓޗǓ��厛�̑啧�����Ƒ啧�a�̌����̒��ŁA����Ɏ��@�̋��剻�������݁A���̂Ƒ����̑���Ƃ��A���ߐ��x�̕���ɂȂ��肩�˂Ȃ���@�I�ȏ������炵�Ă����B�̖��̕��S���傫���Ȃ�A�M���Ǝ��@���x�鍑�ƂȂ��Ă����B�����V�c�͉،��@�����߂Ƃ����s�Z�@�̎��@��}��������j���������B�����厛�i�̑g�D���p�����B �Ƃ���ŁA���������Ƃ̕Q��v�l�Ƃ����R��(��܂�)�c�q�͐`�����Ɏ��S�ϐl�炵�����ł������B�����͖ҁX�����퓬�I�ł������B�O�肩�Ȃ��ēV�c�ɐ�������Ċ����V�c�ƂȂ��Ă���́A�R�鍑��㑺�̋A���l�c�����C���d�p�����B��a����̕��Ђ��ւ�A���k�n���̓��ΐ����ɓc�����C�����x���h�����āA���𐬌������Ă����B���c�����C�ɍ~�����A���鋞�ɘA��Ă���ꂽ�A�C�k�̎w���҃A�e���C�ƃ��C�v�ɂ��E���Ă��܂��m���̂Ȃ��V�c�ł������B �����͐`�����J�����Ă����R�鍑�����ɖڂ����A�ꐧ�I�������s�����߂ɁA�J�s���l�����炵���B����4�N(785)�A�������J�s�ɐs�͂��Ă���������p���������̊J�����ɖ���˂������E���ꂽ�B���̂Ƃ��A�����͓���푁�ǐe�c�Ɍ��^�������A�W�H�֗��z���ɈÎE���ꂽ�B���ꂪ�����V�c�Ɉꐶ�t���܂Ƃ����_�ƂȂ����B�@ |
|
|
���������u�����v
�����V�c�͕������J�s�ɂ������āA�����{�A���씪���ȁA�_�A�����A�����ЂȂǑ����̎{�݂c�����B���̂ЂƂA�܂�A�u�����v�͊����V�c���������������B�����J�s�̗��X�N����15�N(796)�A�����ɐ��l�����c�����B���s�����̓����Ɍ��Ă�ꂽ�̂ŁA���ʂ�u�����v�ƌĂꂽ�B �����͓����E������̒����������c����āA�����Ɛ����̒�����i�銯���ł������B����ƋM���ɐl�C���������������厖�ɂ���āA�u�����v�͎���ɂ��т�Ĕp����Ă��܂����Ƃ����B���̂��������́A�ق�̍��ׂȂ��Ƃł������B�V�����N(824)�̂��ƁA�J��̋F���������ŗ��_���Z�ނƂ����u�_�v�ōs��ꂽ�B�����̋�C�Ɛ����̎�q���F�J�̖@���������B��C�̋F�����V�ɓ͂��A�O���O�ӂ̑�J���~�����B�V���̐M������C�͓V�����N�A�����ɐ��ω���{���Ƃ���^�����@�̌����Ɍg������B���R�A����ɂ����铌���̐������������B �l�C�𓌎��ɒD��ꂽ�����́A��C��҂������A����˂����āA���̍��߂̑w�ɏ��킹���Ƃ����B�J��̋��������ɔs�ꂽ��q(�����)��������̂Ƃ���ŏP�����Ƃ���邪�A���m���|��������ċ�C���P�����Ƃ��v�����A�����̎��l�̎d�Ƃł������낤�B������̑O�̃o�X��Ɂu����n���v������B �u�����v�ōł��Â������͓���̖k�����ʁu�����v�ł���B����15�N�ɑn�����ꂽ�B��t�O�������{���Ƃ����J���Ă���B����18�N(1486)�y�Ꝅ�Őɂ����������������A�c��8�N(1603)�L�b�G���̊�i�ōČ����ꂽ�B�{��d�̖�t�@���{���͈��y���R����̕��t�N��(�������傤)�̍�i�Ƃ�����B ��C���ł��͂����č�����̂��u�u���v�ŁA����21�̂̂����A15�̂͑n�������̂��̂Ƃ�����B���������{�ؑ���A��ϒ����̌���B�����ɗ��̙�䶗����\���B����@���𒆐S�Ɍܒq�@���A������Ɍܕ�F�A�o���Ɍܖ����A���l���ɑ���@�����������l�V���B�l�V���̃��[�_�[�Ƃ��āA��ߓV(���V)�����ۂɏ��A�E��ɓ�鉆���������z�X�����p���ڂɂ��B����3�N(1491)�ɍČ��A�c��3�N(1598)�n�k�ő�j�����̂ŁA�ӂ����яC������A�������@�̉��䂩���������݂܂ʼn��o����Ă���B �u�d���v�͖�t�@����{���Ƃ���邪�A���͖{�����ɂȂ��A���̐c�����t�@�����Ƃ݂��ĂāA���̕������e�K�ɔz�u���Ă���B�܂��A�lj悪�����ǖʂɕ`����A�����������ّ����v�킹��ŊE�̕��͋C�������o���Ă���B�������猚���Ɏ��|�������ɂ�������炸�A�������͓�H���ł��������߁A��C�������ɗ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�܂��A�d���͗����ɂ��Љ�������x���d�ˁA���݂̓��͓���ƌ��̊�i�Ŋ����������̂ł���B���̈ێ��Ǘ����l���āA�����ł͎Q�w�҂ւ̌��J�͓���̊��ԂɌ����Ă���B�����̍������͐̂���s�l�̌ւ�Ƃ�����̂ł������B �Ƃ���ŁA��C��������a�������͍̂O�m14�N(823)�A����V�c���u��������C�ɋ��a����v�Ƃ���������ł���B��C��50�������B����V�c�͋�C�ƍŐ��Ƃ̏@�_�Η����������Ȃ����̂ŁA�Ő��̓V��@�̊m����F�߁A��C�ɂ͐^���@�̍��{����c���銯����^���邱�Ƃɂ����̂ł���B ��t�͂��łɍ���R�ɖ����C����c���ł��������A���c�u�����v��a���邱�ƂɂȂ��Ƃ�����B���݂̓����͏@���@�l�u�����썑���v�Ə̂��Ă���B���@�̍j�̂Ƃ��āu�����������������鎛�@�Ƃ���v�Ƃ������Ƃł���B����V�c�͂��̍l���Ɏ^�ӂ��������Ƃ������Ƃł��낤�B�V�c�͋�C�ɁA����ɖ����̋����ɋ��ނ悤�ɋ��߂��B��C�͓��������ɍu���ƌd���̌����Ɏ��|�������B�u�u���v�͗��̙�䶗��̐��E��A���l��������B�@ |
|
|
������R�C�T����̊J��
���ɐG���悤�ɕՏƋ�����t�͍���R����̌��݂ɂ�����A�܂��A�a�̎R�ɓs�S��x�R�Ɂu�����@�v�����������B���@�́u�I�m��v�㗬�̕��͂�����ɑk��A�u���炬�܂��v���߂��A�u��������v�̑D����őD���~��āA�����I�ɖ�O����o�����Ƃ���ɂ���B���H�ł́A�͓�����s�����s15�`�A����371���ŋ��{�s����ʂ�A�����I�m��ɉ����ĉ���A��O���ɒH�蒅���B ���{�s�����̂܂ܒʂ蔲����371�����ɑ���ƍ���R�Ɏ���B�o�R�̓��͎����@�����x�R�𐔎��Ԃ����ēo��A�悤�₭����R���̂Ƃ���ɒH�蒅���B����R�͕��m�̏C�s��ɂӂ��킵�����R�ł���B��b��������͐[�R�炵���z�~�̂Ƃ��͏C�s�m�Ɍ������Ƃ���ł���B ��������^��ł������I�m�삩�獂��R�ɉ^�яグ��B�u�̓��v�Ƃ����̂�����B�Ȃǂ̑D�ׂ͍�����̑D����ō~�낳�ꂽ�B���Ƃ��A����R���̉��̉@�́u����G�N�v�̗̕�͂͂��z�O����D�ʼn^��A�̓���ʂ肨���߂�ꂽ�B �����@�͌��݁A���E���Y�̎w����Ă��邪�A���̔F��̍����𗝉����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ������t�͍O�m7�N(816)�ɒ��삩�狖���ꂽ����R�^���@�C�T����̊J���Ɏ��|�����Ă����B��t�͏C�s����c����ɂ��āA�܂��A��������̉J�g�R�̎R�[�ɎQ�w�҂̏h���A�S�R�̐���(�Ж���)�Ƃ��āA�����@�������炦���B�J��͎��b(������)�ƂȂ��Ă���B�{���͖��ӕ�F�B���̓`���ɂ��A�����͍O�m7�N�Ƃ���Ă���B����R����Ƃ��āA�ŏ��̓��ꂾ���A���~���̔�������̖�ڂ��ʂ����Ă����B����������R�Q�w�̓o����ɂȂ����Ă���B�̂̂��ƁA�����͏��l���̍���R�ɓ��R�ł��Ȃ������̂ŁA���̎��@�ɂƂǂ܂��ĎQ�w�����B������A�����́u���l����v�ƌĂ�Ă���B ��t�͍O�m8�N����̍���R�J���͒�q�N�́E���b�Ɉς˂Ă����B��9�N�ɍ���R�ɓo��A���N�܂ő؍݂��Ă����B�����l���Ɍ��E�����сA�����������O�m10�N(819)�Ɏ��|�������B����ɂȂ�����t�̕ꈢ�n��(�ʈ�)�͍���R�ɐg�������A���������@�ɏZ�܂���u�����B ��t�͍���R���ꂩ�琔���Ԃ����āA��ɉ�ɒʂ����B���ɋ�x���R�ɒʂ����Ƃ����̂ʼnJ�g�R�́u��x�R�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B�\���Ɂu��e���v������B �������͏��a2�N(835)2���Ɏ����@�ŖS���Ȃ����B��n�͖��ӕ�F�̉��ɂ���B��t����͏��l����R�M�k�̏ے��I���݂ƂȂ�A�����@�͎���ɐ��n�̂悤�ɂȂ����B��������̏����M�҂��Q�w�ɗ��Ă���B �u�����@�v�̖ؑ����ӕ�F�͍���ƂȂ��Ă���B����4�N(892)����̕������̖ؑ������͔镧�Ƃ��Ė�������ɂȂ�܂Œ����Ԍ��J����Ă��Ȃ������B���݂�21�N���Ƃ̊J���Ƃ���Ă���B����ǂ̌�J���͉��N�ゾ�낤���B�@ |
|
|
�������̕��y�Ɍ�����
�ՏƋ�����t�̖����z���͋x�݂Ȃ�������ꂽ�B �ޗǓ��厛�ɑ��������ɂ�����u�^���@�v������(�O�m13�N)�A�����āA��t�͓��厛�\�O��ʓ��ƂȂ����B�،��@���{�R�Ƃ��āA�암�����̒��S�I���݂������啧�Ƒ�u���������厛���@�͐V�������������^���@��������j�I�]�������}�����B���厛�͂��̌�A��s�Z�@�ɐ^���@�ƓV��@�����������@���w�����������ȍ��Ǝ��@�ƂȂ����B���厛�^���@�����̑����������o�����͍̂���b�����~�p�����A����V�c�̒��ɂ����̂ł������B����V�c�̒����捂̊肢���āA���̓��厛�^���@�ŋ�C�ʓ����m�ЂƂȂ����������c�̟����������Ƃ͐�ɏq�ׂ��B ����R�J���Ɏ����߂���A��C�͒����ɏ]���āA��H���ɒ��ʂ��Ă������썑�Օ��̖��Z�r�̑���C���w��(�O�m12�N)�A������������Đ����ɔY�ލ���̐l�������~�����B�y�؋Z�p�̒����ł̕������ɗ������B������t�̏@���E�ɂ�����w���҂Ƃ��Ă̕]���͂��悢�捂�܂�A�O�m14�N(823)���������ɂ��u�����v���������ꂽ�B��C�̐^���������y�̓w�͂Ƃ��̐��ʂ��F�߂�ꂽ�̂������B �u�����v��a����ꂽ��C�͓����̂Ƃǂ܂�A���������̕��y�Ƌ����ɐS���ӂ����B�������@�́u��e���v����C�̏Z�����B���݁A��t�̔O�����s�������Ƒ�t�̍�������e���ɒu����Ă���B�ɂ������ƂɁA�k���N���N��N(1379)12���Ɍ�e���Ď��A���N11���ɍČ����ꂽ�B���̎����k���V�c�͌�~�Z�A���R�͑����`���ł������B�����̖����́u�����v�Ƃ�ꂽ�B ��t�̖����z�������͑������B���Ƃ��A�V��5�N(828)�ɁA��ʏ����̂��߂̊w�Z�u���Y��q�@�v�𓌎��̋߂��Ɍ����B�w��E�w�Ƃ����߂邱�Ƃɂ����B�����āu���Y��q�@���v���c�����B�܂��A�V��7�N(830)�~�a�V�c�̒��ɉ����āu�閧��䶗��\�Z�S�_�v�\�����āA�����̏@�_�����ɂ����B����ɂ����v��u�鑠��_�v�O���Ƃ��Č��Ɍ��サ�Ă���B ����A����R�̊J���ɂ͖c��Ȏ����ƘJ�͂𒍂����܂ꂽ���A�V��9�N(832)�A�悤�₭����R�d�㉾���́u�����v�������B���N(832)8���A������(�܂�Ƃ���)�̗��������s�����Ƃ��ł����B��t�͂��̔N�̏H���獂��R�ɋ����\���A�S���̐^�����@�m���̏C���̎w���ɓ������B ��C�͌��̈Ӗ������߂āA����֏��a���N(834)�Ɂu�{���^���@�A������C�@�v�\���o�̑t����o�A���N���a2�N�Ɂu�䎵����C�@�v���s�����Ƃ��ł����B����ɁA���a2�N(835)2���A���厛�^���@�ŁA�u�@�،o�v�u�ʎ�S�o�錮�v���u�����B ����V�c�Ƌ�C�Ƃ̊Ԃɂ͌����M���W�������Ă����B��C�̕a�C���R�̉B���肢�͍���V�c�̈ԗ��ŕ���������Ȃ������B�����A��t�͓���̏����ɓ���A�����̐l�̎����ƍ��Ƃ̈��J���肤�p���q�����Ɍ����Ă����B���a2�N(835)3��15���A��t�͍���R�̒�q�Ɉ⌾�A3��21���ɓ��₵���B���N�͖�60�������B�ꈢ�����̌��ǂ��悤�Ȍ`�ƂȂ����B 21������t�ՏƋ����̌������ł���B���݂ł������ł͖����A��t�l�������̋��{(��e��)�������Ȃ��A�����ōO�@�s(�����s)���J�����B���̓��͑吨�̐M�҂��W�܂�B�@ |
|
|
����C�̎Ⴂ����̑���
�����̕��k�ɕ��ꂽ��t�ɂ��ď�������q�ׂ�B ��C�̗c���́u�����^���v(�������̂܂���)�B��T5�N(774)�A���썑���x�S(���ǂ̂�����)�����Y�ɐ��܂��B���������̑听�ҕs��O���̓��ł̓��ɐ��܂ꂽ�Ɖ������l������B���͍������c��(�������̂����� ������)�P���B�u�S�i�v�Ƃ����n�����ł���B�S����(�܂�ǂ���)�\���ɑP�ʎ����ł����������ł��낤���B�������ɂ��Ē��ׂĂ݂��B �������ɂ��āA�����`��������B �������͌Ñォ�瑱�������ł���B�V�c�Ƃ��F�삩���a�ɐN�������Ƃ��ɍ~�����唺���̖���ł���B��A�唺�����������p�����_�������B�������𗦂��A����̕��l�Ƃ��ēV�c�Ɏd�����B�����ċ{���̌x�ł��i�����������ꑰ�B�x������{������́u������v�Ƃ��Ă����B�������̓������ɏ]���āA�����������A�u���ǖ�v�ɑւ���ꂽ�Ƃ����B �������̉q�m�ɂ͓��k����A��Ă���ꂽ�����g�ݓ�����Ă����B��C���c���̍��A�Q�c�ɂ܂ŏ��i�����������ѐl(���܂��݂�)�͏��ߍb��{�i�A���ɑ����厛�����A�E�q�m�A�����厛�����A�����厛�����A���ɂ̑��A���������g���o�āA�������ɂ܂ʼnh�B�����l�����A���̉q�m�����炵�����O���Ǝv���B �n���̍�������1�A�d���E�]��ɂ����i�s�V�c�n�Ɠ`�����鍲�����B�{���͒�(������)�B2�A�͓��E���g�E���|�E�z���E�O�g�ɎU����Ă����������B1�A2�͊e�n�̍�����������n���I����(�Ƃ��݂̂��)�Ƃ���ɒ����̏㋉�����������ɏ]�����Ă����B��C�͎]�x�̍������c���`���̎q���B�c��������f���炵�����]�̎�����ŁA�ӎu�̋����q�ł������炵���B ��C�̕�́u�����ʈˁv�B�����呫(���Ƃ̂�������)�̖��ł���B�����呫�͖@���@�̗�������ފw�҂ŁA�����V�c�̍c�q�ɗ\�e���̎��u�߂Ă����B�������͓n���l�̎q���B�ꑰ�ɂ͊w�ҁA�m�����y�o���Ă���B�͓����a��S�Օ��ɖ{���n�������Ă����B���܂̔����E����゠����ɂȂ�B�������̌n��ł���B�c�_�E�`�c��(���܂��ɂ����݂̂���)���J�鎁�_�Ђ��J�s�̂Ƃ��ɁA���s�E���捵��L���쒬�ɑJ�������Ă���B ����8�N(789)�A15�̎Ⴂ��C�͕��鋞���������ɑ呫��K�ˁA�_����w�A�F�o����������B����11�N(792)18�̂Ƃ���w���ɓ���Ă�������B��w���������閾�o(�݂傤)�Ȃ�I�l����w�k�ƂȂ������A�����R�x�C�s�ɓ��邽�߂ɉ���12�N(793)�ɑފw�����B ����ɕ��S�������Ɍ����Ă��A����̔��������呫�ɑ��Ă��A��C�͓����E�E�����̔�r��_���āA�Ȃ������������ɐg�𓊂��������u�W�ڎw�A�v(�낤��������)�������ĕٖ����Ă���B ��C�͏C����̘a��ꠔ��R�u�{�����v�Œ䔯�A�P�g�ŎR�яC�Ƃɓ������B���t�͋Α�(����)�A��C�̐��U�̎t�ɂ�����l�ł���B�Α��͌�ɓޗǁu������v��a���邱�ƂɂȂ�B��C�̎o�̎q�q��(������)����C�͑�����̋Α��ɗa���Ă���B�Ⴂ���납��A�����ƍ����Ȑl�ł������B���x�m�͘a�̎R�x��g��̕�X��o��A�g�����R(����Ԃ���)�Ȃǂɕ����������B����Ɏl�������K�A�]�ƎR�ȂǂŌ������C�s�𑱂����B �Ⴂ�m�͎R�x�C�s�𑱂���ƂƂ��ɁA�ޗǂ̑����(��厛)�Ɠ��厛�A�̋v�Ď��Ȃǂ̏�����K��A�u����o�v���͂��ߖ������o�T���w�ԁB���̎��A�o�T������邽�߂ɖK�₵��������ŁA����u�����v�Ɂu�����厝�@�v�����������B�����ŁA�o�T�̌����ɏڂ�����s�@���@�̎w���ҁu�P��v���������ɖK�˂āA��������Ă���B �P��́u�@�t�������s�h�́v�Ƃ����Ă����B�@���@�̒��_�u���сv�͑P��̕��ł���B������A�u���сv�u�P��v�ƂƂ��Ɉ������ł���B�P��̕�͓����{�q�B����͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł���B�����{�q�͕����V�c�̕v�l�B��(���т�)�c�q���Y��ł���A�����ԁA���_�I�s������A�c�@�̖������ʂ������ɁA�������̑m�����т̐��b�ɂȂ��Ă�������ł���B��(���т�)�c�q�͌�̐����V�c�ł���B���l�����V�c��38�N�U��ɂ��A���R�ɕ�{�q�ɉ�����B�{�q�Ɂu�c�@�v�̖��_�ȏ̍������B�����V�c�͉��₩�Ȑ��i�̐l�ł������悤���B�@ |
|
|
�������V�c�Ɠ������A�����V�c�̕��鋞�J�s
�l�\��㕶��(�����)�V�c�́A�V�q(�Ă�)�V�c�̕P����(����)�c�����Ƃ���n���Ɍb�܂ꂽ���Ȃ����܂�ł���B�ϗ�(�y)�c�q�Ƃ��Ăꂽ�B���͑��Ǎc�q�ł���B�ꈢ�c���ٕ̈�o�u�����V�c�v�͑��Ǎc�q���Y��ł���̂ŁA�y�c�q���炷��A�����V�c�͑c��ɂ�����B�y�c�q��697�N8���ɑc�ꂩ����ʂ����B15�ł������B��߂���V�c�̐�����⍲���邽�߁A�����͑��������������d�����B���̎��A�����s�䓙���A���ߐ��x�̐������s�����B�_���͉��F�̈ߕ��A�_�z�E�z�X�͍��߂𒅂邱�ƂȂǂ���߂�ꂽ�B�ł̋`�����ׂ����������ꂽ�B����Ȃ��Ƃɕ����V�c�萭�̌㔼5�N�͗��ߐ��x�̐����ɂ��ւ�炸�A�V�ЁA���A�Q�[����ɉu�a�������A�s���Ȑ���ł������Ƃ�����B �����V�c�̑��ʂ̂Ƃ��A�����s�䓙�̗{���{�q����������B�y�c�q���I�B��V�̋�C�m������A��Ă��������̖��ł���B���������Ă��ꂢ�Ȗ��ł������Ƃ����B�����V�c�͑̂��キ�A10�N�̎����ŏI����Ă��܂����B�s�K�ȕv�l�{�q�͍c�q��(���т�)���Y��ł���A����𗣂�Ă���B �{�q�̂�����l�̎q�@���@�̎w���ҁu�P��v�͒���Ə@���E�Ɍq����������Ă����B�P��͍c���q���a(��̕���V�c)�̐M�������A�����V�c�̒푁�ǐe���Ƃ��e�����������B ��C���Ⴂ���뒭�߂����鋞�͎��@�̔���Ȃ������܂��ƁA���ېF�W���ɊO���l�������s�������Ă��āA�����̓s���v�킹����̂ł������B��C�͕��鋞�Œ����������w�тȂ���A���ɓn�蕧��������ɋɂ߂����ƍl�����ł��낤�B�����ŁA�����̕��鋞�̋��厛�@�̕��i��z�����邱�Ƃɂ������B �܂��A���������畽�鋞�֑J�s����Ƃ��̌o�܂�ǂ��Ă݂�B �c�_4�N(707)�����V�c�̑��ʂ̔N�ł���B�������ᎀ�ɂ����̂ŁA�ꈢ��(����)�c�����c�ʂ��}篌p�������B���̔N�ɑJ�s�̐R�c���n�܂����B�J�s�̏ق͘a�����N(708)�A�J�s���n�܂����̂͘a��3�N(710)�ł������B�J�s��ϋɓI�ɐi�߁A�����̒��S�ƂȂ����͉̂E��b�����s�䓙�ł������B�������ɂ͍���b�Ώ㖃�C���c��A�������Ǘ����Ă������A�a��4�N(711)�ɉЂ������A�J�s�̐���������ɑ��������̂Ǝv����B �V�s�͈̔͂́A���݂̓ޗǎs�Ƒ�a�S�R�t�߁B�X��̌`���͎鐝�ʂ�𒆉��ɍ��E�ɊX��B�k�Ɍ������Đ������E����A������������A�����č����悩�瓌���ɐL�т��O��(�������傤)������B���݂͂܂��A�����Ƒ�ɓa�A����ɉE��(���̋�)�̋M�l�����ƍ��������Ƃ��Z�ފ��ɂ����Ă�ꂽ�B�����ɂ͊����Ə������Z�ފX���ł����B���̌�A����������̎��@�����X�ƈڒz���ꂽ�B���鋞�̐l���͖�10���l�A�����͖�1���l�A�m�E�����҂̑����͊����̐��Ɠ��������߂Œ�߂��Ă����B ���������畽�鋞�Ɉڒz���ꂽ���@�͍����ɐ^�������(�����V�c�����S�ϑ厛�E���s�厛�E�劯�厛)�A���@������(�]�䎁�����A�@�����E��)�A�E���̖@���@��t��(�V���V�c����E�����V�c�����A�������{��t��)�ł������B����ɁA�R�Ȃ���ڂ����@���@������(�R�ȉX�⎛�A����������)��4�������ł���B������������炵������ʼnؗ�Ȕ��P�E�V���̎��@�炵���ؗ푑���ȉ����ł������B ������͓ޗǂ́u��厛�v�Ƃ�����ꂽ�厛�ł������B�������q�̔���A�����V�c�̑n���ƂȂ����S�ϑ厛(�����炨���Ă�)�ƍ��s�厛(�������̂����ł�)���O�g�̎��ł������B���s�厛�͕������V�c�O�\�O����A��Ė��\�O����ɓ�����Ƃ��ēV���V�c���A�V��2�N�ɑ��c���Ă����B���s�厛�͌�ɑ劯�厛(����������)�Ɖ�������Ă���B ���鋞�̑�����͓�����2��̎��d�������剾�����u�������t�v�ɂ���đn�݂���Ă���B�����͑��2�N(702)�ɓ����A�����̐�������16�N�Ԋw�w�m�ł������B���̐�������͂��������ȉ�����������ł������B��C�́u������͐������̍\���A�_�����ɂ̋ƂȂ�v�Əq�ׂĂ���B�c�O�Ȃ���A���m���N(1017)�Ђʼn������Ď��A�����I����̖ؒ�����9�̂��c�邾���ɂȂ�A���@�͉��N�̑����������߂����Ƃ͂ł��Ȃ������B ����̒r�̓�ɓ�k�ɒ��������������Ă����̂��A�u�������v(������)�ł���B�̖@����(��)���ڐ݂������́B�]�䎁�̎����ł��������A����J�s���@�Ɋ����ƂȂ����B����̖@�����͑�����ɑR����O�_�@�̊w�⏊�ł���A�������ɑR����@���@�̔��̊w�m�̏W�܂�ł������B������������ɏ@���̐������݂��āA�킸���ɐ^���@�̑m��y�o����悤�ɂȂ����B �^�����@�������̉����͎���ɍr�p�����������̖�ڂ������Ă������B�����Ƃ͂Ȃꂽ�m�V���T���Ƃ��Ēh�Ƃ������A�����Ƃ��ď@�����������Ă����B���̑m�V�̈���u�Ɋy���v�Ƃ��Ēq���@�t�������u�q����䶗��v�������ĐM�k���W�߂��B�����ē����̎��@�Ƃ��Ă͏��߂āA�����ɕ揊�������@�ƂȂ����B�����������͗��W�@����Ƃ��Đ����A�����Ȃ��炦�Đ��厛�����ƂȂ�A�u�ω����v�͓��厛�����ɂȂ����B�L���Ȍd���͍]�ˎ���ɏ��������܂܂ł���B�Ɏc���ꂽ�u���v�͖��������Ɍ������Ă���B �Ƃ���ŁA����̒r����k�����]����u�������v�̌d���͍D�����]�ł���B���̎��͓������̎����B�����������v�l���剤�̕a�C����������ċ��s�R�Ȃ̎��@�Ɍ��������u�R�K���v���O�g�ł���B��Ɂu�X�⎛�v���������ꂽ�̂��s�䓙���ړ��������B �������́u�{(����)��t���v����ޗǐ��̋��Ɉڂ��ꂽ�̂��u��t���v�ł���B�ߓS�������u���̋��w�v����k��5���B�����E�����E�������������猩����剾���ł���B�V���V�c���a�C�̍c�@�L��]��(���̂̂����)�̕���������āA�V��9�N(681)�ɑ����肵�āA����[�߂鎛�@����(�����s��a�̒�)�Ɍ��Ă��B�v�H��҂����V���V�c�͎钹���N(686)�ɖv�����̂ŁA�L��]�Ǎc�@(�����V�c)�̎�Ŗ�t���͊��������B�{����t�@���͎O�������A������������ŁA�V���V�c���S�ρE�����n�n���l�̋Z�p�҂������ꑰ�ł��邱�Ƃ������Ă���B���鋞�ւ̈ړ]�����́A�{�V2�N(718)�ł������B�������́u�{��t���v�͏\���I���܂ő������Ă����悤�ł���B ���鋞����鎞�A�u���厛�v�Ɓu�����v�ɐG��Ȃ��킯�ɂ͂����ʁB�����V�c�͊e�n���̎����ɍ������E������(���������E�@�؎�)��u�����Ƃɂ��āA�V��13�N(741)�ɏق��o���Ă����B���鋞�Ɍ��Ă������V�c�̍c�q��e���̒ǏC�̎��u�����R���v(737����)���������Ƃ��āAḎɓߕ���{���Ƃ���啧���ɂȂ����̂��u���厛�v�ł���B�Ӑ^�a��𓂂��珵���A���厛�ɂ�����m�̓��x�V���u����v�������铱�t�Ƃ��āA�܂��،��@���`���u�`����t�Ƃ��ĕ����E�ɐs�����Ă�������B�Ӑ^�a��̈��ތ�́u�����v�͉��d�@�Ƃ��āA���̋��u��t���v�̖k��1�L���̂Ƃ���ɁB�Â��ȋ����������Ă����B �ޗǒ�75�N�̂Ȃ��ŁA�،��@�u���厛�v�A���@�u���厛�v�A���d�@�u�����v�ȂǑ厛���n�����ꂽ�B���̂��ƁA��C�͓ޗǒ������࣏n��������ɂ����̎��@�ŋ��w���w�B ��C����s�Z�@�̎w���҂����ƕ��L���𗬂������Ƃ��ł����̂́A��̎��Ƃ̈ꑰ�Ƃ̗F�D�I�W������������ł���B���ꂱ������C���@���E�ƒ���Ɏ�����鉺�n�ƂȂ��Ă����B �����V�c����s�Z�@�̐����͂������āA���鋞���̂Ă��ɂ��ւ�炸�A�ǂ����Ă������E�ɂ����邱�Ƃ������Ă����B�������̊�����20�N�Ԃ�ɔh�������߂������g�c�ɑm�����܂߂邱�Ƃɂ����B���鋞��s�Z�@�h�̉e���ʂ�������Ȃ������B ����22�N�A��16�������g�D���o���Ɏ��s�����̂ŁA��23�N�̐V�����h���c���I�l�����悤�ɂȂ����B��C�͂��̋@����Ȃ������B ��C�̂悤�Ȏ��x�m�����ɗ��w����ɂ́A�������ꑰ�A�ꈢ���ꑰ�̎x�����Ȃ���Ύ����ł��Ȃ������B���x�m�̐g���ł͌����g�D�ɏ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����̑m���ɂȂ�K�v���������B����23�N(804)�A���厛���d�@�ŁA���x������āA�m�Ђ���C�́A�����呫��R�̖��A�_����������̎����āA�����g�D�ɏ�邱�Ƃ��ł����B��C��31�ɂȂ��Ă����B�����ŁA��C�̎o�̎q�A�������q�A�]�҂Ƃ��Č����g�D�ɏ�荞��ł������Ƃ��L���Ă����B�@ |
|
|
���ނȂ�������[���ċA��
��16�������g�D�ɉ^�悭��荞�߂���C�́A����23�N(804)�t�A��g���o�āA���ÁA�ܓ����o�R���āA���N8���A�\��n���O��āA���B���ь��Ԋݒ��ɕY�������B��w�̓V�ˋ�C�́A�C���Ƌ^��ꂽ��s���\���āA�O���g�߂ł��邱�Ƃ��ؖ�����劈��������Ƃ����B�Ő�����D�����D�͕ʂ̊C�݂ɕY�����Ă���B ��C��s�͉���23�N12���A�����ɓ��邱�Ƃ��o�����B��C�͒����ҐŃC���h�m�ʎ�O���ɞ�����K�����B�����Ş���̋��{�ƐV�ߌo�T��^����ꂽ�B��24�N(805)5���A���������掵�c�A�����̌b�ʘa����K�ˁA�t�����邱�Ƃ��ł����B�b�ʘa���͋�C�̔�}�Ȃ�˔\�Ɗw���A�o�T�̏K�n�ɗ����������A���������̓��{�ł̕��y����C�ɑ����邱�Ƃ����߂��Ƃ�����B ��C��6���ɑ�ߑّ��̊w�@�ƟA7���ɋ����E�̟����B��C�͓�̟ŁA����@���ƌ��������Ƃ����B8���ɂ͓`�@��苗��ʂ̟����B�u���̐��̈��Ղ��Ƃ炷�ŏ�̂��̑���@���v���Ӗ�����B�u�ՏƋ����v�̟������������B�������܁A��C�͐����ƕs��O���䂩��̑勻�P����500�l�قǂ����ҁA��苗��ʂ����Ƃ��I�����B���ꂩ��吨�̐l����䶗��Ɩ����@��̐���A�o�T�̏��ʂɊւ��A�b�ʘa�����������^����ꂽ�B12���b�ʘa���͓��₳�ꂽ�B ��C�͉���25�N(806)3���ɒ������o���A4�����B�ցA�l�����̑؍݁B�����ŁA�y�؋Z�p�A��w�̑��������B�����g�������K�B���̋A���D�ɕ֏�A8�����B���o���A���̓r�ɏA�����B�C��Ŗ\���J�ɑ����A�ܓ����]���ʔV�Y���`�ɂ��ǂ�����B��ɖ{�������F������ƒm������C�͎Q�āA����̒��ɖ����̐������ς�B�C�s���Ă����������������{�̒���Ɍ��ʂ������炷�ƐM������C�͎����u�����@�v�Ɩ��t�����B���ꂩ��A��͐��̍���R�Ƃ�����悤�ɂȂ����B ��C�͑哯���N(806)10���A��ɕ{���d�@�ɑ؍݁A����Ɂu�����ژ^�v���o�����B�����V�c�͊��ɕ���A����V�c�����ʂ��Ă����B20�N�̗��w�\���2�N�ŋA�������̂́u荊�(����)�̍߁v�ɂ�����Ƃ��āA�����͋�����Ȃ������B���܂�ɂ������I������C�w��͔F�߂Ȃ������B��s�����E�̑m����������C�̌��т�M���邱�Ƃ��ł��Ȃ������炵���B�悤�₭����V�c����C�̈̋Ƃ�]�����āA�哯4�N�ɑ����������o���ꂽ�B��C�̋��s�ւ̓��������]�Ȑ܂��������B �A����̋O�Ղɂ��ẮA�u��C���������v�u����V�c�Ƌ�C�v�̍��ڂ��Q�l�ɂ��Ă������������B�@ |
|
|
������R�h�V�u�嚢�@�v�Ɨ�����t����
����Q���s�͍���R�̏h�V�u�嚢�@�v�Ɉꔑ�����B���̂�������̊J��͐���(���傤�ڂ�)������t�ł���B�^���@���여�̑c�B�V�q�V�c�̘Z�����ŁA�����u�P�����v�B���́u������(���ǂȂ���)�v�B��C�̎���u�^��v�����厛�ʓ��̎��A16�œ�����q�ɁB���m(�^��̒�q)�t�@��q�ł������B�o�Ƃ��Ă��璷���ԁA�O�_�@�𒆐S�ɂ��ē�s���@���w�ԁB��N�A�{�i�I�Ɏ�@�A�^�������̐����ƂȂ����B �\���F���V�c�̋A�˂������A�������ґm���Ȃǂ̏d�E�ɁB�M���Љ�Ƃ̌𗬂��d�������t�^��ɔ�ׂāA���������A���_�Ȑl���ŁA�u�^��v�ݐ����͐^���@�ŖT���I���݂ł������B�������A�@�_�ɕ��邱�ƂȂ��A�g��̋���R�ł̎R�x�C�Ƃߏグ�āA�C�s���̐����A�����̑����ɕ�d��ɂ��܂Ȃ������B������A�u���R�h�C�����v�̑c�Ƃ�����B����2�N(890)�A�u��ώ��v�̍���ɁB�t�^�낪852�N�ɑn���������ł���B�����āA����5�N(905)�A�������̎��l���瓌�厛����@��a�����@��ɁB�O�_���w�̋��_�ƂȂ����B ���@�͑��R�̏C������J�����B���16�N(874)�����R�ȏ��쏯����◣�ꂽ�}��R�t�߂Œn�剡�����_�Ƃ����A����̎R��ɗ�_�Ɨ��(����)�����邱�Ƃ��������B����͂����ɁA�y��ω����Ɣ@�ӗ֊ω���������u�y�v����18�N(876)�Ɋ����������B���ꂪ��́u���펛�v�ƂȂ����B�L��Ȉ���͏C����Ƃ��āA�m���̏C�s�Ɏg��ꂽ�B ����2�N(902)�̂��ƁA����ɗ��ω����g�E���ꌠ���𖼏��_�����~�ՁA�u���̖��͐��B�������ɏZ��ł������A�������w��C�Ɍ�ĎO������������āA�Ôܖ��̖������炢�A���{�ɋA�������t�����n���B�}��R�����̍���������Ƃ��Ă���B���ɂ��Ȃ�Ŗ��𐴑�Ɖ��߂��v�Ƃ������B����͐���{�̔q�a�����炦���B���̂ق���t��(�{����t�@��)�A�ܑ哰(���ƒ���̎�)�A�J�R��(�u���A�̂��L�b�G���������ɍČ�)�A�����˂������J�n���Ă������B����͂������B���̏ꏊ�Ƃ����B �������������Ă����B�C����(�}��R)���牺�邱�Ə��ꎞ�ԁA�����ɉ���7�N(907)�A���V�c�̒��莛�u��펛�v���������ꂽ�B������̕������쏯�ɋ߂��B�鐝�V�c�A����V�c�̋A�˂����������̂ŁA�剾�����ł����B�����ɏ��l���A�ٓV���A����{�{�a�����Ă�ꂽ�̂ŁA�M�l�A���l�̎Q�w�҂������Ă������B�����ɂ͉��m�̗���ЂŁA�قƂ�ǂ̌䓰�������āA���ݍ���ƂȂ��Ă���d�����c�������ɍr�p�����B�G�g���c��3�N�`5�N�A�I�B����̖��莛����ڒz�����u�����v���L���ł������B����ɑ��̍��ŗL���ȁu�O��@�v���������B�嚢�@�̊J���(���傤�ڂ�)�̈̑傳���Љ���������̂ŁA�����M�����ׂ����B �Ƃ���ŁA�嚢�@�̔����Z�E��������͕�������A���d���̔z���A������m�Őē������Ƃ������B�u���ƕ���v�Ō����@�̎G�d�����J�Ƃ̗�����Ɏ��グ��ꂽ�l�ł���B�����f�����ďo�ƏC�s�������˂���������͍��쐹�ƂȂ�嚢�@�̍���ƂȂ����B �h�V�̌��߂��Ɉ�˂�����B���ɐ�]�������J�͉��ɐg�𓊂�����ɉ��g�����B��͑嚢�@�̈�˂̖T�̔~�ɗ��܂�A��������̖ڂ̑O�ň�˂ɔ�э��B�ƁA���R�����͏����ɏ����Ă���B��˂̉��ɏ����ȐΓ�������B ����͉����蕶�\���N(1592)�̂��ƁB�G�g�ɗ̍��q��ɑ��ɏ㋞�������ԏ@���A����R�Ɋx�����ԓ���A���������Љ^�̐Δ��[�߂ɑ嚢�@�Ɍ��ꂽ�B���ԓ���͖L��̌ˎ�(�ւ�)���ɂ���Ƃ�����A���喼��F�Ƃ̈ꑰ�Ƃ��āA�����@(�嚢�@�O�g)�Ǝt�d�̌_�������ł�������ł���B�@�͂��̐܂ɁA�嚢�@�̐�Y��苗��Ǝt�d�̌_������B�嚢�@�̍Ւd�ɂ��܂��嚢�@�a���A�@�Α勏�m�̈ʔv������B���ɂƂ��Ċ���ł������B�@ �@ |
|
| ���]�ˎ���̓��a�R�M�ɂ�����ꐢ�s�l�̊��� | |
|
���_�u����O�@���m�ƏC���҂̊�
�]�ˎ���(1600-1868)�����ɓ��a�R�́A�H���R�E���R�Ƌ��ɏo�H�O�R�Ɋ܂܂�A����Ɠ����ɓ���ȏ@���I�A�C�f���e�B�e�B�W�������R�ł���B���̓��a�R�́A�����ɂ��o�H�O�R�Ɛ[���W�������A��������̗�R�́u�������̉@�v�ł������B1 ���a�R�̍ł����Ȃ�ꏊ�́u���O�v�ł���B���O�Ƃ͋���Ȋ�ł���A����̓������̐_��I�Ȑ̕\�ʂ��Ă���B���̌��O�ّ͑��E����@���̖@�g�������A���a�����̕ϐg�Ƃ��Ĕq�߂���B�܂����O�͐�瑐_�ł��铒�a�����ƁA�{�n���ł���ّ��E����@���̎��R�I�}��ł���B����ɂ�蓒�a�M�́A�u�R�x�M�v�Ƃ������u����M�v�ł���ƍl������B ���a�R�[�ɂ͎l�̎R�x�@���W��������B���A�|���Ƒ�ԑ��͓��a�R�̕\���ɂ���A�{�����Ɗ⍪��͗����Ɉʒu���Ă���B���̎l�̎R�x�@���W���ɂ͂��ꂼ��ʓ���������A�����͕\���ɒ��A���Ƒ���V�A�����ɖ{�����Ƒ���������݂��Ă����B�����̕ʓ����́A���a�́u�l�P���v�Ƃ��Ēm���Ă����B�l�P���̏@�h�ɂ��ẮA�c��(1596-1615)�̏I���܂ł͖��炩�ł͂Ȃ����A���i(1624-1644)�����ɂ͐^���@�̉e�����D�ʂɂȂ�B�܂����̎l�P���̖{�����W�ɂ��ẮA�����̖{�����Ƒ�����́A���������܂Ŋ��͍]�ɂ��鎜������{�R�Ƃ��閖���ł��������A�]�ˏ����ɂ͂��̊W�͔��炢���B�\���̒��A���Ƒ���V�͌��\(1688-1704)�܂Ŗ��{���ł���A���̌�A���A���͑�펛�̖����ƂȂ�A����V�͒��J���̖����ɂȂ����B�����̖{�����Ƒ�����͎��������A���̂̔N�Ԏ��������ꂼ��Z�Όܓl�A�l�Όܓl�������B ���a�R�ŏ@���I�����������W�c�͎O��ނɕ�������B�����́A�����ȑm��(���m)�ƁA�C���ҁA�ꐢ�s�l�ŁA�ނ�͋����œ��a�R�̐��Ȃ�n����Ǘ������B2 �����ł́A�C���҂ƈꐢ�s�l�́u�C���̏O�k�v��u�R���O�v�ƌĂꂽ�C�s���̏W�c�ł������B�ꐢ�s�l�̖��O�̈Ӗ��́A�g�ꐶ�������āA�C�s�݂̂��s���l�ԁh���w���Ă���B���ɓ��a�R�̈ꐢ�s�l�́u��s�v(Skt. dhuta�A�l�M)���s���A�u����s�v��A�u�O����s�v�A�u�ܐ���s�v�̂悤�ȋV������A���O�̋߂��ɂ������s��ɉB�ق����B�R�̒��ōs����ꐢ�s�l�̕ʍs�́u�R�āv�ƌĂꂽ�B�ꐢ�s�l�̋�s�ɂ́A�ؐH�s�Ɩ����̐��C�����܂܂�Ă����B���a�R�ł͂��̂悤�ȋ�s���A�ꐢ�s�l�����s���Ă��Ȃ������̂ŁA���̍s�҂����͐��m��C���҂Ƃ́A�S���Ⴄ�K����V������H�����C�s�W�c�������B �ꐢ�s�l�ɂȂ邽�߂ɂ́A�u�C���v�̋V�炪�K�v�������B���̋V��̍ۂɁA�V�����s�҂ɂȂ�҂́A�ꐢ�s�l�Ɍ��O�̑O�ɘA����A�����Łu�C�v�̎����܂܂�鐳���Ȗ��O����������B�Ⴆ�A�{���C��^�@�C�A�S�C�̂悤�Ȗ��O�́A�ꐢ�s�l���w���Ă����B���a�R�̈ꐢ�s�l�̏ꍇ�ɂ́A���̊C�̎��͍O�@��t��C(774-839)�̍Ō�̎�����R�������B�H���R�̈ꐢ�s�l���C���̋V����s�������A�ނ�̏ꍇ�ɂ́A�H���R���J�R�����\�����q�̕ʖ��ł���O�C����R���������������B���a�R�̈ꐢ�s�l�ɂƂ��āA��C�͎����́u���t�v�������̂ŁA�C���̋V��̎��ɁA�V�s�҂͕����̃���������鎖�𐾂��A�u���v(Skt. śīla)�����B3 �����ȑm���̏ꍇ�ɂ́A����̋V��̓L�����A�̒P�Ȃ�o���_�ł���A���K�����Ԃ̍Ō�ɍs����V��Ő����ȑm���ɂȂ邱�Ƃ��ł����B�������A�ꐢ�s�l�̏ꍇ�ɂ́A���邱�Əo���Ȃ������̂ŁA�����̊K�����x�̎���̃��x���܂ł����o��Ȃ������B�܂�A�ꐢ�s�l�́u���m�v��u���O�v�ɋ߂����݂������B �{�����̑m���́A�ꐢ�s�l�̎����u���ؖ��m���K�v�ƕ`�ʂ��A���̃q�G�����L�[����͔r�����ꂽ�s�l�W�c�Ƃ����B�{�����Ƒ�����̕ʓ��͑S�đm���ł���A���̃O���[�v�̎P���ɏC���҂ƈꐢ�s�l�������B�����̕ʓ����ɏ��������ꐢ�s�l�́A���̊Ǘ������錠���������Ă��Ȃ������B����Ƃ͈Ⴂ�A�\���̕ʓ������������A���Ƒ���V�̈ꐢ�s�l�́A�ʓ��Ƃ��Ď����̎����w�������B���A���Ƒ���V�́A���ʂ̎��ł͂Ȃ��u�s�l���v�������̂ŁA�ꐢ�s�l�͑S�Ă̑�Ȗ�����S�����B�Ⴆ�A�L���Ȉꐢ�s�l�̐^�@�C��(�v1783)����V�̕ʓ��ɂȂ�A�c��C��(�v1829)���A���̕ʓ��ɂȂ����B�s�l���̈ꐢ�s�l�͉����F�����s�������A�������s�������o���Ȃ������B�����͕��ʂ̎��Ƃ͈Ⴂ�A�s�l���ɏZ��ł����m���͋��炸�A�����ɏ��������u�U�߁v�����Ȃ������B ���a�R�̈ꐢ�s�l�͓��ނɕ����鎖���o����B���a�R�̕ʓ����ɋ��Z�����ꐢ�s�l�ƁA�o�H���̏������牓�����ꂽ�n��Ⓦ�k�n���A�֓��n���ɋ��Z�����ꐢ�s�l�ł���B���̌�҂̃O���[�v�̈ꐢ�s�l�́A���a�R�Ō��K���̎������I������A�����̌̋���ʂ̒n��Ɉړ����A���a�R�M���L�߂��B�Ⴆ�A��������z�㍑�ł́A���a�R�̈ꐢ�s�l�̊����͋ɂ߂ėD���������B���̏����Z�̈ꐢ�s�l�́A�s�l�������āA�@���̎��H�����A�ꍇ�ɂ���Ă͌����炠�������ɏ������A���̎��̐M�҂̂��߂ɋV��Ȃǂ��s�����B���a�R�̎l�P���́A�������ꂽ�n��̈ꐢ�s�l�̊������ē��邽�߂Ɂu�s�l�G���v�Ƃ����S���҂�C�������B�Ⴆ�A�]�˂̃G���A�̏ꍇ�ɂ́A�{�����̍s�l�G�����c�������̕��@�ɋ��Z���A4 ������̍s�l�G���͔����x�̕��{�@�A���A���̍s�l�G���͓��{�������̘@��@�A�܂�����V�̍s�l�G���͋����̕����@�ɂ��ꂼ�ꋏ�Z�����B5 �ꐢ�s�l�ƏC���҂́A�����Ƃ��C�s�����Ȃ��猱�͂����A���ꂼ��قȂ������K�Ǝ��H���s�����B���a�R�̏C���҂͑S�āu�ݕ��C���ҁv�������B�ꐢ�s�l�ƈႢ�A�W���ɉƂ������A�S���Ƃ��Ď����̓y�n�⎛�̂œ����Ă����B�ꐢ�s�l�͋֗~����������A���a�R�̏C���҂͍ȑяC���҂������B�Ċ��ɂ́A�C���҂͓��҂̂��߂Ɉē���B�ƂȂ�A�h�V�̊Ǘ������Ă����B�C���҂͐V�N�̍ŏ��̎O�����ԂɁA�����̒U�߂̂��߂ɒ��d���ꂽ�u�������v��z�����B���̂悤�Ȋ����́A�����ɂ͈ꐢ�s�l�ɋ֎~����Ă������A���ʂɒ��A���Ƒ���V�̈ꐢ�s�l�́A�s�l���ɔ��܂������҂̂��߂Ɉē���B�̊��������Ă����B���A���Ɩ{�����A������̏C���҂͗t�R�̋߂��ɂ��鎜�����œ���V����s�����B����V�̏C���҂́A�߉��̋߂��ɂ������R�̐뎛�œ����B����ɑ��A�ꐢ�s�l�͏C�s�V���S�ē��a�R�ōs�����B���A���Ƒ���V�̈ꐢ�s�l�́u��l��v�ŎR�Ă��A�{�����Ƒ�����̈ꐢ�s�l�́u���C�v�ŎR�Ă������B���̓�̍s��ŕʍs�����鎞�ɁA�ꐢ�s�l�́u�s���v�Ƃ������ʂȎR�����ɏZ��ł����B�����̂��Ƃ���A���a�R�͈ꐢ�s�l�̋�s�̎R�ł���A�C�����̎R�ł͂Ȃ������B ���a�R�̈ꐢ�s�l�́A�C���҂̓���V��ɎQ����������Ȃ������B����͒P�Ȃ�����I�ȏ��O�ł͂Ȃ��A�ꐢ�s�l���C�����̃q�G�����L�[�ɓ��鎖���o���Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�C�����̏��i�K��͓�����s�����Ɋ�Â��Ă���A����ɂ���ďC���҂͐�B����B�̃����N�ɏ��i���鎖���o����B����ɎQ�����Ă��Ȃ������ꐢ�s�l�͏C���҂ɐ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���i�K��̎��_���猩��ƁA�ꐢ�s�l�͐����ȑm���ƏC���҂̂ǂ��炩�����O�I���݂ŁA�g�_�u����O�h�ƌ����悤�B �@ |
|
|
���I���f�}���h�̍s��
�ꐢ�s�l�̋V��̒��ŁA�u�ʉv�͋ɂ߂đ厖�ȗv�f�������B���̐��߂��́u��v�ƌĂ�A����Ɏg��ꂽ�u���v�Ƃ͈قȂ�A�V��̂��߂̉������B�ꐢ�s�l�͓��H�������A���ʂ̑䏊�̉̏�ŏĂ����H�ו���H�ׂ邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�]���āA�ʉ��q��ĂȂ��H������邽�߂̉ł�����A�얀�̂悤�ȋV����s�����߂̐��Ȃ�ł��������B�������ƌ������B�c��C�̓`�����������߂��A�߉��̉������������x�~�v��ɂ��ƁA�ꐢ�s�l�̏�ّ͑��E����@���̖@�g�́u�q�v��\���Ă���B���a�����̕ϐg�ł��锪��������q�́A�O�@��t�ɏ�̋V���`���A�J�R�̎��ɑ�t�͓��a�R�̈ꐢ�s�l�Ɍ��`�����B6 �R�Ă̎��Ɉꐢ�s�l�͏���g���A����I�ɖؐH�s���s�����B�ꐢ�s�l�ɂƂ��ĖؐH�s�͒P�Ȃ鍒�ނ̐H�ו��������A�̗t���A����H�ׂ邾���ł͂Ȃ��A���g�̌��͂𑝂₷���߂̍s�ł��������B����������A�ؐH�s�͈ꐢ�s�l�̒����R�I�ȗ͂������C�s�������B�Ⴆ�A���a�R���{�̔�ɂ́A�ꐢ�s�l�̖��O�́u����s�ؐH�s�ҁ����v�̂悤�ȃX�^�C���Őɒ����Ă����B����́A����s�ƖؐH�s���ꐢ�s�l�̓��L�ȏC�s�ł��邱�Ƃ���A���̍s�҂̃����N�������A�h�̂�^�C�g���Ƃ��Ă̖������ʂ������B�ꐢ�s�l�̊����̒��ŁA���a�R���{�����̗��z�͋ɂ߂đ�ł������B�܂��A�ꐢ�s�l�͋������鎖���o���Ȃ��������A�����̍�����D���Ă����B�Ⴆ�A�߉��̍s�l���ł����x���ł́A�c���C�̂��p��`���Ă����D����l�C�������B����́A�c���C���ꐢ�s�l�̐����Ȉߑ��𒅂āA����ɑ���@���Ɠ����悤�Ȋ������Ԃ�A�E��ɓƌ�����A����Ő���������p�ł������B�D�̏㕔�ɂ́A�����̂悤�Ȑ_�̂�������Ă������w�䖼�����c�̖�˂̂����ɉƂɎp����Ă͂Ȃ�̉u�̈��_�x�B7 �ꐢ�s�l�̊����ƊW�̂����ԌÂ��j���Ƃ��āA�c��8�N(1603)�ƌc��9�N(1604)�ɏ����ꂽ�l�̖ڈ�������B�ڈ��͍ŏ��ɁA�������̍K��s�̕s���@����A�����̌����@�ƍ]�˂̎��Е�s�ɑ���ꂽ�B���̌㎟�̖ڈ����A�����@����{�����A������A����V�֑����A�e���̊Ԃɓ��_�������N�������B �ŏ��̖ڈ��́A�K��̕s���@�̑m���������@�̑m���Ɉ��āA�����@�ɑ����Ă����ꐢ�s�l�ɂ��Đq�˂����̂ł������B�s���@�͕��ʂ̎��ł͂Ȃ��A���͍��̏��c���s�̋ʑ�V�Ƌ��ɁA�֓��n���̖{�R�h�C�����̎i�ߕ��ł������B�s���@�̑m���̋^�O�́A�����@�ɑ����Ă��铒�a�R�̈ꐢ�s�l���A��B�Ƃ��Ă̊����ƁA�u���߂̂���͂��v�̋V����s�����߂̍��J���������Ă������ǂ����Ƃ����_��₤���̂������B����ɑ����a��3�̎�����̕Ԏ��́A���a�R�̕ʓ��́A�ꐢ�s�l�����҂̂��߂̈ē���B�̊����ƁA�u���߂̂���͂��v�Ƃ����V����s�������֎~���Ă���A�����̊����͓��a�R�̏C���҂Ɍ��肳���A�Ƃ������̂������B �u���߂̂���͂��v���ǂ̂悤�ȋV�炾�������ڍׂ͕s���ł��邪�A�勝2�N(1685)�ɏ����ꂽ�A���a�R�ւ̏���ɂ��Ă̓����L�Ɂu���A�P�v�Ƃ����V��̕`�ʂ��ڂ��Ă���B�����ł́A�k���n���̑��������o�����铹�҂��A�ꐢ�s�l�ɒ��A�P�̋V��𗊂Ə�����Ă���B8 �]���āA�u���߂̂���͂��v�͏���̏��߂ɍs���A���҂𐴂߁A��邽�߂̋V�炾�����ƍl������B�����A�u���߂̂���͂��v�Ɓu���A�P�v�������悤�ȋV��Ȃ�A�ڈ��̒��ŁA�s���@�̖{�R�h�C���҂͂��̎�ނ̋V��������̓Ɛ茠�Ƃ��đ����A�����ȏC���҂ł͂Ȃ������ꐢ�s�l�͂��̋V����s���������Ȃ��Ƌ��������������̂��ƍl������B���ɁA�ꐢ�s�l���^���@�C���W�c�Ƃ��āu���߂̂���͂��v���s���Ă����Ƃ�����A�s���@�̖{�R�h�C���҂ɒ��A�P��K�킴��Ȃ������ł��낤�B�c��18�N(1613)�ɓ���ƍN(1542-1616)�́w�C�����@�x�x�����z���A�{�R�h�C�����̓Ɛ茠�����������B����Ɠ����ɁA�ƍN�͓��R�h�C�����̌`�������F���A���A�P�Ɠ���̋V��Ɋւ��K�����������B�������w�C�����@�x�x�ɏ����ꂽ���R�h�C���҂̒�`�ɍ���Ȃ������ꐢ�s�l�̂悤�ȃA�E�g�T�C�_�[�̍s�҂́u���߂̂���͂��v���s�������o���Ȃ������B �c��9�N�ɏ����ꂽ�ڈ��ɁA�ꐢ�s�l�̒�`���ڂ��Ă���B���̃e�L�X�g�ɂ́A�ꐢ�s�l�́u�����̂���v�u���S�v�ɐ�O����s�l�O�������Ƃ���A���̏�A�u�㊯�v�ł������̂ŁA�����̏C�s�ɂ���ďW�܂����u�����v���O�҂ցu����v����s�҂ł������ƋL����Ă���B9 ����������ƁA�ꐢ�s�l�́u�㊯�s�ҁv�Ƃ��āA����s�ⓒ�a�R�ւ̏���C�s�����K�I�x���҂̂��߂ɍs���A������������A���̃p�g�����́u��v�������邽�߂ɋ�s���s�����̂ł���B���y���R����(1573-1600)����]�ˎ���ɂ����āA�o�H�̕��Ƃ́A���a�R�̈ꐢ�s�l�̔M�S�ȃT�|�[�^�[�ɂȂ�A�����̉Ƃ́u���^���v�v��u�̓��~���v�̂��߂Ɉꐢ�s�l�̋�s���x�������B�Ⴆ�A���\2�N(1593)�ɒ��]���� (1559-1620)�́A�����̊�������邽�߂ɁA���a�R�́u���Q�v�O�S�l�ցA���Ύl�l�ꏡ�����B10���̋��z�ɎO�ѕ��𑫂��A�m���ւ̎{�����㉇�����B���̎j���ɂ́A���a�R�ōs��ꂽ����C�s�̊��Ԃɂ��Ă̋L�q�͂Ȃ����A�\�����I�̑��̎j���ɂ��ƁA���a�R�̑�Q�́u�ꎵ���v�Ɓu���O���v������A���̂��Ƃ���A���]���������������z���l����ƁA���炭�ނ��㉇������Q�́A�u�ꎵ���v�Ɛ��@����A�ɂ߂đ����̑�Q�҂̒��Ɉꐢ�s�l�����ł͂Ȃ��A���a�R�u�́u��艺��s�l�v�Ⓖ�]�Ƃ̉����̎������܂�ł����ƍl������B�����j���ɂ��ƁA���\2�N�ɁA���]�����́u�����Q�s�v���s���ꐢ�s�l�̈�l���㉇���邽�߂ɁA��N�ԂŎO�\�����B�܂�A��l�̍����Ȉꐢ�s�l�̐���s���I���܂ŁA�����͍��v��\���x�������B���̋��z�̉��l�𗝉����邽�߂̔�r�Ƃ��āA��N�Ԃ̖{�����̎��̂̎������Z�Όܓl�A������͎l�Όܓl���������Ƃ��l����ƁA����s���s�������Ȉꐢ�s�l�́A��l�ł��т��������z�{�̗ʂ��W�߂�J���X�}���������Ă������Ƃ�������B���̗��������ƁA�c��5�N(1600)�̊փ����̐킢�̑O�ɁA�����̐퍑�喼�ł������ŏ�`��(1546-1614)�́A�����Ɠ���ƍN�̐폟�Ɋւ���𗧂āA���͍]�̍s�l���ł��������R���̈ꐢ�s�l�Ɏ����̊������A���a�R�ցu�l�\�����R�āv�����ɍs�������B11 �@ |
|
|
���o���_��Ƒ��g���̌`��
�~�C�������ꂽ�ꐢ�s�l�̎��̂́u���g���v��u�~�C���v�ƌĂ�A�l�X�͂�����u���g���v�Ƃ��Đ��߂��B���������ꐢ�s�l�̎��̂ł��鑦�g���́A�����ȍs�҂́u�S�g�ɗ��v�Ɠ������A�M�S�ȐM�̒��S�ł��鐹�Ȃ郂�m�ł���B���g���Ƃ����T�O�͏C�����ɂ���A���͋�C�́w���g�����c�x(�V��1�N�A824)�ٖ̈{�Ɋ�Â��č��ꂽ�v�z�ł���B����������A�C�����̑��g���v�z�͐^�������̑��g�����v�z�̕ϊ��ł���B�]�ˎ���̏C���҂́A�R�ŏC�s���s���s�҂̐g�̖̂{����������߂ɑ��g���̊T�O���g�p�����B�s�҂́u���g�v��u���g�v�́A�{���I�Ɂu���g�v�ƕς��Ȃ����݂ł���̂ŁA���g���ɂȂ鎖���ł���ƍl����ꂽ�B�Ⴆ�A�u�}�g�����g�v�̊T�O�͑��g���̊T�O���琶�܂�A�}�v�ł���s�҂̐g�̂́A���g�Ɓu�s��v�������B���a�R�̈ꐢ�s�l�B�́A���̏C�����̎v�z��������邽�߂ɁA�����Ȉꐢ�s�l�̎��̂𑀍삷�邱�Ƃɂ���āA���g�����`�������B�܂�A�ꐢ�s�l�̑��g���͎v�z�̐��E����g�̐�����荞�̐��E�ւƓ��������B ���a�R�n�̑��g���͑S�Ĉꐢ�s�l�������B���݂��c���Ă��鏯���o�g�̍����Ȉꐢ�s�l�̑��g���́A�{���C(�v1683)�A���C(�v1755)�A�^�@�C(�v1783)�A�~���C(�v1822)�A�c��C(�v1829)�A�����C(�v1854)�A���C(�v1863)�A�c���C(�v1881)�ł���B����{�̖{�����̕ʓ��������{���C�ƁA����V�̕ʓ��������^�@�C�ȊO�̑��̈ꐢ�s�l�́A�F���A���ő�Ȗ�����S���Ă����s�҂������B���a�R�n�̑��g���͓��k�n���ƒ����n���ɂ����݂��Ă���B���̏ꍇ�A���a�R�ɋ��Z���Ă��Ȃ��ꐢ�s�l�̎��̂͂��̒n��ɂ������s�l���Ń~�C��������Ă����B���������ƁA�z�㍑�̕H���ɂ���ω����̑S�C(�v1687)��A�����̑���ɂ���ω����̕��C(�v1903)�̑��g���Ȃǂł���B ����ɑ��g���ɂ��ꂽ�ꐢ�s�l�͋ɂ߂ď��Ȃ������B���ꐢ�s�l�̑啔���͑��g���ɂ��ꂸ�A��őm�����W���I�ȑ������s�����B�Ⴆ�A��c�ɂ���C�����̈ꐢ�s�l�́u���@�v�͓��s�̗������ł���A�s�҂̕�ƈʔv�����̎��Ɉ��u�����B���̂g���Ɍ`�����邽�߂ɂ́A�R�X�g���������ɁA��Ԃ�������ߒ���L����̂ŁA���O���͂ɂ��т����������̐M�҂��W�߂鎖���o�����ꗬ�̈ꐢ�s�l�������Ă��炦�Ȃ��������V�������B�܂�A���g���͎��R�I�Ȍ��ۂł͂Ȃ��A�l�H�I�Ȍ��ۂł���B �ꐢ�s�l�̎��̂���̓I�ɑ��g���ɂ����l�́A�ꐢ�s�l�̒�q�Ɠ��a�R�u�̐G���̂悤�Ȗ��������Ă����u���b�l�v�Ƃ����u���������ƍl������B�܂�A�����Ă���ԂɁA�����Ȉꐢ�s�l�́A�l�X�ȃp�g��������o�ϓI�Ȍ㉇���A����s�̂悤�Ȓ����Ĕ�p�̂�����C�s���s�������o�����B���̋��K�I�Ȏx���̑���ɁA��ʓI�ȐM�҂�u���A���m�����͈ꐢ�s�l�Ɏ����̊肪�����悤�˗������B���U��ʂ��ăT�|�[�g�����ꐢ�s�l�������ɁA���̌㉇�҂����͎����̂����ƐM�𓊎������s�҂̎��̂��̂��̂��A���Ȃ郂�m�Ƃ��āA�̂Ă��ɑ��g����������B����������A�����Ȉꐢ�s�l�̐g�͍̂s�Ҏ��g�̍��Y�ł͂Ȃ��A�㉇�҂̍��Y�ł���ƍl������B�ꐢ�s�l�̎���ɁA���̎���������̊W�����炩�ɂȂ�A���g���͌����B �ꐢ�s�l�Ɛ��b�l�̊Ԃɂ���o���_����������̂Ƃ��āA��l��Ɍ����������s���I��������ɍ��ꂽ�肪��������B���̔�ɂ́A����s�̎n�܂��������L����Ă���B���̓��́A�ꐢ�s�l�́u����v�ŁA���ꂩ��n�܂��s�̗͂ŐM�҂̊��S�Đ��A���鎖�𐾂����ł���B������ɂ́A����s���I����������L����A����́u����̓��v�ƌĂ��B�O�N�ɓn��A�o�ϓI�x�����C�s�������ꐢ�s�l���A���̑Ή��Ƃ��Ďx���҂Ɋ�̐��A�������炵�����ƂȂ�B��ɋL���ꂽ�A����Ɩ���̓��̊Ԃɂ͈ꐢ�s�l�̖��O������A���̂������ɂ́A����s���㉇�������b�l�̖��O�Ɠ��a�R�u�̑������L����Ă���B12 ���̂��Ƃ́A�ꐢ�s�l�Ǝx���҂Ƃ̑o���_��̊W�������Ɏ����Ă���Ƃ����悤�B���̑o���W�͈ꐢ�s�l�̎�����A�M�҂ƒ�q�ɂ���Ĉꐢ�s�l�̎��̂Ȃ���g���ɂ��A���g������鎖�ɂ���Čp������̂ł���B �@ |
|
|
������s�̌����Ƃ��Ă̓y������
�ꐢ�s�l�̎��̂́A���ʂȕ�̒��Ɉ��u����A���̏�Ԃ��u�y������v���Ă���ƌ����A���ʂ̎��̕��ނƂ͈قȂ���̂ł���B�u����v(Skt. samādhi-praviṣṭa)�Ƃ́u���T��v�̗��ł���A�ґz�҂́u�T�v(Skt. dhyāna)���n�߂Ă���u��v�̍ł��[����ނł���u�O���v(Skt. samādhi)�ɓ���܂ł��Ӗ����Ă���B���̒��7�̒i�K�̍Ō�̃X�e�[�W�́u���@�y�Z�v�ƌĂ�A�ґz�҂̐g�S�͐Î~�ƐÎ���i���ɕۂ����o����Ƃ����B����́A�ґz�҂��܂������Ă��鎞�ɁA���̌��@�y�Z���g�̂����S�ɓ����Ȃ���ԂɂȂ�̂ŁA���̂̓����ł��鎀�㋭����z�N�����邱�ƂƏd�Ȃ�B�Ⴆ�A�W���i�T���E�y���[���ɂ��ƁA�C���h�Łu����v�Ƃ������t�͈�̖̂������w���Ɠ����ɁA��̒��ɂ����̂̐�����Ԃ������B13 �m����ꐢ�s�l�̂悤�ȍs�҂́A���ʎ��Ɂu����ɓ���v�ƌ����Ă���B����������A�����̃v���t�F�b�V���i���͂������ȂȂ��B�ނ�̎��S���������߂ɁA�u���v�Ƃ������t�̑���ɁA���Ǝ��̞B���ȋ��E���`����u����v�ƌ������t���g�p����B �ꐢ�s�l�̓y������͎O�N�ƎO�����������B���̌����J���A���b�l�ƒ�q�͖������ꂽ��̂̃~�C������Ԃׂ��B�y������̊��Ԃ͐���s�̒����Ɠ����Ȃ̂ŁA��ɒu����Ă����ꐢ�s�l�̎��̂́A����ł����̂ł͂Ȃ��A�Ō�̐���s�����Ă����ƍl����ꂽ�B����������A�����Ȉꐢ�s�l�̑��V�ł������y������́A�s�҂������Ă��鎞�ɍs�����̐���s�́u�����v�������B����ɍs��ꂽ����s�́A�ō��̏C�s�������ƍl������B�Ȃ��Ȃ炱�̎��ɁA���̌��E���z�����ꐢ�s�l�́A���߂Ĉ��܂��A�H�ׂ��A�Q���ɏC�s�O���ɓ��鎖���o��������ł���B�y������̌��ʂł��鑦�g���́A�M�҂ƍs�҂́u�����v����邽�߂̓��g���ɂȂ����B�Ⴆ�A�w�������C��l�����N�x�ɂ��ƁA���5(1755)�ɒ��C�́A����s���I��������Ɏ��R������������A���̌����J�������ɁA���C�̎��ّ̂͑��E����@���̌����Ɉ͂܂�A�u���g�����Ɛ��点���܂Ӂv�ƋL����Ă���B��ɁA���C�̑��g���͐M�҂����Ƃ́u�����v��s�҂́u���s�v��m�点�邽�߂ɊC�����Ɉ��u���ꂽ�B14 �����Ȉꐢ�s�l�̈�̂��������ʂȍ\������������́A�u�̙��v�ƌĂ�A�n���ɖ��܂�����Ԃ̐��̒����̂���B�Ⴆ�A���C�̙̐��͊ω����̗���Ɍ������A���̍\���͒�ʂɍL���傫�ȕ��������u����A���ʂ͎l������\���̐�̐���Ȃ�A��ʂ͎O�̕���ȁu�W�v�ŕ����Ă���B�ō��ꂽ�����̂̒��ɁA�����ꂽ��Ԃ��ł��邱�ƂɂȂ�B�܂��ꂩ��\�Z���`�̂Ƃ���ɂ́A�S�őg�܂ꂽ�i�q������A���̏�ɕ��C�̎��̂��������A��d�̊����u����Ă����B���̍H�v�ɂ��A��������݂鐅�⎼�x�͊��ڐZ�������A�~�C�����̉ߒ��̈ꐢ�s�l�̎��̂͋�C�Ɉ͂܂�Ă����B�܂����͋ɂ߂Č����ؐ��ŏo���Ă���A���̎����~�C�����̏d�v�ȗv�f�ł���B�Ⴆ�A�C�����̐��C(1795-1872)���������j���ɂ��ƁA����s���I�����c��C�͊C�����ɖ߂�A�����ˑR�u�a�ǁv���A�S���Ȃ����B��q�������c��C�̎��̂��u��d���v�ɓ���A���A���̐V�R�������̗��ɖ��������A�Ƃ����B15 ���b�l�͂��̂悤�ȕ��G�Ȏ�Ԃ̂����鑒�V�̂��߂̏o���S�ĒS���A�ꐢ�s�l�̎��̂��`�������g�̖{����������B �ꐢ�s�l�̎��ƊW����������`���́A�u�y������v�����ł͂Ȃ��A�u�̐g�s�v�̖ʂ�����Ă���B�]���āA�����`���ɓo�ꂷ��ꐢ�s�l�́A���ʑO�Ɏ����I�Ɂu�̙��v�ɓ���A��������Ȃ���u�����g�v��Ƃ����B���̌����`���ɉ����ẮA�O�@��t�̓y��������b��A���ӐM�̉e�����ɂ߂ċ����ƍl������B�Ⴆ�A�W�����E�W�����Q���Z�����͐��l�`�̍\���͂��A�u���ꂽ���l�v�Ɓu�q�ϓI�Ȑ��l�v�̓�ɕ����鎖���o����Əq�ׂĂ���B16���ꂽ���l�̓t�B�N�V���������ꂽ���l�ł���A�q�ϓI�Ȑ��l�͗��j�̕���ɓo�ꂷ��l�Ԃł���B�ꐢ�s�l�̏ꍇ�ɂ����̗��ʂ�����B�܂�A�u���ꂽ�ꐢ�s�l�v�͗��j�I�ȃ��x�����A�s�҂̃J���X�}����`���A�u�q�ϓI�Ȉꐢ�s�l�v�͗��j�͈̔͂̒��ōs�҂̃p���[��\���B���j�Ɠ`���͌q�����Ă���Ɠ����ɁA���������Ă���̂ŁA�u���j�Ɋ�Â��Ă���ꐢ�s�l�v�ƁA�u�����`���Ɋ�Â��Ă���ꐢ�s�l�v�͖������Ă���l�ɂ������邪�A�����u�����v�̈قȂ郌�x���������Ă���B17 ���̓_�ɂ��ă~�V�F���E�h�E�Z���g�[���͗��j�̗v�f�Ő��l�`�f����̂͊ԈႢ�ł���A�܂����l�`�̗v�f�ŗ��j�����߂���̂����ɓ����Əq�ׂĂ���B18 ���̂��Ƃ���A���̔��\�ŕ��͂������j�I���߂̈ꐢ�s�l�́A�����`���̈ꐢ�s�l�Ɖ�������ɂ���Ƒ����A�݂��ɔے肷����̂ł͂Ȃ��ƍl����B �@ |
|
|
����
1. �o�H�O�R�͎R�`���Ɉʒu���Ă���B 2. �u���a�R�R�����ʓ��l[�P��]�v(����1�N�A1804)�B�w��������(��)�x�n�ӗ����ҏW(�߉��A�x�m���������ЁA1964)108−113�ŁB 3. �u�ĕԓ��V���X�o���v(����6�N�A1666)�B�w��������(��)�x�n�ӗ����ҏW�A21�ŁB 4. �c�������͌��݂̓��{���ɓ�����B 5. ���݂̋����͐�t���̑D���s�Ɋ܂܂�Ă���B�]�ˎ���ɂ��̒��ɓ��a�R�u�̐��͋ɂ߂đ��������B 6. �u�T���u�v (���� 9�N�A 1812)�B�w��������(��)�x�n�ӗ����ҏW�A3�ŁB 7. �ː���́w�o�H�O�R�̃~�C�����x(�����A�������@�A1974)141-142�ŁB 8. �v�ۍN���u�Q�w�̒��A�P�\�R���̊����̉𖾁v�A�w�ߐ��C�����̏����x���}���A�v�ۍN���A�g�J�T�ƁA������v��Y�ҏW (�����A��c���@�A2013)�A38�ŁB 9. �u��ڈ��V���v(�c��9�N�A1604)�B�w��������(��)�x�n�ӗ����ҏW�A105�ŁB 10. �u���a���N����V���v(���\3�N�A1594)�B�w�_����n�_�Еҁ\�o�H�O�R�x��32�W�A�ː���͕ҏW(�����A�����ЁA1982)425-426�ŁB 11. �u�����쏑��v(�c��5�A1600)�B�w�R�`���j�\�Ñ㒆���j���x��2�W�A�R�`���j�҂����c��(�R�`�A�������X�A1979)215�ŁB 12. ��l��s�Ҕ�ɂ��āw��������(��)�x�n�ӗ����ҏW�A143-144�ŁB 13. Jonathan Parry, �gSacrificial death and the necrophagous ascetic,�h in Death & the Regeneration of Life ed. Maurice Bloch and Jonathan Parry (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), 96. 14. �u�������C��l�����N�v(�]�ˌ��)�B�w��c�s�j−�j���ҁx��7�W�A�{�ԗS��ҏW(�߉��A�߉����������ЁA1977)701�ŁB 15. �u�L�^���v(����12�A1829)�B�������q�w���{�̃~�C���M�x(�����A�@���فA1999)168-169�ŁB 16. John Jorgensen, Inventing Hui-neng, the Sixth Patriarch: Hagiography and Biography in Early Ch�fan (Leiden-Boston: Brill, 2005), 23. 17. �u�����v�Ƃ����p��̓~�V�F���E�t�[�R�[���́gdiscourse�h�̊T�O������̂ł���B 18. Michele de Certeau, The Writing of History (New York: Columbia University Press, 1988), 270. �@ �@ |
|
| ���O�㚠�����S�u�}�C���v | |
|
���}�C��(���T�����܂̂���)�Ƃ�
�}�C���Ƃ́A���ĒO�㚠�����S(���݂̋��s�{���ߎs�y�щ����S��]��������)�ɂ������Ƃ���鋽���ł��B��Y�����ɗאڂ���傫�ȓ��ł������悤�ł��B ���������}�C�� �`���ɂ��ƁA��N(����701)�O���A�}�C���͎O���O�ӑ������n�k�ɂ�苽���̕��ӂ����c���ĊC�v���Ă��܂��܂��B���̂ӂ��̕������A���{�C�ɕ����Ԑ�C�̌Ǔ��E����(����ނ肶�܁E�ʖ��Y��)�ƌB��(�����܁E�ʖ�����)���Ƃ����Ă��܂��B ���M�̓� �����͈�ʂɁw�����܂���x�ƌĂ�A�n���̋��t����B�̓Ă��M�̑ΏۂƂȂ��Ă��܂��B��������t�������ɕY�����Ė������������Ƃ�����b���������邩��ł��B���t����B�͓��ւ̍v�������������܂���B ���C�l���`�� �O��̚��ɂ͂��āA�̂��ɊC�l���ƌĂ��ꑰ���Z��ł��܂����B�ނ�͍q�C�p�ɏG�łĂ���A�}�C���ɂ���������̊C�l�����Z��ł������̂Ǝv���܂��B�}�C���C�v��A�ނ�͍ł��߂�������Y�������A���Ԃ���������O�㔼���ֈڏZ��]�V�Ȃ�����܂����B ���V�Ζ��_�Ɠ��q�Y���_ �×���芥���ɂ͓V�Ζ�(���܂̂ق�����)�_���A�B���ɂ͓��q�Y��(�Ђ������)�_�����J�肳��Ă��܂��B�Ñ�̒O��ɉ����āA���̓�_��c�_�Ƌ��ł���W�c������܂����B���ꂪ�C����(���܂ׂ̂�����)�Ɩ}�C�A(���������܂̂ނ炶)�ƌĂꂽ�l�B�ł��B�ނ�͒O����x�z����Z�p�ҏW�c�ł����B ���C�����Ɩ}�C�A �V�Ζ��_�Ɠ��q�Y���_(�����E�s�����䔄�_)��c�_�Ƌ��C�����́A�O�㕗�y�L�Ҏ[���ɂ͒��� ��(����)�삩�玒���Ă����l�ł����A�����͒O����x�z���Ă����Ñ㍋���ł����B�{�Îs�ɂ����Đ_��(���̂���)�́A��X�C�������{�i�߂Ă���_�Ђł����A���Ă͓��{�O�i�̈�ł���V�����ł����A�Đ_�Ђ̎Q���ɂ����Ȃ������Ƃ����܂�����A���̐��͂��ǂ�قǐ��܂������������f���܂��B����̖}�C�A�́A�p�\�̗��ɂđ�C�l�c�q�̖����ɕt���A�V���V�c���ʂɐs�͂��Ă��܂��B�@ |
|
| ���}�C���ٕ� �@ | |
|
���w�O�㕗�y�L�c㞁x�̋L��
�w�O�㕗�y�L�c㞁x�Ƃ́A�����I�ɍ��̖��߂ŒO�㍑����o�����n�����Ƃ������ׂ��u�O�㕗�y�L�v�̈ꕔ�ł���A���s�k����Ƃɓ`����Ă������̂��A�\�ܐ��I���ɒO�㍑��V�{�Đ_�Ђ̎Бm�E�q�C���M�ʂ������̂Ƃ���Ă��܂��B���̒��ɁA�}�C���Ɋւ���L��������܂��B �}�C���ҁB[�}�C����] ���́B�����c��������l�l�E�O���B�������O�E�ܗ�����B[�c�����̖���l����l�\�O���@��������O�\�ܗ�����Ɉʒu����] �l���F���C��V�哇��B[�l�ʊF�C�Ɉ͂܂ꂽ��̑哇�ł�����] ���ȑ��̖}�C�ҁB�̘V�`���B���́B[�}�C�Ə̂��鏊�Ȃ́@�̘V�̓`�ĞH���@��] ���V�����匊�����^���F������������n�V���B[ �V�������߂�ɓ���匊�����Ə��F���������̒n�ɓ���������] ���W�C�����ݔV�����V���B���}�͈Ȑ��듈�B[�C���̏����������W�߂����@�����}�Č͂�Ĉ�̓��ƂȂ���] �̉]�}�C��B[�̂ɖ}�C�Ɖ]��] �����B��N�O���Ȉ�B�n�k�O���s�߁B�������ב��C�B[��N�O���Ȉ�@�n�k���O�������@���̋��͈��ɂ��đ��C�ƂȂ���] �Q㘋����V���R����^���_��o�C��B[�Q�������̍��R����Ɨ��_�₪�C��ɏo�Ă���݂̂ł���] �����]�퐢���B�����j�������B[���ł͏퐢���@���͒j�������ƌĂ�Ă���] �����ݐ_�K�B���ՎҁB�V�Ζ��_�^���q�Y���_��B[�������K���݂�@�V�Ζ��_�Ɠ��q�Y���_���Ղ��Ă���] ���C�������}�C�A�����ȍ֑c�_��B[����͊C�������тɖ}�C�A���炪�֍Ղ�c�_�ł���] ���}�C���͌����H �u�}�C���`���͌㐢�̍��b�ł���B�v ���ꂪ���ŋ߂܂ł̃A�J�f�~�Y���̔F���ł����B�}�C�����C�v���錴���ƂȂ�����N(����701)�O���̑�n�k�́A�w�O�㕗�y�L�c㞁x��w�����{�L�x�ɋL�^���c���Ă��܂����A�n���w�I�ɂ͂��̗l�ȓV�ϒn�ق��N�������Ƃ͍l���ɂ������ɉ����A�w�O�㕗�y�L�c㞁x�ɂ͍������U����������������ł��B �Y��(������)�ɂ���V�l��(�����Ƃ���)�_�Ђ́A�V�Ζ��������J�肷��O����w�̌ÎЂŁA���Ă͉���������o�_�̋��t������Q�q�ɖK���������M����Ă��܂����B ������(Oshima)�������Ƃ���(Oitoshima)������������(Ohshiama) �u�}�C���`���͘V�l���_�Ђ̌��Еt���ׂ̈̑n��ł���B�v ���ꂪ�A�J�f�~�Y���̏펯�ł����B ���������u�펯�v ���a30�N��㔼�ɂȂ��āA���ė��̌Ǔ��ƌĂ�Ă������ߎs�̑�Y�����ɂ��悤�₭�C���t�������̖ڂ��������n�߂܂����B ���̉ے��ŁA�w�L��듪��(�䂤������Ƃ���)�x�ƌĂ��Ί펞��̖�肪��������܂����B����͍������1���N�O�̐Ί�ŁA���̍������Y�����ɐl���Z��ł������Ƃ���Ă��܂��B�Â��ď��a51�N�A��Y�����̎O�l(�݂͂�)�n��ŌÑ�̐����y�킪��������܂����B��̒����ɂ���ĎO�l�̐�����\�͂��Ȃ��K�͂Ȃ��̂ł���A�����y�킪���݂̊C�ݐ��Ɩw�Ǖς��Ȃ��ʒu���甭������鎖����A���Ȃ��Ƃ��ޗǎ���ɂ͌��݂Ƃقړ����C�ݐ����������Ă����������������܂����B�]���āA���N�Ԃɓ����C�v����قǂ̓V�ϒn�ق��������Ƃ͍l���ɂ���(��Ôg�ɂ���ĊC�ݐ��ɕω���������͂�)�A�}�C���̑��݂͂�͂肨�Ƃ��b���Ǝv���Ă��܂����B �Ƃ��낪�A��Y�����̑��̒n��Ŏ��X�ɌÑ㐻���̈�Ղ����������Ɏ���A�}�C���͂ɂ킩�ɋr���𗁂т邱�ƂɂȂ�܂��B�C�̖��Ɛ����͂悭���т��Ă��邱�Ƃ��S���̌Ñ㌤���̐��ʂ���킩���Ă��Ă���A�C�̖��Ƃ̊ւ���`���ɉ����ĐF�Z���c���Ă���}�C�������݂��Ă����\�����o�Ă�������ł��B ���w�����S���x�̋L�^ �吳4�N�Ɋ��s���ꂽ�w�����S���x�̌Òn�}�ɂ��ƁA�}�C���͑�Y�����ƑΊ݂̗R�ǐ쉺���悩��Ȃ鋽�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B����͊�����ŋ߂̔��@�������瓱���o���ꂽ�����ɍ��v�������(��Y�����ƗR�ǐ쉺����́A���ɑ����̐�����\����������Ă���)�ł���A���݂ł͂��ꂪ�ʐ��ƂȂ��Ă��܂��B ���}�C���Ǝu�y�� ���������̉����͍ŏ����疵��������Ă��܂����B�w�O�㕗�y�L�c㞁x�ɂ��A��Y�����̐����A���(����)�̒n�����u�y(���炭)���̒n���Ƃ��ďЉ��Ă��邩��ł��B �u�y���͖}�C���ƕ���ŊC���Ƃ̌��т��������n��ł����B�����ɂ͗���t�R���݂�A�R���ɂ͊}�ÕF(�����Ђ�)�_�Ɗ}�ÕP(�����Ђ�)�_�����J�肵���K�����݂����݂��܂����A���̓�_�͊C���̑c�_���ƌ����Ă��܂��B���̑����Ă̎u�y���ł��铌���ߒn��ɂ́A�q��R�̓V���_�ЁA�c��J�R���_�ЁA�����̌�c���_�ЁA���q�̕z���_�ЂȂǁA�C���䂩��̐_���J�����_�Ђ�����������܂��B�C���Ƃ̌��т��������Ƃ�������Y�������u�y���Ƃ���̂��}�C���Ƃ���̂��ł����A����͑�ϓ�����ł��B �������{���ɐ_��̐́A����������ɋ��𖼏���قǂ̑傫�ȓ�������A�n�k�ɂ���Đ��v���Ă��܂����Ȃ�A�����c�����Z���͖}�C������ł��߂��u�y���̉��ݕ��ɗ������� �\��������܂��B�����������Ȃ�A�{���u�y���̈ꕔ���}�C���ƍ�������Ă�����s�v�c�͂Ȃ��Ǝv���̂ł��������� ���Y����Ղ͉������H �Y��(����ɂイ)��Ղ́A���d��(��)�̕��߉Η͔��d���̌��݂ɐ旧���Ĕ��@���ꂽ��ՂŁA�ꕶ����`��������܂łɎ��镡����Ղł��B���̈�Ղ�5300�N�O�̒n�w����A����10�N�Ɋۖ؏M����������܂����B����0�D8���[�g���A���蒷8�`10���[�g���� �傫���́A�ꕶ����O���̂��̂Ƃ��Ă͍ő�E�ŌË��̋���Ȋۖ؏M�ŁA�O�m�q�s���\���\�ł� �����ł��낤�ƌ����Ă��܂��B ���ڂ��ׂ��͔��@���ꂽ�Ƃ��̏ł���A��i��������ꂽ�Ί_�̏�ɁA�M����Ɍ����č��ɖ��܂��Ă������ł��B ���̊ۖ؏M�́A�g���Ȃ��Ȃ�����͐M�̑ΏۂƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H ���{���I�ɂ́A���y��(�������̂�����)���瓌�ɍD����������ƕ������_���V�c���������v���������肪�o�Ă��܂��B ���̒��ʼn��y���́A�w���̓��̍��Ɋ��Ȋۖ؏M�ɏ���Ă��������̂�����x�Ƙb���A��������_���V�c�́A�w������`������(�ɂ��͂�Ђ݂̂���)�ł��낤�x�ƌ�����Ƃ���Ă��܂��B �����`���������A�V�ƍ��ƕF�V�Ζ������`������(���܂Ă邭�ɂĂ�Ђ��ق����肭�����܂ɂ��͂�Ђ݂̂���)�ł���Ȃ�A����͊C���̑c�_�ł���F�Ζ����̖����ł��B �Y����Ղ���o�y�����ۖ؏M���A�w���Ȋۖ؏M�x�������\���͂Ȃ��ł��傤���H �Y���n��́A���Ă͑�O�����̏����ł���A���O���ƋL���܂������A�����Ȍ�͔g���v����(�̂��ɐ�Α��Ɖ���)�̏����ƂȂ�܂����B ���{���I�́A�V���V�c�̑��ʂ̍ۂɗp�ӂ��ꂽ���(�另��̋V�̍ہA���ɐH�ׂ�H��)�̋��[�n�́A�O�g���d���S(�����S�̌��Ǝv����)�Ƃ��Ă���A�]�ˎ���̏����ł���c�ӕ{�u�́A����͐�Α��̎��ł���Ƃ��Ă��܂��B�������Ȃ����Α��͖{���k�n�̖R���������ł���A��̍k�n�ƌ����Έ�ʂɂ͉Y��(���O��)�̎����w���܂��B ���̋��[�n�͗��O���������\���͂Ȃ��ł��傤���H �V���V�c�͑��ʑO�ɂ͑�C�l�c�q(���T�����܂݂̂�)�𖼏���Ă��܂����B���̖��͗{��W�ł������}�C�A(���T�����܂̂ނ炶)�ɗR��������̂Ƃ���Ă��܂��B�}�C�A�͊C���̈�h�ł���A�V���V�c���ʂ̑���J�҂ł��B ���̋��[�n�ɒO�g�������S���I�ꂽ�̂́A�C���䂩��̒n����������ł͂Ȃ��ł��傤���H �j�M�n���q�A�C���A�O���A�V���饥��������Ƃ�����\�����A�Y����Ղŏd�Ȃ荇�����Ƃ��Ă��܂��B�@ |
|
| ���O��̎��Г`���@ | |
|
�������_�Ђ̓`��
�������ਐ_�Ђ̂��鋞�s�{���O��s��R��(�����S��R��)�Ƃ����A�O�㕗�y�L�ɋL�ڂ��ꂽ���{�ŌẨH�ߓ`�����L���ł����A�n����R���ɂ͒O�㕗�y�L�Ƃ͏���������H�ߓ`�����c���Ă���l�ł��B �������_�Ђ̓V���`�� �ނ����ނ����䎡(�Ђ�)�̎R�̒����߂��ɑ傫�Ȕ������r������A���̒r�ɔ��l�̓V���������~��Đ����т����Ă��܂����B ��������Ă����O�E�q��(����˂�)�Ƃ������̎�l���A�@�ꖇ�̉H�߂��B���Ă��܂��܂������߂ɁA�V���̂ЂƂ�͓V�ɋA��Ȃ��Ȃ� �Ă��܂��܂����B�V���͎O�E�q��ƈꏏ�ɕ�炷���ƂɂȂ�A�O�l�̔������������������܂����B �V���͔_�ƁA�{�\�A�@�D��A�肪���ŁA�O�E�q��̉Ƃ͂��Ƃ��䎡�̗��͂�������L���ɂȂ�܂������A�V�������ɑς����˂��V���͎O�E�q��̗��璆�ɁA�u�����l�͖���������q��ŏo�����Ă����́H�v�Ɩ��B�ɐq�˂܂����B���B�͉Ƃ̑单�����w�����܂����B�单���̌��ɉB���Ă������H�߂��������V���́A�H�߂�g�ɒ�����ƁA�삯�߂����O�E�q��Ɂu���������ɉ�܂��傤�v�Ɖ]���c���ēV�ɋA���Ă����܂����B ���������̗l�q���f���Ă����V�̎S(���܂̂��Ⴍ)���u�w���������ɉ�܂��傤�x�ƌ����Ă����v�ƎO�E�q��ɓ`���܂����B��N�Ɉ�x������Ȃ��Ǝv�����O�E�q��́A�V�����c���Ă������[��(�䂤����)�̎���Ɏ����āA�V�����V�ɋA�������Ƃ�Q���߂���ł��܂����B ����Ƃǂ��ł��傤�B�[��͓V�Ɍ������Ă���L�юn�߂܂����B���̖���o���Ă����ΓV�ɍs���邩���m��Ȃ��Ǝv�����O�E�q��́A�[��̖��������ɓo���Ă����A���ɓV��ɒH�蒅���܂����B�V��ŎO�E�q��͓V���ɉ���Ƃ��ł��܂����B �V��œV���ƕ�炵�����O�E�q��́A�V��ɓV��E�ŕ�炵�����Ɗ肢�o�܂����B�V��͓V�̐�ւ̉ˋ��������ɏo���A���������˂���ꂽ��ꏏ�ɓV��E�ŕ�炷���Ƃ�F�߂�Ƃ��܂����B �d���𐿂��������ۂɓV��ƁA������������܂ł͓V�����v���o���Ȃ��Ɩ��Ă����O�E�q��ł������A�V���������̂��܂�������̖�j���Ă��܂��܂��B��j�����r�[�V�̐�͑�^���ɂȂ��Ă��܂��A�O�E�q��͉��E�֗�����Ă��܂��܂����B �V��ňꏏ�ɕ�炷��������Ȃ������O�E�q��ƓV���ł����A���N���������̖�ɂ͓V��������߂����ƂȂ��āA�O�E�q��ƎO�l�̖��ɉ�ɂ���Ă��邻���ł��B ���݁A���O��s��R���̈鍻(�����Ȃ�)�R�̘[�ɂ́A�V���̖����J�����Ƃ���鉳���_�Ђ�����܂��B������̐_�Ђɂ��Q�肷��ƁA���������̎q�������邻���ł��B |
|
|
���F�ǐ_�ЂƗ��{�`��
�Y�����Y�̕���͓��{�e�n�ɓ`�����c���Ă��邻���ł����A���s�{�^�ӌS�ɍ����ɓ`���`���͓��{�ŌÂ̂��̂ŁA�O�㕗�y�L�݂̂Ȃ炸���{���I�▜�t�W�ɂ��L�ڂ���Ă��邻���ł��B�@ ���Y���q�̓`�� ���͐l�c��\���Y���V�c�̌���\��N���������A���n�̋��t�Y���q(����̂��܂�)�͉��ɏo�Ēނ�����Ă��܂������A�s�v�c�Ȃ��ƂɎO���O�ӈ�C�̋����ނ�܂���ł����B���߂ċA�낤�ƊƂ��グ��Ƃ����ɌܐF�̑傫�ȋT������܂����B �T�߂邤���ɖ���ɂ��Ă��܂����Y���q���ڊo�߂�ƁA�T�͔��������P�̎p�ɕς���Ă��܂����B��l�͏퐢�̍�(���{��)�֕����y�������X���߂����܂������A���S�̂����Y���q�͎O�\�O��~�a�V�c�̌��ɂȂ��Č̋��Ɋ҂��ė��܂����B �퐢�̍��֕����Ă���O�S�l�\���N���o�߂��Ă��܂����B �F�ǐ_��(�Y���_��)�́A�Y���q�̊�杂�m�����~�a�V�c������@�(���̂̂ނ�܂����������ł��̂����ɏo�����Ƃ͎v��Ȃ�����(��))�n�ɔh�����A�Y���q��喾�_�Ƃ��č��J���邽�߂ɋ{�a�c�����������n�܂�Ƃ���Ă��܂��B �F�ǐ_�Ђ̗R�����ɂ́A�Y���q�͓��������̑c��ɓ�����A�J���V�c�̌���ł���A���c�͌��ǖ��̎q���œ��n�̗̎�ł���ƋL����Ă��܂��B�܂��ɋ����ׂ��`���ł����A�ٕ��ɂ͍X�ɋ����ׂ��`��������܂��B �퐢�̍��Ƃ͊���(�}�C��)�̎��ł���Ƃ����̂ł��B�����ƌB���̖��O�́w���ƌB���c���ď퐢�Ɏ���x�ɗR������̂ł���A�t�߂̊C��͗��{�C�Ƃ��Ă�Ă��܂��B �`���𑍂čm�肷��Ȃ�A�Y���q�����P�Ə퐢�ɗ��������̂͐���478�N�A�}�C�����C�v�����̂�����701�N�A�퐢����ɍ��̒n�Ɋ҂��Ă����̂�����825�N�ł�����A�Y���q�͖}�C������ł���l�����Ă������ƂɂȂ�̂ł��B |
|
|
����O���_�Ђ͉��̎R���{�ɂȂ����̂�
���s�{���ߎs����O��(�����ɂイ)�ɂ����O���_�Ђ́A���̔������͑�Y������Ə܂����_�Ђł��B�ߗׂ̑��̐_�Ђ������ݔ����_��V�_���������Ă���̂ɑ��āA��O���_�Ђ݂͓̂��g��_���������Ă��܂��B����ɂ͐[������̂ł��B ���r�Ԃ�_�̓`�� ���ߘp�̓��]�̓����Ɉʒu�����O�����ɂ́A�w�{����x�ƌĂ���O���_�ЂƂ����ЂƂA�w���̋{����x�ƌĂ�����Ђ�����܂��B �F��_�Ђł��B �쌱���炽���Ȃ�F��_�Ђ͌��݂ł����s���̘e�ɒ������Ă��܂����A�����͎R�̒��ɒ������Ă����̂������ł��B�F��_�Ђ̐_�l�͑�ςɋC�ʂ������A���̕s�h�������ċ����܂���ł����B��������D������R�̒��ɂ���F��_�Ђ͂悭�����������ł����A�D��肪�s�h���͂��炭(�m�ォ��R�Ɍ������ď��ւ����铙)�ƁA�����ǂ���ɑD�߂Ă��܂����肵�������ł��B���������Ƃɂ��̎R�͍q�C��̖ڈ�ɂȂ�R�ŁA��Y�����ɋ߂Â��ŏ��Ɍ�����R�ł����B����ł͂�������p��������ɂ������܂���B ���̏O�͌F��_�Ђ��R����~�낵�āA�C�������Ȃ��Ƃ���ɉ��߂ĎЂ낤�Ƃ��܂����B�������쌱���炽���ɂ��ċC�ʂ̍����F��_�Ђ̐_�l�̂��ƁA�ЂƂԈႦ�Α����ł�ł��܂������m��܂���B�����ő��l�͈�v���Ă��܂����B�ߍ]�̍�������g��_���������āA�F��_�Ђ̐_�ɑJ�{������Ė�����̂ł��B �F��_�Ђ̐_�͑f���j��(�����̂��݂̂���)�ł���A�ߍ]�̍����犩�����ꂽ���g��_�͑�R��_(������܂����̂���)�A�܂�F��_�Ђ̐_�l�̑��_���܂ł��B���̗��݂��ɂł��Ȃ��͖̂����_�������������ƌ������Ƃł��B ���āA���ݓ��g��_�̕���́A��O���_�Ђ̎�Ր_�Ƃ����J���Ă��܂����A���͓̂��g�_�ЎႵ���͎R���{�Ƃ͂Ȃ��Ă��炸(�����̊z�ɂ͎R���{�ƍ��܂�Ă��邪����)��O���_�Ђ̂܂܂ł��B�����炭�͓��g��_�����������ۂɁA��O���_�Ђ̎����ނ����_���������炾�Ǝv���܂��B���̐_�͌��݂ł���O���_�Ж{�a�������ĉE�����K���J���Ă��܂��B ���݂ł͂������O����������Ȃ��Ȃ����K�̎�ͥ��� �_��̋C�z�������I�ł��鎖����A�O���s�䔄��(�ɂ��Ђ߂݂̂���)�A�Ⴕ����㦏ۏ���(�݂��͂߂݂̂���)�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B |
|
|
�����_�Ђ̍Ր_
���s�{���ߎs�̗R�ǐ쉈�ݕ��ɁA�u���_�Ёv�Ƃ������̐_�Ђ��������Ă��܂��B �������S(���݂̋��s�{���ߎs�y�щ����S��]��)�ł͗B�ꉄ�쎮���_��Ђ̊i�t�����Ȃ���Ă���A�O�㚠���ł��Đ_�ЂɎ����`���Ɗi����������_��(���ɒO��œ��i�̐_�Ђ͒O���m�{�̑�{�̐_�ЁE�咎�_�ЁE�����_��)�ł��B���̂��ߕ��ߎs���Ɍ�������_�Ђ́A�قڗ�O�Ȃ����_�Ђ�ێЂƂ��Ă��J�肵�Ă��܂��B�@ ���_�Ђ̎�Ր_�͕ېH�_�ł���A�T��Ɍ܌��_(���U�y�_�E�e���˒q�_�E���R�P�_�E���R�F�_�E㦏ې��_)�����J���Ă���Ƃ���Ă��܂����A�������{���ҏW�����u���I�_�����v�ɂ́A�Ր_�����ɂȂ��Ă��܂��B�܂�A�{���̍Ր_�͂悭������Ȃ��̂ł��B ���������痈���_�̓`�� �Г`�ɂ��A���@�V�c�̌��N�O���ɁA�R�ǐ��̋��t��X�l�Y�������c��ł����Ƃ���ɁA�w���F�̍��ɏ��A�E��Ɍ܍��̎�A����Ɏ\���g�����_�x���쉺���猻��āA��X�l�Y�Ɂu���n�ɒ����������̂ŎГa�c����v�Ƒ��邵���̂����_�Ђ̋N���肾�����ł��B �w���F�̍��ɏ��A�E��Ɍ܍��̎�A����Ɏ\���g�����_�x �͕ېH�_��A�z�����܂����A�O��̒n�ɉ����āw�܍��ƌK�\�̎�����_�x�Ƃ͖{���A�L���_���w���܂��B���_�Ђ̎�Ր_�͂������߁u�L���ב喾�_�v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���H �Ȃ��A���́w���F�̍��ɏ��A�E��Ɍ܍��̎�A����Ɏ\���g�����_�x �́A���{�C�ɕ����Ԋ������C��n��A�������Ă���Ă��������ł��B����������F�̍��ɏ���Ă���Ă����_�̓`���͑��_�Ђ�M���ɒO�g�E�O��̗R�ǐ여��ɑ����A�����ɍ���߂�����H�ׂ��肷�邱�Ƃ����߂Ă���W��������悤�ł��B �����͊C�v�����}�C���̎c�[�Ƃ���Ă���A�Đ_�Ў�Ր_�̕F�Ζ���(���� �V�Ζ��� �V�ƍ��ƕF�V�Ζ������`������)���~�Ղ����n�Ƃ���Ă��܂��B���_�Ђ̓`���𑍂Ď����̂Ȃ�A�L���_���F�Ζ����̐}�������藧�l�ɂ��v���܂��������� ���ɂ���×����犥���͓Ă��M�̑Ώۂł������������͊m���ȗl�ł��B |
|
|
��������(�܂̂��ł�) �t�R�́A��̎R�̓����ɓ�̕�������B���ꂼ��ɖ��_���݂�A�t�̐_�Ɩ��t���Ă���B���̓��ɍՂ�_�͎ዷ�F�_�E�ዷ�P�_�̓���B���̐��ɍՂ�_�͊}�ÕF(�����Ђ�)�_�E�}�ÕP(�����Ђ�)�_�̓���ł���B���ꂪ�ዷ���ƒO�㍑�̋��ł���A�}�ÕF�_�E�}�ÕP�_�͒O�g�����ł���C���������̑c��ł���B����Ƃ������������A�H�ɂȂ��Ă��F���ς��Ȃ��B�@�@�`�O�㕗�y�L�c㞁E�u�y�����` ���s�{�ƕ��䌧�̓�{���Ɍׂ��Ă��т���t�R(�W��699��)�́A�×���萹�Ȃ�R�Ƃ��Đ��߂��Ă��܂����B���̎R�͕��䌧���l�����璭�߂�A�ӂ��̕����d�Ȃ��ďG��ȎO�p���Ɍ����܂�(�ʖ��E�ዷ�y�m)���A���s�{���ߎs���璭�߂��Ȃ�A�ΎR�ł��������Â̎p���̂܂܂ɂӂ��̕������鎖���o���܂��B �Ñ���_�X���������A�C����Ƃ��Ă�����y�������̎R�̒����ɁA�������\��ԗ��E������(�܂̂��ł�)�͍݂�܂��B�������͔n���ϐ�����F��{���Ƃ���S���ł���ϒ����������ŁA�����V�c���莛�̊i�����ւ�܂��B ����R�� ���Ɍc�_�N���A���̑m�A�Ќ���l�����R�̓�̕��]��ŁA�����ɎR�e�̎����n���R�Ƃ����쌱�̂���R�����������Ƃ�z�N���ꂽ�B�o�R�����Ƃ���A�ʂ��邩�ȏ��̑���̉��ɔn���ω����������A���������ꂽ�̂��A�a�����N(���Z���N)�Ɠ`������B�{�V�N�Ԃɂ́A���ꍑ���R����א���t�����R���A�����匠�����R�����J�����B���ꂪ�A���݂̉��̉@�ł���B ���i��N(�����N)�ɂ́A���H�V�c�A������@�̍s�K�[������A���̎l��������A���V�͘Z�\�܂𐔂��Ĕɉh�����B���n���B��̍���̕�����A������@�̔O�����ł������Ƃ�����B���̌�D�c���̕��ɂ���Ĉ�R���Ƃ��Ƃ��D���ɋA�������A�V����N(��ܔ���N)�א�H�Ă̎�ɂ���ĕ������݁A���ɉƂ̏C�z�����o�āA���ۏ\�ܔN(�ꎵ�O�Z�N)�q��p���ɂ���āA�Q�������̎p�𐮂���Ɏ������B�����́A�������\��ԎD���ŁA�{���n���ϐ����́A�O�\���ꒆ�B��̊ω����ł���A�_�k�̎�蕧�Ƃ��āA�����͋��n�{�Y�A�Ԕn��ʁA�X�ɂ͋��n�Ɉ��ސM���L���W�߂Ă���B ���n���ω��̓`�� ���V�c�̌��A�ዷ���_��Y(���݂̕��䌧��ьS���l��)�̋��t�ɏt���@���v�Ȃ�҂����܂����B�o�����ɗ��ɑ������ĊC�ɓ����o���ꂽ�@���v�́A���ɒ͂܂��ĉ��Ƃ��_��Y�̊C�݂ɖ߂鎖���ł��܂����B����Ƃǂ��ł��傤�B���͔n�Ɏp��ς��đ��苎���čs���܂����B �s�v�c�Ɏv�����@���v�����l�Ƌ��ɔn���̂��Ƃ�H�����Ƃ���A�t�R�̏������ɂ܂ő����Ă���A�����ŏ@���v���͂܂��Ă�������������܂����B�������������̖{���ł���n���ϐ�����F�ɏ�����ꂽ����������@���v�͕���ɓ���A���ɔn���ϐ������Ċ��ӂ̋F��𑱂��������ł��B ���̊�杂͎��̒���ɂ܂ŕ������A�����������̑b�ƂȂ����Ɠ`�����Ă��܂��B ���C�l�̍��� �t�R�̐����̕����J���Ă���}�ÕF�_�E�}�ÕP�_�̓�_���C�����䂩��̐_�ł��鎖�͑O�q�����Ƃ���ł����A�����̕����J���Ă���ዷ�F�_�E�ዷ�P�_�̓�_�ɂ��Ă͂��ꂼ��F�ΉΏo�����E�L�ʕP�ɂȂ��炦���������܂��B���̎����́A�t�R���Ñ�̊C���ʂɂƂ��āA��Ϗd�v�Ȗ������ʂ����Ă��������܂��B ���������̎O�䎛(���ꌧ��Îs)�̑m�A�s���E�o���̏���L�^�ɂ́A�������̊��ɂ��āw�C�l��l�x�ƋL����Ă��邻���ł��B���̋L�^�́A�t�R�ƊC�l�Ƃ̊W��@���ɕ����G�s�\�[�h�ł͂Ȃ��ł��傤���H �������\��Ԑt�R��������r�� ���̂��݂� ������ւʂ��� �������� ���Ƃ��������� �܂̂��̂Ă� |
|
|
�����H��(���˂�)
���s�{���ߎs�̑�Y�����ɂ́A�����Ƃ��ĂԂׂ��R���ӂ�����܂��B�ЂƂ͓���Y�ɂ����R(�W��550��)�ŁA�����ЂƂ͐���Y�ɂ��鑽�H�R(�W��556��)�ł��B������t��O�\�ԎD���ł��鑽�H��(���˂�)�́A���H�R�̒����Ɉʒu���܂��B���ߎs���ŌÂ̎��ŁA��J��͐������q�ٕ̈��E���C�q(�܂낱)�e���A�p���V�c���菊�̊i�����������ł��B �����C�q�e���̎���t�`�� �p���V�c�̌��A�O�㚠�͎瑑�O�ブ��(���݂̑�]�R)�ɁA�p��(������)�E�y��(���邠��)�A�y�F(������)�̎O�S����̂Ƃ��鑽���̋S�����݁A�O��͂܂�Ŗ����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B ����͋S�����ׂ��A�m�E�����̖��C�q�e����叫�R�Ƃ��銯�R�����킷���Ɍ����A��������C�q�e���͈ꖜ�Y����Ȃ��R�𗦂��ĎO�ブ�Ԃ֍U�ߓ���܂������A�S�̗d�p�ɂ͑S�������������A�����������܂����B ���̌������ȂċS���ʂ������ƍl�����e���́A���玵�̖̂�t�@������A�u�������S���ʂ������Ȃ�A���̖�t�@�������J���ĒO��Ɏ������J���܂��v�ƋF������܂����B����Ƃǂ��ł��傤�B�z�ɋ���t����������������܂����B���̔�������擪�ɎO�ブ�Ԃ֍U�ߓ������Ƃ���A���̌��ŋS�͗d�͂������A���R�͖����S���ʂ��������o���܂����B ���ӂ̈ӂ����߂āA�ʂ�e���́A�O��ɖ�t�@���������{���Ƃ��鎵�̎������J���ɂȂ�܂����B �����A�O��ɂ͎��\�����ȏ�ɖ��C�q�e���ɂ܂��`�����c���Ă���A����t�̎����咣���鎛�@���������ȏ゠��܂����A���H�����N�ɂ��ƈȉ��̒ʂ�ł��B ��A���x���E�{��(�^�Ӗ쒬) ��A�͎瑑�E������(���m�R�s��]��) �O�A�|��S�E������(���O��s�O�㒬) �l�A�|��S�E�_�{��(���O��s�O�㒬) �܁A�a�J���E���y��(���O��s��h��) �Z�A�h�쑑�E���莛(�{�Îs) ���A���v���E���H��(���ߎs) ���H���Ɩ��C�q�e�������т�����̂Ƃ��Ă����ЂƂA�w�͂��̂͂���x������܂��B����͑��H���̑n�����ɁA���C�q�e�����[�̕�������^�����Ƃ̈���ꂪ����A���̑�ő���ꂽ���ŁA�������N(�ꔪ��l)�ɖ{�����Č����ꂽ�Ƃ����A��Ɏc���ꌻ�݂Ɏ���܂��B ���������̕�� ���H���̐m������ɂ݂��������Ă��������͎m���͍����O�E�܃��[�g��������{���w�̋���Ȃ��̂ŁA���q�����̌c�h�̕��t�ɂ����̂ƌ����܂��B�͎m���́A���a�\���N(��㔪�O)���C���Ɣ����قł̓W���̂��߂ɁA�i�炭�����𗣂�Ă��܂������A�����ܔN(����O)�ɂ悤�₭���A�肪�����܂����B�������Ȃ��獑�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��邽�߂ɐm����ɖ߂鎖�͏o�����A���݂͑��H���̕a�Ɉ��u����Ă��܂��B ���ߋ��ƌ��� �Òn�}�ɂ��ƁA���đ��H���ɂ͑��d���Ⓔ�g�傪����A�Q���͘[�̕������牄�X�Ƒ����Ă��������킩��܂��B���H�����͂��ߎ��̖�t�����������Ă����t�@�����͑��ĕ������ł���A�e���̎���ł���E���P����ɂ܂ők���i�ł͂Ȃ��Ƃ̎��ł����A���H���́A�`���ɍʂ���ɑ��邾���̗������ɂ߂����@�������̂ł��B ������t��O�\���Ή��R���H����r�� �����̂�Ɂ@�܂��邽�˂́@�������łā@�̂�̂͂Ȃ����@�͂邼���ꂵ���@ |
|
| ���O�㌳�ɐ��`���@ | |
|
���f�r���������V�Ƒ�_
���͐��_�V�c�̌��A���{�����ɉu�a���嗬�s���A�����̔��������S����قǂ̖҈Ђ�U�邢�܂����B���Ԃ�J�����V�c�́A���[�ɓV�_�n�_�ɋF������ ���ɂ�������炸�A���̐����͈���Ɏ~�܂�܂���ł����B ���̍�����A�{���ō��J���Ă���V�Ƒ�_(�A�}�e���X�I�T�~�J�~)�Ƙ`�嚠���_(���}�g�I�T�N�j�^�}�m�J�~)�̕s���ɂ����̂� �v�����ꂽ�V�c�́A�V�Ƒ�_���c���L�L���P��(�g���X�L�C���q���m�~�R�g)�ɑ������J�点�A�`�嚠���_���s�钷���s�h�H(�C�`�V�m�i�K�I�`�m�X�N�l)�ɑ������J�点�A�肢�̌����M����Ȃ��Ă��鎖�����������啨��_(�I�T���m�k�V�m�J�~)�c�c���q ��(�I�T�^�^�l�R�m�~�R�g)�ɑ������J�点���Ƃ���A�悤�₭�u�a�͎��܂�܂����B ���̈ꌏ�ȗ��A�`�嚠���_�͘`��(���}�g�m�N�j)�̑�a(�I�T���}�g)�_�ЂɁA�啨��_�͘`���̑�_(�I�T�~��)�_�Ђɂč��J����邱�ƂɂȂ�̂ł����A�`���̊}�D�W(�J�T�k�C����)���J��ꂽ�V�Ƒ�_�́A����Ȍ��Z�\�N�̍Ό���v���ē�\�܉���J�{���J��Ԃ� �A�ŏI�I�Ɉɐ����̌\���̂قƂ�ɒ������邱�ƂɂȂ�܂��B �V�Ƒ�_���_�{(�ɐ��_�{�𐳂����ď̂���ꍇ�A�u�ɐ��v�͕t���Ȃ�)�̓��{�ɒ�������ȑO�ɗ������������A���ɐ��ƌĂт܂��B ���c���E�L�L���P���Ƙ`�P�� �V�Ƒ�_�̏��K��͉��L�̒ʂ�ł��B �V�Ƒ�_���K�n�ꗗ(�`�P�����I�ɂ��) ��A�` ���@�}�D�W ��A�A�g�T�@�g���{ �O�A�` ���@�ɓ����u�{�{ �l�A�ؔT���@�ދv���_�{ �܁A�g�����@�����_�{ �Z�A�` ���@�\�a�T�䎺��㊯ ���A��a���@�����H�u��{ ���A��a���@���X�g���{ ��A�ɉꍑ�@�B�s��{ �\�A�ɉꍑ�@����{ �\��A�ɉꍑ�@���s���b�{ �\��A�W�C���@�b���_�{ �\�O�A�W�C���@��c�{ �\�l�A���Z���@�ɋv�lj͋{ �\�܁A�������@�����{ �\�Z�A�ɐ����@�K�����{ �\���A�ɐ����@�ދ�g�u�E�R�{ �\���A�ɐ����@�����������Д�{ �\��A�ɐ����@�і썂�{ ��\�A�ɐ����@���X���]�{ ���A�ɐ����@�ɑh�{ ���A�ɐ����@��͔V�댴�{ ��O�A�ɐ����@��c�{ ��l�A�ɐ����@�Ɠc�c��{ ��܁A�ɐ����@�\��{(�����̑�_�{) �V�Ƒ�_�͓����c���L�L���P��������(�~�c�G�V��)�Ƃ��Ċe�n�����K���Ă��܂������A�L�L���P�����V�N�ɂȂ�ɋy��Ō�����c���`�P��(���}�g�q���m�~�R�g)�Ɍ�サ�܂����B�`���A�\�a�T�䎺���{(���E�O�֎R�R�����H)�܂ł͖L�L���P�����A�Ȍ�͘`�P�����V�Ƒ�_�̌���ƂȂ��ď��������K���܂����B ���A�g�T�g���{ �V�Ƒ�_�̑J�{�`�����A��a����̒n���z�������`���������̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��錤���҂����܂��B�Ȃ�قǒA�g�E�I�B�E�g���E�ɉ�E�ߍ]�E�����E�ɐ��͖{���C�l���̐��͉��ł���A�x�z��Ղ��ł߂��Ŗڂ̏��ᎂ��������Ƃł��傤�B �`���̊}�D�W���o�������V�Ƒ�_���ŏ��Ɍ��������̂��A�g�T�g���{�ł����B �A�g�Ƃ́A�O�g�̎��ł��B �O�g���́A�����O�N�ɍ��̒��S�ł������k�܌S(�F��A�|��A�O�g�A�^�ӁA����)����������A�V���ɒO�� ���ƂȂ�܂����B����͒}�����}�O�E�}��A�g�������O�E�����E����ƕ������ꂽ�̂Ƃ͌`���Ⴂ�A�O�g�����̂܂c������ŒO�g�̒��S����O��(�^�j�n�m�~�`�m�V��)�Ƃ����̂ł�����A�א��҂ɉ��炩�̍l�����������̂ł��傤�B �܂��A�`���o�������V�Ƒ�_���ŏ��ɒA�g�����������Ƃɂ����ڂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�ߗׂ̏����������u���Ă��A�^����Ɍ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����R�����݂����Ǝv���邩��ł��B �A�g�T�g���{�́A�O��n���ɍ݂����͂��ł��B�������A�g���{����̉����������̂��������ɂ͂����肵�܂���B�L�͂Ȕ��n���������݂��邩��ł��B �`���̋g���{�ɔ�肳���_�Ђ́A�ȉ��̎O�����ł��B ���Đ_�� �_��̐̂ƌ����鉓����ォ��A���̉��{�̒n�^���䌴�ə��{(���T�m�~��)�Ƃ��\���ĖL���_��������ɂȂ��Ă��܂������A���̌�R���̂ɐ��_�V�c�̌��ɓV�Ƒ�_����a���}�D�W�����J���ɂȂ�A�Ȍ�l�N�Ԍ�����ɂȂ�܂����B�Đ_��(�R�m�W���W��)�̖��̂́A�_��ɕF�Ζ������đD�ɏ���ė��{�ɍs���ꂽ�̎��Ɉ��ޖ��̂ł���A�u�āv����Âɂ����āu�R�v�Ɣ�������������u�R�m�W���W���v�Ə̂��܂��B�Đ_�Ђ̎Њi�́A�ޗǒ��Ȍ�͒O�㚠��V�{�ɗ��A���쎮�����_��Ђɂ��ĎR�A�����������B��̊�����Ђł���A�_�K�͍ŏI�I�ɐ���ʂɂ܂łȂ�܂����B�����̐��ɂ����Ă͍������Ђɗ��܂������A������Џ��i�^���̖��A���a20�N3��25���A���̒鍑�c��͖����v�ŏ��i����������j������܂��B ( �`���ƈٕ� / �u�Ė��_�j���C�������V���n�}(�ʏ́E�C�����n�})�v�́A�C�����̎n�c�F�Ζ������畽�������Ɏ���܂ł̓��喼�ƍ݈ʔN���������L�������̂ł����A����͌���������{�ŌÂ̌n�}�ł���A�n�}�Ƃ��Ă͗B�ꍑ��Ɏw�肳��Ă��܂��B�u�C�����`�����A���Ë��E粒Ë��v�́A�C���������]�N�ɏ��Ė���̐_��Ƃ��ē`�����Ă��������ŁA���Ë��͌㊿����A粒Ë��Ɏ����Ă͑O������̂��̂ł���A�`����(�Õ��Ȃǂ���@��N���������łȂ�)�ł���Ƃ̊w�p�I�Ӓ���Ă��܂��B�����Q���ɒ������鍝���͊��q����̍�Ƃ����Ă���A���̏d�v�������Ɏw�肳��Ă��܂��B���̍����́A���܂�̏o���̗ǂ��̂ɍ����h���A��Ȗ���Đ_�Ђ��o���Ă͓V������p�j���A�l�X���������Ă����̂������ł��B�`���̍����E�〈�d���Y�ɑގ�����Ĉȗ��_�i���h���A�_�Ў��̔C�ɐ����o���Ă���Ƃ̎��ł��B) ���c��_�� �`���ɂ��A��\�㐒�_�V�c�O�\��N(����I���O�\��N)�ɁA�u�ʂɑ�{�n�����ߒ����J��v�Ƃ̍c��_�̌䋳���ɏ]���A�i�v�ɂ��J�肷�鐹�n�����߁A����܂ŕ�ւ���Ă����`�̊}�D�W(���ޗnj�����s)���o�䂳�ꂽ�̂��A���܂������琔�\�N�O�̗y���Ȑ̂ł������B�����āA�܂��A�g(�O�g)��J�K�A���̌�R���ɂ�蓖�Ђ��n�����ꂽ�Ɠ`�����Ă���B�c��_�́A�l�N�̂̂��A��_�ւ����Ƃǂ߂Ȃ���čĂј`�ւ�������ɂȂ�A�������o�āA���_�V�c��\�Z�N(����I���O�l�N)�ɁA�ɐ��̌\����̐��n(���܂̈ɐ��̐_�{)�ɏ�i���ɂ����܂�ɂȂ����B�������A�V�ƍc��_�̌�_�������炤���߂̐��h�҂́A���������ē��Ђ���{�̌��̋{�Ƃ��āu���ɐ����{�v���邢�́u���ɐ��c��_�{�v�u��_�{����v�ȂǂƌĂѐe���݁A���Ɏ���������̓Ă��M�������Ă���B ( �`���ƈٕ� / �c��_�Ђ̎Гa�������č����ɁA�u�����̐��v�ƌĂ���{�̐��̋�������܂��B������N�ɋ߂��Ɛ��肳��邱�̋����ɁA���N�ߕ��̖�̉N�O���A���_�����ɖ�������Ƃ����ɂ���Ă���Ƃ̓`�����炱�̖�������܂��B�c�O�Ȃ��痴���̐��́A���Z��N�ɐM�҂̓����̉���ЂɌ�����ꖳ�S�Ȏp�ɂȂ��Ă��܂��܂������A����ł��͂�邱�ƂȂ����݂Ɏ����Ă��܂��B���_�`���ƊC�l���Ƃ̊֘A�͗L���҂���Ɏw�E����Ƃ���ł���A�������Ђɂ͎O���_��(�@���O���_���J��)���Â��������Ă��鎖������A�ߔN�Ñ�j�W�҂̒��ڂ��W�߂Ă��܂��B��̒���������Ă����Ɉَ�ٗl�Ȏp�̋����ڂɕt���܂����A����́u�������̎��v�ƌĂ�Ă�����ł��B�l�Ԃ̕a�C���z������Ă����쌱���炽���Ȏ��Ȃ̂������ł��B�Q���ɂ��т���O�{�̐�(��������͈̂�{�̂�)�́u���C�q�e������A���̐��v�ƌĂ�Ă��܂��B�y�w偑ގ��ɒO��֔h�����ꂽ���C�q�e��������A���������Ƃ���Ă��܂��B) ���|��_�� �Г`�ɂ��A���m�V�c�Ɏd�����O�g�̑匧��R�闝�̖��E�|��Q���A�ӔN�|��ɖ߂�V�ƍc��_���J�����̂��|��_�Ђ̎n�܂肾�Ɖ]���܂��B�|��_�Ђ͒O���̌ÎЂ��������Ă���A�O��̌��ɐ��`���͒|��_�Ђ����������̂ɂ̂��ɑn�삳�ꂽ���̂��Ƃ��Ă��܂��B�������Ȃ���ʏ팳�ɐ��̖��������鎖�͂Ȃ��A�n���̐l�B����u�(����)����v�ƌĂѐe���܂�Ă��܂��B ( �`�����̑� / �|��_�Ђ͋��s�{�|��S�O�㒬�Ɉʒu���A����1�L�����[�g���l���ɋy�ԛ�����ł��闧��A�O��n���ő�̌Õ��ł���_���R�Õ�(�S��190���[�g��)�A�����p���J�����Ƃ����O�㔼���Ŗk�̓Ɨ���ł���˒x�����R(����������܁@�W��540���[�g��)�A�Ԑl�c�@�`�������ɓ`����Ԑl(������)���Ɉ͂܂��`�Œ������Ă��܂��B) �@ |
|
| �����q�����`���@ | |
|
�y�w偂Ƃ����̂͌��������Ƃ��A��Z���ł���Ƃ������Ă��܂����A��a���Ƃ̑������������l�X���ّ������Ă����G�̂ł��B�O�g(��ɕ�������ĒO��ƂȂ�)�͌Ñ���y�w偂̑��A�Ƃ���A�x�X�����R���h�����ꂽ�n��ł����B�y�w偂Ɠ����R���������������Ƃ���`���́A�ݒn���͑Α�a���Ƃ̑Η��̍\�}���яオ�点�܂��B�Ñ�̒O��n���͑嗤�̕���������A�Ǝ��̂����ꂽ�����������Ă��܂����B�O��ɂ�����y�w偑ގ��̓`���ōł��Â����̂��A�u�O�㕗�y�L�c㞁v�ɋL���ꂽ������}�Ɠ��q�����̓`���ł��B
��������}�ƕC�� ��\�㐒�_�V�c�̌��A������}(�N�K�~�~�m�~�J�T)�ƕC��(�q�L��)����̂Ƃ���y�w偂��O�㍑�̐t�R���ɐ��݂��A�l�X���ꂵ�߂Ă��܂����B����͓y�w偂����ׂ����q����(�q�R�C�}�X�m�L�~)�����銯�R��h�����܂����B�y�w偂�����ł����Ƃ����t�R�́A�Ñ���O����w�̗��ł���A���̎R�ɑc�_���J���Ă����̂��C�l���ł����B ���b��Ɩ� ��������q���������銯�R�́A�t�R���痤����}���ǂ����Ƃ����Ƃɐ������A���������y�w偂̒nj����J�n���܂����B�O�㍑�Ǝዷ���̋��ɓ��������A���R�ƌ���P��������ސ�����܂����B�`�����b�Ɏ��Ă��鎖����A���q�����͂�������R�̍b��Ɩ��t���A�Ȍ�b��̂���n��͖�(�i���E)�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B���͌��݂̐����ł��B�y�w偂����͊C�Ɍ������Ĕs���������ƂɂȂ�܂��B ���C������ �s���𑱂��闤����}��y�w偂Ɠ��q���������銯�R�́A�R�ǐ쐅��ōĂь��˂��܂����B���̐퓬�ŕC������������A���̌��͕ӂ��ʂ�Ԃ����߂������瓖�n�͌����ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B��x�͍~�����l����������}�ł������A�ޘH��f�ׂ��쉺������{������(�����S��т̗̎�)�̌R�����U�߂Ă����ׁA�ꂩ�����̏����ɏo�܂��B���Ȃ͂��A�͂��z���đΊ݂̓��q�����̖{�w�����s�˔j���ׂ����U�����J�n���܂����B�����͌��݂̐猴�ł��B �������̖��ɁE�E�E �s�ӂ�˂��ꂽ���R�ł������A�͌��ɏ|���Y�����ƕ��ׂĖh�����ł߂�ƁA�(���Ȃ�)����Ԕ@������ˊ|���܂����B���̐퓬�œy�w偂̓}�͂قډ�ł��܂������A��̂ł��闤����}�͍s���m�ꂸ�ƂȂ�܂����B�{�w�Ղɂ͍��ł��͎�(�R�E����)�A�|���̒n�����c���Ă��܂��B ���쒀����ǂ�������ꂸ ���q�����͗R�ǂ̍`���I���E���A������}�̍s���������Ƃ���A�^�ӂ̑�R�ɓo������������܂����B�O�㕗�y�L�c㞂̋L�^�́A�����ŏI����Ă��܂��B���Ȃ͂����q�����́A�t�R����y�w偂�ǂ����������̂́A��̂ł��闤����}����鎖�ɂ͎��s���Ă���l�ł��B�^�ӂ̑�R�Ƃ͌��E��]�R�A�M�Ǝv���܂��B ���y�w偂̍Ŋ� ���q�����Ɨ�����}�̐퓬�̖͗l�́A�Ȍ�u�A�n���p�L�v�Ɏp����܂��B�A�n���p�L�ɂ��ƁA������}�͊C�ݓ`���ɒO�ォ��A�n�ɔs�����A�Ŋ��A�n�C�݂̊Z�Y�ɂē��q�����ɓ������ꂽ�Ƃ̋L�^���c���Ă��邻���ł��B ���t�L1�E���q���� ���q�����́A�L�I�n���ɂ��ƊJ���V�c�̎q�Ő��_�V�c�̒�Ƃ����c���ŁA�l�����R�u�O�g���喽�v�̕��ɂ��ČÑ�\�㎁���̑c�Ƃ���Ă��܂����A���݂��^�⎋���鐺��������̐l���ł��B���q�����́A�ߍ]�𒆐S�ɓ��͍b��A���͋g���܂ł̍L���͈͂ɓ`�����c���Ă��܂��B�Ȃ��A���q�����͖{���a玎��̎i�Ղ�����_�ł���A�Î��L�쐬�Ɋ֗^�����a玎��ɂ���Ęa玎��̑c�_�Ƃ��Ă̒n�ʂ�^����ꂽ�̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����������悤�ł��B ���t�L2�E������} �O�㕗�y�L�c㞂ł́A�u�}�S�v�ƋL���āu�E�P�m�R�I���v�Ɠǂ܂��Ă��镔�ʂ����鎖����A������}�͐������́u�N�K�~�~�m�~�E�P�v�Ȃ̂����m��܂���B�J�쌒�ꎁ�͒����w�_�Ɛ��̊ԁx�̒��ŁA�u�~�Ƃ��~�~�͐�Z�̓���n�̐l�X�ɂ���ꂽ���ł���A�ؒ�����ؓ�ɂ����C�l���ŁA�傫�Ȏ��ւ����镗�K�������A���{�ɔ_�k������������`��������n�̓n���l�ł͂Ȃ����v�Ƃ���Ă��܂��B�@ |
|
| �����C�q�e���`���@ | |
|
���q�����̓y�w偓��������Z�܁Z�N��A�O�㚠�ɍĂъ��R���h�������Ɏ���܂����B���q�����ɓ������ꂽ������}(�N�K�~�~�m�~�J�T)�ƕC��(�q�L��)����̂Ƃ���y�w偂͒O�㚠���̐t�R�ɐ���ł��܂������A���C�q�e��(�}���R�V���m�E)��叫�R�Ƃ��銯�R�������̑ΏۂƂ����w�S�x�����́A������}���������Ƃ����O�ブ��(���݂̑�]�R)�ɐ���ł��܂����B
���d�p���g���O�S ��O�\���p���V�c�̌��A�O�㚠�͎瑑�O�ブ��(���݂̑�]�R)�ɁA�p��(�G�C�R)�E�y��(�J���A�V)�A�y�F(�c�`�O�})�̎O�S����̂Ƃ��鑽���̋S�����݁A�O��͂܂�Ŗ����̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B����͋S�����ׂ��A�m�E�����̖��C�q�e����叫�R�Ƃ��銯�R�����킷���Ɍ����A��������C�q�e���́A��c�E�͓c�E�v��E�����̎l�E�m���͂��߈ꖜ�Y����Ȃ��R�𗦂��ĎO�ブ�Ԃ֍U�ߓ���܂������A�S�͗d�p����(����ĂсA�C��n����������A�_���������J���~�点�A�g���B�����茰�ꂽ��)�Ŏa����鎖����Ŏ˂鎖���ł��܂���ł����B ���_���̌����Ɣ����� �S�̗d�͂̑O�ɐl�q�͑S�����������Ȃ�����������e���́A�_���̌������ȂċS���ʂ������Ƃ��l���ɂȂ�܂����B��U�������������e���́A���玵�̖̂�t�@������������ɂȂ�A�u�������S���ʂ������Ȃ�A���̖�t�@�������J���ĒO��Ɏ������J���܂��v�ƋF������A�����ēV�ƍc��_�ƓV�_�n�L�ɋF�肳��܂����B����Ƃǂ��ł��傤�B�e���̌��ւǂ�����Ƃ��Ȃ��z�ɋ���t����������������܂����B���̌����_���̌䌭���ł��邱�Ƃ��@�����e���́A��������擪�ɎO�ブ�Ԃ֍U�ߓ������Ƃ���A���̌������X�ƉB��Ă����S�̎p���Ƃ炵�o���A�S�̗d�͂����Ƃ��Ƃ������Ă��܂��܂����B���̐��Ȃ�͂ɂ���Đg���������Ȃ��Ȃ����S�B�͍ő����R�̓G�ł͂Ȃ��A���C�q�e���͖����������ʂ��������ł��܂����B ���O�S�̖��H �O�S�̂����A�p�ӂƌy���͊��R�ɓ�������܂������A�y�F�݂̂͐����߂��܂����B�y�F�͐����c�����S�B���X�������肢�o�����߁A�e���́u���̖̂�t�@���������u���鎵�̎��̓y�n�����̂����ɊJ���Ȃ�A�������͏����悤�v�Ɛ\����܂����B�S�B�͊�їE��Ŏ����̓y�n���J�������̂��A�O�㔼���̐�[�ɂ��闧��ɕ������܂����B ������t�`�� ���C�q�e����J��̎���t�����咣���鎛�@�́A���ݎ������ȏ゠��܂����A�u���H�����N�v�ɂ��ƈȉ��̒ʂ�ł��B ��A�{��(�^�Ӗ쒬)�E�E�E�E�E�����V�c���菊�A�����{�� ��A������(���m�R�s��]��)�E�E�����N�Ɖ��N�G�͕{�̎w�蕶���� �O�A������(���O��s�O�㒬) �l�A�_�{��(���O��s�O�㒬)�E�E���C�q�e���̂��̂Ɠ`���悪���� �܁A���y��(���O��s��h��) �Z�A���莛(�{�Îs) ���A���H��(���ߎs)�E�E�E�E�E�E�p���V�c���菊�A������t��O�\�ԗ�� �܂��A��]���̔@���@(�Â��͕������ƌĂƎv����B���{�̋S�̌𗬔����ق̂����߂�)�����C�q�e����J��Ɠ`������Ù��ł���A�{���̖�t�@�����̑ٓ����͐e���̌�g���Ɠ`�����Ă��܂��B �X�ɁA�������̎R�������ڎR�Ɖ]���܂����A����͐e�����S�B���������ɕ���ł��銙�ƕڂ�[�߂����ɗR������ƌ����Ă��܂��B���̑�����t���`���̎��Ƃ��ẮA�~�ڎ�(���O��s�v���l��)�E������(�p���A���O��s��{��)�Ȃǂ�����܂��B ���e���̑��� �����A�O�g�E�O��ɂ͎��\�����ȏ�ɖ��C�q�e���ɂ܂��`�����c���Ă��܂��B���̈ꕔ������ �E���s�{���m�R�s�_���Ɂu���J�v�Ƃ����n��������A���C�q�e���͂����Ŏ��̖̂�t�@���������Ƃ̓`��������B �E��]���̌��ɐ��c��_�Ђɂ́A�u���C�q�e������A���̐��v�ƌĂ�鐙�̋�����������B�܂��A�c��_�Ђɂ͖��C�q�e��������������B �E�^�Ӗ쒬�̑咎�_��(���쎮����)�ɂ́A�폟�F��̂��߂ɐe�����炪�������_�����[�߂��Ă����B�܂��A�������̋������J����Ă����B(��������ЂŏĎ�) �E�^�Ӗ쒬�ɁA�u���v�ƌĂ�鋐������B����͑�]�R����e���߂����ċS�������������ŁA�e���͂��̊�𓁂Ŏ~�߂Đ^����ɐ�����̂ł���Ƃ̓`��������B �E���O��s�O�㒬�̒|��_�Ђ́A���C�q�e�������J���Ă���Ɠ`����B�߂��ɂ͓y�F�����Ƃ����u����v������A�u�S�_�ˁv���������Ă���B �E��]���ɔ����ǎu(�~�^���V)�r�_�Ƃ������K������A�e���̑�萬�A�Ɠ����Ɏ���ł��܂������������J���Ă���Ƃ����B �c��Ȗ��C�q�e���`���́A��N�̌������ɂ��S�ގ��̕���w��ۓ��q�`���x�ւƏ����Ă����܂����B ���t�L1�E���C�q�e�� ���C�q�e���́A�p���V�c��O�c�q�ɂ��Đ������q�ٕ̈��ł��B�e���̋S�ގ��`���ɖ�t�M���[���ւ���Ă���̂́A�O��ɂ����镧���̐Z���������l����Ƃ��A��ςɋ����[�����̂�����܂��B�܂���t�@���́A�C���ʂ̈��S�Ɍ䗘�v������Ƃ���Ă��邱�Ƃ���A�C�l���̉e�������B�ꂵ�܂��B ���t�L2�E�p�ӁA�y���A�y�F �����������N(���s�{�w�蕶����)�ɂ͚���(�e���R)�A�ޘO�鍳(�J�����V��)�A�ƌF(�c�`�O�})�̖��œo�ꂵ�܂��B�����҂́A������̌ď̂̕����Â��A�{���͂��̌Ăѕ��ł͂Ȃ��������Ƃ��Ă��܂��B ���t�L3�E�z�����������鑈�� ���N�O�A�������m�R�s��]���ɂ���u���{�̋S�̌𗬔����فv��K�ꂽ�Ƃ��A�^�ǂ����邨���ɂ��b�������ł��܂����B ���邨���H���A ������}������ł����t�R���A�O�S������ł�����]�R���A�Â�����C�m��ʂ̖ڈ�ł���A�C���̎R�ł���A�z�������̖L�x�ȎR�Ƃ��Ēm���Ă��܂����B���̎R���x�z���Ă����̂͊C�l���ł���A���S���ł���܂����B�S�Ƃ͐��S�����̎��Ȃ̂ł��B��]�R���n�߂Ƃ��āA�O��ɂ͑�R�̃^�^���ꂪ����܂����B�z�������ƗD�ꂽ�Z�p���������鎖�́A�Ñ�ɉ����Ă�����ɉ����Ă��A�헪��ɂ߂ďd�v�Ȏ��ł��B�O��̋S�Ɗ��R�Ƃ̐킢�́A�O��̒n�����͂Ƒ�a����́A�z���������D�킾�����̂ł��B�������q�͐`�͏����g���Ď��X�ɒn��������łڂ��Ă����܂������A�O��̍U�����������q�̈ӎu�ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�ł��A�������q����e���C�l�n�̊Ԑl�c�@�ł�����A�C�l���̌��������Ă���̂ł���������@ |
|
| ���O�㎵�P�`���@ | |
|
�����P(���ƂЂ�)
���͗Y���V�c�̌��(�ܐ��I��)�A�O��̋��t�Y���q�͉��ɏo�Ēނ�����Ă��܂������A�O���O�ӈ�C�̋����ނ�܂���ł����B���߂ĊƂ��グ��Ƃ����ɌܐF�̑傫�ȋT������܂����B�T�߂邤���ɖ���ɂ��Ă��܂����Y���q���ڊo�߂�ƁA�T�͔��������P�̎p�ɕς���Ă��܂����B��l�͏퐢�̍�(���{��)�֕����A�y�������X���߂����܂������A���S�̂����Y���q�͌̋��Ɋ҂�A�����ĊJ���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌ����ēn���ꂽ�ʎ蔠���J����ƥ������{�ŌẨY���`�����ɍ����̉F�ǐ_�Ђɓ`����Ă��܂��B ���H�ߓV��(�͂�����Ă�ɂ�) �́A�鍻�R�̎R�[�Ŕ��l�̔������V���������т����Ă��܂����B���̗l�q�����Ō��Ă����V�v�w����l�̓V���̉H�߂��B���Ă��܂������߁A���̓V���͓V�Ɋ҂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A��ނȂ��V�v�w�̗{���Ƃ��ĕ�炷���ƂɂȂ�܂����B�V���͈��E�{�\�E�̋Z�p��`���A�V�v�w�͂�������T���ɂȂ�܂������A������V�v�w�́u���͉䂪���ɔv�Ƃ��ēV����ǂ��o���Ă��܂��܂����B�߂��݂ɕ�ꂽ�V��(�L�F�C�䔄)�́A�ދ�̑��ɍs���������������O��s��R���ɓ`���H�ߓ`���́A�O�㕗�y�L�ɂ��o�ꂷ����{�ŌÂ̂��̂ŁA�ދ�_�Ђɂ͖L�F�C�䔄�����J�肳��Ă��܂��B �����䕔�Ԑl�c��(���Ȃقׂ̂͂��ЂƂ̂Ђ߂݂�) ���䕔�Ԑl�c���́A�Ԗ��V�c�̑����ŗp���V�c�̍@�A�X�ˍc�q(�������q)�̐���ł��B�Z���I���A�����őh�䎁�ƕ������̌��͓��������������܁A�������邽�߂Ɉꎞ���{�C���ݕ��ɔ��Ă����̂��Ɖ]���܂��B���N����A������������s�A��܁A���b�ɂȂ������l�B�֊��ӂ̈ӂ����߂āA�c���͎����̖��O�𗢂ɗ^���܂������A���l�B�́u�ꑽ�����Ɓv�Ƃ��ċꗶ�������ʁA�Ԑl�̎����c���̌�ލ��ɂ��Ȃ�ł������Ɠǂݑւ��Ă��̒n�̒n���ɂ��������ł��B�� ���n�ł͒P�ɊԐl�c�@�ƌĂ�Ă��܂����A�Ԑl�̖��������A�����V�c�̍@�ƂȂ����c���͓݂�A�w�p�㑼���͊Ԑl�c��(�F���V�c�@)�ƌĂ�Ă��鎖����A���������ł͍���������邽�߁A���䕔�Ԑl�c���Ƃ��܂����B ���א�K���V��(�ق����킪�炵��) �א�K���V���́A�퍑�������q���G�̖��ŁA�{�����ʂƉ]���܂��B�D�c�M���̊��߂ōא쓡�F�̒��j�����̌��։ł��A�K���ȓ��X���߂����Ă��܂������A�������q���G����N�D�c�M������(�{�\���̕�)���Ŏ��Ԃ͈�ρA�ʂ͗H����Ă��܂��܂��B�H��̋��O��s��h��������Ŕޏ��̓L���X�g���ɐG��A��ɐM�ɋ~�������߂ăK���V���̐��疼��������܂��B�փ�������O��A���R�ɉגS���镐���̐�����l���Ɏ�낤�Ƃ������R�̌R�������̍א쉮�~���}�P�����܁A�l���ƂȂ邱�Ƃ����ꂽ�K���V���͉��~�ɉ�����A�L���X�g���̋����Ŏ��n�ł��Ȃ����Ƃ���ƘV�ɋ���˂����Đ▽���܂����B���N�O�\���̎Ⴓ�ł����B�U��ʂׂ� ���m��Ă��� ���̒��́@�Ԃ��ԂȂ� �l���l�Ȃ� (�����̋�) �����쏬��(���̂̂��܂�) ��������̘Z�̐�̈�l�Ƃ��ĕS�l���ɂ��̖����c���A�␢�̔����Ƃ��Ēm���鏬�쏬���ɂ́A����`�������`����Ă��܂��B���O��s��{���ɓ`���`���́A�N�V�������������̓r���ł��̒n�ɗ������A���̔�ꂩ��▽�����Ƃ������̂ł��B��{���ɂ́A���������̋傪�`����Ă��܂��B��d�̉Ԃ̓s�ɏZ�͂��� �͂��Ȃ��� �O�d�ɂ������@ �������P(����Ђ�) �����Ɛ~�q���̕��́A�������B�̂Ƃ��鍑�̗̎�ł������A������̗��ɉגS�������^���������}���̍��ɒǕ�����Ă��܂��܂����B�������Ē}�����������o��́A���̓r���Ől�������x����A�O��̎R����v�ɔ�������Ă��܂��܂����B�o��ɑ҂��Ă����̂͒�����킸�̋���ł����B�u���Ƃ��~�q�������ł॥���v�����l���������́A�R����v�̖ڂ𓐂�Ő~�q���������Ƃɐ������܂��������{�苶�����R����v�ɐӂߑ�����ꂽ�����́A���h�ɐ��l�����~�q���������ɗ���O�ɒr�ɐg�𓊂����Ɠ`����Ă��܂��B ���Ì�O(������������) ���`�o�̒�������g�Ɏ������������q�̐Ì�O�́A���O��s�Ԗ쒬�ɐ��܂ꂽ�Ƃ̐�������܂��B����������ċ`�o�ƈ���������A�h���Ă����`�o�̎q�����㒼���ɎE����Ă��܂������S�̐ẤA���܂�̋��̖Ԗ�֖߂�A���̒n��20�]�̒Z�����U���I�����̂��Ɖ]���܂��B�Â̎��𓉂��l�B�́A�Ð_�Ђ��������A�ޏ��̌����Ԃ߂邱�Ƃɂ����Ƃ̎��ł��B�@ �@ |
|
| ���z�K�̐_���� | |
|
��ނ����A�������߂Ă����V�Ƒ��_�́A�o�_�������A�܂������ɏ]���Ă��Ȃ����Ƃ�s���Ɏv���Ă��������ȁB�����ő��_�́A�o�_�����߂Ă���卑��_�ɉ��x���g�����o���āA�o�_���䂸��悤�Ɍ������̂����A�Ȃ��Ȃ��䂸�낤�Ƃ͂��Ȃ������B
�Ō�Ɏg�҂ɂȂ����̂͌��䗋(�����݂��Â�)�_�ł������B �o�_�̈ɖ덲(������)�̕l�ӂŌ����A�t���܂ɓ˂����āA���̐���ɂ������g��Łu�o�_���䂸��v�ƒk�����錚�䗋�_�̐����ɋ�����Ȃ����卑��_�́u���_�̌����Ƃ���ɂ��܂��傤�v�Ƃ������茾��������ǁA�u���͂����̂ł����A�ӂ���̑��q�������Ȃ�ƌ����܂����v�B �����Ō��䗋�_�͂�ɍs���Ă��锪�d�����(�₦���Ƃ���ʂ�)�_���}���ɍs�����_�̑O�Őq�˂�ƁA�u���オ�������������Ȃ�A���̏o�_�͌�q�ɍ����グ�܂��傤�v�ƌ������B �卑��_�́u���ƁA���䖼���_�����܂��̂ŁA���q�˂��������v�Ɛ\���������ȁB���������Ă���ԂɌ��䖼��(�����݂Ȃ���)�_���������ō����グ�Ȃ������ė��āu���ꂾ�B�䍑�ɗ��ĂЂ��Ђ��Ƃ��̂������Ă���̂́B������������悤���v�ƌ��䗋�_�̎�����Ƃ���u�����������������v�ƌ����Ȃ���͂�����悤�ɔ�т̂����B �Ȃ�ƌ��䗋�_�̎�͕X�ɂȂ��Ă����̂��B���x�͕ʂ̎�ɂ��݂�����ƁA���̐n�ɕς���Ă���ł͂Ȃ����B ���x�͌��䗋�_���U�߂Ă����B |
|
|
���䖼��(�����݂Ȃ���)�_���Ђ�����ɁA���䗋(�����݂��Â�)�_�͎��L�������悤�Ƃ����Ƃ���A���䖼���_�̎�́A�Ⴂ����܂�悤�ɂ₷�₷�ƋȂ����Ă��܂����B
��l�������Ď����グ��悤�ȑ��������グ��͎����̌��䖼���_�����A�u����͏��Ă�v�Ǝv�����̂��A�������Ɠ����o�����B���A����ł����䗋�_�͂������ǂ��ė��āA�Ƃ��Ƃ��M�Z���̐z�K�̂قƂ�ɒǂ��߂��B �g�����̏o���Ȃ��Ȃ������䖼���_�́A�u�ǂ��������Ă��������B���͂��̏ꏊ����o�܂���B���ɂ͍s���܂���B�܂��A�䕃�A�卑��_�̖��ɂ͔w���܂���B���d�����(�₦���Ƃ���ʂ�)�_�̌��t�ɔw���܂���B�V�Ƒ��_���܂̋��̂Ƃ���o�_�����䂸�肢�����܂��傤�v�ƌ������B �u�患���v�ƌ����Č��䗋�_�͐M�Z���������B �k�ɕ䍂�x�A���ɔ����x�A���ɋ�x�Ƃ��������R�Ɉ͂܂�Ă���A�����V�̌��䖼���_���A���������o�ė��邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�ƍl�����̂��낤�B �z�K�̂قƂ�ŋC���x�߂悤�Ƃ��Ă�����A�����ɐ̂��炢��n�_�̉k��(�����)�_���A�S�ւ������т炩���čU�߂Ă����B����Ă����䖼���_�͐����Ă������Â���ɂ��ĉʊ��ɐ킢�A�Ƃ��Ƃ����䖼���_���������B�����䖼���_�͐S���D���������̂������B �������k��_�Ǝd���������Ȃ��璇�ǂ��邵�z�K��グ�Ă����������ȁB�@ |
|
|
�����
���䖼��(�����݂Ȃ���)�̓��M�̘H�́A�����삩��P������A���삩�珬����ʂ�z�K�ɓ������ƍl���錤���҂������B����͂Ȃ����Ƃ����ƁA���̓��ɐz�K�_�Ђ��������炾�����ł���B ���J���ɂ́u��{�v�̊��������h�Ȑz�K�_�Ђ�����B���̓��̈�A���y�̑�{�z�K�_�Ђ̗��Ղɂ́A�א��҂���䂷�邢��u������(���s�̔���_�Ђɂ�����)�v�I�ȁu�z�x(��������ǂ�)�v������B�z�͉~�w��g�݁u���[�C�g�}�J�T�[�m���C�v�Ɛ����|���A���̂��������B �u�����q(�����т傤��)�v�ł́A�j��2�l���_���g���ėx��B�u�z�v�ł���Ƃ��Ӗ��s���̊|�����ɂ́A���{�ɑ�������n�������l�X�̑��Ղ�������B ����s�ɗ��āA�P����7�Ђ̓�4�Ђ����䖼�����Ղ�B�����āA�X�ɏ�c�s���c���̉��V���ɂ͋{���ł��Ղ�A�����_�E�����_�����킷�B ��́A���̒n��ʂ��Č��䖼�����z�K�ɓ����鎞�A�����̐_���܂Ɍh�ӂ�\���A�u�����v������čs���ꂽ�����ȁB�u�����v�Œ����Ɏv�������������Ƃ�����B ���䖼���_�́u�͂���ׁv�����ĕ����͂������u���_�v�ł���Ƃ��u�R�_�v�ł���Ƃ��̈�ۂ��������A�{���͐��S�_�ł���B �ŁA�u�����v�ł��邪�A6�N�قǑO�Ɂu���v�̂��Ƃ�������p��̒��Ŋw�B �u�L(�����E�L�S)�v�̂��Ƃ��Ñ�؍���Łu�W���O�v�Ƃ����������B�L�S�͊���ɗ���o����̂�����Ƃ����B |
|
|
�Ԗ�(������)�Ƃ����ԓS�z���̑������S�őL(����)�����u�L���o���@�v�ł́A4��4�ӂ������邻���ł���B
�����ŁA�u�Y�N������E�Y�N���Ȃ��v�́A���̑L���ɍ����������t���ƍl���Ă���B�Ȃɂ���4��4�ӂ����炸�ɁA���܂߂ɓ����A�C��z��Ȃ��ƑL�͏o���Ȃ�����ł���B ���䖼��(�����݂Ȃ���)�͐����_�E�����_�ɋʍ|�̂悤�ȏ㓙�ȓS��������̂ł͂Ȃ����Ɛ������Ă݂�B �܂��_�Ђ̌�_�̂́A�u�y�v�ł��邻���ȁB�{���̐z�K�_��(�D�{)�Ƃ̊W������Ɗw��ł��邱�Ƃ���A�u�D�v�̂��Ƃ��u�D(��)�v�Ƃ������A���͔S�y�̂��Ƃł���B�S�y���̓y�͓S�����܂݁A�Ă����܂��B�D�{����͌����̈��Ƌ��ɏ���̓S�𗘗p�����S���肪�z������ĂȂ�Ȃ��B �R���́u���]���R�v�̈��](�Â��͈��@�Ƃ�)�́u�A�\�v�͋�B�̈��h�ɗR������Ƃ����Ă���B�Q�n���̕x���s�ɂ����h���R������A�����S���a���ɂ����]������B �u�L�I�@���t�̉�ǒʐM47���v�ŗ��Jꤐ搶�́u�n��(�A)���(�W��)�v�́u�A�W���v�������ɓ��ĕ\�L�������̂��u���]�v���Ɛ������Ă���B �Ñォ�當���x�̍����n�A ���c���ɂ͍����_�Ђ����邪�A���͔�颐_�ЂƂ������B�Ñ�؍���̂����ŗ��R�����������ƁA��c���q�Z����w�̌̉����G�q�搶���璚�J�Ȃ��莆�������Ƃ�����B ����11�N9���̂��Ƃł���B�搶�̑��߂������́A����w�̕���ł��傫�ȑ傫�ȑ����ł���B |
|
|
�z�K��Ђ̉��N���Ɂw�z�K�喾�_�G��(�����Ƃ�)�x�Ƃ����G��������A���̎���(���Ƃ���)�Ɂu�k��(�����)�̈����_�������܂�����Ƃ������A�k��͓S�ւ������Ă��炻�ЁA���_�͓��̎}�����Đ������Ӂv�Ƃ���B
�k��Ƃ͐_�����̑c�_�A�k��_�̂��ƂŁA���_�Ƃ͌��䖼��(�����݂Ȃ���)�_�̂��Ƃł���B�k��_�͔s�ꂽ�����䖼���_�͏����A���̌���Ə̂���_(����)�����z�K�Ѝō��̐_���j(�����ق���)���p���A���͑�j�Ɏd����܊��̕M���_�����p�������B ���䖼���_�͐z�K�ɓ����ė����̂ł͂Ȃ��A�u�z�K�v���u�S�̏�v�ł��邱�ƁB�܂��A�Â�����̐��S���s���Ă���k��_�����邱�Ƃ��m���Ă��āA����ė����̂ł��낤�B�u�z�K�v�͌��䖼���_������O����u�z�K�v�������̂ł���B ���Jꤐ搶�́u�z�K�v�́u�S�̏�v��\�����t���Ƃ����Ă���B���̂����u�S�̏�v���Əؖ�����Ă���̂ł���B �����A�k��_�͓S�ւ������Ă��炻�����Ƃ��邪�u�S�ցv�Ƃ͂Ȃ낤���B�w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�̒��ҁA�^�|�풉����́u�S�ցv�́u�S��(���Ȃ�)�v�ł��낤���Ƃ͗e�ՂɎ@������A�Ƃ����Ă���B �S���͐_�����ŗL�̍Ջ�ŁA���𒆐S�Ƃ���X(������)�_���ɗp����B �S���͔����S�����b�p��Ɋ����`��ł���B ���̓S����U��炵�S��(���S�z)�̐�����������X�Βn�ŋF�萿�����A�Ɛ�������Ă���B���K�s�̐M�Z��̋{�̏���_�Ђ�12���̓S����q�������Ƃ��������B |
|
|
�k��(�����)�_�����߂Ă����S�ނ͊��S�z�ł���B���S�z��Fe(�S)�̕i���͉ԛ���₩�����ɔ�ׂ�Η�邪�A�z�K�Ђɓ`���S����6���I��ɂ��Ȃ��s���Ă����Ƃ����̂ł���B
���䖼��(�����݂Ȃ���)�_�́u���̎}�v�������ēS�ւ����߂��Ƃ����̂����u���̎}�v�Ƃ͉����Ӗ�����̂��낤���B �w�M�Z�̓S�x�̒��ҁA����גj�搶�͕M�҂̎t�ł���B�搶�̂����ɂ́u�������̓����͊��S�z��������(��v)�v�Ƃ����B �x�m�����̈�ːK�l�Êق̔��������A�������܁u���̒ʂ�ł��v�Ɩڂ��P�����āA�����������B �����ď�v�Ȃ̂ŁA�̂͐z�K�̌䒌�������̂ɓ��������o���������ł���B�w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�ł́u���̎}�v�Ƃ́u�S��(�����)�����v�ɂ�鍻�S�̎�̋Z�p���ے����Ă���Ƃ����B �܂�A�y�����}���ɓ���Đ�����ɗ������S�����U���ō̂�B���̃U���������ŕ҂��̂�ǂƂ��邻���ł���B �]���̎��Ȑ�ŁA�����ŕ҂U���Ŏ��������B�����ł͍r������B���S�ȂLj����������Ă����Ȃ��B�ł́A�|�̃U���͌����ɉ߂���Ƃ������A�|�̃U���ł͏��X�̍��S���̂ꂽ�B �Ñ�̐l�X�͔E�ϋ������X�̓S���W�ߍ̂����̂ł��낤���B�������Ă邤���A���ߑ����o���B���̂��������Ă��܂��U������蓊�����B ���̘b��������ɂ�����A�N�X�b�Ə��āA�u�����̑��q�͉��ō̂����v�Ƃ����ł͂Ȃ����B |
|
|
���ō��S�������b�͌�ɏڂ������悤�B���͂Ƃ��Ă����̘b�Ȃ̂ł���B
�U���ł̍��S�����̎����͂��܂��s���Ȃ����������䖼���_�͓y��(�撅)�̌Â����S�@�����k��_���V�������S�̎��S�Z�p�������Ă���Ă����_�Ȃ̂ł��낤�B �Â��������쒀���ꂸ�Ɏc�����ė������ɂ́A�ǂ�Ȏ������������̂����l���Ă݂����B �ǂ��l���Ă݂Ă��A�k��_�ƌ��䖼���_�̏o�����߂��_���m�ł͂Ȃ����낤���B �k��_�́u��v�̎����t���A�u��v�u���v�u��v�u�J�v�u��v�u��v���̊����ŏ����\���ꂽ���{��́u�����v�܂��́u�����l�v��\���Ɗw��ł���B�u�����v�͋I���O�����I�ȑO����A���N�����k�[�̓����]�ݖΎR�̍��S���L�x�ɏW�܂鏊�ɐ��S����z���A���A���̊؍��]������т̓S�Y�n�ɓ쉺�A�u�������v�u�������v�u�S���v���̖��Ő��S�𑱂������A����������{�ɐi�o�A���͂��L�����Ɗw��ł���B �M�Z��̋{�̏���_�ЂɁA�������ɓS���▃�������t���Ă������B �w�O���u�x�̓��Γ`�Ɂu�����l��3��(��10m)�قǂ����钷�������悭���A���l���ňꏏ�Ɏ��������Ƃ��邻���ł��邪�A�Ȃ�ƁA�䗧�Y�_���̌��Ɏ��Ă��邱�Ƃ��B �������B�_���͌Â������悭�c���A�Ƃ������t���v���o�����B ���́A���䖼���_�ł��邪�A�u���v�u���v�̕t�����͍����n�ƌ����Ɗw��ł���B��_�͍��u���͕P(�����ʂȂ���Ђ�)�ł���B |
|
|
�z�K���Ђ̔ܐ_�͔��Ⓛ��(�₳���Ƃ�)�_�ł���u����v�Ƃ́u����������v�Ƃ��u�����̓S���v�Ƃ��ǂ߂�̂ŁA���Ă͂��̔ܐ_�́@�n�̓S���̂��P���܂ł������̂��B�ƍl����A���䖼���_���k��_�����S�ɋ쒀���Ȃ��������R�������ɂ��肻���ł���B
���~���A�z�K�̌ΖʂɕX������T���ɕX�����N�����_�n��́A��Ђ̒j�_�����Ђ̔ܐ_�̌��ɒʂ������Ɠ`�����Ă͂��邪�A����ɂ͗��_�M�̖ʉe���Ƃǂ߂����(�����)�̌`�ł���Ƃ������Ă���B ��ւȂ�A�b��O�Y�̉��g�ł͂Ȃ����B ���v�ɂ́u�b��O�Y�`���v������B �Z�B�̉A�d�ɂ�����ȎR�̌��ɗ����Èł̐��E��f������A���邢�ꏊ�ɏo����O�Y�̑̂͑�ւƉ����Ă����B�₪�����ȎR������O�Y�͐z�K���_�ɂȂ����B ���ꂪ�b��O�Y杂̑e�ł���B ���͎O�Y�́u�S�v���������ɒn�����������Ă����̂ł���B�`���̒��Łu���v���u�S���v���Î����Ă���B�u�S���v�Ƃ͐[�������w���Ă���̂ł͂Ȃ��S�z���n�ʂɘI�o���Ă��鏊�������B�O�Y���������A������(�Ƃ͓`���ɂ͂Ȃ���)�S�z�������ȎR�R�[�̊���s�ɂ���A���S�z���́u�z�K�S�R�v�ł��낤�B �������A�������z���n���̎����Y����(79��)�Ɉē����Ē������B���S�z���͓�K���̉Ƃ̍����قǂ̏ꏊ���������B�z���@��ׂɏ����ꂽ�y�́A�R�Ɠ������Ă����B |
|
|
�u�ցv�͊؍����̉��ǂ݂Łu�T�v�ƂȂ�B�S���u�T�v�̊T�O�������ɐ����Ɗw��ł���B�ւ͎��n���D�ށB���̎��n���珉�����̈�삪�n�܂�A�퐶����̓S�ނ̊��S�z�̐������n�܂�B�Ñ�̐l�X�͂������������킩���Ă����̂ł��낤�B
��ւɉ��g�����O�Y�́u���S�E�b��W�c�̂����v�������̂ł͂Ȃ����B �z�K���_����ւƂȂ��ĉ��Ђɍs���Ɣܐ_�́u���͂ǂ�����v�Ɛq�ˁA���_�́u���͍��̔��|���v�Ɠ����������ȁB ���z�K���u��a�v�̔��|���ɍs���Ă݂�ƁA�}�͐��A�����͎̌����ɂ������Ɨ����Ă����B�����������ŁA�}�̐�����炢�����肪�����Ƌ����Ă��ꂽ�͎̂}������m�l�ł���B ���̖̐����Ă���p�������l�͒N�����Ȃ��B ���{�̐��j�Ƃ�����w�Z���j�x�ɐ��ÓV�c5�N8���Ɂu���c���_�E�M�Z�{�g�E�����_���J�炵�ށv�Ƃ���B�u���c���_���{�g�ɐ����_���J�����v�Ɠǂ߂����̂��낤���B��������ƁA���c���_�Ɛ����_�͓��_�Ȃ̂������ς�킩��Ȃ��̂Ō��_�В��Œ��ׂĂ���������A�u�����v�Ɩ��̕t���_�Ђ̍Ր_�͂قƂ�ǁA���䖼���_�ł������B ���c���_�Ƃ����A�u�ߓs��Ð_(���ȂЂ��E�����ÕF)�E�u�ߓs�䔄�_(���ȂЂ߁E�����ÕQ)�ł��邪�A�z�K�n���ɂ͑O�o�̐_���Ղ����_�Ђ͌�������Ȃ��B���A����s���Ԃ̎����Е��Ԑ_�Ђɂ͑O�o�̐_���Ղ��Ă���B�z�K���_�́A�u�ߓs��Ð_�Ƃ͂���Ȃ������̐_�ł��邻���ȁB |
|
|
���̍e�������Ȃ���A�_�X�͎���Ƌ��ɖ��O��ւ��ϐg����̂�������Ȃ��Ǝv���ƁA�l�@����y�������{�����ė���B
�����A����1�z�K���_�̕��g���ƍl������u�_�v�̂��Ƃ��L���Ă݂悤�B �w���o�鏴(��傤����Ђ��傤)�x�Ɂu��{�̖{�R�͐M�Z���Ƃ�����@�����\���@���Z���ɂ͒��̋{�@�ɉꍑ�ɂ͒t(������)�����̋{�v�Ƃ���B �u���̋{�v�͊����䒬�̓�{��Ђ̂��ƂŁA���R�F�����Ղ�A�ɂ͓����ނ������A�ʏ́u���(�ӂ����܂�)�v�ƌĂ����R�Ղ�����B�_�Ћ߂��̒n�����S�Ɋւ�肠��n���������ς��ŁA�F�s�{���G(����Ђ�)�{�i����́u��{�̂����ЂƂ̃��[�c�v�Ƃ��ĎQ�q�̂�����ɓ��ʊ�e���Ă���B���ڂ��ׂ��́A���݂̊؍��Łu��{�v�Ɩ����l�B���吨���āA��{���͐��S�ɊW����Ƃ������Ă���A�Ƃ���B �u�t�����̋{�v�͎O�d���ɉ�s�A�ɉ��̋{�̊���(��������)�_�Ђ̂��Ƃł���B�Ր_�͑�F���A����\���͎̂�̖�����R�ꗎ�������F��(�����ȂЂ���)�_�̂��Ƃ������A����͓S��(���S)��\���Ă��邻���ł��邪�A�������ƂɁA���a�ɐz�K�_�Ђ�����A�b��O�Y�����Ղ肵�Ă���B���̑O�̒r��n���̌����Ƃ͐z�K���Ƃ����B������ɂ��Ă����̒n�́A�n���̌ꌹ���琄�����Ă��A�S���ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B�߂��ɂ͓n���́u�S�̋M�l�v�Ɠǂ߂�u�r�ؐ{�q�_��(���E�_��)�v������A���S�Ɋւ�肠�銋��(�łߌ�)���ɂ܂��т����肵���L��������B |
|
|
���̓�{2�Ђ����S�Ɗւ�肠�邵�A�t�C�S�̕����Ǝv���镗�̐_���z�K���_�̕��g���ƍl������̂ŁA��{�̖{�R�Ƃ͐z�K��Ђł��낤�B�w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�ł͐z�K��Ђ����S�̐_�ł���A�u��{�v�̌ď̂��A���S�̂�����F�̍��a���x����4�{���̂����A����̒������R���Ə̂��Ă����Ƃ��_�������A�����ɋ����q(���R)�_���Ղ邱�ƂɗR�����A�u�䒌�v�̈Ӗ��������ɋ��߂邱�Ƃ��ł���A�Ƃ���B
�䒌�̋N����Ӌ`�ɂ��Ă͏������邪�A�M�҂́u���a��4�{�̉������v���ɓ��S���������̂ł���B �u�䒌�v�Ƃ͂������̒ʂ�A7�N���Ƃ̓ДN�Ɛ\�N�ɍs����䒌(�݂͂���)�Ղ̂��ƂŁA�E�s���Y��ŁA ���y�������Ă̔M�C�Ƌ����̉Q�ɋ�������ł���B���l�̑j�������Վ��͗ǂƂ��ċ������_�͐z�K�l�C���̈�[�ł���B �Ȃ��䒌�͓ДN�Ɛ\�N�Ȃ̂��A�l�@���Ă݂��B �Ђ́A�Ȃ�����ɂ߂���Ƃ��������������A�@�l�͓Ђ��g�[�e��(�����̐_��������铮�A���B���{�l�̎��Ɩ�Ɠ����ł��낤)�ɂ��Ă���B����͉k��_�̏o����\���Ă���C�����ĂȂ�Ȃ��B ���͐\�N�����A�u�\�v�̉���������u�����̎�ň����ς��Đ^�������ɐL���`�����������ł���u�L���v�Ƃ����A�M���M�����S���L(��)���Ȃ���ΐ��i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B ������������������u�\�v�͒b��ɊW���錾�t�ł��낤�B�ДN�Ɛ\�N�̈ӂ͒N���Nj����Ă��Ȃ��B |
|
|
���܂Őz�K���_�̐^�̎p�����߂ė������A�����Őz�K���_���܂Ƃ߂Ă��������B
�z�K���_�Ƃ́A�S�������Z�p���������Â�����̉k��_�ł���A���ɍ��S����̐��S�Z�p�������Ă���ė������䖼���_�ł�����A���(�S�̏�̂���)�Ɖ������b��O�Y�ł���A���̐_�̎u�ߓs���(�����ÕF)�_�ł���A����ɁA�M�Z���̓�{�̖{�R(���R�_)��5�̕��g�̑��̂��z�K���_�Ȃ̂ł��낤�B�u���_�v�Ƃ͐��S�_�ł���Ɖߋ��Ɋw��ł���B�O�o�̐_�X�͂��ׂĐ��S�Ɋւ��_�Ȃ̂ł���B ��Ђɋ߂��t�l�Õ��ł͓S���ɑ����Ƃ����A���|�`�؊���ɓS���������Ǝv����֍s����f�������̑������A�m�~�A�J���i�A�g�A�����̓S�킪���ʂɕ�������Ă����B���z�K���ɂ����J�s�A����s�ɂ������ȌÕ��͑�������B�o�y�S��̐������͂��o���Ă��Ȃ��̂ŁA�O�o�̓S��͓n���̐��i�������A�n��̕����͕s�������������S��̗ʂł���B �z�K���_�̂��G���ł���̂ɂ�������炸�A���J�s����̏���_�Ђł͉��ƕP(�����ł�Ђ�)���Ղ�B����喽�̖��ɓ���̂Ō��䖼���_�̂��傤�����ł��邪�A�ؑ]�̐���(������)�_�Ђɂ܂��鍂�ƕP�͂��̕ʖ��ł���B�u���ƕP�v���u�S�̒n�A���t����(���b����)�P�v�Ɗw��ł���B�S�̏o��n��T�����Ă�����̏����Ȃ̂ł���B ����_�Ђ͌������낷����ɂ���B���ƕP�͌��䖼���_���x���Ă���̂��B |
|
|
�S�������_�����킷�z�K�n��(�x�m����������)�ł́A��������̏Z���Ղ���b��̍��Ղ͌����邪���S�F�̏o�y�͊m�F����Ă��Ȃ��B
�_�Ђ̐_���ɂ���^��(���킸����)�͖��N�����̒��ɁA��Ђ̌�����̕X�̉�����Ԋ^���̂邪�A�Ȃ��^�Ȃ̂��̒Nj��͂Ȃ��Ǝv���B�u����(��)��(��)�v�̌ꌹ�̈���E���Ɓu���S��(�b���)�̋M�l�v�̈ӂ�����Ɗw��ł���B�ꌹ����������Y����A�`���ό`���Đ_���Ƃ��Ďc������ł��낤���B �O�{��4���̓т̓��Ղɑ�R�̎�������ꋟ����ꂽ�����ȁB���̒��Ɉꓪ�A���̗��������邻���ŁA���Ɛz�K���_�̌×�����̊W����������́A�Ɛz�K���s�v�c�ɂ���B�u���v�̌ꌹ��m���Ă�������Β����킩��B���搶�ɂ��u���v�ŕ\�L���ꂽ�u�V�K�v�́u�S�����v��\���A���A�@�n�̐��S����\���Ƃ����B �^���������т����^���ɂ��邪�A���łɐ����������������ے����Ă���悤�Ɏv����B ���Ƃ��Ă̍����������ɂ��Ă��Z�p�͎c���Ă���B���Ƃ��ւƂ��f�t�H�������ꂽ�㊙(�Ȃ�����)���Ñ�؍���ɑ������A�u(�S)�̊J�c�̖����ԁv�Ƃ��A�u�J�c�̊��v�Ƃ��ǂ߁A�z�K���_�́u���͉�X�̏ے����v�u�z�K�͓S�����v�ƕ��Ō��̂��㊙�ł��낤�Ɛ�������B �����A�_��ɑk���āA�_�̌��������ЉƂ̒��ɒ������ɖŖS�������h��������̂ŁA���h���̌ꌹ��T���Ă݂��B |
|
|
���h�����܂��A�u�S�̏�v�Ƃ����Ӗ��̊؍���̗���(��Ƃ�)�\�L�ƂȂ邱�Ƃ�m�����B
�z�K�͂�͂�A�S�܂݂�́u�S�̏�v�ł��邱�Ƃ𐩖��������������B ����Ɍ�_���Ɩ�́u���v�ɂ��Ęb��i�߂Ă݂悤�B �z�K��Ђ��n�߂Ƃ��Ċ֘A����Ђ͌�_��Ɂu���v���f����(�t�̐��ł���Ƃ��A���̗L���͂����ł͖��ɂ��Ȃ�)�B ����s�̑P�����ⓒ���_�Ђł��u���v�ł���B �{�c�P������̏o���A�{�c���Ɋւ���ł��낤�B�{�c�����n�߂Ƃ��āu���v���p���鎁���͔��c�A�z�K�A�_�c�A����(�S��)�A����A���q�A�{��(���̒��ׂ͏[���łȂ�)���ł��邪�A�z�K�̋��q���͐z�K�ЂƐ[���q���肪���艓���������Ă��u���v�͎g���Ă��Ȃ��B �����ł́A���茧�_��̏��l����̖{������v��(����̌���)���u���v�ł���B �A���̃J�W�́u���v�Ƃ��������������A�{�e�͊��p�́u���v�Ƃ���B �M�҂��������߂Č����̂́A��Ђ⊝��s�̎牮�_������̃~�V���O�W���{�Ђ̗��ł���B�N���Ȃ̐A���������ŗt�̌`�͎R�K�Ɏ��Ă��邵�A�����������o�邪�A����̒��͋ł������B���͈ꌩ�v���^�i�X�̎��Ɏ��Ċۂ��{���{���ɖт������Ă��銴���ł������B���Y�͓���ŁA�z�K�Ŏ����͂��Ȃ������ł���B�ǂ���Ŗ�R�𑖂������q�ǂ��̍��ł��A���ڂɂ����������Ƃ��Ȃ��͂����B |
|
|
�u���v�͕��̑@�ۂƂ��Ďg�����Ƃ������Ă���B�N���Ȃł���Ƃ����Δ[���������B
��N��5�����߁A�w�܂Ȃفx���͂����B�����ɂ͕M�҂̋^��ɓ�����ꌹ�̉����ڂ��Ă����B ����܂Łu���v�̉�����u���v���u�b��v���ƒZ���Ȑ��������Ă������A�u���v���u�}(����)�v�Ƃ����Ğ�(������)�̌Ö����ƒm�����B �u�����v�́u(����)�M����v�̈ӂł���Ƃ����B�Ȃ�ƁA���S�F�̂�����(�_���E�_��)�̌ꌹ�u���ɔM����(����)�v�ɂ�������ł͂Ȃ����A�������u�S�̏�v�̐z�K�����炱���̍��v�ł��낤�B �z�K�n���ɍs���A�N�ł��A���_���܂̓`����1��2����B �����̌��̒��Ŋ���s�㌴�̊���_�Ђ̒r�̋��͕Жڂ������ȁB�Жڂ̋��͂��Ȃ���������ǁA���S�̂�����F�̃z�g�����o�S�̏�Ԃ����ߐNJ�ƂȂ����b��E���ے������b�ł��낤�B �܂��A�N���̍Ō�Ɉ�N���g�������𑗂�_��������B����̒r�ɕ�������ƁA�������B�̂��Ȃ��̒r�ɕ��ԂƂ����B ����͏o���Ȃ����A���̒r�炵�����������B �É�����O��s���q�̒r�{�_�Ђ̍����r�ŁA������ɂ͊���̒r�Ƃ҂����荇���`���͂Ȃ����A9��23���̏H���̓��ɁA�Ԕт����Ђɓ���r�ɒ��߂�u���Ђ[�߁v������A���̐Ԕт͗����A�Ȃ�ƁA�z�K�ɕ��ԂƂ����`���ƍs��������B ��Ր_�́u�S��̕P�_�v�ŁA���a�ɂ͌��䖼���������Ƃ��킷�B |
|
|
�x�m�������z�K�S�ł��邵�A��ːK�l�Êقɗאڂ�����j���������قɌ�����̓S�Ɋւ��鎑���̓W��������̂�m���Ă����̂ōs���Ă݂��B
�����͉\�ɋ^���̂Ȃ����̂ł��������A���Ђ̓s���Ŋ����������B �x�m�����͓��k���{�Ɛ�����{��2������傫�ȗځu�t�H�b�T�}�O�i�v�̒��ɂ���B���̂悤�Ȓn��ł͂��܂��܂ȍz���̎Y�o�����邪�A���S�Ɋւ��z���ł͐G�}�Ɏg���ΊD��A�}���K���A������p�ō��S�ށA�������⎥�S�z���ł���B�ؒY�ɂȂ�؎R���L���ȍD�����ŁA�������ォ�璆���܂ł̑��ƂƂ������J���S��Ղ�����A�]�ˎ��㒆�����̂��Ƃ��u�́A���̔��œS�𐁂����v�Ƃ̓`���̂��錊�̔����S��Ղ�����B �u�r�̐Ս��S�̎��Ձv������B���̒r�͑I�S�Ɏg��������łȂ��A�ۑ������˂Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B�l�Êق̔�����i����ɂ��A������������Ђ̍�����Ў�قǂ����S���̂ꂽ�Ƃ�������A�����ʂł���B ���J���S��Ղ̑��ƔN���T�邽�߂̐��S�������s���Ă���B �܂��A�䏊���ɂ͕������҉��~�Ղ�����A���҂͓n���n�̐l�Ŗq�ƍz�R�J���Ɋւ���Ă����Ƃ̍l������B �u�����v�́u�t�Z�v�́u�S�̉��S�Ă��v�u�䏊�v�́u�S�����v�Ɠǂ߂�B �ԐΎR�����̓��}�R(�ɂイ�������)�A���v�ێR(�قǂ��ڂ��)�R�[�ł́A��Â̐̂���S�R�t(��܂�)�����萻�S���s���ė����Ƃ̐���������B����ɉ���(��������)�ɂ͗��h�Ȑz�K�_�Ђ�����B |
|
|
�x�m�����̐��S�Ɋւ�肠��Ղ��������Ō������A��������ƍl���鉿�l�̂���n��ł���B
���āA���䖼���́u���̎}�v�������ĉk��_�ɏ������Ƃ������u���̎}�v�Ƃ͉��Ȃ̂��B �w�Ñ�̓S�Ɛ_�X�x�̒��҂́u���̎}�v�Ƃ́A�S�������ɂ�鍻�S�̎�̋Z�p���ے����A����̍��S�̓U���ō̂�A�U�����(�ނ���)��p�����B⥂͓����ŕ҂��̂�ǂƂ���Ƃ��邪�A������҂�⥂炵���������A�]���̎��Ȑ���Ȑ�ŁA�`���w�I�����ō��S�̑I�z�������B�O�o��⥂ł͍��S�͈����������Ă����Ȃ��̂ŁA�Ō�͍��S�ʂ̑�����茧���R���ɂ����ǔ��k(�����т���)�𗬂��A���̖������S��Ŏ��݂��B ���āA���̐�̍��S��p������������ꂽ���j������B�썻�́A�ԛ��₪���������^��(�܂�)�ƌĂ��㓙�S�ŁA���̒��ɂ́u���v���ƌ��ԈႦ��قǂ̉_�������B �������ʁA�����ʂ�A�����̂ꂽ�͉̂��ŁA����͔����������̍��S��������Ɏc�����B�ڂ̋l��ł���|�U���Ȃ�܂������A������p�����͂��߂ł���B ���Â��v���Ɂu���̎}�v�Ƃ́u��(�������)�v�Ɂu���̎}�v��p�������Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B��ɍ�p�Ƃ��ē��̎}����荞�߂����ɍ���������Ȃ��W�܂�B������A���őI�z����A�ƌ��_�Â������B�@ �@ |
|
| ���z�O�G�b | |
|
���������p�� / ���l��
7���I�㔼����10���I���ߍ��܂Ŕ��l���̎���(�݂݂���)����ɁA�s��(�����ꂢ)�ȉ���(�����)�����Ñ㎛�@�����݂��܂����B���̏ꏊ��������(�����ǂ���)�n��ɂ��邱�Ƃ���A�u�������p��(�͂���)�v�ƌĂ�Ă��܂��B ���݂͔��ɂȂ��Ă��鎛�@�Ղ���A����܂ł̔��@�����ŁA����(����ǂ�)(�{�������u���镧��)�Ⓝ�A�u��(�C�s����)�A����A���̊�d(������)(�����̊�b����)���m�F����Ă��܂��B�����Ɠ��́A8���I�㔼�Ȍ�ɁA�قړ����ꏊ�Ō��đւ����Ă��邱�Ƃ��������܂����B���͈̔͂́A��k��120m�قǂ������Ƃ݂��Ă��܂��B �╨�������o�y���Ă��܂��B�n����(��������)�̌����̌���Ɏg��ꂽ����7���I�㔼�̔��P(�͂��ق�)���̂��́B����́A�����ɂ���č��̈��J(����˂�)��}�钆�����{���A�e�n�̗L�͍����Ɏ��@���������サ�A�e�n�ő��c���i�߂�ꂽ�����ŁA�u����������(�����イ)�̏�(�݂��Ƃ̂�)�v(741)���������I�قǑO�ɂ�����܂��B �����̈�Ղł͏��߂āA�y����̕����̗���(��ق�)(�є�����)��14�_�o�y���܂����B�傫���ƌ`�̈قȂ�2��ނ����邱�Ƃ���A���@�ɂ́A���Ȃ��Ƃ�2�̂̕��������u����Ă����悤�ł��B�傫���ق��̗������琄�肳��镧���̍����́A��(��)���ł����2.4m�A�����Ȃ�4.8m�ɂ��Ȃ�܂��B �a���J��(��ǂ���������)�A���N�ʕ�(�܂�˂���ق�)�Ȃ�8���I�̓����K��(����)��14�_�o�y�B�����ł͈�̈�Ղ��甭�@�����ɂ���čł������̌Ñ�K�݂��������ꂽ���Ⴞ�����ł��B ���l������ψ���́A��N3���A����܂ł̒������ʂ����ƂɁA�������p���̉����z�u�Ǝ��ӌi�ς�`�����C���X�g(8���I�㔼����z��)���쐬���܂����B�����ɗאڂ��Ēb��(����)�H�[(���@�̌��z�E�C�U�ɕK�v�ȓS���i�𒒑�(���イ����))�A���ӂɂ͏W����Õ��Q������܂��B ���여��ɂ́A5���I�̏I��荠���獋��������A�W����z���āA�{�b��(������)(�f�Ă��̓y��)������C�݂ł̐����Ȃǂ̐��Y���x�z���Ă����܂����B6���I�ɓ���ƁA�����͌Õ�(�y�����������)��n�߁A���̈�Ɏ��q��(�����Â�)�Õ�(���l�����s(������))������܂��B ���̑S��32.5m�̑O����~���́A��(�ق�)�����͂ɏ��炵�A���u(�ӂイ)�ɉ~������(����Ƃ��͂ɂ�)����ׂĂ��܂��B�����̐Ύ�����́A�嗤�ɋN�������p�t�`(�����͂�����)�̐{�b��A���m�E�␅���̌���(�܂�����)(���g��)�A�S���̔n��Ȃǂ���������܂����B�푒�҂͎��ʎ�(�݂݂̂킯��)�䂩��̐l���Ƃ݂��Ă��܂��B �ዷ�̎��ʎ��́A�Î��L�̒��ŁA�J��(������)�V�c�̑��ɓ����鎺���É�(�ނ�т��݂̂�)�̖���(�܂���)�Ƃ���Ă��܂��B�ዷ���O���S���瑗���A�ޗǂ̓������Ղ╽�鋞�Ղŏo�y�����؊�(��������)�ɂ��A���ʂ̖����L����Ă��܂��B��������̉��쎮�_����(����������݂傤���傤)�ɋL�ڂ���A���여��ɍL�����q�������(�݂�)�_��(���l���{��(�݂₵��))�̍Ր_�͎����É��ł���A���ʎ����A���̒n���J���c����Ղ�����(�₵��)�Ƃ���Ă��܂��B ���여��́A��a(��܂�)���痈�Z���������̎q�����A���̎����Ƃ��ւ��Ȃ����400�N�ɂ킽���Ď��߂��n��ł������ƍl�����܂��B�������p���́A���̔ɉh���F�肷�鎁��(�����ł�)�Ƃ��Č�������A�������֎����邽�߂ɁA�������i�K�I�ɐ������Ă������悤�ł��B |
|
|
�������� / �z�O�s
�����炨�悻1��N�O�A�w��������x�̍�Ҏ�����(�ނ炳��������)�́A�����O��1�N�]����z�O�̍��{(������)������������(������)(���z�O�s)�ʼn߂����܂����B���A������(�ӂ����̂��߂Ƃ�)������(���傤�Ƃ�)2�N(996)�A�z�O�̍��i(������)�ɔC�����A20��̎������́A���U�ł�����x�A���ƂƂ��ɓs(�݂₱)�𗣂�ĕ�炵���̂ł��B �������́A�c������ɕ��S�����A���̌�͕��e�Ɉ�Ă�ꂽ�悤�ł��B���̈��͊w�҂ł���A�����l�Ƃ��Ă��D�ꂽ�l���ł����B���������q�ǂ��̂���A�킪�����犿�Ђ̍u�`���Ă���̂����ŕ����Ă��āA�����Ɋo�����̂ŁA���̗����Ȗ����u�j��������c�v�ƕ����Q�����Ƃ�����b���B �z�O�ɗ���O�N�A����(�����͑v�̎���)����70�l�]�肪�ዷ�ɕY���A�։�̏����q��(���Ⴍ����)(�O���{��)�Ɉڂ���Ă���A"�O����"�̏����ɔ����Ă��܂����B���́A�v�l�Ɗ��������킵�Ĉӎv�a�ʂ�}�����Ƃ����܂��B �����������̌O��(����Ƃ�)���Ĉ�����������ɂ��āA��Ƃ̐��˓��⒮(���Ⴍ���傤)����́A�u����������Ƃ͎v���Ă��Ȃ������炵���B���������͓I�ȏ��A������A�m���⋳�{�Ŕ|�������_�I���͂̂��鏗�Ǝ��F���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���v�u����Ȕޏ��͓�\�����܂Ŗ����ŁA�������蕶�w�����ɂȂ��Ċ��Ђ╧�T��Ђ��ς�����ǂ݂��������炵���v�ƒ����̒��ŏ����Ă��܂��B���ƈ���ē����́A�����̌����N���10��O������20�Ƒ��������悤�ł��B ����ҏW�����̏W�w�������W�x���畐���ʼnr�̂��݂�Ɓ|�u�����ɂ�������̐��ނ疄(����)�ސᏬ��(������)�̏��ɍ�����܂��ւ�v�A�ڂ̑O�̓���R(�Ђ̂���)�ɍ~��ς��������āA�s�̏����R�ɂ������͐Ⴊ�U�藐��Ă���̂��낤���Ǝv���A���i�̊�(�₩��)�̐l�X����ɐ�R������A��������U���Ă��A�u�ӂ邳�ƂɋA��R�H�̂���Ȃ�ΐS��䂭�Ƃ䂫�����Ă܂��v�ƁA�S�����ꂸ�A�������s�ɋA�肽���Ƃ����v����������悤�ł��B�Ƃ����̂��A�܂����Ƃ��ŁA���e�Ɠ��N�z�̓�����F(�̂Ԃ���)����A�������͋���������Ă���A���S�����Ȃ��܂܁A�h���C����������ĉz�O�ɗ��Ă����̂ł��B �����M���̐Q�a��(����ł�Â���)�뉀���Č������u�����������v(�z�O�s���畟��(�Ђ�������Ղ����傤))�ɂ́A����R�Ɍ������ė���������(���Տ��O(���������)��)��ޓa(��ǂ�)�A��(����)�Ȃǂ��݂����Ă��܂��B��̓��ɖK���ƁA�������̉̂̏�i���ڂɕ�����ł��܂��B ���������ӂ����������́A���̔C��������҂���1�N�]��ŋA���B��F�ƌ���āA�����a�����܂����A�قǂȂ��v�͕a�v�B�킸�����N�̌��������ł����B���̌�A���V�c�̒��{���q(���イ�������傤��)(��������(�݂��Ȃ�)�̖�)�̂��Ƃ�"����W"�Ȃǂ߁A�㐢�Ɏc���������ҏ����w��������x�������グ�܂����B ���a63�N���猻�݂܂ʼnz�O�s�Ŗ��N�J�Â���Ă���u��������A�J�f�~�[�v�̊ďC�Ɍg����������w�҂̌̐����D�q(���݂��悵��)����́A�u�����̍��{�̕�炵�̒��Ō��f���ꂽ�ޏ��̌����|���Ԃ̕��ʂ̖��Ƃ͈�����A�����ĒZ�������������A�n�슈���ɋy�ڂ����e���͌v�肵��Ȃ��v�Əq�ׂĂ��܂��B�z�O�����́A�̑�ȍ�Ǝ��������A�Y�ݑ����Ⴋ�����߂������v���o�̒n�Ȃ̂ł��B |
|
|
�����؏����q�� / �ዷ��
���؏����q��(�܂̂����傤��������)(�@���E����(���傤����))�́A�]�ˎ���̏��߂���̐l�B�u�Ս�(������)�ȔN�v(�˂�)�ɂ���Ĕ敾(�Ђւ�)�����ዷ�̔_�����~�����߁A���������Čy����i���A�Ⴍ���ď��Y���ꂽ�`��(���݂�)�v�Ƃ��Č��`�����Ă��܂����B���Ďዷ�̔_���ł́A�H�ɑ哤���Ƃ��ƈ�Ԃɐ_�I�ɋ����āA������̂����Ɋ��ӂ���K�킵�ł����B�������a�̒n�ዷ���ł́A���̈⓿��`���悤�ƁA�؏`�ɑ哤�����������̂��u������v�Ɩ��t���āA�C�x���g�ȂǂŐU�镑���Ă��܂��B ���؏����q��́A�ዷ�X���̌F��h(���܂��킶�キ)�ɋ߂��V��(����ǂ�)���̏����ŁA�����q����u�_���̐_�l�v�Ƃ����J(�܂�)��F��̏���(�܂̂�)�_��(���a8�N�n��)�����ɂ́A���̂悤�ȗR����(�䂢���傪��)���f������Ă��܂��B �u�փ����̐�̂��ƁA�ዷ�̗̎�ƂȂ������ɍ���(���傤����������)�́A���l�p�ɗՂމ_�l(����҂�)�̒n�ɑs��ȏ��z�����B���̂��ߗ̓��̕S���ɂ͔N�v�̑����Ƃ��J���̒ȂǑ����̕��S��������ꂽ���A���ɂ���܂�1�U4�l�ł������哤�N�v��4�l5��(�܂���5�l)����ɑ��z���ꂽ�B�����āA���̐��x�͗̎傪���䒉��(��������)�ɂȂ�A�V��t�������ĐV�������l�邪�������Ă����߂��Ȃ������B �ꂵ�݂ɂ������S�������́A�N�v���������̒Q��(����)�^�����\���N�ɂ킽���ČJ��Ԃ������A���l�˂ł͑S�����������Ȃ������B�ߔ�����(�ق��Ƃ�����)�̗}���ɂ��������A�����܂ŔN�v�y����i���������V�������� ���؏����q��́A�c��(��������)5�N(1652)5��16���A���ɓ��}(�Ђ���)�쌴����(�͂��)�̌Y�ɏ�����ꂽ�B �������A�����ɂ��ߊ�͕����͂����A�哤�N�v�̈��������͎��������B���ɏ����q���28�̎Ⴓ�ł������v �����j���Ƃ��ẮA����Ƃ̉Ɛb���(�݂˂�)�M�V������(���傤�ق�)5�N(1720)�ɗ�㏬�l�ˎ�̌��s���܂Ƃ߂������w�ʘI�p(���傭�낻��)�x�ɁA�ዷ�̏������������đ哤�N�v�̌y�����肢�o�����ƂŁA�����N(����)�����ɗ�������A��(������)�ł���V���̏���������̉������̂��߂ɏ��Y����Ɠ����ɁA���̊肢�̋������ɂ��Ȃ��Ă���Ƃ��āA�N�v�y���������ꂽ���Ƃ��L����Ă��܂��B ���Y�̌�A�����q�傪����ꂽ���}�̐�����(���傤�݂傤��)�ɂ́A����(����)2�N(1749)�ɓ��}���̐l�X�ɂ���Č��Ă�ꂽ�ܗ֓�(�����Ƃ�)������A��������ŌÂ̕�Ƃ���Ă��܂��B���̂ق���m���̏팹��(���傤����)�ɕ���(�ڂ�����)(1761�N����)�A���Y����p��ɂ͂Ȃ炸�A�����q��̎��킪�p�����V���̐��ƁE���؉Ƃɕ�(1774 �N����)�A�O��(�݂₯)�̋v�i��(���イ������)�ɕ���(1862�N����)������܂��B���l�˂̓{��ɐG��邱�Ƃ����ꂽ���߂��A����������Y���炩�Ȃ��ɂȂ��ċ��{(���悤)���s���Ă���A�u���ؒ����v�̖@�������������܂�Ă��܂��B ���ؐ_�Б���̋{�{�d������́A�u�n���A�F�쏬�w�Z�̎������A�N2��A����(��������)�̑��ނ�������Ă���܂��B������́A�ዷ�S��̔_���̂��߂ɗ����オ��A�����S��(�낤����)�ɓ�����A���̏��������X�Ɗ肢����艺���ߕ�����Ă����Ă��A�Ŋ�(������)�܂ŐM�O���Ȃ��Ȃ������l�B���̌ւ荂���������i���`���Ă��������v�Ƙb����Ă��܂��B |
|
|
�����l�ƕ��鋞 / ���l��
�a��3�N(710)�ɓޗǂ̕��鋞(�ւ����傤���傤)�֓s(�݂₱)���ڂ���Ă���A���N��1300�N���}���A�u����J�s(�����)1300�N�Ձv���ޗǎs�̕���{��(���イ����)�����C�����(11��7���܂�)�ɊJ�Â���Ă��܂��B ����{�E���鋞�Ղ���́A����܂łɑ�ʂ̖؊�(��������)(�����������ꂽ��ɒZ��(����)�`�̖ؕ�)���o�y�B���̒��ɂ́A�����A�n������s�ɉ^�ꂽ���i�ɕt�����Ă���"�D(�ɂӂ�)"����������܂��B �ޗǕ������������́u�؊ȃf�[�^�x�[�X�v�Ō�������ƁA�ዷ��(�킩���̂���)���畽��{�E���֑���ꂽ�u�D�؊ȁv109�_�����X�g�A�b�v���邱�Ƃ��ł��܂��B���̂������́A���N�j�q�ɉۂ���ꂽ���[�̐łł���u��(���傤)�v����߂Ă��܂��B�ዷ�̏ꍇ�́A�Y�X�ŊC��������ꂽ���Łu���v��[�߂܂����B �܂��A�łƂ��ēV�c�ƂȂǂ֍v�i(��������)���������������Ӗ�����u��(�ɂ�)�v�ƋL���ꂽ�؊Ȃ�19�_�m�F����Ă��܂��B�ዷ����͑�(����)���ĊL(������)�A��(�����)�̂����A����(�Ђ���)�A�C���ȂǁA�C�Y�����^��܂����B �u���v���u�сv���A�n���̖�(����)���s�։^�ԋ`�����ۂ����A�ዷ����͓ޗǂ܂ŕГ�3�`4�������ĕ����܂����B �і؊�19�_�̏o���n���݂�ƁA��(�����̂���)(���l�̐t(������)�R���ӈ��)���炪���|�I�ɑ�����13�_�A���������l�̎Ԏ�(�������)������3�_�A�ؒ�(����)��(���݂̍��l���q��(����)�여��)����1�_�A�����ĎO���S�����2�_�ł��B�{������ނȂǂ��v�i������H��(�݂�����)�ዷ�̒��ł��A���l�A�Ƃ�킯�����s�Ƃ̓��ʂȂȂ���������Ă������Ƃ��킩��܂��B 1���������ƁA���a35�N�ɕ���{�Ղ���o�y�����і؊ȂɁA�u�ዷ�����~�S�����ё����(���ɂイ�����̂��Ƃ݂ɂ���������)�c�v�ƋL���ꂽ���̂�����܂��B���~�S�Ƃ���̂́A�ޗǎ���̎ዷ�����A�O���Ɖ��~��2�S�������������߁B��(���݂̍��l����(����)�̂�����)�����̂���(�Ȃꂸ���q���y�H�i�r�̂悤�Ȃ��̂�)���тƂ��ĉ^�ꂽ���Ƃ������A�u�����v�̑��݂��L�����ŌÂ̌����j���Ƃ���Ă��܂��B �����������j�܂��āA���l���ł͍�N�A������̂̎��s�ψ����݂��A�u���ь���s��v�����B�����҂������Ď���l��(�������傤)���s���A�؊ȂɋL���ꂽ��̂�����C������̉������A�z�肳���Ñ�̐��@�ōČ����܂����B ���N4��20�`23���ɂ́A�����L�u6�l��������w�����āA���l������j�̓��u���̎I�X���v(���R(���イ����)�X��)��ʂ�A���s�o�R�ŕ���{�Ղ܂Ŗ�130km������܂����B�r���A�������J�⊦����������A�̒�������l���B�Ñ�ዷ�l�̋�тƘJ��Ɋ��������ł����B������4��24���A�u����J�s1300�N�Ձv����{�Չ��I�[�v�j���O�̓��Ɂu���ь��㎮�v�����s�B�Q���҂ɑ�̂Ȃꂸ����U�镑���A�؊ȂɋL���ꂽ���l�̗��j�ƊC�̍K(����)�̖L�������A�s�[�����܂����B ���l���ł͍��A"��������(�͂����傤)�̒n"�Ƃ��āu�ዷ�����͂��(����)�v�̃u�����h����i�߂Ă��܂��B����ɁA�u���̎I�X���v�����s���̒c�́E�l�Łu���̎I�X�����c��v��g�D�B���Y�i����������ċ��s�̋юs��(�ɂ���������)�ɃA���e�i�V���b�v���o������A�������j���[�Ƃ��āu�I���v��o���ȂǁA�A�g���Ēn��U���Ɏ��g��ł��܂��B �@ �@ |
|
| ���S�l ���s�ҏ��p | |
|
�C������_�哹�̊J�c�Ƃ������s�҂ɂ܂��`�����܂Ƃ߂����̂ł���B�u�����̊�`�D���������Ă��A���̃X�[�p�[�}���Ԃ�(�S�l�I)���g�R�g���`����Ă���B�����āA���s�҂͉��҂ł���A�ǂ̂悤�ɐ������̂��A�������������Ă͂��邪�A��X�Ɍ�����悤�ɂ��Ă��ꂽ�B���ӂ̋���Ȑl�����̊�`���ʔ����B
��́A��a����R��т̍����ł��鍂���Ύ��̎�����N�̈�l���A���ꏗ(���炽���)�ł���B�{���́A�o�_�̉��Ύ��o�g�̑�p�ł���A�����͉�y�ƕ��m�̉ƌn�ł������B��p�͑����ɖS���Ȃ��Ă���B�����͏�������B��p�A�����V�c�̗����A�u�ƌ؋n�v����������閲�����ĉ��D�����Ƃ̐_�b�A���̑��ł���B���p�Ƃ͗c���ł���A���l��̖����`���Ȃ������̂ŁA���̂܂g��ꂽ�B����6�N(634)�A���܂ꂽ�Ƃ��Ɋp���������Ƃ����B3�Ş����������A7�Ŏ��~�̎���\�����u�����B10���ɕ����̕����͂��߁A17�ŏo�Ƃ��A19�ő��(�R�ブ�x�R�n)�ł̏C�s�ɓ������B ����ł͖ؐH(��������)���Đ_�哹(�C��)�̏C�s���s���A��l�ɂȂ��Ď�X�̐_�ʗ͂A�����ׂ�悤�ɂȂ����Ə�����Ă���B���̎R�ɂ͑�������_�Ђ����Ă��B���s�҂͌�ɋg������ֈڂ��Ă���B���̓y�n�_�ł���R�_�����喾�_��q��ł���ƁA�n����F����ӕ�F���o�Ă�����������̂āA�Ō�ɋ�����������������A����ɋA�˂����B�R�ブ�x�𐼂ɉ������V��ł͏C�s���ɕٍ˓V������Ă���B�����ɓV�ٍ͕��V�Ђ������A��ɖ��ʂ֊������ꂽ�B���̂悤�ɒ����̐_���K���̑f�ނƂȂ銈�������B ���s�҂́A��B���瓌�k�܂ł̊e�n�̎R�x�M�Ɋւ��������A�C�����̊J�c�Ƃ���Ă���B�ނ���u�o�R�Ɓv�Ƃ����ׂ����낤�����ɑ����̍��R�ɓo�����Ə�����Ă���B�F�R�A�x�m�R�A�������{�_�ЁA�o�H�O�R�c�B���ł��Ă͎R�̏C���̊J�c�ƂȂ��Ă���B�܂��A�ނ͑m�p�ł͂Ȃ��A���`�Ŋe�n��������悤�ł���B���ɂ���Ȃ���܉������҂��u�D�k��(������)�v�Ƃ����B��D�k�ǂƂ��Ăꂽ�B ���s�҂͑O�S�E��S���]���Ă����B�_�哹�̐_�ʗ͂������Ă������炾�Ƃ���邪�A�u�����́A�����炭�Ñ�̑���R���ɏZ��ł����ٌ`�̎҂����ł������낤�|�ƌ����B������A�����n�̏C���҂��g������u��@���q�v�̃C���[�W�ƍ��������̂��ƁB�܂��A����R�̒n�_�ł������ꌾ��_���z���Ƃ��Ďg�����B���͊���n���̍����ł��������Y���V�c�ɔs��ĖY�ꋎ��ꂽ���͂ł���A��̊���R�̎R�l(�R��)���w���Ă���Ƃ�������Љ�Ă���B �C�����̊J�c�Ɠ����ɍz�R�Ƃ̊W�����肻���ł���B�z�R�̐_�l�́u���R�F�v�ł������B�p�\�̗��ő�C�c�q�͑�F�c�q�ɒǂ��A�g�삩��R��A�u�����o�Ĕ��Z�֗��̂т�B���̔��Z�ʼn��S�����̂��A�s�j���_(���R�F)�ł������B���R�F�Ƃ͍z�Ƃ��o�b�N�Ƃ����V���n�̌R�c�ł���B���s�҂���C�c�q�Ƃ̐����I�ȂȂ�������B��C�c�q���g��R�ɐg�����̂��A����R�̍����ł�������s�҂𗊂��Ă̂��Ƃł���B��ɓV���V�c�ƂȂ��Ď������ⓖ�����̌��݂ł����s�҂ƊW�����B�t�ɍl����ƁA���s�҂Ƃ́A���R�F�Ǝ����z�ƊW�̐V���n�����ł����������m��Ȃ��B�X�ɁA�����p�̐_�ʗ͕͂S�ς̍����ȑm��苭���Ƃ���b������B�����g��ɒ�R���鐨�͂̂悤�ł��������B �����V�c�̂Ƃ��A�؍��A�L��(�]�܉��ʓT��)��槌��ɂ����Ė��s�҂͈ɓ��哇�֗��Y�ɂȂ����B�X�ɁA���֖�l��h�����Ďa�낤�Ƃ���Ɓu�x�m���_�v���o�ē����{���{���ɂ��Ă��܂����|�Ƃ���b���ł��Ă���B���̊ԂɊ؍��A�L���͓ڎ����Ă��܂��B�V�c�̖��Ɂu�k�l�����v������āA���s�҂̌Y�͉����ꂽ�B�Q�������߂�邪�Ŏ����A���ɓn�������F��œ��肵���Ƃ���Ă���B��Ɍ��i�V�c���u�_�ϕ�F�v�̑��薼���������B�@ �@ |
|
| ���ËL�^����݂���R�M�̏��� | |
|
�u��R�����N�G���v�w��R�s���쌱�L�x�𒆐S�ɂ���
���͂��߂� ���͕���̒����ɂ��т�����R(�W��1252���[�g��)�́A�_���̏h���R�Ƃ��āA�Â�����M�ˏ㉺�̌����M���W�߂Ă����B���ɍ]�ˎ��㒆��(���E���a�N�ԁA18���I�㔼)�ȍ~�ɂ́A��R��t(��1)(��������ȍ~�͐擱�t�Ƃ���)�̊����ɂ���R�u�̑g�D�����i�W���A���́E���������͂��Ƃ��A�x�����E�b�M�z�E�[�����ʂ̏����͓S���̕s�������Ɍ܍��L���E�J��E�Ɠ����S�E�����ɐ��Ȃǂ̌������v�����߂āA����Ɂu��R�Q��v(�u��R�w�Łv)���s�����B���̂��߁A�e���ɑ�R�ɒʂ����R�����R���W���J����A�R�[��тɂ͍u�����}���邽�߂Ɍ�t���o�c����h�V��y�Y���X������A�ˁA��O��(��2)(�ɐ����s��6���E�`��s��1��)�̗l����悷��Ɏ������B��R�Q�w�����܂��������̂Ȃ��ɂ́A��ɐi�H���Ƃ��ė��ٍ˓V�ŗL���ȍ]�̓��ɋr���̂��A�Ɠ����S�E�����ɐ��E�a�C�����Ȃǂ��F��҂������A��R�ƍ]�̓��͓����̍]�˂��͂��߂Ƃ���֓������̕����V�R�̓�勒�_�ł��������B ���e�̍l�@�ł́A��R�M�̌`����m���ŕs���̎j���ƍl������u��R�����N�G���v�E�w��R�s���쌱�L�x�Ƃ������L�^�𒆐S�ɂ��āA���̊�Ղ��ǂ̂悤�Ɍ`������Ă��������������邱�Ƃɂ������Ǝv���B�{�_�ɓ���O�ɁA�ȉ��A��������R(��R���E��R���v���_��)�̗��j�ɂ��ďЉ�Ă������B |
|
|
��1�@��R���j
�O��\�����̓��[�Ɉʒu�����R�̎R���́A�R���ɑ�R�_�_���J��Ƃ���ɗR������Ƃ����Ă���B�Â��́u�Α��匠���v�ƌĂ�āA�R���ɂ͋���Ȏ��R��(�֍����_���h���)�����_�̂Ƃ����J�������v���_��(���)������B��R�M�������`�����ꂽ���͓���ł��Ȃ����A�ߋ��ɍs��ꂽ�R�����ӂ̔��@����(��3)�ł́A�ꕶ���������t�̉��]��B���y��Ђ�Õ�����̓y�t��ЁE�{�b��Ђ̂ق��A��������̌o�˚�E�o���Ȃǂ��������ꂽ���Ƃ���A���Ȃ�Â����ォ���R�ɕ�������l�X�����݂��A���̂悤�Ȑl�X�̊Ԃő�R�̎R�x�M�����X�Ɍ`������Ă������ƍl������B�Ƃ��ɓꕶ����̓y��Ђ̈╨�ɂ��ẮA���̓����̐l�X�̐M�̈╨�ł���Ƃ�����ƌ㐢�̏C���҂����������̂ł���Ƃ������ƂɌ�����������A�����Ɍ������݂Ă��Ȃ��B �Õ�����ł́A8���I�����ɐ��������w���t�W�x�̓��̂Ɂu���͕�̗Y�߂����Y�ꗈ�閅�����ĂтČ��L�������ȁv��搂��Ă��邱�Ƃ���A���͕�̗Y��Ƃ��āA���̎R�e���ւ��Ă������Ƃ�����������B�܂�10���I�O���ɍ쐬���ꂽ�w���쎮�x�_����(��4)�ɂ́A���͍��\�O���̈�Ƃ��đ�Z�S�̍��Ɂu���v���_�Ёv�������˂Ă���A�_�����̌��{�ł���_�_���̑䒠�͂��łɓV���N��(724�`748�N)�ɂ͂ł��Ă����Ƃ����̂ŁA���v���_�Ђ̑��n��8���I�O���ɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł���B���傤�ǂ��̍�����A���{�ŗL�̐_���M�ƈٍ���������炳�ꂽ�����M���Z�����a�����_���K�����͂��܂�A����ɂ��̌�A�R�x�M�����ƂƂ����C����������ɂȂ�ƁA�R�̒����ɕs����������{���Ƃ����R������������Ĉ��v���_�Ђ��Ǘ�����ʓ����ƂȂ��āA�u�Α��匠���v�ƈ�̉�������R�M���`�������悤�ɂȂ����ƍl������B ��R���̊J�n�̗R���́A�w㔌Q���ޜn�x��27�S���ƕ��Ɏ��߂��Ă���w��R�����N�x(�^���{)�Ɏ��̂悤�ɋL����Ă���B�V������7�N(755�N)�A���厛����ʓ��̗Ǖّm��(���͍��o�g�A����ɋߍ]���o�g)����R�����J�n���A�����V�c�͓��������ƈ������F�肷�钺�莛�Ƃ��A���́E���[�E�㑍�O���̑d�ł̈ꕔ���[�ĂĎ��@�o�c���s�킹���B���̌�A�V����5�N(762�N)�ɂ͍s��̈▽�ɂ��A��q�������s�������������Ė{���Ɉ��u�����ƋL����Ă���B���̌�̑�R���͌��c2�N(878�N)�̑�n�k�Ƃ���ɂƂ��Ȃ���ɂ��|��E�Ď��������A���c8�N(884�N)�Ɉ��R(�Ő��̓����ʼn~�m�̒�q)�ɂ���čċ�����A�V��@�n�̑m�������̎R�яC�s�̏�Ƃ��Ė�����ۂ����悤�ł���B �����㖖���ɂ́A��R�͍������_�Ђ̒n��(�ێR��)��{���n�Ƃ���ݒn���m���������x�z���鑌�������ɑg�ݍ��܂�A���̑������͋v�����N(1154�N)12���Ɉ��y���@(���s�s������|�c������)�Ɋ�i(��5)����A���Œ��H�@�c�̍c�@������@���q�A����ɂ��̎q�����@���傤�q�ւƓ`��(�����@�̖�220����)����Ă������B ���q����ɓ���ƁA�����������{���J�����������̌�Ɛl�ɂȂ����̂ɂƂ��Ȃ��A��R���͖��{�̔�̂��Ƃň�R���o�c���邱�ƂɂȂ����B���{�̋L�^�ł���w��ȋ��x�ɂ��ƁA����N(1184�N)�ɗ����͍��������̐��c5�����E��8����(��6)���A����2�N(1214�N)�ɎO�㏫�R �����͊ۓ���(�� ���ˎs)5��2�i(��7)���R���̂Ƃ��Ċ�i���āA�V���ו��E���^���v�Ȃǂ��F�肵�Ă���B���̌�A��R���͈ꎞ�r�p���邪�A���i�̍�(1264�`1275�N)�Ɋ��q�ɉ��������^���@�̊w�m�ł����s�[����(��8)(�̂��ɐ�O��6���E�����助�i�E)�ɂ���ĕ�������B��s�ٍ͈�(��)�~���̔�@���C����ړI�ő�R�ɓo��A�S���Ԃ̓�s��s�ɓ���B�t�ł���Ӌ��[��������^����ꂽ��̂̓S���s��������O�Ɉ�S�s���ɋF��ƁA�ڂ̑O�ɕ��{�̌`�����������ǂ남�ǂ낵���s���������p�������A�Ȃ����F����Â���ƁA�S���s�������͂ς��Ɩڂ����J�����Ƃ����B����Ɋ��܂�����s�́A���̎��̕s�������̎p���̂܂܂ɓ�̂̓S���̕s���������𒒑������B���̈�̂����q��K���ɂ�������y��(�p��)�̕s��������(�u���݂̕s���v�ƌĂ�A���݂͊o�������E���d�v������)�ŁA������̂͑�R���̕s��������(���d�v������)�ł���B ���{�Ƒ�R���Ƃ̊W�͑������R�ƁE�����֓������Ƃ�㐙�֓��Ǘ̉Ƃɂ��p������A��R���̂Ƃ��Ċۓ����E���X���A���������R�c�ۓ��R�苽���䑺(�� �����s���c�s)�Ȃǂ⏔���̑��c��̊�i(��9)���s����Ȃǂ��Ĉ�R�̌o�c�͈ێ����ꂽ�B�������A��������㖖���ɂ́A����܂ł̂悤�ȕی�͊��҂ł��Ȃ��Ȃ�����A�O������̐N���⎛���̏C�����͂̐L���ɂƂ��Ȃ��A�w�m�ɂ���R�̌o�c�͍���ȏɂȂ����B����18�N(1486�N)�̓~�ɉ��B�����̓r���A��R�ɓo�R���~�h���������y�@(�֔� �߉q�[�k�̎q�ŁA�V��@�{�R�h�̒����ɂ���F��O�R���Z�E����@���)�́A���̋I�s�̕��W�ł���w�G�L�x(��10)�̒��ŁA���̖�̑�R�͊����Ė���Ȃ������Ə����L���Ă���B���̂��Ƃ������R���������Ă���l�q������������B�퍑����ɓ���ƁA��R�͏C���҂�헪�I�ɗ��p���悤�Ƃ������c���k�����̎x�z���邱�ƂɂȂ�A��R�C�����͓͂V��@�E�{�R�h�ʑ�V(�� ���c���s�����_�Еt��)�̔z���ɑg�ݍ��܂ꂽ�B�i�\2�N(1559�N)���ɍ쐬���ꂽ�w���c���O���̖x(��11)�ɂ��ƁA���̂Ƃ��Ē��S���X��178��467������R���Ɉ��Ă����Ă���B ����ƍN���V���𐧂���ƁA�V��18�N(1590�N)�̏��c�������ɍۂ��āA��R�C�����͂��k����ɗ^���Č�����������ɓG����(��12)���Ƃ�����A�c��10�N(1605�N)�A�ƍN�͑�R�̑�l���ɒ��肵��(��13)�B���̌��ʁA��R�R������͏C�����͂���|���ĎR�����Z�͐��m(�w�m)25���Ɍ��肷��ƂƂ��ɁA�@�|��V��@����Ë`�^���@�֓]�@�����A���͍�������(�� ���ˎs)�̐����q�@�Z���A�@����Y(���c���������o�g�A��{���o�@�J�R)���R������w���ɔC�����Ĕ���V(�\��V�̕M��)�ɏ�Z�����邱�ƂȂǂ𖽂����B����ɖ��{�́A�c��13�N(1608�N)�ɂ͌��w�̂Ƃ��Ď��Y�ɏ����ы�(�� �`��s)57�Η](��14)���A���X�N�ɂ͎��̂Ƃ��č�{�����~72�Η]�Ǝq�����̈ꕔ27�Η]�A������100������n�Ƃ��Ċ�i���A�o�ϓI�ȕی��^����(��15)�B���Ɂu���i�̑�C���v�̍ۂɂ́A�O�㏫�R ����ƌ��͑��c��1���������t����ƂƂ��ɁA�t���ǂ��R�������j�ꎮ���܂߂đ�Q�Ƃ��ē�x���Q�w(��16)�����Ă���B����A���R�𖽂���ꂽ�C���҂����͒�R�̎p�������������тƑ�R�̘[�ɋ����\���A�Ȍ��t�Ƃ��āA�V���ɏh�V�E�y�Y�����o�c��F���E�h�Ɖ��Ȃǂ̋��銈�����s�����Ƃɂ���āA�����̎x���邱�ƂɂȂ����B���̌��ʁA��R��O��(�`��s���ɖ��ђ��A�ɐ����s���ɍ�{�E��ׁE�J�R�E���i�E�ʏ��E�V����6��)�̌`���Ƒ�R�u�̐M���̊g�傪�B������邱�ƂɂȂ����B���������ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�w�J���L�x(��17)�ɂ��ƁA��R�u�͑��́E�������𒆐S�ɖ[���E�b�M�z�E�x�����ɓ��S�~�I�Ɋg�債�A���u��1��5700�A���h�Ɛ���70�����ɂ��B���Ă���B �������A�������N(1868�N)3���ɖ����V���{�ɂ���Đ_�������߂����߂���A�S���I�ɔp���ʎ߉^���̗��������r��钆�ŁA��R���͂��̐�����Ď��ꂽ�B���̋��Ղɂ͐V���Ɉ��v���_�Љ��Ђ��������ꂽ���߁A��R���͏���̓r���̌��ݒn(�����}�@�n)�ɁA����18�N(1885�N)�ɖ����@�Ƃ��čČ�����A�吳4�N(1915�N)�Ɋω����ƍ������Ă悤�₭�J�~�R��R���̋��̂ɕ������B |
|
|
��2�@�u��R�����N�G���v�̐��E
��(1) �u��R�����N�G���v�̏��{�ɂ��� ��R�M�������������w�i�ɂ́A�u��R�����N�v�̖��Ԃւ̗��z����݂����Ǝv����B�����N�ɂ͐^���{�Ɖ����{�̓�n�������݂���B�������X���E�����p���q���E��ؗǖ����̘_�l(��18)�Ɉˋ����Ď����̌����������ƁA�O�҂͊��i14�N(1637�N)�̔N�L��������{�����S�������߂Ƃ���11�_�A��҂͋��\5�N(1532)�̔N�L�������ˎs�����ٖ{�����߂Ƃ���13�_�A���v24�_���m�F(��19)����Ă���B�O�E��҂Ƃ����ꂼ��̓��e�\�L�Ɏ�̍��ق͂�����̂́A��T�ɂ����ē��e�\�����̂��̂ɂ͑傫�Ȉٓ��͔F�߂��Ȃ��B�{�e�ō̂�グ��u��R�����N�G���v�̕��ˎs�����ٖ{(��20)�́A�㊪(�����E�G��e11)�E����(����13�E�G��12)2�����琬��A���̐���N��͉����ɁA�u���\(���\)�ܐp�C�N�e��(9��)�\�O���v�Ƃ���B�܂������͗S���V��^(�ɐ����s����ψ���{�ł͍֓����q�O1���A����s����ψ���{�E��R���{�ł͋k���сA���t���ɖ{�ł͓��R�q��R�r���������A���c�s���y���{�ł͕����ɐD���o)�������L���A��^�͂��̊G�������C���҂Ǝv����匹�V(�s��)�E���w�@(���w�V��)(�ɐ����s����ψ���{�ł͕V�q��R�e�V24�V�̈�A�g��̑��v���r�����A����s����ψ���{�ł͑�R���ɐ��V�q�{�R�E�V��C���r���A���c�s���y���{�ł͖@��S��V�q��R����l�E���d�r)�ɕ�[�E�{������(��21)���Ƃ���������B����ɊG�M�҂ɂ��ẮA�ɐ����s����ψ���{�ɐ������V�~�E�������E�q�傪�f�ڂ����݂̂ŁA���̏��{�ɂ����Ă͑S���s���ł���B ���q�̔@���{���N�͉����{���N�G��13�_�̒��ōł��Â��A�e���N�G���̓��e�\���ɂقƂ�Ljٓ����F�߂��Ȃ����Ƃ���A�㐢�̍]�ˎ���ȍ~�̉��N�G��(�勝���N�q1684�N�r����̈ɐ����s����ψ���{�A���\12�N�q1697�N�r����̓���s����ψ���{�Ȃ�)�̊�ƂȂ����ƍl������B�ȉ��A�{���N�G����E��2����ǂ݉����Ȃ���A��R���J�n�Ɋւ��쌱杂̊T�����Љ�邱�Ƃɂ��悤�B ��(2) �u��R�����N�G���v�̓��e�ɂ��� ���㊪ �́A���͍�(�w���厛���玄�L�x(��22)�ł͋ߍ]�����ÁA�Պ֎t�B�w�����ߏ��x(��23)�ł͋ߍ]���u��A����ɑ��͍�)�̍��i�ɑ�Y��v����(�^���{�E�w���厛�v�^�x(��24)�ł͎������Y��v����)�Ƃ����M�S���ƂĂ������l���������B40�ɂȂ��Ă��ނɂ͎q�����Ȃ��������߁A�@�ӗ֊ω�����(�^���{�ɂ͋L�q�Ȃ�)���āA�ȂƂƂ��ɂ��̑����Ɏq����������悤�Ɉ�S�s���ɋF�O�����k��1�i�l�B�����̂��ƁA�����v�Ȃ̖��̒���80�قǂ̘V�m(��R�̎߉�)������A���ӕ�F�̉��g�Ƃ����@�،o�ꊪ�������āA���������悤�Ɏp���������k��2�i�l�B���̌�Ԃ��Ȃ������v�Ȃɂ͕��E��F�̉��g���Ǝv����قǂ̒j�q���a�����A�����̐l�X�������ςȏj�����đ�ɗ{�炵���k��3�i�l�B�Ƃ��낪���a����50��(�ɐ����s����ψ���{�E����s����ψ���{�Ȃǂł�70���A�^���{�ł�50��)��A���ꂪ�쌴�ɏo�ĐԎq���݂����Ă��錄�ɁA���ė������F�̘h�ɂ����ꂽ�B�v�Ȃ͔ߒQ�ɕ����l�������Ɏ��s�����ĕK���ɐԎq��q�ˋ��߂����A���̍s���͝��Ƃ��Ēm��Ȃ������k��4�i�l�B ���̍��A�ޗǂ̓s�Ɍ����̌��w�Œm�����l�̊w�m������A���̖����o��(�^���{�ł͊w���A�w�����ߏ��x�E�w���厛�v�^�x�ł͋`��)��l�Ƃ������B�ނ͂��鎞�A�������t���ӕ�F�����Ղ��ĕ��@���O�߂đ剾�����������閲�������B������o�߂Đ[�R�ɕ�������傫�ȓ��(�ɐ����s����ψ���{�ł͐��A�^���{�ł͟J��)�����グ��ƁA���̎}�̌��ԂɐԎq�̋����������B��������Č���ƁA���F�̘h�����̒��ɐԎq�������Ă����B�Ԏq��D����낤�Ƃ������A�h����R�������ߎ�ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������k��5�i�l�B�����Ŋo����l�͔O�����̕s�������Ɂu���������Ō������Ƃ��^���ł���Ȃ�A���̎q���ܑ̖����ɂ��Ď��߂������v��7���ԋF�O�����Ƃ���A������1�D�̉�(���ˎs�����ٖ{�̂�)������A��l�ɂ��̎q����n�����B����Č���ƁA���̎q�͋т̎Y�߂�Z���A���̗��ɂ͒a���̔N�����L���Ă��邱�Ƃ��畃�ꂪ���鎖��m��A���낢��Ɛq�˂Ă݂����{���o�����Ƃ͂ł��Ȃ������B���̊ԁA�o����l�͂��̎q��̂悤�ɑ�ɗ{�炵�A���̈����ɂ��u���h���q(�w�W�x(��25)�E�u���厛�啧���N�v(��26)�ł͋��h��l�A�w���厛�v�^�x�ł͋��h��F)�v�ƌĂk6�i�l�B �₪�āu���h���q�v��19�ɒB�������A�t���̊o����l�͗ՏI���}���邱�ƂɂȂ����B���q�͋�ꉂ�炵�A����ɎO������l�𗈌}����Ŋ��̌��i�����͂��������k��7�i�l�B���̌㓶�q�́A��l�̂��߂Ɏ������_�������A�����{���Ƃ��āu���������A�V���ו��A�������@�A���v�O���v���Ђ�����F�O�����B����Ƃ��̐M�͂��ʂ������A�{���̋r�Ɋ|���Ă����ܐF�̎����V�c(�����V�c)�̉��{���Ƃ炵���B�s�v�c�Ɏv�����V�c�́A���g��h�����Ă��̌�����T���������Ƃ���A���̌����������_���̌����甭���Ă��邱�Ƃ�m�����B�����Œ��g�����q�ɂ��̗��R��₢�������ƁA���q�́u�����ɂ͋������@�̋C�����͂�����̂̎��͂ł͂ǂ����Ă��K���������B�V�c�̈Ќ��𗊂�ɂ��đ剾���������������v�Ƃ̎�|��`�����k��8�i�l�B���g�����q�̈ӎu��V�c�ɓ`����ƁA�V�c�͑�ϊ�сA��}���œ��q�������グ�A�u���܂Ŏ��������͂�����̂́A�K�ȕ����̎t���Ɍb�܂�Ȃ������B����͂��O���t���Ƃ��A���̕���q�ƂȂ�v�ƍ������B������ē��q�͏o�Ƃ��ėǕقƉ��������B�������Ă��邤���ɁA�Ǖق͎��̌��ЂƂ����A�����C�s�Ƃ����A��������ɏG�łĂ����̂ŁA���厛(�O�g�͋�����)���������A���̕ʓ��ƂȂ����B�،��@�̊m���͂��̎��_����n�܂�k��9�i�l�B ����A�����Ԉ����q��T�����߂Ă��������v�Ȃ́A�Z�݊��ꂽ�Ƃ������̂āA�Y�]�Ƃ��ʂ�ď������̗��ɏo���B�K����䅓�h��ɑς��Ȃ���킪�q�ɉ�Ȃ����Ƃ�Q�����Ă����k��10�i�l�B�悸�͓����ɐS�̕����܂܂ɗ��𑱂��A�������ƍⓌ�Ƃ̋��̈����G��Ɏ���A�����ŗ��l����䂪�q�̏��邽�߂̎藧�ĂƂ��Đ�̓n��������B�����ő����̔N�����₵�����A���̐��ʂ��ʂ܂܁A�n��͎~�߂邱�Ƃɂ����k��11�i�l�B ������ ���̌�A�����v�Ȃ͓��R�����o�R���ĐM�Z���ɏo�āA��U���͍��R��̗��ɋA�҂����B�̏Z�݊��ꂽ�ꏊ�͌���e���Ȃ��r�p���A�����܂Ɉ�Ԃ���ł������B���̒n�Ɏ~�܂邱�Ƃ��v�����Ȃ��A���C��(��B)��ڎw���čs�����ƂƂ����s��1�i�t�B���C����ڎw���ċr�ɔC���Đi�ނ����ɁA���̓n���ɓ��������B�����ŕ֑D��҂��đD�ɏ�����Ƃ���A���̓n�炩��u��������T���Ă���̂��v�Ǝ��₳�ꂽ�B�����́u���ǂ��͑��͍��̏Z�l�ł��邪�A����70��(50���̌��)�ɂ��ĉ䂪�q��h�ɝ����A���̎q���̍s����T�����߂āA�����Ă���Ԃɐ���Ƃ�������ď���������Ă���̂��v�ƌ�����B����ƁA�n��́u�����݁A�ޗǂ̓s�ɐ����V�c�̕����̎t���Ƃ��āA���厛�̕ʓ��Ǖّm���Ƃ�����������������B���̕��͘h�̑�������o�����l�ƕ����Ă���B�Ⴕ��������A���̕��������ɂ��O����̂��q����ł͂Ȃ��̂��B�q�˂Ă݂Ȃ����v�Ƙb���Ă��ꂽ�B�������ۂ�A�����v�Ȃ͐S�������������ׂ����悤�Ȏv���ŁA�}���ޗǂ̓s�ւƌ��������s��2�i�t �s�ɒ����������v�Ȃ͑������厛�̕ʓ��V��t���@�t�ȂǂɎ��̎����b���Ă݂͂���̂́A���ɗ�W�Ȏd�ł����Ė�O�ɒǂ��o�����s��3�i�t�B�v�Ȃ��啧�a�̓���̖T��ɑe���ȏ����|�������ĉ炵�Ă���ƁA�Ǖق����܂��ܓ����ւ̉����F������A�҂��Ă����B�Ǖق͘V�l(����)�̕����獷�����ތ��ɋC���t���Ă��̗��R��q�˂��B�����Ŏ����͎��̎q�ׂ����ؒ��J�ɐ��������Ƃ���A���̘e�̉��ɂ���O�̍��q��Y�߂ɋL���ꂽ�a���̔N���Ȃǂ���A�������T�����߂Ă����䂪�q�ł���ƒf��ł��A�����Ђ�����ܗ܂̑ΖʂƂȂ����s��4�i�t�B�Ǖِe�q�̑Ζʂ̕��������ɂ��������V�c�́A�����ɏ��a���ĉb�����鋖��^�����B�V�c�͎����ɍĂё��͍��̍��i�ɏA�����Ƃ𖽂���ƂƂ��ɁA�Ǖقɗ��e�ƂƂ��ɑ��͍��ւ̈ꎞ�A����F�߂����A���m�Ƃ��Ă̗_�ꂪ�������ߑ��͍��ł̕��@�O�ʂƏO�����v���ʂ������Ȃ�����ɏ㗌���邱�Ƃ𖽂����s��5�i�t�B���Ȃ����đ��͍����q�̗R�䋽�ɋA�҂��������͋��Ղ̒n�ɉ��`�c���A�ݒn�������Đ���ȉ����Â����s��6�i�t�B���鎞�A�Ǖق͏��l�̋��͂đ��͍����ŕ��@�O�ʁE�O�����v�̂��߂ɑ��������ꏊ��T�����߂��Ƃ���A�傫�ȎR�ŎR�����������R������Ɏ������B�����ł͕����R�`�����L�q����Ă��邪�A����͌×��R�x�C���n�̉��N�ɂ悭�̗p������@�ł�����s��7�i�t�B�Ǖق��擱���ĎR���ɓo��A��������R�����L����3��(9���[�g��)�E�[����2��(6���[�g��)�قnj@��ƁA���̒�����s�������̐Α����o�������B�l�X�́A���̕s�������̎p�����Ėڂ�ῂݑ��|���邪�A�Ǖق̉����F���ɂ���Č��̂悤�ɑh�����B���̍ہA�s�������͂��̎R�͖��ӕ�F�̏�y(�����V��y)�ł���ƌ�����s��8�i�t�B�����ŁA�Ǖق��s�������̎p�Ԃ�Α����瑼�̕��Ɉڂ��ς��Ė���̏O�����v��}�낤�Ƃ����Ƃ���A�R�̓���ɂ������̑���̎}���A�l����|�����@�����̍����֗��������Ǝv������A�����ɋ�ɕ����オ���Č��݂̋����̑O�ɗ��������B�Ǖق͂��̖������ɕs���������ڂ��ς���Ƃ��Ė͍����n�߂����A���̑��D(�p�E�炩����)���������Ȃ������ɕs�������̋��̕ӂ肩���(���̑�R�����N�G�����{�ł͌�)���o�ė����̂ŁA����̎���x�߂��B���̏�ʂɂ͖{�����Ŗ͍�����Ƃ�����ؐM������������s��9�i�t�B���̑����̑O�ŗǕق�21���Ԃɂ킽��F��E�F�����s�����Ƃ���A���R�Ǝl�\��@(���ӌo�ɏo�Ă��銕���V��y�Ƃ������z���̂��ƂŁA�����ł͖��ӕ�F�̉��g������)���o�����A�s�������́u�������t�������@�@�Ԟِ����Ǖف@��R�����앧���@���@�O���{���y�@���n��������@�����O���s���Z�@���쐼���\�����@��`����ז{���@���R�ܕ��\�`���@�ܑ喾�������@��x�Q�w�������@�Ɠ����������a�v�Ƃ���12��̘��������s��10�i�t�B����ɗǕق������̊�(���k�̕���)�̒J�ɂ����A�̉��̒r�̒[�ŁA7���ԋF���������Ƃ���A�r�̒������ւ��o�����A�u�����͑�R����삷��k�֑剤(�^���{�ł͐[���U�ב剤)�ł���B�����ԍr�_�ƂȂ��Čܑ�(���E���E�ϔY�E�O���E�����̈���)�ɐ��܂�A�����̐^����ق��Ȃ��������̂ɂ��̂悤�Ȏg���邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B�����݁A�Ǖُ�l�̖@�{�ɗa���邱�Ƃɂ���Ċ����V�̓��@�ɐ��܂�ς�邱�Ƃ��ł����B����ȍ~�͑�R�ɐ�瑂��đ�R������삵�A�O���𗘉v�������v�Ɛ鐾���A�u�l�\��@�����O�@�����s���ד��@�@��ؓV�l�F�e���@������ސ����@�됅�������q���@�O���ϔY��d�q�@��؏����F�ގU�@�����㐢�����݁v�Ƃ���8��̘��������B�����ɂ͖{�n�Ƃ��Ă̕��E��F�����̏O�����~�ς��邽�߂Ɍ��ɑ��(�^���{�ł͗��_�A��@�P�_)�Ɏp��ς��Đ�瑂����Ƃ����A�{�n��瑐��Ɋ�Â��T�^�I�Ȑ_���K���̌`�Ղ�ǂݎ�邱�Ƃ��ł���s��11�i�t�B��ւ͑�R�ɐM�S����l�X�ɗ��v�������炵�A�ՏI�̍ۂɂ͔ނ����y�Ɉ������A������Nj����đӖ��S������҂ɂ͔���^����Ɩ����̂ŁA�Ǖق͑�ւɎQ�w�҂̕X��}���Ĉ�̗����������Ă����悤�ɍ��肵���Ƃ���A��A�̒�������ꐅ�𗎂Ƃ����B���̑ꐅ�Ƃ́A�^���{�ł́u���_�͓�d�̑�̎�l�v�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ���A�u��d�̑�v�ƌ��Ȃ��Č��Ȃ��ł��낤�B���̒i�Œ��ڂ��ׂ��_�Ƃ��ẮA�����ɂ͈�؋L�ڂ���Ă��Ȃ����s��(�C�����̑c�A�����p)���G��̒��ɓ�S�_�ƂƂ��ɓo�ꂷ�邱�Ƃ���{���N�G���ɂ�����C�����̉e�����_�Ԍ����邱�ƁA�G��ɗ���(���)�̏o���Ɛ��C��������Ă���C�s�҂̎p���`����A��R�M�̍����̈�ł���A��R���Ɛ��ɊW�������������������ƕ`�ʂ���Ă��邱�Ƃ���������s��12�i�t�B �������āA��R�ɂ͎��X�ƕs�v�c�Ȋ���̐�����g�̕��E��F����O�Ɍ��o���āA�O���𗘉v���邱�Ƃ͐̂��獡���݂Ɏ���܂Ŗ����邱�Ƃ��ł���B�܂���R�͓��{���R�ŁA���E���E��E�k�̒��]�Ɍb�܂ꂽ�i���n�ł���A�_���̏h��_���ȎR�Ƃ����ɑ��������B�����E���O�E�o���E�O�d�̓��E�s�������̎Вd�����߂Ƃ��ď�������������A�܂����ӕ�F�ɊW���������V��y���ے�����l�\��@�̖V�ɂ��O����ׁA�����d�ˁA���X�ō��T����E�w��C�s�̋s�͐₦�邱�Ƃ͂Ȃ��A�o����E�̗�n�Ƃ�������������B�������Ă��邤���ɁA�Ǖق̑�R�ł̑ؗ���3���N�ɂ��y�B�����V�c�Ƃ̖���������A��R�O�k�͕]�c���J���A�ǕقȂ���̑�R���̔ɉh�Ƌ������@���ێ��E�������邱�Ƃ����肵�Č���(����s����ψ���{�E��R���{�͌��ƁE���ƁA�^���{�͌��ƁE�V�c)�֑t�����邱�ƂŏO�c�ꌈ�����B�����Ă���ɑ�R�̗l�����X�̊����V�c�ɑt�サ���Ƃ���A�V�c����ϊ��ň��[�E�㑍�E���͍��̏��̂̈ꕔ�����̂Ƃ���|�̖��߂��������B���̑[�u���u�����邱�Ƃɂ���āA��R���͂܂��܂��ɐ����A���@�E���@�Ƃ��ɗ������ēV���ו��A���y�������B�����ꂽ�B���鎞�A�s�������͗Ǖقɑ��邵�āA�u���{���̑�V���͑S�Ď����̎x�z���Ɏ��߂��B�V��������A���y���s���ƂȂ�A���E�J�E���E�̍Г�N���������ɂ́A��R�ɎQ�w���ĉ����F��������A�Г�͑��₩�Ɍ������A���y�����ɂȂ�ł��낤�v�ƌ�����s��13�i�t�B �ȏオ�u��R�����N�G���v�̊T���ł��邪�A���ɂ��̒��ɓo�ꂷ�鑊�͍��̍��i�A��Y��v�����A���̎q�ǕقƑ�R�Ƃ̊W�ɂ��āA��l�@�������Ă݂邱�Ƃɂ��悤�B ��(3) ��Y��v�����ƗǕق̏o�����߂����� �u��R�����N�G���v�ɓo�ꂷ���Y��v�����y�т��̎q�Ƃ����Ǖق̏o���ɂ��ẮA���Ɏw�E���Ă������悤�ɁA���͍����A�ߍ]�����A�ܒ���(���͍��a���E�ߍ]���ڏZ)������A�܂����̑����ɂ��Ă��A���������E�S�ώ����A�S�όn�n���l���Ƒ��������(��27)�Ƃ���ł���B �w��R���N�x(�^���{)�ɂ́A�u�Ǖَґ��͍����q�S�R��(��)���l��A�����������A�����Ǐ��������Y��v�����q��v�ƋL�ڂ���Ă���B�܂��A����4�N(1337�N)�̉��������u���厛���N�G���v�ɂ́A�u�Ǖّm���ґ��͍����(�Z)�S���E�]���m�����m���l��v�Ƃ���A����Ɂw���厛�v�^�x�ɂ��u�m���ґ��͍��l��������v�Ƃ��邱�Ƃ���A�Ǖٕ��q�����͍��������Ɩ��ڂȊW��L����l���ł���ƂƂ��ɁA���̑�����Ղ����͍����q�S�R�䋽����Z�S���E�̉��ꂩ�ɑ��݂����Ǝv����B���̗��҂��r�������A�ǕقƑ�R�Ƃ̊W�A�����ƒn�`�E�n���A��R�Ƃ̎��ߋ����ɂ��闧�n�����A�L�͌Õ��̕��z���X�����Ă���ƁA���q�S�R�䋽������Z�S���E(�� �`��s�k��t�߂ɂ́A���E�E��v�v�ۂ̎��������݂���)���ɂ킩�ɒ��ڂ���Ă���B �Ƃ���ŁA�Ǖق̕��e�Ƃ���鎽��(����ɐ����E���J)���Y��v�����Ƃ͈�̔@���Ȃ�l���ł��낤���B���̐l���ɔ�肳���l���Ƃ��āA���̓����Ɏ��݂����������ɔg�������邱�Ƃ��ł���B���͍��̍����ł���ɔg�ƒ������{�Ƃ̊W�����������j���Ƃ��ẮA�w�����{�I�x�V��20�N(748�N)2���p����(��28)����������B����ɂ��ƁA�u�m�������i�����l��(����)�]���ʏ��(��)���ɔg���O�]�܈ʉ������N�v�Ƃ���B�w���厛�v�^�x�̋L�^���琄�l����ɁA���̎��̏����͓��厛��Ḏɓߕ�(�啧)�����ɍۂ��āA10���̑�ʏ��z����҂̈�l�Ƃ��āA�ɔg���g��2���[���̏��z�𓌑厛�Ɋ�i�����s�ׂ̌��т����I�ɔF�߂�ꂽ���̂ł��������Ƃ���������B���̎�������A�ɔg�����͍��ɂ����đ����Ȍo�ϗ͂�ۗL����ƂƂ��ɁA�����Ƃ̖��ڂȊW��ۗL����l���ł������Ɛ��l���Č��Ȃ��Ǝv���B �܂��A�w���厛�����x�ɂ��ƁA�ɔg�͓V����5�N(761�N)�ɓ��厛����ےÍ������S���w���̖x�]��Y(��g�Â̌�ʂ̗v��)�����Ă���A�ɔg�̍L�͂Ȍ��Պ����Ɠ��厛�Ƃ̖��ڂȌ��ѕt�����w�E���邱�Ƃ��ł���B����ɁA�w�����{�I�x�_��i�_2�N(768�N)2����Џ��ɂ́A�b������(���������C)�̗�(764�N)�̒����̌��J�҂̈�l�Ƃ��Ĉɔg���������A���삩��O�]�܈ʉ�����]�܈ʉ��M�Z�������^����A�u��v�v�Ə̂����ɑ��������ʊK����������ق��A�u��(��)���ɔg�j���̓m�h�H�����q�A���͍��m�����g�׃X�v�Ƃ���B�����Ɍ����鍑���͑剻�O��̂���Ƃ͈قȂ�A������u���ߍ����v�����́u�ߐ������v�ƌď̂������̂ŁA���̐E���ɂ͖{���y�т��̏o�g�҂��ꍑ�ꖼ�C������A���̑����͐_�_���J�ɏ]�������A�Ƃ̐�w�̎w�E(��29)������A�ɔg�̏@�����J�̎��s���ʼn߂ł��Ȃ��Ƃ���ł���B �ȏ�̍l�@����A�u��R�����N�G���v�E�u��R���N�v(�^���{)�Ȃǂɓo�ꂵ�A�Ǖق̕��e�Ƃ���鑊�͍��̍��i�A�������Y��v�����Ƃ͎������ɔg���̐l�ł���A�ނ͒��Ƃ�����a�������̐��������Ƃ���A�����������̌n���������n�������ŁA���͍���Z�S�̑�R����(�� �`��s�k��t��)�ɖ{�ђn��L���Ȃ��琨�͂�L�������A�₪�ē��厛��Ḏɓߕ������ւ̊�i�s�ׂȂǂ��_�@�ɁA�����ւ̐i�o�����݁A�����I�E�o�ϓI�E�@�����J�I�n�ʂ��m�����Ă��������̂ƍl������ �B |
|
|
��3�@�w��R�s���쌱�L�x�̐��E
�����ɍ̂�グ���w��R�s���쌱�L�x(��30)(��R���{�A�S15���E15��)�́A��R�������{�q�@(12�V�̈��)�O�Z�E �S��(��31)������̌������t������̕����������Ƃɂ��Ă܂Ƃ߂����̂ł���B����4�N(1792�N)�ɁA�u���� �䏑�[ �o�_���a�� �������Z�v(��32)�����Ƃ��ďo�ł���A�S�̂�131�b����\������Ă���(�y����1�z�Q��)�B�o�ł̖ړI�́A�{���̉��t�ɂ��ƁA�u��������{��ꕔ�V�����O�S�D���A�Ɩ�ɉh�E���Љ����E�敟�����E���c���萬�A��v�Ƃ��邱�Ƃ���A��R�ɐM�S�����Ďu�Ƃ����ꂼ��v���v���̗l�X�ȋF������߂āA���̂悤�ȏo�Ŏ��ƂɎQ���������Ƃ��M���m����B �o�ł���ɓ������āA�m�E��������34���̎^���E�o���҂�����A���̓���͑O�҂ł͑�R���W�҂���M(�o�œ��Y���̑�R����V�ʓ��E��13��)�O18���A�ˑ����@(�� �ɐ����s�E�Ë`�^���@)�E�Γc�������@(��)�E�]�ˉ��q(�� �����s�k��)�G�f�A��҂ł͍]�˒��l���i�x��(�� �����s���c��)������a�O8���A���͍��Z�l���������S���c��(�� ���c���s)���ܕ��q�O3���ł���B�Ȃ��A���s�����͑�R���W��(����3���͑�R��t)��19����24���A�Ë`�^���@�W�҂�3����3���A���l�ł͍]�˒��l��9����11���A���͍��Z�l��3����8���A���v34����46���𐔂���B�o�Ŕ�p�́A���q�̉��t�Ɏ{��ꕔ�O�S�D������v�ҕ��S�Ƃ���Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�����̍]�˂̑���ł͕S�D����4���~�ƎZ�肳���̂ŁA�ꕔ�O�S�D�̏ꍇ�ɂ͖�4���~�~3����12���~�ƂȂ�B����ɂ���ɑS�̕�����46�����悸��ƁA�����v���z�͖�552���~�ɏ��B�����̈���E�o�Ŏ����ĉ��̕ϓ��Ȃǂ��l���ɓ����ƁA��L�̂悤�ȒP���v�Z�ł͍ς܂���Ȃ�����������Ƃ��Ă��A�Ƃɂ��������̏W���͂��K�v�Ƃ��ꂽ���Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �w��R�s���쌱�L�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�b(�A���A��1���E��1�b�`����6�b�͑�R�����̂��̂̋L���ō\������Ă���̂őΏۊO�Ƃ��āA��2���E��7�b�`��15���E��131�b�܂ł�125�b���l�@�̑ΏۂƂ���)�́A�ǂ̂悤�Ȏ藧�Ă��u����Α�R�s�������̗쌱�������A�o�ŖړI�Ɍf���Ă���悤�ȍ��ڂ�B�����邱�Ƃ��ł���̂����A���������ƍ��m���邱�Ƃɂ���āA��R�M����w�g��E�[������̂Ɉ��̖������ʂ������ƍl������B ��(1) �n�敪�z�̕��� �w��R�s���쌱�L�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�_�ސ쌧���W�̗쌱杂�66�b�ɋy�сA�S�̂�50�������߂Ă���B���ł��Ƃ�킯�A��Z�S(�� �ɐ����E���ˁE�`��s��)�̂����32�b(������48��)�ɂ��B���A���|�I�ɑ��n��Ɣ�r���ČQ���Ă��邱�Ƃ����ڂ����B���ŁA�������S(10�b)�E�����S(8�b)�E���b�S(6�b)�E������S(4�b)�ƂȂ��Ă���A�����̕�����(�� ���l�s�E���s��)�͋ɏ��ł���B����͍�� �S���̋��Z�E�s���͈͂Ƃ���������ƁA��R�̐�߂�ʒu�ɋN�����Ă�����̂ƍl���Ă悢�ł��낤�B ����A���O�n��̋L���ɖڂ�]���Ă݂�ƁA59�b�̂����]�ˎs��(21�b)�E������(11�b�A�A���A�]�ˎs���y�ь��_�ސ쌧�������)�ɂقڏW�����Ă���A���Ɩڗ����ł͉��썑(���Ȗ،��A11�b)������������x�ŁA�헤��(�� ��錧�A3�b)�A�x�͍�(�� �É����A2�b)�A�b�㍑(�� �R�����A2�b)�A��쌧(�� �Q�n���A2�b)�A������(�� ���k�n���A2�b)���X�A�ɏ��ƂȂ��Ă���B���̂悤�Ȍ��ʂ́A��R�̐M���̕��z��m���ŋM�d�ȑf�ނ���Ă�����̂ƍl������B���ɁA���̒��ő�R�̐M���Ƃ͑啝�ɊO���o�_���̏��̘b���o�Ă��邪�A����͕v���]�˂̏����^�̉��~�ɕ���ɗ��ċ}�ɏo�z���A���̌�o�Ƃ��Č����Ɩ����A��R���̖{���ɂ���s�������̓������Ƃ��Ďd���Ă��邱�Ƃ��m�炸�ɁA�v��{�����߂ďo�_�����疺�ƂƂ��ɍ]�˂ɏo�ė�����q���A��R�ւ̐M�S�ɂ���ĕv�ɏ����A�e�q�O�l�Ŗ����ɏo�_���ɋA�҂����Ƃ������قȗ�ł���B ��(2) �N�㕪�z�̕��� ���ɋL�ڂ��ꂽ�N��ɒ��ڂ��Ă݂��ꍇ�A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ�������ł��낤���B�]�ˑO��̘b��͂�������3���ŁA����͑]��Z�킪�s�������Ɋ菑������Đe�̓G�������ʂ�������(��10���E��81�b)�A���͍��P�g���Y���Α��̗쉞�ɂ���Ĕ����{�Ƃ��Đ��߂�ꂽ��(��8���E��75�b)�A�b�B�̋��Y��苗������c�M���̑����̋��S�������F���ɂ���ĕ�����������(��4���E��32�b)�ł���B����ȊO�͂��ׂč]�ˎ���̊��i�N��(1624�`1644)����w��R�s���쌱�L�x���o�ł��ꂽ����4�N(1792�N)�܂ł̘b��ł���B���ł��Ƃ�킯�A���a�E���i�N��(1764�`1781�N)�A�܂�18���I�㔼�ɏW�����Ă���A�S�̖̂�58���ɒB���鐨���������Ă���B���Ɉ��i�N��(44�b�A�S�̖̂�34��)�����̃s�[�N�ł��������Ƃ���������B�]���A��R�M�̍Ő����͕��N��(1751�`1764�N)�ȍ~�Ƃ����A���̎Q�w�Ґ���80���l�`100���l�Ƃ������Ă������A���́w��R�s���쌱�L�x�̐��l������m��ł���ł��낤�B ��(3) �o��l���̕��� �w��R�s���쌱�L�x�Ɋ_�Ԍ�����o��l���ł́A���ƌ����Ă��S�������|�I����(57�l�A��47.5��)���߁A���Œ��l(20�l�A16��)�A���l(6�l�A5��)�A�E�l(6�l�A5��)�Ƃ������s�s������(���v32�l�A26��)������A�ȉ��m��(15�l�A12��)�A����(8�l�A6.4��)�A���m(6�l�A5��)�̏��ɂȂ��Ă���B���̂��Ƃ́A��R�M���S���K�w�𒆐S�Ƃ������^�����̏����M�Ɏx�����Ă����؍��Ƃ������悤�B ��(4) �������v�̓��e���� �ł͏����͈�̑S�́A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��R(��R���E��R���v���_��)�ɊE�F�O�����̂ł��낤���B���̓��e�͑�ʂ��ē���݂����Ǝv����B���̑��́A�a�C����(45�b�A36��)�A���ł��Ƃ�킯�A�u�a�E��a�E��E���S�E�߂����E�����Eᚕa(��33)�Ȃǂ���̉�������̗�Ƃ��ċ������Ă���B������͍Г��(34�b�A27��)�ŁA�Γ�E����E����E���Q������̉������̗�Ƃ��Ďw�E����Ă���B���̑��Ƃ��ẮA���i�̖߂�A�q�b�l���A�務�A���ؐ����A�k�q�a�����X�A���ɏ����̎�X�G���Ȋ肢�����X�Ɩz�o���Ă���B�������A��R�Ð���ɎU�������悤�Ȏ؋�����̗쌱杂͊F���ł���(��34)�B �������v�͂������i���Č��Ă��Ă����A������̂ł͂Ȃ��B���H�s���������ď��߂āA����ɒB������̂ł���Ƃ������Ƃ��w��R�s���쌱�L�x�͊e���Ō���Ď~�܂Ȃ��B�����ŁA�����͂ǂ̂悤�Ȏ��H�s��������Č������v���l�������̂��A�w��R�s���쌱�L�x�̗쌱杂̒�������(��4���E��28�b)�������ɏЉ�邱�Ƃɂ��悤�B ���͍���Z�S�x����(���ɐ����s)�ɐV�E�q��Ƃ����n�����S���������B�ނ͗��e�E�Ȏq��{�炷�邽�߂ɗב��ɕ���ɏo�����A��ɉƂɋA��_�k�ɏ]�����邩�����A���X��R�s������M�����B�ނɂ͓�l�̒j�q�ƎO�l�̏��q���������A��l�̏��q�͑O���̈������炩�A�h��ŕ��������Ɍ����Ȃ������B�����ŕv�w�͊S�Q���A��R�s�����F������߁A���a2�N(1765�N)������i3�N(1774�N)�ɂ����āA�N���ɕS������3����̍C��(�_���Ɋ���|���ĐS�g�𐴂߂邽�߂ɗ␅����s��)�����A����ȊO�̎��ɂ͈�S�s���ɑ�R�s�����ɋF�O�����Ƃ���A���i3�N���玟��ɖ��ِ̕�͑u�₩�ɂȂ�A���e�̊���͂��̏���Ȃ������B�܂��A3����̍C�������n�߂�������˔@�Ƃ��āA���~�̖T��̊�Ԃ��琴�����N�������A�C���݂̂Ȃ炸�p���ɂ����p�ł���悤�ɂȂ����B���̌��ʁA�n��������������Ɉ��y�ƂȂ�A��Y���Ȃ��Ȃ����B����ɔނ͐^�����U�̐l�ł���̂ŁA���l��ንa(�M�a�̈��)�������Ă���ƁA����̐����Ő�C�������A��R�Α��̖ؑ�����a�l�ɍ����f�������A�����ǂ���ɕa�C�������������Ƃ��x�X���������A�ނ炩���K�̎{�������Ȃ������̂ŁA�l�X���瑸�h���ꂽ�Ƃ����B ������̑�R�ւ̑����̔O���������邱�Ƃ͖ܘ_�̂��ƁA���̗�Ɍ�����悤�Ȑ��C���̂ق��A�Q�w�E�f�H�E�얀���E����E�Q�āE�����F���E����E�����E�[�ߑ������Ƃ��������H�s�ׂ����ւ��đ���I�ɍ�p���ď��߂āA�������v���B���E���A����邱�Ƃ��w��R�s���쌱�L�x�͊e�b�Ő����������Ă���B |
|
|
�����тɂ�����
���e�́A�u��R�����N�G���v�E�w��R�s���쌱�L�x���̌ËL�^�ނɈˋ����āA�Ñォ��ߐ��̑�R�M�̌`�����甭�W�̕��݂��l�@�������̂ł��邪�A����͑�R���̘H�T�Ɍ������ꂽ��R���W(��35)��A��R�M�Ɋ֘A�������w(�Ð���E�o�~�E���m�{�E�������L��)�E�����|�\�E�G�掑��(�����G�E�o�Z)���̌����ɂ܂Ŏ�����g�債�A��R�M�𑍍��I�ɔc�����鎎�s�����Ă��������ƍl����B����̂��ᔻ�E������������������K�r�ł���B |
|
|
����
1.�]�ˌ���̌�t�̐��Ɋւ��ẮA�H���ߓ��w���C�����������x(����9�N�q1797�N�r��)�ɂ́A�u�J�~�R��R��������������@�A���O�V�ɏ\���@�A��t�S�\�]�F�A�����ё��ɏ\�܉F�A�݂ȏC���Ȃ�A�������v�ƋL����Ă���B�܂��A������w�⏊�n�������̊ԋ{�m�M���ҁw�V�ґ��͚����y�L�e�x(�V��12�N�q1841�r����)��51 ��������Z�S��10�B�ȉ��A�w���y�L�e�x51�|��Z10�ƕ\�L����)�ɂ́A�u�t�E�S�Z�\�Z���A������{���ɏZ���A���ё��ɂ����Z����A�F�R���ɏZ�����A�C���Ȃ肵���A�c��10�N(1605)�A���Ɉ˂ĉ��R���A�t�E�ƂȂ��A�v�Ƃ��L����Ă���B�����̋L�q����A�]�ˌ���ɂ͌�t��166���������݂����ƍl������B 2.�L�ꖧ�v�w��R��O���̒n���I�����x(���ƔŁA1989�N)�A�K�Y�u��R�o�R�W���`���̊�Ձv(���������w�n���w�A1967�N)�B 3.�Ԑ������w�_�ސ쌧��R�R�������T��x(1960�N)�A���u��R�̘b�v�w���Ȃ��핶����73�x(�_�ސ쌧����������A1977�N)�B 4.�w���쎮�x��u�_�_�v�ɂ́A���͍��ɂ͈��v���_�Ђ̊O�ɑO���_��(�� ���ˎs�l�V�{)�A�������_��(���ɐ����s������)�A��䑽�_��(���O�V�{)�̎Ж����������Ă���(�w�ɐ����s�j�x�����ҁ@�Ñ�E����437�B�ȉ��A�w�s�j�x���@�Ñ�E����437�ƕ\�L����)�B 5.�u���y���@�̏������ϒ����v(�w�_�ސ쌧�j�x������1�@�Ñ�E����(1)798�A�w�s�j�x���@�Ñ�E����21)�B 6.�w��ȋ��x��3 ����N9��17����(�w�s�j�x���@�Ñ�E����357)�B 7.�w���x��22 ����2�N12��1����(�w�s�j�x���@�Ñ�E����419)�B 8.�w��R�s���쌱�L�x��1���E��2�b�u�����J�R��s��l���B�v(�y����1�z�Q��)�B 9.�u�����������̊�i��v(�w�s�j�x���@�Ñ�E����190)�A�u�֓��Ǘ�(�㐙���@)�{�s��ʁv(��194)�A�u�֓�����(��������)��i��ʁv(��196)���B�w�s�j�x�ł͕��������R�c�ێR�苽�����䑺���� �_�ސ쌧���l�s�ۓy�P�J��Ɣ�肵�Ă��邪�A�� �����s���c�s�̌��ł���(�w�p��n���厫�T13�@�����s�x�A178�ŎQ��)�B 10.�w�Q���ޜn�x��18�S(�w�s�j�x���@�Ñ�E����442)�B�V��@����@�����͕���18�N(1486)6�����痂�N5���ɂ����Ėk���E�֓��E���B�������ہA��R���������t�ɗ��������B 11.���R���Z���w���{�j���I��2�@���c���O���̖x�u�З́v(�ߓ��o�ŎЁA1969�N��)�B 12.�w���y�L�e�x51�|��Z10�ɂ́A�u�c�R�̏C���{�P�V(�R���F���ƍ���)�A�k�������ɜn�ЁA�R�w�ɍ݂đ�L�𐁂�����������A�c�c�v�Ƃ���B 13.�яq�֓��w������I�x�c��10�N(1605)1��11�����A�w���y�L�e�x51�|��Z10�B 14.�u�c��13�N(1608�N)10�� ��R�����Y������ƍN�����ʁv(�w�s�j�x���@����R7�A�w�����V�ґ��B�Õ����x��1��)�B 15.�u�c��15�N(1610�N)7�� ��R���ʓ�����V������ƍN�����ʁv(�w�s�j�x���@�Ñ�E����8)�B 16.�w���y�L�e�x51�|��Z10�B 17.�w���͑�R�X���x(��R���v���_�ЕҁA1987�N)�ɑS�������f�ڂ���Ă���B 18.�������X�w�_�ސ쌧��蕨�����|���͑�R���N�|(��)(��)�x(�_�ސ쌧����ψ���A1970�E1971)�A�����p���q�u��R�����N�G�����l�v(�w���ˎs�������������x��31�W�A���ˎs����ψ���A1995�N)�A��ؗǖ��u�������ɏ����̑�R���W�����ɂ��āv(�w�Ĕ�����R���������x�A�ɐ����s����ψ���A2008�N)�B�����̘_�l�́A���e���쐬����ɂ���������v����Ƃ����ł������B 19.�����{�ɂ͕��ˎs�����ٖ{�E�ɐ����s����ψ���{�E����s����ψ���{�E���c�s���y���{�E��R���{�E���C�Ɩ{(2���|�G���E�����̂�)�E���v���_�Ж{�E�蒆�{�E���t���ɖ{�E����j���Ҏ[���{�E���ɖ{�E�l�{(�ޗǎ�)��13�{���A�^���{�ɂ͑���{�����S���{�E���ˎs�����ٖ{�E���C�Ɩ{�E㔌Q���ޜn�{(��27�S��)�E���v���_�Ж{�E��R���{�E���c�s���y���{�E�ÉÓ��{�E�{�������˕��{�E����j���Ҏ[���{�E�V�ґ��͚����y�L�e�{��11�{������B 20.�w��R�̐M�Ɨ��j�x(���ˎs�����فA1987�N)�ƍ������O�f�_���ɁA�S�̂̎ʐ^�łƎߕ����f�ڂ���Ă��邪�A�O�҂ɂ͂���ǂ�������̂��c�O�ł���B 21.���w�V�E�V�E�ɐ��V�E�S��V�͂��ꂼ��A�u�V���Z�N(1786�N)��R���l�ۗ��v(�w�s�j�x���@�Ñ�E����20)�ɓo�ꂷ��B��l�E���d�͕ʓ�����V�̎R��E�R���̎�����d�҂̂��ƁB 22.��]�e�ʒ��A�ۉ�6�N(1140�N)�����B���厛�̏��猩���^�B�w�Z�����p�j���x�����B 23.�w�V������@���j��n�@��31�� �������x����2 �a��1(�w�s�j�x���@�Ñ�E����447)�B 24.�w㔁X�Q���ޜn�x�@�����A�w����{�����S���x�A����p�r�Z���w���厛�v�^�x��1�͖{��͂Ɍf�ڂ���Ă���Ǖّm���`�����B 25.���N�����A�����N���ځB�w㔌Q���ޜn�x�G���A�w����{�����S���x�����B 26.�V��5�N(1536�N)����ŏ�E��2���A��ҕs�ځB 27.���{�M���u�������ɔg�Ɛ��������\�Ǖٓ`�����̈ꏕ�Ƃ��ā\�v(�w�`��s�j�����x��2���A�`��s�j�҂���ψ���ҁA1982�N)�́A���҂̊֘A�j������Ē��J�Ɍ����Ă���B 28.�w����{�Õ����@���厛�����x�V�O�A�V����5�N(761)����28���t588�������B 29.���c���i�u���ߓI���J�`�Ԃ̐����v(�w�Ñ㉤���̍��J�Ɛ_�b�x�ɏ���)�B 30.�\�����Y�u�w��R�s���쌱�L�x�Ɍ����R�M�v(�w���y�_�ސ�x18���A�_�ސ앶�������فA1986�N�B��ɓ��ҁw��R�M�x�ɏ����q���O�@���j�p��22�A�Y�R�t�A1992�N�r�A���u�ɐ����s��ɂ������R�M�\�w��R�s���쌱�L�x�𒆐S�Ɂ\(�w�ɐ����̗��j�x��2���A�ɐ����s�j�ҏW�ψ���ҁA1987�N)�B���e�쐬�ɂ�����A�傢�Ɏ��������B�L���āA�ӈӂ�\�������B 31.�S���͎��݂̐l���ŁA�C�V���s�㋽�̑�R�u�������̓����s�������������Ɂu�������N(1796)���C�Z���g����R���{�q�@�B���S���J����v�Ƃ���B���؎s�юR��������t���̊����N�Ԍ����̒n����5�̂̓���3�̂ɂ��u�����җ{�q�@�B���S���v�Ƃ���B 32.�o�_���́A��������o�g�ō]�˂ɐi�o�����{�����Ε��q�ƕ��ԘV�����≮�ŁA���\11�N(1698)�ɖ��{�̌�p�B���l(�����t�A�� �����s�V�h�捶�����ɋ��Z)�ƂȂ�A���{�̏������ɑ����āA�g�t�R���ɂ̉^�c�ɓ�����قǂɖ��i�����B�a��(���ܘY���F�Ƃ�����)�̑�ȑO����w���Ӂx���̔��������ċ������A�ŏI�I�ɂ͐{�����ɔ����������B�������Z�͍]�˔n��2����(�� �����s��������{���n��)�ɋ��Z���A���c�͐������B���q(�^��)�𖼏�����B�����v���q�w�]�˂̕��Ɩ��Ӂ\���ӂƏo�ŋ����\�x(�g��O���فA���j�������C�u�����[257�A2008�N)�B 33.ᚕa�͏Ǐi�ނƁA�_�o�n�����N����A�э��ǂɌ��t�����イ�Ԃ�ɂ����킽��Ȃ��Ȃ�A�畆�Ɍ��߁E���_�Ȃǂ��ł��A���葫�Ȃǂ̖ڗ��Ƃ��낪�ό`������s���R�ɂȂ����肷�邱�Ƃ��������B�����ԁA�L���Ȏ��ÖȂ��A�s���̕a�C�ƍl�����Ă����B�������A����6�N(1873)�A�m���E�F�[�̈�t�A���}�E�G���E�n���Z���ɂ����ᚋۂ���������A�����ł́u�n���Z���a�v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B���̌�A���̕a�C�͓`����������Ȃ��ƁA��`���̂Ȃ����Ƃ����炩�ɂ���A����ɏ��a22�N(1947)�ɃA�����J�œ�����v���~�����J������A���̖�̕��p�ɂ���Ċ�������悤�ɂȂ�A�C���h�E�C���h�l�V�A�E�������ꕔ�������ẮA���S�ɐ��E����o�ł������B 34.�u�؋��͖~�ɖ߂�ʂƎR�֓����v�Ƃ��A�u�؋������o�ς����ĎR�֓����v���B���{�s���w���͑�R�ƌÐ���x(���[�A1969�N)�B 35.���݁A�ɐ����s����ψ�������ۂ́A�u�Ĕ�����R�����Ɓv�Ɩ��ł��āA�s���̗��j����A�h�o�C�U�[�̕��X�̂����͂����A��R���W�̎��F���������{���ł���B�@ |
|
| �@ | |
|
�@���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@ |
|
 �o�T�s�� / ���p���܂ޕ��ӂ͂��ׂē��g�o�ɂ���܂��B
�o�T�s�� / ���p���܂ޕ��ӂ͂��ׂē��g�o�ɂ���܂��B
�@
| �����{�̌Ó� | |
| �������� | �@ |
|
�V��13�N(741)�ɐ����V�c�������ɂ�鍑�ƒ���̂��߁A�����̓��{�̊e���Ɍ����𖽂������@�ł���A�����m��(�����Ԃ���)�ƍ�����(�����Ԃ�ɂ�)�ɕ������B
�������̂́A�����m�����u�������l�V���썑�V��(�����݂傤���Ă�̂��������̂Ă�)�v�A�������u�@�ؖōߔV��(�ق����߂����̂Ă�)�v�B�Ȃ��A����Δn�ɂ́u������(�Ƃ��Ԃ�)�v�����Ă�ꂽ�B �@ |
|
|
�w�����{�I�x�w���ڎO��i�x�ɂ��A�V��13�N(741)2��14��(���t�́w���ڎO��i�x�ɂ��)�A�����V�c����u�����������̏فv���o���ꂽ�B���̓��e�́A�e���Ɏ��d�������āA�������ŏ����o(�������o)�Ɩ��@�@�،o(�@�،o)���ʌo���邱�ƁA����������̋������ŏ����o���ʂ��A�����Ƃɔ[�߂邱�ƁA�����Ƃɍ����m���ƍ�����1���ݒu���A�m���̖��͋������l�V���썑�V���A�̖��͖@�ؖōߔV���Ƃ��邱�ƂȂǂł���B���̍����Ƃ��āA�m���ɂ͕���50�˂Ɛ��c10���A�ɂ͐��c10�����{�����ƁA�m���ɂ͑m20�l�E�ɂ͓�m10�l��u�����Ƃ���߂�ꂽ
�B
�������̑����͍��{���������ӂɒu����A�����ƂƂ��ɂ��̍��̍ő�̌��z���ł������B�܂��A��a���̓��厛�E�@�؎��͑��������E�������Ƃ���A�S���̍������E�����̑��{�R�ƈʒu�Â���ꂽ�B �Ȃ������V�c�́A���̏ق̈ȑO����A�V��9�N(737)�ɂ͍����ƂɎ߉ޕ���1��Ƌ�����F��2��̑����Ƒ�ʎ�o���ʂ����ƁA�V��12�N(740)�ɂ͖@�،o10�����ʂ����d�������Ă�悤�ɂƂ̏ق��o���Ă���B ���ߑ̐����o�ɂ��Ċ��ɂ������x�����Ȃ��Ȃ�ƁA�������E�����̑����͔p�ꂽ�B�������A�����Ȍ���������̍��������A�����̍������Ƃ͈قȂ�@�h���邢�͐��i�����������@�Ƃ��đ��u�����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���A�����̑����͕�������Ȃ��������A�㐢�ɖ@�؏@�Ȃǂɍċ������Ȃǂ��Č��݂܂ňێ����Ă��鎛�@������B�Ȃ����Ă̍������Ւn�߂��̎�������{��(���@�����Ȃ�)�ŁA�������̈�i��ۑ����Ă��鏊������B �@ |
|
| �@ | |
| �����m���@ | �n�����ݒn�@ | �����@ | �n�����ݒn�@ |
| �o�H������ | (��)�R�`����c�s��� | �o�H������ | (����)�@ |
| ���������� | �{�錧���s��ы�m�� | ���������� | �{�錧���s��ы攒�����@ |
| ���썑���� | �Ȗ،�����s������ | ���썑���� | �Ȗ،�����s�������@ |
| ��썑���� | �Q�n������s������ | ��썑���� | �Q�n������s�������@ |
| �헤������ | ��錧�Ή��s�{�� | �헤������ | ��錧�Ή��s�ᏼ�@ |
| ���[������ | ��t���َR�s���� | ���[������ | (����)�@ |
| �㑍������ | ��t���s���s�y�� | �㑍������ | ��t���s���s�������䒆���@ |
| ���������� | ��t���s��s���� | ���������� | ��t���s��s�����@ |
| ���������� | �����s�������s������ | ���������� | �����s�������s�������@ |
| ���͍����� | �_�ސ쌧�C�V���s������ | ���͍����� | �_�ސ쌧�C�V���s�����k�@ |
| �b�㍑���� | �R�����J���s��{������ | �b�㍑���� | �R�����J���s��{�������@ |
| ���]������ | �É����֓c�s���t | ���]������ | (����)�@ |
| �x�͍����� | (��)�É����É��s�x�͋��J | �x�͍����� | (����)�@ |
| �ɓ������� | �É����O���s�� | �ɓ������� | �É����O���s�쒬�@ |
| �M�Z������ | ���쌧��c�s���� | �M�Z������ | ���쌧��c�s�����@ |
| �z�㍑���� | (��)�V������z�s�ܒq�E���{ | �z�㍑���� | (����)�@ |
| ���n������ | �V�������n�s������ | ���n������ | (����)�@ |
| �����������@ | ���m�����s����@ | ���������@ | (��)���m�����s�@�Ԏ����@ |
| �O�͍������@ | ���m���L��s�������@ | �O�͍����@ | ���m���L��s�������@ |
| ���Z������ | ����_�s�쒬 | ���Z������ | (��)���s�j�S���䒬�����@ |
| ��ˍ����� | �����R�s���a�� | ��ˍ����� | �����R�s���{���@ |
| ���ꍑ���� | (��)�ΐ쌧�����s�Õ{�� | ���ꍑ���� | (����)�@ |
| �\�o������ | �ΐ쌧�����s������ | �\�o������ | (����)�@ |
| �z�������� | �x�R�������s���؈�{ | �z�������� | (����)�@ |
| �ዷ������ | ���䌧���l�s���� | �ዷ������ | (����)�@ |
| �z�O������ | (����) | �z�O������ | (����)�@ |
| �ɉꍑ�����@ | �O�d���ɉ�s�������@ | �ɉꍑ���@ | �O�d���ɉ�s�������@ |
| �ɐ��������@ | �O�d���鎭�s�������@ | �ɐ������@ | (��)�O�d���鎭�s�������@ |
| �u���������@ | �O�d���u���s���������{�@ | �u�������@ | (����)�@ |
| ���厛 | �ޗnj��ޗǎs�G�i���@ | �@�؎��@ | �ޗnj��ޗǎs�@�؎����@ |
| ��a�������@ | �ޗnj��ޗǎs�G�i���@ | ��a�����@ | �ޗnj��ޗǎs�@�؎����@ |
| �I�ɍ����� | �a�̎R���I�̐�s������ | �I�ɍ����� | (��)�a�̎R����o�s�������@ |
| �ߍ]������ | (��)���ꌧ�b��s�M�y������ | �ߍ]������ | (����)�@ |
| �O�g������ | ���s�{�T���s��Β����� | �O�g������ | ���s�{�T���s�͌��ђ��͌��K�@ |
| �O�㍑���� | ���s�{�{�Îs���� | �O�㍑���� | (����)�@ |
| �R�鍑�����@ | ���s�{�ؒÐ�s���Β��ᕼ�@ | �R�鍑���@ | (��)���s�{�ؒÐ�s���Β��@ |
| �͓��������@ | ���{�����s�������@ | �͓������@ | (��)���{�����s�������@ |
| �a�����@ | ���{�a��s�������@ | �a���@ | (����)�@ |
| �ےÍ������@ | ���{���s�V�����捑�����@ | �ےÍ����@ | (��)���{���s�������ē��@ |
| �A�n������ | ���Ɍ��L���s������������ | �A�n������ | ���Ɍ��L���s����������@ |
| �d�������� | ���Ɍ��P�H�s�䍑�쒬������ | �d�������� | ���Ɍ��P�H�s�䍑�쒬�������@ |
| �W�H������ | ���Ɍ��삠�킶�s���؍��� | �W�H������ | (��)���Ɍ��삠�킶�s���@ |
| ���썑���� | ���R���ÎR�s������ | ���썑���� | ���R���ÎR�s�������@ |
| ���O������ | ���R���Ԕ֎s�n�� | ���O������ | (��)���R���Ԕ֎s�n���@ |
| ���������� | ���R�����Ўs��� | ���������� | ���R�����Ўs��с@ |
| ���㍑���� | �L�������R�s�_�Ӓ������ | ���㍑���� | (��)�L�������R�s�_�Ӓ��@ |
| ���|������ | �L�������L���s���g�s | ���|������ | (��)�L�������L���s���g�s�@ |
| ���������� | ���挧����s���{�������� | ���������� | (��)���挧����s���{���@�Ԏ��@ |
| ���ˍ����� | ���挧�q�g�s������ | ���ˍ����� | (��)���挧�q�g�s�������@ |
| �o�_������ | ���������]�s�|� | �o�_������ | ���������]�s�|��@ |
| �Ό������� | �������l�c�s������ | �Ό������� | �������l�c�s�������@ |
| �B���� | �������B��S�B��̓����r�c | �B���� | �������B��S�B��̓����L�@ |
| ���h������ | �R�����h�{�s�������� | ���h������ | �R�����h�{�s���������@ |
| ���卑���� | �R�������֎s���{�{�̓��� | ���卑���� | (��)�R�������֎s���{���{���@ |
| �ɗ\������ | ���Q�������s������ | �ɗ\������ | (��)���Q�������s����@ |
| ���g������ | �����������s���{����� | ���g������ | �����������S�Έ䒬�Έ�@ |
| �]���� | ���쌧�����s������������ | �]���� | ���쌧�����s���������V���@ |
| �y�������� | ���m���썑�s���� | �y�������� | (����)�@ |
| �}�O������ | ���������ɕ{�s���� | �}�O������ | ���������ɕ{�s�����@ |
| �}�㍑���� | �������v���Ďs������ | �}�㍑���� | (��)�������v���Ďs�������@ |
| �L�O������ | ���������s�S�݂₱������ | �L�O������ | (��)���������s�S�݂₱�������@ |
| ��O������ | ���ꌧ����s��a���� | ��O������ | ���ꌧ����s��a���@ |
| �L�㍑���� | �啪���啪�s���� | �L�㍑���� | (��)�啪���啪�s�����@ |
| ����� | ���茧���s���Ӓ������{���G | ����� | (����)�@ |
| �Δn������ | (��)���茧�Δn�s�����������~ | �Δn������ | (����)�@ |
| ��㍑���� | �F�{���F�{�s�o�� | ��㍑���� | �F�{���F�{�s�o���@ |
| ���������� | �{�茧���s�s�O�� | ���������� | �{�茧���s�s�E���@ |
| ��������� | �������������s�������� | ��������� | (����)�@ |
| �F�������� | ���������F������s�������� | �F�������� | (��)���������F������s�V�C���@ |
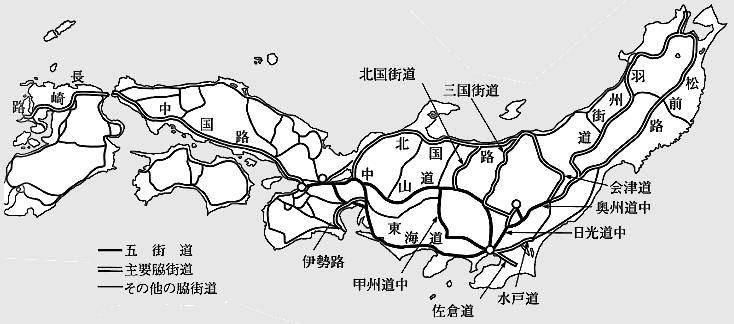
| �����{�̌Ñ㓹�H | |
| �Ñ���{�̒������{�����ォ�畽������O���ɂ����Čv��I�ɐ����E���݂������H�܂��͓��H�Ԃ��w���B�n���ł� 6 - 12 m �A�s�̎��͂ł� 24 - 42 m �ɋy�ԍL�������������A�܂��A�H���`�����I�ł���(���ɒ����� 30km �ȏ�)�Ƃ������������B�����̒���(�@�E��)�ɂ����铹�H���x�̋����e�����z�肳��Ă���B�������H�́A�܂�7���I�����̓ޗǖ~�n�Ō��݂���͂��߁A7���I��������ɑS���I�Ȑ������i��ł������B�����āA8���I�� - 9���I����(�������㏉��)�̍s�����v�ɂ�莟��ɐ��ނ��n�߁A10���I�� - 11���I�����ɔp�₵���B�@ | |
|
���T�v
���{�ɂ����铹�H���݂��n�܂����̂́A5���I���Ƃ���L�^(���{���I)�����邪�A�ڂ����͕������Ă��炸�A�^�⎋����ӌ��������B�L�I�Ɍ�����l�����R�̋L�q�͍s���͈͂��w�����̂ł���m���ȓ��H���̂��w�����̂ł͂Ȃ��B�m���Ȃ̂́A6���I�̓ޗǖ~�n�ɂ����Ăł��낤�ƍl�����Ă���(�؈ᓹ�Ȃ�)�B�����A���̍��Ɍ��݂��ꂽ���H�́A�L�������A�����I�Ȍ`��Ƃ����������͂܂������Ă��Ȃ������B �����I�ȓ��H���v��I�ɐ������ꂽ�̂́A7���I���炾�Ƃ���Ă���B�ޗǖ~�n�ł́A7���I�����ɈȑO�̋{�s���u���ꂽ�~�n������(���݂̍���s�A�����s�Ȃ�)���瓖���̋{�s���u����Ă����������R�c���Ȃǂ̓��H�����݂���A���̌�قǂȂ����āA����ޗǖ~�n��k�シ�钼�����H���A���s����3�{(��c���A���c���A���c��)�����ƂƂ��ɁA����ɒ������钼�����H���͓����ʂ������č��ꂽ(����H)�B�܂��A�͓�����ł͋�����̒������H����g�ɒʂ��Ă���(��g�哹)�A�����2�̑�H�����Ԃ̂����{�ŌÂ̊����A�|���X���ł���B�����̓��H�́A36 - 42 m �Ƃ������ɍL�������������Ă����B���������������H�̏o���̔w�i�ɂ́A7���I�����ɔh�����ꂽ���@�g�ɂ��A�@�̍L��Ȓ������H�Ɋւ��������炳�ꂽ�e��������̂��낤�ƍl�����Ă���B �剻�̉��V�ɂ��646�N�����ɏo���ꂽ���V�̏قł́A�w�`����z���|�̋L�q������A������_�@�Ƃ��Čv��I�Ȓ������H�Ԃ��S���I�ɐ�������n�߂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����������B���V�̏قɂ��ẮA���̐M�ߐ��������č������_���������Ă��邪�A���@�����Ȃǂɂ��A���Ȃ��Ƃ��剻�̉��V����ɂ͋E���y�юR�z���Œ����I�ȉw�H��w��(���܂�)�̐������s���A680�N���܂łɂ͋�B(���C��)�k������֓��n��(���C��)�Ɏ���܂ł̍L�͈͂ɂ킽���Đ������i�悤�ł���B ���{�̉w�`���́A�O�q�����Ƃ���A(�^�U�Ɋւ���c�_�͂��邪)�剻�̉��V�̏قɂ����ď��߂Ē�߂��A8���I�ɐ���E�{�s���ꂽ���߂ɂ����ďڍׂȋK�肪�����ꂽ�B���߂̉w�`���́A�w�H�Ɠ`�H����\������Ă����B�������j���ɂ́u�w�H�v�̗p��͌�������̂́u�w���v�u�哹�v�u�B���v�ȂǂƂ��L�ڂ���A�܂��u�`�H�v�̗p��͌�������Ȃ��B���̂��Ƃ���A���x�Ƃ��Ė��m�ɓ�����߂��Ă������Ƃ��A�܂����̂��������킯�ł͂Ȃ��Ǝv����B�@ |
|
|
���w�H
�w�H�́A�����ƒn���Ƃ̏��A����ړI�Ƃ����H���ŁA�e�n�����_���ŒZ�o�H�Œ����I�Ɍ���ł���A��16km���Ƃɉw�Ƃ��u����Ă����B���߂̒n�����x�͌܋E�����Ƃ����A�����ł���܋E�ƒn���ł��鎵�����琬���Ă������A�����̂��ꂼ��ɉw�H�������ꂽ�B�w�H�͂��̏d�v�x����A��H�E���H�E���H�ɋ敪����A�����A�����ŏd�v�H�������������Ƒ�ɕ{�����ԎR�z���Ɛ��C���̈ꕔ����H�A�����Ɠ��������ԓ��C���E���R�������H�A����ȊO�����H�Ƃ���Ă����B�w�Ƃɒu���n(�w�n�Ƃ���)�́A��H��20�D�A���H��10�D�A���H��5�D�ƒ�߂��Ă���A�g�҂��w�n�𗘗p����ɂ́A�w�邪��t����Ă���K�v���������B�@ |
|
|
���`�H
�`�H�́A��������n���ւ̎g�҂𑗌}���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���A�S���Ƃɓ`�n��5�D�u�����K��ƂȂ��Ă����B�`�H�͊e�n��̋��_�ł���S��(������/�S�ɂƂ�����)������ł������߁A�n���Ԃ̏��`�B���S���Ă����ƍl�����Ă���B ���̂悤�ɁA�w�H�Ɠ`�H�͕ʁX�ɐ�������Ă������A�H�����d�������Ԃł́A�w�H���`�H�����˂邱�Ƃ��������悤�ł���B�w�H�́A�d�v�ȏ����������������|�n���̊Ԃœ`�B���邱�Ƃ���ړI�Ƃ��Ă������߁A�H���͒����I�Ȍ`��������A�����̏W���E���_�Ƃ͖��W�ɘH�����ʂ�A���H���� 9 - 12 m(�ꏊ�ɂ���Ă� 20 m)�ƍL���A�n��Ԃ����ԃn�C�E�F�C�Ƃ��Ă̐��i��F�Z�������Ă����B���āA�`�H�͋����̒n�拒�_�ł���S�ƊԂ����Ԓn�擹�H�Ƃ��Ă̐��i�������B�`�H�͈ȑO����̎��R�����I�ȃ��[�g�Ȃǂ����ǂ���āA�������ꂽ�ƌ����Ă���A���H���� 6 m �O��ł��邱�Ƃ������B���҂̊W�́A������{�ɂ����鍂�����H�ƍݗ����H�Ƃ̊W�ɗގ����Ă���Ƃ̎w�E������B���ۂɁA�Ñ�w�H�ƍ������H�̐ݒ胋�[�g��A�w�ƂƃC���^�[�`�F���W�̐ݒ�ʒu���A�قړ���ƂȂ��Ă��鎖�������������B �ޗǎ���Ŗ������畽�����㏉���ɂ����āA�s�����v�����͓I�ɍs��ꂽ���A�w�`���ɂ����Ă��w��(���܂�)��w�n(������/�͂��)�A�`�n�̍팸�Ȃǂ����{����A�`�H�͎���ɉw�H�֓�������Ă������ƂƂȂ����B�������A�n��̎���Ɩ��W�ɐݒu���ꂽ�w�H�͎���ɗ��p����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A�]���̓`�H���w�H�Ƃ��Ď�舵�����Ƃ������Ȃ����B����ɔ����A�]���̉w�H�͔p�₵�Ă����A���������Ƃ��Ă� 6m ���ɋ��߂��邱�Ƃ���������(�L�������̓��H���ێ��Ǘ����邱�Ƃɂ͑傫�ȕ��S����������ł���)�B 10���I�O���ɕҎ[���ꂽ���쎮�ɂ́A�w�H(����)���ƂɊe�w�����L�ڂ���Ă���A��������ɓ����̉w�H���܂��ɕ������邱�Ƃ��ł���B�������A�w�`���͋}���ɐ��ނ��Ă����A10���I����܂���11���I�����ɂ́A�������ɉw�`�����w�H���p�₵���B�@ |
|
|
�����O���
���ߍ��Ƃ̎x�z���ɒu���ꂽ���O�͌ːЁE�v���E�ܕہE�ւȂǂ̃V�X�e���ɂ���Ė{�ђn�ɔ���t���������A�f���̉^�r�A�����̋��i�A�h�l�E�q�m�E�d���ȂǂƂ��Ă̒��p�Ȃǂɂ���ċ����I�ɓs翊Ԃ̉����𖽂�����ȂǁA���ƂɈړ�������Ă���(���Ƃ�@�������Ȃǎ��I�Ȍ�ʂ����S�ɔے肳��Ă�����ł͂Ȃ�������)�B���ɗf���͗��H���l�͂ł̒����ւ̗A������������Ă����B����́A�ԁE�M�Ȃǂ����Ă�̂͗L�͂Ȓn�������Ɍ��肳��邽�߂ɎԏM�ɂ��A����F�߂�Ɣ[�łɍ����̉���̗]�n�ނ��ƁA�X�ɖ��O�ɓs�����̕��䑕�u�Ƃ��Č����邱�ƂŖ��O�ɍ��ƓI�ȋ������z��������鉉�o��}�����Ƃ��錩��������B���̈���ŁA���l�͌S�Ƃ�w�Ƃł̏h���͔F�߂��Ă������̂́A���O�͉����̖��Ƃ⏬�K�͂Ȏ��@�E�������ďh��������A��h�������肵�Ă����ƍl�����Ă���B���ƂɂƂ��ėf���������ɓs�ɓ͂����ۂ��͏d�v�Ȗ��ł������ƍl�����Ă��邪�A��̓I�Ȑ���ɂ��Ă͕s���Ȃ��Ƃ������B�剻�̉��V����ɁA���l�ȂNJO���̐l�X���q��ł���Ƃ����P�������v����s�ׂ��ւ��閽�߂��o���ꂽ��(�w���{���I�x�剻2�N3���b�\��)�A��������O���ɍ��Ƃ��z�{�������݂�����(�w���ڎO��i�x����:���a2�N6��29���t���������u���������z�{����u���n�D���v)�Ȃǂ̑[�u���m���Ă��邪�A�����͉����̍����⎛�@�A�n���Z���̗͂ɂ��Ƃ��낪�傫�������B �����Ƃ��A���H���l�͂ł̒����ւ̗A���̋����́A�{�B�ȊO�̒n��(���C���E��C��)�ł͎��{������ł���A8���I�㔼����C��A�����{�i�I�ɓ��������悤�ɂȂ�ƁA���̒n��ł����̌���������n�߂��B�₪�āA�d�f�����x���̂��̂̐��ނ�����A�d�ł⊯���͒n�������ӔC���ēs�ɉ^�Ԃ悤�ɂȂ�B���̂��߁A���O�������I�ɓs翊Ԃ̌�ʂ������������邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�܂��ːА��x�̐��ނŖ{�ђn�ɔ�������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ������̂́A���O�̓s翊Ԍ�ʂ͑啝�Ɍ����������߂ɁA�z�{���⏬�K�͎��@�E����Ȃǂ��r�p���A���ߍ��Ɗ��Ƃ͕ʂ̈Ӗ��Ŗ��O�̈ړ��͍���ɂȂ��Ă������B�@ |
|
|
���`��
�L�������ƒ���Ȓ����`��������Ñ㓹�H�́A���ɔ���`�ޗǎ���Ɍ��݂��ꂽ�w�H�ɑ����A�����O���w�H�Ƃ����B�O���w�H�́A�����̏ꍇ 9-12m �A�E���ɋ߂��n��ł� 20m �̓��H���������A���암�ɂ����Ă͒����`�� 30km �ȏ�ɋy�Ԃ��Ƃ��������B�u�˒n�тɂ����Ă��A�Ζʂ�؍킵�A�J�Ԃߗ��āA�����`���ۂ悤�v����Ă����B�܂��A�w�H�̗����ɂ� 2-4m �̑��a���݂���ꂽ�B���a�͉w�H�Ƃ��̎��͂��敪����ƂƂ��ɁA�H�ʏ�̔r���Ȃǂ̖������������ƍl�����Ă���B �`�H�́A��������̌�ʘH�����ǂ���邱�Ƃ������������A�ꏊ�ɂ���Ă͉w�H�Ɠ��l�ɒ����`����������Ƃ��������B���H���́A���@�����ɂ��� 6m �ł���P�[�X���������A�K�������K�i���ݒ肳��Ă�����ł͂Ȃ������ł���B�܂��A��������ɓ���Ɖw�H�̓��H�����`�H�Ɠ����� 6m �ɋ��߂��A���������w�H�Ƃ����B����w�H�ł́A�O���w�H�̘H�������P�����̂���ʓI���������A�قȂ�H�����ݒ肳�ꂽ��`�H���w�H�Ƃ������������B ���@���ꂽ�w�H�́A���������킸���ɌE��ł��邱�Ƃ������B����́A��������l�n�ɓ��ł߂�ꂽ���̂ƌ�����B�E��ł��邱�Ƃɂ��A�����炭���H�����ɂ͐����܂肪�ł��āA�����Ɏx��𗈂������łȂ��A���H�̈ێ��Ǘ��ɂ�����ȘJ�͂�v���Ă����ƍl������B�܂��A�H�ʂɂ͓Q�Ǝv����Ղ��������Ă���B�ȑO�́A�Ñ���{�ŎԂ��p�����邱�Ƃ͂��܂�z�肳��Ă��Ȃ��������A���@���ʂ���́A���Ȃ�p�ɂɎԂ��g�p����Ă����\�����w�E����ӌ�������B ���H�̌��݂Ɋւ��邱�Ƃ́A�قƂ�Ǖ������Ă��Ȃ��B���݂ɂ͔��ɖc��ȘJ���͂�K�v�Ƃ����͂��ł��邪�A�J���͂��ǂ̂悤�ɒ��B�����̂��A�J���͂�d����p�͒N�����S�����̂��A�Ȃǂ͎j�����قƂ�ǂȂ����Ƃ������Ĕ������Ă��Ȃ��B�܂��A���̕����Œ���Ȓ����`��������H��Z�p�ɂ��Ă��������Ă��Ȃ��B�����炭�A�����̑��ʋZ�p�E�y�؋Z�p�������炳�ꂽ�ƍl�����邪�A�ڍׂ͕s���ł���B��������Z�p�҂��A�������̂��A���{�l�������̋Z�p���w�̂���������Ȃ��B�ǂ̂悤�ȍH�@�ɂ��A���H�����݂��ꂽ�������炩�ƂȂ��Ă��Ȃ��B�@ |
|
|
�����i
�w�H�́A�����ƒn���Ԃ̏��`�B�̂��߂̃n�C�E�F�C�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă������A���̖ړI�����Ƃ��ẮA�������L������Ƃ�����肪����B�L�������Œ����I�ȓ��H�ɂ́A�������̐��i���^�����Ă����ƌ����Ă���B ��́A�O���̕o�q�Ɍ����邽�߂̃f�����X�g���[�V�����������Ƃ��錩���ł���B�O������̎g�҂����ɉ�������R�z���͑�H�Ƃ���A���̉w�H���L�����H�������ƂƂ��ɁA�����̉w�n�Ɗ������̉w�Ƃ�����Ă����B���̂悤�ɍ��Ђ��O���Ɏ������߂̖����������Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B �������A�S�Ẳw�H���O���g�߂��ʉ߂����킯�ł͂Ȃ��B�����Œn��̍����E�Z����ւ̃f�����X�g���[�V�����������Ƃ��錩��������B�n��̌o�ϗ́E�Z�p�͂ł͌��݂����Ȃ��K�͂̓��H�̑��݂��A�������{�̋���Ȍ��Ђ��֎����������S���Ă����Ƃ��Ă���B �܂��A�R�p���H�Ƃ��Ă̐��i�������錩��������B���E�e�n�̌Ñ㓹�H������ƁA�R���I�Ȑ��i�������̂������A���{�̌Ñ㓹�H�����̗�O�ł͂Ȃ��Ƃ���B�܂��A���߂ɂ����āA�w�`���͕����Ȃ̏��ǂƂȂ��Ă���A���ォ��ޗǎ���ɂ����čs��ꂽ�R�������̂��߂ɉw�H�Ȃǂ��������ꂽ�\��������B �Ñ㓹�H�́A�n��v��̊���ƂȂ邱�Ƃ��������B�e���암�ł̏𗢂��w�H����ɐݒ肳��Ă�����A�w�H�������ƂȂ���������(�ےÁE�͓��E�a���A���͒}�O�E�}�㍑��)�B���{�⍑�����Ȃǂ̈ʒu�W���w�H����Ƃ��Č��肳�ꂽ�Ǝv���鎖��������������B�@ �@ |
|
| ���܋E���� | |
|
�Ñ���{�̗��ߐ��ɂ�����A�L��n���s�����ł���B�E������(���Ȃ������ǂ�)�Ƃ��Ăꂽ�B1869�N(����2�N)�A�k�C�� (�ߐ�) ���V�݂���Ă���͌܋E�����ƌĂ��B1871�N(����4�N)�̔p�˒u���ȍ~���A�܋E�����͔p�~����Ă��炸�A�ߐ��������p����Ă������A1885�N(����18�N)�ȍ~�͂�����A���݂́A�܋E�����Ƃ��Ă̒n���敪�͂��܂�p�����Ȃ��Ȃ��Ă���B
�������A���݂̓��{�e�n�̒n�����̑���(�k���A�R�z�A�R�A�A�k�C���Ȃ�)�́A�܋E�����ɗR�����Ă���B�܂��A���C���V������R�z�V�����A�k�������ԓ��Ȃǂ̌�ʖԂ�A����z�肳��铌�C�n�k���C�n�k�A�܂��n�k�����т̓�C�g���t�Ȃǂ̖��̂ɂ����̖��c��������B ���X�́A�����ŗp�����Ă����s���敪�u���v�ɕ�������ł���B���{�ɂ�����u���v�̐����ɂ��Ă͑剻���V�ȑO��葶�݂����Ƃ��錩�������邪�A�܋E�����̌��^�͓V���V�c�̎���ɐ��������ƌ����Ă���B�����͑S�����A�s(���鋞�E������)���ӂ��E���܍��A����ȊO�̒n������ꂼ�ꎵ���ɋ敪�����B �����ߎ��ォ��̎��� ���ߎ��ォ��̎����́A�T�˒n�`�I�v���Ɋ�Â��ċ敪����Ă��邪�A���C���ȊO�ł͓��P�ʂł̍s���@�ւ͏�u����Ȃ������B���C���͑嗤�Ƃ̊O���E�h�q��̏d�v�������ɕ{���u����ď������NJ������B�����̒��ł��ł��d�����ꂽ�̂��R�z���ł���A�B��̑�H�ł���B�����̊e���̍��{�́A���ꂼ�ꓯ�����̊�������(�w�H)�Ō���Ă����B�����͑�H�A���H�A���H�ɕ������A�w�H�ɂ͌����Ƃ���30��(��16�L��)���Ƃɉw(�w��)��u���A�w���Ƃɉw�n��������ꂽ�B������n�̐����قȂ��Ă����B�w����(�K���������ӂƂ͌���Ȃ�����)�ɉw����w�q���o���w�˂�u���A�w�n�̈�{�ɂ����点���B�w�Ƃɂ͉�������l�n�̋x���E�h���{�݂�u���A�w��������Ă��銯�l���������`�B����w�g����������Ə��p���̉w�n��ē��̉w�q������B ����玵���ɂ́A�]�ˎ���̌܊X���ȂǂƏd������ď̂�����B�����藧�����قȂ���̂́A�قړ������ɂ͂Ȃ��Ă���B ���̌�A�ו��̋��E�̈ړ����������炭�ύX�͂Ȃ��������A��ɁA�a�l�n����щڈΒn�ɐV���ɖk�C�����u���ꂽ�B�Ȍ�A�܋E�����ƌĂԁB�Ȃ��A�k�C���̋L�^�͌Â��Ė��V�c�̎��㈢�{�䗅�v�̉����܂ők��A���q����ɂ͘a�l���Z�ݓ���\��ق̎�����o�A�]�ˎ���ɂ͏��O�˗̂�V�̂ƂȂ��Ă����n��ɍŌ�ɒu���ꂽ�B �@�@�@���C���@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�10�D �@�@�@���R���@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�10�D �@�@�@�k�����@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�5�D �@�@�@�R�A���@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�5�D �@�@�@�R�z���@��H�A�w�Ƃ��Ƃ�20�D �@�@�@��C���@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�5�D �@�@�@���C���@���H�A�w�Ƃ��Ƃ�5�D�@ �@ |
|
| �����R��1 | |
|
(�Ƃ�����ǂ�)�@�܋E�����̈�B�{�B���������ߍ]�����痤�����Ɋт��s���敪�A����ѓ�����ʂ銲�����H(�Ñォ�璆��)���w���B�����̓ǂݕ��ɂ��ẮA�u�Ƃ�����ǂ��v�̑��ɂ��u�Ƃ�����ǂ��v�u�Ђ�����܂݂��v�u�Ђ����̂�܂݂��v�u�Ђ�����܂݂̂��v�u�Ђ����̂�܂݂̂��v�����āu��܂݂̂��v�ȂǏ�������B�ȉ��̏������܂܂��B
���ߍ]��(���݂̎��ꌧ) �����Z��(���݂̊��암) ����ˍ�(���݂̊��k��) ���M�Z��(���݂̒��쌧) �@���z���� - 721�N�ɐM�Z����蕪���B731�N�ɍē����B���݂̒��쌧�����E�암�ɑ����B ����썑(���݂̌Q�n��) �����썑(���݂̓Ȗ،�) ��������(���݂̍�ʌ��A���ׂ������������s�̂������c���萼�̒n��A����ѐ_�ސ쌧�k����) - 771�N�ɓ��C���ɏ����ύX�B ��������(���݂̕������A�{�錧�A�X���A��茧�A�H�c���k����) - ��������7���I�ɏ헤����蕪���B �@���Δw�� - 718�N�ɗ�������蕪���B���N��ɍĕғ��B �@����㍑ - 1869�N�ɗ�������蕪���B���݂̕��������ʂ�E��Âɑ����B �@���Ώ鍑 - 718�N�ɗ�������蕪���B���N��ɍĕғ��B���݂̕������l�ʂ�ɑ����B �@���֏鍑 - 1869�N�ɗ�������蕪���B���݂̕������l�ʂ�ɑ����B �@�����O�� - 1869�N�ɗ�������蕪���B���݂̋{�錧�ɑ����B �@�������� - 1869�N�ɗ�������蕪���B���݂̊�茧�ɑ����B �@�������� (1869-) - ���O�E��������̕����B���݂̐X���Ɗ�茧��ˌS�B ���o�H��(���݂̎R�`���A�H�c���̈ꕔ) - 712�N�ɉz�㍑�o�H�S�������ďo�H�������Ă�B���N10�������̍��̍ŏ�E�u�����S���o�H���ɕғ��B1869�N�A�H�O���ƉH�㍑�ɕ���������ŁB �@���H�O�� - ���݂̎R�`���ɑ����B �@���H�㍑ - ���݂̏H�c���ɑ����B�@ |
|
|
�����Ƃ��Ă̓��R��
���ߎ���̓��R���́A�E���Ɠ��R�������̍��{�����Ԋ������H�ł���A���ߎ���ɐ݂���ꂽ�����̒��Œ��H�Ƃ��ꂽ�B���������H�Ƃ��ꂽ�̂͋ߍ]�E���Z�E�M�Z�E���E����E�����̊e�����{��ʂ铹�ł���B�������{�E�������k�͏��H�ł���A�k��~�n���ɂ���������{�܂ő����Ă����B���R���ɂ́A30��(��16km)���Ƃɉw�n(�͂��)10�C��������w��(���܂�)���u����Ă����B ��ˁE�o�H�͍s�����œ��R���ɋ敪����Ă������A���{�ɂ͊������H�Ƃ��Ă̓��R���͒ʂ��Ă��Ȃ������B��˂ւ͔��Z���{���߂������݂̊s�ӂ肩��x�H�����Ă����B�܂��o�H���ւ́A���H�Ƃ��ꂽ�k��������{�C���݂ɉ����ĉ����A�o�H���{���o�ďH�c��܂ő����Ă����ƌ����Ă���B���̂ق��A�����Ɏ����O�̓��R�����番�ďo�H���{�Ɏ���x�H���������ƌ����Ă���B �ޗǎ��㓖���́A���R���̎}���Ƃ��ē��R�������H���݂����A��썑�V�c���Ȃ����ĕ������{(���E�{���s)�Ɏ���A�߂��ĉ��썑�����i�ރR�[�X(�܂��͂��̋t)�����R���̗����ł������B���Ȃ킿�������́A�����p�݂̗ߐ����̒��ŗB��A���R���ɑ������B���̓����p�݂̗ߐ����͓��C���ɑ��������A���X�̓��C���́A���͍�����C�H�ŏ㑍���E���[���n��A��������k�サ�ĉ��������ʂɌ������o�H������Ă����B���̌�A�C�H�ɑ��葊�͍����畐�������o�R���ĉ������ɔ����闤�H���J���ꂽ���߁A��T2�N10��27��(771�N12��7��)�ɕ������͓��C���ɓ���ւ�����B�Ȃ��A�b�㍑(�� �R����)�͏x�͍��A�ɓ����ƂƂ��ɓ��C���ɑ����Ă���A���������C���ɑg�ݍ��܂�Ă����B �����A�����͑�͐�ɋ����˂���Z�p�͔��B���Ă��炸�A������(����)�E������E�x�m��E���{��E����E�ؑ]��E���ǐ�E�K���Ɠn�͍���ȑ�͂��������C���������R���̎R���̕����ނ�����S�ƍl�����Ă����B���̂��߁A���C���̓n�͕��@�����������10���I���܂ł͓��R���͊����ɋ@�\���Ă����B ��������ɂ́A������(���s)�Ƃ̊Ԃ̉^�r(�^���l�v)�̓���(���쎮�ɂ��)�͈ȉ��̒ʂ�B���ʓ��͗��H�̍s�������ŁA�O�҂����(����������)�Ō�҂�����B���͒��Ɨf�ƂƂ��ɗ���ɂ�������̂��g�s�������߁A����̖�2�{�̓�����v�����Ƃ����B ���R���F�ߍ]���{(1��/0.5��)�A���Z���{(4��/2��)�A�M�Z���{(21��/10��)�A��썑�{(29��/14��)�A���썑�{(34��/17��)�A�������{(50��/25��) �x�H�F��ˍ��{(14��/7��) �k�����F�o�H���{(47��/24��) �]�ˎ���ɂȂ�ƁA�]�˂𒆐S�Ƃ���܊X������������A�������H�Ƃ��Ă̓��R���́A���R���E�����ᕼ�g�X���E���B�X���Ȃǂɍĕ҂��ꂽ�B |
|
|
�����R�����[�g�ł́A���s�`�����̊T�Z����(810km)
���s -(22km)- ���� (���ꌧ) -(57km)- ���l -(12km)- �s�j�� -(36km)- �� -(26km)- ���Z���� -(56km)- ���Ð� -(100km)- ���K -(55km)- ��c -(20km)- ���� -(22km)- �O�X�� -(41km)- ���� -(112km)- �F�s�{ -(75km)- ���͊� -(152km)- ��� -(25km)- �����@ |
|
|
���s�j��(�ӂ�̂���)
�Ñ㓌�R���̊֏��ł���B���C���̗鎭�ցA�k�����̈����ւƂƂ��ɁA�E����h�䂷�邽�߂ɓ��ɏd������A������O�ւƂ����B�O�ւ��瓌�͓����܂��͊֓��ƌĂꂽ�B ������ �����l ���� �����Z���� �����Ð� �����K �M�B�ɂ͊C���Ȃ����߉��Y���邱�Ƃ��ł����A���Ă͓��{�C���牖���肪����Ă��Ă����B�e�n������Ĕ�������Ă���ƁA���傤�ǂ��̋ߕӂŕi��ɂȂ邽�߁A���K�Ƃ������O�������ƌ����Ă���B�܂��A���{�C���Ƒ����m�����炻�ꂼ�ꉖ���^��Ă���ƁA���̕ӂ�ŗ��҂��������邱�Ƃ��牖�̓��̏I�_�����K�Ƃ�����������B���̐��ɉ����n���Ƃ��ď����S���K��(���A��c�s)������B�Ȃ��A���K�s�̌����́A����͂Ȃ��Ƃ����㐙�������c���ɉ��𑗂����`���`���A�H����R���Ƃ�����A�n���E�n�`����Ȃ���̎O�������Ă���B ����c �ޗǎ��� / ���łɕʏ����J������Ă����Ƃ����B8���I�ɐM�Z���̍������A�������������ꂽ�B�ŏ��̍��{�����̋߂��ɒu���ꂽ�Ƃ����������B�ޗǖ������畽�����㏉���ɂ����Ă̎����ɁA���{�����{�Ɉڂ�B �������� / ����8�N(938�N)�A������ɒǂ��ē��R�������ɂނ��Ċ֓���E�o���悤�Ƃ������吷���A2��29���ɒnj����Ă�������̌R��100�R�ƐM�Z�������t�߂Ő�����L�^���c����Ă���B���̂Ƃ��吷�́A�M�Z���C��Ï�����_�Ƃ���M�Z��q�̖q��(�Ǘ���)���쎁�̉��ɗ�������Ă���B���m�̊ԕ��ł������Ƃ��`��邪�A���m�ȊW�͕s���ł���B���쎁�݂̂Ȃ炸�A���c�^����M�Z���ɂ̊W�ҒB���吷�ɉ�������������R�ɔj�ꂽ�Ƃ����B���̐퓬�ɂ���č������͏Ă��ꂽ���̂ƍl�����Ă���B ����c2 ���R���ɂ��ẮA���̊T�v��O�ɋL���Ă��������A��c�E�����n���ɂ́A�Y��w�E�H���w�Ƃ�����̉w���������B�Y��w�ɂ͔n��15�C�������Ă����B���ʂ̉w��10�C����ł��邪�A���̉Y��w�̏�������Ƃ��ɑ����̂́A�������ە������Ƃ������H���Ђ����Ă������߂ł���B(���������A�ە������̌������ɂ������ѐD�w��15�C�̏���𖽂����Ă����B) ���̉Y��w�́A��@���̓���̕��R�n�ɂ������Ɛ��肳��Ă���B�����Ɂu�{�h�v(���h��)�Ƃ������������c���Ă���A���������R���̊J�ʂ������N�Ԃɑn�����ꂽ�Ƃ����Ù���@��(�̂͑�Ə�����)�����邱�Ƃ��A���̑z��̍����ƂȂ��Ă���B�w�ɂ͉w��������̂��ʗ�ŁA��@��(���)�͉Y��w�̉w���ƍl�����鎛�ł���B ������ ���O�X��(�������Ƃ���) �Q�n�������s����c���ƒ��쌧�k���v�S�y��Ƃ̋��ɂ�����{�̓��ł���B�W���͖� 960 m�B�M�Z�쐅�n�Ɨ����쐅�n�Ƃ��钆��������ł���B���̒��쌧���ɍ~�����J�͓��{�C�ցA�Q�n�����ɍ~�����J�͑����m�֗����B�Ñ�ɂ͉O�X��(�����Ђ̂���)�A�F�{���A�O����ȂǂƂ����A�����ɂ͉P�䓻�A�P�����Ƃ��\�L���ꂽ�B �×����Ⓦ�ƐM�Z�����Ȃ����Ƃ��Ďg���Ă������A��Ƃ��Ă��L���ł������B���̉O�X�₨��яx�́E���͍����̑������蓌�̒n����Ⓦ�ƌĂB�w���{���I�x�i�s�I�ɂ́A���{����(���}�g�^�P��)���Ⓦ���肩��A�҂���ۂɉO�X��(�O����)�ɂāA���[���œ��������Ȃ̒�k�Q�����̂�Łu���(���Â�)�͂�v�Ƃ��������Ƃ���B�Ȃ��w�Î��L�x�ł͂��ꂪ�����₾�����Ƃ���A�ǂ��炪���������Ƃ����_�������݂���B���݂ł��O�X�������ɂ��āA�������֓��������E�֓������ɁA�������M�z�������E�M�z�����ɕ�����Ă���B �O�X���͈͓̔͂�k�ɍL�����A���̓�[�ɓ�������R������͌Õ�����̍��J��Ղ���������Ă���(���R���)�A�Õ����㓖���̌Ó��R���͓��R����ʂ����Ɛ��肳��Ă���B7���I��t����8���I�O�t(������ - �ޗǎ��㏉��)�ɂ����āA�S���I�Ȋ������H(�w�H)�����������ƁA�O�X��ɂ����R���w�H�����݂��ꂽ�B���R��Ղ͂��̎����܂łɔp�₵�Ă���A�O�X��ɂ����铌�R���w�H�͋ߐ��̒��哹�ɂقڋ߂����[�g�������Ƃ�������L�͎�����Ă���B�Ȃ��A���t�W�ɂ݂���悤�ɖh�l�����ɂƂ��Ă͌̋��Ƃ̕ʗ��̏�ƂȂ��Ă����B ��������O�����璆�����̍Ⓦ�ł́A���������x���S���w�����Ǝx�z�ɒ�R���A���Ƃւ̐i�[�������̂����藪�D���铮���������������B�����x���S���w���u�Q���v�ƌ��Ȃ������Ƃ́A���̎����̂��ߏ���2�N(899�N)�ɉO�X��Ƒ�����֊֏���ݒu�����B���ꂪ�O�X�ւ̏����ł���B�O�X�ւ͓V�c3�N(940�N)�ɔp�~����A�����ɉ��x�����������B �Ñ�w�H�͑S���I��11���I�������܂łɔp�₵�Ă���A�O�X��ɂ����铌�R���w�H���������ɍr�p�����Ƃ���Ă���B���̌�A�O�X���ɂ������v��ʘH�́A���O�X�����[�g�̂ق��A���R�����[�g�E�k�⓻���[�g�Ȃǂ�ʉ߂����ƍl�����Ă��邪�A�ǂ̃��[�g���傽����̂ł��������͊m��Ɏ����Ă��Ȃ��B ������ �����A����̒n�́u�a�c�v�ƌĂ�Ă����B�u����v�Ƃ����s�s���̗R���ɂ��ẮA�ȉ��̓`��������B ����邪�a�c��̐ՂɊ��������ۂɁA���ł����ɒ����́A���n���u������v�Ƃ������O�ɉ��߂悤�Ǝv�����B�����ŁA���̌������������M�����Ă��閥�ւ̗��厛�̏Z�E�ł��锒���ɘb�����B�����́u�����Ƃ��Ȃ��Ƃł͂���܂����A���ɂ͉h�͂���A���ɂ͐���������̂͒��������Ƃł͂���܂���B�a�l���A�ƍN�l�̖����Ęa�c�̒n�ɏ��z�����̂͌��͂̒��_�ɗ������喼�ɏo�����ꂽ����ł���܂��B�����ł���w��������x�̈Ӗ����̂��āw����x�Ɩ��t���������悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤��?�v�ƌ������B�����̊ܒ~���錾�t���Ċ�����́A�����Ɂu�a�c�v���u����v�Ɖ��߂��B�����Ĕ��������ւ���]�Z�������L���̎R���ɁA�u����v��2����^�����ӂ̈ӂ�\�����B ���O�� �Â��͉X���Ə������B�����̓ǂݕ��́u�܂���v�B���߂́u���܂���v���Ɛ��肳���B�]�ˎ���ɑO���ɉ��߂�ꂽ�B ���F�s�{ ���n�͌Ñ�і썑�A�ߐ�������ɂ͉��썑�ɑ����A�s��p�여��ɂ͓ꕶ����̑�W���Ղł��鍪�ÒJ���Ղ�����ȂǁA�I���O���l�̐����̏�ł��������Ƃ��m���Ă���B�܂��F�s�{�s���S�s�X�n�͕�������̉��썑�͓��S�r�Ӌ��ŁA���̓��[�𗬂��c�쉈�݂ɂ͋��Ñ����w���A�܂��s�����x�O�𗬂��S�{��̉��݂ɂ͋��ߐ�w���������Ɛ��肳��Ă���A����Ɏs�敽�암�ɂ͋I��4-7���I�Ɍ������ꂽ�Ɛ��肳���Ñ�Õ���Z���Ղ��������݂��A�ˍՎR�[�ɂ͉����t����͓��S�ɂŎg�p���ꂽ���������Ă����q�Ղ�����ȂǁA���R�������ɂ���n��l���̈�W�ϒn�ł������ƍl�����Ă���B ���ɂ͒r�Ӌ��̋����r�Ȃɂ͒n�̐_���J��Ђ����Ă��A�����������ɂ͂�����w�F���{�x�w�F�s�{���_�x�Ƃ��č��J���A���q���ォ��퍑����ɂ����Ă͂��̐_�̂�a�������_�E�ƂŖk�ʕ��m�ł��������ꑰ���F�s�{���𖼏�芙�q��Ɛl�Ƃ��ĉF�s�{��ɋ����A�鉺�ɑ����̕������@���������ĉF�s�{�͓����̓s�ł������Ɣ�g����邱�Ƃ��������B���̉F�s�{�Ђ́A�����������֓��E���B���������邽�߂ɓ����ɔh������������̕��A�����G���̕�����̗��A�����`�̉��B�\��N����A�������̉��B�����A����ƍN�̐��Α叫�R�A�C�ȂǁA���̋@��͓��{�j��̐ߖڂɑO�サ�čs��ꂽ�B �F�s�{�鉺�͊��q�X������(���哹)������Ó��Ȃǂ��ʂ��ʂ̗v�ՂŁA�����͕x�ŏ������̍��Ղ͓����Ó������̐������O�Ȃǂɍ���������B���������E��̕s���艻�ɔ������q�{�̎�̉��ƌ�k�����̑䓪�ɋ����ĉF�s�{�������͂���߁A�ߐڐ��͂̓ߐ{��������R�m���̐N�����ĉF�s�{�͈ꎞ�D��������B�F�s�{���͋��_���J�̑��C�R�Ɉڂ��A���Ȃ��L�b�G�g�̏��c�������ɑ����F�s�{�d�u����ĉF�s�{�ɕ��A���邪�A�G�g�̎��ɑO�サ�ĉ��ՂƂȂ����B���̌�F�s�{���ƂȂ�����쒷���⊗���G�s�͏鉺�ɍ������A���쒬�Ƃ��������l�X�����A�܂����Α叫�R�ƂȂ�������ƍN�͉F�s�{�ЂɊ�i���Ă��������ƂƂ��ɁA�F�s�{���Ó����B���E�������̏h�w�ɖ����A�F�s�{��剜���Ə���{���������h��@�\�����ߐ��F�s�{�鉺�������A�F�s�{�h�͌܊X���̂��������X���E���B�X���̓̒Ǖ��ƂȂ�A�X����̔ɐ��n�Ƃ��đ傢�ɓ�������B �����͂̊�(���炩��̂���) �l����(�˂�������)�E�ܗ���(�Ȃ����̂���)�ƂƂ��ɁA���B�O�ւ̈�ɐ�������֏��ł���B�s���痤�����ɒʂ��铌�R���̗v�Ղɐ݂���ꂽ�֖�Ƃ��Ďj�㖼�����B���������͎s���h�����̈�\�Ƃ��ĔF�肳��Ă���B���̎j�ՂɎw�肳��Ă���B ���̐ݒu�̔N��͕s���ł���B�Z���j�ɂ����锒�͂̏��o��718�N(�{�V2�N)5��2�� (����)�ɗ���������u���́v�Ȃ�5�S�����ĐΔw����ݒu����Ƃ����L���ŁA���̌�728�N(�_�T5�N)4��11�� (����)�ɂ͔��͌R�c�̐V�݂����A������769�N(�_��i�_3�N)3��13�� (����)�ɂ͗������卑�������h�I�����̐\���ɂ���ĉ��炩�̌��т��ʂ������炵���҂ւ̎����t�^���s���A���͌S�ł͏䕔�^�Ƒ唺���^�����ꂼ�ꈢ�������b����ш�����Ðb���������Ă���B�܂�780�N(��T11�N)12��22�� (����)�ɂ͗�������{�����R�̕S�ω��r�N�����Ɉ͂܂��@�ɕm�������u���́v�̐_�Ȃ�11�_�ɋF�����Ƃ��낱���˔j�ł����Ƃ��ĕ��Ђɉ����邱�Ƃ������Ă���B�����������Ƃ���A���}�g�̌R���I�v�ՂƂ��Ă̔��͊ւ̋@�\�͕��������ɂ͉����������̂ƍl�����Ă���B�����������B��������łڂ����B����̍ۂɁA���������͂ɒB�������ɁA�����i�G�ɉ̂��r�ނ悤������ƁA�u�H���ɑ��̘I���Ε��킹�āA�N���z���Ί֎�������v�Ɖr�B �ւ̔p�~�̌�A���̈�\�͒��������āA���̋�̓I�Ȉʒu��������Ȃ��Ȃ��Ă����B1800�N(����12�N)�A���͔ˎ叼����M�͕����ɂ��l���s���A���̌��ʁA���͐_�Ђ̌��ꏊ�������āA���͂̊Ղł���Ƙ_�����B ����� �����G��̉͌��Ɉʒu�������́A���Ắu���G(��������)�v�ƌĂ�Ă����B���̒n�͂̂��ɉ��B�X���Ɨ��O�l�X���̕���_�̏h��Ƃ��ĉh�������Ƃ����������悤�Ɍ�ʂ̗v�Ղł���A�����։������銯�l�̂��߂̗���(���G��)���u����A���a9�N(842�N)�ɂ͒|��_�Ђ����������ȂǁA�Â�����d�v�ȏh�w�ł������B ����6�N(1361�N)�܂łɂ͐�c���������ɓ���A���������_�Ƃ���B��c���́A�͂��ߗ��玁�A�̂��ɈɒB���̉Ɛb�ƂȂ��ē��n���x�z�����B����̌ď̂́A���̏�̑O�ʂɍL���������̂�ꂽ���̂Ɠ`�����Ă���B ������� �����s�́A�{�錧�̂قڒ����Ɉʒu����s�s�ł���B���{��S�B�s�̖��̂͗������{�u�����v�Ɉ��ށB �����Ί펞�ォ��퐶����܂� �s���ɓ_�X�Ƃ���u�˂ɗ��n���锐�؈�ՂƎu����Ղ��狌�Ί펞��̐Ί킪�������Ă���B�ꕶ����O���ɂ͋��x�L�˂�����A�ӊ��ɂ͏����p�ɋ߂����{�͊L�˂ȂǂŐ���ɐ����y����g��������肪�s�Ȃ�ꂽ�B��̑����s��Ɍ��炸�A�����p���݂͊L�˂Ɛ����y��E��\���W�����ĕ��z����n��ł������B�퐶����ɂ́A�s���̌ܖ���n�悩��Ε���o�y���Ă���B�e�^�͊L�˂Ō����������̍��Ղ��c�����y��́A�R�����j�̘_���u�Ί펞��ɂ����v�݁A�l�Êw�j�㒘���ł���B�s���̒�n�Ő��c��삪�c�܂ꂽ�ƍl�����邪�A�Z���͌������Ă��Ȃ��B ���Õ����� �Õ����ォ��G���Z���̏W�����m�F�ł���B�R����ՂƗאڂ���V�c��Ղ͈ꑱ���̑傫�ȏW���ŁA���ɍ����Ղ�����A��ɑ����p����������ꏊ�ɂ������ȏW�����������B�t�߂ɂ͐��c�Ղ��������Ă���B�C�݂̑��n��ɂ͋��Ƃɏ]������l�X����炵�Ă����悤�ł���B�Õ�����̑O���ɂ́A�ܖ���n��ɕ��`���a�悪�c�܂ꂽ�B�Õ��Ƃ��Ă͏��^�̉~���ł����דa�Õ���ێR�͌Õ����z���ꂽ���A�O�҂�7���I�㔼�A��҂͔N��s���ł���B��דa�Õ������ꂽ�����ɂ́A�R�ɑ�㉡����Q�A���{�͉�����Q�A�c���ꉡ����Q�Ƃ����������悪����ɍ��ꂽ�B ���Ñ�̗������{ 8���I�Ɏs��k�����̋u�˂ɑ���邪�z���ꂽ�B�����n�����A�������͈ꎞ�I�ɐΔw���E�Ώ鍑�E�������ɎO������Ă����B�������ꂽ�������͍��̋{�錧����⋷���͈͂ŁA�����͂��̂قڒ����ɂ���B����܂ŌS�R��Ղɂ������������{�́A�_�T���N(724�N)�ɑ��c�Ȃ��������Ɉڂ����Ɛ��肳��Ă���B�����͐��N��ɉ��߂��A�ӂ����э��̕���������{�錧�ɋy�ԍL���������ɖ߂������A�����͂��̍L���������̍��{�ł��葱�����B�����ɂ�9���I���߂܂Œ���{���u����A�o�H���܂Ŋ܂߂����k�n���̐����E�R���̒��S�s�s�ł������B���{�S�̂̒��ł��A���̑�ɕ{�ɑΉ����铌�̐����s�s�Ƃ��ďd�v�Ȉʒu�ɂ������B��s�̓�ɂ͒����L����A�������k�c�삪�������ė��ʂ���������������ɋ����������A�M�ɂ��^�����������B�ޗǎ��ォ�畽������͂��߂܂Œf���I�ɑ������ڈƂ̐킢�̒��ŁA��T11�N(780�N)�ɂ͈Ɏ��햃�C�̔����ōU�ߊĂ����R���ɂ�藪�D�����ꂽ���A�����ɍČ����ꂽ�B�@ �@ |
|
| �����R��2 | |
|
��1�D���R���Ƃ�
�Ñ���{�̒������{�͔��ォ�畽������̑O���ɂ����āA�v��I�ɓ��H�������B�n���ł�6���[�g������12���[�g���̕�������A���̓s���ӂł�24���[�g������42���[�g���̕������������������H�ł������B���R���́A�ޗǎ���ɒ����ƒn�������Ԃ��߂ɁA�����I�ɑ���ꂽ�����ł������B�Ñ�̌܋E�����̈�ł����銯���̖��̂ł������B �E�Ƃ́A��s�̈Ӗ��ł���A���s���ӂ��u�E���v�B���̎��ӌ܃������u�܋E�v�Ƃ��A�E�����Ӎ����u�ߋE�v�ƌĂ�ł����B �������Ƃ� �E�ߋE�̖k���E�����{�̑����m�����u���C���v �E���{�C�����u�k�����v�u�R�A���v �E�����R�ԕ����瓌�k���u���R���v �E�E������쐼���u�R�z���v �E�l�����u��C���v �E��B���u���C���v ������Ɂu�k�C���v�����āA�����Ƃ������B �����R���́u�����v�𑖂�X�� �E�{�X�����u���R���v�u�����X���v �E�e�X�����u���ߍ]�X���v�u�ɓߊX���v�u�씞�X��(�P������)�v�u�������z���v�u����X���v�u��ˊX���v�u��ۊX���v�u�S��X���v�u���Z�X���v�u�k���X���v�u�k�����X���v�@ |
|
|
��2�D���R���̌Ăѕ�
���R�����@�Ƃ�����ǂ��E�Ƃ�����ǂ��B�����܂̂�܂݂̂��B�����āu��܂݂̂��v ���X�����@�����܂����ǂ� ���R���������Łu����ǂ��v�A�����Łu����ǂ��v�ƌĂn�������ł��c���Ă��邪�A�����҂̗p��ł́u�Ƃ�����ǂ��v���ʗp���Ă���B ���u���H�ϐ֕��V�u�v�u�������y�L�v�u���ɓߎj4���v�Ȃǔː�����̕����ɂ͗l�X�ȕ��������Ă��Ă���B�������A���R���������ɏ��������̂́A�F�������𓌎R���̏\�܍��̓s�ɔq�����Ƃ����u���{���I(�i�s�V�c55�N2���p�C��)�v�ł���Ƃ����B�\�܍��Ƃ����̂́u���Z���ȓ��v�ƋL����Ă���B�@ |
|
|
��3�D���R���͂�����ł����̂�
�剻�̉��V(�剻���N645)�ɂ��u�w�n�E�`�n�v���x���o���܂������A���ۂɐ��������ꂽ�̂͑�N(702)�̑��߂����肳�ꂽ����ƌ����Ă��܂��B�u�����{�I�v�̑��2�N(703)�̋L�^�Ɂu���߂Ĕ��Z���̊�h�R�����J���v�Ƃ���A���́u��h�v�Ƃ͖ؑ]�J��ʂ�V���������J�����Ƃ����ʐ��ƁA�_�⓻���z����R�[�X����������āu�w�v�̐������������Ƃ������̓������܂��B���̌�A�ؑ]�H��ʂ����L�^�͂Ȃ��A�_�⓻�z���͑�ς������Ƃ����L�^���������Ƃ����҂��L�͂ƂȂ��Ă���B�@ |
|
|
��4�D���R���͂ǂ��܂ł̓���
���R���̋N�_�́A���i�̓�[�A�ߍ]��(���ꌧ)�̐���(���c)�B�I�_�͋{�錧�̑����܂łł������A�̂��ɂx����ɕ�����āA����͗�����(��茧)�̒_����o�Ďu�g��܂ŁB��������͏o�H��(�R�`�E�H�c)�̏H�c��܂łƂȂ��Ă��܂����A�H�c�ł̓��͌��̓��ƌ����Ă���܂��B�����ɂ��Đ�L���ɒB���Ă��܂��B �ߍ]�̐���(���ꌧ)����n�܂聨���Z�E���(��)���M�Z(���쌧)�����(�Q�n��)������(�Ȗ،�)������(�������Ȗk)���o�H(�R�`�E�H�c)�̏����ł����A������ł͂Ȃ��A���X�̒n����܂Ƃ߂āu���R���v�Ƃ������܂����B�@ |
|
|
��
���{�E�ߍ]��(���ꌧ)�����Z��(���암)����ˍ�(���k��)���M�Z��(���쌧)�E�M�Z���{�����(�Q�n��)�����썑(�Ȗ،�)����㍑(����������)���֏鍑(����������)�����O��(�{�錧)�E����鍑�{���o�H��(�R�`����H�c��)�E�r����(��茧)�@ |
|
|
��5�D���R���ɉw�Ɖw�n�̐��͂ǂ�قǂ�������
�u���쎮�삱�́A�x�����܂߂ėߕ���86�w�������ƋL����Ă��܂��B�M�Z��������15�w�A�w�n����165�C�B�w�ɂ�10�C�قǂ̔n������A�n�ꓪ��5�l����6�l�̉w�q�������ƌ����Ă��܂��B�w�Ɖw�̊Ԃ̋����͒ʏ�30��(16�L��)�Ƃ���Ă��܂����B�w�ɕt�������w�c�̍L����3����(3�w�N�^�[��)�Ɛ��肳��Ă��܂��B�@ |
|
|
��6�D����̎w�}�ʼn^�c����Ă����̂�
�w�ɂ͉w�������܂����B�w���͒���⍑�i����h�����ꂽ��l�ł͂Ȃ��A���̓y�n�̗L�͎҂�y�����C������Ă��܂����B�w���̎d���́A���̖�l��w�g�̑��}�Ȃǂ̂ق��A�w�q��w�n�̔z�u��n�̎d�x�A�w�ƁE�w�c�̊Ǘ��Ȃǂł����B�I�g�I�ɔC������A�C���͏d���A�d�ł�J���͂��̂����Ə�����Ă��܂����B�@ |
|
|
��7�D�w�q�����͂ǂ�Ȏd�������Ă�����
�ڂ����L�^�͂Ȃ��悤�ł����A���Ԑ��̂悤�ɂȂ��Ă��ĉw�ɂɋΖ����Ă����ƌ����Ă���B�w�q�͓y�n�̔_���ŁA�w�n���o���K�v������Ƃ��͂��ł���������悤�ɂȂ��Ă���A�w�g����p�̖�l�Ȃǂ��o�}���A�ו���w�����A�w�n�Ƌ��Ɏ��̉w�܂ōs���A��サ�Ď����̏����w�ɖ߂��Ă����B �܂��A�ʏ�͔n�̐��b����p�g�̂��߂̋x���A�H���A�h���Ȃǂ̎d�������A���ԂłȂ��w�q�͉w�c�̍k��⓹�H�̐��������Ă��܂����B�@ |
|
|
��8�D�w�n�𗘗p�����̂͂ǂ�Ȑl������
�w�n�𗘗p�����̂́A���̖�l�⍑�̖�ڂŒʂ����l�A�w�g(���p�̉ו��Ȃǂ����̉w�܂ő���͂���w�q)�ȂǂŁA�ق��̐l�͕����Ēʂ�܂����B�w�n�𗘗p�����l�̒��ɂ����ʂ̑����Œʍs�����l�ƁA���}�̕▽�߂������Ēʂ�u��w�g�v������A��w�g�͈����10�w�𑖂蔲����悤�ɋK�肳��Ă����ƌ����܂����A10�w��160�L���ɂ��Ȃ�A�����������Ǝv���܂��B�w�n�𗘗p����l�͉w���炵�Ēʍs���܂����B�܂��A�w�܂ōs�����ɓr���œ������Ă��܂������́A����̉A�ȂǂŖ�h�����܂����B�@ |
|
|
��9�D�����͂ǂ����Ēʂ�����
��ʂ̏����͉w�n���g�����Ƃ͂ł��܂���ł����̂ŁA���p�̒ʍs��W���Ȃ��悤�ɒʍs���܂����B�w�H�̎��ӂɂ͉ʎ�(�~�A���A���A�ӓ��Ȃ�)���A�����A�����Ȃ����ɂ͈�˂Ȃǂ��@���Ă��܂����B���H����6���[�g������12���[�g���ƍL���A�����ɂ͑��a�����A����̓��H�ɂ����Ȃ��\���ł����B�@ |
|
|
��10�D�w���͂��܂ő�������
���R���̉w�����Ȃ��Ȃ��������̋L�^�͂Ȃ������ł����A10���I�㔼�̂���ɂ͒n�����x������A�����̋��R�Ȃǂɂ��w�q�̓����Ȃǂ��₦���A�w�˂͗��U�����Ƃ����B�������o�v���A�s�֑���ו���D�����A���l���������A���s���̋g���Ȃǂɂ���ʏ�Q�Ȃǂ���`���A�����E�V�c(931�`946)�̂���ɂ͉w�Ƃ̈ێ�������ɂȂ����ƌ�����B�������A�w���ɂ��w�n�� �������Ȃ��Ȃ��Ă����R�������p����Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ������B���̌���x���̏�ł���h���̏ꏊ�Ƃ��Ďp��ς��ė��p����Ă������B�@ |
|
|
��11�D�w�H�Ɠ`�H
�w�`���͉w�H�Ɠ`�H����\������Ă����B�@�w�H�́A�����ƒn���Ƃ̏��A����ړI�Ƃ��A�ŒZ�̒����Ō���Ă���A30��(��16�L��)���Ƃɉw�Ƃ��u����Ă����B�w�H�͏d�v�x�����H�E���H�E���H�ɋ敪����Ă���A�����Ɠ��������ԓ��R���͒��H�Ɉʒu���Ă����B�w�Ƃɒu���n���w�n�ƌĂсA��H��20�C�A���H��10�C�A���H��5�C�ƒ�߂��Ă����B�w�H�͏d�v�ȏ��𒆉��֓`�B����ړI��A�H���͒����I�ł���A�W���Ƃ͖��W�Ɍ��ς�A���H�����L���A�n��Ԃ����ԃn�C�E�F�C�I�ȓ��ł������B �`�H�́A��������n���ւ̎g�҂𑗌}���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A�S���Ƃɓ`�n��5�C�u�����K�肪�������B�`�H�͌S�Ƃ�����ł������߂ɁA�n���Ԃ̏��`�B���S���Ă����B���R�����I�ȃ��[�g�����ǁA�������ꂽ���̂�����������6���[�g���O�オ�����Ƃ���Ă���B �w�H�Ɠ`�H�͕ʁX�ɐ������ꂽ���A�H�����d��������ł͉w�H���`�H�����˂Ă����B�܂��A����ɓ`�H�͉w�H�ɓ�������čs�����B���̂��ߗ��p����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ�A���x�͎��p�I�ȓ`�H���w�H�Ƃ���Ȃǂ̕ϑJ�����A10���I����11���I�����ɂ͉w�`�����w�H���p�₵���B�@ |
|
|
��12�D���R���̃��[�g��m��
�Ñ㓹�H�ł��铌�R���̃��[�g��m���b�m���Ƃ��āu���쎮�v���グ����B���쎮�ɂ͉w�H���Ƃ̊e�w�����ڂ��Ă��邽�߁A�w�Ƃ̏��݂𐄒肷�邱�Ƃ��o���邩��ł���B�w�ƂƉw�Ƃ����ԃ��[�g�����܂��ȉw�H������o����킯�ł���B�܂��n���͌Ñ㓹�H�ɗR������\��������̂ł���B�n���ł́u�哹(�����ǂ�)�v�u����H�v�u�ԘH(����܂�)�v�u�쓹(����݂�)�v�u�� �v�u�哹�E�R���v�u���(�Ȃ��)�v�Ȃǂł���B�w�ƂɗR������n���́u�n���E�n���E�ԕāv�Ȃǂ����[�g��m��d�v�Ȏ肪����ƌ�����B�ق��ɂ����E��n���A�𗢗]���(�݂�����)�ȂǗl�X�Ȏ肪���肪����B ���ޗǎ���́u���v�́u��v�ƌĂ�Ă����B��v���[�g���u�I�I�T�J�v�u�~�T�J�v�ȂǂƌĂсu�~�T�J�v�͐_���J�鏊�������ď̂ł��������B���ɍ₪�g���Ă���ꏊ�͌Â��n�������m��Ȃ��B��͂���n������ʂ̒n���ւ̋��ł���A���ʂȏꏊ�ł��������B�@ |
|
|
������
1�@�u���쎮�v�����w�`�n���@ ��������̉���N��(901�`919)�ɕҎ[���ꂽ���́B���Ƃ͗��ߊi���̎��ł���A�s���@�̎{�s�ב��̂��ƁB�����w�`�n���́A�����ȊW�̋K��̈�ł���A�w�ƁE�w�H�W�̎j���Ƃ����B 2�@�u�a�����ڏ��v �u�a�����v�Ƃ��Ă�u���쎮�v�Ɠ������ɕ҂��ꂽ���T�B�u���S���v�u�S�����v�Ƃ����S���̍��E�S�E���̈ꗗ�����^����Ă���B 3�@�Z���j �Z���j�Ƃ́u���{���I�v�u�����{�I�v�u���{��I�v�u�����{��I�v�u���{�O����^�v�u�����V�c���^�v�̂��ƁB���̘Z���j��u���ڎO��i�v�Ƃ����lj��@�ߏW�̒��ɁA�w�Ƃ̐V�ݥ�p�~�E�Ĕz�u��A�w�H�H���̕t���ւ��A�w�n���̕ύX�Ȃǂ��o�^����Ă���Ƃ����B 4�@���y�L(�Ñ�) ���ݎc���Ă�����̂́A�헤�A�o�_�A�d���A�L��A��O�����ł���B�������A���y�L�̉w�ƁE���H�W�̋L�ڂƉ��쎮���r���邱�Ƃɂ���ĕω����킩��B 5�@�؊Ȃ�y��Ȃ� �؊Ȃ�y��ɂ͉w�Ɩ����L����Ă��邱�Ƃ�����B �@ |
|
| �����R��3 �E ���Ȃ݂̂� | |
|
���R��(�����܂�܂݂�)�́A�Ñ�̗��߂̂�銯���̈�ŁA�B���쎮�Ɉ˂�ߍ]�������w���N�_�Ƃ��A���Z���E�M�Z���E��썑�E���썑���o�ė������ɒʂ��Ă����B�M�Z���ɂ�����o�H�́A���Z����{�w����M�Z��(�_�⓻)���z�����q�w�ɉ���A�ɓߌS������V���쉈����k�サ�A��ǁE�����E�{�c�E�[��̊e�w���o�đP�m�������z���Ē}���S�ɓ���A�o�u�w���o�āA�ѐD�w�Ŗ{���͓��ɕ�����]���A�ە��������z���ď������Y��w�ɏo�āA�j���w�Ő�Ȑ��n��A���v�S�����w�E���q�w���o�āA�O�X����߂��A��썑��{�w�֎���H�ł������B�Ȃ��}���S�ѐD�w���番����Ėk�������A�X���S���щw���o�čҐ��j���w�œn��A���ÁE���Ӊw���o�ĉz�㍑�Ɏ���x�H���������B���̎x�H�ɂ��Ă͐M�Z�₪��H�ł������̂ŁA�a���Z�N(713)�A�w�H�łȂ����H�̋g�h�H(������)��ʂ����߂Ċo�u�w�ňɓ߂���k�サ�Ă������ƌ���ł���B
���̉w�H���R���̌����̓��́A��a������ɐ��E�����E���Z�̊e�����o�ĐM�Z����z���A�V���쉈���ɖk�サ�A�{�c�w���߂��Ă���k���������A��˓����z���Đz�K�S�֏o�A�X�ɓ��k�i���ĉJ�������z���č��v�S�ɉ���A���v����k���ɐi��ʼnO�X��Ɏ������Ɛ��肳��Ă���B�}���S���o�R���铹�͑���N(702)�ɊJ�ʁB���R���̍ő�̓�́A��̐M�Z�⓻�B�k�̉O�X��y�т��̒��Ԃɂ��錻�ە������ł��������A���C���ɂ͊���̑�͂����݂��Ă��邱�Ƃ������āA��a����ɂ����闤���E�o�H�̊J���ɓ������Ď���ɏd�v�H���ƂȂ�A�ޗǎ���̒����܂ł��̎�v���H�Ƃ���Ă����B ���͂�ӂ�_�̌��ɕ��܂��(����)�Ӗ��͕���̂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�M�Z��ɂā@���t�W���h�l�̉� �M�Z�H�͍��̍�������(�͂�݂������)�ɑ����܂��ނȗ�(����)�͂��䂪�v(��) �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ە������Ł@���t�W����l���́@�@ �ЂȂ�����O�X�̍���z�������ɖ����������Y�炦�ʂ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�X���ɂā@���t�W����l���� |
|
|
���M�Z��
���Ȃ̂��� / �Z�M�����_�⓻ / ���ē��R���ő�̓�Ƃ��Ēm���A����ɂ͌Ñ���J��ՁA�߂��ɂ�ⴖ̓`���̎c�鉀��������B���Z����{�w����z���ĐM�Z�H�ցB �����q�E�ɓߌS ���� / ���ɓߌS���q�����B ����ǁE�ɓߌS ������ / �ѓc�s�a���H �������E�ɓߌS �������� / ��ɓߌS���쑺�����B���Ћˑ��F�Ћˋ��������̒��S�B ���{�c�E�ɓߌS �݂₾ / ��ɓߌS�{�c���B�Ó��R���́A��˓����z���Đz�K�ցB ���[��E�ɓߌS �ӂ����� / ��ɓߌS���֒����Óc�H ���P�m���� ���Ƃ��Ƃ��� / ���{���ƈɓߒJ�̋��E���Ȃ����B�\���{�Ɨ����{�̕�������Ȃ����̈�B�W��889m�B�]�ˎ��㒆�n�̓��O�B�X���͂��̓����z���Ē��R���ƍ��������B ���o�u�E�}���S ������ / ���{�s�F�쑺�䒬�B�������ォ��M�Z���{���u���ꂽ�B ���ѐD�E�}���S �ɂ����� / �㐅���S�l�ꑺ(���ە�����)�ѕ��F�ە������z���̏d�v�ȉw�B�]�ˎ���ە����X���ە����h�B�n���͏h�̓��[�ɂ���ە����ɗR������B���{�˂̔ԏ��ە����ԏ����u���ꂽ�B�z�㍑�֒ʂ��铌�R���x������_(���̉w�͖���)�B ���ە����� �قӂ����Ƃ��� / �}���S�Ə����S���q���d�v�ȓ��B�ە����R�̖k�̔����ɂ���W��1345m�E���R���̓�̈�Ō��������ł������B�����ɂȂ��ăC�M���X�̓o�R�ƃE�G�X�g�����A���̓��Ŗk�A���v�X�A���]�݁A���̑������Ɋ������u���{�A���v�X�v�Ɩ��������ꏊ�B ���Y��E�����S ����� / ���̏����S�ؑ� / �אڂ����c�s�ɉY��̒n�����c��B�w�̏ꏊ�͓��肳��Ă��Ȃ����A���̕ӂ�B���R���̓�ە������z���̏d�v�ȉw�B�����@���O�d��������B�Â�����J�����B�|����E�c����B ���j���E�����S �킽�� / ��c�s�����z�K�ӏW���̋߂�(�Ί݂͒��V��)�B��Ȑ��n��d�v�ȉw�B �������E���v�S ���݂� / �����s�����B �����q�E���v�S �Ȃ����� / �k���v�S�y��E���c��������B ���O�X�� ���������� / �W��958m / ��M�����B���[�̍�{�w�Ƃ̕W����458m�̌�ʂ̓�B���{���I�ɁA���{��������������M�Z�ɓ��鎞�q�O����(�����Ђ̂���)�r�ɂ�����A�q�O����r�ɓo���Ē�k�Q�����̂сA�q���(���Â�)�͂�r�Ƃ������Ƃ���B��썑����(����c��)�ցB�@ |
|
|
���ѐD [����]
�����сE�X���S ���� / �㐅���S���ё� / �ѐD�w���番�ĉz��Ɏ���x�H�̉w�B�����̓��́A�����̐��̌Ó����z���{�鑺�̒n�Ђ֏o�A��k�����o�Ė��щw�Ɏ���A��䑺�̊����g���l���̏�̌Ó�(964m)���z���čX���S�X�����̖���(����[)�ɉ����Ă��āA���ł��Â������c���Ă���B���щw�̐Ղ́A���ѐ_���{���̍k�n�B���т͍]�ˎ���k�����X���̏h��B ���j���E�����S �킽�� / �Ґ��n��d�v�ȉw�B�O�g���E�˕��E����ȂǏ�������B �����ÁE�����S ���� / ����s�O�˂���c�q���ӁB �����ӁE�����S �ʂ̂� / �㐅���S�M�Z����K�܂��͌ÊԁB�z�㍑�ցB�@ |
|
|
���{�c [����]
����˓� �����Ƃ��� / �z�K�S�ƈɓߌS�̋����Ȃ����B�W��1247m�B�z�K����͋}��B�z�K�J�������낷�W�]�͔��Q�B ���R�Y�E�z�K�S ������s�B ���J���� ���܂������Ƃ��� / ���ȎR���k�[�A���������ɂ���B�z�K�R�Y�n��(������s)�ƍ��v�쐼�n��(���]�����E��ȑ��E���Ȓ��E�k��q��)�����ԏd�v�ȓ��B�퍑����z�K���獲�v�֓���̂ɂ��g��ꂽ���B ���t���E���v�S ������ / ���k���v�S�]�����t���B �������E���v�S �������� / �����v�s�厚����(��������)�B��Ȑ��n�蒷�q�ցB�@ �@ |
|
| �����R��4 | �@ |
|
�����R���u�Ñ�̓��v��ǂށB
���グ��Ñ�̓��Ƃ́A���ߍ��Ƃɂ����7���I�㔼����8���I�ɂ����Č��݂���A10���I����܂ŋ@�\�����Ñ㊯���[7���w�H�[�̂��Ƃł���B�s����{�B�Ǝl���E��B��66��2�����ׂĂɒB���A���̓����͓ޗǎ���ɂ�12���[�g���A��������ɂ�6���[�g������{�Ƃ��đs��ȃl�c�g���[�N�ł������B���̒����͂��悻6300�L���A��16�L�����Ƃɉw��(���܂�)��u���A�S���ɂ��悻400�̉w�Ƃɂ͂��ꂼ��20�D����5�D�̉w�n���u���ꂽ�B ���̓��̂��Ƃ�������Ŗ��炩�ɂȂ�ŏ��́A�剻2�N(646)�̉��V�ْ̏��ɂ���B���R���͓��C���ƕ���Œ��H�ł���B��H�͎R�z��������A���̑��̓��͏��H�ł���B�w���쎮�x�����̓��R���ɑ����鍑�́A�ߍ]�E���Z�E��ˁE�M�Z�E���E����E�����E�o�H��8�����ł���B���R���̋N�_�́A�ߍ]�̍�(���ꌧ)����(���c)�ŁA�I�_�͋{�錧�̑����܂łł������A�̂��ɂx����ɕ��@�@����܂��B�\�͗����̍�(��茧)�̒_��u�g�B������͏o�H�̍�(�R�`�E�H�c)�̏H�c��܂�(����)�B�����ɂ���1000�L�����[�g�����z���܂��B �����썑�̓��R�� �����t�W�ɂ������c�����썑�암�̓��R���@�@ ��썑���牺�썑�̍ŏ��̑����w�Ɏ����ŎO���w(��M���V��)�́A�O���̒n���ɂ���āA��������O�}�R�̎��ӂƂ���Ă����B�O�}�R(�W��109���[�g��)�͂��̂�������ے�����R�ŁA���t�W�Ɏ��̉̂�����B ����̎O�}�̎R�̏���̂��@�ܖ�(����)������́@�N���y(��)��������(��14�A3424) �ŏ��ɎO���w���O�}�R�t�߂ɔ�肵���̂́A�w�w�H�ʁx�̑�Δ@�d�ŁA���Ì���(����M�����Ì�)�Ƃ����B�n���̓���ɓ�����A�@�d�͎O�}�̋u�̖k�ɂ�����Ƃ���B�~�m(���o��t)�̕����O���w�̉w���߂��Ƃ̘b������A���̉~�m�̐��n�Ƃ����̂��A���̊�M�����Ì��ł���B�~�m�̐��n�ɂ��āA��M�����p�������̂����ꂩ�Ɗm�F����Ă��Ȃ��B �����@�Ń��[�g�����炩�ȉ��썑�����E�k���̓��R���@�@ ����9�N(1972)�ɍ����V4���o�C�p�X�Ɩk�֓������ԓ��̌�_�ł���F�s�{��O��IC���ӂ̐�����ՂŁA��K�͂ȓ��R����\����������A����12�N(2000)�ɂ܂��A������ՂƂ��̓쐼������3�L���̏�_��E�Ό���Ղł����l�ȓ��R����\�����������B�w�̈ʒu�ŋ^������������w�̓c���w(��O�쒬��_��)���A��_���Օt�߂ɂ������\���������Ȃ����B���썑�{����c���w�܂ł�15.6�L���ŁA�����ɖ����c���Ă���O���E�c�����w�Ԃ̂܂��ɒ��ԓ_�ɉ��썑�{������A�������̉w�Ƃ̊Ԋu���ق�30���ɓ������B�c���w���琙����Ղ��o�Ė�6�L���ɂ킽��k�������ɂ܂������i�ށB���̈ߐ�w(�͓��������{)�͕��o�����_�����2�L���i�n�_�ŁAJR���k�{�����{�w�ɋ߂��B�c���w����17.3�L���ł���B�@ ���w�H�����̌��_�̂ЂƂA���R�� �ߐ�w��ʂ邱�̒����́A����ɋS�{����z����10���L���������ƂɂȂ�B�S�{�삩��8�L���قǂŊ֓�����͏I���A���R���͓ߐ{�̋u�˒n�ɓ���B�����ɒ�����̐�ʂ���������A�n���ł͌Â�����u���R���v�ƌĂ�Ă����B���`�Ƃ̉��B�����ɂ��Ȃ�ł���B���̐�ʂ����͓�ߐ{���Ǝ��ƒ�����ъ�A�쒬�Ƃ̒����E�����3�L���قǑ����B���̒����E����̓��H��������͓��R���ƒf�肵�A���̐���̉X�v�ۂ��A�����Ɍb�܂ꂽ�n�`��O��w�Ƃ̋����W����V�c�w(��ߐ{���Ƃ�ւ�R���X�v��)�ɔ�肵���B ����13�N(20001)�̒��҃�����Ղ̔��@�ŁA��^�̃R�̎��^���������Ղ����o����A�w�Ƃ��S�Ƃł͂Ȃ����Ƃ���Ă���B�܂��Y���Ă��o�y���A�`�Ɠ`���𗠕t�����B ����293�������ɏ��쒬�ɏo�āA�����Ő^�k�ɕϐj���āA���x�́A����294�����̃��[�g�����w�̔֏�w(���Ï㑺���Ï�)�܂Ŗk�シ��B ����294�ɂقڒ������[�g�ō��H������Ɏ���A�����œ߉ϐ��n��A�Ȍ�͂����ނ˂܂�����294���̃��[�g�Ŗk�サ�āA����w(�ߐ{���ɉ���)�ɒB����ƌ������B���悤�ǂ��̑Ί݂̍���294���ɉ����ē��̉w�u���R���ɉ���v������A�Ñ�H�ɂ��Ȃޖ��������Ă���B ����w����͎O����ɉ����A���݂͎�v�n����76����{���͐��ƂȂ��Ă��郋�[�g��i�݁A�ȖE�����������z���āA���悢�旤�����֓����Ă䂭�B�����܂ł̉��썑��7�w�̉w�n���͂�������W���ǂ���10�D�ł���B �@ �@ |
|
| �����R�� | �@ |
|
����ƍN���A�c��5�N(1600)�̊փ����̐킢�̌�A�܂���������̂́A�X���̐����ł����B�]�˂��狞�s�Ɏ��铌�C���\�O�����߁A�����Ōc�����N(1602)���R���Z�\�O���A�����������B�����A�b�B�����A���������̌܊X���{�̒����n�Ƃ��A�h�w�⓹���𐬗��������B����������{�������̋N�_�ł���B
���R���͍]�˓��{�����狞�s�O��勴�܂Ō��Ԗ�S�O�\�ܗ���(��534�q)�̊X���ł��B�}�́A�Z�\��h�̏h��������̂ł��B���Âł͓��C���ō�������̂ŘZ�\���h�Ƃ�����̂�����܂��B���C�������g�ȑ����m�݂�ʂ�C�̓��ɑ��A���R���͌������O�X����ؑ]�H��ʂ�R���ł����B�����œ��C���̌\�O���A�S��\�Z���]��ɑ��A���R���͋����������h��̐������������B����������E�V����E�y�m��Ȃǂ̐엯�߂�A�{�|�K���Ԃ̂悤�ȊC�̑D�����Ȃ��̂ŁA�����ɐl�C�̂��鏗�X���ł����B��㏫�R����Əd�A�\��Ǝ��̌�䏊(����)�����s����}�������A�܂������ɍc���a�{�l���\�l��Ɩɍ~�ł��铌����̎��A����������R����I��ł��܂��B ���{�����Ē��R���̍ŏ��̏h�ꂪ���h�ł��B�]�˂̎l�h�̂ЂƂŁA�i��h�A�����V�h�A��Z�h�ƂƂ��ɁA�����̐H����(�ѐ���)�����āA����}���̐l�X���X��������Ƃ����Ă܂��B�܂��A�̗̂��͖������A�����Łh�����������h�����݂��킵�ĕʂ��ɂ��l�������悤�ł��B ���z�K�́A���R���ƍb�B�X���A���q�X����������ʂ̗v���ł��B���ł��A�h�]�˂���\�ܗ��h�̈ꗢ�˂̔肪�c���Ă���Ƃ̂��ƁB�܂��A�z�K��Ђ̖�O���Ƃ��Ă��h�����h�꒬�ŏh�������Ă��������ł��B�]�˂������ɂȂ�ƁA���������ɏo����悤�ɂȂ�܂����B����܂ł́A�Q�Ό��̑喼�s���{�Ƃ̍~�ł̍s��A���p���s�҂��傾�����킯�ł��B�ꐶ��x�̂��ɐ��Q��͗L�������A���R�������ɂ��A��썑�̖��`�R��Y���R�ւ̎Q�w�A�z�K��Ђ�P�����Q��Ȃǂ�����B���֏オ��ɂ��A�����Ɍi���n�▼�����Ղ������̂Œ��R���𗘗p����l�X���������Ƃ����܂��B �u�ؑ]�H�͂��ׂĎR�̒��ł���B����Ƃ���͑Z�Â����ɍs���R�̓��ł���A����Ƃ���͐��\�Ԃ̐[���ɗՂޖؑ]��݂̊ł���A����Ƃ���͎R�̔����߂���J�̓����ł���B�c�c�v �����́u�閾���O�v�̖`���̈�߂ł����A���R���Z�\��h�̂����\��h���W�܂�ؑ]�H�́A�������R����������ł���B�}�u���R���Z�\��h�v�ɂ��A�ѐ�A�ޗLj�A�����A�{�m�z�A�����A�㏼�A�{���A��K�A�O����A���āA�n�Ă̏\��h�B�L�d�E�p��̕����G�ł́A���R����ؑ]�X���ƌ����Ă��܂��B�ؑ]�J�𒆐S�Ƃ���R�H�ł��邱�Ƃ������������̂ł��傤�B�ؑ]�����͖��{���������V���l��֏��̂ЂƂŁA�]�˂����d�v�ȋ��_�ł����B�֏��ł͒ʍs��`���Ȃ��ƒʂꂸ�A���Ɂu����S�C�ɏo���v���x�����܂����B ���R���ݗ��ȑO�̓��@/�@�]�˖��{�ɂ���Č܊X���̂ЂƂƂ��đ������ꂽ���R���ł����A����ȑO�ɂ����͂���܂����B�u���R���v�ƌĂ�A�Ñォ�璆���ɂ����ē��Ɛ������ԏd�v�ȓ��ł����B�剻�̉��V�ɂ��w���Ȃǂ���������n�߁A�����o���Ă����Ƃ����L�^������܂��B�����ɂȂ�ƁA���q�ɕ��Ɛ������a���A��Ɛl�������u�������q�v�Ƌ삯���铹���K�v�ƂȂ�܂����B�e�n�ɂ�������������A���q�֎��铹�A���q����(���q�X��)������ł��B����ɐ퍑�̌Q�Y�����Ɏ���ɂ́A�Ⴆ�Ε��c�����ؑ]�H�̓`�n�̌p�����s���ȂNJX����h�w��݂��Ă��܂����B���̂悤�ɒ��R�����A���R������ɁA�ꕔ�ł͊��q�X����퍑����ɐ݂���ꂽ�������C���������ꂽ�̂ł��B ���āA���R���́A�ʂɒ��哹�Ƃ������Ă��܂������A�]�˖��{�͐����Z�N(1716)�A�����ɒ��R���ƋL�����Ƃ𖽂��Ă���B���̐G���ɂ́u�܋E�����V���ɓ��R���A�R�A���A�R�z�����Â���R�̓����Z���Ƃ�ݐ\��B���R���̓��̒��̓��Ɍ�̂ɁA�×���蒆�R���Ɛ\���Ɍ�v�Ɛ������Ă��܂��B�n���ɏڂ����V�䔒�̈ӌ��ɂ��A�Ƃ��B����ɑO�q�̂悤�ɁA�ؑ]�H��ʂ邱�Ƃ���A�ؑ]�X���A��h�H�A��c�H�Ƃ������A���C���ɑ��A�P�Ɂu�R���v�Ƃ��Ă�ł����Ƃ̂��ł��B���Ɛ������ԊX���͐l�̌�ʂ���łȂ��A�Ă╨���̗A���A���i�ו��̉^���ɗ��p����A����ɏh�w�̎{�݂���������܂����B�@ �@ |
|
| �����C��1 | |
|
(�Ƃ������ǂ��A���݂݂�)�@�܋E�����̈�B�{�B�����m���̒����̍s���敪�A����ѓ�����ʂ銲�����H(�Ñォ��ߐ�)���w���B
�s���敪�̓��C���́A�E�����瓌�ɐL�т�A�{�B�����m���̒������w�����B����́A���݂̎O�d�������錧�Ɏ��鑾���m���݂̒n���ɑ�������B ���ɉꍑ(���݂̎O�d���̐���) ���ɐ���(���݂̎O�d���̐����Ɠ암�y�юu���������������S��) ���u����(���݂̎O�d���̎u���������ƈ��m���̈��������̊Ԃɂ���ꕔ�̓��X) ��������(���݂̈��m���̐���) ���O�͍�(���݂̈��m���̒����Ɠ���) �����]��(���݂̐É����̐���) ���x�͍�(���݂̐É����̒����y�ѓ���) ���ɓ���(���݂̈ɓ������y�шɓ�����) ���b�㍑(���݂̎R����) �����͍�(���݂̐_�ސ쌧�̒����E����) ��������(���݂̓����s�ƍ�ʌ��A�_�ސ쌧�����̈ꕔ�B���߂͓��R��) �����[��(���݂̐�t���̓암) ���㑍��(���݂̐�t���̒���) ��������(���݂̓����s�̋��c�쓌�݁A��t���̖k���A��ʌ��̒��쓌�݁A��錧�̓쐼��) ���헤��(���݂̈�錧)�@ |
|
|
�����Ƃ��Ă̓��C��
���ߎ���̓��C���́A���C���̏����̍��{���w�H�Ō��Ԃ��̂ŁA�e���ɔh�����ꂽ���l�����������@����ׂɐ������ꂽ�H���w���B���ߎ���ɐ݂���ꂽ�����̈�ŁA���H�ł���B���ߎ���̓��C���̓����́A������]�ˎ���̓����L���A��蒼���I�Ɍ��݂��ꂽ�B ���̈���ŁA�����͑�͐�ɋ����˂���Z�p�͔��B���Ă��炸�A�K���E���ǐ�E�ؑ]��E����E���{��E�x�m��E������E������(����)�Ƃ������n�͂�����ȑ�͂̉������ʉ߂��邽�߁A�ނ��듌�R���̎R���̕������S�ƍl�����Ă�������������A���C���������ɂȂ�̂́A�n�͂̎d�g���������ꂽ10���I�ȍ~�̂��Ƃƍl�����Ă���B �����ɑ唼�����p���ꂽ���߁A�����̐��m�ȓ��ɂ��Ă͋c�_����Ă��邪�A�����ނˈȉ��̂悤�Ȍo�H��ʂ��Ă����l�����Ă���B�@ |
|
|
���E������ߍ��܂�
��s���ɒu���ꂽ�����ɂ́A��a���̉F�ɂ��A���C�����ʂւ̓����������ƍl�����Ă��邪�A���̌�A���鋞�ɑJ�s�����ƁA���鋞���畽��R��k�サ�A�ؒÂ���ؒÐ�̒J�Ԃ𓌂֓����Ĉɉꍑ�ɓ���A�鎭�R���ƕz���R�n�̈ƕ��������z���ʼnz���Ĉɐ����ցA�ؑ]�O���������œn���Ĕ������Ó��ցA���É��s��ʂ�A�O�͍��Ƒ����Ă������ƍl�����Ă���B���悻�A���݂̍���163�����A����25�����A����1�����ɉ��������[�g�ł������B �������A�ؑ]�O��̉������͌×���萅�Q���������A���ۂɂ͑D�ɂ��ړ��������Ă����ƍl�����A���邢�͔╽�鋞����鎭�����o�R���Ă��̂܂܈ɐ����̍`����ɐ��p�����f����C�H���p�����鎖�����������Ƃ݂��Ă���B�����A���̈���ł��������D�ɂ͔n�������邱�Ƃ��o�����A��������n�ɏ���Ă������s�҂͎O�͍����������Ŕn�𑼎҂ɗa���Ĉɐ����Ɍ������D�ɏ��K�v�����������A�A�r���ɔn�̕Ԋ҂�����g���u���Ȃǂ�������(�w���{���I�x�剻2�N3���b�\��)�B���̂��߁A�k����n�ŗ��𑱂��悤�Ƃ���l�̒��ɂ́A�{���͔F�߂��Ă��Ȃ������������{����k�サ�Ĕ��Z���ɂ��铌�R���̕s�j�ւɏo��o�H���p�����Ă����B�ɐ��p�����f����C�H�Ɠ��R���ɏo��e���̑��݂́A�]�ˎ���̎����̓n������Z�H�̌��^�Ƃ��čl���邱�Ƃ��ł���B �������ɑJ�s�����ƁA�N�_���������Ɉڂ������߁A�ɉꍑ����A�ߍ]����ʂ郋�[�g�ɕύX����邱�ƂɂȂ�B�������㏉���ɂ͌��݂̞[�X������ɉꍑ�ɓ���o�H���Ƃ�ꂽ���A886�N(�m�a2�N)�ɗ鎭����ʂ�o�H�ɕύX����A�قڌ��݂̍���1�����̃��[�g�ɏ�����悤�ɂȂ����B �������E���� ���݂̕l���s�t�߂���É��s�t�߂Ɏ���o�H�ɂ��ẮA�]�ˎ���̋����C�������A���C�݊��̃��[�g��ʂ��Ă����Ƃ݂��Ă���B�ĒÎs�ƐÉ��s�̋��͓�ł���A���{��ƌĂ�A���{�����̓����`���▜�t�W�̉̂ɂ��r�܂�Ă���B���n�́A��������ɂ́A���������̉F�Ãm�J�����A�ӂ̍ד��Ƃ��ĕ����Ɍ����悤�ɂȂ�B �x�͍��Ƒ��͍��̍����ɂ��ẮA���Â����a����o�R���đ��������z���A�֖{�Ɏ��鑫���H������Ă����B�������A�������㏉���̕x�m�R�̕��ɂ���Ēʍs�s�\�ƂȂ������߁A�O������A�����J���f�����c�т��锠���H���J����邱�ƂɂȂ����B ���͍��ł́A���͘p�����ɓ��i�݁A���q����O�Y�����֓���A��������Y�ꐅ����n���Ė[�������ɓ���A��������k�サ�āA���[���A�㑍���A���������o�āA�헤���֎��郋�[�g���A�ޗǎ��㏉���̃��[�g�ł������B���̃��[�g����O��镐�����́A�O�X�����̓��R���ɑ����Ă����B�������A����ł͕������ւ̌�ʂ��s�ւł���A���R���Ɋւ�������̏�Ŕ��ł���Ƃ��āA771�N�ɁA�������́A���C���ɈƑւ�����邱�ƂƂȂ����B���̍ہA�֓�����암�̓��C�����傫���t���ւ����A���͍�������k�サ�A���̂܂ܕ������ɓ����āA���݂̓����s�S����ʂ�A���̓����ɍL����A���c����͂��߂Ƃ���A�Â�������E�n�ǐ���̒Ꮌ�ȃf���^�n�т�ʉ߂��āA���݂̐�t���s��s�̉������{�Ɏ���A�X�ɏ헤���ւƌ��������[�g�ɂȂ����B �헤���̐�A�ܗ��ւ̖k���́A���݂̕������l�ʂ�n���암�́A��������◬���I�ł���A�����́A�헤���܂ő����m���݂ɐL�тĂ������C���̉����Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ����������A���̌�A���݂̋{�錧�ɒu���ꂽ�������{�̊NJ����ɒu����邱�ƂƂȂ�A���R���ɑ����邱�ƂƂȂ����B���C���̉����́A�헤���k���œ����ɓ���A�I�q�\���������̍\���J��k�サ�āA���R���ɍ�������A���H�Őڑ����ꂽ�B ����������� �������㒆�����߂���ƁA���ߐ��̒o�ɂɔ����A���Ƃ̌��I�Ȍ�ʂɑ���A��茻���I�ȕK�v�ɔ�����ʂ��s����悤�ɂȂ����ƍl�����Ă���B�X�����L�ɂ́A1020�N�H�ɁA���Ґ����F�W���̕��̏㑍���ւ̕��C���I���A���C����ʂ��ċ��s�ɋA�铹�����L����Ă��邪�A�����ɂ́A�Z������k�����̖n���ƁA���R���̗v�Ղ̂͂��̕s�j�ւ�ʉ߂����ƋL����Ă���A�����̎�����̌�ʏ��M����B ���e�X�� ���C���ɂ́A�R���I�E�n���I���R����A�����ȃ{�g���l�b�N�ƂȂ�|�C���g��A�n���I�I��H�ƂȂ�|�C���g���c����Ă���A���̂悤�Ȍ�ʏ�Ǝ�E�s�ւȕ����ɂ́A�����������邽�߂̘e�X�����u���ꂽ�B�e�X���ɂ͑��͍��̓�������ʂ��Ē����I�Ɍ��Ԓ����X���A�����h���l���̍��̓n���ƐV���֏����I�A�C��֏���ʂ�A�{�⓻���z���A�g�c�h�Ȃ�������h�֔����铹�ł���P�X���A�{����K�����̎����̓n��������āA�Z����������𗤘H�Ō��ԍ����X�����������B���ɁA�P�X���Ɋւ��ẮA��i�n�k�Ƃ���ɔ�����Ôg�ŁA���̓n�����j��Č�ʓr�₵�Ă��܂������Ƃ���A18���I�����ɂ́A���C���{���̌�ʂ��܂邲�ƈ������ʂ��������B�@ �@ |
|
| �����C��2 / ���I�s | |
|
��͕S�Ƃ��̔��ɋ߂Â��āA餂̑��₤�₭�ɗ₵�Ƃ��ւǂ��A�Ȃ����Ȃ����ēk�ɖ����邷�݂̂ɂ��炸�A�����Ă��Â��ɏZ�ׂ͂��Ƃ��v�В�߂ʗL�l�Ȃ�A���̔��y�V�́u�g�͕��_�Ɏ�����A��͑��Ɏ�����v�Ə����ւ�A���͂�Ɏv�Ѝ������B���Ƃ��������t�̂����ւ��D�܂��A���U�����ܖ��̐���]�ށB�����͂���ǂ��A���R�̉��̎Ă̈��܂ł��A���^�_�v�Ђ₷��ӂقǂȂ�A�Ȃ܂���ɓs�̂قƂ�ɏZ��T�A�l�Ȃ݁^�_�ɐ��ɂӂ铹�ɂȂ��Ȃ��B�����g�͒��s�ɗL�ĐS�͉B�قɂ��������B
���T����ɁA�v�͂ʊO�ɁA�m���O�Ƃ��̏H�����\���]��̔�A�s���o�ē��ւ����ނ����L�B�܂��m�ʓ��̋�A�R�d��]�d��āA�͂�^�_�������Ȃ�A�_�𗽂����T�A���^�_�O�r�̂��͂܂�Ȃ��ɂ��T�ށB��ɏ\�]�������ւāA���q�ɉ���t���ԁA���͎R�ٖ���̖�̔��A���͊C�Ӑ����̐������Ȃ�݂��肢���邲�ƂɁA�ڂɗ����X�A�S�Ƃ܂�ӂ��^�_�������u�āA�Y�ꂸ�E�Ԑl������A���̂Â����̌`���ɂ��Ȃ�ƂĖ�B �� ���R�̂قƂ�Ȃ鐲���o�A����̊ւ����߂�قǂɁA��Ђ��킽���]���̔���Q�߂���Ȃ�A�H�����n��āA�ӂ�����̌��e�ق̂��Ȃ�B�[�����H�ɂ��ƂÂ�āA�V�q�P�c���ɍs�����J�̗L�l�v�������B�ނ�����ۂƂ��Ђ��鐢�̐l�A���ւ̂قƂ�ɘm���̏����ނ��тāA�˂ɔ��i�����ĐS�����܂��A�a�̂��r���Ďv���q����B���̕��͂�����������T������������B�L�l�̂��͂��A��ۂ͉����l�̋{�ɂĂ��͂��܂������ւɁA���̊ւ̂�������l�̋{�͌��Ɩ��t����Ƃ��ւ�B ���ɂ��ւ̂���̏��̂�����܂ŐS���Ƃނ鈧��̊� �� ���O���@�A�ΎR�ɂ܂��łĊҌ�L����ɁA�ւ̐������߂������܂ӂƂĂ�܂����܂Ђ����̂ɁA�u���܂��x�䂫���Ӎ�̊��ɂ��ӂ�������̂������߂����v�ƕ���邱���A�����Ȃ肯���S�̕��ɂ��ƁA���͂�ɐS�ڂ�����B �� �֎R�z���߂ނ�A�ŏo�̕l�A���Â̌��Ȃ�Ǖ�����ǂ��A���܂���̂����Ȃ�A�������ɂ����킩�ꂸ�B�̓V�q�V�c�̌��A��a���̉��{�̋{���A�ߍ]�̎u��̌S�ɂ��肠��āA��Â̋{������ꂯ��ƕ��ɂ��A�����͂ӂ邫�c���̐Ղ������Ƃ��ڂ��āA����B ���U�Ȃ݂��Â̋{�̂��ꂵ��薼�̂ݎc���u��̌̋� �� ���ڂ̂̋�ɂȂ�āA���c�̒���œn��قǂɁA�͂邩�ɂ���͂�āA�ޖ������킪��b�R�ɂĂ��̊C���̂��݂T��߂肯��̎v�Џo���āA���s�M�̂��Ƃ̔��g�A�܂��Ƃɂ͂��Ȃ��ĐS�ڂ����B ���̒��𑆍s�M�ɂ悻�ւT�Ȃ��߂����Ƃ��Ȃ��ނ� ���̂قǂ����s�����āA��H�Ƃ��ӏ��ɂ�����ʁB���̌��I���������āA���߂��������̂��Â��ƐS�ڂ����B ���H�̖�H�̒������ӂ₳�͂����Ƃɂ��T��͂��ߐ���� �� ���Ƃ��ӏ�������A���ւ͂邩�ɒ����炠��B�k�ɂ͗��l�������߁A��ɂ͒r�̂����ĉ��������킽��B�ނ��ւ݂̂���A�݂ǂ�ӂ������̂ނ炾���A�g�̐F���ЂƂȂ�B��R�̂������Ђ����˂A�����ğ��f����B�F�菊�^�_�ɓ���āA�����݂Ȃǐ��n��钆�ɁA�����̑łނ�Ĕ��ӂ��܁A�����������₤�Ȃ�B�s�𗧗��l�A���h�ɂ������肯�邪�A���͑ʼn߂邽���Ђ��ق��āA�Ƌ����܂�ɐ��s�ȂǕ������A���͂�䂭���̏K�A�̐�̕����ɂ͂����炴�肯�߂Ƃ��ڂ�B �䂭�l�̂Ƃ܂�ʗ��Ɛ�����肠��݂̂܂����H�̎� �� ���̏h�Ɏ���ʂ�A�̎��̉��̊T�A�V�����ƂЂēǂ���̂̒��ɁA�u���R�����������Č��Ă䂩�ޔN�ւʂ�g�͘V�₵�ʂ�Ɓv�Ƃ��ւ�́A�����ɂ�Ƃ��ڂ��āA�h������܂ق�����ǂ��A�P�������܂ɂƂӂׂ�������āA���������ʁB �������ł��ӂ͉߂ȂR����ʂ����Ȃ̂����͌����Ƃ� �s��ʂ�A�������Ƃ��ӎR���̂�����ɔ��ʁB�܂�Ȃ鏰�̂�����A�H����X��܁T�ɐg�ɂ��݂āA�ވ∤���̕ӂ̑��̐Q�o���A������L���ނƈ��Ȃ邤���ɂ��A�s���������̋�v�ЂU�����āA���Ƃ����������Ȃ��B ���o�Ċ���������ʍ������ɕ��s��тʏ��̏H���� �� ���̏h���o�āA�}���̖쌴�Œʂ���ɁA�V�h�̐X�Ƃ��Ӑ�������B�����[�������́A���ɂ��͂�ލs�����A�͂��Ȃ����錎���Ȃ�A�Ƃ����炸���ڂ�B ���͂炶�ȉ���Ƃ�Ђɂ����������ɂ��V�h�̓m�̉����� �� ���ɕ������P�������A���Â��̉���˂�藬��o�鐴���A���܂�������܂ł��݂킽��āA���ɐg�ɂ��ނ���Ȃ�B�]�M���܂���������Ȃ�A�����̗��l���ق�����Ă��U�݂��ւ�B�����\(�ǂ�������G)���c��̐�A�ݕ��ɑ�ւĂ��炭�Y��ʂ�A���������Ȃ�ǂ��A������ގ��͕������āA����ɂ������ꂸ�B���s���A�u���̕ӂ̐����Ȃ���T���A�����ƂĂ������Ƃ܂��v�Ƃ�߂���A���₤�̏��ɂ�B ���ׂ̖̂����̐����ނ��ԂƂĂ������U�܂ʗ��l���Ȃ� �����Ɖ]���𗧂āA���Z���֎R�ɂ�������ʁB�J�얶�̂����ɂ��ƂÂ�A�R�����̐��Ɏ��J�킽��āA���e�������ʖ̉����A���ɐS�ڂ����A�z�ʂʂ�Εs�j�̊։��Ȃ�B�ݔN�ւɂ���ƌ����ɂ��A�㋞�ɐې��a�́A�u�r�ɂ���͂��U�H�̕��v�Ƃ�܂����ւ�́A�v�o���āA���̏�͕�����܂͂肪������A���₵�����̗t���c��������^�_�o�āAূ��ނȂ����ʼn߂ʁB ������Ƃ��ӏ��ɔ���āA��X����ɐ���ɗ��o�Ă݂�A�H�̍Œ��̐��̋�A�����쐣�ɂ���ЂāA�ƌ��Ȃ݂�������v���݂킽��A��痢�̊O�̌Ðl�̐S�v�Ђ���āA���̎v�Ђ��ƁU�����ւ��������ڂ��A���̂����ɕM����T�A�u�ؗ����o�ĎO���A����ɏh���Ĉꏪ�A���^�_�H��𒆏H�O�ܖ�̌��ɂ����܂��߁A���^�_�������O�r��痢�̉_�ɂ�����v�ȂǁA����Ƃ̏�q�ɏ����鎟�ʂɁA �m�炴�肫�H�̔��̍����������T�闷�Q�̌������ނƂ� �� ���Â̓��h�̑O���߂�A������̐l���܂�āA�����ЁU���v�ɂ́T���肠�ւ�A�����͎s�̓��ɂȂ��肽�邼�Ƃ��ӂȂ�B�����̂����ЁA�薈�ɂނȂ�������ʉƂÂƂ��A�ށu���Ă݂̂�l�ɂ������v�Ƃ�߂�A�̌`���ɂ͂₤���͂�Ă��ڂ�B �ԂȂ�ʐF�����m��ʎs�l�̂����Â�Ȃ�ł��ւ�ƂÂ� �� �������M�c�̋{�Ɏ���ʁB�_�_�̂�����߂���A�₪�Ă܂���Ĕq�ݕ��ɁA�ؗ��N�ӂ肽��m�̖̊Ԃ��A�[���e�����^�_�������������A�����̋ʊ_�F�����ւ���ɁA���߂�ӂɔނ�ӂ��ŕ��ɂ݂��ꂽ�邱�Ƃ���A���̂ɂӂ�Đ_���т��钆�ɂ��A�˂��炠�炻�Ӎ�ނ�̐������炸���ɂ���邳�܁A��̂����₤�Ɍ����āA��������������A��s�܁T�ɂ��Â܂�䂭�����S����������B�L�l�̂��͂��A���{�͑fᵖ���B�͂��ߏo�_���ɋ{���L����B�u���_���v�Ƃ��ւ��a���̗t���A����肼�͂��܂��B����i�s�V�c�̌��ɁA������ɐՂ����ꋋ�ւ�Ƃ��ւ�B�����͂��A���̋{�̖{�̂́A����ƍ������_����B�i�s�̌�q�A���{�����Ɛ\�A�������炰�ċA�苋�ӎ��A���͔����Ɛ��ċ����ӁB���͔M�c�ɂƂ܂苋�ӂƂ��ւ�B ����@�̌䎞�A��]���t�Ɖ]���m�L����B���ۂ̖��ɂ�����āA�����̎�ɂĉ��肽�肯��ɁA��ʎ�����Ă��̋{�ɂċ��{���Ƃ����肯��蕶�ɁA�u�킪�肷�łɖ����ʁB�C������������B�ӂ邳�ƂA���Ƃ�����A���܂��������Ȃ炸�v�Ə����邱���A���͂�ɐS�ڂ����������B �v�o���Ȃ��Ă�l�̋A��܂��@�̌`��������������� �� ���{�𗧂ĕl�H�ɂ����ނ��قǁA�L���̌��e�X�āA�F�Ȃ��璹���^�_�����ƂÂ�킽��A���̋�̂���S�ɍÂ��āA�����^�_���ӂ����B �ӂ邳�Ƃ͓����ւĉ����Ȃ�݊������������̓��������Ȃ� �� �₪�Ė�̓��ɓR�ɂ��T��āA�R���Ȃǂ��߂�قǂɁA���₤�^�_����݂āA�C�̖ʂ͂邩�Ɍ���n���B�g�������ɂāA�R�H�ɂU������₤�Ɍ���B �ʙ��R�̂ق́^�_�Ɩ��s����͔g�H�Ȃ肯�� �� �䂫�^�_�ĎO�͍������̂킽�������A���̋ƕ����m��̉̂�݂��肯��ɁA�݂Ȑl���ꂢ��̏�ɗ܂��Ƃ����鏊��Ǝv�o���āA���̂����������ǂ��A���̑��Ƃ��ڂ������͂Ȃ��āA��݂̂����������B �،̂ɂ������܂̂����݂Ƃ��t�̘I���c��������� �� ���̉Î킪���̍��̎�ɂĉ����鎞�A�Ƃ܂肯�鏗�̂��Ƃɂ��͂�����̂ɁA�u����Ƃ��ɂ䂩�ʎO�͂̔���������Ƃ݂̂�v�Ђ킽��ށv�Ɠǂ肯�邱���A�v�Џo���Ĉ��Ȃ�B ��Ƃ��ӏ��𗧂āA�{�H�R�z���߂�قǂɁA�ԍ�Ɖ]�h�L�BূɗL���鏗��ւɁA��]���Ƃ��o��������͂��B�l�̔��S���铹�A������ɂ���˂ǂ��A�����ʕʂ�������݂����Ђ̐S����������ׂɂāA�܂��Ƃ̓��ɂ����ނ�����A�L����ڂ�B �ʂ�H�ɖ���ʂŊ��̗t�̂����ł�����ʂ����ɂ��ւ肵 �� �{��쌴�ɑŏo����A����̖]�݂��������ɂ��āA�R�Ȃ����Ȃ��B�`���̈��]�������n�������S�n���āA���y�Ƃ��ɑ�䩂���B���̖�̖]�����Ȃ��Ə��������ڂ�B�������̒��ɁA���܂��ӂݕ����铹����āA�s�����܂�Ђʂׂ��ɁA�̕����̎i�A���̂����̔y�ɂ��ق��ĐA�ւ����ꂽ������A���܂��A�Ƃ��̂ނ܂ł͂Ȃ���ǂ��A���^�_���܂Ó��̂���ׂƂȂ�������B���낱���̏����Z�L(�V���E�R�E�Z�L)�͎��̕����̒��A�����̎O���Ƃ��āA���Ɖ]���������ǂ肫�B�W�̐��̕������߂����A�ЂƂ̊Þ��̂��Ƃ����߂Đ������Ȃӎ��A�����l���n�Ă���^�_�̖��Ɏ���܂ŁA���̂��Ƃ������Ȃ͂��A���܂˂����l�̂���ւ����Ƃ͂�A�������߂����Ȃ��߂���B���̖�������đ�������E�Ԍ̂ɁA��������ɂ��Ղ܂ł��A�ޖ�����܂ЂĂ��ւĔ��炸�A�̂��Ȃ���肯��B��O��V�c���{�ɂĂ��͂�����ɁA�w�m�����C���ɂ����ނ����A�u�B�̖��͂��ƂЊÞ��̉r���Ȃ��Ƃ��A�Y��T���Ȃ���B���ق��̔N�̕����̂����сv�Ƃ��ӌ䐻�����͂����肯����A���S�ɂ₠�肯��A���݂������������Ȃ��B�ޑO�̎i���A�������̐Ղ�ǂЂĐl���͂��T�ݕ������ނ��܂�A���̂قƂ�̍s���̂����܂ł��A�v���ĐA�ւ����ꂽ����Ȃ�A��������y�A�݂Ȃ��̏�����E�т��̖��̂��Ƃ��ɂ����݂߂łāA�s���̈��Ƃ��̂܂A���̖{�ӂ͒�Ă����͂��Ƃ������ڂ��B �A�֒u������Ȃ����Ƃ̖����Ȃ����̈����ЂƂ₽�̂܂� �� �L��Ƃ��ӏh�̑O��ʼn߂�ɁA������̂̂��ӂA���̓��͐̂��悭����Ȃ��肵�قǂɁA�߂������ɓn�ӒÂ̍����Ƃ��ӂ����ɗ��l���ق����T�邠�Ђ��A���͂��̏h�͐l�̉Ƌ������ւق��ɂ݂̂����Ȃǂ����ӂȂ�B�Â����̂ĐV�~�ɂ��Ȃ�ЁA���鎖�Ƃ��ЂȂ���A�����Ȃ��ւȂ��Ƃ��ڂ��Ȃ��B�̂��Z�����闢�l�́A������������A���̕����̗��Ȃ�˂ǂ��A�r��܂����������ڂ��B ���ڂ��Ȃ����L��̂��͂鐣���������l�̂킽�肻�߂��� �� �Q��A���]�̂����ЂɁA���t�R�ƕ���邠��B�R���ɉz�����T��قǁA�J��̗��ꗎ���āA�␣�̔g���Ɓ^�_��������A����Ƃ����ӂȂ�B ����Ћ���킽���J��̉����������̎R�ɗ��ɂ��� �� ���{�Ƃ��ӏ��ɍs���ʂ�A���n�肵���ЗL�āA�i�C���ƐS�������B��ɂ͊C������A���M�g�ɂ����ԁB�k�ɂ͌ΐ�����A�l�Ɗ݂ɂ�Ȃ��B���ԂɏF�艓���w�o�āA�����т������ЂU���A��������ɂނ��ԁB���̂ЁU���A�g�̉��A���Â�������킫�������B�s�l�S�������܂��߁A�Ƃ܂邽���ЁA�����o�����Ƃ��ӎ��Ȃ��B�ɓn���鋴��l���ƂȂÂ��B�Â�������B�����_�̖��c�A���Â������S�ڂ����B �s�Ƃ܂闷�Q�͂������͂�˂ǂ킫�ĕl���̋����߂����� �� �M�����h�Ɉ�锑�肽�肵��ǂ���B���Â��銞���̏��^�_�܂�Ȃ錄���A���̉e�܂�Ȃ��w������܂����A�N�ǂ����܂����������ɁA���������ƂȂт��邯�͂ЂɂāA�u��������珰�̉��ɐ��V������v�ƁA�E�т₩�ɑʼnr���肵�����A�S�ɂ������ڂ������B ���̗t�̐[����͌��[���錎�̂���̐F�Ɍ����ɂ� �� �Ȃ��肨�ق����ڂ��Ȃ���A���̏h�����ŏo�čs�߂�قǂɁA����̌��Ƃ��ӏ��ɗ�������B�k���ὁX�Ɨy���ɂ��āA���͊C�̏��߂��B�щ؏J���̂����Ђ͂��Ƃ��������A�����������݂̂���Đ�̐ς�Ɏ�����B���Ԃɏ������^�_�����킽��āA�������ɉ��Â�T�B�����₵�̑��̈��̏��^�_�Ɍ����A���l�ދq�Ȃǂ̐��ɂ�L��ށA���Ƃ����쌴�Ȃ�A���^�_���Ɖr�s�قǂɁA�łꂽ�闷�l�̂�����������A���̔���Ƃ͒m�炸�A�����ɖؑ��̊ω����͂��܂��B�䓰�ȂNj����r��ɂ���ɂ�B���肻�߂Ȃ鑐�̈��̂����ɉJ�I���܂炸�A�N���𑗂�قǂɁA��Ƃ��]�ގ�����āA���q�։���}���l���肯��B���ω��̑O�ɎQ�肽�肯�邪�A�����{�ӂ��Ƃ��Č̋��ւނ��͂A�䓰������ׂ��悵�A�S�̒��ɐ\�u���肯��B���q�ɂĖ]�ނ��Ƃ��ȂЂ���ɂ��āA�䓰����肯����A�l���ق��Q��Ȃ�Ƃ����ӂȂ�B�����ւ����̌䓰�֎Q�肽��A�s�f���̂ɂقЁA���ɂ����͂�Ă������ق�A脉��̉Ԃ��I�����₩��B�菑�Ƃ��ڂ������́A�l���̕R�Ɍ��т�����A�u�O���̂ӂ������C�̂��Ƃ��v�Ƃ��ւ�����̂��������ڂ��āA ���̂����ȓ��]�ɂ���݂������[�����̂���ƕ��ɂ� �� �V���Ɩ��t����n�肠��B��[�����ꂯ�͂����ƌ����A�H�̐��݂Ȃ��藈��āA�M�̋��鎖���݂₩�Ȃ�A�����̗��l���₷���ނ��ւ݂̊ɒ���B���̐쑝��鎞�́A�M�Ȃǂ����̂Â��炭�A�āA��݂̂��ÂƂȂ邽���Б�����ƕ��������A�ޛދ��̐��̗���v�Ђ悹���āA���Ɗ낤���S������B��������ǂ��A�l�̐S�ɂ���Ԃ�A���Â��Ȃ闬�������Ǝv�ӂɂ��A���Ƃӂׂ������Ȃ��́A���ɂӂ�݂��̂��͂����K�ЂȂ�B ���̐�̂͂₫��������̒��̐l�̐S�̂����ЂƂ͌��� ���]�̍��{���̉Y�ɒ��ʁBূɏh����Ĉ��������肽��قǂɁA僂̏��M�������ĉY�̂��肳�܌��߂���A���C�����݂̊Ԃ��A�F��Ƃ����u��āA��ɂ͋ɉY�̔g��������ق��A�k�ɂ͒����̕��S�������܂��ށB���c���ق��肵���{�̏h�ɂ�������B����̖ڂ���Ȃ��炸�́A�����S�Ƃ܂炸�����͂��炴��܂��Ȃǂ��ڂ��āA �Q�̉������̂��炵�����܉Y�ɂ��̂ӂ̗��̖��c�������� ���Ƃ̂܁T�ƕ����Ђ��͂��܂��B���̌�O���߂��ƂāA�����T���v�ЂU����ꂵ�B ��ӂ����������Ă����̂ލ��v�ӂ��Ƃ̂܁T�Ȃ�_�̂��邵�� �� ����̒��R�́A�Í��W�̉̂ɁA�u�悱����ӂ���v�Ƃ�܂ꂽ��A�����������Ƃ͕��u������ǂ��A����ɂ���^�_�S�ڂ����B�k�͑��R�ɂď������͂������A��͖�R�ɂďH�ؘ̉I�������A�J����ɂ��锒�_�ɕ����S�n���āA���̉��܂��Â��A���̂���݈��ӂ����B �ӂ݂܂�ӗ�̂����͂��Ƃ������ĉ_�ɂ��ƂƂӏ���̒��R �� ���̎R�����z���T�P�ߍs�قǂɁA�e��Ƃ��ӏ�����B���ɂ����v�O�N�̏H�̔�A����咆�[���@�s�ƕ������l�A�ߗL�ē��։����ꂯ��ɁA���h�ɔ��肽�肯�邪�A�u�͓̂�z���̋e���A���������݂ė�����ԁA���͓��C���̋e��A���݂ɏh���Ė������Ӂv�ƁA����Ƃ̏�q�ɏ����ꂽ�肯��ƕ��u����A���ɂđ��Ƃ�q�ʂ�ɁA�̂��߂ɏĂ��āA�ތ��̗t���c��ʂ悵�\���̂���B���͌���ƂĎc���u�����ތ`�����ցA���ƂȂ����ɂ��邱���A�͂��Ȃ����̂Ȃ�ЁA���ƁU���͂�ɔ߂�����B �������邩���݂����͂Ȃ��肯��Ղ͐�N�Ƃ��ꂩ���Ђ��� �� �e���n��āA�����قǂȂ��ꑺ�̗�����B���܂Ƃ����ӂȂ�B���̗��̓��̂͂ĂɁA�������œo��₤�Ȃ鉜����������n������A�͂�^�_���ƍL���͌��̒��ɁA��Ȃ炸���ꕪ�ꂽ��쐣�ǂ��A�Ƃ�������Ђ���₤�ɂāA���Ȃ����Ƃ��ӕ���������Ɏ�����B���^�_�n��Č��ނ����A�悻�ߖʔ����ڂ��A�ލg�t�݂���ė��ꂯ�c��Ȃ�˂ǂ��A�����₷��͂�B �����ӂ闷�̂��͂�͑���킽��ʐ����ӂ����F���� �� �O���̏h�𗧂āA���ӂ̍��h�����߂�قǂɁA�ЎR�̏��̉A�ɗ���āA���ꂢ��Ȃǎ�o����ɁA���₶�����ɂЁU���킽��āA�Ă̂܁T�Ȃ闷�߁A�������Ԃ����ނ����ڂ�B �������̂��̂ޖ̂��Ɖ��ׂȂ鏼�̂��炵��S���Đ��� �� �F�Â̎R���z���A�ӂ��Â�͂�����āA�̂̐Ղ������B�ƕ����C�s�҂ɂ��ƂÂĂ�������A���Â��Ȃ��ނƌ��s�����ɁA���̂قƂ�ɎD�𗧂Ă��������A�����̐��̐l����悵��������B�����߂�������Ȃ�A���������Č���ɁA��Â��Ȃ鑐�̈��̂����ɓƂ̑m�L�B�摜�̈���ɕ����������Ă܂�āA��y�̖@��Ȃǂ�������B���̊O�Ɍ���镨�Ȃ��B���S�̂͂��ߐq�˂���A�u��g�����邩���Ȃ���A�����ς���ɐS���炭�A����O���鐫���̂����B��s�Սs�̓Ƃ���������Ƃ��ւǂ��A�R���ɖ����́A���ɂ���ċ߂���ɂ܂����悵�A����l�̂����ւɂ��āA���̎R�Ɉ�����ނ��тT�A���܂��̔N���𑗂�v�悵�ӁB�ނ����f�Ă���z�̉_�ɓ����A�P�O�t�̘n���̂�A���R���̌��ɂ��݂��A���̂������Z�̊���̂���������Ƃ��ւ�B�����̂�����ɂ́A���Ƃ��牌���Ă���悷�����������A�Đ܂��Ԃ�Ȃ����߂܂ł��v�Ђ������邳�ܖ�B�g���ǎR�̗��̒�ɂ�ǂ��A�S�����̉_�̊O�ɂ��܂���A���͂˂ǂ��邭�����āA���^�_���ɐS�ڂ����B �������ƂӐS�̂�����ɂ���܂����T��R�ӂ̏Z���Ȃ�ł� �� ���̈��̂�������������炸�A���Ƃ��ӏ��Ɏ���āA��Ȃ鑲���k�̔N�o�ɂ���ƌ����ɁA�̂ǂ����܂����t���钆�ɁA�u���H�͂��T�����ɂ���F�Â̎R�����ӂ����ӂ̍ד��v�Ƃ�߂�A�S�Ƃ܂�Ă��ڂ��A�������͂�ɏ��t���B ���͖���������ɂ���F�Â̎R�킫�ĐF�L���̂����I �� �P�����߂�قǂɁA����؉A�ɐ������݂����āA�ڂɗ����܂Ȃ�˂���B�l�ɐq�ʂ�A��������ƂȂނ����ӁB���̂����͂�̓y�Ɛ�����Ƃ݂��ɂ��A����[���̂����Â����ւ肯��A�N�^�_���ɏt�̑��ɂ�������Ƃ��ւ鎍�A�v�Џo���āA�����Â��˂ƂȂ�ȂA�����ɂ�����c�炶�Ƃ��͂��B�r�������Ղɂ͂���˂ǂ��A�S���闷�l�́Aূɂ��܂�����Ƃ����B���̊����́A���R���̉��ɂق���A���E�O���̖�����A�����͂�ɐl�Ȃ�����������B�����Ȃ鎖���L����A�����ւ̕���ӂ������āA���ɐg��S���ׂ��ɐ��ɂ���A�ЂƂ܂ǂ����т�Ƃ�v����A�s�̕��ւ͂��̂ڂ肯����ɁA�x�͍�����Ƃ��ӏ��ɂĂ�����ɂ���ƕ������A����ূɂėL����ƈ��Ɏv�Ѝ������B�]��̖@�c�z���֎�����ЂČ�A�u�x�Ƃ��ӏ��ɂĂ����ꂳ�����͂��܂��ɂ���Ղ��A���s�C�s�̂�łɌ��܂��点�āA�u�悵��N�̂̋ʂ̏��ɂĂ����T��ތ�͉��ɂ��͂���v�Ɠǂ肯��ȂǏ���ɁA�܂��Ă������܂̂��̂̎��͐\�ɋy�˂ǂ��A����������Č���ɁA���Ƃ��͂�ɂ��ڂ�B ���ɂ���ɂ����ꂵ�ʂڂ��̓��ׂ̂ɂ��������ƁU�߂��� �� �������ւ��߂����Ă����x��ւA���̐A�ނ�^�_�����Ɍ��Ĕg�ɂނ��ԁB�E�̉����A���^�_�ɕ��ɂ����͂�ĉ��Ȃт��ɂ���B���H�̎v�o�Ƃ����ʂׂ��n���B�̎鐝�V�c�̌䎞�A����Ƃ��ӎҁA���ɂĖd������������B���������炰�߂ɁA�F�����������������͂�����A���ւɎ���ĂƁU�܂肯�邪�A���������Ƃ��ȂЂāA�R�ĂƂ��ӎi�ɂčs���邪�A�u���M�̉̉e�͊������Ĕg���Ă��A�w�H�̗�̐��͂��R���߂��v�Ƃ��ӓ��̉̂��Ȃ��߂���A�܂�����������ƕ��ɂ����͂�Ȃ�B �������ւƂ͂���ōs���l���S����͂ƁU�߂������ ���։�����ʂقǂɁA���ÂƂ��ӉY�L�B�C�Ɍ��Ђ���Ƃɂ�ǂ�Ĕ��肽��A�E�ӂɂ悷��g�̉����A�g�̏�ɂ��T��₤�ɂ��ڂ��āA��������炢�˂�ꂸ�B �������E�ׂɋ߂����������ʔg�ɂ����͂ʂꂯ�� �����͍X�ɂ܂ǂ�ފԂ��ɂȂ���鑐�̖��̂܂�Ԃ��Ȃ�A�Q�o���Ȃ��ł̋�ɏo�ʁB��(�����F�������͎R�G)����Ƃ��ӂȂ�r�E�́A��̂͂��܂��s�߂�قǂɁA���Õ��͂������ɁA�����悷��g�����Ȃ���A�}�������̓`�Г��A���ЂȂ��S�n���āA�����܂��Ȃ����̎��܂ł́A�����Ă��v�͂��肵���̋����ȂǑʼnr���T�A���ƐS�ڂ����B ���Õ����������E�̊�Â��Дg�킯������ʂ�^�_���s �� �����Ƃ��ӏh�̑O��ʂ�قǂɁA�����ꂽ����̑҂���ƂāA����Ƃɂ���������A��q�ɕ��������������A�u���߂�����̈��̂��ނ���ɐς�����邫�x�m�̔���v�Ƃ��Ӊ̖�B�S���肯�闷�l�̂��킴�ɂ�L��ށB�̍��F��̘[�Ɉ����ނ�A�m����A�~�̒����������ĕ�̐��]�݂���B���܂͕x�m�̎R�̂�����ɏh����s�q����B������߂�Е~�ĎR�̐���v�ւ�A�ސ����Ƃ��ɐS���݂Ă��ڂ�B ������͂���ূɂ������тč����̐���v�Ђ�肯�� �� �c�ẲY�ɑŏo�āA�x�m�̍��������A�����ʐ�Ȃ�ǂ��A�ȂׂĂ��܂������ɂ͂��炸�A�����ēV�ɂ���p�A�G�̎R��������Ȃӌ����B��Ϗ\���N�̓~�̔�A���߂̔����L�āA��l�R�̂����U���ɂȂ�ѕ��ƁA�s�Ǎ����x�m�̎R�L�ɏ�����A�����Ȃ�̂��Ƃ��ڂ��Ȃ��B �x�m�̂˂̕��ɂ��U��Ӕ��_��V�É����̑����Ƃ����� �� ���������͂��Â�����������Č���B�k�͕x�m�̘[�ɂāA�����ւ͂�^�_���ƂȂ������L�B�z�������邪���Ƃ��B�R�݂̂ǂ�e���Ђ����āA��������ЂƂ�B�������M���^�_�ɞ������āA�ނꂽ�钹�͂��ق�������B��͊C�̂����ĉ������킽����āA�_�̔g���̂Ȃ݂��Ɛ[���Ȃ��ߖ�B���ׂČǓ��̊�ɎՂȂ��B�͂��ɉ����̋�ɂ�Ȃ���]�ށB���Ȃ����Ȃ��̒��]�A���Â���Ƃ�^�_���ɐS�ڂ����B���ɂ͉����̉������^�_�����n��āA�Y�����̏��ɂނ��ԁB�����̂͊C�̏�ɂ����тāA�H���̎O�̓��̂��Ƃ��ɂ��肯��ɂ��āA���������ƂȂt����ƕ��ɂ��A���̂Â���_��̐��ɂ��₠���ށA���ƁU�����䂩��������B �e�Ђ������̓��]�ɕx�m�̂˂̂��Ԃ���_���������� �� �₪�č����ɂU���Đ�{�̏����Ƃ��ӂ���B�C�̂Ȃ��������炸�A���͂邩�ɐ��킽��āA�̉A���͂��Ȃ��B���ɂ͏M�ǂ��s��ЂāA�̗t�̕�����₤�Ɍ���B�ށu�犔�̏��̂��Ƃ̑o�A��t�̏M�̖����g�v�ƍ���ɂ��A�ނ������͂Âꂸ�A���]���Â��ɂ������ꂽ��B ���n���ΐ�{�̏��̖��Ƃ��݂݂ǂ�ɂU���g�̏ォ�� �� �ԕԂ��Ɖ]������B����Ƃɏh���肽��A�ԒނȂǂ��ƂȂ��E���̂̐��ɂ�A��̂�ǂ荁���Ƃɂ��āA���̂��ނ��������������B�ޔ��^�l�̖锼�̗��Q���A������Ƃ��ڂ�B �������̒ނ���僂̓ςт������Ƃӂ��肪�⑳�ɂ̂���� �� �ɓ��̍��{�Ɏ���ʂ�A�O���̎Ђ݂̂��߂��������ݕ��ɁA���̗����炭���ƂÂ�āA��̂��������_���т킽��A���Ђ͈ɗ\�̍��O���喾�_���������ƕ��ɂ��A�\�������A�ɗ\����j�����ɂ��ĉ̓ǂĕ��Ă���ɁA���ۂ̓V���J�ɂ킩�ɍ~�āA�͂ꂽ���t�������܂��ɗɂ��ւ肯�邠��l�_�̌䖼�c�Ȃ�A�䂤�����������܂��������������ڂ�B �����������c�㐅�̂Ȃ��ꗈ�Ė����܂�����_�����̐_�@ �� ������L���Ȃ�A���݂���������o�A�P�s�߂�قǂɁA�����R�ɂ������ɂ���B�₪�ˍ����d�āA����ȂÂނ����B�R�̒��Ɏ���āA�L�����T�ւ�B�����̐��C�Ɩ��t�A�����̊C�Ƃ��ӂ�����B������瑂̂��Ƃ������������ӂƂ��B��O���a�̉_�ɏd���ρA���Ƃ�鋎R�{���Ƃ��ǂ납��A�ގ���꜂̔g�ɖ]�߂邩���A�K���̐��S���Ƃ����Ђׂ��B�����������Ȃ�A�����g�̍s�q����ׂ��������ւȂNjF��āA�@�{���Ă܂��łɁA �����͎v�З��ꂶ���̊C�̂ӂ����߂��݂�_�ɂ܂����� �� ���R�����z������āA���{�Ƃ��ӏ��ɂƂ܂肽��A���R�C�͂������������J�āA�J��݂Ȃ���܂���B�␣�̔g�����ނ��сA����[�̖�̕��ɂ��߂���B���̌����̕���̉̂ɁA�u�܂���ق���̉����ȁv�Ƃ��ւ�A�v�Ђ悹���Ă��͂�Ȃ�B ����Ȃ���g�݂͂Ȃ����̋��̖��H��邳�ʑ�̂��Ƃ��� �� ���̏h���������Ċ��q�ɒ������̗[�����A�J��ɍ~��A�݂̂������悠�ւʂقǂȂ�B�}���S�ɂ݂̂����͂�āA���E�A�G���A���낱�������ȂǁA����鏊�^�_���A���ƁU�ނ�Ђ܂��Ȃ��đʼn߂ʂ邱���A�S�Ȃ炸���ڂ��B�邩�T��قǂɉ��蒅���ʂ�A�Ȃɂ����̂���Ƃ��₢�ӏ��ɁA���₵���˂�������ĂƁU�܂�ʁB�O�͓��ɂނ��ЂĖ�Ȃ��B�s�l���n���̂��Ƃɍs��A��͎R�߂����đ��ɖ]�ށB���̉����̐��A�_�̂��ւɂ������͂��B���X�̓s�ɂ��ƂȂ�A�₤���͂�ĐS�������B �������T�����邷�قǂɁA��^�_�����Ԃ�ƂāA�a��]�̒z���A�O�Y�݂̂����Ȃǂ��ӉY�^�_���s�Č���A�C��̒��]�����Â��āA�������ɖ������ʔ������^�_�ɂ����Ƃ炸���ڂ���B ���т����͉߂��������̉Y�X���ЂƂȂ��߂̉��̂�M �ʂ悷��O�Y�������̔g�܂��o���錎�̉e�̂��₯�� �� �}���q�̏���\���A�̉E�叫�Ƃƕ������܂ӂ́A�����݂̂��ǂ̋�̐��̖����������l�ɂ�������B���ɂ������̖��ɂ�����āA�`���������Ē��G���Ȃт������A���܂�����ɂ��́T��āA���R�̂߂���������B�c�ق����̏��ɐ�߁A���_��������ɂ����߂��Ă܂��肱�̂����A���ܔɏ��̒n�ƂȂ��B���ɂ��߂����̎�{�́A�����݂ǂ肢��^�_�������A�p�ɂ̂��Ȃւ����鎖�Ȃ��B���]���Ďl�G�̌�_�y�������炸�A�E���ɋĔ����̕�����������Ȃ͂�B���_�̂������݁A�{�Ђɂ��͂炸�ƕ���B��K���͎�ɂ����ꂽ�鎛��B�P���O���ɂ��T�₫�A���̏����ɂЁU���A�O��̑������͂��߂āA�ђr�̘[�Ɏ���܂ŁA���ƂɐS�Ƃ܂�Č���B��䓰�ƕ����́A�Ίނ̂��т���������āA����̂��炽�Ȃ���J�����A�T�m�����Ȃ�ԁA�����̂Â���_�@�̊ς��ƂԂ�ЁA�s�@�����d�ˁA���Ƃ����Ȃւɋ����̂ЁU���������ӁB�����݂̂Ȃ炸�A��T�̏��R�ȉ��A���Y��ꂽ�鏼�̎З��̎��A�܂��^�_�ɐ����ق��B�����ɂ��R��̉Y�Ƃ��ӏ��ɁA����ɕ��̑啧��������悵������l����B�₪�Ă����ȂЂĂ܂��肽��A�����Ƃ��L��B���̂�����q�ʂ�ɁA���Ƃ͉��]���̐l�A�����l�Ƃ��ӂ��̂���B�߂ɂ������̔���A�֓��̍����ڂ��������߂āA���������蓰�ɂ����Ă���B���̌����łɎO����ɂ���ԁB�G�썂������Ĕ��V�̉_�ɓ���A���|���炽�ɂ݂����Ė����̌������T�₩���B���͑����O�N�̌����݂₩�ɂȂ�A���͖��\��O�̂��܂ւ����܂��ɍ����B�ޓ��厛�̖{���́A�����V�c�̐���A�����\��]��Ḏɓߕ���B�V���k�U�ɂ������ЂȂ������Ƃ��������B������ɕ��͔���̂����Ȃ�A�ޑ啧�̂Ȃ���肷�T�߂�B�����ؑ��̂��͂�߂�������ǂ��A����ɂƂ�ẮA�����s�v�c�Ƃ��Ђׂ��B���@���Q����ɂ�����āA�����͂����͂ӂӂ邩�ƗL����ڂ�B �� ���₤�̎��ǂ��������ɂ��A�S�Ƃ܂炸�����͂Ȃ���ǂ��A���ɂ����炭���ɂ������āA��ɏZ�ׂ͂��悷�����Ȃ����Ȃ�ʐg�Ȃ�A�����ӂ�܁T�ɂ��U�s�݂̂��������B�A��ׂ��قǂƎv�Ђ����ނȂ����ߍs�āA�H���~�ɂ����ʁB�h��������ʂ��\��N�̗��̂���ցA���˂��ӂɓ����O�痢�̓��̎v�ЁA�g�ɒm���T�S�n���B���Ȃꂵ���̉����Q��͂�ʂāA������̗��݂̂����ƁU�͂������Ȃ�܂����B���y�̐S�ɍÂ���āA���^�_���Ɠs�̕����Ȃ��߂��܂����A��s�̊傪�ˉ_�ɂ����s������B �A��ׂ��t�����̂ނ̊傪�˂��e�Ă◷�̋�ɏo�łɂ� �� ���T����ɁA�_�����̓����]��̔�A�͂��炴��ɂƂ݂̎��L�āA�s�A�ׂ��ɐ��ʁB���̐S�̂������s�̐Ղ����������������B�т𒅂邳���ւ́A���Ƃ��]�ޏ��ɂ���˂ǂ��A�̋��ɋA���낱�т́A�锃�b�ɂ��Ў�����S�n���B �̋��ւ��ւ�R�H�̖��炵�͎v�͂ʊO�̂ɂ������⒅�� �� �\�����O���̂������A���łɊ��q�𗧂ēs�ւ����ނ��B�h�̏�q�ɏ����B �Ȃ�ʂ�Ǔs�����������Ȃ���������c�̂�������ǂ��ȁ@ �@ |
|
| ���k���� | |
|
(�ق��肭�ǂ��A�ق��낭�ǂ��A���ʂ��݂̂�)�@�܋E�����̈�B�{�B���{�C���̒����̍s���敪�A����ѓ�����ʂ銲�����H(�Ñォ��ߐ�)���w���B
�������Ō����Ƃ���́A�ዷ�A�z�O�A����A�\�o�A�z������щz����w���B�u�k�����v�̌ÌP�́u�N�k�J�m�~�`�v�Łu���̓��v�̈ӂł���(�w���얯�����x)���A�����܂ŋE�����猩���C���[�W�ɉ߂��Ȃ��B�������{�C���́u�R�A���v�ƒn��Ԍ𗬂����Ă���A��Ղ�╨�ɂ��̍��Ղ��c���Ă���B �E������k�ɐL�тāA�{�B���{�C���̖k�����𑍂߂��s�����ł������B ���ዷ��(�����E�ߍ��A���݂̕��䌧�암) = ���~�S(���O��) > ��ьS > �O���S ���z�O��(�卑�E�����A���݂̕��䌧�k��) = �։�S(�p��) > �O���S > �����S > ���H�S > ���S > ���S �����ꍑ(�㍑�E�����A���݂̐ΐ쌧�암) = �]���S(�l��) > �\���S > �ΐ�S > ����S(���X�A���) ���\�o��(�����E�����A���݂̐ΐ쌧�k��) = �H��S > �\�o�S > �P���S > ��F�S ���z����(�㍑�E�����A���݂̕x�R��) = �v�g�S(���Q�A���g) > �ː��S > �w���S > �V��S(�V��) ���z�㍑(�㍑�E�����A���݂̐V�����{�B����) = ���S(�v�D) > �O���S > �����S > �Îu�S > �����S > ���t�S(�ΑD�A�֑D) > �����S > �o�H�S(�a��5�N(712�N)�o�H�����i�E���R���ڑJ) �����n��(�����E�����A���݂̐V�������n�s) = �H�ΌS > �G���S(�G��) > ��ΌS(���)�@ |
|
|
�����Ƃ��Ă̖k����
�Ñ�̖k���n�����u�z���v�Ƃ����n���������`���������j��A�E������k�ɐL�т�H���ł��鎖����A�u�z�H�v�u�k���X���v�u�k���H�v�u�k���X���v�Ƃ��Ăꂽ�B �����ߎ��� ���ߎ���̓��H�Ƃ��Ă̖k�����́A�E���Ɠ��{�C�����������ԘH���ł������B�ߐ����̍��{�����Ԋ����ł���A���H�Ƃ��ꂽ�B�ޗǁE���s������i�ΐ��݂�ʂ�z�O�ւƔ����郋�[�g(���ߍ]�H�Q��)�ł������B7���I���ɁA�V���s�X�n�̈�p�ł�������̕ӂ�ɟّ��z�����ƁA�ّ��k�����̖k���ƂȂ����B��ɉ��L����āA�l���ւ��k���ƂȂ����B �@ |
|
|
����k����
���R�鍑 (1�w) = �F���S�R�ȉw �p�~ <804�N> ���ߍ]�� (4�w) = �u��S�����w 5�D > �u��S�a玉w 7�D > �����S�O���w 7�D <�ዷ�E�z�O���ʂɕ���> > �����S�ی��w 9�D�@ ���ዷ��(2�w) = ���~�S�Z�щw 5�D > �O���S����w 5�D ���z�O��(8�w) = �։�S�����w 8�D <�ዷ�H�ƍ���> > �։�S���f�w 5�D > �����S�i���w 5�D > �O���S�O���w 5�D > �����S�����w 5�D > �O���S���Éw 5�D > ���H�S���H�w 5�D > ���S�O���w 5�D �����ꍑ(7�w) = �]���S���q�w 5�D > �]���S���Éw 5�D > �\���S����w 5�D > �\���S��y�w 5�D > ����S�c��w 5�D > ����S�[���w 5�D <�\�o�E�z�����ʂɕ���> > ����S���R�w 5�D <�\�o�H> ���\�o��(2�w�A�p�w5�w) = �H��S��ˉw 5�D > �\�o�S�z�h�w 5�D > �\�o�S�����w �p�~ <808�N> > �P���S�O��w �p�~ <808�N> > �P���S��s�w �p�~ <808�N> > �P���S�Җ�w �p�~ <808�N> > �P���S��F�w �p�~ <808�N> ���z����(8�w) = ��g�S��{�w 5�D > ��g�S�썇�w 5�D > �ː��S�H���w 5�D > �ː��S����w 5�D > �V��S���w 5�D > �V��S�����w 5�D > �V��S�z���w 5�D > �V��S�����w 8�D > ���z�㍑(9�w) = ���S��C�w 8�D > ���S�G�Ήw 5�D > ���S�����w 5�D > ���S����w 5�D > ���S�����w 5�D > �O���S�O���w 5�D > �O���S�����w 5�D > �Îu�S��Ɖw 5�D > �����S�ɐ_�w 2�D > �����S�n�ˉw 2�z <���n�H> �����n��(3�w) = �H�ΌS����w 5�D > �H�ΌS�O��w 5�D > �G���S�G���w 5�D 10���I�����ɂȂ�ƁA���D�A���D�Z�p�����B���������Ƃ���A�����^���̓�ƂȂ�R�x��Ԃ�����A���i��։ꂩ����{�C���݂Ɍ������q�H�����p�����悤�ɂȂ����B �@ |
|
| ���Ñ㓌�R���Ɛ_�� | |
|
��1�D���R���Ƃ�
���R���@���R���͌Ñ�̌܋E�����̈�ł���A���͈̔͂ɕ~�݂��ꂽ�����̖��̂ł�����B �u���R���v�́A�F�������𓌎R���̏\�܍��̓s�ɔq�����Ƃ����w���{���I�x�̋L��(�i�s�V�c55�N2���p�C��)���j����̏����ł���B���֗Y���͂��̏\�܍��ɂ��āu����������������Ƃ��ėp����ꂽ���̂ŁA�Ó����̂��̂��Ӗ����Ă͂��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B���ۂɁA���݂ł��ʂ̍����Ă͂߂�͓̂��(��1)�B�w���{���I�x�V���V�c14�N7���h�����̏ق́u���R���͔��Z���ȓ��v�ƋL�ڂ���Ă���B�ߐ��{�s�Ɠ������ɔ͈͂��m�肵���Ƃ���(��2)�A�w���쎮�x�����Ȏ��㊪�ł͋ߍ]�A���Z�A��ˁA�M�Z�A���A����A�����A�o�H�̔����𓌎R���Ƃ��Ă���(�}1)�B�ڈΐ����ׂ̈ɌR�m�̊ȉ{��^��̌��Z���s���(����5(786)�N8���b�q��)�A�����x�z�̒��S�n��ł������B �_�⓻�͐M�Z���ɓߌS(���݂̒��쌧���ɓߌS���q���B�����Ð�s�Ƌ���ڂ�)�ɂ���A���R���ɑ�����B�������Ȃ���A�g�h�H�̊J�ʂ��L�����w�����{�I�x�a��7�N7����C���ɂ́u���Z�M�Z�V��A�a����襁A����䅓�v�Ƃ���A�_�⓻�z�����e�Ղł͂Ȃ��������Ƃ��L�^����Ă���B�w���쎮�x�����Ȏ��w�`���ɂ��ƐM�Z�����m�̉w�n��30�D�ł���A�O�ւł���ɐ����鎭�̉w�n��20�D�ł���B�܂��w���쎮�x�����Ȏ��Ə��s�����ł͔��Z���̍�{�E�y��E���w�ƁA�M�Z���̈��m(�ʖ{�ɂ���Ắu���q�v)�̉w�q�̉ۖ����Ƃ����Ă���B��̌X���}�ȈׂɁA�֕��ɉw�n��z�u���A�ۖ���Ƃ��ĉw�̎d���̏]���ɐ�O�����Ă����B�@ |
|
|
��2�D�Ñ��ʂɊւ��錤���Ɣ��@�����̈Ӌ`
�Ñ�̌�ʂɂ��Ă͕����j�w�A���j�n���w�A�l�Êw���猤������Ă���B�����j�w�ł͍�{���Y���ȍ~�A�w�`���̉𖾂����S�Ƃ���Ă����B�Z���j�͒n����ł̐����ɂ��Ă͂قƂ�NjL�q����Ȃ��B�䂦�Ɂw���{��ًL�x�̒n��Ԍ�ʂ����������b�Əo�y��������(�؊ȁA��������)�̌������ʁA����Ɉ�ՁE�╨�̕��͌��ʂ����킹��`�Łu���Ԍ�ʁv�̎��Ԃ����炩�ɂ���Ă���B�܂����j�n���w�ł͏��n��̓��H��\����i�ϕ������s���A�Ñ�w�H�͌v��I�ɕ~�݂��ꂽ�ׂɒ����ł������������������Ă���B�䂦�ɕ����j�w����j�n���w�ɂ��Ñ��ʌ����͍l�Êw�̒������ʂɈˑ����邵���Ȃ��Ƃ����̂�����ł���B �Ⴆ�A�L�I�Łu�Ȗ��v���邢�́u�M�Z��v�Ə�����Ă���̂��_�⓻�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����̂͑��֗Y���ł���B��ꎁ�͐���Ó��n������A���̃f�[�^�𑍍��I�ɍl���鎖�ŌÓ����m���Ă������B�_�⓻�͑�ꎁ�𒆐S�Ƃ��ď��a26(1951)�N�ɒ������ꂽ�B���̍ۂɍ��J�╨���o�y�������ɂ��ޗǎ���Ɂu�a����襁A����䅓�v�Ƃ��ꂽ���Z��M�Z�����̈ʒu���m�肵���B����ɐM�Z��̏����炩�ɂȂ������ŁA�Ñ㓌�R���̋�̓I�Ȍ������\�ƂȂ����̂ł���B�@ |
|
|
��3.�����j�w���琄�肳���u�_��v�Ɛ_�⓻�̍��J���
�u�_�⓻�v�ƌ��݂͌Ă�ł��邪�A�u���v�̌�͓ޗǎ���܂Ŏg�p����Ă��炸�A�u��v���g���Ă����B����͗p���̖��ɉ߂����A�ޗǎ���ȑO�|�ߐ��{�s�ȑO�|�ɂ����R�n�`�𗘗p�������͎g���Ă���B�Ⴆ�A���݂̐_�⓻�ɔ�肳��Ă���M�Z��͓��{���������������̍ۂɉz�����ƋL�I�ɋL�ڂ���Ă���B ���⍑�S�̋��E���ɂ͐_����������Ƃ����M�����������Ƃ́w���t�W�x�����̉̂�A���E���ɂ�����n�悩����J�╨���o�y���Ă���_��������炩�ł���B��ꎁ��4���I�̌㔼�ɂ͂��̂悤�ȕ��K������������_�⓻�̒�������w�E�����B �܂��A��،i�͕����j������Ƃ��A�S����z�������ԃ��x���̌�ʂ��w�E���Ă���B���Ȃ킿�A�����S����z���Ă������̂����A��v���[�g�́u�I�I�T�J�v�u�~�T�J�v�̒n���������Ă������ƁB���̂����u�~�T�J�v�͐_����������A�_���J��Ƃ���������ď̂Ƃ��Ďg���Ă������ƁB�M�Z�����Łu�~�T�J�v�������铻��4���邪�A���̂������R�����[�g��̓���2�ŁA�ߍ]���Ƃ̔�r����|�ߍ]���͎�v���[�g�̒��ł����ɏd�v�Ȓn�̌ď̂ł���u�I�I�T�J�v�Ƌ��Ɂu�~�T�J�v��������ɂ���|�M�Z���́u�~�T�J�v�͗��ߐ�����̂Ƃ����ď̂ł͂Ȃ��A�n�����̂Ƃ����ď̂ł��邱�Ƃ��q�ׂĂ���(��3)�B ���֗Y���Ɛ��R�ьp�������S�ƂȂ��ď��a43(1968)�N�����44(1969)�N�ɍs�Ȃ����_�⓻�E���R���̔��@�����̐���(��4)���Č������A���̍��J�ɂ��ĕ���14(2002)�N9���ɍu���̒��Ő��R�����w�E��������́A (1) ������_�⓻�E���R���ō��J���s���Ă���͖̂��炩�B (2) �ōs���Ă�����J�͑��ɗޗႪ�������ƁB (3) �Z���̐l�B�ɂ���č��J���s���Ă������ƁB �̈ȏ�3�_�ł�����(��5)�B ��؎��͗��j�n���w�̐��ʂ���{�Ñ�j�����ɗp���邱�ƂŁA�_���������A�_���J��u�_�̍�v�|�u�~�T�J�v�|���n�����̂Ƃ������̂ł���Ƃ������A�������30�N�O�ɑ�ꎁ��̒����͂��̉����ɂ��Ď������Ă���B ���E�̈�̍��J�ɂ��Ă͕������{�Ղ̐��k�̋��̍��J��\����������铙�A������ɋL����Ȃ����{�Ñ�̐M�̂��������ߔN�𖾂炩�ɂȂ��Ă���B �]���A���ւ̐M�́w���t�W�x��Z���j���̕����𒆐S�ɘ_�����邱�Ƃ����������B�_��E���R���o�y�̍��J�╨�͍��J���̈ꕔ�Ƃ��Ă������Ԃ������Ă���A���ɗޗႪ�݂��Ȃ����Ƃ���A�����̓����ł���M�Z���ɓ��L�̋��E���J�ł���ƍl������B�����I�ȌÑ��ʂ̌�����i�߂Ă�����Ő_��E���R����Ղ̈Ӌ`�͑傫���A����ĕ]�������߂���ł��낤�B�@ |
|
|
�� ��
1) ��֗Y 1969 �u�Ó��R���̍l�Êw�I�l�@�v�w���{�@��{��w�@�I�v�x��1�S�B�ȉ��A��ꎁ�̘_�͖{���ɂ��B 2) ��������T2(771)�N10���ȉK�ɓ��R�����瓌�C���Ɉڊǂ����(�w�����{�I�x)���̕ύX�͂���B���̕ϑJ�ɂ��Ă͖ؖ{��N 1996 �u���R���|�R����z���ā|�v�؉��Ǖҁw�Ñ���l����@�Ñ㓹�H�x�g��O���ق��Q�Ƃ̂��ƁB 3) �،i�� 1998 �u�Ñ��ʂ̏����v�w�Ñ��ʌ����x8�A���؏��X 4) �֍��M�v 2001 �u���R�ьp���ʐ^�����|�_�⓻�E���R���ɂ��ā|�v�w����13�N�x�@���{�@��{�w�p�t�����e�B�A�\�z�u�摜�̍Đ����p�Ǝ������Ɋւ����b�I�����v���ƕx���{�@��{�w�p�t�����e�B�A���Ǝ��s�ψ���A�Q�ƁB 5) �{�������@���R�ьp���u���u���̍��J�@�|�_��|�v�B(1)�E(2)�͒��������������Ă���A(3)�͍u�����ɐ��R�����w�E���Ă���B�@ �@ |
|
| �����R�������H1 | |
|
�Ñ�̒n���I�s���敪�Ƃ��āA�E���܍��ɁA���C���E���R���E�k�����E�R�A���E�R�z���E��C���E���C���̌܋E����������܂����B�܂������͒n��ď̂ł���Ɠ����ɁA�s����n���ɂ̂т铹�H�̖��̂ł��������̂ł��B���̂悤�ȍs����͓V����(672�`686)���ɐ��������ƍl�����Ă���悤�ŁA�����̓s�͔�䌴�{�ł��B����ɐ悾�����Ė�������V�q���ɂ����ē`�n����w�����n�܂��Ă��āA�V�q���ɂ́u���v�̐ݒ��M�ߔN��(���߂Ă̑S���I�Ȍː�)�̍쐬�ȂǍ��ƂƂ��Ă̎x�z�̐�����������܂����B
���R���͓s���瓌�̎R�ԕ��̍s����Ƃ��̊����������܂��B��������́w���쎮�x�ɂ��ƁA���R���ɑ����鍑�́A�ߍ]�E���Z�E��ˁE�M�Z�E���E����E�����E�o�H�̔��J���ł����A����ȑO�ɂ͊����̕ϑJ���������Ǝv���Ă��܂��B �������́w���쎮�x�ł͓��C���ɑ����Ă��܂����A�ޗǎ���̕�T2�N(771)�ɓ��R�����瓌�C���ɏ����ւ����ꂽ���Ƃ��A�w�����{�I�x�̋L���Ŋm�F�����Ă��܂��B���������ޗǎ���̖����ȑO�ɂ͓��R���ɑ����Ă������Ƃ���A�������͓��R���o�R�œs�ƌq����Ă����킯�Ȃ̂ł��B���̎���̊���(�w�H)�����R���̖{�H����ǂ̂悤�Ȍo�H�ŕ������{�q���ł��������A����܂Ř_�c����Ă��܂����B���̓��R������̕������̉w�H���͂ǂ̂悤�ɌĂ�Ă������͂킩��܂��A���݂ł́u���R�������H�v�ƈ�ʓI�ɌĂ�Ă��܂��B �ł́A���̓��R�������H���������̂ǂ����ǂ̂悤�ɒʂ��Ă����̂��A����܂ł̌������ł킩���Ă��铹����������ɊȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B(���R�������H�̃��[�g�͂���܂ő����̏���������A�ǂ̐����m���ł���Ƃ����̂͌��݂̎��_�ł͌���Â��邱�Ƃ͂ł��܂���B�������ߔN�̍l�Êw�������珙�X�ɂ��̓������炩�ɂȂ�͂��߂Ă��܂��B)�@ |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��T2�N(771)�ȑO�̓����̉w�H (�n�}1)�@ |
|
|
�w�����{�I�x��T2�N(771)10���߉K(27��)��
�u�������t���炭�A�������͎R���ɑ�����嫂����˂ĊC���������A���g�ɑ��ɂ����L�����֓�B���̓��R�̉w�H�͏�썑�V�c�w��艺�썑�����w�ɒB����B����֓��Ȃ�B����ɞ]���ď�썑�W�y�S���܃��w���o�ĕ������ɓ���A���L��ċ�����A�܂����������ĉ��썑�Ɍ��ӁB���ܓ��C���͑��͍��ΎQ�w��艺�����ɒB����B���̊Ԏl�w�ɂ��ĉ��ҕ߂��B����ɍ�������ނɏA�����ƂQ�ɂ߂đ����B�b�珤�ʂ���ɁA���R�������߂ē��C���ɑ����A�����Ƃ���āA�l�n���ӂ��ƍ݂��A�ƁB�t���B�v �ȏ�͕�T2�N�ɕ����������R�����瓌�C���ɏ����ւ������闝�R���L���������ŁA���e���ȒP�ɋL���A�������͓��R���ɑ����Ă��邪�A�����ɓ��C���̌�ʂ������Ă��āA�g�҂̉����������B���C���́A���͍��ΎQ�w����l�w�ʼn������ɒB���Ă��ċ߂��֗��ł���A�������𓌎R�����瓌�C���ɏ�����ւ���A�������X�A�l���n�����S���y�������B�Ƃ������̂ł��B �܂���L�ɐ旧�������̂悤�ȋL��������܂��B �w�����{�I�x�_��i�_2�N(768)3��������� �u�܂��A���������E�����E�͋Ȃ̎O�w�A���������k�E�L���̓�w�́A�R�C���H�������āA�g���ɑ��Ȃ�B��A���H�ɏy���āA�n�\�D��u����ƁB������ɁA�t�Ɉ˂�B�v �������̈��E�����E�͋Ȃ�3�w�ƕ��������k�E�L����2�w�́A���R���Ɠ��C���̘A���H�Ŏg�҂̒ʍs�������B�x�H�Ƃ��ĉw�n5�C��u���Ă��邪�A���H�Ȃ݂�10�C�̉w�n��z���������A�Ƃ����\���o�ł��B ��L�̓�́w�����{�I�x�̋L�����瓌�R�������H�̌o�H�ɂ��āA���܂ł��낢��Ș_�����Ȃ���Ă����悤�ł��B���ł����̓�̖�肪�_���̏œ_�ƂȂ��Ă����悤�ł��B �܂���́A��T2�N�̋L���́u��썑�W�y�S���܃��w���o�ĕ������ɓ���v�ŁA�����ł����u�܃��w�v���ŗL�̉w���ƍl���邩�A�����͉w���Ɖ��߂��邩�Ƃ������ł����B���ۂɗW�y�S�ɂ́u�܉Ӂv�Ƃ����n����������݂��A���̓y�n�Ɍ܃��w���������Ƃ����������܂��B �������A�u�܉Ӂv�̒n���͓��n���ɑ�����Ւn�������u������v�ɂ��Ȃނ��̂Ƃ������߂�����A�܂��A�܃��w���W�y�S�ɂ������Ƃ���A�u�W�y�S�܃��w���v�ƂȂ�A�u�W�y�S���v�Ƃ���ΗW�y�S�Ƃ��Ƃ����Ӗ��ɂȂ�A����ėW�y�S�ɂ͌ŗL�̌܃��w�͂Ȃ������Ƃ���l�����ł��B�����̂��Ƃ���A�܃��w�͉w���ł͂Ȃ��w���Ƃ����������蒅������悤�ł��B�@ |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w���쎮�x�ɂ�铌���̉w�H (�n�}2)�@ |
|
|
��ڂ̖��Ƃ��ĕ�T2�N�̌܃��w���w�����Ƃ���A���̌܉w���_��i�_2�N�̋L���̌܉w(���������E�����E�͋ȁE���������k�E�L��)�Ɠ������̂��w�����ǂ����Ƃ������Ƃł����B
���������E�����E�͋ȉw�́w���쎮�x�ɂ����݂��A���w�ł͉w�n��10�C�A�����E�͋ȉw��5�C���u���Ă���̂ŁA����H����ʼnw�n�����Ⴄ�͕̂s���R�ŁA�w���쎮�x�����̕����E�͋ȉw�͉������{�t�߂œ��C���{�����番����ď㑍���{���������C���̎x���ł������Ƃ���l������܂��B���̂��Ƃ��牺�����̈��E�����E�͋ȉw�͏�̒n�}�̈ʒu�ɂ������ƌ����A���R���{�����畐�����{�ւ̃��[�g�Ƃ��Ă͑傫������Ă��܂��������o�R�̓��R�������H�̃��[�g�̉\���͒Ⴂ���̂ƍ��ł͍l�����Ă���悤�ł��B����āA��T2�N�̉w���ƌ���܃��w�́A�_��i�_2�N�̋L���̌܉w�Ƃ͈قȂ���̂ƍl������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B �l�X�ȓ��R�������H�̑z�胋�[�g���l�����Ă����ȑO�ɑ��āA���݂ł͍l�Êw�ɂ�鏊��s�̓��̏��Ղ⍑�����s�̌Ñ㓹�̈�\����������A��̒n�}�̂悤�ȌÑ㓹�̃��[�g�����݂ł͒蒅������悤�ł��B ���R�������H�ɂ��Ă͏�썑�̐V�c�w�t�߂���{���ƕ�����ėW�y�S��ʂ蕐�����ɓ���܂��B�����Č܂̉w�Ƃ��o�ĕ������{�ɓ���A�Ăѓ����[�g��k�サ�ĉ��썑�����w�œ��R���̖{���ɍ����������̂ƍl������悤�ɂȂ��Ă��Ă��܂��B��썑�V�c�w��蕐�����{���܂ł��̊Ԃ̋�����80�L�����[�g���ŁA�������{�̕t�߂Ɉ�w��u���ĉw�ԋ���(��16�L�����[�g��)��4�w��z�u���Ă݂��(�n�}1)�̂悤�ɂȂ�܂��B �@ |
|
| �����R�������H2 | �@ |
|
(�Ƃ�����ǂ��ނ����݂�)�@�Ñ�ɑ���ꂽ�����̈�B�������R���̖{���̈ꕔ�Ƃ��ĊJ�ʂ��A�̂��Ɏx�H�ƂȂ������ł���A��썑�E���썑���畐�������k�����ɒʂ��ĕ������̍��{�Ɏ��镝12m���̒������H�ł������B�r���ɉw��5�������ƍl�����Ă��邪�A���̖��́E�ʒu�ɂ��Ă͕s���ł���B
���ݒu 7���I�ɗ��ߐ����m�������Ƃ���ɔ����čs�����̐������s���A������u�܋E�����v���ݒu���ꂽ�B���̐��x�ɂ��E���ȊO�̍��X�͂��ꂼ�ꏊ��́u���v�ɑ����A�����ɂ����̍��̍��{�����ԓ����̊��������݂���邱�ƂɂȂ����B ���̍ہA�������͑��͍��ɓ��ڂ���C�����̍��ł͂��������A�ߍ]�����N�_�ɔ��Z���A��ˍ��A�M�Z���A��썑�A���썑�A������(�����͂܂��o�H���͂Ȃ�����)�Ɩ{�B�̓������������铌�R���ɑ����邱�ƂɂȂ����B���̂��߁A���Ƃ��Ă̓��R���ɂ������̍��X����傫���O�ꂽ�Ƃ���ɂ��镐�����̍��{�����ԕK�v���������B ���ʊ����͒n���I�������̍��̍��{��ʂ�Ȃ��ꍇ�A�x�����o���đΏ�����̂���ł���(��F���C���̍b�㍑�E�R�z���̔��썑)�A�������̏ꍇ����썑�{�Ɖ��썑�{�Ƃ̊ԂŖ{�����Ȃ��āA��썑�W�y�S����5�w���o�ĕ������{�Ɏ��郋�[�g���ݒu���ꂽ�B ���̌��ʁA��썑�{�`�V�c�w(��썑)�`�������{�`�����w(���썑)�`���썑�{�Ƃ������[�g���̗p����邱�ƂɂȂ�A�V�c�w�`�����w�Ԃ͒��i�ł͂Ȃ���k�ɂ킽����Y���`�ɓ˂��o��i�D�ƂȂ����B���̓˂��o�������������R�������H�ł���B ���x�����Ɗԓ��ւ̍~�i �����͓��R���̈ꕔ�Ƃ��ĊǗ�����Ă��������H�ł͂��������A����Œ���̊����g��(���R���g)�͏�썑�W�y�S����5�w���o�ĕ������{(�����s�{���s)�֎���������I���ĉ��썑�Ɉړ�����ۂ͍Ăї������������Ԃ��ĉ��썑�{(�Ȗ،��Ȗ؎s)�������Ƃ���������ȗ�����g�ނ��ƂƂȂ�A�l�n�̈����̂��߂ɂ��A�����̓��R���̌o�H�ł������V�c�w�Ƒ����w�Ƃڌ��ԓ��𓌎R�������Ƃ��A�������������̓��C���ɖ߂��������t�オ�Ȃ���A���m�V�c����������������Ƃɂ��A�������͓��R�����瓌�C���ɓ]�����邱�ƂƂȂ����B���̎|�́A�w�����{�I�x��T2�N10��27��(771�N12��7��)���ňȉ��̂悤�ɋL�^����Ă���B �������t�B���U��嫑��R���B�����C���B���g�ɑ��B�L����B�����R郘H�B�n��욠�V�c郁B�B���욠����郁B���֓���B���]�n��욠�W�ٌS�B�S�܃P郁B�����U���B���L�����B���擯���B�����욠�B�����C���ҁB�n���͚��Ι�郁B�B�������B���Ԏl郁B���ҕ߁B�������A�ޑ��Q�ɑ��B�b�����ʁB�����R���B�����C���B���������B�l�n�L���B�t�B �܂�A�u�������͈ȉ��̂悤�ɑt�サ���B�������͍��͓��R���ɑ����邪���C�������˂邽�ߌ��g����������s�������A���������ɓ���ɂ���܂��B���R�w�H�͏�썑�V�c�w(�Q�n�����c�s)���牺�썑�����w(�Ȗ،������s)�ɒB���Ă���A���̓��͔��ɕ֗��ł��B�������Ȃ���A���g�͂��֗̕��ȓ����g�����A��썑�W�y�S����5�w���o�ĕ������Ɏ���A�ދ�����ۂɂ͓�������߂��ĉ��썑�Ɍ������Ƃ�������������Ă��܂��B����A���̓��C���͑��͍��ΎQ�w(�_�ސ쌧���Ԏs)����4�w���o�ĉ������֎����Ă���A���̓��͂����ւ�֗��Ȃ��̂ł��B�ɂ�������炸�A���֗̕��ȓ����̂ĂĔނ̕s�ւȓ������̂͑��Q���ɂ߂đ����Ȃ�܂��B���ǂ��ŗʂ������ʁA���R�������߂ē��C���ɑ�������A���������鏊�ƂȂ�A�l�n�������ł��܂��B(���m�V�c��)�t����������v�ƂȂ��Ă���B ����ɂ���ĕ������͓��R�����瓌�C���ֈڊǂƂȂ�A���C�������͍�����C�H�ŏ㑍���Ɍ��������[�g���畐�����̉��݂�ʂ郋�[�g�ɕύX����č��{�ւ̎x���������ƂɂȂ����B�����ɓ��R�������H�͊�������O��A�ԓ��ɍ~�i����邱�ƂɂȂ����̂ł������B ���~�i�Ȍ� �����H�͍~�i�Ȍ������̊Ǘ����O�ꂽ�����ł��̂܂܈ێ�����A���������瓌�R���ւ̊ԓ��Ƃ��ė��s�҂ɗ��p���ꂽ�B�V��10�N(833�N)�ɂ́A�����H�̒ʉ߂���r���̑����S�Ɠ��ԌS�̊Ԃɍ��{�ɂ���ė��s�҂̋~��{�݁E�ߓc�����J�݂���Ă���A��ʂ������Ă��Ȃ��������Ƃ���Ă���B ����A�V�ҕ������y�L�e�̐Y��S�̋L�q�ɂ��ƁA���R���ɑ��������̕������Y��S�͊����ɂ���X�����ʂ��Ă������ߔɉh�������A(��T2�N(771�N)��)�����������C���Ɉڂ�ƂƂ��ɐl������Ɖ��̒n�ƂȂ����A�Ƃ���B ����c�����R���j���Z�V���n�A�����j�e�A�c�S���\�m�X���j�J�R���o�A�ɞăZ�V�n�i���x�P���h�A���n�ތÑ�m���i���A���C���c���j�ڃ��e��n�A�l�Ճ��X�N�i�N�A����j�Ɖ��m�n�g�i���� �܂��A���ߐ��̐����ƂƂ��ɓ��H�̐������s���͂��Ȃ��Ȃ�A����ɓ��Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ����B�ŏI�I�Ȕp���̎����͕s���ł��邪�A���@�����ɂ���11���I���܂ł͓��Ƃ��Ďg�p����Ă������Ƃ��������Ă��邽�߁A�������㖖���ɂ͊��S�ɔp���ƂȂ����Ƃ݂��Ă���B �Ȃ������ɂ́A���Ă̓��R�������H�ƕ��s����悤�Ȍ`�Ŋ��q�X���㓹����v�ȓ��H�Ƃ��ė��p���ꂽ���A�����͋ߐ��ȍ~�ɔp���ɂȂ����B ����\�̊m�F�n ���݁A�����H�Ƃ��Ċm���Ȉ�\�͓암�𒆐S�ɏW���I�Ɍ������Ă���B�k���ł͂��܂��\���������Ă��炸�A���ӈ�Ղ��Q�l�Ƀ��[�g�𐄒肷��ɗ��܂��Ă���B �������s �������������Օt��(�������s)�����S�����S���w���Ւn��\(�������s��2����) / ������\����K�͂ɔ������ꂽ�S���ł��H�Ȉ�ՂŁA�����s�w��j�ՁB�ꕔ���A�ۑ��[�u������Ă���B ���㐅�{����\(�����s�㐅�{��) �������_����\(�����s����2����) ������c�n��\(�����s���쓌��2����) ���������\(�����R�s�{��1����) ���y����@��\(�����R�s�{��2����) �������R��\(�����R�s�z�K��2����) �ȏ�6�����͋����S�����S���w���Ւn��\�Ɠ��̏��Ղ�����������ē�����\�B ����ʌ� �����̏���(����s�v��) / �����H�̈�ՂƂ��Ă͍ŏ��Ɍ����������́B���{����k�ɒ����ɏオ�����Ƃ���ɂ����邽�߁A���@�������畐���H�̐ՂƖڂ���Ă����B���̌�̍X�Ȃ锭�@�����̌��ʁA���͂ɑ����̌����̐Ղ�e�n�̓y��A�n����o�y���Ă���ׁA�w�Ղ̉\�������ڂ���Ă���B ��������(����s���x) / ��L�̓��̏��Ղ̉����ォ�琄�肵�Ĕ��@�����������ʁA����24�N3���ɓ����\���̈�\���������Ă���B �������O�E��{���(��z�s�I��) / �u郒��v�̖n���y�킪�o�y���A��������w�Ղ̉\���������Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B �����x���(��z�s�I��) / ���݊m���ɕ����H�̈�\�Ƃ��čl�����Ă���Ŗk�̈�ՁB �����g���𗢈��(���S�g������g��) / 2001�N(����13�N)�x�̔��@�Ŋ������̕��������Ñ㓹�H�Ղ���������A���̌�����H�Ղ̉�����̈�Ղœ��l�̔������������B�����H�̈�\�Ƃ̐������Ȃ���Ă��邪�A�������k���ɌX���Ă��邽�߁A�S�ɓ��m�̘A�����A�܂��͏헤���֒ʂ���ԓ��Ƃ������������Ċm�肵�Ă��Ȃ��B�@ �@ |
|
| �����R�������H3 | �@ |
|
����ʌ��k���ƌQ�n���̃��[�g
���R�������H�̃��[�g�Ƃ��āA�����s�{���s�����ʌ���z�s�܂ł͔��@������u�Ñ��ʌ�����v�̑��p�I�Ȓ����ɂ��A�قڂ��̐��胋�[�g���ł܂����悤�ł��B�������A��z�s�Ȗk���痘�����n��܂ł̊Ԃ͐��胋�[�g�̒����͂��܂�i��ł��Ȃ����悤�ł��B���ł���ˎs����F�J�s�܂ł̃��[�g�́A���̌����҂̕��X�ɂ�����407�����ƕ��s����悤�ȃ��[�g�Ƃ����z�肳��Ă��Ȃ��悤�ł��B �����Ă͓��R�������H�̃��[�g�͌����҂ɂ���ėl�X�ɍl�����Ă����悤�ł��B������������Ă�������A�×����쉈����ʂ����A��{�ɉw�Ƃ��z�肳���{��ʂ������Ȃǂ��������悤�ł��B�܂��w�����{�I�x�̕�T2�N�̌܃��w���Q�n���W�y�S���c���̒n���̌܉Ӊw�Ƃ��ĉ��߂�������ʂ����Ƃ�����Ȃǂ�����܂����B ���݂ł͌Ñ�w�H�͕�12���[�g���O��̒������H�Ƃ����������킩���Ă��Ă��܂��B�����Ė؉��ǎ��𒆐S�Ƃ��āu�Ñ��ʌ�����v�̒������ʂ���ʓI�ɒm���Ă��܂��B���R�������H�ɂ��Ă͖ؖ{��N���̌����ɂ��z�胋�[�g�����ڂ���Ă��āA���̑z�胋�[�g�́u�����s���̃��[�g�v�Ɓu��ʌ��암�̃��[�g�v�Ƃ��Ď����Q�l�ɂ����Ă�����Ă��܂����B�����č�ʌ��k���ƌQ�n���̃��[�g���قږؖ{��N���̑z�胋�[�g���Q�l�ɐ��������Ē����܂��B ���g�����Ŕ��@���ꂽ�Ñ㓹 ����ȍŒ�(2002�N2��20��)�Œ����V���̐���ʔŗ��Ɂu�Ñ�̊����Ƌ��r�Ձ@�g���ŏo�y�@���ʂȓy�؋Z�p�v�Ƃ������o�����ڂ��Ă���̂����܂����B������24���Ɉ�Ղ̌��n������s��ꌩ�w���ĎQ��܂����B���̈�Ղ̔������ꂽ�ʒu�͈ȊO�ɂ��ؖ{���̑z�胋�[�g���������ŁA�X�ɕ��������k�k����ڎw���Ă���悤�ł��B���̕�������������ƌF�J�ւ͏o���s�c�������悤�ł��B �g�����Ŕ������ꂽ�Ñ㊯���Ǝv�����Ղ͈ȊO�ɂ��Ꮌ�n�т�ʂ��Ă��܂��B�Ñ㊯���̈�ՂƂ��Ă��Ꮌ�n�т͗ޗႪ���Ȃ��B�����҂̊Ԃł����ڂ���Ă���悤�ł��B�����A�]���z�肳��Ă�������s�����ˎs�܂ł̃��[�g���قڒ����Ńg���[�X�ł���̑��āA�������ꂽ�g�����̈�Ղɂ�����q����ƂȂ�Ƃǂ����ŕ��ʂ̕ύX���K�v�ɂȂ肻���ł��B ��ˎs����F�J�s�܂ł̓��R�������H�̃��[�g�́A����407�����ɕ��s����悤�ɒʂ��Ă����ƍl�����Ă��܂��B�������A���̏ڍׂ͂킩���Ă��܂���B��̒n�}�͍�҂���������ɂ����܂��ɕ`�������̂ł��B�_���ł��邱�Ƃ͎��ۂ̃��[�g�ł͂Ȃ��A���̂悤�ȃ��[�g���l������Ƃ������x�̂��̂ł��B��҂̑f�l�I�z���ŕ`�������̂ŁA�Ñ�̎j�Ղ��q���ł݂���A�����̊��q�X�����Q�l�ɂ������̂ł��B ����ɑ��čׂ����_���͌����҂����ۂɎw�E���Ă��郋�[�g�ł������ł���܂łɂ͎����Ă��Ȃ��悤�ł��B���̌Q�n�����̒n�}�Ŏ����ŕ`���Ă���Ƃ���͔��@�����Ȃǂœ��H��\�����o����A�قڐ��胉�C���Ƃ��čl���邱�Ƃ��ł��铌�R���̖{�H���[�g�ł��B �������R�s���ӂ̌Ñ�j�� ���R�������H�̏���s�����z�s�̑z�胉�C����k�։����ƍ���407���������𓌏��R�s�A�嗢���A�F�J�s�A�ȏ��������ė������n��Q�n�����c�s�ւƌ��������ƂɂȂ肻���ł��B ���̃��C����̌Ñ�̎j�ՂƂ��ẮA�����R�s����{�ɂ��鏫�R�ˌÕ�������A�S��115���[�g���y�Ԍ����L���̑傫�����ւ�O����~���ł��B�����āA���̖k�ɂ͗L���ȋg���S��������A�X�ɖk�Ɍ������Ǝ����㔼���̂��̂Ǝv�����J���q�Ղ�嗢����6���I�㔼�̒z���ƍl�����Ă���O����~���̂Ƃ�����R�Õ��Ȃǂ������܂��B ���̂悤�ɍ���407���������ɂ͌Õ����ォ��ޗǎ���̎j�Ղ������A���̕t�߂̔��u�˂͌Ñォ��l�X�̌𗬂����������Ƃ���ƍl����ꂻ���ł��B ���F�J�s�̒����� �ؖ{��N���ɂ��ƌF�J�s�X�Ȗk�ɒ����I�Ȍ��ݓ������݂��A���̃��C����ɌQ�n�����j�̓������Ŏw�E����Ă���u�A�v�̏����������݂��Ă��āA�X�Ɂu���̓n���v�ƌĂ�鋌�r��̓n�͓_�Ȃǂ������A���̒����������R�������H�P�������ł͂Ȃ����Ƒz�肳��Ă��܂��B ���ޗǐ_�� �ޗǐ_�Ђ͔����S�̎����ЂŁA���O����ޗǂ̓s�Ƃ̉��炩�̊W������Ǝv���Ă��܂��B�ޗǐ_�Ђ̐_�ЂƂ��Ď��̂悤�ȉ]��ꂪ����܂��B �u���B�ʼnڈ̔������������̂ŁA����𐪓����邽�߂ɓޗǐ_�Ђ̐_���ďo�����A�]�킵�i���A�������Ƃ���G�Ȃ��̏�ԂŔN�V�����҂�̂̎ア�҂����s���������Ր_�̂������ŁA�S�������ł������v �ޗǐ_�Ђ��z�蓌�R���ɋߐڂ��邱�Ƃ͒��ڂ����Ɩؖ{���͂����A���R�E���C���̘A���H�Ƃ��Ă̋@�\�������������H�́A�ڈΐ����Ɩ��ڂȌW��肪������̂Ƃ��Ă��܂��B �����ˎR�Õ� �ޗǐ_�Ћ߂��̍���407����(�ȏ��o�C�p�X)�̓��H�[�ɉ��ˎR�Õ��Ƃ����O����~��������܂��B�ܐ��I�����ɑ���ꂽ�ƍl�����Ă��āA���\��������ւ��o�y���Ă��邻���ł��B���̌Õ��̎��ӂ͐��c�ɂȂ��Ă��đ��̌Õ��͌����܂��A�t�߂���͏��֕Ђ�y��Ђ��̏W����Ă��āA�����Ă͌Õ��Q���������ƍl�����Ă��܂��B���̌Õ��Ɠޗǐ_�Ђ͉����֘A�������̂�����̂����m��܂���B ��������̓n�͓_ ���R�������H�͗�������ǂ̕ӂ�œn�͂��Ă����̂��A���݂ł͍ȏ����̓������t�߂�z�肵�Ă���������L�͎�����Ă��܂��B���̋��̕t�߂͋ߐ��ɂ́u�Ì˂̓n���v�ƌĂ���n���ꂪ�������Ƃ����܂��B�Ì˂́u�Ón�v�ŋߐ��ɂ͊��ɌÂ��n���ł��������Ƃ��Ӗ����邻���ł��B�܂��A���`�Ƃ����B�����̂����ɁA���̕t�߂�n�͂����Ƃ����`��������A�w���������L�x�ɏo�Ă���u����̓n�v�����̕t�߂ɍl�����Ă���悤�ł��B���̐V�c�w����Ì˂�n���ĕ������{�Ɍ��������w�g�͍ĂьÌ˂�n�肻�̌㑫�����������ƂɂȂ�̂ł��B �������̓�̍ȏ����ɂ́A�����čȏ��ƒj���Ƃ�����̏��������������ł��B���̊Ԃɂ́u��v�Ə̂�������n���L�тĂ��āA��̏W���t�߂��������{���琔���ČܔԖڂ̉w�Ƃ��������Ƒz�肳��Ă���悤�ł��B ���ȏ����̎����̓� �ȏ����̑�ƍȏ��̑厚���ɒ����I�Ȍ��ݓ������݂��Ă��܂��B���̓����ɉ����Γޗǐ_�Ћ߂���ʂ�F�J�s�X�ւƌ����A�k�͗�����̎��R��h�����Ɍ��������ߐ{�ɏ��s���邳�����J�����Ɠ`���锪���_�Ђ�����܂��B�ؖ{���͂��̑厚���̓������R�������H�P�������ƍl�����Ă��āA���̓������ɔ��R�_��(�����̌䗷��)�������ʂ��Ă��āA�X�ɂ��̐_�Ђ��瓌�̍ȏ��ɔ����_��(���̎�)�����萼�ʂ��Ă��Ă��܂��B���̔��̐��̒j���ɐ_���_��(�j�̎�)����ʂ��Ă���܂����A���̐_�Ђ͈ȑO�͓��ʂ��Ă����Ƃ����܂��B���̎O�̐_�Ђ̔z�u����厚���̓��͏d�v�ȈӖ��������Ă������̂Ɩؖ{���͐������Ă��܂��B ������ɉ˂��铁�����̌Q�n�����͐��ɐΓc�삪�k�����痬�ꍞ�݁A���ɂ͏��͐삪�k�����痬�ꍞ��ł��āA���傤�Njt�O�p�`�̂悤�ɒ���o������n�ɂȂ��Ă��܂��B���̑�n�̐�[���Q�n�����̓n�͓_�ƍl�����Ă��܂��B���̋t�O�p�ɓ˂��o����n�̒�����k�ɉ��т铹�����݂��܂��B���̓��͑��c�s�Ƒ�̋��ɂȂ��Ă��āA���̓������R�������H�ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���悤�ł��B �������ւ̓� ���c�s�Ƒ�̋��̓��͂��̐�Ŗk�������Ɍ�����ς��܂��B���̖k�������̓������R���̑����w�ւƌ��������ƌ����Ă���悤�ł��B���̓��͓r���ɑ�ÕX��ʉ߂��܂����A��ÕX�͗W�y�S�Ƃ��������Ƃ���Ƒz�肳��Ă��ēy�t��Ђ�{�b��Ђ��Z���ɕ��z���Ă��邻���ł��B�܂��ÕX�ɂ͒��ǐ_�Ђ�����w��썑�_�����x�W�y�S�̐���ʒ��ǐ_�Ђɔ�肳��Ă��܂��B ���̓��͑�ÕX�܂ł������݂��Ă��܂��A���̓��̉������C����ɋߐڂ��đ��c�s�����̉�ΐ_�Ђ����݂��A���̐_�Ђ́w��썑�_�����x�R�c�S�̏]�O�ʉ��Ζ��_�ɔ�肳��Ă��܂��B �����Ă��̓��̉������C���͑����s�̍��{���ՂɒB���Ă��܂��B���{���Ղ͑����S�Ƃ̉\���������ƍl�����Ă����Ղł��B�܂���Ղ̕t�߂ɂ͓��R�������w�����������Ƃ��z�肳��Ă���悤�ł��B ���Ì˂���V�c�ւ̓� ����������n�͂�����ɐV�c�w���ʂɌ��������R�������H�͈ȑO����Q�n������ψ���̗��j�̓������Ŋm�F����Ă��閾�Ăȓ��H���Ղ�����܂��B���̓��H���Ղ͑��c�s�Ƒ�̋��̓����k�������ɐ܂��t�߂ɐڑ����Ă������̂ƍl�����Ă��܂��B ���c�s�̉��l�c���ɂ͌Ì˂���V�c�w���ʂɌ������߂̌��ݓ������݂��Ă��܂��B���̉��l�c�̔����n�̎Ε��ʓ������Ɉɍ��{���_�Ђ�����܂��B�ɍ��{���_�Ђ͒���̌Ñ㗤���o�c�ɌW���[���_�Ђŗ��������犩���̓`�������邻���ł��B���Ɨ����Ƃ̌W���͓��R������邱�Ƃ��Ӗ��t�����܂��B ���̎Ε��ʂ̌��ݓ��̉������C���͑��c�s�e������V�c��������ւƒB���Ă��āA�����_�Еt�߂œ��R���̖{�H�ɍ������邱�ƂɂȂ�̂ł��B �����R���A���x�E��m�����[�g �V�c�������䂩�瑺�c�ɂ����Ă̐V�c�@�p���́A�ߔN���@�����������ɍs��ꂽ���R���̋��@�E��m�����[�g�̓�������ɑ��݂��A���̊Ԃ̐V�c�@�p���͓��R���̖k�����a����ɓ]�p�������Ƃ��������Ă��܂��B���R���̋��x�E��m�����[�g�͈ɐ���s����V�c���܂�12�L���قǂ��������ł��邱�Ƃ��m���Ă��āA�����H�Ƃ̕���_�ȓ������������Ă��邱�Ƃ���������Ă��܂��B �����J��� �V�c�����c�Ə�����̐V�c�@�p���̖k���ɂ�����J��Ղ���������Ă��āA��d�������������Ղ�2���ƁA���̌������͂ޖ�180���[�g���l���̍a�Ȃǂ��m�F����Ă��܂��B�����Ղ͊������Ŋ���o�y�����y��̔N�ォ��A���̈�Ղ�7���I�㔼����8���I�㔼�܂ő����������Ƃ����肳��A�V�c�w�Ɋ֘A������Ղł͂Ȃ����ƍl�����Ă��܂��B �������h��� �V�c�����c�̐V�c�@�p���̓�ւ̋��ȓ_����V�c�@�p���Ɠ������ʂŐ��ɐL�т錻�ݓ������݂��܂��B���̓��͂₪�Ďs���łs���H�ƂȂ�I����Ă��܂����A���̂s���H�̐��̋n�������h��Ղ̔��@����ŁA��k���a�Ԃ̐S�X����13.3�`13.7���[�g���̈�\���m�F����Ă��܂��B���a�̖k�����s���H���瓌�ɉ��т铹�ƈ�v���A�X�ɐV�c�@�p���Ƒ����Ă������Ƃ��킩��܂��B �������́w�����{�I�x�̒��ŕ�T2�N�ɓ��R�����瓌�C���ɏ����ւ�����Ă��邱�Ƃ͉��x������Ă��܂����B��T2�N�Ȍ�͓��R���͕������{�������K�v���Ȃ��Ȃ����킯�ł��B���̂��Ƃ͏�썑�V�c�w���牺�썑�����w�֒��ڌ������悤�ɂȂ����̂ł��B �����ŏ�썑�̓��R���{�H�Ɛ��肳���A���x�E��m�����[�g�ȊO�̓��H��\���グ�Ēu���܂��B�V�c���s�Œ������ꂽ���V�c��Ղ͋��x�E��m�����[�g�̖k500���[�g���t�߂ɕ������铹�H��\�����o����Ă��܂��B�����a�Ԃ̐S�X����12���[�g���ōd���ʂ��m�F����Ă��܂��B���̓��H��\�̎����ɂ��Ă̓n�b�L�����Ă��Ȃ��悤�ł����A�V�m���N(1108)�̐�ԕ��ΈȑO�̈�\�ł��邱�Ƃ͂킩���Ă���悤�ł��B ���̉��V�c��Ղ̃��[�g�̓�������ɐV�c�S�Ƃɐ��肳���V�ǎ�����Ղ�����A���̕t�߂ɂ͐V�c�S���Ɛ��肳��鎛��p�������݂��܂��B����500���[�g���k�̓��H��\�Ƌ��x�E��m�����[�g�̊W�͂킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B���̂���Ȃɗ���Ă��Ȃ��t�߂ɕ�12���[�g���O��̓���������݂����̂ł��傤���B����̌����ł��̓䂪�𖾂����̂�҂݂̂ł��B �������� �悤�₭���R�������H�̗����I��邱�ƂɂȂ�܂����B�v���Γ����s�������s�̕ۑ����ꂽ���R�������H�����Ă��犙�q�X���Ƃ͈Ⴄ�Ñ�̓��ɋ����������A�ԊO�҂Ƃ��Ă̓��R�������H���쐬����܂ŐV�����������������܂����B�Ō�ɌQ�n���̐V�c���ɂ���ė��Ĉ���������Ƃ�����܂��B���R���̑��a�Ղƍl�����Ă���V�c�@�p���͂��̓��Ő��i�_�Ђ̋����𗬂�Ă����̂ł����B���i�_�Ђ͐V�c�`�傪�����̂Ƃ��Ɋ��g�����s�����Ƃ���ł��B���q�X���𗷂���҂Ƃ��ĉ������͐q�˂�\��ł������A�ȊO�ɂ����R�������H�Ƃ����Ñ�̓��̗��ŁA���i�_�ЂɒH��t���Ă��܂��܂����B ���q�X���̃z�[���y�[�W���쐬���Ă���l�Ԃ��A�Ñ㊯���̗���ǂ������Ă�����A���q�X���ɌW���[�����i�_�ЂɒH��t�������Ƃ́A���������߂������̂������Ȃ��킯�ł�����܂���B���͐��i�_�Ђ̑傫�Ȓ����̑O�ŐV�c�`�傪��������ɂ͓��R�������H�͒f�ГI�ɂ����݂��Ă����̂��낤���ƁA�ӂƂ���Ȃ��Ƃ��l���Ă���̂ł����B �V�c�`���1333�N�ɂ������犙�q��ڎw���ė��������̂ł��B���̂����ɂ͈����̌��i�����̒��ɕ�����ŗ���̂ł��B�L���L���P�����g���ق̉��Ɏʂ�̂ł����B �@ |
|
| �����q�X���㓹 | |
|
���q�X���㓹�̗��j�I����̗�������Ă݂܂��傤�B
���q�X���͊��q���{��������퍑����̏I���܂ł̖�400�N�Ԃ��X���Ƃ��Đ���ł������킯�ł���܂��B �����400�N�Ԃƌ����Ă����������������̂ł��B �X�������ɑ�������j�Ղ͗��j�I�Ɍ��Ă����̂ǂ�Ȏj�ՂȂ̂��́A ������x�̒m�����Ȃ��ƖK�˂Č��Ă������������Ȃ������芴�����邱�Ƃ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����ő傴���ςɊȒP�ł͂���܂��� ���q�X�������̎j�Ղ̎��_�Ƃ������ƂŁA���q����ȑO�̌Ñォ��퍑����̏I���܂ł̗��j��U��Ԃ��Ă݂܂��傤�B ��y�펞��ɉ����Ċ֓��E�����n���̈�Ղ͓����ɏW�����Ă���悤�ł��B�M�B�a�c���̍��j���Q�n�E��ʌ��̎R�[����o�y���Ă��āA���̂悤�ȉ����̂Ɍ��Ղ̓������݂��Ă����悤�ł���܂��B��ʌ��ł͑�̂ɉ����Ē����n���̎R�ԕ��Ő��������Ă����l�X�������悤�ł��B���Â̎���ɉ����Ă͎�������̊�{�ł��������Ƃ���l���āA�����B�� �ǂ�������ɂ͕��n���� �R�n�̕����s�����悩�����̂ł��傤�B�ꕶ����ɂȂ�Ɛl�X�͏W�����`�����A�W���ƏW�������ԓ��������čs���܂��B�ꕶ����̑O���͋C���g�œ����p�͍�ʌ��̒����ӂ�܂ŊC�ݐ������荞�݁A���̍��̊C�ݐ�(�����ł͎�ɓ암)�t�߂ɂ͐������L�˂��m�F����Ă��܂��B�₪�Ė퐶����ɂȂ�Ɣ_�k���{�i�I�ɍs����悤�ɂȂ�A�l�X�͎R�n�����n�Ɉڂ�A�W���̑��c�����B���A���Ղ�����ɍs��ꂽ���Ƃł��傤�B �����č����荠���Ñ�ɂ����Č��݂̍�ʌ�(�����̍�)�͓��R���Ƃ����n���I�敪�ɑ����A��������� �֓��̕\���ւ͉O�X��������ł������ƍl�����Ă��܂��B �m���ɌÑ㍑�Ɛ��������̈�Ղ�Õ��Q�͓�֓����� �k�֓��̌Q�n��(��썑)������̕������|�I�ɑ����悤�ł��B��ʌ������̐V���������Ȃǂ͓��C������ł͂Ȃ� �k�̕������ւƍL�܂��Ă������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�L���ȋ������S�����o�y������R�Õ�������u�������܌Õ��S�v���͂��߁A�����̎嗧�����Õ��Q�͌��̖k���ɏW�����Ă��܂��B ���ߍ��Ɛ����ɂƂ��Ȃ��������̍��{(���ł�������)�� �����s�̕{��������ɒz����܂����B��썑�̍��{�͌��݂̑O���s�����В��t�߂ł������悤�ł��B �����Ă��̓�̍��̍��{���ŒZ�����Ō��ԂƂ݂��Ɗ��q�X���㓹�� �قڈ�v����̂ł��B���̂��Ƃ��獑�{�����ԓ����㓹�̑O�g�ł��������Ƃ��f���܂��B ���q�X���㓹�����ɂ� �Ƃɂ����Õ�����������܂��B���̒��ɂ͖��炩�ɌÑ�̂��̂Ǝv������̂�����܂��B ���Ɋ��q�X���㓹�����ł͔������� �L�ؕt�߂ɌÕ��Q�������m�F����Ă��āA �����̕t�߂ɂ͌Ñ�̎��@�Ղ�w���t�W�x�֘A�̎j�Ղł���u����̈�Ձv�� �u�唺���^�����v�̈�ՂȂǂ�����܂��B���q�X���㓹�����ɂ͖��A �Ñ�̗q�Ղ������m�F���ꂽ���܂��B ���̑�\�I�Ȃ��̂����R���̐ԏ����q�ՌQ�ł��̗q�Ղ� �����������̊����m�F����Ă���ق��A��ʌ����ŌË��� ���݂̍�ˎs�ɂ��������P���@�ł��鏟�C�p���̊��� �Ă������Ƃ���������Ă��܂��B ���R������J�������z�� ���R���̏��R��Ɏ���t�߂͗q�Ղ������c�݂��Ă��܂��B �a�����N(708)�ɕ������̒����S��蓺���s�Ɍ��コ��N�����a���ƂȂ�a���J�݂���������܂��B�����̑�a�ł͘a��3�N(710)�ɓ��������畽�鋞�ɑJ�s����Ă��܂��B���̌�V��13�N(741)�ɐ����V�c�ɂ�荑�������c�̏ق��o����Ă��āA���q�X���㓹�����ɂ��������U���ɑ��c���ꂽ�������͂��̈�\�̋K�͂����a�̑��������Ɍp���K�͂ł��������Ƃ��m�F����Ă��܂��B �ޗǎ���̍�ʌ��͐����̎R�[�ɓ����̎j�ՂȂǂ������c����Ă��܂��B�����E�������̎R�[�ɂ́u�R�̕ӂ̓��v�ƌĂ��d�v�ȓ�����썑����ł����ƍl�����Ă��܂��B���̓��͊��q�X���㓹�̐������㓹�Ƃقڕ��s����悤�ɒʂ�A�����s�̍���S�͗�T2�N(716)�ɍ������n���l���ڏZ�����Đ݂���ꂽ�Ɠ`�����Ă��܂��B���̓��̉����ɂ͓s���쑺�ɓޗǎ��㏉�߂̑n���Ɠ`���鎜�����⎙�ʌS�_�쒬�̉��쎮���Ћ��s�_�Ђ�����A���Q�n�����ɂ͑��Ӕ���͂��߂Ƃ������O��Ȃǂ�����A�����͂��̒n���̌Ñ㌤���ɂ͌������܂���B �ŋߓ����s�̂i�q���������������w�쓌���̌����S�̌��C����n�̊J���H���ɂƂ��Ȃ��悾���Ĉ�Ղ̔��@�������s���A 340���[�g���ɂ��y�ԌÑ�� ���R���E�����H�̈�\���������ꂽ�����ł��B ���̓��H�Ղ͕{���s�̋��b�B�X�����獑�����s�� �������E�ӂ�܂ł�4�D2�L�����[�g�����܂肪�m�F����Ă��邻���ł��B���̊Ԃقڒ����� ������12���[�g���œ��̗����� ���a���m�F����Ă��邻���ł��B����͊��q�X���̓����Ɛ��肳��Ă��镨���� 2�{�͂�����̂Ŋ��q������X�ɌÂ� 500�N�O�ɂ��ꂾ���̓��H�� �����Ă����Ƃ������Ƃ͋����ł���܂��B ���̓��H��\�͂����ȊO�ɂ͏���s�̊��q�X���㓹������ ���v���̐��ɓ�˒��w�Ə��Z�̕t�߂ŌÑ�̈�Ղ���������Ă��� �����ɂ�12���[�g������ ���a�t���̓��H��\���m�F����Ă��āA ���̈�\�͐�̍������s�̈�\�ƌq����\�����\������̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă��邻���ł��B ��������̏��߂ɍ��c�����C�����Α叫�R�ɔC�����ڈΕ���̂��ߊ֓��̕�������ʂ�ڈɕ����܂��B ���q�X���㓹�ɂ͓c�����C�ɊW���� �`�������X�ɓ`�����Ă��܂��B ����ȂɌÂ�����̐l�̓`��������Ƃ������Ƃ� ���̊X�����̂����Ȃ�̂��瑶�݂������Ƃ��f���܂��B�c�����C�͉��B�Ɍ������̂ł�����B�A �M�Z���ʂɌ������㓹��ʂ����̂ł��傤���B �������㒆���ɂȂ�Ɗ֓��̒n�ł͕��m�c���������Ă��Č����╽���ȊO�ɂ��������}�Ȃǂ̕��m�c���o�ꂵ�Ă��܂��B ����Ȓ����߂ɕ�����̗��A�����ĕ�����̗�����������܂��B �����͓s�̒����W�������� �s�������֓����m�̔����ł����� �����ɒ�������Ă��܂��܂��B�����ĉ��B�őO��N�A��O�N�̖������肱�̎������`�A�`�Ɛe�q�̊���Ō����͊֓����m�c�̓����� �����悤�ɂȂ�܂��B ���������A�ی��̗��̏����O�ɑѓ��搶���`�������q�X���㓹���̑呠(���R��)�Ɋق��\���܂��B�����������̒��������� ���̈������`���ɋ}�P����ĎE����Ă��܂��܂��B ���̎����͊��q�X���㓹�ɓ`��� �����Ƃ��Â��L���ł������̍��ɂ͂��̓��͊X���Ƃ��� ���Ȃ�`���ƂƂ̂��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B ���̌㗊�������q���{���J���܂ł̊Ԃ͕����̗��ɂ�茹���̉�ŏ�ԁA������������b�A�����V�c���ʁA�Ȑm���̋����A �����E���i�̗��Ƒ����܂��B�Ȑm���̋����ɂ���� �ŏ��ɓs�ɓ������̂͌��`���ł����B �`���͑ѓ��搶���`���Ƃ��A�`�����E���ꂽ���� �M�Z�̍��̖ؑ]�֓���Ă����̂ł����B�`���͕��ƈ���s����ǂ��o�����̂ł����A �`���̕����s���ŋ�������A�㔒�͏�c�� �H������ŕ]�������������̂ŗ����̖��Ō��͗��A�`�o��ɂ���ċߍ]�œ�����Ă��܂��܂��B�����͋�����A���R�̐킢�ő��i�e�� �j��[�B�֓����̂ł����R���𗧂Ē����Ċ��q�ɓ���y�m��̐킢�ŕ��ې��R��j��s�������܂��B�`�������㗊���͐l���Ƃ��� �����̖��̑�P�̖��ł������`�����E�����Ƃ��܂����A�v�悪��P�ɘR��`���͊��q�X���㓹��k�֓������čs���܂����A�₪�ē��Ԑ�� �ǂ���ɕ߂܂�E����Ă��܂��܂��B���̌㗊���͒Ǔ��̃^�[�Q�b�g���㔒�͖@�c�ɂ�蔻���ɔC����ꂽ�`�o�Ɍ�����̂ł��B ���Nj`�o�����B�œ�����Ă��܂��A �`�o�������܂��������G�t�Ƒt���w��̓G�ƂȂ� 1189�N�ɉ��B�����ʼn��B��������łڂ��Ă��܂��B �����͏㋞���Č㔒�͏�c�ɉE�߉q�叫�ɔC�����܂����ނ͎��ނ��Ă��܂��B �ނ��]��ł������̂͐��Α叫�R�������̂ł��B ������1192�N�Ɍ㔒�͖@�c������������Ɍ������͐��Α叫�R�ɔC�����ꂱ���Ɋ��q���{�� ���������̂ł��B�����Ċ��q�X���㓹�͗����� ���q�ɓ��蓌���x�z�m���̂���ɂ͂قڊX���Ƃ��Đ�������̐����������Ă����Ǝv���Ă��܂��B�@ �@ |
|
| ���������ɂ��� | |
|
���剻�ȑO�̕������͏헤���̈ꕔ
645�N�̑剻�̉��V�œ��{�ɂ͐V�������Ƃ����܂�܂����B���̍��Ƃ͗��߂Ƃ����@�Ɋ�Â������W�����Ƃł����B ���̗��ߐ��ł͑S����傫���܋E�����ɕ����A���������ɍ��E�S�E���E���E�˂ɕ����Ē������{�����ړ������܂����B���̎d�g�݂ŁA�Ñ�̕������͓��R���̗������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B �����������������ꂽ���͂킩��܂���B�����āA�������̗������̗̈���͂����肵�܂���B�����̍��{(���i�̂���Ƃ���)�͋{�錧�̑����ł����B���̑���邪���{�̋L�^�Ɏn�߂ďo�Ă���̂�724�N�ł��B�������A���̑O�̗{�V�N��(717�`723�N)�ɗ���������鍑�Ɗ�㍑�ɕ��������Ƃ����L�^������܂��B���̂��Ƃ��l����ƁA����邪�����̍��{�ɂȂ�O�ɂ��łɗ���������������Ă����\��������܂��B �u�헤�����y�L�v(713�N)�ɂ́A�������̕l�ʂ�͌��͏헤���̈ꕔ�������Ƃ���܂��B���Ԃ����̔��͂��炢�킫�ɂ����錧��n����헤���̈ꕔ�ł����B�Ƃ������A�剻�ȑO�̏헤���ɂ͖k�̍����͂Ȃ������悤�ł��B�헤���́A��͉�����(��t���k��)�A���͉��썑(�Ȗ،�)�Ƃ����悤�ɋ��E�͂���܂������A�k�̍����͂Ƃ��ɒ�߂��A�헤����k�͂��ׂď헤���Ƃ����ӂ��ɂȂ��Ă����̂��Ǝv���܂��B�ł����畟������̐l�X�����������͏헤���̈ꕔ�Ƃ����ӎ��������Ǝv���܂��B�@ |
|
|
���ŏ��̗������͕������̂���
���̌�A��a����͏헤���̖k�ɗ��������������邱�ƂɂȂ�A�����ł͂��߂ď헤�̖k�ɍ������������邱�ƂɂȂ�܂����B�����͂��Ԃ��G�R�n�̓�[�̔��a�R�ł����B���̎����������̊j�ɂȂ����͕̂������̌���ƕl�ʂ�ł����B�����͓����A��������ł͍ő�̐l���f���n�тł����B���̌���ƕl�ʂ���j�ɁA��Òn���ƌ����ƌ��k�A���ꂩ��{�錧�̈����G�삩���̒n������킹�Ăł����̂��ŏ��̗������ł����B���Ԃ�7���I���ł����B ���̍ŏ��̗���������������ƈ����G��ȓ�̋{�錧�悾�����ƍl���鍪���́A�u��㋌���{�I�v�Ɓu�a�����ڏW�v�Ƃ����j������̐����ł��B �u��㋌���{�I�v�̍����{�I�ɂ́A�剻�̉��V�ȑO�ɁA�S���̒n�����x�z���Ă��������̖����ԗ�����Ă��܂��B���̍����̂��Ƃ������Ƃ����܂��B �����ŁA���̏����̓��k�n���������11�̍��������āA���̒��Ɂu�v�����v�Ɓu�ɋv�����v�A���ꂩ��u���͍����v�Ɓu�Ώ鍑���v��4�����������̂��킩��܂��B �u�v�v�͋{�錧�̘j���S�A�u�ɋv�v�͋{�錧�ɋ�S�̂��Ƃł��B�u���́v�Ɓu�Ώ�v�͂����܂ł��Ȃ�����̔��͊��̂��Ƃł��B�@ �����Ďc��7�̂���6�����͂��ׂĂ��̊Ԃ̗̈�Ɋ܂܂�Ă��܂��B�����ŁA���͂Ɗ�邩��{�錧�암�܂ł��剻�ȑO�̑�a����̐��͔͈͂ŁA���̗̈�𗤉����ɂ����̂��낤�Ɛ����ł��܂��B�܂�A�������̗̈�͈����G���݂̘j���ɋ�Ɣ��͊��̊Ԃɋ��܂ꂽ�̈�ŁA����͂قڕ������̂��Ƃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �������A�{�錧�̖k���ɂ����������͂��܂����B����͑�a����̎x�z�ł��邱�Ƃ������O����~���̕��z���݂�킩��܂��B���k�n���ő�̑O����~���͋{�錧�̖���s�ɂ���܂��B�ł�����A�{�錧�̖k���ɂ����x�ȕ��������l�X�����܂����B�������A�ނ�͑�a����Ƒa���ł��������A��a����ɔ������Ă��̐��͉��ɓ���܂���ł����B�����ŁA�ŏ��̗������͕�������Ƌ{�錧�암��̈�Ƃ��Đ��������̂ł��B �Ñ�̓��k�n���ɂ�����10�����͗������̗̈�ɂȂ�܂����B�c��u�o�H�����v�́A�R�`���̈ꕔ�Ō�ɏo�H�������̊j�ɂȂ�܂����B���̂悤�ɑ�a����͂��łɎx�z���ɂ���n����j�ɐV������������đS���x�z���g�勭������헪���Ƃ��Ă��܂����B�@ |
|
|
�����������12�S
��a����́u��㋌���{�I�v�ɏo�Ă��闤������10�̍������x�z����N�j�����̂܂܌S�ɂ��܂����B ����10�̃N�j�����̂܂܌S�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�u�a�����ڏ��v�Ƃ�����������킩��܂��B���̏����͕������㒆���ɁA�����Ƃ����M�������������̕S�Ȏ��T�ł��B���̖{�ɂ͑S���̌S�Ƌ���������Ă��āA�Ñ�̒n���j�����ł͍ŏd�v�̎j���ɂȂ��Ă��܂��B�u�a�������ڏ��v�ł͒����̂ŁA�ӂ��́u�a�����v�Ɨ����܂��B�����ł��u�a�����v�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ��܂��B �u�a�����v�ɂ��ƁA�������㒆���ɂ͕������ɂ͎���12�S������܂����B �F��(����)�@�@�@�@���n�s�n���@ �s��(�Ȃ߂���)�@�����s�n�� �W�t(���߂�)�@�@ �o�t�n�� �֏�(���킫)�@�@ ���킫�s �e�c(������)�@�@�@���킫�s�암 �M�v(���̂�)�@�@ �����s�n�� ���B(������)�@�@ ��{���s�n�� ����(������)�@�@ �S�R�s�n�� �␣(���킹)�@�@�{���s�n�� ����(���炩��)�@ ���͎s�n�� ���(������)�@�@ ��Îᏼ�s�n�� �떃(���)�@�@�@ �쑽���s�n�� ������́u��㋌���{�I�v�Əƍ�����ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B ���c�������F���S ���H�������W�t�S �Ώ鍑�����֏�S�@ �����e���������e�c�S �M�v�������M�v�S ���ڍ��������όS �Δw�������␣�S ���͍��������͌S ���B�S �s��(�Ȃ߂���)�S ��ÌS �떃�S�@�@�@ ���̕\����A�V�݂̗������͌����8�����Ƌ{��암��2�����̃N�j�����̂܂܌S�ɂ��A����ɉ�ÌS���������̂��ŏ��̗������������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B ���̂��������ƑΉ����Ȃ����B�E�s���E��ÁE�떃��4�S�ɂ��ẮA���̂悤�Ȏ������܂����B ��������̒����ɐ��{���u���쎮�v�Ƃ����s���̎{�s�ב��W��Ҏ[���܂������A���́u���쎮�v�ɁA906�N�Ɉ��όS�����Ĉ��B�S���������Ƃ���܂��B�ł�����A���B�S�͌��͈��όS�̈ꕔ���������Ƃ��킩��܂��B�����悤�ɁA�떃�S�͉�ÌS����A�s���S�͉F���S���番�����Ăł����㔭�̌S�ł����B ��ÌS�ɍ��������Ȃ��������R�͂킩��܂���B������Â͗������̒��ł͖ѐF�̂������S�̂悤�ł��B �u���{���I�v�ɂ͐��_�V�c���l�����R��S���ɔh�����A���̎��A�k�����爢����𓌂ɐi���R�Ɠ��C���̖k���瓌�ɐi���R���o������̂���ÂŁA���ꂪ��Â̌ꌹ���Ƃ������Ƃ��L�ڂ���Ă��܂��B�ÂƂ����̂͑D����̂��Ƃł��B�ł������Â͓�l�̏��R���o������D����Ƃ����킯�ł��B�j���̐^�U�͂Ƃ������A���̂��Ƃ����Â͑�a����̎��ォ��ق��̌���̃N�j�Ƃ͂������n�悾�ƍl�����Ă����̂��킩��܂��B ��Âɂ͑�ˎR�Õ��Ƃ��������ő�̌Õ�������܂��B���̌Õ���3���I�̒z���ŕ����i�Ȃǂ����a����Ƃ̂Ȃ��肪�[�����Ƃ������ł��܂��B�����������Ƃ��l����ƁA��Â͍������x�z����y�n�ł͂Ȃ��āA��a����̒����n�ł���ԑq(�݂₯)�ŁA���̂��߂ɍ��������Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�����܂��B�@ |
|
|
�����E�ɂ���
�Ñ�̍���S�̋��E�͎R�ł����B����͐������̂������ŋ��E���ł��邩��ł��B��́A��̌������݂̐l��������݂̐l�������������ł����狫�E�ɂ͂Ȃ�܂���B�삪���E�ɂȂ�̂͗̒n�������������Ȃ镽������ȍ~�ł��B��͂͂�����ڂɌ����܂����狫�E�ɂ͕֗��ł����B �����œ��{�ł͌Â����E�ƐV�������E�����݂��Ă���̂��ӂ��ł��B�Ⴆ�Έ��όS�̈����G�쓌�݂͓c���S�ł����A���̓�̌S���͐�ł�����A����͂����ƌ�łł������E�ł���̂��킩��܂��B����ɑ��āA�S�R�s�Ɛ{���s�̋��E�͍�����ł��Ȃ���Ί���ł�����܂���B���E�͂��̓�̐�̊Ԃɂ���Ⴂ�R�X�̕�����ł��B�ł�����A���̋��E�͌Ñ�̈��όS�Ɗ␣�S�̋��E�ł������̂��킩��܂��B����������͑S���ɂ���܂��B�@ |
|
|
�������
�Ȃ��A���{�̋L�^�ɂ́A�ޗǎ��㏉���̗{�V�N��(717�`723�N)�ɗ���������鍑�Ɗ�㍑�ɕ����������Ƃ������Ă���܂��B�������A���̕����͖������������悤�ł��B10�N���o���Ȃ��Ō��̗������ɂ��ǂ��Ă��܂��܂����B���̊��E���2�����͖����ɂȂ��Ă܂��{�s���܂������A���̎�����͂肷���ɔp�~�ƂȂ�A���̕������ɂȂ�܂����B �������̕����͓���Ƃ��낪����܂��B���k�n���ł͂ӂ����H�R�n�����E�ɂ��܂��B���̂��ߖk���́A���H�R�n�̐������H�c���R�`���ɂȂ�A��������茧�{�錧�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪���̋K��������ɓK�p����ƁA��Â��P�Ƃň�̌�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂����A����ł͌��Ƃ��ď��������܂��B ���H�R�n�ŕ�����̂������Ȃ�A���ɍl������͈̂����G�R�n�����E�ɂ��邱�Ƃł��B�������A�ޗǎ�����������������̈����G�R�n������ł͂����Ƃ��l���������Ƃ���ł����B�����������G�R�n�͈����G�����Ƃ������悤�ɁA�Ⴂ�R���݂��ǂ��܂ł������Ă��āA��ڂȂ��l���Z��ł��܂��B�ł�����A���������E�ɂ���Ɛl�X�̐������f���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B��������Ƃ�͂蕟�����͕������ň�̂܂Ƃ܂�ɂ��邵���Ȃ��悤�ł��B�@ |
|
|
�����R��
���ߐ��ł͒n���̍��ɂ͍��{��u���A���{�Ɠޗǂ̓s�����Ԋ��������܂����B�������̍��{�͋{�錧�̑����ł����B�ł����瓌�k�n���암�ɂ͑����Ɠޗǂ̓s�����Ԋ���������܂����B���ꂪ���R���ł��B�����ŁA���̓��R���ɂ��Č��Ă������Ƃɂ��܂��B �͎̂����Ԃ�����܂��A���{�ł͂ǂ������킯���n�Ԃ����B���܂���ł����B�ł�����A�ו��͐l���S�����A�n�̔w�ɍڂ��ĉ^�Ԃ����Ȃ��A���̂��߂̐l���Ɣn���K�v�ł����B�����ŁA�]�ˎ���̌܊X���������ł����A���{�͓��̏��X�Ɍ��p�̉ו����^�Ԃ��߂̎{�݂����܂����B���ꂪ�w�ł��B�����āA���̉w�̂��铹�������ɂȂ�܂��B�ޗǎ���ɂ́A���̊����ʼnו����^�Ԃ͉̂w�̂��鋽�̐l�X�ł����B������w��(���܂₲��)�Ƃ����܂��B �s�̂���ޗǂ��瓌���{�ɍs���ɂ́A�����m�݂̓��C���Ɠ��{�C�݂̖k�����̂ق��A�����̓�������܂����B���̓����̓������R���ł��B ���R���́A�����̓��ł�����ǂ��ɂł��悳�����ł����A�}�s�ȎR�x�n�`�̓��{�ł́A���̃��[�g�͈�Ɍ��܂��Ă��܂��܂��B����͈��m�����璆���R�x�n�ɓ���V����̐�݂ɉ������ł��B�V����͒��쌧�̐z�K���痬��Ă��܂�����A���̂܂ܐz�K�̂��鏊�܂ōs���܂��B (�Ñ�̓��R���A�]�ˎ���̒��R���A����̒����������ƁA�����R�x�n�тɂ́A���̓V����݂̓������Ȃ��A���Ԃ�ꕶ����ȗ����̃��[�g�����������ԓ��ł����B) �����āA�z�K���炳��ɓ��ɐi�ނƉO�X���ɏo�܂��B�̂͂��̉O�X�����֓��ւ̌����ł����B�O�X��������Ɗ֓�����ɂȂ�A�Q�n���̑O���ɏo�܂��B���̑O������썑�̍��{�ł����B �O���ɂ͗����삪����Ă��܂��B���̗�����̓�݂͍]�ˎ���ɂ͒��R���ɂȂ�܂����A���R���͑����ւ̓��ł�������k�݂̓��ɂȂ�܂��B�����ł��̓��𓌂ɐi�ނƁA�Ȗ،��̍��̉���s�ɏo�܂��B���̉���s�����썑�̍��{�ł����B ���Ԃ�ŏ��̓��R���͂��̉���s���I�_�ł����B�Ƃ��낪����������������A���R���͂���ɖk�ɐL�т܂����B ���̏ꍇ�����[�g�͌��܂��Ă��܂��܂��B����͋S�{��ɉ����Ėk�サ�A�r������߉ϐ쉈���ɖk�シ�铹�ł��B���̓߉ϐ�͓ߐ{���痬����ł��B�����œߐ{�̂ǂ����͂͂����肵�܂��A�Ƃ��������̂�����̎R���z����ƈ����G��ɏo�܂��B�����ŁA���̈����G��̐�݂��ǂ�ǂ�k�シ��Α����ɍs���܂��B���ꂪ�ޗǎ���̓��R���ł����B�܂�A���R���Ƃ����̂� �V���쁨(�O�X��)�������쁨�S�{��E�߉ϐ쁨�����G�� �Ƃ����傫�Ȑ�ɉ�������݂̓��ł����B �������A���Ԃ��Ԃ��Ȃ����̗������͓��R���ł͂Ȃ����C���ɑ����Ă����Ǝv���܂��B����͕��������헤���̈ꕔ����������ł��B�����ė����̂��Ƃ��u�݂��̂��v�Ƃ����܂����A���̏ꍇ�̓��Ƃ͓��C���̂��ƂŁA���̓��C���̉��n�Ƃ������ƂŁu�݂��̂��v�Ƃ����Ăѕ��ɂȂ����̂ł����B�@ |
|
|
�����C��
�����ł͕������̗��j�Ƃ͒��ڊW����܂��A���C���ɂ��Ă��������Ă����܂��B���C���͑����m�ɉ������ł��B���̓��ł͓ޗǂ���O�d���ɓ���A�É����̊C�ݐ���ʂ��Đ_�ސ쌧�̑������ɏo�܂��B�ޗǎ���ɂ́A���̑����������C���̊֓��̓�����ł����B��������ɂȂ�ƕx�m�R�������A�����͍��̔����ɕς��܂����A����܂ł͑������ł����B �ޗǎ���̓��C���ł͂��̑���������_�ސ쌧�̊��q�ɍs���܂��B�����Ċ��q���炳��ɎO�Y�����̐�[�ɏo�āA��������D�œ����p�����f���܂��B����Ɛ�t���ɏo�܂��B�������㑍���ł��B �����ē����p�̓��[�ɉ����Ėk�サ��t���̍��̎s��s�ɍs���܂��B�������������̍��{�ł����B�s�삩�炳��ɖk�シ��ƈ�錧�̍��̐Ή��s�ɒ����܂��B�������헤���̍��{�œ��C���̏I�_�ł����B���ꂪ�ޗǎ���̓��C���ł��B �ł�����ޗǎ���̓��C���ł͓����͒ʂ�܂���ł����B������ʂ�Ȃ������̂́A�̂́A�����s�S���͗�����̉͌���ɂȂ�A�����͍L���Ƃ������n�тŌ�ʂ̍s�����������������ł��B ��ʓI�ɐ̂͊C�݉����̓����R�ԕ��̓��̕����֗��ł����B����͐삪���邩��ł��B��͏㗬�ł͐앝�����������ĊȒP�ɓn��܂����A�C�ɂȂ���͌���ɂȂ�Ɛ앝���L���Ȃ�A�ȒP�ɂ͓n��Ȃ��Ȃ�܂��B�ł�����A�����V����̂��铌�C���͐��n��̂���ςŁA�ޗǎ��ォ�玺������܂ł͓��C����蓌�R��(���哹)�̕��������g���Ă��܂����B�@ |
|
|
�����R���̌���̉w
�b�����ǂ��ĕ�������̊����ł����A���Ԃ�ŏ��͓��C���̉��������ɕl�ʂ�̓��ł����B�Ƃ��낪�܂��Ȃ����R���ɕς����悤�ł��B����͓��k�n���̓��R���͐푈�̓�����������ł��B �����A��a����͓��k�n���̖k���ʼnڈƐ푈�����Ă��܂����B�����ŁA��n�ɕ��m�═��H���𑗂葱����K�v������܂����B ���m�͓����͕������̂ق��A�헤�Ɖ����E�㑍���璥���������m�ł����B����3���͐l�����������Ήڈΐ푈�̎�͂ł����B���Ԃ�ނ�͈�錧�̊C�����̓�����e�c�̊�(�ܗ��̐�)��ʂ��āA���̍���6�����̃��[�g�ŁA�W�t���s�����F���ő����ɍs���Ă��܂����B���̃��[�g�͈����G�쉈���̓���蕽�R�ŋ������Z���ł�����A���̓����g���͎̂��R�ł����B �Ƃ��낪���̂����푈���������Ȃ�A�푍�̕������ł͊Ԃɍ���Ȃ��Ȃ�܂����B�����ŁA��쉺�앐���̕����������邱�ƂɂȂ�܂����B ��������ƕl�ʂ�̓����A�����G�쉈���̓��R���̕����֗��ɂȂ�܂����B�Ƃ����̂����R�����g���Ώ�쉺�앐���̕��͂��̂܂ܑ����ɑ��邱�Ƃ��ł��܂����A�헤�����㑍�̕��m���A�헤���ʂ��甪�a�R���z���邩�A�v���쉈���ɖk�シ��Č���̍��̒I�q���ɏo�āA�������琼�k�ɐi�߂Γ��R���ō����ł��邩��ł��B ���̓�̓�����������̂����͌S�ł����B�����ŁA���̔��͂ɑ����ɕ��m�ƕ�����⋋���邽�߂̏W�ϒn��������悤�ł��B���ꂪ���͂̊ւł����B�܂蔒�͂̊ւƂ����̂́A�ڈ̐N����h���Ԃł͂Ȃ��A�ڈ��U�����邽�߂̕�⋊�n�ł����B ���̓��R���̋@�\�����������ƁA�w�̋@�\����������Ă����܂��B���������̖@�ߏW�u���쎮�v�ɂ��ƌ���̉w�͎��̒ʂ�ł����B �Y��(����)�|���c(����)�|�␣(�␣)�|����(����)�\���B(���B)�|����(���B)�\���z(�M�v)�\�ɒB(�M�v) ���̂������c�w�͒I�q���ʂ���̓��Ƃ̍����n�ɂȂ��Ă��܂����B���c�w�͍��̒������ɂ���܂����B�����āA�����̔��͌S�̌S����(������S�� ( ���� )�Ƃ����܂�)�͂��̖k�̍��̐�葺�ɂ���܂����B�ł����獡�̐�葺�E�������̂����肪�ޗǎ��ォ�畽�����㏉���ɂ����Ă͌���ł����Ƃ�������Ă������ł����B�@ |
|
|
�����͂̊�
���͂̊ւ́A���͎s�����̊��h�ɂ���j�Ղ̏������̐ՂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���͔ˎ�̏�����M�����܂��܂ȍl�����ĊՂƌ��߂܂����B���݂͍��̎j�ՂɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ͂�����M���100�N�O�̏����m�Ԃ��������Ղ��Ǝv���ė�������Ă��܂�����A����������h�����͂̊Ր��͂������悤�ł��B �����͒I�q���ɒʂ��铹�̓r���ɂ���܂��B�ł�����A���̂�����ɔ��͂̊ւ��������ƍl����͎̂��R�ł��B�������A���̊Ղ͂������܂��B�Ղɂ͋�x��y�ۂ�����A����͊��S�Ɏ�������̎R��̐Ղł��B��s���Ƃ̊Ԃł́A���͊Ձ���������̏�ՂƂ����̂͏펯�ɂȂ��Ă��܂��B ���͂̊ւ́A�ޗǎ���̂����ɑ������R���I�������������悤�ł��B�������A��������ɂȂ�ƁA���s�̋M�������͊ւƂ������̂��炳�܂��܂ɋ�z���A���傤�ǃV���N���[�h�̗z�ւ�����̂悤�ȏ��ɂ������Ȃ��ƍl���ėv�ǂ̃C���[�W���ł�������A���ꂪ���݂��p����Ă���悤�ł��B�Ƃ͂����@���k�Ȃ�Ƃ������A���̓�[�̔��͂ɉڈ̐N����h���v�ǂ��������Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă����܂������܂���B�ł����甒�͂̊ւ͌��X�͕�⋊�n�������Ǝv���܂��B ����Ɛ̂��甒�݂͂͂��̂��̓�����Ƃ��ėL���ł����A���̃C���[�W�͔��͍͂r���Ƃ������k�̎��R�̒��ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�������A��������S�Ȍ���ł��B ���̂��Ƃ͏펯�ōl���Ă��킩��܂��B�����̓ߐ{�͂܂������̉ߑa�n�ł����B�ł�����A���͂��ߑa�n���Ƃ���ƁA���l�͉ߑa�n����ߑa�n�ɗ��邾���ł�����ʂɂǂ��Ƃ������܂���B�����ł͂Ȃ��A���l�����l�̓ߐ{���S�ׂ��C�����ŕ����Ă����ƁA�R�̌������ɓˑR�l�Ƃ��������鑺�����o������B����ŗ��l�ɋ���Ȉ�ۂ�^�����̂����͂ł����B�@ |
|
|
|
|
|
�����L
�������� (�ނ̂���)�@���ē��{�̒n���s���敪�������ߐ����̈�B���R���ɑ�����B�����́u�����v(�݂��̂���)�ƌĂ�A��������܂Łu�����v(�݂��̂�)�Ƃ��Ăꂽ�B���̌�́u�����v(�ނ�)�ƌĂꂽ�B�E�����猩�ĎR��(�̂��̓��R��)�ƊC��(�̂��̓��C��)�̉��Ɉʒu���A���������ɐV�K�ɕ��]�����n����Ɋ܂߂Ă��������߁A�����ɂ���Ĕ͈͕͂ϑJ����B�������N12��7��(����1869�N1��19��)��5���ɕ�������A����1�Ƃ��āA�X���Ɗ�茧��ˌS�ɂ����Ă̒n��ɐV���Ɂu�������v(�肭�����̂��ɁE�ނ̂���)���u���ꂽ�B ���u�����v�̖��̂ƗR�� �w�Î��L�x�ɂ́u�����v�Ƃ���A�w���{���I�x�́u�����v���������Â�����Ɂu�����v���݂��A�Ƃ��Ɂu�����v���u�݂��̂����v�ƌP����B�w�a�����x�́u�����v���u�݂��̂����v�Ƃ���B�u���v�͌Â�����ɂ́u���v�Ɠ��`�Ɏg���Ă���A�u�����v�̌ꌹ�́u�s����݂ĉ������v�ɂ��鍑�̈ӂł���B�u���v���u���v�ɂ������ϋɓI���R�͂킩��Ȃ����A�헤���̏ꍇ�Ɠ������A�u�����v�̈ӂł��Ă����̂ł��낤�B��������̘a�̂Łu�����v�́u�݂��̂��v�Ƃ��ĉr�܂�Ă����B�u�݂��̂��v�́u�݂��̂����v���a���ďk�܂������̂ł���B �u�݂��̂��v���u�ނv�ɕς��������ɂ́A�]�ˎ��ォ��������B��͗����Z�̑厚�Ƃ��ėp�����邱�Ƃ��ӂ܂��āA����Z�Ə����A����ɌP�ǂ݂����Ăāu�ނv�ɂ����Ƃ������̂ŁA�{���钷���w�Î��L�`�x�ŏ������B���B�͌Ñ�E�����ɂ悭�g��ꂽ�������ŁA�u�Z�����v�u�Z����v�u�Z���v�Ƃ�������������������ɂ͂������B������́u�݂��̂��v���u�݂��̂��Ɂv�ɂȂ�A�u�ނ̂��Ɂv�ɓ]�a�����Ƃ������ŁA�ۓc�����w�V������y�L�x�ɂ���B�u�݂��̂��Ɂv�́w�ɐ�����x�ȂǂɌ�����B�@ �@ |
|
| �����͍��Ó��Ƒ�a | |
| ���͂��߂� | |
|
���y��a�́A���̋���Ɛ��̈��n�여��ɂ͂��܂ꂽ��k�ɂ̂т鋷�(���傤����)�̒n�`�ŁA�ω��̋ɂ߂ď��Ȃ���n�ł��邪�A�����ď�Â̎���A�܂����͐삪���̗���A�˒m�̋߂��܂œ��C�ł����������́A���쉈�݂₻�̎x���Ȃ�тɁA���n�여��̒�n�����͘p���p��������]�ŁA��ʐ��ӂ̏���n�тł���A���ɉ���������Ëv��̗����R���甭���鋫��́A���̒n(�㐢�̐[�����t��)���ł������[�������Ɠ`�����A�[���E�[�C�̏̂���[���Ɩ��t����ꂽ�Ƃ����Ă���B
���̌�A�y�n�̗��N���̕ω��ɂ���āA�l�����ς�A���͌���n�̓암�̈���ɂ��̒n���߂邱�ƂƂȂ����B ���y��a�ɁA��Z��������������悤�ɂȂ����̂͂��̎��ォ�炩�͏ڂ��łȂ����A����ɏW�c�������c�܂�A���悢��̋K�͂Ɨ��여��̒Ꮌ����ƁA��n�̐����p���̎��ւ��Ƒ��܂��āA���y�̕����͂����A�����̎p�ƂȂ����̂ł���B |
|
| ���� �����ւ̓� | |
|
���āA�䂪���ŌÕ������������̂́A�O���I�㔼����l���܂̏��߂���Ƃ����Ă��邪�A���̕搧�́A���ߑ�a������`�������E���̍����̊Ԃɍs�Ȃ�ꂽ���̂ł��������A����̐��͂̔��W�ɔ����đQ���e�n���̍����̊Ԃɂ��L�����Ă������ƍl�����A�܂��A�嗤�Ƃ̌�������ƂȂ�ܐ��I�Ȍ�́A�Õ����̂��̂����ɗY�傩���Ȃ��̂ɔ��B���Ă������悤�ł���B
���̂悤�ȌÕ������̍L����́A��a����̓��ꎖ�Ƃ̐i�W�����ƂÂ�����̂Ƃ��āA���ڂɂ���������Ƃ���ŁA���̂悤�Ȏ��㒆���ƒn���Ƃ̌𗬂ɁA�K�v�����ׂ��炴����̂Ƃ��āA�d�含��ттČ����Ă�����̂ɁA�u���v�Ƃ������̂�����B�����āA�����̋ߋE�n���𒆐S�Ƃ�����a���삪�A�n���Ƃ̌𗬍c�����v��A�����s�����m�ł�����̂Ƃ��邽�߂ɁA����������A���̓����ւƁA����Ɍ�ʘH�͔��B���Ă���̂ł���B |
|
| ���� �L�I�̓� | |
|
��(��) �l�����R�̔h��
���āA���́u���v�Ȃ���̂������Ɍ�����悤�ɂȂ����̂́A����F���V�c�̌��N��ꌎ�Ƃ���A���C�����n�߂ĊJ�����Ƃ����Ă���B �����ŁA��Z�㐒�_�V�c�̂Ƃ��A�킪���͎n�߂āA�l�����R�Ȃ���̂��l���Ɍ��킳��āA�����c���̓����ɓ����炵�߂��Ƃ����Ă���B���Ȃ킿�A�k���E���C�E����(�R�z)�E�O�g(�R�A)�̎l���ł����āA�w���{���I�x�ɂ��A��F��(�����Ђ��݂̂��Ƃ�)��k���ɁA���ِ�ʖ�(�����ʂȂ���킯�݂̂���)�𓌊C�ɁA�g���ÕF��(���тЂ��݂̂���)�𐼓��ɁA�O�g���喽(����݂��ʂ��݂̂���)���R�A�ɂ��ꂼ�ꌭ�킳�ꂽ�ƋL����Ă���B ��ɂȂ��āA�����Ɍ��킳�ꂽ�l�l�̏��R�������Ďl�����R�Ƃ����Ă���킯�ł��邪�A���̋L�^���A���邢�́A�`���̈���o�Ȃ����̂ł������ɂ���A���̎���A��a����m�����̎����Ƃ��āA���R���̂悤�Ȃ��Ƃ͂������ł��낤�Ɛ��@���ł���̂ł���B |
|
|
��(��) ���{�����̓����H
�X�ɁA����i�s�V�c�̂Ƃ��ɂȂ�ƁA���{�����ɂ���āA�������s��ꂽ�B�����炭�A�킪�֓��n���A���ɂ킪���͍��ւ́A���̂Ƃ����߂đ��������ӂݓ����ꂽ�A����A���y�̗��j�̏����Ƃ��l��������̂ŁA���������Ă�����_�@�Ƃ��āA�킪���͒n���ɂ́A����Ɋ֘A����`�������܂�Ă���̂ł���B �Ñ�̉p�Y�̎��ւ�P�Ȃ��l���̂��̂Ƃ��ĕ`�����Ƃ́A�`�����w�̏�ł��邪�A���ꂪ����ɒN�ł������ɂ���A���̓����H�͌Ñ�ɂ������ʘH���������̂Ƃ��āA���j�I�ɐ[���Ӌ`�������̂ƍl������̂ł���B �����ŁA�����̎��ւ̒��S�I�l�����N�ł��������̑F���͂��Ă����A�L�I�ɂ������{�����̓����H�ɂ��āA���ꂩ��q�ׂĂ݂����Ǝv���̂ł���B �����A�N�̍c�q�Ɣ܂̒�k�P�́A��a�R�c���S���Ƃ����镺��������Ă̗��ł������B���̎���́A�������A���̂悤�ȓ��H�͑S���Ȃ����m�̒n�ɓ������R�c�́A�R�܂��R�̔����������A���[�������ݕ����A��̏o����Ώ��������A��������J���Ă̏o�R�ł����āA�����̑�a����̍s�����ǂ��܂ŐZ�����A�Ќ����ǂ̒��x�܂ŕ��y���Ă������͏ڂ��ł͂Ȃ����A�r���d�������������������������ȂǍl�����킹��A���̋����͂܂��ƂɈ�卢��ł������Ƃ����悤�B �w�V�ґ��͍����y�L�e�x�ɂ��A�u�Â��l��ɓ����ƕ����Ƌ�����n�A���Â͎R��ɂāA�ʘH�Ȃ��肵���A��Q�ɋ��E�J���A�����̒ʂ���Ɏ��肵���ƁA�k�i�s�L�l�`�����A�����̏������Ēm��ׂ��v�Ƃ���B ���̂���A���͍��̌Ó����ǂ̂悤�ɒʂ��Ă������ɂ��ẮA�w�Î��L�x����сw���{���I�x�̓����̋L���̂Ȃ��ɂ�����x�L����Ă��邪�A�������A���̓����ɂ��Ă͋L�I�Ɏ�̑��Ⴊ����A�٘_����Ƃ���ł���B�����A���{�������x�͍����瑊�͍��ɓ������Ƃ��ɁA���������z���ė������Ƃ����͂������Ȃ悤�ł���B ��1 �w�Î��L�x�̓� �w�Î��L�x�ł́A�ɐ��E�������o�ē��ɐi�݁A�����đ��͂̍��֓������Ƃ��ɁA���̍�����������đ���U���o���A��̓�ɍ��킹�����ƂƂȂ��Ă���A���ꂩ��O�Y�����ɏo�āA��������㑍���ɏM�œn��r��A��k�P�̒��ȓ����̌̎����L���A�₪�ē����ł��̖ړI���ʂ��������́A�A�r���헤�ɂƂ�A�ӂ����ё��͍��֓���A�����̍�����A�����Łu��Ȃ͂�v�̒Q�����̂����A��������b��E�M�Z���o�Ĕ����ɋA��ꂽ�B�ƂȂ��Ă���B ��2 �w���{���I�x�̓� ����A�w���{���I�x�̂ق��ł́A���͈ɐ����x�͂ɗ��āA�����ł܂��A��̓�ɑ������Ƃ��A�ĒÂ̒n�����b���L���Ă���B���̌�A���͍����痤���ɓ����ĉڈ���܂ł̍s���ɂ��ẮA�Î��L�Ƃقړ����ł��邪�A�A�H�ɂ��ẮA�Î��L�Ƒ啪����Ă���A���͏헤�E�b��E�����E���E�M�Z���o�ċA��ꂽ�Ƃ���A��k�P���Â�ł̒Q���̒n���A���ƐM�Z�̋��̉O����(�O�X)�ɂ����ĂȂ��ꂽ�A�Ƃ���Ă���B ��3 ���Ƒ������̌Ó� �ł́A���͍��֓����ė���ꂽ���̌R�c�͂ǂ̂悤�ȓ���i�܂ꂽ�̂ł��낤���B�܂��ƂɁA�ِ��̂���Ƃ���ł��邪�A���܁A�H���E�搶�̐��ɂ��A�����̌Ó������ǂ��Ă݂邱�ƂƂ���B ���������z�������́A���ɂ��т��Ă����q�x�̉���ʂ��Ėk�コ��A�R�k�̕t�߂Ŏ�����n��ꂽ�B����ɂ́A��֖̊{�ɉ����āA���c�̕��ɐi�܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ̘b�����邪�A�����́A��Ó��E�㓇�E���䓇�E�����ȂǂƓ��̂����n�����������Ƃ��A���̕ӈ�т͓��C�ł������Ɛ��肳���̂ŁA��蓹���]�V�Ȃ����Ƃł������Ǝv����B ��q�x�̂ӂ��Ƃ���R�k���ʂɔ����邱�̓��́A�������q��Ó��Ƃ����邫��߂ČÂ����H�ŁA�����̋����R���ɂ́A�����̑ꂪ����A�����Ă̌��m�A���o��l���S���̍s���C�߂��Ƃ���Ƃ����Ă���B ���āA�R�k����̓��s�́A�����̖k���ɉ����āA���c���q��ʂ�A�����̊��c�_�Ђ̂��鏼�c�y�X�ɏo��ꂽ���̂Ǝv����B���ꂩ�瓌�̌Ó��͐쉹��̎l�\�����̌k�J�ɉ����Ėk�サ�A���ɐ܂�A�`�삩��P�g�����z���A��Ɂw���쎮�x�ʼnw(���܂�)�ƂȂ��Ă��閥�ւ�ʂ�A��䑽�_�Ђ̂���O�m�{���߂��A��R�̂ӂ��Ƃ��牺�����ɏo�A������k�サ�ď���ŋʐ��n��A����ɖk�サ�ēޗǎ���Ɋω�����݂���ꂽ�Ɠ`������юR��ʂ�A�����ŏ������n��ꂽ�B �����蓹�͓��k�ɐi��ŁA���Â̂�����Œ��Ð���z���A�������̒n�_�ŁA���͍����Ƃ����鑊�͐��n��ꂽ�B�Ί݂́A���镔���ŁA���̒n����ɂ͎����̗L���_�Ђ̍Ղ�ꂽ���ւ�����A���j�I�ɂ��ɂ߂ČÂ��y�n�ł���B �w�V�ґ��͍����y�L�e�x�ɂ��A�u��q�̌W�鏊�Ȃ�B�Ί݉������ɂĐi�ނ��B�b�z�R�ӂɂ��A�i�\�\��N�A���c�M�����c�����U�߂�ɂ�����A����ɐw���A�������瑊�͐��n��A�Ƃ����L�^����B�㐢�܂ł����̂Ƃ��낪�A���͐�̔g�ɕւȂ肵���Ƃ�m��B�v�Ƃ���B �镔����̉\�̓����́A���̑��͐�̍��݂̍^�ϑ�n�̏��^�����ɓ쉺���A����܂ōs���A���o������������̂ڂ��āA�Ŗ߂̓��ʂ��Č��݂̗p�c�X���ɏo�A�����o�āA����E���q�E���q�E�t�R�E�O�Y�ւƐi�܂�A�����ɒ����ꂽ���̂Ǝv����B �ȏ�́A�搶�̂�������{����̐i�H�𒆐S�ɂ����Ó��ł��邪�A���̌Ó��͓���(�Õ����㏉��)�A��������ʂ����A�������̎�v�������H�Ƃ������ׂ����̂ł������Ɛ��肳���B ���������āA����ȊO�ɂ��A�Ⴆ�A���c����]���u�˂̐����ɉ����Đ��ɏo�A���͘p�ɒʂ���悤�ȁA������x�����A��������e�n�ɂ����āA�n���I�Ȗ������ʂ����Ă����ł��낤���Ƃ��A���R�l������Ƃ���ł���A�������A�K�v�ɉ����āA�����̓��ɂ����ݓ����ꂽ���̂Ǝv����B |
|
|
��(�O) ���{�����̐��b
��1 �w���{���I�x�Ɓw�Î��L�x �Ƃ���ŁA�\�̖�Α���̐��b�ɂ��Ăł��邪�A�w���{���I�x�ɂ��A�u���̍A���{�����A���߂ďx�͍��Ɏ��肽�܂��B���̏��̑������]���A�\���ē����A���̖���g��(��������)�����A�C�����̔@���A���Ηт̔@���A�Ղ܂��Ď�肵���܂��B���{�������̌���M���A�쒆�ɓ���Ď�肵���܂��B�������E������āA���̖�����(�Ђ�)�Ă��B���\����ʂ��m�낵�߂��āA���������Ȃ��ĉ��o���A��(�ނ���)�ĂĖƂ�邱�Ƃ���B�v�ƋL����Ă���B ���́A�w���{���I�x�ɂ��A�x�͍��ɂ�������{�����̖�Α���̌̒n�Ƃ��āA�y�n�̌ØV�����́A���ꂼ��O�����������A�����������ɂ��Ȃސ_�Ђ������Ă���B���Ȃ킿�A�ĒÐ_�ЁE����_�ЁE�����_�Ђ̎O�Ђł����āA�ǂ̎Ђ����쎮���̐_�ЂŌÎЂł��邱�Ƃɂ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ł��邪�A�x�͍��v���S�ɂ���A�ĒÐ_�Еt�߂��A���Â̒n�`���炢���Ė�Α���̋��ւł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����̂��A�����L�͂Ȑ��̂悤�ł���B ����A�w�Î��L�x�ł́A��Α���̒n�𑊖͍��Ƃ��ċL���Ă���B ����ɂ��A�u�̎��ɑ����ɓ���܂��鎞�A���̍�������ē����A���̖�̒��ɑ������A���̒��ɏZ�߂�_�͐r�������U�_�Ȃ�ƁA���ɑ��̐_���ōs�����ɑ��̖�ɓ��������A�������̍����A���̖�ɉ����肯��B�v�Ƃ���A�܂��w�Ì�E��x�ɂ��A�u�`���������̔N�A���͂Ɏ���A��̓�ɋ��ӁB�v�ƁB�ł́A���́w�Î��L�x��w�Ì�E��x�ɂ������͂̒n�Ƃ͉���̒n�Ȃ̂ł��낤���B ��2 ��Α���̒n ���ΐ��搶�́w��a�s�j�N�\�e�x�ɂ��ƌi�s�V�c�l�Z�`�l�O(������Z�`���O)�u���{�������㌴�A�����̂�����ʼnΓ�ɂ���ꂽ�Ɠ`������B��k�P���A���˂����̉̂�����ꂽ�B�v�Ƃ���B �����������Ƃ���Ƃǂ��Ȃ̂��B�ɂ߂ċ���������ł���Ǝv���̂ŁA�����Ɏ������q�ׁA����̂��ᐳ��������ƍl����̂ł���B ���āA���镔���ɂ킽�������́A���͐�̍��݁A�^�ϑ�n�̓���^�����쉺����A���̊C�V���s��J���ʂɌ�����ꂽ�B ���̒n���ɂ́A�u���������A�[���P�����̎R�ɁA������t�A���t�v�Ƃ����ی�������悤�ɁA�����ݑ�̂���ƔF�߂���e��̌Õ����U�݂��Ă���B�܂��A�n���I�ɂ́A���đ��Â̂���A���͉��R�㗢�̓y��Ƃ����Ă����k�ɘA�Ȃ�u�˒n�тł����āA���̒n�قǑ傫�����]��Ԃ̒J���Ȃ��Ă���̂́A���ɂȂ��Ƃ����Ƃ��납��A���̂܂܁A��J�ƌĂ��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă���Ƃ���ł���B �܂��A�㐢�̑��߂ɂ�铌�C�����A�����R���z���đ��͍��֒ʂ������̑����̌�ʘH�ƂȂ����A�l�c�̏h�����̕ӂɂ������Ƃ����A���̂��߁A���͍��{�������̓��H�̗v�Ղ̒n�ł��钆�����̍����̒n�ɂ�����A����ɁA���̍��{���̐ݒu����N�������̌��������U���ƂȂ�A���C�����哹�Ƃ��āA������W���݂��B���ɗ��j�̕K�R�����̒n�ł�����B ����ɁA�ג��̈���������͂��̂������ŁA�����ɂ͌��݁A�А_�Ђ��܂��Ă���B�_�Ђ̋����ɂ́A���̍��|�Ƃ�����Âт������Ȃ���ɕۊǂ���Ă���B �����搶�́A�w���{�n�������x�ɂ��������A�u���쑺�ɁA�Ж��_����A�K���ɐ���A�o��䋖��A�`���ĉ]���A���{�����e�����Ȃ�B�v�ƁB ���āA��J�ɒ����ꂽ���͂��炭�R���A���̕t�߂ɋx�߂�����ꂽ�Ǝv���邪�A���̎��A���̕ӂɋ��Z���鑊���̍����́A�����A�����}���Đ\���ɂ́A�u���̌���ɑ���������āA�����ɑ�ϗ��\�Ȑ_������̂ŁA������Ăق����v�Ƒ���U���o�����B ���́A�����̂��ƂƂ��m�炸�A�P�g�A���̌���ɉ��[���i�������Ƃ���A�ˑR����̕�����������A��@�ɂЂ��B���͂��̘`�䔄���炨����ꂽ���������đ���ガ�A���̕ς�̂�҂��āA�܂��Αŗp������o���A�O���̑��ނ�ɉ����A������ꂽ�Ƃ����B �ȏオ�A���̈�֓`���̑�v�ł���A�ߍ݂̌ØV�����̊Ԃɂ��M�����A�����`�����Ă���Ƃ���ł��邪�A�`���͂ǂ��܂ł��`���ł����āA���̂܂ܐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A�Ȃɂ����̓��������̂Ƃ��āA�܂��A���y�ɂ������g�߂Ȗ��Ƃ��āA���́A���j�I�ɑ傫�ȈӋ`������̂ł͂Ȃ����ƍl������Ȃ��̂ł���B �v���ɁA�����炭�����̂�������Ƃ́A���̒n��蓌�́A���[�����܂ōL����쒆���������̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��A����Ƃ́A���̒n�𗬂��ڋv�K��E����E���n��E����ɐ��������n���������̂ł͂Ȃ��낤���B ���{�����̂��̎���́A�Õ�����̏����Ǝv����̂ŁA�����̗���̑啔�������C�ł����������ł��邵�A���͐�ɂ��Ă����̗���͈˒m�̕ӂ܂ŌÑ��͘p�ɂÂ����C�ł������Ƃ����鍠�ŁA�ڋv�K��E����E���n��E���여��������́A�Ώ����n�̓_��(�Ă�Ă�)����A�r��ł������Ɛ��肷�邱�Ƃ��\�ł͂Ȃ��낤���B �Ƃ��ɁA�����𒆐S�Ƃ��邱�̂�����́A���݂��͂邩�ɖL�x�Ȑ����������Ă����ł��낤�Ǝv������n�삪����A���̌Ώ��ɂ́A��ʏ�Ȃ����Ȃǂ��ɖ��A�����蓌�ɂ̂т鋫��܂ł̑�n�ƁA��̐��ɍL���鑐���E����̍L�������n�ɂ́A���n�тɂÂ��A����܂��A��ʂ̑����ł��������Ƃ��z�������B ���̂��Ƃ��炢���A�����̑����ɂ����鑸�̑���́A���̒n�������Č̒n�Ƃ��Ă��A�����͐������̂ƍl�����邪�@���ł��낤���B ��3 �����̏��� ���āA�����ő������̑��͒n���ɑ��ݓ����ꂽ���̂���́A�䂪���y���ӂ̏Z���͂ǂ��ł������낤���B ���݂̑�a���琼�̊C�V���ւÂ���т͈�ʂ̑����ł������ł��낤���Ƃ́A��ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邪�A���̕���ɂ͊��ɐ�Z�����������Ă��āA�傫���n���̏U�����������Ă��������m��Ȃ��B���̂��߁A�s���c�����y�ڂ����ߌR�c��i�߂�ꂽ���ɑ��āA������āA����������Ƃ��z������A���̑��������ɂ����̂ł��낤�B �����Ĕނ�́A���̓������@��ɁA�Ȍ�傫�ȕω����N�������̂ƍl������̂ł���B���Ȃ킿�A���̈ꌂ�ɂ������ނ�͐��͂������A�������k�̒n�����߂đޓ]�����҂������낤���A�܂��A�Α��̒��Ȃǂ͋A�����āA�n�������ɋ��͂���悤�ɂȂ�A��ɂ́A���̂܂ܒn���̖�l�ɂȂ�A�₪�č��S�����{�����ƁA���̑g�D�̒��ɓ��荞��ł����A��������C�����ꂽ���{�����Ƃ̊ԂɁA�@���ȊW�����悤�ɂȂ����Ƃ��l�����悤�B �Ȃ������ɂ́A�O�m��N(���ꔪ)�����A���́E�����ȉ��֓������ɑ�k�Ђ��������ۂɉ����ꂽ����ɁA�u����_�������ł��Ȃ��ē�������v�Ƃ��邵�A�܂��A�w���쎮�x�ɔޓ��y���̐�����}�����邽�߂̗���Ƃ��āA�u���͍��؈�������Z�S���v�ƍڂ��Ă���̂����Ă��A���������r�I�����̈Α����Z�����Ă������Ƃ͎����Ǝv����B ���̂��Ƃɂ��āA���R���g�搶�́A�A�C�k�����咣����Ă����邪�A���ꂪ����ɁA�����ƒf��ł��Ȃ��ɂ��Ă��A�����̏Z�����A�n�߂đ��ɂ���ĕ����̏����𗁂сA���̌�A�������o��ɂ��������Ď���ɗZ�����āA�₪�Ă͑S����a�����ɉ������Ă��������̂Ǝv����B ��4 ���y�̐l�т� ���j�Ƃ������̂́A�f�ГI�E�˔@�I�Ȃ��̂ł͌����ĂȂ��B������A�̂Ȃ���������ĕϑJ���V��������ւƔ��W���Ă������̂ł���B �킪���y��a�ɁA��Z��������������悤�ɂȂ����̂͂��̎���Ȃ̂��A�ڂ炩�łȂ����Ƃ͑O�ɂ��q�ׂ��Ƃ���ł��邪�A���{�����Ɋ֘A�������̓����ɂ́A���ɂ�����x�̏W���͌`������Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl������B�����āA���̈�̂܂Ƃ܂�Ƃ��āA�����ł���͈͂ɁA�[���E�ߊԁE�����E���c�E����E�[�J�E�����E�����̏����A���Ȃ킿�A���͋��������A���͖ڋv�K������ƂȂ��A�k�͉��ߊԂ���㑐���A��͕��c�̒n��܂ŁA������Z�L�����[�g���A��k�L�����[�g���Ƃ������Ȃ�L�͂Ȓn��������邱�Ƃ��ł��悤�B�����Ă��̏W���̒��S�͋��y��a�̋��[����������ł͂Ȃ��������Ǝv����B �Ȃ��Ȃ�A���̒n���́A��́w�a�����x�ł����[�����͈̔͂ł����āA�͂��߁A�R�[�̑�n����Ꮌ�n�т����߂ĈڏZ���Ă����ނ�ɂƂ��āA�蒅�̒n�Ƃ��ẮA�܂��ƂɊ��D�̒n�ƍl�����邩��ł���B �傫�ȉ͐�𗘗p���āA�����قǂ������@���m��Ȃ����������A�ޓ��ɂƂ��ẮA�N���̖L�x�ȁA�������A�y�n����r�I���R�ȁA���̒n�𗘗p���āA�ĊO�A�����̐l�������W�c�I�ɏZ�݂��A���̗N�����������ɗp���邩�����A�����̓y�n�ɂ��̐���U�����āA�����s�Ȃ��悤�ɂȂ����ƍl������B ���ɋ���̐����́A����������悭�A�����p�������₷���̂ŁA�������炱���ɏZ�݂����ƂɂȂ�A����̐��ڂƋ��ɁA�O�ʂ̒Ꮌ����ɐ��c���J���A�w��̑�n�ɔ����J���Ĕ_�q���c���̂Ǝv����B �������A���̋��여��́A���ʁA�n�`��ې��Q�̋�J�������̂��̂ł͂Ȃ��������̂ƍl������B�����Ŕޓ��́A���̐�����A�����̌��ł���Ƃ���́A���������ߑ��сA�܂��A�ې��Q�̓�ɋ���Ȃ����߂ɂ��A�����_�Ƃ��čՂ�Ƃ������K�����R�ɐ��������Ƃ����������̂ł���B�����āA���ꂪ�����ł����[�����Ђ̉��쎮�[���_��(���͂̌ÎЂ̒��ł��A���̐[���_�Ђ́A���̒����n���Вn���������Ă��炸�A�܂��A�_�Ђł��Ȃ��Ƃ����Ă���B)�̋N��ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B ��5 �[���_�Ђ̂����� �֓��n���̎����Ђ��A���̋N���́A�啔�����A�Õ�����ɂ����̂ڂ邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ă��邪�A�����ŁA���́A���y�̐[���_�Ђɂ��āA�����G��Ă������Ǝv���B ����Y���V�c���N�O���ɑn�Ղ��ꂽ�Ɠ`�����鉄�쎮�̐[���_�Ђ́A�t�J�~�Ƃ����Â��n���Ƌ��ɂ��łɁA�Â����猻�݂̐[�������ɂ����āA�O�ɏq�ׂ��[�����͈̔͂ɋy�ԑ��Ђ̂悤�Ȍ`�ŁA���݂��Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B ���̐[���_�Ђ̍Ր_�́A���Ƃ́A�N���I�J�~�Ƃ����A���_�ŁA�×����F�J�~�J���̐_�Ƃ��ĐM���ꂽ�Ր_�ł������Ɠ`����ꐅ�ɊW�̐[���_�ł������B���s�j�҂���ψ��̎R�蒉�`�搶�̌����Ƃ���ɂ��A��ނ����A���̓y�n�Ɂu�����̉��v�Ƃ����҂����āA�͂��߂Đ[���_�Ђ��Ղ����B���̂����̉��͎���A���Ђ̖k�̒n�ɖ������ꂽ�Ƃ����`�����̂����Ă���B��N�A���Ђ̖k�������P��(���߂���)���o�y�������Ƃ�����A���̒��ɊD�炵�������c���Ă����Ƃ����̂ł���B |
|
| ���O ���C���̐��� | |
|
��(��) �N���Ƃ��̖ړI
���āA��a����ɂ����铌���̏d�v���́A���_�V�c�̎l�����R�h���ȗ��A���悢�拭�܂������A���{�����̓����Ƃ�����厖�Ƃɂ��A�������炱�̑��͒n���ɂ悤�₭����̑哹���J���ꂽ�̂ł���B ���̌�A����ՓV�c�̕������̕���A���s�V�c�̓��C�����@���������ē����Ɏ���u�C�̓��v���C���͂���ɑO�i�����B �����āA�����̔C���A���邢�͓ԑq���̐ݒu�ɂ���ċ�̉�����A���R�̔@���v�l�̉����A���H�̐����Ȃǂ��s�Ȃ�ꂽ�B�w���s�L�x�ɂ��A���̍��͋ߋE�ȓ��̒n�́A���C���E�k�����E���R���̎O���ɕ�������A�u�C�̓��v�Ƃ��Ă̓��C���͑��̓ɂ��������đ����m���݂̏����ɒʂ��Ă����B�����āA�����̊����͑�a����̓����x�z�̗v�ł������̂ł���B�����Ȃ�A���@�g�̔h���A�����̔C���ƒn���s���▯��̕A���邢�́A�v���E����E�R�n���̏�[�A�s�錚�݂̂��߂̏����̎Q���A�~���i�̗A�����A���������a���삪�����o�c�̖ړI�������ė��p���ꂽ�B |
|
|
��(��) �܋E�����Ƒ�E���E���H
�܂��A�Ñ�̂킪���͋E���܂����ƒn���̏��������ɕ�������Ă����B�܋E�Ƃ͑�a�E�R��E�͓��E�a��E�ےÂ̌܂����������A�����Ƃ͓��C�E���R�E�k���E�R�z�E�R�A�E��C�E���C�̎������������B �̂��ɁA�����̎��������Ԍ�ʘH�́A���̏d�v�x�ɂ���āA��H�E���H�E���H�ɕ������B��H�͌R���I�v�Ղ̒n�ƒ�߁A�R�z���Ƃ���ɂÂ����ɕ{�܂ł̘H�ł���A���H�͓��C�E���R�̓ŁA����͉ڈɐڂ����n�ł���A�܂����B�J��̋��_�ł������Ƃ��l������B����ő��̎x���͏��H�ƒ�߂��B |
|
|
��(�O) �w�n�E�`�n�̐��ƍ��S��
�Â��āA�剻��N(�Z�l�Z)�ɂ́A���i�E�S�i�E�֍ǁE�ˌ�E�h�l�E�w�n�E�`�n���̐����s���A�O�Z�����ɉw��u���A�����̒��p���Ƃ��A��H�E���H�E���H�ɂ���Ē�߂�ꂽ���̉w�n���u���ꂽ�B�܂��A����Ƃ͕ʂɌS���ɂ͓`�n�̗p�ӂ��Ȃ��ꂽ�B���̂悤�ȉw�n�E�`�n�͒����ƒn���A�n�����݊ԁA���邢�͒n���Ƃ��̉����ɂ�������p�̘A���ȂǁA�n�͂��̎���ɂ�����B��̌�ʋ@�ւƂ��ėp�����Ă����B���̍��A�킪���͍��ɂ��A���E�S���z(��)����A����܂ł́A���͐�����Ƃ��āA���𑊕����A�����t�����A�O�Y�n�������q�ʂƂ��ĎO�ɕ�����Ă����̂��A��ɂ܂Ƃ߂��đ��͍��ƂȂ�A�����ɌS���u���ꂽ�B���q�S�Ƃ��Ă̌�̍����S�́A���̂Ƃ��ɐ��܂ꂽ�̂ł���B�]���č��͌S�����A�S�͗�(��)�����߁A���͑��ׂ�Ƃ����d�g�݂����܂ꂽ�B �Ȃ��A�����ŐG��Ă����������Ƃ́A�����̑��͍��{���̂��Ƃł��邪�A���̏��ݒn�ɂ��Ă͎�X�̐��������Ĉ�肵�Ȃ����A����ȑO������Ɉ�吨�͂̒��S�n�ł���A�u��ɌÕ����c���������S�C�V�������������肪�ŏ��̒n�ł͂Ȃ����ƍl�����A���ꂪ��N�́A�V�����畽�������̊Ԃɑ�Z�S�Ɉڂ�A�ē]���ė]���S�Ɉڂ������̂Ǝv����B |
|
|
��(�l) �������̓��C���ғ�
�ޗǒ������̎l�����m�V�c��T��N�̏��ɁA�u�������͎R���ɑ�����嫂��A���˂ĊC���������B���g�ɑ��A�L�����֓�B���̓��R���̉w�H�́A��썑�V�c�w��艺�썑�����w�ɒB���B����֓��Ȃ�B�����ď�썑�W�y�S���O���Č܉Ӊw���o�ĕ������Ɏ���A���L��ċ���̓��A������������艺�썑�Ɍ����B�����C���́A���͍��ΎQ�w��艺�����ɒB���B���̊Ԏl�w�A���ҕ߂Ȃ�B����ɍ�������ނɏA���A���Q�ɂ߂đ����B�b�����ʂ���ɓ��R�������߂ē��C���ɑ������߂�A�������āA�l�n���ӂ��Ƃ����B�v�Ƃ���B ����ɂ��Α��͍��́A���Ƃ��Ɠ��C���ɑ����A���̊����͈ɓ��̍��{���o�āA���͍��{�ɂ�����A�������{�ɒʂ��Ă����̂ł��邪�A�������͓��R���ɑ����Ă����̂ŐV���ɓ��C���ɑ������邱�Ƃɉ��߂��̂ł���B����́A���R���͊��g�̉������͂�����������ɁA�������{�ɏo��ɂ͏�썑�{���璷�������ɉ���Ȃ���Ȃ炸�A����ɉ��썑�{�ɒB����ɂ́A�������������Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����s�ւ����������B�Ƃ��낪���C���̕��́A���͍��̈ΎQ�w���牺�����ւ́A���̊ԕ��������̎l�w���o�R���邾���ł����B������ւ�����������ł���B �����Łw�����{�I�x���L�����͈ΎQ��艺���Ɏ��邻�̊Ԃ́u�����l�w�v�ł��邪�A�w���쎮�x�����w�`�n�ɂ��ƁA�������̉w�́A�X���E����(���s�̐��k��)�E���E�L���ƂȂ��Ă���B���̎l�w�͕������̓��C���ғ��ȑO�Ƃ��܂�ς��Ă��Ȃ��Ƃ����Ă��邪�A�����̎l�w�͌�̊��q�X���̓��ƂȂ����Ƃ���ŁA���y�ɂȂ��铹�Ƃ��āA�ɂ߂ďd�v�ȈӋ`���������ł���B |
|
|
��(��) �ΎQ�w�ƕl�c�w
���āA���̈ΎQ�w�͂ǂ��ɂ������̂ł��낤���B���̈ΎQ�w�́A�w�a�����x�̑��͍������S�ɋL�ڂ���Ă���ɎQ���Ɠ����ł��낤�Ƃ������Ƃ͒ʐ��ƂȂ��Ă��邪�A���̈ɎQ���͍��̂ǂ��̒n�ł���̂��A�ِ��̐�����Ƃ���ł��邪�A�哇�����搶�̐��ɂ��u���̈ɎQ���͍��̗L�n��(�����̊C�V���s�L�n)�̓��{���E���͓��E��͓��E���v�ۓ��×����n���Ƒ��̂��ꂽ�n��ŁA�ΎQ�w�͖ܘ_���̋����ɂ������ƐM������B�W�����n�Ƃ͉w�Ƃ̈▼�ɊO�Ȃ�ʂ���ł���B�w�V�ґ��͍����y�L�e�x�ɁA�u����ɓ`�ӁA���̒n�Ɉɐ��O���R�n�̎p�ɂČ������ӁB�˂�Č�n�̏��N���B���㍡�̕����ɉ��މ]�X�B�v�Ƃ���A������ɂ́A���얾�_�̌�����u���ꂽ������I���}�����̖��͋N�����Ƃ��`���Ă���B����ɂ�����w�Ɠ`���ł��邱�Ƃɋ^���͂Ȃ��A�]�X�Ɛ�����A�܂��A�H���E�搶�́A�u���݂̍��Ԓ�(���݂̍��Ԏs)�����̈�̂ł���Ǝv���邩��A�ΎQ�w�̈ʒu�́A���Ԏs�̂Ȃ��̌Â������̍��ԓ��J�̂�����ł��낤�B�����̑��͍��{�́A�����S�̍����t�߂ɂ���������ΎQ�w�͂��̖k����L���قǂ̂Ƃ���ɂ���A����A���{�֖̊�ɂ������Ă����킯�ł���B�]�X�v�Ɛ�����Ă���B �܂��A�X�ɕl�c�w�ɂ��Ă����l�ŁA�w���쎮�x�̕������ɋL�ڂ��ꂽ���͍������S�̕l�c�w���ǂ��ł��������ɂ��ẮA���܂�������Ȃ��A���ԕt�߂Ƃ�����A�C�V���̎��l�c�̒n������Ƃ�����A�܂��A�w���ɇ��l���̎������Ă���Ƃ��납�瓡��t�߂ł͂Ȃ����Ƃ����������B |
|
| ���l �J�y�̓� | |
|
�ł͂��ɁA�ޗǎ���ɂ����铌�C���Ƃ��Ă̑��͍����̓��ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���B
���̑O�ɁA���m�̒ʂ�ޗǎ���́A���㎵�Z�]�N�Ƃ�������߂ė��j�I�ɂ͒Z�����Ԃł��������A���S���ʂ��獑�͂��[����������ł������B�s�ɂ͓��厛�����̗̈e���ւ�A�����ɂ͍������E�����������Ȃ�сA�܂��A���w�̖ʂł́w�Î��L�x�E�w���{���I�x�ɂ��Łw���t�W�x���I�q���ꂽ�B �������A���ꂾ���ɗ����ł́A�l�X�͍��ƓI�Ȏ��ƂɘJ������āA���̓I�ɂ����_�I�ɂ��ꂵ����ł������Ƃ������悤�B ������������̔w�i�̒��ŁA���͍��ɂ����鍑�����̌����́A���C�����哹�Ƃ��āA�ߋ��ߍ݂͂������A�����l����蕨�����^��A���g�͉������A�܂��A�V��j�����킸�A�J���ɒy���Q����l�X�œ��킢�A�J�y�̓��́u�������̓��v�Ƃ��ĉh���A�]���̓��C���͍X�ɔ��W�������̂Ǝv����B �܂��A����ł͎��m�̂悤�ɁA���̎���͊֓������ɂ����ẮA�������h�l�Ƃ��āA�C�n�ɕ���������ł��������B �������̊ېQ(�܂��)�� �R�₦�� ��(��)����ƕt���� ����̐j��(�͂��)�� ���͓̉̂����A���̒n���͍�����h�l�Ƃ��ĔC�n�ɏA�������̂̍Ȃ�����̂Ƃ����A���t�W�ɂ̂����Ă���̂ł��邪�A�킪���y�����肩����A���̖h�l�ɑI�ꂽ�҂��������Ƃ����Ă���B�J�y�̓��͂܂��A���悫�ŕR���ꂽ��A���̐j�ŖD�����܂��ƁA�₳�������̂����Ȃő���o�����u���t�̓��v�ł������Ƃ������悤�B |
|
|
��(��) ���͍����̓���
���āA���������z����ƁA���{�����̂���́A�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�����̏㗬�̎R�k�t�߂œn�͂��A��q��Ó�������ď��c�y�̂ɒB�������̂Ǝv��ꂽ���A���̎���ɂ͂��łɁA�����̔×����̗��n�����i��ł����Ǝv����̂ŁA��q��A��ɂ����Ċ֖{(�w���쎮�x�̍�{)�ɏo�A�������瓌�k�̊��c�_�Ђ̂��鏼�c�y�̂ɏo�����̂ƍl������B���c�y�̂����̓��ւ̓��́A���ցE�O�m�{�E�������E����E�юR�ȂǁA���{�����̎���̌Ó��Ƃقړ����ł������Ǝv���邪�A�юR����́A�����̓��ƕ�����A�قڐ^���ɐi�݁A���˒m�̂�����ő��͐��n��A���Ԃ̓��J�ɓ���A�쉺���āA���{�ɒB���A����E�����E������߂��āA����������(���̏����́A�펞�����؍q����ݒu�̂��߁A�������̂���č��͂Ȃ�)�̂����k��ʂ�A���n��̐����n���A�ØV�̓`����u���Ƃݍ�v�t�߂����A���y�[���_�Ђ̖k�̓m(����)�ɒʂ������̂Ǝv����B�������߂��A�����n��ƌ������͂������J�ŁA�������畐�����ւƒB���Ă����ƍl������B �Ȃ��A���́u���Ƃݍ�v�ɂ��āA�ØV�̓`����Ƃ���ɂ��A�����A���̕ӈ�т͟T��(��������)������ɂ�����ꒋ�Ȃ��Â��A���̏ス�܂���ʂ��ꂽ�}�ȍ⓹�ł��������߂ɗ��l���͗҂����̂��܂�A�u���Ƃ�����ȁA���Ƃ����Ȃ��ŋ}���ł��̍��ʂ蔲����B�v�ƌ����ꂽ��̒n�ł������Ƃ����B ��1 �X���w�̈ʒu �Ƃ��낪�A�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�X���w�̏��݂ł��낤�B���R���g�搶�̌��ɂ��A�u���J�͍O���ܔN�㌎�\�����A���@��l�����˂𗧂��Ēr��Ɏ���̓r����h�������ŁA���A���O�̖��ɁA�ΐ�`����������藈��ĐV�c�`��̐w�ɒy�Q�������ł���B�X�ɓV���N���ɂ͉w���݂̐������������Ɖ]�ւA�×����̒n��������ʂ̗v�H�ɓ����ċ������Ƃɋ^�͂Ȃ��B�w�V�ґ��͍����y�L�e�x���ڂ̓`�n������ȂĐM���Ƃ�ׂ��ł���B�]�ӁA�]���J�������c���`�n��D���ًV�o�V�Җ�B���팭��p�B��А����E�h���B(�k������)�v�Ɛ�����Ă���B ���̂��Ƃ���l����Α����w�ԋ����ɖ�肪����ɂ���A�X���w�������A���J�ɂ������Ƃ����������藧�̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��A�X���̋N��ɂ��Ă��A����́A�~�Z���Ɠǂ݁A�㐣�J�E�����J�E�����J�𑍂����A�O���J�̈ӂł���Ƃ̐�������B������ɂ��Ă��A�[�����琣�J�ɒʂ������̓��́A�������炷�łɏd�v�Ȉ�̘H���ł��������Ƃ͈٘_�̂Ȃ��Ƃ���Ƃ����悤�B ����A�H���E�搶�́A���̓X���ɂ��āu�ޗǎ���ɂ����Ă��A�����炭�������̓X���ł����āA�X���́A�}�`���Ƃ�݁A�w���쎮�x�ɂ����镐�����l�w�̈�ł��邪�A���ݓ����s���c�s�̂����A�ߊԂ̖k�̕����ɒ��J������̂����̈�̂ŁA��������A���c�{���E���t�E����H���o�āA�˕t�߂ő������n��A����̗��ɓ����ĕ������{�ɒʂ����̂ł��낤�B�v�Ɛ�����Ă���B �����A�������Ƃ���ƁA�l�c�w���瓌�ւ̓����A���̂��ƁA�O�ɏq�ׂ����Ƃ͈قȂ�A�r���́A����E���n��̐����n������̖k���番����āA���s�����̖k��ʂ�A���ߊԂ̏h�������A�������璬�J�ɒʂ��Ă����Ó�(��̑�R�X��)���������痘�p����Ă����Ƃ��v����B �����ŁA�l�����邱�Ƃ́A�킪���y��ʂ邱�̓�̓��́A�����炭�A�������łɕ����I�ɔ��B���A���s�҂̏��p�̖ړI�ɂ���Ă��ꂼ�ꗘ�p����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A�������A�[�����ɂ́A�u���͂̌ÎЁv�Ƃ�����[���_�Ђ�����A����������Ę_���邱�Ƃ́A���Ȃ����̂Ǝv���B ��2 �[���_�ЂƌÓ� ���͂̐_�Ђƌ�ʘH�ɂ��čl���Ă݂�ƁA�����Ђ̂قƂ�ǂ��A�Ñ�̌�ʘH�ɖʂ��Ă������Ƃ��킩��B���̂��Ƃ́A��������h�_�̔O�ɂ����������s�҂́A���̗��s�̓r��ŁA�_�Ђɏo����Ȃ炸�Q�q���āA���̊댯��s���������A�O�r�̈��S���F�������̂Ǝv����B �܂����i�����̊NJ����̍�������������Ƃ����A�����̊��g���n���ɉ������������A�����Ƃ����ł������ƍl������B �������l�����킹��ƁA���{�ɋ߂����y�̐[���_�Ђ́A��N�w���쎮�x�̏\�O���ɉ�������قǂ̊i�������Ђł����Ă݂�Έ�ʁE���g���킸�����ȎQ�q�҂����������̂Ɛ��@����A���{����[���_�Ђɒʂ������̌Ó��͓����A��v�Ȋ����ł������Ǝv����B �K���A�����ɖ{�N�ꌎ�u��R���v�Ƃ��Đ[���_�Ђ̋����Ɍ��Ă�ꂽ�ꕶ������̂ŏЉ�Ă��������Ǝv���B ��R�� ��Ր_ ���P�Ɛ_ ���䖼���_ �� �� �㌎�\�ܓ� ���_�Ђ̑n�n�͌Â��������y�L�ɂ��������ܕS�N�O�Y�_�V�c��\��N�O���n�ՂƂ��蒩����̎����L����Ă���B�������쉓�߂̐��h�Ă������̎Ђł����������m����B ���̌㊺���V�c�̌܌����n�ߗ�㍑�i���̎�������X�ɑ��V�c�̌��ɐ��肳�ꂽ���쎮�_�Ж����ɑ��͍��\�O���̎Ђƒ�߂�ꊯ�ЂƂ��Ĉ���ꍑ������ꂽ�B ���N�̌�N�Ղɂ͐_�L���̕����ꂱ�̒n���y���M�̒��S���Ȃ��Ă����B �㐢�������E���c���k���E���c�M�����n�ߏa�J���i�d���E���c���̐M�����ɓĂ����쎞��Ɏ����Ă͊��{��{�����q��d���E���Е�s��{���L�d���͂����ΎQ�w���Гa���c�̂��Ɩ��З̊�i���×����啐���̐��h�͓A�d������߂���̂��������B �����Z�N�\�������z���ɂ�苽�Ђɗ�ꂽ�������N�גn�������̉ЂɗޏĂ����ނȂ�Гa�H�앨�������Ď������B �����l�\��N�����z�K�Ђ����J���z�K�Ђ̍Ր_�͓��Ђ̑��a�ƂȂ����B ���a�\�Z�N�\�ꌎ���Гa���Č����ꂽ������a��\�N�\�_���w�߂ɂ��_�Ђ̍��ƊǗ����p�~���ꌻ�݂͐_�Ж{���ɑ������̒n�����߂̐��h�҂���_�����h����Ă���B �N�� �x����� ���a�\��N�ꌎ �Ȃ��w���͍������u�x�ɂ��A���J�Ɏ���L���Ƃ��Ď��̂悤�ɏ�����Ă���B �u�w�H�͑�Z�S���։w��舤�b�S���b�̕ӂ��o�A���͑������͐��n��ĕl�c�w�ɓ���A���{�ɒB���A�X�ɏo�łĐ[���E���J���߂��s�}�S�ɒʂ����̂ł���B���Ó��͕l�c���A�ʼnz�E�l�\��E����z�Ƒ����č����`�(��������)�𑶂��Ă���B�v �X�ɕt�L�Ƃ��āA�u�l�\��͍����a�ƂȂ��ċ͂Ɍ`瑂��~�ނ�ɉ߂��ʂ��A���ۉ����}�ɗ�R�Ɖ悩��Ă��������A�����͏���v�̓��H���Ȃ��Ă����ƒm����̂ł���B�X�ɌØV�̓`�ӂ鏊�ɂ��A���̂͂����Ɋ֖�݂̐������āA�K�l�\�����l�n�̒ʉ߂��������Ƃ��ӁB�×��̌�ʂ��E���̂ł���B���������͕����ʂ�A�������ۂ��đ��H�����C�߂��▼�ł���Ƃ��ӁA�܂��R���������̗̂l�ɍl������B���Ɂw�Õ��y�L�c�{�[�����̏��x�ɁA�y�Y�Ƃ��ĕ��E�V�����ڂ��A�ؗނ͊��g�̉�����҂��đ����ɏ[�ƋL���Ă�����A����ʎj���̌����ӂɑ��炤�Ǝv�͂��B�v ���̂��Ƃ��炷��A���y�[�����́A�O�ɏq�ׂ��悤�ɁA�������H�Ƃ��ďd�v�Ȗ������ʂ����Ă�������łȂ��A���̒n�ɎY���鋛�ނ́A���g�ɍ��o���ڑҗp�̎Y���Ƃ��āA�ɂ߂ďd�v�Ȗ�ڂ��ʂ����Ă������Ƃ����L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ��3 ���̑��̌Ó� �ȏ�́A�����̑��͍��̎�v�������H�A���Ȃ킿�A���C���̎哹�ɂ��Ď�X�q�ׂĂ����̂ł��邪�A����ȊO�ɂ������I�A���邢�͒n���I�Ȏx�����e�n�ɂ��������̂Ǝv����B ���ł��A��r�I�d�v�Ȏx���Ƃ��āA���c�y�̂���쉺���A���Ɏ���A�����w�o�R�ŊC�݂�ʂ�A�]�����疥�։w�ւƔ����铹�H�����łɗ��p����Ă����悤�ł���B�܂��A����Ƃ͕ʂɁA�C�V���s�́w���y�̎j���x�ɂ́A�u�����͑�Z�S�̖��։w��芦��̓n�Â�g���č����S�{���̈ΎQ�w���o�đO�L��J�l�c�w�Ɏ���A������萣�J�̓X���w�ɏo�āA���Í݂̏����w���o�đ������n���ĕ�����艺���ɒB�����̂ł���B�v�ƋL�邳��Ă���B ����ɂ��A���͐�̓n�͒n�_�́A�����̒��˒m�̒n�_���͂邩�ɓ쉺���Ă��邵�A�܂��A�ØV�̘b�ɂ��A�u���V�c�ɂ͉��c�X���Ƃ����鋌���������āA���ڂɌ��̓�[���c���爼���n���ĕl�c�w�ɒB���Ă����v�Ƃ������B ���̂悤�ɊX���́A�͐�ɂ䂫�킽��ꏊ�ł́A�ǂ����Ă��O�Ղ����G�ƂȂ��Ă��܂��B����́A�͐삪����ɂ��A�����ɂ��A�V�Ђɂ�蕣�����������ς��Ă��܂�����ł���B�������A�X���͂��̐v��������l�����蒼���I�ł��邱�Ƃ��]�܂����͓̂��R�̂��Ƃł����āA���̂��Ƃ��炷��A�������łɁA���։w����ʂɈΎQ�w�E�l�c�w�ւƌ�������v�̊X�����ʂ��Ă����Ƃ������Ƃ��l�����Ȃ����Ƃ͂Ȃ����A�����A���ϑw�n�т̉��[�������Ă������C���A���̍��A�ǂ̒��x�܂Ō��ނ��A���ꂪ�܂��A�ǂ̒��x�n�͂ɕւ�^���Ă��ꂽ�������ƂȂ낤�B ���ՂȔ��f�͂ł��ʂƎv�����A�����炭�A���������Ȍ�̂��Ƃł͂Ȃ��낤���B�Ȃ��A������d�v�ȌÓ��Ƃ��āA�L���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ɁA�㑐�����瓡��Ɏ���A����A���y���k�ɏc�f����x�����A�Â����炠�����Ǝv����B���̓��͌�̑�R�X���Ə̂��铹�ƈꕔ��v����ƍl�����A�㑐��������n��̓������ɏa�J�E�Z����o�ē���ɒB������̂ŁA���ꂩ��͑�́A�����̓��������ǂ��Ċω���ɏo�����̂Ǝv����B ���̓��͂܂��A���q����ɓ���A������̓��A����̐������ɋ������𑖂銙�q���ƕ���ŁA�����q�|���q�ԁA���邢�͏���H�̕{���|���q�Ԃ����ԊX���Ƃ��āA�㐢�܂Őe���܂ꂽ���ł������悤�ł���B |
|
| ���� �����̓� | |
|
�����̐��́A�܁Z�㊺���V�c���s�����s�ɑJ���Ă���A���v�O�N�A�����������q�ɖ��{���J���܂ł̎O��Z�N�Ԃł���B���̎���̍����̐��̑傫�ȕω��Ƃ��ẮA���ߑ̐���������A�M���ꐧ�̐��������܂�A���c���ɑ���āA����ȏ����̔������݂����Ƃł���B
���̌��ʁA�y�n�͍c���E�M���E���Ђ𒆐S�ɏW���������A�₪�āA���̎��ۏ�̊Ǘ��҂ł���n�������𒆐S�ɂ��āA���m�K�������܂�A�����̕��m�͒��������̎x�z�҂����т₩���Ă���������ł���B ���āA������������̗���́A�킪���͍��ɂ��傫�ȕω��������炵�����Ƃ͓��R�ł���B���ɁA���̎�Ȃ��̂ɂ��čl�@���Ă݂悤�B �O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�ޗǎ���̔ɉh�́A���ɕ����𒆐S�Ƃ������Ƌ������̂��̂ł��������A���̎���ɂȂ�ƁA���͍��������n�߁A���̑��̎��@�����A����̎肩��͂Ȃ�āA�����͕���̏����Ɏ��߂��A����ɉ����āA���������̓V�ϒn�قƁA�헐�ɂ���đ��͍��������n�߁A�e���@�́A�������邵���������A���ނ����B �܂��A���̎���ɂȂ�ƁA�����Ă̑剻�̉��V�̐��x�͑S�����Ɖ����A�����̔��B�ɂ�A�����w�i�Ƃ��āA�n�������ɐ������Ă��������A���Ȃ킿�݉Ƃ̗̎�w�́A�����̑������܂ޑ����̏��L�҂ł���M���w�ɁA�Η��ł���܂ł̎��͂�{���A���̌��ʂƂ��āA���̒������ɕ��m�̓��̂������Ă���悤�ɂȂ��Ă����B �킪���͍��ł́A���J�E�`��E�����E�]��E�a�J�E�L�c�E�ї��E��]�����́A���l����o�ĕ��m�̓��̂ɂȂ��đ������x�z����悤�ɂȂ����ҒB�ł���B ���ł��A�a�J���͂��ƕ����̏o�g�Ƃ����A���y�̋��[���n����̗L�������l�ł���B�V�c�̗��ŁA��������Č��т̂��������Ǖ��̎O����̑��̊�Ƃ́A���܂̐��s�ɔC���A�a�J���̏��i�Ƃ��Ď�����U�����Ƃ����Ă���B���̎q�̏d�Ƃ́A���̂��Ƃ��������A���̎q�̏d�����A�a�J���ɏZ��ōݖ����ƂȂ��A�a�J�d���Ɩ��̂����B ���̌�A���̎q���͏a�J���̊e�n�ɕ��C���A�����̑���E�g���A�C�V���̑�J���A���̒n�������ꂼ�ꖼ�̂��āA�������S��т����̔z���ɂ����߂��Ƃ������Ƃł���B ���ɁA���{���ɂ��Ăł��邪�A���̎���̍ŏI�̒n�͑O�ɂ��q�ׂ��ʂ�A���{�{���ł���A�����A�암�C�ӊ��Ɉڍs�����������C���Ƌ��ɐɎ�̊������̂ł���B �܂��A�����̐_�Е��t�̊W�ɂ��ďq�ׂ�ƁA�×������Ƃ͕ʂɁA���{�l�ɂ͌h�_���c�̔O�͋ɂ߂Đ[���A�������x�Ƌ��ɔ��B���u���̐_�v�𒆐S�Ƃ��āA������Ղ鎁�����c�������B�܂��A����Ƃ͕ʂɌ܍��L�����F�O���邽�߂́u�Y�y�_�v���J�邱�Ƃ����������B���̂��߁A���̓�̂��̂��A�_�Ќ`�ԂƂȂ��čՂ�ꂽ�B�����Łu���͌ÎЁv�Ƃ����鎮���Ђɂ��āw���쎮�x�̐_�����ɍڂ����Ă�����̂�������ƁA�_�Ђ͑召�����ď\�O�Ђ��L�^����Ă���B ���͍��\�O�� ���� ���\��� �����S��� �� ���c�B�� �]���S��� �� ����_�� ��Z�S�l�� �� �O���_�� �� �������_�� �� ��䑽�_�� �� ���v���_�� ���b�S��� �� ����_�� �����S�Z�� �� ����_�� �� ���_�� �� �[���_�� �� ���s��m�_�� �� �L���_�� �� �Ώ|���T�� ������݂�ƁA��������A�����̍��{�ɋ߂��A�܂��A���z��Ԃ��炷��A��͑�R�R��̘[�ł���A���̈�͑��͐�̓����̑�n�ɂ܂Ƃ܂��Ă��邱�Ƃ��킩��B����A���@�Ƃ��ẮA��R���E���V(������t)��������A���̎��@(�_�����E�ʑT���E���Ԏ��E�e������)�ƍl�����킹��ƁA�������ɁA���@�͕��n����R�x�n�Ɍ����̌X�������������̂Ǝv����B �Ȃ����̎���̑��͂̓��ɐ݂���ꂽ�ւɂ��Ăł��邪�A���m�̒ʂ�A���B�̖��o�w�̍ہA���`�����L�����H��♂̔�Ȃ�`�����n�Ƃ��ėL���ȁA������(���V�c�A���ד�N�㌎�����A��������)������B |
|
|
��(��) �����H�Ɠ�̌�ʘH
���āA�������̓��ł��邪�A�����ɓ����ĊԂ��Ȃ��A������N(���Z��)�ɁA�x�m�̑唚��������A�]���̓����͂��̍��I�ɂ���āA�ꎞ�ӂ�����Ă��܂����B���̂��߁A�n�߂Ĕ����H�����܂�A�����ɁA�����������Ό����o�č�{�w�ɒʂ��铹���J���ꂽ�B �������A�]���̑������̓����A�Ԃ��Ȃ���������A�����Ƃ��Ă̎g�p�͔p�~����Ă��A���̂܂܁A���͍��ƈɓ����Ƃ����Ԍ�ʘH�Ƃ��āA��ʂ̗��s�҂́A����𗘗p���Ă����B �܂��A���̍��ɂȂ�ƁA���C���Ƃ��Ă̑��͌Ó��́A���C�̌��ނ⍑�{�̈ړ����������āA��H���������邵�����B���A�w���쎮�x�̎���ɂ́A���͍����̊����́A���̖ړI�ɂ���āA�k�H�Ɠ�H�̓�̓������ꂼ�ꗘ�p���ꂽ�B ��1 �k�̌�ʘH �܂��A�k�H�ɂ��ďq�ׂ�ƁA�����H���z����ƁA��{�w�ł���B ���̍�{�w�́A���̓쑫���s�֖{�̋ߕӂł���Ƃ����A���������̉w�`���ɂ��āA�w���쎮�x�ɂ͎��̂悤�ɋL�ڂ���Ă���B ���͍� �w�n �{ ��\��D�B �����E���ցE�l�c �e�\��D�B �`�n ����E�]���E���� �e�ܕD�B ������݂�ƁA��{�͉w�n�̐������D�ƂȂ��Ă���A���̎O�w�͂���������D�ŁA���̐��͍�{�������������Ȃ��Ă���B����́A�����A��Ƃ���ꂽ�������ɑ���z������Ȃ��ꂽ���R�̏��u�ƍl�����邪�A�܂��A�k�̖��ւ��痈��ҁA��̏����w���痈��ҁA���̓�҂���������n�_�ł��������߁A�n�̐����⋭����K�v�����������̂ƍl������B ��{�w���疥�։w�ւ̓��́A�O�ɏq�ׂ��ޗnjÓ��Ƃقړ����ŁA��{�w���瓌�k�Ɏ�����n���ď��c�y�̂ɍs���A�l�\�����̐�ɂ����Ėk���ɐi�݁A�������瓌�ɁA�`��E�P�g�����o�Ė��։w�ɒB�������̂Ǝv����B���։w���瓌�ւ̓��́A�O�m�{�̍��{�ɏo�ĉ�������ʂ�A�������_�Ђ̂�������߂��A��������́A�ȑO�̏���E�юR�E���˒m�ɒʂ���Ó��͒ʂ炸(���̎���ɂȂ�ƁA�ʘH�͑啪�����I�ƂȂ�)�����E�Γc�E���b���o�Č��ɓ���A�����ő��͐��n��A�Ί݂̉͌����ɏo�����̂Ǝv����B���̑��͐�̓n�͒n�_�́A�O�Ɂw���y�̎j���x�ŏq�ׂ��n�_���͏����k�Ɉʂ���Ǝv���邪�A���̍��ɂȂ�ƁA���͐�̗���̑啔�������n������A�n�͂��邱�Ƃ���r�I�e�ՂɂȂ��Ă������̂ƍl������B ���������āA���͐쉈�݂ɂ͕K�v�ɉ��������H�ɐ�(������)���āA�����ɓn�͂̏ꂪ�J���ꂽ���̂Ɛ��@�ł���B���ꂾ���ɂ܂��A���̎���ɂȂ�ƁA�����Ǝx���Ƃ̊W�����G�����ꏔ�_�̗N���Ƃ���ƂȂ����̂ł��낤�B �ł͂��ɁA���̍�������ɐ݂����Ă����Ƃ����鑊�͐�̓n�͒n�_�ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���B �������̒n�_ ��˒m�E�E�E���� ���B�����q�n�������R���v���_�ЂɎQ�w�ɗ����R���ŁA�����h�Ə�˒m�ɂ�������́B��������d�v�Ȍ�ʘH�ł������Ǝv����B �����P���̒n�_ ���P���E�E�E�镔 ���{�����̓����H�ƂȂ��Ă���Ƃ���ŁA��ɑ�R�e���҂Ƃ��ė��p���ꂽ�B �����˒m�̒n�_ ���˒m�E�E�E���ԐV�c ���̒n�_�͓ޗnjÓ��̊������H�Ƃ��ė��p���ꂽ���̂Ǝv����B�Ȃ��A�V�c�Ƃ����n���������悤�ɁA��ɔ_�k���J�����Ƒ����̔_���Ƃ��Ă����p���ꂽ�B �����˒m�̒n�_ ���˒m�E�E�E���Ԏl�J �Â�����A���˒m�����c�̓n���ɂĔ��c�ɒʂ��юR�ω����������ł���B��ɍⓌ�ω�������鏄�瓹�̈�ƂȂ��Ă���B �����̒n�_ ���E�E�E�͌��� �����k�H����������n�_�ŁA���C���̊����Ƃ��āA�܂��A��q�ɒʂ���d�v�Ȗ������ʂ������Ƃ���Ǝv����B�w�V�ґ��͍����y�L�e�x�ɂ͑D�ܓ��n�D���u���Ƃ���㐢�܂ł��̏d�v������Ă���B�܂��A�X���͏h�����Ɍ�������Z�S���c���Ǝ��䑺�̍��萼�Ɍ������Ă���B �����c�̒n�_ ���c�E�E�E�Љ� ���̒n�_�́A���̌˓c�̒n�_�Ƌ��Ɂw���y�̎j���x�ł����A���C���̊����ƍl������Ƃ���ł��邪�A���Ɍ������đD�q�ɏo�Ē��J�����A��R�X���e���҂̈�Ƃ��āA�㐢�܂ŗ��p����Ă����悤�ł���B ���˓c�̒n�_ �˓c�E�E�E��� ��ƌ˓c�ɂ������R�X���̗v�H�ŁA��ɁA�˓c�̔�����肱�̓��ɓ���n�_�ƂȂ����ꏊ�ŁA�L�d�́u�˓c�̓n�v�ŗL���ł���B �ȏオ��̓����̑��͐�n�͒n�_�Ƃ��̌�̗��p�̖͗l�ł���B �����Ŏ��͍ēx�A����Ɋ֘A���铖���̑��͐�̓n�Âɂ��āA��l�̌�����A���̍l�@�̎肪����ɂ������Ǝv���̂ł���B �w���͍������u�x�ɂ��A�u�������͂̓n�ẤA�{��(�C�V����)���V�c�ƁA�Ίݑ��쑺���c�Ƃ̊Ԃɂ������ƍ����`�ւċ���B���V�c�ɂ͌��ɉ��c�X���Ə̂��鋌���̖��c���~�߁A�l�c�̕����Ɍ��ЂĒʂ��ċ���B���b�͈��͂̋`�ł���Ƃ��ЁA���̕����ɑD�q�̒n���𑶂���Ȃǂ����n�ÂƂ̊W���Â��̂ł���B�͎̂O�Y����̎q���Y���p�����̑��쑺�ɔC���Ĉ��͎����̂��A���������𑊐�Ə̂���̂������ċ��R�ł͂Ȃ��B ���a��N�Z����\�Z�������������āA���̓n�Âɕ������˂���ꂽ�B���̊������_�ɓ��� �ꕂ�@�B �x�͍��x�m�� ���͍����� �E��́A�����r���A�n�D������A���Ґl�n���v�s�����A��������B�@���A�����́A���C���V�v�H��B���n�D�����A�������s���B����䢍v���W�v���W��͕ӈ�A�ݓ��o�{�s������n�B��B�ލ������A��������B�g���탌�Q�A���������B�鉺����m������a�����m�B���Z�� �m�����˃����ߒ��C����u�ǎt�A���i�������Z�A�������ȓ�}�~���[���V�A���V��A�u�ǎt�ȓF��ꑊ���C���A�s�������ߓ���B ���L�B����{�n�������ɂ́A���̕����������̓n���ɂ������Ɛ����Ă��邪�A����͉��N�����ɕ����Ɩ��Â��鏬����������������t������ɉ߂��Ȃ��̂ł���B�v�Ƃ���B ����ɂ��A�������C���̗v�H�Ƃ��đ��͐�ɕ������˂���ꂽ���ƁA�܂��A����Ɋ֘A���鎖�����ɂ��Ă͂킩����̂́A���̓n�Â̒n�_�ƂȂ�ƂȂ����͂���悤�ɍl������B ���āA�b��O�̌�ʘH�ɂ��ǂ��ƁA���͈ꉞ���̓n�͒n�_���͌����Ƃ��A��������v�������H�ƍl�����̂ł��邪�A�m������ꂽ�킯�ł͂Ȃ��A�����A���c�̍��ɂ͊��ɍ��{�����ɑJ����Ă����ƍl�����邵�A�w���쎮�x�ɂ��ΎQ�w�̂��Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�g�͂̏������������A�X���̐v�������炢���āA�撼���I�ƂȂ�̂ŁA���̕ӂ�ł͂Ȃ����ƍl����̂ł���B �͌�������]���̌Ó��𓌂ɐi�߂A���y�̐[���_�Ђɏo�邪�A���ꂩ���̏����ւ̓��͓ޗǎ���Ƃقړ����ł������Ǝv����B �����A�����ŋL���Ă��������Ǝv���̂́A����̑J��ς�Ƌ��ɕ������{�ւ̓��́A���̐[���o�R�̓���ʂ炸�A����ɉ��ߊԌo�R�̊X�������p�����悤�ɂȂ����Ɛ�������邱�Ƃł���B ��2 ��H�̌�ʘH �ł́A���ɓ�H�ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���B�����ŁA�܂��A��{�w���珬���w�ւƒʂ��铹�ł��邪�A���̎���̓��ɂ��Ă͑O���ƌ���ɕ�����A��̓����l������Ǝv����B���Ȃ킿�A�ޗǒ��̖������畽���O���ɂ����ẮA�����炭�A���֖̊{���珼�c�y�̂܂ŁA�ȂȂ߂ɓ��k�ɐi�݁A������n��A�]���u�˂̐�����쉺���āA�����Ďt�����̍������݂̒n�Ƃ��������ʂ�A���w�ɒB�������̂Ǝv����B �Ƃ��낪�A������������ɂȂ�ƁA�k�̏��c���o�R����Ƃ����I��̓���ʂ炸�A���̍����łɗ��n�����������A����쉺���n��𗘗p���A��{���璼�ړ���Ɍ����Ēʍs���A�ѐ�̑Ί݂�����Ŏ�����n��A�ѐ���A�����w�ɒB�������̂Ǝv����B ���ɂ́A�l����̓��V�c�̍����Ă�ꂽ�Ƃ�����A�|�펛�̊ω��������������A��������ɂȂ��āA���̔ѐ�Ɉړ]�������̂Ƃ����Ă���B����́A��オ��v�̌�ʘH�łȂ��Ȃ�A���т���������߂ɁA�V���ɊJ���ꂽ�ѐ�Ɉڂ������̂Ǝv���A�����̌�ʘH�̕ϑJ�����̂Ƃ����悤�B ���āA���̏����w���瓌�ւ̓��́A���������C�݂ɂ����Đi�݁A���ؐ��n��A�Z���_�Ђ̂���]�����{�ɒB���A��邩��͂��k���̕����ɓ����Ƃ�A�Ԑ����n���āA���˂̑O���_�Ђɏo�A�����o�āA����ɒB�������̂ƍl������B�H���搶�́A���̍��́u�l�c�̉w�v�́A�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�l�̎������Ă���̂ŁA���̓���̊C�݂ɋ߂��Ƃ���ɂ������̂ł͂Ȃ����Ɛ�����Ă���B �Ƃ���ŁA���瓌�ւ̊����ł��邪�A����͋���ɂ����ēX���w�ɏo�A�]���̕������ւ̓���ʂ������Ƃ��l�����邪�A�w���쎮�x�̂���ɂȂ�ƁA������̖���̓n�D�ݔ��₻��ɔ������H�̐������s����悤�ɂȂ��āA���͒��ړ����p���ݒn�т�ʂ�A�����铌�R�E���C�����̘A���Ƃ��āA���͂Ɖ���A�܂��͏헤�Ɖ��B���ʂ����ԘH�Ƃ��Ĕ��B�����悤�Ɏv���B�܂��A���̌o�H�́A�h�l�����ɂ���āA���Ȃ�Â����痘�p����Ă����Ƃ������Ă���B ��3 ��H�̔��B �ȏ�A���̎���̓�k��̓��ɂ��ďq�ׂĂ������A�����̓��́A���ꂼ�ꏊ�p�̖ړI�ɂ���ė��p����A���͍��{�A�܂��́A�������{�ɊW�̂��銯�g�͖k�H��ʂ�A�܂����́E�����̍��{�ɂ͗p���Ȃ��A�����E�㑍�E�헤�Ȃǂ̍��{�ɍs���ҁA�X�ɂ܂��A�����̍����璼�ڏ㋞����҂͓�H�𗘗p�������̂Ǝv����B �����A�����������Ȍ�ɂȂ�Ɖw�n�̐����p�ꂽ���A����������̂́A���X�̎��Ђ⍋���𗊂��ĕX�Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ւƓ]�����������̂ŁA���܂܂ł̂悤�ɁA��肵�����Ƃ������̂͂�����A�����͑傫���ω��������̂Ɛ��@�����̂ł���B ���̂��Ƃ́A�������N�A�����F�W�̏��̋L�����A�w�X�����L�x�ɂ�����A�ϑJ�������C�����悭���i����Ă���B�܂��A���̓��L�ɂ́A����A�w�Ƃ̂��Ƃ�������Ă��Ȃ����Ƃ��A����̐���(��������)�����̂Ƃ����悤�B ���̂悤�ɂ��āA�����Ă̑��͍����C���́A���N�̂��������͏����A���͎���ɓ암�n��Ɉڂ�A�₪�āA���q����ɋy�ԂƁA���q�𒆐S�Ƃ��Đ��ւ̌�ʘH���J����A���܂܂ŌÑ㓌�C���̊����Ƃ��ĉh�������y��a�ɂ�����ɕς��āA�������̊��q�X�����J����邱�ƂƂȂ�̂ł���B |
|
| �������� | |
|
��R�X�� �ƂԒ��� �O�̖� ������
�H������Z ������� �ܗt�� ��Ȃ� ��̖� ��̖� �E�E�E �E�E�E ���͖�ɐ��܂�A���͖�Ɉ�������́A�q���̍��A�^�Ԃɗ[�Ă����X���ŁA�z�����v���̎R�ɗ�����܂ʼn̂��Â��������̇��͍����Y��Ȃ��B �܂��A���̂���A�c����c�ꂩ�畷�����ꂽ�Â��X���̖��₻��ɂ܂��̘b���A�������o���Ă���B����́A�삠��A�J����A�G����A������́A���t��~���߂��悤�ȍׂ��a��A�[����ʂ��ꂽ�҂����⓹�ŁE�E�E�B�q���S�ɂ��A�������̉����c��̐l�X���A�����ɋv�����Ԃ��̓�������Â��Ă����̂ł��낤���A�����āA���̓y�n�Ƃ̈����̐[�����v���ɂ��A���y�ɑ���傫�Ȉ����������Ă����̂ł������B ���ꂪ�킸���O�Z�`�l�Z�N�̊ԂɁA���y�͒������ϖe���Ă��܂����B���j�Ƃ������̂́A�����ꖬ�̂Ȃ���������ĕϓ]���Ă������̂ƕ�������Ă��邪�A����قǁA�}���ȃe���|�ŕϓ����ɂ߂�����͉ߋ��ɂ������ł��낤���B �����ɁA���͂��̏������N�e����ɓ�����A���Ȃꂽ�X���̂��鑺����������̂ł��邪�A���߂悤�Ƃ��鏿�a�͂Ƃ����A���ɋ����Ă��ꂽ���̂́A�����I�Y���ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�A����̗���̑傫���ω��݂̂ŁA�l�n�̒ʉ߂��������×��̌�ʘH�͎ÂԗR���Ȃ������B ���R�A�Ñ�Ƃ��Ȃ�A���Ƃ��܁Z�N�E��Z�Z�N�ȑO�ł������Ƃ��Ă��A�����̊X�������̂܂܂̎p�ł��낤�͂��͂Ȃ��̂����A�������琶�܂�A���x���̎���̕ϑJ���o�āA�g�߂Ȃ��̂Ƃ��Đe���܂ꂽ�A�q���̂���̌Ó������߂āA���̂܂܂̎p�ł������Ȃ�Ɗ肢�A����ł͂܂��A�����Ñォ��̕����I��Y�̏�ɑ������ꂽ���݂̌�ʘH�̎��ւ����A���܍X�̂悤�ɋ��x�����S�̖������ւ����Ȃ��̂ł������B �K���A��l�̋Ɛт�A�ߋ��̕��̋��y�I�����������Q�l�ɂ����Ă��������A�܂��A�ØV���y�m�l�̕��X�̂����͂����Ȃ��炸�����������Ƃ��ł��A��w�Ȏ��ɂƂ��ẮA���̏�Ȃ���낱�тł����āA�����ɁA�S���犴�Ӑ\���グ�鎟��ł���B �Ζ�l�搶�́A�u���y�̊ϔO�́A�O�̏ꍇ����ϔO�Â�����B���̈�́A�l�͑c��̒n�ɂāA���̐l�����܂�Ă���̂œ��R���̒n�͋��y�ł���B���͐l�͑c��̒n�Ő��܂ꂽ���̂́A���̒n���o�Č��݂̒n�ɂĐ������Ă���l�ŁA�ނ͂���Γ�̋��y�����L���Ă���Ƃ����B��O�͑c��̒n�ł͐��܂ꂸ���݂̒n�ɂĐ��Ƃ����Ă���l�Ŕނ�����̋��y�������Ă���̂��v�Əq�ׂ��Ă���B �������̏Z�ދ��y�́A���������l�X�ɂ���Ă͂����܂�Ă������A������܂������ł���˂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ���ƁA�������̌������鋽�y�̗��j���A��������ɉߋ��̂��̂Ɍ��f����邱�ƂȂ��A�u�̂�����(����)�˂āA�V������m��v�Ƃ���������W�ւ̗ƂƂ��ċ�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł��낤�B �ǂ����A����Ƃ��A���y�̕��X�̂������₲�ӌ��������������������A�����������Ƃ��E�E�E�B �@ �@ |
|
| ���֓��̉͐�j | |
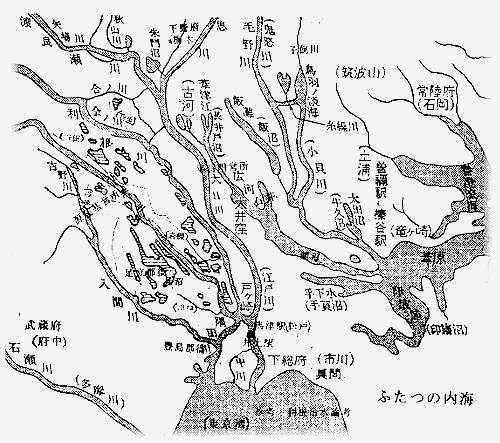 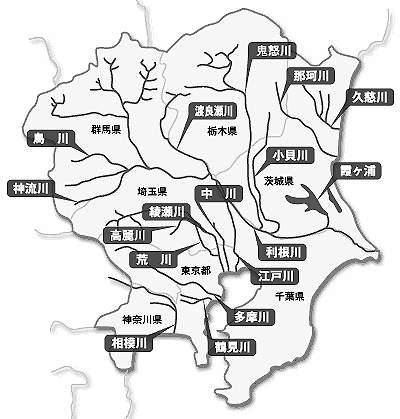 |
|
|
���S�{��
�����쓌�J���Ƃ̈�Ƃ��āA�S�{��͏��L��ƕ�������A��J�s��ؒn��ŗ�����ɍ�������悤�ɉ͓����J�킳��܂����B �S�{��́A�Ȗ،��ƌQ�n���Ƃ̍�̋S�{���𐅌��Ƃ��A�{�여�H����177km���o�Ĉ�錧��J�s�ɂ����ė�����ɍ���������x��ł��B���̗���͓ȖE��闼���ɂ܂�����A�S����ʐς�1,761km2�ɋy�т܂��B �@�������1000�N�O�̋S�{��́A�����̎R�����痬��o�āA��錧���Ȏs����J�a�����̊Ԃœ��ɕ�����A����͓��Ɍ����č��̎��J���ʂ��ď��L��ɍ������A��������͌��݂̋S�{��͓���쉺������A�J�a�����בォ�瓌�����Đ����ŏ��L��ƍ���������ɗ���A��������o�ď헤��(���̗�����)�ɍ������Ă��܂����B�n�߂ɋS�{��Ə��L��̕����H���ɒ��肵���̂́A�ɓޒ����ł��B�����́A����ƍN�ɓo�p���ꂽ���{�㊯���A��̊֓��S��ł���A���̕����H���́A�����쓌�J���Ƃ̈�Ƃ��čs���܂����B���������Ȏs�̓�ɒ�h��z�������Ƃɂ��A�S�{��Ə��L��̊Ԃ𗬂�Ă����L�c��A���(���ڂ���)�̐��ʂ��������āA���ӂɍL�����Ă������n�͎���ɏ��Ȃ��Ȃ�܂����B�����̑��q�̒����⒉���̎���ɂȂ��āA�J�a�������������R�E�ˈ�̊Ԃ̑�n���J���āA������8km�̐V�����͓������A�S�{�����J�s�ŏ헤��(���̗�����)�ɍ���������H�����s���A�S�{��Ə��L��͊��S�ɕ�������܂����B����ɂ��A�����������ɍL��Ȉ�����n���`�����Ă����J���́A�吶�̈�т̐V�c�J�����\�ƂȂ����̂ł��B����ɁA�S�{��ł͉��B��Òn���Ȃǂ���̕����^���H�Ƃ��Ă̏M�^�����B���܂����B |
|
|
���߉ϐ�
���R�͐�̌`�Ԃ����������A�^�����N���Ă����̔�Q��邽�ߐl�X�͐�̋߂��̍���ɏZ��ł������A�ߔN�̓s�s���ɂ��A��߂��̒�n�ɂ��Z�ނ悤�ɂȂ�A�^����Q����悤�ɂȂ����B �߉ϐ�͎��R�L���ŕ\��L���ȉ͐�ł��B�߉ϐ�̔×������^���͎��ӂ̓y�n��Z�������傫�Ȕ�Q�������炵�܂������A����ō^���̋�������ɂ͍^���̎c���Ă������y���̑͐ϓ��ɂ��A�L�x�Ȕ_�앨�����n�ł��_�Ƃ����W���Ă��܂����B���̂��߁A�l�X�͍^���̔�Q���瓦��邽�ߎ��ӂ̍���ɏZ�݁A���Đ������ė��܂������A���ˎs�E�Ђ����Ȃ��s�ł͊J�����i�ނȂ��ŁA��̋߂��̒�n�ɂ������̏ꂪ�L����悤�ɂȂ�A�ߔN�̏o���ł͑傫�ȐZ����Q���邱�ƂɂȂ�܂����B �P���a61�N�@�Z�����ʐ�4,117ha�@�Z����Q�ː�3,580�� �Q����10�N�@�Z�����ʐ�1,726ha�@�Z����Q�ː�1,011�� �R����14�N�@�Z�����ʐρ@411ha�@�Z����Q�ː��@18�� �������ɂ��B ���݂ł́A���a61�N�^�����@�ɒz�玖�ƁA�@�펖�Ɠ��̐������i�߂��A�Z���͈͔͂N�X�������Ă��Ă��܂��B |
|
|
���v����
���˔˂̍��q�n�тƂ��ĊJ�����v���쉈�݂ł́A�x�d�Ȃ�^���̔�Q���瓦��邽�߁A���v�Q�N(1862)�ɒ|�тɂ�鐅�Q�h���т̐������n�߂��A���݂ł������̒n��Ŏc�����Ă��܂��B�܂��A���̑��ɂ�����E�����Ȃǂ̍^���Ƃ̐킢�̗��j���c����Ă��܂��B ���˔�(��������F���˂̉���l�ŗL��)�̍��q�n�тƂ��ĊJ���Ă����v���쉈�݂ł́A�]�˂̐̂���x�d�Ȃ�^����Q���A�ؑ��펟�q��Ƃ����l���A�u�|�̍����^���ɂ������ꂸ�A�����̂ɋC�Â���h�ɒ|��A�����v�̂��v����ł̐��Q�h���т̎n�܂�ƌ����Ă��܂��B�|�т́A�������˔˂ɂ���āu�䗧�R�v(�����Ă��)�Ƃ��ĕی삳��Ă����ƋL�^����Ă��܂��B���݂ł��A�v���여��ɂ͉͌�����㗬��܂ł̊ԂŁA12�����̐��Q�h���т��c���Ă��܂��B���݁A���̐��Q�h���т͂قƂ�ǂ����L�n�ƂȂ��Ă��܂��B�����́A�e�n��̑g���g�D�ŊǗ�����Ă��܂������A���ɂ͊Ǘ��̎肪�s���͂��Ȃ��ӏ��������A��h�̐������i�߂��Ă������݂ł́A�u�ᐅ��݂̕ی�E��h�ւ̐�������̌���(���̐�������߂�)�E�^�����ƂƂ��ɔ×����֗������y���̗}���v�ƌ����������̖ړI�ȊO�ɁA�^�����̗����j�Q���Ă��铙�̍D�܂����Ȃ��v�f�����悤�ɂȂ��Ă��܂����ӏ�������܂��B�����́A����̉͐쐮����i�߂Ă������ŁA��ʂ̕��X�̈ӌ����Q�l�ɂ��Ȃ���A���j�I�Ȏ��������Ƃ��ĕۑ����čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��n��E���S�ɍ^���𗬉������邽�߂ɔ��̐������čs���n��A�ɕ����ĊǗ����Ă������Ƃ��K�v�Ǝv���܂��B�܂��A�v����{��̑�{���x�����t�߂�x��̗���ɂ́A�u����v�ƌĂ���h���A�����Ă��Ȃ��ӏ�������܂��B����́A�^�������t�������Đ��̐�������߂���A�㗬���Œ�h�����×������ɃX���[�Y�ɖ߂�����ƌ������ړI�ő����܂����B���̂悤�ɁA�̂���̍H�@�����݂ł�����̈��S����邽�ߊ�������Ă��܂��B |
|
|
���n�ǐ���
�P �]�ˎ��ォ�痤���ʖԂ����������܂ŕ����A���̓����Ƃ��ĉh�����n�ǐ���B �Q �D���̒�(�ː��E����)���x����n�ǐ���̐��B �R �˂̒�(����E�ٗсE���c�E�ː��E����)���x����n�ǐ���̐��B ���P �n�ǐ���ɂ�����M�^ �ߑ�ɂȂ��ė����ʖԂ����������܂ŁA�n�ǐ���́A��ȕ����̗A����i�ł����B�]�ˎ���ɂ����ẮA�N�v�Ă̗A���Ȃǂ�ړI�Ƃ��ĉ͐���C�H���ƍ��킹�ďM�^�Ԃ̐������i�߂��A�]�ˎ��㒆���ɂ́A�������ꂽ�݂͊́A16�ӏ��ɂ̂ڂ藬��e�n����A�Ă�d�Y�E�؍ށA�������ʂ���ΒY�A�ː��E�����̐D���Ȃǂ��]�˕��ʂ։^�����Ă��܂����B�����ɓ���ƁA����z���݂͊Ɨ����Ƃ̊Ԃɏ��C�D�u�ʉ^�ہv(�S����63m�A����12.6m�A��65�l���e)���A�q���A���q�A�����{�i�����A�S�������������܂ł̊ԁA���ђn��(�ː��E�����E����E�Ȗ�)���瓌���������q�̑��ƂȂ芈�܂����B�܂��A�����z�ł̔�Q��i�����c�������������Ɍ������̂ɗ��p�����Ƃ����b���c���Ă��܂��B ���Q �D���̒��@�ː��E�����@���x�����n�ǐ���̐� �ː��́A�]�ˎ���u���̐��w�v�E�u���̋ː��v�ƕ��я̂����D���̒��Ƃ��ėL���ȂƂ���ł��B�܂��A�����̐D���́A���q����ɂ����ꂽ���M�u�k�R���v�ɂ��o�Ă���قǂ̌Â����炠��n��Y�ƂƂȂ��Ă��܂��B�D���́A�n�ǐ���̖L�x�Ȑ���p�����߂�����z��A�D�����d�グ��Ƃ����̂��傫�ȓ����ł���A�n�ǐ���́A�ߔN�܂Œn��̊�Y�Ƃ��x���Ă��܂����B�Ȃ��A�ߔN�ł́A���w�����̔��B�y�ы@�B���ɂ��A�ό��p�Ƃ��Ắw�F�T�����x���c���݂̂ƂȂ�܂����B ���R �˂̒��Ƌ��ɕ��ޓn�ǐ��� �n�ǐ���̗���ɂ́A���색�[�������͂��߂Ƃ��āA�ٗсE�ː��̂��ǂ�Ȃǖ˂Â��肪������ȂƂ���ł��B���x�̒Ⴂ�~�Ɠ����^�̏��������Ă��A�ǎ��Ȍ��ޗ��ł��鏬���̐��Y�ɓK����Ƌ��ɁA���{�����S�I�ɂ���������u�o�����ٓV�r�v�̂킫���n�߁A�n�ǐ��여��̗ǍD�Ȑ����ɂ�邱�Ƃ��l�����܂��B |
|
|
���G��
�]�ˎ���A�q���݂͊́A���R���̏h�꒬�ł���ƂƂ��ɁA������ŏ㗬�݂̉͊Ƃ��Ĕɉh���܂����B�G��̏M�^�́A�]�˂���̕����̗A�������łȂ��A�]�˕���������B��M�B�A�����ĉz��ւƓ`�����ڂ��ʂ����Ă��܂����B ������ɒʂ���G��̏M�^�́A�]�˂���̕�����������ɉ^�Ԃ����łȂ��A�]�˕�����������B��M�B�A�����ĉz��ւƓ`�����ڂ��ʂ����Ă��܂����B�����d�˂邲�ƂɁA�M�z���ʂ̏��喼�Ɍ��シ����Ă╨����ςݏo���݂͊Ƃ��Ď���ɐ������Ă����܂����B��썑���ɊJ�݂��ꂽ��40�����݂̉͊̒��ŁA��\�I�Ȃ̂��q���݂͊ł��B�����͒��R���̏h�꒬�ł���ƂƂ��ɁA������ŏ㗬�݂̉͊ł����邱�Ƃ���A�]�˂���������בD�ŁA�I�����C�ɂ��ӂ�Ă��܂����B�M�^�ɂ��e�n�ɎY�����]�˂ցA�]�˂���̓���i���n���ւƗ����悤�ɂȂ�A���̍Ő����ɂ́A��300�U�ς݂̑�D���܂߂āA150�z�]��̑D�𐔂����ƌ����Ă��܂��B���̎�舵���ו��́A��ɏ�肪���E���E���ԕ��E�ʂ��E����E�ȁE�����ނŖ�2��2��ʁB����ׂɂ́A�āE�哤�E���E���E�����E�їޓ��A��3���ʂɂ��y�ԑD�ׂ��A��������̐l���ƂƂ��ɉ������Ă����܂����B�b�܂ꂽ�n��������g���g�D�ɂ�鏤���̓Ɛ�Ȃǂɂ���Ĕɉh�����q���݂͊��A����̗���Ǝ��R���ۂɂ́A�R���邱�Ƃ��ł�������ɐ����Ă����܂����B�܂�����1783(�V��3)�N��ԎR�̍��~��ŁA��͐Ȃ�A���S�ȉ^�s���͂��邽�߂̑D��������ɂ́A���܂�ɂ��c��Ȕ�p��v���܂����B���ɁA���۔N�Ԃ��납��A�̎�Ă̕�������������ɍs����悤�ɂȂ�A�e�n�ŕĂ̎s�ꂪ���B���A�݂͊ւ̏o�א�������Ɍ������Ă����܂����B�����đ�O�ɁA������̊J�ʂɂ���Đ��ނ̈�r�����ǂ��Ă����܂����B |
|
|
�����L��
���L��ɂ́A���������Ɋ֓��̎O�剁�Ƃ��ėL���ȕ������A�����A�L�c��������A��P��ha�̔_�n�����邨���Ă��܂��B ���L��́A�Ȗ،��ߐ{�S��ߐ{����ԍ��̎R�n�Ɍ����A�쉺���Č܍s�삨��ё�J������킹�A��錧���C���n��ŗ�����쓌�ɕς��āA��錧�k���n�S���������t�V�c�n��ŗ�����ɍ������闘����̎�v�x��ŁA���̖{�여�H������112km�A�S����ʐς�1,043km2�ł��B�]�˖��{�̗����쓌�J���Ƃ̈�Ƃ��čs��ꂽ�S�{��Ə��L��̊��S�����ƐV�͓��@��ɂ���ċS�{�E���L����̔×����ł������J���́A�吶�̈�т̐V�c�J�����\�ƂȂ�܂����B���L��ł́A�ɓގ��ɂ���āA�������A�����A�L�c�����݂����A�u�J���̎O���v�u���n�̓v�ȂǂƌĂ��V�c�n���a�����܂����B�����O���́A���̋K�͂Ƃ��̎�����\���闭������̉��Ƃ��Ċ֓��L���̂��̂ł��B�܂��A�ɓގ��̎����E�����H�@�͊֓����Ƃ��Ă�A�]�ˎ�����\����y�؋Z�p�ł��B���L��́A�����86��������ł���A�͐�̌��z���ɂ����߁A�^���̌p�����Ԃ������A�×����̏o���������ɂ����A������{�삩��̋t���̉e�����L���Ă��܂��Ƃ���������L���Ă��܂��B������{��̉e�������ł�����̂����a56�N�̍^���ł���A���L��P�Ƃł̏o���͏������������̂́A������{�삩��̋t���ɂ�藴����s���{�n��ɂ����Ē�h���j�炵�A�Z���ʐ�3,396ha�A�Z���Ɖ�5,847�˂̐r��Ȕ�Q���܂����B�܂��A�͐���z�̊ɂ����Ƃ��ł��e�������̂��A���a61�N8���^���ł��B�䕗10���ɂ��W�����J��24���ԉJ��300mm�Ƃ����L�^�I�ȏW�����J�Ɍ�����ꂽ���L�삪�j��Ɏ������̂́A�䕗��߂ʼn����Ƃ����V�C�̉��ł����B�J���オ�������g���ɂ����Ă���l�X�̖ڂ̑O�ŁA���L��̐��ʂ͗��܂�C�z���������ɏ㏸���A���ɂ͖��쒬�ԕl�n��ň쐅���A�×�����������P���܂����B����n�悩������������ꍞ�݁A���َs�̖�1/4���Z�����܂����B����ɉ����̐Ή����ɂ����ĘR�������h������Ɏ���A��Q��4,300ha�A�Z���Ɖ�4,500�˂ɋy�т܂����B���̍ЊQ���_�@�ɁA��Q�̑傫��������q��(�͂�����)�n���V���n�ɑ�������ƂƂ��ɁA���̒n����ɓ_�݂��Ă����T�W�����W�c�ړ]�����A�V���n���ɐV������������Ƃ����S���ł���̂Ȃ����C���Ƃ��s���܂����B |
|
|
�������Y
�����Y���Ӓn��͗�����̓��J�ɂ���āA�^���̑�����ΐ��̒W�����Ȃǂ̑傫�ȉe�����܂����B�܂��A���^�⋙�Ƃɂ��Ă������Y�Ǝ��̔��W�����܂����B ���Ζ��̗R�� �����Y��8���I���ɏ����ꂽ�u�헤�����y�L�v�ɂ͗��C�A�܂��u���t�W�v�ɂ͘Q�t�̊C�Ƃ������ŏo�Ă��܂��B���C�͍��l�̊C�A����̊C�A�M���̊C�A�Q�t�̊C�A����̊C�A�|�Y�A�����̌̑��̂ł����B��������͎�����̊O�̊C�ɑ��āA���̊C�Ƃ��Ă��܂����B�����̖��������悤�ɊC�ł���A���̓��]�ƂȂ��Ă��܂����B���q����� ���̊C�̂������l�̊C�A����̊C�A�M���̊C�A�s���̊C�����킹�āu���̉Y�v�Ƃ����ł��܂����B���ꂪ�����Y�̖��̋N����ł��B �����j�I��������(������̓��J���狏�ؖx�̊�����) �]�ˎ���̏��ߓ����p�ɒ����ł�������������݂̒��q���͌��Ƃ����ɐ��ւ����܂����B���ꂪ���Ɍ���������̓��J�ł��B����ɂ�藘����̉�����������Y��т͍^���̏�P�n��ƂȂ�܂����B���ɓV��3�N�̐�ԎR�啬�ɂ��y���̗����ɂ���ė�����̉͏����㏸���Ă���͏����̏o���Ő��Q����悤�ɂȂ�܂����B����ɑΏ����邽�߂ɖk�Y���玭����ւ̕����H���v�悳��A�����̏��߂ɋ��ؖx�Ƃ��ďv�H���܂����B���͂��̈ꕔ�������`�Ɏp��ς��Ă��܂��B �����^(�]�ˎ���`����) �����Y�E�k�Y��т͌×���萅���ʂ�����ł������A�]�˂̔��W�Ƌ��ɓ��k�n������̕����A��������ɂȂ�A���̏M�^���[�g�Ƃ��ė��p�����悤�ɂȂ�܂����B�����ɂȂ�Ə��C�D���A�q���A�����ʂ͂܂��܂�����ɂȂ��Ă����܂����B�Ƃ��낪�A����29�N�̏���̊J�ʂ�ɓS���̐������i�݁A�܂����̌�o�X��g���b�N�Ȃǂ̗����ʂ��o�ꂵ�A�����ʂ͊����A���̎�i�Ƃ��Ă͓S���E�����ԂɎ��������܂����B�������A���[�J���Ȍ�ʎ�i�Ƃ��ẮA���j�q��ό��q�̗A����i�Ƃ��ď��a40�N��܂ŏM�^�����p����܂����B���ł��A�����̃A�����Ղ�̋G�ߓ��ɂ̓T�b�p�M���s���������A�ό��q���y���܂��Ă��܂��B �����Ƃ̕ϑJ(�����Y�̕������`�������D�`) �����Y������C�ł���������͍���A�X�Y�L�A���Ƃ������C�Y�̋��킪�����������Ƃ��u�헤�����y�L�v�ɋL����Ă��܂��B�������A�]�ˎ���ȍ~�͗����쓌�J�ɂ������Y���W�������Ă������߁A�R�C�E�t�i�E���J�T�M�E�V���E�I�Ȃǂ̎�ނɂ�����Ă��܂����B���̖L�x�Ȑ��Y�������Ǘ����邽�ߍ]�ˎ���̉����Y�E�k�Y�ł́A�����Y�l�\���ÁA�k�Y�l�\�l�ÂƌĂ�鎩���g�D�������Y�����Ǘ�(�����Ǘ�)���Ă��܂����B�����̌������������邽�߂ɏ]���̋��Ƃ̊��K�𖾕��������u�����Y�l�E���Ëc�|���v�͓���ŋ�������Ƃ��̋���A���@�A�����̐����ɂ��ċK�肵�A����ɂ�苙�Ǝ����̕ی삪�}���A�̒������ێ�����܂����B�����ɓ����Ă���n���̋��t�ɂ���đ哿�ԋ��┿�������Ƃ��������Y�Ɠ��̋��@���l�Ă���܂����B���ɔ��������͏��l���ł̑��Ƃő�ʂ̋��l������ꂽ���߃��J�T�M�E�V���E�I���ɗp�����čL�����y���A�������D�������ԓƓ��̌i�ς͉����Y���\���镗�����Ƃ��Ȃ��Ă��܂������A���݂͊ό��p�ɉ^�s����݂̂ƂȂ��Ă��܂��B |
|
|
���_����
�_����́A�O���R�ɂ��̐������Ă��܂��B���Ă��̒n��ł́A�؍ނ̋���������ł���A��O������ɂ����đ��ʂ̖؍ނ�s�s���ɋ������Ă��܂����B�܂��A�G��Ɛ_����̍����_�́A���R�Ɩk���R�̐킢�u�_���썇��v���s��ꂽ��A�u�_����̓n����v���J�݂���铙�A���j��d�v�Ȓn�_�ƂȂ��Ă��܂��B �_����̌��́A�Q�n�A��ʁA����̌������ڂ���O���R�ɂ��̐������Ă��܂��B���Ă��̒n��ł́A�؍ނ̋���������ŁA�_����{�J�ƌĂ�闬��ɂ܂ŁA�X�ыO�����~����A��O������ɂ����đ��ʂ̖؍ނ�s�s���ɋ������Ă��܂����B���̓����́A�{�J�̍ʼn��̒n�ɏ�쑺���Z���J����A���n�ŏW�ނɊւ���l�X�⎙���łɂ���������Ƃ�����܂����B�G��Ɛ_����̍����_�́A���j��̂��猻�݂Ɏ���܂ŁA�d�v�ӏ��ƂȂ��Ă��܂��B�퍑�̎���A���̒n�́A�D�c�M���̉Ɛb�ł���������v�Ə��c���k�����Ƃ̑���7���̑�R�ɂ��s��Ȑ킢�u�_���썇��v�̐��ƂȂ�܂����B�V��10�N(1582)�A�D�c�M�����{�\���̕ςɂ����ꂽ����A�֓��Ǘ̂Ƃ��Ėk�֓��𐧈����Ă���������(���܂̑O��)������v�́A��B�R�𗦂��ċ��s�ɏ�낤�Ƃ��܂����B����ɑ��ď��c���̖k�������A���B���`���k�����M�̘A���R���j�~���悤�Ƃ��A���R16,000�Ɩk���R50,000�����˂��܂����B���͌��݂̐_����t�߂����S�ƂȂ����̂ŁA���̐킢���u�_���썇��v�ƌĂ�ł��܂��B�푈�͖k����̏����ɂ����A���R�͎a���3,760�]��(�����L)�Ɠ`�����Ă��܂��B�u�����A���������̒n�ɖ������A����Ď�˂̖�����(����)�v���V���ɂ͂��̓��˂�����A������������̒n��������(����)�Ƃ����܂��B���݂ł��A�V���ӂ邳�ƍՂ�ɂ����āA���̗E�s�ȗ��j�G�����Č�����Ă��܂��B�]�˂̓����A�㗢���ɂ͏�B�ƕ����̍�����A�_����̓n���ꂪ�J�݂���Ă��܂����B��ɂ͋����˂��Ȃ������������߁A��̌������݂ɍs�����Ƃ͍���ł���܂����B�p��̕����G������A���������˂����Ă��āA�c��̔�����n���D�œn���Ă����l�q�����������܂��B |
|
|
������E������
������̓��J���Ƃɂ��^���̊댯���y�����ꂽ��̒���E�����여��̒�n�т͒n�`���������r���Ԃ���������V�c�J�����s���܂����B���쉈���̏W���̑����́A���쉈���ɏW�����Ă���A���R��h�𗘗p���邱�Ƃŏ����ł��^���̊댯�����瓦��A�M�^�𗘗p���A�W�����`�����Ă��܂����B���̒n��͉͐�Ƃ̐[���ւ��̒��Ől�X�̕�炵���c�܂�Ă������Ƃ���A���݂��u���v��u��v�Ɉ��ޒn�������������܂��B ������ ����́A��ʌ��H���s���㗬�Ƃ��A�嗎�×�����A���r��A����Ȃǂ̑����̎x����W�߂ē쉺���A�����s������̎֍s��Ԃ��ւāA������ƍ����A�㕽��ōr��ƕ��s���ė���A�]�ː��œ����p�ɒ����A���H����84km�A����ʐϖ�1,00km2�̈ꋉ�͐�ł��B����̎x�삪�A�×�����A���r��Ƃ����Ƃ��납����킩��悤�ɁA����́A�]�ˎ��㏉���܂ŗ������r��̖{���ł����B���̌�A�]�ˎ��㏉���ɍs��ꂽ�A������̓��J�Ȃǂ̎��Ƃɂ���Ė{���͈ړ��A���ʂ������������H�͂����ɗp�E�r���H�Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ�܂����B���Ɏx��̑嗎�×�����́A�����p���̈ꕔ�ł��B�����p���́A���݂̍�ʌ��H���s�{�얓���痘����̐����搅���A�r���×�����A�t����ւāA���[�͓����s������܂łÂ��S����40km(�嗬�H��)�̗p�r���H�ł��B1600�N�����A�����쓌�J�ȍ~��Ɋ֓��㊯�ɓߎ��ꑰ�ɂ���ĊJ���ꂽ�Ɠ`�����A���݂ł��Ȃ����썶�݈�т��Ă��܂��B���̊����p�������1700�N�㒆���ɊJ���ꂽ������p�����̗p�r�����H�̊J���ɂ���āA�V�c�̊J�����\�ƂȂ�A����͉͐삪�֍s���J��Ԃ��Ꮌ�n����A�u�]�˂̕đq�v�ɕω����A100���l�s�s�E�]�˂̐������x���܂����B���여��͕W��10m�ȉ��̒Ⴂ�n�悪��߂銄���������A�×����瑽���̍^���ɔY�܂���Ă����n��ł����B�����ƍ^���h��𗼗������邽�߁A�l�X�͐����̒m�b���i���Ă��܂����B ���̖͌^�́A���݂̓����s�����擌������тɈʒu���Ă����㏬�����̏W�����A�Òn�}�����ɕ����������̂ł��B���̐}����A����̐l�X�̕�炵�����̂�܂��B�܂��A�l�X�͒���̋��͓�����ߐ菬������(���ߒr)�Ƃ��A�_�Ɨp��(�㉺�V���p��)�̐����Ƃ��Ă��܂����B���ɒ�h��z���A�^���̔�Q�������₷�����䑤�ɂ͔����A���S�Ȓ�h�̓����ɂ͓c��ڂƏZ����z���A��炵�Ă��܂����B�܂��A���������ӂ��͂��߂Ƃ������쒆����ɂ́A���˂ƌĂ�鐅�h���z���c���Ă��܂��B���˂Ƃ́A���h�̂��߂ɍ����y���肵�A���̏�̌��������Ă����h���z�ŁA�^�����ɓ����邽�߂̏M�܂Ō���ɂ邵�Ă���܂����B���̂悤�ɁA���여��̐l�X�͌J��Ԃ��^���ɑΉ����Ȃ��琶�����c��ł��܂����B �������� ������́A��ʌ�����s���㗬�[�Ƃ���ꋉ�͐�ŁA�����s�ŌÈ�������A�����s�ƍ�ʌ��̌����œ`�E��A�ђ�������킹�A������Œ���ƍ������Ă��܂��B������͍]�ˎ���ȑO�ɂ́A�r��̔h��ł���A��͂ł������ƍl�����Ă��܂��B�������A1600�N�㏉���Ɉɓޔ��O�璉���ɂ��A�r�앪�����ɒ�(���O��)���z����A�r��ƕ�������A�ȍ~�_�Ƃ̗p�E�r���H�Ƃ��Ă̖�����S�����ƂɂȂ�܂��B������̈�т́A����Ɠ������W��10m�ȉ��̒n�悪�唼�����߂܂��B���݂̑����s��т��A���Ă͈�т��Ꮌ�n�ŁA�l�X�͈�����⒆�삪�^�y�����͐ς��Ă���ꂽ�A���R��h�̏���s�������邵���Ȃ��A�]�ˎ��㏉���́A�����Ȍ�ʘH�͂���܂���ł����B�]�ˎ��㏉����1630�N���A�����͓����X���̏h�w�ƂȂ�A�{�w�A�e�{�w�����h��ƂȂ�܂����B���̊X���Əh��̔��W�Ƃ��킹�A��J���Ƃ̍^����Q���Ȃ������ƂƁA�_�Ɨp���̊m�ۂ�M�^�Ɏg�����߂ɁA�������`�E��Ȃǂ̐������s��ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B���݁A�����s���ɂ͑��������ƌĂ��1.5km�قǂ̋��X���ƈ����삪���s���ė�����Ԃ�����܂��B�����́A�]�ˎ���̐����㏼���A����ꂽ�Ƃ����A��������200�N���x�ƌ����鏼���͎c��A������̑�\�I�ȕ��i�Ƃ��āA�l�X�ɐe���܂�Ă��܂��B |
|
  |
|
|
��������
�]�ˎ���ȑO�̗�����́A���݂̓����p�ɒ����ł��܂������A���яd�Ȃ�^������]�˂���邽�߁A����ƍN�ɂ���ė���𓌂ɑւ��啽�m�ɒ����悤�ɂ���厡���H�����s���܂����B������u������̓��J�v�ƌ����܂��B �×��A������͑啽�m�ł͂Ȃ��A���݂̓����p�ɒ����ł��܂����B���݂̂悤�ȗ���ɂȂ����̂́A�����ɓn�鐣�ւ��̌��ʂŁA�ߐ���������s��ꂽ�͐���C�H���́u�����쓌�J���Ɓv�ƌĂ�A����ƍN�ɂ���ē����p���璶�q�ւƗ����ւ���H�����s���܂����B���J���Ƃ̖ړI�́A�]�˂𗘍���̐��Q������A�V�c�J���𐄐i���邱�ƁA�M�^���J���ē��k�Ƃ̌o�ό𗬂�}�邱�Ƃɉ����āA�ɒB���@�ɑ���h���̈Ӗ����������ƌ����Ă��܂��B�H���͓���ƍN���ɓޔ��O�璉���ɖ��߂��A1594�N��̐������ɁA60�N�̍Ό��������āA1654�N�Ɋ������܂����B ���얼�̃��[�c / �u�g�l�v�̌ꌹ�ɂ��Ă͂������̐�������܂��B 1 �A�C�k��ŁA����ȒJ���Ӗ�����u�g���i�C�v�ɗR������B 2 �����A�C�k��ŏ���̂悤�ɍL���đ傫������Ӗ�����B 3 �����n�̕ӂ�ɂ́A�������A���Ȃ킿���������A���ꂪ�����ꂽ���̂ł���B 4 ���H��(�g�l�m�A�^�C)���邢�́A�ō��ÕF(�V�C�l(���g�l)�c�q�R)�Ƃ����l���ɗR������B 5 �����̑吅��R�̕ʏ́A����x�A�����x�A�品��x�ɗR������B �Ȃǂł����A����͂���܂���B�Ȃ��A������̖��̂��o�Ă���ŏ��̕����w���t�W�x�ɂ́A�u���H(�g�l)�v�ƋL����Ă��܂��B�܂��A������͍Ⓦ���Y�Ƃ��Ă�A����͍Ⓦ(�֓�)�ōł��傫����ł���A���{�̐�̒��j�A�܂���{�̐�̑�\�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B |
|
|
���r��
������̓��J�A�r��̐��J / �]�ˎ���̊��i�Z�N(1629)�ɁA�^���h��A�V�c�J���A�M�^�J������ړI�ɁA�r�삩�痘���������t���ւ��H�����s���܂����B�㐢�u������̓��J�A�r��̐��J�v�ƌĂ��͐���C�ł��B �r������H���� / ����43�N�̑�^�����_�@�ɁA�����̉����𐅊Q�����锲�{��Ƃ��āA����22km�A��500���́u�r������H�v�̊J����s���܂����B ����̌��� / ����40�N���т�43�N�̑�^�����_�@�ɁA�^�����̎������ʂ����߂�ړI�Ƃ��āA�ʏ�̒�h�ɑ����p�����ɒz���ꂽ�u����v�ƌĂ���h��26�{���݂���܂����B ���݂̍r��̗��H�́A�]�ˎ��㏉���ɍs��ꂽ�y�؎��Ƃɂ���Ă��̌��^���`�Â����܂����B�]�ˎ���ȑO�̍r��́A���r��𗬂�A�z�J�t�߂œ����̗�����(�×�����)�ɍ������Ă��܂����B�r��͂��̖��̂Ƃ���u�r�Ԃ��v�ł���A���n���[�̌F�J�t�߂�艺���ŁA�����Η��H��ς��Ă��܂����B�֓�����̊J���́A�×��E�������J��Ԃ�������߁A�����ɐ�̐��𗘗p���邩�ɂ������Ă��܂����B�]�ˎ���̊��i�Z�N(1629)�ɁA�ɓޔ��O�璉��(���Ȃт���̂��݂����͂�)���r��𗘍��삩�番������t���ւ��H�����n�߂܂����B�v�����n��(�F�J�s)�ɂ����Č��r��͓̉�����ߐ�A��h��z���ƂƂ��ɐV����J�킵�A�r��̖{�������Ԑ�̎x��ł������a�c�g���̗��H�ƍ��킹�A���c����o�ē����p�ɒ������H�ɕς����̂ł��B�ȗ��A�r��͓̉��͌��݂̂��̂Ƃقړ��l�̌`�ƂȂ�܂����B�㐢�u�v���̊J��v�Ƃ��u������̓��J(�Ƃ�����)�A�r��̐��J(��������)�v�ƌĂ�邱�̉͐���C���Ƃ́A��ʕ���̓������^��������V�c�J���𑣐i���邱�ƁA�F�J�E�s�c�Ȃǂ̌Â����c�n�т���邱�ƁA�؍ނ��^�ԏM�^�̊J���A���R���̌�ʊm�ہA����ɍ]�˂̍^���̖h��Ȃǂ�ړI�ɂ��Ă����ƌ����Ă��܂��B����ɂ���ʓ����Ꮌ�n�͍��q�n�тɐ��܂�ς��A�܂��A�M�^�ɂ�镨���̑�ʗA���͑�s�s�E�]�˂̔ɉh���x���A�]�˂̔��W�͌�w�n�̑��X�̕�炵�����コ���Ă����܂����B |
|
|
���]�ː�
�]�ː여��́A17���I�̍]�˖��{�Ɏn�܂�400�N�Ԃ̎������Ƃ̐ςݏd�˂ɂ��A���Ă̎����n�т���A�����̓����Ƃ��Ă̍��x�ȓy�n���p�����錻�݂̎p�ɕϖe���܂����B�]�ˎ���A�]�ː쉈���ɂ͉͊ݖ������W���A��Ɠ��Ƃ̐ړ_�ɂ���h��(���ˏh�Ȃ�)���Ǝ��̕��������s�s�Ƃ��Ĕ��B���܂����B �]�ː�͈�錧�܉����E��t����c�s�n��ŗ����삩�番�h���A��錧�A��t���A��ʌ��A����ѓ����s�̋����ɗ���āA�����p�ɒ�������ʐ�200km2�A���H����60km(�]�ː�͐쎖��������)�̈ꋉ�͐�ł��B���̍]�ː�́A�]�ˎ���A�l�H�I�ɑ���ꂽ�͐�ł��B���݂͐�t�����q�ɒ����ł��闘����́A�]�ˎ���ȑO�͍�ʕ���������ɂ��Ȃ���āA�����p�ɒ����ł��܂����B�����A�]�ː쉺���͂��̎x��̈�ŁA������Ƃ��Ă��܂����B����ƍN���������Ƃ����Ă���A�]�ˎ��㏉���ɍs��ꂽ������̓��J����(�����p�ɂ������ł�������������݂̒��q���ʂ肩��)�̈�Ƃ���1600�N�㏉���A���݂̐�t���֏h�������(��ʌ�������)�܂ł�18km���J�킳��A�]�ː�͒a�����܂����B�]�ː���͂��߂Ƃ��闘���쐅�n�̐����ɂ���āA�M�^�H����������A�]�ː�͑�s�s�]�˂֊e�n����̔N�v�ĂȂǕ������^�ԗA���o�H�Ƃ��Ĕɉh���܂����B�͐쉈���ɂ́A�݂͊Ƃ���`����������A�傫�ȉ݂͖͊�c�⏼�˂ȂǁA���݂����攭�W�̋��_�ƂȂ�Ǝ��̕��������s�s�Ƃ��Ĕ��B���܂����B�M�^�͓S�������B����吳�܂ŁA�]�ː�̎��ł��傫�Ȗ����̈�ł����B |
|
|
��������
������ł͑�K�͂ȉ��C�H�����s����ȑO����l�X�Ȏ����H�������݂��Ă��܂����B�]�ˎ���ɖ��{�̎������ƂɌg������c���u��(���イ��)�͐��ւ�(�֍s���̃V���[�g�J�b�g)�≺�����ɂ�����A����̒z���Ȃǂ��s���A�S���̉͐�y�؋Z�p�ɑ傫�ȉe����^���܂����B ������͎�s���𗬂��ꋉ�͐�̂Ȃ��ł͔�r�I���z���}�ȉ͐�ł���A�̂���u�����v�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�]�ˎ���u�쏜�䕁����p�v�Ƃ��Ė��{�̎������ƂɌg���A���ꑽ����̎������Ƃɓw�߂��c���u��(���イ���A1662�`1729)�͉������ɂ����鐣�ւ�(�֍s���̃V���[�g�J�b�g)��A����̒z�������s���A��Ɂu�u�������āA�����여�Ƃ����͐�y�؋Z�p���N�������v�ƌ�����قǑS���̉͐�y�؋Z�p�ɉe����^���܂����B������ōŏ��̖{�i�I����K�͂ȉ��C�H���̂��������ƂȂ����̂̓A�~�K�T�����ƌĂ��o�����ł����B�x�d�Ȃ鐅�Q�ɋꂵ��ł����Z���B���吳3�N9��16�������ɑ�����̒z���i���āA�_�ސ쌧���ɉ����܂����B���̎��ނ炪�A�~�K�T�����Ԃ��Ă������Ƃ���A���̎������A�~�K�T�����ƌĂ�ł��܂��B���̎����͓����̗L�g�_�ސ쌧�m���ɂ��z���e���ł̑�������C����^���ɔ�щ��āA��������C�H���ւƎ������Ԃ��ƂɂȂ�܂����B���ꑽ����̂����Ƃ����X�����L���͏��a49�N�̍��]���Q�ł��B�l�Ƃ�������Ɉ��ݍ��܂�Ă����f���͏Ռ��I�ł���A������̂�����Ղ�A���Q�̋��낵�����������܂����B����13�N�ɍ��肳�ꂽ�u�����쐅�n�͐쐮���v�ɂ����Ă��A���̍��]���Q�́u���ő�K�͂̍^���v�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă��܂��B |
|
|
���ߌ���
�̂����J�̂��тɍ^���E�×��������炵�Ă����ߌ���́A��̋K�͂����������Q���₷���n�`�I�ȏ����������āA�����ŋ߂܂ŋM�d�ȗ̋�Ԃ𐔑����c���Ă��܂����B�������A���a40�N������̋}���ȓs�s���ɂ���āA���݂ł́A�ߌ���͍����ł��L���̓T�^�I�ȓs�s�͐�ƂȂ��Ă��܂��B �u�˒n�Ƒ�n�̊Ԃ��֍s���Ȃ���ɂ₩�Ȍ��z�ŗ����ߌ���́A�͏����A�쉈���͒Ⴍ�ĕ���ȉ��ϒn���A�Ȃ��Ă���n�`�I�ȓ����ɂ��A�̂����J�̂��тɍ^���E�×��������炵�Ă��܂����B�퍑����̖�������]�ˎ���ɂ����āA���{�̊e�n�ŗL�͑喼�ɂ���K�͂Ȏ������Ƃ����{����A�L��ȐV�c�J��������ɍs���܂������A�ߌ��여��ł́A���Q���₷���y�n�����Ȃǂ��Ђ����āA�]�ˎ���ɓ����Ă��J���̋K�͂͏��������̂ł����B�܂��A�]�ˎ���ɒߌ���͏M�^�ɂ����Ȃ藘�p�����悤�ɂȂ�A�N�v�Ă��͂��߂Ƃ��镨���̗A��������ƂȂ�܂����B�������A������ȂǂƂ͈قȂ�A�ߌ���͐�̋K�͂����������Ƃ���A�����ł���M�̑傫���������Ă��܂����B���������n�`�I�Ȏ���������āA�ߌ��여��́A�]�˂ɋߐڂ��Ă���Ƃ����n���I�����Ɍb�܂�Ȃ�����A�Љ�o�ϓI�ɔ��W���Ă����n��Ƃ͌������A�����Ɖ��l�Ƃ�����s�s�ɋ��܂ꂽ�n��ł���Ȃ���A�����ŋ߂܂ŋM�d�ȗ̋�Ԃ𐔑����c�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������ɓ���ƁA���{�ōŏ��̓S�����ߌ�������f���ĐV���|���l�ԂɊJ�ʂ��A���l�̐����n��Ȃǂł͊C�ʂ̖��ߗ��Ă��s����悤�ɂȂ�A�ߌ���͌����ł͋��l�H�ƒn�т̑b���z����Ă����܂����B���̌�A�吳12�N�̊֓���k�Ђ����E���ɂ��A���l�s��т��傫�Ȕ�Q���܂������A�����ƂƂ��ɉ��ݕ��̖��ߗ��Ă⓹�H�Ԃ̐����ȂǁA�H�Ɖ����X�ɐi�߂��Ă����܂����B���A���a30�N���̒ߌ��여��́A���R�L���Ȋ����������c����Ă��܂������A���a40�N�����炱�̒ߌ��여����������s�X�����i�݂܂����B���ۓs�s���l�Ɉʒu���A��s�����ɂ��߂��Ƃ����n���I�����ɂ��A������ł͋��l�H�ƒn�т����B���A���a39�N�ɂ͓��C���V�������J�ʂ��A�V���l�w���J�Ƃ��܂����B���̌����O���l��c���s�s���A���������̊J�ʂȂǁA��v��ʋ@�ւ̔��B�ɔ����Ē�����𒆐S�ɋ}���ȓs�s�����i�݂܂����B���̌��ʁA���݂ł͒ߌ���͍����ł��L���̓T�^�I�ȓs�s�͐�ƂȂ��Ă��܂��B |
|
|
�����͐�
���͐�͐������̂��u���͐�(�j����܂�)�v�Ƃ���Ă���A�R�������ł͌��݂ł��u�j��v�Ƃ����ď̂��Ƃ��Ă��܂��B���͐�͌��݁A�_�ސ쌧�̒��������т��悤�ɗ��������͘p�ɒ����ł��܂����A���Ă͑��͌���n������ɓ��Ɍ������ė���A������ɍ������Ă����ƍl�����Ă��܂��B ���͐�͈�ʂɌĂяK�킳��Ă��邱�̖��̂̂ق��Ɂu�j��v�Ƃ������̂������Ă��܂��B����2�̖��̂́u���͐�(�j����܂�)�v�Ƃ��āA���a44�N�Ɉꋉ�͐�Ɏw�肳�ꂽ���ɐ������̂Ƃ��ēo�^����܂����B����́A���͐삪�R�������̋�Ԃɂ����Ă͌j��ƌĂ�A���̖��̂��Â�����e���܂�Ă���A���̖����c�������Ƃ�����]���������������߂ł��B���݂ł����͐�̎R�������̋�Ԃ́u�j��v�Ƃ����ď̂��Ƃ��Ă��܂��B�R���������́A�r���V�R�L�O���Ƃ��ėL���ȔE�씪�C�̐������킹�R�����E�_�ސ쌧���𗬉����܂����A���đ��͐�͑��͌���n�̖k���[�ɂ����ē�ɐi�H��ς����A����ɓ��Ɍ������ė���āA���݂̑����s����s������悤�ɗ��ꑽ����ɍ������Ă����ƍl�����Ă��܂��B���̌㐔�\���N���o�āA���͐�͌��݂̂悤�ȗ��H�ƂȂ�̂ł����A���͐�̗��H�̕ϑJ���u�����͐싴�r�v�����݂̑��͐삩�炨�悻1.2km���ꂽ������s�ɂ���܂��B���̋��r�͊��q����̕����������̉Ɛb�A��яd�����S���Ȃ̋��{�̂��߂�1198�N�ɉ˂������̂��Ƃ���Ă��܂��B���Ȃ݂ɑ��͐�̉͌��t�߂́u�n����v�Ƃ��Ă�Ă��܂����A���̖��̗̂R���͂��̋��̋��{�ɖK�ꂽ�����̔n���ˑR���͐�ɖ\�����A���������n�����Ƃ����`�����疼�t����ꂽ�Ƃ������Ă��܂��B�@ |
|
       �@ |
|
| �@ | |

