倭名類聚抄・「竜・龍」の辞書・九頭竜明神・昇り龍降り龍・鉄の蛇
雑学の世界・補考



 ■龍の起源 |
|
|
龍(ドラゴン)神話は、洋の東西を問わず、どこにでもある。西洋では、竜は退治される存在でしかないが、なぜ東洋では龍が崇められるのか。竜信仰と蛇信仰は同じなのか。なぜ宇宙の開闢は、暗い水の中にいる龍退治から始まるのかといったことを考えながら『龍の起源』を読もう。
■1. 竜と龍はどう違うのか 「龍」という漢字の原型は「竜」である。竜の甲骨文字は、蛇の原字に頭に辛字形の冠飾を付けた形となっており、竜が蛇をモデルに考えられていたことを示唆している。「龍」は、「竜」に躍動飛行するさまを表す旁を加えた字である。竜はもともと水の中に住むと想像されていた動物であるが、天に昇るようになってから龍となったと考えることもできる。竜のモデルは川(母なる海のペニス)であり、龍のモデルは雷(天なる父のペニス)であるという区別をすることもできそうだ。 ■2. 良い蛇と悪い蛇 ファリック・マザーを去勢し、父のファルスを崇拝する文化の人々にとって、母のペニスは悪い蛇、父のペニスは良い蛇ということになる。中国では、後者は龍であり、それは皇帝のようなファルス的存在と同一視された。 「龍が特別に聖なる獣と見られるようになるのとは逆に、蛇のほうは、亀と組み合わされた玄武として四神のひとつとみなされ、また十二支の動物となるものの、蛇はその毒性が強調され、疎まれる動物となった。そのために、嫌われ者と蛇蝎(だかつ)と呼んだり、強欲の人間を蛇豕(だし)といったりするのである。 」 インドでは、ナーガが守護神として崇められていたが、水神アヒは邪神と見られていた。ともにコブラをモデルとした蛇の神である。仏教では、法行龍王という善龍がいる反面、非法行龍王という禍をもたらす悪龍もいた。但し、ナーガは地底に住んでおり、父権的ではない。 エジプトでナーガに相当するコブラの神は、ウラエウスである。ウラエウスは上エジプトで信仰され、王や神の額にその像が付けられていた。これに対して、深淵ヌンに棲む蛇の神アペプは、太陽の神の敵対者だった。太陽神ラーという父性的なファルスに対して、水に棲む蛇が、その敵対者とされていたことに注意しよう。 ユダヤ・キリスト教で、蛇や龍などの水神が敵対視されていた。西洋では、善い蛇などは存在せず、父性的ファルスは、偶像化が許されない抽象的な唯一神に求められる。 ■3. ペルセウス-アンドロメダ型神話 ペルセウス-アンドロメダ型神話とは、次のようなギリシャ神話と類似の神話のことで、世界中に分布している。 「ギリシャのセリポス島にペルセウスという、メドゥサ退治をした青年がいた。エチオピアの王妃、カシオペアは、海の神ポセイドンの怒りをかい、それを鎮めるために、王女アンドロメダを生贄として捧げなければならなかった。クジラの怪物が、海岸の大岩に鎖でつながれたアンドロメダに襲い掛かった時、それを見たペルセウスがメドゥサの首を突き出し、怪物を岩にしてしまった。エチオピアは平和になり、ペルセウスはアンドロメダと結婚した。 」 日本のペルセウス-アンドロメダ型神話としては、スサノヲによる八俣の大蛇退治が有名である。中国の『捜神記』にも、東越の国(福建省)の山の洞穴に棲む大蛇が、毎年八月一日に少女の生贄を要求し、すでに差し出された生贄の数は九人に及んだが、末娘の寄が、団子を食べに来た大蛇を剣で討ち取ったという話がある。その大蛇の目は鏡のようであったという。 生贄を要求する水の怪物ないし山の怪物(龍であることが多い)は、ファリック・マザーの底なしの欲望を意味し、怪物を退治することは、鏡像関係での無限の贈与の反復を打ち切ること、すなわち、去勢を意味する。去勢には、出生時のへその緒の切断、口唇期の離乳、そして男根期に行われる狭義の去勢といくつかの段階があるが、ここでは、狭義の去勢による、肛門期以来続いていた母との贈与体験の終焉に相当する。 ■4. 闇と光のコスモゴニー ユダヤ教の『旧約聖書』は、原初の世界を暗い水として描き、父なる神のおかげで光がもたらされたとしているが、このコスモゴニー(cosmogony 宇宙起源論)は他の創世神話でも同じである。バビロニア神話では、太陽神マルドウクと闇のティアマトが戦い、エジプト神話では、太陽神ラーと深淵ヌンに棲み、ラーの航行を妨げる悪蛇アペプとが戦い、ヘシオドスの『神統記』に描かれているギリシャ神話では、光のゼウスと闇のティタンとが闘い、いずれも光が闇に勝利することで、宇宙が始まる。 インドの『リグ・ヴェーダ』でも、原初は水であり、闇であったが、インドラが悪蛇アヒを切り殺した時、世界に光をもたらしたということになっている。中国の創造神、磐古は、暗い混沌の卵から生まれ、その眼を開くと光明の昼がもたらされた。日本の神話では、天の岩宿神話が類似のコスモゴニーである。アイヌの『ユーカラ』には、英雄アイヌラックルが、日の神を閉じ込めていた魔神を切り殺し、人の世を再び明るくしたという神話がある。闇から光へのコスモゴニーは世界中に存在する。 「旧大陸の古代都市文明だけでなく、新大陸のマヤ文明、ニュージーランド、アフリカ中央部、日本にまで広がりを見せる闇のコスモゴニーを伝播・影響によって説明するのはむずかしい。水のコスモゴニーの全世界的な分布を、農耕文化の拡大に伴い世界各地に広がった祈雨呪術に由来すると考えたのだが、暗黒を水の呪術と結びつける理由は認めがたい。 そうであれば、どこに起源を求めたらよいのか。先に結論を述べれば、闇のコスモゴニーは地域や民族を問わずあらゆる古代人に共通して抱かれていた夜明けの印象に起源する-闇の神話は、人類に普遍的な心性をもとに生まれた、と私は考えるのである。 」 これは、説明になっていない。夜明けの前には夕暮れがあるのに、なぜ夕暮れが宇宙の始まりではないのか。太陽暦が採用されている社会では、日の出とともに一日が始まるが、太陰暦が採用されている社会では、日没とともに一日が始まる。多くの社会では、かつて太陰暦を採用していたのだから、日没と月の出現を宇宙の開闢としても良さそうなのに、そうはなっていない。 またこの説明では、水や竜退治というコスモゴニーの他の要素との関係が不明である。私は、創世神話の原光景を人の出産に求めることで、他の要素を含め、もっと包括的にコスモゴニーを説明するべきだと思う。すなわち、始原における暗闇と水は、子宮内の暗さと羊水のことで、水の中の竜は、その形状から分かるように、母胎と胎児をつなぐへその緒で、人は、このへその緒を切ることで、すなわち竜を切り殺すことで、この世に生まれ、この世の光に眼を開く。 ■ 中国通が書いた龍のトリビア『龍の百科』を読みながら、龍は男なのか女なのかを考えよう。現在の中国人は、男と考えているようだが、もともとそうだったかどうかが問題である。 ■5. 母なる龍としての黄河 龍が川と同一視される時、それは女性的な性格を帯びる。 「中国人は黄河を、慈愛に満ちた「母なる存在」にたとえる反面、一匹の「暴れ巨龍」にもたとえる。」 「母なる存在」と「暴れ巨龍」は両立しないのだろうか。私は、川をファリック・マザーのファルスとみなしている。ファリック・マザーはまさに「暴れ巨龍」にふさわしい。少なくとも、西洋では、常にそう表象されるのである。 ■6. 龍の眼は何を意味するのか 山東省にはこんな民話がある。崔黒子(ツオエヘイツ)という男が、龍の子を見つけて育てたが、大きくなると世話をすることができなくなって、洞窟に連れて行くことになった。崔が皇帝の命令で龍の眼が必要になると、龍は左の目玉を与えて、恩返しをした。この功績で崔は大臣となり、傲慢となり、今度は龍の許可もなく、龍の右目を取ろうとしたところ、龍に呑み込まれてしまった。 日本にも、これに似た「蛇女房」の話がある。 「どこからか来た美しい女が嫁になるが、あるとき昼寝の場面を覗いたら女は蛇になっていた。蛇は見られたことを恥じて山の湖に去ってゆくが、去り際に目玉をくりぬいて、これをしゃぶっているようにと子供に残してゆく。「蛇の目玉」である。話はこの後、その目玉を殿様に召し上げられ、さらにもう一つの目玉まで取られるに及んで、蛇が洪水を起こし、領民一同水の底に消えてゆくと語っている。」 蛇/龍の目は鏡である。自己を鏡像的他者に置き換える死の抱擁という点で、水面に落ちるナルシスの物語や見る人を石にするメデューサの物語と同じモティーフを有している。龍には鏡像的他者、つまり母の性格が残っている。 |
|
 ■「龍」起源考 |
|
| ■青木良輔 『ワニと龍』 | |
|
中国文化における「龍の起源」考としては群書を抜いて出色で、また一方ではワニ学の視点から「恐竜本は嘘ばかり」と論斬している。ちょっとないような怪論です。
■「蛟」と「鼉」-漢代以前の2種のワニ ワニ学書でありながら、同書はまず古代中国文献の渉猟から始まります。BC400ごろ書かれた『礼記』には、「伐蛟取鼉」の語が見えます。「蛟(こう)は駆除し、鼉(だ)は捕獲する」ということです。この二つの生き物は何だろうか? 鼉は『淮南子』に無害でおとなしいとあり、ヨウスコウアリゲーターを指しています。いま華南に棲む温帯性ワニです。穴を掘って冬眠するので、ワニであるのに寒さに強い。戦後になって激減したが、かつてはウジャウジャいたという。 いっぽう蛟は、漢武帝が長江で捕獲して飼っていた-と『史記』にあります。つまりこれも実在した生き物です。鼉(ヨウスコウアリゲーター)と対句だから、蛟もワニだと推定できます。 ■「龍」-殷代の絶滅種? ついで『左伝』『史記』によると、「かつて夏の帝孔甲は龍を飼っていた。それが死んだので肉を食べた」という。ここからは夏代に龍が実在していて、かつそれが崇拝の対象でなかったことが伺えます。(夏王朝は二里頭文化初期にあたる-BC2500ごろ) 歴史学者は、ふるく中国で崇拝されていたのは「蛇」であり、西周中期ごろからそれが「龍」に交替した-と見ています。戦国時代の『左伝』には、「龍は昔はたくさんいたのに、今は何故いなくなったか?」という問答があります。また漢代の『淮南子』は、「蛟龍は淵で寝るが、卵は陸で孵る」「蛟の革は刀剣の装丁にする」と証言します。さらに漢代の『論衡』も、「地上には龍・虎・鳥・亀がいるが、どれもべつに神獣ではない」と言います。 これらもみな「龍/蛟」が実在した動物だったことの証言です。 温暖だった殷以前には、ゾウ(象)・サイ(兕)・キノボリトカゲ(易)なども中原で見られたそうです。これらはその後の寒冷化で、中原では絶滅して実像が忘れられてしまいました。なおサイ(兕)は後代に南方から輸入されて、別に「犀」の字が当てられました。 以上の例から類推するに、「龍」もかつては中原に実在したが、その後の寒冷化で消滅して、正体がわからなくなった可能性が考えられます。 ■「鰐」-明代に絶滅したワニ さてまたかつて華南には、「鰐」がいっぱいいたという。これは巨大で狂暴で、人でも虎でも喰い殺すというのだから、無害なヨウスコウアリゲーターではありえません。「鰐」の字は宋代以降に現れます。「鰐」の害が甚だしいので、明代に夏元吉という高官が、これを駆除する大作戦を行いました。百余の船で生石灰(水と反応して発熱する)を大量に川に投じ、「鰐」たちを煮殺したというのです。15Cの初めです。これで「鰐」は絶滅したとされています。 ■中国の絶滅ワニ-マチカネワニ ときに1963年、広東省で全長7mもあるワニ骨格が出土しました。宋代のものという。中国の学者はイリエワニとかマレーガビアルとか言ってるのだが、それらは熱帯種であるのだから、広東に棲息できたはずはない。青木氏はその鑑定の拙劣を指摘して、これをマチカネワニだとします。マチカネワニは、はじめ西日本で化石が見つかった絶滅ワニで、青木氏自身が同定しました。日本に棲息していたのだから、温帯種だったことは明らかです。上顎の第7歯が大きいことが特徴で、完新世の最大ワニです。 このマチカネワニと見られる骨は、ほかにも雲南など各地で見つかっているそうです。 ■「龍=蛟=鰐」はマチカネワニ! ここから以上の情報を総合して、青木氏は大胆な推論に踏み込みます。「龍=蛟=鰐」は同一種であり、すべてマチカネワニだというのです。 1 西周を崩壊させた寒冷期以前には、華北までマチカネワニが分布していた。温和なヨウスコウアリゲーターと違って、危険な猛獣だったが、そのぶん人に畏敬もされた(トラやコブラと同じ)。これが「龍」と呼ばれた。 2 BC903年には「漢水が凍結した」と記録にあり、おそらくこのとき華北のマチカネワニは絶滅した。とつぜん「龍」が消えた神秘から、人々は「龍が昇天した」と考えた。これ以降、「龍」は想像上の神獣となっていった。 3 のち戦国末~前漢ごろの古代温暖期に、再びマチカネワニは華北でも見られるようになった。だが人々はそれを「龍」とは別物として「蛟」と呼んだ。すでに「龍」は神獣になっていたから、その名で呼べなかったのである。 4 古代温暖期の崩壊で、再びマチカネワニは華北から消失した。この間に「蛟」も「龍」同類として神格化されてしまった。そこで華南のマチカネワニには、さらに「鰐」字があてられた。 5 その華南のマチカネワニたちも、明代の夏元吉による駆除作戦で、ついに地上から絶滅した。 つまりは寒冷化のくり返し→くり返されたマチカネワニの消滅こそが、中国の「龍信仰」を育んだというわけです。文化史と気候歴史学をまたにかけた壮大な推論です。ワニ一徹の視点から、ここまで迫っているのがすごい。なおマチカネワニの学名は、トヨタマフィメイア・マチカネンシス(Toyotamaphimeia-machicanensis)で、青木氏による命名です。むろん「ワニとなって出産した」という神話のトヨタマヒメに因んでます。 なお青木説に対しては、安田喜憲・編『龍の文明史』の読者などから次の反論もあるでしょう。「中国には先史時代から龍はあった。遼河文明で8千年前の龍が出土しているのを知らないのか?」これは遼河文明の根幹に関わる問題です。 |
|
| ■「龍」の起源考1 | |
|
前に、青木良輔『ワニと龍』を紹介しました。それとの絡みで、ここから「龍の起源」を考えます。もとよりここで「龍」というのは、世界の諸文化に見られる「大蛇ふう合成獸」の総称です。生物学における「恐竜」とか、ファンタジー世界の「龍」は含みません。
■「龍」とその類族たち さて世界の諸文化には、「龍」またその類族が大量に知られています。いま試みにその一部だけ並べてみます。 1 中国「龍」 / 中華皇帝権のシンボル。 2 中国「伏義・女媧」 / 人頭蛇身の創世神。ミャオ系が信仰したという。 3 シベリア「ムドゥール」 / 凶兆の天龍(ナーナイ族)。 4 日本「ヤマタノオロチ」 / 多頭の大蛇。スサノオ神に退治される。 5 インド「ナーガ」 / 水を司るコブラ神。霊鳥ガルダと仇敵。 6 インド「ヴリトラ」 / 干魃の大蛇。インドラ神に退治される。 7 バビロニア「ティアマト」 / 太母神で合成獸の姿をもつ。マルドゥク神に退治される。 8 ユダヤ「レヴィヤタン」 / 深淵のワニ霊獣。 9 ギリシア「ヒュドラ」 / 多頭の大蛇。半神ヘラクレスに退治される。 10 西洋「ドラゴン」 / 神の仇敵。聖者ゲオルギウス・大天使ミカエルらに退治される。 11 英国「ワイヴァーン」 / 英国王権のシンボル。 12 北欧「ヨルムンガンド」 / 魔族の大蛇。トール神と相討ちになる。 13 北米「ウンセギラ」 / 角もつ大蛇(スー族)。双子英雄に退治される。 14 中米「ケツァルコアトル」 / 羽毛の蛇神。闇の神テストカリポカと仇敵。 他にも山ほどいるのだが、まあ一端ということで。「龍」というより「大蛇」なものや、7みたいに何だかよくわからないのも混じってます。 ■世界の「龍」の4類型 上に一部を紹介したよう、「龍」とその類族は多種多様で、一まとめに議論の対象にはできません。ごっちゃに扱うと混乱を招くだけです。そこで「龍」とその類族たちを、まずは4類型に分けてみます。 〈D*-呑み込む大蛇〉 先史文化の合成獸が零落した魔物。7ヒュドラ、⑬ウンセギラなどが典型。「呑み込む/死の試練」などの要素に関わる。 〈S -水神の蛇〉 農耕段階で「水神」として崇拝された蛇。5ナーガが典型。また「水神+祖霊神」が結合したのが2伏義・女媧。 〈D1-破壊龍〉 国家段階で〈D*〉が「邪悪のシンボル」とされたもの。4ヤマタノオロチ、6ヴリトラ、7ティアマト、⑫ヨルムンガンドもこれであるが、最も有名なのは⑩ドラゴン。国家英雄に対する「斬られ役」。 〈D2-王権龍〉 国家段階で〈D*〉が「権力のシンボル」とされたもの。⑪ワイヴァーン、⑭ケツァルコアトルもこれであるが、最も有名なのは1中国龍。王権(皇帝権)を表象する。 この関係を大ざっぱに言うと、次のようです。 ●〈D〉と〈S〉は起源が異なる(混同されることもある)。 ●〈D*〉が至悪に堕ちたのが〈D1〉である。 ●〈D*〉が至高に昇ったのが〈D2〉である。 ■実在する動物との関わり なお「龍」とその類族には、たぶんに想像上のものと、実在する動物につよく関わるものがあります。上の例で言うと、5 ナーガは「コブラ」そのもの、8 レヴィヤタンは「ワニ」そのものです。1 中国龍も軸は「ワニ」だが、これは複雑な発展をたどっているので、一見そうとは見えません。 ■安田喜憲説にひとこと なお僕がたいへん批判的に見ている安田喜憲・編『龍の文明史』では、安田氏が次のようなことを言っています。 「西洋では〈龍=悪〉で退治される。これは暴力の文明である。東洋では〈龍=神〉で崇拝される。これは愛の文明である」 …このひと何言っちゃってるんだろう? 上でざっと見ただけでも、西洋にも「王権龍」11 ワイヴァーンがいます。また東洋では「破壊龍」4 ヤマタノオロチや6ヴリトラが退治の対象となっています。僕が安田氏を信用しないのは、このように雑な議論をするからです(だいたい世界中の文明を「暴力/愛」の2型に分類するなんて、考えられない)。 |
|
| ■「龍」の起源考2 | |
|
前回では、世界の諸文化にさまざまな龍類がいること、またそれらを4類型に分けられることを示しました。
〈D*〉-「呑み込む大蛇」。始原の合成獣。 〈S〉 -「水神の蛇」。農耕段階の水神。 〈D1〉-「破壊龍」。国家段階で〈D*〉が零落したもの。 〈D2〉-「王権龍」。国家段階で〈D*〉が昇華したもの。 ここからは主にウラジーミル・プロップの構想を踏まえながら、4類型の分析をしてゆきます。 ■0 始原における崇拝対象 まず最も始原の段階では、人の「信仰」の中心に、1 動物・2 母性・3 死者・4 火の四つがあったことは確実です。 1 動物(獣・魚・鳥など)はすなわち獲物であり、それがやって来てくれること、うまく獲得できることは、切実に祈られたと思われます。クロマニョン人の洞窟壁画などがそれを雄弁に実証している。また 2 母性に対しては、「子どもを産むこと」がやはり切実に祈願された。これもオーリニャック文化の「ヴィーナス」とか「縄文土偶」が実証します。当然のことこの段階は、母権制であったはずです。いっぽう 3 死者(祖霊)に対しては、それが「害をなさないこと/赤子として再生すること」が求められたと思われる。ホモ・サピエンス(やネアンデルタール人)の葬送儀礼がこれを実証しています。いったい未開の思考においては、「死者→祖霊→赤子として再生」という観念はふつうです。アボリジニ、シベリア民族、エスキモーなどにその例は多くあります。4 火は、この段階では「文化」そのもののシンボルです。また火は「喰らう者」として生命の一種と見なされ、それから立ちのぼる煙は昇天する「霊」と見られました。 ■1 「合成獸」と成人儀礼 素の「動物」が祀られた0段階の後に、シンボリックな「合成獸」が祀られる1段階が続きます。未開人から見れば、動物は超能力を備えた存在です。(速く走る/力が強い/空を飛ぶ/よく泳ぐ/感覚が鋭い…など) これらの超能力を合体させたのが、すなわち合成獸であり、未開人から見て万能の存在です。さらにシンボル操作が可能になったこの段階では、合成獣が、母性(女神)や死者(祖霊)とも結合する。これが「女神/神」の発生です。インドやエジプトの獣神たちは、特によくこの痕跡を留めている。なおまた合成獸は、未開結社の成人儀礼でも重要な役割を果たします。作り物の合成獣は、加入者を呑み込み/吐き出すことによって、死と再生の主催者となる。すなわちこれが「呑み込む怪物」の祖型です。北米西岸インディアンなどでは、これはアザラシ型でした。ただ世界では「呑み込む怪物」は大蛇型が圧倒的です。これはヘビがとくに「呑み込む」生物であること、また脱皮をするために「死と再生」のシンボルとして連想されやすいからでしょう。つまりこれが〈D*呑み込む大蛇〉の誕生です。 ■2 農耕段階の「水神の蛇」 農耕段階に入ると、5 水・6 太陽・7 植物(生命樹)への信仰が顕著になります。むろんそれらが農耕の要素であるからです。 5 水神はとくに水源に親和的な動物で表象され、蛇・蛙・魚などの姿を取りやすい。〈S水神の蛇〉はここで生まれる。インドのナーガはまさにこれです。また原始農耕では、水源に生贄(特に若い娘)が投じられたと考えられ、これから死の影を帯びた「水の女霊」ニンフ型の形象も現れます。 6 太陽はとくに空飛ぶ鳥で表象され、ワシ・タカ・カラスなどがこれにあたる。 7 植物は、それが地に埋められて芽吹くことから、やはり「死と再生」のシンボルとなります。これも埋葬死者や(地に埋める)生贄と結合して、女ならペルセポネー/ハイヌウェレ型、男ならアドニス型の植物神を発生します。 さらに農耕は定住を促し、定住からは、4火が「家の火」として初めの私有財産となる。これから「家の火」は3祖霊とも結合して、カマド神に姿を変えます。なお0段階~2段階の前半までは、ずっと母権が強力で、「獣の母」「水の母」「植物の母」など太母(女神)崇拝が中心です。だが牧畜が発展すると、家畜の交配-繁殖を管理する必要から、はじめて「父」の役割が人に知られる。こけから牧畜文化に伴って「父権」の台頭が始まります。 ■3 国家段階の「破壊龍/王権龍」 社会が組織化されてゆく国家段階に入ると、はじめて「父権」が優位に立ち、「母権」は後退してゆきます。そこで「太陽女神」は「太陽男神」へ、「火の女神」は「火の男神」へといった具合に転換してゆく。ここで〈D*呑み込む大蛇〉には二つの変容がありえます。これはもともと成人儀礼で、加入者に「呑み込んで死/吐き出して再生」の試練を与えるものでした。国家英雄が加入者と結びつくと、大蛇は「王神が打ち克つべき魔物」に堕とされてしまいます。これがマルドゥクに倒されるティアマトであり、スサノオに倒されるヤマタノオロチです。すなわち〈D1破壊龍〉の誕生です。逆に国家英雄がじかに大蛇と結びつくと、大蛇は「王神のシンボル」として昇華されます。これが中国の龍、メシーカのケツァルコアトル、英国のワイヴァーンです。すなわち〈D2王権龍〉の誕生です。 以上、あくまで大ざっぱに、普遍的な文明史の中で「龍」の4類型を位置づけてみました。もとより「龍」の個々については、より複雑な事情があります。 |
|
| ■『龍の文明史』 批判1 安田説 | |
|
前回、普遍的な文化史の中に「龍」の4類型を大ざっぱに位置づけました。ところで安田喜憲・編『龍の文明史』は、やはり中国の龍信仰を、「弥生人の原郷」問題と絡めて展開した壮大な論考です。ただし僕の見るところ、その諸説には問題が山ほどある。そこで同書を批判しながら、あわせて僕の考えを述べてゆきます。
■安田喜憲説-2つの問題 安田喜憲・編『龍の文明史』では、数人の論者が登場してそれぞれの「龍の起源」説を述べています。その「序」で安田氏は次のよう主張します。 1 古代中国には、黄河文明・長江文明・遼河文明という文明の三極が存在した。このうち「龍」は遼河文明で発祥した。 2 早くもBC5000頃の遼河(興隆窪文化)では、全長19mもある「石積み龍」が出土している。 3 さらにBC4700~2900頃の遼河(紅山文化)では、美しい「玉龍」も多く出土する。 4 華北の「龍」信仰は、雑穀・父権性の文化である。いっぽう華南には「太陽=鳥」と「水=蛇」信仰があり、稲作・母権制の文化である。この両者が融合して、中国の「龍信仰」が完成された。 5 中東~西洋のドラゴンも、中南米の蛇神(ククルカンやケツァルコアトル)も、おそらく中国の「龍/蛇」信仰が伝播したものである。 このうち1/2/3は、いちおう事実として間違いない。すると第一に問題となるのは、すでに紹介した青木良輔説とのバッティングです。青木氏は、「龍=マチカネワニ」であり、西周中期(BC900頃)以降の寒冷化によってそれが華北で絶滅したことから、「龍」が想像上の神獣となった-と論じていました。だが先史時代からすでに「龍」があったなら、青木説は成り立ちません。これはどう考えるべきでしょうか?第二の問題は、世界中の「龍/蛇神」が中国に起源する-という主張5です。これははたして正しいでしょうか? ■プロップ説の視点から まず第二の問題から片づけましょう。たしかに世界中にはよく似た龍類が知られている。これらはすべて中国単一起源でしょうか?これについては前回で、プロップ説にもとづいて、僕は完全に否定しました。世界の龍類の起源にあるのは、第一に先史時代の成人儀礼で演じられた合成獣〈D*呑み込む大蛇〉であり、第二に〈S水神の蛇〉です。ともにきわめて普遍的な文化であり、キホンは各地で発生したもの。すでにきっちり説明をつけてあります。 ただし伝播も一部には存在するので、いくつかその例も挙げておきます。 ●インドのコブラ神「ナーガ」は、仏典とともに東伝して、中国では「龍」として受容された。 ●日本の大蛇「ヤマタノオロチ」は、後世には中国「龍」の姿で描かれた。 ●バビロンの守護龍「ムシュフシユ」を、バビロンに捕囚されたユダヤ人は邪権のシンボルと見た。これからユダヤ=キリスト教では、神の敵なる龍「ドラゴン」の概念が発生した。 ●ギリシア神話に登場する「ヒュドラ」なども、後世のヨーロッパでは「ドラゴン」の姿で描かれた。 とはいえ〈D*呑み込む大蛇〉や〈S水神の蛇〉が、世界各地で普遍的に発生していたことは動きません。だいたい同書の論者たちは、「龍の起源」を考えるとしながら、プロップ説を視野にさえ入れていないのは信じがたい。〈D*呑み込む大蛇〉が王権時代に敵視されると〈D1破壊龍〉になり、逆に王権と結合すると〈D2王権龍〉になるわけです。この説明は明快で、疑問の余地はないと思います。それに中国→中東はまだともかく、中国→中米への伝播経路なんて想定できるでしょうか? ■「遼河の龍」は[龍]なのか? そして前回挙げた4類型を押さえておけば、「遼河の龍」の位置づけも明らかになるでしょう。遼河文明はまだ国家段階にないのだから、それは〈D2王権龍〉に属する後世の中国[龍]とは違うものです。おそらく「遼河の龍」は、〈S水神の蛇〉をベースにした合成獸と理解されます。馬頭+魚鱗という合成要素も、牧畜(馬)+農耕(水)にふさわしい。つまりこれは龍類ではあるが、甲骨文字[龍]の生物とは別物です。そして甲骨文字[龍]の生物=マチカネワニであったことは、たしかに青木説どおりで間違いないでしょう。 林巳奈夫『龍の話』、「龍はワニを変型させたような単純なものではない」と主張するが、にもかかわらずその挙げている図の[龍]たちは、ワニにしか見えないものです。 |
|
| ■『龍の文明史』 批判2 百田・萩原説 | |
|
■「華南起源の北伝」か/「シベリア起源の南伝」か?
いったい百田-萩原両氏には、次の主張が共通します。 A-「龍信仰」や「世界樹」など多くの東洋信仰は、華南の長江文明に起源する。華北やシベリアなどのそれは、みな華南から北伝したものである。 B-そして長江文明は、弥生人の原郷でもある。 つまり百田-萩原両氏によれば、「龍信仰」を含む東洋信仰の一切は、かつて華南にいた弥生人祖が産み出した-ということになるらしい。しかし林巳奈夫氏は、Aにまったく反対の立場を採り、それらの信仰はシベリア起源で南伝したと主張します。この点では僕も林説を支持します。以下では林説と対照しながら、百田-萩原説のいちいちを斬ってゆきます。 ■1 百田説-「太陽鳥」はニワトリである 安田・百田両氏によれば、雲南~華南には、太陽またニワトリの信仰が濃厚であるそうです。これを根拠に、百田氏は、河姆渡文化(長江文明)の図像に見られる「太陽鳥」はニワトリであると断定します。この図像は『中国古代の神がみ』で紹介したもので、頭に冠毛を持っています。百田氏はこれをオンドリのトサカという。だが『中国古代の神がみ』で、林氏はこれをイヌワシとしていました。翼を広げて天空を駆け、頭に冠毛をもつからです。「天空を駆ける太陽鳥」として林説のイヌワシはふさわしいが、百田説のニワトリはないでしょう。ニワトリはろくに飛べない鳥なのだから。河姆渡文化で(南方産のニワトリでなく)北方産のイヌワシが信仰されていたことは、河姆渡集団が(南方起源でなく)北方起源であることを意味します。 ■2 百田説-龍珠は「鶏卵」である なお1に続いて、百田氏は驚くべきことを主張します。「龍信仰」のもとはニワトリ信仰で、それゆえ「龍のもつ珠」は「鶏卵」である-というのです。つまり百田説によるなら、トサカをもつニワトリが「鶏卵」を抱えていることになります。だがトサカを持つのはオンドリであり、オンドリなら卵を抱えるわけはない。卵を抱えるならそれはメンドリであるはずです。ニワトリが同時にトサカを持ち(=オンドリ)かつ卵を抱える(=メンドリ)ことはありえません。百田説は自己矛盾です。実際には「太陽鳥」はオンドリでなくイヌワシであり、むろん「龍」とは別物です。そして龍の抱えている「珠」とはすなわち「司水珠」であり、龍がほんらい「水神の蛇」であったから持つものです。これは水のシンボルです。「珠」がヒスイ玉であるのも、その青緑色が水を表すからに他なりません。 ■3 萩原説-「射日神話」は華南起源である いったい「射日神話」とは、次のような神話です。 「かつては太陽が三つあって、大地は灼熱で煮立っていた。そこで天神エンドリの子である英雄ハダウが、姉の太陽と妹の太陽を弓で射落とし、中の太陽だけを残した。今でも失われた二つの太陽の幻がたまに見える」(シベリア・オロチ族) 「かつては太陽が十昇って、大地は煮立った。そこで羿(げい)が九つまでを射落として、一つだけを残した」(中国) この話型はシベリア~中国南北~東南アジアまで分布します。萩原氏は、この話型は華南起源で、そこからシベリアまで北伝した-と主張します。しかしこれも林巳奈夫氏が指摘するよう、この神話はシベリアなどの極北で頻繁に見られる光学現象(幻日/パーヘリオン)から生まれたもの。太陽が左右に幻影を伴ったその写真は、見たことのある方も多いでしょう。これは極北の大気がつくる現象で、南方では見られません。すなわち「三つの太陽」は現実にシベリアで観察されるものであり、「射日神話」はそれが神話化されたものです。よってこれはシベリア起源で、南伝したことが明らかです。萩原説は成り立ちません。 ■4 萩原説-「世界樹」は華南起源である これまた広く世界中に「世界樹」の信仰が知られます。中国神話のそれは「扶桑」という。萩原氏は、これも華南に起源すると主張します。しかしやはり林氏は、これまた光学現象(太陽柱/サンピラー)に起源すると指摘します。日の出からまっすぐ光柱が昇り立って、大輪の花に似た光の弧を伴う現象です。日本などの温帯でも現れるが、頻繁に見られるのはやはりシベリアなどの極北です。さらに北欧~シベリアの先史文化は同質性がたいへん高く、その北欧には世界樹「イグドラジル」の信仰が知られている。萩原説によるならば、北欧のイグドラジルも華南から伝播した-というのでしょうか。およそ考えられないことです。これも北方起源の南伝は明らかです。 ■〈O〉系統の問題 最後に遺伝学の視点からダメを押します。YCCからいうと、華南人も華北人も、主力は〈O1/O2/O3〉を含む〈O〉系統のメンバーです。〈O〉系統が、ユーラシアを北回りした〈K〉集団から3.5万年前にシベリアで分岐し、最終氷期を華北で耐えつつ、南方や東方へ分岐を広げたことは、すでに明らかになっています。つまり華南集団も、もとは北方系であり、それゆえシベリア起源の神話や信仰を共有するのは当然です。よって「シベリア起源の南伝」をいう林説は正しいのであり、「華南起源の北伝」をいう百田-萩原説は成り立ちようがありません。その各論が矛盾だらけであることも、いちいち指摘したとおりです。 |
|
 ■鼉(トゥオ)[中国の妖怪] |
|
|
鼉(鼍)〔tuó〕(トゥオ) 豬婆龍(猪婆龙)〔zhū-pó-lóng〕(チュー・ポー・ロン) 揚子鰐(扬子鰐)〔yáng-zĭ-è〕(ヤン・ヅー・エー) 河や湖に棲む巨大なワニの化け物。中国では狸や狐のように、ワニも化けて出るらしい。人間に化けて悪さをする。『西遊記』では西海龍王の甥として黒水河で悪さをしていた。
■ 化け物ワニ、人を化かす 鼉(トゥオ)は日本では鼉(だ)として知られていて、豬婆龍(猪婆龍)、あるいは揚子鰐とも呼ばれるが、特別、化け物を表す単語というわけではない。もともと、鼉は中国語の《ワニ》、特に「ヨウスコウワニ」を指す単語である。日本ではよく狸や狐、あるいは猫なんかが人間を化かすことがある。どうやら、中国ではワニもその類いとされたようで、鼉は、しばしば人間に化けて悪さをしていたらしい。『幽明録』には、この鼉が人間に化けて悪さをした話が載っている。 晉陵民蔡興忽得狂疾,歌吟不恒。常空中與數人言笑,或云/“當再取誰女?” 復一人云/“家已多。”後夜,忽聞十餘人將物入里人劉餘之家,餘之拔刀出後戶, 見一人黑色,大罵曰/“我湖長來詣汝,而欲殺我?”即喚“群伴何不助餘邪?” 餘之即奮刀亂砍,得一大鼉及狸。 劉義慶『幽明录』 晋陵(江蘇省常州市)の劉余之の家を、ある一団が襲った。この一団、実は鼉と狸が化けたものだったという話だ。あるとき、劉余之の家に十数人の一団が娘をさらいにやってきた。劉余之は刀を抜いて彼らに立ちふさがる。するとリーダー格の黒い男が「俺は湖の主だぞ!」と言って仲間をけしかけて襲い掛かってきたというのだ。そこで彼はこの一団と必死に戦って撃退する。後には鼉と狸の死体が残っていたという。 『幽明録』では6メートル以上もある巨大なワニの姿をした怪物で、河や湖の主のような存在だったというが、実際のヨウスコウワニは長さ2メートルほどの小型のワニである。 ■ 西海龍王の甥っ子、三蔵法師をさらう この怪物の鼉、実は『西遊記』にも登場している。第四十三回「黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回(黒水河の妖怪が僧侶を連れ去り、西海龍王の子が鼉を捕まえて帰る)」の話の中で、三蔵法師は黒水河の化け物である鼉にさらわれる。 あるとき、天竺を目指す三蔵一行は黒水河にぶつかる。ごうごうと音を立てて流れる河だ。すると船頭が小船に乗ってやってくるではないか。全員は乗れそうにない。そこでまず、猪八戒と三蔵法師が小船に乗り込んで対岸を目指すことにした。河の半ばまで差し掛かったとき、船はあっという間に波間に呑み込まれてしまった。実はこの船頭、鼉が化けたもので、修行を積んだ坊主を食べて不老長寿を得ようとしていたのだ。三蔵法師はまさに格好の標的だったわけだ。沙悟浄が慌てて河に飛び込んで追いかけると、鼉は水中にある衝陽峪黒水河神府という屋敷で宴会の準備をしていた。沙悟浄が彼に戦いを挑むがなかなか決着がつかない。そこで沙悟浄は化け物を水面に誘い出そうとする。孫悟空に加勢してもらえば勝てると考えたわけだ。ところがこの化け物、屋敷を離れるとまた水中に戻って宴会の準備を始めてしまう。さすがの孫悟空も、相手が水中にいては手が出せない。川岸で二人が頭を抱えていると、そこに黒水河の河神が現れた。どうやらこの化け物、西海龍王の妹の9番目の息子で、最近、この黒水河にやってきて、河神の屋敷を奪って、ここいらの水軍を蹴散らし、やりたい放題に暴れまわっているのだというのだ。西海龍王の甥と聞いた孫悟空は直接、西海龍王に訴え出ることにする。何も事情を知らなかった西海龍王はびっくり仰天、慌てて息子の摩昴太子を派遣し、鼉を連れ戻すのである。こうして無事、三蔵法師は救出されたというわけだ。 |
|
 ■鼉龍鏡(だりゅうきょう) |
|
|
青銅製 径38.3 古墳時代(4世紀)
鼉龍とは想像上の動物で、ワニの一種ともいわれている。この鏡は主として中国の環状乳神獣鏡をまねて作られた仿製鏡で、乳をめぐる蟠龍の長くのびた胴の上に神像と口に棒状のものをくわえた小獣形をおく。神像と蟠龍が頭を共有しているのがこの種の鏡の特徴である。外区の画文帯は本来の飛禽走獣文が変形されて、僧侶の使う払子のような形になっている。このように図文はかなり変形しているが、仿製鏡としてはデザインが精密で鋳上がりもよい。 この鏡と文様構成のよく似た鼉龍鏡が山口県柳井茶臼山古墳から出土しているが、こちらも径四四・五センチという大型品である。仿製鏡の製作にあたって、これらの鏡のように、もとの中国鏡よりはるかに大きなものを作ることも行なわれた。奈良県柳本大塚古墳、福岡県平原遺跡出土の内行花文鏡、大阪府紫金山古墳出土の勾玉文鏡などもその例である。このような大型で精巧な鏡を鋳造することができたということは、当時の技術水準の高さを物語っている。 |
|
 ■鼉太鼓(だだいこ) |
|
|
雅楽に用いられる楽太鼓のうち最大のもので、太鼓の周囲を宝珠形の五色の雲形板で囲み、さらにその外側をおびただしい朱色の火焔が取り巻いていることから、火焔太鼓ともよばれます。太鼓の革は、赤、白、黒の絹を撚りあわせた調緒で鼓のように締め、革面には漆で金箔を貼りつけます。朱の胴の太鼓の革面に三つ巴を描き、雲形板の頂上に日輪の飾りを掲げる左方太鼓と、胴を緑に彩色して革面に二つ巴を描き、頂上に月輪の飾りを掲げる右方太鼓があり、左方太鼓は太鼓の左右に金色の二頭の龍、右方太鼓には二羽の鳳凰が刻まれています。つねに左方・右方一対で用います。
■ 舞楽の楽太鼓として使用される太鼓で、本来は左方・右方が対になり、左方舞・右方舞にあわせて打分けられる。左方は雲上の鼉龍1双、右方は鳳凰1双をそれぞれ浮彫にした火焔を用い、火焔の尖端には日月の象(かたどり)を置く。太鼓の革面と尖端の象などを欠くが、本作は左方の太鼓である。胴は一木を刳り抜いて作り、内部は布着せの朱塗り、周縁に太い鉄輪をはめ、内側に細い鉄輪を2輪、上部に鉄製の取手を付す。本来極彩色が施されていたのであろうが、現状は剥落して木地が露出する。火焔ならびに竜の彫刻は鎌倉以前と考えられる。これに類するものとしては唐招提寺に天平時代のものとして存在するだけである。 |
|
 ■鼉竜 Daryu (中国) |
|
|
別名:鼉魚(だぎょ)、土竜、穿山甲(せんざんこう)。センザンコウのこと?『本草綱目』によれば、ダは江湖によくいる動物で、ヤモリなどに似ていて体長は1~2丈。背中に鱗甲がある。「気」を吐いて雲をつくり、雨を呼ぶ。深い穴に身を潜めている。人々はこの竜の鳴き声を聞いて天候を占う。 |
|
 ■陸游の誕生 |
|
|
陸游は宋が金によって滅ぼされる前年、淮河を行く船の中で生まれた。淮南路転運副使だった父の陸宰が任期を終え、任地の寿春(安徽省)から都の開封へ向かう途中だった。
宣和七年十月一七日の朝のこと、俄に強い風雨があり、船の中にまで吹き込んでくるほどだったが、陸游が生まれると、ただちに止んだという。 この自分が生まれたときのことを、陸游は後に七一歳の誕生日を迎えた日に、詩に詠んだ。 十月十七日予生日也孤村風雨蕭然偶得二絕句予生於淮上是日平旦大風雨駭人及予墮地雨乃止(十月十七日は予の生日也、孤村風雨蕭然たり、偶たま二絕句を得たり、予は淮上に生まる、是の日平旦に大風雨ありて人を駭かす、予の地に墮つるに及んで、雨乃ち止む) 少傅奉詔朝京師 少傅詔を奉じて京師に朝す 檥船生我淮之湄 船を檥いで我を生む 淮の湄 宣和七年冬十月 宣和七年冬十月 猶是中原無事時 猶ほ是れ中原に事無かりし時 我が父が詔を奉じて都へと向かう途上、淮河のほとりに船をつないで私を生んだ、時に宣和七年冬十月のこと、まだ世の中に異変が起こる前のことであった。(少傅は父親陸宰の最終官職名、京師は都のこと) 我生急雨暗淮天 我生まれしとき急雨淮天を暗くす 出沒蛟鼉浪入船 蛟鼉を出沒せしめ 浪船に入る 白首功名無尺寸 白首 功名 尺寸も無く 茅簷還聽雨聲眠 茅簷に還た雨聲を聽きつつ眠る 自分が生まれたとき驟雨が淮河の空を暗くし、蛟鼉が出没して波は船の中にまで入ってきた、あれから七〇年、白髪頭になって功名心も消え去ったいま、こうしてあばら家の中で雨の音を聞いている |
|
 ■中庸の仏教的解釈 (第四段、第三小段、第二節) |
|
|
「天地の道は一言にして尽くす可きなり。其の物たる二ならざれば、其の物を生ずること測(はか)られず。天地の道は博(はく)なり。厚(こう)なり。高(こう)なり。明なり。悠なり。久なり。
今、夫(そ)れ天は、斯(か)く昭昭(しょうしょう)の多きなり。其の窮まり無きに及んでは、日月星辰(じつげつせいしん)繋(かか)り、万物を覆(おお)う。今、夫れ地は、一撮土(いっさつど)の多きなり。其の広厚(こうこう)なるに及びては、華、嶽(がく)を載せて重しとせず、河(かわ)、海、振(ふる)うも洩(も)らさず。万物を載せるなり。今、夫れ山は、一巻石(いっけんせき)の多きなり。其の広大なるに及びては、草木の之に生じ、禽獣の之に居(きょ)し、宝蔵(ほうぞう)興るなり。今、夫れ水は、一勺(いっしゃく)の多きなり。其の測られざるに及びては、黿(げん)、鼉(だ)、蛟(こう)、竜(りゅう)、魚(ぎょ)、鼈(べつ)を生じ、貨財を殖(しょく)す」 黿は大亀、鼉はワニ、蛟は鮫(さめ)、鼈は亀のこと。一撮土は一撮(ひとつま)みの土のことで、一卷石は丸くつぼめた手のひらに載せた石のことで、一勺は柄杓(ひしゃく)一杯のことです。宝蔵は安楽行品に説かれている智慧の宝蔵のことで、柔和忍辱と大慈悲心、そして智慧の宝蔵が人々に仏法を説く時に菩薩が背負う、 三鈷杵(さんこしょ)でもあります。 私訳してみますと、 天地の道とは一、すなわち無分別の空の道です。それが分別されて陰と陽の気の二つになります。陰と陽の気が大自然の陰徳によって調和されて、この大地に万物が生み出されます。天地の道、すなわち自然の摂理とは、博厚(はくこう)、高明、悠久、すなわち深遠(じんおん)にして微妙(みみょう)で不変なる宇宙の真理です。 この天空には沢山の星々が輝いています。それらを見極め尽くすことなど出来ません。太陽も月も星も天空に輝き、自然の摂理に随い、この地球の万物を暖かく覆い包んでいます。 この地球は一掴みの土が積もり積もって出来た巨大な大地です。その広く厚きこと、木や草、山を載せても重いともしません。河や海が波立ち、荒れてもその水を大地の間に抱(かか)えて、外へ溢れさせるようなことも無く万物を載せ、養い育てています。 この山々にしても、手のひら一杯の石がたくさん集まって出来たものです。その広大さは草や木も生じさせ、動物や鳥たちの住処(すみか)にもなっています。まさに生き物たちは、この自然界で生きるための知恵を教えてくれているのです。この自然界は智慧の宝蔵なのです。 地球上の海や川の水も柄杓(ひしゃく)一杯の水が積もり積もって集まって出来たものです。この大地の水の量は測ることも出来ません。そこでも自然の摂理に随い、大亀やワニ、サメの類や竜魚、小さな魚類や亀の仲間の類をたくさん繁殖させ育てているのです、と語られています。 一なる空から陰と陽の二つの気が生じ、大自然の陰徳により陰陽の気が調和されて、万物が生み出されることを語り、また、すべての巨大な大地も山も海も、ほんの一握りのものが集まって出来ていることを、すなわち日々の精進の大切さを教えている一節です。 次に続きます。 「詩に曰く、惟(こ)れ天の命は、穆(ぼく)にして已(や)まず、と。蓋(けだ)し、天の天たる所以(ゆえん)を曰(い)うなり。於呼(ああ)不顕(ふけん)なるかな、文王の徳と純、と。蓋し、文王の文たる所以を曰うなり。純も亦已まず」 穆は稲穂が稔った様ですが、天の万物を生み出し、滋養する行いのことで、不顕は行いを誇ること無く謙虚なことです。 私訳してみますと、 詩経に詠われています。天の行いは万物を生みだし、万物を滋養し育んでも、何一つ見返りを求めること無く、名誉や諡(おくりな)などを求めることもありません。それでいて、万物に施す恩恵は常に平等で、滞ることもありません。これは、まるで、あの謙虚な文王の徳と純朴さのようです。天の行いは常に謙虚で、見栄や外聞にとらわれることが無いので、その純粋さを失うことはありません、と述べています。この文王の下りは、儒家が後から無理に挿入したために、皇帝賛美になっており、仏教の教え、すなわち菩薩道からは遠いものになっています。 荘周菩薩は逍遥遊篇で、至人に己無く、神人に功無く、聖人に名無し、と語っています。 |
|
 ■青竜 |
|
|
(せいりゅう、せいりょう、拼音: qīnglóng チンロン) 中国の伝説上の神獣、四神(四霊・四象)、および四竜の1つ。東方青竜。蒼竜(そうりゅう)ともいう。
その名前から青色をしていると受け取られることが多いが、「青」の原義は青山(せいざん)・青林(せいりん)のように緑色植物の色であり、本来は緑色をしているとされる。 東方を守護する。長い舌を出した竜の形とされる。青は五行説では東方の色とされる。また、青竜の季節は春とされている。 天文学上は、二十八宿の東方七宿に対応する。東方七宿(角宿・亢宿・氐宿・房宿・心宿・尾宿・箕宿)をつなげて竜の姿に見立てたことに由来する。 道教における人格神化した名前では、東海青龍王敖広と呼ばれる。 清瀧権現の善女龍王は中国・青龍寺に飛来したという。 秩父神社の「つなぎの龍」が青龍である。 俳句において春の季語である「青帝(せいてい)」・「蒼帝(そうてい)」・「東帝」と同義であり、春(東・青)の象徴である。但し、「炎帝」・「白帝」・「玄帝(冬帝)」と違い、「青帝」はあまり使われない季語であるため、小型の歳時記や季寄せから削除されている場合が多い。なお、春のことを「青春」ともいう。 |
|
 ■四神 |
|
| (しじん) 中国の神話、天の四方の方角を司る霊獣である。四獣(しじゅう)、四象(ししょう)ともいう。東の青竜(せいりゅう)・南の朱雀(すざく)・西の白虎(びゃっこ)・北の玄武(げんぶ)である。五行説にも中央に黄竜(書籍によっては麒麟を据える場合もある)を加え数を合わせた上で取り入れられている。淮南子などによると、方角には四獣と共に季節神として五帝を補佐する五佐のうち四佐が割り当てられている。これらの四佐のほうを四神と呼ぶこともある。また、瑞獣の四霊(麒麟・鳳凰・霊亀・竜)を四神と呼ぶこともある。 | |
|
四神(四獣)にはそれぞれ司る方位、季節、そしてその象徴する色がある。
四神 四方 四季 四色 五佐 五行 青竜 東 春 緑(青) 句芒(こうぼう) 木 朱雀 南 夏 赤(朱) 祝融(しゅくゆう)/朱明(しゅめい) 火 白虎 西 秋 白 蓐収(じょくしゅう) 金 玄武 北 冬 黒(玄) 玄冥(げんめい) 水 |
|
|
■星宿との関係
中国天文学では、天球を天の赤道帯に沿って東方・北方・西方・南方の四大区画に分け、それぞれに四神(四象)を対応付けた。これらを東方青竜・北方玄武・西方白虎・南方朱雀と呼ぶ。 これは二十八宿を七宿ごとにまとめ、その星座を組み合わせた形を龍・鳥・虎・亀(正確には蛇が亀に絡まっている姿)の4つの動物の姿に見立てたことによる。例えば、東方青竜であれば、角は龍の角、亢は龍の頸、氐房は龍の身体、尾は龍の尾を象っている。また戦国時代は五行説により土=中央=黄、木=東=青、金=西=白、火=南=赤、水=北=黒というように五行と方位(五方)・色(五色)が結びつけられており、これらの動物も各方角が表す色を冠し、青竜(蒼龍)・玄武・白虎・朱雀(朱鳥)とされた。なお、ここでいう東方・北方・西方・南方は天球上の東西南北ではなく、地平から見た方位であり、天上の十二辰と地上の十二支が一致したときの天象(春の星空)を基にしている。 なお四象の境界は二十八宿に基づいているため、均等ではなく、十二次と十二辰の区分とは一致しない。『漢書』律暦志の度数(周天を365度とする)では、 東方宿 - 75度 北方宿 - 98度 西方宿 - 80度 南方宿 - 112度 となっている。 |
|
|
■四神にちなむもの
青龍偃月刀、白虎隊、朱雀門、玄武洞、玄界灘など、四神にちなんだ事物は数多い。 会津藩では武家男子を中心に年齢別に50歳以上の玄武隊、36歳から49歳までの青龍隊、18歳から35歳までの朱雀隊、17歳以下の白虎隊と四神の名前を部隊名とし軍構成していた。 人生を四季に例え、若年期を「青春」、壮年期を「朱夏(しゅか)」、熟年期を「白秋(はくしゅう)」、老年期を「玄冬(げんとう)」と表現することがある(玄冬は、春に芽吹く土壌作りの時期として幼少期とする説もある)。日本の詩人北原白秋の号はこれに由来している。 |
|
|
■日本のフィクションにおける四神
日本では、1990年代に入る頃に若年層向けの小説、漫画、コンピュータゲームなどに登場するケースが増加。さらにその後の1990年代中頃に起こった風水ブームによってさらなる知名度が形成され、創作の題材としての人気が拡大再生産された。 日本の作品内での四神の扱われ方は実に様々である。個々の名称に関しては青竜、朱雀、白虎、玄武をそのまま使う作品が多いが、総称では元のまま「四神」ないし「四獣」を使う作品ばかりではなく「四神獣(ししんじゅう)」や「四聖獣(しせいじゅう)」といった造語を用いる作品が珍しくない。また、原義のまま四方を司る神獣として登場する以外に、人間や器物の名称として名前のみが使われるだけ(例 「陸上防衛隊まおちゃん」では兵器の名前として登場、「天元突破グレンラガン」では螺旋四天王のガンメンの名前として登場(この作品では四神の名称を少しもじっている)、「怒首領蜂大往生」では各ステージのボスの名前として登場(この作品では名前の読みは四神と同じだが当て字が異なっている))、またはその逆に名前は違っているが青い龍、赤い鳥、白い虎、(緑の)亀という組み合わせの四種の獣が登場するという作品(『爆転シュートベイブレード』)もある。本来の五行中の4要素(木、火、金、水)でなく四大元素(地水火風)に当てはめた例もある(例 「セイントビースト」シリーズでは主人公の4人の天使に四神の二つ名があり、4人それぞれが地水火風の各属性を持っている)。又、四神の扱いの変形として、『五星戦隊ダイレンジャー』では、巨大気伝獣にその存在が顕れるだけではなく、本編の重要キャラクターとして、“孔雀”なる女性が登場した。更に、『ふしぎ遊戯』の様に、人の姿を取る事も出来たりする例もある。 なお、中国では玄武は亀に蛇が絡まる姿で表現されることが多く、高松塚古墳の物もこの姿だが、日本のフィクションに登場する玄武は亀だけの姿で描かれる場合が大多数である。また玄武という名の通り、本来は黒が象徴色だが、象徴色が黒ではなく緑になっているのもよく見られる。本来緑が象徴色なのは青竜だが、文字通り青が象徴色になっている場合が多い。 |
|
 ■四竜 |
|
|
(しりゅう) 道教において四海を治めるとされる、蒼竜(青竜)、白竜、赤竜(紅竜)、黒竜の四人の竜王である。通常は「四海竜王」という。
地上では、蒼竜は東方、白竜は西方、赤竜は南方、黒竜は北方に潜み棲むとされる。 竜を真の姿として現れるが、普段は人間風の竜として、龍宮でエビやカニ達に守られている。海を統治すること以外に、雲と雨を操る。怒らせると、都市を洪水にしてしまう。東海竜王の蒼竜がもっとも大きい領土をもつという。それぞれ別名がある。 東方蒼龍(東海龍王): 敖廣(ごうこう),廣徳王 南方赤龍(南海龍王): 敖欽(ごうきん),廣利王 西方白龍(西海龍王): 敖閏(ごうじゅん),廣順王 北方黒龍(北海龍王): 敖順(ごうじゅん),廣澤王 『瑞応記』によれば、四竜の長として応竜がおり、長は年老いて四神の中央を守護する黄竜になるとされる。そのため、黄竜は応竜より上の立場となる。しかし、蒼竜(青竜)は四竜と四神のどちらにも含まれている。 北宋の皇帝徽宗が青竜神、赤竜神、白竜神、黒竜神にそれぞれ王の位を与えたという、風流天子と呼ばれるにふさわしい伝説がある。 |
|
|
■西遊記における四海竜王
西遊記における四竜は孫悟空にしてやられる役回りである。孫悟空は東海龍王敖廣の竜宮の地下に「海の重り」として置いてあった如意金箍棒を四竜の他の宝とあわせ奪い取ってしまう。四竜は相談して玉帝に悟空の悪行を訴える。 西海龍王・敖閏の第三太子・玉龍は、火事を起こして宝珠を焼いてしまい、西海龍王がその罪を玉帝に訴えたため、罰として笞打ちのうえ死罪を言い渡された。その後、観世音菩薩の西海龍王へのとりなしもあって死罪は免じられ、三蔵法師の馬となるべく、蛇盤山の鷹愁澗に住み、五百年間三蔵が来るのを待ち続けていた。しかし、肝心の三蔵が来た時にはそうとは気付かず、三蔵が乗っていた白馬を呑んでしまい、代わりとして白馬になっているという役である。西遊記成立以前の泉州開元寺の仁壽塔(西塔、嘉元年1237年完成)浮彫に、剣を持った姿(馬とつながっている)が東海火龍太子と刻まれ、梁武帝、唐三藏、猴行者とともに見られる。 |
|
 ■四霊 |
|
|
(しれい) 『礼記』礼運篇に記される霊妙な四種の瑞獣のことをいう。四瑞(しずい)。
麒麟(きりん)は信義を表し、鳳凰(ほうおう)は平安を表し、霊亀(れいき)は吉凶を予知し、竜(りゅう)は変幻を表すという。短く麟(りん)・鳳(ほう)・亀(き)・竜(りゅう)とも言う。 四神と通用する(四神を四霊と呼ぶ、あるいは四霊を四神と呼ぶ)。 |
|
| ■麒麟 | |
|
(きりん、普通話でチーリン:qílín) 中国神話の伝説上の動物。鳥類の長である鳳凰と並んで、獣類の長とされる。 日本と韓国ではこの想像上の動物に似た偶蹄目キリン科の動物の名前になっている。
形は鹿に似て大きく背丈は5mあり、顔は龍に似て、牛の尾と馬の蹄をもち、雄は頭に角をもつとも言われる。背毛は五色に彩られ、毛は黄色い。頭に角があり、本来は1本角であることから、西洋のユニコーンと比較されることもある。ただし2本角、もしくは角が無い姿で描かれる例もある。 普段の性質は非常に穏やかで優しく、足元の虫や植物を踏むことさえ恐れるほど殺生を嫌う。 神聖な幻の動物と考えられており、1000年を生き、その鳴声は音階に一致し、歩いた跡は正確な円になり、曲がる時は直角に曲がるという。また、動物を捕らえるための罠にかけることはできない。麒麟を傷つけたり、死骸に出くわしたりするのは、不吉なこととされる。 また、『礼記』によれば、王が仁のある政治を行うときに現れる神聖な生き物(=瑞獣)であるとされ、鳳凰、亀、龍と共に「四霊」と総称されている。このことから、幼少から秀でた才を示す子どものことを、「麒麟児」「天上の石麒麟」などと称する。 孔子によって纏められたとされる古代中国の歴史書『春秋』では、誤って麒麟が捕えられ、恐れおののいた人々によって捨てられてしまうという、いわゆる「獲麟」の記事をもって記述が打ち切られている。 鳳凰と同じく名称に雌雄の区別がありオスの麒麟を「麒(き)」、メスを「麟(りん)」とするが、この雌雄を逆にしている資料もある。また、上記「獲麟」のように「麟」一字で雌雄の別なく麒麟を表すことも多い。 麒麟にはいくつか種類があると言われ、青い物を聳弧(ショウコ)、赤い物を炎駒(えんく)、白い物を索冥(さくめい)、黒い物を角端(かくたん)、黄色い物を麒麟と言う。 |
|
| ■鳳凰 | |
|
(ほうおう、拼音: Fènghuáng ) 中国神話の伝説の鳥、霊鳥である。鳳皇とも。日本や朝鮮など東アジア全域にわたって、装飾やシンボル、物語・説話・説教などで登場する。
鳳(ほう)はオス、凰(おう)はメスを指し、『本草綱目』によれば、羽ある生物の王であるとされる。「聖天子の出現を待ってこの世に現れる」といわれる瑞獣(瑞鳥)のひとつで、『礼記』では麒麟・霊亀・竜とともに「四霊」と総称されている。 中国最古の類語辞典『爾雅』によれば、嘴は鶏、頷は燕、頸は蛇、背は亀、尾は魚で、色は黒・白・赤・青・黄の五色で、高さは六尺程とされる。 後世の中国や日本では変異があり、日本では一般に、背丈が4-5尺はあり、その容姿は前部が麟、後部が鹿、頸は蛇、背は亀、頷(あご)は燕、嘴は鶏、尾は魚であるとされる。五色絢爛な色彩で、羽には孔雀に似て五色の紋があり、声は五音を発するとされる。 また、現代の中国では一般に、頭はキンケイ、胴体はオシドリ、尾は孔雀、足は鶴、嘴はオウム・インコ、翼はツバメとされる。 鳳凰は、霊泉(醴泉〈れいせん〉、甘い泉の水)だけを飲み、60-120年に一度だけ実を結ぶという竹の実のみを食物とし、梧桐の木にしか止まらないという。『詩経』には「鳳凰鳴けり、彼の高き岡に。梧桐生ず、彼の朝陽に」とある。 鳳凰の卵は不老長寿の霊薬であるとされるとともに、鳳凰は中国の西方にあるという沃民国(よくみんこく)やその南にある孟鳥国(もうちょうこく)にも棲むといわれ、その沃民国の野原一面に鳳凰の卵があると伝えられる。 また仙人たち(八仙など)が住むとされる伝説上の山崑崙山に鳳凰は棲んでいるともいわれる。 ■歴史 殷の時代には風の神、またはその使者(風師)として信仰されていたといわれる。また「風」の字と、「鳳」の字の原型は、同じであったともいわれる。 春秋時代の『詩経』『春秋左氏伝』『論語』などでは、「天子が正しい政治を行った際に現れる」「聖天子の出現を待ってこの世に現れる瑞獣」といわれる。『礼記』では麒麟・霊亀・応龍とともに「四霊」とのひとつとされる。 後には五行説の流行により、四神のひとつ朱雀と同一視される。例えば漢代の緯書には、鳳凰を火精としているものがある。 ■鳳凰の異名・種類 鳳凰の異名または同系名鳥王、雲作、雲雀、凰、叶律郎、火離、五霊、仁智禽、神鳥、仁鳥、聖禽、丹山隠者、長離、鳳、朋、明丘居士、鸞(らん)、霊鳥、鵷鶵(えんすう)などがある。 また前述の通り、鳳凰は朱雀と同一視されることもある。またその形態から、インド神話の神で、マレー半島、インドネシアの聖鳥ガルダ(迦楼羅)との類似が指摘されている。 『山海経』には、五色の鳥として鳳鳥・鸞鳥・皇鳥の3つが挙げられるほか、黄鳥・狂鳥・孟鳥・夢鳥なども鳳凰と同一とする説もある。 「毛詩陸疏広要」によれば、鳳凰のうち赤いのを鳳、青いのを鸞、黄色いのを鵷鶵、紫のをガクサク、白いのを鵠としている。 ■鳳凰・鸞・朱雀 同じ霊鳥として、鸞があり、鳳凰と混同または同一視される。唐の『初学記』(727)によれば、鸞とは鳳凰の雛のこととされる。また江戸時代の『和漢三才図会』は鸞を実在の鳥とし、中国の類書『三才図会』からの引用で、鸞は神霊の精が鳥と化したものとする。また鳳凰が歳を経ると鸞になるとも、君主が折り目正しいときに現れるとしている。またその声は5音の律、赤に5色の色をまじえた羽をたたえているとされ、鳳凰の伝承と混合しているのがみられる。朱雀は四神の一つであり、南と火を司る神あるいは聖なる動物とされる。その姿が鳥であることや、他の四神との兼ね合い(龍、虎、亀は縁起のいい動物である)から鳳凰と同一視されることがあるが、鳳凰と朱雀は厳密には別物である。ただし、鳳凰と朱雀が鳥の中でも特別な存在であることから、朱雀が鳳凰と同類であっても大きな不都合はない。 また、鳳凰・鸞・朱雀は、装飾や図像表現においては、厳密に区別されない場合が多い。 |
|
| ■霊亀 | |
|
(れいき) 古代中国の神話等に登場する怪物の一種とされ、四霊の一つにあげられている。
中国神話等では、背中の甲羅の上に「蓬莱山(ほうらいざん)」と呼ばれる山を背負った巨大な亀の姿をしており、蓬莱山には不老不死となった仙人が住むと言われている。 東洋の神話等においては、亀は千年以上生きると強大な霊力を発揮し、未来の吉凶を予知出来たのではないかと言われており、霊亀もまた千年以上を生きた亀が強大な霊力を得た事で変異・巨大化したのではないかと言われている。 |
|
| ■竜 | |
|
(りゅう、りょう、龍) 中国神話の生物。古来神秘的な存在として位置づけられてきた。
旧字体では「龍」で、「竜」は「龍」の略字である。「龍」は今日でも広く用いられ、人名用漢字にも含まれている。 ドラゴンの訳語として「竜」が用いられるように、巨大な爬虫類を思わせる伝説上の生物全般を指す場合もある。さらに、恐竜を始めとする化石爬虫類の種名や分類名に用いられる saurus (σαῦρος、トカゲ) の訳語としても「竜」が用いられている。このように、今日では広範な意味を持つに至った「竜」であるが、本項では、中国の伝説に起源を持つ竜を説明する。 |
|
 ■四凶 |
|
| (しきょう、Si-xiong) 古代中国の舜帝に、中原の四方に流された四柱の悪神。書経と左伝に記されているが、内容は各々異なる。 | |
|
■渾沌
(こんとん、拼音: húndùn ) 中国神話に登場する怪物の一つ。四凶の一つとされる。その名の通り、混沌(カオス)を司る。 犬のような姿で長い毛が生えており、爪の無い脚は熊に似ている。目があるが見えず、耳もあるが聞こえない。脚はあるのだが、いつも自分の尻尾を咥えてグルグル回っているだけで前に進むことは無く、空を見ては笑っていたとされる。善人を忌み嫌い、悪人に媚びるという。 他では、頭に目、鼻、耳、口の七孔が無く、脚が六本と六枚の翼が生えた姿で現される場合もある。道教の世界においては、「鴻鈞道人(こうきんどうじん)」という名で擬人化されている事があり、明代の神怪小説封神演義ではこの名で登場している。 荘子には、目、鼻、耳、口の七孔が無い帝として、渾沌が登場する。南海の帝と北海の帝は、渾沌の恩に報いるため、渾沌の顔に七孔をあけたところ、渾沌は死んでしまったという(内篇、応帝王篇、第七)。転じて、物事に対して無理に道理をつけることを『渾沌に目口(目鼻)を空ける』と言う。 |
|
|
■窮奇
(きゅうき、拼音: qióngjī チョンジー) 中国神話に登場する怪物の一つ。四凶の一つとされる。 中国最古の地理書『山海経』では、「西山経」四の巻で、ハリネズミの毛が生えた牛で、邽山(けいざん)という山に住み、犬のような鳴き声をあげ、人間を食べるものと説明しているが、「海内北経」では人食いの翼をもったトラで、人間を頭から食べると説明している。五帝の1人の少昊に不肖の息子がおり、その霊が邽山に留まってこの怪物になったともいう。 『山海経』にならって書かれた前漢初期の『神異経』では、前述の「海内北経」と同様に有翼のトラで、人語を理解し、人が喧嘩していると正しいことを言っている方を食べ、誠実な人がいるとその人の鼻を食べ、悪人がいると獣を捕まえてその者に贈るとしている。 思想書『淮南子』では、「窮奇は広莫風(こうばくふう)を吹き起こす」とあり、風神の一種とみなされていた。日本の風の妖怪である鎌鼬を「窮奇」と表記することがあるが、これは窮奇が風神と見なされたことや、かつての日本の知識人が、中国にいるものは日本にもいると考えていたことから、窮奇と鎌鼬が同一視されたためと考えられている。春秋左氏伝や後漢書にも登場する。 |
|
|
■饕餮
(とうてつ、拼音: tāotiè ) 中国神話の怪物。体は牛か羊で、曲がった角、虎の牙、人の爪、人の顔などを持つ。饕餮の「饕」は財産を貪る、「餮」は食物を貪るの意である。何でも食べる猛獣、というイメージから転じて、魔を喰らう、という考えが生まれ、後代には魔除けの意味を持つようになった。一説によると、蚩尤の頭だとされる。 殷代から周代にかけて青銅器や玉器の修飾に部分的に用いられる(饕餮文/とうてつもん)。この頃の王は神の意思を人間に伝える者として君臨していた。その地位を広く知らしめ、神を畏敬させることで民を従わせる為に、祭事の道具であるこのような器具に饕餮文を入れたものとされる。良渚文化の玉琮には、饕餮文のすぐ下に王の顔が彫られたものも出土している。そのため、饕餮の起源は良渚文化の栄えた長江流域で崇拝された神だったといわれている。ただし、これらの装飾が当初から饕餮と呼ばれる存在の描写であったという証拠は何もなく、後世に饕餮文と呼ばれているだけである。そのため、中国考古学の専門家である林巳奈夫はこれを「獣面紋」と呼んでいる。 渾沌(こんとん)、窮奇(きゅうき)、檮杌(とうこつ)とともに「四凶」ともされる。『神異経』をひけば「饕餮、獣名、身如牛、人面、目在腋下、食人」という。 明代には、竜の子である「竜生九子」の一つで、その五番目に当たるとされた。飲食を好むという。故に鼎の模様とされる。 |
|
|
■檮杌
(とうこつ(とうごつ)、拼音: táowù ) 中国神話に登場する怪物の一つ。四凶の一つとされる。 虎に似た体に人の頭を持っており、猪のような長い牙と、長い尻尾を持っている。 尊大かつ頑固な性格で、荒野の中を好き勝手に暴れ回り、戦う時は退却することを知らずに死ぬまで戦う。 常に天下の平和を乱そうと考えている。「難訓(なんくん。「教え難い」の意)」という別名がある。 すなわち、『神異経』を引けば、「西方荒中有焉、其状如虎而犬毛、長二尺、人面虎足、猪口牙、尾長一丈八尺、攪乱荒中、名檮杌、一名傲狠、一名難訓」とある。 |
|
 ■伝承 天女と五頭竜 / 江島縁起 |
|
|
むかし・・・というても、千四百年も遠いむかしになろうか。
そのころ鎌倉の深沢に、まわりが四十里という湖があり、主の五頭竜がすんでいた。 悪い龍でな。 山くずれや洪水を起こし、田畑を埋めたり押し流したりして、村人をくるしめておった。 ときには火の雨をふらすこともあり、村人は山のほら穴にかくれ、まわりを石でかこんでいたと。 ある日、五頭竜は津村の水門のところにあらわれて、はじめて村の子を食った。 それから村人は、ここを「初くらい沢」と名づけて近よらなかった。 津村の長者には16人の子がいたが、一人残らず五頭竜にのまれてしまったと。 おそれおののいた長者は、死んだ子を恋したいながら西の里に屋敷をうつしていった。 それで、深沢から西の里へ行く道を子死恋(こしごい)とよぶようになり、それが腰越(こしごえ)になったのだと。 そうしたとき、天地をゆるがすたいへんなことが起こった。 欽明天皇13年4月12日だったと。 まっ黒い雲が天をおおい、深い霧がたちこめ、大地震が起こった。 山はさけ、沖合からは高波が村をねらっておそいかかってきた。おどろおどろと地鳴りがして、地震は十日のあいだつづいたが、23日の辰の刻(とき)に、うそのようにとまったと。 村人がホッとしたとき、こんどは海底から大爆発が起こり、まっかな火柱とともに岩が天までふきあげられて、小さな島ができた。 これが江の島なのだと。 五頭竜は、このありさまを湖の中から目をむいて見まもっていた。 すると、天から美しい姫が紫の雲にのり、2人の童女をつれてしずしずと島におりてきた。 そのとき、どこからともなく美しい音楽が流れ、こうばしいかおりがただよったと。 「うーむ、なんと美しい姫じゃ。よ~し、わが妻にむかえるぞ」 五頭竜は、波をかきわけて江の島へ行くと、「わしはこのあたりをおさめる五頭竜。姫を妻にむかえよう」といった。 「なんと申す五頭竜。おまえは田畑をおし流し、なんのとがなきおさな子までのみ、あらんかぎりの罪をおかしてきた。 天女はそのような者の妻にはなりませね」 天女はそういうと洞窟の中へはいってしまったと。 五頭竜は、すごすごと帰っていったが、つぎの日にまた江の島へやってきた。 「天女さま、どうかゆるしてくだされ。これからは心をあらため村をまもります。どうか信じてくだされ。五頭竜は生まれかわります」 天女は、五頭竜のかたい心を信じて、しずかに手をさしのべた。 それからの五頭竜は、ひでりの年には雨をふらせ、みのりの秋には台風をはねかえし、津波がおそったときには波にぶち当たっておし返していた。 しかしそのたびに、五頭竜のからだはおとろえていった。 ある日、五頭竜はなみだながらに、「わたしの命もやがておわるでしょう。これからは山となって村をお守りいたします」と、海をわたって帰ると一つの山になった。 これが片瀬の竜口山で、山の中腹には竜の形をした岩があって、江の島の天女をしたうように見つめていたと。 村では、ここに五頭竜を祀った社を建て、竜口明神と名づけた。 明神さまに祀られている神は玉依姫命だが、本殿には五頭竜の木彫りのご神体がおさめられている。 そして、60年に一度の「巳年式年祭」のときには、木彫りの五頭竜をみこしにのせ、江の島へつれていって天女の弁財天とあわせている。 |
|
|
■解説
五頭竜を祀る竜口明神の祭神は玉依姫命だが、御神体は木彫りの五頭竜です。その五頭竜の彫刻には、養老7年(723)江の島の岩窟にこもった僧泰澄(683~768)が、毎日船で来ては彫り続け、明神に収めたという伝説があります。また、竜口という名前は、山腹の岩石の形が竜に似ていて、江の島の方を向いて口を開いていたので付けられたといいます。江の島の弁財天は厳島、竹生島の弁財天とならんで、日本の三弁財天の一つに数えられています。江の島は、鎌倉時代のころまでは全島が信仰の対象とされて、みだりに島へ渡ることはできないようになっていましたが、江戸時代には弁天信仰の地として栄え、浮世絵などで見ると、大変な賑わいです。突然海底から浮き上がったといわれる江の島の誕生の不思議さと、古い時代の信仰の神秘性に、想像を絶するような力を持つ竜という空想上の動物が結び付けられ、語り伝えられることによって、弁財天への信仰がさらに高められてきたのでしょう。 |
|
 ■伝承 水を飲みに出た竜 |
|
|
足柄上郡中井町井ノ口の米倉寺には、左甚五郎が彫ったという「阿(あ)の竜」「吽(うん)の竜」がある。
二頭の竜は、太い丸柱をのぼるようにからみついているが、からだはバラバラにきりはなされている。 それでも竜は、生きているように、阿の竜は口をくわっとひらき、吽の竜はくやしそうに歯をくいしばって目をらんらんと光らせ、今にも飛びかかってきそうである。 むかし、寺のちかくに一人のばさまが住んでおった。 ばさまは寺の竜をおそれて、寺参りにいってもそこそこに帰ってくるのだった。 ある年の夏だった。 米倉寺から葛川にかけての田や畑が、なにものかに荒らされることがあった。 「おれたちが汗水たらして作った稲や野菜畑を荒らすなんてとんでもねえ」 「それも、いつも決まったところだ。寺から葛川までのあいだにある田や畑だ。いったいだれのしわざだ」 村では、竹槍を持った元気のいい若者を立たせて見張っていたが、なんとしてもつかまえることができなかった。 でも、野荒らしは続いていた。 それも、作物をぬすんでいくのではない。 作物をなぎたおしていくのだ。 その後が一筋の道のようになって残っていた。 「まるで大蛇の通ったあとのようじゃ。 それに二つの道ができている」。 村人は、なぎたおされた稲をおこしていた。 雨がいく日もふらないと、野荒らしははげしくなった。 ある夜のこと、ばさまが、里へいって葛川ぞいに帰ってくると、川の中で水しぶきをあげて泳いでいるものがいる。 「こんな夜にいったいだれだろう。村の若い衆かな」 ばさまは、木のかげにかくれてうかがっていた。 川の中には、火の玉のように光るものが四つ動いている。 しばらくすると、何か黒い大きなものが水しぶきをあげて川から上がり、からだをうねらせて畑の方へ向っていった。 「あっ!りゅ、竜じゃ。米倉寺の竜じゃっ!」 ばさまがさけんだとき、黒雲がとつぜんまき起こり月をかくし、 あたりをやみにしたかと思うと、濁流がうなって流れてきた。 ばさまは、命からがら家へ帰ったが、つぎの日は、昨夜のことがうそのように空はカリッと晴れていた。 ばさまは、昨夜、葛川で見たことを村の衆に話した。 「まさか米倉寺の竜が。あれは彫りものの竜だぜ。それが川へ水を飲みにくるなんて」 と、だれも信じてくれなかったが、ばさまがまちがいなくこの目で見たというので、寺へ行ってみることにした。 ばさまは、こわがって行こうとしなかったが、むりやり連れていかれた。 おそるおそる竜のところへ行ってみると、竜のからだはびっしょりとぬれ、田や畑のどろがついていた。 「や、やっぱり野荒らししていたのは竜だ。きっと葛川へ水を飲みに出たのだ」 ということになって、村人は、竜が水を飲みに出られないようにと、目に角釘を打ちこみ、からだを切れぎれにしてしまったと。 |
|
|
■解説
この話しの竜は左甚五郎が彫ったといわれていますが、江戸時代の名工左甚五郎の彫刻には、しばしばこういう伝説が語られています。川崎市幸区下平間の称名寺の山門にも、左甚五郎作といわれる竜がありました。戦災で焼失してしまいましたが、この竜にも野荒らしの伝説が語られていました。むかし、寺の近くの田畑が何者かに荒らされる夜が続いた。村では見張りを立てたが、犯人を突き止めることができなかった。ある日、村人の一人が称名寺の前を通ると、山門の竜に泥が付いていた。その泥の跡は田から続いていたので、竜が野荒らしをしたということになり、動けないように目に五寸釘を打ち込んだ。横浜には竜にまつわる興味ある話が伝わっています。中区から磯子区にかけての地形を、昔の人は竜が波をけって海底から躍り出た姿に見立てていたのです。磯子区滝頭の滝頭山蜜蔵院、同区岡村町の泉谷山竜珠院、南区堀ノ内町の青竜山宝生寺同区蒔田町の南竜山無量寺、中区元町にあった海竜山増徳院(現在は南区平楽にうつっています)がそれぞれ竜の体の各部分に当たりそのため山号または寺名に必ず竜の字が用いられているといいます。どの寺が竜のどの部分なのか、現在は、はっきり伝えられていませんが、滝頭という地名は竜頭から発したといわれ、滝頭山は昔は竜頭山と呼ばれていたようです。また竜珠院の珠は玉、すなわち目を表すと伝えられています。この五寺は、五竜山とも総称されていました。宝生寺の池には、夜になると青竜が水を飲みに来て、夜が明けると帰って行った。という伝説が伝えられています。 |
|
 ■龍泉伝説 |
|
|
彦山は善正が山を開き、忍辱(にんにく)が後を継いで、神仏の教えを広めたが、そのあとを継ぐ者がなく、ながく荒れるにまかされていた。
やがて、法蓮という僧が出て忍辱の教えを興したので衆徒は千人にのぼり、中興の祖といわれる。 法蓮は宇佐氏で、宇佐郡小倉山で苦修連行し、兼ねて医術をおさめて多くの人びとの病気を直した。 その徳風は文武天皇の耳にも達し、大宝三年(七〇三)に詔を発して法蓮の功績に対して豊前国の野四十町を賜った。(「続日本紀」にある)。 ところが、法蓮の真の願いはまだまだ大きく、このあたり一帯の人びとが豊かに暮らせることであった。 そこで、如意宝珠を手に入れ、その力で広く生活に悩んでいる人びとを救おうと考えたのである。 するとある夕方のこと、空中から声があって、彦山の窟に摩尼珠があり、神が出し惜しんで守っているが、熱心に求むれば得ることができるであろうという。 法蓮は喜んで山中を回ると、多聞窟というのがあった。 守護神は毘沙門天の化身であり、福徳の名が四方に知られているので、そう名づけられたものである。 窟の岩は光り輝き、木の枝はおもしろく、流れ出る水は円く流れて岩をうるおしている。 それより先、大宝元年(七〇一)八幡大神は唐に渡り三年経って帰って来たが、小倉山に登り地主神の北辰に対して「自分はここに住んで、あなたと一緒に人びとの利益をはかりたいが、どうだろう」とたずねた。 北辰は承諾して「西方に山があって、その山の彦山権現は岩窟に玉を埋め、一方の金剛童子に守護させている。 その玉を求めてきて、人びとを窮乏から救いなさい」ということであった。 八幡大神は彦山に向う途中、香春明神に会って相談した。 すると香春明神は「岩窟の玉のことはよく知っている。今は法蓮という者が玉を得ようとして修行している。彼に頼みなさい」という。 八幡神はさっそく老翁に化けて般若窟に出かけた。 法蓮は老翁に会って、神の化身であることを知っていたが、「どこの人か」とたずねると、老翁は「近くの年寄りです。あなたの弟子にしていただきたくて来ました。しかも、あなたにお願いがあります。」と答えた。 法蓮が「何ぞや」というと、老翁は「もしあなたが玉を手に入れたら私に下さい。他に何も望みません」というのである。 法蓮はその願いを受け入れた。 法蓮と老翁はますます修行を積むと、予定の一二年にならないのに、霊蛇が玉を握り岩窟を破って現れ法蓮に与えた。 法蓮は両手で衣の左袖をひろげて押しいただいた。この窟を玉屋というのはそれからのことである。 それ以後この岩窟の穴からは、常に清水が湧き出て、どんな干天でもかれることはなく、体にひたせば病気は治り、飲めば寿命は延び、天下に異変があるときは必ず濁るというのである。 法蓮は、この玉を得たのは彦山権現の賜と考え、まず上宮に登り、次いで宇佐に行って神徳に感謝の意を表しようとした。 二〇余町ばかり行くと、老翁がひざまずいて「宝珠を私にください」という。 法蓮は与えるには惜しいと思う気持があり、ことわった。 老翁は怒って「僧が約束を破るとは何事か」とののしったので、そこを師忘れ坂という。 それでも法蓮は与えたくない。 そこで老翁は法蓮に向かって実際に与えなくてもよいから「お前にやる」といってくれと頼んだ。 法蓮は黙っていることができなくなって「お前にやる」といったところが、玉が飛び出して老翁の手中に落ちた。 老翁は望みがかなえられたと、喜びいさんで走り去った。 法蓮はたとえ神のすることでも玉を奪い返そうと決心し、はるか前方に向かって火印を結ぶと、猛火が四方より燃えがり老翁は逃げるところがない。 したがって、その地を焼尾という。 ところが老翁は、空中に舞いあがって去った。 法蓮もまた飛んで、下毛郡諌山郷猪山(大分県山国町)の頂上から、大声で老翁の悪口をいったので、その声は伊予国の石鎚山まで聞えた。 さすがの老翁もこれには閉口し、金色のタカとなり、一匹の黄犬をつれて猪山まで引き返して来た。 そしていうには、「私は八幡である。昔は三種の神器で万民を安らかに暮らせるようにしたが、神となった今では、この一つの玉で百王を守りたいので許してもらいたい。 私がこの玉を得たら、宇佐宮に安置して地鎮とし、寺を建てて弥勒菩薩を祀り、あなたを寺の主にして恵を広くいつまでも続けたい」と述べた。 法蓮も異存があるわけでなく、石の側に立って和解した。それで、その石を和典石という。 |
|
 ■伝承 阿蘇の池の大龍 |
|
|
あと一人の名僧を臥験といい、般若窟で千日の修行の後、その力を試そうと、岩窟の前の切口三尺くらいのサクラの木を左右に縄のように練った。
それでも、その木は花や実をつけて茂ったので臥験は木練上人といわれた。 上人はやがて阿蘇山に登り、そこにある池が光り輝き、清く澄んでいるのを見て、池の主に会いたいと思った。 そこで、般若経を一生懸命に唱えていると、まずタカが現れ、更に僧侶・小竜・十一面観音が次々に現れたが、その一つ一つを池の主ではないとしりぞけ、お経を唱続けた。 やがて山は動き池は騒いで、九頭八面の大竜が出現した。 九頭にはおのおの三つの目を持っており、火炎をはき、そのはく息は大風のようであった。 上人は、竜にのまれると思い、念力をこめ持っている金剛杵を大竜の正面の三つの眼をめがけて打ちこんだ。 すると、竜は姿を消し、四方はあまねく晴れわたった。 上人は、池の主に会う願いを達したと山を下りかかる、にわかに大雨が降って、川は洪水になり、渡れないので山中の道を探した。 すると一軒の小屋があり、一人の若い女性がいるので泊めてくれと頼むと、快く承諾した。 上人が裸になって濡れた着物をかわかそうとしていると、女性はそれを見て、自分の着物を着せようとした。 上人は、行者にとって女性は不浄のものだから、その着物はつけられないとことわった。 すると、女性は怒って仏様は慈悲平等の心を教えていて、浄、不浄などをいわないといい、上人がことわるのを無理に着せようとした。 そうしている間に上人に欲心が起こり、まだ知らない男女の交わりを試そうと女人を押えつけた。 女性は抵抗して、まず口を吸えといったが、上人は自分は日夜、口で秘密真言を唱える身だから、それはできないという。 しかし、女性はそれでは目的が達せられないというので、しかたなく上人が口を吸ったとたん、舌をかみきられた。 上人は気絶してその場に倒れ、女性は大竜になって天に昇った。 上人が意識をとりもどしてあたりを見ると、女性も家も自分の舌もなく、山中に独り取り残されていた。 上人は犯した罪を悔い、不動明王に念じて舌をもとどおりにして下さいと一心に念じていると、一四~五歳くらいの童子が出て来て上人の舌をなでた。すると舌は元どおりになり、心身ともに安らかになった。 そのとき空から声があり「御岳に登って実体を拝すべし」という。 そこで上人はただちに御岳に登ると、再び空から声があり「眼根に支障があるから本物を見ることが出来ないのだ」という。 そこで、上人は印を結びひたすらひたすらざんげの行をしていると現れたのが十一面観音の姿である。 上人が望んだ池の主の実体で、仏の慈悲によって人びとの幸せを広めようとする姿である。 上人は欣喜雀躍し、礼を言って山を去った。 |
|
 ■龍になった甲賀三郎 / 信濃の民話 |
|
|
むかし、立科山のふもとに、太郎、二郎、三郎の兄弟がすんでいた。
年ごろになると三人は嫁さんをもらったが、中でも末の三郎は、この里では見かけぬ美しい人を妻にすることができた。 太郎と二郎は、三郎の幸せがねたましくもあり、美しいその妻をほしくもあり、ある日、悪い考えをおこして三郎を山の狩に誘いだした。 立科山の奥には、人穴という大きな穴があった。 石をなげこむと、ごーんと音がして底しれぬ深さの穴である。 その穴の前までくると、太郎と二郎は三郎にむかっていった。 「三郎。この穴はどのくれえふけえだべ。」 「三郎。おめえ、この穴さへえってみな。」 気のいい三郎は、兄たちのはかりごととは知らず、藤蔓につかまって穴の奥へおりていった。 「それ、うまくいった。つなあきれ。三郎を落とせ!」 二人の兄は、さっそく山刀で藤蔓をきりおとし、とんとん山をかけくだっていくのだった・・・。 その日から、美しい妻の三郎をよぶ声が山々をわたるようになった。二人の兄は三郎の妻をひきとめ、わざとやさしい声でこんなことをいった。 「へえ(もう)、三郎は熊にでもくわれてしまったべよ。三郎のことはあきらめて、おらたちのとこさくるがええ・・・。」 「たまげることはねえ。生きてるもんなら、そのうちけえってくるずら・・・。」 しかし、三郎の妻はきちがいのように山へかけだして、そのまま見えなくなってしまった。 「三郎やーい。三郎やーい。」とよぶ悲しい声だけが、昼も夜も遠い山の向こうから聞こえてきたが、それも三日、四日とたつと、だんだん細く小さくなって、しまいには聞こえなくなってしまった。 ふかい人穴へおちた三郎は、ふしぎに命が助かった。はじめて兄たちにだまされたことを知ると、なつかしい妻のことが思われて胸がはりさけそうになった。 けんめいに穴から出ようと、暗い地の底をはいずりまわっていると、急に目の前が明るくなって一人の老婆が現れた。 「地の上のお方よ。さあ、この餅を食べていきなされ。」 老婆は左手に粟餅をさしだし、右手で一筋の道をゆびさした。 まず三郎がその餅を食べると、今まであれほど思いつめていた美しい妻のことも忘れてしまった。 三郎は老婆のいわれるままに、とぼとぼと一筋の道を歩いていった・・・・・。長い時が流れて、やがてひろびろとした地下の村里にでた。 みわたすと、遠い山のすそ野には雪が降り、村人は正月を祝っていたが、近くの村には梅が咲き、うぐいすがないていた。 むこうの村では田植えをやり、田の草をとっていると思うと、こちらの村では稲をかり、栗をひろい、子どもたちは鹿を追ってもみじの山をかけめぐっていた。 三郎が村に入ると、大人も子どもも集まってきた。 「お武家さまが来た。りっぱなお武家さまがきた。」と、口々にさけんで、村人たちは三郎を美しいお姫さまの御殿へつれていくのだった。 三郎はお姫さまと一緒にくらすことになった。かわいい子どもが生まれて、いつか、9年の年月がすぎていった・・・。 ある日、一人静かに本を見ていた三郎は、この地の下の国の他に、地の上の国のあることを知った。 いろいろと思いをめぐらすと、ふと、遠い昔に忘れさった美しい妻の顔がよみがえってきた。 獲物をおってかけめぐった立科山のことも、ありありと目の前にうかんできた。三郎は急に悲しくなって、はらはらと涙をこぼした。 するとお姫さまがそれを見つけ、おどろいて三郎のそばへやってきた。 「三郎!なぜ泣いているの。なにがそんなに悲しいですか・・・。」 そこで三郎は、今までのことをのこらずうちあけ、手を合わせて頼むのだった。 「一日でも良いから地の上へ返しておくれ。どうか、地の上へかえる道を教えておくれ・・・。」 お姫さまはしばらくもの思いにしずんでいたが・・・ 「お前の気持ちはよくわかります。地の上へいくまでには長い年月がかかるけど、それでは九つのおむすびを持ってでかけて下さい。」と、自分でおむすびを作って三郎にもたせてくれた。 そのおむすびは一つ食べると、長い間何も食べないですむというふしぎなおむすびであった。 お姫さまは泣きながら、三郎を村はずれまで送っていった・・・。 どれほどの年月が流れたのか・・・。美しい妻の名を呼びながら、三郎は夢中でくらい穴の中からかけていった。 眠りもせず、休みもせず、それでも不思議なおむすびを食べたせいか、すこしも疲れずに走っていった・・・。 長い長いたびを続けて、三郎はやっと地の上に出た。浅間山のすそ野、真楽寺の大沼の池の中から三郎は姿を現した。 すると、通りかかった子どもたちが、わーっと叫んでにげだした。 「蛇だ。蛇だーっ。」「おっかねいよう。とてつもねえでっけえ龍がでたよう。」 その声におどろいて、自分の姿を水にうつすと、いつのまにか三郎の体はおおきな龍にかわっていた。変わり果てた姿を悲しみ、三郎はしばらくその池のほとりで泣いていたが、それでもなつかしい妻を一目見ようと立科の山をさして池をはい出していった。 ちかずの森まできて後をふりかえると、自分の尾はまだ大沼の池の中にあった。 立科の双子の池にたどりついて、また後ろをふりかえると、自分の尾ははるか遠い前山の村里の高い松の木にかかっていた。 しかし、美しい妻の姿ももと居た家も里も見つからず、三郎はおーおー泣きながら、妻の名をよんで立科の山をめぐった。 しまいには狂ったようにあらあらしく山から山を走ったので、山の木はばさばさと砕けて四方にちり、おそろしい地鳴りが立科山から八ヶ岳までひびきわたった。 三郎の泣き叫ぶ声は黒雲をよび、山も谷も深いキリで包んでしまった。 ただ、西の諏訪湖のあたりに一筋の光りがさして、そこだけがまぶしいほどに明るく見えた。 三郎は我にかえって高く高く首をもたげた。 「おお、あれこそなつかしい妻の声だ。」 三郎はたちまち黒雲のうずを巻き起こし、どどーっと空をとんで一息に諏訪湖をさして飛び去っていくのだった・・・。 かつて、三郎を失った美しい妻は、悲しみのあまり諏訪湖へ身をなげ、そのまま龍の姿になって湖の底にすんでいたという。 今瀬も冬がきて諏訪湖に氷がはりつめると、上の宮のある中州村の湖畔から下諏訪の下の宮の浜へかけて、一夜のうちに氷の山脈ができるのは、美しい妻のところで1年、そして地下のお姫さまのところへ1年とかよっていく三郎の通る路だともいわれている。 |
|
|
■解説
この「甲賀三郎伝説」は民話として取り上げられていますが、口伝民話というよりは、南北朝時代の説話集「神道集」におさめられた諏訪明神の蛇体の由来の物語です。 その神道集の「諏訪縁起の事」によると、甲賀三郎は安寧天皇から五代の孫で、近江国は甲賀郡の地頭をしていた甲賀権守諏胤(こうがごんのかみよりたね)の三男で、その名を甲賀三郎諏方(こうがさぶろうよりかた)といい、その妻は、大和の春日郡にある三笠山明神の春日権守の孫の春日姫のことだということです。 本文は大変長くて、民話の方ではかなりカットされています。三郎が人穴に落ちてから再び地上に出てくるまでに、どれだけの地底の諸国を行脚したかというと、好賞国から草微国、草底国をはじめなんと73の国にも及んでいます。 その中で、民話に出てくるお姫さまは73番目の維まん国(ゆいまんこく)の維摩姫のことです。また9つのおにぎりと民話では語られてますが、説話の方では、維摩姫の父親が鹿の生肝でつくった餅を千枚もらって、恋しい春日姫に会うためにひすら地上の日本を目指しやっとの思いで浅間の嶽に出た。 しかしその姿は人間ではなく龍蛇だった。だが不思議なことに、僧侶たちが人間の姿に戻れる呪文を教えてくれたので人間の姿に戻ることが出来、無事春日姫に会うことができた。 この時の僧侶たちは、実は三郎を守護する白山権現、富士浅間大菩薩、熊野権現、日吉(ひえ)大明神、山王大明神、松尾大明神、稲荷大明神、梅田大明神、広田大明神、王城鎮守の大明神、そして三郎の氏神である近江国の鎮守の兵主(ひょうず)大明神だったそうです。 その後二人は、中国の平城国にわたり、早那起梨の天子にあって神道の法を授けられた。「高天ガ原に神とどまり、神々の末孫神ろぎ神ろみの命をもって」と受けて虚空を飛べる身となった。 また「国内の荒ぶる神たちを神払えに払う」と受けて、悪魔・外道たちを他へ退ける神通力を会得した。また「科戸の風の天の八重雲を吹き払うごとく」と受けて、いながらにして三千世界を見通す徳を得た。「焼釜の利釜をもって生い茂った木の根元を打ち払うごとく」と受けて一切世間の有情非情が心の内に思うことを空でさとれる徳を得た。 「大津のほとりにいる大船の舳(へさき)の綱を解き放し、艫(とも)の綱を解き放して、大海の底に押し放すごとく」と受けて、賞罰覿面に有効な、衆生を育てる徳を得た。 その後、氏神である兵主大明神の使者が来て、三郎は諏訪大明神という名で上の宮として現れ、春日姫は下の宮として現れたということです。 また、維摩姫もこの国に渡ってきて浅間大明神となり、三郎を陥れた次郎は若狹の田中明神となり、太郎は下野の国の示現太郎大明神になり、父甲賀権守は赤山大明神、母は日光権現となったと書かれています。 |
|
 ■信濃には神無月はない |
|
|
毎年十月になると神様が出雲国へ集まって国造りの相談をすることになっておりました。
そこで十月はどこの国の神さまもお留守になり、神さまがいない月というので神無月というようになりました。 ところがある年のこと、信濃国の諏訪の龍神様の姿だけがどうしてもみえません。 そのうちに見えるであろうと待っていましたが、しまいには待ちくたびれてしまい、「信濃の神さまはどうした、病気か、それとも遅刻か、いつまで待たせる気だ。」 と、神々たちがさわぎ出しました。 すると天井からでかい声がしました。 「わしはここだ。」 「紅葉と龍」 神様たちはどこだどこだと天井をふりあおいで真蒼になりました。 天井の梁に樽(たる)ほどもある龍がきりきりと巻きつき真っ赤なへら(舌)をぺろぺろ出しているではありませんか。 「信濃国は遠いので、こういう姿でやってきたのだ。わしの体はこの家を7巻き半しても、まだ尾は信濃の尾掛の松にかかっている。部屋に入って座らずと思ったが、神々がたを驚かしても悪いと思って天上にはりついとった。何なら今からそこへ降りていこう。」 というなり龍神様はずるずると天井からおりはじめました。 神様たちは蒼くなって、「いやいやそれには及ばん、なるほど信濃は遠いで大変であろ、これからはどうかお国にいて下され。会議の模様や相談はこちらから出向いてしらせにいく。」と、あわてふためいて手をふりました。 龍神様はからからと笑って、「そうか、それは有り難い。」とみるみる黒雲に乗って信濃国の諏訪湖へおかえりになり、湖のそこ深く姿をけしました。 それだから、信濃国には神無月はないといいます。 |
|
|
■解説
なんと、家を7巻き半し、更に出雲から信濃までの距離をもってしても尚、まだ尾は信濃の尾掛の松にかかっていると言うのですから、その大きさと言ったら想像を絶するものがありますね。それでは、諏訪大明神が龍であるお話しを続けたいと思います。 諏訪大明神画詞(すわだいみょうじんえことば)南北朝期(1356年)に製作された諏訪社最古の縁起書(縁起5巻、諏訪祭7巻からなっている。残念ながら図書館、本屋、古本屋と当ってみたが見つかりませんでしたので、黒田日出男さん著「龍の住む日本」から引用させていただくと、諏訪大明神は軍神・戦神であると紹介しています。 それは二度に渡る蒙古襲来のときに、諏訪大明神は龍体となって現れ、なんと日本軍と一緒になって闘ったというのです。 後宇多院の御宇、弘安2年(1295年)の夏のことであった。諏訪社で神事が行われていた時、日中に異変が起こった。大龍が雲に乗って西へ向ったのである。参詣の人々が目を凝らしてみると、雲間に檜皮(ひわだ)の色がひらひらと見えた。一頭の龍であろうか、それとも数頭の龍であろうか。首尾は見えなかった。これは、諏訪大明神が「大身」つまり龍体を現して、本朝に※贔屓(ひいき)しようとする姿である。この出現がどのようなしるしであるのかははっきりしない。 実はこの後宇多院の御代のはじめ、文永11年(1274年)10月の蒙古襲来の時には、諏訪大明神が発向したので、蒙古の軍船が漂倒したことがあったのだけど、これほどのことではなかった。 そこでこの度はいかなることが起こるであろうかと疑っていたところ、やはり大元の将軍夏貴らに率いられた大軍が襲来してきた。 六百万艘の船を和漢の中間の洋上につらねて、先陣が数万艘来朝し後陣の続くのを待っていると聞こえてくる。 しかるに同年6月25日、悪風がにわかに吹いてきて、蒙古軍の兵船は、あるいは転覆し、あるいは破裂してしまい、軍兵はみな沈没して、日本侵略は失敗に終わった。 ・・・この尊神化現の大龍の姿は、博多の津で同時に出現されたので、石築地の工事のために発向していた軍卒らも、それに力を得て蒙古軍を責めたのだとは、後から聞いたことである。・・・という。 中世時代、蒙古の勢力が強くて、日本は大変脅威に感じていたのは事実で、蒙古襲来絵詞によると、二度の元寇のうち、二度目の蒙古軍の規模は相当大きかったようです。かたや鉄砲を使う蒙古軍に対し日本軍は刀や長刀しかなかったので、諏訪の明神さま初め神々様たちの加勢がなかったら歴史は変わっていたかも知れません。 まさに「神国日本」といわれる所以と言えそうです。 ■贔屓(ひいき) ここで贔屓という言葉が出てきましたので、龍の九匹の子どもについて面白いお話しがありますのでご紹介します。池上正治著「龍の百科」によりますと、明代、文人の楊慎の編纂した「升庵外集」に「俗説では、龍は九つの子を生む。それは龍の形をなさないが、それぞれに好むところ(役割)がある」として以下のように解説しているそうです。 一番目は贔屓(ひいき)といい、形はカメに似て、重いものを負うことを好む。いまは碑の下のてつとなる。 二番目はり吻(りふん)といい、形はケモノに似て、遠くを望むことを好む。いまは屋上の獣頭となる。 三番目は蒲牢(ほろう)といい、形は龍に似て、吼えることを好む。いまは鐘の上の紐(ちゅう)となる。 四番目は(へいかん)といい、形はトラに似て、きわめて威圧的である。それゆえ常に獄門に立てる。 五番目は(とうてつ)といい、形は獣に似て、いたく飲食を好む。そのため鼎(かなえ)のふたに立てる。 六番目は(はちか)といい、形は怪魚に似ておりはなはだしく水を好む。それゆえ橋の柱に立てる。 七番目は(がいさい)といい、形は龍に似ており、殺すことを好む。それゆえ刀の環(たまき)に立てる。 八番目は(しゅんげい)といい、形は獅子に似ており、きわめて煙や火を好む。それゆえ香炉に立てる。 九番目は(しょう図)といい、形は大カエルないしタニシに似て、閉じることを好む。それゆえ門の舗(ドア・ノブ)に立てる。 これらの龍の九つの子は、いずれも高貴な存在で、瑞祥を意味し、しかも、親の威光というわけでもないが、邪を退けて、安全を保つ役目をすると書いておられます。江島神社の奥津宮にある手水舎に、贔屓とみられる亀が柱の台座になっています。また普段何気なく使っている「贔屓」という言葉は、ここから来ているのだそうです。 |
|
 ■世界のドラゴンと竜(龍) |
|
|
世界中の神話・伝説にみられ、竜、ドラゴンとして呼ばれるもの、あるいは蛇の姿をしたものとして、その種類は膨大。(ドラゴンのもともとの意味も蛇(サーペントserpent)、または巨大な海の魚をさした言葉である)
主に荒れ狂う自然の力の象徴と考えられ、人間側に危害を加える存在として英雄に倒されるという形が多い。 ケルト神話には雪を降らせるドラゴンがでてくるのが興味深い。 スラヴ、ロシアなどでは3つ頭、三つ首のドラゴンが定番のようである。またマジャール(ハンガリー)の民話に出てくるドラゴンは複数の頭(7、12、24など)を持ち、数が多いことが強さの比喩になっているようである。頭の数が多くなることで強さをしめす同例に北欧の民話の妖精トロール等がある。 ヨーロッパ各地での名称は関連項目等を参照されたい。ドラゴンdragon自体の語源は古代ギリシャのドラコンdrakon(蛇、竜、巨大な海の魚) からきている。 ラテン語draconem(draco)は巨大なサーペント、古フランス語dragon、ゲルマンでdrakontos等。 またヘブライ語の旧約聖書の「蛇」を訳すためにも用いられた。あるいは「大きな海の怪物」タンニンtanninを訳すのにあてられたのだとも。 日本では「竜巻」(たつまき)という言葉があるが、細長く水上等から天へ伸びるその様に対し、アフリカ東部ではスワヒリ語でニヨカ(蛇の意)と呼ぶ。湖にいる大きな蛇が天へ登っているのだという。ここには全く同種の感性が働いている。 中国北部に黒竜江という河があるが、この河の氾濫は黒竜が起こすというのでこの名で呼ばれているという。 また優れた馬が跳ぶ様を「玉竜」と表現した詩もある。 ヨーロッパでは竜と火、というイメージが強い。銃をあらわすガンGUNという語もDragonの語尾からきているという。 また、近世に出現した銃火器を装備した騎兵をドラグーンDragoon(竜騎兵と訳される)と呼んだりした。 「恐竜の化石=悪魔」とした伝承がヨーロッパにあったが、世界各地で神や巨人などのものとされる伝承が多い。 また、まさしく漢方では動物の化石骨を「竜骨」として薬にした。海のものだが「竜涎香」(りゅうぜんこう)というものもある(クジラ由来)。 不思議なものが竜のもの扱いされるということもみられる。(竜珠など) ドラゴン(魔物)を倒してお姫様を救うという、英雄物語の鉄板のモチーフは、現代においても失われることはない。 |
|
|
■アジ・ダハーカ 【イラン:ゾロアスター教:ドラゴン,竜】 Azi Dhaka
イラン、ザラドゥシュト(ゾロアスター)教の伝承における怪物。悪神アンラ・マンユの率いる魔物のひとつで、三頭・三口・六眼の竜だという。アングラ・マインユ(アーリマン)の怪物として表現されたものともされる。アジ・ダハーカは地上の王座を奪い支配した。欠乏と貧困、飢えと渇き、老年と死、悲しみと嘆き、極端な暑さと寒さ、悪魔と人間の混淆をもたらしたという。しかし善神アフラ・マズダの息子アータルと戦い敗れた。竜は深い大洋の底へ引き渡されたか、高い山の上に繋がれたという。アジ・ダハーカは世界の終わりには、そこから逃げ出し、人類の3分の1を殺戮することを運命づけられているという。 ■アナンタ 【インド,ヒンドゥー:蛇神,竜王,ドラゴン】 Ananta インド、ヒンドゥー教のナーガ、蛇王(ナーガラージャ)。「アナンタ」は「無限なるもの」「終わりのない」の意味だという。またはシェーシャという別称か、そのナーガと同一視されるようだ。ヴィシュヌが世界創造の合い間に休む時、この1000の頭のナーガの上に横になるという。シェーシャの頭部(コブラ蛇である)は日よけにもなるが、あくびをすると地上に地震がおきるという。余談だが、2009年、時計メーカーのセイコーがこの名称を使った「アナンタ」という製品を作った。遊戯王カードに「邪龍アナンタ」があるが本来、邪龍ではない。 ■アンタボガ 【インドネシア:ドラゴン,竜】 antaboga またはヒャン・アナンタボガ、デワ・アンタとも。インドネシア、バリの伝承。地球の7層にわたって君臨するサン・ナガラジャ(蛇の大王)。インドのアナンタ竜にあたる。世界のはじまりには、この巨大な蛇しかいなかったが、瞑想によってベダワンという亀を創り出し、この亀の甲羅の上に2匹の蛇と、地下世界の蓋である黒い石がのっていた。ある民話ではデワ・アンタの流した涙が卵に変わり、その卵から美女デヴィ・スリや、豚(猪)の魔物サン・カラブアット、サン・ブドバイが生まれた。 ■イエロ 【オーストラリア先住民族:オーストラリア東南部:大蛇】 オーストラリア先住民族の伝承。オーストラリア東南部において巨大な蛇、またはウナギとして語られる。別の地域ではカリイと呼ばれる。赤い毛の生え、大きな頭、大きな口を持ち、口から水が勢いよく流れだすという。このような蛇の霊と子孫である多くの生きた蛇たちという伝承は、オーストラリア先住民族に広く分布し、 1.巨大で空想的な姿 2.水中に住み、水を飲みこみ、せき止め、再び吐き出す 3.蛇に呑みこまれた人々、死ぬかあるいは呪力と健康を獲得 するという3つの共通する特徴を持つようだ。 ■イルルヤンカシュ 【ハッティ:ドラゴン、竜】 illuyankas ハッティの神話にでてくる竜形の神、魔物。嵐の神と戦い、一度は勝つが、嵐の神は復讐のため女神イナラシュに罠を仕組ませた。イナラシュはぶどう酒、果物のジュースなど様々な飲み物を甕になみなみと満たし、イルルヤンカシュやその子供たちに飲ませた。住みかに帰れなくなるほど飲み食いした彼らを、人間のフパシャシュが隠れていた小屋から飛び出してきて強力な縄で縛り上げた。そして嵐の神が竜たちを殺した。女神イナラシュが協力を頼んだフパシャシュは、協力する条件で女神と一晩ともに過ごした。イナラシュはフパシャシュが神の力を得たかもしれないので彼をタルッカ国の高台の家に住まわせ窓から外を見ることを禁じた。それは彼が妻子をみかけて家族のもとに帰りたくなることがないようにするためだったが、フパシャシュは禁を破って家族のもとに帰りたいと言ったのでイナラシュは彼を殺した。同じ粘土板には違うイルルヤンカシュ退治の物語も書かれていた。その話では一度敗れた嵐の神はイルルヤンカシュに心臓と眼を奪われた。嵐の神は人間の娘との間に男子をもうけ、後にイルルヤンカシュの娘と結婚させた。嵐の神は息子に奪われた体の一部のことを聞き出させ、それらを取り戻した。元の体にもどった嵐の神はイルルヤンカシュを倒し、自分の息子も殺した。 |
|
|
■インバヌマノリュウ 【日本:ドラゴン、竜】 印幡沼(印旛沼)の竜
日本・千葉県の伝説に出てくる竜。印幡沼の主で巨大な竜だったという。沼のほとりの村が気に入り、時々若者の姿で遊びに行っていた。村人は竜が化けた若者に首のところにあざのようにうろこが残っているので見分け、ごちそうや土産物でもてなした。ある日照りの激しい年、竜は村人が困っているのを見て黒雲を呼び、沼をまっぷたつに割って天にあがった水柱の中で、目を光らし天をにらんでいた。すると大粒の雨が降り村人が喜んでいると、轟音とともに稲妻が三方に走り、黒い固まりが3つ飛び散った。大雨はしばらく降って、村人は沼の主の竜神のおかげだと喜んだ。すると白い髭の老人がやってきて「お前たちは幸せ者だ。天の大竜神は沼の竜に勝手に雨を降らさないよう止めていたのだ」と言った。村人たちは、自分たちのために天の大竜神に体を裂かれた沼の主に感謝し、竜の亡骸をさがすと角、腹、尾に3つにわかれていた。それぞれの場所に竜角寺、竜腹寺、竜尾寺を建て供養した。 ■ヴァースキ 【インド、ヒンドゥー:蛇神、竜王、ドラゴン】 Vasuki インド、ヒンドゥー教のナーガ、蛇王(ナーガラージャ)。神々が不老不死の飲み物、霊薬アムリタを造る乳海攪拌の時、棒の代わりに使われたという。後にシヴァ神が魔よけの帯に使ったという。ナーガは人間の姿や多頭の蛇、コブラ蛇の姿で描かれているものもある。 ■ウムガルナ 【アフリカ:アマ・ズールー民族:大蛇】 アフリカ南部、アマ・ズールー民族の伝承の大蛇。アマ・ズールー民族では大蛇ウムガルナが住んでいるというので、その湖の水を使うことを恐れているという。 ■ウンセギラ 【北アメリカ:スー族:水蛇】 Uncegila 北アメリカ先住民のスー民族の神話伝承に怪物、魔物、水蛇。一種のドラゴン、竜といえるだろうか。火打ち石も鱗で覆われた巨大な雌の水蛇。心臓は水晶で目は炎を放つという。海に棲んでいるが年に数回ネブラスカ州まで大津波を伴い泳いでいき、すべての水を塩水に変え人間が使えないようにするという。ある二人の若者がこのメス蛇の弱点を知り、その動きを鈍くする魔法で武装し退治にいった。ウンセギラは二人をみて水から体を持ち上げた。若者の一人は蛇が動けないように呪文を唱え、一人は頭から7番目のポイントを撃って殺した。このことに太陽が喜び、視界をすべて乾かし大地を再び出現させた。水晶の心臓を手に入れた二人は預言の力を得たが無知な者に心臓を奪われ破壊されてしまった。(心臓に魔力があるという部分はファーブニルとの類似を想起させる) ラコタ・スー民族の伝説のウンセギラUnhcegilaは巨大な怪物、ドラゴンで人を捕まえて食べるという。人がいなくなるとウンセギラのせいにされるという。 ■エインガナ 【オーストラリア先住民族:虹蛇】 オーストラリア先住民族(アボリジニ)、ポンガポンガ民族の伝承で崇拝される虹蛇。虹蛇とは天空にかかる虹を、地上の水場と天を結ぶ蛇だと考えるもの。 |
|
|
■エキドナ 【ヘレネス(ギリシャ):女神,蛇】 Echidna
ヘレネス(ギリシャ)の神話・伝承の女神。半人半蛇。怪物、魔物たちの母。産みの親。名前は「蛇」の意味。ヘシオドスの著述にある。ポルキュスとケートーの娘。洞窟の中で生まれたこの女神は男っぽい気性の巨大な怪物で上半身は眼のきらめく頬の美しい女性、下半身は恐ろしい大蛇。人間にも不死の神々にも似ていなかったという。すばやい動きで、洞窟の中でいろいろなものを生のまま飲み込む。この洞窟は神々から住居として与えられたものでアリマと呼ばれ、ホメロスでは「テュポーエウスの寝室」と呼ばれている。夫のテュポーエウスとの間に多くの魔物、怪物を産んだ。 冥界の犬ケルベロス 頭が2つ、蛇の尾の番犬オルトロス(オルトス) スフィンクス(ギリシャのオイディプス物語の父はオルトロス) ネメアのライオン(ヘラクレスの12の試練、父はオルトロス) レルネー湖の水蛇ヒュドラ(父はテュパオーン) 魔獣キマイラ エキドナは百目巨人アルゴスに、眠っている時に殺されたという。ヘスペリデスの園の番人の竜、または蛇(オピス)のラドン(ラードーン)はエキドナと兄弟とも、エキドナの子ともいわれるようだ。 ■エクシュキュ 【サハ:ドラゴン、竜】 シベリア地域、サハ民族の伝承の大蛇。人間の国と川で区切られた向こう側の世界を支配している。燃える火の海を越えた、氷の丘の上の巣に棲んでいる。伝承物語の主人公の勇者を、死後の国へ連れていこうとする。「死後の馬に飛び乗れ。死に装束をつけろ。死後にとる食事を食べるのだ」と勇者にいうが、勇者に殴り殺されてしまう。エクシュキュが死んだ後、世界に太陽がもどり、野原に川があらわれた。 ■エレンスゲ 【エウシュカルドゥナック:ドラゴン,竜】 herensuge エウシュカルドゥナックの伝承にでてくる怪物。名前は「3分の1の蛇」の意。エウシュカルドゥナックの伝承におけるドラゴンといえる怪物。 ■オウリュウ(応龍) 【中国:神、龍】 応龍(鷹龍)/応竜(鷹竜)/ying long/おうりゅう/おうりょう 中国の神話の神、竜(龍)。竜は千年(または五百年)生きると翼をもち応竜(鷹竜)になるという伝承がある。中国の南の果ての霊山、恭丘山にいるという。もともと天上の神々だったが神と人間の戦いの時、人間に味方したため地上へ追放され、この山にとどまったという。水や風を自由に扱い風雨を司る神として人々に恩恵を与えていたという。また伝承では女神 女媧(ジョカ)と戦った敵とされているという。結局負けて服従したという。黄帝と蚩尤(しゆう)が戦った時、黄帝は女媧の助言で応竜が助けに呼ばれ、蚩尤の風伯(風神)、雨師(雨神)に対しより強い風雨の力で戦った。結局、蚩尤は倒されてしまった。神の蚩尤を黄帝たちと殺したことで、さらに天に昇ることを許されなくなったという。黄帝と蚩尤の戦いは「述異記」などにみられるが、別の助っ人がくる話もある。伝説の王、舜の治水の時にも、実際の治水を行った禹(う)が女媧の血筋であることから応竜を呼んだともいう。 また山海経にも応龍の記述がいくつか見えるようだ。第十四大荒東経には、大荒の南極に応龍が棲むという。図の注に「鷹龍 龍身有翼」とあるがあまり翼は目立たないようだ。文章では「応龍は蚩尤と夸父(こふ)を殺したので、天に復帰することができなくなった。ゆえに天下しばしば旱(ひでり)する。旱したときに応竜の形をまねると、やがて大雨がふり出す」 また「和漢三才図会」に「恭丘山に応龍がいる。応龍とは翼のある龍をいう。昔蚩尤と黄帝が争ったときに黄帝は応龍に命じて干翼の野を攻めさせた。また女媧はこれを乗物とした。禹帝が治水を努めたときにも応龍は協力した」とある。 ■カンナカムイ 【アイヌ:竜神,雷神】 kanna kamuy アイヌの神話伝承の竜神[龍神 Dragon Deity]、雷神。アイヌ語でカンナは「上(方)」、カムイは「神」の意味。霊場を守る竜神ともいわれるようだ。またオキクルミ(アイヌラックル)の父神の雷神でもあるという。クンネカムイという雷神の名前もみられる。(クンネkunne 黒い、暗い、の意味) |
|
|
■クエレブレ 【エスパニャ:ドラゴン,竜】 cuelebre
エスパニャの伝説におけるドラゴン。地底に通じている泉に棲むという。若いうちは、家畜や人間を襲い血を吸い、年を経て、鱗が大きく硬くなると、海へ出て財宝の番をする。喉が弱点で、そこを撃てば倒せる。一説ではヘレネス神話のラドンがこのドラゴンの由来だという。 ■クリカラ(倶梨迦羅) 【仏教,日本:竜王,不動明王】 倶梨迦羅/倶利伽羅/KURIKARA 倶梨迦羅竜王とも。日本、仏教の伝承。不動明王の変化身のひとつの竜王。サンスクリット語kulikaあるいはkrkaraの音訳。倶哩迦羅、倶力迦羅、古力迦、矩里迦とも書く。この名に関した名刀、名物「大倶利伽羅広光」がある。 竜王の形相は、不動明王の持ち物である利剣(煩悩を断つ智慧の剣)と竜の形にした羂索(けんざく 一端に金剛杵の半形を、他端に鐶[かん]をつけた五色の索条)とをあわせたものであるようだ。また、四足、黒色蛇身で、煩悩を焼き尽くす知恵を象徴する火焔に包まれ、盤石の上に立つ利剣に巻き付きその剣を飲み込もうとしている図像で表される。倶梨迦羅竜王を俗に倶梨迦羅不動と称するという。この竜身呑剣(-どんけん)の図柄は、日本での不動信仰の隆盛とともに広くみられるようになり、 刀身の彫刻、彫金細工、刺青(いれずみ)などに使用された。名刀の資料にあたるとこの倶梨迦羅がよくみられる。入れ墨模様は「倶梨迦羅紋々(-もんもん)」という。また、きりきり回りながら落ちることを「倶梨迦羅落とし」という。 ■コウリュウ(黄龍) 【中国:五行:神、霊獣】 黄龍/黄竜/こうりゅう/おうりゅう 中国の伝承で、五行思想において東西南北の中央に配される霊獣、神。黄huangは、黄色、土、黄金など意味する。また皇帝を象徴する。その場合爪は5本に描かれるようだ。金の都は「黄龍府」と呼ばれた。また年号にも黄龍は度々使われている。「黄龍の景観と歴史地域」という世界遺産がある。 五行は木・火・金・水・土の5つ。東・南・西・北・中央に方位が配される。青(緑)・赤・白・黒・黄の五色が配される。 ■コクギョクタイ(黒玉帯) 【韓国朝鮮:宝物,竜】 朝鮮、韓国・朝鮮半島の伝承の宝物。新羅第三十一代神文王(在位681-992)が死後、海龍となり倭人から国を護る父、文武王(在位661-681)が使わした龍から宝物、黒玉帯を受け取った。その時一緒に、不思議を成していた山の竹について、教わり作った宝物の笛が「万波息笛」(マンパシクジョク)である。神文王の子、孝昭王(在位692-702)は、子供、太子の時、この黒玉帯についてる装飾が龍だと見抜くことができた。「試しにひとつはずして小川に沈めればわかります」というのでそうすると、地が崩れるような大きな音とともに、装飾は巨大な龍になり天に昇っていった。その跡は淵になり人々は「龍淵」と呼んだという。 ■ゴリニチ 【ロシア:ドラゴン】 gorynich ロシアの伝説、民間伝承のドラゴン、竜。同様の語をゴリニッヒ gorynich 、ゴルィニシチェとも。ある物語では、邪悪な魔法使いネマル・チュロヴェクの甥で、魔法使いは皇帝の娘をさらい、このドラゴンと結婚させようとした。勇敢な王子たちが救出しようとしたが皆失敗した。門番のイワンがなのりでて皇帝から魔法の剣サモセクを与えられ、困難な旅のすえ皇女の元にたどりつき、魔法の剣サモセクに、巨人に変身した魔法使いとゴリニチは真っ二つにされた。 |
|
|
■ゴルィニシチェ 【ロシア:ドラゴン,竜】
またはゴルィヌィチ。ロシアの英雄叙事詩ブィリーナ等の伝承、民話にでてくる魔物、大蛇。名前はロシア語で山を意味するゴラーгораに由来する。3つの首、12の尾の大蛇で口から炎を吐き、2枚の翼で轟音とともに空を飛ぶ。人語を話すこともできる。英雄ドブルィニャに、一度目破れた時は「未来永劫広野で戦わない、血を流す争いをしない」と証文を書いた。しかし、その後すぐキーエフの都でウラジミール公の姫君ザバーヴシカをさらった。公の命でやってきてドブルィニャに、証文をたてにとられて、姫を連れ戻された。また巨人化する邪悪な魔法使いとその甥の竜 ゴリニチの物語では皇帝の姫をさらったので魔法の剣サモセクで真っ二つに斬られ退治された。山に対する畏敬の念が山の擬人化、神格を持ったともいえる勇者ゴルィニャ、またはゴルィヌィチとして語られる場合もある。スロベニア,ロシアでゴリニッヒ gorynichという竜人の魔物もいる。 ■ザッハーク 【イラン[ペルシャ]:蛇,竜王】 イラン[ペルシャ]の神話伝承、叙事詩シャー・ナーメ(王書)にでてくる悪王。蛇王。悪魔にそそのかされ、呪文で両肩に1匹ずつ蛇が生え、毎日人間の脳みそを食わせている非道の王。暴君竜王ザッハーク。在位期間が1000年という伝説の王。神話の魔物アジ・ダハーカ(竜[蛇]ダハーカ) の化身的にあつかわれる。ゾロアスター教伝承ではアンラ・マンユに創られたとも。王書でもアジュダハー(竜)はザッハークの別名のように扱われている。伝説上の王ジャムシード王の御世のおわりごろに登場する。バウリの地のクリンタ城で暴虐の限りを尽くしたともいう。バウリはバビロンのことで、アッシリアの王の侵略の記憶とも、自然の暴風の雲の擬人化だという説もある。伝承なので確定はされないだろう。砂漠の民、アラブの王マルダースの息子で、勇敢で軽率で大胆、「ベーワルアスプ」(ベーワルは数[近世ペルシア語で1万]) と呼ばれた。アラビア馬を1万頭所有。まだ王子だったある日の明け方、悪魔イブリースに悪の心に染まるよう呪文かけられた。悪魔に加担し、父王を落とし穴に落として殺し、王となる。さらに悪魔は料理人に化けザッハークに肉食や血を飲むことをすすめ、さまざまな美食を用意した。ザッハークが褒美をくれるというと「王の両肩に口付けさせてほしい」と言い、口付けし、目と頬をあてた。すると肩から黒い蛇が1匹ずつはえてきた。王は悲しみ、蛇を切り落としたがまた生えてきた。医師たちが治療、魔法をこころみたがだめだった。悪魔が医師にまぎれこみ「人間の脳みそを餌に与えればいずれ死ぬ」というウソを教え、多くの人間を殺すたくらみをした。イラン各地で争いがおき、ジャムシード王の威光の衰えのなか、竜の姿をした恐るべき王としてザッハークが王位を奪った。ジャムシードは逃げて100年隠れた。出てきた彼をザッハークは鋸で2つに切った。ザッハークはジャムシード王の姉妹、月のような美女アルナワーズ、とシャハルナーズを拉致し、殺害や略奪を教え込み、欺瞞と魔法を教えて邪に養った。毎夜、2人の若者が身分問わず王宮に連行され、料理人が治療の薬と称して殺して脳をとりだし蛇に与えた。 (心ある気高いイラン人2人が料理人として志願し、生贄の2人のうち1人を逃がし、ひとり分の脳に羊の脳を混ぜてごまかし、苦悩のなか被害を半分にした。助けた者が200人に達すると砂漠に住む彼らの許へ山羊や羊を送り助けた。彼らがクルド民族になったという) ザッハークは時々、妬みを抱くと兵士をひとり選んで「悪魔と共謀した」として殺した。また名高く美しい深窓の清い娘がいると有無をいわさず侍女としてはべらせた。王としての風習も道徳も信仰もないザッハークの余命が40年になった時、ザッハークは自分が成敗される悪夢をみた。国中の賢明な司祭をよびよせ、王の腰帯、玉座をだれが継ぐか答えよといった。正しく答えなければ死ぬ、とも。司祭たちはザッハークが倒される予見を告げるのに「正しく答えても、正しく答えなくても俺ら死ぬよね?」と悩んだ。ズィーラクという司祭の中でも賢く慎重なものが運命を全て語った。まだ誕生していないがファリドゥーンに倒されると。ザッハークは玉座から落ちて気を失い、気をとりもどすと公然とまた密やかにファリドゥーンを探させ、安らぐことも眠ることもなかった。その後、父や乳母代わりの牛ビルマーヤが殺されたファーリドゥーンは、鍛冶屋カーヴェの造った武器、予見通りの牛頭の鋼の矛を持って、ザッハークを倒しにエルサレムへ向かった。 (エルサレムは中世ペルシャ語[パフラヴィー語]で「ガンゲ・ディジュフーフト」アラビア語で「バイトル・ムカツダス(聖なる家)」) ザッハークは、人間と悪魔、妖精の混成軍をつくったり、魔法の国インドを征服にでかけていた。 もどったザッハークに、英雄ファリドゥーンは矛の一撃で蛇王の兜を打ち砕いたが、そこで天使スルーシュがあらわれ、彼の天命のときがきていないので、縛り上げて指定の場所に監禁するよう言った。 獅子の皮の紐でしばりあげられ(予知夢では自分の皮だったが) 、デマーヴァンド山に運ばれ、石に両腕に釘うたれて血がながれつづけた。 デマーヴァンド山に監禁されたザッハークはその後長く生きていて山の麓から流れる温水はザッハークの尿だという。 ■シカイリュウオウ(四海龍王) 【中国:ドラゴン、龍】 中国の伝承で、四方の海に配された龍王(四海、は天下、世界全体の意味もある)。西遊記などの物語では東海龍王が長兄とされるようだ。東海龍王は海底の水晶宮に住むという。封神演義でも哪吒ナタ(ナタク)が東海龍王の第三太子敖丙を殺したり事件を起こす話がある。 以下、各資料にみられる四海龍王の名前。 「封神演義」東海龍王敖光(ごうこう) 「呪術と占星の戦国史」東海龍王敖光(ごうこう)/西海龍王敖順/南海龍王敖明/北海龍王敖古 「幻獣ドラゴン」東海龍王 滄寧徳王敖広/西海龍王 赤安洪聖済王敖潤/南海龍王 素清潤王敖欽/北海龍王 敖順 「創竜伝」東海青竜王 敖広/西海白竜王 敖閏/南海紅竜王 敖紹/北海黒竜王 敖炎(ごうえん) ■シェーシャ > アナンタ 【インド,ヒンドゥー:蛇神、竜王、ドラゴン】 Ananta インド、ヒンドゥー教のナーガ、蛇王(ナーガラージャ)。「アナンタ」は「無限なるもの」「終わりのない」の意味だという。またはシェーシャという別称か、そのナーガと同一視されるようだ。ヴィシュヌが世界創造の合い間に休む時、この1000の頭のナーガの上に横になるという。シェーシャの頭部(コブラ蛇である)は日よけにもなるが、あくびをすると地上に地震がおきるという。余談だが、2009年、時計メーカーのセイコーがこの名称を使った「アナンタ」という製品を作った。遊戯王カードに「邪龍アナンタ」があるが本来、邪龍ではない。 ■ジンガナ 【オーストラリア:グウィング民族:虹蛇】 オーストラリア北部のアーネムランド地域西部の先住民族、グウィング民族の伝承の虹蛇。虹蛇とは天空にかかる虹を、地上の水場と天を結ぶ蛇だと考えるもので、グウィング民族ではこのジンガナが、乾季と雨季のバランスを正しく保ってくれると考えている。ジンガナに尊敬の念を表すことで天候の不順がなくなるという。グウィング民族の中でも南部のユーカリの疎林のある平原に住む人々が雨乞い、雨やみの儀式を行い、低地の人々は洪水をさける傾向があるため、雨乞いの儀式はみられないようだ。アーネムランド北東部ではロック・パイソンという岩場に棲む大型のヘビが雨を司ると考えられている。 |
|
|
■ズメイ 【スラヴ:ブルガリア:ドラゴン,竜】 Змей
ブルガリアの伝承におけるドラゴン(竜)、蛇、蛇身の怪物。同様の綴りで、ツメイ・ゴリニッヒスロベニア,ロシア ■ズメウ 【ルーマニア:ドラゴン,竜】 ルーマニアの民話における竜、蛇、蛇身の怪物。名前は蛇、竜を意味する名詞からきていて「竜人」の意。民話では人間を食べる怪物として恐れられているが、人間の知恵にまけてしまうというストーリーが多いようだ。 ■ズメヤ 【セルビア:ドラゴン,竜】 Змиjа Zmija(ラテン文字表記) セルビアの民話における竜、蛇、蛇身の怪物。名前はセルビア語で蛇、竜を意味する。 ■スモク 【ポルスカ:ドラゴン,竜】 Smok ポーランドの民話におけるドラゴン、竜。おそらく、東ヨーロッパ諸国のズメウ(ルーマニア)、ズメイ(ブルガリア)、ズミヤ?Змиjа(チェコ)などと同系統の言葉だと思われる。 ■セイリュウ(青龍) 【中国:神:四神】 青竜/青龍(蒼龍・そうりゅう) せいりょう、とも。中国の伝承で方位や星宿の象徴の神。四方を司る天の四神のひとつ。東を司る。また、さそり座が蒼龍とされていた。(「蒼龍」は「そうりゅう」とも 漢字の読みがいろいろなのは時代ごとに違う発音が伝わってくるため等) また出世、地位、名誉、男児などを司る。 風水での四神相応の考え方では東に川の流れがあることを青竜とする。また陰陽の思想においては西の白虎と対になり、陰虎と陽龍として表されることもある。 三国志の関羽の武器に天の青龍に関係した伝説のある青龍偃月刀がある。また十二天将にも四神の名がみえる。 日本でもキトラ古墳の星宿図に四神(青龍、朱雀、白虎、玄武)が描かれている。日本語の読みではセイリョウともいう。 |
|
|
■ツメイ・ゴリニッヒ 【スロベニア,ロシア:ドラゴン,竜,蛇人】 zmei gorynich
スロベニア、ロシアの伝承の蛇、竜人の怪物。スラヴ圏でよくみられる魔物。スロベニア語での竜はzmajとも表記。ズメイ Змей(ブルガリア)、 ゴリニチgorynich、 ゴルィニシチェ、ゴルィヌィチ(ロシア)という名称もある。奇怪な混成の蛇で、体は爬虫類で頭が人間、または頭と胴が人間で下半身が蛇の姿で描かれる。魔女ババ・ヤガに関係していて、人々にとって脅威となっていた。特に、ひとりでいる女性がこの怪物の罠にかかってさらわれやすいという。 ■ドラク 【チェコ:ドラゴン,竜】 Drak チェコの伝承におけるドラゴン、竜。ドラックとも。ある民話では12の頭を持つドラクがでてくる。他でもみられるモチーフだが、姫を助けるためドラクを倒したあと、舌を切り取っておき、後で主人公が自分が倒した本人だという証にした。主人公が旅の途中で、狼、熊、獅子に出会い、矢で射殺そうとするが「役に立つから矢をうつな」といわれ、彼らを従えて旅をし、力をあわせて竜退治するという、日本の桃太郎の話と同じモチーフがあるのがおもしろい。 ■ドラコス 【ヘレネス:ドラゴン,竜】 ΔΡΑΚΟΣ drakos ヘレネス(ギリシャ)の民話における怪物。一つ目の人食い巨人。dracoは英語風表記か。複数系ドラコイ ΔΡΑΚΟΙ。名前はドラコン ΔΡΑΚΟΝ、蛇、竜からきていて、本来、竜人といった意味だが、民話によく見られる「人間を襲って食べたりするので恐れられているが、知恵がまわらず逆に痛い目にあう」怪物のモチーフを踏襲している。日本でいう鬼や狐狸の類のような役どころを演じる。民話ではキュクロプスのポリュペモス等のイメージが重なっているようだが、本来はルーマニアのズメウ、ブルガリアのズメイと同じ竜人としての怪物であったようだ。 ■ナーガ 【インド,仏教:ドラゴン,竜】 Naga インド神話。ナーガは蛇形の精霊、神。大地の宝の番をする神格化された強大な蛇。時に人間にとって危険なものもいる。頭が多数の姿で描かれることもある。八大竜王のひとつ、ヴァースキ は乳海攪拌の時、棒のかわりにつかわれ、また後にシヴァが魔除けの帯に使ったという。またヴィシュヌが世界創造の時、1000の頭を持つシェーシャあるいはアナンタ(無限なるもの、の意) というナーガの上に横になって休むという。仏教では仏典の見張りをする水の神とも。また竜王の一人ムチリンダは瞑想するブッダを護ったという。インド、ヒンドゥー文化の影響かマレーシアでも竜をナーガと呼ぶ。 ■ナーガラージャ 【インド,仏教:ドラゴン、竜】 nagaraja (竜王) インド神話。ナーガは蛇形の精霊、神。ラージャは王の意。この場合の蛇はコブラのこと。ナーガラージャは雨を自由自在に降らせ川、湖、海をまもっているという。稲妻によって火災がおこらないように注意している。春には天に昇り冬には大地深く潜んでいるという。ナーガの住む地下世界はパーターラという。ヴェーダ神話の中にもアナンタなどいくつか出てくるが、仏法では八大竜王とされる。ナンダ、ウパナンダ、サーガラ、ヴァースキ、タクシャカ、アナヴァタプタ、マナスヴィン、ウトパラカ、あるいは他にムチリンダなどが出てくる。この竜の王という考え方は仏教とともに中国に入り、独特の四海竜王が作られたとも。またインドネシアでもヒンドゥー教との習合からナーガラージャがみられる。 |
|
|
■ニーズホッグ 【ゲルマン,北欧:ドラゴン、竜】 Nìðhoggr
ニズホッグ、ニドホッグ、ニドヘグとも。北欧神話に出てくる黒い大蛇、ドラゴンともいえる魔物。名前は「死体を裂くもの」の意。 世界樹ユグドラシルの根の一本が届いているニヴルヘイムで、この根に噛り付いている。エッダ詩「巫女の予言」では死人たちの体を吸う描写が、また翼で空を飛び、死体を運ぶ描写もでてくるようだ。 ■パロロコン 【北アメリカ:ドラゴン,竜】 北アメリカ先住民族、ホピ民族の伝承に出てくる大蛇。名前は「角のある水の蛇」の意。水の象徴で雄には角がある。また、地震の神格も持つ。地下の泉に潜んでいて、時がくると翼で太陽にむかって飛び、雷雲を呼んで落雷となって雨と一緒に落ちて地下へ帰るという。2月頃の新月に行われるこの神の祭では、神をかたどった張子に司祭が食事を捧げたり、祖先をかたどる泥頭(コエムシ)道化が蛇と格闘して投げとばされたりする。東洋の龍と同様、神性が非常に強いが、水、蛇との関連は世界中に存在する竜、ドラゴンに類似する。 ■ファフナー(ファーヴニル) 【ゲルマン,北欧:巨人:ドラゴン,竜】 Fafner/Fafnir(ドイツ語) ファーヴニル、ファーブニル、ハーフニルとも。ゲルマン、北欧神話、伝承にでてくるドラゴン、竜。巨人の種族であるとともにドラゴンへと姿を変えた者。エッダではファーヴニル(ファフナー)のことを「老いた巨人」と表現する箇所もある。ファーヴニルは勇者シグルズに、ファフナーはジークフリートに倒される。 ■ピグチェン 【南アメリカ:ドラゴン,竜】 南アメリカ、チリの伝承に出てくる有翼の大蛇。昼は山の中の大木で寝ている。夜になると起きだし、長い舌で人間や家畜の血を吸う。体毛に猛毒をもち触れた者は即死する。倒すには大木に閉じ込め石油をかけて燃やす。牛の角笛の音が嫌いだという。 ■ヒュドラ 【ヘレネス:ドラゴン、竜】 hydra ヘレネス(ギリシャ)神話に出てくる怪物、蛇の魔物。ドラゴン的ともいえる。 半蛇の女神エキドナの子。レルネーの沼沢地に棲み、平原にでてきて家畜や土地を荒らした。その巨体に9つ頭を持ち、真ん中のものは不死だった。ヘラクレスが2番目の試練としてこの怪物を殺すために戦った。不死でない頭は叩き潰されても傷口から2つの頭が生えるので、従者のイオラーオスが頭の付け根を焼くと生えてこなくなった。戦いの途中で、女神ヘラが化け蟹のキャンサーを応援に差し向けたが、ヘラクレスに踏み潰されてしまった。不死の頭は切り離され、レルネーからエライウースに通じる道の傍に埋められ、その上に重い石をのせられた。この時ヒュドラからとった胆汁は矢に毒として塗られた。星座のうみへび座(海蛇座、ヒドラHydra)はこのヒュドラで、女神ヘラが化け蟹のキャンサーと一緒に空へあげた。星座のヒドラの中で最も明るい星、二等星のアルファードは 「孤独な星」の意。ラテン語ではコル・ヒドラ(ヒドラの心臓)といわれる。九つ頭の蛇という事では、日本にも九頭竜(くずりゅう)という地名や神社がある。 |
|
|
■ファラク 【イスラーム:蛇:死の国】
イスラームの伝説にでてくる下方世界の火の中にいる蛇。その口の中に6つの冥府がある。千一夜物語第496夜に、この記述がみられる。ファラクがいる場所は、大地を支える魚バハムートのいる海よりもはるか下方の空間で、人知が及ばない世界であるともいうが、その果てにある死の国ということになろうか。あるいはその象徴といえるだろう。別の伝説では6つの冥府は、バハムートも上方、大地の山頂の天使の頭上にあるともいう。 ■フェルニゲシュ 【マジャール:ドラゴン,竜】 Fernyiges hollófernyigesとも。翼を持った魔物で竜たちの首領だという。「黒竜フェルニゲシュ」という訳があるがMTA SZTAKIの英語-マジャール語辞典ではhollóはraven(ワタリガラス、漆黒の)が訳語だったが「白いholló」でオオハクチョウのことを指すなど、hollóの意味の理解は英語を通してだと難しいかもしれない。ある種の鳥を指す言葉らしい。フェルニゲシュはある王の城の開かずの間に、石桶に囚人として閉じ込められていたが、勇者ヤーノシュが好奇心から逃がしてしまう。フェルニゲシュはヤーノシュに3つのものを与える(3回命を助ける、といった意味のもの)といい飛び去ったが、途中でヤーノシュの妻である王女をさらっていった。ヤーノシュには3人の姉がいて、その夫たちは6つ、12、24の頭を持つ竜でフェルニゲシュのことを「我々の首領だが誰もがいまいましく思っていた」といい、それで閉じ込められていたのだという。夫たちはフェルニゲシュが飛び去ったのに気づいていれば石像に変えてやったのにと強がるが、また「我々3人が千匹集まってもかなわない」とも語る。ヤーノシュは、義兄である3匹の竜たちの助けで、6歩で60マイル進める6本足の駿馬を手に入れ、王女を救い出す。フェルニゲシュは自分の持っていた20歩で20マイル進める5本足の馬で追いかけるが当然追いつかない。フェルニゲシュに鞭で叩かれ血を流しながら走るフェルニゲシュの馬は、兄である6本足の馬に助けを求める。兄馬は「急上昇して、急降下すればいいじゃないか」という。弟の5本足の馬はいわれた通りにすると、フェルニゲシュは地面に叩き落され絶命した。 ■ボイナ 【アメリカ先住民族:ジャマイカ:蛇】 中南米、ジャマイカ島の伝承。灰色の蛇で、土地に恵みの雨をもたらす雨雲の神格を持つ。 ■ミドガルズオルム 【ゲルマン:ドラゴン,竜】 ヨルムンガンドルとも。ゲルマン、北欧神話、エッダに出てくる巨大な蛇のような魔物。ロキ神と女巨人アングルボダの子。名前は「ミッドガルドの蛇」の意。ミッドガルドの大地を取り巻く海を現すという世界蛇。自分の尾をかんで輪となっている姿で現される。 ■ムシュフシュ 【バビロニア:ドラゴン,竜】 mushus またはシリシュとも。シュメール、アッカド、バビロニアの魔物。ムシュフシュはシュメールの言葉で「怒れる蛇」、「怒りの毒蛇」の意。角のある蛇の頭と胴体と尾。ライオンの前足と鷲の後ろ足という姿で描かれる。鷲の翼を持つこともある。尾がサソリのものである場合もある。最古のものはアッカドのもので、嵐と戦いの神ティシュパクの乗騎のような役割だったようだが、後にバビロニアではマルドゥークを背に乗せている。以後、通りや宮殿の守護獣として壁画に彫刻された。また災いよけに、ムシュフシュの像を埋めるように指示した呪文や、王の碑文に姿が彫られたりした。 |
|
|
■ムチリンダ 【インド:仏教:ドラゴン,竜】 Mucalinda
ムチャリンダとも。竜王・蛇神ナーガラージャの一人。大嵐の時、とぐろをまいて(7回まく)ブッダを包み頭を広げて雨よけになり、瞑想にふけるブッダをまもったという。(7日間まもったという)。ブッダが瞑想をとくと、ムチリンダは若者の姿となり、仏教に帰依したという。この物語はパーリ語の経典「大品」に伝わる菩提樹の下に7日、ニグローダ樹の下に7日、ムチャリンダ樹の下に 7日間坐っていた、その時の話であるという。 ■ムドプカン 【北東アジア:オロチョン民族:ドラゴン,竜】 オロチョンの伝承における龍神。風雨の象徴と考え、まつっている。角、鱗と爪を持ち、飛んだり泳いだりできる。体は非常に長く大きい。言い伝えでは、ある時ムドプカンが落ちてきて家三軒を潰してしまったという。オロチョンの巫術師シャーマンは逆境、不猟、自然災害時にムドプカンに祈りを捧げる。 ■メリュジーヌ 【フランス,ケルト:ドラゴン,蛇:女神】 Melusine フランス、ポワトゥー地方中心の民間伝承にでてくる半人半蛇の女性の魔物。子孫を支配し魔術を司るケルトの古代の女神に対応しているらしい。富をもたらし、建物を建てる。実在のリュジニャン家の始祖譚の様相をもつ。母は妖精モルガンの姉妹、泉の守護妖精プレッシーナ。父はアルバニア(スコットランド)王エリナス。夫となったものや、人間に対して禁忌があり、毎週土曜日、下半身が蛇の姿にもどる姿をみられてはならない。姿を見られると立ち去らねばならないが、ヴイーヴルvouivre、ギーブルguivreとよばれる大蛇の姿で再び姿を見せるという。14世紀末~15世紀初めジャン・ダラス、クードレットによってリュジニヤン家の始祖にしたてられ、物語が作られた。 1393年、散文「メリュジーヌ物語」をジャン・ダラスが、1401年以降、クードレットは「メリュジーヌ物語あるいはリュジニャン一族の物語」を領主に命じられ著述。上記の物語では領主の妻となったメリジューヌが、蛇の姿を夫に見られてしまう。それだけなら人間としての生活をたもてたが、夫がそれを人に話してしまったので、翼のある、下半身が蛇の姿となり飛び去ってしまった。夫との間に優れた資質の子、一つ目などの異形の子供たちをもうけた。 ■ヤトノカミ(夜刀神) 【日本:蛇神】 日本の伝承の蛇神。「常陸国風土記」行方郡の段に記された蛇神。ヤト、ヤツは谷あいの低湿地のことだという。または国語辞典では谷(やつ、やと)となる。伝承では継体天皇の時代、箭括麻多智(やはずのまたち)という豪族が「西の谷の葦原」の開墾を始めたが、夜刀神の群れに邪魔され、激怒して鎧を着、仗(ほこ)を取り、この神々を打ち払った。その後、杭を立てて境界をつくり、みずから祝(ほふり 祀祭者)となり夜刀神をまつったという。森や川などにひそむ神々を畏怖し崇めたので、たたりを恐れ、崇拝したという。 ■ヤマタノヲロチ 【日本:ドラゴン,竜】 八俣遠呂智(記)/八岐大蛇(紀) [(記)は古事記での漢字表記、(紀)は日本書紀での漢字表記] 日本神話に出てくる大蛇。頭と尾が8つあり、背中には松や柏が生え、八つの山、八つの谷いっぱいに広がる巨体で眼は赤酸漿(あかほおずき)のようだという。または、一つ一つの頭に岩松が生えていて、両脇には山があり、とても強いともいう。二柱の神、脚摩乳(アシナヅチ)、手摩乳(テナヅチ)の老夫婦の子供を食い殺していたが、残った娘のクシイナダヒメ(奇稲田姫)を助けるため、スサノオノミコトに酒または、毒の入った酒を飲まされて眠っているところを斬り殺された。この時使った剣はトツカノツルギ(十拳剣)とも、ともカラサビノツルギ(韓鋤の剣)とも、オロチノアラマサ(大蛇の麁正)ともアマノハハキリノツルギ(天蝿斫剣)ともいう。日本書紀で、十拳剣でずたずたに斬ったとも、韓鋤の剣で頭と腹をきったとも書かれている。尾を切ると剣が刃こぼれしたので、よく見ると中に剣があって、クサナギノツルギと呼ばれた。ヤマタノヲロチは出雲の国の簸(ひ)の川の上流で倒されたという。世界各地にある英雄譚の例にもれずドラゴン退治の類話である。 |
|
|
■ヤム 【カナン:神:ドラゴン,竜】
カナンの神話における竜神。名前は「海の神」の意。 ■ラドン 【ヘレネス:ドラゴン,竜】 ladon ヘレネス(ギリシャ)神話に出てくる、ヘスペリデスの園の黄金のリンゴの木を守るドラゴン。半蛇の女神エキドナの兄弟、または子といわれる。顎の関節が尾にあり、体全体が巨大な口となっている。一説では体長約800mメートルという。その口には象の牙ほどの歯が並んでおり鋭い剣より鋭利で、その皮は矢が通じない。または、頭が100あるともいわれる。火を吐くともいう。ヘラクレスが11番目の試練として、黄金のリンゴを得るため、ラドンのもとにやってきた時、唯一の弱点である口の中に、蜂の巣を投げ込まれ、無数の蜂に刺されて死んだ。りゅう座Dracoは、このヘスペリデスの園の黄金のリンゴの木の番龍ラドンなのだという。 ■ラーフ 【インド:魔神,ドラゴン,竜】 Rahu インド、ヒンドゥーの伝承における太陽と月の交点の名前。ケトゥとラフがある。ラフは「苦しめる者」を意味する。下半身が蛇もしくは竜(の魔神)で乳海攪拌の時、神々から不死の水アムリタを盗み飲んで不死となった。しかしすぐヴィシュヌ神に首を斬られ、首だけとなった不死のラーフは、太陽と月を追いかけ飲み込むという(日食、月食)。中国に伝わって、計都(けいと)、羅喉(らごう)といわれた。ヨーロッパでも太陽と月の南北の交点(2つの軌道は5度傾いているため昇降の差がある)ノウド、ノードは、ドラゴンの頭(ヘッド)(カプト・ドラコニス)/ドラゴンの尾(テイル)(カウダ・ドラコニス)、といわれる。シャカ(釈迦)の息子で十大弟子のひとり、ラーフラ(羅睺羅らごら)の名は蝕としてのラーフに由来する面もあるようだ。 ■リュウ 【中国,アジア:ドラゴン,竜】 竜/龍 中国の伝承で、360種類の、鱗のある動物たちの長。日の出、春、豊穣を象徴し、春分に天に昇るともいう。また四神の一つ、東の青龍として星にも配された。漢字の「龍」は左上の「立」は童の字の音を表し、月は肉を表す。右側は肉のあるものが空を飛んでいく様を表す。中国古代から様々な伝承に登場する。また王、皇帝との結びつきも強い。伝説上の皇帝、ウ(兎)は龍から生まれたとも龍形の姿であったともいう。 黄龍は五行の中心であり、皇帝を象徴した。後に仏教からナーガラージャ、竜王という考え方が入ってくる。 ■リョウマ(竜馬、龍馬) 【中国,日本:神獣】 リョウマ/リュウメ/龍馬/竜馬/りゅうめ 中国、日本の伝承。中国で語りつがれ信じられていた龍の体と馬の前半身を持つという天の神々の使い。天と地の間を飛ぶことができるという。中国の皇帝の陰陽の概念を象徴的に示すとも。日本では、竜馬りゅうま、りゅうめ、とも。非常にすぐれた馬、駿馬(しゅんめ)のこと。りょうめ、りょうば、たつのうま、とも。また将棋で、角(かく)の成ったもの。成り角。「竜馬(りゅうめ)の躓(つまず)き」という言葉もある。どんなすぐれた人にも失敗のあることをいう。 日本の幕末の志士、坂本竜馬(さかもとりょうま 生没1836-1867)の名前でもしられる。 |
|
|
■リンドブルム(リンドワーム) 【ゲルマン,ドイツ:ドラゴン,竜】 Lindwurm (ドイツ)/Lindorm(デンマーク)
ゲルマンの伝承におけるドラゴンの名称。意味は「リンデン樹の下の蛇」。デンマークの民話で結婚して最初の夜が明けたときベッドに「子供ができない」と記された不思議にあった王妃が、ある老婆から日没に皿を庭の西北に裏返して置いておき日の出の時取ると紅白のバラの花が咲くから、赤いバラを食べれば男の子、白なら女の子ができる。ただ2つ食べてはいけない」という話を聞いて試したが、バラがあまりにもおいしかったので2つとも食べてしまった。すると月満ちて生まれてきたのが一匹のリンドワームだった。戦争から帰国した王は驚いたが、「あなたが私の父と認めないなら、あなたも城もたたきつぶす」と脅された。さらに妻がほしいというので他国の王女を迎えるが寝室に入るなり食べてしまう。2人目も同じことになり、 2つの国から娘を殺されたと戦争になってしまう。3人目を要求されて王は断ろうとするが、「あなたも城も叩き潰す」と言われ、仕方なく羊番の娘を迎えることにした。娘は竜王子の妻にされると聞き、悲しんで森を歩いていると、一人の老婆に出会い、事の次第を話すと、助言してくれた。老婆の言う通り、10枚の肌着、灰汁の桶、ミルクの入った桶を用意してもらって寝室へ行き、王子に肌着を脱ぐように言われた時、竜王子にも皮を脱ぐように言い、王子が9枚皮を脱ぐと、もう脱ぐ皮もなく、血みどろの肉の塊のようになった。さらに、娘は老婆に言われた通り、小枝を灰汁に浸して、王子の体を激しく打ち、ミルクの中で洗い9枚の肌着でくるみ腕に抱き眠った。朝、目をさますと王子は美しい青年になっていた。ワーム、ブルムはドラゴン系モンスターなどの名称に非常に多く使われている。 ■ロンブオン 【ベトナム:ドラゴン,竜】 rong vuong/龍王 ベトナムの民話に出てくる龍王。海中にある南海国の王。龍はcon rongともいう。珊瑚の建物が立ち並ぶ宮殿に住んでいて、難破船から手に入れた真珠や金銀の宝物を持っている。また祈願について書かれた古い魔法の書を持っている。この書の内容を身につければどんな願いもかなえられる。 ■ワイバーン 【ブリテン:ドラゴン,竜】 wyvern ブリテン(イギリス)の2本足で翼をもったドラゴン。ブリテン(イギリス)では4本足のものはドラゴン、2本足のものはワイバーンと区別して呼ぶ。先端にトゲのある毒蛇の尾をもつ。元々はフランスのドラゴン、ヴイーヴルVouivreの名が英語読みに変化していく中で、Wivrer、Wivre、Wyvernになったようだ。ワイバーンは紋章にも描かれ、「強い敵意」を表し、戦争時や軍隊で用いられた。 ■ワーム 【ブリテン(イギリス):ドラゴン,竜:蛇】 Worm ワームとはブリテン(イギリス)で、ドラゴン、巨大な蛇のこと。中世ではワームとドラゴンは区別されて考えられていたとも。古英語ではwurm、wyrmとも。または足、骨、毛、のない柔らかく細長い生き物、蛇(サーペントserpent)、ミミズ(earthworm)、サナダムシなど。「這う」を意味する語に由来するという。ドラゴン、蛇形の魔物としてはバイパー、ワームはワイバーンが語源になっているともいう。また古ノルウェー語ormr(北欧の蛇、ヨルムJorm)やドイツ語wurm、デンマークormの「蛇」とも共通する語。スコットランドのメスター・ストゥアー・ワーム(海蛇に似た姿で頭3つ)、イングランド北部ヨークシャー、ダラムのラムトン・ワームなどの伝承がある。余談だが蛇だけでなく「虫」的な意味も持つが、東洋でも竜、蛇に類する生き物が虫へんの漢字を持っていたり、インドでは、グラ(求羅)というトカゲのような虫は風を食べて竜になる、という伝承など似た考え方がみられる。 |
|
 ■トリスタンの龍退治 |
|
|
ケルトの伝承の英雄。英語トリストラムとも、ドイツ語トリストラントともいう。元のピクト人の言葉でDrustan。名前は「悲しみの子」の意。あるいはDrustにはriotふしだら、放蕩、騒ぎ、tumult騒ぎ、心の乱れなどの意味がある。ケルトとはいうものの中世にはヨーロッパで広く人気を博した物語として流布された。コーンウォールに実在したかもしれない人物。古くは12c世紀のフランスのものがある。マビノギオンにはこの物語の原型と思われるものもあるという。物語ではイズー(イゾルデ)によるゲッシュ(魔術的誓約)によりイズーを愛さなくてはならなくなる。フランスの物語では媚薬によるものにかわっている。
英雄物語らしく様々な戦いが描かれる。叔父の王の危機には敵将モレオール(魔法の剣を持つという)と、貢物をよこすかどうか、小島で一騎討ちする。ついたとき、自分の船を壊して、相手がなぜかと問うと、生きて帰るものは一人だからそちらの一隻あれば足りるという。まるで武蔵と小次郎の巌流島のようである。この戦いで、モレオールは討ち果たすものの、モレオールの毒槍の一撃をうけたため、王の元へ帰ったあと一人船に行く先をまかせ旅にでる。いきついた先がイズーの国で、トリスタンは身分をふせ、治療の技にすぐれたイズーの治療で一命をとりとめる。 トリスタンが仕える王のもとを離れ、イズーと森で暮らしてる時につくった 「無駄なしの弓(必中の弓)」は人間でも獣でも狙った場所に必ずあたるという。 思いがけず、国の仇敵ともいえる男を救ってしまったイズー。後に語られる。 「恋の大歓喜、大悲哀を嘗めて愛しあい、やがては同じ日のうちに彼は彼女のため、彼女は彼のために、死んでいったのかを」 「トリスタンとイズー」に関する物語については12世紀頃の成立とされるが、様々な版、詩により物語が断片的に伝えられている。 トリスタンは素性を隠し、イズー姫のもとで治療をうけるが、治って正体がばれる前に自分の国に帰った。 国ではトリスタンを良く思わない者たちがトリスタンを迫害し無理難題をおしつける。王のためにイズー姫を手に入れてくるようにしむける。 再びイズー姫の国アイルランドへ行く。 イズーの国では龍がいて、倒したものに黄金の髪のイズー姫を褒美にくれるという 20人の騎士が命を落とした真っ赤な目は炭火のよう、頭は大蛇の形、額に2本の角、耳は長く毛を生やし爪はライオンのよう、尻は蛇、鱗を生やした鷲のような体。鱗は強靭で槍は砕け、腹も硬く剣撃もきかない。爪は盾を折った。鼻から毒気を吐き、鎧の金属は黒く変色した。トリスタンは口の中へ剣をつき入れ心臓を2つに裂いた。倒した証拠に舌を切り取ってとっておいたが舌から滴る毒汁に全身をおかされ倒れてしまった。 その間にイズーの国の家臣、赤鬚のギャランゲランという男が来て、龍が死に、龍を倒したらしい男も死んでいるらしいのをいいことに龍の首を切り落とし自分が倒した、と王のもとへいった王は信じてなかったので要求を査定するため3日間の間に家臣に王宮に集まるようにふれた。 イズーは真実を知るべく、龍退治の現場に。馬具の取り付け方の違う馬の死体を見て異国の勇士が龍を倒したと思う。さがすとトリスタンが倒れているのをみつけ息があるので治療する。 この美男の勇士がギャランゲンを打ち倒せるだろうと喜ぶイズー。武具の手入れをしようと鎧や剣をみる。見事な武具だが、剣には刃こぼれがある。もしや、とモレオールの頭から抜き取った剣の破片をもってくるとぴったりあわさる。ここにいたり、この勇士が仇敵トリスタンと知る。 体の自由のきかない中でトリスタンの知略は、私はあなたに2度命を救われている。あなたには私の命を奪う権利がある。しかしそれであなたは何をえるのか、私を殺してギャランゲランと寝床をともにしながら、私の命をうばったことを思いだすといいだろう、と。イズーは考え直し、仲直りのしるしの肩へのキスをする。 かつてモレオールが貴国から乙女を奪おうとしたように、私を得てはした女にするためにきたのか、と。違う、不思議なことがあり、燕があなたの金髪をもってわが国にきた。この髪の乙女を探しにきたのです、と。 イズーは王に、ギャランゲンのウソを暴く勇士がいるが、その者の過去の罪を許してくれることを約束してください、という。諸侯も約束するようすすめる。王が約束したあと、紹介された勇士はトリスタン。モレオールとの決闘で覚えているものが騒ぎ出す。しかし、王が許しの口付けをしたため騒ぎは収まる。トリスタンが龍の舌をしめし、決闘をもちかけるがギャランゲンは勇気なく罪を覚悟した。トリスタンはイズーを自分のマルク王の妃にむかえるためにきた、と宣言する。 イズーは悲しんだ。トリスタンは自分が手にいれるためにきたのではなかったのだ。しかし諸侯の前で約束はかわされた。 イズーの母の王妃は、姫に使えるブランジァンにぶどう酒をわたす姫が異国の王に愛されるようにしなければならない。マルク王と姫が二人の時にさしだし飲むようにするのだと。神草を調じたこのぶどう酒は一緒に飲んだ二人を身も心もひとつにし、生きている間も死んだあとも永久に愛し合わせるのだと。 イズーは生まれた国を離れ、自分のものにせず獲物のように敵国に連れ去るトリスタンを恨みさえしていた。 ところがブランジァンがいないとき、イズーを慰めようと言葉をかけるトリスタン。二人はのどが渇き例のぶどう酒をのんでしまう。そこへ戻ってきたブランジァン。二人は恋と死をのんでしまった、と嘆く。そして二人は自分の心に悩んだのちに、トリスタンは私はあなたの臣下で、王の妃だ、というがイズーはあなたが私の殿なのだ、といい、結ばれてしまう。 のちにイズーはマルク王の妃になるが、最初の夜に、その身を委ねたのはブランジァン、彼女が自ら身代わりとなり処女をささげ、そして夜ごとに身代わりとなった。 直接みたわけではないが、船上でのことを疑い、トリスタンをおとしいれようという 4人の悪人臣下の讒言などもありながら、二人は密会したり、その場を見つかっても奇跡的にうまく言い逃れたりをくりかえしながら、とうとう二人は謀にかかり、二人会いたくなるような場面をつくられ、見つかってしまった。 そして結局トリスタンとイズーは二人して落ち逃れていくことになる。 |
|
 ■蜃気楼の伝説 |
|
|
●蜃気楼と見られる記述が初めて登場したのは、紀元前100年頃のインドの「大智度論」第六まで遡る。この書物の中に蜃気楼を示す「乾闥婆城」という記述がある。また、中国では『史記』天官書の中に、蜃気楼の語源ともなる「蜃(あるいは蛟)の気(吐き出す息)によって楼(高い建物)が形づくられる」という記述がある。日本語の「貝やぐら」は、蜃楼の蜃を「かい」、楼を「やぐら」と訓読みにしたことばである。
> 私が気になっていたのは、この中の中国の「蜃」についてです。 ●蜃(しん)とは、蜃気楼を作り出すといわれる伝説の生物。古代の中国と日本で伝承されており、巨大なハマグリとする説と、竜の一種とする説がある。蜃気楼の名は「蜃」が「気」を吐いて「楼」閣を出現させると考えられたことに由来する。霊獣の一種とされることもある。 "竜の一種とする説がある"とありましたけど、最初のWikipediaの「蜃(あるいは蛟)の気(吐き出す息)」のうちの蛟(みずち)も竜の一種です。 > まず、ハマグリ説。 ●中国の古書『彙苑』では、ハマグリの別名を蜃といい、春や夏に海中から気を吐いて楼台を作り出すとある。この伝承は日本にも広く伝わっており、江戸時代の鳥山石燕による妖怪画集『今昔百鬼拾遺』でも、「蜃気楼」の名で大ハマグリが気を吐いて楼閣を作り出す姿が描かれており、解説文で中国の『史記』を引用し、「蜃とは大蛤なり」と述べている。 > 私はハマグリ説しか記憶にありませんでした。しかし、Wikipediaの記載はむしろ竜の方が長いです。 ●一方で竜とする説は、中国の本草書『本草綱目』にあり、ハマグリではなく蛟竜(竜の一種)に属する蜃が気を吐いて蜃気楼を作るとある。この蜃とはヘビに似たもので、角、赤いひげ・鬣〔たてがみ〕をもち、腰下の下半身は逆鱗であるとされている。蜃の脂を混ぜて作ったろうそくを灯しても幻の楼閣が見られるとある。さらにこの蜃の発生について、ヘビがキジと交わって卵を産み、それが地下数丈に入ってヘビとなり、さらに数百年後に天に昇って蜃になるとしている。宋の百科辞典『卑雅』の著者である陸佃も同様、蜃はヘビとキジの間に生まれるものと述べている。また『礼記』にはキジが大水の中に入ると蜃になるとあり、この発想は日本にも伝わっている。 > ただ、同じ『礼記』には以下のように書いているそうです。 ●『礼記』の「月令」では、蜃にハマグリと竜の2通りの説があるのは、ハマグリの蜃が竜族の蜃と同名であるために、両者が混同されたためと述べられている。 > この書き方からすると、ハマグリが正解なんでしょうね。ただ、龍族でも蜃がいるのですね。ややこしい。また、日本での蜃について。 ●日本において蜃を竜の一種とする説は、宝永年間の本草書である『大和本草』に記述されている。また江戸時代の百科辞典『和漢三才図会』には、竜類に属する蜃が蜃気楼を起こすという記述、大型のハマグリである車螯(わたりがい)が蜃気楼を起こすという記述の2種類があり、車螯は別名を蜃ともいうが、竜類の蜃とは別種のものとされている。 > それから、蛟との関係性。 ●虫という漢字の由来は、ヘビをかたどった象形文字で、本来はヘビ、特にマムシに代表される毒を持ったヘビを指した。読みは「キ」であって、「蟲」とは明確に異なる文字であった。蟲という漢字は、元は「生物全般」を示す文字であり、こちらが本来「チュウ」と読む文字である。古文書においては「羽蟲」(鳥)・「毛蟲」(獣)・「鱗蟲」(魚および爬虫類)・「介蟲」(カメ、甲殻類および貝類)・「裸蟲」(ヒト)などという表現が見られる。しかし、かなり早い時期から画数の多い「蟲」の略字として「虫」が使われるようになり、本来別字源の「虫」と混用される過程で「蟲」本来の生物全般を指す意味合いは失われていき、発音ももっぱら「チュウ」とされるようになり、意味合いも本来の「虫」と混化してヘビ類ないしそれよりも小さい小動物に対して用いる文字へと変化していった。貝の種類を表す漢字には虫偏のものが多い(「蛤」など)。架空の神獣である「竜(龍)」に関しても虫偏を用いる漢字が散見される。「蛟」(ミズチ、水中に住まうとされる竜、蛟竜(こうりゅう)、水霊(みずち)とも呼ばれる)、蜃(シン)(同じく水中に住まうとされる竜、「蜃気楼」は「蜃」の吐く息が昇華してできる現象だと考えられていた)、虹(コウ、にじ、「虹」は天に舞う竜の化身だと考えられていた、虹蛇(こうだ、にじへび)という表現も用いられる)などといった標記が代表的なものである。ただ、竜(龍)に関する文字については、架空の「生物」として「蟲」の意を付与した虫偏を用いているのか、「ヘビの神獣化」として「虫」の意を付与した虫偏を用いているのかには賛否が分かれる。 > もともと竜と貝は見分けづらいようですね。同じく漢字に関してですけど、「辰」の字。これは竜のイメージがありますけど、十二支は後付であり、本来動物と対応していたわけでありません。そして、歴史的に見ると、「辰」の字は本来「竜」よりも「貝」に関係があったように思える記載がありました。 ●その字源については『説文解字』では陰陽説から三月に陽気が動きはじめて雷が震動し、民が農作業を始める時期であり、芽が出る「乙」と変化の「匕」、声符の「厂」で構成される形声文字とする。しかしながら、甲骨文を見ると、三角状のものから丸と長く伸びる毛のようなもので描かれており、貝殻を開いて足を出した二枚貝に象る象形文字であり、「蜃」の本字と考えられている。辰が農作業と関わる意味が生じたのは貝殻を農具に用いたことからとも、磨製石器の形が貝に似ることからとも考えられる。偏旁の意符としては農作業に関することを示す。また声符としてはシンといった音を表す(唇・震・晨・振・娠…)。 > ここにも"「蜃」の本字と考えられている"ことから、やはり竜ではなくハマグリと考えた方が自然なように感じます。 |
|
 ■三井寺の鐘 |
|
|
近江八景の一つに「三井の晩鐘」があるが、まつわる話は蛇女房譚の典型話でもある。ただし、良く知られる子に目玉をやり目の見えなくなった蛇女房のために鳴らす三井寺の鐘、というストーリーのほかに、もう一系統の話がある。
蛇女房譚そのものは全国に広くあり、他地域での紹介も多いので、目玉をくれる、蛇が母である、といったその主筋そのものに関する考察は他に回そう。今回ここでは「竜蛇と鐘」に注目したいのだ。まずは典型話の方を見てみよう。 ■三井の鐘1 近江八幡市──昔、近江の滋賀の里にすむ一人の若者が魚を売って暮らしていた。いつ頃からか美しい娘が漁に出る若者を見送るようになり、やがて二人は夫婦になる。 ところが、子供まで生まれたある日、女は自分が琵琶湖の竜神の化身であり、もう湖にもどらねばならないことを告げ、男が止めるのにもかかわらず湖へ沈んでしまった。 男は昼間はもらい乳をして子を育て、夜は浜へ出て呼び、現われた妻が乳を飲ませて去ってゆくという毎日であったが、ある時、妻は自分の右の目玉をくり抜いて乳の代わりにと渡す。子供は目玉をなめると泣きやんだが、しばらくしてなめつくしたので、浜に出て今度は左の目玉をもらってやる。 その時妻は、両目が無くなって方角もわからないから、毎晩三井寺の釣鐘をついてくれ、それで二人の無事も確かめられるので──と頼む。それから毎晩、三井寺では晩鐘をつくようになったという。(『近江むかし話』) ■ 『まんが日本昔ばなし』では「へび女房」というタイトルで東北地方のものと思われる同系の話が放映されていた。先の筋では女自らが正体を告げているが、「へび女房」のように出産時の「見るなの禁」の次第で正体が知られ去る、という筋も多い。 さて、この話では「鐘」はただ単に方向・時間を報せるために出てくるだけで特に竜蛇と結びつく要素ではないのだが、琵琶湖周辺に語られるもう一系統の「三井の晩鐘」の話を見てみよう。 ■三井の鐘2 蒲生郡竜王町──亀さんという人が嫁を死なせて、子守りをしていると、子供が小さい蛇をなぶり殺ししようとしているので蛇を買って川へ逃がしてやった。しばらくして、美しい女が亀さんの家へ来て、自分の乳が張るから子供にあげようと言って、子供の乳のいる間世話をしてくれる。 亀さんが嫁になってくれと頼んでも「女房にはなれない」と言い、子供の乳がいらなくなると暇をもらうと言って帰ってしまう。亀さんが後を付けてゆくと、海に向って飛びこんだのである。普通の人ではないと思う。 女は「正体を見つけられた」と言って、もう二度とは来ないが、自分は三井寺の鐘になっているので鐘をついて思い出してくれと言い残す。それで、三井寺の鐘の正体は琵琶湖の竜神だといわれている。(『竜王町のむかし話』) ■ 『大系』はこちらの系統の話が表題話となっている。これは「蛇女房」というより「蛇報恩」といった話である。そして興味深いのは「三井寺の鐘の正体は琵琶湖の竜神」と言っていることだ。実は、三井寺の鐘はもとより竜宮と縁が深い。 これは詳しくは俵藤太の話となるのでそちらに回すが、三井寺には藤太が竜宮から得たという鐘もあるのだ。このことからここで指摘したいのは蛇女房譚の最後に鐘が出てくるのは、竜蛇と鐘が密接に結びついたものだからではないか、という点だ。 各地の沈鐘伝説には鐘を水神とする側面があり、それはそれで別途追うが、三井寺の鐘の伝説には竜蛇そのものをそこへ接続させて行くハンドルがある。「三井寺の鐘」とは、典型話だけでなく、蛇女房・蛇報恩・俵藤太の三つの話の束なのだと覚えておかねばならない。 |
|
 ■満濃池の竜神 / 香川県仲多度郡・満濃池 |
|
|
「日本の竜蛇」と竜と蛇をひとくくりに扱っているが、それが日本の「竜−蛇」の特徴でもある。お隣中国では龍は龍、蛇は蛇、と別物だという感覚が強いようだが、日本には明瞭な境はない。と、言うよりそもそも「竜」の話などほとんどなかったのだと言って良いだろう。大概の「竜の話」も、もとをただせば大蛇譚だったものが下って竜だと表現されるようになった、という具合である。そんなわけで日本では竜蛇はわりと自在に通じている。では、讃岐の満濃池の竜神の話を通して、そのような「竜−蛇」の一面を見ていってみよう。
■満濃池物語 (要約) 満濃池は『今昔物語』にも記述のある古代の巨大な溜め池である。大同年間に造られ、後に弘法大師空海が補修・完成させたと伝わっている。このような歴史を持つ池(湖だが)なので、人の手による水とはいえ、やがて竜神も棲みつくようになる。 あるとき、満濃池の竜神は小さな蛇に姿を変えて堤の上で日に当たっていた。すると近江比良山の天狗が鳶に化けて飛来し、小蛇を攫って比良山へ連れ帰ってしまった。小蛇は竜に戻ろうとしたが、それには一滴でも良いから水がなければならない。しかし、比良山の洞窟には水がなかった。 今度は天狗は比叡山の僧を攫ってきた。小蛇はその僧が持っていた水瓶から水をもらい竜の本体に戻ることができた。竜は宙を飛んで僧を比叡山へと送り返し、自分も満濃池へと戻った。しかし、例の天狗に仕返しをしないと気が住まない。 機会を狙っていると天狗が法師に姿を変え、京の町を歩いているのを見つけたので、竜は早速襲い掛かって蹴り殺してしまったそうな。 ■ 『今昔物語』にも記述のある満濃池、というよりこの天狗に攫われる竜の話そのものが『今昔物語』にある。古い話なのだ。満濃池は弘法大師伝説の地でもあり、これらが絡んで周辺楽しい類話が沢山あってそれも興味深いが、今回は一点、「龍」と「竜−蛇」という側面のみの話としよう。 この話の面白いところは日本的な竜蛇の有り様と、中国の龍の有様の影響を受けた様子とが同時に描かれている点にある。まず、話中竜神は小蛇となってひなたぼっこをしている。このように竜−蛇は連続したもの、置換可能なものというイメージが強い。蛇が大蛇となり、ヌシともなれば角が生え、さらに宙でも舞うようになったら竜なんだろう、くらいのものである。しかし、ディティールとなると中国の話からもたらされたものが見える。 水が枯れると神通力が失われるのは河童の頭の皿だが、これは中国の龍の頭にあるという「博山」という器官(瘤)がもとであろうと思われる。龍は博山の水気(沢水)が枯れると飛べなくなるのだそうな。さらに古くは伏羲・女媧神話の原型とも言われる苗族の祖先譚の雷神も水を得て復活している。満濃池の竜の話もこのような性質・伝承を引いているのだろう。しかし、日本では普段はひなたぼっこするような小蛇で描かれることになるのだ。中国の「龍」の有様が強くもたらされたはずなのに、「竜−蛇」の枠組みになって(戻って?)しまうのである。 私はこれは「日本は太古からの蛇神信仰が色濃く残り、龍のイメージが定着しなかった」という単純な話ではないと考えている。先走ったことを言えば、龍をその対称とするほどの強力な王が出現しなかったのが日本なのだ。「龍学」と言っている私は日本を「龍の国」だとは思っていない。日本龍学はこの国が「竜−蛇の国」であるという方向へ行くと思う。きっとそこで、この満濃池の畔でひなたぼっこをする小蛇の竜を思い出すことになると思うのだ。 ■龍と竜−蛇について 私は「龍」を中国の皇帝がその対称とするような、「必ずしも現実に存在する生き物の延長である必要のない」ところまで形而上化の進んだ存在を指す場合に用いている。逆に「竜−蛇」で表すのは「どこかで大地・海と繋がっている、そこから生まれたことを前提とする」存在のことである。 無論個人的かつ便宜的な分別ではあるし、世界的にはまた違った話にもなるだろう。簡単には「竜」は蛇の延長、「龍」はそこから切れた先の何か、というところである。ちなみに漢字の龍と竜の字義に違いはない。竜の繁字体が龍である。 |
|
 ■なぜ竜がいないのに竜宮なのか |
|
|
■1. 竜とは何か
中国における竜(龍)、ヨーロッパにおけるドラゴンの語源は何だろうか。ドラゴンは、蛇を意味するギリシャ語、ドラコーンに由来する。竜の甲骨文字は、蛇の原字の頭に辛字形の冠飾を付けた形となっいる。だから、蛇をモデルにした動物である。 しかし、竜やドラゴンは、たんなる蛇ではない。それは、たしかに、爬虫類のような鱗を持ち、胴体は蛇のように長いが、他方で、空を飛ぶ。西洋のドラゴンなどは、鳥のように翼を持つ。ここからわかるように、竜とは、蛇と鳥という二大トーテムを合成した空想上の動物である。アメリカ大陸では、ケツアルコアトルという、羽のはえた蛇が崇拝されていたが、あれも一種の竜だと考えてよい。 中国では、鳳凰が、龍と並んで崇拝されているが、鳳凰も竜と同様に合成獣である。龍が部分的に鳥の蛇であるのに対して、鳳は部分的に蛇の鳥である。中国の龍には、角が生えているが、これは、中国の伝承によれば、雄鶏の角を盗んだものだということになっている。鳳凰は、首の部分が蛇であるとされている。 |
|
|
■2. 日本の空崇拝は海崇拝である
蛇信仰が純粋な地母神崇拝に基づくのに対して、竜信仰は、母権宗教から父権宗教への移行期に現れる。日本神話は、そうした移行期のコスモロジーに基づいて作られている。国つ神に対する天つ神の優位は、日本文化が父権的であることを示しているように見えるかもしれないが、実は、そうではない。日本文化には今日に至るまで、縄文時代の母権的価値観が色濃く残っている。 例えば、アマテラスは、太陽神のはずなのに、女であり、高天原にいるはずなのに、鎌倉時代に書かれた『通海参詣記』では、蛇だったということになっている。このことは、縄文時代に地母神に仕えていたシャーマン、蛇巫が、弥生時代には太陽神に仕える日巫女(ひみこ)となり、それが後に太陽神と同一視されるようになったからだと推測できる [永井 俊哉/縦横無尽の知的冒険, p.173-183]。 蛇をトーテムとする縄文文化は、弥生時代になって衰えたが、蛇憑きは、最近まで中国地方や四国地方に残っていた。『古事記』は、ヒナガヒメの正体を蛇としているが、これも蛇を地母神とする古い観念の残存であろう。 『記紀』が成立するころには、海崇拝よりも空崇拝の方が強くなった。しかし、日本は、父権宗教のように、地下や海を悪魔の領域とはせずに、空を海の一種とすることで、海崇拝から空崇拝へとスムーズに移行することができた。そのことは、太陽船という観念にみてとることができる。 船がその上に太陽をのせて陸地をめざして訪れるという太陽船の信仰は、東南アジアにひろくみられる信仰であり、そしてまたそれは日本でも古墳時代にはあきらかに信じられていました。そのことは、古墳の壁画にそのような太陽をのせた船、つまり太陽船が描かれていることでわかります。[筑紫 申真/アマテラスの誕生] 太陽船という観念は、古代エジプトにも存在した。青い空をよぎる太陽は、青い海をよぎって航行する船に乗っているかのようである。 過渡的な地母神崇拝の時代においては、空は第二の海であり、しばしば地母神の胎内と同一視された。このことを、高天原の語源分析で示そう。「たかまがはら」は、タカ+アマ+ハラの三つの言葉から成り立っている。このうち、“Ama”は、シュメール語や中国広東語 で「母」を意味し、日本語の「あま(尼・天)」は、そこに由来している。タカを「高貴な」、アマを「母」、ハラを「腹」と解釈するならば、高天原とは、聖母の母胎のことで、高天原からの天孫の降臨とは、ニニギが、聖母の胎内から産まれ落ちたということになる。これは、母なる海から人間が生まれるという母権時代のモデルを九十度回転させただけである。 |
|
|
■3. 天橋立伝説は何を意味するのか
日本神話においては、この世からあの世への通路は、水平方向でも、垂直方向でも、橋として表象される。『丹後国風土記逸文』には、それを示すこんな件がある。 国をお生みになった大神、イザナギノミコトが、天にお通いになろうとして、橋を建立なさった。それで、アマノハシダテといった。神がお休みになっている間に倒れてしまった。[新編日本古典文学全集 (5) 風土記, 丹後国風土記逸文] 天橋立は、京都府宮津湾にある砂嘴で、日本三景の一つとして知られる景勝地であるが、古代の日本人は、この橋を、天と地を結ぶ橋が倒れたものと表象していた。もっとも、実際の順序は逆で、最初に水平方向の現実の橋があって、次に、垂直方向の橋を想像しているわけで、この実際の順序は、現実的な蛇の信仰から想像的な龍の信仰へという思惟の歴史を反映している。 天橋立の景観は「飛龍観」と呼ばれている。股のぞきをすると、海と空が逆転し、天橋立が、空を飛ぶ龍のように見えるからである。実際に股から覗いたわけではないが、天橋立の写真とそれを天地逆にした写真を掲載したので、それをご覧いただきたい。図4は、空が海で、海が空だと思えば、昇竜の写真のように見えないだろか。 図3 海中の竜としての天橋立 図4 空中を飛ぶ竜としての天橋立 [図3を上下逆にしたもの] 天に架かる橋という想像を可能にした自然現象として、虹を挙げることができる。「虹」という漢字は、「蛇」と同様に、「虫」の字が付くが、この「虫」は昆虫という意味ではなくて、本来は、爬虫類の形を模した象形文字である。だから、虹は一種の竜と考えられていたと考えてよい。なお、虹は雄の方で、雌の虹は、霓(本来は、虫偏に兒)と呼ばれていた。甲骨文に「昃(ゆふぐれ)にまた出霓(虫偏に兒)ありて北よりし、河に飮(みづの)めり」とあって、虹が現れるのは、竜が河水を飲みに下る時とされていた[白川静/字通]。 虹は実体のない橋であり、竜のような幻想のモデルにふさわしい。浦島伝説においても、この世と竜宮とをつなぐ橋は、禁忌を犯すことで、虹のようにあっという間に消え、浦島は竜宮に戻ることができなくなってしまった。 |
|
|
■4. 天橋立伝説と浦島伝説と羽衣伝説を結ぶ線
ところで、天橋立の話を載せている『丹後国風土記逸文』に、浦島伝説とならんで羽衣伝説が記されているが、これは偶然ではない。羽衣伝説は、中国の七夕伝説の影響を受けたりして、様々なバージョンを生むことになるのだが、典型的には、次のような要素を持つストーリーである。 1. ある男が、水浴びをしている天女を見つけ、近くに脱ぎ捨ててある羽衣を盗んで隠してしまう。 2. 羽衣を見つけられない天女は天に帰ることができず、止むを得ず、羽衣を盗んだ男と結婚する。 3. その後、男の油断により、天女は羽衣を見つけ、天に戻ってしまう。 4. 男は追いかけるが、天の川の向こうには渡ることができない(七夕的付加) 羽衣伝説は、男が彼岸に行く代わりに女が此岸に来るという点で、竜宮伝説の逆になっている。竜宮伝説では、女が積極的に誘ったのに対して、羽衣伝説では、男が強引に女を引き寄せる。だから、羽衣伝説は、竜宮伝説の続きであると解釈すると、わかりやすい。竜宮伝説が、胎内から出てしまって、戻れなくなる話であるのに対して、羽衣伝説は、胎内に戻ろうとして、失敗する話なのである。 羽衣伝説は、後に、鶴女房という民話になり、それはさらに、木下順二が書いた『夕鶴』という演劇で有名になった。鶴女房のあらすじは、以下のようなものである。 昔、一人暮らしをしている、ある貧乏な若者が鶴を助けてやった。すると、しばらくして、美しい娘が、その若者の家を訪れ、彼の女房になった。彼女は、機織部屋を作ってもらい、「私が部屋を出てくるまで、絶対に中をのぞかないでください」と言って、その部屋で機を織り、美しい布を織った。若者は、その布を売って、金持ちになった。ところが、ある日、若者は、なぜ女房が、糸もないのに、機を織ることができるのか不思議に思って、機織部屋を覗いてしまった。すると、部屋の中では、鶴が、自分の羽を嘴で抜いて、機を織っていた。女房は、助けた鶴だったのである。彼女は、「あなたに本当の姿を見られては、もうあなたのおそばにはいられません」と言うと、空へ舞い上がって、二度と戻らなかった。 これは、かなり浦島太郎物語に近くはないだろうか。羽衣伝説も、竜宮伝説も、仏教的な因果応報の影響を受けたためなのか、後世には、鶴の恩返しや亀の恩返しといった動物報恩譚が付け加えられた。中を覗くなという禁忌とそれを男が破ることによる別離という点でも、似ている。中国版竜宮伝説である「袋の中の鳥」では、袋を開けると、青い鳥が飛んでいくという場面があったが、青い鳥は、青い服を着ていた乙女のことだから、その点では、夕鶴に似ている。 鶴女房の話では、羽衣伝説の天女が鶴という鳥になった。なぜ鶴が選ばれたのだろうか。私は、鶴が蛇のように長い首を持っているからだと思う。西洋の神話では、天女が白鳥であることが多いが、白鳥の首も、蛇のように長い。これらは、いずれも、中国の鳳凰に相当する鳥だ。七夕の牽牛星(アルタイル)と織女星(ベガ)が、はくちょう座を構成しているのも、偶然ではないのかもしれない。 |
|
|
■5. なぜ鶴女房は機を織ったのか
七夕(しちせき)は、日本では「たなばた」と訓ずるが、「たなばた」は、本来「棚機(棚のように見える横板のついた織機)」であったはずだ。日本の鶴女房も中国の織姫も、機を織っていた。アマテラスも記紀では、機を織っている。機を織るということにはどのような意味があるのだろうか。 機を織ることは、女の伝統的な仕事である。フロイトは、女が衣類を編むのは、ペニス羨望ゆえに、擬似ペニスを作りたがっているからだと説明している。しかし衣類はペニスの形をしていない。むしろ糸をペニスと見立て、織物を母体とするならば、機織機で、糸が織物へと織り込まれていくさまは、川が海に注ぎ込む様子と似ている。 しかしながら、機織姫伝説では、視覚的象徴よりも聴覚的象徴のほうが重要である。鶴女房が機を織る姿を見ることができなくても機を織る音は聞こえていた。また、これとは別に、日本各地に、川や池など水の底で機を織る女性の伝説が残っているが、ここでも、姿は見えず、音だけが聞こえる。 では、機を織る音は、何の象徴なのだろうか。私は、それは、胎内の音の再現ではないかと考えている。胎内音は海の波打つ音に似ている。そして、波の音の周期と、胎内で聞こえる心臓の鼓動の周期と、機織の音の間隔は、ほとんど同じである。 浦島太郎物語では、機織が出てこないが、これは海の寄せ来る波の音が、胎内回帰願望を掻き立てる背景音として十分効果を発揮しているからである。これに対して、川や池など、それがない所では、機織の音で、代替となる背景音を作らなければならない。 |
|
|
■6. 人は胎内振動の再現に共鳴する
胎児は聴覚が十分発達していないので、胎内音を聞くというよりも、むしろそれを振動として感じたはずだ。私たちの意識は、胎内での体験を忘れているが、私たちの無意識は、今でも胎内の生命のリズムに深く共鳴する。クラブでは、人々は、子宮の中のような暗闇の中で、ビートに合わせて体を揺すり、エクスタシーに酔うが、それは胎内にいた時の記憶が甦るからなのだろう。 フロイトが指摘するように、乳幼児は、身体を機械的に揺すられることに性的興奮を感じる。むずかる赤ちゃんも、ゆりかごに入れて揺り動かしてやると、寝つかせることができる。幼児は、ブランコが好きだし、鉄道で揺られることも好きである。そのため、鉄道の運転手になりたがる少年は少なくない。 少年たちは、鉄道での出来事に、尋常ならざる謎めいた関心を向け、空想が活発になる年頃(思春期の少し前)になると、その出来事をこの上ない性的象徴の核にするのが常である。[フロイト/性欲論三篇] |
|
|
■7. 銀河鉄道999のモチーフは胎内回帰願望である
松本零士の代表作の一つに『銀河鉄道999』という漫画がある。母を殺した機械伯爵に復讐し、永遠の命を手に入れるため、少年・星野鉄郎が、母そっくりの美女メーテルとともに、銀河鉄道に乗って、銀河の彼方へと旅立つという物語である。 この漫画は、彼が18歳の時、九州からSL機関車で上京した時の体験が元になっている。松本は、当時を振り返って、こう言っている。 18歳の時に夜汽車に乗って上京した。ところが、血が騒いでいて、なかなか寝付けない。それで一晩中、列車の中で空想に耽っていたわけです。がら空きの夜汽車の反対側の窓に、幻のような絶世の美女が前を向いて座っている。そういう姿を想像しながら、いつの日か、そんな場面が入ったマンガを描きたい、アニメを作りたいと思っていた。夢がそこで芽生えていた。メーテルの原型も、その時にでき上がっていたのかも知れません。ぼくはSLに乗って上京した最後の世代。というのも、上京した明くる年、帰郷のために乗った列車はディーゼルに変わっていたので。でも、だからこそ、志を立ててどこかに向かう時には、どうしてもSLでないと具合が悪いと思ったんですね。実は打ち明け話をすると、このシリーズをはじめる時に「新幹線型ではどうか」という話もあったんですね。でも、私は絶対イヤだと。[BBガイド_『銀河鉄道999』記者会見] 窓の向こうに映った美女は、鏡像的他者であり、理想化された母である。ちなみに「メーテル」はギリシャ語で「母」という意味である。少年・星野鉄郎は、もちろん、少年時代の松本である。 松本が興奮して寝ることができなかったのは、彼が汽車に揺られながら胎内回帰の体験をしたからである。胎内で聞く母の心臓の鼓動は蒸気機関車に乗ったときの音とそっくりである。この重厚感あふれるゆっくりとしたテンポの音は、新幹線のせわしい音で代替できない。松本が「絶対イヤ」と言ったのも当然である。 フロイトによれば、汽車に乗って旅に出ることは、死別の象徴である。『銀河鉄道999』のテーマも死別である。この話の根底にあるのは、《機械的なもの=無機的なもの》という死んだ状態への回帰であり、フロイト的に言えば、死への欲動である。 人は母と別れ、母へと戻っていく。銀河鉄道の長く伸びた、ペニスの形をした車体は、胎内回帰のための橋である。それは、また、蛇の形にも似ているが、汽車が空を飛ぶという銀河鉄道999の幻想的なシーンは、竜のイメージを表していると言うことができる。 |
|
|
■8. なぜ竜宮なのに亀姫なのか
話を浦島太郎に戻そう。中国の竜宮伝説には竜女が登場するが、浦島伝説では、竜女の代わりに亀姫が出てくる。現代の浦島太郎物語では、亀と乙姫様は別だが、本来は両者は同一である。琉球諸島に伝わる浦島伝説では、水際に漂う長い髪の毛三本を拾って、持ち主である美女に返してやったところ、お返しとして、竜宮に連れて行ってもらうという筋書になっていて、水中にたゆたう女の長い髪の毛が竜をイメージしているが、竜自体は出てこない。 それでも、亀は、竜や蛇や鳥と同様に、ファリック・マザーのシンボルである。股間から子供の顔が出ている妊婦の姿を想像してみてほしい。それは、亀の姿そっくりである。亀の首は、蛇やペニスに似ている。そして、甲羅は、母体に相当し、その箱のような形状は、子宮を象徴する。浦島太郎は、亀に出会い、亀の甲羅である竜宮へと入っていったのである。 女性が子供を産みたがるのは、欠如したペニスの代替物を子供に求めるからである。股間から産まれる子供は、まさに母にとってのファルスである。そして、母から欲望されることを欲望する子供は、自分が母のファルスとなることを想像する。亀は、この母子相姦的な、ファリック・マザー幻想を象徴する格好の動物なのである。 アイルランドの竜宮伝説では、美しい乙女、ニアヴが馬に乗って現れた。女性が馬に跨っている様を想像してみよう。馬の頭は、女性の股間から生えたペニスのように見えないだろうか。オシーン伝説でも、やはりファリック・マザーが動物のメタファーで表されている。 日本の異類女房譚のもう一つの変種として、蛤女房の話がある。貝は子宮を、蛤の二枚貝が作る割れ目は女陰を、そこから出される舌の足はペニスを表す。蛤が出す粘液糸は、「蛤の蜃気楼」と呼ばれている。蜃気楼の「蜃」の字は、オオハマグリのことで、オオハマグリが吐き出す妖気の中には楼閣が見え、それが竜宮伝説につながったと考えることができる。 | |
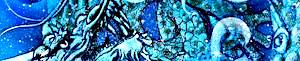 ■ドラゴン |
|
|
(ギリシア語: δράκων, drakōn、ラテン語: draco、英語: dragon、フランス語: dragon、ドイツ語: Drache、ロシア語: дракон, drakon) トカゲに似た、或いはヘビに似た強く恐ろしい伝説の生物。鋭い爪と牙を持ち、多くは翼をそなえ空を飛ぶことができ、しばしば口や鼻から炎や毒の息を吐くという。大抵は巨大であるとされる。体色は緑色、真紅、純白、漆黒などさまざまである。
■竜と龍 日本語ではこの語は「竜」と訳される。この語で示される生物には二種類あり、一つはこの項で語られているドラゴン、もう一つは、アジアに広く分布する伝説上の蛇のような生物(一説にはワニが起源)、いわゆる中国風の竜である(→竜を参照)。一部のファンタジー愛好家を中心に、前者を「竜」、後者を旧字体の「龍」で書き分ける慣習があるが一般には漢字で区別されることはない(中国語文化圏では略字体と伝統字体を1つの文書に混ぜて用いることはない)。 この2種類の生物は厳密には分けて考えられることもできるが、鱗に覆われた爬虫類を思わせる巨大な体、超自然的な能力など共通する点も多く、同一視する向きもある。この場合、東洋の「竜(龍)」に対してドラゴンを「西洋竜(西洋龍)」と称する場合もある。 ■ドラゴンの発生とその遍歴 元々は原始宗教や地母神信仰における自然や不された存在だったと思われる。キリスト教的世界観では、蛇は悪魔の象徴であり、霊的存在を意味する翼が加わることで、天使の対としての悪魔を意味することがある。時代が流れ、「自然は人間によって征服されるべきもの」等といった思想の発生や新宗教が生まれ、新宗教が旧宗教の信者を取り込む際等に征服されるべき存在の象徴(征服されるべき者=悪者)として選ばれた事もある。 ■神話学におけるドラゴン 語源は古代ギリシャ語まで遡る。英語の文献に"dragon"という語が現れ始めたのは1250年頃ラテン語: dracoに由来。さらにこの語は古典ギリシア語: δράκωνに由来する。δέρκομαι(「はっきりと視る」の意)から派生した。 古代ギリシアでは大ヘビ、クジラ、トカゲ、ワニ等の体躯の大きい水棲生物類をひっくるめてこう称していた。聖書ではタンニーンと呼ばれ、水棲巨獣だけでなくジャッカル(現在では全くの別物して扱われている。ただし、ごく一部の古代の壁画等では犬やライオンような頭部を持つ竜が絵描かれていることが多い)をも指すこともあった。キリスト教(ヨハネの黙示録)では悪魔を指す言葉でもあり、このことから邪悪な生き物であるというイメージが付きまとう。また、狼やユニコーンと同じく、七つの大罪の一つである『憤怒』を象徴する動物として扱われる事もある。イギリスでは竜退治で有名な聖ジョージ(聖ゲオルギウス、イングランド他の各地と騎士の守護聖人)の象徴「セント・クロス・ジョージ」が有名である。この場合はドラゴンに十字が添えられた図で表される。 ただし、ウェールズの赤い竜(ア・ドライグ・ゴッホ)や、アイスランドの国章に置かれているランドヴェッテルの竜は守護竜として国の象徴とされる。西欧においてもドラゴンはすべてが邪悪の象徴ではないことに留意したい。 なお、子どもは成長に従ってドラゴンベビー・ドラゴンパピー・ドラゴネット(dragonet)等と呼ばれる。 西洋の伝説において、ドラゴンはサーペント(大蛇)のような姿をしている。ドラゴンは翼のある生物とされるにもかかわらず、とくにゲルマン系の伝説ではしばしば地下の洞穴をすみかとしている。 ■スラヴ神話 スラヴ神話のドラゴンは、ズメイと呼ばれる。この竜は人間とよく似た性質を持っている。たとえば、ブルガリアなどの伝説では、ドラゴンには雌雄があり、人間同様の外見の差異が認められる。雌雄のドラゴンは、まるで兄弟姉妹のように見えるが、農耕神としては全く違う性質を持っている。 メスのドラゴンは、人類を憎んでおり、天候を荒らしたり作物を枯らしたりして、兄弟であるオスのドラゴンといつも喧嘩をしているとされる。それに対してオスのドラゴンは、人を愛し、作物を守るとされている。炎と水は、ブルガリアのドラゴンの神格を表すのによく使われ、メスのドラゴンは水の特質、オスのドラゴンは炎の特質とされることが多い。ブルガリアの伝説では、ドラゴンは3つの頭を持ち、蛇の体に翼を持つ生物とされている。 ロシアやベラルーシ、ウクライナでは、ドラゴンは悪の存在であり、四本の足を持つ獣とされている。そう高くはないが知性を持ち、しばしば小さな町や村を襲い、金や食物を奪う。頭の数は1〜7つ、もしくはそれ以上であるが、3〜7の頭を持つのがもっとも一般的である。頭は、切り口を火であぶらなければ復活するとされる。しかし、ユラン (ロシアの伝承)、チュヴァシ竜のような例外的に敵対的ではない竜も存在する。ロシアは中央アジアの遊牧民族の侵攻を度々受けており、そのため中国や中央アジアの竜信仰が伝播されたためである。 ドラゴンの血はとても有毒であり、地表にも吸い込まれないとされる。 |
|
 ■印旛沼の竜伝説 |
|
|
■印旛沼の竜伝説1
龍腹寺の創建は大同2年(807)と伝えられている。竜「腹」寺の名前には、こんな伝説がある。 「昔」、印旛沼周辺一体に旱魃が続き人々は非常に苦しんでいた。これを見かねた印旛沼の主の竜が大(龍)王にそむき雨を降らせた。竜は天へ戻りかけたが大王の怒りに触れ身体を裂かれた。竜の身体は頭・腹・尾の3つに分れ地上に落ちてきた。頭は栄の竜角寺、腹はここ本埜の竜腹寺、尾は八日市場の竜尾寺に落ち、それぞれの寺で手厚く葬られた。という。 この旱魃を救った竜の話の「昔」は、天平3か4年(731)の事だと言う。2本の角を持つ頭を収めた龍角寺には、天平3か4年と伝わり、この時より竜閣寺から竜角寺と名を変えたと言う。 腹を収めた龍腹寺には延喜十17年(917)に同じ様に大旱魃で祈雨祈祷し降雨のあと寺に竜の腹が落ちていた、とも伝わる。 この2寺とは離れている八日市場の龍尾寺には、「・・和銅2年(709)元明天皇の時、全国的な大旱魃に襲われ人民が飢餓に苦しみ、天皇は勅使に命じ釈命上人を導師として請雨法を修法して雨乞いをした。其の折に、総領村の浜より竜神が空に向って舞い昇った。その時竜の尾が垂れ下った所から、尾垂総領村(おたれ)となり、後に尾垂村となった。現在の匝瑳郡光町尾垂がそれである。空中高く昇った竜神は、間もなく凄まじい雷名と共に、その躰が三ツ切断されて堕ち、同時に激しい雨が振り出して、七日七夜の間降り続いたと云う、それによって枯死寸前の生物は皆悉く蘇生したと伝記されて居る。三ツに断たれた竜神の頭は下総国埴生庄に、腹は下総国印西庄に、尾は北條庄大寺郷にそれぞれ堕ちて埋妃(まつ)られた。即ち頭は印旛郡栄町竜角寺に、腹は印旛郡印西町竜腹寺に、尾は大寺の寺に埋妃り、勅使釈明上人名付けて「天竺山尊蓮院龍尾寺」となる。以来関東の三龍の寺と呼ばれるに至った。(注、大寺とは古代官寺を指した。それより大寺村となる。)・・」(天竺山龍尾寺略縁起) これらをみると大旱魃が何度も襲っていることが分る、恐らく大同以前から水に近い印旛から太平洋にかけ龍神への信仰が根強くあったと思われる。広い地域で共通の龍が3つに分断されたとの話は、この3寺のつながり、また後の佐倉宗吾似た事件があったのでは、壬生氏の栄えるきっかけとか、3つは3ヶ所の反(乱)拠点か、など思わせる。 |
|
|
■印旛沼の竜伝説2
印旛沼は近年の開発で湖沼は様変わりしていますが、上空から見ると竜の形をしているそうです。 昔、日照りの為にお経を唱えていると、小竜の化身が現れ雨を降らせてくれました。しかし小竜は、大竜によって「頭」と「胴」と「尻尾」に切り裂かれ天から降ってきたのです。 落下した所へ供養の為に造られたのが「頭」は龍角寺、「胴」は龍腹寺、「尻尾」が龍尾寺と令名された。 今昔物語(嘉承元年(1106))の中にある話と似ています、今昔物語では奈良県下に於いて龍が四つに切り裂かれ、それぞれ龍海寺、龍心寺、龍天寺、龍王寺となっています。 印旛沼西岸地域には他にも龍神降雨伝説があり白井市清戸地区に伝わっている、清戸には「清戸の泉」(船橋カントリー番ホール脇)があり清戸宗像神社東側にある薬王寺には「青龍山薬王寺並びに堂作弁財天女縁起」の版木が保管され、文政11年(1828)再版とあることから古くから伝えられているものと思われます。龍神のお告げで作られた水枯れしない湖沼で「清戸泉」といわれます。 ■天竜山龍腹寺、印旛郡本埜村(もとのむら)龍腹寺 本尊は釈迦如来、大同2年(807)僧空海の開基、開山は慈観、慈雲山龍福寺「腹」ではなく「福」です。延喜17年(917)龍伝説の発祥により天龍山龍腹寺の山号となる、「福」が「腹」に変わる。利根川図志より。 本殿?は、空家で民家の佇まいと化している、甍には玄林山とあり、天台宗寺院で玄林山勝光院と号する。本尊は釈迦如来です。最盛期には二十五坊にも及ぶ規模を誇ったと言われています。 中世には千葉胤直によって五重塔が建立されましたが、小田原北条氏との兵火で焼亡しました。 竜腹寺地蔵堂の梵鐘には「印西荘龍腹寺玄林山大鐘」と刻まれており、南北朝時代の搗座(つきざ)が一つという珍しい鐘楼が残っています。地蔵堂には延命地蔵尊が祀られています。 また山田寺式瓦の出土した木下別所廃寺が元々の竜腹寺ではないかとの説もあります。 仁王門の二体の金剛力士像は全体を伺うことが出来ない、大同二年(806)に建立、度々の火災により、現存の仁王像は嘉永六年(1853)に作られたもの、昭和49年~昭和52年にかけて修復されました、 「無乳仁王尊」又は「乳無し仁王尊」として名高く「乳」に関する願いは、遂かけて成就するという。 ■天竺山寂光院龍角寺 印旛郡栄町龍角寺、和銅2年(709)竜女の化身で開基、天平2年(730)徳僧釈命上人が七堂伽藍を建立し龍閣寺から天平3年竜伝説により龍角寺となり、「閣」から「角」に変わりました。 当地には古代から仏教寺院が存在したことは間違いない。発掘調査によって、金堂が西、塔が東に建つ「法起寺式伽藍配置」の遺構が出土され、瓦の様式から、この地には七世紀後半には伽藍が存在したことが明らかとなっています。これは、佐倉風土記の伝える草創伝承よりもさらに古い年代である。 寺は中世には衰微していたらしく、承久二年(1220)上総介平常秀が再興しているが、その後もたびたび火災に遭っています。 戦国時代には千葉氏の外護を受け、天正19 年(1591)には徳川家康より20 石を与えられている。 今では、火災で当時の建物が焼失し、本堂跡、仁王門跡、塔跡などにより、在りし日の姿がしのぶ事が出来るのみとなってしまいました。 ■天竺山尊蓮院龍尾寺 千葉県匝瑳市(八日市場市)大寺の龍尾寺は龍角寺の同じ天平3年に同じ。真言宗、本尊は釈迦如来。 弘法大師の井戸水が現在でも使われている古刹です。南北朝時代の板碑があり市指定文化財となっている。 ■佐原市の観福寺、新義真言宗豊山派妙光山蓮華院観福寺 真言宗豊山派(ぶざんは)の巨刹で、本尊は聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)で、寛平2年(890)弘法大師が布教の折りにお泊まりになったため、お堂を建てたのが起こりと伝えられています。 関東厄除弘法大師、佐原新四国大師霊場88ヶ所の祈願寺で「親大師」といいます。国重要文化財の釈迦如来、薬師如来、地蔵菩薩、十一面観音の四体の金剛坐像を拝観してきました。親大師霊場巡拝は4月6日から一週間毎年行なわれています。寺社の住職により詳細な説明を受け、更に厳重に栓錠された宝殿を開錠される光景だけで、中にある尊仏を拝観できる意義を感じられずには居られませんでした。 住職のお話で、当山には「三大厄除け大師像」が祀られています、ということでした。関東三大厄除け大師は、川崎大師、西新井大師と佐野厄除大師をいうので、観福寺の三大厄除大師像は、関東とは別物となります。実は弘法大師が自ら作られた京都の三大厄除大師像なのです。他に、境内には伊能忠敬、楫取(伊能)魚彦、伊能頴則などのお墓があります。 ■京都の三大厄除大師像 当寺にあるという、弘法大師が自ら造られた三大厄除け大師像を拝観したいですね。 一体目は山城国の大蔵寺、二体目は武州河原の平間寺で三体目の京都嵯峨の大覚寺の弘法大師像が当山に移されています。 当山33世鏡覚(けいかく)和尚阿闍梨(あじゃり)の法弟の関係であった大覚寺へ赴き「東国庶民人結縁の為に新四国霊場を開創したことを告げる」と「親大師」として御像が贈られ移されました。 現在まで開帳したこと無し、少し謎が残りますね。 |
|
 ■世界のドラゴンと竜(龍)2 |
|
| ■ギリシャのドラゴン | |
|
■エキドナ Echidna
ギリシャ神話に登場する、下半身が蛇で上半身が美しい女性の姿をした怪物。アルカディアの洞窟に棲み、美しい女性の上半身だけを見せて旅人を誘惑しては食っていたが、最後は百眼の巨人アルゴスに殺された。怪物の母とも呼ばれる彼女はたくさんの怪物を生み出している。地獄の番犬ケルベロス、レルネのヒュドラ、三頭の怪物キマイラ、スフィンクス、ネメアのライオン、黄金の林檎を護るラドン。
■オピーオーン Ophion 古代ギリシャの秘教であるオルペウス派の人々が信じていたとされる宇宙蛇。オルペウス派の思想によると、世界は始め一つの卵しかなく、その中からオピーオーンが生まれ、その身体から神々などが生まれたとされる。世界最初の王とされているが、大地ガイアの息子のクロノスに敗れ、地中深くに追放されたのだという。 ■ケクロプス CeCrops ギリシャ神話の中で都市国家アテナイを建国したとされる半神半蛇の怪物。上半身は髭を生やした人間の男性で、下半身が蛇の姿をしている。大地から生まれたとされている。怪物の姿ではあるがアテナイの王で、半ば神のような存在としてアテナイの人々から崇拝された。この国がアテナイと呼ばれる以前、この国の所有権を争いアテナとポセイドンが対立した。その時、ケクロプスがアテナを選んだことで、この国はアテナイと呼ばれるようになった。 ■スパルトイ Spartoi 地面にまいたドラゴンの歯より生まれた武装した戦士。テバイの泉に棲むドラゴンをカドモスが退治した後にドラゴンの歯を地面にまいたところ、スパルトイが生まれて互いに争い5人だけが残り、テバイの貴族の祖となったという。余った竜の歯は巡り巡ってコルキスの王アイエテスの手に渡り、その地でスパルトイとなってイアソンと戦ったという。 ■テバイの竜 The Theban Dragon ギリシャ神話に登場するテバイにあるアレスの泉を守っていたとされる巨大なドラゴン。軍神アレスの末裔で、黄金の鱗に覆われた蛇の姿で、身体が毒の汁で膨れていたとされる。泉に近づく者を許さず、カドモスがこの地に来た時も、泉に水を汲みに来た彼の部下を殺してしまった。これが命取りで、カドモスによって退治されてしまう。この竜の歯を地面にまいたところ、スパルトイが生まれたという。 ■デルピュネ Delphyne ギリシャ神話に登場する怪物。下半身が蛇、上半身が人間の乙女の姿をしており、口からは火を吐く。テュポンがゼウスと戦って手足の腱を切り取って奪った時、これをコリユコスという岩穴に隠して番をしたのがデルピュネだという。アポロンが退治したピュトンと同一視される事もある。 ■ヒュドラ Hydra ギリシャ神話に登場するアルゴス近郊の沼沢地に棲んでいた怪物。9本の首があり1本だけは絶対に不死身であった。首を切り落とすと切り口から2本の首が生えてきたため、ヘラクレスは首を切り落とすたびに従者のイオラオスに焼かせて再生を防ぎ、最後の1本を大きな岩で下敷きにして倒した。この怪物の血には恐ろしい毒性があり、不死の者でも耐え難い苦しみを味わう。ヘラクレスはこの血を持ち帰り、敵と戦う時に矢に塗った。 ■ピュトン Python ギリシャ神話に登場するデルポイの山に棲んでいたとされる竜。デルポイは神託所があったことで有名だが、ピュトンは以前からあったテミスの神託を護っていたが、アポロンがやって来てピュトンを退治して 大地の裂け目に投げ込んでデルポイの神託所を開いたという。神託所では巫女たちが興奮状態で神の言葉を伝えるが、この興奮状態はピュトンの死体から出るガスによるものだという説もある。 ■ラドン Ladon ギリシャ神話に登場するドラゴン。100個の頭を持っているともいわれる。世界の西の果ての、昼夜の境目にあるヘスペリスの園で黄金の林檎の木を護っている。けして眼を閉じないうえ、100個の頭でいろいろな声、あるいはいろいろな国の言葉で話すという。ヘラクレスに殺されたという説もある。 |
|
| ■欧州のドラゴン | |
|
■ウロボロス Ouroboros
自分の尾を咥えた格好で宇宙を取り巻いているという蛇。無限を表す一種の象徴文字で、古代ギリシャの地図には世界を取り巻く大海にウロボロスが描かれることがあった。ゾディアック(黄道帯)の12宮図でも、その周りをウロボロスが取り囲んでいることがある。グノーシス派(キリスト教)ではこの世を呑みこむ存在の象徴として護符などにその姿を描き、ヘルメス哲学ではこの世を構成する根源的物質の象徴としてウロボロスを用いた。 ■ドラゴン Dragon ヨーロッパの竜たちの総称。巨大な四本足の蜥蜴の姿で蝙蝠のような翼がある。その名前はギリシャ・ローマ時代に「蛇」を意味した「ドラコ」から派生したもので、元々は蛇の形をしていた。時代が下るにつれ、今の一般的な形になった。性格は邪悪で、口から火や煙を吹くものも多い。また、不思議な魔力があり、その血を浴びただけで不死身となり、肉を食べれば予知能力が身につくという。 ■リンドブリム Geflugelterlindwurm 翼があり空を飛ぶことのできるドラゴンの総称。翼のないものはリンドドレイクという。長く尖った鰐のような口に鋭い牙が並び、背中に蝙蝠のような翼があり、尾の先端が鏃のような形になっている。紋章学では「雄々しさ」「容赦のなさ」を表す。空と関係の深いドラゴンで、空を棲家とする。 ■ワーム Worm ヨーロッパのドラゴン。古い伝承では巨大な蛇のような細長い姿をしており、翼も足もない。ぬるぬるの身体をしており、口から毒の息を吐き、身体を斬られてもすぐ元通りになる。普通は井戸や泉に棲み、近づいてきた乙女を食ってしまう。 |
|
| ■イギリスのドラゴン | |
|
■ジャバウォック Jabberwock
『鏡の国のアリス』(ルイス・キャロル)に登場する怪物。魚のような頭に細長い首を持つ。全身が鱗で覆われ、立って歩く恐竜のような二本の腕と二本の脚があり、長い尾がある。そんなに強くなく、炎のように輝く瞳を持っていたが、動きが炎のようにゆらゆらとゆっくりだったため、戦士にいとも簡単に首を刎ねられた。 ■スマウグ Smoug 『ホビットの冒険』(J.R.R.トールキン)に登場するドラゴン。巨大な蛇のような身体に四本の足を持ち、背中に翼が生えている。身体の中では火が燃えており、口や鼻から煙が吹き出しているという。恐ろしい怪物で、ホビットたちが暮らす世界の「荒地の国」に棲み、ときおり村を襲っては家畜やホビットを食っていた。口から吐く炎が最大の武器なので、大量に水がある場所は苦手。 ■ドレイコ Drake 映画「ドラゴン・ハート」に登場するドラゴン。ファイアー・ドレイクの一種。不思議な魔力を持ち、自由に空を飛び、人間の言葉を話し、口からは火を吹く。半死状態のイングランドの王子を自分の心臓の半分を与えて蘇生させたが、王子が邪悪な心を持っていたため、別の場所に隠れ棲む。その後、騎士とともに邪悪な王に挑むが、彼と王は一心同体であったため王を殺すには彼を殺さねばならなかった。 ■ファイアー・ドレイク Firedrake イギリスに棲むドラゴン。口から火を吹く。洞窟や土葬の墓などに隠された財宝を護るドラゴンで、火の精霊または死者の魂だという。その名の通り、全身が火に包まれた状態で空から舞い降りることもあり、こんな時は辺りが昼間のごとく明るくなったという。 ■ラベンダー・ドラゴン Lavender Dragon 『ラベンダー・ドラゴン』(イーデン・フィルポッツ)に登場するドラゴン。背中に翼のある全長10m以上のドラゴンで、身体は空色の鱗に覆われ、太陽の光を浴びると全身が色とりどりに輝き、花壇のように見えるという。性格は優しく、人を攫ったり食べたりはしない。人間が幸せに暮らせるにはどうすれば良いか考え、恵まれない人や孤児が幸せに暮らせるようにと小さな村を作った。 ■ワイバーン Wyvern イギリスに棲んでいるドラゴン。ヴィーヴルがイギリスに入って変化したものだという。鷲のような二本の足と蝙蝠のような翼を持ち、顔は鰐のように長く伸び、口には牙が並び、尾の先端が銛のような形をしている。普通は陸に棲んでいるが、中には湖に棲んでいるものもおり、足の指に水掻きがあるという。 |
|
| ■北欧・ドイツのドラゴン | |
|
■ニーズヘッグ Nidhogg
北欧神話に登場する地獄のドラゴン。死者の国ニヴルヘイムにあるフヴェルゲルミルという名の泉に、無数の蛇たちと一緒に棲む。世界樹ユグドラシルの根をかじり、世界の存在を脅かしている。死者の国の泉には人間の死体も浮かんでいるが、ニーズヘッグはこれらも食べている。鱗があり、翼もあるドラゴンで、ラグナロク(神々の黄昏)の時には地上に出現して空を飛び回るという。 ■ファーブニル Fefnir 北欧系の古い伝説に登場する邪悪なドラゴン。英雄ジークフリートに退治されたことで知られる。『ヴォルスンガサガ』(十二世紀頃)によれば、ファーブニルは毒のあるドラゴンで、大地を震わせて歩く怪物だった。心臓に魔力があり、これを食べたジークフリートは鳥の声が理解できるようになり、アルベリッヒの罠にかからずにすんだ。 ■ヨルムンガンド Jormungand 北欧神話の中で、人間の棲む大地を取り巻いているといわれる巨大な蛇。ミッドガルド蛇ともいう。ウロボロスのような存在で、自分の口を咥えた格好で、人間の世界に横たわっている。ラグナロクの時には激しい津波を起こし、口から毒を吐きながら大地に攻めあがってくる。雷神トールと戦い、相打ちとなる。 |
|
| ■フランスのドラゴン | |
|
■ヴィーヴル Vouivre
フランスを中心にした地方に棲むドラゴン。巨大な蛇の身体に蝙蝠の翼を持っている。雌しか存在せず、普段は地下世界に暮らしている。地上に現れるときは身体全体が炎になり、人を食うこともあった。瞳がルビーやガーネットで出来ていたため、暗闇の中でも瞳を光らせて自由に飛び回ることが出来た。川などで水を飲む時にはその目を取り外して岸辺に置いておく習慣があり、この時に目玉を盗まれると盲目になってしまったという。 ■コカトリス Cockatrice バシリスクの変種とされる怪物。フランスを中心に棲息する。鶏冠のある雄鶏の身体にドラゴンの翼、蛇の尾を持つ。睨まれただけで生き物は死に、吐く毒の息で植物は枯れ、飛ぶ鳥も落ちる。 ■コカドリーユ Cocadrile バシリスクの変種とされる怪物。フランスを中心に棲息し、コカトリスのことを指すこともある。『フランスの田園伝説集』(ジョルジュ・サンド)の中でいっていることによれば、コカドリーユは小さな蜥蜴の姿で、人目につかないところを歩き回り、一晩で信じられない大きさになるという。口から吐く毒で疫病が発生する恐ろしい生き物。退治する方法は沼地を干すか、箱の中に閉じ込めて飢え死にさせるしかないという。 ■タラスクス Tarasque フランス中部のローヌ河に棲んでいたといわれるドラゴン。怪物レヴィアタンと驢馬が交わって生まれた怪物で、鰐に似ており、人間を一呑み出来るほど巨大だった。6本足で、身体は甲羅のような鱗で覆われ、長い牙がある。獰猛で、毒の息を吐き、炎に包まれた糞を飛ばして船や旅人を襲ったので、近くの村人は大いに困ったという。『黄金伝説』(十三世紀)によれば、聖マルタによって捕らえられ、後に村人たちが石を投げて殺した。 ■ペルーダ Peluda ラフェルテベルナール一帯の土地を、口から火を吹いて荒らしまわった怪獣。頭と尻尾は蛇のようで、4本の脚があり、身体は獅子のたてがみのような長い毛で覆われている。背中には毒のある刺のようなものが背骨に沿って生えている。 ■メリュジーヌ Melusine 上半身が美女、下半身が蛇で、背中に翼があるフランスの怪物。ヴィーヴルの仲間。 |
|
| ■中国の龍 | |
|
■応龍 Ouryuu
中国神話に登場する帝王、黄帝に直属していた龍。四本足で蝙蝠のような翼があり、足には三本の指がある。水を蓄えて雨を降らせる能力があり、黄帝と怪物蚩尤が争ったときは、嵐を起こして黄帝の軍の応援をした。しかし、蚩尤と争ったことで邪気を帯び、神々の住む天へ昇ることが出来なくなり、以降は中国南方の地に棲んだという。 ■化蛇 Kada 中国で洪水を起こすとされた翼のある蛇。現在の河南省、陽山を流れる川に数多く棲んでいたという。中国古代の地理書『山海経』では、化蛇の姿として、顔は人面で身体は山犬、鳥の翼を持つとしている。山犬の身体と言っても足はなく、進む時は蛇行するということらしい。 ■蛟龍 Kouryuu 中国の龍で、鱗のある龍のこと。江戸中期に成立した図鑑『和漢三才図会』によれば、蛟龍は眉が交わっており、蛇に似ていて鱗があるとされ、四本足で胴体は幅が広く楯のようで、頭は小さく首の回りに白い模様があるとされている。大きいものは太さが5mもあるという。 ■吉弔 Kicchou 中国の広東、広西地方にいたといわれた怪物の一種。水辺や森に棲む。龍と亀の合成獣で、蛇の頭に亀の身体を持ち、甲羅は何重にもなった龍の鱗でできている。ただ、頭と尾は長過ぎて甲羅に入りきらないという。亀のように見えるが立派な龍の仲間とされている。 ■黄龍 Kouryuu 中国の龍。黄色い龍で、中国の古代から伝わる五行思想では四方を護る青龍、朱雀、玄武、白虎の中央に位置する聖獣だとされる。五行思想で黄色に対応する土徳にあたる時代によく出現するという。ひじょうに縁起の良い龍。 ■黒龍 Kokuryuu 中国の龍で、黒い龍のこと。南方の熊楠の『十二支考』に、長さが3m以上あり、前脚は2本あるが後脚はなく、尾を引き摺って歩く黒龍の話しがある。龍は多くの場合、神聖な生き物とされるが、黒龍には邪悪な側面もある。しかし、五行思想では黒は北に位置するものなので、黒龍は北方を守る神聖な龍とされる。 ■四海龍王 Shikairyuuou 中国で四方の海を支配していたとされる四人の龍王。本来は龍の姿をしているが、普段は人間の姿をしている。東海龍王の敖広、南海龍王の敖潤、西海龍王の敖欽、北海龍王の敖順がいる。それぞれが龍の代表者だが、その中では東海龍王が代表者といえる。 ■修蛇 Shuuda 中国神話において、天帝が尭だった時代に南方の洞底湖に棲んでいたとされる大蛇。巴蛇ともいう。黒い身体に青い頭を持ち、体長が180mとも1800mともいわれ、その巨大な身体で波を起こして漁民たちを苦しめた。また、巨大な象を丸ごと呑み込み、3年後にその骨を吐き出したが、吐き出された骨は腹痛の薬になったという。修蛇は人々に害を与えすぎたために、英雄げい、に退治されたが、その骨を集めると山ができたという。 ■燭陰 Shokuin 紀元前の中国で書かれた『山海紀』の中で、中国北方の鐘山という霊山に棲んでいたとされる龍神。燭龍ともいう。龍の身体に人の顔を持ち、赤い身体は長さが4000kmもあった。燭陰は自然界を司る神で、眠ったり食べたりする事はなく、目を開くと昼になり、閉じると夜になった。息を吹きかけると凍えるような冬となり、息を吸い込むと夏になった。普段はあえて息をしないが、ちょっと息を吹いただけで激しい風が起きたという。 ■青龍 Seiryuu 中国で四神のひとつとされている神聖な龍。姿は通常の龍と変わらないが、その名の通り青い色をしている。四神は五行思想と結びついているので、青い色の青龍は東方を守護し、春に出現するとされている。 |
|
|
■銭塘君 Sentoukun
中国唐時代の小説『柳穀伝』に登場する巨大な龍。300m以上もある巨大な赤龍で、ぎらぎら輝く目があり、舌も鱗もたてがみも赤い色をしている。とんでもない暴れ者で、この龍が出現する時には地を揺るがすような大音響が響き、龍の身体のまわりでは雷が鳴り、雨や霰も吹き荒れるという。もともとは銭塘江という川の水神だったが、尭が天帝だった時代に大洪水を起こし、五岳という有名な五つの名山を水浸しにしたため、神の職を辞したのだという。 ■相柳 Souryuu 中国神話の中で、尭が天帝だった時代に地上を荒らし回ったとされる九個の頭を持つ巨大な蛇。地理書『山海経』では九個の人間の頭を持つとされる。この怪物は英雄の禹が地上の洪水を治めたあとに出現し、九個の頭であらゆる物を食い尽くした。しかも、相柳が進んだあとは毒のある水が溢れた沼沢地と変わり、どんな生き物も住めなくなった。禹は人々の為にこの怪物を倒したが、流れた血が染みた大地には何も育たず、人も住めなくなったという。 ■チ Chi 中国において、山や沢に棲んでいるとされた小さな龍。額に角がなく、赤や白、あるいは蒼色しており、龍や蛟龍の幼生のようなものだともいわれる。岩や木陰といった湿った場所を好み、小さな虫や動物を食って生きており、あまり人目に付くところには出現しなかったという。 ■毒龍 Dokuryuu 中国の龍。中国に古くから伝わる龍ではなく、中近東から輸入された西洋風のドラゴンがこう呼ばれたという。中国の龍のほとんどが神聖とされている中、毒龍は邪悪で、火炎や毒煙を吐いて人間を苦しめた。優れた僧や神通力の持ち主には敵わないらしく、最後に降伏してしまうことが多い。 ■白龍 Hakuryuu 中国において、天帝に仕えたとされる龍。龍は基本的に空を飛べるが、白龍は特に空を飛ぶ速度が速かった。時折、魚に化けて地上の泉などで泳いでいることもある。『果てしない物語』(ミヒャエル・エンデ)に登場するホワイトドラゴンの元となったと考えられる。 ■馬絆蛇 Bahanda 中国の四川省や雲南省の川に棲んでいたとされる蛟龍の一種。「馬絆」と呼ばれることもある。人を襲って食らうこともあり、人々に恐れられた。全体としては蛇のようだが、頭は猫か鼠のようで、その頭に星のような白い部分があるという。とても巨大であり、移動する姿はまるで小屋が転がるようだったという。身体が生臭くぬるぬるしており、馬絆蛇が出現すると、川や風が臭くなったという。 ■龍 Ryuu 中国や日本の川や海に棲むとされる怪物。自由に雨や暴風を起こす力があるので、古くは雨乞いの神とされた。蛇のような長い胴体に四本の足を持ち、頭に角がある姿をしている。後漢王朝末の学者・王符の唱えた九似説では、頭は駱駝、角は鹿、目は鬼、耳は牛、腹は蜃、鱗は魚、爪は鷹、手の平は虎に似ているという。蛇が500年生きると鱗ができ、さらに500年生きると龍になり、角と翼が生えるともいわれる。 |
|
| ■日本の龍 | |
|
■アヤカシ Ayakashi
画集『今昔百鬼拾遺』(鳥山石燕)に描かれている巨大な海蛇。関西から九州にかけての西国の海に出現したもので、時折船に乗り上げるが、あまりの長さのため通り過ぎるのに3日はかかるという。この時蛇の身体からは大量の油が出て船に溜まり、汲み出さないと船が沈む。海で死んだ者の霊だという説もある。 ■イクチ Ikuchi 茨城県の海に棲んでいたとされる長さ数kmの巨大な海蛇。『譚海』(津村淙庵)に記述がある。それによれば、イクチはアヤカシと同種のものらしく、船を見つけると近づき乗り越えて行く。やはり身体からは大量の油が出て船に溜まり、汲み出さないと船が沈む。アヤカシより小さいのか、数時間で乗り越えていくという。 ■大蛇 Orochi 日本の山などに棲む巨大な蛇の総称。蛇は世界中で霊的な存在として崇拝されるが、それが巨大になった大蛇は地霊としての力も特別大きいとされた。八岐大蛇や九頭竜も大蛇の仲間である。 ■清姫 Kiyohime 男を思うあまり蛇になってしまった女。安珍清姫伝説として知られている。紀州(和歌山県)にある彼女の家には熊野参詣の山伏が宿泊しており、清姫はまだ幼い頃から父にいわれるままに将来の夫だと信じ込んでいた。が、山伏にそのつもりは無く逃げ出した。そのため、清姫は恋しさのあまり10mはある大蛇となって、目から血の涙を流して男を追いかけたのである。口から火を吐き、最後には男を焼き殺してしまったという。 ■九頭竜 Kuzuryuu 奈良時代に神奈川県の芦ノ湖に棲んでいたという九つの頭を持った龍。もともとは一つの頭しかなく、近隣の村々を襲っては女や子供を食い、山火事や干ばつを起こして村人を困らせた。そこに万巻上人がやって来て、断食して祈ると竜が現れたので、罪を責めて湖底にある倒杉に縛りつけた。この時に竜は九つの頭を持つ九頭竜に生まれ変わり、以降は山や村を守ることを誓った。 ■七歩蛇 Shichihoda 怪奇小説集『伽婢子』(浅井了意)の中で、京都東山に出現した奇怪な蛇。毒蛇で、噛まれると七歩も歩かぬうちに死ぬので「七歩蛇」と呼ばれた。長さ6cm程の小さな蛇だが、姿は龍のようで四本の足がある。色は真っ赤で鱗の間が金色に光り、耳は立っている。東山のある屋敷で、数多くの奇怪な蛇が出現したのを退治すると、ある日庭の樹木が枯れ、庭石も砕け散った。砕けた石の下からこの蛇が出現したのだという。 ■槌の子 Tsuchinoko 昭和40年代に話題となった幻の蛇。体長は30cm~1m、胴の直径が10cm前後、腹の部分だけは平らで、ビール瓶に三角形の頭と細い尾をつけたような奇妙な姿をしている。 ■トウビョウ Toubyou 中国地方や四国地方にいるという蛇の霊の憑き物。トンベ、トンボともいう。長さ20cmで鉛筆くらいの太さの蛇の姿をしている。薄黄色の腹部を除いて淡黒色で、首の周りに黄色いすじの輪がある。トウビョウに憑かれた家は「トウビョウ憑き」と呼ばれ、その家は金持ちになる。 ■野槌 Noduchi 日本で古くから実在すると考えられている架空の動物。蛇のようだが、直径15cm、長さ1mくらいで、太さの割に短い。ちょうど柄の無い槌のような形をしている。奈良時代の歴史書『古事記』や『日本書紀』の中では山野の精とされているが、時代が下るにつれ怪物のような存在となった。 ■蛟 Mizuchi 山や川の精霊が蛇に化身して霊力を発揮するようになったもの。水田耕作が盛んになった弥生時代には、水を管理する水神のような存在だったが、仏教伝来以降は邪悪な怪物と考えられるようになった。仁徳天皇時代(313年即位)に岡山県の川島川に巨大な蛟が出現し、人々を困らせたという話がある。 |
|
|
■罔象女 Mizuhame
水の精霊が化身した蛇のような生き物。古い時代は蛇、のちに龍の姿と考えられ、蛟龍と同じものともいわれた。水神とされ、それを祀った神社の女神になっていることもある。この女神が司る川などの底には龍宮城があるといわれている。 ■夜刀神 Yatonokami 山中の谷間や底湿地を守護する蛇。『常陸国風土記』に、茨城県に出現した夜刀神の話しがある。それによると継体天皇(507年即位)の頃、葦原を開墾して水田を開くと、たくさんの角の生えた蛇が来て妨害したという。孝徳天皇(645年即位)の頃、同じ場所で池の堤防を築こうとすると、やはり夜刀神が来て邪魔した。が、「天皇に逆らう者は打ち殺す」と言ったところ、皆逃げ出したという。 ■八岐大蛇 Yamatanoorochi 日本神話に登場する大蛇。八つの谷と八つの峰を覆うほどの大きさで、頭が八つあり、尾も八つに分かれている。背中には苔が生え、檜や杉までが茂り、腹は血でぬるぬるとしている。目は鬼灯のように赤く、口からは炎のような毒の息を吐いたのだという。八岐大蛇は島根県の斐伊川上流の村にどこからかやって来て、村に住む老夫婦の娘を毎年一人ずつ食らっていたが、須佐之男命の計略にかかって殺された。この時、尾から出て来たのがかの有名な天叢雲剣(草薙の剣)である。 ■ラプシヌプルクル Rapushinupurukuru アイヌの伝説に登場する龍。その名は「翅の生えている魔力のある神」という意味で、翼の生えた大蛇の姿をしているという。蛇と同じく、暑い時には活発で、寒くなると凍えて動きが鈍くなる。ある物語では洞爺湖の主とされており、寒い季節に湖に浮かび上がると寒さを訴え、「火を焚け、火を焚け」と繰り返したという。暑い季節に火の側でこの名を呼ぶことは恐ろしいこととされた。 |
|
| ■インドのドラゴン | |
|
■アガースラ Agahsura
アガジャラという巨大な蛇に変身することを得意とした悪魔族アスラの一人。クリシュナが、旅の途中でアガースラの領地を通った時、アガースラは巨大な蛇に化け、口を大きく開けて待ち受けた。初めは気付かなかったが、胃に入る前に異臭に気付き脱出して二人の戦いが始まり、アガースラは退治された。 ■アナンタ Ananta インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。千の頭を持つ竜で、その名は「無限」を意味し、世界の始まりと最後にだけ出現するとされる。インド神話ではこの世が始まる以前、宇宙は混沌とした海だったとされ、この時代に三大主神の一人であるヴィシュヌ神がアナンタを船がわりにして、この上で眠っていたという。 ■ヴァースキ Vásuki インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。特に古い時代に崇拝された。「乳海撹拌」と呼ばれる物語で活躍している。まだ神々の支配権が確立していない頃、神々とアスラ(悪魔)が不死の飲料アムリタを手に入れようとしていた。この時神々は巨大なマンダラ山を引き抜き、それを海中の巨大亀の背中に立て、その山にヴァースキを巻きつけて、その両端を神々とアスラが引っ張り合って大海をかき混ぜてアムリタを作った。 ■ヴリトラ Vrtra 古代インドの宗教文献「リグ・ヴェーダ」に登場する巨大な竜。名前には「障害」という意味がある。天から流れ出る川の水を塞き止めて人々を苦しめた。ヴリトラは不死身であったが口の中だけは弱点で、インドラにそこを攻撃されて死んだ。毎年生まれ変わるともいわれ、その度にインドラと戦ったという。 ■カーリヤ Kaliya インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。全てのナーガの祖先といわれている。元々ヤムナー川に棲んでいたが、その毒の為に川は沸騰し、樹木は枯れ、鳥たちは死んだ。これを見たクリシュナはカーリヤの鎌首を踏みつけてラマナカ島に移住させた。これで鎌首に足跡が残ってしまったが、これのお陰で彼の一族には誰も危害を加えることができなくなったという。 ■カルコータカ Karkotaka インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。カーリヤの兄弟にあたる有力な王で、人間にとり憑いた悪魔を払ったり、人間を小人にする力があった。 ■シェーシャ Sesa インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。千の頭を持った巨大な蛇。ヒンズーの宇宙観では世界は七つの層にわかれているが、シェーシャはそのさらに下におり、その頭で世界を支えている。カルパと呼ばれている一時代の終わりに炎を吐いて宇宙を焼き尽くすといわれている。 ■タクシャカ Taksaka インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。この世に最初に生まれたナーガ族の一人。他のナーガたちと同じ姿をしている。ある聖者のために復讐したという話しもある。 ■ナーガ Naga インド神話に登場する半神の蛇(竜)。コブラか、上半身が人で下半身が蛇の姿をしているといわれている。ヒンズーの宇宙観である七層の各層に棲んでおり、悪魔的なものから神として奉られているものもいる。多くの部族があり、各部族の王や有力者はナーガラジャ(蛇王または竜王)と呼ばれる。 ■ナーガラジャ Nagaraja インド神話に登場する蛇神ナーガの王の総称。仏典では竜王と記されている。普通のナーガはコブラと同じような姿をしているが、王たちは巨大だったり頭が複数あることが多い。アナンタ、シェーシャが有名。 ■ムチャリンダ Muchalinda インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。菩提樹の下で瞑想する仏陀の偉大さに感銘し、仏陀を見守った。その間大きな嵐が起こると、その身体を七回巻きつけて七日間風雨から守った。 |
|
 ■世界のドラゴンと竜(龍)3 |
|
| ■西洋竜 | |
|
■アイトワラス
リトアニアに伝わる空飛ぶドラゴン。その環境によってさまざまな姿になる。家の中では黒猫、あるいは黒い雄鶏の姿だが外に出ると空飛ぶドラゴンか、火の尾を持つ蛇の姿をとる事もある。 ■アジ・ダハーカ ペルシア・ゾロアスター教の創世神話に登場するドラゴン。アジは「蛇」を意味するが現代のペルシァ語ではアジ・ダハーカは「ドラゴン」を意味する。アジ・ダハーカは有翼の竜蛇と表現される。苦悩、苦痛、死を象徴する三つの頭を持ち、各頭に6つの目と3組の牙がついている。翼自体の非常に大きく広げると天が隠れるという。ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』によれば「三口あり、三頭あり、六眼あり、千術あり、いとも強く」とあった。また身体を切られると、その度に切られた部分は害虫や毒虫に変わるという。 ■アスディーグ 古代ペルシャ(現在のイラン)神話に登場するドラゴン。多くのドラゴンとは異なり、身体が白いのが特徴。この恐ろしいドラゴンは、神話の英雄ロスタムの敵だった。彼は、ギリシャ・ローマ神話の英雄だったヘラクレスと同じく、数々の課せられた任務を果たし自らの最終的な勝利を達成するために、敵を倒さねばならなかった。 ■アスピス アスピスは「蛇」を意味するがこの怪物は中世ヨーロッパの伝説や伝承ではドラゴンを指している。通常のドラゴンよりは小型で、60cmしかない。文献によっては翼が有るとも無いとも言われる。猛毒を有するため染んだアスピスの皮膚に触れただけでも命にかかわる。噛まれれば、どんな生物も即死する。しかし、その注意をそらす方法が一つだけある。音楽でアスピスを悩ませるのである。獲物を捕獲する際、自分にこんな弱点があることを知ったアスピスは尾の先端を片方の耳に押し込み。もう片方の耳は地面に押し付けて、音楽の感度を鈍化させる。アスピスがこんな姿勢でいれば獲物は確実に逃げ出すことができる。 ■アルクラ シベリヤのブリヤート神話と信仰に登場する巨大な獣。もしくはドラゴン。アリチャ、またはアラコという名でも知られる。翼の有るドラゴンで、黒い翼を広げると空が全て隠れ、光がまったく届かなくなるほど大きい。このドラゴンは天界の住処で定期的に太陽や月を飲み込むが、余りに熱すぎて飲み下せず、それを吐き出さざるを得ないという。ブリヤート族は太陽か月に噛み跡を見つけると太陽が飲み込まれるのを防ぐため、怪物に向かって石を投げる。しかし、神々はよりよい解決法を考え出した。彼らはアルクラを半分に切断し、後ろ半分は地球に落下させた。その後、アルクラが天の光のどちらかを飲み込もうとしても太陽や月は真ん中の切り口から外に零れ、安全に空に戻った。今日、月に見られる模様は月を飲み込もうとして失敗したアルクラの牙によってできた窪みである。 ■イルルヤンカシュ ヒッタイト神話に登場するドラゴン。この混沌のドラゴンは多数の頭を持つ大蛇の怪物である。その最後については二つの説がある。最初の説によると女神イナラシュは天候神を負かしたばかりの強欲なドラゴン、イルルヤンカシュを招き盛大な酒盛りを開く。酒宴でイルルヤンカシュは次々に運ばれるご馳走を平らげ、イラナシュとその恋人バシヤシュの注いでくれる酒に酔いしれて、二人に縛り上げられてしまった。そこへ現れた天候神がイルルヤンカシュを殺しバラバラにして地上に撒き散らした。もう一つの説によるとイルルヤンカシュはその巨大な身体を神々に巻きつけて目と心臓を奪い取り、衰弱させた。そこで天候神の息子はイルルヤンカシュの娘を誘惑し、神々の目と心臓を自分に贈ってくれないかと持ち掛ける。目と心臓を取り戻した神々はイルルヤンカシュを見事打ち倒したという。 ■ウィグル フランスの伝承と伝説に登場する奇怪な爬虫類。ウィグルはギーヴルとも呼ばれワイヴァーンのフランス版ヴイーヴルと似ている。ヴィグルは翼の無いドラゴンの様な姿で描かれるが、他のドラゴンとは違って衣服を着ているものだけを襲う。だから攻撃をかわすには、衣服を脱ぎ捨てることである、そうすればウィグルは逃げ去っていってしまうという。 ■ヴィシャップ アルメニアの伝説に登場するドラゴン。ヴィシャップはアララト山の頂上に棲むと言われる恐ろしいドラゴンである。多くの英雄がこのドラゴンを探して殺そうとした。それはヴィシャップが地方を荒らすからだというだけではなく、ヴィシャップの血はそれに触れた武器はどんな物でも非常に有毒なものに変えてしまうので、僅かに傷付けただけでも相手を殺す事ができると言う伝説の為でだった。 ■ウォントリーのドラゴン イングランド北部のヨークシャーに伝わる伝説と伝承に登場するドラゴン。物語が詳しく載っている『パーシーの遺物』という写本に書かれたウォントリーは、今日の地名ではウォーンクリフと思われる。物語にはこの地方の英雄であるメア・ホールのモアが、このドラゴンと戦うため大釘で覆われた特別製の鎧一式を作ってもらう様子が語られている。彼がドラゴンの弱点の背中を蹴り上げた時、ドラゴンは彼を襲おうとして組みかかった時、鎧の大釘に突き刺され敗れ去ったという。 ■ウルローキ イギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』に登場するドラゴン。この奇怪な生物は、太陽の第一期にアングバンドの穴で、邪悪なモルゴスによって育てられた伝説や伝承上の対応物である火龍と同様に、蝙蝠の様な翼で飛び、破壊的な火を全てに吐きかける。外見が恐ろしいのと同じくらいに恐れられており、他の生物はウルローキがやってくるとみな等しく怖がるという。中でも最も恐ろしいのは黒竜アンカラゴン、エレボールのドラゴンであり、スマウグ、グウラルングという名前である。 |
|
|
■ウンセギラ
米国先住民ラコタ・スー族の伝承と伝説に登場する怪物、巨大なドラゴンで、人間に対して攻撃的で人を捕まえて食べる。誰かがいなくなると、ウンセギラのせいにされている。 ■黄金竜スマウグ イギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』に描かれたドラゴン。ウルローキの種族で、火龍の仲間。鉄の鱗が生え、大きな蝙蝠の翼を持つ巨大なドラゴン。ドワーフの宿敵であり、ドワーフの守りを破って要塞を略奪し全ての宝を盗み、ドワーフの王国を200年にわたって支配した。そこへホビット族のビルボ・バキンスが本当の王トーリン・オーケンシールドと12人のドワーフ達を連れてやってきた。彼らは鎧で固めたスマウグの身体の唯一の弱点は下腹部の小さな箇所だと知っていたので、スマウグが空中に上ろうとした時、弓の達人バルドが黒い矢でそこを射て、スマウグを退治したという。 ■ガアシエンディエタ 米国の先住民セネカ族に伝わる巨大なドラゴン。口から火を吐き、炎の尾を残しながら天空をかけるとされる。その為、「流星の炎を持つドラゴン」とも呼ばれる。このように炎のイメージを持つガアシエンディエタだが、その住処はセネカ族の住む土地の川や湖の水底にあるという。 ■ガウロウ 米国の先住民オザーク族の伝説や伝承に登場する巨大なドラゴン。このドラゴンの姿をした怪物は少なくとも全長6mはあり、額からは牙のような突起物が生えている。Ⅴ・ランドルフが1951年に書き記したところによると19世紀のオザーク山地に棲んでいたという。 ■ガーゴイル 北東フランスの伝説や伝承に登場するドラゴン、ガルグイユとも呼ばれる。ルーアン周辺の田園地帯を流れるセーヌ川の沼地に棲む怪物。セーヌ川に嵐や竜巻を起こしてボートを転覆させ釣り人達を飲み込んでしまう。時には牛や人間を沼地に引きずりこみ水中で食べることもあったという。7世紀にルーアンの聖職者、サン・ロマンがガーゴイル退治を決意するまで数多くの犠牲者が出ていた。サン・ロマンは磔にされた二名の死刑囚を沼の外れへ連れて行きガーゴイルをおびき出そうとした。姿を現したガーゴイルをサン・ロマンは十字架で串刺しにし、飾り帯を首に巻きつけた。犬の様に繋がれて動きを封じられたガーゴイルはルーアンに連行され住民達に殺された。それ以来、雨水を教会の屋根から流すための怪物の形をした吐水口がガーゴイルと呼ばれるようになったという。 ■ガンジ ペルシア(現イラン)の伝承に伝わるドラゴン。財宝や宝石を収めた蔵を守るガンジの額にも、宝石が一粒埋め込まれている。 ■ギータ スペインの伝説や伝承に登場するドラゴン。「ギータ」とは、ドラゴンに似つかわしい名前とは思えないが「足を蹴り上げているラバ」を意味する。だが元の意味は失われ、代わりに口から火を吹く怪物という姿が長く語り継がれている。現在では町でギータの人形がパレードで練り歩き聖体の祝日を祝うカタロニア地方のベルガの祭りに参加する人々を悪魔から守っている。ギータは蛇に似た巨大なドラゴンで緑色の身体を持ち、その首はネス湖の怪物のように長くのびている。巨大な牙の生えた顔は真っ黒で狡猾な目が大きく開かれた赤い口の上に光っている。 ■キャムパクティ メキシコの人々の間で信じられ、語り継がれてきたドラゴン。退治された原書の巨大生物で、その身体から大地が作られたとされる。 ■キュノプロソビ 地中海沿岸の伝説や伝承に登場するドラゴン。ドラゴンの身体と足と鉤爪と翼を持ちながら、犬の頭を持つとされている。また毛皮に覆われ、顎鬚がある。鋭い叫び声とシューという音で仲間と通信し、自分たちと同じく、サハラ砂漠北部に棲むアンテロープや山羊を餌食とする。 ■蛇の王(king of the snakes) スウェーデンの民間伝承に登場する蛇族の恐ろしい守護霊。頭に冠羽を持つ蛇に似た巨大なドラゴンとして描かれる。『ハマル年代記』の中の伝承によれば、誰かが最初に蛇を一匹見て殺した。すると次々と別の蛇が現れてきたが、それらも最後には殺された。するとキング・オブ・ザ・スネークの巨大な頭が現れて、見たものを攻撃したので、見たものは命からがら逃げ出したという。 |
|
|
■グラウルング
イギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』に描かれたドラゴン。太陽の第一紀にアングバンドの地下要塞で邪神モルゴスによって造りだされた最も凶暴で強い力を持つドラゴン。ウルローキの指すベルリアンドの戦いの「焔流れる合戦」の際に解き放たれ、エルフたちに攻撃を仕掛けた。火龍や冷血龍はグウラルングの子孫に当たるグウラルングを退治したのは英雄トゥーリン・トゥラムバールだが、グウラルングの毒血にやられて相打ちとなった ■クリリ 古代シュメール神話に登場するドラゴンの一種で、後にマーマンとなった。カオスの象徴とするドラゴンとして描かれる事もあれば、魚人間の一種として描かれる事もある。 ■黒龍アンカラゴン イギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』に描かれたドラゴン。太陽の第一紀に邪悪なモルゴスによってアングバンドの地下坑で飼われていた火龍の一頭で、怒りの戦いの際の大合戦で殺された。その時他の火龍も全て同様に殺された。 ■ゴリニチ ロシアの伝説や民間伝承に登場する恐ろしいドラゴン。邪悪な魔法使いネマル・チェログは皇帝の娘をさらって、暗く巨大な城に幽閉し、甥であるドラゴンと結婚させようとした。 ■ゴリシュチェ ロシアの伝説や民間伝承に登場するドラゴン。12の頭を持つ巨大な怪物で、ソロチンスクの山地の洞窟に棲んでいる自分の子供達の為に人間を捕まえる。ゴリシュチェに襲われたロシア人の若者達はまるで牛の群れのように洞窟の奥深くに集められ、最後の時を待つのである。 ■サファト 中世ヨーロッパの動物寓話集や旅行記に登場するドラゴン。翼の有る蛇に似て、ドラゴンの頭を持つ。雲の上の天に生息し、地上からはめったにその姿が見られないとされた。 ■シルシュ メソポタミアのバビロニニア神話に登場するサーペント・ドラゴンのムシュフシュの別名。ティアマトの群れにいる多くのドラゴンの一匹。 ■スヴァラ アルメニアの伝説と伝承に登場するドラゴン。巨大な黄色いドラゴンで、頭には大きな角、牙、耳があり、人間の腕も持っていた。辺り全ての物に毒を注入していたが、英雄クルサースパに退治された。 ■スキタリス 古代の文献と中世ヨーロッパの動物寓話集に描かれた怪物。名前はscitulusと言うラテン語に由来し「優雅な」と言う意味。翼の有るドラゴンで、前足2本と、蛇の頭と尾を持つ。大変美しい玉虫色の皮膚を持っていたので、それを見た人はうっとりと見とれていたと言う。だがこれは罠であり、スキタリスは大変ゆっくりとしか歩けないが、獲物がぼうっと見とれている間に近づき、攻撃して殺すので、狩をする必要が無い。12世紀のラテン語の動物寓話集、1220年頃の動物寓話異集によれば、大変高熱を発するので、厳しい霜の中でも外に出てきて蛇と同じように脱皮したと言う。 ■スティヒ アルバニアの伝承に登場する巨大なドラゴン。口と鼻孔から炎と火を吹く。宝の山の守護者。 |
|
|
■ストレンヴルム
スイスの伝承に登場する、恐ろしいドラゴン。トカゲの頭に猫の頭をし、ドラゴンのいぼの付いた身体の先には長い尾が付いている。全身は鱗で覆われ、赤い血管と剛毛があちこちにある。人間に対しては、後ろ足で立って人間より高くそびえ、恐ろしい姿を見せ付ける。フランスとオーストラリアをつなぐアルプスの道には沢山の話が残っており。そこではタッツェルヴルムと呼ばれている。 ■ダハク ペルシア(現イラン)のゾロアスター教の信仰と伝説のドラゴン。地上の価値有る物を破壊する事に精を出す邪悪な生物。英雄スラエオタナは数々の危険を乗り越えた後にこの獣を殺すことはできなかったものの、打ち倒し山の麓に鎖で永久につなぎとめた。予言によれば、最後の戦いと最後の審判の日が近づいたときダハクは鎖を解き、破壊を繰り広げる。 ■タラスカ スペインの伝説と伝承に登場するドラゴン。もともとこのドラゴンは南フランスのタラスクに深く関係があるようで、子供を食べるとして恐れられるドラゴンの典型である。今日ではタラスカの模型が、ポンデヘドラのレドンデラで聖体の祝日に大勢の人々によって退治される。その腹中に小さな子供達が座っている状態で行進するのである。 ■タラスク フランスの中世の伝説に登場するドラゴン。タラスクはリヴァイアサンとボナコンの子供と言われており、巨大な雄牛の身体と熊の足を持つとされた。タラスクはエスク・ラ・シャペル地方の田舎で恐怖の的だったが聖マルタがタラスクを鎮めて退治した。それ以来タラスクは町のパレードで行進するようになったと言う。 ■タンニン 旧約聖書とヘブライ語文書に登場する怪物。タンニンは非常に強力な蛇と考えられる。原書の混沌の蛇またはドラゴンであり、リヴァイアサンやラハブと同じものなのかもしれない。 ■チョドーユドー ロシアで語り継がれ、信じられていたドラゴン。口から猛烈な火を吐く多頭の恐ろしいドラゴンと言われる。恐るべきババ・ヤガの子供と言う説もあれば、女巨人を最高に邪悪な形にしたものと言う説も有った。更にこの生物はババ・ヤガと関連の有るもう一匹の邪悪なドラゴンである、不死身のコシュチェイの同胞とも言われた。 ■ツーバン ペルシア神話に登場するドラゴン。沢山の頭を持つ、火を吹く巨大なドラゴンとされる。より古いサーペント・ドラゴンから変化したものかもしれない。アラブ世界の伝説ではティニンとして知られている。 ■ティアマト シュメールとバビロニアの神話に登場する世界ドラゴン、あるいは宇宙ドラゴン。ティアマトは雌のドラゴンで、巨大な蛇のような身体は武器を通さず、2本の前足と大きな尻尾があり、頭には大きな角が付いているとバビロニアの天地創造神話『エヌマ・エリシュ』に書かれている。またティアマトは「大洪水を起こす龍」とも呼ばれ、戦いの場では毒を撒き散らし、敵ばかりで無く見方まで圧倒される鬼気を発し呪力で持って敵をなぎ払ったと言う。数々の魔物を生み出したことで有名である。 ■トゥリヘンド エストニアの伝承に登場する家の守り神的なドラゴン。プークあるいはピスハンドとして知られ、蛇のような身体で4本足の長さ60cmのドラゴンとして描かれ、主人の為に宝を盗んだり守ったりする。地方では翼を持ち空を飛び、燃える尾を持つ。 ■ドラコンティディス ギリシャ・ローマ神話に登場するドラゴン、「ドラゴンの子孫」の意。アリストバネスの作品『蜂』で、ドラゴンに変えられた後の英雄ケクロプスに与えられた名前。 |
|
|
■ニーズヘグ
北欧神話に登場する最も邪悪な黒い飛竜。冥界で死者の身体を引き裂いたり、世界全体を支えているトネリコの木『ユグドラシル』の根を地中でかじって、世界の存続を脅かす事から、「嫉妬深いドラゴン」「死体を引き裂くもの」「恐ろしい噛み付き獣」「あざ笑う殺人者」「怒りに燃えてとぐろを巻くもの」など様々な名称で呼ばれている。 ■バシリク フランスの民間伝承に登場するドラゴン。家畜や人間を連れ去って食べるだけでなく、恐ろしい目で睨みつけた見た物全てを石にする力でヴィエンヌ周辺の田舎町を苦しめた。町はさびれ、恐れられたがとうとう有名な騎士フレタールがバシリクを打ち倒しコレーンの泉の奥底に追い払った。しかし、この乱暴な獣はそれで終わりはしなかった。10年ごとに昇って来て再び姿を現すからだった。しかし、もし監視者がバシリクから見られる前にこの怪物を見つければ水底に送り返せると言われていた。しかし、もし湖の淵の水面に到着するのを誰も見なければその地域は再び悲運に見舞われると言う。 ■ビスターンの龍 イングランド、ハンプシャー州ビスターンのバークレー家に伝わるドラゴン。16世紀以前に古英記で記された伝説には、退治しようとする者全てを殺し、その地方を荒らしていた恐ろしいドラゴンとモリス・バークレー卿が対決した様子が物語られている。 ■ピュトン ギリシャ・ローマ神話に登場するドラゴン。デルポイ付近を襲ったデウカリオンの大洪水後に残った泥から生まれたとされている。ピュトンは大変大きく成長し、守護する神託所をすっぽり囲んでとぐろを巻いた。このドラゴンの最後はアポロンにヘパイストスの鍛造した矢で射られてピュトンは苦しみながら死んだ。遺骸が腐って異臭を放っていた場所がデルポイの神託所となり、アポロンは、勝利を記念してピュトン競技を創始した。 ■火龍(1) ヨーロッパのケルトの伝説とゲルマン人の伝説に登場するドラゴン。火を吐き空を飛ぶ偉大なドラゴンでありイギリス諸島の湿地帯や沼沢地またはヨーロッパ北部の山の深い洞窟に生息するといわれている。どんな所に棲んでいるにしても、この火龍の第一の仕事は財宝の守護であり彼らは恐ろしい敵であると言う。 ■火龍(2) イギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』の中でウルローキと呼ばれるドラゴンの一種。邪悪なモルゴスによって生み出されたこの恐ろしい生物は伝説のドラゴンと同様に蝙蝠の様な翼で空を飛び回る事ができ地上のあらゆる物に破壊的な火を吐きかけた。この仲間の中でも特に恐ろしいのは黒龍アンカラゴン、黄金龍スマウグ、そしてグウラルングの三頭だったという。 ■ベル 旧約聖書のダニエル書で言及されているドラゴン。ダニエルが捕らえられていたバビロニア帝国で尊敬と崇拝の対象になっていた。 ■ムシュフシュ 古代バビロンとメソポタミアの神話に登場する巨大な宇宙的ドラゴン、シルシュとも呼ばれる。ドラゴンの身体が蛇の尾で終わり、その先には毒を持つ針が付いている。後ろ足は鷹だが、前足を含めた前半身は獅子。頭は蛇だが角があり、頭頂の突起が首まで繋がっている。全体が皿のような鱗に覆われ、マルドクの町であるバビロンのイシュタル門を守護したと言われている。 ■ラドン龍 ギリシャ・ローマ神話に登場する怪物ドラゴン。巨大な身体は鱗に覆われ100の頭に光る200の目が付いていると言われる。ラドン龍はテュポンとエキドナの子であるとか、あるいは女神ヘラの被造物であるなど様々に言われる。しかし、ラドン龍をヘスペリデスの黄金のリンゴ園に置いたのはヘラだった、そこでラドン龍は木の幹に巻きついて番をした。しかし、英雄ヘラクレスは12の難行の11番目としてリンゴを必要としていた。彼はラドン龍を見事に射止めて戦うまでも無く即死させ、リンゴを奪った。ヘラは自分のドラゴンが死んでいるのを見つけると星座として天に据えた。そしてヘラクレスは勝利を記念してラドン龍の絵入りの盾を持ったと言う。 ■ラハブ 旧約聖書とヘブライ語の文献に登場する怪物。長大な海蛇で、強い力を持ち原書の混沌を体現する蛇又はドラゴンとされる。エホヴァと戦って頭を割られ、身体を刺し貫かれて死んだ、名の意味は「凶悪」「嵐」などでユダヤの民が敵対するエジプトを呼ぶときの名でもあった |
|
|
■冷血龍
ギリスの学者、作家J・R・R・トールキンの小説『ホビット』と『指輪物語』に登場するドラゴン。この恐ろしい生物は、太陽の第一紀にアングバンドで邪悪なモルゴスから生まれた。冷血龍は鉄の鱗に覆われた巨大な身体、翼、巨大な牙、巨大な鉤爪を持つと描写されている。(伝説のドラゴンと違い、飛ぶことはできない) 悪が信仰に打ち勝ち、冷血龍たちは中つ国の人々の間で大混乱を引き起こすが、怒りの戦いでほぼ完全に滅ぼされた。しかし、太陽の第3期に再び現れて灰色山脈に豊かな金鉱を見つけたドワーフ達を追い詰め、秘密裏に彼らを殺し、強欲に金を奪い取る。その後、エオセオド国の族長の息子である勇敢なフラムが、冷血龍のリーダー芋虫スカサと戦って相手を殺すと、他の冷血龍達は逃げ去った ■ローズマリーワーム イングランドの伝説と民間伝承の醜いドラゴン。通常は翼を持たない巨大なドラゴンで、身体の前部は二本足の蛇に似ている。中世のヨーロッパでしばしば詩篇や寓話などに書かれた。『ライレル詩篇書』にはこれらの怪物が数多く登場しヨーロッパの広い地域を荒廃させたと言う。 ■ロタン メソポタミア神話のドラゴン、現在のシリアにあるウガリットの遺跡ラス・シャラムラから出土した神話文書では。七つの頭をもつ巨大なドラゴンとして描写され、バアル神がこの怪物を退治したと記されている。ヘブライ神話のレヴァイアサンやバビロニア神話のティアマトと同様に原初のカオスを象徴するサーペント・ドラゴンである。 ■レインボードラゴン 読んで字の如く、虹の竜である。レインボードラゴンは宝物守護系の竜であり、その尾を捕まえることができれば、莫大な財宝が手に入ると言う。尾は虹の両端のどちらかであるから、財宝を欲する人には究極の二者択一が待っている。頭の方を選んでしまうと、その場で食べられてしまう。一説によるとレインボードラゴンは邪悪な小人ゴブリン達が財宝を守るために創造したものであると言う。あるいは、財宝が持つエネルギーが竜の形で放散されていると言う意見もある。 ■ムーンボー・ドラゴン レインボードラゴンの親戚であるが、こちらは夜に出る虹である。満月ないしそれに近い月齢で天候その他の諸条件が整った場合のみ出現する神秘の竜である。ムーンボードラゴンは異界への扉であり、アーチをくぐる事ができれば妖精界へ旅立つ事になると言われている。妖精界から帰還するにしても、あちらの世界でムーンボードラゴンを見つけなければならない。従ってこの手段で異界冒険をする人間は、往々にしてゆきて帰らぬ人になってしまう。それでも良いと言う人にのみ、利用をお勧めする。 ■ミラージュ・ドラゴン 地平線ないし水平線に出没し、独特の妖気を放って蜃気楼を作る竜。妖精界の門番的存在であり,俗界の者を迷わせて追い返すことを職能とする。 ■ワイバーン 2本足の細い身体をした飛龍。翼には鉤爪があり、これが前足の代わりである、双頭の獅子又は鷲等、盾に描く紋章のために図案として生み出されたものと言われる。16世紀まではウィヴァーと呼ばれており、トカゲのような姿をした羽根のある小さな龍であった。 ■ワイアーム 手足の龍ワームに翼の付いた者。長い身体をくねらせながら空を飛ぶ、着地はできないので水上に着水する。泳ぎも蛇の様に得意である。知能は低く、獣並と言える。 ■ビュレス・ドラゴン イングランド地方サフォークとエセックスの境に有るスタウア川流域に伝わるドラゴン。其処に有るピュレスという町で1405年に僧侶によって記録された。その姿は、胴が太く、頭には鬣が生え、歯は鋸の様に鋭く長い尾を持っていると言う。ドラゴンは羊飼いを殺し、羊も食った。そこで領地の家臣や村人らが退治しようとしたが、矢を跳ね返し、丈の長い葦の生える沼へと飛び込んだと言う。現在、ピュレス辺りの村にはワーミングフォード(大長虫の浅瀬)という村があり、教会等の各建物にドラゴンの彫刻が見られるのは、過去にそんな事件があったからだと言う。 ■ヘンハム・ドラゴン イングランド地方エセックスに現れたドラゴン。全長は2.4~2.7m鱗に覆われたゴツゴツした肌、直立した首に大きな目、環節状の足、尾は三叉と、一般的にイメージされるドラゴンと同じ特徴を持つ。そしてこのドラゴンは1668年に熊手で退治されたと伝わっている。この騒動により。ヘンハム・ドラゴンはその後居酒屋「エセックス・サーペント亭」の商紋になり、300年後の1968年には「ドラゴン300年記念祭」が催されるなど、かなり象徴的な出来事だったと見える。現在大英博物館には、その記念祭のパンフレットが所蔵されている。 ■テーバイの竜 ギリシャ神話の中で、テバイにあるアレスの泉を守ったとされる巨大なドラゴン。軍神アレスの末裔で、黄金の鱗に覆われた蛇の姿をしており、身体が毒の汁で膨れていたとも言われている。泉に近づく者を許さず、英雄カドモスがこの地に来たときも水を汲みに来た彼の部下達を殺したと言う。この為、カドモス自身の手で殺されてしまうが、彼がドラゴンの歯を取って地上にまくと、其処からスパルトイという戦士たちが植物のように地面から生えてきたと言う。 ■ラベンダードラゴン イギリスの作家イーデン・フィルポッツの作品『ラベンダードラゴン』に登場するドラゴン。背中に翼の有る全長10m以上のドラゴンで、全身は空色の鱗に覆われており、太陽の光を浴びると色とりどりに輝いて、まるで花壇の様に見えると言う。性格も優しく、人をさらったり食ったりする事はしなかった。ラベンダードラゴンは、人間が幸福になるにはどうすればいいかを考え、恵まれない人や孤児が幸福な生活を送る事ができる小さな村を作ったと言う。 |
|
| ■東洋龍 | |
|
■青龍
中国で四神の一つとされている神聖な龍。姿は通常の龍と変わらないが、その名の通り青い色をしている。古代の壷等に描かれた青龍の場合、頭だけは白色や黄色の物もある。四神は五行思想と結びついているので、青い色の青龍は東方を守護し、春に出現するとされている。 ■応龍 中国神話に登場する帝王の黄帝に直属していた龍。4本足で蝙蝠のような翼が有り、足には三本の指が有る。水を蓄えて雨を降らせる能力があり、黄帝と怪物シユウが争ったときは、嵐を起こして黄帝の軍を応援した。しかし、シユウと争った事で邪気を帯び、神々の天へ登る事ができなくなり、以降は中国南方の地に棲んだと言う。応龍のいる南方の地には雨が多いのに、それ以外の場所には旱魃に悩むようになったと言う。 ■蛟龍 中国の龍の一種で、鱗の有る龍の事。江戸中期に成立した図鑑『和漢三才図絵によれば』蛟龍は眉が交わっており、蛇に似ていて鱗があるとされる。また、4本足で、胴体は幅が広くて楯のようで、頭は小さく首の周りに白い模様があるなどしてとしている。大きいものは太さが5mもあるという。空を飛ぶとき数多くの魚を引き連れていると言う。中国漢代の哲学書『准南子』では、介燐と言う生き物から蛟龍が生まれそこから最終的には魚類が誕生したとしている。 ■黄龍 中国の龍の一種。黄色い龍で中国に伝わる五行思想では四方守る青龍、朱雀、玄武、白虎の中央に位置する聖獣だとされる。五行思想で黄色に対応する土徳にあたる時代によく出現すると言う。中国では瑞獣の出現を記念して改元を行う事があるが、黄龍が出現したと言うことで「黄龍」と改元されることもあった。 ■黒龍 中国の龍の一種で、黒い龍の事。南方熊楠の『十二支考』に長さが3m以上あり、前足は2本あるが後足は無く、尾を引きずって歩く黒龍の話がある。龍は多くの場合に神聖な生き物とされるが。黒龍には邪悪な側面もある。中国神話の中には、この世が誕生して間もない頃に中原一帯を荒らし回った黒流がいて、女禍と言う女神に退治されたと言う話がある。五行思想では黒は北に位置するものなので、黒龍は北方を守る神聖な龍とされる。 ■四海龍王 中国で四方の海を管理していたとされる4人の竜王。本来は龍の姿をしているが、普段は4000mも有る人間の姿をしていると言う。東海龍王のゴウコウ、南海龍王のゴウジュン、西海龍王のゴウキン、北海龍王のゴウジュンがいる。それぞれが龍の代表者だがこの中では東海龍王が代表者といえる。龍王は皆それぞれの海の底に美しい竜宮城を構え、王として君臨している。雨を司るのが彼らの仕事だが、彼らの上には天界の王である、玉帝がいて、降雨を命じると言われている。 ■チ 中国において、山や沢に棲んでいたとされる小さな龍。額に角が無く、赤や白、或いは蒼色をしており、龍や蛟龍の幼生の様な物だとも言われる。岩や木陰のような湿った場所を好み。小さな虫等を食って生きており、あまり人目に触れる場所には出現しないと言う。チが湿った場所を好むのか、チその者が場所を湿らせるのかはっきりしないが、有る場所からチがいなくなった為にその場所から湿気がなくなったという話も残されている。 ■馬絆蛇 中国の四川省や雲南省の川に棲んでいたとされる蛟龍の一種。「馬絆」と呼ばれることもある。人を襲って食うことがあり、人々に恐れられていたと言う。全体としては蛇に似ているが、頭は猫か鼠の様で、その頭には星の様な白い部分があるという。とても巨大であり、移動する姿はまるで小屋が転がるようだったと言う話も残っている。身体が生臭くぬるぬるしており、馬絆蛇が出現すると、川はもちろん、風まで臭くなったと言う。 ■毒龍 中国の龍の一種。中国に古くから伝わる龍ではなく、中近東から輸入された西洋風のドラゴンが中国ではこう呼ばれたと言う。中国の龍はほとんどが神聖とされるが、毒龍は性格も邪悪で口から火炎や毒煙を吐いて人間を苦しめたと言う。有る話では西域の積雪山の池に棲む毒龍は百人の商隊を皆殺しにしたという。しかし、優れた僧や神通力の持ち主にはかなわないらしく最後には降伏してしまうことが多い。 ■白龍 中国において天上界の皇帝である天帝に仕えているとされた龍の一種。龍は基本的に空を飛べるが、白龍は特に空を飛ぶ速度が速く、これに乗っていれば他の龍に追いつかれないとも言う。時折魚に化けて地上の泉などで泳いでいる事もある。 |
|
|
■神龍
中国神話に登場するドラゴン。シェンロンは雨を司り、風に乗せて雨を呼ぶ。聖なるドラゴンとも呼ばれる美しい玉虫色をして、5本の足指を持つ、ドラゴンの皇帝シェンロンの姿を描いた衣服を着ようとする者は死刑に処される。シェンロンと関わりを持ってよいのは中国の皇帝だけだからである。 ■チーロンワン チーロンワンは中国の伝説や広く知られる伝承に登場するドラゴンである。名前は「雨龍」と訳せる。この恵み深い東洋龍は家庭用水の管理者として考えられていた。チーロンワンは大地に水を与える竜王に対する宗教的崇拝にその起源に有する。 ■九頭龍 奈良時代に神奈川県の芦ノ湖に棲んでいたと言う9つの頭を持つ龍。元々は1個で、周辺の村々を襲っては女や子供を食い、山火事や旱魃を起こして村人を困らせていた。そこに万巻上人がやってきて、断食して祈ると悪龍が現れたので罪を責めて湖底に生える逆杉に縛り付けた。このとき龍は9個の頭を持つ九頭龍に生まれ変わり、以降は山や村を守ることを誓ったので上人は九頭龍神社を建てて竜神を祀ったと言う。 ■ラプシヌプルクル アイヌの伝説に登場する龍の一種。その名は「翅の生えている魔力のある神」と言う意味で翼の生えた大蛇の姿をしていると言われる。蛇と同じように、暑い時には活発で、寒くなると凍えて鈍くなる。ある物語では、この龍は洞爺湖の主とされており、寒い季節に湖に浮かび上がると盛んに寒さを訴え「火を焚け」「火を焚け」と繰返したと言う。 ■伏蔵龍 中国の伝説と伝承に登場する龍。秘宝の龍としても知られ、名前が示すとおり地下にある鉱物資源全ての守り主である。 ■アナンタボガ インドネシア、ジャワ島の神話と伝説に登場する龍。古代の伝統的な神話に出展するワヤン劇では、アナンタボガは龍族の王で、冥界を自分の領土としている。彼の妻はデ=ヴィー・ナーガギニーと呼ばれている。名前と地位から考えて、ともにヒンドゥー教の蛇であるアナンタ、シェーシャ、ナーガ、ナーギニーと同等であるようだ。 ■アパララ インド、ペルシャワール州の仏教説話に登場する龍。伝説によればアパララは現在のパキスタン領であるペシャワール高地のスワット川の源に棲み、支配していたと言う。この恐ろしい怪物は仏陀に飼いならされ、改宗したと言う。 ■シンヒカー インドのヒンドゥー教神話に登場する女の龍。猿神ハヌマーンの敵である。ハヌマーンは、シンヒカーの口の中に飛び込み彼女の腹を引き裂いて飛び出して殺した。 |
|
| ■ワーム | |
|
■グロスターワーム
ワーム(worm)とは北欧形の竜を指す言葉であり、本来はミミズの意である。グロスターワームは12世紀のイギリス中西部に位置するグロスター界隅に出没した無翼無脚毒竜であり、全長50メートルのミミズを想像すればいい。この化け物が放つ毒気の為に、動植物は全て死滅したと言われる。退治したいなら、爆発物ないし可燃物を腹の中に送り込むとよい。ワーム系の連中は理屈も何も通用しないモンスターであるから出会ったら最後やるか、やられるかしか無いのである。 ■ストールワーム ブリテン島と北欧の伝説に登場する蛇、名前は『大蛇』という意味。体がスカンディナヴィア全域を覆うほど大きかった。北の海に生息するが、この怪物が出現するとブリテン島全てが洪水になった。宥める為に人身御供が行われ、それ以上災害を与えられないようにした。だが、王女が次の犠牲に決まると、王はストールワームを退治したものに国土の半分を与えると申し出た。それを知ってアシパトルが名乗り出た。アシパトルは、ゆっくり燃える泥炭を使った策略を編み出し、怪物が口を開けた隙に燃える泥炭を次から次へと投げ込んだ。泥炭は怪物の腹で燃え続けた、ストールワームがのたうち回った跡がデンマーク、スウェーデン、ノルウェーの国境となりスカゲラク海峡も作り出した。顎を擦り付けて、吐き出した歯が北海に飛び込んでオークニー諸島、フェロー諸島、シェットランド諸島になった。燃える身体が縮んで球状となり、これが現在のアイスランドになった。 ■ブラッハ・プハディ スコットランド沖のヘブリディーズ諸島の民間伝承に登場する水棲生物。魔法使いのシャックルと言う名でも知られており、巨大なワームあるいは蛭に似ていて、頭頂部に9つの眼を持つ。この生物は島々の湖や川の浅瀬はもちろん低地地方のパースシャーにも棲んでいた。馬に乗ってこういった浅瀬を渡る人は、ブラッハ・プハディに注意しなければならなかった。ブラッハ・ブハディは馬の匂いを嗅ぎ付け、あっという間に馬の足にくっ付いて川に引っ張り込み食べてしまうのである。 |
|
| ■蛇 | |
|
■ナーガ
インドの蛇神、女性のナーガはナーギニーと呼ばれ皆大変に美しく賢いと言われている。生と死の両面を司っており、敵を一撃で倒す事のできる猛毒と身体に受けたどんな傷も癒す事のできる不死身の力を持っている。また、神の蛇に相応しく、誰にも気づかれずに不意打ちする事もできる。インドの七層に別れている地下世界の内、最下層であるパーターラに棲み付き、彼らの持つ世界最高の宝石の数々で、地下世界を照らしていると言う。カンボジアのアンコールワット遺跡はナーガの都と呼ばれるようにナーガの彫像が多数あり、ナーガ信仰が多かった事が偲ばれる。 ■ナーガラージャ 蛇神ナーガの王達の事。2本の手と足を持つ蛇の姿や、人間の上半身を持つ半人半蛇の姿で現される。中には見事な翼を背に持つ者もあり、美しい。何れも並みのナーガより強力な力を持つ。ナーガラジャ達の中でも著名な者としては、ナーガ達の母神カーリヤ。その息子であり千の頭とあらゆる魔法の源泉である如意宝珠を持つシェーシャ。神々とアスラが戦っていた時代から大地を支えているというヴァースキ、賢者カーシャパの息子でクリシュナ神の加護を受けたカーリヤ等がいる。 ■ヴリトラ 「宇宙を覆う者」「宇宙を塞ぐ者」という意味の名の竜である。古代インドのヴェーダ時代から存在する悪竜。雷神インドラの宿敵であり、地上の七つの川を占領し太陽を暗黒に包んで地上を飢饉に陥れていた。ヴリトラの力は強力で、どんな神も太刀打ちできない。ひとたびはインドラはヴリトラに飲み込まれてしまう、この時インドラは諸天の助けでヴリトラが欠伸した所で逃げ出したと言う。そこでヴィシュヌ神の仲介によって、平和条約が結ばれた。このときヴリトラは「木、石、鉄、乾いた物、湿った物の何れによっても傷つかず、インドラは昼も夜も自分を攻める事ができない」という条件を勝ち取った。しかし、インドラは、昼でも夜でもない夕暮れ時に、木・石・鉄でなく乾いても湿ってもいない海の泡の柱を用いてヴリトラを倒したのだった。ヴリトラが倒されると、宇宙を不才でいた穴が開いて、大雨が地に降り注いだという。 ■アナンタ ヒンドゥー神話の永遠不死の世界蛇。「無限」を意味する。ヴィシュヌは、ブラフマーの夜と呼ばれる宇宙の静寂期間はこの大いなる蛇のとぐろの中で眠るという。其の姿はナーガの大王たるキングコブラである。ヴィシュヌ神が横になって夢想している時、其の頭をもたげてさしかけ天蓋とする其の夢想が世界を作るのだという。人間の姿をとる事もあり、ヴィシュヌの化身といわれるクリシュナの異父母バララーマとなった。しかしある日、物思いにふけっていたところ、口から蛇が這い出てしまい、以後、バララーマは魂の抜け殻になってしまったという。 ■ヴァースキ インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。特に古い時代に崇拝された。「乳海撹拌」と呼ばれる物語で活躍している。それによると、神々の支配権がまだ確立していない頃、神々とアスラが不死の飲料アムリタを手に入れようとした事があった。このとき神々は巨大なマンダラ山を引き抜き、それを海中の巨大亀の背に立て、その山の上にヴァースキを巻きつけると、其の両端を神々とアスラが引っ張って大海を掻き混ぜ、アムリタを作ったといわれる。 ■カーリヤ インド神話に登場する蛇神ナーガの一人。蛇の姿をしており、全てのナーガの祖先とされる。もともとヤムナー川に棲んでいたが、其の毒のため川は沸騰し樹木は枯れ、鳥達も死んだとされる。是を見たクリシュナ神がカーリヤの鎌首を踏みつけ、ラマナカ島に移住させた。この戦いの名残としてカーリヤ一族の鎌首にはクリシュナの足跡が残ったが、神の足跡のおかげで、其の一族には誰も危害を加える事ができなくなったという。 ■カルコータカ インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人。全てのナーガの祖先とされるカーリヤの兄弟に当たる有力な王で、人間に取り付いた悪魔を追い払ったり、人間を小人にする力があった。『マハーバーラタ』の中で知られる『ナラ王物語』では、悪魔カリに取り付かれていたナラ王が、毒のあるカルコータカに森の中で噛み付かれたが、その毒は悪魔にだけ作用し王自身は無事だったとされている。また、ナラ王はカルコータカの魔法で小人にされてしまったという。 ■シェーシャ インド神話に登場する蛇神ナーガの王の一人で千の頭を持つ巨大な蛇の姿をしている。ヒンドゥー教の宇宙観では世界には七層の地下界があるとされるが、シェーシャがいるのは更にその下で千の頭で全ての大地を支えていると言われる。千の頭の一つ一つには卍の印がついているうえ、イヤリング、王冠、花冠もついている。カルパと呼ばれる一時代の終わりには炎を吐いて宇宙を焼き尽くすといわれている。同じナーガのアナンタと同一視される事もあるという。 ■タクシャカ インドの蛇神ナーガの王の一人。この世に最初に生まれたナーガ達の一人である。他のナーガと同じ蛇の姿をしているが、有る聖者の為に復讐したと言う物語が残っている。あるとき、無言の行を行っていた聖者をクル族の王パリークシットが侮辱するという事があった。是を知った聖者の息子は王に復習してくれるようにタクシャカに願った。タクシャカはその願いを聞き、小さな虫に化けて王に近づくと、突然大蛇に変身して王を噛み殺したという。 ■ムチャリンダ インド神話に登場する、半身の蛇族であるナーガの王の一人。仏教説話の中で、仏陀に帰依したとされている。ある時仏陀は有る菩提樹の下で瞑想にふけっていたが、その菩提樹にムチャリンダが棲んでいたとされている。彼は仏陀の偉大さに気づき、黙って見守り続けた。やがて大きな嵐が起こると、自分の蛇の体を七回仏陀に巻きつけて、七日間にわたって雨から護り、その後で人間の若者の姿になって仏陀に帰依したのである。 |
|
|
■ムシュマッヘー
古代バビロニアの創世神話『エマヌ・エリシュ』に登場する蛇。日本語では「七頭の怪物」と呼ばれるが、その名の通り七つの頭があったという。原初母神であるティアマトが主神マルドゥクと戦うために生み出した。11匹の怪物の中の一つで、歯は鋭く、徹底的に残酷で、その体は血の変わりに毒液によって満たされていたという。実際の戦いの中では殆ど活躍せず、ティアマトが敗れるとマルドゥクによって捕らえられてしまった。 ■ファラク イスラム教に関連した神話に登場する巨大な蛇。大地を支えるバハムートの巨体の下に横たわるこの宇宙蛇の体内には地獄の火と永遠が置かれているという。 ■アンゴント 米国千住民ヒューロン族の信仰と伝承における巨大な蛇。敵意に満ち、極めて有害な毒を持つ爬虫類で、湖、川、洞窟、森、冷たいじめじめした奥地の、人気の無い荒涼とした場所に澄むと言われる。棲家から非常に長いとぐろを伸ばし、人間の居住者に災害と病気をもたらす。祈祷師は効果的な魔法薬を作るため、この巨大な爬虫類を探しにいく。しかし、アンゴントの皮膚は僅かな欠片でも致命的な毒があるので、その様な恐ろしい物を運んでくる人間に期待しても無駄だった。 ■イアキュルス ヨーロッパの文学伝承に登場する怪物。ローマの詩人マルクス・アンナエウスの作品『ファルサリア』で言及され、後年、動物寓話集を始めとする、中世の文献にも書かれた。この怪物は翼の生えた巨大な蛇で、2本の前足を持つとされる事もある。高い木に登り枝の中に身を潜めると言うその奇襲の仕方が特に恐ろしいとみなされている。イアキュルスは格好の獲物が木に近づくとその背中に飛び降り、首に噛み付いて息の根を止めてしまう。「槍」を意味するイアキュルスと言う名が付けられたのはその為である。 ■イサの飛ぶ蛇 中世ヨーロッパのキリスト教伝説に登場する蛇。中世の旅行者の報告によれば、この最も邪悪な蛇はエチオピアの砂漠のコカトリスの卵から孵ったとされる。この蛇はコカトリスより危険で、空を飛んで攻撃する事ができた。 ■ウグラスラ インドのヒンドゥー教神話に登場する悪霊のような蛇。クリシュナが幼かった頃、ウグラスラは神の成長を止めようとして彼を丸呑みにした。しかし、クリシュナは突然成長を早め、完全に大人になったので、蛇の身体は彼を入れておけなくなり、弾けてしまったと言う。それでクリシュナは自由になった。 ■ウラエウス 古代エジプト神話に登場する蛇。ラー神の太陽の円盤の周りを巻き付いている毒を吐く巨大な蛇。ラー神が小箱に自分の髪の毛数本と杖と一緒にウラエウスを入れておいた所、ゲブとその従者がその小箱を開けた。その結果、ウラエウスの毒を強く吹きかけられて仲間は皆死に神の父ゲブは重体になった。また別の伝説によると、ウラエウスは女神ハトホルの警護役であるという。 ■ヴルパングエ チリのアンデス地方に住む人々に伝わる伝説と信仰に登場する奇怪な蛇。ヴルパングエは様々に描かれ、狐に似た頭を持つ巨大な蛇だったり。大きな円形の、平らまたは膨らんだ身体で端に沿って目が付いている。人間を餌食にする非常に危険な生き物なので、ヴルパングエが居る恐れの有る水域で洗濯したり水浴びする者は居ないと言う。 ■エデンの蛇 旧約聖書の創世記とヘブライ語の文献はエデンの蛇が、最初の人間アダムとイブを誘惑したと述べている。この蛇は、各時代の美術上の習慣によって、様々な姿で描かれている。大抵は大変大きくて、知恵の樹をぐるりと取り囲んでいるが、時として違った姿に描かれる時も有る。古い時代の絵では、人間の顔をしていたとも有る。又、鶏冠や孔雀の羽毛と羽が付いている姿もあった。イギリスの初期の美術作品では北欧神話のリンドオルムの様に馬の要素をもたせている例が多い。 ■エピロテス ギリシャ・ローマ神話に登場する巨大で超自然的な蛇。太陽神アポロンが多数の珍しいドラゴンを飼っていた堀で、生まれた庭の巨大な守護霊。このデルポイのピュトンのドラゴンの子孫達は周辺の住民の未来を予言する道具だった。毎年、裸の乙女がこのドラゴンの生贄に捧げられる事になってたが、人々がこの献上を拒めばその年は不幸続きとなり、ドラゴンの一頭がこの生贄にありつければその年は幸運続きとなった。 |
|
|
■エル・クエレブレ
スペインの伝承に登場する蛇。巨大で有翼の飛翔する蛇で、森の洞窟や滝に棲むと言われる。エル・クエレブレは巨富の護り主とも言われるが、この生物を見つけた者は誰も戻らず、したがって誰にも伝える事はない ■オン・ニオント 米国北東部の先住民ヒューロン族の伝承と信仰に登場するホーンド・サーペント。額に生えた大きな角で山や谷間を削り、深い裂け目を作ったとされる。この蛇の角は護符として大いに尊重されたと言う。 ■キチクネビク 米国で先住民の伝承や信仰に登場する巨大な蛇。マニトゥ・キネビクとしても知られるこの「偉大なる蛇」は1675年頃に神父ルイ・ニコラが伝えている。余りに強大なため、一口でバッファローを飲み込めるほどだった。蛇の姿をしているが、背中に沿って角或いは背骨が突き出している。その大きさにも拘らず、地上でも水の中と同じくらい俊敏に動く事が出来た。 ■キチ・アトハシス 米国の先住民ミクマク族の伝承と信仰に登場する、水棲の巨大な蛇。伝承によれば、二人のシャーマンがそれぞれ自分の蛇の守護霊に姿を変えて能力の違いを明らかにしようとした。一人はウィーウィルメックに変身し、もう一人はキチ・アトハシスに変身した。二人はメイン州にワシントン郡あるボイデン湖で戦った。彼らがのた打ち回ることで湖水に大きな振動が生じ、それ以来湖には常に波が立つようになったという。 ■キツィナッカス 米国の先住民レナペス族及びアルゴンキン族の伝承や信仰に登場する巨大な蛇。ワッセナールが1631年に『ニューホーランド旅行記』に記した所によると、シャーマンが神聖な儀式のために、の巨大な蛇の真似をし、その存在を信じさせた。 ■キャムーディ 南アメリカのギアナの人々の伝説と信仰における巨大な蛇。ある狩猟団が1896年に作成した報告書に、彼らが暗い密林で巨大な倒木の上で休んでいた時の事が書かれている。その内、一人が「木」が動き出したと言い出した。全員が地面に飛び降りると「木」は身体を起こし、滑る様に藪に入っていった。一行はこの生物こそキャムーディで知られる巨大な守り主であると主張した。 |
|
 ■ヨーロッパにおける竜(ドラゴン)の系譜 |
|
|
ヨーロッパにおける竜(ドラゴン)を、まずキリスト教と神話の2つに分け、キリスト教については大天使ミカエルと聖ゲオルギウスに、神話については、ジークフリートとヘラクレスに区分した。
■大天使ミカエル 大天使ミカエルについては、新約聖書の最後に掲載されている『ヨハネの黙示録』の内容が基本となる。黙示録に書かれている大天使ミカエルとドラゴンとの戦いを、《写本》の挿絵、聖画像(イコン)、宗教画や彫刻に取り上げられ、多くの例を見ることができる。 <ヨハネ黙示録12章1-6節 太陽の女と七つの頭の竜> 女は太陽を身につけ、月の上に載り、12の星の冠を戴いていた。この女性はすぐに出産しようと苦痛で叫んでいた。7つの頭と10の角を持ち、頭には7つの冠を載せている大きな赤いドラゴンが女の前に歩み寄る。ドラゴンの尻尾はきわめて長かった。このドラゴンは、女性が産んだ子供を食べてしまおうと待ち構えていた。生れた子供は男子で、将来人々を治める運命を持っており、この子供は天の神の御座に引き上げられる。女は荒野に逃げて、神の庇護を受けたという。 <ヨハネ黙示録12章7-9節 聖ミカエルとドラゴン> さて天で戦いが起きた。ミカエルとその御使の天使たちが、ドラゴンと戦った。ドラゴンと仲間の天使たちは応戦したが破れ、天に彼らの居場所はなくなった。そこで、この巨大なドラゴン(悪魔ともサタンともよばれる)は追放され、地に投げ落とされ、彼に従っていた天使たちもともに投げ落とされた。 ■聖ゲオルギウス カッパドキアのセルビオス王の首府ラシア付近に、毒気を振りまく巨大なドラゴンがいた。人々は毎日2匹ずつの羊を生け贄にすることで、災厄から逃れた。 まもなく羊を全て捧げてしまい人を生け贄として差し出すこととなり、王の娘がくじに当たってしまった。王は城中の宝石を差し出すことで逃れようとしたが、許されず8日間の猶予を得る。 そこに通りかかったゲオルギオスはドラゴンの話を聞き、ドラゴン退治に乗り出す。ゲオルギオスは生贄の行列の先頭にたちドラゴンに対峙、毒の息を吐いてゲオルギオスを殺そうとした開いたドラゴンの口に槍を刺して倒す。ゲオルギオスは姫の帯を借り、ドラゴンの首に付けて村まで連れてきた。 ゲオルギオスは「キリスト教徒になると約束しなさい。そうしたら、このドラゴンを殺してあげましょう」と言って、異教の村はキリスト教の教えを受け入れた。 後に、ゲオルギオスはキリスト教を嫌う異教徒の王に捕らえられ拷問を受け、斬首され殉教者となった、という後日談がある。 聖ゲオルギウスの物語にもいくつかのお話があるが、いずれも、ドラゴンに襲われる町、生贄にされる王女、ドラゴン退治、異教徒の改宗、などがモチーフとなっている。 スペインのカタルーニャ地方の《サンジョルディ伝説》では、白い馬にまたがり槍を持った騎士、赤いバラ(ドラゴンが流した血)がモチーフとして加わる。毎年4月23日は《サン・ジョルディの日 St.jordie’s day》とされ、愛する人に美と教養、愛と知性のシンボルとして、1本の薔薇と1冊の本を贈ってこの日を祝っている ■ゲルマン神話ジークフリート 北欧系の古い伝説には、邪悪なドラゴンが登場し、英雄ジークフリートに退治されるというお話がたくさんある。この毒のあるドラゴンは、ファーブニル(fevnir)、ファフニール(fefnir)と呼ばれるもので、大地を震わせて歩く怪物。 心臓に魔力があり、これを食べたジークフリートは鳥の声が理解できるようになり、アルベリッヒの罠にかからずにすんだ。また、ドラゴンを退治したときに浴びた返り血により、ジークフリートは刃を受けても傷つかない体になった。 ワーグナーが作曲した楽劇《ニーベルングの指環》の第二夜でジークフリートが登場する。ワーグナーは当初、北欧神話の英雄であるシグルス(右の写真参照)の物語をモチーフとした『ジークフリートの死』として着想したが、次第に構想がふくらみ現在の形となった。 ■ギリシャ神話ヘラクレス ヘラクレスはギリシャの神々の最高神ゼウスを父に、ペルセウスの孫アルクメーネ王女(人間の女)を母として生まれた半神半人。嫉妬深いゼウスの正妻ヘラは、二匹の毒蛇を送り赤ん坊のヘラクレスを殺そうとするが、これをヘラクレスがつかみ殺し、長じてギリシャ一の英雄と崇められた人物。 ヘラクレスはアルゴスの暴君エウリュステウスに12の難題(12の功業)を命じられる。いずれも困難な無理難題だったが、超人的な力と神々の助けでこれらをやり遂げる。 この功業が完了した後、ヘラクレスはケンタウルスのネッソスと争い、巫女であったデイアネイラを妻として勝ち得るが、後に妻子を殺すという悪行もしている。 ネッソスの企みによってその血に浸され、毒となった衣をまとったために命を落とす。自ら火中に身を投じ焼死し、天に昇って星座に位置を占めた。 ■エピローグ 大天使ミカエルの物語に対して当初は、天使と悪魔という概念でとらえていた。以下のような解釈があるので紹介しておきたい。 天にいる一部の天使が反乱を起こす。神はこういう堕落した天使をドラゴンの姿にし天国から突き落とす。ドラゴンはもともと竜の形ではなく、天にいた天使がサタン(悪魔)としてドラゴンになり地上に落とされた。 龍を語るときに、龍、竜、ドラゴンという言葉が登場するが、私は、《善い龍》と《悪い竜(ドラゴン)》の2つに使い分けている。文献の中にも同じ考えのものもあるが、あえて定義していないものも多く、定説かどうかはわからない。 |
|
|
■龍の起源
龍の起源を探るに際して、まず、ズバリ題名の荒川 紘氏の『龍の起源』を参考にし、他の書籍も見てみると、龍の起源についてはたくさんの説があり、一筋縄では語ることができないこともわかってきた。現時点での、《龍の起源》に対する私の視点は、 ●古い時代の人々の生活を通して《龍を象徴や概念として意味づける》こと / 後に政治的、宗教的な要素も加わって龍の概念が創られる ●《龍のかたちを形態学的に見る》こと が必要ではないかということである。このことは、この数年続けてきた視点としての《龍の謂れとかたち》にも通じるものである。龍の起源を知るためには、遺跡や神話の中に登場する事実をもとにした検証も必要だと思う。深入りすると、とめどもない世界に踏み込むことになるが、先人たちの文献などを学び、教えを乞い、私が理解できたことや感じたことを紹介したい。 ■龍はいつ創造されたか 龍の起源に対し様々な見方があり、龍の出現した時期に対しても正確な答(定説)をさがすことは難しい。現在見つかっている最古の龍と思われるものは、地面に石を置いて形作られた、揚家窪(ようかわ)遺跡の約8000年前の2匹の龍(1.4m、0.8mの長さ)という説がある。また、歴博のフォーラムでは、中国の河南省濮陽縣西水披遺跡で紀元前4000年ころの墓に貝を敷き詰めて龍と虎らしき動物を表現している写真が投影された。この写真は明らかに、龍と虎の姿を見て取れるものである。龍は世界各地に分布しているが、その形態や性格には、西アジアを分岐点として、東西2つの系列が存在している。 ●インド、中国大陸、日本、南方諸島 ●ヨーロッパ大陸、アフリカ大陸、ヨーロッパに関連する地域 2つの系列が存在しているとしても、《龍》という概念を大きくひとつにくくることができるのか。その根底には洋の東西を問わない共通したものがあるのではないか。人類が狩猟から農耕や牧畜を生活基盤とした頃に、《龍》という概念が生まれたという説が根強い。農耕には水が必要であり、これは古代人にとって自由にならないものである。自然の脅威と災害を免れようという人間の願いから、水に対して神通力を持つ霊獣として《龍》を生み出した。自然現象を起こす偉大な力を何らかの形態にして表現しようとした時に、大蛇や鰐などのかたちから龍を創造した。これは、龍を象徴として意味づけることからみた龍の起源の説として納得出来るところがある。 ■インドにおけるナーガ インドでは、コブラをモデルとした蛇の神である多頭のナーガが守護神として崇められていた。仏法に取り込まれて仏法を護持するナーガラジャ(龍王)となった。仏教では、龍族の王を天竜八部衆(八大龍王)として仏法を護持する役割を与えた。仏教では、法行龍王という善龍がいる反面、非法行龍王という禍をもたらす悪龍もいた。仏典が中国に伝わった際、ナーガラジャが「龍」や「龍王」などと訳され、仏教伝来以後の中国の龍の成り立ちにも蛇神ナーガのイメージがおおきな影響を与えた。 ■中国 中国人は黄河を《母なる存在》にたとえる反面、一匹の《暴れ巨龍》にもたとえた。黄河などの大河を抱える中国にとっての河川の氾濫、山崩れ、地震、雷、台風、日食などが龍の仕業と考えられていた。インドでは蛇神であるナーガは中国では《龍》、《龍王》と訳され、龍王は悪の力と敵対して人に利益をもたらすものとして、神聖な守護の力を象徴するものとなった。中国では二つの角と五つの爪を持つ龍は皇帝を象徴するものとして神聖視されており、その姿は、宮殿、玉座、衣服、器物などに描かれた。そして単なる畏怖の対象としてだけでなく、瑞兆としても扱われるようになった。 ■日本 日本では雨を降らせ大地を潤すシンボルとして、蛇の信仰が広く浸透していた。インドのナーガが中国では《龍》、《龍王》と訳され、それが様々な文化とともに日本に入り、日本の蛇神への信仰と融合して日本の龍の概念とかたちができた。そして、龍神は雲や雨水をつかさどる水神として農民に信仰されるようになった。日本神話においても蛇退治の話が存在する。素佐之男命(すさのおのみこと)と八岐大蛇(やまたのおろち)との一戦に登場する蛇も龍の一種とされる。 ■ヨーロッパ 西洋の神話や伝承では、ドラゴンは悪に立ち向かう聖人や英雄の敵として登場する。神の秩序や創造の力に対する混沌を象徴する悪魔としてドラゴンは位置づけられた。聖人や英雄はドラゴンと戦って混沌の源を排除する。西洋のドラゴンは、巨大な蜥蜴・鰐・鷲・獅子などで構成され、その形態においても東洋の龍とは異なっている。 ■エピローグ 龍の起源について、以上のように整理するのは単純すぎるとは承知の上であるが、現時点での私の理解であり、今後龍に接するときの道しるべとしたい。 東洋では龍は神獣として位置づけられ、ヨーロッパのドラゴンは邪悪なものとされているのはなぜであろうか。 西洋と中国の古代人の自然に対する考えの違いが原因であろう。 西洋において、混沌の源としてのドラゴンを退治するということは、人間が自然を支配できると考えたことの表われである。 中国においても河の氾濫をひきおこす龍は恐れられてはいたが、その恐怖は畏敬の対象として崇められた。古代中国人は、人間の力をはるかに超越した自然を征服しようとはせず、自然とともに共生しようとした。そして、中国における龍は皇帝のシンボルとしてあがめられるようにもなった。 なお、ヨーロッパのドラゴンは邪悪なものの象徴だけではなく、龍のパワーを崇拝している例もあることは別の機会に語ることにしよう。 |
|
|
■天使ミカエルとドラゴンの戦い(ヨハネの黙示録)
聖書の最後の文書『ヨハネの黙示録』の中で、天使ミカエルがドラゴンを退治するシーンは《写本》の挿絵、聖画像(イコン)、宗教画や彫刻に取り上げられ、多くの例を見ることがでる。前々回にはタピストリーに織られた例も示した。天使ミカエルとドラゴンとの戦いを中心に、『ヨハネの黙示録』の中で、ドラゴンが登場するいくつかのシーンを紹介する。 ■太陽の女と七つの頭の竜<12章1-6節> 女は太陽を身につけ、月の上に載り、12の星の冠を戴いていた。彼女は生みの苦しみでのたうち、大変な苦痛で叫んでいた。7つの頭と10の角を持ち、頭には7つの冠を載せている大きな赤いドラゴンが女の前に歩み寄る。このドラゴンは、女性が産んだ子供を食べてしまおうと待ち構えていた。生れた子供は男子で、将来人々を治める運命を持っており、この子供は天の神の御座に引き上げられる。女は神によって用意された荒野に逃げて、神の庇護を受けた。この英雄が誕生直後に直面する脅威は多くの神話において英雄が進む道である。(ヘラクレスの例など)。ドラゴンは神の敵対者であり、龍の赤い色は反乱や炎や血のしるしである。七頭はこのドラゴンがカオスを起こすドラゴンであることを示しており、十角はそれが巨大な力を持っていることのあかしである。 ■天使ミカエルとドラゴンの戦い<12章7-9節> さて天で戦いが起きた。天使ミカエルとその御使の天使たちが、ドラゴンに戦いを挑んだ。ドラゴンと仲間の天使たちは応戦したが破れ、もはや天に彼らの居場所はなくなった。そこで、この巨大なドラゴン(悪魔ともサタンともよばれ、全人類を惑わす者)は追放され、地に投げ落とされる。彼に従っていた天使たちもともに投げ落とされる。天には神だけでなく天使たちも居る。神は、天使のミカを選んで聖ミカエルと詠んだ。《エル》というのは神という意味である。神と対立する天使は堕落させられることによって、サタンのひとりとしてのドラゴンとして示される。サタンは、反キリスト、あるいは反神である。 ■女を追うドラゴン<12章13-17節> 地に投げ落とされたドラゴンは女を追う。しかし、女には鷲の翼がはえ、それが女を神によって用意された避難場所へと運ぶ。(中略)ドラゴンは女を征服できないことを知ると口から水を吐き出し、女を溺れさせようとした。地は口を開けその水を飲みこんだ。するとドラゴンは激怒して、女の残した子供たちと戦うために立ち去った。ドラゴンは世界を再び水のカオスに押し流そうとする。 ■海と地から上がってくる獣<第13章1-18節> 第13章は地上でのお話。少しわかりにくいが記してみる。ドラゴンは海の岸に近づく。すると一頭の獣が立ちあがってくる。この獣はそれぞれ神を冒涜するような名前の付いた七つの頭と冠で飾られた十の角をもっている。ドラゴンはこの獣に彼の力と王座と権威を委ねる。地上の人間たちはドラゴンを崇拝し、またこの獣を崇拝してこう言う「この獣に匹敵するようなものは誰がいよう。誰がそれと戦いを始められるような力を持っていよう」。この獣は神を冒涜し、聖なる者たちと戦い、これを打ち負かす。それから第二の獣が地中から姿を現す。第二の獣は、第一の獣から全権を委任され、権力を行使する。(中略) それを崇拝しないものは殺される。地上から出てきたこの獣は全員に命じて右手あるいは額の上に刻印を押させる。この刻印をつけているものだけが、物を買い、売ることができる。この獣が持っている七つの頭は《崇拝に値するもの》、《世界の救世主》、《神の息子》、《主で神》のように神を冒涜するような威厳称号が付いたローマ皇帝を象徴している。冠で飾られた十の角は支配者の権力と威厳の印。この海から出てきた獣は、明らかにキリストの反対像、アンチキリストとして描かれている。地中から出てきた第二の獣は悪魔ドラゴンの似姿であり《偽預言者》と記される。ドラゴンと2頭の獣は統一体(三位一体)をあらわした悪の象徴である。 ■最後の審判<19章11-21節> 天が開き軍勢を引連れた白馬に騎乗した騎士が現れると、獣は全世界の王たちとその軍勢を集めて騎士の軍団に戦いを挑む。獣とこの獣の前でしるしを行って、獣の刻印を受けた者、その像を拝む者とを惑わしたにせ預言者は捉えられ、生きながら硫黄の燃えている火の池に投げ込まれる。残りの者は騎士の口から出てきた鋭い剣で殺される。この騎士は最後の審判のために姿を現すキリストであると言われる。 ■ドラゴンと2頭の獣の最期<20章1-10節> この2頭の獣の裁きのあとで淵の鍵をもったひとりの天使が天から下りてきて、ドラゴンを捕まえて巨大な鎖につなぎ、千年間淵に鍵をかけて閉じ込める。千年が過ぎ、ドラゴンは暫くの間もう一度解き放たれる。ドラゴンは地の4つの端にいる諸民族を決戦のために招集し聖なる者の町を包囲する。その時、天から火が降ってきて、彼らを全滅させる。ドラゴンは火と硫黄の海の中に放り投げられた。海から上がってきた獣と陸から上がった偽予言者もともに、日夜苦しめられるのである。 ■エピローグ 《黙示》とは、打ち明け、啓示との意味であり、『黙示録』を現代史的な解釈で考察してみる。淵から生まれた獣に見たものは後に、ローマ皇帝、ナポレオン、ヒットラーという形姿をとって実現された。ユダヤ人とキリスト教徒の迫害、ヒトラー崇拝を拒否するものは殺され、党章をつけたものだけが出世できる等々。キリスト教徒にとって、淵から上がってきた獣の姿はどの時代においても現実的な意味を持っている。アンチキリストの象徴としてドラゴン(と2頭の獣)が位置づけられている。 |
|
|
■聖ゲオルギウスの竜(ドラゴン)退治
■聖ゲオルギウスの龍退治 聖人伝(『黄金伝説』) 聖ゲオルギウスの信仰の強さを伝えた伝説は、多くの場所でその地方の伝説などが付け加えられて広まった。馬に乗ったドラゴンを退治する聖ゲオルギウスの描写が見つかったのは10世紀以降になってからのこと。聖人伝(『黄金伝説』)は、ヤコブス・デ・ウォラギネによって13世紀に編まれた聖人伝の選集であり、聖ゲオルギウスの伝説においても、すべての伝承の流れのまとめと言ってもよい。聖ゲオルギウスについては、個別の物語として古い殉教者の報告の前におかれている。 <物語> リュピア(現在のリビア)の小さな町シレナの近くに毒気を振りまく巨大なドラゴンが棲みついていた。ドラゴンは、湖や近くの森で獲物を捕らえて食べることに飽きると、猛毒を吐きながら目についたもの、人であれ動物であれ腹が満たされるまで食べた。町の人々はドラゴンの怒りを和らげるために、毎日2匹ずつの羊を生け贄にすることで、災厄から逃れた。羊の数が少なくなると羊1頭と代わりに若者か娘を生贄に差し出した。生贄は籤によって決めていたが、王の娘がくじに当たってしまう。王は城中の財宝や国の半分を与えるから娘を生贄にしないでくれと頼むが、自分の子供を生贄にされた人々は許さない。8日間、王は娘の不幸を嘆いたが、人々の要求に負け娘を犠牲にすることに。王女は、ドラゴンの棲む湖のほとりに連れて行かれて、ドラゴンが現れるのを待つ。王女は悲嘆に暮れてすすり泣いているときに、聖ゲオルギオスが馬に乗ってやってきて、王女になぜ泣いているかを尋ねる。王女は訳を説明し、危険だからゲオルギオスに早く逃げるように勧める。ドラゴンが水から這い上がって王女に迫った時、ゲオルギオスは馬に飛び乗り襲ってくるドラゴンに向かって馬を進める。ゲオルギオスはドラゴンが開けた口の中に槍を突き刺して喉を貫き(槍を投げて心臓を突き刺すという表現もある)、ドラゴンは大地に崩れ落ちる。王女が聖ゲオルギオスに言われたとおりドラゴンの首に帯をつなぐと、ドラゴンは飼いならされた子犬のようにおとなしく王女のあとについてきた。王女がドラゴンを町に連れてくると、人々は悲鳴を上げて逃げ惑う。その時聖ゲオルギオスは、「恐れてはいけない。神様が、あなたたちをこのドラゴンから救うために私をあなたたちのもとへ遣わしたのです。ですから、キリスト教を信じ、全員洗礼を受けなさい。そうすれば、私はこのドラゴンを打ち殺してあげよう」という。王が洗礼を受け、国民のすべてが洗礼を受けた。ゲオルギオスは剣を抜きドラゴンを打ち殺した。この日、2万人が洗礼を受けた。王は聖母マリアと聖ゲオルギオスを讃えて美しい教会を建てさせた。祭壇の真下(祭壇の上との記述もある)から泉が湧き出て、この泉はそれを飲んだ人のすべて病人を癒した。 物語は一旦ここで終わるが、以下のように続く。聖ゲオルギオスは王から莫大な財産の申し出を受けるが、彼はそれを受取ろうとせず、それを貧しい人々に分け与えてもらった。その後で、彼は王に四つのことを守るように勧めた。教会を保護し、司祭を敬い、熱心にミサを聞き、貧しい人々のことを忘れないように、と。それから聖ゲオルギオスは王に接吻して馬で去って行った。聖ゲオルギオスに退治されるドラゴンは、大天使ミカエルが天から地上に投げ落としたドラゴンであり、戦いは天上から地上に舞台を移したとみることができよう。聖ゲオルギオスは大天使ミカエルの地上の姿であり、天上でドラゴンに苦しめられた《太陽の女》が地上での王女である。すなわち、この女性はシンボル化された聖母マリアということであり、聖ゲオルギオスはマリアを救うことでキリスト教を守ったことで評価をされることになる。聖ゲオルギオスはドラゴンを退治した後で、王より王女の夫として迎えたいと願う、という記述も見られるが、王女が聖母マリアとすれば、二人は結婚してめでたしめでたし、とはできないことがわかる。英雄と処女の神聖な結婚式の代わりをするのは《洗礼》というところまでは、私の考えが及ばないところである。 ■聖ゲオルギウスの龍退治 十字軍戦士の守護聖人 聖ゲオルギウスのもう一つの位置づけは、十字軍戦士の守護聖人。彼の赤い十字の紋はすべての十字軍の目印となる。1099年のエルサレムに侵攻のとき、指揮官の命令に従ってこの町を攻撃する勇気がない騎士たちの前に、赤い十字架の付いた白い鎧を着た聖ゲオルギウスが現れる。彼の合図により騎士たちは勇気を奮い起こして町を奪取し、イスラム教徒を打ち殺した。ここでは、聖ゲオルギウスは《キリスト教徒の将軍》であり、異教徒に対する戦いの象徴である。ここでは、イスラム教徒をドラゴンに見立てており、単なる善と悪の戦いではなく、政治的・世俗的な要素が入ってきている。ドラゴンは、敵対するもの、忌むべきものとして、キリスト教にとってはイスラム教であり、政治的な要素という見方をすれば、ヒトラーであり、スペインのカタルーニャ地方の《サン・ジョルディ伝説》では、退治されるドラゴンはフランコである等、いくつもの例を挙げることができる。 |
|
|
■ゲルマン神話より《ジークフリートの竜(ドラゴン)退治》
■北欧神話における《シグルス》とワーグナーの《ジークフリート》 《ジークフリート》は《シグルス》のドイツ名である。ワーグナーは神話や伝説など素材に、1848年から1874年にかけて《序夜と三夜のための舞台祝典劇》と題する楽劇《ニーベルングの指環》を完成した。《指環》は、上演するのに約15時間を要する長大な作品である。神話の内容も膨大でストーリーも複雑である。今回紹介する物語は、『ドラゴン神話図鑑』(ジョナサン・エヴァンス著)を参考にした。シグルスと竜(ドラゴン)の物語は、著者のジョナサン・エヴァンスが、ヴォルスンガ・サガによる散文の物語を下じきにし、13世紀ごろにまとめられた古アイスランド語の詩歌集『古エッダ』も参考に書いたものである。ここに紹介する物語は、ワーグナーの《指環》では、第二日《ジークフリート》の第一幕《森の中の洞窟》と第二幕《森の奥》の部分に相当する、全体のなかのごく一部である。 ■シグルスと竜(ドラゴン)の物語 シグルスは、フーナランドの最も有力な王であるヴォルスングの息子のシグムンドとエリュミ王の王女ヒョルディーヌとの間に誕生する。シグルスはヒャ-ルプレイクの王宮で養育され、フレイズマルの息子のレギンという加治屋が養父となる。シグルスの養父であるレギンにはファーヴニルとオトルという二人の兄がいる。殺された二男のオトルの代償に一家は財宝と《黄金の腕輪》を手に入れる。長男のファーヴニルは、この財宝欲しさに父のフレイズマルを殺害し、グニタヘイズにその財宝を積み上げて、黄金の寝床を作る。ファーニヴニルは恐ろしく邪悪になり、獰猛なドラゴンに姿を変え、自分以外の誰をもその黄金に近づくのを許さなかった。財産の相続権を失った養父のレギンは、ドラゴンを殺して宝をうばえ、とシグルスにけしかける。シグルスは信頼に足る剣が必要だと訴えたのに応じて、レギンは剣を鍛えるが満足なものができない。シグルスは母親ヒョルディーヌのところへ行き、父の折れた名剣《グラム》を受け取ると鍛冶場に持ち帰る。レギンが白熱するまで熱し、火花を飛び散らせてふた打ちで剣を溶接し、これまでより力を込めて鍛え、名剣グラムがよみがえる。シグルスはグラムを携えて数々の戦いにおもむき、剣の価値を証明し、莫大な財宝を手に入れて帰った。レギンは「今度はファーヴニル(ドラゴンに姿を変えているレギンの兄)の首を落として俺との約束を果たせ」と耳打ちする。シグルスは、ドラゴン(ファーヴニル)が棲むグニタヘイズへの道とドラゴンの通り道を教わり、ドラゴンの通り道に潜むための溝を掘る。長いひげを生やし、つば広の帽子をかぶった老人から、ドラゴンの血を流すためのもう一本の溝を掘るように勧められ、シグルスは教えられたとおりにする。非常に大きく、獰猛で、あたり一面に蒸気と毒を吐き出しながらドラゴンが道を這い下りてくる。ドラゴンの腹が溝を横切って日差しが遮られた時、シグルスは真っ暗闇の中で剣(グラム)を突き上げ、素早く深々と突き刺して、柄を、手を、上腕を、そして肩口までを傷口に潜り込ませる。そうして剣を引き抜くと、シグルスは肩から剣の先までドラゴンの血にまみれていた。ドラゴンは痛みにのたうち、苦しみながら頭と尾を激しく打ち振っていたが、やがてその動きも弱々しくなり、横たわってほとんど動かくなった。レギンが現れ、ドラゴンの血を飲むと、シグルスにドラゴンの心臓を焼いて食わせろと命じる。シグルスは巨大な心臓を串刺しにして火に炙り、中まで焼けたかどうか確認するため心臓から泡立つ血を味見してみる。ところが、指を口に入れた途端、近くの木に止まっていた小鳥たちが、レギンがシグルスを殺して財宝を奪うために来たことを囀っているのを聞き分ける。シグルスはグラムを抜き、レギンの首を刎ねる。それから、ドラゴンの肉を食べ、ドラゴンのねぐらに行き、愛馬の鞍に黄金を詰め、新たな冒険へ旅立つ。 ■物語の展開 この後シグルスは、燃え盛る炎の中で眠るブリュンヒルデの目をさまさせ《神聖な結婚》をする。しかし、魔法にかけられて、ブリュンヒルデのことを忘れ、クズルーンと結婚する。そして、財宝目当ての彼女の兄弟たちに殺される《死》の段階へ物語は展開してゆく。 ■エピローグ 地下鉄のリヒャルト・ワーグナー広場駅には、2008年にも訪れてレリーフを見た。当初は推測だったレリーフの絵柄がジークフリートであると確認したのは、武器が短剣またはナイフであること、ドラゴンの左肩の真下に剣を刺すという約束事に則っていることが裏付けとなった。 DRACHEN BLUT(竜の血)という名の赤ワインを頂いた。ジークフリートが竜と闘った伝説の町ケーニヒスヴィンターのピーパー(Pieper)醸造所で作られたもの。 添えられた説明書には、ライン川沿いにあるこの町の後方には山がそびえ、その上には2つのお城があり、山の急斜面にワイン用のブドウ畑が造られていること、ジークフリートはこの町の山に住んでいた竜を退治しその返り血を浴びて、不死身の身体を手に入れた(ワーグナーの《指輪》でのジークフリート)という説明が書かれている。 赤ワイン《竜の血》はまだ味わっていない。これを飲むと、声なき声が聞こえ、不死身の体になると暗示されているのだが。 |
|
|
■ギリシャ神話より《ヘラクレスのドラゴン退治》
■ヘラクレスの誕生と逸話 ヘラクレスはギリシャの最高神ゼウスと人間の女アルクメネのあいだに生まれた半神半人。ゼウスの正妻であるヘラは夫ゼウスの浮気に嫉妬し、人間の女から生まれた子供に敵意を抱くことから、物語は展開する。ジョナサン・エヴァンス著『ドラゴン神話図鑑』を下敷にお話を要約して示す。 ミケーネ王の娘アルクメネはミケーネの王位を継いだ従兄弟のアンフィトリュオンと結婚する。アンフィトリュオンは暴れる雄牛を鎮めるために投げた棍棒が義父にあたり、義父を死なせてしまい、アルクメネとともにクレオン王のもとに亡命する。美しいアルクメネは、夫アンフィトリュオンの留守中に、アンフィトリュオンに化けたゼウスと臥所を共にする。その晩遅く城に帰りついた夫とともに床に就く。そして、アルクメネは双子の男の子を出産する。イフィクレスは夫の種による子で、普通の子だった。ゼウスの子は祖父の名をとってアルケイデス(のちのヘラクレス)と名付けられる。ゼウスは全ギリシャを支配する王をアルケイデスにする予定だったが、ヘラの奸策により、エウリュステウスが王になる。そのために、ヘラクレスは苦難の道を行くことになる。 ■ヘラクレスの幼いころの逸話 ゼウスの妻のヘラは、夫ゼウスの浮気に嫉妬し、2匹の毒蛇を二人のゆりかごに送り込む。ところが、赤ん坊のアルケイデスが蛇たちを捕まえて絞め殺し、ヘラのたくらみは失敗に終わる。これは、アルケイデスが将来大きなことを成し遂げるという前触れだった。 ■成人になるヘラクレス アルケイデスは、音楽、体術、剣術、様々な運動競技を学び、18歳のころには、180cmもある美男子に成人する。ある日、運動競技の腕前の褒美として、テスピオス王の宴会に招かれ、その地に滞在。王の50人の娘が彼の子を産んだ。アルケイデスは、テーベへ戻る途中に、テーベの敵を倒し、クレオンに気に入られ、娘のメガラを妻とし、子にも恵まれ、幸せに暮らす。しかし、アルケイデスはヘラ(父ゼウスの妻)のたくらみにより、発作的な狂気に襲われ、妻と子供たちにあらぬ疑いを抱き皆殺しにしてしまう。テーベを後にて行ったデルポイで、女の信託者によって《ヘラの栄光》と言いう意味の《ヘラクレス》という名に改名させられる。 さらに、12年間エウリュステウス(ヘラのたくらみによりヘラクレスの代わりにギリシャの王になった)に忠実に仕えることができたら、不死を得るであろうと告げられる。ヘラの姦策によってエウリュステウスに仕えることになり、ヘラクレスはエウリュステウスからいずれも実現不可能と思われる12の難業をこなすように命じられる。 ■ヘラクレスの12の難業 ヘラクレス立ち向かう12の難業の中で、神話的な怪物のうち3匹のドラゴンまたはドラゴンみたいな動物が登場する。 ヒュドラ(第2話) / レルナの沼地に棲むテュポンとエキドナの子であるヒュドラは、周辺の土地を荒らし、人や家畜を殺していた、ヒュドラには9つの頭があり、不死以外の頭が切り落とされると、そこから2つの頭がはえてくる。ヘラクレスが対峙した時には、ヒュドラの頭は百かそれ以上になっていた。ヘラクレスが頭を切り落とすたびに、イオラオス(ヘラクレスの甥)が切り口を焼き焦がして、新しい頭が生えてこないようにした。最後に不死の頭を切り落とすと、ヒュドラはみずから流した猛毒の血たまりのなかで死ぬ。ヘラクレスは自分の矢の矢じりを血に浸し、武器とした。 ゲリオンの牛(第10話) / 世界の西の果てのエリュテイア島がありその島では、牛の群れがいた。牛の群れは巨大なドラゴン《ゲリオン》がその番をしていた。ヘラクレスは、その島を見つけ、牛の群れを生け捕りにし、王のもとに連れ帰ることを命じられる。ヘラクレスは長い旅をしてその島にたどり着き、エウリュティオンと番犬オルトロスを殺す。それから、人間の頭を持ち、鱗に覆われ、先のとがった尾をとぐろに巻いているゲリオンと戦い、毒矢の半分を使いゲリオンを倒した。牛を連れての帰郷の旅は長くつらいものだったが、テーベに帰り着き、エリュテイア島の牛をエウリュステウス王に献上した。 ヘスペリスの黄金のりんご(第11話) / ヘラクレスはエウリュステウス王から、西の果てにある楽園ヘスペリデスの中央にある巨木の黄金のりんごをもいで、エウリュステウス王のもとへ持ち帰ることを命じられる。黄金のリンゴを食べると不死を得るとされていた。海神ネレウスに楽園への道をひそかに教えてもらい、リンゴの樹へ続く道を見張っている百の頭を持つドラゴン《ラドン》を見つける。ヘラクレスはラドンを魔法で眠らせてから殺し、リンゴを手に入れた。 |
|
|
■ヨーロッパの善い龍
■ヴォーティガーンの城 ブリトン人の王国がサクソン人による侵略で荒廃してくると、ヴォーティガーン王はスノードン山の上に城を築こうとした。ところが、石工たちが基礎を積み上げて、その日の仕事を終えるたびに、地中深くにいる何者かが大地を震わせて基礎を壊し、工事を振り出しにもどしてしまう。王の相談を受けた魔法使いたちは、父親無しで生まれた少年を殺して、血を城の基礎に撒けば、いかなる城攻めにも耐え得る丈夫な基礎になるという。 ■マーリンという名の少年 王国中に使いが出され、マーリンという少年が探し出され、母親と共に王宮に呼び出される。母親が語るところによると、彼女は高貴な生まれの未婚の乙女だったが、あるとき美しい若者が部屋に現れて、彼女と語らい、口づけをすると消えてしまった。その後、若者は何年も経ってから再び姿を現し、一度だけ臥所を共にして消えてしまうが、その時彼女のお腹には若者の子が残された。身の上を語り終えた母親と少年は、魔法使いたちが、少年の血を城の基礎に撒き、城を強固にしなければならないと告げたことを知らされる。 ■赤いドラゴンと白いドラゴンの戦い これを聞いたマーリンは、偽りを暴くために魔法使いたちを集めてもらうよう、王に嘆願する。マーリンは魔法使いたちに、城の基礎の下に何があるかと尋ねる。魔法使いたちは知らないと言い放つ。マーリンに命じられて石工たちが掘ると池が出てきた。それから、マーリンは池の下に何があるかと魔法使いたちに尋ねた。彼らが知らないと言い放つと、マーリンは池の水を取り除くように命じ、こう述べる。 「ああ、王よ、池の水が取り除かれれば、その下に二つの洞窟があることがわかりましょう。その洞窟の中にこそ、問題の根源が眠っているのです」 王は、干上がった池のふちに行き見ていると、赤いドラゴンと白いドラゴンが洞窟から出てきた。二匹は互いに口から火を噴いて相手に近づき、つかみ合って争ったが、白いドラゴンの方が赤いドラゴンを凌駕し、干上がった池のふちに相手を追い詰めた。だが、赤いドラゴンはそこで再び力を集め、白いドラゴンを打ち負かした。 王はマーリンに、これは何の前触れかを尋ねる。 ■マーリンの予言 赤いドラゴンはブリトン人を、白いドラゴンはサクソン人をあらわしている。悲しいかな、赤いドラゴンは白いドラゴンに敗れ、白いドラゴンは赤いドラゴンの洞窟を占領するでしょう。ブリトン人を根絶やしにせんとして、あらゆる山や谷はひとつの平原にされ、川には血があふれます。しかし、長き時を経て白いドラゴンは力を取り戻し、勝利するでしょう。ブリトン人の庭には、異国の種が蒔かれ、赤いドラゴンは池の対岸で苦しみながら待つのです。三百年を経てついに我ら人の復習が白いドラゴンを襲い、あ奴らの種は我らの庭からを根こそぎにされ、その生き残りもことごとく滅ぼされます。ウェールズ全土が喜びに満ち、かつてのような緑が生い茂るのです。王は、マーリンの予言にはもちろん聡明さにも驚嘆した。そこで、王は、自分がいかなる死を迎えるかについても尋ねる。(以下は省略) ■ウェールズの旗 赤いドラゴンがブリトン人の国家の自立と、侵入してきたサクソン人の排除の象徴となっている。ケルトの建国伝承では、この赤いドラゴンはかつて大地が出来た頃に、地震や災厄を起こしていた黒いドラゴンを打ち倒し、ケルトの地に平和をもたらしたとされる。ウェールズの国家的象徴である赤いドラゴンの神話は、サクソン人の前にブリテンに侵入してきたローマ人によってもたらされた。ローマ帝国が小アジアへ遠征した際に旗に描かれたドラゴンを見て、自らの軍旗に赤いドラゴンを使用したと言われる。ウェールズの旗は白と緑の地に赤い龍を配したもので、15世紀に確定し、赤い龍が国を守る象徴として今もウェールズ全域で広く使用されている。英語で《Welsh Dragon》とも呼ばれ、赤い色は《血》を、ドラゴンの姿は《独立》を現しているという。ラグビーのウェールズ代表の愛称は《レッド・ドラゴン》であり、ラグビーの名門として力を誇っている。しかし、最初の英国旗が制定された時、既にウェールズはイングランドに併合されてしまっていたために、英国旗にかつてのウェールズ旗のデザインが採用される事は無く、現在の英国旗に赤いドラゴンの姿は見る事はできない。 ■善い龍の例 龍には超自然的な能力を持ち、神聖視され、荘厳で、強力な意思を持つものとして崇拝されている《善い龍》もある。イギリスでは、ワイヴァーンと称される二本の足と翼を持ったドラゴンが霊力を持つ聖なる動物として扱われている。英国王室の紋章、ロンドン市の紋章、ロンドン橋、ミッドランド鉄道会社の紋章、レドン・ホール市場の入り口などに見られる。古代ローマでは強い力を象徴する龍を軍旗に用いて戦意を鼓舞していた。 船に龍頭をかたどったものがあり、トレドでは闘牛士が使う刀剣の柄に龍のレリーフを、バロセロナでは建物の入り口の装飾に龍のレリーフを見た。ガウディのグエル別邸の門塀では鉄製の龍のレリーフが置かれ、邸宅の入口をガードしている。マイセンでは龍の絵柄をあしらった磁器が今も販売されており、ドレスデン陶磁美術館(ツヴィンガー宮殿)には、18世紀に製作された16点の紅い龍の絵柄の磁器が展示されている。 |
|
 ■竜について |
|
|
竜についての見解は、西洋文化圏と東洋文化圏で随分違っている。
ここでは西洋の竜を「ドラゴン」もしくは「竜」、東洋のそれを「龍」と表記することでその違いを表現するものとする。 また、竜の具体的な説話については後程ご紹介するとして、ここでは竜というものの存在そのものについて見ていきたいと思う。 それではまず、西洋のドラゴンについて語ろう。 先ず、竜のモデルは、といえば、皆さんも良くご存知のとおり、先史時代の恐竜や蛇などの爬虫類である。 「ドラゴン」と言う言葉の原型は「ドラッヘ」(ギリシャ語のドラコーン)という語で、もともと「蛇」を意味するものである。この「ドラッヘ」なる蛇竜は、大きなワニのような顔をしていて、牙のある口と獲物を捕らえる舌を持ち、鱗状の堅い皮で覆われ、背中には櫛状の刺があり、鉤爪を持った短い足、蝙蝠のような羽と強力な長い尾を持っていた。この生き物は水中、或いは地上(洞窟)に生息していたが、空を飛ぶこともできた(飛行竜)のだそうだ。 さて、それではここで、心理学的な「ドラゴン」というものについて迫ってみよう。 ドラゴンとは、人間の心に棲む悪と破壊的な力の象徴であり、人間の内面世界の居住者である。 「竜は人間の弱く無防備な意識を育て支えるか、もしくはそれを飲み込み破壊する、人間のプシュケ(魂)の深くに棲む非人格的な力の化身である」とも言える。 また、西洋の竜にまつわる逸話といえば必ずと言っていいほど竜退治が出てくるのだが、これは、自意識と無意識の制御されない、飲み込む力との間に生じる、命を脅かす戦いを示す元型的な象徴である。 良く分からない方もいらっしゃるかと思うので、分かり易い言葉でまとめよう。 要するに、西洋の竜とは「人間の破壊的な心の象徴」であり、竜退治は「無意識に潜む不安や破壊衝動を自我で制する事」だということだ。 ではここで「神話の竜退治」についての心理学的な解釈について語ろうと思う。 有名な心理学者C・Gユングによれば、〔神話の英雄は「目覚めた自我の典型的な姿」であり、その冒険行は「自己化の道」である。水は「集合的無意識の象徴」であり、水から立ち上がったドラゴンは、その否定的な側面をとって意識される「集合的無意識の中にあるグレート・マザーの典型」である〕らしい。 これでは意味がさっぱりわからないと思うので、ここで補足を。 C・Gユングは、人間の心というものは人それぞれ違うが、深層意識の中には万人共通のファクターがいくつも存在している、とした。そのファクターのことを元型(アーキタイプ)と呼び、代表的な元型は影(シャドウ)、太母(グレートマザー)、アニマ、アニムス、老賢者(オールドワイズマン)の4つである。大雑把に言えば、、これらの元型が外界の刺激を受けて互いに反応しあい、人の思考・行動パターンを左右する、というわけだ。 そこで、上記にあるグレート・マザーが何を象徴しているかというと、これは「無意識の象徴」「常に飲み込まれる脅威に晒されている自我が生まれ出でてくる根源」なのである。勿論良い意味での解釈もあるのだが、竜退治の竜に現れるグレート・マザーの性質は否定的な母親像を表す。例えて言えば、神話の竜退治における英雄は「子供(自我)」であり、竜は「母親(無意識)」なのだ。子供が成長して自立しようとするのを、過保護な母親が妨げようとしているようなものなのである。 ここで本来の竜の話に戻るが、西洋の竜といえば絶対に無意識だの破壊のだのといった人間の心の象徴かというと、そういうわけではない。西洋の竜にはもうひとつの意味がある。 それは、元々は古くからその地に伝わる土着の神が、移民や植民等によって異民族が入ってきた際に、邪悪な存在として作り変えられてしまったものだ。 異民族が入ってくると、当然土着の宗教とは異なる宗教、異なる神々が入ってくることになる。当然新しく入ってきた人々は自分達の宗教を原住民たちに広めようとする。とはいえ、古くからの信仰を捨てさせ、新しい宗教を受け入れさせるのは難しい。そこで土着の神々を邪神や悪魔といったものに作り変え、自分達の信仰する神々によってそれらを打ち倒す、という神話を作るのである。こうすれば新しい宗教も比較的受け入れられやすい。 特に竜の場合は、元々地母神と呼ばれる類の神々である場合が多い。 そもそも竜のルーツは大蛇である。蛇は脱皮し再生していく姿から「自然の永遠の循環の象徴」とされる。このような特徴から古代の人々は、万物が生まれ、また還っていく大地を連想したのであろう。これが正しい神によって倒され、その死体から天地が創造されて世界ができた、というのが神話でよくある「天地創造」である(一神教では、世界は全能にして父なる神が創りたもうた、という事になるのだが)。 結局のところ、竜というものはいかにも邪悪なもの、というように思われているが、神も魔物もそう大差は無いのだろうと私は思う。 次は東洋の龍について見てみよう。 東洋では、龍は豊饒な大地や皇帝の権力、創造的なもの等の象徴であり、隠れた宝(英知、幸福、長寿)の番人である。 特に中国では龍は最も古い象徴であり、紋章動物である。肯定的な力を持った善意の霊である。龍は天上の龍として神々の居住を見張り、龍神として、雨や風を統括し、豊かな実をもたらす洪水を起こし、地龍として川を清め、海を深くする。そもそも中国神話では世界や人間といったものを創造したのは龍神の女渦と伏義であったという。その後中国は彼らの子孫である黄帝に治められ、更にその子孫が夏王朝を建てる、というのが史実以前の中国の歴史、という事になっている(最も、そんなものは神話であって歴史ではないと言う人もいらっしゃるらしいが)。それぐらい中国では龍は信仰されているのだ。 他にも東洋にはインドや日本の龍(但し日本の龍は中国から来たものなのだが)がいるのだが、やはり東洋の龍は西洋の竜に比べて「龍神」「天の遣い」的な要素が多く、人間を加護するものとされているようだ。 何故西洋と東洋でこれほど竜という存在に対する扱いが違うのか。 それはどうやら思想の違いによるものらしい。 そう、西洋思想は二元論的であり、東洋思想は包括的なのである。 西洋思想は「敵か味方か」というある意味非常に分かりやすい考え方である。彼らが信仰する神は「善」であり、それに反するものは皆「悪」なのだ。故にドラゴンは「邪悪なものの化身」として描かれる。 一方、東洋思想は「万物流転」「輪廻転生」的な部分がある。 全てのものが流れ、めぐりめぐっている以上、「絶対不変な善」や「絶対不変の悪」などというものは存在しないのだ。 また、タイジー(対極)といって、相互に補い合い依存しあっている根源的な力である陰と陽を表す中国の象徴にも見られるように、東洋では陰も陽もどちらも無くてはならないもの、互いに依存し合うものであるとされている。どちらかが完全にどちらかを葬ってしまえば、世界のバランスが崩れてしまう。故に「陽」と「陰」は在っても、「善」と「悪」はないのだろう。 このような東西の思想の違いが竜の存在にも相違を与えているのだろうと思われる。 しかし、こうして改めてみてみると、西洋の「破壊の象徴」たるドラゴンも、東洋の「創造を司るもの」としての龍も、やはりどちらも実に興味深いものだと思う。その存在そのものは勿論のこと、その裏に隠された人々の心理、思想、倫理といったものも、非常に興味深い。 幻想的な物語の竜もいい、ゲームのドラゴンのように強いモンスターとしての竜も面白い。しかし、人々の思想の象徴としての竜こそが本当の意味での竜の正体なのかも知れない。 |
|
 ■田原藤太竜宮入りの話 / 南方熊楠 |
|
|
■藤原秀郷
(ふじわらのひでさと) 平安時代中期の貴族・武将。下野大掾藤原村雄の子。室町時代に「俵藤太絵巻」が完成し、近江三上山の百足退治の伝説で有名。もとは下野掾であったが、平将門追討の功により従四位下に昇り、下野・武蔵二ヶ国の国司と鎮守府将軍に叙せられ、勢力を拡大。源氏・平氏と並ぶ武家の棟梁として多くの家系を輩出したが、仮冒の家系も多い。 出自を藤原北家魚名流とするのが通説だが、「実際には下野国史生郷の土豪・鳥取氏で、秀郷自身が藤原姓を仮冒した」という説もある(あるいは古代から在庁官人を務めた秀郷の母方の姓とする)。 俵藤太(田原藤太、読みは「たわらのとうだ」「たわらのとうた」、藤太は藤原氏の長、太郎」の意味)という名乗りの初出は『今昔物語集』巻25「平維茂 藤原諸任を罰つ語 第五」であり、秀郷の同時代史料に田原藤太の名乗りは見つかっていない。由来には、相模国淘綾郡田原を名字の地としていたことによるとする説、幼時に山城国近郊の田原に住んでいた伝説に求める説、近江国栗太郡田原郷に出自した伝説に求める説など複数ある。 秀郷は下野国の在庁官人として勢力を保持していたが、延喜16年(916年)隣国上野国衙への反対闘争に加担連座し、一族17(もしくは18)名とともに流罪とされた。しかし王臣子孫であり、かつ秀郷の武勇が流罪の執行を不可能としたためか服命した様子は見受けられない。さらにその2年後の延長7年(929年)には、乱行のかどで下野国衙より追討官符を出されている。唐沢山(現在の佐野市)に城を築いた。 天慶2年(939年)平将門が兵を挙げて関東8か国を征圧する(天慶の乱)と、平貞盛・藤原為憲と連合し、翌天慶3年(940年)2月、将門の本拠地である下総国猿島郡を襲い乱を平定。複数の歴史学者は、平定直前に下野掾兼押領使に任ぜられたと推察している。この功により同年3月従四位下に叙され、11月に下野守に任じられた。さらに武蔵守、鎮守府将軍も兼任するようになった。 ■百足退治伝説 近江国瀬田の唐橋に大蛇が横たわり、人々は怖れて橋を渡れなくなったが、そこを通りかかった俵藤太は臆することなく大蛇を踏みつけて渡ってしまった。その夜、美しい娘が藤太を訪ねた。娘は琵琶湖に住む龍神一族の者で、昼間藤太が踏みつけた大蛇はこの娘が姿を変えたものであった。娘は龍神一族が三上山の百足に苦しめられていると訴え、藤太を見込んで百足退治を懇願した。 藤太は快諾し、剣と弓矢を携えて三上山に臨むと、山を7巻き半する大百足が現れた。藤太は矢を射たが大百足には通じない。最後の1本の矢に唾をつけ、八幡神に祈念して射るとようやく大百足を退治することができた。藤太は龍神の娘からお礼として、米の尽きることのない俵などの宝物を贈られた。また、龍神の助けで平将門の弱点を見破り、討ち取ることができたという。 秀郷の本拠地である下野国には、日光山と赤城山の神戦の中で大百足に姿を変えた男体山(または赤城山)の神を猿丸大夫(または猟師の磐次・磐三郎)が討つという話があり(この折の戦場から「日光戦場ヶ原」の名が残るという伝説)、これが秀郷に結びつけられたものと考えられる。 また類似した説話が下野国宇都宮にもあり、俵藤太が悪鬼・百目鬼を討った「百目鬼伝説」であるが、これも現宇都宮市街・田原街道(栃木県道藤原宇都宮線)側傍の「百目鬼通り」の地名になっている。 「三上山を7巻き半と聞けばすごいが、実は8巻き(鉢巻)にちょっと足りない」という洒落がある。これは古典落語「矢橋船」などで用いられている。 |
|
| ■話の本文 | |
| この話は予の知るところでは、『太平記』十五巻に出たのが最も古い完全な物らしい、馬琴《ばきん》の『昔語質屋庫《むかしがたりしちやのくら》』二に、ある書にいわくと冒頭して引いた文も多分それから抄出したと見える。その『太平記』の文は次のごとし。いわく、 (延元元年正月、官軍|三井寺《みいでら》攻めに) 前々《せんぜん》炎上の時は、寺門の衆徒、これを一大事にして隠しける九乳《きゆうにゆう》の鳧鐘《ふしよう》も、取る人なければ、空しく焼けて地に落ちたり、この鐘と申すは、昔竜宮城より伝はりたる鐘なり、その故は承平の頃俵藤太|秀郷《ひでさと》といふ者ありけり、ある時この秀郷、たゞ一人|勢多《せた》の橋を渡りけるに、長《たけ》二十丈ばかりなる大蛇、橋の上に横たはつて伏したり、両の眼は輝いて、天に二つの日を掛けたるがごとし、双《なら》べる角《つの》の尖《するど》にして、冬枯れの森の梢《こずえ》に異ならず、鉄《くろがね》の牙上下に生《お》ひ差《ちご》ふて、紅の舌|炎《ほのお》を吐くかと怪しまる、もし尋常《よのつね》の人これを見ば、目もくれ魂消えて、すなはち地にも倒れつべし、されども秀郷、天下第一の大剛の者なりければ、更に一念も動ぜずして、彼《かの》大蛇の背《せなか》の上を、荒らかに踏みて、閑《しずか》に上をぞ越えたりける、しかれども大蛇もあへて驚かず、秀郷も後を顧みずして、遥《はる》かに行き隔たりける処に、怪しげなる小男一人、忽然《こつぜん》として秀郷が前に来《きたつ》ていひけるは、我この橋の下に住む事すでに二千余年なり、貴賤往来の人を量り見るに、今|御辺《ごへん》ほどに剛なる人いまだ見ず、我に年来《としごろ》地を争ふ敵あつて、動《やや》もすれば彼がために悩まさる、しかるべくは御辺、我敵を討つてたび候へと懇《ねんごろ》に語《かたら》ひけれ、秀郷一義もいはず、子細あるまじと領状して、すなはちこの男を前《さき》に立て、また勢多の方へぞ帰りける、二人共に湖水の波を分けて水中に入る事五十余町あつて、一の楼門あり、開いて内へ入るに、瑠璃《るり》の沙《いさご》厚く、玉の甃《いしだたみ》暖かにして、落花自ずから繽紛《ひんぷん》たり、朱楼紫殿玉の欄干|金《こがね》を鐺《こじり》にし銀《しろがね》を柱とせり、その壮観奇麗いまだかつて目にも見ず、耳にも聞かざりしところなり。 | |
| この怪しげなりつる男、まづ内へ入つて、須臾《しゆゆ》の間に衣冠を正しくして、秀郷を客位に請《しよう》ず、左右|侍衛官《しえのかん》前後花の粧《よそお》ひ、善尽し美尽せり、酒宴数刻に及んで、夜既に深《ふけ》ければ、敵の寄すべきほどになりぬと周章《あわて》騒ぐ、秀郷は、一生涯が間身を放たで持ちたりける、五人|張《ばり》にせき弦《づる》懸けて噛《く》ひ湿《しめ》し、三年竹の節近《ふしぢか》なるを、十五束|二伏《ふたつぶせ》に拵《こしら》へて、鏃《やじり》の中子《なかご》を筈本《はずもと》まで打ち通しにしたる矢、たゞ三筋を手挟《たばさ》みて、今や/\とぞ待ちたりける、夜半過ぐるほどに、雨風一通り過ぎて、電火の激する事|隙《ひま》なし、暫《しばら》くあつて比良《ひら》の高峯《たかね》の方より、焼松《たいまつ》二、三千がほど二行に燃えて、中に島のごとくなる物、この竜宮城を指《さ》してぞ近づきける、事の体《てい》を能々《よくよく》見るに、二行に点《とぼ》せる焼松は、皆|己《おのれ》が左右の手に点したりと見えたり、あはれこれは、百足蛇《むかで》の化けたるよと心得て、矢比《やごろ》近くなりければ、件《くだん》の五人張に十五束|三伏《みつぶせ》、忘るゝばかり引きしぼりて、眉間《みけん》の真中をぞ射たりける、その手答へ鉄を射るやうに聞えて、筈を返してぞ立たざりける、秀郷一の矢を射損じて安からず思ひければ、二の矢を番《つご》うて、一分も違《ちが》へず、わざと前の矢所《やつぼ》をぞ射たりける、この矢もまた、前のごとくに躍り返りて、これも身に立たざりけり、秀郷二つの矢をば、皆射損じつ、憑《たの》むところは矢一筋なり、如何《いかん》せんと思ひけるが、屹《きつ》と案じ出だしたる事あつて、この度射んとしける矢先に、唾を吐き懸けて、また同じ矢所をぞ射たりける、この矢に毒を塗りたる故にや依りけん、また同じ矢坪を、三度まで射たる故にや依りけん、この矢眉間の只中《ただなか》を徹《とお》りて、喉の下まで、羽《は》ぶくら責めてぞ立ちたりける、二、三千見えつる焼松も、光たちまち消えて、島のごとくにありつる物、倒るゝ音大地を響かせり、立ち寄りてこれを見るに、果して百足の※[虫+玄]《むかで》なり、竜神はこれを悦びて、秀郷を様々に饗《もてな》しけるに、太刀|一振《ひとふり》、巻絹《まきぎぬ》一つ、鎧一領、頸|結《ゆ》うたる俵一つ、赤銅《しやくどう》の撞鐘《つきがね》一口を与へて、御辺の門葉《もんよう》に、必ず将軍になる人多かるべしとぞ示しける。 | |
| 秀郷都に帰つて、後この絹を切つて使ふに更に尽くる事なし、俵は中なる納物《いれもの》を、取れども/\尽きざりける間、財宝倉に満ちて、衣裳身に余れり、故にその名を、俵藤太とはいひけるなり、これは産業の財《たから》なればとて、これを倉廩《そうりん》に収む、鐘は梵砌《ぼんぜい》の物なればとて、三井寺へこれを奉る、文保《ぶんぽう》二年、三井寺炎上の時、この鐘を山門へ取り寄せて、朝夕これを撞きけるに、あへて少しも鳴らざりける間、山法師ども、悪《にく》し、その義ならば鳴るやうに撞けとて、鐘木《しもく》を大きに拵へて、二、三十人立ち掛りて、破《わ》れよとぞ撞きたりける、その時この鐘、海鯨《くじら》の吼《ほ》ゆる声を出して、三井寺へ往《ゆ》かふとぞ鳴いたりける、山徒いよ/\これを悪《にく》みて、無動寺《むどうじ》の上よりして、数千丈高き岩の上をば、転《ころ》ばかしたりける間、この鐘|微塵《みじん》に砕けにけり、今は何の用にか立つべきとて、そのわれを取り集めて、本寺へぞ送りける、ある時一尺ばかりなる小蛇来つて、この鐘を尾を以て扣《たた》きたりけるが、一夜の内にまた本の鐘になつて、疵《きず》付ける所|一《ひと》つもなかりけり云々。 | |
| この鐘に似た事、支那にてこれより前に記された。予が明治四十一年六月の『早稲田文学』六二頁に書いた通り、『酉陽雑俎』(蜈蚣《むかで》退治を承平元年と見てそれより六十八年前に死んだ唐の段成式著わす)三に、歴城県光政寺の磬石《けいせき》、膩光《つや》滴《したた》るがごとく、扣《たた》けば声百里に及ぶ、北斉の時、都内に移し撃たしむるに声出ず、本寺に帰せば声|故《もと》のごとし、士人磬神聖にして、光政寺を恋《した》うと語《うわさ》したとある。『続古事談』五に、経信大納言言われけるは、玄象という琵琶は、調べ得ぬ時あり、資通|大弐《だいに》、この琵琶を弾《ひ》くに調べ得ず、その父|済政《なりまさ》、今日この琵琶|僻《ひが》めり、弾くべからざる日だと言うた、経信白川院の御遊に、呂の遊の後律に調べるについに調べ得ず、古人のいう事、誠なるかなと言われたとある。和漢とも貴重な器具は、人同様心も意気地もありとしたのだ。鐘が鳴らぬからとて、大騒ぎして砕いたなど、馬鹿げた談《はなし》だが、昔は、東西ともに大人が今の小児ほどな了簡の所為多く、欧州でも中世まで、動物と人と同様の権利も義務もありとし、証人に引き、また刑の宣告もした(『ルヴィユー・シャンチフィク』三輯三巻、ラカッサニュの説)。されば時として、無心の什器《じゅうき》をも、人と対等視した例も尠《すくな》からず、一六二八年、仏国ラ・ロシェルに立て籠った新教徒降った時、仏王の将軍、かの徒の寺に懸けあった鐘を下ろし、その罪を浄めるため、手苛《てひど》く笞懲《うちこら》したは良かったが、これを買った旧教徒に、王人をして代金を求めしむると、新教徒が旧教に化した時、その借金を払うに三年の猶予ある、因ってこの鐘も三年待ってくれと言ったとは珍譚じゃ(コラン・ド・プランチー『遺宝霊像評彙《ジクショネール・クリチク・デー・レリク・エ・デー・イマージュ・ミラクロース》』一八二一―二年版、巻三、二一四頁)。 | |
| 『太平記』に三井の鐘破れたるを、小蛇来り尾で叩いて本に復したとあるは、竜宮から出た物ゆえ、竜が直しに来た意味か、または鐘の竜頭が神異を現じた意味だろう、名作の物が、真物同然不思議を働く例は、『酉陽雑俎』三に、〈僧一行異術あり、開元中かつて旱す、玄宗雨を祈らしむ、一行いわく、もし一器上竜状あるものを得れば、まさに雨を致すべし、上内庫中において遍ねくこれを視せしむ、皆類せずと言う、数日後、一古鏡の鼻の盤竜を指し、喜びて曰くこれ真竜あり、すなわち持ちて道場に入る、一夕にして雨ふる〉。『近江輿地誌略』十一には、秀郷自分この鐘を鋳て三井に寄附せりとし、この鐘に径五寸ばかりの円き瑕《きず》あり、土俗いわく、この鐘を鋳る時、一女鏡を寄附して鋳物師に与う、しかれども、心|私《ひそ》かに惜しんだので、その鏡の形に瑕生じたと。また『淡海録』曰く、昔|赤染衛門《あかぞめえもん》、若衆に化けてこの鐘を見に来り、鐘を撫《な》ぜた手が取り著《つ》いて離れず、強く引き離すと手の形に鐘取れた痕《あと》なり、また染殿后《そめどののきさき》ともいうと。『誌略』の著者は、享保頃の人だが、自ら睹《み》た所を記していわく、この鐘に大なる※[比+皮]裂《ひびわれ》あり、十年ばかりも以前に、その裂目へ扇子入りたり、その後ようやくして、今は毫毛《ごうもう》も入らず、愈《い》えて※[比+皮]裂なし、破鐘を護《まも》る野僧の言わく、小蛇来りて、夜ごとにこの瑕を舐むる故に愈えたりと、また笑うべし、赤銅の性、年経てその瑕愈え合う物なり、竜宮の小蛇、鐘を舐《ねぶ》りて瑕を愈やす妙あらば、如何ぞ瑕付かざるように謀《はか》らざるや、年経て赤銅の破目愈え合うという事、臣《それがし》冶工に聞けりと。予今年七十六歳の知人より聞くは、若い時三井寺で件《くだん》の鐘を見たるに※[比+皮]裂筋あり、往昔弁慶、力試しにこれを提《さ》げて谷へ擲《な》げ下ろすと二つに裂けた、谷に下り推《お》し合せ長刀《なぎなた》で担《にの》うて上り、堂辺へ置いたまま現在した、またその鐘の面に柄附《えつき》の鐘様の窪《くぼ》みあり、竜宮の乙姫《おとひめ》が鏡にせんとて、ここを採り去ったという、由来書板行して、寺で売りいたと。 | |
| 何がな金にせんと目論み、一つの鐘に二つまで瑕の由来を作った売僧輩《まいすはい》の所行《しわざ》微笑の至りだが、欧州の耶蘇《ヤソ》寺にも、愚昧な善男女を宛《あ》て込んで、何とも沙汰の限りな聖蹟霊宝を、捏造《ねつぞう》保在した事無数だ。試みに上に引いたコラン・ド・プランチーの『評彙』から数例を採らんに、ローマにキリストの臍帯《さいたい》および陰前皮《まえのかわ》と、キリストがカタリン女尊者に忍び通うた窓附の一室、またアレキシス尊者登天の梯《はしご》あり。去々年独軍に蹂躙されたランスの大寺に、石上に印せるキリストの尻蹟あり、カタンにアガテ女尊者の両乳房、パリ等にキリストの襁褓《むつき》、ヴァンドームにキリストの涙、これは仏国革命の際、実検して南京玉と判《わか》った。またローマに、日本聖教将来の開山ハビエロの片腕、ロヨラ尊者の尻、ブロア附近にキリストの父が木を伐る時出した声、カタロンとオーヴァーンは、聖母マリアの経水|拭《ふ》いた布切《ぬのぎれ》、オーグスブールとトレーヴにベルテレミ尊者の男根、それからグズール女尊者の体はブルッセルに、女根と腿《もも》はオーグスブールに鎮坐して、各々随喜恭礼されたなど、こんな椿事《ちんじ》は日本にまたあるかいな。 | |
| されば弁慶力試しや、男装した赤染衛門の手印などは、耶蘇坊主の猥雑《わいざつ》極まる詐欺に比べて遥かに罪が軽い、それから『川角太閤記《かわすみたいこうき》』四に、文禄元辰二月時分より三井寺の鐘鳴りやみ、妙なる義と天下に取り沙汰の事と見ゆ、これも何か坊主どもの騙術《まやかし》だろうが、一体この寺の鐘性弱いのか、またさなくとも、度々《たびたび》の兵火でしばしば※[比+皮]裂《ひびわれ》たのを、その都度よい加減に繕うたが、ついに鳴りやんだので、その※[比+皮]裂や欠瑕を幸い、種々伝説を造って凡衆を誑《たぶら》かしたのだろう、かようの次第で三井の鐘が大当りと来たので、これに倣《なろ》うて他にも類似の伝説附の鐘が出て来たは、あたかも江戸にも播州《ばんしゅう》にも和歌山にも皿屋敷があったり、真言宗が拡まった国には必ず弘法大師|三鈷《さんこ》の松類似の話があったり(高野のほかに、『会津風土記』に載った、磐梯山恵日寺の弘法の三鈷松、『江海風帆草』に見ゆる筑前立花山伝教の独鈷《とっこ》松、チベットにもラッサの北十里、〈色拉寺中一|降魔杵《ごうましょ》を置く、番民呼んで多爾済《ドルジ》と為《な》す、大西天より飛来し、その寺|堪布《カンボ》これを珍《め》づ、番人必ず歳に一朝観す〉と『衛蔵図識』に出《い》づ)、殊に笑うべきは、天主教のアキレスとネレウス二尊者の頭顱《されこうべ》各五箇ずつ保存恭拝され、欧州諸寺に聖母《マドンナ》の乳汁《ちち》、まるで聖母は乳牛だったかと思わるるほど行き渡って奉祀され居るがごとし。 | |
| すなわち『近江輿地誌略』六一、蒲生《がもう》郡川守村鐘が嶽の竜王寺の縁起を引きたるに、宝亀《ほうき》八年の頃、この村に小野時兼なる美男あり、ある日一人の美女たちまち来り、夫婦たる事三年ののち女いわく、われは平木の沢の主なり、前世の宿因に依ってこの諧《かた》らいを為《な》せり、これを形見にせよとて、玉の箱を残して去った、時兼恋情に堪えず、平木の沢に行って歎くと、かの女|長《たけ》十丈ばかりの大蛇と現わる、時兼驚き還ってかの箱を開き見るに鐘あり、すなわち当寺に寄進す、かの沢より竜燈今に上るなり、霊験新たなるに依って、一条院勅額を竜寿鐘殿と下し賜わり、雪野寺を竜王寺と改めしむ、承暦《しょうりゃく》二年十月下旬、山徒これを叡山《えいざん》へ持ち行き撞けども鳴らねば、怒りて谷へ抛げ落す、鐘破れ瑕《きず》つけり、ある人当寺へ送るに、瑕自然愈合、その痕今にあり、年|旱《ひでり》すれば土民雨をこの鐘に祈るに必ず験あり、文明六年九月濃州の石丸丹波守、この鐘を奪いに来たが俄《にわか》に雷電して取り得ず、鐘を釣った目釘を抜きけれど人知れず、二年余釣ってあったとあるは、回祖《マホメット》の鉄棺が中空に懸るてふ[#「てふ」に「〔という〕」の注記]欧州の俗談(ギボン『羅馬帝国衰亡史《デクライン・エンド・フォール・オブ・ゼ・ローマンエンパイヤー》』五十章註)に似たり。 | |
| 竜燈の事は、昨年九、十、十一月の『郷土研究』に詳論し置いた。高木君の『日本伝説集』一六八頁には、件《くだん》の女が竜と現じ、夫婦の縁尽きたれば、記念《かたみ》と思召せとて、堅く結んだ箱を男に渡し、百日内に開くべからずと教えて黒雲に乗って去った。男百日|俟《ま》たず、九十九日めに開き見るに、紫雲立ち上って雲中より鐘が現われたとあるは、どうも浦島と深草少将を取り交《ま》ぜたような拙《つたな》い作だ。また平木の沢には鐘二つ沈みいたが、一つだけ上がった方は水鏡のように澄み、一つ今も沈みいる方は白く濁る、上がった方の鐘は女人を嫌いまた竜頭を現わさず、常に白綿を包み置く、三百年前一向宗の僧兵が陣鐘にして、敗北の節谷に落し破ったが、毎晩白衣の女現われ、その破目《われめ》を舐めたとあるから、定めて舐めて愈《なお》したのだろ、これらでこの竜王寺の譚《はなし》は、全く後世三井寺の鐘の盛名を羨んで捏造された物と判りもすれば、手箱から鐘が出て水に沈むとか、女を忌む鐘の瑕を女が舐めて愈したなど、すこぶる辻褄合わぬ拙作と知れる。 | |
| 『太平記』に、竜神が秀郷に、太刀、巻絹、鎧、俵、鐘、五品を与えたとあれど(『塵添※[土へん+蓋]嚢抄《じんてんあいのうしょう》』十九には如意《にょい》、俵、絹、鎧、剣、鐘等とあり、鎧は阪東《ばんどう》の小山《おやま》、剣は伊勢の赤堀に伝うと)、巌谷君が、『東洋口碑大全』に引いた『神社考』には、太刀のほかの四品、『和漢三才図会』には太刀、鎧、旗、幕、巻絹、鍋、俵、庖刀、鐘と心得童子《こころえのどうじ》、計九品と一人、太刀の名|遅来矢《ちくし》と出《い》づ。寛永十年頃筆せられた『氏郷記』巻上にも、如上の十種を挙げた。鍋を早小鍋、俵を首結俵とし居る。また一伝に、露という硯《すずり》も将来したが竹生島へ納むとあり、太刀は勢州赤堀の家にあり、避来矢《ひらいし》の鎧は下野国《しもつけのくに》佐野の家にあり、童は思う事を叶《かな》えて久しく仕えしが、後に強《きつ》う怒られて失《う》せしとかや、巻絹は裁《た》ち縫うて衣裳にすれども耗《へ》らず、衣服に充満《みち》けるが、後にその末を見ければ延びざりけり、鍋は兵糧を焼《た》くに、少しの間に煮えしとなり。これも後には底抜けて、その破片《かけ》は蒲生家にありとぞ聞えし、俵は米を取れども耗らず、粮《かて》も乏しき事なし、それ故に名字を改め、俵藤太とぞ申しける。されども、将門《まさかど》退治の後、ある女房俵の底を叩いて米を開《あ》ければ、一尺ばかりの小蛇出で去りしより、米出でざりけり、これより始まりて、今俵の底を叩かぬ謂《いわ》れとなり、また秀郷の末孫、陣中にて女房を召し仕わざるも、この謂れとかや云々。秀郷を神と崇めて勢多に社あり(『近江輿地誌略』に、勢多橋南に秀郷社竜王社と並びあり、竜王社は世俗乙姫の霊を祭るという、傍なる竜光山雲住寺縁起に、秀郷水府に至りて竜女と夫婦の約あり、後ここに祭ると)、されば秀郷の子孫、勢多橋を過ぐるには、下馬して笠を脱ぎ、鈎匙《さじ》、小刀、鞭《むち》、扇等、何にても水中へ投げ入れ、礼拝して通るに必ず雨ふるなり云々、また曰く、下野国佐野の家にも秀郷より伝えし鎧あり、札に平石権現と彫り付け牡蠣《かき》の殻も付きたり、かの家にては「おひらいし」の鎧とて答拝せらるとなり、またかの鎧竜宮より持ちて上りし男、竜二郎、竜八とて二人あり、これも佐野家に仕えけるが、竜二郎は断絶す、竜八は今において佐野の秋山という処にこれあり、彼らが子孫は必ず身に鱗ありとなり、避来矢《ひらいし》の鎧と書き、平石にてはなしと、以上『氏郷記』の文だ。 | |
| 『近江輿地誌略』に、ある説に鐺《なべ》は、蒲生忠知の室は内藤帯刀《ないとうたてわき》女《むすめ》なり、故に蒲生家断絶後内藤家に伝う、太刀は佐野の余流赤堀家に伝う(蒲生佐野ともに秀郷の後胤《こういん》だ)。この宝物を負い出でたる童を、如意と名づく、その子孫を竜次郎とて、佐野の家にあり、後《のち》宮崎氏と称すると出《い》づ、何に致せ蒲生氏|強盛《ごうせい》の大名となりてより、勢多の秀郷社も盛んに崇拝され、種々の宝物も新造されて、秀郷当身の物と唱えられたらしい。『誌略』に雲住寺縁起に載った、秀郷の鏃を見んと、洛西妙心寺に往って見ると、鏃甚だ大にしてまた長く、常人の射るべき物ならず、打根《うちね》のごとし、打根は射る物でなく手に掛けて人に打ち付くる物なり、尚宗とある銘の彫刻および中真《なかみ》の体、秀郷時代より甚だ新しいようだから、臣寺僧に問うに、この鏃は中世蒲生家よりの贈品で、秀郷の鏃という伝説もなし、ただ参詣人、推して秀郷の鏃と称えるのですと対《こた》えたとある。 | |
| 『明良洪範《めいりょうこうはん》』二四には、天正十七年四月、秀吉初め男子(名は棄君)を生む、氏郷累代の重器たる、秀郷|蜈蚣《むかで》射たる矢の根一本|献《たてまつ》る、この子三歳で早世したので、葬処妙心寺へかの鏃を納めたとあるから見ると、氏郷重代の宝だったらしい。 | |
| さて秀郷を俵藤太という事、この人初め下野の田原てふ地に住み(あるいはいう大和の田原で生まる、またいう近江の田原を領せり)、藤原氏の太郎だった故、田原藤太といいしを、借字して俵と書くようになって、俵の字を解かんとて竜宮入りの譚を誰かが作り出したであろうと、馬琴《ばきん》が説いたは、まずは正鵠《せいこく》を得たものだろう。それから『和漢三才図会』に〈按《あん》ずるに秀郷の勇、人皆識るところなり、三上山蜈蚣あるべし、湖中竜住むべし、而《しか》して十種宝物我が国中世用の器財なり、知らず海底またこれを用うるか、ただ恨むらくはその米俵巻絹世に存せざるなり〉という事は、『質屋庫』に引いた『五雑俎』四に、〈蘇州東海に入って五、六日ほど、小島あり、濶《ひろ》さ百里余、四面海水皆濁るに、独りこの水清し、風なくして浪高きこと数丈、常に水上紅光|見《あら》われ日のごとし、舟人あえて近づかず、いわくこれ竜王宮なり、而して西北塞外人跡到らざるの処、不時数千人樹を□木を※[てへん+曳]《ひ》くの声を聞く、明くるに及んで遠く視るに山木一空、いわく海竜王宮を造るなり、余|謂《おも》えらく竜水を以て居と為す、豈《あに》また宮あらん、たといこれあるもまたまさに鮫宇貝闕なるべし、必ずしも人間《じんかん》の木殖を藉《か》らざるなり、愚俗不経一にここに至る〉とあるより翻案したのだろう。さて『和漢三才図会』の著者が、〈けだし竜宮竜女等の事、仏経および神書往々これを言う、更に論ずるに足らず〉と結んで居るが、一概に論ずるに足らずと斥けては学問にならぬ、仍《よ》ってこれから、秀郷の竜宮入りの譚の類話と、系統を調査せんに、まず瑣末《さまつ》な諸点から始めるとしよう。 | |
| 『氏郷記』に、少時間《すこしのま》で早く物を煮得る鍋を、宝物に数えたり、秀郷の子孫に限り、陣中女房を召し仕わざる由を特書したので、件《くだん》の竜宮入りの譚は、早鍋世に極めて罕《まれ》に、また中古の欧州諸邦と等しく、わが邦でも、軍旅に婦女を伴れ行く風が存した時代に出来たと知らる。今も所により、米升《こめのます》を洗うを忌むごとく、何かの訳で俵の底を叩くを忌んだのに附会して、ある女房俵の底叩いて蛇を出したと言い出したのであろう。外国にも、米と竜と関係ある話がある。これは蛇が鼠を啖《くろ》うて、庫を守るより出た事か、今も日本に米倉中の蛇を、宇賀神など唱え、殺すを忌む者多し。 | |
| 『外国事』にいう、毘呵羅《ひから》寺に神竜ありて、倉中に往来す、奴米を取る時、竜|却後《ひっこ》む、奴もし長く取れば竜与えず、倉中米尽くれば、奴竜に向い拝すると、倉|即《やがて》盈溢《みちあふ》る(『淵鑑類函』四三七)。『高僧伝』三に、〈迦施《かし》国白耳竜あり、毎《つね》に衆僧と約し、国内豊熟せしむ、皆信効あり、沙門ために竜舎を起す、並びに福食を設け、毎に夏坐《げざ》の訖《おわ》るに至り、竜すなわち化して一少蛇と作《な》る、両耳ことごとく白し、衆|咸《みな》これ竜と識《し》る、銅盂《どうう》を以て酪を盛る、竜を中に置き、上座より下に至りてこれを行くこと遍し、すなわち化し去る、年すなわち一たび出づ、法顕また親しく見る〉。 | |
| ある蛇どもが乳を嗜む事は、一九〇七年版、フレザーの『アドニス篇』に載せて、蛇を人間の祖先と見立てた蛮人が、祖先再生までの間これを嬰児《みどりご》同様に乳育するに及んだのだろうとあるを、予実例を挙げて、蛇が乳を嗜むもの多きより、これを崇拝する者乳を与うるのだと駁《ばく》し置いた(一九〇九年『ノーツ・エンド・キーリス』十輯十一巻、一五七―八頁)。蛇また竜が豊作に縁ありてふ事は、フレザーのかの書五九頁、一九一一年版『エンサイクロペジア・ブリタニカ』二十四、蛇崇拝の条等に見ゆ。ここに面白きは、ハクストハウセンの『トランスカウカシア』に載せた伝説「米の発見」てふ奴《やつ》だ、いわくアブラハムの子シャー・イスマエル既に全世界を従え、大洋を囲んで無数の軍兵に、毎人一桶ずつ毎日その水を汲《く》ませ、以て大海を乾《ほ》し涸《か》らそうと懸った、かくて追々海が減る様子を、海の民が海王に告げると、王彼らに「敵軍水を汲むに急ぎおるか、徐々《そろそろ》行《や》りおるか見て来い、急いで行りおるなら、彼らはほどなくへこ垂《た》れるはずだ、徐々|行《や》っておるなら、われら降参して年貢を払わにゃならぬ」と言った。これ誠に名言で、内典にも大施太子、如意宝珠を竜宮に得、海を渡って少眠《まどろ》む内、諸竜にその珠を盗まれしが、眼覚めて、珠を復《とりかえ》さずばついに空しく帰らじと決心し、一の亀甲を捉《と》って海水を汲み涸《ほ》さんとした。海神問うらく、海水深庭三百三十六万里、世界中の民ことごとく来て汲んだって減らぬに限《きま》った物を、汝一身何ぞ能く汲み尽くし得べきと。太子|対《こた》えて、〈もし人至心にして所作事あるを欲せば、弁ぜざるなし、我この宝を得まさに用いて一切群生を饒益し、この功徳を以て用いて仏道を求むべし、わが心|懈《おこた》らず、何を以て能わざる〉と言ったので、海神その精進強力所作に感じ、珠を還し、その根性強さでは、汝必ず後身|成道《じょうどう》すべき間、その時必ず我を弟子にしてくれと頼んだ、大施太子は今の釈迦で、海神は離越これなりとある(『賢愚因縁経』八)。 | |
| さて、海王が視《み》に遣った民が還って、陸王は海を汲むに決して急がず、毎卒日に一桶ずつ汲むと告げたので、海王しからば降参と決し、使をシャーに遣わした。その使の言語一向分らぬから、シャーこれを牢舎し、一婦をその妻として同棲せしめると子が出来た、その子七歳になり、海陸両世界の語を能くすから、これを通弁として、海王の使がシャーの前に出で、海王降参の表示《しるし》として、何を陸王に献《たてまつ》るべきやと問うと、百ガルヴァルだけ糧食《かて》を上《たてまつ》れと答う。使これを海王に報ずると、大いに困って、われは大海所有一切の宝を献るべきも、百ガルヴァルてふ莫大の食料は持たぬといった。百ガルヴァルは、日本の二四一九貫二〇〇匁で、大した量でないがこの話成った頃の韃靼《タタリア》では、莫大な物だったのだ。そこでシャー、しからば五十ガルヴァルはと問うと、海王それも出来ぬから、自分の后と諸公主《むすめども》を進《まいら》そうと答えた。このシャー女嫌いと見え、しからば二十五ガルヴァルはというと、それだけなら何とか拵《こしら》えて見ますと言って献った、その海王の粮《かて》というは稲で、もとより水に生じ、陸に生きなんだが、この時より内地諸湖の際に植えられたとある。 | |
| 秀郷が、竜宮から得た巻絹や俵米は尽きなんだが、一朝|麁忽《そこつ》な扱いしてから出やんだちゅう談に似た事も、諸邦に多い。『五雑俎』十二に、〈巴東寺僧青磁碗を得て、米をその中に投ず、一夕にして満盆皆米なり、投ずるに金銀を以て皆|然《しか》り、これを聚宝※[怨の心に代えて皿]《じゅほうわん》という、国朝沈万三富天下に甲たり、人言うその家にかの宝盆ありと〉、これは少し入れると一盃に殖えるので、無尽の米絹とやや趣きが差《ちが》う。欧州には、金を取れども尽きぬ袋の話多く、例せば一八八五年版クレーンの『伊太利俗談《イタリアン・ポピュラル・テールス》』に三条を出す。『近江輿地誌略』三九、秀郷竜宮将来の十宝の内に、砂金袋とあるもこの属《たぐい》だろう。古ギリシアのゼウス神幼時乳育されたアマルティアてふ山羊の角を折ってメリッセウスの娘どもに遺《おく》り、望みの品は何でもその角中に満つべき力を賦《つ》けた(スミス『希臘羅馬人伝神誌名彙《ジクショナリ・オヴ・グリーク・エンド・ローマン・バヨグラフィ・エンド・ミソロジー》』巻一)。 | |
| 仏説に摩竭陀《まかだ》国の長者、美麗な男児を生むと同日に、蔵中|自《おの》ずから金象を生じ、出入にこの児を離れず、大小便ただ好《よ》く金を出す、阿闍世王これを奪わんとて王宮に召し、件《くだん》の男名は象護を出だし、象を留むるにたちまち地に没せり、門外に踊り出で、彼を乗せて還った、彼害を怖れ仏に詣り出家すると、象また随い行き、諸僧騒動す、仏象護に教え象に向い、我|今生《こんじょう》分《ぶん》尽きたれば汝を用いずと言わしむると、象すなわち地中に入ってしまった、仏いわく昔|迦葉仏《かしょうぶつ》の時、象護の前身|一《ある》塔中菩薩が乗った象の像少しく剥《は》げたるを補うた功徳で、今生金の大小便ばかり垂れ散らす象を得たとあるが、どんな屁を放《ひ》ったか説いていない(『賢愚因縁経』十二)。 | |
| 『今昔物語』六に、天竺《てんじく》の戒日王、玄奘三蔵に帰依して、種々の財を与うる中に一の鍋あり、入りたる物取るといえども尽きず、またその入る物食う人病なしと見えるが、芳賀博士の参攷本に類話も出処も見えず、予も『西域記』その他にかかる伝あるを知らぬ、当時支那から入った俗説じゃろう。ヒンズー教の『譚流朝海《カタ・サリット・サラガ》』に、一樵夫夜叉輩より瓶を得、これを持てばどんな飲食も望みのまま出来るが、破《わ》れればたちまち消え失せるはずだ、やや久しく独りで楽しんでいたが、ある夜友人を会し宴遊するに、例の瓶から何でも出《い》で来る嬉しさに堪えず、かの瓶を自分の肩に載せて踊ると、瓶落ち破れて、夜叉のもとへ帰り、樵夫以前より一層侘しく暮したと出《い》づ。アイスランドの伝説に、何でも出す磨《ひきうす》を試すとて塩を出せと望み挽くと、出すは出すは、磨動きやまず、塩乗船に充《み》ち溢《あふ》れて、ついにその人を沈めたとあり。『酉陽雑俎』に、新羅国の旁※[施のつくり]《ぼうい》ちゅう人、山中で怪小児群が持てる金椎子《きんのつち》が何でも打ち出すを見、盗み帰り、所欲《のぞみのもの》撃つに随って弁じ、大富となった、しかるにその子孫戯れに狼の糞を打ち出せと求めた故、たちまち雷震して椎子を失うたと見ゆるなど、いずれも俵の底を叩いて、米が出やんだと同じく、心なき器什《どうぐ》も侮らるると瞋《いか》るてふ訓戒じゃ。 | |
| それから、竜神が秀郷に送った無尽蔵の巻絹の因《ちな》みに、やや似た事を記そう。ハクストハウセン(上に引いた書)がペルシアの俗談と書いたは、支那の伏羲|流寓《さすらえ》て、ある富んだ婦人に宿を求めると、卑蔑《さげすん》で断わられた。次に貧婦の小舎《こや》を敲《たた》くと、歓び入れてあるたけの飲食《おんじき》を施し、藁の床に臥さしめ、己は土上に坐し終夜眠らず、襦袢を作って与え、朝食せしめて村外れまで送った。伏羲嬉しさの余り、その婦に汝が朝手初めに懸った業は、※[日+甫]《くれ》まで続くべしと祝うて去った。貧婦帰ってまず布を度《さ》し始めると、夕まで布尽きず、跡から跡から出続いたので、たちまち大富となった。夜前伏羲を断わった隣の富家の婦聞いて大いに羨《うらや》むと、数月の後伏羲また村へ来た、かの婦|強《し》いて自宅へ迎え取り食を供し、夜中自室へ蝋燭|点《とも》し通夜仕事すると見せ掛け、翌朝|予《かね》て拵え置いた襦袢を呈し、食を供えて送り出すと、伏羲前度のごとく祝した。悦んで帰宅の途中、布を度《さ》す事のみ念じて宅へ入る刹那《せつな》、自家の飼牛が吼《ほ》える、水を欲しいと見える、布を量る前に水を遣らんと水を汲んで桶から槽《ふね》に移すに、幾時経っても、桶一つの水が尽きず、夥しく出続き家も畠も沈み、牛畜溺死し、村民大いに怒り、かの婦わずかに身を以て免《のが》れたとある。 | |
| 一六一〇年頃出たベロアル・ド・ヴェルヴィルの『上達方《ル・モヤン・ド・パーヴニル》』三九章にも似た話あって遥《ずっ》と面白い。いわくマルサスのバラセ町へ貧僧来り、富家に宿を求めると、主婦無情で亭主|慳貪《けんどん》の由言って謝絶した。次に貧家へ頼むと、女房至誠懇待到らざるなかったので、翌朝厚く礼を述べ、宿銭持たぬは残念と言うと、金が欲しさに留めたでないと言う、因って神に祈って、汝が朝し始めた事は何でも晩まで続くべしと祝して去った、女房一向気に留めず、昨日拡げ置いた布を巻き掛けると、巻いても巻いても巻き尽きず、手が触《さわ》るごとに殖えて往く、ところへかの僧を門前払いにした婦やって来て、仔細を聞き、追い尋ねてやっとかの僧を見附け、わが夫の性がころりと改まったから、今夜|情願《どうぞ》拙宅へと勧めると、勤行《ごんぎょう》が済み次第参ろうとあって、やがてついて一泊し、明朝出立に臨み前夜通りの挨拶の後、僧また汝が朝始めた業は昏《くれ》まで続くべしと言って去った。待ってましたと、大忙《おおいそ》ぎで下女に布を持ち来らしめ、度《さし》に掛かろうとすると、不思議や小便たちまち催して、忍ぶべうもあらず、これは堪《たま》らぬ布が沾《ぬれ》ると、庭へ飛び下りて身を屈《かが》むる、この時遅くかの時早く、行《ゆく》尿《しし》の流れは臭くして、しかも尋常の水にあらず、淀《よど》みに浮ぶ泡沫《うたかた》は、かつ消えかつ結びて、暫時《しばし》も停《とど》まる事なし、かの「五月雨《さみだれ》に年中の雨降り尽くし」と吟《よ》んだ通り、大声※[口+曹]々|驟雨《ゆうだち》の井を倒《さかさ》にするごとく、小声切々|時雨《しぐれ》の落葉を打つがごとく、とうとう一の小河を成して現存すとは、天晴《あっぱれ》な吹きぶりじゃ。 | |
| 『氏郷記』に、竜宮から来た竜二郎、竜八の二子孫必ず身に鱗ありとは、垢《あか》が溜り過ぎたのかという人もあらんが、わが邦の緒方の三郎(『平家物語』)、河野道清(『予章記』)、それから松村武雄氏の祖(『郷土研究』二巻一号、二四頁)など、いずれも大蛇が婦人に生ませた子で、蛇鱗を具《そな》えいたと伝え、支那隋の高祖も竜の私生児でもあった者か、〈為人《ひととなり》竜顔にして、額上五柱八項あり、生まれて異あり、宅旁の寺の一尼抱き帰り自らこれを鞠《やしな》う、一日尼出で、その母付き自ら抱く、角出で鱗|起《た》ち、母大いに驚きこれを地に墜す、尼心大いに動く、亟《いそ》ぎ還りこれを見て曰く、わが児を驚かし、天下を得るを晩《おそ》からしむるを致す〉。『続群書類従』に収めた「稲荷鎮座由来」には、荷田氏の祖は竜頭太とて、和銅年中より百年に及ぶまで稲荷|山麓《さんろく》に住み、耕田採薪した山神で、面竜のごとく、顔光ありて夜を照らす事昼に似たり、弘法大師に約して長くこの地を守る、大師その顔を写して、当社の竈戸殿に安置すと見ゆ。既に竜顔といえば鱗もあったるべく、秀郷に従うた竜二郎竜八は、この竜頭太に傚《なろ》うて造り出されたものか、一八八三年版、ムラの『柬埔寨王国誌《ル・ロヨーム・ジュ・カンボジュ》』二に、昔仏|阿難《あなん》を従え、一島に至り、トラクオト(両舌ある大蜥蜴《おおとかげ》)の棲める大樹下に、帝釈《たいしゃく》以下天竜八部を聚《あつ》めて説法せし時、余食《くいのこし》をトラクオトに与え、この蜥蜴はわが説法を聴いた功徳により、来世必ず一国の王とならん、しかしその国の人民、皆王の前身舌二枚ある蜥蜴たりし業報《むくい》にかぶれ、いずれも不信実で、二枚舌使う者たるべしといったが、この予言通り、カンボジア人は不正直じゃと出《い》づ。これは竜の子孫に鱗の遺伝どころか、両舌竜の後身に治めらるる国民全体までも、両舌の心性を伝染したのだ。『大摩里支菩薩経』に、〈※[口+縛]酥枳竜口より二舌|出《い》づ、身弦線のごとし〉とあるのは、トラクオトなどより転出した物か、アリゾナのモキス人、カシュミルの竜種人など、竜蛇の子孫という民族所々にある、これらも昔は鱗あるといったのだろう。 | |
| それから『氏郷記』に、心得童子《こころえのどうじ》主人の思う事を叶《かな》えて久しく仕えしが、後に強《きつ》う怒られて失《う》せしとかやとあるは、『近江輿地誌略』に、竜宮から十種の宝を負い出でたる童を如意《にょい》と名づけ、竜次郎の祖先だとあると同人で、如意すなわち主人の意のごとく万事用を達すから心得童子と釈《と》いたのであろう。『今昔物語』に、支那の聖人|宮迦羅《くがら》、使者をして王后を負い来らしめ、犯して妊《はら》ませた話あり。唐の金剛菩提三蔵訳『不動使者陀羅尼秘密法』に、不動使者を念誦《ねんじゅ》して駆使せば、手を洗い楊枝《ようじ》を取るほどの些事より、天に上り山に入るまで、即刻成就せしむ、天女を将《も》ち来らしむるもたちまち得、何ぞいわんや人間界の人や物や飲食をやとあり。『部多大教王経』には、真言で部多《ヴェーターラ》女を招き妹となし、千|由旬《ゆじゅん》内に所要の女人を即刻取り来らしむる法あり。『大宝広博秘密陀羅尼経』には、随心陀羅尼を五万遍誦せば、※[女+綵のつくり]女王后を鈎召し得とあり。『不空羂索陀羅尼経』に、緊羯羅《こんがら》童子を使うて、世間の新聞一切報告せしむる方を載せ、この童子用なき日は、一百金銭を持ち来り、持呪者に与う、しかしその銭は仏法僧のために用《つか》い却《はた》し、決して吝《おし》んじゃいけないとは、例の坊主勝手な言で、果してさようなら、持呪者は只働《ただばたら》きで余り贏利《もうけ》にならぬ、この緊羯羅は瞋面怒目赤黄色狗牙上に出で、舌を吐いて唇を舐め、赤衣を着たという人相書で、これに反し制※[てへん+適]迦《せいたか》は、笑面黄白色の身相、人意を悦ばしむと見ゆ。この者も持呪者のために一切の要物《いるもの》を持ち来り、不快な物を除《の》け去り、宅舎《いえ》を将ち来り掃灑《そうじ》し、毒害も及ぶ能わざらしめるなど至極重宝だが、持呪者食時ごとに、まず飲食をこれに与え、また花香|花鬘《けまん》等を一日欠かさず供えずば、隠れ去って用を為《な》さぬとある。 | |
| 『不動使者陀羅尼秘密法』に、〈不動使者小童子形を作《な》す、両種あり、一は矜禍羅《こんがら》と名づく(すなわち宮迦羅《くがら》)、恭敬小心の者なり、一は制※[咤-宀]迦と名づく、共に語らい難く、悪性の者なり、なお人間悪性の下にありて、駆使を受くといえども、常に過失多きがごときなり〉。『亜喇伯夜譚《アラビヤンナイツ》』に名高いアラジンが晶燈《ランプ》さえ点《とぼ》せば現れた如意使者、グリンムの童話の廃兵が喫烟《きつえん》するごとに出て、王女を執り来った使者鬼など、万事主人の命に随うたが、『今昔物語』の宮迦羅同前、余りに苛酷に使えば怒りて応ぜず、また幾度も非行をし過すに、不同意だったと見える。秀郷の心得童子が、主人の子孫に叱られて消え去ったは、全く主人の所望にことごとく応ぜなんだ故で、矜羯羅《こんがら》よりは制※[咤-宀]迦《せいたか》に近い、かかる如意使者は、欧州の巫蠱《ふこ》(ウィチクラフト)また人類学にいわゆるファミリアール(眷属鬼)の一種で、諸邦眷属鬼については、『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』一九一〇年版、六巻八頁に説明あり。 | |
| 一九一四年版、エントホヴェンの『グジャラット民俗記《フォークロール・ノーツ》』六六頁に、昔インドモヴァイヤの一農、耕すごとに一童男被髪して前に立つを見、ある日その髪を剪《き》り取ると、彼随い来って復さん事を切願すれど与えず、髪を小豆納《あずきいれ》の壺中に蔵《かく》す。爾来彼童僕となって田作す、そのうち主人小豆|蒔《ま》くとて、童をして壺《つぼ》より取り出さしむると、自分の髪を見附け、最《いと》重き小豆一荷持って主人に詣《いた》り、告別し去った、この童はブフット鬼だったという。ブフットすなわち上に引いた部多《ヴェータラ》かと思うが、字書がなき故ちょっと判らぬ、とにかくこれも如意使者の一種、至って働きのない奴《やつ》に相違ない。 これでまず竜宮入り譚の瑣末《さまつ》な諸点を解いたつもりだ。これより進んでこの譚の大体が解るよう、そもそも竜とは何物ぞという疑問を釈こう。 | |
| ■竜とは何ぞ | |
| 昔孔子|老※[耳+(冂<はみ出た横棒二本)]《ろうたん》を見て帰り三日|談《かた》らず、弟子問うて曰く、夫子《ふうし》老※[耳+(冂<はみ出た横棒二本)]を見て何を規《ただ》せしか、孔子曰く、われ今ここにおいて竜を見たり、竜は合《お》うて体を成し散じて章を成す、雲気に乗じて陰陽は養わる、予《われ》口張って※[口+脅]《あ》う能わず、また何ぞ老※[耳+(冂<はみ出た横棒二本)]を規さんや(『荘子』)。『史記』には、〈孔子|去《ゆ》きて弟子にいいて曰く、鳥はわれその能く飛ぶを知り、魚はわれその能く游《およ》ぐを知り、獣はわれその能く走るを知る。走るものは以て罔《あみ》を為すべし、游ぐものは以て綸《いと》を為すべし、飛ぶものは以て※[矢+曾]《いぐるみ》を為すべし。竜に至ってわれ知る能わず、その風雲に乗りて天に上るを。われ今日老子に見《まみ》ゆ、それなお竜のごときか〉とある、孔子ほどの聖人さえ竜を知りがたき物としたんだ。されば史書に、〈太昊《たいこう》景竜の瑞あり、故に竜を以て官に紀す〉、また〈女※[女+咼]《じょか》黒竜を殺し以て冀州《きしゅう》を済《すく》う〉、また〈黄帝は土徳にして黄竜|見《あらわ》る〉、また〈夏は木徳にして、青竜郊に生ず〉など、吉凶とも竜の動静を国務上の大事件として特筆しおり、天子の面を竜顔に比し、非凡の人を臥竜と称えたり。漢高祖や文帝や北魏の宣武など、母が竜に感じて帝王を生んだ話も少なからず。かくまで尊ばれた支那の竜はどんな物かというに、『本草綱目』の記載が、最《いと》要を得たようだから引こう。いわく、〈竜形九似あり、頭駝に似る、角鹿に似る、眼鬼に似る、耳牛に似る、項蛇に似る、腹蜃に似る(蜃は蛇に似て大きく、角ありて竜状のごとく紅鬣、腰以下鱗ことごとく逆生す)、鱗鯉に似る、爪鷹に似る、掌虎に似るなり、背八十一鱗あり、九々の陽数を具え、その声銅盤を戞《う》つがごとし、口旁に鬚髯あり、頷下に明珠あり、喉下に逆鱗あり、頭上に博山あり、尺水と名づく、尺水なければ天に昇る能わず、気を呵して雲を成す、既に能く水と変ず、また能く火と変じ、その竜火湿を得ればすなわち焔《も》ゆ、水を得ればすなわち燔《や》く、人火を以てこれを逐えばすなわち息《や》む、竜は卵生にして思抱す〉(思抱とは卵を生んだ親が、卵ばかり思い詰める力で、卵が隔たった所にありながら孵《かえ》り育つ事だ。インドにもかかる説、『阿毘達磨倶舎論《あびだつまくしゃろん》』に出《い》づ、いわく、〈太海中大衆生あり、岸に登り卵を生み、沙内に埋む、還りて海中に入り、母もし常に卵を思えばすなわち壊《こぼ》たず、もしそれ失念すれば卵すなわち敗亡す〉、これ古人が日熱や地温が自ずから卵を孵すに気付かず、専ら親の念力で暖めると誤解するに因る)、〈雄上風に鳴き、雌下風に鳴く、風に因りて化す〉(親の念力で暖め、さて雄雌の鳴き声が風に伴《つ》れて卵に達すれば孵るのだ、『類函』四三八に、竜を画《えが》く者の方《かた》へ夫婦の者来り、竜画を観《み》た後、竜の雌雄|状《さま》同じからず、雄は鬣《たてがみ》尖り鱗《うろこ》密に上《かみ》壮《ふと》く下《しも》殺《そ》ぐ、雌は鬣円く鱗薄く尾が腹よりも壮《ふと》いといい、画師不服の体を見て、われらすなわち竜だから聢《たしか》に見なさいといって、雌雄の竜に化《な》って去ったと出《い》づ、同書四三七に、斉の盧潜竜鳴を聞いて不吉とし城を移すとあり、予も鰐鳴を幾度も聞いた)、〈その交《つる》むときはすなわち変じて二小蛇と為《な》る、竜の性粗猛にして、美玉|空青《ぐんじょう》を愛《め》づ、喜んで燕肉を嗜む(ローランの『仏国動物俗談《フォーン・ポピュレール・ド・フランス》』巻二、三二二頁に、仏国南部で燕が捷く飛び廻るは竜に食わるるを避けてなりと信ぜらるとある)、鉄および※[くさかんむり/罔]草《もうそう》蜈蚣|楝葉《せんだんのは》五色糸を畏る、故に燕を食うは水を渡るを忌み、雨を祀るには燕を用う、水患を鎮むるには鉄を用う、『説文』に竜春分に天に登り、秋分に淵に入る〉。 | |
| 支那に劣らずインドまた古来竜を神視し、ある意味においてこれを人以上の霊物としたは、諸経の発端|毎《つね》に必ず諸天神とともに、諸竜が仏を守護聴聞する由を記し、仏の大弟子を竜象に比したで知れる。『大方等日蔵経』九に、〈今この世界の諸池水中、各《おのおの》竜王ありて停止《とどま》り守護す、娑伽羅等八竜王のごときは、海中を護り、能く大海をして増減あるなからしむ、阿奴駄致《あぬたっち》等四竜王、地中を守護し、一切の河を出だす、流れ注ぎて竭きることなし、難陀《なんだ》優波難陀《うばなんだ》二竜王、山中を守護するが故に、諸山の叢林鬱茂す云々、毘梨沙《びりしゃ》等、小河水にて守護を為す〉。それから諸薬草や地や火や風や樹や花や果や、一切の工巧《てわざ》や百般の物を護る諸竜の名を挙げおり、『大灌頂神呪経《だいかんじょうしんじゅきょう》』に三十五、『大雲請雨経』に百八十六の竜王を列《なら》べ、『大方等大雲経』には三万八千の竜王仏説法を聴くとあり、『経律異相』四八に、竜に卵生・胎生・湿生・化生の四あり、皆先身|瞋恚《はらたて》心《こころ》曲《まが》り端大《たんだい》ならずして布施を行せしにより今竜と生まる、七宝を宮となし身高四十里、衣の長さ四十里、広さ八十里、重さ二両半、神力を以て百味の飲食《おんじき》を化成すれど、最後の一口変じて蝦蟇《がま》と為《な》る、もし道心を発し仏僧を供養せば、その苦を免れ身を変じて蛇※[兀+虫]《へびとかげ》と為るも、蝦蟇と金翅鳥《こんじちょう》に遭わず、※[#元/黽]※[(口+口)/田/一/黽]《げんだ》魚鼈《ぎょべつ》を食い、洗浴《ゆあみ》衣服もて身を養う、身相触れて陰陽を成す、寿命一劫あるいはそれ以下なり、裟竭《さがら》、難陀等十六竜王のみ金翅鳥に啖われずとある。金翅鳥は竜を常食とする大鳥で、これまた卵胎湿化の四生あり、迦楼羅《かるら》鳥王とて、観音の伴衆《つれしゅ》中に、烏天狗《からすてんぐ》様に画かれた者だ。これは欧州やアジア大陸の高山に住む、独語でラムマーガイエル、インド住英人が金鷲《ゴルズン・イーグル》と呼ぶ鳥から誇大に作り出されたらしい、先身高慢心もて、布施した者この鳥に生まる。 | |
| 『僧護経』にいわく竜も豪《えら》いが、生まるる、死ぬる、婬する、瞋《いか》る、睡《ねむ》る、五時《いつつのとき》に必ず竜身を現じて隠す能わず。また僧護竜宮に至り、四竜に経を教うるに、第一竜は黙って聴受《ききとり》、第二竜は瞑目《ねむりて》口誦《くじゅ》し、第三竜は廻顧《あとみ》て、第四竜は遠在《へだたっ》て聴受《ききとっ》た、怪しんで竜王に向い、この者ら誠に畜生で作法を弁えぬと言うと、竜王そう呵《しか》りなさんな、全く師命《しのいのち》を護らん心掛けだ、第一竜は声に毒あり、第二竜は眼に毒あり、第三竜は気に、第四竜は触《さわ》るに毒あり、いずれも師を殺すを虞《おそ》れて、不作法をあえてしたと語った。また竜の三患というは、竜は諸鱗虫の長で、能く幽に能く明に、能く大に能く小に、変化極まりなし、だが第一に熱風熱沙|毎《いつ》もその身を苦しめ、第二に悪風|暴《にわ》かに起れば身に飾った宝衣全く失わる、第三には上に述べた金翅鳥に逢うと死を免れぬ、それから四事不可思議とは、世間の衆生いずこより生れ来り、死後いずこへ往くか判らぬ、一切世界衆生の業力《ごうりき》に由《よ》りて成り、成っては壊《くず》れ、壊れては成り、始終相続いて断絶せぬ、それから竜が雨を降らすに、口よりも眼鼻耳よりも出さず、ただ竜に大神力ありて、あるいは喜びあるいは怒れば雨を降らす、この四をいうのじゃ(『大明三蔵法数』十一、十八)。 | |
| 『正法念処経』にいわく、瞋痴多行《おこりどおし》の者、大海中に生まれて毒竜となり、共に瞋悩乱心毒を吐いて相害し、常に悪業を行う。竜が住む城の名は戯楽《けらく》、縦横三千|由旬《ゆじゅん》、竜王中に満つ、二種の竜王あり、一は法行といい世界を護る、二は非法行で世間を壊《やぶ》る、その城中なる法行王の住所は熱砂|雨《ふ》らず、非法行竜の住所は常に熱沙|雨《ふ》り、その頂あり、延《ひ》いて宮殿と眷属を焼き、全滅すればまた生じて不断苦しみを受く、法行竜王の住所は七宝の城郭七宝の色光あり、諸池水中衆花具足し、最上の飲食《おんじき》もて常に快楽し、妙衣厳飾|念《おも》うところ随意に皆あり、しかれどもその頂上常に竜蛇の頭あるを免れぬとある。今も竜王の像に、必ず竜が頭から背中へ噛《かじ》り付いたよう造るは、この本文を拠《よりどころ》としたのだろ。さて竜に生まるるは、必ずしも瞋痴《ばかにおこ》った者に限らず、吝嗇《けち》な奴も婬乱な人も生まれるので、吝《けち》な奴が転生した竜は相変らず慳《しわ》く、婬《みだら》なものがなった竜は、依然多淫だ。面倒だが読者が悦ぶだろから、一、二例を挙げよう。 | |
| 『大毘盧遮那加持経《だいびるしゃなかじきょう》』に、人の諸心性を諸動物に比べた中に、広大なる資財を思念するを竜心と名づけた。わが邦で熊鷹根生というがごとし。今日もインドで吝嗇漢《しわんぼう》嗣子なく、死ねば蛇と化《な》って遺財を守るという(エントホヴェン輯『グジャラット民俗記《フォークローアノーツ》』一一九頁)。すべてインドで財を守る蛇はナガ、すなわち載帽蛇《コブラ・デ・カペロ》で、多くの場合に訳経の竜と相通ずる奴だ(後に弁ずるを読まれよ)。『賢愚因縁経』四に、波羅奈国の人苦心して七瓶金を蓄え、土中に埋み碌《ろく》に衣食せず病死せしが、毒蛇となってその瓶を纏《まと》い数万歳を経つ、一朝自ら罪重きを悟り、梵志《ぼんし》に托し金を僧に施して、蛇身を脱《のが》れ天に生まれたとあり。『今昔物語』十四なる無空律師万銭を隠して蛇身を受けた話、また聖武天皇が一夜会いたまえる女に金《こがね》千両賜いしを、女死に臨み遺言して、墓に埋めしめた妄執で、蛇となって苦を受け、金を守る、ところを吉備大臣《きびのおとど》かの霊に逢いて仔細を知り、掘り得た金で追善したので、蛇身から兜率天《とそつてん》へ鞍替《くらがえ》したちゅう話など、かのインド譚から出たよう、芳賀博士の攷証本に見るは尤も千万だ。降って『因果物語』下巻五章に、僧が蛇となって銭を守る事二条あり。『新著聞集《しんちょもんじゅう》』十四篇には、京の富人溝へ飯を捨つるまでも乞食に施さざりし者、死後蛇となって池に住み、蓑《みの》着たように蛭《ひる》に取り付かれ苦しみし話を載す。 | |
| 婬乱者が竜と化《な》った物語は、『毘奈耶雑事』と『戒因縁経』に出で、話の本人を妙光女とも善光女とも訳し居るが、概要はこうだ。室羅伐《スラヴァスチ》城の大長者の妻が姙《はら》んだ日、形貌《かお》非常に光彩《つや》あり、産んだ女児がなかなかの美人で、生まるる日室内明照日光のごとく、したがって嘉声《かせい》城邑《じょうゆう》に遍《あまね》かった。しかるところ相師あり、衆と同じく往き観て諸人に語る、この女後まさに五百男子と歓愛せんと、衆曰くかかる尤物《べっぴん》は五百人に愛さるるも奇とするに足らずと、三七日《さんしちにち》経て長者大歓会を為《な》し、彼女を妙光と名づけた。ようやく成長して容華《すがた》雅麗《みやびやか》に、庠序《ぎょうぎ》超備《すぐれ》、伎楽管絃備わらざるなく、もとより富家故出来得るだけの綺羅を飾らせたから、鮮明遍照天女の来降せるごとく、いかな隠遁仙人離欲の輩も、これを見ればたちまち雲を踏み外す事受け合いなり、いかにいわんや無始時来|煩悩《ぼんのう》を貯え来った年少丈夫、一瞥《いちべつ》してすなわち迷惑せざらんと長口上で讃《ほ》めて居るから、素覿《すてき》無類の美女だったらしい。諸国の大王、太子、大臣等に婚を求めたが、相師の予言を慮《おもんぱか》り、彼ら一向承引せず、ただ彼女を門窓|戸※[片+(戸の旧字+甫)]《こゆう》より窺う者のみ多くなり、何とも防ぎようがないので、長者早く娘を嫁せんとすれど求むる者なし。時に城中に一長者ありて、七度妻を娶《めと》りて皆死んだので、衆人|綽号《あざな》して殺婦と言った。海安寺の唄に「虫も殺さぬあの主様《ぬしさま》を、女殺しと誰言うた」とあるは、女の命を己れに打ち込みおわらしむてふ形容詞だが、今この殺婦は正銘の女殺しの大先生たるを怖れ、素女はもちろん寡婦さえ一人も取り合わぬ。相師の一言のおかげで、かかる美容を持ちながら盛りの花を空《むだ》に過さしむるを残念がって、請わるるままに父が妙光を殺婦に遣った心の中察するに余りあり。 | |
| 殺婦長者既に多くの妻を先立てし罪業を懼《おそ》れ、新妻を娶ると直《す》ぐさま所有《あらゆる》鎖鑰《じょうかぎ》を彼女に附《わた》し、わが家の旧法仏僧に帰依すれば、汝も随時僧に給事して、惰《おこた》るなかれというた。爾来僧を請ずるごとに、妙光が自手給事するその間、美僧あれば思い込んで記《おぼ》え置く。ある日長者外出するとて、わが不在中に僧来らば必ず善く接待せよと言って置き、途上数僧に逢うて、われは所用あって失敬するが、家に妻が居る故必ず食を受けたまえというたので、僧その家に入ると、妙光たちまち地金を露《あら》わし、僧の前にその姿態嬌媚の相を作《な》す。僧輩無事に食い了《おわ》って寺に還り、かかる所へ往かぬが好かろうと相戒めて、明日より一僧も来ない。長者用済み還って妻に問うに、主が出で往った日来た限り、一僧も来らずと答う、長者寺に往って問うに、われら不如法《ふにょほう》の家に入らぬ定めだと対《こた》う。長者今後は必ず如法に請ずべければ何分前通りと切願して、僧輩も聞き入れ、他日来て食を受く、長者すなわち妙光を一室に鎖閉《とじこ》め、自ら食を衆僧に授くるその間、妙光室内でかの僧この僧と、その美貌を臆《おも》い出し、極めて愛染《あいぜん》を生じ、欲火に身の内外を焼かれ、遍体汗流れて死んだ。長者僧を供養しおわり、室を開けて見れば右の始末、やむをえず五色の氈《せん》もてその屍を飾り、葬送して林中に到る。折悪《おりあ》しく五百群賊盗みし来って、ここに営しいたので、送葬人一同逃げ散った。群賊怪しんで捨て去られた屍を開き、妙光女魂既に亡《うせ》たりといえども、容儀儼然活けるがごとく、妍華《けんか》平生に異ならざるを覩《み》、相《あい》いいて曰く、この女かくまで美艶にして、遠く覓《もと》むるも等類なしと、各々|染心《ぜんしん》を生じ、共に非法を行いおわって、礼金として五百金銭を屍の側において去った。天明《よあけ》に及び、四方に噂《うわさ》立ち皆いわく、果して相師の言のごとく、妙光女死すといえども、余骸なお五百人に通じ、五百金銭を獲たと。妙光死して天竺の北なる毘怛吐泉《びたとせん》の竜となり、五百牡竜来って共に常にこれに通じた。世尊諸|比丘《びく》に向いその因縁を説きたまわく、昔|迦葉仏《かしょうぶつ》入滅せるを諸人火葬し、舎利《しゃり》を収め塔を立てた時、居士女《こじのじょ》極めて渇仰して明鏡を塔の相輪中に繋《つな》ぎ、願わくはこの功徳もて後身世々わがある所の室処《へや》光明照耀日光のごとく、身に随《つ》れて出ん事をと念じた。その女の後身が妙光女で、願の趣聞き届けられて、居所室内明照日光のごとくだった。かく赫耀《かがやき》ながら幾度も転生《うまれかわ》る中、梵授王の世に、婆羅尼斯城の婬女に生まれ賢善と名づけ、顔容端正人の見るを楽《よろこ》ぶ。ところで予《かね》て王の舅《しゅうと》と交通した。ある時五百の牧牛人《うしかい》芳園で宴会し、何とよほど面白いが、少女の共に交歓すべきを欠くは残念だ、一人呼んで来るが好《い》い、誰が宜《よか》ろうと言うと、皆賢善女賛成と一決し、呼びに行くと、かの婬女金銭千文くれりゃ行こう、くれずば往かぬというたので、まず五百金銭を与えて歓を得、戯れ済んでまた五百金銭を渡せば如何《いかん》といい、婬女承諾して五百銭を受け、汝ら先往きて待ちおれ、我|※[靜の爭に代えて見]飾《みじまい》して後より行こうという。衆去りて後婬女われかく多勢を相手に戯れては命が続かぬ、何とか脱《のが》れようをと案じて、かつて相《あい》識《し》った王舅に憑《たの》みて救済を乞わんと決心し、婢をして告げしめしは、かくかくの次第で、妾|迂闊《うかつ》の難題を承諾したが、何が何でも五百人は一身で引き受けがたい、さりとて破談にせば倍にして金を返さにゃならず、何とか銭も返さず身をも損ぜぬよう計らいくだされたいと頼むと、平常|悪《にく》からぬ女のこと故、王の力を仮りて女を出さず五百銭をも戻さずに、五百人を巻いてしまわせた。爾時《そのとき》辟支仏《へきしぶつ》あって城下に来りしを、かの五百|牧牛人《うしかい》供養発願して、その善根を以てたとい彼女身死するとも残金五百銭を与えて、約のごとく彼と交通せんと願懸《がんかけ》した。その業力《ごうりき》で以来五百生の内、常に五百金銭を与えて、彼女と非法を行うたと仏が説かれた。これで仏の本説は、人の善《よ》き事は善く、悪《あ》しき事は悪しく、箇々報いが来り、決して差し引き帳消してふ事がないと主張するものと判る。すなわち鏡を捧げた功徳で発願通り飛び切りの別嬪《べっぴん》に生まれるが、他の業報《むくい》で娼妓に生まるるを免れず、娼妓営業中五百人を欺いた報いで、牧牛人輩の発願そのまま、五百金銭を与えて死骸を汚さるるを免れぬは、大功は小罪を消し一善は一悪を滅すと心得た今日普通の業報説と大いに差《ちが》うようで、こんな仏説を呑み込み過ぎると、重悪を犯した者は、小善を治めても及び着かぬてふ自暴気味《やけぎみ》を起すかも知れず、今日の小乗仏教徒に、余り大事業大功徳を企つる者なきは多少この理由にも基づくなるべし。 | |
| アドルフ・エルトンの『世界周遊記《ライセ・ウム・ジェ・エルデ》』(一八三八年版、二巻一三頁)に、シベリアの露人が、新年に試みる指環占の中、竜てふ名号をいう事あるにより、この占法《うらかた》は蒙古より来れりと断じた。これは蒙古はインドと支那の文物を伝え、この二国が竜の崇拝至って盛んだから、竜てふ名号は蒙古を経て、二国よりシベリアに入ったとの推定であろう。予はこの推定を大略首肯するに躊躇せぬ。しかしかかる物を読んで、竜をアジアの一部にのみ流《おこな》われた想像動物と信ずる人あらば、誤解も甚だしく、実は竜に関する信念は、インドや支那とその近傍諸国に限らず、広く他邦他大州にも存したもので、たとえば、ニューギニアのタミ人元服を行う時、その青年必ず一度竜に呑まるるを要し(一九一三年版、フレザー『不死の信念《ゼ・ビリーフ・イン・インモータリチー》』一巻三〇一頁)、西北米のワバナキインジアンに、竜角人頭に著《つ》きて根を下ろし、伐《き》れども離れぬ話広く行われ(『万国亜米利加学者会報《トランサクチョン・ジュ・コングレス・アンターナチョナル・デー・アメリカニスト》』一九〇六年、クェベック版、九二頁)、西人がメキシコを発見せぬ内、土人が作った貴石のモザイク品に、背深緑、腹真紅、怒眼、鋭牙、すこぶる竜に似たものが大英博物館にあったので、予これは歌川派画工が描いた竜を擬《まね》たのだろと言うと、サー・チャーレス・リードが、聢《しっか》り手に執って見よというから、暫《しばら》く審査すると、全く東半球に産せぬ響尾蛇《ラットル・スネーク》の画の外相だけ東洋の竜に酷《よく》似たと判った。しかるにその後、仏人サミュール・ド・シャムプレーンの『一五九九―一六〇二年西印度および墨西哥』(ナラチヴス・オヴ・ア・ヴォエージ・ツー・ゼ・ウェスト・インジース・エンド・メキシコ、一八五九年英訳)を見るに、メキシコの響尾蛇の頭に両羽あり、またその地に竜を産し、鷲の頭、蜥蜴《とかげ》の身、蝙蝠《こうもり》の翹《つばさ》で、ただ二大脚あり。大きさ羊のごとく、姿怖ろしけれど害を為《な》さぬとあった。因ってかの国にも、古来蛇、蜥蜴などを誇張して、竜の属《たぐい》の想像動物を拵《こしら》えあったと知った。濠州メルボルン辺に棲《す》むと伝えた巨蛇《おろち》ミンジは、プンジェル神の命のままに、疱瘡と黒疫《ペスト》もて悪人を殺すに能《よ》く、最《いと》高き樹に登り尾もて懸け下り、身を延ばして大森林を踰《こ》え、どの地をも襲う。また乾分《こぶん》多く、諸方に遣わして疫病を起す。この蛇来る地の人皆取る物も取らず、死人をも葬らず、叢榛《こもり》に放火して、速やかに走り災を脱れた(一八七八年版、スミス『維多利亜生蕃篇《ゼ・アボリジンス・オヴ・ビクトリア》』巻二)といえる事体、蛇よりは欧亜諸邦の毒竜の話に極めて似居る。例せばペルシアの古史賦『シャー・ナメー』に、勇士サムが殺した竜は頭髪《かみ》を地に※[てへん+曳]《ひ》いて山のごとく起り、両の眼|宛然《さながら》血の湖のごとく、一たび※[口+皐の白にかえて自]《ほ》ゆれば大地震動し、口より毒を吐く事洪水に似、飛鳥|竭《つ》き、奔獣尽き、流水より鱷《がく》を吸い、空中より鷲を落し、世間恐怖もて満たされ、一国のために人口の半ばを喪《うしの》うたと吹き立て、衆経撰『雑譬喩《ぞうひゆ》経』に、昔|賈客《こかく》海上で大竜神に逢う、竜神汝は某国に行くかと問うに、往くと答えると、五升|瓶《がめ》の大きさの卵一つを与え、かの国に行かば、これを大木の下に埋めよ、しからざれば殺すぞという。恐ろしくてその通り埋めてより国中疫病多し、王占いてかの蟒卵《ぼうらん》を掘り出し焼き棄てると疫が息《や》んだ。後日かの賈客、再び竜に逢って仔細を語ると、奴輩《やつら》を殺し尽くさぬは残念というから、その故を問う。我|本《もと》かの国の健児某甲だった。平日力を恃《たの》んで国中の人民を凌轢《りょうれき》せしも、一人としてわれを諫むるなく、為《な》すがままに放置《すてお》いたので、死後竜に生まれて苦しみ居る故に、返報に彼らを殺そうとしたのだといった。また、舎衛国に、一日縦横四十里の血の雨ふる。占師曰く、これは人蟒《じんぼう》が生まれた兆だ、国中新生の小児をことごとく送り来さしめ、各々一空壺中に唾《つばは》かしむれば、唾《つばき》が火となる児がそれだというので試みると、果して一児が人蟒と別った、因ってこれを無人処《ひとなきところ》に隔離し、死刑の者を与えると、毒を吐いて殺す事前後七万二千人、ある時獅出で来て吼声四十里に達したので人蟒を遣わすに、毒気を吐いてたちまちこれを仆《たお》した。のち人蟒老いて死せんとする時、仏《ぶつ》、舎利弗《しゃりほつ》して往き勧めて得脱《とくだつ》せしむ。人蟒われいまだ死せざるに、この者われを易《あなど》り、取次もなしに入り来ると瞋《いか》って毒気を吐くを、舎利弗慈恵を以て攘《はら》い、光顔ますます好《よ》く、一毛動かず。人蟒すなわち慈心を生じ、七たび舎利弗を顧みて、往生昇天したとある。竜気を稟《う》けて生まれてだにこんなだ。いわんや竜自身の大毒遥かに人蟒や蟒卵に駕するをやで、例せば、難陀《なんだ》※[烏+おおざと]波難陀《うばなんだ》二竜王、各八万四千の眷属あり、禍業の招くところ、悩嫉心を以て、毎日三時その毒気を吐くに、二百五十|踰膳那《ようじゃな》内の鳥獣皆死し、諸僧静かに度を修する者、皮肉変色|憔悴《やせ》萎《しお》れ黄ばんだので、仏|目蓮《もくれん》をして二竜を調伏せしめた(『根本説一切有部毘奈耶』四四)。 | |
| かく竜てふ物は、東西南北世界中の大部分に古来その話があるから、東洋すなわち和漢インド地方だけの事識れりとて、竜の譚全体を窺うたといわれぬ、英国のウォルター・アリソン・フィリップ氏の竜の説に、すこぶる広く観て要を約しあるから、多少拙註を加えて左に抄訳せり。ついでに述ぶ、前節に相師が妙光女を見て、この女必ず五百人と交わらんといった話を述べたが、一八九四年版ブートン訳『亜喇伯夜譚補遺《サップレメンタリー・ナイツ》』一にも、アラビアで一《ある》女生まれた時、占婦|卜《ぼく》してこの女成人して、必ず婬を五百人に売らんと言いしが中《あた》った事あり、わが邦にも『水鏡』恵美押勝《えみのおしかつ》討たれた記事に「また心|憂《う》き事|侍《はべ》りき、その大臣の娘|座《おわ》しき、色《いろ》容《かたち》愛《めで》たく世に双人《ならぶひと》なかりき、鑑真《がんじん》和尚の、この人千人の男に逢ひ給ふ相|座《おわ》すと宣《のたま》はせしを、たゞ打ちあるほどの人にも座せず、一、二人のほどだにも争《いか》でかと思ひしに、父の大臣討ち取られし日、御方《みかた》の軍《いくさ》千人ことごとくにこの人を犯してき」、いずれも妙光女の仏話から生じたらしいと、明治四十一年六月の『早稲田文学』へ書いて置いた。『呉越春秋』か『越絶書』に、伍子胥《ごししょ》越軍を率いて、その生国なる楚に討ち入り、楚王の宮殿を掠《かす》めた時、旧君たりし楚王の妃妾を強辱して、多年の鬱憤を晴らしたとあった。『将門記《しょうもんき》』に、平貞盛《たいらのさだもり》と源扶《みなもとのたすく》敗軍してその妻妾|将門《まさかど》の兵に凌辱せられ、恥じて歌詠んだと出づ。強犯されて一首を吟《くちずさ》むも、万国無類の風流かも知れぬが、昔は何国《いずく》も軍律|不行届《ふゆきとどき》かくのごとく、国史に載らねど、押勝の娘も、多数兵士に汚された事実があったのを、妙光女の五百人に二倍して、千人に云々と作ったのであろう。 | |
| フィリップ氏曰く、竜の英仏名ドラゴンは、ギリシアにドラコン、ラテンのドラコより出で、ギリシアのドラコマイ(視る)に因《ちな》んで、竜眼の鋭きに取るごとしと。ウェブストルに、竜眼怖ろしきに因った名かとある方、釈《と》き勝《まさ》れりと惟《おも》う。例せば上に引いたペルシアの『シャー・ナメー』に、竜眼を血の湖に比べ、欧州の諸談皆竜眼の恐ろしきを言い、殊に毒竜バシリスクは、蛇や蟾蜍《ひきがえる》が、鶏卵を伏せ孵《かえ》して生ずる所で、眼に大毒あり能く他の生物を睨《にら》み殺す、古人これを猟った唯一の法は、毎人鏡を手にして向えば、彼の眼力鏡に映りて、その身を返り射《い》、やにわに斃死《へいし》せしむるのだったという(ブラウン『俗説弁惑《プセウドドキシア・エピデミカ》』三巻七章、スコッファーン『科学俚俗学拾葉《ストレイ・リープ・オヴ・サイエンス・エンド・フォークロール》』三四二頁以下)。シュミットの『銀河制服史《ゼ・コンクエスト・オヴ・ゼ・リヴァー・プレート》』に、十六世紀に南米に行われた俗信に、鱷《がく》井中にあるを殺す唯一の法は鏡を示すにあり、しかる時彼自分の怖ろしき顔を見て死すとあるは、件《くだん》の説の焼き直しだろ。わが邦にも魔魅《まみ》、蝮蛇《まむし》等と眼を見合せばたちまち気を奪われて死すといい(『塵塚物語』三)、インドにも毒竜視るところことごとく破壊す(『毘奈耶雑事』九)など説かれた。フ氏曰く、竜は仮作動物で、普通に翼ありて火を吐く蜥蜴《とかげ》また蛇の巨大なものと。まずそうだが、東洋の竜が千差万別なるごとく、西洋の竜も記載一定せぬ、中世英国に行われたサー・デゴレの『武者修行賦』から、その一例を引かんに、ここに大悪竜あり、全身あまねく火と毒となり、喉|濶《ひろ》く牙大にしてこの騎士を撃たんと前《すす》む、両足獅のごとく尾不釣合に長く、首尾の間確かに二十二足生え、躯《み》酒樽に似て日に映じて赫耀《かくよう》たり、その眼光りて浄玻璃《じょうはり》かと怪しまれ、鱗硬くして鍮石《しんちゅう》を欺く、また馬様の頸《くび》もと頭を擡《もた》ぐるに大力を出す、口|気《いき》を吹かば火焔を成し、その状《さま》地獄の兇鬼を見るに異ならず(エリス『古英国稗史賦品彙《スペシメンス・オヴ・アーリー・イングリッシュ・メトリカル・ローマンセズ》』二版、三巻三六六頁)、フ氏続けていわく、ギリシア名ドラコンは、もと大蛇の義神誌に載せ、竜は形容種々なれど実は蛇なり。カルデア、アッシリア、フェニキア、エジプト等、大毒蛇ある諸国皆蛇また竜を悪の標識とせり、例せばエジプト教のアポピは闇冥界の大蛇で、日神ラーに制服され、カルデアの女神チャーマットは、国初混沌の世の陰性を表せるが、七頭七尾の大竜たり。ヘブリウの諸典また蛇あるいは竜を死と罪業の本とて、キリスト教の神誌これを沿襲せり。しかるにギリシア、ローマには一方に蛇を兇物として蛇髪女鬼《ゴルゴー》、九頭大蛇《ヒドラ》等、諸怪を産出せる他の一方に、竜種《ドラゴンテス》を眼|利《するど》く地下に住む守護神として崇敬せり。例せば医神アスクレピオスの諸祠の神蛇、デルフィの大蛇、ヘスペリデスの神竜等のごとしと。熊楠バッジ等エジプト学者の書を按ずるに、古エジプト人も古支那と同じく、竜蛇を兇物とばかり見ず善性瑞相ありとした例も多く、神や王者が自分を蛇に比べて、讃頌したのもある。 | |
| さてフ氏またいわく、一汎《いっぱん》に言えば竜の悪名は好誉より多く、欧州では悪名ばかり残れり。キリスト教は古宗教の善悪の諸竜を混同して、一斉にこれを邪物とせり、かくて上世《そのかみ》の伝説外相を変えて、ミカエル尊者、ジョージ尊者等、上帝に祈りて竜を誅した譚となり、以前ローマの大廟《カピトル》に窟居《くっきょ》して大地神女《ボナ・デア》を輔《たす》け人に益した神蛇も、法王シルヴェストル一世のために迹《あと》を絶つに及べり。北欧の大蛇《おろち》も、東方南方の大蛇と性質同じく罪悪の主、隠財の守護にして、人が好物を獲るを遮る。故に中世騎士勇を以て鳴る者竜を殺すをその規模とし、近世と余り隔たらぬ時代まで学者も竜|実《まこと》に世にありと信ぜり。ただし研究追々進みては、竜も身を人多き地に置き得ず、アルプス山中無人の境をその最後の潜処としたりしを、ジャク・バルメーンその妄を弁じてよりついに竜は全く想像で作られたものと判《わか》れり。これより前一五六四年死せるゲスネルの判断力、当時の学者輩に挺特せしも、なおその著『動物全誌』(ヒストリア・アニマリウス)に竜を載せたるにて、その頃竜の実在の信念深かりしを知るべしと。 | |
| フ氏曰く、竜の形状は最初より一定せず、カルジアのチャーマットは躯に鱗ありて四脚両翼を具せるに、エジプトのアポピとギリシア当初の竜は巨蛇《おろち》に過ぎず。『新約全書』末篇に見えた竜は多頭を一身に戴《いただ》き、シグルドが殺せしものは脚あり。欧州でも支那でも、竜の形状は多く現世全滅せる大蜥蜴類の遺骸を観て言い出したは疑いを容《い》れず。支那や日本の竜は、空中を行くといえど翼なしと。 | |
|
熊楠いわく、支那でも、古く黄帝の世に在った応竜は翼あった。また鄒陽《すうよう》の書に、〈蛟竜《こうりょう》首を驤《あ》げ、翼を奮えばすなわち浮雲出流し、雲霧|咸《みな》集まる〉とあれば、漢の世まで、常の竜も往々有翼としたので、『山海経』に、〈泰華山蛇あり肥遺と名づく、六足四翼あり〉など、竜属翼ある記事も若干ある。結局翼なくても飛ぶと讃えてこれを省いたと、蛇や蜥蜴に似ながら飛行自在なる徴《しるし》に翼を添えたと趣は異にして、その意は一なりだ。フ氏の言いぶり古エジプトの竜も、単に大蛇にほかならぬようだが、日神の敵アポピは、時に大蛇、時に鱷《がく》たり(バッジ『埃及諸神譜《ゼ・ゴッズ・オブ・ゼ・エジプシアンス》』一)、その他の大蛇にも、脚や翼を具えたのがある故、蛇よりは竜夥《りょうなかま》のものだ。西洋の竜とても、ローマの帝旗として竜口を銀、他の諸部を彩絹《いろぎぬ》で作り、風を含めば全体|膨《ふく》れて、開《あ》いた口が塞《ふさ》がれなかった、その竜に翼なし。さてローマ帝国のプリニウスの『博物志《ヒストリア・ナチュラリス》』に、竜の事を数章書きあるが、翼ある由を少しも述べず、故にフ氏が思うたほど、東西の竜が無翼有翼を特徴として区別判然たるものでない。また『五雑俎』に、竜より霊なるはなし、人得てこれを豢《か》う。唐訳『花厳経《けごんぎょう》』七八に、〈人あり竜を調《なら》す法を善くす、諸竜中において、易く自在を得〉、西洋にも昔はそうと見えて、プリニウス八巻二十二章に、ギリシア人トアス幼時竜を畜《か》い馴《な》らせしに、その父その長大異常なるを懼《おそ》れ沙漠に棄つ、後トアス賊に掩撃された時、かの竜来り救うたとある。フ氏は、インドの竜について一言もしおらぬが、『大雲請雨経』に、大歩、金髪、馬形等の竜王を列し、『大孔雀呪王経』に、〈諸《もろもろ》の竜王あり地上を行き、あるいは水中にあって依止を作《な》し、あるいはまた常に空裏を行き、あるいはつねに妙高に依って住むあり(妙高は須弥山《しゅみせん》の事)、一首竜王を我慈念す、および二頭を以てまたまた然り、かくのごとく乃至《ないし》多頭あり(『請雨経』には五頭七頭千頭の竜王あり)云々、あるいはまた諸竜足あるなし、二足四足の諸竜王、あるいは多足竜王身あり〉と見れば、梵土でも支那同様竜に髪あり、数頭多足あるもありとしたのだ。二足竜の事、この『呪王経』のほかにも、沈約の『宋書』曰く、〈徐羨之《じょせんし》云々かつて行きて山中を経るに、黒竜長さ丈余を見る、頭角あり、前両足皆具わり、後足なく尾を曳《ひ》きて行《ある》く、後に文帝立ち羨之|竟《つい》に凶を以て終る〉などあれど、東洋の例至って少ない。しかるに西洋では、中古竜を記するに多くは二脚とした。第一図はラクロアの『|中世の科学および文学《サイエンス・エンド・リテラチュール・オヴ・ゼ・ミッドル・エージス》』英訳本に、十四世紀の『世界奇観』てふ写本から転載した竜数種で、第二図は一六〇〇年パリ版、フランシスコ・コルムナのポリフィルスの題号画中の竜と蝮と相討ちの図だが、ことごとく竜を二脚として居る。この相討ちに似た事、一九〇八年版スプールスの『アマゾンおよびアンデス植物採集紀行』二巻一一八頁に、二尺|長《たけ》の鱷が同長の蛇を嚥《の》んだところを、著者が殺し腹を剖《さ》くと、蛇なお活《い》きいたとあるし、十六世紀にベスベキウス、かつて蛇が蝦蟆《がま》を呑み掛けたところを二足ある奇蛇と誤認したと自筆した(『土耳其紀行《トラヴェルス・インツー・ターキー》』一七四四年版、一二〇頁)。マレー人は、鱷の雄は腹の外の皮が障《さわ》る故、陸に上れば後二脚のみで歩むと信ず(エップの説、『印度群島および東亜細亜雑誌《ゼ・ジョーナル・オブ・ゼ・インジアン・アーキペラゴ・エンド・イースターン・アジア》』五巻五号)、過去世のイグアノドン、予がハヴァナの郊外で多く見たロケーなど、蜥蜴類は長尾驢《カンガルー》のごとく、尾と後の二脚のみで跳《は》ね歩き、跂《は》い行くもの少なからず、従《よ》ってスプールスが南米で見た古土人の彫画《ほりえ》に、四脚の蜥蜴イグアナを二脚に作《し》たもあった由。 「第1図 14世紀写本の竜画」のキャプション付きの図 「第2図 1600年版 竜と蝮の咬み合い」のキャプション付きの図 |
|
| また『蒹葭堂雑録』に、わが邦で獲た二足の蛇の図を出せるも、全くの嘘《うそ》蛇《じゃ》ないらしい。ワラス等が言った通り、鱷や諸蜥蜴が事に臨んで、前二脚のみで走り、またいっそ四脚皆用いず、腹と尾に力を入れて驀《まっしぐ》らに急進するが一番|迅《はや》い故、専らその方を用いた結果、短い足が萎靡《いび》してますます短くなる代りに、躯が蛇また蚯蚓《みみず》のごとく長くなり、カリフォルニアとメキシコの産キロテス属など、短き前脚のみ存し、支那、ビルマ、米国等の硝子蛇《グラス・スネーク》や、濠州地方のピゴプス・リアリス等諸属は前脚なくて、後脚わずかに両《ふたつ》の小刺《こはり》、また両《ふたつ》の小鰭《こひれ》となって痕跡を止め、英仏等の盲虫《ブラインド・オルム》、アジアやアフリカの両頭蛇《アムフィスパイナ》は、全く足なく眼もちょっと分らぬ。『類函』四四八に、〈黄州に小蛇あり、首尾|相《あい》類《たぐ》う、因って両頭蛇という、余これを視てその尾端けだし首に類して非なり、土人いわくこの蛇すなわち老蚯蚓の化けしところ、その大きさ大蚓を過ぎず、行は蛇に類せず、宛転《えんてん》甚だ鈍し、またこれを山蚓という〉。『燕石雑志』に、日向の大|蚯蚓《みみず》空中を飛び行くとあるは、これを擬倣したのか。とにかく蜥蜴が地中に棲んで蚯蚓《みみず》様に堕落したのだが、諸色|交《こもご》も横条を成し、すこぶる奇麗なもある。『文字集略』に、※[虫+璃のつくり]《ち》は竜の角なく赤白蒼色なるなりと言った。※[虫+璃のつくり]わが邦でアマリョウと呼び、絞紋《しぼりもん》などに多かる竜を骨抜きにしたように軟弱な怖ろしいところは微塵《みじん》もない物は、かかる身長く脚と眼衰え、退化した蜥蜴諸種から作り出されたものと惟う。したがって上述の諸例から推すと、西洋で専ら竜を二足としたのも、実拠なきにあらず、かつ竜既に翼ある上は鳥類と見立て、四足よりも二足を正当としたらしい。支那で応竜を四足に画いた例を多く見たが、邦俗これを画くに、燕を背から見た風にし、一足をも現わさぬは、燕同様短き二足のみありという意だろう。 | |
| 一三三〇年頃仏国の旅行僧ジョルダヌス筆、『東方驚奇編《ミラビリア・デスクリプタ》』にいわく、エチオピアに竜多く、頭に紅玉《カルブンクルス》を戴《いただ》き、金沙中に棲み、非常の大きさに成長し、口から烟状の毒臭気を吐く、定期に相集まり翼を生じ空を飛ぶ。上帝その禍を予防せんため、竜の身を極めて重くし居る故、みな楽土より流れ出る一《ある》河に陥《お》ちて死す、近処の人その死を覗《うかが》い、七十日の後その尸《しかばね》の頭頂《いただき》に根生《ねざし》た紅玉を採って国の帝に献《たてまつ》ると。十六世紀のレオ・アフリカヌス筆、『亜非利加記《アフリカイ・デスクリプチオ》』にいう、アトランテ山の窟中に、巨竜多く前身太く尾部細く体重ければ動作労苦す、頭に大毒あり、これに触れまた咬まれた人その肉たちまち脆《もろ》くなりて死すと。すべて鱷《がく》や大蛇諸種の蜥蜴など、飽食後や蟄伏中に至って動作遅緩なるより、竜身至って重してふ説も生じたであろう。インド、セイロン、ビルマ等の産、瓔珞蛇《ダボヤ》は長《たけ》五尺に達する美麗な大毒蛇だが、時に街中《まちなか》車馬馳走の間に睡りて毫《ごう》も動かず、いささかも触るれば、急に起きて人畜を傷つけ殺す(サンゼルマノ『緬甸帝国誌《ゼ・バーミース・エンパイヤー》』二十一章)。仏|竹園《ちくおん》で説法せし時、長老比丘衆中を仏の方向き、脚を舒《の》べて睡るに反し、修摩那比丘はわずかに八歳ながら、端坐しいた。仏言う、説法の場で眠る奴は死後竜に生まれる。修摩那は一週間|経《た》ったら四神足を得べしと(『長阿含経《じょうあごんぎょう》』二十二)。また給孤独園《ぎっこどくおん》で新たに出家した比丘が、坐禅中睡って房中に満つる大きさの竜と現われた、他の比丘これを見て声を立てると、竜眼を覚ましまた比丘となりて坐禅する。仏これを聞いて竜の性睡り多し、睡る時必ず本形を現わすものだと言いて、竜比丘を召し、説法して竜宮へ還し、以後竜の出家を許さなんだ(『僧護経』)。『類函』四三八に、王趙|方《かた》へ一僧来り食を乞い、食|訖《おわ》って仮寝《うたたね》する鼾声夥しきを訝《いぶか》り、王出て見れば竜睡りいた。寤《さ》めてまた僧となり、袈裟一枚大の地を求むるので承知すると、袈裟を舒《の》ばせば格別大きくなる。かくて広い地面を得て、大工を招き大きな家を立てると、陥って池となり、竜その中に住む。御礼に接骨方《ほねつぎのほう》を王氏に伝え、今も成都で雨乞いに必ず王氏の子孫をして池に行き乞わしむれば、きっと雨ふるとある。これは、『阿育《アソカ》王伝』の摩田提《マジアンチカ》尊者が大竜より、自分一人坐るべき地を乞い得て、その身を国中に満たして※[よんがしら/(厂+(炎+りっとう))]賓国《けいひんこく》を乗っ取った話(『民俗』二年一報、予の「話俗随筆」に類話多く出《い》づ)、また柳田君の『山島民譚集』に蒐《あつ》めた、河童《かっぱ》が接骨方を伝えた諸説の原話らしい、『幽明録』の河伯女《かはくのむすめ》が夫とせし人に薬方三巻を授けた話などを取り雑《ま》ぜた作と見ゆ。とにかくかようの譚は、瓔珞蛇《ダボヤ》など好んで睡る爬虫に基づいたであろう。熱帯地で極暑やや寒き地で、冬中|鱷《がく》は蟄伏する(フムボルト『回帰線内墨州紀行《トラヴェルス・ツー・エクエノクチカル・アメリカ》』英訳十九章)。シュワインフルトの『亜非利加の心臓《イム・ハーツュン・フォン・アフリカ》』十四章に、無雨季節には鱷いかな小溜水にも潜み居ると言い、パーキンスの『亜比西尼住記《ライフ・イン・アビッシニヤ》』二十三章に、鱷その住むべき水より、遠距離なる井の中に住んで毎度羊を啖《くら》いしが、最後に水汲みに来た少女を捉《と》り懸りて露《あら》われ殺された由見ゆ。支那書に見ゆる蟄竜や竜、井の中に見《あら》われた譚は、こんな事実を大層に伝えたなるべし。それからトザーの『土耳其高地の研究《レサーチス・イン・ゼ・ハイランズ・オヴ・ターキー》』巻二に、近世リチュアニア、セルビア、ギリシア等で、竜《ドラコン》は竜の実なく一種の巨人《おおびと》采薪《たきぎとり》狩猟《かり》を事とし、人肉を食うものとなり居るも、比隣《となり》のワラキア人はやはり翼と利《とき》爪《つめ》あり、焔と疫気を吐く動物としおる由を言い、件《くだん》の竜《ドラコン》てふ巨人に係る昔話を載す。ラザルスてふ靴工、蜜を嘗《な》めるところへ蠅集まるを一打ちに四十疋殺し、刀を作って一撃殺四十と銘し、武者修業に出で泉の側に睡る。その辺に棲める竜かの刀銘を読んで仰天し、ラ寤《さ》むるを俟《ま》ちて請いて兄弟分と為《な》る、竜|夥《なかま》の習い、毎日順番に一人ずつ、木を伐り水汲みに往く、やがてラが水汲みに当ると、竜の用うる桶一つが五十ガロン入り故、空《から》ながら持ち行くに困苦を極む、いわんや水を満たしては持ち帰るべき見込みなし、因って一計を案じ、泉の周囲を掘り廻る。余り時が立つので、見に来ると右の次第故何をするかと問う、ラ答うらく、毎日一桶ずつ運ぶのは面倒だからこの泉を全《まる》で持って帰ろうとするところだ、竜いわく、それを俟つ間に吾輩渇死となる、汝を煩わさずに吾輩ばかり毎日運ぶ事としよう。次にラが木伐《ききり》の当番となり、林中に往き、縄で所有《あらゆる》樹を絆《つな》ぎ居る、また見に来て問うに対《こた》えて、一本二本は厄介故、皆持って往こうと言うと、その間に竜輩凍死すべければ、以後汝を休ませ、吾輩毎日運ぶべしと言った。誠に厭《いや》なものを兄弟分にしたと迷惑の余り竜輩評議して、ラが睡るに乗じ斧で切り殺すに決した。ラこれを窃《ぬす》み聞き、その夜|木槐《きくれ》に自分の衣を著《き》せ臥内《ねや》に入れ、身を隠し居るとは知らぬ竜輩来て、木が屑になるまで※[石+欠]《き》り砕いて去った。ラ還って木を捨てその跡へ臥す。鼾が高いので、竜輩怪しみ何事ぞと問うに、今夜痛く蚋《ぶと》に螫《さ》されたと対う。あんなに強《したた》か斧で※[石+欠]ったのを蚋が螫したとは、到底手に竟《おえ》ぬ奴だ、何とかして立ち退《の》かそうと考え、翌旦《あくるあさ》ラに、汝も妻子をちと訪ねやるがよい、大金入りの袋一つ上げるからと言うと、汝らのうち一人その袋を担《かた》げて随《つ》いて来るなら往こうと言う。因って竜一人|従《とも》してラの宅に近づくと、暫く待っておれ、我は先入って子供が汝を食わぬよう縛り付けて来るとて宅に入り太縄で子供を括《くく》り、今竜が見え次第大声でその竜肉を啖《く》いたいと連呼《よびつづ》けよと耳語《ささや》いて出で、竜を呼び込むと右の通りで竜大いに周章《あわ》て、袋を落し逃れた。途上狐に会って子細を話すと、痴《たわ》けた事を言いなさんな、ラザルスごとき頓知奇《とんちき》の忰《せがれ》が何で怖かろう、われらなどはあの家に二羽ある鶏を、昨夜一羽平らげ、只今また一羽|頂戴《ちょうだい》に罷《まか》り出るところだ、嘘と想うなら随《つ》いて来なせえといって、竜を自分の尾に括り付けてラの宅に近づく、ラこれを見て狐に向い、われ汝に竜を残らず伴《つ》れて来いと言ったに、一つしか伴れて来ぬかと呼ばわる。竜さては狐と共謀して、吾輩《われら》を食うつもりと合点し、急ぎ奔《はし》ると、※[てへん+曳]《ひ》きずられた狐は途上の石で微塵《みじん》に砕けた。ラは最早《もはや》竜来る患《うれい》なければ、安心してかの袋の中の金で巨屋を立て、余生を安楽に暮したそうだ。竜をかかる愚鈍なものとしたのは、主として上述の川に落ちて死ぬほど、身重く動作緩慢なりなどいう方面から起っただろう。 | |
| 一二一一年頃ジャーヴェ筆『皇上消閑録《オチア・インペリアーナ》』を見ると、その頃既に仏国でも、竜は詰まらぬ河童様の怪魅と為《な》りおり、専ら水中に住み、人に化けて市へ出るが別に害をなさず、婦女童児水浴びるを覗い、金環金盃に化けて浮くを採りに懸るところを引き入れて自分の妻に侍せしむとあり。また男を取り殺した例も出でおる。わが国に古くミヅチなる水の怪《ばけもの》あり。『延喜式』下総《しもうさ》の相馬《そうま》郡に蛟※[虫+罔]《みづち》神社、加賀に野蛟《のづち》神社二座あり。本居宣長はツチは尊称だと言ったは、水の主《ぬし》くらいに解いたのだろ、また柳田氏は槌《つち》を霊物とする俗ありとて、槌の意に取ったが、予は大蛇をオロチ、巨蟒をヤマカガチと読むなどを参考し、『和名抄』や『書紀』に、蛟《こう》や※[虫+礼のつくり]《きゅう》いずれも竜蛇の属の名の字をミヅチと訓《よ》んだから、ミヅチは水蛇《みずへび》、野蛟《のづち》は野蛇《のへび》の霊異なるを崇《あが》めたものと思う。今も和泉、大和、熊野に野槌と呼ぶのは、尾なく太短い蛇だ(『東京人類学会雑誌』二九一号の拙文を見よ)。その蛟《みづち》が仏国の竜《ドラク》同様変遷したものか今日河童を加賀、能登でミヅチ、南部でメドチ、蝦夷《えぞ》でミンツチと呼ぶ由、また越後《えちご》で河童|瓢箪《ひょうたん》を忌むという(『山島民譚集』八二頁)。『書紀』十一に、武蔵人と吉備中国《きびのなかつくに》の人が、河伯《かわのかみ》また大※[虫+礼のつくり]《みづち》に瓠《ひさご》を沈めよと註文せしに沈め得ず、由ってその偽神なるを知り、また斬り殺した二条の話あるを見ると、竜類は瓢を沈め能わぬ故、忌むとしたのだ。日本に限らぬと見えて、『西域記』にも凌山氷雪中の竜瓢を忌むとある。ビール言う、瓢に容れた水凍りて瓢を裂く音大なるを忌むのだとは迂遠に過ぎる。それらまさかこの禁忌の源《もと》であるまいが、一九〇六年版ワーナーの『英領中央亜非利加土人篇《ゼ・ネチブス・オブ・ブリチシュ・セントラル・アフリカ》』に、シレ河辺鱷害殊に多い処々で、婦女水を汲みに川に下りず、高岸上より長棒の端に付いた瓢箪で汲むから、その難に逢わぬとは、竜や鱷に取りて瓢は重々不倶戴天の仇と見える。 | |
| フィリップ氏また竜が守護神たり怖ろしい物たるより、古く武装に用いられた次第を序し、ホメロスの詩に見えたアガメムノンの盾に三頭《みつがしら》の竜を画き、ローマや英国で元帥旗に竜を用いたり、ノールス人が竜頭の船に乗った事などを述べ居るが、今長く抄するをやめ、一、二氏の言わぬところを補わんに、古エジプト人は、ウレウス蛇が有益なるを神とし、日神ラーはこの蛇二頭を、他の多くの神や諸王は一頭を前額《ひたい》に戴《いただ》くとした(バッジ『埃及諸神譜《ゼ・ゴッズ・オヴ・ゼ・エジプチアンス》』二、三七七頁)。仏教の弁財天や諸神王竜王が額や頭に竜蛇を戴く、わが邦の竜頭《たつがしら》の兜《かぶと》はこれらから出たものか。支那にも『類函』二二八に、竜を盾に画く、〈また桓元《かんげん》竜頭に角を置く、あるいは曰くこれ亢竜《こうりゅう》角というものなり〉。盾や喇叭《らっぱ》を竜頭で飾ったのだから、兜を同じく飾った事もあるべきだが、平日調べ置かなんだから、喇叭も吹き得ぬ、いわんや法螺《ほら》においてをやだ。 | |
| ただしエリスの『古英国稗史賦品彙《スペシメンス・オヴ・アーリー・イングリッシュ・メトリカル・ローマンセス》』二版一巻六二頁に、古ブリトン王アーサーの父アサー陣中で竜ごとき尾ある彗星を見、術士より自分が王たるべき瑞兆と聞き、二の金竜を造らせ、一をウィンチェスターの伽藍に納め、今一を毎《つね》に軍中に携えた。爾来竜頭アサーと呼ばれた。これ英国で竜を皇旗とする始まりで、先皇エドワード七世が竜を皇太子の徽章《しるし》と定めた。さてアサー、ロンドンに諸侯を会した宴席で、コーンウォール公ゴーロアの美妻イゲルナに忍ぶれど色に出にけりどころでなく、衆人の眼前で、しきりに艶辞を蒔《ま》いたを不快で、かの夫妻退いて各一城に籠《こも》り、王これを攻むれど落ちず。術士メルリン城よりもまず女を落すべく王に教え、王ゴーロアの偽装で入城してイゲルナを欺き会いて、その夜アーサー孕《はら》まる。次いでゴーロア戦死し、王ついにイゲルナを娶《めと》り、これもほどなく戦死、アーサー嗣《つ》ぎ立て武名を轟かせしが、父に倣《なろ》うてか毎《つね》に竜を雕《ほ》った金の兜を着けたとあれば、英国でも竜を兜に飾った例は、五、六世紀の頃既にあったのだ。 | |
|
フィリップ氏またキリスト教法で竜を罪悪の標識、天魔の印相とする風今に変らざる由を述べていわく、中世|異端《ヘレシー》を竜に比し、シギスモンド帝はジョン・フッスの邪説敗れた祝いに、伏竜てふ位階を新設した。また中世地獄を画くに、口を開き火を吐く竜とした。悪魔を標識せる竜の像を祭会《まつり》の行列に引き歩く事も盛んで、ルアンのガーグイユ竜などもっとも高名だ。かかる竜の像は追々その本旨を忘れ、古ギリシアの善性竜王《ドラコンテス》同様、土地の守護神ごときものに還原され了《しま》ったとは、わが邦諸社の祭礼に練り出す八岐大蛇《やまたのおろち》が本《もと》人間の兇敵と記憶されず、災疫を禳《はら》い除くと信ぜらるるに同じ。また天文に竜宿《ドラコ》なるは、その形蛇に似たから名づけたらしいが、ギリシアの神誌にヘラクレスに殺されて竜天に上りてこの星群となったというと。熊楠いわく、インドでも〈柳宿は蛇に属す、形蛇のごとし、室宿は蛇頭天に属す、また竜王身光り憂流迦《うるか》といい、ここには天狗と言う〉。日本で天火、英国で火竜《ファイアドレーク》と言い、大きな隕石《いんせき》が飛び吼《ほ》えるのだ。その他支那で亢宿《こうしゅく》を亢金竜と呼ぶなど、星を竜蛇と見立てたが多い。それから『聖書《バイブル》』にヨハネが千年後天魔獄を破り出て、世界四隅の民を惑わすと言ったを誤解して、紀元一千年が近くなった時全欧の民大騒ぎせし事、明治十四年頃世界の終焉《おわり》が迫り来たとて、わが邦までも子婦《よめ》を取り戻したり、身代を飲み尽くした者あったに異ならず。その時欧州に基督敵《アンチ・クリスト》現出して世界を惑乱させ、天下|荒寥《あれすさ》むといい、どこにもここにも基督敵産まれたといって騒いだ。その法敵も多く竜の性質形体を帯びた物だった(『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』巻三)。第三図は、この法敵とキリストと闘うところだ。またそれに次いで大流行だった如安《ジャン》法王の伝というは、九世紀に若僧と掛落《かけおち》した男装の女が大学者となって、ついにレオ四世に嗣《つ》いで、ローマ法王となり、全く男と化けて世を欺きいた内、従僕の子を姙みし天罰で、あろう事か街の上に産み落したその場で死に、その子は世界終る時|出《い》づべき法敵として魔が取り去ったそうだ。この女は死して地獄に落ちるので地獄を竜の口としある(ベーリング・グールド『中世志怪』)。基督敵《アンチ・クリスト》同前の説が仏教にもありとはお釈迦様でも気が付くまい。すなわち『大法炬陀羅尼経』に、悪世にこの世界|所有《あらゆる》悪竜大いに猛威を振い、毒蛇遍満して毒火を吐き人畜を螫《さ》し殺し、悪人悪馬邪道を行い悪行を専らにすと説かれた。 「第3図 1493年版アンチ・クリストの世の図」のキャプション付きの図 |
|
| ■竜の起原と発達 | |
| 一八七六年版ゴルトチッヘルの『希伯拉鬼神誌《デル・ミスト・バイ・デン・ヘブレアーン》』に、『聖書』にいわゆる竜は雲雨暴風を蛇とし、畏敬《いけい》せしより起ると解いた。アラビア人マスージー等の書に見る海蛇(『聖書』の竜《タンニン》と同根)は、その記載旋風が海水を捲《ま》き上ぐる顕象たる事明白で、それをわが国でも竜巻といい、八雲立《やくもたつ》の立つ同様下から立ち上るから竜をタツと訓《よ》み、すなわち旋風や竜巻を竜といったと誰かから聞いた。支那やインドで竜王を拝して雨を乞うたは主《おも》にこれに因ったので、それより衍《ひ》いて諸般の天象を竜の所為《しわざ》としたのは、例せば『武江年表』に、元文二年四月二十五日|外山《とやま》の辺より竜出て、馬場下より早稲田町通りを巻き、人家等損ずとあるは、明らかに旋風で、『新著聞集』十八篇高知で大竜家を破ったとか、『甲子夜話』三十四江戸大風中竜を見たなど、いずれも竜巻を虚張《こちょう》したのだ。『夜話』十一に、深夜烈風中竜の炯眼《ひかるめ》を見たとは、かかる時電気で発する閃光だろう。『熊野権現宝殿造功日記』新宮に竜落ちて焼けたとあるは前述天火なるべく、『今昔物語』二十四雷電中竜の金色の手を見て気絶した譚は、その人臆病抜群で、鋭い電光を見誤ったに相違ない。『論衡《ろんこう》』に雷が樹を打ち折るを漢代の俗天が竜を取るといったと見え、『法顕伝』に毒竜雪を起す、慈覚大師『入唐求法記』に、竜闘って雹《ひょう》を降らす、『歴代皇紀』に、伝教《でんぎょう》入唐出立の際暴風大雨し諸人悲しんだから、自分所持の舎利を竜衆に施すとたちまち息《や》んだと出づ。ベシシ人は竜を有角大蛇とし、地竜海竜と戦い敗死し天に昇りて火と現ずるが虹なりと信ず(スキートおよびブラグデン『巫来半島異教民族篇《ペーガン・レーセス・オヴ・ゼ・マレー・ペニンシュラ》』二)。東京《トンキン》人は月蝕を竜の所為《しわざ》とす(一八一九年リヨン版『布教書簡集《レットル・エジフィアント》』九巻一三〇頁)。かく種々の天象を竜とし竜と号《な》づけた後考うると、誠に竜はこれらの天象を蛇とし畏敬せしより起ったようだが、何故《なぜ》雲雨暴風等を特に蛇に比したかと問われて、蛇は蚯蚓《みみず》、鰻等より多く、雲雨等に似居る故と言うたばかりでは正答とならぬ。すなわちどの民も、最《いと》古く蛇を霊怪至極のものとし、したがって雲雨暴風竜巻や、ある星宿までも、蛇や竜とするに及んだと言わねばならぬ。『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』十一版二十四巻に、スタンレイ・アーサー・クック氏が蛇崇拝を論じて、この問題は樹木崇拝の起原発達を論ずると等しく、一項ごとに人間思想史の諸問題を併せ解くを要し、事極めて複雑難渋だと述べ居る。それに竜となると角があったり火を吐いたり、異類異様に振る舞うから、その解決は蛇より数層むつかしく、孔子のいわゆる竜に至っては知るなきなりだ。加之《そのうえ》拙者本来八岐大蛇の転生《うまれがわり》で、とかく四、五升呑まぬと好い考えが付かぬが、妻がかれこれ言うから珍しく禁酒中で、どうせ満足な竜の起原論は成るまいが、材料は夥《おお》くある故、出来るだけ遣って見よう。 | |
| まずクック氏は、蛇類は建築物や著しき廃址に寓し、池《いけ》壁《かべ》樹《き》の周囲《ぐるり》を這《は》い、不思議に地下へ消え去るので、鳥獣と別段に気味悪く人の注意を惹《ひ》いた。その滑り行く態《さま》河の曲れるに似、その尾を噛《か》むの状大河が世界を環《めぐ》れるごとく、辛抱強く物を見詰め守り、餌たるべき動物を魅入《みい》れて動かざらしめ、ある種は飼い馴《な》らしやすく、ある種は大毒ありて人畜を即死せしめ、ある物を襲うに電と迅さを争うなど、夙《つと》に太古の人を感ぜしめたは必定なれば、蛇類を馴らし弄《もてあそ》んだ人が衆を驚かし、敬われたるも怪しむに足らず。あるいは蛇の命長く、定時に皮を脱ぎかえるを見て、霊魂不死と復活を信ずるに及んだ民もあるべしと述べて、竜の諸譚は蛇を畏敬するより起ったように竜と蛇を混同してその崇拝の様子や種別を詳説されたが、竜と蛇の差別や、どんな順序で蛇てふ観念が、竜てふ想像に変じたか、一言もしおらぬ。 | |
| 上に述べた通り、古エジプトや西アジアや古欧州の竜は、あるいは無足の大蛇、あるいは四足二翼のものだったが、中世より二足二翼のもの多く、また希《ま》れに無足有角のものもある。インドの那伽《ナーガ》を古来支那で竜と訳したが、インドの古伝に、那伽は人面蛇尾で帽蛇《コブラ》を戴き、荘厳尽くせる地下の竜宮《バタラ》に住み、和修吉《ヴァスキ》を諸那伽の王とす。これは仏経に多頭竜王と訳したもので、梵天の孫|迦葉波《カーシャバ》の子という。日本はこの頃ようやく輸入されたようだが、セイロン、ビルマ等、小乗仏教国に釈迦像の後に帽蛇が喉を膨《ふく》らして立ったのが極めて多い。『四分律蔵《しぶりつぞう》』に、仏|文※[馬+鄰のへん]《ぶんりん》水辺で七日坐禅した時、絶えず大風雨あり、〈文※[馬+鄰のへん]竜王自らその宮を出で、身を以て仏を繞《めぐ》る、仏の上を蔭《おお》いて仏に白《もう》して言わく、寒からず熱からずや、飄日のために暴《さら》されず、蚊虻のために触※[女+堯]せらるるところとならずや〉、風雨やんでかの竜一年少|梵志《ぼんし》に化し、仏を拝し法に帰した、これ畜生が仏法に入った首《はじめ》だと見ゆ。 | |
|
帽蛇《コブラ》(第四図)は誰も知るごとく南アジアからインド洋島に広く産する蛇で、身長六フィート周囲六インチに達し、牙に大毒あるもむやみに人を噛まず、頭に近き肚骨《あばらぼね》特に長く、餌を瞰《ねら》いまた笛声を聴く時、それを拡げると喉が団扇《うちわ》のように脹《ふく》れ、惣身《そうみ》の三分一を竪《た》てて嘯《うそぶ》く、その状極めて畏敬すべきところからインド人古来これを神とし、今も卑民のほかこれを殺さず。卑民これを殺さば必ず礼を以て火葬し、そのやむをえざるに出でしを陳謝《いいわけ》す。一八九六年版、クルックの『北印度俗間宗教および民俗誌《ゼ・ポピュラル・レリジョン・エンド・フォークロール・オブ・ノルザーン・インジア》』二巻一二二頁に拠《よ》れば、その頃西北諸州のみに、那伽《ナーガ》すなわち帽蛇崇拝徒二万五千人もあった。昔アリア種がインドに攻め入った時、那伽種この辺に栄え、帽蛇を族霊《トテム》としてその子孫と称しいた。すなわち竜種と漢訳された民族で、ついにアリア人に服して劣等部落となった。件《くだん》の畜生中第一に仏法に帰依した竜王とは、この竜種の酋長を指《さ》したであろう。俗伝にはかの時|仏《ぶつ》竜王が己れを蓋《おお》いくれたを懌《よろこ》び、礼に何を遣ろうかと問うと、われら竜族は常に金翅鳥《こんじちょう》に食わるるから、以後食われぬようにと答え、仏すなわち彼の背に印を付けたので、今に帽蛇にその印紋ある奴は、鳥類に食われぬという。かく那伽はもと帽蛇の事なるに、仏教入った頃の支那人は帽蛇の何物たるを解せず、その霊異《ふしぎ》にして多人に崇拝さるる宛然《さながら》支那の竜同然なるより、他の蛇輩と別たんとて、これを竜と訳したらしい。ただしインドにおいても那伽を霊異とするより、追々蛇以外の動物の事相をも附け加え、上に引いた『大孔雀呪王経』に言わるる通り、二足四足多足等支那等の竜に近いものを生じたが、今に至るまで本統の那伽は依然帽蛇で通って居る。支那に至っては、上古より竜蛇の区別まずは最も劃然《かくぜん》たり。後世日本同様異常の蛇を竜とせる記事多きも、それは古伝の竜らしき物実在せぬよりの牽強《こじつけ》だ。
「第4図 帽蛇」のキャプション付きの図 |
|
| 全体竜と蛇がどう差《ちが》うかといわんに、『本草綱目』に、今日の動物学にいわゆる爬虫類から亀の一群を除き、残った諸群の足あるものを竜、足なきを蛇とし居る。アリストテレスが爬虫を有鱗卵生四足(亀と蜥蜴)、卵生無足(蛇)、無鱗卵生四足(蛙の群)に別ったに比して、亀と蛙を除外しただけ分類法が劣って居るが、欧州でも近世まで学者中に獣鳥魚のほか一切の動物を虫と呼び通した例すらあれば、それに比べて『綱目』の竜蛇を魚虫より別立し、足の有無に拠って竜類すなわち蜥蜴群と蛇群を分けたは大出来で、その後本邦の『訓蒙図彙』等に竜は鱗虫の長とて魚類に、蛇は字が虫篇|故《ゆえ》蝶蠅などと一つに虫類に入れたは不明の極だ。さて支那にも僧など暇多い故か、観察の精《くわ》しい人もあって、後唐の可止てふ僧托鉢して老母を養い行《ある》きながら、青竜疏《せいりょうそ》を誦する事|三載《みとせ》、たちまち巨蟒《うわばみ》あって房に見《あらわ》る。同院の僧居暁は博物《ものしり》なり、曰く蛇の眼は瞬《またた》かぬにこの蟒《うわばみ》の眼は動くから竜だろうと、止香を焚《た》いて蟒に向い、貧道《それがし》青竜疏を念ずるに、道楽でなく全く母に旨《うま》い物を食わせたい故だ、竜神|何卒《なにとぞ》好《よ》き檀越《だんおつ》に一度逢わせてくださいと頼むと、数日後果して貴人より召され、夥しく供養されたという(『宋高僧伝』七)。拙者も至って孝心深く、かつ無類の大食なれば、可止法師に大いに同感を寄するが、それよりも感心なは居暁の博物《ものしり》で、壁虎《やもり》の眼が瞬《またた》かぬなど少々の例外あれど、今日の科学|精覈《せいかく》なるを以てしても、一汎《いっぱん》に蛇の眼は瞬かず、蜥蜴群の眼が動くとは、動かし得ざる定論じゃ。それを西人に先だって知りいたかの僧はなかなか豪《えら》いと南方先生に讃《ほ》めてもらうは、俗吏の申請で正六位や従五位を贈らるるよりは千倍悦んで地下に瞑するじゃろう。ただし、生きた竜の眼を実験とは容易にならぬこと故、これを要するに、例外は多少ありながら、竜蛇の主として別るる点は翼や角を第二とし、第一に足の有無にある。『想山著聞奇集』五に、蚯蚓《みみず》が蜈蚣《むかで》になったと載せ、『和漢三才図会』に、蛇海に入って石距《てながだこ》に化すとあり、播州でスクチてふ魚|海豹《あざらし》に化すというなど変な説だが、蛆《うじ》が蠅、蛹《さなぎ》が蛾《が》となるなどより推して、無足の物がやや相似た有足の物に化ける事、蝌蚪《かえるご》が足を得て蛙となる同然と心得違うたのだ。これらと同様の誤見から、無足の蛇が有足の竜に化し得、また蛇を竜の子と心得た例少なからぬ。南アフリカの蜥蜴蛇《アウロフィス》など、前にも言った通り蜥蜴の足弱小に身ほとんど蛇ほど長きものを見ては誰しも蛇が蜥蜴になるものと思うだろ。『蒹葭堂雑録』の二足蛇のほか本邦にかかる蜥蜴あるを聞かぬが、これらは主に土中に棲んで脚の用が少ないから萎減《いげん》し行く退化中のもので、アフリカに限らず諸州にあり。実際と反対に蛇が竜に変ずるてふ誤信を大いに翼《たす》け、また虫様の下等竜すなわち※[虫+璃のつくり]竜《あまりょう》てふ想像動物の基となっただろう。※[虫+璃のつくり]竜は支那人のみならずインド人も実在を信じたらしい(『起世因本経』七、『大乗金剛|髻珠《けつじゅ》菩薩修行分経』)。『本草綱目』にいう、〈蜥蜴一名石竜子、また山竜子、山石間に生ず、能く雹《ひょう》を吐き雨を祈るべし、故に竜子の名を得る、陰陽折易の義あり、易字は象形、『周易』の名けだしこれに取るか、形蛇に似四足あり、足を去ればすなわちこれ蛇形なりと〉、『十誦律』に、〈仏舎衛国にあり、爾時《そのとき》竜子仏法を信楽す、来りて祇※[さんずい+亘]《ぎおん》に入る、聴法のため故なり、比丘あり、縄を以て咽に繋ぎ、無人処に棄つ、時に竜子母に向かいて啼泣す〉、母大いに瞋《いか》り仏に告ぐ、仏言う今より蛇を※[罘の不に代えて絹のつくり]《あみ》する者は突吉羅罪《ときらざい》とす、器に盛り遠く無人処に著《お》くべしと。いずれも蛇を竜の幼稚なものとしたので、出雲|佐田社《さだのやしろ》へ十月初卯日ごとに竜宮から竜子を献《たてまつ》るというも、実は海蛇だ。『折焚柴記《おりたくしばのき》』に見えた霊山《りょうぜん》の蛇など、蛇が竜となって天上した談は極めて多い(蛇が竜に化するまでの年数の事、ハクストハウセンの『トランスカウカシア』に出《い》づ)。 | |
| 故にフィリップやクックが竜は蛇ばかりから生じたように説いたは大分粗漏ありて、実は諸国に多く実在する蜥蜴群が蛇に似て足あるなり、これを蛇より出て蛇に優《まさ》れる者とし、あるいは蜥蜴や鱷《がく》が蛇同様霊異な事多きより蛇とは別にこれを崇拝したから、竜てふ想像物を生じた例も多く、それが後に蛇崇拝と混合してますます竜譚が多くまた複雑になったであろう。『古今図書集成』辺裔典二十五巻に、明の守徐兢高麗に使した途上、定海県総持院で顕仁助順淵聖広徳王てふ法成寺《ほうじょうじ》関白流の名の竜王を七昼夜祭ると、神物出現して蜥蜴のごとし、実に東海竜君なりと出《い》づ。画の竜と違い蜥蜴のようだとあれば、何か一種の蜥蜴を蓄《こ》うて竜とし祠《まつ》りいたのだ。『類函』四三七、〈『戎幕間談《じゅうばくかんだん》』曰く、茅山《ぼうざん》竜池中、その竜蜥蜴のごとくにして五色なり、昔より厳かに奉ず、貞観《じょうがん》中竜子を敷取し以て観《み》る、御製歌もて送帰す、黄冠の徒競いてその神に詫《わ》ぶ、李徳裕その世を惑わすを恐れ、かつて捕えてこれを脯《ほ》す、竜またついに神たる能わざるなり〉、これは美麗な大|蠑※[虫+原]《いもり》を竜と崇めたのだ。本邦には蜥蜴や蠑※[虫+原]の属数少なく余り目に立つものもないので、格別霊怪な談も聞かぬが、外国殊に熱地その類多い処では蛇に負けぬほどこれに関する迷信口碑が多い。欧州でも、露国の民はキリスト教に化する前、家ごと一隅に蛇を飼い、日々食を与えたが(一六五八年版ツヴェ『莫士科坤輿誌《コスモグラフィー・モスコヴィト》』八六頁)、そのサモギチア地方民は十六世紀にもギヴォイテてふ蜥蜴を家神とし食を供えた(英訳ハーバースタイン『露国記《ノーツ・アッポン・ラッシア》』二巻九九頁)。 | |
| 『抱朴子』に、〈蜥蜴をいいて神竜と為《な》すは、但《ただ》神竜を識《し》らざるのみならず、また蜥蜴を識らざるなり〉、晋代蜥蜴を神竜とし尊んだ者ありしを知るべし。『漢書』に漢武|守宮《やもり》を盆で匿し、東方朔《とうぼうさく》に射《あ》てしめると、竜にしては角なく蛇にしては足あり、守宮か蜥蜴だろうと中《あ》てたので、帛《きぬ》十疋を賜うたとある。蜥蜴を竜に似て角なきものと見立てたのだ。上に引いた通り、『周易』の易の字は蜴《とかげ》の象形といったほど故、古支那で蜥蜴を竜属として尊んだのだ。蜥蜴は墓地などに多く、動作迅速でたちまち陰顕する故、サンタル人は、睡中人の魂|出行《である》くに、蜥蜴と現ずと信ず(フレザー『金椏篇《ゴルズン・バウ》』初版一巻一二六頁)。『西湖志』に、銭武粛王の宮中夜番を勤むる老嫗が、一夜大蜥蜴燈の油を吸い竭《つ》くしたちまち消失するを見、異《あやし》んで語らずにいると、明日王曰く、われ昨夜夢に魔油を飽くまで飲んだと、嫗見しところを王に語るに王|微《すこ》しく哂《わら》うのみとあれば、支那にも同様の説があったのだ(『類函』四四九)。後インドではトッケとてわが邦の蜥蜴に名が似て、カメレオンごとく能《よ》く変色する蜥蜴、もと帝釈の宮門を守ったと伝う(ロウ氏の説、一八五〇年刊『印度群島および東亜細亜雑誌』四巻二〇三頁)。 | |
| 濠州のジェイエリエ人伝うらく、大神ムーラムーラ創世に多く小さき黒蜥蜴を作り、諸《もろもろ》の※[虫+支]行《はう》動物の長とす。次にその足を分ちて指を作り、次に鼻それより眼口耳を作り、さて立たしむるに尾が妨げとなるから切り去ると蜥蜴立ちて行き得、かくて人類が出来たと(スミス『維克多利生蕃篇《ゼ・アボリジンス・オヴ・ヴィクトリア》』二、四二五頁)。古エジプト人は、蜥蜴を神物とし、その尸をマンミーにして保存奉祀した。西アフリカのウォロフ人は、蜥蜴を家神として日々牛乳を供え、マダガスカル人もこれを守護神とした(『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』巻二、九、二八)。近世ギリシアでは、ストイキア神夜家や野などに現ずる時、あるいは蛇あるいは蜥蜴あるいは小さき黒人たり(ライト『中世論集《エッセイス・オン・ゼ・ミドル・エージス》』一巻二八六頁)。蜥蜴の最も尊ばれたは太平洋諸島で、ポリネシア人これを神とし、人間の祖とし、斎忌の標識は専ら蜥蜴と鮫だ(ワイツおよびゲルランド『未開民史《ゲシヒテ・デル・ナチュルフォルケル》』巻六)。フィジー島では、地震神の使物を大蜥蜴とし、マオリ人は蜥蜴神マコチチ、人を頭痛せしむと信ず。ニューヘブリデスの伝説に、造物主初め人を四脚で、豚を直立して行《ある》かしめた。諸鳥と爬虫類これを不快で集会す。その時一番に蜥蜴、人と豚の行きぶりを変ずべしというと、鶺鴒《せきれい》は元のままで好いと主張した。蜥蜴直ちに群集を押し潜《くぐ》り、椰樹《やしのき》に登って豚の背に躍び下りると、豚前脚を地に著《つ》けた、それより豚が四脚、人は直立して行《ある》く事になったという(ラツェル『人類史《ゼ・ヒストリー・オヴ・マンカインド》』英訳、一)。メラネシア人は、蜥蜴家に入れば死人の魂が帰ったという(一九一三年版フレザー『不死の信念《ゼ・ビリーフ・イン・インモータリチー》』一巻三八〇頁)。アフリカのズールー人言う、太初大老神ウンクルンクル※[虫+堰のつくり]蜒《カメレオン》を人間に遣わし、人死せざれと告げしめしに、このもの怠慢《なまけ》て途上の樹に昇り睡る。神また考え直して蜥蜴を人間に遣《や》り人死すべしと告げしむると、直ぐ往ってそう言って去った跡へ※[虫+堰のつくり]蜒やっと来て人死せざれと言ったが間に合わず、先に蜥蜴から人死すべしと聞いたから、人間皆死ぬ事となった。それからズールー人が思い思いになって、あるいは蜥蜴が迅く走って、死ぬといって来たと恨んで見当り次第これを殺し、あるいは※[虫+堰のつくり]蜒が怠慢《なまけ》て早く好報を齎《もたら》さざりしを憤って、烟草《タバコ》を食わせ、身を諸色に変じ、悩死するを見て快と称う。南洋ヴァトム島人話すは、ト・コノコノミャンゲなる者、二少年に火を取り来らば死せじ、しからずば汝ら魂は死せず、身は死すべしと言いしに取り来らず。因って汝ら必ず死すべし。イグアナとヴァラヌス(いずれも蜥蜴の類)と蛇は時々皮|蛻《ぬ》ぎ、不死《しせじ》と罵ったので、人間永く死を免れずと。フレザーかようの話を夥しく述べた後、諸方に蛇と蜥蜴が時々皮を蛻《ぬぎかえ》るを以て毎度若返るとし、昔この二物と人と死なぬよう競争して人敗し、必ず死ぬに定まったと信ずるが普通なりと結論したが、これも蛇や蜥蜴それから竜が崇拝さるる一理由らしい。 | |
|
右の話にあるヴァラヌスは、アフリカから濠州まで産する大蜥蜴で、まず三十種ある、第五図はナイル河に住み、水を游《およ》ぐため尾が横|扁《ひらた》い。鱷《がく》の卵を貪《むさぼ》り食うから土人に愛重さる。この一属は他の蜥蜴と異なり、舌が極めて長い。線条《いとすじ》二つに分れたるを揺り出す状《さま》蛇と同じ。故に支那でこれを蛇属としたらしく、〈鱗蛇また巨蟒、安南雲南諸処にあり、※[虫+冉]蛇《うわばみ》の類にして四足あるものなり、春冬山に居し、夏秋水に居す、能く人を傷つく、土人殺してこれを食う、胆を取りて疾を治し甚だこれを貴重す〉という(『本草綱目』)。学名ヴァラヌス・サルヴァトル、北インドや支那から北濠州まで産し、長《たけ》七フィートに達しこの属の最大者だ。前に述べたカンボジア初王の前身大蜥蜴だった故、国民今に重舌《にまいじた》を遣《つか》うとあるはこの物だろう。セイロンではカバラゴヤと呼び、今もその膏《あぶら》を皮膚病に用い、また蒟醤葉《きんまのは》に少し傅《つ》けて人に噛ませ毒殺す。『翻訳名義集』に徳叉迦竜王《とくしゃかりょうおう》を現毒また多舌と訳しあるは、鱗蛇に相違なく、毒竜の信念は主にこの蜥蜴より出たのだろう。
「第5図 エジプトの大蜥蜴ヴァラヌス・ニロチクス」のキャプション付きの図 |
|
| 仏在世、一種姓竜肉を食い、諸比丘またこれを食うあり、竜女仏の牀前《しょうぜん》に到りて泣く、因って仏竜の血骨筋髄一切食うを禁じ、身外皮膚病あらば竜の骨灰を塗るを聴《ゆる》すとあるも、この蜥蜴であろう。また倶梨迦羅竜王《くりからりゅうおう》支那で黒竜と訳し、不動明王の剣を纏《まと》い居る。これも梵名クリカラサで一種の蜥蜴だ。このほか仏経の諸竜の名を調べたら諸種の蜥蜴を意味せるが多かろうが、平生飲む方に忙しき故、手を着けなんだ。それから今の学者が飛竜《ドラゴ》と呼び、インドのマドラスや後インドに二十種ばかり産する蜥蜴ありて、長《たけ》十インチ以内で脇骨が長くて皮膜を被り、伸縮あたかも扇様で清水《きよみず》の舞台から傘さして飛び下りるごとく、高い処から斜に飛び下りること甚だ巧《うま》い。全く無害のものだが、われらごとき大飲家は再従兄弟《ふたいとこ》までも飲みはしないかと疑わるるごとく、蜥蜴群に毒物と言わるるものが多いからこれも憂《うき》には洩《も》れぬわが身なりけりで、十六世紀に航海大家マゼランと一所に殺されたバルボサの航海記に、マラバル辺の山に樹から樹へ飛ぶ翼ある蛇あり、大毒ありて近づくものを殺すとあるは、覿切《てっきり》この物の訛伝だ(一五八八年版ラムシオ『航海旅行記全集《ナヴィガショニ・エ・ヴィアッジ》』一巻三〇〇葉)。マレー半島のオーラン・ラウト人信ずらく、造物主|人魂《たましい》を石に封じ、大盲飛竜して守らしむ。その乾児《こぶん》がかの地に普通の飛竜で毎《いつ》も天に飛び往き、大盲飛竜より人魂を受けて新産の児輩《こども》に納《い》れる。故に一疋でも飛竜を殺さば、犯人子を産んでも魂を納れてくれぬとてこれを殺さず。またこの飛竜能く身を鱷に変じ、大盲飛竜の命令次第人を水に溺らせ殺すという(スキートおよびブラグデン、二巻二七頁)。支那の応竜始め諸方の翼ある竜の話は、過去世のプテロダクチルスなど有翼蜥蜴の譚を伝え、化石を見て生じたという人もあれど、予はこの現存する飛竜てふ蜥蜴に基づいたものと惟《おも》う。インドで蜥蜴を見て占う事多く、タミル語の諺に「全村の吉凶を予告する蜥蜴が汁鍋に堕《お》ちた」というは、まずはわが「陰陽師身の上知らず」に似て居る(一八九八年『ベンガル亜細亜協会雑誌』六八巻三部一号五一頁)。カンド人は、誓言に蜥蜴の皮を援《ひ》いて証とす(バルフォール『印度事彙《ゼ・サイクロベジア・オヴ・インジア》』三版二巻七三〇頁)。いずれも以前蜥蜴を崇拝した遺風であろう(紀州日高郡|丹生《にゅう》川で、百年ばかり昔淋しい川を蜥蜴二匹上下に続いて游《およ》ぎ遊ぶを見、怖れて逃げ帰りしを今に神異と伝え居る)。それから前文中しばしば言った通り、今一つ竜なる想像動物の根本たりしは鱷で、これは従前蜥蜴群の一区としたが、研究の結果今は蜥蜴より高等な爬虫の一群と学者は見る。現在する鱷群が六属十七種あって、東西半球の熱地と亜熱地に生ず。インドに三種、支那の南部と揚子江に各一種あり、古エジプトや今のインドで鱷を神とし崇拝するは誰も知るところで、以前は人牲を供えた。近時も西アフリカのボンニ地方や、セレベス、ブトン、ルソン諸島民は専ら鱷を神とし、音楽しながらその棲《すみか》に行き餌と烟草を献《たてまつ》った。セレベスとブトンでは、これを家に飼って崇敬した。アフリカの黒人も鱷家近く棲むを吉兆として懼れず(シュルツェ著『フェチシスムス』五章六段)。バンカ島のマレー人は鱷の夢を吉とし婦人に洩らさず(エップ説)。マダガスカルの一部には鱷を古酋長の化身とし、セネガル河辺では鱷物を取れば祝宴を開く(シュルツェ同上)。フィリッピンのタガロ人は鱷に殺された者、雷死刃死の輩と同じく虹の宮殿に住むとした(コムベス著『ミンダナオおよびヨロ史』一八九七年マドリッド版六四頁)。ソロモン諸島人は鱷が餌を捉うるに巧智極まる故、人のほかに魂あるは鱷のみと信ず(一九一〇年版ブラウン著『メラネシアンスおよびポリネシアンス』二〇九頁)。下《ラワル》ニゲリア人は鱷は犯罪ある者にあらずんば食わずとてこれをその祖先神または河湖神とし、殺さばその住《とど》まる水|涸《か》ると信じ、また鱷その身にかつて※[口+敢]《くろ》うた人の魂を蔵《かく》すという(レオナード『下《ラワル》ニゲル|およびその諸民族《エンド・イツ・トライブス》』)。ボルネオには虎と鱷を尊び、各その後胤《こういん》と称し、これを盾に画く者あり(ラツェル『人類史《ヒストリー・オヴ・マンカインド》』)。 | |
| これらの諸伝説迷信はいずれも多少竜にも附存す。レオ・アフリカヌスがナイル河の鱷、カイロ府より上に住むは人を殺し、下に住むは人を捉《と》らずといえるも、竜に善性と兇悪あるてふに似たり。昔ルソンで偽って誓文した者※[#「魚+王の中の空白部に口が四つ」、第3水準1-94-55]に食わるとし(一八九〇年版アントニオ・デ・モルガ『菲列賓諸島誌《スセソス・デ・ラス・イスラス・フィリピナス》』二七三頁)、一六八三年版マリア法師の『東方遊記《イル・ヴィアジオ・オリエンタリ》』四一五頁にいう、マラバルの証真寺に池あり、多く鱷を養い人肉を与う。これを証真寺というは、疑獄の真偽を糾《ただ》さんため本人を池に投ずるに、その言真なれば鱷これを免《ゆる》し偽なれば必ず※[口+敢]う。偽言の輩僧に賄賂して呪《まじない》もて鱷を制し己《おのれ》を※[口+敢]《く》わざらしむと。『南史』にも、今の後インドにあった扶南国で鱷を城溝に養い、罪人あらば与うるに、三日まで食わねば無罪として放免すと見ゆ。デンネットの『フィオート民俗記』に、コンゴ河辺に鱷に化けて船を覆《かえ》し、乗客を執《とら》え売り飛ばす人ありといえるは、目蓮等が神通で竜に化した仏説に似たり。鱷の梵名種々ありて数種皆各名を別にするらしいが、予は詳しく知らぬ。その内クムビラてふはヒンズ語でクムヒル、英語でガリアル、またガヴィアルとて現存鱷群中最も大きく、身長二十五フィートに達し、ガンジス、インダス河より北インドの諸大河に棲み、喙《くちばし》細長く尾の鼻端大いに膨れ起り、最も漢画の竜に似たり。 | |
| マルコ・ポロの紀行に、宋帝占うて百の眼ある敵将にあらずんば、宋を亡ぼし得ずと知ったところ、元将|伯顔《バヤン》の名が、百眼と同音で、宋を亡ぼしたとある。これは確か『輟耕録』にも見えいた。ここをユール注して、近世も似た事あり、インドの讖語《しんご》にバートプールの砦は大鱷にあらざれば陥れ能わずと言うた。さて砦が英軍に取られて梵志がはて面妖なと考えると、英軍の主将名はコムベルメールで、これに近いヒンズ詞《ことば》クムヒル・メールは鱷君の意だから讖語が中《あた》ったと恐れ入ったと書いた。そのクムヒルの原語クムビラの音訳が薬師の十二神将の宮毘羅《くびら》、仏の大弟子の金毘羅比丘《こんぴらびく》、讃岐に鎮座して賽銭を多く占《せしめ》る金毘羅大権現等で、仏典には多く蛟竜と訳し居る。 | |
| 支那で古く蛟と呼んだは『呂覧』に、※[にんべん+次]飛《しひ》宝剣を得て江を渉る時二蛟その船を夾《はさ》み繞《めぐ》ったので、飛江に入って蛟を刺し殺す。『博物志』に孔子の弟子|澹台滅明《たんだいめつめい》璧《たま》を持って河を渡る時、河伯その璧を欲し二蛟をして船を夾ましむ。滅明左に璧右に剣を操って蛟を撃ち殺し、さてこんな目腐り璧はくれてやろうと三度投げ込んだ。河伯も気の毒かつその短気に恐縮し三度まで投げ帰したので、一旦《いったん》見切った物を取り納むるような男じゃねーぞと滅明滅多無性に力《りき》み散らし、璧を毀《こわ》して去ったと出づ。その頃右|体《てい》の法螺談《ほらばなし》大流行と見え、『呉越春秋』には椒丘※[言+斤]《しょうきゅうきん》淮津《わいしん》を渡って津吏の止むるを聴かず、馬に津水を飲ます。津水の神果して馬を取ったので、※[言+斤]|袒裼《たんせき》剣を持って水に入り、連日神と決戦して眇《すがめ》となり勝負付かず、呉に之《ゆ》きて友人を訪《たず》ねるとちょうど死んだところで、その葬喪の席で神と闘って勝負|預《あず》かりの一件を自慢し語ったとは無鉄砲な男だ。その席に要離《ようり》なる者あって、勇士とは日と戦うに表《かげ》を移さず、神鬼と戦うに踵《きびす》を旋《めぐ》らさずと聞くに、汝は神に馬を取られ、また片目にまでされて高名らしく吹聴《ふいちょう》とは片腹痛いと笑うたので、※[言+斤]大いに怒り、その宅へ押し寄ると、要離平気で門を閉じず、放髪|僵臥《きょうが》懼《おそ》るるところなく、更に※[言+斤]を諭《さと》したのでその大勇に心服したとある。その後曹操が十歳で※[言+焦]水《しょうすい》に浴して蛟を撃ち退け、後人が大蛇に逢うて奔るを見て、われ蛟に撃たれて懼れざるに彼は蛇を見て畏ると笑うた。また晋の周処|少《わか》い時乱暴で、義興水中の蛟と山中の虎と併せて三横と称せらるるを恥じ、まず虎を殺し次に蛟を撃った。あるいは浮かびあるいは沈み数千里行くを、処三日三夜|随《つ》れ行き殺して出で、自ら行いを改めて忠行もて顕《あらわ》れたという。 | |
| これらいずれも大河に住んでよほど大きな爬虫らしいから鱷の事であろう。支那の鱷は只今アリガトル・シネンシスとクロコジルス・ポロススと二種知れいるが、地方により、多少の変種もあるべく、また古《いにしえ》ありて今絶えたもあろう。それを※[(口+口)/田/一/黽]竜《だりょう》、蛟竜また鱷と別ちて名づけたを、追々種数も減少して今は古ほどしばしば見ずなり、したがって本来奇怪だった竜や蛟の話がますます誇大かつ混雑に及んだなるべし。いわんや仏経入りてより、帽蛇《コブラ》や鱗蛇を竜とするインド説も混入したから、竜王竜宮その他種々数え切れぬほど竜譚が多くなったと知る。 | |
| ■竜の起原と発達(続き) | |
| 上に引いたフィリップ氏の言葉通り、今の世界に絶迹《ぜっせき》たる過去世期の諸爬虫の遺骸化石が竜てふ[#「てふ」に「〔という〕」の注記]想念を大いに助長したは疑いを容《い》れず。『類函』四三七に〈『拾遺記』に曰く、方丈の山東に竜場あり、竜皮骨あり、山阜《さんぷ》のごとし、百|頃《けい》に散ず、その蛻骨の時に遇えば生竜のごとし、あるいはいわく竜常にこの処に闘う、膏血《こうけつ》流水のごとしと。『述異記』に曰く、普寧県に竜葬の洲《す》あり、父老いう竜この洲において蛻骨す、その水今なお竜骨多し、按ずるに山阜|岡岫《こうしゅう》、竜雲雨を興すもの皆竜骨あり、あるいは深くあるいは浅く多く土中にあり、歯角脊足|宛然《さながら》皆具う、大なるは数十丈、あるいは十丈に盈《み》つ、小さきはわずかに一、二尺、あるいは三、四寸、体皆具わる、かつて因って采《と》り取《あつ》めこれを見る、また曰く冀州|鵠山《こくさん》に伝う、竜千年すなわち山中において蛻骨す、今竜岡あり、岡中竜脳を出す〉。件《くだん》の竜葬洲は今日古巨獣の化石多く出す南濠州の泥湖様の処で、竜が雲雨を興す所皆竜骨ありとは、偉大の化石動物多き地を毎度風雨で洗い落して夥しく化石を露出するを竜が骨を蛻《ぬぎか》え風雨を起して去ると信じたので、原因と結果を転倒した誤解じゃ、『拾遺記』や『述異記』は法螺《ほら》ばかりの書と心得た人多いが、この記事などは実話たる事疑いなし、わが邦にも『雲根志《うんこんし》』に宝暦六年美濃巨勢村の山雨のために大崩れし、方一丈ばかりな竜の首半ば開いた口へ五、六人も入り得べきが現われ、枝ある角二つ生え歯黒く光り大きさ飯器のごとし、近村の百姓怖れて近づかず耕作する者なし、翌々年一、二ヶ村言い合せ斧鍬など携えて恐る恐る往き見れば石なり、因って打ち砕く、その歯二枚を見るに石にして実に歯なり、その地を掘れば巨大なる骨様の白石多く出《い》づと三宅某の直話《じきわ》を載せ居る、古来支那で竜骨というもの爬虫類に限らず、もとより化石学の素養もなき者が犀象その他偉大な遺骨をすべてかく呼ぶので(バルフォール『印度事彙』一巻九七八頁)、讃岐小豆島の竜骨は牛属の骨化石と聞いた。つい前月も宜昌附近にかかる化石が顕われて、天が袁皇帝に竜瑞を降したと吹聴された、山本亡羊の『百品考』に引いた『荒政輯要』には月令に〈季夏漁師に命じて蛟を伐つ、鄭氏いわく蛟を伐つと言うはその兵衛あるを以てなり〉とあるを解くとて、蛟は雉と蛇と交わり産んでその卵大きさ輪のごときが埋まりある上に、冬雪積まず夏苗長ぜず鳥雀|巣《すく》わず、星夜|視《み》れば黒気天に上る、蛟|孵《かえ》る時|蝉《せみ》また酔人のごとき声し雷声を聞きて天に上る、いわゆる山鳴は蛟鳴で蛟出づれば地崩れ水害起るとてこれを防ぐ法種々述べおり、月令に毎夏兵を以て蛟を囲み伐つ由あるは周の頃土地開けず文武周公の御手もと近く鱷《がく》が人畜を害う事しきりだったので、漢代すでにかかる定例の鱷狩りはなくなった故|鄭《てい》氏が注釈を加えたのだ。それより後は鱷ますます少なくなって蛟とは専ら地下の爬虫孵り出る時地崩れ水|湧《わ》き出るを指《さ》す名となったので、その原由は鱷が蟄居より出で来るよりも主として雷雨の際土崩れ水出で異様の骨骸化石を露わすにあっただろう、『和漢三才図会』四七、〈およそ地震にあらずして山岳|暴《にわか》に崩れ裂くるものあり、相伝えていわく宝螺跳り出でて然《しか》るなり〉。『東海道名所記』三、遠州今切の渡し昔は山続きの陸地なりしが百余年ばかり前に山中より螺貝《ほらがい》夥しく抜け出で海へ躍《と》び入り、跡|殊《こと》のほか崩れて荒井の浜より一つに海になりたる事、唐土の華山より大亀出でし跡池となり田畠に灌《そそ》ぎしごとしと載す、予の現住地紀州田辺近き堅田浦《かただのうら》に古《いにしえ》陥れると覚ぼしき洞窟の天井なきような谷穴多く(方言ホラ)小螺の化石多し、土伝に昔ノーヅツ(上述|野槌《のづち》か)ここに棲み長《たけ》五、六尺太さ面桶《めんつう》ほどで、頭と体と直角を成して槌のごとく、急に落ち下りて人々を咬《か》んだといい今も恐れて入らず、これ支那の蛟の原由同然かかる動物の化石出でしを訛伝したらしい、小螺化石多く出るから小螺躍び出て地を崩したというはずのところノーヅツなる奇形化石に令名をしてやられて今もその谷穴をノーヅツと称う。ただし『類函』二六、〈福建の将楽県に蛟窟あり、相伝う昔小児あり渓傍の巨螺を見て拾い帰り、地に穴し瀦水《ちょすい》してこれを蓄え、いまだ日を竟《お》えざるにその地横に潰《つい》え水勢|洶々《きょうきょう》たり、民懼れ鉄を以てこれに投じはじめて息《や》む、今周廻|寛《ひろ》さ畝《ほ》ばかりなるべし、水|清※[轍の車に代えてさんずい]《せいてつ》にして涸れず〉とあれば、支那でも地陥《じすべ》りと蛟と螺を相関わるものとしたのでその訳を一法螺吹こう。インド人サラグラマを尊んで韋紐《ヴィシュニュ》の化身とし蛇また前陰の相とす、これは漢名石蛇で、実は烏賊《いか》や航魚《たこぶね》とともに頭足軟体動物《ケファロポタ》たるアンモナイツの多種の化石で、科学上法螺と大分違うが外相はやはり螺類だ、その状蛇や蛟が巻いた像に似居る故これを蛇や蛟の化身と見て地陥りは蛇や蛟の化身たる螺の所為と信じたものか、サラグラマは仏典に螺石と訳し(『毘奈耶破僧事』十一)一の珍宝としあり、鶴岡八幡宮神宝の弁財天蛇然の自然石なるを錦の袋に入れて内陣にあり(『新編鎌倉志』一)というもこれか。近時化石学上の発見甚だ多きに伴《つ》れて過去世に地上に住んだ大爬虫遺骸の発見夥しく竜談の根本と見るべきものすこぶる多い。しかし今とても竜の画のような動物は前述鱗蛇、鱷飛竜などのほかにも世界に乏しからぬ。したがって亡友カービー氏等が主張した、過去世に人間の遠祖が当身《そのみ》巨大怪異の爬虫輩の強梁跋扈《きょうりょうばっこ》に逢った事実を幾千代後の今に語り伝えて茫乎《ぼうこ》影のごとく吾人の記憶に存するものが竜であるという説のみでは受け取れず、予はかかる仏家の宿命通説のような曖昧な論よりは、竜は今日も多少実在する鱷等の虚張《こちょう》談に、蛇崇拝の余波や竜巻地陥り等諸天象地妖に対する恐怖や、過去世動物の化石の誤察等を堆《つ》み重ねて発達した想像動物なりというを正しと惟《おも》う。 | |
|
竜譚の発達に最も力を添えたは海蛇譚で、海蛇の事は予在外中数度『ネーチュル』その他でその起原を論戦したが、事すこぶる煩わしいからここには略して竜譚に関する分だけを述べよう。『玉葉』四十に寿永三年正月元日伊勢怪異の由を源義仲の注進せる内に、元日の夜大風雨雷鳴|真虫《まむし》蛇打ち寄せられ津々に藻に纏われてあるいは二、三石あるいは四、五石(石は百か)皆生きあり、両三日を経て紛失しおえぬ、およそ昔も今も真虫海より打ち上げらるる事は伊勢国に候《そうら》わず、件《くだん》の蛇海より来り寄す云々と見ゆ。これすなわち海蛇で鰻様に横|扁《ひらた》き尾を具え海中に限って住むがインド洋太平洋とその近海に限る、およそ五十種あり(第六図)。知人英学士会員ブーランゼー方で見たはインド洋産七、八フィートあった、熊野で時々取るを予自ら飼い試みるにブーランゼー始め西人の説に誤謬多し、そのうち一論を出し吹き飛ばしてくれよう。『唐大和尚東征伝』や蘭人リンスコテンの『東印度紀行《ヴォヤージュ・エス・アンドリアンタル》』(一六三八年アムステルダム版、一二二頁)を見ると、昔はアジアの南海諸処に鑑真のいわゆる蛇海すなわち海蛇夥しく群れ居る所があったらしい、『アラビヤ夜譚』のブルキア漂流記に海島竜女王|住処《すみか》を蛇多く守るといい、『賢愚因縁経』に大施が竜宮に趣く海上無数の毒蛇を見たとあり、『正法念処経』に〈熱水海毒蛇多し、毒蛇気の故に海水をして熱せしめ一衆生あるなし、蛇毒を以《もちい》る故に衆生皆死す〉と見ゆる、海蛇はいずれも毒牙を持つからの言《こと》だ、これら実在のものと別に西洋には古来海中に絶大の蛇ありと信ずる者多く、近年も諸大洋で見たと報ずる人少なからず、古インドに勇士ケレサスバ海蛇を島と心得その脊《せ》で火を焼く、熱さに驚き蛇動いて勇士を顛倒したと言い、十六世紀にオラウスが記したスウェーデンの海蛇は長《たけ》二百フィート周二十フィート、牛豕羊を食いまた檣《ほばしら》のごとく海上に起《た》ちて船客を捉え去ったといい、明治九年頃チリ辺の洋中で小鯨二疋一度に捲き込んだ由その頃の新聞で見た。『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』十一版二十四巻にかかる大海蛇譚の原因は海豚《いるか》や海鳥や鮫や海狗や海藻が長く続いて順次起伏して浮き游《およ》ぐを見誤ったか、また大きな細長い魚や大烏賊を誤り観《み》たか、過去世に盛えた大爬虫プレシオサウルスの残党が今も遠洋に潜み居るだろうと論じ居る。『甲子夜話』二十六に年一、二度佐渡より越後へ鹿が渡海するに先游ぐもの頸《くび》と脊のみ見え、後なるはその頷を前の鹿の尾の上に擡《もた》げて游ぎ数十続く、遠望には大竜海を游ぐのごとく見ゆとある、今も熊野の漁夫海上に何故と知らず巨※[魚+賁]《おおえび》などの魚群無数続き游ぎ、船坐るかと怖れ遁《に》げ帰る事ありとか、またホーズと呼ぶ長大の動物尾も頭も知れず連日游ぎ過ぐるに際限を見ず、因って見込みの付かぬをホーズもない事というと聞く、かかる物実際存否の論は措《お》いてとにかく西洋に大海蛇の譚あるようにインドや支那で洋海に大竜棲むとし海底に竜宮ありと信ずるに及んだのだ、また俗に竜宮と呼ぶ蜃気楼も蜃の所為とした、蜃は蛇のようで大きく腰以下の鱗ことごとく逆に生えるとも、※[虫+璃のつくり]竜《あまりょう》に似て耳角あり背鬣紅色とも、蛟に似て足なしともありて一定せず、蜃気楼は海にも陸にも現ずる故|最寄《もより》最寄で見た変な動物をその興行主が伝えたので、蜃が気を吐いて楼台等を空中に顕わすを見て飛び疲れた鳥が息《やす》みに来るを吸い落して食うというたのだ(『類函』四三八)。また月令季秋雀大水に入って蛤《はまぐり》となり孟冬《もうとう》雉大水に入って蜃となる、この蜃は蛤の大きなものだ、欧州中古|石※[虫+劫]《かめのて》が鳧《かも》になると信じわが邦で千鳥が鳥貝や玉※[王+兆]《たいらぎ》に化すと言うごとく蛤類の肉が鳥形にやや似居るから生じた迷説だが、邦俗専ら蜃をこの第二義に解し蛤が夢を見るような画を蜃気楼すなわち竜宮と見るが普通だ。
「第6図」のキャプション付きの図 |
|
| インド、アラビア、東南欧、ペルシア等に竜蛇が伏蔵を守る話すこぶる多い、伏蔵とは英語でヒッズン・トレジュァー、地下に匿《かく》しある財宝で、わが邦の発掘物としては曲玉や銅剣位が関の山だが、あっちのは金銀宝玉金剛石その他|最《いと》高価の珍品が夥しく埋まれあるから、これを掘り中《あ》てた者が驟《にわ》かに富んで発狂するさえ少なからず、伏蔵探索専門の人もこれを見中てる方術秘伝も多い。『起世因本経』二に転輪聖王《てんりんじょうおう》世に出《い》づれば主蔵臣宝出でてこれに仕う、この者天眼を得地中を洞《とお》し見て有王無王主一切の伏蔵を識《し》るとあるから、よほど古くより梵土で伏蔵を掘って国庫を満たす事が行われたので、『大乗大悲分陀利経』には〈諸大竜王伏蔵を開示す、伏蔵現ずる故、世に珍宝|饒《おお》し〉という。前文に述べた通り伏蔵ある地窖《あなぐら》や廃墟や沼沢には蛇や蜥蜴類が多く住み、甚だしきは鱷を蓄《か》って宝を守らせた池もある故、自然とこれらの動物をあるいは神物あるいは吝人が死後竜蛇になって隠財を守ると信じたのだ、さてかの国々の蛇は大抵水辺を好み沙漠に棲むものまでも時に湖に游ぐ事あり(バルフォル『印度事彙』三巻五七四頁)、予が毒竜の現物と上に述べた鱗蛇は在インドの英人これを水蜥蜴と通称するほど水辺を好み、蛟竜の本品たる鱷が水に住むは知れ切ったところだ、かつ伏蔵もとより地下に限らず沼沢中に存するも多き故竜を以て地下また水中の伏蔵主とししたがって財宝充満金玉荘厳せる竜宮が地下と水中にありとしたのだ、ヒンズ教に地下に七住処ありて夜叉《やしゃ》、羅刹《らせつ》等住み最下第七処パタラに多頭《ヴァスキ》竜王諸竜を総《す》べて住むというは地底竜宮で『施設論』六に〈山下竜宮あれば、樹草多きに及ぶ、山下竜宮なかれば、樹草少なきに及ぶ〉とあり、水中の竜宮は有名な無熱池を始め河湖泉井までもすこぶる例多く秀郷が往ったのも琵琶湖底にあったのだ。『出曜経』八に無厭足とて名から大強慾な竜王が己を祀《まつ》りて富を求むる婆羅門を使い富家の財をことごとく地下に没入せしに、富家の主人竜泉に至りわが財宝は正道もて獲たればみだりに竜に取らるべきにあらずとて、金を泉に投ずるに水皆湧き熱し竜王懼れ金を出して皆|還《かえ》したとあり。『続古事談』四に「祇園社の宝殿の中には竜穴ありといふ、延久の焼亡の時梨本の座主《ざす》その深さを量らむとせしに五十丈に及んでなほ底なしとぞ」、これらで見ると地底に水あまねくことごとく海に通ずれば井泉河湖に住む小中竜王の大親分たる大竜王は大海に住み、大海底の竜宮の宏麗《こうれい》泉河湖沼のものに比して格別なる事既に経文より引いたごとく、これ陸地諸水がついに海に入るごとく陸地諸宝も必ず海に帰すとした上、船で運ぶ無量の珍宝財宝が難破のため多く海に沈むからの見解で、近い話は前日八阪丸とともに没した莫大の金額も古人なら竜宮を賑《にぎ》わし居ると信じたはずだ、わが邦の弟橘媛《おとたちばなひめ》古英国のギリアズンなど最愛の夫を救わんと海に入ったすら多く、仏書に風波を静めんとて命よりも尊んだ仏舎利や経文を沈めた譚も少なからず、アフリカのギニアの浜へ船久しく著《つ》かぬ時その民一切の所有品を海に抛げ込んでその神に祈り、ために神官にくれる物一つもなくなる故神官余りかかる大祈祷を好まなんだ由(ピンカートン『航海旅行記全集《ゼネラルコレクション・オヴ・ヴォエイジス・エンド・トラヴェルス》』十六巻五〇〇頁)。されば竜宮に永年積んだ財宝は無量で壇の浦に沈んだ多くの佳嬪らが竜王に寵せられて竜種改良と来るから、嬋娟《せんけん》たる竜女が人を魅殺した話多きも尤もだ、竜宮に財多しというが転じて海に竜王住む故大海に無量の宝ありと『施設論』など仏書に多く見ゆ。 | |
| また鮫《ふか》類にもその形竜蛇に似たるが多く、これも海中に竜ありてふ信念を増し進めた事疑いなし、梵名マカラ、内典に摩竭魚と訳す、その餌を捉《と》るに黠智《かつち》神のごとき故アフリカや太平洋諸島で殊に崇拝し、熊野の古老は夷神はその実鮫を祀りて鰹《かつお》等を浜へ追い来るを祈るに基づくと言い、オランラウト人は鮫と鱷を兄弟とす、予の鮫崇拝論は近い内『人類学雑誌』へ出すが、少分《すこし》は六年前七月の同誌に載せた「本邦における動物崇拝」なる拙文に書き置いたからそれに譲るとして、竜と鮫の関係につきここに述ぶるは、上に言うた通りわが邦でタツというはもと竜巻を指した名らしく外国思想入りて後こそ『書紀』二十六、斉明《さいめい》天皇元年〈五月《さつき》の庚午《かのえうま》の朔《ついたちのひ》、空中《おおぞらのなか》にして竜に乗れる者あり、貌《かたち》唐人《もろこしびと》に似たり、青き油《あぶらぎぬ》の笠を着て云々〉など出でたれ、神代には支那の竜と同じものはなかったらしい、『書紀』二に豊玉姫《とよたまひめ》産む時夫|彦火々出見尊《ひこほほでみのみこと》約に負《そむ》き覘《うかが》いたもうと豊玉姫産にあたり竜に化《な》りあったと記されたが、異伝を挙げて〈時に豊玉姫|八尋《やひろ》の大熊鰐《わに》に化為《な》りて、匍匐《は》い逶※[虫+也]《もごよ》う。遂に辱められたるを以て恨《うらめ》しとなす〉とあり、『古事記』には〈その産に方《あた》っては八尋の和邇《わに》と化りて匍匐い逶蛇《もこよ》う〉とあり、その前文に〈すべて佗国《あだしくに》の人は産に臨める時、本国《もとつくに》の形を以て産生《う》む、故に妾今もとの身を以て産を為《な》す、願わくは妾を見るなかれ〉、これは今日ポリネシア人に鮫を族霊《トテム》とする輩が事に触れて鮫の所作を為すごとく、姫が本国で和邇を族霊とし和邇の後胤と自信せる姫が子を産む時自ら和邇のごとく匍匐《は》ったのであろう、言わば狐付きが狐の所作犬神付きが犬神の所作をし、アフリカで鱷神が高僧に詑《つ》く時言語全く平生に異なり荐《しき》りに水に入らんと欲し、河底を潜り上って鱷同然泥中に平臥するがごとし(レオナード著『下《ラワー》ニゲル|およびその民俗篇《エンド・イツ・トライブス》』二三一頁)。さて『古事記』にこれより先かの尊豊玉姫の父|海神《わたつみ》のもとより帰国の時一|尋《ひろ》の和邇に乗りて安著し、その和邇返らんとする時|所佩《みはかせ》る紐小刀《ひもがたな》を解いてその頸に付けて返したまいし故その一尋の和邇を今に佐比持神《さひもちのかみ》というと見え、『書紀』に稲飯命《いなひのみこと》熊野海で暴風に遭《あ》い、ああわが祖は天神《あまつかみ》母は海神なるにいかで我を陸にも海にも厄するかと言い訖《おわ》って剣を抜きて海に入り鋤持神《さひもちのかみ》となるとある、この鋤の字を佐比と訓《よ》む事『古事記伝』では詳《つまび》らかならず、予種々考えあり、ここには煩わしきを憚《はばか》って言えぬが大要今日の鶴嘴《つるはし》様に※[金+纔のつくり]《は》曲ってその中央に柄が付いた鋤を佐比と言い、そのごとく曲った刀を鋤鈎《さひち》というたと惟《おも》う、中古にも紀朝臣|佐比物《さひもち》、玉作佐比毛知など人の名あればその頃まで用いられた農具だ、彦火々出見尊が紐小刀を和邇の頸に附けてその形が佐比様すなわち鶴嘴様になりしよりその和邇を佐比持神というたてふ牽強説で、宣長が「卑しけど雷|木魅《こだま》きつね虎竜の属《たぐい》も神の片端」と詠んだごとく、昔は邦俗和邇等の魚族をも奇怪な奴を神としたのだ、さて鮫の一類に撞木鮫《しゅもくざめ》英語でハンマー・ヘッデット・シャーク(槌頭の鮫)とて頭丁字形を成し両端に目ありすこぶる奇態ながインド洋に多く欧州や本邦の海にも産するのが疑いなくかの佐比神だ、十二年前熊野の勝浦の漁夫がこの鮫を取って船に入れ置き、腓《こむら》を大部分噛み割《さ》かれ病院へ運ばるるを見た、獰猛な物で形貌奇異だから古人が神としたのも無理でない、これで和邇とは古今を通じて鮫の事で神代既に熊和邇、佐比持などその種類を別ちおったと知る、国史に鱷をワニと訓ませ『和名抄』『新撰字鏡』などその誤りを改めなんだは、その頃の学者博物学に暗かった杜撰《ずさん》で、今も北国や紀州の一部である鮫をワニと呼ぶ通り、国史のワニは決して鱷でなく鮫だという事を明治二十六年頃の『日本』新紙に書いた人があったがなかなかの卓説だ、御名前を忘れたが一献差し上げたいから知った人があらばお知らせを乞う、昨年十月の『郷土研究』に記者が人を捕る鮫の類は深海に棲む動物で海岸に起ったこのワニの譚に合わず、鮫すなわちワニという説は動物分布の変遷てふ事を十分考察せぬ者の所為と評しあったが、この記者自身が動物分布の変遷を一向構わぬらしい、鮫の住所様々なるは『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』十一版二十四巻に便宜のためこれを浜辺、大海、深海底と住所に随って序《つい》で論じあるで判《わか》る。アフリカ、南米、濠州等には川に鮫住む事多く昔江戸鮫が橋まで鮫が来たとは如何《いかが》だが、『塩尻』五三に尾張名古屋下堀川へ鰹群来した事を記して、漁夫いう日でり久しき時鮫内海に入り諸魚を追うて浜近く来るとあり。田辺浜の内の浦などいう処は近年まで鮫毎度谷鰹てふ魚を谷海とて鹹水《かんすい》で満ちた細長き谷間へ追い込み漁利を与えた故今も鮫を神様、夷子《えびす》様など唱え鮫というを忌む、日高郡南部町などは夏日海浴する小児が鮫に取られた事少なからず、されば汽船発動機船などなかりし世には日本の海岸に鮫到り害を為《な》す事多かったはずで、『今昔物語』の私市宗平《きさいちのむねひら》、『東鑑』の朝比奈義秀《あさひなよしひで》など浜辺でワニを取った様子皆鮫で鱷にあらず、ハワイやタヒチ等の浜辺に鮫を祭る社あって毎度鮫来り餌を受け甚だしきは祠官を負うて二十|浬《かいり》も游ぎし事エリスの『多島海研究《ポリネシアン・レサーチス》』四、ワイツおよび《ウント》ゲルランド『未開人民史《ゲシヒテ・デル・ナチュルフォルケル》』六等に見ゆ、三重県の磯部大明神にかかる鮫崇拝の遺風ある話は予の「本邦における動物崇拝」に載せた、要するに和邇が鮫にして鱷でなきは疑いを容れず、ただし熱地には鱷が海辺に出る事も鮫が川に上る事もありて動物学の心得もなき民種はこれを混用するも無理ならず、したがってオラン・ラウト人ごとく二者を兄弟としたり、ペルシアの『シャー・ナメー賦』に鱷大海に棲むとしたは有内《ありうち》の事だ。 | |
| ■本話の出処系統 | |
| 上の三章で長たらしく竜の事を論じたは、それが分らぬ内は秀郷竜宮入りの話中の毎事毎項が分らぬからだ、竜の事はなかなか複雑でとても十分にこの誌上で悉《つく》し得ぬが、まず上の三章で勘弁を願うとしてこれからこの話の出処系統論に取り掛ろう。まず『左伝』に鄭大水出で竜時門の外に闘う。『正法念処経』七十に竜と阿修羅と赤海下に住み飲食《おんじき》の故に常に共に闘う、〈また大海あり、名づけて竜満という、諸竜あり、旃遮羅と名づく、この海中に住み、自ら相闘諍す〉。古英国メルリン物語に地下の赤竜白竜相闘って城を崩し、ガイ・オヴ・ワーウィック譚にガイ竜獅と戦うを見、獅に加勢し竜を殪《たお》し獅感じてガイに随うこと忠犬のごとしとある。仏経には竜は瞋恚《しんい》熾盛《しじょう》の者といえるごとくいずれの国でも竜猛烈にして常に同士討ちまた他の剛勢なものと闘うとしたので、既に喧嘩《けんか》通しなれば人に加勢を乞うた例も多い、『類函』三六六に宣城の令張路斯その夫人との間に九人の子あり、張釣りに行って帰るごとに体湿りて寒《ひ》え居る、夫人怪しみ問うと答えて言う、我は竜だ、鄭祥遠も実は竜で我と釣り処を争うて明日戦うはず故九子をして我を助けしめよ、絳※[糸+稍のつくり]を領《えり》にしたは我、青※[糸+稍のつくり]は鄭だといった、明日いよいよ戦いとなって九子青※[糸+稍のつくり]を目的に鄭を射殺し皆竜と化《な》ったとある。同書四三八に『太平広記』を引いていわく、黄※[土へん+敦]湖に蜃(上に出た通り竜の属)あって常に呂湖の蜃と闘う、近邨《きんそん》で善く射る勇士程霊銑方へ蜃が道人に化けて来ていう、われ呂湖の蜃に厄《くる》しめらる、君我を助けなば厚く報ずべし、白練《しろねり》を束ねたる者は我なりと、明日霊銑|邨《むら》の少年と湖辺に鼓噪《こそう》すると須臾《しばらく》して波湧き激声雷のごとく、二牛|相《あい》馳《は》せるを見るにその一|甚《いと》困《くる》しんで腹肋皆白し、霊銑後の蜃に射《い》中《あ》てると水血に変じ、傷ついた蜃は呂湖に帰る途上で死んだとまであって跡がないが約束通りぐっすり礼物を占《せし》めただろう、『続捜神記』から『法苑珠林』に引いた話にいわく、呉の末臨海の人山に入って猟し夜になって野宿すると身長《みのたけ》一丈で黄衣白帯した人来て我明日|讐《かたき》と戦うから助けくれたら礼をしようというたので、何の礼物に及びましょう必ず助けましょうというと、明食時君渓辺に出よ、白帯したのは我黄帯は敵だといって去った、明日出て見ると果して岸の北に声あり草木風雨に靡《なび》くがごとく南も同様だ、唯《と》見《み》ると二大蛇長十余丈で渓中に遇うて相《あい》繞《まと》うに白い方が弱い、狩人射て黄な奴を殺した、暮方に昨《きのう》の人来って大いにありがたい、御礼に今年中ここで猟しなさい、明年となったら慎んで来ないようといって去った、狩人そこに停《とど》まり一年猟続け所猟《えもの》甚だ多く家巨富となった、それでよせば好いに数年の後前言を忘れまた往き猟すると白帯の人また来て君はわが言を用いずここへ死にに来た、前年殺した讐の子すでに長じたから必ず親の仇と君を殺すだろうが我知るところでないと言ったので、狩人大いに恐れて走らんとするところへ黒装束した三人皆長八尺の奴が来て口を張って人を殺したとあるから毒気に中《あ》てたんだろ。芳賀博士はこの話を『今昔物語』十巻三十八語の原《もと》と見定められた、その話は昔|震旦《しんたん》の猟師海辺に山指し出た所に隠れて鹿を待つと、海に二つの竜現われ青赤|※[口+敢]《く》い合い戦うて一時ばかりして青竜負けて逃ぐ、その夜そこに宿り明日見れば昨と同時にまた戦うて青竜敗走した、面白くてその夜もそこに宿って三日目にまた戦うて青竜例の通りというところを、猟師|箭《や》を矯《た》めて赤竜に射中《いあ》てると海中に入って、青竜も海に入ったが玉を※[口+敢]《くわ》え出で猟師に近づき吐き置いて海に入った、その玉を取りて家に返りしより諸財心に任せ出で来て富に飽き満ちたというのだ、如意宝珠《にょいほうじゅ》とて持つ人の思いのままに富を得繁盛する珠を竜が持つとはインドに古く行われた迷信で、『新編鎌倉志』に如意珠二種あり、一は竜の頸の上にあり、一は能作生珠と号して真言の法を行うて成る、鶴岡八幡宮の神宝なるは能作生珠だ、その製法呪法は真言の秘法というとある。『華厳経《けごんぎょう》』に一切宝中如意宝珠最も勝るとあり。『円覚鈔』にいう、〈如意と謂うは意中|須《ま》つところ、財宝衣服飲食種々の物、この珠ことごとく能く出生し、人をして皆如意を得せしむ〉。『大智度論』には〈如意珠仏舎利より出《い》づ、もし法没尽する時、諸舎利、皆変じて如意珠と為《な》る〉。『類函』三六四、〈『潜確類書』に曰く竜珠|頷《あご》にあり蛇珠口にあり〉。『摩訶僧祇律』七に雪山水中の竜が仙人の行儀よく座禅するを愛し七|巾《まき》巻きて自分の額で仙人の項《うなじ》を覆い、食事のほか日常かくするので仙人休み得ず身体|萎《くたびれ》羸《や》せて瘡疥を生ず、ところへ近所の者来り若い女に百巻捲かれても苦しゅうないが竜に七巾ではお困りでしょう、よい事がある、竜は天性|慳吝《けんりん》で、咽上に宝珠あるからそれを索《もと》めなさいと教え、竜また来ると仙人彼に汝われをさほど愛するなら如意宝珠をくれというた、竜われこの宝あればごく上饌《じょうせん》と衆宝を出し得るなれ、これは与うべからずとて淵に潜んで再び来なんだと載す。『正法念処経』二九などを見ると宝珠を求めて竜蛇を殺す事多かったらしく、今のインド人も蛇の頭にモホールてふ石あり夜を照らし蛇毒を吸い出す、人見れば蛇自ら呑んでしまいまた自分が好く人に与うるがこれを得る事すこぶる難しと信じ(エントホヴェン編『グジャラット民俗記』一四三頁)、アルメニア人の説にアララット山の蛇に王種あり、その中一牝蛇を選立して女王とす、外国より蛇群来り攻むれど諸蛇脊にかの女王を負う間は敵常に負け却《しりぞ》く、女王に睨《にら》まるれば敵蛇皆力なし、この女王蛇口にフルてふ光明石を含み夜中これを空に吐き飛ばすと日のごとく輝くという(ハクストハウゼン著『トランスカウカシア』英訳三五五頁)。一八三九年死んだ北インド王ランジットシンは呪言を書いた宝石を右臂の皮下に納めおったので、百事思うままに遂げたというは人造如意珠すなわち能作生珠だろう(フォンフュゲル『|迦※[さんずい+(一/(幺+幺)/土)]弥羅および西克王国遊記《カシュミル・ウント・ダス・ライヒ・デル・シエク》』巻三、頁三八二)、『大智度論』に竜象獅鷲の頭に赤玉あり、欧州で蛇王バリシスク宝冠を戴き(ブラウン『俗説弁惑《プセウドドキシア・エピデミカ》』三巻七章ウィルキン注)、蟾蜍《ひきがえる》の頭に魔法と医療上神効ありてふ蟾蜍石《ブフォニット》ありなど(一七七六年版ペンナント『英国動物学《ブリチシュ・ゾオロジー》』三巻五頁)多く言ったは、交通不便の世に宝玉真珠等の出処を知らぬ民が、貴人の頭上に宝冠を戴くごとく希有《けう》の動物の頭にかかる貴重物を授くと信じたからで、後世その出処がほぼ分ってもなお極めて高価な物は竜蛇の頭より出ると信じたのであろう。 | |
| 右様に竜が戦いに負けて人に救いを求めた話が少なからぬに、馬琴はその『質屋庫』三にそれらを看過して一言せず、湖の竜が秀郷の助力を乞うた譚をただただ唐の将武が象に頼まれて巴蛇《うわばみ》を殺し象牙を多く礼に貰うて大いに富んだてふ話を作り替えたものと断じたは手脱《てぬか》りだ(馬琴が言うた通り巴蛇象を食い三年して骨を出すと『山海経《せんがいきょう》』にあれば古く支那で言うた事で、ローマのプリニウスの『博物志《ヒストリア・ナチュラリス》』八巻十一章にも、インドの大竜大象と闘うてこれを捲き殺し地に僵《たお》るる重量で竜も潰《つぶ》れ死すと見ゆ)、『質屋庫』より数年前に成った伴蒿蹊《ばんこうけい》の『閑田次筆《かんでんじひつ》』二やそれより七十年前出来た寒川辰清《さむかわたつきよ》の『近江輿地誌略』十一に引いた通り、『古事談』に次の話あれば勇士が竜を助けて鐘を得た話は鎌倉幕府の代既にあったのだ。その文を蒿蹊が和らげたままに概略を写すとこうだ。三井寺の鐘は竜宮より来た、時代分らず昔粟津の冠者てふ勇士一堂を建つるため鉄を求めて出雲に下る、海を渡る間大風|俄《にわか》に船を覆《くつがえ》さんとし乗船の輩泣き叫ぶ、爾時《そのとき》小童小船一艘を漕ぎ来り冠者に乗れという、その心を得ねどいうままに乗り移ると風浪|忽《たちま》ちやむ、本船はここに待つべしと示し小船海底に入りて竜宮に到る、竜宮の殿閣奇麗言うべからず、竜王出会いて語《いえ》らく、従類多く讐敵に亡ぼされ今日また害せらるべし、因って迎え申したから時至れば一矢射たまえと乞う、諾《うべな》いて楼に上って待つと敵の大蛇あまたの眷属《けんぞく》を率いて出で来るを向う様《ざま》に鏑矢《かぶらや》にて口中に射入れ舌根を射切って喉下に射出す、大蛇退き帰るところを追い様にまた中ほどを射た、竜王出でて恩を謝し何でも願いの品を進《まいら》すべしという、冠者鐘を鋳んと苦辛する状《さま》をいうと、竜王甚だ易《やす》き事とて竜宮寺に釣るところの鐘を下ろして与う、粟津に帰り一所に掲げ堂を建つ、広江寺これなり、時移ってかの寺破壊の後わずかに住持の僧一人鐘の主たりしが、藤原清衡砂金千両を三井寺僧千人に施す、その時、三綱某五十人の分を乞い集め五十両を広江寺の法師に与う、法師悦んでかの鐘を売り三井寺に釣る、広江寺は叡山の末寺なれば衆徒この事を洩《も》れ聞いて件《くだん》の鐘主の法師を搦《から》め日あらず湖に沈めたとある、誠に『太平記』の秀郷竜宮入りはこの粟津冠者の譚から出たのだ、さて秀郷竜王を助けた礼に俵米巻絹ともに取り用いて尽きざるを貰うたというた原話は『今昔物語』十六の第十五語だ。概略を述べると今は昔京に年若き男貧しくて世を過すに便なかりしが、毎月十八日に持斎して観音に仕え百寺に詣る事年来なり、ある年九月十八日に例のごとく寺々に詣るに南|山階《やましな》辺へ行く道の山深き所で五十ばかりなる男一尺ばかりなる小蛇を杖の先に懸け行くを見子細を尋ぬると、われは年来|如意《にょい》と申す物を造るため牛角を伸ぶるにかかる小蛇の油を取ってするなり、若き男その如意は何にすると問うた、知れた事だお飯《まんま》と衣のために売るのだと答う、若き男小蛇を愍《あわれ》み種々押問答の末ようやく納得させ、自分の着たる綿衣に替えて小蛇を受け、この蛇は何処《どこ》に在ったかと問いかの小池に持ち行き放ち、さて寺へ行こうと二町ほど過ぎると十二、三ばかりの女形美なるが微妙の衣袴を着たるに逢う、その女いわくわが父母君がわが命を助けくれた恩を謝せんとて迎えにわれを使わしたとて池の方へ伴《つ》れて行き、暫《しばら》く待ちたまえとてたちまち失《う》せぬ、さて出て来て暫く眼を閉じよという、教えのままに眠入《ねい》ると思うほどに目を開けという、目を開けて見れば微妙《めでた》く飭《かざ》った門あり、また暫く待って七宝で飾った宮殿を過ぎて極楽ごとき中殿に到る、六十ばかりの人微妙に身を荘《かざ》り出で来り、強いてかの男を微妙《いみじ》き帳床に坐らせ、己れは子あまたある末子なる女童この昼渡り近き池に遊ぶを制すれど聴かず、そのまま遊ばせ人に取られて死ぬべかりしを其《そこ》に来合せ命を助けたもうとこの女子に聞いた嬉しさに謝恩のため迎え申したと言って、何とも知れぬ旨《うま》い物を食わす、さて主人いわく己は竜王なり、今度《このたび》の酬《むくい》に如意の珠を進ぜんと思えど、日本人は心|悪《あ》しくて持ちたまわん事難し、因ってかの箱をというて取り寄せ開くと中に金の餅一つあり厚さ二寸ばかり、それを取り出して中より破って片破《かたわ》れを箱に入れ今一つの片破れを男に与えて、これを一度に仕《つか》わず要に随うて片端より破って仕いたまわば一生涯乏しき事あらじという、男これを懐にして今は返ろうと言うに、前《さき》の女子来て例の門に将《つ》れ出で眠らせて池辺に送り出し重ね重ね礼を述べて消え失せた、家に帰れば暫《しば》しと思う間に数日経ていた、この事を人に語らずこの金の餅の片破れを破れども破れども元のように殖《ふ》えて尽きず、入要の物に替えければ万《よろず》の物豊かに極めたる富人として一生観音に仕えたが己れ一代の後はその金餅失せて子に伝わらなんだという。芳賀博士の『考証今昔物語集』にこの話を挙げた末に巻三の十一条および浦島子伝を参閲せよとあるが、浦島子の事は誰も御承知で、『今昔物語』三の十一語は迦毘羅衛《かびらえ》の釈種《しゃくしゅ》滅絶の時、残った一人が流浪して竜池辺で困睡する所へ竜女来り見てこれを愛し夫とし、竜女の父竜王の謀《はかりごと》で妙好|白氈《はくせん》に剣を包んで烏仗那《うじゃな》国王に献じ、因って剣を操りて王を刺し代って王となり竜女を後と立てた談《はなし》で両《ふたつ》ながら本話に縁が甚だ遠い。また考証本にこの竜女を救うてその父から金餅を得た話の出処を挙げおらぬが、予は二十年ほど前に見出し置いたから出さんに、東晋の仏陀|跋※[足へん+它]羅《ばーどら》と法顕共に訳せる『摩訶僧祇律』三十二にいわく、仏舎衛城に在《いま》す時、南方|一邑《あるむら》の商人八牛を駆って北方|倶※[口+多]《くしゃ》国に到り沢中に放ち草を食わしむ、時に離車種の者竜を捕り食うが一竜女を捕えた、この竜女|布薩法《ふさつほう》を受けたれば殺心なく、鼻に穴開け縄を通して牽《ひ》かれ行く、商人竜女の美貌を見て慈心を起しとあるが、全体竜女は婉妍人間婦女の比にあらず、今もインドで男子をして魂飛び魄散ぜしむるほどの別嬪を竜女と称うる(エントホヴェンの『グジャラット民俗記』一四三頁)くらい故、この商人も慈心も起せばほ[#「ほ」に白丸傍点]の字でもありやしたろう、この商人離車に一牛を遣るからその竜女を放てというも聴かず、因って種々|糶《せ》り上げて八牛で相談調い竜女を放った、商人こんな悪人はまた竜女を取るも知れぬと心配して、その行く方へ随って行くと一《ある》池の辺で竜が人身に変じ商人に活命の報恩にわが宮へ御伴《おとも》しようと言う、商人いわく汝ら竜の性卒暴、瞋恚《しんい》常なし、我を殺すかも知れぬから御伴は真《ま》ッ平《ぴら》と、竜女いわくわが力|能《よ》くかの離車を殺すも我布薩法を受けた故殺さなんだ、いわんや活命の大恩ある人を殺すべきや、少しく待ちたまえといってまず入り去った、この辺竜宮の門あり、二竜を繋《つな》げり、商人その訳を問うと答うらく、この竜女半月中三日斎法を受く、わが兄弟二人この竜女を守る事堅固ならず、離車に捕わるるに及んだで繋がれいる、何卒《なにとぞ》救い助けたまえ、一体竜宮の飲食に種々ある、一度食うて一生懸って消化するもあり、二十年で消化するも七年でするもあれば、閻浮提《えんぶだい》人間の食もある、君もし宮に入って何に致しましょうと馳走の献立を伺われたら、閻浮提人間の食を望みたまえと、問わぬ事まで教えくれた、ところへ竜女来って商人を呼び入れ宝牀褥上に坐らせ何の食を食わんと欲するかと問うので、閻浮提人間の食を望んだ、すると竜女種々の珍饌を持ち来りさあお一つと来《く》る、商人今ここへ来る門辺に竜二疋繋がれあったが何の訳ぞと問うに、そんな事は問わずに召し上がれという、余りに問い返すので余儀なく彼は過ちある故殺そうと思うと答う、商人汝彼ら殺さずばわれ食事せん、釈《ゆる》さぬ内は一切馳走を受けぬと言い張ったので竜女も我を折り、直様《すぐさま》釈す事はならぬが六ヶ月間人間界へ擯出しようと言ってやがてかの二竜を竜宮から追い出した、商人竜宮を見るに種々の宝もて宮殿を荘厳す、商人汝かく快楽多きに何のために布薩法を受くるかと問うと、我々竜に五事の苦しみあり、生まるる時、眠る時、婬する時、瞋《いか》る時、死ぬ時、本身を隠し得ず、また一日のうち三度皮肉地に落ち熱沙身を暴《さら》すと答う、何が一番竜の望みかと問うと、畜生道中正法を知らぬ故人間道に生まれたいと答う、もし人間に生まれたら何らを求むるかと問うと、出家が望みと答う、出家を誰に就《つ》いてすべきかと問うと、如来|応供《おうぐ》正※[彳+扁]知、今舎衛城にあって、未度の者を度し未脱の者を脱したもう、君も就いて出家すべしと勧めたのでしからば還ろうと言うと、竜女彼に八|餅金《へいきん》を与え、これは竜金なり、君の父母|眷属《けんぞく》を足《みた》す、終身用いて尽きじと言い眼を閉じしめて神変もて本国に送り届けた、宅では商人の行伴《つれ》来りてこの家の子は竜宮へ往ってしもうたと報《しら》せたので、眷属宗親一処に聚《あつ》まり悲しみ啼《な》く、ところへまたかの者生きて還ったと告ぐる者あり、一同大歓喜で出迎え家に入って祝宴を張った、席上かの八餅金を出して父母に与え、これは竜金で截《き》り取って更に生じ一生用いて尽きず、これを以て楽《らく》に世を過されよ、ただ願わくは父母我に出家を聴《ゆる》せと望み、父母放たざるを引き放ちて祇※[さんずい+亘]精舎《ぎおんしょうじゃ》に詣り出家したそうじゃ、竜女が殺さるるところを救うたのも、竜宮へ迎えて珍饌で饗応されたのも、殊に餅金を受けて用いれども尽きなんだ諸点が合うて居るから、『今昔物語』の話は北インドの仏説から出たに相違なく、『近江輿地誌略』三九秀郷竜宮より得た十宝中に砂金袋を列せるは、たまたま件《くだん》の餅金を得た仏話が秀郷竜宮入譚の幾分の原話たる痕《あと》を存す、『曼陀羅秘抄』胎蔵界の観音院に不空羂索《ふくうけんじゃく》あり、『仏像|図彙《ずい》』に不空羂索は七観音の一なり、南天竺の菩提流支が唐の代に訳した『不空羂索神変真言経』にこの菩薩の真言を持して竜宮に入りて如意宝珠を竜女より取り、また竜女を苦しめて涙を取り飲んで神通と長寿を得、竜女の髪を採りて身体に繋《か》け、一切天竜羅刹等を服従せしむる等の法を載す、上引の『今昔物語』の文に竜の油を以て如意を延ばすとあるは、この話の主人公たる若者が観音に仕えたとあるに因み、七観音の一たる不空羂索の真言で右様の百事如意の法を求むる事あるを、如意てふ手道具と心得違うたのでなかろうか。 | |
| これも従来気付いた人がないようだが、秀郷が竜に乞われて蜈蚣《むかで》を射平らげたてふ事も先例ある。『今昔物語』巻二十六の九にいわく、加賀の某郡の下衆《げす》七人一党として兵仗を具えて海に出で釣りを事とす、ある時風に遭《お》うて苦しむと遥かに大きな島ありて、人がわざと引き寄するようにその島に船寄る、島に上りて見廻すほどに二十余歳らしい清げな男来て汝たちを我が迎え寄せたるを知らずや、風は我が吹かしたのだといって微妙な飲食もて饗応しさていうは、ここより澳《おき》にまたある島の主我を殺してこの島を取らんと常に来り戦うをこれまで追い返したが、明日は死生を決し戦うはず故、我を助けもらわんとて汝らを迎えたと、釣り人ども出来ぬまでも命を棄て加勢申さん、その敵勢はいかほどの人数船数ぞと問うと、男それはありがたい、敵も我も全く人でないのを明日見なさい、従前敵が来るとこの滝の前に上陸せしめず海際で戦うたが、明日は汝らを強く憑《たの》むから上陸させて戦うて我堪えがたくならば汝らに目を見合すその時|箭《や》のあらん限り射たまえと、戦いの刻限を告げ確《しっ》かり食事して働いてくれと頼んで去った、七人木で庵を造り鏃《やじり》など鋭《と》いで弓弦《ゆづる》括《くく》って火|焼《た》いて夜を明かし、朝に物|吉《よく》食べて巳《み》の時になりて敵来るべしといった方を見れば、風吹いて海面荒れ光る中より大きな火二つ出で来る、山の方を望めば草木|靡《なび》き騒ぐ中よりまた火二つ出で来る、澳より近く寄するを見れば十丈ばかりの蜈蚣で上は□□に光り左右の眼(?)は赤く光る、上から来るは同じ長さほどの臥長《ふしたけ》一抱えばかりな蛇が舌|嘗《なめ》ずりして向い合うた、蛇、蜈蚣が登るべきほどを置いて頸を差し上げて立てるを見て蜈蚣喜んで走り上る、互いに目を瞋《いか》らかして相守る、七人は蛇の教えの通り巌上に登り箭を番《つが》えて蛇を眼懸けて立つほどに蜈蚣進んで走り寄って互いにひしひしと咋《くわ》えて共に血肉になりぬ、蜈蚣は手多かるものにて打ち抱きつつ(?)咋えば常に上手なり、二時ばかり咋う合うて蛇少し弱った体《てい》で釣り人どもの方へ目を見やるを、相図心得たりと七人の者ども寄りて蜈の頭から尾まである限りの箭を筈本《はずもと》まで射立て、後には太刀で蜈の手を切ったから倒れ臥した、蛇引き離れ去ったから蜈蚣を切り殺した、やや久しゅうして男極めて心地|悪気《わるげ》に顔など欠けて血出でながら食物ども持ち来って饗し喜ぶ事限りなし、蜈蚣を切り放って木を伐り懸けて焼き了《お》う、さて男釣り人どもに礼を厚く述べ、この島に田作るべき所多ければ妻子を伴れて移住せよ、汝ら本国に渡らんには此方《こなた》より風吹かさん、此方へ来んには加賀の熊田宮に風を祈れと教えて、糧食を積ませ乗船せしむると俄かに風吹いて七人を本国へ送る、七人かの島へ往かんという者を語らい七艘に乗船し、諸穀菜の種を持ち渡りその島大いに繁昌《はんじょう》するが猥《みだ》りに内地人を上げず、唐人敦賀へ来る途上、この島に寄って食物を儲《もう》け、鮑《あわび》など取る由を委細に載せ居る、これを以て攷《かんが》えると秀郷が蜈蚣を射て竜を助けた話も、話中の蜈蚣の眼が火のごとく光ったというも、『太平記』作者の創《はじ》めた思い付きでなく、少なくとも三百年ほど前だって行われたものと判る。英国に夜燐光を発する学名リノテーニア・アクミナタとリノテーニア・クラッシペスなる蜈蚣二つあり、学名は知らぬが予米国で一種見出し、四年前まで舎弟方に保存しあったが砕けしまった、かかる蜈蚣多分日本にも多少あるべし、蜈蚣の毒と蝮蛇の毒と化学反応まるで反対すと聞いたが、その故か田辺|辺《へん》で蜈蚣に咬《か》まれて格別痛まぬ人蝮蛇咬むを感ずる事|劇《はげ》しく、蝮蛇咬むをさまで感ぜぬ人蜈蚣に咬まるれば非常に苦しむと伝う、この辺から言ったものか、『荘子』に螂蛆《むかで》帯を甘んず、注に帯は小蛇なり、螂蛆|喜《この》んでその眼を食らう、『広雅』に螂蛆は蜈蚣なり、『史記』に騰蛇これ神なるも螂蛆に殆しめらる、『抱朴子』に〈南人山に入るに皆竹管を以て活ける蜈蚣を盛る、蜈蚣蛇あるの地を知り、すなわち管中に動作す、かくのごとくすなわち草中すなわち蛇あるなり、蜈蚣蛇を見れば能く気を以てこれを禁ず、蛇すなわち死す〉。『五雑俎』九に竜が雷を起し、大蜈蚣の玉を取らんとて撃った話あり、その長《たけ》一尺以上なるは能く飛ぶ、竜これを畏《おそ》る故に常に雷に撃たるという、竜宮入りの譚に蜈蚣を竜の勁敵としたるもまことに由ありだ、西洋には蜈蚣蛇を殺すという事下に言うべし。 | |
|
秀郷の譚に蜈蚣が湖水中の竜宮を攻めたすら奇なるに、『今昔物語』の加賀の海島の蜈蚣が海を渡った大蛇を襲うたは一層合点行かぬという人もあろう、しかし欧州西部の海浜波打ち際に棲《す》む蜈蚣二属二種あり、四十年ほど前予毎度和歌浦の波止場の波打ち懸る岩下に小蜈蚣あるを見た、今日は既に命名された事と想う、さて貝原先生の『大和本草』に「ムカデクジラ長大にして海鰌のごとし、背に鬣《たてがみ》五あり尾二に分る、足左右各六すべて十二足あり肉紅なり、これを食えば人を殺す、大毒あり」、『唐土訓蒙図彙』にその図あったが、貝原氏の説に随ってよい加減に画いた物に過ぎじと惟《おも》う、かかる変な物今日まで誰も気付かぬは不審と、在外中種々捜索すると、やっとサー・トマス・ブラウンの『ノーフォーク海岸魚等記』(十七世紀)に、「予また漁夫が海より得たちゅう物を見るにロンデレチウスが図せるスコロペンドラ・セタセア(蜈蚣鯨の意)に合い十インチほど長し」とあるを見て端緒を得、ロンデレチウスの『海魚譜《リブリ・デ・ピッシブス・マリンス》』(一五五四年版)と『水族志余篇《ウニウエルサエ・アクアチリウム・ヒストリアエ・パルス・アルテラ》』(一五五五年版)を求めたが、稀書で手に入らず、しかし幸いに一六〇四年版ゲスネルの『動物誌《ヒストリア・アニマリウム》』巻四にロ氏の原図を出しあるを見出した、一七六七年版ヨンストンの『魚鯨博物志《ヒストリア・ナチュラリス・デ・ピッシブス・エト・セチス》』巻五の四四頁には一層想像を逞《たくま》しゅうした図を出す、この二書に拠るに蜈蚣鯨を満足に記載したは、ただ西暦二百年頃ローマ人エリアヌス筆『動物性質記《デ・ナチュラ・アニマリウム》』十三巻二十三章あるのみで、その記にいわく、蜈蚣鯨は海より獲し事あり、鼻に長き鬚あり尾|扁《ひらた》くして蝦《えび》(または蝗《いなご》)に似、大きさ鯨のごとく両側に足多く外見あたかもトリレミスのごとく海を游《およ》ぐ事|駛《はや》しと、トリレミスとは、古ローマで細長い船の両側に長中短の櫓を三段に並べ、多くの漕手が高中低の三列に腰掛けて漕いだもので、わが邦の蜈蚣船(『常山紀談』続帝国文庫本三九八頁、清正が夫人の附人輩《つきびとら》川口にて蜈蚣船を毎晩に漕ぎ競べさせたとある)も似たものか、さてゲスネルはかかる蜈蚣鯨はインドにありといい、ヨンストンはその身全く青く脇と腹は赤を帯ぶといった、それからウェブストルの大字書にスコロペンドラ(蜈蚣)とスペンサーの詩にあるは魚の名と出で居る、これだけ列《つら》ねて一八九七年の『ネーチュール』五六巻に載せ、蜈蚣鯨は何物ぞと質問したが答うる者なく、ただその前インドの知事か何かだったシンクレーヤーという人から『希臘詞花集《アントロギアイ・グライカイ》』中のテオドリダス(西暦紀元前三世紀)とアンチパトロス(紀元前百年頃)の詩を見ろと教えられたから半日ほど酒を廃して捜すと見当った、詩の翻訳は不得手ゆえ出任せに訳すると、テの詩が「風南海を攪《かき》まわして多足の蜈蚣を岩上に抛《な》げ揚げた、船持輩この怪物の重き胴より大きな肋骨を取ってここに海神に捧げ置いた」、アの方は「何処《いずこ》とも知れぬ大海を漂浪したこの動物の遺骸破れ損じて浜辺の地上にのたくった、その長さ四丈八尺|海沫《かいまつ》に沾《ぬ》れ巌石に磨かれたるを、ヘルモナクス魚取らんとて網で引き上げ、ここにイノとパライモンに捧げた、この二海神まさにこの海より出た珍物を愛《め》で受くべし」てな言《こと》だ、マクグレゴル注にここに蜈蚣というはその足の数多しというでなく、その身長きを蜈蚣に比べたので、近世評判の大海蛇のような物だろうと言い、シュナイデルはこれぞエリアヌスのいわゆる蜈蚣鯨なりと断じた、これは鯨類などの尸《しかばね》が打ち上がったその肋骨の数多きを蜈蚣の足と見たのだろ、レオ・アフリカヌスの『亜非利加記』にメッサの海浜のある社の鳥居は全く鯨の肋骨で作る、蜈蚣鯨が予言者ヨナを呑んでここへ吐き出した、今も毎度この社前を過ぎんとする鯨は死んで打ち上がる、これ上帝この社の威厳を添えるのだとは、そりゃ聞えませぬ上帝様だ、『続博物誌』に曰く、李勉※[さんずい+并]州にありて異骨一節を得、硯と為すべし、南海にいた時海商より得、その人いうこれ蜈蚣の脊骨と、支那でも無識の人は鯨の脊骨に節多きを蜈蚣の体と誤認したのだ、有名な一八〇八年九月スコットランドのストロンサ島に打ち上がった五十五フィートの大海蛇は、これを見た者宣誓して第七図を画き稀有《けう》の怪物と大評判だったが、その骨をオエン等大学者が検して何の苦もなく一判りにセラケ・マキシマなる大鮫と知った(同図ロ)。その心得なき者は実際|覩《み》た物を宣誓して画いてさえかく途方もなき錯誤を免れぬ事あり(一八一一年『エジンボロソーネリアン博物学会報告』巻一、頁四二六―三九。一八五七年版『依丁堡皇立学士会院記事《プロシージングス・オヴ・ゼ・ロヤル・ソサイエチー・オヴ・エジンボロ》』巻三、頁二〇八―一五。一八六〇年版ゴッス『博物奇談《ゼ・ロマンス・オヴ・ナチュラル・ヒストリー》』三二七頁)。したがって『隋書』に〈真臘国《カンボジア》に浮胡魚あり、その形※[魚+且]に似る、嘴|鸚※[母+鳥]《おうむ》のごとく八足あり〉、また『類函』四四九に『紀聞集』を引いて天宝四載広州海潮に因って一蜈蚣を淹《ひた》し殺す、その爪を割《さ》きて肉百二十斤を得とあるも、鯨類か鮫類の死体の誤察から出た説だろう。以上拙考の大要を大正二年の『ノーツ・エンド・キーリス』十一巻七輯に載せ更に念のため諸家の批評を求めると、エジンボロのゼームス・リッチー博士の教示にいわく、エリアヌスが筆した蜈蚣鯨はゴカイ類のある虫だろう、ゴカイ類の頭に鬚あるを鼻に長鬚ありといい、尾に節ありて刺あるが鰕《えび》(または蝗《いなご》)に似、両側に足多くトリレミスごとく見ゆとは、ゴカイ類の身に二十対あり二百双の側足《パラポチア》ありて上下二片に分れ波動して身を進むる様に恰当《よくあた》り、鯨は古人が大きな海産動物を漠然総称したので、英国ノルウェー北米等の海から稀に獲るネレイス・ヴィレンスちゅう大ゴカイの長《たけ》一フィートより三フィートで脊色深紫で所々|黯青《あんせい》また緑ばかりで光り、脇と腹は肉色であるいは青を帯びたる所がヨンストンのいわゆるその身全く青く脇と腹赤を帯ぶに合いいる、ローマのプリニウス等かかるゴカイを海蜈蚣《スコロベントラ・マリナ》と号《な》づけ、鈎《はり》を呑めばその腸をまるで吐き出し鈎を去って腸を復呑《のみもど》すと書きいるとあって、この鈎一件についても説を述べられ予と論戦に及んだがここに要なければ略す、女文豪コンスタンス・ラッセル夫人よりも書面で教えられたは、哲学者ジョン・ロック一六九六年(わが元禄九)鮭の胃を剖《さ》いて得た海蚣をアイルランドの碩学で英学士会員だったモリノー男に贈り、男これを解剖してロンデレチウスやヨンストンの蜈蚣鯨とやや差《ちが》う由を述べ、ロックの記載とともに同年版行したとあって、熊楠がこの学問上の疑論を提出した功を讃められたが、対手《あいて》が高名の貴婦人だけにその書翰《しょかん》を十襲して「書くにだに手や触れけんと思うにぞ」と少々神経病気味になって居る。さてこれらの教示を得てますます力を得また捜索するとプリニウスの海蜈蚣の事は、リッチー博士より前にクヴィエーが既《はや》そのゴカイ類たる由を述べ居る、もっとも、博士とは別な点から起論されたが帰する所は一で、ここに引いても動物専門の人でなくては解らぬ、このクヴィエーは最高名な動物学者で一世ナポレオンに重用されて仏国学政の枢機を運用し、ブルボン家恢復後も内務大臣になると間もなく死んだ、定めて眼が舞うほど忙しかった身を以て海蜈蚣の何物たるまで調べいたは、どこかの大臣輩がわずかな酒に酔っ払ったり芸妓に子を生ませたりして能事とすると大違いだ、それからゴカイ類には、サモア島で年に二朝しか獲れずしたがって王に限って食うたパロロ・ヴェリジス、わが国備前の海蛭、支那の土笋や禾虫(畔田翠嶽《くろだすいがく》の『水族志』に出《い》づ)など食品たるものもあるが、その形背皆|蚯蚓《みみず》に足を添えたようで魚釣りの餌にするのみ食い試みぬ人が多い、一五六八年版ジャク・グレヴァン・ド・クレルモンの『毒物二書《ド・リヴル・ジュ・ヴェナン》』一三八頁に古人一種の蜈蚣を蛇殺し(オフィオクテネ)といい能く蛇を咋《く》い殺したとあって、貝原先生同様人の唾が蜈蚣の大敵たる由を言うたは、秀郷唾を鏃《やじり》に塗りて大蜈蚣を殺したというに合う、それから海蜈蚣すなわちゴカイが人を咬《か》めば毒あるのみならず触れても蕁麻《いらくさ》に触れたように痛むというた、十二年前東牟婁郡勝浦港に在った時、毎度その近傍の綱切島辺の海底に黄黒斑で二、三間も長い海蜈蚣が住むと聞いて例の法螺談《ほらばなし》と気に留めなんだが、右のごとく教示やら調査やらで気が付き当田辺湾諸村人に質《ただ》すと諸所で夏日海底から引き揚げて石灰に焼く菊銘石《きくめいいし》の穴に一尺から一間ほど長い海蜈蚣が棲むと聞いて前祝いに五、六升飲んで出懸けると炎日のため件《くだん》の虫がたちまち溶け腐りて漆のごとくなりおった、よほど大きな物で容れる器がないとの事だ、以上述べたところで秀郷蜈蚣退治の先駆たる加賀の海島で蜈蚣海を游いで大蛇と戦った譚も多少根拠あるものと別《わか》り、また貝原氏が蜈蚣鯨大毒ある由記したのも全嘘《まるうそ》でないと知れる、氏の『大和本草』に長崎の向井元升《むかいげんしょう》という医者の為人《ひととなり》を称し毎度諮問した由記しあれば、蜈蚣鯨の一項は向井氏が西洋人か訳官《つうじ》から聞き得て貝原氏に伝えたのかも知れぬ、第八図はゴカイの一種ネレイス・メガロプスが専ら水を游ぐ世態をやや大きく写したので、大小の違いはあるが実際海蜈蚣また蜈蚣鯨の何様《いかよう》の物たるを見るに足る。
「第7図」のキャプション付きの図 「第8図」のキャプション付きの図 |
|
|
これを要するに秀郷竜宮入りの譚は漫然無中有を出した丸嘘談でなく、事ごとにその出処根底ある事上述のごとく、そのうち秀郷一、二の矢を射損じ第三の矢で蜈蚣を射留めたと言うに類した那智の一蹈※[韋+鞴のつくり]《ひとつたたら》ちゅう怪物退治の話がある、また『近江輿地誌略』に秀郷竜女と諧《かの》うたという談については、古来諸国で竜蛇を女人の標識としたり、人と竜蛇交わって子孫生じたと伝え、〈夜半人なく白波|起《た》つ、一目赤竜出で入る時〉など言い竜蛇を男女陰相に比べて崇拝した宗義など、読者をぞっとさせる底の珍譚山のごとく、上は王侯より下|乞丐《こつがい》に至るまで聞いて悦腹せざるなく、ロンドンに九年|在《い》た中、近年大臣など名乗って鹿爪らしく構え居る奴原《やつばら》に招かれ説教してやり、息の通わぬまで捧腹《ほうふく》させ、むやみに酒を奢《おご》らせる事毎々だったが、それらは鬼が笑う来巳の年の新年号に「蛇の話」として出すから読者諸君は竜の眼を瞼《みは》り蛇の鎌首を立て竢《ま》ちたまえというのみ。ついでに言う、秀郷の巻絹や俵どころでなく、如意瓶《にょいがめ》とて一切欲しい物を常に取り出して尽きぬ瓶を作る法が『大陀羅尼末法中一字心呪経』に出で居る、慾惚《よくぼ》けた人はやって見るが宜《よろ》しい。(大正三[#「三」に「ママ」の注記]年十二月六日起稿、大竜の長々しいやつを大多忙の暇を窃《ぬす》んで書き続け四[#「四」に「ママ」の注記]年一日夜半成る)(大正五年三月) |
|
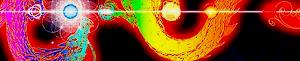 ■蛇に関する民俗と伝説 / 南方熊楠 |
|
| 『古今要覧稿』巻五三一に「およそ十二辰に生物を配当せしは王充の『論衡』に初めて見たれども、『淮南子《えなんじ》』に山中|未《ひつじ》の日主人と称うるは羊なり、『荘子』に〈いまだかつて牧を為さず、而して※[爿+羊]《しょう》奥に生ず〉といえるを『釈文』に西南隅の未地《ひつじのち》といいしは羊を以て未《ひつじ》に配当せしもその由来古し」と論じた。果してその通りなら十二支に十二の動物を配る事戦国時既に支那に存したらしく、『淮南子』に〈巳の日山中に寡人と称せるは、社中の蛇なり〉とある、蛇を以て巳に当てたのも前漢以前から行われた事だろうか。すべて蛇類は好んで水に近づきまたこれに入る。沙漠無水の地に長じた蛇すら能く水を泳ぎ、インドで崇拝さるる帽蛇《コブラ》は井にも入れば遠く船を追うて海に出る事もあり。されば諸国でいわゆる水怪の多くは水中また水辺に棲《す》む蛇である(バルフォール『印度事彙』蛇の条、テンネント『錫蘭博物志《ナチュラル・ヒストリ・オヴ・セイロン》』九章、グベルナチス『動物譚原《ゾーロジカル・ミソロジー》』二)。わが邦でも水辺に住んで人に怖れらるる諸蛇を水の主というほどの意《こころ》でミヅチと呼んだらしくそれに蛟※[虫+罔]※[虫+礼のつくり]等の漢字を充《あ》てたはこれらも各支那の水怪の号《な》故だ。現今ミヅシ(加《かが》能《のと》)、メドチ(南部)、ミンツチ(蝦夷)など呼ぶは河童なれど、最上川と佐渡の水蛇|能《よ》く人を殺すといえば(『善庵随筆』)、支那の蛟同様水の主たる蛇が人に化けて兇行するものをもとミヅチと呼びしが、後世その変形たる河童が専らミヅシの名を擅《ほしいまま》にし、御本体の蛇は池の主淵の主で通れどミヅチの称を失うたらしい。かく蛇を霊怪《ふしぎ》視した号《な》なるミヅチを、十二支の巳《し》に当て略してミと呼んだは同じく十二支の子《し》をネズミの略ネ、卯《ぼう》を兎の略ウで呼ぶに等し。また『和名抄』に蛇《じゃ》和名《わみょう》倍美《へみ》、蝮《ふく》和名《わみょう》波美《はみ》とあれば蛇類の最も古い総称がミで、宣長の説にツチは尊称だそうだから、ミヅチは蛇の主の義ちょうど支那で蟒《うわばみ》を王蛇と呼ぶ(『爾雅』)と同例だろう。さてグベルナチスが動物伝説のもっとも広く行き渡ったは蛇話だといったごとく、現存の蛇が千六百余種あり。寒帯地とニューゼーランドハワイ等少数の島を除き諸方の原野山林沼沢湖海雑多の場所に棲み大小形色動作習性各同じからず、中には劇毒無類で人畜に大難を蒙《こうむ》らするもあれば無毒ながら丸呑みと来る奴も多く古来人類の歴史に関係甚だ深い。故にこれに関する民族と伝説は無尽蔵でこれを概要して規律正しく叙《の》ぶるはとても拙筆では出来ぬ。だが昨年三月号竜の話の末文に大分メートル高く約束をしたから、今更黙ってもおれず、ざっと次のごとく事項を分け列ねた各題目の下に蛇についての諸国の民俗と伝説の一斑《いっぱん》を書き集めよう、竜の話に出た事なるべくまた言わぬ故|双《ふたつ》参《あわ》せて欲しい。 | |
| ■名義 | |
| 本居宣長いわく、「『古事記』の遠呂智《おろち》は『書紀』に大蛇とあり、『和名抄』に蛇和名|倍美《へみ》一名|久知奈波《くちなわ》、『日本紀私記』にいふ乎呂知《おろち》とあり、今俗には小さく尋常なるを久知奈波といひ、やや大なるを幣毘《へび》といふ、なほ大なるを宇波婆美《うわばみ》といひ、極めて大なるを蛇《じゃ》といふなり、遠呂智とは俗に蛇といふばかりなるをぞいひけむ云々」。またいわく、「『和名抄』に蛇和名倍美|※[虫+元]蛇《げんじゃ》加良須倍美《からすへみ》※[虫+冉]蛇《ぜんじゃ》仁之木倍美《にしきへみ》とありて幣美《へみ》てふ[「てふ」に「という」の注記]名ぞ主《むね》と聞ゆる、同じ『和名抄』蝮の条に、〈俗あるいは蛇を呼ぶに反鼻と為す、その音|片尾《へんび》〉といへるは和名倍美とは似たれども別なりと聞ゆ、反鼻は本より正名にあらず一名なるを、その音を取りて和名とすべきにあらず、それも上代この御国になかりし物は漢の一名などをも取りて名づくる例かれこれあれども、蛇などは神代よりある物なれば名もなかるべきにあらず云々、その上幣美といふ名は広くいひ習はしたるやうに聞ゆるをや、しかればこは反鼻の音と自然似たるのみなりけり」。また『和名抄』に蟒蛇《ぼうじゃ》、和名|夜万加々知《やまかがち》、『古事記』に赤加賀智《あかかがち》とは酸漿《ほおずき》なりとあれば、山に棲んで眼光強い蛇を山酸漿《やまかがち》といったのであろう。今もヤマカガシちゅう蛇赤くて斑紋あり山野に住み長《たけ》六、七尺に及び、剛強にして人に敵抗す。三河の俗説に愛宕または山神の使といい、雷鳴の際天上すともいう(早川孝太郎《はやかわこうたろう》氏説)。ありふれた本邦の蛇の中で一番大きいからこれを支那の巨蟒《きょぼう》に充《あ》てたものか。普通に蟒に充てるウワバミは小野蘭山これを『和名抄』の夜万加々智とす。深山に棲み眼大にして光り深紅の舌と二寸ばかりの小さき耳あり、物を食えば高鼾《たかいびき》して睡《ねむ》る由(『和漢三才図会』)、何かの間違いと見え近頃一向かかる蛇あるを聞かず。ただし昔到る処林野多くも深くもあった世には、尋常のヤマカガシなども今より迥《ずっ》と老大のもありたるべく、それらを恐怖もて誤察し種々誇大のウワバミ譚をも生じたなるべし、『本草綱目』には巨蟒《きょぼう》一名|鱗蛇《りんじゃ》と見えて、さきに書いたごとく大蛇様で四足ある大蜥蜴だが、〈蟒は蛇の最も大なるもの、故に王蛇という〉といい(『爾雅』註)、諸書特にその大きさを記して四足ありと言わぬを見れば、アジアの暖地に数種あるピゾン属の諸大蛇、また時にはその他諸蛇の甚だしく成長したのを総括した名らしい。ここに一例としてインド産のピゾン一種人に馴《な》るる状《さま》を示す(図略す)。これは身長二丈余に達する事あり。英人のいわゆる岩蛇《ロック・スネーク》だ。 | |
| 『和名抄』に仁之木倍美《にしきへみ》と訓《よ》んだ※[虫+冉]蛇は日本にない。予漢洋諸典を調べるに後インドとマレー諸島産なる大蛇ピゾン・レチクラツスに相違ない。この学名はその脊紋が網眼に似居るに基づき、すこぶる美麗でかの辺の三絃様な楽器の胴に張りおり、『本草』に〈※[虫+冉]蛇嶺南に生ず、大なるは五、六丈、囲り四、五尺、小なるも三、四丈を下らず〉とあるが、『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』十一版に南米熱地産なるアナコンダに次いで諸蛇の最大なるものとあり。アはベーツ説に四十フィートに達するそうだが、ピゾン・レチクラツスは三十フィートまで長ずというから『本草』の懸値《かけね》は恕《ゆる》すべしで、実に東半球最大の蛇だ。さて『本草』に〈身斑紋あり、故に錦纈《きんけつ》のごとし春夏山林中にて鹿を伺いてこれを呑む云々〉とあるは事実で、その肉や胆《い》の薬効を『本草』に記せると実際旅行中実験した欧人|輩《ら》の話とが十分二者を同物とする拙見を扶《たす》け立たしむ。マルコ・ポロ南詔国《なんしょうこく》の極めて大きな蛇を記して「その長《たけ》三丈ほど、太さ大樽のごとく、大きな奴は周り三尺ばかり、頭に近く二前脚あり、後足は鷹また獅子の爪ごとき爪でこれを表わすのみ、頭すこぶる大きく眼は巨なる麪麭《パン》より大きく、口広くして人を丸嚥《まるの》みにすべく歯大にして尖《とが》れり、これを見て人畜何ぞ戦慄せざらん、日中は暑ければ地下に躱《かく》れ夜出て食を覓《もと》め、また河や湖泉に行き水を飲む、その身重き故行くごとに尾のために地|凹《くぼ》む事大樽に酒を詰めて挽《ひ》きずりしごとし、この蛇往還必ず一途に由る故、猟師その跡に深く杭《くい》を打ち込み、その頂に鋭き鋼《はがね》の刃|剃刀《かみそり》様なるを植え、沙《すな》もて覆うて見えざらしむ。かかる杭と刃物を蛇跡へ幾つも設け置いたと知らないかの蛇は、走る力が速ければ刃の当りも強くしてやにわに落命してしまう、烏これを見て鳴くと、猟師が聞き付け走り来ると果して蛇が死んでおり、その胆を取りて高価に售《う》る。狂犬に咬まれた者少しく服《の》まば即座に治る、また難産や疥癬に神効あり、その肉また甘《うま》ければ人好んで購《あがな》い食う」と言った。『淮南子《えなんじ》』に、越人※[虫+冉]蛇を得て上《よき》肴《さかな》となせど中国人は棄て用いるなし。『嶺表録異』に、晋安州で※[虫+冉]蛇を養い胆を取りて上貢としたと載せ、『五雑俎』に、〈※[虫+冉]蛇大にして能く鹿を呑む、その胆一粟を口に※[口+禽]《ふく》めば、拷椋《ごうりゃく》百数といえどもついに死せず、ただし性大寒にして能く陽道を萎せしめ人をして子なからしむ〉。ランドの『安南風俗迷信記』にこの蛇土名コン・トラン、その脂を塗れば鬚生ずとあれば漢医がこれを大寒性とせるは理あり、『※[土へん+卑]雅』には〈※[虫+冉]蛇の脂人骨に著《つ》くればすなわち軟らかなり〉。さてマルコの書をユールが注して、これは鱷《がく》の事だろう、イタリアのマッチオリは鱷の胆が小|瘡《かさ》や眼腫に無比の良薬だといったと言うたは甚だ物足らぬ。両《ふたつ》ながら胆が薬用さるるからマルコの大蛇と鱷と同物だとは、不埒《ふらち》な論法なる上何種の鱷にもマルコが記したごとき変な肢がない。予|謂《おも》うにマルコはこの事を人伝《ひとづて》に聞書《ききがき》した故多少の間違いは免れぬ。すなわち頭に近く二前脚ありとは全く誤聞だが、ここに件《くだん》の大蛇が※[虫+冉]蛇すなわちピゾン・レチクラツスたる最も有力な証拠はすべて蛇類は比較的新しき地質紀に蜥蜴類が漸次四脚を失うて化成した物で、精確にこれまでが蜥蜴類これからが蛇と別つ事はならぬ。されば過去世のピゾノモルファ(擬蟒蛇《うわばみもどき》)など体長きこと蟒蛇に逼《せま》りながら確かに肢を具えていた。さて※[虫+冉]蛇《ボイダエ》群の蛇はおよそ六十種あり、熱帯アメリカのボアやアナコンダ、それから眼前予の論題たる※[虫+冉]蛇《ピゾン》、いずれも横綱|著《つき》の大蛇がその内にある。知人英学士会員プーランゼーは、※[虫+冉]蛇《ボイダエ》群は蛇のもっとも原始な性質を保存すと言った。その訳はこの一群の諸蛇蜥蜴を離るる事極めて遠からず、腰骨と後足の痕《あと》をいささかながら留めおり、すなわち後足の代りに何の役にも立たぬ爪二つ相対して腹下にある。これ正しくマルコが鷹また獅の爪ごとき爪が後足を表わすといえるに合い、南詔国(現時雲南省とシャン国の一部)辺に※[虫+冉]蛇(ピゾン・レチクラツス)のほか大蛇体でかかる爪もて後足を表わすものなければ、マルコは多少の誤りはあるとも※[虫+冉]蛇を記載した事疑いを容れず、予往年ロンドンに之《ゆ》きし時、この事をユールに報ぜんとダグラス男に頼むと、ユールは五年前に死んだと聞いて今まで黙りいたが、折角の聞を潰《つぶ》してしまうは惜しいから今となっては遼東の豕かも知れぬが筆し置く、この※[虫+冉]蛇もまた竜に二足のみあるてふ説の一因であろう。 | |
| 英語でサーペントもスネイクも、蛇とは誰も知り居るが、時にサーペント|および《エンド》スネイクと書いた文に遭《あ》う。その時は前者は人に害を加うる力ある蝮また蟒蛇等でその余平凡な蛇が後者だ。ヴァイパーとは上顎骨甚だ短く大毒牙を戴いたまま動かし得る蛇どもで、和漢の蝮もこれに属するからまず蝮と訳するほかなかろう。それからアスプといってエジプトの美女皇クレオパトラが敵に降らばその凱旋《がいせん》行列に引き歩かさるべきを恥じこの蛇に咬まれて自殺したとある。これはアフリカ諸方に多いハジ蛇なりという。これは既述竜の話中に図に出したインドのコブラ・デ・カペロ(帽蛇《ぼうじゃ》)に酷《よく》似るが喉後の眼鏡様の紋なし。インドで帽蛇を神視しまた蛇|遣《つか》いが種々戯弄して観《み》せるごとく古エジプトで神視され今も見世物に使わる物である。帽蛇は今も梵名ナーガで専ら通りおり、那伽《ナーガ》は漢訳仏典の竜なる由は既述竜の話で繰り返し述べた。また仏教に摩※[目+侯]羅伽《まほらか》てふ一部の下等神ありて天、竜、夜叉、乾闥婆《けんだつば》、阿修羅、金翅鳥《がるら》、緊那羅《きんなら》の最後に列《なら》んで八部を成す。いずれも働きは人より優《まし》だが人ほど前途成道の望みないだけが劣るという。この摩※[目+侯]羅伽は蟒神には大腹《たいふく》と訳し地竜にして腹行すと羅什《らじゅう》は言った。竜衆《ナーガ》すなわち帽蛇は毎度頭を高く立て歩くに蟒神衆は長く身を引いて行くのでこれは※[虫+冉]蛇《ピゾン》を神とするから出たのだ。 | |
| ■産地 | |
| ニューゼーランドハワイアゾールス等諸島や南北|冱寒《ごかん》の地は蛇を産せぬ。ギリシア海に小島多く相近きに産するところの物有無異同あり。例せばシフノス島には毒蛇あり、ケオス島に蠍《かつ》、アンチパロス島には蜥蜴のみありて全く蛇なし(ベントの『シクラデス』九〇頁)。『大和本草』に四国に狐なしというが『続沙石集』に四国で狐に取り付かれた話を載す。いずれが間違って居るかしら、『甲子夜話』に壱岐《いき》に※[鼬の由に代えて晏]鼠《うごろもち》なしとある。ロンドンなどは近代全く蛇を生ぜぬという、アイルランドは蛇なきを以て名高く、伝説にこれはパトリク尊者の制禁に因るという。この尊者の生国は定かならず、西暦三七二年頃生まれ十六歳で海賊に捉われアイルランドに売られて人奴となりしが脱《のが》れて大陸に渡り、仏国で修業およそ十四年ついに僧正となり法皇の命を奉じてアイルランドに伝道した。その国のドルイド教の僧輩反抗もっとも烈しかったので尊者やむをえずその沃野《よくや》を詛《とこ》うてたちまち荒れた沼となし川を詛うて魚を生ぜざらしめ缶子を詛うていくら火を多く焼《た》いても沸かざらしめ、ついにかの僧輩を詛うて地中に陥り没せしめた。一朝その徒と山中におり寒風堪ゆべからなんだ時、氷雪を集めて息を吹き掛けるとたちまち火となったと詠んだ詩人もある。尊者また太鼓を打ちてアイルランドから毒虫を駆り尽くすに余り力を入れ過ぎて太鼓中途で破れ、その挙また破れかかった時神使下ってこれを繕い目出たく悪虫を除き去り、爾来《じらい》永久この国の土に触れば蝮が即死する。この国の石や砂を他邦へ持ち行き毒虫を取り廻らせば虫その輪を脱け出で得ず皆死す。この国の木で圏《わ》を画くもまたしかり。一説に狼と鼬《いたち》と狐には利《き》かぬとあり。また一説にはこれら皆|空《うそ》で実は尊者の名パトリックをノールス人がパド・レクルと間違え蟾蜍《ひき》を(パダ)逐《お》い去る(レカ)と解した。蟾蜍を欧人は大変な毒物とするところから拡げて、すべての悪性動物を制禁して生ずるなからしめたというたんだそうな(チャンバース『日次事纂《ブック・オヴ・デイス》』二、『フォクロール』五巻四号)。アイスランドも蛇なきを以て聞えた。ボスエルの『ジョンソン伝』に、ジョンソンわれ能くデンマーク語でホレボウの『氷州《アイスランド》博物誌』の一章を暗誦《あんしょう》すと誇るので試《やら》せて見ると、「第五十二章蛇の事、全島に蛇なし」とあるばかりだそうな。熊楠ウェブストルの字書を見るとルジクラス(可笑《おかし》い)の例としてド・クインシーの語を引く。いわくファン・トロールの書に「アイスランドの蛇―なし」これだけを一章として居ると。前年一英人ファン・トロールの書をデンマークより取り寄せ仔細に穿鑿《せんさく》せしもかかる章を見ざりしと聞く。ド・クインシー例の変態精神から心得違うてかかる無実を言い出したなるべし。 | |
| ■身の大きさ | |
| ベーツの『|亜馬孫河畔の博物学者《ゼ・ナチュラリスト・オン・ゼ・リヴァー・アマゾンス》』アナコンダ蛇が四十二フィートまで長じた事ありと載せ、テッフェ河汀で小児が遊び居る所へアナコンダが潜み来て巻き付いて動き得ざらしめその父児の啼《な》くを聞きて走り寄り、奮って蛇の頭を執らえ両|齶《あご》を※[てへん+止]《ひ》き裂いたと言う。錦絵や五姓田《ごせだ》氏の油絵で見た鷺池平九郎の譚もまるで無根とも想われぬ。アマゾン辺の民|一汎《いっぱん》に信ずるはマイダゴア(水の母また精)とて長《たけ》数百フィートの怪蛇あり、前後次第して河の諸部に現わると。『千一夜譚《サウザンドナイツ・エンド・ア・ナイト》』に海商シンドバッド一友と樹に上り宿すると夜中大蛇来てその友を肩から嚥《の》みおわり緊《きび》しく樹幹を纏《まと》うて腹中の人の骨砕くる音が聞えたと出で、有名な東洋ゴロ兼|法螺《ほら》の日下|開山《かいさん》ピントはスマトラで息で人殺す巨蛇に逢ったといい、ドラセルダ、ブラジルのサンパウロを旅行中その僕《しもべ》大木の幹に腰掛くると動き出したから熟《よく》視《み》ると木でなくて大蛇だったと記した。『山海経《せんがいきょう》』に巴蛇《はじゃ》象を呑む、一六八三年ヴェネチア版ヴィンセンツオ・マリヤの『東方行記《イル・ヴィアジオ・オリエンタリ》』四一六頁にインドのマズレ辺に長九丈に達する巨蛇ありて能く象を捲き殺す、その脂は薬用さる、『梁書』に〈倭国獣あり牛のごとし、山鼠と名づく、また大蛇あり、この獣を呑む、蛇皮堅くして斫《き》るべからず、その上孔あり、乍《はや》く開き乍く閉づ、時にあるいは光あり、これを射て中《あつ》れば蛇すなわち死す〉。日本人たるわれわれ何とも見当の付かぬ珍談だが何か鯨の潮吹《しおふき》の孔などから思い付いた捏造《ねつぞう》説でなかろうか。昔ローマとカルタゴと戦争中アフリカのバグダラ河で長百二十フィートの蛇がローマ軍の行進を遮《さえぎ》った。羅《ロ》の名将レグルス兵隊をして大弩《おおゆみ》等諸機を発して包囲する事|塁砦《るいさい》を攻むるごとくせしめ、ついにこれを平らげその皮と齶をローマの一堂に保存した(プリニの『博物志《ヒストリア・ナチュラリス》』八巻十四章)。北欧の古伝に魔蛇ヨルムンガンド大地を囲める大洋にありて尾を口に啣《くわ》え大地を繞《めぐ》り、動く時は地震起る(マレー『北方考古篇《ノルザーン・アンチクイチース》』)。インドの教説に乳洋中にシェシャ蛇ありて常紐天《ヴィシュニュ》その上に眠る。この蛇頭に大地を戴く。『山海経』に〈崑崙《こんろん》山西北に山あり、周囲三万里、巨蛇これを繞り三周するを得、蛇ために長九万里、蛇この上におり、滄海《そうかい》に飲食す〉。十六年ほど前アンドリウスはエジプトで長六十フィートなる蛇の化石を発見した。 | |
| ■蛇の特質 | |
| 蛇の特質は述べ尽くされぬほどあるだろうから、思い出すままに少々書いて見る。豊後の三浦魯一氏の説に(『郷土研究』二巻三号、以下この雑誌を単に『郷』と書き、巻数と頁数は数字のみ挙ぐる)蛇を川に流しこっちに首を向ければ戻って来る。向う岸の方に向ければ帰って来ぬとあるは何でもない事のようだが、蟾蜍が首を向けたと反対の方へ行くと全く異《ちが》って面白い。『古史通』に「『神代巻抄』に人を呪詛《じゅそ》する符などをば後様《うしろざま》に棄つる時は我身に負わぬという、反鼻《へび》をも後様に棄つれば再び帰り来らずというと見えたり」、紀州西牟婁郡では今もこうして蛇を捨てる。本邦でも異邦でも蛇が往来|稀《まれ》ならぬ官道に夏日臥して動かぬ事がある。これは人馬や携帯品に附いて来る虫や様々の遺棄物を餌《くら》うためでもあろう。ルマニヤの俗伝にいわく昔犬頭痛甚だしくほとんど狂せんとし、諸所駈け廻るうち蛇に邂逅《でくわ》せ療法を尋ねた。蛇いわく僕も頭痛持ちだが蛇の頭痛療法を知ると同時に犬の頭痛療法を心得おらぬから詰まらない。犬いわく汝《おまえ》の事はどうでもよい、とにかく予《おれ》の頭痛を治す法を教えてくれ後生《ごしょう》だ。蛇いわくそれそこにある草を食べなされ、直ちに治ると、犬すなわち往きてその草を食い頭痛たちまち快くなった。人さえ背恩の輩多き世に犬が恩など知ろうはずなく、頭痛が治った意趣返しをやらにゃならぬと怪《け》しからぬ考えを起し、蛇を尋ねておかげで己の病は治ったが頃日《このごろ》忘れいた蛇の頭痛療法を憶《おも》い出したと語り、蛇に懇請されてそれなら教えよう、造作もない事だ、汝が頭痛したら官道に往って全く総身を伸ばして暫《しばら》く居れば輙《たやす》く治ると告げた。蛇教えのままに身を伸ばして官道に横たわり居ると、棒持った人が来て蛇を見付けると同時に烈しくその頭を打ったので、蛇の頭痛はまるで何処《どこか》へ飛んでしまった。蛇は犬の奸計とは気付かず爾来頭が痛むごとに律義に犬の訓《おし》え通り官道へ横たわり行く。つまり頭が打ち砕かれたら死んでしまうから療治も入《い》らず。幸い身を以て遁《のが》れ得たら太《ひど》く驚いて何処かへ頭痛が散ってしまうのである(一九一五年版ガスター著『羅馬尼《ルーマニア》禽獣譚』)。コラン・ド・プランシーの『妖怪字彙《ジクショネーランフェルナル》』四版四一四頁には、欧州に蛇が蛻《かわぬ》ぐごとに若くなり決して死なぬと信ずる人あるという。英領ギヤナのアラワク人の談に、往時上帝地に降《くだ》って人を視察した、しかるに人ことごとく悪くて上帝を殺そうとし、上帝怒って不死性質を人より奪い蛇蜥蜴甲虫などに与えてよりこれらいずれも皮脱で若返ると。フレザーの『|不死の信念《ゼ・ビリーフ・イン・インモータリチー》』(一九一三年版)一に、こんな例を夥しく挙げて昔|彼輩《かれら》と人と死なざるよう競争の末人敗れて必ず死ぬと定ったと信ずるが普通だと論じた。この類の信念から生じたものか、本邦で蛇の脱皮《ぬけがら》で湯を使えば膚《はだ》光沢を生ずと信じ、『和漢三才図会』に雨に濡れざる蛇脱《へびのかわ》の黒焼を油で煉《ね》って禿頭《はげあたま》に塗らば毛髪を生ずといい、オエンの『老兎巫蠱篇《オールド・ラビット・ゼ・ヴーズー》』に蛇卵や蛇脂が老女を若返らすと載せ、『絵本太閤記』に淀君妖僧日瞬をして秘法を修せしめ、己が内股の肉を大蛇の肉と入れ替えた。それより艶容|匹《たぐい》なく姿色衰えず淫心しきりに生じて制すべからず。ために内寵多しとあるは作事ながら多少の根柢はあるなるべし。本邦で蛇は一通りの殺しようで死に切らぬ故執念深いという。これに反し蝮は強き一打ちで死ぬ。『和漢三才図会』に蝮甚だ勇悍《ゆうかん》なり、農夫これを見付けて殺そうにも刀杖の持ち合せない時、これに向って汝は卑怯者だ逃げ去る事はならぬぞといい置き、家に還って鋤《すき》鍬《くわ》を持ち行かば蝮ちゃんと元のままに待って居る。竿でその頭を※[てへん+孑]《せせ》るにかつて逃げ去らず。徐々《そろそろ》と身を縮め肥えてわずかに五、六寸となって跳び懸かるその頭を拗《ひし》げば死すとある。蝮は蛇ほど速く逃げ去らぬもの故、人に詞《ことば》懸けられてその人が刀杖を取りに往く間待って居るなど言い出したのだ。 | |
| 英国や米国南部やジャマイカでは、蛇をいかほど打ち拗《ひし》ぐとも尾依然動きて生命あるを示し、日没して後やっと死ぬと信ず(『ノーツ・エンド・キーリス』十輯一巻二五四頁)。英のリンコルンシャーで伝うるは、蛇切れたら切片が種々動き廻り切り口と切り口と逢わば継ぎ合うて蘇る。それ故蛇を殺すにはなるべく多くの細片に切り※[坐+りっとう]《きざ》めばことごとく継ぎ合うに時が掛かる、その内に日が没《い》るから死んでしまうそうじゃ。日向《ひゅうが》の俗信に、新死《しんし》の蛇の死骸に馬糞と小便を掛けると蘇ると(『郷』四の五五五)。右リンコルンシャーの伝は欧州支那ビルマ米国に産する蛇状蜥蜴《オフィオサウルス》を蛇と心得て言い出したのだ。外貌甚だ蛇に似た物だが実は蜥蜴が退化して前脚を失い後脚わずかに二小刺となりいる。すべてこんな蜥蜴が退化してほとんどまたは全く四脚を失うたものと真の蛇を見分けるには、無脚蜥蜴の瞼《まぶた》は動くが蛇のは(少数の例外を除いて)動かぬ。蛇の下齶の前《さき》にちょっと欠けた所があって口を閉じながらそこから舌を出し得るが蜥蜴の口は開かねば舌を出し得ぬ。また蛇の腹は横に広くて脇から脇へ続いて大きな鱗一行(稀に二行)を被るに蜥蜴の腹は鱗七、八行またそれより少なくとも一行では済まぬ。それから蜥蜴の腹を逆《さか》さに撫でるに滑らかなれど、蛇の腹を逆撫ですると鱗の下端が指に鈎《かか》る。また無脚蜥蜴は蛇の速やかに走るに似ず行歩甚だ鈍い。さて蛇状蜥蜴《オフィオサウルス》はすべて三種あるが皆尾が体より遥かに長くその区分がちょっとむつかしい。その尾に夥《おびただ》しく節あり、驚く時非常な力で尾肉を固く縮める故ちょっと触《さわ》れば二、三片に断《き》れながら跳《おど》り廻る。これは蜥蜴の尾にも能く見るところで切った尾が跳り行くのに敵が見とれ居る間に蜥蜴は逃げ去るべき仕組みだ。こんな事から米国でも欧州でも蛇状蜥蜴《オフィオサウルス》を硝子蛇《グラス・スネーク》と呼ぶ。鱗が硝子《ガラス》様に光り長い尾が硝子のごとく脆《もろ》く折れるからだ。したがって支那にも『淮南子』に神蛇自らその尾を断ち自ら相続《あいつ》ぐ、その怒りに触ればすなわち自ら断つ事刀もて截《た》つごとし、怒り定まれば相就《あいつ》いて故《もと》のごとし。『潜確類書』に〈脆蛇一名片蛇、雲南の大侯禦夷州に出《い》づ、長二尺ばかり、人に遇わばすなわち自ら断ちて三、四となる人去ればすなわちまた続《つな》ぐ、これを乾して悪疽《あくそ》を治す云々〉。米国でも硝子蛇ちょっと触れば数片に折《さ》け散りまた合して全身となるといい、それより転じて真の蛇断れた時|艾《よもぎ》のような草で自ら続《つ》ぎ合すという(オエン『|老兎および巫蠱篇《オールド・ラビット・ゼ・ヴーズー》』)。 | |
| プリニウス言う、ハジ(アフリカの帽蛇)の眼は頭の前になくて顳※[需+頁]《こめかみ》にあれば前を見る事ならず、視覚より足音を聴いて動作する事多しと。テンネントの『錫蘭博物志《ゼ・ナチュラル・ヒストリー・オブ・セイロン》』にいわく、セイロンで蛇に咬まるるはほとんど皆夜なり。昼は人が蛇を見て注意すれど闇中不意に踏まば蛇驚いて正当防禦で咬むのだ。故に土人闇夜外出するに必ず錫杖《しゃくじょう》を突き蛇その音を聴いて逃げ去ると。しかるに蝮は逃ぐる事遅いから英国労働者などこれを聾と見、その脊の斑紋実は文字で歌を書いて居るという。その歌を南方先生が字余り都々逸《どどいつ》に訳すると「わが眼ほど耳がきくなら逃げ支度して人に捉《と》られはせぬものを」だ。鶯も蛙も同じ歌仲間というが敷島の大倭《おおやまと》での事、西洋では蝮が唄を作るのじゃ。蛇は多く卵で子を生むが蝮や海蛇や多くの水蛇や響尾蛇《ラトル・スネーク》は胎生だ。『和漢三才図会』に蝮の子生まるる時尾まず出で竹木を巻き母と子と引き合うごとく、出生後直ぐに這い行く、およそ六、七子ありという。ホワイトの『セルボルン博物志』には、蝮の子は生まるると直ぐ歯もないくせに人を咬まんとす、雛鶏|趾《けづめ》なきに蹴り、羔《こひつじ》と犢《こうし》は角なきに頭もて物を推し退くと記した。いわゆる蛇は寸にしてその気ありだ。蟾蜍《ひきがえる》など蛙類に進退|究《きわ》まる時頭を以て敵を押し退けんとする性あり。コープ博士だったかかくてこの輩の頭に追々角が生《は》える筈といったと覚える。支那の書に角ある蟾蜍の話あるは虚構とするも、予輩しばしば睹《み》た南米産の大蛙ケラトリフス・コルナタは両眼の上に角二つある。それ羔《こう》犢《とく》角なきに衝《つ》く真似し歯もなき蝮子が咬まんとするは角あり牙ある親の性を伝えたに相違ないが、件《くだん》のコープの説に拠ると、いずれも最初に衝こう咬もうという一念から牛羊の始祖は角、蝮の始祖は牙を生じたのだ。ブラウンの『俗説弁惑《プセウドドキシア》』三巻十六章にヘロドテ等昔の学者は、蝮子母の腹を破って生まる。これ交会の後雌蝮その雄を噛み殺す故、その子父の復仇に母の腹を破るのだと信じた。かく蝮は父殺しを悪《にく》むもの故ローマ人は父殺した人を蝮とともに嚢《ふくろ》に容れて水に投げ込み誅したと出《い》づ。ただし天主教のテクラ尊者は蛇坑に投げられ、英国中古の物語に回主がサー・ベヴィス・オブ・ハムプタウンを竜の牢に入れたなどいう事あれば、ローマ人のほかに蛇で人を刑した例は西洋に少なからぬじゃ。東洋では『通鑑《つがん》』に後漢の高祖が毒蛇を集めた水中に罪人を投じ水獄と名づけた。また仏経地獄の呵責を述ぶる内に罪人蛇に咬まるる例多きは、インドにも実際蛇刑があったに基づくであろう。わが邦にそんな実例のあった由を聞かねど、加賀騒動の講談に大槻蔵人一味の老女竹尾が彼輩姦謀|露《あら》われた時蛇責めに逢うたとあるは多分虚譚であろう。大水の時蛇多く屋根に集まり、わずかに取り縋《すが》りいる婦女や児輩が驚き怖れて手を放ち溺死する事しばしばあったと聞く。 | |
| 毒蛇が窘《くるし》められた時思い切って自分の身を咬んで絶命するという事しばしば聞いたが、毒蛇を酒精に浸すと困《くるし》んで七転八倒し、怒って自分の体に咬み付いたまま死ぬ事あり、また火を以て蠍《かつ》を取り囲むにその毒尾の尖《さき》を曲げて脊を衝いて死する事もあるが、これらは狂人が自身を咬むと等しく、決して企ててする自殺でなくまた毒分が自身を害するでもないから、ただ自殺と見えるばかりだ。朝鮮にある沖縄人から前日報ぜられたは、以前ハブ蛇多き山を焼くとかように自身を咬んだまま死んだハブばかり間《まま》見当った由。仏が寺門屋下に鴿《はと》蛇猪を画いて貪《どん》瞋《しん》痴《ち》を表せよと教え(『根本説一切有部毘奈耶』三四)、その他蛇を瞋恚《しんい》の標識とせる事多きは、右の擬自殺の体を見たるがその主なる一因だろう、古インド人も蛇自殺する事ありと信じたと見える。たとえば『弥沙塞五分律《みしゃそくごぶんりつ》』に舎利弗《しゃりほつ》風病に罹《かか》り呵梨勒果《かりこくか》一を牀脚辺に著《つ》けたまま忘れ置いて出た。瞿伽離《くがり》見付けて諸比丘に向い、世尊|毎《いつ》も舎利弗は欲少なく足るを知ると讃むるが我らの手に入らぬこの珍物を蓄うるは世尊の言と違うと言った。舎利弗聞いてその果《み》を棄てた。諸比丘それは大徳病気の療治に蓄えたのだから棄つるなかれと言うと、舎利弗われこの少しの物を持ったばかりに梵行人をして我を怪しましめたは遺憾なり、捨てた物は復《ふたた》び取れぬと答えた。仏|言《のたま》わく、舎利弗は一度思い立ったら五分でも後へ退《ひ》かぬ気質だ。過去世にもまたその通りだった。過去世一黒蛇あり、一犢子を螫《さ》した後穴に退いた。呪師羊の角もて呪したがなかなか出で来ぬから、更に犢子の前に火を燃して呪するとその火蜂と化《な》って蛇穴に入った黒蛇蜂に螫され痛みに堪えず、穴を出でしを羊角で抄《すく》うて呪師の前に置いた。呪師蛇に向い、汝かの犢を舐《ねぶ》って毒を取り去るか、それがいやならこの火に投身せよと言うと蛇答えて、彼この毒を吐いた上は還《また》これを収めず、たとい死ぬともこの意《こころ》を翻さぬと言いおわって毒を収めず自ら火に投じて死んだが舎利弗に転生《うまれかわ》った。死苦に臨むもなお一旦吐いた毒を収《とりい》れず、いわんや今更に棄つるところの薬を収めんやと。『十誦律毘尼序《じゅうじゅりつびにじょ》』にこの譚の異伝あり。大要を挙げんに、舎婆提《しゃばてい》の一居士諸僧を請《しょう》ぜしに舎利弗上座たり。仏の法として比丘の食後今日は飲食美味に飽満たりや否やと問う定めだったので、僧ども帰りて後仏が一子|羅喉羅《らごら》その時|沙弥《しゃみ》(小僧)たりしにかく問うに得た者は足り得ざる者は不足だったと答えた。仔細を尋ぬるに上座中座の諸僧は美食に飽きたが、下座と沙弥とは古飯と胡麻滓《ごまかす》を菜に合せて煮た麁食《そしょく》のみくれたので痩《や》せ弱ったという。仏舎利弗は怪《け》しからぬ不浄食をしたというを聞きて、舎利弗食べた物を吐き出し、一生馳走に招かれず布施を受けずと決心し常に乞食した。諸居士|何卒《なにとぞ》舎利弗が馳走を受けくれるよう仏から勧めて欲しいと言うと、仏|言《のたま》わく舎利弗の性もし受くれば必ず受けもし棄つれば必ず棄つ、過去世もまたしかりとて毒蛇だった時火で自殺した一件を説き種々の因縁を以て舎利弗を呵《しか》り、以後馳走に招かれたら上座の僧まず食いに掛からず、一同へあまねく行き届いたか見届けた後食うべしと定めたそうじゃ。而《しか》して件《くだん》の毒蛇を呪する法を舎伽羅呪《しゃがらじゅ》だと書き居る。そんなもの今もあるにや、一九一四年ボンベイ版エントホヴェンの『グジャラット民俗記《フォークロール・ノーツ》』一四二頁に或る術士は符※[竹かんむり/(金+碌のつくり)]《ふろく》を以て人咬みし蛇を招致し、命じて創口《きずぐち》から毒を吸い出さしめて癒す。蛇咬を療ずる呪を心得た術士は蛇と同色の物を食わず産蓐《さんじょく》と経行中の女人に触れると呪が利かなくなる。しかる時は身を浄《きよ》め洗浴し、乳香の烟を吸いつつ呪を誦《ず》して呪の力を復すと見ゆ。 | |
| ■蛇と方術 | |
| インドは毒蛇繁盛の国だけに、その呪法が極めて多い。『弥沙塞五分律』に、一比丘浴室の火を燃さんとて薪を破る時、木の孔より蛇出で、脚を螫《さ》して比丘を殺した。仏|言《のたま》わくかの比丘八種の蛇名を知らず、慈心もて蛇に向わず、また呪を説かずして蛇に殺されたとて、八種の蛇名を挙げたるを見るに、竜王の名多し。仏経の竜は某々の蛇にほかならぬからだ。その呪言は、〈我諸竜王を慈《いつく》しむ、天上および世間、わが慈心を以て、諸|恚毒《いどく》を滅し得、我|智慧《ちえ》を以て取り、これを用いこの毒を殺す、味毒無味毒、滅され地に入りて去る〉、仏曰く、この呪もて自ら護る者は、毒蛇に傷殺されずと。味毒無味毒とは、蛇の牙から出る毒液に、味あると味なきとあるを、古くインド人が試み知ったと見ゆ。 | |
| 一九〇六年版、ドラコット女史の『シムラ村話《ヴィレージ・テールス》』二一八頁にいわく、インドの小邦ラゴグールの王は、帽蛇《コブラ》を始め諸蛇の咬んだのを治す力を代々受け伝う。毒蛇に咬まれた人、糸一条を七所結び頸に掛け、ジェット・シン、ジェット・シンと唱え続けながら、王宮に趨《おもむ》く途中、結び目を六つまで解く、宮に入って王の前で、七つ目の結びを解く、時に王水をその創《きず》に灌《そそ》ぎ、また両手に懸け、一梵士来りて祈りくれると、平治して村へ還ると。トダ人蛇咬を療するに、女の髪を捻《ねじ》り合せて、創の近処三所括り呪言を称う(リヴァルス著『トダ人篇』)。いかなる理由ありてか、紀州でウグちゅう魚に刺されたら、一日ばかり劇しく痛み、死ぬ方が優《まし》じゃなど叫ぶ時、女の陰毛三本で創口を衝《つ》かば治るという。『郷土研究』二巻三六八頁にも、門司でオコゼに刺された処へ、女陰の毛三筋当て置けば、神効ありと出《い》づ。ある人いわく、ウグもオコゼも人を刺し、女は※[ゴマ]※[ゴマ]※[ゴマ]※[ゴマ]。その事大いに異なれど国言相通ず。陰陽和合して世間治安する訳だから、魚に一たび刺された代りに※[ゴマ]※[ゴマ]※[ゴマ]※[ゴマ]仇を、徳で征服する意で、女人の名代にその毛を用いるのだと。これは大分受け取りがたい。しかし女の髪といい、三という数がインドのトダ人の呪術にもあるが面白い。 | |
| 『古事記』にも、須佐之男命《すさのおのみこと》の女|須勢理毘売《すせりびめ》が、大国主命《おおくにぬしのみこと》に蛇の領巾《ひれ》を授けて、蛇室中の蛇を制せしめたとあれば、上古本邦で女がかかる術を心得いたらしい。インドの術士は能く呪して、手で触れずに蛇を引き出し払い去る(一九一五年版エントホヴェンの『コンカン民俗記』七七頁)。アツボットの『マセドニアン民俗《フォークロール》』に、かの地で蛇来るを留むる呪あり。「諸害物の駆除者モセスは、柱と棒の上に投鎗を加えて、十字架に像《かた》どり、その上に地を這う蛇を結い付けて、邪悪に全勝せり、モセスかくて威光を揚げたれば、吾輩は吾輩の神たるキリストに向いて唄うべし」という事だ。欧州で中古|禁厭《まじない》を行う者を火刑にしたが、アダム、エヴァの時代より、詛《のろ》われた蛇のみ厭《まじな》う者を咎《とが》めなんだ。蛇を見付けた処から、少しも身動きせざらしむる呪言は「汝を造れる上帝を援《ひ》いてわれ汝に、汝の機嫌が向おうが向くまいが、今汝が居る処に永く留まれと命じ、兼ねて上帝が汝を詛いしところのものを以て汝を詛う」というのだ(チャムバースの『ブック・オブ・デイス』一巻一二九頁)。『嬉遊笑覧』に、『萩原随筆』に蛇の怖るる歌とて「あくまたち我たつみちに横《よこた》へば、やまなしひめにありと伝へん」というを載せたり。こは北沢村の北見伊右衛門が伝えの歌なるべし。その歌は、「この路に錦|斑《まだ》らの虫あらば、山立姫に告《い》ひて取らせん」。『四神地名録』多摩郡喜多見村条下に、この村に蛇除《へびよけ》伊右衛門とて、毒蛇に食われし時に呪いをする百姓あり、この辺土人のいえるには、蛇多き草中に入るには、伊右衛門/\と唱えて入らば、毒蛇に食われずという、守りも出す。蛇多き時は、三里も五里も、守りを受けに来るとの事なり、奇というべしといえり。さてかの歌は、その守りなるべし。あくまたちは赤斑なるべく、山なし姫は、山立ひめなるべし。野猪をいうとなん、野猪は蛇を好んで食う、殊に蝮《まむし》を好む由なり。予在米の頃、ペンシルヴァニア州の何処《どこ》かに、蛇多きを平らげんとて、欧州より野猪を多く輸入し、放ちし事ありし。右の歌、蛇を悪魔とせしは、耶蘇《ヤソ》教説に同じ。梨《ありのみ》と言い掛けた山梨姫とは、野猪が山梨を嗜《この》むにや、識者の教えを竢《ま》つ。 | |
| 三河国|池鯉鮒《ちりふ》大明神の守符、蛇の害を避く。その氏子の住所は蛇なく、他の神の氏子の住所は、わずかに径《こみち》を隔つも蛇棲む。たといその境|雑《まじ》るもかくのごとし(『甲子夜話』続篇八〇)。和歌山近在、矢宮より出す守符は妙に蝮に利《き》く。蝮を見付けてこれを抛《な》げ付くると、麻酔せしようで動く能わずというが、予|尋常《なみ》の紙を畳んで抛げ付けても、暫くは動かなんだ。世に蝮指というは、指を緊張して伸ばし、先端の第一関節のみ折れ曲がりて、蛇の鎌頸状を成すので、五指ことごとくそうなるを苦手《にがて》といい、蛇その人を見れば怖れて動かず、自在に捕わるそうだ(『郷土研究』四の五〇二)。予の現住地の俗信に、蝮指の爪は横に広く、癪《しゃく》を抑うるに効あり、その人手が利くという。拙妻は左手のみ蝮指だから、亭主|勝《まさ》りの左|利《きき》じゃなかろうかと案じたが、実は一滴も戴《いただ》けませんから安心しやした。それからまた、苦手の人蟹を掴み、少時経つとその甲と手足と分れてしまうという、『仏説穣麌梨童女経』は、蛇を死活せしむる真言を説いた物だ。 | |
| 蛇で占う事、『淵鑑類函』四三九に、『詩経類考』を引いて、江西の人、菜花蛇てふ緑色の蛇を捕え、その蟠《わだかま》る形を種々の卦《け》と名づけ、禍福を判断し俚俗これを信ずと出《い》づ。『酉陽雑俎』に、蛇|交《つる》むを見る人は三年内に死す。ハツリットの『|諸信および民俗《フェース・エンド・フォークロール》』二に、古ローマ人は蛇の動作を見て卜《うらの》うた。ロッス説に、水蛇と陸上の蛇の闘いは、人民の不幸を予示すと。アツボットいわく、マセドニア人、首途《かどで》に蛇を見れば不吉として引き還すと。ラームグハリット言う、ニルカンス鳥は、女神シタージの使物として、インドに尊ばる帽蛇、蛙を啣《くわ》え、頭にこの鳥を載せて川を渡るを見る人は、翌年必ず国王となると。南方先生裸で寝て居る所へ、禁酒家の娘が百万円持参で、押し付け娵入《よめい》りに推し懸くるところを見た人はという事ほど、さようにあり得べからざる事である。 | |
| ハツリット説に、一八六九年アルゼリアのコンスタンチナ市裁判所で、夫が妻の貞操を疑うて、その鼻と上唇を截《き》った裁判あった時、妻の母いわく、この男は悋気《りんき》甚だしいから、妾それを止めんとて、高名な道士に蛇の頭を麻の葉に裹《つつ》んでもらい、婿の頭巾の襞《ひだ》の中へ入れるつもりでしたと言い、傍聴人に向って、何とこの法が一番能く利くでありませぬかと問うと、たちまちアラブ人数名頭巾を脱いで、銘々そうともそうとも、吾輩も悋気が豪《えら》いからこの通りと言って、件《くだん》の禁厭品《まじないもの》を取り出し示したが、陪席の土人官員一名、また判官の問いをも俟《ま》たず、僕も妻について焼かぬ間もなしだから、この通り蛇頭を戴きおります、蛇頭は男子を強力、女人を貞実ならしむる物ですと述べたそうだ。ブラックの『俚薬方篇《フォーク・メジシン》』五九頁に、英国サセックスの俗頸|腫《は》れた時、蛇を頸の上に挽《ひ》きずり、罎《びん》に封じ固く栓して埋めると、蛇腐るに随って腫れ減ずと見ゆ。これは英国で、蝸牛《かたつむり》や牛肉や林檎《りんご》に疣《いぼ》を移し、わが邦《くに》でも、鳥居や蚊子木葉《いすのきのは》に疣を伝え去るごとく、頸の腫れを蛇に移すのだ。紀伊、伊勢等で蛇の屍を丁寧に埋め、線香供え日参すれば、歯痛癒ると信じ、予小時毎度頼まれて蛇を殺した。中世スペインの天主教名僧、ロムアルドの遺骸を、分配供養して功徳とせんと、熱心の余り、上人《しょうにん》を殺さんとしたごとし。今となっては仔細判らざれど、初めは蛇の屍で歯を撫《な》で、痛みを移して埋めたであろう。三河で病人久しく一の場所で臥せば、青大将に血を吸わるという(『郷土研究』三の一一八)。 | |
| 『英国人類学会雑誌』十巻三〇九頁にいう、ソロモン島では、人の余食を神池の魚や蛇に食わせば、その人死すというと。インドのパンジャブで伝うるは、孕婦《ようふ》の影、蛇に懸れば、その蛇盲となると(『パンジャブ随筆問答雑誌』一)。また、コルベル・ロンギシムスは、医神エスクラピウスの使で、その到る処万病を除くとて、ローマの軍隊遠征にこの蛇数|疋《ひき》を伴れ行いた。米人リーランドの『俗伝に残った、ユトラスカとローマの旧習』(一八九二年ロンドン版)にいわく、「イタリアのロマニヤ地方の民、邪視と妖巫《ようふ》を避け、奇幸を迎うるため壁に蛇を画く、ただし尾を上に頭を下に、身体諸部混雑して結び居るを要す。また二、三の蛇、互いに纏うた処を編み物にして戸口に掲ぐる。ペルシアで絨氈《じゅうたん》の紋の条を、なるべく込み入って相|絡《から》んだ画にするも、邪視を禦《ふせ》ぐためだ」とあって、長々その理由を演《の》べ居る。すべてかくのごとく小むずかしく縺《もつ》れ絡んだ蛇の画を、護符として諸多の災害を避くるは、イタリアに限らず、例せば一切経中に見る火難|除《よ》けの符画も、熟《よく》視《み》るとやはり蛇の画だ。日本でも吾輩幼時、出雲の竜蛇、その他蛇の画符を悪魔除けとして、門戸に貼《は》ったのが多かった。リーランドいう、妖巫や邪視する人が、かく縺れ絡んだ物を見ると、線の始めから終りまで、細《くわ》しく視届けるその間に、邪念も邪視力も大いに弱り減ずる故、災難を起し得ぬ。ちょうど疳持《かんもち》の小児が、むつかしくぐずり掛かるところへ、迷宮様に道筋を引き廻した図や、縺れ解けぬ片糸を手渡せば、一心不乱にその方をほどきに懸る内、最初思い立ちいた小理窟は、忘れてしまうがごとしと。ここにいえる妖巫、英語でウィッチ、伊語でストレガ、女人殊に老女が、左道を修め鬼魅に事《つか》え、悪念を以て人畜を害する者で、中には世襲の妖巫輩出する部落も家族もある。而《しか》してその妖巫の眼力が邪視だ。本邦にも、飛騨《ひだ》の牛蒡《ごぼう》種てふ家筋あり、その男女が悪意もて睨《にら》むと、人は申すに及ばず菜大根すら萎《しぼ》む。他家へ牛蒡種の女が縁付いて、夫を睥《にら》むとたちまち病むから、閉口してその妻の尻に敷かれ続くというが、てっきり西洋の妖巫に当る。 | |
| 邪視英語でイヴル・アイ、伊語でマロキオ、梵語でクドルシュチス。明治四十二年五月の『東京人類学会雑誌』へ、予その事を長く書き邪視と訳した。その後一切経を調べると、『四分律蔵』に邪眼、『玉耶経』に邪盻《じゃけい》、『増一阿含』に悪眼、『僧護経』『菩薩処胎経』に見毒、『蘇婆呼童子経』に眼毒とあるが、邪視という字も『普賢行願品』二十八に出でおり、また一番好いようでもあり、柳田氏その他も用いられ居るから、手前味噌ながら邪視と定め置く。もっとも本統の邪視のほかにインドでナザールというのがあって、悪念を以てせず、何の気もなく、もしくは賞讃して人や物を眺めても、眺められた者が害を受けるので、予これを視害と訳し置いたが、これは経文に因って見毒と極《き》めるがよかろう。 | |
| 南欧や北アフリカからペルシア、インドに、今もこの迷信甚だ行われ、悪《にく》み蔑《みさぐ》るどころか賞めてなりとも、人の顔を見ると非常に機嫌を損じ、時に大騒動に及ぶ事あり。故に邪視を惧るる者、ことさらに悪衣を着、顔を穢《よご》し痣《あざ》を作りなどして、なるべく人に注視されぬようにし、あるいは男女の陰像を佩《お》びて、まず前方の眼力をその方に注ぎ弱らしむ。支那の古塚に、猥褻《わいせつ》の像を蔵《おさ》めありたり。本邦で書箱|鎧櫃《よろいびつ》等に、春画《まくらえ》を一冊ずつ入れて、災難除けとしたなども、とどの詰まりはこの意に基づくであろう。アイルランドには、古建築殊に寺院の前に、陰を露わせる女の像を立てたるものあり、邪視の者に強く睨まるれば火災等起る。しかるにその人の眼、第一に女陰の方へ惹《ひ》かれて、邪力幾分か減散すれば、次に寺院を睥んでも、大事を起さぬ。すなわち女陰が避雷柱《かみなりよけ》のような役目を務むるのじゃと。かの国人で、只今大英博物館人類学部長たるリード男の直話だった。わが邦で、拇指を食指と中指の間に挟《はさ》み出し人に示すは、汝好色なりという意という事だが、イタリア人などにそれを見せると、火のごとくなって怒る。それから殺人に及んだ例もある。自分を邪視力ある者と見定め、その害を避けんとて、陰相を作り示すと心得て怒るのだ。仏経に鴦掘魔《おうくつま》僧となり、樹下に目を閉じ居る。国王これを訪《おとな》い眼を開きて相面せよといいしに、わが眼睛|耀《てり》射《い》て、君輩当りがたしと答え、国史に猿田彦大神、眼|八咫鏡《やたのかがみ》のごとくにして、赤酸漿《あかかがち》ほど※[赤+色]《かがや》く、八百万《やおよろず》神、皆|目勝《まか》ちて相問うを得ずとある。いずれも邪視強くて、他《ひと》を破るなり。さて天鈿女《あまのうずめ》は、目人に勝《すぐ》れたる者なれば、選ばれ往きて胸乳《むなち》を露わし、裳帯《ものひも》を臍下に垂れ、笑うて向い立ち、猿田彦と問答を遂げたとあるは、女の出すまじき所を見せて、猿田彦の見毒を制服したのだ。 | |
| 『郷土研究』四巻二九六頁、尾佐竹猛氏、伊豆|新島《にいじま》の話に、正月二十四日は、大島の泉津村|利島《としま》神津島とともに日忌《ひいみ》で、この日海難坊(またカンナンボウシ)が来るといい、夜は門戸を閉じ、柊《ひいらぎ》またトベラの枝を入口に挿し、その上に笊《ざる》を被《かぶ》せ、一切外を覗《のぞ》かず物音せず、外の見えぬようにして夜明けを待つ。島の伝説に、昔泉津の代官|暴戻《ぼうれい》なりし故、村民これを殺し、利島に逃れしも上陸を許されず。神津島に上ったので、その代官の亡霊が襲い来るというのだが、どうも要領を得ぬとある。吾輩一家でさえ、父の若い時の事を、父に聞いても分らぬ事多く、祖父の少時の事を、祖父に聞くと一層解しがたく、曾祖高祖等が履歴を自筆せるを読むに、寝言また白痴のごとき譫語《たわごと》のみ、さっぱり要領を得ぬが、いずれも村の庄屋を勤めた人故、狂人にもあるまじ、その要領を得がたきは、彼らが朝夕見慣れいた平凡極まる事物一切が、既に変り移ってしまったから、彼らが常事と心得た事も、吾輩に取っては稀代の異聞としか想われぬに因る。 | |
| 一九〇三―四年の間、グリーンランドのエスキモ人の中に棲んだ、デンマルク人ラスムッセンの『|極北の人民《ゼ・ピープル・オヴ・ゼ・ポラー・ノース》』を読むに、輓近《ばんきん》エスキモ人がキリスト教に化する事多きより、一代前の事は全く虚誕のごとく聞えるが、遺老に就いて種々調べると、欧人が聞いて無残極まり、世にあり得べからずと思われる事や、奇怪千万な行いなどは、彼らに取ってはありふれた事で、欧人が聞くに堪えぬと惟《おも》う話のその聞くに堪えぬところが、彼らのもっとも面白がるところである。したがって欧人が何とも要領を得ず、拙作極まる小説としか受け取れぬ諸誕は、ことごとく実在した事歴を述べたものだと論じ居る。新島《にいじま》の伝説もこの通りで、代官暗殺云々は全く事実であろう。代官の幽公が来るのを懼れて、戸を閉じ夜を守ったも事実であろう。柊は刺で、トベラは臭気で悪霊を禦ぐは分りやすいが、笊《ざる》を何故用いるか。種彦《たねひこ》の『用捨箱《ようしゃばこ》』巻上に、ある島国にていと暗き夜、鬼の遊行するとて戸外へ出でざる事あり。その夜去りがたき用あらば、目籠を持ちて出るなり、さすれば禍なしと、かの島人の話なりといえるは、やはり新島辺の事で、昔は戸口にも笊を掛け、外出にも持ち歩いたであろう。種彦は、江戸で二月八日|御事始《おことはじめ》に笊を門口に懸けた旧俗を釈《と》くとて、昔より目籠は鬼の怖るるといい習わせり、これは目籠の底の角々は☆|如此《かく》晴明九字(あるいは曰く晴明の判)という物なればなり。原来の俗説、ただ古老の伝を記すと言ったが、その俗説こそ大いに研究に用立つなれ。すなわちこの星状多角形の辺線は、幾度見廻しても止まるところなきもの故、悪鬼来りて家や人に邪視を加えんとする時、まずこの形に見取れ居る内、邪視が利かなくなるの上、この晴明の判がなくとも、すべて籠細工の竹条は、此処《ここ》に没して彼処《かしこ》に出で、交互起伏して首尾容易に見極めにくいから、鬼がそれを念入れて数える間に、邪視力を失うので、イタリア人が、無数の星点ある石や沙や穀粒を、袋に盛って邪視する者に示し、彼これを算《かぞ》え尽くすの後にあらざれば、その力|利《き》かずと信ずると同義である。節分の夜、豆|撒《ま》くなども、鬼が無数の豆を数え拾う内に、邪力衰うべき用意であろう。 | |
| かつて強盗多かった村人に聞いたは、強盗盛んな年は、家に小銭を多く貯え置く、泥的御来臨のみぎり、二、三問答の上、しからばやむをえない、貴公らに金を仮りたとあっては相済まぬ、少々ながら有金すっかり進呈しよう、大臣にでもなったら返しくだされ、その節は、子供を引き立てくだされなど、能《いい》加減に述べて、引き出しを抽《ひ》いて、たちまち彼奴《かやつ》の眼前へ打ち覆《かえ》すと、無数の小銭が八方へ転がり走る。泥公一心これを手早く掻き込むに取り忙ぎ、銭の多寡を論じたり、凶器を弄《もてあそ》ぶに暇なく、集めおわりてヘイさようならで慌《あわ》て去るものだ。強盗に逢ったら僕の名を言いたまえ、毎度逢って善い顧客だから麁略《そりゃく》にすまい、貴下のような文なしには、少々置いて行くかも知れぬと教えくれたが、まだ一度も逢わぬから、折角の妙案も実試せぬ。全体予の事を、人々が女に眉毛を読まれやすいと言うを、いかにも眉毛が鮮かなと讃めてくれると思うたが、拙妻聞いて更に懌《よろこ》ばぬから、奇妙と惟《おも》いいた。ところが『郷土研究』四の四三三頁に、林魁一君が、美濃の俗伝を報じた内に、眉毛に唾《つば》を塗ると毛が付き合うて、狐その数を読む能わず、したがって魅《ばか》す事がならぬとあるを読んで大いに解り、〈人書を読まざればそれなお夜行のごとし〉と嘆じた。マアこんな訳故、新島の一条も、もと目籠を以て邪視を避くる風が、エジプト、インド、東京《トンキン》、イタリア等同様、日本にもありしが、新島ごとき辺土に永く留まった。そこへ代官暗殺されその幽霊の来襲を惧《おそ》るる事甚だしくなりて、今更盛んに目籠を以てこれを禦ぎしより、ついに専ら代官殺しが、日忌の夜笊を出す唯一つの起りのよう、訛伝《かでん》したのであろう。 | |
| 邪視は、人種学民族学、また宗教学上の大問題で、エルウォーシー等の著述もあり。本邦これに関する事どもは、明治四十二年五月の『東京人類学会雑誌』と、英京の『ネーチュール』に拙文を出したから、御覧を願うとして、改めて蛇と邪視の関係を述べんに、前述のごとく蛇の画もて、鬼や妖巫の邪視を禦ぎ、大効あると同時に、蛇自身の眼にも、強い邪視力があると信ずる民多し。いわゆる蛇の魅力(ファッシネーション)だ。 | |
| ■蛇の魅力 | |
| 『塵塚《ちりづか》物語』は、天文二十一年作という、その内にいわく「ある人の曰く、およそ山中広野を過ぐるに、昼夜を分たず心得あるべし、人気|罕《まれ》なる所で、天狗魔魅の類、あるいは蝮蛇を見付けたらば、逃げ隠るる時、必ず目を見合すべからず。怖ろしき物を見れば、いかなる猛《たけ》き人も、頭髪立て足に力なく振い出《い》づ。これ一心顛倒するに因ってかかる事あり。この時眼を見合すれば、ことごとくかの物に気を奪われて、即時に死するものなり。ほかの物は見るとも、構えて眼ばかりは窺《うかが》うべからず。これ秘蔵の事なり。たとえば暑き頃、天に向いて日輪を見る事暫く間あらば、たちまち昏盲として目見えず。これ太陽の光明|熾《さかん》なるが故に云々。万人に降臨して、平等に臨みたもう日天さえかくのごとし、いわんや魔魅|障礙《しょうげ》の物をや、毫髪《ごうはつ》なりとも便を得て、その物に化して真気を奪わんと窺う時、眼を見るべからずとぞ」。曖昧な文だが、日本にも邪視を怖るる人あり、蛇に邪視ありと信じた証に立つ。この論に、日の光が人の眼を眩ますを、邪視に比したは、古エジプトで諸神の眼力極めて強く、能く諸物を滅すとせるに似て面白い。たとえば、古エジプトの神ホルスは、日を右眼とし、月を左眼とし、その眼力能く神敵たる巨蛇アペプを剄《くびき》る。また神怒れば、その眼力叢林を剿蕩《そうとう》す。またラー神の眼、諸魔を平らぐるに足るなど信じた。『薩婆多論』に、むしろ身分を以て毒蛇口中に入るも、女人を犯さざれ、蛇に三事ありて人を害す、見て人を害すると、触れて害すると、噛んで害するとあり。蛇と等しく女人にも三害あり。もし女人を見れば、心欲想を発し人の善法を滅す、もし女人の身に触るれば、身中罪を犯し、人の善法を滅す。もし共に交会せば、身重罪を犯し人の善法を滅す。また七害あり。一には、もし毒蛇に害せらるればこの一身を害すれど、女人に害せらるれば、無数身を害す云々と、長たらしく女の害、遥かに蛇に勝《まさ》れる由数え立て居る。ここに蛇見て人を害すとあるは、インドでも蛇は邪視を行うとしたのだ。ただし女人には、邪視や見毒のほかに、愛眼というやつがあって、その効果もっとも怖ろしい。本町二丁目の糸屋の娘、姉が二十一、妹が二十、諸国諸大名は刃《やいば》で殺す、この女二人は、眼元で殺すと唄うこれなり。その糸屋はどうなったか、博文館は同町故、取り調べて史蹟保存とするがよい。要するに女人は、毒蛇よりも忌むべしなどいうは、今日に適せぬ愚論で、中古の天主徒が洗浴を罪悪として、某尊者は、幾年|浴《ふろ》に入らなんだなど特書したり、今日の耶蘇《ヤソ》徒が禁酒とか、公娼廃止とか喋舌《しゃべ》ると同程度の変痴気説じゃ。一六四四年、オランダで出版された『ヒポリツス・レジヴィヴス』てふ詩は、手苛《てひど》く婦女を攻撃したものだが、発端に作者自ら理論上女ほど厭な者はない、しかし実行上好きで好きで神と仰ぐと断わって居るは、最《いと》粋な人だ。惜しい事にはその本名が伝わらぬ。上に引いた『薩婆多論』の述者も、多分こんな性の坊主だろう。 | |
| 女の方へ脱線ばかりすると方付《かたづ》かぬから、また蛇の方へ懸るとしよう。まず蛇の魅力の豪い奴から始める。『酉陽雑俎』の十に、〈蘇都瑟匿国西北に蛇磧あり、南北蛇原五百余里、中間あまねき地に、毒気烟のごとくして飛鳥地に墜つ、蛇因って呑み食う〉、これは地より毒烟上りて、鳥を毒殺するその屍を蛇が食うのか、蛇がその磧《すなはら》一面に群居し、毒気を吐きて鳥を堕《おと》し食うのか判らぬ。蛇が物を魅するというは、普通に邪視を以て睥《にら》み詰めると、虫や鳥などが精神|恍惚《とぼけ》て逃ぐる能わず、蛇に近づき来り、もしくは蛇に自在に近づかれて、その口に入るをいうので、鰻が蛇に睥まれて、頭を蛇の方へ向け游《およ》ぎ、少しも逃げ出す能わなんだ例さえ記されある。『予章記』に、呉猛が殺せし大蛇は、長《たけ》十余丈で道を過ぐる者を、気で吸い取り呑んだので、行旅《たびびと》断絶した。『博物志』に、天門山に大巌壁あり、直上数千|仭《じん》、草木|交《こもご》も連なり雲霧|掩蔽《えんぺい》す。その下の細道を行く人、たちまち林の表へ飛び上がる事幾人と知れず。仙となりて昇天するようだから、これを仙谷と号《な》づけた。遠方から来て昇天を望む者、この林下にさえ往けば飛び去る。しかるにこれを疑う者あり、石を自分の身に繋《つな》ぎ、犬を牽《ひ》いて谷に入ると犬が飛び去った。さては妖邪の気が吸うのだと感付き、若少者《わかもの》数百人を募り捜索して、長数十丈なる一大|蟒蛇《うわばみ》を見出し殺した(『淵鑑類函』四三九)。 | |
| プリニウスいわく、ポンツスのリンダクス河辺にある蛇は、その上を飛ぶ鳥を取り呑む、鳥がどれほど高く速く飛んでも必ず捉わると。『サミュール・ペピスの日記』一六六一年二月四日の条に、記者ある人より聞いたは、英国ランカシャーの荒野に大蛇あり、雲雀《ひばり》が高く舞い上がるを見て、その真下まで這い行き口を擡《もた》げて毒を吐かば、雲雀たちまち旋《かえ》り堕ちて蛇口に入り、餌食となると書いた。コラン・ド・プランシーの『妖怪辞彙《ジクチョネーランフェルナル》』五版四一三頁に、ペンシルヴァニアの黒蛇、樹下に臥して上なる鳥や栗鼠《りす》を睥むと、たちまち落ちてその口に入るといい、サンゼルマンの『緬甸帝国誌《ゼ・バーミース・エンパイヤー》』に、ビルマ人は、蛇が諸動物を魅して口へ吸い込む、かつて大きな野猪が、虎と噛み合うていたところを、大蛇がこの伝で呑んだといい、帽蛇に睥まれた蛙は、哀鳴してその口に飛び入り食わるというとある。ペンナントいわく、響尾蛇《ラトル・スネーク》、樹上の栗鼠を睨めば、栗鼠|遁《のが》れ能わず悲しみ鳴く、行人その声を聞いて、響尾蛇がそこに居ると知る(熊楠、米国南部で数回かかる事あった)。栗鼠は樹を走り、上りまた下り、また上り下る。一回は一回より増えて多く下る。この間蛇は、栗鼠を見詰めて他念なく、人これに近づくもよほど大きな音せねば逃げず、最後に栗鼠蛇の方へ跳び下りるを、待ってましたと頂戴《ちょうだい》しおわると。ル・ヴァーヤンも、親《みずか》ら鳥が四フィートばかり隔てて、蛇に覘《ねら》わるるを見しに、身体|痙攣《ひきつり》て動く能わず。傍人蛇を殺して鳥を救いしも、全く怖れたばかりで死にいた証拠には、その身を検《しら》べしに少しも疵《きず》なかった。また二ヤードほど距てて蛇に覘わるる鼠を見しに、痙攣《ひきつり》て大苦悩したが、蛇を追い去って見れば鼠は死にいたりと。米国のバートンこれを評して、世に事々《ことごと》しく蛇の魅力というは、蛇に覘《ねら》わるる鳥獣がその子供の命を危ぶみ恐れて叫喚するまでの事で、従来魅力一件を調べると、奇とすべき事がただ一つあるのみ、それは観察も相応に、理解もよい人にして、なおこんな愚説を信ずる一事だと言ったが、フェーラーが言ったごとく、蛇に執《とら》われ啖《く》わるるまで一向蛇を恐れぬ動物も、やはり蛇に魅せられるから、魅力すなわち恐怖とも言えぬ。 | |
| 明治十九年秋、予和歌山近傍岩瀬村の街道傍の糞壺の中に、蛙が呻《うめ》くを聞き、就《つ》いて見ると尋常《なみ》の青大将が、蛙一つ銜《くわ》え喉へ嚥《の》み下すたびに呻くので、その傍に夥しく蛙がさして、驚いた気色もなく遊び游《およ》ぎ居るを、蛇が一つ呑みおわりてまた一つ、それからまた一つと夥しく取って啖うのだ。予四十分ばかり見ていたが、大分腹も日も北山に傾いて来たから、名残《なごり》惜しげに立ち去った。この場合、もし魅力これ恐怖といわば、壺中で四十分も自在に游ぎ廻る間に、一疋くらいは壺から外へ逃げそうなものだ。しかるに阿片に酔わされた女が、踏み蹴《け》られても支那人の宅を脱せぬごとく、朋輩《ほうばい》が片端から啖わるるを見、呻き声を聴きながら、悠々と壺中に游ぎて壺外に跳び出ぬは、魅力が恐怖と別事たるを証する。洵《まこと》や蛇は寸にしてその気ありで、予当時動物心理学などいう名も知らなんだが、よほど奇妙と思うて、当日の日記に書き留め居る。ロメーンズは諸家の説を審査した後、ある動物は蛇に睥まれて精神混乱し、進退度を失うて逃れぞこない、蛇の口に陥り、また蛇近く走り行くのだろうと言った。 | |
| 川口孫次郎氏説に、蛇が苺《いちご》を食うという俗説あり。実際について観察すると、蛇が苺を食うでなくて、苺の蔭に潜《ひそま》り返って水に渇した小鳥が目に立ちて、紅い苺を取りに来るところを捉《と》るのらしいと(『飛騨史壇』二巻九号)。『酉陽雑俎』十六に、〈蛇に水草木土四種あり〉、水や草叢《くさむら》に棲む蛇は本邦にもあり。支那の両頭蛇(蜥蜴《とかげ》の堕落したもの)などは土中に住む。純《もっぱ》ら樹上に住む蛇は熱地に多く、樹葉や花と別たぬまで美色で光る。これは無論他動物をして、蛇自身の体の、花や葉と思い近付かしめて捉うる擬似作用で、本邦のある蛇が苺の下に隠れて鳥を捕うると同じ働きだ。さて予幼年の頃、しばしば蟾蜍《ひき》を育てたが、毎度蟾蜍が遠方にある小虫を見詰むると、虫落ちてそれに捉わるるを見、その後|爬虫《はちゅう》や両棲類や魚学の大家、英学士会員ブーランゼー氏に話すと、そんな事があるものかと笑われたが、人に笑われる者、必ずしも間違って居るにも限らぬと思い、帰朝後長々蛙類を飼い試むるに、幼年の時驚いたほどの事が今も実現する。壺の中へカジカ蛙をあまた容《い》れ、網蓋《あみぶた》の小孔より蠅を入れると、直様《すぐさま》蛙の口へ飛び込んで嚥まるるもあれば、暫時して蛙の方へ飛び行き捉わるるもある。熟《とく》と観察するに、壺中の石の配置や光線が網眼に映る工合、蠅を飛び下す小孔の位地から蠅を持ち行きやる人の手の左右など、雑多の事情に応じて、蠅が孔より飛び入る方角|趨勢《すうせい》がほぼ定まりある。蛙のうち最も賢き奴一疋これを知りて、その日蠅が飛び入りて、必ず一度留まるべき処に上り俟《ま》ちて居ると、蠅をやるごとにちょうどその蛙の口に吸わるるごとく飛び行きて啖わる。五、六度もかくのごとくで一つも過《あやま》たぬ。その蛙が飽き足りて食わぬとなると、今度は蠅が飛び入りて、この蛙の辺にちょっと留まり、更に転下して岩の上の蛙の口に堕つる事、魅力もて吸わるるごとし。もしそれを脱るると、また他の蛙の方へ飛び行きて啖わる。能々《よくよく》観ると、岩面よりも岩の上に高坐した蛙の方が留まりやすき故、蠅が留まりに行って啖われるので、これらも大抵野猪と同じく、蠅の飛ぶ道筋が定まりおり、その道筋に当る所々に、蛙が時移るごとに身を移して、頭を擡《もた》げて待ちいるので、時と位置により、蛙の色種々に少しながら変るもなるべく蠅を惹《ひ》き寄せる便りとなるらしい。一度|忰《せがれ》が牧牛場から夥しく蠅を取り、翼を抜いて嚢《ふくろ》に容れ持ち来り、壺の蓋を去って一斉に放下せしに、石の上に坐しいた蛙ども、喜び勇んで食いおわったが、例の一番賢い蛙は、最初人壺辺に来ると知るや、直様《すぐさま》蓋近き要処に跳び上がり、平日通り蠅を独占しようと構えいたが、右の次第で、全く己より智慧《ちえ》の劣った者どもにしてやられ、一疋も蠅が飛ばねば一疋も口に入らず、極めて失望の体だった。 | |
| 蛇の魅力はまだ精査せぬが、蟾蜍《ひき》が毒気を吹いて、遠距離にある動物を吸い落すというはこんな事で、恐怖でも何でもなく、虎や大蛇アナコンダが、鹿来るべき場所を知りて待ち伏せするような事で、蟾蜍や蛙の舌は、妙に速く出入するがあたかも吸い落すよう見ゆるのじゃ。レオナードの『下《ラワー》ナイジァー|およびその諸民族《エンド・イツ・トライブス》』に、アジュアニなる蛇、玉を体内に持ち、吐き出して森中に置き、その光で鼠蛙等を引き寄せ食い、さてその玉を呑み納む。その玉円く滑らかにして昼青く夜光る。この玉を食中に置かば諸毒を避く。ただし蛇の毒には利かず。この玉を取らば光を失えども諸動物を引き寄する力は依然たる故、猟師これを重んじ高価に売買すとあって、著者の評に、これは蛇が眼を以て魅する力あるを、大層に言い立てたのであろうとある。 | |
| ■蛇と財宝 | |
| 竜の条で書いた通り、欧亜諸国で伏蔵すなわち財宝を匿《かく》した処にしばしば蛇が棲むより、竜や蛇が財宝を蓄え護るという伝説が多い。また吝嗇家《しわんぼう》死して蛇となるともいう。『十誦律』に、大雨で伏蔵|露《あらわ》れたのを仏が見て、毒蛇だというと、阿難も悪毒蛇だといって行き過ぎた。貧人聞き付けて往き見れば財宝多し。それを持ち帰って大いに富む。その人と不好《ふなか》な者が、この者宝蔵を得ながら王に告げぬは不埒《ふらち》と訴えければ、王召してことごとくその財物を奪うたとあるを、『沙石集』などに、財は人に禍する事毒蛇に等し、故に仏も阿難も、かく言ったと解したは最もだが、全体インドでは、伏蔵ある所必ず毒蛇が番すると一汎《いっぱん》に信ずるより、時に取ってかかる名言を吐いたのだ。『南史』に、〈梁武帝元洲苑に幸《みゆき》し、大蛇道に盤屈し、群小蛇これを繞るを見る、みな黒色、宮人曰く恐らくこれ銭竜ならん、帝銭十万貫を以て蛇処を鎮め、以てこれを厭す〉、これ支那でも蛇を銭の神としたのだ。 | |
| アルバニアは俗伝に蛇が伏蔵を護り時々地上へ曝《さら》して、財宝に錆《さび》や黴《かび》の付くを防ぐ。牧羊人かつて蛇が莫大の金を巻けるを見、予《かね》て心得いた通り牛乳一桶をその辺に置き潜み窺うと、案の定かの蛇来て乳を飲み尽くし、また金を巻きいたが、渇いて何ともならずついに遠方へ水を求めに往った。その間に牧羊人大願成就|忝《かたじけ》ないと、全然《そっくり》その金を窃《ぬす》み得た(ハーンの『アルバニッシュ・スチュジエン』巻一)。ハクストハウセンが記したはアルメニア人言う、昔アレキサンドル王、その地にその妻妾を封じ込め、蛇をして守らしめたとあるも美女を財貨と同視しての談だ。インドで今も伝うるは、財を守る蛇はすこぶる年寄りで色白く体に長毛あり、財を与えんと思う人の夢にその所在を教え、その人寤《さ》め往きてこれを取らば、蛇たちまち見えなくなると(一九一五年版エントホヴェンの『コンカン民俗記《フォークロール・ノーツ》』七六頁)。また身その分にあらざるに、暴力や呪言もてかかる財を取った者は、必ず後嗣|亡《な》しと(同氏の『グジャラット民俗記』一四〇頁)。『類聚名物考』七は『輟耕録』を引いて、宋帝の後胤《こういん》趙生てふ貧民が、木を伐りに行って大きな白蛇己を噬《か》まんとするを見、逃げ帰って妻に語ると、妻白鼠や白蛇は宝物の変化《へんげ》だといって夫とともに往き、蛇に随って巌穴に入り、黄巣《こうそう》が手ずから※[やまいだれ+(夾/土)]《うず》めた無数の金銀を得大いに富んだというが、世俗白鼠を大黒天、白蛇を弁財天の使で福神の下属《てした》という。西土の書にも世々いう事と見ゆと載す。 | |
| かく蛇が匿れた財宝を守るというより転じて、財宝が蛇に化《な》るとか、蛇の身が極めて貴い効用を具うるてふ俗信が生じた。ドイツの古話に、蛇の智慧ある王一切世間の事を知る。この王|昼餐《ちゅうさん》後、必ず人に秘して一物を食うに、その何たるを識《し》る者なし。その僕これを奇《あや》しみ私《ひそか》にその被いを開くと、皿上に白蛇あり、一口|嘗《な》むるとたちまち雀の語を解し得たので、王の一切智の出所を了《さと》ったという。北欧セービュルクの物語に、一僕銀白蛇の肉一片を味わうや否や、よく庭上の鶏や鵝《が》や鶩《あひる》や鴿《はと》や雀が、その城間もなく落つべき由話すを聴き取ったとあり。プリニウス十巻七十章には、ある鳥どもの血を混ぜて生きた蛇を食べた人能く鳥語を暁《さと》ると載す。ハクストハウセンの『トランスカウカシア』にいわく、ある若き牧牛人|蛇山《オツエザール》の辺に狩りし、友に後《おく》れて単《ひと》り行く、途上美しき処女が路を失うて痛《いたく》哭《なげ》くに遭《あ》い、自分の馬に同乗させてその示す方へ送り往く内、象牙の英語で相惚《アイボレー》と来た。女言う、妾実は家も骨内《みうち》もない孤児だが、ふと君を一日|見《み》進《まい》らせてより去りがたく覚えた熱情の極、最前のような啌《うそ》を吐《つ》いたも、お前と夫婦に成田山《なりたさん》早く新勝寺《しんしょうじ》を持って見たいと聞いて、男も大いに悦び伴《つ》れ帰って女房にした。ところが一日インドの道人《ファキル》遣って来り、その指環に嵌《は》めた層瑪瑙《オニキス》の力で即座にかの女を蛇の変化《へんげ》と知ったというのは、この石変化の物に逢わばたちまち色を失うからだ。道人すなわち窃《ひそ》かにその由を夫に告げ、啌と思うなら物は試《ため》し、汝の妻にその最も好む食物を煮|調《ととの》わしめ、密《そっ》と塩若干をその中に投じ、彼が遁《のが》れ得ぬよう固く家を鎖《とざ》し、内には水一滴も置かず熟睡したふりで厳に番して見よと教えた。夫その通りして成り行きを伺うとは知るや知らずや、白歯のかの艶妻が夜に入りて起き出で、家中探せど水を得ず、爾時《そのとき》妻|頸《くび》限りなく延び長じ、頭が烟突から外へ出で室内ただ喉の鳴るを聞いたので、近処の川の水を飲み居ると判った。夫これを見て怖れ入り、明日道人に何卒《なにとぞ》妻を除く法を授けたまえと乞うと、道人教えて、妻をして麪麭《パン》を焼かしめ竈《かまど》に入れんとて俯《うつむ》くところを火中に突き落し、石もて竈口を閉じ何ほど哀願しても出でしむるなかれ、出ださば汝は必ず殺されんと言った。夫またその通り行い、妻竈中で種々言い訳すれど一向心を動かさぬを見極め、ああ道人わが秘密を君に洩らした、彼はわが灰を獲んと望むのだ、君わが秘密を知ったと気付いたなら、われは君を活かし置かなんだはずだと叫んで焼け死んだ。美妻の最後の無惨さに、夫悔い悲しむ事限りなく、精神|魍魎《もうりょう》として家を迷い出で行方知れずなってしまった。道人恐悦甚だしく、残らずかの蛇女の灰を集め、一切の金属を黄金に点化し、大金持に成らんしたそうだ。 | |
| エストニアの伝説に、樵夫《きこり》二人林中で蛇をあまた殺し行くと、ついに蛇の大団堆《おおかたまり》に逢い、逃ぐるを金冠戴ける蛇王が追い去《はし》る。一人|振廻《ふりかえ》り斧でその頭を打つと、蛇王金塊となった。サア事だと前の処へ還れば、蛇の団堆でなくて黄金ばかり積まれいた。因ってこれを分ち取り、その半を以て、寺一つ建てたという。わが邦も竹林などに蛇夥しく聚《あつ》まる事あり、蛇の長競《せいくら》べと俗称す。また熊野などに、稀に蝮が群集するを蝮塚と呼ぶ(『中陵漫録』巻十二に見ゆ)。なに故と知らねど、あるいは情欲発動の節至って、匹偶《つれあい》を求むるよりの事かと惟う。諸邦殊に熱地にはこんな事多かるべく、伏蔵ある所においてするもしばしばなるべければ、したがって蛇王宝玉を持つ説も生じただろう。アルメニア人信ずらく、アララット山の蛇に王種あり、一牝蛇を選んで女王と立つ。外国の蛇群来り攻むれど、諸蛇脊に女王を負う間は、敵敗れ退く。女王睨めば敵蛇皆力を失う。この女王蛇口にフルてふ玉を含み、夜中空に吐き飛ばすと、日のごとく輝くと。これいわゆる蛇の長競べが、海狗《オットセイ》や蝦蟆《がま》同様、雌を争うて始まるを謬《あやま》り誇張したのだ。 | |
| 『甲子夜話』八七に、文政九年六月二十五日、小石川三石坂に蛇多く集まり、重累《かさな》りて桶のごとし、往来人多く留まり見る。その辺なる田安殿の小十人の子、高橋千吉十四歳いう、箱のごとく蛇の重なりたる中には必ず宝ありと聞くとて、袖をかかげ右手を累蛇の中に入れたるに肱《ひじ》を没せしが、やや探りて篆文《てんぶん》の元祐通宝銭一文を得、蛇は散じて行方知れずと。田舎にては蛇塚と号《な》づけて、往々ある事とぞとありてその図を出だし、径《わたり》高さ共に一尺六、七寸と附記す(第一図[#図省略])。竜蛇が如意《にょい》宝珠《ほうしゅ》を持つてふ仏説は、竜の条に述べた。インドのコンカン地方で現時如意珠というは、単に蛇の頭にある白石で、これを取ればその蛇死す。蛇に咬まれた時これをその創《きず》に当つれば、たちまち毒を吸って緑色となるを、乳汁に投ずれば毒を吐いて白色に復《かえ》り乳は緑染す。かように幾度も繰り返し用い得という。またいわく、老蛇体に長毛あるは、その頭に玉あり、その色虹を紿《あざむ》く、その蛇夜これを取り出し、道を照らして食を覓《もと》む。深い藪中に棲み人家に近づかず、神の下属《てした》なれば神蛇《デブア・サールバ》と名づく。サウシの『随得手録《コンモンプレース・ブック》』二に、衆蛇に咬まれぬよう皮に身を裹《つつ》み、蛇王に近づき撻《う》ち殺してその玉を獲たインド人の譚《はなし》あり。 | |
| エストニアの俚談にいわく、ある若者奇術を好み、鳥語を解したが、一層進んで夜中の秘密を明らめんと方士に切願した。方士その思い止まるが宜《よろ》しかろうと諫《いさ》めたれど聞き入れぬから、そんならマルク尊者の縁日の夜が近付き居る、当夜蛇王が七年目ごとの例で、某処で蛇どもの集会を開くはず、その節蛇王の前に供うる天の山羊乳を盛った皿に麪麭《パン》一片を浸し、逃げ出す先に自分は口に入れ得たら、夜中の秘密を知り得ると教えた。やがて尊者の縁日すなわち四月二十五日が昏れると、件《くだん》の若者方士が示した広い沢へ往くと、多くの小山のほか何にも見えず、夜半に一小山より光がさした。これ蛇王の信号で、今まで多くの小山と現われて動かず伏しいた無数の蛇ども、皆その方へ進み行き、小山ついに団結して乾草|堆《たい》の大きさに積み累《かさ》なった。若者恐る恐る抜き足して近寄り見れば、数千の蛇が金冠を戴いた大蛇を囲み聚《あつ》まりいた。若者血|凝《かたま》り毛|竪《た》つまで怖ろしかったが、思い切って蛇群中に割り込むと、蛇ども怒り嘯《うそぶ》き、口を開いて咬まんとすれど、身々密に相《あい》纏《まと》うて動作自在ならず、かれこれ暇取る内に、若者蛇王の前の乳皿に麪麭《パン》を浸し、速やかに口に含んで馳《か》け出した。衆蛇|追躡《ついじょう》余りに急だったから、彼ついに絶え入った。旭の光身に当って、翌旦蘇り見れば、かの沢を距つる既に四、五マイル。早《はや》何の危険もないから、終日眠って心身を安め、次夜果して望むところの霊験を得たが、試しのため林中に入るとたちまち浴場が現われ、ただ見る金の腰掛けと、銀の垢磨《あかす》り、銀の盥《たらい》が美々しく列《つら》なりあった。小杜《こもり》の蔭に潜んで覗《のぞ》きいると、暫時して妍華超絶|止《ただ》に別嬪どころでなく、真に神品たる処女、多人数諸方より来り集い、全く露形して皎月《こうげつ》下に身を洗う。正にこれ巫女廟の花は夢の裡《うち》に残り、昭君村の柳は雨のほかに疏《おろそ》かなる心地して、かの者餓鷹の※[奚+隹]を見るがごとく、ただ就いてこれ食いおわらんと要したが、また思い返していずれ菖蒲《あやめ》と引き煩い、かれこれと計較《くらべみ》る内、惜しきは姿、東方明けなんとすると、一同たちまち消え失せた。これら美女、実は草野《かやの》の女王の娘どもで、各森林の精たり。その後今一度彼らの艶容を窺わんと、夜々脚を林中に運べど、処女も浴場も再び現われず、あてもない恋の焔《ほのお》に焦れ死んだ。されば忘れても夜中の秘密研究など志すべきでない。 | |
| それから『想山著聞奇集』に、武州で捕えた白蛇の尾尖《おさき》に玉ありたりとて、図を出す。尾尖に大きな小豆《あずき》粒ほどの、全く舎利玉通りなる物、自ずから出来いた由見ゆ。十六年ほど前、和歌山なる舎弟方の倉に、大きな黄頷蛇《あおだいしょう》の尾端|夙《と》く切れて、その痕《あと》硬化せるを見出したが、ざっとこの図に似いた。余り不思議でもなきを、『奇集』に玉と誇称したのだ。毎度尾を引き切れた蛇はかようになるらしく、ロンドン等の地下鉄道を徘徊する猫の尾が、短くなると同じ理窟だ。かく尾切れた蛇を神とし、福を祈る風大和に存すと聞いた。『郷土研究』一巻三九六頁に見た中国の蛇神トウビョウも蛇に似て短いとは、かかる畸形の一層烈しいのでなかろうか。インドのカーシャ|丘《ヒルス》地方の迷信に、蟒蛇《うわばみ》が人家に寓《やど》れば大富を致す。悪人諸方を廻り人を殺して、耳鼻唇髪を切り取り、蟒蛇に捧げて自家に招きおらしむ。土民これを怖れて単身藪林に入らず、蟒蛇を奉崇する家は、何ほど物を売るも更に減らず、したがって金が殖えるばかりちゅう旨《うま》い話だ(一八四四年版『ベンガル亜細亜協会雑誌』十三巻六二八頁)。 | |
| ■異様なる蛇ども | |
| 前項にいった、わが邦中国のトウビョウ蛇神が、体短く中太いというについて、必ず聯想さるるは、野槌《のづち》という蛇である。『沙石集』に叡山の二僧相約して、先立ちて死んだ方が後《おく》れた者にきっと転生《うまれかわ》り、所を告ぐべしといった後、まず死んだ僧が残った僧の夢に見えて、我は野槌に生まれたといった。それは希《まれ》に深山にある大きな獣で、目鼻手足なく口ばかりありて人を食う。これ名利を専らにして仏法を学び、口先のみ賢く、智の眼、信の手、戒の足一つもなかったから、かかるのっぺら坊に生まれたと出《い》づ。『和漢三才図会』には、これを蛇の属としいわく、〈深山木竅中これあり、大は径五寸、長《たけ》三尺、頭尾均等、而して尾尖らず、槌の柄なきものに似る、故に俗に呼びて野槌と名づく、和州吉野山中、菜摘川、清明の滝辺に往々これを見る、その口大にして人脚を噬《か》む、坂より走り下り、甚だ速く人を逐う、ただし登行極めて遅く、この故にもしこれに逢わば、すなわち急ぎ高処に登るべし、逐い著く能わず〉。『紀伊続風土記』に、ほとんど同様の事を記し、全身蝮のごとく、噛まば甚だ毒あり、牟婁郡山中稀に産す、『嶺南雑記』に、〈瓊州冬瓜蛇あり、大きさ柱のごとくして長《たけ》ただ二尺余、その行くや跳び躍る、逢々として声あり、人を螫《さ》し立ちどころに死す〉とあると同物だろうという。予が聞き及ぶところ、野槌の大きさ形状等確説なく、あるいは※[鼬の由に代えて晏]鼠《もぐらもち》様の小獣で悪臭ありというが、『沙石集』の説に近い。あるいは、長五、六尺で面桶《めんつう》ほど太く、頭が体に直角をなして附した状、槌の頭が柄に著いたごとしといい、あるいは長二尺ほどの短大な蛇で、孑孑《ぼうふり》また十手を振り廻すごとく転がり落つとも、馬陸《やすで》ごとく環曲《まがっ》て転下すともいい、また短き大木ごとき蛇で大砲を放下するようだから、野大砲《のおおづつ》と呼ぶ由を伝え、熊野広見川で実際見た者は、蝌斗《かえるこ》また河豚《ふぐ》状に前部肥えた物で、人に逢わば瞋《いか》り睨み、大口開きて咬まんとする態すこぶる滑稽《おどけ》たりといった。日高郡川又で聞いたは、この物|倉廩《くら》に籠《こも》る事往々ありと。また大和丹波市近処に捕え来て牀下《ゆかした》に畜《か》うと、眼小さく体|俵《たわら》のように短大となり、転がり来て握り飯を食うに、すこぶる迂鈍《うどん》なるを見たと語った人あり。写真を頼むと安く受け合《い》れたが、六、七年も音沙汰を聞かぬ。 | |
| 野槌は最初神の名で、諾冉二尊が日神より前に生むところ、『古事記』に、野神名|鹿屋野比売《かやぬひめ》、またの名|野椎《ぬつち》の神という。『日本紀』に、草祖草野姫《くさおやかやぬひめ》またの名|野槌《のづち》と見えて草野の神だ。その信念が追々堕落する事、ギリシアローマの詩に彫刻に盛名を馳《は》せた幽玄絶美な諸神が、今日|藪沢《そうたく》に潜める妖魅に化しおわったごとくなったものか。『文選』の和訓には、支那の悪鬼|人間《じんかん》にありて怪害を作《な》すてふ野仲《やちゅう》をノヅチと訳した。それからちょうど古ギリシアローマの名神に、蛇妖となり下ったものあるように、野槌も草野の神から悪鬼、次に上述通りの異態な蛇を指す号《な》と移ったものか。 | |
| 今より千十余年前成った『新撰字鏡』に、蝮を乃豆知《のづち》と訓《よ》んだ。ほとんど同時に出来た『延喜式神名帳』、加賀に野蛟神社《のづちのやしろ》二所あり。『古事記伝』に拠れば、ノヅチは野の主の意らしい。予山中岸辺で蝮を打ち殺したつもりで苔など探し居ると、負傷した蝮が孑孑《ぼうふり》様に曲り動いて予の足もとに滑り落ち来れるに気付き、再び念入れて打ち絶やした事三、四回ある。したがって俗伝の野槌は、かように落ち来る蝮から生じた譚で、あるいは上世水辺の蛇を、ミヅチすなわち水の主、野山の蝮をノヅチ野の主と見立てたのかとも思う。ただし野槌に似た動物が、実際世界にないでなく、例せばウロペルチス(円盾《ペルタ》状の尾の義)の一族およそ四十種、南インドとセイロンに産す。山林の土中に棲み、眼至って小さく、両齶に歯あり、尾甚だ短く太く、斜めに截《き》り取られたようで、その端円盾のごとく、その表面|粗《あら》し。それを地に押し著けて歩く、その状あたかも古欧州の軍士が円盾を手で使い分けたごとく、わが邦人に解るように言うなら、塚原老翁が鍋蓋を以て宮本武蔵と立ち廻ったごとしだ。紀州でモッコクの木を食う蠹《きくいむし》に、ちょうど同様の尾を同様に使うのがあるが何というものか知らぬ。予はウロペルチスの生きたのを見た事なけれど、類推すると余り活溌なものでなかろうが、周章《あわて》る時は孑孑様に騒ぎながら、岸より落ちて人を驚かすほどの事はあろう。 | |
| 支那でいわゆる冬瓜蛇はこの族のものかと惟《おも》うが日本では一向見ぬ。『西遊記』一に、肥後五日町の古い榎《えのき》の空洞《ほら》に、長《たけ》三尺余|周《めぐ》り二、三尺の白蛇住む。その形犬の足なきかまた芋虫に酷《よく》似たり。所の者|一寸坊蛇《いっすんぼうへび》と呼ぶ。人を害せざれど、顔を見合せば病むとて、その木下を通る者頭を垂るとあり。デル・テチョの『巴拉乖《パラガイ》等の史』に、スペインのカベツア・デ・ヴァカが、十六世紀の中頃ペルーに入った時、八千戸ある村の円塔に、一大蛇住み、戦死の尸《しかばね》を享《う》け食い、魔それに托して予言を吐くと信ぜられた。その蛇長二十五フィート、胴の厚さ牛ほどで、頭至って厚く短きに、眼は不釣り合いに小さく輝く、鎌のごとき歯二列あり。尾は滑《すべ》だが、他の諸部ことごとく大皿様の鱗を被る。兵士をして銃撃せしむると大いに吼《ほ》え、尾で地を叩き震動せしめた故、一同仰天せしもついに殺しおわったと載せ、一八八〇年版ボールの『印度藪榛生活《ジャングル・ライフ・イン・インジア》』には、インド山間の諸王が、世界と伴うて生死すと信じ、崇拝するナイク・ブンスてふ蛇を目撃せし人の筆録を引いていわく、この蛇岩窟に棲み、一週に一度出て、信徒が献じた山羊児や鶏を啖《くら》い、さて堀に入りて水を飲み、泥中に転び廻りついに窟に返る。その泥上に印した跡より推さば、この蛇身長に比して非常に太く径二フィートを過ぐと。これら諸記に依って測るに、東西両世界とも時にある種の蛇が特異の病に罹り、全体奇態に太り過ぎるのでなかろうか。早川孝太郎氏説に、三河で蛇が首を擡《もた》げたところを撃たば飛び去る。それを捜し殺し置かぬと、ツトまたツトッコてふ頭ばかりの蛇となる。その形槌に類する故、槌蛇と呼んだと記憶すと。佐々木繁氏来示には、陸中遠野地方で、草刈り誤って蛇の首を斬ると、三年経てその首槌形となり仇をなす。依ってかかる過失あった節は、われの故《せい》じゃない、鎌の故だぞと言い聞かすべしというと。これらどうやら上古蛇を草野《かやの》の主とし、野槌と尊んだ称《となえ》から訛《あやま》り出《い》でた俗伝らしい。 | |
| 米国にやや野槌に似た俗信ある蛇フップ・スネークを産す。フップとは北※[窗/心]翁が、「たがかけのたがたがかけて帰るらん」と吟じた箍《たが》すなわち桶輪だ。この蛇赤と黒と入り乱れて斑を成し、瑳《みが》いた磁器ごとく光り、長三|乃至《ないし》六フィート、止期《やみご》なしに種々異様に身を曲げ変る。それを訛ったものか、昔人この蛇毒を以て他動物を殺さんとする時、口に尾を銜《ふく》みて、箍《たが》状《なり》になり、電《いなずま》ほど迅く追い走ると言ったが、全く啌《うそ》で少しも毒なし、しかし今も黒人など、この蛇時に数百万広野に群がり、眼から火花を散らして躍り舞う、人その中に入れば躍り囲まれて脱し得ず、暈倒《うんとう》に及ぶと信ずる由。牡牛蛇《ブル・スネーク》も米国産で、善《よ》く牡牛のごとく鳴くと虚伝さる。一八五六年版アメリア・モレイの『米国等よりの書翰集』で見ると、当時ルイジヤナ州に牛の乳を搾《しぼ》る蛇あり、犢《こうし》のごとく鳴いて牝牛を呼び、その乳を搾ったという。支那の南部に蛇精多く人に化けて、旅人の姓名を呼ぶ。旅人これを顧み応《こた》うれば、夜必ずその棲所《とまり》に至り人を傷つく、土人枕の中に蜈蚣《むかで》を養い、頭に当て臥し、声あるを覚ゆれば枕を啓《ひら》くと蜈蚣|疾《と》く蛇に走り懸り、その脳を啗《くら》うというは大眉唾物だ(『淵鑑類函』四三九)。 | |
| 一八六八年版コリングウッドの『博物学者支那海漫遊記《ラムブルス・オブ・ア・ナチュラリスト・オン・ゼ・チャイナ・シー》』一七二頁注に、触れたら電気を出す蛇を載す。一七六九年版、バンクロフトの『ギヤナ博物論』二〇八頁にいう火蛇《ファイア・スネーク》は、ギアナで最も有毒な蛇だが、好んで火に近づき火傍に眠る印度人《インデアン》を噛むと。またいう、コンモードは水陸ともに棲む、長《たけ》十五フィート周十八インチ、頭|扁《ひらた》く濶《ひろ》く、尾細長くて尖《とが》る、褐色で脊と脇に栗色を点す。毒なしといえどもすこぶる厄介な代物で、しばしば崖や池を襲い鵞や鶩《あひる》を殺す。土人いわく、この蛇自分より大きな動物に会えば、その尖った尾を敵手の肛門に挿し入れてこれを殺す、故にその地の白人これを男色蛇《ソドマイト・スネーク》と称うと。どうも虚譚《うそ》らしいが、これにやや似て実際今もあるはブラジルのカンジル魚だ。長わずか三厘三毛ほどで甚《いと》小便の臭《にお》いを好み、川に浴する人の尿道に登り入りて後、頬の刺《とげ》を起すから引き出し得ず。これを以てアマゾン河辺のある土人は、水に入る時|椰子殻《やしがら》に細孔を開けて男根に冒《かぶ》せる。また仏領コンゴーの土人は、最初男色を小蛇が人を嚥《の》むに比し、全然あり得べからぬ事と確信した(デンネットの『フィオート民俗篇』)。 | |
| 件《くだん》の男色蛇に似た事日本にもありて、『善庵随筆』に、水中で人を捕り殺すもの一は河童、一は鼈《すっぽん》、一は水蛇、江戸近処では中川に多くおり、水面下一尺ばかりを此岸《しがん》より彼岸《ひがん》へ往く疾《はや》さ箭《や》のごとし。聢《しか》と認めがたけれど大抵青大将という蛇に似たり、この蛇水中にて人の手足を纏《まと》えど捕り殺す事を聞かず。また出羽最上川に薄黒くして扁《ひらた》き小蛇あり、桴《いかだ》に附いて人を捕り殺すという。この蛇佐渡に最《いと》多しと聞く、河童に殺された屍は、口を開いて笑うごとく、水蛇の被害屍は歯を喰いしばり、向歯《むこうば》二枚欠け落ち、鼈《すっぽん》に殺されたのは、脇腹章門辺に爪痕入れりと見え、『さへづり草』には、水辺一種の奇蛇あり、長七、八寸より二尺余に至る。色白く腹薄青く、人の肛門より入りて臓腑を啖い、歯を砕きて口より出《い》づ、北国殊に多し、越後にて川蛇、出羽にてトンヘビなどいえるものこれなり(熊楠故老に聞く、トンとは非道交会の義)と云々。さればこの蛇の害に依って水死せる者を、その肛門の常ならざるについて、皆|水虎《かっぱ》の業とはいい習わしたるものか云々。また女子の陰門《まえ》に蛇入りしといえるも、かの水蛇の事なるべし。かかれば田舎の婦女たりとも必ず水辺に尿する事なかれ、といいおる。予在英のうち本邦の水蛇について種々取り調べたが、台湾は別として本土に一種もあるらしくなかった。現住地田辺附近で、知人が水蛇らしいものを釣った事を聞くに、蛇らしくも魚らしくもあって定かならぬ。上述北国の水蛇は評判だけでも現存するや。諸君の高教を冀《こいねが》う。柳田君の『山島民譚集』に、河童の類語を夥しく蒐《あつ》めたが、水蛇については一言も為《さ》れ居ぬ。本篇の発端にも述べ懸けた通り、支那の竜蛟蜃など、蛇や鱷《がく》や大蜥蜴に基づいて出来た怪動物が常に河湖淵泉の主たり。時に人を魅し子を孕ます。日本の『霊異記』や『今昔物語』に、蛇女に婬して姙ませし話や、地方に伝うる河童が人の妻娘に通じて子を産ませた談が能《よ》く似て居る。 | |
| また河童が馬を困《くる》しむる由諸方で言う。支那でも蛟が馬を害した譚が多く、『※[土へん+卑]雅《ひが》』にその俗称馬絆とあるは、馬を絆《つな》ぎ留めて行かしめぬてふ義であろう。『酉陽雑俎』十五に、〈白将軍は、常に曲江において馬を洗う、馬たちまち跳り出で驚き走る、前足に物あり、色白く衣帯のごとし、※[榮の木に代えて糸]繞《えいじょう》数|匝《そう》、遽《にわか》にこれを解かしむ、血流数升、白これを異《あやし》み、ついに紙帖中に封じ、衣箱内に蔵《かく》す、一日客を送りて※[さんずい+産の旧字]水に至る、出して諸客に示す、客曰く、盍《なん》ぞ水を以てこれを試さざる、白鞭を以て地を築いて竅《あな》と成す、虫を中に置き、その上に沃盥《よくかん》す、少頃《しばし》虫|蠕々《ぜんぜん》長きがごとし、竅中《きょうちゅう》泉湧き、倏忽《しゅっこつ》自ずから盤《わだかま》る、一席のごとく黒気あり香煙のごとし、ただちに簷外《えんがい》に出で、衆懼れて曰く必ず竜なり、ついに急ぎ帰り、いまだ数里ならずして風雨たちまち至る、大震数声なり〉。かかる怪に基づいて馬絆と名づけたらしい。『想山著聞奇集』に見えたわが邦の頽馬というは、特異の旋風が馬を襲い斃《たお》すので、その死馬の肛門開脱する事、河童に殺された人の後庭《しり》と同じという。それから『説文』に、〈蛟竜属なり、魚三千六百満つ、すなわち蛟これの長たり、魚を率いて飛び去る〉。『淮南子《えなんじ》』に、〈一淵に両蛟しからず〉、いずれも蛟を水族の長としたのだ。これらを合せ攷《かんが》うるに、わが邦のミヅチ(水の主)は、最初水辺の蛇能く人に化けるもので、支那の蛟同様人馬を殺害し、婦女を魅し婬する力あったが、後世一身に両役|叶《かな》わず、本体の蛇は隠居して池の主淵の主で静まり返り、ミヅチの名は忘らる。さてその分身たる河童小僧が、ミヅシ、メドチ、シンツチ等の号《な》を保続して肛門を覘《うかご》うたり、町婦を姙ませたり、荷馬を弱らせたりし居ると判る。もし本土の何処《どこ》かに多少有害な水蛇が実在するかしたかの証左が挙がらば、いわゆる河童譚はもと水蛇に根拠した本邦固有のもので、支那の蛟の話と多く相似たるは偶然のみと確言し得るに至らん。 | |
| 角ある蛇の事、『大清一統志』一五三に、※[分+おおざと]州神竜山に、長《たけ》寸ばかりの小蛇頭に両角あるを産す。『和漢三才図会』に、青蛇は山中石岩の間にあり、青黄色にて小点あり、頭大にして竜のごとく、その大なるもの一丈ばかり、老いたるは耳を生ず。またウワバミにも、鼠の耳様な小さき耳ありと載せ、数年前立山から還《かえ》った友人言ったは、今もかの辺には角また耳ある蛇存すというと。『新編鎌倉志』には、江島の神宝蛇角二本長一寸余り、慶長九年|閏《うるう》八月十九日、羽州《うしゅう》秋田常栄院尊竜という僧、伊勢|詣《まいり》して、内宮辺で、蛇の角を落したるを見て、拾うたりと添状《そえじょう》ありとて図を出す。日本に角また耳というべきものある蛇が現存するとは受け取れぬようだが、外国にカンボジヤのヘルペトン、西アフリカのビチス・ナシコルニスなど鼻の上に角ごときものあり。北アフリカの角蝮《ホーンド・ヴァイパー》は眼の上に角を具う。それから『荀子』勧学篇に、※[縢の糸に代えて虫]蛇《とうだ》足なくして飛ぶとは誠に飛んだ咄《はなし》だが、飛ぶ蛇というにも種々ありて、バルボサ(十六世紀)の『航海記』に、マラバル辺の山に翼ある蛇、樹から樹へ飛ぶと言ったは、只今英語でフライイング・ドラゴン(飛竜)と通称する蜥蜴の、脇骨長くて皮膜を被り、それを扇のごとく拡げて清水の舞台から、相場師が傘さして落ちるように、高い処から巧《うま》く斜めに飛び下りる事|※[鼬の由に代えて吾]鼠《むささび》に同じきを言ったらしい。 | |
| 『天野政徳随筆』には、京都の人屋に上り、たちまち雨風に遇った折、その顔近く音して飛ぶ物あり、手に持った鉄鎚《てっつい》で打ち落し、雨晴れてこれを見るに長四尺ばかりの蛇、左右の脇に肉翅を生じてその長四、五寸ばかり、飛魚の鰭《ひれ》のようだったと載す。プリニウスやルカヌスが書いたヤクルスてふ蛇は、樹上より飛び下りる事矢石より疾く、人を傷つけてたちまち死せしむというは、上述わが邦の野槌の俗伝にやや似て居る。一九一三年再版、エノックの『太平洋の秘密』(ゼ・セクレット・オブ・ゼ・パシフィック)一三一頁に記された、南メキシコのマヤ人の故趾に見る羽被った蛇も、能く飛ぶという表示であろう。したがって蛇の霊なる奴は、飛行自在という信念が東半球にのみ限らぬと判る。上に述べた飛竜ちゅう蜥蜴を、翼ある蛇と訛伝したのは別として※[縢の糸に代えて虫]蛇《とうだ》足なくして飛ぶなどいうたは、件《くだん》の羽を被った蛇同様、ただ蛇を霊物視する余り生じた想像に過ぎじと確信しいたところ、数年前オランダ(?)の学者が、ジャワかボルネオかセレベスで、樹の間に棲む一種の蛇の躯が妙に風を含むようになりおり、枝より滑り落ちる際|※[鼬の由に代えて吾]鼠《むささび》や飛竜同然、斜めに寛々と地上へ下り著《つ》くを見て、古来飛蛇の話も所拠《よりどころ》ありと悟ったという事を、『ネーチュール』誌で読んだ。 | |
| このついでに言う、蛇を身の讎《かたき》とする蛙の中にも、飛蛙《フライイング・フログ》というのがある。往年ワラスが、ボルネオで発見せるところで、氏の『巫来《マレー》群島篇』に図せるごとく、その四足に非常に大きな蹼《みずかき》あり、蹼はもと水を游《およ》ぐための器だが、この蛙はそれを拡げて、樹から飛降を便《たす》くという(第二図[#図省略])。予往年大英博物館で、この蛙アルコール漬《づけ》を見しに、その蹼他の蛙輩のより特《すぐ》れて大なるのみ、決して図で見るほど巨《おお》きになかった。例のブーランゼー氏に質《ただ》すと、書物に出た図はもちろん絵虚事《えそらごと》だと答えられたから、予もなるほどことごとく図を信ずるは、図なきにしかずと了《さと》った。しかるにその後ワラスの書を読むと、かの蛙が生きたままの躯と蹼の大きさを比べ記しある。それに引き合すとかの図は余り吹き過ぎたものでない。因って考うるに、蛙などは生きた時と、死んでアルコール漬になった後とで、身の大きさにすこぶる差違を生ずるから、単にアルコール漬を見たばかりでは、活動中の現状を察し得ぬのじゃ。 | |
| さて可笑《おか》しな噺《はなし》をするようだが、真実芸術に志|篤《あつ》き人の参考までに申すは、昔鳥羽僧正、ある侍法師絵を善くする者の絵、実に過ぎたるを咎《とが》めた時、その法師少しも事とせず、左《さ》も候わず、古き上手どもの書きて候おそくずの絵などを御覧も候え、その物の寸法は分に過ぎて、大に書きて候云々と言ったので、僧正理に伏したという(『古今著聞集』画図第十六)。この法師の意は、ありのままの寸法に書いては見所なき故、わざと過分に書くといったのだが、実際それぞれの物どもも、活溌に働く最中には、十二分に勢いも大きさも増すに相違ない。予深山で夕刻まで植物を観察し、急いで小舎《こや》に帰る途上、怪しき大きな風呂敷様の物、眼前に舞い下るに呆《あき》れ立ち居ると、変な音を立て樹を廻り行くを見ると、尋常の※[鼬の由に代えて吾]鼠《むささび》で、初め飛び落ち来った時に比して甚だ小さい。この物勢い込んで飛ぶ時、翅《はね》が張り切りおり、なかなか博物館で見る死骸を引き伸ばした標品とは、大いに大きさが違うようだった。 | |
| さて欧州で名手が作ったおそくずの絵を見た内に、何の活動もなきアルコール漬を写生したようなが多く、したがってこの種の画は、どうも日本の名工に劣るが多く思われたは、全く写生に執心する余り、死物を念入れて写すような事弊に陥ったからであろう。故に西洋人の写生が、必ずしも究竟の写生でなく、東洋風の絵虚事が、かえって実相を写し得る場合もあると惟《おも》う。この事は明治三十年頃、予がロンドンのサヴェージ倶楽部で、アーサー・モリソンに饗応された席で同氏に語り、氏は大いに感心された。その後|河鍋暁斎《かわなべきょうさい》がキヨソネとかいうイタリア人に、絵画と写真との区別心得を示した物を読んだ中にも、実例を出して、似た事を説きあったと憶《おぼ》える。件《くだん》のモリソンは、何でもなき一書記生から、奮発して高名の小説家となった人で、日本の美術に志厚く予と親交あったが、予帰朝後『エンサイクロペジア・ブリタンニカ』十一版十八巻に、その伝を立てたるを見て、ようやくその偉人たるを知った位、西洋には稀に見る淡白謙虚な人である。 | |
| ■蛇の足 | |
| 六月号へ本篇三を出し未完と記しながら、後分を蛇の体同様長々と出し遅れたは、ちょうどその頃|谷本富《たにもととめり》博士より、三月初刊『臨済大学学報』へ出た「蛇の宗教観」を示された。その内には自分がまさに言わんとする事どもを少なからず説かれおり、ために大きな番狂わせを吃《く》い、何とも致し方なくて、折角成り懸かった原稿を廃棄し、更に谷本君の文中に見ぬ事のみを論ずるとして再度材料蒐集より掛かったに因る。 | |
| さて前項に『さへづり草』を引いて、出羽にトンヘビとて、人の後庭《しりえ》を犯し、これを殺す奇蛇ある由、トンとは古老の説に、非道交会を昔の芝居者などが数うるに、一トン取る二トン取るといったそうだから、南米にあるてふ男色蛇《ソドマイト・スネーク》と同義の名らしい。果してそんな水蛇が日本にあるなら、国史に見えた※[虫+礼のつくり]《みづち》、今も里俗に伝うる河童は、本《もと》かようの水蛇から生じた迷信だろうという意を述べ置いたところ、旅順要港部司令官黒井将軍より来示に、自分は両国の橋の上に御大名が御一人|臥《のさ》って御座ったてふ古い古い大津絵節《おおつえぶし》に、着たる着物は米沢でとある上杉家中に生まれた者で出羽の事を熟《よく》知るが、かの地にトウシ蛇という、小形で体細く薄黒く川を游ぐものをしばしば見た。而《しか》して自分らの水游ぎを戒むるとて、母が毎《いつ》も通し蛇が水游ぐ児の肛門より入りてその腸を食い、前歯を欠いて口より出ると言うを聞き怖《お》じた。一度もその事実を見聞した事なきも、水死の尸は肛門開くもの故、水蛇に掘られたであろうと思うて、言い出したものか。トウシ蛇とは肛門より腹中へ通し入るの義らしく、トウシをトシと略書したるを、かの書にトンと誤写せるにあらずやと、とにかくかようの水蛇と話が、羽州に存するは事実だとあった。これで古史の※[虫+礼のつくり]や、今俗伝うる河童は、一種の水蛇より出たろうてふ拙見が、まず中《あた》ったというものだ。全体水蛇は尾が海蛇のように扁《ひら》たからず、また海蛇は陸で運動し得ず、皮を替えるに蜥蜴同然片々に裂け落ちるに、水蛇は陸にも上り行《ある》き全然《まるきり》皮を脱ぐ。もっともその鱗や眼や鼻孔等が、陸生の蛇と異なれど、殺した上でなければ確《しか》と判らず、したがって『本草啓蒙』『和漢三才図会』など、本邦にも水蛇ありと記せど、尋常陸生の蛇がたまたま水に入ったのか、水面を游ぐ蛇状の魚を見誤ったのか知りがたかったところ、黒井中将に教えられて、浅瀬を渡る水蛇が少なくとも本邦の北部に産すと知り得たるは、厚く御礼を申し上ぐるところである。 | |
| 海蛇の牙に大毒あるが、水蛇は人を咬《か》むも無害と、『大英百科全書』十一版二十五巻に見えるが、十二巻にはアフリカに大毒の水蛇ありと載せ居る。かほど正確を以て聞えた宝典も、巻|累《かさ》なればかかる記事の矛盾もありて読者を迷わす。終始一貫の説を述べ論を著わすは難くもあるかなだ。まして本篇などは、多用の片手間に忙ぎ書くもの故、多少前後|揃《そろ》わぬ処があってもかれこれ言うなかれと、蛇足と思えど述べて置く。琉球の永良部鰻《えらぶうなぎ》など、食用さるる海蛇あるは人も知るが、南アフリカのズーガ河に棲む水蛇も、バエイエ人が賞翫する由(リヴィングストンの『宣教紀行《ミショナリ・トラヴェルス》』三章)このついでに受け売りす。ケープ、カフィル人は魚を蛇に似るとて啖《く》わずと(バートンの『東亜非利加初行記《ファースト・フートステプス・イン・イースト・アフリカ》』第五章)。 | |
| 蛇足の喩《たと》えは『戦国策』に見ゆ。昭陽楚の将として魏を伐《う》ち更に斉を攻めた時、弁士|陳軫《ちんしん》斉を救うためこの喩えを説き、昭陽に軍《いくさ》を罷《や》めしめた。一盃の酒を数人飲まんとすれど、頭割りでは飲むほどもなく一人で飲むとあり余るから、申し合せて蛇を地に画き早く成った者一人が飲むと定め、さて最も早く蛇を画いた者が、その盃を執りながら、この蛇の足をも画いてみせようと画き掛くる内、他の一人その盃を奪い取り、蛇は足なきに定まったるに、無用の事をするから己《おれ》が飲むとて飲んでしまい、足を画き添えようとした者その酒を亡《うしの》うた。公も楚王に頼まれて魏を破ったら役目は済んだ。この上頼まれもせぬ斉国を攻むるは、真に蛇足を書き添える訳だと説いたのだ。ムショーの『艶話事彙《ジクショネール・ド・ラムール》』にも、処女が男子に逢《あ》い見《まみ》えし事の有無は、大空を鳥が飛び、岩面を蛇が這った足跡を見定むるよりも難いと、ある名医が嘆じたと載す。この通りないに相場の定まった蛇の足とは知りながら、既に走り行《ある》く以上は、何処かに隠れた足があるのであろうと疑う人随分多く、そんな事があるものかと嘲る人も、蛇がどうして走り行くかを弁じ得ぬがちだ。誠に愍然な次第故、自分も知らぬながら、学者の説を受け売りしよう。 | |
| そもそも蛇ほど普通人に多く誤解され居るものは少ない。例せば誰も蛇は常に沾《ぬ》れ粘ったものと信ずるが、これその鱗が強く光るからで、実際そんなに沾れ粘るなら沙塵が着き、重《おも》りて疾く走り得ぬはずでないか。その足に関する謬見は一層夥しく、何でも足なければ歩けぬと極《き》めて掛かり、何がな足あるにしてしまわんと種々の附会を成した。支那の『宣室志』にいう、桑の薪で炙《あぶ》れば蛇足を出すと。オエン説に米国の黒人も蛇は皆足あり炙れば見ゆという由。プリニウスの『博物志』巻十一に、蛇の足が鵝の足に似たるを見た者ありと見ゆ。しかるに近来の疑問というは、支那道教の法王張天師の始祖張|道陵《どうりょう》、漢末|瘧《ぎゃく》を丘社に避けて鬼を使い、病を療ずる法を得、大流行となったが、後《のち》蟒蛇に呑まる。その子衡父の屍を覓《もと》めて得ざりければ、鵠《はくちょう》の足を縻《つな》いで石崖頂に置き、白日昇天したと言い触らし、愚俗これを信じて子孫を天師と崇《あが》めた(『五雑俎』八)。 | |
| ギリシアの哲学者ヘラクレイデース常に一蛇を愛養し、臨終に一友に嘱してその屍を隠し、代りにかの蛇を牀上に置き、ヘラクレイデースが明らかに神の仲間に入った証と言わしめたと伝うるもやや似て居るが、張衡が何のために鵠の足を崖頂に縻《つな》いだものか。道教の事歴にもっとも精通せる妻木直良氏に聞き合せても、聢《しか》と答えられず、鵠も鵝も足に蹼《みずかき》あり概して言わば古ローマ古支那を通じて蛇の足は水鳥の足に似居ると信じたので、張衡その父が蟒蛇に呑まれたのを匿《かく》し転じて、大蛇に乗りて崖頂に登り、それから昇天したその大蛇が、足を遺したと触れ散らしたのであるまいか。昇天するだけの力を持った大仙が、崖頂まで大蛇の仲継を憑《たの》まにゃならぬとは不似合な話だが、呉の劉綱その妻|樊《はん》氏とともに仙となり、大蘭山上の巨木に登り鋳掛屋《いかけや》風の夫婦|連《づれ》で飛昇したなどその例多し。蜻※[虫+廷]《とんぼ》や蝉《せみ》が化し飛ぶに必ず草木を攀《よ》じ、蝙蝠《こうもり》は地面から直《じか》に舞い上り能わぬから推して、仙人も足掛かりなしに飛び得ないと想うたのだ。既に論じたごとく、実際蟒蛇には二足の痕跡を存するから張衡の偽言も拠《よりどころ》あり。 | |
| イタリアのグベルナチス伯説に、露国の古話に蛇精が新米寡婦方へその亡夫に化けて来て毎夜|伴《とも》に食い、同棲して、晨《あさ》に達し、その寡婦火の前の蝋《ろう》のごとく痩《や》せ溶け行く、その母これに教えて、他《かれ》と同食の際わざと匕《さじ》を堕《おと》し、拾うため俯《うつむ》いて他《かれ》の足を見せしむると、足がなくてニョッキリ尾ばかりあったので、蛇精が化けたと判り、寡婦寺に詣《もう》で身を浄《きよ》めたといい、北欧の神話にも、ロキス蛇が馬に化けた時足から露顕したといい、インド『羅摩衍譚《ラーマーヤナ》』に、雌蛇のみ能く雄蛇の足を弁《わきま》え知るとある。これらは皆夫の陰相を尾と称え、その状を確かに知るは妻ばかりという寓意《ぐうい》だと解った。グ伯は梵学者また神誌学者としてすこぶる大家だが、ややもすれば得意の言語学に僻して、何でも陰具に引き付け説く癖がある。蛇の足を覗《うかが》うと尾だったてふは、単に蛇は主として尾の力で行くと見て言ったと説かば、陰具などを持ち出すにも及ぶまい。回教学有数の大著、タバリの『編年史』にいわく、上帝アダムを造り諸天使をしてこれを敬せしめしに、エブリスわれは火より造られたるにアダムは土で作られたから、劣等の者を敬するに及ばぬといい、帝|瞋《いか》りてエを天より逐い堕す。エ天に登りて仕返しをと思えど、天の門番リズワンの大力あるを懼《おそ》れ、蛇を説いて自分を呑んで天に往き密《そっ》と吐き出さしめ、エヴァを迷わしアダムを堕した。アダム夫妻もと只今の人の指と足の趾《ゆび》の端にある爪の通りの皮を被りいたが、惑わされて禁果を吃《く》うとその皮たちまち堕ち去り丸裸となり、指端の爪を覩《み》て今更楽土の面白さを懐《おも》うても追い付かず。蛇もまた人祖堕落の時まで駱駝《らくだ》ごとき四脚を具え、人を除《の》けてはエデン境内最も美しい物じゃったが、禁果を偸《ぬす》み食った神罰たちまち至って、楽土諸樹木の四の枝が低《た》れ下り、四つの罪人永く追いやられ、アダムはヒンドスタンに、エヴァはジッダに、蛇はイスパハンに、エブリスはシムナーンに謫居《たっきょ》した。上帝蛇を悪《にく》むの余りその四脚を去り、永《とこし》えに地上を跂《は》い行かしむと。今の欧米人これを聞いたら笑うに極まっているが、実は臭い物身知らずで、彼らの奉ずる『聖書』にも十二世紀まではかかる異伝を載せあった由。 | |
| 日本でも釈迦死んで諸動物皆来り悲しみしに、蚯蚓《みみず》だけは失敬した故罰として足なしにされたというが、紀州には蛇の足に関する昔話あり、西牟婁郡水上てふ山村で聞いたは、トチワビキてふ蛙、昔日本になかったが、トチワの国より蛇に乗って渡り来る。報酬に脚を遣《や》ろうと約したに今以て履行せず、蛇恨んで出会うごとこの蛙を食うに、必ず脚より始むという。その蛙を検するに何処にもある金線蛙《とのさまがえる》だった。トチワすなわち常磐《ときわ》国については、大正元年十一月の『人性』に拙見を出した。似た話もあるもので、東牟婁郡高田村に代々葬後墓を発《あば》き尸を窃《ぬす》み去らるる家あり。これはその先祖途中で狼に喫《く》われんとした時、われに差し迫った用事あり、それさえ済まば必ず汝に身を与うべしと紿《あざむ》いてそのまま打ち過ぎしを忘れず、その人はもちろん子孫の末までもその尸を捉り去り食うという。上述水上の里話を聞いてから試すと、予が見得た限り蛇は蛙を必ず脚より食うが、亀は頭より蛙を食う。しかるに、アストレイの『新編紀行航記全集《ア・ニュウ・ゼネラル・コレクション・オヴ・ヴォエージス・エンド・トラヴェルス》』巻二の一一三頁に、西アフリカのクルバリ河辺に、二十五また三十フィートの大蛇あって全牛を嚥《の》むが、角だけは口外に留めて嚥む能わずとポルトガル人の話を難じ、すべて蛇は一切の動物を呑むに首より始む、角を嚥み能わずしていかでか全牛を呑み得んと論じある。なるほど鼠などを必ず首から呑むが、右に言った通り蛙をば後脚から啖い初むる故一概に言う事もならぬ。インドのボリグマ辺の俗信に、虎は人を殺して後部より、豹は前方より啖うという(ボールの『印度藪榛生活《ジャングル・ライフ・イン・インジア》』六〇五頁)。 | |
| ガドウ教授蛇の行動を説いて曰く、蛇は有脊髄動物中最も定住するもので、餌と栖《すみか》さえ続く中は他処へ移らず、故に今のごとく播《ち》るには極めて徐々漸々と掛かったであろう。その動作迅速で豪《えら》い勢いだが、真の一時だけで永続せぬ事南方先生の『太陽』への寄稿同然とは失敬極まる。蛇の胴の脊髄とほとんど相応した多数の肋骨《あばらぼね》を、種々変った場面に応じて巧く働かせて行き走る。その遣り方はその這うべき場面に少しでも凸起の、その体の一部を托すべきあるに遇わば、左右の肋骨を交《こもご》も引き寄せて体を代る代る左右に曲げ、その後部を前《すす》める中、その一部(第三図[#図省略])また自ら或る凸起に托《の》り掛かると同時に、体の前部今まで曲りおったのが真直ぐに伸びて、イからハに進めらる。この動作をもっとも強く助勢するは蛇の腹なる多くの横|濶《ひろ》い麟板で、その後端の縁《へり》が蛇が這いいる場面のいかな微細の凸起にも引っ掛かり得る。この麟板は一枚ごとに左右一対の肋《あばら》と相伴う。されば平滑な硝子《ガラス》板を蛇這い得ず。その板をちょっと金剛砂で磨けば微細の凸起を生ずる故這い得。また蛇の進行を示すとてその体上下に波動し、上に向いた波全く地を離れ、下に向いた波のみ地に接せるよう描いた画多きも、これ実際あり得ぬ事じゃと。第四図[#図省略]は予在英中写し取った古エジプトの画で、オシリス神の像を毀《こわ》した者を大蛇ケチが猛火を吐いて滅尽するところだが、蛇が横に波曲すればこそ行き得ると知った人も、横に波動するを横から見たところを紙面に現わすは非常な難件故、今日とても東西名手の作にこの古エジプト画と同様、またほぼ相似た蛇を描いて人も我も善く出来たと信ずるが少なからぬ。ガ氏また古画に蛇|螺旋《らせん》状に木を登るところ多きを全く不実だといったが、これは螺旋状ならでも描きようがあると思う。されば神戦巻第一図に何の木をも纏《まと》わず、縁日で買った蛇玉を炙《あぶ》り、また股間《またぐら》の※[やまいだれ+節]腫《ねぶと》を押し潰《つぶ》して奔り出す膿栓《のうせん》同様螺旋状で進行する蛇が見えたは科学者これを何と評すべき。ただし既に述べ置いた通り、美術としては絵嘘事《えそらごと》も決して排すべきにあらねど、ここにはただかかる行動を為《な》す蛇は実際ないてふ小説を受け売りし置く。 | |
| 予の宅に白蛇棲んでしばしば形を現わすが、この夏二階の格子の間にその皮を脱ぎしを見付け引き出そうとすれど出ず。それは只今言った通り蛇の腹の多数の麟板の後端が格子の木の外面にある些細な凸起に鈎《かか》り着いて、蛻《ぬけがら》を損せずに尾を持って引き出し得ぬと判り、格子の外なりし頭を手に入れその方へ引くと苦もなく皮を全くし獲れた。無心の蛻すらかくのごとくだから、活きた蛇が穴中に曲りその腹の麟板が多処に鈎り着き居るを引き出すは難事と見え、『和漢三才図会』に、穴に入る蛇は、力士その尾を捉えて引くも出ず、煙草脂《タバコやに》を傅《つ》くれば出《い》づ。またいわく、その人左手自身の耳を捉え右手蛇を引かば出づ、その理を知らずといえり。この辺で今伝うるは、一人その尾を捉え他の一人その人を抱きて引けば出やすしと。 | |
| 十六世紀のレオ・アフリカヌスの『亜非利加記《デスクリプチョネ・デル・アフリカ》』第九篇には、沙漠産ズッブてふ大蜥蜴をアラブ人食用す。この物疾く走る。穴に入りて尾のみ外に残るをいかな大力士が引いても出ず。やむをえず鉄器もてその穴を揺り広げやっと捉え得とあるも似た事だが、蜥蜴の腹の麟板は、物に鈎《かか》る端を具えぬから、此奴《こやつ》はその代り四足に力を込めてその爪で穴中の物に鈎り着くのであろう。この通りの拙文を訳してロンドンで出したるに対し、一英人いわく、日本人は皆一人で蛇の尾を捉えて引き出し得ぬらしいが、自分はかつてインドで英人単身ほとんど八フィート長の蛇を引き出すを見たと。ブリドー大佐の説には、往年インドで聞いたは、土着の英人浴中壁の排水孔《みずぬきあな》より入り来った蛇がその孔より出で去らんとする尾を捉え引いたが蛇努力して遁《のが》れ行った。翌日また来れど去るに臨み、まず尾を孔に入れ、かの人を見詰めながら身を逆さまに却退したとありしを見れば、剛力の人がいっそ伝説など知らずにむやみに行けば引き出し得るも、常人にはちょっとむつかしい芸当らしい。こんな事から敷衍した物か、蛇の尻に入るは多くは烏蛇とて小さくて黒色なり。好んで人の尻穴に入るにその人さらに覚えずとぞ。この蛇穴に少しばかり首をさし入れたらんには、いかに引き出さんとすれども出る事なし。寸々《ずたずた》に引き切っても、首はなお残りて腹に入りついに人を殺す(とはよくよく尻穴に執心深い奴で、水に棲むてふ弁《ことわ》りがないばかり、黒井将軍が報《しら》されたトウシ蛇たる事疑いを容れず)。これを引き出すに「猿のしかけ」という木の葉にて捲き引き出せば、わずかに尾ばかり差し出たるにても引き出すといえり云々と、『松屋筆記』五三に出づ。 | |
| ■蛇の変化 | |
| これに関する話は数え切れぬほど多いからほんの言い訳までに少々例を挙ぐる。『和漢三才図会』に「ある人船に乗り琵湖を過ぎ北浜に著く、少頃《しばし》納涼の時、尺ばかりの小蛇あり、游ぎ来り蘆梢に上り廻り舞う、下り水上を游ぐこと十歩ばかり、また還り蘆梢に上る初めのごとし、数次ようやく長丈ばかりと為る、けだしこれ升天行法か、ここにおいて黒雲|掩《おお》い闇夜のごとし、白雨《はくう》降り車軸の似《ごと》し、竜天に升《のぼ》りわずかに尾見ゆ、ついに太虚に入りて晴天と為る」。誰も知るごとく、新井白石が河村随軒の婿《むこ》に望まれた折、かようの行法に失敗して刃に死んだ未成の竜の譚を引いて断わった。支那には『述異記』に、〈水※[兀+虫]五百年化けて蛟と為り、蛟千年化けて竜と為る〉。※[兀+虫]《き》とは『本草』に蝮の一種と見えるから、水※[兀+虫]とは有害の水蛇を指したと見える。西土にも蛇が修役を積んで竜となる説なきにあらず。 | |
| 古欧州人は蛇が他の蛇を食えば竜と化《な》ると信じた(ハズリットの『|諸信および俚伝《フェース・エンド・フォークロール》』一)。ハクストハウセン説に、トランスカウカシア辺で伝えたは、蛇中にも貴族ありて人に見られずに二十五歳|経《ふ》れば竜となり、諸多の動物や人を紿《あざむ》き殺すためその頭を何にでも変じ得。さて六十年間人に見られず犯されずば、ユクハ(ペルシア名)となり全形をどんな人また畜にも変じ得と。天文元年の著なる『塵添※[土へん+蓋]嚢抄《じんてんあいのうしょう》』八に、蛇が竜になるを論じ、ついでに蛇また鰻に化《な》るといい、『本草綱目』にも、水蛇が鱧《はも》という魚に化るとあるは形の似たるより謬《あやま》ったのだ。文禄五年筆『義残後覚《ぎざんこうかく》』四に、四国遍路の途上船頭が奇事を見せんという故蘆原にある空船に乗り見れば、六、七尺長き大蛇水中にて異様に旋《めぐ》る、半時ほど旋りて胴中|炮烙《ほうろく》の大きさに膨れまた舞う内に後先《あとさき》各二に裂けて四となり、また舞い続けて八となり、すなわち蛸《たこ》と化《な》りて沖に游ぎ去ったと見ゆ。例の『和漢三才図会』や『北越奇談』『甲子夜話』などにも蛇蛸に化る話あり。こんな話は西洋になけれど、一八九九年に出たコンスタンチンの『|熱帯の性質《ラ・ナチュール・トロピカル》』に、古ギリシアのアポロン神に殺された大蛇ピゾンが多足の竜ヒドラに化ったちゅうは、蛇が蛸になるを誇張したのであろうとあるは、日本の話を聞いて智慧附いたのかそれとも彼の手製か、いずれに致せ蛸と蛇とは似た物と見えるらしい。 | |
| ただに形の似たばかりでなく、蛸類中、貝蛸オシメエ・トレモクトプス等諸属にあっては、雄の一足非常に長くなり、身を離れても活動し雌に接して子を孕ます。往時学者これを特種の虫と想い別に学名を附けた。その足切れ去った跡へは新しい足が生える。古ギリシア人は日本人と同じく蛸飢ゆれば自分の足を食うと信じたるを、プリニウスそれは海鰻《はも》に吃い去らるるのだと駁撃した。しかし宗祇『諸国物語』に、ある人いわく、市店に売る蛸、百が中に二つ三つ足七つあるものあり、これすなわち蛇の化するものなり。これを食う時は大いに人を損ずと、怖るべしと見え、『中陵漫録』に、若狭《わかさ》小浜の蛇、梅雨時|章魚《たこ》に化す。常のものと少し異なる処あるを人見分けて食わずといえる。『本草啓蒙』に、一種足長蛸形|章魚《たこ》に同じくして足|最《いと》長し、食えば必ず酔いまた斑《はん》を発す。雲州でクチナワダコといい、雲州と讃州でこれは蛇の化けるところという。蛇化の事若州に多し。筑前では飯蛸《いいだこ》の九足あるは蛇化という。八足の正中に一足あるをいうと記せるごとき、どうもわが邦にも交合に先だって一足が特に長くなり体を離れてなお蠕動《ぜんどう》する、いわゆる交接用の足(トクユチルス(第五図[#図省略]))が大いに発達活動して蛇に肖《に》た蛸あり。それを見謬って蛇が蛸に化《な》るといったらしい。キュヴィエーいわく、欧州東南の海に蛸類多き故に、古ギリシア人蛸を観察せる事すこぶる詳《つまび》らかで、今日といえども西欧学者の知らぬ事ども多しと。わが邦またこの類多く、これを捕るを業とする人多ければ、この蛇が蛸に化る話なども例の一笑に附せず静かに討究されたい事じゃ。それから蛸と同類で、現世界には化石となってのみ蹟《あと》を留むるアンモナイツは、漢名石蛇というほど蟠《ま》いた蛇に酷《よく》似いる。したがってアイルランド人はその国にこの化石出るを、パトリク尊者が国中の蛇をことごとく呪して石となし、永くこれを除き去った明証と誇る由(タイラー『原始人文篇《プリミチヴ・カルチュール》』一巻十章)、一昨年三月号一六三頁にその図あり。 | |
| 『続歌林良材集』に、菖蒲が蛇になる話あり。『方輿勝覧《ほうよしょうらん》』に、湖北岳州府の池に棲んだ大蛇を呂巌《りょがん》が招くと出て剣に化けたといい、美女の髪が蛇になった話は、藤沢氏の『伝説』信濃巻に出で、オヴィジウスの『|変化の賦《メタモルフォーセース》』には、人の脊髄が蛇となると述べた。ルーマニアの伝説に拠ると、人の血を吸う蚤《のみ》は蛇から出たのだ。いわく、太古ノア巨船《アルク》に乗って洪水を免るるを、何がな災を好む天魔、錐《きり》を創製して船側を穿ち水浸りとなる、船中の輩急いで汲み出せども及ばず、上帝これを救わんとて、蛇に黠智《かっち》を授けたから、『聖書』に蛇のごとく慧《さと》しといったのじゃ。ここにおいて蛇来ってノアに、われ穴を塞いで水を止めたら何をくれるかと問うた。さいう爾《なんじ》は何を欲するかと問い返すと、蛇洪水|息《や》んで後、われと子孫の餌として毎日一人ずつくれと答う。途轍《とてつ》もない事と思うても背に替えられぬ腹を据えて、いかにも日に一人ずつ遣ろうと誓うたので、蛇尾の尖《さき》を以て穴を塞ぎ水を止め天魔敗走した。洪水息んでノア牲《いけにえ》を献《たてまつ》って上帝に謝恩し、一同大いに悦ぶ最中に蛇来って約束通り人を求めて食わんという。ノアこの人少なに毎日一人ずつ取られては、たちまち人種が尽きると怒って、蛇を火に投じ悪臭大いに起ちて上帝を不快ならしめた。由って上帝風を起し蛇の尸灰を世界中へ吹き散らし、蚤その灰より生じて世界中の人の血を吸う。その分量を合計すればあたかも毎日一人ずつ食うに等しいから、ノアの契約は永く今までも履行され居る訳になると。 | |
| それから三河で伝うるは、蝮《まむし》は魔虫で、柳かウツギの木で打ち殺すと立ちどころに何千匹となく現われ来ると(早川孝太郎氏説)。盛夏深山の渓水に、よく蝮が来て居る。それを打ち殺して、暫くして往き見ると、多分他の蝮が来て居るは予しばしば見た。紀州安堵峯辺でいう、栗鼠《りす》は獣中の山伏で魔法を知ると、これややもすれば樹枝に坐して手を拱《きょう》し礼拝の態を為《な》すに基づく。さて杣人《そまびと》一日山に入りて儲けなく、ちょっと入りて大儲けする事もあればこれも魔物なり。杣人山中で栗鼠に会うに、杣木片《そまこっぱ》すなわち斧で木を伐った切屑また松毬《まつかさ》を投げ付けると、魔物同士の衝突だからサア事だ、その辺一面栗鼠だらけになると。また日高郡丹生川大字大谷に、蚯蚓《みみず》小屋ちゅうは昔ここの杣小屋へ大蚯蚓一疋現われしを火に投ずると、暫くの間に満室蚯蚓で満たされその建物倒れそう故逃げ帰った、その小屋|址《あと》という。随分|信《うけ》られぬ話のようだが何か基づく所があるらしい。 | |
| 明治十八年、予神田錦町で鈴木万次郎氏の舅《しゅうと》の家に下宿し、ややもすれば学校へ行かずに酒を飲み為す事なき余り、庭上に多き癩蝦蟆《いぼがえる》に礫《こいし》を飛ばして打ち殺すごとに、他の癩蝦蟆肩を聳《そび》やかし、憤然今死んだ奴の方へ躍り来た勇気のほど感じ入ったが、それをもまた打ち殺し、次に来るをも打ち殺し、かくて四、五疋殺したので蛙も続かず、こっちも飽きが出て何しに躍り来たか見定めなんだが、上述の蝮を殺した実験もあり、また昔無人島などで鳥獣を殺すとその侶《とも》の鳥獣が怕《おそ》れ竄《かく》れず、ただ怪しんで跡より跡より出で来て殺された例も多く読んだから攷《かんが》うると、いかなる心理作用よりかは知らぬが、同類殺さるを知りながら、その死処に近づく性《たち》の動物が少なからぬようで、蚯蚓などの下等なものは姑《しばら》く措《お》き、蝮、栗鼠ごときやや優等のもの多かった山中には、一疋殺せば数十も集まり来る事ありしを右のごとく大層に言い伝えたのかと想う。 | |
| ただしかかる現象を実地について研究するに、細心の上に細心なる用意を要するは言うまでもないが、人の心を以て畜生の心を測るの易《やす》からぬは、荘子と恵子が馬を観《み》ての問答にもいえる通りで、正しく判断し中《あ》てるはすこぶる難い。たとえば一九〇二年に出たクロポートキン公の『互助論《ミューチュアル・エード》』に、脚を失いて行き能わぬ蟹を他の蟹が扶《たす》け伴れ去ったとあるを、那智山中読んで一月|経《へ》ぬ内に、自室の前の小流が春雨で水増し矢のごとく走る。流れのこっちの縁に生えた山葵《わさび》の芽を一疋の姫蟹が摘み持ち、注意して流れの底を渡りあっちの岸へ上り終えたところを、例の礫を飛ばして強く中てたので半死となり遁《のが》れ得ず、爾時《そのとき》岩間より他の姫蟹一疋出で来り、件《くだん》の負傷蟹を両手で挟《はさ》み運び行く。この蟹走らず歩行遅緩なれば、予ク公の言の虚実を試《ため》すはこれに限ると思い、抜き足で近より見れば、負傷蟹と腹を対《むか》え近づけ両手でその左右の脇を抱き、親切らしく擁《かか》え上げて、徐《そぞ》ろ歩む友愛の様子にアッと感じ入り、人を以て蟹に及《し》かざるべけんやと、独り合点これを久しゅうせし内、かの親切な蟹の歩み余りに遅く、時々立ち留まりもするを訝《いぶか》り熟視すると何の事だ、半死の蟹の傷口に自分の口を接《あ》て、啖《く》いながら巣へ運ぶのであった。これを見て予は書物はむやみに信ぜられぬもの、活動の観察はむつかしい事と了《さと》った次第である。 | |
| 蛇が他の物に化け、他の物が蛇になる話はかくのごとく数え切れぬほど多い。また蛇が自分化けるでなく、人を化けしむる力ありてふ迷信もある。ボルネオの海《シイ》ダヤク人はタウ・テパン(飛頭蛮《ろくろくび》)を怖るる事甚だし、これはその頭が毎夜体を離れ抜け出でて、夜すがらありたけの悪事を行い、旦《あした》近く体へ復《かえ》るので里閭《りりょ》これと交際を絶ち、諸《もろもろ》の厭勝《まじない》を行いその侵入を禦《ふせ》ぎ、田畠には彼が作物を損じに来る時、その眼と面を傷つくるよう竹槍を密《ひそ》かに植うる。あるいはいう、昔その地を荒らした大蛇の霊がわが舌を取って食い得たら、頭だけ飛行自在にしてやると教えたに始まると(六年前四月二十日の『ネーチュール』)。 | |
| 蛇が人に化けた例は諸国甚だ多く、何のために化けたかと問うと、多くは『平家物語』の緒方家の由緒通り、人と情交を結ばんとしてである。また人が蛇に化けて所願を遂げた例もありて、トランスカウカシアの昔話に、アレキサンダー大王はその実偉い術士の子だった。この術士常にマケドニア王フィリポスの后オリムピアスを覬覦《きゆ》したがその間《ひま》を得ず、しかるに王軍行して、后哀しみ懐《おも》う事切なるに乗じ、御望みなら王が一夜還るよう修法《しゅほう》してあげるが、蛇の形で還っても構わぬか、人の形ではとてもならぬ事と啓《もう》すと、ただ一度逢わば満足で、蛇はおろかわが夫が真実還ってくれるなら、糞蛆《せっちむし》の形でもこちゃ厭《いと》やせぬと来た。得たり賢し善は急げと、術士得意の左道を以て自ら蛇に化けて一夜を后と偕《とも》に過ごし、同時に陣中にある王に蛇となって后に遇う夢を見せた。軍《いくさ》果て王いよいよ還ると后既に娠《はら》めり。王怪しんでこれを刑せんとす。后いわく、爾々《しかじか》の夜王は蛇となって妾と会えりと。聞いてびっくり苅萱道心《かるかやどうしん》なら、妻妾の髪が蛇となって闘うを見て発心したのだが、この王は自分が蛇となった前夜の夢を憶い出して奇遇に呆《あき》れ、后を宥《ゆる》してまた問わず。しかし爾後蛇を見るごと、身の毛|竪立《よだ》ちて怖れたそうだ。烏羽玉《うばたま》の夢ちゅう物は誠に跡方もない物の喩えに引かるるが、古歌にも「夢と知りせば寤《さめ》ざらましを」と詠んだ通り、夫婦情切にして感ずる場合はまた格別と見え、『唐代叢書』五冊に収めた『開元天宝遺事』に、〈楊国忠《ようこくちゅう》出でて江浙に使し、その妻思念至って深し、荏苒《じんぜん》疾くなり、たちまち昼夢国忠と○、因って孕むあり、後に男を生み朏《ひ》と名づく、国忠使帰るに至るにおよび、その妻|具《つぶさ》に夢中の事を述ぶ、国忠曰く、これけだし夫婦相念い情感の至る所、時人|譏誚《きしょう》せざるなきなり〉。国忠の言を案ずると、フィリポス王同然自分もちょうどその時異夢を見たのだろう。 | |
| 仏典に名高い賢相|大薬《マハウシャダ》の妻|毘舎※[にんべん+去]《ヴィサクハ》女、美貌智慧|併《ならび》に無双たり。時に北方より五百商人その国へ馬売りに来り、都に名高き五百妓を招きスチャラカ騒ぎをやらかしけるに、商主一人少しも色に迷わず、夥中《かちゅう》最も第一の美妓しきりに誘えど、〈我邪念なし、往返徒労なり〉と嘯《うそぶ》いたとは、南方先生の前身でもあったものか、自宅によほどよいのがあったと見える。かの妓|躍気《やっき》で、君は今堅い事のみ言うが、おのれ鎔《と》かさずに置くべきか、していよいよ妾に堕された日は、何をくれるかと問うと、その場合には五馬を上げよう。もしまた当地滞留中いささかも行いを濫《みだ》さなんだら、和女《そなた》われに五百金銭を持って来なと賭《かけ》をした。それからちゅうものは前に倍して繁《しげ》く来り媚び諂《へつら》うに付けて、商主ますます心を守って傾く事なし。諸商人かの妓を気の毒がり、一日商主に城中第一の名代女の情に逆らうは不穏当と忠告すると、商主誠に思召《おぼしめし》ありがたきも昨夜夢に交通を遂げた。この上何ぞ親しく見《まみ》ゆるを要せんと語る。かの妓伝え聞いて、人足多く率い来て商主に対《むか》い、汝昨夜われとともに非行したから五馬を渡せと敦圉《いきま》き、商主は夢に見た事が汝に何の利害もあるものかと大悶着となって訴え出で、判官苦心すれど暮に至るも決せず、明日更に審査するとして大薬《マハウシャダ》その家に還ると、毘女何故|晩《おそ》かったかと問うと、委細を語り何とか決断のしようがないかと尋ねた。毘女|其式《それしき》の裁判は朝飯前の仕事と答えて夫に教え、大薬妻の教えのままに翌日商主の五馬を牽《ひ》き来て池辺の岩上に立たせ、水に映った五馬の影を将《ひき》去れ、〈もし影馬実に持つべき者なしと言わば、夢中行欲の事もまた同然なり〉、と言い渡したので、国王始め訴訟の当人まで嗟賞《さしょう》やまなんだという。 | |
| 古ギリシアの名妓ラミアは、己の子ほど若い(デメトリオス)王を夢中にしたほど多智聡敏じゃった。その頃エジプトの一青年、美娼トニスを思い煩うたが、トが要する大金を払い得ず空しく悶《もだ》えいると、一霄《いっしょう》夢にその事を果して心静まる。ト聞いて、只《ただ》には置かず揚代《あげだい》請求の訴を法廷へ持ち出すと、ボッコリス王、ともかくもその男にトが欲するだけの金を鉢に数え入れ、トの眼前で振り廻さしめ、十分その金を見て娯《たの》しめよとトに命じた。ラミア評して、この裁判正しからず、子細は金見たばかりで女の望みは満足せねど、夢見たばかりで男の願いは叶《かの》うたでないかと言ったとは、この方が道理に合ったようであり、読者諸士滅多に夢の話しもなりませんぞ。このラミアの説のごとく、行欲の夢はその印相を留むるの深さ他の夢どもに異なり、時として実際その事ありしよう覚えるすら例多ければ、さてこそフィリポス王ごとき偉人もその后の言を疑わなんだのだ。後年アレキサンダー大王遠征の途次、アララット山に神智広大能く未来を言い中《あ》つる大仙ありと聞き、自ら訪れて「汝に希有《けう》の神智ありと聞くが、どんな死様《しにざま》で終るか話して見よ」と問うと、「われは汝に殺されるべし」と答えたので、しからばその通りと王鎗を以て彼を貫く、大仙ここにおいて、汝実にわが子だとて、昔蛇に化けて王の母を娠ませた子細を語って死んだそうじゃ。晋の郭景純が命、今日日中に尽くと、王敦《おうとん》に告げて殺されたと似た事だ。『日本紀』に、大物主神《おおものぬしのかみ》顔を隠して夜のみ倭迹々姫命《やまとととびめのみこと》に通い、命その本形を示せと請うと小蛇となり、姫驚き叫びしを不快で人形に復《かえ》り、愛想|竭《づ》かしを述べて御諸山《みもろやま》に登り去り、姫悔いて箸《はし》で陰《ほと》を撞《つ》いて薨《こう》じ、その墓を箸墓というと載す。 | |
| 未聞の代には鬼市《きし》として顔を隠し、また全く形を見せずに貿易する事多し(一九〇四年の『随筆問答雑誌《ノーツ・エンド・キーリス》』十輯一巻二〇六頁に出た拙文「鬼市について」)。これ主として外人を斎忌《タブー》したからで、それと等しく今日までも他部族の女に通うに、女のほかに知らさず。甚だしきは女にすら自分の何人たるを明かさぬ例がある。さて昔は日本にも族霊《トテム》盛んに行われ、一部族また一家族が蛇狼鹿、その他の諸物を各々その族の霊《トテム》としたらしいてふ拙見は、『東京人類学会雑誌』二七八号三一一頁に掲げ置いた。かくて稽《かんが》うると大国主神《おおくにぬしのかみ》は蛇を族霊《トテム》として、他部族の女に通いしが、蛇を族霊とする部族の男と明かすを聞いて女驚くを見、慙《は》じて絶ち去ったと見える。由って女も慙じて自ら陰を撞いて薨ずとあるを、何かの譬喩のように解かんとする人もあるようだが、他部族の男の種を宿さぬよう麁末《そまつ》な手術を仕損じてか、とにかくその頃の婦女にはかようの死様《しにざま》が実際あったので、現今見るべからざる奇事だから昔の記載は虚構だと断ずるの非なるは先に論じた。 | |
| また西アフリカのホイダー市には、近世まで大蛇を祀《まつ》り年々|棍《クラブ》を持てる女巫《みこ》隊出て美女を捕え神に妻《めあ》わす。当夜一度に二、三人ずつ女を窖《あな》の中《うち》に下すと、蛇神の名代たる二、三蛇|俟《ま》ちおり、女巫《みこ》が廟の周《ぐる》りを歌い踊り廻る間にこれと婚す。さて家に帰って蛇児を産まず人児を産んだから、人が蛇神の名代を務めたのだ(一八七一年版シュルツェの『デル・フェチシスムス』五章)。『十誦律』に、優波離《うばり》が仏に詣り、〈比丘の呪術をもって、自ら畜生形と作《な》り、行婬す〉、また〈三比丘の呪術をもって、倶に畜生形と作って行婬〉する罪名を問う事あり。ローマの諸帝中、獣形を成して犯姦せし者数あり。宋以来支那に跋扈《ばっこ》する五通神は、馬豚等の畜生が男に化けて降り来り、放《ほしいま》まに飲食を貪《むさぼ》り妻女を辱しむる由(『聊斎志異』四)、これは濫行の悪漢秘密講を結び、巧みに畜《けもの》の状をして人を脅かし非を遂げたのであろう。 | |
| 人が蛇になった話は蛇のある地には必ず多少あって、その変化の理由も様々に説き居る。貪慾な者蛇となって財を守るとは、インド東欧西亜諸方に盛んな説で悪人生きながら蛇になる話はアフリカ未開人間にも行わる(一九〇三年版マーチン女史の『バストランド』十五章)。ただし貪欲でも悪人でもなくて蛇になった話もあって、甲賀三郎は、高懸山の鬼王とか、蛇に化けた山神を殺したとか(『若狭郡県志』二、『郷』三の十に引かれた『諸国旅雀』一)、その報いとしてか悪人の兄どもに突き落された穴中で、三十三年間大蛇となりいたが、妻子が念じて観音の助けで人間になり戻り二兄を滅ぼし繁盛した。羽州の八郎潟の由来書に、八郎という樵夫《きこり》、異魚を食い大蛇となったという(『奥羽永慶軍記』五)。しかし『根本説一切有部毘奈耶《こんぽんせついっさいうぶびなや》雑事』に、女も蛇も多瞋多恨、作悪無恩利毒の五過ありと説けるごとく、何といっても女は蛇に化けるに誂《あつら》え向きで、その例|迥《はる》かに男より多くその話もまたすこぶる多趣だ。 | |
| 慙《は》じて蛇になった例は、陸前佐沼の城主平直信の妻、佐沼御前|館《やかた》で働く大工の美男を見初《みそ》め、夜分|閨《ねや》を出てその小舎を尋ねしも見当らず、内へ帰れば戸が鎖されいた。心深く愧《は》じ身を佐治川に投げて、その主の蛇神となり、今に祭の前後必ず人を溺《おぼ》らすそうだ(『郷』四巻四号)。愛執に依って蛇となったは、『沙石集』七に、ある人の娘鎌倉若宮僧坊の児《ちご》を恋い、死んで児を悩死せしめ、蛇となって児の尸《しかばね》を纏《まと》うた譚あり。妬みの故に蛇となったは、梁の※[希+おおざと]《ち》氏(『五雑俎』八に見ゆれど予その出処も子細も詳らかにせぬから、知った方は葉書で教えられたい)や、『発心集《ほっしんしゅう》』に見えたわが夫を娘に譲って、その睦《むつ》まじきを羨むにつけ、指ことごとく蛇に化《な》りたる尼公《あまぎみ》等あり。 | |
| もしそれ失恋の極蛇になったもっとも顕著なは、紀伊の清姫《きよひめ》の話に留まる。事跡は屋代弘賢《やしろひろかた》の『道成寺考』等にほとんど集め尽くしたから今また贅《ぜい》せず、ただ二つ三つ先輩のまだ気付かぬ事を述べんに、清姫という名余り古くもなき戯曲や道成寺の略物語等に、真砂庄司の女《むすめ》というも謡曲に始めて見え、古くは寡婦また若寡婦と記した。さて谷本博士は、『古事記』に、品地別命《ほむじわけみこと》肥長比売《ひながひめ》と婚し、窃《ひそ》かに伺えば、その美人《おとめご》は蛇《おろち》なり、すなわち見《み》畏《かしこ》みて遁《に》げたもう。その肥長比売|患《うれ》えて海原を光《てら》して、船より追い来れば、ますます見畏みて、山の陰《たわ》より御船を引き越して逃げ上り行《いでま》しつとあるを、この語の遠祖と言われたが、これただ蛇が女に化けおりしを見顕わし、恐れ逃げた一点ばかりの類話で、正しくその全話の根本じゃない。『記』に由って考うるに、この肥長比売は大物主神の子か孫で、この一件すなわち品地別命がかの神の告《つげ》により、出雲にかの神を斎《いつ》いだ宮へ詣でた時の事たり。上にも言った通り、この神の一族は蛇を族霊《トテム》としたから、この時も品地別命が肥長比売の膚に雕《え》り付けた蛇の族霊の標《しるし》か何かを見て、その部族を忌み逃げ出した事と思う。大物主神は素戔嗚尊《すさのおのみこと》が脚摩乳《あしなつち》手摩乳《てなつち》夫妻の女を娶《めと》って生んだ子とも裔《すえ》ともいう(『日本紀』一)。この夫妻の名をかく書いたは宛字《あてじ》で、『古事記』には足名椎手名椎に作る。既《はや》く論じた通り、上古の野椎ミツチなど、蛇の尊称らしきより推せば、足名椎手名椎は蛇の手足なきを号《な》としたので、この蛇神夫妻の女を悪蛇が奪いに来た。ところを尊が救うて妻とした「その跡で稲田|大蛇《おろち》を丸で呑み」さて産み出した子孫だから世々蛇を族霊としたはずである。 | |
| 予は清姫の話は何か拠るべき事実があったので、他の話に拠って建立された丸切《まるきり》の作り物と思わぬが、もし仏徒が基づく所あって多少附会した所もあろうといえば、その基づく所は釈尊の従弟で、天眼第一たりし阿那律《あなりつ》尊者の伝だろう。この尊者については、近出の『仏教大辞彙』などに見える珍譚|甚《いと》多い。例せば阿那律すでに阿羅漢となって、顔容美しきを見て女と思い、犯さんとしてその男たるを知り、自らその身を見れば女となりおり、愧じて深山に隠れ数年帰らず。阿那律その妻子の歎くを憐《あわれ》み、その者を尋ねて悔過せしめ、男子となり復《もど》って家内に遇わしめた(『経律異相』十三)。『四分律』十三に、毘舎離の女他国へ嫁して姑と諍《いさか》い本国へ還るに、阿那律と同行せしを、夫追い及んで詰《なじ》ると、〈婦いわく我この尊者とともに行く、兄弟相逐うごとし他の過悪なし〉と、夫怒りて阿を打ってほとんど死せしめたと出るが、阿は高の知れた人間の女に、心を動かすような弱い聖《ひじり》でなく、かつて林下に住みし時、前生に天にあって妻とした天女降って、天上の楽を説くに対し、〈諸《もろもろ》の天に生まれ楽しむ者、一切苦しまざるなし、天女汝まさに知るべし、我生死を尽くすを〉と喝破《かっぱ》したは、南方先生若い盛りに黒奴《くろんぼ》女の夜這《よば》いを叱《しか》り卻《かえ》したに次いで豪い(『別訳雑阿含経』巻二十、南方先生|已下《いか》は拙《やつがれ》の手製)。『弥沙塞五分律《みしゃそくごぶんりつ》』八に、〈仏、舎衛城に在り、云々。時に一の年少の婦人の夫を喪う有りて、これなる念《おも》いを作《な》す。我今まさに何許《いず》くかに更に良き対を求めるべし、云々。まさに一の客舎を作り、在家出家の人を意に任せて宿止せしめ、中において択び取らんと。すなわち便《ただ》ちにこれを作り、道路に宣令して、宿るを須《ま》つ。時に阿那律、暮にかの村に至り、宿所を借問す。人有りて語りて言う、某甲の家に有りと。すなわち往きて宿を求む。阿那律、先に容貌|好《よ》きも、既に得道の後は顔色常に倍せり。寡婦、これを見て、これなる念いを作《な》す。我今すなわち已《すで》に好き胥《むこ》を得たりと。すなわち、指語すらく中に宿るべしと。阿那律すなわち前《すす》みて室に入り結跏趺坐《けっかふざ》す。坐して未だ久しからずしてまた賈客あり、来たりて宿を求む。寡婦答えて言う、我常に客を宿すといえども、今已に比丘に与え、また我に由らずと。賈客すなわち主人の語を以て、阿那律に従きて宿を求む。阿那律寡婦に語りて言う、もし我に由らば、ことごとく宿を聴《ゆる》すべしと。賈客すなわち前に進《い》る。寡婦またこれなる念いを作す。まさに更に比丘を迎えて内に入らしむべし、もし爾《しか》せざれば、後來期なからんと。すなわち内に更に好き牀を敷き燈を燃し、阿那律に語りて言う、進みて内に入るべしと。阿那律すなわち入りて結跏趺坐し、繋念して前に在り。寡婦衆人の眠れる後に語りて言う、大徳我の相|邀《むか》える所以の意を知れるや不《いな》やと。答えて言う、姉妹よ汝が意は正に福徳に在るべしと。寡婦言う、本《も》とこれを以てにあらずと、すなわち具《つぶ》さに情を以て告ぐ。阿那律言う、姉妹よ我等はまさにこの悪業を作《な》すべからず、世尊の制法もまた聴《ゆる》さざる所なりと。寡婦言う、我はこれ族姓にして年は盛りの時に在り、礼儀|備《つぶ》さに挙がりて財宝多饒なり。大徳の為に給事せんと欲す。まさに願うべき所、垂《なに》とぞして納められよと。阿那律これに答えること初めの如し。寡婦またこれなる念いを作す。男子の惑う所は惟《た》だ色に在り。我まさに形を露《あらわ》にしてその前に立つべしと。すなわち便《ただ》ちに衣を脱して前に立ちて笑う。阿那律すなわち閉目正坐し、赤骨観を作す。寡婦またこれなる念いをなす。我かくの如しといえども、彼猶お未だ降らずと。すなわち牀に上りこれと与《とも》に共に坐さんと欲す。是において阿那律踊りて虚空に昇る。寡婦すなわち大いに羞恥し、慚愧の心を生じ疾く還りて衣を著し、合掌して過ちを悔い、云々。阿那律妙法を説き、寡婦聞き已《おわ》りて塵を遠ざけ垢を離れて、法眼の浄なるを得たり〉。これが少なくとも、熊野の宿主寡婦が安珍に迫った話にもっともよく似居る。 | |
| 『油粕《あぶらかす》』に「堂の坊主の恋をする頃、みめのよき後家や旦那に出来ぬらん」とあるごとく、双方とも願ったり叶《かな》ったり。明き者同士なれば、当時の事体、安珍の対手《あいて》を清姫てふ室女とするよりは、宿主の寡婦とせる方恰好に見える。外国でも色好む寡婦、しばしば旅宿を営んだ(ジュフールの『売靨史』や、マーレの『北土考古篇《ノーザーン・アンチクイチース》』ボーン文庫本三一九頁等)。一九〇七年版カウエルおよびラウス訳『仏本生譚《ジャータカ》』五四三に、梵授王の太子、父に逐われ隠遁《いんとん》せしが、世を思い切らず竜界の一竜女、新たに寡なるが他の諸竜女その夫の好愛するを見、ついに太子を説いて偕《とも》に棲むところあるなど、竜も人間も閨情に二つなきを見るに足る。この辺で俗伝に安珍清姫宅に宿り、飯を食えば絶《はなは》だ美《うま》し。窃《ひそ》かに覗《のぞ》くと清姫飯を盛る前必ず椀《わん》を舐《な》むる、その影|行燈《あんどん》に映るが蛇の相なり。怪しみ惧《おそ》れて逃げ出したと。 | |
| ■蛇の効用 | |
| この辺でまた伝えしは、前掲トチワの国では蛇を常食としダシを作ると。されば現時持て囃《はや》さるる「味の素」は蛇を煮出して作るというも嘘でないらしいと言う人あり。琉球で海蛇を食うなどを訛伝《かでん》したものか。効用といえば未開半開の世には蛇が裁判役を勤めた。昔琉球で盗人を検出するに、巫女蛇を連れ来り、衆人を集め示せば、盗人に食い付きていささかも違《たが》わず、故に盗賊なかりしと(『定西法師伝』)。熊楠案ずるに『隋書』に日本人の獄訟《うったえ》を、〈あるいは小石を沸湯中に置き、競うところの者にこれを探らしむ、いわく理曲なればすなわち手|爛《ただ》る、あるいは蛇を甕中に置きこれを取らしむ、いわく曲なればすなわち手を螫《さ》す〉。前者は武内宿禰《たけのうちのすくね》などが行った湯起請《ゆぎしょう》で国史にも見える。それと記し駢《なら》べたるを見ると古く蛇起請も行われたるを、例の通り邦人は常事として特に書き留めなんだが、支那人は奇として記録したのだ。礼失して野に求むてふ本文のごとく、かかる古俗が日本に亡びて、琉球に遺存したのだ。それよりも珍事は十字軍の時、回将サラジンが大蛇を戦争に使わんとしたので五月号に出し置いた。西洋で鰻を食うに、骨切りなどの法なく、ブツブツと胴切りにして羹《しる》に煮るを何やら分らずに吃《く》う。ウィリヤム・ホーンの書を見ると、下等な店では蛇を代用するもあるらしい。由って在英中得も知れぬ穢《きたな》い店どもへ多く入りて鰻汁を命じ、注意して視《み》たが最早そんな事はせぬらしかった。『今昔物語』など読むと、本邦でも低価な魚として蛇を食わせ、知らぬが仏の顧客を欺く事も稀にあったらしいが、永良部鰻《えらぶうなぎ》てふ海蛇のほかに満足に食用すべきものなきがごとし。昔支那から伝えた還城楽《げんじょうらく》は本名|見蛇楽《けんじゃらく》で、好んで蛇を食う西国人が蛇を得て悦ぶ姿を摸したという。古今風俗の違いもあるべきが、支那より西に当って蛇を食う民を捜すと、『聖書』に爬虫類を啖う禁戒あれば、ユダヤ教やキリスト教の民でまずはない。しかるに回教を奉ずるアラビア人は、無毒の蛇を捕え頭を去り体を小片に切り串に貫き、火の上に旋《まわ》しながらレモンや塩や胡椒《こしょう》等を振り掛け食う。欧人これを試みた者いわく、腥《なまぐさ》くてならぬ故臭い消しに炙《あぶ》る前、その肉をやや久しく酢に漬け置くべし味は鰻に優るとも劣りはせんと(ピエロチの『パレスチン風俗口碑記』四六頁)。 | |
| 支那や後インドで※[虫+冉]蛇肉《ぜんじゃにく》を賞翫《しょうがん》し、その胆を薬用する事は本篇の初回に述べた。プリニウス言う、エチオピアの長生人《マクロビイ》アトス山の住民等蝮を常食とし、虱《しらみ》生ぜず四百歳の寿を保つと。一六八一年に成ったフライヤーの『|東印度および波斯新話《ア・ニュウ・アッカウント・オヴ・イースト・インジア・エンド・パーシア》』一二三頁に、蝮酒は肺癆《はいろう》を治し、娼妓の疲れ痩せたるを復すといい、サウシの『随得録《コンモンプレース・ブック》』四には、蝮酒は能《よ》く性欲を強くするとある。『本草綱目』に、醇《よき》酒《さけ》一斗に蝮一疋活きたまま入れて封じ、馬が溺《いばり》する処に埋め、一年経て開けば酒は一升ほどに減り、味なお存し蝮は消え失せいる。これを飲めば癩病を癒すとある。蝮は興奮の薬力ある物か。予が知る騎手など競馬に先だち、乾した蝮の粉を馬に餌《えば》うと、甚だ勇み出すといった。先日の新紙に近年蛇を薬用のため捕うる事大流行で、鯡《にしん》を焼けば蛇|聚《つど》い来るとあったが虚実を知らぬ。 | |
| 一六六五年再版ド・ロシュフォーの『西印度諸島博物世態誌《イストア・ナチュラル・エ・モラル・デ・イール・アンチュ》』一四二頁に、土人の家に蛇多く棲むも鼠を除くの効著しき故殺さずと見え、『大英百科全書』四に両半球に多種あるボア族の大蛇いずれも温良《おとなし》く、有名なボア・コンストリクトルなど、人と同棲して鼠害を除くとある。その鼠害というはなかなか日本のような事でなく、予かつて虫類を多く集め来り、針もて展翅板《てんしばん》へ留め居る眼前へ鼠群襲い来り、予が一疋の蝶に針さす間に先様から鼠に粉※[くさかんむり/韲]《ふんさい》され、一方へ追い廻る間に他方より侵来して何ともなる事でなかった。かかるところにあっては蛇の姿を嫌がるどころにあらず、諸邦でこれを家の祖霊、耕地の護神とせるは尤《もっとも》千万《せんばん》と悟った。さる功績あらばこそ堅固なキリスト信教国の随一たるスウェーデンですら、十六世紀まで蛇を家の神と祀《まつ》った。「蛇の変化」の項で記したホイダーの蛇神大崇拝のごとき、この国に蛇ほど尊きものなきごとくしたは不思議に堪えぬ。しかるにその実状を視《み》た公平な論者は、古く既にこの神と冊《かしず》かるる蛇が毒蛇どもを殺し、田畑に害ある諸動物を除く偉功を認めかく敬わるるは当然だといった(アストレイ、三の三七頁)。わが国の農民が、蛇家に入るをミが入ると悦ぶも、もと蛇が大いに耕作を助けた時の遺風と知れる。 | |
| それから随分危険ながら蛇が著しく人を助くる今一件は、その毒を鏃《やじり》に塗りて蠢爾《しゅんじ》たる最も下劣な蛮人が、猛獣巨禽を射殺して活命する事だ。パッフ・アッダーはほとんどアフリカ全部に産し、長《たけ》四、五フィートに達する大毒至醜の蝮で、その成長した奴は世界でもっとも怖るべき物という。この蝮は平生頭のみ露わして体を沙中に埋め、その烈毒を憑《たの》んで猥《みだ》りに動ぜず。人畜近くに及び、わずかに首を擡《もた》ぐ。人はもとより馬もこれに咬まるれば数時の後|斃《たお》る。しかるにこの蛇煙草汁を忌む事抜群で、この物煙草汁に中《あた》って死するは、人がこの物の毒に中って死するより速やかだから、ホッテントット人これを見れば、煙草を噛んでその面に吹き掛け、あるいは杖の尖《さき》にその脂《やに》を塗りて、これに咬み付かしむればたちまち死す。ブシュメン人、この蛇の動作鈍きに乗じ、急にその頸を跣足《はだし》で蹈み圧《おさ》え、一打ちに首を切り、さて寛《ゆっく》りその牙の毒を取り、鏃に着くるに石蒜《ひがんばな》属のある草の粘汁を和す。ブシュメン用いるところの弓は至って粗末なるに反して、その矢は機巧を究め、蘆茎を※[竹かんむり/幹]《やがら》とし、猟骨を鏃とし、その尖に件《くだん》の毒を傅《つ》けて※[竹かんむり/幹]中に逆さまに挿し入れ蔵《おさ》め置き、用いるに臨み抜き出して尋常に※[竹かんむり/幹]の前端に嵌《は》め着く。このブシュメン人は濠州土人|火地人《フェージャン》等と併《なら》びに最劣等民と蔑《べっ》せらるるに、かくのごとき優等の創製を出した上に、パッフ・アッダーを殺すごとその毒を嚥《の》まば、蛇毒ついにその身を害し能わざるべきを予想し、実行したるは愚者も千慮の二得というべし。 | |
| ウッドの『博物画譜』にいわく、パッフ・アッダーに咬まれたのに利く薬|聢《たし》かに知れず。南アフリカの土人は活きた鶏の胸を開いて心動いまだ止《や》まぬところを創《きず》に当てると。一七八二年版ソンネラの『東印度および支那紀行』にいわく、インドのカリカルで見た毒蛇咬の療法は妙だった。若い牝鶏の肛門を創に当て、その毒を吸い出さしむると少時して死す。他の牝鶏の尻を当てるとまた死す。かくて十三回まで取り替ゆると、十三度目の者死なずまた病まず。その人ここにおいて全快したと。多紀某の『広恵済急方』という医書に、雀の尻上を横|截《ぎ》りした図を出し、確か指を切って血止まらざるを止めんとならば、活きた雀を腰斬りしてその切り口へ傷処をさし込むべしとあったと記憶するが、これらいずれも応急手当として多少の奏効をしたらしい。 | |
| ■(付)邪視について | |
| 一巻二号九二頁に石田君がセーリグマン氏の書いた物より引かれた一条を読んで、近時の南支那にも、昔の東晋時代と同じく邪視を悪眼と呼ぶ事を知り得た。過ぐる大正六年二月の『太陽』二三巻二号一五四―一五五頁に、予は左のごとく書き置いた。 | |
| 邪視英語でイヴル・アイ、伊語でマロキオ、梵語でクドルシュチス。明治四十二年五月の『東京人類学会雑誌』へ、予その事を長く書き邪視と訳した。その後一切経を調べると、『四分律蔵』に邪眼、『玉耶経』に邪盻《じゃけい》、『増一阿含』および『法華経』普門|品《ぼん》また『大宝積経』また『大乗宝要義論』に悪眼、『雑宝蔵経』と『僧護経』と『菩薩処胎経』に見毒、『蘇婆呼童子経』に眼毒とあるが、邪視という字も『普賢行願品《ふげんぎょうがんぼん》』二八に出でおり、また一番よいようでもあり、柳田氏その他も用いられおるから、手前味噌ながら邪視と定めおく。もっとも本統の邪視のほかに、インドでナザールというのがあって、悪念を以てせず、何の気もなく、もしくは賞讃して人や物を眺めても、眺められた者が害を受けるので、予これを視害と訳し置いたがこれは経文に拠って見毒と極《き》めるが良かろう。 | |
| ここにいえる、邪視の字が出おる『普賢行願品』は、唐の徳宗の貞元中、醴泉寺《れいせんじ》の僧般若が訳し、悪眼の字が出おる『増一阿含』は、東晋時代に苻堅に礼接された曇摩難提が訳した。故に両《ふたつ》ながら昨今始まった語でなく、悪眼は今よりおよそ千五百四十年前、邪視は今よりおよそ千百三十年前既にあったと知らる(『高僧伝』巻一、『宋高僧伝』巻三)。而《しか》して石田君が『晋書』から引かれた衛※[王+介]《えいかい》の死に様は、『南方随筆』に載せた裏辻公風と同じくいわゆる見毒(ナザール)に中《あた》ったらしい。小児を打ち続けて発病せしむると、撫《な》で過ぎて疳《かん》を起させると差《ちが》うほど邪視と差う。 | |
| また石田君はデンニス氏の書から、支那で妊婦やその夫は、胎児とともに四眼をもつ者として、邪視の能力者として、一般から嫌忌さるる由を引かれた。『琅邪代酔編』巻二に、後漢の時、季冬に臘《ろう》に先だつ一日大いに儺《おにやらい》す、これを逐疫という、云々、方相氏は黄金の四目あり、熊皮を蒙《かぶ》り、玄裳朱衣して戈《ほこ》を執り盾《たて》を揚ぐ、十二獣は毛角を衣《き》るあり、中黄門これを行う、冗縦僕財これを将《もち》いて以て悪鬼を禁中に逐う、云々。その時中黄門が、悪鬼輩速やかに逃げ去らずば、甲作より騰眼に至る十二神が食ってしまうぞと唱え、方相と十二獣との舞をなして、三度呼ばわり廻り、炬火《たいまつ》を持ちて疫を逐い端門より出す云々とある。『日本百科辞典』巻七、追儺《ついな》の条にも明示された通り、当夜方相は戈で盾をたたき隅々《すみずみ》より疫鬼を駈り出し、さて十二獣を従えて鬼輩を逐い出すのだ。一九〇二年頃の『ネーチュル』に、インドにある英人ジー・イー・ピール氏が寄書して、犬の両眼の上に黄赤い眼のような両点あるものは、眠っていても眼を※[目+爭]《みは》り居るよう見えるから、野獣甚だこれを恐れて近附かぬと述べた。そんな事よりでもあろうか、パーシー人は、人死すれば右様の犬(本邦の俗四つの眼と呼ぶ)を延《ひ》いてその屍を視せ、もはや悪鬼が近付かずとて安心すという。米国で出たハムポルト文庫所収の何かの書に出あったが、今この宅にないから書名を挙げ得ぬ。しかしパーシー人からも親しく聴いた事だ。方相の四目もそんな理由で、いわば二つでさえ怖ろしい金の眼を二倍持つから、鬼が極めて方相におじるのだ。方相が十二神を従えて疫を逐う状は、『日本百科大辞典』の挿画で見るべし。しかるに後世方相の形が至ってにくさげなるより、方相を疫鬼と間違えたとみえ、安政またはその前に出た『三世相大雑書』などに、官人が弓矢もて方相を逐う体を図したのをしばしばみた。只今拙宅の長屋にすむ人もそんな本を一部もちおるが、題号|失《う》せたれば書名を知りがたい。惟《おも》うにデンニス氏が記せるところも、最初方相四眼もて悪鬼を睨みおどした事が、件《くだん》の『大雑書』の誤図と等しく、いつの間にか謬伝されて、方相四眼もて人に邪視を加うると信ぜられ、妊婦やその夫や胎児も、他の理由から人に忌まるるに乗じて、かようの夫婦や胎児までも四眼ありて、邪視を人に及ぼすと言わるるに及んだものか。(昭和四年一〇月、『民俗学』一ノ四) | |
| ■(付)邪視という語が早く用いられた一例 | |
| 余り寒いので何を志すとなく、明の陳仁錫の『潜確居類書』一〇七をそこここ見ておると、鶏廉狼貪、魚瞰鶏睨、魚不瞑、鶏邪視とある。この文句は何から採っただろうと、『淵鑑類函』四二五、鶏の条を探ると、〈王褒《おうほう》曰く、魚瞰鶏睨、李善|以為《おも》えらく魚目|瞑《つむ》らず、鶏好く邪視す〉とある。鶏はよく恐ろしい眼付きで睨むをいうので、この田辺辺で古く天狗が時に白鶏に化けるなどいい忌む人があったは、多少その邪視を怖れたからだろう。白いのに限らず鶏をすべて嫌うた村もあったときく。『拾遺記』一、※[禾+砥のつくり]支の国より堯に献じた重明の鳥は、〈双睛目あり、状《かたち》鶏のごとし、能く猛獣虎狼を搏逐す、妖災群悪をして、害為す能わざらしむ、(中略)今人毎歳元日、あるいは木を刻み金を鋳す、あるいは図を画きて鶏|※[片+(戸の旧字+甫)]上《ゆうじょう》に為す、これその遺像なり〉。その他支那で鶏を以て凶邪を避けた諸例は、載せて Willoughby-Mcade,‘Chinese Ghouls and Goblins’. 1928. pp. 155-157. に出《い》づ。またマレー群島中、アムボイナやマカッサーの人はその辺の海に千脚ある大怪物すみ、その一脚を懸けられてもたちまち船が覆《くつが》える、がこの怪物鶏を怖れるからとて、船には必ず鶏を乗せて出発するという(Stavorinus, “Account of Celebes, Amboyna, etc.”, in Pinkerton,‘Voyages and Travels’, vol. xi. p. 262, London, 1812)。これら種々理由あるべきも、その一つは鶏の邪視もて他の怪凶をば制したのであろう。王褒は有名な孝子かつ学者で、『晋書』八八にその伝あり。李善は唐の顕慶中、『文選』を註した(『四庫全書総目』一八六)。熊楠十歳の頃、『文選』を暗誦して神童と称せられたが、近頃年来多くの女の恨みで耄碌《もうろく》し、件《くだん》の魚瞰鶏睨てふ王褒の句が、『文選』のどの篇にあるかを臆《おも》い出し得ない。が何に致せ李善がこれに註して、魚瞰とは死んでも眼を閉じぬ事、鶏睨とはよく邪視する事を解いたのだ。前項に、邪視なる語は、唐の貞元中に訳された『普賢行願品』に出でおり、今(昭和四年)より千百三十年ほどの昔既に支那にあったと述べたれど、それよりも約百四十年ほど早く行われいたと、この李善の註が立証する。また魚瞰について想い出すは、予の幼時、飯のサイにまずい物を出さるると母を睨んだ。その都度母が言ったは、カレイが人間だった時、毎々《つねづね》不服で親を睨んだ、その罰で魚に転生して後《のち》までも、眼が面の一側にかたより居ると。さればカレイも邪視する魚と嫌うた物か[延享二年大阪竹本座初演、千柳《せんりゅう》、松洛《しょうらく》、小出雲《こいずも》合作『夏祭浪花鑑《なつまつりなにわかがみ》』義平治殺しの場に、三河屋義平治その婿団七九郎兵衛を罵《ののし》る詞《ことば》に、おのれは親を睨《ね》めおるか、親を睨むと平目になるぞよ、とある。ヒラメもカレイも眼が頭の一傍にかたよりおるは皆様御承知]。『後水尾院《ごみずのおいん》年中行事』上に、一参らざる物は王余魚、云々。またカレイ、目の一所によりて附し、その体異様なれば参らずなどいう女房などのあれども、それも各の姿なり、その類の中に類いず、こと様にあらばこそと見ゆ。(二月二十八日) | |
|
追加 前項に、今より千二百七十年ほどの昔、唐の顕慶年間、李善が書いた『文選』の註に、鶏好邪視とあるを、邪視なる語のもっとも早くみえた一例として置いた。その後また捜索すると、それより少なくとも五百二十年古く、後漢の張平子の『西京賦』に、〈ここにおいて鳥獣、目を殫《つく》し覩窮《みきわ》む、遷延し邪視す、乎長揚の宮に集まる〉。注に『説文』曰く、〈睨は斜視なり、劉長曰く、邪睨邪視なり〉、同上、麗服|※[風にょう+昜]菁《ようせい》、※[目+名]藐流眄《べいびょうりゅうべん》、一顧|傾城《けいせい》とある*を、山岡明阿の『類聚名物考』一七六に引いて、邪視をナガシメと訓じあるを見あてた。この邪睨は邪視と同じくイヴル・アイを意味し、支那でイヴル・アイをいい表わした最も古い語例の一つだろう。ナガシメは紀州田辺近村の麦打ち唄に「色けないのに色目を使う」というイロメで、流眄によく合えど、邪睨邪視には合わない。また同項に引いたマレー群島で海中の怪物が鶏を怖るるてふ話に近きは、琉球にもあって、佐喜真《さきま》君の『南嶋説話』二九頁に出《い》づ。(昭和六年四月)
* 註に※[目+名]は眉睫《びしょう》の間、藐、好《よ》き視容なり。 |
|
|
■南方熊楠
南方熊楠は、慶応3年4月15日(明治になる前年1867年の5月18日)、紀州和歌山城下に生まれました。 幼少時から『和漢三才図絵』全巻を筆写するなど、熊楠は和漢書により学問的基礎を築いていきました。和歌山中学卒業後、東京大学予備門に入学しますが(同期に夏目漱石、正岡子規など)、20歳で中退します。アメリカに渡って遊学し、隠花植物(菌類や地衣類、藻類、蘚苔類など)や粘菌を求めて各地を点々とします。 26歳で渡英し、ロンドンへ。ロンドンでは大英博物館で東洋関係の資料の整理を手伝いをする仕事を得ます。大英博物館では資料閲覧を許され、博物学・人類学などの書物を筆写し、古今東西の知識を吸収します。科学雑誌『ネイチャー』や随想問答雑誌『ノーツ・エンド・キリース』にしばしば論文を寄稿し、掲載され、欧米の学者に注目されます。チャールズ・ダーウィン、ハーバード・スペンサーと並んで世界三大碩学のひとりと謳われるほど、熊楠の名声は高まりました。またロンドンでは孫文と親交を結んでいます。 14年に及ぶ海外遊学の後、 1900年(明治33年)、34歳で帰国。熊野の那智山の旅館の1室を借り、植物の調査を始めます。3年の植物調査の後、1904年(明治37年)、口熊野、田辺を訪れ、田辺の中屋敷町に家を借り、定住しました。その2年後の1906年(明治39年)、40歳で闘鶏神社の神官の娘の田村松枝と結婚。1男1女をもうけます。 田辺では、隠花植物や粘菌の研究のかたわら、国内外に民俗学関係などの論文を発表(熊楠は那智や田辺という日本の辺地にあっても、『ネイチャー』や『ノーツ・エンド・キリース』に寄稿を続け、『ネイチャー』には1914年まで、『ノーツ・エンド・キリース』には1933年まで論文を発表しています)。 しかし、ちょうど熊楠が結婚した年に施行された1町村1社を原則とする神社合祀令が熊楠の植物研究に影を落とします。 明治政府は記紀神話や延喜式神名帳に名のあるもの以外の神々を排滅することによって神道の純化を狙いました。 熊野信仰は古来の自然崇拝に仏教や修験道などが混交して成り立った、ある意味「何でもあり」の宗教ですから、小さな神社は片っ端から合祀の対象となり、神社林が伐採されました。歴代の上皇が熊野御幸の途上に参詣したという歴史のある熊野古道・中辺路の王子社までもが合祀され、廃社となり、神社林の破壊が行なわれました。 熊楠にとって神社林は貴重な生物が住む貴重な研究の場所であり、神社合祀の嵐が熊野に吹き荒れるなか、熊楠は神社林が破壊されることに怒りを爆発させ、神社合祀反対運動に立ち上がりました。地方新聞に神社合祀反対意見を投書し、住民を説得に出かけ、中央の学者に書簡で訴えるなど、神社合祀に対して死にもの狂いで闘いました。留置場に拘留され、罰金を課せられるなどの目に会いながら熊楠は命をかけて闘いました。 熊楠の神社合祀反対運動が報われたのが、熊楠63歳のとき。1929年(昭和4年)、熊楠は昭和天皇への粘菌学の進講を行ないます。熊楠が保護に努めた田辺湾に浮かぶ神島(かしま)に昭和天皇を迎え、御召艦長門上で粘菌学を進講。粘菌標本110点を進献しました。 神島は1936年(昭和11年)には国の天然記念物に指定されました。 1941年(昭和16年)12月、日本軍の真珠湾攻撃からおよそ3週間後の29日に、熊楠死去。享年75。田辺郊外の真言宗高山寺に埋葬されました。 |
|
 ■倭名類聚抄 〔龍魚部〕 |
|
| 和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)は、平安時代中期に作られた辞書である。承平年間(931年 - 938年)、勤子内親王の求めに応じて源順(みなもとのしたごう)が編纂した。中国の分類辞典『爾雅』の影響を受けている。名詞をまず漢語で類聚し、意味により分類して項目立て、万葉仮名で日本語に対応する名詞の読み(和名・倭名)をつけた上で、漢籍(字書・韻書・博物書)を出典として多数引用しながら説明を加える体裁を取る。今日の国語辞典の他、漢和辞典や百科事典の要素を多分に含んでいるのが特徴。当時から漢語の和訓を知るために重宝され、江戸時代の国学発生以降、平安時代以前の語彙・語音を知る資料として、また社会・風俗・制度などを知る史料として国文学・日本語学・日本史の世界で重要視されている書物である。 | |
| ■〔1〕龍 | |
|
文字集畧云、龍、{力鐘反、太都}
{下総本には「和名」二字あり。『日本書紀』「神代紀」、「斎明紀」に同訓あり。太都(タツ)は、もともと(蓋)『爾雅』に謂うところの「螣蛇」(トウダ)であろう。郭璞(カクハク)は「能く雲霧を興して其の中に遊ぶものなり」と云う。また『荀子』は「蛇無足而飛」と云う。『説文』は、「螣、神蛇なり」と云う。今猶、太都(タツ)は、雲中に在り尾を垂らし有るものである。越後の海辺でよく見ることができ、これを、太都万岐(タツマキ)と謂う。恐らくは龍にあらず。} 〔注〕 (1-1)文字集略: もじしゅうりゃく:古書注参照。中国古字書だが、亡佚して伝わらない。「和名抄引書」:文字集略、[隋志]文字集略六巻{梁、阮考緒撰}、[旧志]同一巻{阮考緒撰}、[新志]阮考緒文字集略一巻 、[現在]。……なお、「和名抄引書」で、「引書」の注記として記した経籍志の略記は次のとおり。[隋志]は、『隋書』「経籍志」(『隋書』巻三十二、志第二十七)、[旧志]は『旧唐書』「経籍志」(旧唐書巻四十六、志第二十六)、[新志]は『新唐書』「芸文志」(唐書巻五十七、志第四十七)、[漢志]は『漢書』「芸文志」(漢書巻三十芸文志第十)に記された書名を記し、[現在書目]あるいは[現在(書)]は、わが国で891年ごろ成立した『日本国見在書目録』に記載された書名を記す。 (1-2)1神代紀:【日本書紀】(岩波文庫『日本書紀』坂本・家永他校注)巻第二(神代紀かみよのしものまき)第十段、「海幸山幸説話」中の弟山幸である「彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)」が海神(わたつみ)の宮で豊玉姫(とよたまびめ)と出会い、妻に娶り、豊玉姫が龍(竜:たつ:そして別記一書に「八尋熊鰐」ヤヒロワニ)に化身して、海辺で「鸕[玆鳥]草葺不合尊」(うがやふきあえずのみこと)を生む、云々の件で、次のように記す。(第2冊164頁):後に豊玉姫、果して前の期の如く、其の女弟玉依姫を將ゐて、直に風波を冒して、海辺に来到る。臨産む時に逮びて、請ひて曰さく、「妾産まむ時に、幸はくはな看ましそ」とまうす。天孫猶忍ぶること能はずして。窃に往きて覘ひたまふ。豊玉姫、方に産むときに竜(たつ)に化為(な)りぬ。而して甚だ慙ぢて曰はく、「如し我れを辱しめざること有りせば、海陸相通はしめて永く隔絶つこと無からまし。今既に辱みつ。将に何を以てか親昵しき情を結ばむ」といひて、乃ち草を以て児を裹みて、海辺に棄てて、海途を閉ぢてただに去ぬ。、故、因りて児を名けまつりて、彦波瀲武鸕[玆鳥]草葺不合尊(ひこ・なぎさ・たけ・うがやひこあへずのみこと)と曰す。後に久しくして、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)崩りましぬ。日向の高屋山上陵に葬りまつる。/…中略…/2(172p)一に云はく豊玉姫の侍者、…中略…時に豊玉姫、八尋(やひろ)の大熊鰐(わに)に化為(な)りて、云々。3(178p~)一書(あるふみ)に曰はく、兄(このかみ)火酢芹命、能く海の幸を得。故、海幸彦(うみのさちびこ)と号く。弟彦火火出見尊、能く山の幸を得。故、山幸彦(やまのさちびこ)と号す。…中略…豊玉姫、自らに大亀に馭りて、女弟玉寄姫を将ゐて、海を光らして来到る。時に孕月已に満ちて、…中略…則ち八尋大鰐(やひろのわに)に化為りぬ。…以下略。4斉明天皇同訓: 【日本書紀(岩波文庫版第4冊)】第二十六、「元年春正月」の条に続けて、「夏五月庚午朔空中ニ龍(タツ)ニ乗レル者有リ、貌(カタチ)唐人(モロコシビト)ニ似テ青キ油笠(アブラキヌノカサ)ヲ著キテ葛城ノ嶺(タケ)ヨリ馳テ膽駒山(イコマノヤマ)ニ隠」 (332p)と載る。 (1-3)爾雅「螣蛇」:古書注参考:TDB「爾雅注疏十一巻」巻第十釋魚第十六:螣、螣蛇 (チン、トウダ)【(郭璞)註】龍類也、能興雲霧而遊其中、淮南云蟒蛇(モウダ){螣、上音朕(チン) 、下音騰(トウ)}。【疏】{蛇似龍者也。名螣、一名螣蛇。能興雲霧而遊其中也。 蟒當為奔。案淮南子覧冥篇説女媧云、功烈上際九天、…以下略。 (1-4)荀子「螣蛇」:荀子「勧学篇」第5セクション「君子結於一」(君子はひとつのことをなすにも積み重ねて心を用い一にしてのぞむことこそがトップに昇る喩を表す)。「螣蛇無足而飛、梧鼠五技而窮」螣蛇(トウダ)は足を持たずとも空を飛べるのに、梧鼠(ごそ=鼫鼠せきそ:ムササビ)は五つの技(飛、登、泳、潜、走)を持つのに窮する道をたどることもある。 (1-5)説文 :古書注参照:【説文】(「説文解字十五巻」TDB)第十三巻虫部:螣:神它也。{荀卿曰、螣蛇無足而飛。毛詩叚借為[虫貸’]字。}从虫朕聲。{徒登切。六部} (1-6)越後海辺冣’多:越後海辺最多:冣’(冖→宀) (1-7)太都万岐:タツマキ:1【本草綱目啓蒙】(東洋文庫4冊)(3-191)(巻之三十九、鱗之一、竜類九種)竜 タツ{和名鈔}〔一名〕鱗中長{名物法言}…中略…竜ハ神霊ノ物ニシテ親シク形ヲ見ルコトナリ難シ。…中略…俗ニ、タツノ天上スルト云。是ハ蛇類俗ニタツト呼モノニシテ螣蛇ナリ。真ノ竜ニハ有ズ。諸蛇ノ条下ニ、螣蛇化竜ト云モノナリ。…以下略。2『本朝食鑑』(人見必大著)には、鱗介部に「竜」の記載なく、「蛇虫部」冒頭の「蛇」釈名に竜記事を載せる。3越後(新潟)に、螣蛇・タツが「最多」、「よく現れ見ることができる」と記し、それを「タツマキ」と呼ぶと注したが、その出典を示しておらず不詳。ただ、この引用の典拠を髣髴させる記述が文化8年(1811)柳亭種彦序記のある橘崑崙著、葛飾北斎画『北越奇談』に見える。第1巻「龍蛇ノ奇」の「竜巻にあふ」記述と、北斎の見開き挿絵もあって「越後」の「竜巻」は、けっこう広く知られていた話であったのだろう。4 【東遊記】(後編三)(橘南谿 著。寛政7~9〈1795~1797〉年刊)(WKDB):登龍 越中越後の海中、夏の日龍登るといふ甚多し。黒龍多し。黒雲一村虚空より下り來れば、海中の潮水其雲に乘じ逆卷のぼり、黒雲を又くはしく見れば、龍の形見ゆることなり、尾頭などもたしかに見て、登潮は瀧の逆に懸るが如し、又岩瀬と云所、宮崎といふ所まで、十餘里の間に竟りて、黒龍登れるを見しと云、又鐵脚道人退冥の手代、越後の名立の沖を船にて通りし時、海底に大龍の蟠れるを見しといふ、蟠龍を見る事は、此手代に限らず、彼海底には折々ある事となり、是等は皆慥なる物語なりき、…以下略。34書該当箇所と北斎「編者崑崙新潟にて龍巻にあふ」を真名真魚字典:龍(その他16画)に載せる。 |
|
|
四足五釆、甚有二神霊一也、
{下総本は、龍’は龍に作る。那波本も同じ。『干禄字書』に謂う。「龍’龍上通下正。」天文本は、「也」の上に「者」の字あり。廣本も同じ。} 白虎通云、鱗虫三百六十六、而龍’為之長也、 {引用する文は原書(『白虎通』)に載っていない。『易本命篇』は「有鱗之蟲三百六十、而蛟龍爲二之長一」を載せ、また、『孔子家語』「執轡篇」に「鱗蟲三百有六十、而龍為二之長一」と云う。おそらく源君は、これらの書からの引用するところを誤ったものだろう。『説文』は、「龍は、鱗蟲の長なり。能く幽とし、能く明とし、能く細とし、能く巨とし、能く短とし、能く長とする。春分きたりて天に登り、秋分となりて淵に潜る。肉と飛の形を从え、童の省形〔立:リュウ〕を声とする」と云う。} 鈔本文読み下し:龍’ 文字集略は云う。龍’。{力鐘の反。太都(タツ)。}/四足五釆(しそくごべん)にして、甚だしく神霊を有するものなり。/白虎通は云う。鱗(りん)虫は三百六十六ありて、龍は、之の長と為すなり。 〔注〕 (1-6)龍’龍:干禄字書(上聲十丁ウに載る):中国で「進士考」(科挙試験)の目安として刊行された標準字形とその異体字を並べた字書。二ないし三の楷書字体をあげ、俗(俗字)・通(通字)・正(正字)を示した。龍については、龍’(通:字形は右図参照)、龍”(通:字形略)、龍(正)としている。 (1-7)白虎通:びゃっこつう:後漢の章帝建初四年(西暦79年)に、宮中の「白虎観」に集めて古典の字義を論議させ、そのいわゆる「白虎観論議」を班固らが整理してまとめた書をいう。4巻。「白虎通義」、「白虎通德論」とも呼ばれる。「白虎」は四神の一で、西方をつかさどる。○「和名抄引書」(17丁裏)白乕通{露…中略…○龍〈疑〉} (1-8)易本命篇:『大戴礼記』39篇中の1篇「易本命篇第八十一」。「蛟龍」は〔3〕に記す。 (1-9)孔子家語(こうしけご):「論語」に漏れた孔子一門の説話を蒐集したとされる古書。10巻。散逸し伝わらない。 (1-9)説文:1【説文解字】(徐鉉校訂「大徐本」汲古閣本)(WLDB):龍(篆):鱗蟲之長、能幽能明、能細能巨、能短能長、春分而登天、秋分而潛淵。从肉飛之形、童省聲。{臣鉉等曰、象[宛-ウ]轉飛動之皃}凡龍之属皆从龍。{力鍾切}2【説文解字】「説文解字注十五巻」(段注)(TDB):龍:鱗蟲之長、能幽能朙〔=明〕、能細能巨、能短能長 {四句一韻}。春分而登天、秋分而潛淵。{二句一韻。毛詩蓼蕭傳曰、龍寵也、謂龍即寵之叚借也。勺傳曰、龍和也、長發同謂龍爲邕、和之叚借字也。}从肉。{與能从肉同。}[@]肉飛之形。{[@]肉二字依韻會補 、無此則文理不完、六書故、所見唐本、作从肉从飛及童省。按从飛謂[@2]飛省也。从及謂[@3]反、古文及也。此篆从飛、故下文受之以飛部。}童省聲。{謂[@4]也。力鍾切九部 }凡龍之属皆从龍。: 簡約すれば、「龍は鱗蟲の仲間の長であり、その姿は、幽かに見えるかと思えば明らかに見えもし、細かいかと思えば巨にもなり、短くもなれば長大でもあって、変幻の能力をもっている。春分になると天に登り、秋分になると淵に潜る。 「肉」(の象形:月)を従(从)えて、空を飛ぶ形(龍のツクリの字形)をあらわし、「童」の省字「立」を聲音(リュウ)とする。「臣鉉等曰:象[宛-ウ]轉飛動之皃」:[宛-ウ]:エンは、エビのように体を折り曲げるさま 、「皃」=「貌」であるから、空をくねくねと蛇のように飛ぶさまを象っている。 (1-9-2)毛詩蓼蕭傳:毛詩(詩経)小雅、南有嘉魚之汁(なんゆうかぎょのじゅう)に含む「蓼蕭」(りくしょう)篇。 「既見君子/為龍為光」(すでにくんしをみれば、龍となり光となる)に対して、【毛傅】が「龍は寵なり」と注した。つまり、この「龍」は、次行の「徳」に通じ、めぐみ深いお方、という意味の「寵」(ちょう)と読む、ということである。 (1-9-3)段注は、(1-9)1の大徐本の旁の字形について修正を加え、解字の補説を行っている。「从肉飛之形」では、「文理不完全」であるとして、「[@]肉の二字を韻會により補」っている。「韻会」は『古今韻會挙要』(古書注参照)で、第一巻平聲上、ニ冬の「龍」を、右下画像(WLDBより)のように記す。 |
|
| ■〔2〕虯龍 | |
|
文字集略云、虯、{音球、}龍 之無レ角青色也、
{下総本は、「虯」を「虬」に作る。廣本も同じである。」。『龍龕手鑑』が「虬虯同上」と云う。廣本は、「無」は「有」に作る。」。『淮南子』「注」は、「角有るを龍とし、角無きを虯とす。」と云う。また、『楚辞』「離騒」及び「天問」「注」は、「角無きを虬と曰う。」と云う。また、『慧琳音義』は『韻英』を引用して、「虯は角無き龍なり。」と云う。また、『玉篇』、『廣韻』も同じである。『後漢書』「馮衍伝」「注」は、また「虯龍は之れ角無きものなり。」と云う。 然るに、『説文』は、「虯、龍子有レ角者」と云う。『廣雅』は「角有るを龍と曰い、角無きを龍と曰う」と云う。『初学記』及び『玄應音義』は、『廣雅』を引用して「作レ虯、作レ螭」という。『集韻』は、「虯」は、又「」に作り、「螭」は、又「」に作る。是れらの用例に見るとおり、「有レ角」、「無レ角」の二説が古くより記されてきたが、いまだに、いずれを是(ぜ)とするかの説を知ることができないのである。} 抄本文読み下し:虯龍(キュウリョウ) 文字集略は云う。虯{音は球(キュウ)。}龍、これ角無 くして、青色なり。 〔注〕 (2-1)「文字集略」注1-1参照。古書注参照。 (2-2)龍龕手鑑(KDB)第四巻:虫部第二[平聲]虬{無角龍也又居幽切}虯{同上○今増}。 (2-3)淮南子注: 有角為龍、無角為虬:【淮南子】『淮南鴻烈解』(KLDB)巻第六「覧冥訓」:往古之時、四極廢、…中略…名聲被後世、光暉重萬物。乗雷車、服駕應龍、驂青虯、{〔高誘注〕:駕應徳之龍在中為服、在旁’為驂、有角為龍、無角為虬、一説、応龍有翼之龍也。}援絶瑞、…以下略。 (2-4)屈原『楚辞』(古書注参照)「離騒」 「天問」:(1)駟玉虬以乘鷖兮、溘埃風余上征。及び、「天問」 :焉有虬龍、負熊以遊:『楚辞章句』王逸注:有角曰龍、無角曰虬。なお、『楚辞集注』の朱熹注も「離騒」(同)、「天問」(虬見上) を云う。 (2-5) 慧琳音義:古書注慧琳音義(一切経音義)参照。:「韻英」:唐・陳庭堅[チンテイケン]撰(「輯佚資料」):元庭堅(?~756年頃)[新志]玄宗韻英五巻天宝十四載撰:[南部新書]天寶時,翰林學士陳王友元庭堅撰「韻英」十卷。 (2-5-2)中電CBETA:一切經音義卷第九十:翻經沙門慧琳撰:前高僧傳音下卷:第九巻:劉虯(糾幽反韻英云無角龍也荊州隱土名也捨宅為寺)。 (2-6)【玉篇】(大廣益会玉篇三十巻・張氏重刊宋本玉篇)(TDB):1巻第二十三○龍部第三百八十一{凡八字}龍{力恭切。能幽明大小登天、潜水也。又寵也。和也。君也。萌也。}2巻第二十五○虫部第四百一{五百二十五字}虫{略}…中略…蛟{古爻切。蛟龍也。}虯{奇樛切。無角龍。}螭{丑支切。無角如龍而黄。} (2-7)【廣韻】(五巻・張氏重刊宋本廣韻TDB)1上平聲巻第一:{都宗}冬第二{鐘同用}/ニ○冬{都宗切。七}/三○鐘{職容切。十八}…○龍{通也。和也。寵也。鱗蟲之長也。易曰、雲従龍。又、姓。舜納言龍之後。力鐘切。九}/2上平聲巻第一:{章移}支第五{脂之同用}/五○支{章移切。二十九。}…○摛{丑知切。九}螭{螭無角如龍而黄、北方謂之地螻。}/3下平聲巻第二:{羽求}尤第十八{侯幽同用}/{胡鉤}侯第十九/{於虯}幽第二十/二十○幽{於虯切。七}…○虯{無角龍也。渠幽切、又居幽切、七} (2-8)後漢書馮衍傳注:【後漢書】(WLDB)巻二十八下:馮衍傳第十八下:建武末、上疏自陳曰、臣伏念高祖之略而陳平之謀、…中略…駟素虯而馳騁兮、乗翠雲而相佯。就伯夷而折中兮、得務光而愈明{四馬曰駟。虯龍、之、無角者也。楚詞曰。駟玉虯以乗翳兮。…以下略} (2-9)説文云、虯、龍子有角者:1【説文解字】(徐鉉校訂「大徐本」汲古閣本)(WLDB):虯(篆):龍子有角者。从虫[Ч]聲。{渠幽切}2「説文解字十五巻」TDB)説文解字注:虯(篆):龍無角者。{各本作龍子有角者。今依韻会所據正。然韻会尚誤多子字。李善注、甘泉賦引説文、虯龍無角者、他家所引、作有角、皆誤也。王逸注、離騒天問両’言有角曰龍、無角曰虯。高誘注、淮南同。} (2-10)廣雅:釋魚:記載未見。 この部分だけ複写し忘れのため後日要確認。 (2-11)初学記:古書注参照。 記載未見。要確認。 (2-12)玄應音義:古書注(一切経音義)参照:中電CBETA:一切經音義:記載未見。要確認。 (2-13)集韻:【集韻】(WDB):巻之四平聲四:尤第十八{于求切。與侯幽通}侯第十九{胡溝切}幽第二十{於虬切}…中略…○虯[黽’]{渠幽切。説文龍子有角者或作[黽’]。文十九。}:[草〈早→黽〉]=[黽’]/平聲巻之一:支第五{章移切。與脂之通}:五○支[支/巾]{章移切。}…中略…○摛[扌離]{抽知切。}…螭[多它]彲離{説文若龍而黄、北方謂之地螻。一説、無角螭、或作[多它]彲離。} (2-14)未知此以孰為是也(いまだ、此れ孰れを以って是とするかを知らず。):【広雅疏証】(光緒五年淮南書局重刊本)(巻第十下)釋魚:「皆與説文、廣雅異説、未知孰是。」つまり、王念孫説を参考にして、記している可能性が強い。 |
|
| ■〔3〕螭龍 | |
|
文字集略云、螭、{音知、}龍 之無レ角赤白蒼色也、
{『説文』は、「龍の若(ごと)くにして黄色、北方では、これを地螻(ちろう)と謂う。或いは云う。角無きを螭(ち)と曰う。」と云う。『廣雅』は「角無きを龍(ちりょう)と曰う」と云う。『集韻』は、螭は又、に作る。つまり、此に云う「龍之無角」と書くところと合う。『上林賦』は、「赤螭」(せきち)と云い、楊雄『解嘲』は「絳螭」(こうち)と云う。ここで云う「蒼」は恐らく衍字であろう。 抄本文読み下し:螭龍(ちりょう) 文字集略は云う。螭。{音は知(ち)}龍の角無くして、赤白(蒼)色なり。 〔注〕 (3-1)螭: 前掲注 2-7参照。「ち」。「みずち」「あまりょう」。 (3-2) 「文字集略」注1-1参照。 (3-3) 説文:【説文解字】(徐鉉校訂「大徐本」汲古閣本)(WLDB):若龍而黄、北方謂之地螻、从虫离聲、或云、無角曰螭。丑知切。 (3-4):[多它]:ち。螭と同じ。 前掲注2-13参照。 (3-5)上林賦:司馬相如「上林賦」(じょうりんのふ)。 (3-6)楊雄:(前53~紀元18年)漢の思想家。字は「子雲」。「法言」「楊雄方言」。 『文選』巻35の揚雄「解嘲」に「絳螭」見えず。『漢書』第87下楊雄伝下第五十七の「楊子曰」(WLDB本6丁表)に続く「解難其辞曰」 (8丁表)のセクションに「独不見夫翠、糾絳螭之將登乎天」 が載る。顔師古注に「師古曰虯螭解並在前」とあり、87上揚雄傳上に「駟蒼螭兮六素虯」の注に「師古曰。四六駕数也。言或四或六也。螭似龍一名地螻、虯即龍之無角者」という。順原文は、この「蒼螭」をイメージしてのものかもしれない。とすれば、衍字「蒼」も、この漢書揚雄傳の記述をも指すのか。要検討。絳=コウ:深紅の赤。……記載ミスか、自筆原本からの版本化の際のミスか、確認の要あり。 |
|
| ■〔4〕蛟 | |
|
説文云、蛟、{音交、美都知、日本紀私記用二大虯二字一、}
{下総本は、「和名」二字あり。」廣本は、「虯」を「虬」に作る。廣本は「私記」の二字は無い。是れに似て、「大虬」は、(『日本書紀』巻第十一)「仁徳六十七年紀」に見える。} 抄本文読み下し:蛟 説文は云う。蛟{音は交(こう)。美都知(みづち)。日本紀私記は、大虯の二字を用う。} 。/龍の属なり。山海経は云う。蛟は、虵に似て四脚。池魚は二千六百を満たし、則ち蛟来たりて之の長となす。 〔注〕 (4-1)蛟:こう。みずち。 (1)【類聚名義抄(観智院本)】蛟{⊥交。ミツチ。}虬虯{⊥球、二正、龍。}大虬{ミツチ}(2)参考:【新撰字鏡(天治本)】蛟{胡肴反。龍名、美止知。}:ミトチ。龍魚部の箋注に「新撰字鏡」が引用されるのは、〔6〕鯨鯨からであり、注(6-6)参照。 (4-2) 「説文」虫部:龍之属也、池魚満三千六百、蛟来為之長、能率魚飛、置笱水中、即蛟去。从虫交聲。古肴切。 (4-3)日本紀私記:古書注参照。 (4-4)日本書紀巻第十一「仁徳天皇六十七年」:有大虬、令苦人:是歳、吉備中国の川嶋河の派に、大虬(みつち)有りて人を苦びしむ。(岩波文庫版(二)276頁) |
|
|
龍’之属也、山海経云、蛟似レ虵而四脚、池魚満二二千六百一、則蛟来為二之長一
{『説文』虫部は「蛟、龍之属也、池魚満二三千六百一、蛟来為二之長一」と云う。又、『山海経』「南山経」は、「禱過(とうか)の山より(ぎんすい)出でて、その水中に虎蛟(ここう)多し。」と云う。郭璞「注」は、「蛟は蛇に似て四足、龍の属」と云う。此の順抄文にある引用は、『説文』『山海経』の二書からのものであって、錯出殽雑した記述になっている。然るに、『太平御覧』は、此の引用と全く同じである。疑うらくは、『修文殿御覧』が二書から引用して伝写に際して錯誤したものを、源君及び李昉が、いずれもそのまま踏襲し引用したものによるのであろう。廣本は、『山海経』の下に注字あり、是に似て、「二千」とあるのは、『説文』に従い「三千」と作るにあたるものであろう。天文本は、「池魚」以下十三字なく、伊勢廣本も同じである。」 蛟をもって「美都知」とし、大虯をもって「美都知」とする。その説は同じではなく、蛟の一名は大虯ではない。 又、『万葉集』に「虎爾乗古屋乎越而青淵爾鮫龍取將來劔刀毛我」(とらにのりふるやをこえてあをぶちにみづちとりこむつるぎたちもが)と云う。「鮫龍」は即ち「虯龍」の異文である。『中庸』の「黿鼉鮫龍」(げんだこうりゅう)、『釈文』は、もと「蛟」に作るのが、是である。宜く「美都知」「若多都」と訓む。今本「左女(サメ)」と訓むのは、「鮫」字によるものであるが、誤りである。『淮南子』「道應訓」に「蛟龍水居」とあり、その注に、「蛟は水蛟、その皮に珠あり、世人は刀剣の口となす。」とし、注者、高誘は蛟龍をもって鮫魚となしたが、其の誤りは『万葉集』の旧訓と同一である。} 抄本文読み下し:蛟 説文は云う。蛟{音は交(こう)。美都知(みづち)。日本紀私記は、大虯の二字を用う。} 。/龍の属なり。山海経は云う。蛟は、虵に似て四脚。池魚は二千六百を満たし、則ち蛟来たりて之の長となす。 〔注〕 (4-5)山海経:古書注参照:南山経: 郭璞注:山海経の郭璞注記:【山海経箋疏】(WLDB)山海経第一「南山経」南次三経之首曰天虞之山、…中略…東五百里禱過之山、…中略…[浬〈里→艮〉]水出焉、而南流注于海、其中有虎蛟 {【郭注】蛟似蛇四足龍属。 【郝疏】懿行案。郭氏江賦云、水物怪錯、虎蛟鉤蛇、本此水経注引裴淵広州記云、[浬〈里→艮〉]水有錯魚、博物志云、東海蛟錯魚生子、子驚還入母腸、尋復出與水経注合、疑、蛟錯即虎蛟矣、所以謂之虎者初学記三十巻引沈宝臨海水土異物志云、虎錯長五尺黄黑斑耳目歯牙有似虎形、唯無毛或変化成虎、然則虎蛟之名蓋以此又任昉述異記云、虎魚老者為蛟疑、別是一物也}、其状魚身而蛇尾、其音如鴛鴦、食者不腫{【郝疏】懿行案、説文云、腫癰也}、可以已痔{【郝疏】懿行案、説文云、痔後病也}。 (4-5)錯出殽雑:錯雑、混じって。 (4-6)修文殿御覧:古書注参照。:「太平御覧」の元となったとされる北斉に成立した類書。梁の「華林遍略」と並び称される。亡佚書。【和名抄引書】(63丁オ)御覧{目録。[番]魚。水滴器。}/[隋志]{雑}聖壽堂御覧三百六十巻/[旧志]{類書}修文殿御覧{三百六十巻}[新志]{類書}祖孝徴等修文殿御覧三百六十巻[現在] 。 (4-7)李昉等:「太平御覧」宋の太宗の命により977年成立した1000巻の類書。李昉(925~996年)らが編撰。 (4-8)万葉集:古書注参照。第16巻・3833:岩波文庫本:「新訂新訓 万葉集」(佐々木信綱編)下巻176頁:虎(とら)に乗り古屋(ふるや)を越えて青淵(ぶち)に鮫龍(みづち)とち来(こ)む劔立(つるぎたち)もが:[題詞]境部王(さかひべのおほきみ)、數種の物を詠める歌一首{穂積親王の子なり} (4-9)中庸:礼記中庸(巻十六第三十一):今夫水,一勺之多,及其不測,黿鼉鮫龍魚鼈生焉,貨財殖焉。「天地の道は一言にして尽くすべきなり云々」のセクション。引用の訓みは「げんだこうりゅう」。読み下しは「今夫レ水ハ一勺ノ多キナリ、其ノ測ラザルニ及ビテハ黿鼉鮫龍魚鼈(ゲンダコウリュウギョベツ)生ジ貨財殖ス」:(天地自然のありよう〔道〕は博く深く厚く、そしてあくまでも高く光明にあふれ、無限にはるかで永遠に久しいものである)ということを受けて、「そもそもこの水系の世界は、ただのひと勺いの水が集まり、それが測りしれない多きなものになると、この水世界には黿鼉(げんだ)や、鮫龍(こうりゅう)や、魚鼈(ぎょ べつ)のいけるものたちが生まれそして棲み、そして真珠や珊瑚のような財宝となるものも殖産されるのである」。黿鼉を字義通り訳せば「おおきなかめ」と「わに」となるが、そのような象徴的な水棲動物たちを指すと考えてよいだろう。鮫は蛟と同で、龍と一緒になって「ミズチやタツなどのいろいろな龍たち」でよいだろう。魚鼈は、現実世界でも確認のできている「魚や亀たち」という義であろう。鮫は、明らかに現代理解する「サメ」ではない。 (4-9)淮南子道応訓:「道応訓第十二」に「蛟龍水居」の記述なし。「原道訓第一」に載る。「夫萍樹根于水、木樹根於土、鳥排虚而飛、獸蹠實而走、蛟龍水居、虎豹山處、天地之性也。」()(そもそも、浮き草が水に根を生やし、樹木が大地に根付き、鳥が虚空を飛び、獣は実に地を踏みつけながら走り、蛟龍が水に棲み付き、虎豹は山をねぐらにする、それ、すべて天地の性である……というような意味)。「蛟、水蛟、其皮有珠、世人以為刀劍之口」高誘注は原典出所未確認。 |
|
| ■〔5〕魚 | |
|
文字集略云、魚{語居反、宇乎、俗云伊乎、}
{下総本は、「和名」二字あり。」『日本書紀』「神代紀」に、魚を「宇乎」(うを)と訓む。 「紆鳴」(うを)は又、継体紀春日皇女歌に見える。「伊乎」( いを)は、『栄花物語』「楚王の夢」巻、「御裳着」(おんもぎ)の巻に見える。} 抄本文読み下し:魚 文字集略は云う。魚{語居の反。魚(うお)。俗に伊乎と云う。/水中連行するものにして、蟲の惣名なり。 〔注〕 (5-1)文字集略:古書注参照。前掲注(1-1)。 (5-2)神代紀魚:【日本書紀】(岩波文庫)(一)(222頁)『日本書紀』巻3・神武天皇即位前紀戊午年(つちのえ・うま・とし)九月(ながつき)條:天皇又因祈之曰……吾今当以厳瓮天……沈于丹生之川。如魚無大小、悉酔而流。……乃沈瓮於川。其口向下。頃之魚皆浮出……。:天皇、又因りて祈(うけ)ひて曰(のたま)はく、……「吾今当(われいままさ)に厳瓮(いつへ)を以(も)て丹生之川(にうのかは)に沈めむ。如し魚(いを)大(おほ)きなり小(ちひさ)しと無く、悉(ふつく)に酔(ゑ)ひて流れむこと、……」とのたまひて、……しばらくありて、魚(いを)皆浮き出でて、水の随(まま)に噞喁(あぎと)ふ。……岩波文庫版では「魚:いを」と訓み、「うを」の訓みは、神代紀第一段「開闢(あめつちひら)くる始に云々、譬へば游ぶ魚(いを)の水上に浮けるが猶し。」(16頁)ほか、原文「魚」を「いを」と訓み、「うを」を見ない。他のテキストに、神代紀第一段の魚の訓みをみると、『伴信友校 日本書紀』(慶長4年清原國賢跋:慶長15年野子三白跋:明治16年岸田銀香刊)(KLDB)、飯田武郷『日本書紀通釈』いずれも「うを」と訓む。また、岩波文庫本『古事記伝』(一)(187頁)に、「タダヨヘル」の注に、宣長は「書紀に、開闢之始(アメツチハジメノトキ)、云々、譬二猶游魚之浮水上一也云々。(ウヲノミヅニウケルガゴトキナリキ)」と訓んでいる。 (5-2-2)魚を、ナ、トト、ウヲ、イヲと呼ぶ、それぞれの呼びわけについて、宣長の整理を『古事記伝』(古書注参照)に見てみることにしよう。(1)(4-19p)鳥遊は、登理能阿曽備(トリノアソビ)と訓べし。…中略…野山海川に出て、鳥を狩(カリ)て遊(アソ)ぶをいふなり。…中略…是レ狩(カリ)をも遊(アソ)びと云証なり。…中略…是レもなほ魚釣(ナツル)を云なるべし。○取魚は、師の須那杼理(スナドリ)と訓れつるぞ宜しき。(2)(4-87p)○真魚咋は、麻那具比(マナグヒ)と訓べし。魚(ウヲ)を那(ナ)と云は、饌(ケ)に用る時の名なり。【只何となく海川にあるなどをば、宇乎(ウヲ)と云て、那(ナ)とは云ハず。此ノけぢめを心得おくべし。】書紀ノ持統ノ巻に、八釣魚(ヤツリナ)てふ蝦夷(エミシ)の名の訓注に、魚此ヲ云レ灘(ナト)。万葉五【二十三丁】に奈都良須(ナツラス)、【魚釣(ナツラス)なり。】これら釣魚(ツルウヲ)は、饌(ケ)の料なる故に、那(ナ)と云り。…中略…さて菜(ナ)も本は同言にて、魚にまれ菜にまれ、飯に副(そへ)て食(ケフ)物を凡て那(ナ)と云なり。…中略…万葉十一【四十二丁】に、朝魚夕菜(アサナユフナ)、これ朝も夕も那(ナ)は一ツなるに、魚と菜と字を替て書るは、魚菜に渉る名なるが故なり。さて其ノ那(ナ)の中に、菜よりも魚をば殊に賞(メデ)て、美(ウマ)き物とする故に、称(ホメ)て真那(マナ)とは云り。【故レ麻那は魚に限りて、菜にはわたらぬ名なり。今ノ世に麻那箸(マナバシ)麻那板(マナイタ)など云も、魚を料理(トトノフ)る具に限れる名なり。】さて、真魚咋(マナグヒ)と云名目(ナ)は中昔の記録ぶみなどに、魚-味と云ヒ、今ノ俗に魚-類の料-理と云ほどのことゝ聞ゆ。(3)○如ニ魚鱗一所造之宮室(イロコノゴトツクレルミヤ)。魚鱗は伊呂古(イロコ)と訓べし。和名抄に、唐韻ニ云ク、鱗ハ魚ノ甲也。文字集略ニ云ク、龍魚ノ属ノ衣ヲ曰レ鱗ト。和名以呂久都(イロクツ)。俗云伊呂古(イロコ)。字鏡には、鰭ハ魚ノ背上ノ骨、又伊呂己(イロコ)とあり。【和名抄に、以呂久都と云るは心得ず。又伊呂己をば、俗云とあれど、俗には非じ。さて又これを、今は宇呂古と云フ。此ノ宇(ウ)と伊(イ)とは、何れか古へならむ。魚をも、中昔には伊袁(イヲ)と云へれども、今は多く宇袁(ウヲ)と云を、古言にも宇袁(ウヲ)と云り。然れば、鱗も、中昔にこそ伊呂古(イロコ)とのみ云ヘれ、古事は宇呂古(ウロコ)なりけむも知リがたし。されど古書に然云るを未ダ見ざれば、姑ク和名抄に随ひて訓るなり。】(4)(筑摩書房本居宣長全集第十一巻)三十一之巻○御食之魚は、美氣能那(ミケノナ)と訓べし、【又魚を、麻那(マナ)とも訓べし、上巻に、真魚(マナ)とあると同じければなり、】大神の御饌(ミケ)の料の魚なり、【 又御食(ケ)を、太子へ係(カケ)て、太子の御饌の料の魚と見ても通(キコ)ゆ、天皇は凡て己レ命の御うへにも御某(ミナニ)と詔ふこと常なれば、太子も准へて御自(ミミヅカラ)も御気(ミケ)と詔ふべし、されど於レ我(アレニ)とあるよりのつゞきを思ふに、なほ大神の御食の魚と見る方まさるべし、】魚は、食ノ料にするをば、凡て那(ナ)と云例なり、【 此事上に既に出ヅ、】さて如此我(カクアレ)に御食の魚(ナ)給へりとある、一言に、大神の御恵(ミメグミ)を深く辱(カタジケナ)み喜(ヨロコ)び謝(マヲ)し賜ふ意おのづから備(ソナ)はりて聞ゆ、【 古語は簡(コトズクナ)にして、かく美(メデタ)がりき、かの書紀の漢(カエア)ざまの潤色(カザリ)の語の多くうるさきと思ひ比(クラ)ぶべし、】 (5-3)紆鳴:継体紀春日皇女歌:『日本書紀』巻十七継体天皇七年九月條(岩波文庫版181~182p):莒母唎矩能……以簸例能伊開能/美那矢駄府/紆鳴謨/紆陪[仁(二→爾)]堤々那皚矩……:陰国(こもりく)の……磐余(いはれ)の池の、水下(みなした)ふ、魚(うを)も、上(うへ)に出て嘆く……。 (5-4)栄花物語、楚王夢、御裳着:岩波書店『日本古典文学大系』(旧版)(75・76巻)『榮花物語』(梅沢本。旧三条西家本):第76巻: (1)卷第十九:御裳ぎ:114頁(4~7行):僧前(そうぜん)などこの殿にて仕(つか)うまつるべき仰言(おほせごと)…中略…講師達(かうじたち)、中心のどかなるところにて、…中略…「十千の魚、十二部經の首題の名字を聞(き)ゝて、…後略。 (2)卷第廿六:楚王のゆめ:221頁(13~15行):御乳母(めのと)の夫(おとこ)播磨守泰通(やすみち)、はかなき魚(いを)果(くだ)物、何(なに)の物も見(み)ゆるをば、よる夜半(よなか)わかずまづ++と運(はこ)び參(まい)らせし事の絶(た)えにたれば、あはれに悲(かな)しくいひ續(つゞ)け戀奉(たてまつ)る。……用例のうち一例。 |
|
|
水中連行蟲之惣名也、
{下総本に之の字なし。伊勢広本も同じ。『周禮』「考工記」「梓人(しじん)」注に、「連行魚属」と云う。阮氏の蓋本(文字集略)は此による。『説文』は「魚、水蟲也、象形、魚尾は燕尾と相似る」とある。} 抄本文読み下し:魚 文字集略は云う。魚{語居の反。魚(うお)。俗に伊乎と云う。/水中連行するものにして、蟲の惣名なり。 〔注〕 (5-5)水中連行:蟲:考工記梓人:周礼冬官考工記第六:「梓人為筍虡」:梓人(しじん)は工作を司る。「筍虡」(ジュンキョ)は、鐘(かね)や磬(けい)をかけてつるして楽器とした道具。動物や魚類などの形をしたものを掛けたり、その道具に彫刻したらしい。そのいわれが書いてあるが、ちょっと難しいので後日調べて触れることにする。そこに、獣(「大獣」)を五にわけ、「脂者=牛羊属」(ウシやヒツジのなかま)、「膏者=豕属」(ブタのなかま)、「蠃者=虎豹貔[貓(苗→离)]属」(浅毛:薄毛のケモノの仲間)、「羽者=羽鳥属」(羽を持つ鳥のなかま)、「鱗者=龍蛇属」(龍蛇の仲間で鱗を持つ生物のなかま)とする。前二者の「脂者」と「膏者」は祭祀の牲(いけにえ)として使うためであり、後三者の「蠃者」「羽者」「鱗者」は、筍虡の道具の使用についてとして述べている。次に、この三つの生き物たちを、外形や骨(甲羅)のつき方、前進する際の這い方を、郤行(隙間を空けて進むもの?)、横ばいするもの、連れ添って群れを成すもの(連行魚属)、くねくねと進むもの(紆行蛇属)、次に鳴き方飛び方及び小さな虫の仲間で分類する。詳細は略すが、「外骨、内骨、郤行、仄行、連行、紆行、以脰鳴者、以注鳴者、以旁鳴者、以翼鳴者、以股’鳴者、以胸鳴者、云之、小蟲之属、以為雕琢」。当時の、生物を外形や行動形態、殻や甲羅や鱗の有無、鳴き方などで分類して識別する方式が述べられて興味深い。森枳園(立之)著に「千魚一観録」という魚類を、行動や外形など観察者の目を第一義的に識別の基準に置き分類を試みた「奇書」ともいえる本が手元にある。森は、渋江抽斎を継承する考証学の系譜に位置し、また医学を学び、後明治維新後漢方医方の教祖的な立場にたった人物だが、実は、このような西欧分類学がわが国に定着する過程にあって、考証と科学とを結びつけるような観察眼を生かした経験科学の試行(思考)を行った人物でもある。この書は、魚類学の上から観て非科学的であって噴飯モノときって棄てられて、翻刻も科学者による紹介も全く為されてこなかった書物だが、日本が西欧科学が席巻するにいたる過程(明治15年記載自筆校本)で、あえて、西欧分類学には目もくれず、東洋的学と自然観察眼を機軸に、魚類を分類した意欲的な業績として再評価を加えるべき価値があるのではないかと思う。これはのちに稿を改めて触れたい。 (5-7)説文(TDB『説文解字十五巻』):魚、水蟲也。象形、魚尾與燕尾相佀。〔段注〕{其尾皆枝故象枝形、非从火也。語居切、五部}凡魚之属皆从魚。(佀=似) |
|
| ■〔6〕鯨鯢 | |
|
唐韻云、大魚、雄曰レ鯨、{渠京反、}雌曰レ鯢、{音蜺、久知良}
{『廣韻』は、「鯨」を[畺]に作り、下に「鯨」字を出し、「上同」と云う。伊勢廣本は、鯨は、[亰]に作る。那波道圓本も同じ。」。『龍龕手鑑』は、「鯨或[亰]」に作る。下総本和名二字あり。區[施(也→尼) ]’羅(クヂラ)は、『日本書紀』「神武紀」の御歌に見ゆ。『本草和名』に載る「鯨」、『日本書紀』「敏達紀」に載る「鯨魚」と同じ訓みであろう。『新撰字鏡』は、「鼇」に「久知良」、「鯢」に「女久知良」(メクヂラ)の訓みを載せている。}。 抄本文読み下し:鯨鯢 唐韻は云う。大魚。雄は鯨{渠京の反}と曰い、雌は鯢{音は蜺(ゲイ)。久知良(クヂラ)。}と曰う。/淮南子曰く。鯨鯢、魚之王なり。 〔注〕 (6-1)唐韻:古書注参照:最古の韻書「切韻」(601年、陸法言撰)の修訂版として 8世紀中ごろ成立。5巻だが亡失して伝わらない。『唐韻』を修訂したものが『広韻』(大宋重修広韻:だいそうちょうしゅうこういん:古書注参照)で陳彭年らによって1008年成立。 【廣韻】(五巻・張氏重刊宋本廣韻TDB):下平聲巻第二:{古行}庚第十二{耕清同用}:十二○庚{古行切。十二}…○擎{擧也。渠京切。十一}[畺]{大魚。雄曰[畺]、雌曰鯢。}鯨{上同}2下平聲巻第二:{與早}陽第十{唐同用}:○強{巨良切。四}[畺]{鯨魚別名、又其京切。} (6-2)龍龕手鑑 :古書注参照。:1【龍龕手鑑】(KDB):第三巻魚部第三十五。[平聲]○鯨{音擎ー鯢魚王也又雄曰ー雄曰鯢也}/[亰]/[畺]{或作}/[敬]{俗}/○鯢{正 。五兮切。鯨ー也}/[児]{通}2【龍龕手鑑】(WLDB):巻一下平聲:魚部第三十五:[敬]{俗}/[畺]{或作} /鯨{通}/[亰]{正。音擎[亰]鯢魚正也。又雄曰[亰]、雌曰鯢也。四。}/鯢{通。}/[児]{正。五兮反。鯨[児]也。ニ。} (6-2-2)箋注の際に手元においていた『龍龕手鑑』は、ここで MANAが参照した京大蔵本(KLDB、8巻本)とも、早大蔵本(WLDB、4巻本)とも異なり、わが国刊本の原本となったとされる「朝鮮国刊本」で、『経籍訪古志』巻第二に載る「龍龕手鑑八巻」(朝鮮国刊本・求古楼蔵)。「求古楼」とは蔵書印に記す号(湯島狩谷氏求古楼図書記)であり、書誌に次のように載る。「遼僧行均字廣濟集、有統和五年沙門智光序、毎巻首有全(金イ)州郷校上五字、又有一印、{文字漫滅不可読}共出韓人、又有蟠桃院印、及如実庵図書記印、此本原係能登石動山僧大惠旧物、大惠没後帰求古楼、」この経緯については、木村正辞「欟齋雑攷」巻2「龍龕手鑑」(前記古書注)参照。 (6-3)區[施(也→尼]’羅 :區旎羅佐夜(くぢらさや):日本書紀巻3神武天皇即位前紀戊午(つちのえうまの)年八月(214頁)「莬田の高城に……」の歌に含まれる。「……辭藝破佐夜羅孺、伊殊區波辭、區旎羅佐夜離、固奈瀰餓、那居波佐麼、……」(しきはさやらす、いすくはし、くちらさやり、こなみか、) について、文庫版では、區旎([施(也→尼])羅(クヂラ)を「鷹等」として、「……わなを仕掛けてまっていると、鴫はかからず鷹がかかった。これは大漁だ……」(訳:講談社学術文庫「日本書紀(上)」96頁参照) と訳す。「くち:鷹の総称:古事類苑・動物部・鷹934頁:八雲御抄三下鳥」からだが、もうひとつの解釈が「くぢらさや:鯨障」と「鯨」説である。 岩波文庫版も、補注巻第三12(396p下段)で、「イスクハシの語義未詳、クヂラにかかる形容語。仁徳紀に、鷹をクチという由の注があるので鷹と解するが、クヂラは鯨の意ととるべきか。イスクハシを形容語として挿入したものか。磯細(くは)しの意か。……以下略」と鯨説に言及している。同歌は、古事記中巻神武天皇東征にあり(岩波古典文学大系156~157p)に載る。注記(倉野憲司)に、「いすくはし」は「未詳」とある。同補注に「イスクハシは勇細(イサクハシ)で、鯨の枕詞であると記伝〔MANA:古事記伝〕は説き、武田博士はイススキ(身ぶるいすること)のイスに花グハシ、などの名グハシなどのクハシが接続して、身ぶるいの精妙なるの意をなして、次のクヂラ(鷹ら)の枕詞としたのであろうとされている。」を載せる。また「くぢら」の注記に「記伝は鯨年、武田博士は新村博士の説によって『鷹ら』(仁徳紀に『百済俗、号此鳥曰倶知。』とあって、その下に『是今時鷹也』と分注している)としておられるが、共にしっくりしない。」のだという。古事記伝にも載る「くぢら:鯨」説については、本注が長くなるので真名真魚字典「鯨」項に載せる。 (6-4)本草和名:古書注参照:鯨:真名真魚字典「鯨」項に載せる。 (6-5)日本書紀敏達紀「鯨魚」:真名真魚字典「鯨」項に載せる。 (6-6)新撰字鏡:古書注参照:真名真魚字典「鯨」項に載せる。「新撰字鏡」は、「久知良」の「知」により、「享和本」あるいは、「享和本」を本に編んだ「群書類従」本であることがわかる。これらは抄本であり、完本である天治本は、いまだ世に現れていなかった。箋注成稿(文政3・1827年)ののち、完全な内容の傳本が、まず文政年中に巻2、巻4が発見され、安政3・1856年に残10巻が発見され、「新撰字鏡」(天治本)12巻の全貌がしられることになったのである。 |
|
|
淮南子云、鯨鯢、魚之王也、
{引用する文は原書(『淮南子』)には載っていない。『慧琳音義』は、『淮南子』を引用し「鯨魚死而慧星出」と云い、また、「許叔重」(『淮南子注』)を引用して、「鯨魚之王也」と曰う。則ち、ここに引用した文は、許慎 『淮南子注』から引用した注文であって、『淮南子』から直接引用したものではない。さらに、「鯢」の字はおそらく衍字であろう。」。「鯨魚死而慧星出」は、『淮南子』「天文訓」、及び「覧冥訓」に見える。 『説文』は、「[畺]、海大魚也。春秋伝曰、取二其[畺]鯢一」という。また、続けて鯨(篆)字を載せ、鯨は「[畺]或从レ京」とし、鯢字を載せていない。別に「鯢」を条目としてあげ、「剌(盧達切:ラツ)魚」と云っているが、ここにおける用例には合うものではない。『淮南子』も、「西京賦」薛綜注も、皆、「鯨大魚」と云う。また、『春秋左氏伝』宣公十二年、「左伝正義」は、(晋の)裴淵「広州記」を引用し、また「呉都賦」「劉逵注」は、「異物志」を引用し、いずれも「雄曰鯨、雌曰鯢」と云う。また、劉逵は、「一説に、鯨は鳳を言うがごとく、鯢は皇を言うがごとくなり。」と云う。王念孫は、「雌鯨は之れを鯢と為すごとく、また雌虹は之れを蜺と為すなり」と曰う。} 抄本文読み下し:鯨鯢 唐韻は云う。大魚。雄は鯨{渠京の反}と曰い、雌は鯢{音は蜺(ゲイ)。久知良(クヂラ)。}と曰う。/淮南子曰く。鯨鯢、魚之王なり。 〔注〕 (6-7) 魚之王:「淮南子」本文には確かに載っていない。慧琳音義:1一切経音義巻十五:鯨鯢:上渠迎反、説文云海中大魚也、淮南子云鯨魚死而彗星出、左傳云大魚也、許叔重曰魚之王也、或作[畺]下音霓、杜注左傳云[此/隹]鯨也、説文刺魚也、並形聲字。〔[此/隹]=雌〕2同第56巻:鯨鷁:又作[畺]同渠京反、許叔重注淮南子云、鯨魚之王也、異物志云、鯨魚數里或死、沙中云、得之者皆無目俗云其目化為明月珠也鯢鯨之雌者也、左傳鯨鯢大魚也、説文作[兒+鳥]、司馬相如作[赤+鳥]或作[畐+鳥]、埤蒼作[舟+益]、字書作鷁同五歴’反水鳥也善高飛也。3第81巻:鯨海:上[竝/見]迎反、許叔重曰、鯨魚之王、字統從畺作[畺]海中大魚也、長千餘里、説文從魚畺聲今從京作鯨通用字。〔[竝/見]=竟・竸・競〕/鯨波:巨迎反、許叔重注、淮南子云鯨魚海中最大魚也、説文亦同或作[畺]字。4第83巻 、第86巻:鯨鯢:1とほぼ同略。5第92巻:1、2とほぼ同略(但し杜注左傳云鯨鯢大魚也、に続けて「顧野王云鮑食小魚也」を載せる)……「中華電子佛典協會(CBETA)」(大正新脩大藏經 第五十四冊 No. 2128《一切經音義》CBETA 電子佛典 V1.85 普及版)より。 (6-8)許叔重:許慎。「隋書経籍志」にいう、「淮南子二十一巻{漢淮南王劉安撰許慎注}」であり、「鴻烈間詁」と呼ばれる。 古書注淮南子参照。 (6-9)許慎注文:「新美篇・輯佚資料」(参考文献)第七雑家類「淮南子許氏注:天文訓」:鯨魚死而彗星出/鯨魚之王也、並慧琳音義十五、五十六、八十一、八十三、八十六、九十二、玄應音義十九、諸道勘文四十五、又慧琳音義引注云鯨魚海中最大魚也。 (6-10)天文訓及覧冥訓:『淮南子』巻三「天文訓」、巻六「覧冥訓」(箋注原文「冥覧訓」は「覧冥訓」が正しい。 (6-11)説文 (段注):1[畺](篆)海大魚也{〔段注〕此海中魚最’大者、字亦作鯨、羽獵賦作京、京大也。}从魚畺聲{〔段注〕渠京切、古音在十部。}春秋伝曰取其[畺]鯢。{〔段注〕宣公十二年左氏伝文、劉淵林注、呉都賦、裴淵広州記、皆云、雄曰鯢、雌曰鯢、是此鯢非刺魚也。}鯨(篆)[畺]或从京{〔段注〕古京音如姜} 。2鯢(篆)剌魚也。{剌、盧達切、或作刺者誤。剌魚者乖、剌之魚謂其如小皃能縁木、史漢謂之人魚。釋魚曰、鯢大者謂之鰕。郭云、今鯢魚似鮎四脚、前似彌猴、後似狗、聲如小皃啼、大者長八九尺、別名鰕。按此魚見書傳者、不下數十處、而人不之信少見、則多怪也。余在雅州親見之、廣雅[内]鯢也。亦謂此集韵有[剌/魚]字、剌之俗。}从魚兒聲。{形與聲皆如小皃、故从兒、舉形聲關會意也。五雞切。十六部。}……「史漢謂之人魚」の「史漢」とは、「史記」と「漢書」を並べてこう呼ぶ。 (6-12)不載鯢字(鯢字を載せず):前注記に見るように、[畺]を正篆としてあげ、続けて、「鯨」の篆字を載せている説文の同一記事中には、「鯢字を載せず」という意味であろう。 (6-13)西京賦薛綜注:『文選』「西京賦」:海若游於玄渚、鯨魚失流而蹉跎。{薛綜注:海若、海神。鯨、大魚。善曰。楚辭曰。令海若舞馮夷。又曰。臨沅、湘之玄淵。薛君韓詩章句曰。水一溢而為渚。三輔舊事曰。清淵北、有鯨魚、刻石為之、長三丈。楚辭曰。驥垂兩耳、中阪蹉跎。廣雅曰。蹉跎、失足也。 (6-14)1春秋左氏伝、宣公十二年:KDB『十三經註疏』「春秋左傳註疏六十卷」第二十三巻二十八オ:武非吾功也、古者明王伐不敬、取其鯨鯢而封之以為大戮、於是乎有京観以懲淫慝:「其の鯨鯢(ゲイゲイ)を取りて之を封じ、以て大戮(タイリク)と為す 」として、鯨を悪逆の巨魁(白川静)と譬え 「懲淫慝」す記述を載せる。2左伝正義引裴淵広州記:晉・杜預:註:鯨鯢大魚名、以喩不義之人呑食国{唐・陸德明音義○鯨、其京反、鯢、五兮反、懲、直升反、慝、他得反}、唐・孔穎達:疏:【注】鯨鯢大魚名、○正義曰、裴淵広州記云、鯨鯢長百尺、雄曰鯨、雌曰鯢、目即名月珠也、故死即不見、眼晴也、周處風土記云、鯨鯢海中大魚也、俗説出入穴即為朝水。 (6-13)呉都賦劉逵注: 【文選・呉都賦】(TLDB)1異物志云:鯨魚、長者數 千里、雄曰鯨、雌曰鯢、或死於沙上、得之者皆無目、俗言其目化為明月珠。……中略……一説曰。鯨猶言鳳、鯢猶言皇也。2「異物志」不詳だが、「新美篇・輯佚資料」地理類に「異物志:後漢・楊孚撰」 が載る。「南州異物志」と併記して載せている。【「和名抄引書」】南州異物志[隋志]{地理}異物志一巻{後漢議郎楊孚撰}南州異物志一巻{呉’丹楊太守萬震撰}[旧志]南州異物志一巻{萬震撰}[新志]萬震南州異物志一巻。 なお、「長者数千里、」は、李善注舊本では、「長者数十里、小者数十丈」となっている。 (6-14)王念孫:(オウネンソン:1744~1832) (古書注参照):清代中期の考証学者。字は懐祖。「廣雅疏証」「読書雑志」ほかを著す。「雌鯨ハ蜺ト為ス」の出典は 『広雅疏証』巻第十下「釋魚:[内]鯢也」か、爾雅釈天の「螮蝀虹也」の釈文であろう。原典未確認のため後補記する。 (6-15)雌鯨:蜺:「虹蜺」「虹霓」(いずれも「コウゲイ」)、「にじ」のこと。爾雅釈天「風雨」(KDB):螮蝀虹也【晉・郭璞註】俗名、美人ト為ス。虹、江東デト呼ブ。{闕名音○螮音啼、蝀丁穴切、雩于句切}蜺挈貳【註】蜺ハ雌虹也。(屈原)離騒ニ見ユ。挈貳其ノ別名。……以下略……【宋 邢[日/丙]疏】螮蝀之ヲ雩ト謂う。……中略……月令ハ季春ノ月ニ虹始テ見ユ。音義ニ云フ。虹雙出ス。鮮盛ナル者ガ雄ト為ス。雄ヲ虹ト曰フ。闇ナル者ハ雌ト為ス。雌ヲ蜺ト曰フ。是レ、陰陽交会ノ気ニシテ、純陰純陽、則チ虹トス。……以下略。 |
|
| ■〔7〕孚・布 | |
|
臨海異物志云、[孚][布]、{浮布二音、伊流賀、}
{下総本は、「和名」二字あり。」『新撰字鏡』は、「鮪、伊留加」(イルカ)を載せる。また、『古事記』、『出雲風土記』は、「入鹿」に作る。}、 大魚色黒一浮一没也、 {『臨海異物志』は伝本がない。『太平御覧』が『魏武四時食制』を引き、「[孚][布]魚は、黒色で、大きさは百斤ある猪のごとし。黄色い色をして肥え食すべからず。数体(枚)連なり、浮いたり、沈んだりしながら泳ぐ」と云う。この箇所の引用と同じであろう。」。『廣韻』の「鯆」字の注に「鯆[孚]魚名。亦、[布]に作る。」とある。『晋書』『廣雅』に、「[甫/寸][孚]は[菊]也」とある。しかるに、[甫/寸]はまた、鯆の字の異文である、と『廣韻』に見える。すなわち、[孚][布]をさかさまにしたものの字に似ている。『四時食制』は、「[孚][市]」に作り、これとほぼ同じ文体になっている。また、『説文』に「[肺(月→魚)]魚也、楽浪番国に出ず」とある。} 抄本文読み下し:[孚][布] 臨海異物志は云う。[孚][布]。 {浮布ニ音。伊流賀(イルカ)。}/大魚、色黒く、一浮一没するなり。/兼名苑は云う。[孚][布]、一名鯆[畢]{甫畢二音。}、一名[敷][常]{敷常二音}。野王案う。一名江豚。 〔注〕 (7-1)臨海異物志: 古書注参照。輯佚し伝本無し。【「和名抄引書」】に、地理書「臨海異物志」とあり、[隋志]地理「臨海水土異物志一巻」{沈瑩撰}と記される。抄のほか、日本にのみ残存する天文を中心とした専門類書「天地瑞祥志」にも同書のことが載る。 (7-2)新撰字鏡:古書注参照。【新撰字鏡(享和本)】魚部七十一(831)鮪’{榮美反。上。伊留’加。} (7-3)古事記:入鹿:古書注参照:古事記中巻仲哀天皇(岩波 大系227p~/岩波文庫137p~) 及び「古事記伝」三十一之巻「○毀鼻入鹿魚」の記事はMANA字典「[孚]」の該当テキストをみよ。本セクションの引用記事についても整理して載せたので参照されたい。 (7-4) 出雲風土記:入鹿:古書注参照:「出雲風土記」島根郡 :凡南入海所在雑物、入鹿…中略…海松等之類至多、以下略。 (7-5) 太平御覧が引く魏武四時食制:古書注「太平御覧」、「四時食制経」 参照:『太平御覧』九百三十八巻:鱗介部十一:[孚][市]魚 :魏武四時食制云、[孚][市]魚黒色、大如百斤豬、黄肥不可食、数枚相随、一浮一沈、一名数常見首、出淮及五湖。 (7-6) 百斤:斤:重さの単位:一斤16両、周代256グラム、唐以後は約600グラム。現代中国は500グラム。 (7-7)廣韻、鯆:【廣韻】(TDB):古書注参照:1上平聲巻一:{遇倶}虞第十{模同用}:十○虞{遇倶切。}○敷{芳無切。三十六}[孚]{魚名}/十一○模{莫胡切。十二}…○逋{博孤切。十三}鯆{鯆[孚]魚名、亦作[布]。}…○[禾専]{普胡切。十二}鯆{魚名、又江豚、別名天欲風則見。}鱄{上同}2上聲巻三 :九○麌{虞矩切。三}…○甫{方矩切。十九}脯…鯆{大魚} (7-8)晉書::古書注参照: 注(7-15)参照。 (7-9)廣雅:[甫/寸][孚][菊]也:【広雅疏証】( 王念孫)(光緒五年淮南書局重刊本)(巻第十下)(二十一丁表~同丁裏)釋魚:[甫/寸][孚]、[匊]也。{説文、[匊]魚也。出 樂浪潘國、一曰、[匊]出九江、有両乳、一曰溥浮、與[甫/寸][孚]同。玉篇、[甫/寸][孚]魚、一名江豚、欲風則踊。[甫/寸]、一作鯆、晉書夏統傳、初作鯔[烏’]躍、後作鯆[孚]引、何超音義引埤蒼云、鯆[孚]、[匊]魚也、一名江豚、多膏少肉。[甫/寸][孚]之転語為[孚][市]。説文、[市]、魚也、出樂浪潘國。御覧引魏武四時食’制云、[孚][市]魚黒色、大如百斤豬、黄肥不可食’、数枚相随、一浮一沈、一名敷常見首、出淮及五湖。郭璞、江賦云、魚則江豚海豨。李善注引南越志云、江豚似豬。本草拾遺云、江[豬(者→屯)]状如[豬(者→屯)]、鼻中為声、出没水上、舟人候’之、知大風雨。案即今之江豬是也。海豬以江豬而大、一名奔[孚]。江賦注引臨海水土記云、海豨豕頭、身長九尺。本草拾遺云、海[豬(者→屯)]生大海水中、候’風潮出没、形如[豬(者→屯)]、鼻中為声、脳上有穴、噴水直上、百数為羣。酉陽雑俎云、奔[孚]一名[@]、大如船、長二三丈、色如鮎、有両乳在腹下、頂上有孔通頭、気出嚇々、作声必大風、行者以為候’。案説文、[匊]有両乳、奔[孚]有両乳在腹下、則即[匊]魚也。奔[孚][甫/寸][孚]、語之転耳。郭璞注、爾雅、[既’/魚]是[逐]云、尾如[匊]魚、鼻在額上、能作声、少肉多膏。情状與江豚相近。蓋亦[匊]之類也。[匊]、各本譌作[菊]、惟影宋本不譌。} (7-10)説文:説文解字に[孚][布]は載らず、[市](ハイ)と[菊-クサカンムリ](キク)が載る。廣雅を引用した 「[菊]」は、[匊]が正しい。[孚](7画)に整理して載せたので参照されたい。 |
|
|
兼名苑云、[孚][布]一名鯆[畢]、{甫畢二音}、一名[敷][常]{敷常二音}、
{下総本には、[孚][布]の二字がなく、廣本も同様である。」。[甫][畢]、[敷][常]の二名は、諸書に見ることができず、『太平御覧』が「四時食制」を引いて「[孚][市]一名を敷常という」といっていることから、[敷][常]は、「敷常」の俗字であろう。}、 抄本文読み下し:[孚][布] 臨海異物志は云う。[孚][布]。{浮布ニ音。伊流賀(イルカ)。}/大魚、色黒く、一浮一没するなり。/兼名苑は云う。[孚][布]、一名鯆[畢]{甫畢二音。}、一名[敷][常]{敷常二音}。/野王案う。一名江豚。 〔注〕 (7-11)兼名苑:参考古書名注参照。〔10〕人魚、鮫等にも載る。 (7-12)[敷][常]は、「敷常」の俗字:中国の「諸書に見ることができない」と書いているように、要注意字であり、再検討を要する。敷をフと読ませることで、この字がかかわりを持つことはあっても、「常」の字を伴って、「フ・ジョウ」という訓み(東洋文庫「本朝食鑑」4では、訳注者がフジョウのルビをふっている。221ページ)で、[孚][市]、[孚][布]と同義 の俗字とするのは、検討を要す。たとえば、前セクション(7-5)の太平御覧に引用された「魏武四時食制云」の該当箇所は、諸橋大字典では「一名数常見首」と書いてい るが、「数」は「敷」の誤植であろう。また、下総本の写本である「早稲田大学蔵本」「和名類聚抄」五の「龍魚」の[孚][布]の項には、次セクション「一名江豚」に割注し「睹頖’反、上之[布][敷][常]三字為不見不審也」とある。この割注者が、下総本の書写をしたものであるのか、どの段階で書き加えられたものかも、今後検討を要する。 |
|
|
野王案一名江豚、
{今本『玉篇』魚部に「[甫/寸][孚]魚は、一名を江豚といい、風を欲するように(水中や水上を)踊る」とあるところを引いたものだろう。『晉書』「夏統傳」に「鯆[孚]」を作る。『何超音義』が『埤蒼』を引き、「鯆[孚][匊]魚也、一名江豚、多膏少肉」と云う。『説文』は「[匊]魚也、楽浪番国に出ず。一に[菊’]と曰う。九江に出でて、両乳有す。一に、溥浮(ふふ)と曰う。」と云う。則ち、[甫/寸][孚]、[鯆][孚]、[孚][布]、[孚][市]は、皆、「溥浮」の俗字である。『酉陽雑俎』に載せる「奔[孚]」も、また、この語の転じたものであろう。『證類本草』が、陳蔵器(の「本草拾遺」)を引用して、「江[猪(者→屯)]の状は[猪(者→屯)]のようであり、鼻から声を発し、没していたかとおもうと水上に現われでる。海にでて漁師たちは、この様子をうかがい、大風雨を予測する」と書いている。江[猪(者→屯)]とは、江豚のことであろう。「出没水上」とは、すなわち『異物志』の「一浮一没」のことであろう。又、海豨あり、一名海豘、一名、奔[孚]とも書いている。 郭璞「江賦」に、「江豚海豨」とあり、(『文選』)注に、『臨海水土記』を引いて「海豨は豕頭、身長九尺」と云う。 陳蔵器は、「海豘(かいとん)は、大海の水中に生じ、風潮を候(うかが)い出没する。形は豘の如く、鼻中より声を為す。脳上に孔ありて、直上に水を噴く。百数の群を為す。」と云う。『酉陽雑俎』は、「奔[孚](ほんふ)一名[@](けい)。大きさは船の如くにして、長さは二、三丈。体色は鮎(ナマズ)のようで、腹下に両(ふたつ)の乳がある。頭のてっぺんには孔があり、そこから気を噴出し、赫赫(かくかく)たる声を発すると、必ず大風が吹く。船乗りたちは、これをもって海相(かいしょう)を候(うかが)う。」と云う。} 抄本文読み下し:[孚][布] 臨海異物志は云う。[孚][布]。 {浮布ニ音。伊流賀(イルカ)。}/大魚、色黒く、一浮一没するなり。/兼名苑は云う。[孚][布]、一名鯆[畢]{甫畢二音。}、一名[敷][常]{敷常二音}。野王案う。一名江豚。 〔注〕 (7-13) このセクションは、前掲注(7-9)に見るごとく、王念孫『広雅疏証』の「[甫/寸][孚]、[匊]也。」の記述 を内容としている。「王念孫曰」を記していないのは、おそらく、日本で、王念孫研究の大切さを認識していた松崎慊堂らの説文研究の成果の一つとして箋注 をしたのであろうが、出典は明示すべきであろう。 (7-14)顧野王撰「玉篇」:大廣益会玉篇三十巻・張氏重刊宋本玉篇(TDB)魚部第三百九十七 :[甫/寸]{一名江豚、欲風則踊。 }/[孚]{[甫/寸][孚]也.} (7-15)晉書夏統傳:晉書巻九十四:列傳第六十四:隱逸傳 :夏統:統乃操柂正櫓、折旋中流、初作鯔[烏’]躍、後作鯆[孚]引、……「鯔[烏’]躍」は、【諸橋大漢和】に「水中遊戯の状」。 (7-16)何超音義:晋書第百三十巻、付晉書音義三巻。「音義三卷、唐何超撰」:[新志]何超晋書音義三卷處士。 (7-17)埤蒼: 古字書だが、亡佚し伝わらない。新唐書芸文志:「張揖広雅四巻又埤蒼三巻、三蒼訓詁三巻」 (7-18)説文[匊]魚:[孚](7画)参照。 (7-19)酉陽雑俎「奔[孚]」:古書注参照。唐 ・段成式撰になる怪異譚を集めた書。20巻・続集10巻。860年頃成立。 奔[孚]:巻十七広動植之ニ、鱗介篇魚貝類:六七二「奔[孚]」(ほんふ)(平凡社東洋文庫『酉陽雑俎』3、187p):奔[孚]は、一名、[@](けい)という。魚でもなく、蛟(みずち)でもない。大きさは船ほどで、長さは、ニ、三丈ある。色は、なまずに似ている。両乳が腹の下にある。以下略。……[@]は画像参照。原典未確認。 (7-20)証類本草:古書注「証類本草」 参照。:【證類本草】(政和本草:WDB)巻第二十蟲魚部上品総五十種:二十三種陳蔵器餘:20-8-56b1:海豚魚:味鹹、無毒。…中略…生大海中。候風潮出。形如[犭屯]鼻中聲、脳上有孔、噴水直上、百數為羣。人先取得其子、繋著水中、母自來就而取之。其子如蠡魚子、數萬為群、常隨母而行。亦有江[犭屯]、状如[犭屯]、鼻中為聲、出没水上、海中舟人候之、知大風雨。…以下略:全文は[孚](7画)参照。 (7-21)異物志、一浮一没:注(7-1)を見よ。 (7-22)郭璞、江賦、江豚海豨:『文選』第12巻「江賦」:古書注参照。:【文選】(嘉靖金臺汪諒校刊本:TLDB)魚則江豚{徒昆}海豨’{喜}、叔鮪{于軌}王鱣{音邅。南越志曰。江豚似豬。臨海水土記曰。海豨’、豕頭、身長九尺。郭璞山海經注曰。今海中有海豨’、體如魚、頭似豬。爾雅曰。[各]、[叔]鮪。郭璞曰。鮪屬、大者王鮪、小者叔鮪。王鱣之大者、猶曰王鮪。[各]音洛。}…以下略。関連文は[孚](7画)参照。 (7-23) 臨海水土記:古書名参照。及び、注(7-1)を見よ。 (7-24)陳蔵器云:前掲注(7-20)後半参照。 (7-25)前掲注(7-13)で指摘した王念孫「広雅疏証」の引用文例を組み合わせて記述しているため、構文上の重複が見られる。 |
|
| ■〔8〕鰐 | |
|
麻果切韵云、鰐{音萼、和邇、}
{下総本には「和名」二字がある。」『新撰字鏡』及び『日本書紀』神代紀に同じ訓みを与える。} 抄本文読み下し:鰐 麻果切韵(マカセツイン)は云う。 鰐。{音は萼(ガク)。 和邇(ワニ)。}/鱉(ヘツ)に似て、四足有り。喙は長さ三尺にして、甚だしく利(するど)い歯をもって、虎及び大鹿が水を渡らんとすると、鰐は、之を撃ち、皆(ことごと)く中断す。 〔注〕 (8-1)麻果切韵(まかせついん):【「和名抄引書」】麻果切韻{[金+瓜]○鰐○[高/木]}/現在書目 切韻五巻{麻果撰}〔頭注:△〕。「麻果撰」は「麻杲撰」。古書注「切韻」を見よ。 (8-2)新撰字鏡 (しんせんじきょう):【新撰字鏡(享和本)】魚部七十一(831b下3)鰐、鱷{同。五各反。和尓。}/(831a下2)[卑’]{薄佳反。知奴、又、和尓。} (8-3)日本書紀神代紀: 【日本書紀】(岩波文庫『日本書紀』坂本・家永・井上・大野校注)1巻第一(神代上第八段)(102p~)一書(あるふみ)に曰はく〔第六の一書〕、大国主神、……中略……又曰(い)はく、事代主神(ことしろぬしのかみ)、八尋熊鰐(やひろわに)に化為(な)りて、三嶋(みしま)の溝樴姫(みぞくひひめ)、或(ある)は云はく、玉櫛姫(たまくしひめ)といふに通ひたまふ。……以下略。2巻第二(神代下第十段)(172p~)時(とき)に豊玉姫、八尋(やひろ)の大熊鰐(わに)に化為(な)りて匍匐(は)ひ逶虵(もごよ)ふ。…以下略。 |
|
|
似レ[敝/魚]有二四足一、喙長三尺、甚利歯、虎及大鹿渡レ水、鰐撃レ之皆中断、
{(『文選』)「呉都賦」劉逵注に『異物志』を引用して、「鰐魚長二丈余、有四足似鼉、喙長三尺、甚利歯、虎及大鹿渡水、鰐撃之皆中断」(鰐魚は長さが二丈あまりで、四本の足を持つ。鼉(ダ)に似て、四足有り。喙は長さ三尺にして、甚だしく利(するど)い歯をもって、虎及び大鹿が水を渡らんとすると、鰐は、之を撃ち、皆(ことごと)く中断す。)と云う。『麻果切韻』は、蓋し、これを本(もと)にしており、鱉(ヘツ)は、恐らく鼉(タ)の誤りであろう。 『説文』の「鰐」は[虫屰」に作り、「似蜥易、長一丈、水潜、呑水、即浮、出日南」と云う。」。(ここでいう)「鰐魚」は、わが国(皇国)に産してはいない。(わが国でいう)「和邇」(ワニ)は、鮫魚(サメ)の一種であろう。大きな頭をして、口は特に大きく(巨)、大きなものになると、人を呑み込む。(和邇の)漢名は不詳である。 抄本文読み下し:鰐 麻果切韵(マカセツイン)は云う。 鰐。{音は萼(ガク)。 和邇(ワニ)。}/鱉(ヘツ)に似て、四足有り。喙は長さ三尺にして、甚だしく利(するど)い歯をもって、虎及び大鹿が水を渡らんとすると、鰐は、之を撃ち、皆(ことごと)く中断す。 〔注〕 (8-3) 呉都賦劉逵注:【文選】(嘉靖金臺汪諒校刊本:TLDB)巻第五:京都下:呉都賦:左大冲。劉淵林注:前略……於是乎、長鯨呑航、修鯢吐浪。躍龍騰蛇、鮫鯔琵琶。王鮪{偉 }鯸鮐、[印]{印}龜[番][昔]。烏賊擁劍、[勾/黽]{古侯}[辟/黽]{辟}鯖鰐。涵泳乎其中。{航舡之別名、異物志云、鯨魚長者数十里、小者数十丈、…中略…鰐魚長二丈餘、有四足、似鼉、 喙長三尺、甚利齒、虎及大鹿渡水、鰐撃之皆中斷。生則出在沙上乳卵、卵如鴨子、亦有黄白、可食。其頭琢去齒、旬日間更生、廣州有之。涵、沉也。楊雄方言曰 、南楚謂、沉為涵。泳、潜行也、見爾雅。言已上魚龍、潜沒泳其中。 善曰。莊子曰、呑舟之魚、碭而失水。周易曰、見龍在田、或躍在淵。楚辭曰、騰蛇兮後從。文子曰、騰蛇無足而騰。鯔、音菑。[台]、音夷。[番]、甫袁切。[昔]、甫亦切。鰐、五洛切。涵、音含。}…以下略。 (8-4)異物志:前掲注(7-1)を見よ。 (8-5)鼉(タ)、鱉(ヘツ)は 、真名真魚字典「その他25画」参照。また、鱉(ヘツ)は 、後條〔77〕鼈(「その4・5」)の箋注あり。 (8-5)説文鰐:説文に「鰐」「鱷」字なく、[虫屰]を載せる.1【説文解字】(徐鉉校訂「大徐本」汲古閣本)(WLDB):(右画像)[虫屰](篆){似蜥易、長一丈、水潜呑人、即浮。出日南。从虫屰声。吾各切。}2【説文】(「説文解字注十五巻」經韵樓蔵版)(WLDB):[虫屰] 佀蜥易。長一丈。{當同鼉、下云長丈許、}水潜呑人、即浮。出日南也。{劉注呉都賦曰、異物志云、鰐魚長二丈餘、有足似鼉、長三尺、甚利歯、虎及大鹿渡水、鰐撃之、皆中断。生子則出在沙上乳卵、卵如鴨子、亦黄白、可食、其頭琢去歯、旬日閒更生、廣州有之、按拠劉注則不必、日南郡乃有其物也、}从虫屰声。{吾各切、五部、俗作[虫咢]鰐鱷、} (8-6)【古事記】(岩波日本古典文学大系『古事記祝詞』古事記:倉野憲司校注)上巻(大国主神―稲羽の素兔)(91~92p) 故(かれ)、痛み苦しみて泣き伏せれば、最後(いやはて)に来(き)たりし大穴牟遲の神、其の莵をみて、「何由なにしかも汝なは泣き伏せる。」と言ひしに、莵答へ言まをししく、「僕われ淤岐おきの島に在りて、此の地ところに度わたらむとすれども、度らむ因よし無かりき。故かれ、海の和邇{この二字は音を以ゐよ。下は此れに[交+攵]。}を欺あざむきて言ひしく、…中略…『汝は我に欺かえつ』と言ひ竟をはる[皀+卩]ち、最端(いやはし)に伏せりし和邇(わに)、我(わ)を捕へて悉に我が衣服きものを剥ぎき。……○上記岩波日本古典文学大系本「海の和邇」頭注。《三三》鰐、海蛇、鰐鮫などの諸説があるが、海のワニとあることと、出雲や隠岐島の方言に鱶や鮫をワニと言っていることを考え合わせて、鮫と解するのが穏やかであろう。(91p)日本における「ワニ」と「サメ」については、『世界大博物図鑑』(2魚類)「サメ」(23~39p)中の「ワニとサメ」(34~35p、38p)の整理がわかりやすい。 |
|
| ■〔9〕鮝魚 | |
|
辯色立成云、鮝魚、{居媛反、布加、今案未レ詳}
{「鮝」字は、諸書に見ることがない。「居媛(きょえん)」の反切(はんせつ)とする拠(もと)は、則ち、その字が、[*1]を声符としているところにあるのだろう。「卷」「拳」等の字と同じ(声符をもつ字)である。「正字通」に鮝字が載る。これは俗に「鯗’」字だが、「鯗’」息両の反切(ショウ)であり、蓋し、養省声を従える。則ち、是の字ではない。下総本には「和名」二字あり。恐らく是にあらず。廣本も、また、ない。鮝魚をもって布加(フカ)となすが、その典拠はわからないままだ。} 抄本文読み下し:鮝魚 弁色立成( ベンジキリュウジョウ)は云う。 鮝魚。{居媛(キョエン)の反。 布加(フカ)。 今案ずるに詳ならず。} 〔注〕 (9-1)弁色立成:参考古書名注参照。 (9-2)*1:「箋注倭名類聚抄」国会図書館活字本。判別困難な字形だが、原本から活字化するときに原著の字義を考慮すると、*1=*2であろう。収’→廾(にじゅうあし)の象形は、両手をそろえて物をささげるさまを表している(*4の下半分の象形→朕:鰧オコゼの場合はチン・トウ)。「共」の字に含まれる。*3は、音「ケン」で、種が散らばらないように両手で丸めて受けるさまを表している(【学研大漢和字典】574頁)。卷(まく)や、拳(まるくまいたこぶし)の構成要素になる。*4は、「京大本許氏説文解字」からの*3の篆文。拳(ケン)は、*3を音符(ケン)として、「手」を加えて作られた文字 である。 (9-3)居媛反:「反」は「反切」。「卷拳等の字と同じ」とは、何を言わんとしているのか、『広韻』の韻目配列により補注しておこう。1鮝:説文、玉篇、広韻、集韻に載らず。2「居媛」を反切とする字には、「玉篇」に「桊」(ケン)が載る。【玉篇】(大廣益会玉篇三十巻・張氏重刊宋本玉篇)(TDB):巻第十二(木部一百五十七:八百二十二字)桊{居媛切。牛鼻桊}:ピンイン=A:去聲:居倦切(juàn)、B:平聲:驅圓切(quān,quán):【標註訂正康煕字典】〔唐韻〕居倦切。〔集韻〕古倦切、竝音眷。3【説文】牛鼻中環也。从木[*3]聲。居倦切。4【廣韻】(五巻・張氏重刊宋本廣韻TDB)去聲巻第四:{蘇見}霰第三十二{線同用}:三十二○霰{蘇佃切。九}/三十三○線{私箭切。四}…○瑗{王眷切又于願切。五}…媛……○眷{居倦切。十五}睠捲弮卷桊…[*3]…○捲{渠卷切。五}5【廣韻】下平聲巻第二:{蘇前}先第一{仙同用}:一○先{蘇前切又蘇薦切。四}/二○仙{相然切。}…○權{巨員切。二十三}拳…巻{九免、九院二切}…捲。6:【集韻】(WDB)巻之三:平聲三:一○先{蕭前切。}/二○[僊(旁→興/巳)]僊{相然切。二十九}仙…○巻{驅圓切。十八}…弮…棬桊…拳…以下略。……ということの説明はできるが、「弁色立成」が「鮝」を「フカ」として、去聲「ケン」の声符を持つグループに加えたことの理由は、いうごとく「未知所拠」ままである。 なにが、大切かというと、「未知」であり、現代の整理においてもわからない、という原理追求の必要という点にあるのではなく、このような、不可思議な文字の配列(ジャンルわけ)が生まれ、ほとんど根拠を特定できない〝文字とその訓み〟が誕生してしまう、という、そのことに、〝気づいて〟いて、いちおう「説文」「広韻」などの研究による当時の中国音韻学(考証学)をいかした日本語の解明が必要という問題意識に基づきチェックを入れている点に着目すべきなのだと思う。 (9-4)1「鯗’」の字形を再確認すること。2サメとフカとの和名呼称の検討をすべし。ペンディング。 (9-5)【箋注倭名類聚抄】〔14〕鮫の項目を見よ。 |
|
| ■〔10〕人魚 | |
|
兼名苑云、人魚、一名鯪魚、{上音陵、}魚身人面者也、
{疑うらくは、魚身以下「六字」、これ『兼名苑』注文なりや。『山海経』「海内北経」は、「陵魚、人面、手足魚身、海中に在り」と云う。『兼名苑』の注は、蓋し、之を本(もと)としているのだろう。『説文』に「鯪」字は載っていない。『山海経』に依れば、則ち、古くは「陵魚」に作るを知る。丘陵土中に在るをもって「陵魚」の名がつき、(その姿かたちは)人面に手足在るをもって、「人魚」という名がつけられた。『楚辞』「天問」に「鯪魚何所」と載る。王逸は「鯪魚は鯉なり。一に、鯪は鯉なり、四足あり、南方に出づ」と曰う。「呉都賦」は、「陵鯉は獣の若<ごと>し。」という。劉逵注は、「陵鯉に四足あり。その状は獺の如し、鱗甲は鯉に似て、土穴中に居る、その性は好んで蟻を食う」と云う。「陶別録」注(『証類本草』「名医別録」陶弘景の注に)は「鯪鯉は能く陸にすみ、能く水にあそぶ。岸に出で、鱗甲を開き、その状は死すが如し。蟻をして入らしめれば急閉して、水に入り、甲を開き、皆これ浮き出んとするを食す。故に蟻瘻を主とす」(鯪鯉はよく陸上を動き回り、水にも入って、岸べに上がると、鱗甲を開き、死んだようになっている。もし、蟻が入ってくると急に閉じて、水に入って甲羅を開くと蟻が浮き出してくるので、之を食べる。故に蟻瘻を持っている、)と云う。} 抄本文読み下し:人魚 兼名苑( ケンメイエン)は云う。人魚。一名鯪魚。{上音陵(リョウ)。 魚身人面のものなり。}/山海経注は云う。声は小兒の啼くが如し。故に之を名づく。 〔注〕 (10-1)兼名苑:参考古書名注参照。 (10-2) 山海経、海内北経:古書注参照:陵魚:郝懿行疏・郭璞伝【山海経箋疏】(WLDB):山海経第十二(3冊)海内北経:陵魚人面、手足、魚身、在海中 {懿行案。楚詞天問云。鯪魚何所。王逸注云。鯪魚、鯉也、一云鯪魚、鯪鯉也、有四足、出南方。呉都賦云。陵鯉若獸、劉逵注云、陵鯉有四足、状如獺、鱗甲似鯉、居土穴中、性好食蟻。引楚詞云。陵魚曷止。王逸曰。陵魚陵鯉也。所引楚詞與今本異、其説、陵鯉即今穿山甲也、云性好食蟻、陶注本草説之極詳、然非此経之陵魚也。穿山甲又不在海中、此皆非矣、査通奉使高麗見海沙中、一婦人肘後有紅鬣、號曰、人魚、蓋即陵魚也。陵人声相転、形状又符是此魚審矣。又初学記三十巻引此経云、鯪魚背腹皆有刺如三角菱、北堂書鈔一百三十七巻亦引此経而云、鯪鯉呑舟。太平御覧九百三十八巻引作鯪魚呑舟、疑此、皆郭注誤引経文、今本竝脱去之也。} (10-3)説文に鯪字載らず:確かに載らない。但し、前掲注(6-11)に見るとおり、「鯢(篆)剌魚也。{剌、盧達切、或作刺者誤。剌魚者乖、剌之魚謂其如小皃能縁木、史漢謂之人魚。釋魚曰、鯢大者謂之鰕。郭云、今鯢魚似鮎四脚、前似彌猴、後似狗、聲如小皃啼、大者長八九尺、別名鰕。」と段注の注文に載せている。 (10-4)楚辞、天問、王逸曰。:古書注参照:前掲注(10-2)の『山海経箋疏』の郝懿行疏(注)に「呉都賦」「陶注本草=別録注」(「太平御覧」)引用が何れも載る。:「楚辞」天問:鯪魚何所(りょうぎょいづれのところぞ)、[斬(車→鬼)]堆焉處(きたいいづくにかをる)、羿焉日[張(長→畢)]、烏焉解羽。○王逸注「鯪魚、鯉也。一云鯪魚、鯪鯉也、有四足、出南方。」○楚辞集注(朱熹注)「鯪、一作陵」○楚辞補注「山海経、西海中、鯪魚有、四足人面人手魚身、見則風濤起、天対云、鯪人貌」 (10-5)呉都賦劉逵注:古書注参照:【文選】(嘉靖金臺汪諒校刊本:TLDB):前略……其荒陬{子侯}譎{決}詭、則有龍穴内蒸、雲雨所儲。陵鯉若獸、浮石若桴。雙則比目、片則王餘。窮陸飲木、極沈水居。泉室潛織而巻綃、淵客慷慨而泣珠。開北戸以向日、齊南冥於幽都。{陬、四隅、謂邊遠也。湘東新平縣有龍穴、穴中黒土、天旱、人人便共以水沾穴、則暴雨應之、常以此請雨也。陵鯉、有四足、状如獺、鱗甲似鯉、居土穴中、性好食蟻。楚辭曰。陵魚曷止。王逸曰。陵魚、陵鯉也。浮石、體虚輕浮、在海中、南海有之。桴、舟也。比目魚、東海所出。王餘魚、其身半也。俗云、越王鱠魚未盡、因以殘半棄水中為魚、遂無其一面、故曰王餘也。朱崖海中有渚、東西五百里、南北千里、無水泉、有大木、斬之、以盆甕承其汁而飲之。水居、鮫人水底居也。俗傳鮫人從水中出、曾寄寓人家、積日賣綃、綃者、竹孚兪也。鮫人臨去、從主人索器、泣而出珠満盤、以與主人。日南人北戸、猶日北人南戸也。善曰。尚書曰、宅朔方曰幽都。謂日既在北、則南冥與幽都同。王餘、泉客、皆見博物志。窮陸、見後漢書。史記曰。秦始皇地南至北向戸、北據河為塞。 (10-6)陶注別録云:『証類本草』「名医別録」陶弘景注に云う。 【證類本草】(政和本草:WDB)巻第二十二蟲部下品總八十一種:一十二種名醫別録(墨字)(8-130~131):鯪鯉甲:微寒。主五邪驚啼悲傷、燒之作灰、以酒或水 、和方寸匕、療蟻瘻。{三字分墨塗云。其形似鼉而短小、又似鯉魚、有四足、能陸能水。出岸開鱗甲、伏如死、令蟻入中、忽閉 而入水開甲、蟻背浮出、於是食之。故主蟻瘻。…以下略。……「名医別録」:現在伝えられる「証類本草」の元となっているのが陶弘景編著になる500年ごろ成立した「本草経集注」。この 「本草経集注」は、当時すでに成立していた「神農本草経」と「名医別録」を合編し加注した書で、『證類本草』(政和本草:WDB)においては、本條における「鯪鯉甲」の載る、巻第二十二「蟲部下品總八十一種」は、「一十八種神農本経{白字}」「一十二種名医別録{墨字}」「二種唐本草先附{注云唐附}」「五種今附{皆医家甞用有放注云今附}」「八種新分條」「三十六種陳蔵器餘」と目録に記す。「証類本草」は、「本草経集中」以来の、薬物の増補改定にあたって、前代の原本の書式を(「白字」は墨べたに白抜き字。墨の黒字併用)そのまま踏襲し、増補して版本化していくことで、古い記事は、そのまま(誤植は当然あるが)新版に伝えられることで、「雪ダルマ式」(真柳氏の言葉を借りれば)の編成となる。そのため、「一定の規則に従えば過去の文献にさかのぼれることも不可能ではない」という利点があるが、煩雑、重畳な内容になるデメリットはある。『本草綱目』は、この重畳となった記事内容を、編者によって整理し、項目を立て直しより、利用の便に応えるために企図制作されたものである。ところが、「本草綱目」のような編集をしてしまうと、一度、誤植や編者による誤記や創意による挿入や削除された内容になってしまうと、原典のほうが正しい記述の場合には、その誤りのまま、後世に伝わり、復元は難しいという、マイナス面が生じる。箋注にあたって、この点を配慮したものか、当時、既に広く流布していた「本草綱目」(や「本朝食鑑」のような編著作)からの引用は一切せず、「新修本草」「證類本草」を使用し、 「順抄文」「本草和名」「医心方」などとの校訂をしていることは、当然の考証方法とはいえ、以下箋注にあたって多出するため一言触れておきたい。 (10-7)「主蟻瘻」:「蟻瘻」は どうよんだらよいのか。『医心方』「雉」に「治蟻瘻」とある。その症状にかかっている、もっていると読むのでよいであろうか。 |
|
|
山海経注云、聲如二小兒啼一、故名レ之
{『山海経』「北山経」に「龍候之山決々之水出焉、其中多人魚、其状如[帝]魚、四足、其音如嬰兒」と云う。「郭璞注」に「或曰、人魚即鯢也、似鮎而四足、聲如小兒啼、今亦呼鮎爲[帝]」と云う。「之」とは是の引用であろう。『史記』秦始皇帝本紀は、「葬始皇酈山、以人魚膏為燭」と云う。(裴駰)「集解」は、「徐廣注」を引用して「人魚似鮎四脚」と曰う。(張守節)「正義」は、「廣志」を引き「鯢魚聲如小兒啼、有四足、形如鱧、出伊水」と云う。『水経』「伊水」注は、『廣志』を引き、「如鯪鯉」に作る。『証類本草』の「[夷]魚」の條に、陶隠居を引き「人魚似[是]而有四足、聲如小兒」と云う。陳蔵器は「鯢魚在山溪中、似鮎有四脚長尾、能上樹、聲如小兒啼、故曰鯢魚、一名人魚」と云う。 抄本文読み下し:人魚 兼名苑(ケンメイエン)は云う。人魚。一名鯪魚。{上音陵(リョウ)。魚身人面のものなり。}/山海経注は云う。声は小兒の啼くが如し。故に之を名づく。 〔注〕 (10-8)山海経北山経:[帝](9画)をみよ。山海経注:「郭璞注」 :山海経第三:(第2冊)北山経:北次三経之首曰太行之山{略}…中略…又東北二百里曰龍候之山、無草木、多金玉、決決之水出焉{略}而東流注于河、其中多人魚{懿行案、人魚即鯢魚。爾雅云。鯢大者謂之鰕是也。鯢古文省作兒。周書王會篇云、穢人前兒又是也。兒从几、即古文人字又人兒声転、疑経文古本作兒魚、闕脱其上即為人魚矣、}其状如[帝]魚四足、其音如嬰兒{[帝]見中山経、或曰人魚即鯢也。似鮎而四足、声如小兒嗁、今亦呼鮎為[帝]、音嗁。 懿行案。[帝]當為[弟]、説文云、[弟]大鮎也。郭云、見中山経者少室山休水中多[帝]魚是也。又云。人魚即鯢者水経注云、伊水又東北流注於洛水、引広志曰、鯢魚声如小兒嗁、有四足、形如鯪鯉、可以治牛出伊水也。司馬遷云、之人魚、故其著史記曰、始皇帝之葬也。以人魚膏為燭、徐広曰、人魚似鮎而四足、即鯢鯢魚也、}食之無癡疾{懿行案、説文云、癡不慧也。中山経云、[帝]魚食者無蟲疾與此異} (10-9)史記 :古書注を見よ。:『史記』一百三十巻(司馬遷「撰」:裴駰「集解」:司馬貞「索隠」:張守節「正義」)(TDB)秦始皇本紀第六: 前略……九月、葬始皇酈山。始皇初即位、穿治酈山……中略……以水銀為百川江河大海、機相灌輸 {略}、上具天文、下具地理。以人魚膏為燭、{徐廣曰、人魚似鮎、四足、○正義曰廣志云、鯢魚聲如小兒啼、(有四足、)形如鱧、可以治牛、出伊水、異物志云、人魚似人形、長尺餘、不堪食、皮利於鮫魚、鋸材木入、項上有小穿、氣從中出、(秦始皇冢中以人魚膏為燭、 即此魚也)出東海中、今台州有之、按、今帝王用漆燈冢中、則火不滅、}、度不滅者久之。 (10-9-その2)1集解:しっかい: 裴駰「史記集解」。2正義:せいぎ:張守節「史記正義」 (10-10)水経伊水注:『水経注』「伊水」條に含む注文:古書注参照:1『水経注』乾隆39(1774)年序、戴震校本(WLDB)巻十五「伊水」:(25丁裏~26丁表)又東北至洛陽縣南北入于洛。/伊水自闕東北流枝津右出焉{案近刻枝訛作之}…中略…伊水又東北流注于洛水。 廣志曰。鯢魚聲如小兒嗁{案近刻脱嗁字}有四足、形如鯪鱧{案近刻脱鯪字}、可以治牛出伊水也。司馬遷謂之人魚、故其著史記曰、始皇帝之葬也、以人魚膏為燭。徐 廣曰、人魚似鮎而四足、即鯢魚也。2同巻二十八「沔水」(ベンスイ):(13丁表~15丁表)沔水{案此巻云々略}又東過堵陽縣堵水出自上粉縣{案堵水出下云々略}北流注/…中略…/又東過中盧縣東維水自房陵縣維山東流注之{案云々略}…中略…沔水、又南 與疎水合水出中盧縣西南東流至[邵(召→已)]縣北界{案云々略}、 東入沔水謂之疎口也{案近刻脱之字}、水中有物、如三四歳小兒、鱗甲如鯪鯉、射之不可入、七八月中好在磧上、自曝{案上近刻訛作中}[桼卩]頭、似虎掌爪、常没水中、出[桼卩]頭、小兒不知、欲取弄戲、便殺人、或曰、人有生得者、摘其皐’厭可小小使{案近刻作可以小使}、名為水虎者也{案虎近刻訛作唐}。 (10-10-その2)『廣志』は、亡佚書だが、和名抄、医心方など日本の古辞書、本草書など古書に引用されている「博物誌」的書とされ、『隋書』「経籍志」には、「[隋志]{雑}広志二巻{郭義恭撰}[新志]郭義恭広志二巻。」(【「和名抄引書」】より)と「雑家」の書として記される。 (10-10-その3)箋注文は、「廣志」を引用して「如鯪鯉」と書くが、本注で参照した「水経注」の諸本原文によっていくつかの疑問点が浮んできた。(1)引用原文の『水経注』「伊水」の載る「広志」文に「鯪鯉」は載らない。つまり、この前のセンテンスに載る「史記正義」の「形如鱧」「出伊水」を補注するための引用であるのだから、「鯪鯉」か「鱧」であるかは別にしても、「伊水」條からの引用でなければおかしい。見たテキストには「如鯪鱧」(あるいは明以前の古本『水経注』なら「如鱧」)と載っていたはずである。つまり、(10-10)1からは、正しくは「鯪鱧」(あるいは「鱧」)となる。「鱧」を「鯉」と読み直して引用したのなら、そのむね注しなければ、『水経注』の原文には、それが誤りの記述であろうと、引用の誤りとなる。(2)しかし、そう単純に結論を出せない別の読み方もできる。深読みして、「伊水」條ではなく、2の「沔水」條を読んで、「如鯪鯉」引用したとすれば、引用句は正しいが、(1)で書いたように、引用例文として適切ではない。「沔水」條を引用したのではなさそうだ。(3)つまり、「史記正義」が引用した「広志云」は、ⅰ「鯢魚聲如小兒啼、有四足、形如鱧、」である。それを箋注した「水経伊水注」の「広志」引用句は、ⅱ「如鯪鯉」とのみ記す。「水経伊水注」の1の戴震校本テキストには、ⅲ「鯢魚聲如小兒嗁{案近刻脱嗁字}有四足、形如鯪鱧{案近刻脱鯪字}、 」を載せる。ⅰ、ⅱ、ⅲについて、「啼」=「嗁」を同義とみて、「鱧」字を「鯉」字に読み間違えて、「人魚」の箋注を意識したのか、「鯪鯉」としてしまった可能性は高い。あるいは、直筆稿本には、「鯪鱧」とあって、森立之による活字版制作中に、「鯪鯉」としてしまったのかの何れかであろう。ただし、これは、直筆稿本をみれば確認できることで、後日、要確認事項とする。 (10-10-その4)しかし、本條の「人魚」及び「鯪鯉」あるいは「鯪」「鯉」そして「鱧」のそれぞれの字義の解釈を整理するうえで、もう一点、注意しておかなければいけないことがある。つまり、戴震校本に見える「{案近刻脱鯪字}」についてである。つまり、この注記は、戴震を含めて、清代考証家たちの「水経注」の清代校本、清以前宋代までの古本「水経注」など諸本校訂作業の過程で、「形如鱧」の句には、「水経」元文あるいは、「酈道元が編撰」し注を加えた「水経注」元文にはあった「鯪」が欠失していて、「形如鯪鱧」と正した、と書いてあるのである。しかし、この修正そのものが問題であった。前掲注(10-8)に見た『山海経』郭璞注が「廣志」該当箇所の引用句には「鯢魚声如小兒嗁、有四足、形如鯪鯉、」としており、この引用をきちんと検討して、「鯪鯉」と二字直すのならまだしも、古本『水経注』の「廣志」引用句「形如鱧」に「鯪」一字が抜けているとしたことがそもそもの誤まりであったのだろう。 (10-10-その5)清末以降の『水経注』研究により、現代版の最新テキストでは、この箇所は、また「形如鱧」に戻されている。「鱧」を「鯪鯉」に正さなかったのには、校訂者の考証するうえでの「正」に対する姿勢が伺えるように考えられる。箋注の注釈とははなれるが、引用しておこう。その校訂者とは、『箋注倭名類聚抄』を高く評価し、また森立之ら薫陶を受けた漢学、本草学、医学者らと交流を深め、渋江抽斎・森立志編『経籍訪古志』の価値をいち早く見抜き、日本より先に中国での刊行を実現させた「楊守敬」(ようしゅけい)(1839~1915)である。 (10-10-その6)楊守敬校訂・熊会貞編『水経注疏』四十巻(KJTDB):巻十五「洛水」:伊水又東北流注于洛水。廣志{撰人闕巻七隋書不著欽古類書多引之}曰{朱箋曰、謝云、廣志以上、疑有脱落趙云。按無闕文也。蓋其體例如此不得以人魚事、與上文義不属疑之}。鯢魚聲如小兒嗁{朱脱嗁字、趙増云、小兒下、爾雅釈魚註、有嗁字、史記始皇本紀、正義同全載、並増。守敬按。御覧〈九百三十八〉引廣志無嗁字、}有四足、形如鱧{趙云、鱧謂鯪鱧也、本草陶隠居云、鯪鱧、形似鼉而短小、又似鯉水〔魚〕、有四足、山海経曰、〔第五中山経:又西二百里〕蔓渠之山、伊水出焉、有獸焉、其名曰馬腹、其状如人面虎身、其音如嬰兒、是食人。此與沔水注、中盧疎水之水虎頗相類、道元又以人魚釈之詳見下、全載、増鯪字。守敬按。史記始皇本紀、正義、御覧〈九百三十八〉引廣志、並無鯪字。不必増。}、可以治牛出伊水也。司馬遷謂之人魚{朱箋曰、山海経、〔第五中山経:又西一百四十里〕厭染之水出、傅山之陽、南流注于洛、其中多人魚。不云、伊水豈。古今相沿并厭染之水、名伊水乎。趙云。案厭染之水見洛水注、朱氏只知人魚字出厭染之水、而不悟伊水、亦有馬腹之文也。}、故其著{朱作著其。朱箋曰。一作其著。全趙載改}史記{始皇本紀}曰、始皇帝之葬也、以人魚膏為燭。徐廣曰、人魚似鮎而四足{守敬按。始皇本紀、集解引}、即鯢魚也。〔KJTDBは、写本で、後日良刊本で容確認。〕……趙一清撰『水経注撰刊誤』(12巻)(古書注参照)では、「鱧は鯪鱧を謂うなり」として、その理由に「本草陶隠居云」に「鯪鱧」の注文を例文としてあげているが、これは、前掲注(10-6)に見るように「鯪鯉甲」の読み誤りであるが、楊守敬は、とくにこの箇所の「誤」を批正せず、引用句を挙げるにとどめている。そして、「史記始皇本紀」、「史記正義」、「太平御覧〈九百三十八〉」の廣志引用句には「鯪」字を載せていない、文献上の事実のみをあげて、「鯪鯉」と修正することは可能かもしれないが、あえて、清代テキストで、全て「鯪」字を加えたが、「増やす必要はなし」(不必増)と断じた。つまり、「本文に、鮎に似て四足という人魚の姿かたちや聲状を示し、鯢魚と呼ぶことで、明白であり、また、沔水の條にも人魚をのせ、山海経との記述 上の整合性からも《形は鱧の如し》の言葉のままが、古本にあっているのだ」と言外で主張しているのだろう。楊守敬の考証学の姿勢とみてもよいように思う。たまたま、箋注においては、「鯪鯉」と記してしまったことは「画竜点睛」を欠いたミスかもしれないけれど、考証に対する姿勢は箋注と楊守敬(また王念孫にも)校訂にも相通じる基本的なものなのであろう。これは、訳注者の読み方であって、この「鯪鯉」と「鯪鱧」と「鱧」の記述の校訂にあたっての考証について、楊守敬の的確な指摘以外の注解を見ないので、ぜひ批判を仰ぎたいと思う。 (10-11) 証類本草:鮧魚: 【證類本草】(古書注参照)(政和本草:WLDB)巻第二十巻蟲魚部:[夷] …中略…{陶隱居云。此是[是](音題)也。…中略…又有人魚、似[是]而有四足、聲如小兒、食之療瘕疾、其膏燃之不消耗、始皇驪山冢中用之、謂之人魚膏也。荊州、臨沮、青溪至多此魚、唐本注云。[夷]魚、一名鮎魚、一名[是]魚。…以下略}。真名真魚字典:鮧(6画)前掲注(10-6)も参照。……医心方巻三十「鮧魚」:本草云として引用されている。なお、「鮧魚」(いぎょ)については伊沢蘭軒の小論がある。 (10-12)陳蔵器云:【證類本草】(古書注参照)(政和本草:WLDB)巻第二十巻蟲魚部總五十種:二十三種陳蔵器餘:(8-58~59)鯢魚:鰻[麗]注、陶云。鰻[麗]能上樹。蘇云。鯢魚能上樹、非鰻[麗]也。按、鯢魚一名王鯆、在山溪中、似鮎、有四脚、長尾、能上樹、天旱則含水上山、葉覆身、鳥來飲水、因而取之。伊洛間、亦有聲如小兒啼、故曰鯢魚、一名[蒦]魚、一名人魚。膏燃燭不滅、秦始皇塚中用之。陶注鮎魚條云、人魚即鯢魚也。 |
|
|
■
『山海経』が云うところの「人魚」は、即ち「鯢魚」のことである。今、俗に「山椒魚」と呼び、或は、「半割」と呼ぶものである。その聲は小兒の如く啼くことから、「人魚」と名づけ、或は「鯢魚」と名づけたものである。『日本紀略』は、延暦十六年八月己己の記述として、「掖庭溝中、獲魚長尺六寸、形異常魚或云椒魚、在深山澤中、」と云う。『文徳実録』は、仁寿二年三月の條に「癸酉、近江國得魚、形似獼猴、異而献之故老皆云椒魚也」と云う。即ち、この魚のことである。「椒気」があり、故にこれを「椒魚」と謂う。『日本書紀』推古二十七年紀には「近江國言於蒲生河、有物其形如人」と云う。又、(続けて同年條には)「攝津國有漁父沈罟於堀江、有物入罟、其形如兒、非魚非人、不知所名」と云う。けだし、是の、鯢魚は二あり、一は「鰌」に似て四足、大きさは五、六寸に過ぎず、よく木によじのぼり(縁)、 啼かない。下條に載る「波之加美伊乎」が是である。他の一は、「鮎」に似て四足、長さは二、三尺に至り、声を発し、木にはよじのぼらない。則ち、『山海経』に載ったものが是であろう。陳(蔵器)氏の「上樹聲如小兒啼」というものは、二種を混同して説いたものであろう。 抄本文読み下し:人魚 兼名苑( ケンメイエン)は云う。人魚。一名鯪魚。{ 上音陵(リョウ)。 魚身人面のものなり。}/山海経注は云う。声は小兒の啼くが如し。故に之を名づく。 〔注〕 (10-12) 鯢魚:山椒魚:参照【本草綱目啓蒙】(平凡社東洋文庫、小野蘭山著「本草綱目啓蒙」3)「鯢魚」MANA字典鯢項に記す。 (10-13)日本紀略:古書注参照。 延暦十六年:桓武天皇(797年)「日本後紀」卷第六「桓武紀六」に同文載る。「掖庭」=同「掖廷」宮中の正殿わきににあって、皇妃・宮女が住んでいる御殿。後宮。 (10-14)文徳実録:古書注参照。 仁寿二年は西暦852年。「仁寿二年三月癸酉(みずのととり)、近江國得魚、形似獼猴、異而獻之、故老皆云、此椒魚也、昔時見有此物、」の記述は巻の四に載る。獼猴は「大きなサル」(【学研新漢和】)。獼は、新撰字鏡に「つくり:弥」をのせ「武移、左留’」(bu-iの反切、サル)とする。 (10-15)推古二十七年紀:日本書紀第二十二巻「二十七年夏四月己亥朔壬寅。近江国言。於蒲生河有物。其形如人。/秋七月。摂津国有漁父。沈罟於堀江。有物入罟。其形如児。非魚非人。不知所名。」「二十七年の夏四月(なつうづき)の己亥(つちのとのい)の朔(ついたち)壬(みづのえ)(の)寅(とら)(のひ)に、近江国言(まう)さく、蒲生河(がまふがは)に物有り、其の形(かたち)人(ひと)の如し、とまうす。」/「秋七月(あきふみづき)に、摂津国に漁夫(あま)有りて、罟(あみ)に入る。其の形児(わかご)の如し。魚(いを)にも非ず、名(なづ)けむところを知らず」(岩波文庫『日本書紀』四、132p、より) (10-16)鰌に似て:この場合の鰌を訓むとすれば「ウナギ」(ムナキ)と読むのが妥当だろう。箋注「鰻[麗]」の項に「證類本草は陶隠居を引用し、樹木によじのぼり(縁レ木)藤花を食す。形は[單]に似る。又、鰌がいて、これも似ているが体長が短い」とある。同項およびMANA字典「鰻」(11画)の「本草和名」等参照。 (10-17)同じくMANA字典「鰻」(11画)参照。 前掲注(10-6)、同注(10-11)、同注(10-12)参照。 |
|
|
■
「鯪魚」は則ち「鯪鯉」のことであり、今の人は、その甲をもつと謂う種類を「穿山甲」、一名「人魚」という。その顔かたち(面略)が人間に似ていることから「人魚」の名前がついているのであって、「人魚」と同じ名といえども、同じものではない。またはるか別の種類のものであるが、源君は、同一のものと混同し、誤ってしまったのだろう。源君が(ここに)挙げた「人魚」は、疑うらくは、これは海にすむ人魚のことであろう。つまり、鯪鯉にあらず、また、鯢魚でもない。『史記正義』は又、『異物志』を引いて「人魚似人形、長三尺餘、不堪食、皮利於鮫魚、項上有小穿、氣從中出、」という。「東海に出る者」とは蓋し是であろう。『異物志』は「以為秦始皇冢中為燭」者と続けるが、これは、おそらくその名を混同しているのであろう。下総本に、『山海経』以下十三字無く、伊勢廣本も同じである。} 抄本文読み下し:人魚 兼名苑( ケンメイエン)は云う。人魚。一名鯪魚。{ 上音陵(リョウ)。 魚身人面のものなり。}/山海経注は云う。声は小兒の啼くが如し。故に之を名づく。 〔注〕 (10-18)鯪:鯪鯉:前記注(10-1~5)参照。 (10-19)穿山甲:センザンコウ:「爾雅翼」「釈魚」:鯪鯉四足、似鼉而短小、状如獺、遍身鱗甲、居土穴中、蓋獸之類、非魚之屬也、特其鱗色若鯉、故謂之鯪鯉。又謂之鯪豸、野人又謂之穿山甲、以其尾能穿穴、故也能陸能水、出岸間鱗甲不動如死、令蟻入、蟻滿便閉甲入水開之、蟻皆浮出、因接而食之、故能治蟻瘻。 (古今圖書集成:故宮博物院典藏雍正四年銅字活版本テキストDB)(原典テキスト未見のため要確認):前記注(10-4)、注(10-5)を参照されたい。 (10-20)史記正義:異物志を引いて:注(10-9)および(10-9-その2)を見よ。 |
|
| ■〔11〕鮪 | |
|
食療經云、鮪、{音委、}一名黄頬魚、{之比、}
{『日本書紀』「武烈紀」の訓注に「鮪、此を慈寐(シビ)と云う。」を載せる。『万葉集』に同じ訓みを載せている。『毛詩』は「魚麗于羀、鱨鯊」(魚が[羀(あみ)に麗(かか)る、[嘗](ショウ)と鯊(サ)と)、『毛詩正義』は、陸[王幾]の『毛詩草木鳥獣蟲魚疏』(陸璣疏)を引用して、「[嘗]は一名黄頬魚」と云う。また、『山海経』「東山経」は、「番條の山に減水出づ。その中に[感]魚がいる。その魚、一名を黄頬」と云う。しかし、いままでに、「鮪」の別称を「黄頬」とする文章は聞いたことがない。『食療経』が何を(出典元として)根拠としているのかを知らず。」下総本には、(「之比」の前に)「和名」のニ字がついている。} 抄本文読み下し:鮪 食療經( ショクリョウケイ)は云う。鮪、{音委( イ)。}一名黄頰魚(コウキョウギョ)、{之比(シビ)、}/ 爾雅注(ジガチュウ)は云う、大は王鮪(オウイ)と為し、小は[*2]鮪(シュクイ)と為す。 〔注〕 (11-1) 食療経(ショクリョウケイ):古書注参照:【「和名抄引書」】 によれば、順抄本文中に、13箇所に載る。八巻龍魚部には、本項龍魚部「鮪」、龜貝部「蟹」「沙嚢」が載る。【「和名抄引書」】には、経籍志等を記さず、中国伝来書 に列するのみで、書誌不詳。 (11-2)武烈紀: 『日本書紀』巻第十六「武烈天皇」(岩波文庫版『日本書紀』第三冊,146p~):影媛(かげひめ)、曾(いむさき)に真鳥大臣(まとりのおほおみ)の男(こ)鮪(しび)に姧(をか)されぬ。{鮪、此(これ)をば玆寐(しび)と云ふ。}太子の期り……以下略。 (11-3)鮪:しび:1岩波文庫版 『日本書紀(三)』注六(147p):清寧記〔古事記、下つ巻清寧天皇〕には「平群臣之祖、名志毘臣」とあり、菟田首(うだのおびと)の女、大魚(おふを)を歌垣で顕宗天皇と争って殺されたとある。記紀いずれの形が本来のものか明らかでないが、津田左右吉は……中略……書紀編纂の際に顕宗天皇についての物語を武烈天皇の話にすり換えたのであろうとしている。2同内容について「古事記伝」第43(清寧)(吉川弘文館増補全集本第四)2119~2134p参照。○補注(1):「シビ」と訓むことについては、〔14〕鮫の注14-13(a)(b)において、大魚とサメのサンスクリット語言説に関連してシミ≒シビの訓みとのかかわりに触れているので参照されたい。 「大魚」を「オウオ」「オオウオ」と読めば「シビ」(マグロ)だが、「タイギョ」「ダイギョ」と読めば鯨(クジラ)となる。○補注(2):古代魚名を考えるとき、この「大魚」は、異種間の枠を越えて、いろいろな姿に変化しながら登場する重要なキーワードとなる。グループわけにトライしてみる要あり。 (11-3-2)魚名を冠した、或は含む古代史文献に登場する人名(しび、このしろ、ふな 、いるか等)については、ブログ版MANAしんぶんに整理して載せておいた。 (11-4)万葉集:1巻六(938)「山部宿禰赤人の作れる歌一首」藤井乃浦爾鮪釣等海人船散動……(ふじいのうらにしびつるとあまぶねさわぎ云々)(岩波文庫本上巻253p)、2巻十九(4218)「漁夫の火の光を見る歌一首」鮪衝等海人燭有射里火之……(しびつくと、あまのともせるいざりびの云々)(岩波文庫本280p) (11-5)そのほか鮪(6画)用例参照。 (11-6)毛詩:魚麗:詩経、小雅、魚麗(ぎょり)篇(TDB「毛詩注疏二十巻」722)。いわゆる「饗宴詩」として位置づけられる篇で、[嘗](ショウ:ギバチ:魚種の解釈は加納喜光氏「漢字の博物誌」による)、鯊(サ:カマツカ)、[方](ホウ:トガリヒラウオ)、[匽](エン:ドジョウ)、鯉(リ:コイ)などが登場する。 原文テキスト:[嘗](14画)。 (11-7)正義引陸璣疏云、[嘗]一名黄頬魚:TDB「毛詩注疏二十巻」孔頴達疏(「毛詩正義」)[嘗’]揚者魚有二名、釈魚無文、陸璣疏云、[嘗’]一名黄頬魚是也、似燕頭 、角身、形厚而長大、頬骨正黄、魚之大而有力解飛者、徐州人謂之揚黄頬通語也。鯊[它]釈魚文、郭璞曰、今吹沙也。陸璣注云、魚狭而小常張口吹沙故曰吹沙。此寡婦笱(かふこう:魚所留也=簗:ヤナ:固定式網漁具)而得[嘗’]鯊之大魚是衆’多也。……以下略。 (11-8)東山經云: 『山海経』「東山經」云:【山海経箋疏】(郭璞伝/郝懿行箋疏。還読樓校刊本)(WLDB)古書注参照:山海経第四東山經(2-29~30):又南三百里、曰 、番條之山、無草木、多沙。減水出焉{音同減損之減。 懿行案〔略〕}、北流注于海、其中多[感]魚{一名黄頬、音感。 懿行案。[感]一名[乇]。説文云、[乇]哆口魚也。廣雅云、[氐][亢][唐]、[乇]也。玉篇云、[乇]黄頰魚、郭氏注、上林賦云、[乇][感]也。一名黄頰、與此注合、又謂之[嘗]、小雅魚麗篇,毛伝云、[嘗]楊也。陸璣疏云、今黄頰魚也。似燕頭、魚身、形厚而長大、頬骨正黄、魚之大而有力、解飛者、徐州人謂之楊、黄頰通語也。今、江東呼黄鱨魚、亦名黄頰魚、尾微黄、大者長尺七八寸許。} (11-8-その2)(A)黄頬魚是也。似燕頭、角身、形厚而長大、頬骨正黄。(B)今黄頰魚也。似燕頭、魚身、形厚而長大、頬骨正黄。……「角身」(角ばった姿)、「魚身」(魚の姿)。今手元に、陸璣「毛詩草木鳥獣蟲魚疏」なく、要確認。○参考:和刻本「陸氏草木鳥獣蟲魚疏図解」(淵在寛述)(TLDB-鴎外文庫)(読み下す)魚麗于羀鱨鯊:「[嘗’]一名揚、今ノ黄頬魚、燕頭ニ似テ、魚身、形厚クシテ長ク、骨正ニ黄ナリ、魚ノ之大ニシテ力ラ有テ飛スルコトヲ解スル者ナリ、徐州ノ人、之ヲ揚ト謂フ、黄頬ハ通語ナリ。今マ、江東黄[甞]魚ト呼ブ、亦タ黄頰魚ト名ク、尾微ク〔カスカニ〕黄ナリ、大ナル者長サ尺七八寸許、[沙]ハ吹沙ナリ、…以下略」……参考:「一名揚」は「楊」とかくテキストあり。遥(ヨウ)に通じ、「解飛者」と書いていることから、「鰩」をも想起させる。 (11-9)この節は、「鮪」に「黄頬」の名をかぶせた源君の出典元を探そうとして、見つからなかったという件である。「本草和名」には載せていない「鮪」と同音のイ「[夷]」に「黄頬」を与えていることと関係アリやナシや。この点から発し、鮪と[亶]と「シュク」とのかかわりから考証を進めるのが次の節である。 |
|
|
爾雅注云、大為ニ王鮪一、小為ニ[*2]鮪一、
{『爾雅』「釈魚」郭璞注は、二つの「為」字を、「者名」の二字に作る。此の引用(「爾雅注云」)は蓋し(『爾雅』の)「旧注」によっている。今本の郭璞『爾雅注疏』は[*4]に作る。 陸徳明『爾雅釈文』は「叔」〔[*3]〕に作り、「字林」は[*4]に作る、と云う。是は、陸徳明が見た『爾雅』「郭璞注」もまた[*4]に作ってはいなかった、ということであろう。『呂氏春秋注』は、「鮪魚似鯉而大」と云い、『礼記正義』は、「爾雅郭璞注」を引用し、「似[亶]而小、建平人呼[各]子、一本云、王鮪似[亶]、口在頷下、音義、似[亶]、長鼻、體無鱗甲」と云う。『毛詩正義』は「陸璣疏」を引用して、「鮪魚形似[亶]而靑黑、頭小而尖、似[夷]兜鍪、口亦在頷下、其甲可以摩薑、大者不過七八尺、益州人謂之[亶]鮪、肉色白、味不如[亶]也」と云う。鮪は未詳だが、「口在頷下、其甲可摩薑、肉色白」(の特徴)に拠れば、是は則ち鮫魚の類であろう。「之比」(シビ)に非ず。「鮪」を訓じて「之比」とするのは、允(あ)たっていない。「之比」(シビ)は「万具呂」(マグロ)の仲間(属)で、嶧山君( 錦小路嶧山)は、『大倉州志』に載る「金槍魚」が「之比」に充(あ)たる、と云う。那波本は、[*2]を「叔」に作る。『干禄字書』は、「*2叔上俗下正」と云う。} 抄本文読み下し:鮪 食療經は云う。鮪、{音委(イ)。}一名黄頰魚(コウキョウギョ)、{之比(シビ)、}/ 爾雅注(ジガチュウ)は云う、大は王鮪(オウイ)と為し、小は[*2]鮪(シュクイ)と為す。 〔注〕 (11-10)爾雅注:古書注参照。爾雅郭璞注より以前の「旧注」によっている。 (11-11)釈魚郭注:爾雅注疏巻十「釈魚第十六」(テキスト:TDB「爾雅注疏十一巻」):[各][*4]鮪【註】鮪[亶]属也、大者名王鮪、小者名[*4]鮪、今宜 都郡自京門以上江中通出[覃][亶]之魚有一魚状似[亶]而小建平人呼[各]子即此魚也{[各]音洛[*4]音叔鮪音偉【疏】郭義具注云陸璣云、鮪魚形似[亶]而青黒、頭小而尖、似鉄兜鍪口、亦在頷下、其甲可以摩薑、大者不過七八尺、益州人謂、之[亶]鮪、大者為王鮪小者為[*4]鮪、一名[各]、肉色白、味不如[亶]也、今東萊遼東人謂、之尉魚、或謂、之仲明、仲明者楽浪尉也、溺死海中化為此魚、又曰、河南鞏県東北厓ニ山腹有穴、旧説云、此穴與江湖通鮪従此穴而来北入河西上龍門入漆沮、故張衡賦云、王鮪岬居山穴為岬謂此穴也、月令季春薦鮪於寝廟天官漁人春薦王鮪是也、} (11-12)釈文又作叔:唐の陸徳明撰(音釈)「爾雅三巻」「爾雅釈文」。 『経典釈文』古書注参照。後日確認の上加注。 (11-13)字林:晋の呂忱撰。主な字書の成立関係は小生作成「魚名考参考年表」参照されたい。 (11-14) 呂氏春秋注:『呂氏春秋』高誘注:おそらく「本味篇」:和之美者、陽樸之薑、招搖之桂、越駱之菌、鱣鮪之醢、大夏之鹽…以下略の注。原典テキスト手元になく未確認のため後日加注する。 (11-15)礼記正義:テキストTDB「十三経注疏」(汲古閣刊)「礼記注疏六十三巻」:「天子始乘舟、薦鮪于寢廟」○正義曰。案爾雅釋魚云、[各][*4]、郭景純〔郭璞〕云、似[亶]而小、建平人呼[各]子、一本云、王鮪似[亶]、口在頷下。音義云、大者為王鮪小者為[*4]、鮪似[亶]長鼻、體無鱗甲。(画像D:546)。鄭玄・注、陸徳明・音義。孔頴達・疏(正義)。山海経郭璞注にほぼ同じ記述あり(「鮪(6画)」参照。 (11-15)毛詩正義:TDB「毛詩注疏二十巻」孔頴達疏(「毛詩正義」)第三巻之ニ碩人篇(273~279:278):「河水洋洋、北流活活、施罛濊濊、[亶]鮪發發、葭菼@@、庶姜孽孽、庶士有朅。」【箋】略。【疏】{〈伝〉罛魚罟、至送女者○正義曰。 前略…陸璣云、[亶]鮪出江海、三月中従河下頭来上、[亶]身形似龍、鋭頭、口在頷下、背上腹下皆有甲、縦廣四五尺、今於盟津東石磧上釣取之、大者千餘斤、可蒸為[確(石→月)]、又可為鮓、魚子可為醤、鮪、魚形似[亶]而青黒、頭小而尖、似鐡兜鍪、口亦在頷下、其甲可以摩薑、大者不過七八尺、益州人謂之[亶]鮪、大者為王鮪、小者為[尗]鮪、一名[各]、肉色白、味不如[亶]也。……以下略。} (11-16)建平人:三国呉の一郡、現在の四川省巫山県一帯。 (11-17)嶧山君: 錦小路嶧山:丹波頼理のこと。 (11-18)大倉州志: 国会図書館蔵書「諸州府志」(特1-2181)に「大倉州志物産」あり。未見。「金槍魚」 :「大倉州志」を出典に含む福井春水編『掌中名物撰』(天保4・1833年刊)に「マグロ 金槍魚(清俗)」と載る。 「キンソウギョ」と読むのだろうが、中国において、マグロを指す漢字として使われるようになったのは明代以降と思われるが不詳。 (11-19)干禄字書:「古書名注」参照。 |
|
| ■〔12〕鰹魚 | |
|
唐韵云、鰹、{音堅、漢語抄云、加豆乎、式文用二堅魚二字一。}
{堅魚は、『延喜式』四時祭、齊宮寮、齊院司、大嘗祭、中務省、陰陽寮、主計寮、織部司、大膳職、大炊寮、主殿寮、内膳司、造酒司、主水司、京職、主膳監等の式に見える。『新撰字鏡』に、[甞]、魴、[惟]、[比/土]、[竟]を載せ、皆、「加豆乎」(カツオ)の訓みを与えている。疑うらくは、(『新撰字鏡』の加豆乎に訓ませた五字のうち)[比/土]は 、鰹の譌(カ)字であろう。 抄本文読み下し:鰹魚 唐韵は云う。鰹、{音堅( ケン)。漢語抄は云う。加豆乎(カツヲ)。式文は、堅魚二字を用う。} /大[同]なり。大は鰹を曰い、小は[兌]を曰う。{音奪(ダツ)。野王案ずるに、[同]の音は同(ドウ)にして、[彖/虫]魚なり。[彖/虫]魚は、下文に見ゆ。今、案ずるに、堅魚となすべきは、この義、いまだ詳ならず。} 〔注〕 (12-1) 唐韵:古書名注「唐韻」(とういん)を見よ。 (12-2)漢語抄:古書名注「揚氏漢語抄」(ようしかんごしょう)を見よ。 (12-3)式文:延喜式:古書注参考: 「国史大系」1卷第1~5、神祇:四時祭上:二月祭(10-4):鰒。堅魚各五両。…中略…烏賊。煮堅魚各二両。…中略…鰒。堅魚。二斤。…以下略。2巻第22~23、民部省:(592-2)伊豆国:堅魚煎一…中略…壱岐島/三斤。堅魚九斤。{西海道諸国、十一斤十両。} 3巻第24、主計寮上:(598-4)凡諸国輸調。…中略…(599-6)乾鮹九斤十三両。乾螺十斤十両。堅魚九斤。{西海道諸国、十一斤十両。…中略…}煮堅魚六斤七両。熬海鼠八斤十両。/凡中男一人輸作物。…中略…(600-4)堅魚一斤八両三分。{西海道諸国二斤。}4同:(603-1)志摩国調。雑鰒。堅魚。熬海鼠。雑…中略…庸。輸鮑。堅魚。鯛楚割。5同:(605-5)駿河国調。煮堅魚二千一百卅斤十三両。堅魚二千四百十二斤。庸。…中略…中男作物。…中略…堅魚煎汁。堅魚。 6以下堅魚類を収める国のみ記す。伊豆国、相摸国、安房国、紀伊国、阿波国、土佐国、豊後国、日向国、……以下略。 箋注記載引用例詳細は[鰹](11画)にのせる。「堅魚」(カツヲ)、「乾堅魚」(ホシカツヲ)、「煮堅魚」(ニカツヲ)、「堅魚煎」「堅魚煎汁」(いずれもカツオノイロリ)が載り、渋沢敬三:式内魚名:『祭魚洞襍考』(1954年岡書院。その後、「渋沢敬三著作集」第1巻1992年平凡社刊、「日本民俗文化体系3、渋沢敬三」宮本常一編著、昭和53年、講談社に載る。)に、カツオと訓み載せる。 (12-3-その2) 国立奈良文化財研究所「木簡画像データベース」を利用すると、「堅魚」を検索すると25件がヒットする。「鰹」のデータはゼロである。 (12-4)新撰字鏡:古書注参照。[鰹](11画)参照。 前掲注(6-6)に示したとおり見たのは、「享和本」(群書類従本)である。鰹字には、「加豆乎」の訓みはなく、また上記画像には載せていない「魴」は、「魴[魚+旁]同。方音。赤尾魚。不奈。又堅魚。」とこれも「加豆乎」の訓みはない。 (12-5)譌:「カ」と音で読み、 「ナマリ」、「ナマ」ると訓む。鰹を正字として、草行書のような略体字を介して、異体字が生れる過程を考えると、筆書きにより書写された文字を、写本あるいは刻字する際に、楷書体化された表記がされると、読者は本字とは別の字体として認知してしまうことによって、異体化していくと考えられる。 「譌(訛)」字は、このようにして「俗字」化していくことによって生れた字体を指すものと考えられる。 説文研究をベースにした、同音によって字義を同じくする諧聲字と区別して、「俗字」としての「訛字」を位置づけているということであろう。[鰹](11画)も参照されたい。 |
|
|
大[同]也、大曰レ鰹、小曰レ[兌]、{音奪、野王案[同]音同、[彖/虫]魚也、[彖/虫]魚見二下文一、今案可レ為二堅魚一之義未レ詳、}
{下総本には、標目「魚」字はなく、恐らくは是(ゼ)とすべきではないであろう。『廣韻』は、大[同]とし、[同]の一字に作る。」。『爾雅』は、「鰹の大なるものが[同]、小なるものは[兌]」と云う。『唐韻』は之に依っているのであろう。『玉篇』の[蠡]は、大[同]のことである。『廣韻』には、[同]の上に大字がなく、恐らくは脱字であろうか。」 『説文』には、鰹、[兌]の字は載っていない。『玉篇』は、「[同]は、鱧魚なり。[蠡]は[同]なり。」と云う。『説文』は、「[同]、魚名。一に[蠡]を曰うなり。」と云い、続けて、「[蠡]、[同]なり。」と云う。顧氏『玉篇』は、蓋し、之れ(『説文の記述』)によって、「蠡」に「魚」を従え、「[蠡]」を作ったのであろう。 而して、『本草』白字は、「蠡魚、一名[同]魚」と云う。故に、源君は、魚字を従えない「蠡」を引用したのだろう。然り、恐らくは、顧(野王)氏の舊い用例ではなく、[蠡]は即ち「玄鯉魚」のことであって、下文で本條が述べる加豆乎(カツオ)の字に宛てることはできない。 抄本文読み下し:鰹魚 唐韵は云う。鰹、{音堅( ケン)。漢語抄は云う。加豆乎(カツヲ)。式文は、堅魚二字を用う。} /大[同]なり。大は鰹を曰い、小は[兌]を曰う。{音奪(ダツ)。野王案ずるに、[同]の音は同(ドウ)にして、[彖/虫]魚なり。[彖/虫]魚は、下文に見ゆ。今、案ずるに、堅魚となすべきは、この義、いまだ詳ならず。} 〔注〕 (12-6) 廣韻:TDB(大廣益会玉篇三十巻、廣韻五巻)下平聲巻第二:先第一(72):一○先{蘇前切、又、蘇薦切。}…○堅{古賢切。十七}鰹{[同]大曰鰹、小曰[兌]、[兌]音奪。} (12-7) 大[同]也:顧野王撰「玉篇」(大廣益会玉篇)(TDB同前):鰹{古田切。大[同]也。} (12-8)爾雅:TDB(爾雅注疏十一巻巻第十釈魚第十六):鰹大[同]小者[兌]【註】今青州呼小[麗]為[兌]{鰹音堅、[同]音同、[兌]音奪。}【疏】此即上云鱧也、其大者名鰹、小者名[兌]、故注云、今青州呼小[麗]為[兌]、[麗]與鱧音義同。 (12-9)説文 :「鰹」「[兌]」:「説文解字」に載らない意味とは何か:つまり、爾雅には載って(注12-8参照)いるが、説文には載らず。 (12-10)玉篇[蠡]:玉篇(TDB):[同]{直壟切。鱧魚也。又直久切。}[蠡]{力啓切。[同]也。}鱧{同上} 。 (12-11)本草白字:WBT「 寛永16(1639)年京都刊本「重刊証類本草(重修政和経史証類備用本草)」序例、明・成化4(1468)年版翻刻本」 より。:「開宝重定本草{開宝七年〔974〕詔ニテ新定本草ノ釈スル所ノ薬類或ハ允アタワザルコト有ルヲ、又、劉翰〔りゅうかん〕、馬志〔まし〕等に命テ重詳定ス。頗ル増損有リ。仍テ翰林学士・李眆、知制誥・王祐、扈蒙等ニ命テ重テ此ヲ看詳ス。神農諸説ハ白字ヲ以テ、之ヲ別テ、 名医ノ伝スル所ハ、即チ墨字ヲ以テ并ス。目録供二十一巻。}」(序列第43丁表)。これ以後「神農本草経」の365薬を白字にし、その他の増補された「名医別録」などの条文(365薬)を墨で記した併記式により増補・加注が重ねられていった(真柳誠「中国本草と日本の受容」)。 (12-12)「神農本草経」江戸・嘉永七年、森立之校正本によるテキスト(東亜医学協会公開「中国医学古典テキスト」):蠡魚 一名鮦魚。味甘寒。生池澤。治濕痺面目浮腫。下大水。 (12-12-その2)【證類本草】(政和本草:WDB)巻第二十巻蟲魚部(上品) 蠡{音禮}魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢{音盤}白一名 鮦{音銅}魚生九江池澤取無時{陶隠居云今皆作鱧字、舊言是公蠣蛇所變、然亦有相生者、至難死。…以下略 (12-13)本草和名:蠡魚{陶景注云今作鱧字}一名調魚{揚玄操音重}一名鮪{大者也古今注}和名波牟。〔元簡頭注〕按、蠡魚、本草一名[同]魚、[同]音重、如是、調乃[同]之訛、又按、古今注鯉之大者曰[亶]、[亶]之大者曰鮪、乃知一名鮪大者也、古今注九字、当是在前鯉條。〔森立之書き込み〕後要検討。 |
|
|
■
加豆乎(カツオ)は、是れ、加多宇乎(カタウオ)を省略して呼んだ名であり、加多(カタ)とは即ち、頑愚の意味である。『本朝月令』に、『高橋氏文』を引いて、「磐鹿六獦命 (イワカムツカリノミコト)、舳(トモ)を顧(カエリミ)すれば〔魚(ウヲ)〕多く追い来(ク)、即ち磐鹿六獦命、角弭(ツヌハズ)の弓(ユミ)をもって、遊(ウカ)べる魚の中に当てしかば、即ち弭(ハズ)に著(ツ)きて出(イデ)て、忽(タチマ)ち数隻(アマタ)を獲(エ)し、仍号(ナヅケ)て頑魚(カタウヲ)と曰う。此(コ)を今諺(イマノコトバ)で堅魚(カツヲ)と曰う。今、角(ツヌ)をもって鉤柄(ハリ)を作り堅魚(カツヲ)を釣る、此は之を由とするなり、」を載せる。今の漁人は、魚を釣るに、その群れ集まるを見て、餌を取り、その集まってきた海上に投げ散(い)れると、魚は争って餌に食いつき、このときをみて、鹿の角で作った鉤の付いたしかけを投げ入れ、魚を獲るという。『高橋氏文』がいうように、加豆乎(カツオ)は、頑魚であることがよく知れるのである。 抄本文読み下し:鰹魚 唐韵は云う。鰹、{音堅( ケン)。漢語抄は云う。加豆乎(カツヲ)。式文は、堅魚二字を用う。} /大[同]なり。大は鰹を曰い、小は[兌]を曰う。{音奪(ダツ)。野王案ずるに、[同]の音は同(ドウ)にして、[彖/虫]魚なり。[彖/虫]魚は、下文に見ゆ。今、案ずるに、堅魚となすべきは、この義、いまだ詳ならず。} 〔注〕 (12-14)「本朝月令」所引「高橋氏文」:引用部分を 『伴信友全集』第三に載る伴信友『高橋氏文校注』の訓み下しに基づき訳すと「磐鹿六獦命(いわかむつかりのみこと)、…中略…、還る時、舳( トモ)を顧りみすれば、魚がたくさん追って来ました。すぐに磐鹿六獦命は、角弭(つのはず)の弓をもって、遊(うか)べる魚たちの中に、弭(はず)を著 (つ)き出すと、たちまち数隻(あまた)の魚が獲れました。仍ってこの魚を頑魚(かたうお)と号(な)づけました。この魚獲りの諺が、今の堅魚 (かつお)の名前に伝わったのです。今は、角で鉤と柄をつくり、堅魚を釣ることの、これが由来となっています。」となる。伴信友は「角弭之弓(ツヌハズノユミ)」 を注して、「弭(ハズ)に角を入(ハメ)たる弓なり{古の弓は、楢槻梓などの木弓なり、}和名抄に角弓、爾雅注云、弭今之角弓也、都能由美、とあるも、この角弭弓に当たる訓なるべし。 」と言う。関連箇所の原文テキストは[鰹](11画)に載せた。 (12-15)今以レ角作二鉤柄一釣二堅魚一、此之由也、:「角弭弓」をどのように漁具として使ったのかは、この文章からは具体的にはよくわからない。ハズにはめたツノの部分を擬餌針にみたてて、魚群の中に入れると、魚がかかる、という「漁具の仕掛け」という読み方をして、考を進めた伴信友は、それでもイメージがわかないために、「此注文いと意得がたく、前に安房の國人に尋問ふに、其國わたりの海人の鰹釣るさまを見聞」きしたのだという。以下が、その答えであり、擬餌針をつかった古代鰹漁のようすが描かれているので長くなるが引用する。 (12-16)「牛角の先のかたを、魚の口に合(カナ)ふべく削作りて餌代(エノシロ)とし、其旁に鉄鉤(クロガネノツリバリ)を結付(ユヒツケ)て、其牛角の本の方に小孔(チヒサキアナ)を穿(エリ)て、釣繩を貫(トホ)しかため、さて本方(モトベ)七八寸囲(マハリ)なる大竹を、八九尺ばかりに切て釣棹として、釣るならひなりと談れり。以レ角作ニ鉤柄一、といへるに合ひてきこゆ、{此注文秘抄に釣ニ堅魚一の三字を脱し、作を爲と書り。また今字を脱し、柄字を槁橋橘など書る本あるは悉 く訛なり、また之字無き本もあり、此はいづれにてもあるべし、}又いはく、近世或は其餌代の角を[侯](フグノ)皮にて包み、又は鳥の[木+離][木+徒](フグケ)の黒きを少しく角に纏(マツヒ)着などすれば、よく釣食ふものなりといへり。なほ海人が心々に、とかくこしらへてものするなるべし。かくて艇(ヲブネ) 〔テブネか?〕に乗りて海原をうかがひ、鰹の集れる處に到りて、船を乗列(ナ)めて、鉤の角を投入るれば、群寄りて競ひ食ふを、大聲を揚ていかめしくいきほひて、時のまに あまた釣上るなり、あまりに多く集れる時、たゞ船をしるべに群り競ひ寄りて、船中にも跳入り、また往来(ユキヽ)の他船(アダシフネ)をも慕ひ追来(オヒク)ばかりなる事も、まれ \/にありと聞けりと語れり、後に上總伊豆相摸の國人の語れるも、とり\"/ながら大むね同じ。/注本朝食鑑、凡漁人釣レ鰹以ニ犢角及鯨牙一、……〔以下略 〕といへり、既に己が聞たるとおほかた同じ趣ながら、はやくむかし人の記しおけるがおむかしくて注(か)き添へつ、/此時の古事に、いとよく合ひてきこゆるにあはせて考ふるに、上に以ニ角弭之弓一當ニ游魚之中一、即着レ弭而出忽獲ニ數隻一、といへる其弓弭は、牛角にてぞ製りたりけむ、其を游べる堅魚の中に擬ひたりければ、やがて其角に喫着て、水を出たるを捕れる由にきこえたり、」(前掲全 集第三、58~59p)関連箇所の原文テキストは[鰹](11画)に載せた。 |
|
|
■
然り、堅魚は、仮借(かしゃ)字である。本居氏は云う。是の魚は、古くは、皆、乾脯(ほじし)にするために之を用いる。賦役令、大神宮儀式帳、貞観儀式、及び延喜式の如くに、之を称するに、皆、斤をもってするのは、その堅さが他魚の脯に過(まさ)るものとして実証されていることがあるからである。故に名を堅魚と曰う。その説もまた通用したことによって、後の人は「鰹」という字を作った。けだし、皇国(わがくに)が製するところの二つの合わせ字〔魚+堅=鰹〕としてみたとき、鰹は、[同](の字義)と同じではない。源君は、鰹が二つの合わせ字として使われることを知らなかったために、『唐韻』の鰹字を引用し、鰹は即ち蠡魚のことであって、この間いわれてきた堅魚にはあらずとし、「未詳」という字を用いて、これに疑いをもたず、深く考察をすることがなかったのであろう。 抄本文読み下し:鰹魚 唐韵は云う。鰹、{音堅( ケン)。漢語抄は云う。加豆乎(カツヲ)。式文は、堅魚二字を用う。} /大[同]なり。大は鰹を曰い、小は[兌]を曰う。{音奪(ダツ)。野王案ずるに、[同]の音は同(ドウ)にして、[彖/虫]魚なり。[彖/虫]魚は、下文に見ゆ。今、案ずるに、堅魚となすべきは、この義、いまだ詳ならず。} 〔注〕 (12-17)仮借:かしゃ(假借): 漢字の造字法の一つで、許慎は『説文解字』序において、漢字を、1象形、2指事、3会意、4形成、5転注、6仮借に分類し、これを「六書」(りくしょ)と呼んだ。6番目の「仮借」は、「字の意味に関係なく、音だけ借りて言葉をうつすこと」(【学研新漢和大字典】)をいうが、和名と漢字の表記のかかわりについては、「説文解字」の解釈だけでは、説明ができず、もっと幅の広い解釈をしている。源順序文の箋注で、その注意点を挙げている。 (12-18)本居氏云:古事記伝:古書注参照:『古事記伝』(吉川弘文館増補全集第四、2032頁~)四十一之巻「朝倉宮上巻」(雄略天皇)「河内(かふち)に幸行(いでまし)き。爾(か)れ山の上に登りまして、国内(くに)望(みしせ)れば、堅魚(かつを)を上(あげ)て舎屋(や)を作れる家有り。天皇其の家を問はしめ云(のたまは)く。其の堅魚を上げて作れる舎屋は、誰(た)が家ぞととはしめたまひしかば、志幾(しき)の大県主が家なりと答白(まを)しき、……」【傳】○堅魚(カツヲ)は、屋ノ上なる堅魚木(カツヲギ)なり。まづ、堅魚と云魚は、 和名抄に唐韻ニ云ク鰹ハ大[同]也云々、漢語抄ニ云ク加豆乎式文ニ堅魚ノ二字ヲ用フとあれど、漢国の鰹は当らず。加都袁(カツオ)と云名は、加多宇袁(カタウヲ)の切(ツヾマ)りたるにて、即チ堅魚(カタウヲ)とは書るを、{古書には皆此字を書り、}後に此の二字を合せて、此方(こゝ)にて鰹字は作れるにこそあれ、{漢国の鰹字を当たるには非ず、漢国の鰹は鱧(ハム)にて、堅魚(カツヲ)とは大(イタ)く異なり}。さて古にいわゆる堅魚(カツヲ)と云るは此ノ魚の肉を長く裂(ワリ)て煎(ニ)て乾(ホシ)たるいはゆる鰹節(カツヲブシ)のことにて、貞観儀式延喜式などに多く見えたる皆是なり、{故に堅魚幾(いく)斤とあり、儀式に堅魚一連ともあり、又和名抄塩梅類に本朝式ニ云堅魚煎汁ハ加豆乎(カツヲ)以呂利(イロリ)とあるも、鰹節の煎汁なり、}さる故に堅魚(カタウヲ)とは云なり。もと生魚の名には非ず。{今ノ世とても、海ありて此生魚ある国々にてこそ生(ナマ)なるを加都袁(カツヲ)と云ヒ鰹節をば鰹節といへ、京などにては常に加都袁(カツヲ)と云は、鰹節のことなり、}さて、屋ノ上に置ク加都袁岐(カツヲギ)も其の形の鰹節に似たる故の名なり、……以下略 |
|
|
■
加豆乎(カツオ)は、西土にこれと同じものはなく、漢名に該当するものはないのであろう。『中山伝信録』という書に、「佳蘇魚、削二黒饅魚肉一、乾レ之為レ脯、長五六寸、梭形、出二久高一者良、食法、以二温水一洗一過、包二芭蕉葉中一、入レ火略煨、再洗浄、以利レ刀切レ之、三四切勿レ令レ断、第五六七始断、毎一片形如二蘭花一、漬以二清醤一更可レ口、」と云う。佳蘇魚は、即ち加豆乎であり、いわゆる堅魚節(かつおぶし)のことである。則ち琉球では、黒饅魚を加豆乎(かつお)にあてている。 下総本は、「大日」以下六字に分注をつけ、伊勢廣本には、是の六字がなく、及び二字が抜けており、皆(原本とは)非とするものであろう。 下総本の、「野王案[同]」の四字、及び「[彖/虫]魚也」の三字を、正文として記している。廣本も同じである。」 野王『玉篇』の「鰹は是れ[同]」とし「[同]は即ち蠡魚」を引いて、堅魚に非ず、とする証明をしたのであるから、則ち、野王案以下文を正文とすることは非とするべきであろう。下総本は、「案」の下に「云」字が有り、また、[彖/虫]字は蠡に作る。那波本も亦た蠡に作る。 抄本文読み下し:鰹魚 唐韵は云う。鰹、{音堅( ケン)。漢語抄は云う。加豆乎(カツヲ)。式文は、堅魚二字を用う。} /大[同]なり。大は鰹を曰い、小は[兌]を曰う。{音奪(ダツ)。野王案ずるに、[同]の音は同(ドウ)にして、[彖/虫]魚なり。[彖/虫]魚は、下文に見ゆ。今、案ずるに、堅魚となすべきは、この義、いまだ詳ならず。} 〔注〕 (12-18)西土:中国をさす。 (12-19) 中山伝信録:清の康煕58(1719)年に琉球尚敬王の冊封使として来島した徐葆光が記した使録が「中山伝信録」。初版は康煕60(1721)年刊。自序に、命を奉じ康煕58年6月に琉球に来て8ヵ月滞在したとあり、その間に、琉球の制度、礼儀、風俗などを見聞した記録を図入りで記した。「中山」(ちゅうざん)は、琉球国王名。全6巻。その六巻が「風俗・日用器具・市場・武器・月令・物産・語彙」の「物産」の鰹節の製法について載る。明和3(1766)年京都で出版された「重刻」版が、琉球大学付属図書館「伊波普猷文庫」DBに画像公開されている。 (12-20) 中山伝信録云:〔佳蘇魚〕削二黒饅魚肉一、乾レ之為レ脯、長五六寸、梭形、出二久高一者良、食法、以二温水一洗一過、包二芭蕉葉中一、入レ火略煨、再洗浄、以利レ刀切レ之、三四切 [皆]勿レ令レ断、第五六七始断、毎一片形如二蘭花一、漬以二清醤一更可レ口、:明和3年重刻板では、忽令の前に「皆」が入る。箋注版の脱字であろう。訳すと「〔佳蘇魚〕は、別名、黒饅魚。その身肉を削(割)り、之を乾し、乾し肉とする。その長さは五~六寸で、梭(ヒ:織り糸の横糸を通す具)のかたちをしている。「久高」(久高島)に出来たものが良い。食製法は、温水でひとくぐりさせて洗い、芭蕉の葉で包み、略煨 (うずみ火)にいれ(蒸し焼きにし)、もう一度洗浄する。その後、よく切れる刀で三ないし四切れに切り、さらに五~七に切り分け(第五六七始断の意味が良くわからない?)ると、その一片が蘭の花のようであり、清んだ醤(ひしお)に漬け、それを口に入れる。」となろう。ただし、「佳蘇魚」=カツオ(節)としてほぼ断定していることに検討を加える要あり。琉球の清との交易に関する文書には、同一書に「佳蘇魚二百個」とともに「鰹節一箱(二百塊)」(沖縄の歴史情報第5巻DB、翁姓家譜(伊舎堂家))や「佳蘇魚三十個」「鰹節一匣」(同、鄭氏家譜(古波蔵家)が併記されてあり、いわゆる現在のカビ付けと乾燥を繰り返してカチカチになった鰹節(ホンブシ)をのみ想起するのではなく、ナマリ節、生節などの製品をも考慮して再検討したほうがよいだろう。 (12-20-その2)堅魚と鰹、カタウオとカツオの字源考証において、前掲注12-14~12-16、伴信友『高橋氏文考注』において、「京にても諸國の中にても、鰹節を、たゞに鰹といふ處、彼此きこえたり、但し式に堅魚筥二十四合、腊(キタヒ)筥五十五合など見えたる堅魚は、上に云へるごとく、腊の堅きにて、鰹節のことなるべく、腊はきたひのよわき品をいへるなるべし、また堅魚脯(カツヲノホジシ)とあるは、そのきたひのまだしきをいへるにて、今俗になまりといひ、又なまり節(ブシ)ともいふ、これにて其はきたひに對へてなまりといへるなるべし、又式に煎堅魚(ニカツヲ)若干斤と見えたるは、脯のまだしきなるべし、又堅魚煎汁(カツヲイロリ)若干斤とあるは、鮮堅魚(ナマカツヲ)の膏油(アブラ)を煎取(ニトリ)たるを云、今も海人の其を貯置て、醤油(ヒシヲ)に和(アハ)せて物を煮るとぞ、是なるべし、さて又式に堅魚ならぬ魚類に、鯖(サバ)、鰒(アハビ)、烏賊(イカ)、螺(サヾエ)、蛸(タコ)などをも若干斤と書るも、他物の例によるに乾物(ヒモノ)なるべきを、然書ても用足(コトタ)りて通えたりしなるべし、さて件の竪魚のくさ\"/の造りざまは、今さだかに知べき由なけれど、せめて試にいへるなり、」と補注しており、正当なる指摘である。 |
|
| ■〔13〕[乞]魚 | |
|
玉篇云、[乞]、{居迄反漢語抄云、古都乎、式文用二乞魚二字一、}
{乞魚皮の字は、齊宮寮、内膳司、主膳監等の式に見える。備後鞆浦に「許都宇乎」(コツウオ)あり。是について、小野蘭山は、「許都宇(コツウ)のことであり、色は黒と白(色皂白)で、口は頷(あご)の下についていて、長さは、小さいものは四五寸、大きなものは二丈余りになる。尾は燕尾のごとし。是れは、『寧波府志』に載る燕尾鯊に当るものであろう。」と云う。錦小路嶧山君は、「燕尾鯊は俗に左賀菩宇(サガボウ)と呼ぶものである。」と曰う。 抄本文読み下し:[乞]魚 玉篇は云う。[乞]、{居迄反。漢語抄は云う。 古都乎(コツヲ)。式文は、 乞魚二字を用う。} /魚名なり。 〔注〕 (13-1)玉篇:TDB「大廣益会玉篇三十巻(張氏重刊宋本玉篇)」:[乞]{居乞切。断魚也。} (13-2)漢語抄:参考古書注。 (13-3)式文:「国史大系」:1乞魚皮:延喜式第五巻:斎宮:月料:乞魚皮十五斤。/同第三十二巻内膳司:乞魚皮廿斤十三両。/同第四十巻主水司:乞魚皮十五斤。2許都魚皮:同第二十四巻主計寮上:凡中男一人輸出物…中略…許都魚皮…中略…雑魚腊各二斤、…中略…、備前国…中略…中男作物、…中略…許都魚皮、…中略…備中国…中略…中男作物、…中略…許都魚皮、…中略…備後国、…中略…中男作物、…中略… (13-4)小野蘭山曰「許都宇云々」:『本草綱目啓蒙』(平凡社東洋文庫、小野蘭山著「本草綱目啓蒙」3)254頁訳文「燕尾鯊{寧波府志}は、コツウオ{備後鞆}」以下。同書、巻之四十、鱗之四、無鱗魚「鮫魚」項首題(250頁)に「サメ シャカボウ〔一名〕海鯊魚{通雅} 潮鯉{広東新語} 皮〔一名〕[台]魚皮{千金方}」。 (13-5)寧波府志:ねいはふし:古書注参照:燕尾鯊(あえて読めば「エンビサ」「エンビザメ」):【寧波府志】(張時徹・纂修。周希哲・訂正。嘉靖39[1560]序)(WLDB):第十二巻「物産(鱗之属)」鯊魚{皮上有沙、故名有、白蒲鯊、黄頭鯊、白眼鯊、白蕩鯊、青頬鯊、班鯊、牛皮鯊、狗鯊、鹿文鯊、[夷]鯊、[歮]鯊、燕尾鯊、虎鯊、犂到鯊、香鯊、熨斗鯊、丫髻鯊、剣鯊、刺鯊、鋸鯊、其類甚多} (13-6)色皂白:皂=[白/七][白/十](音ソウ)で「黒い」色。皂白(そうはく)は「黒と白」(【学研新漢和大字典】) (13-7)錦小路嶧山:ニシキコウジエキザン。 医師、本草家。錦小路(丹波)頼理(よりただ)の号である。『本草薬名備考和訓鈔』(文化4・1807)刊。 「嶧山君曰」として、多くの引用をしている。人名注参照。 (13-8)左賀菩宇(サガボウ):『物類称呼』(岩波文庫版)巻之二(49~50ページ):鮫魚 さめ○播州にて○のそといふ。越前にて○つの字と云。その故は、此魚捕(とら)へて磯(いそ)へ上れば假名(かな)の“つ”の字の形に似たりとて、越前の方言につの字となづくと也。大和にては○ふかと云。さめと[亶]魚(ふか)とは大イに同しくしてすこしく異(こと )也。ふかの類多し。或は白ぶか、うばぶか、かせぶか、鰐(わに)ぶか、もだま、さゞいわり等有、皆さめの類なり。四国及九州に、“さめ”の称なし。すべて“ふか”と呼び、又江戸にて一種○ぼうざめと云有。下野国宇都宮(うつのみや)辺にては○さがぼうとよぶもの也。江戸にて云○ほしざめを、西海にて○のうそうと云。江戸にて○しゆもくざめと云を、西国にて○念仏坊といふ。是土佐の国にて云○かせぶかなり、又土佐にて一種○なでぶ〔ふ〕かといふ有。船端(ふなばた)に人立時は、必尾をもてなて落すと也。 |
|
|
魚名也、
{乞魚は「主計寮式」に見え、或は、「許都魚」に作る。乞魚は「許都魚」であり、仮借字である。源君は、もって、玉篇の[乞]字となすとしているが、恐らく、こじつけ(牽強)であろう。} 〔注〕 (13-9)主計寮式:前掲注(13-3)に載せる。 (13-10)前掲注13-1、13-2参照。 (13-11)1中国における鮫・鯊・鱶・鯗及び鮝の字形及び字義の検証が要検討。2サメ・フカの生物としての呼称と乾し魚及び皮など加工製品の呼称の整理をする必要があろう。「のうさば」について。3[乞]の字体再検討。玉篇の「断魚」とは何か。「乞」の字体と、「兌」の字体との比較検討→(a)ハモ(鱧)、カツオ(鰹)、[同]魚など大魚につながる字体の検証、(b)タチウオ:[斉]⇔エツ・ダツ・ハモなど「太刀」(タチ)形魚類の呼称の検証、……を課題としたい。 |
|
| ■〔14〕鮫 | |
|
陸詞切韻云、鮫{音交、佐米、}
{下総本には、「和名」二字あり。/『本草和名』、『新撰字鏡』も同じ訓みを与えている。又、『新撰字鏡』に載る、[台]、鰹、[因]についても、皆同じ訓みを与えている。} 抄本文読み下し:鮫 陸詞切韻は云う。鮫、{音は交。 佐米。} /魚皮に文有り。刀剣を飾るべきものなり。/兼名苑は云う。一名は[氐][弥/魚]。{低迷二は音なり。}/本草は云う。一名は[昔]魚。{上は倉各の反なり。}/拾遺は云う。一名は鯊魚。{上の音は沙なり。字も亦[少]に作る。} 〔注〕 (14-1) 陸詞切韻:りくしせついん:古書注参照:陸法言撰「切韻」 。 (14-2)本草和名:古書注参照:「本草和名(寛政刊・古典全集本)」 (右画像):鮫魚{仁諝音交}一名[昔]魚皮{仁諝音、倉各反、装刀靶者也}一名[亙’][弥/魚]{位迷二音}一名[壊(土→魚)]雷一名青目一名黄頭{已上四名出兼名苑}一名鯊魚一名鰒甲{出拾遺}和名佐女。 (14-3)新撰字鏡:古書注参照: 既に見てきたように「享和本」ないし「群書類従本」によって箋注している。:【新撰字鏡(享和本)】(掲載順)1[台][追]{同。[勑]丈○○○反。壽也。老也。佐女。}2鮫{今作蛟。古希反。有文可飾刀劔。佐女。}3鰹{古年反。平。大[同]。魚名。佐女。}4[囙]{左女}……「佐女」という字において『本草和名』と同じ訓みである。「囙」=「因」として箋注文にのせたのだろう。 (14-3-その2)参考:【新撰字鏡(天治本)】(掲載順)1[台][追]{同字。[勑?]丈反。壽也。老也。■〔佐〕女}3鮫{今作蛟、古又有}3鰹{古年反。平。大[同]。則反伊加。魚名。}「鰹」には「サメ」の音を与えていない。また、「[因]」なし。「享和本」は「魚へん+旁り:囙(=イン)」に「左女」の訓みを与えている。「囙」=「因」として、享和本に載った理由を、【新撰字鏡(天治本)】の復刻として「古典索引叢書3」(全國書房昭和19年発行)編纂者である澤潟久孝(おもだかひさたか)氏による小学篇:[番]{加世佐波}[力]{佐比目左地魚女}[恵]{左波}[地]{波江。佐女。}に対する〔頭注〕に、「(一)加世佐波○地―治・魚囙―[魚へん+囙]」○[魚ヘン+地]―[魚へん+也]・女―波」を与えている。 (14-4)右画像の赤線と青線で印をつけた注文のある「[力]」字に注目した、澤潟博士は、割注として1行目右上から下によみ、2行目左上から下に読む、普通の読み方をするかぎりでは「佐女」の訓みは無く、箋注にも佐女と訓む字に含ませていないのだが、「佐女」(左女)と読む、読み方を見つけた。つまり、「佐比目左地魚女」→「佐比/目/左/地/魚/女」→「佐比地」「目」→「囙」→「魚囙」→[囙](左女)の組み合わせが、可能になるというのである。この〔頭注〕は、享和本との対比の中で、つけているので、享和本の編者(写本者)が、天治本の写本について、別系統の写本を見たか、その知識を持っていた可能性を示唆していると見ることができよう。それは、【類聚名義抄(観智院本)】(鮫(6画)同項参照 )の、「サメ」及び「佐女(左女)」と訓む字形整理からも推量することができそうである。 |
|
|
魚皮有文、可以飾刀劔者也、
{『説文』は、「鮫海魚、皮可飾刀」と云う。『玉篇』は、「鮫、[昔]属、皮有文」と云う。陸詞(『切韻』)は蓋し、之を本にしている。『廣韻』は、また「鮫、魚名、皮有文可飾刀」と云う。『山海経』「中山経」は、「漳水流れ出て、その中に、鮫魚が多くいる」と云う。『山海経』注に、「鮫は鮒魚の類であり、皮には珠の文様があり、堅い。尾の長さは三、四尺あり、人を螫す毒はもっていない。皮は、材料の角(カド)を磨き細工したりする(皮のヤスリ)のに使われたり、刀剣を飾るために使われる。今、臨海郡に之を産する。」と云う。} 抄本文読み下し:鮫 陸詞切韻は云う。鮫、{音は交。 佐米。} /魚皮に文有り。刀剣を飾るべきものなり。/兼名苑は云う。一名は[氐][弥/魚]。{低迷二は音なり。}/本草は云う。一名は[昔]魚。{上は倉各の反なり。}/拾遺は云う。一名は鯊魚。{上の音は沙なり。字も亦[少]に作る。} 〔注〕 (14-5)説文:【説文】(「説文解字注十五巻」TDB):鮫:海魚也。皮可飾刀。{【段注】今所謂沙魚、所謂沙魚皮也。許有[少]字、云从沙省、蓋即此魚、陳蔵器曰、沙魚状皃非一、皆皮上有沙、堪揩木、如木賊、蘇頌曰、其皮可飾刀靶、按其皮可磨錯、故通謂之[昔]魚、音措各切、有鐇[昔]、有橫骨在鼻前、如斤斧形者也、有出入[昔]、子朝出求食、暮還入母腹中者也、淮南子鮫革犀兕為甲冑、中山経有鮫魚、郭云即此魚、中庸黿鼉鮫龍、本又作蛟。}从魚交声。{古肴切、二部、}……『本草綱目 』「鮫魚」及び左思『呉都賦』「[印]龜[番][昔]」も参照のこと。 (14-6)玉篇: 【玉篇】(大廣益会玉篇三十巻・張氏重刊宋本玉篇)(TDB):[少]{所加切、鮫魚}/鮫{古爻切、[昔]属、皮有文}/[昔]{倉合切、又音錯} (14-7)廣韻:鮫: 【廣韻】(五巻・張氏重刊宋本廣韻TDB):下平声巻第二:肴第五(82)鮫{魚名、皮有文可飾刀} (14-8) 山海経中山経:山海経注:鮫魚:1箋注文:鮫、鮒魚、類也、皮有二珠文一而堅、尾長三四尺、未レ有毒二螫人一、皮可下飾二刀劔口一、錯中治材角上、今臨海郡亦有レ之「人を螫す毒はもっていない」:原文:未有毒螫人:「未(いまだ……せず)」を「末(マツ:スエ)」とすると、意味が逆転し、尾の先の部分に毒があり、人を螫す、となる。このほうが自然な読みの流れであろう。 【標註訂正康煕字典】渡辺温篇が「末」であり、「末」のほうが正しいようだ。たしかに、鮫魚を、河にすむ魚と云う解釈から、サメのような魚ではないとすると、「未」のほうが正しいと云うことになる。しかし、鮫皮については、抄「調度部、弓劔具、鮫皮」に本草音義を引用して「鮫魚皮装刀[木+覇者也]」があるので、本項は明らかに「サメ」について源君は描いていることが推測されることから、「末」を「未」に読みまちがえたのか もしれない。2郝懿行【山海経箋疏】(WLDB):第五「中山経」:中次八經荊山之首、曰景山…中略…多文魚…中略…東北百里、曰荊山、…中略…其中多黄金、多鮫魚{鮫、鮒魚類也。皮有珠文而堅、尾長三四尺、末有毒螫人、皮可飾刀劒口、錯治材角、今臨海郡亦有之。音交。:懿行案。鮫魚即今沙魚。郭注、鮒字譌、李善注、南都賦引此注云。鮫[昔]屬是也、又云。皮有斑文而堅斑、疑珠字之譌。初学記三十巻引劉欣期広州記曰鮫魚出合浦、長三尺、背上有甲珠文堅彊、可以飾刀口、又可以鑪物、與郭注合、三尺疑當為三丈字之譌。又引此經荊山譌作燕山、郭注、尾有毒譌、作尾青毒、張揖注、子虚賦云、蛟條魚身而蛇、尾皮有珠也。蛟即鮫字古通用。}。其獸多閭麋{似鹿而大也。:懿行案…以下略}…以下略。 |
|
|
兼名苑云、一名[氐][弥/魚]、{低迷二音、}
{『本草和名』は、同書文を引く。「低迷二音」もまた、『本草和名』と同じ。『廣雅』に「河[氐][乇]也。[氐]音齒之」という。『玉篇』に「[氐]尺尸切、鮪[氐]也」と云う。『廣韻』に「[氐]處脂切、魚名」と云う。音義は、(このように)それぞれに異っている。恐らくは、同じ字ではないのであろう。[弥/魚]字は、『玉篇』、『廣韻』、『集韻』には皆載っていない。「鮫、一名[氐][弥/魚]」は出典が不明なのである。 『玄應音義』は、「[土氐]彌、律中低彌皆作迷字、應言帝彌祇羅、 此云大身魚也」と云う。則ち、[土氐]彌は魚名であり、梵語の対訳であったが、後の人が魚編にして「[氐][弥/魚]」に作ったものであることが知れよう。『龍龕手鑑』は、「[互]の音は低」「[彌]は俗字にして音は彌」とする。まさに、これが、その(『玄應音義』に云う)「大魚」のことであり、「鮫」の一名にあたるのである。『兼名苑』はまた、「摩竭」を「鯨」とする。その意図するところは同じであるので略す。下総本[氐]は[互]に作り、伊勢廣本も同じ。『龍龕手鑑』もまた、[互]に作る。『干禄字書』に「互氐上通下正、諸従氐者竝準此」と云う。」} 抄本文読み下し:鮫 陸詞切韻は云う。鮫、{音は交。 佐米。} /魚皮に文有り。刀剣を飾るべきものなり。/兼名苑は云う。一名は[氐][弥/魚]。{低迷二は音なり。}/本草は云う。一名は[昔]魚。{上は倉各の反なり。}/拾遺は云う。一名は鯊魚。{上の音は沙なり。字も亦[少]に作る。} 〔注〕 (14-9)兼名苑:古書注参照。 (14-10)本草和名:注14-2参照。【本草和名】は、「位迷」と書く。同書元簡頭注及び森父子書き込みにも指摘されているように、「位」は「低」である。 (14-11)[氐]の音は、廣雅(s-i)、玉篇(s-i)、廣韻(s-i)字義は異なるが、音はいずれもS音(シ)。 (14-12)玄應音義:玄應一切經音義:古書注参照。「低彌皆作迷字」→「低迷」 (14-13) (a)〔第二卷大般涅槃經卷三十六〕「善男子。…中略…。迦葉菩薩白佛言。…中略…。言常沒者。所謂大魚受大惡業身重處深。…中略…。如是大魚。…中略…。謂坻彌魚。身處淺水樂見光明故出已住。」……「サメ」の語源が仏教経典に含まれる「[土+氏]彌」(大身魚)の梵語対訳語彙からきているという、「箋注」は、これまでの魚名語源考証では、触れられてこなかったことであり、注目すべき整理である。このセクションから、[氐][弥/魚]の訓みは、もともとの字音である「シメイ」「シミ(シビ)」が、あったことと、「低」の音によって示された「テイメイ」あるいは「テイミ」の訓みが通用して来たことがわかる。次のセクションに示された[昔]の訓みである「シャク」「サク」「セキ」及び、「沙」及び「少」を作り字とする「サ」「ショウ」の訓みに共通する「S」の音とが、関係し絡まりあいながらサメの呼称が変化していくことの特徴を見出すことが出来る。 (14-13)(b)補注:大魚が「シミ(シビ)」であるとすると、「大魚」である〔11〕鮪の古名「志毘」「志比」のシビの訓みにも通じるということになるのかもしれない。これは、要検討としよう。 |
|
|
本草云、一名[昔]魚、{上倉各反、}
{『証類本草』「蟲魚部」「下品」に「鮫魚皮、即ち刀靶を装する、[昔]魚皮なり」と云う。『本草和名』に「鮫魚一名[昔]魚皮、此云一名」と云う。則ち、源君は蓋し、『本草和名』に従い之を引用したのである。『説文』に、「[昔]」字なし。蓋し、是の字(鮫)と魚皮(の字義)との交錯によって「[昔]魚」と名したものであろう。後に、魚を从え、[昔]の字に作ったのであろう。} 抄本文読み下し:鮫 陸詞切韻は云う。鮫、{音は交。 佐米。} /魚皮に文有り。刀剣を飾るべきものなり。/兼名苑は云う。一名は[氐][弥/魚]。{低迷二は音なり。}/本草は云う。一名は[昔]魚。{上は倉各の反なり。}/拾遺は云う。一名は鯊魚。{上の音は沙なり。字も亦[少]に作る。} 〔注〕 (14-14)すでに以下の「箋注」がされていることを前提に読むべし。「箋注・巻五、調度部第十四、弓劔具七十四」鮫皮:仁諝本草音義云、鮫魚皮、{鮫音交、佐女乃加波、}{昌平本下総本有和名二字、}装刀欛者也、{本草和名云、鮫魚一名[昔]魚皮、鮫魚下云仁諝音交、[昔]魚皮下云、仁諝音倉各反、装刀靶者也、此所引即是、而欛作靶、為異、按説文、把、握也、転注凡物所握持之處謂之把、禮記曲禮、左手承弣、注云、弣、把中、釈文云、把、音覇、手執之處也、是也、後劔柄以皮装、故従革作靶、遂與轡革之靶混無別也、其欛字亦説文所無、後俗諧聲字、則欛靶並把字之俗、非別字也、説文云、鮫、海魚、皮、可飾刀、」鮫又見龍魚類、} (14-15)証類本草:古書注参照。 (14-16)前記注14-14中の「仁諝本草音義」 (じんしょほんぞうおんぎ)は輯佚書。「仁諝」撰「新修本草音義」(「新美篇・輯佚資料」)。 (14-17)「証類本草」蟲魚部「鮫魚皮」の條は、「下品」ではなく「中品」に載る。要確認。 (14-18)「本草和名」前記〔注〕14-2参照。 |
|
|
拾遺云、一名鯊魚、{上音沙、字亦作レ[少]、}
{『證類本草』を引いて「沙魚」を作る。『本草和名』もこれと同じように引用したものであろう。『説文』に「[少]、魚名、出楽浪潘國、从魚沙省声」と云う。『玉篇』は「[少]、鮫魚、」と云う。「六書故」に「鯊、海中所産、以其皮如沙而得名」と云う。則ち、[少]は、沙、あるいはまた鯊に作るのである。また、『毛詩』(小雅)に「魚麗于羀、[嘗]鯊」と云う。『毛詩正義』に、陸璣疏を引用して「魚狹而小、常張口吹沙、故曰吹沙」と云う。『爾雅』に「鯊[它]」と云う。郭璞「注」は「今吹沙小魚」と云う。『廣韻』に「鯊魚名、今吹沙小魚」と云う。[少]は、上に記したとおりであり、その名の由来(所以)は、異なっている。} 抄本文読み下し:鮫 陸詞切韻は云う。鮫、{音は交。 佐米。} / 魚皮に文有り。刀剣を飾るべきものなり。/兼名苑は云う。一名は[氐][弥/魚]。{低迷二は音なり。}/本草は云う。一名は[昔]魚。{上は倉各の反なり。}/拾遺は云う。一名は鯊魚。{上の音は沙なり。字も亦[少]に作る。} 〔注〕 このセクションは、鮫は鯊(魚)とも書き、鮫の皮製品を指すことばとして使われたが、もうひとつ、「沙」(サ、スナ)を介して「今吹沙小魚」を指す字として使われるようになったという、整理をしている。 「大魚」の義を持つ「鮫」が、「小魚」であり名もつかぬ雑魚(ザコ)(ハゼやカジカやギギなど異種だが有る特徴を備えた魚たちのグループの総称)を指す字「鯊」と もかかわりを持って変じたことを示唆したものとして読むこともできるだろう。 (14-19)拾遺云:「本草拾遺」陳蔵器云う。 (14-20)六書:漢字の形・音・意味の成り立ちを説明する六つの原理。象形・指事・会意・形声(諧聲)・転注・仮借(許慎説文叙)。説文段注のもととなった段玉裁「六書音韻表」参照。 (14-21)六書故:「正字通」(【標註訂正康煕字典】渡辺温篇より読下し)青き目赤き頬。背の上に鬣(タチヒレ)有り、腹の下に翅有り。味肥美。六書故に曰。海中に産する(所)。其の皮、沙の如きを以って名を得る。哆(は)る口。鱗無し。胎生。…以下略。 (14-22)又毛詩云、魚麗云々:前掲〔注〕11-5、11-6、11-7参照。 (補)〔9〕鮝の項(フカ)を見よ。 |
|
| ■〔15〕[宣]魚 | |
|
弁色立成云、[宣]{音宣、波良可、今案所出未詳、式文用腹赤二字、}
{下総本は、[宣]の下に「魚」字あり。廣本も同じ。下総本注首に「上」字有り。『新撰字鏡』に同じ訓みを載せる。「腹赤」は延喜宮内省、内膳司等の式に見える。 抄本文読み下し:[宣]魚 弁色立成は云う。[宣]、{音は宣。 波良可(ハラカ)。今案ずるに所出は詳ならず。式文は腹赤二字を用う。} 〔注〕 (15-1)[宣]は、中国の古字書、史料に類似形も見出せない、本邦で作られた文字 (国字)であろう。「腹赤の奏」(はらかのそう)あるいは「腹赤の御贄の奏」(はらかのみにえのそう)。「アイ嚢抄」(アイ:[土+蓋])正保3年板 (文安2年成立)(35丁表)、巻四の二十五「奏(ソウ)スル氷様(ヒノタメシ)腹赤(ハラカ)の御贄(ミニエノ)事」 に次のように載る。 「是ハ宮内省ノ奏スル事也。氷様ト申ハ、只氷リ也。去年納メタル所々ノ氷様ヲ、今日節会ノ次ニ奏聞スル也。是ヲ凍スル池ヲハ、氷池(ヒイケ)、ト曰也。延喜式ニモ、氷池ノ祭リヲ註シ侍リ。喩ヘハ氷ノ多ク生ハ聖代ノ験シ、氷ノ居サルハ、凶年ノ相也。仍テ氷ノ居サルハ、凶年ノ相也。仍テ氷ノ御祈トテ、大法ナト行ルヽ也。様(タメ)シトハ、寸法程ラヒノ分際アル故也。仁徳天皇ノ御于ニ額田大中彦(ヌカタオオナカヒコノ)皇子ノ初テ、氷ヲ奉ラセ給シ也。其後ヨリ、季冬毎ニ国々、是ヲ接(オサメ)テ、氷室ヲ置レシナリ。 次ニ、腹赤ノ魚トテ、筑紫ヨリ奉也。昔ハ節会ナントニ軈テ供シケルニヤ。腹赤ノ食様トテ、食サシタルヲ皆取リ渡シテ、食給ヒケルトナン。景行天皇ノ御時、肥後ノ国毛宇土(ケウト)ノ郡長浜ニテ、此ノ魚ヲ釣リ奉ヲ、毎年ノ節会ニ供スヘキ由、定メ置レケル也。」 (15-2)弁色立成:古書注参照。 (15-3)新撰字鏡:1【新撰字鏡(天治本)】小学篇、[宣]波良加。2【新撰字鏡(享和本)】(群書類従本も同)[宣]波良加。 (15-4)『古事類苑』(動物部十六魚)1300~1304頁にわたり用例21を揚げる。しかし、なぜ「宣」を旁として「はらか」と読ませるのかは不詳である。[宣]についての考証は、(1)伴信友「比古婆衣」 「巻のニ」に載る「腹赤」、(2)明治に至り天皇臨幸に際して熊本県知事より依頼を受けて執筆された、内柴御風「腹赤御贄考」の二つの著作が「通説となっている鱒は後人が赤魚から転用してこじつけたもので、ニベサニの語のもととなる「ニベ」を献上したことが元となっている」ニベ説をとる。 訳注子も、 この2つの論が正しいと支持したい。 |
|
| ■〔16〕鰩 | |
|
陸詞切韵云、鰩{音遙、度比乎、}
{『新撰字鏡』に、「[要]、止比乎」が載る。} 魚之鳥翼能飛也、 {『廣韻』は、「鰩 文鰩魚、鳥翼能飛、白首赤喙、常に西海に遊び、夜には北海に向かい飛ぶ。」と云う。『山海経』「西山経」三の巻は、「泰器の山、観水が流れ、西に流れて于流沙に注ぐ。ここにたくさんの文鰩魚がいて、その姿(状)は鯉魚のよう。魚の体には翼がつき、蒼い文様があって、白首に赤い喙を持つ。常に西海に遊び、夜になると飛ぶ。」と云う。陸氏は蓋(おそら)く、これを本にしているのであろう。また、『證類本草』は、「陳蔵器(餘)」を引用し、「文鰩は、南海に出で、大きさは長さが一尺ばかり、翅を持ち、尾と斉(ひと)しいくらいのおおきさだ。一名は、飛魚。飛水に群れるほどいて、海人(漁師)たちは、この魚の現れる様子をうかがって、大風(アラシ)が起こることを予測する。『呉都賦』に〈文鰩は、夜飛び、網に觸(ふれ)る〉 とあるのは、この魚のことである。」と云う。『説文』には、鰩字なく、「常に西海に行き東海に遊ぶ」という、前掲引用文に依って(考慮するなら)、則ち、古くは、「遙」の字を用いたのであろう。} 抄本文読み下し:鰩 陸詞切韵は云う。鰩、{音は遙。 度比乎(トビヲ)。/魚の鳥翼をもって能く飛ばん。} 〔注〕 (16-1) 陸詞切韵:りくしせついん:(14-1)鮫項「陸詞切韻」参照。古書注「切韻」を見よ。 (16-2)1新撰字鏡(群書類従本)魚部七十一:[要]{止比乎}。2新撰字鏡(天治本)魚部第八十七:[瑶(王→魚)]{要遥反。平。有翼能飛}。/小学篇:[要]{止比宇}。 (16-3)廣韻:(TDB)下平聲巻第二(80):{相焦}宵第四[瑶(王→魚)]{文[瑶(王→魚)]魚鳥翼能飛白首赤喙常游西海夜飛向北海}。 (16-4)西山經云:山海経西次三經:山海経西山經第三の巻:又西百八十里、曰泰器之山。觀水出焉、西流注于流沙。是多文鰩魚(郭注1)、状如鯉魚、魚身而鳥翼、蒼文而白首、赤喙、常行西海、遊于東海、以夜飛。其音如鸞雞(郭注2)、其味酸甘、食之已狂、見則天下大穰(郭注3)。:(郭注1)音遙。(郭注2)鸞雞、鳥名、未詳也。或作欒。(郭注3)豐穰收熟也。韓子曰、穰歳之秋。 (16-5)陸氏:陸詞切韻云、つまり陸法言切韻「鰩」。 (16-6)證類本草:古書注参照。 【證類本草】(政和本草:WDB)巻第二十巻蟲魚部(8-56):文鰩魚{餘招反}無毒。婦人臨月帶之、令易産。亦可臨時焼為黑末、酒下一錢匕。出南海、大者長尺許、有翅與尾齊、一名飛魚、羣飛水上、海人候之、當有大風。呉都賦云。文鰩夜飛而觸網、是也。。 (16-7)呉都賦:古書注参照。 【文選】(嘉靖金臺汪諒校刊本:TLDB)巻第五:京都下:呉都賦(30丁裏):前略…結輕舟而競逐、迎潮水而振緡{密}。想萍實之復形、訪靈夔於鮫人。精衛銜石而遇繳{酌}、文鰩{遙}夜飛而觸綸。北山亡其翔翼、西海失其遊鱗。{略} (16-8)夜飛び 、網に觸(ふれ)る:前注のように、「文鰩夜飛而觸綸」とあ り、「觸レ綸」は「つりいとに触れる」 であり、諸本のテキストに「網」とするものはない。「網」は「綸」を正とする。 なお、「触」は「かかる」と読めなくもない。また、この文の前に載る「精衛銜石而遇繳」の「繳」は「弋繳」(ヨクシャク)で、「いぐるみ:鳥を射るために、矢に糸をつけたもの。繳は、絡ませるためのひも」。つまり、海上で鳥を射るための仕掛けに、飛んできた「文鰩」(トビウオ)が絡まってくる、そういうシチュエーションであることを考慮すべし。 (16-9)「説文」には、鰩字なく、:許慎「説文解字」に宋の徐ゲンが校訂を加えたものを「大徐本」とい う。徐鉉撰の際に許慎「説文」未収の親字を加えており、その字を「新附字」という。但し、段玉裁『説文解字注』(「段注」)には、この新附字は採用されていない。つまり、「鰩」は、新附字の一 であり、もともとの「説文」には鰩字はな かった。そして、鰩字が生れる前の、古い時代には、「遙」の字を用いて「飛ぶ魚」を表していた、と読むことでよいであろう。 (16-9-その2)【説文解字】(徐鉉校訂「大徐本」汲古閣本)(WLDB):鰩{文鰩。魚名。从魚[謠-言]聲。余招切。}〈新附〉 |
|
| ■〔17〕鯛 | |
|
崔禹食經云、鯛、{都條反、多比、}
{下総本は、「和名」二字あり。/『本草和名』『新撰字鏡』『万葉集』は、いずれも同じ訓みを与える。『新撰字鏡』は、「鱧」を、また、「太比」と訓む。 抄本文読み下し:鯛 崔禹食経は云う。鯛、{都條の反。多比(タヒ)。/味甘。冷。無毒。貌は[即’]に似て、紅鰭の者なり。} 〔注〕 (17-1)崔禹食經:古書注参照。 (17-2)都條反:テフ・チョウ :【廣韻】(五巻・張氏重刊宋本廣韻TDB)鯛:下平聲巻第二:三○蕭{蘇彫切}○貂{都聊切。二十二}鯛{魚名}○迢{徒聊切。二十二}條{略} (17-3)本草和名:古書名注参照。:鯛{音徒聊反}、又有尨魚{治体相似出崔禹}、和名多比。 (17-4)新撰字鏡:古書名注参照。:1天治本:巻九魚部第八十七 :鯛{都聊反。太比。}2享和本・群書類従本:魚部第七十一:鯛{都聊反。太比。}/鱧{礼音。太比。} (17-5)万葉集:岩波文庫版:1巻9(一七四〇)水江の浦島の子を詠める一首並に短歌/春の日の かすめる時に 住吉(すみのえ)の 岸に出でゐて 釣船(つりぶね)の とをらふ見れば 古(いにしえ)の 事ぞ思ほゆる 水江(みずのえ)の 浦島の兒が かつを釣り 鯛(たひ)釣りほこり 七日まで 家にも来(こ)ずて 海界(うなさか)を 過ぎてこぎ行くに 海若(わたつみ)の……/右の件の歌は、高橋連蟲麻呂の歌集の中に出でたり。2巻16(三八二九)長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)の歌八首より:酢、醤、蒜、鯛、水葱を詠める歌/醤酢(ひしほす)に蒜(ひる)搗(つ)き合(か)てて鯛(たひ)願ふ吾にな見えそ水葱(なぎ)の羮(あつもの)。 |
|
|
味甘冷無毒、貌似レ[即’]而紅鰭者也、
{『医心方』 を引くが、原典には、「無毒」の下になお若干字あり、「紅鰭」の下に「堅鱗」の二字あり、「者也」の字はない。」。『説文』の「鯛骨端脆也」は、この義にあらず。『玉篇』『廣韻』とも「魚名」とだけ云う。是れは、蓋し、崔氏がいうところと同じである。崔氏は、鯛の姿(状)について、「[即]に似て、紅の鱗をもつ、それが太比として疑うところはない。」と云う。西土において後世いうところの棘鬛が、即ち是であろう。『閩中海錯疏』は、「棘鬛は、[即]に似て、大きく、その鬛は、棘の如くで、紅紫、」という。さらに同書は、続けて、「「嶺表録異」では、名を、吉鬛とし、泉州では、之を、鬐鬛、又の名を、奇鬛と名づけている。」と記している。} 〔注〕 (17-6)医心方:古書注参照: 無毒の下になお若干字:【醫心方(安政版)】(叢書日本漢方の古典1「醫心方 食養篇」巻末影印)巻30: 鯛 崔禹云、味甘冷無毒、主逐水、消水腫、利小便、去痔虫、破積聚、欬逆上気、腸、主出敗瘡中虫、利筋骨。貌似鯽、而紅鰭、堅鱗。和名、多比。 (17-7)説文「鯛」:「説文解字注十五巻」TDB:古書注参照:骨耑脃也、从魚周声。{都僚切。如其義則当與鯁 、篆相属、篇韵皆曰、魚名何也}……「鯛骨端脆也」:「端=耑」「脆=脃」。骨の端が脆い。 (17-8)玉篇、広韻:大廣益会玉篇三十巻・廣韻五巻(TDB):1張氏重刊宋本玉篇:鯛{丁幺切、魚名}……幺(ヨウ・エウ)、つまりtcho-「テフ」「チョウ」。2張氏重刊宋本廣韻:巻2、下平聲第ニ{蘇凋}蕭第三: 三○蕭{蘇彫切。十六}…○貂{都聊切。二十二}鯛{魚名}。 (17-9)閩中海錯疏 :びんちゅうかいさくそ:古書注参照。 :巻上鱗部上:棘鬛、似[即]而大、其鬛如棘、色紅紫。嶺表録異、名吉鬛。泉州謂之鬐鬛、又名奇鬛。 (17-10)嶺表録異 :唐の劉恂撰。3巻。中国南方の風土産物を図で説明した書。「嶺表録」とも称される。 |
|
| ■〔18〕尨魚 | |
|
崔禹食經云、尨魚、{久路太比、}
{下総本には「和名」二字有り。『本草和名』の「尨魚」は「鯛」の條に有り。別の「和名」はない。} 與レ鯛相似而灰色、 {『本草和名』の鯛の條に、尨魚が載り、「治体相似、出崔禹」という。「鯛に似て灰色」というのは、今、関東にて「久路太比(クロタヒ)」と謂い、関西では「知沼(チヌ)」と謂う魚のことである。『弁色立成』の「海[即]魚」も「尨魚」に当てるが、この二つは、姿も似ておらず同じものではない。しかして、関西では一種は「久路太比(クロタヒ)」と呼び、「知沼(チヌ)」とを別にしている。源君があげた是(尨魚)は「久路太比(クロタヒ)」であろう。} 抄本文訓み下し文:厖魚(ボウギョ) 崔禹食経(サイウショクケイ)は云う。厖魚。{久路太比(クロダヒ)。}/鯛と相似して灰色なり。 〔注〕 (18-1) 崔禹食經:(17-1)注:古書注参照。 (18-2) 本草和名:前掲注(17-3)参照。 (18-3)「治体」:詠み方がよくわからない。 「治体」(ti-tai)の反切で、taiという意味か。また、音で訓み「チタイ」として、「根本」という意味から「根本から似ているもの」とでも読むのだろうか。 要検討。 (18-4) 灰色:「古事記伝」では「クロ」という訓みを与えている。次注参照。 (18-5) 【古事記伝】(第十七之巻・神代十五之巻「綿津見宮の段」:岩波文庫版(四)311~313頁)○赤海[即’]魚は、多比(タヒ)と訓べし。鯛なり。書記には、赤女(アカメ)とありて、赤女ハ鯛魚ノ名也と注あり。【但シ此ノ注は、後ノ人のしわざにもあらむか。】一書には、赤女或ハ云二赤鯛一トとあり。又一書には、赤女とありて、即赤鯛也と注せり。さて、仲哀ノ巻に、海[即]魚(タヒ)とあると、和名抄に、弁色立成云、海[即]魚ハ知沼(チヌ)、とあるとを合せて見れば、赤海[即]魚は、鯛(タヒ)なること決(ウツナ)し。【知沼(チヌ)は、鯛の色灰色(クロ)き物にて、黒鯛(クロダヒ)の類なり。和名抄に、知沼(チヌ)と久呂多比(クロダヒ)とは別なれど、遠からぬ物なり。さてつねの鯛は、知沼(チヌ)と形全く同くて、色赤き故に、赤海[即]と書るなり。橿を白檮と書るたぐひなり。又仲哀ノ巻なるは、色の赤き黒きを一ツにして、海[即]魚を鯛にあてたるものなり。凡て古書に、物の漢名を書ること、其人の心々にて、右の如く少しづつの違ヒあり。彼此(カレコレ)をよく考ヘ合せて、定むべし。よくせずはまぎれぬべきものぞ。】多比(タヒ)は、和抄には、崔禹錫食經云、鯛ハ味甘ク冷無レ毒。貌似レ(テ)[即’](フナニ)、而紅鰭ナル者ト也。和名多比(タヒ)と見え、字鏡にも、鯛ハ太比(タヒ)とあり。【師は、此(コヽ)の赤海[即]魚をも、書紀に依て、アカメ(ルビ○○○)と訓れたり。其(ソレ)もさることなれども、此記の例、若シあかめならむには、直(タヾ)に赤女と書クべきなり。さて又書紀の赤女を赤鯛也とあるに依て、或説に、鯛の中の一種、殊ニ色赤きなりとするは、わろし。後ノ世にこそさもあらめ、上代には、さばかり細(コマカ)に分て、名ヅくることはなかりしぞかし。赤鯛とあるも、即チよのつねの鯛にて、黒鯛の類もあるに対へて、赤ノ字は添ヘたるものなり。然るにかの仲哀ノ巻に、海[即]魚をタヒ(ルビ○○)と訓るにつきて。此(コヽ)の赤海[即]魚をも、アカダヒ(ルビ○○○○)と訓て、かの殊に赤き一種と心得るは、非なり。又アカチヌ(ルビ○○○○)と訓るのも、非なり。】さて、この多比(タヒ)の下に、那母(ナモ)てふ辞を読ミ添フべし。語の勢ヒ必ズ然るべし。 (18-6)弁色立成:古書注参照。 |
|
| ■〔19〕海[即’] | |
|
弁色立成云、海[即’]魚、{知沼、[即’]見二下文一}
{下総本には「魚」字がなく、「和名」二字あり。『日本書紀』「仲哀紀」は、「海[即’]魚」が載り、「多比(タヒ)」と訓む。その訓みは、(抄文でいう「チヌ」と書紀でいう「タヒ」とは)同じではないけれども、(「海[即’]魚」と)「魚」字がつく方を是(タヒ)とすることを証すべし。本書(抄本文)は、「弁色立成」を引用して、その例文には、「和名」字がついていない。(『倭名類聚抄』諸本のうち)「和名」字がついているものは、おそらくは、抄原本としては非ではないだろうか。廣本も、また「和名」字はつかない。『新撰字鏡』には、[卑]が載り、「知奴(チヌ)」と訓みを与えている。 『閩中海錯疏』に「烏魚似[即’]而大、尾鬣倶黒、力能跋扈」と載る。是に記すものを「知奴(チヌ)」に充てたい。} 抄本文読み下し: 海[即’](カイセキ) 弁色立成(ベンジキリュウジョウ)は云う。 海[即’]魚(カイセキギョ)。 {知沼(チヌ)。[即’](セキ)は、下文に見ゆ。} 〔注〕 (19-1)[即’]=鯽は、「セキ」あるいは「ソク」と訓む。この記述、箋注の読み下しは 短いがなかなか難しい。ようするに、和名抄の「海[即]」は、和名「チヌ」をさしている 。日本書紀は、同じ[即]という字を用いて、「海[即]魚」と書き、訓みのとおり「たひ」=鯛(神代紀の海幸山幸の段でいう「赤海[即]魚」と同じ)を意味する。これは、前項〔注〕18-5で引用した、本居宣長「古事記伝」の記述に示されているとおりである。同じ「海[即]」 (魚)という字でありながら、日本書紀の記述の魚と、「閩中海錯疏」で書いている、烏魚(ウギョ:カラス色をしたサカナの意:黒い色の尾背びれをもつ、チヌ:クロダイ )とは異なる。本項の「[即’]」は、閩中海錯疏のチヌのことである、というような文意となろう。 (19-2)弁色立成:古書名注参照。 (19-3)仲哀記:日本書紀仲哀紀:古書注参照:【日本書紀】(岩波文庫『日本書紀』坂本・家永・井上・大野校注):1原文(489p):日本書紀巻第八/足仲彦天皇 仲哀天皇/前略○夏六月辛巳朔庚寅、天皇泊于豊浦津。且皇后従角鹿發而行之、到淳’田門、食於船上。時海鯽魚、多聚船傍。皇后以酒灑鯽魚。々々〔鯽魚〕即酔而浮之。時海人多獲其魚而歓曰、聖王所賞之魚焉。故其處之魚。…以下略。2本文(126p)足仲彦天皇(たらしなかつひこのすめらみこと) 仲哀天皇(ちうあいてんわう)/…中略…夏六月(なつみなづき)の辛巳(かのとのみ)の朔(ついたち)庚寅(かのえのとら・のひ)に、天皇(すめらみこと)、豊浦津(とゆらのつ)に泊ります。且(また)、皇后(きさき)、角鹿(つぬが)より発ちて行(いで)まして、淳’田門(ぬたのみなと)に到りて、船上(みふね)に食(みをし)す。時に、海鯽魚(たひ)、多(さは)に船(みふね)の傍に聚(あつま)れり。皇后、酒(おほみき)を以て鯽魚(たひ)に灑(そそ)きたまふ。鯽魚、即ち酔ひて浮びぬ。時に、海人、多(さは)に其の魚(いを)を獲て歓びて曰はく、「聖王(ひじりのきみ)の所賞(たま)ふ魚なり。故(かれ)、其の処(ところ)の魚、六月(みなづき)に至りて、常に傾浮(あぎと)ふこと、酔へるが如し。其れ是の縁(ことのもと)なり。…以下略。 (19-4)新撰字鏡:古書注参照:1【新撰字鏡(享和本)】[卑1]{薄佳反。知奴。又、和尓。}/2【新撰字鏡(天治本)】[卑1][卑2]{二同薄佳反。知奴。又、和尓。} (19-5)閩中海錯疏:古書注参照:【閩中海錯疏】(国会図書館蔵本写本)烏魚似[即’]而大、尾鬣倶黒、力能拔扈。□似烏而短、身圓口小、目赤鱗黒、一名鯔、味與[時]相似、冬深脂膏滿腹至春漸瘦無味。 |
|
| ■〔20〕王餘魚 | |
|
朱厓記云、南海有二王餘魚一、{加良衣比、俗云加禮比、}
{下総本に「和名」二字あり。加良衣比(からえひ)は、深根輔仁『本草和名』によっている。「加良」(から)とは、美称を意味する。是の魚の形が「韶陽魚」に似て、味がとてもよい(最美)ことから名づけられた。今、俗に「加禮比」(カレイ)と呼ぶ。源君が編じた時代の俗称と同じである。} 抄本文読み下し:王餘魚(おうよぎょ) 朱厓記(しゅがいき)は云う。南海に王餘魚有り。{ 加良衣比(からえひ)。俗に加禮比(かれひ)と云う。} 〔注〕 (20-1) 輔仁:深根輔仁(ふかねのすけひと)が編じた「本草和名」:古書注参照:寛政刊・古典全集本・下巻:1[比]目{必勢反、貌以牛脾黒色、一目両方相合乃得行}一名[去]{廻於反}一名鰈{他臘反}一名[介]{何邁反}一名板魚{音板出兼名苑}/2王餘魚{郭璞云、王餘皆雖有二片其実一魚也、不比行者、名王餘也、比行者名比目也、捜神記云、昔越王為鱠、割魚而未切、堕半於海中、化魚、名曰王餘也、出七巻食經、}和名加良衣比。 (20-2) 加良(から)、美称:【言海】(370p中)始めて、日本に来たりしに起こり、転じて三韓をも呼べるなり。古へ、三韓渡来の物事に添えていへる語、珍とし美(ほ)むる意あり。 (20-3) 邵陽魚(エイ)に似て:平らたく薄い魚形をさして「似」とする。〔25〕[覃]及び〔42〕邵陽魚をみよ。 だが、「似邵陽魚」というフレーズが載る出典は不詳。ありそうで見つからない。 |
|
|
昔越王作レ鱠、不レ尽、餘レ半棄水、因以二半身為一レ魚、故名曰二王餘一也、
{『隋書』「珠厓伝」一巻は、偽燕の蓋泓撰になる。『太平御覧』は「朱崖傅」を引く。抄本文に引く「朱厓記」とは、是の書のことだろう。今はこの「傅」は亡佚し伝わらない。」。『漢書』「武帝紀」に「珠厓(シュガイ)、儋耳(タンジ)」が載る。注に、「二郡は、大海中崖岸の辺にあり、そこには、真珠が出る。故に珠厓と曰う。」と云う。則ち、「朱厓」は、「珠厓」に作る。『文選』「呉都賦」劉逵の注に「王余魚は、半身の姿をしている(其身半也)。俗に越王が魚の膾(なます:細い糸づくりのサシミ)にして食べたが、食べつくさないままに、半身を残し、その身を水中に棄てたと云う。その身が魚となったが、一面だけの姿をしていたため、その魚を〈王余魚〉というようになった」と云う。抄本文に引用された記述はその逸話によっている。『本草和名』は、「捜神記」を引き、また「昔、越王は膾をつくり、魚を半身に切ったが、切り残して海中に堕てた。それが魚と化し、名づけて〈王餘〉という。七巻食經に出ている。」と云う。今本の『捜神記』には載っていない。伊勢本は、「曰王餘」の下に「魚」字あり。那波本も同じである。 抄本文読み下し:王餘魚(おうよぎょ) 朱厓記(しゅがいき)は云う。南海に王餘魚有り。{ 加良衣比(からえひ)。俗に加禮比(かれひ)と云う。} /昔越王は、鱠(なます)を作 せしが、尽さず、半を餘し、水に棄つ、因 りて半身、魚となすをもって、名づけて王餘と曰うなり。 〔注〕 (20-4) 隋書珠崖傳一巻:「和名抄引書」:{△/御覧引目朱崖傳}朱崖記{王餘魚}[隋志]{地理}珠崖傳一巻{僞燕聘晉使蓋泓撰}……「僞」:対立する国家を、自らの 国を正として、それに対して見下した呼称とする場合に使う。 (20-5) 漢書武帝紀:班固撰。注は「顔師古(がんしこ)」:古書注参照:【漢書】順治13・1656年、汲古閣版(20冊)(WULDB):(第2冊)『前漢 書』「武帝紀」第六:孝武皇帝…中略…六年冬十月、發隴西、天水、安定騎士及中尉…中略…遂定越地[佀-ニンベン]、以為南海、蒼梧、鬱林、合浦、交阯、九真、日南、珠厓、儋耳郡。{應劭曰。二郡在大海中崖岸之邊。出真珠、故曰珠崖。儋耳者、種大耳。渠率自謂王者耳尤緩、下肩三寸。張晏曰。異物志、二郡在海中、東西千里、南北五百里。珠崖、言珠若崖矣。儋耳之云、鏤其頰皮、上連耳匡、分為數支、状似雞腸、累耳下垂。臣瓚曰。茂陵書珠崖郡治*都、去長安七千三百一十四里。儋耳去長安七千三百六十八里、領縣五。師古曰。儋音丁甘反、字本作瞻。[耳覃]音審。}定西南夷…以下略。 (20-6) 呉都賦劉逵注:古書注参照 :【文選】(嘉靖金臺汪諒校刊本:TLDB)巻第五:京都下/呉都賦:「陵鯉若獣、浮石若桴、雙則比目、片則王餘、……」に対する李善注:鯪鯉、有四足、…中略…王逸曰、……比目魚、東海所出、王餘魚、其 身半也、俗云、越王鱠魚未盡、因以残半棄水中為魚、遂無其一面、故曰、王餘也、朱崖海中有渚、東西五百里、南北千里、無水有泉…中略…王餘、泉客、皆見博物志……以下略。 (20-7) 本草和名引捜神記:注20-1の2参照。 (20-8) 今本捜神記に載らず:1太平御覧、巻九百三十八「比目魚」:捜神記曰、東海名餘腹者皆越王為膾、割而未切、墜半於水化為魚。/臨海水土記曰、両片特立合体倶行{比目魚也}。/嶺表録異曰、比目魚南人謂之、鞋屜魚、江淮為之拖沙魚。2捜神記テキスト(叡茶山房サイトより):巻十三(330話)江東名餘腹者、昔呉王闔閭江行、食膾有餘、因棄中流、悉化為魚、今魚中有名呉王膾餘者、長數寸、大者如筋、猶有膾形。……御覧引用原文(あるいは古本捜神記)では「越王云々」とあり、今本捜神記では、本草綱目も引用する「呉王(闔閭)云々」となっていることをさしているのだろうか。 後日再検討すべし。 (20-9) 七巻食經:古書注「食經」参照。 |
|
|
■
『爾雅』には、「東方に比目魚有り。比(並)ばざれば行かず。その名、之を鰈と謂う。」という。「郭璞注」は「その姿は牛の脾臓(脾)のようで、鱗は細かく、紫黒色をしている。一眼である。1片の身を2片相い合わすことによって前に泳ぐ(行)ことができる。今、水中にこの魚を産し、江東では又、王餘魚と呼んでいる」と云う。また、郭氏は、「比目魚贊」という文章を記しているが、そのなかで、「<比目>は、連なりあっている姿をして、もう一方の別の身を<王餘>と名づけている。2片あるといえども、その実、身はひとつの魚である。身をひとつに合せてもくっつきすぎず、身はふたつに離れているといっても離れすぎてはいない。これをもって、<比目>と<王餘>の二つの身で一つの体をなしている。」と書いている。 また「呉都賦」は、「双(雙)とは、一方(則)が〈比目〉で、もう一方(片則)が〈王餘〉」といっている。そのフレーズについて、劉逵は「比目魚は東海に出づるところでは、王餘魚といい、その身は半分の姿をしている。」と注を与えている。この賦の記述は、(前述したとおり)爾雅によって、「比目」を「雙」(並ぶ)といい、越王の事により「王餘」を片方の身とした。蓋し、諸魚の姿は両側の片方にひとつづつ目はついているものだ。この魚は、1片に二つの目が相並んでついている。ゆえに「比目」の名がついているのである。目のついていない半身のほうを、捨て去ってしまったような姿をしているので、またの名を「王餘」としている。実際は、「比目」「王餘」は、古今(同じものの)「異名」であって、「不レ比不レ行」という表現は、著者によるこじつけ話にすぎない。郭氏による「一眼両辺相会乃得レ行」の説は、根拠のないものであろう。劉逵は、注に「王餘が比目の片半分というのは非である」と書いている。 抄本文読み下し:王餘魚(おうよぎょ) 朱厓記(しゅがいき)は云う。南海に王餘魚有り。{ 加良衣比(からえひ)。俗に加禮比(かれひ)と云う。} /昔越王は、鱠(なます)を作 せしが、尽さず、半を餘し、水に棄つ、因 りて半身、魚となすをもって、名づけて王餘と曰うなり。 〔注〕 (20-10) 爾雅「東方有比目魚焉、不比不行、其名謂之鰈」: 古書注参照:爾雅注疏巻第六、釋地第九の冒頭「九府」に載る。九府は、各州(国)の産物を蔵する「八方」と、すべての美物が集まるところを一にくわえて九を数えたもの。その九府の冒頭に「東方云々」の句が載る。郭璞註として「状似牛脾鱗細紫黑色、一眼兩片相合乃得行、今水中所在有之、江東又呼為王餘魚{鰈、音蝶}」を載せる。 (20-11) 郭璞著「比目魚贊」:比目之鱗、別號王餘、雖有二片、其實一魚、協不能密、離不為疏、是以比目王餘為一物:「芸文類聚」第99巻に載る。 (20-12) 呉都賦劉逵注:前掲注20-6参照。 (20-12) こじつけ話:原文では「付会」。 (20-12) 劉逵による「非である」という注記は「呉都賦」には載っていない。別書の注とすればどこに載るのか未確認。要検討。 (20-13) 補注:前掲注20-11の「爾雅釋地」「九府」の「比目魚」(東方)は、「比翼鳥」(南方)及び「比肩獣」(西方)及び「比肩民」(北方:この中に「枳首蛇」:二つの頭を持つ蛇を五方目として描いている)を含めて、四種の「片」身動物(人)の一であり、この四動物が「四方中国之異気」として描かれていることに注意しておくことが必要である。というより、この「異気」を放つ「異形」の生物を、豊かな産物を生み、美物のあつまる国を描く「釋地」(いわば「地理編」)冒頭に登場させる爾雅編纂者の「狙い」が興味深いのである。片身だけでは意味を持たず、片身×2(あるいは雌雄)が一体となってことをなせることと、幸いや夫婦和合から国の繁栄のシンボルと置く思想がなかなかに面白い。 |
|
|
■
「爾雅翼」にいたっては、「王餘は長さ5、6寸、身は丸まっこく、筋がみえるように白く透き通っていて、無鱗であり、まるで鱠(なます)の魚とでもいえようか。ふたつの目は黒い点がついているようだ。〈博物志〉は、〈呉王の江行は鱠を食し、あまったものを、川の流れに棄てると、魚の姿に化した。呉王の鱠餘と名づけた。〉と云う。今では〈鱠残魚〉という名で呼ばれ、またの名を〈銀魚〉という。」と書いている。李時珍(「本草綱目」鱠残魚の項)は、これらが本になっている。つまり、(前記「捜神記」が書いた)「越王が鱠(糸づくりのサシミ)をつくって、半分を海中に棄てると、それらが魚に化した」という記述と、(「博物志云とする、呉王闔閭が揚子江を舟で行くとき、云々」の記述)が非常に似ていたこともあって、かえって、「王餘魚」と「鱠残魚」とが、その後、ごっちゃになって伝えられてしまったということなのだろう。} 抄本文読み下し:王餘魚(おうよぎょ) 朱厓記(しゅがいき)は云う。南海に王餘魚有り。{ 加良衣比(からえひ)。俗に加禮比(かれひ)と云う。} /昔越王は、鱠(なます)を作 せしが、尽さず、半を餘し、水に棄つ、因 りて半身、魚となすをもって、名づけて王餘と曰うなり。 〔注〕 (20-14) 爾雅翼:古書注参照:【爾雅翼】(古今圖書集成:故宮博物院典藏雍正四年銅字活版本テキストDB参照):王餘長五六寸、其圓如筋、潔白而無鱗、若已鱠之魚但目兩點黒耳。博物志曰呉王江行、食鱠、有餘、棄于中流、化為魚、名呉王鱠餘。高僧傳則云、寶誌對梁武帝食鱠、帝怪之、誌乃吐出小魚鱗尾、依然金陵尚有鱠殘魚。二説相似。然呉王之傳、則自古矣、此魚與比目不同、劉淵林解、呉都賦第見其稱雙、則比目片則王餘、遂云比目魚、東海所出、王餘魚其身半也。俗云、越王鱠魚、未盡、因以其半棄之遂無其一面故曰王餘則是以王餘為比目之半而郭氏解比目亦云、状如牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之、江東又呼為王餘魚、亦與劉説相似。予按二物今浙中皆有之、絶不類比目乃只一目生、近海處土人謂之鞵底魚、王餘状如前説、今猶呼鱠殘魚。又名銀魚。多暴為脯、又作顏、色可愛自是一種非比目之半也。 (20-15) 博物志:「呉王江行、食鱠有余、棄於川中流、化為魚、名呉王鱠餘、今猶呼鱠残魚、又名銀魚、」上注「爾雅翼」において引用したフレーズである。 (20-16) 李時珍:李時珍著「本草綱目」鱗部第四十四巻:鱠残魚:〈釈名〉王餘魚{綱目}、銀魚」{〈時珍曰〉按博物志云、呉王闔閭江行、食魚膾、棄其残余於水、化為此魚、故名、又作越王、及僧寳誌者益出傳会不足致弁。}……以下「集解」略。……この場合の魚膾は「銀魚」つまり『国訳本草綱目第十冊』同条で、木村重博士が註校訂している「支那ニハしらうを属ハ四種アリ、スベテ銀魚(インユー)と呼バル、…中略…日本のしらうをに似ル」(562頁)シラウオのナマス(鱠)をさす。前掲註20-7の捜神記の古本(比目=つまり鰈・カレイ)と今本(銀魚:つまり白魚・シラウオ)の用例記述の混乱をも想定しての上で本文を書いているのがわかる。文末で、李時珍自体が、「呉王闔閭」をあえて名前入りであげ、「越王」の引用をせずに「益出傳会不足致弁」と断じていることをも含めて、「読者もこのへんの事実経過をきちんとふまえて読んでほしいのだよ」という声が聞こえてきそうな箋注である。 (20-17) 「絶相似、還混」:非常に(絶)似ていたこともあって(相似)、かえって(還)、(「王餘魚」と「鱠残魚」とが、その後、)ごっちゃになって(混)(伝えられてしまった)。 |
|
 ■「竜・龍」の辞書 |
|
|
「竜・龍」(りゅう・りょう)
龍(竜) / 1大蛇に似て、四足、つの、長いひげのある想像上の動物。たつ。ア)〔仏〕インド神話で、蛇を神格化した人面蛇身の半神。大海や地底に住し、雲雨を自在に支配する力を持つとされる。仏教では古くから仏伝に現れ、また仏法守護の天竜八部衆の一つとされた。「竜神・竜宮」イ)中国で、神霊視される鱗虫の長。鳳(ほう)・鱗(りん)・亀(き)と共に四瑞の一つ。よく雲を起こし雨を呼ぶという。「竜虎・画龍点睛」ウ)ドラゴンのこと。2化石時代の、大形の爬虫類を表す語。「恐竜・首長竜」3すぐれた人物のたとえ。「臥竜(がりょう)・独眼竜」4天子に関する物事に冠する語。「竜顔」5将棋で飛車の成ったもの。「竜王」 龍神 / 神秘な力を持っているのでいう。川・海・湖などの水の神。また、雨をつかさどる神。竜王。竜1に同じ 天竜八部衆 / 仏法を守護するとされる8種の異類。天・竜・夜叉・乾だつ婆(けんだつば)・阿修羅・迦楼羅(かるら)緊那羅(きんなら)・摩ご羅迦(まごらが)のこと。もと古代インドの神々で鬼竜の類。八部。八部衆。竜神八部。 竜淵 / 竜の住むふち。 竜王 / 1(仏)竜族の王。仏法を守護するものとする。密教で雨を祈る本尊とする。水を治める神。湖や河のほとりにまつられる。竜神。八大竜王。2将棋で、飛車が成ったもの。成り飛車。 八大竜王 / 難陀(なんだ)竜王/跋難陀(ばつなんだ)竜王/娑迦羅(しゃから)竜王/和修吉(わしゅきつ)竜王/徳叉迦(とくしゃか)竜王/阿那婆達多(あなばだった)竜王/摩那斯(まなし)竜王/優鉢羅(うはつら)竜王の8竜王の総称。法華経の会座に列した語法の竜神。水の神、雨乞いの神ともされる。八大竜神。金かい集「時によりすぐれば民のなげきなり―雨やめたまへ」 難陀(なんだ) 梵語Nanda / 1釈尊の異母弟。釈尊に従って出家し、妻を慕って法服を捨てようとしたが、瑞に遇って阿羅漢果を得た。孫陀羅(すんだら)難陀。2釈尊の弟子の一。もと牧場者であったので、1と区別して、牧場難陀という。36世紀頃のインドの仏教僧で、唯識十大論師の一。4(梵語Nanda)波斯匿(はしのく)王が仏に万灯を供養した時、ただ一灯を捧げた貧女の名。5八大竜王の一。跋難陀と兄弟。 跋難陀(ばつなんだ)梵語Upananda / 1仏弟子の一。仏の涅槃(ねはん)を聞いて歓喜したという悪比丘(ひく)。また、一群で悪事をなして制戒の原因となったという六群比丘の一。2八大竜王の一。優跋難陀(うばなんだ)竜王。 娑迦羅(しゃから)竜王 梵語Sagara / 1八大竜王の一。法華経の会座に列したという護法の竜神。請雨法の本尊。和修吉(わしゅきつ)竜王/徳叉迦(とくしゃか)竜王/阿那婆達多(あなばだった)竜王/相摩那斯(まなし)竜王/優鉢羅(うはつら)竜王 竜王申し / (訛ってジュウオウモウシとも)竜王に向かって雨乞いをすること。また、その唱え言。 真竜 / 真の竜 ⇔画竜 画竜 / 画に書いた竜 ⇔真竜 画竜点睛 / [歴代名画記(7)](梁の画家 張僧よう(ちょうそうよう)が、金陵安楽寺の壁画に白竜を描いて、その睛(ひとみ)を書き込んだところ、たちまち風雲生じて白竜は天に上ったという故事から)事物の眼目となるところ。物事を立派に完成させるための最後の仕上げ。また、わずかなことで、全体が引き立つ例え。「―を欠く」 竜駕 / 1竜に乗る。2天子が乗る車。天子の乗物。「竜車・竜輿」 竜角 / 和琴(わごん)・筝(そう)の部分名。甲の頭部および尾部(和琴は頭部のみ)に近く胴幅いっぱいに架した、言をのせる枕木。⇒雲角 竜閣 / 立派な楼閣。とくに仏寺をいう。 竜河洞 / 高知県中部、香美郡土佐山田町にある鍾乳洞。総延長約4キロメートル。弥生時代の洞窟遺跡がある。天然記念物。 竜眼 / ムクロジ科の常緑高木。中国南部の原産。葉は羽状複葉、小葉は革質、楕円形。春、多くの白色の芳香ある五弁花を、褐毛ある円錐花序に開く。雌雄異株。果実は球形でれいし。 竜眼肉 / 竜眼の種子。肉質・甘味の仮種皮で被われる。生食しあるいは乾果として食用又は生薬とする。 竜巻 / (その形が、竜が天空に昇るさまを想像させるのでいう)空気の細長い強い渦巻きの一種。積乱雲の底から濾斗状の雲が下垂し、海面または地上に達する。風速は毎秒100mを超えることもあり、海水・漁船・砂塵・家屋・人畜などを空中に巻き上げ、被害を与える。海上竜巻と陸上竜巻とがある。 竜の馬 / すぐれた良馬。千里の馬。駿馬。 竜の落とし子 / ヨウジウオ科の海産の硬骨魚。全長約10cm。体は骨板で覆われ、頭は馬の首のような形。直立して泳ぎ、柔らかい尾で海草に巻きつく。雄は腹部に育児嚢を持ち、雌の産んだ卵を入れて孵化させる。これを左手に握っていれば、お産を軽くすると伝える。浅海の藻場に産する。海馬。竜の駒。うおうま。 竜の口(りゅうのくち) / 1竜頭の形を胴や鉄などで作り、口から水の出るようにした物。神社の御手洗場などにある。2樋の口の水を吐き出すところ。 竜ノ口(たつのくち) / 藤沢市片瀬の、片瀬川河口の東岸の地名。むかし鎌倉時代の刑場で、1275年、元の使者を切った所。また日蓮上人の法難の地(竜口寺)。 竜の駒 / 1竜の馬に同じ。2タツノオトシゴの別称。 竜の御顔 / 天子の顔。りょうがん。 竜の宮姫 / 1竜宮にいる姫。2海神豊玉彦の娘、豊玉姫。 竜飛崎 / 青森県北西部、津軽半島北端の岬。津軽海峡に臨み、北海道の白神岬に対する。 竜田揚げ / (揚がった色が赤いので紅葉の名所竜田川にちなむ)魚・肉などを醤油と味りんにつけ、片栗粉などをまぶして油で揚げた料理。 竜田川 / 1奈良県の北西部、生駒郡にある川。2文様の名。流水にもみじ葉を散らしたもの。 竜顔 / 1まゆのところの骨が高く出た人相。2天子の顔 探竜頷 / 竜のあごの下にあるという玉を得ようとして探ること。大きな利益を得ようとして非常な危険を冒すことのたとえ。 竜忌 / 火を焚くことを忌む日。 竜旗 / 天子の旗じるし。二匹の竜のもつれあう様子を描いてある。 竜騎兵 / フランス16~17世紀以降、ヨーロッパで銃を持った騎馬兵。 またその伝統をつぐ装甲騎兵隊の兵。 竜吟調 / 十二律の下無(しもむ)の別名。 竜駒 / 1走ることがはやいすぐれた馬。2幼い時から聡明な少年。 竜宮 / 深海の底にあって竜神の住むという宮殿。浦島太郎の説話で名高い。竜の宮。竜の都。うみのみやこ。たつのみやい。竜宮城。 竜宮造り / 楼門形式の一つ。下部は漆喰塗りで、中央をアーチ型通路とした門。日光大猷院皇嘉門・長崎崇福寺(そうふくじ)楼門など。 竜宮の乙姫の元結の切外し / 〔植〕アマモの別称。 竜宮の使い / リュウグウノツカイ科の海産の硬骨魚。全長5.5m。体は側扁し、著しく長い。鰭は赤く、体は銀白色。青森県以南の日本近海、北太平洋東部、インド洋の深海に分布。 竜宮祭 / 瀬祭に同じ。 竜華 / 1竜華樹の略。弥勒菩薩がその下で成道するという樹。2竜華会の略。 竜華越え / 京都市左京区大原小出石町から滋賀県大津市竜華に至ると峠道。京都北門の要害。途中越え。 龍血樹 / リュウゼツラン科の常緑高木。カナリヤ諸島原産。高さ20mに達する。最も長寿の樹で、樹齢数千年に及ぶ。幹の上端が多数に分岐して剣状の葉を密生。帯緑色の花を穂状に開く。幹から竜の血を連想させる樹脂を分泌。これを麒麟血(きりんけつ)といい、着色剤・防錆剤に用いる。 竜虎 / 1たつと、とら。2強いものや、すぐれているもののたとえ。3力の伯仲する二人の英雄のたとえ。4竜虎の気。天子となるしるしの雲気。天子を象徴するもの。5人品や風采のすぐれている形容。6文章のすぐれていること。 竜虎相搏つ / 〔慣〕実力の伯仲した強豪同士が相対して戦う 竜行虎歩 / 竜のようにいき、虎のように歩く。堂々として威厳のある歩き方。 竜骨 / 1太古の象などの骨が地中から掘り出されたもの。→それを解熱剤とする。2船底の中心線を、へさきからともへ貫く、背骨のような梁材。キール。3竜骨突起の略。 竜骨座 / 南天の星座。大犬座の南、3月下旬の夕刻に南中するが、日本からは地平に近く良く見えない。首星は全天第2の輝星カノーブス。老人座。 竜骨車 / (形が竜に似るからいう)水をすくいあげて田に注ぐ揚水機。中国から伝わり、江戸前期畿内を中心に普及。りゅうこしゃ。りゅうこし。 竜座 / 北天の星座。子熊座の周囲を取り巻き、7月下旬の夕空に高く見える。 竜作 / 〔書経(舜典)〕中納言の異称。 竜山文化 / 中国新石器時代における二大文化のうち、新しい方のもの。古い方の仰しよう文化から発展し、中国文化の母胎となる。山東省歴城県竜山鎮の城子崖遺跡によって命名。ロンシャン文化。 竜車 / 1天子が乗る車。天子の乗物。「竜駕」 / 2神仙の乗る車。 竜種 / 1走ることがはやいすぐれた馬。2幼い時から聡明な少年。3帝王の子孫。4すぐれた子。賢い子。 竜樹 / 150~250年頃の南インドのバラモン出身の僧。小乗仏教から後に大乗仏教に転じ、空(くう)の思想を説いた。中観派の祖。また、中国・日本の諸宗はすべて竜樹の思想 竜驤虎視(りゅうじょうこし) / (竜のようにのぼり虎のように視る意)英雄・豪傑が一世に威をふるうさま。 竜陣 / 山を前に、河を後ろに控えて陣する陣立(じんたて)。 竜神温泉 / 和歌山県中部、日高川上流にある温泉。泉質は重曹泉。 竜陣囃子(りゅうじんばやし) / 長唄囃子の一つ。主として海の場面で、笛・太鼓・大太鼓・ちゃっぱ(小形のシンバル)などを討ち合せる。 竜髭 / 1竜のひげ。2竜のような立派なひげ。転じてりっぱな容貌。4草の名。りゅうのひげ。 竜船 / 1へさきに竜の首の彫刻を飾った、天子の乗る船。2大きな船。3端午の節句に競争する船。 竜泉洞 / 岩手県東部、下閉伊(しもへい)郡岩泉町にある鍾乳洞。延長1.7キロメートル余。高知県の竜河洞に対して命名。 竜翔 / 1竜が天空をかける。2竜のように空中を飛びかける。 竜瑞 / 竜が天からくだるという吉兆。 竜蛇 / 1竜と、蛇。2りっぱな人間のたとえ。3非凡な人と凡人。4りっぱな才能を持ちながらいんとんする。5水勢や筆勢の力強い形容。6矛などの細長い兵器のこと。 竜笛 / 笛の一種。笛の頭に竜の頭を描いた飾りがあるもの。 竜灯 / 1竜を描いた灯籠。2海中の燐が発する光。鬼火。4神社に奉納する神灯。 竜灯鬼 / 奈良興福寺にある。首に竜をまきつけ頭上に六角灯籠を載せた鬼の姿の木像。1215年康弁作。 竜頭 / 1)1竜の頭。2科挙(官吏登用試験)の第一位の合格者。3かぶとや旗などの上につける、竜の頭をかたどった飾り「たつがしら」とも読む。4竜の頭の彫刻を施した船。天子の乗る船。2)1つり鐘のつりて。2腕時計や懐中時計の、ねじを巻くつまみ。 竜頭蛇尾 / 竜の頭とへびの尾。はじめは盛んでおわりには衰えることのたとえ。 竜吐水 / 1消化用具。大きな箱の中に押上げポンプの装置を備え、横木を上下にして、箱の中の水を吹き出すようにしたもの。2水鉄砲の別称。 竜女 / 竜宮にいるという仙女。特に、8歳で成仏したという紗迦羅(しゃから)竜王の娘。 竜の雲を得る如し / 〔慣〕竜が雲を得て典に昇るように、英雄・豪傑などが機会を得て盛んに活躍するさま。 竜の玉 / リュウノヒゲの実。青色・球状で、良く弾むので「はずみ玉」といって子どもがもてあそぶ。 竜の髭を蟻がねらう / 〔慣〕 到底かなわない者に反抗することの例え。 竜は一寸にして昇天の気あり / 〔慣〕 すぐれているものは、小さな時から普通のものとは違った所がある。 竜盤類 / 恐竜を構成する二群の一つ。分類上は竜盤目という。骨盤がトカゲ類に似ているのでこの名がある。ティラノサウルスを含む肉食性の獣脚類と、アパトサウルスを含む植物性の竜脚類とに分かれる。 竜鬢筵(りゅうびんむしろ) / ほそいを五彩に染めて織った筵。「はなござ」の類。竜鬢。 竜門 / 1山峡の名。2司馬遷のこと。 登竜門 / 1出世の糸口を手に入れる。有力者にとりたてられ有名になること。2そこを通れば立身出世できる関門。 竜鱗 / 1竜のうろこ。また、その模様。2竜のうろこのように、高く低く連なるさま。3金・銀・宝玉・波・雪などのきらめくさま。4美しいてんしょの形容。5 待つの老木の幹の形容。 竜鳴 / 1竜の鳴き声。2横笛の異称。竜吟。 竜胆 / 山野に自生する草の名。 竜脈 / 風水説では,名山や霊山を24の型にわける。それぞれの山の頂上に竜神がいるが,その竜神のいるところから麓にむかって地脈が流れている。その地脈を竜脈という。 竜穴 / 竜脈が山の麓から平地にかかろうとしたところに霊妙な場所がある。そこが竜穴である。竜穴を中心に家を建てると,家が繁栄すると説く。 |
|
|
■辰・竜・龍・ドラゴン ■辰について 辰(たつ、しん)は十二支のひとつである。通常十二支の中で第5番目に数えられる。前は卯、次は巳である。辰年は、西暦年を12で割って8が余る年が辰の年となる。辰の月は旧暦3月。辰の刻は午前8時を中心とする約2時間。辰の方は東南東よりやや南寄り(南東微北)の方角である。 五行は土気。陰陽は陽である。 ■辰の意味 「辰」は『漢書』律暦志によると「振」(しん:「ふるう」「ととのう」の意味)で、草木の形が整った状態を表しているとされる。 ■辰と龍(竜)の関係 辰と龍の関係は卯年の兎と同じような関係です。十二支の中の文字を人々(庶民、子供)にわかりやすく説明する(覚えやすくする)ために神話上の動物に置き換えたものです。辰には龍が置き換えられました。龍は実在の動物ではありませんが中国神話の生物。古来神秘的な存在として位置づけられてきました。 ■龍と竜の違い 漢和辞典で「りゅう」を引くと常用漢字の「竜」は「龍」の省略体だとか省略形の俗字だと書かれています。 「大漢語林」(大修館書店) 常用漢字の竜は省略体による。「新字源」(角川書店) 常用漢字竜は省略形の俗字による。「角川漢和中辞典」(角川書店) 新字体(竜をさすと思われます)は俗字。というわけで、「竜」は「龍」を省略した字体で、意味の違いは無いと考えてよいでしょう。 現在、日本の漢字体系としては「龍」が旧字体で「竜」が新字体で常用漢字となっている。龍は人名用漢字として広く使われている。 しかし、旧字体が「龍」だが、字としては「竜」の方が古く、甲骨文字から使われている。それを荘厳にするため複雑にしたのが「龍」である。だから竜のほうが先との反論もある。 これも文献的にも正しいようだ。亀甲文字では竜のように見える文字が使われている。 亀甲文字は漢字ではなく、中国で制定された漢字としては「龍」が最初であり竜は後で作られたその省略形または俗字だというのが正しいと思う。 結論としては龍が旧字体で竜が新字体で常用漢字、意味は同じである。どっちを使ってもいい。 ■龍(竜)とドラゴンの違い 和英辞書で「龍」(竜)を引いてみると、「dragon」と出ます。英和辞書で、「dragon」を引いてみると、「龍」(竜)と出ます。だから「龍」(竜)とドラゴンは一緒です。違いはありません。 東洋の「龍」は尊ぶべき存在 / 日本人にとって、「龍」は、しばしば「龍神」様として、民話などに現れます。「龍神」様は、雨をもたらして農耕の実りを豊かにしてくださる、有り難い存在ですね。しかし怒らすと自然災害などで戒められるのでこわい存在でもある。神社の手水舎(てみずや)には、よく龍の彫り物があり、その口から清水が流れています。龍神さんから戴いた清水で手を清めるのですね。国語辞典で「龍」を調べると、「縁起のよい動物。天子や豪傑にたとえる」とあります。「龍顔」(りゅうがん)」とは、天子様のお顔のことですね。 中国でも、龍は大いに尊ばれています / 黄河の上流に龍門という急流があり、鯉がその龍門を登り切ると、龍になるという伝説がありました。その伝説から、通り抜ければ立身出世ができる関門のことを登龍門(とうりゅうもん)と呼ぶようになりました。龍になるということは、とても素晴らしいことなのです。 東洋では神様に近い存在で畏れ敬われる存在。龍を退治しようなどとは決して思わないですね。 ドラゴンは / 西洋のドラゴンは悪者である。イメージとして形はゴジラみたいなのが多いですね。ドラゴンは火を噴いたりして大暴れはするし直接人を殺したりする。物語でも最後は英雄に殺される。これはキリスト教の影響だという説もある。そもそも、西洋キリスト教世界の精神的バックボーンである聖書「黙示録」に、天使たちがドラゴンと戦って退治したという記述があります。だからドラゴンは悪者で退治すべきものとなったのでしょう。英国では口うるさい姑(しゅうとめ)のことをドラゴンのようだとたとえるそうです。 東洋の龍も言い方を変えると人は殺すが直接ではなく、(怒ると)自然災害によって間接的に人に害を与える。しかし証拠はないので龍神様が殺されたり、退治されたという話は全く聞かない。ただし大蛇の化け物(ヤマタノオロチ、龍ではない)は殺された。(スサノオノミコトの話) |
|
 ■九頭竜明神 |
|
|
■九頭竜明神
箱根の芦ノ湖は、むかしは鑁字池(ばんじがいけ)ともよばれていた。また、万字池と書くこともあった。鑁字池の深い水底に、悪い竜がすんでいた。この竜は、村里をおそっては人を食うので、人びとはおそれていたが、あまりのひどさにたまりかねて、人身御供をささげることにし、一人の娘をえらんだ。 娘は、村のためにと言い聞かされ、湖の底にしずめられることになった。そのころ、万巻上人というえらい坊さんが、箱根の山中で修行をしていた。人身御供のことを聞いた上人は、娘の命を助け、村人の苦しみを永久になくすために、法力で竜をこらしめようと思い立った。 上人は、村人たちにいいつけ、湖の底へ下りていく石段を作らせ、その上にすわって苦行をはじめた。苦行は、くる日もくる日も続けられた。満願の日、竜は法力にうちのめされ、力なく水面にあらわれ、おかした罪をわびた。だが上人はゆるさず、湖の底に生えている逆さ杉に、きびしくしばりつけた。 すると竜は、九つの頭を持つ九頭竜になり、もう決して悪いことはせず、山と村を守ることをちかった。上人は、ちかいのかたいことを知って竜をゆるし、九頭竜明神の名で祀りこめた。 その後里人は、人身御供の代わりに、毎年三斗三升三合三勺の赤飯を九頭竜明神にささげて、村の安全を祈ることにした。赤飯は、白木のいれものにおさめて御供船に乗せ、楽船や供船がしたがって湖の中心に行き、湖底にしずめた。この入れ物がうき上がると、竜神が受け入れなかったしるしとして、不漁や山火事などのわざわいが起こるという。 ■解説 この伝説に出てくる万巻上人の名は、人名辞典の類には出てきませんが、関東地方のあちらこちらに事跡が伝わっています。満願が本当の名だが、毎日、日課を決めて経文を読み、ついに一万巻を読んだので、万巻上人とよばれるようになった、ともいわれています。諸国の霊地を巡り歩き、常陸(ひたち・茨城県)の鹿島神宮に初めて神宮寺を建て、また、箱根に箱根三所権現(はこね・さんしょ・ごんげん)を建てたと伝えられている。熱海温泉についても、次のような伝えがあります。万巻上人が、鹿島から箱根へ志す途中、海上を見渡すと、波間に煙が上がり、炎さえ出て、魚が死んでいった。立ち止まって経を読んでいると、薬師如来が白髪の老人となって現われ、「汝の仏力をもって、温泉を海中から山里に移し、病気治療に役立てよ」と教えて消え失せた。 上人は、海岸の洞に入って断食をして祈ること三七日、満願に至って、海中の温泉は止まり、山の間から噴出する霊泉に変わった。 万巻上人の事跡として各地に伝えられている事柄から考えると、万巻とは一人の人物ではなく、修行僧の一種に、万巻あるいは満願と称する一団があったと理解すべきかもしれません。 九頭竜は、仏教では密教を守護する神と説明されています。この外に、江の島弁天に出てくる五頭竜や、八竜というのもあって、もともと想像上の動物だった竜は、さまざまな伝説によってますます奇怪な姿に発展したのでした。 ■箱根神社 芦の湖の湖水祭の元は、お供物祭とも、竜神祭とも呼ばれて、陰暦6月14日に行われていた行事でした。江戸時代には、山伏が百枚の白木の皿に強飯を盛って湖水に投げ入れたといい、その皿はかつて一枚も浮き上がったことは無い。などともいわれていました。 このように、湖水へ神供を投げ入れる神事では、このほかにも近江(おうみ・滋賀県)の日枝神社(ひえ・じんじゃ)で、四月十四日の「神幸祭(しんこうさい)」に行われる『粟御供献備式(あわごくけんびしき)』が知られています。 また、遠江(とうとうみ・静岡県)の桜の池で、秋の彼岸に行われる「納櫃祭(のうひつさい)」では、氏子の青年が、冷たい池の中心まで泳いで行って、強飯(こわめし)を入れたお櫃を水中に沈めて、竜神にささげ吉凶を占う神事が伝わっています。 |
|
|
■箱根神社1 / 由緒
箱根神社は、古来関東総鎮守箱根大権現と尊崇されてきた名社で、交通安全・心願成就・開運厄除に御神徳の高い運開きの神様として信仰されています。 当社は、人皇第五代孝昭天皇の御代(二四〇〇有余年前)、聖占上人が箱根山の駒ケ岳より、同主峰の神山を神体山としてお祀りされて以来、関東における山岳信仰の一大霊場となりました。 奈良朝の初期(天平寅子元年、七五六)、萬巻上人は、ご神託により現在の地に里宮を建て、箱根三所権現と称え奉り、仏教、とりわけ修験道と習合しました。平安朝初期、箱根路が開通しますと、往来の旅人は当社に道中安全を祈りました。 鎌倉期、源頼朝は深く当社を信仰し、ニ所詣(当社と伊豆山権現参詣)の風儀を生み、執権北条氏や戦国武将の徳川家康等、武家による崇敬の篤いお社として栄えました。 近世、官道としての箱根道が整備され、箱根宿や関所が設けられますと、東西交通の要(交通安全祈願所)として当神社の崇敬は益々盛んになり、庶民信仰の聖地へと変貌しました。 こうして天下の険箱根山を駕籠で往来する時代から、やがて自動車に変る近代日本へと移行しますが、その明治の初年には、神仏分離により関東総鎮守箱根権現は、箱根神社と改称されました。爾来、明治六年、明治天皇・昭憲皇太后両陛下の御参拝をはじめ、大正・昭和の現代に至るまで、各皇族方の御参拝は相次いで行われました。 最近では、昭和五十五年、昭和天皇・皇太后両陛下の御親拝に続いて、翌五十六年、皇太子浩宮殿下も御参拝になりました。また、民間でも吉田茂元首相はじめ政財界人の参拝や年間二千万人を越える内外の観光客を迎えて、御社頭は増々殷賑を加えているのも、箱根大神の御神威によるものであります。 |
|
|
■箱根神社2
■箱根神社のルーツ 箱根神社のルーツを語るには、まず駒ヶ岳(標高1356m)山頂にある「箱根 元宮(もとつみや)」の話から始めなければいけません。 現在の「元宮」は、昭和39年(1964年)、西武鉄道の創始者の堤康次郎氏が、箱根の神様に奉納した社殿です。箱根神社には、「拝殿」と「本殿」があります。通常、本殿には神様がいらっしゃるのが一般的ですが、元宮には「本殿」はなく「拝殿」だけしかありません。つまり元宮は神様を拝むための社殿(拝殿)なのです。 普通、本殿には御扉(みとびら)があります。元宮にもそれに似た御扉がありますが、扉を開けるとそこには真正面に箱根連山の最高峰「神山」(標高1438m)を拝する形式になっています。 箱根山で一番高い神山は、神様が降臨される神聖な山だったわけです。 今の箱根神社が建ったのは奈良時代中期といわれ、それ以前は、神山が拝礼の対象であったようで、この神山が箱根神社のルーツであるといわれています。そして元宮がある駒ヶ岳は神山を直近に拝する祭場として、今も神々の祭りが斎行されているのであります。 毎年10月24日、箱根元宮では神山を拝して「御神火祭」が行われます。このお祭りは駒ケ岳山頂で御神火をおこし、その火を神山の神様に捧げたのち、箱根神社をはじめ箱根全山の神社に御供するお祭りです。(10月24日:御神火祭、25日:御神火巡行祭) ■箱根大神様 神山(箱根山の主峰)には、箱根大神様と言われる三容の神様がいます。 瓊瓊杵尊(ニニギノミコト) 木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト) 彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト) その神様をお祀りしたのが今の箱根神社です。他にも箱根山中には様々な神様が祀られており、駒形神社には、駒ヶ岳の地主神、駒形大神が祀られています。 また冠ヶ岳(大涌谷)の高根神社には、「能善権現」(のうぜんごんげん)と言われていた、熊野の神が祀られており、熊野の神は“温泉の神”とも言われています。そして、芦ノ湖に九頭龍権現が祀られた九頭龍大神があります。 そのため箱根山は、その山の全体に神が宿るまさに霊山なのです。 ■万巻上人 万巻上人(まんがんしょうにん)は、勅願により箱根権現(箱根神社)を建立したとされる人物です。 上人は、神と仏を結ぶ聖僧(しょうそう)であり、また奈良時代、東は鹿島から西は伊勢にいたるまで、 広範囲に宗教活動を行ない、神社や仏閣を作った有名な人物です。 箱根権現を建立する前は、茨城県の鹿島神宮の神宮寺、そして箱根権現の後には、伊勢の多度大社の神宮寺を建てたとされ、それぞれの場所にこの万巻上人の遺跡、あるいは古文書が残っています。 ■箱根山の歴史 箱根神社には『筥根山縁起并序』という巻物があり、箱根山開創の歴史を伝えています。これは鎌倉時代の建久二年(1191)、ちょうど鎌倉幕府ができる1年前に作られた縁起です。“箱根山の由来”、“箱根神社の成り立ち”あるいは“九頭龍伝説”、それから“歴代の武将がどのように箱根神社を崇敬したか”など、奈良時代~鎌倉時代(1191)までの歴史が、この『筥根山縁起并序』に書かれています。 すなわち、言い伝えや伝説が書物として形を変えずに残っているわけです。 『筥根山縁起并序』は甲本、乙本があり、神社に保管されています。原本は伝わっていませんが、室町時代の写本が2巻存在し、1巻は箱根町の文化財として箱根神社の所蔵庫に納められ、もう1巻は宝物殿に展示されています。箱根の歴史を学ぶ上で、『筥根山縁起并序』は欠かせない史料なのです。 ■筥根山縁起并序と平家物語 NHKの大河ドラマが始まり、今話題の「平清盛」。実は平清盛と『筥根山縁起并序』には、繋がる物語があります。 平家全盛の時代、誰も平家に反抗する人はいなかった頃に、源氏、後白河法王らが平氏討伐に動き始める時のことです。 奈良の興福寺に信救得業(しんきゅうとくごう)と言うもの凄く頭のいい知識僧がいました。 この知識僧は、別に大夫房覚明の名前も持ち、後に源義仲の右筆を務めました。信救得業(大夫房覚明)は、誰も平清盛を批判する人がいない時にあえて興福寺より、三井寺、あるいは比叡山延暦寺の僧兵に向かって檄を飛ばします。興福寺に以仁王(もちひとおう)より平氏討伐の手紙(以仁王の令旨)が届き、それを受けて檄文を送ったわけです。 檄文には「清盛入道は平氏の糟糠(そうこう)、武家の塵芥(じんがい)」と書かれ、「清盛は平氏の味噌っ粕(糟)、武士のゴミ(塵)だ」とまで罵倒したすごい表現です。勿論、それを聞いた平清盛は大変激怒し「首をはねろ」と言って、信救得業を追補しようとします。 追われる身となった信救得業は、自ら身を隠し奈良から北陸方面へ逃げます。信救得業は木曾義仲(源義仲)の元で右筆となり、準備を固めて木曾義仲と共に平氏を京都から追い出す事に成功します。 その後、木曾義仲は源頼朝と仲違いし討たれる事となりました。同時に信救得業は行方不明になりましたが、実は箱根神社に潜伏していました。そして、箱根別当の右腕となり、『筥根山縁起并序』を作ったとされています。 |
|
|
■箱根権現の御免勧化
■箱根権現の起り 箱根は万巻上人が開いた霊場だということで有名だ。この方は京の都でお生まれになって、出家してから読んだ経典がなんと一万巻、それで誰がつけたか「万巻」さ。「満願」ではない。たくさん読んだからって呼び名にするなんて鼻持ちならないお方と思わず、周囲でそう呼んで上人を尊敬していたと思えばいい。 万巻上人が箱根にお出でになったのが天平宝字の頃というから奈良時代。なんでも常陸国鹿島明神の社に参籠すること八年、箱根に来られて習練苦行すること三年。ある夜夢に箱根山の仙人たちが現われて、「我等は往古よりこの山にて衆生を救度する神である。汝この峯に住して修行観想して現世後世の利益を満たすべし」と告げられた。 この仙人たち、言い終わったらなんと文殊・観音・彌勒の三菩薩に姿を変えた。そこで上人歓喜して信心骨髄に徹して修行されたとかいう。凡人にはわからないが高僧はよく夢をみるんだねえ。私らでも知ってる有名なお話だ。箱根山の縁起を書いたのも、時代がずーっと下って、宣伝上手なお坊さんだろうな。 では、湖のそばにお社が出来上がったのはどうしてか。万巻上人が箱根山で仏道修行にご精進なされているのが天聞に達したんだとさ。上人の霊夢に現われた三人の仙人たちを勧請するために、勅願によって壮厳で美麗な仏塔や神祠が造営されたという話だ。神も仏も一緒くたの時代だから、上人が箱根権現の神を勧請されたといっても不思議ではない。 万巻上人より前はどうだったかと聞かれても、万巻上人でさえ不確かなのに、それ以前のことを私は知らない。上人は多くの僧や修験の行者たちの代表ってわけだ。その意味では「万人」上人だ。 箱根ばかりじゃない。近くには伊豆の走湯権現があるし、東に大山、西に富士浅間と、この辺りの嶺々はどこも霊場だ。万巻上人は熱海でも伝説が残っていて、海中の湯を陸に祈り寄せたというのだから、祈祷の力というか何と云うか、恐るべしだ。 ■香煙ただよう霊場だった それ以後、鎌倉に入る頃までを、私はこれもよく知らない。ただ、箱根山に勢力を張っていたのが昔は天台宗であったとか、箱根権現は広大な領地を持っていたとか、威勢のいい話が伝わっている。 頼朝公が石橋山の合戦に敗れたときには、当時の別当はその危急を救って再起に助力した。そのため頼朝公の崇敬篤く、神領を寄進し度々社参もしている。おかげで権現の社殿の造営をはじめ、別当寺、根本中堂、常行三昧堂から法華三昧堂まで造り上げた。神と仏を祀るに十二分なものだ。 お山に参って話を伺うと、この頃には僧が百二十人を超え、社頭は参詣の武士と庶民が日ごと踵(きびす)を接する賑わいだったという。また、湖には朝の香の煙がただよい、声明は陽が差す樹の間に籠り、夕日が照らす峰々には鐘声がこだまするという、文字通りの法悦の霊場だった。 そのあと一度社殿が焼けたこともあったが、すぐさま北条泰時が再建したというから、崇敬の念、依然衰えずといえる。 箱根が霊場であったことは、今でも精進池畔にたくさんの石仏や石塔が残っていることでも知れる。 箱根山の修行者たちや庶民が信仰の証しに残したものだ。えらい人が紙に書いたものは私らが目にすることは出来ないが、道や池の傍らにある石仏石塔なら誰でも知れる。 箱根山は大森にも北条にも庇護されていたが、天正十八年(一五九〇)太閤秀吉公の小田原攻めのとき箱根山の坊さんたちは北条方に味方したため、社壇を焼かれてしまったそうだ。 それから先は、箱根山から御免勧化の御役の者(勧進さん)が来ているから、そちらに聞いた方がいい。私の後を何か話しておくれよ。 ■「勧進さん」の話 「そうですね。私は箱根権現御免勧化の御役を勤めまする者でございます。顧みますれば、古来から箱根は霊場でありました。 念仏の和讃にもございます。 帰命頂礼箱根山 麓に立ちし六地蔵 参ろとすれば雲かかる 雲に邪見はなけれども 我が身に邪見のある故に 花のようなる子を殺し あまりその子を恋しさに 三寸鉦皷を腰につけ 二寸の撞木を手に持ちて 四国西国廻れども 我が子に似たる子もあらじ さらばやがて寺参り 寺へ参りて眺むれば 開きし蓮華は散りもせず 摘みし蓮華は散り失せる 則ち我が子もあの如く 念仏申して思いきり・・・ このように、箱根山は心に苦患をかかえる者が、女も男も集まるところでした。それは誰が支配者であるとかは関わりないものでございます。 家康公は、箱根権現に伊豆の澤地(さわじ)村高二百石を寄進されました。社壇の再建も家康公によるものです。別当義山様の十年に亘る御努力により慶長十七年(一六一二)に着工され、伽藍全部が新築という大掛かりなものでありました。こののち、義山様は関東古義真言の触頭に任じられ、また僧正に昇進なさいました。 今、別当を金剛王院と云い、東福寺とは申しません。天正のときに東福寺もそこに従う寺々も絶え果てしまいました。慶長の再建の折り、東福寺の塔中金剛王院が西堂ヶ島に残っていたことから、これを権現の別当坊となしたのであります。 芦ノ湖の用水の話も少し致しましょう。寛文三年(一六六三)、芦ノ湖の水を御厨方面の灌漑の用に使いたいから力を貸してほしい、ついては神前に立願成就の願文を捧げたいと、駿東の深良村の名主と工事を請負った友野與右衛門たちがお山に来て申し出ました。芦ノ湖の水は権現の水なのです。別当の快長様はこれを快諾し、公儀の免許を得るために三年、たいへんな御苦労をされたそうであります。工事には三年半を費やし、延べ人数八十三万余人といいます。寛文十年に隧道が完成し、二十九ヶ村の畑地が田になったのです。 話を社殿に戻しますと、寛文と元禄に大規模の修築がなされました。両度に亘って小田原の殿様が造営奉行を勤められております。しかしながら公儀の金銭的な支えもこれが最後で、寛保の頃には修理維持はすべて寺社の自費によるべしとなりました。そのため公儀を頼ることができなくなって、この頃から寺社の勧化(勧進)がよく行なわれるようになったのでございます。 小田原との関係は、稲葉さまから大久保様に替わられてから宜しからずという状況でありまして、仙石原村との境界争い、次いで芦之湯の帰属争いなど揉め事が続いて、とても支援がかなうものではありませんでした。」 ■三度目の御免勧化 「実は、箱根権現の御免勧化はこれまで三度行なわれました。寛延の御免勧化が最初でありました。別当の隆雅様は寺社奉行の大岡越前守様に勧化を願い出まして、相模・陸奥・常陸の三ヶ国の勧化と箱根往来勧化を許されました。御免勧化は公儀のお墨付きの勧化ですから、願い出てもなかなか許されるものではありません。許しが出ますと、相模・陸奥・常陸の御領主御代官に伝えられ、領内に御触れが廻ります。しかし、三ヶ国勧化は期間一ヶ年の取りまとめ勧化でして、巡行して廻ることなく行なわれました。そのためか浄財は思うほどには集まらず、諸堂の雨漏りの修理をしたという程度で終りました。二度目は明和のとき、別当の隆山様が発起致しました。それというのも伊豆の三島明神では公儀の寄附と拝借金で大修理を行なったからであります。公儀から寄附や拝借金を得るというのは大社大寺でなければ叶いません。そこで、いつも張り合っている三島でやれるなら箱根でもと、公儀に金三千両と材木百挺の寄附、金二千両の拝借を願い出たのです。澤地村の高二百石のうち別当分の百石を返済の担保に充てることまで申し出ております。これに対して金五百両の寄附と金五百両の拝借金があり、これはこれで有難いことでしたが、とてもこれでは修理に足りるものではありません。そのため関八州及び江戸市中において勧化することを願い出て許されたのです。しかし、それでも出費が嵩んだのか修理が終らず、富くじの興行まで願い出まして、免許を得て大坂は道頓堀で五年の富くじ興行を打ち、ようやく社殿の大修理をなしとげたということでございます。三度目は寛政の二年になります。三ヶ国勧化を二ヶ年に限って許され、そのときには浄財六十余両を得たと云われます。しかし、諸堂の大修理は千両二千両の資金を要する大事業であります。別当の隆照様は公儀に多額の寄附と拝借金そして材木の調達を願い出ましたが、許されませんでした。」 ■今度は四度目の御免勧化 「箱根権現の諸堂のうち修理を要する個所は幾つもございますが、祈祷護摩所や鐘楼は破損の甚だしいままであります。由緒ある大きな御輿の修理もしたい。そこで今回の四度目の御免勧化になったのであります。享和の二年(一八〇二)、公儀から三ヶ国勧化と箱根往来勧化の許しを得ました。この度の期限は三ヶ年、三ヶ国は相模・武蔵・甲斐です。箱根往来勧化は、権現の門前や関所の口で道行く人々に寄進をお願いするというものです。箱根山には現在、別当の金剛王院に僧が五人、俗人が八人、そして坊中子院に僧四人、近くの興福院には僧俗三人、賽之河原の堂守に僧が二人。合わせて二十二人。この他に四軒の社役人と承仕・柴灯・神楽人・社人・定使・山伏などがいて、お坊さんたちに仕えております。今日このように勧化(勧進)に廻っております私は、権現の社人であります。谷津村の名主の亀右衛門さんには、ただ勧化をお願いすると云うわけにはまいりません。少し箱根山の台所事情をお話致しますと、箱根権現は澤地村の高二百石と祈祷料等の収入で賄っております。澤地村の年貢については、江戸のはじめに山内はこの年貢米分配で別当と別当を補佐する坊中の子院(六院)とが揉めたことがございます。結局折半して別当分は百石。もっとも澤地村は表高二百石ですが実際の収穫高は二百二十石余になっております。また、祈祷料等の収入はおよそ年に七十両ほどでして、両方合わせても現状を維持するに精一杯であります。そういうわけですから、この度の勧化にも是非とも浄財をお願いしたいという次第であります。私の話はこの辺で勘弁していただきましょう。」 ■銀拾匁 御苦労様。「勧進さん」はさすがお山の人だ。私どものの知らないお山の様子も御存知だね。箱根では寛政の戌年(二年〈一七九〇〉)に相模武蔵甲斐の三国に勧化の免許があって、集まった浄財が六十余両ということだった。今度は干支がひとまわりした今年、享和の戌の年(二年〈一八〇二〉)から三ヶ年の勧化がはじまった。三国勧化と箱根往来勧化だ。村ではどうしたか。私の控えは次の通り。 「戌年より子年迄三ヶ年間、箱根山権現御免勧化、村中名前銀拾匁づつ帳面に附け、箱根山金剛王院自身相廻り申され候」 享保の二年から四年までの三ヶ年の、公儀お墨付きの箱根権現の勧化があった。村の連中の名前と金額を奉加帳に書付けた。勧化には箱根山の別当金剛王院自ら廻っておられる。そういう内容だ。 権現様と御縁を結ぶ機会、一紙半銭で宜(よろ)しゅうございますと「勧進さん」は言うが、そうはいかない。谷津の村で銀拾匁。銀拾匁は、金一両を銀六十匁として、六分の一両。伊勢の御師(おんし)が廻ってくるときは金壱分弐朱出している。それに較べれば半分以下だが、伊勢は両宮、それに二十年にいっぺんだもの。 今度の勧化でどれだけよくなるかわからないが、折りをみて箱根に出かけよう。甘酒茶屋で休んだ後、山路から湖畔の赤い鳥居を見つけると、ああ箱根に来たなあと思うよ。 |
|
|
■九頭竜伝説
これは芦ノ湖が万字が池と呼ばれていた頃の話である。九頭竜はアニメーションのようないきさつで怒り狂っていた。しばらく姿を見せなかった九頭竜だが、それは嵐の前の静けさだったのだ。 「竜神さまのたたりが恐ろしい」 「このまま何事もないといいがのぉ」 村人は不安な日々を送っていたが、そんなとき突然、疫病が村に蔓延した。コロリとかいう恐ろしい病だった。そして、やっと疫病が治まったかと思うと、今度は山火事が起きたり、湖水が溢れて洪水が起きたりした。 「このままでは村が全滅してしまう」 「竜神さまが怒ったのじゃ、竜神さまの心を鎮めねばならん」 箱根村では毎夜、寄り合いが開かれた。 「むごいことじゃが、毎年ひとりずつ娘を竜神さまに捧げることにしたらどうじゃろう。そうすれば怒りが鎮まるかもしれん」 「いけにえか…。やむを得んな」 その後、毎年、白羽の矢の立った家の娘が湖に沈められ、竜神の怒りを鎮めることになったのだが…。あるとき、この話が箱根山中で修業をしていた万巻上人(まんがんしょうにん)の耳に入った。 「なに? 竜神にいけにえを差し出すだと?」 上人は山を下りて村へ飛んで行った。 「かわいい娘を…。さぞ辛かったであろう。かくなる上は、この万巻上人、み仏の力によって竜神を退治してくれようぞ。皆の衆、湖に向かって石段を作ってくだされ!」 村人が石段を作ると上人はそこに座り、三、七、二十一日の間、断食して一心不乱に祈り続けた。万巻上人のマンガン攻撃は湖中の九頭竜を大いに苦しめ、ついには九頭竜を降参させた。 「もうたまりません。おゆるしください」 「許せん。おまえの犯した罪は山よりも重い」 「そこをなんとか・・・」 「ダメだ、もう二度と湖上に来てはならぬ!」 上人はそう言うと九頭竜を湖底に生えている逆さ杉に鎖で縛り付けた。 それから、どれくらいの年月が流れただろうか。ある夜、九頭竜は上人に涙ながらに訴えた。 「犯した罪のつぐないをしとうございます。どうか鎖を解いてください」 上人が九頭竜を信じて鎖を解いてやると、九頭竜は山に入って姿を消してしまった。それからというもの、村にはなんの災害も起こらなくなり、村人は安心して暮らせるようになった。 「これはきっと、九頭竜が守ってくれているからだ。守り神にして祀ろう」 村人達は芦ノ湖の小さな島に社を建てた。これが九頭竜神社である。そして、竜神へのお供えとして毎年一度三斗三升三合三勺の赤飯を船に乗せていき、竜神が縛られていたという逆さ杉のところに沈めるようになった。 この神事は今も湖上祭(竜神祭)に受け継がれている。7月31日の夕闇せまるころ、箱根神社では三斗三升三合三勺の赤飯を入れたお櫃(ひつ)を船に乗せ、宮司がひとり付き添って逆さ杉のところへ赤飯を沈めに行くのだ。 このとき、箱根神社の大燈篭に火が灯されるのだが、この火は氏子が竜神に捧げる聖火で、この行事を“竜灯祭”という。もしも赤飯を入れた櫃が浮き上がると、それは、竜神が受け取ることを拒んだということらしい。そうなるとその年は不漁になったり、山火事、疫病が流行るという。 その他に、竜灯祭で船を漕ぐ船長は一切無言を守らなければならず、櫃を沈めての帰りには決して逆さ杉の方を振り返ってはならならないという厳しい掟がある。もし、この掟を破れば、その年に大水が出ると言われているのだ。 なお、沈められた櫃は、三日三晩たって南足柄市の大雄山駅に近い清左衛門地獄、別名“浮泉”という深い深い池に浮かび上がると言われているのだが、それを見た者は誰もいない。 ■解説 ※箱根神社は757年に万巻上人が社殿を建てたと言われており、守り神は九頭竜である。 ※逆さ杉というのは湖底に真っ直ぐ立っている杉のことだ。地震によって湖岸の土砂とともに水中へ押し流されたため、ほぼ真っ直ぐ上を向いたまま今でも湖底にそびえ立っている。 ポイントとしては小杉ノ鼻の北側、水深25メートル付近。九頭竜神社の沖、水深30メートル付近。 シンゴの沖などにあり、レイク・トローリングの際に注意が必要。枝が朽ち果てて真っ直ぐな1本の棒のようになっているから魚探ではわかりづらい。 なお、逆さ杉の水中写真を見たければ、【芦ノ湖情報】に戻って【箱根町のホームページ】に飛んでみてほしい。 ※現代において、『白羽の矢が立つ』という言葉は、大抜てき人事など、良い意味で使われている。しかし、元々は恐ろしい言葉なのだ。前ページでも書いた通り、むかしは人身御供(ひとみごくう)という習慣があって、白羽の矢が立った家の娘がいけにえにされていたのである。1,000年も経つと言葉の意味がまったく変わってしまうという見本だろう。 白羽の矢は誰が放ったものかわからないが、誰かが秘密裏に放ったらしい。むかしの家屋は藁葺きだったから、天に向かって矢を放てば、どこかの屋根に矢が刺さったのである。 なお、箱根神社境内に矢立ての杉という巨木がある。Tomy は白羽の矢の話を読んで、『矢立ての杉から白羽の矢が放たれたのかもしれない』とにらんだのだが・・・。 これは全然違っていた。箱根神社は武運に御利益があるということで、古くは坂上田村麻呂が東夷遠征の時、また、源義家が阿倍貞任追討の時に、この大杉目掛けて一矢を献じ、武運を祈願したそうだ。 なお、箱根神社には石段の下の湖に平和大鳥居というドデカイ鳥居が建っているが、これは日米講和条約の締結を記念して建てられたそうで、歴史はそんなに古くない。(アニメは時代考証がいいかげんだから鵜呑みにしてはいかんよ) |
|
 ■昇り龍・降り龍 |
|
|
昇り竜 / 天に向かって上昇している竜。転じて、勇壮果敢で勢い付いている様子を形容する表現。
昇り龍/昇り竜/昇竜/登竜 降り龍/降り竜/下竜/降竜 |
|
|
単に昇っている龍の姿、降っている龍の姿では謂われの答えにはなっていませんよね。
実際、上野東照宮唐門の左甚五郎作『昇り龍』『降り龍』の彫刻は構図からすると右がどちらかと言うと昇り龍ですが社務所のパンフレットによると『偉大な人ほど頭を垂れるという諺に由来する』と言うことから頭を垂れている唐門左の龍が『昇り龍』だそうです。この諺は、詠み人知らずの俳句『実るほど頭を垂れる稲穂かな』が元(の解説)ではないかと思われますが、そもそも、上る下るの上り龍・下り龍ではなく昇天・降臨の昇り龍・降り龍なので、構図だけでは判断できないですが『降り龍』に関しての説明は無い様で、なんとも説得力に欠ける気もします。意味としての昇り龍に関してはだいたい想像の付くところ、降り龍の存在の意味謂われが知りたいところですよね!! 謂れに関しては、紀元前後頃インドで起った大乗仏教に遡り調べないとなりませんが、この教義の中の一つに『上求菩提(じょうぐぼだい)下化衆生(げけしゅじょう)』と言うものがございます。菩提(ぼだい)とは菩薩(ぼさつ)になるための悟りのことで、煩悩即菩提(ぼんのう そく ぼだい)如意宝珠(にょいほうじゅ)を煩悩その物として説くこともございます。 仏教の教えですのでさまざまな解釈、深い意味がございますが、簡単に説明しますと。意味は、上求菩提(悟りを求め修行に励むこと)昇り龍に相当、下化衆生(命あるもの全てに悟りを説くこと)降り龍に相当、この教えを意味したものとして、神社の鳥居に刻まれた神域を守護する昇り龍・降り龍は一対になっていることが多いはずです。また、龍の持つドラゴンボール(如意宝珠)は龍や摩伽羅魚の脳、鳳凰の肝から採れるともいわれますが、空海の教えでは、『自然道理如来分身者也(自然の道理にして如来の分身)』と説いていて最高位の如来より下位の仏像の中に持つものもいます。 仏像では、これらの物を持物(じもつ)と言い仏像の法力や功徳を象徴する物であり、主な物として、薬壺・蓮華・宝剣・金剛杵・錫杖・戟・宝珠・日輪・月輪・水瓶・経巻・輪宝・羂索・払子・警策・宝搭等があり、薬師如来の薬壺や観音菩薩の水瓶等その仏像特有の持物もありますが、多くの仏像では同じような物を手にしている事もあり、如意宝珠もそのなかの一つで、如意輪観音が右の第二手に虚空蔵菩薩・地蔵菩薩・吉祥天・弁財天は左手に持っています。このように、龍は古来から神仏と密接な関係があったようです。 当店の昇り龍の木札はドラゴンボール(如意宝珠)を追う姿、降り龍は手(前足)に持っている姿を彫っています。謂れの解釈からすると目標に向かい修行(修業)を修める過程では昇り龍を持ち目標を達成した後は降り龍を持つと言う使い方にも適した構図となっています。 『降り龍』は、字面から受ける感じでは運気が下がるような気がどうしてもしてしまいがちですが、降り龍は、天から舞い降り地上の守り神であるとされ、上がる下がるのくだりではなく、降臨のくだるであり、意のままに様々な願いをかなえることの出来るドラゴンボールを持つ姿は、まさに最強の姿となります。運気が下がるどころか運気が上がる(運気を手中にした)ことを意味した姿となっております。 昇り龍・降り龍どちらも諸説ございますが、輪廻転生(りんねてんしょう)命あるものの生涯をこうあるべきと現しているのかも知れません。大乗仏教の教義の中の一つ『上求菩提(じょうぐぼだい)下化衆生(げけしゅじょう)』に当てはめた説が有力ではないかと思われます。 |
|
|
■上野東照宮の唐門の左甚五郎の昇り龍と降り龍
上野東照宮は、龍楽者を自称するものにとっては興味ある対象である。ここには、唐門(向唐門)に左甚五郎の昇り龍と降り龍の彫刻がある。また、唐門の前の両側には国宝に指定されている6基の燈籠がある。燈籠の中台には龍のレリーフが施されている。唐門と銅燈籠については、私のホームページ《龍の謂れとかたち》で紹介している。上野東照宮は、2009年1月12日に社殿内部の昇殿拝観を終了し、2013年まで修復工事が行われた。全体が極彩色に復元され、2014年1月6日から社殿の公開(社殿の内部には入ることが出来ない)が始まった。唐門の左甚五郎の龍の彫刻も以前の金箔を除去して彩色され、以前とは異なった趣の龍として甦っている。《龍の謂れとかたち》に、昇り龍と降り龍の2007年に撮影した写真と今回撮影した写真を並べて紹介している。 ■上野東照宮 東照宮とは、徳川家康公(東照大権現)を神様としてお祀りする神社。日光東照宮、久能山東照宮が有名だが、全国各地に数多く存在する。 そのため、他の東照宮と区別するため上野東照宮と呼ばれているが、正式名称は東照宮。御祭神は、徳川家康公、徳川吉宗公、徳川慶喜公。1616年2月4日、お見舞いのために駿府城に赴いた藤堂高虎と天海僧正は、危篤の家康公の病床に招かれ、三人一つ所に末永く魂鎮まるところを作ってほしい、という遺言を受けた。藤堂高虎は幕府の許可を得て忍ヶ丘(現・上野の山)の屋敷内に家康を祭神とする宮祠を元和9年(1623)に造った。これが上野東照宮の始まりとされる。(上野の地名は藤堂高虎の領地である伊賀上野にその地形がよく似ているということで付けられたという) その後、藤堂高虎は二代将軍秀忠に江戸に家康をお祀りする寺の造営を進言し、当時、高虎の下屋敷と弘前藩、越後村上藩の三屋敷があった忍ヶ丘に、天海を開祖とした《東叡山寛永寺》を寛永2年(1625)に開山した。この寛永寺境内に東照宮(当時は《東照社》とよばれた)が寛永4年(1627)に建立された。 ■宮号 正保3年(1646)、朝廷は家康に《東照宮》の宮号を贈り、それ以後家康を祭る神社を東照宮と呼ぶようになった。 ■家光公が大規模に造営替え 三代将軍家光は高虎が建てた社殿が気に入らず、慶安4年(1651)に全面作り替えを命じた。その年の4月に完成したのが上野東照宮の現存する社殿。当時は東叡山寛永寺の一部だったが、戦後神仏分離令により寛永寺から独立。 その後、戌辰戦争でも焼失せず、関東大震災でも倒れることなく、先の大戦でも不発弾を被っただけで社殿の崩壊を免れた。上野東照宮は、江戸の面影をそのまま現在に残す、貴重な文化財建造物である。 ■東照宮の造り 前方の拝殿と後方の本殿を幣殿(石の間)でつなぐ《権現造り》という構造で、中尊寺金堂を真似たような総金箔の建物だった。そのため、この社殿は金色殿と呼ばれている。現在、金色殿をはじめ、唐門(からもん)・透塀(すきべい)・灯籠(とうろう)などが国の重要文化財に指定されている。本格的な江戸建築を間近で見ることのできる神社である。 ■唐門 唐門は慶安4年(1651)に建築された。前後が唐破風、左右の本柱(円柱)2本と控柱(方柱)2本で上部組物を受けた向(むこう)唐門であり、正式名称は、唐破風造り四脚門。門の内側の両側上部にある松竹梅と金鶏鳥の彫り物は室町・桃山の技術を集大成した傑作である。 ■左甚五郎作と伝えられる昇り龍・降り龍 社殿を囲う透塀との間にある柱の内外4額面には左甚五郎の作と伝えられる昇り龍と降り龍が嵌め込まれている。外側から見ても、内側から見ても、右の龍の頭が下を向き、左の龍の頭が上を向いている。上を向いているのが昇り龍かと思うが、そうではない。偉大な人ほど頭を垂れるという諺に由来して、頭が下を向いているものが昇り龍と呼ばれている。 ■講談『名工甚五郎の水呑みの竜』 三代将軍家光が上野寛永寺の鐘楼建立にあたり、四隅の柱に甚五郎をはじめ木彫の名人4人を選んでそれぞれ1匹ずつの龍を彫らせた。甚五郎の彫った龍だけがなぜか夜な夜な柱から抜け出して不忍池に水を飲みに降りるようになり大騒動となる。そこで甚五郎が「可愛そうだが足止めをする」と言って金槌で龍の頭へくさびを打ち込むと、その夜から龍は水を飲みに降りなくなった、という話。寛永寺の跡地に昔の鐘楼と鐘は残っているが、鐘楼の四本柱に龍の木彫はない。すぐ傍の上野東照宮の唐門の本柱の額面に昇り龍と下り龍の高彫りがあって、東照宮ではこれが甚五郎作の《水呑み龍》だと伝えている。 ■子規の句 上野東照宮には、明治26年に詠まれた正岡子規の句がある。 秋淋し毛虫はひ行く石畳 |
|
|
■昇龍・降龍の鳥居
鳥居は、神社の象徴であり、門の一種として神域と俗域の境界を示すものとされている。その語源は「通り入る」、また、鶏の止り木の「鶏居」であるといわれる。鳥居の中には昇龍・降龍を刻んだものもあるが、これらは多分に仏教的色彩の濃い鳥居で、神仏習合したともいえる。龍は寺社の柱、欄間、天井、門扉などでもよく見かけるが、「鳥居に刻まれた龍」は、神域を守護するものとして、山門の仁王像や獅子、狛犬と同様の役割を担っている。 昇龍・降龍は、「上求菩提、下化衆生」という仏教の教義を意味するとされる。上求菩提とは、悟りを求めて厳しい修行に励むこと、下化衆生とは、慈悲を持って他の衆生に救済の手を差し伸べることを意味し、これら両方を合わせて修得すべきこととされている。 |
|
|
■辰の年
年始祭に御詣りをするという事は、この一年をスムースに渡れるか、渡れないかの第一歩です。辰は季節により働き方が異なり、春は昇り龍、秋は下り龍、夏は伏せ龍、冬は歩き龍と言われています。夏の龍はグルグルと巻いて顔だけ持ち上げて人間達、万物を見守るのです。 龍は、海に千年、山に千年、川に千年、最低でも三千年を経過しなければ、龍とは言わないのだそうで、雨の日も風の日も、人間達に汚されながら、一心不乱に道を学び、修業をなさるのです。 幸いの道は、右巻きですが、それを左巻きに、或は逆向きに、或は下向けて流れていったりと、真理の道を間違ったケースが多く、その罪が重なって、幸いを得る事が出来ません。現在の人間は、自尊心ばかり高まり、自分の功績ばかり表に出したがる人が多く見られますが、龍神様は、決して自分のした事は表に出さず、陰で守護した人を支える陰徳の神様なのです。 辰の年というのは、何万年も修業なさった龍が本年を守護なさるので、力が非常に強く神通自在であると御教祖様は仰せでございました。故に、松竹梅の内の特に竹の徳をしっかり積んで、身体で奉仕し、その徳を高めるならば、必ず望みは叶うと申されています。 本年は、龍の生気の火を吹く年であり、気性が激しく心の煩悩の炎を吹き消し、道、生活、愛行の三つを大祖神の御心に添って行くならば、天の恵みの無限億万円を受け取る事が出来るのです。辰の年は、火の精の働きが強く、地震や火事の火難もありますが、儲かる方も、火の関係が成功するのです 現代は、我が我が、と自分の我欲に捕われて、海の徳を積んでいない人が多いため、幸いを頂けないのです。海の徳とは、生まれる徳、育てる徳です。一番は、お導きで、人助けをして、あなたも私も助かりましょうという、この大祖教の御教えを人に伝えてあげる事です。神、先祖、人、この天地人の道にしっかりと心定めをして、今年こそ良い年になります様に、神に願って、新年の御挨拶と致します。 |
|
 ■上求菩提・下化衆生 (じょうぐぼだいげけしゅじょう) 仏教用語。菩薩(ぼさつ)が上に向かっては菩提(真理と智慧(ちえ)とが一体となっている悟り)を求め(自利(じり))、下に向かっては衆生(しゅじょう)(生きとし生けるもの)を教化(きょうけ)する(利他)ことをいう。すなわち自利(智慧門)・利他(慈悲門)の菩薩行を要約したことばであるが、菩薩のサンスクリット語ボーディサットバbodhi-sattva(菩提・衆生)を分解して語源解釈を行ったものであるともいう。 ■2 阿弥陀如来は右手をかざし、左手を下に向けて差し出している姿で表現されます。これは【上求菩提 下化衆生】を表現しているとされています。悟りを極める修行をしつつ、衆生救済に奔走することが修行の王道であるという教えです。この教えの根拠として【利自即利他】(りじそくりた)という考え方があります。自分を利することと他人を利することを別に考えてはいけないということです。これを別にして考えた場合、必ず苦しみの原因となっていきます。これを【六大煩悩】といいます。自分を利することを、他人を利することと両立させる方向で考えた場合、ここに幸福の芽が出てくるという考えが前提としてあるのです。 「情けは他人の為ならず」という有名な言葉があります。よく話題に上ってくるので、「情けを掛けるのはその人の為にならない」と解釈する人は、最近では少なくなってきたと思います。この言葉が【利自即利他】を指していると同時に、【上求菩提 下化衆生】を現代的に言い換えた言葉なのです。悟りを極めようとすると、最初の段階では主として自己変革・自分作りの修行になりますが、最終的には他人を導くリーダー・指導者の修行になっていくので、「究極の悟りとは、多くの人をを導く能力を持つことだ。」と理解する必要があります。 これを説明するのに最適なのが【愛】です。「情け」を「愛」に置き換えてみてください。普通は「愛されたい」と思うものです。そしてそれ故に苦しむものです。利自と利他が両立していない状態です。そこで、「与える愛」の実践をお奨めしています。「見返りを求めることなく、兎に角、愛を与え切りなさい。」そうお奨めしています。その愛の深さ、純粋さが本当に相手に伝わった時、絶対の信頼と共にあなたは愛されるでしょう。これが「情けは他人の為ならず」の本当の意味なのです。悟りの世界においては、リーダー・指導者としての資質の向上、能力の向上という結果として返ってきます。つまり、どれだけ他人のことを考えられるか、他人のために行動できるかが悟りの鍵になっているということを知っておかなければなりません。 ■3 サブテーマに「みんなで幸せになれるよう」とありますが、「幸福は、ただ、自力でつかむしか、道はない。自力でつかむ意思、希望をあたえてやることが、隣人の愛では、精いっぱい可能な範囲である。『俗つれづれ草(吉川英治著)』」と記されています。 親が子供のために尽くす姿の中に同事という教えを見出すことが出来ます。親が子供とゲームで遊んだり、キャッチボールをしたりする時、親は子供と同じ姿です。しかし、これが、子供と遊ぶ為でなく、親がゲームに夢中になれば、堕落となります。親が子供の宿題を手伝う時、子供の立場に立って教えなければ、子供は理解出来ません。つるかめ算に旅人算(たびびとざん)。通過算(つうかざん)に流水算(りゅうすいざん)。難しい宿題がでてくると、親も必死で勉強します。 ある時、子夏(しか)が孔子(こうし)に顔回(がんかい)についてたずねました。孔子は、「顔回の仁なることは私にまさっている。」と答えました。子夏はさらに、子貢(しこう)についてたずねました。孔子は、「子貢の弁舌は私にまさっている。」と答えました。次に、子路(しろ)については、「子路の勇気あることは私にまさっている。」と答え、子張(しちょう)については、「子張の重々しくキッとしていることは私にまさっている。」と答えました。 そこで子夏が、「それでは、この四人はどうしてあなたに師事するのか。」とたずねると、孔子が言うには、 「顔回は、よく仁なることはできるが、仁に反することはできない。子貢は、能弁(のうべん)ではあるが、訥弁(とつべん)になることはできない。子路は、勇気はあるが、臆病(おくびょう)になることはできない。子張は、荘重(そうちょう)ではあるが、和光同塵(わこうどうじん)することはできない。私は、仁を行うこともできるが不仁を行うこともできる。私は、能弁のこともあるが、訥弁のこともある。私は、勇気をもって断行することもあるが、臆病なこともある。私は、重々しくキッとしていることもあるが、皆と一つになり和合する時もある。これらの四人が私に師事するのはこのためである。」 自由を得た上で、自分がつねに向上することをめざしてこそ、人の身になって尽くすことができるのです。これが上求菩提 下化衆生(じょうぐぼだい げけしゅじょう)です。 ■4 ブッダがお誕生のときに右手で上をさし、左手で下をさしています。これは普通、「天上天下唯我独尊」(この世に自分より尊いものはない)という意昧にとっていますが、「上水菩提、下化衆生」の象徴として見たほうがいいと考えております。「上水菩提、下化衆生」こそが人間の生きる道。であろうと思われます。 ブッダの話し伝えた言葉の中に闇夜を照らす光を見つける。 ブッダの教えている人間の生き方というものについて、人間というのは「そのとき」によって生き方が変わってきます。戦国時代の仏教と、泰平の時代の仏教とは違うし、高度成長期の仏教と、いまのような平成の時代の仏教は違いますね。人間は、その時代その時代に応じて、仏教という広い宝の山から自分たちの生きる指針を取り出していました。だから、「あの時代にはあれ、この時代にはこれ」でいいと思われます。 そう考えると、いまの時代は人問の命が軽くなっていて、みんなの気持ちが僻(ひがみ)になっていますから、誰もがこの不安な世の中を安心して生きていけるような心強い教えを求めていると思います。いろんな社会的不安もある、老後の不安もある、それから政治家やお役所も信用できそうもありませんね。隣人さえも安心できませんし、いまは小学校の子どもに「知らない人から声をかけられたら走って逃げろ」と教えているところもあるらしいです。それほど人間不信の世の中に、穏やかな気持ちで不安というものを抱かずに生きていけるような教えを仏教の中から探すことが、いまの最大のテーマだろうと思います。 不安の時代、僻(ひがみ)の時代の中で、明るく落ち着いた気持ちで自信を持って生きていくことを大事にして仏教と向き合うべきではないでしょうか。仏教は、闇を照らしてくれる光の役目かもしれません。世の中の闇や心の闇を、淡い光でもいいから、ほんの一瞬でもいいから、照らしてくれる。その光が射してくれば安心できる。仏教というのはそういう光なのだと思います。 「仏教はよりよく生き、よりよく死ぬための教え」ではないでしょうか。 ■5 上求菩提と下化衆生。それは釈尊の説法に最初から語られていたことだった。ところが仏教の最初の500年間は、上求菩提だけを目指してゆく。なぜだったのか? それは釈尊という存在があまりにも偉大すぎたからだという。釈尊の輝くばかりの人格が、人々の憧れになっていたということだろう。思想的訓練を積み重ねた者が説いたからこそ、多くの人々が仏になりたいと願い、仏の道を求める上求菩提の心が広まっていったのだ。 キリストは、その生涯を処刑によって30余年で閉じてしまう。そこに釈尊のような思想的訓練の積み上げは為しえなかった。ゆえにキリストの神々しさは人間離れした神的存在となり、キリスト教徒は、誰も神になろうとは考えなかったのだという。 釈尊は80歳でその永き生涯を閉じるまで、ひたすらに心というものを訪ね続けた。その思想的な深まりはとてつもない。 釈尊亡き後、仏教はその憧れを追い続け、500年という長い年月を経て釈尊の思想に辿り着く。上求菩提と下化衆生の融合、菩薩の姿にようやくと対面するのだ。 釈尊の思想の深さを物語る話がある。 あるバラモンの問い「沙門よ、わたしは田を耕し、種をまいて食を得ている。あなたも自ら耕し、種をまいて食を得てはどうか」 すると仏陀はサラリと答えて言った。「バラモンよ、私も耕し、種をまいて食を得ている」 それを聞いて、彼のバラモンはわが耳を疑うような顔をして、じっと仏陀のおもてを見つめていたが、やがて問うて言った。 「だが、わたしどもは、誰もまだ、あなたが田を耕したり、種をまいたりする姿を見たものはいない。いったいあなたの鋤はどこにあるのか。あなたの牛はどこにいるのか。あなたは何の種をまくのか。」 仏陀は言った。 「信はわがまく種である。智慧はわが耕す鋤である。身口意の悪業を制するは、わが田における除草である。精進はわがひく牛にして、行きて変えることなく、われを安らけき心にはこぶ」 釈尊は、飽くなき向上の心が、我が最大の生産活動だと云っている。人が生きることの意味を、終わりのない向上の道筋と捉えていたのだ。 向上の先にある、究極の姿が仏ということであった。仏を求めて道を辿る姿が上求菩提であり、その後ろ姿が、周囲に自分も仏を目指したいという気持ちを立ち起こす。それが下化衆生ということなのだ。 内に内にと成長を求める人の姿は、人々に感動を与えるのだ。その姿が憧れとなり、私も頑張ろうという気持ちが湧き起こる。 上を往く者の姿が、下に居る大衆を化する。それには、上を往く者が下を向いていてはダメだろう。先行する者は、常に前を見つめて歩み続けることだけ考えたい。 こうすればいいよ、ああするといいよ。それはヤメたほうがいい。このようにやりなさい。 前を往く者は、つい指導を考えてしまう。それはとても楽な方法だ。 でも、後ろを振り返って向き合うところに自己の向上はない。楽な道を選ぼうとする気持ちは、慢心からやってくるのだ。 こんないいことがあったよ。大変なことがあったけど、面白い事に気がついたよ。 自らに厳しく、常に向上し前進し続ける者の言葉には、相手に対する強制がない。自分が面白いと感じたこと、うれしかったこと、ただ、感動を周囲に伝えてゆくだけだ。 さて、自身の言葉はどうなっているだろう? ■6 下化衆生 三十年以上も前になるが、私は僧堂を引いて初めて鎌倉の小庵の住職になった。檀家が一軒もない寺だったので庭掃除と畑仕事を日課とし、後は毎月一週間僧堂へ修行に出掛けるという日々を過ごしていた。三年ほど経った頃、建長寺本山の宗局が入れ替わり新しい総長さんが決まった。ある時その総長さんが来られて、教学部へ入って欲しいと言ってきたのである。一端は躊躇したがこれも永年お世話になった宗門への御恩返しと思い引き受けることにした。ところがいざ勤めだして解ったことは、これは説教師さんの親玉役で、大変なことになってしまったと思った。というのも私はいたって口下手で、人前に出るとやたら上がってしまう性格であったからだ。出来るだけそういうことにならないよう念じていたのだが、物事は逃げ腰になると後を追いかけるようにやってくる。早速管長貌下の御親化が始まり、その随行を命ぜられた。 御親化とは建長寺派の寺院を管長自ら一ケ寺ずつ巡ってお詣りをし、その寺の壇信徒と親しく話し合う行事である。大抵は一日に何ケ寺も廻ることになるので管長、総長、部長を囲んでざっくばらんな茶飲み話で次ぎに移る。しかしその時の小田原地区は十ケ寺と比較的少ない寺院数だったので、二ケ寺から説教を依頼された。当然、教学の私が担当という事になり、否応なくお引き受けすることになった。 私の師匠は何時も、「禅僧はぺちゃぺちゃ喋るな!ぺちゃぺちゃ言うのは足らんからだ。徳利でも中身が一杯詰まっているか空っぽなら幾ら振っても音はしない。しかし底の方にちょっと有るとぴちゃぴちゃと音がする。これと同じで、修行を少しかじった程度の奴が一番ベラベラ喋る。こういう安っぽい禅僧になんか成るんじゃない!」 これが口癖だった。だから教えを忠実に守り、無口が美徳と思って人前に出ることは極力避けてきた。そんなわけで私の口下手はますます加速されていった。そういう状況下でこういう仕儀となり、一応準備をしては行ったものの、正直なところ胸の内は不安で一杯、身の縮む思いであった。やがて依頼されたお寺に到着し、型通りの諷経や茶飲み話も終わりお説教という段になった。すると其れまで正面真ん中に居られた管長祝下は、「ではこれから教学部長さんの有り難い御法話がございますので皆さんと一緒に拝聴しましょう。」 と言って、私の真ん前にどかっと座られたのである。只でさえ自信がないところへこれで、気も動転し訳が分からなくなった。一般の方には理解できないかも知れないが、我々修行者にとって老師や管長は恰も雲上人のようなもので、側に居るだけでも畏まって身が固くなるものなのだ。その頃の私は一応和尚に成っていたとはいえ、現役の雲水でもあったわけで、この時の異常な緊張感は想像を絶するものだった。兎も角与えられた時間、無我夢中で話をした。しかし我ながら酷いものだった。話は支離滅裂の上、こともあろうに善男善女を前にして、丹霞天然という中国の禅僧が、いきなり本堂に上がって仏像を引きずり出し斧で割って焚き火をし、尻を焙ったという話をしてしまったのだ。どうしてこんな話になったのか今だによく解らない。人間極度に緊張するととんでもないことを口走る見本のようなものである。これにはさすがの管長も呆れかえって、「もう一ケ寺のお説教は私がさせて頂きます。」 と言われた。穴があったら入りたいとはこの事である。先方の和尚はいきなり管長猊下が話し始めたので、経緯が解らず目を丸くしていたが、兎も角その場は冷や汗を掻きながらも何とか無事に済んで帰山した。 その夜まんじりともせず一日の出来事を思い出し失敗の原因は何であったか反省した。それは〝話なんかくだらん!〝という思いが在ったこと、また〝爺さん婆さん相手ならなんとでも成るわい〟と、高を括っていたことなどである。その頃の私は僧堂の坐禅修行が何よりも尊く、世事などどうでも良いと思っていた。それが間違いだったのだ。上求菩提下化衆生という言葉がある。宗旨の蘊奥を極め、恰も高い山の天辺で我一人潔し言うが如き澄んだ心境を得て、もう一方では娑婆世界の真っ只中にまみれながら衆生と共に生きて禅を説いてゆく。この双方が出来て初めて立派な禅僧と言えるのである。これは一からやり直さなければならないと感じた。 その後、瑞龍寺へ転住し師家となり、以前にも増して人前で喋らなければならない立場になった。しかしあの時の大失態が私にとっては本当に良い経験になった。以前お茶会でも大恥を掻いたことがあるが、それを契機にお茶の稽古に励んだことがある。「失敗学のすすめ」(畑村洋太郎著)の中にあるように、「失敗は成功の元」、失敗こそが新たな創造を生む。お互い大いに失敗をして恥を掻き、襟を正し真撃に生きたいものである。 |
|
 ■関羽と張飛、伏龍と鳳雛 関羽雲長と張飛益徳。劉備の義兄弟として日本でも人気が高いこの二人ですが、中国にいったことのある人であれば、ご存知の通り、関羽はリアルに神として祭られていて、古くから商売をしている店などでは必ずと言っていいほど、像が置いてあったりします。で、関羽だけならいいんですが、オマケで張飛も祭られているんですねw。まぁ、まじめなところだと違うのかもしれませんが、結構適当なところだと、狛犬のような感じで、左に関羽、右に張飛がJoJoも真っ青なポージングで屹立していたりします。 オイオイ適当だなぁ。と中国にいったときは思っていたのですが、これは別にあながち間違いでもないようで、関羽の「関」は閉じるという意味、張飛の「張」は開く、という意味で対義語になっているのです。そして「羽」と「飛」は同義語。そういうわけで、二人の関係は、「左手と右手、違いはあれども二つで一つ」みたいな意味を持つ存在なわけです。この二人は偽名といいますから、おそらく侠者時代の本名から、劉備とともに義勇軍に加わるときに自ら名付けたんでしょうね。 「兄者(劉備)、これからは我々は兄者の右手と左手、阿形と吽形でござる。」みたいな感じで。(正史のほうには、義兄弟という記述こそありませんが、同じ布団で寝た。というようななかの良さを感じさせる記述はあるようです。)1800年の時を超えて、彼らの息遣いが聞こえてくるようです。詳しくは調べてませんが、雲長と益徳もおそらく対義語・同義語の関係だと思います。長と徳は完全に同義語ですしね。 歴史で見ても、彼らの性格も右手と左手のような関係です。関羽は学もあったので上に厳しく、下に優しくというマネジメント。張飛は学がないことがコンプレックスだったのか、上には弱く、下に厳しく。という性格。関羽はその自信から時に傲慢なところもあったが、張飛が役職や立場にこだわる場面、劉備や軍師に反対する場面は出てきません。いい意味ですごく素直な子供のようなキャラです。 これは自分の目で見たわけではないですが、中国で上演される三国志の劇でもちびっこに一番人気なのは張飛で出てくるだけで笑い声がおこるとのことです。この人間味あふれるところが張飛の魅力なんでしょうね。 さて、そんな右手と左手の関係が崩れる時、すなわち関羽が樊城の戦いで敗れ、死を迎えたとき、蜀の運命も決まります。時は蜀が漢中を奪取し、蜀の版図を歴史上最大に広げた直後。本軍の動きと呼応し、関羽は曹仁が守る樊城を攻め、あと一歩のところまで魏を追い詰めます。が、外交の失敗により、一時的に魏と呉が連合を組み関羽を挟撃。その偉大な英雄は死を迎えます。 右手(関羽)を失った劉備と張飛は感情の赴くまま無謀な大軍勢で呉を攻めます。その途上、張飛は部下に殺され、劉備は無謀な攻めが失敗し、その命運がつきます。(夷陵の戦い) 蜀は、夷陵の無謀な戦いと敗北によりその命運が尽きた…。というか魏を倒す可能性をゼロにしてしまったといわれますが、僕はどちらかというと、より重要な決戦は樊城の戦いだったと思います。関羽の死とともに、蜀はその命を絶ったのだと。ただ、その人間味あふれる一群の人々の行動が、規模から見たら朝廷に対する一反乱軍に過ぎない蜀を2000年続き、愛される物語の主人公に仕立て上げたのだと考えると、彼らもまた勝者だったと思えてきます。 さて、蜀の命運が尽きた…。という意味では、もっと前にその命運が尽きていたともいえます。具体的にいうと、鳳雛の死ですね。 ■ 「天下三分の計」というのは、土地もなく民もいない劉備に孔明が授けた、本当に天才戦略家、孔明だからこそ描けた策なのですが、その要となる益州攻略(蜀の建国)を軍師として行ったのが、鳳雛こと龐統でした。 国もなく、民もなく髀肉之嘆をかこっていた劉備は司馬徽こと水鏡先生に会います。そして、「伏龍と鳳雛このどちらかを得れば天下も握れる。」と いう話を聞きます。伏龍はまだ池の淵で眠り、天に昇ろうとしない龍のことで、諸葛亮をさします。そして、鳳雛というのは鳳凰の雛のことで、龐統のことを指 します。まだ世に見出されていない才能がいるよ。ということを劉備に伝えているのですが、先ほどのどちらかを得れば~というのは実は創作物である三国志演義の話で、正史では「伏龍と鳳雛を手に入れれば天下を握れる。」という表現がされています。そう、「両方ゲットしなきゃだめよ」といわれているのです。三国志演義で「片方でいいよ」という変更は、架空の女性、貂蝉を生みだしたのと同じぐらい、大きな創作だったと思います。 おそらく、諸葛亮を神格化するために、このような表現をしたと思うのですが、実際は司馬徽の人物評がきわめて正しかった。なぜなら、諸葛亮は政治家であり、龐統は軍略家であったから。戦略家と戦術家といってもいい。 事実、益州攻略の際に全軍の軍師として劉備に同行したのは龐統でした。天下三分の計を劉備に示した戦略家は諸葛亮です。そして、単身呉にわたり、呉を赤壁の戦いに焚きつけた外交官も諸葛亮です。荊州の地を肥沃に育て、戦えるだけの陣容を整えたのも諸葛亮です。諸葛亮は慧眼を持つ戦略家であり、強靭 な外交官であり、すぐれた政治家でした。けれども、軍師ではなかったのです。 蜀の領土拡大にあたりその役にあたったのは、龐統であり、法正でした。龐統はその益州を攻略する際に、流れ矢にあたり死亡します。本当に不運な死だったわ けですよ。(演義では劇的に語られてますけどね。)その不運の死も実は避けることができて、劉備が蜀に入ったときに何も知らない劉璋をとらえてのっとって しまうことを進言しており、その助言が受け入れられていれば、もっと早く蜀をとることができたし、龐統も死ぬことはなかったんですね。 ちなみに付け加えておくと、天下三分の計を示したのは諸葛亮ですが、劉備は大義がないとして、実行に移そうとしなかったわけです。これを決心させたのが龐統で、攻略の計画を立案したのも龐統なので、演義で語られている以上に龐統SUGEEEEEE!なわけです。(ちなみに諸葛亮とはお互いの才能を認め合う 仲であり、劉備に冷遇される龐統を積極的に推挙したのも諸葛亮なわけです。最強コンビでした。) で、不幸にして、益州攻略の最中に流れ矢にあたり龐統は命を失います。しかし、蜀はその拡大の歩みを止めるわけにはいきません、益州と荊州の一部を手に入れただけではとても魏や呉に対抗できないからです。軍師として、龐統の後任にあたったのは、益州出身の法正です。法正は性格が悪く徳のない男でしたが、その軍師としての才能はなかなかのもので(個人的には凄く好きなキャラです)、漢中という魏を伺うことのできる重要拠点を奪取する作戦を立案し、実行します。しかし、法正も漢中奪取でその脳漿をしぼりつくしたのか、翌年無くなります。日露戦争の指揮をとった児玉源太郎が命を燃やしつくして死んだのと似たような状況かと思います。 さて、そうなると、蜀という中央から離れ、人口も少ない立地が蜀の首を絞めることになります。すなわち、人材がいない。人材が集ってこない。ただでさえ、国力的には反乱軍の規模です。まともな軍師がいなくなった蜀は、もともと軍師というよりも政治家であり、外交官である諸葛亮に軍事もゆだねます。明らかにオーバーワークです。 後に彼が軍師の才を見出したのは馬謖であり、重用したのですが、孔明に見る目がない。ということもあるのかもしれませんが、それ以前に人材戦略の面でもう負けていたんですね。優秀な人材が集う環境を作れなかった点で。だから、その中で多少輝いていた馬謖に過度の期待をせざるを得なかった…。と。 ちなみに、諸葛亮の戦い方は極めて正攻法でセオリー通り。国を豊かにし、出来る限り多くの戦力を整え(それこそ、現在の軍隊と同じように5カ年計画で北伐を考えていたふしがあります。すごい能吏だったわけです。)技術の発展を促し、まっすぐに戦う。 まっすぐに戦うと、攻める側は勝ちきれない。兵力だけでいったら、魏も同じかそれ以上は用意できるわけですから。(もちろんそこは孔明のこと、自分が動くときは必ず呉も動かし、魏の兵力を集中できないようにしていました。) ただ、まっすぐに攻めるだけではなかなか勝てないのも事実。結果、孔明の北伐はすべて無駄足に終わります。もし、策をたてることができる龐統が傍らにいたら…。 歴史にifは禁物です。だからこそ、三国志演技でも「伏龍と鳳雛を手に入れれば天下を握れる。」という正史に準じた記述にしてほしかったところです。なぜなら、龐統が死んだところで、天下に覇を唱える蜀の悲劇が伝わってくるから。孤軍奮闘する、諸葛亮の苦悩も物語に彩りを加えるに違いありません。 法正の策によって、漢中を制圧したころが、蜀の国力が最大だったころです。蜀はその歴史において、傍らに龐統ないし法正といった軍師がいたときしか、その領土を広げることができていないのです。(正確に言うと諸葛亮も南蛮を制圧してますが規模的に余りにも小さいです。)劉備を天下に送り出し、天下を狙う一縷の望みを作りだした諸葛亮ですが、その天下三分の計は、龐統の死という身近な人物一人の死で幕を下ろしてしまったのかもしれません。 [ 諸葛亮の南蛮制圧の時の軍師は前述の馬謖。馬謖はのちに命令違反で大敗を喫し、諸葛亮に「泣いて馬謖を斬られ」ます。時間のあるときにでも彼のことを書いてみようかと思います。失敗を糧に大化けする可能性もゼロではなかったと思うのですが。] |
|
 ■伊那下神社 当神社は山の神(山の幸)、海の神(海の幸)をお祀りしています。神社のつたえに牛原山の伝説と言う話があります。 今、むかし昔の大むかしに、思いを馳せるならば、牛原山の麓は、大きな木がうっそうと生い茂り、昼間もなお暗く、屏風のように立った岩と岩の間から、水がほとばしり、その水は神竜窟という大きな滝壺に落ち、そこには二匹の龍が住んでいたという。年代の移りと共に滝壺の水がだんだん涸れはじめ、一匹の龍は天に昇り空に消え、もう一匹の龍はこの地が離れがたく地に伏したという。 今もなお化身となった岩があります。牛原山の中空に、往々にして白い雲の靄(もや)がかかることがあります。これを『貫木の雲』天に消えた龍が、地に伏した龍を慕い、天へと迎えいれる浮き橋で、豊作の兆候であり、いい年になるぞと、古老は喜び、里人に伝えたということです。 竜神と言うと水の化身が龍になり、天にのぼります。これは地上からの水蒸気が雨雲となり天から恵みをもたらします。この水は山々の木々が保水し、山のミネラルを吸収して、海に流れ豊かな漁場が出来ると言います。私たちはの祖先は、これを神々の恵みとして感謝しています。今の生活では、蛇口をひねれば水がでます。デンシレンジで暖めれば食事が出来る時代です。だけど当たり前でない。今、当たり前のように生活していますが、当たり前ではないんだぞ、と、お寺があり、お宮があり教えているような気がいたします。神社の本殿には、この伝説に因んでか、神殿のとびらの両脇には登り龍と降り龍の彫刻が施されています。江戸時代のもので当時の大工さんたちの優れた業がみられます。 境内の傍らには神明水という清水が湧き出ています。『甘みがあっていい水だ』と地元の方や遠方からも汲みに来ます。もっぱらお茶に使っていますが、こうした人の生活に欠くことの出来ない自然の恵みがはるか悠久の昔より滾々と湧き出しています。 古く松崎湾は、牛原山麓まで奥く深く来ていまして、神社の鳥居付近まで海の波が寄せて、舟人は浪や風をさけるために、この地に舟を繋ぎ境内の傍らから湧き出る御神水を汲み、或いは山の恵み・海の恵みに感謝し、朝な夕なに敬虔な祈りを捧げたことと思います。原始の時代より始まっているので、当神社の創建についてはわかりませんが御祭神は山の神である彦火火出見尊・海の神である住吉大神がまつられております。 元は社がありません。牛原山そのものが神の宿るところでありました。その牛原山の頂上には、三本松と呼ばれる松がありまして、そのところで儀式が行われました。この松は、昭和の初めまで空に聳えていて、海上交通の目標でもありました。時代の進みにつれて山の神を麓でまつるようになりました。現在の社殿に向かって左側にある大きな岩が祭場となりました。この岩は亥子岩(いのこいわ)と呼ばれ、山の神をお招きし儀式が行われました。いつごろ神社が出来のたかわかりませんが、伊那下神社を俗に唐大明神とも称えられました。そのいわれは、4世紀後半、日本書紀に記されている神功皇后の新羅遠征伝承がありますが、皇后さまが遠征のその帰りに山口県の長門の豊浦に留まりまして、そのあと、この松崎に来まして、皇后の船をお守りした住吉の大神を当神社に合わせまつり、唐大明神と称えました。唐の国から来た外国の神さまで蕃神とも言います。ですから、伊那下のイナは新羅から日本へと造船技術を伝えた帰化人で、その船造の職人さんたちの集団をイナと言ったようです。 神社の伝えでは、このころ、社殿を建立したんではないかと伝えています。この由緒にちなんで、入江長八が当神社に神功皇后・武内宿禰と応神天皇の漆喰人形の像を奉納しています。それから、鎌倉時代初期の文書に建暦元年(1211)の鰹船安堵状があります。今から八〇〇年前のもので、この文書には、「仁科庄松崎下宮の鰹舟二艘は・・・」とはじまりまして、松崎という名前がはじめて見え、北条時政の花押があります。そして、町内でも最も古い古文書です。 その当時、付近の漁業権は下宮、そのころは下宮と呼ばれました。伊那下神社が漁業権をもっており、二艘の鰹舟(明神丸)を所有していました。この舟は供採船(カミノヨブネ)と呼ばれ、神さまにおえするために幕府から特別に許された船です。その舟には明神丸と書かれた幟旗を掲げ、漁労をしました。里人たちの生活は神さまのお陰で保証されていたんではないでしょうか。この明神丸の幟は、供採幟(カミノヨノボリ)と言われ、御差置と称えられました。特に尊重された鰹舟の安堵状、免許状でした。明治初期まで認められており、明治二年には、韮山県にたいして、カミノヨ船の儀は先例によって差し置かれるようにとの願い出に、韮山県から、これまで通り取り立て苦しくないと返答しています。だいたい600年もの間、恩典をうけていたことになります。 鎌倉時代の御成敗式目、その当時の法律ですが、第一条に、神社を修理し祭祀を専らにすべきこととありまして、神社をきれいに整備し、おまつりを盛んにすることは神の御威力(ミイツ)を高めることであり、それは、取りも直さず、私たちがより大きな神の恵みを頂くことにほかならないと言っています。つまり、祭りには、欲得がありません。里人みんなで豊年万作を祈り、大漁を祈り、そして、取れた物を先ず、氏神様、先祖さんにお供えし、それから、お下がりを皆なでいただき感謝してお祝いします。こうしたことが祖先(おや)から子、子から孫へと、連帯と受け継がれてきました。今を生きる人と人が、神社を心のよりどころとして、ささえ合って、励まし合って、お互いが協力し合うという心の要ともなるものでした。それが、地域の共同体を支える大きな力となるんだと、この第一条を掲げていると思います。 また、鎌倉時代には源頼朝公が寄進したと伝える松藤双鶴鏡(国宝まで指定された鏡です)江戸時代には、伊豆の金山奉行の大久保長安が寄進した金銅製釣灯籠(これは県の指定の文化財です。)それから韮山の代官江川太郎左右衛門が参詣の折、寄進した伊那下の神号額があります。あるいは、弁財船の絵馬が残っており、江戸や名古屋の、廻船を営んだ船乗りたちの名前が書かれていまして、伊那下神社が地元のみならず、駿河湾を往き来した人たちからも信仰をあつめていたことをこの絵馬が教えてくれます。そして山岡鉄舟書、入江長八鏝仕上げの伊那下の大額など、各時代を背景にして武門武将の崇敬厚く、神社が心のよりどころとなって来ました。 拝殿向左の舞殿に『長和久理』と書かれた額があります。和は長く、理は久しと読みます。和することは、とこしえに長く栄え、ことわりのあること、道理に叶ったことは、幾久しく栄えるという人生や社会の理念をあらわしています。11月2.3日神社の例祭には、この舞殿で地元の若者たちが三番叟を奉納し、神さまの御心を和め、天下太平、五穀豊穣、千秋万歳を舞い納めます。世界が平和で、お米をはじめとした食べ物が豊かに稔り、千年も万年も、いつまでも生きられるように、長く栄えますようにとの御祈祷でもあります。先人たちが、口伝えに郷土芸能の形を変えずに受け継いて来たということ、それは、人の命には限りがありますが、その形を受け継ぐことで連帯と先人たちの心が永久に今の人たちに生きている。祖先(おや)と共に生きている。ということだとおもいます。 祖先が子孫繁栄を祈り、暮らしの便利をよくしてきから現在の恵まれた生活があります。そのお陰に感謝の心をあらわします。もし祖先たちが過ちを犯し、してはならないことがあったら、それを反省し、立派な人、立派な郷土、立派な国をつくろうというのが、敬神崇祖の発露だと思います。 社務所には「礼を以て心を制す」の書があります。礼と言うのは、相手に対する思いやりの心を形に表すと言うことですので、神さまにも、人に対してもこの感謝の心を形に表すことが大切だと思います。目に見えない神、仏をあらわすことの大切さ、神棚、仏壇に手を合わせて形に表します。神棚まつりは、毎日の祈りをとうして、「子供や孫に感謝の心、命の大切さを伝えてゆきたい、自分の事だけでなくみんなが幸せに暮らせるように祈る」ということですので、神を敬い祖先(おや)を崇めるという教えは、各家毎にあってこそ、家庭が治まり、地域が治まり、国が治まる。といことだと思います。 だからこそ、日本人の精神として受け継がれ、そして次の世代に伝えて行くという責任感があったと思います。 神社とは神の住みます人人のひとつのこころからだをばいふ 人人に普く神の住みませばその御殿舎(みあらか)を神社といふ かむながらの道より という和歌があります。 神社というのは、そこに住む人々の心の表れであり、心のよりどころにならなければならない所です。お寺お宮を見ればそこに住む人の心がわかると言われます。 神、仏を信じる心が美しい建物となり、そこに住む一人一人が神、仏を信じ、感謝の心を捧げてこそ神社なんだと思います。 昨今、各地域で過疎化と高齢化が進み、子供や若者が減少し、神社のまつりを中心とした伝統文化の継承が年々難しくなっています。集落の限界が叫ばれる地方もあるそうです。伝統文化を受け継ぐには何か配慮が必要だとおもいますが、今、神職として思えば、できる、できないではなく、こころざし次第だと私は思っています。 |
|
 ■リーダーの易経 / 時の変化の道理を学ぶ まず始めに指摘しておくべきことは、「易経」は単なる占いの本ではないということだ。本書でも最初にこの点を指摘している。ここを理解できないと、「占いなんて・・・」という至極当然の反応を起こし、折角のチャンスを逃してしまう。 易経は四書五経の筆頭にあげられる儒教の経典であり、帝王学の書、すなわち国を治める君主が学ぶべき書物とされてきた。なぜ、占いと帝王学が関係するのかと言えば、わずかな兆しから将来を察する直観力が、時の流れを見抜く洞察力が、栄枯盛衰の変化の道理をわきまえることが、リーダーには求められるためだ。将来を見通すのに必要なのは占いなのではない。時の変化の原理原則を知ることだ。荘子には「占わずして吉凶を知る」と、荀子には「善く易を為むる者は占わず」とある。そのためのテキストが「易経」である。 本書は、易経の内容を帝王学(リーダー論)という観点から平易に解説したものである。易経に示されている六十四卦の中から、最も代表的な卦である乾為天を詳述し、その他のいくつかの卦をもって補足している。乾為天は、龍伝説に喩えて記されており、地に潜んでいた龍が力をつけ、飛龍になって勢いよく昇り、そして降り龍となるという龍の成長過程になぞらえて、栄枯盛衰の変遷過程を説いている。そこには、人や組織の成長と衰退の原理原則が明らかにされており、成長の各段階において、リーダーとして為すべきことが示されている。 乾為天において、龍は次の六段階を経るとされる。 1 潜龍:地に潜み隠れたる龍。 確乎とした高い志を描き、実現のためにの力を蓄える段階。 2 見龍:人を見て学ぶ龍。 師となる人物を見付け、基本を修養する段階。 3 君子終日乾乾す:一日中、朝から晩まで、意志をもって努力する龍。 自分の頭で考えて創意工夫し、独自性を生み出そうとする段階。 4 躍龍:タイミングを計る龍。 独自の世界を創る手前の段階。 5 飛龍:大空を飛翔する龍。 一つの志を達成し、隆盛を極めた段階。 6 亢龍:傲り高ぶりのために降り龍となる。 一つの達成に行き着き、窮まって衰退していく段階。 この乾為天が易経を代表する卦である理由は、乾為天がすべて陽からなるためだ。易経は陰陽思想を基礎とするが、陰と陽は1つのものの二面であり、陰と陽は変化して循環し、陰と陽は交ざり合うことで新たなものへと進化する。陰と陽のいずれか一方がなくなれば、変化、成長、発展はない。この観点から、すべて陽からなる乾為天の危険性が窺い知れる。このため、潜龍、見龍、君子終日乾乾す、躍龍を経て、飛龍へと成長していく過程において、陰の要素が重要だと指摘されている。 陽は、積極、剛健、推進を表す。陽は強く、常に前に進む。このため、飛龍はワンマンになりやすく、自分の力を誇示して、周りと能力を競ってでも大将でいたいと思う。人の言うことは聞かないで、自己主張する。飛龍が亢龍にならないためには、受容、寛容という陰の要素が肝心である。易経が説く陰陽思想とは、このようなものである。 リーダーたらんとする志を持つのであれば、易経の教えに耳を傾けるべきであろう。 |
|
 ■鉄の蛇 |
|
|
■日高見国(ひたかみのくに)
日本の古代において、大和または蝦夷の地を美化して用いた語。『大祓詞』では「大倭日高見国」として大和を指すが、『日本書紀』景行紀や『常陸国風土記』では蝦夷の地を指し大和から見た東方の辺境の地域のこと。 『釈日本紀』は、日高見国が大祓の祝詞のいう神武東征以前の大和であり、『日本書紀』景行紀や『常陸国風土記』での日本武尊東征時の常陸国であることについて、平安時代の日本紀講筵の「公望私記」を引用し、「四望高遠之地、可謂日高見国歟、指似不可言一処之謂耳(四方を望める高台の地で、汎用性のある語)」としているが、この解釈については古来より様々に論じられている。 例えば、津田左右吉のように、「実際の地名とは関係ない空想の地で、日の出る方向によった連想からきたもの」とする見方もある。神話学者の松村武雄は、「日高見」は「日の上」のことであり、大祓の祝詞では天孫降臨のあった日向国から見て東にある大和国のことを「日の上の国(日の昇る国)」と呼び、神武東征の後王権が大和に移ったことによって「日高見国」が大和国よりも東の地方を指す語となったものだとしている。また、「日高」を「見る」ということでは異論はなく、「日高」は「日立」(日の出)の意味を持つので、『常陸国風土記』にある信太郡については、日の出(鹿島神宮の方向)を見る(拝む)地、ということではないかともされ、旧国名の「常陸」(ヒタチ)は、「日高見道」(ヒタカミミチ)の転訛ともいわれる。 その他様々にいわれているが、いずれにしろ特定の場所を指すものではないということでも異論はなく、ある時の王権の支配する地域の東方、つまり日の出の方向にある国で、律令制国家の東漸とともにその対象が北方に移動したものと考えられている。北上川という名前は「日高見」(ヒタカミ)に由来するという説もあり、平安時代には北上川流域を指すようになったともされている。戊辰戦争直後には北海道11カ国制定にともない日高国が設けられ、現在は北海道日高振興局にその名をとどめる。 ■新説 金田一京助は、「公望私記」が「四望高遠之地」とするのを批判し、「北上川」は「日高見」に由来するという説を唱えている。高橋富雄は、この「日高見」とは「日の本」のことであり、古代の東北地方にあった日高見国(つまり日本という国)が大和の国に併合され、「日本」という国号が奪われたもの、としている。歴史書などの史料による裏づけがあるわけではないが、いわゆる東北学のテーマとして、話題になっている。 |
|
|
■アラハバキ
日本の民間信仰的な神の一柱である。現在、公的な観光案内類を含め、源流を辿ると偽書である『東日流外三郡誌』に由来する記述が見られることがあり、非常な注意を要する。 起源は不明な点が多く、歴史的経緯や信憑性については諸説ある。 偽書『東日流外三郡誌』の中で遮光器土偶の絵が示されているため、フィクション作品中などでそのようなビジュアルイメージが利用されることから、その印象に引きずられている例も見られるなど、古史古伝・偽史的な主張において利用されたり、それらが学術的に確認されたものと誤認されることも多い。 荒脛巾神の祠がある神社は全国に見られるが、その中には客人神(門客神)としてまつられている例が多い。客人神については諸説があり、「客人(まれびと)の神だったのが元の地主神との関係が主客転倒したもの」という説もある。 ■偽書『東日流外三郡誌』における扱い 偽書である『東日流外三郡誌』では以下のようにある。従って、アラハバキに関し、この節にあるものに類似した記述には一般に注意を要する。 「まつろわぬ民」であった日本東部の民・蝦夷(えみし、えびす、えぞ)がヤマト王権によって東北地方へと追いやられながらも守り続けた伝承とするもの。荒脛巾神(あらはばきがみ)ではなく「アラハバキカムイ」といい、遮光器土偶の絵が付されている(遮光器土偶は、『東日流外三郡誌』の地元である津軽の亀ヶ岡遺跡のそれが特に有名である)。また神の名だけではなく、民族の名としても使われ、蝦夷(えみし)という呼び方は大和朝廷からの蔑称であり、自称は「荒羽吐族」であるとしている。このため、神の名ではなく民族の名としてのアラハバキも一部に知られることになった。『東日流外三郡誌』では、アラハバキカムイは荒羽吐族の神々という意味の普通名詞ないし称号であり、具体的には安日彦と長髄彦であるとする説、いにしえの神で安日彦長髄彦と似た境遇(追放?放浪?)の神だったという説、イシカホノリ(「末代の光」という意味)という名の神であるとする説、死の神イシカと生命の神ホノリの二神であるとする説、などが出てくる。いずれにしろ『東日流外三郡誌』では、アラハバキというのは元は民族の名であって神の名ではなく、「アラハバキ族が信奉する神」という意味で後に神の名に転じたという認識になっている。 ■武内裕/縄文神説 / 縄文神の一種という説が雑誌『ムー』等でよくいわるが、これは『東日流外三郡誌』を独自に援用した武内裕が70年代に唱えたのが最初である。 ■アラハバキ諸説 ■足腰の神説 / 民間の俗説 「荒脛巾神」という文字から、脛(はぎ)に佩く「脛巾(はばき)」の神と捉えられ、神像に草で編んだ脛巾が取り付けられる信仰がある。多賀城市の荒脛巾神社で祀られる「おきゃくさん」は足の神として、旅人から崇拝され、脚絆等を奉げられていたが、後に「下半身全般」を癒すとされ、男根をかたどった物も奉げられた。神仏分離以降は「脛」の字から長脛彦を祀るともされた。 ■蛇神説 / 吉野裕子 吉野裕子の、かつての日本の、蛇を祖霊とする信仰の上に五行説が取り入れられたとする説で唱えられているもの。吉野によれば、「ハバキ」の「ハハ」は蛇の古語であり、「ハハキ」とは「蛇木(ははき)」あるいは「竜木(ははき)」であり、直立する樹木は蛇に見立てられ、古来祭りの中枢にあったという。伊勢神宮には「波波木(ははき)神」が祀られているが、その祀られる場所は内宮の東南、つまり「辰巳」の方角、その祭祀は6、9、12月の18日(これは土用にあたる)の「巳の刻」に行われるというのである。「辰」=「竜」、「巳」=「蛇」だから、蛇と深い関わりがあると容易に想像がつく。ちなみに、「波波木神」が後に「顕れる」という接頭語が付いて、「顕波波木神」になり、アレが荒に変化してハハキが取れたものが荒神という説。 ■塞の神説 / 谷川健一 宮城県にある多賀城跡の東北に荒脛巾神社がある。多賀城とは、奈良・平安期の朝廷が東北地方に住んでいた蝦夷を制圧するために築いた拠点である。谷川健一によれば、これは朝廷が外敵から多賀城を守るために荒脛巾神を祀ったとしている。朝廷にとっての外敵とは当然蝦夷である。つまりこれは荒脛巾神に「塞の神」としての性格があったためと谷川は述べている。さらに谷川は、朝廷の伝統的な蝦夷統治の政策は「蝦夷をもって蝦夷を制す」であり、もともと蝦夷の神だったのを、多賀城を守るための塞の神として祀って逆に蝦夷を撃退しようとしたのだという。また、衛視の佩く脛巾からアラハバキの名をつけたともいっている。 ■製鉄民説 / 近江雅和 先の、多賀城跡近くにある荒脛巾神社には鋏が奉納され、さらに鋳鉄製の灯篭もあるという。多賀城の北方は砂金や砂鉄の産出地であり、後述する氷川神社をも鉄と関連付ける説がある。近江雅和は門客人神はアラハバキから変容したものであると主張、その門客人神の像は片目に造形されていることが多いことと、片目は製鉄神の特徴とする説があることを根拠として、近江は「アラ」は鉄の古語であると主張し、山砂鉄による製鉄や、その他の鉱物を採取していた修験道の山伏らが荒脛巾神の信仰を取り入れたのだという。また足を守るための「脛巾」を山伏が神聖視していたと主張、それが、荒脛巾神が「お参りすると足が良くなる」という「足神」様に変容した原因だろうと推測している。真弓常忠は先述の「塞の神」について、本来は「サヒ(鉄)の神」の意味だったと述べていて、もしその説が正しければ「塞の神」と製鉄の神がここで結びつくことになる。 ■氷川神社との関係 荒脛巾神が「客人神」として祀られているケースは、埼玉県大宮の氷川神社でも見られる。この摂社は「門客人神社」と呼ばれるが、元々は「荒脛巾(あらはばき)神社」と呼ばれていた。だが、現在の氷川神社の主祭神は出雲系であり、武蔵国造一族とともにこの地に乗り込んできたものである。これらのことを根拠として、荒脛巾神は氷川神社の地主神で先住の神だとする説もある。 氷川神社は、出雲の斐川にあった杵築神社から移ったと伝わり、出雲の流れを汲む。出雲といえば日本の製鉄発祥の地である。しかし、音韻的に斐川は「シカワ」から転訛したという説と、氷川は「ピカワ」から転訛したという説を双方とって、両者に全く繋がりはないという説もある(しかし、シカワ説もピカワ説も格別有力な説というわけではない)。 この大宮を中心とする氷川神社群(氷川神社、中氷川神社、女氷川神社に調神社、宗像神社、越谷の久伊豆神社まで含めたもの)はオリオン座の形に並んでおり、脇を流れる荒川を天の川とすれば、ちょうど天を映した形になっているとみる説もある。氷川神社は延喜式に掲載されている古社ではあるが、氷川神社の主祭神がスサノオであるという明確な記述は江戸時代までしか遡れない。 ■四天王寺との関係 聖徳太子が、物部守屋との仏教受容をめぐる戦いを制して、日本初の大寺である大阪市の四天王寺を建てたが、この四天王寺について、アラハバキ及び縄文系との関わりを指摘する者もいる。四天王寺の敷地の元来の地名は「荒墓邑」(あらはかむら)である。四天王寺の北側に磐船神社(饒速日命の降臨地)が元々あったとされ、物部氏は饒速日命を始祖とする一族であるから、この四天王寺の地は本来、物部発祥の聖地であったという説もある。 |
|
|
■一
蝦夷研究の第一人者である高橋富雄「古代蝦夷を考える」では、北上川の水源を、岩手山と姫神山が東西で並ぶ辺りが川としてほぼ尽きる事から、その左右に並ぶ山に影響され、信仰ないし伝説が生じたと考えた。 北上川とは古代は日高見川である事から、そのヒタカミの名を有する山として姫神山に着目した。姫神山(1124m)は、日高見の名を留める最北の証であると。姫神(ヒメカミ)は転訛であろうとし、ヒタカミ→ヒナカミ→ヒンカミ→ヒメカミが、その転訛の過程であろうと推定している。その日高見(ヒダカミ・ヒタカミ)は、ヒナカミ、ヒノカミ、ヒカミとも転訛されている事は、ほぼ疑いの無い事だとしている。 その北上川であり日高見川は、姫神山の麓を水源として岩手の内陸部を流れ、宮城県の石巻市から、その流れを海へと注いでいる。「延喜式神名帳」に名を記している桃生郡鎮座している日高見神社は「三代実録」によれば本来”日高見水神社”であり、日高見川の河神を祀っていたとされている。つまり日高見の基点が姫神山の麓であり、終点が日高見水神社であるのが、日高見川の流れであるという事は、それが日高見国の示す範囲を意味しているのかもしれない。 高橋富雄は、陸前高田に鎮座する氷上神社も本来、日高見神社であったろうとしている。その氷上神社の現在は、衣太手神、理訓許段神、登奈孝志神を祀っている形だが、もしくは天照大神、素戔男尊、奇稲田姫を祀っているとも云われる。本殿の両脇には、末社として足名椎命・手名椎命が配されている事から、素戔男尊、もしくは奇稲田姫のイメージが思い浮かぶ。 氷上神社の境内で気になったのは、池の中に戸隠明神として九頭竜が祀られていた。九頭竜は国津竜でもあり、十一面観音を祀る長谷寺の地主神でもある。その長谷寺での九頭竜とは本来、滝神である事がわかっている。そこでフト、本殿を両脇にある、足名椎命・手名椎命を祀る末社を思い出したのだが、足名椎命・手名椎命とは、「足が無い、手が無い」という意味で蛇であると、吉野裕子「蛇」では指摘している。そしてその話に登場する素戔男尊は、ヤマタノオロチを退治して、その尻尾から草薙の剣を手にしている。そうしてみると、まるで氷上神社には蛇を祀っているイメージが重なるのだ。 ところで同じ氷上神社でも、奥州市にある氷上神社を見てみよう。この奥州市氷上神社の創建は「元和三丁巳歳(1617)三月。別当内野三蔵院、気仙郡高田村(現陸前高田市)に鎮座せる氷上神社の御分霊を小梁川右膳地行の御除地たる烏帽子山頂に勧請せしに始まる。」とあり、陸前高田の氷上神社の分霊である事がわかる。しかし、その神の名は瀬織津比咩であり、早池峯の神と同じであった。瀬織津比咩は穢祓の神ともされているが、本来は水神であり龍蛇神でもある。陸前高田の氷上神社に龍蛇祭祀が色濃く出ている事と、関係があるのだろうと思われる。 |
|
|
■二
岩手県で一番高い山は、岩手山(2041m)である。その岩手山には、坂上田村麻呂伝承が強く残っているが、ある意味蝦夷征伐を為した坂上田村麻呂であるから、それは勝利者による偽りの伝承とみても良いのだろう。ただ全て偽りという訳では無く、その中には真実を包み隠しているものがあると思われる。例えば、岩手三山伝説である。姫神山は、男神の婦神山(めかみやま)とされてきた。しかし、その姫神山とは別に、早池峯山もまた正妻、いや妾であるという伝説がある。つまりこれは、蝦夷国を支配した朝廷側が一番高い岩手山を支配した形で語られ、それに従えようと姫神山と早池峯山をも支配したという意味にも捉える事が出来る。 岩手山は以前、巖鷲山(がんしゅざん)と呼ばれた。巖鷲山は「がんしゅ」という音が後に「岩手(がんしゅ)」として充てられ、いつしか現在の岩手山(いわてさん)となった。その岩手山に関わる「巖鷲山縁起」には田村麻呂が伊勢国の鈴鹿山で立烏帽子と名乗る神女・鈴鹿明神と出会い、導かれるまま岩手郡の巖鷲山に巣食う大武という鬼退治に至った。この後に鈴鹿明神は巖鷲山の東の峰に祀られ、里人はこれを御姫嶽と呼び、立烏帽子の神女是なりと記されている。ところが調べれば、この鈴鹿明神は、早池峯の神でもある事がわかった。その事実は、伊勢神宮の祭祀でも確認できるのだが、これは後に記す事とする。 高橋富雄の言う通りに、姫神山が元々日高見の転訛からの名付けられた山であるならば、姫神山に祀られる神と、北上川の終点に位置する、河神である水神を祀っていたとされる日高見水神社が祀る神とが同一でなければ、意味が通じなくなる。その姫神山に祀られる神とは、早池峯山と同じ瀬織津比咩という神である。つまり、岩手山山伝説というものは、蝦夷国を支配した朝廷側が岩手山の名を借りて、姫神山と早池峯山に鎮座する瀬織津比咩を支配したという話に捉える事が出来るのだ。早池峯神社と姫神嶽神社の成立はどちらも大同年間となる。ここでの問題は、大同年間に瀬織津比咩が祀られたのか、それ以前から祀られていたのかという事になるだろう。 早池峯神社の伝承には、始閣藤蔵が来内の地にて早池峯に向かい、金が採れたら宮を祀ると祈願した結果、見事に金は採れて、始閣藤蔵は早池峯の山頂に宮を建てたという事である。これは早池峯神社の創建に関わる伝承ではあるが、よくよく読めば、既に早池峯には神がいたという事になる。その神に祈願して金が発見されたという事だろう。 早池峯神社の本殿には、画像に見られる鉄滓を絵馬としたものが奉納されている。鉄滓はノロとも呼び、タタラの過程で出る金糞でもあるが、花の様に見える事から初花と云われ、これをタタラ場では金屋子神に捧げるという。それと同じものが、早池峯神社の神に奉納されている。これは早池峯の神が水神であり、穢祓の神ではあるが、早池峯山に鎮座している山神であるからとも捉える事が出来る。だが鉄滓は金糞であり、役に立たないレッテルを貼られているが、火之迦具土神を産んだ為に伊邪那美が死に、その糞尿から金屋子神が生まれているのだが、それと共に弥都波能売神も生まれているのだ。 弥都波能売神は別にミヌマとも呼ばれ、水沼君の水神を意味する。この水沼君の水神とは、詳細は不明だが宗像神の以前に祀られていた水神であるようだ。それが何故か、伊邪那美の糞尿から化生している。奇しくも、遠野の多賀神社に祀られる祭神は、伊弉諾と何故か水神である弥都波能売神であるが、これは近江国の多賀大社から分霊されたものとして「多賀大社文書」には記録されている。 水神である弥都波能売神は竜蛇神とも結び付けられているが、実は鉄滓である金糞のノロの形も、花以外に蛇として見立てられていたという伝承がある。つまり、早池峯神社に奉納されていた鉄滓である初花は、鉄の蛇でもあったのだろうか。考えてみれば、役に立たない鉄の意を持つ鉄滓だが、片手が無い、片足が無いのも役立たずのレッテルが貼られているが、その片足、片手に結び付けられるのは蛇でもある。蛇は、無駄なものを排除した究極の形であるとされているが、人間の立場に立てば、手も足も無いというのは役立たずでもある。その役立たずのレッテルを貼られた鉄滓が、蛇の見立てだとしても、何ら不思議でもない。 |
|
|
■三
アラハバキは、荒覇吐、荒吐、荒脛巾などの漢字をあてる。アラハバキの「アラ」は、山伏用語で「鉄・砂鉄」を意味するが、「鉄の蛇(日高見とアラハバキ)其の二」で画像を紹介した早池峯神社に奉納されている初花である鉄滓の絵馬もタタラで世界ではアラと呼び、鉄を意味する。 素戔男尊がヤマタノオロチ退治に使用したのは十拳剣であるが、別名天之尾羽張(アメノオハバリ)剣、または天羽々斬(アメノハハキリ)剣と云う。その天羽々斬もまた、別に布都斯魂剣(フツシミタマノツルギ)、蛇之麁正(オロチノアラマサ)とも云うのだが、ハハは蛇の古語でもあり、ハハキは箒でもあり、やはり蛇を意味する。ヤマタノオロチを退治した剣もまた蛇であり「蛇を以て蛇を制す」であったのだろう。そして、ヤマタノオロチもまた尻尾から草薙の剣を生み出している事から、ヤマタノオロチもまた鉄の蛇の意であろうか。つまりアラハバキとは、鉄の蛇を意味するか、鉄を作る蛇の民の意であるのだろう。画像は、遠野に隣接する住田町の荒脛神社内に奉納されている、藁製の草履と、鉄製の草履だ。いつしか本来の意味が伝わらず、アラハバキという音から連想された、脛から履物にまで零落してしまったのだろう。 東和町の丹内山神社の御神体に、アラハバキ大神の巨石がある。その丹内山神社の創建は、承和年間(834~847)に空海の弟子が不動尊像を安置し、「大聖寺不動丹内大権現」としたのが始まりであると伝えられる。「丹内」は「種内」とも「胎内」とも伝えられる。「種内」も「胎内」も大まかに言えば、内包される意味を有する。御神体の巨石にも穴があり、そこを潜る事を「胎内潜り」と云う事から、「丹内」と「胎内」は御神体の大岩を通して出来た神社名では無いかとの推測が成り立つ。 また当初は「大聖寺不動丹内大権現」というのは「権現」そのものが神々の借りの姿をいう事から、不動明王というのは神々の表だった借りの姿である。「胎内仏」という言葉もあるように、本来は表だっての不動明王であり、その胎内には本来の神が眠っていると考えて良いだろう。そういう意味を含んでの丹内山神社であろうと自分は考える。ところが「谷内権現縁起古老伝」には「当社の大神は地神なり。同郡東晴山邑滝沢の滝に出現す。」とある。「谷内権現縁起古老伝」に記される「滝沢の滝」とは、現在の滝の沢神社の御神体と祀られる滝である。その神社こ祀られる祭神の名は、早池峯に祀られる瀬織津比咩である。実際に丹内山神社へ行くとわかるのだが、参道を通って本殿へ行くと丹内山神社の方向が、滝の沢神社へ、そして早池峯山に向けられているのがわかる。つまり、丹内山神社と滝の沢神社と早池峯が一直線に並ぶ様に意図して建てられたのだろう。ある意味、丹内山神社は早池峯神社の遥拝所でもあると思われる。そして、アラハバキ大神の大岩だが、遠野の東禅寺内にある影向石と同じであろう。東禅寺の影向石もまた、早池峯大神が降り立った石である。丹内山神社の大岩もアラハバキ大神の降り立った大岩の意であろう。 実際に、丹内山神社には、早池峯神社と同じく鉄滓の絵馬が奉納されている。初花としての鉄滓は、金屋子神に奉納するのだが、鉄の蛇としての鉄滓は、アラハバキ大神に奉納するのかもしれない。とにかく、丹内山神社を通して、アラハバキ大神とは早池峯大神でもあり、その名が瀬織津比咩である事が理解できるのだ。ところで気になるのはアラハバキ大神の大岩の案内板に坂上田村麻呂の名が登場し崇敬していたと記されている。ここで、岩手山を拠点とした坂上田村麻呂が、姫神山と早池峯山の同一の女神である瀬織津比咩を、いかに意識していたかわかるようなものである。 |
|
|
■四
丹内山神社でアラハバキ大神と早池峯大神が同体であるという、一つの証明になったとは思う。それとは別に、氷上神社を考えてみたい。高橋富雄によれば、陸前高田の氷上神社は本来、日高見神社であろうとしている。奥州市の氷上神社は、その陸前高田の氷上神社から瀬織津比咩が分霊されて創建された氷上神社だ。しかし陸前高田の氷上神社には、その瀬織津比咩名前は無いのが現状となっている。だが、境内を散策すると、そこには水神らしき竜蛇神が祀られているのが理解できる。 また、住田町の高瀧神社は、陸前高田の氷上神社から分霊されたのは瀧神でもあり、鉄の草鞋を奉納した事から、アラハバキ神でもあろうとされる。具体的な神の名は無いが、奥州市の氷上神社に祀られている瀬織津比咩とは瀧神でもある事から、高瀧神社に祀られる神とは瀬織津比咩であったろうと思われる。しかし、瀧神そのものを陸前高田の氷上神社に見つける事が出来ない。つまり、陸前高田の氷上神社から、瀬織津比咩の名前が消されたとう事が理解できる。 「延喜式神名帳」に記載される陸奥国桃生郡に鎮座する日高見神社は本来、日高見水神社であり、日高見川(北上川)の河神を祀る神社とされていたようだ。高橋富雄によれば、その日高見国は岩手山と姫神山の間を水源とし、姫神山が日高見の名の転訛の元に付けられた名であろうと説いている。そして日高見国の基点が姫神山の麓から始まり、 桃生郡の日高見水神社までの北上川流域でなかったかと推測している。しかしそれでは、陸前高田の氷上神社が日高見神社であったならば、北上川から距離的にもかなり離れている為に疑問も残るところだ。しかし、陸前高田の氷上神社と日高見神社の結び付きを見いだせるならば、それはアラハバキ大神を祀るという点で結びつくのではなかろうか。 陸前高田の氷上神社から分霊された高瀧神社には、瀧神でありながら、鉄の草履が奉納されている。それは、瀧神である神がアラハバキ神でもあったという残存でもある。実際、アラハバキ大神と瀧神の融合は丹内山神社で明らかになっているが、陸前高田の氷上神社もまた同じであろうと推測できる。 古老の話では、室根山と氷上山は狼煙で繋がっていたという話を聞いた事がある。狼煙といえば、安倍氏の館繋がりで、次々と狼煙を上げて奥に伝えていたという伝承があるが、確かどこかの大学が、早池峯山と岩木山が古代に狼煙で繋がっていたという事を検証する為、岩木山で上げた狼煙を早池峰山頂かせ見る事が出来るかという実験が行われ、それは見事に実証できたと。古代の蝦夷は、山伝いに狼煙で連絡していたという。当然、室根山と氷上山が繋がっていたとしても、何等不思議ではない。 ところで、陸前高田の氷上神社には、理訓許段神社、登奈孝志神社、衣太手神社の三社が祀られているが、それぞれ西宮・中宮・東宮とされ、それは本来、室根山、氷上山、五葉山に祀られているものが氷上神社の里宮と奥宮にまとめられたものであろうとされている。これを仮に気仙三山とでも言おうか。しかし、それとは別に、五葉山を起点としての三山が別にある。それは、五葉山、六角牛山、早池峯山の三山である。これらを全て繋げた場合、室根山から始まって、早池峯山まで狼煙のラインが出来上がるのだ。そして当然、早池峯山から岩木山まで繋がる壮大な狼煙のラインとなる。古代の蝦夷は山を支配し、狼煙による連絡網を敷いていたというのは、現代でも証明できたのは先に紹介した通りである。更に突き詰めれば、古代の山々は、神々で繋がっていたとも考えられる。 |
|
|
■五
前回、五葉山の名前が登場したが、五葉山山頂には日枝神社が鎮座し、また画像の日の出岩と呼ばれる巨石があり、太陽信仰の名残だと云われている。自分もそれまでそれを信じてきたが、日高見(ヒタカミ)を調べていくと、それは違うのではと思えてきた。 氷上神社もまた、氷上(ヒカミ)であり日神(ヒカミ)を祀るとされていた。そして、日高見もまた「ヒタカミ」であり、日の高みをイメージされている。それは「ヒ+タカミ」と区切り考えられた為でもあった。 月が東方から昇る意は何かというと「ヒタ」と云われる。常陸は「ヒタミチ」とされ「ヒタカの道」とされる。「日本書紀(景行天皇二十七年二月)」に「東の夷の中に、日高見國有り。」とある。また「常陸国風土記」に「この地は、本、日高見国なり」とあるのは、日高見国は、常陸国の東方を差していた。つまり常陸国とは日高見国の入り口の意でもあった。 「古今和歌集」の注釈に「ひさかたとは、月の異名也。此月、天にあるゆへに突きにひかれて、そらをもひさかたのあめと云へり。」とあるが、「久方(ひさかた)」の「かた」は「区切られた所、県・国」を意味する。そして常陸が「ひた+ち」であり、日高見が「ひた+か」の組み合わせであるが「か」は「場所」を意味する事から「ひさかた」も「ひたか」も同じ意である事がわかる。つまり「ひさ」も「ひた」も月の意であった。 長く日高見国は、太陽が高く差し込み照らす広く平らな国とも解釈されていたが、「ひた」を月の意に変えれば、日高見の「見」は「望む」でもあるので、常世思想の中に月が東の海辺に接する理想的な地という観念が、日高見ではないかとの説がある。つまり日高とは常世であり、常世辺でもあるという事から、日高見国とは、その理想的な常世辺を望む地の意ともなる。この常世思想であり浄土思想は、奥州藤原氏の理想とした世界である事も付け加えておこう。 古代人は、夜の闇を恐れていたという。それ故、夜世界とは神か、魑魅魍魎の跋扈する世界だと思われていた。太陽が昇って、やっと人間の世界が始まると思われていた為、神世界である夜の始まりが一日の始まりでもあった。つまり神を迎えるのは夜であった事を考えれば、五葉山での信仰の本来、月迎え信仰では無かっただろうか?例えば、遠野の白望山山頂にある石碑は、月迎えの信仰であり、それは星の信仰に繋がるものであった。太平洋から昇るのは太陽でもあり、月でもある事を踏まえれば、五葉山で信仰されていたのは月信仰であったとしても不思議ではない。太陽暦が導入されたのは持統天皇(645年~703年)時代ではあるが、それが巷の世に普及したのは、かなり後になったからであった。 月には変若水信仰が付随し、月神と水との繋がりは深い。陰陽とは太陽と月であり、男と女を表している事から、水神とはたいていの場合女神である。各風土記に、男神と女神の争いを記したものがいくつかある。それは、水の流れの争いであるが、最後は女神が勝利して、男神はその山から立ち去るという伝承は、現在の山々に祀られる神が殆ど女神である事を考えた場合、かなり象徴的な伝承であると思う。 その女神であり水神である瀬織津比咩が、早池峯に祀られ、姫神山で、そして室根山で祀られている。そしてそれが恐らく氷上山にも祀られているとなれば、恐らく五葉山もそうなる可能性はああるだろう。つまり、仮の気仙三山、室根山・氷上山・五葉山。そして、釜石からの沿岸の三山が、五葉山・六角牛山・早池峯山となれば、それは一つの瀬織津比咩ラインを意味する。それは蝦夷平定の際に、朝廷が一斉に祀ったのではなく、元々祀られたものを改編した可能性が見いだせる。 例えば氷上山と五葉山が日神信仰であるとは説いているが、それが持統天皇時代の天照大神との結び付きと太陽暦の導入に対応させる為、月信仰を太陽信仰に改めたと考えれば納得するものである。 蛇信仰で有名な三輪山は円錐の形であり、それは蛇のとぐろを巻いた姿であると信仰されてきた。カカでありカガは、蛇の古語として鏡餅(カガミモチ)は、蛇のとぐろを巻いた姿を現したものであった。 画像は、室根山と姫神山だが、やはり円錐形をしている。古代人は、どこかでその山に、蛇を見出したのかもしれない。似た様な円錐形の山に竜蛇神を祀るのは自然の流れなのだろう。それでは早池峯はどうかといえば、手前の薬師岳を"前薬師"という事から、まとめて早池峯に属する山と考えられていたのだろう。その薬師はやはり、円錐形の山であり、三輪山を意識せざる負えない。ただ気仙三山全てが円錐形では無いし、必ずしも蛇信仰は山の形から入るだけでは無いのはわかる。ただ山神の使いとしての動物は、蛇・狼・猪である事から考えても、山には蛇・狼・猪を結びつけて考える風潮はあったであろう。水を生み出し、樹木を生み出し、獣を生み出し、鉱物を生み出す山は、「古事記」におけるヤマタノオロチの姿の記述は「檜と椙と生ひ」とあるように、山そのものが蛇であるかのようである。そう思えば、山に祀る神とは竜蛇神となるのは当然の事かもしれない。 |
|
|
■六
古代世界は、蛇に覆われている。アラハバキが鉄の蛇であるならば、それは星の蛇にも成り得る。「日本書紀纂疏」には、こう書かれている。 然らば則ち石の星たるは何ぞや。曰く、春秋に曰く、星隕ちて石と為ると「史記(天官書)」に曰く、星は金の散気なり、その本を人と曰うと、孟康曰く、星は石なりと。金石相生ず。人と星と相応ず、春秋説題辞に曰く、星の言たる精なり。陽の栄えなり。陽を日と為す。日分かれて星となる。 巨石信仰に見られるものは、鉱物である金の信仰でもあるが、それは星の信仰にも繋がる。「雄略天皇記」で空を渡る虹が竜蛇と見立てられたように、夜空にかかる天の川もまた竜蛇に見立てられた。瀧であり、川であり、山であり、虹であり、そして夜空にかかる天の川にさえ古代人は竜蛇を見立てた。蝦夷国において、その様々な竜蛇の頂点に立つのは、早池峯という山になるのだろう。丹内山神社の御神体のアラハバキの大岩は、星であり、金の散気であるのなら、安倍一族が祀った星の宮神社もまた、星の信仰と共に、産金信仰をしていたという事であろう。アラハバキ大神とは、その両方に跨る大神の意でもあろう。 安倍貞任の御魂をも祀っている早池峯は、やはり安倍氏がアラハバキ神を祀ったという貞任山の奥にある新山という地から眺めた姿が上記の画像である。貞任山は、遠野の東西に二つあって、先人の調べによれば、どちらからも早池峯を遠望するようになっているという。薬師岳と早池峯を合わせた姿は、まるで前方後円墳のようであると自分は思う。恐らく安倍貞任も、魂の墓所として早池峯を定めて信仰したのだろう。その安倍貞任を含む安倍一族であり、蝦夷国に住む者達にとっての心の支えが早池峯であり、そこに祀られる瀬織津比咩という女神であったろうと思うのだ。 その瀬織津比咩は、伊勢神宮の荒祭宮に、天照大神の荒御魂として祀られている。近江雅和「アラハバキ神と古代史の原像」によれば、様々な別宮がある中で、内宮神域にあるのは、瀬織津比咩を祀る荒祭宮だけであると。他の別宮とは異なり、神嘗・月次のいわゆる伊勢神宮の三節祭には、幣束が内宮と荒祭宮だけに奉納され、旧四月と旧九月の神衣祭では内宮と荒祭宮だけに神服織殿で織った神衣を供えるなど、内宮の天照大神と同格の扱いを受けて他の別宮とは断然格式が違うのだと。 更に荒祭宮の位置は、式年遷宮をする東西の殿地の中でも一番古い地であり、内宮の古い形を取られており、荒祭宮の祭神こそが、古い内宮の地主神であったろうとされている。皇祖神を祀ると云われる伊勢神宮で、何故にそこまで早池峯大神でもある瀬織津比咩が優遇されるのだろうか? その瀬織津比咩を祀る荒祭宮だが、「子持山縁起」によれば、天武天皇の時代に荒人神として出現したという児持大明神とは正式には「アラハバキ姫」だという。「伊勢神宮のあらがきの内におはします、則ちあらはばき是なり。」と。「あらがきの内」は荒祭宮を示し、そこに祀られる瀬織津比咩とは、アラハバキ姫であり、伊勢の地主神であるという事らしい。 その瀬織津比咩は荒祭宮だけではなく、現在の伊勢神宮の外宮がある伊勢市の山田から宮川を遡った山奥に、皇太神宮の別宮になっている瀧原宮であり「天照大神の遙宮」と呼ばれる別宮がある。「伊勢国風土記」の逸文によれば「倭姫命は、船に乗って度会河の上流にのぼり、瀧原の神の宮を定めた。」とある。そこに祀られる神は「天照大神の荒御魂」であり、即ち瀧神である瀬織津比咩である。そしてその瀧原宮とは遥宮(とおのみや)ともいい、恐らく早池峯の麓の遠野という地の語源になっているのではと考える。実際に、伊勢を離れ遥か遠い野である蝦夷の地の早池峯という山に鎮座させられた遠野の地とは、ある意味遥宮であり、遠野宮である。そのアラハバキ姫とも呼ばれる瀬織津比咩が何故に伊勢の地に祀られ、そして蝦夷国に祀られたのかは、豊受大神と常陸国の関係があるのだと考える。 |
|
|
■七
遠野から和山峠を通った先に、初神という地がある。そこは前九年の役で敗走した安倍一族の末裔が住み付いたと云われている。その初神地には、安倍一族が祀っていた星の宮神社というものがあったが、昭和時代に廃村となり信仰そのものも廃れてしまったようだ。その安倍氏の末裔の某氏は現在笛吹峠を越えたところの青の木に移住しているが、その某さんに星の宮神社の事を聞くと「星の信仰というよりも、天と地と、そして水などの自然を信仰とする壮大な教義だったのを覚えている…。」と答えてくれた。 宮城県岩出山町に、荒脛社がある。その荒脛社の縁起は「祭神は天・地・水の三神を基として、日輪を父なる神、万物を育む地、水を母なる神とする自然信仰で、二千年に及んで鎮座する産土神である。」と、この内容は初神で安倍氏の末裔が祀っていた星の宮神社と同じものであった。 「陸奥抄史」には、こう書かれている。「猿ヶ石南北に存在せる貞任山の二山これに解くべきかぎありとも曰ふ遠野村に今亡き西法寺は日下将軍の建立せし古寺なりと曰ふ荒覇吐神社社貞任山二山にありと曰ふも定かならずと地住の人曰ふ。」 日下将軍とは安倍氏の事であるが、その安倍氏が東西の貞任山にアラハバキ神社を建立したという。しかし現在、その痕跡を貞任山に見出せない。しかし、東の貞任山の南側に下った初神の地に祀られていた星の宮神社の教義は、宮城県の荒脛社と同じであったという事はもしかして、東の貞任山に建立された荒覇吐神社が移転されたものではなかろうか?そう考えて思いつくのは、岩手県住田町にある荒脛神社である。西の貞任山を南方に下った地に鎮座する住田町の荒脛神社も、西の貞任山に建立された荒覇吐神社が移転されたものではないのかとの推測が成り立つ。 ところで星の宮神社を調べると、一番多く密集して建立されている地域は栃木県から茨城現にかけてだ。それは古代において、常陸国を含む毛野国であった。星の宮神社の祭神は、石析神、根析神であったりもするのだが、その殆どは天御中主命(国常立尊)を主祭神として祀っている。新井白石「古史通」において、毛野国と重複する常陸国の那珂川を中心にした地域は那珂郡の領域でもあり、古代においては中ノ国と呼ばれていた。そこを、天御中主命の拠点としている。その常陸国でもある地域に伝わる「花園山縁起」に、こう記されている。 「安倍貞任、宗任ノ兄弟大高城ニ籠リ星ノ御門ノ子孫ナリ。」 初神の安倍氏の末裔によれば、星の宮神社は星を祀る神社では無かったという事だが、常陸国での安倍一族は星の御門の子孫とされている。これはつまり、星に対する概念の問題になるだろう。そこで再び「日本書紀纂疏」を思い起こせば、天から降ってきた隕石が磐座信仰となり、それは金の散気であるという産金・治金信仰でもある。遠野も含め、遠野に隣接する荒脛神社がある住田町もまた産金、治金の地であった事を考えれば、安倍氏が星の御門という定義は当て嵌まるのだろう。 その星の宮神社の主祭神である天御中主命だが、何故か豊受大神と同体であると云われている。「止由気宮儀式帳」によれば、丹波国から豊受大神を向い入れたというが、「丹後国風土記」での豊受大神の物語は昔話風となっているが、元々どこからか飛んできて丹波国に居付いだのが豊受大神であった。それでは豊受大神は、どこから来たのか?という問題が生じる。 ところが常陸国の「我国間記」に「我国ノ御山ハ日本開始メの峰ニシテ、豊受産ノ神社有リ、後に尊ノ号ヲ常立ノ尊ト奉称。…即チ太神宮ナリ後に丹州、今ハ伊勢ニ移リシ給フ。伊勢の外宮、近江多賀大社御同神体ナリ。」とある。丹州とは、丹後国と丹波国の両国を含む中国風の別称となる。この「我国間記」の信憑性には疑問符が付くものの、結局のところ豊受大神とはどこから来たのかが未だに不明である事を考慮に入れ、その豊受大神と天御中主命が同体同神であるならば、伊勢神宮の外宮に祀られる豊受大神の謎に迫ると共に、その外宮の豊受大神を祀る指示が、渡会氏の祭祀権を有する荒祭宮から発せられている。その荒祭宮に祀られているのは、初めに紹介したように、天照大神の荒御魂であり、早池峯大神でもある瀬織津比咩である事から、これからは瀬織津比咩と豊受大神の関係を考える事にしよう。 |
|
|
■八
遠野の六角牛山には、天人児伝説が付随している。天人児とは天女であり、一般的に羽衣伝説と呼ばれるものだ。その羽衣伝説は遠野において、六角牛山だけではなく、遠野の各館ごとにも付着してると菊池照雄「山深き遠野の里の物語せよ」で指摘している。 真立館(松崎町松崎 御前沼 荷渡観音 御前様) 小田沢館(青笹町中妻 荷渡観音 御前沼 御前様) 月山神社(上郷町字南田 御前沼 御前様 千手観音) 佐野館(上郷町佐野 御前沼 御前様 薬師観音) 御前(綾織町新田 御前沼 御前様) 天ヶ森館(附馬牛町安居台天ヶ森下 御前沼跡 御水神宮) 荒矢館(附馬牛町荒屋 御前様) 羽衣伝説の伝播は、一つは共通する女神の伝承であろうし、または養蚕の伝えに付随したものでもあろう。または祖先が天から降りてきたという権威付けにも利用されたのかもしれない。ところで遠野においての羽衣伝説と共に語られる沼の御前は、遠野だけではなく遠野をはみ出す形で点在している。それを調べると、全てでは無いのだが、共通する神の姿が見えてくる。そういう意味から、全国の羽衣伝説も、一斉に語られたのではなく、何かの共通性を以て語られたのだろう。 ところで、日本最古の羽衣伝説とは「近江国風土記」と「丹後国風土記」の二つとなるが、その一つの「丹後国風土記」の羽衣伝説は、伊勢神宮の外宮に祀られる豊受大神に結び付けられている。ある意味、日本の頂点に立つ伊勢神宮に祀られる豊受大神が天女と同一視されるのならば、全国の天女の登場する羽衣伝説の背後に豊受大神の影が見えなければならないのだが、残念ながらそれが無いというのは不思議な事でもある。中世になって、内宮の天照大神よりも、外宮の豊受大神重視の祭祀になっているのだが、その影響が全国に感じられないのは何故なのだろうか。ただ、江戸時代になってのお伊勢参りとは、内宮の天照大神に対する参詣では無く、太平の世となった江戸時代に安定した稲作への祈願から、御饗都神でもある豊受大神の参詣が流行ったという事らしい。 伊勢神宮の外宮に祀られる豊受大神の出自は一般的に「止由気宮儀式帳」によるものとされ、天照大神の御饌都神として連れてこられたのが豊受大神であった。しかしこれは、王権側が内宮に奉仕していた度会氏に対して、天照大神よりも一段低い神格を祀らせ、伊勢勢力の弱体化と従属性を狙ってのものだとされている。しかし、滝の宮である遥宮を祀り、また天照大神の荒御魂を祀る荒祭宮の奉祭にあたっていた磯部氏と度会氏が共謀・・・いや、磯部氏=度会氏とも云われる。 荒祭宮は内宮に所属し、天照大神の荒御霊として別宮扱いしたのは朝廷側であったが、そこから発せられる託宣は無視できないものであり、その荒祭宮の主導権を磯部氏と度会氏が握り、朝廷側に対して抵抗していた。その荒祭宮の託宣などを介して、徐々に力を付けた度会氏は、いつしか外宮の豊受大神に「皇」の文字を付けて祀るようになった。「皇字沙汰文」は、その時の騒動を記している。 「外宮の神の御鎮座の次第は「日本書紀」には見えていない。だが「風土記」には、丹波国与謝郡比治の眞名井に湯浴みした天女と見える。これが外宮の御饌の神である。」 この内宮からの問いに対し、外宮の反論は下記の通り。 「その天女とはワクムスヒの子のトヨウケビメの事だろう。当外宮の御神のことではない。出現の時代といい、祖神といい、豊受大神とは雲泥の差があり懸隔も甚だしい。一口に御饌の神といっても、ある神は神祇官、ある神は機殿、ある神は式内社に祀られている。当外宮においては、調御倉・酒殿に祀る。つまりこれらの神々は種々で、一様ではない。何をもって御饌の神と呼んでいるのか。訝しい。そればかりではない。訴状のいう天女とはワクムスヒの子だが、詳しい書を見るとスサノオの子となっている。このように天女トヨウケビメと豊受大神とはまったく別の神であり、内宮の訴えは、正理に背いた根拠のない申し立てである。」 実はこれ、度会氏が密かに新たな神話の創作を組み込んだ「神道五部書」によって豊受大神の権威付けを施したようであった。その「神道五部書」は奈良時代以前の作だとされていたが、実際は鎌倉時代に作られたものであったよう。その中の「神祇譜伝図記」「御鎮座伝記」によれば、いずれも伊弉諾と伊邪那美が八尺瓊勾玉を空に捧げて化生した神を豊受大神としている。これは「日本書紀」での宇迦御魂命の化生をモチーフに作られたものと云われている。 これらの作為はとどまる事を知らず、密教の曼荼羅をも導入し、内宮と外宮の位置を確立した。内宮には胎蔵界曼荼羅を導入し、大日如来で日輪であるとし、外宮は金剛界曼荼羅を導入し、大日如来で月輪とし、これにより内宮の天照大神は日天子であり日徳を象徴し、外宮の豊受大神は月天子で水徳の象徴とされた。更に天御中主命との合体によって、天照大神よりも格上の大元神となったようである。 これらによって、伊勢神宮における天照大神の地位は失墜し、その天照大神を祀る内宮の千木は、天に向けて豊受大神の齎す水を受ける様に内削ぎになったのだという。当然、豊受大神を祀る外宮の千木は、地に向けるよう外削ぎとなった。つまり、天神は豊受大神であり、地神は天照大神となったという事になる。 「神皇実録」によれば、天御中主命は一水の徳によって万物の命を救った。だから御気津の神であるとし、その天御中主命と同体の豊受大神も御気津の神であるとされた。ちなみに"御気津"とは水の古語となり、水はその略語であるらしい。 似た様な名前で本来、豊受大神招かれた御饌都の神はいつしかトヨウカノメであるとされ、御気津と御饌都の違いによって隔離された。このように、荒祭宮からの託宣を機に力を付けた度会氏は、朝廷によって天照大神の下であった筈の豊受大神は、いつの間にか天照大神を凌ぐ神に昇華され、水神としての最高位となった。これらの事実から、度会氏の内宮に対する抵抗とは別に、水神に対する執拗な拘りを感じる。とにかく、本来の豊受大神とは御饌都の神であり、今でも酒殿に祀られている止由気比売であろう。それでは外宮に祀られる水神である豊受大神とは本来、違う神名であったものが豊受大神とされていると考える。 |
|
|
■九
近江雅和「記紀解体」によれば、磯部氏から出たのが度会氏だとして、その磯部氏は伊勢を離れ、上野国へ移住している。そこで作られたのが「子持山伝承」であった。物語形式のこの伝承は、取るに足りない話なのかもしれないが、かなり興味深い内容になっている。先に紹介したように、伊勢神宮の荒祭宮に祀られる神は「アラハバキ姫」と称された。そのアラハバキ姫は鈴鹿出身の女性で、後には夫婦神となり、夫は鈴鹿明神となり、その妻は津守明神となった。その鈴鹿の津守明神が伊勢神宮の荒祭宮に祀られるのだが、その荒祭宮は時々鳴動する荒ぶる神であったようだ。 ところで、坂上田村麻呂伝説に登場する鈴鹿山の鬼女の果ては、坂上田村麻呂と共に蝦夷国へと行き蝦夷征討の助けとなって、烏帽子姫として姫神山に祀られた。鬼が最後は、神として祀られたという事になる。その鬼ではあるが、外宮に祀られる豊受大神もまた、鬼の性格を有している。中山太郎「さんばい考」では「通称、鬼役といわれるお毒見役を務めるのが外宮の性格であり、豊受大神は散飯鬼である。」としている。散飯鬼とは、太元明王であり曠野鬼神とも呼ばれ、北方鎮護の毘沙門天の眷属でもある。その毘沙門天の現人神とも云われる坂上田村麻呂もまた、鈴鹿の鬼女を調伏し、眷属としているのを付け加えておこう。そして姫神山に祀られた神こそは、伊勢神宮の荒祭宮に祀られる瀬織津比咩という神でもあった。 荒祭宮に祀られる神が荒ぶる鬼女でもあったのだが、外宮の性格もまた荒ぶる鬼女でもあるのはどうした事か。「続日本記」に「文武天皇二年十二月乙卯、多気大神宮を度会郡に遷す。」とあるのは、瀧原宮にも祀られていた地主神を祀り取られ、まとめて宇治に引っ越したという事である。しかし宇治の地には、やはり荒祭宮に祀られていた地主神がいた。そこで大和朝廷は、南伊勢の土着の農民であった荒木田氏を登用し内宮で天照大神を祭祀させ、皇大神宮の最高の神主である禰宜ととしたのは、磯部氏と度会氏の弱体化を図る為でもあった。しかし、地主神が祀られていた伊勢に強引に天照大神が割って入った為に、内宮敷地内の荒祭宮を残して、地主神の祭祀は分断されてしまったが、渡会氏は外宮を打ち出して対抗した。それから暫くは、内宮と外宮の争いが続くのだが、その外宮に祀られている地主神の存在を見てみよう。 まず、度会氏の求めたものは前回書いたように、外宮の立場が内宮を上回るという野心だった。それはつまり、天照大神よりも豊受大神の存在を高める事に尽くしたという事ではある。しかし、ここで考えなければならないのは、天照大神が伊勢に鎮座した為に、磯部氏や渡会氏が祀っていた地主神が追いやられたという事。その地主神をさて置いて、やはり他から運ばれてきた豊受大神という存在に思い入れを持てたのか?という疑問が生じる。何よりも外宮の立場を高めた度会氏は、外宮を月の宮とする事で、豊受大神を御饌都神から水の古語である御気津神、つまり水神の最高位に置いたという事である。 ここで、伊勢神宮の祭祀状態が記されている「元初の最高神と大和朝廷の元始」を確認してみようと思う。まず荒祭宮の天照大神の荒御魂である瀬織津比咩だが、月殿に於いての御魂の形は、天鏡の尊鋳であり、多賀の宮の御魂と同じとしている。ここでの疑問は、日の宮である筈の内宮の敷地内にある荒祭宮の神が月であると言っているようなものだ。 また、豊受大神の荒御魂は伊弉諾が右目を洗い化生した月天子であるとし、それは天御中主命であるともし、またそれは多賀の宮と同じであるとしている。それでは多賀の宮を見てみると、豊受大神荒御魂の名は、気吹戸主であるとし、もしくは神直日大直毘神であるとしている。この多賀の宮に坐す気吹戸主とは「大祓祝詞」においての祓戸四神のうちの一柱の神である。また、神直日大直毘神も調べれば、穢祓によって誕生した神であり、それは八十禍津日神を解体し四柱の神の二柱の神に過ぎない。 神直日・大直毘神は、京都の櫟谷宗像神社に祀られる田霧姫と市杵嶋姫命の二柱の神に、渡月橋を挟んだ対岸の大井神社の神を合わせて、宗像三女神となるとされていた、その大井神社に祀られていたのが神直日大直毘神であったが、それは八十禍津日神の解体された神であった。その八十禍津日神神とは、天照大神の荒御魂である瀬織津比咩である。つまり、天照大神であり、豊受大神の荒御魂とは、どちらも瀬織津比咩であるという事になる。これは先に記してきたように、度会氏が伊勢での対抗手段として内宮所属の荒祭宮の祭祀権を行使して外宮の力を強大にし、豊受大神をも利用して、地主神であったアラハバキ姫である瀬織津比咩の祭祀を大和朝廷から密かに隠れて作り上げたものであると考える。 ここで、アラハバキ神に関する教義を振り返ってみよう。これは蝦夷国において、安倍氏が信仰していた内容と同じものである。 「天・地・水を基として、日輪を父なる神とし、万物を育む地であり山であり、そして水を母なる神とする。」 これは度会氏が豊受大神を御気津(水)の神として新たに作り上げた神話と内容が近似している。度会氏の拘りは、水の神に一貫していたのは、敢えて丹後国から来た止由気を豊宇気毘売神と豊受大神分離させ、豊宇気毘売神を単なる御饌都神にして、豊受大神を水神の最高位に据えた事だ。しかしそれは背後に元々祀っていた地主神を荒御魂に据え、内宮と外宮の両方の祭祀権を得る為の策略であったという事だろう。 「日本書紀(垂仁天皇二十五年三月)」に天照大神が登場し、伊勢のイメージを言葉に表している。 「是の神風の伊勢國は、常世の浪の重浪歸する國なり。」 常世とは、永久に変わらない神域。死後の世界でもあり、黄泉もそこにあるとされる。「永久」を意味し、古くは「常夜」とも表記した。」つまり常世とは、夜の世界である事から、垂仁天皇記での「是の神風の伊勢國は、常世の浪の重浪歸する國なり。」とは月の光を浴びた波が押し寄せる意でもある。それはつまり、伊勢神宮そのものが月を重視している意味でもある。 荒祭宮に祀られる天照大神の荒魂は水神でもある瀬織津比咩となるのだが、それでは一つの神として和魂と荒御魂の二つがあるなら、その属性は同じであるべきだった。しかし、天照大神は日の神であり、荒御魂である瀬織津比咩は月神であり水神であるのはおかしいと考えてきた。しかしそれは、あくまで伊勢神宮という存在そのものが月の宮であり、表向きは日天子と月天子を祀る内宮・外宮の両宮に分かれてはいるが、表向きの祭神のどちらの荒御魂が月天子であり水神である瀬織津比咩である事から、伊勢神宮の本来は月の宮であり、それはアラハバキ神の教義にも合致するのである。 |
|
|
■十
続けて豊受大神について書いてきたわけだが、中世に新たに作られた神話によって豊受大神は、崇高な神となった。その新たな神話の下敷きが、「日本書紀」の一書の所伝であった。その中で化生したのは倉稲魂命であった。 「又飢しかりし時に生めりし兒を、倉稲魂命(ウカノミタマ)と申號す。」 古代史系の本を読むと、殆どが豊受大神は「トヨウケ」であり、「ウケ」は「ウカ」と同じものであるから、トヨウケもウカノミタマも同神である。そして保食(ウケモチ)神も、大宜都(オオゲツ)比売も同じだとされている。更には、国常立尊=天御中主命=豊受大神は同神とされている為に、かなりの混乱が生じる。例えば日本で一番多く祀られている稲荷神社の祭神は倉稲魂命の場合が、その殆どであるのだが、それではそれは豊受大神でもあり、天御中主命でもあるのか?これは豊受大神を最高神に仕立て上げようとした弊害だったのではなかろうか。何故なら御饌都神である止由気であり保食神と、天地開闢の神である筈の国常立尊や天御中主命は分けるべきであるからだ。 鎌倉時代に行われた伊勢神宮の遷宮の時、倉稲魂命の御神体が移動途中で誤って落とされ、御神体であった「瑠璃の壺」が露顕してしまったそうな。その為に奉仕者の物忌は責任を取らされ解任されたそうである。現実としての外宮は、御食や御酒を司る神々がひしめいているいる為に、その御神体の殆どが甕や壺であるという。しかしここで、非常に気になる神名が浮かぶ。その名前は、天津甕星であり、別名香香背男という神だ。 確かに甕(ミカ)は「カメ」とも読み、水や穀物を入れる容器でもある。しかし平田篤胤「古史伝」では「甕は甕速日神の甕と同じく、伊迦と通ひて厳く大なるを云ふなり。」とある。つまり「厳めしい」「威力」の意味をも持つのが「甕」であった。 その天津甕星であり香香背男は常陸国に居た。ここで気になるのは先に紹介した「我国間記」の一文である。「我国ノ御山ハ日本開始メの峰ニシテ、豊受産ノ神社有リ、後に尊ノ号ヲ常立ノ尊ト奉称。…即チ太神宮ナリ後に丹州、今ハ伊勢ニ移リシ給フ。伊勢の外宮、近江多賀大社御同神体ナリ。」信憑性を疑う「我国間記」ではあるが、まったく無意味に書かれたものでもなく、何かの意図を以て書かれたものだろうとは察する。ただ恐らくだが一文の最後「近江多賀大社御同神体ナリ。」は、伊勢神宮の多賀の宮の間違いであろう。それは、多賀の宮の祭神が豊受大神の荒御魂である事から確実であろう。 一気に天津甕星へ行きたいが、その前に少し寄り道をする事としよう。実は以前から「日本書紀(景行天皇記)」に気になっていた箇所があった。 「神宮に獻れる蝦夷等、晝夜喧り譁きて、出入禮無し。」 これは捕虜とした蝦夷を伊勢神宮に放つのだが、昼夜構わず大声を出して騒いだとされている。その前に、何故に捕虜を伊勢神宮に放したのかの理由がわからない。それと似た様なものに「続日本記(和銅六年)」の隼人に関する記述に、こうある。 「隼人、昏荒野心にして、憲法に習はず。因りて豊前国の民二百戸を移して、相勧め導かしむ。」 この隼人に関する記述は「日本書紀(景行天皇記)」における、武内宿祢の蝦夷に対する記述に近似している。それは平らげようとする意図から、蝦夷も隼人も同じようなものだというのだろう。それにあたって朝廷側は5000人もの人を移住させ隼人の指導にあたったとされるが、その時一緒に運ばれて来たのは八幡神であったそうだ。その時の祭神は三柱の神で、応神天皇、神功皇后、豊受大神であったと云われる。 確かに隼人は何度も反乱を起こしているが、それは蝦夷も同じだ。その反乱なのだか、蝦夷も隼人も同じ養老四年に反乱を起こしている。養老四年の蝦夷の反乱は五ヵ月で落ち着いたのだが、その反乱の要因は上毛野氏が蝦夷の信仰する水神を祀る山に駒形神を勝手に祀った事からであった。しかし大野東人は「蝦夷を以て蝦夷を喩」政策から、反乱が広がる事も無く五ヵ月で懐柔している。その同じ養老四年に、隼人も反乱を起こしている。この時、朝廷側にある迷信が蔓延っていた。それは「庚申年には蝦夷の反乱が起こる。」というものだった。庚申とは近代となって星待ちの民間信仰の印象が強く思われているが、実際は北辰であり、妙見信仰との繋がりの深いものである事を付け加えておこう。隼人の住んでいた大隅に八幡神が祭祀された。今では鹿島神宮とも云うが、その鹿島神宮は北に向けて建てられている。東北での北向き神社で有名なのは胡四王(こしおう)神社であるが、それは本来「星王(ほしおう)」であり、妙見信仰からのものであろう。 大迫の早池峯神社が何故に早池峯に向けずに、遠野の早池峯神社に向けて建立されたのかは、遠野早池峯神社の遥拝所であったという説明も間違いではないが、正確には北辰を頭の上に抱く早池峯こそが真の姿であるという事を重視してのものだった。つまり、妙見と早池峯は繋がって信仰されていた。また早池峯神社の御神体の一つである又一の滝もまた本来は太一の滝であり、これは伊勢神宮の太一信仰と繋がってくる。 宇佐八幡が北辰殿を採用したのは、聖武天皇時代であった。思えば八幡神社が稲荷神社と一位二位を争う程にこれだけ全国に広がっているのは、まず朝廷側の方針に沿うような祭祀を行い、国家神を目指していたのだと思える。それ故に妙見を採用し、蝦夷や隼人・熊襲を平定する為に、それらがひれ伏するする神を祭神としたと考えるのが妥当であるだろう。養老二年において、蝦夷平定を祈願し、熊野から熊野神が蝦夷国に運ばれた。同じ時代、九州の地では隼人の反乱を抑える為に、八幡神が用いられた。「鬼を以て鬼を制す」という言葉を実践するには、ある神を信仰する民俗を説き伏せるには、同じ神を以てするのが有効であったのだと思う。大野東人の「蝦夷を以て蝦夷を喩」が個人の政策方針ではなく、国家である朝廷側の方針であるならば、それは同じ養老四年の隼人の反乱にも採用された筈だ。ただ蝦夷側には熊野神であり、隼人側には八幡神の違いはある。しかし、遠野の六角牛神社に祀られている宇佐明神を紐解くと、それは宗像の湍津姫であり、それは瀬織津比咩でもあった事を踏まえれば、蝦夷も隼人のどちらも、同じ神の力によって平定されたという事になるのである。 となれば、景行天皇時代に蝦夷が伊勢神宮に連れてこられた理由は、蝦夷を大人しくさせる意図があってのものだったのだろう。しかし、蝦夷は騒いだ。だが、隼人もまた騒いだという。ただその騒ぎ方は「日本書紀」によれば「吠狗」「狗吠」と云われるものであった。しかしその「狗吠」の発動は、神聖なものに対しても発動された。その「狗吠」の正確さはわからぬが、要は犬の遠吠えであったろうと云われる。狼は山神の眷属と云われるが、隼人は天皇の行列の守護役にもなり、国の境や道路の曲がりなどで狗吠を発していた。行列の先払いとして、邪気・邪霊を払っていたとされるのは露払いであり、それは貴人や神霊などの高貴な者を先導する事である。それは朝廷側に服属してからのものではなく、元々隼人が有していた呪術であり、恐らく隼人が信仰する神に対するものを行ったという事であろう。そして隼人がそれを行った場所とは、伊勢神宮での事であるのは、隼人の信仰する神が伊勢神宮にも居たという事であろう。その神域を護る為の狗吠であったのは、理解できるのだ。 |
|
 |
|
|
■十一
皇祖神を祀ると云われる伊勢神宮に、アラハバキ姫とも云われる瀬織津比咩が祀られているのは何故なのか。伊勢神宮は、内宮と外宮に分かれる祭祀形態ではあるが、外宮の豊受大神は複雑怪奇な神であり、そもそも本当に伊勢神宮に祀るべき神なのかを考えても疑問符が付く。何故なら、出自の怪しいものは神であろうと人間であろうと、"そういう場所"には入れる筈も無いからだ。だが、荒御魂という形で、内宮と外宮に瀬織津比咩の姿があるのは、そもそも本来の祭神を背後に置いて、表面を取り繕った作為が行われたとしても不思議ではない。 外宮の豊受大神は、天女としてどこからか飛んできた存在であり、それ以前の足取りが不明ではある。しかし常陸国の「我国間記」において「我国ノ御山ハ日本開始メの峰ニシテ、豊受産ノ神社有リ、後に尊ノ号ヲ常立ノ尊ト奉称。…即チ太神宮ナリ後に丹州、今ハ伊勢ニ移リシ給フ。伊勢の外宮、近江多賀大社御同神体ナリ。」と記されている事から、常陸国に着目してみる事にする。しかしこの「我国間記」の描写は、常陸国がまるで高天原であるかのような記述である。ただ高天原の解釈は、先人の学者たちが築いた軌跡でもあるから、簡単には否定もできないが、考古学の見地から言えば、関東周辺の古来からの古墳群を歴史上であり神話上どう説明するのかという疑問点が残る。景行天皇記のヤマトタケルの伝説によれば、未開の地であった筈の関東であり吾妻が、これほどの古墳群を有する国である記述は「記紀」に無い事が大きな疑問である。 「伊勢國風土記 逸文」にはこうある「天津の方に國あり。其の國を平けよ。」と天日別命に命令する。その天津方とは、伊勢国から数百里の遥か彼方であり、それは恐らく関東近辺を言っているのだろうとされる。しかし天津という表現は、天そのものであり、それは高天原を意味していても不思議ではない。辺鄙な場所を夷とも云い、蝦夷国は都から遥か遠く離れた辺鄙な地であり、夷の地だ。「日本書紀」の一書に歌が詠まれている。 天なるや 弟棚機の 頸がせる 玉の御統の 穴玉はや み谷 二渡らす 味耜高彦根 天離る 夷つ女の い渡らす迫門 石川片淵 片淵に 網張り渡し 目ろ寄しに 寄し寄り来ね 石川片淵 この歌は天照大神が、天雅彦に命令し「豊葦原中國は、是吾が兒の王たるべき地なり。然れども慮るに、残賊強暴横惡しき神者有り。故、汝先づ往きて平けよ。」恐らく、この「日本書紀」の話に合わせてできたのが「遷却崇神詞」という祝詞であったのだと思う。この祝詞には日高見という名称が登場するが、それは後で書く事としよう。その前にだ、この歌の解釈は先人も苦労していたようで、簡単に訳せば下記の通りになる。 「天上の機織女が首に掛けている首飾りの玉、穴が開いた玉のように、谷に渡る 味耜高彦根 」 「田舎女が瀬戸を渡り魚を捕るため、石川の片岸に網を張り渡したが、 その田舎女が網目を引き寄せるようにこちらへ渡って来なさい。石川の片淵よ」 簡単に訳せば意味があるような無いような歌である。ところで夷が辺鄙な意味を持つ事から田舎に住む女とも訳されるが、これは天を隔てた遠い所にいる女と訳せば、前歌の弟棚機と結び付く事となる。細かい解説は抜きにして、持論を云う事にする。まず東国に荷渡・二渡・などという神社や観音があるが、それは別に鶏とも鬼渡ともいろいろな漢字があてられているが、この歌に登場する「二渡らす(ふたわたらす)」とは、二荒山を指すと考える。 古代の秘伝の薬に関する本を読んでいると、とにかく簡単に解明されないよう、意味の無い漢字をあてたり、句読点を違う箇所につけたりして難解としている。その技法はわらべ歌にも伝わっており、真意を誤魔化して伝えるのは、歴史書であろうが、あるものと思っている。まあ「古事記」などでは今まで大和言葉で解明できなかったものがアイヌ語を適用してみると理解できたものもあるので、史書であろうが、いろいろな視点から見るべきだとは思っている。中途半端ではあるが、今回この辺とする。 |
|
|
■十二
自書「古代蝦夷を考える」で高橋富雄は日高見に対する想いを学会に向けて、こうぶつけている。 祝詞日高見国の定説的理解は、日高見国の問題の歴史化の芽を摘んでしまった。日本古代国家成立史上の謎解明の道も塞いでしまった。わたくしはそうおもっている。祝詞の日高見も景行紀のそれも同じものだったはずなのに、祝詞学者たちは両者を別々のものと考える定説をつくりあげてしまった。この人たちは、すべて権威ある国学者たちであった。そのために、この人たちの権威のもとにつくりあげられたオオヤマト国家学説も、権威ある歴史学説として、今なお支配的である。われわれは今その全面的な再検討を迫られている。 ■ 問題となったのは「六月晦大祓詞」と「還却崇神詞」の両方に日高見が登場する事からであった。景行紀において、武内宿祢の甘言によって始まった蝦夷討伐の中に日高見国が含まれていた。それは恐らく、陸奥国の日高見国であろうと思われてはいたが「還却崇神詞」にも登場する日高見国の扱いから、まつろわぬ民であり国の総称としての日高見国となってしまった。それは「還却崇神詞」が天照大神の命により、天穂日葦原中国平定のために出雲の大国主神の元に遣わされた話の流れが「還却崇神詞」に記されている為、その舞台が出雲であろう事から、日高見は景行紀の「東夷の中、日高見国あり」の狭まれた中の存在から「大倭という名の日高見国」と漠然とした存在になった事を高橋富雄は嘆いていた。 しかし、この神話の舞台が出雲では無く関東であるならどうなるだろう?話の終わりには、高天原からの返し矢によって死んだ天若日子とそっくりな味耜高彦根が登場し、天若日子とそっくりな事を憤慨している。この物語で注目すべきは、味耜高彦根は天若日子と似て非なる存在であるという事を訴えている。それを考慮して思うに、人だけでなく、その舞台となった地も似て非なる場所では無かったのか?と思うのだ。 誰かの書にて「記紀」に対する疑問を述べていた。日本で一番高い筈の霊峰富士が、何故に「記紀」に登場しないのかと。天智天皇時代に、鹿島神宮の修復に人などを派遣している。また天武天皇時代には、天武天皇が伊豆で発生した大地震をしきりに気にしている。朝廷側が気にする東国の記述が何故少ないのか。ましてや近畿からも遠望できる富士山が登場しないのはおかしいと。高天原は遠い彼方の存在であるが、それは海の彼方であり山の彼方でもある。人がなかなか辿り着けない地を高天原とした可能性から、何故に富士山が除外されているのか。関東には多くの富士見台と呼ばれる地名があるのは、そこから富士山が見えるからだ。古代人の思考からも富士山を高天原と見做さないのは確かに不自然な事でもある。 そしてだ、味耜高彦根を祀る神社の多くは関東にある。また天地開闢の神とも云われる天御中主命を一番多く祀る地は茨城県である。その茨城県の「我国間記」では「天地開闢の地」と記されている。しかし古代史の中心は近畿以南となっており、東国軽視の風潮が蔓延している。その為に「還却崇神詞」の舞台が出雲であるという定説から高橋富雄も嘆いた。しかしその嘆きも「還却崇神詞」の舞台が東国になれば歓喜に変わる事だろう。 鶏が鳴く 東の国に 高山は さほにあれども 二神の 貴き山の 並み立ちの 見が欲し山と 神代より 人の言ひ継ぎ 国見する 筑波の山を 冬こもり 時じき時と 見ずて行かば まして恋しみ 雪消する 山道すらを なづみぞ我が来る 「万葉集382」 東の国に高い山は沢山あれど、中でもとりわけ男神と女神のいます貴い山で二つの嶺の並び立つさまが心を惹きつける山とと、神代の昔から人が語り継いで、春ごとに国見の行われてきた筑波の山よ、それなのに今はまだ冬でその時期ではないからと国見をしないで行ってしまったら、これまで以上に恋しく思われるだろうと、雪融けのぬかるんだ山道を苦労しながら、私はやっと今この頂まで登って来た。 「万葉集382訳」 この「万葉集382」をどう解釈するか。筑波の山は筑波山であり、伊弉諾と伊邪那美を祀る山でもある。この筑波山が神代・・・つまり神の時代から語り継がれていたとされた山であった。また謎の境の明神というものがある。筑波山が聳える茨城県側に、伊弉諾が祀られ、福島県側に伊邪那美が祀られている。それがまた、宮城県の多賀城側に伊弉諾が祀られ、それ以北の蝦夷国に伊邪那美が祀られている。火之迦具土神を産んで死んだ伊邪那美は黄泉の国へ行き、黄泉津大神となった。それによって伊弉諾の現世とは、千曳岩によって区切られてしまった。それをそのまま、朝廷の支配側と被支配側にわければ、その境の明神の示すものが何であるか想像がつく。 実際の話、関東近辺に広がる一大古墳郡が発掘されているが、誰も歴史に照らし合わせて説明できていない。実情は関東の古墳群は学会から無視されている形で「記紀」の神代の話が進められている。だが関東の古墳群は、一つの王国の証であるのは間違い無いだろう。神話の舞台を東国に当て嵌めて考えても、なんらおかしくは無いと思えるのだ。 |
|
|
■十三
大和岩雄「神社と古代王権祭祀」では鹿島神宮の建御雷神の本来は、甕を使用する武甕槌であったとしている。それは、鹿島を表現する歌にも読み取れる。 神さぶる かしまを見れば 玉たれの 小かめはかりそ 又のこりける「扶木抄(藤原光俊)」 この歌からも鹿島の本来は、かめ(甕)は神代より留まっている壺であるという意であり、それが鹿島を表しているともとれる。「新編常陸国風土記」では「常陸国の海底に、一つの大甕あり、その上を船にて通れば、下に鮮やかに見ゆるといへり。古老伝えいふ。此の大甕太古は豊前にありしを神武天皇大和に移したまひき。景行天皇当国に祀りたまふ時、此の甕をも移したまへるにこそあれといへり。」この記述から察すれば、この大甕は九州から運ばれてきたものなのたろうか?いや、別の言い方をすれば、九州の海神族が常陸の国へ進出し、その御神体を海に沈めて祀ったとも取れる。 鹿島神宮摂社息栖神社の伝承にも、海中に瓶があったと伝える。また阿波国の甕浦神社の御神体は大甕で、海の底にあった大甕が一夜海鳴りをさせて上がってきた伝承がある。また「琉球神道記」には鹿島明神について書かれており「鹿島の明神は、元はタケミカヅチの神なり。人面蛇身なり。常州鹿島の海底に居す。一睡十日する故に、顔面に牡蠣を生ずること、磯の如し。故に磯良と名づく。」鹿島神宮の御神体が甕であるらしいのがわかるのだが、それがどうも磯良となるのは、海神族の影響が鹿島にもあったという事だろうが、それでも武甕槌からは、そのイメージが浮かばない。あくまでも悪しき荒ぶる神々を平らげる為の存在のイメージが強すぎるせいか。ただ磯良であるなら、安曇族の進出が常陸国にあったという事になる。 大庭佑輔「竜神信仰」には、対馬に安曇族の祀った和多都美神社があり、それと共に多くの関連する神社を調べた詳細が記されている。それよ戸は白蛇であり白龍であり、白い水を伴う存在であると。その対馬と同じ九州の闇無浜神社に伝わる古縁起「豊日別宮伝記」には、下記のような伝承がある。 瀬織津比咩は、伊奘諾尊日向の小戸の橘の檍原に祓除し給ふ時、左の眼を洗ふに因りて以て生れます。日の天子大日孁貴なり。天下化生の名を、天照太神の荒魂と曰す。所謂祓戸神瀬織津比咩是れなり。中津に垂迹の時、白龍の形に現じ給ふに依りて、太神龍と称し奉るなり。 伝承の最後に記されている「太神龍」だが、常陸国での竜神の表記に「妙泉太神龍」もしくは「妙泉大龍神」というものがちらほら見かける。妙泉といえば、遠野の早池峯神社の前身が妙泉寺である事を考え見れば、この影響を受けて命名されたのが早池峯妙泉寺なのだろうか。そしてもう一つ気になるのは、対馬の白龍に付随する白い水だ。中国地方に祀られる瀬織津比咩と白い水が何故か結び付けて語られ、遠野の六角牛の天人児伝承にも白い水が付随する。また、岩手県の花巻地域にはり早池峯を中心とする三女神伝承があるのだが、その一つ呼び石の地に鎮座する水白神社があるのだが、地域の古老に聞けば早池峯の神であると云う。 鹿島の大甕が磯良と結び付くのであるならば、その大甕は器であろうが、それは白い水を入れる甕でもあろうか。大甕から注がれる水は一筋の滝をイメージしてしまうからだ。 対馬周辺では磯良=白蛇=白龍であり、その依代は白い布であり白い水でもあるようだ。これは宗像のみあれ祭りでの神の依代が白い布であるのと一致する。白い布は水の流れにも重なり、瀧の落ちる水を瀑布と表現するのと同じである。湍津瀬(たぎつせ)とは、激しく流れる水でありそのまま白い水をも意味し、瀧そのものでもあるとされる。落差が僅かでも滝であるとするのは瀧の概念の一つでもあるが、瀧をイメージする激しい流れもまた瀧と同一視されている。それは遠野にも釜淵の瀧が、それと同じである。 茨城県静神社には天羽槌雄神が祀られているというが、その神社に伝わる伝承では、静神社の神は蛇体の女神で、その昔に出雲の神殿を七巻半も巻いて集まった神々を驚かせたと云う。その為なのか、静神社を祀る地も神無月では無いそうである。これは早池峯も神無月では無い事に対応するものであろうか。その静神社の神は、何故か鹿島神宮の高房社に祀られ、昔から鹿島神宮では本殿より先に高房社を参拝しなければならないしきたりになっているという。静神社の祭日は申酉の日となってというが、陰陽五行では申は水気であり水の発生を意味し、酉は金気で盛んになるという。つまり祭神の蛇体の女神は、水気と金気を纏う女神でもあるという事だろう。 静神社で古来から有名なお守りは「蛇除の御守」つまり静神社は本来、蛇神を祀っていたが、その神を抑える為に天羽槌雄神が祀られたのだろう。その正体は恐らく香香背男。カカは蛇の古語であり、女になった伝承もある事から、本来は蛇体の女神であると思わる。何故なら蚕を食べる鼠を捕食するのは蛇だからだ。その養蚕の保護をする蛇を排除する蛇除けの御守があるとはどういう事だ。となれば、静神社の祭神の本来は、蛇神でもある香香背男であった可能性は高い。天羽槌雄神をどう見ても、蛇神とは重ならないのであるから。 養蚕の守護は、いつしか蛇から猫に変わったようだ。しかし、その共通点は陰獣であり、女の性質を持つという継承のようでもある。猫が死ぬと、その死体は三叉路(辻)に埋めるのは、多くの人に踏み固めて貰い、その怨霊を封じ込める意図からだという。これを神社に適用させれば、蛇神である祟り神は、人の多く参拝する神社に合祀せよという事か。となれば、静神社に祀られた蛇神の女神が何故に鹿島神宮にも祀られているのか想像がつく。いや、静神社と同じ蛇神が鹿島神宮の本来の祭神である可能性もあるだろう。そして香香背男の名前をもう一度見直す必要性があるだろう。今まで香香背男には「男」という漢字があてられていた為に男神であるという認識が一般的であったが、それを純粋に「カカセオ」という音表記から考えてみたい。香香背男の別名天津甕星である事から、鹿島神宮との繋がりが想定できるからだ。 |
|
|
■十四
「文徳実録」に、鹿島の磯に大己貴命と少彦名命が現れた逸話が紹介されている。先に紹介した、鹿島と大甕の話も全て海であった。その海に関する神事が、鹿島を含む常陸国に多い。「会瀬旧述」には、会瀬浦の地名由来が紹介されているが、それは海の磯場に天の川の信仰が展開されていた。 「其より磯つたへに女浪、男浪を左右より打合せ、渚岸まで寄せ来れば、自然と陰陽和合の地にして、二星それぞれ相賀し給ふ。磯の瀬にして会するが故に、地名会瀬の浦と名付けしもの也。(抜粋)」 この会瀬浦は別名七夕磯ともいうようだが、それとは別に須弥山磯、または蓬莱磯とも呼ばれ、山岳信仰との関わりを持っているのはひとえに、天(アマ)は海(アマ)でもあるという事だろう。そしてそれは、アマである磯場に星が降り立つことを示唆している。 また常陸国には別の祭礼として、多くの磯出神事がある。これは、神迎えの神事でもあるようだ。それは磯に出現した神を再現する神事でもあった。神事の対象は磯である石。例えば物部氏の祀る石上神宮も、磯上神宮であるように、磯と石は同じものであった。これが陸地の石に神が降り立ったという伝承が付随する石を影向石とも云う。所謂、磐座信仰でもある。しかし常陸国でのこの磯出神事に出現する神は、殆ど大己貴命であるのは、どうやら日光と関係してくるようだ。 関東平野の灌漑用水には、利根川、鬼怒川、那珂川、久慈川などの川が利用されるが、その水源は那須岳、男体山、赤城山、榛名山など群馬県や栃木県の山々になっている。その中でも日光連山は奈良時代には、その山々を観音の浄土である補陀落の地として認識されたようだ。その日光連山には大己貴命、田心姫、味耜高彦根が祀られている。その神々の中心となる大己貴命が磯に出現するのは、常陸国と日光二荒山との関連が深いと云う証であろう。そしてそれはまた、山と海の関わりが深いという意味にもなる。その山と海とを繋ぐものは、川という水の流れであった。 山岳信仰では、人々の魂は山に登るとされる。しかし灯篭流しでは、魂の依代の灯篭が川下へと流れていく。しかしこれは、山である天(アマ)と海(アマ)が連動しているという事でもある。つまり山に登った魂は川の流れを伝って海へと向かうのは、その信仰の循環を意味する。その海で出現した神は雲となって登り、山に雨を降らせる。そういう自然の循環から竜神が想像された。その為、海に出現する神は竜神でなくては成らない筈だ。常陸国の自然と信仰に影響を与える二荒山には、星の信仰と蛇の信仰が存在する。 勝道上人が7歳の時に明星太子に仏法を興すことを訓えられ、日光開山は明星太子の導きであるとして、男体山開山後に川の南岸に星の宮を祀ったと云う。香香背男の別名が天津甕星であり、その天津甕星は金星であると今ではそう認識されている。これは天台宗になどの三光信仰の頂点に立つものが金星である事に関連している。その勝道上人が川岸に星の宮を祀ったというのは、やはり川の流れを意識していたものと思える。それは、川は山と海とを繋げる一筋の流れでもあり、それは一筋の竜蛇でもあるからだ。天空に広がる天の川もまた竜に見立てられたのは、川そのものが竜として認識され、それを天空に投影されたものであった。会瀬浦の別名七夕磯にある二つの磯(石)は星として表現されている。それは星堕ちて石となり、それは金の散気であるという信仰が定着しているからであった。 ところで「いわき市史」によれば、胡摩磯に白山神社の神と二荒神社の神が出現したとあるが、両神は同じ神であるのだろうか?このいわき市の白山神社の縁起書は皆無で、一体どういう神を祀っているのかはわからないそうだ。しかし、日光二荒山神社から勧請された、同じいわき市の二荒神社の神と同じく胡摩磯に出現する事から、同じ神であると想定される。 また、常陸国では神の出現する磯をサクともオンネ磯とも云われる。「オンネ磯」は「御根磯」であろうとされ、「根」は「よりどころ」の意もある事から、神の依代としての磯であり石の意であろう。ところが「サク」は正式には「咲浪」であり「サクロ・サクラ」とも呼ばれるようだ。春に咲く桜が「サク・ラ」「サ・クラ」と分割して思索されているが、結局は咲浪と同じ神の依代の意であろうと思う。その咲浪に関する伝承には、海に潜った海士が鮑を抱いて現れたという。「海中ノ事ヲ云ハズ、只此レ以降、鮑ヲ取ル事ナカレ」と告げ、仏門にはいったという。また別に「西金砂山縁起」によれば、延暦25年に西金砂の神が鮑の小舟に乗って水木の海に着いたとある。鮑は磯に付着して生息するもので、磯に出現する幣物として使われている実際、山に囲まれた遠野にある神社の祭壇に、鮑の殻を祀っているのをよく見かける。鮑は幣物であり、神の乗り物でもあると知られている為であろう。そして、その鮑などが付着する磯そのものが神格化されて作られたのが、安曇磯良であるのは理解できる。「八幡愚童訓」や「八幡宮御縁起」によると磯良は「常陸国または筑前の海に住む。」これは「琉球神道記」に記されている「鹿島の明神は、元はタケミカヅチの神なり。人面蛇身なり。常州鹿島の海底に居す。一睡十日する故に、顔面に牡蠣を生ずること、磯の如し。故に磯良と名づく。」に対応するものだ。磯良の本来は、白龍であり白蛇と説明したが、これらを全て結び付ければ、鹿島神宮の神とは蛇神であり、それは二荒山の蛇神であろうと想定でき、それに加え金星が関係するのが理解できる。 |
|
|
■十五
鹿島神宮の社殿は北向きに建てられ、何故か神坐は東向きとなっている。その理由は定かで無いとされながら、出雲大社に似た様な造りであると云われている。その鹿島の語源に甕島説があり、甕山を起こりとする香山(かしま)が鹿島に代わったというものだ。また神島という神の鎮まる島という説もある。「常陸国風土記」には、こう記されている。 「高天の原より降り来し大神のみ名を、香島の天の大神と偁ふ。天にては則ち、日の香島の宮と號け、地にては則ち、豊香島の宮と名づく。」 ただ「香島」は「かぐしま」と呼んでいたともされている説があるのだが、そこで思い出すのが鹿児島である。その鹿児島に聳える霧島山を天孫降臨の地としている事から、この鹿島の地との重複性がある。その霧島山の麓に鎮座するのが鹿児島神宮で、鹿島神宮と同じ北向きであると云うが、この共通点はなんであろうか。北向きとして考えた場合、つまり鹿児島神宮の背後には霧島山では無く、桜島に向けて参拝するという事にもなる。桜島は古代に鹿児島とも呼ばれた説がある事から、本来は桜島の神を祀る神社であった可能性があるかもしれない。鹿児島は隼人の本拠地でもあり、その隼人の信仰する地主神が桜島に祀られ、その神が伊勢神宮にも祀られている可能性はあるのだろうか。だがこれ以上の鹿児島神宮の詮索は、別の機会にする事にしよう。 鹿島神宮は北向き社殿で神坐は東向きであると書いたが、東は海である事から神坐の武甕槌は海を睨んでいる形となる。北上川の支流であり、早池峯を水源とする猿ヶ石川の下流に、坂上田村麻呂が猿ヶ石川を交通路として移動する蝦夷を睨む形にして兜跋毘沙門天立像を祀ったとされているのに近いのでは無かろうか。鹿島の御神体は大甕であるというが、武甕槌も甕の字があるという事から、武甕槌の御神体とも云われるが、武甕槌はいつしか甕を外され建御雷神となった。しかし甕も雷も蛇神のイメージにはあるが、本来の蛇神は鹿島の海にある甕であり磯であり、蛇神である磯良神ではないだろうか。その蛇神を睨むように建御雷神は、鹿島神宮に鎮座していると考えるのが普通であろう。 伊邪那美が火之迦具土神を産んで死んだのだが、その火之迦具土神の迦具は「カグ」で輝く意を持っている為か火の神とされているが別に、母親を殺した忌子ともされている。古代からの習俗に、鬼子を見分ける方法が伝わっている。生後1年の赤子に、一升餅を背負わせる方法だ。これは生れて1年の赤子は、一升餅を背負って歩けるわけがないという前提であった。過去に、一升餅を背負って歩いたのは、酒呑童子であり、茨城童子という鬼子であった事から、それらと同じ子を鬼子として間引きしたと云われる。つまり忌子であり鬼子は、両親から離されたのであった。 香香背男であり、天津甕星には何故「天」が付くのか。それが天孫族の一員であったなら、それは親に逆らった忌子でもあり鬼子でもあったのかもしれない。それ故に排除されたのが、香香背男であり天津甕星だったのか。聖武天皇時代に妙見信仰は、庶民が祀るのを御法度にされた。江戸時代になっても星の信仰は邪教とされたのは、太陽も月も無い夜というのは、星は輝いてはいるが、真っ暗な夜という事に加え、石川五右衛門が庚申の日生まれという事から、星の輝く夜というのは泥棒の暗躍する夜であるとされた。しかしそれは、それ以前から天津甕星という星の惡神の影響が無かったとは言えない。 古代に何があったのか、なかなか知る術は無いのだが、香香背男であり天津甕星が封じ込められたのだけは理解できる。その香香背男は神名に「男」が付けられている為に男神と思ってきた。しかし香香背男をカカセオとし「カカ」が蛇の古語とし、「セオ」を考えた場合、遠野の大蛇退治の伝説が頭を過った。 遠野の土淵に流れる小烏瀬川は、早池峯から転げ出した石が滝に落ちて、そこが小烏瀬川の滝となり、その川が小烏瀬川となったとの伝承がある。その小烏瀬川に、大蛇の舌出岩、大蛇の胴体である続石、そして大蛇の尾石の三分割に分かれて点在している。その大蛇の尾石がある地を現在は大樽という地名になってはいるが、どうも古くは大垂であったようだ。大垂は大きく垂れる意でもあり、大きく水が垂れ落ちる意でもあって滝の意にもなる。その大樽の地に鎮座する神社は、水破大明神を祀る神社となっているが、別当に聞いてみると本来は白龍神社であったそうな。小烏瀬川の瀬の尾に大蛇であり白龍の尾石を祀っている。流れの速い瀬は滝にも通じる事から、瀬の尾とは滝の意にもなるようだ。つまりカカセオのセオとは、滝の意でもあるよう。そこで思い出すのが二荒山の麓に祀られる滝尾神社だ。 |
|
|
■十六
香香背男なのだが、隠岐島の海上に星神島(ほしのかみしま)で香香背男が竜神として、いつの時代かわからない古代に祀られていた。星神島には禁足地となっている場所に神聖な泉が湧いており、島民が雨乞いをする場合は、禁足地に入りその泉の水を汲むと、香香背男がその汲まれた水の分だけ雨を降らせるのだと。ところがこの地に祀られる香香背男の神名は「鹿賀瀬雄命」としているが、どうやら女神であるらしい。ここで思い出すのは「琉球神道記」だ。 「鹿島の明神は、元はタケミカヅチの神なり。人面蛇身なり。常州鹿島の海底に居す。一睡十日する故に、顔面に牡蠣を生ずること、磯の如し。故に磯良と名づく。」 琉球で鹿島の神を述べているが、琉球から遠く離れた常陸国の鹿島の神の事を述べるには、少々ピンときていなかった。しかし鹿島が実は神島とも記す事を知り、もしかしてこの星神島とは星の神島であり、星の鹿島でもあるのだと思える。 静神社の神が実は龍蛇の女神とわかり、その龍蛇の女神が鹿島神宮の高房社に祀られ、鹿島神宮の祭神である建御雷神よりも先に参拝しなくてはならないしきたりがあるというのは、鹿島の御神体が大甕である事からも、天津甕星とも云われる香香背男であるのだろう。その常陸国の香香背男が、分霊もされていない西国の隠岐島の沖の星神島に鹿賀瀬雄命という神名で祀られている。しかし鹿賀瀬雄命は、あくまでカカセオという音に漢字を適当にあてたものだろう。しかしその中にも鹿という文字に注目すれば、鹿島が香島であり「カグシマ」とも「カゴシマ」とも云われる事から、この星神島の香香背男もまた鹿島との関係があるのだろうと推察する。つまり「琉球神道記」の言う鹿島とは、この星神島の鹿賀瀬雄命と混同しているのではなかろうか。いや混同というよりも、元々は龍蛇神である香香背男が常陸国の鹿島神宮に祀られたと考えるのが通常だろう。鹿島の神が磯良であるならば、それは白龍であり白蛇の姿が本来であるからだ。 常陸国の香香背男の伝承の中に、富士山にいた香香背男が天孫族に追われて逃げたというものがある。富士山に関しては前にも書いたとおり、高天原としての資質はじゆうぶんに有り得る霊峰でもある。まつろわぬ神としての天津甕星である香香背男が富士山を追われたという伝承は、自然と受け入れる事は出来る。ところで日光にある富士山の姿がが映る池に、富士山の女神が映ったので二荒山に祀ったというものがあるが、これが富士山を追われた香香背男と結び付くのは定かでは無いが、星神島で祀られる実は女神であるいう鹿賀瀬雄命の神名を見た時に思い浮かぶのは滝尾神社であった。前に書いたように、滝は瀬でもある。滝尾神社の祭神は田心姫となっているが、これは9世紀に田心姫が祀られたからであり、それ以前は謎でもある。この滝尾神社の神は、何故か鶏を忌み嫌うと伝わる。ここで思い返すのは、星は太陽も月も無い夜空に輝くものであり、その存在が輝いているのは夜が明けるまでである。 全国に伝わる鬼などの伝承に、一番鶏が鳴くまでに石段を作るとか山を重ねて大きくするなどの伝承があるが、その夜の闇に跋扈する鬼達等が忌み嫌うものは、夜明けを告げる鶏である。滝尾神社の祭神が鶏を忌み嫌うというのは、夜の闇で輝く星を消すからでもあると考える。また鶏は伊勢神宮の使役でもある事から、伊勢を忌み嫌うとも捉え様か。それは天照大神が出ると共に隠される存在の神であると考えても良いだろう。 画像の氷雨除けの御札は、横瀬町資料館に展示してるもので、秩父・仙台まほろばの道さんから借り受けた画像です。 武甲山の御嶽神社と熊野神社に伝わる氷雨除けの御札がある。なるほど武甲山の御嶽神社にはヤマトタケルが祀られている。「古事記」では白猪が山神の使役となっているが、「日本書紀」では白蛇が登場し、氷雨を降らせている。牛頭天王の様に厄災はその厄神を祀ってこそ護られるという前提に立てば、武甲山の神も熊野大神も氷雨を降らせる存在と捉えて良いだろう。 ところで常陸国の香香背男のそれほど古くないであろう伝承に、香香背男は別名「コオラサメ」とも呼ばれるとある。「サメ」を「鮫」と捉えた場合、取りとめのないものに思えるが、香香背男が龍蛇神であると考えれば「日本書紀」での氷雨を降らせたのが山神であり、その使役の白蛇ならば、「コオラサメ」とは本来「氷雨」を読み間違って「」「コオリサメ」と読んだものが「コオラサメ」と読まれ伝わったのでは無いかと考える。熊野三社権現と伝わる熊野だが、熊野権現であり熊野大神とは那智の神を意味し、それは那智の滝神でもある事から、氷雨を降らせる神と考えても不思議では無いだろう。そして香香背男が龍蛇神であるならば、当然氷雨を降らせる事も出来るだろう。 鹿島神宮から分霊された、いわき市の鹿島神社と白山神社の神は、二荒山から、いわき市の磯に出現する伝承から考えても、鹿島神宮と静神社と二荒山は繋がってくる。その二荒山に祀られている神の中で、それらに関連出来るのは滝尾神社の祭神だけてあろう。恐らく香香背男は作られた仮の名であり、本来の正体は龍蛇の女神であるのだろう。 |
|
|
■十七
「磐裂神の奇端」によれば「汝、山川を跋渉して三神にあい奉り、勝地を草創して、遠く末代の群生を救うべし。我は、天にありては太白星となりて顕れ、この國に降りては、磐裂の荒神たり。」この文を要約すれば、「星堕ちて石となる。」であろう。ただし、その中心の星は太白星である。 栃木県と茨城県に数多くの星の宮神社が祀られ、その祭神で一番多く祀られているのは磐裂神、根裂神であり、磐筒男神や香香背男がその後にくる。火之迦具土神が伊弉諾に切られた後、その火之迦具土神の血が広がって化生したのが磐裂神。根裂神であり、そのあとに石筒之男神などであるが、筒が星を意味する事から、あの一文には安曇族の神を羅列したのではないかとも云われる。これらの多くが栃木県と茨城県に広がって多く祀られているのは、この地域に星の信仰が根付いたという事であろうし、その中心はやはり、二荒山なのだろう。しかし勝道上人をの導いた太白である金星の信仰を、二荒山神社に祀られている祭神から感じないのはどういう事であろうか? 菊池展明「エミシの国の女神」で、愛知県の天白神と太白神について言及している。天白神を祀る神社は合計27社となり、そのうち一番多い天白神社の祭神は瀬織津比咩となっており、次に宇迦御魂命であり、3番目に香香背男となっている。太白であり金星を、菊池展明は「天に白々と光る星」として考えているが、その天白神の実際は養蚕神であった。しかし、その養蚕神として香香背男が祀られている事を踏まえれば、太白と天白が自然と結び付くのである。 静神社の祭神は天羽槌雄神であるようだが、静神社の創建に関わったのは秦氏であり物部氏とも伝えられる。その後に忌部氏が支配して、天羽槌雄神を祀ったようである。やはり静神社の祭神は龍蛇神であったのは明白である。その静神社の祭神だが、天羽槌雄神の以前は、どうやら天手力雄神であったようだ。つまり龍蛇神の後に、二度の祭神変更があったようだ。その天手力雄神で思い出すのは、長野県に鎮座する戸隠神社である。戸隠神社の祭神も天手力雄神であるが、本来は地主神である九頭竜が祀られているのを天手力雄神が封じ込めたという事になっている。恐らく静神社も、戸隠神社と同じ系譜を踏んでいるのだろう。 愛知県の養蚕に関する天白神社の祭神の一番多くが瀬織津比咩となっているのは、遠野の伊豆神社に伝わる伝承からも理解できる。しかし、その天白神社の祭神に香香背男が祀られているという事は、恐らく瀬織津比咩と香香背男は同一神では無いかと思えるのだ。それは前回紹介した、星神島の鹿賀瀬雄命(カカセオ)という女神が、聖なる泉を護る龍蛇神であった事と、瀬織津比咩の別称である撞賢木厳之御魂天疎向津媛命を結びつけた時に納得するのだ。 甕は、厳めしいでもあった。その事により、天津甕星も武甕槌も武神であるとされているが、「撞賢木厳之御魂天疎向津媛命」の「厳之御魂」に着目し、それを「甕之御魂」に変えたとしても不自然さは無い。逆に言えば撞賢木厳之御魂天疎向津媛命は撞賢木甕之御魂天疎向津媛命でも良い事になる。三浦茂久「月信仰と再生思想」によれば、様々な用例を踏まえ撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とは「月が空を西に去っていく事。」と解いている。月は、変若水の信仰などから水の精でもある。その水を汲み置く「甕」の文字を「厳」に置き換えて撞賢木甕之御魂天疎向津媛命とすれば、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とは月の女神であり御気津神であるとわかる。伊勢神宮は「伊勢神宮は月の宮?」で書いたように、恐らく月の宮であろう。その月の宮である伊勢神宮の荒祭宮に、撞賢木"甕"之御魂天疎向津媛命が祀られるのは自然の事である。ならば甕を通じても、瀬織津比咩と香香背男が同神である可能性は高い。 ここで再び、伊勢神宮に戻ろう。荒祭宮には本来の神であるアラハバキ姫とも呼ばれる神が祀られており、現在は天照大神の荒御魂として瀬織津比咩が祀られてはいる。そして伊勢神宮の外宮にはその荒祭宮を支配していた度会氏が伊勢神宮そのものを支配して、豊受大神を前面に押し出し外宮を優位に付けた。 豊受大神は丹後国から来た御饌都神であると伊勢神宮の外宮に運ばれた由来を持つが、度会氏が御気津神という水神の最高位に昇華させた。その外宮は本来御饌都神の集まりの宮である為、多くの御饌都神がいるのだが、豊受大神は御饌都神では無く、御気津という水神にした理由は甕では無かったか。豊受大神の荒御魂を祀る多賀宮の祭神は瀬織津比咩の別称であった。その豊受大神は、常陸国の「我国間記」によればも元々は常陸国にいた女神であり、それが丹後国を経由して伊勢に祀られたとある。 中世神話は新たに作られた神話であり、神々の編纂が成された。極端な例として、宗像三女神が五女神となったのも中世神話である。その中で、豊受大神は止由気でもあり天御中主命と同体とされ、更に宇迦御魂命、大気都比売神、保食神などとも同じとされたのは、豊受大神自体の神格を誤魔化す為でもあったのだろう。 その常陸国に多くある月とも関係しそうな星宮神社の祭神を調べると、豊受大神は一社だけしかない。栃木県の星宮神社を調べても無い。それでは御饌都神として養蚕関係の神社を調べても、豊受大神の名前は無い。それでは「我国間記」に記されている豊受大神が常陸国出身の神であるというのは嘘なのだろうか?豊受大神は丹後国に天女としてどこからか飛来した事になっている。天女の羽衣と養蚕の結び付きは、全国に多く定着している物語ではあるが、豊受大神をそういう神としているのは丹後国だけである。素直に信じれば、豊受大神は丹後国出身であるとなるのだが、やはりどこからか飛来してきたのが豊受大神であるならば、本当の豊受大神の出身地がある筈である。 |
|
|
■十八
天女の羽衣伝説を考えて、遠野での天女伝説は天人児として伝えられ、それは六角牛から飛来した事になっている。しかし、遠野には豊受大神を祀る神社が殆ど無い。伊勢神宮の外宮に祀られる豊受大神が天女の大元であるならば、六角牛山を祭祀する六角牛神社と六神石神社のどちらかに豊受大神がいても良い筈である。六角牛山の祭祀を掌握していたのは、既に廃寺となっていた六角牛山善応寺であった。その六角牛山善応寺に祀られていた神々の中に、宇佐明神という神が祀られていた。その宇佐明神とは、九州においては湍津姫神となっていたが、その正体は瀬織津比咩であった。天女であり水神系の神である存在は、六角牛山においては瀬織津比咩だけであった。 また同じ女神として祀られているのは神功皇后であるが「日本書紀(神功皇后記)」において、神意を聞こうとする時に神功皇后が真っ先に名前を呼んだ神名は撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、瀬織津比咩の異称であった事を考えれば、その撞賢木厳之御魂天疎向津媛命である瀬織津比咩を呼ぶ為に祀られているのが神功皇后であろうか。考えてみれば、六角牛山に住吉三神も祀られている事からも「日本書紀(神功皇后記)」を考えれば、神功皇后が真っ先に呼んだ撞賢木厳之御魂天疎向津媛命を省いて、住吉三神だけ祀る筈も無い。更に六神石神社には養蚕宮という御饌都神が祀られているのは、天女伝説との結び付きを示している。それに対応できるのは、伊勢神宮の御饌都神の集まりである外宮の多賀宮に祀られる瀬織津比咩でしかないだろう。 常陸国の鹿島神宮での御神体は、海に沈んでいるという大甕であった。だからこそなのか、本殿に祀られている建御雷神は海の方向である東を向いている。その海には神が磯であり石に出現する磯出という神事が、常陸国で広く行われている神事でもあった。その中に、二荒山から降りた神が出現するとあるのは、勝道上人の奇譚からくるものであったよう。それは「星堕ちて石」となるものであり、その中心は太白である金星となる。その星の信仰が、常陸の磯場にあり、それを七夕磯とも呼ばれており、やはり磯である石が星に見立てられていた。 二荒山は栃木県に属するのだが、常陸国はその二荒山から水の恩恵を受け、その二荒山を遠くに見て信仰していた。これらを考えても、二荒山と鹿島神宮が関係無いとは言い切れないだろう。その鹿島神宮に参拝して真っ先に拝まなければならないのは、高房社に祀られている静神社の祭神である龍蛇神であった。この龍蛇神は養蚕の守護神であり、御饌都の神でもある。静神社の祭神は天羽槌雄神となっているが、それ以前が天手力雄神である事を考えれば、天手力雄神が戸隠神社で九頭竜を封じ込めているのだが、それと同じように長谷寺に祀る十一面観音の本来が地主神である九頭竜の祭祀であった事を考え合わせても、常陸国の静神社に祀られる神は龍蛇神であり、それは同じ大甕倭文神社に祀られる香香背男である天津甕星であろう。大甕倭文神社という名前そのものも、「大甕」と「倭文」と分けてみても、どちらも御饌都神を祀っているのがわかる。 不服はぬ神甕星香々背男が久慈郡大甕山の巨石に変じて、日ごと成長し天にもいたらんとする。この悪しき神に対し、香取の経津主命と鹿島の武甕槌命が、武神である武葉槌命を遣わし、岩に姿を変えた甕星香々背男を金の沓で蹴り上げると、岩を砕け、一つは神磯として今に伝わる「おんねさま」になり、あとの石は石神、石塚、石井に飛んだ。 大甕倭文神社の由緒は上記であるが、つまり香香背男の影向するのは石でもあり、石そのものが本体でもあるという事。それはつまり、磯出である。それを天羽槌雄神が蹴り割ったというのは、その魂の復活を阻止したという意味であり、天羽槌雄神が建御雷神の命を受けて香香背男の磯出を封印したとの事であろう。それ故に、静神社と大甕倭文神社の祭神が天羽槌雄神になっているのは、どちらも香香背男である子天津甕星を封印する為に祀られたのだろう。 室町時代に成立した「日本書紀纂疏」では、星に関してこう記述されている。 然らば則ち石の星たるは何ぞや。曰く、春秋に曰く、星隕ちて石と為ると「史記(天官書)」に曰く、星は金の散気なり、その本を人と曰うと、孟康曰く、星は石なりと。金石相生ず。人と星と相応ず、春秋説題辞に曰く、星の言たる精なり。陽の栄えなり。陽を日と為す。日分かれて星となる。 故に其の字日生を星と為すなりと。諸説を案ずるに星の石たること明らけし。また十握剣を以てカグツチを斬るは是れ金の散気なり。 この「日本書紀纂疏」の一文を読んでも、香香背男は金星であり石であるのだが、もう一つ金であるという事だ。金は、黄金・白銀・黒金など金属を総称して金である事から、金属の神であったのが香香背男であり天津甕星であった。その本体が龍蛇神であるならば、それは「鉄の蛇」という事である。 甕は御饌都神の証でもあるが、甕は厳でもあり、それは荒ぶる神でもあるという二面性を持つ神だ。つまり甕の御魂でもあり、厳の御魂でもあるのは、前回に書いたように撞賢木厳之御魂天疎向津媛命が撞賢木甕之御魂天疎向津媛命でもあるという事と同じである。 |
|
|
■十九
愛知の天白神社から瀬織津比咩は天白神でもあるのはわかったが、別に「麻栽培の神」とも云われ別名として「天白羽神」でもあるとされている。それで面白いのが「古語拾遺」である。「記紀」には記されていない事が書かれてあった。それは天照大神が天岩戸に籠って、他の神々が天照大神を天岩戸から出す準備をしている時の話である。 天香山の銅を取りて、日の像の鏡を鋳しむ。長白羽神(伊勢国の麻続が祖なり。今の俗に、衣服を白羽と謂ふは、此の縁なり。)をして麻を種ゑて、青和幣と為さしむ。天日鷲神と津咋見神とをして穀の木を種植ゑて、白和幣(是は木綿なり。己上の二つの物は、一夜に蕃茂れり。)を作らしむ。天羽槌雄神(倭文が祖なり。)をして文布を織らしむ。天棚機姫神をして神衣を織らしむ・所謂和衣なり。 「古語拾遺(抜粋)」 ■ 長白羽神の別名は天白神であるから、つまり香香背男ではないかともされる天白神と、その香香背男を倒した筈の天羽槌雄神が一緒に、天照大神を天岩戸から出す為の準備をしているおかしな話になっている。「古語拾遺」は大同元年の成立とされるが、若干のズレはあるようだ。ただ「中臣・忌部相訴」によるものであるらしい。とにかくこの一文を読めば、香香背男も天羽槌雄神の養蚕神という事になろう。 天白信仰を長白羽神由来とするらいしが、それから白い衣類を白羽と云うのだと。大嘗祭や神今食の大祭に、天子が湯殿で禊に用いる浴衣を天の羽衣と呼ぶが、それは白羽とも呼ばれたようだ。「古語拾遺」に記されているように、長白羽神は麻続を祖とするが、それは姫命が垂仁天皇26年、飯野高丘宮に機屋を作り、天照大神の服を織らせ、そこを服織社と名付け、神麻績氏の住む麻績郷で荒衣を織らせたとする。つまり麻の衣の事をいうのだろう。旧四月と旧九月の神衣祭では内宮と荒祭宮だけに神服織殿で織った神衣を供えるという内宮と同格に祀られる荒祭宮の祭神を考えれば象徴的な神事である。 極端に言ってしまえば、香香背男は天の羽衣を織り、天羽槌雄神は倭文を織ったという事だろう。しかしそれは、やはり「古語拾遺」に記されているように、忌部氏が阿波から関東に移り住んで安房国となり、それから徐々に進出して、常陸国の静神社をも支配下に置いて、天羽槌雄神を祀ったのではなかろうか。それ以前の祭神が天手力雄神である事を考えれば、忌部氏の権威の象徴が天羽槌雄神である為に、静神社と大甕倭文神社に天羽槌雄神を祀ったのだろう。恐らく「日本書紀」での一書での天羽槌雄神の登場は、その頃に書き加えられたものではなかろうか。 ここで再び、豊受大神に戻ろう。「我国間記」によれば、常陸国を祖国とし、丹後国を経由して伊勢に祀られたとする豊受大神だが、常陸国にはその痕跡を見出せない。しかし、天女という共通項を持って繋がるのは、恐らく静神社に祀られていたであろう蛇神でもあった香香背男であり天津甕星である。金星を意味する天白神であり天白羽神が羽衣を織ったという「古語拾遺」からも、天羽槌雄神と天女は結び付かない。となれば、豊受大神という名を借りて、伊勢神宮の外宮に祀られたのは、今までのパズルのピースを組み合わせていくと、それは天津甕星でもある香香背男であり、その実態は龍蛇神でもあり、アラハバキ神でもある瀬織津比咩でしかない。 もう一つ、近江雅和「記紀解体」によれば、伊勢神宮には太一信仰があると述べている。太一は最高の神であり、その居所は北極中枢だとされ、北極星の神霊化であるとしている。いわば北辰信仰であり、妙見信仰である。ところで妙見信仰を調べていると、星の宗教とも云われる天台宗において、北極星と北斗七星、そして金星である太白が同一視されていた。簡単に言ってしまえば、星を尊ぶ信仰の上にまとめられたのだろう。それは三光信仰・・・つまり、太陽と月を合わせて、明星(金星)とし、その星を最高とするものと、妙見をも含めてしまっての星信仰となったのではなかろうか。仏教が盛んになった聖武天皇時代も、聖武天皇は妙見信仰に心を傾けた。その星信仰を継承した桓武天皇時代となり、桓武天皇は庶民に星の信仰を禁じた。その桓武天皇の死後、平城天皇と嵯峨天皇の時代の大同年間に「古語拾遺」が成立したのは、星神を悪神とし庶民から星の信仰を消し去ろうとした意図があったのではなかろうか。それは先に記した天羽槌雄神という神を、後から「日本書紀」の一書に書き加えたのではという疑念も加味している。何故なら「子持大明神縁起」からも、荒祭宮に祀られる鈴鹿を出自とするアラハバキ姫とされる神が、いつしか鈴鹿の鬼女として、蝦夷国を舞台とする蝦夷征伐の話に、坂上田村麻呂と共に語られるのは、やはり大同年間の事であったからだ。 遠野の早池峯の麓に流れ落ちる滝は、早池峯神社の御神体でもある。その名を又一の滝とは言うが、それを紐解けば本来「太一の滝」であった事が理解できた。それは早池峯が北に聳える山であり、妙見信仰の影響を強くして語られる山とされたからだ。その早池峯を信仰した安倍一族であり、奥州藤原氏は、羽黒修験との関係も深かった。その羽黒に建立された五重塔は、平将門が建立したという伝説も生じているが、内藤正敏「羽黒山・開山伝承の宇宙観」によれば、その五重塔内部には妙見が祀られていた。 ところで、藤原氏の勅命によって岩手県と秋田県にまたがる地域で二万程の新山寺や新山神社が建立されたというが、その新山神社の祭神は玉依姫であり羽黒権現となっているが、それは仮の神名であり、その本来の神名は、早池峯大神である瀬織津比咩であった。大迫の早池峯神社が、遠野早池峯神社に向けて建てられているのも、早池峯山そのものが北を重視した山である事からである。だから大迫の早池峯神社は、遠野早池峯神社を経由して、北に聳える早池峯を拝む事になる。 妙見神とは、大亀に乗った女神として現される。大亀は大瓶であり、大甕でもある。ここで思い出すのは、鹿島神宮の御神体が大甕であるという事。そしてそれは、龍蛇神でもある。陰陽五行での亀は玄武を意味し、北の守護にあたり、水を意味する。鹿島神宮が何故に北向きの社殿で、祭神である建御雷神が大甕が沈む東の海の方向を向いているのかという、パズルのピースを構築していくと、そこに現れる神は、伊勢神宮の荒祭宮に祀られる天照大神の荒御魂である瀬織津比咩の姿になるのである。 |
|
|
■二十
栃木県と茨城県に跨って多くの星の宮神社が点在しいるのは、やはり星に対する信仰があったのだとも理解できる。しかし、調べてみると、その星の宮神社の多くは、磐裂神、根裂神を祀り、星の信仰よりも農耕に関する信仰が多いのだという。高藤晴俊「日光山鉢石星宮考」によれば、江戸時代初期には磐裂神、根裂神を祀ってはおらずに、殆どが虚空蔵菩薩が祀られていたらしい。虚空蔵は「こくぞう」と読まれ「穀蔵」と漢字をあてられたことから、農業神にもなっている。後に、磐裂神、根裂神に変わっても、磐裂・根裂という意味は、土地の開拓にも通じる事から農民に広く信仰されたそうだ。それでは、星の宮神社は石も星も関係ないのかと調べると、古くから祀られている星の宮神社には虚空蔵菩薩と妙見信仰が一体化している事例が多いという。虚空蔵菩薩は仏教の普及によるものであうが、どうもそれ以前は妙見を祀っていた節がある。 その星の宮神社の中で気になるのは、太平山神社だ。その太平山神社は別に太平山三光神社とも云われ、その境内社に星宮があり、香香背男が祀られている。太平山神社の開祖は慈覚大師円仁であるらしいが「太平山傳記」によれば、淳和天皇の御宇に九月二十二日に太平山に登った円仁の前に北斗七星の神が顕れ、その神が隠れた後に、その本地仏である虚空蔵菩薩を拝したという。元々太平山は円仁の介入の前に、信仰されていた霊山であったようだ。これによれば、妙見神は虚空蔵菩薩と一体という事になる。 ところが「太平大権現略記」によれば、垂仁天皇の御宇に天一目大神を祀っていたとある。これはつまり、太平山神社自体が、円仁の前に創建されていたのか、それとも社殿が無く、天一目大神が山に祀られていたのか定かでは無くなる。ただ言えるのは、恐らく栃木県や茨城県に広がる星の宮神社の祭神は、虚空菩薩以前は妙見神であり、天一目大神の可能性があったようだ。天一目大神は、製鉄・鍛冶の神でもある。実際に、太平山の奥宮には剣宮があって天目一神を祀っている。更に付け加えれば、祓戸四柱之大神を祀っていた。 この茨城県と栃木県にまたがる太平山という山の名称だが、遠野にはかって天台宗の積善寺があり、その向かいの山を太平山と呼んだ。現在、遠野の伊勢両宮は本来土淵町に鎮座していたものを、源頼朝の奥州征伐の後に栃木県から来た阿曽沼氏の時代に建立された積善寺の向かいの太平山にその伊勢両宮を移転した。 栃木県の太平山神社の言い伝えに鰻を食べないというのがあるが、その鰻は蛇とも混同され、水神の使いであるという。その鰻は、太平山に伊勢の神を導いたとされている。遠野での積善寺の構造は、積善寺そのものには不動明王を祀り、その奥宮を見ると六角牛山と、水神・不動と刻まれた石塔が建っている。つまりこれは、この積善寺の奥宮に、不動明王と共に六角牛山の水神を祀ったという事だろう。その向かいの太平山には伊勢両宮が祀られている事から、積善寺と太平山の伊勢の神を結ぶものは水神の使いという構造を、阿曽沼氏が遠野に持ち込んだものと思える。 そしてもう一つ、秋田県に聳える霊山にも太平山がある。そこに鎮座する神社は太平山三吉神社という。菅江真澄「月の出羽道」には、こう記されている「比咩賀美箇嵩。此御嶽は瀬織津比咩を祀ると云ひ、また??幡千々比咩を齋と云ひ…。」この比咩賀美箇嵩が、現在の太平山である。これは恐らく、関ヶ原の戦いの後に西軍に味方した物部系氏族である佐竹氏が秋田県に移り住んでから、その太平山信仰を持ち込み、比咩賀美箇嵩を太平山と改名したのであろう。それは比咩賀美箇嵩に祀られている神が、太平山に祀られている神と同じであった為の可能性は強いだろう。その栃木県の太平山三光神社は「太平山傳記」によれば、下記のような祭神となっている。 太平山権現→天孫太神 (星) 熊野大権現→伊弉諾 (日) 日光大権現→大己貴命 (月) 天孫太神は、天照大神の事なのか。また熊野権現とは本来、那智神の事であるのを付け加えよう。そして、日光大権現が大己貴命となっているが、これは二荒山の時にでも言及する事とする。 栃木県の太平山三光神社と、秋田県の太平山三吉神社の名前は殆ど似ている。祭神も三柱の神となっており、それは大己貴大神、少彦名大神、三吉霊神になっている。ただ、三吉霊神とは実在した人物を後に神として崇めた事から祀られているが、これでは元々祀られていた筈の瀬織津比咩の名前が見えない。しかし、秋田太平山山中には御滝神社が鎮座しており、そこに祓戸神として祀られていた。これが秋田太平山における唯一の、瀬織津比咩の残存である。栃木の太平山神社がどうも慈覚大師円仁の介入によって変わったように、それを継承した佐竹氏が、同じくして秋田の太平山に持ち込んだものと思える。となれば恐らく、秋田の太平山の本来も、太平山三光神社ではなかったのか?星の宮神社の全てが水辺に建立されているのも、星信仰と水神信仰が結びついての五穀豊穣祈願になっているのは、虚空蔵菩薩や石析神、根析神が祀られている事からも理解できる。虚空蔵菩薩は金星を守護とするもので、それは太白神でもあり天白神でもあって、香香背男や瀬織津比咩と結び付くからだ。 |
|
 |
|
|
■二十一
太平山を調べると、二荒山の影響を多分に受けているのがわかる。それは太平山の古神祠扉に、別当日光西本坊権少僧都 昌宣の名が記されいる。この昌宣という人物は、日光修験の整備に力を入れた人である。更に男体山山頂遺跡には「太平山 連祥院 奉納男体山 承応二 」との銘が刻まれているものが出土している。この事からも、日光と太平山の深い繋がりが伺える。 そして、もう一つの共通する事がある。太平山はわずか300m程度の山である。その太平山に慈覚大師円仁は、入山する事が出来なかったという伝承が伝わる。少し違うが、勝道上人もまた一日か二日あれば登れる筈の二荒山に、長い年月をかけて登っているのは、既に山にいる勢力との交渉に時間を費やした為だと云われている。勝道上人と円仁との時間差は、大同年間を前後する程度だ。その頃は、桓武天皇の蝦夷支配が強化されている時代であり、それに反発する蝦夷が多かった時代だ。蝦夷は、山でその力を発揮したと云われるが、考えてみれば普段山に登らない人間が、頻繁に山に登っている人間と比較した場合、慣れも含めて、その体力には格段の差がある。平地を歩く体力と、山の急な坂道を歩く体力や脚力は、比べようが無いだろう。恐らく、太平山や日光二荒山に根付いていた勢力とは、蝦夷であったろうと想像できる。 ところで、前回記した太平山三光信仰において「太平山権現→天孫太神 (星)」であるとしている。これは太平山が星の信仰を重視しているものではあるが、天孫太神が天照大神であるならば、それは日になる筈であるが、それが星であるのはどういう事であろう。星堕ちて石となり、それは金の散気である事を踏まえて導き出される神とは、アラハバキ姫とも云われた、天照大神荒御魂でもある荒祭宮の神になるのではなかろうか。アラハバキ神に関しては、以前に氷上神社の祭神がそうであったように、また荒脛神社の教義からも、星と石と金の信仰を見出せる事から、この太平山に祀られていた神とは蝦夷が奉斎するアラハバキ神であったろうと想定できる。 「懸社太平山神社御由緒調査書」によれば「下二十一社ハ往古ヨリ神秘トシテ社号神名ヲシハス総称シテ単ニ星宮ト称セシヲ後ニ氏子村々ノ鎮守ニ移セン」という記述から、太平山を中心に氏子の村々に星宮神社が勧請されていった事がわかる。その星の澪神社の普及を調べると、二荒山の隆盛と連動していた。例えば江戸時代になっても多くの星の宮神社が普及しているが、それまで衰退した二荒山信仰であるのが、徳川幕府が天海僧正を起用してから二荒山信仰が再び日の目を見る様になると共に、星の宮神社も増えていった。つまり太平山を中心とする星の宮神社の普及は、二荒山信仰の隆盛無しでは有り得なかったと思えるのだ。逆に言ってしまえば、二荒山信仰と太平山信仰とは密接な繋がりを持ち、祭神もまた共通するものであると考える。それは恐らく、二荒山も太平山も蝦夷の信仰していた神を崇めていたが、蝦夷征伐の後に、天台宗の僧である慈覚大師円仁の介入によって、その祭神の編纂が行われたのだと考える。それでは、二荒山信仰を考えてみよう。 二荒山で有名なのは、赤城山の大百足と二荒山の大蛇との争いである。遠野にも似た様な伝承が伝わっており、伝説の狩人である旗屋の縫が神に頼まれて、五葉山の大蛇を退治する話となっている。二荒山での話は、小野猿丸が二荒の神(大蛇)に頼まれて、赤木の大百足を退治するのだった。しかし「日光神戦譚」によれば、小野猿丸の代わりに登場しているのは、唵佐羅麽女であり、その力によって二荒山の神が勝利している。その唵佐羅麽女とは、赤城の沼の竜神であるという。どうも、小野氏の進出により、本来は唵佐羅麽女であったものが、小野猿丸に書き換えられたという事らしい。その小野氏であるが、関東に二つの小野氏に関わる小野神社が二つあり、その一つの小野神社に瀬織津比咩を祀り、もう一つの小野神社に荒覇吐神を祀るというのは示唆的である。 それとは別に日光には「朝日長者物語」があり、その主人公の有宇中将が都落ちをし東北の朝日長者の娘を娶り、やがて離れ離れになって非業の死を遂げるが、その後に一波乱があって最後は、その夫婦が日光の神となったというものである。ところで遠野には朝日巫女の伝説があり、朝日長者の娘が行方不明になり、長い年月を経て再び戻って、遠野に起きた洪水を修行してきた巫女の法によって村を助ける話がある。その巫女は一説には、二荒山で修行したとも云われる。それが日光に伝わる「朝日長者物語」と結び付くものであるならば、神懸かった遠野の娘が二荒山の神となったという話になってしまう。それは暗に、蝦夷の信仰していた女神を二荒山に祀ったともとれるのだ。 東北のマタギは殆ど日光権現に許可を得た日光派に属するマタギで、高野派というのは皆無である。それ故に、旗屋の縫の大蛇退治の話も伝わっているのが理解できる。ただ、朝日巫女の伝説は、実体があるようで、なかなか掴み切れないのが実情だ。水を自在に操る巫女であったようで、川の流れをも変えてしまった程の力を持っていた事から龍神の生まれ変わりとも云われている。遠野において、その朝日巫女は朝日神として石碑に名を刻まれ、また別にある山に墓石が建てられて供養されている。現実と幻想が交差しているのが朝日巫女という存在でもある。とにかく唵佐羅麽女であり、東北の娘などが二荒山に味方した事によって、二荒山が勝利したという方程式は崩れない。ただ、そのどちらも本体は、龍神に関係する女であったようだ。いや、女神といって良いのであろう。 |
|
|
■二十二
また少し二荒山から太平山に戻るが、近江雅和「消された星信仰」には、気になる記述があった。 関東平野を一望できる太平山である。平野を中にして東の筑波山と対峙している古来からの霊山であった。天長十年(833年)に慈覚大師円仁が開山して山上に太平権現を祀り、神体山男体山の前山としたといわれる。 筑波山が登場したが、筑波山は加波山と連なる連山でもある。男体山と女峰山との連山の間にあるのが太平山であり、男体山→太平山→筑波山は、ほぼ一直線になる。つまりどちらにも対応するのが太平山であり、ある意味どちらの遥拝所としての機能もあり、またどちらの山の影響を受けているとも考えられる。 近江雅和「消えた星信仰」には、その太平山の図が掲載されており、御影山と並ぶ連山でもあるのが太平山なのであろうか。その二つの山の間に三輪神社があるという事は、物部系の影響を受けていると共に、やはり祀られる神とは蛇神であろうと想定できる。太平山三光神社の本地仏は虚空蔵菩薩であり、その本地仏を納めているのが太平山星宮神社である事から、古代信仰形態はやはり星の神である香香背男になるのではなかろうか。 連山となる山の形はM形となり、左右と真ん中で、三つの谷を有する事になる。筑波山の連山も含め、三谷を二渡れば、二荒山へと行き着く。夷振歌は、舞台も全く違う連動性の無い歌が、二つ連なって紹介されているのは、逆に言えば、二つの歌を合わせて意味を持たせているのだとも思える。その舞台は、この関東に置いてのみ意味の成す歌となったのだと考えるが、これの言及は後にする事としよう。 ところで、二荒山を調べるにあたって、気になる氏族は阿曽沼氏である。奥州藤原氏を滅ぼした源頼朝の命を受け、遠野に移り住み支配したのが阿曽沼氏であった。本来は佐野氏であったが、安蘇郡に住んでいた事から阿曽沼と名乗ったという。しかし、そのまま安蘇氏と名乗っても良い筈なのが、何故か安蘇に沼を加えて、阿曽沼と名乗ったのはどういう事であろう。これも多分に、安蘇郡の影響を受けていると思われるが、定かでは無い。 二荒山と赤城山の戦いを調べると、その原因は沼の争奪戦であったと云われる。また各風土記に登場する荒ぶる女神の話は、山での水の争奪戦の後、女神が男神をどこかに追いやる事で帰結している。かたや沼の奪い合いであり、かたや水の奪い合いであり、どちらも水である事には変わりない。その安蘇郡の習俗を調べると、雨乞いの時には中禅寺湖の水を汲みに行くというものであった。これは以前、星神島に祀られる香香背男の大事にしている泉から水を汲むと、その汲んだ分だけ雨を降らせるという雨乞い法と同じ意味であろう。実は、古代では中禅寺湖は安蘇郡に属していた。 五来重が二荒信仰を、元々あった中禅寺湖の水神信仰が当地の千手観音の信仰になっていたので、二荒山信仰は山岳信仰であると共に、湖水信仰であると述べている。となれば、二荒山と赤城山が争奪した沼とは、中禅寺湖であったのだろうか。ただ、勝道上人上人が、二荒山の山頂を征服した後に中禅寺湖畔に神宮寺を建立し4年過ごしたのは、そこに居付く民族の教化にあたっていたのも、その民族にとっても中禅寺湖は重要だったという事であろう。中世になって成立した「補陀落山建立修行日記」には、延暦三年(784年)歌浜に白蛇が現れたとある。「補陀落山建立修行日記」は都合よく書かれた胡散臭い書であると云われるが、ある意味真実をついているのかもしれない。何故なら、星上島での香香背男とは蛇神であり、それが磯良と結び付くものならば、その正体は白蛇である。その白蛇は九州において、瀬織津比咩であると云われる事から、北に聳える早池峯の麓である遠野に移り住んだ阿曽沼氏は、初めから瀬織津比咩という神を祀る地である事を知っていたのではなかろうか?阿蘇の沼とは白龍の棲家であり、その安蘇という地名もまた、九州の阿蘇との関わりがある事から、安蘇の水神を祀る中禅寺湖に仕える意での阿曽沼という改姓ではなかったろうか。 また、勝道上人が二荒山で雨乞いをしたとの記述があるが、それは日光修験にあった雨乞い法であると思われるが、その雨乞い法に深く関わっているのは東密である真言宗、または空海であろう。時代的には勝道上人の後に台頭した空海であるが、その勝道上人の業績を「沙門勝道、歴山水、瑩玄珠之碑」によって讃えている。その中の文字から、明星天子や竜王が活躍したような記述がある。 画像は、神泉苑での空海の雨乞い法だが、池から龍神が現れている。見た目は大蛇であるが、この時代に龍と蛇の違いは無かったのである。藪元晶「雨乞儀礼の成立と展開」によれば、神泉苑においての空海は呪力をもって龍を水瓶の中に加持し籠らせたという。注目したいのは、水瓶である。これはつまり甕であり、鹿島神宮の御神体であり、海に沈んでいるものであり、それは二荒山から出現するものでもある。その甕には龍が入っていると繋がる、空海の雨乞い法である。しかし、誰しも空海の様に呪力があるわけでもない。その後の神泉苑での雨乞い法とは、池の水を抜いて鐘太鼓を叩くものに変化している。これも池の水を抜くというのは、その抜かれた分だけの池の水を補充しようと龍神が雨を降らせるものに対応する。種太鼓を叩くのは、その龍神を呼ぶ為であり、池の水が無くなった事を知らせる方法である。これもつまり、星神島での雨乞い方法と同じという事である。 また水瓶であり甕だが、本来は水を入れるから水瓶でもあるのだが、その水気とは龍でもある。つまり甕とは、元々龍神を納めるための器であるのだと思う。よって鹿島神宮の御神体の大甕であれ、大甕倭文神社の祭神も龍神でなくてはならない筈。また二荒山そのものが大蛇という伝承から察すれば、その棲家は中禅寺湖でしかないのだろう。 |
|
|
■二十三
「補陀洛山修行日記」には、弘仁十一年(820年)日光を訪れた空海は、見つけた滝に白糸の滝と名付け、その背後にある亀の形をした山があるので、それを亀山と名付けた。亀山の麓に、年に二度の大風を吹き出す大きな羅刹堀の穴があって竜の棲家になっているので、空海はその穴を大竜穴と名付け、庵として住む事にしたという。その後白糸の滝傍にあったと云われる八葉蓮華池で結壇し、仏眼金輪の法を修したところ、その結願の夜に八葉蓮華池から、小さな白い珠が飛び出したという。その小さい珠に問うと天補星と名乗った。天補星は虚空蔵菩薩の化身でもあった。その天補星である小さな白い珠を祀ったのが日光山輪王寺にある小玉堂なそうである。そしてその後に大きな白い珠が飛び出して、空海が問うと「我は妙見尊星、大師の請いにより現れた。この峰は女体の神の居られる所だから、その神をお祀り申せ。我の棲家は中禅寺である」と答えたという。空海は、その後中禅寺に妙見大菩薩を祀ったという。さらに呪文を唱え神霊の降下を願うと、神々しい天女が雲間より現れた。そこで空海は、弟子とともに竜穴の上に堂を建て女神を祀った。それが今の瀧尾神社であり、先の年二度の大風を出す羅刹堀の穴を辟除結界した事などが、二荒の謂れともされている。 ところで竜穴であった羅刹堀の穴だが、羅刹とは北方鎮護の神である毘沙門天の眷属として仏法守護の役目を担わされるようになる全身黒色で、髪の毛だけが赤い鬼とされる。しかし、転じて吉祥天にもなるとされるのは、そのまま蝦夷征伐に来た坂上田村麻呂を助太刀した鈴鹿の鬼女と云われた鈴鹿明神であり、その後に姫神山に祀られたりした話を想起する。そして蓮華の池から、太白であり妙見が飛びあがるのは、そのまま遠野三山の伝説にも繋がりそうな話である。 「日光狩詞記」によれば、男体山の山神は、男神であるという認識と、女神である認識があるようだが、圧倒的に女神であるという認識が多数になっている。例えば、下山衣文「古代日光紀行」を読むと、男体山を望む平野部では男根を象った物を奉納するという。これは古来から、山神は醜いものを好む事から、海のオコゼや男根を象った物を奉納すると同じである。ただそれは、山神が女神であるという前提に従うものだ。二荒の語源説に、男体山と女峰山の二神を祀るからというものがあるが、山頂から発掘される遺跡からみても、信仰の殆どが男体山に集中しているという。つまり二荒山とは女峰山を含める連山だとしても、その信仰は男体山に集中している為、男体山を二荒山と言っても良いのだろう。それは当然、その神の棲家である中禅寺湖を含めての二荒山という事だろう。 ところで話を「補陀洛山修行日記」に戻すが、池から虚空蔵菩薩と妙見菩薩が出て来たという話になっている。例えば、虚空蔵菩薩を祀っていた佐野市の星宮神社の旧社地は、塚が七つあって七星の形に配置されていた為に星宮妙見菩薩を祀っていたとも云われる。また栃木県における妙見に関する神社の殆どが、日光連山の山村において祀られ、その日光連山とは日光修験の修行場である事から、日光修験と妙見信仰の深い繋がりを感じる。 勝道上人の時には明星を感得したかのようであるが、これが空海の属していた真言宗と結び付いてから、妙見信仰の色合いが濃くなったとも取れる。しかし、前回書いたように中禅寺湖畔には、蝦夷らしき先住民が信仰していた神がいたようである。それは女神であり、竜蛇神であったようだ。また男体山山頂には、今は諏訪大社にだけ見られるサナギの鈴と呼ばれる鉄鐸が奉納されている。他にも、遺跡からは鉄に関するものが多く出土している事から、鉄と蛇のイメージが強く重なる。そう、本来祀られていた神とはアラハバキ神ではなかったのかと。 「花園山縁起」には「安倍ノ貞任、宗任ノ兄弟、多賀郡ノ山を隔テテ大高城ニ籠り星ノ御門ノ子孫ナリ。」とある。大高城とは現在の福島県に属するようだが、また別に栃木県にも安倍貞任伝説がある事から、この関東にも安倍貞任という蝦夷の英雄の伝説があるのは、同じ民族が住んでいたという事であろう。また、星の御門という事であるが、やはり先に紹介したように安倍一族の末裔は星宮神社を祀っており、その教義はアラハバキ神社のそれと同じであった事から、関東周辺にも蝦夷の信仰の残存がある事を伺える。それはつまり、関東が蝦夷国であった時代に遡り、征服されていった地は新たに為政者によって、その信仰が塗り替えられていったという憶測に繋がる。そこで二荒山であるが、あれだけ高い山であるから、昔の装備では簡単に行けないのが理解できると共に、何故に白山やら英彦山、そして二荒山であり早池峯もそうだ。一斉に真言宗や天台宗の僧が、山を極めて開祖となる話が日本中に広がったのは、旧勢力の信仰を塗り替える算段が仏教勢力に出来上がったからではなかろうか。勝道上人が長年かけてやっと二荒山に登ったのも、その先住民族の教化に時間を有したからという説に対応する。当然、地元の早池峯であれ、始閣藤蔵が早池峯の頂を極め奥宮を建て、その後に麓に妙泉寺が建立されたのも、先住民が信仰する神を仏教色に塗り替える為であったろう。 下山衣文「古代日光紀行」に面白い記述があった。 「私は、前世で重い罪を犯したので、今、神となっている。その為に、この地方では災害や疫病が絶えない。仏によって、私が神の身から救われれば、災害や疫病もなくなるだろう。」 確かに本来、神とは一方的に祟る存在であった。民衆は、祟らないで下さいと一方的にお願いするしか無かったものを、仏教が入り込んでから、現世利益というものが登場した。つまり祀って一生懸命参拝すると、願いが叶うというもの。となれば、今まで一方的に祟る存在であった神が、仏と習合する事によって、民衆に利益を与える事が出来るとなれば、それに飛びつくのは当然だった。それから本地垂迹に則って、仏は神の上に位置した。しかし利益を希望する民衆からは、その受け入れが容易であったのは理解できる。神を損なわずに、仏を受け入れるが、真言宗や天台宗が行ってきた信仰の教化であったのだろう。つまり、神の棲む山を仏僧が征服する事によって、他民族の信仰する神を取り込んだのが神仏習合であり、それは朝廷側の狙いであったのだと思うのだ。これは全国規模で行われた為、どこでも本来の祭神がわからなくなっていったのだと思う。その消されてしまった神の代表格が、早池峯の女神であったのではなかろうか。 |
|
|
■二十四
二荒山神社の祭神は現在、大己貴命・田心姫・味耜高彦根となっている。これは、平安末期からも鎌倉初期に成立したであろうと云われる「下野国二荒山鉢石星宮御鎮座伝記」によるものらしい。しかしそれは「補陀洛山修行日記」に登場している神らしき存在を筋の通った神に置き換えただけのようである。 「補陀洛山修行日記」に登場する神のその一つは「其姿如夜叉、著青黒衣、左手接腰右手捲二龍蛇」という青黒い衣を来た蛇神のようであった。また別に、白蛇が登場し、そして「一人天女、其姿花麗、其齢三十余」と「一人束帯把笏整衣冠、威儀儼密、其歳五十有余、黒白半髪也」が登場している。それは実際四柱の神でもあるのだが、そのうち白蛇は「立神祠祭白蛇之神、是号中禅寺」と、単に中禅寺に祀ったとされる。つまり最初に登場した蛇体の神が味耜高彦根となって、天女らしきが田心姫、威厳のある神が大己貴命とされたのだろう。 「日光山滝尾建立草創日記」は、鎌倉時代に成立した国指定の重要文化財であるが、それに記されている内容に注目したい。「滝尾籠衆山伏自別所盗出之、出羽国竜赤寺下着及三十余年」途中は略したがつまり、この写本は滝尾別所に伝来したが盗難に遭い、出羽国竜赤寺に持ち去られたが、再び滝尾社に返還されたという内容だ。竜赤寺とは、現在の山形県の立石寺となる。この立石寺は慈覚大師円仁が開祖となっているが、何故に当初は竜赤寺(りうしゃくじ)と号したのかわかっていない。ただ、赤い竜で想起されるのは、「補陀洛山修行日記」の当初に登場した蛇神である。記されている「左手接腰右手捲二龍蛇」という姿を読んで思い出すのが青面金剛である。青面金剛の姿は「日本石仏辞典」によれば「腰に二大赤蛇を纏う。両脚腕上に亦大赤蛇を纏い」とあり、まさに「補陀洛山修行日記」に登場した蛇神に近似している。二荒山に登場した蛇神の姿を学者は一笑に付すが、青面金剛として考えるならば筋が通るのだと思う。当然、山形県の立石寺の当初の竜赤寺とは、青面金剛を意味して号された寺名ではなかろうか。 「青面金剛」は、中世に確立されたようだ。古代においての青は黒と同じであったが、この中世の頃には「青」というものは「水」を意味する色として認識された為、恐らく「青面金剛」の「青面」は水を意味するのだろう。「金剛」は、北斗七星を意味する事から、水と北斗七星を結びつける存在が、この「青面金剛」の本来の意味だろうと考えるのだ。そして当然、それは水神でもある妙見信仰に繋がる。 また、やはり二荒山に伝わる「草創日記」に二荒山を指して「此嶽有女体霊神」とある事と、先の「「補陀洛山修行日記」」においても「我は妙見尊星、大師の請いにより現れた。この峰は女体の神の居られる所だから、その神をお祀り申せ。我の棲家は中禅寺である。」事からも、二荒山の神とは女神であり、妙見神である事がわかる。恐らく「下野国二荒山鉢石星宮御鎮座伝記」では、日光連山の男体山と女峰山を分けて髪を分祀したのも、熊野修験の修法を二荒山に取り入れ日光修験を成立させた辨覺の時代に起因するものと思われる。熊野の三所権現を三光と結び付け、それを日光連山に重ねたものであろう。よって、大己貴命・田心姫・味耜高彦根は後世の祭神であり、本来祀っていた神とは鉄の蛇であるアラハバキ神に他ならないだろう。 二荒山である現在の男体山に祀られる神とは、滝尾神社の神であるのがわかった。その滝尾神社の参道には、無数の男根を象った物が祀られていたという。こういう生殖に関する信仰を持つ神とは山神であり、その男根を象ったモノ、別にコンセイサマ信仰と呼ばれるものは縄文時代まで続くものである。 二荒山の前山とされたいる太平山の三光信仰では、太平山大権現(星)・熊野大権現(日)・日光大権現(月)となっているが、香香背男をも祀る太平山が星なのは理解できる。また、八咫烏の熊野もまた太陽であるのも理解できる。ところが日光大権現が何故月なのかは説明できない。陰陽五行での陰とは女であり月であり、水を意味するからだ。古代の祭祀の基本は、彦神と姫神という陰陽の和合で成り立っている。だが、各風土記における山において、彦神と姫神が水争いで袂を分けているのは、そのまま七夕信仰に結び付けられ、天の川が彦神と姫神を分け隔てたとする古代中国からの伝承がすんなり受け入れられたとも、そういう日本の伝承を考慮に入れたものと思われる。 上つ毛野 安蘇のま麻むら かき抱き 寝れど飽かぬを あどか我がせむ 上記は「万葉集3404」の歌であるが、安蘇は栃木県の安蘇郡をいうのだが、古代では現在の群馬県を含む地であったようだ。その安蘇郡は、麻の名産地で養蚕が盛んであったらしい。養蚕は現在でも群馬県に盛んだが、有名なのは桐生市だ。桐生市には有名な白滝姫の伝説がある。古代においても関東一円に養蚕文化は、かなりの広がりを見せた。その中に倭文氏の進出があったのだろう。それ故に、静神社や大甕倭文神社も、その倭文氏の影響がある。 その倭文神社だが、遠野にも倭文神社があり、祭神は画像の通り、天照大神と下照姫に瀬織津比咩となっている。恐らくこれは三光信仰を意味する祭神であり、太陽は天照大神であり、下照姫は「シナテル」と「シタテル」が同義であり「シナテル」は月が仄かに光る意となるので月。そして恐らく瀬織津比咩は、大甕倭文神社や静神社を見ても香香背男そのものが星神であり、それは蛇神である事から、星神としての瀬織津比咩という事だろう。つまり、香香背男=瀬織津比咩である事を意味しての祭神であると思われる。 瀬織津比咩は、土渕の琴畑に白滝と呼ばれる滝があり、そこに祀られた神が瀬織津比咩であった。それが明治時代となり、土淵五日市の倭文神社に合祀されたのだが、白滝姫と倭文神の関係を考えてみたい。倭文氏は初めて日本に七夕に関する伝承を組み入れた氏族であり、それが以前に紹介した夷振歌に繋がるのだと思えるからだ。 |
|
|
■二十五
安蘇郡に中禅寺湖が属し、その阿蘇郡での雨乞い方法が、中禅寺湖の水を汲む事だったのは前回に記した。また二荒山と赤城山の争いは、沼争いであったようだが、どうもそれは中禅寺湖の事であったようだが、それとは別に赤城山にも沼はあり、その沼には唵佐羅麽女(オンサラマニョ)という存在がいて、二荒山の神に味方したと「日光神戦譚」に紹介されている。 その赤城山を祀る赤城神社の由緒によれば、赤城神社とは山と沼との信仰であるといい、その主祭神は赤城大明神であり、小沼宮には豊受大神と倉稲魂命が祀られている。伝説では大蛇と大百足の争いのイメージが強い為か、赤城大明神とは大百足なのか?と勘違いしそうだが、赤城大明神の正体は不明。しかし尾崎喜左雄「上野国の信仰と文化」によれば、伊勢崎市の赤城神社所蔵の懸仏は弘長四年銘で「二大明神御正躰一面」とあり、表面に千手観音座像を陰刻してある事から、赤城大明神の本地は千手観音である事がわかる。これは中禅寺に千手観音が祀られているのと同じであり、五来重は千手観音は水神信仰の本地であると説いている。大蛇と大百足との争いは、なんだったのだろう?いやそれはつまり、同じ水神を祀る二荒山であり赤城山に大百足という存在が攻め入ったという事を意味しているのだろう。それ故、赤城山の沼に棲む唵佐羅麽女が同族の二荒山の神に味方したという事。 「日光神戦譚」によれば、その唵佐羅麽女が赤城の神に嫁いだという事は、和平が結ばれた事を意味する。となればやはり、赤城大明神とは大百足をトーテムとする部族であったろうか。百足もまた産鉄民族の象徴である事から、赤城山は元々二荒山に斎く産鉄民族の縄張りであったが、似た様な別の部族が赤城山に入り込んで争ったが、最後は和平を結んだという事なのだろう。ただ、御正躰が千手観音である事から、二荒山同様、赤城山の本来の神の棲家もまた湖であり沼である事が理解できる。 二荒山と赤城山との沼争いとは、その沼に棲む水神の女神を争う事であったのはわかる。そしてもう一つ気になるのは、阿蘇だ。以前にも紹介した、遠野における館跡と御前沼と天女に関する地をもう一度表示してみよう。 真立館(松崎町松崎 御前沼 荷渡観音 御前様) 小田沢館(青笹町中妻 荷渡観音 御前沼 御前様) 月山神社(上郷町字南田 御前沼 御前様 千手観音) 佐野館(上郷町佐野 御前沼 御前様 薬師観音) 御前(綾織町新田 御前沼 御前様) 天ヶ森館(附馬牛町安居台天ヶ森下 御前沼跡 御水神宮) 荒矢館(附馬牛町荒屋 御前様) ■ 上記の館の館主は不明という事で、何故に御前沼を祀り、天女伝説が付随しているのも、また不明となっている。ただ、地域が松崎・青笹・上郷・綾織となっているのに注目したい。 遠野の歴史によれば、阿曽沼氏は奥州征伐の後、遠野十二郷を領地にしたとなっているが大川善男「遠野の寺社由緒考」によれば、その当時の郷とは狭いもので、阿曽沼氏の領地は猿ヶ石川・早瀬以北であり、上郷・青笹・土渕・松崎・附馬牛の限定される地であったようだ。つまり天女伝説の付随する館跡は、綾織を除いての殆どが阿曽沼氏の領地となっている事から、阿曽沼氏の関係者が持ち込んだ信仰であろう。その阿曽沼氏は元々佐野氏を名乗っていた事からも、上郷町の佐野館跡は、阿曽沼氏の影響からであったろうと思えるのだ。その阿曽沼氏の姓は、栃木県の安蘇郡と沼から発生したものだと思える。それはつまり、安蘇郡における信仰の影響からであろう。 茨城県の民俗・習俗を調べても、古代から磯出などの神事があるという野は、恐らく南方の海人族の進出があってのものだろう。例えば、長野県に安曇野市があるのも、安曇氏が天竜川を遡って進出したせいであると云われる。 関東一円には星宮神社に付随して、ウナギ信仰が伝わっている。ウナギは虚空蔵菩薩の眷属であるから食べないというものだ。しかし元々ウナギ信仰があるところに虚空蔵菩薩信仰が結び付いた為と云われるが、そのウナギ信仰と共にナマズ信仰もまた存在する。それ故に、ある地域ではナマズは食べないがウナギは食べるという地もある。そのナマズだが、例えば鹿島神宮の要石は地中に潜むナマズが暴れると地震が起きるので、そのナマズを抑える為の要石であると云われる。ところが伊勢暦では地中に潜むモノは龍であり地震蟲とも云われるものが暴れるので地震が起きるとも云われている。しかし、ナマズも龍も水に潜むモノだ。 そのナマズを、信仰する地域がある。それは、九州の阿蘇地方である。俗に蹴裂伝説と云われるものに、阿蘇の健磐龍命が昔、開田の為に外輪山の一角に立って阿蘇を見上げると噴煙が見え、その下に大きな湖が見えた。その湖を蹴破り湖の水を外に出した。その時湖の主の大鯰が引っ掛かり水が途中で止まっていた。その鯰の鼻に蔓で作った太い縄を通しひっぱって鯰をどけたという。それで湖の水が流れ引いたので、水で豊かになった地で稲作を始めたが思わしくなかったと。それは鯰の祟りであったとされ、それからその一帯では鯰を捕る事も食べる事もしなくなったという。 阿蘇の御祭神は、阿蘇山の火口に溜まった池に祀られている。北の神霊池である第一火口を一宮とし健磐龍命を祀り、中の神霊池の第二火口に阿蘇津比咩を、そして南の神霊池の第三火口に彦御子命を祀っている。つまり、山の池を神霊の住む地としているのは、赤城山であり二荒山と同じである。更に阿蘇地方には健磐龍命の父を中心とした天女伝説が、かなり多く分布している。これらの伝承から察するに、栃木県の安蘇郡も、九州の阿蘇地方からの移民が多く住み付いたのではないかとの憶測が成り立つのではなかろうか。付け加えれば、阿蘇に嫁いだ阿蘇津比咩とは、日下部吉見神社の水神である瀬織津比咩であった事は、何度も書いてきた。つまり神繋がりで、阿蘇山信仰と二荒山信仰が結び付いてくるのである。 |
|
|
■二十六
二荒山を中心とする信仰が、どことなく阿蘇の信仰に似通っていると書いたが、その二荒山を遠望する平野部は毛野国に属していた。毛野国は、初期の大和政権の成立し、それらの勢力が東国に進出したのが4世紀前半以降であろうとされている。つまり謎の4世紀に属する時代に氏族の進出があったわけだから、正確にはわからない。ただその頃には既に阿蘇という地名はあったのは確かである。また気になるのは偽書と云われる「東日流外三郡誌」に登場する阿蘇辺族だ。何故「アソ」という名の付く部族名になっているかという事。自分は、「阿蘇の部族(アソノブゾク)」の転訛が「阿蘇辺族(アソベゾク)」になったのでは?と思ってしまう。 遠野には、早池峯を中心とする不地震の森の伝説が広がっている。古代に、安住の地を求めて移住した部族がいたのでは無いかととも云われるのだが、九州の地には動乱もあり、そして阿蘇山の噴火もあり、それを恐れた民族の移動の可能性も否定できないだろう。実際、遠野には今でこそ姓を変えたが、過去には阿蘇氏を名乗っていた家もある。また菊池氏もそうだが、阿蘇の自然と信仰を受けた一族が東北に移り住んでする。 例えば岩手県には、菊池神社が一ヶ所だけある。そこに住む人は明治時代に移り住んだそうだが、その時に九州の菊池神社の神を分霊してもらい、今の地に祀ったという。 その神とは、水神姫大神と水神大神であった。現在の菊池神社の祭神は、菊池氏歴代の当主であり、こういう神霊を祀ってはいない。しかし現に、こうして分霊された水神を岩手の地に持ち込んで大事に祀っている事実がある。この水神とは恐らく、阿蘇の神であろうと思う。阿蘇神社の祭神は健磐龍命と阿蘇津比咩であり、どちらも水神の扱いになっている。そして、菊池氏と阿蘇神社の共通するものは、家紋である。 「違い鷹の羽」の家紋は、菊池氏よりも阿蘇神社で採用したのが古く、その由来は現在宮山であり、古くは鷹山という霊山で阿蘇権現(健磐龍命)の月馬が遊んでおり、阿蘇権現はその馬を鷹山の地主神吉松神に献上したという。その吉松神とは日下部吉見神の事であるそうだ。水神を祀る日下部吉見の娘を娶った阿蘇権現(健磐龍命)であるから、阿蘇の地を征服した健磐龍命が和平の名の元に、地主神の娘を貰い娶ったという事になろう。つまり、阿蘇地域は元々日下部吉見の水神を祀る地域であったという事になる。阿蘇神社の神事に御前迎えというものがあるか、その姫神の依代となる御神木を採りに(迎えに)行くのが鷹山であるそうだ。その鷹山にちなんで出来たのが、違い鷹の羽紋であるようだ。 「菊池氏要略」の年表を見ていると、菊池氏は寿永四年(1185年)に家紋を日足紋から揃鷹羽紋に改むとある。日足紋は元々日下部氏の家紋であり、太陽の光が後光のように差している図柄で、この後光の光を「足」と見立ててのもののようだ。つまり日下部氏は「日」を奉じる氏族であり、その後裔の菊池氏もまた「日」を奉じる氏族であるのだ。熊本の菊池郡を「菊池郡市神社誌」で読み調べてみると、殆どが阿蘇の神を祀っている。違い鷹の羽家紋が元々日下部吉見の霊山からきているものであるなら、日下部氏は日足紋と共に違い鷹の羽紋も持っていたという事。家紋の表紋、裏紋を持っている氏族は珍しいものではない。その日下部氏と繋がる菊池氏が違い鷹の羽紋を使用するのに、同族であるから何ら問題は無い。 阿蘇家であり阿蘇神社の違い鷹の羽紋は、権威の象徴であるという。それはある意味、鷹を権威としていた日下部氏を支配した事による鷹山という聖地奪取の象徴としての違い鷹の羽紋であったか。実際、蝦夷征討の過程で、支配した地から次々に朝廷へ、幕府へと鷹を献上する例が江戸時代まで続いたという。遠野では、織田信長に小友町の鷹鳥屋の鷹を献上した話が有名である。つまり、鷹を献上するとは権威の失墜でもあるのだろうか。その鷹を献上するという事例の一番古くは、紀元前での菊池氏と繋がる日下部氏の地であった阿蘇地方が健磐龍命に支配されたという事になる。そして、何故に蝦夷国で支配されるたびに、鷹が献上され続けて来たのか。それは、古代に阿蘇地方から逃げ延びて住み付いた人間を、朝廷側が理解していた為では無かろうか。それが「東日流外三郡誌」で云う阿蘇辺族・・・つまり、阿蘇の部族ではなかったか?それは、阿蘇の部族に伝えられる征服された古代の記憶を呼び覚ます行為が、鷹の献上であったのかもしれない。 |
|
|
■二十七
天女の話をしよう。伊勢神宮の外宮に祀られる豊受大神は、丹後国に降り立った御饌都の天女として連れてこられた。それでは、その豊受大神はどこから飛来したかというのが謎ではあったが、常陸国の「我国間記」には、常陸国から丹後国経由で伊勢神宮に行った事になっている。その信憑性には疑問符が残るものの、それ相応の伝承なり、神がいてこその「我国間記」の一文であろう。 天女の羽衣とは「古語拾遺」によれば、衣服の古語を白羽と云い、その「古語拾遺」によれば、天照大御神が天岩屋に隠れた時、麻を植えて青和幣を作った神で、その神名を天白羽神という。この天白羽神は以前、天白神でもあるとし、金星を意味する太白神つまり香香背男でもあろうとした。常陸国久慈郡には、養蚕の神社として天羽槌雄神を祀る静神社と、天白羽神を祀る天志良波神社とがある。この天羽槌雄神と天白羽神が「古語拾遺」では、並んで仲良く天照大神を天岩戸から出す為に協力しているのは、倭文氏と忌部氏の関東進出があっての事だと云う。しかし、静神社に祀られる神は倭文氏の進出以前は天手力雄神であり、それ以前は蛇神であった。そして、天志良波神社に祀られる天白羽神も、香香背男であり瀬織津比咩ともなる養蚕神にもなる。蛇神は養蚕における蚕を喰い破る鼠を捕食する事から養蚕の神にもなっている。つまり、静神社も天志良波神社も、それを祭祀している倭文氏と忌部氏の影響を受けて、祀る祭神が決められたのだろう。しかし、それ以前は秦氏が信仰する神を、秦氏の没落によって忌部氏と倭文氏がそれを受けて、神名の交代があったと思われる。それは、倭文織物(シズオリモノ)を古代では「志豆波多(シズハタ)」という事から、それは本来秦氏に関係するものが、後に秦氏が消え倭文氏に移行したという意味だろう。また、静神社の祭神が鹿島神宮の高房社に祀られているというのも、高房の房は恐らく麻の意だろうから、忌部氏の進出と倭文氏の繋がりの深さを意味している。 遠野の清瀧姫の伝説は、群馬県桐生市の白滝姫伝説の影響を受けてのものだと以前に書いた。琴畑渓流にある白滝と、その白滝を祀る白滝神社(または清瀧神社)の祭神は瀬織津比咩であった。この琴畑という地名は、この地に移住した秦氏が畑仕事の合間に琴を奏でた事からの地名であると云う。また、この琴畑渓流沿いに伝わるマヨヒガ伝説に登場する朱塗りの椀は、遠野に朱塗り文化が無い事から、秦氏の持ち込んだ伝説だと云われている。つまり、白滝と白滝神社もまた秦氏との関係が濃厚で、桐生の白滝姫伝説にも秦氏の影がある事から、祭神の瀬織津比咩を含む白滝は養蚕を意味するものであろう。それ故に、この白滝神社に祀られていた瀬織津比咩は、明治時代に土淵町五日市の倭文神社に合祀されたのは、当然の流れであったろう。 天女伝説を調べると、やはりその起源は古代中国へと行き着く。元は神仙思想に基づくもので、日本での王朝時代には、既に影響を与えていたようだ。天女伝説には白鳥が登場するが、古代の白鳥とは鷺であったり鶴であったり、そのまま白鳥でもあった。要は大型の白い鳥は全て白鳥と見做されたようである。ところが、古代中国「列仙全傳」によれば、白鳥では無く白龍にのって飛行するとある。その白龍の仲間として白鳥も登場し、その中の白鵞の空から堕ちるのに「劉女これに乗って去る。」事が天女伝説の原型に近いか。その後の「捜神記」では、最も日本の天女伝説に近い話が掲載されている。それは仙女が鶴に化すものであり、単なる天女伝説に留まらず「三光を観見し、北斗に遭う。」という星の信仰と繋がっている。この話の伝播は、古代ギリシアから古代中国を経ての流れであろうとされている。 熊本県の阿蘇山を中心とする周辺にも天女伝説は多くあり、その中に田鶴原は湿地帯で鶴が舞い降り、健磐龍命は鶴に乗って天空を駆けたとの伝説があった。これは恐らく、劉女が白龍に乗って天空を駆けるという古代中国の伝説の影響を受けているものだろう。龍であり蛇は、首の長さと魚を丸呑みにするその姿と動きが水辺の白鳥に似通っている事から同族とされていた。つまり健磐龍命が鶴に乗って天空駆けたのは、日下部吉見の龍蛇神を捕まえた事にかかる伝説だろう。そしてそれは、現在でも行われている御前迎えの神事に繋がって来るものであろう。また、阿蘇神社の家紋が、鷹とは別に舞鶴をも採用しているのは、天女を鶴に見立ててのものであろう。 |
|
|
■二十八
天女を調べていると誰もが気付くとは思うが、七夕伝説に似通っている。水辺を中心とし、天女という織女が男と出逢って別れる図式は、七夕伝説と言っても良いほどだ。天女伝説の定着は王朝時代(奈良時代~平安時代)とされているが、弥生時代の銅鐸に紡いだ糸を巻く桛を持つ女性が描かれている絵を七夕と結び付けて考えられているが、それは天女伝説に結び付けても違和感が無いだろう。 古代中国での天の川伝承の原型は、黄河か揚子江から発生したと云われる。天の川は天の河とも書き、それは古代中国の「天河」からきており、それは黄河の「河」が意識されている。黄河の水は天上より来て海に到り、再び天の河に戻ると云われている。これは、天の川と地上の川は繋がっているとの考えからだ。以前に紹介した常陸国の七夕磯もまた、二荒山(天)から神が降り、その磯(石)に影向するという伝説であり、これも古代中国思想の影響を受けたものであろう。 ところで天河で思い出すのが、奈良県吉野郡天川村に鎮座する天河神社だ。菊池展明「円空と瀬織津姫(下)」には、その天河神社に関する記事があり、天武天皇七月の勅命に、こう記されていると。 「弥山山頂に祀る天女を麓に移し、大神殿を造営し、吉野総社となして祭れ」 まず、山頂を天と見做しているという意識がわかる。謡曲「羽衣」でも、天女の坐すところは月宮殿であり、元は天上界であった。その天とは天空でもあり、その天空に聳える山でもある。その天女を麓に移して祀った天河神社には七夕神事があり、大峯山の神が牛頭天王と年に一度の逢瀬を果たすというもの。現在、天河神社は弁財天が祀られているが、弁財天女でもある。「神振山伝説」によれば、弥山山頂の天女が示現し袖を振りながら五色の雲に乗って高く舞い上がって行くという奇端を感得したとあり、天女伝説と七夕伝説の融合を、この天河神社に見出す。更に付け加えれば菊池展明「円空と瀬織津姫(下)」では、この天河神社の祭神の本来は、天照大神荒御魂であり瀬織津比咩であったと結んでいる。 天の川安の川原に定まりて神競は時待たなくに(柿本人麻呂) 菊池展明は、天河神社の創始を上記の柿本人麻呂の歌と同じ年であると解いている。それは素戔男尊と天照大神の誓約場面を意味しているとし、それは宗像三女神の誕生の場面でもある。宗像三女神の湍津姫神は瀬織津比咩である事は明らかになっているが、その湍津姫神を祀る宗形の中津宮のある大島には天の川があり、その天の川の両岸には織女宮と牽牛宮という小さな祠が祀られている。更に、その大島には禁足地があって、そこは妙見を祀っているのだと。つまり宗像三女神の中で一番、星信仰と深い繋がりのあるのは湍津姫神であり、瀬織津比咩という事になるのだろう。 天女伝説は王朝時代に定着としてはいるが、これが七夕伝説と融合するものであるなら、それは先に紹介した弥生時代の銅鐸に描かれた織女の絵から、どこまで遡るのかはわからないが、天女の原型らしきが「捜神記」に記されているという事は、4世紀には既に天女伝説は定着していたと考えて良いだろう。古代中国の神仙思想は霊山と結び付くものが多い事から、山頂にいる女神は天女であるが、「神振山伝説」はその表現から、更に仏教思想が融合しているのがわかる。それ故に、天河神社に祀られる天女は瀬織津比咩ではなく、弁財天女となったのは理解できる。 月であり太白であり妙見であり北辰は、厳密に言えば、月・金星・北極星・北斗七星などであるが、いつしか混同し、全てが星の信仰として統合されたようであった。多面的な姿を誇る瀬織津比咩ではあるが、やはり本来は水神であり、その水を神聖視した人々によってあらゆるものに組み込まれていったのだろう。逆に言えば、多様性を持つ瀬織津比咩である為に、その姿を消すという事は「記紀」において、多くの神々を誕生させなければ、その失った穴を埋める事が出来なかったという事だろう。考えてみれば、水に対する意識とは全国共通であり、その水を支配する水神が乱立するなど有り得ないだろう。神社の根本は、彦神と姫神から発生している。神社で柏手を打つのは本来四拍とされているのは、例えば「お~い、お茶!」と言ってパンパンと手を叩くのは、一人を呼ぶ為の仕草である。それを、出雲大社と同じくパンパン、パンパンと四拍するというのは、彦神と姫神の二柱の神を呼ぶ為でもある。陰陽とは男と女であり、それは火神と水神である。その原初である火神と水神がバラバラにされた為、「記紀」では整合性を取る為に、多くの神々を誕生させたという事だろう。 |
|
|
■二十九
天河神社の天女が瀬織津比咩であるとは書いたが、やはり菊池展明「円空と瀬織津姫(下)」で紹介されている静岡県に鎮座する瀬織戸神社に祀られる瀬織津比咩の祭神説明では「天照大神と素戔男尊の第二王女」「一般に"弁天さん"」と呼ばれているとある。第二王女とは、田心姫に続く二番目の湍津姫神である事は間違いなく、これは湍津姫神が瀬織津比咩であるという、もう一つの現存する証明でもある。また、その瀬織津比咩が天女でもある弁財天とされているのは、山の頂に坐す女神は山神でもあり、その山神は春に麓に降り立って田の神となる伝承が、まるで天女の飛来の様である事から弁財天と習合されたのではなかろうか。となればやはり、常陸国の「我国間記」に記される丹後国に飛来した天女とは、豊受大神の名で語られた、大甕倭文神社、静神社、そして鹿島神宮の高房社に祀られてある香香背男としての瀬織津比咩である可能性は高いだろう。 羽衣を奪われ天界に戻れなくなった天女を、堕天使ならぬ堕天女と呼ぶ。その堕天女となった経緯は、たまたま男が羽衣を見つけたので奪ったというのが一般的である。しかしリアリティを持った伝承は、唯一阿蘇に伝わるもので、阿蘇神社の御前迎え神事に結び付いている。 赤水宮山に健磐龍命が行ったら山女がいた。この山女は日下部吉見の姫が赤水に来ていたもので、健磐龍命がこの姫を強引に担げて来て自分の嫁にした。嫁盗みを神様がやったので、阿蘇の人々にも許されている。実際にも行われていた。姫を盗む途中で十二か所寄って来る。化粧原は十二か所目になり、ここから夜になるので松明を出す。そして赤水のお宮で強引に姫の穴鉢を割る(犯す)。それからお宮(阿蘇神社)に連れ込んで高砂(結婚式)をする。お宮に連れ込んだが、姫が生まれ在所に帰りたいというので羽衣を隠した。子供が十二人生まれる。これが阿蘇神社の十二の宮である。子供が多く生まれたので、安心して歌を歌う。「姫の羽衣は千把こずみの下にある。」それで姫は羽衣を見つけ、生まれ在所に帰った。 嫁盗みといえば、日本人と顔が似ているというキルギス国での誘拐結婚は、今でも有名だ。そのキルギスの風習が伝わったわけでもなかろうが、日本の古代にも似た様な事があり、世界中でも国を侵略し、その国の姫を奪うという話を列挙すればキリが無いくらいだ。そういう意味から堕天女という言葉は、そのまま「奪われた姫」という言葉に変えても違和感が無い。 健磐龍命は神武天皇の孫と云われ、その命を受けて阿蘇地域を支配したようである。そういう意味から、地主神である日下部吉見の水神を力によって支配したのだと理解できる。子供が出来ながらも、尚も故郷へ帰ろうとする天女の行動は、力による支配に対しての反抗でもあるのだろう。昔話での異類婚は、正体を知られた鶴であり、狐などが、子供を作りながらも、その子供を捨ててまで人間界から去ると云う悲話になっているが、その天女伝説の原初とは恐らく、阿蘇神社に伝わる姫(水神)の強奪ではなかったか? 天の川は、天空に浮かぶ竜の姿にも例えられる。それは天の川と地上の川が繋がっているという信仰にもよる。それについては、やはり「円空と瀬織津姫(下)」に、筆者による読み下しの祭神説明があるのを見よう。 そもそも天川と申すは、天神七代の御末伊弉諾伊弉冉二尊の御本宮、吉野熊野宮とも、吉野熊野之中宮とも申し伝え、生身天女の御鎮座、天照姫とも奉崇して今伊勢国五十鈴之川上に鎮り坐す天照大神別体不二之御神と申し伝え、故に大峯山の内道場とも、或は日域の古伝にいうところの天安河とはすなわち今の天川なりと申し伝え候。 これによればつまり、この奈良県の天川が天安河であるとしている。つまり「記紀」での天照大神と素戔男尊の二神が天の安河を挟んで誓約を行ったという神話は、日本における天の川伝説の原型となるのかもしれない。それ故なのか、古代中国の地上に流れる黄河であり、天空に流れる天の川を意味する「天河」を採用した天河神社は、天安河でもあると伝えている事から星の伝説を意識しての神社であろうし、天照大神と素戔男尊の誓約のシーンを紐解く重要な地なのかもしれない。 天の川鏡にうつす神なれや来る度毎に再拝しつゝ(円空) この歌は、円空が何度か天河神社に来て詠んだ歌だと云うが「鏡に映す神」で思い出すのが、宗像の中津宮のある大島である。「古今集紫雅抄」によれば、筑前大島の中津宮の天の川に盥を浮かべ、その水鏡に映る織女と出逢い、神仕えになったとの伝承がある。水鏡に映る神は織女であり、それは奈良県の天川においては天女であるのだろう。そして「肥前國風土記」である。 姫社の郷、此の郷の中に川あり、名を山道川といふ。其の源は郡の北の山より出で、南に流れて御井の大川に會ふ。昔者、此の川の西に荒ぶる神ありて、路行く人、多に殺害され、半ば凌ぎ、半ば殺にき。時に、祟る由を卜へ求ぐに、兆へけらく「筑前の國宗像の郡の人、珂是古をして、吾が社を祭らしめよ。若し願に合はば、荒ぶる心を起さじ」といへば、珂是古を覔ぎて、神の社を祭らしめき。珂是古、即ち、幡を捧げて祈禱みて云ひしく、「誠に吾が祀を欲りするならば、此の幡、風の順に飛び往きて、吾を願りする神の邊に堕ちよ」といひて、便卽て幡を挙げて、風の順に放ち遺りき。時に、飛び往きて、御原の郡の姫社の杜に堕ち、更還り飛び来て、此の山道川の邊に落ちき。此に因りて、珂是古、自ら神の在す處を知りき。其の夜、夢に、臥機と絡垜と、儛ひ遊び出で來て、珂是古を厭し驚かすと見き。ここに、亦、女神なることを識りき。卽て社を立てて祭りき。爾より巳來、路行く人殺害されず。因りて姫社といひ、今は郷の名と為せり。 この姫社は今では七夕の神にもなっているのだが、それ以前は往来の人を殺す恐ろしい荒ぶる女神であった。その正体は、機織りに関する神である事から女神とわかるが、その神名は明らかになってはいない。しかし宗像の郡の人の珂是古は巫女であろうから、その巫女が幡を神の依代としての占は、宗像のみあれ祭りそのものである。つまり珂是古は宗像三女神の中で、機織りに関係する女神を姫社に祀ったという事である。その後に七夕神社となっている事を付け加えれば、この荒ぶる女神の正体は養蚕神でもあり、七夕に関係する神でもある。つまりそれは、中津宮に祀られる湍津姫神とみるべきである。 その中津宮のある大島だが、神社の関係者に聞いたところによれば、奥に隠れた禁足地があり、そこに妙見神を祀ると云うが、それは熊本の八代妙見とも関連するらしいが、八代よりも古い、妙見の原型とも云われる。妙見の女神は大亀に乗ってやってきたと云うが、その大亀(オオガメ)は何故か関東以北になると狼(オオガメ)となり、また白馬と変化する。その妙見と七夕と、そして天女に結び付く神が宗像の湍津姫神であり、天照大神の荒御魂となる瀬織津比咩という事になる。 |
|
|
■三十
天女としての豊受大神を見直した場合、「丹後国風土記」では、波の郡比治の真奈井に天下った天女が、和奈佐の老夫婦に懇願されて比治の里に留まり、万病に効くという酒を醸し評判を得る。これによって御饌都神となり伊勢神宮の外宮に祀られた筈の豊受大神であった筈が伊勢神宮の外宮の酒殿祀られているのは「天逆太刀。逆鉾。金鈴。加徒神定十座也。」となっているのは「倭姫命世紀」に「豊葦原瑞穂の国の内に、伊勢加佐波夜の国は、よき宮所見定め給て、天上よりして投降し給ひし天の逆太刀・天の逆鉾・大小の金鈴等是也。」からの神であろうが、何故に酒殿なのか理解できない。ただ豊受大神は新たな中世神話によって御気津の神に昇格しているので、その代わりとして酒殿に逆鉾が祀られたのは、酒をかき混ぜる意からであろうか。 その酒であるが、一番古くは「古事記」において素戔男尊がヤマタノオロチを退治する場面に、酒が登場する。透明な清酒は「播磨国風土記」に清酒(すみさけ)として登場しているが、現在の清酒であるかは定かでは無いらしい。古代の酒は、大抵は白濁した白酒であり、今の濁酒と同じであるようだ。遠野の天女と沼の御前の伝説に登場するのは、白濁した水である白水であるのも、あるいは酒を意味していたのだろうか。ここで気になる氏族がいる。それは、秦氏だ。 秦氏の崇敬する神社に松尾大社があるが、平安京遷都後は東の賀茂神社と共に「東の厳神(賀茂)、西の猛霊(松尾)」と並び称され西の王城鎮護社に位置づけられていた。中世以降は酒の神としても信仰され、現在においても醸造家からの信仰の篤い神社である。酒の神として評判になったのは中世以降であるが、古くに酒造りの技術を持ち込んだのは秦氏であるとも云われている。常陸国の静神社もそうであるが、織物や酒、そして水に関する事には秦氏の影がちらつく。酒を古くは「クシ」と言ったらしく、酒を飲むと人の心を奪う事から「奇し(クシ)」「怪し(ケシ)」が転じたものとされている。酒の原料は米である事を思えば、素戔男尊と結ばれた奇稲田姫はその名から酒そのものの神でもあるようなのであるから、素戔男尊の心を奪ったのであろうか? ところで、その松尾大社の祭神に中津島姫命がいる。この中津島姫命とは、宗像大社が祀る中津宮の姫神で湍津姫神の事を言う。松尾大社は、東端の八坂神社(祇園社)と対峙して、西の松尾山に鎮座する。前回書いたように、天照大神と素戔男尊の誓約の場面が、古代における天の川の場面ではなかったかとしたが、それは素戔男尊が牛頭天王という牛を意味する神でもあるからだ。その牛頭天王を祀る八坂神社が東に鎮座し、それに対峙する形で松尾大社、そして湍津姫神を祀るというのは意味が深いと考える。何故なら、湍津姫神は瀬織津比咩でもあり、天女とも云われる存在。そしてその別名は、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、その意味は天空から西へと向かう月の意味を有する神名だ。八坂神社の祇園祭では一年に一度、鈴鹿山の会所に鈴鹿権現である瀬織津比咩が登場するのは、ある意味天の川の逢瀬でもあるように思える。「子持大明神縁起」によれば、伊勢神宮の荒祭宮に祀られる神の名は、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とされ、その出自は鈴鹿からの神であった。 また、秦氏といえば、その秦氏の一族である泰澄の白山信仰を思い出すが、「白山大鏡」において洞窟内に出現した白龍とは瀬織津比咩であった。そして京都(山城国)のかっての愛宕郡に、北斗七星が降った霊山である比叡山の麓の八瀬の意味は「神の河瀬」であり、その同じ愛宕郡には愛宕山がある。その愛宕山に愛宕神社の創始者もまた、白山と同じ泰澄であったのは、何か意味があっての事ではなかろうか。奇しくも、遠野の愛宕神社の祭神が瀬織津比咩であるのは、愛宕神社そのものが、何かの因縁をもつ神社であると考えるのだ。 |
|
 |
|
|
■三十一
白山の開祖泰澄は、愛宕の開祖でもあった。それは、何か意味があったのだろうか?白山を水の信仰とすれば、愛宕は火の信仰となる。そのあたりに、何かの意味を有しているのだろうと思える。 原島知子「火事と愛宕山」を読むと、愛宕山の奇妙な風習が紹介されてあった。愛宕山の宿場としての清瀧村は愛宕信仰上、重要な位置を占める地であるようだ。清瀧村を流れる清滝川は、伊勢内宮の五十鈴川と同様の水垢離場である。その清瀧村での愛宕山詣での描写が司馬江漢「江漢西遊日記」に記されている。 「路ふもとより五十町清滝なと云処ありて、路々喰物あり、人をも泊まる。女土器を投げる妙なり。」 これは江戸時代中期であるが、この土器を投げる習俗そのものはいつまで遡るかわからないという。大森恵子「愛宕信仰と験競べ」では、それを更に掘り起こしている。この土器を投げる行為とは、死者が極楽に往生するといった意味。死者の供養をする為には、品物を投げて散供するのだと。それがもしも荒ぶる神に対するものであるならば、祟らないでくれとの祈願からの土器投げであろうと説いている。 ここで気になったのは、崇徳上皇だ。崇徳上皇が愛宕神社で呪詛を行い天皇を呪い殺したという噂が広まったのは、元々愛宕神社が呪詛と関係ある神社ではなかったのか?愛宕神社に伊弉諾が祀られているのは、火神である軻遇突智を切り殺した為での火伏せの意味からであろう。その軻遇突智もまた、愛宕山に祀られている。しかし軻遇突智の怨念は生きていた為、崇徳上皇事件は起きたのだと思う。山田雄司「崇徳院怨霊の研究」によれば、その呪詛の方法とは、近衛天皇の霊が巫女に口寄せしての事によれば、誰かが呪詛して愛宕山の天公像の目に釘を打った為、自分は目が見えなくなり、ついには無くなってしまったとの事だった。そこで白河法皇をその像を調べると、果たしてその通りであったとの事である。 軻遇突智は、母である伊邪那美を殺した忌子だと云う。愛宕の漢字は「愛」という漢字に「宕」という石で蓋をする意味の漢字の組み合わせだ。愛した我が子を封印したという意味になるのだろうか?古代では、流れる血によって新たな生命が生まれると信じられていた。軻遇突智の首を斬り落とし、流れる血によって多くの神々が誕生した事を踏まえれば、迦具土神は神々の誕生の為の生贄であったのだと思える。しかし怨念とは無念の為せる極みである事を思えば、軻遇突智とは本来、別の神ではなかったか?何故なら、生まれてすぐに殺された軻遇突智は、怨みというものが育つ前に死んだのではなかろうか。つまり、ある神が、その神名を伏せられて軻遇突智という仮の名を付けられ「記紀」での神話上で生贄として殺された。だからこそ無念であり怨霊が発生した為、それを知っていた関係者が崇徳上皇を貶める為に、愛宕神社での呪詛事件を起こした。 「記紀」の神話は、多くの神々を誕生させ過ぎた。例えば、伊弉諾が黄泉国から脱出して禊祓いした時に誕生した四神は、元々八十禍津日神という一柱の神が、四分割されて発生した。その八十禍津日神も、本来は天照大神の荒御魂であった事を考えれば、軻遇突智の死によって誕生した神もまた同じ可能性があるのではなかろうか。つまりだ、軻遇突智という火神は、その火という属性を考えた場合、「記紀」から姿を消した謎の火の神である可能性はある。山田雄司は、怨霊と龍とは、深い関わりがあると説いている。「愛宕山縁起」では、空也上人が愛宕山に参詣したおり、女人に変化して現れた大蛇が成仏を願ったので、念仏を受け、その代わりに清泉を湧き出させたという因縁がある。愛宕の本地神である勝軍地蔵尊(ショウグンジゾウソン)の名の本来は、蛇神でり風神でもあるミシャグチ、シャクジンからの変化であるようだ。つまり勝軍地蔵尊そのものが、蛇であり龍を意味している。その愛宕山に祀られる軻遇突智命(カグツチノミコト)は別に「イカヅチノミコト」と読む。京都でのイカヅチ神とは賀茂別雷神社の賀茂大神を意味する。しかし本来は、天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊であろうと云われる。 土器片を清滝川に投げ入れる習俗で思い出すのは、羽黒神社である。羽黒神社の鏡池に鏡を投げ入れるのは、鏡が白銅鏡(ますかがみ)であり、月を意味する水の依代でもある事から、水神の供養でもある。それと同じに、愛宕山の清滝川に土器の破片を投げ入れるのは、土器が火神の依代であるという事だろう。つまり火神の怒り、祟りを鎮め供養するという意味であるのだと思う。 愛宕大権現の本地仏は白猪乗り武神像であり、愛宕大権現の化身動物が白猪で火の神だと信じられている。猪は多産である事から多産の神であるとなるが、男神で多産?という疑問符が付く。だが考えれば、軻遇突智の死によって多くの神々が誕生した事から、つまり火神とは、軻遇突智(イカヅチノミコト)であろう。 白蛇が水神である瀬織津比咩の化身とも云われるが「記紀」において、蝦夷征伐をしたヤマトタケルを滅ぼしたのは山神の化身で、「日本書紀」においては「白蛇」であり、「古事記」においては「白猪」となる。これが秦氏の一族である泰澄の行動と重なる。「日本書紀」と「古事記」において、何故に山神の化身が、白蛇と白猪に分かれたのか。それはある意味、「記紀」の関係者が水龍と火龍の分断を意図的に施した為ではなかろうか。泰澄はそれを知っており、だから水の信仰である白山を開き、そして火の信仰である愛宕を開いた。それはつまり、「記紀」によって抹殺された、火龍である天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊と、水龍である瀬織津比咩の供養としての白山と愛宕山の開山ではなかったのか? 崇徳上皇は、怨霊となって大天狗になった。愛宕山には太郎坊という天狗がいるが、太郎とは長男の意味を持つ事から、天狗の頂点に立つ大天狗であり、その大元は怨霊の変化となった大天狗であった可能性はあるだろう。その太郎坊の正体は、御霊神であろうし、それは軻遇突智であり天照國照彦天火明櫛玉饒速日尊なのだろう。 東北において、竈の火に樒(シキミ)をくべるのは、愛宕山の習俗が、そのまま全国に広まったからだという。樒の実は毒を持っており魔除けにもなるという。また樒の語源は「悪しき実」からきているという。全国の竈に祀られる竈神とは、非業の死を遂げた者が、竃神として祀られているのだが、その竈の命である火は、愛宕の火でもあった。愛宕大権現に樒を供えるのは、ただ単に樒が愛宕山に自生していただけではなかろう。樒による呪力「魔除け」の効果を期待して、土器片を投げるのと同じく「祟らないでください。」という祈願であった筈だ。それは非業の死を遂げた火龍の祟りを恐れての習俗であろう。 ここで軻遇突智(カグツチ)の「カグ」は、かぐや姫と同じ「光り輝く」の意であり、「ツチ」は霊の意であり水龍である「ミヅチ」と同じで蛇を意味する事から、火龍であるだろう。また香香背男の香香(カカ)は、蛇の古語であり、瀬男(セオ)は水の尾で「綺麗な水の湧くところ。源流」を意味し、また別に「カカセ」とは「穢祓」の意がある事から水龍であろう。「日本書紀 神功皇后記」に「星辰」を「あまつみかぼし」と読んでいる。「辰」は龍でもあるが、日・月・星の総称でもあり、要は三光信仰か。つまり、香香背男でもある天津甕星は龍神であり星神であり、そして水龍という事になる。 |
|
|
■三十二
近江雅和「記紀解体」において、こう記している。「外宮の主祭神は豊受大神であるが、天御中主命、国常立尊、御気津神の諸神はいずれも豊受大神の別名であり、更に「記紀」の初めに出る天御中主命と国常立尊は「大元尊神」と同一神であるとした事である。」 その天御中主命だが、日本で一番多く天御中主命を祀っているのは、茨城県であり、古代の常陸国であった。それは星宮神社に多く祀られている。確かに、天御中主命の代わりに国常立尊となっている場合もあるが、それらが同神である事の変化によるものだ。そして再び「我国間記」によれば、豊受大神はこの常陸国から伊勢へ行ったとある。その豊受大神が天御中主命であるならば、天御中主命を多く祀る常陸国は豊受大神を祀っていたという事になるのか。「倭姫世紀」では「御気津神、宇迦御魂命というのは大自在天の子で、天御中主命である。」としている。この「倭姫世紀」は奈良時代に作られたものとされているが、実際は中世であるようだ。つまり、前にも書き記したように外宮祭祀において、伊勢の度会氏が実権を握る為に、豊受大神を権威付けたのが中世という時代であるが、実際は荒祭宮に祀られる神をカモフラージュする為の豊受大神の権威付けであったのは、その伊勢神宮の歴史から理解できる。 そして「大元尊神」とは、始原の意味であり、外宮の神とはまず初めに生まれた神であるという事になる。これは中世に記された「中世神話」に、御饌都神であった筈の豊受大神が御気津神という、世の初めの原初的な水神に昇華されるという後付け神話であった。それはつまり、元々豊受大神とは御饌都の神であったのだが、荒祭宮の神を表に出せない為に、代わりに豊受大神を前面に出して伊勢神宮の支配権、祭祀権を度会氏が手にする為の苦肉の作であったのだろう。そして、それと同時に益々謎が深まるのが、荒祭宮の神を何故に表に出せなかったのかという事である。それはつまり、荒祭宮のアラハバキ姫と呼ばれる神こそが「大元尊神」であり「アラハバキ神」であるからなのだろう。 伊勢には「太一」という信仰が根深くある。皇大神宮遷宮に先立って行われる杣始祭にも太一の幟が立てられ、遷宮の用材にも太一の文字が刻まれ、奉仕する人々の帽子にも太一の文字があり、明治時代まで続けられてきた贄海神事での神官の乗る舟の旗印も太一である事から、度会神道そのものが太一であり大元神であるという。陰陽五行は別に「太一陰陽五行」とも云われ、「太一(一元思想)」「陰陽(二元対立思想)」「五行(循環原理)」という三つの要素から成り立っている。つまり太一は最高の神であり、大元の神であった。その太一の居所は北極中枢だとされ、北極星の神霊化であり宇宙の大元であるとされているのは、以前紹介した妙見曼荼羅を見れば明らかだ。 ところで天皇という名称は、天武天皇が「天皇大帝」という太一を意味する言葉を採用した事から始まる。太一とは北辰であり、妙見でもある不動の北極星を意味するのだが、仏教にのめり込んで奈良の大仏を作った聖武天皇でさえ別に妙見神を深く信仰したのは、妙見神が自らの地位に関係するからであったのだろう。考えてみれば古代の神事が、何故夜に行われたのかも、月や星を信仰していたからではなかったか。だからこそ、天皇が太陽神である天照大神を祀る事に違和感を覚える。太陽が昇れば、星は消えるからだ。つまり、自らを投影する北極星が輝く夜だからこそ神事が行われたと考える方が納得するのである。 大元神は太一であり妙見と繋がるとは書いたが、石田隆義「山陰の民俗と原始信仰」によれば「荒神と大元神は同神異名の神であって、穀霊でもある。」としており、その大元神の形は上の画像で示される。この大元神の画像絵は、出雲東部から伯耆地方にかけて、荒神の神木の下に甕をいけて、酒を造り、その出来具合によって年占をする習俗という事だが、甕そのものに蛇を入れて蛇神として祀った場合もあるという。甕とは蛇を入れるものであったらしいが、ここで思い出すのは鹿島神宮である。思い出して欲しいのは、鹿島神宮の御神体は海に沈む大甕であり、本来の祭神も本殿に祀られる武甕槌ではなく花房社に祀られる蛇神である事だ。甕と蛇が、出雲周辺の習俗から繋がりそうである。 その大元神の形を示したものを、「遠野物語拾遺32」に登場する熊野神社でも見かけた事がある。 橋野の中村という処にも昔大きな沼があった。その沼に蛇がいて、村の人を取って食ってならなかった。村ではそれをどうともすることが出来ないでいると、田村麻呂将軍は里人を憐れに思って、来て退治をしてくれた。後の祟りを畏れてその屍を里人たちは祠を建てて祀った。それが今の熊野神社である。社の前の古杉の木に、その大蛇の頭を木の面に彫って懸けておく習わしがあった。社の前の川を太刀洗川というのは、田村麻呂が大蛇を斬った太刀を、ここに来て洗ったからである。 「遠野物語拾遺32」 吉野裕子「蛇」によれば、蛇は大元神であり、それを祀る蛇巫は祭祀の中枢にいたとしている。縄文中期に発掘された蛇巫女の土人形が、その存在を示しているという。「古事記」などからも、蛇はかなり重要な位置に属している存在であったのは理解できる。しかし「遠野物語拾遺32」での坂上田村麻呂による大蛇退治しかり、「古事記」におけるヤマタノオロチしかり、かって神であった蛇を忌み嫌い遠ざけて行った何等かの理由があったのだろう。 |
|
|
■三十三
前に、常陸国には二荒山の影響があると書いた。鹿島神宮の御神体の大甕でさえ、二荒山からのものであった。その二荒山だが、下山衣文「古代日光紀行」では、男体山山頂遺跡から鉄鐸131個が出土しているという。この鉄鐸は「サナギの鈴」とも呼ばれ、「佐奈伎鐸」とも書き記す。 サナギとは「小蛇」の意であるようだ。「ナギ」は蛇の古語であり、イザナギ神もまた蛇であった。イザナギ、イザナミは「凪」と「波」を意味し、それがクネクネとうねる様が蛇の動きを彷彿させる事から来ている。そして、この「サナギの鈴」は、音響を以て神意を伝える重要な神呪のアイテムであるという。上の動画の様に、蛇は怒る時、その尾を振動させて、その振動する尾が振れるもの次第で、響きが変わる。その蛇の出す音を意識されて作られたのが、サナギの鈴ではないかと云われる。大抵の場合、サナギの鈴は6つ連なるのは、十二支の子から始まって6番目が巳である事から、蛇を意識して6つのサナギの鈴をつけるのだと云う。 古代では、蚕の守り神が蛇とされたのは蚕の繭玉を「竜精」と称し、竜蛇の子供でもあったからだ。その蚕は蛹(サナギ)でもあり、サナギの鈴の名称であり、その造形は蛹にも通じる。岩手県の浪分神社の祭神が瀬織津比咩であり、養蚕の守り神でもあるのは、瀬織津比咩が竜蛇神であるからだ。 そして再び「ナギ」だが、それはウナギにも通じ、ウネウネとうねる様は、蛇でもありウナギもまた同属とされた。そのウナギは栃木県に多く祀られる星宮神社に祀られる神の眷属とされるが、本来は蛇であったのだろう。何故なら、星宮神社は二荒山の影響を受けて建立されたからだ。蛇を祀る二荒山の神威は、栃木県や茨城県に影響を与え、そのサナギの鈴繋がりから諏訪との関係も深く関わる。その二荒山の蛇とは、以前に書いた通り、滝尾神社の祭神である田心姫に繋がるのだが、実は田心姫ではなく瀬織津比咩となるのは、過去に記した。 もう一度、鹿島神宮へ戻ろう。鹿島神宮の御神体は、海中に沈む大甕であり、その甕とは蛇を入れる器である。それは出雲地方に伝わる習俗から見出せる。例えば出雲では、白蛇を甕に入れ初穂を供えて家の守護神としていたなどと、蛇を飼っていたようである。ただ飼うと言ってもペットとは違う。その甕に大元神である蛇の霊威を閉じ込めておくという事である。それを鹿島神宮に当て嵌めれば、二荒山の蛇を封じ込めたのが鹿島神宮である事になる。本殿に祀られる武甕槌より先に、花房社に祀られる蛇神を参拝しなければならないのは、その蛇神の霊異を鎮める為であろう。また鹿島神宮には、要石がある。地面下に潜むナマズを抑える為だとあるが、実際は龍脈を抑えるのが要石の役割である。つまり鹿島神宮の役割とは、竜蛇神を抑え封じ込める役割として建立された神社であると想定される。その一つは二荒の蛇神であり、もう一つは実は蛇神であった静神社の神であり、穢祓の意味を持つ「カカセオ」という名の蛇神。それは、滝尾神社と同じ瀬織津比咩であった。 小野神社というものがある。一番有名なのは、武蔵国一宮の小野神社で、祭神は瀬織津比咩である。その小野神社の御札が、上の画像となる。青は水を表し、赤は火を表す。太一陰陽五行に則れば、陰陽の水と火は、太一において一元となる。その両方を兼ね備えた形で瀬織津比咩の御札があるというのは意味深であろう。そして、その小野神社は多摩においてはアラハバキ神を祀り、塩尻の小野神社では建御名方神を祀っている。また、町田の小野神社は小野篁を祀っているが、小野篁は冥界を自由に出入りした人間であり、それはつまり地下を移動するのは、諏訪の蛇となった甲賀三郎に通じる。 全国の小野という地名の殆どは、小野氏から発祥していると云われる。諏訪大社との関係の深い、塩尻の小野神社は不明であるが、恐らく小野氏との関連が見いだせるのではなかろうか。何故なら、列挙した小野神社の祭神は、瀬織津比咩であり、アラハバキ神であり、建御名方神という事は、大元神が竜蛇神である事から、全て関連してくるのだ。その竜蛇神である大元神だが、それが早池峯神社に関わるのは、大分県の宇佐神宮に関わってくる。次は、宇佐神宮へと飛ぶ事にしよう。 |
|
|
■三十四
早池峯山は何度も語ってきたように、北に鎮座してこその山であった。大迫の早池峯神社が遠野の早池峯神社に向けて建てられているのも方違えの呪法であり、遠野の早池峯神社を経由して、北に鎮座する早池峯山を拝む為であった。 奥州藤原氏の初代清衡が、出羽国、陸奥国両国の一万余りの村毎に一ヶ寺を建立したと云われるのは、新山寺であり新山神社だとされている。その新山神社に祀られているのは玉依姫という仮の名であり、本当の神名は瀬織津比咩であり、それは羽黒権現としても祀られていた。その羽黒権現を祀る山形の羽黒神社には、国宝となる平将門が建立したとも云われる五重塔がある。その内部には妙見神が祀られている事から、羽黒修験は北を重視していた事がわかる。 また、早池峯の麓にある又一の滝だが、恐らく太一の滝からの変化したものであると以前に述べた。それは妙見曼荼羅を早池峯に当て嵌めて見た時に、それがありありと理解できるのだ。そしてそれと同じ構造が、室根山にも見て取れた。山頂は天に通じるもので、滝は民に通じるものであった。 平田篤胤「古史伝」では「必ずここは大虚の上方、謂ゆる北極の上空、紫微垣の内を云なるべし。此紫微宮の辺は、高処の極にて天の真区たる処なれば、此ぞ高天原と云べき処なればなり。」と、高天原を称して述べているのは、高天原が本来、北辰崇拝に基づくものと考えたからである。そして妙見では、五と三の数字を重んじる。北極五星は天上の最も尊貴な星とされるのだが、その中でも三星は特に尊い星とされている。その三と五の組み合わせに関する神話が「古事記」に登場する。それは天照大神と素戔嗚尊による誓約の場面だ。そこで三女神と五男神が生れるのだが、その後の扱いを見ても、三女神の扱いを重視しているのは、三女神と三星が結び付くからと考える。その三女神は宗像三女神で、水神である。その宗像三女神の中でも多岐都比売命を祀る中津宮である大島には星の宮があるのを知った。またその大島には星の信仰をしたであろう安倍一族の安倍宗任の墓も存在する。以前、多岐都比売命は瀬織津比咩であると書いたが、星を通してここでも繋がる。とにかく「古事記」に於いても、水神と星神の結び付きが成されていたのである。 そして「早池峯山妙泉寺文書」によれば、筑紫の宇佐八幡宮から宝剣が伝わっている。 早池峰山大権現之御宝剣ハ 筑紫宇佐住八幡宮息細工スト伝 陰分ニ細工成就スルカ放ニ銘ハ陰光ト打 前代未聞之宝剣ト伝申 右御宝剣妙不思議数度有之由 由来伝ル者也 当時現在之密僧等信シテ可守護者也 拝見之砌者 十七日之間精進潔斎 早且 着浄衣スト 往古ヨリ伝之 猥リニ不可拝見伝々 当時現住未世之僧等謹テ可守護乃也 何故に宇佐八幡宮から宝剣が伝わったのか謎であり、その宝剣が今どこにあるのかも謎である。ただ一番の問題であり驚きは、蝦夷国であった遠野という田舎の地に鎮座する早池峯妙泉寺に宇佐八幡宮から宝剣が伝わっていたという事だろう。 また別に、六角牛山善応寺の由緒が「早池峰山妙泉寺文書」に記されている。六角牛山善応寺とは、かなり以前に廃寺となった伝説の寺院である。そこには住吉四社の本地として 「第一殿薬師 第二殿大日 第三殿弥陀 第四殿六角牛新山宮」とあり、神道の垂迹として「第一坐天照大神 第二坐宇佐明神 第三底筒中筒表筒 第四坐神功皇后」とある。取り敢えずの違和感は、薬師の垂迹に天照大神が坐し、大日如来の垂迹としてあるべきの天照大神の代わりに宇佐明神が坐している。密教系の教義によれば、大日如来の垂迹は不動明王となっている。それが六角牛善応寺よれば、宇佐明神となる。それでは、この宇佐明神とは何であろうか? 早池峯山妙泉寺であり、早池峯神社の創建が大同元年、六神石神社の創建が大同二年と一年のズレがある。岩手県内には、広きに渡って多くの大同二年創建の神社仏閣があまたの如くあるのも、やはり坂上田村麻呂の蝦夷征伐と呼ばれたものに対応しているのだとは感じていた。当初の寺院の殆どが天台宗の影響を受け、その開祖に慈覚大師円仁が登場している。その円仁の誕生の地は常陸国である事から、その円仁の祭祀傾向を常陸国の祭祀から探して見てみる事にした。 常陸国の「金砂両山大権現縁起」では、主となる祭祀神社は二つあり、東金砂山と西金砂山の神社が一番古い形であるようで、やはり円仁が関わっていた。西金砂山が本宮らしく、創建が大同元年であり、そこには大己貴命であり千手観音が祀られ、東金砂山の創建は大同二年となり、そこには少彦名命であり薬師如来が祀られていた。陸奥国も含め、常陸国でも神社仏閣の創建年代が大同元年、大同二年とするものが多いが、一つの法則があった。 伊勢神宮に本宮と外宮があるように、どうも両宮方式を採用して祀っているようであった。何故に大同の年号が多いのかという理由も、恐らく坂上田村麻呂の功績を神懸りと考え、その神威を付随させる事によって東国の経営にあたったと考えられているのが一般的の様である。その坂上田村麻呂に関係する「清水寺建立記」には、陸奥国在任中の田村麻呂将軍が、大同元年十一月二十七日付の書状で、清水寺に氏寺の建立を願ったとあり、その清水寺の氏寺としての概念に坂上田村麻呂の神威を結び付け、陸奥国に多くの大同元年、二年の神社仏閣が建立された要因であったようだ。これらから早池峯と六角牛に結び付けてみると、本宮と考えられる早池峯には千手観音、もしくは十一面観音が祀られ、別宮であろう六角牛には、薬師如来が祀られたという事だろう。これは天台宗が国家鎮護の思想に則って考えられたもののようで、千手観音&十一面観音の垂迹である、大己貴命と少彦名命をみれば、国家の形成、新たな国造りを願っているのがわかる。 六神石神社には確かに少彦名命の伝承があり、薬師如来が祀られている。早池峯には十一面観音が祀られているが、大己貴命に対応するのは恐らく「遠野物語拾遺126」にも紹介されている、三面大黒の話がそれであろう。大己貴命は大国主の別名と云われ、その大国主は大黒様と重ねられ広まっている。国造りとしての少彦名命であり薬師如来は、薬師としての国の使命であったろう。薬の民俗を調べると薬は単に薬としてでなく、国民の命を護ろうとする国家思想の礎の一つであった。その国家形成の概念が、早池峯と六角牛の里宮に施され、恐らく二重構造として、早池峯山と前薬師と呼ばれる薬師岳に施されたのだと思う。 ところで、宇佐明神に戻ろう。宇佐明神とは聞きなれない言葉だと思い調べると、「エミシ国の女神」の著者でもある風琳堂氏が自身のブログに、鹿児島の加紫久利神社を紹介する中に、宇佐明神が載っていた。「鹿児島県神社明細書」での加紫久利神社の項に「姫太神」と記され、その姫太神の下に「宇佐明神湍津姫命 胸肩明神田心姫命 厳島明神市杵嶋姫命」とある。 それとは別に、大分県の八津嶋神社の縁起書「影向山八石宮八津嶋大明神縁記」では「第一田心姫。筑紫胸肩神。第二湍津姫命筑紫宇佐嶋神。則是以湍津姫命為当宮降臨本神矣。第三市杵嶋姫命。安藝国厳嶋神也」と。「第二湍津姫命筑紫宇佐嶋神。則是以湍津姫命為当宮降臨本神矣」から、この八津嶋神社には宇佐嶋神として女神である湍津姫が降臨しているという事は、宇佐八幡宮で祀られる姫神とは湍津姫であったのか。 とにかく、宇佐明神が湍津姫であるならば、早池峯神社に奉納された宇佐八幡宮の宝剣と、六角牛に祀られる宇佐明神から、早池峯及び六角牛と宇佐との関係が見えてくる。以前「三女神伝説(多岐都比売命と瀬織津比咩)」において、櫟谷宗像神社の祭祀形態から、湍津姫は瀬織津比咩であると確認した。これらの情報から早池峯神社に祀られる瀬織津比咩という神は、宇佐八幡宮と宗像大社との縁が深い神である事が見えてこよう。何故に早池峯神社に宇佐八幡宮から宝剣が奉納されたのかは、宇佐八幡宮の姫神と同神が祀られていたからと考えれば納得するのだ。そしてそれは一年のズレが生じながら、天台宗の祭祀法に則って六角牛にも祀られた。つまり、早池峯&六角牛には、同じ神である宇佐の姫神であり、宗像の湍津姫である、瀬織津比咩が祀られたのだろう。 |
|
|
■三十五
坂上田村麻呂の蝦夷征伐の後に建立された早池峯神社であるという事から、宇佐明神が遠野に祀られた理由、そして宇佐からの宝剣の奉納とは、やはり宇佐八幡宮としての武力からきているのだと思われる。宇佐八幡神を後に応神天皇と神功皇后を据え置いたのは、三韓征伐を行った武神としてのものだろう。つまり、早池峯山と室根山とは、違った意識の元に瀬織津比咩が勧請されたのではなかろうか。 ところで「東日流外三郡誌」を世に送り出した和田家には、別に「和田文書」というものがある。その中に「北斗抄」というものがある。そこには宇佐の大元神社の事が書かれている。 筑紫の国に宇佐大神大元大神がある。これは出雲大神の遷宮という。出雲の宮はもと荒覇吐神であったが、倭神を入れて現在の場所に移したものであるという。古の風習で残っているのは荒覇吐神に拝する拝礼である、三礼四拍一礼なる荒覇吐神の拝礼に、三礼ではなく二礼をなすほか、四拍一礼は同じである。もとの荒覇吐神は門神として、内宮を外に出して残っている。 「東日流外三郡誌」に並んで、この和田文書も偽書の認定を受けているが、実際に宇佐には、その霊地である御許山に大元神社が鎮座している。鳥居から先は禁足地になっているようで不明だが、それが宇佐家に伝わる文書に記されている。 「神代上第六段の条に見える宇佐嶋の旧跡地と伝えられる御許山の頂上に、太古から宇佐氏族の氏上によって祀られていた比売大神(宇佐明神)を勧請した。この祭神は間違いなく宇佐家の母系祖神であって・・・。」 「和田文書」云々以前に、宇佐の大元の神とは宇佐明神であるという。大元の神とは竜蛇神であるいう事。また、それが早池峯山と六角牛山に勧請された事実だけは揺るぎ無いだろう。 「和田文書」に、宇佐の大神は出雲から遷宮されたというが、宇佐八幡宮の祭祀氏族である宇佐氏、辛島氏、大神氏の三氏族になるが、そのうちの大神氏は三輪氏系である為、出雲系氏族である事から、和田氏はそれを意識して出雲から遷宮されたと書いたのかもしれない。しかし、日本中の神社を見渡せば、天照大神を中心とする天孫系祭神よりも、出雲系の祭神が多く祀られている事実から、「古事記」などに記されている国譲り神話も実は嘘ではないかと疑ってしまう。藤原不比等がその藤原という名の、他の樹木に寄生する藤という存在を意識し、自らは決して表に出ず、天皇を傀儡する事で、その権力を行使したかのように、出雲族もまたその可能性は否定できないのではないか? 宇佐の伝承を読むと、八幡を「ハチマン」と呼んだのは平安時代に入ってからで、それ以前は「ヤハタ」と呼んでいた。大神氏と妥協した宇佐氏と辛島氏の後に、官幣大社八幡宮が成立するが、何故か三氏族各々が八幡大神の発現伝承を唱え、その時期を欽明天皇の御代の事にしている。その中で、宇佐氏の場合は、下毛郡の三角池の主である龍神を八幡大神としていた。大分大学名誉教授富来氏によれば、三角は巳棲で三角池(みすみいけ)は龍神の棲む池であると。そして、この池の真薦(まこも)が隼人征伐の際の、八幡大神の御神験になったと解いている。つまり、三角池の真薦から御神体を作ったという事か。 その三角池があるのは、薦神社であり別名大貞八幡宮と呼ばれ、全国八幡宮の総本宮「宇佐神宮」と深い関わりを持つ、承和年間(834~848年)創建の由緒ある古社である。社内にある三角池を御神体としており、池を内宮、社殿を外宮と称している。 ところで、豊前豊後地方では、大蛇の事を「ヤータロウ」もしくは「ヤハタロウ」「ヤワタロウ」と呼ぶようである。これを考えみれば、宇佐氏にとっての「八幡(ヤハタ)」とは「龍蛇」を意味するのだろう。 例えば、岩手県花巻市東和町に丹内山神社があるが、その祭神は北東に離れた滝沢神社に顕現した瀬織津比咩であった。それと同じ様に宇佐氏の奉斎する宇佐明神は御許山の大元神社に鎮座するのだろうが、その顕現した姿は三角池の龍神なのだろう。それは、和魂と荒御魂の関係に等しい。和魂とは「ニギル」という言葉に関係し、握るとはその掌によって作られた空間にモノが一杯に満ち溢れる状態を「握る(ニギル)」という言葉の意味となっている。逆に荒御魂は外に顕現した生命であり、姿である。それはつまり、潮満珠と潮涸珠の関係に等しい。 去年の事だが、宮崎県日南市の鵜戸神宮が、古事記編纂1300年を記念し「古事記」に登場する神宝「潮満珠(しおみつたま)」「潮涸珠(しおふるたま)」を戦後初めて一般公開した。画像の向って右が潮満珠であり、向かって左が潮涸珠である。神功皇后の伝説にも、住吉大神の化身である龍神から授けられた二つの玉「潮干珠(しおひるたま)」「潮満珠(しおみつるたま)」があり、名称が若干違うが同じものである。 ここで、画像から潮涸珠の形に注目したい。珠といいながら、潮涸珠の形は円錐形をしている。それは造形から鏡餅にも似ているし、ある意味三輪山の形にも似ている。この三角錐の形の根源とは、蛇のとぐろを巻いた姿を表しているのである。つまり、和魂はその空間が満ち足りている潮満珠に等しく、潮干珠は、荒御魂と同じく外に顕現した生命の形をしている。つまり潮干珠とは、和魂が顕現した蛇と捉えても良いのではなかろうか。何故なら、その潮干珠と潮干珠を自在に操った神功皇后が「日本書紀」において、真っ先に呼んだ神名こそ、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、天照大神の荒御魂であった。撞賢木厳之御魂天疎向津媛命は、瀬織津比咩の異称である。それはつまり神功皇后が、和魂と荒御魂をも自在に操った存在と捉えて良いのではないか。宇佐氏の奉斎する武神としての八幡大神とは、和魂と荒御魂を一元とした大元の神であるから、それを自在に操る事の出来た神功皇后を、宇佐氏の聖地である小椋山の第三殿に祀ったのでは無かろうか。一般的には応神天皇を祀ったついでに神功皇后が祀られた様に云われているが、本来は宇佐明神の巫女としての扱いであったと想像する。その宇佐氏の聖地である小椋山だが、元々は宇佐氏の比咩神と北辰の神を祀る地であった事から、この宇佐の地でも、龍蛇神と妙見神が繋がって来るのだ。 |
|
|
■三十六
宇佐明神を取り上げたが、ここでもう一度、伝説の寺院六角牛善応寺の祭祀を確認してみよう。「第一殿薬師 第二殿大日 第三殿弥陀 第四殿六角牛新山宮」とあり、神道の垂迹として「第一坐天照大神 第二坐宇佐明神 第三底筒中筒表筒 第四坐神功皇后」 そして、現在の六神石神社に伝わる由緒が下記の通りになっている。 ■ 人皇第51代平城天皇の御代、大同2年(807)時の征夷大将軍坂上田村麻呂、蝦夷地平定のため蒼生の心伏を願い神仏の崇拝をすすむ。時に六角牛山頂に薬師如来、山麓に不動明王、住吉三神を祀る。爾来陸奥の国中の衆民、衆団をなして登山参拝あとを絶たず、霊山として山伏の修行者も多く集まる。 第54代仁明天皇の嘉祥年代(848-851)元住吉といえる地に社殿を建立し、住吉神を遷し奉り住吉太神宮と称す。 山頂の堂宇再三の山火事に被災し、後鳥羽天皇の文治5年(1189)阿曽沼公石洞の地に神地を寄進して神殿を建立。山頂の祭神を遷奉り六角牛新山宮と称し、六角牛山善応寺を創設し祭事を司掌させた。後に住吉太神宮の新座地を川向い(現在の六神石神社の地)に定め奉遷す。 寛文年中(1661-1673)南部領となるに及び社領95石を寄納される。六角牛新山宮は住吉太神宮に合祀される事となり、享保10年(1725)奉遷。明治5年(1872)青笹村社六神石(ろっこうし)神社と改まる。大正4年(1915)9月、供進神社に指定される。 表筒男命 中筒男命 底筒男命:(住吉三神) 住吉大神は、禊祓の御神格をもって御出現になりましたので、禊祓の神であり神道でもっとも重要な「祓」のことを司る神です。また、住吉大神は海上安全の守護神であり、奈良時代、遣唐使の発遣には、必ず朝廷より住吉大社には奉幣があり、その海上無事を祈りました。(三陸の漁師の人々は、六角牛山を目印に漁をしたと言われ、昔は漁師の人々の参拝も多かったと言われています。) 産業商業・文化・貿易の祖神と仰がれ住吉大神の広大な御神徳はあまねく世に知られています。(家内安全、商売繁盛、交通安全) 息長帶比売命 息長帶比売命(おきながたらしひめのみこと)は、八幡神こと誉田別命を生んだ聖母神も呼ばれ、子孫繁栄のシンボルとして祀られています。そのご神徳は、安産子宝・子育てを中心として、勝運・開運・招福・悪病災難除け・方位除け、無病息災、延命長寿などです。 大己貴命 大己貴命は別の御名を大国主命ともうしあげ、縁結びで知られる出雲大社にお祀りされている神様です。いまも家運隆昌・事業繁栄の福徳の神として崇め祀られています。俗に大己貴命は“だいこくさま”として慕われ御神徳はまことにあらたかであります。 「六神石神社の記載を抜粋」 ■ ところで、六神石神社の名は、明治時代の神仏分離の際、既に青笹村の六角牛神社があった為に、読みお同じとしてあてる漢字を「六神石」とした為であり、六角牛も六神石も同じである。その六角牛の祭祀を見れば、総体的に住吉大神を中心にしている事がわかる。その住吉大神だが、宗像大社の伝承によれば「宗像神の子が住吉大神で、住吉大神の子が八幡神(応神天皇)である。」という。 少し違うが田中卓「住吉大社神代記の研究」を読んでると、仲哀天皇の亡くなった晩に、神功皇后と大神は、夫婦の秘め事をしたという。この大神とはどの神を言っているのかわからぬが、その記述は下記の通りとなる。 「この夜に天皇惚に病発りて以て崩りましぬ。『是に皇后、大神と密事あり。』」 ところが「八幡宇佐宮御託宣集」では「住吉縁起」を紹介する中の記述に、大帯姫が敵を破りたいと神に祈ると、住吉大神が出現し神功皇后と結ばれ、その後に八幡が生まれたとされている事から「住吉神代記」に登場し神功皇后と結ばれたのは住吉大神と理解できる。この神功皇后と結ばれた住吉大神とは、武内宿祢の事を意味しているのではというのが一般的見解の様だ。まあ、これはさて置いて、六神石神社の由緒で気になったのは「住吉大神は、禊祓の御神格をもって御出現になりましたので、禊祓の神であり神道でもっとも重要な「祓」のことを司る神です。」という箇所だ。「鉄の蛇(日高見とアラハバキ)其の三十四」で、恐らく慈覚大師円仁の祭祀法から、遠野にも両宮方式が採用され、早池峯は本宮で、六角牛は外宮とされたのではないかと書いた。現在広く伝わる「大祓祝詞」には、瀬織津比咩の神名か祓戸大神の名で穢祓の祝詞が読まれている事から、大元の穢祓神とは早池峯に祀られる瀬織津比咩であり、住吉大神はそれに準ずるものであるという認識だ。 ここで思い出したのが、仲哀天皇の死んだ後、その仲哀天皇を祟った神を神功皇后が呼び出し、真っ先に呼ばれた神名が撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、住吉大神はその後であった。この順列はまるで「古事記」での伊弉諾が黄泉国から帰還した後に中津瀬で禊祓をした時に、真っ先に登場したのが、大禍津日神、八十禍津日神、別名を瀬織津比咩であり、その後に住吉三神が登場している。これは伊弉諾が死の国である黄泉国から帰還したのという死の匂いを祓う為のものであり、また神功皇后のそれは、仲哀天皇の死の穢れを祓うものでもあったと思える。つまり、神功皇后のした神事とは穢祓であったのだろう。しかし解せないのは、仲哀天皇の死後に住吉大神と結ばれた神功皇后であったが、その後に仲哀天皇を祟った神がやはり住吉大神であったという事。 また別に、神功皇后で解せないのは「日本書紀 神功皇后記」において天照大神が登場し「我が荒魂をば、皇后に近くべからず。」と述べた事である。荒魂が撞賢木厳之御魂天疎向津媛命である事は明白。ここで仲哀天皇を祟った神が、天照大神の荒魂である撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、住吉大神であるのに、天照大神の荒魂だけを神功皇后から遠ざけようとしているのは何故なのか?だが、先に紹介した六角牛善応寺の祭祀をもう一度確認すれば、宇佐明神が天照大神の荒魂である事から「第一坐天照大神 第二坐宇佐明神 第三底筒中筒表筒 第四坐神功皇后」という祭祀は、それらが全て揃っているのである。中央から遠く離れた東北の遠野という地を考えみ、また遠野の語源の一つと考えられる、伊勢神宮の遥宮(とおのみや)が遠野の語源に関わるのであるならば、遠野の六角牛の祭祀こそ、隠蔽すべき祭祀形態では無かったのだろうか。そして「日本書紀 神功皇后記」には興味深い一文が紹介されている。三韓征伐においての新羅王の誓いの言葉に「東にいづる日の、更に西に出づるには非ずは・・・河の石の昇りて星辰(あまつみかほし)と為るに除ずして…。」と、太陽が昇る東を強調し、西へ向かうのを否定し、星辰(あまつみかほし)になる事を否定している。撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とは、月が西へと向かう意味であり、更に星辰=天津甕星(あまつみかほし)にならぬとは、天皇に逆らわないという意味である。「河の石の昇りて星辰と為る」とは、天津甕星が竜蛇神であり、それは石から為るという事である。これは「日本書紀纂疏」の「星堕ちて石となる」に対応する言葉である。また以前に甕=厳である事から、天照大神の荒魂である撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とは甕之御魂でもあるとした。つまり、「日本書紀 神功皇后記」において、天照大神が自らの荒魂を神功皇后に近づけては成らないと述べた事は、神功皇后にこそ瀬織津比咩とを結びつける何かがあるのでは思わせてしまうのだ。考えてみれば、瀬織津比咩を祀る早池峯であり六角牛には、宇佐の影響がある。その宇佐には第三殿に神功皇后が祀られ、六角牛にも神功皇后が祀られているのは、宇佐に祀られる宇佐明神と、遠野に祀られる瀬織津比咩との深い関係を意味しているのではなかろうか。それらは最後に大元神であるアラハバキ神の祭祀に関わるのだと思えるのだ。 |
|
|
■三十七
前回、神功皇后の疑問について書いた。その疑問とは、仲哀天皇を祟った神で真っ先に呼ばれた神が、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であり、その後に呼ばれたのが住吉大神であった。どちらも仲哀天皇を祟った神でありながら、その後に天照大神が登場し、私の荒魂を神功皇后に近付けてはならないとした。つまり、ここでも尚、天照大神の荒魂は祟り神であるという事なのだろうか。しかし、この荒魂を天照大神の御心ともしている。天照大神の御心である筈の荒魂が、神功皇后を祟るとはおかしいではないか。そしてその荒魂から神功皇后を遠ざけようと、天照大神が語ったのであれば、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命とは天照大神の御心では無く、天照大神とは別人格の一柱の神であらねばならぬ。 天照大神の荒魂は、荒祭宮に祀られる撞賢木厳之御魂天疎向津媛命であるが、その別名が瀬織津比咩である事はじゅうじゅう承知である。それは以前に、伊勢の祭祀権を奪われた度会氏が内宮に属している荒祭宮を支配していた事から、荒祭宮を中心とし外宮の豊受大神を根源的な御気津神という水神に昇華させて、伊勢神宮全体の支配権をものにした。それは恐らく、単なる御饌都の神であった豊受大神という仮名の神を前面に出し、その裏に隠れる荒祭宮に祀られるアラハバキ姫とも呼ばれる、瀬織津比咩を守る為の手段ではなかったか?とした。それは度会氏にしてみれば、元々の地主神を見捨てて、豊受大神に乗り換える筈が無いという判断からのものであった。何故なら、アラハバキ姫とは大元の神であったからだ。 似た様な形で、宇佐氏が祀る姫神とは、三角池に潜む龍神であり、それは宇佐氏の聖地である御許山の頂に祀る、大元神である宇佐明神という姫神であった。しかしその後、三輪氏系の大神氏が宇佐に進出し、辛島氏を含めて三氏合同の祭祀が行われ、そこで八幡神が誕生した。八幡神はその後、応神天皇とされ、それに伴い神功皇后みまた祀られている。その八幡神は「ヤハタ」とも読むのだが、豊前・豊後国地方では「ヤハタ・ヤワタ」は蛇神の意味を持ち、大神氏を交えて宇佐八幡神宮とした時に、宇佐氏は竜蛇神の意味をも含めた八幡神とした為に納得したのではなかろうか。宇佐氏にとっての八幡神の本来は、御許山に祀る大元神である竜蛇神であった筈だ。この表向きの八幡神を祀る宇佐氏と、表向きの豊受大神を祀る度会氏がどうも重なって思えてしまう。いや思うというより、大元神が本当にアラハバキ神であるならば、度会氏も宇佐氏も時代の不遇の流れと共に、密かに同じ神を祀っていた事になる。 「住吉大社神代記」によれば、第一殿から第三殿までは住吉三神が祀られるが、第四殿では神功皇后となっているが、本来は名前不明の姫神であったのを、後に神功皇后としたという。とろで六角牛の祭祀の原初は、住吉三神となっているが、もう一座は不動明王とされているが、その不動明王という名は、あくまでも仏教色を強く出してからのものであろう。その不動明王とは、六角牛山麓の不動の滝に祀られる神であり、その傍に不動の形で鎮座する大岩を不動岩とも呼ぶ事から、六角牛に祀られる不動明王とは、あくまでその神を守る為の脇侍である可能性が高い。その関係はすでに「十一面観音と不動明王、そして瀬織津比咩」で書き記している。つまり不動明王とは、六角牛に祀られた瀬織津比咩の脇侍であり、本来は瀬織津比咩と住吉三神が祀られる形が正式な祭祀であろう。そして、その祭祀形態を「住吉大社神代記」に重ねてみれば、住吉三神と姫神という形が瀬織津比咩になり変わってもおかしくはないだろう。つまり六角牛の祭祀とは、そのまま住吉大社の祭祀形態を当て嵌めたものと思える。ここで気になるキーワードは牛である。 ここで、遠野三山の一つ石上山が鎮座する綾織の七夕伝説を紹介しよう。 ■ 機織の上手な娘がおり、今まで様々な織物を織ってきたが、天女の羽衣のようなものを織ってみたいと、毎日朝と晩に、神様へ御灯明と御神酒を供え願っていたという。すると二十一日目の晩に牛を連れた貴人が機織娘の前に立ち、こう言った。 「お前の願いを叶えてやる。牛に乗れ。」 貴人は娘を牛に乗せ、高い山の上の大きな石のある処へ連れて行き、そのまま何処かへと行ってしまったそうな。山の上で見る星々はまこと綺麗なもので、手を伸ばせば取れそうだと思わせる程の輝きを見せ、娘はその星々に見とれていたが、急に寂しくなり涙が流れてきたのだと云う。 其の時、夜空に流れ星が沢山流れたと思ったら、下方から牛に機織道具を積ませ、先程の貴人と美しい女性が娘に近付いて来たのだと。そしてまた何処からともなく、まるで昼間の様に周囲を明るく照らす美しい女性が現れた。そして三人で石の上に機織道具を組み立て、機織が始まったのだと云う。 周囲を明るく照らす女性が機を織り、他の二人はその手元となっていてた。織物は東の山の上に太陽が昇ると同時に織り上げられ、その見事な出来栄えに娘は驚きを隠せなかったという。 「この織物は、山桑の葉を食う蚕の糸で織った織物だ。残った糸と共に、お前に全てやるから持って行くが良い。」 娘はふと気付くと、石の上に綾綿と糸があり、先程の三人はどこかへ消え失せてしまっていたそうな。しかし、何処からともなく声が響いてきたのだという。 「わたしは六角牛山の住吉三神の穴の上筒男命で、機織の道具を持って来られたお方は石上山の神である伊邪那美命、光を出して機を織られた方は、早池峰山の瀬織津比咩である。」 この時から、この機を織った石上山が鎮座する地域を綾織と呼んだと言うことである。そして、六角牛山の御祭神は牽牛星、早池峰山の御祭神は織女星、石上山の御祭神は白鳥で、これから石上神社の御条は旧七月七日となったと云う。 ■ この伝説には、光を放つ貴人が登場する。それは早池峯に祀られる瀬織津比咩であった。娘の織った機織りは、瀬織津比咩の放つ光の中で織られ、太陽が昇る時に織り上げたという事は、瀬織津比咩が放つ光とは、太陽の光では無く、星の輝きか月光のそれであったのだろう。夜は、魑魅魍魎と神々の時間帯であると云われるのも、本来は太陽の下では神々は姿を表さないものであるからだ。この伝説の登場する神に、瀬織津比咩と住吉神、そして牛が登場している。それは七夕に関する伝説には、織女と牽牛が登場するので当然であろう。その牛が、神功皇后伝説にも登場している。 奈良時代から平安時代に編纂された「備前国風土記」には、神功皇后の乗った船の前に大牛が登場し、舩が転覆しそうになった。その時に住吉神が登場し、その大牛を投げ飛ばしたという話がある。この伝説をどう捉えるかだが、神功皇后と住吉大神は結ばれたという伝承がある以上、これもまた七夕の変化形では無いかと考える。何故なら本来の七夕伝承とは、降雨の祈願に生贄として牛を殺したというものであるからだ。住吉大神によって投げられた大牛とは、犠牲の牛を意味しているのではなかろうか。今では牽牛を、織女と逢瀬を繰り返す相手として確立されているが、実は牽牛とは「牽引された牛」そのものであろうとされている。それはつまり、遠野に伝わるオシラサマの牛バージョンであるのが、七夕の話なのだと考える。また逆に、オシラサマの話も七夕に重ね合わせてできたのではなかろうか。 では牛を殺す雨乞い祈願において、どういう神が必要なのか?それは、雨をもたらす神(竜蛇神)であり、もしくはそれを呼ぶ巫女。そして、牛の死による穢れを祓う為の、穢祓の神であろう。こうしてみると、神功皇后伝説で大牛を投げ飛ばした住吉大神は、牛による穢れを祓ったものとも思える。それは住吉大神もまた、穢祓の神であるからだ。 奇しくも遠野三山において、何故か六角牛山の頂だけで、千駄木が焚かれ雨乞い祈願が行われて来た。それを知らない人々は昔、六角牛山の頂から煙が立ち上るのを見、六角牛山が噴火したと思ったらしい。遠野の町から見ても、遠野三山で一番目立つ山は六角牛山である。その山から煙が立ち上がれば、人々は当然驚いた事であろう。それでは何故、水神である瀬織津比咩を祀る早池峯山で雨乞い祈願が行われなかったのか?ただ、滝壺に牛馬の骨などを投げ入れ、その水を穢して神を怒らせて雨を降らせる方法があったそうだが、それは最終手段であったそうだ。恐らく、又一の滝でも行われたのかもしれない。しかし、早池峯山頂での千駄木だけは聞いた事が無い。それは標高の違いもあったであろうし、また山としての格の問題もあったのではなかろうか。 |
|
|
■三十八
「籠目紋(ダビデの星)の意味」 住吉大社の様な祭祀形態の六角牛山であるが、六角牛新山宮として建立された六神石神社の神紋は菊紋となる。何故に菊紋なのかはわかってないが、菊紋で思い出すものがある。それは伊勢神宮の石灯篭には、菊紋と籠目紋が刻まれている。籠目紋は、ダビデの星とも呼ばれ、日ソ同祖論を唱える者も多いが、以前に五角形を調べた時、古代の日本では星は丸で表し、尖ったものは魔除けの棘であろうとしている。つまり、それが五芒星であろうが六芒星であろうが、それは星では無く魔除けを意味しているのだろう。 以前、元六神石神社の宮司であった千葉正吾氏が、六角牛とは「むつのうし」と読み「陸奥の牛」を意味するのではないか?と述べていた。確かに「陸奥の牛」は語呂が良いのだが、それでは「陸奥の牛」とは、どういう意味を成すのか?については疑問符が付いたままだった。また神社庁が発行していて、一般には出回っていない書には、六角牛を「おろこしやま」としていた。「お」は「御」である尊称であろうから、「ろこしやま」と呼ぶのが正式なのかと思ったのだが、これは中世以降の読み名であり、山を省けば「ろこし」という意味を成さない山となる。だいたい漢字の「六角牛」とは、いつから始まったのかが皆目見当がつかない。社伝を読む限り、大同年間には既に六角牛となっていたようである。音読みは近世になって広まった読みである事から「ろこし」「ろっこし」もしくは、やはり「むつのうし」と読むのが正しいのだと思える。しかし「角」を「かど」と読んだらどうなるのか?これを六芒星に当て嵌めて考えてみれば、六つの角は「かど」であり「つの」でもある。 現在の由緒によれば、大同7年に六角牛の頂に薬師如来を祀り、それと共に山麓に不動明王、住吉三神を祀ったとあるが、千葉正吾氏の書による年表によれば、坂上田村麻呂により住吉三神と不動明王が祀られたとしている。ここには薬師如来は入っていない。時代的には仏教色が強い時代である筈なので、不動明王は理解できるが、住吉三神もまた本地で表記されるべきである。 1189年、阿曽沼氏の時代に山頂の祭神を遷奉り六角牛新山宮として六角牛山善応寺を創設し祭事を司掌させたとある。その六角牛山善応寺が後に移転し、現在の六神石神社となっているようだ。その第一殿の本地垂迹の本地は、薬師如来とし、垂迹が天照大神としている。そして、第二殿の本地は大日如来とし、その垂迹が宇佐明神としている。通常、大日如来の垂迹が天照大神とされるか、密教系における本地垂迹は、大日如来が本地とされ、その垂迹が不動明王となる。ただ、第二殿の大日如来を天照大神の御心と解すれば、その垂迹が湍津姫である宇佐明神となるのは理解できる。ただ、薬師如来の垂迹を天照大神とする事は、全国の祭祀を見渡しても有り得ないのだ。また、住吉三神は第三殿に祀られ、その本地が弥陀となるのも解せないところ。そして第四殿には、本地が六角牛新山宮奉号住吉であり、その垂迹が神功皇后となっているのは、住吉神と神功皇后の関係から、住吉神に対する巫女としての神功皇后を祀ったという事か。しかし全体的に、この六角牛山善応寺の本地垂迹の祭祀は、理にかなっておらず、おかしいと言わざる負えない。 再び、六と言う数字を考えてみよう。以前、二荒山の山頂から発掘されたものに六つ連なったサナギの鈴があった。それは諏訪での祭祀にも使われる、やはり六つ連なるサナギの鈴だ。その六が意味する事は、干支の子から始まって六番目の巳を意味する為に六つ連なる形とされた。つまり、六と言う数字そのものは、蛇を意図しているという事。それを形作れば、六芒星であり、籠目模様であり、亀甲となる。だが、六芒星は古代日本では星と見做さない為に、候補とはされない。残っているものが、籠目紋様か亀甲紋様となる。 早池峯妙泉寺の末寺であった、土淵の常堅寺の境内の石垣は亀甲の形で組まれている。これが、たまたまなのか、意図的なのかは定かでは無いが、それ以外にも常堅寺には亀を見つける事ができる。陰陽五行において、北には玄武が鎮座している事になる。北に聳える早池峯としての信仰が常堅寺にも伝わっている事から、玄武を意味する亀があったとしても、驚く事ではないだろう。 その玄武とは蛇と亀の結び付きだというのが一般的に知られるが、その玄武は蛇を噛んでいる姿で表すのが正式である。古代中国では、蛇を悪しきものとしていた。疾病という漢字も蛇が体内に入り込んで病気になったという事を意味している。その蛇を噛む亀とは、ある意味魔除けとなるのであった。 また籠とは、龍を竹で囲んで封印したという意味を有する。その籠を竹で編んで、籠目の形を作るのだが、その形が六芒星の様な籠目模様であり、それは魔除けを意味する。つまり、伊勢神宮の灯篭に刻まれている籠目紋様が本来、伊雑宮のものであったというならば、伊雑宮に蛇が封印されている印だと考えても良いだろう。その蛇とは何か?その伊雑宮神職の磯部氏の祖先とされる伊佐波登美命と玉柱屋姫命の二座が祀られていたが、伊雑宮御師である西岡家に伝わる文書では、祭神「玉柱屋姫命」は「玉柱屋姫神天照大神分身在郷」と書かれる。そして同じ箇所に「瀬織津姫神天照大神分身在河」とある事から、伊雑宮には早池峯山や六角牛山で祀られている瀬織津比咩がいるというのがわかった。 籠目紋から亀甲部分を抜き取ると、三角形だけが残る。この三角形だけで家紋としているので有名なのは、北条氏である。その北条氏が江ノ島弁財天に子孫繁栄を祈願した時、美女変身した大蛇が神託を告げ、三枚の鱗を残して消えたことに因むというが、三角形は古代から蛇の鱗を意味している。つまり、籠目紋そのものは、亀と蛇の組み合わせであり、北に鎮座する玄武を意味しているのだ。 六という数字が蛇を意味し、その六つの角もまた蛇を意味する。もう一度、伊勢神宮の石灯篭を見れば、菊紋の下に籠目紋が刻まれている。その伊雑宮の鰹木と千木だが、千木は内削ぎで、鰹木は6本の偶数となっている。俗説ではあるが、女神を祀る場合は偶数の内削ぎだと云われるが、その鰹木が6本であるのも蛇神の女神である事を意味しているように思える。実際に祀られている瀬織津比咩が蛇神である事は、今更言うまでもない。 また、その籠目紋が坂上田村麻呂や義経にも関係する鞍馬寺や、籠神社と眞名井神社にあるのも意味深であると思う。これは後で書き記す事としよう。 この伊勢神宮の別宮である伊雑宮と瀧原宮をまとめて、遥宮(とおのみや)と呼ぶ。伊雑宮もそうだが、瀧原宮にもまた天照大神の荒魂という形で瀬織津比咩が祀られている。つまり、遥宮とは瀬織津比咩を祀る別宮でもあるのだ。これを遠野の地に当て嵌めてみれば、籠目紋を有する伊雑宮を六神石山の六神石神社。そして又一の滝を有する早池峯山と早池峯神社を瀧原宮と考えてみれば、遠野盆地そのものが、伊勢神宮から遥か遠くに祀られた遥宮(遠野宮)とされたのではなかろうかと思える。そして六角が籠目であるのならば、六神石神社の表紋を菊紋とし、裏紋としての籠目紋が六角牛という山の名に隠されたのならば、六角牛山そのものに蛇神である瀬織津比咩が祀られているという事になろう。 実際に、六神石神社の本殿中央などに、蛇の額が飾られ、まさに六角牛山というものは蛇を祀る山であるという事が理解できる。その蛇神が籠目によって封印されたのが、六角牛という山ではなかろうか。そして六角牛の「牛」とは、やはり星と関係するのだろう。 |
|
|
■三十九
ところで関東に大きな影響を与えていた二荒山だが、その二荒山の遥拝所でもある太平山には元々天目一箇神が祀られていたという。ところで「我国間記」によれば、豊受大神は天女として丹波経由で伊勢に祀られたとあるが、その丹波一之宮出雲大神宮の御神体は御陰山であり、その祭神は、三穂津彦大神、別名御蔭大神と三穂津比咩が祀られている。 美穂津比咩で思い出すのが、天女の羽衣で有名な静岡県の三保の松原だ。そこには御穂神社があり、祭神は大己貴命と美穂津比咩となっている。実は、丹波一之宮出雲大神宮に祀られる三穂津彦大神とは、大国主でもあるので、この御穂神社の祭神と同じという事になる。また御穂神社の離宮で、羽衣の松の傍らに鎮座する、駿河湾をのぞむ浜辺にある羽車神社という小さな神社がある。祭神はやはり三穂津彦命と三穂津姫命。 由来によれば三穂津彦命・三穂津姫命が羽車に乗って降臨し、羽車神社を経て御穂神社へ向かったという。天女が単体で飛来したとは別に、羽車にのって夫婦神が降臨したとい伝説だ。豊受大神という天女が飛来した丹波の一之宮に祀られる女神が、三保の松原の天女でもある美穂津比咩であるのは、豊受大神と関係があるのか無いのか。しかし、美穂津比咩とは別に、三穂津彦大神である別名御蔭大神が気になる。 御蔭大神を調べると「播磨国風土記 揖保郡」に「品太の天皇のみ世、出雲の御陰の大神、枚方の里の神尾山に坐して、毎に行く人を遮へ、半は死に、半は生きけり。」同じ「播磨国風土記 揖保郡」の話で、稻種山で大己貴命と少彦名命名が「彼の山は、稻種を置くべし。」と国造りを行っている最中に、同じ大己貴命が神尾山で通る旅人をを殺していたとは、少々おかしい。そこで御陰大神を調べると、京都の舞鶴に彌伽宜神社があり、祭神が天御影大神、誉田別大神とある。「播磨国風土記」が「品太の天皇のみ世」とあったので、応神天皇である誉田別の時代であった為に一緒に祀られたのだろうか。由緒を見ると、下記の様にあった。 彌伽宜神社は通称大森神社と呼ばれ古来近郷によく知られたお宮でありまして、其の御祭神は天御影命亦の名は天目一箇命 と申し神代において刀、斧等諸道具を造り始められた産業の始祖で、皇孫命に仕えて天孫降臨になった三十二神の内の一神にして、創立年代は今から二千六十余年前即ち人皇十代崇神天皇の御宇十一年丹波道主之命の御親祭のなった延喜式内の御社です。 それでは出雲の御陰大神とは、大国主ではなく天目一箇神なのであろうか?その御陰をキーワードとして調べると、下鴨神社の前は御蔭通りと呼び、初め賀茂大神は比叡山西麓の御蔭神社に降臨したと伝えられる。その下鴨神社前の御陰通りを進むと、三上山の麓に鎮座する御上神社へと辿り着く。祭神は天之御陰大神=天目一箇神である。そして、三上山として有名なのは俵藤太のムカデ退治だ。 実は、早池峯の麓で代々早池峯大神を祀る家がある。早池峯山を望むある山の中腹にある奥宮には一の権現とし、早池峯大神を祀っている。 そして、その里宮には早池峯神社と並んで南宮神社が鎮座している。別当の方に聞くと、どちらも早池峯大神に欠かせない神社であるという事だ。その南宮神社は、美濃一之宮の南宮大社からの勧請であると云う。その南宮大社には、やはり金屋子神=天目一箇神が祀られているのだが、そこには何故か平将門伝説も伴っている。先程、御上神社は三上山に関係し、俵藤太のムカデ退治で有名だとしたが、実はその背景に、平将門の乱平定があると云われる。ここまでくれば恐らく、御陰大神を通して琵琶湖、そして二荒山と結び付くのだと思える。 |
|
|
■四十
琵琶湖を挟んで、比叡山と三上山がある。その三上山には、大百足がいた。その大百足は、瀬田唐橋で水を飲む傍ら、付近を通った女性を襲っていた。ある時、俵藤太は龍姫という女性に、それを退治して欲しいと頼まれた。大百足を退治した後、その龍姫に竜宮へ案内された。これは三井寺に伝わる伝説を簡単に説明したものだが、一般的には下記の様に伝わっている。 近江国瀬田の唐橋に大蛇が横たわり、人々は怖れて橋を渡れなくなったが、そこを通りかかった俵藤太は臆する事なく大蛇を踏みつけて渡ってしまった。その夜、美しい娘が藤太を訪ねた。娘は琵琶湖に住む龍神一族の者で、昼間藤太が踏みつけた大蛇はこの娘が姿を変えたものであった。娘は龍神一族が三上山の百足に苦しめられていると訴え、藤太を見込んで百足退治を懇願した。藤太は快諾し、剣と弓矢を携えて三上山に臨むと、山を七巻き半する大百足が現れた。藤太は矢を射たが大百足には通じない。最後の1本の矢に唾をつけ、八幡神に祈念して射るとようやく大百足を退治することができた。藤太は龍神の娘からお礼として、米の尽きることのない俵などの宝物を贈られた。また、龍神の助けで平将門の弱点を見破り、討ち取る事が出来たと云う。 これは二荒山と赤城山の大蛇と大百足の話と対比され語られるが、赤城山が三上山に対応するなら、二荒山はどこであろう?これは恐らく、比叡山では無いかと考える。出雲の御陰大神とは、天目一箇神だと前回述べたが、初め賀茂大神は、比叡山西麓の御蔭神社に降臨したと伝わる。その御陰神社の祭神は、賀茂建角身命荒魂と玉依日売命荒魂となっている。比叡山西麓に降臨した賀茂大神はその後、現在の下鴨神社の場所に祀られるが、その下鴨神社の前は御蔭通り。それを突き進むと、瀬田唐橋を渡って御上神社と繋がる。その御上神社の祭神は、天之御影神となる。しかしもう一柱の神が居た。その一柱の神を、息長水依比売と云う。 御陰繋がりで、かたや比叡山側の御陰神社には、賀茂建角身命と玉依日売命が祀られ、かたや三上山側の御上神社には天之御影と息長水依比売が祀られる。これを、どう捉えるべきであろう。ちなみに、御上神社の名の本来は、御神であろうとされているが、別に水上だとも云われている。つまり三上山も本来は、御神山であり、水上山であったという事。 そして、もう一つ気になるのは、瀬田唐橋が黄泉の国と繋がるという伝説がある事。そして別に、佐久奈谷にもまた黄泉の国と繋がるという伝説がある。「蜻蛉日記」には、佐久奈谷が登場する。訳注には、佐久奈谷とは桜谷の古名であると。「蜻蛉日記」の文中では「いざ、佐久奈谷見には出でむ(さあ、佐久奈谷へ行こう)」と言うと「口引きすごすと聞くぞ(冥土に吸い込まれると聞く。)」と答えるくだりがある。「八雲御抄」によれば「佐久奈谷(桜谷)、是は祓の詞に冥土を伝ふと云へり。」とある。 佐久奈谷には佐久奈度神社が鎮座し、祓戸四神が祀られているのだが、その中の一柱の神は、早池峯の神でもある瀬織津比咩である。ところで曽我一夫「田原籐太秀郷と龍宮」を読むと、何故に遠野に百足退治の話が伝わるのか、何故に二荒山とは別に、琵琶湖に似た様な話が伝わるのか、そして黄泉の国と伊勢とが結び付くという、目から鱗が落ちそうな事が書き記してあった。 |
|
 |
|
|
■四十一
「太平記」に、俵藤太が小男の案内で湖水の中に入っていく描写がある。 「二人共に湖水の波を分けて水中に入ること五十余町あってひとつの楼門あり」 これを曽我一夫「田原籐太秀郷と龍宮」では、ほぼその距離にあたるのは大石の佐久奈度神社であるとしている。「興福寺官務諜疏」には、天智天皇の代に右大臣中臣金連が"大石佐久那太理神"を勧請したとある。佐久奈谷は、桜谷とも呼ばれる。桜谷の古名は佐久奈谷であって、「タニ」を「タリ」とも云う事から佐久那太理は佐久奈谷であるという解釈は成り立つ。また佐久那太理の「太理」は「垂り」でもあり、滝の落ちる様、もしくは水がなだれ落ちる様を意味する。つまり佐久奈度神社が創建される以前から佐久奈谷には、瀧神が祀られていたのだろう。 佐久奈度神社の旧社殿は水没したらしく、佐久奈度神社は現在の地に移されたようだ。その旧社殿の裏手には、やはり滝があったらしく、それこそ「さくなだりに落ちたぎっていた。」という。そして佐久奈度神社の宮司によれば、その滝壺に近付くと地の底に吸い込まれると云われていたそうな。これは「蜻蛉日記」と同じ伝承が続いていたという事だろう。ただその地の底とは、竜宮であったか、黄泉の国であったか。俵藤太は瀬田唐橋から竜宮へと案内された。その竜宮の水門は、佐久奈度神社の裏手にあった滝壺の底であった。その佐久奈度の滝の伝承が伝わっている。 「建武の頃、一人の僧が断食して佐久奈度の滝で七日間の行をした。満願の日、一匹の白龍が滝の中から現れたかと思うと、瀬田川を琵琶湖の方に向けて昇り始めた。不思議に思った僧は、川の西岸沿いにこれを追跡したが、瀬田唐橋のところで見えなくなった。」 つまり、図で示せばA地点の瀬田唐橋から瀬田川の下流、赤丸で印をつけている佐久奈度神社までが、俵藤太の行程であり、瀬田唐橋と佐久奈谷が竜宮及び黄泉国の入り口でもあるのだろう。ただ、黄泉国は「古事記」には記されているが、竜宮という名称そのものの初見は、室町時代成立の「御伽草子」であるという。ただ竜宮という名称は、それ以前にも遡れる可能性があるが、せいぜい平安末期ではなかろうか。しかし、狩野敏次「昔話にみる山の霊力」によれば、竜宮という名称以前に、山などの滝や池が水界と繋がっている伝承も見受けられる事から、既に山に進出した安曇族などの海人族が伝えた伝承に、後から竜宮思想が結び付いたのだろう。 その竜宮思想を持ち歩いた一族に、小野氏がいる。小野氏は古代の氏族である和邇氏系であり、近江国滋賀郡小野村(現在の滋賀県大津市内)周辺を本拠とした。また、山城国愛宕郡小野郷も支配下にあったと考えられている。先に紹介した賀茂大神が初めに降臨した地には御陰神社が鎮座し、その式内社に小野神社がある事からも、小野氏と賀茂大神の関係も深いのだろう。実際、山城国愛宕郡には出雲郷、賀茂郷、小野郷があり、同じ愛宕郡で同居していたのだ。話は違うが、兵庫県の井関三神社に、瀬織津比咩が祀られているのだが、瀬織津比咩を勧請したハ瀬氏は愛宕郡からの勧請であるとされている。しかし、その愛宕郡からは、瀬織津比咩の名前を見つける事が出来ないでいる。可能性が高いのは、やはり賀茂の関係神社であろうと思われる。何故なら、比叡山の麓に属する愛宕郡だが、その比叡山の西側に賀茂建角身命と玉依姫が降臨している。そして、琵琶湖を挟んで対峙する形に、大ムカデの伝承がある三上山の御上神社がある。その構図を二荒山に対比させた場合、二荒山の大蛇が比叡山に重なるのだ。そして「類聚三代格」での官符に当時、左中弁兼攝津守であった小野朝臣野主が、猿女の養田が山城国小野郷と近江国和邇村にあったので、小野臣と和邇部臣が本来猿女を貢すべき氏でないのに、養田の利を貪って猿女を供給しているが、これはよくないから早くやめさして欲しいと訴えたので、小野臣、和邇臣が猿女を貢するのを廃し、猿女公の女一人を縫殿寮に貢進するように命じたとある。 猿女とは古代、神祇官に属し、祭祀などの時に、神楽の舞などの奉仕をした巫女でもある。つまり、神との間を取り持つ存在でもある事から、二荒山の大蛇を助けた猿丸に近い存在であり、その猿丸は正式に小野猿丸という。「日光神戦譚」によれば、小野猿丸の代わりに登場しているのは、唵佐羅麽女という、赤城の沼の竜神であるという。どうも、小野氏の進出により、本来は唵佐羅麽女であったものが、小野猿丸に書き換えられたという事らしいが、その唵佐羅麽女に重なるのが、御上神社に祀られる息長水依比売であろう。これは後で書き記す事とする。更に付け加えれば、創建は不明で再建が17世紀とされる事からそう古くは無いと思うが、その小野氏の膝元に猿丸神社が建立されている。祭神は、二荒山の大蛇を助けた小野猿丸である事から、二荒山の大蛇の伝承は小野氏が伝えたのは確実であろう。 その小野氏で思い出すのは、小野篁だ。小野篁は、井戸から地獄へと自在に出入りしていたという伝説があるが、その小野氏の本拠地には黄泉国の入り口があり、俵藤太のように出入りできたという伝説もまた小野氏によるものであった。 ところで、遠野で俵藤太の系譜に属するのは、阿曽沼氏であった。阿曽沼氏は現在の栃木県の阿蘇郡に住んでいて小山氏と名乗っていたが、後に阿曽沼と改正している。その阿曽沼氏であり小山氏だが、先の佐久奈度神社の南東に「小山屋敷」と呼ばれる丘があるという。そこには八幡神社が鎮座しており、天文九年(1540年)の棟札には「時の地頭 小山源左衛門殿」とあるのだと。瀬織津比咩を祀る佐久奈度神社の地頭が阿曽沼氏である事から、遠野での早池峯祭祀にもかなり阿曽沼氏の信仰が入り込んでいると間違いないであろう。前にも記したように、栃木県の阿蘇郡の雨乞いは、二荒の神の本地である中禅寺湖の水を汲んで来る事が絶対であった事から、栃木県の小山氏は二荒の神を信仰していた。そして、佐久奈度神社の地である大石龍門の地を治めていた小山氏は、早池峯の神と同じ佐久奈度神社の神を信仰していたのだろう。ここで、佐久奈度神社・二荒神社・早池峯神社が、大蛇を中心に繋がってくる。しかし、阿曽沼氏が遠野で建立したと伝わる諏訪神社は、大百足退治ではなく大蛇退治の伝説として伝わる。しかしこれは恐らく、後に遠野を統治した南部氏の改竄によるものだと以前、「蛇と百足(諏訪神社縁起の疑問)」では書いた。また別に、遠野の猿丸として旗屋の縫の大蛇退治の話も、二荒山の大蛇伝説の亜流であり、恐らく南部氏の改竄によるものであったのだろう。他にも上郷町の日出神社の蛇神を平伏させている南部氏の伝承もまた、阿曽沼氏の影響を懸念しての改竄であったと考える。恐らく、早池峯に伝わる伝説もまた南部氏による介入によって、かなり変わったのではなかろうか。それ故に「遠野物語」や、遠野市内の各郷土史に伝わる早池峯伝承も疑ってかかる必要があるだろう。 話が脱線したが、今度はこの佐久奈度神社~瀬田唐橋の地が、伊勢へ結び付く事を書こうと思う。 |
|
|
■四十二
前回書いた様に、異界である黄泉国の入り口は、俵藤太が百足退治をした瀬田橋から佐久奈度神社の鎮座する佐久奈谷(桜谷)の間であった。佐久那太理とは、水の激しく落ち滾る様であり滝を意味する。その佐久那太理の滝壺がまさに黄泉国の入り口であった。そこを佐久奈谷という名が付いたのだが「近江国輿地志略」によれば、桜谷は「佐久奈止社の辺をいふ。此地即佐久奈谷なり。」とされており、桜谷の古名が佐久奈谷となっており、佐久奈度神社の辺りとなっている。「ラ」と「ナ」と読みは違うが、よくある音韻交代によるものらしいが、元々佐久奈谷は桜の名所でもあった為、自然と桜谷となった可能性もある。 春ならで桜谷をば見にゆかじあきともあきぬ道の遠さに 桜谷まことに匂ふころならば道をあきとは思はざらまし にほてるや桜谷より落ちたぎる浪も花さく宇治の網代木 平安後期には、上記の歌が詠われていたようだが、落ち滾る浪と桜花が交じり合う美しい景観であったようだ。その桜の花びらと共に、滝壺に吸い込まれる様は、黄泉国というよりも浄土をイメージしたのだろうか?この桜の花びらも落ち滾る滝壺から白龍が現れた伝説があるが、まさしく瀬織津比咩が滝神であり桜神である例えではなかろうか。 ところで本居宣長の説によれば「佐久那太理」の「サ」は「真」と同じで「真下垂(マクダタリ)」の意であるとしているのだが、昨今スピリチュアル系の瀬織津比咩説に「マグダラのマリア」と結び付けて広めているのはもしかして、この本居宣長説を拡大解釈したものであろうか?とにかく「佐久那太理」の「ダリ」は「谷」であり「垂り」にも通じる事から、落ち滾る滝を意味しているのは明らかである。そして桜もまた水との繋がりが深く、桜は人間の依代ともなり、人間の代わりに穢を受けて吸い込み川へと流す役目があり、穢祓神である瀬織津比咩とも縁が深い樹木である。まさしく、その両方を兼ねた地が佐久奈谷であったのだろう。 ところで佐久奈度神社の鎮座する地を大石龍門の地というのは、佐久奈谷の滝壺から竜宮の門に辿り着く伝承から来ているのもあるが、佐久奈度神社社記には「天瀬織津比呼尊者天照大神荒魂内宮第一の摂神也」と記されているのだが、この「大石」という地名も本来は「忌伊勢(おいせ)」に発した地名であるという。それがいつしか、大石となったらしい。古来から、伊勢神宮を参拝する者は、必ず佐久奈度神社でお祓いを受けるのが常であったようだ。その為か以前は祓戸大神宮と呼ばれ、別に元伊勢と呼んでいたという。 それでは、佐久奈谷の滝壺から龍門を潜って、どこに行くというのか。竜宮思想は平安時代に伝わったものだが、それがすんなりと受け入れられたのは元々常世思想が普及していた事もある。その常世思想と竜宮思想が結び付いた。伊勢と竜宮だが、「日本書紀(垂仁天皇二十五年三月)」に天照大神が登場し、伊勢のイメージを「是の神風の伊勢國は、常世の浪の重浪歸する國なり。」という言葉で表している。常世の「ヨ」とは、生命力を表し豊穣の源泉であるとされている。つまり常世の波が押し寄せる伊勢とは、生命力の溢れる地であるという事だろう。 しかし、常世とは常夜とも書き表す。常夜の波とは東方の海の彼方から押し寄せる波である。伊勢神宮には天照大神という太陽神が祀られている事から、その太陽が昇る海の光を浴びた波と云うイメージを常世の生命力と結び付ける場合が多い。しかし古今東西、満月の夜に魚が岸に寄って産卵し、狼は夜に狩をした。そして人間は、その狼の狩を満月の夜に垣間見、狼を師として仰いだ。生と死の交錯する夜は、月の光があってこその生命力を感じる時間帯であった。その常世国の伊勢国と同じ様な地がある。それが、日高見国であった。 月が東方から昇る意は何かというと「ヒタ」と云われる。常陸は「ヒタミチ」とされ「ヒタカの道」とされる。「日本書紀(景行天皇二十七年二月)」に「東の夷の中に、日高見國有り。」とある。また「常陸国風土記」に「この地は、本、日高見国なり」とあるのは、日高見国は、常陸国の東方を差していた。つまり常陸国とは日高見国の入り口の意でもあった。 「古今和歌集」の注釈に「ひさかたとは、月の異名也。此月、天にあるゆへに突きにひかれて、そらをもひさかたのあめと云へり。」とあるが、「久方(ひさかた)」の「かた」は「区切られた所、県・国」を意味する。そして常陸が「ひた+ち」であり、日高見が「ひた+か」の組み合わせであるが「か」は「場所」を意味する事から「ひさかた」も「ひたか」も同じ意である事がわかる。つまり「ひさ」も「ひた」も月の意であった。 長く日高見国は、伊勢国と似た様に太陽が高く差し込み照らす広く平らな国とも解釈されていたが、「ひた」を月の意に変えれば、日高見の「見」は「望む」でもあるので、常世思想の中に月が東の海辺に接する理想的な地という観念が、日高見ではないかとの説がある。つまり日高とは常世であり、常世辺でもあるという事から、日高見国とは、その理想的な常世辺を望む地の意ともなる。となれば、日高見国も伊勢国も、同じ観念上に立つ国であり、その国を包み込む神もまた同じ可能性はある。その日高見国と伊勢国とに共通する神とは、瀬織津比咩しかないではないか。 とにかく追ってみれば、賀茂の地と琵琶湖畔の大石の地、更に伊勢と二荒山を結び附けている氏族は小野氏であるようだ。ところで常世と似た様な観念に補陀落というものがある。補陀落思想は、仏教色の強くなった二荒山にかかるものだ。その補陀落(ふだらく)が二荒(ふたあら)となった説は、少々苦しいように思える。ここで以前に紹介した歌の一部を、もう一度記そう。 天なるや 弟棚機の 頸がせる 玉の御統の 穴玉はや み谷 二渡らす 味耜高彦根 この歌の中の「み谷 二渡らす」を折口信夫は「三谷を一渡しし、更にあちらから此方へ今一渡しするだけの畏るべき長大な御身を持たせられる」存在と解している。そして「記紀」においてヤマタノオロチの表現を「蔓延於八丘八谷之間」とするのは、蛇を意味するものだとされている事から、この歌の「み谷 二渡らす」は蛇を意味する事から、恐らく「二荒(ふたら)」とは補陀落では無く、蛇を意味しての命名では無かったか。とにかくこの琵琶湖の地から、賀茂・伊勢・二荒、そして日高見へと繋がるようである。 |
|
 |
|
| ■「太平記」 巻第十五 | |
|
■三井寺(みゐでら)合戦並(ならびに)当寺撞鐘(つきがねの)事(こと)付(つけたり)俵藤太(たはらとうだが)事(こと)
東国の勢既(すで)[に]坂本に著(つき)ければ、顕家(あきいへの)卿(きやう)・義貞朝臣、其外(そのほか)宗(むね)との人々、聖女(しやうによ)の彼岸所(ひかんじよ)に会合して、合戦の評定(ひやうぢやう)あり。「何様(いかさま)一両日(いちりやうにち)は馬の足を休(やすめ)てこそ、京都へは寄(よせ)候はめ。」と、顕家(あきいへの)卿(きやう)宣(のたまひ)けるを、大館(おほたち)左馬(さまの)助(すけ)被申けるは、「長途(ちやうど)に疲れたる馬を一日も休(やすめ)候はゞ中々(なかなか)血下(さがつ)て四五日は物(もの)の用に不可立。其(その)上(うへ)此(この)勢(せい)坂本へ著(つき)たりと、敵縦(たとひ)聞及共(ききおよぶとも)、頓(やが)て可寄とはよも思寄(おもひより)候はじ。軍(いくさ)は起不意必(かならず)敵を拉(とりひしぐ)習(ならひ)也(なり)。只今夜(こんや)の中(うち)に志賀(しが)・唐崎(からさき)の辺(へん)迄打寄(うちよせ)て、未明(びめい)に三井寺(みゐでら)へ押寄せ、四方(しはう)より時(とき)を作(つくつ)て責入(せめいる)程ならば、御方(みかた)治定(ぢぢやう)の勝軍(かちいくさ)とこそ存(ぞんじ)候へ。」と被申ければ、義貞朝臣も楠(くすのき)判官(はうぐわん)正成(まさしげ)も、「此義(このぎ)誠(まこと)に可然候。」と被同て、頓(やが)て諸大将(しよだいしやう)へぞ被触ける。 今上(いまのぼ)りの千葉勢是(これ)を聞(きい)て、まだ宵(よひ)より千(せん)余騎(よき)にて志賀の里に陣取る。大館(おほたち)左馬(さまの)助(すけ)・額田(ぬかだ)・羽(はね)川六千(ろくせん)余騎(よき)にて、夜半(やはん)に坂本を立(たつ)て、唐崎の浜に陣を取る。戸津(とつ)・比叡辻(へいつじ)・和爾(わに)・堅田(かたた)の者共(ものども)は、小船七百(しちひやく)余艘(よさう)に取乗(とりのつ)て、澳(おき)に浮(うかめ)て明(あく)るを待(まつ)。山門の大衆(だいしゆ)は、二万(にまん)余人(よにん)、大略(たいりやく)徒立(かちだち)なりければ、如意越(によいごえ)を搦手(からめて)に廻(まは)り、時の声を揚(あ)げば同時に落(おと)し合(あはせ)んと、鳴(なり)を静めて待明(まちあか)す。 去(さる)程(ほど)に坂本に大勢(おほぜい)の著(つき)たる形勢(ありさま)、船の往反(わうへん)に見へて震(おびたた)しかりければ、三井寺(みゐでら)の大将細川(ほそかはの)卿(きやうの)律師(りつし)定禅(ぢやうぜん)、高(かうの)大和(やまとの)守(かみ)が方より、京都へ使を馳(はせ)て、「東国の大勢坂本に著(つき)て、明日可寄由其聞(そのきこ)へ候。急(いそぎ)御勢(おんせい)を被添候へ。」と、三度(さんど)迄被申たりけれ共(ども)、「関東(くわんとう)より何(なに)勢(せい)が其(それ)程迄多(おほく)は上(のぼ)るべきぞ。勢(せい)は大略(たいりやく)宇都宮(うつのみや)紀清(きせい)の両党の者とこそ聞(きこ)ゆれ。其(その)勢(せい)縦(たとひ)誤(あやまつ)て坂本へ著(つき)たりとも、宇都宮(うつのみや)京に在(あり)と聞(きこ)へなば、頓(やが)て主の許(もと)へこそ馳来(はせきたら)んずらん。」とて、将軍事ともし給はざりければ、三井寺(みゐでら)へは勢の一騎をも不被添。 |
|
|
夜既(すで)に明方(あけがた)に成(なり)しかば源(げん)中納言(ぢゆうなごん)顕家(あきいへの)卿(きやう)二万(にまん)余騎(よき)、新田(につた)左兵衛(さひやうゑの)督(かみ)義貞三万(さんまん)余騎(よき)、脇屋(わきや)・堀口・額田(ぬかだ)・鳥山(とりやま)の勢一万五千(いちまんごせん)余騎(よき)、志賀(しが)・唐崎の浜路(はまぢ)に駒を進(すすめ)て押寄(おしよせ)て、後陣(ごぢん)遅(おそ)しとぞ待(まち)ける。前陣の勢先(まづ)大津(おほつ)の西の浦、松本の宿(しゆく)に火をかけて時の声を揚(あ)ぐ。三井寺(みゐでら)の勢共(せいども)、兼(かね)てより用意(ようい)したる事なれば、南院(なんゐん)の坂口に下(お)り合(あつ)て、散々(さんざん)に射る。一番に千葉介(ちばのすけ)千(せん)余騎(よき)にて推(おし)寄せ、一二の木戸(きど)打破(うちやぶ)り、城の中へ切(きつ)て入り、三方(さんぱう)に敵を受(うけ)て、半時許(はんじばかり)闘(たたか)ふたり。 細川(ほそかはの)卿(きやうの)律師(りつし)定禅(ぢやうぜん)が横合(よこあひ)に懸(かか)りける四国の勢六千(ろくせん)余騎(よき)に被取篭て、千葉(ちばの)新介(しんすけ)矢庭(やには)に被打にければ、其(その)手(て)の兵(つはもの)百(ひやく)余騎(よき)に、当(たう)の敵を討(うた)んと懸入(かけいり)々々(かけいり)戦(たたかう)て、百五十騎(ひやくごじつき)被討にければ、後陣に譲(ゆづつ)て引退(ひきしりぞ)く。二番に顕家(あきいへの)卿(きやう)二万(にまん)余騎(よき)にて、入替(いれか)へ乱合(みだれあつ)て責(せめ)戦ふ。其(その)勢(せい)一軍(ひといくさ)して馬の足を休(やすむ)れば、三番に結城(ゆふき)上野入道・伊達(だて)・信夫(しのぶ)の者共(ものども)五千(ごせん)余騎(よき)入替(いれかはつ)て面(おもて)も不振責(せめ)戦ふ。其(その)勢(せい)三百(さんびやく)余騎(よき)被討て引退(ひきしりぞき)ければ、敵勝(かつ)に乗(のつ)て、六万(ろくまん)余騎(よき)を二手(ふたて)に分(わけ)て、浜面(はまおもて)へぞ打(うつ)て出(いで)たりける。新田左衛門(さゑもんの)督(かみ)是(これ)を見て、三万(さんまん)余騎(よき)を一手(ひとて)に合(あは)せて、利兵(りへい)堅(かたき)を破(やぶつ)て被進たり。細川雖大勢と、北は大津の在家(ざいけ)まで焼(やく)る最中(さいちゆう)なれば通(とほ)り不得。 |
|
|
東は湖海(こかい)なれば、水深(ふかう)して廻(まはら)んとするに便(たよ)りなし。僅(わづか)に半町にもたらぬ細道を只一順(じゆん)に前(すす)まんとすれば、和爾(わに)・堅田(かたた)の者共(ものども)が渚(なぎさ)に舟を漕並(こぎならべ)て射ける横矢(よこや)に被防て、懸引自在(かけひきじざい)にも無(なか)りけり。官軍(くわんぐん)是(これ)に力を得て、透間(すきま)もなく懸(かか)りける間、細川が六万(ろくまん)余騎(よき)の勢五百(ごひやく)余騎(よき)被打て、三井寺(みゐでら)へぞ引返(ひつかへ)しける。額田(ぬかだ)・堀口・江田・大館(おほたち)七百(しちひやく)余騎(よき)にて、逃(にぐ)る敵に追(おつ)すがふて、城の中へ入(いら)んとしける処を、三井寺(みゐでらの)衆徒五百(ごひやく)余人(よにん)関(きど)の口に下(お)り塞(ふさがつ)て、命を捨(すて)闘(たたかひ)ける間、寄手(よせて)の勢百(ひやく)余人(よにん)堀の際(きは)にて被討ければ、後陣(ごぢん)を待(まつ)て不進得。其(その)間に城中より木戸を下(おろ)して堀の橋を引(ひき)けり。 義助是(これ)を見て、「無云甲斐者共(ものども)の作法(さほう)哉(かな)。僅(わづか)の木戸(きど)一(ひとつ)に被支て是(これ)程の小城(こしろ)を責(せめ)落さずと云(いふ)事(こと)やある。栗生(くりふ)・篠塚(しのづか)はなきか。あの木戸取(とつ)て引破(やぶ)れ。畑(はた)・亘理(わたり)はなきか。切(きつ)て入れ。」とぞ被下知ける。栗生・篠塚是(これ)を聞(きい)て馬より飛(とん)で下(お)り、木戸を引破(やぶ)らんと走寄(はしりよつ)て見れば、屏(へい)の前に深さ二丈余(あま)りの堀をほりて、両方の岸屏風(びやうぶ)を立(たて)たるが如くなるに、橋の板をば皆刎迦(はねはづ)して、橋桁許(はしげたばかり)ぞ立(たち)たりける。二人(ににん)の者共(ものども)如何(いかに)して可渡と左右をきつと見(みる)処に、傍(そば)なる塚の上(うへ)に、面(おもて)三丈許(ばかり)有(あつ)て、長さ五六丈もあるらんと覚へたりける大率都婆(おほそとば)二本あり。爰(ここ)にこそ究竟(くきやう)の橋板(はしいた)は有(あり)けれ。 |
|
|
率都婆(そとば)を立(たつ)るも、橋を渡すも、功徳(くどく)は同じ事なるべし。いざや是(これ)を取(とつ)て渡さんと云侭(いふまま)に、二人(ににん)の者共(ものども)走寄(はしりよつ)て、小脇(こわき)に挟(はさみ)てゑいやつと抜く。土の底五六尺掘入(ほりいれ)たる大木なれば、傍(あた)りの土一二尺(いちにしやく)が程くわつと崩(くづれ)て、率都婆(そとば)は無念抜(ぬけ)にけり。彼等(かれら)二人(ににん)、二本の率都婆(そとば)を軽々(かるかる)と打(うち)かたげ、堀のはたに突立(つきたて)て、先(まづ)自歎(じたん)をこそしたりけれ。「異国には烏獲(をうくわく)・樊■(はんくわい)、吾朝(わがてう)には和泉(いづみの)小次郎・浅井那(あさゐな)三郎、是(これ)皆世に双(なら)びなき大力(だいぢから)と聞ゆれども、我等が力に幾程(いくほど)かまさるべき。云(いふ)所傍若無人(ばうじやくぶじん)也(なり)と思(おもは)ん人は、寄合(よせあつ)て力根(ちからね)の程を御覧(ごらん)ぜよ。」と云侭(いふまま)に、二本の率都婆(そとば)を同じ様(やう)に、向(むかひ)の岸へぞ倒し懸(かけ)たりける。 率都婆(そとば)の面(おもて)平(たひらか)にして、二本相並(あひならべ)たれば宛(あたか)四条(しでう)・五条の橋の如し。爰(ここ)に畑(はた)六郎左衛門(ろくらうざゑもん)・亘理(わたり)新左衛門(しんざゑもん)二人(ににん)橋の爪(つめ)に有(あり)けるが、「御辺達(ごへんたち)は橋渡(わた)しの判官に成り給へ。我等(われら)は合戦をせん。」と戯(たはむ)れて、二人(ににん)共橋の上をさら/゛\と走(はしり)渡り、堀の上なる逆木(さかもぎ)共(ども)取(とつ)て引除(ひきのけ)、各(おのおの)木戸(きど)の脇にぞ著(つい)たりける。是(これ)を防ぎける兵共(つはものども)、三方(さんぱう)の土矢間(つちさま)より鑓(やり)・長刀を差出(さしいだ)して散々(さんざん)に突(つき)けるを、亘理新左衛門(しんざゑもん)、十六(じふろく)迄奪(うばう)てぞ捨(すて)たりける。 畑六郎左衛門(ろくらうざゑもん)是(これ)を見て、「のけや亘理殿、其屏(そのへい)引破(やぶつ)て心安く人々に合戦せさせん。」と云侭(いふまま)に、走懸(はしりかか)り、右の足を揚(あげ)て、木戸(きど)の関(くわん)の木の辺(へん)を、二蹈三蹈(ふたふみみふみ)ぞ蹈(ふん)だりける。余(あまり)に強く被蹈て、二筋(ふたすぢ)渡せる八九寸の貫(くわん)の木、中より折(をれ)て、木戸の扉も屏柱(へいはしら)も、同(おなじ)くどうど倒れければ、防がんとする兵五百(ごひやく)余人(よにん)、四方(しはう)に散(ちつ)て颯(さつ)とひく。一の木戸已(すで)に破(やぶれ)ければ、新田(につた)の三万(さんまん)余騎(よき)の勢、城の中へ懸入(かけいつ)て、先(まづ)合図(あひず)の火をぞ揚(あげ)たりける。是(これ)を見て山門の大衆(だいしゆ)二万(にまん)余人(よにん)、如意越(によいごえ)より落合(おちあつ)て、則(すなはち)院々(ゐんゐん)谷々(たにだに)へ乱(みだれ)入り、堂舎・仏閣に火を懸(かけ)て呼(をめ)き叫(さけん)でぞ責(せめ)たりける。 |
|
|
猛火(みやうくわ)東西より吹懸(ふきかけ)て、敵南北に充満(みちみち)たれば、今は叶(かなは)じとや思(おもひ)けん、三井寺(みゐでら)の衆徒共(しゆとども)、或(あるひ)は金堂(こんだう)に走入(はしりいつ)て猛火(みやうくわ)の中に腹を切(きつ)て臥(ふし)、或(あるひ)は聖教(しやうげう)を抱(いだい)て幽谷(いうこく)に倒れ転(まろ)ぶ。多年止住(しぢゆう)の案内者(あんないしや)だにも、時に取(とつ)ては行方(ゆきかた)を失ふ。況乎(いはんや)四国・西国の兵共(つはものども)、方角もしらぬ烟(けぶり)の中に、目をも不見上迷ひければ、只此彼(ここかし)この木の下岩(いは)の陰(かげ)に疲れて、自害をするより外(ほか)の事は無(なか)りけり。されば半日許(ばかり)の合戦に、大津・松本・三井寺(みゐでらの)内に被討たる敵を数(かぞふ)るに七千三百(しちせんさんびやく)余人(よにん)也(なり)。抑(そもそも)金堂(こんだう)の本尊(ほんぞん)は、生身(しやうしん)の弥勒(みろく)にて渡(わたら)せ給へば、角(かく)ては如何(いかが)とて或(ある)衆徒御首許(みくしばかり)を取(とつ)て、薮(やぶ)の中に隠(かく)し置(おき)たりけるが、多(おほく)被討たる兵(つはもの)の首共(くびども)の中に交(まじは)りて、切目(きりめ)に血の付(つき)たりけるを見て、山法師(やまほふし)や仕(し)たりけん、大札(おほふだ)を立(たて)て、一首(いつしゆ)の歌に事書(ことがき)を書副(かきそへ)たりける。 「建武二年の春(はる)の比(ころ)、何(なん)とやらん、事の騒(さわが)しき様に聞へ侍りしかば、早(はや)三会(さんゑ)の暁(あかつき)に成(なり)ぬるやらん。いでさらば八相成道(はつしやうじやうだう)して、説法利生(せつほふりしやう)せんと思ひて、金堂(こんだう)の方(かた)へ立出(たちいで)たれば、業火(ごふくわ)盛(さかん)に燃(もえ)て修羅(しゆら)の闘諍(とうじやう)四方(しはう)に聞ゆ。こは何事(なにこと)かと思ひ分(わ)く方も無(なく)て居たるに、仏地坊(ぶつちばう)の某(それがし)とやらん、堂内(だうのうち)に走(はしり)入り、所以(ゆゑ)もなく、鋸(のこぎり)を以て我が首(くび)を切(きり)し間、阿逸多(あいつた)といへ共(ども)不叶、堪兼(たへかね)たりし悲みの中(うち)に思ひつゞけて侍(はんべ)りし。山を我(わが)敵(てき)とはいかで思ひけん寺法師(てらほふし)にぞ頚(くび)を切(きら)るゝ。」前々(せんぜん)炎上の時は、寺門の衆徒是(これ)を一大事(いちだいじ)にして隠しける九乳(きうにゆう)の鳧鐘(ふしよう)も取(とる)人なければ、空(むなし)く焼(やけ)て地に落(おち)たり。 |
|
|
此鐘(このかね)と申(まうす)は、昔竜宮城(りゆうぐうじやう)より伝りたる鐘也(なり)。其(その)故は承平(しようへい)の比(ころ)俵藤太秀郷(たはらとうだひでさと)と云(いふ)者有(あり)けり。或(ある)時此秀郷(このひでさと)只一人勢多(せた)の橋を渡(わたり)けるに、長(たけ)二十丈(にじふぢやう)許(ばかり)なる大蛇(だいじや)、橋の上に横(よこたはつ)て伏(ふし)たり。両の眼(まなこ)は耀(かかやい)て、天に二(ふたつ)の日を卦(かけ)たるが如(ごとし)、双(なら)べる角(つの)尖(するど)にして、冬枯(ふゆかれ)の森の梢に不異。鉄(くろがね)の牙(きば)上下に生(おひ)ちがふて、紅(くれなゐ)の舌炎(ほのほ)を吐(はく)かと怪(あやし)まる。若(もし)尋常(よのつね)の人是(これ)を見ば、目もくれ魂(たましひ)消(きえ)て則(すなはち)地にも倒(たふれ)つべし。されども秀郷天下第一(だいいち)の大剛(だいかう)の者也(なり)ければ更に一念も不動ぜして、彼大蛇(かのだいじや)の背(せなか)の上を荒(あらら)かに蹈(ふん)で閑(しづか)に上をぞ越(こえ)たりける。 然(しか)れ共(ども)大蛇も敢(あへ)て不驚、秀郷も後(うし)ろを不顧して遥(はるか)に行隔(ゆきへだ)たりける処に、怪(あやし)げなる小男(こをとこ)一人忽然(こつぜん)として秀郷が前に来(きたつ)て云(いひ)けるは、「我(われ)此(この)橋の下に住(すむ)事(こと)已(すで)に二千(にせん)余年(よねん)也(なり)。貴賎往来(きせんわうらい)の人を量(はか)り見るに、今御辺(ごへん)程(ほど)に剛(かう)なる人を未(いまだ)見ず。我(われ)に年来(としごろ)地を争ふ敵有(あつ)て、動(ややもすれ)ば彼(かれ)が為に被悩。可然は御辺(ごへん)我(わが)敵を討(うつ)てたび候へ。」と、懇(ねんごろ)にこそ語(かたら)ひけれ。秀郷一義(いちぎ)も不謂、「子細有(ある)まじ。」と領状(りやうじやう)して、則(すなはち)此(この)男を前(さき)に立てゝ又勢多(せた)の方(かた)へぞ帰(かへり)ける。 二人(ににん)共(とも)に湖水(こすゐ)の波を分(わけ)て、水中に入(いる)事(こと)五十(ごじふ)余町(よちやう)有(あつ)て一(ひとつ)の楼門(ろうもん)あり。開(ひらい)て内へ入るに、瑠璃(るり)の沙(いさご)厚く玉の甃(いしだたみ)暖(あたたか)にして、落花自(おのづから)繽紛(ひんふん)たり。朱楼紫殿玉欄干(たまのらんかん)、金(こがね)を鐺(こじり)にし銀(しろかね)を柱とせり。其(その)壮観奇麗、未曾(いまだかつ)て目にも不見耳にも聞(きか)ざりし所也(なり)。此(この)怪しげなりつる男、先(まづ)内へ入(いつ)て、須臾(しゆゆ)の間に衣冠(いくわん)を正(ただ)しくして、秀郷を客位(きやくゐ)に請(しやう)ず。左右侍衛官(しゑのくわん)前後花の装(よそほひ)善(ぜん)尽(つく)し美(び)尽(つく)せり。酒宴数刻(すごく)に及(およん)で夜既(すで)に深(ふけ)ければ、敵の可寄程(ほど)に成(なり)ぬと周章(あわて)騒ぐ。秀郷は一生涯が間身を放(はな)たで持(もち)たりける五人(ごにん)張(ばり)にせき弦(つる)懸(かけ)て噛(く)ひ湿(しめ)し、三年竹(さんねんだけ)の節近(ふしぢか)なるを十五束(じふごそく)二伏(ふたつぶせ)に拵(こしら)へて、鏃(やじり)の中子(なかご)を筈本(はずもと)迄打(うち)どほしにしたる矢、只三筋(さんすぢ)を手挟(たばさみ)て、今や/\とぞ待(まち)たりける。夜半(やはん)過(すぐ)る程(ほど)に雨風一通(ひととほ)り過(すぎ)て、電火の激(げき)する事隙(ひま)なし。 |
|
|
暫有(しばらくあつ)て比良(ひら)の高峯(たかね)の方より、焼松(たいまつ)二三千(にさんぜん)がほど二行に燃(もえ)て、中に嶋の如(ごとく)なる物、此龍宮城(このりゆうぐうじやう)を指(さし)てぞ近付(ちかづき)ける。事の体(てい)を能々(よくよく)見(みる)に、二行にとぼせる焼松(たいまつ)は皆己(おのれ)が左右の手にともしたりと見へたり。あはれ是(これ)は百足蜈蚣(むかで)の化(ばけ)たるよと心得て、矢比(ころ)近く成(なり)ければ、件(くだん)の五人(ごにん)張(ばり)に十五束(じふごそく)三伏(みつぶせ)忘るゝ許(ばかり)引(ひき)しぼりて、眉間(みけん)の真中(まんなか)をぞ射たりける。其手答(そのてごたへ)鉄(くろがね)を射る様(やう)に聞へて、筈(はず)を返してぞ不立ける。秀郷一(いち)の矢を射損(そんじ)て、不安思ひければ、二の矢を番(つがう)て、一分も不違態(わざと)前の矢所(やつぼ)をぞ射たりける。此(この)矢も又前の如くに躍(をど)り返(かへり)て、是(これ)も身に不立けり。 秀郷二(ふた)つの矢をば皆射損(そん)じつ、憑(たのむ)所は矢一筋(ひとすぢ)也(なり)。如何せんと思(おもひ)けるが、屹(きつ)と案じ出(いだ)したる事有(あつ)て、此度(このたび)射んとしける矢さきに、唾(つばき)を吐懸(はきかけ)て、又同矢所(おなじやつぼ)をぞ射たりける。此(この)矢に毒を塗(ぬり)たる故(ゆゑ)にや依(より)けん、又同(おなじ)矢坪(つぼ)を三度(さんど)迄射たる故(ゆゑ)にや依(より)けん、此(この)矢眉間(みけん)のたゞ中を徹(とほ)りて喉(のんど)の下迄羽(は)ぶくら責(せめ)てぞ立(たち)たりける。二三千(にさんぜん)見へつる焼松(たいまつ)も、光忽(たちまち)に消(きえ)て、島の如(ごとく)に有(あり)つる物、倒るゝ音(おと)大地を響(ひび)かせり。立寄(より)て是(これ)を見るに、果して百足の蜈蚣(むかで)也(なり)。竜神(りゆうじん)は是(これ)を悦(よろこび)て、秀郷(ひでさと)を様々(さまざま)にもてなしけるに、太刀一振(ひとふり)・巻絹(まきぎぬ)一(ひとつ)・鎧一領(いちりやう)・頚結(ゆう)たる俵(たはら)一(ひとつ)・赤銅(しやくどう)の撞鐘(つきがね)一口(いつく)を与(あたへ)て、「御辺(ごへん)の門葉(もんえふ)に、必(かならず)将軍になる人多かるべし。」とぞ示しける。 |
|
|
秀郷(ひでさと)都に帰(かへつ)て後此(この)絹を切(きつ)てつかふに、更に尽(つくる)事(こと)なし。俵は中なる納物(いれもの)を、取(とれ)ども/\尽(つき)ざりける間、財宝倉(くら)に満(みち)て衣裳(いしやう)身に余れり。故(ゆゑ)に其(その)名を俵藤太(たはらとうだ)とは云(いひ)ける也(なり)。是(これ)は産業(さんげふ)の財(たか)らなればとて是(これ)を倉廩(さうりん)に収む。鐘は梵砌(ぼんぜい)の物なればとて三井寺(みゐでら)へ是(これ)をたてまつる。文保(ぶんほう)二年三井寺(みゐでら)炎上の時、此(この)鐘を山門へ取寄(とりよせ)て、朝夕是(これ)を撞(つき)けるに、敢(あへ)てすこしも鳴(なら)ざりける間、山法師(やまほふし)共(ども)、「悪(にく)し、其義(そのぎ)ならば鳴様(なるやう)に撞(つけ)。」とて、鐘木(しもく)を大きに拵(こしら)へて、二三十人(にさんじふにん)立懸(たちかか)りて、破(われ)よとぞ撞(つき)たりける。 其(その)時此(この)鐘海鯨(くぢら)の吼(ほゆ)る声を出(いだ)して、「三井寺(みゐでら)へゆかふ。」とぞ鳴(ない)たりける。山徒(さんと)弥(いよいよ)是(これ)を悪(にく)みて、無動寺(むどうじ)の上よりして数千丈(すせんぢやう)高き岩の上をころばかしたりける間、此(この)鐘微塵(みぢん)に砕(くだけ)にけり。今は何の用にか可立とて、其(その)われを取集(とりあつめ)て本寺へぞ送りける。或時(あるとき)一尺(いつしやく)許(ばかり)なる小蛇(こへび)来(きたつ)て、此(この)鐘を尾を以[て]扣(たた)きたりけるが、一夜(いちや)の内に又本(もと)の鐘に成(なつ)て、疵(きず)つける所一(ひとつ)も無(なか)りけり。されば今に至るまで、三井寺(みゐでら)に有(あつ)て此(この)鐘の声を聞(きく)人、無明長夜(むみやうぢやうや)の夢を驚かして慈尊(じそん)出世の暁(あかつき)を待(まつ)。末代(まつだい)の不思議(ふしぎ)、奇特(きどく)の事共(ことども)也(なり)。 |
|
 |
|