�V����1�E�V�����_��2�E�v�g���}�C�I�X�̓V����3�E�V�����G�L4�E�E�E�@
�Ñ�̉F�����E�����̉F�����E���{�l�̉F����1�E���{�l�̉F����2�E�u�����v�̗��j
�@
�G�w�̐��E�E��l
�@�@�@


|
�n����1�E�n����2�E�R�y���j�N�X�̒n����3�E�n����4�E�F���E�n����5�E�n����6�E�R�y���j�N�X�̒n����7�E�K�����I�̐��U�E�n�����̔��Q�E�E�E�@ �V����1�E�V�����_��2�E�v�g���}�C�I�X�̓V����3�E�V�����G�L4�E�E�E�@ �Ñ�̉F�����E�����̉F�����E���{�l�̉F����1�E���{�l�̉F����2�E�u�����v�̗��j �@ |
|
|
�G�w�̐��E�E��l �@�@�@  |
| �������H�E�a�� | |
|
|
|
|
|
|
|
Photo. Harada |
|
| �@ | |
| ���n���� 1 | |
| �n���������Ă���A�Ƃ����w���̂��ƁB�V�����ɑ`����w���ł���A�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X���������B���z���S���Ƃ��������A�n���������Ă��邩�ǂ����Ƒ��z���F���̒��S�ɂ��邩�ǂ����͌����ɂ͈قȂ�T�O�ł���A�n�����́uHeliocentrism�v�̖��Ƃ��ĕs�K���Ƃ̎w�E������B | |
|
�����j
�@ ���Ñ�̒n���� �@ �Â��A���X�g�e���X�̎��ォ��R�y���j�N�X�̓o�ꂷ��16���I�܂ŁA�n���͉F���̒��S�ɂ���A�܂��̓V�̂������Ă���Ƃ����V�������M�����Ă����B �@ �������A�R�y���j�N�X�ȑO�ɂ��A�n���������Ă���ƍl�����҂͂����B�L���ȂƂ���ł̓s�����I�X�ŁA�ނ͉F���̒��S�ɒ��S������A�n���⑾�z���܂߂Ă��ׂĂ̓V�̂����̎�������]����ƍl�����B�܂��A�v���g�����P�̃C�f�A�ł��鑾�z���F���̒��S�ɂ���ƍl���Ă����B�����ă��I�i���h�E�_�E���B���`���܂��n�����Ɋւ�����e�����X�^�[��e�ɋL���Ă���B �@ ���Ɍ��o���Ă����̂́A�C�I�j�A����̍Ō�̃A���X�^���R�X�ł���B�ނ́A�n���͎��]���Ă���A���z�����S�ɂ���A5�̘f�������̎�������]����Ƃ��������������B�ނ̐����D��Ă���̂́A���z�𒆐S�Ƃ��āA�f���̔z�u���͂�����Ɗ��S�Ɏ��������Ƃ��B����͒P�Ȃ�u���z���S���v�Ƃ����v�������z�������̂ł���B�قƂ�ǁu�Ȋw�v�ƌĂԐ����ɒB���Ă���B�I���O280�N�ɂ��̐����������Ĉȗ��A�R�y���j�N�X���o�ꂷ��܂ŁA1800�N���̊ԁA�l�ނ̓A���X�^���R�X�̐����ɒB���邱�Ƃ͂Ȃ������B �@ �L���Ӗ��ł͂������n����(���z���S��)�ɓ���B �@ ���V�����̗D�� �@ 2���I�ɂ̓N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X���V������̌n�����A�Ȍ�R�y���j�N�X���o�ꂷ��16���I�܂ł��ꂪ�x�����ꂽ�B�v�g���}�C�I�X�̑̌n�Ȃ�A�����̌덷�͂����Ă��f���̓������v�Z���邱�Ƃ��ł������A�n���͎~�܂��Ă���̂�����A�������c����邱�Ƃ��l�����ɍςB�������ē���I�Ȑ����Ɋւ������A�V����������Γ��ɕs���R�͂Ȃ��Ȃ����B �@ �Ƃ͂����A�������ȂƂ���͑��݂����B�Ⴆ�� �@ 5�̘f���̂��ׂĂ̋O���v�Z�ɁA�K���u1�N�v�Ƃ����P�ʂ��o�Ă��� �@ �f���̏��������̂��̏��ł��邩�Ƃ��������̒��s���� �@ �n�����猩�����A�ΐ��̊�ȓ�����������Â炢 �@ �f���̈ʒu�\��ɂ��덷������ �@ �Ȃǂ���������B�������A�����̌��ۂ�������A�����Șf���̈ʒu�\����o����V���͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B �@ �܂��A���[���b�p�ł͌Ñ�M���V�A����ȍ~�Ȋw�͒���A�����[�}�鍑�ŖS��͈Í�������}���邱�ƂɂȂ�B��q����悤�Ƀ��[���b�p�ɂ����ĉȊw���Ăї�������̂̓��l�b�T���X�ȍ~�ł���B �@ �����������R�ŁA�Ȋw�I�ȓ�_���܂݂Ȃ�����A16���I�Ɏ���܂ł����ƁA�V�����͎x�����ꂽ�B �@ ����q�C���� �@ �V�����̑̌n�͒��炭�M�����Ă������A�₪�Ă��̂��܂��܂Ȃق���т����m�����Ă����B �@ ��q�C����ȑO�A�q�C�͉��ݍq�C�ł��藤�n��������ꏊ�����D���^�q���Ȃ������B�����ڈ�̂Ȃ���C���ł͍s���悪�����炸�A�q�s�ł��Ȃ������B���j�Ղ̓o�ꂪ������\�ɂ��A���ʎ��Ɛ��m�Ȑ��}������Ή��m�ł������̈ܓx�����m�ɔc���ł���悤�ɂȂ����̂ł���B�����������̐��\�ɂ͖�肪���Ȃ肠�����B���ɘf���̈ʒu�͐��x�P�ʂł̌덷����ɂ������B �@ ����ɂ���1��肪�����������B1�N�̒������A�����g�p����Ă��������E�X���1�N���킸���ɒZ�������̂ł���B���̌��ʁA��̏�̋G�߂Ǝ��ۂ̋G�߂ɖ�10���̂��ꂪ�����Ă����B�L���X�g���ł͏t���̓����ړ��j�Փ��̌v�Z����ɂȂ��Ă���A10��������Ă���͖̂�肪�������B���̖��̓��W���[�E�x�[�R���ɂ���Ē�N����Ă������A1�N�̐��m�Ȓ����������炸��300�N�ԕ��u����Ă����B �@ �����g���Ă���(�����āA���\�|�^�~�A���ォ�猻��Ɏ���܂ł����{�I�ɂ͕ς��Ȃ�)1�N(��A�N)�̒�`�́A���_�܂��͎��_���玟�̓������_�܂��͎��_�܂ł̎��Ԃł���B�������A16���I�����ɐM�����Ă����v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł́A1�N�Ƃ����l�͑��̓V���w�I�Ȓl����͌Ǘ������Ɨ��̗ʂŁA���z�̈ʒu�𐔏\�N���琔�S�N�ȏォ���đ��肷��ȊO�ɁA1�N�̒l�����肷����@���Ȃ������B�N�[���ɂ��A���̊ϑ��ɂ͑�ςȍ�������A�������16���I�ȑO�̓V���w�҂�������ɔY�܂��邱�ƂɂȂ����B �@ ���R�y���j�N�X�̓o�� �@ �J�g���b�N����̎i�Ղł������R�y���j�N�X�́A���̌덷�ɒ��ڂ����B�ނ͒n������V�v���g����`�̑��z�M�Ƃ��đ����Ă����ƌ����A���̂悤�ȏ@���I���R����A�ނɂƂ��Đ��m�łȂ�1�N�̒������g��ꑱ���邱�Ƃ͏d��Ȗ�肾�����B�R�y���j�N�X�̓A���X�^���R�X�̌�����m���Ă���A���z�𒆐S�ɒu���A�n�������̎����1�N�����Č��]������̂Ƃ��āA1�P���N��365.25671���A1��A�N��365.2425���ƎZ�o�����B1�N�̒l��2��ނ���̂́A1�N�̊�z�̈ʒu�ɂƂ邩�A���̍P���̈ʒu�ɂƂ邩�̈Ⴂ�ɂ��B �@ �R�y���j�N�X��1543�N�̖v���钼�O�A�v�����܂Ƃ߂������w�V�̂̉�]�ɂ��āx�����s�����B�����ł͒n�����̑�����@��v�Z���@�����ׂċL�����B�������ĒN�ł��������@��1�N�̒�����A�e�f���̌��]���a�𑪒肵�Ȃ�����悤�ɂ����B�R�y���j�N�X���n�����̑n�n�҂Ƃ����̂́A���̂悤�Ɍ����s�Ȃ������߂ł���B �@ �܂����̋Ɛтɂ��āA�K�����I�E�K�����C����u���z���S�����������v�ƕ]���ꂽ�B �@ ���R�y���j�N�X�ȍ~�̊w�� �@ ���̌�A���[�}���c�O���S���E�X13���ɂ����1582�N�ɃO���S���I��쐬����邪�A����̗��_�ɂ̓R�y���j�N�X�̒n�����͗��p����Ȃ�����(�������v�g���}�C�I�X�̓V�������g���Ă͂��Ȃ�)�B �@ �������A�R�y���j�N�X�������ŏ��߂ă��e����ŏЉ���A���r�A�V���w�̌��̉^�s�̗��_��Z�o����1�N�̒l�́A����̍ۂɎQ�l�ɂ��ꂽ(�R�y���j�N�X�̌��̉^�s���_�́A�A���r�A�Ƃ͓Ɨ��ɍĔ��������Ƃ�����������)�B |
|
|
���R�y���j�N�X�̒n����
�@ �R�y���j�N�X�̒n�����́A�P�ɓV�����̒��S��n�����瑾�z�Ɉʒu�I�ȕϊ������������̂��̂ł͂Ȃ��B�n�����ł́A1�̘f���̋O�������̘f���̋O�����Œ肵�Ă���B�܂��A�S�f��(�n�����܂�)�̌��]���a�ƌ��]�����̒l���݂��Ɋ֘A�������Ă���B�e�f���̌��]���a�́A�n���̌��]���a�Ƃ̔�Ō��肳���(���ۂ̋����́A���̎���ɂ͂܂�������Ȃ�)�B���l�ɁA�n���Ɗe�f���̋������Z�o�ł���B���ꂪ�A�v�g���}�C�I�X�̓V�����Ƃ̑傫�ȈႢ�ł���B�v�g���}�C�I�X�̓V�����ł́A�ǂ�Ȍ`�ł��A�f���Ԃ̋����𑪒肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�܂��A�n�����ł͊e�f���̌��]���a�A���]�����́A�S�f���̒l�����ꂼ��̒l�Ɗ֘A���Ă��邽�߁A�ǂ����̒l�������ł��ς��ƁA�S�̂̑̌n�����ׂĕ���Ă��܂��B������A�v�g���}�C�I�X�̓V�����ɂ͂Ȃ��傫�ȓ����ł���B���́A�ꕔ���ł��킸���ȕύX��F�߂Ȃ��̌n���ł������������Ƃ��A�R�y���j�N�X�ɂ��̐����^�����Ɗm�M���������R���ƍl���錤���҂������B �@ �R�y���j�N�X�̒n�����ł́A�f���́A���z�𒆐S�Ƃ���~�O��������]����B�f���͑��z����߂����ɐ����A�����A�n���A�ΐ��A�ؐ��A�y���̏��ł���(���̎���A�V�����⏬�f���͂܂���������Ă��Ȃ�)�B���]�����̒Z���f���͑��z����߂��Ȃ��Ă���B�������A���ۂɂ́A�P���ȉ~�O�������ł͊e�f���ׂ̍��������̐����������A�R�y���j�N�X�̒����ł́A�v�g���}�C�I�X���ł��g���Ă������S�~���^���̐����Ɏg��ꂽ�B���ۂɂ͘f���̋O�����^�~�ł͂Ȃ��ȉ~�ł��邽�߁A�P���ȉ~�ł͉^���̐��������Ȃ��������߂����A�R�y���j�N�X�͘f���̉^�����������̉~�^���̍����Ő����ł���ƐM���Ă������߁A�ȉ~�O���ɋC�t�����Ƃ͂Ȃ�����(���ۂɂ̓R�y���j�N�X�̎g�����l�̐��x�͈����A�ǂ���ɂ��Ă��ȉ~�O�������邱�Ƃ͍������)�B �@ ���R�y���j�N�X��̒n���� �@ �R�y���j�N�X�̌�A�n�����ɓ��ӂ���V���w�҂͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�������A�����̊w�҂����Â����̂𐳂������̂ƍl���A�V�������̂�r�����悤�Ƃ����A�Ƃ����͎̂�j���Ƃ͈قȂ�B�x���҂���������Ȃ������̂ɂ͖��m�ȗ��R���������B�R�y���j�N�X�̒����́A�ǂ��炩�Ƃ����Ɨ��_���ɋ߂��A1�N�̒����͎Z�o���邱�Ƃ͂ł��Ă��A5�̘f���̓��������S�Ɍv�Z������@�͋L����Ă��Ȃ���������ł���B�v�Z�ɕK�v�Ȓl���A�����̂��������ɎU����ċL����Ă���A���̒��������Řf���̈ʒu�\����s���͍̂���ł������B�����̑����̓V���w�҂��~���Ă����̂́A���_���ł͂Ȃ��A�\�ɂ��鐔�l�����Ă͂߂Čv�Z����Θf���⌎��v�Z�ł�����ȕւȐ��\�ł������B �@ ���̌�A1551�N�ɁA�G���X���X�E���C���z���g���A�R�y���j�N�X���������ꂽ�w�v���C�Z�����\�x���쐬�����B�������A�v�g���}�C�I�X�̓V�����������]�~�̐����������߂Ɍv�Z���ώG�ł���A�덷�̓v�g���}�C�I�X���Ƒ債�ĕς��Ȃ�����(���ۂɂ́A�킸�������v���C�Z�����\�̂ق����덷��������)�B�f���̈ʒu�v�Z�ɂ͂���ȍ~���V�����Ɋ�Â��č��ꂽ�A���t�H���\���\�����s���Ďg��ꑱ�����B�������A�I�[�E�F���E�M���K���b�`�́A�A���t�H���\���\�͂��̎���Ƀv���C�Z�����\�Ɏ���đ���ꂽ�Ǝ咣���Ă���B �@ ����܂ŁA�f���̈ʒu�\��̓v�g���}�C�I�X�����g�p���Ȃ���s���Ȃ������B�������̕��@���l�Ă��ꂽ���Ƃ����������A�v�g���}�C�I�X�������̂����x�ŗ\�ł�����̂͑��݂��Ȃ������B�������A�R�y���j�N�X�����g�p���Ă��A�����ȏ�̐��x�Řf���̈ʒu�\�s���邱�Ƃ������������̎���ɁA�B���ł������v�g���}�C�I�X���̐�ΐ��͑傫���h�炢���B �@ �e�B�R�E�u���[�G�́A�P���̔N�������������̖]�����ł͊ϑ��ł��Ȃ��������Ƃ���A�n���͎~�܂��Ă�����̂Ƃ������A���z��5�̘f�����]���Ēn���̎�������]����Ƃ����ܒ��Ă��������B�ŏ��ɒn�����Ɏ^�������E�ƓV���w�҂́A�R�y���j�N�X�̒��ڂ̒�q���e�B�N�X���������n�l�X�E�P�v���[�������B�P�v���[�̓u���[�G�̋��������҂ł���(����Ƃ����L�q�����邪�A�P�v���[���g�͋��������҂Ƃ��Č}����ꂽ�A�Ǝ咣���Ă���A�܂��A�u���[�G���g���P�v���[�ɑ����Ďc���Ă��鏑�Ȃɂ��A����Ƃ��Č}����Ƃ��������͂Ȃ�)�A�u���[�G�̖c��Ȋϑ��L�^����1597�N�A�u�F���̐_��v�������B�R�y���j�N�X���Ɋ��S�Ɏ^������Ǝ咣���ăR�y���j�N�X��i�삵���B�����ɒǐ�����`�ŁA�K�����I�E�K�����C���܂��n�������������B |
|
|
���Ñ㒆���́u�n�����v
�@ �Ñ㒆���ɂ����Ă��A�Ɠ��ȁu�n�����v�����݂����B�w��q�x�́u�X�J�v�̌̎��̌����ɂ́u���炪����V�n���A�����̉F����Ԃ̂Ȃ��Ō���A�����ۂ��ȕ��ɂ����Ȃ��v(�v�V�n�A��ו�)�Ƃ���A�������łɁA�F���I�X�P�[���̒��ł́u�V�n�v�ł��������ȑ��݂��Ƃ����F�������������Ƃ��킩��(�������A�Ñ㒆���l�́u�V�n�v�����́u�n���v�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ�����)�B����ɗ��s�����u���v�ł��A�f�p�Ȓn�������U�������B�Ⴆ�w�t�H�x�ɂ����������ɂ́u�V�͍������A�n�͉E�����v(�V�����A�n�E��)�A�u�n�����Α����V�ۂɌ�(����)���v(�n���������V��)�Ƃ���B�w�����x(���o)�̈��ɍڂ���u�l�V���v�́A��n�͖��N�A������k����я㉺�ɓ����Ă���A�Ƃ�������Ȓn�����ł��邪�A�u��n�͏�Ɉړ����Ă���̂����A�l�Ԃ͊��m�ł��Ȃ�(�����u�n�P���s�~�A�l�s�m�v)�B����͂��傤�ǁA���������D�ɏ���Ă���l�ɂ́A�D�������Ă��邱�Ƃ��m�o�ł��Ȃ��悤�Ȃ��̂��v�Ƃ��킹�Đ����Ă���_�����ڂ����B���̖��@�����A�������������Ɠ��̒n�������ӂ܂��Ċ������r��ł���(�u�V�v)�B��q�̂Ƃ���A���m��Heliocentrism(���z���S���B���㒆����ł́u���S���v)�̖��Ƃ��āu�n�����v�͕s�K�ł���Ƃ���ӌ�������B�Ñ㒆���́u�n�����v�́AHeliocentrism�Ƃَ͈��̉F���ςł͂�����̂́A�u�n�E���v�u�n���������V�ہv�u�n�P���s�~�v�Ȃǖ��m�Ɂu�n���v������A�����ʂ�̒n�����ł������B |
|
|
�������C�X�������E�̒n����
�@ �E�}���E�n�C���[���̎���̃C�X�����̓V���w�҂́A���łɁu���z���S���v(�n����)��m���Ă������A������������邱�Ƃ̓C�X�������̐�����`����U�������댯���������̂Ŗق��Ă����A�Ɛ��������������B���̍����̈�́A�E�}���E�n�C���[���̎l�s��(���o�C���[�g)�̒��̎��̈��ł���B �@ ��邱�̐��ɂ���܂ǂ��� �@ �v���炭�@���͉��]�̔@���� �@ ���z�͓��ɂ��Đ��E�͒̍� �@ ���炻�̓��ɉe�G�̔@���E�������� �@ ���̑��A�R�y���j�N�X�̒n�������A���̓C�X�������E�̓V���w�ɂ��̌��^���������Ɛ�������w�����炠��B �@ ����A�A�u�[�E���C�n�[���E�A���E�r�[���[�j�[(973�N - 1048�N)�́A���̒����u�}�X�E�[�h��T�v�ɂĒn�������L�ڂ��Ă���B�܂��A(�n�������ǂ����͕s������)�A�b�o�[�X���̃}�A���[���̎���ɁA�A�����t���[���Y�~�[�����[�t���e�X��̖k�A�V���W���[��������p���~���t�߂Œn�������̂ł���Ƃ̑O��Ōo�ܓx�y�юq�ߐ��ʒ��̑��ʂ��s���Ă���(���̑��ʌ��ʂ��炷��ƁA�n���̎�����39000Km�A���a��10500Km�ƂȂ�)�B |
|
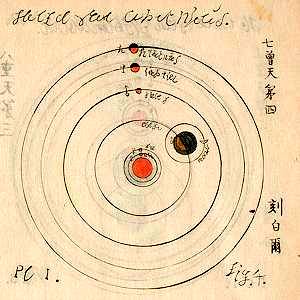 �@ �@���n�����Ɠ��{ �@ ����g�@�̎���ɃL���X�g���ȊO�̊���m���̗A�����������Ƃ��ɁA�ʎ��̖{�ؗlji���w�a���n���}���x�Ɓw�V�n�p�@�x�̒��œ��{�ōŏ��ɃR�y���j�N�X�̒n�������Љ���B�{�ؗlji�̒�q�̎u�}���Y���w��ېV���x�̒��ŃP�v���[�̖@����j���[�g���͊w���Љ���B��Ƃ̎i�n�]�����w�a���V���x�Œn�����Ȃǂ̐��m�V���w���Љ�A�w�a���V���}�x�Ƃ������}��������B��҂̖��c������1763�N�ɁA���E�ŏ��߂ăP�v���[�̑ȉ~�O���̒n������p���Ă̓��H�̓����̗\���������B���{�͐��m�V���w�Ɋ�Â�����@�ɉ����悤�ɍ���������ԏd�x��ɖ����A1797�N�Ɍ��⑾�z�̉^�s�ɑȉ~�O�����̗p����������������������B�a��i�C�炪�A���m�V���w�̐��ʂ�������āA�V�ۗ�����������A1844�N�Ɋ����������A��������ɑ��z����������܂Ŏg��ꂽ�B |
|
 �@ �@���i�n�]����s�V���}�t�̐}������@ 18 ���I�A����͍������ɂ���Ȃ���A���{�ŗB��O���D�������J�`�s�s�ł������B�����ʂ��đ����̘a�����������{�ɂ����炳��A�����ɐ��m�̒n���w��V���w������ɓ`�������B�i�n�]���͓V��8 �N(1788)�̒��藷�s���_�@�ɘa���ʎ��{�ؗlji�ƒm�荇���A�n�������͂��߂Ƃ���n���V���̒m������������B�]�˂ɖ߂����]���́A���̌��A�̎��R�Ȋw�֘A�̓��ʼn��i�𐧍삵�A���̒��ōŏ��̏����ȓV���֘A��i������8 �N(1796)�́s�V���}�t(�_�ˎs��������)�ł���B����͒����̓`���I�ȓV���}�̏�ɁA���m�̐����G���d�˂ĕ`���Ă���A�����Ƃ��Ă͎a�V�ȕ\���ł������B�{���\�ł́A���̍�i�̐V���Ȑ}������𖾂炩�ɂ������B �@ ��s�����ɂ����č]���́s�V���}�t�̐}���́A�C�G�Y�X��w���ɂ�钆���ŐV�̓V�����w�V�o����x���̐}���ƁA���{�ɓ`�������a�����̐����}���������ꂽ���̂ł���Ƃ���Ă����B����ɁA���㖋�{�V�����a��t�C�̎����ɂ��V���ȓ��{�̐��������������A�����Ƃ��ẮA�����Ő�[�̒m�����l�ߍ��܂ꂽ��i�ł������ƌ�����B�]�����ʂ����a�����̓V���}�́A�s�u���E���E�}�t(��������������)�ɕ`���ꂽ���V���}���ʂ����t���f���b�N�E�f�E�E�B�b�g�́s�V���}�t(�l��)�����}�ƌ����Ă����B���������̍�i�͗������炩�ɂ���Ă��Ȃ��B �@ �����ŁA�]��������5 �N(1793)�Ɂs�n���S�}�t�𐧍삵���ہA�ނɏ����������n���ǂƂ̊W�ɒ��ڂ���B�n���ǂ͊���3 �N(1791)�����ɂ��A���{�����u���E�̓V�n���V��C��C����A�ꎞ�V�����ɋΖ������l���ł���B�n���ǂɂ��V�n���V��C�̋L�^���w�����ɓV�n�����C����L�x�̓��e����A�s�V���\��{�۔z����\���h�}���t(����7 �N)�����̕����Ƃ��āA���ݍ�������}���قɏ�������Ă��鎖�����������B����͉���12 �{�̐��������꒼����ɕ`���ꂽ��i�ł���A�]���́s�V���}�t�ɕ`���ꂽ12 �{����28 �h�Ƃ��d�ˍ��킹���}���l�����������Ă����B�܂�A�]�����l�ɉF���̊O�����猩�ĕ`�����m��12 �{���ɍ��킹�āA������28 �h�]��������i�������̂ł���B �@ �܂��A�n���ǂ̑��q�k�R���ނ́A���㏫�R�g�@�̎���ɓ`�������Ǝv����a�����s�t�B�b�Z�������u���E���E�}�t(��������������)�̖͎ʁs�a���l�������n���S�}�Ǝʁt(����4�`6 �N���A�V����w�t���V���}����)�𐧍삵�Ă���B�]���̐����}���́A�n���ǂ̂��̂����f�E�E�B�b�g�ɋ߂������l������ƁA�������u���E�̌n���ł���s�t�B�b�Z�������t��͎ʂ������ނ̉e���͂��傫�������̂ł͂Ȃ����ƍl������B�������A���m�̓V���}�Ƃ������́A�k�R�W�z�E�������q(�n���ǁE�n����)�ƍ]���ȍ~�ɂ����Đ����͌����Ȃ��B����͍]�ˌ�����疋���ɂ����āA�}���ɔ��W���闖�w�Ƌߑ�V���w�̓����ɂ��A�㐢�ɂ����Ă��̎�肪�Ȃ݂��邱�Ƃ�������������ł���ƌ����邾�낤�B |
|
 �@ �@���]�ˎ���̉F���� �@ 1610�N�A�K�����I�E�K�����C(1564-1642)�͎���̖]������`���Ėؐ��̉q�������A���̑��������̒m�������ƂɁA�n�������������B�n�����͂��������j�R���E�X�E�R�y���j�N�X(1473-1543)���A�w�V�̂̉�]�ɂ��āx(1543)�Ƃ��������̒��Ř_�������̂��ŏ��ł��邪�A�����͂قƂ�ǎ����ꂸ�A�K�����I�̔����ƃ��n�l�X�E�P�v���[(1571-1630)�ɂ��f���̑ȉ~�^���̉𖾂ɂ���āA���̐������𖾂炩�ɂ����B�����������̋L�q�ɔ�����Ƃ������R�ŁA���[�}���c����1616�N�ɂ�����ւ����B �@ ����A���{�ł́A�]�����̓`���͌c���\���N(1613)�Ƒ����������A�����p���ēV�̂��ϑ����邱�Ƃ͍]�˒����ɂȂ�܂łȂ������B���m�V���w����������ȑO�̓��{�ł́A�����N���́u�W�V��(�����Ă�)�E�ӓV��(����Ă�)�v��A�����������u�{��E��(����݂�������)�v�Ȃǂ��F���ςƂ��Ēm���Ă����B �@ ���{�ɂ�����V���w�Ƃ͎�Ƃ��ė����邽�߂̂��̂ł���A��Z�V���w�ƌĂ�邱�Ƃ�����B��̌v�Z���s���ɂ������ẮA�O���̒��S�����z�ł��낤�ƒn���ł��낤�Ƃ�������Ⴂ�͂Ȃ��A���{�ɂ����Ēn�������傫�Ȗ��Ƃ���邱�Ƃ͂Ȃ������B �@ ���u�V���}���v���\���N(1688)�����@�����͒��@ �@ ���u�ِ���؉^�C��(�ׂȂ����)�v�@�c���O�N(1650)���@��쒉��(����̂��イ����)�ҏq�A���䌺��(�ނ������傤) �@ �\�Z���I�Ȃ��A���{�ŃC�G�Y�X��ɂ��z�����n�܂�ƁA����ɂƂ��Ȃ����m�V���w���`����ꂽ���A�����͐��m�ɂ����Ă����܂��v�g���}�C�I�X�̓V�������M�����Ă����B��쒉���͓��{�ɋA�������|���g�K���l�鋳�t�ł���B�{���������ꂽ�͍̂]�ˎ���ɂȂ��Ă��炾���A���̓��e�̓X�y�C���l�C�G�Y�X��m�y�g���E�S���X(1535-1600)���́w�V���_�x(1595)�����~���ɂ��Ă���Ƃ݂���B�����ŕ`����Ă���F���͒��S�ɒn�������݂��A���̎��ӂɌ��A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y�������A����ɊO���ɐ��X���ڂ�����h�V�A�����s�����V�A�����^�����s���@���V�����݂���Ƃ����\���ɂȂ��Ă���B �@ ���u�V�o����(�Ă��킭����)�v�@���ۏ\�ܔN(1730)�@���q�Z(�䂤���낭)���@���쐳�x(�ɂ����킹�����イ)�P�_�@ �@ �{���������Ŋ��s���ꂽ1675�N�́A���m�ł͂��łɒn�������嗬�ƂȂ�����������ł��邪�A���q�Z�̓C�G�Y�X��m�̉e�������w���ɂ���A���c�����ւ��Ă���W�ŁA�n������F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������ƍl������B���̌��ʂƂ��Ė{���ł́A�������̓V�����̐}�ɂ��킹�āA�V�����ƒn������ܒ������悤�ȃe�B�R�E�u���[�G(1546-1601)�̉F���ς��Љ��Ă���B���{�ł�1630�N���荽�����n�܂�A�L���X�g���Ɋւ��鏑���̗A������������Ă������A���یܔN(1720)�ɔ��㏫�R����g�@�ɂ���ċ֏��߂����߂���ƁA���쐳�x(1693-1756)�ɂ��P�_�̂���ꂽ���̂����s����A���x�X�g�Z���[�ƂȂ����B �@ ���u��ۍl��(�ꂫ���傤��������)�@��ҁv�@�������N(1742)�Ē� �@ �����ł͓��{�ƈقȂ�A�L���X�g���鋳�t�̓`���鐼�m�V���w�������Ɍ��I�Ɏ�����āA���m���̌v�Z�@��p��������ꂽ�B�������A���̂��߂������Ēn�����̓����͒x�ꂽ�B�{���ɐ旧�w��ۍl���@�㉺�ҁx(贐����N�A1723)�ł͓V�̂̉^�����~�^���̑g�ݍ��킹�Ő�������e�B�R�̑̌n���̗p����Ă������A��҂ɂȂ�Ƃ����ɁA���z�E���̉^���ɂ��Ă̂݁A�P�v���[�̑ȉ~�O�������̂���ꂽ�B���{�ł͊����̉���(������N�A1797)�̍ۂɌ�������A������ɂ͑��z�E���̑ȉ~�O�����������ꂽ�B�������Ȃ���f���ɂ��Ă͏㉺�҂̂܂܂̉~�^���Ƃ����B �@ ���u���z���������(�����悤���イ���傤��������)�v�@�����l�N(1792)�@�{�ؗlji(���Ƃ���傤����)��@ �@ ���u��ېV���v�����\�N(1798)�����@�u�}���Y(���Â�������) �@ �{�ؗlji(1735-1794)�͒���̒ʎ��̐E�ɂ���A����ɒʂ��Ă����B����������A���ڗ�������m�����闧��ɂ��������߁A���{�ɏ��߂ăR�y���j�N�X�̒n�������Љ�邱�ƂɂȂ����B�u���z����������v�͉p�W���[�W�E�A�_���X�̓V����(���e�����1766�A�����1770)��a�����̂ŁA�����ł͒n�����͂��łɎ����̂��̂Ƃ��č̂������Ă���B�܂��f���̉^���ɂ��Ă��P�v���[�̑ȉ~�O���_�Ɋ�Â��Ă���B����������ʎ��o�g�ŁA�{�ؗlji�̒�q�ł��������u�}���Y(1760-1806)�́A�p�W�����E�P�C��(1671-1721)�̒���(���e�����1700�A����� "Inleidinge tot de waare Natuur-en Sterrekunde" 1741)��|�A�w��ېV���x(�����\�N�|���a��N�A1798-1802)���������B�����܂ŊϔO�I�ȗ����ɂƂǂ܂����{�ɑ��āA�u�}�̓j���[�g���͊w�������������Œn������_���Ă���B���Ȃ݂ɒn�����Ƃ������t�����͎̂u�}���Y�ł���B �@ ���u�V�I�(�����ꂫ����)�v�@�V�ێ��N(1836)�@�a��i�C(���Ԃ��킩������)�A�����M��(����������Ƃ�) �@ ���a�O�N(1803)�A��������(�����͂��悵�Ƃ�)�͖��{���畧�̓V���w�҃������f(1732-1807)�̒���̗���ŁwAstronomia of Sterrekunde�x(1773-1780)�̒����𖽂���ꂽ�B�����͖{���ɖ������M�S�ɖ|�����A�����̑O�ɖS���Ȃ�A�Ȍ���ԏd�x(�͂��܂����Ƃ�)�A�����i��(�����͂������₷)�A�a��i�C�炪�����p�����B�������Ăł����������̂��w�V�I��x�ł��邪�A�������f�̓V�����������ɖ|���̂ł͂Ȃ��A���{�̓`���I�ȗ�̃X�^�C���ɕҎ[���Ȃ������̍قƂȂ��Ă���B�����֎����Ă��ɘf���^���̌v�Z�ɂ͑ȉ~�O�����̂�����ꂽ�B�{���͌�ɓV�ۂ̉���(�V�ۏ\�O�N�A1842)�̑b�ƂȂ������A����͒����̗�ɕ키�̂ł͂Ȃ��A��������ɂ������߂Ẳ���ł���A�܂��]�ˎ���Ō�̉���ƂȂ����B �@ |
|
|
���n�����̂����炵������
�@ �n�����͒P�Ȃ�f���̋O���v�Z��̖��݂̂Ȃ炸�A���̓N�w�ҁA�Ȋw�҂�ɑ傫�ȉe����^�����B�n�����̐��܂ꂽ������Ȋw�v���̎���Ƃ������̂́A����قǂ܂łɉȊw�S�̂ɗ^�����A�����āA�Ȋw���l�Ԃ̐����ɉe����^���n�߂�����ł��邱�Ƃ������f���Ă���B �@ �g�펯���Ђ�����Ԃ�(�ؖ�����Ă���)�V���h���u�R�y���j�N�X�I�]��v�ȂǂƌĂԂ̂́A���̖��c�ł���B |
|
|
���K�����I�ٔ�
�@ �K�����I�E�K�����C�́A�n�����ɗL���ȏ؋��𑽂��������B��\�I�Ȃ��͖̂ؐ��̉q���ŁA���̔����͂����n���������Ȃ�A���͎��c����Ă��܂����낤�Ƃ����n�����ւ̔��_���ɂ�����̂������B�܂��A�K�����I�͋����̖����������ϑ��B����́A�n���Ƌ����̋������ω����Ă��邱�Ƃ��������̂������B�܂��K�����I�͑��z���_���ϑ��B���z���܂����]���Ă��邱�Ƃ��������B�K�����I�͂�����_���Ŕ��\�����B�����͂��ׂāA�n�����ɗL���ȏ؋��ƂȂ����B�K�����I�͒��̊������n�����̏؋��Ǝv���Ă������A��ɒ��̊����͌��̈��͂ɂ����̂��Ƃ��āA�ے肳�ꂽ�B �@ ���[�}���c����1616�N�ɁA�R�y���j�N�X�����ւ���z�����o�����B�n�������������K�����C�́A1616�N��1633�N��2�x�A���[�}�ْ̈[�R�⏊�ɌĂяo����A�n�����������Ȃ����Ƃ�鐾������ꂽ�B���̎��́u����ł��n���͉���Ă���v�̙ꂫ�́A���ۂɂ����ꂢ���Ƃ����m�ł���؋��͑��݂��Ȃ����A�`���Ƃ��Č��݂Ɏ���܂Ō��p����Ă���B �@ ���K�����I�ٔ��ȍ~ �@ ���Ƃ��K�����I���ْ[�̔��������Ƃ��Ă��A�����̃��[�}���c�ɂ̓C�^���A���O�ł̌��͎͂�����Ȃ������B���n�l�X�E�P�v���[�́A�_�����[�}�鍑�c���t���w��(�{��t�萯�p�t)�ł���Ȃ���A���R�ƒn���������������A���������[�}���c������֏��Ɏw�肳��Ă��A����𗝗R�ɔ��Q���邱�Ƃ͂Ȃ������B�R�y���j�N�X�̐��͂��̎咣�ɔ����Ď��]�~���܂ޕs���S�Ȃ��̂ł������̂ŁA�P�v���[�͊ϑ��L�^�Ȃǂ��炱���ȉ~�O���ɏC�������B����Ɂw���h���t�\�x(���h���t���\)�����A1627�N�A���������B����ȑO�̐��\��30�{�̐��x�������h���t���\�͋}���ɕ��y���A���c�������ƌ������ƁA�f���̈ʒu�͒n��������ɂ��Ȃ���Όv�Z�ł��Ȃ����オ�n�܂�������B �@ �������A�P�v���[���K�����I���A�܂��A�������̎��c����Ȃ��̂��A�n�������̎~�܂�Ȃ��œ��������Ă���̂��A�Ƃ����^��ɂ͐��m�ȓ������o���Ȃ��܂܂ł����B���������������̂́A�A�C�U�b�N�E�j���[�g���̓o���҂K�v���������B�j���[�g����������莮�����邱�Ƃɂ��A�n�����͂��ׂĂ̋^��ɓ����A���A�f���̈ʒu�̌v�Z�ɂ���Ă����̐��������ؖ��ł���w���ƂȂ����̂ł���B �@ �����A���̏ؖ����m�łƂ���ɂ́A�W�F�[���Y�E�u���b�h���[�̌��s���̔������K�v�ƂȂ�B �@ �֑��ł͂��邪�A���[�}���c���Ȃ�тɃJ�g���b�N�������ɓV������������A�n���������F�����̂́A1992�N�̎��ł���B�������A����̓K�����I�ٔ������ł��������Ƃ�F�߁A�K�����I�ْ̈[���c�������ۂ̕⑥�A�Ƃ����`�ł̕\���ł������B�K�����I�̎�����359�N���o�߂��Ă����B |
|
|
���n�����Ə@��
�@ �n�����̉���̍ہA�K���Ƃ����Ă����قǁA�n�������L���X�g���̏@���Ƃɂ���Ĕ��Q���ꂽ�A�Ƃ����咣������邪�A����ɂً͈c���ƂȂ���ӌ�������B���̂��߁A���_�L����B �@ �����Q���ꂽ�Ƃ���闝�R �@ �j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�́A���Q������A���̊������30�N�ɓn���Ĕ��\�����߂�����B���\�����̒��O�ł������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A���Q����������Ǝ҂ɂ���āA�u�����ɐ��w�I�ȉ���ł���v�Ƃ����A�����������҂ɖ��f�ł����Ċ��s���ꂽ�B �@ ���\����A�n�����Ɏ^������V���w�҂͏o�Ȃ������B���炩�ɐ������͂��̒n�����ɑ��ēV���w�҂��������̂悤�ȍs�����Ƃ����̂́A���Q�����ꂽ���߂ł���B �@ �}���e�B���E���^�[�́A�R�y���j�N�X���ɂ��āA�u���̔n���҂͓V�n���Ђ�����Ԃ����Ƃ��Ă���v�Əq�ׁA�n������ے肵���B���ʁA�v���e�X�^���g�ł��A�n�����̓A�C�U�b�N�E�j���[�g���̓o��܂Ŕ��Q�̑ΏۂƂȂ�B �@ �n�������������W�����_�[�m�E�u���[�m�́A1600�N�ɉΌY�ɏ����ꂽ�B �@ �K�����I�E�K�����C�͒n���������������߂ɔ��Q���ꂽ�B �@ 1616�N�Ƀ��[�}���c���͒n�������ւ����B �@ 1633�N�Ɏ��̃��[�}���c�E���o�k�X8���́A����K�����I�E�K�����C�ɑ����2��@���ٔ��ňْ[�̔������������B���̔w�i�ɂ͎O�\�N�푈�ɂ��J�g���b�N���͂̉v������Ă���������������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A1616�N��1835�N�܂Ń��[�}���c������֏��ɂ��ꂽ�B �@ �ȏ�̏��_�ł́A��̘_�|������������Ă���B�u�n�����������֎~���ꂽ�v�Ƃ������ƂƁA�u������ۂɒn������M����҂𔗊Q�����v�Ƃ������Ƃ��B�O�҂͐��������A��҂͕K�������������Ȃ��B����͒n�������R���Ƃ����Ƃ������A���ۂɏR���Ƃ����߂ɂ͏R���Ƃ����߂̌��͂�v����B�ȏ�̏��_�ł́A���̓�̂��Ƃ���������Ă���B���̂����ŁA�_�|�Ƃ��ẮA�K���������������̂ł͂Ȃ��B �@ �����_ �@ ����ɑ��A�n�����ւ̔��Q�Ǝv������̂́A�P�ɃK�����I���C�^���A���ł̌��͓����Ɋ������܂ꂽ���߂ŁA�K�����I�𔗊Q���邽�߂ɒn���������R�Ɏg��ꂽ�������Ƃ����咣�������B���̗��_�̍����͎��̂Ƃ���B �@ �R�y���j�N�X�������̔��\�����߂�����̂́A����A���ł������ꍇ�A������J�g���b�N����̖��_�⌠�Ђ����Ă���̂����ꂽ���߂ł���B �@ �R�y���j�N�X�̒n�����́A�ʖ{�̌`��1514�N���납�痬�z���Ă���A��������𔗊Q�E�֎~����̂Ȃ�A���s�ȑO�ɔ��ցE�����ɂȂ�͂��ł���B �@ �R�y���j�N�X�́A�������߂Â��O�ɁA�����̉���{���v���e�X�^���g�ł�������q�̃��e�B�N�X�̖��Ŋ��s���Ă��邪�A���҂Ƃ��ɔ��Q���Ă��Ȃ��B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�ɂ́A���[�}���c�ւ̌���������B�����A�����������ɂ͑���̋����K�v�������͂��ł���A���̂��Ƃ���������J�g���b�N����n�����𔗊Q���Ȃ������͖̂��炩�ł���B �@ �O���S���I��ւ̉���ɍۂ��āA���[�}���c�O���S���I13�������X�ɐݒu��������ψ���́A����ɕK�v��1�N�̒����̎Z�o�ɁA�R�y���j�N�X�́w�V�̂̉�]�ɂ��āx�̐��l���g�p����(�������A���̊w�҂̐��l���g�p����)�B �@ �v���e�X�^���g�ł������}���e�B���E���^�[���ᔻ�����̂́A�J�g���b�N����̂��̂ł���B���^�[���n������ᔻ�������R�́A����ɒn�������������R�y���j�N�X���J�g���b�N����̎i�Ղ���������ł���B�܂����^�[�͑����Đl����`�Ȃǂ̌ÓT�⎩�R�w�̌����ɂ͔ᔻ�I�ł������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx(1543�N����)�̈���S���҂̓v���e�X�^���g�ł���B�v���e�X�^���g�͑O�q�̃��^�[�̗�ŕ�����Ƃ���A�n�����ɂ͓�������ᔻ�I�ł������B���ꂪ�e�����Ė��f�őO�������������ꂽ�ƍl������B �@ �n�����ɂ����Ɏ^������V���w�҂����܂�o�Ȃ������̂́A�R�y���j�N�X�̒l�̐��x�������A�V�����Ōv�Z�����Ƃ��Ɣ�ׁA�f���̈ʒu�����܂萳�m�ɎZ�o�ł��Ȃ��������߂ł���B���̏؋��ɁA���n�l�X�E�P�v���[�������Ɛ��x�̂悢�w���h���t���\�x���o���ƁA�u���ԂɑS���[���b�p�̓V���w�҂�������g���͂��߂��B �@ �W�����_�[�m�E�u���[�m�����t��ɂȂ����̂́A���z�����S���ƌ���������ł͂Ȃ��A�����ɃJ�g���b�N������������ᔻ�������߂ł���B�܂��A�u���[�m�͓V���w���������`�Ղ͂��邪�A�V���w�҂ł͂Ȃ�(�V�̌v�Z�Ȃǂ��s���Ă��Ȃ�)�B�u���[�m�̐��̒��̓V���w�Ɋւ��镔���ŁA������ł��{�点�������́A���z�͂��̑��̍P���Ɠ�����ނ̐��ŁA���ʂȐ��ł͂Ȃ��A�܂��F���ɂ͓���̒��S�͂Ȃ��A���̈Ӗ��Œn�������ʂȐ��łȂ��Əq�ׂ������ł���B�������u���[�m�̂��̐��͐��������A���������悤�ɍl���Ă����V���w�҂������ƍl�����Ă��邪�A�����咣����҂͓����͂܂����Ȃ������B �@ �K�����I�ٔ��́A�n�������ق������̂ł͂Ȃ��A�����A�o�����͂��߂Ă����K�����I�̏o���̓���������߂ɁA���G��������㩂ł���A�n�����͂��̂��߂̗��R�Ɏg��ꂽ�����ł���B���̏؋��ɁA�n�����������Ĉْ[�Ƃ��ꂽ�l���́A�K�����I�Ȍ�A�N�����Ȃ��B�܂��K�����I�ȑO�ɂ����Ȃ��B(�u���[�m�̗L�ߗe�^�ɂ͂͂�����n�����Ƃ͏����ĂȂ�)���̎���A���[�}���c�����n�������ւ����͎̂����ł��邪�A����̓K�����I��L�߂ɂ��邽�߂ɁA��ɗ��R������K�v�����������߂ł���B �@ �K�����I�͌h�i�ȃJ�g���b�N���k�ł������ɂ�������炸�A�Ȋw�̖��ɂ��Ă͋���̌��Ђ�A���X�g�e���X�N�w�ɖӖړI�ɏ]���������₵�A�N�w��@������Ȋw�����鎖������B���̎����K�����I�ٔ��ɉ����āA�K�����I���ْ[�̓k�Ƃ��čق����錋�ʂɂȂ������ƌ�����B���ہA���̋��c�E���o�k�X8���͓����̓K�����I���x�����Ă������A���̌�͏���Ԃ����悤�ɃK�����I����鐺�������x���������B �@ �w�V�̂̉�]�ɂ��āx�́A1616�N�A�K�����I�ٔ��̎n�܂钼�O�ɁA�֏����X�g�ɋ�����ꂽ���A�\�����̏C�����s���܂łƂ��������t���ł���B1620�N�ɂ͍폜���ׂ��Ƃ��ꂽ�ӏ����݂���ꂽ�B �@ ���n�������ᔻ���ꂽ���R�ƍl�����Ă������ �@ �����ɂ́A�_�̂������ő�n�������Ȃ��Ȃ����ƋL�q����Ă���A�L���X�g���̐��E�҂́A��n���������Ƃ��\���Ǝ咣����̂͐_�̈̑傳���ؖ��ł���̂ŁA��肪�Ȃ����A��n�������Ă���Ǝ咣����̂́A�_�̈̑傳��ے肷�邱�ƂɂȂ�ƍl�����Ƃ����B �@ 1539�N�Ƀ}���e�B���E���^�[���A�ŏ��ɏ@���I�Ȗ��Ƃ��Ēn������ᔻ�����B���^�[�͋����̃��V���A�L�ł̃C�X���G���l�ƃA�����l��������Ƃ��ɐ_�����z�̓������~�߂��Ƃ�����Ղ̋L�q�Ɩ�������Ǝw�E�����B �@ �K�����I�ٔ��̍ō��ӔC�҂��������x���g�E�x�����~�[�m���@���́A��n�̉����𗧏ł���ƐM���邪�A��n�̉^�����ؖ��ł��邩�͋^��Ɏv���Əq�ׂ��B �@ �A���X�g�e���X�̗�������ރX�R���w�̊w�҂́A�V�������������A���X�g�e���X�̗��_���ے肳���̂��莋�����Ƃ����B �@ �J�g���b�N����A�K�����I�́w�V�̑Θb�x�̒��ŁA�n������������M���Ɍ����������A���X�g�e���X�h�̊w�҂̓��[�}���c�E�E���o�k�X8�������Ă����������̂��ƍl�����Ƃ����B �@ �J�g���b�N����͑��z�����c�̏ے����ƍl���Ă����̂ŁA���z�����S�ɂ���Ƃ����l���ɂ��Ă͖�莋���Ȃ������Ƃ����B���c����1620�N�ɃR�y���j�N�X�́w�V�̂̉�]�ɂ��āx�ɑ��Ē��������߂��Ƃ��ɂ́A�F���̒��S�Ɋւ���L�q���n���̉^���Ɋւ���L�q����莋���ꂽ�ƌ����Ă���B �@�@ �@ |
|
| ���V�����ƒn���� 2 | |
|
��1�D�n�����Ə@���ٔ�
�@ �݂Ȃ���́A�u�n�������z�̉�������Ă���B�v�Ƃ����b�������Ƃ�����܂����B���ꂪ�A16���I�ɃR�y���j�N�X���������n�����ł��B �@ �����́u�n���̉��z��킭���₻�̂ق��̐��X������Ă���B�v�Ƃ����V�������M�����Ă��܂����B�������Α��z��͓�����o�Đ��ɂ����݂܂��B�n�ʂ������Ă��邱�ƂȂǂ܂����������܂���B�n�����~�܂��Ă��ēV�������Ă���ƍl����͓̂��R�ł��B �@ ���̂���̐l�́u�n�����v��������l�������A�u�l�X���܂ǂ킷�킷�傤�����v���Ǝv���܂����B���ہA�@�����v�ŗL���ȃ��^�[�Ȃǂ� �@ �u�n���������āA���z�������Ȃ��Ȃǂƃf�^�����Ȃ��Ƃ������Đ��̒��̐l���܂ǂ킷�̂́A�܂��������������B�v �@ �Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂��B �@ �����ŁA�n����������ɔ��W�����āA �@ �u���������Z�ނ悤�Ȑ��E(���z�n)�́A���̉F���̒��ɖ����ɂ���B�v �@ �Ə������u���[�m�Ƃ����l�́A�u�����璍�ӂ����Ă��l���܂ǂ킷�f�^�����������������B�v�Ƃ��āA���Ԃ�̂����ɏ������܂����B �@ �܂��A�����ō�����]�����œV�̊ϑ������āu�n�����v�𐳂����Ɗm�M���čL�߂��K�����I���u�@���ٔ��v�ɂ������u�n�����͊Ԃ��������ł����B�v�ƌ��킳��܂����B���̂Ƃ��u����ł��n���͓����Ă���B�v�ƂԂ₢���Ƃ����b�͂��܂�ɗL���ł��B |
|
|
��2�D�A���X�^���R�X�ƒn����(1)
�@ �n�����Ƃ����ƍŏ��ɏ������̂̓R�y���j�N�X�ł���Ǝv���Ă��܂��B�������A���͍�����2300�N���O(�I���O301�N����)�ɒn�������������l�����܂����B�Ñ�M���V�A�̃A���X�^���R�X�Ƃ����l�ł��B �@ ����Ȃ��Ƃ������ƁA �@ �u�m���ɂ�����������Ȃ����A����Ȑ̂ɂ͂��킵���ϑ��Ȃǂł��Ȃ��������낤����A���̐��͓��őz�����������ŁA�Ȋw�I�Ƃ͂����Ȃ��̂���Ȃ��̂��ȁB�Ȋw�I�Ȃ��傤�������Ƃɂ��Ēn�������������̂͂�͂�R�y���j�N�X���ŏ�����Ȃ��̂��ȁB�v �@ ����Ȃӂ��Ɏv���l�����邩������܂���B�{���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�A���X�^���R�X�̍l�����ߒ�����������ɂӂ�Ԃ��Ă݂܂��傤�B |
|
|
���A���X�^���R�X�̒n���� / ���炵���w�̉��p
�@ �A���X�g�e���X�������A�n���𒆐S�ɂ��̂܂��z������Ă���(�V����)�ƍl���Ă������A�Ñ�M���V���̃A���X�^���R�X�͋�ɕ����Ԕ��������Ď��̂悤�ɍl�����B�u���͋��`������A���̂��傤�ǔ������Ƃ炳��Ă���̂͑��z�����^�����炠�����Ă��邩��ɂ������Ȃ��B���z�r�A�����l�A�n��E�Ƃ���A�O�p�`SME�́A�p�r�l�d�p�Ƃ��钼�p�O�p�`�ƂȂ�B�����ŊpSEM�𑪂�A�pMSE�����߂��Ē��p�O�p�`SME�̑����`��������B��������A���z�́A���̉��{�̋����ɂ��邩���킩��B���Ƒ��z�͓���ł͂قƂ�Ǔ����傫���Ɍ����邩�瑾�z�����̉��{�̑傫������ׂ���B����ɒn���͌��̖�3�{�Ȃ̂ő��z���n���̉��{�����������B�v�ƁE�E�E�����ŃA���X�^���R�X�́A���ۂɑ��z�Ɣ����̊p�x�𑪒肵��87�x���B�pE�r�l�@90-87��3�x�ƂȂ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����Œ��p�O�p�`SME��`���AME����ɂ���SE�𑪂��19�{���B�u���z�́A����19�{�傫���B�n���̒��a�́A���̖�3�{�Ȃ̂ő��z�́A�n���̖�6�{�̑傫�����B���̏d���́A�n���̖�200�{�ȏ�ƂȂ邾�낤�B�v�����܂Œ��ׂăA���X�^���R�X�́A���̂悤�Ɍ��_�Â����B �@ �u����ő��z�́A�n����肸�[�Ƒ傫�����Ƃ��킩�����B�n�����͂邩 �ɑ傫�Ȃ��̂��n���̂܂���1��1��܂���Ă���ƍl����͕̂s���R���B������V�����́A�܂������Ă���B�����Ə������n�����傫�����z�̂܂����܂���Ă���ɂ������Ȃ��B�v �@ �����̑��萸�x�͍����Ȃ������̂ŁA���Ȃ萔���Ɍ덷������܂��B���ۂ̑��z�́A���������܂ł̖�390�{�A�d���͒n���̖�33���{�ł��B�������A����ł����z�ƒn�����ׂ��ł́A�܂�����Ȃ����z�̋��傳�𐄒�ł�����̂ł��B2000�N�ȏ�O�Ɏ萻�̊ϑ����Ə����I�Ȋw��p���Ă��ꂾ���̌��_�����Ƃ́A���炵�����Ƃł��B����͋q�ϓI�����̏�ɗ��������w�I�ȋA���ł���A�Ñ�l�ł���Ȃ���A���X�^���R�X�̍����I�Ȏv�l�W�J�ɂ͋�����������ł��B �@ |
|
|
��3�D���̖�������
�@ ���̌`�����Ă���ƃC�̂悤�ɕς��܂��B�ǂ����Ăł��傤���B �@ ���߂�ƁA���͓V�ɒ���t�������~�̂悤�ɂ������܂��B�������{���͊ۂ����̂悤�Ȍ`�����Ă��܂��B���͉����ė��̓I�ɂ͌����Ȃ��̂ŁA���~�̂悤�Ɍ�����̂ł��B�����Č��͒n���̂܂����1�����ʼn���Ă��܂��B �@ �ł͂��̌���n�����猩����ǂ̂悤�Ɍ�����̂ł��傤���B �@ �܂����͌����o���Ă��Ȃ��̂ŁA���z�̌���������Ȃ��ƒn�����猩�邱�Ƃ��ł��܂���B�ł����猎�̑��z�ɖʂ��Ă��锼�������������邱�ƂɂȂ�܂��B���͊ۂ����̂Ȃ̂ɁA���낢��Ȍ`�ɕς���Č�����̂́A���z�ɏƂ炳��Ă��錎�̕��������������邩��ł��B |
|
|
��4�D���H�̘b
�@ �n�����猩��ƌ��Ƒ��z�͂قƂ�Ǔ������炢�̑傫���Ɍ����܂��B �@ �����ŁA�������傤�Ǒ��z�̊Ԃɂ͂���ƁA���z�����̌��ɂ�������Ă��܂����Ƃ�����܂��B���ꂪ���H�ł��B �@ ���z�ƒn���̋����͋G�߂ɂ���ď����ς��̂ŁA�n�����猩�����z�̑傫���͂ق�̏�������Č����܂��B �@ �܂��A���ƒn���̋��������ɂ���ĕς��̂ŁA�n�����猩�����̑傫�����ς��܂��B �@ �����Œn�����猩��ƁA���ɂ���Č��̕������z���傫����������A�������������肵�܂��B�����傫��������Ƃ����H�ɂȂ�ƁA���z�͌��Ɋ��S�ɂ�������܂��B�����Ȃ����Ƃ��F�����H�Ƃ����܂��B �@ �t�Ɍ��̕������z�ɔ�ׂď�����������Ƃ����H�ɂȂ�ƁA���͑��z��S�����������Ƃ��ł����A���z�̎��肪������͂ݏo���ėւ̂悤�ɂȂ�܂��B��������H�Ƃ����܂��B �@ ���ɂ���ĊF�����H�ɂȂ�������H�ɂȂ����肷�邭�炢�ł�����A�n�����猩�����z�̑傫���ƌ��̑傫���͂قƂ�Ǔ����Ƃ������Ƃ��ł��܂��B |
|
|
��5�D�A���X�^���R�X�ƒn����(2)
�@ �n������݂����z�ƌ��̑傫���͂قƂ�Ǔ����ł��B�A���X�^���R�X�́A�u���z�ƌ��̖{���̑傫���͂ǂ��Ȃ̂��낤�B���Ƃ��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����낤���B�v�ƍl���܂����B�����āA���̂悤�ȕ��@���l���܂����B �@ �u���������̎��A���z�͌���^������Ƃ炵�Ă���B���̂Ƃ����z�ƌ�������p�x�𑪂�A�O�p���ʂ̕��@�Œn�����猎�E���z�܂ł̋����̔䂪�킩��͂����B�v �@ �A���X�^���R�X�͂����������������ɂȂ鎞��҂��đ��肵�A87�x�Ƃ������ʂ܂����B(�������l��89�x50 ���ł��B) �@ �����đ��z�͌����19�{�������Ƃ���ɂ��邱�Ƃ�m��܂����B���Ƒ��z�̌������̑傫�����������Ƃ��l����Ƒ��z�͌���蒼�a��19�{���傫�����ƂɂȂ�܂��B |
|
|
��6�D���H�̘b
�@ ���ɃA���X�^���R�X�͌��⑾�z���n���̉��{�傫�����m����@�͂Ȃ����ƍl���܂����B�����āA���H���ϑ�����Ό��ƒn���̑傫��������ׂ邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��v�����܂����B �@ ���������̐}�̂悤�ɂ����Ă������Ƃ����܂ɋN����܂��B���ꂪ���H�ł��B �@ ����͌����n���̂����ɓ��邽�߂ł��B�ł����猎�ɂ���n���̂����̌`����n���̑傫�����킩��܂��B �@ �������ċ��߂�ƒn���̂����̒��a�͌��̖�3�{�ł��B�����������͒n�����͂Ȃ��ɂ�ď������Ȃ�̂Œn���̒��a������3�{�Ƃ����킯�ł͂���܂���B���ۂ̒n���̒��a�͌��̖�4�{�ł��B �@ �������A�A���X�^���R�X�͒n���̒��a�͌��̖�3�{�ƍl�����悤�ł��B |
|
|
��7�D�A���X�^���R�X�ƒn����(3)
�@ �A���X�^���R�X�͑̐ςɂ��āA���͒n����1/25�A���z�͒n����300�{�̑傫���Ɛ������܂����B��������͌��Ɠ����悤�ɑ��z���n���̉�������Ă���ƍl�����Ă��܂����B�������A�A���X�^���R�X�͂��̐��ɋ^��������܂����B �@ �u�n����300���̑傫���������z���A�����ۂ��Ȓn���̂܂������Ȃ�Ă��Ƃ�����̂��낤���B�ނ��낻�̋t���ƍl����������R����Ȃ��̂��ȁB�v �@ �A���X�^���R�X�͂����l���āA�u�n�����v�\�����̂ł��B�����������̂��炢�w�҂���(�X�g�A�w�h)����́A�u�n���������Ă��邾�Ȃ�āA����ȃo�J�������͐M�����Ȃ��B����ȍl���͐_�ւ̖`�����B�v�ƌ���������܂����B �@ �A���X�^���R�X�̐����͌��݂킩���Ă��鐳�����l�ɔ�ׂ�Ɣ��ɂЂ����߂Ȃ��̂ł����B���z�͌����400�{�������ɂ���܂��̂ŁA���z�͒n���̉���130�����̑傫���������̂ł�(�d���ł����ƒn����33����)�B �@ �������l�͂Ƃ������A�A���X�^���R�X�́u���̂悤�ɑ傫�ȑ��z���A����ׂ��̂ɂȂ�Ȃ����炢�����Ȓn���̂܂������Ƃ������Ƃ����M�����Ȃ��B�v�ƍl�����̂ł��B |
|
|
��8�D�V���� / �v�g���}�C�I�X�@ �Ñ�M���V�A�l�́A�ꕔ�̊w�҂��̂����ƁA���ׂĂ̐��͒n���𒆐S�ɂ��ĉ~�^�������Ă���ƍl���Ă��܂����B �@ ����������ł́A�킭���̕��G�ȓ����͐����ł��܂���B�����Ńv�g���}�C�I�X�Ƃ����l�́A����܂ł̊w�҂̍l�����W�听���āA�킭���̓���������߂Đ��m�ɐ����ł���V�����������܂����B�킭���͒P�Ɍ��܂����O��������̂ł͂Ȃ��A�O����ɒ��S�����鏬���ȉ~�O��(���]�~)�̏���A1�N�̎����ʼn��ƍl�����̂ł��B�����āA����ł����܂��ϑ��ɍ���Ȃ��Ƃ��ɂ͂���Ɏ��]�~���d�˂���A���S�����炷�Ȃǂ̏C�����قǂ����܂����B�������đ�ϗǂ����x�ł킭���̓�����������邱�Ƃɐ������܂����B |
|
|
��9�D�n�����ӂ����� / �R�y���j�N�X�@ �������ď\���Ȑ��x�ł킭���̓���������ł��邱�ƂɂȂ�ƁA�V�����ɋ^������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ�܂����B �@ �������A��肪�������ꂽ��ł͂���܂���B���Ƃ��ΐ����Ƌ����͑��z���炠�錈�܂����p�x�ȏ�͂Ȃ�邱�Ƃ͂���܂��A���̗��R�͐����ł��܂���B�܂��A�킭�������z�̂܂����������͂܂��܂��ł����A���]�~�̏���������͂Ȃ����ǂ̂킭����1�N�ł��B���̗��R�������ł��܂���B �@ �u�킭���̓��������m�ɗ\���ł���̂�����A����ȍׂ��Ȃ��Ƃ͂ǂ��ł������ł͂Ȃ����B�v �@ �����̊w�҂͂����l���Ă��܂����B�������A���������V�����ɋ^��������A�����ł��Ȃ��l�����܂����B�|�[�����h�l�̃R�y���j�N�X�ł��B �@ �u�m���ɂ킭���̈ʒu�𐳊m�ɒm�邱�Ƃ͂ł���B�������A���_�I�ɂ͖������炯���B�������킭�������ۂǂ��ɂ����Ăǂ̂悤�ɉ^�����Ă���̂��A�S�������Ă���Ȃ��B�F���̖{���̎p���m�肽���B�v �@ �R�y���j�N�X�͓����N�������Ñ�̊w������������̒��̗���(���l�b�T���X)�̒��ŁA�Ñ�̊w�҂̖{��ǂ݂܂����B�����̋^�����������q���g�������Ȃ����ƍl��������ł��B�����āA�Ñ�ɂ��n�����������Ă����l�̂��邱�Ƃ�m��܂����B �@ �u���ꂾ�I���ꂪ�{���̉F���̎p���I�I�v �@ �R�y���j�N�X�͂���܂ŋ^��Ɏv���Ă������Ƃ��ׂĂ��u�n�����v�Ȃ�Ή������邱�Ƃ��킩��A�����ւ��т܂����B �@ �킭���̕��G�ȓ����́A�����n���̏ォ�猩�Ă������߂������̂ł��B���]�~��������1�N�Ȃ̂͒n�������z�̂܂�����������1�N����������ł��B�����Ƌ��������z���炠��p�x�ȏ�͂Ȃ�Ȃ����R���킩��܂��B���̓�̂킭���͒n���̓���������Ă����̂ł��B�f���̔z�u(����)��m�邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �R�y���j�N�X�́u�V���̉�]�ɂ��āv�Ƃ����{�ŁA�����Y�ꋎ���Ă����n�����\���܂����B�������A�n�����͂Ȃ��Ȃ�������܂���ł����B |
|
|
��10�D�n�����̏؋�
�@ �u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ɓu�R�y���j�N�X�̒n�����v�̐}������ׂȂ���A�z��Y�N�ƉԎq���b�������Ă��܂��B �@ �z��Y�u�����������]�����Ō���A�V���������������n���������������A�킩��̂ł͂Ȃ����ȁB�v �@ �Ԏq�u���B�ǂ����āB�v �@ �z��Y�u�V�����ł́A�n�����猩���ꍇ�A����������͂������z��w�ɂ��Ă��邩��A�O�����̂悤�Ɍ����Č�����͂��ł���B��Δ����^��ۂ��`�Ɍ����邱�Ƃ͂Ȃ��B�ł��n�������������Ȃ�O�����^�̎������邪�A�����^�▞���^�ɋ߂��`�̎�������͂����B�v �@ �Ԏq�u�Ȃ�قǁB���ꂶ��A������������ώ@���Ĕ����^�▞���^�ɂȂ�Ƃ������邩�ǂ����ׂ�����̂ˁB�v �@ �݂Ȃ�����A�u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ɓu�R�y���j�N�X�̒n�����v�̐}������ׂȂ���l���Ă݂Ă��������B �@ �]�����Ō���ƁA����������͖{���Ɍ��̂悤�Ɍ������肵�Č�����̂ł��傤���B �@ �����E�����̊ϑ� / �����͂������z�̋߂��ɂ���̂ł�����ƌ����Â炢�킭���ł��B�R�y���j�N�X�͐�����1�x���������Ƃ��Ȃ������Ƃ����b������܂��B�ł������́A���̖��̒ʂ肽���ւ邭�P�����ŁA���z���炩�Ȃ�͂Ȃ��̂ł����ƌ��₷���킭���ł��B�]�������g���Β��Ԃł����邱�Ƃ��ł��܂��B�ł����邢�Ƃ��ɂ́A����Ō��邱�Ƃ��ł��邭�炢�ł��B�����Ė]�����Ŋώ@����ƁA�O�����^�Ɍ�����Ƃ�������܂����A�n������݂đ��z����ł����ꂽ�Ƃ��ɂ͔����^�ɁA�n������ł������͂Ȃꂽ�Ƃ��ɂ͖����ɋ߂��`�Ɍ����܂��B����͒n���������������Ƃ̂��傤���ł��B�ł�����搶�Ɍ����Ă��炢�܂��傤�B |
|
|
��11�D�ǂ��炪���������͐����Ȋϑ��� / �e�B�R�E�u���[�G�@ �R�y���j�N�X���u�V���̉�]�ɂ��āv�Ƃ����{�Œn�����\���Ĉȗ���1���I�ɂ킽���āA�V������M����w�҂Ƃ̊ԂŘ_���������܂����B �@ �e�B�R�E�u���[�G�Ƃ����l�́u�ǂ��炪���������͐����Ȋϑ��ŏؖ������v�ƍl���A���̈ʒu�ϑ��𑱂��܂����B �@ �u�����n�������z�̎��������Ă���Ȃ�1�N�̎����Ő��̌���������������͂����v�ƍl�����̂ł��B���̌��ʁA�e�B�R�́u�킭���͑��z�̎�������A���z�͒n���̎�������v�Ƃ����Ǝ��̓V�����������܂����B�����琸���Ɋϑ����Ă��A���̌���������ɕω��͂Ȃ���������ł��B �@ ���̌�e�B�R�͎����̐����m���߂邽�߁A16�N�Ԃɂ킽���ĉΐ��̈ʒu�ω����A����Ƃ��Ă͂��ǂ낭�ׂ����x�Ŋϑ����܂����B���̂�������̊ϑ����ʂ��A���w�ɂ��킵����q�̃P�v���[�ɂ������āA�Ȃ��Ȃ�܂����B |
|
|
��12�D�f���̋O���͑ȉ~ / �P�v���[�@ �e�B�R�̒�q�ŁA�ΐ��̂�������̊ϑ��������g�����Ƃ������ꂽ�P�v���[�́A�킭���̉^���̖@��������w�͂����܂����B�e�B�R�͓Ǝ��̓V�������l���Ă����̂ł����A��q�̃P�v���[�́A���͒n�����𐳂����Ǝv���Ă��܂����B �@ �P�v���[�͉ΐ��̊ϑ����ʂ�p���āA�n���̋O�������肵�悤�ƍl���܂����B�ΐ������z�̎����������(���]����)��687���ł��B687�����Ƃɉΐ��͌��̈ʒu�ɖ߂��Ă��܂��B���̎��̉ΐ��̈ʒu(����)����n���̋O�������߂��킯�ł��B�P�v���[�͒n���̋O���͒��S�̂��ꂽ�~(���S�~)�ł���ƍl���Ă��܂����B�����ł��̒��S�̂���(���S��)�Ɖ~�̑傫���������߂��̂ł��B �@ ���ɁA�������ċ��߂��O�����n�����ǂ̂悤�ɓ������Ƃ����@���������悤�Ƃ��܂����B�����āA�n�������z���牓���Ƃ��͂������A�߂��Ƃ��͑������Ƃ�m��܂����B�P�v���[�́u�킭���̑����͑��z����̋����ɔ���Ⴗ��B�v�Ƃ������������ƂɌ����܂����B�����Ă��Ɂu�킭���Ƒ��z�����Ԑ������P�ʎ��Ԃɂ������ʐς͈��ł���B�v�Ƃ����������@�������܂����B������u�P�v���[�̑�2�@���v�܂��́u�ʐϑ��x���̖@���v�Ƃ����܂��B �@ ���ɃP�v���[�́A���߂�ꂽ�n���̋O�������Ƃɉΐ��̋O�������߂悤�Ƃ��܂����B�ΐ��̋O�������R���S�̂��ꂽ�~�O�����Ǝv���Ă����̂ł����ǂ������܂������܂���B�܂��A��ɔ��������ʐϑ��x���̖@�������m�ɂ͂��Ă͂܂�܂���B�P�v���[�͓����������܂����B �@ �u�ǂ����Ԃ������Ȃ̂��낤�B�p�x�ɂ���8���قǂ̂��ꂪ����B�e�B�R�搶�̊ϑ��͐��m�Ō덷�͂�������1�`2���̂͂��Ȃ̂ɁB�v(�p�x��1����1�x��1/60�ł��B) �@ �����āA�P�v���[�̓e�B�R�̊ϑ����ʂƍ���Ȃ��������ЂƂЂƂ������Ă����܂������킩��܂���B�����čŌ�ɁA�u���������A�ΐ��̋O�����~�ƍl���Ă��邱�Ƃ��Ԃ������ł͂Ȃ����낤���B�v�ƍl���܂����B����́A����܂ł�����^�������Ƃ̂Ȃ����Ƃł����B �@ �u�V�̐��E�͊��S������O���͉~�ȊO�l�����Ȃ��B�v������������l���Ă����̂ł��B�u�~�łȂ��Ƃ�����킭���͂��������ǂ�ȋO�����������Ă���̂��낤�B�v�~�łȂ��O���͖����ɍl�����܂��B���ꂩ��̃P�v���[�́A���낢��ȋO�������肵�Ă͌v�Z���Ċm���߂�Ƃ��������𑱂��܂����B�����Ă��ɉΐ��̋O���͂��~�O���ł��邱�Ƃ����Ƃ߂��̂ł��B �@ �������ăP�v���[�́u�킭���͑��z�̎�����A���z����̂��傤�_�Ƃ������~�O�����������B�v�Ƃ����@��(�P�v���[�̑�1�@��)�����܂����B |
|
|
��13�D���E�̒��a / �P�v���[�̒��a�̖@���@ �P�v���[�͎Ⴂ���납��u�F���̒��a�v�Ƃ����l�����ɋ����S�������Ă��܂����B�u�F���ɂ͐����Ȓ��a������ɂ������Ȃ��B�v�Ƌ����M���Ă��܂����B��1�E��2�@����������A�P�v���[�͂킭�������̉^�����������ɊW�Â���K������ǂ����߂܂����B������10�N��A���ɑ�3�̖@�������܂����B����́A�u�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B�v�Ƃ������̂ł��B�P�v���[�́u���ꂱ�������ԁA�ǂ����߂Ă����F���̒��a���B�v�Ƃ������ƂŁA�u���a�̖@���v�Ɩ��t���܂����B�������ăP�v���[�́A�킭���̉^���Ɋւ���3�̖@�������܂����B �@ �P�v���[�̖@�� �@ �y��1�@���z�킭���͑��z�̎�����A���z����̏œ_�Ƃ������~�O�����������B �@ �y��2�@���z�킭���Ƒ��z�����Ԑ������P�ʎ��Ԃɕ`���ʐς͈��ł���B �@ �y��3�@���z�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B �@ ���̎���܂ŁA�R�y���j�N�X�̒n�����ł́A�v�g���}�C�I�X�̓V�����̂悤�ɂ킭���̓����𐳊m�ɕ\�����Ƃ��ł��܂���ł����B�����N���������Ă������̎��]�~���g���A���ǂɉ��ǂ��d�˂��V�����̕������m�Ȃ̂́A����Γ�����O�Ȃ̂ł��B�������A�P�v���[��3�@���ɂ���āA�n�����ł��킭���̓�����V�����Ɠ����悤�ɐ��m�ɗ\�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B |
|
|
��14�D���̂���K�����I�� / �����̖@���@ ���̂���A�ӂ�q�̓������◎���̖@���ȂǂŗL���ȃK�����I�́A����̖]�������g���ĉF���̐_����������Ă��܂����B�����āA���̃N���[�^�⑾�z�̍��_�A�y���̗ւȂǂ����܂����B �@ �܂��A�ؐ��̎�������4�̉q�������܂����B�����̉q���͍��ł��u�K�����I�q���v�ƌĂ�Ă��܂��B���̗l�q�̓R�y���j�N�X���咣����u�n�����̉F���v�̖͌^�̂悤�ł����B�K�����I���n�������x�����Ă��܂����B�����āA�����̔��������Ƃɂ��āu���E�̕v��u�V���Θb�v�Ƃ����{�������܂����B �@ �P�v���[���킭���̂��������@�����������āA�n�����̐��������Ƃ��ؖ���������A�K�����I�͒n�����ɂ܂��傫�Ȗ����������܂����B����͕��̂̉^���Ɋւ�����Ɋ�{�I�Ȗ��ł��B�u�n���������Ă���Ȃ����͂Ȃꂽ�������Ă���Ԃɒn�ʂ������̂Ő^���ɗ�����͂��͂Ȃ��B���^���ɗ�����̂͒n�����~�܂��Ă��邵�傤���ł���B�v�V�������x������l�͂��������Ēn������M����l�ɔ��_���܂����B�K�����I�́A�����D�̃}�X�g����𗎂Ƃ��Ă��͐^���ɗ����邱�Ƃ���A�u���̑����œ������̂̏�ł́A�~�܂��Ă���Ƃ��Ɠ����͊w�@�����Ȃ肽�B�v�Ƃ����u�K�����I�̑��ΐ������v�����܂����B�����āA�u���ΐ������v�����藧���߂ɂ́A����܂ŐM�����Ă����u�͂Ɖ^���̊W�v�����{���猩�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â��܂����B �@ ����܂ł́A�u���̂ɗ͂������Ȃ���A�����Ă��镨�͕̂K���~�܂�B���̂����������邽�߂ɂ͏�ɗ͂������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƍl�����Ă��܂����B�������K�����I�́u�����D�̏�Ŏ���͂Ȃꂽ���^���ɗ����邽�߂ɂ́A�͑D�Ɠ��������œ��������Ȃ��痎���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���������āA�w���̂ɗ͂������Ȃ��Ƃ��A�����Ă��镨�̂͂��̑�����ۂ��ē���������x�͂����B�v�ƌ��_�����̂ł��B����́u�n�����v�Ɠ����悤�ɁA����܂ł̏펯�����������唭���ł����B������u�����̖@���v�ƌ����܂��B(��Ƀj���[�g�����u�^���̑�1�@���v�Ƃ��Ď��̂悤�ɂ܂Ƃ߂܂����B) �@ �y�^���̑�1�@���z�����̖@�� / ���̂ɗ͂������Ȃ��ꍇ�A�Î~���Ă��镨�̂͐Î~�������A�^�����Ă��镨�̂́A���̑��x��ۂ��ē��������^���𑱂���B �@ �Ƃ���ő��ΐ������Ƃ����A�u�K�����I�̑��ΐ������v�̂ق��Ɂu�A�C���V���^�C����(����)���ΐ������v�Ƃ������̂�����܂��B���̌����́u�K�����I�̑��ΐ������v�������ƈ�ʉ��������̂ł��B���Ȃ킿�A�u���ΓI�Ɉ�l�ȑ��x�ʼn^�����Ă�����̂̒�(���邢�͏�)�ł́A�͊w�@�������łȂ��A����d�C�E���C�ȂǁA�����镨���@�����S�������ɂȂ�B�v�Ƃ������̂ł��B |
|
|
��15�D�j���[�g���̔��z
�@ ���ɂ���̂��j���[�g���ł��B�j���[�g���̓K�����I�̌���p���ŁA���̂ɗ͂��������ꍇ�̖@�������܂����B�u���̂͂܂������ɑ���Ȃ��ꍇ������B����͂ǂ������킯���낤�B�v�j���[�g���̌��_�͂����ł����B�u���Ƃ��Γ����Ă��镨�̂���납�炨���Ε��͉̂�������B���Ό����Ȃ猸������B������͂�������A�����͕ς��Ȃ����^���̌������ς��B�ǂ�ȏꍇ�ɂ���A���̂̑����ƌ����A�܂葬�x��ς���ɂ́A�Ƃɂ����͂��K�v�Ȃ̂��B�v �@ �������ăj���[�g���́u�^���̖@���v�����܂����B �@ �y�^���̑�2�@���z�^���̖@�� / ���̂ɗ͂�������ƁA�͂̌����ɉ����x����B���̉����x�͉������͂ɔ�Ⴕ�A���̂̎��ʂɔ���Ⴗ��B �@ �������ăj���[�g���́A�킭�������z�̎�����^������Ƃ��A���̐ڐ������ɂ͉��̗͂�����Ȃ����Ƃ��������܂����B�������A�킭���ɗ͂��S�R�����Ȃ�������A�킭���͂܂������i����ł��B���ۂɂ͂킭���͒����^���𑱂���킯�ł͂���܂���B�͂������Ȃ��Ƃ����璼�i���Ă������͂��̏�(�o�f)�����A�����Ƒ��z�ɂ�����Ƃ���(�o�h)�܂ŋO�����˂��Ȃ����܂��B���̌��ʂƂ��āA�P�v���[�̌����悤�ɑȉ~�O����`���̂ł��B �@ �킭�������z�̎������邽�߂ɂ́A��ɑ��z�Ɍ������͂������Ă���Ηǂ����Ƃ�m�����j���[�g���́A�u���̗͂͂����炭���z���킭�����������邽�߂��낤�B�v�ƍl���A���̂킭������������̖͂@�������悤�Ƃ��܂����B �@ �j���[�g���͐��w�̓V�˂ł�����܂����B�����Ŕ����E�ϕ��Ƃ����V�������w�����Ă��܂��قǂł����B �@ �킭���̉^���̓P�v���[��3�̖@���Ŋ����ɐ����ł��܂��B�j���[�g���̓P�v���[��3�@�������藧���߂ɂ͂ǂ�ȗ͂������悢�̂����A���ӂȐ��w���g���čl���܂����B�����āA�ʐϑ��x�����Ƃ����P�v���[�̑�2�@���́A�u�킭���ɓ����͂���ɑ��z�̕����������Ă�������悢�v���Ƃ��ؖ����܂����B �@ �܂��A�u�킭���̌��]������2��́A���z����̕��ϋ�����3��ɔ�Ⴗ��B�v�Ƃ�����3�@�������藧���߂ɂ́A�u���̗͂����z����̋�����2��ɔ���Ⴕ�Ď�܂��Ă����B�v�Ƃ���Ηǂ����Ƃ����A�����ɁA���̂悤�ȗ͂������u�킭���̋O���͂��~�ɂȂ�B�v�Ƃ�����1�@�����ؖ��ł��܂����B �@ ����܂ł̂Ƃ���A���̓j���[�g���͉������Ȃ������̂Ɠ����ł��B�Ȃ��Ȃ�A�j���[�g���̓P�v���[�������������Ƃ�ʂȂ��Ƃ�(����)�ŕ\�����������ɂ����Ȃ�����ł��B���ۃj���[�g���͂��̐��I�̑唭���������������ƂƂ͍l�����A�����ɔ��\���悤�Ƃ͂��܂���ł����B���\�N�����āA�n���[�a���ŗL���ȃn���[�������m���āA�}���Ŕ��\����悤�ɑ����܂����B����ł悤�₭���\�����̂ł��B���̂��߃j���[�g���ƓƗ��ɓ����@���������t�b�N�Ƃ̊ԂŐ�挠�����̘_���������N�������ƂɂȂ�܂����B�����悤�Ȃ��Ƃ͔����E�ϕ��̔����ɂ��Ă��A���C�v�j�b�c�Ƃ����l�Ƃ̊ԂŋN���܂����B �@ �j���[�g���͗͂Ƃ������̂̍��{�I�Ȑ����Ɋւ���@�����������܂����B��p����p�̖@���Ƃ����܂��B����ɂ��Ă͕ʂȋ@��ɏڂ��������܂��傤�B �@ �y�^���̑�3�@���z��p����p�̖@�� / ���̂`�����̂a�ɗ͂�����ڂ��Ƃ��A���̂a�͕��̂`�ɗ͂������Ԃ��B�����̗͓͂����p����ɂ���A�傫���͓����������͔��ł���B |
|
|
��16�D�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āu���L�v���̖͂@��������
�@ �悭�u�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āA���L���̖͂@���������B�v�ƌ����܂��B����͖{���ł��傤���B���܂ł̂��b���Ă����݂Ȃ���́A�u����Ȃ̂������B�v�Ǝv���ł��傤�B�u���z���킭������������͂́A������2��ɔ���Ⴗ��B�v�Ƃ����@���̓P�v���[��3�@�����琔�w�I�ɓ����ꂽ���̂ł��B�����S�����痎����̂����Ĕ������ꂽ�킯�ł͂���܂��A�܂����������͂�������܂���B �@ �{���͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�������A�u�S���̉R�Ƃ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����l�����܂��B���̐l�͂����z�����܂��B �@ �������łɃK�����I�ɂ���āA�ؐ��̎����4�̉q��������Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂����B����͏����ȑ��z�n�݂����Ȃ��̂ŁA�q���͖ؐ��Ɉ��������Ă���悤�ł����B�����n���Ɉ��������Ă��̎��������Ă��܂��B�����Č��Ƃ����̂̓K�����I�ɂ���āA�n���Ɠ������R��J������A�傫�Ȋ�̌ł܂�ł��邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B �@ �����Ńj���[�g���͎��̂悤�ɍl���܂����B �@ �u�P�v���[��3�@���𐬂藧������͂́A�ʂɑ��z���L�̂��̂ł͂Ȃ��悤���B�ؐ��Ɖq���A�n���ƌ��Ƃ̊Ԃɓ����͂��������̂��낤�B�Ƃ������Ƃ́A�ǂ�ȓV�̂����̓V�̂���������Ƃ͌����Ȃ����낤���B����A�܂Ă�B�K�����I�����炩�ɂ����悤�ɁA���͑傫�Ȋ�̂悤�Ȃ��̂��B�n�������Ċ�̌ł܂�B�₪������������Ă���B�c�E�B�v �@ �j���[�g��������Ȃ��Ƃ��l���Ă���Ƃ��A�����S������c�B �@ �u�������I�����Ƃ������I�V�̂���łȂ����ׂĂ̕��̂ɑ��̕��̂���������͂�����̂��I�I�����n���̎��������Ă���̂́A�n���������������邩��B�����S��������̂��n���������S���������邩��B�n���Ƃ����̂͊�̌ł܂�B��̌ł܂肪�����S����������B���Ƃ��������������B�������Ƃ����炻���ɓ]�����Ă���₾���ă����S�����������Ă���͂����B�v �@ �������āA�j���[�g���̓����S�����痎����̂����āA�u���ׂĂ̕��̂����̕��̂������B�v�Ƃ����u���L�v���̖͂@�������܂����B �@ �j���[�g���́A����Ɏ��甭��������p����p�̖@���ƁA���̂ɓ����d�͂����̕��̂̎��ʂɔ�Ⴗ�邱�Ƃ��g���Ď��̂悤�Ɍ��_���܂����B �@ �y���L���̖͂@���z���ׂĂ�2�̕��̊ԂɈ��͂������A���̈��͂̑傫���͂����̎��ʂ̐ςɔ�Ⴕ�A������2��ɔ���Ⴗ��B �@ �j���[�g���́u���L���̖͂@���v�́A�P�v���[��3�@����������邽�߂ɐ��݂����ꂽ�̂ł����A�j���[�g���̂��炵���́A�P�ɂ���ɂƂǂ܂炸�A�����O���Ɉ����~�߂Ă���͂��������镨��(�����S���)�ɓ����͂Ɠ������̂ł���A�܂����ׂĂ̕��̊Ԃɓ������̂ł��邱�Ƃ����ʂ������Ƃɂ���Ǝv���܂��B �@ �������ăj���[�g���́u�̖͂@���v�̈�ł���u���L���̖͂@���v�Ɓu�^���̖@���v�����܂����B�u�̖͂@���v�́u���L���̖͂@���v�ȊO�ɂ�����������܂����A�u�^���̖@���v�͈��������܂���B�u�^���̖@���v�������������āA�݂�ȈႤ�������o���ꂽ�獢���Ă��܂��܂��B �@ ������������Ȃ��u�^���̖@���v�������̂ł�����A�j���[�g���������ɂ��炵���������킩��ł��傤�B |
|
|
��17�D���͗����Ă���
�@ �����n���̂܂������Ƃ������Ƃ́A�����n���Ɂu���������Ă���v���Ƃ��Ӗ����܂��B�n��̕��̂�1�b�Ԃ�5���ʗ����܂��B�ł͒n���̔��a��60�{���ꂽ����1�b�Ԃɂǂ̂��炢�����Ă���̂ł��傤���B �@ �z��Y�@60�{����Ă���ƒn���̈��͎͂�܂�̂ŗ����鋗���͏������Ȃ�̂��ȁB �@ �Ԏq�@�����ˁB5����1/60��10�����ʂ�����H �@ �z��Y�@����A�Ⴄ��B���L���͂͋�����2��ɔ���Ⴗ��Ƃ����̂�����A1/60��2���1/3600�ɗ͎͂�܂��Ȃ��H �@ �Ԏq�@�����A�������B�v�Z����ƁA���[�ƁA1�`2�����ʂ�����B �@ �z��Y�@�m���Ɍv�Z�ł͂����Ȃ邯��ǁA�����P���ɍl���Ă����̂��ȁB |
|
|
��18�D���������鋗��
�@ �n���\�ʂŕ��̂�1�b�Ԃɐ��m�ɂ�4.9�������܂��B�����Č��͒n���̔��a�̖�60�{���ꂽ�Ƃ��������Ă��܂��B���L���̖͂@���ɂ��ƁA���͂͋�����2��ɔ���Ⴕ�܂��B�ł����猎�̋O��������Œn���̈��͂́A1/602��1/3600�Ɏ�܂��Ă���͂��ł��B �@ ���L���̖͂@�������Ƃɂ���ƁA �@ 4.9m/3600��0.0014m��1.4mm �@ ���͖�1.4mm�����邱�ƂɂȂ�܂��B �@ �������A�{���Ɍ���1.4mm�����Ă���̂ł��傤���B���L���̖͂@���͖{���ɐ������̂ł��傤���B���ɂ�����m���߂Ă݂܂��傤�B �@ ���͒n���̔��a�̖�60�{�̂Ƃ���A�܂�384�A000km�͂Ȃꂽ�Ƃ��������Ă��܂��B�������1�J���A���m�ɂ� 27.3���Œn���̂܂���1�����܂��B���̂��Ƃ��猎�̓����������v�Z����ƁA�E�E�E�ƂȂ�܂��B �@ �ł́A���ۂ�1�b�ԂɌ��������鋗�����v�Z���Ă݂܂��傤�B�}�Ł�MM''O�Ɓ�M"M'M�͑����ł��B�Ƃ���łl�l�h�����ł�����A �@ 2�q�F�������F���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ 2�~384000�F1.02��1.02�F���@�@�@�@�@�@�@ �@ ���L���̖͂@�����狁�߂����̗��������ƁA���̌��]������27.3���Ƃ����������狁�߂����������͂҂������v���܂��B����͖��L���̖͂@�����m���ɐ��������Ƃ̏ؖ��Ƃ����܂��B�j���[�g���������v�Z�����āu���L���̖͂@���v�̐��������m�M�����Ƃ������Ƃł��B |
|
|
��19�D���������͂͑��z�̕����傫��
�@ ���ɓ����n���̈��͂Ƒ��z�̈��͂ł͂ǂ��炪�傫���̂��낤�B�u�����n���̂܂�������Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�n���̈��͂̕����傫���̂ł͂Ȃ����B�v�����v�����l������ł��傤�B���L���̖͂@�����g���Čv�Z���Ă݂܂��傤�B �@ ���z�|���Ԃ̕��ϋ����͒n���|���z�Ԃ̖�400�{�A���z�̎��ʂ͒n���̖�33���{�ł��B���L���͂̑傫���́A���ʂɔ�Ⴕ������2��ɔ���Ⴗ��̂ŁA�n�������ɂ���ڂ����͂̑傫����1�Ƃ���Α��z�̈��͂� �@ �܂�A���ɓ������z�̈��͂͒n���̈��͂��A2�{�ȏ�傫���̂ł��B |
|
|
��20�D�������z�̎��������Ă���
�@ ���z�𒆐S�ɂ��Ă݂�ƁA���͂ǂ�ȋO����`���Ă���̂ł��傤�B��̗̂l�q��`���Ɖ��̐}�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B���͌������z�̎��������Ă���̂ł��B�����Č��ɓ������z�̈��͂����S�͂ƂȂ��Ă��܂��B�n���̈��͂͌��̋O�������E�ɗh�炵�Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ������܂��B �@ �u�������z�̎�������̂͒n���ɘA����Ă��邩��ŁA�����n���̈��͂��Ȃ��Ȃ�Ό��͑��z�̎�������Ȃ��Ȃ��Ȃ����ȁB�v �@ �����v���l�����邩���m��܂���B����������Ȃ��Ƃ͂���܂���B�����n���Ɉ��͂��Ȃ������Ƃ�����A���͒n���Ɠ����O�����������đ��z�̎�����Ȃ߂炩�ɉ�邱�ƂɂȂ�܂��B |
|
|
��21�D�F���V�j�̘b
�@ �X�y�[�X�V���g���ɏ�����F����s�m���D�O�ɏo�āA�F���V�j�����Ă���l�q���e���r�ȂǂŌ������Ƃ�����ł��傤�B���̂Ƃ��A�F����s�m�ɓ����͂͒n���̈��͂����ł��B�X�y�[�X�V���g�����l���������͔͂��ɏ������قƂ�Ǔ����Ă��Ȃ��Ƃ����ėǂ�����ł��B���������̂��߂ɉF����s�m���n���ɗ����Ă�������A�X�y�[�X�V���g��������c���ꂽ��͂��܂���B�X�y�[�X�V���g���Ɠ����O���������ʼn��܂��B�F����s�m�͂���Έ�̐l�H�q��(�l�ԉq��)�ƂȂ��Ēn�������Â��܂��B �@ �Ƃ���ł��̂Ƃ��A�X�y�[�X�V���g���̒���F����s�m�͖��d�͏�ԂƂȂ��Ă��܂��B�������A���d�͏�ԂƂ����Ă��u�d��(���L����)�������Ă��Ȃ��B�v�Ƃ����킯�ł͂���܂���B�u�d�͂����������̂́A���̂̎��ʂɊW�Ȃ����ׂē����^��������v�̂Ŗ��d�͂ɂȂ�̂ł��B���̂��Ƃ́u���������v�ƌĂ�A��{�I�ɂ̓K�����I�������������Ƃł��B �@ �A�C���V���^�C���͂��́u���������v�Ɓu��ʑ��ΐ������v�����ƂɁu���L���̖͂@���v�ɑ���u��ʑ��ΐ����_�v��ł����āA�d�͂̂Ȃ��ɂ��ǂ݂܂����B�u��ʑ��ΐ������v�Ƃ����̂́u���ꑊ�ΐ������v������Ɉ�ʉ��������̂ł��B�u���ΓI�Ɉ�l�ȑ��x�ʼn^�����Ă���ꍇ����łȂ��A�ǂ�ȉ^�������Ă����蕨�̏�⒆�ł��A�����@���͓����ɂȂ�B�v�Ƃ��������ł��B �@ ���z�̈��͂��錎��n���́A�n���̈��͂���X�y�[�X�V���g����F����s�m�Ɠ������Ƃł��B���ƒn���͑��z�̈��͂��Ă��܂����A����Ζ��d�͋�Ԃɕ�����ł���Ƃ����ėǂ��̂ł��B�����n���̈��͂��������߂ɁA���͒n���̎�������܂��B�ł����猎��n���Ɉ������߂Ă������߂̗͂́A���z�̈��͂��傫���K�v�͂܂���������܂���B�@ �@ |
|
| ���R�y���j�N�X�͂Ȃ��n�������������̂� 3 | |
| �R�y���j�N�X���A�����x�z�I�������v�g���}�C�I�X�̓V�����ɔ����Ēn�������咣�������Ƃ́A�@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����ƌĂׂ���̂ł͂Ȃ������B�R�y���j�N�X�̃��f���̓v�g���}�C�I�X�̃��f���������m�ł��Ȃ���ΒP���ł��Ȃ������B����ɂ�������炸�A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n�����������A������ɖ��������V���w�҂����Ȃ��炸�����̂́A�������z���q�̃l�I�v���g�j�Y�������s���Ă�������ł���A�����Ă���͓������ߑ㏬�X���ƌĂ�銦����ł��������ƂƊW������B | |
|
��1 �R�y���j�N�X�̒n�����ɉȊw�I�������͂������̂�
�@ �n����ɑ��݂��鎄�������A�n���͐Î~���A�^�����Ă���͓̂V�̂̕��ł���Ƃ݂Ȃ����Ƃ͎��R�Ȃ��Ƃł���A�×��A���������n�����S�̓V���������R������Ă����B�Ñ�M���V���̎���ɂ́A�T���X�̃A���X�^���R�X�ȂǁA���z���S�̒n������������҂����Ȃ��炸�������A�ނ�ْ͈[�Ƃ��Ĉ����A���[���b�p�ł�16���I�܂ŁA�n�����S�̓V�������A�L���X�g���Ƃ������I�ȃR�X�����W�[�Ƃ��ĐM�����Ă����B �@ �����Ɍ����A�n����������Ƃ��V�������Ƃ������́A���z���S��������Ƃ��n�����S�����Ƃ������Ɠ����ł͂Ȃ��B�����C���h�̐��w�҂ɂ��ēV���w�҂̃A�����o�[�^�́A�F���̒��S��n���Ƃ����A�n�����n���𒆐S�Ɏ��]���Ă��邱�Ƃ�F�����Ă����B�����C�X�����̕����w�ҁA�C�u���E�A�����n�C�T���������悤�Ȍ�������������A���������n�����S�̒n�����͒n�����S�̓V�������瑾�z���S�̒n�����ւ̉ߓn�I�`�Ԃƈʒu�t���邱�Ƃ��ł���B �@ �n�����S�̓V�����͑����̐l�ɂ���Ē��ꂽ���A���ł��A�Ñネ�[�}�̎���Ɍ��ꂽ�A���N�T���h���A�̃N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�̓V���w�́A�ł����_�I�Ȋ����x�������A�w�I�ɐ�������Ă���A�ނ̒���w�A���}�Q�X�g(Almagest)�x�́A�����ɂ�����ł����Ђ̂���V���w���ł������B�������A1543�N�ɏo�ł��ꂽ�w�V����]�_(De revolutionibus orbium coelestium)�x�ŁA�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�́A�v�g���}�C�I�X�̒n�����S�̓V������ے肵�A�ߑ�ōŏ��ɑ��z���S�̒n�������������B �@ �ȉ��̐}�̉E���́A�w�V����]�_�x�Ɍf�ڂ���Ă���V���̊T���}�ŁA���̐}�ł́A�n���̎�����܂���Ă���̂͌������ŁA�F���̒��S�ɑ��z(SOL)������A���̎�����A�������珇�ɁA�����A�����A�n���A�ΐ��A�ؐ��A�y�������A��ԊO���ɂ́A�s���̓V�������邱�Ƃ�������Ă���B�}�̍����́A������̒n�����S���Ɋ�Â��V���̊T���}�ŁA�F���̒��S�͒n���ŁA���̎�����A�������珇�ɁA���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y��������Ă���B �@ ���z���S�̒n�����́A���̌�A���n�l�X�E�P�v���[��K�����I�E�K�����C�ɂ���Ďp����A�ߑ�V���w�̃p���_�C���ƂȂ����B�ȉ��̃A�j���[�V�����́A�P�������ꂽ���z(���F�̓_)���S�̒n�����ƒn��(�F�̓_)���S�̓V�����Ɋ�Â��ΐ�(�ԐF�̓_)�̋t�s��������郂�f���ł��邪�A�O�҂̕�����҂����ΐ��̋O�����P���ƂȂ�B������A�����ł́A���z�n�̘f���̉^���́A���z���S���Ɋ�Â��Đ��������B �@ �ł́A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n���������������Ƃ́A�������x�z���Ă����@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����Ƃ݂Ȃ��Ă悢�̂��낤���B�������Ǝv���Ă���l���������A���ۂɂ͂����ł͂Ȃ������B�g�[�}�X�E�N�[���������悤�ɁA�u�R�y���j�N�X�̃V�X�e���́A�v�g���}�C�I�X�̃V�X�e���Ɣ�ׂāA�P���ł��Ȃ���ΐ��m�ł��Ȃ��v���炾�B �@ �ǂꂾ���P���ł����m�ł��Ȃ�������̓I�Ɋm���߂悤�B�R�y���j�N�X�̍ŏI�I�ȗ��_�ł́A�ȉ��̐}(a)�Ɏ�����Ă���悤�ɁA�n���� OE �𒆐S�Ƃ����~�O���ʼn�]���A���� OE �́AO �𒆐S�ɂ������Ɖ�]���A�����Ă��� O �����z S �̎������]����B�ΐ��́A�ȉ��̐}(b)�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���]�~�ʼn�]���A���̎��]�~�́A�n���̋O���̒��S�ƈ��̊w�I�W���������_�AOM �𒆐S�Ƃ����]�~�O�������]����B �@ 1609�N�ɃP�v���[�́A�f�������z����̏œ_�Ƃ���ȉ~�O������A���̑��x�͑��z�Ƃ̋����ɔ���Ⴗ�邱�Ƃ��������A�R�y���j�N�X�́A�f�����~�O������~�^������Ƃ����O��̂��ƁA�f���̕s�K���ȉ^�����~�^���̑g�ݍ��킹�Ő������悤�Ƃ������߁A���̃��f���͕��G�Ȃ��̂ƂȂ����B���̂悤�ȕ��G�ȃ��f���Řf���O�����v�Z���邱�ƂɎ��p�I�ȃ����b�g�͂Ȃ��B����ɂ�������炸�A�R�y���j�N�X�����z���S������A�����Ȃ�ʐl�X������ɖ������ꂽ���R�͉��������̂��B�N�[���͎��̂悤�Ɍ����Ă���B �@ ���̖₢�ɑ��铚���́A�w�V����]�_�x�ɖ��ڂ̋Z�p�I�ڍׂ���e�Ղɓǂ݉������Ƃ͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�R�y���j�N�X���g���F�߂�悤�ɁA���z���S�̓V���w�����ۂɑi���Ă��邱�Ƃ́A���p�I�Ƃ��������R���I�ł��邩�炾�B�V���w�҂ɂƂ��āA�R�y���j�N�X�̃V�X�e����I�Ԃ̂�����Ƃ��v�g���}�C�I�X�̃V�X�e����I�Ԃ̂��Ƃ����ŏ��̑I���́A�����ς��̖��ł������肦���A��̖��́A���肵����c�_�����肷���ōł�����Ȃ��ƂȂ̂ł���B�������A�R�y���j�N�X�I�]�����ł���悤�ɁA��̖��͂ǂ��ł��悢���ł͂Ȃ��B�w�I�ȃn�[���j�[�������鎨�́A�R�y���j�N�X�ɂ�鑾�z���S�̓V���w�ɂ����ĐV���ȋϐ��Ɠ�������邱�Ƃ��ł����̂ł���A���̋ϐ��Ɠ��ꂪ�F������Ă��Ȃ������̂Ȃ�A�����Ȃ�]����Ȃ�������������Ȃ��B �@ �R�y���j�N�X�́A�w�V����]�_�x�ŁA�n�����S�̓V�����ɍ������Ȃ����Ƃ��~�X�咣���Ă���B���̎咣�͐��������A��ʓI�Ɍ����āA�ǂ̊ϑ��n�_����^�����L�q���邩�͜��ӓI�Ȗ��ŁA���x��P�����ɑ卷���Ȃ��Ȃ�A���z���S����������ƒn�����S�����́u��̖��v�ƂȂ炴��Ȃ��B�ȉ��́A�w�V����]�_�x�ŃR�y���j�N�X�����z���S�����咣���Ă���ӏ��ł��邪�A�����ǂ߂A���̍����͉Ȋw�I�ł͂Ȃ��A�ނ���@���I�M�O�Ƃł��ĂԂׂ����̂ł��邱�Ƃ��킩��B �@ �����̒��S�ɂ́A�ԈႢ�Ȃ����z���Î~���Ă���B�Ƃ����̂��A�N���A���̍ō��ɔ��������@�m�F���n�ɂ����āA���̃����v�m���z�n���A�������炷�ׂĂ��ɏƂ炵�o�����Ƃ��ł���ꏊ�m�F���̒��S�n�ȊO�̂��ǂ��ꏊ�ɒu�����Ƃ��ł��悤���B���ہA���z�́A�u�F���̃����v�v�A�u�F���̐S�v�A�u�F���̎x�z�ҁv�ƌĂ�邪�A���������ď͕̂s�K�ł͂Ȃ��B�w�����X�E�g���X���M�X�g�X�͑��z���u�ڂɌ�����_�v�ƌĂсA�\�|�N���X�́w�G���N�g���x�́u���ׂĂ����n���ҁv�ƌĂ�ł���B�������đ��z�́A���ɉ����ɍ��邩�̂��Ƃ��A���̎������]����f���̉Ƒ����x�z����̂ł���B �@ ���ǂ̂Ƃ���A�R�y���j�N�X�����z���S�̒n���������������Ƃ́A�@���I���M�ɑ���Ȋw�̏����ȂǂƂ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�`���I�ȏ@���I�M�O�ɕʂ̏@���I�M�O��Βu�����������Ƃ������ƂɂȂ�B�ł́A�R�y���j�N�X���M�����@���Ƃ͉��������̂��B�����Ƃ��L�͂Ȍ��́A�������s���Ă������z���q�̐_��v�z�A�l�I�v���g�j�Y���ł���B |
|
|
��2 �l�I�v���g�j�Y���͂Ȃ��n�����@�t�����̂�
�@ �l�I�v���g�j�Y�� �Ƃ́A���[�}�鍑�����3���I�ɁA�G�W�v�g�o�g�̃v���e�B�m�X���A500�N�O�̎v�z�ł������v���g���̓N�w(�v���g�j�Y��)���p�����č��グ���_��v�z�̂��Ƃł���B15���I�̃t�B�����c�F�ŁA�}���V���I�E�t�B�`�[�m���A���f�B�`�Ƃ̕ی�̂��ƃv���g����v���e�B�m�X�̒��������e����ɖ|��ƁA�ނ�̎v�z���ĂуC�^���A�Ńu�[���ɂȂ����B �@ �l�I�v���g�j�Y���́A���[�}�鍑����ɗ��������I���G���g�̐_��v�z�̉e�����Ă���A�{���̃v���g���N�w����͂��Ȃ��E�����v�z�ł��������A�v���e�B�m�X�ɂ͓Ǝ��̎v�z��������Ƃ������o�͂Ȃ��A�t�B�`�[�m���v���e�B�m�X���v���g���̐^���Ȍp���҂ƔF�����Ă����B�����瓖���́u�l�I�v���g�j�Y���v�Ƃ������t�͂Ȃ������B���̌��t�́A�v���g���̖{���̓N�w�ƌ㐢�ɂ�����������ʂ��邽�߁A19���I�Ƀt���[�h���q�E�V�����C�A�}�n�[���l�Ă������̂ł���B �@ �v���g�j�Y���̒��S�̓C�f�A�_�ł���B�v���g���ɂ��A�C�f�A�Ƃ́A���o�I�Ώۂ����ϔO�̂��Ƃł���B���o�I�Ώۂ��ꎩ�̂̓C�f�A�ł͂Ȃ��B�Ⴆ�Ή~�̃C�f�A���l���Ă݂悤�B���̐��E�ɂ́A���o�̑ΏۂƂȂ�ۂ����͑��݂��邪�A�����͂ǂ���w�I�ɒ�`���ꂽ���S�ȉ~�ł͂Ȃ��B����ɂ�������炸�A�����������S�ȉ~�̊ϔO(�C�f�A)�𗝉�������̂́A�����������ăC�f�A�̐��E�ɏ������A�����z�N���邩��ł���B�w���m���x�ɓo�ꂷ��z�N���ł���B�����ŁA�C�f�A�̐��E�́A���̊��S���䂦�ɁA�^�̎��݂ł���A����ɑ��Ċ��o�̑ΏۂƂȂ邱�̐��E�̓C�f�A��͕킵�č��ꂽ�U��̉��ۂɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@ �C�f�A�̐��E�̓����ɂ����Ă�����ɊK�w�������āA���������C�f�A��F�����邱�Ƃ��ł���̂́A�C�f�A�̃C�f�A�Ƃł������ׂ��P�̃C�f�A�̂������ł���B�v���g���́A�w���Ɓx�ɂ����āA�P�̃C�f�A�ƈ�ʂ̃C�f�A�ƃC�f�A�̔F���҂Ƃ̊W�z�Ƒ��z���Ō�������̂ƌ��镨�̊W�ɚg���Ă���B �@ �����P�̎q���ƌ����Ă����̂͑��z�̂��Ƃ��Ɨ������Ă���B�P�͑��z�������Ɨޔ�I�Ȃ��̂Ƃ��Đ��ݏo�����B���Ȃ킿�A�v�҂ɂ���Ēm���鐢�E�ɂ����āA�P���s�m����́t�Ɓs�m������́t�ɑ��Ď��W�́A�����鐢�E�ɂ����āA���z���s������́t�Ɓs��������́t�ɑ��Ď��W�Ƃ��傤�Ǔ����ł���B �@ �P�̃C�f�A�Ɋ�Â��ăC�f�A������A�C�f�A�Ɋ�Â��Ċ��o�I�Ȑ��E�����ꂽ�Ƃ���v���g�j�Y���́A�_���P�ӂŐ��E��n�������Ƃ���L���X�g���̎v�z�Ɠ����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�v���e�B�m�X�́A�L���X�g���k�ł͂Ȃ��������A�P�̃C�f�A���u��ҁv�ƌĂсA�����_�Ɠ��ꎋ�����_���I�ȉ��߂��{�����B�v���e�B�m�X�ɂ��A��҂��痝�����A��������썰���u���o�v���A���l�Ȑ��E�����o���Ă���B�v���e�B�m�X�́A��҂z�ɁA�����̗��o�z���˂ɁA�썰�z�����ċP�����ɚg���Ă���B �@ �v���g���ɂƂ��Ă��A�v���e�B�m�X�ɂƂ��Ă��A���z�͑P�̃C�f�A�̔�g�ł����āA�P�̃C�f�A���̂��̂łȂ����Ƃ͂������A��ʓI�ȃC�f�A�ł���Ȃ��A����Ȃ銴�o�̑Ώۂɂ����Ȃ��B�������A�t�B�`�[�m�͑P�̃C�f�A�Ƒ��z�ꎋ���A���̌��ʃt�B�`�[�m�̃l�I�v���g�j�Y���͂��Ȃ��瑾�z���q�̏@���̂悤�ɂȂ����B�R�y���j�N�X�̓t�B�`�[�m�̑��z���q�v�z�̉e�����đ��z���S�̒n�������l�Ă����̂ł͂Ȃ����ƃN�[���͌����B �@ �Ⴆ�A�t�B�`�[�m�́A���z���ŏ��ɂ������V�̒����ɍ��ꂽ�ƒ���ɏ������B�������ɑ��z�̈Ќ��Ƒn���I�@�\�ɂӂ��킵�������̈ʒu�͑��ɂ͂��蓾�Ȃ��B���������̈ʒu�̓v�g���}�C�I�X�̓V���w�Ƃ͗����s�\�ł���A��������A������l�I�v���g�j�Y���̖����������邽�߂ɁA�R�y���j�N�X�͑��z���S�̐V�����V�X�e�����\�z����Ɏ������̂�������Ȃ��B �@ �ł́A�Ȃ����̎���ɑ��z���q�̎v�z�����s�����̂��B��������ɍl���Ă݂悤�B |
|
|
��3 �n�����ƓV�����̎���w�i�͉���
�@ �ߑ�ȑO�̓V���w�ł́A���̉^�s�����������ׂ��V�̂́A���z�ƌ��ƌ܂̘f���Ɍ����Ă����B�n�����܂߂����̓V�̂̉^�����L�q���邾���Ȃ�A�n�����S�̓V�����ł����z���S�̒n�����ł�����I�ɊԈႢ�Ƃ͌������A�ǂ����I�Ԃ��́u��̖��v�Ȃ����͏@���I�ȃR�X�����W�[�̖��Ƃ������ƂɂȂ�B�����̉Ȋw�҂��@���I���R�œV���w�I���_�𐳓������邱�Ƃ͂Ȃ����A�R�y���j�N�X�̎���܂ł́A�܂�V���w�Ɛ萯�p�����m�ɕ�����Ă��Ȃ���������ɂ����ẮA�@���I�ȓ��@���d�v�Ȗ������ʂ����Ă����ƌ����Ă悢�B �@ �ł́A���̏@���I���@�͉���w�i�ɂ��Ă����̂��B�ߋ��̗��j��U��Ԃ�ƁA���g���ɂ͓V�������A������ɂ͒n��������������X�������Ď�邱�Ƃ��ł���B�Ȋw���@������Ɨ�����ȑO�̎����ɂȂ����̂悤�Ȃ��Ƃ�������̂��A���R���l����K�v������B �@ �C��ƃR�X�����W�[�̊W �@ ���g�̎���敪/�R�X�����W�[ �@ �Ñ㊦���(800~250BC) / �Ñ�M���V���̎���B�T���X�̃A���X�^���R�X�Ȃǂ����z���S�̒n���������B �@ �Ñ㉷�g��(250BC~AD400) / �Ñネ�[�}�鍑�̎���B�v�g���}�C�I�X���n�����S�̓V�������W�听����B �@ ���������(AD400~950) / �����C���h�ŃA�����o�[�^���n���̎��]���咣���A���̔F�����C���h�ōL�܂�B �@ �������g��(AD950~1250) / �����C�X�����Ȋw�̑S�����B�v�g���}�C�I�X�̒n�����S�̓V�������x�z�I�ƂȂ�B �@ �ߑ㊦���(AD1250~1830) / �R�y���j�N�X�A�P�v���[�A�K�����I�Ȃǂɂ�鑾�z���S�̒n���������y����B �@ �ߑ㉷�g��(AD1830~����) / �F���ɂ͒��S���Ȃ����Ƃ��킩��B���z�͍Ăѓ����I�Ȉʒu�������B �@ �ǂ̕����ɂ����z���q�̎v�z�������ꏭ�Ȃ��ꂠ����̂����A���q�̔O�́A���z��������܂銦����ɂ����ċ��܂�B����͋t�ł͂Ȃ����Ǝv���l�����邩������Ȃ����A�����v���l�́A�J��͂ǂ��������ɍs������̂Ȃ̂����l���Ă݂�ׂ����B���R�M���������l���A�J���~�炷�ƐM����_���̂��A���̐_�ɑ��ĉJ�������̂́A�J���~��Ȃ����������A��鯂ŋꂵ��ł��鎞�ł���B���l�ɁA���z�������ቺ���A�앨������Ȃ��Ȃ��ď��߂Ď������͑��z�̂��肪���݂��������A����������炵�Ă����ƐM���Ă��鑾�z�_�𐒔q������̂Ȃ̂ł���B �@ ���z�����������Ȏ��A�앨�͗ǂ�����A�������͓��ɓw�͂����Ȃ��Ă������Ă������Ƃ��ł���B���z�������ቺ����Ƃ���Ƃ͋t�̌��ʂƂȂ�A�������́A�������т邽�߂ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B���z���������������Ƃ������Ƃ́A�����Ă������z�̒�~�ƈӎ�����A�������̑��������Ƃ������Ƃ͒n���̉^���Ƃ������z�ɂȂ���B���z�����������ȉ��g���ɂ͏펯�I�ȓV�������M�����A�����ł͂Ȃ�������ɂȂ�ƒn������������ْ[�������̂́A���������v�z�X�����w�i�ɂ���̂ł͂Ȃ����낤���B �@ ���Ԃ�A�����̐l�͂������������������Ă���Ɗ����邱�Ƃ��낤�B�������A����͉Ȋw�I�Ȑ����Ɋ��ꂽ����l�̕Ό��Ƃ������̂ł���B�R�y���j�N�X�̎���܂ł́A�V���w�́A�V�̉^�����ے���`�I�ɉ��߂���萯�p�̎�������܂����S�ɒE�p���Ă��Ȃ������B�v�g���}�C�I�X�́w�A���}�Q�X�g�x�����V���w�҂ł���Ɠ����Ɂw�e�g���r�u���X�x�����萯�p�t�ł����������A�R�y���j�N�X���܂��A�V���w�����łȂ��A�萯�p�̕������Ă���B������A�R�y���j�N�X�̗��_���Ȋw�I�������Ɍ����ے���`�I�ȍ����Ɋ�Â��Ă����Ƃ��Ă��A����͋����ɒl���Ȃ����ƂȂ̂ł���B�@ �@ |
|
| ���n���� 4 | |
|
�R�y���j�N�X(1473�|1543)���A�n�����������Ă����A�K�����I(1564�|1642)���܂��n�����\�����B�R�y���j�N�X�͒n�����𐔊w�I�����Ƃ������߂ɏ@���ٔ��ɂ������邱�Ƃ͂Ȃ��������A�n���͕s���ł���A�V�������Ă���Ƃ��鐹���̋L�q����A�K�����I�ْ͈[�҂Ƃ��ď@���ٔ��ɂ������A�������������߂���Ȃ����n�ɒǂ����܂ꂽ�B�u����ł��n���͉���Ă���v�Ƃ����̂́A�K�����I�̌��t�Ƃ���Ă���B�K�����I�̖��_���s���A�_�[�E�B���̐i���_���w�����ȏ�̂��́x�ƔF�߂�ꂽ�́A�����̊Ԃ̃p�E��2��(1920-2005)�̎��ł���B
�@ �K�����I���A�n�������ؖ����������́A�����̖����������ώ@���Ă��āA�s�v�c�Ȃ��Ƃ��������Ƃł���Ɠ`����Ă���B �@ �������O����(�H)�ɂȂ������ƁA����(�H)�ɂȂ������Ƃł́A���̑傫�����Ⴄ�ƌ������ƂɋC�Â����B�O������ɂȂ������͑傫���A������ɂȂ������͏�����������Ƃ����̂ł���B �@ �f�l�̎��ɂ͎c�O�Ȃ�������̖���(�H)�Ƌ����̐V��(�H)�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�s���z��ῂ������āt�A�������O�����A�O���������������邱�Ƃ͂ł���悤�Ɏv����B �@ �n���Ƌ����̋����́A�����ɋ߂��قlj����A�O�����ɋ߂��قNj߂��Ɉʒu����B�}�Ō���Έ�ڗđR�ł͂��邪�A���̐}���l������ȑO�ɁA�����̑傫���̑��Ⴉ��A�������n�������z�̎��������Ă���ȂǂƁA�悭���l���������̂ł���B �@ �K�����I�̍l������������Ƀj���[�g���̖��L���̖͂@��������A�A�C���V���^�C���̑��ΐ�����������̂��Ƃ�������������B �@ �u�悭�ώ@����v�Ƃ������Ƃ��^�������������肾�Ăł��邱�Ƃ̏ؖ����B �@ ����Ȃ��Ƃ��l���Ă���ƁA���������̖������o�鍠�ɂȂ��Ă��܂����B �@ �����łӂƎv�����̂ł���B �@ �n���̐ԓ��t�߂̉~����40077Km���������B�n���͈���Ɉ��]����̂ŁA�ԓ��t�߂̐l�́A����1670Km�̑����œ��Ɍ����Đ������ł��邱�ƂɂȂ�B �@ �ɓ_(�k�ɓ_�E��ɓ_�t�߂̒n��)����1m���ꂽ�l�̈���ɉ�鋗���͖�3m�B����ƁA�����ɗ����Ă���l�͎���125cm�œ��Ɍ����ĉ�]���Ă��邱�ƂɂȂ�B�ڎ�蒎�����x���X�s�[�h���B �@ ����Ȃɂ��̂������X�s�[�h�̍�������ɂ�������炸�A�ԓ��ɋ���l���ɓ_�ɋ���l���A���ɖ�1��Km�̘r�������Ă�����A����Ⴄ���ƂȂ����肷�邱�Ƃ��ł���B �@ ����҂Ă�A���R�[�h�Ղ����Ă�������Ȃ��������H �@ ���S�t�߂̃X�s�[�h�͒x���A�~�Ղ̒[�̕��قǃX�s�[�h���������A���R�[�h�Ղɂ����S�~�́A�݂��̈ʒu�W��ۂ��Ȃ������Ă����B �@ ����͂�A�b�͓r�����Ȃ������֍s���̂����A�n���͑��z�̎������N�����Ĉ��肷��̂����A�n��������Ă����X�s�[�h�́A����107�A229Km�Ȃ̂��������B�S�r�A�g�������Ēǂ����Ȃ������m��Ȃ��B �@ ���z�n���̂��̂���͂̒��ʼn���Ă���A��͂��r�b�O�o���̔j��̃X�s�[�h�ɏ���Ă��̂������X�s�[�h�Ŏl�������ɍL�����Ă���Ƃ�������A���͂�������������̃X�s�[�h�ňړ����Ă���̂��낤���H �@ ���o����O���琢�E�ȂǂƂ������̒P�ʂ̌��_�������ɂ���̂����A�����͓V�����������̂��n�������������Ƌ^��������Ă����B �@ �I���O6�`5���I���̃C���h�ɂ́A���J���i�邱�Ƃ�E�ƂƂ��A�A�[���A�l(���̒n�悩��C���h�N�����Ă�������)�ɂ��C���h������_�b�I�ɐ����A�l�⎩�R�͐_�X��F���n����(�������u�u���t�}���v�ƌĂ�ł͖`����������Ȃ���)��������̂Ƃ���x�[�_���T��M��o�������ƁA���̐��E�ɂ͂������̗v�f�������āA����炪�W�����Ă��̐����\�����Ă���ƍl�����V�����}�i(����)�����@�����͂Ƃ��Ă������ƌ����Ă���B �@ �V�����}�i�B�́A�N�����E����������Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��A���̐��ɑ��݂���S�Ă̂��̂́A���݂ɊW���������Ő������A���̊W�̊ւ�肪��ł���Ƃ������Ƃ��ő�̉ۑ�ł������B �@ �߉ނ������V�����}�i�B�̈���ł������B���̂�����̂��Ƃ́A�u�k�Њw�p���Ɂw���ɂ̂��������������Ɓx(�c�㑾�G��)�ɏڂ����L�ڂ���Ă���B �@ ������栚g�������̂ŁA���������V�����̗l�Ȑ����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B���̓o�������̍l�����傢�ɉe�����Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������B�A�j���f��w�V��̏郉�s���^�x�̗l�ɁA���E�����ɕ����Ă���G���������̂��B���}���������Ėʔ������A�����͐����Ⴄ�B �@ �n���̒n���͏����h�炢�ł���̂ŁA�n�����猩���k�ɂ̕����Ƃ����͍̂��^��(�R�}�����I����O�ɂ́A�����傫���Ԃ�铮���̂悤�Ȃ���)�ɂ���āA�F����Ԃ̒��ł̐�ΓI�k�ɂƂ����̂͂Ȃ��āA��25800�N�������ɋɕ������ړ�����Ƃ����̂ł���B �@ �����ߏ\�����y�ɋɊy��y�������āE�E�E�E�ƌo���ɂ��邪�A����Ƒ҂��āB�����̍��͂����Ă��قړ�ɕ����Ƃ��k�ɕ����͒n�����猩���F���̍��W�Ƃ��Ă̌����͂��̂����A�����ƌ����Ă��A�n���͈����1��]���Ă��āA���̐�����12���Ԍ�ɂ͉F�����W���猩��Ɠ����ɂȂ��Ă��܂��B �@ �ĂȁA���������l����ƁA���o�T��������l�̓��̒��ɂ́A�n�����ł͂Ȃ��āA�V�����������̂����m��Ȃ��B���₢��A�������������I�ȈӖ��ł͂Ȃ��āA��������ň�����I����Ă����A�܂�l���̏I���̕����Ƃ��āA���̕��p���ϔO�I�ɕ\�������̂��Ƃ����B�N�w�Ƃ������͓̂�����̂��B �@ ���������A�u�Ɋy�v�Ƃ������t��������̂̓N�}���W���E(�������Y�@350-409)�Ƃ����l�������B �@ �u�r���ƌځv�Ƃ������t�������āA�u�܂������̑��������Ȃ����v�ƌ����̂�����ǂ��A�F���Ƃ����傫�Ȑ��E�̒�����A�������̐����l�����Ă݂�ƁA�Ȃ�Ə����Ȑ������ł����āA�����Ȃ��ƂɃN���N�����A�W�����Ƃ��Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�W���Ƃ��Ƃ��Ȃ��琶���Ă��錻���������Ă���B �@ �_�˂̖�i�͕S���h�����Ƃ����̂�����ǂ��A���̈��̖�����̉��ɁA�����s�҂�����Εv�w���܂�����A�͂��܂��ߗׂƂ̂��ߎ����A�����Ċ��������Ƃ��y�������Ƃ�����������Ă���B �@ �F���̓r�b�O�o���Ŏn�܂����Ƃ����̂����A�r�b�O�o���̔��o�ɏ���Ă��̂����Ă��鎄�����Ȃ̂�����A���߂Ď�̓͂��͈͂̒��ł́A�s��ՓV�ł͂Ȃ��A���z���M�Ő����Ă����������̂ł���B �@ �u���͎��ł����ėǂ������B�������ł���������A���͂��Ȃ��ɏo����B���Ȃ��ɏo��ėǂ������v�Ƃ��������l��ڎw���̂������̖{���̊肢�ł���ƌ���ꂽ���������B���͂��̔����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�u���͎��łȂ����������悩�����B���Ȃ��Əo������Ȃ������v�ƌ����Ȃ�����͐����Ă���̂����m��Ȃ��B�F���Ƃ����������j�̒��ŁA���̂��������Ă���Ƃ��������͂Ȃ��킢�Ă��Ȃ��̂��낤���H �@�@ �@ |
|
| ���F�� | |
|
���F���̎n�܂�
�@ �u�F���͂ǂ��܂ł킩���Ă��邩�v�Ƃ����\��������̂́A����ƉF���Ƃ����̂��킩���Ă�������ł��B�F�����n�܂��āA���낢��i�����Č��݂̎p�Ɏ����Ă��܂����A����������������肾�ẮA���݂̎p����A���ߋ��֑k���Ă������ƂɂȂ�킯�ł��B�܂蕁�ʂ͎��Ԏ��ǂ���Ɏn�܂肪�����āA���݂܂ŕω����Ă����܂����A�����ɒ��ׂ���͋߂����璲�ׂĂ����̂ŁA���݂��班���́A�����Ă��̂܂��̂Ƃ����悤�ɒH���Ă����킯�ł��B���̈Ӗ��ł́A�A�[�I���@�ƌ����܂����A���ݒm���Ă���m�������ɂ��Ă��ߋ��𐄑����Ă����܂��B�������b�Ƃ��Ă͕K�����Ԏ��ɉ������b�����Ă����킯�ł��B���������āA�l�X���F����F������Ƃ������Ƃ́A�܂����݂̒m���Ă��鐢�E��F��������ŁA���ߋ��͂ǂ��������̂��낤���Ƃ����悤�ɐ������Ă����킯�ł��B �@ �܂��F���̔F���̗��j����H���Ă݂�ƁA��ԏ��߂ɉF���Ɋւ��ĕ`���ꂽ�}�́A�G�W�v�g�l���`�����F���}�ł��B�������A���̐}���`�����O�̐_�b����ɂ��F���_�͂���܂����B���E�������閯���͐_�b�������Ă��܂����A�����ɂ͋��ʂ�����肪����܂��B�ǂ̂悤�ɂ��ĉF�����n�܂����̂��A�ǂ̂悤�ɂ��Đl�Ԃ����܂ꂽ�̂��A�ǂ̂悤�ɂ��ĕ��������܂ꂽ�̂��A�Ƃ����̂��_�b��3�̎��ł��B�F�������̂悤�Ȃ��̂��琶�܂ꂽ�Ƃ��A������A������ƌ����ēV�ƒn�������ꂽ�Ƃ��A���邢�͓V����l�X���~��Ă��āA���̐��E��n�����Ƃ��A�l�X�ȉF���_�b������܂����A����͋�z�������E�ł��B�@ |
|
|
�����Ԙ_
�@ ��̓I�ɉF���̎p��`���������̂́A���������B���n�߂Ă���ł��B���ꂩ�玄�����̎�芪���Ă��鐢�E���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�Ƃ������Ƃ��A��̓I�Ȍ`�ɕ\���悤�ɂȂ����킯�ł��B����1���G�W�v�g�l���`�����F���}�ł��B����͉F���}�ƌ����Ă��{���͒n�}�ł��B�������G�W�v�g�̐l�X�ɂƂ��ẮA���̐��E���F���������킯�ł��B �@ �Ƃ��낪�C���h�l���`�����F���}�ɂȂ�ƁA����ɐ[���ɂȂ�܂��B�F���̌��t�̈Ӗ��������Ă����܂��ƁA�F���́u�F�v�͋�ԁA�u���v�͎��Ԃ��Ӗ����܂��B���������āA�F���_�Ƃ����͎̂��ԋ�Ԙ_�ł��B���������Ԃ��Ԃ͒��ږڂɌ����Ȃ��̂ŁA���̌`��ω��A���邢�͉^����ʂ��Ď��Ԃ��Ԃ�F�����Ă����킯�ł��B�܂��ɃC���h�l���`�����F���}�ɂ͎��Ԙ_�������Ă���킯�ł��B���_�A��Ԙ_�������Ă��܂��B�C���h�l�͒n�����ۂ��ƔF�����Ă����̂ŁA�����ł����ۂ��`���Ă���܂��B�����Ă��̉��ɎR������܂��B����̓G�x���X�g�𒆐S�Ƃ����R�ł����A�����ł����{��R(����݂���)�ł��B���E�̒��S�ɂ���R�̂��Ƃł��B���̉��ɒn���������āA���̒n�����ۂ�3���x���Ă��āA����ɂ��̉����T���x���Ă���B�����Ă��̉��������ƈꊪ�������ւ��x���Ă���Ƃ����}�ł��B���̎R�A�n���A�ہA�T�A�ւ̓C���h�̐l�X�ɂƂ��Ă̋�Ԙ_�ł��B���ɏہA�T�A�ւƂ����̂̓K���W�X��A�C���_�X��A���邢�͂��̗���̖��тŒ��ǂ������邵�A�G�ł����铮���A�܂�g�߂ȓ�����`���Ă��āA���ꂪ���E���x���Ă���Ƃ������Ƃł��B���͎��������ݍ������Ƃ��Ă���ւ̊G�ł��B����͉����Ӗ�����̂��B����͎��Ԙ_���Ӗ����Ă���킯�ł��B�v����ɓ����n�܂��\���Ă��āA�����ƒ����l���������āA�I��肪����B���̏I��肪���̎n�܂�Ɍq�����Ă����B�����Ă܂����Ԃ��o���āA�I��肪���āA�܂����̎n�܂�Ɍq�����Ă����B�܂菄�鎞�Ԃ̊T�O�������ɕ`����Ă���킯�ł��B���Ԃ͏���Ƃ������Ƃł��B �@ ���Ԙ_�ɂ�2����܂��āA1�͂��̂悤�ɏ��鎞�Ԃ��A���Ǝ����J��Ԃ��Ă����Ƃ����T�_�ł��B��������1�N�������ł��B1�N���t�ɑ����萶���A�Ăɐ������A�H�Ɏ���t���A�₪�Đ����Ď���ł����B�����������ō��ꂽ�V�����킪����o���āA�܂��V���Ȑ��Ɏp����Ă����A�]���։�Ƃ������t�ɂ�����܂����A���낢��p��ς��Ȃ���A���Ǝ����J��Ԃ��Ȃ��琶���Ă����̂ł��B�����Ă���1�̎��Ԙ_�́A���m���A�L���X�g���I�Ƃ����ׂ���������܂��A�V�n�n���Ő��E���n�܂����Ƃ����T�_�ł��B��ڎU�ɍŌ�̐R���Ɍ����Ď��Ԃ�����I�ɗ���Ă����A�Ō�̐R���Ńn���}�Q�h��������Ƃ����A���Ԃ�����I�ɗ������̂ł��B���̈���I�ɗ���鎞�ԂƏ��鎞�ԁA�ǂ��炪�ǂ��A�����Ƃ����l�����ł͂Ȃ��āA���Ԙ_�Ƃ��ė����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃł��B����I�ɐi���A�i�����邾���ł͂Ȃ��āA�����Ƃ�������邮�����Ă���悤�ȏz���鎞�Ԃ̒��Ŏ������͐����Ă���킯�ł��B�����A���ɑ��z�������āA��ɑ��z������ŁA���̌J��Ԃ��̒��Ő����Ă���킯�ł��B���̌J��Ԃ��̒��ŏ��鎞�Ԃ��Ă���Ɠ����ɁA�������Ɛi�����Ă����Ƃ����A����2�̑g�ݍ��킹�Ő����Ă��܂��B������ɂ��Ă��C���h�l���l�����}�́A�܂�������ԂƎ��ԂƂ���2�̂��̂������ɕ`����Ă��܂��B���̕ӂ�͐_�b�������i��ŁA�N�w�I�ȍl�������F���}�Ƃ��ČŒ肵���킯�ł��B �@ |
|
|
���V�����ƒn����
�@ �����Ė{���̈Ӗ��ł͉Ȋw�I�ł͂���܂��A���������ώ@�Ɋ�Â��Đ��������F���_������܂��B���ꂪ�A���X�g�e���X�̉F���_�ł��B�A���X�g�e���X�͓V�����������܂����B�n�����F���̒��S�ɂ���A���z�ƌ��ȊO��5�̘f�����n���̎��������Ă��āA�y���ޕ��̍P���V�����������Ɖ���Ă���Ƃ����l�����ł��B�A���X�g�e���X�̎��R�w�̕����̍����͉A��C�A���A�y�ł��B�����Ă���4�̌��f��g�ݍ��킹�āA���ׂĂ̂��̂��o���オ���Ă���ƍl�����킯�ł��B�n�܂�ƏI��肪������̂������^���ŁA����͒n���̐��E�ł���B�܂��A�n�܂肪�Ȃ��A�I�����Ȃ��A��ɉ���Ă���^�����~�^���Ƃ��A����͘f���̐��E���Ƃ����l�����ł��B���ɂ��f�����E�̓G�[�e���łł��Ă���A�F���͗L���ł���A�^��͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃ������܂����B���̃A���X�g�e���X�̉F���_��2000�N�ɂ킽���Đl�X���M�p�������̂ł����A�ώ@�Ɋ�Â��Ă���͎̂����ł��B �@ �������ώ@�ɂ���ē���ꂽ�����Ƃ����Ō����ɓ����Ă���͂�ʂ����^���́A���͈Ⴄ���̂ł���A����̓A���X�g�e���X�̎��R�w���l�����Ŕ��ɑ厖�Ȋϓ_�ł��B�Ⴆ�A���X�g�e���X�́A���̂͊O����͂������Ȃ���Ή^���͂��Ȃ��ƍl���܂����B����͎������̐��E��������O���ƍl�����Ă��܂����A�{���ɖ��C�̂Ȃ��Ƃ���ł���A�����o���Ă��镨�͎̂~�܂�Ȃ��킯�ł��B�������C����ؖY��ė��z�I�ȏ��l������A�����Ȃ��Ă����������܂��B�����O�͂���������A�����������ς��܂��B���̂悤�ɒP�Ɋώ@�����ł����ƁA���C������̂ʼn����Ȃ��Ɠ����܂���B�������{���̐^���́A���C������čl������A�����Ȃ��Ă����̑����œ��������܂��B���̏�Ŗ��C�Ƃ������ʂ��l����Ύ~�܂錻�ۂ��N���܂��B�܂薀�C�͊O�͂Ŏ~�߂悤�Ƃ���͂ł��B�͂��������炱���A�~�܂�����A���x�̕ω����N����킯�ł��B���������Ă����Ō��������̂́A�������ώ@���邱�Ƃɂ���Ă��鎖�������炩�ɂȂ����Ƃ��Ă��A���̎����͐^���ł��邩�ǂ����͂킩��Ȃ��A�����ɐ^���ƌ��Ă��܂��Ɗ�Ȃ����ƂɂȂ�Ƃ����킯�ł��B�^���Ƃ����̂́A���̏ꍇ���Ɩ��C�ɂȂ�܂����A�]�v�Ȃ��̂����������߂ɁA�Ⴄ�悤�Ɍ����Ă���̂ł���Ƃ������Ƃł��B�Ⴆ�Α��z�������珸���āA���ɒ���ł����̂��A�������̎p�͑��z���n���̎��������Ă���悤�Ɍ����܂��B �@�����������ے肵���̂��A�R�y���j�N�X�̒n�����ł��B�R�y���j�N�X�̍l�����͑��z�����S�ɂ���A�n�������̎��������Ă��āA�������͂��̉���Ă����ɂ��邩��A���z����������A���肵�Ă���悤�Ɍ�����Ƃ����l�����ł��B���̂悤�ɉ��肷��ƁA�������������z�̋߂��ɂ���Ƃ������Ƃ��A�����ɐ����ł��܂��B�����͏��̖����▾���̖����ƌĂ�āA���z�Ɋ��Y���ď������蒾�肵�Ă��܂��B����͋��������z�̂����߂�������Ă���Ɨ�������Ηǂ��킯�ł��B����͖{���ɃR�y���j�N�X�I��]���ł��B���̂悤�Ȃ��Ƃ͏������邾���ł͍l���悤������܂���B�������l�X�ȉ^���ׂ�ƁA���̂悤�ɉ��߂���̂����R�ł������̂ŁA�n�������o�Ă��܂����B |
|
|
���K�����I�E�K�����C
�@ �n�����͎���ɍL�����Ă����܂������A���̒��ł���ɑ厖�Ȕ���������܂����B����̓K�����I�E�K�����C�̔����ł��B�K�����I�́A�F����悭�����m�̂悤�ɁA�U��q�̓����������܂����B�܂��A�ނ͒n������M���Ă��ď@���ٔ��ɂ�����ꂽ�����A��������������ɁA�u����ł��n��������Ă���v�Ƃ����悤�əꂢ���ƌ����Ă��܂��B �@ ����������ȏ�ɔނ͉F���_�ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂����B����̓K�����I���]������p���ď��߂ĉF�����ϑ������l���Ƃ������Ƃł��B�]�����������ō���Ă݂āA���̖]�����Ŗ��߂āA�ؐ���4��q���������Ƃ��A�����f�R�{�R���Ă��邱�Ƃ�A���z�ɍ��_�����邱�Ƃ������Ƃ������Ƃ́A���Ԃ��m���Ǝv���܂��B�����Ă��܂�m���Ă��܂��厖�Ȃ��Ƃ́A�ނ͖]�����œV�̐�������Ƃ������Ƃł��B�����ēV�̐�͑����̐��̏W�c�ł���Ƃ������Ƃ����܂����B�v����ɔނ͖]�����Ō��āA���z�������ɂ��鐢�E���L�����Ă���Ƃ������Ƃ����܂����B�A���X�g�e���X��R�y���j�N�X�͑��z�n�̒��S���n���ɂ���̂��A���z�ɂ���̂��A���̑��������Ă��܂������A�����ł͂Ȃ��āA���̑��z�������ɂ���A�v����Ɏ������̉F���͖����̑��z���U����Ă��鐢�E�ł���Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����̂��K�����I�ł��B���̈Ӗ��ł͔��ɍL���F����Ԃ̒��ɖ����̑��z�A�܂萯���U����Ă��āA�����̑��z�̂��ɁA�����̒n���̂悤�Șf�������݂��邩������Ȃ��Ƃ����l�����́A17���I�̎n�ߍ��ɂ͂����L�����Ă����Ƃ������Ƃł��B |
|
|
���n�[�V�F��
�@ ���E�������ł���Ƃ����l�����́A���Ƀ��l�T���X���ɏo�Ă��܂����B��q�C���o�āA�l�X�ȐV�����y�n��l�ނ������̂ŁA�V�㐢�E���������E�Ȃ̂ł͂Ȃ����ƍl����悤�ɂȂ����̂ł��B���̂��Ƃ��͂�����Ǝ������̂��n�[�V�F���ł��B�n�[�V�F���͌��a45�Z���`�̖]�����ŁA�V�̐�̒��̐��̎U���ׂ܂����B�ނ͓V���ʂ���Ղ̖ڂ̂悤�ɐ��ĔԒn�����āA�e�Ԓn���Ƃɐ��������邩�Ƃ����̂𐔂��Ă����܂����B����ɂ��̐������邳���Ƃɐ����Ă������̂ł��B���ɖ��邢�������A�^���炢�̖��邳�����A�����炢�̐������Ƃ����悤�ɐ����Ă����܂����B �@ �����Ĕނ͂��ׂĂ̐��݂͂�ȓ������邳�ł���Ɖ��肵�܂����B����Ɩ��邭�����鐯�͋߂��ɂ���A�Â������鐯�͉����ɂ���Ƃ������ƂɂȂ�A�O�������z�Ƃ��Đ��̕��z�邱�Ƃ��ł��܂����B�ނ͑��z��n�����F���̐^�ɂ���Ǝv���A���̎��𒆐S�Ɉ���������̂_�ƌĂсA���̉�ł���ƍl���܂����B���������ăn�[�V�F���́A���Ƃ����̂͌��݂ƒ��a�̔䂪5��1���炢�̘c�Ȋi�D�ɂ܂��Ă���ƍl���܂����B���̍l�����͐������̂ł����A���͎������͐^�ɏZ��ł���̂ł͂Ȃ��A�[�����̕��ɏZ��ł���̂ł��B�����Ď��ۂ͂����Ɣ��a���傫���~�ՂɂȂ�܂��B�������͒[�̕��ɏZ��ł���Ƃ���ƁA������������������ƌ����Ȃ�����������܂��B�����Đ�������������������V�̐�Ƃ��Č����Ă���Ƃ������Ƃł��B�܂��A�����c�ɕ��z���Ă��邩�炱���A�V�̐�̂悤�ɂȂ��Č�����Ƃ������߂������킯�ł��B�����Ĕނ͂��̂悤�Ȑ��̉�A�܂萯�_���F���ɓ]�X�Ƒ��݂��Ă���ƍl���܂����B����_�����ƌĂ�ł��܂��B |
|
|
����͉F��
�@ �n�[�V�F���̗\�z�ɑ��Ď��ۂǂ̂悤�ɂ��̉F����Ԃɂ͐����U����Ă���̂��ׂ錤�����A���ꂩ��150�N�߂��������Ă��܂����B�����čŏI�I�ɂ͋�͉F���Ƃ����l�����Ō��������܂����B����͑�_��(�O���[�g�f�B�x�[�g)�ƌ����܂����B�A���h�����_�启�_�Ƃ�����N�قǑO����m���Ă��āA���̂悤�ɓ_�Ō�����̂ł͂Ȃ��āA�L�����Č�����启�_�������āA���̃A���h�����_�启�_���V�̐�̒��ɂ��鐯�̏W�c�Ȃ̂��A�V�̐�̊O�ɂ���W�c�Ȃ̂��Ƃ�����_�����N�������킯�ł��B�����Ă��̉������@�͋����𑪂邱�Ƃł����B�����𑪂��ēV�̐�̒[���������ɂ���ΊO�ɂ���A�߂��ɂ���ΓV�̐�̒��̐��c�A�܂萯�̏W�c�ł���Ƃ������Ƃł��B�������͂قƂ�ǓV�̐�̒��ɂ��鑼�̐��c�Ɠ������邳�Ȃ̂ŁA�����O����ʂ����Ȃ��̂ł��B �@ ���̂悤�Ȏ��ɁA�ό����Ƃ������邳���K���I�ɕω����鐯���g���ċ��������肷����@���J������܂����B�ό����̖��邳�̎����Ɛ�Ό��x�Ƃ����A���̐������X�����Ă���S�G�l���M�[�Ƃ̊ԂɊW�����邱�Ƃ��킩��A���̊W�𗘗p�����̂ł��B�ό����̎����𑪂�A��Ό��x�����߂āA�����Đ�Ό��x�ƌ������̖��邳���r���ċ��������߂�Ƃ������@�ł��B�����Ă��̕��@���g�����Ƃɂ���ăA���h�����_�启�_�͓V�̐�̊O�ɂ����āA�V�̐�̑傫����3000�{�������ɂ���Ƃ������Ƃ��킩��܂����B���������ʂ̋߂��ɂ��鐯�̏W�c�Ɠ������炢�̖��邳�Ȃ̂ŁA���X�����Ă�������������Ƃ������Ƃł��B���ہA�A���h�����_�启�_�͓V�̐������薾�邢�̂ł����A�������炢�A���邢�͂���ȏ�ɖ��邢���̏W�c�ł���Ƃ������Ƃ��킩��A����ŋ�͂ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B��͂͐������悻1�牭����2�牭�A�傫�����̂�3�牭���炢�W�܂������̂ł��B���������Z��ł���͕̂��ׂ�������͂ł��B�����Ă����V�̐���(Milky Way Galaxy)�ƌĂ�ł��܂��B���̂悤�ɋ�͂Ƃ�����ɕ������ł܂�A���Ƃ��ċP���Ă��āA���ꂪ�_�X�ƉF����Ԃɕ��z���Ă���Ƃ������Ƃ�1924�N�ɖ��炩�ɂȂ�A��͉F�������m�����܂����B |
|
|
���c���F��
�@ �������́u����v�]�����Ƃ����]�������g�����Ƃɂ���āA��艓���̐��E�̎p��m�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����܂ł͂��߂��Ƃ��낵���ʐ^�Ŏʂ��Ȃ������̂ŁA��z���邾���ł����B���������ɉ����ɂ����͂��ʂ���悤�ɂȂ����̂ŁA�F�������ԓI�ɐi�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ƃ����l��������̓I�Ȏp�Ō�����悤�ɂȂ�܂����B �@ �����Ă��̐i����m�邽�߂ɂ́A����1�d�v�Ȕ���������܂����B����͖c���F���ł��B���͋��1��1�ɑ��āA���̋�͂܂ł̋����Ǝ��������̑��x�A���̋�͂��������ɋ߂Â��Ă��邩�A���������Ă��邩�Ƃ������̂ł����A����2��Ɨ����Ċϑ��ł���悤�ɂȂ�܂����B�߂Â��Ă��邩�A���������Ă��邩�Ƃ����̂̓h�b�v���[���ʂ��g���đ���܂��B���̃h�b�v���[���ʂ͗L���ł��ˁB�T�C������炵�Ȃ���߂Â��Ă���ƃT�C�����̉��������������āA��������ƁA�T�C�����̉����Ⴍ��������Ƃ������ۂł��B���������ŁA�������߂Â��Ă���Ɛ����ɂ����A���Ō����������A���Ō����Δg�����Z�����ւ���܂��B�����ĉ��������Ă�����������̌�����͔g�����������A�܂�Ԃ����ɂ���܂��B����ɂ���Ď��������̑��������o���邱�Ƃ��ł��܂��B �@ ��͂ɂ��āA�����o�����͎̂��̓K�X�ł��B�K�X�����x�̍�����Ԃɂ��Ă����ƁA������������o���܂��B�����ăK�X�̐����A�Y�f��_�f�A���f�ȂǁA�ǂ̂悤�Ȍ��f�ł��邩�ɂ���āA���ꂼ�ꂻ�̌��f���ƂɎw��������Ă��܂��B�����ĒY�f�Ȃ炱�̔g���A���f�Ȃ炱�̔g���A�_�f�Ȃ炱�̔g���Ƃ����悤�ɁA�e�C�I�����ƂɌ��܂����g���̌��������o���܂��B������P���ƌ����āA�g�����ƂɌ����Ċϑ����܂��B�����ĉ��������Ă���V�̂���̌��͐Ԃ����ɂ����̂ŁA�ǂꂾ�����ꂽ���𑪂�A�ǂꂭ�炢�̑����ʼn��������Ă��邩�����o���邱�Ƃ��ł��܂��B�A���h�����_��͎͂������̂����߂��ɂ����͂ł����A�b��200�L�����炢�Ŏ������ɋ߂Â��Ă��Ă��āA���悻30���N��ɂ̓A���h�����_�Ǝ������̋�͂͂Ԃ���̂ł͂Ȃ����ƌ����Ă��܂��B���������̂悤�ȗ�O�������ƁA�قƂ�ǂ����������牓�������Ă��܂��B �@ �����ĉ������鑬��v������r�ɔ�Ⴗ��Ƃ����W�����̂��G�h�E�B���E�n�b�u���ł��B�������鑬���������ɔ�Ⴗ��Ƃ����̂́A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɋN���蓾��̂��ƌ����ƁA1�ȒP�ɍl������̂́A�Ⴆ�Ή^����̐^�Ɏq�ǂ��������W�܂��Ă��āA��Ăɏ���ȕ����ɑ���o�����Ƃ��܂��B��������Ƒ��̑����q�قlj����ɍs���A���̒x���q�قNj߂��ɍs���܂��B����͉������鋗���͑����ɔ�Ⴕ�Ă���Ƃ������Ƃł��B����͉������鑬���͋����ɔ�Ⴗ��Ƃ������ƂƓ������ƂȂ̂ŁA���������F���̒��S�ɂ��āA�߂��̋�͂��������̏ꏊ���牓�������Ă����A���̂悤�Ȋϑ����ʂ������ł���킯�ł��B���������������F���̒��S�ɂ���Ƃ����͍̂l���ɂ����̂ŁA�ǂ̋�͂��猩�Ă������悤�ɔ�юU���Ă����悤�Ɍ�����d�|��������ɈႢ�Ȃ��Ƃ����킯�ł��B���̎d�|���Ƃ͉F���̖c���ł��B �@ �������F�����c�����Ă���Ƃ͍l���ɂ����̂ŁA���̂悤�ɍl���܂��B�݂Ȃ����l�ЂƂ肪��͂��Ƃ��āA���̉F����Ԃ̊e�_�Ŏ~�܂��Ă���Ɖ��肵�܂��B�����ď��������đ傫���Ȃ��Ă����Ƃ���ƁA�N���猩�Ă��ׂ̐l�Ɖ��������Ă����悤�Ɍ����܂��B�����čX�ɏc�E���E�����̔䂪���ɂȂ�悤�ɉ��������Ă����܂��B�܂��1m�̐l��1�b�Ԃ�1m�A2m�̐l��1�b�Ԃ�2m��������Ƃ��܂��B����Ə�ɔ䂪���ɂȂ�A�`�͈��̊i�D��ۂ��܂��B����ƒN���猩�Ă��݂�Ȃ���������A�܂�������ő傫���Ȃ��Ă��܂��B�����ď����傫���Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ��F����Ԃ��c�����Ă���ƍl���܂��B�܂�F���̋�ԓ_�Ɋe��͎͂~�܂��Ă��āA�F����Ԃ��c�����邽�߂ɂ��݂��ɉ��������Ă���ƍl����킯�ł��B���̂悤�ɍl����Ɖ������鑬���������ɔ�Ⴗ��Ƃ������Ƃ��A�F����Ԃ̂ǂ̋�͂��猩�Ă������悤�Ȗ@���Ƃ��Đ������܂��B�����ĉF����Ԃ��c�����Ă��邽�߂ɋ�͂����݂��ɉ��������Ă���ƍl����킯�ł��B |
|
| ���r�b�O�o�����_
�@ �O�͂̂悤�ȍl�������ƁA���݂̑傫���ɔ�ׂĉߋ��͂������������������A�X�ɑO�͍X�ɏ����������Ƃ����悤�ɉߋ��։ߋ��ւƑk���Ă����ƁA�F����1�_�ɏW�܂��Ă��܂��킯�ł��B���Ȃ��Ƃ����݂��̋�͓��m�����݂��ɏd�Ȃ肠���āA���ׂĂ̋�͂�1�̓_�ɏd�Ȃ�ƍl������Ȃ��킯�ł��B�����ŕ����w������`�Ƃ������t���Љ�Ă����܂��B�����w�ɂ�������`������܂��āA�����w�҂͂��ꂪ�ے肳��鍪���̂Ȃ�����́A�����Ɉٗl�ł��ɒ[�܂ōl���܂��B���������Ă��ߋ��֖߂��Ă��������ɁA�r���ł�߂闝�R���Ȃ�����͂����Ƌɒ[�܂ōl���ĉF���̎n�܂�A�܂莞�Ԃ��[����1�_����n�܂����ƍl����킯�ł��B1�_����n�܂����Ƃ������Ƃ́A���ׂĂ̓_������1�_�ɂ���̂ŁA���݂͗���Ă��邷�ׂĂ̓_�����S�ɂȂ��Ă���ƌ����܂��B�����ĉF����1�_����n�܂����ƍl����ƁA���ׂĂ̕�����1�_�ɏW�܂��Ă���̂ŁA���x�����̂����������킯�ł��B���ꂩ�疧�x�������Ƃ������Ƃ́A������Ƌl�܂��Ă���̂ŁA���ɉ��x�̍�����Ԃ���o�������ƍl�����܂��B�������̒m���Ă��镨���A�Ⴆ�ΐl�Ԃ͕̑̂��q�̉�A�����q�łł��Ă��܂��B���̉���悭����ƌ��q����ł��Ă��āA���q���悭����ƁA���q�j�Ɠd�q����ł��Ă���B�܂��A���q�j�͗z�q�ƒ����q����ł��Ă���Ƃ����悤�ɁA���낢��ȕ����K�w����ł��Ă��܂��B���������ɖ��x��������ԂȂ̂ŁA���ׂĂ̕����K�w�����Ă��܂��A�{���Ɍ����I�Ȃ��̂���̏�Ԃ���o�������ƍl������Ȃ��킯�ł��B���̂悤�ȍ����x�E�����x�ł��ׂĂ̕��������Ă��܂��Ă����Ԃ���o�����āA����Ɏ������̒m���Ă��镨���\��������Ă����Ƃ����l�������r�b�O�o���F���ƌ����܂��B�r�b�O�o���Ƃ����̂͑唚�����_�ƌ����܂��B���e�������������ɁA���ɍ����x�E�����x��Ԃő��������Ŗc�����J�n���邱�ƂƁA�F���̎n�܂肪���Ɏ��Ă��āA�����x�E�����x��Ԃ�����ɋ}���Ȗc���ʼnF�����n�܂����ƍl����l�����ł��B �@ �r�b�O�o�����_�͎��̂悤�ȗ��_�ł��B�F���͔��ɏ��������E����n�܂�A�����Ď���ɖc�����āA���̉ߒ��ʼnF���ɑ��݂���������̕����A�Ⴆ�Αf���q�A���q�j�A���q�A�l�ԁA�f���A���z�n�A��͂Ȃǂ̍\�������܂�Č��݂܂Ŏ������Ƃ����l�����ł��B���̃r�b�O�o�����_�͉F���_�̐����h���_�ƍl�����Ă��܂��B �@ �����ĉF���i���̃V�i���I�͏ڂ����͌����܂��A���̂悤�ɕ`���܂��B�F�����n�܂����̂�10�̃}�C�i�X44��b�Ƃ����A�ƂĂ��Z�����Ԃł����A���̎���ɉF�������܂�܂����B�����Đ�قǘb�����A���Ƀ~�N���ȕ����̎���A�܂�f���q�̎��オ����A���q�j�̔������N���鎞�オ����A���ꂩ��v���Y�}��ԂƂ����āA�d�ׂ������q�̏�Ԃ�����A���ꂩ�猴�q���ł��āA���q�̉�ł����͂����܂�āA�����ėl�X�ȋ�͉F���̍\�������܂�Ă��܂����B �@ ���̓r�b�O�o���F���̒��Ŕ��ɓ�₾�ƌ����Ă����肪2����܂��B1�͉F���̑n���ł��B�F���͂ǂ̂悤�ɂ��Ďn�܂����̂��Ƃ������ł��B����Ɋւ��Ă͂܂������͏o�Ă��܂���B���͓����͉i���ɏo�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�w�n���L�x�ɂ��ΉF���͖�����n�܂����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�v����ɖ�����n�܂����ƍl������Ȃ��킯�ł��B������������A�K�����̕��͂ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B���������āA���ɂ������Ƃ��납��n�߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��킯�ł��B�z�[�L���O�̘b������܂����A�����͎��Ԃ��Ȃ��̂Řb���܂���B�����Ă���1����͂̌`���A��͉F�����ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��Ƃ������ł��B��͉F���Ƃ����̂͌��ݎ��������ϑ����Ă���F���ł��B����Ɋւ��Ă͂�����x�̗������i��ł��܂����B |
|
| ���F���̍\��
�@ �n�[�V�F���͂���̈�ɂ���V�̐�̒��̐��̕��z�������ɒ��ׂāA���_�̐}��`���܂����B���݂̓V���w�҂�����1��1��͂ɖ]������������1��1�����𑪂��Ă��܂��B�����𑪂�Ƃ����Ă����ۂ̓h�b�v���[���ʂ��g���āA�ǂꂭ�炢�̑����ʼn��������Ă��邩�ׂĂ��܂��B�S�̂�7000�قNj�͂������āA�n�[�V�F�����`�����}�ɂ�1700���炢����A���1��1�ɖ]�����������ăh�b�v���[���ʂ𑪂��Ă����킯�ł��B10�N�قǑO�ł����A���̎d��������̂�5�N�Ԃ��������ƌ����Ă��܂��B���݂͂ق�1�N�łł��܂��B���ꂭ�炢�������ǂ��Ȃ��Ă��܂����A����ł�1700�ł��B �@ �����Ă��̋�͕��z���ォ�猩���悤�Ȑ}����A�F���Ƃ������t������܂����B��͂����݂��Ă���̈�Ɋۂ��������Ă��A���̗̈�̒��ɂ͂قƂ�Nj�͂͌����Ȃ��̂ŁA������ƌĂ�ł��܂��B��͂�������̂͂��̊ۂ����̏�Ɍ����܂��B���傤�ǃV���{���t�ɑ��𐁂������A���ĂāA���̖A�������f�ʂɌ�����킯�ł��B�����Ă��̖A�̖��̕����ɂ�����Ƃ���ɋ�͂��W�����Ă���Ƃ����A�F���̖A�\������������܂����B���ꂪ15�N�قǑO�ł��B��ԑ傫���A�̃T�C�Y�����1�����N���炢�ł��B���������点������5�����N���炢�̋������ɂ����ĖA�����݂��ɂԂ��荇���Ă���悤�Ɍ����܂��B���_���̎p�͉F���̂���������ɂ����ʂ��Ă���ł��傤����A�F���͖A���Ԃ��荇���Ă���p�ʼni���ɎU����Ă���Ƃ����C���[�W���ǂ��̂ł͂Ȃ����ƂȂ��Ă��܂��B������1�����N���炢�̃X�P�[���ŖA�\��������Ă���Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B���͂܂����̖A�\���̌����͂͂�����Ƃ͂킩���Ă��܂���B���R�̂����ɂł���Ƃ����l�����܂����A�{���Ɏ��R�̂����ɂł���̂��A���������p���������̂�������܂���B����1�̃q���g�Ƃ��āA�u�A�v�Ƃ������͂����ւ�Ɂu��v�Ə����܂��B�u��v���u�ȁv�������˂��o�Ă��܂��B�����Ă��́u�A�v�̈Ӗ����l����ƁA�����ւ�͐��ł��B�����āu��v�͐Ԃ����Ȃ̂ł��B�����ɐԂ�����������D�w�̎p�̏ی`���������́u��v�ł��B���������āA�����Ɍ��������̂������Ă���p�𐅂ŕ��ł�����̂��A���Ƃ������Ƃł��B���ہA�������Ő����Ԃ�������A��قŐ�����������A�C�݉��Ŕg��������Ƃ���ȂǂŖA���������Ă��܂��B�܂�G�l���M�[�����̒��ɓ��������ʂƂ��ĖA���o��킯�ł��B�����Č�������p������Ƃ���ł����A�A����������̂ł��B���������āA����������Ă���F���̖A�\����������������p���������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l������킯�ł��B�܂��A��͂���������W�܂��Ă���̈���O���[�g�E�H�[���ƌĂ�ł��܂��B�O���[�g�E�H�[���I�u�`���C�i�������̒���ł�����A����͉F���ɂ����閜���̒���A�v����ɐ��������̒���̂悤�ɔ��ɔ����Ǐ�ɏW�܂��ĘA�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B��̂��̖����̒����6�����N���炢�����Ă��܂��B���������ɓn���ċ�͂����ɔ����Ǐ�ɘA�Ȃ��Ă���̈悪���݂��āA���̂悤�ȗ̈悪���ӏ������݂���炵���Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B �@ ���݁A1990�N����5�{���炢�����̈�܂ł̋�͕��z�ׂ悤�Ƃ����������n�܂��Ă��܂��B�܂��\���i��ł��Ȃ��̂ŁA�ǂ̂悤�ȍ\��������̂������܂���B�������n�߂�1990�N��A1980�N�ォ���ׂ�Ƃق�20�{�����܂ŁA�܂�100�����N�̗̈�܂ōL���ċ�͕��z�ׂ�Ƃ������Ƃ��i�݂���܂��B������100�{�ɂȂ�ƁA�ϑ�����ׂ���͂̐��͋�����3��ɔ�Ⴗ��̂ŁA100���{�ɂȂ�܂��B����͑̐ς�������3��ɔ�Ⴗ�邩��ł��B���͔��ɖ]�����̐��\���オ��A�@�B�����ꂽ�̂ŁA1�̋�͂̋����𑪂�̂�15��������Α����悤�ɂȂ�܂����B�n�b�u����1924�N�ɑ��������́A1�̋�͂܂ł̋����𑪂�̂�30���Ԃ�����܂����B��ӂ�5���Ԃ��炢�������Ԃ������̂ŁA��ɂȂ�ƃV���b�^�[���J���Ă�����5���Ԓǂ������āA�V���b�^�[����āA�܂����̓����������Ɍ����ăV���b�^�[�J���āA�Ƃ������Ƃ�6���ԌJ��Ԃ��܂����B�����č���5���ŎB���悤�ɂȂ�܂������A100���͂ƂĂ������ł��B���������낢��Ȗ]���������܂��g���āA�����I�ɋ�͂̎p�A���z�ׂ悤�Ƃ������Ƃ��s���Ă���̂ŁA2015�N���炢�ɂ�100�����N���炢�܂ł̉F���̍\�����T�˂킩���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̒��Ŗ{���ɐV�����\����������̂��ƌ�����ƁA�킩��܂���Ƃ��������悤������܂���B�Ƃ������Ƃ͉F���̍\�����ǂ̂悤�ɂ��Ăł������̖{���I�ȗ��_���܂�������Ƃł��Ă��Ȃ��킯�ł��B���̈Ӗ��ł́A���͗��_���Ȃ̂ł����A���_�̊ϓ_������܂��s�\���Ȃ܂܂Ȃ킯�ł��B���������āA�����͉F���̎p�����N���ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A���_�̕����撣���āA�{���ɂ��������\�������̂悤�Ȏ��Ԍo�߂łł���Ƃ������Ƃ��ؖ��ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă��܂��B�@�@ �@ |
|
| ���n���� 5 | |
|
���Ñ�M���V���̓V���w
�@ �Ñ�M���V���ł́A�V���ϑ��̃f�[�^��p���āu�V���w�v�ƌĂׂ�̌n�����肠���Ă����B�s�^�S���X�́A����܂ł̐_�b���痣��č����I(�F���̒����Ɛ��w�I�\��)�ȉF���_���͂��߂ď������B����ɁA�V�����Ƃ��ăA���X�g�e���X(Aristoteles�ABC384-322)�A�n�����Ƃ��ăA���X�^���R�X(Aristarchos�ABC310��-230��)�����ꂼ��L���ł���B �@ ���A���X�g�e���X�ɂ��V���� �@ �A���X�g�e���X��Ñ�̐l�X�͉F���̒��S�͒n���łȂ���Ȃ炸�A���̂܂����e�f������]���Ă���Ƃ��A�V�������������B �@ (1)�@�S�F���͍P���V���̓���(���m�ɂ́A�O�ʂ̓���)�ɂ���B �@ (2)�@�P���V���̓����ɂ́A���炩�̕���(�d�����Ȃ��y�����Ȃ������ł���G�[�e��)�����݂��Ă��Đ^��ł͂Ȃ��B �@ (3)�@�P���V���̊O���ɂ́A�������݂��Ȃ��B �@ (4)�@�F�����Ƃ���ƁA�n�����痣��Ă���_��24���ԂŒn���̎����������鎖�͂ł��Ȃ��Ƃ��A�F���͗L���ł���B �@ (5)�@�F���͗L���ł��邱�Ƃ���A���̌`�͋��ł��蒆�S������A���̒��S�͒n���łȂ���Ȃ�Ȃ��B �@ �܂��A�n�������`�ł��邱�Ƃ��A���H�̎��̒n���̉e�̌`������������B���H�̎��̒n���̉e�̌`�͉~�`�ɋ߂��`�����Ă���B�n�����]���̉~������A���̉e�͉~�ɋ߂��`�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B���������ăA���X�g�e���X�́A�n���ɂ��ċ��`�ł���Ƃ����B �@ ���A���X�^���R�X�ɂ��n���� �@ ���̂悤�ɁA��������̐l���V�����������钆�ŁA�A���X�^���R�X�͒n�����������A�B��̒����ł���w���z�ƌ��̑傫���Ƌ����ɂ��āx�ɂ����đ��z�ƌ����ꂼ��̋����Ƒ傫����s���m�ł͂��邪�w�I�ɎZ�o�����B �@ �܂��A���X�^���R�X�́A3�̂��Ƃ����肵���B �@ (1)�@�P���Ƒ��z�͕s���ł���B �@ (2)�@�n���͑��z�𒆐S�Ƃ��ĉ~�^���ʼn�]���Ă���B �@ (3)�@�P���V���͖c��ȑ傫���������Ă���B �@ ���̂悤�ɁA�A���X�^���R�X�͑��z���S�����������B����3�̉�����A�ȉ��̂悤�ɓW�J���Ă���B �@ (1)�@��1�}�ɂ����āA�������m�ɔ����ł���Ƃ��A��EMS�͒��p(90��)�ł���B �@ (2)�@���̂Ƃ��́�MES������ł����ESM�����߂���B �@ (3)�@���ꂩ��AES��EM�̔�(�n������̑��z����ь��ւ̋����̔�)���Z�o�ł���B �@ (4)�@����ɁA���z�ƌ��̎����a�͂������0.5���ł��傤�Ǔ���������AES��EM�̔�̒l�́A���z�ƌ��̒��a�̔�ƂȂ�B �@ �A���X�^���R�X�́A��MES���ϑ����āA87���āAES��EM�̔�܂��͑��z�ƌ��̒��a�̔��19�F1�Ƃ����B �@ ��2�}�̂悤�ɁA�����n���̉e(�~���`)�̒��S��ʉ߂���悤�Ɍ��H���N����Ƃ����Ƃ炦�Ċϑ����s���B���H���J�n����u�Ԃ��猎�̑S��������I���܂ł̎��ԂƓ���I������u�Ԃ���Ăь��̈ꕔ���e�̊O�ɏo�n�߂�u�Ԃ܂ł̎��Ԃ𑪒肵���Ƃ��낿�傤�Ǔ����������B���z�ƌ��̒��a�̔��19�F1�Ƃ������ʂƂ��̌��H�̊ϑ������2�}�̂悤�ȊW���������A���̒��a��d�A�n���̒��a��D�Ƃ���ƁA �@ x�F2d��(x+20R)�F19d �@ ����сAx�F2d��(x+R)�FD �@ ���ꂩ��Ax��(40/17)R�A�@���̒��a��d��(20/57)D��0.35D �@ �܂��A���z�̒��a��19d��(20/3)D �@ ����āA���z�A���̒��a��D�P�ʂŋ��܂�B�Ƃ���ł��łɂ��̎���A�n���̒��aD�̒l�͋��߂���̂ŁA���z�A���̒��a�����܂�B����ɁA���z�����������a��0.5���ł��邱�Ƃ���A����������z�ƌ����g�̂��ꂼ��̒��a��(360��/2��)��0.5����360/�Δ{�̋��������n�����痣��Ă��邱�Ƃ��킩��̂ŁA���z�A���Ƃ̋��������܂�B(�����������Ȋϑ����u��]���������Ȃ��������߂ɁA�f�[�^���s���m�ł������̂Ŏ��ۂƂ͂��Ȃ������l�ƂȂ��Ă��܂����B) �@ �������A�A���X�^���R�X�̏������n�����͏@���I�e���Ȃǂ̂��߁A�ȍ~���炭�̓A���X�g�e���X�̓V�������̗p����邱�ƂƂȂ����B |
|
|
���v�g���}�C�I�X�ɂ��t�s�^���̐���
�@ �v�g���}�C�I�X(Ptolemaios�ABC367-283)�́A�V�̂ɂ��ď����ꂽ�w�A���}�Q�X�g�x�ŗL���ɂȂ����B���́w�A���}�Q�X�g�x�́A�v�g���}�C�I�X�̗��_�݂̂ł͂Ȃ��A�v�g���}�C�I�X�ȑO�̗��_�̏W�听�ł���B�w�A���}�Q�X�g�x�ɂ��ƁA �@ ��1.�@�藝�̏��� [��] �@ ��2.�@�V��͉�]���� �@ �Ñ�l�ɂƂ��Ă��ϑ��ɂ���Ă��̖��ɂ��Ă̍ŏ��̊ϔO��̂ɏ\���ł��������Ƃ͋^���Ȃ��B�����āA���̉�]�ɂ���āA�V���̊ϔO�����܂ꂽ�B���̉^���́A������ł��Ȃ��A�܂��Ă͒n������o��Ƃ��Ɍ������Ƃ��ɏ�����̂ł��Ȃ��A��]���Ă���̂ł���B���`�ł��闝�R�́A �@ (1)�@�V�̂̉�]�^�����s����ꍇ�ɁA�ł��s���̂悢�}�`�͕��ʂł͉~�ł���A���̂ł͋��ł���B�~�͕��ʐ}�`�̂Ȃ��ōő�ł���A���͗��̂̂Ȃ��ōő�ł���A�V���͕��̂̂Ȃ��ōő�ł���B �@ (2)�@���ׂĂ̕��̂̒��A�G�[�e���͂��̕������ł��ł��葊��(�ψ�)�Ȃ��̂ł���B�����ȕ���������ꂽ���̂̕\�ʂ́A�����ȕ����������Ă���B�����āA�����������ł���悤�ȗB��̕\�ʂ́A���ʂł͉~�ł���A���̂ł͋��ł���B�����A�������ʓI�ʼn~�Տ�ł������Ȃ�A�n����̈قȂ����ꏊ���璭�߂�l�ɂƂ��Ċۂ��`�ɂ͌����Ȃ��B�G�[�e���͑����I�ȗ��̂ł���̂ŁA���`�ł���B�����āA���̕������݂��ɑ����ł���̂ŁA�G�[�e���͓����~�^��������B �@ ��3.�@�n���͖��炩�ɑS�̂Ƃ��ċ��`�ł��� �@ �n���͖��炩�ɋ��`�ł���B���̂��Ƃ́A��������т��̑��̐��̏o�v���n����̂��ׂĂ̏Z���ɂƂ��ē����ɋN����̂ł͂Ȃ��A�܂����̏Z���ɁA����ɐ��̏Z���ɋN���邱�Ƃ���킩��B�܂��A���̎��ԍ��͂��݂��̋����ɔ�Ⴗ�邱�Ƃ���n���̕\�ʂ͋ȗ������̋��`�ł��邱�Ƃ��킩��B �@ ��4.�@�n���͓V��̒��S�ɂ��� �@ �n���̂܂��Ɍ����鎖���͒n����V���̒��S�ɒu�����Ƃ��ɋN����B���̂��Ƃ́A����3�̏ꍇ��ے肷�邱�Ƃɂ���Đ�������Ă���B �@ (1)�@�n�������ꂼ��̋ɂ��瓙�����ł͂��邪�����炸��Ă��鎞�B �@ ���̏ꍇ�A�n�����ł̐��̑傫���Ƌ����͊e�ɂœ���ł͂Ȃ��A�܂������o������쒆�܂ł̎��ԂƓ쒆��������܂ł̎��Ԃ͓���ł͂Ȃ��B����́A���X�̌o���ɔ�����B �@ (2)�@����ɂ����Ă������ꂩ�̋ɂɋ߂����B �@ �ǂ��ł��n�������V����㉺�s����2�����ɕ�������̂Ŕ�����B�����́A�n������2�������ꓯ�ꔼ�~���n���̏㉺�ɂ���ׂ��ł���B �@ (3)�@����ɂ��Ȃ������ɗ��ɂ��瓙�����ł��Ȃ����B �@ (1)��(2)���ے肳�ꂽ�̂ŁA���̉����������B �@ (1)�A(2)�A(3)����A�����n�����V���̒��S�ɂȂ������璁���ɍ�����������B �@ ��5.�@�n���͓V��ɑ��ē_�̂��Ƃ����̂ł��� �@ �n����̔C�ӂ̓_����ώ@�������̑傫���Ƌ����́A���ꎞ���ɂ��ׂĂ̏ꏊ���瓯���悤�Ɍ����A�قȂ����ꏊ���瓯��̐������Ă��ω����Ȃ����Ƃ���A�P���V���܂ōL�����Ԃɔ�ׁA�n���͖��炩�ɓ_�̂��Ƃ����̂ɂ����Ȃ��B�܂��A�n�����͓V���2��������ׂ��Ȃ̂ŁA�n����������̑傫���������Ă������ɂ��锼�~��艺�ɂ��锼�~���傫���Ȃ��Ă��܂��B �@ ��6.�@�n���͂Ȃ��̈ʒu�ω������Ȃ� �@ 4�̒n���͓V��̒��S�ɂ���Ƃ����ؖ��ɂ��A�n���͑��̏ꏊ�Ɉڂ��ꂽ��A���S����o�邱�Ƃ͐�ɂł��Ȃ��B���̗��R�́A �@ (1)�@�����ψʂ��������Ȃ�A�n�������S�ȊO�ɂ���Ƃ��̌���(4��(1)�A(2)�A(3))���N�����Ă��܂��B �@ (2)�@�n����̏d�����̂͒��S�Ɍ������ė�������̂ŁA�n���̂悤�ȏd�����͓̂V���̒��S�Ɍ��������Ƃ���B����āA���łɓV���̒��S�ɂ���d�����̂͑��֓������Ƃ��Ȃ��B �@ (3)�@�����n���������Ă�����A�n����̎x�����Ȃ�����(�_�A������ꂽ���́A��ԓ����Ȃ�)�́A�n���Ɏ��c����Đ��Ɍ�ނ���悤�Ɍ�����͂��ł���B���ۂ��̂悤�Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��B �@ ��7.�@�V��ɂ͈قȂ�2�̊�{�I�^�������� �@ �V��̈قȂ�2�̊�{�I�^�����A �@ (1)�@�����琼�ւ̕��s�~(���z�Ȃ�)�̉^�� �@ (2)�@�����瓌�ւ̍P���V���̉^�� �@ �Ƃ����B(1)�͌��݂̌������ł͎��]�ɂ������^���A(2)�͌��]�ɂ��N���^����\�킵�����̂ł���B �@ ���̂悤�ɁA�Ñ�̐l�X�͉F��������ƍl���A����ɒn���𒆐S�ɑ��̘f������]���Ă���ƍl���Ă����B���̗��_�ɂ̓q�b�p���R�X(B.C.190��-B.C.120��)�̍l�����̂������Ă���B�q�b�p���R�X�́A�P���ȓ����~�^���ł͂Ȃ����Ƃ���A���]�~�Ɨ��S�~��p�����B �@ �����]�~ �@ �Ƃ��Ɏ��]�~���ɂ��A�f���̏��s�E�t�s�^���A����ɃA���X�g�e���X���ؖ��ł��Ȃ������t�s���̘f���̖��邳�̕ω���������ꂽ�B���]�~���Ƃ́A�u�n���𒆐S�Ƃ��āA��]����~(�]�~)��̂���_�𒆐S�Ƃ��ĉ�]������]�~���f�����^�s����v�Ƃ������̂ł���(��5�})�B����Ęf���̋O���́A��6�}�̂悤�ɂȂ�B �@ ���]�~��̘f�����]�~�̊O���ɂ���Ƃ��͎��]�~�Ə]�~�̉^�����d�Ȃ荇���A���]�~��̘f�����]�~�̓����ɂ���Ƃ��͎��]�~�͏]�~�̉�]��ł������悤�Ɍ�����B���������āA�t�s�^�����N����B�܂��A�t�s�^�����N���Ă���t�߂́A�f�����n���Ɉ�Ԑڋ߂����t�߂ł���B���������āA�t�s���ɘf���͍ł����邭������B �@ ���]�~�́A�t�s�^���̏ؖ������ł͂Ȃ��A�ʐϑ��x���̖@���ɍ��킹�悤�Ƃ����邱�Ƃŗp����ꂽ�B���������]�~����������p���邱�Ƃɂ���Ęf���̉^�s�X�s�[�h���ϑ��f�[�^�ɍ����悤�ɒ��������B����āA�w�A���}�Q�X�g�x�ł́A1�̘f���ɂ�������̎��]�~���p�����Ă���(�\1)�B �@ �����S�~�E�G�J���g�_ �@ �܂����S�~(��7�})�ɂ��A���݂ł����ƃP�v���[�̑�2�@���u�ʐϑ��x���̖@���v�̖����������悤�Ƃ����B���S�~�Ƃ́A�f���O���̒��S���班�����ꂽ�Ƃ���ɒn����u���A�f���́A���S���p���x���Ƃʼn^������Ƃ����l���ł���B�q�b�p���R�X�́A���z�ɂ��Ă͗��S����0�D04166�Ƃ��A���z�̎��ۂ̈ʒu�Ɨ��_�̂�����킸��1���Ƃ����B �@ �܂��A���S�~�̑��ɃG�J���g�_�Ƃ������̂������l������(��8�})�B�G�J���g�_�Ƃ́A�f���O���̒��S���班�����ꂽ�Ƃ���ɒn����u���A���̒��S���͂���Ŕ��Α��̓��������̏��ɂ���_E�ł���B�f���́A���S�ł͂Ȃ����̃G�J���g�_�𒆐S�Ɋp���x���Ƃʼn^������Ƃ����l���ł���B �@ ���̍H�v�ɂ��A�f�����n���̋߂��ł͑����A�n�����牓���Ƃ��͒x���^�����邱�ƁA�܂�u�ʐϑ��x���̖@���v�����܂��������邱�Ƃ��ł����B(���G�J���g�Ɩʐϑ��x���̖@��)�������A��l�~�^���̌������ᔽ������̂ɂȂ�A�̂��̃R�y���j�N�X�̔ᔻ���邱�ƂɂȂ����B �@ ���]�~���]�~�̌n�Ŋe�f���̉^����\���ɂ́A���ꂼ��̘f�����ƂɕʁX�̎��]�~���]�~�̌n�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���z�⌎�͋t�s�^�����s��Ȃ����߁A�]�~�����ʼn^����\�����Ƃ͉\�ł���B���̘f���ɂ��ẮA���]�~�Ə]�~�̉�]�̊����⑊�ΓI�ȑ傫�����e�f���̊ϑ����ʂƍ����悤�ɒ������邱�Ƃɂ���Ęf���̉^����\�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B�v�g���}�C�I�X�́A�ΐ��E�ؐ��E�y���Ƌt�s�̓�������E���E���ƂȂ�ϑ��f�[�^�ɍ��킹�Ď��]�~�̑傫������E���E���ƂȂ�Ƃ����B�܂��A���f���ł͋����E�����Ǝ��]�~���������Ȃ�A�����̒��S�͂��Ȃ炸�n���Ƒ��z�����Ԑ���ɂ���ƌ��߂��B���̂悤�Ɍ��߂��̂́A���f�����˂ɑ��z�̋߂��ɂ��邱�Ƃ��������߂ŁA�ő嗣�p(�n�����猩�����z�Ɠ��f���̗����ő�p�x)�̊ϑ��f�[�^�ɍ��킹�āA���]�~�̑傫�������ꂼ�ꌈ�肵���B |
|
|
���R�y���j�N�X�ɂ��n����
�@ �R�y���j�N�X(Nicholas Copernicus�A1473-1543)�́A�w�V�̂̉�]�ɂ��āx�ɂ����Ĉȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B �@ ��1.�@�F���͋��`�ł��邱�� �@ �@�܂��A�F���͋��`�ł���Ƃ������Ƃ������K�v������B���`�ł��闝�R�́A �@ (1)�@�ł����S�Ȍ`�ł���B �@ (2)�@�ł��e�ς��傫���B �@ (3)�@�F���̑��̘f��(���z�E���E��)�����`�ł���B �@ (4)�@���H�͋��`�ɂȂ鐫���������Ă���B �@ ��2.�@��n(�n��)���܂����`�ł��邱�� �@ �n���܂�(�����R�A�[���J�Ȃǂ̗�O��������)���`�ł���B���̗��R�́A �@ (1)�@�ǂ�����ł��k���ɍs���l�ɂƂ��Ėk�l�����������Ȃ�A��̐��X�͏o�Ȃ��B �@ (2)�@���ɂ̌X�́A��n��i�����ɔ�Ⴗ��B �@ �����܂����`�ł���B���̗��R�́A �@ (1)�@�q�C���ɑD�̂���͌����Ȃ����n���}�X�g�̏ォ��͌�����B �@ (2)�@����Ă����D�𗤒n���猩��ƃ}�X�g��̖�����́A���X�ɉ��~���A���ɂ͌����Ȃ��Ȃ�B �@ ��3.�@�ǂ̂悤�ɂ��đ�n(�n��)�͐��Ƌ���1�̋��`���Ȃ��̂� �@ �n������芪����m�͊C�������A�Ⴂ���������Ă���B���Ƒ�n�͂��̏d���ɂ�蒆�S�������A���n���c�����߂ɐ��͑�n��菭�Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A��n�̏d���̒��S�Ƒ傫���̒��S�͓���ł���B �@ ���������āA�ȉ��̎���������B �@ (1)�@���Ƒ�n��1�̏d�S�ֈ��������Ă���B �@ (2)�@���ɒn���̒��S�͂Ȃ��B �@ (3)�@��n�͐����d���̂ŁA�Ⴂ�����͐��Ŗ��������B �@ (4)�@���͑�n��菭�Ȃ��B �@ ��4.�@���V�̂̉^���͈�l�ʼn~��A�i���I�ł���A�Ȃ��������̉~(�^��)���獇������Ă��邱�� �@ �V�̂̉^���͉~��ł���B���̗��R�́A �@ (1)�@���̂������V���̉^���͉~��ɉ�]����B �@ (2)�@�~��͏��߂��I�����Ȃ��A����𑼕������ʂ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@ �������A�V���̋O�������������߂ɁA���̉^���͕��G�ł���B �@ �܂��́A�����^��(�����琼��)�ɂ��āB����͊ȒP�A���Ăł���B���Ԃ́A�����ő�����B �@ ���ɁA�����瓌�ւ̉^��(���z�E���E5�f��)�ɂ��āB���z��1�N�A����1�����������悤�ɁA����5�f�������ꂼ��ɈقȂ����ŗL�̉�]������(�������Ⴄ)�B����āA�V����1�ł͂Ȃ��B�܂��A�����͂���Ƃ��͒n���ɐڋ߂��A����Ƃ��͉�������B�ɂ�������炸�A���^���͉~��ł��邩�����̉~����Ȃ��Ă���B����炪���̖@���ɂ���Ď����I�ɋN�����Ă��邱�Ƃ���A�~�^���łȂ��Ă͂����Ȃ��B�����āA���̘f�����ϑ��I�^��������悤�Ɍ�����̂́A��]�̐^���ɒn�������݂��Ȃ�����ł���B����āA�n�����猩��Ƌ������ω����Č�����(���̑傫�����ω����Č�����)���Ƃ����炩�ɂȂ�B �@ ��5.�@�n���ɉ~�^�����ӂ��킵�����ǂ����A����т��̏ꏊ�ɂ��� �@ �����ł́A2�Œn�������`�ł��邱�Ƃ����łɏؖ����ꂽ�̂ŁA���̋��`�ɏ]���^��������̂��A�܂����̉^���̏ꏊ�͉F���̉����ł���̂����l����B�ꏊ�I�ω��ł���ƌ��Ȃ������̂̂��ׂẮA�����鑤(�f��)�̉^���ł��邩�A���鑤(�n����̊ϑ���)�̉^���ł��邩�A�܂������̂��ꂼ��̉^���ɂ��B�Ⴆ�A��������֓����������Ă�����̂̊Ԃɂ͉^���͊��m����Ȃ��B�����ŁA�V�̂̉^��������̂͒n������ł���B�n���������Ă���A���̉^���͊O�E�ɍČ������ł��낤(�����͋t)�B �@ ���̂悤�ɉ��肷��ƁA���f�����n���ɋ߂Â����艓���������肷�邱�Ƃ��ؖ��ł���B����́A�n���̒��S�����f���̉~�^���̒��S�Ƃ͈قȂ��Ă��邩��ł���B �@ ��6.�@�n���̑傫���ɑ���V�̍L�傳�ɂ��� �@ ����Ȃɑ傫���n�����V�̑傫�������ׂ�Ɣ��ɏ������B�F���͔��ɑ傫�����L���ł���B �@ ��7.�@�n�����A����Β��S�Ƃ��āA�F���̐^���ɐÎ~���Ă���ƂȂ��Ñ�l�����͍l�����̂� �@ �A���X�g�e���X�̎咣�ɂ��ƁA �@ (1)�@���ɂ͏d���A�y��������Ƃ����B�����āA�n�͍ł��d��(�d�����̂́A�n�A���B�y�����̂́A��C�A��)�Ƃ��ꂽ�B�d�����̂́A���S�֍s�����Ƃ���B���S�֍s�������̂͂���ɒ��S�֍s�����Ƃ��A�Î~����B����āA�n���͉F���̒��S�Ŏ���̏d���ɂ���ĐÎ~����B �@ (2)�@�����A�n������]����Ȃ�A���̉^���͔��ɑ������߂ɒn����̕��͎U��U��ɂȂ�A����������̂͐^���ɐi�܂Ȃ��B �@ ��8.�@�O�q�̏��_���ւ̘_������т����̕s�\���� [��]�@ ��9.�@�n���ɕ����̉^�����t�^���ꂤ�邩�A����щF���̒��S�ɂ��� �@ �n����1�̘f���ƍl������B �@ �F���̒��S�͑��z�ł���B�n������]�^�����Ă��邱�Ƃɂ���ĔN���^���A���f���̂��܂��܂ȗ��E�t�s�E���s�������ł���B �@ ��10.�@�V���̏����ɂ��� �@ �܂��A�O�ɏq�ׂ��ȉ��̎����m�F����B �@ (1)�@�n������ь��̉�]�^���̒��S�́A���̏��f���Ƌ��ɑ��z�̎�����ړ����A���z�̋߂��ɂ͉F���̒��S�����݂���B �@ (2)�@���̑��z�͕s���ł���A���z�������Č�����̂͒n���̉^���̂��߂ł���B �@ (3)�@�F���̑傫���͋���ł���B �@ �����ɁA �@ (1)�@�F���̋ύt�B �@ (2)�@�ؐ��̏��s�E�t�s�^���́A�y���̂�����傫���B�܂��A�����̂���́A�����̂�����傫���B �@ (3)�@�ؐ��̏��s�E�t�s�^���́A�y���̂�����H�ł���B�܂��A�ΐ�������̂���́A�����̂�����H�ł���B �@ (4)�@�y���E�ؐ��E�ΐ��́A���̏o�����v�Ƌ��ɏo�Ă���Ƃ��̕����n���ɋ߂Â��Ă���B �@ ���l���ɓ���āA�V���̏������l����B �@ �V���̏����́A �@ ���́A��ԍ����͍̂P���V���ł���B�P���V���́A�s���ł���B �@ ���ɗ���̂́A�ŏ��̘f���ł���y���ł���B�y���́A30�N�ň��]����B �@ ���́A�ؐ��ł���B�ؐ��́A12�N�ň��]����B �@ ���́A�ΐ��ł���B�ΐ��́A2�N�ň��]����B �@ ��4�Ԗڂ̏ꏊ���A�N����]����߁A�n���Ƃ������]���錎���܂܂��B �@ ��5�Ԗڂ̏ꏊ�́A�����ł���B�����́A9�����ň��]����B �@ �Ō�ɑ�6�Ԗڂ̏ꏊ���A�����ł���B�����́A80���Ԃň��]����B �@ �����āA�^���ɑ��z���Î~���Ă���B �@ ��11.�@�n����3�d�^���ɂ��Ă̘_�� �@ �n����3�d�̉^�������Ă���B �@ ��1�́A�n�������̎���̐����瓌�ւ̉�]�A�܂莩�]�B �@ ��2�́A�n���̒��S�̔N���^���ł���B����������瓌�ւ̉�]���Ă���B �@ ��3�́A�X�̔N���^���ł���B����͋t�œ����琼�ւ̉�]���Ă���B �@ ��12.�@�~�̌��̒����ɂ��� [��] �@ ��13.�@���ʎO�p�`�̕ӂƊp�ɂ��� [��]�@ ����炩��A���ڂ��ׂ��� �n����(���z���S��)���̗p�������ƁA����ɔ����A�f���̏��s�E�t�s�^���̐������������������Ƃł���B |
|
|
���V����(���]�~��)����n�����ց@ ���n����(���z���S��)�̗̍p �@ �R�y���j�N�X�́A�u�f���́A��l�~�^��������v�Ƃ��������ɒ����Ɏ��]�~�����C�����Ă������B �@ �ȉ��̐�������B���߂���n���������ƍl���Ă�����ł͂Ȃ��A�u���z���n���𒆐S�ɉ�]���Ă���v�Ƃ������Ƃ�O��Ƃ��Ă����B�n���𒆐S�Ƃ��đ��z����]���A���z�𒆐S�Ƃ��đ��̂��ׂĂ̘f������]����悤�ȃ��f��(���̂悤�ȉF���̌n�́A�V���w�҃e�B�R�E�u���[�G(Tycho Brahe�A1546-1601)�̖����Ƃ��Č�Ɂu�e�B�R�̑̌n�v(��5�})�ƌĂ�Ă���)���l���Ă����B �@ �R�y���j�N�X�́A�V��(�����Ōł��k�̂悤�Ȃ���)�Ƃ������̂��l���āA�f�����ꂼ�ꂪ�V���ɖ��ߍ��܂�Ă���ƍl���Ă������߁A���z���n���̎������]����ƍl����ƁA�ΐ��V���Ƒ��z�V�����������Ă��܂��B�V�������̓I���݂ł������A���̂��݂��ɐZ�����Ď��R�ɉ�]����Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ������B���z���n���̎������]���邱�Ƃ̓R�y���j�N�X���̗p���Ă����V���Ƃ����T�O�ɔ����Ă��܂��B���̖����A�n�������z�̎������]����ƍl�����Ƃ��A�V�����������邱�Ƃ�������ꂽ�̂ł���B��l�~�^������邱�Ƃ���n�܂����R�y���j�N�X�̌����́A�n���̌��]�^����K�v�Ƃ����̂ł���B���̂悤�ɂ��ăR�y���j�N�X�́A�n���𒆐S�Ƃ����F���̍l���A�n����(���z���S��)��������悤�ɂȂ����B �@ ���f���̏��s�E�t�s�^���̐��� �@ ���ɁA�f���^���̎�v�ȕs�K�����ł���f���̋t�s�^�����������B��7�}�́A�����Ă���n������P���V���Ƃ����Î~�������̂�w�i�ɂ��������Ă���O�f���̌������̈ʒu�ł���B��8�}�́A���f���̌������̈ʒu�ł���B���z�𒆐S�Ƃ���~�O���ɂ�����n���̈ʒu�͓_E1�AE2�A�c�AE7�Ŏ�����Ă���B����ɑΉ�����f���̈ʒu�́AP1�AP2�A�c�AP7�Ŏ�����Ă���B�����āA����ɑΉ�����f���̌������̈ʒu�͒n������f���ւ̐�������ɍP���V���ƌ�������܂ŐL�����o�����Ƃ��ł��邪�A�����1�A2�A�c�A7�Ŏ�����Ă���B �@ ��7�}(�O�f���ɂ���)����͎��̂��Ƃ�������B�P���̊Ԃł̘f���̌������̉^����1��2�A2��3�ւ͏��s�^���ł���A�����Řf����3��4�A4��5�ւ͋t�s�^�����Ă���悤�Ɍ�����B�����āA�Ō�ɂ͍Ăт��̉^���͌��ɖ߂�A5��6�A6��7�ւ͏��s�^���ƂȂ�B�܂��A��8�}(���f���ɂ���)����͎��̂��Ƃ�������B�P���̊Ԃł̘f���̌������̉^����1��2�ւ͏��s�^���ł���A�����Řf����2��3�A3��4�A4��5�A5��6�ւ͋t�s�^�����Ă���悤�Ɍ�����B�����āA�Ō�ɂ͍Ăт��̉^���͌��ɖ߂�A6��7�ւ͏��s�^���ƂȂ�B �@ �n�������̋O���̎c��̕������܂���Ă���Ƃ��A�f���́A���z���͂���Œn���̔��Α��ł͏��s�^���𑱂���B���������āA�R�y���j�N�X�̑̌n�ł́A�n�����猩���f���͑����̏ꍇ�A���s�^�������Ă���悤�Ɍ�����B�t�s�^�����N����̂́A�n�����f���ɍł��߂��t�߂����ł���B����āA�t�s�^�����N����Ƃ��A�f�����ł����邢�B����͊ϑ��ƈ�v���Ă���B���̂悤�ɃR�y���j�N�X�́A�f���̕s�K���^��(���s�E�t�s�^��)�z�𒆐S�Ƃ��Ēn���⑼�̘f������]���A�����̎����̍��݂̂Ō��܂�A�f�����t�s�̍ۂɍł����邭�Ȃ邱�Ƃ����]�~�������P���ȃ��f���Ő������邱�Ƃ��ł����B �@ �ȏォ��A�v�g���}�C�I�X�̎��]�~�����D�ꂽ�_�����邪�A���w�I���f���Ƃ��ăv�g���}�C�I�X�̑̌n�ƃR�y���j�N�X�̑̌n���r����Ɠ����ł���B������2�̑̌n�Ƃ����S�������ŁA�f�����~�O�����Ƃ��Ă��邱�ƁA���ׂĂ̘f���̋O���ʂ�����ʂł��邱�Ƃ��O��ł���B(���V����(���]�~��)�ƒn�����Ƃ̊w�I�W) �@ �v�g���}�C�I�X�̒���w�A���}�Q�X�g�x�̎���ɂ́A�����̐�Βl�͑���ł����A���̕����ł��鑊�Βl(r�^R�Ae�^R)�̂ݒm���Ă����B���̂��߁A�]�~���a R�͈ꗥ60�ɂ����ݒ�ł��Ȃ������B����āA�v�g���}�C�I�X��r�^R�ƌ���l��1�^a���ׂ�ƁA�O�f���ł���ΐ��A�ؐ��A�y���ɂ����Ēl�͂قړ����ł���B����āA�n������݂��f���ʒu�̕����͂قړ����ł���B����́A�ϑ��l��荇�킹������ł���Ǝv����B����́A���Βl�̂ݒ�߂Ă����A�����}�`�ɂ�����p�x�̕s�ϐ��ɂ���āA�n������݂��f���ʒu�̕����͐�������߂邱�Ƃ��ł�������ł���B�Ⴆ�Α�1�}�̂悤�ɁA�ΐ�M��M'�Ɉړ����Ă��A�t�ɉΐ�M'��M�Ɉړ����Ă��n��E���猩�Ă�����ς��Ȃ��B �@ �����̐�Βl�ɂ��ẮA�e�B�R�E�u���[�G�ƃP�v���[���o�āA�n���O���̒��a����ӂƂ���O�p���ʂɂ��ϑ��l����ɓ������B �@ ���V����(���]�~�����v�g���}�C�I�X�^)���瓱�����ΐ��̉^�s �@ �܂��A���]�~�����l����B�v�g���}�C�I�X�̎���́A�e�f���̌�����������������炸�A�ϑ��l���獇�킹�����̂ł���B����āA���ׂĂ̘f���Ԃ̋����̃X�P�[���𐳊m�ɕ`���B���z����ΐ��܂ł̋����a�Ƃ����]�~��`���A���zS(���F)����n��E(���F)�܂ł̋��������]�~�̔��a�Ƃ���B����āA�ΐ��̈ʒuM(�ԐF)�A�O���͑�2�}�̂悤�ɂȂ�B �@ ���e�B�R�E�u���[�G�̐�(�V�����ƒn�����̒���)���瓱�����ΐ��̉^�s �@ ���ɁA�e�B�R�E�u���[�G(Tycho Brahe�A1546-1601)�̉F���̌n(��3�})���l����B�e�B�R�̍l���́A�V�����ƒn�����̒��Ԃł���A�n���̂܂������A���z�A�P���V������]���A���̑��z�̂܂��𐅐��A�����A�ΐ��A�ؐ��A�y������]���Ă���B �@ �e�B�R�E�u���[�G�̉F���̌n�ł́A�n���𒆐S�Ƃ��đ��z���܂��A���̑��z���]�~�̒��S�Ƃ��ĉΐ�(�e�f��)������Ă���B�ΐ�(�e�f��)�͎��]�~�ƂȂ��Ă���B �@ �����ł��A���ׂĂ̘f���Ԃ̋����̃X�P�[���𐳊m�ɕ`���B���z����n���܂ł̋����a�Ƃ����]�~��`���A���z����ΐ��܂ł̋��������]�~�̔��a�Ƃ���B����āA�ΐ��̈ʒu(M�E�ԐF)�A�O���͑�4�}�̂悤�ɂȂ�B �@ ���V����(���]�~�����v�g���}�C�I�X�^)�ƃe�B�R�E�u���[�G�̐��̊w�I�W �@ ���ׂĂ̘f���Ԃ̋����̃X�P�[���𐳊m�ɕ`�����V�������瓱������2�}�ƒn�������瓱������4�}�Ƃ�g�ݍ��킹��ƁA��5�}�̂悤�ɂȂ�A�ΐ��̈ʒu(M�E�ԐF)�A�O���͈�v����B �@ ��6�}��x-y���W�ŁA���z����n���ւ̃x�N�g����aE�Ƃ��A���z����ΐ��ւ̃x�N�g����aM�Ƃ��A�n������ΐ��ւ̃x�N�g����aEM��aM-aE�Ƃ���B �@ ��v���闝�R�́AaM��-aE�Ƃłǂ�����]�~�ƌĂ�ŁA�ǂ�������]�~�ƌĂԂ��́A�Ăѕ��̖��ł����āA�w�I�ɂ͊��S�ɓ���������ł���B �@ ���t�s�^���ɂ��� �@ ���z�A�n���A�ΐ����꒼���ɕ��t�߂ő��z�̓����ɉΐ��͈��������ċt�s����B�܂����̂Ƃ��́A�ΐ����n���ɍł��߂Â����ł�����B ����́A�v�g���}�C�I�X�̐������ۂ̗l�q�ł���R�y���j�N�X�̐��������ł���B �@ �� �@ ���̂悤�ɁA�v�g���}�C�I�X�̓V����(���]�~��)����R�y���j�N�X�̒n�����֓]���̊W��\�����Ƃ��ł���B�V����(���]�~��)���A�]�~�̔��a�̑傫�������z����ΐ��܂ł̋���(��aM��)�A���]�~�̔��a�̑傫�������z����n���܂ł̋���(��aE��)�ł���A�e�B�R�E�u���[�G�̐��ł̘f���O���Ɠ����O������̂ł���B�������A��X�������F���ł���̂͘f������ǂ̕����Ɍ����邩�ł���B������v�g���}�C�I�X��́A�\1�̂悤�ɘf���̐��m�Ȉʒu���͂�����킩���Ă��Ȃ������̂ł���B |
|
|
���K�����C�̖]�����ł̔���
�@ �K�����I�E�K�����C(Galileo Galilei�A1564-1642)�́A�]����(�K�����C���]�����������킯�ł͂Ȃ�)��p���āA�l�X�ȓV�̊ϑ����s�����B�K�����C�́A�w���E�̕x(1610)�ŁA�ȉ��̂悤�ɕ��Ă���B �@ ��1.�@���\�ʂɂ��� �@ �K�����C�́A�]������p���āA�����ϑ������B����ƌ��͑�1�}�̂悤�ɁA �@ (1)�@�O�����̂Ƃ��A�Í����ƏƖ����̋��E���͑N�₩�ȗ��`�ł͂Ȃ��A��l�łȂ����������̋Ȃ��肭�˂�������`���Ă���B �@ (2)�@�����_�́A�Ɩ����ł͍����A�Í����ł͂��炫��Ɩ��邢�B����Ɠ����悤�Ȍ��i�́A�n��ł�������B �@ ���̂��Ƃ���A���̕\�ʂɂ́A�����̓N�w�҂��咣���Ă���悤�Ȋ��炩�ň�l�Ȋ��S�ȋ��̂ł͂Ȃ��B�n�\�Ɠ����悤�ɋN���ɂƂ�ł���B�R��J������n�\�Ɖ���ς��Ȃ��B �@ �Ƃ������Ƃ��킩�����B �@ ����āA�V(�������)�͊��S�Ȃ���̂ł��鋅����ł��Ă���Ƃ������͕����ꂽ�B���̂悤�ɁA���ƒn���Ƃ̗ގ��������炩�ɂȂ����B �@ ��2.�@�P���ɂ��� �@ �K�����C�͍P���ɂ��āA���v����Ɍ����鐯�́A���Ƃ��ꓙ���ł����Ă���Ϗ�����������B���Ƃ���A���̌������̑傫���́A�{�̂ɂ���Ăł͂Ȃ����̌��ʂɂ���ĕς��B �Ƃ����B����āA�P���͉F���̂͂邩�����ɑ��݂��A�F���͑�ύL��ł���ƍl�����B �@ ��3.�@�ؐ��̎l�q���ɂ��� �@ �܂��A�K�����C�̖]�����͗D��Ă������߁A���R�ɖؐ��̎����4�̐��������B�ŏ��̓��ɔ�������4�̐��̈ʒu�Ɨ����A���X���A�E�E�E�Ɍ���4�̐��̈ʒu�͈���Ă����B���̊ϑ����ʂ��܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B �@ (1)�@�ގ������Ԋu�Ŗؐ��Ɍ�ꂽ��旧�����肵�Ă���B �@ (2)�@����߂Č��肳�ꂽ�L����ɂ����Ă̂݁A�ؐ����瓌�ցA���邢�͐��ֈړ�����B �@ (3)�@�ؐ��̋t�s�^���̍ۂɂ��A���s�^���̍ۂɂ������悤�ɐ�������B �@ ���̂��Ƃ���A �@ (1)�@�����̘f��(4�̐�)���ؐ��̎������]���Ă���B �@ (2)�@�ؐ���4�̐����ꏏ��12�N�����ő��z�̎������]���Ă���B �@ (3)�@4�̐��͈قȂ�O������]���Ă���B �@ �Ƃ��A����4�̐���ؐ��̉q���Ƃ����B �@ ���̖ؐ��̉q���̔����ɂ���āA�R�y���j�N�X�̉F���̌n��ے肵�Ă����w�ҒB�Ɉ�𓊂����B�ނ�́A�R�y���j�N�X�̌n�ɂ����鑾�z�̎���̘f���̉�]�͎�����邪�A�n���ƌ����ꏏ�ɑ��z�̎������]���A�n���̎����������]���Ă���̂ɋ^������B�������A�ؐ��̉q���̔����́A���̋^�����菜�����ƂɂȂ낤�B�ؐ��͒n���Ɠ����悤�ɑ��z�̎������]���A4�̉q���͌��Ɠ����悤�ɖؐ��̎������]���Ă���B�f�������z�̎������]���A����̘f���̎���𑼂̘f������]���Ă���Ƃ������Ƃ͉����^���ׂ����Ƃł͂Ȃ��B���̂悤�ɁA�R�y���j�N�X�̒n������⋭�����B �@ ��4.�@���z���_�ɂ��� �@ ����ɁA���z���ϑ����A���_�������B���_�́A �@ (1)�@���z�ʂ��炸���Ɨ���Ă��炸�A�t�����Ă��邩�ɂ߂ċ߂��B �@ (2)�@������̂͐������A������̂͏��ł��Ă����B���̊��Ԃ́A�s�K���ł���B �@ (3)�@���_�̑啔���́A�s�K���Ȍ`�����Ă���B�����āA�₦���ω����Ă���B �@ (4)�@�Â����₦���ω����Ă���B �@ (5)�@1�̍��_��2�A3�ɕ������邱�Ƃ�1�Ɍ������邱�Ƃ�����B �@ �Ƃ������Ƃ������B�������A���̂悤�Ȗ������ȌʓI�^���̑��ɑS�̂ɋ��ʂ���^��������B����́A �@ (1)�@��l�ȉ^���ɂ���Ă��݂��ɕ��s����`���Ȃ��瑾�z�̖{�̂�ʉ߂���B�@ (2)�@���_�́A���z�̗��ɂɋ߂Â��ɂ�āA�^���͏������A��������ɂ�A�^���͑傫���B �@ ���Ƃł���B���̂��Ƃ���A���_�́A���z�ʂɕt�����Ă��āA���z�̎��]�ɂ�ē������Ƃ��킩�����B�܂��A���_�́A�����Ɛ[���������Ă��邱�Ƃ��ϑ����ꂽ�B �@ ���̑��z�̍��_�̔����ɂ���Ă��A�V(�������)�͊��S�Ȃ���̂ł��鋅����ł��Ă���Ƃ������͕�����A�V�ƒn�͕ʐ��E�ł���Ƃ������͔ے肳�ꂽ�B �@ �܂��K�����C�́A�w�V���Θb(�v�g���}�C�I�X�ƃR�y���j�N�X�̓�吢�E�̌n�ɂ��Ă̑Θb)�x(1632)���o�ł����B���̏��́A�R�y���j�N�X�̒n������V���ϑ���V�����^���_�ɂ���ĕ⋭�������A�K�����C�ٔ����Ђ����������ƂȂ����B �@ �w�V���Θb�x��1���ڂ́A�A���X�g�e���X�́w�V�̘_�x�ւ̔ᔻ�Ƃ����`�œW�J�����B �@ ����2���ڂ́A�n������ے肷��l�X�̎咣���Ă����Ƃ����`�œW�J�����B�����n������ے肵�Ă����l�����́A �@ (1)�@�����n�������]���Ă���̂Ȃ�A�n����̕���(��C�E�����グ��ꂽ���̂Ȃ�)�͌��Ɏ��c����邾�낤�B�@ (2)�@�����n�������]���Ă���̂Ȃ�A�n����̕��͉̂��S�͂ʼnF���Ɍ������ē����o����邾�낤�B �@ �Ǝ咣���Ă����B�����ŃK�����C�́A(1)�̎咣�ɓ����邽�߂ɁA�L���ȁu�D�̃}�X�g����̗��������v���Ƃ肠���A �E�E�E �@ �͑D�������Ƃ��Ă��悤�ƂƂĂ����������Ă��悤�ƁA��ɓ����ꏊ�ɗ����邱�Ƃ��������ł��傤�B�ł�����A��n�ɂ��Ă��D�ɂ��ĂƓ��������ɂ���ȏ�A����ɓ��̍����ɗ����邱�Ƃ���͑�n�̉^���ɂ��Ă��Î~�ɂ��Ă��������_����邱�Ƃ͂ł��܂���B �@ �܂��K�����C�́A(2)�̎咣�ɑ��ẮA�n���\�ʂ���㏸���悤�Ƃ���X���̑傫��(���S��)�ƒn���̒��S�֗������悤�Ƃ���X���̑傫��(�d��)���r���悤�Ƃ����B�����ŁA��҂̑傫���͗��������͗������Ԃ�2��ɔ�Ⴗ��(�uy=0.5gt2�v)�Ƃ����@���ɏ]���Ă��邱�Ƃ������o�����B�������A���S�͂̑傫���͗ʓI�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂Œ��ςɑi����`�Łu�ɂ߂ď������v�Ƃ����B�@ ����āA�F���Ɍ������ē����o����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ƃ����B �@ �ȏ�ɂ��K�����C�́A�R�y���j�N�X�̒n������V���ϑ���V�����^���_�ɂ���ĕ⋭�����B |
|
|
����]�n�̐��E(�t�[�R�[�̐U��q)
�@ 19���I�����A�R�y���j�N�X(Nicholas Copernicus�A1473-1543)�̒n������K�����C(Galileo Galilei�A1564-1642)�ɂ��ؐ��q���̊ϑ��Ȃǂɂ��n���̌��]�⎩�]�͈�ʓI�ɔF�߂��Ă����B�������A�n���̎��]�ڒn��Ŋm�����i�������Ă��Ȃ������B���̂悤�Ȓ��ŁA1851�N�Ƀt�[�R�[(Jean Bernard Leon Foucault�A1819-1868)�͋���ȐU��q(����67���A������16�b)��p���āA�n���̎��]��l�X�̖ڑO�Ŏ������Č������B(�t�[�R�[���͂��߂Ď������s�����Ƃ��́A�킸������2m�̐U��q�ł������B) �@ �ȒP���̂��ߖk�ɂŎ������s�����ꍇ���l����B �@ �U��q�́A�F�����(���]���W�n)����ώ@����ƒP�U������B�����n��(��]���W�n)����ώ@����ƐU��q�́A�P���ȒP�U���ł͂Ȃ��U���ʂ���]����悤�Ɍ�����B����Ėk�ɂł́A�U���ʂ͐i�s��������E���ɋȂ����A1���Ŏ��v����1��]����悤�Ɍ�����B �@ �t�[�R�[�͂����n���̎��]�̏Ƃ����̂ł���B��ɂł́A�U���ʂ̉�]�͋t�ɂȂ�B�܂��A�ɈȊO�̈ܓx�ł́A�d�͂̕�������]���ƕ��s�łȂ����߂ɁA��]������1�����������Ȃ�B�܂�A�ܓx���ӂ̂Ƃ���ł́A1��(���m�ɂ́A�n���̎��]����23����56��54�b)�ŁA360���~sin�ӂ����U���ʂ���]����B����āA�V���ł́A38��N�Ȃ̂ŁA360���~sin38��=221.6���ƂȂ�A1���ԂŖ�9����]����B�����āA���̒n���̎��]�ɂ���Đ�����R���I���̗͂ɂ��A�n���̑�C�E�C�͉^���̕�������]������̂ł���B���̘b�́A�����ǂ��m���Ă�����̂ł���B �@ �V���~���[�V�����ł́A��]���W�n�̎������ȒP�ɕω������邱�Ƃ��ł�(��]���W�n�̎������U��q�̎���)�A�����̎����̔�ɂ��A�U��q�̋O�Ղ͗l�X�ȉԕٌ^�ɂȂ�B �@ �U��q�̎����ɉ�]�������߂Â��Ă���ƁA�R���I���̗͂��傫���Ȃ�A�U��q�̋O�Ղ͑傫���Ȃ�����B�����āA�U��q�̎����Ɖ�]�����Ƃ���v(��]���W�n�̎������U��q�̎���)�����Ƃ��A �U��q�̉^������]���W�n����ώ@����ƁA�����^���ł͂Ȃ����S�ȉ~�^���ɂȂ�B �@ �������A�~�^�������Ă���悤�Ɍ�����U��q�̋O�Ղ��A���]���W�n����ϑ�����A�P���ɒP�U�������Ă���̂ł���B�܂�A��(�U����)�̒���P�U�����A���̓�����]�^�����Ă��邾���Ȃ̂ł���B���̂悤�ɁA��]���W�n���猩���U��q�Ɣ��]���W�n���猩���U��q�́A����n�̈Ⴂ�ł����ē����U��q�ł���B �@�@ �@ |
|
| ���n���� 6 | |
|
���V��������n������
�@ �V�̂̌����̂ЂƂɁA�V�����ƒn�����Ƃ������̂�����܂��B �@ �V�����Ƃ́A �n���̎���̓V�̂��n���𒆐S�Ƃ��ĉ���Ă���Ƃ����l�����B�����Ēn�����Ƃ́A�n�����F���̒��S�ł͂Ȃ��A �n���͂����܂ł��q���̂ЂƂő��z�̎�������邮�����Ă���Ƃ���߂ł��B �@ ���݂ł͌��킸�����Ȓn����������Ƃ���Ă���킯�ł����A400�N�قǑO�܂ł͓V������������O�Ƃ��Ďx������Ă��܂����B���������ǂ̂悤�ɂ��ēV��������n�����ւƈڂ�ς���Ă������̂ł��傤���B �@ ���v�g���}�C�I�X �@ ���������V�����Ƃ́A�Ñ�M���V���� �v�g���}�C�I�X���ł��o�������_�ŁA�J�g���b�N�����x��������Ă����l���ł����B�܂�A���̓V�������x�����Ȃ��w�҂͋��c����e������A�ň��̏ꍇ���Y�ɂ�����Ă��܂��Ă����̂ł��B �@ ���������n�����ۂ��ł��Ƃ��A�d�͂Ƃ����T�O���܂��Ȃ�����ł��B���z�͓������萼�ɒ��ށA�n�ʂ������Ă���ȂǑS�������Ȃ������B�V�������x�����ꂽ�̂�������܂��ł��B �@ ���R�y���j�N�X�̓o�� �@ �����ɕ\�ꂽ�̂��A�J�g���b�N���̎i�Ղ����� �R�y���j�N�X�ł��B�ނ͓V�����ł͐����̂��Ȃ����������̑������A�n�����ł���ΐ��������Ǝ咣���܂��B�������A�����ɂ͖]�������Ȃ��A�l�X��[��������؋�����邱�Ƃ��ł����ɂ��܂����B �@ ���K�����I �@ 17���I�ɓ���]�������������ꂽ���ƁA���̒n�������x�������̂� �K�����I=�K�����C�ł��B�ؐ��ɂ�4�̉q�������݂��Ă��邱�ƁA�����ċ����̖��������Ƒ傫�����ω����Ă��邱�ƂȂǁA�V�����ł͐������ł��Ȃ����ۂ����Ă����܂����B �@ �������A�����̎嗬�͂�͂�V�����B��肷���Ă��܂����K�����I�͏@���ٔ��ɂ������A���������Ԃɕa�����Ă��܂��܂����B �@ ���Ȃ݂ɂ��̔N�ɁA���L���́A�����Ēn����������Â��銵���̖@�����`�t���� �A�C�U�b�N=�j���[�g�������܂�Ă��܂��B �@ ���@���ٔ��̌� �@ �K�����I�̒e���̌�A ���n�l�X=�P�v���[���o�ꂵ�܂��B �@ �ނ͎��g�̊ϑ��L�^����A�q���̊G�`���N���͑ȉ~�ł��邱�Ƃ��A�����ă��h���t�\�ƌĂ��V�̕\���o�ł��܂����B�V�����ł͐��������Ȃ�����������Ƃ������Ƃ����_�̒��ōL�܂�n�߂��̂ł��B �@ �����čŌ�ɓo�ꂷ��̂� �A�C�U�b�N=�j���[�g���ł��B�ނ͖��L���͂Ɗ����̖@����g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�n���������Ă��Ă����̐��ɐ������Ă���l�����ɂ͉e�����Ȃ����Ƃ�����Â��܂��B �@ ����ɂ��A�V�����̖�����j�����n�������V�����_�Ƃ��Ďx������Ă������ƂɂȂ�̂ł��B�@�@ �@ |
|
| ���R�y���j�N�X�̒n���� 7 | |
|
�n�����������A�`���I�ȉF���ς����R�y���j�N�X�B
�@ �������]�������甭������Ă��Ȃ���������ɁA�ނ͂ǂ�����Ă��̍l���ɂ��ǂ蒅�����̂��낤���H �����Ĕނ̊v���I�Ȗ{�A�w�V���̉�]�ɂ��āx(1543)�͖{���Ɋv���I�ȓ��e�������̂��낤���H�R�y���j�N�X�̖{���o�ł����܂ł̌o�܂�ǂ��Ȃ���A�ނ��n���������������̐^�ӂɔ���B |
|
|
���k��
�@ 1539�N�A�t�B��\�㔼�̈�l�̎�҂��A�_�����[�}�鍑�암�̊X�j�������x���N�𗷗����āA�k�ւƌ��������B �@ �ړI�n�́A�o���g�C���݂̓s�s�A�t�����{���N�B�����|�[�����h�Ɉʒu���邱�̊X�܂ł́A�j�������x���N���炾�ƒ��������ł�800�L���߂�����B�ނ�����قǂ̒�������`���Ă܂ŗ��ɏo���̂ɂ́A���R���������B�ǂ����Ă��A����l���ɉ���������̂��B �@ ��҂̖��́A�Q�I���N�E���A�q���E���e�B�N�X�Ƃ������B���B�b�e���x���N��w�\�\���̎���ɂ́A���^�[�ɂ��@�����v�̒��S�n�������\�\�Ŋw�ʂ��������A�����Ő��w�̍u�t�����Ă����l���ł���B�����A��w�ŋN��������������������ăj�������x���N��K�ꂽ���ƂŁA�ނ̉^���͕ς�����B��ȉ\�����ɂ����̂��B�Ȃ�ł��A�t�����{���N�ɏZ�ނ���w�҂��A�܂������V�����V���w���_���������Ă���炵���B����ɂ��ƂȂ�ƁA�n���̎���z������Ă���̂ł͂Ȃ��A���̊m�łƂ����n���̕������z�̎��������Ă���Ƃ����̂��c�c�B �@ �ɂ킩�ɂ͐M����l�����������A���e�B�N�X�͑傢�ɋ����������A�b���Ă݂悤�ƌ��S�����B����͖l�̉��������A���e�B�N�X������قǎ䂫����ꂽ�̂́A�ނ��萯�p�ɊĂ��������S�̂����������̂�������Ȃ��B�����A������A�n�������z�̎��������Ă���̂��������Ƃ����Ȃ�A�萯�p�ɗ^����e���ɂ͌v��m��Ȃ����̂��������B�Ȃɂ��낱�̎���A�萯�p�ƓV���w�͖��ڂȊւ������w�╪�삾�����̂��B�V���w�҂������ɐ萯�p�t�ł�����Ƃ����̂́A�����Ē������b�ł͂Ȃ������B �@ �j�������x���N�ŏo������V���w�҂̃V�F�[�i�[�Ə��Џ��̃y�g���C�E�X���A���̎Ⴂ���w�҂̗��������㉟�������炵�������B��l�́A���̐V�����V���w���_�����ЂƂ��{�ɂ��ďo�ł������ƍl���Ă����̂��B���ہA���e�B�N�X�̓t�����{���N�ւ̎�y�Y�Ƃ��Č܂̏��Ђ������čs�����̂�����ǂ��A���̂����O�̓y�g���C�E�X���o�ł������̂������B����͈�����{�����˂Ă����̂ł͂Ȃ����ƁA�Ȋw�j�̌����҂͐������Ă���B �@ �Ƃ������A���e�B�N�X�͖k�ւƌ��������B�l��͐��肵�ă|�[�����h�ɍs���A���łɎ��Ԃ𐔏\�N�k���āA���̐V�����V���w���_���ǂ̂悤�ɂ��č\�z���ꂽ�̂������Ă������Ƃɂ������B �\�\�����A�̐S�Ȃ��Ƃ������Y��Ă����B���̐l���́A���̖����j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�Ƃ����B |
|
|
���V���w�Ƃ���
�@ �|�[�����h�Œ��̉͐�A���B�X����̒����Ɉʒu����X�g�����́A�n���U�����̈ꗃ��S���s�s�Ƃ��āA15���I���ɂ͑傢�ɔɉh���Ă����B�R�y���j�N�X�͂��̊X�ŁA1473�N��2��19���ɐ������ƍl�����Ă���B �@ �T���ȏ��l�K���̉ƒ낾�������A10�̍��ɕ��e���S���Ȃ������߁A���̌�͕���̔����Ɉ�Ă�ꂽ�B�㌩�l�ƂȂ������̔����́A�ɂ߂Č��i�ō����I�Ȑl���������Ɠ`�����Ă���B���n��ɂ������Ă����B����@�̊w�ʂ��������A����g�D�̒��ŏo�����A1489�N�ɂ̓��[�~�A�Ƃ����n��̎i���ɂ܂łȂ����B����ɂ��̔����́A����̎x�z�͂�ۂ��߁A����g�D�̏d�v�Ȗ�E��g���Ōł߂悤�Ƃ������B���������킯�ŁA�R�y���j�N�X�Ɣނ̌Z�́A���̂��߂ɃN���N�t�̑�w�ւƑ����邱�ƂɂȂ����̂������B �@ �����̑�w�Ƃ����̂́A��ʋ��{�ɂ�����N�w���ƁA�_�w�E�@�w�E��w�Ƃ������I�ȎO�̏㋉�w������Ȃ��Ă��邱�Ƃ����������B���E�҂Ɩ@���Ƃƈ�҂������I�ȐE�Ƃł���̂́A�Í������قړ������ۂ炵���B���Ȃ݂ɁA��w�Ƃ����Ă�����̂悤�ɃL�����p�X������킯�ł͂Ȃ��Buniversitas(university�̌ꌹ)�Ƃ������t�͂��Ƃ��ƁA���t��w���̑g���̂��Ƃ��Ӗ����Ă����B������A�R�y���j�N�X���u�N���N�t��w�֍s�����v�Ƃ����̂́A�u�N���N�t�̊X�ɂ��������t�E�w���̑g���ɓo�^���āA�ǂ����̉Ƃ⋳��Ȃǂōs��ꂽ�������̍u�`�����v�Ƃ����Ӗ��ɗ�������K�v������B �@ �R�y���j�N�X��22�̍��܂ŃN���N�t�ɂ����炵�����A���ۂɉ���������̂͂悭�������Ă��Ȃ��B�����A���w�ƓV���w�̍u�`�\�\�ӊO�Ɏv����������Ȃ����A�����͓����A�N�w���ŋ�������u��ʋ��{�Ȗځv�������\�\�ɋ������������̂͂����炭�ԈႢ�Ȃ����낤�B �@ �R�y���j�N�X�����̎����Ɏ�ɓ���A�S���Ȃ�܂ł����Ǝ����Ă����{������B����͓���̖{�Ɖ������̔�����Ԃ��Ĉ�ɂ������̂ŁA���������ɂ͂������̏d�v�ȃ�����������Ă����B���̃����ɂ��Ă͌�ŐG��邱�ƂɂȂ邪�A�ЂƂ܂��͂��̖{�ɒ��ڂ��Ă݂悤�B �@ ����̖{�́A�w�A���t�H���\�\�x(���F�l�c�B�A�A1492�N��)�Ɓw�O�p���\�x(�A�E�O�X�u���N�A1490�N��)�Ƃ������̂ł���B�ǂ�����A���̉^�s���v�Z���邽�߂̃f�[�^�E�u�b�N���ƍl���Ă��炦�������Ǝv���B���̂����w�A���t�H���\�\�x�́A13���I�ɃJ�X�e�B�[����(�X�y�C��)���A���t�H���\10���̖����ĕҎ[���ꂽ�\�ŁA�D���ȏꏊ�E�����ɘf�����ǂ��ɂ��邩���v�Z�ł���D����̂������B������́w�O�p���\�x��15���I�ő�̓V���w�҃��M�I�����^�k�X�̎�ɂ����̂ŁA��ɐ萯�p�̌v�Z���菕�����邽�߂̂��̂����A���m���e�����E�ł����炭���߂ă^���W�F���g(tan)�̐��l���ڂ����{�ł�����B�ǂ����17���I�O���܂ŌJ��Ԃ��ł��d�˂Ă���A�V���w�̕���̃x�X�g�Z���[�������ƌ����Ă����B �@ ���̓���̖{������@�����t���悤�ɁA�����̓V���w�Ƃ����̂́A�������܂���(�f��)�����ǂ̈ʒu�ɂ���(������)�����v�Z����w�₾�����B�Ȃ�����Ȍv�Z���K�v���ƌ����A����͗����邽�߂ł�����A�܂��萯�p�̂��߂ł�����B�������́u�V���w�v�ƕ����ƁA����Ȗ]�����Ő����ϑ�������A�F���̍\����藧�����@���ɂ���ĉ𖾂�����Ƃ��������Ƃ��v�������ׂ邯��ǂ��A���̎���̓V���w�ɂ������������͋C�͂܂������Ȃ��B�R�y���j�N�X�́A�m���ɓV���w�̕���ŗ��j�Ɏc��Ɛт��������̂����A�f���̊Ԃɓ������̖͂@�����m��Ȃ��������A�]�����Ő����������Ƃ���Ȃ������\�\�����������̎���ɂ͂܂��A�]��������������Ă��Ȃ��̂��I�@�R�y���j�N�X�������ɂȂ����̂́A�ق��ł��Ȃ��A���̉^�s�́u�v�Z�v�������B���܂̊��o���炷��A����͓V���w�Ƃ��������ނ���A���w�Ƃ��������������肭��悤�Ȑ��E�ł���B |
|
|
���C�^���A�ɂ�
�@ �{���[�j����w��1088�N�ɑn�݂��ꂽ���[���b�p�ŌÂ̑�w�ŁA���ɖ@�w����̋���ŗ��j�I�ɂ��̖���m���Ă���B�R�y���j�N�X��1496�N�̏H�A23�̂Ƃ��ɃC�^���A�ɂ���Ă��Ă��̖����w�ɓo�^���A�@���̕����n�߂��B��̔������R�y���j�N�X�̂��߂Ɂu�i���������Q������v�Ƃ�����������̃|�X�g���m�ۂ������߁A����@���w�ԕK�v���������̂��B�i���������Q������Ƃ����̂́A�i���\�\�܂�ނ̔����\�\��⍲���Ă��̒n��̍s���E���@�E�i�@�S�ʂ̎d�����s���A���������Ƃł��Ăׂ����ȐE�̂��Ƃł���B���Ȃ݂ɔ������g�A�{���[�j����w�ŋ���@�̊w�ʂ��������A�Q������̃|�X�g�ɏA���Ă����B���̂��Ƃ͂Ȃ��A�����̓R�y���j�N�X(�Ƃ��̌Z)�ɁA�����Ɠ����o������܂��悤�Ƃ����킯�ł���B �@ �����R�y���j�N�X�́A���̃{���[�j�����w���ɂ͋���@�̊w�ʂ����Ȃ������B�����Ă��̑���Ɂ\�\�ƌ����Ă悢���ǂ����͒肩�łȂ�����ǂ��\�\�M���グ���̂��V���w�������B���̎����̃R�y���j�N�X�̊����ɂ��ẮA���܂܂��ɔނ̌��ւƌ������Ă��郌�e�B�N�X����N�A��������Ă���B �@ �킪�t�ł�����Ƃ���̔��m�m���R�y���j�N�X�n�́A�{���[�j���ɂ���ꂽ�Ƃ��A�ɂ߂Ċw������l���h�~�j�R�E�}���A�m���{���[�j����w�V���w�����n�́A�w���Ƃ������͂ނ���A���肩�ϑ��̏ؐl�ł���܂����B����Ƀ��[�}�ł�1500�N���A��������27�ł������A�w�������̑�Q�̑O�ŁA�܂������̐l�X�Ɏ��͂܂�āA���w�ɂ��ċ�������Ă���A���̎�̊w��ɂ͏n�B���Ă����܂����B �@ ����͂������Ɍ֒��������̊������邪�A�R�y���j�N�X�����̎����Ƀ{���[�j���ƃ��[�}�ł��ꂼ��V���ϑ����s�����Ƃ����L�^�͎c���Ă���B�@�w�̕������Ă��Ȃ�����A���w�ƓV���w�̕��ɂ��������S���������̂͊m�����낤�B �@ ��1501�N�A�R�y���j�N�X�́A���x�̓p�h���@�ɂ���Ă����B���̎���A�{���[�j����w���@�w�̃��b�J�������Ƃ���A�p�h���@��w�͈�w�̃G���T�������B�R�y���j�N�X�̓{���[�j�����炢������A������(�I)���w�����̋��A�ĂуC�^���A�܂�(�I)�A���x�͈�w�̕������ɗ����̂��B�����Ƃ��l�Ƃ��ẮA�R�y���j�N�X�����w�����������̂͒P�ɓV���w�̕��𑱂�������������ł͂Ȃ����Ƃ����C������킯�����c�c�B �@ �Ƃ������A�R�y���j�N�X�̓p�h���@��w�œ�N�Ԋw��A1503�N�Ƀt�F���[����w�ŋ���@�̊w�ʂ��擾���ċA������(���ǁA��w�̊w�ʂ͎���Ă��Ȃ�)�B�킴�킴�ʂ̑�w��I�̂́A�K�v�o����Ȃ��Ă��ނ��炾�����炵���B�����Ă���ȍ~�A�R�y���j�N�X�͊�{�I�ɂ����ƁA���[�~�A�i����ɂƂǂ܂��Ĉꐶ�𑗂邱�ƂɂȂ�B�����A�b�̕�������[�~�A�Ɉڂ��O�ɁA�����̃C�^���A�̏ɂ��Ă��������b���Ă������Ƃɂ��悤�B���ƌ����Ă����̎���A�C�^���A�̓��l�T���X�̍Ő������}���Ă����̂�����B |
|
|
���v�g���}�C�I�X�E�����@�C���@��
�@ ���l�T���X�ƕ����ƁA�Ȃ�Ƃ����Ă��܂��G��⒤�����v�������ԁB�������Ȋw�ɂƂ��Ă��A���l�T���X�͂ƂĂ��d�v�ȈӖ��������Ă����B���̎���ɂȂ��Ă悤�₭�A�Ñ�M���V�A�̕����E�w�₪�ڂ������������悤�ɂȂ������炾�B �@ �Ñ�M���V�A�Ƃ����͍̂����ł����A���m�̂قƂ�ǂ�����w��(���R�Ȋw���܂߂�)�̏o���_�ƌ��Ȃ���Ă���B�������̓��l�T���X�̎���ɂȂ�܂ŁA���悻��N�ȏ���̊ԁA�����l�͌Ñ�M���V�A�Ȋw�̈�Y���قƂ�ǒm��Ȃ������B�Ñ�M���V�A�̖{�i�I�ȁu�����v�͂�������12���I���Ɏn�܂�̂����A���������u�����v�������I�ɑ������̂��A14���I����16���I�ɂ����ẴC�^���A�E���l�T���X�̎��ゾ�����̂ł���B �@ �u�����v�Ƃ͌����Ă��A��̂̈�Ղ����@���ꂽ�Ƃ����悤�ȈӖ��ł͂Ȃ��B�Ñ�M���V�A�̕����́A�����ł͂قƂ�ǖY�ꋎ���Ă��܂��Ă������A����(�����[�}�鍑)��A���r�A�̐l�X�����̈�Y���p���A�Ǝ��ɔ��W�����Ă����B�����͂��������u��i�I�ȁv�����ɑ������A�����|�ċz�����邱�ƂŁA�ߑ�I�ȉȊw�̊�Ղ�����Ă������̂��B�R�y���j�N�X���C�^���A�Ŗڂ̓�����ɂ����̂́A���������Ñ�̈�Y�����ݐi�s�`�ŕ������������i�������B �@ �����������l�T���X�^�������̃C�^���A�ɗ��w���Ă��������̂��Ƃ͂����āA�R�y���j�N�X�����̊ԂɃM���V�A����w�B�����ċA����ɂ́A�w���P�E�c���E���̏��ȏW�x�Ȃ�M���V�A��̖{��|��E�o�ł��邱�Ƃ������Ă���(1509�N)�B�����ł͎����Ă����M���V�A��̕������������A�w��p��ł��郉�e����ɖ|�邱�Ƃ��A�����̗��s�������B�����Ƃ��A���̖{�͂��������u�莆�̏��������{�v�̂悤�Ȃ��̂ł����āA�킴�킴�قǂ̉��l�͂Ȃ��炵���̂����c�c�B �@ �Ƃ͂����A�Ñ�M���V�A(����у��[�})�̕����Ƃ������l�T���X�̐��_�́A�R�y���j�N�X�̓V���w�����ɂƂ��Ă����ɏd�v�ȈӖ��������Ă���B�Ñ�M���V�A�ő�̓V���w�҃v�g���}�C�I�X�̒�����A�����ł̓��l�T���X�̎���ɂȂ��Ă悤�₭�A�{�i�I�Ɍ�������n�߂����炾�B �@ �v�g���}�C�I�X�́A�R�y���j�N�X�̎��ォ��k�邱��1200�N�ȏ�O�A�I����2���I�ɌÑ�M���V�A�̓s�s�A���N�T���h���A(���݂̓G�W�v�g�Ɉʒu����)�Ŋ����l���ŁA����܂ł̓V���w���_���W�听�����w���w�I�����S13���x���������B���̖{�͂��ꂩ��700�N�قnj�A9���I�ɂȂ��ăA���r�A�̓V���w�҂̒��ڂ��W�߂�悤�ɂȂ�A�A���r�A��ɖ|���B���̍ہA�����炭���̓��e�����܂�ɐ����������炾�낤�Ǝv���̂����A���̖{�́w�ő�̏��x�ƌĂꂽ�B�����āA���ꂩ�炳���300�N���o����12���I�ɂȂ��Ă悤�₭���e����ɖ|��A�A���r�A��́w�ő�̏��x�������^�C�g���A�w�A���}�Q�X�g�x�̖��Œm����悤�ɂȂ����B �@ ���e����Łw�A���}�Q�X�g�x��1515�N�ɍŏ��̈���{���o�ł���A�R�y���j�N�X���������肵���B�Ƃ���ŁA���܁u�ŏ��̈���{�v�ƌ���������ǂ��A�O�[�e���x���N�����������ɂ�銈�ň���������̂�1450�N���̂��Ƃ��B����܂Ŗ{�Ƃ����͎̂�ŏ����ʂ����̂������̂ɁA���ꂩ�甼���I��ɂ͂����A������ꂽ�{���������Ȃ��Ȃ��Ă������ƂɂȂ�B���������A�R�y���j�N�X�͊w������ɂ��łɁA����̃f�[�^�E�u�b�N�̈���{����ɓ���Ă����B���傤�nj��オ�C���^�[�l�b�g�̍L�����y��������ł���悤�ɁA�R�y���j�N�X�́u����v���v�̉��b���\���Ɏ邱�Ƃ̂ł����ł������̐���ɑ����Ă����̂��B �@ �����Ƃ��A�ŏ��̈���{���o��O����A�w�A���}�Q�X�g�x�͎菑���̎ʖ{�̒i�K�ŏڂ�����������A�V���w�҂̂������ōL���m����悤�ɂȂ��Ă����B���ɁA�R�y���j�N�X�̎g���Ă����w�O�p���\�x�̒��҂ł����郌�M�I�����^�k�X�́A���ڃC�^���A�܂ŗ����ėl�X�ȃM���V�A�ꕶ������肵�A�����O��I�Ɍ��������B���̐��ʂ͎���A�w�A���}�Q�X�g�j�v�x�Ƃ��ďo�ł���(1496�N)�A���̖{�̓R�y���j�N�X�̈��Ǐ��ƂȂ�B�܂��A�ނ��W�߂��ʖ{�����Ƃɂ��āA1538�N�ɂ͂��ɁA�w�A���}�Q�X�g�x�̃M���V�A�ꌴ�T�����߂ďo�ł��ꂽ�B���́A���e�B�N�X���R�y���j�N�X�ւ̎�y�Y�Ƃ�����̌܍��̖{�̂���������A���̃M���V�A��Łw�A���}�Q�X�g�x�Ȃ̂��B�R�y���j�N�X��������������A����������Ԃ��Ƃ��낤�B �@ ���āA���e�B�N�X������Ă���܂łɂ́A�܂����Ԃ�����悤���B�ނ̓�����҂������ɁA�w�A���}�Q�X�g�x�ɏ�����Ă����V���w���_�Ƃ͂ǂ�Ȃ��̂Ȃ̂��A�ȒP�ɐ������Ă������Ƃɂ������B |
|
|
���u�ő�̏��v
�@ �w�A���}�Q�X�g�x�̐����́A�ꌩ����ƕs���Șf���̓������A�����ȍH�v�ɂ���ė\�����Ă������Ƃɂ���B �@ �u�f���v�Ƃ����̂̓M���V�A��́u���܂悤�l�v�ɗR�����錾�t�ŁA�����͐����E�����E�ΐ��E�ؐ��E�y���E���E���z�̎����w���Ă����B����������悤�ɁA����͍����A�l�炪�u�f���v�ƌĂ�ł�����̂Ƃ͈Ⴄ�B����Ō����Ȃ��V������C�����������Ă��Ȃ��͖̂]�����̂Ȃ����ゾ���瓖�R���Ƃ��Ă��A�Ȃ����⑾�z���f���Ȃ̂��H�@����́A���̓�̐����A�ق��̌܂̐��Ɠ����悤�ɁA���ɋP�������̊Ԃ��u���܂悤�v���炾�B �@ �V�̐��̑啔���́A��N��ʂ��Ă��̈ʒu���������ς��Ă���(���Ƃ��A�I���I�������ĂɌ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ�)�B���������������̓������͋K���I�ŁA�݂Ȉ�Ăɓ����Ă����B���Ȃ���A�V������ȃh�[���ɐ������\����Ă��āA���ꂪ�ۂ��Ɖ�]���Ă��邩�̂悤���B�\�\�Ñ�M���V�A�ȗ��A���������h�[���͖{���ɑ��݂��Ă���ƍl�����A�u�V���v�ƌĂ�Ă����B �@ �Ƃ��낪�A�f���̓������͈Ⴄ�B���z�⌎���܂߂����̘f���́A�ǂ���P���̓\������V���Ƃ͂܂������W�Ȃ������̂��B������A�`���I�ɂ́A���̎��̘f���͂��ꂼ��ʂ̓V���ɓ\��t���Ă���Ƃ��ꂽ�B�P���̓V���ƍ��킹�đS���Ŕ��̓V��������A���ꂪ����q�̂悤�ɏd�Ȃ��ĉF�����ł��Ă���ƍl����ꂽ�̂������B �@ �f���̓������̒��ł����ɕs���Ȃ̂́A�����E�����E�ΐ��E�ؐ��E�y����������u�t�s�v�Ƃ������ۂł���B���̌܂̐��́A���i�͐����̊Ԃ𓌂ɐi��ł����̂����A���̃X�s�[�h�͂���x���Ȃ��āA�₪�Ē�~���Ă��܂��B����ƍ��x�́A����܂łƋt�ɁA�܂萼�����ɓ����n�߂�B����Ɋϑ��𑱂���ƁA�܂����������~���āA�Ăѓ������ɁA�������Ȃ��������̂悤�ɓ����o���B���̊�ȓ������͂����������Ȃ̂��낤�B�����\������ɂ͂ǂ���������̂��낤���H �@ �v�g���}�C�I�X���g�����̂́A��l����p�������]�~�Ƃ�����@�������B�v�g���}�C�I�X�͂���ɃI���W�i���ȍH�v�������Ďg�����̂����A�܂����̊�{�I�ȍl�������猩�Ă������B �@ �����ɏ������}�ŁA�F���̐^�ɂ����ē����Ȃ��̂��n���ł���B����͎������̓���o���͈͓̔��ł͐�Ίm���Ǝv����O��ŁA���́A���̒n�����猩���Ƃ��ɘf�����ǂ̕����Ɍ����邩�A�Ƃ������Ƃ��B �@ �����ŁA�f���̓�����������邽�߂ɁA��̉~���o�ꂷ��B�n��(�d)�𒆐S�Ƃ���傫�ȉ~(�}�ł͗ΐF)�͓��~�ƌĂ�A���̉~�̏���A�_�b�����̑����ʼn�]����B���ɁA���̓_�b�𒆐S�Ƃ��āA������̏����ȉ~(�ԐF)������B����ɂ͎��]�~�Ƃ������O���t�����Ă��āA���̉~�̏���A�f��(�o)�����̑����ʼn�]����B�܂�f���́A���~�̏����]������]�~�̏����]����B�e�T�̏�ɏ��T������Ă���悤�Ȃ��̖͌^���g���ƁA�f���͓�̉�]���������ꂽ���ʁA�_���ŕ`�����悤�ȓ�����������B�����Ă����n�����璭�߂�ƁA�����ɋt�s���Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B �@ ���ꂾ���ł��Ȃ��Ȃ������Ǝv���̂����A�v�g���}�C�I�X�͂���ɐ�i�B���~�Ǝ��]�~�̒P���Ȗ͌^�ł́A�ώ@�f�[�^����̂��ꂪ���Ȃ肠�����̂��B�����Ńv�g���}�C�I�X�́A���̖͌^���킸���Ɂu���炷�v�헪�ɏo���B���ꂪ������̐}(�}2)�ł���B �@ ���x�́A���~�̒��S(�l)���A�n�����炸�ꂽ�Ƃ���ɒu����Ă���B���Ⴂ���Ȃ��łق������A�n�����F���̒��S����O�ꂽ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���~�̕����F���̒��S���班�����ꂽ�Ƃ������Ƃ��B�����ł���ɁA�v�g���}�C�I�X�͂�����A����I�ȍH�v������B���~�̏����]����_�b�́A���͂�~�̏�����̑����ł͓����Ȃ��B�����ł͂Ȃ��A�_�d'(����͂l������Œn���d�̔��Α��ɂ���)�̎�����A���̉�]���x�ʼn��̂�(�m���Ă���l�̂��߂ɕ����̗p��Ō����ƁA�d'�̎���̊p���x�����Ƃ�������)�B���̍H�v�́u�G�J���g�v�ƌĂ�A���ꂱ���܂��ɁA�w�A���}�Q�X�g�x���u�ő�̏��v�ɂ����v���������B������g�����Ƃɂ���āA�f���̈ʒu�̗\���͊i�i�ɐ��m�ɂȂ����̂��B �@ �s���̒n�����F���̒��S�ɐ������v�g���}�C�I�X�̓V���w���_�́A�l�������z����������y���ɐ��k�Ȃ��̂ŁA�����̊ϑ��f�[�^�Ƃ��悭��v���Ă����B����������萯�p���s�����肷��ɂ͏\�����������A�덷���o�Ă����ꍇ�ł��A���]�~�⓱�~��K�x�ɂ��炵���肷�邱�Ƃɂ���Ė͌^���C���������ł悩�����B�ƌ������ނ���A���ꂪ�V���w�҂̎d���������ƌ����Ă������B�������A�n�����Î~���Ă���Ƃ����l���͎������̓���o���Ƃ������Ɉ�v���Ă���B���������ǂ��ɁA�n���������Ă���Ȃǂƍl���闝�R������̂��낤���H�@�\�\���ꂪ����̂��B���́A�u�ő�̏��v�̂䂦��u�G�J���g�v�����A�R�y���j�N�X���n�������咣���邫�������������̂ł���B |
|
|
���w�R�����^���I���X�x
�@ 1503�N�ɃC�^���A����A��������A�R�y���j�N�X�͔����̕⍲���E���E����Ƃ��ē����悤�ɂȂ����B�Ƃ��낪���N��A�R�y���j�N�X�͓ˑR�����̌�������A�t�����{���N�ɈڏZ����B���R�͂͂����肵�Ȃ����A�����Ƃ��ẴL�����A��ςނ��Ƃ��̂ĂāA�V���w�Ɏ��Ԃ���������I�̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B���ہA�قڂ��̍��ɁA�R�y���j�N�X�͐V�����V���w���_���l���Ă����̂��B�R�y���j�N�X�͂��̊T�v���܂Ƃ߁A�N���N�t�̓V���w�҂����ɑ������B�w�R�����^���I���X�x(�����Ėw���_�x)�ƌĂ�邱�̎菑���̘_�������A�R�y���j�N�X���n���������\�����ŏ��̒��삾�����B �@ �w�R�����^���I���X�x�̏��ɓ����镔���ŁA�R�y���j�N�X�́A�v�g���}�C�I�X���̎��]�~���_�ɔ��̈ӂ�\������B�u�Ȃ��Ȃ�A�����̗��_�͂���ɂ������̃G�J���g�~��z�肵�Ȃ���Εs�\���ł��������A���������~�̂����ŁA���͓��~��ɂ����Ă��ŗL�̒��S�ɂ����Ă���Ɉ�l�ȑ����œ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ���������������ł���v�B�O�ɐ��������悤�ɁA�G�J���g���g���ƁA�f���̉�]����X�s�[�h�͈��łȂ��Ȃ�B���ꂪ�R�y���j�N�X�̖ڂɂ̓��[���ᔽ�Ɖf�����̂��B�����ŃR�y���j�N�X�́A�u�~�����̂����ƍ����I�Ȕz�u�v���Ȃ����̂��ƍl�����B�܂�A���̑��x�ʼn~�^������Ƃ������[����j�邱�ƂȂ��A�f���̓��������܂������ł���悤�Ȗ͌^�͍��Ȃ����̂��ƍl�����̂��B �@ ���̎��s����̐Ղ́A�R�y���j�N�X�́u�m�[�g�v�Ɏc���Ă���B�O�ɃR�y���j�N�X�������Ă�������̃f�[�^�E�u�b�N�̂��Ƃ�b�����Ƃ��A���̓���͔����ƈꏏ�Ƀo�C���h����Ă����ƌ������̂��o���Ă��邾�낤���B�u�m�[�g�v�ƌ������̂͂��̔����̂��ƂŁA���̂����̈ꖇ�ɁA�w�R�����^���I���X�x�ȑO�ɏ����ꂽ�ƌ����郁������������B���̉Ȋw�j�����҂ɂ��A���̓��e����ǂݎ���̂͂����������Ƃ��B�u�R�y���j�N�X�́u�n���������v���Ƃ��܂����肵�ĒT�����J�n�����̂ł͂Ȃ��B�w��l�~�^���̌����x�ɒ����ł��낤�Ƃ��āA���]�~���̏C���Ɏ�������̂ł���v(�����w�R�y���j�N�X�E�V����]�_�x184-5��)�B�܂�A�n���������Ƃ����A�C�f�B�A�́A�v�g���}�C�I�X���̓V���w���_���C�����悤�Ƃ������ʂ������Ƃ����̂ł���B �@ ���������ƁA�R�y���j�N�X�ȑO�ɂ��A�����悤�Ȃ��Ƃ��l�����l�X�������B�����13���I����14���I�ɂ����Ċ����A���r�A�̓V���w�҂̈�h�ŁA�Ȋw�j�ƊE�ł́u�}���[�K�w�h�v�ƌĂ�Ă���B���̐l��������͂�A���̑��x�ł̉~�^���Ƃ������Ƃ��d�����ăv�g���}�C�I�X��ᔻ���A���̗��_�Ɏ�̍��C�����������B�ڂ������Ƃ͏Ȃ�����ǂ��A�G�J���g�̑���ɕʂ̉~�������������āA����ł����ăG�J���g�Ɠ����悤�ȋ@�\���Č������̂��B�����Ėʔ������ƂɁA���̊w�h�̍l�Ă������_�́A�R�y���j�N�X�̂��̂Ƃ�������Ȃ̂ł���\�\������_�A�n���������Ƃ������Ƃ������āB �@ �}���[�K�w�h�̗��_���R�y���j�N�X�ɉe����^���Ă����Ƃ������m�ȕ��I�؋��́A���̂Ƃ��닓�����Ă��Ȃ��B����ɂ́A�A���r�A�̓V���w���_���r�U���c�鍑���o�R���ăC�^���A�ɓ`���A���w���̃R�y���j�N�X�̒m��Ƃ���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă��邪�A�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ��B�l�I�ɂ́A�n�������R�y���j�N�X�̊��S�ȓƑn�������Ƃ�����A�A���r�A�̐�l��������p�������_�W���������ʂ������ƍl����ق������}���`�b�N�ł����Ȃ��Ǝv���B���A�A���r�A�V���w�ƃR�y���j�N�X�̊W���ǂ��l����ׂ����ɂ��ẮA���Ƃ̂������ł��܂����_���o�Ă��Ȃ��悤���B �@ �b���w�R�����^���I���X�x�ɖ߂����B���̏��_�͈����������Ȃ���������ǂ��A�V���w�҂����̊Ԃł͂��Ȃ�]���ɂȂ����炵���B���R�A�R�s�[�@�ȂǂȂ����ゾ����A�������������l�͂�����菑���ŏ����ʂ��B�����Ă܂��ʂ̐l�ɑ���B�������ăR�y���j�N�X�̃A�C�f�B�A�́A�������A���R�~�ɋ߂��`�ōL�܂��Ă������B���e�B�N�X���R�y���j�N�X�̂��Ƃ����ɂ����̂����̌��ʂ��������A������ܔN�قǑO��1533�N�ɂ́A���[�}�E�J�g���b�N�̔鏑�������c�ɃR�y���j�N�X�̍l������������Ƃ����L�^�����c���Ă���B �@ ���Ȃ݂ɋ���͂��̂Ƃ��A�ʂɉ��̑[�u������Ă��Ȃ��B�n�����̓L���X�g����ɂ���Ēe�����ꂽ�Ƃ����C���[�W�����邩������Ȃ����A����n�������莋����悤�ɂȂ�͎̂��́A�R�y���j�N�X���牽�\�N����̂��ƂȂ̂��B���������̘b�͂܂��A�ʂ̋@��ɂ��邱�Ƃɂ������B |
|
|
�����Z�ȓ��X�A�n���Ȏd��
�@ �w�R�����^���I���X�x���琔�N���1514�N�A���[�}���c���ł͋���̗�̉��v���c�_�ɏ���Ă����B���c�̓��[���b�p���̓V���w�҂Ɉӌ����o���悤���߁A�����l�\���炢�������R�y���j�N�X�ɂ��A���̈˗����������B���̃G�s�\�[�h�́A�R�y���j�N�X�����łɓV���w�҂Ƃ��Ă��̖���m���Ă������Ƃ������Ă���\�\���ɖ{��_�����o�ł������Ƃ��Ȃ��ɂ�������炸�I�\�\����ǂ��A���̂Ƃ���R�y���j�N�X�́A�����ēV���w�ɐ�O���Ă����킯�ł͂Ȃ��B �@ ���̈˗��̂�������N�O�A�i����������̔������ˑR�S���Ȃ��Ă����B�قƂ�ǔނ̗͗ʂɂ���Ď��߂��Ă������[�~�A�͐����I�Ɍ�������Ԃɒǂ����܂�A1520�N�ɂ͂��ɗ��Ɛ푈��ԂɂȂ����B�R�y���j�N�X�͂ǂ����Ă������ƌ����ƁA�Ȃ�Ɛ푈���I���܂ł̌ܔN�ԁA���[�~�A�̒����Ő퓬�̎w���Ɍg���A�ꎞ�͎i���㗝�Ƃ���������̃g�b�v�̐E�ӂ��ʂ����Ă����B����ł����x���V���ϑ����s������͂��Ă����悤�����A����ȏŌ����ɏW���ł����Ƃ͑z���ł��Ȃ��B �@ �푈���I����Ă��A�R�y���j�N�X�͎Q������Ƃ������������E�̎d���ŖZ�����A�o�ϐ���ȂǂɊւ���Ă����B���ꂾ���łȂ��A�C�^���A�Ŋw��w�̒m�����g���āA��҂Ƃ��Ă��������Ă����B�R�y���j�N�X�͂����������Z�ȓ��X���߂����A�����Ԃ��g���ēV���w���������Ă����炵���B �@ �c�O�Ȃ���A�R�y���j�N�X�̌������w�R�����^���I���X�x�ȍ~�A�ǂ̂悤�ɐi�W�����̂��͂悭�킩��Ȃ��B���̌エ�悻�O�\�N�̊Ԃɏ����ꂽ�V���w�W�̂��̂́A���F���i�[�Ƃ����V���w�҂̖{�ɂ��Ĕᔻ�I�ɃR�����g�������Ȃ����m���Ă��Ȃ��B�����Ă��̏��Ȃ����Ă��A�̐S�̃R�y���j�N�X���g�̐��ɂ��Ắu�ʂ̂Ƃ���Ő������悤�Ǝv���Ă��܂��v�Ə�����Ă��邾�����B����ȊO�ɂ킩���Ă���̂́A�����̗��_�ɕK�v�ȃf�[�^���W�߂邽�߂ɉ��x���V���ϑ����s�����Ƃ������ƂƁA1535�N���ɂ͗��_�̎�ȕ��������������ł��Ă����炵���Ƃ������Ƃ��炢�ł����Ȃ��B �@ �������A�����n���Ƃ����A�C�f�B�A�͂Ƃ����ɃR�y���j�N�X�̓��̒��ɂ��������A�w�R�����^���I���X�x�Œ��ԓ��ɂ͌��\���Ă����B����ǂ��A�f���̈ʒu�̌v�Z���d���Ƃ���V���w�̐��E�ł́A�����n���Ƃ������u���g���Đ��m�Ȍv�Z���ʂ��o���Ȃ���ΈӖ����Ȃ������B�R�y���j�N�X�����Z�ȓ��X�̍��Ԃ�D���ē�\�N�ȏ�������Ď��g��ł����̂́A�ϑ��f�[�^�ƍ����悤�ɉ~�̑g�ݍ��킹��������ɏC������Ƃ����A���Ƃ��n���Ȏd���������̂��B�����Ɍ��킹�Ă��炤�ƁA�R�y���j�N�X�������ʼn����v���I�Ȃ��Ƃ����Ă���Ƃ�����ۂ͑S���Ȃ��B�v�g���}�C�I�X�ȗ��̓`���I�ȓV���w�\�\�~�����܂��g�ݍ��킹�Ęf���̓������Č�����Ƃ������̐��w�A���邢�͂ނ���p�Y���\�\�ɁA������Ƃ����H�v��t�������������ɂ����v���Ȃ��̂��B �@ ��������ł��A���́A���̍H�v���u������Ƃ����v���x�ł͍ς܂���Ȃ��悤�Ȃ��̂��������Ƃɂ���B�N���ǂ��l���Ă݂Ă��A�l�����̗����Ă��邱�̒n���������Ă���Ƃ͓���M�����Ȃ��ł͂Ȃ����I�@�Ȃ�قǁA�w�R�����^���I���X�x�̒��ł́A�~�̐������n�����̏d�v�Ș_�ɂȂ�̂��Ə�����Ă����B�����A�n���������Ă���ƍl������܂��������ł���ƌ���ꂽ�Ƃ���ŁA�n���������Ă���Ɣ[���ł���킯�ł͂Ȃ����낤�B �@ �R�y���j�N�X���g�A�����̗��_���l�X�Ɏ���Ă��炦��Ƃ������M�͂Ȃ��Ȃ����ĂȂ������B�ŏI�I�ɏo�ł��ꂽ�{�̒��ł��A�u�����̐V��ƕs�𗝂��̂䂦�Ɍy�̂����̂�����āA��Ă����q��S�����~���Ă��܂������Ǝv�����قǂł����v�ƍ������Ă��邭�炢�Ȃ̂��B������\�\�������ق��ɂ����R�͂��邾�낤���\�\�悤�₭�̂��Ƃŗ��_���قڊ������A���e���������߂Ă����̂ɁA�R�y���j�N�X�͂�����o�ł��悤�Ƃ��Ȃ������B �@ �����������Ă��邤���ɁA���͗����1539�N��5�����}����B�R�y���j�N�X�̂Ƃ���ɁA��l�̎�҂�����Ă����B���e�B�N�X�̓����ł���B |
|
|
���o�łւ̓��̂�
�@ ���e�B�N�X���R�y���j�N�X�̂��Ƃ�K�ꂽ�Ƃ��A�R�y���j�N�X�͂��łɘZ�\��������߂��Ă����B���̘V�l�Ǝ�҂̂������łǂ�Ȃ��Ƃ肪���킳�ꂽ�̂��́A�z��������ق��ɂȂ��B�����A�����エ�悻�l�����ŃR�y���j�N�X�̌��e��(�S���ł͂Ȃ���)�ǂ݁A���̗��_���قڃ}�X�^�[���āA���e�B�N�X���R�y���j�N�X�̍ŏ��́\�\���B��́\�\��q�ɂȂ������Ƃ͊m���ł���B�Ƃ���A���N�ɂ킽���Ĉ�l�Œn���Ɍ����𑱂��Ă����V�l���A�����������Ă������̎�҂�傢�Ɋ��}�����̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B �@ ���e�B�N�X�͎t�̓V���w���_���w�����łȂ��A���̊T�v��{�ɂ܂Ƃ߁A���N�t�Ɂw������x�Ƒ肵�ďo�ł����B���̖{�́A�o�ŕ��Ƃ��ăR�y���j�N�X�̐������߂ĉ���������̂ŁA�n�����ɑ���l�X�̔��������������ϑ��C���̖�ڂ��ʂ������B�K���A�R�y���j�N�X�̐S�z���悻�ɔ����͏�X�ŁA���������N�ɂ͍Ĕł���Ă���B���Ȃ݂ɁA���e�B�N�X�͂��Ƃ��Ɓw������x�̎��M���\�肵�Ă����̂����A����͌��Ǐ�����Ȃ������B����A����������ƁA�����K�v���Ȃ��Ȃ����ƌ����ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B���e�B�N�X�̏�������āA���ɃR�y���j�N�X�{�l���A�����̖{������ɉׂ����e�̉�����Ƃ��n�߂��̂��B �@ ������O�̂��Ƃ����A�ǂ�Ȃɑf���炵���A�C�f�B�A���낤�ƁA���\����Ȃ���ΐ��E�������Ƃ͂Ȃ��B���̈Ӗ��ŁA���e�B�N�X�̎d���͂ƂĂ��d�v�������B����A���e�B�N�X�����ł͂Ȃ��B�R�y���j�N�X�̗��_�����ɏo��܂łɂ́A���ɂ��l�X�Ȑl���ւ���Ă���B �@ ���Ƃ��A�o�ł��ꂽ�{�̒��ŃR�y���j�N�X���g���u��e�F�v�ƌĂ�ł���M�[�[�i���B�ނ́A�V�����V���w���_���o�ł���悤������������l�������B���e�B�N�X���w������x�̒��Ō���Ă���Ƃ���ɂ��A�ǂ����R�y���j�N�X�͂��Ƃ��Ɓu�v�g���}�C�I�X�����ނ���A���t�H���\�\��^���āv�A�����̗��_���̂��̂̓��e���o�ł���̂ł͂Ȃ��A����Ɋ�Â��ĎZ�o�����f�[�^�E�u�b�N���o�ł��悤�ƍl���Ă����炵���B�����M�[�[�͂���ł͕s�\�����Ǝ咣���A���ɐ����ɐ��������̂��Ƃ����B �@ ���ꂩ��l�Ƃ��ẮA�{�̏o�ł𐿂����������Џ��y�g���C�E�X�̋C�T���傢�ɕ]�����ׂ����Ǝv���B���̐l���́A�w�����ɉ��l������̂ƍl���đ����̊w�p���̏o�ł��肪���������łȂ��A��������������c�ރj�������x���N�̊X���D�ꂽ�w�҂𐔑����y�o���Ă��邱�Ƃ��ւ�Ɏv���Ă����B�u���悻�ǂ����̂͂�������قƂ�ǑS���E�ւƗA�o�����̂ł�����A�m�D�ꂽ�w�҂̒��삪�n��������S���E�Ɍ������ďo�ł����̂������W�����肷��ł��傤���B���̂Ƃ���A���͂��̓_�ʼn䂪�X����^����ɒl����ƐM���Ă���܂��v�B�t�����{���N�؍ݒ��̃��e�B�N�X�Ɉ��Ă��莆�ɂ���������Ă���̂�����Ƃ��A�l�́A�R�y���j�N�X�̖{�͌����Ē��҈�l�̎�ɂ���Đ��ɏo���̂ł͂Ȃ����Ƃ���������̂��B �@ �������āA1542�N��5�����A�܂�R�y���j�N�X�̂��Ƃɂ���Ă��Ă���قڎO�N��ɁA���e�B�N�X�͎t�̌��e�������ăj�������x���N�ւƖ߂��Ă����B�����y�g���C�E�X�̂Ƃ���ň����Ƃ��n�܂�A���e�B�N�X�����̊ēɂ��������B�������A���e�B�N�X�͏H����ʂ̊X�̑�w�ŋ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ŁA�m�l�̐_�w�҃I�W�A���_�[�Ɍ��������B�����āA�N�͕ς����1543�N�̏����A���ɃR�y���j�N�X�̎咘�w�V����]�_�x���o�ł��ꂽ�B |
|
|
���R�y���j�N�X�̉F��
�@ �w�V����]�_�x�͑S����6������Ȃ�B���̂�����1�����n�����̑S�ʓI�Ȑ���(�ƁA��ŕK�v�Ȑ��w�̏���)�ɏ[�Ă��Ă���̂ɑ��A�c���5���ł͐��̓����̌v�Z�ɂ��Ẵe�N�j�J���ȏڍׂ����X�Ɖ������Ă���B���̐��I�ȕ��������A�V���w�҃R�y���j�N�X���w�R�����^���I���X�x�ȍ~�̎O�\�N���₵�ė��_�̐��x���グ�悤�Ƃ����w�͂̌����������킯���B�����l�ɂ͂��̏ڍׂ�������邾���̗͗ʂ��Ȃ����A��������҂���Ă���Ƃ��v���Ȃ�����A�����ł͑�1���ŏq�ׂ��Ă�����e�ɂ��āA�Ƃ�킯�R�y���j�N�X�̍l����F�����ɂ��Ęb���ɂƂǂ߂Ă��������B �@ ��1���̑�10�͂́u�V���̏����ɂ��āv�Ƒ肳��Ă��āA���̒��ŃR�y���j�N�X�̍l����F���̍\�����q�ׂ��Ă���B�����ŁA�R�y���j�N�X���u�V���v�Ƃ����`���I�Ȍ��t���g���Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ăق����B����ȑO�̐l�X�Ɠ������A�R�y���j�N�X�ɂƂ��Ă��A�V���͌����đz����̂��̂ł͂Ȃ������B�R�y���j�N�X�͒n�������������ƌ����邯��ǂ��A����͎��̂Ƃ���A�n���̓\������h�[������]����Ƃ������Ƃ������̂��B �@ ����܂�����ŁA���̐}�����Ăق����B����́w�V����]�_�x�̒��M���e�̒��ɂ���A�F���̌n�̐}�ł���B�^�Ɂu���z�v(sol)�Ə�����A�������芪���悤�ɁA���̓V�����d�Ȃ荇���Ă���B�~���̂��̂ł͂Ȃ��~�Ɖ~�ɋ��܂ꂽ�������V���ŁA�ׂ荇���V�������傤�ǐڂ��ĕ���ł��邱�Ƃ����̐}�͎����Ă���(�c�O�Ȃ��ƂɁA�o�ł��ꂽ�{�ł͂���ɑΉ�����}��������������Ă��āA���̂��Ƃ�������ɂ����Ȃ��Ă��܂��Ă���)�B �@ ���̎��̓V���́A�ԍ����U���Ă��鏇�ɁA�O������P���A�y���A�ؐ��A�ΐ��A�n���ƌ��A�����A���������ꂼ��^��ł���B���̏��Ԃ͊ϑ��f�[�^���猈�肳��Ă���A���͂��̓_�������A�R�y���j�N�X���̍ő�̒����������B�Ƃ����̂��A����܂ł̒n�����S���̗���ł́A�V���̏��Ԃ����肵�悤�Ƃ���Ǝ�ϓI�Ȑ��������炴��Ȃ��������炾�B�܂�A�R�y���j�N�X�͗��j�㏉�߂āA�o���f�[�^�ɑS�ʓI�Ɋ�Â��F����������ƌ�����̂ł���B �@ �Ƃ���ŁA���̐}�����Ă������ł́A�R�y���j�N�X�̉F���͓V�������܂��d�Ȃ荇���āA�ϐ������Ă���悤�Ɍ�����B�������́A���̐}�ɕ`����Ă���͈̂��̗��z�ŁA�{���͂����Ƙc��ł����B�Ȋw�j�̐��Ƃ����̖{�̑�2���ȍ~�̃e�N�j�J���ȋc�_�͂����Ƃ���A�V���ƓV���̊Ԃɂ͂��Ȃ茄�Ԃ��ł��Ă��܂����Ƃ��킩�����̂��B�Ƃ�킯�A��ԊO���̍P���V���Ƃ��̎��̓y���V���̊Ԃɂ́A�c��ȋ�Ԃ��L�����Ă���B�R�y���j�N�X�̗��_�ɏ]���Čv�Z���Ă݂�ƁA���z����P���V���܂ł̋����́A���z����y���V���܂ł̋����̎���750�{�ɂ��B����I�@�������A���̍P���V���܂ł̋����\�\����͂܂�A�F���̑傫���Ƃ������ƂȂ̂����\�\�́A�`���I�ɍl�����Ă�������400�{�ȏ�傫���B�R�y���j�N�X�̗��_�́A�����ʂ�F����c�������Ă��܂����B �@ ��������ł��A�R�y���j�N�X�̉F���͂����܂ŗL���̑傫���������B�P���V���̊O���ɂ͉����Ȃ��A���E�͂����ŏI����Ă���B�����ĉF���S�̂̌`�͋���ł���B�\�\���łɌ����Ă����ƁA�w�V����]�_�x��1���͂܂��A�u�F���͋��`�ł��邱�Ɓv�Ƒ肳�ꂽ��1�͂���n�܂�A�ȉ��A�u��n���܂����`�ł��邱�Ɓv(��2��)�A�u�ǂ̂悤�ɂ��đ�n�͐��Ƌ��Ɉ�̋�����Ȃ��̂��v(��3��)�Ƒ����B�v����ɉF���͉����牽�܂Řc�݂̂Ȃ��~�������͋��̑g�����łł��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��āA�ǂ����R�y���j�N�X�͂�قǁA�~(��)�Ƃ����}�`�ɓ��ꍞ��ł����悤���B �@ ����Ƃ�����A��قǂ̐}�ł͞B���ɂ���Ă���d�v�ȃ|�C���g������B����́A�F���̒��S�͂ǂ��ɂ���̂��Ƃ�����肾�B�}���������ł́A���z�����S�ɂ���͖̂��炩�Ɏv����B�������́A�R�y���j�N�X�͖{�̒��ŁA�u���z�̋߂��ɉF���̒��S�����݂���v�Ə����Ă���̂ł���B�Ăѐ��Ƃ��w�E����Ƃ���ł́A�R�y���j�N�X�̐��w�I�ȗ��_�ł́A�n���̋O���̒��S�͑��z�ƈ�v���Ă��Ȃ��B�����ė��_��d�v�Ȃ̂́A���z�ł͂Ȃ��n���̋O���̒��S�̕��Ȃ̂��B�R�y���j�N�X�̒n�����́u���z���S���v�Ƃ��Ă�邱�Ƃ����邪�A�����Ɍ������̌Ăѕ��͕s�K���Ƃ������ƂɂȂ�B �@ ���āA�����܂ł̐����ł������肢�����������Ǝv���̂����A�R�y���j�N�X�̉F�����́A�n���������Ƃ������̈�_�������A�l�����������m���Ă���F���̎p�Ƃ͑傫���قȂ��Ă���B�V��������n�����ցA�Ƃ����L���b�`�t���[�Y�́A�l�����̎v���`���F�������R�y���j�N�X�̎�Ő��ݏo���ꂽ�Ƃ������Ƃ�S���Ӗ����Ȃ��̂��B�������A�R�y���j�N�X���_�̃e�N�j�J���ȕ����ɂ��Ă��A�ڂ������j�����̌��ʁA�v�g���}�C�I�X���̗��_���Ȍ��������킯�ł��Ȃ���Η\�����x���D��Ă����킯�ł��Ȃ��Ƃ������_���o����Ă���B��������Ƃ܂��܂��A���������^�₪�����痣��Ȃ��B�w�V����]�_�x�́A�͂����Ċv���I�Ȗ{�������̂��낤���H |
|
|
���\�����ʌ���
�@ �R�y���j�N�X�̐e�F�M�[�[���w�V����]�_�x����ɂ����̂́A�o�ł��琔�������o�߂���7���̂��Ƃ������B�ނɂƂ��āA����͂ƂĂ����S�[���o�����������ɈႢ�Ȃ��B�Ƃ����̂��A���͂��̂Ƃ����łɁA�R�y���j�N�X�͂��̐��������Ă����̂�����c�c�B�Ƃ��낪�A�y�[�W���߂����Ă݂��M�[�[�́A��Ȃ��ƂɋC���t�����B�u�ǎ҂ցv�Ƒ肷��O���������ɁA����Ȃ��Ƃ�������Ă����̂��B �@ ���ہA�m�V���w�҂̍l�Ă���n�����̉����m�܂�n�����n���^�ł���Ƃ����K�R���͂Ȃ��A����ǂ��납�{���炵���Ƃ����K�R������Ȃ��̂ł���A�ނ���ϑ��ɍ����v�Z�������炷���ǂ����Ƃ�����̂��Ƃ����ŏ\���Ȃ̂ł���B �@ �܂��N���A�������Ɋ֘A���邱�Ƃʼn����m���Ȃ��Ƃ�V���w�Ɋ��҂��Ȃ��悤�ɁB�Ȃ��Ȃ炻��͌����Ă����������̂�ł��Ȃ��̂�����B �@ ����̓R�y���j�N�X���g�̌��t�ł͂Ȃ��A�ƃM�[�[�͒��������B�Ȃ�قǁA���Ԉ�ʂ̓V���w�҂����ɂƂ��ẮA�~��g�ݍ��킹���f���^���̖͌^���{���ɉF���̍\����\���Ă��邩�ǂ����͖��łȂ���������Ȃ��B�d�v�Ȃ̂́A������g���Đ��m�ȗ\�����ł��邩�ǂ����Ƃ������ƂȂ̂�����B����ǂ��A�R�y���j�N�X�͈���Ă����B�n�����͌v�Z�̂��߂̒P�Ȃ铹��Ȃ̂ł͂Ȃ��āA�ނ͖{���ɒn���������Ă���ƍl���Ă����̂��B�R�y���j�N�X�̓V���w�́A���̃e�N�j�J���ȕ����ł͌Ñ�M���V�A�ȗ��̓`���������ɕێ����Ă��āA�v���I�Ȃ悤�ɂ͑S�R�����Ȃ��B����ǂ��A����ɂ���Ă��̐��E�̐^�������炩�ɂȂ�ƐM���Ă����Ƃ����_�ŁA�R�y���j�N�X�͂܂������v���I�������̂ł���B �@ �M�[�[�ɂ́A���̑O������t���������̂��N�Ȃ̂����@���������B���e�B�N�X�̌���Ĉ�����ē����A�_�w�҃I�W�A���_�[�ɈႢ�Ȃ��B�I�W�A���_�[�́A�_�w�҂�N�w�҂���n�����ɑ���ᔻ���o��̂����z���āA�����Ă݂�ΐ���ł��Ƃɂ����̂ł���B����ǂ��M�[�[�ɂ��Ă݂�A����͖S���e�F�̈̋Ƃ�䖳���ɂ���ɓ������B�M�[�[�̓��e�B�N�X�Ɏ莆�������A����Ȃ��Ƃ������I�W�A���_�[���A�y�g���C�E�X�Ƃ��ǂ������B����ɁA���̑O�����������폜���ďo�ł��������Ƃ������炵���̂����A�c�O�Ȃ��炻��͎������Ȃ������B���e�B�N�X���܂��A���̑O�����ɂ͔������o�����B�ق��̐l�Ɂw�V����]�_�x�悷��ɂ�����A�ނ͂��̕�����Ԃŏ������̂������B �@ �������A���������������m���Ă���̂͂����ꕔ�̐l�Ԃ����������B���̑O�����ɂ͏������Ȃ���������A�����m��Ȃ��ǎ҂�����A���̕������R�y���j�N�X���������悤�Ɍ����邾�낤�B�����Ă��̓ǎ҂́A���̖{�ɏ�����Ă��邱�Ƃ͌v�Z�̂��߂̋��\�Ȃ̂��Ɣ[�����Ă��܂����낤�B���ہA�w�V����]�_�x�̏o�Ō�A�n������֗��Ȍv�Z�̓���ƌ���l�����\�\����͂܂��A�V���w�Ƃ�������̓`���I�Ȏp���̔��f�Ȃ̂����\�\�́A���\�N�ɂ킽���ĕW���I�Ȍ����ł��葱�����̂������B �@ �R�y���j�N�X�̒n�����͊m���Ɋv���I�������B����ǂ��A���ꂪ���ɂ��Đl�X�̍l����ς����킯�ł͂܂������Ȃ��B�n�����{���ɓ����Ă���Ƃ����l�������s������܂łɂ͂���ɔ����I�ȏ�̔N�����K�v�ŁA���������̂������ɂ́\�\����A����͂܂��ʂ̂��b�ł���B �@ 1543�N5��24���A�R�y���j�N�X�͗ՏI�̏��ɂ������B�M�[�[���`���Ă���Ƃ���ł́A���̉������O���炷�łɍ�����Ԃ������炵���B �@ ���̈��ʂ��A�܂��ɂ��傤�ǂ��̓��A���������w�V����]�_�x�����҂̂��Ƃɓ͂����B�����炭�R�y���j�N�X���g�́A���̖{��ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��������낤�\�\���̑O�����������܂߂āB�������āA�R�y���j�N�X�͌�̎���ɂ����炳�����̂����邱�ƂȂ��A�o�ł��ꂽ�{�������c���Ď��\�ł��̐����������B�]�k�����A�u�v���vrevolution�Ƃ������t�́A�V�̂��O�������邱�ƁA�܂�u��]�vrevolutio���A���̌ꌹ�Ƃ��Ă���B�@�@ �@ |
|
| ���K�����I�̐��U | |
|
��1�D�V�˂̒a��
�@ �؉ƏZ�܂��̖��� / �����̓V�F�C�N�X�s�A �@ ����1564�N��2��15���A�K�����I�E�K�����C�̓C�^���A�̃s�T�Ő��܂ꂽ�B�C�M���X�̌���ƃV�F�C�N�X�s�A�Ɠ����N�̐��܂�ł���A�K�����I�̐��܂ꂽ���t2��15���́A���l�T���X�Ō�̋����A�~�P�����W�F���̎���3���O�̂��Ƃł���B�����A�C�^���A�͊e�s�s�𒆐S�Ƃ��������ƌQ�ɕ�����Ă���A�K�����I�����܂ꂽ�g�X�J�i������͌N�吧�̍��ŁA���̃C�^���A�����̍��X���l�A���l�T���X���I���Ă̒��������̎���ɓ��낤�Ƃ��Ă����B �@ �K�����I�E�K�����C�Ƃ��������I�Ȗ��O�́A�K�����C�Ƃ�������P���`�ɂ����K�����I�Ƃ������t�𖼂ɂ������̂ŁA����͍����݂ł������g�X�J�i�n���̌Â�����̊��K�ɂ����̂ł���B�K�����C�Ƃ̓g�X�J�i�̋��ƂŁA�ߋ��ɂ̓g�X�J�i���a���̍s���������y�o���Ă���B�܂��A�ꑰ�ɂ̓K�����I�Ɠ����̈�t������A�t�B�����c�F��w�ň�w�̍u�`�����Ă����Ƃ����B �@ ����̓����[�g �@ �K�����I�̕��A���B���`�F���c�B�I�͍�����������Ȃ����y���t�ŁA�Ƃ͂���قǗT���łȂ��A�K�����I�����܂ꂽ���A��Ƃ̓s�T��3�̃o���R�j�[�̂���4�K���ẴA�p�[�g����Ă����B���̌�A���͒P�g�t�B�����c�F�Ɉڂ邪�A1574�N�A�K�����I��Ƃ͕��ƍ������A���߂ĉƑ��ł̐������n�܂����B���q�K�����I�������l�A�����[�g�𑑌��ɉ��t����̂��D�B�K�����I�̓T���^�E�}���A�C���@�t���̊w�Z�ɓ��w���邪�A�ڂ̉��ǂ̎��Â𗝗R�ɂ��āA���������߂Ă���B���̕a�C����N�̕a�̂��ƂȂ̂��A����Ƃ��ފw�̂��߂̒P�Ȃ�����Ȃ̂��A����͕�����Ȃ��B |
|
|
��2�D�N����
�@ ���R�Ȋw��ւ̓��� / ��t��ڎw�����N���� �@ �s�T��w���ʂ̑厞�v�B�@�K�����I�̕��A���B���`�F���c�B�I�͑��q�K�����I����҂ɂ��悤�ƍl�����B���̂��܂��܂ȉ��̌��ʁA1581�N�A�K�����I�̓s�T��w�ɓ��w����B�����̃s�T��w�ɂ͈�w���Ɩ@�w���A�����Č��݂̋��{�ے��ɑ������鋳����s���w�|�w�����������B�܂��A�K�����I�͈�w���ւ̐i�w��ڎw���āA�w�|�w���ɓo�^����B�������A���̐��K�̉ے����I���邱�ƂȂ��A3�N���̍ݐЂ̌�ɑފw�����B���̎��A���łɃK�����I�͊w��ւ̓���S�Ɍ��߂Ă����悤�ł���B�����A��w�ɐE��Ƃ��Ă��A��w�𒆑ނ����Ƃ����o���͂��Ȃ炸�����s���ɂȂ���̂ł͂Ȃ������B���͂���т̂ق�����������̂ł���B �@ ���s�T�̑吹���@ ���̂���A�吹�����̃V�����f���A�̗h����ώ@���āA�U��q�̓������̌����������Ƃ����B�@ ���t�Ƃ̏o� �@ �K�����I���w���牓�����������̂ЂƂɁA���w�҃��b�`�Ƃ̏o�������B�g�X�J�i�{����K�����I���K�˂��Ƃ��A�{��t�����w�҃I�X�e�B���I�E���b�`�����[�N���b�h�w���������Ă��錻��ɂ��܂��o���킵���̂������B��w�̊O�ɂ��郊�b�`����K�����I�͎��R�ŁA�����Ď��p�I�Ȋw�����������B�K�����I���Ƃ��ɋ������������̂̓A���L���f�X�ŁA���̎��ۓI�A�����I�Ȏv�l���@�́A�A���X�g�e���X�̊w��ψ�F�ɐ��܂�����w����A�܂��܂��K�����I�����������̂������B �@ ���A�E���� �@ �s�T��w�𒆓r�ފw�����K�����I�́A�l�X�Ȍ����Ɏ��g��ł���B�����A��w�����ɂȂ邱�Ƃ����z���āA�A���X�g�e���X�ɂ��Ă̍u�`�m�[�g������Ă����B1586�N�A�K�����I�̓A���L���f�X����̊w�K�Ɋ�Â������w���V���x�������Ă���B�����āA�ނ͂��̏����Ђ������đ�w���������Ă̏A�E�������J�n����B�܂��A�K�����I�̓��[�}�ɗ��������B���[�}��w�ƃ{���[�j����w�̋����E��ڎw�����A��������ƒf����B1588�N�A�p�g���@��w�̐��w�����ɂȂ낤�ƃ��F�l�c�B�A���a���ɏo�����邪���s�B����Ƀs�T��w�Ő��w�����̋�Ȃ������A�����ɂ����킷�邪�A��͂莸�s�����B�t�B�����c�F��w�ւ̏A�E�����܂��������A���w�͂��������B1589�N�A�s�T��w�̃|�X�g���Ăы�ȂɂȂ�A���̘Q�l����ɂ��K�����I�͋Ɛт𒅎��ɂ����Ă������Ƃ������āA�悤�₭�A���w�����̐ȂɏA�����̂ł������B �@ ���s�T��w���w�����ɏA�C �@ �L�͎҂̌�돂�������āA�s�T��w���w�����ɏA�C�����K�����I�̑ҋ��́A�����������ėǂ��Ƃ͂����Ȃ������B�ĔC���F�߂��Ă���Ƃ͂����A�C����3�N�A�N���60�X�N�[�h�����Ȃ������B�s�T��w�̓������������ς���200�X�N�[�h�Ă������Ƃ��l����ƁA�K�����I�̔����Ԃ�͖������낤�B�s���͂��낢�날�邪�A���̂Ƃ��̃K�����I�̌o�Ϗ���l���Ă��A�s�T��w���w�����̐E��f�邱�ƂȂǁA�K�����I�ɂ͓���ł��Ȃ����Ƃ������B |
|
|
��3�D�s�T��w���w��������
�@ �����ȑ�w����ƌ����ւ̖v�� / �͊w�ɖ����ɂȂ� �@ �Ⴋ�K�����I�̏ё��C���X�g�B�@�g�X�J�i������̃s�T��w�ŃK�����I���S�������̂́A���[�N���b�h�w�ƃv�g���}�C�I�X�̓V���w���̒��߂������B�K�����I�͂����܂Ő��w���t������A���_�I���邢�͎��ۓI�ȓV���w�������邱�Ƃ͂Ȃ������͂��ł���B���_�I�ȓV���w�́A�N�w�҂��A���X�g�e���X�̒���Ɋ�Â��ču�`���Ă���A�K�����I�̗̕��ł͂Ȃ������̂��B �@ ���̍��A�K�����I�������ɂȂ��Ă����̂́A�͊w�̖�肾�����B�^���A�Ƃ��Ɏ��R�����̖��Ɏ��g�݁A�d���̈قȂ�ӂ��̕��̗̂������x�ɂ��čl�@�����炵�Ă����B�K�����I�̗L���Ȉ�b�Ɂu�s�T�̎Γ��̎����v�Ƃ������̂�����B�Γ��̂Ă���d���̈Ⴄ��̏d��𗎂Ƃ��āA�ǂ��炪��ɐڒn���邩�����������A�Ƃ������̂��B����ǂ��A�K�����I�����ۂɂ��̎������s�����Ƃ��������͌������Ă��Ȃ��B�v�l�����Ƃ��Ă͍l���Ă����悤�����A���ۂ̎����͍s���Ă��Ȃ������悤���B���̂悤�ɁA�`�������낢��Ƃ���̂��K�����I�̈̑傳�������Ă���̂�������Ȃ��B �@ �����|�]�_ �@ �s�T��w�̍u�`���ɂ���K�����I�̑S�g���B�܂��A�K�����I�͂��̃s�T����ɕ��w�ɂ��X�|���Ă���B�^�b�\�ƃA���I�X�g�Ƃ�����l�̎��l�ɂ��Ă̕��|�]�_���L���Ă���B�K�����I�͒[���ō����ȃA���I�X�g�̎����D�Ƃ����B �@ ���̕��|�]�_�͂������A�͊w�ɂ��Ă̌������A�K�����I�͑�w�ł���������邱�Ƃ͂Ȃ������B��w�ł̍u�`���e�Ƃ������̂͋��t�̍ٗʂŌ��߂�����̂ł͂Ȃ��A�K�����I�͋��ԈˑR�Ƃ����w��������邵���Ȃ������̂��B�������w���̂Ƃ��ɕs�����������u�`���e���A�K�����I�́A���g�����t�ł���ɂ�������炸�A��������̂܂܋����Ȃ�������Ȃ������B |
|
|
��4�D�h���ւ̑���
�@ �s�T����p�h���@�� / �p�h���@��w���w�����ɏA�C �@ �p�h���@��w�̃K�����I�̋����B�@1592�N�A�K�����I�̓s�T��w���������E����B���̗��R�́A�s�T��w�Ɏ������ӂ邤�g�X�J�i����̕s�]��������A���Ƃ��A�A���X�g�e���X�h�̓N�w�҂ɍU�����ꂽ����A���Ƃ��A���܂��ܐ�������邪�A�����Ƃ����ړI�Ȍ����ƂȂ����̂́A�s�T��w�ł̑ҋ��̈������낤�B�K�����I���s�T��w�����߂�O�N�A�K�����I�̕����}�����A�K�����I�͉ƒ��Ƃ��ĕ��A���A�킽���Ƒ���{��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ����B�����Ƃ����܂������Ă����Ƃ͌����Ă����Ȃ��K�����I�ɂ́A���悢�ҋ��A��̓I�ɂ͍����������ȃ|�X�g�ֈڂ�K�v���������̂��B���̎����傤�ǃ��F�l�c�B�A���a���̃p�h���@��w�̐��w��������ȂɂȂ��Ă����̂ŁA�K�����I�͗L�͎҂̎x�������p���āA���̐E�ɉ��債���̂������B�����āA�@�˂Ȃ��p�h���@��w�ɏA�E�����K�����I�̔C����4�N�A�N����啝�ɑ������B �@ �������Ƃ��K���Ȏ��� �@ �p�h���@�ł̂��悻8�N�Ԃ̐������A��ɃK�����I�́u�����Ƃ��K���Ȏ���v�Əq�ׂĂ���B�p�h���@��w�́A�����̃��[���b�p�̒m�I���S�n�ł���A�A���v�X�Ȗk�̍��X���ӂ��߁A�S���[���b�p����D�G�Ȋw�����W�܂��Ă��Ă����B�p�h���@��w�͈�w�������S�̑�w�ŁA�_�w�����d�����߂�ق��̑�w�����A�Ȋw�ɂ������Ď��R�ȋ�C���������B�܂��A���F�l�c�B�A���a�������[�}���c���ƑΗ����Ă������Ƃ������āA�@���I�Ɏ��R�ȁA�܂�A�v�z�I�Ɏ��R�Ȃ��̒n�ŁA�K�����I�͂��̐��U�̋Ɛт̔����ȏ�̂��̂��A���F�l�c�B�A���a���p�h���@��w���w�����̎����ɐςݏグ��̂ł���B |
|
|
��5�D�����w�ƓV���w�̖��J��
�@ ���p�����d�������w��ւ̎��g�� / �Ȋw�Ǝ��p�� �@ �K�����I���l�����u�Ȋw�v�ɂ́u���p���v���d�����ꂽ�B�����̃��[���b�p�Ŋw��ƍl�����Ă������̂́A���R�w�|(���x�����A�[�c)�ƌĂ��A���@�E�C���w�E�_���w�E�Z�p�E�w�E�V���w�E���y��7�w�Ȃ̂��Ƃ��w���B����炪������u���R�v�Ȃ̂��Ƃ����ƁA����͓��̂�g�̂���Ƃ����Ӗ��ł���A�܂肱��烊�x�����A�[�c�͎v�قƌ��t�������琬�藧���Ă���Ƃ����킯�ł���B����A�G��⌚�z�A���ʂƂ������Z�p�I�c�݂ɑ��ẮA�������[���b�p�ɂ����Čy���E�̎�����Ă����B�������A�w������Ɏt���b�`����p�����ԓx���A�K�����I�������̋Z�p�ɑ��Đ^���Ɍ��������킹���B�v�ق��ɂ��邾���łȂ��A�u���p�I�v�Ȋw����K�����I�͖]�݁A���ꂪ�㐢�A�u�Ȋw�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�̂������B �@ �����l�K�����I �@ ���̎��p�I�Z�p�̎��H�Ƃ��āA�K�����I�́u�w�I�E�R���w�I�R���p�X�v�Ɩ��t�������ڂ������B����͒�K����g�ݍ��킳�ꂽ�R���p�X�ɖڐ��肪���Ă���A���̃R���p�X���K�����I���������g�p��������ɂ��������Ďg�����ƂŁA���Ƃ��A��C�����Ƃ��̊p�x�ƉΖ�̗ʂ����肷�邱�Ƃ��ł���̂ł���B1606�N�܂łɁA�K�����I�͂��̃R���p�X��200�ȏ㔄��グ���B�ނ͂��̃R���p�X�̍����Ǝg���������\�����A�K�����I�ɕ�V�����҂����ɂ�������������B���̂悤�Ȃ����̐ꔄ�ɂ���āA�K�����I�͂���Ȃ�̎������B����Ȃ�P�ǂȉȊw�҂̘g�ɂƂǂ܂�Ȃ��A���l�Ƃ��Ă̎p�����̂Ƃ��̃K�����I�Ɍ��o�����Ƃ��ł���B �@ ���͊w�������݂̂� �@ 1604�N�A�s�T��w�������ォ�瑱���Ă����͊w�������A���ɑ傫�Ȑ��ʂƂȂ��Ă����ꂽ�B���̗̂����^���ɂ��āA����𐔎��ł���킹�邱�Ƃ������̂������B��̓I�ɂ́A1�ɁA�����^���ɂ���Ēʉ߂��鋗�������Ԃ̓��ɔ�Ⴕ�Ă��邱�ƁA2�߂́A���̂͗��������ɔ�Ⴕ�Ă��̑��x�𑝂��A�Ƃ������Ƃ��B�O�҂͊m���ɂ��̂Ƃ��肾���A�������A��҂͊Ԉ���Ă���B�����ɔ�Ⴗ��̂ł͂Ȃ��A���Ԃɔ�Ⴕ�āA���̂͑��x�𑝂�����ł���B�������A�Ƃ��������A�K�����I�́A���̗̂����^���Ƃ������R�̌��ۂ𐔎��ŕ\���ł��邱�Ƃ����_�Â����̂��B�K�����I���͊w�ɂ��čŏI�I�ɍl�����܂Ƃ߂�̂́A1608�N����ɂȂ�̂ł͂��邪�A����1604�N�̔����́A�m���ɕ����w���t�����Ӗ����Ă����B �@ ���C�e�̋O���ƕ����w �@ �K�����I���͊w�̖��ɔM�S�Ɏ��g�̂��A�ނ��u���w�v���d���������炾�����B�͊w�̖��́A�C�e�̋O���Ƃ����ɂ߂Ď��ۓI�Ȃ��Ƃ���ƒ������Ă����B �@ �Ƃ���ŁA�K�����I�̂��̗͊w�����̐��ʂ������ɂ���ē���ꂽ���̂��A����Ƃ����_�I�Ȏv�قɂ���ē��B�������̂��A���̔��f�͓���B���̎���ɂ͐��m�Ȏ��v���u���Ȃ��K�Ȏ�����������͂قƂ�ǂȂ������B�����̌��ʓ���ꂽ���_�Ƃ��������A���R���ۂ����w�ƌ��т��̂��Ƃ����K�����I�̐M�O�������炵�������ƍl�������������������낤�B |
|
|
��6�D�]�����̐���
�@ �K�����I�V���w�̂͂��܂� / �V���̏o�� �@ 1604�N�ɏo���������V���̎c�[�B�V���w�҃P�v���[�̋L�^�ɏڂ������Ƃ���u�P�v���[�̐V���v�ƌĂ��B���V���́A�县�ʐ��������̍ŏI�i�K�ő唚�����N�������ۂł���B(�摜�FNASA/ESA/R.Sankrit and W.Blair�|Johns Hopkins University)�@1604�N�̏H�A�V�����ւт������ɏo�������B�V���Ƃ����Ă��A����͌��݁u���V���v�ƌĂ�Ă�����̂����A���̌��ۂ͓����ɂ����đ厖���������B�A���X�g�e���X�̐��E�ςł͌�������̐��E�͕s�ς�����A�u�����V�����ł���v���ƂȂǂ��肦�Ȃ����炾�B����āA���́u�V���v����������̉F���ł̌��ۂȂ̂��A���邢�͌��������̋C�ۓI�Ȍ��ۂȂ̂����A���ƂȂ����B�K�����I�͂��̐V������������̐��E�̂��̂��ƌ��J�u�`�Ŏ咣�����B�܂�������ؖ����邽�߂ɁA�n��̓�n�_����́u�����v�𑪒肵���B�������������ɐV��������̂Ȃ�A����ꏊ�ɂ���ĐV��������������������ɈقȂ��Ă���͂��ł���B�����āA�K�����I�̎咣�ǂ���A���́u�����v���Ȃ����Ƃ������炩�ɂȂ����B �@ ���F���ւ̏��� �@ ����ɃK�����I�͂��̐V����n�����̏ؖ��ɗ��p���悤�Ƃ���B�n��̓�n�_����̊ϑ��ł͎����������Ȃ��ɂ��Ă��A�n���������Ă���Ȃ�A���]�O����̓�n�_����ϑ�����Ύ�����������͂��ł���B�������A�������̊ϑ��ɂ���Ă����̎����͓����Ȃ������B����͓����̋Z�p�A����������ł̊ϑ��ł́A�d���̂Ȃ����ƂȂ̂ł��邪(���A���̒��V���͌���̊ϑ����x�ł���������͕s�\�Ȃقlj���)�A���̎�����K�����I�͂��炭�̊ԁA�]�����̊ϑ��ɂ���Ċm�M��܂ŁA�n�����ւ̐M���������Ă����悤���B������ɂ���A���̐V���̓A���X�g�e���X�I���E�ς�h�邪�����̂͊m���ł���A�K�����I�̓�������������n�܂�̂������B �@ ���]���������삷�� �@ 1609�N�A�K�����I�͂��̐l���̕���������I�ɒ�߂邱�ƂɂȂ�B����͍ō��̉h�_�̂͂��܂�ł���A�����ɐ�]�ւ̏o���_�ł��������B�āA�I�����_�Ŗ]���������ꂽ�Ƃ����\�����F�l�c�B�A�Ŏ��ɂ����K�����I�́A����̎�������݂��B�����ǂ��̎���̖��A�N���ɂ�20�{�̔{���̖]�����̐���ɐ��������̂������B �@ ���]���������_�� �@ �܂��A�N���]�����������̂��A�Ƃ����_�ŁA�K�����I�͂��̓�����������Ă����B�K�����I�́u���w�Ɋ�Â��āv�Ƃ��u���ܗ��_�Ɋ�Â��āv�]������������Ǝ����̒���̂Ȃ��Ŏ咣���Ă��邪�A���̎���͂܂����ܖ@�����m���Ă��Ȃ�����A���̃K�����I�̕\���́A�o���I�Ȓm���ɂ��Ƃɂ������Ƃ����Ă��������Ȃ̂ł��낤�B�ނ���A�K�����I�����ꂽ�̂́A�]�������������������̔����ł��邩�̂悤�ɋU�����Ǝv��ꂽ�_�ɂ���B�����A�w���E�̕x�̃^�C�g���y�[�W�ɂ́A�u�t�F�����c�F�M���ɂ��ăp�h���@��w���w�҃K�����I�E�K�����C�ɂ���āA�ނ��ŋߔ����������ዾ(�]�����̂���)��p���Ċϑ����ꂽ�����c�c�v�Ƃ���A���̋L�q�ɂ���āA�K�����I�͓G�Ύ҂���u�R�����Đ��{�����܂��Ă���v�Ɣ��ꂽ�̂ł���B������d���̂Ȃ����Ƃł͂��邪�A����ǂ��A�����̃��[���b�p�ɂ����ăK�����I�����삵���]�����������\�̍������̂͂Ȃ������̂ł��邩��A�K�����I���N�̏������肸�ɖ]��������������Ƃ��ւ�Ƃ��Ă��Ă��A����͂���Ő����Ȃ��Ƃ��Ƃ������悤�B |
|
|
��7�D���̐��E
�@ �����Ēn��̐��� / ���Ɩؐ� �@ ����̖]�����œV�̂��ώ@����K�����I��`�����z���C���X�g�B�@�]�������ߋ�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�Ȋw�I�Ȋϑ����u�Ƃ����̂́A�ԈႢ�Ȃ��K�����I�E�K�����C���̐l�ł���B�ނ��{�i�I�ɓV�̊ϑ����n�߂��̂�1609�N��12������̂��ƂŁA�܂�����͌��̊ϑ��L�^�Ƃ��Č��݂ɓ`�����Ă���B�]�������Ƃ����Č������́A�A���X�g�e���X���l���Ă������̂Ƃ͂܂�ň�����B���́A���炩�ł����S�ȋ��ł��Ȃ��A�����ɂ́A���̒n��Ɠ����悤�ɎR��J������̂��K�����I�͒m�����̂������B �@ ���N1610�N�A�K�����I�͖ؐ���]�����Ŋϑ�����B�����āA�ؐ���4�̐����Ă��邱�ƂɋC�Â����B�ϑ��𑱂���ƁA����4�̐����A���̍P���Ƃ͈Ⴂ�ؐ��̍��E���s�����藈���肵�Ă���̂����������B1��15���A�K�����I�͂����4�̐����ؐ��̎��������Ă���̂��Ɗm�M�����B �@ �����f�B�`�� �@ �����̔������K�����I�͂܂��A�g�X�J�i������̃x���U���I�E���B���^�Ɏ莆�ŕ����B���̂Ȃ��ŁA���̒n�`�ɂ��āA�ؐ�����鐯�ɂ��āA��͂ɂ��āA�q�ׂĂ���B�K�����I�͂����̐V�������g�X�J�i����R�W���ɓ`���悤�Ǝv�����̂��B����́A�Ȃ̗��g�̂��߂ł���B �@ �K�����I�́A���̐��E�ɐ������������݁A�����̏o�����l���Ă����B2���ɂȂ��āA�K�����I��4�̐V�f���A�܂�ؐ��̉q�����ǂ̂悤�ɖ������ׂ����ɑ��k���Ă���B�R�W�����Ƃ���ׂ����A�g�X�J�i�����y�o���Ă���̂����f�B�`�Ƃ�����A���f�B�`���Ƃ���ׂ����B�ؐ��̉q���̐��ƃ��f�B�`�Ƃ̌Z��̐�����v���邱�Ƃ������āA���f�B�`�����̗p�����B�������āA�ؐ��̉q�����̂��̂��K�����I���烁�f�B�`�Ƃւ̌���i�ƂȂ����̂��B |
|
|
��8�D�w���E�̕x
�@ �ϑ����ʂ��ɏo�� / �P�v���[�̔��� �@ �w���E�̕x�̕\��(�摜�FIstituto e Museo di Storia della Scienza�A Florence)�@�K�����I�̐V�����́A�w���E�̕x�Ƃ������̏����ƂȂ��Đ��Ԃɓ`����ꂽ�B1610�N3��12���ɏo�ł��ꂽ�w���E�̕x�́A���܂��܂Ȕ������Ђ����������B�K�����I�̌��t�ɂ��₭���������̂̓P�v���[�ł���B �@ �v���n�ɏZ�ލc��t�����w�҃��n�l�E�P�v���[�́A�K�����I�̐���m���āA�ނɍő���̎^���𑗂�ɂƂǂ܂炸�A����ɂ��̐���l�����B�P�v���[�͑O�N1609�N�ɁA���łɘf���̋O�����ȉ~�ł��邱�Ƃ��ؖ����A�n���������łȂ��̂ɂ��Ă����B�܂��A�K�����I�ɑ��A�]�����̐�����@�ɂ��ăA�h���@�C�X�����Ă���B�K�����I�̓����Y�����ʂɉ��H���Ă������A�����Y��o�Ȗʂɖ������ق����]�����̐��\���オ�邱�Ƃ��P�v���[�̓K�����I�ɓ`���Ă���̂��B �@ �P�v���[���g�����ۂɖ]�������̂����ăK�����I�̔������m�F����̂́A�w���E�̕x�̊��z���K�����I�ɓ`���Ă���̂��Ƃ������B�K�����I���P�����̑I���ɑ������]�����ŃP�v���[����������O�ɁA���ɎR��J������̂Ȃ炻���ɐl�X���Z��ł���ɈႢ�Ȃ��A�Ƃ��łɃP�v���[�̓K�����I�Ɏ莆���o���Ă���B �@ �����Ԃ̔��� �@ ����ǂ��A�K�����I�̔����ɑ��āA�P�v���[�̂悤�ȑԓx���������̂͂ނ����O�I�������B�����̒m���l�́A�قƂ�ǃA���X�g�e���X��`�҂ŁA�w�����x���������ȂɐM���Ă����̂ŁA�K�����I�̐��́A�A���X�g�e���X�Ɓw�����x�̗�����ے肷����̂��Ƒ������A�Ƃ��Ă����������̂ł͂Ȃ������̂ł���B���ۂ̉F�����ǂ������邩�A�������E���ǂ��l���邩�A�̕����d�v�Ȗ��ł����āA�]�����Ŗؐ��̉q��������������Ƃ����āA���ꂪ�����͂����Ƃ͌���Ȃ������̂ł���B �@ ���y�� �@ 1610�N6���A�K�����I�͖]������y���Ɍ�����B�����āA�y����3�̐�����ł��Ă���̂�m��̂������B���ۂ́A�K�����I�̖]�����ł͉𑜓x���Ⴂ���߁A�y���̊͌������A3�̐����A�Ȃ��Ă���悤�Ɍ������̂ł���B�K�����I�͂��̔������܂��g�X�J�i������̃��B���^�ɂ����m�点���B�܂��A�������V�������������Ƃ̏؋����c�����߁A�C�^���A��h�C�c�̗F�l�����ɂ̓A�i�O����(�Í�)�ɂ��ē`�����B���̃A�i�O������������P�v���[�́A�K�����I�������V�����������̂��Ƃ������Ƃ͕������Ă��A���̓��e��������Ȃ����߁A�K�����I�̍�����A�i�O��������ǂ��邱�Ƃɐ����₷���ƂɂȂ����B �@ �y���̊ϑ��͍s���l�܂����B3�Ɍ����邻�̐������͊ł���Ƃ������z�̓K�����I�ɂ͂Ȃ������B����ǂ��A�y���̗l�q�͖ؐ��Ƃ��̉q���Ƃ͑S���Ⴄ�B���ǁA���_�̓����Ȃ��܂ܓy���̊ϑ����I�����B�y���Ɋ�����̂����������̂́A1655�N�ɃI�����_�̉Ȋw�҃z�C�w���X���{��100�{�̖]�����Ŋϑ������Ă���̂��Ƃł���B �@ ���K�����I�̐헪 �@ �K�����I��1610�N�̑O��������100��قǂ̖]�����삵�Ă���B�K�����I�́A���̎���]���������[���b�p�e�n�̗v�l�����Ɂw���E�̕x�ƈꏏ�ɁA�g�X�J�i�����̑�g�����̎��ʂ��Ĕz�����̂������B����ɂ���āA�K�����I�̖����ƂƂ��Ƀg�X�J�i����̌��Ђ������߂��B�����̃K�����I�̍s�ׂ́A���F�l�c�B�A���a���̃p�h���@��w�ł̏����͖����\���ł���Ƃ͊������Ȃ��K�����I���g�X�J�i������ɊM���������Ǝv���Ă̂��Ƃ������̂�������Ȃ��B |
|
|
��9�D�h���ƏI���̂͂��܂�
�@ ���F�l�c�B�A����t�B�����c�F�� / �N�w�҃K�����I �@ �p�h���@��w�����郔�F�l�c�B�A���a���́A���̖��̂Ƃ��苤�a���ł������̌N�傪����킯�ł͂Ȃ��B������A���R�Ȋ��ŁA�N��̊�F�������������肷��K�v���Ȃ��B�܂��A���[�}���c���Ƃ̑Η��W����A�@���I�ɂ������Ȃ��y�n���Ȃ̂������B�������A�����̑ҋ��ɕs�������K�����I�́A���̃��F�l�c�B�A�𗣂�g�X�J�i������ɉh�_�ƂƂ��ɊM�������悤�Ɖ��B�g�X�J�i��������B���^�́A�K�����I�Ɏ��Ƃ�����`���̂Ȃ��s�T��w���ʋ����A�܂��g�X�J�i����t�����w�Ҍ��N�w�ҁA�Ƃ��ċ����邱�Ƃ����B�������āA1610�N�A�K�����I�̓t�F�����c�F�A������̂������B�K�����I������������̂́A�P�Ȃ鐔�w�҂ł͂Ȃ��A�u�N�w�ҁv�Ƃ��Ă̌������������B���ۓI�Ȃ��̂����v�ٓI�Ȃ��̂̂ق�����ʂƂ���铖���̃��[���b�p�ɂ����āA�K�����I���N�w�҂Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃ́A���̂܂ܔނ̒n�ʂ������Ȃ������Ƃ��Ӗ����Ă����B �@ ���F�l�����̊뜜 �@ �K�����I�̗F�l�����́A���̃t�B�����c�F�s���̌��f�ɂ݂Ȕ������B�m���ɂ���͏o���ł��邵�A�N����������͂邩�ɂ悭�͂Ȃ�B�������A��l�̌N��Ɏd����Ƃ������Ƃ͊댯���傫���B�N��̐S�ς���A���̎��ɂ���āA�Ȃ̒n�ʂ͂��낭�����ꋎ�邱�Ƃ�����̂��B�܂��A�C�G�Y�X��̗͂������g�X�J�i������Ŏ��R�Ȕ������ł���Ƃ�����Ȃ��B�F�l�����̓K�����I�ɖ|�ӂ����߂����A�K�����I�̈ӎu�͌ł�����������Ȃ��B�K�����I�̌�̔ߌ��́A���̂Ƃ�������ɂ͂��܂��Ă����̂������B �@ ���ЂƂ�̑��q�A�ӂ���̖� �@ �K�����I�͐��U�A�������Ȃ������B�������A����͐����Ȏ��������Ă��Ȃ��Ƃ��������ł���A���Ƃ��ΏC���m���������Ȃ��悤�ɁA�����̊w�҂̕��V���Ȃ炢�@����͓Ɛg�ł������A�Ƃ����������B�܂�A�K�����I�ɂ͓����̍Ȃ�����A�܂����̍ȂƂ̊ԂɂЂƂ�̑��q�Ƃӂ���̖����������Ă����̂������B �@ �K�����I�̎�����̍ȃ}���i�E�K���o�Ƃ̓��F�l�c�B�A�ŏo������悤�ł���B�����āA���B���W�j�A�A�����B�A�A���B���`�F���c�B�I��3�l�̎q�����A�K�����I�̃p�h���@��w��������ɐ��܂�Ă���B�t�F�����c�F�A������ہA�ȂƂ͗��ʂ����B���ꂩ��K�����I�͒������B���W�j�A�Ǝ��������B�A�̂ӂ���̖����C���@�ɓ���悤�Ɖ��B���̂Ƃ�������10�A������9�ŁA�Ƃ��ɏC���@�ŕ�炷�ɂ͗c�������B�K�����I�̕��e�Ƃ��Ă̎q�ւ̈�����^�킹����̂������ɂ͂���̂����A�K�����I�̌o�ϓI��ƒ�̎���炵�Ă���͎d���̂Ȃ����̂������̂�������Ȃ��B���j���B���`�F���c�B�I�Ƃ̊Ԃɂ́A�����m�����������B�K�����I�̓��B���`�F���c�B�I�Ƀs�T��w�Ŗ@�w���w���Ă���B�K�����I�͂������q�̘Q����Ȃ���A�������B���`�F���c�B�I�͎��f�Ȑ������������Ă��āA�����Ε��ɋ��̖��S�������B�ӔN�A�K�����I�̎x���ƂȂ��Ă��ꂽ�̂́A�C�����ƂȂ��Ė����}���A�E�`�F���X�e�ƕς������������������B�K�����I�̉Ƒ�����́A�ǂ�������s�a�̂ɂ�������������Ă����B |
|
|
��10�D�m�M
�@ �����ʒn�����̏؋� / ���� �@ �K�����I�̉Ȋw�I�Ɛт̓t�B�����c�F�ɓ]�����Ă���Ⓒ���}����B�܂��]�����ɂ��V�̊ϑ��𑱂����K�����I�͋����ɖ������������邱�Ƃ������B1610�N12���A�����̖����������ϑ������K�����I�́A���̔������A�i�O����(�Í�)�ɂ��ėL�͎҂�m���l�ɓ`�����B�������A�A�i�O�����ɂȂ��Ă���̂�����A�K�����I�����������̂��A�m�点���Ƃ������͕�����Ȃ��B������A�P�v���[�͂܂�����A�i�O��������ǂ��邽�߂̖��ʂȓw�͂����邱�ƂɂȂ�B���N�A�K�����I�̓A�i�O�����̉����\����B�������������������Ă��邱�Ƃ���A�f���������ł͔������Ă��Ȃ����ƁA�����āA���z�̎��������Ă��邱�ƁA���̌��_���K�����I�͊m�M�����̂������B �@ �����z���_ �@ 1613�N�A�K�����I�́w���z���_�Ƃ��̏������Ɋւ���b�Əؖ��x�Ƃ��������o�ł��Ă���B���z�̍��_���f���Ȃǂł͂Ȃ��A���z�̕\�w�ł̌��ۂł��邱�ƂƁA���_�̓������瑾�z�����]���Ă��邱�Ƃ��咣���Ă�����̂ł���B���̖{�̐����̔w�i�ɂ́A�n������F�߂邩�ǂ����ɂ��ẴK�����I�Ƃ��̑��̊w�҂ɂ�錃�����_��������B���̖{���̂��_�G�ւ̔��_�Ƃ��Ă̎莆�ł���A���������K�����I�́w���E�̕x�Ȍ�A�������c�_�ɂ��炳��A�܂��K�����I�����̉Q�̂Ȃ��Ɏ����э���ł������B����ւ̔ᔻ�ɑ��A���ɖَE���A���ɉ�ɔ��_�����B�����ɂ́A�^�������߂��M�Ǝ����̎��Ȍ����▼�_�~�Ȃǂ���̂ƂȂ����A�K�����I�̐l�i���̂��̂�����Ă����B �@ �����[�}�ւ̖��_�̓� �@ �K�����I�͂��̐��U��6��A���[�}��K�₵�Ă��邪�A���ꂼ��̗��̈Ӗ������͑傫�����ƂȂ�B�Ⴂ�Ƃ����[�}��K�ꂽ�Ƃ��A�ނ͋����E�邱�Ƃœ��������ς��������B�����̗���ׂ��h�����v���A����ɐS�����ǂ点�Ă����B�]������p�����V�̊ϑ��ɂ�锭�������������ă��[�}�ɗ��������̂�1611�N�̂��Ƃ������B���[�}�ւ̗���2�x�ڂŁA���̂Ƃ��K�����I�̓g�X�J�i����̗p�ӂ����`�ɏ���ė������A���[�}�̃g�X�J�i��g�̓@��ɑ؍݂����B�K�����I�͂܂��C�G�Y�X����͂��߂Ƃ��鋳��W�҂ɁA�����̔�����������悤�Ƃ����B �@ �K�����I�͋���̐l�����ɂ��D�ӓI�Ɏ����ꂽ�悤�ł���B�V�����ƒn�����̂ǂ��炪���������ɂ��Ă͌��������Ȃ��܂܂ł͂��������A���̕\�ʂ�ؐ��̉q���A�����̖��������ȂǁA�K�����I�̐V�������̂��̂��^���l�͂��Ȃ������B���̃��[�}�K��͖��_�̂����ɏI������̂������B �@ �����̊����ƒn���� �@ ���̂���ɂ́A�K�����I�͒n�����̐������𗝉����A�m�M���Ă����B�ނ͖]�����ɂ��ϑ����s���O����n�����̉\���ɂ��čl���Ă����悤�����A������n�����̐M�҂ƂȂ����̂��́A�͂����肵�Ȃ��B�K�����I���n������M����悤�ɂȂ����̂́A���͓V���ϑ������R�ł͂Ȃ��B���̖�����������A�K�����I�͒n�������v���������̂��B�������A���݂̉Ȋw�ł͒��̊����ƒn�����͒��ڂɂ͂Ȃ���Ȃ��B���̓_�A�n�������m�M����܂ł̉ߒ��͍�����܂ނ��̂ł��������A���ǁA1610�N�ɑ��z�̍��_�Ƌ����̖���������ڂ̓�����ɂ��āA�K�����I�͒n�������^���悤�̂Ȃ��^�����ƍl�����̂������B |
|
|
��11�D��ꎟ�ٔ�
�@ �G�Ύ҂��� / ���� �@ �K�����I�̖��������܂�ƂƂ��ɁA�ނւ̓G�ӂ͂������ɑ��債�Ă������B�K�����I�͓G�����₷�����i�������B�K�����I�͎������ᔻ���ꂽ�Ƃ��̔��_�Ƃ��āA����������Ȃ��܂łɓO��I�ɍU�����_�j���Ă��܂��̂������B�Ȋw�Ə@���̑Η��Ƃ��������A�K�����I�Ƃ����l���̂��̂��A�n�����ւ̔����������Ă����ʂ������ɂ���B �@ �K�����I�ւ̔��Ƃ́A��̓I�ɂ̓K�����I�̎咣����n�������w�����x�ɔ����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������̂������B�K�����I���悭�v���Ă��Ȃ������[�j�Ƃ����_�����K�����I�����[�}�ْ̈[�R�⏊�ɍ��������B�������i�����Ă���Ƃ��m�炸�K�����I�̓��[�}�����K���A�����̐������炩�Ɏ咣�����B����ȃK�����I���̋��c�p�E���X�ܐ����s�����Ɋ����Ă������Ƃ������āA�ŏ��̏@���ٔ����͂��܂����̂������B �@ ������߂Ȃ� �@ ���̍ٔ��́A���͂ƂĂ������Ȃ��̂������B�K�����I�͓��X�Ǝ�����W�J���Ă������A������߂��邱�Ƃ��Ȃ������B�����Ƃ������̂��o���A���܂������Ƃ́A�t�H�X�J���[�j�Ƃ����i�|���̃J��������_���̏������A�R�y���j�N�X�n�����Ɓw�����x�̋L�q��a�������悤�Ƃ��鏑�����ւ����A�R�y���j�N�X�́w�V���̉�]�ɂ��āx�Ƒ��̈���̏������A���������܂ʼn{�����~�ƂȂ��������ł������B�܂�A�K�����I�͂Ȃ�̙�������Ȃ������̂ł���B �@ �����̒m�I�V�Y�̂悤�ȍٔ��́A�K�����I�ɑ����̕s���Ȏv���������������ŁA�ނ̑ԓx�ɉe�����y�ڂ��Ȃ������B������A�K�����I�͂̂Ɏ����̌����𑱂���ꂽ���A�܂������ɔӔN�̔ߌ���������邫�������ƂȂ邱�Ƃ��Ȃ������B �@ ���a���̏o�� �@ 1618�N�̏H�A�a�����������ŎO�o�������B�������ꎟ�ٔ��ȍ~�A���ق�����Ă����K�����I���ӌ������߂�ꂽ�B �@ �A���X�g�e���X�̍l���ɂ��A��������̐��E�͊��S�����ł���A�ω��͋N���Ȃ��B������A�������ɉ����ٕς��N�����Ƃ���A����͌��������̐��E�̘b�ł���A�܂肻��͋C�ی��ۂƓ��l�̂��̂ł���B �@ �P�v���[�̎t�ł���e�B�R�E�u���[�G�Ƃ����V���w�҂́A�a�����F���ɖ����Ă���G�[�e�����Ă�镨�����Ïk�������̂Œ����^�������Ă�����̂ƍl�����B �@ �K�����I�͑O�N���ɑ̒�������ď��ɕ����Ă���A���ڂ����̜a�����ϑ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B����ł��ނ͎v�Ă����炵�l�����B�a���͌��������̌��ۂŒn�ォ�痧�������������������z�̌��˂��Ă���A�ƃK�����I�͌��_���B�A���X�g�e���X�̍l���ɋ߂��Ȃ��Ă��܂������A�a���������^�������Ă���Ƃ����_�ł̓e�B�R�E�u���[�G�ɏ]���Ă����B �@ ���F���͈ꊪ�̏��� �@ �K�����I�͉F������̏����ɂ��Ƃ����B�����āA���̏����͐��w�ŋL�q����Ă���Ǝv���Ă����B�Ƃ炦�ǂ���Ȃ�����ӂ�Ȑ��E���A�w��ɂ͐��w�I�ɕ\���ł���@��������A�ƃK�����I�͐M���Ă����B����̜a���Ɋւ��Ă��A�a���������Ă���Ȃ�A���w�I�ɊȒP�ɐ����̂������^�������Ă���ׂ��Ȃ̂ł������B �@ 1623�N�A�K�����I�́w����ӎ����x�Ƃ��������o�ł���B�����ɂ́A�F���Ƃ��������͐��w�̌���ŏ�����Ă���A���w���w�Ԃ��ƂɂȂ��ɂ͉F���𗝉����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����K�����I�̎��R�ς����m�Ɏ�����Ă����B�ߑ�̉Ȋw���A���܂��ɐ��܂�悤�Ƃ��Ă����̂������B |
|
|
��12�D�w�V���Θb�x
�@ ���c���Ƃ̖����A�����ĈÓ] / ���c�E���o�k�X���� �@ 1623�N�A�K�����I�̌Â�����̗F�l�������}�b�t�F�I�E�o���x���[�j�����c�ɑI�o����A�E���o�k�X�����ƂȂ����B�K�����I�͂��̋��F���j�����߁A1624�N�Ƀ��[�}��K��Ă���B���̂Ƃ��̃��[�}�K��͂����Ƃ��₩�Ȃ��̂ƂȂ����B���c���琔�X�̕���������A����ɂ͑��q���B���`�F���c�B�I�̂��߂̔N���̖��������B���̂Ƃ��A���c���ɂ̓K�����I�̒m�l�����l������A���c���͐g���ɂ���Đ�߂��Ă���悤�Ȃ��̂������B�K�����I�ɂ͂��͂�S�z���邱�Ƃ͉����Ȃ��悤�Ɏv�����B������A���̊����������ɂ����n�������钘�w�V���Θb�x�����M���邱�Ƃ̃��X�N���K�����I�͍l���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂��B�����ċ��c�E���o�k�X�������A�K�����I�̗F�Ƃ������l�̗���ƃJ�g���b�N�̎w���҂ł��鋳�c�Ƃ������l�̗�����͂����蕪���Ă������Ƃ܂ł́A�K�����I�͋C�Â��Ȃ������B �@ ���w�V���Θb�x�̊��s �@ �w�V���Θb�x�̎��M�͕K�����������ł͂Ȃ������B�ЂƂɃg�X�J�i����ւ̋{�d��������B����͑�w�ɏ��������Ɍ����𑱂��Ă���K�����I�ɂƂ��Ĕ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ�����B�����āA�����ЂƂw�V���Θb�x�̎��M��W�����̂́A�K�����I�̌��N�������B �@ �ނ͂��̂���g�̂̊߂��ɂޕa������Ă����B�ǏЂǂ��Ƃ��ɂ͏��ɂ͂���ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��قǂł������B�܂��A1630�N�ɂ́A�y�X�g�����[���b�p�S�y�ő嗬�s���A�K�����I���g�͊������Ȃ��������̂́A�a�C�������ꋇ���Ȑ�����������ꂽ�B �@ ���܂��܂ȍ���̂����A1632�N�A�w�V���Θb�x�����s�����B �@ ���s���ȗ\�� �@ �K�����I�́w�V���Θb�x���o�ł���ɂ�����A�܂����[�}�ł̌��{��ʂ����Ƃ���B1630�N�A���[�}�ɍs���A���c���͂��߂Ƃ��鋳��̊W�҂Ɖ�A�b��I�ł͂��邪�o�ŋ��邱�Ƃ��ł����B�������A�\�z�O�������̂̓��[�}�ł̏o�ł������邱�ƂɂȂ��Ă����t�B�f���R�E�`�F�V�Ƃ����M�����}������̂ł���B�����ŃK�����I�͌v���ύX���t�B�����c�F�ł̏o�ł��l���n�߂�B�{���Ȃ���[�}�ɂ��������Ǐo�����A�ŏI�I�ȏo�ŋ�����肾�������A�y�X�g�̗��s�ɂ���ʂ��Ւf����Ă������߁A���{���t�B�����c�F�Ŏ邱�Ƃɂ����̂������B �@ ���o�ŋ��̎����� �@ �w�V���Θb�x�͎��͂��̌��{���ʂ��Ă����B�o�ł̋���1632�N��2���Ɋ��s���ꂽ�B�������A7���A���c�����̖{�������������Ă���A������ׂ��Ƃ�����������܂łǂ��ɂ��{�𑗂�Ȃ��悤�����Ă��邱�Ƃ�ˑR�ɒm��̂������B��x�͏o�ł������ꂽ�������Ȃ����˂ɋ֎~�ɂȂ����̂��A���m�ȗ��R�͂͂����肵�Ȃ��B�������A�O���͂������B�K�����I�ɋ߂��l�������c�̂����獶�J��h�]�̂��߂ɊO��Ă����̂ł���B �@ �w�V���Θb�x�͒n����������Ă͂��邪�A���̒n�����̍ő�̍����̊����ɋ��߂Ă����B�V���ϑ��ł̔����͒n�������x��������̂ł͂��邪�A�K�����I�ɂƂ��Ă���͗��_�̎和�ɂȂ���̂ł͂Ȃ������B�w�V���Θb�x�ɂ��Ă̚��X������̂قƂ�ǂ́A���̃K�����I���Ƃ����Ȋw�I�ȉ߂����w�E������̂ł͂Ȃ������̂́A����Ȃ��Ƃ��낤�B�w�����x�⋳��ւ̑ԓx�ɂ��āA�K�����I�͔ᔻ���ꂽ�B�K�����I�͊w��̐��E���琭���̐��E�̓o��l���Ƃ��āA���܂��܂Ȕᔻ�̖�ʂɗ�������邱�ƂɂȂ����̂��B |
|
|
��13�D�@���ٔ�
�@ �Ō�̍ő�̍��� / ���[�}�ւ̌������� �@ �K�����I�ْ̈[��R������ٔ��̓��[�}�ōs���邱�ƂɂȂ�A�K�����I�ɂ̓��[�}���c�����א��Ȃւ̏o����������ꂽ�B�g�X�J�i������݂��^���Ă��ꂽ�`�ɏ���āA�K�����I�̓A�y�j���R�������f�����B���̓��͒��������������B1633�N�A�K�����I�̓��[�}�ɓ�������B �@ ���̍Ō�̃��[�}�ւ̗��́A���J�ƍ��܂ɖ����Ă����B����܂ł̃K�����I�̐l���͍����Ƃ͌����Ȃ��Ƃ��A�h���Ɩ��_�����Ă����B��������㗬�̎s���Ƃ��ĉ߂����Ă������܂ł̉h�����ꋎ�낤�Ƃ��Ă���B���[�}�̊X�̋�C�͂�����ł��āA�����̉�����肪�ڂɂ����̂������B �@ ���l�� �@ �ٔ��̑��_�ƂȂ����̂́A��ꎟ�@���ٔ��̎��ɒn�������u�����Ȃ�d���ɂ����Ă��v�u�����Ȃ��v���Ƃ����߂��ꂽ�̂��ǂ����A�Ƃ������Ƃ������B�������̂悤�Ȗ��߂�������Ă����̂Ȃ�A�w�V���Θb�x�̊��s�͂��̖��߈ᔽ���s�������ƂɂȂ�B�������鎑������́A��ꎟ�@���ٔ��ł��̂悤�Ȗ��߂�������Ă������Ƃ𗧏�����̂͂Ȃ��B�܂�A�K�����I�́A�n�������ْ[���ْ[�łȂ����Ƃ����@����̗��R�Ƃ͊W�Ȃ��A�����ɍٔ��̎葱����i�Ǘ��R�ɂ����āA�l�߂������̂��B �@ �ٔ��́A�n���������������������Ȃ������c�_����ꏊ�ł͂Ȃ������B�K�����I�̖��߈ᔽ��₤���̂������B�l���̐�̌����Ă���K�����I�ɂƂ��āA�����ł̓����͕s�тł����Ȃ��B�K�����I�́A����͂��̂Ȃ��߂�F�߂Č��Y�����҂��邱�Ƃɂ����̂������B �@ ������ �@ 1633�N6��22���A�ْ[�R�₪�J����Ă����T���^�E�}���A�E�\�v���E�~�l�����@����Ŕ����������n���ꂽ�B�����̗v�_��3�A�w�V���Θb�x���֏��Ƃ��邱�ƁA���א��Ȃ��]�ނ����̊��ԁA���ȓ��̘S���ɓ���邱�ƁA�܍߂̂��߂�3�N�Ԃɂ킽���Ė��T1��7�̉��ߎ��т������邱�ƁA�ł���B �@ �����������n���ꂽ���ƁA�K�����I�͂Ђ��܂����Ĉْ[������s�����B�n�����̌����݂Ƃ߁A�߂��������ꂽ�B���̎��A�K�����I�ɂ͂��͂�L�͂Ȕ�҂����Ȃ������B�ނ̐��_�����낤���ĕۂ��Ă����̂́A�Ƒ��Ƃ��J�����������B �@ �������� �@ �N�̕��ɂȂ��āA�K�����I�͋A��������ꂽ�B�ٔ��̂��������K�����I�_�I�Ɏx���������}���A�E�`�F���X�e�Ƃ́A�t�B�����c�F�x�O�̏W���A���`�F�g���ɂ���Ƃł̐����������͑����Ȃ������B�}���A�E�`�F���X�e��1634�N4��2���Ɏ��ʁB���̌�A�e�����ĂъĎ₵����킹�悤�Ƃ�������肭�������A�V�l�͌ǓƂȂ܂܂̐����������邱�ƂɂȂ����B �@ ����ɓ�ւ��ꂽ�K�����I�Ɏ��R�͏��Ȃ������B�Ƃ��琔m���ꂽ����ɏo������̂ɂ��A�ώG�Ȏ葱����K�v�Ƃ����B�ǂ����悤���Ȃ������̂Ȃ��ŁA�v�ق������Ȃ̈ӎ������Ă����B�ނɂ��܂��l���邱�Ƃ̎��R�͂������B�t�ɁA���R�͎����̓��̒��ɂ����Ȃ������̂������B �@ �K�����I�͂��̂悤�ȕs�K�ȏ��ŁA�V���������̎��M�Ɏ�肩����B�ނ̓��]�͋x�ނ��Ƃ��Ȃ������B��ɐV�����l�������ɕ�����ł��āA������y���ŏ�������Ă������ƂŎ��g���Ԃ߂悤�Ƃ��Ă����̂������B |
|
|
��14�D�w�V�Ȋw�Θb�x
�@ ������x�A�^���̌��� / �o�ōH�� �@ �w�V�Ȋw�Θb�x�͗͊w�̌������܂Ƃ߂����ł���B�w�V���Θb�x���l�A�C�^���A��ɂ��Θb�̌`���ŋL�q���Ă���B1635�N�̉ĂɈꉞ�̊������݂����̏��ɂ��āA���͂�����ǂ��ŏo�ł��邩�A�Ƃ������Ƃ������B���R�A�C�^���A�ɂ͏o�ł������Ă����Ƃ���͂Ȃ��B����Ȑ܁A�I�����_�̏o�ŋƎ҃G���[���B�����K�����I��K�₵�A�o�ł������Ă���邱�ƂɂȂ����B�������A�I�����_�̓��[�}���c���ƑΗ�����v���e�X�^���g�̍��ł���A����ȂƂ���ŋ��c���̋��Ȃ��o�Ŋ������s���A����Ȃ�Y�����Ă��܂��\�����������B�����ŁA�K�����I�͒m�b�����ڂ�B�K�����I���p�h���@�ő�w���������Ă�������̋����q�ō݃��[�}�̃t�����X��g�m�A�C�����݂Ɩʉ���K�����I�́A�m�A�C�����炽�܂��܃I�����_�̃G���[���B���̎�ɓn�����̂��Ƃ������Ƃɂ��āA���������R�̂��������w�V�Ȋw�Θb�x�̌����̂Ȃ��ɋL�����B���ۂ́A�K�����I���G���[���B���ɒ��ړn�����̂ɂ��������炸�A�ł���B �@ 1638�N7���Ɂw�V�Ȋw�Θb�x�͏o�ł����B���Ƃ��ٔ��ō߂�F�߂Ă��Ă��A�K�����I�͐^���̌������߂悤�Ƃ��Ă����B�����������^���𐢂ɒm�点�����A�Ǝv���Ă����B�����āA���̑㏞�͑傫���A�w�V�Ȋw�Θb�x���o�ł���邱��A�K�����I�͑S�ӂɂȂ��Ă����B�K�����I�̉Ȋw�҂Ƃ��Ă̎d���͏I���悤�Ƃ��Ă���B���Ƃ́A�����̎���҂��A���������邾���ł���B �@ �����q�M�L �@ 1635�N�A�t�B�����c�F�̒��S���ɏZ�ޑ��q���B���`�F���c�B�I�Ɠ������邱�Ƃ������ꂽ�K�����I�ł͂��������A���N�ɂ́A�x�O�̃A���`�F�g���̉Ƃɂ܂��߂����B�����āA�K�����I�̍Ō�̒�q�ŁA�ŏ��̓`�L��ƂƂȂ郔�B���`�F���c�B�I�E���B���B�A�[�j�������ɂ���Ă��āA�������͂��܂����B��C�̈��͂ɂ��Č������A���₪�������e����������ɂ����Ƃ��ɂł���u�g���`�F���̐^��v�̔����҂Ƃ��Ēm����G���@���W�F���X�^�E�g���`�F�����M�L�Ҍ��b������Ƃ��Ă����ɉ�������B �@ �K�����I�́w�V�Ȋw�Θb�x�̉��M���l���Ă����B���q�M�L�ŕ�������Ă������B�����āA���̎d�����������Ȃ��܂܁A�K�����I�̑̒��͈����Ȃ��Ă����B1641�N�H�̔��a����2�����ԋꂵ��A��1642�N1��8���ɉi�������B78�ɂȂ�1�����O�̂��Ƃ������B �@ ������̖��_ �@ �K�����I�̓g�X�J�i�����̌��I�ȑ��V���o�ė�_�ɂ܂���\�肾�������A���̌v�悪���[�}���c���ɒm���ƁA���c���͂���𒆎~����悤�Ƀg�X�J�i�����ɖ��߂��o�����B���ǁA�K�����I�͎��I�ȑ��V�̂̂��A�t�B�����c�F�̃T���^�E�N���[�`�F����̌��K�C���m��q�����̏������ɑ���ꂽ�B �@ 1737�N�ɂȂ��āA�K�����I�̈�[�́A����W�҂̗ՐȂ̂��ƁA��q�����狳��̖{���Ɉڂ���A��_������ꂽ�B�w�V���Θb�x�����c���̋֏��ژ^����͂����̂́A1757�N�̂��Ƃł���B �@ 1979�N�A���[�}���c���n�l�E�p�E�����K�����I�ٔ��̍Ē����𖽂��A1992�N�A�K�����I��L�߂Ƃ����J�g���b�N����̌�肪�F�߂�ꂽ�B �@ �K�����I�̖��_�͎���ɏ��X�ɉ��Ă����A18���I�Ȃ��ɂ͒N���ނ�ᔻ���Ȃ��Ȃ��Ă����B�����āA�����ɃK�����I�̈̑傳�͍��܂��Ă������B�@�@ �@ |
|
| ���n�����͂Ȃ����Q���ꂽ�̂� | |
| �L���X�g���́A�Ȃ����Ēn������ے肵�āA�V�������x�����Ă����̂��낤���B����ɐ����ɏ�����Ă���L�q�Ɩ������邩�炾���Ȃ̂��B�L���X�g�����ꌠ�@����ے肷�镃���@���ł���_�ɒ��ڂ��āA�l���悤�B | |
|
��1. �L���X�g���͒n������ے肵�Ă���
�@ �K�����I�E�K�����C���A�V������˂��A�n�������x���������ǂŁA�@���ٔ��ɂ������A�ْ[��������v���ꂽ��A�u����ł��n���͓����Ă���v�ƙꂢ���Ƃ�����b�́A�@�����Ȋw�����S�ɂ͋��������邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��ے�����G�s�\�[�h�Ƃ��ėL���ł���B �@ ���̃G�s�\�[�h�́A�������Ȃ���A�悭�l���Ă݂�Ɣ������ł���B�������u����ł��n���͓����Ă���v�Ƃ����ꂫ�����͂ɕ��������Ȃ�A�ْ[�R�₪��蒼���ɂȂ�͂������A���������͂ɕ������Ȃ��悤�ȏ����Ȑ��řꂢ�Ă����̂Ȃ�A���̂悤�ȃG�s�\�[�h���㐢�ɓ`���͂��͂Ȃ��B �@ �K�����I���{���Ɂu����ł��n���͓����Ă���v�ƙꂢ�����ǂ����͕ʂƂ��Ă��A�ނ��A1633�N�ɏ@���ٔ��ɂ�����ꂽ���Ƃ͎j���ł���A�����ْ[��������Ȃ�A33�N�O�Ƀ��[�}�ʼn��Ԃ�ɂȂ����W�����_�m�E�u���[�m�Ɠ����^�������ǂ����ł��낤���Ƃ��m���ł���B �@ �����A�ӊO�Ȃ��ƂɁA�K�����I�ɐ旧���āA�n����������R�y���j�N�X�́w�V����]�_�x�́A�R�y���j�N�X�̎���A1543�N�ɉ��̌��{���邱�ƂȂ��o�ł���A���R�ɓǂ܂�Ă����B����́A16���I�ɁA���[�}�E�J�g���b�N����A325�N�̃j�P�[�A����c�ō̗p���������E�X��ƌ����̋G�߂Ƃ̂�����莋����悤�ɂȂ�A���m�ȗ�@��V���ɐ��肷�邽�߂ɁA�V���w�҂����̎��R�Ȍ��������サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ���������ł���B���[�}�E�J�g���b�N����́A�����Ēn������e�F���Ă����킯�ł͂Ȃ��A�R�y���j�N�X�̒n�������A���ݐ��̂Ȃ����w�I�����A�v�Z���ȒP�ɂ��邽�߂̓���I�֖@�Ƃ��ċ����Ă����܂łł���B �@ �n�������@���I�ȗ��ꂩ��ŏ��ɔᔻ�����̂́A�@�����v�̊���A�}���e�B���E���^�[�������B���^�[�́A�w�V����]�_�x���o�ł����4�N�O�A�n�����̉\���A �@ ���̂��҂͓V���w�S�̂��Ђ�����Ԃ����Ƃ��Ă���B���V���A�����܂�ƌ������̂́A���z�ɑ��Ăł����āA�n���ɑ��Ăł͂Ȃ��B �@ �ƒn�����̒҂�ᔻ�����B�v���e�X�^���e�B�Y���́A�w�����x���ʂ�ɉ��߂��錴����`������A�w�����x�̋L�q�Ɩ�������V���ɑ��Ă͌����������̂��B���[�}�E�J�g���b�N������A1582�N�ɁA���݂܂Ŏg���邱�ƂɂȂ�O���S���E�X��𐧒肷��ƁA����ɓV���w�̕ی�҂���}���҂ւƕϖe�𐋂��邱�ƂɂȂ�B |
|
|
��2. �n�����Ɩ������鐹���̋L�q
�@ �ł́A�n�����́A�w�����x�̂ǂ̂悤�ȋL�q�Ɩ�������̂��낤���B�����āA����͂ǂ̂悤�ȏ@���I����s��ł���̂��낤���B�w�����x�ɂ́A�u���z������v�Ƃ��u���z�����ށv�Ƃ����\�����o�Ă���(���сA19:6�G�`���̏��A1:5)���A���������\���́A�n������M���Ă��錻�݂̉�X���X��g���Ă���\���ł���A�����ʂɏ@���I�Ȋܒ~������킯�ł��Ȃ��̂ŁA���͂Ȃ��B���ƂȂ�̂́A�ȉ��̓�ł���B �@ ��2.1. ��n�̈��� �@ �܂��A�w�����x�ɂ́A�_�̎x�z�̂������ő�n�����肵�A�s���ƂȂ����Əq�ׂĂ���ӏ�(���сA93:1�G96:10�G104:5�G���u��A16:30)������B���́A�m�j�Љ�͂����ɂ��Đ��������̂��n�ŁA���_��-�L���X�g�����A���߂ď������������S�ɍ��������j�������̏@���ƈʒu�t�������A���̐����́A�w�����x�̓V��������������ł��L���ł���B�w�����x�́A���Ȃ�V�̓����ɂ��A��Ȃ��n�����ƂȂ��������Ȃ��Ȃ������Ƃ��������Ă���B�m���ɁA�V�����I�ȉF���ςł́A�j�̏ے��ł��鑾�z���A���̏ے��ł����n�̏�������ւ��ĊM�����Ă���悤�ɂ�������B �@ ��2.2. �_�̈ӎu�ɂ�鑾�z�̒�~ �@ �w�����x�ɂ́A����ɁA�_�̈ӎu�ő��z���Î~������A�t�s�����肷�邱�Ƃ�����Ă���ӏ�(���V���A�L�A10:12-13�G�L���A20:11)������B���Ƀ��V���A�L�̈ȉ��̉ӏ��́A���^�[���w�E���Ĉȗ��A�V�����̍����Ƃ���Ă����B �@ �傪�A�����l���C�X���G���̐l�X�ɓn���ꂽ���A���V���A�̓C�X���G���̐l�X�̌��Ă���O�Ŏ���������Č������B �@ ����Ƃǂ܂�A�M�u�I���̏�ɁB����Ƃǂ܂�A�A�������̒J�ɁB �@ ���͂Ƃǂ܂�A���͓�������߂��B�����G��ł��j��܂ŁB�w���V�����̏��x�ɂ����L����Ă���悤�ɁA���͂܂����A���V�ɂƂǂ܂�A�}���ŌX�����Ƃ��Ȃ������B �@ �傪���̓��̂悤�ɐl�̑i�����͂���ꂽ���Ƃ́A��ɂ���ɂ��Ȃ������B��̓C�X���G���̂��߂ɐ��ꂽ�̂ł���B �@ [�����A ���V���A�L�A10:12-14] �@ �����A���z�����Ƃ��Ɠ����Ă��Ȃ��̂Ȃ�A���z�Ɂu�Ƃǂ܂�v�Ƃ������Ƃ͖��Ӗ��ɂȂ�B�K�����I�́A���̎����z���~�߂������͎��]�������Ƃ����V���߂��o���Ă��邪�A���z�����]���~�߂�����Ƃ����āA�n���⌎�����]�^�����~����K�R���͂Ȃ��B�C�X���G���l�ƃA�����l�Ƃ̐킢�ɂ����ċN�������̊�Ղ��ǂ����߂��邩�Ɋւ��ẮA�×��c�_���₦�Ȃ����A�����ł��A�����́A�����ʂ�̈Ӗ��ł͂Ȃ��āA�ے��I�Ӗ���ǂݎ�邱�Ƃɂ��悤�B �@ ��ʂɁA���z���j�������A��n�������������ے�����̂ɑ��āA���͗�����L�̐��������B�C���m�P���e�B�E�X3���́A���c���ƍc�錠�z�ƌ��̊W�ɚg���Ă��邪�A����́A�����̌��͎҂ł���c����A���c�ƈ�ʖ��O�Ƃ̒��ԂɈʒu�t���邽�߂ł���B���p�����ӏ��ł́A���͑��z�ɏ����鈵�����Ă���B���z�����������邪�A���́A�j�������ɑ�����B�킢���I���܂ŁA���z�ƌ����v���Ȃ������A���Ȃ킿�j�������ł�������C�X���G���l�����̂ĂȂ��������Ƃ�`�ʂ��邱�ƂŁA�j�_���n�E�F�̌���삪���������Ƃ��\������Ă���B |
|
|
��3. �Ȃ������̖����͋��e�ł��Ȃ��̂�
�@ �ȏ�A�n�����ɔ����鐹���̋L�q�̏ے��I�Ӗ�����ǂ����B�����̉ӏ��Ɍ��炸�A���_��-�L���X�g���́A�������q�̏@���Ƃ̐킢��ʂ��čL���������j�����̂ŁA�w�����x�ɂ́A�j�������Ə��������Ƃ̑Η����A�B�ꂽ���Ƃ��ĕp�o����B�����āA���̑Η��𗝉����Ă���A�Ȃ��L���X�g�����n�������댯���������������Ă���B�ȉ��A2.1. ��2.2. �Ɋւ��āA���͂��Ă݂悤�B �@ ��3.1. �Ȃ���n�͈��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂� �@ �܂��A2.1. �ɂ��Ă����A�_�̎x�z�̂������ő�n���s���ƂȂ��Ă���̂��Ƃ���Ȃ�A��n�������o�����Ƃ́A�_�̎x�z�������邱�Ƃ��Ӗ�����B�L���X�g���̐��E�҂����́A�n���������Ƃ������Ƃ́A���łɐ������Ă��ƂȂ����Ȃ��Ă����͂��̏��������̕s���ȓ����Ǝ�����̂ł���B �@ ��ꎟ�K�����I�ٔ��ɂ�����i�w���̍ō��ӔC�҂������x�������~�[�m���@���́A�u���z�̕s�����Ƒ�n�̉����ɂ��Ẳ������̍ق����܂����U���̂��ؖ����邱�ƂƁA��n�̉^���̐^�����𗧏��邱�ƂƓ����ł͌����ĂȂ��B���͑��̓_�̕��͏ؖ��ł���ƐM����B�������A���̓_���ؖ��ł��邩�ǂ����͋^��Ɏv���B�����炱�������^�킵���ꍇ�́A�l�͂���܂ŋ��c�l���ɂ���ĉ��߂���Ă����w�����x�̈Ӗ����̂ĂĂ͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ����Ă��邪�A����͂ǂ��������ƂȂ̂��낤���B �@ �R�y���j�N�X�́w�V����]�_�x�̏o�ł��������Ƃ��������ł��邪�A�L���X�g���̐��E�҂����́A�n�������ۂɓ����Ă���ƌ����Ă͂����Ȃ����A�n�����������Ƃ����_�I�ɉ\���Ǝ咣���邱�Ƃɂ͖�肪�Ȃ��ƍl���Ă����B����͂���Ȃ�Ë��ł͂Ȃ��B�������A��n�����Ƃ��Ɠ����悤���Ȃ��Ƃ���̂Ȃ�A��n�����肵�Ă���̂́A�_�̎x�z�̂������ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B��n�̉����́A�_�̈̑傳��F�����邽�߂ɂ͂ނ���K�v�������̂ł���B �@ ��3.2. �Ȃ��n�������z�����Ă͂����Ȃ��̂� �@ ����2.2. �ɂ��Ă����A�������A���z�̓����^�����A�n���̎��]�ɂ���ċN����̂��Ƃ���Ȃ�A���Ɩ����コ���Ă���̂́A�V�ł͂Ȃ��āA��n�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂�A�n�������m�肷�邱�Ƃ́A���̌��O�ƕs�݂��x�z���錠�͂����Ȃ�V�����Ȃ��n�ւƈϏ�����邱�Ƃ�e�F���邱�ƂɂȂ�킯�ŁA�L���X�g���̂悤�Ȓj���@���Ƃ��ẮA���̂悤�Ȍ��͂̎��Ȕے��F�߂�킯�ɂ͂����Ȃ��B |
|
|
��4. �j�������Ƃ��Ẳ�
�@ �n�����̒҂��܂߂��ْ[�҂̍ٔ��́A�����ٔ��Ƃ͎�ނ��قɂ��Ă����ɂ�������炸�A���҂́A�L�ߎ҂����Ԃ�ɂ���Ƃ������ʓ_�������Ă����B�����̃��[���b�p�ɂ́A���Y�ɂ́A�i��Y�A�a��Y�A�l�̌Y�A�ԌY�A�Y�ł��̌Y�A�M�E�̌Y�A����ł̌Y�ȂǁA���낢��Ȏ�ނ��������ɂ�������炸�A�Ȃ��A�����ƈْ[�҂ɑ��ẮA�ΌY�������̂��B �@ ���̗��R�́A�W�F���_�[�̑Η����l����A���炩�ł���B�́A���Ɠ��l�ɑ��z�̑����ł���A�j�������ɑ�����B���������āA������ْ[�҂��ΌY�ŏĂ��s�������Ƃ́A�j�������ŏ��������E����ے��I�ȃZ�����j�[�Ȃ̂��B�������A���m�̈Èł��L���X�g���̐^���̌��Ō[�ւ���Ƃ����Ӗ������߂��Ă���B�C�M���X�ł́A18���I�̖��܂ŁA�ΌY���A�����̔ƍߎ҈�ʂ����Y�ɂ���Ƃ��Ɏg��ꂽ�Ƃ��������́A�ΌY���A�W�F���_�[�E�R���V���X�ȌY���ł��������Ƃ���Ă���B �@ ���Ȃ݂ɍ]�ˎ��㏉���̓��{�ł́A�L���V�^�����t�ɉΌY�ɏ�����ꂽ���A����́A�i�V���i���X�e�B�b�N�ȓ��@�Ɋ�Â����̂ŁA�����ɂ̓W�F���_�[�̑Η��͂Ȃ��B�L���V�^���e���́A�_�����{���O���̐N��������Ƃ�����`�����ōs��ꂽ�̂ŁA���z�_�̖���ł���V�c���ے�������A���Y�̍ۂɎg��ꂽ�ƍl���邱�Ƃ��ł���B |
|
|
��5. �����ƒn�����̐ړ_
�@ �b�����[���b�p�ɖ߂����B�������A�T�o�g(�����Ƃ̉���)�ɎQ������͖̂�A���ɐ[��ł���B�����j�������ɑ�����̂ɑ��āA�ł͏��������ɑ����邩�炾�B�V�͑�n�ɑ��Ēj���̗̈悾���A�V�̒��ł��A���Ɩ�Ƃ����`�ŁA�j�������Ə��������̑Η�����������Ă���B�T�o�g�͖閾����������{�̖����ŏI���̂�����A���������Ԃ�ɂ���Ė��E���邱�Ƃ́A���̏o�ƂƂ��ɁA�����▂���������Ă������ۂ̍Č��ƌ��邱�Ƃ��ł���B �@ �����V�������������̂Ȃ�A���Ȃ�V�͎���̈ӎu�ő��z�����点�A�����Ɩ������������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�B�����A�����n�������������̂Ȃ�A��Ȃ��n�́A����̈ӎu�ő��z���������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ�B �@ ���z���p�������ƁA����܂ő��z�̌�(�L���X�g���̐^��)�̂������Ō����Ȃ������A�M���V���_�b��[�}�_�b�ɓo�ꂷ��ً��k�̐_�̖�������ꂽ�f��������A�T�o�g�̃_���X�̂悤�ȕs�K���ȋO����`���Ȃ���A�Ŗ����绂���B���z���K���������O����`�������̏ے��ł���̂ɑ��āA�f���́A���̖��̒ʂ�����鐯�ŁA�������̏ے��ł���B���z������A�Ŗ�͏����邪�A����͕�Ȃ��n�̈ӎu�Ŏp�������̂ł����āA���Ȃ�V�̈ӎu�ɂ��̂ł͂Ȃ��B����́A�����I�@���̐��E�҂ɂƂ��ẮA�ꌠ�I�@���̋����������z���s�ׂł���B������A�L���X�g���̐��E�҂����́A����̈ӎu�Ŗ����ƒn�����̒҂����Ԃ�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ �����ٔ����ْ[�R����Ƃ��ɃX�P�[�v�S�[�g���ۂł���B�l�ԂƎ��R�̑Η��W�́A�l�Ԃ̓����ŁA�j�Ə��̑Η��W�Ƃ��Ĕ��������B������A���͐l�ԂƎ��R�̋��E��Ɉʒu���闼�`�I���݂Ƃ��ĕ\�ۂ����B�����A�ْ[�҂��A�L���X�g���k�ƈً��k�Ƃ̋��E��̗��`�I���݂ł���B�����⏗�������̐��q�҂����́A��̈Ӗ��ŁA���E��̗��`�I���݂ł���A�L���X�g���Ɋ�Â��j�Љ�̎x�z����@�ɕm�����Ƃ��ɁA�V�X�e���̃G���g���s�[���k�����邽�߂ɁA�X�P�[�v�S�[�g�Ƃ��Ĕr�������^���ɂ���B �@ �ْ[�̒��ɂ́A�������q�҂łȂ����̂��������A�L���X�g�����������������́A�ً��k�̂قƂ�ǂ͒n��_���q�҂���������A�ْ[�҂́A���������̐��q�҂Ƃ��āA�ꊇ���Ĕ��Q���ꂽ�B���́A�n�������A���Ƃ��Ƃ͒j�������̐��q���琶�܂ꂽ�̂����A�L���X�g���́A���������̊�ŁA���������̐��q�ƌ�����Ă��܂����B |
|
|
��6. �F���̒��S�͑��_�ł͂Ȃ�
�@ �p��ł́A�n�����̂��Ƃ��u���z���S�� the heliocentric theory�v�A�V�����̂��Ƃ��u�n�����S�� the geocentric theory�v�ƌĂ�ł���B�������A�n�����Ƒ��z���S���A���邢�͓V�����ƒn�����S���́A�T�O�I�ɓ����ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A�n���͉F���̒��S�ɂ����Ď��]���Ă���ƍl����Ȃ�A���̐��́A�n�����ɂ��Ēn�����S���Ƃ������ƂɂȂ�B�T�O�I�ɓ����ł͂Ȃ���̐��������������Ƃ�����̎n�܂�ł���B �@ �ŏ��ɒn�������������̂́A�s�^�S���X�h�̃s�����I�X(BC5���I��)�ŁA���̗��_�͒n�����ł���Ȃ���A�n�����S���ł����z���S���ł��Ȃ������B��Ɍ��ꂽ�s�^�S���X�h�̃q�P�^�X��G�N�p���g�X�Ȃǂ́A�n�����F���̒��S�Ƃ���n�������������B���z���S���ƒn�����Ƃ����g�ݍ��킹��I�̂́A�T���A�̃A���X�^���R�X(BC310-230�N��)�ŁA�ނ́A�n���̎��]�ƌ��]���咣����ȂǁA���̌��_�͂���߂ċߑ�I�������B �@ �������A�Ñ�M���V���ɂ́A�n�����S�̓V������������N�w�҂������B�ŏI�I�ɁA�������[���b�p�ɂ����Ē���̒n�ʂ邱�Ƃ��ł����̂́A�v�g���}�C�I�X���܂Ƃ߂������n�����S�̓V�����ŁA���̗��_�́A�A���X�g�e���X�̉F���_�̂悤�ȒP���ȓ��S�V�����Ƃ͈قȂ�A���]�~�����Ęf���̌�������̕s�K���ȓ������������ȂǁA�V�����Ƃ��Ă͊����x�����������B �@ ��ʂɁA�Ñ�M���V���̓N�w�҂́A������ώ@���y������X���ɂ��邪�A�V���w�Ɋւ��Ă��R��ł����āA�ނ�̓V���w�I���_�́A�Ȋw�I�����Ƃ��������A�N�w�I���邢�͏@���I�ȃR�X�����W�[�Ƃ��Ă̐F�ʂ����������B���́A�m�j�Љ�͂����ɂ��Đ��������̂��n�ŁA�Ñ�M���V���̓N�w�����_��-�L���X�g���ƂƂ��ɁA�������������������j�������Ƃ��Ĉʒu�t�������A�M���V���ōŏ��ɁA���ł������ɒj��������ł��o�����N�w�ҁA�v���g���͑��z���F���̒��S���ƍl���Ă����B �@ �v���g���́A�����ɔ��I��(�܂���I��)�C�f�A��^���݂Ƃ݂Ȃ����ŏ��̓N�w�҂ł���A�ނ̃C�f�A�_�́A����߂Ēj�����q�I�ł���B�L���ȓ��A�̔�g�⑾�z�̔�g����킩��悤�ɁA�v���g���́A���z�����ɂ̃C�f�A�ł���P�̏ے��Ƃ��Ă����B������A�ނ��A���z���F���̒��S�Ɉʒu�t���Ă��A�s�v�c�ł͂Ȃ��B���̂悤�ɁA�����j�������Ɋ�Â��Ă��Ă��A���z���S��`���A�����邱�Ƃ�����A�V�������A�����邱�Ƃ�����B �@ �����A�Ȋw�j�̖{�Ȃǂ́A�V��������n�����ւ̃p���_�C���E�V�t�g��E�l�Ԓ��S��`�Ƃ��ē����t���A���[�}�E�J�g���b�N����n�����𔗊Q�����̂́A�n�����S��`������������Ȃ��������炾�Ɖ�����Ă���B�����A���̂��Ȃ��݂̉���ɂ͎���X����������Ȃ��B�C���m�P���e�B�E�X3�����g����悤�ɁA���z�����c���Ƃ���Ȃ�A���z���S��`�͋��c���S��`�Ƃ����A���[�}�E�J�g���b�N����ɂƂ��Ă͓s���̗ǂ��R�X�����W�[�ɂȂ�̂ŁA���Q����K�v�͂Ȃ��Ȃ�B �@ 1620�N�ɁA���c���}�����{���Ȃ́A�R�y���j�N�X�́w�V����]�_�x�ɉ��ӏ����̒����𖽂��Ă���B���{���Ȃ́A��5�͂̉F���̒��S�ɂ��ďq�ׂ��ӏ��ɑ��ẮA�u�n�����F���̐^���ɂ���ƍl���悤���A�^������O�ꂽ�Ƃ���ɂ���ƍl���悤���A�ǂ��ł��悢�v�ƃR�����g���Ă���̂ɑ��āA�u�n���̉^���̐^�����ɂ��Č��R�Ǝ�舵���A���̐Î~���ؖ�����Â̓`���I���_����j�Ă���v��8�͂ɑ��ẮA�͑S�̂����E�̑ΏۂƂȂ肤��Ə����Ă���B���[�}�̋��c�����A���z���S���ƒn�����̂ǂ���ɖڂ�����𗧂ĂĂ������͖����ł���B |
|
|
��7. ���R�ɑ��郍�S�X�̗D��
�@ �w�����x�́A�n�����F���̒��S�ł���Ƃ͎咣���Ă��Ȃ��B����܂Ō��Ă����悤�ɁA�w�����x�Ƃ̐������Ŗ��ɂȂ������Ƃ́A��n�������āA���z���Î~���邱�ƂȂ̂��B���z���S�������Q�����̂́A���ꂪ�n�����ɂ���������ɂ����ĂȂ̂ł����āA���z���S�����̂́A��ꎟ�I�Ȕ��Q�̃^�[�Q�b�g�ł͂Ȃ������B �@ ����ɂ��Ă��A�L���X�g���̐��E�҂����́A�ǂ����Ă������w�����x�̈ꎚ���ɂ܂ōS�D�����̂��낤���A�Ɠǎ҂͕s�v�c�Ɏv����������Ȃ��B�K�����I���A�N���X�e�B�[�i����܈��̎莆�̒��Łu�_�́w�����x�̑��������t�̒������łȂ��A����ȏ�ɁA���R�̏����ʂ̒��ɁA������Ă��̂��p���������܂��v�ƌ����āA�n�����ւ̗��������߂Ă��� �B �@ �������A�������͂����ŁA�w���n�l�������x�̖`���ɂ���u�͂��߂Ɍ��t���肫�v�Ƃ���������v���N�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�j�������́A���R�ł͂Ȃ��Č��t(���S�X)�ɗD�ʂ�u���B�u�͂��߂Ɏ��R���肫�v�ƍl����K�����I�́A�L���X�g���̐��E�҂��炷��A�s���R�����t�𐒔q����A�����Ȃ��ْ[�������̂��B�@�@ �@ |
|
| ���V���� 1 | |
|
�n���͉F���̒��S�ɂ���Î~���Ă���A�S�Ă̓V�̂��n���̎�������]���Ă���Ƃ�����ŁA�R�X�����W�[(�F���_)��1�̗ތ^�̂��ƁB��ʂ��āA�G�E�h�N�\�X���l�Ă��ăA���X�g�e���X�̓N�w�̌n�ɂƂ肱�܂ꂽ���S�V�������ƁA�v�g���}�C�I�X�̓V������2�킪����B�P�ɓV�����ƌ����ꍇ�A�㔭�ōŏI�I�ɑ̌n�������������v�g���}�C�I�X�̓V�����̂��Ƃ��w�����Ƃ������B���݂ł͊ԈႢ�Ƃ����B
�@ 2���I�ɃN���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�ɂ���đ̌n�����ꂽ�A�n�����ɑ`����w���ł���B�n�����F���̒��S�ɂ���Ƃ����n�����S���Ƃ��������A�n���������Ă��邩�ǂ����ƁA�n�����F���̒��S�ɂ��邩�ǂ����͌����ɂ͈قȂ�T�O�ł���A�V�����́uGeocentric model (theory) (���n���𒆐S�Ƃ����\���͌^)�v�̖��Ƃ��ĕs�K���Ƃ̎w�E������B�Ȃ�������ł́u�n�S���v�Ƃ����B��q����A�����^�̐��E�̒��S�ɐl�Ԃ��Z��ł���Ƃ������E�ςƓV�����͌����ɋ�ʂ����(�������A���{��ł́A�u�V�����v�Ƃ����ꂪ���Ă�ꂽ���߁A�V��̓V�̂��^�����Ă���Ƃ������E�ς̑S�Ă��V�����ł���ƌ������邱�Ƃ�����)�B13���I����17���I���܂ł́A�J�g���b�N������F�̐��E�ς������B �@ �Ñ�A�����̊w�҂��F���̍\���ɂ��čl�����q�ׂ��B�Ñ�M���V���ł́A�A���X�g�e���X��G�E�h�N�\�X�́A�F���̒��S�ɂ���n���̎����S�V�̂����]���Ă���Ƃ������������Ă������A�G�N�p���g�X�́A�n�����F���̒��S�Ŏ��]���Ă���Ƃ������������A�s�����I�X�͒n�������z���F���̒��S�ł͂Ȃ������]���]���Ă���Ƃ������������A�����͎���ꂽ���I���O280�N���A���X�^���R�X�́A�F���̒��S�ɂ��鑾�z�̎����n�������]���Ă���Ƃ������������Ă���(�Ñ�M���V�A�ȊO�̉F���ςɂ��Ă͌�q)�B�K�����I�E�K�����C�̓R�y���j�N�X�̎��z���S���̔����҂ł͂Ȃ��u������Ă������݂������Ċm�F�����l�v�Ə����Ă���B �@ �����̊w��������m���炵�����̂��W�߁A�̌n�������̂��v�g���}�C�I�X�ł���B�q�b�p���R�X�̐��ɉ��ǂ����������̂��ƍl�����Ă��邪�A�m�͂Ȃ��B�n�����F���̒��S�ɂ���Ƃ��������������w�҂͂���ȑO�ɂ����邵�A�f���̈ʒu�v�Z���r�I�ɐ��m�ɍs�����҂�����ȑO�ɂ������A�ŏI�I�ɑS�Ă�̌n�������v�g���}�C�I�X�̖����Ƃ�A���Ȃ����̌`�̓V�����́A�v�g���}�C�I�X�̓V�����Ƃ��Ă��B �@ �V�����ł́A�F���̒��S�ɂ͒n��������A���z���܂ߑS�Ă̓V�͖̂�1�������Ēn���̎�������]����B�������A���z��f���̑����͈قȂ��Ă���A����ɂ���Ď����ɂ�茩����f�����قȂ�ƍl�����B�V���Ƃ����d����������A���ꂪ�n���⑾�z�A�f�����܂ޑS�Ă̓V�̂��ݍ���ł���B�P���͓V���ɒ���t���Ă��邩�A�V���ɂ������ׂ������ł���A�V���̊O�̖����肪�R��Č�������̂ƍl�����B�f����P���́A�_�������Ȃ��͂ʼn����ē����Ă���B������ω��͒n���ƌ��̊Ԃ����ŋN���A�����艓���̓V�̂́A����I�ȉ^�����J��Ԃ������ŁA�i���ɕω��͖K��Ȃ��Ƃ����B �@ �V�����͒P�Ȃ�V���w��̌v�Z���@�ł͂Ȃ��B����ɂ͓����̓N�w��v�z�����荞�܂�Ă���B�_���n�����F���̒��S�ɐ������̂́A���ꂪ�l�Ԃ̏Z�ޓ��ʂ̓V�̂�����ł���B�n���͉F���̒��S�ł���Ƌ��ɁA�S�Ă̓V�̂̎�l�ł�����B�S�Ă̓V�̂͒n���̂����ׂł���A��l�ɏ]���`�ʼn^������B�������[���b�p�ɂ����ẮA�����A���X�g�e���X�N�w�����̑̌n�̘g�g�݂Ƃ��Ď���Ă��������L���X�g���_�w�ɍ��v������̂Ƃ��āA�V�����������ȉF���ςƌ��Ȃ���Ă����B14���I�ɔ��\���ꂽ�_���e�̏������w�_�ȁx�V���тɂ����Ă��A�n���̎�������E���z�E�ؐ��Ȃǂ̊e�V���V�����S�~��Ɏ�芪���A����ɂ��̏�ɍP���V�A�����V����ю����V���\�z����Ă����B �@ �X�ɓV�����́A�����ɂ����Ă͊ϑ������Ƃ̐������ɂ����Ă��n�������D�ʂɗ����Ă����B���Ȃ킿�A�����n�������{���ł���A�P���ɂ͔N���������ϑ������͂��ł���B�������A�����̋Z�p�ł͂��̂悤�Ȃ��̂͌�������Ȃ������B |
|
|
���V�����̗��j
�@ ���G�E�h�N�\�X�̓��S�V�� �@ �I���O4���I�A�Ñ�M���V�A�̃G�E�h�N�\�X�́A�n���𒆐S�ɏd�w����V������މF�����l�����Ƃ����B������O���̓V���ɂ͍P�����U��߂��Ă���(�P����)�A�V�̖k�ɂ����ɁA���悻1���œ����琼�։�]����(�����^��)�B���z�������V���͍P�����ɑ��ċt�����ɐ����瓌�ցA���悻1�N�ʼn�]����(�N���^��)�B���z�̉�]���͍P�����̉�]���Ƃ͌X���Ă��邽�߂ɁA1�N�̊Ԃł��̓쒆���x���ς��A�G�߂����������B�P�����Ƒ��z�̊Ԃɂ͘f�����^�s������V����u�����B�n�����猩�Ęf���͐����̒����������Ɠ����悤�Ɍ�����B����͍P�����ɑ��Ęf�����^�ԓV���̑��Ή^���Ő������ꂽ���A�f���͓V����ő�����ς�����A�t�s�Ƃ����Ĉꎞ�������t�ɓ������Ƃ�����B�t�s��������邽�߂ɁA�������̉�]�����⑬�x�̈قȂ镡���̓V����1�̘f���̉^�s�ɗp�ӂ����B�����̓V���͓����ʒn�������ʂ̒��S�Ƃ��鋅�̂ł������̂ŁA�n�����炻�ꂼ��̘f���܂ł̋����͕ω����邱�Ƃ͂Ȃ��B�G�E�h�N�\�X�̓��S�V���̓A���X�g�e���X�̉F�����ɑg�ݓ����ꂽ�B �@ ���A�|���j�E�X�̎��]�~ �@ �I���O3���I���̃A�|���j�E�X���邢�͋I���O2���I�̃q�b�p���R�X�́A�f�����P�ɉ~�^����`���̂ł͂Ȃ��A�~�̏�ɏ���������ȉ~�̏���ƍl�����B���̏����ȉ~�����]�~�A���]�~������Ă���傫�ȉ~���]�~�ƌĂԁB���o�I�ɂ́A�V���n�̏�蕨�̃R�[�q�[�J�b�v������ɋ߂��B�R�[�q�[�J�b�v�̎����𒆐S���猩��ƁA2��ވȏ�̉~�^������������āA�i�ޕ����⑬�����ω�����悤�Ɍ�����B����ɂ���Ęf���̐ڋ߂ɂ�閾�邳�̕ω��A���s�Ƌt�s�̑��x�̍����G�c�ɐ����ł����B �@ �S�Ă̘f�������ꕽ�ʏ�ɂ��鑾�z�𒆐S�Ƃ����~�O�����^�����Ă���̂ł���A�n�����猩���f���̉^���́A�~�O����1�̎��]�~�݂̂ŋL�q���邱�Ƃ��ł���͂��ł���B�������A�����̘f���̉^���͂��̂悤�ɂ͂Ȃ��Ă��炸�A�f���̉^����V�����Ő��m�ɋL�q���邽�߂ɂ͂�蕡�G�ȑ̌n���K�v�ɂȂ�B���̂��߃q�b�p���R�X�ȍ~�A�v�g���}�C�I�X���n�߂Ƃ��Ă��܂��܂ȓV�������f��������A�ŏI�I�ɂ͒n�����̃R�y���j�N�X�A�P�v���[���o�ăj���[�g���̖��L���̖͂@���Ɋ�Â��F�����f���Ɏ��邱�ƂɂȂ�B �@ ���]�~�Ǝ��]�~ �@ �]�~�Ǝ��]�~(���イ����Ƃ��イ�Ă�ADeferent and epicycle)�Ƃ́A�V�����ɂ����Č��A���z�A�f���Ȃǂ̉^�s���x��i�s�����̕ω���������邽�߂ɁA�I���O3���I�̏I��荠�Ƀy���K�̃A�|���j�E�X���l���o�����T�O�ł���B���̍l�����ŁA�����m���Ă���5�̘f���̏��s�E�t�s��A�n���Ƃ̋�������肭�����ł����B �@ �V�����ł́A�f���͎��]�~�ƌĂ�鏬���ȉ~��`���Ȃ���A�]�~�ƌĂ��傫�ȉ~�O�������]����ƍl�����Ă����B�ǂ���������ŁA�����Ƃقڕ��s�ɂȂ��Ă����B���̌n�ł̘f���̋O�Ղ��G�s�g���R�C�h�Ƃ����B �@ �]�~�́A���S���S(�G�J���g)�ƒn���Ƃ̒��ԓ_�𒆐S�Ƃ���~�ł���B���]�~�͏]�~�̗��S���S�𒆐S�Ƃ��ĉ�]����B�f�������]�~����鑬�x��p���x�͈��ł���B �@ �N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�̓A���}�Q�X�g�̒��Řf���̏]�~�̑��ΓI�ȑ傫���ɂ��Ă͗\�������A�W���I�ȏ]�~�ɂ��Čv�Z���s���������ł���B����́A�ނ��S�Ă̘f�����n�����瓙�����ɂ���ƐM���Ă����킯�ł͂Ȃ�����ł���A�ނ͎��ہA�f���̔z��ɂ��čl���Ă����B��Ƀv�g���}�C�I�X��Planetary Hypotheses�̒��Řf���̋������v�Z���Ă���B �@ �O�f���́A�V������P�������������Ɠ����A�~�܂��Č����邱�Ƃ�����B����͏��s�ł���B���܂ɏՂɋ߂��ʒu�ɗ������ɂ́A�P����葁�������Č����邱�Ƃ�����B���̎����t�s�ł���B�v�g���}�C�I�X�̃��f���ł́A���̌��ۂ��ꕔ���܂������ł��Ă���B �@ ���f���́A��ɑ��z�Ƌ߂��ʒu�Ɍ����A���̏o�O�����̓����̒Z�����ԂɌ�����B�����������邽�߂Ƀv�g���}�C�I�X�̃��f���ł͐����Ƌ����̓����͌Œ肳��A���S���S�Ǝ��]�~�̒��S�����Ԓ����͏�ɑ��z�ƒn�������Ԓ����ƕ��s�ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă���B |
|
|
���v�g���}�C�I�X�̑̌n
�@ 2���I�ɃA���N�T���h���A�Ŋ����v�g���}�C�I�X�͎��]�~��������A���S�~�ƃG�J���g (equant) ���A�̌n�������B�P�����̒��S�͒n�������A�f���̏]�~�̒��S�͂���Ƃ͈قȂ�(���S�~)�B���]�~�̒��S�͗��S�~���葬�ł͉��Ȃ����A�G�J���g�_���炱�������ƈ��̊p���x�œ����Ă���B �@ �}�͔�r�I�ȒP�ȗ�ł��邪�A����ł��}������Ă���傫�ȗ��S�~�Ə����Ȏ��]�~�̂ق��ɁA���S�~�̒��SX�̉^���A�P�����̓����^���A�G�J���g�_�𒆐S�Ƃ���p�x�ȂǁA����1�̘f���̉^�s��5�̓���������ł���B �@ �v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł͒n������f���܂ł̕��ϋ����ɂقڑ������闣�S�~�̌a���ǂ��̂��Ă��A�������������ł�����]�~����邱�Ƃ��ł���B�Ƃ肠�����e�f���̎��]�~���d�Ȃ荇�����Ƃ�����邽�߁A�n������A���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y���̏��ɐςݏd�˂Ă������B���̊O�����P���������͂ށB���̉F�����́A�G�E�h�N�\�X�A�A���X�g�e���X�̓��S�V���̊g���`�Ƃ�������B �@ �v�g���}�C�I�X�̑̌n�͓����Ƃ��Ă͔��ɗD�ꂽ���̂ł���A�n���𒆐S�Ɖ��肵�Ęf���⑾�z�̉^�����������ɂ́A����ȏ�̂��͖̂����ƌ����Ă��悢�B����(����Ȏ��͂��蓾�Ȃ���)���z�n�̘f���̉^�����S�ĉ~�^���ł������̂Ȃ�A�v�g���}�C�I�X�̑̌n�łقڊ����ɐ������ł����ł��낤�B��������ɖ��炩�ɂȂ�ʂ�A���͘f���͑��z���œ_��1�Ƃ����ȉ~�^�������Ă���A����ȍ~�̓V�����̔��W�́A�ȉ~�^�����~�^���Ő��������߂̔��W�ł������B �@ ���v�g���}�C�I�X��̓W�J �@ �v�g���}�C�I�X�̑̌n���܂Ƃ߂��w�A���}�Q�X�g�x�́A�����C�X�������E���o�Ē������[���b�p�ֈ����p����A���悻1500�N�ɂ킽���ċ��ȏ��I�Ȍ��Ђ������������B �@ ����A6���I�C���h�̃A�����o�[�^ (Aryabhata) �͑��z���S�̒n�����Ɋ�Â����Ǝv���邢�����̌v�Z���c���Ă���B�C���h�ɂ͌Ñ�M���V�A�̓V���w�������Ă��Ă���A���̉e�����w�E����Ă���B�ނ̒����8���I�ɃA���r�A��ɁA13���I�ɂ̓��e����ɖ|��Ă���B �@ 8���I�ɃA�b�o�[�X�������݂����s�o�O�_�[�h�́A�w���j�Y�������A�����̌p���ƃC���h�����Ȃǂ��o��u��ځv�ł���A�C�X�����Ȋw�̒��S�n�ƂȂ����B9���I���V���A�n���Ŋ����o�b�^�[�j�[�́A�ڂ����ϑ����s���A�v�g���}�C�I�X�̑̌n���p�����W�������B �@ 14���I�}�����[�N���̃_�}�X�J�X�ɋ����C�u���E�A�����V���[�e�B�� (Ibn al-Shatir) �́A�V�����̗���ɗ����Ȃ���G�J���g�_��r������A�R�y���j�N�X�Ɛ��w�I�ɂ�������̌n���l�����B�~�^�����璼�������^�������o����@�̓V���[�e�B���ɐ悾����13���I�̃i�X�B�[���E�A�����f�B�[���E�g�D�[�X�B�[ (Nasir al-Din Tusi) �ɂ���ĕ҂ݏo����Ă���(�g�D�[�X�B�[�̑Ή~�ATusi-couple)�B�ނ�̋Ɛт��R�y���j�N�X�̐��ɉe����^�����\�����w�E����Ă��邪�A�؋��͔F�߂��Ă��Ȃ��B |
|
|
�����[���b�p�ł̎�e�ƓW�J
�@ �\���R������C�x���A�����ɂ����郌�R���L�X�^�A�n���C�f�ՂȂǂ́A���[���b�p�ƃC�X�������E�Ƃ̐ڐG�������ɂ����B11-13���I�ɂ����āA�C�X�����Ȋw�̐��ʂ̓V�`���A�����̎�s�p�������A�J�X�e�B�[���������̎�s�g���h�ȂǂŐ��͓I�Ɍ�������A�|�����ꂽ(��12���I���l�T���X)�B�A���X�g�e���X�ȂnjÑ�M���V�A�̕������A�A���r�A���̏d��Ƃ����`�Ń��[���b�p�ɂ����炳�ꂽ�B����܂ł̃J�g���b�N����̐_�w�̓A�E�O�X�e�B�k�X�Ȃǃ��e�������ɂ��A�l�I�v���g�j�Y������Ղɂ������̂ł������B1210�N�Ƀp���̐��E�҉�c���A���X�g�e���X�������邱�Ƃ��֎~����ȂǁA�V�������������m�����̂����邱�Ƃɒ�R�͂��������̂́A13���I�㔼�Ɋ���A���x���g�D�X�E�}�O�k�X��g�}�X�E�A�N�B�i�X��ɂ��A���ǂ̓A���X�g�e���X�̓N�w�̓X�R���w�̎嗬�ƂȂ�B �@ �v�g���}�C�I�X�̑̌n��������āA13���I�ɃJ�X�e�B�[���������̃A���t�H���\10���̂��ƂŕҎ[���ꂽ�w�A���t�H���\�V���\�x�́A���̌�̕���Ȃ����17���I�܂Ń��[���b�p�Ŏg���Ă����B15���I�̃h�C�c�Ńv�g���}�C�I�X�Ȃǂ̌������������M�I�����^�k�X(���n���E�~���[���[)�̋Ɛт́A�ނ̎���1496�N�Ɂw�A���}�Q�X�g�j�v�x�Ƃ��ďo�ł���A�R�y���j�N�X�̌����ɑ傫�ȉe����^�����B���̍��ɂȂ�ƁA�w�A���}�Q�X�g�x���A���r�A�ꂩ��̏d��ł͂Ȃ��A�M���V�A�ꌴ�T�ɓ����邱�Ƃ��ł��Ă����B �@ 16���I�̃��[���b�p�Ńj�R���E�X�E�R�y���j�N�X���n�������������B�R�y���j�N�X�̐��͑��z�𒆐S�ɒn�����܂ޘf�������]����Ƃ����_�ʼn���I�ł���Ƌ��ɁA�G�J���g�_��r�����đS�Ẳ^�s��召�̓����~�^���ŋL�q�����B�������Ȃ���R�y���j�N�X�̐����A�~�^����O��ɂ��Ă���Ƃ����_�ɂ����ẮA�]���̓V�����Ɠ����ł������B�{���ł���Αȉ~�^�������Ă���f���̉^�����~�^���Ő������邽�߂ɏ����]�~���K�v�������̂ŁA�v�Z�̎�Ԃ̓v�g���}�C�I�X�Ƒ債�ĕς��Ȃ��������A�\�����x���傫���オ�邱�Ƃ͂Ȃ������B�n���̈ʒu�������Ȃ�P���̌�����������ω�����͂��Ȃ̂ɁA�����̊ϑ����x�ł͂���(�N������)���F�߂��Ȃ��������Ƃ��A�R�y���j�N�X�̐��������ɂ͎�����Ȃ��������R�ł���B�R�y���j�N�X�̐����p���ŁA�G���X���X�E���C���z���g���A�w�v���C�Z�����\�x���쐬�������A���]�~�̐����v�g���}�C�I�X�̓V�����������₵�Ă��܂��A����Ɍv�Z��ώG�ɂ��Ă��܂����B �@ �R�y���j�N�X���̉e�����āA17���I�̃e�B�R�E�u���[�G�́A�����ʒn���𒆐S�ɂ��Ȃ�����A���ƒn���������f�������z�̉�������F�����l�����B�e�B�R�̑��z�n�̓v�g���}�C�I�X�̓V�����̔��W�`�Ƃ�������B�v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł����z�n�Ƃ������̂��S�����݂��Ȃ�������ł͂Ȃ��B���f���ł��鐅���Ƌ����̗��S�~�̉�]�p�́A���z�̂���Ɠ����ł������B�������O�f���͕ʈ������ꂽ�B���f����n�����猩��Ƒ��z���炠����x�ȏ�͗���邱�Ƃ͂Ȃ����A�O�f���͑��z�̔��Α��ւ���荞�ށB �@ �v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł́A�n������A���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y���̏��ɐςݏd�˂Ă����B���̔z��Ő����A�����A���z������ƁA���̏��ɗ��S�~�̌a���傫���Ȃ�B�������A�e�B�R�͂������ɂ����B���]�~���d�Ȃ荇�����Ƃ���ɂ��Ȃ�����ꂪ�ł��A����ɉ����Ď��]�~�̌a��ς���ƒn������̎������������ł�����̂��ł���B���̌n�ł͑��z�̉��𐅐��A���������B����ɊO�f���������悤�ɂł��邪�A���̏ꍇ�͗��S�~�̌a�Ǝ��]�~�̌a�̑召�����]����B�������A���X ���S�~�̌a > ���]�~�̌a �ł������̂́A���]�~���m���d�Ȃ荇��Ȃ����߂̗v���ŁA�������蕥���Ɩ��ł͂Ȃ��Ȃ�B���Ȃ킿�A�e�B�R���j�����v�g���}�C�I�X�̝|�͎��]�~���m�̏d�Ȃ�ł������B���̃v�g���}�C�I�X�̑̌n�ł����S�~���m�͏d�Ȃ��Ă����̂�����A���]�~���m�̏d�Ȃ���������͕̂s���R�ȗv���������̂�������Ȃ��B �@ 16���I�Ƀj�R���E�X�E�R�y���j�N�X���n��������������ɂ��A�V�����������������͑������B�V�����ϑ����ꂽ���Ƃ́A�P���̒��ɂ��ω��������������ƂɂȂ�B����艓���ł͂����Ȃ�ω����N���Ȃ��Ƃ����A���X�g�e���X�I�F���ςɂƂ��āA����͑傫�Ȗ��ƂȂ����B����ɁA�e�B�R�E�u���[�G���a�����ϑ����A���̓V�̂�����艓���ɂ��邱�Ƃ��ؖ������B����͌������_���B�����͜a�����C�ی��ۂƂ��čl���悤�Ƃ������̂������B |
|
|
���n����
�@ 17���I�ɂȂ��Ė]��������������A�V�����ɕs���Ȋϑ����ʂ����X�Ƃ����炳���B�����������͖]������B���p�t���g����Ȋw�I�Ȏ��ł���ƍl����҂������A�܂��ˑR�Ƃ��Ďc��@���I���͂ɂ���ēV�������̂Ă�w�҂͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ������B�V�����̗D�ʐ��́A���z�̎����n�������]����Ȃ猎�͋O����ۂĂ��ɔ��ōs���Ă��܂��ł��낤�Ƃ����ᔻ�ɑ��A�����̒n���������ł��Ȃ������_�ɂ������B�������A1610�N�ɃK�����I�E�K�����C���]������p���Ėؐ��ɉq�������邱�Ƃ������B�@���̔����ɂ��A�V�����͖ؐ��̌������ł����Ă��܂�Ȃ����R�̐����ɋ������B �@ ����ɁA���n�l�X�E�P�v���[���f���̉^���͑ȉ~�^���ł��邱��(�P�v���[�̖@��)������B�P�v���[�̐��͓V�����₻��ȑO�̒n�������f�������y���ɃV���v���ɓV�̉^�s������ł��A�������P�v���[�̖@���Ɋ�Â����h���t���\�̐��m�����N�̖ڂɂ����炩�ɂȂ�c�_�͎����Ɍ��������B�P���̔N�������������ϑ��ł��Ȃ��Ƃ����n�������f���̎�_�́A���̑唭���̑O�ɂ͍����ł����Ȃ������B �@ �j���[�g���́A�P�v���[�̖@�����x�����銵���̊T�O���n�߂Ƃ����^���̖@���A����і��L���̖͂@���Ƃ������ՓI�Ȗ@�����������B�����̖@���͓V�������Ƃ�ɂ���n�������Ƃ�ɂ���傫�ȓ�ł������V�̉^���̌����͋y�ь��������Ȃ����R�ɉ�^�����B����ɁA�f���Ɍ��炸�A���납��P���܂ŁA�F���̂����镨�̂̉^�����قڊ��S�ɗ\���E�����ł����i�ƂȂ����B�����̈��|�I�Ȍ��тɂ���āA�n�����S���Ƃ��Ă̓V�����͊��S�ɉߋ��̂��̂ƂȂ����B |
|
|
���������ƓV����
�@ �������ɂ����āA�Ñ�M���V�A�E�Ñネ�[�}�����Ɠ����̓V�����͖�����������Ă��Ȃ��B���\�|�^�~�A�����ł́A�ڂ����f���̈ʒu�ϑ����ʂ��S�y�Ƃ��ďo�y���Ă��邪�A���̕������ǂ̂悤�Ȑ��E�ς������Ă����̂��͕s���ł���B�������A�����̕����́A�ϑ��҂������n�𒆐S�Ƃ����F���ς������Ă����B�Ñ�C���h�ł́A�{��R��(�w�r�̏�ɃJ�������A���̏�Ƀ]�E������āA���̏�ɐl�Ԃ̏Z�ސ��E������Ƃ������E��)���������A�Ñ㒆���ł́A�W�V����ӓV����������ꂽ�B�������A�����̕����ƌÑ�M���V�A�����Ƃ́A�w��̏�ő傫�ȐڐG���������Ƃ͂������A�����̐���V�������݂��ɉe����^�������ǂ����ɂ��Ă͏ڂ��������͂Ȃ��B�����Ǝ��̖����F���_�Ƃ���������̌`���ɂ́A�V�������e�������ƍl���錤���҂����邪�A�m�͂Ȃ��B�Ñ�M���V�A�E�Ñネ�[�}�����̂悤�ɁA�f���̖��邳�̕ω���t�s�ɂ��ĉ~�^���Ő������悤�Ƃ������݂͊F���ł������B �@ �O�q�����ʂ�A���̌�A�V�����͌Ñ�M���V�A�E���[�}����A���r�A���������o�Ē����ɓn��A�A���r�A�ƒ����œƎ��̔��W�𐋂����B�����̕����������Ɏ����Ă������E�ςƂ̘����́A���ɖ��Ƃ͂Ȃ炸�A���̒n�̒m���l�͒�R���Ȃ������̊w�������ꂽ�B�������A�A���r�A�A�����ł̓V�����̔��W�͎�Ɋϑ����x�̌���ŁA�̌n�̔��W�͂��܂�Ȃ������B |
|
|
���n������̉F����
�@ �n�����ȍ~�A�F���̒��S�͒n���ł͂Ȃ��A���z�ɂ���ƍl������悤�ɂȂ����B�Ⴆ�ΉF����Ԃł̍P���̕��z�}��`�����E�B���A���E�n�[�V�F���́A���z����͌n�̒��S�ɑ��݂���ƍl���Ă����B �@ �������Ȃ���j���[�g���̖��L���̖͂@���́A���z���F���̒��S�ł͂Ȃ��\��������������̂ł��������B���z�n�̘f�������z�̂܂������]���Ă���̂́A���z�̎��ʂ����z�n�̘f���̎��ʂɔ䂵�āA�y���ɑ傫������ɉ߂����A���z���F���̒��S�ł���Ƃ��闝�R�͑��݂��Ȃ��B�j���[�g�����g�����z���F���̒��S�ł���Ƃ͏q�ׂĂ͂��Ȃ��B���������O�q�̃E�B���A���E�n�[�V�F�����A��d���̌����ɂ���āA���z�n�O�̓V�̂ɂ����Ă��P�v���[�̖@�����������鎖�����������B �@ ���̌�̌����ɂ��A���ۂɑ��z�͉F���̒��S�ł͂Ȃ��������炩�ɂȂ����B�j���[�g���̗͊w�@���́A���ʓI�ɋ����̒n�����������苎�邱�ƂɂȂ����B�����čP���̔N���������ϑ��ł��Ȃ����́A�P�������Ȃ艓���ɂ��鎖���Ӗ����A�ɂ�������炸�n���܂ōP���̌����͂����́A�P�������z�ɕC�G�A�������͂���ȏ�ɖ��邭�P���V�̂ł��鎖���Ӗ������B�܂葾�z���܂��A�F���ɐ��������݂���P���̂ЂƂɉ߂��Ȃ��������炩�ɂȂ����B �@ ���݂ł͑��z�͋�͌n���\�����閳���̐���1�Ƃ��āA���̐��X�Ƌ��ɋ�͌n�̒��S�̎��������Ă��邱�Ƃ��m���Ă���A��͌n�̒��S����͖�26,000 - 35,000���N�̋����ɂ���B���̋�͌n���܂����̉F���ňړ���������A�����̋�͂�1�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��m���Ă���B���Ȃ킿�A���z���F���̒��S�ł���Ƃ���ÓT�I�Ȓn�����͊ԈႢ�Ƃ���Ă���B �@ ����̈�ʓI�ȉF���ςł́A�S�Ă̕����͊e�X���ΓI�ɉ^�����Ă���̂ł����āA�F���̂ǂ����̕����ɒ��S������Ƃ����l�����x�����Ȃ��B�F���ɂ͓��ʂȏꏊ�����������݂��Ȃ��̂ł���A���̍l�������F�������Ƃ����B�A���A�V�̂̉^�����ߎ��v�Z���邽�߂ɁA���w�I�ɍ��W�̒��S��ݒ肷���@�͂悭�g�p����Ă���B �@ ����ł���Ƃ͈Ⴄ�F���ς����_�҂����݂���B�����w�҂̃W���[�W�E�G���X�́A�F���ɗ��̓��ٓ_�����݂��A�n���͂��̐����̈ʒu�ɂ���Ƃ����B�F���̒��S�Ƃ�����ł͂Ȃ����A���̉F���ɂ����ē��ʂȈʒu�ɒn�������݂���Ƃ������ł���B�Ȃ����ٓ_�̐����ɒn�����ʒu���邩�Ƃ����ƁA���ٓ_�ɋɂ߂ċ߂��ꏊ�͉��x�����ɍ����A�������l�Ԃ����݂����Ȃ����߁A��X�l�Ԃ����݂���ꏊ�͓��ٓ_�Ƃ͍ł����ꂽ�ʒu�ɂ���ׂ��Ƃ���B���̂悤�ɉF���̍\���̗��R��l�Ԃ̑��݂ɋ��߂�l�������A�l�Ԍ����Ƃ����B |
|
|
������̓V����
�@ 2004�N�����V����̌����҂̃A���P�[�g�ɂ��ƁA���w����4�����u���z�͒n���̎��������Ă���v�Ǝv���Ă���A3���͑��z�̒��ޕ��p�����Ȃ��Ƃ������ʂ��o���Ƃ����B�����Ȋw�Ȃ̓��قɂ��ƁA�u�����̂��Ƃ́A���w�Z�ŋ��炷��B�v�Ƃ̂��Ƃ������B����A�N�w�҂̉i��ςȂǂ́A�o�������Œm���ɂ�炴��Ȃ�����ɑ��A�ᔻ���l���邱�Ƃ��q�������ɐ����Ă���A�P�ɒn������^���Ƃ��āu���炷��v�̂��Ó����ǂ����͍���̋c�_���K�v�ł���B�ׂ�ڂ��ȘJ�͂�v���邱�ƂɂȂ邪�A���̘J�͂����}��Ȃ���A�V�����̗���œV�̂̉^���𐔊w�I�ɋL�q���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł���B�V���������m�ȌÑ�l�̖ϑz�ł͂Ȃ��A�k���Ȑ��w�I�w�i���������Ȋw�I�̌n�ł��������Ƃ�F�������邱�Ƃ��K�v�ł���B�A���A�V����(�n�����S��)���������̂͂����܂Ő��w�I�ɂł����āA�����I(�͊w�I)�ɂ͂�����S�ɔj�]���Ă���B �@ �Ȃ��A�n�����S���Ƃ��Ă̓V�����͌��ł��������A���z�������Ă���Ƃ����Ӗ��ł̓V�����́A���݂ł͐V���ȈӖ��������ĕ������Ă���B�j���[�g���̖��L���̖͂@���́A���z���F���̒��S�ł͂Ȃ��\����������������̂ł����������A���ۂɑ��z�͉F���̒��S�ł͂Ȃ������B���݂ł͑��z�͋�͌n���\�����閳���̐��̂ЂƂƂ���(���傤�ǒn�������̘f���Ƌ��ɑ��z�̂܂�������Ă���悤��)���̐��X�Ƌ��ɋ�͌n�̒��S�̂܂�������Ă��邱�Ƃ��m���Ă���A���̋�͌n���܂����̉F���ɖ����ɑ��݂����͂̈�ɉ߂��Ȃ����Ƃ��m���Ă���B�@�@ �@ |
|
| ���V�����_�� 2 | |
|
2003�N�I���ɁA�����������z���X�g�̑g�ȁu�f���v����u�W���s�^�[�v����{��̎��ʼn̂��A�b�c���~���I���Z���[�ɂȂ����B���̖ؐ��ɂ͒T���q���ő�C�̑�Ԕ����g�߂ɂȂ�������A���]������12�N�ł��邱�Ƃ�����ʐ_�Ƃ��Ă̑��ΐ_��㐯�̎l�Ζؐ��ȂnjÂ��A�z���������c���Ă���B
�@ �ؐ��Ɍ��炸�����I�ɉ^�s���鐯���u�f�����v�Ƃ͕ς��Ǝv���Ă������A���X�́u�f�r�ҁv���Ӗ�����M���V����planetai����������ƒm�����̂́A�җ���߂��Ă̂��Ƃł���B�䍑�ł́u�V���v�����ł��u�s���v�ƌĂ�ł����悤�ŁA�S�ēV�̂��n�����S�ɉ^�s���Ă���ƍl�����V�����̖��c�ł���B �@ ���ɒn���������Ȃ��Ƃ���A�����鉓���̐��͈ʒu����܂����P��(Fixed Star)�ƂȂ�A�߂��̑��z�n�̘f���͑��ΓI�ɕs�K���ɉ^�s���Ă���悤�Ɍ�����B �@ 2004�N4���̐V���ɂ́A���{�̏��w���̎l�����A���z���n���̎��������Ă���Ǝv���Ă���ƒ������ʂ��o�����A���݂͒��w�̉ے��Œn�����������邻�������瓖�R�̌��ʂȂ̂��낤�B���������Ȃ���ΐl�Ԃ͂����l����̂����ʂł���B �@ ���ہA��X�ɂ��Ă��n������M���鍪��������A���m�ɐ����ł���Ƃ��v���Ȃ��B���������̊w�Z�̗��Ȃ̎��Ԃɋ�����āA���̂܁T�������Ǝv���Ă��邾���ŁA����̎�ʼn������m���߂��킯�ł͂Ȃ��B �@ �����֍�N2005�N�̉āA�V���ɑ��z�n�\�Ԗڂ̘f���������ƃA�����J���甭�\����Ęb��ɂȂ����B���ꂪ2006�N�ɂȂ�Ƃ���Ɍ����lj�����āA���v�\��ɂȂ�Ƒ����ꂽ���A�����̖��S���悻�ɖ��ɐ�������݂����̂ł���B �@ �B�A�f���̒�`�͒肩�łȂ��A1930�N�����̖������ł����f���ł͂Ȃ��Ƃ̋c�_�������Ă���A�܂��Ă�V�����̏\�Ԗڂ̂��̂Ȃǁu2003UB313�v�Ȃ�L���ł����Ȃ��B �@ ���������������͌���菬�����O�������̑��z�n�̘f���ƈقȂ��Ă���A�a���ƕ���킵���̂ł���B���]������76�N�̃n���[�a�������ꂽ�̂�1986�N���������A���ꂪ����̂��̂ł�560�N�Ƃ�����Ɛl�̎����ɔ�ׂ��܂�Ɋ|�����ꂽ�b�ŁA�ƂĂ��������N���Ȃ��b�ɂȂ��Ă��܂��B �@ �����ɍ���͏]���q�����Ƃ��Ă������̂���������̂������w�b�͂�₱�����B �@ ���̐́u�������������ǂĂ��߂��v�Ƒ��z�n�ɂ͋�̘f��������Ɗo�����͉̂��������̂��Ǝv��ʂł��Ȃ��B �@ �z���X�g�̑g�Ȃ��n���������Ď������Ȃ����A�������͒m���Ȃ�����̍�Ȃ������̂��B���̐��̖��́uPluto�v�ƃM���V���_�b�̉���̍��̐_�ł���B���͖̂�K���e�Ƃ��������̊w�҂ŁA�u�H�����v�Ƃ����Ă��������炵���B���ʓI�Ɂu�������v�ɂȂ������A������ɂ��Ă��H��▻�y�̉���z��������������ȑ��݂������̂ł���B �@ ���̂����ł��Ȃ��낤���A�Ƃ��Ƃ�����A�f���ɍ��ۓI�Ȓ�`���Ȃ������f���Ɋi�������ꂽ���A�Ō�܂Řf�����������B �@ ���z�n�̘f������ł��낤�Ɠ���̐����ɉ���W�͂Ȃ����A�L���F���ɂ͑��ɂ����z�n�O�f��������͂��ƒT���𑱂���l�B������A�l�Ԃ̒m�I�����ƍl����Ζʔ����B�@ �@ ����ŁA���ł������𒆐S�ɂ��̂��l���鎞��w�i���݂�A�u�V�����v�͂܂��ɐl�Ԃ̐S���̏ے��̂悤�Ɍ�����B �@ �����̖̂�t���ǒ��ō��c�D���̎t���ł��������{�È����A�s�u�ɏo�āu�V�����v�R�̔@������Ă����̂��悭�����Ă��邪�A�V���̋S�˂��W���Ɖ\�̓���̈�x�N�w�ȂŊw�w�m������A�����������悭����������ł̊m�M�Ƃ������̂��낤�B �@ �������ߍ����������绂���W�R�`���[�I�l���̏ꍇ�́A���p�ȓV�����_�҂̊�������B �@ ���l�ɍ���̘f���������A�l�Ԃ̏���ȓs���ł̋c�_�������悤�Ɏv����B�@�@ �@ |
|
| ���v�g���}�C�I�X�̓V���� 3 | |
|
�V�����A�Ƃ������t�͍L���m���Ă��܂��B�n���͓����Ă��炸�A�n���͐��E(�̂̌��t�ł������E�Ƃ͌��݂̉F�����w���܂�)�̒��S�ɒ������A���̎���z���̓V�̂������Ă���Ƃ����ƂĂ��f���Ȑ��ł��B�n�����A���Ȃ킿���Ȃ��̏Z��ł���Ƃ��A�������A�֎q���A�p�\�R���̃��j�^�����Ȃ��ƈꏏ�ɍ����œ����Ă��邾�Ȃ�ĕ��ʂ͍l�����܂���B������n���͓����Ă��炸�A�����Ă���͓̂V�Ȃ̂��A�Ƃ����X�^���X�ł��B
�@ ���̓V�����͑f�p�ȍl���Ȃ̂ł����ƈȑO���炠�����̂ł����A 2���I����A�A���L�T���h���A�����̎���ɓV���w�҃v�g���}�C�I�X��������Ƒ̌n�����Ă��܂��B�n���͐��E�̒��S�ł����Ƃ��Ă���Ƃ�������̂��ƁA�����̊ϑ����ʂƑ傫�Ȏv�l�ł��肠����ꂽ�Ƃ����܂��B�����ŏ����̊ϑ����ʂƂ������̂́A��̃e�B�R�u���[�G��P�v���[�������Ȋϑ������ǂ���ɂ������ƂƑΔ䂳���邽�߂ł��B �@ �������琯�ɂ͍P���Ƙf�������邱�Ƃ��������Ă��܂����B�P���Ƃ����̂͑��z��A�����������Ă���͂邩�ޕ��̍P�ɂЂ���P���Ă��鐯�ł��B�����{�P���ƒ��߂Ă���Ɛ��������������Ă��邱�Ƃ�������܂����A�����͂����Ɠ����`��ۂ��Ă��܂��B 1�N��ʂ��ď����������鐯���͕ς��܂����A�������\�����鐯�̈ʒu�W�͕ς���Ă��܂���B�܂�łȂɂ�����̂��̂ɐ����ւ���āA���̋����ƁA��������Ɛ����������Ă���悤�ł��B���̋��͓V���ƌĂ�܂��B �@ �������ΐ��Ƃ������Ƃ��͂����ł͂Ȃ��A����Ƃ��͍P����ǂ������A����Ƃ��͋t�߂肵�A���������������ɓ����Ă���悤�Ɍ����܂��B����A�l�͂����ƌ������ƂȂ��ł����ǁA�����炵���ł��B����Ȃ킯�ŋ�����ΐ��͌˘f�����A�f���Ɩ��t�����Ă��܂��B�P�����������ĂȂ�������V������������n���𒆐S�ɉ�]���Ă���A�Řb�͊ȒP�������̂ł����A�f���̂��Ƃ�m���Ă�������ɂ���ł͘b���Еt���܂���ł����B �@ �����Ńv�g���}�C�I�X����́A�f����2�̉~�^���̍����Ƃ��čl���܂����B�܂��n���𒆐S�ɂ����~�����l���܂��B���ɁA���̉~��������ɏ����ȉ~��������Ă���ƍl���܂��B �@ ����ɂ���āA����Ƃ��͋t�s�����肷��f���̉^����������Ă��܂����B���������͉~�������̂Łu���]�~�v�A�傫�����̉~�͏������̂��^�Ԃ���u�����~�v�ƌĂ�܂��B�Ȃ����G�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����A�Ƃ肠���������̊ϑ����x�ł͂���Ő����������̂ł����B �@ ���̃v�g���}�C�I�X�̓V�����͑����̐l�����Ɏ�����A�����ԐZ�����Ă��܂����B����������������������̂��R�y���j�N�X�ł��B�V�ł͂Ȃ��n���������Ă���Ƃ����A�R�y���j�N�X�̒n�����ł��B���݂ł́A���z�̎����n���������Ă���Ȃ�ĒN�ł��m���Ă��܂����A�V�������Ă��悤�ƒn���������Ă��悤�ƁA���ʐ������Ă���Ԃ�ɂ͒��ڊ����邱�Ƃ͂Ȃ��ł���ˁB�ł͂ł́A�ǂ����ăR�y���j�N�X�͒n�������v�������̂ł��傤���B�@�@ �@ |
|
| ���V�����E�G�L 4 | |
|
���~�̌�
�@ �u�A���X�g�e���X�́A5�̘f���Ƒ��z�A����7�̓V�̂����̂ɁA27�̉~������ƍl�����B�v�g���}�C�I�X�͉~��34�ɑ��₵�A��̓V���w�҂��~������ɂ��������B�ϑ����x���オ��A�ׂ����^�������X�Ɍ����������߂ł���B�ŏI�I�ɂ�16���I�܂łɐ��\���̉~���g�p����邱�ƂɂȂ����Ƃ����B�������A���̉~�̌����Ȃɂ䂦�ɂ��̌��łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��m�ɓ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�v �@ �Ȃ��A���̒i�����Ȃ������Ƃ����ƁA34�Ƃ�������1514�N���R�y���j�N�X����e�w�R�����^���I�X�x�̒��Ŏ����̉~�̐��Ɍ��y�������̂ŁA�v�g���}�C�I�X�̂��̂ł͂���܂���A���炩�ȊԈႢ�ł��B������v�g���}�C�I�X���g�����~�̐��͂����炩? �R�y���j�N�X�̓v�g���}�C�I�X�ɂ���5�f���̗��S�~��n���̌��]�O���ɒu���������̂ŁA5���Ȃ��Ȃ����͂����ƍl����ƃv�g���}�C�I�X�̉~��39�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����ۂ��A�v�g���}�C�I�X�̃G�J���g���������߂ɃR�y���j�N�X�͏����]�~�������̂ŁA5�f���ƒn���A���ƂŌv7�lj��B�������v�g���}�C�I�X���2�����Ƃ���A�v�g���}�C�I�X���g�����~�̐���32�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�����̐��_�͊ԐړI�Ȃ��̂ŁA�������A�R�y���j�N�X��1514�N�����34���g���Ă����Ƃ��Ă��A�w�V���̉�]�ɂ��āx��E�e����1543�N�ɂ͂��̐����ς���Ă��邩������܂���B���ɂ͊m���Ȃ��Ƃ�������Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠�������̋L�q�͍폜���܂����B �@ 1.�G�E�h�N�\�X(�I���O4���I) 27 �@ 2.�J���b�|�X(�I���O4���I) 34 �@ 3.�A���X�g�e���X(�I���O4���I) 56 �@ 4.�v�g���}�C�I�X(2���I) 43 �@ 5.�R�y���j�N�X(1514�N����) 35 �@ 6.�A�~�[�R(1536�N) 107 �@ 7.�t���J�X�g��(1538�N) 79 �@ 8.�R�y���j�N�X(1543�N) 49 �@ �������A�����̐������͂��낢�낢�날���āA�A���X�g�e���X�̂���22�͐��x���グ�邽�߂̂��̂ł͂Ȃ����A�v�g���}�C�I�X�Ŋe�f���̔N���^���̌v�Z�ɕK�v�Ȃ����𐔂����34�ł��B�R�y���j�N�X�͂�͂�w�R�����^���I�X�x(�����Ȃ��P������������34�B�Ԉܕ����ɓ��������߂�4���������38)����w�V���̉�]�ɂ��āx�܂ł�14���₵�Ă��܂��B�A�~�[�R�ƃt���J�X�g���́A�ׂ�ڂ��ɑ����ł����A�v�g���}�C�I�X�Ƒ̌n���Ⴄ(���S��)�̂ŁA���x�͏オ�炸�A����ɂ��ƂÂ����\�͍���Ă��Ȃ��ȂǁA���p�I�ɂ͖�������Ă����悤�ł��B��\�I�Ȑ��\�����ꂽ���̂Ō����A(4)�ɂ��ƂÂ��A���t�H���\���\��34�A(8)�ɂ��ƂÂ��v���C�Z�����\��48�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B �@ �u�ŏI�I�ɂ�16���I�܂łɐ��\���̉~���g�p����邱�ƂɂȂ����Ƃ����B�v�Ƃ��������ɂ��āA��������܂����B1949�N�Ƀn�[�o�[�g�E�o�^�[�t�B�[���h���_���w�ߑ�Ȋw�̒a���x�̒��ŁA�R�y���j�N�X�̉����ł́u�V���̑�����80����34�Ɍ����Ă���v�Əq�ׂ����߂ɁA�ꎞ���ꂪ�ʐ��ƂȂ����悤�ł��B�R�y���j�N�X���w��16���I�̃p�h���@��w�̊w�h�̒��ɂ͓��S�V�����f���ɂ��ƂÂ��āA�~�𑝂₵���w�҂����܂����B�������A�����M�����Ă���A�R�y���j�N�X�������Ă����w�A���t�H���\�\�x�́A13���I�ɍ쐬���ꂽ���̂ł��B���́w�A���t�H���\�\�x���A1532�N�V���e�t���[�́w�V�̗�x���A�g���Ă����~�̐���2���I�̃v�g���}�C�I�X��(�v�Z�ɕK�v�Ȍ��������������)34���瑝�����Ă��Ȃ����Ƃ��A1973�N�A�M���K���b�`���Čv�Z�ɂ�莦���܂����B�@ |
|
|
���V�����ƃL���X�g����
�@ �u�L���X�g���E�̋��͂ȉ���ɂ���1500�N�Ԏx�����ꂽ�B�v�Ƃ���܂����A�V�������������т��̂́A�R����L�͂Ȑ�������Ȃ���������ŁA�����16���I�̃R�y���j�N�X�ɍ̂�A�I����17���I�ɍ̂�A�L���X�g����֗^����̂͂�������100�N�ł�������܂���B���邢�̓R�y���j�N�X�̒n����������Ŗ��ɂȂ�̂̓K�����I�ٔ��̂Ƃ��ŁA1616�N���납��1633�N�B�P�v���[�̐��ɂ��ƂÂ��w���h���t���\�x�������̂�1627�N��,����͐��x���ǂ������̂ŋ}���ɕ��y���������ł��B��������ƃL���X�g����(�J�g���b�N����)�̒�R���L���������̂́A1500�N�̂����́A��������20�N�ɖ����Ȃ����ԂƂ������ƂɂȂ�܂��B �@ ����ɁA�v�g���}�C�I�X�̓V�����ɂ��Č����A8���I����̐��S�N�̓C�X���������ŕێ�����Ă����̂ł���A�J�g���b�N���������̂�����̂�13���I����̃X�R���w����ł��B�Ƃ肠��������1���͍폜���Ă��܂��B�J�g���b�N����Ƃ̊W���L�q����Ƃ���A�T�v�̍ŏI�i���ɁA�u17���I�A�J�g���b�N����ɂ��K�����I�ٔ��ɂ����āA�V������ے肷��n�����͕��c�ƂȂ����B�v���炢�̕��͂�lj����邩�ł��B �@ �u13���I����17���I���܂ł́A���[�}����̌��F�̐��E�ς������v�Ƃ����̂̓I�b�P�[�Ȃ̂ł����A�v�g���}�C�I�X��̓W�J�̂Ƃ���Ɂu�����A���[�}����́A�����̌������֎~�������v�Ƃ����L�q���lj�����܂����B���́u�����v�Ƃ́A������̘b�ł��傤��? 4���I��〜5���I�̍����Ȑ_�w�҃A�E�O�X�e�B�k�X�̓M���V�A�N�w�ɒʂ��Ă��܂������A�����13���I�̃X�R���w�ɂ��p������Ă��܂��B�@ |
|
|
���V�����ŋL�q����J��
�@ �u����̓V�����v�̐߂Ɂu�ׂ�ڂ��ȘJ�͂�v���邱�ƂɂȂ邪�A���̘J�͂����}��Ȃ���A�V�����̗���œV�̂̉^���𐔊w�I�ɋL�q���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł���B�v�Ƃ����L�q������܂��B �@ �V�����ŋL�q���邱�Ƃ́A�n�����ɔ�ׂ���قǂ����ւ�Ȃ̂ł��傤��? �@ ���Ƃ��Βn�����猩��������̕��p���Z�o���悤�Ƃ���Ƃ��A �@ 1. �R�y���j�N�X�̌n���ƁA���Ԃ͂ǂ���ł��ǂ��ł����A�܂����z�𒆐S���ɂ��Ēn�������̋O����̂ǂ��ɋ��邩���v�Z���A���ɋ������O����̂ǂ��ɋ��邩���v�Z���A�Ō�ɂ��̒n��������������Ԑ��̕��p���v�Z���܂��B �@ 2. �v�g���}�C�I�X�̌n���ƁA�܂����z�̕������v�Z���܂��B���ɋ����̗��S�~�̉�]�p�͂���Ɠ����Ȃ̂ł���𗘗p���A���Ƃ͎��]�~�ȍ~���v�Z���ċ����̈ʒu���Z�o���܂��B�Ō�ɕs���̒n�����炻�̋������Ԑ��̕��p���v�Z���܂��B �@ �g�����t�������Ⴂ�܂����A���͓������Ƃ����Ă��܂��B�n�����̋L���ɂ́u�R�y���j�N�X���������ꂽ�w�v���C�Z�����\�x�����ꂽ���A�v�g���}�C�I�X�̓V�����������]�~�̐����������߂Ɍv�Z���ώG�ł���A�덷�̓v�g���}�C�I�X���Ƃ������ĕς��Ȃ������B�v�Ƃ���܂��B �@ ���ꂼ��̌v�Z�ɂ�������̏����]�~�������āA�v�Z�������ւ낤�Ƒz������̂́A�O�����ǂ��ߎ����邩�̖��ł����āA�V�������n�������Ƃ������ł͂���܂���B�ȉ~�ŋߎ���������ƒP�����Ƃ����̂����̂ЂƂł��B�V�����ł����ꂼ���ȉ~�ŋߎ����邱�Ƃ͂ł��܂��B�n���O�������G�ȗ��R�̂ЂƂɌ��̉e��������܂����A����͑ȉ~�ŋߎ����Ă��c��ʂ̖��ł����A������j���[�g���Ő�������̂́A�������������肷�邾���ŁA�v�Z�̎�Ԃ�����킯�ł͂���܂���B �@ �������ɂ˂��B�P�ɁA�u�n�����v(���̒��g�����ł���)�Ɛ��w�I�ɂ��Ȃ��v�Z��n�����Œ肵�����W�n�ł��A����͂���ň�̓V�����̑̌n�ɂȂ邾�낤����A�����������Ƃ͂킩��܂��B�܂��A���Ȃ����x��ڎw���Ȃ���ۂ̌v�Z�͑������肪���Ȃ��Ă��ނł��낤�u�n�����v�̂ق��������Ɓu�ȒP�v�ł͗L�낤���Ǝv���܂����B���ƁA�V�����Ƃ������̂������߂炦��̂���ʓI���ǂ����Ƃ���������ɑ��_������̂����B�܂��A�V�����Ƃ������̂������܂ŏ����]�~���ɘA�˂���@���ƋK�肷��̂��_�҂̏���Ƃ����Ώ��肾���A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�̐��E���A�V�����ƒn�����̂ǂ��炩�Ƃ݂Ȃ��̂͂�������i���Z���X���낤���c�B�܂��́A���𑈓_�ɂ���̂������߂Ȃ��ƁA�b�������܂Ȃ������B �@ �Y���i���́u����́v�Ȃ̂ŁA���̒n�����̓P�v���[�̂��̂ŁA�j���[�g���ŗ��t����ꂽ������w���Ă���̂ł��傤�B����ɑ��u�V�����v�̌��t�ŌĂ�Ă���̂́A�������[���b�p�������Ă����F���ρA�A���X�g�e���X�ƃv�g���}�C�I�X�̍����ɂ����̂��w���Ă���悤�ł��B���̉F���ς́A���̂��̂ō\������Ă��܂��B���̂����V�����̃R�A��1�����A�Y���i���͂��̂����u�ׂ�ڂ��ȘJ�́v��5�̖��A�߂̍Ō�ɂ���u�����I(�͊w�I)�ɂ͂�����S�ɔj�]���Ă���B�v��2�̖��ɂ��ċc�_���Ă���悤�ł��B �@ 1. �n���͉F���̒��S�ɂ���A�����Ȃ��B����ɓV�������琼�֓����^���A�����瓌�֔N���^�������Ă���B �@ 2. �n���𒆐S�ɁA���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y���A�P���������̏��ɑw�𐬂��Ă���B �@ 3. �P���͍P�����ɓ\����Ă��邩�A���ł���B �@ 4. �������͓V�̐��E�ł���A�����艺�̐��E�Ƃ͊u�₵�Ă���B �@ 5. ���z�A�����܂ފe�f���̔N���^���𗣐S�~�A�G�J���g�A���]�~�ŋߎ������B �@ �����ۂ��A����̖��Ƃ��āA�n���̏�ɗ�����̎q��������������グ��ƁA���z���n���̎��������Ă���悤�Ɍ����邱�Ƃ��ǂ��������邩�Ƃ�������_���Ă��܂��B���̖��ɁA����̎���̓���̒n��ŐM�����Ă����V���������グ�āA����������~�낷���Ƃɂǂ�ȈӖ�������̂ł��傤��? �V�����́A���܂��܂ȕ����ł��낢��ɐ�������Ă��܂��B �@ �Ƃ肠�����A����̖��͕ʈ����̂ق����ǂ��ł��傤�B�u����̓V�����v�̐߂͂����������āA���̑���V�����̂��낢��ȗތ^���������߂ƁA���ȋ���̖��ɂ��ĐG���߂�V���ɍ��̂��ǂ��ł����ˁB���܂�˂����b�ɂȂ�Ɩl�ɂ͎�ɂ����Ȃ��̂ŁAPortal:�����w��Portal:�V���w�ł�����Ƃ��������Ă��炦��悤�ɍ��m���o���Ă݂܂��B �@ ���肪�Ƃ��������܂��B���Ƃ��ẮA�u�ׂ�ڂ��ȘJ�́v�Ɓu�����I(�͊w�I)�Ȋ��S�j�]�v�̕������A���̒i���̋L�q�͖��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B ��݊|����悤�ł����A���̒i���́u�n�����S���Ƃ��Ă̓V�����͌��ł������v�ƌ������ėǂ��̂ł��傤��? �n�������S���Ǝv���Ă�����A���z�����S�������B���Ǝv����͌n�̒��S�͕ʂ̂Ƃ���ɂ����āA���̋�͌n�͉F���̂ق�̈ꕔ�ł����Ȃ��B���͂��̕��ʂɈÂ��̂ł����A���݂̉Ȋw�̍Ő�[�̗����Ƃ��āA�F���̒��S�Ƃ����̂́A�ǂ����ɂ���̂ł��傤��? �@ �u�ׂ�ڂ��ȘJ�́v�͒��x���Ȃ̂ł����Ă����Ƃ��Ă��A�u�����I(�͊w�I)�Ȋ��S�j�]�v�͎����Ƃ��������l������܂���B������u�V�����v�������t����悤�ȁu�͊w�@���v���܂ށu�����w�̌n�v���\�z���ꂽ���Ƃ͈�x�������͂��ł����A�����ɂ����Ă����̂悤�ȁu�����w�̌n�v���\�z���邱�Ƃ͏o���Ȃ��͂��ł��B�u�V�����v�͂��̋N�����獡���ɂ�����܂ŁA��x����Ƃ������w��(�͊w��)�̗��_�ł��������Ƃ͖����̂ł��B �F���ɓ���̒��S�͂Ȃ��A���邢�͒��S���`���邱�Ƃ͏o���Ȃ��A�Ƃ����̂����݂̉F���_�̗��ꂩ�猩��������Ǝv���܂��B �@ �����ł��傤�B���ɒ��S�������̂ɁA�n�����S�������Ƃ����̂��������藈�Ȃ���ł��B���̒i���ɂ́u�F���̂��������ɒ��S��u���̂͌��ł���B�v�Ƃ̕��������Ȃ��ƕ�����ɂ����̂ł͂ƁB �@ �u�V�����v�������t����悤�ȁu�͊w�@���v���܂ށu�����w�̌n�v���\�z���ꂽ���Ƃ͈�x�������Ƃ������Ƃ́A���̂Ƃ���ł��B�������A�e�B�R�̑��z�n�ŁA�e�O����ȉ~�ɂ�����A�͊w�I�ɂ͉��̖��������͂��B�c�P���Ƃ̊W�ŁA�܂����ł�����? �@ �e�B�R�̃��f�����ƍP���Ƃ̊W�A���Ɍ��s����N�������̌���������ł��Ȃ��_���v���I�Ȗ��ɂȂ�܂��B�ŏI�I�ɓV�����Ɉ�����n�����̂̓j���[�g���͊w�̊m�������łȂ��A���̓��16�A17���I�Ɋϑ��I�ɔ������ꂽ���Ƃ��傫���Ƃ����_�������ׂ����낤�Ǝv���܂�(�p��łɂ͏�����Ă��܂���)�B�܂��A�F���ɓ���̒��S�����݂��Ȃ��Ƃ����̂͂��̒ʂ�ł����A�u���z�n�̏d�S�v�͊ϑ�����n�ɂ�炸��ӂɌ��܂�A���z�̓����ɂ���܂�(���z�̐��m�Ȓ��S����͂킸���ɂ���Ă��܂���)�B�ł��̂ŁA�n�����ɂ́u���z�n�̏d�S�n���猩���`���v�ł���Ƃ������ʂȈӖ������邱�Ƃ��Y��Ă͂����Ȃ��ł��傤�B �@ �V�����͂����܂ł��n�����琯���ϑ������Ƃ��ɂ��̐����V����łǂ��Ɉʒu���邩��\�����邽�߂̑̌n�ł��B�܂����ꂷ���Hina����̂����悤��16���I�̎��_�ł��łɔj�]���Ă���킯�ł����A���ƁA����I�ȈӖ��ł̗͊w��̖��Ɍ��y����Ȃ�A�u�Ȃ��������̂悤�ȉ^��������̂��v���������K�v������܂��B�n�������S�ł���Ƃ����̂Ȃ�A�n�������S�ɂ����ē����Ȃ����R��������Ȃ���Ȃ�܂��A�����͊w�@�����g���čs���͕̂s�\�Ƃ����Ă悢�ł��傤�B���w�I�ɂ͂ǂ����Œ肵�Čv�Z���Ă����Ȃ����ł����A�����w�I�ɂ́u�n�����~�܂��Ă���v�Ƃ����̂Ȃ�u���ɑ��Ď~�܂��Ă���̂��v�u�ǂ����Ď~�܂��Ă��邱�Ƃ��ł���̂��v��������Ȃ���Ȃ�܂���B �@ �{�ł͂Ȃ��ׂ����Ƃ���ł����A���s���̔�����1727�N�A�N��������1838�N�A�t�[�R�[�̐U�q��1851�N�ŁA�����̊ϑ��I������18���I����19���I�ɂ����ĂƂ������ƂɂȂ�܂��B �@ ����ɗ]�k�ł����A�e�B�R�̑��z�n�ɑȉ~�O����K�p����Ƃ������z�͎������̎v���t���ł͂Ȃ��悤�ł��B1798�N�̊�����A���������F������`���Ă���悤�ł��B �u���z�n�̏d�S�v�Ƃ����̂͐������z�Ȃ���A�Ȃ�قǂƎv���܂����B�����܂ł䂩���Ƃ��A2�̂̉�]�͂ǂ�����ɂƂ��Ă��ǂ����A2�̂̏d�S�𒆐S�ɍ̂�̂����R���Ƃ����̂������܂��B�����ŁA���L�q�́u�J�́v�͎c���A�u�ׂ�ڂ��v����邱�Ƃ��Ă��܂��B���Ȃ킿�A�u�ׂ�ڂ��ȘJ�͂�v���邱�ƂɂȂ邪�A���́v�܂ł��폜�B�u�J�͂����}��Ȃ���A�V�����̗���œV�̂̉^���𐔊w�I�ɋL�q���邱�Ƃ͉\�Ȃ̂ł���B�v�Ƃ���B �@ �u�ׂ�ڂ��v�̗R����������܂����B1949�N�Ƀn�[�o�[�g�E�o�^�[�t�B�[���h���_���w�ߑ�Ȋw�̒a���x�̒��ŁA�R�y���j�N�X�̉����ł́u�V���̑�����80����34�Ɍ����Ă���v�Ƃ��āA�v�g���}�C�I�X�̗��_�ɑ��u�v�Z�Ɨ\���Ƃ����_�ł̓R�y���j�N�X�̗��_�̕����ȕցv�ƁA�q�ׂ����߂ł��B���ꂪ���ł��邱�Ƃ́A��̌����Ŗ��炩�ɂȂ�܂����B �@ �u����̓V�����v�Ȃ̂Ƀv�g���}�C�I�X�̌n�ƃR�y���j�N�X�̌n�̑Δ����ɂ���̂ł����H�Ȃςł��B�܂��v�g���}�C�I�X�̌n���V�����Ȃ�A�����������ۂ́u�V�̂̉^���v�Ȃ͋L�q���Ă��Ȃ������Ɂu�V�̂̈ʒu�W���v�Z�v���Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�܂�����菑�������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂��ˁB�Ƃ������A�c�_��������ƍs�����߂ɂ́A�����ǁu����̓V�����v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ̂����͂����肳���Ă����Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��傤�B �@ �����ł��ˁB���ɋL���S�̂Ɂu�V�����v���ǂ���`���邩�l�������˂Ȃ�Ȃ���������܂���B�T�v�`���Łu�v�g���}�C�I�X�̌n���V�����v�Ƃ��Ă��邩��A�L�҂Ƀo�^�[�t�B�[���h�̉Ȋw�v���_�����ɂ����āA�����Ɂu�ׂ�ڂ��v�Ƃ������t���������̂ł͂Ȃ����Ƒz�������܂łł��B�@ |
|
|
�����j�I�E�����I�Ȋϓ_
�@ ���̋L���́u�G��L���v�̂悤�ł����A�����G��Ȃ̂��悭������܂���B����͂Ƃ������A��������������̂́A�u�V�����v�Ƃ͂������������A�Ƃ������j�I�E�����I�Ȓ�`�E���������@���Ă���Ƃ������A�����̂��Ƃ��Ƃ��ďȂ��Ă���悤�Ɏv���܂�(�Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃɂ��C�Â��Ă��Ȃ��̂��Ǝv���܂�)�B�u�ْ[�v�̊T�O�ŁA�ْ[�Ɛ����͕⊮�W�ɂ���A�q�ϓI�ɂ́A�ْ[�E�����͌��܂�Ȃ��A�������߂邩�Ƃ����ƁA������o�ς�R����A����咣�́u�x�����́v�̗D�z�����Əq�ׂĂ��܂��B�ْ[���Ƃ����咣�E���E���_�E�@���E���h�ɂ��ċL�q����ꍇ�́A���̗��_�E���E�h�̗���ɗ����āA�܂��A���ꂪ�ǂ��������̂����q�ׁA����ɑ��A���̐����ْ[�Ƃ���A�܂��͊Ԉ���Ă���Ƃ������̎咣��A�������q�ׂ���̂ł��B�Ȋw���_�̏ꍇ�́A�ǂ��炪�Ȋw�I�ɐ������������Ƃ������j�̌��ʂ����܂��B �@ �u�V�����v�Ƃ����̂́A�����������Ȃ̂��B���݂̒�`�����ƁA�u�V����(�Ă�ǂ�����)�́A���ׂĂ̓V�̂��n���̎�������]���Ă���Ƃ����w���̂��Ɓv���ƂȂ��Ă��܂����A�V�̊ϑ��́A�Ñ�M���V�A�����łȂ��A�Ñ�G�W�v�g�A�Ñ�C���h�A�Ñ㒆���A�Ñ�o�r���j�A�A�}���E�A�X�e�J�Ȃǂł��s���Ă���A�}���E�A�X�e�J�͒m��܂��A���̑��̂ǂ��̕����ł��A��̂悤�ȁu���ׂĂ̓V�̂��n���̂܂������]���Ă���v�Ƃ����u�l�����w���v���������͂��ł��B�Â��ł��ƁA��`���������������ڂ����悤�ł����A�������A�u�v�g���}�C�I�X���̌n�������w���v�Ƃ����͖̂{���Ȃ̂��Ƃ����^�₪�N����܂��B�u�̌n���v�̈Ӗ������ł����A�v�g���}�C�I�X�ȑO�̐l�������Ă����A�����ӌ��́A�V�����ł͂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���B�܂��A�C���h�⒆���ł��V�������Ǝv���܂����A�����͓V�����Ƃ͌ĂȂ��̂��B �@ �R�y���j�N�X�Ƃ��̘b�ŏo�Ă��鐼���̓V�����ƒn�����̘b�́A��{�I�ɂ́A�u�Ñ�M���V�A�̓V���w���_�v���u�C�X�����Ȋw�ł̓V���w���_�v���u������11���I����14,15���I���܂ł̃C�X�����Ȋw�̊w�K�Ƌc�_�v���u�����̓V���w�c�_�_���v�ƂȂ��Ă���͂��ł��B�u�Ñ�M���V�A�v�̑O�ɁA�G�W�v�g��o�r���j�A�̓V���w���W����͂��ł��B�Ȋw�͂��ׂāA�����ɂ����āA15���I���ɂǂ������A�Ñ�M���V�A�Ȃǂ̎v�z���C�����Č��^���ł��A��������͐��������̋c�_�⌤���Ŕ��W���Ă��āA�����݂̂������ȉȊw��z�����A�Ƃ����b������悤�ł����A����͖{���̂��ƂȂ̂��A�Ƃ����^�₪����܂��B �@ �Ñ�C���h�ɂ��Ñ㒆���ɂ��A�B���_�҂���^�_�҂����݂��A�����Ȃǂ́A�u�O���v�Ƃ������Ă��܂����A�����F���Ƃ����l�����̋N�����������ƁA�o�Ă���̂͒ʏ�A�Ñ�M���V�A�̎��R�N�w�҂����̃A���P�[�A�f���N���g�X�̃A�g���X(���q)�Ȃǂł��B�u�V�����v�Ƃ��u�n�����v�Ƃ������T�O�T���p��͒N�������o�����̂��A��̉�����`�Ȃ̂��A�����ł̃R�y���j�N�X��K�����I�Ȃǂ𒆐S�ɂ����b�����Ɍ��肳��Ă���悤�Ɏv���܂��B���̌���͍\���܂��A���̏ꍇ�A���̏������ł́u�V�����v�͂ǂ��Ȃ�̂��B(�b����������Ă���悤�Ɏv���邩���m��܂��A�����ɂ����ċߑ�Ȋw�����������c�c�܂��́A�����悤�Ɍ�����c�c���Ƃ́A�ǂ������Ӗ�������̂��A�������S�ϓ_�ł͂Ȃ��A�ʂ̕����ϓ_���猩��ƁA�Ⴄ��肪�o�Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł�)�B �@ �����ł��B�u�V�����v��ʂ��ŏ��ɒ�`���Ȃ���A�T�v�ȍ~�́u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ŋт���Ă���悤�Ɏv���܂��B�S�ʓI�ɉ���ł���̂��ǂ����A�ł��Ȃ���A�����ł́u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�������������Ƃ����f�菑�������邩�c�B�u�v�g���}�C�I�X�̓V�����v�Ɍ����Ă��A�u�����ɂ����āA15���I���Ɂc�v�ɋ߂������ɕ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�V���w�j�̋L���ɁA�p��ł�������ʂ������A�����̔����͋I���O5���I�s���^�S���X�ɂ��Ƃ����L�q�������āA�����Ă��܂��܂������A���ł��Ñ�M���V�A�Ƃ����T���͂Ƃ��ǂ�����܂��ˁB �@ ��Ăł����A�`����`���u�V����(�Ă�ǂ�����)�́A���ׂĂ̓V�̂��n���̎�������]���Ă���Ƃ����w���̂��ƁB�n�����ƑΒu���A�����̉Ȋw�j����镶���ł́A���Ƀv�g���}�C�I�X�̓V�����������B�{�e�ł͂���ɂ��ĉ������B�v�Ƃ���̂͂������ł��傤��? �u�n�����v�ɂ��Ă��u�R�y���j�N�X�������A�P�v���[�Ɉ����p���ꂽ�v�ƌ��肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ���������܂��B �@ �t�����X�v���̋L���ɁA�t�����X�v���������ېV�ɗ^���������������Ȃ��Ă��N������͌���Ȃ��ł��傤�B�������A���̊W���Ȃ��Ƃ͂����܂���B�������A���������������Ȃ���Ă��Ȃ���A�����āA���ꂪ�����̌����҂Ɏ�����Ȃ���A�S�Ȏ��T�ɏ����̂͑������邩�Ӗ����Ȃ��ł��傤�B���̋L���Ɍ����̐i���e�����ׂĐ��荞�܂�Ă���Ƃ͌����܂��A�������Ȃ���Ă��Ȃ������܂������Ă��Ȃ����_�ɂ��āA�����������_���Ȃ��Ƃ����͕̂����Ⴂ�̋��ł���ƔF�����܂��B �@ �V�����Ɋւ��Č����A���������A�n�����ۂ��A�Ƃ����T�O�����݂��Ȃ������ł́A�V�����Ƃ����F���ς��o�Ă��܂���B���Ȃ��Ƃ��A�u�n���v���Î~���Ă���A�Ƃ������Ƃ�F�����Ă��Ȃ��ƁA�V�����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���̈Ӗ��ł́A��]�V���Ȃǂ�p�����A���X�g�e���X�Ȃǂ̐��́A�T�O�Ƃ��Ă͓V�����̒��ɓ��R����܂��B�����A����͋L�����ɏ����Ă���̂ł킴�킴����K�v���͊����܂���B �@ ���\�|�^�~�A�����ł͍P����f���̊ϑ��L�^�������o�Ă��܂����A�ނ�̎����Ă����F���ς��ǂ��ł������̂��A�����܂ŏڂ������Ƃ������Ă���S�y�͏o�Ă��Ȃ����A��͂��ς�ł��Ȃ��悤�ł��B�܂��A�A���X�g�e���X�I�ȁA�n���������Ȃ�n��̂��̂͂��ׂĐ���������A�Ƃ����悤�ȓN�w����������Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�n�ʂ������̌n���l����\�����\���ɂ��肦�܂��B�M���V���ȑO�̕����ł́A���E�͔�����ɂƂ炦���邱�Ƃ����������悤�ł��B�����A���������b�͒n�����̋L���ł͂Ȃ��A�F���_�Ƃ��̋L���ōs���ׂ��ł��傤�B����Ȓn��(�n���ł͂Ȃ�)�̏㔼�������~��̓V���ɂȂ��Ă��āA�����ɒ���t��������1��1��]����Ƃ����F���ς������Ă��������͂���������悤�ł����A���̒i�K�ł͒ʏ�͓V�����Ƃ͌���Ȃ��悤�ł��B�����̕������ǂꂭ�炢�����d�v�����Ă������ɂ���Ă��A�V���������܂�邩�ǂ����͕ς��ł��傤�B����z���čq�C���Ђ�ς�ɍs���Ă��������̂ق����A�n�����ۂ��Ƃ����T�O�ɂ��Ă͎���₷���悤�ł��B(�������͊ۂ����A�����̑D�͔��悩�猩���n�߂܂��̂�) �@ ���̌�A�v�g���}�C�I�X�̌n���A���r�A�Ɏ������܂�A����ɒ����ɂ��������܂�Ă��ꂼ�ꔭ�W���܂����A���ꂼ��̕������u�n�����ۂ��v�u�V���������Ă��ꂪ�����v�Ƃ����T�O��F���������Ƃ��ɁA���ꂼ��̕����̑̌n�Ƃ̔�݊������ɂȂ��āA���ꂪ�傫�Ȑ��ςƂ��Ɍ��т����̂Ȃ炻��͂���ŏ����K�v�͂���ł��傤���A�����������̂��Ȃ��悤�ł��B �@ �V�����Ƃ́A�n�����ɑ��錾�t�ł����āA���̒n�����Ƃ̓R�y���j�N�X�̂��̂ł���Ƃ������ꂩ��́A����ŗǂ��ł��傤�B�������A�u�Ñ�M���V�A�E�Ñネ�[�}�����ȊO�ł́A�V�����ɗނ���F���ς͐��܂�Ȃ����A���W���Ȃ������B�v�Ƃ����̂́A�����ꒃ�ł��傤�B�u����́u�n���v�����E�̐^�ɕ�����ł���v�̂�(���̋L���Ō���)�V�����ƒ�`���Ă̂��Ƃł��B�Ȃ�����łȂ���ΓV�����ƌ����Ȃ��̂��A��n���Œ肳�ꂸ������ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�����܂���B����F�����Ƃ��Ă��A6���I�C���h�̃A�����o�[�^(Aryabhata)�́A���������n�����������Ă��܂��B�ނ̏���8���I�ɂ̓A���r�A��ɁA13���I�ɂ̓��e����ɖ|��Ă��܂��B�v�g���}�C�I�X�̓V�������R�y���j�N�X�̒n�����̕����Ō��ɂ���A���Ȃ��Ƃ��C���h�͖����ł�����B �@ ���������܂��Ă��A�u�V�����v�Ƃ�����͌��X���{��ɂ������T�O�ł͂Ȃ��Ageocentric model�̖�ł��B�{���̈Ӗ���ƁA�u�n�����S���v�ɂȂ�܂�(����͖{�����Ɍ��y������܂�)�B�]���āA�u�n���v�Ƃ����T�O�����݂��Ȃ������œV����������Ƃ����咣���̂��������Ȃ��ƂɂȂ�܂��B�����̎���̓��{�̊w�҂�geocentric model�Ɂu�V�����v�Ƃ����������Ă����߂ɂ��悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���킯�ŁA����͎��⑼�̂��̋L���̎��M�҂̐ӔC�ł͂���܂���B����Ȃ�u�n�����S���v�Ɉړ�����悢�Ǝv���邩������܂��A��������Œ艻�����p����}�ɕς���͍̂���ł��B�m���ɁA�u�n�����S���v�Ƃ�������D��Ŏg�������҂Ƃ��͂��邱�Ƃ͂��܂����A����ł������Ă��̏ꍇ�A�u�n�����S��(�V����)�v�Ȃǂƒ��ߕt���ł��B����google�q�b�g���Ƃ��͂��܂�C�ɂ��Ȃ��ق��Ȃ̂ł����A����Ă݂�ƁA2���قǁu�V�����v�̂ق��������Ȃ��Ă��܂��B�������ɂ��ꂾ�����|�I�ȍ�������ƁA�u�L�����͒n�����S���v�ł���ׂ��A�Ƃ����咣���s���킯�ɂ������܂���B�܂��A���̌�́A�V���w�����̗p��ł͂Ȃ��A�N�w�̗p��ł����邽�߁A�ǂ��炩�̕���̓s���ŏ���ɕς���킯�ɂ������܂���Binterlink�������ɂȂ�Ε�����Ƃ���A���Ƃ��Ήp��łł́A�V�����͔�����̃h�[���^�̐��E�ςƂ͂͂������ʂ����Ɩ����������Ă���܂��B���̌��y�����{��łɑ���Ȃ������̂͊m���Ȃ̂ŁA�������������Ă����܂��B������̐��E�ς́A�u���n�V�����f���v�Ƃ��������������������錤���҂�����悤�ł����A�m���Ȏg�p�Ⴊ�����ł����Ɍ�����Ȃ������̂ŁA�����Ă��疼�O���������Ƃɂ��܂��B �@ �A�����o�[�^�ɂ��ẮA�ނ��M���V�A�̓V���w�ɂӂꂽ���Ƃ͂قږ����ł��B���Ȃ��Ƃ��A�p��łɂ͂���ɂ��Ă̌��y������܂��B�M���V�A�œV���������܂�Ă���A�A�����o�[�^�̎���܂�500�N�ȏ゠��܂��B�v�g���}�C�I�X���琔���Ă�400�N�ł��B�t�ɁA�C���h�̍ł��Â��C���h�����̔蕶�̔N����A�����[���b�p�̕����ŃC���h����(�A���r�A����)���o�ꂷ��܂ŁA400�N�͂������Ă܂���B�A�����o�[�^�̎���A�����[���b�p�ƃC���h�ɂ�(�A���r�A�Ƃ������Ԓn�_���������ɂ���)�ԐړI�ɐڐG���������̂�����A�A�����o�[�^�ւ̌��y�́A�u���炭�A�M���V�A�̓V���w�ɉe������āv�ƌ��y���ׂ��ł��B�̂ŁA�������������Ă����܂��B������p��łɌ��y������̂ō����������̂ɖ��͂Ȃ��ł��傤�B�@ |
|
|
������̒n����������ł���?
�@ �V�����ł��n�����S���ł��\���܂��A�u����̒n����������ł���v���Ƃ�v���Ƃ��鍇���I���R������܂���B�u�R�y���j�N�X���ᔻ�̑ΏۂƂ��đI���v�Ƃł���`����ق����A����ۂǐ����ł��B���̌��ߕt���ɂ͕s���Ȃ���A��`�ƊT�v�̖������Ƃ肠�����������邽�߂ɁA��`���u�V����(�Ă�ǂ�����)�́A���ׂĂ̓V�̂��n���̎�������]���Ă���Ƃ����w���̂��ƁB ����ƒn��ɂ��A���܂��܂ȉF���ς����݂������A16���I�̃��[���b�p�ŃR�y���j�N�X�������n�����ɑΒu���āA�Ƃ��Ƀv�g���}�C�I�X�̓V�������w�����Ƃ������B�{�L���ł͂���𒆐S�ɉ������B�v�ƁA�����ς��܂����B �@ �����I���R�Ȃ����Ă��A���K�I�ɂ��������Ă���̂Ȃ炵�������Ȃ�����Ȃ��ł����B�Ƃ͂����Ă��A������ꂾ����Ƃ����ē��{�ꉻ�����Ƃ��ɕt���I�ȈӖ����t��������Ă͂����Ȃ��Ƃ����b�������̂ŁA�u�V�����v�Ƃ������{��̎g�����Ƃ��āA�u�n���v�T�O���܂܂Ȃ��l������������x�L�܂��Ă���Ƃ������������Ⴊ����̂Ȃ�A�������̓I�ɒ��������ŁA���̂悤�ȍl�����ɐG���̂��ԈႢ�Ƃ͂����Ȃ��Ǝv���܂����B �@ �����͂����Ă��A���Ƃ��w���E��S�Ȏ��T�x��2�łł��A�n�������S�Ƃ����̂��O��̒�`�ɂȂ��Ă��܂��BShinobar���������Ă���͂��́A������w�V����]�_�x�������ł��B123�y�[�W��125�y�[�W������������BShinobar���́A�����̒�����܂���B�V�������A������Œn�ʂ�����Ƃ������E�ς��܂ނƂ�����`���s�������{��g�p�҂̐E�ƓV���w�҂��Ꭶ����Ȃ��ꍇ�A����(����)�L�q�ɖ߂��܂��B �@ �V�����́u����̒n����������ł���v���Ƃ�v���Ƃ���̂��A�u���K�I�v���ǂ����ł��B�����Ap123�́u�n�����F���̒��S�ɐÎ~���A�V�������v�Ƃ����l����V�����Ƃ��Ă��܂��B�u�V�����ł͒n���炾�Ƃ��Ă���v�Ƃ����u����v�������A�u�V�����ł��n���͊ۂ��ƑO�Ă����v�Ǝw�E���Ă��܂��B����́A�V�����ɂ͒n�������炾�Ƃ������̂��܂ނƂ����̂����K�I�����A�����Ƃ��i�������v�g���}�C�I�X�ł͒n�����ۂ��Ƃ������Ƃ��A���Ƃ͒m���Ă���Ɠǂނ��Ƃ��ł��܂��B���Ƃ̊Ԃł́u�V����=�G�E�h�N�\�X/�A���X�g�e���X/�v�g���}�C�I�X�v���Ƃ����咣�����邩������܂��A�����������Ă��܂Ă悢�̂��ǂ����c�B�u�n�������S�v�Ƃ����̂��O��Ƃ������Ⴂ�܂����A�I��2���I�A�㊿��̒����ł͒��t���ӓV���ɂ��ƂÂ��V���V(�ӓV�V)������Ă��܂��B���̒��S�͒n���ł��傤? ����Ƃ��A������Ȃ�����u�n���v����Ȃ�����? �@ ���`�����ĂȂ�����n������Ȃ��ł��ˁB�V������geocentric model�̖��ł������A����͎��ւ����܂���B���{��Ɍ��炸�A���̂̎��ʂ����ۂ̓��e��I�m�ɕ\���Ă��Ȃ����Ƃ͂悭����܂��B�u�P���v�Ƃ�����ɂ��Ă��A�u���V���͍P���ł���v�ƌ����������_�ŁA�u�P�v�v�ɋP���킯����Ȃ������Ƃ��Ă͓��e��I�m�ɂ͕\���Ă��܂��ˁB�w�p�p��̒�`�͉\�Ȍ��茵�i�ł���ׂ��ŁA�\����Ȃ����A���₠�Ȃ��̓s���ŏ���ɂ͕ς���킯�ɂ͂����܂���B������ɂ��Ă��A���Ⴂ�ȊO�̎g�p�Ⴊ�Ȃ���`�����̂܂c���킯�ɂ͂����܂���B���}�ɒ�`�҂��m�F���Ă��������B�m�F����Ȃ��ꍇ�͌��ɖ߂��܂��B �@ geo���邢��Earth�����`���ǂ����ł��Bwikipedia�p��ł̒�`�����ɂ́ugeocentric model�Ƃ́AEarth���F���̒��S�ŁA���̉����c�B�v�u���̑̌n�́A�Ñ�M���V�A�ň�ʓI�ɐM�����Ă����B�v�u�Ñ㒆���ɂ����l�̍l�����������B�v�u�Ñ�M���V�A�⒆��(���[���b�p)�� geocentric model�́A���`�� Earth���g�ݍ��킳��Ă���̂���ł���B���������Ă���́A�������̐_�b�ɓo�ꂷ��A�����ƌÂ� flat Earth model�Ɠ����ł͂Ȃ��B�v�Ȃǂ���܂��Bwikipedia�p��ł̒�`�́Ageo=Earth�����`�ł���Ƃ͌���Ȃ����Ageocentric model���Ñ�M���V�A�̂��̂���Ƃ͌����Ă܂���B���{��Ō��L���̊T�v�ɂ���u�����^�̐��E�̒��S�ɐl�Ԃ��Z��ł���Ƃ������E�ςƓV�����͌����ɋ�ʂ����B�v�Ƃ������͂́A�u�Ñ�M���V�A�⒆���� geocentric model�́v�ƌ��肵�Ă���p��łƂ͈قȂ��Ă��܂��B �����Ap125�͖`���A�u�c�V�̂̉^�s�Ɋւ��Ă��܂��܂ȗ��_����o����Ă������A�����ł͂����ԗ��ł��Ȃ��B�R�y���j�N�X�𗝉�����̂ɕK�v�Ȕ͈͂ɏ��q�����肷��v�ƒf���Ă��܂��B�����̌����u�V�̂̉^�s�v=�u�V�����v�ł͂Ȃ��Ǝ咣���邱�Ƃ��ł��܂����A���́u�V�����v�́u�R�y���j�N�X���ᔻ�̑ΏۂƂ��đI���v�Ƃł���`����ق����A����ۂǐ����Ƃ����̂́A���̘_�ł��B�܂��A�����́u�V�����v�ɓ��S�V�����Ɠ��~�����]�~����2�������Ă��܂��B���Ȃ��Ƃ��u�V�������v�g���}�C�I�X�̓V�����v�ł͂���܂���B �@ �u�R�y���j�N�X���ᔻ�̑Ώہv�Ƃ�������`�́A�P�ɂ��Ȃ����咣���Ă��邾���ŁA����̓��{��̓V���w�Ŏ嗬�̒�`�Ƃ͓��ꌾ���܂���B���������Ȃ�A���̒�`�҂��Љ�Ă��������B���x�������܂����A���Ȃ��̖ϑz�ŋL�������ς���Ă͍���܂��BWikipedia�́A���Ȃ����������Ǝv�����Ƃ�����ɐ�`���Ă܂��ꏊ�ł͂���܂���B �@ �܂��A���Ƃ��A�������A�V�����ł͒n�ʂ͕���ł͂Ȃ��Ƃ킴�킴�f���Ă���Ƃ���Ƃ��������Ė������闝�R���肢�܂��B�p��ł́A����Ȓn�ʂ̃��f���͓V�����ł͂Ȃ��Ƃ킴�킴�f���Ă���̂�����AEarth������łȂ��͖̂����ł��B���͕ʂɁA�Ñ�M���V���̂��̂�����geocentric model���Ƃ͌����Ă��܂���B�������ォ�O�̎���ɕʂ̕����Ŏ������Ƃ��l�����w�҂�����A����������낵���A�����A���`�̓V���̒��ɁA����̒n����������ł���Ƃ������f���́A���̂��Ñ�M���V���ȊO�ł͐��܂�Ȃ��������A���邢�͎嗬�̉F���ςɂ͂Ȃ�Ȃ������A�ƌ����Ă��܂��B �@ ������ɂ��Ă��A���������̒��Ȃ��܂܂ǂ�ǂ�L���̏����������s���Ă�����悤�Ȃ̂ŁA�ЂƂ܂��A����������Ă��Ȃ���`�����͌��ɖ߂��܂��B��`�҂�������܂�����A�u�N�X�͂���������`������Ǝ咣���Ă���v�Ƃ����`�Ŗ{���ɖ߂��Ă��������B�܂��A���̂ق��ɂ��A����Ɋ�Â������������A�������撼���Ă����܂��B �@ ���͐V���Ȏ咣�����Ă���̂ł͂Ȃ��A�u����̒n�������E�̐^�ɕ�����ł���v���Ƃ�V�����̗v���Ƃ���_��Wikipedia�p��łƂ͈قȂ��Ă���Ǝw�E���������ł��B�p��ł�geo=Earth�͋��`�ł���ƌ����Ă��炸�A�����̟ӓV����geocentric model�̒��Ԃɓ���Ă��܂��B���낢���geocentric model�����邤���u�Ñ�M���V�A�⒆���� geocentric model�́v�ƁA�킴�킴�����t���A���`��Earth�Ƃ����_�ő��Ƃ͈Ⴄ�Ƃ��Ă��܂��B�܂�A�V������ʂ����`��Earth�����Ƃ͂��Ă��܂���B�p����ǂ����ǂ݂ɂȂ邩�Ƃ������ł�����܂����B �@ ���Ƃ��A�w���E��S�Ȏ��T�x�ł́A2�`6���I�ɃA���X�g�e���X������������ɍs��ꂽ���A���̌�A���̌����̓A���r�A���E�Ɉڂ�A12�`13���I�Ƀ��[���b�p�ōĂь�����������ɂȂ������ƂƁA���̎���A�L���X�g���_�w�ƑΗ��������Ƃ��L����Ă��܂��B�֗߂����ۂɏo���͂��ł����A�ǂ̃��x���ŏo���̂�(�o�`�J�������ڋ֎~�����̂��A����̏C����֎~�����̂��Ȃ�)�͂����ɂ͏o�܂���ł����B��Y�M��w���ƃ��C���\����13���I�ɂ�����N�w�̏��T�O�x�Ƃ����A���̖��ɂ��Ă̐�发������悤�ł��������ł��B �@ �V�����ƃL���X�g����Ɋւ��錏�́A�L���Ɂu���[���b�p�ł̎�e�ƓW�J�v�̐߂�݂��ď����Ă����܂����B ����͂��Ă����A�V�����Ɂu����̒n����������ł���v���Ƃ�v���Ƃ���Modeha����̂��l���́AWikipedia�p��łɂ��A�w���E��S�Ȏ��T�x�ɂ��������̂ł��B�w���E��S�Ȏ��T�x�̓V�����́A�u�V�̂̌������̉^�����L�q����̂ɁC�n���̎��]�C���]������ (�����̏ꍇ�͒n����s���̒��S�ɒu�����q�n�����S�� geocentric model (geocentric theory) �r�Ɋ�Â�)�C�V�E���^�����邱�Ƃɂ���Đ������悤�Ƃ�����������B�v�Ƃ���܂��B�܂�A�p���geocentric model�ɂ�(�M���V�A��N���Ȃ̂�?)�n�������邪�A���{��̓V�����́A�����łȂ����̂��܂ނƂ�������ł��B�����ۂ��AWikipedia�p��łɂ�� geocentric model�ɂ���geo=Earth�͋��`�ł���ƌ����Ă��炸�A�����̟ӓV����geocentric model�̒��Ԃɓ���Ă��܂��B �@ �ӓV���Ɋւ��錾�y�́A�p��łɂ͌�������Ȃ��̂ł����ǂ��ɂ������̂����Ă��������B������ɂ��Ă��A�ӓV����flat earth����Ȃ��ł���ˁB�O�q�����Ƃ���A�u�V�����v�Ƃ�����͌���݂₷���̂łȂ�ׂ��g��Ȃ��悤�ɂ��Ă��錤���҂͂��܂��B����z��Y�̒�`�������ǂ߂�Ƃ����̂Ȃ�A����͑���ɂ��ƌ��肵�ċL���ɏ����̂͂��܂�Ȃ���Ȃ��ł����B�����A����͓��S�������ƃv�g���}�C�I�X�̌n�̏Љ���ŁA�n�ʂ�����ȃ��f���܂Ŋ܂ނƂ܂ł͂͂�����咣���ĂȂ��悤�ł����B����͂�����������̌��y��O�O�ɒ��ׂ�K�v�͂���ł��傤�ˁB�������Ƃ��Ă��A�������A�V�����͒n�ʂ�����ł͂Ȃ��Ƃ͂����茾�����Ă���ȏ�A���̕����������킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B �@ ���Ȃ����T���Ƃ��ďo���ꂽ Wikidepdia�p��ŁA�w���E��S�Ȏ��T�x�A�����w�V����]�_�x��3�̂���������A�u����̒n����������ł���v���Ƃ�v���Ƃ͂��Ă��Ȃ��Ǝw�E���������ŁA�����u����ɂ��v�Ƃ��A�V���Ȏ咣�����t���ė����킯�ł͂���܂���B����́u�V�����v�Ɓu�n�����S���v����ʂ��Ă���悤�ł����A������p125�Łu�V�̂̉^�s�Ɋւ��Ă��܂��܂ȗ��_�v�Ɓu�V�����v�ƌ��t��ς��Ă���悤�ł��B�������u���܂��܂ȗ��_�v�̈ꕔ���ȗ����闝�R�́A�R�y���j�N�X���𗝉�����̂ɏd�v�łȂ����炾�ƌ����Ă���A���̏͂ɋ��������̂������V�������ƁA�͂�����Ƃ͌����Ă��܂���Bp124���A�ǂݕ��̖��ł��BWikidepdia�p��ł́A������(7��16��)���̍ŏ��̕������o���Ė܂����B�Ñ�M���V�A�̐����Љ�����ƁA�u���l�̍l���͒����ł��c�v�Ƃ��Ă��܂��B���ꂩ��A���{��Ō��L���́u�����^�̐��E�̒��S�ɐl�Ԃ��Z��ł���Ƃ������E�ςƓV�����͌����ɋ�ʂ����B�v�ƁAWikidepdia�p��ł̋L�q�uThe geocentric model was usually combined with a spherical Earth by ancient Greek and medieval philosophers. Thus, it is not the same as the older flat Earth model implied in some mythology. �v�Ƃ͈�v���Ă��܂���B�p���́A�u�Ñ�M���V�A�⒆���̂��́v�̑��ɂ� geocentric model�����݂��邱�Ƃ��܈ӂ��Ă��܂��B3��ʂ��āA���̈�ۂ́A�u�V����=�G�E�h�N�\�X/�A���X�g�e���X/�v�g���}�C�I�X�v�Ƃ͌����ꂸ�A�u�V�����v�̒�`�ɂ͕�������Ƃ������Ƃł��B �@ ���l�̍l���͒����ł�...�̕����ɂ́A[citation needed]�^�O(�N������Ȃ��ƌ����Ă�̂��؋���������^�O)�������Ă���̂ŁA���̈ꕶ�����͍����ɂ��Ȃ��ق��������Ǝv���܂��B������ɂ��Ă��A���̕��͂����ł͟ӓV���ւ̌��y���ǂ����͕�����܂���B�ł͂��̕����͉p��ł�������ƍׂ����āA�u�V�����́A�n�������`�ł���Ƃ������ƈ�̉����A�Ñ�M���V�A���璆���܂Ŏg��ꂽ�B���̃��f���́A�����ƈȑO�̐_�b�Ȃǂɏo�Ă���u����Ȓn���v�̐��E�ςƂ͈قȂ�v���炢�ɂ��Ă����܂����H ������ɂ��Ă������́A�V�����͒n�ʂ�����ł͂Ȃ��ƌ��y���Ă��邱�Ƃ͎������Ȃ��Ǝv���܂����B �@ �����A�u�V����=�G�E�h�N�\�X/�A���X�g�e���X/�v�g���}�C�I�X�v�Ƃ�������ƁA���������L���̂闧���2����Ǝv���̂ŁA���L����O�҂̗���œ��ꂷ��̂������Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�����A����ł�2�̗����F�߂�ׂ��ŁA���̒f����Ȃ�������Ď̂Ă�̂͂�낵���Ȃ��B���Ƃ��A�����́A�v�g���}�C�I�X�Ȃǂɑ��閳�m���u����v(p123)�ƌĂ�ł���̂ŁA�V�����ɂ����낢�날��Ƃ��������́A���������ɂ͔ے肳��܂���B���������͎��̎咣�ł����A�u�V����=�G�E�h�N�\�X/�A���X�g�e���X/�v�g���}�C�I�X�v�Ƃ�������́A�ߑ�Ȋw�̃��[�c���Ñ�M���V�A�����ɋ��߂�A����ȗ��j�ςł��B�n�����猩�����̓������k�ɗ\���ł����̂́A�v�g���}�C�I�X�����ł͂Ȃ��B�v�g���}�C�I�X�����܂�邸���ƑO(�I���O104�N)�ɍ쐬���ꂽ�O����́A���z�A����5�f���̈ʒu�\�����A�ǂ̂��炢�̐��x���m��Ȃ����A�ڂ��Ă���B�A�����o�[�^�̗���o�����̂��A�Ñ�M���V�A�A�C���h�A�����C�X�����̊Ԃɂ݂͌��̉e�����F�߂��Ă���A�����̐��w�ƓV���w�̗��j�ł��C���h�͖��������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����C�X�����̃o�b�^�[�j�[�̋Ɛт̓R�y���j�N�X�����p���Ă��܂��B �@ �ʂɃC�X�����⒆���̐��ʂ����悤�Ƃ͎v���܂��B�����A���̋L���ɂ���ȏ�̍v�������炩�ɂȂ��Ă��邩�Ƃ����Ƃ����Ƃ������Ȃ��Ǝv���܂����B���ꂪ���Ȃ��̎咣�łȂ��A��ʓI�Ɏ����ꂽ���̂Ȃ�A�����Ă����܂�Ȃ��ł��傤�ˁB�������A�咣�҂����āB�C�X�����⒆���������ƕ]���������Ƃ����͕̂�����܂�������A������L���ɓ����̂́A���̕]���������Ǝ�����Ă���ɂ��Ă��������B �@ �u�����������ꂪ����v�Ȃ�A������������̓��{��g�p�҂̌����҂�{���Ă��āA�u�N�X�ɂ��v�Ə�����낵���ł��傤�B�������A���Ȃ��Ƃ������́A�u�V����(�n�����S��)�v�Ə����Ă��܂�����A�����2�`�Ɉ����Ă���͖̂����ł��B���m�ƌĂ̂́A����͓V�����ł͂Ȃ��Ƃ����͂����肵�������̈ӎv�\���ŁA���ꂪ��肾�Ƃ����錾�ł��傤�B�����ɂ��A�n�ʂ�����ȉF���ς��V�����Ƃ����̂͌���Ă���A�Ƃł������������ɕς��܂����H �@ �����̗�@�ɂ��ẮA�������i��ł��珑���ׂ��ł��傤�B�������c���Ă��Ȃ��Đ��x��������Ȃ��̂ł́A�c�_�̂��悤������܂���B�����A���ꂪ����Ȃ�ȏ�̐��x�Ŏg�������̂ŁA�ǂ������F�����f���������Ă����̂�������̂Ȃ珑���Ă����܂�Ȃ��ł��傤�ˁB���������ςȁA�p�x15�x���x�̌덷�ł����̂Ȃ�A�V�����݂����ȃ��f�����l���Ȃ��Ă��T�Z�͂ł���͂��Ȃ̂ł����������@��������܂��B�����Ƃ������͓�\���h��������܂��B �@ �T���ė����ƌ���ꂽ�̂ŁA������Ǝ��T�ނׂĂ݂܂����B �@ 1.�w���E��S�Ȏ��T�x�A���}�� (2000?)�u�V�̂̌������̉^�����L�q����̂ɁC�n���̎��]�C���]������ (�����̏ꍇ�͒n����s���̒��S�ɒu�����q�n�����S�� geocentric model (geocentric theory) �r�Ɋ�Â�)�C�V�E���^�����邱�Ƃɂ���Đ������悤�Ƃ�����������B�v �@ 2.�w���{��S�ȑS���x�A���w�� (1987)�u�F���̒��S�ɒn�����Î~���A���̎��͂Ō��A���z�A5�f���A���P�����e�ʂ̓V��������]����Ƃ����F���͌^�B�n�����S���B�v�Ƃ��邪�A�Ñ�G�W�v�g�̊ۓV����A�C���h�̐{��R���A�����̊W�V�����܂߂�B �@ 3.�w��g�Ȋw�S�ȁx�A��g���X (1989)�u�킽�������̂����n���Î~���Ă��āA����𒆐S�Ɍ��A���z�A�f���A����ɍP�����܂���Ă���Ƃ�����B�v �@ 4.�w�����w���T�x ����ŁA�|���� (1992)�u���m�ł͒n�����S���Ƃ����B�v�Ƃ��A�G�E�h�N�\�X�ƃv�g���}�C�I�X�A�e�B�R�̂ق��ɁA�n���̌��]��F�߂��A���]�݂̂�F�߂�����܂߂�B �@ 5.�w�Ȋw�j�Z�p�j���T�x�A�O���� (1994) �n�����S���Ƃ��āA�Ƃ��ɒ�`�͋L�����A�Ñ�G�W�v�g�̕��n������Ñ�M���V�A�A�v�g���}�C�I�X�܂ł��T�ρB �@ �ƁA�܂��A���������o���o���ł��B�V�����̌��L����4�́w�����w���T�x�̗���ɂقڋ߂��Ƃ��������ł��B���̑���4�͂�������u����̒n����������ł���v���Ƃ�v���Ƃ͂��Ă��܂���B �u�V�����v�Ƃ������{��̗R���Ƃ��ẮA�]�ˎ���ɃR�y���j�N�X�̐����Љ�ꂽ�Ƃ��Ɂu�n�����v�Ƃ�����ꂪ�g���A����̑`��Ƃ��āu�V�����v�Ƃ������t���ł��������ł��B����͒n�����������ǂ����ł��̂ŁA���]�͔F�߂邪�A���]�͔F�߂Ȃ��Ƃ������͂ǂ���ɓ���̂��A������Ȃ��Ȃ�܂��B�u���z���S���v���u�n�����S���v���Ȃ�A���]�̗L���͕s��Ƃ��A�n���̌��]��F�߂邩�ǂ����ŕ����邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃł��傤�B �u�n�����v���邢�́u���z���S���v�̑�\���R�y���j�N�X/�P�v���[�Ƃ����Ƃ��A����ɑΒu����u�V�����v���邢�́u�n�����S�����A�u�n�����v�ȊO�̉F���ς��ׂĂƂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�w�����w���T�x�ȊO�́A����ɋ߂��l�����Ɉ˂��Ă���悤�ł��B���̗���ɑ��āA���̌��t�Ō����u�R�y���j�N�X����ɔᔻ�̑ΏۂƂ��đI���v���u�V�����v�ƌĂԗ��������ł��傤�B�����̌��t�ł����u�R�y���j�N�X�𗝉�����̂ɕK�v�Ȕ͈͂ɏ��q�����肷��v�Ƃ������Ƃł��B�V�����̌��L�������̗���Ő�����W�J���邱�Ƃ͍\��Ȃ��̂ł����A��ʓI�ɁA���邢�͊��K�I�ɁA�����ƍL���̂闧������邱�Ƃ�F�߂āA�L���`���ɒf�菑�����ׂ����Ƃ����̂��A���̈ӌ��ł��B �@ ���ꎫ�T�I�Ȃ��̂ł����̂ł�����A�w�厫�сx����(1988�N)�͒n�����S���Ɠ��`�Ɉ����Ă��āA���S�������Ǝ��]�~�����̗�����(���ꂾ����)�Љ�Ă��܂��B�V�ł͎茳�ɂȂ������ɒ��ׂ��܂���ł����B�ȑO���������������̂́A�V���w�҂��ǂ������Ă��邩�A�ł����B��ʓI�ȍ��ꎫ�T���M�҂ƁA�w�p��̐��Ƃ��g���p��̒Ԃ��Ӗ�����H���Ⴄ�̂͂悭���邱�ƂŁA���Ƃ����ܖ��Ȃǂ������ł��B�O�q�����Ƃ���A���������Ă��鍑�ꎫ�T������̂Ȃ�A�u���ꎫ�T�ɂ͂��������Ă�����̂�����v�Ə�����낵���B�u�������w�p��͌����ɕ�������邱�Ƃ������A����������h�����߂ɁA�V����(�n�����S��)�ȂǂƏ��������҂�����v�Ƃł����������܂����H �ǂ���ɂ��Ă��A1990�N��㔼�ȍ~�̕����ł͓V�����͒n�����S���Ƃ�����̂������悤�ł����B�����Shinobar���̒����ł������ł��ˁB���Ȃ݂ɁA���E��S�Ȏ��T�͊m���ŐV�ł�1988�N�ł��B����ňًc���Ȃ��̂ł�����A�������������܂��B �@ �܂����������悤�Ő\����Ȃ��̂ł����A1990�N����������ɈӖ����ω������ƌ�������������̂ł����H���������Ȃ���̗��R���m�肽���Ƃ���ł����B �@ ������́w�V����]�_�x���o���̂�1993�N�Ȃ̂ŁA���̖e����^�����\���͂���Ǝv���܂��B���̐��_�ł����B �@ �Ȃ�قǁB�ǂ����A�ǂ������ɂ������芄����ƌ����b�ł��Ȃ��悤�Ȋ����ł��ˁB���܂�˂�����ł����ꂱ���Ǝ��̌����ƌ���ꂩ�˂܂��A�ǂ̕ӂ܂ŋL���ɔ��f���邩����Ƃ���ł��B���ꂪ�A�V���w���T�Ȃ猻�ݎ嗬�̉��߂��������Ă����̂ł������̂ł����ǁA�S�Ȏ��T�ƌ��������l����ƁA������x�͂���ȑO�̎g�����ɂ��Ă������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂�������܂���B �@ ����2�ɕ����Ęb�����Ȃ�������܂���B �@ 1.�u�V�����v���u�n�����S���v���B����͒n���̎��]�͔F�߂邪�A���]�͔F�߂Ȃ���������̂ŁA�u�n���� vs.�V�����v�����u���z���S�� vs.�n�����S���v�̂ق�����Ƃ��ēK���Ƃ�����̂��A�ŋߑ����Ă���悤�ł��B���Ƃ��ƒn�������]�����]�������n�����Ƃ��A����ȊO��V�����Ƃ��Ă����̂ŁA�Ӗ��͕ς���Ă��炸�A��ꂪ�ς���ė��Ă���Ƃ������Ƃł��B �@ 2.�u�V����(�n�����S��)�v�͈̔͂��ǂ��܂ō̂邩�B����ɂ��Ă͎���I�ȌX���͌���ꂸ�A�u�V����(�n�����S��)=�G�E�h�N�\�X/�A���X�g�e���X/�v�g���}�C�I�X�v�ɂƂǂ߂�ꍇ�ƁA�����ƍL���̂�ꍇ������Ƃ������Ƃł��B�@ |
|
|
������̓V�����̌㔼����
�@ �u����̓V�����v�̌㔼����������IP�̃��[�U�[�ɂ���āu�傫�Ȍ�T�v�܂��́u�������S�����v�Ƃ��č폜����Ă��܂����A�u�傫�ȁv�u���S�v�Ƃ��������t������قǂ̌�T�A�����������ǂ��ɂ���̂��s���ł��B�Y���ӏ��͉ߋ��ɂ��c�_�̑ΏۂɂȂ��Ă��܂����A��T�╶�������Ƃ̎w�E�͂���܂���B �@ �O���̋L�q�́A�i��N�w�̌����Ɋւ�����̂ł���̂ɑ��A�㔼�t�������͖��炩�ɈႤ�����̓��e������ł��B�܂��́A�i��N�w�̋L�����َ��Ȃ̂�������܂��A���ۂ͂�����̂ق�����ɂ������̂ł́H�@�F�����̂悤�ɓǂ߂Ȃ��Ƃ����̂ł���Δ��_�̂��悤������܂��E�E�E �@ ���̍��ڂŐ�������Ă���̂́u����̓V�����v�ł���A�u�i��N�w�ƓV�����v�ł͂���܂���B�{�����ɂ��u�i��ςȂǁv�Ə�����Ă���悤�ɁA�i��N�w�͂����܂Łu�P���ɓV������^���Ƃ��ċ����邱�Ƃւ̋^��v�̈��ł�������܂���B�u����̓V�����v�̓o��̌o�܂��A�������������ł͂܂��u���w����4�����]�X�v�̘b��������A����ɑ��锽�_(?)�Ƃ��ĉi��N�w��������A�X�Ɍ���ɂ�����V�����̈Ӌ`(?)�ɂ��ď���������ꂽ�悤�ł��B �@ ������������܂��A���������S�ɓ^�|���Ă��邱�ƂɊF����͑S�R�C�t���Ȃ��̂ł��ˁB�܂��A������Q��ւ邱�Ƃ͂���܂���Ŏ����܂���B���ꂪ Wikipedia �Ƃ������̂ł��ˁB �@ ��̓I�ɂǂ̂悤�Ɂu���������S�ɓ^�|���Ă���v�̂���w�E����������K���ł��B�{���ɕ������^�|���Ă���̂ł���A�S�Ȏ��T�̋L�q�Ƃ��ċɂ߂ĕs�K�ł��̂ŁA���̋L����ǂފF����̂��߂ɂ����肢���܂��B �@ �w�A���x�ȉ��A����ȑO�ƑS�R�W�Ȃ����e�ɂȂ��Ă��܂��B�������i��N�w���ᔻ���Ă���A�܂��ɂ��̓��e���L�q����Ă���̂ł��B�������w���w�I�ɐ������ĕ����I�E�͊w�I�ɔj�] �Ƃ͉��������Ă���̂��s���ł��B����͕����w�������������̂���l�����������̂Ǝv���܂����A�܂��ɂ��������ԓx�����i��͔ᔻ���Ă���̂ł��B�L�����������Ƃ����l�Ȃ�A�lj�͂����Ă��������B �@ �܂��A�u2004�N�����V�����〜�v�Ɓu�Ȃ��A〜�v�̓^�C�g��(����̓V����)�Ɋ֘A����ʌ̘b��ł���A���҂̊֘A���͕K�������K�v�Ȃ��Ǝv���܂��B���́u�A���v����i�����܂ł̈ꕶ�݂̂ł��傤�B ������Ă�����e�ɂ��Ăł����A�w���w�I�ɐ������āx�Ƃ́u�V�������f���Ɋ�Â������ɂ���āA�V�̂̉^��(�n�����猩��)��\���ł���v�Ƃ����Ӗ��Ő������Ƃ������Ƃł���A�w�����I�E�͊w�I�ɔj�]�x�́A�u�������V�������f���𐳓�������͊w�̌n�͉ߋ��ɑ��݂������Ƃ��Ȃ��A��������݂��Ȃ��ł��낤�v�Ƃ����Ӗ��Ŕj�]���Ă���Ƃ������Ƃł�(�n�����𐳓�������͊w�̌n�͂�����݂��Ă��܂�)�B����ē��e���͉̂��疵����s���̂ł͂Ȃ��A�u�V�����v�̋L�����悭�ǂ߂Η����ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���܂����A���킩��₷���\���ɂ��ׂ��]�n�͂���ł��傤�B �i�䎁�́w�n������^���Ƃ��āu���炷��v�̂��Ó����ǂ����x�Ƃ����₢�ɑ��A�uNo�v�ƌ����Ă���킯�ł��ˁB�������A���̖₢�ɑ��ẮuYes�v�Ɠ����闧������݂��܂��B�V�����̖��Ɋւ���i�䎁�̔ᔻ���K���ǂ����ɂ́A���R�^��̗]�n������܂��B���݂̋L�q�ł́A�Ō�̈ꕶ�������Ɖi�䎁�̗���ɑ���ᔻ�������Ă��܂��A�������ɖ�肪����悤�Ɏv���܂��B �@ �i��́uNo�v�Ƃ͂����Ă��܂���B�i��͌����ēV�����]�X�Ɍ��y���Ă���̂ł͂Ȃ��A����������Ƃ����̂܂���Ă��܂��Ƃ����ԓx��ᔻ���Ă���̂ł��B��͂蕶����ǂ�ł��܂���ˁB�\���܂����B�������E�o���g�������Ă���悤�ɁA���͂͏����ꂽ�r�[�ɓǎ҂̂��̂ɂȂ��Ă��܂��̂ł�����B�w�j�]�x�Ƃ������t���ǂސl�ɂ���ĈقȂ������߂��Ă���̂ł��B���̓ǂݕ��͓��R�قȂ��Ă��܂����A�����Ď��͌��܂낤�Ǝv���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��炢�͎���Ă��������B �@ ���̋L���̃e�[�}�́u�V�����v�ł�����A���̂悤�ȕ������炷��u����̓V�����v�̑��i���ڂ́u���w����4�����]�X�v�Ƃ���ɑ��錩���ɂ��Ă̍��ڂɂȂ�͂��ł��B�����g�͉i�䎁�ɂ��ĉ����m��܂��A�����ʼni�䎁�̘b�́A�u���w����4�����]�X�v�ɑ��錩���̈�Ƃ��ďo�Ă���̂��Ɨ������Ă��܂����B�������A219.196.247.221�����������悤�ɉi�䎁���V�����]�X�Ɍ��y���Ă���̂ł͂Ȃ��Ȃ�A�i�䎁�ɂ��āu�V�����v�̍��ڂŌ��y����K�v�͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�u����������Ƃ����̂܂���Ă��܂��v���Ƃ̐���͈�ʘ_�ŁA�V�����n�����ɌŗL�̖��ł͂���܂���B �@ ����ł́A�O�����폜����������ł��傤���B���̂܂܂ł͕��͂̓r������^�|���Ă���Ƃ������Ԃ͉��P����܂��A�L�����������F������i��N�w�̔ᔻ�̑ΏۂɂȂ��Ă���̂͌��ł��傤����B �@ �ʂɉi�䎁�̔ᔻ�̑ΏۂɂȂ�ɂ͌��ł����ł�����܂��A�u�V�����v�̋L���ł���ɂ�������炸�A�V�����Ƃ͂قƂ�NJW�̂Ȃ��u�i��N�w�v���ᔻ���Ă��邱�Ƃ�������Ă���A�Ƃ������R��(�u�^�|�v�u�j�]�v�ƌ����Ă܂������ǂ͂����������Ƃł��傤)�L������������폜�����͕̂s�K���Ǝv���܂����A�l�I�ɂ��s�����ł��B ����͂Ƃ������A�폜����͉̂i�䎁�ɒ��ڊW���镔�������ŗǂ��ł��傤�B���̑��̕ύX���܂߂�����ĂƂ��� �w2004�N�����V����̌����҂̃A���P�[�g�ɂ��ƁA���w����4�����u���z�͒n���̎��������Ă���v�Ǝv���Ă���A3���͑��z�̒��ޕ��p�����Ȃ��Ƃ������ʂ��o���Ƃ����B�����Ȋw�Ȃ̓��قɂ��ƁA�u�����̂��Ƃ́A���w�Z�ŋ��炷��B�v�Ƃ̂��Ƃ��������A���{�ɂ����闝�ȗ���A�Ȋw���e���V�[�̒Ⴓ�Ƃ��킹�Ė�莋����ӌ�������B����ŁA����ȘJ�͂�v���邱�ƂɂȂ邪�A���ꂳ���}��Ȃ���A�V�����̗���œV�̂̉^���𐔊w�I�ɋL�q���邱�Ƃ͉\�ł���A�P�ɒn������^���Ƃ��āu���炷��v�̂��Ó����ǂ����ɂ͋c�_�̗]�n������B�V���������m�ȌÑ�l�̖ϑz�ł͂Ȃ��A�k���Ȑ��w�I�w�i���������Ȋw�I�̌n�ł��������Ƃ�F�����邱�Ƃ͑�ł���B�A���A�V����(�n�����S��)���������̂͂����܂Ő��w�I�ɂł����āA�����I(�͊w�I)�ɂ͂�����S�ɔj�]���Ă���B�x ���Ă��܂��B �@ �w�A���x�ȉ����w�A���A�V����(�n�����S��)�𐔊w�I�ɋL�q���邱�Ƃ͉\�ł��邪�A����ɂ���ĒN�����e�Ղɗ����ł��邩�Ƃ����_�ł͋ɂ߂đÓ����������Ă���̂ł���x�Ƃ��ׂ��ł��傤�ˁB���ς�炸�w�j�]�x�̈Ӗ������ɂ͂��߂܂���B �@ �`�����烌�x���̐��x�ł���A�V�������n���������w�I�ɂ͓���(�ǂ��炪����Ƃ�����������)�ł��̂ŁA���̕ύX�͕s�v�ł��傤�B�V�����̂ق�������ȘJ�͂��K�v�ɂȂ�͎̂��p�I�Ȑ��x�Ōv�Z����ꍇ�ł��B�u�j�]�v�ł����A�V�����͂܂����Ƀj���[�g���͊w�̉^���̑�1�@���ɔ����Ă���(�n���E���z�n�̏d�S�������^�������Ȃ����߁B���z���Œ肵���ꍇ�͋ߎ��I�Ɋ����^���ƌ��Ȃ���)�A���̂��߈ȍ~�̋c�_���j�]���܂��B �@ ���w�I�ɋL�q�\�Ƃ́A�ߑ㕨���w�̗���ł͍��W�n�̑I�ѕ��̂��Ƃ��Ǝv���܂��B���W�n��ς���Ɣj�]����Ƃ������Ƃ��A�����ς�킩��܂���B�j�]����ꍇ�͐��w�I�ɋL�q�s�\�ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv���܂��B �@ �m���ɒn�����Î~����悤�ȍ��W�n��I�ׂA�V�̂̓V�����I�ȉ^���͖��L���́{�����͂Ŗ��Ȃ��L�q�ł��܂��B�������A���̂悤�ɓV�����E�n�����̐�����I�ɖ₤�ꍇ�A���W�̂Ƃ肩���ɗR�����銵���͕͂��ʂ͏��O����Ǝv���܂��B �@ �w����́|�x�ƂȂ��Ă��܂����̂Łw�V�����x���̂��̂��ϖe���Ă����悤�ɓǂݎ��܂����B�w����ɂ�����V�����̗���x�Ƃł��������W��ł���Ό�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���H �@ �����ł��ˁB�ł͍ŏ��̒i����2006�N�ŏ��������̂ɂ��A�\����w����ɂ�����V�����̗���x�ɂ���A�ł�낵���ł��傤���H �@ ���\�ł��B �@ ����̋L���ł͓��e���啝�ɍ���Ă���A���w���ւ̃A���P�[�g�ƓV�������֘A�t����L�q���������߁A���̕���������ɍ��킹�ē��{�̗��ȋ���Ƃ����߂ɕ������܂����B�܂��A�c��̕������A�V�����Ƃ̊֘A�ɂ��Ă̋L�q�������Ȃ��Ă��邽�߁A�܂��A��̋c�_�ɂ���w�V�����x���̂��̂��ϖe���Ă����Ƃ�������������Ȃ��悤�ɁA�ߖ�������̉F���ςɕύX���܂����B����ɂȂ�\����܂��A���Ȃǂ���܂����炲�w�E���������B��낵�����肢���܂��B�@�@ �@ |
|
| ���Ñ�̉F���� | |
| ������
�@ �Ñ㒆���ł́A���łɉF�����A�P�ɋ�ԓI�ȂЂ낪�肾���łȂ��A���Ԃ����܂ފT�O�Ƃ��đ����Ă����B���̂��Ƃ́A�I���O2���I�̑O������́w�̓�q�x�ɁA�u���×������V���@�l���㉺���V�F�v�Ƃ����L�q�����邱�Ƃł킩��B�Ӗ��́A�u���v�Ƃ͉��×������Ȃ킿���ԁA�u�F�v�Ƃ͎l���㉺���Ȃ킿��Ԃ̂��Ƃ��ƁA�����Ă���̂ł���B �@ �V�~�n���̉F�� / ��n�͋���Ȑ����`���Ȃ��Ă���A�V�͂����肳��ɑ傫���~�`(�V�̒��S�͖k�ɐ�)�A�܂��͋��`(�k�ɐ��Ƒ�n�̒��S�����Ԑ������ʂ̎�)�B �@ �W�V�� / ��n�͂��o�����`�ŁA���̏�ɔ����`�̉����̂悤�ȓV�������Ă���B �@ �ӓV�� / ���`�̉F���̒��S�ɗ����̂悤�ɒn������B �@ ���� / �u�V�͗��Ƃ��Ď��Ȃ��v�܂莿�������Ȃ��ȋ�Ԃ������ɑ����Ƃ��������F���_�B���̒��ɕ����Ԋe�V�̂͂��ꂼ��Ǝ��̋K���ɑ����ĉ^�����Ă���Ƃ���B �@ ���C���h �@ �C���h�ł́A�l�̏@��(�q���h�D�[���E�����E�W���C�i���E�V�[�N��)�����ꂼ��Ǝ��̉F���_�������Ă����B���̍ő�̂��̂͋I���O10�����I������N�̊Ԃɐ������Ƃ����C���h�ŌÂ̏@�������w���F�[�_�x�ł���B�w���F�[�_�x�̓��O�E�T�[���E���W�F���E�A�^�����@�̎l���琬��A����C���h�̓N�w�A�@���A���w�̍������Ȃ����̂ł���B�w���F�[�_�x�̓o���������̐��T�ŁA�o�����������y���̖��ԐM�Ȃǂ��z�����đ傫���ϖe�����`�̂��̂��q���h�D�[���B �@ �F���̍\���ɂ��Ă̊�{�I�Ȍ����́A�n�Ƌ�C�ƓV�̎O�w���琬��Ƃ������́B�����Ēn�E��C�E�V�͂��ꂼ�ꂪ����ɎO�̑w�ɕ������B�܂�F���͑S���ŋ�w�ɕ������ƍl����B �@ �l�Ԃ��Z�ނ͎̂O�w�̒n�̍ł����������ŁA���E�̓�w���x�z����̂͐_�̑Η��҃A�X��(���C��)�B�V�Ƃ͐_���Ӗ�����Ɠ����ɐ_�̏Z�ލ������̂��ƂŁA�����ɂ����Ă͓V�̎O�w�͗~�E�E�F�E�E���F�E�Ƌ敪����A���Ȃ݂ɍō��V�́g�L���V�h�ł���B��C�̎O�w�͓V�̋�ԁA�n�̋�ԁA���̒��Ԃ̋�Ԃƕ������A�_��J�͒n�̋�Ԃɂ���A���z�͂��̏�̋�Ԃ�ʉ߂���Ƃ���Ă���B �@ ������ �@ �����ł́A�Ñ�C���h�̉F���ς��p���A���E�͕���Œ��S�ɐ{��R�Ƃ��������R�������藧���A���͂���̎R�Ɣ��̊C���͂�ł���ƍl�����B�{��R�̓���ɂ́A���֕��F(�Ȃ��Ԃ��イ)�ȂǂƂ����̎l�̑嗤������A�l�ԂȂǂ��������Ă���ƂƂ��ɁA���E���E���Ȃǂ͐{��R�𒆐S�ɉ�]���Ă���Ƃ������́B���̐{��R�F���ς�8���I���ɐ���䶗�(�ق��܂�)�Ȃǂ�ʂ��ē��{�ɓ`��������A�V���I�F���ς��_������悤�ɂȂ����̂͐��m����n�������`����Ă���B�����̉F���ϊς͒n�������ƂȂ��鐼�m�V���w�Ɛ^��������Η�������̂ƂȂ����B �@ ���A�g���X—�V���x���鋐�l— �@ �A�g���X�́A���l���^�C�^���̈�l�ŁA��ϗD�ꂽ�˔\�������A�A�t���J�̖k���̃}�E���^�j�A�Ƃ������̉��ł����B�q��ɂ��b�܂�A�v���A�f�X�̎��l�o���A�q�A�f�X�̔��l�o���̓A�g���X�̖��ł����B�A�g���X�͂��Ƃ��Ɖ��₩�Ȑ��i�ő������Ƃ��D�݂܂���ł������A��_�[�E�X�����N���m�X�Ƃ̌��͑����ōŌ�̑�푈���s�����ۂɁA�^�C�^�����̈�l�Ƃ��Ă�ނ������A�����������̂ł����B��\�N�̐푈�̌��ʁA�N���m�X�A�^�C�^�����A���́A��s���L���n���̂Ȃ炭�ւƒǕ�����A�������߂��Ă��܂��܂����B�A�g���X���A��_�[�E�X���由�Ƃ��Ĉꐶ�V���x����悤�ɖ�����ꂽ�̂ł����B���̌�A��x�́A�w���N���X�ɓV��S���ł��炢�܂������A�܂��V��S�����ƂɂȂ����̂ł����B���̌�A���f���[�T�̎�������Ēʂ肪�������y���Z�E�X�ɗ���ŁA������ɂ��Ă��炢�A�V��S����ɂ���J�����Ă��炢�܂����B���݁A�}�E���^�j�A�k���ɗL��A�g���X�R�����A�ɂȂ����A�g���X�ł���Ƃ����Ă��܂��B �@ ���M���V�� �@ ��n�͕������~�ՂŁA�I�P�A�m�X�Ƃ�����m�ɕ�����ł���Ƃ����B���͉�X���E�����͂ނ����łȂ��A���z�����������ܔM���������C�œV��̐��̋���q�s���Ă���B�M���V���_�b�ł́A��_�[�E�X�̖��߂ɂ��A���l�A�g���X���V���x���Ă���B�_�b���ȍ~�̃M���V���ɂ����ẮA�F���̒��S�ɂ͂��̒n��������A���̎�������E�����E�����E���z�E�ΐ��E�ؐ��E�y���̏��Ԃ�7 �̐�������Ă��āA���̊O���ɐ��̒���t�����V��������Ă���Ƃ����V������������ꂽ�B���������ꂾ���ł͘f���̗���t�s�������ł��Ȃ����ߘf���͎��]�~���������Ȃ������Ă�Ƃ������]�~�����l���o����V�����͊�������A���̌�ꕔ���݂ł��M�����Ă���B�V�����́A�܂��N�w�҃A���X�g�e���X�́w�V�̘_�x�ɂ����Ďn�܂�A�V���w�҃q�b�p���R�X�̎��]�~�̍l�������āA�v�g���}�C�I�X�Ɏ����Ċm�����ꂽ�B �@ ���o�r���j�A(���\�|�^�~�A) �@ �Ñ�o�r�����l�́A��n�́A���͂��m�Ɉ͂܂�Ă��āA���̑�m���܂�������ǂň͂܂�Ă���A���̏��a���^�̓V�䂪�A�[�`��ɂ������Ă���ƍl���Ă����B�V��̓����͐^���Âł��肾���̖�̐��E�ł���A�V��̓��Ɛ��ɂ́A���ꂼ�ꌊ���J����Ă���A���z�⌎�͂������o���肷�邱�ƂŁA���Ɩ邪�J��Ԃ������̂ƍl���Ă����B �@ ���G�W�v�g �@ �Ñ�G�W�v�g�l�́A�n���͐A���ł������ĉ�����鏗�_�Q�u�̎p�ł���ƍl���Ă����B�����āA�V�̐_�k�g�́A�̂�܂�Ȃ��đ�C�̐_�Ɏ����グ���Ă�����̂ƍl�����Ă����B���z�̐_���[�ƌ��̐_�́A���ꂼ���̏M�ɏ���āA�����A�V�̃i�C����������Ď��̈łɏ����Ă������̂ƍl���Ă����B �@ ���}���E�A�X�e�J �@ �}���E�A�X�e�J�l�́A���̐��́A���Ɉ͂܂ꂽ�~�Տ�̌ł܂�ƌ��Ȃ��Ă����B���̉~�Տ�̌ł܂�����͂ސ��́A�V�ƈ�̂ɂȂ��Ă���A4�����Ő_�X�̍����グ���r�Ŏx�����Ă����B�V��E�́A13�E���琬�藧���Ă���A�����ɂ͘f���E���E��E�Í����ے�����h���S�����Z��ł����B�܂��A�n���E�́A9�E���琬�藧���Ă����B���҂́A���O�̍s���ɉ�����9�̂����ꂩ�ɍs���A9�Ԗڂ̊E�ɍs���Ɩ��ƂȂ���ł����B�����ɂ���푈�Ŏ��˂A�V���ɍs�����Ƃ��o���邱�ƂɂȂ��Ă����B �@ �����_�� �@ �N���A�삪����A�R��C�������n�����E�̒��S�ɂ���B��n�̎��͂͊C�ň͂܂�A���̊C�̊O���A��C�̂���ꏊ�ƂȂ��ꏊ�̋����V�ł���B��n�̉��ɂ͐�ɒʂ��鉺�E�̐�(�n���̊C)������A����ɂ��̉��ɃC���t�F���m������B�V�̉����͕��̒������ł���A����͏�E�̐��E��E�q���E�̒������ł���B�����Ă��̏����V�������Ă���B |
|
|
���L���X�g��(���_����) / �����E�n���L(�V������)
�@ 1: 1 ���߂ɁA�_�͓V�n��n�����ꂽ�B �@ 1: 2 �n�͍��ׂł����āA�ł��[���̖ʂɂ���A�_�̗삪���̖ʂ��Ă����B �@ 1: 3 �_�͌���ꂽ�B�u������B�v�������āA�����������B �@ 1: 4 �_�͌������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B�_�͌��ƈł��A �@ 1: 5 ���𒋂ƌĂсA�ł��ƌĂꂽ�B�[�ׂ�����A�����������B���̓��ł���B �@ 1: 6 �_�͌���ꂽ�B�u���̒��ɑ��B���Ɛ�����B�v �@ 1: 7 �_�͑���A���̉��Ƒ��̏�ɐ���������ꂽ�B���̂悤�ɂȂ����B �@ 1: 8 �_�͑���V�ƌĂꂽ�B�[�ׂ�����A�����������B���̓��ł���B �@ 1: 9 �_�͌���ꂽ�B�u�V�̉��̐��͈���ɏW�܂�B���������������B�v���̂悤�ɂȂ����B �@ 1:10 �_�͊���������n�ƌĂсA���̏W�܂��������C�ƌĂꂽ�B�_�͂�������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B �@ 1:11 �_�͌���ꂽ�B�u�n�͑����萶��������B��������ƁA���ꂼ��̎������������ʎ����A�n�ɉ萶��������B�v���̂悤�ɂȂ����B �@ 1:12 �n�͑����萶�������A���ꂼ��̎�������ƁA���ꂼ��̎��������������萶���������B�_�͂�������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B �@ 1:13 �[�ׂ�����A�����������B��O�̓��ł���B �@ 1:14 �_�͌���ꂽ�B�u�V�̑��Ɍ��镨�������āA���Ɩ���A�G�߂̂��邵�A����N�̂��邵�ƂȂ�B �@ 1:15 �V�̑��Ɍ��镨�������āA�n���Ƃ点�B�v���̂悤�ɂȂ����B �@ 1:16 �_�͓�̑傫�Ȍ��镨�Ɛ���A�傫�ȕ��ɒ������߂����A�����ȕ��ɖ�����߂�����ꂽ�B �@ 1:17 �_�͂�����V�̑��ɒu���āA�n���Ƃ炳���A �@ 1:18 ���Ɩ�����߂����A���ƈł�������ꂽ�B�_�͂�������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B �@ 1:19 �[�ׂ�����A�����������B��l�̓��ł���B �@ 1:20 �_�͌���ꂽ�B�u�����������̒��ɌQ����B���͒n�̏�A�V�̑��̖ʂ��ׁB�v �@ 1:21 �_�͐��ɌQ������́A���Ȃ킿�傫�ȉ����A�����߂������������ꂼ��ɁA�܂��A�����钹�����ꂼ��ɑn�����ꂽ�B�_�͂�������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B �@ 1:22 �_�͂����̂��̂��j�����Č���ꂽ�B�u�Y�߂�A������A�C�̐��ɖ�����B���͒n�̏�ɑ�����B�v �@ 1:23 �[�ׂ�����A�����������B��܂̓��ł���B �@ 1:24 �_�͌���ꂽ�B�u�n�́A���ꂼ��̐��������Y�ݏo���B�ƒ{�A�������́A�n�̏b�����ꂼ��ɎY�ݏo���B�v���̂悤�ɂȂ����B �@ 1:25 �_�͂��ꂼ��̒n�̏b�A���ꂼ��̉ƒ{�A���ꂼ��̓y�����̂�ꂽ�B�_�͂�������āA�ǂ��Ƃ��ꂽ�B �@ 1:26 �_�͌���ꂽ�B�u��X�ɂ����ǂ�A��X�Ɏ����āA�l�낤�B�����ĊC�̋��A��̒��A�ƒ{�A�n�̏b�A�n�����̂��ׂĂ��x�z�����悤�B�v �@ 1:27 �_�͌䎩���ɂ����ǂ��Đl��n�����ꂽ�B�_�ɂ����ǂ��đn�����ꂽ�B�j�Ə��ɑn�����ꂽ�B �@ 1:28 �_�͔ނ���j�����Č���ꂽ�B�u�Y�߂�A������A�n�ɖ����Ēn���]�킹��B�C�̋��A��̒��A�n�̏�������������ׂĎx�z����B�v �@ 1:29 �_�͌���ꂽ�B�u����A�S�n�ɐ�����A��������Ǝ��������������A���ׂĂ��Ȃ������ɗ^���悤�B���ꂪ���Ȃ������̐H�ו��ƂȂ�B �@ 1:30 �n�̏b�A��̒��A�n�����̂ȂǁA���ׂĖ�������̂ɂ͂��������H�ׂ����悤�B�v���̂悤�ɂȂ����B �@ 1:31 �_�͂�����ɂȂ������ׂĂ̂��̂��䗗�ɂȂ����B����A����͋ɂ߂ėǂ������B�[�ׂ�����A�����������B��Z�̓��ł���B �@ 2: 1 �V�n�����͊������ꂽ�B �@ 2: 2 �掵�̓��ɁA�_�͌䎩���̎d������������A�掵�̓��ɁA�_�͌䎩���̎d���𗣂�A�����Ȃ������B �@ 2: 3 ���̓��ɐ_�͂��ׂĂ̑n���̎d���𗣂�A�����Ȃ������̂ŁA�掵�̓���_�͏j�����A���ʂ��ꂽ�B �@ 2: 4 ���ꂪ�V�n�n���̗R���ł���B��Ȃ�_���n�ƓV��ꂽ�Ƃ��A �@ 2: 5 �n��ɂ͂܂���̖��A��̑��������Ă��Ȃ������B��Ȃ�_���n��ɉJ��������ɂȂ�Ȃ���������ł���B�܂��y���k���l�����Ȃ������B �@ 2: 6 �������A�����n������N���o�āA�y�̖ʂ����ׂď������B �@ 2: 7 ��Ȃ�_�́A�y(�A�_�})�̐o�Ől(�A�_��)���`�Â���A���̕@�ɖ��̑��𐁂������ꂽ�B�l�͂������Đ�����҂ƂȂ����B �@ 2: 8 ��Ȃ�_�́A���̕��̃G�f���ɉ���݂��A����`�Â������l�������ɒu���ꂽ�B |
|
|
�����{
�@ ������u�����ݐ_�b�v�ɂ�����F���ρE���E�ρB�������A���{���I(720)�ƌÎ��L(712)�ł́A��舵�������قȂ��Ă���B����ɂ��ẮA�V��l���͂����q�ׂĂ���B �@ ���{���I�̐_�b�ƌÎ��L�̐_�b�Ƃ̊W�ɂ��āA�ЂƂ��ƌ����Ă����܂��傤�B �@ ���{���I�́A�䂪���ŏ��̊���̗��j���ł��B�_�b�̕��������j�Ƃ͌����܂��A�_���V�c�ȉ��̗��j���q�̓��ɒu����Ă��܂��B �@ �����ē��{���I�Ҏ[�҂́A����ꗬ�̊����ł���A�m���l�ł����B�����Ƃ��ē���̍s���������̍쐬�Ɍg������A�m���l�Ƃ��āA��ɒ����̕�����Ɛ肵�A�g�ɂ��Ă��܂����B���ߍ��Ƒ��n���̍��ƓI�v���W�F�N�g�ɔ��F����܂����B �@ �ł�����A�`���𗝉����āA���͂Ƃ��Đ��m�Ɏc���\�͂�����܂����B�ڂ̑O�ɂ��鎖���d���A��ςɑ���Ȃ��m��������܂����B�����炱���`���d���A�{���ƈقȂ�����A���邢�͖�������`���ł��A�ꏑ(����ӂ�)�Ƃ��āA������Ǝc���܂����B �@ ���{���I�ɂ́A���������q�ϐ�������܂��B�����Ė{���́A���{���I�Ҏ[�҂��̗p�����A�_�b�̌����I������߂ł��B����ȏ�̌��Ђ́A���ƓI�ɂ͂������A���Ԃɂ�����܂���ł����B �@ ����ɑ��Î��L�́A����1�l�̌Î��L���C�^�[���쐬�������̂ɂ����܂���B�Î��L���C�^�[�̕Ȃ́A�Î��L�̕��͂̂�����Ƃ���Ɏc����Ă��܂��B���̕Ȃ�c������A�Î��L�̉��l���]���ł��܂��B�Î��L�̉��l�́A�Î��L���C�^�[�̕��͍쐬�\�͂�����ɁA�傫����肩�����Ă��܂��B�Ƃ�����Ύ�ςɕ肪���ȏ����ł��B �@ ���āA���{���I�́A���E�̐������A�A�z�_�Ƃ��������N�w�̎蕨�������Đ������邱�Ƃ���n�܂�B�����āA�V�ƒn�������āA���̒��Ɂu�_��(����)�v�����܂ꂽ�Ƃ���(���{���I��1�i)�B���R�̒��ɐ_�����܂ꂽ�Ƃ����v�z�ł���A���̓_���{���I�́A�_�b�炵���ƌ����邾�낤�B �@ ���ÁA�V�n����������Ă��Ȃ����A�����Ă܂��A�z���ʂ�Ă��Ȃ��������A�ӓׂƂ��Ă܂�Ō{���̂悤�Ɍ`����܂��Ă��Ȃ����A���R�̋C���W�܂��ĕ��̒������܂܂��悤�ɂȂ����B���̐����P���Ă�����̂͂��Ȃт��ēV�ƂȂ�A�d�������Ă�����̂́A�ς���ł܂��Ēn�ƂȂ������A�����P�����̂͏W�܂�₷���A�d�����������̂͌ł܂������B������V���܂������āA�n�͌�ɒ�܂����B�����Ă��̌�ɐ_�����܂ꂽ�B�����玟�̂悤�ȓ`��������A�V�n�����܂�鏉�߁A���y���܂�������Y���l�́A�Ⴆ��ƗV��������ŕ����Ă���悤�������B���̎��ɓV�n�̒��ɁA��̕����������B���̌`�͈��̉�̂悤�������B����͐_�ƂȂ����B�������헧�����ɂ̂Ƃ������݂̂��Ƃƌ����B���ɋM�����Ƃ���Ƃ����B����ȊO�͖��߂��Ƃ����B���ɔ������݂��Ƃƕ\���B�ȉ��S�Ă���ɏ]���B���ɍ����Ƒ����ɂ����݂̂��ƁB���ɖL�Οّ��Ƃ悭�ނʂ݂̂��ƁB���킹�ĎO���̐_�����܂ꂽ�B�ޓ��͗z�C�݂̂Ő������B����䂦�ɏ����Ȓj�Ƃ��Đ������B �@ �������Î��L�{���`���́A�����Ȃ�A �@ �u�V�n���߂����߂�ᢂЂ炯�����v�A�u���V�������܂̂͂�v�Ɂu�V�V�䒆��_���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂��݁v�u����������_�����݂ނ��Ђ̂��݁v�u�_�Y�����_���݂ނ��Ђ̂��݁v�����������Ƃ��Ă���B�����Ă����3�_�́A�u�Ր_�ЂƂ肪�݁v�ƂȂ��Đg���u誂����v�Ƃ����̂��B �@ �����āu���ɁA���t�킩�������������Ԃ�̔@�����ĊC�����炰�Ȃ��Y�ւ鎞�v�A�F���u���z�d�����筐_���܂��������тЂ����̂��݂ƓV�V�헧�_���߂̂Ƃ������̂��݂������B����2�_�͓V���x����_�ŁA������Ր_�ƂȂ��Đg���B�����B �@ �����ɂ����ˁB�L�������킹�ʑ�O��Ƃ��č��V���Ƃ������E�ƍ���������_�����݂ނ��Ђ̂��݂�3�_�������Ă���̂��B���́A���V���ƍ���������_�����݂ނ��Ђ̂��݂�3�_���A�Î��L�̓����ł��萢�E�ςȂ̂��B �@ �����œ��{���I��U��Ԃ��Ă݂�ƁA���{���I�{���́u�V�v�Ƃ������E�ς��̗p���A�u���V���v�Ƃ����}�C�i�[�Ȑ��E�ς͍̗p���Ă��Ȃ��B�Î��L�͂ǂ����B�ǂ����A�u�V�V�헧�_���߂̂Ƃ������̂��݁v�Ƃ����A�u�V�v�Ƃ������E�ςɓo�ꂷ��_���o�������Ȃ�����A�����ɁA�u���V���v���E�ς�`���ɂ��������Ƃ����̂��^���̂悤���B�@�����Ă݂�A2�̐��E�ς����Ԃ��Č���Ă���B�Î��L���C�^�[�́A���炩�̗��R�ŁA���V����3�_�����������������Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B �@ ���{���I�ł́A�����āA �@ �d�d���v�Ŕ����̐_�����ꂽ�B�A�z�̋C����ɂȂ��Č��ꂽ�B����䂦�j�_�Ə��_�����ꂽ���헧�����ɂ̂Ƃ������݂̂��Ƃ���A�ɚ����������Ȃ��݂̂��ƁE�ɚ��f�������Ȃ݂݂̂��ƂɎ���܂ł��A�_�����ォ�݂̂�ȂȂ�ƌ����B �@ �ɚ����������Ȃ��݂̂��ƁE�ɚ��f�������Ȃ݂݂̂��Ƃ͓V�������܂̂����͂��̏�ɗ����āA���ɑ��k���āA�u���̉��̕��ɂǂ����č����Ȃ��̂��낤���v�ƌ����āA�V�V�������܂̂ʂق������́A�ʂ̂��ƁB������ʂƓǂށB�����w�����낵�đ~���T���Ă݂��B����Ƃ����ɐC�������邱�Ƃ��������B�����Ă��̖��̐悩��H���������A�Â�ł܂��Ĉ�̓��ɂȂ����B����𖼕t�����f�I�����̂��낵�܂Ƃ����B �@ ����A�Î��L�ł́A �@ �u�V�_���������̖��݂��Ƃ����āv�A�Ɏדߊ�_�����Ȃ��̂��݂ƈɎדߔ��_�����Ȃ݂̂��݂ɁA�u���̕Y�ւ鍑���C�ߗ�����łߐ����v�Ɩ��߂��A�u�V�̏������܂̂ʂق��v��^�����B������2�_�́A�V�̕����ɗ����ēV�̏������܂̂ʂق��Łu�d���������낱����Ɂv���������Ĉ����グ���B���̎��H�藎���������ł܂��āA�u�ɔ\��C�����̂��낵�܁v�ƂȂ����B �@ �Î��L�ł́A2�_�́A�u�V�_�v�ɖ������Ă��̍�Ƃ����Ă��邪�A���{���I�{���ł͂���Ȗ��߂͍s�Ȃ��Ă��Ȃ��B �@ ���̌�́A���{���I���Î��L��2�_�ɂ��u�����݁v�̃n�i�V�ƂȂ�B �@ �Ƃ���ŁA���{���I���Î��L���A�l�Ԃ̔����ɂ��Ă͉�����낤�Ƃ��Ă��Ȃ��B���S�ł���B��ʂ̐l�X�́A�P�Ȃ�J���͂Ƃ����l�����Ă��Ȃ����̂悤���B���Ɋւ���`�����A�ق�̒f�Ђ����邾���B�v����ɁA���̌��͎҂��쐬�����A���̌��͎҂ɂƂ��Ă̐_�b�ł����Ȃ��̂��낤�B�����������E������B�_�b�𖼏��̂ł���A���̐��E��l�Ԃ����ǂ̂悤�ɔ��������̂��A�V�ƒn�Ƒ��z�ƌ��Ɛ������ǂ̂悤�ɂł����̂�������Ăق������̂��B��X���Ȃ����̐��E�ɂ���̂�������Ă����A�_�b�Ƃ������̂ł͂Ȃ����낤���B �@ �X��F���ɂ��A �@ ���{�l�̍l����u�_�v�͐l�Ԃ𗝑z�����邢�͔����������̂��A�����łȂ�����M����Ȃ����̂��Ƃ������Ƃł��B����͂��̎R�A���̐X�A���̐�A���邢�͂��̊C���X�A�����鏊�ɋ��āA�_�b�̎���ɂ��łɁu���S���v(�₨��낸)�ƕ\������Ă����̂ł��B���Ɂu���V�����v�������ʂ�V�̍����Ƃ���ɂ���ƍl����ꂽ�Ƃ��Ă��A�����͒n��́u���v�Ɩ{���I�ɂ͈��Ȃ��Ƃ���ł���A�����ɏZ�ސ_�X�͐l�ԂƓ��l�̐��������Ă����̂ł��B���{�l�̑z���͂ɂ������Ƃ����l�����Ȃ������̂ł����āA���z�I�Ȑ�Ύ҂���L����Ƃ���́A�l�Ԃ��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ԂƂ��Ắu�V�v�����݂��邱�Ƃ����v�������Ȃ������̂ł��B �@ �r�쎁(�É���w)�́A�����u���{�l�̉F���ρv�ɂ����āA�Î��L����ѓ��{���I�̒��Łu�_�b�I�ł���Ȃ���Ǝ��̉F���ς����肾����Ă����v���ƁA�����Ă��ꂪ�͂邩�Ȍ㐢�̎v�z�ɂ����������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������Ȃ��玟�̂悤�ɂ������܂����B �@ ���̈���ŁA���{�l�̊�͓V��̐��E�����n��̎��R�ɒ�����Ă����B���l�ŁA�G�߂ƂƂ��ɑ��ʂȕω����݂��镗�y�̂Ȃ��Ő��������Ă�������ł��낤�A���t�W�ł͌��͉r(����)���Ă��A������̂͐�����قǂ����Ȃ��A�قƂ�ǂ��n��̎��R���r�������̂ł���B�Î��L�E���{���I�̕`���u���V�����v���A�R�삪���葐�̂�����n��I�ȋ�Ԃł������B���̎��R���s���������B���R�͉r���Â��A���R�I�ȉF���Ƃ̈�̉��𗝑z�Ƃ���v�z�����肩�����o�������̂ł���B �@ �Ō�̃Z���e���X����킩��悤�ɁA����͌Ñゾ���Ɍ��肳���b�ł͂���܂���B�����Ă����ɂ͑������d�v�Ȏ����������̂������Ă��܂��B���̈�́A���{�l�ɂƂ��ẲF���͒n��̎��R�̉�����̂��̂ł����āA�����̊Ԃɕs�A��������Ƃ͍l���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �@ �u���͉r���Ă��A������̂͐�����قǂ����v�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����ɍL���闤�ƊC���������{�l�̊S���������R�E�ł������Ƃ������Ƃ̔��f�ł��傤�B����ł����͑��z�Ɏ������邭�傫���V�̂ł��邵�A����ɖ���㞂��Ƃ������I�ȕω��������A����ɊC���̊����Ƃ������֘A���A�܂������̐����Ƃ����W������悤�Ɍ�����قǂŁA�l�̊S��~�����Ă�v�f�𑽂������Ă��܂��B����ɑ��Đ��́A1�N�������Ƃ���P���̊ɂ₩�ȓ����ƁA���̘f���̈ꌩ�s�K���ȓ��������邾���ŁA������x�̌`����w�I�l�@�����Ȃ���Γ��퐶���Ƃ̊W������悤�ɂ͌����܂���B����ŁA�������{�l�̊S�������������Ƃ͂Ȃ������̂ł��B�@�@ �@ |
|
| ������(����)�̉F���ρu�{��R�Ƃ́v | |
|
�����ł́A�����ɂ�镧���̉F���ς��Љ�����Ǝv���܂��B���͌��z���ɂ����̉F���ς����f����Ă���̂ł��B �����ē������ꂪ�Ȃɂ��Ȃ��g�����t��n���ɂ������A���̉e�����c���Ă���̂ł��B�����ɂ͂��܂��܂Ȍo�T�⌾�t�����邪�A���ǂ͗։�(����)�Ɖ�E(������)��2�̎v�z�ɂ��������̂ł��낤�B��E�Ƃ͗։��Ẳ�E�ł���B�։�Ɖ�E�̗�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����]���̕����̉�����́A�����Ă��͉�E�Ɋւ�����̂ł������B�����F���ς̑̌n������������1�ɃC���h5���I�̕��m���@�X�o���h�D�́u��ɘ_(��������)�v������B���̒��́u���i(���ق�)�v�Ƃ���1�͂ɂ�����{��R(����݂���)�����q�ׂ��Ă���B
�@ ���̉F���ς����{�Ɏ�����Ă���A���{�e�n�ɂ��̉F���ςɂ��₩������������ꂽ�B�{��R�Ƃ��A�n���J�Ƃ��A��Ƀ����Ƃ������O������ł���B���Ƃ��A�Ȗ،��̗�R�u��r(�ӂ���)�R(����)�v(�j�̎R�̂���)�́A���̗ގ�����ω��̏�y�u��ɗ��E���ɗ�(�ӂ��炭)�R(����)�v�Ƃ���A�����u��r(�ɂ���)�v�������I�ȁu����(�ɂ�����)�v�ɏ���������ꂽ�Ƃ����B �@ ���ɗ��R���邢�͕��ɗ��Ƃ́A�C���h�̓�C�݂ɂ���A�ϐ�����F�̏Z���Ƃ����R�̂��ƁB�{��R�Ƃ����̂́A�����F���ςɏo�Ă���n���I�ȎR�ł���B����͋���̒��ɕ���(�ӂ����)�Ƃ������̂�������ł���̂ł���B�`�͉~�Տ�ő傫���͎����Ȃ��قǑ傫���B���̏�ɓ������~�Տ�̐���(�������)���ڂ��Ă���B���ւ̑傫���́A���a��120��3450�R�{(�䂶���)������80���R�{�ł���B���̐��ւ̏�ɋ���(������)���ڂ��Ă���B���ւ̑傫���́A���a�͐��ւƓ���120��3450�R�{�ŁA������32���R�{�ł���B���֏�̕\�ʂɎR�A�C�A���Ȃǂ��ڂ��Ă���B �@ 1�R�{����7�L�����[�g�� �@ ���ɊȒP�ɂ��Ƃ�����A���ցA���ցA���ւ��d�Ȃ�����̓I�ȃC���[�W�Ƃ��Ă͂��炢���āA���̏�ɕ��C�����āA���̕��C���̏�Ƀo�[�X�f�B�E�P�[�L���ڂ����p���v�������ׂ�Ƃ悢�B �@ ���ւƋ��ւ̂������߂͋��֍�(������)�ƌĂ�A�u�������֍ۂ������܂���v�Ƃ����悤�ȕ\���Ɏg����B�܂�u���֍ہv�́A�u�^��v�u�O��I�v���Ӗ����Ă���̂ł����āA���֍ۂ̈�p�ɂ��މ�X�ɂƂ��ẮA���֍ۂ��^�̒�Ƃ����킯���B �@ ���ւ̏��9�̎R������B�����ɍ������т����̂��{��R�ł���B�{��R���Ƃ�܂����S���`�̎R(�R��)��7����B���Ȃ킿���S�~�ł͂Ȃ��l�p�`�ł�����7�̎R�����{��R���Ƃ�܂��Ă���B �@ �{��R���Ƃ�܂��l�p�`�̎R���́A�Ȃ�ƂȂ��s���~�b�h��A�z���Ă��܂��B�����ł͂����������E�E�ّ��E����䶗��ł���킵�Ă��܂��B�@�@�@�@�@ �@ ���֏��8�̉�L��̊C������B�O�q�̉�L��̎R���̊Ԃ��A���ꂼ��C�ɂȂ��Ă���̂��B������7�͒W���̊C�ŁA�O�̑傫�Ȃ̂������̊C�ł���B �@ ���̉����̊C�̒���4�̓���������ł���B4�̓��݂͂Ȍ`���Ⴄ�B���̓��͔����`�A��̓��͑�`�A���̓��͉~�`�A�k�̓��͐����`�ł���B �@ �����ł͓�̓������Љ��B��̓��͌`����`�Ƃ����Ă��قƂ�ǎO�p�`�Ƃ����ׂ���`�ł���B��ӂ�2000�R�{�A���ӂ�3�D5�R�{�A�Εӂ����ꂼ��2000�R�{�ł���B���̓�̓��A�֕��B(����Ԃ��イ)���A��X�̏Z�ސl�ԊE�ł���B �@ �Ȃ�ƁA���̎O�p�`�ɋ߂���`�̓��́A���̓C���h���嗤�̌`�ɂ��ƂÂ������̂ł���B����́A���̓��̂��낢��̓�����������f�ł���B �@ �܂��A���̖k���ɐ�R������B����̓q�}�����̂��Ƃł���B���̐�R�̖k�ɒr(���M�Y�r)������A���̒r���K���W�X�́A�C���_�X�́A�I�N�T�X�́A�V�[�^�[�͂̋��ʂ̌��ɂȂ��Ă���B �@ �����A���݉�X�̒n�}�ł́A����4�͓̉͂���̌���͗���Ă��Ȃ��B�������A����4�̉͂̂��ꂼ��̏㗬����������ƁA����炪�قڌ����_��1�̑傫�Ȍ�����B�}�i�T��������(�`�x�b�g���@�}�p��)�ł���B �@ ����������Ɛ̂̓}�i�T���������傫���āA�{����4�̉͂̋��ʂ̌��ɂȂ��Ă����̂�������Ȃ��B �@ �����Ă��̏@���I�F���ς́A���̉F���̂ǂ����ɒn���������Ă���B �@ �n���̓C���h�̌��t�u�i���J(naraka)�v�̈Ӗ�ł���B�����������ɓ���O�A�u�n���v�Ƃ������t�͒����ɂ͂Ȃ������B�i���J�̉���͓ޗ��ށA�ޗ�(�Ȃ炭)�ł���B�i���J�𒆍���ɖ|���Ƃ��n���Ƃ������t���ł����B �@ ������A����̏����̓ޗ��Ƃ��Ďc���Ă���B �@ �n���̐��A��ށA�傫���Ȃǂɂ��āA���܂��܂Ȍo�T�����܂��܂̐����q�ׂĂ���B�����ł́u��ɘ_�v�𒆐S�ɐ�������B �@ �܂��A���M�n��������B����8�̒n���͏d�Ȃ肠�����֕��B(����Ԃ��イ)�̉��ɑ��݂���B�ォ�炻�̖��O���L���Ă����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@ �����Ƃ����@ Samjiva �@ ���ꂱ�����傤�@ Kalasutra �@ �O�����ゲ���@ Samghata �@ �����������傤�@Raurava �@ �勩�������傤�@Maharaurava �@ ���M����˂@ Tapana �@ ��M�����˂@ Pratapana �@ ���Ԃނ���@ Avici �@ ����炻�ꂼ�ꗧ���̂��Ȃ��āA�c�ɐςݏグ���Ă���(�n���[���w���Ȃ��Ă���)�B �@ �ŏ㕔�́u�����n���v�Ƃ����̂́A�ߐl���ӂ߂����Ȃ܂�Ď���ŁH���A�Ăт�݂������Ďb���̐����������𖡂키���Ƃ��ł���n���ł���A���̓_�ŁA��u�̋x�݂��Ȃ������Ȃ܂�Â���ʼn��w�̒n���u���Ԓn���v�ƑΏƂ��Ȃ��B�u���ԁv�Ƃ����̂́A�u�ꂵ�݂��Ԓf�Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B �@ �n���͂���ŏI���ł͂Ȃ��B�ǂ̔M�n�����l�ǖʂ�1����������Ă��āA1�̖傲�ƂɎ��ɂ�����4��̕��n�������Ă���B���M�n���S�̂ł͌���128�̕��n���������ƂɂȂ�B�@8*16=128 �@ ��(�Ε�)��(�Ε�)(�Ƃ���)���n�� �@ ����(���ӂ�)���n�� �@ �N�n(�ق�����)���n�� �@ ���(�����)���n�� �@ ��(�Ε�)��(�Ε�)���n���ł͔M�����D�̒����������A�������n���ł͎��̂ƕ��̓D���ɂ���A�E�W���ɍ�����������A��������Ԃ���B �@ �n���͂܂��I���ł͂Ȃ��B����ɔ����n���Ƃ������̂�����B������֕��B�̉��A��n��(�M�n��)�̂������ɂ���Ƃ����B���̎�ނ͎��̂Ƃ���ł���B �@ ��(���ɕ�)���Ɂ@���Ԃ� �@�@�@�@ Arbuda �@ ��h���Ɂ@�ɂ�Ԃ� �@�@�@�@�@�@�@Nirarbuda �@ ��(���ɕ�)��(����)�Ɂ@������ �@Atata �@ �(���Â�)�(���Â�)�k�@������ Hahava �@ �ՌՔk�@������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Huhuva �@ ��(����)�����@���͂� �@�@�@�@�@�@ Utpala �@ �������@�͂ǂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@ Padma �@ ���d�������@�܂��͂ǂ� �@�@�@ Mahapadma �@ ��3�A4�A5�̒n���̖��݂͂ȋꂵ�݂̐��̋[����ł���B���Ȃ킿�A�ߐl�͊����̂��߂ɂ��ꂼ��̒n���Łu�A�^�^�v�A�u�n�n���@�v�A�u�t�t���@�v�Ƃ����ߖ�������̂ł���B �@ �����̒n���́A������ɂł������������̂ł͂Ȃ��B�������Ԃ������āA���X�ɍl���o�������̂ł���B�n���Ȃǂ��l�����w�m�́A�����̑m�������Ɍ���Ȃ��B�n���̊ϔO�́A�C���h�l�S�̂ɋ��ʂ̎v�z�I���Y�ł���B�W���C�i���ɂ��q���Y�[���ɂ�������������̒n���̃��X�g������B �@ �I�[�X�g���A�̃C���h�w�҃��B���e���j�b�c�́A�W���C�i���T�̒n���̃��X�g���u�T�f�B�X�e�C�b�N�v�Ƃ����Ă���B �@ �n�̉��ɒn��������Ƃ���A�n�̏�ɂ͓V�E������B �@ �Ȃ��A�����Łu�V�v�Ƃ����Ƃ��A����́u��vsky �Ƃ� heaven �Ƃ����ꏊ��\�����t�ł͂Ȃ��A���������݂Ƃ��Ă̐_ god ���Ӗ�����Ƃ������Ƃł���B���Ƃ��Β�ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�Ƃ����V(�ڂ�Ă�)�Ƃ����悤�ɁB �@ �u�V�v�̌���� deva �ł���B����̓��e����� deus �Ɠ������t�ł���B2�̌���͂Ƃ��ɃC���h�E���[���b�p��ɑ�����B �@ �u�V�v���_���Ӗ�����̂ɑ��āA�u�V�E�v�͋�Ԃ��Ӗ�����B �@ ���āA���т��������V������B�����̐��E�ς͑��_���ł���B �@ �܂��A���E�ɏZ�ޓV�Ƃ��̏Z������������Ă������B�{��R�́A����ɏo�Ă��镔���͐������̂ŁA�ǂ̕ӂ�����8���R�{�ł���B���̗����̂̉��������l�V���Ƃ��̎艺�����̏Z�݂��ł���B �@ ���̏Z�݂��͂����4�K���Ăł���B���ʂ���1���R�{�̍����̂Ƃ���ɁA�l���ɒ���o�������F�����_�̂��Ƃ����̂�����B1��6��R�{���Ƃ֒���o���Ă���Ƃ����B �@ ���̃��F�����_����A�����1���R�{�������Ƃ���ɁA���̃��F�����_������B�����8��R�{�������Ƃ֒���o���Ă���B �@ �����1���R�{�������Ƃ���ɁA���̃��F�����_�������āA4��R�{��������o���Ă���B �@ �����1���R�{�������Ƃ���ɁA���̃��F�����_�������āA2��R�{����o���Ă���B �@ ��̃��F�����_�قǓ��ւЂ�����ł���̂́A����������Ă���u���ƌ��v�̖���A�z�����Ėʔ����B �@ ��ԏ�̃��F�����_�ɂ͎l��V(�l�V��)�Ƃ��̐g�����Z��ł���B�l�V���Ƃ́A�����̎����V�A��̑����V�A���̍L�ړV�A�k�̑����V(������V)�ł���B �@ �l�V���̎艺�����̏Z�݂��́A����3�̊K�ł���B�������A�ނ�̎艺�����͂��̂ق��ɁA���o�R�Ȃ�7�̎R����A���z�⌎(�{��R�̒����Ɠ�����������]���Ă���)�Ȃǂɂ��A�����Ă���B �@ ���ɐ{��R�̒���Ɂu�O�\�O�V�̏Z�݂��v������B�{��R����̒����Ɂu�P������v�Ƃ������̓s�邪����B��ӂ̒���2500�R�{�̐����`�ŁA����1�R�{���ł���B�����͋��łł��A�n�ʂ͖�(�_�H)�̂悤�Ȃ��̂łł��Ă���B �@ ���̓s��̒����Ɏꏟ�a(���サ�傤�ł�)�Ƃ����A��ӂ̒���250�R�{�̐����`�̋{�a������B��X�̕�ŏ��藧�Ă��A���̘O�t�̒Ǐ]�������Ȃ��B���̎ꏟ�a�����O�\�O�V���̑��l�ҁA��ߓV(�������Ⴍ�Ă�)�̏Z�݂��ł���B �@ ����܂łɓV��A�n��A�n���̐��E����������B�����܂ł͑��̏@���I�F���ςƋ��ʂ���_�������ł��낤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ �������̕����I���E�ς�m��ƁA����ɁA���̋����͂ǂ����Ƃ����^�₪�����悤�B�u�����y�v�͂ǂ����B���́u��ɘ_�v�̉F���_�ɂ́A�u�����y�v�Ƃ������̂͂Ȃ��B����͑�敧���̐��ݏo�����ʂ̊ϔO�ł���B�@�@�@�@�@ �@ ����ł́A�u��ɘ_�v�̉F���_�ł́A���͂ǂ��ɂ���̂��B�����炭�A���F�E�̂���ɏ�ɂ���̂ł��낤�B�Â��{��R�}���݂�ƁA���͖��F�E�̏�ɕ`����Ă���B�������A�������͖��F�E�Ɠ��l�A���̐��E����Ԃz���Ă���ƍl����ׂ��ł��낤�B �@ ���܂܂ŏq�ׂĂ����~�E�A�F�E�A���F�E���܂Ƃ߂āu�O�E�����v�ƌĂԁB�܂�A�L�����������O��̐��E�ł���B�u�O�E�v�́u�S�F���v�Ƃ����悤�ȈӖ��ł悭���ɗp������B�u�q�͎O�E�̎��v�Ƃ��u�O�E�ɉƂȂ��v�Ƃ������悤�ɁB �@ �����I�F���ς̒�𗬂�Ă�����̂́A�ƂƗ։�̎v�z�ł���B�։�Ƃ������t�́A�����鐢�E�ł̐����̂��肩�������Ӗ�����B�����̂��肩�����́A5�킠�邢��6��̐�����Ԃ̊Ԃōs����B �@ �u�Z���낭�ǂ��v(6�̖����鋫�E)�A���Ȃ킿�n���A��S�A�{���A�l�ԁA���C���A�V��6��ނ̐��E��������B�@�@�@ �@ �u���܂ꂩ���v�̎v�z�̓u�b�_�̓`�L�ɂ����f���Ă���B���͉��x���O�������肩�����A�C�s����Ŋ����҂Ƃ��Č����̂��B���T�̂����ɑO������(�{���)�Ƃ����̂����邪�A����͕����O���łǂ̂悤�ɐ��X�̌����������q�ׂ����̂ł���B����ɂ��ƁA���͑O���ʼn��⎭�ɂȂ��Đ��܂ꂽ���Ƃ�����B �@ �։�̎v�z�ƂƂ��ɏd�v�Ȃ̂́A�Ƃ̎v�z�ł���B�Ƃ̓C���h�̌��t�J���}�܂��̓J���}���̖��ł����āA�u�s�ׁv���Ӗ�����B�����āA����ƂƂ��ɂ��̍s�ׂ̂��e���͂��������B�s�ׂƂ����Ă��P�ɐg�̂̍s�ׂ����łȂ��A����s�ׂƐ��_�s�ׂ��܂܂��B�܂��e���͂Ƃ����̂��A�P�Ɉꐶ�̊Ԃ����肤��e���͂����łȂ��A�����ɂ܂łÂ��e���͂��܂܂��B �@ �Ƃ̍�p�͎����I�ɓ������̂ł���B�����Đ_�̂��Ƃ��ْ�҂̉����K�v�Ƃ��Ȃ��B�悢����������A�悢���ʂ����܂�A��������������Έ������ʂ����܂��B����͎��R�@�I�Ȗ@���ł���B �@ ���Ǝ����Ƃ������t�����邪�A����͎����������Ȃ����s�ׂ̌��ʂ���������A�Ƃ������Ƃ�\���Ă���B������A�����ł́u��������v�Ƃ��u�n���ɂ��Ƃ����v�Ƃ��͌���Ȃ��B�u����v�̂ł���A�u�n���� ������v�̂ł���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@ ���܂ŏq�ׂĂ����F���ς́A��Ɂu��ɘ_�v�ɂ��ƂÂ������̂ł���B���������́A�n���ƋɊy��ɂ���(�Z�b�g�ɂ���)�l���Ă���B�������A�n���Ɋւ��Ă���قǏڂ����q�ׂ��u��ɘ_�v�́A�Ɋy�ɂ��Ă͈ꌾ�������Ă͂��Ȃ��B�n���ƋɊy�Ƃ́A��X���z���������̂悤�ȁA�ŏ�����ōl�������ꂽ���̂ł͂Ȃ��̂��B �@ �Ɋy�̐������͂��߂�܂��ɁA�܂��u�O�k���E�v��������Ă������B�O�k���E�Ƃ́A��X�̏Z�ނ��̐��E�������A�߉ޏo���̕���ƂȂ�A���������̑ΏۂƂȂ������E�ł���B �@ ���Ɂu�����y�v���������B�F���ɂ͂�������̕������āA���ꂼ��ŗL�̍��y�����L���āA�����ɂ������Ă���B���̍��y�́u���y�v�Ƃ��u��y�v�Ƃ��Ă��B �@ ���̑�\�I�Ȃ��͖̂�t�@���́u��ڗ����E�v�A����ɔ@���́u�Ɋy��y�v�ł���B�܂����y�ł͂Ȃ����A���y�Ɏ������̂Ƃ��āA�ω���F�́u��ɗ�(�ӂ��炭)�R(����)�v(�C���h�̓���C���ɂ���Ƃ����)������B �@ �����̏�y�̒��ŁA�̂��ɒf�R�L���ɂȂ�̂��Ɋy��y�ł���B �@ �u���y�v�͑�敧���ɂ����Đ��܂ꂽ�T�O�ł���B�u��ɘ_�v�ł́A���łɐ��������悤�ɁA���͎O�E����E�o���Ė��ɋA���Ă���B���̊��S�ɖ��ɋA���邱��(���]���ςނ�˂͂�)���A���敧���̂߂����ō��̋��n�ł���B�ނ�ɂƂ��ẮA�����܂��`��L���A�����y�ɂ����Ċ�������Ƃ������Ƃ͍l�����Ȃ��B �@ �Ƃ��낪�A��敧���ł́A�������͕����y�̌��݂��߂����ďC�Ƃ��A�����y�����݂��������Ȃ�A������O��(���ザ�傤)�������ɓ�������邽�߂ɉi���Ɋ����𑱂���B �@ �ł͋Ɋy��y�͂ǂ��ɂ���̂ł��낤���B�O�E�̒��ɂ���Ƃ����̂ƁA�O�ɂ���Ƃ����̂ƁA2�̐�������B���̂悤�Ɉӌ���������Ă���̂ɂ͗��R������B�O�E�͌ÓT�I�F���ς̐��ł���̂ɁA�����y�͂��̉F���ςɂ͐�����Ă��Ȃ������̂�����B �@ �������A�O�k(�l�ԊE)����̋Ɋy(�{��R�̒���)�̋����Ɋւ��ẮA�u16��8��R�{(�R�{����7�q)�v�Ƃ�����v��������������B�@�@�@�@ �@ �Ɋy�Ƃ͂ǂ̂悤�ȂƂ���ł��낤���B�����́A���̖��̎����Ƃ���A�ɂ߂Ċy�����Ƃ���ł���B���̐��̂悤�ȋꂵ�݂͈�Ȃ��B�����āA�����͌����s�����Ȃ��قǔ������Ƃ���ł���B����ŏ���ꂽ�r��O�t������B���������������������������ł��������Ă���B �@ �����āA���̍��ɂ͈���ɕ��Ƃ��̈���ɕ��ɂ�����ω��E�����̓��F�����āA���̂��ƂɁA�M�S�ɂ���Ă����ɐ��܂�ς�����L���̐l����������B�������A�����݂͂Ȓj���ł���B�O���ŐM�S�̂������������������ɐ��܂ꂩ����Ă���̂����A�ޏ���͒j�̎p�ɂ�����Ă��܂��Ă���B�Ƃ����̂́A�����Ƃ����̂͗ŕs�K�Ȑ��ł���̂ŁA�Ɋy�ł͂��ׂĂ��K���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ϓ_����A�����͒j���ɕς����Ă���̂��B �@ ������Ǝ߉ނ͂����B�݂Ȃ��̍��ɐ��܂�悤�Ɗ�����ĂȂ����B�����ł͗L���̐l�����ƈꏏ�ɂȂ��̂�����B�����A���̍��ɐ��܂��̂ɂ́A�킸���ȑP�s�@�ł͑���Ȃ��B���̖���O���āA���X��S�s���ɓw�߂�Ȃ�A���̐l�����ʂƂ��ɁA�߉ނ͂������̐��҂ƂƂ��ɁA���̐l�̑O�ɂ���Ă��Ă����B���̐l�͎��ɗՂ�ł��S�݂���邱�Ƃ��Ȃ��A�Ɋy��y�Ɍ}������̂ł���B�@�@ �@ |
|
| �����{�l�̉F���� / ���]1 | |
|
�{���́A�薼�̒ʂ���{�l�̉F���ς��Ñォ�猻��܂Œǂ������̂ł��B�Ƃ͂����Ă��A���{�l�͉F���ς����甭�W�����Ă����킯�ł͂���܂���B�����ł͂Ȃ��A�O���̐�[�I�ȉF���v�z��3��ɂ킽���Ď���A���̓s�x���{�I�ɏ������Ă����̂ł��B
�@ �O���v�z��e�̑�1��ڂ́A������C���h�̎v�z�����ꂽ����ł��B��2��ڂ́A�|���g�K���l��X�y�C���l�̐鋳�t�ɂ���ăA���X�g�e���X�I�ȉF���̌n�������炳�ꂽ�L���V�^���̎���ł��B��3��ڂ́A���[���b�p�ƃA�����J����ߑ�Ȋw�Ƃ��̉F���ς��ڐA���ꂽ��������ł��B�����ЂƂ̓����Ƃ��āA���{�l�̉F���ς̊�w�ɂ͑�n�I�Ȣ�_��Ƣ���R��̐��_�����ꑱ���Ă����Ƃ������Ƃ��������܂��B�@ |
|
| ����1�́@�l�ƉF�� | |
|
7���I�㔼�A�嗤�ɂ������@�E�����ꍑ�Ƃ̐����A�V���ɂ�锼������̓����Ƃ������ۏ�̉��ŁA���{�������W���I���Ƒ̐��̐������ۑ�ƂȂ�܂��B�����S�����̂��A672�N�p�\�̗��ɏ��������V���V�c�ł��B
�@ �p�\�̗��̂Ƃ��A�V��(�����͑�C�l�c�q)�͋�����_�ɂ��Ď��������Ɠ`�����܂�(�V���ƋC�ۂ������čl������悤�ɂȂ����͍̂ŋ߂̂��Ƃł��B)�B �@ �w���{���I�x�ɂ��A�u�V���v�ɒ����Ă����V���́A���ʂ�4�N��ɓV���ϑ����ł���u�萯�䣂�ݗ����܂��B �@ ���ړI�͐肢�ɂ������̂����A�E�E�E�̓s�œV�c�����悷��g�D�I�ȓV�̂̊ϑ����͂��܂��Ă����E�E�E�B �@ �����̓V���u�[���Ƃ����Ă��悢����ɁA�V���}���`����Ă��������ˌÕ���L�g���Õ��̒z�����Ȃ���Ă����B �@ ���{�̔���Ɍ������ꂽ�����ˌÕ��ƃL�g���Õ��̌����ɂ͓V���}���`����Ă��܂����B �����ˌÕ��̓V���}�͗l���I�Ȃ��̂ł����A�L�g���Õ��̕��͎��ۂ̐��̔z�u�ɏ]���Ă��邾���łȂ��A�V�̐ԓ��A�����A���K�A�O�K��4�̉~���`����Ă��܂��B�V���}�́A�����o�R�œ��{�ɓ`��������̂Ɛ�������܂��B �@ ���Ԃ��r�a�̂��ڂ��Ă��܂��B �@ ����̑ł����ې�(��)����Ύ��ɂ͂Ȃ�ʂ��͂Ȃ������� �@ �ۂ�炵�Ď�����m�点���Ƃ������Ƃł����A�c�O�Ȃ��玄�ɂ͍Ō�̢���͂Ȃ���������̕����������ł��܂���B�@ |
|
| ����2�́@���{�_�b�̉F�� | |
| �r�삳��́A���{�_�b�̉F���ςɂ́A�����̉F�����Ɛ����̉F�����Ƃ�����Ƃ��܂��B�����̉F�����Ƃ́A[�V]���V��(�����܂��͂�)�|�����̒���(�����͂�̂Ȃ�����)�|����̍�(��݂̂���)[�n��]�ł��B����A�����̉F������[��]�o�_�|��a�|�ɐ�[��]�Ƃ������̂ŁA���̏o�Ɠ��v�����ԁu���̉F�����v�Ƃ��Ă�ł��܂��B
�@ �����āA�����\���鍂�V���ƈɐ��A�����\���鉩��̍��Əo�_���C���[�W�I�ɏd�ˍ��킳��邱�ƂɂȂ�܂��B �@ �V�c�Ƃ����ď̂������N���ł��邱�Ƃ͒m���Ă��܂����A���V���������N���ł���A�u�����̒����v�͊���̒������̂��́A�n�����E�u����̍��v�͒����ł������Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B �@ �����̉F���ɂ͑嗤�����̔Z���ȉe�����F�߂��܂��B �@ �w�Î��L�x�w���{���I�x�̑n���_�b�ɂ́A�ێR�^�j�̂����u�Ȃ�v�^�A�u����v�^�A�u���ށv�^�Ƃ����O�̌^�̐_�b����������o�Ă��܂��B �@ �������A�L�I�̑n���_�b�S�̂��x�z����̂́u�Ȃ�v�^�ł��B �@ �����A�L�I�ł͉F���̌����̏�Ԃ�Ⴆ��̂Ɂu��������(���Ԃ�)�v�u�C��(���炰)�v�u����(��������)�v�u�{�q(�Ƃ�̂�)�v�u����(�����Ԃ���)�v�u�C��ɕ����ׂ�_�v�Ȃǂ̕\�����g���Ă��܂��B �@ �u����v�͐������鈯�̉�ł���A�u�{�q�v(��)�͒����̉F���n���_�����������̂ł��B �@ �������A���̑��͈�̉��ł��傤���B �@ ���҂͕��i���i�������āA�����͂�����������A������s�V�s���̂��߂̐���������O(���)�p�̗p�ꂾ�����Ƃ����܂��B �@ �����ł́u�V�v�Ɓu�V���v�̊ϔO�������I�ɂ��d�v�ł����B |
|
|
�������̓`���I�F���_
�@ ��1�D�W�V��(�����Ă�) �@ �����̓`���I�ȉF���ς́A�V�͉~�`�Œn�͕��`(�l�p�`)�Ƃ����V�~�n���̉F���ł����B �@ �V�~�n�����Ɋ�Â��ŌẨF���\���_���A�u�V���n�����ʂł���A�V�͓̂V�ƂƂ��ɓV�̒��S�ł���k�ɐ��̂܂��𓌂��琼�Ɉ���Ɉ��]����v�Ƃ����W�V���ł��B �@ �W�V���̓V�n�́A���������W(����)�����Ă��n�Ԃ⋍�Ԃ̂悤�ł��B �@ �Ñ㒆���̔n�Ԃ⋍�Ԃ̗`(����)�͕��`�ł���A�����ɂ͉~�`�̊W�������Ă��܂����B �@ �W�V���̏ڍׂȉ������3���I�ɐ��������w��鏎Z�o(���イ�Ђ���)�x�ł��B �@ �������A�W�V���ł͌����̓V�̉^�s�����܂������ł��܂���ł����B �@ ��2�D�ӓV��(����Ă�) �@ �����ŁA�㊿����ɐV���ɓo�ꂵ���̂��A�u���ʂ̓V�����̏�ɕ����ԕ��`�̑�n�̂܂�����]����v�Ƃ����ӓV���ł��B �@ �����炭�́A�w(������)�𒆐S�ɉ�]����n�Ԃ⋍�Ԃ̎ԗցA���邢�͐��Ԃ��璅�z���ꂽ�F���̍\���_�Ɛ�������܂��B �@ �㊿�̑��j��(�V���E��@�Ȃǂ��i�銯�E)�ł��������t(���傤����)�́w�ӓV�V�x�̒��şӓV����_���A�u�V�͌{���̂悤�Ȃ��̂ł���A�V�̖{�̂͊ۂ��Ēe�ۂ̂悤�ł���B�n�͌{���̒��̗����̂悤�ł����āA�Ǘ����ē����Ɉʒu����B�v�Əq�ׂĂ��܂��B �@ �ӓV�������Ƃɍ��ꂽ�̂��u�ӓV�V�v�ŁA����͌Ñ�ł����Ƃ����I�ȓV�̊ϑ���B�ł����B �@ �ӓV���̓�_�́A�̓V�̂ł��鑾�z���Ȃ����������ƂȂ���n�̉��̐��̒��ɓ����Ă�����̂��Ƃ������Ƃł����B �@ �������A�ӓV���͂��̌�̒����Ŏx�z�I�ȓV���w���ł��葱���܂��B �@ ��3�D�V���} �@ �V���}�����ꂽ�Ƃ��������̍ŌÂ̋L�^�́w�W���x�V���u�ŁA�W�̕���(�݈�265�`296)�̂Ƃ��A���j�߂̒�(����)���V���}���쐬�����Ƃ����L�q������܂��B �@ �������A��������ŌÂ̓V���}�͑v��1247�N�A�h�B�̍E�q�_�ɐɍ��܂ꂽ���̂ŁA�����ɕ`���ꂽ�̂͐����̈ʒu����1078�`85�N�̊ϑ��Ɋ�Â����̂ł��B �@ �h�B�̍E�q�_�̓V���}�ɂ́A�V�̐ԓ��A����(���z�̓�)�A���K(�k�ɐ��𒆐S�Ƃ����ɒn������Ɍ�����V��̋��E)�A�O�K(�n�����̉��ɉB���Ƃ��͂����Ă����E�ɓ���V��̋��E)��4�̉~���`����Ă��܂��B �@ �����́A�W�V���̉F���_�ŗ������₷���V���w�̊T�O�ł��B �@ ��4�D�u�V�v�Ƃ����T�O�̐��i �@ �����ł́u�V���v�ɂ�艤����オ�s���܂����B �@ �V���邢�͓V���́A�����̌������x�z�𐳓���������̂ł���Ɠ����ɁA�v���̌����ł�����܂����B �@ �܂��A���̓����V���n��̎��R���ۂ��x�z����Ƃ��l�����Ă��܂����B �@ �V�͂��Ƃ��Ƃ͓V�̐_�ł������A���X�ɂ��̐l�i���͔���Ă����܂��B �@ �E�q(�O551�`�O479)�́A�w�_��x�z�ݕтŁu�V������������A�l���s���S�������v(�V�͉�������Ȃ����A�l�G���߂��点�����炳����)�Əq�ׂĂ��܂��B �@ ���̍E�q�̓V�́A�ӎu�Ɗ�����������A�l�i���𔖂߂����O�I�ȓV�ł��B �@ ����ŁA�V�͊W�V����ӓV���ɂ݂���悤�ȁA��n�����R�̓V�ł�����܂����B �@ �_�Ǝ��R�Ƃ̗��ʂ����������Ȃ���A�V�͒����v�z�̊j�S�Ɉʒu���������̂ł��B �@ �����A�V�̊T�O�́A���Ƃ��Ƃ̓��[���V�A�̑������̏�Ƃ��Ă����V�q���̊Ԃɔ��B���āA�V�q�����璆���ɓ����Ă������̂ƍl�����܂��B �@ ��5�D��q�w�̉F���_ �@ 11���I�ɖk�v�̎�w�҂����ɂ���Ċ�b���z����A12���I�ɓ�v�̎�q�ɂ���ďW�听���ꂽ�̂��A�V����q�w�ł��B �@ ��q�w�́A�����̒����̎v�z�E���x�z���Ă��������⓹���ɑR���A�E�q��Ўq�̋����𗝘_�I�ȓN�w�ɑ̌n���������̂ł��B �@ ���̓����́A�]���̎�w�v�z�̊j�S�ɂ������u�V�v���p���Ȃ�����A������u���v�Ƃ������ՓI�ȊϔO�ɒu�������A����ɍ����I�����I�ƍl�����Ă����u�C�v�Ƒg�ݍ��킹�āA���R�Ɛl�Ԃ��܂ޑ̌n�I�ȉF���_�̍\�z�Ɍ����������Ƃł��B �@ ��q�ɂ��A�u���v�����R�Ɛl�Ԃ��܂ޑS�F�����т������ł��B �@ ����́A�P�Ɏ��R���x�z���镨���ł��邾���łȂ��A�l�Ԃ��]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ϗ��ł�����܂��B �@ ��̓I�ɂ����A�Ő�����Ă����悤�Ȑm�`��q�M�̌�A�Ƃ��ɌN�b���q�̏㉺�I�������d������܂��B �@ �F���̑n���ɂ��ẮA�A�z�̋C����]�������A���̉�]�̒������ɑ͐ς����C����n���`���A���̊O������]����C����V�����܂ꂽ�Ƃ��܂��B �@ ��q�́A�������Đ��܂ꂽ�F���ɂ��ẮA�ӓV�����Ƃ�܂��B �@ �l�Ԃ��C����̐������ł���A���͋C�̏��U�Ƃ���܂����A���̐l�Ԃ��V�n���т��u���v�Ɏx�z����܂��B �@ �F���Ɛl�Ԃ͑�F�������F���̊W�ő������܂��B �@ �l�Ԃ̗��z�͐l�~�������ēV���Ɏ��邱�Ƃł���A���̕��@�Ƃ��ꂽ�̂��u���h�v�Ɓu�����v�A���Ȃ킿�S���W�������Ď����̐g�𐳂����ۂ��A�������đS�F���̍���ɂ��闝�𐳂������߂邱�Ƃł��B �@ ���̂��߁A��q�w�́u���w�v�Ƃ��Ă�܂����B����́u���w���v�̈Ӗ��Ƃ͑�Ⴂ�ł��ˁB�@ |
|
|
�������A���{�ł͓V�c�̒n�ʂ̐������͌����I�ȘA�����ɂ���ĕۏႳ��A������ے�����̂͑另�ՂƂ����V���ł����B
�@ �����Ɣ�ׁA���{�̐_�b�͒n��I�ł���A���R�I�ł���A�Ȃɂ�����앶���̐F�ʂ��Z�����Ƃ������Ƃ��ċ������܂��B(�u�L�����̐���̍��v�Ȃ�) �@ �V�q��q�ɑ�\����铹�Ƃ̊�{�I�Ȏv�z�́u���R�v�ɂ���܂����B �@ ���́u���R�v�́u���̂�����Ȃ邱�Ɓv�܂�u���R���v�̈Ӗ��Ŏg���Ă���A���R�E�̎��R�Ɠ����Ӗ��ł͂���܂��A���������҂�ʂ̂��̂Ƃ݂Ă��Ȃ�Ȃ��ƍr�삳��͂����܂��B �@ �R�쑐�ؒ��b�Ȃǂ́u���R�v�͐l�ׂ��������Ă��Ȃ��A�u���̂�����Ȃ���́v�Ƃ����Ӗ��Łu���R�v�ȑ��݂ł��B �@ �u���R�v�Ƃ�����́A���ł�(������)��k������ɂ͈�ʂɂ����R�E�̈Ӗ��Ŏg����悤�ɂȂ�܂��B�������̎����p��Ƃ��Ĉ��p����Ă��܂��B �@ ���Ƃ́u���v�́u�V���̕�v�u�����̕�v�Ƃ����Ă��܂����B �@ �F���̌����͑�n�I�Ȃ��̂ł���A�����I�Ȃ��̂ł���Ɨ�������Ă����B�V�q���ɂ����[���F������]�����炳�ꂽ�V���j���I�E�����I�Ȍ����ł���̂ɑ��āA���Ƃ̓��͏����I�E�ꐫ�I�Ȍ����ł���B �@ ���{�l�̓`���I���R�ςɂ��Ă̂܂Ƃ߂͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B �@ ���{�l���݂�����̎��R������v�z�����邱�Ƃɂ͕s�M�S�Ȗ����ł��������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�Ȃɂ������{�l�͎��R���r�������ł������B�@ |
|
| ����3�́@�����̉F���@ | |
| ��3�߂ł͖����̉F���ł���֑ɗ��A��5�߂ł͒n���A��6�߂ł͐����Ɋy��y���A���ꂼ��������܂��B��8�߂ł͖@�R�Ɛe�a�̎��R�A���ɐe�a�́u���R�@��(���˂�ق���)�v�ɂ��ĉ�����Ă��܂��B�@ | |
|
�������̐{��R�F���_�@ 4�E5���I���̃C���h�l���e(���@�X�o���h�D)�́A�l���㔼�ő�敧���ɓ]�����A��敧����2�̑傫�ȗ���̂����F���_�I�ȁu�B��(�䂢����)�v��n�n���ĕ�F�ɂȂ����Ƃ���܂����A�]���O�͏��敧���̊w�҂ł���w�����B����ɘ_(���т��܂�������)�x�A�ʏ́w��ɘ_�x�Ƃ��������N�w��̌n�I�ɐ����������킵�Ă��܂��B �@ ���{�j��ő�̏@���v�z�Ƃ͕��������̑n�n�҂̈�l�ł����C(774�`835)�Ƃ��đ���̓��ӂ�������Ǝv���܂����A�ނ̎咘�w�閧��䶗��\�Z�S�_(�Ђ݂܂炶�イ���イ������)�x�͓��{�l�ɂ�镧���̏��߂Ă̑����I�ȋc�_�ł������łȂ��A�ŏ��̉F���_�I���q�ł������āA�w��ɘ_�x�̐{��R�F����������Ă��܂����B �@ �����ł́w�\�Z�S�_�x�Ɋ�Â��Đ{��R�F�����݂Ă����܂��B �@ ���E�͋���ɕ����ԕ��ւ̏�ɉ~�Տ�̐��ցE����(������)���d�Ȃ�A���̏��8�̊C��9�̎R�A4�̑�F��8�̓������݂��܂��B �@ ���̎R�ƊC�̒��S�ɐ{��R�����т������܂��B �@ �{��(�����)�̓X���[���̉���ŁA�Ӗ�Ė����R�Ƃ������܂��B �@ ���̐��ʂ���̍������A�����̍���(���C�̐[��)��8���R�{(�䂶���)�ł��B �@ �{��R�̌`��͊p���ŁA���ʂ̕���8���R�{�A������C�ʂ̏�ɏo�Ă��镔���͂��傤�Ǘ����̂ƂȂ�܂��B �@ �ގ��́A�k�ʂ����A���ʂ���A��ʂ��ڗ�(�G�������h)�A���ʂ������ł��B �@ ��ŏo�Ă����u�R�{�v�͒����̒P�ʂŁA���Ԃ�1���ɑ���鋗���Ƃ������܂����A�͂����肵����`�͂���܂���B �@ �����A������߂ɂ���8���R�{�͖�13�������ƂȂ�܂��B �@ ���ł͒n���̔��a��6�A400�����Ƃ���Ă���̂ŁA�n���̒��a��肿�傤�Ljꌅ�傫���킯�ł��B�����牽�ł��f�J��������(^^ �@ �{��R�̂��傤�ǒ��Ԃ̂Ƃ���ɂ͎l�������l�V�����Z�ގl�V���V������܂��B �@ �V���w�I�ɏd�v�Ȃ̂́A�����ɂ͑��z�ƌ��Ɛ��X���ʒu���A�����͐{��R�𒆐S�ɉ�]���Ă��邱�Ƃł��B �@ ���z�̑傫����51�R�{�A���̑傫����50�R�{�B�������Ȃ�(^^ �@ �{��R�̎���͓��S�I��7�̊O�֎R�����͂݁A����ɂ��̊O����S�͎R(�Ă�����)���݂͂܂��B �@ 7�̊O�֎R�͕��`�ŋ�����Ȃ�A�S�͎R�͉~�`�œS����Ȃ�܂��B �@ �O�֎R�ƓS�͎R�̊ԂɁA������k��4�̑�F������܂��B �@ �e��F�̌`�́A���͔����`�A���͉~�`�A��͋t��`�A�k�͐����`�A�e��F�ɂ�2�̓����t�����܂��B �@ ��̑�F���֕��F(����Ԃ��イ)�Ƃ����A�l�Ԃ̏Z�ނƂ���Ƃ���܂��B�����̃C���h���嗤�����f���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B �@ �{��R�F���ɂ�28�̓V�����݂��܂��B �@ ��ԉ����l�V���V�A�����{��R�̒���ɂ��� �Ƃ����V�A3�Ԗڂ���͐{��R�̏��ƂȂ�A�����珇�ɖ閂�V�A�s���V(�Ƃ��Ă�)�A���y�V(���炭�Ă�)�A�������ݓV(�����������Ă�)�Ɩ��t�����Ă��܂��B �@ �����6�̓V���܂Ƃ߂ė~�E(�Z�~�V)�Ƃ����܂��B �@ �s���V�͊����V�Ƃ������A�l�ԊE�ɐ��܂��O�̎߉ނ��Z��ł����Ƃ���ŁA����56��7�疜�N��ɒn��ɍ~��Ă���\��̖��ӕ�F���C�s���Ă��܂��B �@ (�]�k�ł����A�{�V���������̎��𓉂��u�i���̒��v�̖{�l�����{�ɂ́u�����̓V�̐H�v�Ƃ����\�����o�Ă��܂��B) �@ �~�E�̏��18�̐F�E�A�����4�̖��F�E�����݂��܂��B �@ �����͐l�Ԃ̉�E�ւ̒i�K�ɑΉ�����Ƃ���A��ɍs���قǗ��z�I�Ȑ��E�ƂȂ�܂��B �@ ����ɁA�{��R���E���炠�܂��ď��琢�E���\�����A���琢�E����W�܂��Ē��琢�E���\�����A���琢�E����W�܂��ĎO��吢�E���\�����A�������̉F���ƍl���܂��B �@ �܂�O�琢�E�Ƃ����̂́A���3�{��3000�ł͂Ȃ��A���3���10�����Ӗ�����̂ŁA�����ӂ��B �@ �u���E�v�͕����̉F����\�����߂ɍ��ꂽ����ŁA�u���v�͎��ԁA�u�E�v�͋�Ԃ��Ӗ�����̂ŁA���E�͎���I���݂ƍl�����܂��B �@ ���ł��u���v�͍X�V���Ȃǒn������킷���̂Ƃ��Ďg���Ă��܂��ˁB �@ ������]�k�ł����A �@ �u�O�琢�E������E���A��ƒ��Q�����Ă݂����B�v�Ƃ����̂́A�����̎u�m�ł��鍂���W�삪������L���ȓs�s��(�ǂǂ���)�ł��B��͒����_�b�ɂ��Ƒ��z�ɏZ��ł��āA�����ł͑��z�̏ے��Ƃ���Ă��܂��B�@ |
|
| ����4�́@�L���V�^���V���w�@ | |
|
16���I���ɃL���V�^���V���w�ɂ���āu�n�����v�����{�ւ����炳��A�蒅�����o�܂������Ă��܂��B
�@ �n�����̉F���_�̍u�`�����{�ōŏ��ɍs��ꂽ�̂́A1580�N�ɐݗ����ꂽ�L��̕{��(���̑啪�s)�̃R���W�I(�C�G�Y�X��̐鋳�t�{���̂��߂̍�������@��)�ŁA1583�N�ɗ��������X�y�C���l�鋳�t�y�h���E�S���X(1535�`1600)�ɂ���Ăł����B �@ �������[���b�p�ł͍D��I�ȓ��{�l�Ɛ킢���{���R���I�ɐ������ĕz�����邱�Ƃ͕s�\���ƔF������Ă���A������{�l�͒m�I�D��S���������������߃L���X�g���̒m�I�D�ʐ����������Ƃɂ��z����e�Ղɂ��悤�Ƃ����悤�ł��B �@ �����ŁA���{�l�C���m�s����(�ӂ���)�n�r�A��(1565�`1621)���A1605�N�Ɋ��s�����L���X�g���̋������w����ⓚ(�݂傤�Ă�����ǂ�)�x�ŕ����A�̉F���_��ᔻ���܂����B �@ ����ɑ��A��1606�N�A�����23�̎Ⴋ�ї��R(1583�`1657)����q�w�̗��ꂩ��n�r�A���̂������s�̓�؎��ɏ�荞��Ř_���݁A���̂������w�r��h(�͂��₻)�x�Ɏc���܂����B �@ ��Ș_�_�́A�V�ƒn�̊W�A��n�̌`��A���̗̂����^���A���E�̑n���ł��B �@ �ї��R�͓V�~�n���Ɠ��~�Õ��̌��������n�͉~(��)�ł͂��蓾�Ȃ��Ǝ咣���܂���(���~�Õ��Ƃ́u�����҂͉~�A�Â��Ȃ�҂͕��Ȃ�v�Ƃ�����q�w�̌���)�B �@ ����ɑ��n�r�A���́A���ɐi�߂��D��������߂�Ƃ��������ƁA�n���Ɍ����J���Đ𗎂Ƃ��ΐ͒n���̒��S�ɗ��������͂����Ƃ����咣���q�ׂ܂��B �@ �܂��A�F���ɂ͎n�߂������ďI��肪�Ȃ��Ƃ����n�r�A���̎咣�ɑ��A�ї��R�͎n�߂�����ΏI��������͂����Ɣᔻ���܂��B �@ ���҂̘_���́A���̎�q�w�̉F���_�Ɛ��̃X�R���N�w�̉F���_�̑Ό��ł����B �@ �c�_�͐��|���_�ɏI��炴��Ȃ������̂ł����A�݂��ɑ���̎v�z�̌����I�ȂƂ���ɓ��ݍ��_���ł������_�ɈӋ`������܂����B �@ ��q�w�ɂ���L���V�^���ɂ���A�����̓��{�ɂ�����V���̎v�z�E�@���������̂ł��B �@ ���̌�A�n�r�A���́A���ɒe�����ꂽ�킯�ł��Ȃ��̂ɃL���X�g�����̂āA1620�N�ɂ͕����A��i�삵�ăL���X�g����ᔻ�������w�j��F�q(�͂�������)�x���o�ł��܂��B �@ �������A��������F���_�ɂ����Ă͒n�����͎̂Ă܂���ł����B �@ ���R�E�n�r�A���_������50�N���1656�N�ɏo�ł��ꂽ�w�����ِ�(����ׂ�)�x�ł́A�n������������܂��B �@ ���҂͓����̑�\�I��҂ł�����䌳��(���傤)(1609�`77)�ł��B �@ �����́A�L���V�^���̉F���_���q�ׂ��{�_�ɑ��錳���ِ̕��Ƃ����`�����Ƃ�܂����A�{�_�̓��e����́u�V�����v�����������|���g�K���l���_���̃t�F���C��(���{���E��쒉���A1580���`1650)�������̂ł��B �@ �������A�L���X�g���I�ȓV�n�n�����Ȃǂ̕����͏Ȃ���A�A���X�g�e���X�I�l����͎�q�w�̌܍s���̗��ꂩ��ᔻ���Ă��܂��B �@ ���ꂪ�]�ˎ�����{�ɂ�����n�����̎�e�̂����ł����B�@ |
|
| ����5�́@�n�����̎�e�@ | |
|
�L���V�^���V���w���������ꂽ����ɂ̓��[���b�p�ł̓R�y���j�N�X�̒n�����͂��łɒm���Ă���A�܂��K�����I��P�v���[��������ł������A�J�g���b�N�̐鋳�t���ْ[�ł���n�������킴�킴�Љ�邱�Ƃ͂���܂���ł����B
�@ �w�����ِ��x�ł́A�{�_�Œn�������ے�I�ɏЉ��A�����ِ̕����{�_���x��������̂ł����B �@ �n������{�i�I�ɓ��{�ɏЉ���̂́A�I�����_�ʎ�(�ʖ�̂��ƁB�����̑��̐E�Ɠ��l�ɐ��P)�̉ƌn�������{�ؗlji(���Ƃ���傤����)(1735�`1794)�Ǝu�}���Y(���Â�������)(��̒�����ށA1760�`1806)�ł����B �@ �{�́w���z����������x��1792�`3�N�ɒ����A�u�}�́w��ېV���x��1802�N�Ɋ��������܂��B �@ �Ƃ��ɏo�ł͂���Ȃ������̂ł����A�ʖ{�̌`�ŗ��z���܂����B �@ �w���z����������x�̓P�v���[�̖@���̃��x���ł����A�w��ېV���x�ł͂��̍����ƂȂ�j���[�g���̖��L���̖͂@���Ɖ^���@�����Љ��Ă��܂��B��҂ł͖����F���_���F�߂Ă��܂��B �@ �܂��A�w��ېV���x�͉F���̑n���Ɋւ��āu���ו���(�Ԃ�ς�)�}���v�Ƃ������̂�t���Ă��܂��B �@ ����́A��q�w�̉F���n���_�ƃj���[�g���͊w��g�ݍ��킹�āA���ז����́u�C�v����f�����a�����ȉ~�O�������]����悤�ɂȂ������Ƃ����������̂ŁA���1895(����28)�N�Ɏ�시�g(���̂���������)�ɂ���āA�J���g�E���v���X�̐��_���ɕC�G������̂ƕ]������܂����B �@ ���l�̐��͒n�������S�ł���Β����́w�V�o����(�Ă��킭����)�x�Ȃǂɂ��łɂ������̂ł����A���z���S�̐��Ƃ��Ă͏��߂Ăł��B �@ �n�����̈Ӌ`�����ϋɓI�ɕ]�������̂́A�i�n�]���A�R��崓�)�Ƃ������ݖ�̎v�z�Ƃł���A�ނ�ɂƂ��Ēn�����͐��m�����̍��x�Ȑ��E�F���ے�������̂Ɨ�������Ă��܂����B �@ �i�n�]��(����������)(1747�`1818)�͉�Ƃ��{�ƂŁA���{�ŏ��̓��ʼn�Ƃł��B �@ ����ƂƂ��ɁA���m�Ȋw�̍������ɐ��ȐM�����A�n�����̌[�֎҂ƂȂ�܂����B �@ �ނ́A���E�n���̏��Ɛ��E�n�}(���ʼn�)���o�ł�����A1796�N�Ɂw�a���V���x�A1808�N�Ɂw�������V���}���x�A1816�N�Ɂw�V�n��杁x�Ƒ������Œn�����̉���������s���܂��B �@ �����F���_���p�����Ă��܂��B �@ �i�n�]���Ɋւ��ďd�v�Ȃ̂́A�F���̖������ɑ���l�Ԃ̔����������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ނ̐l�Ԋςł��B �@ �������ɑ��݂��鑾�z(�P��)�Ƃ��̂܂�����]����f���B���̘f���̂ЂƂɏZ�ސl�Ԃ͑動��ɕY���ЂƗ��̈��ł���A��n����������C�̏����ɂ����Ȃ��B�����ł���A�l�Ԃ̋M�G�ȂLjӖ����Ȃ��B �@ ���w�t�g�O�M�L�x�ł́u��V�q���R��艺�m�_�H����l��H�Ɏ���܂ŊF�ȂĐl�ԂȂ�v�Ƃׂ̂Ă����B �@ �������Ĕނ́A�ߑ�̉F���_�̔F������l�Ԃ̕����ɓ��B�����̂ł��B �@ �R��崓�(��܂�����Ƃ�)(1748�`1821)�͑��̗��֏��E�����̔ԓ��ł������A���Z�Ȏ��Ԃ������Ċw����w�сA�V���Ƃ̖��c����(������イ)��ɂ̐掖�قɓ��債�ēV���w���C�߂܂����B �@ �₪�Ĕނ́A�{�A�i�n�A�u�}��̒�������A�n�����̗h�邬�Ȃ��x���҂ƂȂ�܂����B �@ 55�̂Ƃ�����73�̂Ƃ��܂ŏ����������S�ȑS���I�_�l�w���̑�(����)�x�́u�V���v�́A�n�������ڐ������V���w�ɓ��Ă��Ă��܂��B �@ 崓����A�i�n�]���Ɠ��l�ɖ����F���_���̂�܂������A崓��ɂ͍]���̂悤�ȕ����v�z�݂͂Ƃ߂��܂���B�������A��q�w����w�v�ٓI�ȍ�����`�Ƒ�㏤�l�̌����I������`�ɉ����āA���m�Ȋw�̍�����`��崓���O�ꂵ�����_�_�ƗB���_�ɓ����܂����B �@ ���n���Ȃ��Ɋy���Ȃ�����Ȃ����U�L����̂͐l�Ɩ��� �@ ���_������(������)���Ȃ����̒��Ɋ�ӂ����̂��Ƃ͗P(�Ȃ�)�Ȃ� �@ �w���̑�x�͊��s����܂���ł������A�ʖ{��50���ȏ㌩�����Ă��܂��B�@ |
|
| ����6�́@���w�I�F���_�̐����@ | |
|
���w�Ƃ́A�]�ˎ���ɂ����ČÎ��L�Ȃǂ̓��{�̌ÓT���������邱�Ƃɂ����{�Ǝ��̕�����v�z�����o���āA�������w�Ȃǂ̊O���v�z��ᔻ�E�r�������w�⒪���ŁA�����̑������Ύv�z�ɑ傫�ȉe����^���܂����B
�@ ���̑�\�I�l���Ƃ��Ă͖{���钷(1730�`1801)�A���c�Ĉ�(1776�`1843)�Ȃǂ��������܂��B �@ ���w�́A�F���_�ɂ����Ă͒n���॒n�������e��A���̈���ŕ������q�w�̉F���_��ᔻ���܂����B �@ ����́A���w�������̎��R�Ȋw�Ɛe�a�I����������ł͂Ȃ��A���Ƃ��ƕ������q�w�̂悤�Ȋ������ꂽ�F���_�̑̌n�������Ă��Ȃ��������߂ɂ������Ēn���E�n�������e��₷���������炾�ƍl�����܂��B �@ �� �@ �u��7�́@�����̋ߑ㉻�ƉF���ӎ��v�ł͓����ӎO�A�u��8�́@����F���_�Ƃ̏o��v�ł͉Ėڟ��A���c�����Y�A�a�ғN�Y�A�ˍ⏁�A���L�F�A�{�V������̉F���ς��A�A�C���V���^�C���Ƃ��̖K���̉e�����܂ߘ_�����Ă��܂��B���������ϋ����[��(���Ƃ��Γ����L���X�g�҂ł�������ӎO�Ɖ��L�F�̑Δ�Ȃ�)�̂ł����A�ȗ������Ă��������܂��B�@�@ �@ |
|
| �����{�l�̉F���� / ���]2 | |
| ����E���� | |
|
�w���{�l�̉F���ρx�́A�É���w�����r��h��(1940�|)���㈲�����{�ŁA�r�쎁�́u�͂��߂Ɂv�̖`���Œ���̖ړI���u���{�l�͉F�����ǂ̂悤�ɂ݂Ă������B�Ñォ�猻��܂ŁA���{�̗��j�Ɍ���ꂽ�F���ς̕ϑJ�������˂Ă݂����v�ƌ����\�킵�Ă��܂��B���̖ړI���炷��Δ�r�����̊ϓ_���d�v�ł��邱�Ƃ͖��炩�ł��B�ǂ��̍��ł��A���j�̑啔����ʂ��āA�F���ς͌`�����̖��ł�������ނ���`����̖��ł���܂����B���������Ă���͕����Ɛ[���ւ���Ă��܂��B���{�ɘb�������Ă��A���{�l���O���̕����̉e�����Ȃ��������ɂǂ�ȉF���ς������Ă������Ƃ������Ƃ����{�ŗL�̕����f���Ă��邾���łȂ��A�O���̉F���ς��Љ�ꂽ�Ƃ��ɂ�����ǂ��������A�ǂ��ϗe���������Ƃ������Ƃ����{�����̓����Ƒ傢�ɊW���Ă��܂��B����͂܂��Ƀx�l�f�B�N�g���w�����̌^�x�̒��Ō������u�������v(recast)�ł��B�����̌^(patterns of culture)�́A���̎����^�Ƃ��ċ@�\����̂ł��B�w���{�l�̉F���ρx�ɂ̓x�l�f�B�N�g�Ƃ����l�����A�w�����̌^�x�Ƃ����������o�Ă��܂��A�r�쎁�͂��́u�������v�ɓ����錻�ۂɒ��ڂ��Ă��܂��B����́A�u�͂��߂Ɂv�̒��Ń��[���b�p�̉F���_�𒆐S�Ƃ����l�@�ɕ邱�Ƃ����߂����̒i���ɕ\���Ă��܂��B
�@ �������A����͗��j�̈ꕔ�ł����Ȃ��B���[���b�p�̉F���_�ɏo��O�A���{�ɂ͒�����C���h�̉F���v�z���C���z���ē`�����Ă����B���̈ȑO�ɂ��A���̋ɓ��̓����̕��y�ƎЉ�ɍ��������F���ς�������Ă����͂��ł���B���̂悤�ɁA������Ñ�E�����ɂ��L���Ă݂�ƁA���{�l�́A�O���̕����̉e�����Ȃ�����A���{�l�ɌŗL�Ȋ�������Đ��E�̑S�̐��ƒ��������Ƃ炦�悤�Ƃ��Ă����̂ɋC�Â��B�����ɓƎ��ȉF���Ɛl�ԂƂ̊W�����߂Ă������Ƃ���������B �@ �����čr�쎁�́A���{�l�̉F���ς̗��j�ɎO�̐ߖڂ����邱�Ƃɒ��ӂ��܂��B����́A�܂�����A���ɃL���V�^���̐��I�A�Ō�ɖ�������ł��B��Ƃ��Ă����̎���ɐV�����F���ς����ꍞ��ł����o�܂��q�ׂ�̂���1�́A��4�͂���ё�7�͂ł��B�����̐ߖڂɑ����āA���̓s�x�V�����F���ς��u���{�I�ɏ�������Ƃ����ߒ��v�������Ă��܂��B�����ɂ��ẮA���ꂼ���2�|3�́A��5�|6�͂���ё�8�͂����Ă��Ă��܂��B �@ �����ł́A�w���{�l�̉F���ρx�̑S�̂��ꋓ�Ɏ�肠����̂łȂ��A�O�ɕ������āA��1�|3�͂��u����1�F�Ñ�E�����v�A��4�|6�͂��u����2�F�ߐ��v�����đ�7�|8�͂��u����3�F�ߑ�E����v�Ƃ��čl�@�������܂��B����͖{���̘b�ɓ���O�Ɂu�͂��߂Ɂv�̒��̒��ڂ��ׂ����ɐG��Ă����܂��傤�B����́A���{�l�̉F���ς̗��j�S�̂�ʂ��Ă̈�ۂ��q�ׂ����t�ł��B�r�쎁�́w�Î��L�x����сw���{���I�x�̒��Łu�_�b�I�ł���Ȃ���Ǝ��̉F���ς����肾����Ă����v���ƁA�����Ă��ꂪ�͂邩�Ȍ㐢�̎v�z�ɂ����������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������Ȃ��玟�̂悤�ɂ������܂����B �@ ���̈���ŁA���{�l�̊�͓V��̐��E�����n��̎��R�ɒ�����Ă����B���l�ŁA�G�߂ƂƂ��ɑ��ʂȕω����݂��镗�y�̂Ȃ��Ő��������Ă�������ł��낤�A�w���t�W�x�ł͌��͉r(����)���Ă��A������̂͐�����قǂ����Ȃ��A�قƂ�ǂ��n��̎��R���r�������̂ł���B�w�Î��L�x�w���{���I�x�̕`���u���V�����v���A�R�삪���葐�̂�����n��I�ȋ�Ԃł������B���̎��R���s���������B���R�͉r���Â��A���R�I�ȉF���Ƃ̈�̉��𗝑z�Ƃ���v�z�����肩�����o�������̂ł���B �@ �Ō�̃Z���e���X����킩��悤�ɁA����͌Ñゾ���Ɍ��肳���b�ł͂���܂���B�����Ă����ɂ͑������d�v�Ȏ����������̂������Ă��܂��B���̈�́A���{�l�ɂƂ��ẲF���͒n��̎��R�̉�����̂��̂ł����āA�����̊Ԃɕs�A��������Ƃ͍l���Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ�������̏d�v�ȃ|�C���g�ł���u���R�I�ȉF���Ƃ̈�̉��𗝑z�Ƃ���v�z�v�ɋ��菊��^���Ă��܂��B ���̌���Ƃ���ł́A�����͂�������x�l�f�B�N�g���w�e�Ɠ��x�̒��Ő������p�̕����Ƌ����֘A�������Ă��܂��B �@ ���͂���܂łɉ��x���A���{�l���l�Ԃz�����Ύ҂̑��݂�F�߂Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��ĉ�����Ă��܂����B���{�l�̍l����u�_�v�͐l�Ԃ𗝑z�����邢�͔����������̂��A�����łȂ�����M����Ȃ����̂��Ƃ������Ƃł��B����͂��̎R�A���̐X�A���̐�A���邢�͂��̊C���X�A�����鏊�ɋ��āA�_�b�̎���ɂ��łɁu���S���v(�₨��낸)�ƕ\������Ă����̂ł��B���Ɂu���V�����v�������ʂ�V�̍����Ƃ���ɂ���ƍl����ꂽ�Ƃ��Ă��A�����͒n��́u���v�Ɩ{���I�ɂ͈��Ȃ��Ƃ���ł���A�����ɏZ�ސ_�X�͐l�ԂƓ��l�̐��������Ă����̂ł��B���{�l�̑z���͂ɂ������Ƃ����l�����Ȃ������̂ł����āA���z�I�Ȑ�Ύ҂���L����Ƃ���́A�l�Ԃ��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ���ԂƂ��Ắu�V�v�����݂��邱�Ƃ����v�������Ȃ������̂ł��B�����Ē��z�I�Ȑ�Ύ҂��l�����Ȃ����Ƃ���A�l�X�͎��̂悤�Ɍ����Ă�����j�ɂ��������čs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B �@ ���{�l�̐����ɂ����Ēp���ō��̒n�ʂ��߂Ă���Ƃ������Ƃ́A�p��[���Ɋ����镔���܂��͍��������ׂĂ����ł���悤�ɁA�e�l�����Ȃ̍s���ɑ��鐢�]�ɋC��z��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�ނ͂������l���ǂ��������f�������ł��낤���A�Ƃ������Ƃ𐄑�����������悢�̂ł����āA���̑��l�̔��f����ɂ��Ď��Ȃ̍s���̕��j���߂�B�݂�Ȃ������K���ɏ]���ăQ�[�����s�Ȃ��A���݂��Ɏx���������Ă��鎞�ɂ́A���{�l�͉����ɂ₷�₷�ƍs�����邱�Ƃ��ł���B �@ �u���l�̔��f����ɂ��Ď��Ȃ̍s���̕��j���߂�v�Ƃ������Ƃ́A���݂��Ɏx���������W���ێ����邽�߂Ȃ̂ł��B���̕��j�ɂ���ē������̊��͓��{�l�̎Љ�I�s���̂���߂ďd�v�ȗv�f�Ȃ̂ł��B�����ł����Ă݂�A���̎R�ɂ��A���̐X�ɂ��A���̐�ɂ��A���̊C�ɂ����ޔ��S���̐_�X�Ƃ���̊��������Ƃ��̗v�ł��B�r�쎁������̕��Ō����\�킵�����Ƃ́A�����l����ΑS�ʓI�ɒp�̕����ƌ��т��܂��B �@ ���̂悤�ɁA���{�l�̉F���ςƁA�p�̕����Ƃ̊Ԃɂ͋����W������̂ł��B���̂��Ƃ́A�w���{�l�̉F���ρx���ڂ����ǂ�ł����Ƃ܂��܂����炩�ɂȂ�܂��B �@ ����ł͌Ñエ��ђ����̓��{�l�̉F���ς��������͂����܂��傤�B��قnj����e�͂̃^�C�g��������킩��悤�ɁA�L�q����Ă�����e�̎��ԓI�������猾���Ƒ�2�́A��1�́A��3�͂̏����ɂȂ�܂��B�r�쎁�́A��قnj���ꂽ�u�ߖځv��悸�������闧���������̂Ŕ���̂��Ƃ��ŏ��Ɍf���A���ꂩ�炻�̑O��̎���̂��Ƃ��q�ׂ��̂ł��傤�B�����������ł́A��Ƃ��Ă͎��Ԏ��ɂ����������Ō��ۂ����Ă����܂����A���̎O�̏͂̊_������蕥���Ęb��i�߂܂��B �@ �r�쎁�́A�w�Î��L�x�w���{���I�x�ɒ��ڂ��܂����B��2�͂̓������ɂ��̕����̐��i�ɂ��Ă̌������q�ׂ��Ă��܂��B �@ ��䌴���߂��V�c�_�Ƃ��鍑�Ƒ̐���@�I�ɋK�肵�悤�Ƃ����̂ɂ������āA�w�Î��L�x�Ɓw���{���I�x�͓V�c�ɂ�铝���̐�������_�b�I�`���ɂ��ƂÂ��Ė��炩�ɂ��悤�Ƃ���C�f�I���M�[�̏��ł������B�����̎j���ɂȂ炢�Ȃ�����A�����ɂ́A�����̎j���ɂ݂͂��Ȃ����i���������B���ߐ��Ƃ��������́u�ߑ㉻�v��i�߂����ŁA���̓����̌�����_�b�ŗ��t���悤�Ƃ��鉤���̈Ӑ}���Z���Ɏ咣���ꂽ���������̂ł���B �@ �������̌����͑Ó����Ǝv���܂��B�����Ă���ɑ����ďq�ׂ�ꂽ��2�͂̃��W�����Ƃ������ׂ����̕��́A�r�쎁���Ӑ}�������ǂ����͂Ƃ������A���{�����̌^�ɂ�钆���̉F���v�z�̒������ւ̌��y�ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �����������ڂ���̂́A���̐_�b�����{�l�̉F���ςƕs���ł������Ƃ����_�ł���B�L�I����ǂ݂Ƃ����{�l�̉F���ςɂ������̉F���v�z�̉e�����݂Ƃ߂���̂����A�������A�Ñ�̒����Ő��������W�V����ӓV���Ƃَ͈��ȉF���ł���B�L�I�̂Ȃ��œV�~�n���̉F��������邱�Ƃ��Ȃ��B�_�X�͓V�ƒn��Ɋ��邪�A�V���w�I�ȓV�n�ւ̊S�͋H���ł���B�ނ���A�嗤�����̉e���������Ȃ�����A����ɔ������邩�̂悤�ɁA�`���I�Ȃ��́A���{�I�Ȃ��̂։�A���悤�Ƃ���Ǝ��ȉF���ӎ����ł��o����Ă����B�L�I�̉F���̓����������ɂ���A����������{�l�̐S�̌Ñw�ɗ���Ă����F���ς��ǂ݂Ƃ��B �@ �u�W�V���v�u�ӓV���v����сu�V�~�n���̉F���v�Ƃ��������p��ɂ��ẮA��1�͑�2�߁u�l�ƒ����F���_�v�Ő�������Ă��܂��B�����v��ƁA�����̌Ñ�̊w���ɂ��Α�n�͋���Ȑ����`���Ȃ��Ă���A�V�͂����肳��ɑ傫���~�`�܂��͋��`�ł���Ƃ����̂ł��B���ꂪ�u�V�~�n���̉F���v�ł��B�����ēV���~��ł���Ƃ���̂��W�V���A��n�����͂ދ��ʂł���Ƃ���̂��ӓV���ł��B�O�҂ł͓V�̒��S�͖k�ɐ��ł���Ƃ���A��҂ł͖k�ɐ��Ƒ�n�̒��S�����Ԑ������ʂ̎��ł���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��āA���̒��S���邢�͎��̂܂��ɓV�������^��������Ƃ����̂ł��B �@ ���̂悤�Ȓ����̊w�������{�ɏЉ�ꂽ�̂�7���I�̏����ł��낤�ƍl�����Ă��܂��B���ꂩ�琔�\�N�o�����V���V�c(�݈�672�|686)�̎���ɂ悤�₭�V�̊ϑ���(�萯��)���ݒu����A���̖�l���z�u����܂����B�����̓V�̊ϑ��̖ړI�͒n��ɋN����ُ�Ȏ��R���ۂ�Љ�I�ώ��̗\����m�邱�Ƃɂ������̂ł����A����ɂ͒����Ŕ��B�����w���𗝉����Ȃ���Ȃ�܂���B����䂦���Ȃ��Ƃ������̍��������͊W�V���܂��͟ӓV����m���Ă����͂��ł��B���ɁA7���I�㔼�܂���8���I�����ɒz���ꂽ�Ǝv���鍂���ˌÕ���L�g���Õ��̌����̓V��ɂ͐��̐}���`����Ă���A��������҂ł͖��炩�ɟӓV���f�������������Ă��܂��B����ɂ�������炸�A712�N�ɏo���オ�����w�Î��L�x�ɂ��A720�N�Ɋ��������w���{���I�x�ɂ��A�_�X�̊��鎞��̋L�q�ɂ͂��̂悤�ȉF���ς̕З������Ȃ��̂ł��B �@ ����ł͋L�I�̓��e�͒����̎v�z�Ɩ��W�Ȃ̂��Ƃ����ƁA�����ł�����܂���B�L�I�ł́A���z�̐_�Ƃ��čō��̒n�ʂɂ���V�Ƒ�_(���܂Ă炷�����݂���)�͍��V��(�����܂��͂�)�ɋ��āA�����̑��ł���Ԕ\�玌|��(�ق̂ɂɂ��݂̂���)�ɓ��{�����߂邱�Ƃ𖽂��A�n��ɍ~�Ղ������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�����ĔԔ\�玌|���̎q�������̍����x�z���A�Ñ�V�c�����m�������Ƃ����킯�ł��B�������Ȃ���r�쎁�������Ƃ���ɂ��ƁA�V�Ɏ���̐_������Ƃ����v�z�͒����̂��̂ŁA�Â����{�ɂ͖��������Ƃ������Ƃł��B �@ �V���ł���Ԕ\�玌|�����~�Ղ����Ƃ��̓��{�́A���l���ł͂Ȃ��A��Z�������܂����B�L�I�ɂ͂��̐�Z���̏������ƓV�������Ƃ̊Ԃł����Ȍ��⓬�������������Ƃ��L�^����Ă��܂��B��Z���̒��ōł��傫�����͂������Ă����̂́A�卑�喽(�������ɂʂ��݂̂���)�ɗ������A�R�A�n���������n�Ƃ��镔���ł������A�ނ�͕��a�I�Ȍ��̌��ʓV�������ɍ������邱�Ƃɓ��ӂ��܂����B���������ׂĂ̕��������������킯�ł͂Ȃ��A�����Ό������퓬���s�Ȃ��܂����B�����Ď��ɂ͖d�����p�����A�܂����鎞�ɂ͎c�s�Ȏ�i�ňꕔ�����F�E���ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�����܂����B�������ċ�B���瓌�k�n���암�ɋy�Ԓn��Ɏx�z�����m�������̂ł����A�e�n���̐�Z���������������ƂɌŗL�̕����������Ă����̂ŁA�����҂ł���V�������͔ނ�����邽�߂ɓV�c�Ƃɓ��ʂȌ��Ђ����邱�Ƃ��`����K�v�������Ă����̂ł��B���̂��߂ɐ�i���ł������������炢�낢��ȕ����������̂ł����A�����Ƃ������͂Ȕ}�̂��g���Ă��̌��Ђ����o������Ƃ������@����������w�т܂����B�������ċL�I���Ҏ[���ꂽ�̂ł��B �@ ��������������l����A�����ɒ����̐�i�I�Ȏv�z����������Ă��邱�Ƃ͗����ł��܂��B�������Ȃ��牽���牽�܂Œ����̎v�z�ɗ���킯�ɂ͂����܂���B����Ȃ��Ƃ�����ƒN�̖ڂɂ����b�Ƃ��������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��܂��B���Ԃ�A�W�V����ӓV���ȂǂƂ������͓̂����̓��{�l�̊��o���炷��Έٗl�Ȃ��̂ł������̂ł��傤�B16���I�̃��[���b�p�̐l�X�ɂƂ��Ă̒n�������ǂ�Ȃ��̂ł����������l�������͑z���ł��܂��B�����ߐ��̃��[���b�p�ƈႤ�̂́A�V�������͎҂̎x�z�͂̊g��̂��߂ɖ𗧂C�f�I���M�[�̌���ł��蓾���Ƃ������Ƃł��B�Ñ���{�ł́A�y���̎v�z�Ƃ̋}���ȑΗ�������Ȃ���V�����v�z�ŏ��������Ђ�O�ʂɉ��������Ƃ���������A���ꂪ���������̂ł��B�������y���̎v�z���������Ƃ��Ă��A�̂��l�������Ƃ���ɋ��āA���̐l�̖��߂����叫���R���𗦂��Ă�������~��Ă���Ƃ������x�̘b�Ȃ����邱�Ƃ��\�Ȃ̂œV���~�ՂƂ����؏������ł����̂ł��낤�Ǝv���܂��B���������Ƃ��Ɠ��{�l�̓��̒��ɂ��鐢�E���邢�͉F���́A�R��J������Ƃ��Ă���{�I�ɂ͐����̍L����������̂ł������̂ł��B�w���{�l�̉F���ρx�̑�2�͑�2�߁u�����̉F���@�\�@�퐢�̍��ƛE(�͂�)�̍��v�ł́A�������̏؋��ɂ���Ă��ꂪ������Ă��܂��B �@ �u�͂��߂Ɂv�̒��Ō���ꂽ�u���͉r���Ă��A������̂͐�����قǂ����v�Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����ɍL���闤�ƊC���������{�l�̊S���������R�E�ł������Ƃ������Ƃ̔��f�ł��傤�B����ł����͑��z�Ɏ������邭�傫���V�̂ł��邵�A����ɖ���㞂��Ƃ������I�ȕω��������A����ɊC���̊����Ƃ������֘A���A�܂������̐����Ƃ����W������悤�Ɍ�����قǂŁA�l�̊S��~�����Ă�v�f�𑽂������Ă��܂��B����ɑ��Đ��́A1�N�������Ƃ���P���̊ɂ₩�ȓ����ƁA���̘f���̈ꌩ�s�K���ȓ��������邾���ŁA������x�̌`����w�I�l�@�����Ȃ���Γ��퐶���Ƃ̊W������悤�ɂ͌����܂���B����ŁA�������{�l�̊S�������������Ƃ͂Ȃ������̂ł��B �@ �x�l�f�B�N�g���u�ނ�(���{�l)�͂����ς獡�����ɂ�����̂ɏW������v�Ƃ������t�͂��̏ꍇ�ɂ��^���ł��B��������グ�Ă����ɐl�Ԃz�����_�̗̈悪����Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��l����̂́A���{�̒p�̕����Ƃ͖����̂��ƂȂ̂ł��B�����ȗ��������{�l�������Ă���7��7���̐��Ղ�͌��������̕��K�ł��B����́A����̓��{�l������12��24���̃p�[�e�B�Ɠ��l�A��i���̐l�����Ă��邱�Ƃ��u���l�̔��f����ɂ��Ď��Ȃ̍s���̕��j���߂�v�Ƃ��������Ɋ�Â��Ď�����Ă���Ƃ����Ӗ��ł͒p�̕����f���邱�Ƃł����A���̍Ղ�̎���Ƃ������ׂ��D�����V��̑��ł���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͍��ł͂قƂ�ǖY�ꋎ���āA��N�Ɉ�邵���������Ƃ̂ł��Ȃ��v�w�̕��ꂾ������������Ă��܂��B�����Ă��̖�₩�ȏ���t�������������f���ċq��U�����X�X�͐���������܂����A�����̐��̒��̓���w�����āu���ꂪ�D���A���ꂪ��������v�ƌ������Ƃ��ł���̂́A���{�l�̑S�̂��猩��Ό����đ����Ƃ͌����Ȃ��V���t�@�������ł��B�@ |
|
| �� | |
|
�Ñォ�璆���ɂ����ĊO���̉F���ς��������ꂽ�ߒ��ɒ��ڂ��܂��傤�B
�@ 7���I�㔼�̓V���V�c�̎���ɐ萯�䂪�ݒu����A���̖�l���V�̊ϑ����n�߂��̂́A�V�̌��ۂ��n��̎��R���ۂ�Љ�ۂɉe�����y�ڂ��ƍl����ꂽ����ł����B����͒�������`������v�z�ɏ]�����l�����ł��B���̐萯��̂��Ƃ������������������܂��傤�B �@ �V���̓V���ւ̊S�����̂悤�Ȑ����I�u���Ɛ藣���Ă͍l���������B�V�̂̓��������Ƃ̋��S�������\������ƍl�����Ă�������Ȃ̂ł����āA�V���̌l�I�Ȏ�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��B�w���{���I�x�V���I�̘Z����(�V���l)�N�̋L���ɂ́A�m��A�V���A����A�������ǂ�u�A�z���v(����悤��傤)�Ƃ��������̖����݂Ƃ߂���悤�ɁA�V�̂̊ϑ��Ɛ萯�͍��ƓI�Ȏ��Ƃ������̂ł���A�V���Ƃӂ����W�����̍쐬�⎞���̊Ǘ������ߍ��Ƃ̉^�c�ɂ͌��������Ƃ��ł��Ȃ������B �@ �A�z���̐E���̂Ȃ��œV���ɏ]������̂��V�����m�B�V�̂̊ϑ��ɂ�����B���̂��߂ɐݗ����ꂽ�̂��V���ϑ����̐萯��ł������B���̂ق��̐E���ɂ��Ă����ƁA�A�z�t�͐肢�̐��ƂŁA�n���̋g���̔��f���S������B�V����O�N�ɂ͐V�����s�̓y�n�����������߂ɉA�z�t���h������Ă���B��̍쐬��S������̂���m�B�V���ܔN�ƘZ�N�̋L���ɂ́A�����̍��(������)�ɂ����Ȃ���u����v(������������)�Ƃ����V�����݂��邪�A���̓������肷��̂���m�ł������낤�B�u�R���v(�낤����)�Ƃ�ꂽ�����v���Ǘ����A�ɏ]�������̂��R�����m�ł���B�����v�͐��̓V�q�V�c���c���q�̎���ɐݒu����Ă����B �@ �����܂ł͔���̂킪���̐��x�̐����ł����A����ɑ����Ă���𒆍��̐��x�Ɣ�r���������q�ׂ��Ă��܂��B �@ ���̉A�z���͒����E���ɂ�����V���A��@�A�R������(������)��g�D�ł����j��(���������傭)�Ɩm�����Ƃ��镔���ł��鑾�m��(�����ڂ�����)�����킹�����̂ł���B�V�����m�E��m�E�R�����m�����j�ǂł����Ȃ��Ă����E�����A�A�z�t�����g���ł����Ȃ��Ă����E����S�������B�A�z�t�Ƃ����ď͉̂A�z�܍s���������Ƃ���肢�ł��邱�Ƃɂ��B�����̐��x�ł͖m�������@����ʂɂ�����Ă����̂����A���{�ł͉A�z���Ƃ����ď̂��������������悤�ɁA�肢�����S�ƍl�����Ă����B �@ �萯��͒����Ñ�̓V���ϑ����u���v(�ꂢ����)�ɑ������邪�A�����萯��Ƃ�Ƃ���ɂ��A�z���̐��i���݂ĂƂ��B�������A�萯�䂪�ǂ̂悤�Ȏ{�݂ł���A�����łǂ̂悤�ȕ��@�œV�̂̊ϑ������ꂽ�̂��A�L�^�͂Ȃɂ��c����Ă��Ȃ��B����ł��A�����⒩�N�̎�������A���̈ʒu�̊ϑ���B��e�̒������瑾�z�̍��x�𑪂邽�߂́u�\�v(���̓����v)�Ȃǂ��u����Ă������̂Ɛ��������B����ȑO���瑶�݂��Ă��������v���������Ă����̂�������Ȃ��B�萯��̐ݒu�ꏊ�ɂ��ẮA��㔪��N�ɐ����v�̎{�݂̈ꕔ�Ƃ݂��鋋���ǂ␅�������̖k�����ɂ��鐅��(�݂�����)��Ղ��甭�@���ꂽ���A���Ȃ��ꏊ�Ŋm�F���ꂽ�����Ղ�萯��ɂ��Ă悤�Ƃ���ӌ�������B �@ �V�̊ϑ��Ɛ�m�����Ƃ̎��ƂƂ��čs�Ȃ��ɂ������Đ�i���ł��铂�̐��x��͕킷��̂��ł��ߓ��ƍl������̂ł����A���ۂɂł����̂͊ێʂ��ł͂Ȃ��A�����ɈႤ���x�ł������̂ł��B�����ł͐�m����@����ʂɂ������̂ɂ��ꂪ�t�ɂȂ�A�u���v�ƌĂ�Ă����ϑ������u�萯��v�ƌ����������Ƃ������Ƃ́A�V�̂̉^�s�Ɏx�z�����l�Ԃ̐���(���Ƃ��Δ_��)�̐����I�������m�����邱�Ƃ����ނ��됭���̈��肠�邢�͌l�̋g���̕��ɋ����S��������Ă������Ƃ��Î����Ă��܂��B�����ɂ��܂��A�l�Ԃz�����ΓI�ȉ��l��F�߂Ȃ����{�l�̍l����������̂������Ă��܂��B �@ ���̂��Ƃ́A��1��4�߁u���Ԃ̒����v�ŏq�ׂ��Ă��鎖������������Ƃ͂����肵�܂��B�����ł͑O������ɏ��߂đg�D�I�ȗ����Ă���20���I�����ɑ��z��ֈڍs����܂ł̖���N�̊Ԃ�50����̉���s�Ȃ�ꂽ�̂ɑ��ē��{�ł́A���ォ�畽�������܂ł͒����ł̉���ɒǏ]���ĎO�������������̂́A���̌�]�ˎ��㏉���܂ŖS�N���̊ԉ�������Ȃ������Ƃ�������������܂��B����ł͗�m�͉������Ă����̂��Ƃ����ƁA�r�쎁�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �@ �A�z���ŏd�����ꂽ�̂͗�̎�p�I�ȕ����A�A�z���̗�m�̎�Ȏd���́u���v(�����イ�ꂫ)�̍쐬�ɂ������B���̓��̋g���f���邽�߂́A�E�E�y�E���E���̌܍s�⌚(����)�E��(�̂���)�E��(�݂�)�E��(������)�E��(������)�E��(�Ƃ�)�E�j(��Ԃ�)�E��(���₤)�E��(�Ȃ�)�E�[(������)�E�J(�Ђ炭)�E��(�Ƃ�)�̏\��(���傭)�A����ɁA����(������)���A�A��(����)���A���S���A�C�����Ƃ��������t���̂ł���B �@ ��قǖ����̖��̂Ɋւ��ďq�ׂ����͂������������ɂ���ė��t�����܂��B����䂦���̈�A�̎����́A�x�l�f�B�N�g���Ō������u�������v�̗Ⴞ�ƌ����Ă����������Ȃ��ł��傤�B�������A���̏ꍇ�ɂ͓��{�����̌^�̂��Ƃ������Ɂu�[�����ꂽ�ӎu�̎��R�v�Ɓu���ȐӔC�v�ł���ƍl����K�v�͂���܂���B�����肢���炩��܂��ȁu�p�̕����v���l������Ώ\���ł��B���ӎ��̂����ɒp�̕����ɏ]�����{�l�Ƃ��Ắu�e�l�����Ȃ̍s���ɑ��鐢�]�ɋC��z��v�Ƃ������Ƃ���Ȃ̂ł��B�u���]�v�ƌ����Ă��A���E���Ƃ����{���Ƃ����悤�ȑ傫�����̂��l����K�v�͖ѓ�����܂���B�u���{�l���猩��A�����̑����Ă��鐢�E�ő��h�����A����ł����\���ȕł���v�̂ł��B�����Ɠ�������ɁA�����̑�����Љ�(�E��)�ŕ]������邱�Ƃ���Ȃ̂ł����āA�����̎���i���N�����o������ɗ�̕s���̂��߂ɂ��Ƃ��Δ_�ƂɎx�Ⴊ�����邩������Ȃ��Ƃ����悤�Ȏ��͑傫�����ł͂���܂���ł����B������͂邩�ɑ傫�����́A���݂̐����̐����ɒ��ڌ��т������̋g���ɂ������̂ł��B �@ �r�쎁�́A����̌��͎҂�m���l�̑ԓx�����̒ʂ�v�܂����B �@ ���܂��܂ȑ嗤�̕����������������A���{�l�����҂����̂͌������v�A���p�̋Z�p�Ǝ�p�ł���B���Ƃɂ��V���ϑ��������Ȃ��Ă��A���̔w��ɂ���F���̗��_�I�Ȗ��ɖڂ��ނ����l�q�͂Ȃ��B�W�V������V���Ƃ������Ñ㒆���̉F���_�ɂ������Ďx���Ƃ����Ƃ��Ƃ������ϋɓI�Ȕ����͓`�����Ă��Ȃ��̂ł���B �@ �����̗��v�́A���ゾ���łȂ��A���j�̑S���Ԃ�ʂ��ē��{�l�������S�����������̂ł��B����́A�l�Ԃz�����Ύ҂�S�ɕ`�����Ƃ̂Ȃ������Ƃ��Ă͓��R�̂��Ƃł��B�����Ă��̂��Ƃ́A�V���w���w�Ɋւ��邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A�@���ɂ����Ă������������Ȃ������̂ł��B��1�͂Ƒ�3�͂̑啔���ŕ����̓`���ƕϗe�ɂ��ĉ�����Ă��܂����A�����ł���͂茻���̗��v�𒆐S�ɐ��������̂֒��������N���������Ƃ��킩��܂��B���Ɍf���钷�����p���͍��������������O�ɏ�����Ă�����̂ł����A���̒�������K�m�Ɍ����\�킵�Ă��܂��B �@ ���łɔ���ɐ{��R�̖͌^��������y�}���`����͂����B�������A�����̐l�X�������Ɋ��҂����̂͂Ȃɂ����������v�ł������Ƃ������Ƃ����߂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���A�l�V�����A�@�����Ƃ��������@�͐폟��a�C�������F�肵�Č������ꂽ���Ƃɂ��Ă͂��łɂׂ̂��Ƃ���ł���B �@ �w���{���I�x�ɂ��ƁA�Z���Z(�V����)�N�ɓV���V�c�͍c�@(�̂��̎����V�c)�̕a���̉������F���Ė�t�����������Ă���B�V�c�̕a���d���Ȃ����Ƃ��ɂ��A�쌴�������劯�厛�ł͕����̂��߂̓njo���Ȃ���A�ω���������ꂽ�B���̂��߂ɑ����̑m�����o�Ƃ��A�{���ł��m�̌���(��������)��̏C�s�ł������(����)�������Ȃ���B�������A����ł������̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�Z���Z(�钹��)�N�̋㌎����ɓV���͕�����B �@ ���ꂾ���łȂ��B�����ɂ͓V�����������͂�����ƐM�����Ă����B���(�Ђł�)�̂Ƃ��̍~�J�F������J(�Ȃ�����)�̂Ƃ��̎~�J�F��ɂ������̑m�����������������B�V���ܔN�̝�鯂̂����ɂ́A�����̑m���Ɠ�m�ɋF�点�A�J���Ăڂ��Ƃ����B���̂Ƃ��ɂ́A�����Ȃ��J�͍~��Ȃ��������A�V�����N�̎������甪���ɂ����Ă̝�鯂̂����ɂ͕S�ς̑m�̓���(�ǂ�����)���J��������Ȃ��A���̂Ƃ��ɂ́A�J�ɂ߂��܂ꂽ�Ƃ����B �@ �킢�ł̏������F���Ď��@�����Ă���B�V�c��c�@�̕a�C����������đ��������ɂƂ߁A���̂��߂ɑ����̑m���o�Ƃ�����B�J���F��njo��������B���̂Ƃ������́A�Ђ����A�����܂˂����Ƃ�ړI�Ƃ��錻�����v�̂��߂̎�p�������B���łɂ݂�����̓V���u�[���ƒʒꂷ��Ƃ���ł���B�Ƃ��������A�\���̊W�ɂ���Ƃ����悤���A�萯�p���N���肤��g����\������̂ɂ������A���̕����̎�p�̂ق��͍ЉЂ��瓦�����r�������B�V���ϑ������鯂����ꂽ�Ȃ�A�J��̕�����p�������Ȃ�ꂽ�ł��낤�B �@ �V���V�c�̂��납��썑�̂��߂̕������O�ʂɂ����������悤�ɂȂ����B���Ƒ̐��̐����ƂƂ��ɁA���Ƃ̔ɉh�ƈ��S�������̎��͂Ɋ��҂��ꂽ�̂ł���B�Ȃɂ����A�V�����ŁA�������悭����A�u�a�͗��s(�͂�)�炸�A���͈����ł����Ăق����B���̌��ʁA�����A���y�A�l�����ЉЂ��������A���J�������炵�Ă����Ƃ����w�������o(�����݂傤���傤)�x��w�m���o(�ɂ�̂����傤)�x���Ƃ��ɏd�������悤�ɂȂ����B�Z���Z(�V����)�N�ɂ͎g���������ɂ��킵�ė��o��������Ă���B���ƌ��͂ƕ����̌������{�i������B �@ ��E(������)�����ɂ̖ڕW�Ƃ��镧������l���ŏ��Ɋw�̂́A�����̋ꂩ�猻���I�ɓ������@�A�������v�̏@���������B�l�́A�����̓V���w����萯�p���w�сA������V������p�Ƃ��Ď�e�����̂ł���B �@ �����̎�e�͓��{�j�̒��œ��M���ׂ��傫���o�����̈�ł�����x�l�f�B�N�g�����ڂ��܂����B�u�e�X���m�������v�̒��ł́u�����I�ɓ��{�͎x�߂��畧�����A�w���Ƃ���邽�߂ɏ��ꂽ�x�@���Ƃ��đ�X�I�ɍ̂���ꂽ�v�Ƃ�����������܂��B���L�ɂ��Ɓw�x�̒��̓W���[�W�E�T���\���̒�������̈��p���Ƃ������Ƃł����A����ł����������Z�������̒��ɖ{���I�ɏd�v�ȊT�O���܂܂�Ă���̂�F�����Ă������Ƃ��킩��܂��B�u���̃W�����}�v�ɂ́A�u�K�^���F�肷��V���͂��邪�A�܍߂̋V���͂Ȃ��v�Ƃ����ꕶ������܂��B�����čX�ɁA��̈��p���̍Ō�̒i���Ō����Ă���u��E�����ɂ̖ڕW�Ƃ��镧���v������Ƃ͈قȂ鐫���̂��̂ɒ������ꂽ���Ƃɂ��Ắu�C�{�v�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B �@ ���̂悤�ȓN�w�͓��{�ɂ͌����Ȃ��B���{�͈�啧�����ł���ɂ�����炸�A���܂����ė։�Ɵ��ς̎v�z�������̕����I�M�̈ꕔ���ƂȂ������Ƃ͂Ȃ��B�����̋����́A�����̑m���������l�I�Ɏe��邱�Ƃ͂����Ă��A���O�̕��K�▯�O�̎v�z�ɉe�����y�ڂ������Ƃ͈�x���Ȃ��B���{�ł͏b�⒎���A�l�Ԃ̍��̐��܂�ς�肾����Ƃ������R�ŁA�E���ʂ悤�ɂ���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�܂����{�̑�����o���ɂƂ��Ȃ��V���́A�։�v�z�̉e����S�R�Ă��Ȃ��B�։����͓��{�I�Ȏv�z�̌^�ł͂Ȃ��B���ς̎v�z���܂��A��ʖ��O�ɑS�R��������Ă��Ȃ�����łȂ��A�m�����炪����Ɏ�������āA���ǂȂ����Ă��܂��Ă���B�w��̂���m�������́A���T�g�����k���l���J�����l�Ԃ́A���łɟ��ς̋��n�ɂ���̂ł���A���ς͍������ɁA���Ԃ̂������ɂ���A�܂��l�͏��̖̒��ɂ��A�쐶�̒��̒��ɂ��u���ς�����v�A�ƒf������B���{�l�͐̂����ɁA����̐����̋�z�ɂ͋����������Ȃ������B�ނ�̐_�b�͐_���݂̕���͓`���Ă��邪�A���҂̐����̂��Ƃ͏q�ׂĂ��Ȃ��B�ނ�͕����̎���ɂ�������ʉ���̎v�z�������ĂĂ��܂����B�ǂ�Ȑl�Ԃł��A�ł��g���̒Ⴂ�S���ł����A���˂Ε��ɂȂ�B���d�ɍՂ��Ă���Ƒ��̈ʔv��\�����t�����ɁA�u�����܁v�ł���B���̂悤�Ȍ��t�Â��������镧�����͂ق��ɂ͂Ȃ��B�����ĕ��}�Ȃ������ʂ̎��҂ɂ��āA���̂悤�ɑ�_�Ȍ����������鍑�����A���ς̒B���ȂǂƂ����悤�ȍ���ȖڕW�𒆐S�ɕ`���Ă��Ȃ��Ƃ����Ƃ́A�\������������Ƃ���ł���B���������Ƃ���łǂ݂̂����ɂȂ���̂Ȃ�A�l�Ԃ͉����킴�킴�ꐶ�U���̂��ꂵ�߂āA��ΓI��~�̖ڕW�ɓ��B���悤�Ɠw�͂���K�v�͂Ȃ��B �@ ���̈��p���ɕ`����Ă���u���ρv�̓��{�I�����́A����Ƃ������͂ނ��뒆���ɐ����������̂�������܂���B�������A������Ƃ����ĕ����`���̓����͂����łȂ������ȂǂƂ͌����܂���B���ɑ嗤����n���������m��ނ̒n�ŏC�Ƃ��ċA���������{�l�m�����{���̗։�Ɵ��ς̎v�z��������Ƃ��Ă��A���ꂪ���̍��ɍ��t���Ȃ������Ƃ���������F�߂Ȃ��킯�ɂ͎Q��܂���B �@ ����́A�����w���فx�̒��Ńt�F���C����17���I�����̓��{�Œ��N�ɂ킽���Ċ���̕z���ɐg���S����������Ɏ��̂悤�Ɍ����\�킵�����ۂƂ�������ł��B �@ �m�������Ƃ͂������̍��ɂ͂��O�⎄�����̏@���͏��F�A�������낳�ʂƂ������Ƃ������B�c�c���̍��͏��n���B�₪�Ă��O�ɂ��킩�邾�낤�ȁB���̍��͍l���Ă������A�����ƕ|�낵�����n�������B�ǂ�ȕc�����̏��n�ɐA������A��������͂��߂�B�t�����͂�Ă����B��X�͂��̏��n�Ɋ���Ƃ����c��A���Ă��܂����B �@ �������A������A���{�ɏ㗤�����Ƃ���ɒ������ꂽ�̂ł��B �@ ���̌�A�����̓��{�ŕ����I�F���ς��ǂ̂悤�ɕω����Ă��������Ƃ������Ƃɂ��Ă͑�3�́u�����̉F���v�ŏڂ���������s�Ȃ��Ă��܂��B���̎�v�ȓ_�́A���ӐM���爢��ɐM�ւ̈ڂ�ς�ɔ����Đ������ɓY���u�V�v�̎v�z���琅�����ɓY���u�Ɋy�v�̎v�z�ւ̕ϑJ�ɂ���A���ꂪ���ẨF���ςւ̉�A�ƌ�����Ƃ����������q�ׂ��Ă��܂��B�����Ă��̕ω��ƕ��s���āA�����ƁA�Ɋy��n���Ƃ̊Ԃ̋������������l������悤�ɂȂ������Ƃ��w�E����Ă���A���ɂ͂ЂƂ̒뉀�̒��ɏ�y���Č����鎎�݂����s�Ȃ�ꂽ�Ƃ������Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B�@ |
|
| ���ߐ� | |
|
���{�j�̋ߐ��������n�܂����̂��͂����ȍl����������܂����A���[���b�p�l�̓n���A�Ƃ��ɃL���X�g���z���҂̓n���𒆐��Ƃ̋�ʂ�^����w�W�̈�ƌ��邱�Ƃ��ł��܂��B�ނ�́A����܂œ��{�l���z�����邱�Ƃ����Ȃ������َ��̕��������̍��ɏЉ�����肩�A�ϋɓI�ɔނ�̎v�z�\�������A���E�ς���щF���ς��܂݂܂��\���ڐA���悤�Ǝ��݂��̂ł��B
�@ �V���A�n���A���̊Ԃɂ��邠���镨�����A�A�����A�������A�l�Ԃ��A��͑S�m�S�\�̐_�ɂ���č��ꂽ�Ƃ����̂��L���X�g���̋��`�̊�{�I�ȑO��ł��B�����đ�n�����`�ł���Ƃ������̓L���X�g���̐����ȑO���炠��܂����B�����Ԃ���͎��ۓI�ȈӖ��̖R�������ł������A15���I�����Ȍ�n���w�I�������������Ɏ����Ċm�ł�����ɂȂ�܂����B�����Ĕނ炪���{�ɓ��B����16���I�����ɂ́A�����m���Ă��邷�ׂĂ̑嗤��s���S�Ȃ���L�ڂ������E�n�}���`����A�n���V������Ă��܂����B�����ĕz���̂��߂ɓ��{�֓n�������J�g���b�N���k�����́A�n�����F���̒��S�ɐÎ~���Ă��āA���̎��͂�����A���z��A�f�����V�g�ɓ�����Ȃ��瓮�����A�X�ɂ��̊O����V���������Ă��āA�����ɍP��������߂��Ă���Ƃ����F�����f������{�l�ɋ����܂����B���̓V�����́A�A���X�g�e���X�ɂ���đ听���ꂽ�Ñ�M���V���̎��R�w�ƍ��v���A�������L���X�g���̋��`�Ƃ��������Ȃ��̂ł��B �@ ��n�����`�ł���Ƃ���n�����ƓV�������ŏ��ɓ��{�l�ɋ������̂̓t�����V�X�R�E�U�r�G��(1506�|1552)�ŁA���{�ł̕z��������1549�N����̖�3�N�Ԃł����B�R�y���j�N�X�̒n���������\����Ă���6�N�قnj�̂��ƂŁA�������A����͂܂����F����Ă��܂���ł����B�R�y���j�N�X�̐����x�������u���[�m���ΌY�ɏ�����ꂽ�̂͊ւ�������Ɠ���1600�N�ł��B���[���b�p������{�ւ̒m�I���̓`�B�������ς�J�g���b�N�̕z���҂ɂ���čs�Ȃ��Ă����̂ł�����A�����n�����������㕚�����Ă����͓̂��R�ł��B���{�l�����z���S�̒n�����ɂ��čl����悤�ɂȂ����̂́A����g�@(1684�|1751)�ɂ��m���A���֎~�ߊɘa�Ȍ�ŁA18���I���㔼�ɂȂ��Ă���̂��Ƃł��B �@ �����̎����ʂ��ē��{�l���������[���b�p�ɉ萶���A������v�z���ǂ��~�߂����Ƃ������Ƃɂ͂����ւ����������܂��B���ҍr�쎁�͑�ʂ̎�������g���Ă����Nj����A���ڂ��ׂ������ɓ��B��������łȂ��A�]�ˎ��㒆���̍��w�҂��������m�̉F���_�ƁA�L�I�ɋL�q���ꂽ�_�b�Ƃ̗Z����}�������Ƃ����_���A�u�_��͍����Ɨ����ł���\���̐钷�ɂ͂��܂鍑�w�̐��_�͋ߑ�̓��{�ɂ��Z���e�𗎂Ƃ����ƂɂȂ�v�Ǝw�E���܂����B �@ �b�x��B�U�r�G�������{�ŕz�����n�߂Ă��琔�\�N�ԁA���l���̕����m�����q�w�҂���̔����͂��������̂́A�L���V�^���͎��R�ɍs�����邱�Ƃ��\�ł����B���̊��Ԓ��ɓ��{�l�M�k�����悻�l�\���l�ɂ��B�������ƁA�����Ă��̌�L�b�G�g�̎����̖����ɒe�����n�܂�A1614�N�Ɏ����Ă��ɓ��얋�{���S�ʓI�ȋ��Ɛ鋳�t�Ǖ����s�Ȃ������Ƃ͂悭�m���Ă���ʂ�ł��B�����Ēe���̍Ō����߂��������̂������̗��̒����ł����B�Ȍ㖾���ېV�܂ŁA�B��L���V�^���͎c�������̂́A���R�ƃL���X�g����_���邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B�Ƃ��낪�n��������ѓV������_���邱�Ƃ݂͜�Ȃ��s�Ȃ�ꂽ�̂ł��B �@ ���̏؋��ɁA17���I�̒�����2���̉F���_����������Ă��܂��B��͌��䌳��(����悤)��1656�N�ɏ������w�����ِ��x�ł���A���܂ЂƂ́A����Ƃقړ������ɏ����ꂽ�Ɛ��肳���w��V�����x�ŁA���҂͏��ь���(����Ă�)�Ƃ����l�ł��B���̓���ɂ͋��ʂ̎�{������܂��B����́A�y�h���E�S���X(1535�|1600)�Ƃ����C�G�Y�X��m�����{�ōs�Ȃ��u�`�̃e�L�X�g�Ƃ���1590�N��ɏ������w�V���_�x(de Sphaera)�ł��B�w�V���_�x�̓J�g���b�N�̋��`�m�Ɏ����Ă��܂����A�w�����ِ��x�ł��A�w��V�����x�ł��A�@���I�ȋL�q�͏Ȃ���A�����ς�V���w�Ǝ��R�w�Ɋւ��鎖�����������グ���Ă��܂��B���̓���������̐l�ɓǂ܂ꂽ���ǂ����͕�����܂��A16���I�㔼�ɓ`���������m�̉F���ς��f�₹���A���R�Ǝp���ꂽ���Ƃ������؋��Ƃ��Čy���ł��܂���B�������̉F���ς́A18���I�ɒ���̓V���w�Ґ���@��(���傯��)�����킵���{�ɂ���đ����̐l�ɒm��ꂽ�̂ł��B����̏ꍇ�ɂ͒����l�m�w�҂����킵���{�̉e�����傫�������Ƃ������Ƃł����A�Ƃɂ����L���X�g���ȊO�̂��̂��C�O�������邱�Ƃɂ͊��e�ł������ƌ����܂��B�����Ă��̑ԓx�́A���{�̒��ɂ����ėv�E���߂��V�䔒���̉���Ƃ����d�v�Ȏd���������a��t�C�ɂ����Ă����l�ł���܂����B���̂��Ƃ��r�쎁�͎��̂悤�Ɍ����\�킵�܂����B �@ �t�C�┒�Ƃ������{�̒����̐l�Ԃ܂ł����A�_�ɂ��V�n�̑n�����͔r�˂��Ȃ�����A�V���n�����͎����B�X�R���N�w�̍��i�ł���L���X�g���I�Ȏv�z�͑ނ��Ă��A�A���X�g�e���X�I�ȉF���_�͎c���B���ꂪ�A�L���X�g�����Ƃ����Ċw���[���b�p�F���_�ɂ��������{�I�ȑԓx�ƂȂ����B �@ �n�������`����ꂽ�Ƃ��ɂ����{�l�̊Ԃɂ͋��┽���̂悤�Ȃ��̂��N����Ȃ������̂ł��B �@ �r�쎁�ɂ��ƁA���z���S�̒n�������킪���ɏЉ�ꂽ�̂�18���I�㔼�ɃI�����_�̖{�̘a��Ƃ��Ăł������Ƃ������Ƃł��B�n���̎��]�ɔے�I�Ɍ��y���������͂���ȑO�ɂ��������Ƃ������Ƃł����A�F���ς�傫�����������̂͒n���̌��]�Ƃ����ϔO�̓����ł������̂ł�����A���]�����Ɍ��y�������̂͂��قǏd�v�ł͂���܂���B���̈Ӗ��ŏd�v�ȓ��{��̕����́A����̒ʎ��̉Ƃɐ��܂ꂽ���w�Җ{�ؗlji��1770�N�Ȍ�ɏ������l���̖{���Ƃ������Ƃł��B���̒��ł��ł��ڂ����̂�1792�|93�N�ɏ����ꂽ�w���z����������x�ł��B����́A�W���[�W�E�A�_���X�Ƃ����C�M���X�l�����킵���{�̃I�����_��ł����Ƃɂ������̂ŁA�r�쎁�ɂ��ƁA�P�v���[�̑ȉ~�O���_�Ɋ�Â��n�����A�f����q���̉^���A���H�E���H�̐��N�ɂ��Ă̌����I�Ȑ�������łȂ��A���z�̎��]�A�n���̌��]�Ǝ��]�A�f���̋O���̌X�Ίp�x�A�O�����a�Ɖ�]�����A���̍�]�����Ȃǂɂ��Ă��ڂ������l�������Đ������Ă���Ƃ������Ƃł��B�������A�����̖{�͊��s���ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�ʖ{�Ƃ��Č���ɓ`�����Ă���̂ł��B �@ �w���z����������x�͂��������ڂ������e�������Ă���̂ł����A����Ό��ۘ_�����ŁA���_�ɂ͐G��Ă��܂���B�j���[�g���́w�v�����L�s�A�x�����ɏo�Ă���S�N�ȏ�o�����Ƃ��̂��Ƃł���A�{������Ɋւ���������ǂ`�Ղ�����ɂ�������炸���y����Ă��Ȃ��̂ł��B���������̓_�́A�{�̒�q�ɂ�����u�}���Y��1802�N�Ɋ��������w��ېV���x�ɂ���ĕ���Ă��܂��B���̖{�����s���ꂸ�ʖ{�Ƃ��ė��z�����̂ł����A�C�M���X�l�W�����E�P�C���́w���R�N�w�E�V���w����x(1725�N��)�̃I�����_������{�Ƃ������̂ŁA�j���[�g���̗͊w�̗v�_�𐳊m�ɕ\�����������łȂ��u�}�̓Ǝ��̈ӌ��������܂�ł��܂��B�����Ƃ��A���̈ӌ������ɂ͎�q�w�̉A�z�������f���Ă��܂��B���̈Ӗ��Ŗ{�͂܂������I�Ȃ��̂����������Ă����̂ł����A���̔��ʂɍr�쎁�͎��̂��Ƃ�F�߂Ă��܂��B �@ ����ł��A�u�}�͉F���̖������݂͂Ƃ߂�B�u���z���P�������s���̉Άv�ł���A�����̍P�����u�L�喳�ӂ̓V�ۂɎU�����v�Ă���Ƃ����B�����̃��[���b�p�ł݂͂Ƃ߂���悤�ɂȂ��Ă������̂́A�ȑO�ɂ͋������������߂��ꂽ�����F�����ł���B���{�ł͂��������Ȃ�Ǝ������B �@ �����āA�������Ȃ��`�ł͂����Ă��n�����͓����̒m���l�̊ԂɍL����A����ɋ����S�������ݖ�̎v�z�Ƃ�����܂����B���̑�\�I�Ȑl�����i�n�]��(1747�|1818)�ƎR��崓�(1748�|1821)�ł��B �@ ���̓�l�͓�����̐l�ł����A�]���͍]�˂ɏZ�މ�ƁA崓��͑��̗��։��̔ԓ��ƁA������������������Ă��܂����B����ɂ�������炸���̓�l�����ɍ�����`�I�ȍl�����Ƃ����_�ŋ��ʂ��Ă����̂͂����ւ��[�����Ƃł��B�]���͂��Ƃ��Ɖ�ƂŁA�����G��`���Ă����̂ł����A���ꌹ���̉e�����ėm��Ɨ��w�ɊS�������A�I�����_���̐��E�n�}�����Ă���������肷�邤���ɐ����̓V���w�̒m�����z�����܂����B���̒���������崓������̓V���w��E�������ĕS�ȑS���I�_�e�w���̑�x�̒��Ɋm�M���������̂ł��B �@ �]���̑ԓx��v�Ă����q�ׂ܂����B �@ �]���̗͓_�͓��{�̓`���I�Ȏv�z�ɂ������āA���m�̉Ȋw�v�z�̗D�ʐ����ꊇ���Ă݂Ƃ߂�Ƃ���ɂ������B���v�z�ƍۗ����đΗ����Ă����̂��n�����A������]���͒n�����ɂ������Â��A���̌[�ւɗ͂𒍂����̂ł���B �@�Ƃ����āA�]�����L���X�g���ɂ�������ԓx�͕ʂł������B�_�ɂ��V�n�̑n���݂͂Ƃ߂Ȃ��B�w�t�g�O�M�L�x(�����ς낤�Ђ���)�ł͐����̃A�_���ƃC�u��m�A�̔��M���Љ�邪�A�V�n�̑n���ɂ��ẮA�u�V�n�J������O�l�Ȃ��A�̂ɒm��ׂ����Ȃ��v�Ƃ����đނ���B���m������]�����邪�A�����܂ł����ꂪ�����I�ł���ƍl����Ƃ��낾���ł���B�������Ɏ���Ă���̂ł͂Ȃ��B �@ 崓����n���������ՂɎ��ꂽ�킯�ł͂���܂���B���̏؋��Ƃ��čr�쎁�́A�w���̑�x�̏��e�{�ɂ����镶���̒��Ɏ��̕������邱�Ƃ��w�E���Ă��܂��B �@ �n���V�̖@�A���ւ𒆐S�Ƃ��Ė��Õϓ��Ȃ��B�n�y�ܐ���V�P���݂Ȑ���B���͒n��S�Ƃ��Đ���A�n���V�ɂ�Ĉ������A���s��x���̊O�͐��Ă���ׂ��B��������Ɩ��n�����B��̌N�q��҂ׂ��B �@ �܂�A�e�ՂɐM�����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���������ꂩ�牽�N���o���ď����ꂽ�w���̑�x�́u�V���v�̏͂ɂ͐��m�l�̌������ʂ�_�j���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƔF�߂鎟�̕����܂܂�Ă��܂��B �@ ���z�͓V�n�̎�Ȃ�B�n�͎�ɂ��炸�B���z���������đ��j(���̓V��)�̓����́A�����Ȃ�ׂ��B���ɂĂ������b�̐l�͑�D�ɂ̂�Ēn��������A���̒m�炴�鏊�����邱�ƁA�����̋y�ԂƂ���ɂ��炴��A�V�n�̂��Ƃ͂���ɔC���āA���̑������˂Ԃ�(�Ȃ߂�)�̂ق��͂���܂����Ȃ�B�K���������m�̏p���^�����Ȃ���A�����M���ď]���ׂ����̂Ȃ�B �@ �������Ȃ��炱���P���Ȑ��m���q�ƌ��Ă͂Ȃ�܂���B���m�̉F���_���A�܂�����܂ł킪���ōs�Ȃ��Ă����������q�w�̉F���_���\���ᖡ������ŁA�������ɂ����đO�҂ɌR�z���グ����Ȃ��Ɣ��f���Ă̔����Ȃ̂ł��B�L�I�̉F���������b���A�����̐{��R�����A�����̊W�V���E�ӓV�����A崓��Ɍ��킹��u�����̋Y�ɂ��y����Ȃ�B���m�l�Ɍ��������ɂ́A�O�̏����Ƃ��ւǂ��������T�ւďӂׂ��v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����ł��ē��m�̊w�������ł����ł������l�ƌ��ߕt�����̂ł͂���܂���B���̂�����̋@���́A�r�쎁�̕��ɂ���Č���̂��悢�Ǝv���܂��B �@ �w���̑�x�̏I�͂ɋ߂��u���S��v�Ɓu���S���v�ł́A�����Ɏ�q�w�̋S�_�_�����ʂɂ�������B�Ƃ��ɁA�V�䔒�́w�S�_�_�x�ɂނ���ꂽ�ᔻ�����т����A�u����Ƃ�ׂ��Ƃ���Ȃ��v�ł���B崓����A�l�Ԃ̐�������q�w�̐����Ƃ���C�̗��_�Ő������邪�A��q�w�̗썰�_�ɂ͗^���Ȃ��B��q�w�ɂ���u�S�_�v(����̗썰)�̑��݂͔ے肳���B�l�Ԃ͖��ɋA��̂��B �@ �����Ɛ_���ɂ�������U���͑S�҂ɂ킽��B�Ɋy��n���͑��݂��Ȃ��B�։��]�������肦�Ȃ��B�ɐ��_�{�̗쌱�ȂǂȂ��A�����������Ă��_���������邱�ƂȂǂȂ��B�_���������݂��Ȃ��̂ł���B �@ 崓����w���̑�x�Ő^�ɂׂ̂��������̂́A���̖��_�_�ƗB���_�������̂ł���A�u�V���v�Ř_�����n�����͂��̓������Ƃ��������Ă���B �@ 崓������S�Ȕᔻ���_�̎�����ł��������Ƃ��킩��܂��B �@ �����A�n���������l�����Ȃ������킯�ł͂���܂���B�O�Y�~��(1723�|1789)�͒n�����̐������Ă������F�߂悤�Ƃ��Ȃ������Ƃ������Ƃł����A����ɂ��čr�쎁�͂����q�ׂ܂����B �@ �~�����n������e�F�ł��Ȃ������̂́A�n�����S�������Ƃɂ����A���R�Ɛl�Ԃ�I�ɐ�������u�𗝁v�̓N�w�̌n���m�����Ă�������ł������ƍl������B���̉�����ł���w����x�͈ꎵ���ܔN�Ɋ������Ă����̂ł����āA�������n�������݂Ƃ߂�A�ނ̓N�w�̌n�͔j�]���˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�ނ��A�����ɔ~���̕ێ琫���w�E���Ă��悢���A���Ȃ̓N�w�ւ̎��M�̕\���Ƃ����ׂ��ł��낤�B �@ ���������l�����܂������A�S�̂Ƃ��Ă͑��z���S�̒n�����͓��{�l�̊ԂɃX���[�X�ɓ����Ă����܂����B�r�쎁�́A���{�ɒn�������`������̂��x�ꂽ�ő�̗��R�̓��[���b�p����̋����ɂ������Ƃ��Ă��܂��B���̑��̗��R�Ƃ��ẮA���łɐG�ꂽ�悤�ɁA�J�g���b�N���k�����̓`�����D�܂Ȃ������Ƃ����_���������܂��B�����čr�쎁�͎��̂悤�Ɍ����Ă��܂��B �@ �n�����ɂ���������{�l�̑ԓx�ɂ��̗��R�����Ƃ߂�͓̂���B���łɂ݂��悤�ɁA���{�l�̂������ɂ͒n�����ւ̔����͂قƂ�ǂ݂Ƃ߂��Ȃ������B����́A���{�l���n�����̍������𗝉����Ă����Ƃ��������A�n�����̏ꍇ�������ł������悤�ɁA���{�l�̉F���_�I�Ȗ��ւ̊S�̊����n�������R�Ȃ���e�������Ɨ������ׂ��ł��낤�B �@ �����Ă���ɁA���̂��Ƃ����y����Ă��܂��B �@ �~���̂悤�ȓN�w�҂����݂������A�x����Ȃ�����A�n�����͔�r�I�X���[�Y�ɓ��{�Ɉړ����ꂽ�B�������Ȃ���A�n���������ăj���[�g���̗͊w�����{�ɈڐA����Ă��A���ꂪ���{�̉Ȋw�v�z�Ɏh����^���A�V���ȉȊw�̔��B�����Ȃ����_�@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B�j���[�g���͊w�����ƂɐV�����Z�p���J�������Ȃ������B�@ |
|
| �� | |
|
16���I�㔼�ɃL���X�g���z���҂����ɂ���đ�n�����`�ł���Ƃ����n�����ƁA�V�����O�k�Ƃ���K�w�I�\�����������V�E���n���𒆐S�Ƃ��ĉ�]����Ƃ����V�����Ƃ������炳��A���̌�L���X�g���������I�ɔr�����ꂽ��ɂ����̒n�����E�V������_����͎̂��R�ł��������ƁA������18���I�㔼�ɂȂ��ăI�����_����A���������Ђ�ʂ��Ēn�������m���A����ɂƂ��Ȃ��ĉF���������̍L��������Ƃ����m�����������ꂽ�Ƃ��ɂ����{�l�͎v�z�I�Ō��������Ȃ��������A����W�����悤�Ƃ����Ȃ��������Ƃ��O��q�ׂ��܂����B�ȒP�Ɍ����A���m�l���w�҂����Ԃ�ɂ��Ă��܂��قǐ��_�I�Ռ�����V���������Ă����{�l�͂�����u�����A�����ł����v�ƌ����ĕ����������̂ł��B
���͂��̈Ⴂ���߂̕����ƒp�̕����̈Ⴂ�Ƃ��Ĕc�����܂��B
�@ ���{�l�́A���m�l�̖ڂŌ����Ƃ��ɂ́u���@�Ǝv����s�ׁv�C�Ő��F���邱�Ƃ�����̂ł��B�n���������߂ĕ������ꂽ�Ƃ��Ɂu�����A�����ł����v�ƌ����ĕ��������̂́A���m�l�ɂ��Ă݂�Ζ��@�Ǝv����s�ׂ��ȒP�ɒʂ��Ă��܂��̂Ɠ������炢�s���Ȃ��Ƃł��傤�B�����ɂ́A���m�l�̎Љ�ł͌��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��A���{�l�Ɠ��̍s���̌^������̂ł��B�s���̌^�͕����̌^�ł͂���܂��A�����T���|��ɂȂ�܂��B�ޏ��͂��������s���̌^���������T���o���A����炪�ǂ̂悤�ɐ�������̂��͂��邱�Ƃɂ���ē��{�������p�̕����̈��ł��邱�Ƃ����A�����Ă���ɂ��̒p�̕����̒��Łu�[�����ꂽ�ӎu�̎��R�v�Ɓu���ȐӔC�v����F�Ƃ�����̂ł��邱�Ƃ�˂��Ƃ߂܂����B �@ ���m�ł͂Ȃ��n�������u���@�Ǝv����s�ׁv�Ɨގ��̂��̂ł��邩�̂悤�Ɏ��ꂽ�̂��Ƃ����ƁA�l�Ԃ��������邱�̒n��ƁA�_���ȓV��E�Ƃ���ʂ��钁�����ے肳��邩��ł��B�����̋�����Ƃ���ł́A�S�m�S�\�̗B��_�͓V��E�ɋ����܂��B���̓V��E�ł͒n��(�����E)�̌����Ƃ͂܂������Ⴄ�������x�z���Ă���̂ŁA�����ɑ����錎�A���z�A�܂̘f������і����̍P���͌����Ēn��ɗ����Ă��Ȃ��̂ł��B���̐��Ȃ钁�����^���̂̓L���X�g���k�Ƃ��Ă͖��@�Ǝv����s�ׂł������̂ł��B �@ �Ƃ��낪�n�����ɂ��ƁA�����A�����A�ΐ��A�ؐ�����ѓy���͒n���̓��ނł���A���͒n���ɏ]��������̂��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����́A�V��E�ƒn��E�̊Ԃɂ���ׂ������̍��{�I�ȉ��ς��Ӗ����܂��B����́A�ꌩ�����Ƃ���A�_��M���邩�ǂ����Ƃ������Ƃɂ��������Ɍ����܂��B�ł��A�n������M���邩��Ƃ����Ă��ꂪ�K�������Ɛ_��ے肷�邱�Ƃ��Ӗ�����킯�ł͂���܂���B�K�����I���A�j���[�g�����A�����ƌ�̎���ł̓A�C���V���^�C�����A���̑��ɂ���������̐l�������Ȋw�I�^���d���邪�䂦�ɂ܂��܂��M�S���ł������̂ł����A�ߐ������ɂ͈��|�����̐l�X�͖�肪��N���ꂽ�Ƃ��������Ŗ������ł���ׂ��M���ے肳�ꂽ�悤�Ɋ����A���̖��̂���������������҂��u���@�Ǝv����s�ׁv�������悤�Ɏv�����̂ł��傤�B �@ �Ȃ����ꂪ�u���@�v�ł��邩�𗝉�����ɂ́A�x�l�f�B�N�g���u�����ۑ�\���{�v�Ō��������̌��t���v���o���K�v������܂��B �@ ���鍑���������ʂ��Đ����߂郌���Y�́A���̍������p���郌���Y�ƈقȂ��Ă���B����ꂪ���̂����鎞�ɕK�������ʂ��Ă���ዅ���ӎ����邱�Ƃ͍���ł���B�ǂ̍��������Ƃ����炵������Ȃ��Ƃ���ɂ��Ȃ��B�����Ă��鍑���ɂ��̍����ɋ��ʂ̐l���ς�^����A�œ_�̍��킹���A����(�p�[�X�y�N�e�B�u)�̎����̂����A���̍����ɂ́A�_�l����^����ꂽ�܂܂̕��i�̔z�u�Ƃ����ӂ��Ɏv�����܂�Ă���B �@ �u�p�[�X�y�N�e�B�u�v�́A�����̏ꍇ�u���ߖ@�v�Ɩ�Ă��܂��B�������̎��_��������Ƃ��ɁA����ɋ߂����̂͑傫�������A�������̂ł������ɂ���Ώ�����������Ƃ������ۂ���̉�ʏ�ɒ����ɍČ������@�̂��Ƃł��B�����Ώۂł����_��ς��ĕ`�������Ԃ������G�ɂȂ�̂͗e�Ղɗ����ł��邱�Ƃł��傤�B�������u�p�[�X�y�N�e�B�u�̎����̂��v�Ƃ����̂͂����܂Ŕ�g�ł����āA��ԔF���̖��Ƃ��Ă̓V�����ƒn�����̔�r�Ƃ������ƂƂ͉��̊W������܂���B �@ ����������ł��ߐ������ɒn������������ꂽ�Ƃ��ɂ́A���[���b�p�̐l�X�́u�_�l����^����ꂽ�܂܂̕��i�̔z�u�v����邩�A����Ƃ��̂Ă邩�ƑI���𔗂�ꂽ�悤�Ɋ������̂ł��B�����Ĕނ�́A������̂Ă�̂͐_�l�ɔw���Ĉ����ɉ��S����u���@�v�ȍs�ׂ��Ǝv�����̂ŁA�n�������x������w�҂��Ă��E�����̂ł��B �@ ������{�l����p���Ă���p�[�X�y�N�e�B�u�ɂ��A�l�Ԃ��N�����Ƃ̂ł��Ȃ��_���ȓV�E�ȂǂƂ������̂͑��݂��܂���B�����������{�l�ɂ́A�l�Ԃz����B���̐_�ȂǂƂ������̂͌����܂���B�����������̂�������p�[�X�y�N�e�B�u������Ă��Ȃ��̂ł��B������16���I�ɃJ�g���b�N���k����V������������ꂽ�Ƃ��ɂ́A�͂������ł����ƁA������킸�ɕ�������܂������A���{�l�̐��_�̍��ꂪ����ɂ���ĉe�������킯�ł͂���܂���B�����Ă��ꂩ���S�N�قnjo���āA�I�����_�l�������Ă��������ɂ���Ēn������m�����Ƃ��ɂ��Ȃ�قǂ���Ȃ��̂��ȂƊȒP�Ɏ���܂����B������ɂ��Ă����ꂪ�u�V�ɂ܂��܂�����̕��v��M���邩�A�M���Ȃ����Ƃ������ƂɌ��т��킯�ł��Ȃ��A�����I�v�z�ɉe�����y�ڂ������Ȃ������̂Ŗ��{�������Ȃ������̂ł��B �@ ���������킯�ŁA���m�l���n������m�����Ƃ��Ɏ����_�I�Ռ�����{�l����������͓̂���̂ł����A�F���_�Ƃ͈Ⴄ���ɂ���Ǝ����Ռ��̗Ⴊ���邱�Ƃ��w�E���Ă����܂��傤�B���ł͂���������Ƃ��Ċo���Ă���l�����Ȃ��Ȃ�܂������A1945�N9��29���̒��A�V����������u�Ԃɓ��{�l�����������̂͂��̏Ռ��Ɏ��Ă����ƍl�����܂��B���̐V����1�ʃg�b�v�ɁA���a�V�c�ƃ}�b�J�[�T�[����������ŗ����Ă���ʐ^���f�����Ă��܂����B���̎ʐ^�ɂ��ăW�����E�_���[���w�s�k��������߂āx�ŏq�ׂ����̌��t�͎��ɓK�ł��B �@ �ȏ�̂悤�Ȕw�i�̂��ƂŁA���{�S�̂����̎ʐ^(�u���̎ʐ^�v�ɖT�_)�ɏo������̂ł���B����͑S��̊��Ԃ�ʂ��čł��L���ȉ摜�ł���A�����㌎�����̐V���Ɍf�ڂ��ꂽ�B�ʐ^�͐�q�̓V�c�Ƃ́u��v�L���̉e�𔖂����A�����Ȃ̌��{������ʑ����ɂ�����(���_�̔Ԍ������ɂƂ��Ă͂܂������Z�������ł�����)�B���������ĂȂ���������Ȃ́A���̓��̐V����������悤�Ƃ����̂ł���B�ʐ^�ɂ́A�}�b�J�[�T�[�ƓV�c���A�}�b�J�[�T�[�̏h���ꏊ�̈ꎺ�ŕ���ŗ����Ă������A�ǂ��炪���傫�Ȍ��͂������Ă��邩�͈�ڗđR�ł������B�}�b�J�[�T�[�ō��i�ߊ��̓J�[�L�F�̊J�݃V���c�ɌM�͂������A��������ɂ��āA���������Ђ����āA�C�y�Ƃ����Ă����悤�Ȏp���ŗ����Ă���A�������V�c�������낷�悤�Ȓ��g�ł������B�����A�i�ߊ��̍��ɗ��V�c�́A�瑕�̃��[�j���O�p�ŋْ����ė����Ă���B��l�̎w���҂̔N��̍����A�}�b�J�[�T�[�̏�������߂�v���ł������B�����}�b�J�[�T�[�����͘Z�܍B�l�l�̓V�c�́A�}�b�J�[�T�[�̑��q�ł����Ă����������Ȃ��N��ł������B �@ ���̎ʐ^���Ȃ����{�l�̐��_�ɑ傫���Ռ���^�����̂��A�u�����Ȃ̌��{������ʑ����ɂ������v�̂��́A�����V�c�̎ʐ^���ǂ��������̂ƍl�����Ă�������m��Ȃ���Η������ɂ�����������܂���B�w�e�Ɠ��x�́u�������������v�ɂ��鎟�̕��́A�P�ɓV�c�����l�_(����ЂƂ���)�Ƃ��Đ��h����Ă����Ƃ����悤�ȊϔO�I�Ȑ��������ł͌����s���Ȃ����̂��I�݂ɕ\�����Ă��܂��B �@ �Ⴆ�A�����̊w�Z�̉Ђɂ���ā\���̐ӔC�͑S�R�Ȃ��̂����\�ǂ̊w�Z�ɂ��f���Ă���V�c�̎ʐ^���댯�ɕm�����Ƃ������R�Ŏ��E�����Z������������B���t�̂Ȃ��ɂ��܂��A���̎ʐ^���~���o�����߂ɔR��������Z�ɂ̒��ɔ�э���ŏĂ����l�тƂ��吨����B�����̐l�тƂ͎��ʂ��Ƃɂ���āA�ނ炪���ɑ���u�`���v�ƓV�c�ɑ���u���v�Ƃ������ɏd�����Ă��邩�Ƃ������Ƃ��ؖ������̂ł���B �@ ���������_���ȓV�c�̎ʐ^��V���ɍڂ���Ƃ������Ƃ������ꑽ�����Ƃł����B�������V�c�ɑ�����{�l�̂��̂悤�ȍl�������A���ǂ̂Ƃ���A�V�����Ɠ��l�̓������ǂ��ď����Ă����܂����B���m�l���n�����ɓ����ł������悤�ɁA���{�l���u�l�ԓV�c�v�\1946�N1��1���ْ̏��œV�c���炪���炩�ɂ����ϔO�\�ɓ����ł����܂����B�����Đ��m�l���L���X�g�����̂ĂȂ������悤�ɁA���{�l�͓V�c�����̂ĂȂ������̂ł��B������̏ꍇ�ɂ��x�l�f�B�N�g�������u�p�[�X�y�N�e�B�u�̎����v���ύX���ꂽ�̂ł͂���܂���B����͐̂������قƂ�Lj��Ȃ��̂ł����A�x�l�f�B�N�g���g������g���g�����Č����\�킷�Ȃ�A�]������A���[�_�[��A���ː��Z�p�������B���ĈȑO�ɂ͌����Ȃ��������̂�������悤�ɂȂ����ɂ����܂���B���̒��x�̂��Ƃł��l�Ԃ͑傫�����_�I�Ռ���������̂ł��B���ꂩ�琄������Ȃ�A�p�[�X�y�N�e�B�u�̎�����ς��邱�Ƃ͎�����s�\���ƍl�����܂��B �@ �n�����ɑ��鐼�m�l�̑ԓx�Ɠ��{�l�̑ԓx�Ƃ̊Ԃɑ傫���Ⴂ�����邱�Ƃɂ��Ă͂���ł����܂��Ȑ������ł����Ǝv���܂����A�܂��ʂ̖�肪�c���Ă��܂��B18���I���Ȃ���19���I�����ɂ́A�j���[�g���̗͊w�̖@�������{�̈ꕔ�̒m���l�ɒm���܂����B����ɂ�������炸���{�l�͂���W�����邱�Ƃ����Ȃ������̂ŁA19���I�㔼�́u�����J���v�ɍۂ��ĉ��߂Ă�����p��̏�����ʂ��Ĉꂩ����������˂Ȃ�܂���ł����B �@ �����������ۂɂ��Ă��w�e�Ɠ��x�̎��_���猩�Ă����K�v������܂��B�u�����̈�̉��Ԃ��v�ɂ��鎟�̕��ł��B �@ ���{�l�͂Ȃ܂Ȃ܂ƋL������Ă���҈ȊO�̑c��ɑ���F�s���d�����Ȃ��B�ނ�͂����ς獡�����ɂ�����̂ɏW������B�����̏������A���{�l�́A���ۓI�v���A�������͌������Ȃ������̐S����]���ɕ`���o�����Ƃɑ��鋻���̌��@��_���Ă��邪�A���{�l�̍F�s�ς́A�����̂���ƑΏƂ��Ă݂�ƁA��͂肱�̂��Ƃ𗧏����̎���Ƃ��Ė𗧂B �@ ���{�l�̓��F�̈���u���ۓI�v���A�������͌������Ȃ������̐S����]���ɕ`���o�����Ƃɑ��鋻���̌��@�v�ɂ���Ƃ����̂́A�x�l�f�B�N�g�����łȂ��A���{�l�łȂ��ώ@�ҁA�����҂̑������F�߂Ă��邱�ƂȂ̂ł��B�����ł����Ă݂�A�j���[�g���̋Ɛт����Ƃ��ΖC�p�̗��_�̊m���ɖ𗧂�������Ȃ��Ƃ������x�̂��Ƃ����l�����Ȃ������̂͋��R�łȂ����Ƃ��킩��܂��B�����������Ƃ��l����ɂ͑����Ƃ����ۓI�v�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@ ���ۓI�Ȏ��������{�l�ɂƂ��đ�łȂ����Ƃ́A�ʂ̏��ł����y����Ă��܂��B�u�e�X���m�������v�ɂ���u�n�}�v�̔�g�ɂ��Č��Ă����܂��傤�B �@ ���{�ɂ́A�N���s�ׂ́A�������ꂪ���s�̍s���́u�n�}�v�̏�ŋ�����Ă��Ȃ��s�ׂł���Ȃ�A�K�����������Ƃ����ۏ����ۂɗ^�����Ă����B�l�͂��́u�n�}�v��M�������B�����Ă��́u�n�}�v�Ɏ�����Ă��铹�����ǂ鎞�ɂ݈̂��S�ł������B�l�͂�������߁A���邢�͂���ɔ��R���邱�Ƃɂ����Ăł͂Ȃ����āA����ɏ]�����Ƃɂ����ėE�C�������A���������������B�����ɖ��L����Ă���͈͓��́A���m�̐��E�ł���A���������āA���{�l�̊Ⴉ�猩��A�M�������鐢�E�ł������B���̋K���̓��[�Z�̏\���̂悤�Ȓ��ۓI�ȓ��������ł͂Ȃ��āA���̏ꍇ�ɂ͂ǂ����ׂ����A�܂����̏ꍇ�ɂ͂ǂ����ׂ����A���m�Ȃ�ǂ����ׂ����A�܂������Ȃ�ǂ����ׂ����A�Z�ɂ͂ǂ������s�ׂ��ӂ��킵���s�ׂ��A�܂���ɂ͂ǂ������s�ׂ��ӂ��킵���s�ׂ��A�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����������ׂ��ɋK�肵�����̂ł������B �@ ���{�l�́A�u���[�Z�̏\���̂悤�Ȓ��ۓI�ȓ��������v�ɏ]���čs�����邱�Ƃɓ���܂��A���낢��ȋ�̓I�Ɋւ��Ĉ�X�ׂ����K�肳�ꂽ�u�n�}�v�ɏ����Ă���Ƃ���ɍs�����邱�Ƃ�ǂ��Ƃ��܂��B�j���[�g���̉^���̖@���͎��R���ۂ��ɓx�ɒ��ۉ��������̂ł�����A��������̂܂܁u�n�}�v�̋L�ڎ����Ƃ݂Ȃ��Ă��قƂ�ǖ��ɗ����܂���B����ł��̖@���̉��l��F���ł��Ȃ������̂ł����A���m�l�����̒��ۓI�Ȗ@������o�����Ĕ��ɗL�p�ȋZ�p����������J���������ƁA�����Ă��ꂪ��O�̌[�ւƋ������т��Ă��邱�Ƃ�m���Ă���悤�₭���̏d�v���ɋC�t���ĕ��ɔM������悤�ɂȂ����̂ł��B �@ �ł͂Ȃ����{�l�͒��ۓI�Ȏv�����D�܂Ȃ��̂ł��傤���B�w�e�Ɠ��x�́u���̃W�����}�v���玟�̕������p���܂����B �@ ���{�l�̐����ɂ����Ēp���ō��̒n�ʂ��߂Ă���Ƃ������Ƃ́A�p��[���Ɋ����镔���܂��͍��������ׂĂ����ł���悤�ɁA�e�l�����Ȃ̍s���ɑ��鐢�]�ɋC��z��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B�ނ͂������l���ǂ��������f�������ł��낤���A�Ƃ������Ƃ𐄑�����������悢�̂ł����āA���̑��l�̔��f����ɂ��Ď��Ȃ̍s���̕��j���߂�B �@ �����������������藧���߂ɂ́A���̑��l�Ǝ����Ƃ̍l���������Ȃ��Ƃ���ɂ����ċ��ʂłȂ���Ȃ�Ȃ��B���݂��ɂǂ������l���������Ă���̂��킩��Ȃ��悤�ł͂���Ȑ����͕s�\�ł���A���������Ď��Ȃ̍s���̕��j���߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���������킯�ŁA�u���ۓI�v���v��u�������Ȃ������̐S����]���ɕ`���o�����Ɓv�Ƃ������A���ǂ��ǂƐ������Ȃ���Α��l�ɗ�������Ȃ����̂́A���{�l�̎Љ���ɂƂ��Ă͂ނ���ז��ȑ��݂ł���B���{�l������ɋ����������Ă���̂͂��̂��߂ł���B �@ ���ǁA���{�l���j���[�g���̉^���̖@�����ɂȂ�܂ŕ������炩���ɂ��Ă������Ƃ͒p�̕����ɂ���Đ������t���̂ł��B�@ |
|
| �� | |
|
�����m���̊ԂŐ{��R(����݂���)�F�������p����A18���I����19���I�ɂ����Ă���Ɋւ��鏑��������������ꂽ���Ƃ��q�ׂ��Ă��܂��B���������̐��́A�]�ˎ���ɂ͂��͂�m���l�����ɂ͑���ɂ���Ȃ����̂ɂȂ��āA���c�̒������ŕۑ�����Ă����ɂ����܂���B
�@ �͂ő傫����苓�����Ă���̂́A�{���钷(1730�|1801)�ƕ��c�Ĉ�(1776�|1843)�̉F���_�ł��B���̂ق������M��(1769�|1850)�̉F���_�ɂ��G��Ă���A�܂����낢��ȈӖ��ł̎��R�ρA���E�ς��߂����Đ��ˊw�A��q�w�����ė��w�A����ɂ͔m�Ԃ�NJ��̎v�z�ɂ����y����Ă��܂����A�����ł͐钷�ƓĈ��̉F���_�ɂ��Ď�Z�ɏq�ׂĂ����܂��傤�B �@ �钷�̉F���_�̗v�_�́A�L�I�ɋL�ڂ���Ă���F�������̐_�b�ƁA���m�l���`�����V���n�����Ƃ̗Z���ɂ���܂��B�����̐����{��R�F�������A�����ōl����ꂽ�W�V����ӓV�����A�����Ɋ�Â��Ȃ��l�H�I�ȉF���ςƂ��Ĕr������܂����B�ނ̌���Ƃ���ł́w�Î��L�x�������u���������̂�����������ւ����āA�Âւ��`�֓`�ւ���܁T�ɋL���ꂽ�v���ł������̂ł��B�����ēV���n�������^������̂ƍl����ꂽ�̂ł����A�L���X�g���̑n���_�b�ɂ͐G�ꂸ�A�L���X�g���ɑ���ᔻ�͂��Ă��܂���B �@ ����ɂ��ƁA�钷�́w�Î��L�x�̖`���ɂ������V�V�䒆��_(���߂݂̂Ȃ��ʂ��̂���)�E����Y�����_(�����݂ނ��т̂���)�E�_�Y�����_(���݂ނ��т̂���)�̎O�_�͓V�n�̐����ȑO���狕��̒��ɑ��݂��Ă����ƍl���Ă��܂����B�钷�͂��̎O�_�̂����̌�̓�_���F���̐����ɂ����������Ƃ��܂������A���̓�_�����o�����Ƃ͌����Ă��炸�A�u�䓿�v�ɂ���Đ������ꂽ�Ƃ��Ă���̂ł��B�����ɐ������ꂽ���̂́u����(�������Ԃ�)�̔@�����āA���炰�Ȃ�������ւ�v�F���ł������̂ł����A�w�Î��L�x�ɂ��Ƃ����Ɂu����(��������)�̂��ƖG(��)����(����)�镨�v�������āA�����ɂ܂��̐_���o���������ƂɂȂ��Ă��܂��B�钷�́A���̖G�����镨�Ƃ́u����(��������)�ɕY�v���Ƃ���́u�ꕨ�v�ł���Ƃ��A���̈ꕨ����V�n�������E���������ƍl���܂����B �@ �钷�̂��̃A�C�f�A�͔ނ̒�q�������f(�͂��Ƃ�Ȃ��ˁB1754�|1824)�ɂ���Ĕ��W�������A�w�Î��L�`�x�̕t�^�w�O��l�x�ɂ����ēV���n�����ƗZ�������̂ł��B�r�쎁�͂�������̂悤�ɗv�܂����B �@ �܂��A�钷�̗����ɂ��������āA�V�n�̏o���ȑO�ɋ��ɑ��݂��Ă����̂́A�V�V�䒆��_�E����Y�����_�E�_�Y�����_�B����A���ɂ͉F���̌����ƂȂ�ꕨ�����܂�A����Y�����_�Ɛ_�Y�����_�̓����ɂ��A���̈ꕨ����V���G���������āA�c��̕�������n�ƂȂ�A�����ŁA����̍����n��ɐ���~��B�����ɂ����Ē��f�́A�V�����V�����͑��z�ł���A����̍��͌��ł���Ɖ��߂����B�������A�����̒����͍c���ƊO�����ӂ��ޒn���ł���B������~��Ƃ����̂́A�L�I�ɂ݂͂Ƃ߂��Ȃ����A���f�́A�V�Ƒ�n�̕����ɂȂ��炦�āA����̍����ꕨ���番�������Ɛ��@����B���V�����E�����̒����E����̍��Ƃ��������I�ȉF���\���_�ɂ��c�_�ƂȂ��Ă���B �@ �Â��āA���z(�V)�E�n�E��(����)�̕������͂��܂�A�₪�đ��z�ƌ��͓Ɨ��̓V�̂ƂȂ��Ēn���̂܂�����]����悤�ɂȂ�B�n�����S�̉F���̊����ł���B�@�c(����)�c �@ ���f���钷�Ɠ��l�A�����Ǝ̉F���_�ɂ������Ă͔ے�I�ł���B�w�O��l�x�̖`���łׂ̂Ă���悤�ɁA�C���h�̐��́u���U���̏���(���݂Ȃ���)���\�����@���A�ϐ�(�݂��育��)�Ȃ�A�_(������)�ӂɂ����炸�v�ł���A�����̐����u�������F�ϐ���v�ł���B����ɂ������āA�킪���ɓ`���V�n�J蓂̐��́A�u�����T�������̂�����������ӂ邱�ƂȂ��A����̂܂ɂ܂ɁA�_����`�͂藈�ɂ���A���ꂼ���U(���͂�)�Ȃ��A�^(�܂���)�̐��ɂ͗L�肯��v�ł���B�����ŁA������钷�Ɠ��l�A�u�C�H(���݂�)��S�ɂ܂����āA���܂˂���(�߂�)�肠�肭�ɂ��āA���̑�n(������)�̂��肩�����A�悭����(�݂���)�߂āA�n�͉~(�܂�)�ɂ��āA����(����)�ɕ��x����A�����͑��̏㉺����v���Ƃ��l���������[���b�p�̉F���_�ɂ��^�ӂ�\����B���̃��[���b�p�̉F���_�́A�����E�C���h�̉F���_�Ƃ͈Ⴂ���傫���̂����A���{�́A�ꕨ����V�E�n�E�����܂��Ƃ������Ƃ��ꗂ����������Ƃ��Ȃ��B�L�I���璆�f���ǂ݂Ƃ����F���n���_�ƃ��[���b�p�̒n�����S���Ƃ͗���������Ƃ����B �@ �r�쎁�͂���ɑ����āA���̉F���ς͒��f�̓Ƒn�Ƃ������͂ނ���钷�̐��ƌ����ق����������Ă���Ƃ����Ӗ��̂��Ƃ��q�ׂĂ��܂��B �@ ���{�̌Ñ�̐_�b�Ɛ��m�̋ߐ��̉F���_�Ƃ����ѕt����Ƃ����ꌩ��ȑ��삪�Ȃ��\�ł������̂��Ƃ����_�ɂ��ẮA�r�쎁�́u�L�I�́A��n�̌`��ɂ��Ă��A�V�̂̉^�s�ɂ��Ă���̓I�ɂׂ̂邱�Ƃ��Ȃ��B������L�I�͂ǂ�ȉF���\���_�ł���荞�ނ��Ƃ��ł����v�Ƃ��Ă��܂��B���̌����͌��ۂ̈�ʂ��Ƃ炦�����̂Ƃ��ČX���ɒl���܂����A ���͂��̊O�ɂ����܈�l���ɓ���Ă��悢���Ƃ�����Ǝv���܂��B����ɂ��ẮA���c�Ĉ��̐������Ă���\���܂��傤�B �@ �������f�́w�O��l�x�������ꂽ�̂�1791�N�ł����A���ꂩ��21�N���1812�N�ɁA�钷�̖�l�ł��������c�Ĉ����w��\�^���x(���܂݂̂͂���)�������܂����B�ނ͂��̒��Ő钷�E���f�̉F���_����o�����ēƎ��̌���������������W�J���܂����B�r�쎁�̉���ɂ��ƓĈ��͂Ђ����ɃL���X�g���̕�����ǂ�ł����炵���A���̖{�̐����ɃL���X�g���̉e���ƌ�����L�q�����邻���ł��B������ ���͐_�w�̖��ɂ͗������炸�A�F���_�����ɒ��ڂ��܂��B�Ƃ��ɋ����[���͍̂r�쎁�ɂ���Ď��̂悤�Ɍ����\�킳��Ă��邱�Ƃł��B �@ ���łɒ��f�ɂ���čm��I�ɎƂ߂��Ă����n�����́A�Ĉ��ɂȂ�ƁA���ϋɓI�ɏ��F�����悤�ɂȂ�B�w��\�^���x�œĈ��͑��z�ƌ��Ƒ�n�̐�����_�����Ƃ���ŁA�u�n�͑��ɕY���A���ɂ��ĉ����̂ł���v�Ƃ��ׂ̂Ă����B������A���z�����Ǝv���̂́A�u���Ƃ��A�M�ɏ���Đ���s�����A�M���~�܂��Ă��Ċ݂��ڂ�悤�ɍl���邱�ƂƓ������Ƃł���v�B�L�I�̐_�b�͒n����������e�\�������B �@ �������A�Ĉ��͑�n�������n���������[���b�p������{�ɓ`����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A���łɋL�I�̐_�b�Ɋ܂܂�Ă����Ƃ����B���[���b�p�̐������{�̐��Ɏ��Ă����̂ł����āA���̋t�ł͂Ȃ��B�i�n�]���ɂƂ��Ēn�����͐��m�������ے�������̂ł��������A�Ĉ��͂������{�̂��̂Ƃ���B���[���b�p�̉Ȋw������Ȃ���A�_�b�I�ȃi�V���i���Y���Ɛ܂荇�킹�悤�Ƃ���̂ł���B �@ �L�I�̓��e�ƃ��[���b�p�̉F���_�Ƃ����ѕt����Ĉ��̑ԓx�́A�钷�E���f�̏ꍇ�Ɠ��������Ɍ����Ă���A���O�ɏo�Ă��܂��B �@ ���̎O�l�̍s���̃p�^�[��������Ƃ��A���́w�e�Ɠ��x�́u�~����̓��{�l�v�Ɉ��p���ꂽ������d�Y�̉�����A�z���܂��B���̉�����1945�N10���A�ČR�ɂ����{��̂��J�n����Ă���ŏ��̒鍑�c��ɂ����ē��t������b�Ƃ��čs�Ȃ�ꂽ���̂ŁA���p���ꂽ�͎̂��̕����ł��B �@ �V���{�̐��{�́A�����̑��ӂd���閯���`�I�Ȍ`�Ԃ����B(����)�B�킪���ɂ����Ă͌×��A�V�c�͍����̈ӎu�����̂ݐS�Ƃ��Ă���ꂽ�B���ꂪ�����V�c�̌��@�̌䐸�_�ł����āA���������Ɍ����Ƃ���̖���I�����́A�܂��������̐��_�̌����ƍl���邱�Ƃ��ł���B �@ �x�l�f�B�N�g�͂���Ɏ��̃R�����g��Y���܂����B �@ ���̂悤�ȃf���N���V�[�̐����́A�A�����J�l�ǎ҂ɂ͑S�����Ӗ��A���Ȗ��Ӗ��ȉ��̂��̂Ǝv����̂ł��邪�A���{�������I�ȃC�f�I���M�[�̏�ɗ����́A���̂悤�ȉߋ��Ƃ̓��ꎋ�̊�b�̏�ɗ������A���������e�ՂɎs���I���R�͈̔͂��g�����A�����̕�����z���グ�邱�Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ͋^���̗]�n���Ȃ��B �@ ���w�҂̉F���_�ƁA������d�Y�̖����`�_�Ƃ̊Ԃɂ́A�ߋ��Ƃ̓��ꎋ�Ƃ������ʂ̃p�^�[��������܂��B���{�l���v�z�������Ƃ��ɂ́A���ꂪ�{���͐̂�����{�ɂ��������̂��ƍl���Ȃ���Έ��S�ł��Ȃ��̂ł��B���̃p�^�[���ɑ�������̂͑��ɂ���������܂��B���Ƃ���1890�N�ɟД����ꂽ���璺��ł����A���ꂩ�甼���I�]�ɂ킽���ē��{�̋���E����F�ɓh��ׂ������̒���̃x�[�X�͎v�z�ł���A����ɋߑト�[���b�p�̎v�z����������Ă���ɂ�������炸�A����͍c�c�A�c�@���Ȃ킿�V�c�̐�c�̈⓿���Ƃ������Ƃɂ��Ă��܂��B�n������n�������w�Î��L�x�ƌ��ѕt������A�����`�������V�c�̎v�z���ƌ������肷��̂���O�I�Ȓ������ƌ����킯�ɂ͂����܂���B �@ �ł͂Ȃ����{�l�Ɏv�z�����ꂳ����ꍇ�ɉߋ��Ƃ̓��ꎋ�����ʂ�����̂ł��傤���B���̂��Ƃ��l����Ƃ��ɂ́A�w�e�Ɠ��x�́u���{�ɂ́A�N���s�ׂ́c�v�Ɏn�܂镶���v���o���K�v������܂��B�x�l�f�B�N�g���������悤�ɁA���m�̐��E�ɂ�����̂Ȃ���{�l�ɐM�������̂ł��B����䂦����v�z�����悤�Ƃ���ꍇ�ɁA����͐V�K�̎v�z�̂悤�Ɍ����邯��ǂ����͐̂���킪���ɂ��������̂���ƌ����Γ��{�l�͈��S���Ď���܂��B�܂����{�l��������Ȃ��v�z�ɏo������Ƃ��ɂ́A���ꂪ���m�̐��E�ɂ������̂Ɠ������Ǝv�����ނ��Ƃɂ���Ĉ��S���������܂��B�t�����V�X�R�E�U�r�G�������߂ē��{�l�ɃL���X�g�����������Ƃ��ɓ��{�l�͂��̐_�f�E�X�̂��Ƃ����@���Ƃ��ĎƂ߂܂������A���Ԃ�A�����v��Ȃ���ΐS�̒��ɍ������N�������̂ł��傤�B���������u�ߋ��Ƃ̓��ꎋ�̊�b�v�������Ă͂��߂ăL���X�g��������邱�Ƃ��ł����̂ł��B�n�������A�n�������A���璺��Ɍ����Ă���u�����O�j�y�{�V�A�w���C���A�ƃ��K�q�A�ȃe�q�\���[���V�A���탒���A�V�A�i�f���v���L���A�������J�L�v�Ƃ����A��������ɂ͌����������܂��͌ł��֎~����Ă���������S�����ɏ��シ�邱�Ƃ��A���{�������`�I�Ȑ������邱�Ƃ��A���łɂ����ƑO����u�n�}�v�ɍڂ��Ă����̂��ƁA�������g�ɂ��A���l�ɂ������������邱�Ƃɂ���Ď���鏀�����ł����̂ł��B �@ �v�́A���{�l�̐����ɂ����đ��l(�eothers�f�ł����āeoutsiders�f�ł͂���܂���B���������Đe�Z����܂݂܂�)���ǂ��������f�������ł��낤���𐄑����邱�Ƃ�����߂ďd�v�ł���A����Ɠ����Ɏ������ǂ��������f�������������l�ɂ���ėe�Ղɐ�������邱�Ƃ����l�ɏd�v������ł��B���̂��߂ɂ͒��ۓI�Ȍ����Ɋ�Â��čs������͕̂s�K���ł���A���̏ꍇ�ɂ͂�������A���̏ꍇ�ɂ͂ǂ�����Ƃ������Ƃ���̓I���ڍׂɋL�ڂ��ꂽ�u�n�}�v�����L���Ă���ɏ]���̂����{�l�Ƃ��Ă͍ł��ǂ����@�Ȃ̂ł��B�@ |
|
| ���ߑ�E���� | |
|
�ŏ��ɒ��ڂ����̂́A����@�g�́w�����}���x(1868�N��)�ł��B����͎O������Ȃ镨���w�̏����̉�����ł����A���́u���̎O�v���V���w�ɓ��Ă��Ă���A���̒��Œn��������ђn�������L�q����Ă��܂��B�O�ɏq�ׂ��悤�ɂ����́A18���I�����ɂ̓I�����_�̏�����ʂ��Ċw�҂����ɒm���Ă��܂������A��ʐl�ɂ͂قƂ�ǒm���Ă��܂���ł����B����̓A�����J�̊w�҂����킵�������Ɋ�Â��ď�������̋��ȏ��Ƃ��Ďg�����Ƃ̂ł���{���������̂ł��B���̈Ӗ��ł��̒��q�͉���I�Ȃ��̂ł����B�r�쎁�͂��̓��e�̊T�����������Ƌ��ɁA����̎v�z�ɂ��Ă��q�ׂĂ��܂��B����́A�w�w��̂����߁x�Ō����Ă���悤�ɁA�l�Ԃ͐��܂���M�G�㉺�̋�ʂ�g�ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�g���̍���͊w��ɗ���ۂ��ɂ��̂ł����āA�w��ɗ�܂Ȃ���Έ�g�̓Ɨ��͎��������A��g�̓Ɨ����Ȃ����Ȃ��l�X�̍��͓Ɨ����ł��蓾�Ȃ��Ƃ����l���𒆐S�ɂ�����̂ł����B�v����Ɍ[�ւ��ړI�ł����āA�F���_�Ɋւ���m�����A���Ƃ̓Ɨ��ɍv��������l�ނ̏펯�@�\�@�����Ƃ͂����茾���ΊO���l�ɔn���ɂ���Ȃ����߂̔����@�\�@�Ƃ��ċ�����ꂽ�̂ł��B���̍l�������W���Ă�������ł́A�����Ȓm�I�����ɑ��铲�ۂ��͂ނ�������̒Nj����d������ԓx���Z���ɂȂ��Ă����X�������R�̂悤�Ɍ���Ă��܂����B
�@ �������{�̉Ȋw�Z�p���琭������̐��ɕ��s������̂ł����B1877�N�ɂ͓�����w���J�݂���A���ꂪ���W����1886(����19)�N�ɂ͒鍑��w�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂������A���̖ړI�́u���Ƃ̐{�v�ɉ�����w�p�Z�|���������y�ё����]��(����̂�)���l������v���ƂƂ���܂����B�l��`�ł͂Ȃ��A���Ǝ�`���͂�����Ƒł��o���ꂽ�̂ł��B���̓_�Ɋ֘A���čr�쎁�́A�����q�ׂĂ��܂��B �@ ���̌��ʁA�Ȋw�ɂ�������Z�p�I�Ȍ��n����̕]�������܂�B���w��������鍑��w�̗��ȑ�w���ƂȂ�A�̂��ɂ͑�w�����E������b���C�����e�r��[�́A���ȑ�w���̂Ƃ��ɒ��킵���w���w�V���x�ŁA���w�́u�����̗��w�v�Ɓu���p�̗��w�v�Ƃ���Ȃ邪�A�^���̔�����ړI�Ƃ���u�����̗��w�v�ɂ��Ă��A���ꂪ�A�u���n�Ƃ̎��Ƃ�艽�{�̎��v�v����������Ƃ����_�ł̂ݏd�v�������Ƃ̌������ׂ̂Ă����B���̂��߁A��[�ɂƂ��ė��w�́A�Z�p�̊�b�Ƃ��Ă̗L�p�����������߂��Ă��������w�Ɖ��w�Ƃ��̎��ӕ���ł������B�Ȋw���Z�p�̊�b�ł���Ƃ����̂́A�����̃��[���b�p���x�z���Ă����Ȋw�v�z�ł��邪�A�]�ˎ���̗��w�E�m�w�̉Ȋw�ς����������Ƃ��݂邱�Ƃ��ł��悤�B�������v�̂��߂̉Ȋw�ł���B �@ �ǎ҂݂̂Ȃ���́u�������v�v�Ƃ������t�������ŏ��߂Č���ꂽ�̂łȂ����Ƃ��������ł��ˁB�r�쎁�͑�1�͂ŌÑ�́u�����J���v�Ɍ��y�����Ƃ��ɂ����q�ׂ܂����B �@ ���܂��܂ȑ嗤�̕����������������A���{�l�����҂����̂͌������v�A���p�̋Z�p�Ǝ�p�ł���B���Ƃɂ��V���ϑ��������Ȃ��Ă��A���̔w��ɂ���F���̗��_�I�Ȗ��ɖڂ��ނ����l�q�͂Ȃ��B�W�V������V���Ƃ������Ñ㒆���̉F���_�ɂ������Ďx���Ƃ����Ƃ��Ƃ������ϋɓI�Ȕ����͓`�����Ă��Ȃ��̂ł���B �@ ����Ƃ܂����������p�^�[���̍s������������ɂ��������̂ł��B����͓��{�l�ɂƂ��Ă͂��܂�ɂ����R�ŁA�������ӎ������ɍs�Ȃ��܂������A�����l�̖ڂɂ͈ٗl�Ɍ����܂����B �@ ���̂��Ƃ��͂����茾�����l���̈�l���G���E�C���E�x���c(1849�|1913)�ł��B�ނ͈�w�҂ʼnF���_�Ƃ͒��ڂ̊W�������Ă��܂���ł������A�Ȋw�Z�p�̐�������̎�e�Ƃ������Ƃ��l������ۂɌ������Ă͂Ȃ�Ȃ��_���s���w�E�������������܂����B����1901�N11��22���A�ꏊ�͓����̏��ΐ�A�����A�����鍑��w�W�҂ɂ���čÂ��ꂽ�ނ̍ݐE25�N�j���̐ȏ�ł̂��Ƃł��B�����ɂ͕�����b�e�r��[���͂��߂Ƃ��āA�鍑��w�̑����A�����̋����A�w������Ȃ��Ă��܂����B���̉����̊j�S�����͎��̂Ƃ���ł��B �@ ���Ȃ킿�A�킽�����̌���Ƃ���ł́A���m�̉Ȋw�̋N���Ɩ{���Ɋւ��ē��{�ł́A�����ΊԈ�����������s���Ă���悤�Ɏv����̂ł���܂��B�l�X�͂��̉Ȋw���A�N�ɂ��ꂱ�ꂾ���̎d��������@�B�ł���A�ǂ������̏ꏊ�ւ��₷���^��ł����Ŏd�����������Ƃ̂ł���@�B�ł���ƍl���Ă��܂��B����͌��ł��B���m�̉Ȋw�̐��E�͌����ċ@�B�ł͂Ȃ��A��̗L�@�̂ł���܂��āA���̐����ɂ͑��̂��ׂĂ̗L�@�̂Ɠ��l�Ɉ��̋C����̑�C���K�v�Ȃ̂ł���܂��B �@ �������Ȃ���A�n���̑�C�������̎��Ԃ̌��ʂł���悤�ɐ��m�̐��_�I��C���܂��A���R�̒T���A���E�̂Ȃ��̋�����ڎw���Ċ����̌��o�����l�X������N�ɂ킽���ēw�͂������ʂł���܂��B����͋��̓��ł���A���@�\�@����������Ȑl�X�����т����������Ŏ��������ł���A���𗬂����邢�͐g���Ă���Ď��������ł���܂��B����͐��_�̑哹�ł���A���̓��̔��[�ɂ̓s�^�S���X�A�A���X�g�e���X�A�q�|�N���e�X�A�A���L���f�X�̖��O�������܂����A���̓��̈�ԐV�����ڕW�̐ɂ̓t�@���f�[�A�_�[�E�B���A�w�����z���c�A�t�B���q���E�A�p�X�g�[���A�����g�Q���̖��O�����邳��Ă��܂��B���ꂱ�����[���b�p�l������Ƃ���ŁA���E�̉ʂĂ܂ł��g�ɂ��Ă��鐸�_�Ȃ̂ł���܂��B �@ ���N�I�@���N���܂������O�\�N�̊Ԃɂ��̐��_�̏��L�҂𑽐��A���̒��ԂɎ����ꂽ�̂ł���܂��B���m�����͏��N�ɋ��t�𑗂����̂ł���܂����A�����̋��t�͔M�S�ɂ��̐��_����{�ɐA�����A�������{�������g�̂��̂��炵�߂悤�ƂƂ����̂ł���܂��B�������A�����̎g���͂����Ό������܂����B���Ƃ��Ƃ����͉Ȋw�̎�����Ă�l����ׂ��ł���A�܂������Ȃ낤�Ǝv���Ă����̂ɁA�����͉Ȋw�̉ʎ���蔄�肷��l�Ƃ��Ď�舵��ꂽ�̂ł����B�����͎���܂��A���̎킩����{�ʼnȊw�̎����ЂƂ�łɐ����đ傫���Ȃ��悤�ɂ��悤�Ƃ����̂ł����āA���̎������A��������Ă�ꂽ�ꍇ�A�₦���V�����A�������܂��܂��������������Ԃ��̂ł���ɂ�������炸�A���{�ł͍��̉Ȋw�́u���ʁv�݂̂�����炩����낤�Ƃ����̂ł���܂��B���̍ŐV�̐��ʂ�����炩����p�������Ŗ������A���̐��ʂ������炵�����_���w�ڂ��Ƃ��Ȃ��̂ł��B �@ ���̔����͎�����w�p�I�ȃG�b�Z�C���Ɉ��p����܂����A�����Ԃ��ꂪ���ʂ����苓�����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����̖��Ɋ֘A���āu�x���c�͂����������v�Ƃ����ӂ��Ɉ����A�Z���R�����g���Y������̂���Ԃł���܂����B���ɂ͂��̉������w���āu���{�̊w��݂̍���ɏd��Ȓ�����^�����v�ƌ������l������܂������A�����Ȃ�Ӗ��ŏd��Ȃ̂��Ƃ������Ƃ܂ł͖������Ȃ������̂ł��B�N�����A���̉�������(���邢�͓ǂ�)�l�X���F��l�Ƀx���c�̈Ӑ}�𗝉��ł���͂����Ǝv������ł����̂ł��B�v����ɁA�x���c�̐X����i���͓��{�l�̉E�̎��ɓ����č��̎�����o�Ă��܂����̂ł��B���{�l�͔ނ����̏�Ȃ����h���A����ł̎l�����I�ɂ킽�鋳��ƌ����̌��т��]���Đ���ȏj�����Â��A���h�ȋL�O�i�悷��Ƃ����ō��̉h�_��������ɂ�������炸�����Ȃ����̂ł��B���{�l�́u�������v�v���S�̉��l�ς́A������܂łɋ��łł������ӎ�����Ȃ����̂Ȃ̂ł��B���ꂱ���x�l�f�B�N�g�̌����u�p�[�X�y�N�e�B�u�̎����v�������炵�����̂̍D��̈�ł��傤�B �@ �����čr�쎁�����̂悤�Ɍ����\�킵����ԂɂȂ��Ă������̂ł��B �@ ���Ă̑�w�����f���ɐ��܂ꂽ�B��̑�w�ł��铌����w�E�鍑��w�ɖ������Ƃ�S�����������ƍ����Z�p�҂̗{����Ɛ肳����(��ڂ̒鍑��w�ł��鋞�s��w�����܂��̂́A��Z�N��̈ꔪ�㎵�N�ł�����)�B���̈Ӗ��ŁA������w�̑n�݂��ʂ������Ӗ��͑傫�������B�����������ɁA����́A���̌�̓��{�̑�w�Ɠ��{�̋ߑ㉻�̐��i�������K�肷�邱�ƂɂȂ����B���{�l�̉F���ς̗��j�ɂ��Ă��ł���B �@ ���m�ł́A���ł�18���I���Ƀn�[�V�F�����V���������A����ɋ�͌n�̍\���Ɋւ��鏉���I�Ȑ�����o����Ă��܂������A�J���g�A���v���X�̐��_�����������Ă��܂����B������19���I�ɂ͗͊w�I�v�Z����|��Ƃ��ĊC���������������Ƃ������I�ȏo����������A�X�ɖ]�����̐��\�̌���ɂ���ċ�͌n����F���ɑ������݂��铇�F���̈�ł��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ�������I�Ȑi�����������̂ł��B���̒��ł̓��{�̏́A�r�쎁�̕\���ɂ��u���n���̓�����w�Ő���ł������͓̂V�̌���������n�ɂ��Ă̌����ł���v�Ƃ������Ƃł����B����ܓx�ϑ����ɋ������ؑ��h(�Ђ���)��1902�N�Ɉܓx�ϓ��Ɋւ��Ăy���������͓̂��{�̓V���w�j�ɓ��M�����Ɛтł����A��������̕����̒��Ɉʒu���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�����Ă��̕��������L������̂Ƃ��ē��{�����ł̏d�͂�n���C�̑��肪����ɍs�Ȃ��܂����B���������Y�������̎��C�̌����Ƃ��������̐�[�̖��ɐi�o�����̂����������w�i�������Ă̂��Ƃł����B�r�쎁�͂����炳�܂ɂ͌��y���܂���ł������A���������z�������̊J���Ƃ��R���Z�p�̌���ɊW������ʂɗ͂�������A�F���̍\���Ƃ����悤�ȁu���Ƃ̐{�v�v���牓�����͌y��ꂽ�̂ł��B �@ �r�쎁�͂��������b�̌�Ői���_�̎�e�Ƃ���Ɋ֘A����Љ�w��̘_�c�ɂ��ďq�ׂĂ��܂����A�����ł͂���ɗ�������Ȃ����Ƃɂ��܂��B������ނ�������ӎO(1861�|1930)�̎v�z�ɂ��ďq�ׂ��Z�N�V���������ڂ������܂��B �@ �����͔M�S�ȃL���X�g���k�ł����B�ނ̐M�̓��W�J���ŁA�l���g�D���������F�߂��A�_�ɂ���đ���ꂽ�F��������ł���Ƃ���������Ƃ�܂����B�����Ĕނ́A�L���X�g���ƉȊw�Ƃ̊Ԃɖ���������Ƃ͍l���Ă��܂���ł����B�r�쎁�́A�w�L���X�g���ⓚ�x���玟�̕������p���Ă��܂��B �@ �ނ��_��M����ɂ���Ă̂݁A���̌��\�͔ނɕ��^������̂ł���܂��B�삪���ɏ��܂ł͕��̉Ȋw�����͎n�܂�܂���B�c�c�V�R��_�̈ӎu�̔����ƌ��āA���͎n�߂ēV�R�̐^�������A�����������i(��)��ł������������Ɨ~����̔O������̐S�ɋN��̂ł���Ǝv���܂��B �@ �����ɗp�����Ă���u�V�R�v�Ƃ�����ɂ��čr�쎁������������Ă��܂��B�������͉p���nature�ɂ������ł����A�u���̂�����R����́v�ł͂Ȃ��̂Łu���R�v�Ƃ͌���Ȃ��̂ł��B����́u�V(���n����)�v�ɂ���đ���ꂽ���̂ƍl�����̂ł��B�����Ĕނ́A�����ɂ����1910�N�ɏ����ꂽ���̕������p���܂����B �@ ��R(�������Ȃ���)�Ȋw�͐_���F���̊O�ɔ�������\�͂炴�肵��嫂��A����(�u�����v�Ɍ��_)�ɔނ�F�߂���Ȃ��A�������I�ɑ�Ȃ�F���A�������I�ɐ��ׂȂ�F���A���Ɛo�Ƃ͑��֗����A�l���(����)�Ƃ͑��q����A�F���͈�̂ł���A�g�̂���̂ł��邪�@���Ɉ�̂ł���A�l�����֗����A����̊��t�͑S�̂��z����A�����ĔV�ꂷ��ɗ썰������A�F�����L�@��(�I���K�j�Y��)�łȂ��Ȃ�Ύ~�ށA�R��ǂ��L�@�̂ł���ȏ��(�����ĉȊw�͗L�@�̂ł���Ɖ]��)�V�ꂷ��ɑ��썰���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�_�͉F���̗썰�ł���B �@ �����ɐ����Ă���v�z�́A�K�����I��j���[�g���̂��̂ƂقƂ�Ǔ����ƌ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ȋw�ɋ��R���̘_������������Ă��Ȃ����������Ƃ��ẮA�����鎩�R���ۂ����R���鍇�����ɓ�����Ă���悤�Ɍ�����̂�_�̌��(�݂킴)�ƌ��āA�_�̑��݂ɑ���m�M���ł߂�l���������̂͗����ł��邱�Ƃł��B�����A���{�l�̑命���͂����łȂ������Ƃ������Ƃ������ł��B���������Ӗ��ŁA�����͓��{�l���ꂵ���l���ł������̂ł��傤�B �@ �ނ����{�l���ꂵ�Ă����Ƃ������Ƃ́A�r�쎁�����̂悤�ɏ����\�킵�Ă��邱�Ƃ�������Ď��܂��B �@ ���Z�O�N�̍u���u���{���̑卢��v�ł́A���̂悤�ȕ����ᔻ�̊ϓ_����A�����̓��{�̓��[���b�p�̐��_����藣���ꂽ���[���b�p�̋ߑ㕶���݂̂�ێ悵�Ă���Ǝw�E����ƂƂ��ɁA���{�̍���̌����ɂ��Ă͒[�I�ɁA�u���{�l���L���X�g�����̗p�������āA�L���X�g���I�������̗p�������Ɓv�ɂ���A�Ƃ݂Ă����B�����ɂ��A���R�▯�����l�ނ̒a���ƂƂ��ɂ���̂ł͂Ȃ��A�L���X�g���̐��_���O��ƂȂ��ďo���������̂ł���B���������āA���[���b�p�����ɂ���ē��{�l�̐��_�����ꂩ����v���悤�Ƃ���Ȃ�A���̕����̍���ɂ���L���X�g�����̂�˂Ȃ�Ȃ��B�܂�A�u�V���l���_�v�́u�V�v���̂��̂��݂�����̂��̂Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ �����Ɍ����Ă�������̍s���̂����u�����̓��{�̓��[���b�p�̐��_����藣���ꂽ���[���b�p�̋ߑ㕶���݂̂�ێ悵�Ă���Ǝw�E�v�������Ƃ́A�x���c�̉����Ɠ����p�^�[���������Ă��܂��B�x���c�����[���b�p�l����ɂ��Ă����u���_�̑哹�v����{�l���̂ĂČڂ݂Ȃ����Ƃ���ɂ��܂����B�����A�x���c�̓L���X�g����O�ʂɌf���邱�Ƃ����܂���ł����B����́A�s�^�S���X�A�A���X�g�e���X���X�Ƃ�����L���X�g���k�̋Ɛт��l���ɓ��ꂸ�ɂ͍ς܂Ȃ����炾�Ǝv���܂��B���̓_�A�����͎��삪���������ƌ����Ă��d�����Ȃ��ł��傤�B���������Ƃ����삪�������������Ƃ��Ă��A�����̓x���c�Ɨގ��̃p�[�X�y�N�e�B�u��������̂ł��B�ނ̂��Ƃ���{�l���ꂵ�Ă����ƕ]����̂͊ԈႢ�ł͂���܂���B �@ ����ɍr�쎁�́A���{�̃L���X�g���S�̂�����20�N��㔼�Ȍ�M�҂̌���������Ɏ��������œ����̊������L���łȂ��������Ƃɂ��Ă����������Ă��܂��B �@ ���͂Ƃ̊W��r���A�C�G�X Jesus �Ɠ��{ Japan �Ƃ����u��̂i�v�����b�m�[�Ɂu���{�I�L���X�g���v��ǂ����߂Ȃ���A�_�̑������F��������Ƃ��A���ڂɐ_����^�����w�Ԃׂ��ł���Ƃ��������̖������`�ɂ��Ă��A�������Đ����Ƃ͂����Ȃ������B�����I�E���z�I�Ȃ��̂�r������{�̓y�n�ɃL���X�g����A���t����͎̂�������B�������삪�w���فx�Ńt�F���C���Ɍ�点���u�ǂ����Ă�������������ʂȂɂ��v�Ƃ������ɓ��������������Ă����̂ł���B �@ �r�쎁�́u�����̋ߑ㉻�ƉF���ӎ��v�̍Ō�̃y�[�W�ł����q�ׂ܂����B �@ �L���X�g���̕z�����ĊJ����A���R�����^���̌����ƂȂ����V���l���_���ꐢ���r���Ă��A�L���X�g���́u�V(���_)�v�Ƃ����`����w�I�����͓��{�Љ�ɍ��Â����Ƃ͂Ȃ������B�I�Ȓ��F�̐��_�́u���璺��v�̊�b�ɂ������A����͏��w�Z������Ƃ����đS�Љ�I�ɐZ�������̂����A���F�̏�ʊT�O�ł������V����������邱�Ƃ͂Ȃ��B�V�c�匠�����L���ꂽ�鍑���@�ł��A���̍����͎̓V�ɂ��̂ł͂Ȃ��A������n�Ƃ��������I�A�����ƎЉ�L�@�̐��ɑ���ꂽ�Ƒ����Ƙ_�ɂ��Ƃ߂�ꂽ�B�V�͓V�c�̂Ȃ��ɉB���ꂽ�̂ł���B �@ �܂��ɂ��̒ʂ�ł��B����́u���F�̏�ʊT�O�ł������V����������邱�Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ����_�ɂ��Ăł����A���́u�V�v�𐒔q����v�z�ɗR������u�m�v�̊T�O�����{�l�ɂ���ė뗎������ꂽ���Ƃ��w�e�Ɠ��x�́u�����̈�̉��Ԃ��v�Ř_�����Ă��܂��B�x�l�f�B�N�g�́A���͊ш�́w�����@�����x����u���{�ł͂����̎v�z�͖��炩�ɓV�c���Ƒ��e��ʂ��̂ł������B���������āA�w���Ƃ��Ă������A�������肻�̂܂e���ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ������v�Ƃ������t�����p���A���{�ł́u�m�v�͗ϗ��̌n�̊O�ɒǕ����ꂽ���ƂȂ��āA�����̗ϗ��̌n�̒��ŗL���Ă��������n�ʂ��炷�����肨�Ƃ���Ă��܂����ƌ����܂����B�@ |
|
| �� | |
|
�����̂悤�ɁA�����ɖ��̏o�Ă�����{�l�͂�������Ȋw�̐��Ƃł͂���܂���(�{���͉Ȋw�̕���ɒʂ����l�ł����A�����ł͕��w�҂Ƃ��Ę_�����Ă��܂�)�B�������A���̏͂ɂ͊��l���̓��{�l�Ȋw�҂̋Ɛтւ̌��y������܂����A����炪���{�l�̉F���ς̖��Ƃ��Ă͎�苓�����Ă͂��Ȃ��̂ł��B
�@ ����́A�F���_�̃p���_�C����]��������悤�ȋƐт����{�l�w�҂ɂ���ċ�����ꂽ���Ƃ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��痈�Ă���悤�Ɏv���܂��B������ۂ�������������A���{�l�ɂƂ��ẲF���_�́A���o�����̂ł͂Ȃ��A��e������̂ł������̂ł��B���̂��Ǝ��̂������_�I�l�@�̎��ł��肦�܂����A��e�ɍۂ��Ăǂ������Ƃߕ��������̂��Ƃ����b�ɂȂ�ƁA���͂�Ȋw�҂̖��ł�����v�z�Ƃ̖��ɂȂ�킯�ł��B�O�̑�7�͂ł��łɂ����ł����B�����ł͕���@�g�Ɠ����ӎO�Ƃ����݂��ɑ傫���قȂ鉿�l�ς���������l�̉Ȋw�҂łȂ��l�����傫����苓�����܂����B���̑�8�͂ł����̊ϓ_���ێ�����A�Ȋw�҂łȂ����l�̘_�q���l�@�̑ΏۂɂȂ��Ă���̂ł��B�������A ���͂����ɐ[���������邱�Ƃ����܂���B�����Ƃ��Ď�苓����̂́A���{�l�̊ԂŃA�C���V���^�C���̐l�C�����ɍ��������Ƃ������ƂƁA���ꂩ����{�l�����R�Ƃǂ��ւ�肠���Ă������Ƃ������Ƃł��B �@ �F���_�̃p���_�C���]���ƌ����Βn�����Ƃ��r�b�O�o���Ȃǂ������̎������v���o����܂����A���̒��ɂ͕K���A�C���V���^�C���̑��ΐ����_���܂܂�܂��B��8�́u����F���_�Ƃ̏o��v�����̑��ΐ����_�̘b����n�܂��Ă��܂��B1920�N��ɂ킪���Łu���ΐ����_�u�[���v�ƌ����Ă��悢�Љ�ۂ����������ƂɊ֘A���čr�쎁�����̂悤�ɏq�ׂĂ��邱�Ƃ͌������܂���B �@ �Ȃ��A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�͂���قǓ��{�l�̊S����̂��B���̏̓��[���b�p�̏ꍇ�Ƃ͂������Ă����B�ߑト�[���b�p�Ȋw�̃p���_�C���ł���j���[�g���͊w�̔ے�̓��[���b�p�l�Ɉ��Ռ��������炵���̂ł��邪�A���{�l�͖ډ��j���[�g���͊w���w�K���A����j���[�g���͊w���p���_�C���������ȑO�������̂ł��邩��A�j���[�m���͊w���������Ƃ����Ă��A���[���b�p�l�̂悤�ȏՌ��������邱�Ƃ͂Ȃ������B�ނ���A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�̏Ռ��́A���̓_�ł̓��[���b�p�l�ɂƂ��Ă������ł��������A����I�Ȋ��o�Ƃ͑�����Ȃ����ʂ������炷�Ƃ����_�ɂ����Ăł������B���̂⎞�Ԃ̐L�яk�݁A��Ԃ̘c�݁A���E�̂Ȃ��L���̉F���A���ʂƃG�l���M�[�̓������Ȃǂł���B �@ ������A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�̂��߂���ԂƎ��Ԃ̊ϔO���j���[�g���̂���ƈقȂ�A��펯�ŗ��������������̂ł���Ƃ��Ă��A����ɂ������闝�_�I�Ȕ����͂قƂ�ǂ݂��Ȃ������B�ꍂ�u�t�̕����w�҂ł������y��s��(�ӂ���)�̂悤�ɃA�C���V���^�C���̑��ΐ����_�Ɉًc����������̂�����ꂽ���A�����H�ȗ�ł������B�n������n�����ɂ���������{�l�̑ԓx�ɂ����ʂ���B �@ �����ɂ́u�n������n�����ɂ���������{�l�̑ԓx�ɂ����ʂ���v�s���̃p�^�[��������̂ł��B�n������n�����ɂ���������{�l�̑ԓx�ɂ��Ă͍r�쎁�̖{�̑�4�́u�L���V�^���V���w�v�Ƒ�5�́u�n�����̎�e�v�ʼn������Ă���A ���͂���ɂ��ĕ��͂����܂����B���{�l�̑ԓx���u�ȒP�Ɍ����A���m�l���w�҂����Ԃ�ɂ��Ă��܂��قǐ��_�I�Ռ�����V���������Ă����{�l�͂�����w�����A�����ł����x�ƌ����ĕ����������̂ł��v�ƌ����\�킵�܂������A�ꌩ�����Ƃ���A���ΐ����_�̏ꍇ�ɂ͂����ł͂Ȃ������悤�Ɍ����܂��B���q�����́w�A�C���V���^�C���E�V���b�N1�x(1991�N�A�͏o���[�V��)��1�́u���{�㗤�v�ɂ��A1922(�吳11)�N�A�C���V���^�C�����C�H�_�˂ɓ����������Ƃ𗂓��̓����V���e���͂��ꂼ��傫�����A���̂悤�Ȍ��o�����f�����Ƃ������Ƃł��B �@ �A�C���V���^�C�����m���� �@���e�t�̂₤�ȉ������@���ɗ͂�u�����D��̓y�Y�b�@�v�l�̖ʂɂ͔鏑���̔�ꂪ�������@(��㖈���V���A�Љ�ʃg�b�v�A�O�i) �@ �w�Ȋw�E�̋��l�x����@�A�C���V���^�C�����m�_�˂֒��@�m���̍��ۓI�W������@(��㒩���V���A�m��ʑ��g�b�v�A�O�i) �@ �̑�Ȃ�u���v�̔@���P���ā@�w�E�̋��l�A���m����@�u���ɉQ�����o�}�ւ̌Q�@(�_�ːV���A�Љ�ʑ�j�g�b�v�A�O�i) �@ �k��ۂŗ��������@���@���̃A���m�@���{�̖ؑ����z�����������@(�_�˖��V�A�Љ�ʃg�b�v�A�O�i) �@ ���E�w�E�̋��l�@�A�C���V���^�C�����m�@��(���悢��)�������ΐ����_�́@����ł͖����ƑD���Ō��@(���s���o�V���A�Љ�ʒ��L���A��i) �@ ���ꂾ��������A�u�����A�����ł����v�ƕ����������Ƃ����\���������O��Ɍ����邩������܂���B��������ʌ����̓����V�����傫����苓��������ƌ����Ĉ�ʐl�����ΐ����_�𗝉������ƍl����킯�ɂ͂����܂���B���͂ނ�����Ƃ̕��ɂ���܂��B���̑��ΐ����_�𗝉������͂��̊w�҂����̊Ԃ��炻��ɑ���ً`���邢�͔ᔻ�_���قƂ�nj����Ȃ������Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��B������u�����A�����ł����v�ƕ����������ƌ����̂́A�\�����ǂ�����������܂��A���Ȃ炸�����ԈႢ�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B �@ �ł́A�A�C���V���^�C���ɑ����ʂ̓��{�l�̔M���I�Ƃ������銽�}�Ԃ�͉��ɗR�����Ă����̂ł��傤�B������l����Ƃ��ɂ́A�ނ����̑O�N�Ƀm�[�x�������w�܂����Ƃ������Ƃ�Y���킯�ɂ͂����܂���j���[�g���ȗ��̕����w�̑̌n����V����Ƃ����傫���Ɛт��������l�����ƕ�������A�������m�[�x����҂��ƌ�����A���ꂾ���ł������{�l�͔ނɍō��̌h�ӂ�\���܂��B�������A������ƌ����Ĕނ̌������Ƃ𗝉������Ƃ͌�����܂���B�O���x���c�̉����̂悤�ɁA�E�̎��ɓ����č��̎�����o�Ă��܂����Ƃ������Ƃ����蓾���̂ł��B �@ ����ɏ��X�t�������܂��傤�A�����̃m�[�x����҂́A�S�����ʂ��āA�قƂ�ǑS�������[���b�p�l�܂��̓A�����J�l�ł���(��O�́A���w�܂����^�S�[��������l�ł�)�B�܂�A���{�����ɂ͂��̓_�Ō�����ׂ邱�Ƃ̂ł���l�͈�l�����Ȃ������̂ł��B����ŃA�C���V���^�C���́A�w�҂Ƃ��Ắu�K�w���x�v(hierarchy)�̒��ł͂��ׂĂ̓��{�l����ɋ���ƍl����ꂽ�̂ł��B���ʂ̓��{�l�͊K�w���x�̒��_�ɗ��l��ᔻ���Ȃ��Ƃ������Ƃ��������ł��傤�B�ᔻ�������T����͈̂��̎v�l��~�ł��B���Ƃ����������Ƃ��Ă��A�u�����A�����ł����v�ƕ��������̂Ɠ������ʂɂȂ�܂��B����ɂ���ē����̓��{�l�����w�҂̑ԓx��������邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �r�쎁�͑��ΐ����_�ɑ�����{�l�̑ԓx�̂��Ƃ��q�ׂ���ŁA�b���]�����ăA�C���V���^�C�������������{�̈�ہA�Ƃ��ɓ��{�̌|�p�Ɋւ����ۂɌ��y���Ă��܂��B�����ŃA�C���V���^�C�����Đ_�_�I�ȃX�s�m�U�̐_��M���Ă������ƂɐG��Ă�����p�������t�͎��̂Ƃ���ł��B �@ ���̓_�Ŏ����ӖڂƋ��Q�̔O���瓦��邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���R�Ɛl�ԂƂ͈�̗l�� Stileinheit �ȊO�̉��������܂Ȃ��قǂɈ�Ɍ���Ă���B���ۂɂ��̍��ɗR�����邷�� �Ă̂��̂́A���炵������₩�ł���A���ۓI�ł��`����w�I�ł��Ȃ��A��Ɏ��R�ɂ���ė^����ꂽ���̂Ƃ��Ȃ�ٖ��Ɍ��т��Ă���B �@ �����čr�쎁�͂���Ɏ��̃R�����g��Y���܂����B �@ �������A����̓A�C���V���^�C���̐V���������ł͂Ȃ��B�u���R�Ɛl�ԂƂ̈�̗l���v�Ƃ����̂́A���������A���́A�@���A�뉀�����w�̐��E�ɂ܂ł݂Ă������{�����̓����ɂق��Ȃ�Ȃ��B�������ɁA�X�s�m�U�ɂ����Ă����R�Ɛl�Ԃ́u�_�����R�v�ɓ��ꂳ��Ă���B�������A����͓��{�̕����ɂ݂�ꂽ�Z���Ƃ������̂ł͂Ȃ��B���R�̒��������o���������ł̐_�Ƃ̓��ꉻ�ł���B �@ �u����̓A�C���V���^�C���̐V���������ł͂Ȃ��v�Ƃ����̂́A���Ƃ����t�J�f�B�I�E�n�[���ɑO������邱�Ƃ��ł���̂ł��B �@ ���ꂩ��b��6�l�̓��{�l�̎��R�ςɈڂ��Ă����܂��B�����Œ��ڂ����l���́A�Ėڟ��A���c�ЕF�A���c�����Y�A�a�ғN�Y�A�ˍ⏁�A���L�F����ы{���ł��B���̐l�����͂���������炩�̈Ӗ��Łu���R�Ɛl�ԂƂ̈�̗l���v�ɐړ_�������Ă����̂ł��B�������A���̕����ɂ��Ă͂����ł͗�������Ȃ����Ƃɂ��܂��B �@ �r�쎁�́A�W���[�W�E�K���t��1946�N�ɔ��\�����F���n���_�ɒ[����r�b�O�o�����_�̉�������Ă��܂��B���̉���������ŌJ��Ԃ����Ƃ͂��܂��A�r�b�O�o�������ۂɂ������Ƃ����؋��͂��ł�1960�N��ɔ�������Ă���A���݂̉F�������܂ꂽ�o�܂͐������ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�������r�b�O�o�����O�ɉF�������݂������A���Ԃ͑��݂����̂��Ƃ����_���߂����āA1982�N�ɂ`�E�r�����Q�����V���\���A���݂��_���������Ă��܂��B�K���t�̐��ł́A���Ԃ͉i���Ɍo�߂��Ă���A�F���͖c���Ǝ��k���J��Ԃ��Ă���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A�r�����Q���̓r�b�O�o�����O�ɂ͉F�����A���Ԃ����݂����A�܂������̖�����F�������܂ꂽ�Ǝ咣�����̂ł��B�r�쎁�͂�����u�����Ȃ�ƁA�r�b�O�o�����_�́A���_���E�L���X�g���̓V�n�n�����̕����ł���悤�ɂ��݂���v�ƕ]���Ă��܂��B�����Ă���ɑ�����{�l�̑ԓx�ɂ��Ă͂��������܂����B �@ �L���X�g���k�̑����Ȃ����{�l�̂������ł��r�b�O�o�����_�ւً̈c�͕�����Ȃ��B�u������̑n���v�ɂ��Ƃ��ɔ����͂Ȃ��悤�ł���B����͋����ׂ����Ƃł͂Ȃ����낤�B���w�҂̕��c�Ĉ����������A�L���X�g���́u������̑n���v�̋��`������Ă����̂��B�������A�͂����āA���{�l�ɂ���ăr�����Q���̂悤�Ȍ��������܂��ł��낤���Ƃ����A���{�l�̉F���ς̗��j����l���Ă��A�ے�I�ɂȂ炴������Ȃ��B�F���ς͂��̎Љ�̕����I�Y���Ȃ̂ł���B �@ �r�쎁�́A�u���{�l�̉F���Ǝ��R�v�̂͂��߂̕����œ��{�l�����R�Ƃǂ��ւ���Ă�������v�܂����B�ނ͂܂������ɓ��{�͍H�Ƃ̔���I�Ȕ��W�������������A����ɂ���ē����͎̂��R�́u��j�Łv��㏞�Ƃ����L�����ł������Ǝw�E���A�u���āA���������{�l�͎��R�Ɉ�܂ꐶ���Ă������Ƃ�S�ꂩ�犴���Ƃ邱�Ƃ̂ł��������ł������v�ɂ�������炸�u���R�̔j��ɂ��������C�ł�����̂��v�Ƌ^����N���܂����B�����Ď��̂悤�ɁA���̎��ƉF���ςƂ����ѕt���܂����B �@ ������܂��A���{�l�̉F���ςƖ��W�ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B���{�l�́A�C��n���Ă������܂��܂ȉF���I�v�z���w�ԋ@��������̂����A�z���N������˂Ȃ�Ȃ��̂́A����ɂ���ĉF���Ǝ��ȂƂ̊W�A���R�Ɛl�ԂƂ̊W�m�ɂ���v�z�Ƃ��Ă͎�����Ȃ������Ƃ������Ƃł���B�w���t�W�x�̉r�����R�Ƃ̈�̊��͂��܂������Â���B�����Ė��́A���̂Ƃ����{�l�͎��R��������l�Ԃł͂��������A�����ɁA���R�ɊÂ���l�Ԃł��������Ƃ����_�ł���B���ׂĂ𐅂ɗ�����悤�ɁA�p�����ł��������R���Ȃ�Ƃ����Ă����I�@���ɂ́A���̎��R�ւ̊Â����A���R�ɓ݊��ȁA�����Ę����Ȑl�Ԃ����݂������f�n�ƂȂ����Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�a�҂̕��y�_�ł͐������������Ƃ���ł���B �@ ����������A���{�l�͎��R�������Ă����Ƃ͂����Ă��A����͉F���I�Ȏ��R�ł͂Ȃ������Ƃ������Ƃł���B���{�l�̍D���R�͋ߖT�I�ȏ����R�A�R���̎��R�A���̎��R�A�킪�Ƃ̒�̎��R�A�a�̓I���R�A�o��I���R�Ƃ����Ă悢�B���o�ɂ܂݂ꂽ�s��l�������ɓ���A������邽�߂̎��R�ł������B �@ ���̂悤�Ȏ��R�ɐ�����l�ԂɂƂ��Ă̎傽��S�͉F���I�Ȑl�ԊW�ł͂Ȃ����Љ�I�Ȑl�ԊW�ł����Ȃ��B���Ȃ̈ʒu���˂ɐ��Ԃ̂Ȃ��Ŕ��f�A���̂��߂Ɍ������v�����A��������l���鎩�O�̘_����ϋɓI�ɂ��Ƃ��Ƃ��Ȃ��B�����ł́A�^�̑Η��_�͂����ɂ͂��ꂸ�A�_��������Ă��u���v�I�_���łڂ�����Ă��܂��B�P�������m�ɂ��ꂸ�A���������̂܂܍m�肳��Ă��܂��B�������x�z����̂́A�u���R�v�ȋ����̂��ێ����悤�Ƃ���{�\�I�Ȃ��́A���͂��������u���R�v�Ȓ����Ƃ����Ƃ߂��A���͂ւ̌}�����u���R�v�ƂȂ�B����ȁu���R�v�ȎЉ�̂Ȃ��ŁA���R�̔j��͂Ƃ߂ǂȂ��i�s����B �@ �r�쎁�́A�A�C���V���^�C�������{�ɂ����鎩�R�Ɛl�ԂƂ́u��̗l���v�ƌ����\�킵�����̂��m�肵�A�Ėڟ����͂��ߊ��l���̓��{�l�������c�������̂ɂ��ꂪ���f���Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��܂������A�Ō�ɂ��̕����f���Ă��ꂪ���̌��E�������Ă��邱�Ƃ��w�E�����̂ł��B ���͔ނ̎咣���ɂ����Ďx�����܂��B �@ ���̈��p���̗v(���Ȃ�)�́A�u���{�l�̍D���R�͋ߖT�I�ȏ����R�c�c�ł������v�Ƃ������ɂ���܂��B���ꂪ�u���Љ�I�Ȑl�ԊW�v���傽��S���Ƃ��邱�ƂƖ��ڂȊW�������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��B�u���Ȃ̈ʒu���˂ɐ��Ԃ̂Ȃ��Ŕ��f�v�u�������v�����A��������l���鎩�O�̘_����ϋɓI�ɂ��Ƃ��Ƃ��Ȃ��v�u�^�̑Η��_�͂����ɂ͂��ꂸ�A�_��������Ă��q���r�I�_���łڂ�����Ă��܂��v�u�P�������m�ɂ��ꂸ�A���������̂܂܍m�肳��Ă��܂��v�u�q���R�r�ȋ����̂��ێ����悤�Ƃ���{�\�I�Ȃ��́v�ɂ���Ďx�z�����A�����āu���͂��������q���R�r�Ȓ����Ƃ����Ƃ߂��A���͂ւ̌}�����q���R�r�ƂȂ�v�Ƃ����̂́A��������p�̕�������o���s���p�^�[���ł��B �@ �������Ȃ�����{�l�́A����ɑ���̗v�����ۂ���B���l���璇�Ԃ͂���ɂ���A��掂���Ƃ����傫�ȋ��Ђ�����邽�߂ɁA�ނ�͂������������o�����l�I�Ȋy���݂����ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�ނ�͐l���̏d�厖�ɂ����ẮA�����̏Փ���}�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȍ^�Ɉᔽ���邲�������̐l�тƂ́A����ɑ��鑸�h�̔O����r������Ƃ����댯�ɂ�������B����d����@(�u���d�v����)�l�Ԃ́A�u�P�v���u���v���ł͂Ȃ��āA�u���҂ǂ���̐l�ԁv�ɂȂ邩�A�u���҂͂���̐l�ԁv�ɂȂ邩�A�Ƃ������Ƃ�ڈ��Ƃ��Ă��̐i�H���߁A���l��ʂ́u���ҁv�ɂ������߂ɁA���Ȃ̌l�I�v�������Ă�B���������l���������A�u�p��m��v�A�����ɐT�d�Ȃ����ꂽ�l�Ԃł���B���������l���������A�����̉ƂɁA�����̑��ɁA�܂������̍��ɖ��_�������炷�l�тƂł���B �@ ���{�l�͎��R������Ƃ��ɂ������ɐl���ς𓊉e���܂����B�l���ɂ����čł��d�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐��l��ʂ́u���ҁv�ł����A���́u���l�v�Ƃ����̂͒ʏ퉽�S�l�Ƃ����悤�ȑ����ł͂���܂���B�܂�����A���ꂩ��Z��Ɣz��҂ł��B���̎��ɂ͐e�ނ�אl�A�����ĐE��̏�i�A����(�w���A���k�ł���A���t�⋉�F)�����̔��e�ɓ���܂��B�E�Ə�̌ڋq�������ł��܂���(����������������܂��B���Ƃ��A�����Ƃł���A���[�̏���҂ł͂Ȃ��A���ڊ�����킹�����悪�d���܂�)�B���������̒��x���z�����L���͈͂����ɂȂ邱�Ƃ͋H�ł��B���͈̔͂ł��܂�����Ă����ΐl���͊y�����߂����܂��B���͈̔͂��z����Љ�̂��Ƃ�{�C�ōl����l�͂���߂ċH�ł��B�l�X�ɐ����铹�������A��Y����̋~�ς����ׂ����l�ł����u�������O���͓x����v�ƌ������ƐM�����Ă��܂��B�܂�����𗣂ꂽ���̋�ł͏��X�܂����������Ƃ����Ă��u���̒p�͂����̂āv�ł��B �@ ���{�l�����R�Ƃ̊ԂɁu��̗l���v�����̂�����Ɠ��l�̃Z���X�ɂ����Ăł����āA������������n�_���猩����͈͂��邢�͎����̋L���ɂ���͈͂��������Ȃ̂ł��B�u�V�̌��ӂ肳������Ώt���Ȃ�O�}�̎R�ɏo�ł��������v�͉����ꏊ�Ɏv����y���鎍�ł����A��҂����łɌo�������͈͂��z���܂���B���{�̎��l�́A�R�̔ޕ��̋��ɂ���ƌ����Ă���Ƃ���̂܂����ʁu�K�v���v�����������Ƃ����悤�Ȏ�����낤�Ƃ͂��܂���B�x�l�f�B�N�g�����{�����̌^�̈�Ƃ��ċ������u�[�����ꂽ�ӎu�̎��R�v�����������Ă���̂ł��B���́u�[�����ꂽ�v�Ƃ������肪���邩�������ŁA���������C�ƃJ�[���E�u�b�Z�͐F���̈Ⴄ�������܂����B�����Ă��̌���Ƃ͖����̐��m�̉Ȋw�҂͎��X�ƐV�����F���_���J�����܂������A���̌�����̌^�Ƃ��Ĕw�����Ă�����{�̉Ȋw�҂́A���m�l���J���������̂����ȉ��߂ɂ���ă��f�B�t�@�C���邱�Ƃ͂��܂����A�ނ�Ɠ��������̉���I�ȐV����҂ݏo�����Ƃ͋��Ȃ̂ł��B�@�@ �@ |
|
| ���u�����v�̗��j | |
|
����ԁA�ŏ��ɐ����݂Ă����̂͒N�H
�@ �������グ��ƁA�����P���Ă��܂��B�ŋ߂́A�X�̖����肪�ǂ�ǂ邭�Ȃ��Ă��܂��āA��������̐��X�A���V�̐�������邱�Ƃ�����Ȃ��Ă��܂����B�ł��A�Ԃō����R�Ȃǂɓo��ƁA(���n���ł͂�����Ƃ���ړ�������ƁH)�̂̐l�������݂��悤�Ȗ��V�̐�����y���ނ��Ƃ��ł��܂��B �@ �@��N�p���b�g���������Ɂu��ԁA�ŏ��ɐ����݂Ă����̂͒N�H�v�Ƃ������₪�͂��܂����B�N�Ƃ�������ɂ͓������Ȃ������̂ł����A���낢�뒲�ׂĂ��������ɁA����Ȍ��������\����Ă��܂����B����ɂ��ƁA�t�����X�̃��X�R�[�lj�(1��5��`1���N�O)�ɕ`���ꂽ�������̍����_�X���A���������̂�����A�܂��Ă̑�O�p�Ɩ͎ʂ����Ǝv����A�Ƃ����̂ł��B���̌�������������A�u�����݂Ă�����L�^�����ŌÂ̐l�X�́v1��5��`1���N�O�̃t�����X�ɏZ�ދ��Ί펞��̌|�p�Ƃ����A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤���B �@ ���u�����v�Ƃ� �@ ���ꂩ�玞�オ�i�݁A�̂̐l�X�́A���邢�����ނ���Łu�����v��z���`���܂����B�����Ƃ́A���Ɛ������сC������l���A����ȂǂɌ����ĂāC�V����̋敪�Ƃ������̂ł��B �@ �����́A�p��ŁA�R���X�e���[�V����constellation�ł��Bcon�́u���Ɂv�Ƃ����Ӗ�������Astella�́u���v�Ation�͖����ɂ�����̌��t�ł��̂ŁA����u���̏W�܂�v�u���̎U���v�ƂȂ�ł��傤�B �@ ���ݕ��ʂɎg���Ă��鐯���́A���m����`����ꂽ�����ł��B�������A���{�Ő����Ƃ����A���������܂ł́A�����̐����u���h�v�ł����B���m�̐��������{�ɓ����Ă����������ȍ~���A���炭�̊ԁAconstellation�́u���h�v�Ɩ�A�吳�����������Ɓu�����v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����悤�ł��B �@ �������̋N�� �@ ���āA�����́A���A�ǂ��ł��ꂪ�������̂ł��傤���B �@ ���āA�����́u�M���V�A�����v�ƌĂ�Ă������オ����܂����B�������̂悤�ɁA�����ɂ́A���؈�ࣁA�h���}�`�b�N�A���}���e�B�b�N�ȃM���V�A�_�b���`����Ă�������ŁA�����̗��j���A������3000�N�قǑO�̃M���V�A�Ŏn�܂������̂ƍl�����Ă����̂ł��B�������A������100�N�Ə����O�ɂȂ��āA�����Ԙb�͈���Ă��܂����B �@ ���̃C���N�̂�����ɁA�`�O���X��E���[�t���e�B�X��Ƃ�����̑傫�Ȑ삪�����āA�����ɂ��Ȃ�Â����當�����h���Ă����̂͂��������Ǝv���܂��B���j�̋��ȏ��ł����Ȃ��݂́u���\�|�^�~�A�����v�ł��B���\�|�^�~�A�����Ƃ����A�S�y�Ȃǂɐ�����w���̂悤�Ȃ��̂ō��u�����ь`�����v���L���ł����A���̂����ь`���������荞�܂ꂽ�S�y�Ȃǂ���A�����̏ڂ����l�q�A�����ăM���V�A�ȑO�̐����̌Â����j�����炩�ɂȂ��Ă����̂ł��B���ł́A�����́A�M���V�A��茻�݂͂����Ƃ����ƌÂ���5000�N���邢�͂���ȏ���O�ɁA���̃C���N�𒆐S�Ƃ������\�|�^�~�A�n���ŋN���������̂Ƃ���Ă��܂��B �@ ���̃K�C�h�u�b�N��肢�̖{�ɂ́A�悭�u��5000�N�O�A�J���f�B�A�l(�V�o�r���j�A�l)�Ƃ����r�������A��r�̔Ԃ����Ȃ���A��ɐ����������Ă������v�Ƃ���܂��B�����̐l�����̂悤�ȕ��͂�ڂɂ��A���ꂪ�펯���Ƃ��v���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������A���������܂�ł��B�����̋N����ɂ��ẮA���́A�܂��܂��͂����肵�Ȃ����Ƃ���������܂����A�J���f�B�A�l�������͖̂�3000�N�O�̂��Ƃł����A�J���f�B�A�l�������ƌÂ��������5000�N���O�ɃV�����[���l��A�b�J�h�l�Ƃ������l����������n�߂��̂������̎n�܂�̎n�܂�ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂�����ƂȂ��Ă��܂��B�@ |
|
|
��1�D�t�����`���\�|�^�~�A
�@ ��(1)�V�����[���l�E�A�b�J�h�l �@ �V�����[���l�́ABC.3500����ɔɉh�����Z���n(���\�|�^�~�A�ꂵ���A�b�J�h�l��o�r���j�A�����Ă��A�����l�A�V�o�r���j�A�����Ă��J���f�A�l�A�V���A�𒆐S�Ɋ����t�F�j�L�A�l�A�C�X�������A���u�l�Ȃ� )�̔_�k�����ł��B�_�a�Ⓝ�ȂǓ����������̌��z�������݂������ƂȂǂ��킩���Ă��܂��BBC2400���A�������Z���n�̔_�k�����A�b�J�h�l�ɐ�������܂����A�V�����[���l���A�b�J�h�l���A���ɍ��x�ȕ�����z�����_�k�����ŁA������悭���Ă����`�Ղ�����܂��B2�̖����̓`���ɂ��A �@ �P���S�̂́u�V�̗r�̌Q�v �@ ���z�́u�V�����r�v �@ �f���́u�V�����r�̐��v�A���ɂ݂͂ȗr���������� �@ �g�W�u�W�A�i�h�Ƃ������邢���́u�V�̗r�̌Q�̗r�����v �@ �����҂́A�W�u�W�A�i���A���N�g�D���X�ƍl���Ă���A�������ꂪ�������Ƃ���A���łɁA�����������̌��^���ł����������A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@ �������Ȃ���A�V�����[���l���A�b�J�h�l���A���݂��g���Ă��鐯�����̂��̂��������Ƃ������ڂ̏؋����Ȃ��̂��ɂ��Ƃ���ł��B�V�����[���l�ɂ���Đ����̖��O��G�������ꂽ�S�y�́A���̂Ƃ���܂������Ƃ����Ă����قnj������Ă��Ȃ�����ł��B�������A���\�|�^�~�A�ňȍ~�����Ă��鐯���̖��O�́A�����Ă����V�����[����ŏ�����Ă��邻���ł��B���������Ƃ��납��A�������͂��߂Ă������l�Ƃ��ăV�����[���l�̖��O���������Ă���킯�ł��B �@ �ł�����A�����̌��`���V�����[���l������A����ɑ������\�|�^�~�A�̐l�������A�b�J�h�E�A�����E�A�b�V���A�E�J���f�A(�o�r���j�A)�Ƃ������l���������A�����Ƃ��Ĕ��W�E�������Ă������̂ł͂Ȃ����ƍl����̂����R�Ȃ킯�ł��B���̓����A�����̖��O�������ꂽ�V�����[���̔S�y�����@������������Ƃ����ł��ˁB �@ ��(2)�A�����l�E�J�b�V�[�g�l�@ ���āA�͂��߂čl�Êw�I�ɐ����̖��O���o�ꂷ��̂́A�������4000�N�O�̂��Ƃł��B�I���O2000�N���A�V�����[���E�A�b�J�h�l�̂��ƂɃA�����l(�A�����l�Ƃ�����)�ł��B�A�����l�́A�u�ڂɂ͖ڂ����ɂ͎����v�Œm����w�n�������r�@�T�x�ŗL���ȌÑ�o�r���j�A����������������B�ނ���A�V�����[���E�A�b�J�h�̍��x�ȕ������p���ł��܂����B�A�����l�̂��c�����A������3800�N�O��BC1800�̋L�^�ɂ́A��(�������܍�)�A�V�̎�l(�I���I��)�Ƃ�����������A���݂����肢�̐����Ƃ��Ēm����u�����\���v�̂����A���āE���ɁE�Ă�т����������9�������o�ꂵ�Ă��܂��B�܂�A���̃A�����l���A�u�m���ɐ������������A�Ƃ肠�����m���Ȑl�����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�_�Ƃ��s�����߂ɁA�������悭�ώ@���G�߂�m��K�v��������A�₪�ė�������Ă������̂ł��傤�B �@ ���̌�A�n�������r�����S���Ȃ��āA�Ñ�o�r���j�A���o�r������1���������ނ��Ă����ƁA�J�b�V�[�g���ɍ����̂��Ƃ��Ă��܂��܂��B�J�b�V�[�g�̎����400�N�������܂����A���܂�悭�͒m���Ă��܂���B�������A���E��(�N�b�h���[)�ƌĂ��Δ肪�傫�����ڂ���܂��B �@ �N�b�h���[�́A�����̎�Ɏ������y�n���L�ɂ��Ă̐��̂悤�Ȃ��̂��Ƃ���Ă��܂��B���`�����ƊG��������Ă��āA���̊G�ɂ͓����̎p�������`����Ă��܂��B���ẮA���ꂪ�����G���Ƃ����Ă��܂������A�c�O�Ȃ���A�_�X�̎p(�V���{���}�[�N)�ł���A�Ƃ������ƂɌ��݂͗������Ă���悤�ł��B �@ �������A�N�b�h���[�̊G�̒��ɂ́A�����M��T�\���l�ԁA�����߂������_���������肵�āA���ꂪ�����̂��ƂɂȂ��Ă������A�Ƃ����������ł������ł��B �@ ��(3)�A�b�V���A �@ �������2700�N�O�̋I���O6�`7���I�A�A�b�V���A���ƌĂ�鎞��ɂȂ�ƁA����12���������łȂ�36�̐������A�S�y�ɕ`�����悤�ɂȂ��Ă����܂��B�A�b�V���A�̉��̒��ł��L����B.C.669����626�̃A�b�V���[���E�o�j�p�����́A�S�y������������܂����B���̒��ɂ����Ȑ����������ꂽ�����������܂܂�Ă��܂��B����12�������܂�36�̐������݂����Ă���A�����̊�{���m���������Ƃ����������܂��B �@ ��(4)�J���f�B�A�l �@ �������3100�O�ɂȂ�ƁA��قǏЉ���J���f�B�A�l���o�ꂵ�܂��B�J���f�B�A�l�͋I���O1100�N����A���\�|�^�~�A�ɂ���Ă����A�����n(���̃V���A�̂�����)�n���V�q���ł��B���̂���̃l�u�J�h�l�U��1�������������E�ɂ͂��č��E��������E���݂ւэ��Ȃǂ̐��������F�߂��Ă��܂��B �@ B.C.645������B.C.550���܂Ŕɉh�����J���f�B�A����(�V�o�r���j�A����)�́A�J���f�B�A�l���N�����������ł����A�ނ�́A�V���w�E���w�ȂǂB�����܂����B�u�V���w�̓J���f�B�A�̎��v�Ƃ�����قǁA�J���f�B�A�̎��R�Ȋw��V���w�͍��x�ł����B1�N��12�J���A1�T�Ԃ�7���A1����24���ԁA�p�x��1����360�x�Ƃ��������݂̏펯�ƂȂ��Ă���P�ʂ́A�݂ȃJ���f�A�ŎY�܂�܂����B�܂��A�f���̉��������H�\��ȂǁA���Ȃ肵������ƌv�Z����A�S�y�ɂ����̐������c����Ă���Ƃ����܂��B �@ ���@ �G�W�v�g�����ƓV���w �@ �����̋N���̓��\�|�^�~�A�n���ł����A�Â�����A�G�W�v�g�ł��V���w�����B���Ă��܂��B �@ �Ñ�G�W�v�g�̒��S�n�́A�i�C���쉺���̍L���O�p�B(�f���^�n��)�ƃi�C���쒆���̍ג������암���̊֓��n���قǂ̖ʐς̏ꏊ�ł����B�i�C����ł́A���N�ĂɂȂ�Ƒ�J�������A�����ɍ����R�̐�������d�Ȃ�A�����E�����͍^���Ɍ�������̂ł����B�^���͂܂��A�l�X�ɔ엀�ȓy�n��^���A��������_�Ƃ��L���ɔ��B���܂����B �@ �Ñ�G�W�v�g�l�́A�\�e�B�X(�����̏�̐��̈Ӗ��A�������ʍ��̃V���E�X)���d�v�����܂����B����́A�S�V�ň�Ԗ��邢���ł������Ƃ������ƂƁA�V���E�X���Ă̊ԑ��z�̌��Ŗ�70�����p�������Ȃ��Ȃ�����A�Ď��̍����̏o���O�Ɍ����n�߂�ƁA�Ԃ��Ȃ��i�C����̑������n�܂邩��ł��B���̃V���E�X���\�e�B�X�����̏o�̒��O�Ɍ����o�������A�G�W�v�g��̌��U�Ƃ���A���̂悤�Ȓ��Ӑ[���ϑ�����A1�N��365���Ƃ����A���݂����������g���Ă��鑾�z�����ɓ���邱�ƂɂȂ����̂ł��B �@ ���̂悤�ɁA�G�W�v�g�ł��V���w�����B���A�����������܂����B�G�W�v�g�͑��z�̒ʂ蓹�ɂ�����36����������C���𑪂�܂����B������3000�N�O�̋I���O1000�N���ɂ́A�N���I�p�g�����V�����s�ōs�����Ƃ����G�W�v�g�̃f���f����Ղ̃C�V�X�_�a�̓V��ɂ͂قƂ�NJ��S�ȑS�V�̐������`�ʂ���Ă��܂��B���̂���A�G�W�v�g�ł͐����̒m���͂��Ȃ荂�x�Ȃ��̂ƂȂ����؋��ł��傤�B���̂Ȃ��ŁA���q���A�€���A�o�q���A���������̓��\�|�^�~�A�̐����Ƃ͓����ł����A���̂ق��̓G�W�v�g�Ǝ��̐������`����Ă��܂��B�����̓��\�|�^�~�A�̐����Ƃ͂��Ȃ肱�ƂȂ�܂��B �@ ��(5)�t�F�j�L�A�l �@ ���āA�Ăу��\�|�^�~�A�̐����̗��j�ɖ߂�܂����A�I���O2000�N������A���̃V���A�̂�����n���C�̓������݂ɂ̓t�F�j�L�A�l�Ƃ����A�D�ɏ���Ėf�Ղ��s���̂����ӂȃZ���n�̖��������܂��B���̖����́A�q�C�̂��߂ɐ����Ȗڈ�ɂ���K�v����A���\�|�^�~�A�̌Ñ㐯���̒m�������Ȃ莝���Ă����̂ł��B�ނ�́A�ꍇ�ɂ���ẮA�W�u�����^���C����ʂ��đ吼�m�ɂ킽������A�Ђ���Ƃ���ƃA�����J�嗤�ɂ��킽���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����Ă��܂����A�q�C�̎�ȖړI�́A�������ォ�當�����N�������M���V�A�Ƃ̊Ԃ̖f�Ղ������̂ł��B�@�ł�����A���\�|�^�~�A�Ŕ����E���W���������̒m���́A�₪�āA�t�F�j�L�A�l�ɂ���ČÑ�M���V�A�ɂ����炳��邱�ƂɂȂ�܂��B�@ |
|
|
��2�D���B���@�`�M���V�A����
�@ �M���V�A�ɓ`����������̒m���́A��z�͖L���ȃM���V�A�̎��l��N�w�ҁE�Ȋw�҂ɂ���Ď���ɁA�M���V�A�×��̐_�l��`���A���A�W�A�̑����ʂɌÂ�����`���_�b��`���̐_�X�A�p�Y�Ȃǂ��̒��ɓ��Ă͂߂Ă����܂��B���ꂪ�A��࣍��Ȑ����_�b�̎n�܂�ɂƂȂ��Ă����킯�ł��B �@ ��(1)�z�����X �@ �܂��A�M���V�A�ŌÂ̕���(������)�́A�I���O9���I���z�����X�̏������u�C���A�X�v�Ɓu�I�f���b�Z�C�A�v�ł��B�u�C���A�X�v�̓g�����푈�Ŋ���p�Y�����̕���A�u�I�f���b�Z�C�A�v�́A�g�����푈��̉p�Y�I�f�B�b�Z�E�X�̖`������ł����A���̂Ȃ��ɂ͍��������������M���V�A�_�b�̎�v�Ȃ��̂������Ă������łȂ��A���z�⌎�A�v���A�f�X��q�A�f�X�A�������܍��A�I���I�����A�����������A�I���I���̐��E�V���E�X�Ȃǂ̐�����̖��O�������܂܂�Ă��āA�M���V�A�������l�����ōŌÂ̕����ƂȂ��Ă��܂��B �@ �܂����������Ǝ�芪���@�����̐������ׂĐs�����āA�v���C�A�_�X�̎������A�q���A�_�X(�J��)���A�r�X�����I�[���[�I�[����A�F�̐��ƂāA���ԂŐl���k�l�Ƃ�Ԃ��́A���̐����͓����Ƃ�������邮�����āA�I�[���[�I�[����ڂ̓G�ɂ��A����������̃I�[�P�A�m�X(�ɗm)�̐��Z��ɓ���Ȃ��Ƃ���(�C�[���A�X��18��) �@ ��(2)�w�V�I�h�X �@ �I���O8���I���Ƃ���鎞��̃w�V�I�h�X�́A�w�d���Ɠ��X�x�Ƃ������O�̐������r�������������Ă��܂��B����́A���炵�Ȃ������𑗂������߂邽�߂ɏ������Ƃ���܂����A���̗r�����̃J�����_�[�ŁA�����ɂ̓v���A�f�X�A�q�A�f�X�A�I���I�����A�V���E�X�A�A���N�g�D���X�̖��O����������Ă��܂��B �@ �܂��A�ނ́w�_���L�x�Ƃ������������Ă��܂����A����̓M���V�A�̐_�X�̌n��������������̂ŁA�Ȃ��[�E�X�����E���x�z����悤�ɂȂ����̂�����������Ă܂��B �@ ��(3)6���I�̎��l���� �@ �I���O6���I�ɂ����āA�M���V�A�̎��l���������グ�鐯���́A����ɑ����Ă��܂��B���Ƃ��A�M���V�A�̍�ƃA�O���I�X�e�l�X�͍����̂����܍�(�L�m�X�������̔�)��킵���������A�N���^���̎��l�G�s���j�E�X�͂€���€�債����̃J�y���������A�V���X�̎��l�t�F���L�f�X�̓I���I���������ނƂ������������Ƃ����V���w��̎������q�ׂ���A�A�g���X�̖��ł���v���A�f�X��7�l�o���̓`���������A�w���j�R�X�̓q�A�f�X�̌`�A�܂�5���I�̃~���g�X�̃~���g�X�̎��l�w�J�^�C�I�X�͂��݂ւэ��̓`���Ȃǂ�`���悤�ɂȂ�܂��B �@ �I���O5���I�̃A�e�l�̓V���ƃG�E�N�e�����́A�V�C�J�����_�[���쐬���A���̒��ŁA�݂����߁E�킵�E�������ʁE����ނ�E�͂����傤�E���邩�E���ƁE�I���I���E�y�K�X�X�E����A�q�A�f�X�A�v���A�f�X�������A�����ƋC��̈ڂ�ς��ɂ��ĂɌ��y���Ă��܂��B �@ ��(4)�A���g�X �@ ����Ɏ��オ����A�I���O3���I���ɂȂ�ƁA�\���C�ň�t�E���l�Ƃ��Ċ����A���g�X(BC315�`240)���o�ꂵ�܂��B�ނ͂�������O�̓V���w�҃G�E�h�N�\�X�Ȃǂ̓V���w����1154�s�ɉC���������w�t�@�C�m���i�x�������܂����B���̒��ŁA�M���V������݂���44�̐����A����͓����m���Ă������ׂĂ̐����ł���A���̌`��o�v�A�����_�b���߂��钷�҂̎��B���ݒm���鐯���̑������܂܂�A���ꂪ��Ƀ��e���ꉻ���ꃍ�[�}�������ɋy��ł����Ƃ����A����I�Ȑ���������ƂȂ�܂��B �@ ���@ �k�V19���� / �������܁E�����܁E���������E��イ�E�P�t�F�E�X�E�J�V�I�y���E�A���h�����_�y���Z�E�X�E�E�����E�y�K�X�X�E���邩�E���債��E�w���N���X�E���ƁE�͂����傤�E�킵�E��E����ނ�E�ւт���(�ւт��܂�) �@ ����13���� / ���Ђ��E�������E�ӂ����E���ɁE�����E���Ƃ߁E�Ă�т�E������E���āE�€�E�݂����߁E�����E�v���A�f�X �@ ��V12���� / �I���I���E���ʁE�������E�A���S�E������E�G���_�k�X�E�݂Ȃ݂̂����E��������E�P���^�E���X(�������݂��܂�)�E���݂ւсE�����ՁE���炷 �@ �ւт����ƂւсA�P���^�E���X�Ƃ������݂��������̂́A�q�b�p���R�X��v�g���}�C�I�X�B�v�g���}�C�I�X��48�����ɂ��邱���܍��ɂ͐G��Ă��Ȃ��B �@ ��(5)�q�b�p���R�X �@ �I���O2���I�ɂȂ�ƁA�g���R�̃j�P�A���܂�̃q�b�p���R�X(BC190�`120)�Ƃ����̑�Ȋϑ��V���w�҂�����܂��B�ނ̌��т̑��́A�܂��A���̈ʒu���ϑ����A���̈ʒu���J�^���O�������u���\�v���쐻�������Ƃł��B�A���g�X�́A���ۂɂ͂��܂萯���ώ@���Ă��Ȃ������悤�ł����A�A���g�X�̋L�^���C��������ŁA����Ō����邷�ׂĂ̐��̈ʒu�ƌ��x�𐳊m�Ɋϑ����A���̂���1080�����܂ސ��\���쐬���܂����B����ɂ�49�������L�^����Ă��܂��B �@ �ނ��ώ@���āA���邳�ނ������@���A���邢����1�����Ƃ��ē���Ō�����ł��Â�����6�����Ƃ��A6�i�K�ɕ�����Ƃ������̂ł��B�܂�A���݂��킽���������g���Ă���A���邳�̕��ޕ��@�ݏo�����l�ł��B���݂ł́A����ɉȊw�I�ɁA1������6�����̖��邳�̍���100�{�Ƃ�1���̈Ⴂ��2.5�{�Ƃ��Ă��܂����A������ɂ��Ă��A�V���w�j��ɖ����c����V���w�҂Ƃ����܂��B�ނ́A�ڂ����ϑ��ɂ���āA��������Ƌ��ɂ��̈ʒu�������Ă��邱�Ƃɂ��C�Â��܂����B����́A�������̒n���̉�]���̕������A����Ƌ��ɕω�����u���v�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B �@ ���̃q�b�p���R�X�̈̋Ƃ��������A�q�b�p���R�X�q����1989�N�ɂ����������A12���̐��̈ʒu���A����܂ł�100�{�̐��x�Ŋϑ����܂����B�����6���̂b�cROM�ɂȂ�܂������A����܂ł̂ǂ�Ȑ��̕\���������x�ŁA�����̐����܂܂�Ă��܂��B �@ ��(6)�g���~�[��48���� �@ ����Ɏ���͂�����A�I����2���I�ɂȂ�ƁA�����̌Ñ㐯�����W�听������厖�Ƃ��ʂ�����܂��B�M���V�A�̓V���w�ҁE���w�ҁE�n���w�ҁE���R�N�w�҂̃v�g���}�C�I�X��N���E�W�I�X�ł��B�p��ǂ݂ł́A�g���~�[�ƌĂ�܂����A�g���~�[�̂ق����䂪���ł͈�ʓI��������܂���B �@ �ނ́A�����̐�������48���ɓ����������A�咘�w�V���w��S�x�������܂��B�w�V���w��S�x�́A�M���V�A��Łw���K���E�V���^�N�V�X�x�Ƃ����薼�ł������A�A���r�A��ɖ|��āw�A���}�Q�X�g�x�Ƃ��A���ꂪ���[���b�p�ɋt�A������w�A���}�Q�X�g�x�̂ق����L���ɂȂ�܂����ɁB�V���w��S�Ƃ������O�̒ʂ�A���̖{�͌Ñ�V���w�̏W�听�ł���A������u�V�����v���m��������̂ł�����܂����B��ɁA�R�y���j�N�X��K�����I���o�Ēn�����������܂ŁA���̍l�����́A�����E�L���X�g���̋����ƌ��т��āA���m�̎v�z�E�w��E�������x�z������̂ɂȂ��Ă������̂ł��B �@ ���̊ԁA�����̐��́A��������������������A���O���ς�炸�A�v�g���}�C�I�X�̐����������Ǝg��ꑱ���܂����B16���I�܂�1500�N�Ԃ������Ɠ����`�Ŏg��ꂽ�̂ł��B�����āA����48������47�܂ł��A�������������g���Ă��鐯���ł��B����48�����́A�u�Ñ�48�����v�܂��͢�g���~�[(�v�g���}�C�I�X)��48������ƌĂ�Ă��܂��B�@ |
|
|
��3�D�ߑ�̐V�ݐ���
�@ �Ƃ������ƂŁA�����Ƃ����Ԃ�1500�߂��A����͋ߐ��ɂȂ�܂��B�ߐ��ɂȂ��āA���2�̗��R�ŁA�V�����������ǂ�ǂ�lj�����܂��B �@ �ЂƂ́A�Â������ϑ����ꂽ��A�]�����̔����Ȃǂɔ����āA��̂ǂ̕����ɂ��ڂ���������悤�ɂȂ��Ă���������ł��B���́A�v�g���}�C�I�X�̐����́A���邢���̂Ȃ��ڗ����Ȃ��Ƃ���́A�ǂ̐����ɂ������Ȃ��u�̕����v���������̂ł��B����ł́A�V�̊ϑ��ɂ͕s�ւł��B���ꂪ��ڂ̗��R�ł��B �@ ��ڂ̗��R�́A1420�N������1620�N����ɂ����ČJ��L����ꂽ�u��q�C����v�ɂ���āA����܂Ő��m�̐l�������s�������Ƃ̂Ȃ���ܓx�n���A����ɐԓ����z���ē씼���ɑ����^�Ԃ悤�ɂȂ������Ƃł��B�씼���ɂ����ƁA�k�����ł݂͂��Ȃ�����������̂ł��B�D��i�߂�ɂ͐��̈ʒu��m��˂Ȃ炸�A�����������m�q�C��̕K�v��������A����܂ł͂Ȃ�������̐V�����������K�v�ɂȂ��Ă����킯�ł��B �@ �������āA16���I�̔�����A��300�N�ԁA�V��������������Ƃ������������V���w�҂�A���}�E�V���V������ЂƂ����ɂ���Đ���ɂ����Ȃ���悤�ɂȂ��Ă������̂ł��B �@ 17���I�����`18���I�̃o�C���[�A���J�C���́A����܂Œm���Ă��Ȃ������씼���̋�̐������l�Ă����V���w�҂ł��B�܂��A�`�R��u���[�G��o���`�E�X�A�փx���E�X���A����܂ł̐����̊Ԃ߂�悤�ɁA�V���Ȑ������t�������Ă����܂����B �@ ��(1)�`�R�E�u���[�G �@ �V���������o�����ŏ��̐l�́A16���I�Ɋ����`�R�E�u���[�G�ł��B�`�R�́A�f���̈ʒu�Ƃ��̕ω����Ɋϑ������l�ł����A���̋M�d�Ȏ������g���Č�ɁA�f���̓��������������̂���q�̃P�v���[�ł��B�`�R�́A1572�N�Ƀ`�R�̐V��������ȂǁA�����̌��т������Ă��܂����A�����̗��j�̏�ł́A�q�b�p���R�X������Ȃ���v�g���}�C�I�X��48�����̒��ɓ���Ȃ������u���݂̂����v���������l�ł��B �@ ��(2)�o�C�G��(�o�C���[) �@ ���[�n���E�o�C���[(1572�`1625)�́A�h�C�c�암�o�C�G�����̔_���ɐ��܂ꂽ�ٌ�m�ł������A�A�}�`���A�V���ƂƂ��Ă����܂����B�ނ́A�w�E���m���g���A,1603�x��31�ŏo�ł��A���݂܂Ŗ����c���Ă��܂��B�w�E���m���g���A�x�́A�v�g���}�C�I�X��48�����ɁA��̐���12��lj����A�S�V1709���̐���`����51���̐��}�ł��B �@ �P���^�E���X���̉��ɁA�����͐����Ȑ����ɂ͂Ȃ�܂���ł�������\����`���A�P���^�E���X���̈ꕔ�ɂ����A����12�̓�̐�����V��������܂����B �@ �E�ӂ����傤�E�J�����I���E�������E��E�݂��ւсE�C���f�B�A���E�����Ⴍ�E�ق������E�݂Ȃ݂̂����E���債���傤�E�Ƃт����E�͂����B �@ ���̂����A�͂����́A�̂��ɂ͂����ƂȂ��āA���ɓ`����Ă��܂��B�܂��A�`�R�����������݂̂����́A����Ă��܂���B�܂��A�}�[�����启�_���A�}�[�������Ƃ��ē��ꂽ�Ƃ�����Ă��܂����A�肩�ł͂���܂���B �@ �����̓씼���̐����́A�o�C���[�����ڌ��ċL�^�����킯�ł͂Ȃ��A�I�����_�̍q�C�ƃy�g���X�E�e�I�h���X���ώ@�������̂��Ƃ���Ă��܂��B �@ �܂��A�o�C���[�́A�e�����̐��X�ɁA���邢���Ԃ� �@ ���A���t�@�E���x�[�^�E���K���}�E�f���^�E�ÃG�v�V�����E�ă[�[�^�E�ŃG�[�^�E�ƃZ�[�^�E�ǃC�v�V�����E�ȃJ�b�p�E�Ƀ����_�E�ʃ~���[�E�˃j���[�E�̃N�V�[�E�̓I�~�N�����E�p�C�E�σ��[�E�ЃV�O�}�E�у^�E�E�҃��[�v�V�����E�Ӄp�C�������̓t�B�[�E�������̓s�[�E�ԃJ�C�E�Ճv�V�[�E�փI���K �@ �ƃM���V�������̃A���t�@�x�b�g��t�����̂ł����A���ꂪ���݂��V���ϑ��Ƃɂ���Ė����̂悤�Ɏg������̂ƂȂ�A�u���̃o�C�G�������v�ƌĂ�Ă��܂��B �@ ��(3)�V���[ �@ �݂Ȃ���́A����ȋ^��������܂��H�@�����Ƃ����ƁA�Ȃ��M���V�A�_�b�ɂ���ċr�F���ꂢ��̂ł����āA�Ȃ��A����قnj��Ђ�U������L���X�g���ł͂Ȃ��̂ł��傤���B�����ɃL���X�g���Ɋւ�鐯���͂Ȃ��̂ł��傤���B �@ ���́A�L���X�g���̗��ꂩ��L���X�g���V�ɓo�ꂷ��l�X�⓹����G�Ƃ��Đ��삵���l�����܂��B15���I�A�L���X�g�������Ń��^�[���@�����v���N�������̂͗L���ł����A���̉��v�h�E�v���e�X�^���g�ɃC�G�Y�X��̔����v�^�����A���Ƀh�C�c�ʼn^�����N�����܂����B���̃h�C�c�ŁA�M�S�ȃJ�g���b�N���k�ŃC�G�Y�X��̉���ł������V���[�Ƃ����l�́A����܂ł̐����ɕς��āA�_�r�f���E�m�A�̔��D�E�\���ˍ��E�L���X�g�̎����t�����A���y�e�����Ȃǂ̐�����`���܂����B�������A���̐��������́A�܂������g���邱�Ƃ͂���܂���ł����B �@ ��(4)�P�v���[ �@ �f���̉^���̖@���������P�v���[�́A�`�R�̒�q�ł����A2���I�̃��[�}�c��n�h���A�k�X���������A���e�B�m�E�X���������܂����B�A���e�B�m�E�X�́A���A�W�A�̃r�e�B�j�A�Ƃ����������Ă���ꂽ�z��̒j�̎q�ŁA�c��n�h���A�k�X�����킢�����Ă������݂̐l���ł��B�A���e�B�m�E�X�́A130�N�Ƀi�C����ł��ڂꎀ��ł��܂��A�c��͒Q���߂��݁A�����ɂ��܂����B����́A�o�C���[��`�R�A�����J�g�����A�Â����̂Ƃ��ĔF�߂Ă��܂������A�P�v���[�͂���𐳎��Ȑ����Ƃ��Ă��܂��܂����B���݂́A�킵���ƂȂ��Ă��܂��B �@ ��(5)�o���`�k�X �@ �P�v���[�̖��ƌ��������h�C�c�̐��w�҂ŁA�����������イ���E�L�������A�������E�e�B�O���X����4��V�݁B���݂����������イ���E�L��������2���c���Ă��܂��B �@ ��(6)�����[�G �@ �t�����X�̓V���w�҂ŁA�͂ƍ��A��\����������܂����B�������Ⴍ���E���̂͂ȍ��́A�F�߂��Ă��܂���B �@ ��(7)�n���[ �@ ���L���͂̔����҃j���[�g���̗F�l�ŁA�n���[�a���̌������炻�̉�A��\�������A�C�M���X�̓V���w�҃G�h�����h�E�n���[�́A�C�M���X���̃`���[���Y2���̖��_���L�O���āu�`���[���Y�̊~�̖؍��v��V�݂������̂́A���̌���ł��Ă��܂��܂����B�܂��A�������`���[���Y�̐S���Ƃ����Ӗ��̃R���E�J��������傤����������̖��O�ɂ��܂������A���̃R���E�J�����Ƃ������O�́A���݂��g���Ă��܂��B �@ ��(8)�L���q �@ ���݂̃h�C�c�̈ꕔ�A�v���V�A�̉����V���w�҂̃L���q�́A�ނ��g���Ă������E�x���w����1�����������āA�u�u�����f���u���O�̉����Ⴍ�v�������������A���̌�͎g���Ȃ��Ȃ�܂����B �@ ��(9)�w�x���E�X �@ 17���I�̃|�[�����h�̓V���w�҃w�x���E�X�́A�|�[�����h�̉�����3���ɕی삳��ėD�ꂽ�V�̊ϑ����s���܂������A���݂������Ɏg���邱���ˁE�������E���āE�Ƃ����E��܂˂��E�낭�ԂE��傤�����7����������܂������A�P���x���X�E�������E�}�G�i���X�R����3�����͂�����Ă��܂��܂����B �@ ��(10)���J�[�� �@ 18���I�̓V���w�҃j�R���E���[�C�E�h�E���J�C���́A�p���̎q�ߐ��������v�Z������A��̐��X�̈ʒu���ϑ��������͔h�̓V���w�҂ł����B�씼���ɁA�ߑ�I�ȗ����w�@��Ȃǂ̑����A�����E����т��傤�E���傤���E���傤�������E���傤�������E�e�[�u���R�E�Ƃ����E�͂�(�͂�)�E�͂��ԂE�ڂ����傤�E�|���v�E���`�N���E�����13������V�݁B�܂��A1756�N�A����Ȑ��������S�����A������4�������A�Ƃ��E�فE�炵���E��イ���Ƃ��܂����B �@ ��(11)�����j�G �@ �t�����X�̓V���w�҂ŁA�s�G�[���E�V�������E�����j�G(1715-1799)�B�p����w�̕����w�����ŁA1782�N�Ƀn�[�V�F�����V����������O�ɁA���x���V�����f���Ƃ͋C�Â����ɓV�������ώ@�����l�B�ƂȂ������Ƃ��ݍ���V�݂������A�����Ƃ�������Ă��܂��܂����B �@ ��(12)���̑� �@ �|�[�����h�̐_���|�X�c�H�u�g��18���I�ɂւт������̒��ɂ������A�u�|�j�A�g�t�X�L�[�̂��������v�A������18���I�̓V���w�҃W���Z�t�E�W�����[���E���E�t�����Z�E�h�E���E�����h���������y�C���E�˂��E�Ď��҃��V�G���E�ǖʎl���V�Ƃ���4�������A���ł͂܂������Y�ꋎ���Ă��܂��B�������A�ǖʎl���V���́A���݂�1���Ɋ��������イ�������Q�̕ʖ��u���Ԃ������Q�v�Ƃ��āA�킸���ɐ������тĂ��܂��B�@ |
|
|
��4�D�����̊m��
�@ ���̂悤�ɂ��āA�����̒����ȓV���w�҂̊ԂŐV������肪���s�����̂ł����A�ő�130�قǂɂ��Ȃ�A�ꎞ�͍�����ԂƂȂ��Ă��܂��܂����B�����ŁA20���I�ɂȂ��āA���E�̓V���w�̋��_�Ƃ������ׂ����ۓV���w�A���ł��̖�肪���グ����悤�ɂȂ�A�I�����_�̃f���|���g���ψ����Ƃ��鏬�ψ��1922�N�ɂ����A�����Ȃ������⍑�ۓI�ɒʗp���Ă��Ȃ����͎̂���ɔp�~�A���̋��ڂ��A���Ă͋Ȑ����������̂��ɁA���Ȃ��獻���̒��̍������̂悤�Ɋm�肵�A88�̐����ɐ��������B1931�N�Ɋm�肵�܂����B �@ ���݁A�������̂��̂ɉȊw�I�ȈӋ`�͂��܂肠��܂���B�������A�����́A���ꐯ���ώ@������A�V���ϑ��Ƃ������ϑ��E�ǐՂ����肷��̂ɖ𗧂��܂��B���Ƃ��A�V���ɂ́u���č��V��2001�v�ȂǂƁA�o�����������V���̖��̂ƂȂ�܂��B�u�����������Q�v�Ƃ��������Q�̖��̂��w�ۓI�ɔF�߂�ꂽ�������̂ł��B�܂��A�V�a�����u�������ɏo���v�Ƃ����j���[�X�������ƁA���E���̓V���w�҂�ϑ��Ƃ́A���̋G�߂Ɛ���������ϑ��\���ԑт�c�����A���̔ӂ̊ϑ��v��𗧂Ă�肪����Ƃ��܂��B���݂ł́A88�̐����������ɔF�߂��Ă��܂����A���̖����́u����̏Z���v�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�@�@ |
|
| �@ | |
|
���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@ |
|