“ъҳIҗн‘ҲӮЖҺ‘Ӣа’І’BҒE“ъҳIҗн‘ҲҺОӮЯҳ_ҒEӢZҸpӮӘҗ§ӮөӮҪ“ъҳIҗн‘ҲҒE“ъҳIҗн‘ҲҺһӮМҠO–ұҸИӮМӢрӮ©ӮіҒEҺR–{Ң •әүqҒE“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYҒE‘еҺRҠЮҒEҒE
–ң”ҺӮЙҢ©ӮйҚЕҗVӢZҸpҒE“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпҒE”Һ——үп”N•\ҒEҒEҒE
Ғ@
ҺGҠwӮМҗўҠEҒE•вҚl
Ғ@Ғ@Ғ@


| ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ1 | |
| –ҫҺЎ37”N2ҢҺ8“ъ-–ҫҺЎ38”N9ҢҺ5“ъ(1904-1905)‘е“ъ–{’йҚ‘ӮЖғҚғVғA’йҚ‘ӮЖӮМҠФӮЕ’©‘N”ј“ҮӮЖ–һҸF“м•”ӮрҺеҗнҸкӮЖӮөӮД”ӯҗ¶ӮөӮҪҗн‘ҲӮЕӮ ӮйҒB—јҚ‘ӮНғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘ӮМ’ҮүоӮМүәӮЕҸIҗнҢрҸВӮЙ—ХӮЭҒA1905”N9ҢҺ5“ъӮЙ’чҢӢӮіӮкӮҪғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӮЙӮжӮиҚuҳaӮөӮҪҒB Ғ@ | |
|
ҒЎҗн‘Ҳ–Ъ“IӮЖ“®Ӣ@
ҒЎ‘е“ъ–{’йҚ‘ ҺOҚ‘ҠұҸВӮЁӮжӮСӢ`ҳa’cӮМ—җҢг–һҸFӮрҗЁ—НҢ—ӮЖӮөӮДӮўӮҪғҚғVғA’йҚ‘ӮЙӮжӮй’©‘N”ј“ҮӮЦӮМ“мүә(’©‘NҺx”z)Ӯр–hӮ¬ҒA“ъ–{ӮМҲА‘S•ЫҸбӮр–Ъ“IӮЖӮөӮҪҗн‘ҲҒB ҒЎғҚғVғA’йҚ‘ —Й“Ң”ј“ҮӮМ—·ҸҮҒA‘еҳA‘dҺШҢ “ҷӮМҠm•ЫӮЖ–һҸFӮЁӮжӮС’©‘NӮЙӮЁӮҜӮйҺ©Қ‘Ң үvӮМҲЫҺқҒEҠg‘еӮр–Ъ“IӮЖӮөӮҪҗн‘ҲҒB ҒЎҠЦ—^Қ‘ҒEҗЁ—Н “ъ–{‘Ө / ‘еҠШ’йҚ‘(ҲкҗiүпӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯйҗe“ъ”h’mҺҜҗlӮЖҗe“ъ”h—ј”З)/ ғCғMғҠғX’йҚ‘(“ъүp“Ҝ–ҝ) / ғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘ ғҚғVғA‘Ө / ‘еҠШ’йҚ‘(ҚӮҸ@ӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺx”zҺТҠKӢүӮЖҗeҳI”hҒE“Ж—§”h’mҺҜҗl) / ғtғүғ“ғX(ҳI•§“Ҝ–ҝ)/ ғhғCғc’йҚ‘ Ғ@ |
|
|
ҒЎҠПҗн•җҠҜ
“ъҳI‘o•ыӮЙ‘Ҫҗ”ӮМҠПҗн•җҠҜӮӘ”hҢӯӮіӮк“ъ–{ӮЙӮНғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘ҒAғhғCғc’йҚ‘ҒAғIҒ[ғXғgғҠғAҒҒғnғ“ғKғҠҒ[’йҚ‘ҒAғXғyғCғ“ҒAғCғ^ғҠғAҒAғXғCғXҒAғXғEғFҒ[ғfғ“ҒҒғmғӢғEғFҒ[ҳAҚҮҒAғuғүғWғӢҒAғ`ғҠҒAғAғӢғ[ғ“ғ`ғ“ҒAғIғXғ}ғ“’йҚ‘ӮМ13№Қ‘Ӯ©Ӯз70җlҲИҸгӮМ•җҠҜӮӘ”hҢӯӮіӮкӮДӮўӮҪҒB“ъүp“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮҫғCғMғҠғXӮ©ӮзӮМ”hҢӯӮӘҚЕ‘ҪӮМ33җlӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBҠПҗн•җҠҜӮН“ъҳIҗн‘ҲӮМҗнҢPӮрҺқӮҝӢAӮҰӮи‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЕҗ¶Ӯ©ӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB ғCғMғҠғXҒ@ғGғBғӢғ}Ғ[ҒEғnғӢғfғBғ“ ғAғҒғҠғJ ғAҒ[ғTҒ[ҒEғ}ғbғJҒ[ғTҒ[ҒEғWғ…ғjғAҒA•ӣҠҜӮЖӮөӮД‘§ҺqӮМғ_ғOғүғXҒEғ}ғbғJҒ[ғTҒ[ӮрҳAӮкӮДӮўӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҗн‘ҲӮМҗ«Ҡi
“ъҳIҗн‘ҲӮН20җўӢIҸүӮМӢЯ‘г‘Қ—НҗнӮМ—v‘fӮрҠЬӮсӮЕӮЁӮиҒAӮЬӮҪ“сҚ‘ҠФӮМӮЭӮИӮзӮё’йҚ‘ҺеӢ`(Ҹ@ҺеҚ‘)ҠeҚ‘ӮМҠOҢрҠЦҢWӮӘҠЦ—^ӮөӮҪғOғҚҒ[ғoғӢӮИӢK–НӮрӮаӮБӮДӮўӮҪҒBӮұӮМӮұӮЖӮ©ӮзҒAүЎҺиҗT“сӮН“ъҳIҗн‘ҲӮН‘ж0ҺҹҗўҠE‘еҗн(World War Zero)ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДӮўӮйҒB Ғ@ |
|
| ҒЎ”wҢi | |
|
ҒЎ’©‘N”ј“ҮӮрӮЯӮ®Ӯй“ъҳI‘О—§
‘еҠШ’йҚ‘ӮНҚы••‘Мҗ§Ӯ©Ӯз—Ј’EӮөӮҪӮаӮМӮМҒA–һҸFӮрҗЁ—НүәӮЙӮЁӮўӮҪғҚғVғAӮӘ’©‘N”ј“ҮӮЙҺқӮВ—ҳҢ ӮрҺиӮӘӮ©ӮиӮЙ“мүәҗӯҚфӮрҺжӮиӮВӮВӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮНҚӮҸ@Ӯр’КӮ¶”„Ӯи•ҘӮнӮкӮҪҸЯҸйҒEӢҫҢ№ӮМҚzҺRҚМҢ@Ң Ӯв’©‘N–k•”ӮМҗX—С”°ҚМҢ ҒAҠЦҗЕҢ ӮИӮЗӮМҚ‘үЖҠо”ХӮрҺж“ҫӮө’©‘N”ј“ҮӮЕӮМүeӢҝ—НӮр‘қӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAӮМҗiӮЯӮй“мүәҗӯҚфӮЙҠлӢ@Ҡҙ(1861”NӮЙғҚғVғAҢRҠН‘О”nҗи—МҺ–ҢҸӮӘӮ ӮБӮҪҲЧ)ӮрҺқӮБӮДӮўӮҪ“ъ–{ӮӘӮұӮкӮзӮр”ғӮў–ЯӮөүс•ңӮіӮ№ӮҪҒB “–ҸүҒA“ъ–{ӮНҠOҢр“w—НӮЕҸХ“ЛӮр”рӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAӮНӢӯ‘еӮИҢRҺ–—НӮр”wҢiӮЙ“ъ–{ӮЦӮМҲі—НӮр‘қӮөӮДӮўӮБӮҪҒB1904”N2ҢҺ23“ъҒAҠJҗн‘OӮЙҒuӢЗҠO’Ҷ—§җйҢҫҒvӮрӮөӮҪ‘еҠШ’йҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮйҢRҺ–Қs“®ӮрүВ”\ӮЙӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙ“ъҠШӢc’иҸ‘Ӯр’чҢӢӮөҒAҠJҗнҢг8ҢҺӮЙӮН‘жҲкҺҹ“ъҠШӢҰ–сӮр’чҢӢҒA‘еҠШ’йҚ‘ӮМҚаҗӯҒAҠOҢрӮЙҢЪ–вӮр’uӮ«Ҹр–с’чҢӢӮЙ“ъ–{җӯ•{ӮЖӮМӢҰӢcӮрӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒB‘еҠШ’йҚ‘“аӮЕӮа—ӣҺҒ’©‘NӮЙӮжӮйӢҢ‘Мҗ§ӮӘҲЫҺқӮіӮкӮДӮўӮйҸуӢөӮЕӮН“ЖҺ©үьҠvӮӘ“пӮөӮўӮЖ”»’fӮөӮҪҗi•аүпӮН“ъҠШҚҮ–MӮр–ЪҺwӮ»ӮӨӮЖ“S“№•~җЭҚHҺ–ӮИӮЗӮЙ5–ңҗlӮЖӮаӮўӮнӮкӮй‘е—КӮМҗlҲхӮр”hҢӯӮ·ӮйӮИӮЗҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮД“ъ–{ӮЦӮМӢҰ—НӮрҗЙӮөӮЬӮИӮ©ӮБӮҪҒB Ҳк•ыҒAҚӮҸ@Ӯв—ј”ЗӮИӮЗӮМӢҢ—ӣ’©Һx”zҺТ‘wӮН“ъ–{ӮМүeӢҝ—НӮрӮ ӮӯӮЬӮЕӮа”rҸңӮөӮжӮӨӮЖҺҺӮЭҒA“ъҳIҗн‘Ҳ’ҶӮЙӮЁӮўӮДӮағҚғVғAӮЙ–§Ҹ‘Ӯр‘—ӮйӮИӮЗӮМҠOҢрӮр“WҠJӮөӮДӮўӮБӮҪҒBҗн‘Ҳ’ҶӮЙ–§ҺgӮӘ“ъ–{ҢRҠНӮЙӮжӮиҠCҸгӮЙӮД”ӯҢ©ӮіӮкҒA‘еҠШ’йҚ‘ӮНҸр–сҲб”ҪӮр”ЖӮ·ӮЖӮўӮӨҺё”sӮЙҸIӮнӮйҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ“ъүp“Ҝ–ҝ
ғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒA•s“ҖҚ`ӮрӢҒӮЯӮД“мүәҗӯҚфӮрҚМ—pӮөҒAҳI“yҗн‘ҲӮИӮЗӮМҸҹ—ҳӮЙӮжӮБӮДғoғӢғJғ“”ј“ҮӮЙӮЁӮҜӮй‘еӮ«ӮИ’n•аӮрҠl“ҫӮөӮҪҒBғҚғVғAӮМүeӢҝ—НӮМ‘қ‘еӮрҢxүъӮ·ӮйғhғCғc’йҚ‘ӮМҚЙ‘ҠғrғXғ}ғӢғNӮН—сӢӯӮМ‘г•\ӮрҸWӮЯӮДғxғӢғҠғ“үпӢcӮрҺеҚГӮөҒAҳI“yҗн‘ҲӮМҚuҳaҸр–сӮЕӮ ӮйғTғ“ҒEғXғeғtғ@ғmҸр–сӮМ”jҠьӮЖғxғӢғҠғ“Ҹр–сӮМ’чҢӢӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиғҚғVғAӮНғoғӢғJғ“”ј“ҮӮЕӮМ“мүәҗӯҚфӮр’f”OӮөҒAҗiҸoӮМ–өҗжӮрӢЙ“Ң’nҲжӮЙҢьӮҜӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB ӢЯ‘гҚ‘үЖӮМҢҡҗЭӮрӢ}Ӯ®“ъ–{ӮЕӮНҒAғҚғVғAӮЙ‘ОӮ·ӮйҲА‘S•ЫҸбҸгӮМ—қ—RӮ©ӮзҒA’©‘N”ј“ҮӮрҺ©Қ‘ӮМҗЁ—НүәӮЙӮЁӮӯ•K—vӮӘӮ ӮйӮЖӮМҲУҢ©ӮӘ‘еҗЁӮрҗиӮЯӮДӮўӮҪҒB’©‘NӮр‘®Қ‘ӮЖӮөӮДӮўӮҪҗҙӮЖӮМ“ъҗҙҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮөҒA’©‘N”ј“ҮӮЦӮМүeӢҝ—НӮр”rҸңӮөӮҪӮаӮМӮМҒA’ҶҚ‘ӮЦӮМҗiҸoӮр–Ъҳ_ӮЮғҚғVғAҒAғtғүғ“ғXҒAғhғCғcӮ©ӮзӮМҺOҚ‘ҠұҸВӮЙӮжӮБӮДҒAүәҠЦҸр–сӮЕҠ„ҸчӮрҺуӮҜӮҪ—Й“Ң”ј“ҮӮНҗҙӮЙ•ФҠТӮіӮкӮҪҒBҗўҳ_ӮЙӮЁӮўӮДӮНғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮаҺ«ӮіӮёӮЖӮўӮӨӢӯҚdӮИҲУҢ©ӮаҸoӮҪӮӘҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЙӮН—сӢӯҸ”Қ‘ӮЖҗнӮҰӮйӮҫӮҜӮМ—НӮН–іӮӯҒAҗӯ•{“аӮЕӮНҲЙ“Ў”Һ•¶Ӯзҗн‘Ҳүс”р”hӮӘҺе—¬ӮрҗиӮЯӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘғҚғVғAӮНҳIҗҙ–§–сӮрҢӢӮСҒA“ъ–{ӮӘҺи•ъӮөӮҪ—Й“Ң”ј“ҮӮМ“м’[ӮЙҲК’uӮ·Ӯй—·ҸҮҒE‘еҳAӮр1898”NӮЙ‘dҺШӮөҒA—·ҸҮӮЙ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМҠо’nӮр‘ўӮйӮИӮЗҒA–һҸFӮЦӮМҗiҸoӮрүҹӮөҗiӮЯӮДӮўӮБӮҪҒB 1900”NӮЙғҚғVғAӮНҗҙӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪӢ`ҳa’cӮМ—җ(Ӣ`ҳa’cҺ–•ПҒAӢ`ҳa’cҺ–ҢҸ)ӮМҚ¬—җҺыҸEӮМӮҪӮЯ–һҸFӮЦҗNҚUӮөҒA‘S“yӮрҗи—МүәӮЙ’uӮўӮҪҒBғҚғVғAӮН–һҸFӮМҗA–Ҝ’nү»ӮрҠщ’иҺ–ҺАү»ӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒA“ъүp•ДӮӘӮұӮкӮЙҚRӢcӮөғҚғVғAӮН“P•әӮр–с‘©ӮөӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘғҚғVғAӮН—ҡҚsҠъҢАӮрүЯӮ¬ӮДӮа“P‘ЮӮрҚsӮнӮё’“—ҜҢRӮМ‘қӢӯӮрҗ}ӮБӮҪҒBғ{Ғ[ғAҗн‘ҲӮрҸI—№ӮіӮ№ӮйӮМӮЙҗн”пӮр’І’BӮөӮҪӮҪӮЯҚ‘—НӮӘ’бүәӮөӮДғAғWғAӮЙ‘еӮ«ӮИҚ‘—НӮр’ҚӮ°ӮИӮўҸуӢөӮЕӮ ӮБӮҪғCғMғҠғXӮНҒAғҚғVғAӮМ“мүәӮӘҺ©Қ‘ӮМҢ үvӮЖҸХ“ЛӮ·ӮйӮЖҠлӢ@ҠҙӮр•еӮзӮ№ҒA1902”NӮЙ’·”N–nҺзӮөӮДӮўӮҪҢЗ—§җӯҚф(үhҢхӮ ӮйҢЗ—§)ӮрҺМӮДҒA“ъ–{ӮЖӮМ“Ҝ–ҝӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮҪ(“ъүp“Ҝ–ҝ)ҒB“ъ–{җӯ•{“аӮЕӮНҸ¬‘әҺх‘ҫҳYҒAҢj‘ҫҳYҒAҺRгp—L•ьӮзӮМ‘ОҳIҺеҗн”hӮЖҒAҲЙ“Ў”Һ•¶ҒAҲдҸгҠ]Ӯзҗн‘Ҳүс”р”hӮЖӮМҳ_‘ҲӮӘ‘ұӮ«ҒA–ҜҠФӮЙӮЁӮўӮДӮа“ъҳIҠJҗнӮрҸҘӮҰӮҪҢЛҗ…Ҡ°җlӮзҺө”ҺҺmӮМҲУҢ©Ҹ‘(Һө”ҺҺmҢҡ”’Һ–ҢҸ)ӮвҒA–ң’©•сҺҶҸгӮЕӮМҚK“ҝҸHҗ…ӮМ”сҗнҳ_ӮЖӮўӮБӮҪӢcҳ_ӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮДӮўӮҪҒB 1903”N4ҢҺ21“ъӮЙӢһ“sӮЙӮ ӮБӮҪҺRгpӮМ•К‘‘ҒE–ізБҲБӮЕҲЙ“ЎҒEҺRгpҒEҢjҒEҸ¬‘әӮЙӮжӮйҒu–ізБдҪүпӢcҒvӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBҢjӮНҒAҒu–һҸF–в‘иӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒAүдӮЙү—ӮДҳIҡ ӮМ—DүzҢ Ӯр”FӮЯҒA”VӮрӢ@ӮЖӮөӮД’©‘N–в‘иӮрҚӘ–{“IӮЙүрҢҲӮ·ӮйӮұӮЖҒvҒAҒuҚҹӮМ–Ъ“IӮрҠС“OӮ№ӮсӮЖ—~Ӯ№ӮОҒAҗн‘ҲӮрӮаҺ«Ӯ№ӮҙӮйҠoҢе–іӮ©ӮйүВӮ©ӮзӮёҒvӮЖӮўӮӨ‘ОҳIҢрҸВ•ыҗjӮЙӮВӮўӮДҲЙ“ЎӮЖҺRгpӮМ“ҜҲУӮр“ҫӮҪҒB ҢjӮНҢгӮЙӮұӮМүп’kӮЕ“ъҳIҠJҗнӮМҠoҢеӮӘ’иӮЬӮБӮҪӮЖҸ‘ӮўӮДӮўӮйӮӘҒAҺАҚЫӮМӢLҳ^—ЮӮЕӮНӮЮӮөӮлҲЙ“ЎӮМҗTҸdҳ_ӮӘ—DҗЁӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕҒAҢгӮМ“ъҳIҢрҸВӮЙ”ҪүfӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ’ј‘OҢрҸВ
1903”N8ҢҺӮ©ӮзӮМ“ъҳIҢрҸВӮЙӮЁӮўӮДҒA“ъ–{‘ӨӮН’©‘N”ј“ҮӮр“ъ–{ҒA–һҸFӮрғҚғVғAӮМҺx”zүәӮЙ’uӮӯӮЖӮўӮӨ‘ГӢҰҲДҒAӮўӮнӮдӮй–һҠШҢрҠ·ҳ_ӮрғҚғVғA‘ӨӮЦ’сҲДӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҗПӢЙ“IӮИҺеҗнҳ_ӮрҺе’ЈӮөӮДӮўӮҪғҚғVғAҠCҢRӮвҠЦ“ҢҸB‘Қ“ВӮМғGғ”ғQҒ[ғjғCҒEғAғҢғNғZҒ[ғGғtӮзӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮЕӮа‘қӮҰӮВӮВӮ ӮБӮҪғҚғVғAӮМ—ҳҢ Ӯр–WҠQӮіӮкӮйӢ°ӮкӮМӮ Ӯй‘ГӢҰҲДӮЙӢ»–ЎӮрҺҰӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙғjғRғүғC2җўӮвғAғҢғNғZғCҒEғNғҚғpғgғLғ“—ӨҢR‘еҗbӮаҺеҗнҳ_ӮЙ“Ҝ’ІӮөӮҪҒBҸнҺҜ“IӮЙҚlӮҰӮкӮОҒAӢӯ‘еӮИғҚғVғAӮӘ“ъ–{ӮЖӮМҗн‘ҲӮрӢ°ӮкӮй—қ—RӮНүҪӮа–іӮ©ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮМҸdҗbӮМ’ҶӮЕӮағZғӢғQғCҒEғ”ғBғbғeҚа–ұ‘еҗbӮНҒAҗн‘ҲӮЙӮжӮБӮД•үӮҜӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮЙӮ№ӮжғҚғVғAӮӘ”ж•ҫӮ·ӮйӮұӮЖӮрӢ°Ӯкҗн‘Ҳүс”рҳ_Ӯр“WҠJӮөӮҪӮӘҒAӮұӮМ“–ҺһүҪӮМҺАҢ ӮаӮИӮ©ӮБӮҪ‘еҗbүпӢcӢc’·(ҢгӮМҸ\ҢҺҸЩҸ‘ӮЕҺс‘Ҡ‘Ҡ“–ӮЙӮИӮйғ|ғXғg)ӮЙҚ¶‘JӮіӮкӮҪҒBғҚғVғAӮН“ъ–{‘ӨӮЦӮМ•Ф“ҡӮЖӮөӮДҒA’©‘N”ј“ҮӮМ–kҲЬ39“xҲИ–kӮр’Ҷ—§’n‘СӮЖӮөҒAҢRҺ––Ъ“IӮЕӮМ—ҳ—pӮрӢЦӮёӮйӮЖӮўӮӨ’сҲДӮрҚsӮБӮҪҒB “ъ–{‘ӨӮЕӮНҒAӮұӮМ’сҲДӮЕӮН“ъ–{ҠCӮЙ“ЛӮ«ҸoӮҪ’©‘N”ј“ҮӮӘҺ–ҺАҸгғҚғVғAӮМҺx”zүәӮЖӮИӮиҒA“ъ–{ӮМ“Ж—§ӮаҠлӢ@“IӮИҸуӢөӮЙӮИӮиӮ©ӮЛӮИӮўӮЖ”»’fӮөӮҪҒBӮЬӮҪғVғxғҠғA“S“№ӮӘ‘SҗьҠJ’КӮ·ӮйӮЖғҲҒ[ғҚғbғpӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮйғҚғVғAҢRӮМӢЙ“Ң•ы–КӮЦӮМ”hҢӯӮӘ—eҲХӮЖӮИӮйӮМӮЕҒAӮ»ӮМ‘OӮМ‘ОҳIҠJҗнӮЦӮЖҚ‘ҳ_ӮӘҢXӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮД1904”N2ҢҺ6“ъҒA“ъ–{ӮМҠO–ұ‘еҗbҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮН“–ҺһӮМғҚғVғAӮМғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgӮрҠO–ұҸИӮЙҢДӮСҒAҚ‘Ңр’fҗвӮрҢҫӮў“nӮөӮҪҒB“Ҝ“ъҒA’“ҳIҢцҺgҢI–мҗTҲкҳYӮНҒAғүғҖғXғhғӢғtҠO‘ҠӮЙҚ‘Ңр’fҗвӮр’К’mӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҠeҚ‘ӮМҺvҳf
“мғAғWғAӮЁӮжӮСҗҙӮЙҢ үvӮрҺқӮВғCғMғҠғXӮНҒA“ъүp“Ҝ–ҝӮЙҠоӮГӮ«“ъ–{ӮЦӮМҢRҺ–ҒAҢoҚП“IҺxүҮӮрҚsӮБӮҪҒBҳI•§“Ҝ–ҝӮрҢӢӮСғҚғVғAӮЦҺ‘–{Ӯр“ҠүәӮөӮДӮўӮҪғtғүғ“ғXӮЖҒAғ”ғBғӢғwғӢғҖ2җўӮЖғjғRғүғC2җўӮЖӮӘүҸҗКҠЦҢWӮЙӮ ӮйғhғCғcӮНҗSҸо“IӮЙӮНғҚғVғA‘ӨӮЕӮ ӮБӮҪӮӘӢп‘М“IӮИҺxүҮӮНҚsӮБӮДӮўӮИӮўҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҠOүЭ’І’B
җн‘ҲҗӢҚsӮЙӮН–c‘еӮИ•ЁҺ‘ӮМ—A“ьӮӘ•sүВҢҮӮЕӮ ӮиҒA“ъ–{ӢвҚs•ӣ‘ҚҚЩҚӮӢҙҗҘҗҙӮН“ъ–{ӮМҸҹҺZӮр’бӮӯҢ©җПӮаӮй“–ҺһӮМҚ‘ҚЫҗўҳ_ӮМүәӮЕҠOүЭ’І’BӮЙ”сҸнӮЙӢкҗSӮөӮҪҒB“–ҺһҒAҗӯ•{ӮМҗн”пҢ©җПӮаӮиӮН4үӯ5җз–ңү~ӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮМҢoҢұӮЕҗн”пӮМ1/3ӮӘҠCҠOӮЙ—¬ҺёӮөӮҪӮМӮЕҒAҚЎүсӮН1үӯ5җз–ңү~ӮМҠOүЭ’І’BӮӘ•K—vӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕ“ъӢвӮМ•Ы—LҗіүЭӮН5җз2•S–ңү~ӮЕӮ ӮиҒA–с1үӯү~ӮрҠOүЭӮЕ’І’BӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠOҚ‘ҢцҚВӮМ•еҸWӮЙӮН’S•ЫӮЖӮөӮДҠЦҗЕҺы“ьӮр“–ӮДӮйӮұӮЖӮЖӮөҒA”ӯҚsҠz1үӯү~ҒAҠъҠФ10”NҗҳӮҰ’uӮ«ӮЕҚЕ’·45”NҒAӢа—ҳ5Ғ“ҲИүәӮЖӮМҸрҢҸӮЕҒAҚӮӢҙҗҘҗҙ(ҠOҚВ”ӯҚs’cҺеҗИ)ӮНҢj‘Қ—қҘ‘\”H‘ ‘ҠӮ©ӮзҲП”CҸуӮЖ–Ҫ—ЯҸ‘ӮрҺуӮҜҺжӮБӮҪҒB ҠJҗнӮЖӮЖӮаӮЙ“ъ–{ӮМҠщ”ӯӮМҠOҚВӮН–\—ҺӮөӮДӮЁӮиҒAҸүүсӮЙҢvүжӮіӮкӮҪ1000–ңғ|ғ“ғhӮМҠOҚВ”ӯҚsӮаӮЬӮБӮҪӮӯҲшӮ«ҺуӮҜҺиӮӘҢ»ӮкӮИӮўҸуӢөӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҒA“–ҺһӮМҗўҠE’ҶӮМ“ҠҺ‘үЖӮӘҒA“ъ–{ӮӘ”s–kӮөӮДҺ‘ӢаӮӘүсҺыӮЕӮ«ӮИӮўӮЖ”»’fӮөӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮӯӮЙғtғүғ“ғXҢnӮМ“ҠҺ‘үЖӮНғҚғVғAӮЖӮМ“Ҝ–ҝ(ҳI•§“Ҝ–ҝ)ӮМҺи‘OӮаӮ Ӯи“–ҸүӮН”сҸнӮЙ—в’WӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮҪғhғCғcҢnӮМӢвҚs’cӮаҗTҸdӮЕӮ ӮБӮҪҒB җҘҗҙӮН4ҢҺӮЙғCғMғҠғXӮЕҒAҠz–К100ғ|ғ“ғhӮЙ‘ОӮөӮД”ӯҚsүҝҠiӮр93.5ғ|ғ“ғhӮЬӮЕ’lүәӮ°ӮөҒA“ъ–{ӮМҠЦҗЕҺы“ьӮр’п“–ӮЖӮ·ӮйҚDҸрҢҸӮЕҒAғCғMғҠғXӮМӢвҚsүЖӮҪӮҝӮЖ1ғ–ҢҺҲИҸгҢрҸВӮМ––ҒAӮжӮӨӮвӮӯғҚғ“ғhғ“ӮЕӮМ500–ңғ|ғ“ғhӮМҠOҚВ”ӯҚsӮМҗ¬ҺZӮр“ҫӮҪҒBӮЬӮҪғҚғ“ғhғ“ӮЙ‘ШҚЭ’ҶӮЕӮ ӮиҒA’йҗӯғҚғVғAӮр“GҺӢӮ·ӮйғhғCғcҢnӮМғAғҒғҠғJғҶғ_ғ„җlӢвҚsүЖғWғFғCғRғuҒEғVғtӮМ’mӢцӮр“ҫҒAғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮМӢа—ZҠXӮЖӮөӮДҺcҠz500–ңғ|ғ“ғhӮМҠOҚВҲшӮ«ҺуӮҜӮЁӮжӮС’ЗүБ—ZҺ‘ӮрҠl“ҫӮөӮҪҒBӮұӮМҲшӮ«ҺуӮҜӮЙӮВӮўӮДӮНғҚғ“ғhғ“Ӣа—ZҠXӮЖӮөӮДӮағjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮМҺQүБӮН“nӮиӮЙҸMӮМҠПӮӘӮ ӮБӮҪҒB‘ж1үсӮН1904”N5ҢҺ2“ъӮЙүј’ІҲуӮЙӮұӮ¬ӮВӮҜӮҪҒB ҢӢүК“–ҸүӮМ’І’BӢа—ҳӮрҸгүсӮй6%ӮЕӮМ’І’B(Ҡ„Ҳш”ӯҚsӮИӮМӮЕҺАҺҝӢа—ҳӮН7”NҸһҠТӮЕ–с7%)ӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒAүһ•еҸуӢөӮНғҚғ“ғhғ“ӮӘ‘еҗ·ӢөӮЕ•еҸWҠzӮМ–с26”{ҒAғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮЕ3”{ӮЖӮИӮи‘еҗ¬ҢчӮМ”ӯҚsӮЖӮИӮБӮҪҒB1904”N5ҢҺӮЙҠӣ—ОҚ]ӮМ“nүНҚмҗнӮЕғҚғVғAӮрҲі“|ӮөӮД“ъ–{ӮӘҸҹ—ҳӮ·ӮйӮЖҚ‘ҚЫҺsҸкӮЕ“ъ–{ҠOҚВӮНҲА’иӮөҒA‘ж2үсӮМ1904”N11ҢҺӮМ6.0%(ҸһҠТ7”NӮЕҺАҺҝ–с7.4Ғ“)Ӯр’кӮЖӮөӮДҒA1905”N3ҢҺӮМ‘ж3үсӮЕӮН4.5Ғ“ӮЕӮМҺШӮиҠ·ӮҰ’І’B(3үӯү~ҒAҠ„Ҳш”ӯҚsӮИӮМӮЕҸһҠТ20”NӮЕҺАҺҝ5.0Ғ“ҒA’S•ЫӮНүҢ‘җҗк”„үv)ӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒB‘ж3үсӮ©ӮзӮНғhғCғcҢnӮМӢвҚs’cӮаҺQүБӮө•еҸWӮН‘еҗ·ӢөҒA‘ж5үсӮ©ӮзӮНғtғүғ“ғXҢnӮМӢвҚs’cӮаҺQүБӮөӮҪӮӘ(үpҘ•§ғҚғXғ`ғғғCғӢғhӮаӮұӮМүсӮЕӮЖӮаӮЙҺQүБ)ӮұӮМӮЖӮ«ӮЙӮНӮ·ӮЕӮЙ“ъҳIҗн‘ҲӮНҸIҢӢӮөӮДӮўӮҪҒB ҢӢӢЗ“ъ–{ӮН1904”NӮ©Ӯз1906”NӮЙӮ©ӮҜҚҮҢv6ҺҹӮМҠOҚВ”ӯҚsӮЙӮжӮиҒAҺШӮиҠ·ӮҰ’І’BӮрҠЬӮЯ‘ҚҠz1–ң3000ғ|ғ“ғh(–с13үӯү~Һг)ӮМҠOүЭҢцҚВӮр”ӯҚsӮөӮҪҒBӮұӮМ“аҚЕҸүӮМ4үсҒA8200–ңғ|ғ“ғhӮМӢNҚВӮӘҺАҺҝ“IӮИҗн”п’І’BҺ‘ӢаӮЕӮ ӮиҒAӮ ӮЖӮМ2үсӮНҚDҸрҢҸӮЦӮМҗШӮи‘ЦӮҰ”ӯҚsӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮИӮЁ“ъҳIҗн‘ҲҠJҗн‘O”NӮМ1903”N(–ҫҺЎ36”N)ӮМҲк”КүпҢvҚО“ьӮН2.6үӯү~ӮЕӮ ӮиҒAӮўӮ©ӮЙӢҗҠzӮМҺ‘Ӣа’І’BӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮӘ•ӘӮ©ӮйҒB Қ‘ӮМҲк”КҘ“Б•КүпҢvӮЙӮжӮйӮЖ“ъҳIҗн‘ҲӮМҗн”п‘ҚҠzӮН18үӯ2629–ңү~ӮЖӮіӮкӮйҒB Ғ@ |
|
| ҒЎҢoүЯ | |
|
ҒЎҠJҗнҺһӮМ—јҢRӮМҠо–{җн—Ә
ҒЎ“ъ–{‘Ө ҠCҢRӮӘ‘жҲкҠН‘аӮЖ‘ж“сҠН‘аӮрӮаӮБӮД—·ҸҮӮЙӮўӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрҹr–ЕӮИӮўӮө••ҚҪӮөҒA‘жҺOҠН‘аӮрӮаӮБӮД‘О”nҠCӢ¬Ӯр—}ӮҰҗ§ҠCҢ ӮрҠm•ЫӮ·ӮйҒBӮ»ӮМҢг—ӨҢRӮӘ‘жҲкҢRӮрӮаӮБӮД’©‘N”ј“ҮӮЦҸг—ӨҒAҚЭ’©‘NӮМғҚғVғAҢRӮрӢм’ҖӮөҒA‘ж“сҢRӮрӮаӮБӮД—Й“Ң”ј“ҮӮЦӢҙ“ӘҡЖӮр—§ӮД—·ҸҮӮрҢЗ—§ӮіӮ№ӮйҒBӮіӮзӮЙӮұӮкӮзӮЙ‘жҺOҢRҒA‘жҺlҢRӮрүБӮҰӮҪҺlҢВҢRӮрӮаӮБӮДҒA–һҸF•Ҫ–мӮЙӮДғҚғVғAҢRҺе—НӮр‘ҒӮЯӮЙҹr–ЕӮ·ӮйҒBӮМӮҝӮЙүҲҠCҸBӮЦҗiҢӮӮөҒAғEғүғWғIғXғgғbғNӮМҚU—ӘӮЬӮЕ‘z’иҒBҠCҢRӮЙӮжӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМҹr–ЕӮНғҲҒ[ғҚғbғpӮжӮиүсҚqӮӘ—\‘zӮіӮкӮйғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“һ’…ӮЬӮЕӮЙҚsӮӨҒBҢR—ЯӢ@ҠЦӮӘ—ӨҠCҢR•А—с‘О“ҷӮЖӮИӮБӮҪҸүӮЯӮДӮМҗн‘ҲӮЕӮ ӮйҒB ҒЎғҚғVғA‘Ө “ъ–{‘ӨӮМҸг—ӨӮр’©‘N”ј“Ү“м•”ӮЖ‘z’иҒBҠӣ—ОҚ]•tӢЯӮЙҢRӮрҸWҢӢӮіӮ№ҒA–kҸгӮ·Ӯй“ъ–{ҢRӮрҢ}ҢӮӮіӮ№ӮйҒBҢ}ҢӮҗнӮЕ“ъ–{ҢRӮМ‘OҗiӮрӢ–ӮөӮҪҸкҚҮӮНҒA“ъ–{ҢRӮрҲшӮ«•tӮҜӮИӮӘӮзҸҮҺҹғnғӢғrғ“ӮЬӮЕҢг‘ЮӮөҒA•вӢӢҗьӮМү„ӮСӮ«ӮБӮҪ“ъ–{ҢRӮрҹr–ЕӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҗн—ӘӮЙ•ПӮнӮйҒB‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮН–і—қӮЙҢҲҗнӮрӮ№ӮёҒAғҲҒ[ғҚғbғp•ы–КӮ©ӮзӮМ‘қүҮӮр‘ТӮВҒBӮҪӮҫӮөғҚғVғA‘ӨӮЕӮНӮұӮМҺһҠъӮМҠJҗнӮр‘z’иӮөӮДӮЁӮзӮёҒA—·ҸҮӮЦүсҚq’ҶӮҫӮБӮҪҗнҠНғIғXғҠғғҒ[ғrғғӮӘҠФӮЙҚҮӮнӮИӮ©ӮБӮҪӮИӮЗҒAҸҖ”хӮН–ң‘SӮЖҢҫӮҰӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҠJҗн
ҒЎҠJҗнҺһӮМ“ъ–{ҠCҢRӮМҺеӮИҗ퓬ҠН’ш ҳAҚҮҠН‘а ‘жҲкҠН‘а Ғ@Ғ@Ғ@‘жҲкҗн‘а(җнҠН6җЗҒFҺOҠ}ҒA’©“ъҒAҸүҗЈҒA•~“ҮҒA•xҺmҒA”Ә“Ү) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҺOҗн‘а(–hҢмҸ„—mҠН4җЗҒFҗзҚОҒAҚӮҚ»ҒAҠ}’uҒAӢg–м) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҲкӢм’Җ‘а(Ӣм’ҖҠН4җЗҒF”’ү_ҒA’©’ӘҒAүаҒAӢЕ) Ғ@Ғ@Ғ@‘ж“сӢм’Җ‘а(Ӣм’ҖҠН4җЗҒF—ӢҒAһOҒA“dҒAҸҢ) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҺOӢм’Җ‘а(Ӣм’ҖҠН3җЗҒF”–ү_ҒA“Ңү_ҒA—ш) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҲк’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒF‘ж69ҚҶ’шҒA‘ж67ҚҶ’шҒA‘ж68ҚҶ’шҒA‘ж70ҚҶ’ш) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҸ\Һl’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒFҗз’№ҒA”№ҒAҗ^’ЯҒAкF) ‘ж“сҠН‘а Ғ@Ғ@Ғ@‘ж“сҗн‘а(‘•ҚbҸ„—mҠН6җЗҒFҸoү_ҒA”ЦҺиҒAҗуҠФҒAҸн”ХҒA”Әү_ҒAҢбҚИ) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҺlҗн‘а(–hҢмҸ„—mҠН4җЗҒFҳQ‘¬ҒAҚӮҗз•дҒAҗVҚӮҒA–ҫҗО) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҺlӢм’Җ‘а(Ӣм’ҖҠН4җЗҒF‘¬’№ҒAҸtүJҒA‘әүJҒA’©–¶) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҢЬӢм’Җ‘а(Ӣм’ҖҠН4җЗҒF—zүҠҒA‘pү_ҒA—[–¶ҒA•s’mүО) Ғ@Ғ@Ғ@‘жӢг’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒF‘“‘йҒAйщҒAҠеҒAүҚ) Ғ@Ғ@Ғ@‘ж“сҸ\’ш‘а(җ…—Ӣ’ш3’шҒF‘ж62ҚҶ’шҒA‘ж63ҚҶ’шҒA‘ж64ҚҶ’шҒA‘ж65ҚҶ’ш) ‘жҺOҠН‘а Ғ@Ғ@Ғ@‘жҢЬҗн‘а(4җЗҒF’Бү“ҒAҸј“ҮҒAӢҙ—§ҒAҢө“Ү) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҳZҗн‘а(–hҢмҸ„—mҠН4җЗҒFҸH’ГҸFҒAҳaҗтҒAҗ{–ҒҒAҗз‘г“c) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҺөҗн‘а(—Ә) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҲк’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒF‘ж43ҚҶ’шҒA‘ж42ҚҶ’шҒA‘ж40ҚҶ’шҒA‘ж41ҚҶ’ш) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҸ\Ҳк’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒF‘ж73ҚҶ’шҒA‘ж72ҚҶ’шҒA‘ж74ҚҶ’шҒA‘ж75ҚҶ’ш) Ғ@Ғ@Ғ@‘жҸ\ҳZ’ш‘а(җ…—Ӣ’ш4’шҒF”’‘йҒA‘ж71ҚҶ’шҒA‘ж39ҚҶ’шҒA‘ж66ҚҶ’ш) ҒЎҠJҗнҺһӮМӢЙ“ҢғҚғVғAҠCҢRӮМҺеӮИҗ퓬ҠН’ш ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а(—·ҸҮҠН‘а) Ғ@Ғ@Ғ@җнҠН7җЗ(ғcғFғTғҢҒ[ғ”ғBғ`ҒAғҢғgғ”ғBғUғ“ҒAғyғҢғXғ”ғFҒ[ғgҒAғ|ғӢғ^ғ”ғ@ҒAғyғgғҚғpғ”ғҚғtғXғNҒAғZғ”ғ@ғXғgҒ[ғ|ғҠҒAғ|ғxҒ[ғ_) Ғ@Ғ@Ғ@‘•ҚbҸ„—mҠН1җЗ(ғoғ„Ғ[ғ“) Ғ@Ғ@Ғ@–hҢмҸ„—mҠН8җЗ(ғpғӢғүҒ[ғ_ҒAғfғBғAғiҒAғAғXғRғҠғhҒAғ{ғ„Ғ[ғҠғ“ҒAғmҒ[ғEғBғbғNҒAғUғrғ„Ғ[ғJҒAғүғYғ{ғCғjғNҒAғYғWғMҒ[ғg) Ғ@Ғ@Ғ@–CҠНҒEҗ…—Ӣ–CҠН6җЗ(ғOғҠғ~ғ„ғVғ`Ғ[ҒAғAғbғҸғwғWғkғCҒAғMғҠғ„Ғ[ғNҒAғ{Ғ[ғuғӢҒAғtғTҒ[ғhғjғNҒAғKғCғ_ғ}Ғ[ғN) Ғ@Ғ@Ғ@Ӣм’ҖҠН18җЗ(ҸЪҚЧ—ӘҒB‘јӮЙҠJҗнҢгӮМҸvҚHҠНӮӘҗ”җЗ) ғEғүғWғIғXғgғNҸ„—mҠН‘аӮМҺеӮИҗ퓬ҠН’ш Ғ@Ғ@Ғ@‘•ҚbҸ„—mҠН3җЗ(ғҚғVғAҒAғOғҚғӮғ{Ғ[ғCҒAғҠғ…Ғ[ғҠғN) Ғ@Ғ@Ғ@–hҢмҸ„—mҠН1җЗ(ғ{ғKғgғBҒ[ғҠ) Ғ@Ғ@Ғ@җ…—Ӣ’ш17җЗ җmҗмҚ`ӮЙҸҠҚЭӮөӮҪҗ퓬ҠН’ш Ғ@Ғ@Ғ@–hҢмҸ„—mҠН1җЗҒFғҸғҠғ„Ғ[ғO Ғ@Ғ@Ғ@–CҠН1җЗҒFғRғҢҒ[ғc “ъҳIҗн‘ҲӮМҗ퓬ӮНҒA1904”N2ҢҺ8“ъҒA—·ҸҮҚ`ӮЙӮўӮҪғҚғVғA—·ҸҮҠН‘аӮЙ‘ОӮ·Ӯй“ъ–{ҠCҢRӢм’ҖҠНӮМҠпҸPҚUҢӮ(—·ҸҮҢыҚUҢӮ)ӮЙҺnӮЬӮБӮҪҒBӮұӮМҚUҢӮӮЕӮНғҚғVғAӮМҠН’шҗ”җЗӮЙ‘№ҸқӮр—^ӮҰӮҪӮӘ‘еӮ«ӮИҗнүКӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB“Ҝ“ъҒA“ъ–{—ӨҢRҗжҢӯ•”‘аӮМ‘ж12Һt’c–Шүz—·’cӮӘ“ъ–{ҠCҢRӮМ‘ж2ҠН‘аүZҗ¶җн‘аӮМҢмүqӮрҺуӮҜӮИӮӘӮз’©‘NӮМҗmҗмӮЙҸг—ӨӮөӮҪҒBүZҗ¶җн‘аӮН—Ӯ2ҢҺ9“ъҒAҗmҗмҚ`ҠOӮЙӮД“Ҝ’nӮЙ”hҢӯӮіӮкӮДӮўӮҪғҚғVғAӮМҸ„—mҠНғ”ғ@ғҠғғҒ[ғOӮЖ–CҠНғRғҢҒ[ғGғcӮрҚUҢӮӮөҺ©’ҫӮЙ’ЗӮўҚһӮсӮҫ(җmҗмү«ҠCҗн)ҒB2ҢҺ10“ъӮЙӮН“ъ–{җӯ•{Ӯ©ӮзғҚғVғAҗӯ•{ӮЦӮМҗйҗн•zҚҗӮӘӮИӮіӮкӮҪҒB2ҢҺ23“ъӮЙӮН“ъ–{ӮЖ‘еҠШ’йҚ‘ӮМҠФӮЕ“ъ–{ҢRӮМ•вӢӢҗьӮМҠm•ЫӮр–Ъ“IӮЖӮөӮҪ“ъҠШӢc’иҸ‘ӮӘ’чҢӢӮіӮкӮйҒB ғҚғVғA—·ҸҮҠН‘аӮН‘қүҮӮр—ҠӮЭӮЖӮө“ъ–{ӮМҳAҚҮҠН‘аӮЖӮМҗі–КҢҲҗнӮр”рӮҜӮД—·ҸҮҚ`ӮЙ‘ТӢ@ӮөӮҪҒBҳAҚҮҠН‘аӮН2ҢҺӮ©Ӯз5ҢҺӮЙӮ©ӮҜӮДҒA—·ҸҮҚ`ӮМҸo“ьӮиҢыӮЙҢГӮў‘D”•Ӯр’ҫӮЯӮД••ҚҪӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒAҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪ(—·ҸҮҚ`•ВҚЗҚмҗн)ҒB4ҢҺ13“ъҒAҳAҚҮҠН‘аӮМ•~җЭӮөӮҪӢ@—ӢӮӘ—·ҸҮҠН‘аӮМҗнҠНғyғgғҚғpғuғҚғtғXғNӮрҢӮ’ҫҒA—·ҸҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮрҗнҺҖӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨҗнүКӮрҸгӮ°ӮҪӮӘ(Ңг”CӮНғ”ғBғҠғQғҠғҖҒEғ”ғBғgғQғtғgҸӯҸ«)ҒA5ҢҺ15“ъӮЙӮНӢtӮЙ“ъ–{ҠCҢRӮМҗнҠНҒu”Ә“ҮҒvӮЖҒuҸүҗЈҒvӮӘғҚғVғAӮМӢ@—ӢӮЙӮжӮБӮДҢӮ’ҫӮіӮкӮйҒBҲк•ыӮЕҒAғEғүғWғIғXғgғNӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮҪғҚғVғAӮМғEғүғWғIғXғgғNҸ„—mҠН‘аӮНҒAҗПӢЙ“IӮЙҸoҢӮӮөӮД’КҸӨ”jүуҗнӮр“WҠJӮ·ӮйҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{ҠCҢRӮН‘жҺOҠН‘аӮЙ‘гӮнӮиҸг‘ә•F”VҸе’ҶҸ«—ҰӮўӮй‘ж“сҠН‘аӮМ‘е•”•ӘӮрҲшӮ«”ІӮўӮДӮұӮкӮЙ“–ӮҪӮзӮ№ӮҪӮӘ•Я‘ЁӮЕӮ«ӮёҒAғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аӮН4ҢҺ25“ъӮЙ“ъ–{ҢRӮМ—A‘—ҠНӢаҸBҠЫӮрҢӮ’ҫӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМҺһ•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮМҸӯҚІӮНҒAҗнҢг–ЖҠҜӮЖӮИӮБӮҪҒB |
|
|
ҒЎү©ҠCҠCҗнҒE—Й—zүпҗн
Қ•–ШҲЧъй‘еҸ«—ҰӮўӮй“ъ–{—ӨҢRӮМ‘жҲкҢRӮН’©‘N”ј“ҮӮЙҸг—ӨӮөҒA4ҢҺ30“ъ-5ҢҺ1“ъҒAҲА“Ң(Ң»ҒE’O“Ң)ӢЯҚxӮМҠӣ—ОҚ]ҠЭӮЕғҚғVғAҢRӮр”jӮБӮҪ(Ҡӣ—ОҚ]үпҗн)ҒB‘ұӮўӮДүң•ЫиЭ‘еҸ«—ҰӮўӮй‘ж“сҢRӮӘ—Й“Ң”ј“ҮӮМү–‘еҡТӮЙҸг—ӨӮөҒA5ҢҺ26“ъҒA—·ҸҮ”ј“ҮӮМ•tӮҜҚӘӮЙӮ Ӯй“мҺRӮМғҚғVғAҢRҗw’nӮрҚU—ӘӮөӮҪ(“мҺRӮМҗнӮў)ҒB“мҺRӮН—·ҸҮ—vҚЗӮМӮжӮӨӮИ–{Ҡi“I—vҚЗӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҢҳҢЕӮИҗw’nӮЕҒA‘ж“сҢRӮНҺҖҸқҺТ4,000ӮМ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮҪҒB“ҢӢһӮМ‘е–{үcӮН‘№ҠQӮМ‘еӮ«ӮіӮЙӢБңұӮөҒAҢ…ӮрҲкӮВҠФҲбӮҰӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖӢ^ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB‘ж“сҢRӮН‘еҳAҗи—МҢгҒA‘ж1Һt’cӮрҺcӮөҒA—Й—zӮр–ЪҺwӮөӮД–kҸгӮөӮҪҒB6ҢҺ14“ъҒA—·ҸҮүҮҢмӮМӮҪӮЯ“мүәӮөӮДӮ«ӮҪғҚғVғAҢR•”‘аӮр“ҫ—ҳҺӣӮМҗнӮўӮЕҢӮ‘ЮҒA7ҢҺ23“ъӮЙӮН‘еҗОӢҙӮМҗнӮўӮЕҸҹ—ҳӮөӮҪҒB —·ҸҮҠН‘аҚUҢӮӮНӮӨӮЬӮӯӮўӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{ҠCҢRӮН—ӨҢRӮЙ—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘӮр—vҗҝҒAӮұӮкӮрҺуӮҜ”T–ШҠу“T‘еҸ«—ҰӮўӮй‘жҺOҢRӮӘ—·ҸҮҚU—ӘӮЙ“–ӮҪӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB8ҢҺ7“ъӮЙӮНҠCҢR—ӨҗнҸd–C‘аӮӘ—·ҸҮҚ`“аӮМҠН‘DӮЙҢьӮҜ–CҢӮӮрҠJҺnӮөҒA—·ҸҮҠН‘аӮЙ‘№ҸқӮр—^ӮҰӮҪҒBӮұӮкӮрҺуӮҜӮД—·ҸҮҠН‘аӮН8ҢҺ10“ъӮЙ—·ҸҮӮ©ӮзғEғүғWғIғXғgғNӮЙҢьӮҜӮДҸoҢӮҒA‘ТӮҝҚ\ӮҰӮДӮўӮҪҳAҚҮҠН‘аӮЖӮМҠФӮЕҠCҗнӮӘӢNӮұӮБӮҪҒBӮұӮМҠCҗнӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮӘҺёӮБӮҪҠН’шӮНӮнӮёӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҚЎҢгҸoҢӮӮЕӮ«ӮИӮўӮжӮӨӮИ‘еӮ«ӮИ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮД—·ҸҮӮЦҲшӮ«•ФӮөӮҪ(ү©ҠCҠCҗнҒEғRғӢғTғRғtҠCҗн)ҒBғҚғVғAӮМғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аӮНҒA6ҢҺ15“ъӮЙ—A‘—‘DҸн—ӨҠЫӮрҢӮ’ҫӮ·ӮйӮИӮЗ(Ҹн—ӨҠЫҺ–ҢҸ)ҠҲ”ӯӮИ’КҸӨ”jүуҗнӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪӮӘҒA8ҢҺ14“ъӮЙ“ъ–{ҠCҢR‘ж“сҠН‘аӮЙүUҺRү«ӮЕ•Я‘ЁӮіӮкӮҪҒB‘ж“сҠН‘аӮНғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аӮЙ‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰӮ»ӮМҢгӮМҠҲ“®Ӯр‘jҺ~ӮөӮҪ(үUҺRү«ҠCҗн)ҒB—·ҸҮҠН‘аӮНҸoҢӮӮрӮ Ӯ«ӮзӮЯҚмҗн”\—НӮрҺёӮБӮДӮўӮҪӮӘҒA“ъ–{‘ӨӮЕӮНӮ»ӮкӮӘҠm”FӮЕӮ«Ӯё‘жҺOҢRӮН—vҚЗӮЙ‘ОӮө‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮр8ҢҺ19“ъӮЙҠJҺnӮөӮҪҒBӮҫӮӘғҚғVғAӮМӢЯ‘г“I—vҚЗӮМ‘OӮЙҺҖҸқҺТ1–ң5,000ӮЖӮўӮӨ‘е‘№ҠQӮрҺуӮҜҺё”sӮЙҸIӮнӮйҒB 8ҢҺ––ҒA“ъ–{ӮМ‘жҲкҢRҒA‘ж“сҢRӮЁӮжӮС–м’Г“№ҠС‘еҸ«—ҰӮўӮй‘жҺlҢRӮНҒA–һҸFӮМҗн—ӘӢ’“_—Й—zӮЦ”—ӮБӮҪҒB8ҢҺ24“ъ-9ҢҺ4“ъӮМ—Й—zүпҗнӮЕӮНҒA‘ж“сҢRӮӘ“м‘ӨӮ©Ӯзҗі–КҚUҢӮӮрӮ©ӮҜҒA‘жҲкҢRӮӘ“Ң‘ӨӮМҺR’nӮрүIүсӮө”wҢгӮЦҗiҢӮӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮМҺi—ЯҠҜғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮН‘SҢRӮр“P‘ЮӮіӮ№ҒA“ъ–{ҢRӮН—Й—zӮрҗи—МӮөӮҪӮаӮМӮМғҚғVғAҢRӮМҢӮ”jӮЙӮНҺё”sӮөӮҪҒB10ҢҺ9“ъ-10ҢҺ20“ъӮЙғҚғVғAҢRӮНҚUҗЁӮЙҸoӮйӮӘҒA“ъ–{ҢRӮМ–hҢдӮМ‘OӮЙҺё”sӮ·Ӯй(Қ№үНүпҗн)ҒBӮұӮМӮМӮҝҒA—јҢRӮН—Й—zӮЖ•т“V(Ң»ҒEаc—z)ӮМ’ҶҠФ•tӢЯӮр—¬ӮкӮйҚ№үНӮМҗьӮЕ‘ОҗwӮЙ“ьӮБӮҪҒB 10ҢҺ15“ъӮЙӮНғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«—ҰӮўӮйғoғӢғ`ғbғNҠН‘а(җіҠmӮЙӮНғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮ©Ӯз’ҠҸoӮіӮкӮҪ‘ж“с‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а)ӮӘ—·ҸҮ(—·ҸҮҠЧ—ҺӮМҢгӮНғEғүғWғIғXғgғN)ӮЦҢьӮҜӮДғҠғGғpғ„Қ`ӮрҸo”ӯӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҚU—Ә
‘жҺOҢRӮН—·ҸҮӮЦӮМҚUҢӮӮр‘ұҚs’ҶӮЕӮ ӮБӮҪҒB10ҢҺ26“ъӮ©ӮзӮМ‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮӮаҗнүКӮН—LӮБӮҪӮаӮМӮМҺё”sӮЖ”»’fӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮз8ҢҺҒ`10ҢҺӮЬӮЕү©ҠCҠCҗнӮрӢІӮсӮЕ‘ұӮўӮҪҚ`“аӮЦӮМ–CҢӮӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮМүу–ЕӮЙӮНҗ¬ҢчӮөӮДӮўӮҪҒB11ҢҺ26“ъӮ©ӮзӮМ‘жҺOүс‘ҚҚUҢӮӮаӢкҗнӮЙҠЧӮйӮӘҢғҗнӮМӮ·ӮҰҒA12ҢҺ4“ъӮЙ—·ҸҮҚ`“аӮрҲк–]ӮЕӮ«Ӯй203ҚӮ’nӮМҗи—МӮр’Bҗ¬ӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгӮа‘жҺOҢRӮНҚU—ӘӮр‘ұҚsӮөҒA—Ӯ1905”N1ҢҺ1“ъӮЙӮНғҚғVғAҢR—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ӮрҚ~•ҡӮіӮ№ӮҪҒB—·ҸҮҠН‘аӮНҠН’шӮрӮ·Ӯ®ӮіӮЬҺg—pӮЕӮ«ӮИӮўӮжӮӨӮЙ‘SӮДҺ©’ҫӮіӮ№ӮҪҒB Қ№үНӮЕӮН—јҢRӮМ‘ОҗwӮӘ‘ұӮўӮДӮўӮҪӮӘҒAғҚғVғAҢRӮНҗVӮҪӮЙ‘OҗьӮЙ’…”CӮөӮҪғOғҠғbғyғ“ғxғӢғN‘еҸ«ӮМҺе“ұӮМӮаӮЖҒA1ҢҺ25“ъӮЙ“ъ–{ҢRӮМҚЕҚ¶—ғӮЙҲК’uӮ·ӮйҚ•Қa‘д•ы–КӮЕҚUҗЁӮЙҸoӮҪҒBҲкҺһҒA“ъ–{ҢRӮНҗнҗь•цүуӮМҠлӢ@ӮЙҠЧӮБӮҪӮӘҒAҸHҺRҚDҢГҸӯҸ«ҒA—§Ң©Ҹ®•¶’ҶҸ«ӮзӮМ•ұҗнӮЙӮжӮиҠлӢ@Ӯр’EӮөӮҪ(Қ•Қa‘дүпҗн)ҒB2ҢҺӮЙӮН‘жҺOҢRӮӘҗнҗьӮЙ“һ’…ӮөӮҪҒB |
|
|
ҒЎ•т“Vүпҗн
“ъ–{ҢRӮНҒAғҚғVғAҢRӮМӢ’“_ҒE•т“VӮЦҢьӮҜӮҪ‘еҚмҗнӮрҠJҺnӮ·Ӯй(•т“Vүпҗн)ҒB2ҢҺ21“ъӮЙ“ъ–{ҢRүE—ғӮӘҚUҢӮӮрҠJҺnҒB3ҢҺ1“ъӮ©ӮзҒAҚ¶—ғӮМ‘жҺOҢRӮЖ‘ж“сҢRӮӘ•т“VӮМ‘Ө–КӮ©Ӯз”wҢгӮЦҢьӮҜӮД‘OҗiӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮН—\”хӮр“Ҡ“ьӮөҒA‘жҺOҢRӮНғҚғVғAҢRӮМ–ТҚUӮМ‘OӮЙ•цүуҗЎ‘OӮЙӮИӮиӮВӮВӮа‘OҗiӮр‘ұӮҜӮҪҒB3ҢҺ9“ъҒAғҚғVғAҢRӮМҺi—ЯҠҜғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮН“P‘ЮӮрҺwҺҰҒB“ъ–{ҢRӮН3ҢҺ10“ъӮЙ•т“VӮрҗи—МӮөӮҪӮӘҒAӮЬӮҪӮағҚғVғAҢRӮМҢӮ”jӮЙӮНҺё”sӮөӮҪҒB ӮұӮМҢӢүКӮрҺуӮҜӮД“ъ–{‘ӨӮЙҲЛ—ҠӮрҺуӮҜӮҪғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘‘е“қ—МғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғgӮӘҳa•ҪҢрҸВӮрҠJҺnӮөӮҪӮӘҒAҠФӮаӮИӮӯ“ъ–{ӢЯҠCӮЙ“һ’…Ӯ·ӮйғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙҠъ‘ТӮөӮДӮўӮҪғҚғVғA‘ӨӮНӮұӮкӮрӢ‘”ЫӮөӮҪҒBҲк•ы—ј—ӨҢRӮНҲкҳAӮМҗнӮўӮЕӮЖӮаӮЙ‘еӮ«ӮИ‘№ҠQӮрҺуӮҜҚмҗнҢp‘ұӮӘҚў“пӮЖӮИӮБӮҪӮҪӮЯҒAӮ»ӮМҢгӮНҸIҗнӮЬӮЕҺl•ҪҠX•tӢЯӮЕӮМ‘ОӣіӮӘ‘ұӮўӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠCҠCҗн
ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮН7ғ–ҢҺӮЙӢyӮсӮҫҚqҠCӮМ––“ъ–{ӢЯҠCӮЙ“һ’BҒA5ҢҺ27“ъӮЙҳAҚҮҠН‘аӮЖҢғ“ЛӮөӮҪ(“ъ–{ҠCҠCҗн)ҒB5ҢҺ29“ъӮЙӮЬӮЕӮнӮҪӮйӮұӮМҠCҗнӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНӮ»ӮМҠН’шӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮрҺёӮўҺi—Я’·ҠҜӮӘ•Я—ёӮЙӮИӮйӮИӮЗүу–Е“IӮИ‘ЕҢӮӮрҺуӮҜҒAҳAҚҮҠН‘аӮН‘rҺёҠНӮӘҗ…—Ӣ’ш3җЗӮЖӮўӮӨҳAҚҮҠН‘аӮМҲк•ы“IӮИҲіҸҹӮЙҸIӮнӮБӮҪҒBҗўҠEӮМғ}ғXғRғ~ӮМ—\‘zӮЙ”ҪӮ·ӮйҢӢүКӮН—сӢӯҸ”Қ‘ӮрӢБңұӮіӮ№ҒAғҚғVғAӮМӢәҲРӮЙӢҜӮҰӮйҚ‘ҒXӮр”MӢ¶ӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮМҢӢүКҒA“ъ–{‘ӨӮМҗ§ҠCҢ ӮӘҠm’иӮөҒAғҚғVғA‘ӨӮаҳa•ҪӮЙҢьӮҜӮД“®Ӯ«ҸoӮөӮҪҒB |
|
|
ҒЎҠ’‘ҫҚU—Ә
“ъ–{ҢRӮНҳa•ҪҢрҸВӮМҗiӮЮӮИӮ©7ҢҺӮЙҠ’‘ҫҚU—ӘҚмҗнӮрҺАҺ{ӮөҒA‘S“ҮӮрҗи—МӮөӮҪҒBӮұӮМҗи—МӮӘҢгӮМҚuҳaҸр–сӮЕ“мҠ’‘ҫӮМ“ъ–{ӮЦӮМҠ„ҸчӮрӮаӮҪӮзӮ·ӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҚuҳaӮЦ
ғҚғVғAӮЕӮНҒA‘ҠҺҹӮ®”s–kӮЖҒAӮ»ӮкӮрҠЬӮЯӮҪ’йҗӯӮЙ‘ОӮ·Ӯй–ҜҸOӮМ•s–һӮӘ‘қ‘еӮөҒA1905”N1ҢҺ9“ъӮЙӮНҢҢӮМ“ъ—j“ъҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮДӮўӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМ–ҫҗОҢі“сҳY‘еҚІӮЙӮжӮйҠv–Ҫү^“®ӮЦӮМҺxүҮҚHҚмӮӘӮұӮкӮЙ”ҸҺФӮрӮ©ӮҜҒAҗн‘ҲҢp‘ұӮӘҚў“пӮИҸоҗЁӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒB“ъ–{ӮаҒA“–ҺһӮМ–RӮөӮўҚ‘—НӮрҗн‘ҲӮЕҺgӮўүКӮҪӮөӮДӮўӮҪҒB—јҚ‘ӮН8ҢҺ10“ъӮ©ӮзғAғҒғҠғJҒEғ|Ғ[ғcғ}ғXӢЯҚxӮЕҸIҗнҢрҸВӮЙ—ХӮЭҒA1905”N9ҢҺ5“ъӮЙ’чҢӢӮіӮкӮҪғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӮЙӮжӮиҚuҳaӮөӮҪҒB “ъ–{ӮН19Ӯ©ҢҺӮМҗн‘ҲҠъҠФ’ҶӮЙҗн”п17үӯү~Ӯр“Ҡ“ьӮөӮҪҒBҗн”пӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮНҗнҺһҚ‘ҚВӮЙӮжӮБӮД’І’BӮіӮкӮҪҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ҢRӮМҸн”х•ә—Н20–ңҗlӮЙ‘ОӮөӮДҒA‘Қ“®Ҳх•ә—НӮН109–ңҗlӮЙ’BӮөӮҪҒBӮИӮЁҒAӢrӢCҺSҠQӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҒu—ӨҢRӮЕӮМӢrӢCҺSҠQҒvҒAҒuҠCҢRӮМҸуӢөҒvӮрҺQҸЖӮМӮұӮЖҒB |
|
| ҒЎүeӢҝ | |
|
ҒЎ“ъ–{
ғҚғVғA’йҚ‘ӮМ“мүәӮр—}ӮҰӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҒAүБӮҰӮДҗнҢгӮЙ“ъҳIӢҰ–сӮӘҗ¬—§ӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒA‘ҠҢЭӮМҗЁ—НҢ—ӮрҠm’иӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ӮНғҚғVғAӮМӢәҲРӮ©Ӯз“ҰӮкҲА‘S•ЫҸбӮр’Bҗ¬ӮөӮҪҒBӮіӮзӮЙ’©‘N”ј“ҮӮМҢ үvӮрҠm•ЫӮЕӮ«ӮҪҸгҒAҗVӮҪӮЙ“Ңҗҙ“S“№ӮМҲк•”ӮЕӮ Ӯй“м–һҸF“S“№ӮМҠl“ҫӮИӮЗ–һҸFӮЙӮЁӮҜӮйҢ үvӮр“ҫӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪғҚғVғAӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪӮұӮЖӮНҒA—сӢӯҸ”Қ‘ӮМ“ъ–{ӮЙ‘ОӮ·Ӯй•]үҝӮрҚӮӮЯҒA–ҫҺЎҲЫҗVҲИ—ҲӮМүЫ‘иӮЕӮ ӮБӮҪ•s•Ҫ“ҷҸр–сүьҗіӮМ’Bҗ¬ӮЙ‘еӮ«ӮӯҠс—^ӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA“ъ–{ӮНҚЕ‘еӮМ–Ъ•WӮН’Bҗ¬ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҚuҳaҸр–сӮМ“а—eӮНҒA”…ҸһӢаӮрҺжӮкӮИӮўӮИӮЗҚ‘–ҜӮЙӮЖӮБӮД—\‘zҠOӮЙҢөӮөӮў“а—eӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҒA“ъ”д’JҸД‘ЕҺ–ҢҸӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮөӮДҠe’nӮЕ–\“®ӮӘӢNӮұӮБӮҪҒBҢӢүКүъҢө—ЯӮӘ•~Ӯ©ӮкӮйӮЙӮЬӮЕӮЙҺҠӮиҒAҗн‘ҲӮрҺw“ұӮөӮДӮ«ӮҪҢj“аҠtӮН‘ЮҗwӮөӮҪҒBӮұӮкӮНғҚғVғA‘ӨӮЦӮўӮ©ӮИӮйҺгӮЭӮЖӮИӮйӮұӮЖӮр”й–§ӮЙӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮМҗӯҚфӮЙүБӮҰҒAҗV•·ҲИүәғ}ғXғRғ~ҠeҺРӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲӮрҲшӮ«ҚҮӮўӮЙҸoӮөӮДҗн‘ҲӮЙ‘ОӮ·ӮйҚ‘–ҜҠъ‘ТӮрҗшӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҸCҗіӮӘ—ҳӮ©ӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҚ‘–ҜӮМ‘ҪӮӯӮНҗн‘ҲӮрӮөӮДӮўӮйҚ‘—НӮМҺАҸоӮр’mӮзӮіӮкӮёҒA–ЪҗжӮМҸҹ—ҳӮЙӮжӮБӮДғҚғVғAӮӘҠИ’PӮЙӢь•һӮіӮ№ӮзӮкӮҪӮжӮӨӮЙҚцҠoӮөӮҪ”Ҫ“®Ӯ©Ӯз—ҲӮДӮўӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮД“ъ–{ҢRӮЁӮжӮСҗӯ•{ӮНҒA—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜӮМғXғeғbғZғӢӮӘҚ~•ҡӮөӮҪҚЫӮЙ‘СҢ•ӮрӢ–Ӯ·ӮИӮЗҒA•җҺm“№җёҗ_ӮЙ‘ҘӮи”sҺТӮр”сҸнӮЙҗaҺm“IӮЙҲөӮБӮҪӮЩӮ©ҒAҗн‘Ҳ•Я—ёӮр”сҸнӮЙҗl“№“IӮЙҲөӮў“ъ–{җФҸ\ҺҡҺРӮағҚғVғA•әҗнҸқҺТӮМӢ~ҚПӮЙҗs—НӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮНҚ‘“аҠe’nӮЙ•Я—ёҺы—eҸҠӮрҗЭ’uӮөӮҪӮӘҒAҲӨ•QҢ§ӮМҸјҺRӮЙӮ ӮБӮҪҺ{җЭӮӘ’ҳ–јӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒAғҚғVғA•ә‘ӨӮЕӮНҚ~•ҡӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒuғ}ғcғ„ғ}ҒAғ}ғcғ„ғ}ҒvӮЖҠЁҲбӮўӮөӮҪӮЖӮўӮӨғGғsғ\Ғ[ғhӮаӮ ӮйҒBҸIҗнҢгҒA“ъ–{Қ‘“аӮМғҚғVғA•ә•Я—ёӮНғҚғVғA–{Қ‘ӮЦ‘—ҠТӮіӮкӮҪӮӘҒAҢF–{Ң§ӮМҢ§•ЁҺYҠЩҺ––ұҸҠӮЙҺы—eӮіӮкӮДӮўӮҪғҚғVғAҢRҺmҠҜӮНӢAҚ‘ҢҲ’иӮМ“ъӮЙ‘SҲхҺ©ҺEӮөӮДӮўӮйҒB ӮЬӮҪҒAҢіҳVӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҺQ–d‘Қ’·ӮЖӮөӮДҗн‘ҲӮрҺwҠцӮөӮҪҺRгp—L•ьӮМ”ӯҢҫ—НӮӘҚӮӮЬӮиҒA—ӨҢRӮНҒu‘е—Ө’йҚ‘Ғvҳ_ӮЖғҚғVғAӮЙӮжӮйҒu•ңҸQҗнҒvӮМүВ”\җ«ӮрҸҘӮҰӮДҒA1907”NӮЙӮНҺRгpӮМҺе“ұӮЙӮжӮБӮД•ҪҺһ25Һt’c‘Мҗ§ӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮЖӮөӮҪҒu’йҚ‘Қ‘–h•ыҗjҒvҲДӮӘ“ZӮЯӮзӮкӮйҒBӮҫӮӘҒAҗнҢгӮМҚаҗӯ“пӮ©ӮзҺt’c‘қҗЭӮНҸҮ’ІӮЙӮНӮўӮ©ӮёҒA18Һt’cӮр20Һt’cӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮМҗҘ”сӮрҸ„ӮБӮД—L–јӮИ2ҢВҺt’c‘қҗЭ–в‘иӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮД—·ҸҮ—vҚЗӮЕӮМҗ퓬ӮЙӢкӮөӮЯӮзӮкӮҪ—ӨҢRӮНҒAҗнҢгҒAғҚғ}ғ“ҒEғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRӮЙӮжӮБӮД’zӮ©ӮкӮДӮўӮҪ—·ҸҮ—vҚЗӮМҡЖ—ЫӮр–Н•нӮөҒAүiӢv–h—ЫӮЖҢДӮОӮкӮҪүүҸK—pҚ\‘ў•ЁӮр—ӨҢRҸKҺu–мҳB•әҸк“аӮЙҚ\’zҒAүүҸKӮИӮЗӮрҚsӮў—vҚЗҗнӮМҗнҸpӮЙӮВӮўӮДҢӨӢҶӮөӮҪӮЖӮўӮӨғGғsғ\Ғ[ғhӮӘҺcӮіӮкӮДӮЁӮиҒA“–ҺһӮМ—ӨҢRӮЙ—^ӮҰӮҪүeӢҝӮМ‘еӮ«ӮіӮр•ЁҢкӮБӮДӮўӮйҒB ӮИӮЁҒA”…ҸһӢаӮӘҺжӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒA‘е“ъ–{’йҚ‘ӮНғWғFғCғRғuҒEғVғtӮМғNҒ[ғ“ҒEғҚҒ[ғuӮЙ‘ОӮөӮДӢа—ҳӮр•ҘӮў‘ұӮҜӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҒu“ъҳIҗн‘ҲӮЕҚЕӮа–ЧӮҜӮҪҒvғVғtӮНҒAғҚғVғA’йҚ‘ӮМғ|ғOғҚғҖ(”ҪғҶғ_ғ„ҺеӢ`)ӮЦӮМ•с•ңӮӘ—ZҺ‘ӮМ“®Ӣ@ӮЖӮўӮнӮкҒAӮМӮҝӮЙғҢҒ[ғjғ“ӮвғgғҚғcғLҒ[ӮЙӮаҺ‘ӢаүҮҸ•ӮрӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎғҚғVғA
•s“ҖҚ`ӮрӢҒӮЯҒA“`“қ“IӮИ“мүәҗӯҚфӮӘӮұӮМҗн‘ҲӮМ“®Ӣ@ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮБӮҪғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒAӮұӮМ”s–kӮрҠъӮЙӢЙ“ҢӮЦӮМ“мүәҗӯҚфӮрӮаӮЖӮЙӮөӮҪҗN—ӘӮр’f”OӮөӮҪҒB“мүәӮМ–өҗжӮНҚДӮСғoғӢғJғ“ӮЙҢьӮ©ӮўҒAғҚғVғAӮН”ДғXғүғ”ҺеӢ`Ӯр‘S–КӮЙҸҘӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӮұӮМӮұӮЖӮӘ”ДғQғӢғ}ғ“ҺеӢ`ӮрҸҘӮҰӮйғhғCғcӮвҒA“ҜӮ¶ӮӯғoғӢғJғ“ӮЦӮМҗN—ӘӮрҠйӮЮғIҒ[ғXғgғҠғAӮЖӮМ‘О—§ӮрҸөӮ«ҒA‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМҲшӮ«ӢаӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮЬӮҪҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМ”sҗнӮЙӮжӮй–ҜҸOӮМҗ¶ҠҲӢкӮ©ӮзҒAҢҢӮМ“ъ—j“ъҺ–ҢҸӮвҗнҠНғ|ғ`ғҮғҖғLғ“ӮМ”ҫ—җ“ҷӮжӮиҺnӮЬӮйғҚғVғA‘жҲкҠv–ҪӮӘ—U”ӯӮіӮкҒAғҚғVғAҠv–ҪӮМҢҙҲцӮЖӮИӮйҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҗјүў
ғCғMғҠғXӮН“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮЙӮжӮи“ъ–{ӮЦӮМ•]үҝӮрүьӮЯӮДӮЁӮи1905”N8ҢҺ12“ъӮЙ“ъүp“Ҝ–ҝӮрҚUҺз“Ҝ–ҝӮЙӢӯү»Ӯ·Ӯй(‘ж“сүс“ъүp“Ҝ–ҝӢҰ–с)ҒB “ъҳIҗн‘ҲӮрӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЙ“ъҳIҠЦҢWҒAүpҳIҠЦҢWӮӘӢ}‘¬ӮЙүь‘PӮөҒAӮ»ӮкӮјӮк“ъҳIӢҰ–сҒAүpҳIӢҰҸӨӮр’чҢӢӮөӮҪҒBҠщӮЙ’чҢӢӮіӮкӮДӮўӮҪүp•§ӢҰҸӨӮЖ•№Ӯ№ӮДҒAүўҸBҸоҗЁӮН“ъҳIҗн‘ҲҲИ‘OӮМүpҒEҳI•§ҒE“ЖҡТҲЙӮМҺOҗЁ—НӮӘ“C—§ӮөӮДӮўӮҪҸуӢөӮ©ӮзҒAүp•§ҳIӮМҺOҚ‘ӢҰҸӨӮЖ“ЖҡТҲЙӮМҺOҚ‘“Ҝ–ҝӮМ‘О—§ӮЦӮЖҢьӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДғCғMғҠғXӮНүј‘z“GҚ‘ӮрғҚғVғAӮ©ӮзғhғCғcӮЙҗШӮи‘ЦӮҰҒAғhғCғcӮНғCғMғҠғXӮЖӮМҢҡҠНӢЈ‘ҲӮрҠg‘еӮөӮДӮдӮӯҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎғAғҒғҠғJ
ғAғҒғҠғJӮНғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӮМ’ҮүоӮЙӮжӮБӮДӢҷ•vӮМ—ҳӮр“ҫҒA–һҸFӮЙҺ©ӮзӮаҗiҸoӮ·ӮйӮұӮЖӮрҠйӮсӮЕӮЁӮиҒA“ъҳIҚuҳaҢгӮН–һҸBӮЕғҚғVғAӮ©ӮзҸч“nӮіӮкӮҪ“Ңҗҙ“S“№ҺxҗьӮр“ъ•ДҚҮ•ЩӮЕҢoүcӮ·Ӯй—\”хӢҰ’иӮрҢj“аҠtӮЖҗ¬—§ӮіӮ№ӮДӮўӮҪ(ҢjҒEғnғҠғ}ғ“ӢҰ’иҒA1905”N10ҢҺ12“ъ)ҒBӮұӮкӮНғAғҒғҠғJӮМ“S“№үӨғnғҠғ}ғ“ӮрҺQүжӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕҒAғnғҠғ}ғ“ӮМҺ‘Ӣа–КӮЕӮМӢҰ—НҺТӮӘғNҒ[ғ“ҒEғҚҒ[ғuӮ·ӮИӮнӮҝғWғFғCғRғuҒEғVғtӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМӢҰ’иӮНҸ¬‘әҠO‘ҠӮМ”Ҫ‘ОӮЙӮжӮиӮ·Ӯ®ӮіӮЬ”jҠьӮіӮкӮҪҒB“ъ–{ӮЦҠOҚВӮвҚuҳaӮЕӢҰ—НӮөӮҪғAғҒғҠғJӮНӮ»ӮМҢгӮаҒuӢ@үпӢП“ҷҒvӮрҢfӮ°ӮД’ҶҚ‘җiҸoӮрҲУҗ}ӮөӮҪӮӘҒAҺvҳfӮЖӮНӢtӮЙ“ъүpҳIҺOҚ‘ӮЙӮжӮи’ҶҚ‘Ң үvӮ©Ӯз’чӮЯҸoӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨҢӢүКӮЖӮИӮБӮҪҒB ‘е“қ—МғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғgӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–с’чҢӢӮЙҺҠӮй“ъҳIӮМҳa•ҪҢрҸВӮЦӮМҚvҢЈӮӘ•]үҝӮіӮк1906”NӮМғmҒ[ғxғӢ•ҪҳaҸЬӮрҺуҸЬӮөӮҪӮӘҒA”ЮӮМ‘О“ъҠҙҸоӮНғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaӮЦӮМӢҰ—НҲИҚ~ҒAӢ}‘¬ӮЙҲ«ү»ӮөӮДӮдӮӯҒB “ъ”д’JҸД‘ЕҺ–ҢҸӮМҚЫҒA“ъ–{ӮМҢQҸOӮМ“{ӮиӮӘҚuҳaӮрҲҙҗщӮөӮҪғAғҒғҠғJӮЙӮаҢьӮҜӮзӮкӮД“ҢӢһӮМ•ДҚ‘ҢцҺgҠЩӮИӮЗӮӘҸPҢӮӮМ‘ОҸЫӮЖӮИӮБӮҪӮұӮЖӮЕҒAғAғҒғҠғJӮМҗўҳ_ӮН•®ҠSӮөү©җFҗlҺнӮЦӮМҗlҺнҚ·•КҠҙҸоӮрӮаӮЖӮЙӮөӮҪү©үРҳ_ӮМҚӮӮЬӮиӮЖӢӨӮЙҒA‘О“ъҠҙҸоӮӘҲ«ү»ӮөӮДғAғҒғҠғJҚ‘“аӮЕ“ъ–{җl”rҗЛү^“®ӮӘ•ҰӮ«ӢNӮұӮйҲкҲцӮЖӮИӮйҒB ӮұӮкӮз“ъ•ДҠЦҢWӮМӢ}‘¬ӮИҲ«ү»ӮЙӮжӮиҒA‘ж“сүс“ъүp“Ҝ–ҝӢҰ–сӮЕ“ъ–{ӮЖӮМ“Ҝ–ҝӮрҚUҺз“Ҝ–ҝӮМҗ«ҠiӮЙӢӯү»ӮөӮҪӮОӮ©ӮиӮМғCғMғҠғXӮНҒA“ъ•Дҗн‘ҲӮЙҠӘӮ«ҚһӮЬӮкӮйӮұӮЖӮрҲШӮкҺnӮЯӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҗҙ’©
“ъҳIҗн‘ҲӮМҗнҸкӮЕӮ ӮБӮҪ–һҸFӮНҗҙ’©ӮМҺеҢ үәӮЙӮ ӮБӮҪҒB–һҸF‘°ӮЙӮжӮйүӨ’©ӮЕӮ ӮйҗҙӮНҢҡҚ‘ҲИ—ҲҒA•ғ‘cӮМ’nӮЕӮ Ӯй–һҸFӮЙӮНҠҝ–Ҝ‘°Ӯр“ьӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨ••ӢЦҗӯҚфӮрҺжӮиҒA’ҶҚ‘“а’nӮМӮжӮӨӮИ–ЪӮМҚЧӮ©ӮўҚsҗӯҗ§“xӮаҚМ—pӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠJ”ӯӮаҚЕ“м•”ӮМ—Й“ҢҒE—ЙҗјӮрҸңӮ«җiӮсӮЕӮЁӮзӮёҒAӮұӮӨӮөӮҪӮұӮЖӮаҢҙҲцӮЖӮИӮБӮД19җўӢI––ӮМғҚғVғAӮМҗiҸoӮЙ‘ОӮөӮД‘ОүһӮӘ’xӮкҒA“Ңҗҙ“S“№ӮвғnғӢғsғ“ӮрҺnӮЯӮЖӮ·ӮйҗA–Ҝ“sҺsӮМҢҡҗЭӮЬӮЕӢ–Ӯ·ӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙӢ`ҳa’cӮМ—җӮМҚ¬—җӮМ’ҶӮЕ–һҸFӮНҠ®‘SӮЙғҚғVғAӮЙҗ§ҲіӮіӮкӮҪҒB1901”NӮМ–kӢһӢc’иҸ‘’чҢӢҢгӮағҚғVғAӮМ–һҸFҗиӢ’ӮӘ‘ұӮўӮҪӮҪӮЯӮЙҒA’Ј”V“ҙӮвеНҗўҠMӮН“ҢҺOҸИӮМҚsҗӯ‘Мҗ§Ӯр“а’nӮЖ“ҜҲкӮЖӮ·ӮйӮИӮЗӮМ“қҺЎӢӯү»ӮрҺе’ЈӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯөҗҙ’©ӮМ‘ОүһӮН’xӮкҒAӮ»ӮӨӮөӮДӮўӮйӮӨӮҝӮЙ“ъҳI—јҚ‘ӮӘҠJҗнӮөҒAҺ©Қ‘ӮМ—М“yӮЕ‘јҚ‘“ҜҺmӮӘҗнӮӨӮЖӮўӮӨҺ–‘ФӮЖӮИӮБӮҪҒB ҸIҗнҢгӮНҒA“ъ–{ӮН“–ҸүҸҘӮҰӮДӮўӮҪ–һҸFӮЙү—ӮҜӮй—сҚ‘ӮМӢ@үпӢП“ҷӮМҢҙ‘ҘӮр–|ӮөҒA“ъҳIӮӘӢӨ“ҜӮөӮД—ҳҢ Ӯр•ӘӮҜҚҮӮӨӮұӮЖӮрүжҚфӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪҸуӢөӮЙҠлӢ@ҠҙӮрӮВӮМӮзӮ№ӮҪҗҙ’©ӮН’ј—кҒEҺR“ҢӮ©ӮзӮМҠҝ–Ҝ‘°ӮМҲЪ–ҜӮрҸ§—гӮөӮДҗlҢы–§“xӮМҢьҸгӮЙ“wӮЯҒAҸIҗнӮМ—ӮҒX”NӮМ1907”NӮЙӮН“а’nӮЖ“ҜӮ¶ҒuҸИҒE•{ҒEҢ§ҒvӮЙӮжӮйҚsҗӯҗ§“xӮрҠm—§ӮөӮҪҒBӮ Ӯйҗ„ҢvӮЙӮжӮйӮЖҒA1880”NӮ©Ӯз1910”NӮЙӮ©ӮҜӮДҒA“ҢҺOҸИӮМҗlҢыӮН743–ң4җзҗlӮ©Ӯз1783–ң6җзҗlӮЬӮЕ‘қүБӮөӮДӮўӮйҒBӮіӮзӮЙ“Ҝ”NӮЙӮНеНҗўҠMӮМ–k—mҢRӮМҲк•”ӮӘ–һҸFӮЙ’“—ҜӮөҒAҢxҺ@—НҒE–hүq—НӮр‘қӢӯӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA“ъҳIӮМҚs“®ӮЦӮМҺ•Һ~ӮЯӮрӮ©ӮҜӮҪҒBӮЬӮҪҒA“ъҳIӮМҺқӮВ—ҳҢ ӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒAғAғҒғҠғJҺ‘–{Ӯр“ұ“ьӮөӮД‘ҠҢЭӮМҗЁ—НӮрҢЎҗ§ӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕ‘ОҚRӮрҗ}ӮБӮҪӮӘҒAеНҗўҠMӮМҺёӢrӮв“ъ–{‘ӨӮМҚHҚмӮаӮ ӮиҒAӮӨӮЬӮӯӮўӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA1917”NӮМғҚғVғA’йҚ‘•цүуҢгӮН“ъ–{ӮӘҲкҺиӮЙ—ҳҢ ӮМ•}җAӮЙ‘–ӮиҒA1932”NӮЙӮН–һҸBҚ‘ӮрҢҡҚ‘ӮөӮҪҒB‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗнӮЕ“ъ–{ӮӘ”sӮкӮД–һҸBҚ‘ӮӘ–Е–SӮ·ӮйӮЖҒA‘гӮнӮБӮДҗNҚUӮөӮДӮ«ӮҪғ\ҳAӮӘҗi’“ӮЙҸжӮ¶ӮД“ъ–{ӮМҺcӮөӮҪғCғ“ғtғүӮрҺқӮҝӢҺӮиҒA—·ҸҮҒE‘еҳAӮМ‘dҺШҢ ӮрҺе’ЈӮөӮҪҒB’ҶүШҗl–ҜӢӨҳaҚ‘ӮӘ–һҸFӮрҠ®‘SӮЙҸ¶Ҳ¬ӮөӮҪӮМӮН1955”NӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮиҒA“ъҳIҗн‘ҲӮ©Ӯз50”NҢгӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ң»‘г’ҶҚ‘ӮМҚӮҚZ—рҺjӢіүИҸ‘ӮЕӮН“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮВӮўӮДҒAғҚғVғAӮ ӮйӮўӮН“ъ–{ӮМӢЯ‘гү»үЯ’цӮМҲк•”ӮЖӮөӮДҗGӮкӮзӮкӮДӮўӮйӮаӮМӮМҒAҸЪӮөӮӯҢҫӢyӮНӮөӮИӮў(җҙ’©ӮМ—М“yӮЕӢNӮ«ӮҪ“_Ӯр’ҶҗSӮЙӢLҸqӮ·ӮйӮМӮӘ‘ҪӮў)ҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ‘еҠШ’йҚ‘
ҠJҗн‘OӮМ‘еҠШ’йҚ‘ӮЕӮНҒA“ъ–{”hӮЖғҚғVғA”hӮЕӮМҗӯ‘ҲӮӘҢp‘ұӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮМҗнӢө—DҗЁӮрҢ©ӮДҒA“ҢҠw“}ӮМҢn—сӮ©ӮзҲкҗiүпӮӘ1904”NӮЙҗЭ—§ӮіӮкҒA‘еҸO‘wӮЕӮМҗe“ъ“I“Ж—§ү^“®Ӯ©ӮзҒA“ъ–{ӮМҺxүҮӮрҺуӮҜӮҪҚҮ–Mү^“®ӮЦ”ӯ“WӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮө“–ҸүӮМҲкҗiүпӮМ“}җҘӮНҠШҚ‘ӮМҺ©Һе“Ж—§ӮЕӮ ӮБӮҪҒB җн‘ҲҢгҒA’©‘N”ј“ҮӮЕӮН“ъ–{ӮМүeӢҝӮӘҗв‘еӮЖӮИӮиҒAӮМӮҝӮЙ‘еҠШ’йҚ‘ӮН—lҒXӮИҢ —ҳӮр“ъ–{ӮЙҲПҸчӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮиҒAӮіӮзӮЙӮН“ъ–{ӮМ•ЫҢмҚ‘ӮЖӮИӮйҒB1910”N(–ҫҺЎ43”N)ӮМ“ъҠШ•№ҚҮҸр–сӮМ’чҢӢӮЙӮжӮиҒA‘еҠШ’йҚ‘ӮН“ъ–{ӮЙ•№ҚҮӮіӮкҒA–Е–SӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘
ғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘ӮН“ъ–{ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗн•zҚҗӮөӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮНҗ퓬ӮЙҺQүБӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚuҳaүпӢcӮЙӮНҸөӮ©ӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҚ‘ҚЫ–@ҸгӮНҒAғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘ӮЖ“ъ–{ӮНҗн‘ҲӮрҢp‘ұӮөӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҠп–ӯӮИҸу‘ФӮЙӮИӮБӮҪҒBӮИӮЁӮұӮМҗн‘ҲҸу‘ФӮН‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙӮЁӮўӮДҒA1945”NӮЙ“ъ–{ӮӘҳAҚҮҚ‘ӮЙҚ~•ҡӮөҒAӮ»ӮМ’ҶӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘ӮМҢгҢpҚ‘үЖӮЕӮ ӮйғҶҒ[ғSғXғүғrғAҺРүпҺеӢ`ҳA–MӢӨҳaҚ‘ӮӘҠЬӮЬӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ӮзүрҸБӮөӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪ2007”N7ҢҺӮЙғZғӢғrғAҒEғӮғ“ғeғlғOғҚӮ©ӮзҗVҚ‘үЖғӮғ“ғeғlғOғҚӮЖӮөӮД•Ә—Ј“Ж—§ӮөӮҪҚЫӮМҚ‘ҢрҺч—§ӮЙӮжӮиүьӮЯӮДҠm”FӮіӮкӮДӮўӮйҒB ӮИӮЁҒAӮұӮМӮжӮӨӮИӮұӮЖӮНғ”ғFғӢғTғCғҶҸр–сӮЙҸөӮ©ӮкӮИӮ©ӮБӮҪғAғ“ғhғүҢцҚ‘ӮЙӢNӮ«ӮДӮўӮйҒBҚ‘ҚЫ–@ҸгӮНҒAғAғ“ғhғүҢцҚ‘ӮН‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮр—BҲкҢp‘ұӮөӮДӮўӮйҸу‘ФӮЙӮИӮБӮҪҒB ҸгӢLӮЙӮВӮўӮДҒA2006”N(•Ҫҗ¬18”N)2ҢҺ14“ъӮЙ—й–ШҸ@’jӢcҲхӮӘҒAҒuҲкӢгҒZҺl”NӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮӘ“ъ–{ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮНӮ ӮйӮ©ҒBғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮМ‘г•\ӮНҸөӮ©ӮкӮҪӮ©ҒB“ъ–{ӮЖғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮМҗн‘ҲҸу‘ФӮНӮЗӮМӮжӮӨӮИҺи‘ұӮ«ӮрӮЖӮБӮДҸI—№ӮөӮҪӮ©ҒBҒvӮЖӮМ“а—eӮМҺҝ–вҺеҲУҸ‘Ӯр’сҸoҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{җӯ•{ӮНҒAҒuҗӯ•{ӮЖӮөӮДӮНҒAҗзӢг•SҺl”NӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚҚ‘ӮӘүдӮӘҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮҪӮұӮЖӮрҺҰӮ·ҚӘӢ’ӮӘӮ ӮйӮЖӮНҸі’mӮөӮДӮўӮИӮўҒBғӮғ“ғeғlғOғҚҚ‘ӮМ‘SҢ ҲПҲхӮНҒAҢдҺw“EӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЙӮЁӮўӮДҚsӮнӮкӮҪҚuҳaүпӢcӮЙҺQүБӮөӮДӮўӮИӮўҒBҒvӮЖӮМ“ҡ•ЩҸ‘ӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒBғӮғ“ғeғlғOғҚӮМ—рҺj#ҳA–MҚД•ТӮ©ӮзҚД“Ж—§ӮЦӮаҺQҸЖӮіӮкӮҪӮўҒB ӮИӮЁҒA“ъүp“Ҝ–ҝӮМӢK’иӮЙӮжӮиҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮӘ“сғ–Қ‘ҲИҸгӮЖҗн‘ҲҸу‘ФӮЙӮИӮБӮҪҸкҚҮҒAғCғMғҠғXӮЙӮаҺQҗнӢ`–ұӮӘҗ¶Ӯ¶ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйҒBүјӮЙ“ъ–{ӮӘғӮғ“ғeғlғOғҚӮМҗйҗн•zҚҗӮр–іҺӢӮөӮИӮ©ӮБӮҪҸкҚҮҒAӮ©ӮИӮи–пүоӮИ–в‘иӮрҲшӮ«ӢNӮұӮ·ӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚӮНҒA‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнҺһӮЙӮЁӮўӮДҒAғWғ…ғlҒ[ғ”Ҹр–сҒEғnҒ[ғO—ӨҗнҸр–сӮЙүБ–ҝӮөӮИӮўӮЬӮЬӮЙҺQҗнӮөӮҪӮҪӮЯҒAӢK’иӮЙӮжӮБӮД‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМҺQҗнҚ‘‘SӮДӮЙ—јҸр–сӮӘ“K—pӮіӮкӮИӮўӮЖӮўӮӨ‘е–в‘иӮрҲшӮ«ӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎӮ»ӮМ‘јҠeҚ‘
“–ҺһҒAүў•Д—сӢӯӮМҺx”zүәӮЙӮ ӮиҒAҢгӮЙ“Ж—§ӮөӮҪҚ‘ҒXӮМҺw“ұҺТ’BӮМүсҢЪҳ^ӮЙҒu—LҗFҗlҺнӮМҸ¬Қ‘ӮӘ”’җlӮМ‘еҚ‘ӮЙҸҹӮБӮҪӮЖӮўӮӨ‘O—бӮМӮИӮўҺ–ҺАӮӘҒAғAғWғAӮвғAғtғҠғJӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪ’nҲжӮМ“Ж—§ӮМӢCҠTӮЙ’eӮЭӮрӮВӮҜӮҪӮиҗlҺнҚ·•КүәӮЙӮ ӮБӮҪҗlҒXӮр—EӢC•tӮҜӮҪҒvӮЖӢLӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҗA–Ҝ’nҺһ‘гӮЙӮЁӮҜӮйҠҙҠSӮМӢLҳ^ӮӘҗ”‘ҪӮӯҢ©ҺуӮҜӮзӮкӮйҒB ӮЬӮҪҒA‘жҲкҺҹғGғ`ғIғsғAҗн‘ҲӮЕҒAғGғ`ғIғsғA’йҚ‘ӮӘғCғ^ғҠғAүӨҚ‘ӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҗж—бӮӘӮ ӮйӮӘҒAӮұӮкӮНүp•§ӮМ‘S–К“IӮИҢRҺ–“IҺxүҮӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮНҒA—LҗFҗlҺнҚ‘үЖ“ЖҺ©ӮМҢR‘аӮЙӮжӮйҒA”’җFҗlҺнҚ‘үЖӮЙ‘ОӮ·ӮйӢЯ‘гҸүӮМҸҹ—ҳӮЖҢҫӮҰӮй(ҠФҗЪ“IӮЙӮҫӮӘҒAғCғMғҠғXӮӘғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҠсҚ`Ӯв•вӢӢӮр–WҠQӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪҒB)ҒBӮЬӮҪҒAҗв‘ОҢNҺеҗ§(ғcғ@Ғ[ғҠғYғҖ)Ӯр‘ұӮҜӮйҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй—§ҢӣҢNҺеҚ‘ӮМҸҹ—ҳӮЖӮўӮӨ‘Ө–КӮаӮ ӮБӮҪҒBӮўӮёӮкӮЙӮөӮДӮа“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮӘӢyӮЪӮөӮҪҗўҠE“IүeӢҝӮНҢvӮи’mӮкӮёҒA—рҺj“I‘еҺ–ҢҸӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮН•ПӮнӮиӮИӮўҒB “ъ–{ӮЙ—ҲӮДӮўӮҪғhғCғc’йҚ‘ӮМҲгҺТғGғӢғ”ғBғ“ҒEғtғHғ“ҒEғxғӢғcӮНҒAҺ©•ӘӮМ“ъӢLӮМ’ҶӮЕ“ъҳIҗн‘ҲӮМҢӢүКӮЙӮВӮўӮДҒuҺ„ӮӘӮұӮМ“ъӢLӮрҸ‘ӮўӮДӮўӮйҠФӮЙӮаҒAҗўҠE—рҺjӮМ’ҶӮМҸd—vӮИ1ғyҒ[ғWӮӘҢҲ’иӮіӮкӮДӮўӮйҒvӮЖҸ‘ӮўӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМүeӢҝӮрҺуӮҜӮДҒAғҚғVғAӮМҗA–Ҝ’nӮЕӮ ӮБӮҪ’nҲжӮвғAғWғAӮЕ“БӮЙ“Ж—§ҒEҠv–Ҫү^“®ӮӘҚӮӮЬӮиҒAҗҙ’©ӮЙӮЁӮҜӮй‘·•¶ӮМҗhҲеҠv–ҪҒAғIғXғ}ғ“’йҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮйҗВ”NғgғӢғRҠv–ҪҒAғJҒ[ғWғғҒ[ғӢ’©ӮЙӮЁӮҜӮй—§ҢӣҠv–ҪӮвҒA•§—МғCғ“ғhғVғiӮЙӮЁӮҜӮйғtғ@ғ“ҒEғ{ғCҒEғ`ғғғEӮМ“Ң—Vү^“®ҒAүp—МғCғ“ғh’йҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮйғCғ“ғhҚ‘–ҜүпӢcғJғӢғJғbғ^‘еүп“ҷӮЙүeӢҝӮр—^ӮҰӮДӮўӮйҒB Ғ@ |
|
| ҒЎғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–с | |
|
(Portsmouth Treaty, Treaty of Portsmouth, Portsmouth Peace Treaty) ғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘‘е“қ—МғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғgӮМҲҙҗщӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮЖғҚғVғA’йҚ‘ӮЖӮМҠФӮЕҢӢӮОӮкӮҪ“ъҳIҗн‘ҲӮМҚuҳaҸр–сҒB“ъҳIҚuҳaҸр–сӮЖӮаҸМӮ·ӮйҒB1905”N(–ҫҺЎ38”N)9ҢҺ4“ъ(“ъ–{ҺһҠФӮЕӮН9ҢҺ5“ъ15Һһ47•Ә)ҒAғAғҒғҠғJ“Ң•”ӮМҚ`ҳp“sҺsғ|Ғ[ғcғ}ғXӢЯҚxӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢR‘ў‘DҸҠӮЙӮЁӮўӮДҒA“ъ–{‘SҢ Ҹ¬‘әҺх‘ҫҳY(ҠO–ұ‘еҗb)ӮЖғҚғVғA‘SҢ ғZғӢғQғCҒEYҒEғEғBғbғeӮМҠФӮЕ’ІҲуӮіӮкӮҪҒB
ӮЬӮҪҒAҸр–с“а—eӮрҢрҸВӮөӮҪүпӢc(“Ҝ”N8ҢҺ10“ъҒ|)ӮМӮұӮЖӮрғ|Ғ[ғcғ}ғXүпӢcҒA “ъҳIҚuҳaүпӢcҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮИӮЗӮЖҢДӮФҒB “ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҸIҺn—DҗЁӮр•ЫӮБӮДӮўӮҪ“ъ–{ӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнҗнҸҹҢгӮМ1905”N(–ҫҺЎ38”N)6ҢҺҒAӮұӮкҲИҸгӮМҗн‘ҲҢp‘ұӮӘҚ‘—НӮМ–КӮЕҢАҠEӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒA“–Һһүp•§—сӢӯӮЙҢЁӮр•АӮЧӮйӮЬӮЕӮЙҗ¬’·ӮөҚ‘ҚЫ“IҢ ҲРӮрҚӮӮЯӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘ӮЙ‘ОӮөҒu’Ҷ—§ӮМ—FӢb“IҲҙҗщҒv(ҠOҢр•¶Ҹ‘)Ӯрҗ\Ӯө“ьӮкӮҪҒB•ДҚ‘ӮЙҲҙҗщӮрҲЛ—ҠӮөӮҪӮМӮНҒA—ӨүңҚ‘ҲкҠЦ”Л(ҠвҺиҢ§)ҸoҗgӮМ“ъ–{ӮМ’“•ДҢцҺgҚӮ•ҪҸ¬ҢЬҳYӮЕӮ ӮиҒAҲИҢгҒAҳa•ҪҢрҸВӮМ“®Ӯ«ӮӘүБ‘¬ү»ӮөӮҪҒB ҚuҳaүпӢcӮНҒA1905”N8ҢҺӮЙҠJӮ©ӮкӮҪҒB“–ҸүғҚғVғAӮНӢӯҚdҺpҗЁӮрҠСӮ«ҒuӮҪӮ©ӮҫӮ©Ҹ¬ӮіӮИҗ퓬ӮЙӮЁӮўӮД”sӮкӮҪӮҫӮҜӮЕӮ ӮиҒAғҚғVғAӮН•үӮҜӮДӮНӮўӮИӮўҒBӮЬӮҫӮЬӮҫҢpҗнӮаҺ«ӮіӮИӮўҒvӮЖҺе’ЈӮөӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҢрҸВӮНҲГҸКӮЙҸжӮиҸгӮ°ӮДӮўӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮЖӮөӮДӮНӮұӮкҲИҸгӮМҗн‘ҲӮМҢp‘ұӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮйӮЖ”»’fӮөӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪӮұӮМ’І’вӮрҗ¬ҢчӮіӮ№ӮҪӮў•ДҚ‘ӮНғҚғVғAӮЙ“ӯӮ«Ӯ©ӮҜӮйӮұӮЖӮЕҺ–‘ФӮМҺыҸEӮрӮНӮ©ӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAғҚғVғAӮН–һҸBӮЁӮжӮС’©‘NӮ©ӮзӮН“P•әӮөҒA“ъ–{ӮЙҠ’‘ҫӮМ“м•”ӮрҠ„ҸчӮ·ӮйӮаӮМӮМҒAҗн‘Ҳ”…ҸһӢаӮЙӮНҲкҗШүһӮ¶ӮИӮўӮЖӮўӮӨғҚғVғA‘ӨӮМҚЕ’бҸрҢҸӮЕҢрҸВӮН’чҢӢӮөӮҪҒB”ј–КҒA“ъ–{ӮНҚў“пӮИҠOҢр“IҺжҲшӮр’КӮ¶ӮДҗhӮӨӮ¶ӮДҸҹҺТӮЖӮөӮДӮМ‘М–КӮрҸҹӮҝҺжӮБӮҪҒB ӮұӮМҸр–сӮЙӮжӮБӮДҒA“ъ–{ӮНҒA–һҸB“м•”ӮМ“S“№ӢyӮС—М’nӮМ‘dҺШҢ ҒA‘еҠШ’йҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй”r‘ј“IҺw“ұҢ ӮИӮЗӮрҠl“ҫӮөӮҪӮаӮМӮМҒAҢRҺ–”пӮЖӮөӮД“ҠӮ¶ӮДӮ«ӮҪҚ‘үЖ—\ҺZҲк”N•ӘӮМ–с4”{ӮЙӮ ӮҪӮй20үӯү~Ӯр–„ӮЯҚҮӮнӮ№ӮйӮҪӮЯӮМҗн‘Ҳ”…ҸһӢаӮрҠl“ҫӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA’чҢӢ’јҢгҒAҗнҺһ’ҶӮЙ‘қҗЕӮЙӮжӮй‘П–Rҗ¶ҠҲӮрӢӯӮўӮзӮкӮДӮ«ӮҪҚ‘–ҜӮЙӮжӮБӮД“ъ”д’JҸД‘ЕҺ–ҢҸӮИӮЗӮМ–\“®ӮӘӢNӮұӮБӮҪҒB Ғ@ |
|
| ҒЎҢрҸВӮМҢoҲЬ Ғ@ | |
|
ҒЎҢрҸВӮЙҺҠӮйӮЬӮЕ
1905”N3ҢҺҒA“ъ–{ҢRӮНғҚғVғAҢRӮр”jӮБӮД•т“V(Ң»ҚЭӮМаc—z)Ӯрҗи—МӮөӮҪӮаӮМӮМҒAҗ퓬”\—НӮНӮ·ӮЕӮЙҢАҠEӮр’ҙӮҰҒA•җҠнҒE’e–тӮМ’І’BӮМ–Ъ“rӮа—§ӮҪӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒBҲк•ыӮМғҚғVғAӮЕӮН“Ҝ”N1ҢҺӮМҢҢӮМ“ъ—j“ъҺ–ҢҸӮИӮЗӮЙӮЭӮзӮкӮйҚ‘“аҸоҗЁӮМҚ¬—җӮЖғҚғVғA‘жҲкҠv–ҪӮМҚLӮӘӮиҒAӮіӮзӮЙғҚғVғAҢRӮМӮ ӮўӮВӮ®”s–kӮЖӮ»ӮкӮЙӮЖӮаӮИӮӨҺг‘Мү»ҒA“ъ–{ӮМӢӯ‘еү»ӮЙ‘ОӮ·Ӯй—сӢӯӮМ•|ӮкӮИӮЗӮаӮ ӮБӮДҒA“ъҳIҚuҳaӮрӢҒӮЯӮйҚ‘ҚЫҗўҳ_ӮӘӢӯӮЬӮБӮДӮўӮҪҒB 1905”N5ҢҺ27“ъӮ©Ӯз28“ъӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕӮМҠ®‘SҸҹ—ҳӮНҒA“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҚuҳaӮЦӮМҗвҚDӮМӢ@үпӮЖӮИӮБӮҪҒB5ҢҺ31“ъҒAҸ¬‘әҡж‘ҫҳYҠO–ұ‘еҗbӮНҒAҚӮ•ҪҸ¬ҢЬҳY’“•ДҢцҺgӮЙӮ ӮДӮДҢP“dӮр”ӯӮөҒA’Ҷ—§Қ‘ғAғҒғҠғJӮМғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮЙҒu’јҗЪӮ©ӮВ‘S‘RҲкҢИӮМ”ӯҲУӮЙӮжӮиҒv“ъҳI—јҚ‘ҠФӮМҚuҳaӮрҲҙҗщӮ·ӮйӮжӮӨӢҒӮЯҒA–ҪӮрҺуӮҜӮҪҚӮ•ҪӮН—Ӯ“ъҒu’Ҷ—§ӮМ—FӢb“IҲҙҗщҒvӮр‘е“қ—МӮЙҗ\Ӯө“ьӮкӮҪҒB •Д‘е“қ—МӮМ’ҮүоӮр“ҫӮҪҚӮ•ҪӮНҒAҸ¬‘әҠO‘ҠӮЙ‘ОӮөҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXӮНҚҮҸOҚ‘җӯ•{ӮМ’јҠҚ’nӮЕӢЯҚxӮЙғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢR‘ў‘DҸҠӮӘӮ ӮиҒAҸhҺЙӮЖӮИӮйғzғeғӢӮаӮ ӮБӮДҒA“ъҳI—јҚ‘ӮМ‘SҢ ҲПҲхӮНҢЭӮўӮЙ—ЈӮкӮДӢNӢҸӮЕӮ«ӮйӮұӮЖӮр“`ӮҰӮДӮўӮйҒB ғpғҠ(ғҚғVғAҲД)ҒAҺЕг§ӮЬӮҪӮНғҸғVғ“ғgғ“D.C.(“ъ–{ӮМ“–ҸүҲД)ҒAғnҒ[ғO(•ДүpҲД)ӮрүҹӮіӮҰӮДӮМҠJҚГ’nҢҲ’иӮЕӮ ӮБӮҪҒBғ|Ғ[ғcғ}ғXӮНҒAғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮМ–k•ы–с400ғLғҚғҒҒ[ғgғӢ’n“_ӮЙ—§’nӮөҒAҢRҚ`ӮЕӮ ӮйӮЖ“ҜҺһӮЙ•К‘‘ӮМҢҡӮҝ•АӮФҠХҗГӮИ”рҸӢ’nӮЕӮаӮ ӮиҒAҢx”хӮӘӮ«ӮнӮЯӮД—eҲХӮИӮұӮЖӮ©ӮзҢцҺ®үпҸкӮЙ‘I’иӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮЬӮҪҒA•ДҚ‘“аӮМҠJҚГӮЙӮНҒAғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғgӮМҒu“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮД—\ӮМ“w—НӮӘҚЕӮа—ҳүvӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨӮМӮИӮзҒAӮўӮ©ӮИӮйҺһӮЙӮЕӮаӮ»ӮМҳJӮрҺ·ӮйҒv(ҠOҢр•¶Ҹ‘)ӮЖӮўӮӨ”ӯҢҫӮЙҸЫ’ҘӮіӮкӮйҗe“ъ“IӮИҗ«ҠiӮЙүБӮҰҒAҚuҳaӮМ’І’вҚHҚмӮр—ҳ—pӮөҒA•ДҚ‘ӮрӮөӮДҚ‘ҚЫҺРүпӮМҺе–рӮҪӮзӮөӮЯҒAҸ]—ҲғҚғVғAӮМӢӯӮўүeӢҝүәӮЙӮ ӮБӮҪ“ҢғAғWғAӮЙӮЁӮўӮДҒA“ъҒE•ДӮаӮУӮӯӮсӮҫҗЁ—НӢПҚtӮМҺАҢ»ӮрӮНӮ©ӮйӮЖӮўӮӨҺvҳfӮӘӮ ӮБӮҪҒB ’ҶҚ‘ӮМ–еҢЛҠJ•ъӮрҠиӮӨғAғҒғҠғJӮЖӮөӮДӮНҒA“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМӮўӮёӮкӮ©ӮӘҲі“|“IӮИҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮД–һҸBӮр“ЖҗиӮ·ӮйӮұӮЖӮН”рӮҜӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮиҒAӮұӮМғAғҒғҠғJӮМ—§ҸкӮЖҒAҚ‘“аӮМҠv–Ҫү^“®—}ҲіӮМӮҪӮЯҗн‘ҲҸIҢӢӮр–]ӮЮғҚғVғAҒAҗн—НӮМҢАҠE“_Ӯр’ҙӮҰӮДҸҹ—ҳӮрҠmҺАӮЙӮөӮҪӮў“ъ–{ӮМӮ»ӮкӮјӮкӮМҠу–]ӮӘҲк’vӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBғhғCғcҒEғtғүғ“ғX—јҚ‘Ӯ©ӮзӮаҒAҒuғҚғVғAӮМ“аж`ӮӘғtғүғ“ғXҠv–ҪӮМҺһӮМӮжӮӨӮЙ—ЧҚ‘ӮЙ—eҲХӮИӮзӮҙӮйүeӢҝӮрӢyӮЪӮ·ӢсӮӘӮ ӮйҒv(ҠOҢр•¶Ҹ‘)ӮЖӮөӮДҚuҳaӮӘ‘ЕҗfӮіӮкӮДӮўӮҪҒBғӢҒ[ғYғxғӢғgӮМ’ҮүоӮНӮұӮкӮр“ҘӮЬӮҰӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ”wҢiӮЙӮНҒA•ДҚ‘ӮӘӮ»ӮМ’·Ҡъҗн—ӘӮЙӮЁӮўӮДҒAҸ]—ҲҒuғӮғ“ғҚҒ[ҺеӢ`ҒvӮЖҸМӮіӮкӮДӮ«ӮҪ“`“қ“IӮИҢЗ—§ҺеӢ`Ӯ©ӮзӮМ’EӢpӮрҗ}ӮлӮӨӮЖӮ·ӮйҺv’ӘӮМ•Пү»ӮӘӮ ӮБӮҪҒB ғӢҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮНҒA’“ҳIғAғҒғҠғJ‘еҺgӮМғWғҮҒ[ғWҒEғ}ғCғ„Ғ[ӮЙғҚғVғAҚc’йӮЦӮМҗа“ҫӮр–ҪӮ¶ӮҪӮ ӮЖҒA1905”N6ҢҺ9“ъҒA“ъҳI—јҚ‘ӮЙ‘ОӮөҒAҚuҳaҢрҸВӮМҠJҚГӮрҗіҺ®ӮЙ’сҲДӮөӮҪҒBӮұӮМ’сҲДӮрҺу‘шӮөӮҪӮМӮНҒA“ъ–{ӮӘ’сҲДӮМӮ ӮБӮҪ—Ӯ“ъӮМ6ҢҺ10“ъҒAғҚғVғAӮӘ6ҢҺ12“ъӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮИӮЁҒAғӢҒ[ғYғxғӢғgӮНҢрҸВӮр—L—ҳӮЙҗiӮЯӮйӮҪӮЯӮЙ“ъ–{ӮНҠ’‘ҫ(ғTғnғҠғ“)ӮЙҢRӮр”hҢӯӮөӮД“Ҝ’nӮрҗи—МӮ·ӮЧӮ«ӮҫӮЖҲУҢ©ӮрҺҰҚҙӮөӮДӮўӮйҒB “ъ–{ӮМҚ‘“аӮЙӮЁӮўӮДҒAҺс‘ҠҢj‘ҫҳYӮӘ“ъ–{ӮМ‘SҢ ‘г•\ӮЖӮөӮДҚЕҸүӮЙ‘ЕҗfӮөӮҪӮМӮНҒAҠO‘ҠҸ¬‘әҡж‘ҫҳYӮЕӮНӮИӮӯҢіҳVҲЙ“Ў”Һ•¶ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢjҗӯҢ (‘ж1ҺҹҢj“аҠt)ӮНҒAҚuҳaҸрҢҸӮӘ“ъ–{Қ‘–ҜӮЙҺуӮҜ“ьӮкӮӘӮҪӮўӮаӮМӮЙӮИӮйӮұӮЖӮр“–ҸүӮ©Ӯз—\Ң©ӮөҒAӮ»ӮкӮЬӮЕ4“xҺс‘ҠӮр–ұӮЯӮҪҲЙ“ЎӮЕӮ ӮкӮОҚ‘–ҜӮМ•s–һӮрҳaӮзӮ°ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҠъ‘ТӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҲЙ“ЎӮНӮНӮ¶ӮЯӮНҲшӮ«ҺуӮҜӮДӮаӮжӮўӮЖӮўӮӨҺpҗЁӮрҺҰӮөӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA”ЮӮМ‘ӨӢЯӮНҒAҗнҸҹӮМүh—_ӮНҢjӮӘӮЙӮИӮўҒAҚuҳaӮЙӮжӮБӮДҗ¶Ӯ¶ӮйҚ‘–ҜӮМ”ҪҠҙӮрҲЙ“ЎӮӘҲкҺиӮЙҲшӮ«ҺуӮҜӮйӮМӮН”nҺӯӮ°ӮДӮўӮйӮЖӮөӮД–Т”Ҫ‘ОӮөҒAҚЕҸI“IӮЙӮНҲЙ“ЎӮа‘SҢ ‘еҺgӮЦӮМҸA”CӮрҺ«‘ЮӮөӮҪҒB ҢӢӢЗҒA“ъҢьҚ‘йK”м”Л(Ӣ{ҚиҢ§)ӮМүәӢү”ЛҺmҸoҗgӮЕҒA‘ж1ҺҹҢj“аҠt(1901”N-1906”N)ӮМҠO–ұ‘еҗbӮЖӮөӮД“ъүp“Ҝ–ҝӮМ’чҢӢӮЙҢчӮМӮ ӮБӮҪҸ¬‘әҡж‘ҫҳYӮӘ‘SҢ ‘г•\ӮЙ‘IӮОӮкӮҪҒBҸ¬‘әӮНҒAҗg’·150ғZғ“ғ`ғҒҒ[ғgғӢӮЙ–һӮҪӮКҸ¬’jӮЕҒA“–Һһ50ҚОӮЙӮИӮй’ј‘OӮЕӮ ӮБӮҪҒBҲЙ“Ў”Һ•¶ӮаӮЬӮҪҢрҸВӮМ—eҲХӮЕӮИӮўӮұӮЖӮрӮжӮӯ’mӮБӮДӮЁӮиҒAҸ¬‘әӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒuҢNӮМӢA’©ӮМҺһӮЙӮНҒA‘јҗlӮНӮЗӮӨӮ ӮлӮӨӮЖӮаҒAҢб”yӮҫӮҜӮН•KӮёҸoҢ}ӮҰӮЙӮдӮӯҒvӮЖҢкӮиҒA—гӮЬӮөӮДӮўӮйҒB ‘ОӮ·ӮйғҚғVғA‘SҢ ‘г•\ғZғӢғQғCҒEғEғBғbғe(Ңі‘ ‘Ҡ)ӮНҒA“–Һһ56ҚОӮЕҗg’·180ғZғ“ғ`ғҒҒ[ғgғӢӮрүzӮ·‘е’jӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗн‘OӮНҚаҗӯҺ–Ҹо“ҷӮ©Ӯз“ъҳIҠJҗнӮЙ”Ҫ‘ОӮөӮДӮўӮҪӮаӮМӮМҒAӮ©ӮкӮМҳa•Ҫҳ_ӮН‘О“ъӢӯҚd”hӮЙӮжӮи‘ЮӮҜӮзӮкҒAҗн‘Ҳ’ҶӮНғҚғVғA’йҚ‘ӮМҗӯҢ ’Ҷҗ•ӮжӮиү“ӮҙӮҜӮзӮкӮДӮўӮҪҒBғҚғVғAҚ‘“аӮЕӮНҒA‘SҢ ӮЖӮөӮДғEғBғbғeӮӘҚЕ“K”CӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҸO–ЪӮМҲк’vӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҚc’йғjғRғүғC2җўӮН”ЮӮрҚDӮЬӮИӮ©ӮБӮҪҒBғEғүғWҒ[ғ~ғӢҒEғүғҖғXғhғӢғtғҚғVғAҠO‘ҠӮН’“•§‘еҺgғlғҠғhғtӮрҗ„‘EӮөӮҪӮӘғlғҠғhғtӮНӮұӮкӮрҺ«‘ЮӮөҒAғҖғүғrғҲғt’“ҲЙ‘еҺgӮаҲшӮ«ҺуӮҜӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒAҢӢӢЗғEғBғbғeӮӘ“o—pӮіӮкӮҪҒBғEғBғbғeӮНҒAҚc’йӮжӮиҒuҲкӮЙӮ¬ӮиӮМ“y’nӮаҒAҲкғӢҒ[ғuғӢӮМӢаӮа“ъ–{ӮЙ—^ӮҰӮДӮНӮўӮҜӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҢө–ҪӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯғEғBғbғeӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғX“һ’…ҲИ—ҲӮЬӮйӮЕҗнҸҹҚ‘ӮМ‘г•\ӮМӮжӮӨӮЙҗUӮй•‘ӮўҒAғҚғVғAӮН•KӮёӮөӮаҚuҳaӮр—~ӮөӮДӮЁӮзӮёҒAӮўӮВӮЕӮаҗн‘ҲӮрӮВӮГӮҜӮйҸҖ”хӮӘӮ ӮйӮЖӮўӮӨҺpҗЁӮрӮӯӮёӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒB Ӯ·ӮЧӮДӮМҗн—НӮЙӮЁӮўӮДғҚғVғAӮжӮи—тҗЁӮЕӮ ӮБӮҪ“ъ–{ӮНҒAҠJҗн“–ҸүӮжӮиҒAҗн‘ҲӮМҠъҠФӮр–с1”NӮЙ‘z’иӮөҒAҗжҗ§ҚUҢӮӮрӮЁӮұӮИӮБӮДҗнӢөӮӘ—DҗЁӮИӮӨӮҝӮЙҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮаӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪҒBҠJҗнҢгҒA“ъ–{ҢRӮӘҳAҗнҳAҸҹӮрӮВӮГӮҜӮДӮ«ӮҪӮМӮНӮЮӮөӮлҠпҗХ“IӮЖӮаӮўӮҰӮҪӮӘҒA3ҢҺӮМ•т“VүпҗнӮМҸҹ—ҳҲИҢгӮН•җҠнҒE’e–тӮМ•вӢӢӮа“rҗвӮҰӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA“ъ–{ҢRӮНҢҲӮөӮДғҚғVғAҢRӮЙ‘ОӮөҢҲҗнӮр’§ӮЮӮұӮЖӮИӮӯҒAӮРӮҪӮ·ӮзҚuҳaӮМӢ@үпӮрӮӨӮ©ӮӘӮБӮҪҒB5ҢҺ––ӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕғҚғVғAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮөӮҪӮұӮЖӮНҒAӮ»ӮМҗвҚDӮМӢ@үпӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ӯ·ӮЕӮЙ“ъ–{ӮНӮұӮМҗн‘ҲӮЙ–с180–ңӮМҸ«•әӮр“®ҲхӮөҒAҺҖҸқҺТӮН–с20–ңҗlҒAҗн”пӮН–с20үӯү~ӮЙ’BӮөӮДӮўӮҪҒB–һҸBҢR‘ҚҺQ–d’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮНҒA1”NҠФӮМҗн‘ҲҢp‘ұӮр‘z’иӮөӮҪҸкҚҮҒAӮіӮзӮЙ25–ңҗlӮМ•әӮЖ15үӯү~ӮМҗн”пӮр—vӮ·ӮйӮЖӮөӮДҒA‘ұҚsӮН•sүВ”\ӮЖҢӢҳ_ӮГӮҜӮДӮўӮҪҒBӮЖӮӯӮЙүәӢүҸ«ҚZӮӘ—EҠёӮЙҗiҢӮӮөӮДҗнҺҖӮөӮҪҢӢүКҒAӮ»ӮМ•вҸ[ӮН—eҲХӮЕӮИӮ©ӮБӮҪҒBҲк•ыҒAғҚғVғAӮНҒAҠCҢRӮНҺёӮБӮҪӮаӮМӮМғVғxғҠғA“S“№Ӯр—ҳ—pӮөӮД—ӨҢRӮр‘қӢӯӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮ ӮиҒAҗVӮҪӮЙ‘қүҮ•”‘аӮӘүБӮнӮБӮДҒA“ъ–{ҢRӮрҲі“|Ӯ·Ӯй•ә—НӮрҸWӮЯӮВӮВӮ ӮБӮҪҒB ҺсҗИ“Б–Ҫ‘SҢ ‘еҺgӮЙ‘IӮОӮкӮҪҸ¬‘әӮНҒAӮұӮӨӮөӮҪ•ЎҺGӮИҺ–ҸоӮрӮ·ӮЧӮД’mҺ»ӮөӮҪӮӨӮҰӮЕүпӢcӮЙ—ХӮсӮҫҒBҸ¬‘әӮМҲкҚsӮН1905”N7ҢҺ8“ъҒA“n•ДӮМӮҪӮЯүЎ•lҚ`ӮЙҢьӮ©ӮӨҗVӢҙ’вҺФҸкӮрҸo”ӯӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮМӮЖӮ«җVӢҙүwӮЙӮН‘еҗЁӮМҗlӮӘҸWӮЬӮиҒA‘еҠҪҗәӮЕ–ңҚОӮөҒAҸ¬‘әӮрҗ·‘еӮЙҢ©‘—ӮБӮҪҒBҸ¬‘әӮНҢjҺс‘ҠӮЙ‘ОӮөҒuҗVӢҙүw“ӘӮМҗlӢCӮНҒAӢAӮйӮЖӮ«ӮНӮЬӮйӮЕ”Ҫ‘ОӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮЕӮөӮеӮӨҒvӮЖӮВӮФӮвӮӯӮжӮӨӮЙҚҗӮ°ӮҪӮЖ“`ӮнӮБӮДӮўӮйҒBҲдҸгҠ]ӮНӮұӮМӮЖӮ«ҒAҸ¬‘әӮЙ‘ОӮө—ЬӮр—¬ӮөӮДҒuҢNӮНҺАӮЙӢCӮМ“ЕӮИӢ«ӢцӮЙӮҪӮБӮҪҒBӮўӮЬӮЬӮЕӮМ–ј—_ӮаҚЎ“xӮЕӮҫӮўӮИӮөӮЙӮИӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒvӮЖҢкӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒBҸ¬‘әҲкҚsӮНҒAғVғAғgғӢӮЙӮН7ҢҺ20“ъӮЙ“һ’…ӮөҒAҲкҸTҠФҢгғҸғVғ“ғgғ“ӮЕғӢҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮЙ•\Ңh–K–вӮрӮЁӮұӮИӮўҒA’ҮүоӮрҲшӮ«ҺуӮҜӮДӮӯӮкӮҪӮұӮЖӮЙҺУҲУӮр•\–ҫӮөӮҪҒB ҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮНҒA“ъ–{ӮӘҚuҳaҸрҢҸӮЖӮөӮДҢfӮ°ӮҪ‘ОҳI—vӢҒ12ҸрӮМӮИӮ©ӮЙ”…ҸһӢаӮМҲкҸрӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮр’mӮиҒAҒuҢjӮМ”nҺӯӮӘҸһӢаӮрӮЖӮйӢCӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒvӮЖҢкӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB“ъҳIҠJҗн‘OӮЙҸ¬‘әҠO‘ҠӮЙҒuҺө”ҺҺmҲУҢ©Ҹ‘ҒvӮр’сҸoӮөӮҪҺө”ҺҺmӮМ‘г•\ҠiӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйҢЛҗ…Ҡ°җlӮНҒAҚuҳaӮМҚЕ’бҸрҢҸӮЖӮөӮДҒuҸһӢа30үӯү~ҒAҠ’‘ҫҒEғJғҖғ`ғғғbғJ”ј“ҮҒEүҲҠCҸB‘S•”ӮМҠ„ҸчҒvӮрҺе’ЈӮөҒAҗV•·ӮаӮЬӮҪҢЛҗ…”ҺҺmӮМҺе’ЈӮрӢ“Ӯ°ӮйӮИӮЗӮөӮДҚ‘–ҜӮМҠъ‘ТҠҙӮрҗшӮиҒAҚ‘–ҜӮаӮЬӮҪҗнҸҹӢC•ӘӮЙ•ӮӮ©ӮкӮДӮўӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМүәҠЦҸр–сӮЕӮНҒA‘дҳpӮМҠ„ҸчӮМӮЩӮ©”…ҸһӢаӮа“ҫӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{Қ‘–ҜӮМ‘ҪӮӯӮН‘еҚ‘ғҚғVғAӮИӮзӮОӮ»ӮкӮЙҢ©ҚҮӮБӮҪ”…ҸһӢаӮрҺx•ҘӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЖҗMӮ¶ҒAҚJҠФӮЕӮНҒu30үӯү~ҒvҒu50үӯү~ҒvӮИӮЗӮМҗ”ҺҡӮӘҲкҗl•аӮ«ӮөӮДӮўӮҪҒB“ъ–{Қ‘“аӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAҗӯ•{ӮМҺvҳfӮЖҚ‘–ҜӮМҠъ‘ТӮМӮ ӮўӮҫӮЙ‘еӮ«ӮИҠuӮҪӮиӮӘӮ ӮиҒAҲк•ыҒA“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮЖӮМӮ ӮўӮҫӮЕӮНҒAҒu”…ҸһӢаӮЖ—М“yҠ„ҸчҒvӮМ2ҸрҢҸӮЙҠЦӮөӮДҚЕҢгӮМҚЕҢгӮЬӮЕӢcҳ_ӮӘ‘О—§ӮөӮҪҒB ғҚғVғA‘SҢ ‘еҺgғEғBғbғeӮНҒA7ҢҺ19“ъҒAғTғ“ғNғgҒEғyғeғӢғuғӢғNӮрҸo”ӯӮөҒA8ҢҺ2“ъӮЙғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮЙ“һ’…ӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮҝӮЙӢLҺТүпҢ©ӮрҺҺӮЭҒAғWғғҒ[ғiғҠғXғgӮЙ‘ОӮөӮДӮНҲӨ‘z—ЗӮӯ‘ОүһӮөӮДҒAҗф—ыӮіӮкӮҪҳbҸpӮЖғҶҒ[ғӮғAӮЙӮжӮиҒA•ДҚ‘ӮМҗўҳ_ӮрҚIӮЭӮЙ–Ў•ыӮЙӮВӮҜӮДӮўӮБӮҪҒBғEғBғbғeӮНҒA“–ҸүӮ©Ӯз“ъ–{ӮМҚuҳaҸрҢҸӮӘ”…ҸһӢаҒE—М“yҠ„ҸчӮр—vӢҒӮ·ӮйӮ«ӮСӮөӮўӮаӮМӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр‘z’иӮөӮДҒAӮ»ӮұӮрӢӯ’ІӮ·ӮкӮО•ДҚ‘–ҜӮӘғҚғVғAӮЙ‘ОӮөӮД“ҜҸоҗSӮрӮаӮВӮжӮӨӮЙӮИӮйӮҫӮлӮӨӮЖҚlӮҰӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҺАҚЫӮЙҒu“ъ–{ӮН‘ҪҠzӮМ”…ҸһӢаӮр“ҫӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAҗн‘ҲӮр‘ұӮҜӮйӮұӮЖӮаҺ«ӮіӮИӮўӮзӮөӮўҒvӮЖӮўӮӨ“ъ–{”б”»ӮМ•с“№ӮаӮИӮіӮкҒAҲк•”ӮЕӮНҒA“ъ–{ӮНӢа‘KӮМӮҪӮЯӮЙҗн‘ҲӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮ©ӮЖӮўӮӨҚDӮЬӮөӮ©ӮзӮҙӮй•—•]ӮаҢ»ӮкӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЙ‘ОӮөӮДҸ¬‘әӮНҒAҠOҚ‘ӮМҗV•·ӢLҺТӮЙғRғҒғ“ғgӮрӢҒӮЯӮзӮкӮҪҚЫҒuӮнӮкӮнӮкӮНғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЦҗV•·ӮМҺнӮрӮВӮӯӮйӮҪӮЯӮЙ—ҲӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўҒB’k”»ӮрӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙ—ҲӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒvӮЖӮ»ӮБӮҜӮИӮӯ“ҡӮҰҒAӮИӮ©ӮЙӮНҢғ“{ӮөӮҪӢLҺТӮаӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBҸ¬‘әӮНӮЬӮҪҒAғ}ғXғҒғfғBғAӮЙ‘ОӮө”й–§ҺеӢ`ӮрҚМӮБӮҪӮҪӮЯҒAҢ»’nӮМҗV•·ӮЙӮНғҚғVғA‘ӨӮӘ’сӢҹӮөӮҪҸо•сӮМӮЭӮӘҢfҚЪӮіӮкӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB–ҫӮзӮ©ӮЙҸ¬‘әӮНғ}ғXғҒғfғBғAӮМҸd—vҗ«Ӯр”FҺҜӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚuҳaүпӢc
ҚuҳaүпӢcӮМҢцҺ®үпҸкӮНғҒғCғ“ҸBғLғ^ғҠҒ[ӮЙҸҠҚЭӮ·Ӯйғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢRҚHҸұ86ҚҶ“ҸӮЕӮ ӮБӮҪҒBҠCҢRҚHҸұ(ғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢR‘ў‘DҸҠ)ӮНғsғXғJғ^ғJҗмӮМ’ҶҸFӮЙӮ ӮиҒAҗ…ҳHӮМ‘ОҠЭӮӘғjғ…Ғ[ғnғ“ғvғVғғҒ[ҸBғ|Ғ[ғcғ}ғXҺsӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМ‘г•\’cӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҺsӮЙ—ЧҗЪӮ·Ӯйғjғ…Ғ[ғLғғғbғXғӢ(en)ӮМғzғeғӢӮЙҸh”‘ӮөҒAӮ»ӮұӮ©Ӯз‘DӮЕҚHҸұӮЙ•ӢӮўӮДҢрҸВӮрҚsӮБӮҪҒB ҢрҸВҺQүБҺТӮНҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ ӮйҒB “ъ–{‘Ө ‘SҢ ҲПҲхҒFҸ¬‘әҡж‘ҫҳY(ҠO–ұ‘еҗb)ҒAҚӮ•ҪҸ¬ҢЬҳY(’“•ДҢцҺg) җҸҲхҒFҚІ“ЎҲӨ–ӣ(’“ғҒғLғVғR•Щ—қҢцҺg)ҒAҺRҚАү~ҺҹҳY(ҠO–ұҸИҗӯ–ұӢЗ’·)ҒAҲА’B•фҲкҳY(ҠO–ұҸИҺQҺ–ҠҜ)ҒA–{‘ҪҢF‘ҫҳY(ҠO–ұ‘еҗb”йҸ‘ҠҜ)ҒA—ҺҚҮҢӘ‘ҫҳY(ҠO–ұҸИ“с“ҷҸ‘ӢLҠҜ)ҒAҸ¬җјҚF‘ҫҳY(ҠOҢрҠҜ•в)ҒA—§үФҸ¬ҲкҳY—ӨҢR‘еҚІ(’“•ДҢцҺgҠЩ•t—ӨҢR•җҠҜ)ҒA’|үә—EҠCҢR’ҶҚІ(’“•ДҢцҺgҠЩ•tҠCҢR•җҠҜ)ҒAғwғ“ғҠҒ[ҒEғfғjғ\ғ“(ҠO–ұҸИҢЪ–в) ғҚғVғA‘Ө ‘SҢ ҲПҲхҒFғZғӢғQғCҒEғEғBғbғe(Ңі‘ ‘ҠҒE”ҢҺЭ)ҒAғҚғ}ғ“ҒEғҚҒ[ғ[ғ“(’“•Д‘еҺg(ҠJҗнҺһӮМ’““ъҢцҺg)) җҸҲхҒFAҒEғvғүғ“ғ\ғ“(ҠO–ұҸИҸр–сӢЗ’·)ҒAғtғҮҒ[ғhғӢҒEғtғҮҒ[ғhғҚғ”ғBғ`(ғyғeғӢғuғӢғN‘еҠwҚ‘ҚЫ–@ҠwҺТҒEҠO–ұҸИҢЪ–в)ҒANҒEғVғ|ғt(‘е‘ ҸИ—қҚаӢЗ’·)ҒAVҒEғGғӢғӮғҚғt—ӨҢRҸӯҸ«(’“үp—ӨҢR•җҠҜ)ҒAAҒEғTғӮғCғҚғt—ӨҢR‘еҚІ(Ңі’““ъҢцҺgҠҜ•t—ӨҢR•җҠҜ)ҒAIҒEғRғҚғXғgғEғFғc(ғEғBғbғe”йҸ‘ҒBҢгҒA’“җҙҢцҺg)ҒACҒEғiғ{ғRғt(ҠO–ұҸИҸ‘ӢLҠҜ) ҚuҳaүпӢcӮНҒA1905”N8ҢҺ1“ъӮжӮи17үсӮЙӮнӮҪӮБӮДҚsӮнӮкӮҪҒB8ҢҺ10“ъӮ©ӮзӮН–{үпӢcӮӘҺnӮЬӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA”сҢцҺ®ӮЙӮНғzғeғӢӮЕҢрҸВӮ·ӮйӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪҒB 8ҢҺ10“ъӮМ‘жҲкүс–{үпӢc–`“ӘӮЙӮЁӮўӮДҸ¬‘әӮНҒAӮЬӮё“ъ–{‘ӨӮМҸрҢҸӮр’сҺҰӮөҒA’ҖҸрӮ»ӮкӮрҗRӢcӮ·ӮйҺ|Ӯр’сҲДӮөӮДғEғBғbғeӮМ—№үрӮрӮҰӮҪҒBҸ¬‘әӮӘғEғBғbғeӮЙҺҰӮөӮҪҚuҳaҸрҢҸӮНҺҹӮМ12үУҸрӮЕӮ ӮйҒB 1. ғҚғVғAӮНҠШҚ‘(‘еҠШ’йҚ‘)ӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМҗӯҺЎҸгҒEҢRҺ–ҸгӮЁӮжӮСҢoҚПҸгӮМ“ъ–{ӮМ—ҳүvӮр”FӮЯҒA“ъ–{ӮМҠШҚ‘ӮЙ‘ОӮ·ӮйҺw“ұҒA•ЫҢмӮЁӮжӮСҠД“ВӮЙ‘ОӮөҒAҠұҸВӮөӮИӮўӮұӮЖҒB 2. ғҚғVғAҢRӮМ–һҸBӮжӮиӮМ‘S–К“P‘ЮҒA–һҸBӮЙӮЁӮҜӮйғҚғVғAӮМҢ үvӮМӮӨӮҝҗҙҚ‘ӮМҺеҢ ӮрҗNҠQӮ·ӮйӮаӮМҒAӮЬӮҪӮНӢ@үпӢП“ҷҺеӢ`ӮЙ”ҪӮ·ӮйӮаӮМӮНӮұӮкӮрӮ·ӮЧӮД•ъҠьӮ·ӮйӮұӮЖҒB 3. –һҸBӮМӮӨӮҝ“ъ–{ӮМҗи—МӮөӮҪ’nҲжӮНүьҠvӮЁӮжӮС‘PҗӯӮМ•ЫҸбӮрҸрҢҸӮЖӮөӮДҲкҗШӮрҗҙҚ‘ӮЙҠТ•tӮ·ӮйӮұӮЖҒBӮҪӮҫӮөҒA—Й“Ң”ј“Ү‘dҺШҸр–сӮЙ•пҠЬӮіӮкӮй’nҲжӮНҸңӮӯҒB 4. “ъҳI—јҚ‘ӮНҒAҗҙҚ‘ӮӘ–һҸBӮМҸӨҚHӢЖ”ӯ’BӮМӮҪӮЯҒA—сҚ‘ӮЙӢӨ’КӮ·ӮйҲк”К“IӮИ‘[’uӮМҺ·ҚsӮЙӮ ӮҪӮиҒAӮұӮкӮр‘jҠQӮөӮИӮўӮұӮЖӮрҢЭӮўӮЙ–с‘©Ӯ·ӮйӮұӮЖҒB 5. ғҚғVғAӮНҒAҠ’‘ҫӮЁӮжӮС•Қ‘®“ҮҒAҲкҗШӮМҢцӢӨүc‘ў•ЁҒEҚаҺYӮр“ъ–{ӮЙҸч—^Ӯ·ӮйӮұӮЖҒB 6. —·ҸҮҒA‘еҳAӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺьҲНӮМ‘dҺШҢ ҒEҠY‘dҺШҢ ӮЙҠЦҳAӮөӮДғҚғVғAӮӘҗҙҚ‘ӮжӮиҠl“ҫӮөӮҪҲкҗШӮМҢ үvҒEҚаҺYӮр“ъ–{ӮЙҲЪ“]Ңр•ҚӮ·ӮйӮұӮЖҒB 7. ғnғӢғrғ“ҒE—·ҸҮҠФ“S“№ӮЖӮ»ӮМҺxҗьӮЁӮжӮСӮұӮкӮЙ•Қ‘®Ӯ·ӮйҲкҗШӮМҢ үvҒEҚаҺYҒA“S“№ӮЙҸҠ‘®Ӯ·Ӯй’YҚBӮрғҚғVғAӮжӮи“ъ–{ӮЙҲЪ“]Ңр•ҚӮ·ӮйӮұӮЖҒB 8. –һҸBүЎҠС“S“№(“Ңҗҙ“S“№–{җь)ӮНҒAӮ»ӮМ•~җЭӮЙӮЖӮаӮИӮӨ“БӢ–ҸрҢҸӮЙӮөӮҪӮӘӮўҒAӮЬӮҪ’PӮЙҸӨҚHӢЖҸгӮМ–Ъ“IӮЙӮМӮЭҺg—pӮ·ӮйӮұӮЖӮрҸрҢҸӮЖӮөӮДғҚғVғAӮӘ•Ы—Lү^“]Ӯ·ӮйӮұӮЖҒB 9. ғҚғVғAӮНҒA“ъ–{ӮӘҗн‘ҲҗӢҚsӮЙ—vӮөӮҪҺА”пӮр•ҘӮў–ЯӮ·ӮұӮЖҒB•ҘӮў–ЯӮөӮМӢаҠzҒAҺһҠъҒA•ы–@ӮН•К“rӢҰӢcӮ·ӮйӮұӮЖҒB 10. җ퓬’Ҷ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮҪҢӢүКҒA’Ҷ—§Қ`ӮЙ“ҰӮ°үBӮкӮөӮҪӮи—}—ҜӮіӮ№ӮзӮкӮҪғҚғVғAҢRҠНӮрӮ·ӮЧӮДҚҮ–@ӮМҗн—ҳ•iӮЖӮөӮД“ъ–{ӮЙҲшӮ«“nӮ·ӮұӮЖҒB 11. ғҚғVғAӮНӢЙ“Ң•ы–КӮЙӮЁӮўӮДҠCҢR—НӮр‘қӢӯӮөӮИӮўӮұӮЖҒB 12. ғҚғVғAӮН“ъ–{ҠCҒAғIғzҒ[ғcғNҠCӮЁӮжӮСғxҒ[ғҠғ“ғOҠCӮЙӮЁӮҜӮйғҚғVғA—М“yӮМүҲҠЭҒAҚ`ҳpҒA“ьҚ]ҒAүНҗмӮЙӮЁӮўӮДӢҷӢЖҢ Ӯр“ъ–{Қ‘–ҜӮЙӢ–—^Ӯ·ӮйӮұӮЖҒB Ӯ»ӮкӮЙ‘ОӮөӮДғEғBғbғeӮНҒA8ҢҺ12“ъҢЯ‘OӮМ‘ж“сүс–{үпӢcӮЙӮЁӮўӮДҒA1.2.3.4.6.8.ӮЙӮВӮўӮДӮН“ҜҲУӮЬӮҪӮНҠо–{“IӮЙ“ҜҲУҒA7.ӮЙӮВӮўӮДӮНҒuҺеӢ`ӮЙӮЁӮўӮДӮНҸі‘шӮ·ӮйӮӘҒA“ъ–{ҢRӮЙҗи—МӮіӮкӮДӮўӮИӮў•”•ӘӮН•ъҠьӮЕӮ«ӮИӮўҒvҒA11.ӮЙӮВӮўӮДӮНҒuӢьҗJ“I–сҠјӮЙӮНүһӮ¶ӮзӮкӮИӮўӮӘҒA‘ҫ•Ҫ—mҸгӮЙ’ҳ‘еӮИҠCҢR—НӮр’uӮӯӮВӮаӮиӮНӮИӮўӮЖҗйҢҫӮЕӮ«ӮйҒvҒA12.ӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒu“ҜҲУӮ·ӮйӮӘҒA“ьҚ]ӮвүНҗмӮЙӮЬӮЕӢҷӢЖҢ ӮН—^ӮҰӮзӮкӮИӮўҒvӮЖ•Ф“ҡӮ·ӮйҲк•ыҒA5.9.10ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA•s“ҜҲУӮМҲУӮрҺҰӮөӮҪҒBӮұӮМ“ъӮНҒA‘ж1ҸрӮМҠШҚ‘–в‘иӮЙӮВӮўӮДӮіӮзӮЙ“ҘӮЭҚһӮсӮҫҢрҸВӮӘӮИӮіӮкӮҪӮӘ“пҚqӮөӮҪҒB 8ҢҺ14“ъӮМ‘ж3үс–{үпӢcӮЕӮН‘ж2ҸрҒE‘ж3ҸрӮЙӮВӮўӮДҳbӮөҚҮӮнӮкҒA“пҚqӮөӮҪӮаӮМӮМҚЕҸI“IӮЙ‘ГҢӢӮөӮҪҒB15“ъӮМ‘ж4үс–{үпӢcӮЕӮН‘ж4ҸрӮМ–һҸBҠJ•ъ–в‘иӮӘ“ъ–{ҲД’КӮиӮЙҠm’иӮіӮкҒA‘ж5ҸрӮМҠ’‘ҫҠ„Ҹч–в‘иӮН—јҺТ‘О—§ӮМӮЬӮЬҗж‘—ӮиӮіӮкӮҪҒB16“ъӮМ‘ж5үс–{үпӢcӮЕӮН‘ж7ҸрҒE‘ж8ҸрӮӘ“ўӢcӮіӮкҒA‘ж7ҸрӮНҢҙ‘Ҙ“IӮИҒA‘ж8ҸрӮНҠ®‘SӮИҚҮҲУҗ¬—§ӮЙҺҠӮБӮҪҒB 8ҢҺ17“ъӮМ‘ж6үс–{үпӢcҒA18“ъӮМ‘ж7үс–{үпӢcӮЕӮНҸһӢа–в‘иӮр“ўӢcӮөӮҪӮӘҒAҗ¬үКӮӘҸгӮӘӮзӮёҒAҸ¬‘ә‘SҢ ӮМҲЛ—ҠӮЙӮжӮБӮДҒAӮ©ӮЛӮДӮжӮи“n•ДӮө“ъ–{ӮМҚL•сҠOҢрӮр’SӮБӮДӮўӮҪӢаҺqҢҳ‘ҫҳYӮӘғӢҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮЖүпҢ©ӮөӮДҒAӮ»ӮМүҮҸ•ӮрӢҒӮЯӮҪҒBғӢҒ[ғYғxғӢғgӮН8ҢҺ21“ъҒAғjғRғүғC2җўӮ ӮДӮЙ‘PҸҲӮрӢҒӮЯӮйҗe“dӮр‘—ӮБӮҪӮӘҒA23“ъӮМ‘ж8үс–{үпӢcӮМ“ъ–{‘ӨӮ©ӮзӮМ‘ГӢҰҲДӮаҚc’йӮМҲУӮрҺуӮҜӮҪғEғBғbғeӮЙӮжӮБӮДӢ‘җвӮіӮкӮДӮўӮйҒB ғӢҒ[ғYғxғӢғgӮНҚДӮСҲҙҗщӮЙҸжӮиӮҫӮөӮҪӮӘҒAғjғRғүғC2җўӮЙҚuҳaӮрҠ©ӮЯӮй2“x–ЪӮМҗeҸ‘ӮМ•ФҸ‘ӮрҺуӮҜҺжӮБӮҪӮЖӮ«ҒuғҚғVғAӮЙӮНӮЬӮБӮҪӮӯғTғWӮр“ҠӮ°ӮҪҒBҚuҳaүпӢcӮӘҢҲ—фӮөӮҪӮзҒAғүғҖғXғhғӢғtҠO‘ҠӮЖғEғBғbғeӮНҺ©ҺEӮөӮДҗўҠEӮЙӮ»ӮМ”сӮрҳlӮСӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮКҒvӮЖҢыҚrӮӯҢкӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮДӮўӮйҒB8ҢҺ26“ъҢЯ‘OӮМ”й–§үпӢcӮаҢЯҢгӮМ‘ж9үс–{үпӢcӮаҗ¬үКӮИӮӯҸIӮнӮБӮҪҒB ҢрҸВӮӘ“пҚqӮөҒAӮұӮкҲИҸгӮМҸч•аӮН•sүВ”\ӮЖ”»’fӮөӮҪҸ¬‘әӮНҒA’k”»‘ЕӮҝҗШӮиӮМҲУӮр“ъ–{җӯ•{ӮЙ‘Е“dӮөӮҪҒBҗӯ•{ӮНӢЩӢ}ӮЙҢіҳVӮЁӮжӮСҠt—»ӮЙӮжӮйүпӢcӮрҠJӮ«ҒA8ҢҺ28“ъӮМҢд‘OүпӢcӮрҢoӮДҒA—М“yҒEҸһӢаӮМ—vӢҒӮр—ј•ыӮр•ъҠьӮөӮДӮЕӮаҚuҳaӮрҗ¬—§ӮіӮ№ӮйӮЧӮөҒAӮЖүһ“ҡӮөӮҪҒB‘SҢ Һ––ұҸҠӮЙӮўӮҪҗҸҲхӮа“ъ–{Ӯ©Ӯз”hҢӯӮіӮкӮҪ“Б”hӢLҺТӮаӮұӮкӮЙӮНҲк“ҜҸХҢӮӮрҺуӮҜӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮұӮкӮЙ‘OҢгӮөӮДҒAғjғRғүғC2җўӮӘҠ’‘ҫӮМ“м”ј•ӘӮНҠ„ҸчӮөӮДӮаӮжӮўӮЖӮўӮӨҸч•аӮрӮЭӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨҸо•сӮӘ”сҢцҺ®ӮЙ“`ӮҰӮзӮкӮҪӮҪӮЯҒA8ҢҺ29“ъҢЯ‘OӮМ”й–§үпӢcҒAҢЯҢгӮМ‘ж10үс–{үпӢcӮЕӮНҢрҸВӮӘҗi“WӮөҒA“мҠ’‘ҫҠ„ҸчӮЙғҚғVғA‘ӨӮӘ“ҜҲУӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҚuҳaӮӘҺ–ҺАҸгҗ¬—§ӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙҗжӮҫӮҝҒAғEғBғbғeӮНӮ·ӮЕӮЙ“мҠ’‘ҫӮМҠ„ҸчӮЕҚҮҲУӮ·ӮйӮұӮЖӮрҢҲҗSӮөӮДӮўӮҪҒB‘ж10үсүпӢcҸкӮ©Ӯз•КҺәӮЙ–ЯӮБӮҪғEғBғbғeӮНҒu•ҪҳaӮҫҒA“ъ–{ӮН‘S•”Ҹч•аӮөӮҪҒvӮЖӮіӮіӮвӮ«ҒAҗҸҲхӮМ•ш—iӮЖҗЪ•«ӮрҠмӮсӮЕҺуӮҜӮҪӮЖӮўӮнӮкӮДӮўӮйҒBғAғҒғҠғJӮвғҲҒ[ғҚғbғpӮМҗV•·ӮНҒAӮіӮ©ӮсӮЙ“ъ–{ӮӘҒuҗl“№Қ‘үЖҒvӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҸЬҺ^ӮөҒA“ъ–{җӯ•{ӮНҠJҗнӮМ–Ъ“IӮр’BӮөӮҪӮЖӮМӢLҺ–ӮрҢfҚЪӮөӮҪҒBҚc’йғjғRғүғC2җўӮНҒAғEғBғbғeӮМ•сҚҗӮр•·ӮўӮДҚҮҲУӮМҗ¬—§ӮөӮҪ—Ӯ“ъӮМ“ъӢLӮЙҒuҲк“ъ’Ҷ“ӘӮӘӮӯӮзӮӯӮзӮөӮҪҒvӮЖӮ»ӮМ—Һ’_ӮФӮиӮрҸ‘Ӯ«ӢLӮөӮДӮўӮйӮӘҒAҢӢӢЗӮМӮЖӮұӮлҒAғEғBғbғeӮМҢҲ’fӮрҺуӮҜ“ьӮкӮйӮЩӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB9ҢҺ1“ъҒA—јҚ‘ӮМӮ ӮўӮҫӮЕӢxҗнҸр–сӮӘҢӢӮОӮкӮҪҒB ҲИҸгӮМӮжӮӨӮИӢИҗЬӮрҢoӮДҒA1905”N9ҢҺ5“ъ(ҳI—п8ҢҺ23“ъ)ҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢRҚHҸұ“аӮЕ“ъҳIҚuҳaҸр–сӮМ’ІҲуӮӘӮИӮіӮкӮҪҒBғҚғVғAҢR•”ӮЙӮНӢӯӮў•s–һӮӘҺcӮиҒAғҚғVғAӮМҸҹ—ҳӮрҠъ‘ТӮөӮДӮўӮҪ‘еҠШ’йҚ‘ӮМҚc’йҚӮҸ@ӮНҗв–]ӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҚҮҲУ“а—e
ғ|Ғ[ғcғ}ғXүпӢcӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{‘SҢ Ҹ¬‘әҡж‘ҫҳYӮМ‘Ф“xӮНғҚғVғA‘SҢ ғEғBғbғeӮЖ”дҠrӮөӮДӮНӮйӮ©ӮЙ—вҗГӮЕӮ ӮБӮҪӮЖғҚғVғA‘ӨӮМ–T’®ҺТӮӘҠҙ’QӮөӮДӢLӮөӮДӮўӮйҒBӮ·ӮЕӮЙ“ъ–{ӮМҢRҺ–—НӮЖҚаҗӯ—НӮНҢАҠEӮЙ’BӮөӮДӮЁӮиҒAӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮё“ъ–{ӮМҚ‘–Ҝ‘еҸOӮНӮ»ӮМӮұӮЖӮрҸ[•Ә”FҺҜӮөӮДӮўӮИӮўӮЖӮўӮӨҸуӢөӮМӮИӮ©ҒAғҚғVғAӮМ–һҸBҒE’©‘NӮ©ӮзӮМ“P•әӮЖӮўӮӨ“ъ–{ӮӘӮ»ӮаӮ»Ӯа“ъҳIҗн‘ҲӮрӮНӮ¶ӮЯӮҪ–Ъ•WӮрҺАҢ»ӮөҒAҗVӮҪӮИҢ үvӮрҠl“ҫӮөӮДӢӯҚ‘ӮМ’ҮҠФ“ьӮиӮрүКӮҪӮөӮҪҒB ғEғBғbғeӮНҒAғҚғVғAҚ‘“аӮЙҸҸҗнӮМ”s–kӮНҺқӢvҗнӮЙҺқӮҝҚһӮЮӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҺжӮи–ЯӮ·ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЖӮ·Ӯйҗн‘ҲҢp‘ұ”hӮӘ‘¶ҚЭӮ·ӮйӮИӮ©ӮМҢрҸВӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚuҳaүпӢcӮӘҢҲ—фӮөӮҪҸкҚҮӮЙӮНҒAғEғBғbғeӮӘҺёӢrӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮЩӮЪҠФҲбӮўӮИӮўҸуӢөӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚ‘“аӮМҚ¬—җӮаӢЙҢАҸу‘ФӮЕӮ ӮиҒAҠv–Ҫ‘O–йӮЖӮўӮБӮДӮжӮ©ӮБӮҪҒBғEғBғbғeӮНҸ¬‘әҲИҸгӮМӢҮҸуӮЙҗgӮрӮЁӮ«ӮИӮӘӮзҒA“ъ–{ҢRӮӘҗNҚUӮөӮҪҠ’‘ҫ‘S“ҮӮМӮӨӮҝҒA–kҲЬ50“xҲИ“мӮрӮ ӮҪӮҰӮҪӮҫӮҜӮЕ–k•”Ӯ©Ӯз“P‘ЮӮ·Ӯй–с‘©ӮМӮЭӮИӮзӮёҒA”…ҸһӢаҺx•ҘӮўӮрӮЁӮұӮИӮнӮИӮўҺ|ӮМҚҮҲУӮр“ъ–{Ӯ©ӮзҺжӮи•tӮҜӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB Қuҳa“а—eӮМҚңҺqӮНҒAҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ ӮйҒB 1. “ъ–{ӮМ’©‘N”ј“ҮӮЙү—ӮҜӮй—DүzҢ Ӯр”FӮЯӮйҒB 2. “ъҳI—јҚ‘ӮМҢR‘аӮНҒA“S“№Ңx”х‘аӮрҸңӮўӮД–һҸBӮ©Ӯз“P‘ЮӮ·ӮйҒB 3. ғҚғVғAӮНҠ’‘ҫӮМ–kҲЬ50“xҲИ“мӮМ—М“yӮрүiӢvӮЙ“ъ–{ӮЦҸч“nӮ·ӮйҒB 4. ғҚғVғAӮН“Ңҗҙ“S“№ӮМ“аҒA—·ҸҮҒ|’·ҸtҠФӮМ“м–һҸFҺxҗьӮЖҒA•t‘®’nӮМ’YҚzӮМ‘dҺШҢ Ӯр“ъ–{ӮЦҸч“nӮ·ӮйҒB 5. ғҚғVғAӮНҠЦ“ҢҸB(—·ҸҮҒE‘еҳAӮрҠЬӮЮ—Й“Ң”ј“Ү“м’[•”)ӮМ‘dҺШҢ Ӯр“ъ–{ӮЦҸч“nӮ·ӮйҒB 6. ғҚғVғAӮНүҲҠCҸBүҲҠЭӮМӢҷӢЖҢ Ӯр“ъ–{җlӮЙ—^ӮҰӮйҒB “ъ–{ӮН1905”N10ҢҺ10“ъҒAҚuҳaҸр–сӮр”бҸyӮөҒAғҚғVғAӮН10ҢҺ14“ъӮЙ”бҸyӮөӮДӮўӮйҒB Ғ@ |
|
| ҒЎүeӢҝҒ@ | |
|
ҒuӢаӮӘ—~ӮөӮӯӮДҗн‘ҲӮөӮҪ–уӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖӮМҗӯ•{ҲУҢьӮЖӢӨӮЙ”…ҸһӢаӮр•ъҠьӮөӮДҚuҳaӮрҢӢӮсӮҫӮұӮЖӮНҒA“ъ–{ҲИҠOӮМҠeҚ‘ӮЙӮНҚDҲУ“IӮЙҢ}ӮҰӮзӮкҒAҒu•ҪҳaӮрҲӨӮ·ӮйӮӘӮдӮҰӮЙҗ¬ӮіӮкӮҪүp’fҒvӮЖҠ…ҚСӮр‘—ӮБӮҪҠOҚ‘ғҒғfғBғAӮаҸӯӮИӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{Қ‘–ҜӮМ‘ҪӮӯӮНҒAҳAҗнҳAҸҹӮМҢRҺ–“Iҗ¬үКӮЙӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAӮЗӮӨӮөӮД”…ҸһӢаӮр•ъҠьӮ·ӮйӮ©ӮҪӮҝӮЕҚuҳaӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮМӮ©ӮЖ•®ӮБӮҪҒB—L—НҺҶӮЕӮ ӮБӮҪҒw–ң’©•сҒxӮаӮЬӮҪҸ¬‘ә‘SҢ ӮрҒu’ўҠшӮрҲИӮДҢ}ӮҰӮжҒvӮЖӮ·ӮйҺРҗаӮрҢfҚЪӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮаӮөҗн‘ҲҢp‘ұӮӘҢRҺ–“IӮИӮўӮөҚаҗӯ“IӮЙ“ъ–{ӮМ•үүЧӮр’ҙӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮрҢцӮЙ”ӯ•\Ӯ·ӮкӮОҒAӮ»ӮкӮНғҚғVғAӮМҗн‘ҲҢp‘ұ”hӮМ”ӯҢҫ—НӮрҚӮӮЯӮДҗн‘ҲӮМ’·Ҡъү»Ӯр‘ЈӮөҒAӮ©ӮҰӮБӮДҚuҳaӮМҗ¬—§ӮрҠлӮӨӮӯӮ·Ӯй•|ӮкӮӘӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒAҗӯ•{ӮНҺАҸоӮрҗіҠmӮЙҚ‘–ҜӮЙ“`ӮҰӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB
“ъ–{җӯ•{ӮЖӮөӮДӮНҒAӮұӮМӮжӮӨӮИ‘еӮ«ӮИғfғBғҢғ“ғ}ӮрӮ©Ӯ©ӮҰӮДӮўӮҪӮӘҒAүКӮҪӮөӮДҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaҸр–с’чҢӢӮМ9ҢҺ5“ъҒA“ҢӢһӮМ“ъ”д’JҢцүҖӮЕҸ¬‘әҠOҢрӮр’eҠNӮ·ӮйҚ‘–Ҝ‘еүпӮӘҠJӮ©ӮкҒAӮұӮкӮрүрҺUӮіӮ№ӮжӮӨӮЖӮ·ӮйҢxҠҜ‘аӮЖҸХ“ЛӮөҒAӮіӮзӮЙҗ”–ңӮМ‘еҸOӮӘҺс‘ҠҠҜ“@ӮИӮЗӮЙүҹӮөӮ©ӮҜӮДҒAҗӯ•{ҚӮҠҜӮМ“@‘оҒAҗӯ•{ҢnӮЖ–ЪӮіӮкӮҪҚ‘–ҜҗV•·ҺРӮрҸPҢӮҒAҢр”ФӮв“dҺФӮрҸДӮ«‘ЕӮҝӮ·ӮйӮИӮЗӮМ–\“®ӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪ(“ъ”д’JҸД‘ЕҺ–ҢҸ)ҒBҢQҸOӮМ“{ӮиӮНҒAҚuҳaӮрҲҙҗщӮөӮҪғAғҒғҠғJӮЙӮаҢьӮҜӮзӮкҒA“ҢӢһӮМ•ДҚ‘ҢцҺgҠЩӮМӮЩӮ©ҒAғAғҒғҠғJҗl–qҺtӮМ“ӯӮӯғLғҠғXғgӢіүпӮЬӮЕӮаҸPҢӮӮМ‘ОҸЫӮЖӮИӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAҗӯ•{ӮНүъҢө—ЯӮрӮөӮ«ҢR‘аӮрҸo“®ӮіӮ№ӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪ‘ӣҸпӮНҒAҗн‘ҲӮЙӮжӮй‘№ҠQӮЖҗ¶ҠҲӢкӮЙ‘ОӮ·ӮйҸҺ–ҜӮМ•s–һӮМӮ ӮзӮнӮкӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҚuҳa”Ҫ‘Оү^“®ӮН‘SҚ‘ү»ӮөҒA”Л”ҙҗӯ•{”б”»ӮЖҢӢӮСӮВӮўӮДҒA—Ӯ1906”N(–ҫҺЎ39”N)ҒAҢj“аҠt(‘ж1Һҹ)ӮН‘ЮҗwӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪҒB җҙҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒA1905”N12ҢҺҒA–һҸB‘PҢгҸр–сӮӘ–kӢһӮЙӮЁӮўӮДҢӢӮОӮкҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӮЙӮжӮБӮДғҚғVғAӮ©Ӯз“ъ–{ӮЙҸч“nӮіӮкӮҪ–һҸB—ҳҢ ӮМҲЪ“®ӮрҗҙҚ‘ӮӘ—№ҸіӮөҒAүБӮҰӮДҗVӮҪӮИ—ҳҢ ӮӘ“ъ–{ӮЙ‘ОӮө•t—^ӮіӮкӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA“м–һҸF“S“№ӮМӢg—СӮЬӮЕӮМү„җLӮЁӮжӮС“Ҝ“S“№Һз”хӮМӮҪӮЯӮМ“ъ–{ҢRҸн’“Ң ӮИӮўӮөүҲҗьҚzҺRӮМҚМҢ@Ң ӮМ•ЫҸбҒAӮЬӮҪҒA“Ҝ“S“№ӮЙ•№ҚsӮ·Ӯй“S“№ҢҡҗЭӮМӢЦҺ~ҒAҲА•т“S“№ӮМҺg—pҢ Ңp‘ұӮЖ“ъҗҙ—јҚ‘ӮМӢӨ“ҜҺ–ӢЖү»ҒAүcҢыҒEҲА“ҢӮЁӮжӮС•т“VӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{җlӢҸ—Ҝ’nӮМҗЭ’uҒAӮіӮзӮЙҒAҠӣ—ОҚ]үEҠЭӮМҗX—С”°ҚМҚҮ•ЩҢ Ҡl“ҫӮИӮЗӮЕӮ ӮиҒAӮұӮкӮзӮНӮўӮёӮкӮаҗнҢгӮМ–һҸFҢoүcӮрҗiӮЯӮйҠо‘bӮЖӮИӮиҒA“ъ–{ӮМ‘е—ӨҗiҸoӮНҲИҢгӮўӮБӮ»ӮӨ–{Ҡiү»ӮөӮҪҒB ‘еҠШ’йҚ‘ӮЙҠЦӮөӮДӮНҒA7ҢҺӮМҢjҒEғ^ғtғgӢҰ’иӮЕғAғҒғҠғJӮЙҒA8ҢҺӮМ‘ж“сҺҹ“ъүp“Ҝ–ҝҸр–сӮЕғCғMғҠғXӮЙҒAӮіӮзӮЙӮұӮМҸр–сӮЕӮНғҚғVғAӮЙ‘ОӮөӮДӮаҒA“ъ–{ӮМҠШҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй”r‘ј“I—DҗжҢ ӮӘ”FӮЯӮзӮкҒA11ҢҺӮМ‘ж“сҺҹ“ъҠШӢҰ–сӮЙӮжӮБӮДҠШҚ‘ӮНҠOҢрҢ ӮрҺёӮБӮҪҒB12ҢҺҒAҺс“sҠҝҸйӮЙ“қҠД•{ӮӘ’uӮ©ӮкҒAҠШҚ‘Ӯр“ъ–{ӮМ•ЫҢмҚ‘ӮЖӮөӮҪҒB“ъ–{ӮНӢӯҚ‘ғҚғVғAӮЙӮжӮӨӮвӮӯҸҹ—ҳӮөҒAҗўҠEӮМҒuҲк“ҷҚ‘ҒvӮМ’ҮҠФ“ьӮиӮрүКӮҪӮөӮҪӮӘҒAӮўӮБӮЫӮӨҚ‘–ҜӮМӮ ӮўӮҫӮЕӮНҸ]—ҲӮМҚ‘үЖ“IӮИ–Ъ•WӮӘҢ©ҺёӮнӮкҒAҚ‘–ҜӮМғRғ“ғZғ“ғTғXӮН•цүуӮМ—l‘ҠӮр’жӮөӮҪҒB ғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғxғӢғg•Д‘е“қ—МӮНҒAӮұӮМҸр–сӮр’ҮүоӮөӮҪҢчҗСӮӘ•]үҝӮіӮкӮДҒA1906”NӮЙғmҒ[ғxғӢ•ҪҳaҸЬӮрҺуҸЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAӮұӮМҸр–сӮМӮМӮҝғAғҒғҠғJӮНӢЙ“Ң’nҲжӮЦӮМ”ӯҢҫҢ ӮЖҠЦ—^ӮрӮөӮҫӮўӮЙӢӯӮЯӮДӮўӮБӮҪҒBғӢҒ[ғYғxғӢғgӮМҲУ—~“IӮИ’ҮүоҚHҚмӮЙӮжӮБӮДҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮНҚ‘ҚЫҺРүпӮЙӮЁӮҜӮйҒuғAғҒғҠғJӮМҗўӢIҒvӮЦӮМ‘жҲк•аӮЖӮИӮБӮҪӮЖӮўӮӨ•]үҝӮаӮ ӮйҒBӮҫӮӘҸгӢLӮМӮжӮӨӮИ–\“®ҒEҚuҳa”Ҫ‘Оү^“®ӮӘ“ъ–{Қ‘“аӮЕӢNӮұӮБӮҪӮұӮЖӮНҒA“ъ–{җӯ•{ӮӘҺқӮБӮДӮўӮҪҗн‘ҲҲУҗ}ӮЦӮМ•sҗMҠҙӮрҗAӮҰӮВӮҜӮйҢӢүКӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB ғҚғVғAӮЕӮНҒAҚc’йӮМҗкҗ§Һx”zӮЙ‘ОӮ·Ӯй•s–һӮӘҺРүпӮр•ўӮўҒA10ҢҺӮЙ“ьӮйӮЖғCғ“ғtғҢҒ[ғVғҮғ“ӮЙ‘ОӮ·ӮйҚ‘–ҜӮМ•s–һӮНҲкӢ“ӮЙ”ҡ”ӯӮөӮДғ[ғlғXғg(ғ[ғlғүғӢҒEғXғgғүғCғL)ӮМ—l‘ҠӮр’жӮөӮҪҒBҚuҳaүпӢcӮМғҚғVғA‘SҢ ӮЕӮ ӮБӮҪғZғӢғQғCҒEғEғBғbғeӮНғAғҢғNғZғCҒEғIғ{ғҢғ“ғXғLҒ[ӮЖӢӨ“ҜӮөӮДҚ¬—җҺыҸEӮМӮҪӮЯӮЙҸ\ҢҺҸЩҸ‘ӮрӢN‘җҒAҚc’йғjғRғүғC2җўӮНӮ»ӮкӮЙҸҗ–јӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮИӮЁӮағҚғVғA‘жҲкҠv–ҪӮЙӮЖӮаӮИӮӨҚ¬—җӮН1907”NӮЬӮЕӮВӮГӮўӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ•вҗа
ҒЎ—рҺjҲвҺYӮЖӮөӮДӮМғ|Ғ[ғcғ}ғX •ДҚ‘“аӮЕӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮЙӮ©Ӯ©ӮнӮй—рҺjҲвҺYӮМ•Ы‘SҠҲ“®ӮӘҗiӮЯӮзӮкӮДӮўӮйҒB “ъ–{‘SҢ ӮӘҸhҺЙӮЖӮөӮҪғEғFғ“ғgғҸҒ[ғX—ХҠCғzғeғӢӮН1981”NӮЙ•ВҚҪӮіӮкӮҪӮЬӮЬӮЖӮИӮБӮДӮЁӮиҒAҳVӢҖү»ӮӘ’ҳӮөӮӯҒAүJҳRӮиӮвҸқӮЭӮаӮРӮЗӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒAғ|Ғ[ғcғ}ғX“ъ•ДӢҰүпӮӘ‘ӢҢыӮЖӮИӮБӮДҒuғEғFғ“ғgғҸҒ[ғX—FӮМүпҒvӮӘҗЭ—§ӮіӮкҒAғzғeғӢӮМҚДҢҡҢvүжӮӘ—§ӮДӮзӮкҒA•ңҢіҚмӢЖӮӘӮИӮіӮкӮҪҒB ҢцҺ®үпҸкӮЖӮИӮБӮҪғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢRҚHҸұӮЕӮНҒA1994”N3ҢҺҒAүпӢc“–ҺһӮМҺКҗ^ӮвҺ‘—ҝӮр“WҺҰӮ·ӮйҸнҗЭӮМҒuғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӢL”OҠЩҒvӮӘҠJҗЭӮіӮкӮҪҒB2005”NҒAҳVӢҖү»ӮМӮҪӮЯҠCҢRҚHҸұӮр•ВҚҪӮ·ӮйӮЖӮМҗӯ•{ҢҲ’иӮӘ”ӯ•\ӮіӮкӮҪӮӘҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕӮНӮ»ӮкӮЙ‘ОӮ·Ӯй”Ҫ‘Оү^“®ӮӘӢNӮұӮиҒAӮ»ӮМҢӢүКҒA•ВҚҪӮН“PүсӮіӮкӮДӮўӮйҒB ӮЬӮҪҒAҢ»’nӮЕӮНҒA“ъ•ДҳI3Қ‘ӮМҗк–еүЖӮЙӮжӮйҒuғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaҸр–сғtғHҒ[ғүғҖҒvӮӘҠф“xӮ©ҠJҚГӮіӮкӮДӮЁӮиҒA2010”NӮЙӮНғjғ…Ғ[ғnғ“ғvғVғғҒ[ҸBӮЕ9ҢҺ5“ъӮрҸBӮМӢL”O“ъӮЙӮ·ӮйҸр—бӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒB ҒЎғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘ҺQҗнӮЙӮВӮўӮД ғӮғ“ғeғlғOғҚҢцҚ‘ӮН“ъҳIҗн‘ҲӮЙҚЫӮөӮДғҚғVғA‘ӨӮЙ—§ӮҝҒA“ъ–{ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗн•zҚҗӮөӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘӮ ӮйҒBӮұӮкӮЙӮВӮўӮДӮНҒA2006”N(•Ҫҗ¬18”N)2ҢҺ14“ъӮЙ—й–ШҸ@’jӢcҲхӮӘҒAҒuҲкӢгҒZҺl”NӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮӘ“ъ–{ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮНӮ ӮйӮ©ҒBғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮМ‘г•\ӮНҸөӮ©ӮкӮҪӮ©ҒB“ъ–{ӮЖғӮғ“ғeғlғOғҚүӨҚ‘ӮМҗн‘ҲҸу‘ФӮНӮЗӮМӮжӮӨӮИҺи‘ұӮ«ӮрӮЖӮБӮДҸI—№ӮөӮҪӮ©ҒvӮЖӮМ“а—eӮМҺҝ–вҺеҲУҸ‘Ӯр’сҸoҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{җӯ•{ӮНҒAҒuҗӯ•{ӮЖӮөӮДӮНҒAҗзӢг•SҺl”NӮЙғӮғ“ғeғlғOғҚҚ‘ӮӘүдӮӘҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮҪӮұӮЖӮрҺҰӮ·ҚӘӢ’ӮӘӮ ӮйӮЖӮНҸі’mӮөӮДӮўӮИӮўҒBғӮғ“ғeғlғOғҚҚ‘ӮМ‘SҢ ҲПҲхӮНҒAҢдҺw“EӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЙӮЁӮўӮДҚsӮнӮкӮҪҚuҳaүпӢcӮЙҺQүБӮөӮДӮўӮИӮўҒvӮЖӮМ“ҡ•ЩҸ‘ӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB ғҚғVғAӮМҢц•¶Ҹ‘Ӯр’ІҚёӮөӮҪӮЖӮұӮлҒAғҚғVғA’йҚ‘ӮӘғӮғ“ғeғlғOғҚӮМҺQҗн‘ЕҗfӮр’fӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЖӮИӮиҒA“Ж—§ӮөӮДӮаҗн‘ҲҸу‘ФӮЙӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮӘҠm”FӮіӮкӮҪҒB Ғ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ2 | |
|
–ҫҺЎ37”N(1904”N)2ҢҺӮМҠJҗнӮ©Ӯз—Ӯ–ҫҺЎ38”N(1905”N)8ҢҺӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮЬӮЕӮМ18ғ–ҢҺӮЙӮнӮҪӮиҒA“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮЖӮМҠФӮЕҗнӮнӮкӮҪҗн‘ҲӮрҢҫӮўӮЬӮ·ҒB
–ҫҺЎ37”N(1904”N)2ҢҺ4“ъӮЙӢЩӢ}Ңд‘OүпӢcӮЙӮЁӮўӮДғҚғVғAӮЖӮМҚ‘Ңр’fҗвӮЖҠJҗнӮЖӮрҢҲ’иӮөӮҪ“ъ–{ӮНҒA8“ъӮЙӮНғҚғVғAҠН‘аӮЖҸүӮЯӮДҢрҗнӮрҚsӮўӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒA9“ъӮЙӮН ҒuҳIҚ‘ӮЙ‘ОӮ·ӮйҗйҗнӮМҸЩ’әҒv ӮӘҸoӮіӮкҒAғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮӘ–{Ҡi“IӮЙҠJҺnӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB ӮИӮЁҒAҒuҸЩ’әҒvӮЖӮНҒA“VҚcӮӘҲУҺuӮр•\ҺҰӮ·Ӯ镶Ҹ‘ӮМӮұӮЖӮрҺwӮөӮЬӮ·ҒB җн‘ҲӮӘ’·ҲшӮӯӮЖҒA“ъ–{ӮНҢRҺ–“IӮЙӮНҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮДӮўӮҪӮаӮМӮМҚ‘—НӮН’ҳӮөӮӯҸБ–ХӮөҒAӮЬӮҪҲк•ыӮМғҚғVғAӮЕӮаҚ‘“аӮЕҠv–ҪӮӘӮЁӮұӮиҒA—јҚ‘ӮЖӮаӮЙҗн‘ҲӮМҢp‘ұӮӘҚў“пӮИҸуӢөӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕҒAғAғҒғҠғJӮМғZғIғhғAҒEғҚҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮМҲҙҗщӮЙӮжӮиғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcӮӘҠJӮ©ӮкӮЬӮөӮҪҒB 1Ӯ©ҢҺӮЙӢyӮФҢрҸВӮМҢӢүКҒA–ҫҺЎ38”N(1905”N)9ҢҺ5“ъҒA“ъҳIҚuҳaҸр–сӮӘҸҗ–јӮіӮкҒA10ҢҺ16“ъӮЙ”бҸyӮөҒA11ҢҺ25“ъғҸғVғ“ғgғ“ӮЙӮЁӮўӮД”бҸyҸ‘ӮӘҢрҠ·ӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB ҒuҳIҚ‘ӮЖӮМҚuҳaӮЙҠЦӮ·ӮйҸЩ’әҒv ӮНҒA“ъҳIҚuҳaҸр–с’чҢӢӮЙӮВӮўӮДӮМ“VҚcӮ©ӮзӮМҸЩ’әӮЕӮ·ҒB ––”цӮЙӮ ӮйҒuҢд–јҢдҺЈҒv(Ӯ¬ӮеӮЯӮўӮ¬ӮеӮ¶)ӮЖӮНҒAҒuҢд–јҒvӮӘ“VҚcӮЙӮжӮйҸҗ–јҒAҒuҢдҺЈҒvӮӘ“VҚcӮМҲуҠУӮрӮ»ӮкӮјӮкҲУ–ЎӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҢҙҺ‘—ҝӮМ––”цӮЕҒA’ј•MӮМҸҗ–јӮЖҲуҠУӮрҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB Ғu“ъҳIҚuҳaҸр–с”бҸyӮЙҠЦӮ·Ӯйҗ•–§ү@үпӢc•MӢLҳ^Ғv ӮЙӮНҒA–ҫҺЎ38”N10ҢҺ4“ъҒA–ҫҺЎ“VҚc—ХҗИӮМүәӮЕҠJӮ©ӮкӮҪ“ъҳIҚuҳaҸр–с”бҸyҲДҢҸӮЙҠЦӮ·Ӯйҗ•–§ү@үпӢcӮЙӮЁӮҜӮйҲЙ“Ў”Һ•¶Ӣc’·ӮМ•сҚҗӮӘҠЬӮЬӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҲЙ“ЎӮМ•сҚҗӮЙӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҲУӢ`ӮЖғҚғVғAӮЖӮМҚuҳaҸр–сӮр’чҢӢӮ·ӮйӮЙҚЫӮөӮДӮМ“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМҚlӮҰ•ыӮӘӮжӮӯҢ»ӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҲЙ“Ў”Һ•¶ӮНҒAҚuҳaҸр–сӮМ”бҸyӮМҗҘ”сӮр”»’fӮ·ӮйӮЙҚЫӮөӮДӮНҗўҳ_ӮвҸOӢcү@ӮЖӮНҲкҗьӮрүжӮөҒAғҚғVғAӮМҢpҗн”\—НӮвҗўҠEӮМҸуӢөӮИӮЗҠJҗнҲИ—ҲӮМӮ·ӮЧӮДӮМҸуӢөӮЙҸЖӮзӮөӮД”»’fӮ·ӮйӮжӮӨҲПҲхӮЙ‘ЈӮөҒA”бҸyҲДҢҸӮН‘SүпҲк’vӮЕүВҢҲӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҒuҳIҚ‘ӮЙ‘ОӮ·ӮйҗйҗнӮМҸЩ’әҒv
“V—CӮр•Ы—LӮө–ңҗўҲкҢnӮМҚcвNӮр‘HӮЯӮй‘е“ъ–{Қ‘Қc’йӮН’үҺА—E•җӮИӮй“р—LҸOӮЙҺҰӮ·ҒB “VӮМҸ•ӮҜӮЙӮжӮБӮДҗж‘c‘гҒXҚcҲКӮрҢpҸіӮөӮДӮ«ӮҪүЖҢnӮЙ‘®Ӯ·Ӯй‘е“ъ–{Қ‘ӮМҚc’йӮНҒA’үҺАӮЙӮөӮД—EҠёӮИ“рӮзҚ‘–ҜӮЙҲИүәӮМӮұӮЖӮр’mӮзӮ№ӮйҒB ’ҪдўӮЙҳIҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҗнӮрҗйӮ·ҒB’ҪӮ©—ӨҠCҢRӮНӢXӮӯ‘S—НӮрӢЙӮЯӮДҳIҚ‘ӮЖҢрҗнӮМҺ–ӮЙҸ]ӮУӮЦӮӯ’ҪӮ©•S—»—LҺiӮНӢXӮӯҠeҒX‘ҙӮМҗE–ұӮЙ—ҰӮР‘ҙӮМҢ ”\ӮЙүһӮөӮДҚ‘үЖӮМ–Ъ“IӮр’BӮ·ӮйӮЙ“w—НӮ·ӮЦӮөҒB–}Ӯ»Қ‘ҚЫҸрӢKӮМ”НҲНӮЙү—ӮДҲкҗШӮМҺи’iӮрҗsӮөҲвҺZӮИӮ©ӮзӮЮӮұӮЖӮрҠъӮ№ӮжҒB ’ҪӮНӮұӮМ•¶Ҹ‘ӮЕҒAғҚғVғAӮЙ‘ОӮ·Ӯйҗн‘ҲӮрҚsӮӨӮұӮЖӮр•zҚҗӮ·ӮйҒB’ҪӮМ—ӨҢRӮЖҠCҢRӮНҒAӮәӮРӮЖӮа‘S—НӮрӮВӮӯӮөӮДғҚғVғAӮЖҗнӮБӮДӮЩӮөӮўҒBӮЬӮҪ’ҪӮМӮ·ӮЧӮДӮМ•”үәӮзӮНҒAӮ»ӮкӮјӮкӮМҗE–ұӮвҢ ҢАӮЙүһӮ¶ӮДҚ‘үЖӮМ–Ъ“IӮӘ’Bҗ¬ӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙ“w—НӮөӮДӮЩӮөӮўҒBҚ‘ҚЫ“IӮИҸр–сӮвӢK”НӮМ”НҲНӮЕҒAӮ ӮзӮдӮйҺи’iӮрӮВӮӯӮөӮДҢлӮҝӮМӮИӮўӮжӮӨӮЙҗSӮӘӮҜӮжҒB ҲТӮУӮЙ•¶–ҫӮр•ҪҳaӮЙӢҒӮЯ—сҚ‘ӮЖ—FӢbӮр“ДӮӯӮөӮДҲИӮД“Ң—mӮМҺЎҲАӮрүiү“ӮЙҲЫҺқӮөҠeҚ‘ӮМҢ —ҳ—ҳүvӮр‘№ҸқӮ№Ӯ·ӮөӮДүiӮӯ’йҚ‘ӮМҲА‘SӮрҸ«—ҲӮЙ•ЫҸбӮ·ӮЦӮ«Һ–‘ФӮрҠm—§Ӯ·ӮйӮН’ҪҸgӮЙҲИӮДҚ‘ҢрӮМ—vӢ`ӮЖҲЧӮө’U•йҠёӮДҲбӮНӮіӮзӮЮӮұӮЖӮрҠъӮ·ҒB’ҪӮ©—LҺiӮа–’”\Ӯӯ’ҪӮ©ҲУӮр‘МӮөӮДҺ–ӮЙҸ]ӮР—сҚ‘ӮЖӮМҠЦҢW”NӮр’ҖӮУӮДүvҒXҗeҢъӮЙ•ӢӮӯӮрҢ©ӮйҒBҚЎ•sҚKӮЙӮөӮДҳIҚ‘ӮЖзХ’[ӮрҠJӮӯӮЙҺҠӮйжҜ’ҪӮ©ҺuӮИӮзӮЮӮвҒB ’ҪӮМҚlӮҰӮНҒA•¶–ҫӮр•Ҫҳa“IӮИӮвӮиӮ©ӮҪӮЕ”ӯ“WӮіӮ№ҒAҸ”ҠOҚ‘ӮЖӮМ—FҚDҠЦҢWӮр‘ЈҗiӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAғAғWғAӮМҲА’иӮрүiү“ӮЙҲЫҺқӮөҒAӮЬӮҪҒAҠeҚ‘ӮМҢ —ҳӮв—ҳүvӮр‘№ӮИӮнӮИӮўӮжӮӨӮЙӮөӮИӮӘӮзҒA––үiӮӯ“ъ–{’йҚ‘ӮМҸ«—ҲӮМҲА‘SӮӘ•ЫҸбӮіӮкӮйӮжӮӨӮИҸуӢөӮрҠm—§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮ ӮйҒBӮұӮкӮН’ҪӮӘ‘јҚ‘ӮЖҢрҸВӮ·ӮйҚЫӮЙҚЕӮаҸdҺӢӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘӮзӮЕҒAҸнӮЙӮұӮӨӮөӮҪҚlӮҰӮЙҲб”ҪӮөӮИӮўӮжӮӨҗSӮӘӮҜӮДӮ«ӮҪҒB’ҪӮМ•”үәӮзӮаҒAӮұӮӨӮөӮҪ’ҪӮМҲУҺvӮЙҸ]ӮБӮДӮіӮЬӮҙӮЬӮИҺ–•ҝӮрҸҲ—қӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮЕҒAҠOҚ‘ӮЖӮМҠЦҢWӮН”NӮӘӮҪӮВӮЙӮВӮкӮДӮЬӮ·ӮЬӮ·ҢъӮўҗeҢрӮрҢӢӮФӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒBҚЎҒA•sҚKӮИӮұӮЖӮЙғҚғVғAӮЖҗнӮӨҺ–ӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮНҢҲӮөӮД’ҪӮМҲУҺuӮЕӮНӮИӮўҒB ’йҚ‘ӮМҸdӮрҠШҚ‘ӮМ•Ы‘SӮЙ’uӮӯӮвҲк“ъӮМҢМӮЙ”сӮ·ҒBҗҘӮк—јҚ‘—ЭҗўӮМҠЦҢWӮЙҲцӮйӮМӮЭӮИӮзӮ·ҠШҚ‘ӮМ‘¶–SӮНҺАӮЙ’йҚ‘ҲАҠлӮМҢqӮйҸҠӮҪӮкӮНӮИӮиҒB‘RӮйӮЙҳIҚ‘ӮН‘ҙӮМҗҙҚ‘ӮЖӮМ–ҫ–сӢy—сҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй—ЭҺҹӮМҗйҢҫӮЙҚSӮНӮзӮ·ҲЛ‘R–һҸFӮЙҗиӢ’ӮөүvҒX‘ҙӮМ’n•аӮриЭҢЕӮЙӮөӮДҸIӮЙ”VӮ𕹓ЫӮ№ӮЮӮЖӮ·ҒB “ъ–{’йҚ‘ӮӘҠШҚ‘ӮМ•Ы‘SӮрҸdҺӢӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮНҒAҚр“ъҚЎ“ъӮМҳbӮЕӮНӮИӮўҒBүдӮӘҚ‘ӮЖҠШҚ‘ӮНүҪҗў‘гӮЙӮаӮнӮҪӮБӮДҠЦӮнӮиӮрӮаӮБӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҠШҚ‘ӮМ‘¶–SӮН“ъ–{’йҚ‘ӮМҲА‘S•ЫҸбӮЙ’јҗЪҠЦҢWӮ·ӮйӮ©ӮзӮЕӮаӮ ӮйҒBӮЖӮұӮлӮӘҒAғҚғVғAӮНҒAҗҙҚ‘ӮЖ’чҢӢӮөӮҪҸр–сӮвҸ”ҠOҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДүҪ“xӮаҚsӮБӮДӮ«ӮҪҗйҢҫӮЙ”ҪӮөӮДҒAҚЎӮҫӮЙ–һҸBӮрҗиӢ’ӮөӮДӮЁӮиҒA–һҸBӮЙӮЁӮҜӮйғҚғVғAӮМҢ —НӮр’…ҺАӮЙӢӯү»ӮөҒAҚЕҸI“IӮЙӮНӮұӮМ“y’nӮр—М—LӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйҒB ҺбӮө–һҸFӮЙӮөӮДҳIҚ‘ӮМ—М—LӮЙӢAӮ№ӮсҢБҠШҚ‘ӮМ•Ы‘SӮНҺxҺқӮ·ӮйӮЙ—RӮИӮӯӢЙ“ҢӮМ•Ҫҳa–’‘fӮжӮи–]ӮЮӮЦӮ©ӮзӮ·ҒBҢМӮЙ’ҪӮНҚҹӮМӢ@ӮЙҚЫӮөҗШӮЙ‘ГӢҰӮЙ—RӮДҺһӢЗӮрүрҢҲӮөҲИӮД•ҪҳaӮрҚPӢvӮЙҲЫҺқӮ№ӮЮӮұӮЖӮрҠъӮө—LҺiӮрӮөӮДҳIҚ‘ӮЙ’сӢcӮө”јҚОӮМӢvӮөӮ«ӮЙҳiӮиӮДҺЖҺҹҗЬҸХӮрҸdӮЛӮөӮЯӮҪӮйӮаҳIҚ‘ӮНҲкӮаҢрҸчӮМҗёҗ_ӮрҲИӮД”VӮрҢ}ӮЦӮ·ҒB үјӮЙ–һҸBӮӘғҚғVғA—МӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮҰӮОҒAүдӮӘҚ‘ӮӘҠШҚ‘ӮМ•Ы‘SӮрҺxүҮӮөӮҪӮЖӮөӮДӮаҲУ–ЎӮӘӮИӮӯӮИӮйӮОӮ©ӮиӮ©ҒA“ҢғAғWғAӮЙӮЁӮҜӮй•ҪҳaӮНӮ»ӮаӮ»ӮаҠъ‘ТӮЕӮ«ӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBҸ]ӮБӮДҒA’ҪӮНӮұӮӨӮөӮҪҺ–‘ФӮЙҚЫӮөӮДҒAүҪӮЖӮ©‘ГӢҰӮөӮИӮӘӮзҺһҗЁӮМӮИӮиӮдӮ«ӮрүрҢҲӮөҒA•ҪҳaӮр––үiӮӯҲЫҺқӮөӮҪӮўӮЖӮМҢҲҲУӮ©ӮзҒA•”үәӮрӮЁӮӯӮБӮДғҚғVғAӮЖӢҰӢcӮіӮ№ҒA”ј”NӮМҠФӮӯӮиӮ©ӮҰӮөҢрҸВӮрҸdӮЛӮДӮ«ӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘҒAғҚғVғAӮМҢрҸВӮМ‘Ф“xӮЙӮНҸчӮиҚҮӮўӮМҗёҗ_ӮНӮЬӮБӮҪӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB һD“ъ–нӢv(ӮұӮӨӮ¶ӮВӮСӮ«ӮгӮӨ)“k(ӮўӮҪӮёӮз)ӮЙҺһӢЗӮМүрҢҲӮр‘Jү„Ӯ№ӮөӮЯ—zӮЙ•ҪҳaӮрҸҘ“№ӮөүAӮЙҠC—ӨӮМҢR”хӮр‘қ‘еӮөҲИӮДүдӮрӢьҸ]Ӯ№ӮөӮЯӮЮӮЖӮ·ҒB–}Ӯ»ҳIҚ‘Ӯ©ҺnӮжӮи•ҪҳaӮрҚDҲӨӮ·ӮйӮМҗҪҲУӮИӮйӮаӮМҹ|Ӯа”FӮЮӮйӮЙ—RӮИӮөҒBҳIҚ‘ӮНҠщӮЙ’йҚ‘ӮМ’сӢcӮр—eӮкӮ·ҠШҚ‘ӮМҲА‘SӮН•ыӮЙҠлӢ}ӮЙ•mӮө’йҚ‘ӮМҚ‘—ҳӮНҸ«ӮЙҗN”—Ӯ№ӮзӮкӮЮӮЖӮ·ҒB ӮҪӮҫӮўӮҪӮёӮзӮЙҺһҠФӮрӢу”пӮөӮД–в‘иӮМүрҢҲӮрҗжү„ӮОӮөӮЙӮөҒA•\ӮЕ•ҪҳaӮрҸҘӮҰӮИӮӘӮзҒAүAӮЕӮН—ӨҠCӮМҢR”хӮр‘қӢӯӮөӮДҒAүдӮӘҚ‘ӮрӢь•һӮіӮ№ӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒBӮ»ӮаӮ»ӮағҚғVғAӮЙӮНҒAҺnӮЯӮ©Ӯз•ҪҳaӮрҲӨӮ·ӮйҗҪҲУӮӘҸӯӮөӮаӮЭӮзӮкӮИӮўҒBғҚғVғAӮНӮұӮМҺһ“_ӮЙӮИӮБӮДӮа“ъ–{’йҚ‘ӮМ’сҲДӮЙүһӮ¶ӮёҒAҠШҚ‘ӮМҲА‘SӮНҚЎӮЬӮіӮЙҠлҢҜӮЙӮіӮзӮіӮкҒA“ъ–{’йҚ‘ӮМҚ‘үvӮНӢәӮ©ӮіӮкӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйҒB Һ–ҠщӮЙдўӮЙҺҠӮйҒB’йҚ‘Ӯ©•ҪҳaӮМҢрҸВӮЙҲЛӮиӢҒӮЯӮЮӮЖӮөӮҪӮйҸ«—ҲӮМ•ЫҸбӮНҚЎ“ъ”VӮрҠшҢЫӮМҠФӮЙӢҒӮЮӮйӮМҠOӮИӮөҒB’ҪӮН“р—LҸOӮМ’үҺА—E•җӮИӮйӮЙҳЯ—ҠӮө‘¬ӮЙ•ҪҳaӮрүiү“ӮЙҚҺ•ңӮөҲИӮД’йҚ‘ӮМҢхүhӮр•Ы‘SӮ№ӮЮӮұӮЖӮрҠъӮ·ҒB Һ–‘ФӮНҒAҠщӮЙӮұӮұӮЬӮЕҲ«ү»ӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{’йҚ‘ӮН•Ҫҳa“IӮИҢрҸВӮЙӮжӮБӮДҸ«—ҲӮМҲА‘S•ЫҸбӮр“ҫӮжӮӨӮөӮҪӮӘҒAҚЎӮЖӮИӮБӮДӮНҢRҺ–ӮЙӮжӮБӮДӮұӮкӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўҒB’ҪӮНҒA“рӮзҚ‘–ҜӮӘ’үҺАӮЙӮөӮД—EҠёӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр—ҠӮЭӮЖӮөӮДҒA‘¬ӮвӮ©ӮЙүiӢv“IӮИ•ҪҳaӮрүс•ңӮөҒA“ъ–{’йҚ‘ӮМүhҢхӮрҠmӮҪӮйӮаӮМӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮрҠъ‘ТӮ·ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҒuҳIҚ‘ӮЖӮМҚuҳaӮЙҠЦӮ·ӮйҸЩ’әҒv
’Ҫ“Ң—mӮМҺЎ•ҪӮрҲЫҺқӮө’йҚ‘ӮМҲА‘SӮр•ЫҸбӮ·ӮйӮрҲИӮДҚ‘ҢрӮМ—vӢ`ӮЖҲЧӮөҸg–йңжӮзӮ·ҒBҲИӮДҚc—QӮрҢхҢ°Ӯ·ӮйҸҠҲИӮр”OӮУҒB•sҚKӢqҚОҳIҚ‘ӮЖзХ’[ӮрҢ[ӮӯӮЙҺҠӮйҒB–’ӣҶӮЙҚ‘үЖҺ©үqӮМ•K—vӣЯӮЮӮр“ҫӮіӮйӮЙҸoӮҪӮиҒB ’ҪӮНҒAғAғWғAӮМ•ҪҳaӮрҲЫҺқӮөӮД“ъ–{’йҚ‘ӮМҲА‘SӮр•ЫҸбӮ·ӮйӮұӮЖӮр‘јҚ‘ӮЖӮМҢрҚЫӮЙҚЕӮаҸd—vӮИӮұӮЖӮӘӮзӮЖӮөӮДҒA“ъ–й“w—НӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮӨӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒA“VҚcӮМӮНӮ©ӮиӮІӮЖӮӘҢхӮиӢPӮӯӮаӮМӮЖӮИӮйӮжӮӨ”OҠиӮөӮДӮ«ӮҪҒBҺc”OӮИӮӘӮзҚр”NҒAғҚғVғAӮЖҗн’[ӮрҠJӮӯӮЙҺҠӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮНүдӮӘҚ‘ӮМҺ©үqӮМӮҪӮЯӮЙ•K—vӮЕӮвӮЮӮр“ҫӮИӮўӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB җҘҢЕӮжӮиүдӮ©Қc‘cҚcҸ@ӮМҲР—мӮЙ—ҠӮйӮЖе«—}–’•¶•җҗb—»ӮМҗE–ұӮЙ’үӮЙүӯ’ӣ–ҜҸҺӮМ•тҢцӮЙ—EӮИӮйӮМ’vӮ·ҸҠӮИӮзӮ·ӮЮӮНӮ ӮзӮ·ҒBҢрҗн“сҸ\ү{ҢҺ(ӮҰӮВӮ°ӮВ)’йҚ‘ӮМ’n•аҠщӮЙҢЕӮӯ’йҚ‘ӮМҚ‘—ҳҠщӮЙҗLӮУҒB’ҪӮМҚPӮЙ•ҪҳaӮМҺЎӮЙӢӮҒXӮҪӮйжҜ“kӮЙ•җӮрӢҮӮЯҗ¶–ҜӮрӮөӮДүiӮӯ–N“L(ӮЩӮӨӮДӮ«)ӮЙҚў(ӮӯӮйӮө)ӮЬӮөӮЮӮйӮр—~Ӯ№ӮЮӮвҒB ӮұӮкӮНӮаӮҝӮлӮсүдӮӘ“VҚcүЖӮМҗж‘cӮМҲРҢхӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮНӮ ӮйӮӘҒA“ҜҺһӮЙ•¶ҠҜӮвҢRҗlӮӘҗE–ұӮЙ’үҺАӮЕҒAӮЬӮҪ‘еҗЁӮМ–ҜҸOӮӘ—EҠёӮЙҚvҢЈӮөӮҪӮ©ӮзӮЙӮЩӮ©ӮИӮзӮИӮўҒB“сҸ\ғ–ҢҺӮМҗнӮўӮрӮЦӮД“ъ–{’йҚ‘ӮМҠо”ХӮНӮаӮНӮвӢӯҢЕӮЖӮИӮиҒAҚ‘үvӮр‘еӮ«ӮӯҗLӮОӮөӮҪҒB’ҪӮНҸнӮЙ•ҪҳaӮИ“қҺЎӮрӮаӮЖӮЯӮД“w—НӮөӮДӮЁӮиҒAӮҜӮБӮөӮД•җ—НӮрҚsҺgӮөӮДҗlҒXӮӘ’·Ӯӯҗн—җӮЙӢкӮөӮЮӮжӮӨӮИҺ–‘ФӮр–]ӮсӮЕӮНӮўӮИӮўҒB ҡҢ(ӮіӮ«)ӮЙҲҹ•Д—ҳүБҚҮҸOҚ‘‘е“қ—МӮМҗl“№Ӯр‘ёӮР•ҪҳaӮрҸdӮ·ӮйӮЙҸoӮДӮД“ъҳI—јҚ‘җӯ•{ӮЙҠ©ҚҗӮ·ӮйӮЙҚuҳaӮМҺ–ӮрҲИӮДӮ·ӮйӮв’ҪӮНҗ[Ӯӯ‘ҙӮМҚDҲУӮр—ИӮЖӮө‘е“қ—МӮМ’үҢҫӮр—eӮк”TӮҝ‘SҢ ҲПҲхӮр–ҪӮөӮД‘ҙӮМҺ–ӮЙ“–ӮзӮөӮЮҒB җжӮЙғAғҒғҠғJҚҮҸOҚ‘‘е“қ—МӮӘҒAҗl“№ӮЖ•ҪҳaӮр‘ёҸdӮ·Ӯй—§ҸкӮ©ӮзҒA“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМ—јҚ‘җӯ•{ӮЙҚuҳaӮЙӮВӮўӮДӮМҠ©ҚҗӮӘӮ ӮБӮҪҒB’ҪӮНӮ»ӮМҚDҲУӮЙҗ[ӮӯҠҙҺУӮөӮД‘е“қ—МӮМ’үҚҗӮЙҸ]ӮўҒA‘SҢ ҲПҲхӮр”C–ҪӮөӮДҚuҳaӮМҢрҸВӮр’S“–ӮіӮ№ӮҪҒB Һў—Ҳ”Юүд‘SҢ ӮМҠФҗ”ҺҹүпҸӨӮр—Э(Ӯ©Ӯі)ӮЛүдӮМ’сӢcӮ·ӮйҸҠӮЙӮөӮДҺnӮжӮиҢрҗнӮМ–Ъ“IӮҪӮйӮаӮМӮЖ“Ң—mӮМҺЎ•ҪӮЙ•K—vӮИӮйӮаӮМӮЖӮНҳIҚ‘‘ҙӮМ—vӢҒӮЙүһӮөӮДҲИӮДҳaҚDӮр—~Ӯ·ӮйӮМҗҪӮр–ҫӮЙӮөӮҪӮиҒB’Ҫ‘SҢ ҲПҲхӮМӢҰ’иӮ·ӮйҸҠӮМҸрҢҸӮр——ӮйӮЙҠF‘PӮӯ’ҪӮ©Һ|ӮЙ•ӣӮУҒB”TӮҝ”VӮрүГ”[”бҸyӮ№ӮиҒB Ӯ»ӮМҺһҲИ—ҲҒAүдӮӘҚ‘ӮЖғҚғVғAӮМ‘SҢ ҲПҲхӮНүҪ“xӮаҢрҸВӮрҸdӮЛҒAүдӮӘҚ‘ӮӘ’сҲДӮөӮҪӮ»ӮаӮ»ӮаӮМҗн‘ҲӮМ–Ъ“IӮЖғAғWғAӮМ•ҪҳaӮЙ•K—vӮИҺ–•ҝӮЙӮВӮўӮДӮНҒAғҚғVғAӮНӮ»ӮМ—vӢҒӮЙүһӮ¶ӮДҒA•ҪҳaӮр–]ӮсӮЕӮўӮйӮЖӮўӮӨҗҪҲУӮр–ҫӮзӮ©ӮЙӮөӮҪҒB’ҪӮН‘SҢ ‘еҺgӮӘҺжӮиҢҲӮЯӮҪҸр–сӮрҢ©ӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮНӮ·ӮЧӮД’ҪӮМҠу–]’КӮиӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒAӮұӮМҸр–сӮрҠмӮсӮЕ”бҸyӮөӮҪҒB ’ҪӮНдўӮЙ•ҪҳaӮЖҢхүhӮЖӮр•№Ӯ№ҠlӮДҸгӮНҲИӮД‘cҸ@ӮМ—миg(ӮкӮўӮ©Ӯс)ӮЙ‘О(ӮұӮҪ)ӮЦүәӮНҲИӮДҳЎҗС(ӮРӮ№Ӯ«)ӮрҢгҚ©(ӮұӮӨӮұӮс)ӮЙжД(ӮМӮұ)Ӯ·Ӯр“ҫӮйӮрҠмӮР“р—LҸOӮЖ‘ҙӮМ—_ӮрҳсӮЙӮөүiӮӯ—сҚ‘ӮЖҺЎ•ҪӮМҢcӮЙ—ҠӮзӮЮӮұӮЖӮрҺvӮУҒBҚЎӮвҳIҚ‘–’ҠщӮЙӢҢ–ҝӮрҗqӮД’йҚ‘ӮМ—F–MӮҪӮиҒB‘ҘӮҝ‘PзБӮМӢbӮр•ңӮөӮДҚXӮЙүvҒX“ЦҢъӮрүБӮУӮйӮұӮЖӮрҠъӮ№ӮіӮйӮЦӮ©ӮзӮ·ҒB ’ҪӮНӮұӮкӮЙӮжӮи•ҪҳaӮЖүhҢхӮМ—ј•ыӮр“ҫӮҪӮМӮЕҒA‘cҗжӮЙҠзҢьӮҜӮӘӮЕӮ«ӮйӮОӮ©ӮиӮ©ҒA‘еӮ«ӮИҢчҗСӮрҢгҗўӮЬӮЕҲвӮ·ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮрҠмӮСҒA“рӮзҚ‘–ҜӮЖӮұӮМүh—_ӮрӮЖӮаӮЙӮөӮДҒAүiӢvӮЙҸ”ҠOҚ‘ӮЖӮМ•ҪҳaӮрҲЫҺқӮ·ӮйӮұӮЖӮр–]ӮЮҒBҚЎӮвғҚғVғAӮЖӮНӮ·ӮЕӮЙҗн‘OӮМҠЦҢWӮр•ңҠҲӮөӮДӮЁӮиҒA“ъ–{’йҚ‘ӮМ—FҗlӮЕӮ ӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝ—FҚD“IӮИ—ЧҚ‘ӮЖӮөӮДӮМҲИ‘OӮМҠЦҢWӮЙ–ЯӮБӮҪӮӘҒAӮіӮзӮЙҗe–§ӮИҠЦҢWӮЙӮИӮйӮұӮЖӮНӢ^ӮўӮИӮўҒB ҲТӮУӮЙҗўү^ӮМҗi•аӮНҚ ҚҸ‘§ӮЬӮ·Қ‘үЖ“аҠOӮМҸҺҗӯӮНҲк“ъӮМңжӮИӮ©ӮзӮЮӮұӮЖӮр—vӮ·ҒBҳо•җ(ӮҰӮсӮФ)ӮМүәүvҒX•ә”хӮрҸCӮЯҗнҸҹӮМ—]–ъҒXҺЎӢіӮр’ЈӮи‘RӮөӮДҢгҺnӮД”\ӮӯҚ‘үЖӮМҢхүhӮр–ібd(ӮЮӮ«ӮеӮӨ)ӮЙ•ЫӮҝҚ‘үЖӮМҗiү^Ӯрүiү“ӮЙ•}ҺқӮ·ӮЦӮөҒB ’ҪӮМҚlӮҰӮЕӮНҒAҗўҠEӮМҗi•аӮНҲкҺһӮҪӮиӮЖӮаҺ~ӮЬӮйӮұӮЖӮНӮИӮўӮМӮЕҒAҚ‘“аҠOӮЙӮВӮўӮДӮМ—lҒXӮИҗӯ–ұӮНҲк“ъӮМ—P—\ӮаӢ–ӮіӮкӮИӮўҒBҗн‘ҲӮрӮвӮЯӮДӮаӮЬӮ·ӮЬӮ·ҢR”хӮрҗ®ӮҰҒAҗнӮўӮЙҸҹӮБӮҪҢгӮЕӮіӮзӮЙҗӯҺЎӮЖӢіҲзӮрҸ[ҺАӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҒAҚ‘үЖӮМүhҢхӮрүiү“ӮЙ•ЫӮҝҒAҚ‘үЖӮМҗi•аӮрүiү“ӮЙ•ЫҺқӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒB ҸҹӮЙа»(ӮИ)ӮкӮДҺ©ӮзҚЩ—}Ӯ·ӮйӮр’mӮзӮ·йҒ‘У(Ӯ«ӮеӮӨӮҫ)ӮМ”OҸ]ӮДҗ¶Ӯ·ӮйӮ©ҺбӮ«ӮНҗ[Ӯӯ”VӮрүъӮЯӮіӮйӮЦӮ©ӮзӮ·ҒB“р—LҸO‘ҙӮк‘PӮӯ’ҪӮ©ҲУӮр‘МӮөүvҒX‘ҙӮМҺ–ӮрӢОӮЯүvҒX‘ҙӮМӢЖӮр—гӮЭҲИӮДҚ‘үЖ•xӢӯӮМҠоӮрҢЕӮӯӮ№ӮЮӮұӮЖӮрҠъӮ№ӮжҒB Ҹҹ—ҳӮөӮД–ы’fӮөҒAҺ©•ӘӮ©ӮзӮ»ӮМӮЁӮұӮИӮўӮрҢ©’јӮөӮҪӮиүьӮЯӮҪӮиӮ·ӮйӮұӮЖӮрӮөӮИӮўӮЕҒAйҒӮиҚӮӮФӮБӮҪӮи‘УӮҜӮҪӮиӮ·ӮйҚlӮҰӮӘҗ¶Ӯ¶ӮйӮұӮЖӮӘҢҲӮөӮДӮ ӮБӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒB“рӮзҚ‘–ҜӮНӮжӮӯ’ҪӮМҲУҺvӮЙҸ]ӮўҒAӮЬӮ·ӮЬӮ·ӮұӮМӮұӮЖӮЙ—гӮЭҒAҚЎҢгӮаӢО•ЧӮЙ“ӯӮўӮДҒAҚ‘үЖӮӘ•xӮЭӢӯӮӯӮИӮйҠо‘bӮрӢӯҢЕӮЙӮ·ӮйӮжӮӨ“wӮЯӮзӮкӮжҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҒu“ъҳIҚuҳaҸр–с”бҸyӮЙҠЦӮ·Ӯйҗ•–§ү@үпӢc•MӢLҳ^Ғv
Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@Ғ@—BҚЎҸ‘ӢLҠҜӮрӮөӮДҳN“ЗӮ№ӮөӮЯӮҪ“ъҳIҚuҳaҸр–сӢy’ЗүБ–сҠјӮНҒAҺ–ӢЙӮЯӮДҸd‘еӮИӮйӮрҲИӮДҒAӢc’·Һ©Ӯз•сҚҗӮМ”CӮЙ“–ӮйӮұӮЖӮЖӮ№ӮиҒBҢдҸі’mӮМ’КҒAҚр”NҲИ—ҲҸ\”ӘүУҢҺӮМүiӮ«ӮЙҳiӮйҗн‘ҲӮрҸIӢЗӮ№ӮөӮЮӮйҸр–сӮЙӮөӮДҒAҚҹӮМҗн‘ҲӮМҲЧӮЙӮНҗ”Ҹ\–ңӮМҢR‘аӮрӢ]җөӮЙӢҹӮөҒAҸ\—L—]үӯү~ӮМӢаҠzӮр”пӮөҒAҗӢӮЙҗ퓬ӮМүҪӮкӮМ“ъӮЙ‘§ӮЮӮ©ӮН–wӮЗ—\‘ӘӮ·Ӯй”\ӮнӮҙӮйҢ`җЁӮИӮиӮөӮЙҒA•ДҚ‘‘е“қ—МӮМ”ӯҲУӮЙҲЛӮи“ъҳI—јҚ‘ӮЙҠ©ҚҗӮөҒAҚuҳa’k”»ӮрҠJҺnӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮиҒA‘ҙӮМҢӢүК–{Ҹр–сӮМ’чҢӢӮрҢ©ӮйӮЙҺҠӮкӮиҒBҚҹӮМҸр–сӮН‘OҢГ”д—ЮӮИӮ«ҠЦҢWӮрҗ¶ӮёӮйҸр–сӮЙӮөӮДҒAҺ–‘МӢЙӮЯӮДҸd‘еӮИӮйӮрҲИӮДӢc’·Һ©Ӯ©Ӯз•сҚҗӮМ”CӮЙ“–ӮиӮҪӮиҒB Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@Ғ@ӮҪӮҫӮўӮЬҸ‘ӢLҠҜӮӘҳN“ЗӮөӮЬӮөӮҪ“ъҳIҚuҳaҸр–сӮЁӮжӮС’ЗүБӮМҸрҚҖӮНҒA“а—eӮӘӮ«ӮнӮЯӮДҸd‘еӮЕӮ·ӮМӮЕҒAӢc’·ӮЭӮёӮ©ӮзӮӘ•сҚҗӮр’S“–ӮөӮЬӮ·ҒBӮІҸі’mӮМӮЖӮЁӮиҒAҚр”NӮ©ӮзӮМ18ғ–ҢҺӮМ’·Ӯ«ӮЙӮнӮҪӮйҗн‘ҲӮрҸIӮнӮзӮ№ӮйҸр–сӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮМҗн‘ҲӮМӮҪӮЯӮЙҗ”Ҹ\–ңӮМ•әҺmӮрӢ]җөӮЙӮөӮДҒA10җ”үӯү~ӮМӢаҠzӮрҺgӮў(Ң»ҚЭӮМ–с5Ғ`10’ӣү~ӮЙ‘Ҡ“–)ҒAҢӢӢЗӮНҗнӮўӮӘӮўӮВҸI—№Ӯ·ӮйӮМӮ©ӮЬӮйӮЕ—\‘ӘӮЕӮ«ӮИӮўҸоӢөӮЙӮИӮБӮДӮЁӮиҒAғAғҒғҠғJ‘е“қ—МӮМ”ӯҲДӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМ—јҚ‘ӮЦӮМҠ©ҚҗӮӘӮИӮіӮкҒAҚuҳaӮМҢрҸВӮӘҠJҺnӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮДҒAӮ»ӮМҢӢүКӮұӮМҸр–сӮӘ’чҢӢӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҸр–сӮНүЯӢҺӮЙ—бӮМӮИӮўҠЦҢWӮрҗ¶ӮЭҸoӮ·Ҹр–сӮЕӮ ӮиҒAҺ–‘ФӮНӢЙӮЯӮДҸd‘еӮЕӮ ӮйӮҪӮЯӢc’·ӮЭӮёӮ©ӮзӮӘ•сҚҗӮөӮЬӮ·ҒB Қuҳa’k”»ӮЙ•tӮДӮНҒA“аҠtӮЙү—ӮДҸ[•ӘҗRӢcӮрҗsӮіӮкҒAҺ§ӮөӮДҺҠ‘ёӮМҢдҚЩүВӮр“ҫӮД‘SҢ ҲПҲх”hҢӯ‘OӮЙ•vӮк•vӮк‘Ҡ“–ӮИӮйҢP—ЯӮр—^ӮҰӮзӮкӮйӮұӮЖӮЖҗ•–§ү@ӮЙү—ӮДӮНҢ©ӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒBҺ§ӮөӮД‘SҢ ҲПҲхӮН‘е–ҪӮрҲШ(Ӯ©ӮөӮұ)ӮЭ’k”»ӮМ‘ОҺиӮЙ‘ОӮөҒAҗg—НӮМҢАӮиӮрҗsӮөҗЬҸХӮрҗӢӮ°ӮҪӮйӮаӮМӮЖҢ©ӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒB‘RӮйӮЙҚҹӮМҸр–сӮЙ•tӮДӮНҗ\Ӯ·ӮЬӮЕӮаӮИӮӯҒAҚ‘ҳ_ӮН“C•Ұ(ӮДӮўӮУӮВ)ӮМҗЁӮр’жӮөӮҪӮиҒBӢc’·ӮНҸ”ҢNӮЖӢӨӮЙҗГӮЙҠJҗнҲИ—ҲӮМҸуӢөӮрҸnҺ@ӮөҒA–{Ҹр–сӮЙ‘ОӮ·ӮйҢд”бҸyӮЙ•tӮ«Һ^”ЫӮрҢҲӮөҒAӮұӮұӮЙҢN‘OӮЙү—ӮДҗ№—¶(Ӯ№ӮўӮиӮе)ӮрҲАӮ¶•тӮйӮМҺи’iӮрҺ·ӮзӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёӮЖҺv—ҝӮ·ҒB Қuҳa’k”»ӮЙҠЦӮөӮДӮНҒA“аҠtӮЕҸ[•ӘӮЙҗRӢcӮөӮВӮӯӮіӮкҒAӮ»ӮөӮД•ГүәӮМӮЁӢ–ӮөӮр“ҫӮД‘SҢ ҲПҲхӮМ”hҢӯӮМ‘OӮЙӮ»ӮкӮјӮкҚЧӮ©ӮИҺwҺҰӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪӮұӮЖӮНҗ•–§ү@ӮЕӮІ‘¶Ӯ¶ӮМӮұӮЖӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮөӮ©Ӯа‘SҢ ҲПҲхӮН“VҚc•ГүәӮМ–Ҫ—ЯӮрҺуӮҜҸіӮиҒAҳbӮөҚҮӮўӮМ‘ҠҺиӮЙ‘ОӮө‘S—НӮрӮВӮӯӮөӮДҢрҸВӮрҗ¬ӮөҗӢӮ°ӮҪӮЖҚlӮҰӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAӮұӮМҸр–сӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯҚ‘ӮМҗўҳ_ӮН—lҒXӮИҲУҢ©ӮӘ’сҸoӮіӮкҒAҢғӮөӮӯӢcҳ_ӮрҗнӮ©ӮнӮ·ҸуӢөӮЖӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӢc’·ӮНӮЭӮИӮіӮсӮЖӮЖӮаӮЙҗГӮ©ӮЙҠJҗнӮ©ӮзӮМҸуӢөӮрҗ[ӮӯҢ©Ӯ«ӮнӮЯҒAӮұӮМҸр–сӮЙ‘ОӮ·Ӯй“VҚc•ГүәӮМӮІ”бҸyӮЙӮВӮўӮДӮМҺ^”ЫӮрҢҲ’иӮөҒAӮұӮұӮЕ•ГүәӮМ‘OӮЕӮ»ӮМӮІҗS”zҺ–ӮрҺжӮиҸңӮ«ӮІҲАҗSӮўӮҪӮҫӮӯҺиӮҫӮДӮрӮЖӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖҚlӮҰӮЬӮ·ҒB ҚҹӮМҸр–сӮЙ•tӮДӮН”б•]•S’[ӮИӮиҒBҗўҠФӮМ”б•]Ӣcҳ_ӮНҢЕӮжӮи”VӮр“xҠOҺӢӮ·Ӯй–уӮЙӮНӮ ӮзӮҙӮкӮЗӮаҒAҗ•–§ү@ӮМӢcҺ–ӮНҺҠ‘ё• җSӮМӢcҺ–ӮИӮиҒBҗўҠФӮМӢcҳ_ӮЖүҪ“ҷҠЦҳAӮ·ӮйҸҠӮИӮӯҒAҸOӢcү@ӮМ”@Ӯ«ӮЖӮН‘еӮЙҗ«ҺҝӮрҲЩӮЙӮөҒAҸd‘еӮИӮйҺ–ҢҸӮЙ•tӣӮ’f(ӮөӮсӮҫӮс)ӮрҢҲӮ№ӮзӮйӮйӮЙ•ы(Ӯ ӮҪ)ӮиҒA•г—ғ(ӮЩӮжӮӯ)Ӯө•тӮйҸҠӮ ӮйӮЧӮ«ӮаӮМӮЙӮөӮДҒA”VүдҒXӮМҗE•ӘӮИӮиҒBӣӮ’fӮ№ӮзӮйӮйӮЙ•ығҠҒAҗФҗSӮрҗsӮөҺvҸўӮЙҠҗӮӨ—lӮЙӮ·ӮйӮұӮЖүдҒXӮМҗEҗУӮИӮиҒB ӮұӮМҸр–сӮЙӮВӮўӮДӮН—lҒXӮИҲУҢ©ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҗўҠФӮМ”б”»ӮЖӢcҳ_ӮНӮаӮҝӮлӮс–іҺӢӮ·Ӯй–уӮЙӮНӮўӮ«ӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҗ•–§ү@ӮНҚ‘үЖӮМҸd‘еӮИҺ–•ҝӮрҳ_ӢcӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЕӮ·ҒBҗ•–§ү@ӮНҒAҗўҠФӮМӢcҳ_ӮЖ‘SӮӯҠЦҢWӮөӮДӮўӮй•”•ӘӮӘӮИӮӯҒAҸOӢcү@ӮИӮЗӮЖӮНҗ«ҠiӮӘ‘еӮ«ӮӯҲЩӮИӮБӮДӮЁӮиҒAҸd‘еӮИҺ–ҢҸӮЙӮВӮўӮД•ГүәӮӘ”»’fӮөҢҲ’иӮ·ӮйӮЙӮ ӮҪӮБӮДҒA•вҚІӮіӮ№ӮД’ёӮӯӮЖӮұӮлӮӘӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮұӮкӮӘүдҒXӮМҗE–ұҸгӮМ–{•ӘӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒB•ГүәӮӘӮІҢҲ’fӮіӮкӮйӮЙӮ ӮҪӮБӮДҒAҗ^җSӮрӮВӮӯӮөӮДӮЁҚlӮҰӮЙ“KӮӨӮжӮӨӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүдҒXӮМҗE–ұҸгӮМҗУ”CӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒB Ҹn(ӮВӮзӮВ)ӮзҺvӮӨӮЙҗўҠФӮМӢcҳ_•ҙҒXӮҪӮй’ҶӮЙү—ӮДҗ•–§ү@ӮНҗГӮЙҚl—КӮөӮД’k”»ӮЙӮН‘ОҺиҚ‘ӮМӮ ӮйӮұӮЖӮИӮкӮО–{Ҹр–сӮМ’чҢӢӮЙ•tӮДӮН‘SҢ ҲПҲхӮМ–ҪӮр•тӮ¶ӮҪӮйҺТӮ©ҒAҗg—НӮМҢАӮиӮрҗsӮөӮҪӮйӮаӮМӮЖҢ©ӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒB ӮжӮӯӮжӮӯҚlӮҰӮДӮЭӮЬӮ·ӮЖҒAҗўҠФӮЕ—lҒXӮИӢcҳ_ӮӘҸoӮДӮўӮй’ҶӮЕҗ•–§ү@ӮН—ҺӮҝ’…ӮўӮДҚl—¶ӮөҒA’k”»ӮЕӮНӮ©ӮҜӮРӮ«ӮрӮ·Ӯй‘ҠҺиҚ‘ӮӘӮўӮйӮаӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒAӮұӮМҸр–сӮМ’чҢӢӮЙӮВӮўӮДӮН•ГүәӮМ–Ҫ—ЯӮрҺуӮҜӮҪ‘SҢ ҲПҲхӮӘ‘S—НӮрӮВӮӯӮөӮҪӮаӮМӮЖҚlӮҰӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB “GҚ‘ӮНҒA–һҸFӮМ–мӮЙү—ӮДӮұӮ»”sӮкӮҪӮйӮаҒAҸ®ӮЁҗн‘ҲӮрҢp‘ұӮ·ӮйӮМ—НӮ ӮиҒB–”“GҚ‘ӮНҗнӮЙ”sӮкӮҪӮйӮа–ўӮҫҚ~ӮрҗҝӮўҳaӮрҗҝӮўӮҪӮйӮаӮМӮЙӮ ӮзӮёҒBҗўҠEӮМҸуӢөӮЙҠУӮЭҚuҳa’k”»ӮМҠJҺnӮЙ“ҜҲУӮөӮҪӮйӮаӮМӮИӮйӮрҲИӮДүд‘SҢ ҲПҲхӮНҗg—НӮМҢАӮиӮрҗsӮөӮДҗЬҸХӮМ”CӮЙ“–ӮиӮҪӮйӮаҒA‘ҙӮМҢӢүКҒA‘ОҺиҚ‘ӮНүд—vӢҒӮМ‘ҚӮДӮр—eӮкӮҙӮиӮөӮНҺ–ҺАӮИӮиҒB “GҚ‘ӮН–һҸBӮМ‘е’nӮЕӮН”sӮкӮҪӮаӮМӮМҒAӮИӮЁҗн‘ҲӮрҢp‘ұӮ·Ӯй—НӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒA“GҚ‘ӮНҗнӮўӮЙӮН”sӮкӮҪӮаӮМӮМҒAӮўӮЬӮҫҚ~•ҡӮрӢҒӮЯӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮаҳa•ҪӮрӢҒӮЯӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҗўҠEӮМҸуӢөӮрҚlӮҰӮҪҸгӮЕҒAҚuҳaӮМҢрҸВӮрҠJҺnӮ·ӮйӮЖ“ҜҲУӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAүдӮӘ‘SҢ ҲПҲхӮН—НӮМҢАӮиӮрӮВӮӯӮөӮДҢрҸВӮМ”C–ұӮЙӮ ӮҪӮБӮҪӮаӮМӮМҒAӮ»ӮМҢӢүКҒA‘ҠҺиҚ‘ӮНүдҒXӮМ—vӢҒӮр‘SӮДҺуӮҜ“ьӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮұӮЖӮНҺ–ҺАӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒB җӯ•{ӮМҢ©ӮйҸҠӮЖҗўҸг–іҗУ”CӮМӢcҳ_ӮЖӮНҢЕ(ӮаӮЖ)ӮжӮи•„ҚҮӮ·ӮйӮұӮЖ“пӮөҒB‘SҢ ҲПҲхӮЙү—ӮДҗg—НӮрҗsӮ·ӮаҒAҢӢӢЗ‘ГӢҰӮ·Ӯй”\ӮНӮҙӮйҸкҚҮӮЙү—ӮДӮНҒAҗӯ•{ӮНӮұӮМҸр–сӮрҲИӮДҸIӢЗӮрҚҗӮ®ӮЧӮ«ӮвҒAҸ«–”(ӮНӮҪӮЬӮҪ)’k”»Ӯр”j—фӮ№ӮөӮЮӮЧӮ«ӮвҒBҺбӮө’k”»•s’ІӮЙӢAӮөӮҪӮйӮЖӮ«ӮНҒAҸ«—ҲүҪӮкӮМ“ъӮЙү—ӮДҗн‘ҲӮМҸIӢЗӮрҚҗӮ®ӮЧӮ«ӮвҒA–wӮсӮЗ—\ҠъӮө”\ӮНӮҙӮйҢ`җЁӮИӮиӮЖҗMӮёҒB җӯ•{ӮМҢ©үрӮЖҗўҠФӮМ–іҗУ”CӮИӢcҳ_ӮЖӮНҒAӮ»ӮаӮ»ӮаҲк’vӮөӮЙӮӯӮўӮаӮМӮЕӮ·ҒB‘SҢ ҲПҲхӮӘ‘S—НӮрӮВӮӯӮөӮДӮаҢӢӢЗ‘ГӢҰӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҸкҚҮӮНҒAҗӯ•{ӮНӮұӮМҸр–сӮЕҗн‘ҲӮМҸIӮнӮиӮрҚҗӮ°ӮйӮЧӮ«ӮИӮМӮ©ҒAӮ»ӮкӮЖӮаҢрҸВӮрҢҲ—фӮіӮ№ӮйӮЧӮ«ӮИӮМӮ©ҒAӮаӮөҒAҢрҸВӮӘӮӨӮЬӮӯӮўӮ©ӮИӮўҺһӮНҒAҸ«—ҲӮўӮВӮЙӮИӮБӮҪӮзҗн‘ҲӮМҸI—№ӮрҚҗӮ°ӮзӮкӮйӮМӮ©ҒAӮЩӮЖӮсӮЗ—\‘ӘӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҸоҗЁӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНӮЬӮёҠФҲбӮўӮИӮўӮЖҠmҗMӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҚҹӮӯҚ‘үЖӮМҲАҠлӮрҲк’fӮМүәӮЙҢҲӮ·ӮЧӮ«ҚЫӮЙҸҲӮөӮДҒAҗӯ•{ӮНҠл“№Ӯр”рӮҜҒAҲА‘SӮМ“№ӮрҺжӮиҒAҷтҡlӮМҠФӮЙӢcӮр’иӮЯҒAҗУ”CӮр•үӮўҒAҚҹӮМҸгҗ”–ңӮМҗl–ҪӮр‘№ӮөҸ\җ”үӯӮМҢR”пӮр”пӮіӮсӮжӮиӮНҒAҗl“№ӮМҸгӢyҺРвlҚ‘үЖ(ӮөӮбӮөӮеӮӯӮұӮБӮ©)ӮМ—ҳҠQӮжӮи‘ЕҺZӮөӮДӢcӮрҢҲӮ№ӮзӮкҒAҚЎ“ъҒA–{Ҹр–сӮМҢд”бҸyӮр‘tҗҝӮ№ӮзӮкӮҪӮйӮұӮЖӮЖҗ•–§ү@ӮНҢ©ӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙҚ‘үЖӮМҸd‘еӮИҲДҢҸӮр‘Ұ’fӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҺһҒAҗӯ•{ӮНҠлҢҜӮИ“№Ӯр”рӮҜҒAҲА‘SӮИ“№Ӯр‘I‘рӮөҒA’ZҺһҠФӮМ“аӮЙӢcҳ_ӮрӮЬӮЖӮЯҒAҗУ”CӮр•үӮўҒAӮіӮзӮЙҗ”–ңӮМҗl–ҪӮрҺёӮўҸ\җ”үӯӮМҢR”пӮр”пӮвӮ·ӮжӮиӮНҒAҗl“№ҸгӮЖҚ‘үЖӮМ—ҳүvӮ©ӮзҚlӮҰӮДӢcҳ_ӮрҢҲ’иӮөӮДҒAҚЎ“ъҒAӮұӮМҸр–сӮМӮІ”бҸyӮр“VҚc•ГүәӮЙҗ\ӮөҸгӮ°ӮДҚЩүВӮрӮ ӮЁӮ®ӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮаӮМӮЖҗ•–§ү@ӮЕӮНҚlӮҰӮҙӮйӮр“ҫӮЬӮ№ӮсҒB –{ҢҸӮНӢЙӮЯӮДҸd‘еӮИӮйӮрҲИӮДҸ”ҢNӮаҺҠ‘ёӮЖҚ‘үЖӮМ—JӮр•ӘӮҪӮйӮйҢдҚlӮЙӮДҸ[•ӘҚuӢҶӮ№ӮзӮкӮҪӮйӮұӮЖӮЖҺv—ҝӮ·ҒBӢc’·ӮНҚЧ–ЪӮЙҸВӮйӮжӮиӮНҒA‘е‘МӮЙ•tҒAҠJҗнҲИ—ҲӮМ‘ҚӮДӮМҸуӢөӮЙҸЖӮөӮДҢдҺҗжm(ӮөӮ¶ӮгӮс)ӮЙ“ҡӮҰ•тӮй•ыүВӮИӮйӮЧӮөӮЖҗMӮ¶ҒAҲУҢ©Ӯр’ВҸqӮөӮҪӮйҺҹ‘жӮИӮиҒBҢдӢcҳ_ҢдҺҝ–вӮМ“_Ӯ ӮзӮО“–ӢЗ‘еҗbӮаҸoҗИӮ№ӮзӮкӢҸӮйҢМҒAҗҸҲУӮЙҲЧӮіӮкӮДүВӮИӮиҒBҢдҚl—¶ӮМҸгҢҲ’иӮ ӮзӮсӮұӮЖӮр•ОӮЙҠу–]Ӯ·ҒB –{ҢҸӮНӢЙӮЯӮДҸd‘еӮИӮМӮЕҒAӮ ӮИӮҪ•ыӮа•ГүәӮЖҚ‘үЖӮМҗS”zӮр•Ә’SӮ·ӮйҚlӮҰӮ©ӮзҸ[•ӘӮЙӮІҢҹ“ўӮіӮкӮҪӮұӮЖӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӢc’·ӮНҚЧӮ©ӮўҺ–•ҝӮЙҢҫӢyӮ·ӮйӮжӮиӮНҒA‘S‘М“IӮИҢ©’nӮ©ӮзҒAҠJҗнҲИ—ҲӮМ‘SӮДӮМҸуӢөӮЙӮаӮЖӮГӮўӮД•ГүәӮМӮЁҗqӮЛӮЙ“ҡӮҰӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйӮЖҠmҗMӮөҒAҲУҢ©ӮрҸqӮЧӮҪҺҹ‘жӮЕӮ·ҒBӮІӢcҳ_ҒAӮІҺҝ–вӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮзҒA’S“–‘еҗbӮаҸoҗИӮіӮкӮДӮЁӮиӮЬӮ·ӮМӮЕҒAҗҸҲУӮЙӮЁӮЛӮӘӮўӮўӮҪӮөӮЬӮ·ҒBҸn—¶ӮМҸгӮЕҢҲ’иӮіӮкӮйӮжӮӨҒAҗШӮЙҠу–]ӮөӮЬӮ·ҒB Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@ҠeҲКӮЙӮЁӮўӮДҢдҲУҢ©ӮрҸqӮЧӮзӮйӮй•K—vӮИӮӯҒA–”ҢдҺҝ–вӮИӮӯӮОҚМҢҲӮ·ҒBҢд”бҸyӮ№ӮзӮйӮЧӮ«ӮаӮМӮЖ”FӮЯӮзӮйӮйҒBҸ”ҢNӮМӢN—§ӮрҗҝӮӨҒBҒk‘SүпҲк’vҒl Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@Ғ@‘SүпҲк’vӮрҲИӮДҺ^җ¬Ӯ№ӮзӮкӮҪӮиҒB Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@ҠeӢcҲхӮЙӮЁӮўӮДӮІҲУҢ©ӮрҸqӮЧӮзӮкӮй•K—vӮӘӮИӮӯҒAӮЬӮҪӮІҺҝ–вӮаӮИӮҜӮкӮОҚМҢҲӮөӮЬӮ·ҒB“VҚc•ГүәӮӘӮІ”бҸyӮіӮкӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮЬӮ·ҒBӮЭӮИӮіӮсӮМӢN—§ӮрӮЁҠиӮўӮөӮЬӮ·ҒBҒk‘SүпҲк’vҒl Ӣc’·(ҲЙ“Ў)Ғ@‘SүпҲк’vӮрӮаӮБӮДҺ^җ¬ӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ3 | |
| ҒЎ1. “ъҳIҗн‘ҲӮМҢҙҲц Ғ@ | |
|
ҒЎ(1) “ъҳIҗн‘ҲӮМ—рҺj“IҲУӢ`
“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA1904”NҒ`1905”NӮЙӮ©ӮҜӮДҒAҗVӢ»ӮМ‘е“ъ–{’йҚ‘ӮЖҒAҳV‘еҚ‘ғҚғVғA’йҚ‘ӮӘҒA’ҶҚ‘“Ң–k•”(–һҸB)ӮрҺеҗнҸкӮЖӮөӮДҗнӮБӮҪҒA’йҚ‘ҺеӢ`ӮМ—М“yҠl“ҫҗн‘ҲӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҢғҗнӮНҒAғAғҒғҠғJӮӘ’ҮүоӮ·ӮйҢ`ӮЕҸIҢӢӮ·ӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМҢӢүКӮНҒA“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҒu”»’иҸҹӮҝҒvӮҫӮБӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒA“ъ–{ӮНҒAӮ»ӮМҗн‘Ҳ–Ъ“IӮрҠ®‘SӮЙ’Bҗ¬ӮөӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒAҠ®ҸҹӮЖҢҫӮБӮДӮаҚ·ӮөҺxӮҰӮИӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB ӮұӮМҗн‘ҲӮМҢӢүКҒAҠщӮЙҗҠҗЁӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒA–v—ҺӮЦӮМҲк“rӮр’HӮиҒA1917”NӮМғҚғVғAҠv–ҪӮЕүу–ЕҒA•цүуӮөӮЬӮ·ҒB ӢtӮЙҒA‘е“ъ–{’йҚ‘ӮНҗўҠEӮМҒuҢЬ‘еҚ‘ҒvӮЙҗ¬ӮиҸгӮӘӮиҒA“ҢғAғWғAӮЕ‘еӮўӮЙ”eӮрҸҘӮҰӮйӮЙҺҠӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМ“ЛҸoҗUӮиӮӘғAғҒғҠғJӮвғCғMғҠғXӮМӢt—ШӮЙҗGӮкҒA1941”NҒ`1945”NӮМ‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲӮЙ”sӮкӮйӮұӮЖӮЕҒAғAғWғAӮМ”eҢ Қ‘үЖӮМ’nҲКӮрҺёӮӨӮЙҺҠӮйӮМӮЕӮ·ҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНҒAҸҹҺТӮЕӮ Ӯй“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДӮаҒA”sҺТӮЕӮ ӮйғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮДӮаҒAӮЬӮіӮЙү^–ҪӮМ“]Ӣ@ӮЖҢҫӮҰӮйҗӯҺЎ“I‘еҺ–ҢҸӮЕӮөӮҪҒB ӮўӮвҒAӮ»ӮкҲИҸгӮЙҒAҢгҗўӮМҗӯҺЎҺjӮЙҸd—vӮИүeӢҝӮрӢyӮЪӮөӮЬӮөӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНҒAҒu—LҗFҗlҺнӮӘ”’җFҗlҺнӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҒAҗl—ЮҺjҸгӮНӮ¶ӮЯӮДӮМӢЯ‘гҗн‘ҲҒvӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ“–ҺһӮМҗўҠEӮНҒA’nӢ…ӮМ—Ө’n–КҗПӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮр”’җlӮӘҺx”zӮөӮДӮЁӮиҒA‘е‘Ҫҗ”ӮМү©җFҗlҺнӮвҚ•җl(ӮВӮЬӮи—LҗFҗlҺн)ӮНҒA”’җlӮЙҗA–Ҝ’nҺx”zӮіӮкҒA“z—кӮМӮжӮӨӮИӢ«ӢцӮЙҠГӮсӮ¶ӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМ“–ҺһҒA—LҗFҗlҺнӮМҠ®‘SӮИҺеҢ Қ‘үЖӮНҒA‘SҗўҠEӮЕ“ъ–{ҒAғgғӢғRҒAғ^ғCҒAғGғ`ғIғsғAӮМ4Қ‘ӮҫӮҜӮЕӮөӮҪ(’Ҷ•ДӮв“м•ДӮНҒA”’җlӮЖ—LҗFҗlҺнӮЖӮМҚ¬ҢҢӮЙҺx”zӮіӮкӮДӮўӮҪӮМӮЕҒAҸғҗҲӮИ—LҗFҗlҺнӮМҚ‘үЖӮЖӮНҢ©ӮИӮөӮЬӮ№Ӯс)ҒBӮ»ӮМӮұӮЖӮ©ӮзӮаҒA“–ҺһӮМҸуӢөӮМүЯҚ“ӮіӮӘ—ЗӮӯ•ӘӮ©ӮйӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒA”’җlӮМ—LҺҜҺТӮНҒAӮұӮМҸуӢөӮрҒu“–‘RҒvӮҫӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮзӮНҒAҒu—LҗFҗlҺнӮИӮЗҒAғuғ^Ӯв”nӮЖ“ҜӮ¶ӮИӮМӮҫӮ©ӮзҒAүдҒXӮЙҺ”ҲзӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮӘ“–‘RӮҫӮөҒAӮ»ӮМ•ыӮӘӮ©ӮҰӮБӮДҚKӮ№ӮИӮМӮҫҒvӮИӮЗӮЖҢцҢҫӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҸғҗҲӮИ—LҗFҗlҺнӮМҚ‘үЖӮЕӮ Ӯй“ъ–{ӮӘҒA”’җlҚ‘үЖғҚғVғAӮЙ’§җнӮөҒAӮұӮкӮрҢ©Һ–ӮЙ‘ЕӮҝ•үӮ©ӮөӮҪҺ–ҺАӮНҒA”’җlӮҪӮҝӮрбУ–ЪӮіӮ№ҒAӮ»ӮөӮД”ЮӮзӮМҺx”zӮЙӢкӮөӮсӮЕӮўӮҪ—LҗFҗlҺнӮҪӮҝӮЙ—EӢCӮр—^ӮҰӮЬӮөӮҪҒB ҒuүҙӮҪӮҝӮҫӮБӮДҒAӮвӮкӮОҸo—ҲӮйӮсӮҫҒI“ъ–{ӮрҢ©ҸKӮҰҒIҒv ӮұӮӨӮөӮДҒA‘SҗўҠEӮМҗA–Ҝ’nӮЕ“Ж—§ү^“®ӮӘҠӘӮ«ӢNӮұӮиҒAҺ©—RӮМ•—ӮӘҗўҠEӮр•ўӮӨҢӢ––ӮрҢ}ӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНҒA‘Sҗl—ЮӮМ•аӮЭӮрүiү“ӮЙҗіӮөӮў•ыҢьӮЙ•ПӮҰӮҪҒAүжҠъ“IӮИҺ–ҢҸӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB “ъ–{җlӮНҒAӮаӮБӮЖҢЦӮиӮрҺқӮБӮД—ЗӮўӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) –{“–ӮНҒA“ъ–{ӮМ•үӮҜӮҫӮБӮҪҒH
ӮөӮОӮөӮОҺЁӮЙӮ·ӮйӢcҳ_ӮЙҒAҒu“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA–{“–ӮН“ъ–{ӮМ•үӮҜӮҫӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҠwҚZӮМ—рҺjӮМҺцӢЖӮЕҒAӢіҺtӮӘҗ¶“kӮЙӮ»ӮӨӢіӮҰӮДӮўӮйӮМӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB Һ„Ң©ӮрҢҫӮӨӮИӮзҒAӮұӮМӢcҳ_ӮНҠ®‘SӮИҠФҲбӮўӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮаӮ»ӮаҒAҒu–{“–ӮН•үӮҜӮҫӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮӘҳ_—қ“IӮЙ•ПӮЕӮ·ҒBҗн‘ҲӮМҢӢүКӮЙӮНҒAҒuҸҹӮҝҒvӮ©Ғu•үӮҜҒvӮ©ҒuҲшӮ«•ӘӮҜҒvӮМ3Һн—ЮӮөӮ©–іӮўӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМ’ҶӮЙҒAҒu–{“–ҒvӮвҒuүRҒvӮӘ“ьӮй—]’nӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB ҠwҚZӢіҺtӮӘҢыӮЙӮ·ӮйҒu–{“–ӮН•үӮҜҒvӮЖӮўӮӨӮМӮНҒAӮұӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮЕҢҫӮБӮДӮўӮйӮМӮҫӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB Ғu“ъ–{ӮНҒA’ZҠъӮЕҗн‘ҲӮӘҸIӮнӮБӮҪӮ©ӮзҸҹӮБӮҪӮМӮҫҒBӮаӮөӮа’·Ҡъү»ӮөӮДӮўӮкӮОҒA•әҲхҗ”ӮЙҸҹӮйғҚғVғAӮӘҸҹӮБӮДӮўӮҪӮНӮёӮИӮМӮҫҒBӮҫӮ©ӮзҒA–{“–ӮН•үӮҜӮИӮМӮҫҒv ӮұӮМҗа–ҫӮНҒAҳ_—қ“IӮЙҠФҲбӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҺАҚЫӮМҗн‘ҲӮНҒAҠmӮ©ӮЙ’ZҠъӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮН“ъ–{ӮМҗн‘ҲҺw“ұҺТӮҪӮҝӮӘҒA’ZҠъӮЙҸIӮнӮйӮжӮӨ“w—НӮөӮҪӮ©ӮзӮ»ӮӨӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮВӮЬӮиҒAӮұӮМҗн‘ҲӮӘ’ZҠъӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮНҒA“ъ–{ӮМҚмҗнҸҹӮҝӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӮдӮҰӮЙҒAҒu“ъ–{ӮМҸҹ—ҳҒvӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮЙ•ПӮнӮиӮНӮИӮӯҒAҒu–{“–ҒvӮаҒuүRҒvӮа–іӮўӮМӮЕӮ·ҒB ӮЬӮҪҒAҲк•”ӮМҳ_ҺТӮНҒA•әҲхӮМ‘№–Хҗ”ӮрҚӘӢ’ӮЙҒu–{“–ӮН“ъ–{ӮМ•үӮҜҒvӮЖҺе’ЈӮөӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮ·ҒBҠmӮ©ӮЙҒA•Я—ёӮрҠЬӮЯӮИӮў•ә‘аӮМҺҖҸқҺТҗ”ӮЕӮНҒA“ъ–{ӮМ•ыӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҺе’ЈӮаҒAҳ_—қ“IӮЙҠФҲбӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB җн‘ҲӮМҸҹӮҝ•үӮҜӮЖӮўӮӨӮМӮНҒA•әҲхӮМ‘№–ХӮМ‘ҪүЗӮЕҢҲӮЬӮйӮМӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҗн‘ҲӮМҸҹ”sӮНҒAҒuҗн‘Ҳ–Ъ“IӮӘ’Bҗ¬ӮЕӮ«ӮҪӮ©”ЫӮ©ҒvӮЕҢҲӮЬӮйӮМӮЕӮ·ҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЕҒAҗн‘Ҳ–Ъ“IӮр’Bҗ¬ӮөӮҪӮМӮН“ъ–{ӮМ•ыӮЕӮөӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҒAӮ ӮкӮН–в‘иӮИӮӯҒu“ъ–{ӮМҸҹ—ҳҒvӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҲЩҳ_ӮрҚ·ӮөӢІӮЮ—]’nӮИӮЗӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB Ӯ»ӮаӮ»ӮаҒA‘№–ХӮМ‘ҪӮіӮЕҸҹ”sӮӘҢҲӮЬӮйӮЖӮўӮӨӮМӮИӮзҒA’·ҺВӮМҗнӮўӮН•җ“cӢR”nҢR’cӮМҸҹ—ҳӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйӮөҒAғmғӮғ“ғnғ“Һ–•ПӮв—°ү©“ҮӮМҗнӮўӮН“ъ–{ҢRӮМҸҹ—ҳӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҝӮбӮўӮЬӮ№ӮсӮ©ҒH(Ӯ»ӮкӮјӮкҒAҗD“c“ҝҗмҳAҚҮҢRҒAғ\ҳAҢRҒAғAғҒғҠғJҢRӮМ•ыӮӘҒAҺҖҸқҺТҗ”ӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·)ҒB ӮЖӮұӮлӮЕҒAӮЗӮӨӮөӮД“ъ–{ӮМҠwҚZӢіҺtӮвҺҜҺТӮНҒAҒu“ъҳIҗн‘ҲӮр“ъ–{ӮМ•үӮҜҒvӮЙӮөӮҪӮӘӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮ»ӮкӮНҒAҗнҢг“ъ–{ӮЙ– ү„ӮөӮҪӮўӮнӮдӮйҒuҺ©ӢsҺjҠПҒvӮМҺdӢЖӮЕӮ·ҒBҚ¶—ғҺv‘zӮЙ•ОҢьӮөӮҪ“ъӢі‘gӮНҒAҗн‘OӮМ‘е“ъ–{’йҚ‘ӮМӢЖҗСӮрҒA‘SӮД”Ы’иӮ·ӮйӮжӮӨӮИӢіҲзӮр“WҠJӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҚЎ“ъҒA‘ҪӮӯӮМ“ъ–{җlӮӘҲӨҚ‘җSӮрҺёӮБӮДӮўӮйӮМӮНҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮЕӮ·ҒB ӮЕӮаҒAүдҒXӮМҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮйҺРүпӮЙӮНҒAҒwҗв‘ОҲ«ҒxӮИӮсӮД‘¶ҚЭӮөӮЬӮ№ӮсҒB‘е“ъ–{’йҚ‘ӮНҒAҠmӮ©ӮЙҲ«Һ–ӮаӮөӮҪӮЕӮөӮеӮӨӮӘҒA—ЗӮўҺ–ӮҫӮБӮДӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМ‘SӮДӮр”Ы’и“IӮЙӢіӮҰӮй“ъӢі‘gӮМ•ыҗjӮНҒAӢіҲзӮЖӮўӮӨӮжӮиҒuҗф”]ҒvӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB ӮЖӮаӮ ӮкҒA“ъ–{ӮМҺбҺТӮМ‘ҪӮӯӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙ‘ОӮөӮД”Ы’и“IӮИҚlӮҰӮрҺқӮҪӮіӮкӮДӮўӮйҒB Ӯ»ӮөӮДҒAӮұӮМҸ¬ҳ_ӮМҚЕ‘еӮМ–Ъ“IӮНҒAҗф”]ӮМҺф”ӣӮ©ӮзҺбҺТӮҪӮҝӮрүр•ъӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) “ъ–{ӮМҗн‘Ҳ–Ъ“I
ӮЬӮёҒAҠо–{“IӮИ‘O’сӮ©Ӯзҗа–ҫӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB “–ҺһӮМҗўҠEӮНҒAӮўӮнӮдӮйҒu’йҚ‘ҺеӢ`ӮМҺһ‘гҒvӮЕӮөӮҪҒBҢR‘аӮвҢoҚПӮМ—НӮЕ‘јҚ‘ӮвҲЩ•¶–ҫӮр”jүуӮөҒAҗA–Ҝ’nҺx”zӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҒAӮІӮӯ“–ӮҪӮи‘OӮМӮжӮӨӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB—НӮұӮ»ӮӘҗіӢ`ҒA—НӮұӮ»ӮӘ‘SӮДӮЕӮөӮҪҒB—НӮМ–іӮўӮаӮМӮНҒAӮ»ӮМҗ¶‘¶ӮрӢ–ӮіӮкӮёҒAӢӯҺТӮМ‘җҠ ҸкӮЙӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮ·ҒB ҚЕӮаҺcҚ“ӮЙ’йҚ‘ҺеӢ`Ӯрҗ„җiӮөӮҪӮМӮНҒAӮаӮҝӮлӮсҒA”’җFҗlҺнӮМғҲҒ[ғҚғbғpӮЕӮ·ҒB”ЮӮзӮНҒAғLғҠғXғgӢіҒAӮИӮ©ӮсӮёӮӯғvғҚғeғXғ^ғ“ғgӮМ•ОӢ·ӮИҗўҠEҠПӮЙ”ӣӮзӮкҒAғҲҒ[ғҚғbғp•¶–ҫ(ҒҒғLғҠғXғgӢі•¶–ҫ)ҲИҠOӮМ•¶ү»ӮвҺн‘°ӮрҢy•ҺӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮзӮМҗGҺиӮНҒAҺеӮЖӮөӮДҲЩӢі“kӮЕӮ Ӯй—LҗFҗlҺнӮҪӮҝӮЙҸPӮўҠ|Ӯ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҒA—LҗFҗlҺнӮМҠ®‘SӮИҺеҢ Қ‘үЖӮНҒA20җўӢIӮМҸү“ӘӮЕӮН4Қ‘ӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМ’ҶӮЕҚЕ‘еҗЁ—НӮЕӮ ӮБӮҪғgғӢғR’йҚ‘ӮНҒAӮ»ӮМ—М“yӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮрғҚғVғAӮЖғCғMғҠғXӮЙ’DӮўҺжӮзӮкҒA’f–––ӮӮМҠлӢ@ӮЙҡbӮўӮЕӮўӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{Ӯвғ^ғCӮвғGғ`ғIғsғAӮӘ“Ж—§Ӯр•ЫӮҝӮҰӮҪӮМӮНҒAӮұӮкӮзӮМҚ‘ӮӘҒAӮҪӮЬӮҪӮЬ”’җlҗЁ—НҠФӮМӢПҚtӮМ’ҶҠФ“_ӮЙӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҚKү^ӮЙҢbӮЬӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB—бӮҰӮО“ъ–{ӮНҒAғCғMғҠғXӮЖғtғүғ“ғXӮӘ“ӘҸгӮЕбЙӮЭӮ ӮБӮДҢЭӮўӮЙҢЎҗ§ӮөӮ ӮБӮДӮӯӮкӮҪӮЁүAӮЕҒAӮ»ӮМҢ„ҠФӮрӮВӮўӮДӢЯ‘гү»Ӯрҗ„җiӮЕӮ«ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ“ъ–{ӮНҒA19җўӢIҸI”ХӮЙҺҠӮйӮЬӮЕҒA260”NӮаӮМ’·Ӯ«ӮЙӮнӮҪӮБӮДҚҪҚ‘ӮрӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒA’йҚ‘ҺеӢ`ӮМ–ӮҺиӮ©ӮзҚ‘•xӮрҺзӮй‘[’uӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғAғҒғҠғJӮвғҚғVғAӮӘӢӯ‘еӮИ•җ—НӮр”wҢiӮЙӮөӮДҠJҚ‘Ӯр”—ӮйӮЖҒAӮаӮНӮвҲАҸZӮөӮДӮўӮзӮкӮйҺһ‘гӮНҸIӮнӮиӮрҚҗӮ°ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAӮИӮ©ӮО–і—қӮвӮиҠJҚ‘ӮіӮ№ӮзӮкӮҪ“ъ–{ӮНҒAӢҶӢЙӮМ‘I‘рӮр”—ӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB ҒE ”’җlӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮйӮМӮ©ҒB ҒE ү©җFҗlҺнҸүӮМ’йҚ‘ҺеӢ`Қ‘үЖӮЙҗ¶ӮЬӮк•ПӮнӮйӮМӮ©ҒB “ъ–{ӮМ‘I‘рӮНҒAҢгҺТӮЕӮөӮҪҒB “ҝҗм–Ӣ•{ӮЙҺжӮБӮД‘гӮнӮБӮҪ–ҫҺЎҗӯ•{ӮНҒA–Т—уӮИҒu•xҚ‘Ӣӯ•әҗӯҚфҒvӮр“WҠJӮөҒAҸ]—ҲӮМҒu••Ңҡ“IӮИ”_‘әҚ‘үЖҒvӮрҒAҲкӢCӮЙҒu’йҚ‘ҺеӢ`“IӢЯ‘гҚHӢЖҚ‘үЖҒvӮЙүь‘ўӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМүЯ’цӮЕӢNӮ«ӮҪҗн‘ҲӮӘҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЖ“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ2ӮВӮМҗн‘ҲӮМҚЕӮаҸd—vӮИҸЕ“_ӮНҒAҒu’©‘N”ј“ҮӮМӢA‘®–в‘иҒvӮЕӮөӮҪҒB ’©‘N”ј“ҮӮНҒAҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯ“ъ–{ӮЙ’n—қ“IӮЙҚЕӮаӢЯӮў—Ө’nӮЕӮ ӮБӮДҒAӮ»ӮМҚ‘үЖҗн—ӘӮЙӢyӮЪӮ·Ҹd—vҗ«ӮНҢvӮи’mӮкӮИӮўӮаӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB19җўӢI––ӮМҺһ“_ӮЕҒAӮұӮұӮр—М—LӮөӮДӮўӮҪӮМӮНҒAҒuҠШүӨҚ‘ҒvӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМҚ‘ӮНҒAҢRҺ–—НӮаҢoҚП—НӮа‘OӢЯ‘г“IӮИҗ…ҸҖӮМӮЬӮЬӮЕҒAӮўӮВҠOҚ‘ӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮБӮДӮаҺd•ыӮӘӮИӮўҸуӢөӮЙ’uӮ©ӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ’©‘NӮӘҒAӮ»ӮкӮЬӮЕ“Ж—§Ӯр•ЫӮБӮДӮўӮзӮкӮҪӮМӮНҒA’ҶҚ‘(җҙ’йҚ‘)ӮМ‘®Қ‘ӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ’ҶҚ‘ӮНҒA19җўӢI––ӮМ’iҠKӮЕҒA”’җlҗЁ—НӮЙ‘ҪӮӯӮМ—М“yӮрҗNҗHӮіӮкҒAӮаӮНӮв”јҗA–Ҝ’nӮЖҗ¬ӮиүәӮӘӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҚЎӮв’©‘NӮНҒAҺ©•ӘӮРӮЖӮиӮЕ’йҚ‘ҺеӢ`җЁ—НӮЖҗнӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB “ъ–{ӮНҒA“–ҸүӮНҒA’©‘NӮЙӢZҸpүҮҸ•ӮрҚsӮўҒA“ъ–{ӮЖ“Ҝ—lӮМ’йҚ‘ҺеӢ`Қ‘үЖӮЙҗ¶ӮЬӮк•ПӮнӮБӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӢӨӮЙҺиӮрҢgӮҰӮД”’җlҗЁ—НӮЙ—§ӮҝҢьӮ©ӮЁӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҚ‘ӮЕӮН•ЫҺз“IӮИҗЁ—НӮӘӢӯӮӯҒAүьҠvӮИӮЗӮЩӮЖӮсӮЗ–]ӮЯӮИӮўҸу‘ФӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮНҒAғtғүғ“ғXӮ©ғҚғVғAӮ©ғhғCғcӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮЕӮөӮеӮӨҒBӮ»ӮӨӮИӮБӮҪӮзҒA“ъ–{ӮНҠ®‘SӮЙ”’җlҗЁ—НӮЙ•пҲНӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB ӮұӮкӮНҒA“–ҺһӮМ“ъ–{җlӮЙӮЖӮБӮДҒAӮҪӮўӮЦӮсӮИӢ°•|ӮЕӮөӮҪҒBӮҝӮеӮБӮЖӮЕӮаҢ„ӮрҢ©Ӯ№ӮҪӮзҒA“ъ–{–{“yӮЬӮЕҒAӮҪӮҝӮЬӮҝҸжӮБҺжӮзӮкӮДӮөӮЬӮӨӮЕӮөӮеӮӨӮ©ӮзҒB “ъ–{ӮНҒA‘ЕӮБӮДҸoӮЬӮ·ҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA’©‘N”ј“ҮӮрҗЁ—НүәӮЙ’uӮ«ҒAӮұӮұӮрӢҙ“ӘҡЖӮЙӮөӮД”’җlҗЁ—НӮМҗiҸoӮр–hӮ¬ӮЖӮЯӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮӘҒAӮўӮнӮдӮйҒu“ъ’й50”NҺx”zҒvӮМ–ӢҠJӮҜӮЕӮөӮҪҒB Һ„ӮНҒAҒu“ъ’й50”NҺx”zҒvӮрҗі“–ү»Ӯ·ӮйӮВӮаӮиӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB“ъ–{җlӮМҗSӮМ’кӮЙҒAҒuӮ№ӮБӮ©Ӯӯ’йҚ‘ҺеӢ`Қ‘үЖӮЙӮИӮБӮҪӮсӮҫӮ©ӮзҒAҗA–Ҝ’nӮМҲкӮВӮЕӮаҺқӮҪӮИӮӯӮҝӮбғJғbғRӮӘ•tӮ©ӮИӮўӮөҒAҗјүў—сӢӯӮМ’ҮҠФ“ьӮиӮӘҸo—ҲӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨӢC•ӘӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮНҠmӮ©ӮЕӮ·ҒB ӮҪӮҫҒAӮұӮМҺһ‘гӮНҒAҸоӮҜ—eҺНӮМ–іӮўҒuҗHӮӨӮ©җHӮнӮкӮйӮ©ҒvӮМҗўҠEӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮНҒAҢҲӮөӮД–YӮкӮДӮНӮИӮзӮИӮў“_ӮЕӮөӮеӮӨҒBҗN—ӘӮіӮкӮҪӮӯӮИӮўӮМӮИӮзҒAҗN—ӘӮ·Ӯй‘ӨӮЙүсӮйӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒuҺгӮўҒvӮЖҺvӮнӮкӮҪӮӘҚЕҢгҒAӮҪӮҝӮЬӮҝҗHӮў•ЁӮЙӮіӮкӮйӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮсӮИ“ъ–{ӮНҒAӮЬӮёӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮЙҸ@ҺеҢ ӮрҺқӮВ’ҶҚ‘ӮЖ‘ОҢҲӮөӮЬӮ·ҒB“ъҗҙҗн‘Ҳ(1893Ғ`94)ӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҢӢүКҒA’©‘N”ј“ҮӮН“ъ–{ӮМ•ЫҢм—МӮЙӮіӮкӮйӮМӮЕӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҸоҗЁӮЙҗШҺ•қNҳrӮөӮҪӮМӮНҒAғҚғVғAҒAғhғCғcҒAғtғүғ“ғXӮЕӮөӮҪҒB”ЮӮзӮНҒAҒuӮҝӮӯӮөӮеӮӨҒAҗ¶ҲУӢCӮИғTғӢӮЙҗжӮрүzӮіӮкӮҝӮЬӮБӮҪҒIҒvӮЖ“{ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮұӮЕҒA“ъ–{җӯ•{ӮЙӮЛӮ¶ҚһӮсӮЕҒA“ъ–{ӮӘ’ҶҚ‘Ӯ©Ӯз‘dҺШӮөӮҪ—Й“Ң”ј“ҮӮИӮЗӮр’DӮўҺжӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮўӮнӮдӮйҒuҺOҚ‘ҠұҸВҒvӮЕӮ·ҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМҚ‘—НӮЕӮНҒAӮЖӮДӮа”ЮӮзӮЙ’пҚRӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсӮ©ӮзҒA“ъ–{җlӮНҒuүзҗdҸҰ’_ҒvӮрҚҮҢҫ—tӮЙҒA•ңӢwӮМҺһӮр‘_ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҒuҺOҚ‘ҠұҸВҒvӮЕҒAҚЕӮа—ҳүvӮр“ҫӮҪӮМӮНҒA’n—қ“IӮЙ’©‘NӮЙӢЯӮўғҚғVғAӮЕӮөӮҪҒB‘е—ӨӮЦӮМ“ъ–{ӮМүeӢҝ—НӮрҺгӮЯӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮұӮМҚ‘ӮНҒA’ҶҚ‘“Ң–k•”(–һҸB)Ӯв’©‘N”ј“ҮӮрҗA–Ҝ’nӮЙӮөӮжӮӨӮЖ“®Ӯ«ҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB’ҶҚ‘җӯ•{ӮМ”чҺгӮИ’пҚRӮрқӣӮЛӮМӮҜӮДҒAҢR‘аӮр–һҸBӮМӮЭӮИӮзӮёҒA’©‘N”ј“ҮӮЙӮЬӮЕ‘—ӮиҚһӮсӮҫӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮӘғҚғVғAӮЙ’DӮнӮкӮйҒEҒEҒEҒB “ъ–{җӯ•{ӮМҸЕ‘ҮӮНҒA–ЪӮр•ўӮнӮсӮОӮ©ӮиӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ӮЖӮөӮДӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮрүдӮӘҺиӮЙҺыӮЯҒA–һҸBӮНҗјүў—сӢӯӮ©ӮзӮМ’Ҷ—§’n‘СӮЖӮөӮД’ҶҚ‘ӮЙ•ЫҺқӮіӮ№ӮДӮЁӮ«ӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ·ӮИӮнӮҝҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМҗн‘Ҳ–Ъ“IӮНҒAҒuғҚғVғAӮМҗЁ—НӮрҒA’©‘N”ј“ҮӮЖ–һҸBӮ©ӮзӢм’ҖӮ·ӮйҒvӮұӮЖӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(4) ғҚғVғAӮМҗн‘Ҳ–Ъ“I
ҺҹӮЙҒAғҚғVғAӮМҺ–ҸоӮрҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮеӮӨҒB ғҚғVғAӮНҒAӮаӮЖӮаӮЖғҲҒ[ғҚғbғp“Ң•”ӮЙҲК’uӮ·Ӯй”_ӢЖҚ‘ӮЕӮөӮҪҒB13җўӢIӮЙғӮғ“ғSғӢӮМҗN—ӘӮЙ‘ҳӮўҒAӮ»ӮМҗA–Ҝ’nӮЖӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAғCғҸғ“—Ӣ’йӮзӮМҠҲ–фӮЕӮжӮӨӮвӮӯ“Ж—§Қ‘ӮМ‘М–КӮрҺжӮи–ЯӮөӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAҗVҗ¶ғҚғVғAӮЖҢҫӮҰӮЗӮаҒA••Ңҡ—МҺеӮЖ”_“zӮЙӮжӮБӮДҚ\җ¬ӮіӮкӮҪҒA’xӮкӮҪ”_ӢЖҚ‘ӮЕӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМҸуӢөӮр‘еӮ«Ӯӯ•ПӮҰӮҪӮМӮНҒA18җўӢIӮМғsғҮҒ[ғgғӢ‘е’йӮЕӮ·ҒBӮұӮМӢҗҗlӮНҒAғXғEғFҒ[ғfғ“ӮвғgғӢғRӮрҳAҗнҳA”jӮөҒAӮВӮўӮЙҠCӮЦӮМҸoҢыӮрҠl“ҫӮөӮЬӮөӮҪҒBғyғeғӢғuғӢғN(Ң»ғTғ“ғNғgҒEғyғeғӢғuғӢғN)ӮНҒAғҚғVғAҸүӮМҠCҠO–fҲХҚ`ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҢгҒAҗјүў•¶–ҫӮрҢ©ҸKӮБӮДҢoҚП”ӯ“WӮЙ“wӮЯӮйғҚғVғAӮЕӮ·ӮӘҒAҸ\•ӘӮИ•s“ҖҚ`(“~ӮЕӮа“ҖӮзӮИӮўҚ`)ӮӘ–іӮўӮҪӮЯӮЙҒAҺvӮӨӮЩӮЗӮМҢoҚПҗ¬’·ӮрҗӢӮ°ӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮЬӮ№ӮсҒB “–ҸүӮНҒAғgғӢғRӮр’@ӮўӮД’n’ҶҠC•ы–КӮЙҸoӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮаӮМӮМҒAғҚғVғAӮМҗЁ—НҠg’ЈӮрӢ°ӮкӮйғCғMғҠғXӮЖғtғүғ“ғXӮӘҒAӮ»ӮМ‘OӮЙ—§ӮҝҚЗӮӘӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAҳI“yҗн‘ҲӮвғNғҠғ~ғAҗн‘ҲӮМҢӢүКҒAғҚғVғAӮНҒAӮұӮМ•ы–КӮЦӮМҗiҸoӮр’f”OӮ№ӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “мӮЦӮМҗiҳHӮрҚЗӮӘӮкӮҪӮ»ӮМӢҗ‘еӮИҗGҺиӮНҒA”дҠr“IҗјүўҗЁ—НӮӘҺи”–ӮИ“ҢӮЦӮЖҢьӮ©ӮўӮЬӮ·ҒB’ҶҚ‘ӮЖӮМҗ”“xӮЙӮнӮҪӮйҠp’ҖӮМҢгҒAӮжӮӨӮвӮӯ“ъ–{ҠCӮЙ—ХӮЮҚ`ҳpӮрҠl“ҫҒBӮұӮұӮрҒAғEғүғWғIғXғgғbғN(“ҢӮрҗӘ•һӮ№ӮжҒAӮЖӮўӮӨҲУ–Ў)ӮЖ–јӮГӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒA’ҶҚ‘ӮМҗҙүӨ’©ӮМҺг‘Мү»ӮрҢ©ӮҪ”ЮӮНҒA’gӮ©ӮўҚ`ӮрӢҒӮЯҒA“мӮЦ“мӮЦӮЖүәӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҗҙүӨ’©ӮрңҳҠ…ӮөҒA’ҶҚ‘“Ң–k•”ӮЙ“Ңҗҙ“S“№Ӯр•~җЭӮөӮҪғҚғVғAӮНҒAӮ»ӮМҗж’[ӮЙӮ ӮйҚЧ’·Ӯў—Й“Ң”ј“ҮӮрҒAҒuҺOҚ‘ҠұҸВҒvӮЕ“ъ–{Ӯ©ӮзӮаӮ¬ҺжӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ”ј“ҮӮМ“Л’[ӮЙҲК’uӮ·Ӯй—·ҸҮҚ`ӮНҒAғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮД”OҠиӮМҒA–LӮ©ӮИ•s“ҖҚ`ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAӮНҒA—·ҸҮҚ`ӮЙ‘еҠН‘аӮр”hҢӯӮөӮЬӮөӮҪҒBҒu—·ҸҮҠН‘аҒvӮЕӮ·ҒBҚAҢіӮЙҷ¶ҺсӮр“ЛӮ«ӮВӮҜӮзӮкӮҪ“ъ–{ӮНҒAҗkӮҰҸгӮӘӮиӮЬӮөӮҪҒBӮаӮНӮвҒA“ъ–{ҠCӮЖ“ҢғVғiҠCӮМғVҒ[ғҢҒ[ғ“ӮНҒAғҚғVғAӮМҺvӮӨӮӘ–ҷӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҲИҸгӮМӮұӮЖӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮйӮжӮӨӮЙҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйғҚғVғAӮМҗн‘Ҳ–Ъ“IӮНҒAҒuӢкҗЯӮМ––ӮЙҠl“ҫӮөӮҪ“ҢғAғWғAӮМҢ үvӮрҲЫҺқӮөҒAӢӯү»Ӯ·ӮйӮұӮЖҒvӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(5) ғCғMғҠғXӮМҺ–Ҹо
’йҚ‘ҺеӢ`ӮМҺһ‘гӮНҒAҗ¶Ӯ«”nӮМҠбӮр”ІӮӯӮжӮӨӮИҢғӮөӮў“¬‘ҲӮМҺһ‘гӮЕӮөӮҪҒB’йҚ‘ҺеӢ`Ҹ”Қ‘ӮНҒAҢЭӮўӮЙ•ЎҺGӮИ“Ҝ–ҝӮвӢҰ’иӮрҠфҸdӮЙӮаҢӢӮСҒAҠщ“ҫҢ үvӮрҺзӮиӮВӮВҒAҗVӮҪӮИғ`ғғғ“ғXӮр–мҸbӮМӮжӮӨӮЙ‘_ӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ’ҶӮЕӮаҒAҚЕ‘еӮМҠщ“ҫҢ үvӮМ•ЫҺқҺТӮНҒA‘ҫ—zӮМ’ҫӮЬӮИӮў’йҚ‘ғCғMғҠғXӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМғCғMғҠғXӮНҒA“–‘RӮИӮӘӮзҒAҗVҗiӢCүsӮМғүғCғoғӢӮЕӮ ӮйғhғCғcӮвғҚғVғAӮМ“®ҢьӮЙҗ_ҢoӮрҗлӮзӮ№ӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBғhғCғcӮвғҚғVғAӮНҒAӮўӮнӮО’йҚ‘ҺеӢ`ӮМҢг”ӯ‘gӮЕӮ·ҒB”ЮӮзӮӘҗЁ—НӮрҗLӮОӮ»ӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖҒA•K‘R“IӮЙғCғMғҠғXӮМҠщ“ҫҢ үvӮӘӢәӮ©ӮіӮкӮйӮМӮЕӮ·ҒB ғCғMғҠғXӮЖғhғCғcӮНҒAғAғtғҠғJӮв’ҶӢЯ“ҢӮЕҢғӮөӮў’Х”—ӮиҚҮӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ‘О—§ӮӘҒAӮвӮӘӮД‘жҲкҺҹ‘еҗнӮЦӮМ”аӮрҠJӮӯӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМҢ„ӮрӮВӮўӮДҒAғҚғVғAӮӘ’ҶҚ‘ӮЦӮМҗGҺиӮрҗLӮОӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒA”јҗA–Ҝ’nӮЕӮ ӮБӮҪ’ҶҚ‘ӮЙҚЕӮаӢҗ‘еӮИ—ҳҢ ӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮМӮӘғCғMғҠғXӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBғCғMғҠғXӮНҒA‘еӮўӮЙҸЕӮиӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA“ҢғAғWғAӮЙ‘еҢRӮр”hҢӯӮ·Ӯй—]—TӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮ©ӮзҒA”ЮӮН—L—НӮИғpҒ[ғgғiҒ[ӮрӢҒӮЯӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМғpҒ[ғgғiҒ[ӮЙҒAғҚғVғAӮрҗHӮўҺ~ӮЯӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖҚlӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ҢғAғWғAӮМғpҒ[ғgғiҒ[ҒAӮ»ӮкӮНҒAҗVӢ»ӮМ‘е“ъ–{’йҚ‘ҲИҠOӮЙ—LӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAҒu“ъүp“Ҝ–ҝҒvӮӘҢӢӮОӮкӮЬӮ·(1902”N)ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(6) ғAғҒғҠғJӮМҺ–Ҹо
ғAғҒғҠғJӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙүeӢҝӮрӢyӮЪӮөӮҪ‘еҚ‘ӮМҲкӮВӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮұӮлӮНҒAӮжӮӨӮвӮӯ“м–kҗн‘ҲӮЖӮўӮӨ“а—җӮрҸжӮиүzӮҰӮҪӮОӮ©ӮиҒBӮўӮнӮОҒA’йҚ‘ҺеӢ`ӮМҢг”ӯ‘gӮЕӮөӮҪҒB 20җўӢIҸү“ӘӮМ’йҚ‘ҺеӢ`ӢЈ‘ҲӮрҳлбХӮ·ӮйӮЖҒAҗж“ӘӮр‘–ӮйғCғMғҠғXӮЖғtғүғ“ғXӮрҒAҲк”nҗgҚ·ӮЕғhғCғcӮЖғҚғVғAӮӘ’ЗӮўҒAӮіӮзӮЙӮ»ӮМҢгӮр“ъ–{ӮЖғAғҒғҠғJӮӘ’ЗӮўӮ©ӮҜӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҸуӢөӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғCғMғҠғXӮНҒAҗ^ҢгӮлӮЙӮўӮД–ЪҸбӮиӮИғҚғVғAӮрҸRӮи—ҺӮЖӮ·ӮҪӮЯҒA—yӮ©ӮЙҢг•ыӮЙӮўӮД“––КӮМӢәҲРӮЙӮИӮзӮИӮў“ъ–{Ӯр—ҳ—pӮөӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДғAғҒғҠғJӮНҒAӮұӮМҸуӢөӮМ’ҶӮЕӢҷ•vӮМ—ҳӮр“ҫҒAҲкӢCӮЙҸгҲКӮЙ—xӮиҸoӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA“ъ–{ӮЖғCғMғҠғXӮМ—ј•ыӮЙү¶Ӯр”„ӮйӮұӮЖӮЕҒAғҚғVғA“P‘ЮҢгӮМ’ҶҚ‘ҺsҸкӮЦӮМҗiҸoӮрҠйӮсӮҫӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮМҢӢүКҒAғҚғVғAӮН—yӮ©Ңг•ыӮЙ’E—ҺӮөҒAӮвӮӘӮДӢӨҺYҺеӢ`Ҡv–ҪӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕҒAӮұӮМ’йҚ‘ҺеӢ`ғҢҒ[ғXӮрҚ~ӮиӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮЙҺжӮБӮД‘гӮнӮБӮҪ“ъ–{ӮНҒA•№‘–Ӯ·ӮйғhғCғcӮЖҺиӮр‘gӮсӮЕҒAҚЎ“xӮНғCғMғҠғXӮЖғtғүғ“ғXӮМ”eҢ ӮЙ’§җнӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮрҢ}ӮҰҢӮӮБӮҪүp•§ӮНҒAғAғҒғҠғJӮМ—НӮрҺШӮиӮД“ъ“ЖӮр•ФӮи“ўӮҝӮЙӮ·ӮйӮаӮМӮМҒAҺ©ӮзӮа”жӮкҗШӮБӮДҢг•ыӮЙ’E—ҺҒBӮұӮкӮӘҒA‘ж“сҺҹ‘еҗнӮЕӮ·ӮЛҒB ҢӢӢЗҒA20җўӢIӮМ”eҢ ӢЈ‘ҲӮНҒAғүғCғoғӢӮҪӮҝӮрҗUӮи—ҺӮЖӮөӮДғgғbғvӮЙ”тӮСҸoӮөӮҪғAғҒғҠғJӮМҲкҗlҸҹӮҝӮЙҸIӮнӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮӨӮўӮӨҺӢ“_ӮЕ—рҺjӮрҢ©ӮйӮЖҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙүКӮҪӮөӮҪғAғҒғҠғJӮМ–рҠ„ӮНҒAӮҪӮўӮЦӮсӮЙӢ»–Ўҗ[ӮўӮаӮМӮӘӮ ӮйӮМӮЕӮ·ҒB ғAғҒғҠғJӮНҒA“ъ–{ӮЖғCғMғҠғXӮЙ‘ОӮөӮДҒAғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮзҺxүҮӮрҗЙӮөӮЬӮИӮўҺ|Ӯр–с‘©ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҚ ҚҮӮрҢ©ӮДҳa•ҪӮрҲҙҗщӮ·ӮйӮұӮЖӮа–с‘©ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғAғҒғҠғJӮМҺӢҗьӮНҒAӮ¶ӮБӮЖҗнҢгӮМ’ҶҚ‘ҺsҸкӮЙ’ҚӮӘӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ӮНҒAғCғMғҠғXӮЖғAғҒғҠғJӮМҒu‘ОғҚғVғA”eҢ “¬‘ҲҒvӮМ“№ӢпӮЖӮөӮДҺgӮнӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
| ҒЎ2ҒD—јҢRӮМҗн‘ҲҢvүж | |
|
ҒЎ(1) “ъ–{ӮМҗн‘ҲҢvүж
“ъ–{ӮМҺw“ұҺТӮҪӮҝӮНҒA“–ҸүӮНғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮЙҸжӮиӢCӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB җнӮБӮДӮаҒAҸҹӮҝ–ЪӮӘ–іӮўӮЖҺvӮнӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Қ‘—НӮЙ—тӮйӮМӮЭӮИӮзӮёҒA“ъ–{ӮНӮаӮЖӮаӮЖҺ‘Ң№ӮМ–RӮөӮў“ҮҚ‘ӮИӮМӮЕӮ·ҒBҗјүў—сӢӯӮр‘ҠҺиӮЙҗн‘ҲӮ·ӮйӮұӮЖӮИӮЗҒAӮЗӮӨҚlӮҰӮДӮағiғ“ғZғ“ғXӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕҒAҗҙүӨ’©ӮаҢрӮҰӮДҒAҢрҸВӮЕғҚғVғAӮрүҹӮіӮҰҚһӮаӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBӢп‘М“IӮЙӮНҒA–һҸBӮЖ’©‘NӮрҒAӮЗӮҝӮзӮЖӮа’Ҷ—§ү»ӮіӮ№ӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғAӮНҒAӮўӮБӮҪӮсӮНҸр–сӮЙүһӮ¶ӮҪӮаӮМӮМҒAӮҪӮҝӮЬӮҝ•^•ПҒB–һҸBӮНӮЁӮлӮ©ҒA’©‘N”ј“ҮӮЙӮЬӮЕҢR‘аӮр‘—ӮиҚһӮЮҺn––ҒB “ъ–{ӮНҒAӮаӮНӮвҗн‘ҲӮрҢҲҲУӮ№ӮҙӮйӮр“ҫӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮсӮИ“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮД—L—ҳӮИ“_ӮНҒAҗўҠEҚЕ‘еӮМҢoҚП‘еҚ‘ӮЕӮ ӮйғCғMғҠғXӮвғAғҒғҠғJӮМғoғbғNғAғbғvӮӘҸ\•ӘӮЙҠъ‘ТӮЕӮ«Ӯй“_ӮЕӮ·ҒB•nӮөӮў“ъ–{ӮЕӮ ӮБӮДӮаҒAҺ‘ӢаӮЖҺ‘Ң№ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA”дҠr“IҠyҠП“IӮИҢ©җПӮаӮиӮр—§ӮДӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒA–в‘иӮНҗн—НӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮНҒAӮЗӮӨӮөӮжӮӨӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB “ъ–{ӮМҚмҗнҢvүжӮНҺь“һӮЕӮөӮҪҒB ҒuҸҸҗнӮЙӮЁӮўӮДҠпҸPҚUҢӮӮрӮөӮ©ӮҜҒA“GӮМҗн—НӮӘҗ®ӮнӮИӮўӮӨӮҝӮЙӮұӮкӮрҠeҢВҢӮ”jӮ·ӮйҒBӮ»ӮөӮДҗнӢөӮӘ—L—ҳӮЙҗi“WӮөӮДӮўӮйӮӨӮҝӮЙҒAғAғҒғҠғJӮЙҳa•ҪӮр’ҮүоӮөӮДӮаӮзӮӨҒBҗн‘ҲҠъҠФӮН’·ӮӯӮД1”NӮ©1”N”јӮЕӮ ӮйҒv Ҹd—vӮИӮМӮНҒAҗн‘ҲҠъҠФӮрҒu1”NӮ©Ӯз1”N”јҒvӮЖҺ–‘OӮЙҢҲӮЯӮДӮўӮй“_ӮЕӮ·ҒB“ъ–{ӮМҚ‘—НӮЕӮНҒAӮ»ӮкҲИҸгӮМҗн‘ҲӮМҠg‘еӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮйӮЖӮМ‘мүzӮөӮҪ”»’fӮЕӮөӮҪҒB’·ҠъҗнӮЙӮИӮкӮО•ә—НӮӘҢНҠүӮ·ӮйӮМӮЭӮИӮзӮёҒA•җҠн’e–тӮМҗ¶ҺYӮаҢАҠEӮЙ’BӮ·ӮйӮЕӮөӮеӮӨҒBӮЬӮҪҒAүp•ДӮ©ӮзҺ‘ӢаӮр’І’BӮЕӮ«ӮйӮЙӮөӮДӮаҒAӮ ӮЬӮиӮЙӢҗҠzӮМҠOҚВӮр”ӯҚsӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЖҒAҢгӮМҗў‘гӮЙ•ү’SӮӘҠ|Ӯ©ӮБӮДӮөӮЬӮӨӮҫӮлӮӨӮұӮЖӮр—¶ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҢ©ҺҜӮНҒAҢгӮМҸәҳaӮМҢR”ҙӮвҒAҢ»‘гӮМҗӯҺЎүЖӮҪӮҝӮЙӮНӢyӮСӮа•tӮ©ӮИӮўҗ[ӮіӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҚ·ӮНҒAӮўӮБӮҪӮўӮЗӮұӮ©Ӯз—ҲӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒH –ҫҺЎҗӯ•{ӮМҺс”]ӮҪӮҝӮНҒAҺбӮўҚ Ӯ©Ӯз–Ӣ––ӮМҢҢүҢӮМ’ҶӮр‘~ӮўҗцӮиҒAҗн‘ҲӮМ”ЯҺSӮіӮрҒAҗgӮрӮаӮБӮД–ЎӮнӮБӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҗн‘ҲӮӘҒAҺРүпӮЙӮЖӮБӮДӮМ•K—vҲ«ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮаҸ\•ӘӮЙ”FҺҜӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮҫӮ©ӮзӮұӮ»ҒAҗн‘ҲӮМҗҘ”сӮЙӮН‘еӮўӮЙӮҪӮЯӮзӮўӮИӮӘӮзҒAӮўӮҙҗн’[ӮӘҠJӮ©ӮкӮҪӮЖӮҪӮсҒA–мҸbӮМӮжӮӨӮЙ’fҢЕӮҪӮйҲУҺvӮЕҗнӮўӮрҗ„җiӮөӮДӮўӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮкӮНҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯҒAҗн‘ҲӮЙ‘ОӮ·ӮйғҠғAғҠғeғBӮр‘rҺёӮөҒAӮвӮзӮИӮӯӮДӮа—ЗӮўҗн‘ҲӮрғ_ғүғ_ғү‘ұӮҜӮДҚ‘Ӯр–Е–SӮЙ’ЗӮўӮвӮБӮҪҸәҳaӮМҢR”ҙӮвҒAүҪӮМҚӘӢ’Ӯа–Ъ“IӮа–іӮӯҢыҗжӮҫӮҜӮЕ•ҪҳaӮрӢ©ӮФҢ»‘гӮМӢу‘z“IӮИ•ҪҳaҺеӢ`ҺТӮҪӮҝӮЙӮНҒAӢyӮСӮаӮВӮ©ӮИӮўӢ«’nӮЕӮөӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮр“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮЙ“ұӮўӮҪҚЕӮаҸd—vӮИ—vҲцӮНҒAӮұӮӨӮөӮҪҗн‘ҲҺw“ұҺТӮҪӮҝӮМҢ©ҺҜӮМҗ[ӮіӮЙӮ ӮБӮҪӮМӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) ғҚғVғAӮМҗн‘ҲҢvүж
‘ОӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮНҒAӮ ӮЬӮиӮұӮМҺ–‘ФӮрҗ[ҚҸӮЙҚlӮҰӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮаӮҝӮлӮсҒA—LҗFҗlҺнӮМ“ъ–{Ӯр•ҺӮБӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨ‘Ө–КӮаӮ ӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB Ӯ»ӮкҲИҸгӮЙҸd—vӮИӮМӮНҒAӮұӮМ“–ҺһӮМғҚғVғAӮЙӮНҒAҚ‘ҚфӮрҢҲ’иӮ·ӮйӮЬӮЖӮаӮИӢ@ҠЦӮӘ‘¶ҚЭӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҺ–ӮЕӮ·ҒB ӮўӮҝӮЁӮӨҒAҚc’йӮӘҗкҗ§җӯҺЎӮрҚsӮӨҚ‘ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҚc’йғjғRғүғC2җўӮНҒA—DҸ_•s’fӮИ–VӮҝӮбӮсӮЕҒAҺжӮиҠӘӮ«ӮҪӮҝӮМҢҫӮўӮИӮиӮЕӮөӮҪҒBҺ©•ӘҺ©җgӮЕӮНҒAҚ‘ҚфӮрҢҲӮЯӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮсӮИҚc’йӮМ‘ӨӢЯӮҪӮҝӮНҒAӮ»ӮМ‘ҪӮӯӮӘ’nҺеӢM‘°ӮЕӮ·ҒB”ЮӮзӮНҒAӢ{’мғTғҚғ“ӮМ’ҶӮЕҒA“ъ–йҒA”h”ҙҚR‘ҲӮвҢ —Н“¬‘ҲӮЙ–ҫӮҜ•йӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠЦҗSӮНҒAҺ©•ӘӮҪӮҝӮМҺ„—ҳҺ„—~ӮЙӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮМүЯ’цӮЕҒA•nӮөӮў”_–ҜӮҪӮҝӮӘӢкӢ«ӮЙӮ ӮҰӮІӮӨӮЖӮаҒA“Ң—mӮЕ“ъ–{ӮЖӮМҢҲ’и“IӮИ–ҖҺCӮӘӢNӮұӮлӮӨӮЖӮаҒA”ЮӮзӮЙӮНӮЗӮӨӮЕӮа—ЗӮўӮұӮЖӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮаӮҝӮлӮсҒA—ЗҺҜ”hӮаӮўӮЬӮөӮҪҒB—бӮҰӮОҒA‘ ‘ҠӮМғEғCғbғeӮНҒA‘ОҠOҗн‘Ҳ‘S”КӮЙ”Ҫ‘ОӮМ—§ҸкӮрҠСӮўӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮИӮәӮИӮзҒAғҚғVғAӮМҚаҗӯӮӘӢҮ–Rү»ӮөҒA”jҺYҗЎ‘OӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮЬӮҪҒA“ъ–{ӮрҺӢҺ@ӮөӮҪ—ӨҢR‘еҗbғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮНҒAӮұӮМҗVӢ»Қ‘ӮМҚ‘—НӮвҚ‘–ҜӮМҺmӢCӮӘ•ҺӮиӮӘӮҪӮўӮұӮЖӮрҢ©ӮДҺжӮиҒAӮұӮМӢӯ“GӮЖӮМҗн‘ҲӮЙӮН”Ҫ‘ОӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҸӯҗ”ӮМ—ЗҺҜ”hӮМҲУҢ©ӮНҒAҸнӮЙ‘еҗЁӮМӢрҺТӮЙүҹӮө—¬ӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМӢрҺТӮҪӮҝӮНҒA•КӮЙҗн‘ҲӮр–]ӮсӮҫӮнӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBүҪӮаҚlӮҰӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮЖӮМҚ‘ҢрӮр”j’]ӮіӮ№ӮҪӮМӮНҒAҠщҸqӮМӮЖӮЁӮиҒAғҚғVғAҢRӮМҲк•ы“IӮИ’©‘NӮЦӮМ’“—ҜӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМӢрҚsӮрӢӯҚsӮөӮҪӮМӮНҒA’©‘NӮЙ—ҳҢ ӮрҠm•ЫӮөӮДҒuғJғl–ЧӮҜҒvӮрҠйӮсӮҫӮЧғ]ғuғүғ]ғtӢЁӮМ“Ж’fӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҚ‘ӮМҲУҺvӮЖӮН–іҠЦҢWӮИӮЖӮұӮлӮЕҒAҺ„—ҳҺ„—~ӮрҠйӮЮӢ{’мӢM‘°ӮӘҒu–\‘–ҒvӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ·ҒB ӮЬӮйӮЕҒA40”NҢгӮМ“ъ–{ӮМҺpӮрҢ©ӮДӮўӮйӮжӮӨӮЕӮ·ӮЛҒB—рҺjӮНҢJӮи•ФӮ·ӮЖӮНҒA—ЗӮӯҢҫӮБӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB ӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕҒA“Ң—mӮЙӮЁӮҜӮйғҚғVғAӮМҗн—НӮНӢЙӮЯӮД•nҺгӮЕӮөӮҪҒB“ъ–{ӮӘҚUӮЯӮДӮӯӮйӮЖӮўӮӨҺ–‘ФӮрҒAӮЩӮЖӮсӮЗ‘z’иӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB“ъҳIҗн‘ҲӮМ‘SҠъҠФӮр’КӮ¶ӮДҒAғҚғVғAҢRӮМ‘ОүһӮӘҸнӮЙҢгҺиӮЙүсӮБӮҪӮМӮНҒAӮЬӮіӮЙӮ»ӮМӮҪӮЯӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) ҺR–{ҠC‘ҠӮМ‘еүp’f
“ъ–{ӮЖӮўӮӨҚ‘ӮЙӮНҒAҸнӮЙ’v–Ҫ“IӮИ‘еғnғ“ғfӮӘ•tӮ«ӮЬӮЖӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮНҒAҒuҺl•ыӮрҠCӮЙҲНӮЬӮкӮҪҒAҺ‘Ң№ӮМ–RӮөӮў“ҮҚ‘ҒvӮЖӮўӮӨ“_ӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮНҒAҠOҚ‘ӮМҗN—ӘӮ©ӮзҚ‘“yӮрҺзӮйҸгӮЕӮН—L—pӮИӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮҝӮзӮ©Ӯз‘ЕӮБӮДҸoӮйҸкҚҮӮЙӮНӮҪӮўӮЦӮсӮИғnғ“ғfӮЖӮИӮиӮЬӮ·ҒB Һ–ҺАҒA16җўӢIӮМ–LҗbҸGӢgӮНҒA’©‘Nҗ…ҢRӮЙғVҒ[ғҢҒ[ғ“Ӯр”jүуӮіӮкӮҪӮҪӮЯӮЙҒA’©‘NҸo•әӮЙҺё”sӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ҒB –ҫҺЎӮМ“ъ–{ӮНҒA“ҜӮ¶“QӮр“ҘӮЮӮнӮҜӮЙӮНӮўӮ«ӮЬӮ№ӮсҒBӮаӮөӮағҚғVғAӮЙ“ъ–{ӢЯҠCӮМҗ§ҠCҢ Ӯр’DӮнӮкӮҪӮзӮЗӮӨӮИӮйӮМӮ©ҒH•ә—НӮр‘е—ӨӮЙ‘—ӮкӮИӮӯӮИӮйӮҫӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҚz•ЁҺ‘Ң№ӮНӮЁӮлӮ©ҒAҗH—ҝӮ·Ӯз—A“ьӮЕӮ«ӮИӮӯӮИӮБӮҪ“ъ–{Қ‘ӮНҒAҚ‘–ҜӮМҗ¶ҠҲӮрҺзӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёӮЙүу–ЕӮөӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮұӮЕ•ЁӮрҢҫӮӨӮМӮНҒAӮвӮНӮиҒuҠCҢR—НҒvӮЕӮ·ҒB“ъ–{ӮНҒAғCғMғҠғXӮЖ“Ҝ—lҒAүҪӮӘүҪӮЕӮаҠCҢRӮрӢӯӮӯӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҚ‘ӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМ“–ҺһӮНҒAҢRҠНӮМҢҡ‘ўӢZҸpӮӘ“ъҗiҢҺ•аӮМҗЁӮўӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—L—lӮНҒA90”N‘гӮМғpғ\ғRғ“ҺsҸкӮМҸуӢөӮЙ—ЗӮӯҺ—ӮДӮўӮЬӮ·ҒBӢZҸpӮМҗҲӮрҸWӮЯӮДҢҡ‘ўӮөӮҪҚЕҗVүsҗнҠНӮНҒAӮнӮёӮ©3”NҢгӮЙӮН’В•…ү»ӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮіӮДҒA–ҫҺЎҗӯ•{ӮНҒA‘nҗЭ“–ҸүӮ©ӮзҚ‘–hӮЙ‘еӮўӮЙҗ_ҢoӮрҢӯӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҚЕҸүӮНҒA“ъ–{—с“ҮӮМҠCҠЭүҲӮўӮЙӢҗ‘еӮИ‘е–CӮрҗҳӮҰӮВӮҜӮДҒA“GҚ‘ӮМҠН‘DӮМҗN“ьӮЙ”хӮҰӮЬӮөӮҪҒB—бӮҰӮОҒAҚЎ“ъӮМҺбҺТғXғ|ғbғgҒuӮЁ‘дҸкҒvӮНҒAӮаӮЖӮаӮЖӮұӮӨӮөӮҪ‘е–CӮМҒu‘дҸк(ҒҒҗҳ•tҸк)ҒvӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮвӮӘӮДҒA“ъ–{ӮМҚ‘—НӮӘҗL’ЈӮөӮД—ҲӮйӮЖҒAҚЎ“xӮНҢRҠНӮрҸWӮЯӮДҠCҢRӮрҢҡҗЭӮөӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМӢZҸp—НӮЕӮНҒAӢҗ‘еӮИҗнҠНӮрҢҡ‘ўӮ·ӮйӮұӮЖӮНҸo—ҲӮЬӮ№ӮсҒBҸ]ӮБӮДҒAҺе—НҠНӮЙӮВӮўӮДӮНҒAүў•ДӮ©ӮзӢҗҠzӮМҺ‘ӢаӮрӮНӮҪӮўӮДҚw“ьӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮёҒAӮұӮұӮЕҢ–Ң–жҖжҖӮМӢcҳ_ӮӘӢNӮ«ӮЬӮөӮҪҒB•nӮөӮў“ҮҚ‘ӮЕӮ ӮБӮҪ“ъ–{ӮНҒA–RӮөӮўҚ‘”пӮМҢӯӮиҢJӮиӮЙӢкҳJӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕҒAӮИӮйӮЧӮӯҲАүҝӮИҺOӢүҠНӮрҚw“ьӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨҲУҢ©ӮӘҲі“|“I‘Ҫҗ”ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮкӮЙҲЩӢcӮрҸҘӮҰӮҪӮМӮӘҒAҠCҢR‘еҗbӮҫӮБӮҪҺR–{Ң •әүqӮЕӮ·ҒB”ЮӮНҒA“ъҗiҢҺ•аӮМҢҡҠНӢЈ‘ҲӮЙ’Қ–ЪӮөҒAҒuӮИӮйӮЧӮӯҚӮүҝӮЕҚӮҗ«”\ӮМҠН‘DӮрҚw“ьӮ·ӮйӮЧӮ«ӮҫҒvӮЖҺе’ЈӮө‘ұӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB”ЮӮМҗа“ҫ—НӮ Ӯй•ЩҗгӮНҺҹ‘жӮЙҺьҲНӮр“®Ӯ©ӮөҒAӮ»ӮөӮД“ъ–{ҠCҢRӮНҒAҗўҠEҚЕҚӮӮМҗ«”\ӮрҺқӮВғCғMғҠғXҗ»ҢRҠНӮр‘өӮҰӮҪҲк‘еҠН‘аӮЦӮЖҗ¬’·ӮөӮДҚsӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЕҠl“ҫӮөӮҪ”…ҸһӢаӮМ–wӮЗӮӘҒAҢRҠНӮМҚw“ьӮЙҺgӮнӮкӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB ҺR–{ҠC‘ҠӮМӮұӮМҢ©ҺҜӮМҚӮӮіӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮрҸҹ—ҳӮЙ“ұӮӯҢҲ’и“IӮИ—vҲцӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ3ҒDҠJҗн | |
|
ҒЎ(1) ҠпҸPҚUҢӮ
“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA“ъ–{ҢRӮМҠпҸPҚUҢӮӮЙӮжӮБӮД–ӢӮрҠJӮҜӮЬӮөӮҪҒB —ӨҢRӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮМҗјҠЭӮЙ‘еҢRӮр‘—ӮиҚһӮЭҒAҠCҢRӮНҒAҗ…—Ӣҗн‘аӮр—·ҸҮҚ`ӮЙҗц“ьӮіӮ№ӮДҒAғҚғVғA—·ҸҮҠН‘аӮЙ–йҠФӢӣ—ӢҚUҢӮӮрҺdҠ|ӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҺһӮЙҒA1904”N(–ҫҺЎ37”N)2ҢҺ8“ъҒB •sҲУӮрҸХӮ©ӮкӮҪғҚғVғAҢRӮНҒA‘е‘№ҠQӮрҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB ҠщӮЙҚ‘ҢрӮН’fҗвӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“–ҺһӮМҚ‘ҚЫ–@ӢKӮЕӮНҒAҚ‘ҢрӮӘ’fҗвӮөӮҪҚ‘үЖҠФӮЙӮНҒAҗйҗн•zҚҗ–іӮөӮМҚUҢӮӮӘ”FӮЯӮзӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒA“ъ–{ҢRӮМҠпҸPҚUҢӮӮН”ЪӢҜӮИйxӮЬӮө“ўӮҝӮЕӮНӮИӮӯҒAҚ‘ҚЫ“IӮЙ”с“пӮр—ҒӮСӮйӮұӮЖӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮӘ•sҲУӮрҸХӮ©ӮкӮҪ—қ—RӮНҒAӮвӮНӮи“ъ–{ӮрҢyӮсӮ¶ӮДӮўӮҪӮұӮЖӮЖҒAӮаӮЖӮаӮЖ•…ӢҖҠҜ—»‘МҺҝӮЕӮ ӮйӮӘӮдӮҰҒAҸоҗЁ”»’fӮӘҺGӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯӮИӮМӮЕӮөӮеӮӨҒBҠпҸPӮрҺуӮҜӮҪ—·ҸҮҚ`ӮЕӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМҠCҢRҺmҠҜӮӘҸг—ӨӮөӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМ‘ҪӮӯӮНғpҒ[ғeғBҒ[ӮЕ•ӮӮ©Ӯк‘ӣӮўӮЕӮўӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮўӮжӮўӮжҗн‘ҲӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒAғҚғVғAӮНҒAҺ©ҢRӮМ•s—ҳӮИҸоҗЁӮЙҸүӮЯӮДӢCӮГӮўӮДңұ‘RӮЖӮөӮЬӮ·ҒBӢЙ“ҢӮЙӮНӮЩӮЖӮсӮЗ—ӨҢRӮр’uӮўӮДӮЁӮзӮёҒAҠCҢRӮа“ъ–{ӮЙ—тӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҢRҠНӮМҗ”ӮН“ъ–{ӮЙ•C“GӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӢҢҺ®ҠНӮӘ‘ҪӮӯӮДҒAӮЖӮДӮағCғMғҠғXҗ»ӮМҚӮҗ«”\ҠНӮЕҗиӮЯӮзӮкӮй“ъ–{ҠCҢRӮЙҸҹӮДӮйӮЖҺvӮҰӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮұӮЕ”ЮӮзӮНҒA’·ҠъҺқӢvҗнӮМҚ\ӮҰӮЙ“ьӮиҒAӮ»ӮөӮД–{Қ‘Ӯ©ӮзӮМ‘қүҮӮр‘ТӮБӮДҢҲҗнӮр’§ӮЮ•ыҺ®ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAӮНҒAғhғCғcӮЖӮМҚ‘Ӣ«ӮЙҗ”•S–ңӮМ‘еҢRӮр—iӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮрғVғxғҠғA“S“№ӮЕӢЙ“ҢӮЙ‘—ӮиҚһӮЯӮОҒA—Ө•әӮМҗ”ӮЕ“ъ–{ӮрҲі“|ӮЕӮ«ӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB ӮЬӮҪҒAғҚғVғAӮНғҲҒ[ғҚғbғpӮМғoғӢғgҠCӮЖҚ•ҠCӮЙӮ»ӮкӮјӮк‘еӢK–НӮИҠН‘аӮрҺқӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒAӮұӮкӮрӢЙ“ҢӮЙ‘—ӮиҚһӮЯӮОҒAӮвӮНӮиҗ”ӮМҸгӮЕ“ъ–{ҠCҢRӮрҲі“|ӮЕӮ«ӮйӮНӮёӮИӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДҒA“ъ–{ӮНҒAӮұӮӨӮөӮҪҸоҗЁӮр’mҺ»ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒAғҚғVғAҢRӮӘ‘қүҮӮр“ҫӮДӢӯү»ӮіӮкӮй‘OӮЙҒAӢЙ“Ң’nҲжӮр“dҢӮ“IӮЙҗ§ҲіӮөӮДҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮаӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНҒA—ӨҠCӮЖӮаӮЙҒAӮЬӮіӮЙҺһҠФӮЖӮМҗнӮўӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) •ВҚЗҚмҗн
ғҚғVғAҢRӮӘҺзӮиӮЙ“ьӮБӮҪӮҪӮЯҒA“––КӮМ“ъ–{ҢRӮМҗiҢӮӮНӢЙӮЯӮДҸҮ’ІӮЕӮөӮҪҒB ӢЙ“ҢғҚғVғAҠCҢRӮМҺе—НӮНҒA—·ҸҮҚ`ӮрҠо’nӮЖӮ·ӮйҒu—·ҸҮҠН‘аҒvӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМҗн—НӮНҒA“ъ–{ҠН‘аӮЖӢK–НӮМҸгӮЕ•C“GӮөӮДӮўӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒA—vҚЗү»ӮіӮкӮҪ—·ҸҮҚ`“аӮЙ—§ӮДӮұӮаӮиҒA“ъ–{ӮМ’§җнӮЙүһӮ¶ӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮ№ӮсҒB“ъ–{ҠН‘аӮНҚ`ҠOӮЕҗШҺ•қNҳrӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМӮЁүAӮЕ“ъ–{ӮМ—A‘—‘D’cӮНҲА‘SӮЙү©ҠCӮрүҹӮө“nӮиҒA’©‘N”ј“ҮӮМӮЭӮИӮзӮё—Й“Ң”ј“ҮӮМ“мҠЭӮЙӮЬӮЕ‘е—КӮМ—Ө•әӮр—g—ӨӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB —Й“Ң”ј“ҮӮрҺзӮБӮДӮўӮҪғҚғVғA—ӨҢRӮНҒAӮаӮЖӮаӮЖ•ә—НӮӘҸӯӮИӮ©ӮБӮҪҸгӮЙҒA–Ў•ыӮМҠCҢRӮӘ–р—§ӮҪӮёӮЕҒA“G•әӮМ—g—ӨӮрҠИ’PӮЙӢ–ӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒA—LҢшӮИ”ҪҢӮӮрҚsӮҰӮЬӮ№ӮсҒBҸ¬ӢЈӮиҚҮӮўӮрҢJӮи•ФӮөӮИӮӘӮз–һҸBӮМүң’nӮЦӮЖ“P‘ЮӮөӮДҚsӮ«ӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғA—ӨҢRӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзӮМ‘қүҮӮр‘ТӮБӮДӮ©Ӯз”ҪҢӮӮЙ“]Ӯ¶Ӯй•ыҗjӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ҳк•ыҒA“ъ–{—ӨҢRӮНҒA3ӮВӮМғӢҒ[ғgӮЕ—Й“Ң”ј“ҮӮр–kҸгӮөҒA—Й—zҺsӮЕҚҮ—¬ҒBӮ»ӮМҢгҒAҲкӢCӮЙ–һҸBӮМғҚғVғAҢRҺе—НӮЙҢҲҗнӮр’§ӮЮҺиӮНӮёӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМҗiҢӮӮНҒAӢЙӮЯӮДҸҮ’ІӮЙҗiӮЭӮЬӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{ҢRӮМҢлҺZӮНҒAҒu—·ҸҮҠН‘аӮӘҳUҸйӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒvҺ–ӮЕӮ·ҒB—·ҸҮҠН‘аӮНҒAӮаӮҝӮлӮсү°•aӮҫӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB”ЮӮзӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғp•ы–КӮ©ӮзӮМ‘қүҮӮр‘ТӮҝҒAӮұӮкӮЖҚҮ—¬ӮөӮҪҢгӮЕҒA“ъ–{ҠCҢRӮЙҢҲҗнӮр’§ӮЮ•ыҗjӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҚӮҗ«”\ҠНӮӘ‘ҪӮў“ъ–{ҠCҢRӮЖӮўӮҰӮЗӮаҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮМ“GӮЖ—·ҸҮӮМ“GӮМҚҮ—¬ӮрӢ–Ӯ№ӮОҒA”ЮүдӮМҗн—Н”дӮН2ҒF1ӮЖӮИӮиҒAҸҹӮҝ–ЪӮН–іӮӯӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮВӮЬӮиҒA“ъ–{ҢRӮӘҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮМғҚғVғAҠН‘аӮӘ—ҲүҮӮ·Ӯй‘OӮЙҒAүҪӮЖӮөӮДӮЕӮа—·ҸҮҠН‘аӮр’ЧӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “xҸdӮИӮй’§”ӯӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAӮЗӮӨӮөӮДӮаҸoӮДӮ«ӮДӮӯӮкӮИӮў—·ҸҮҠН‘аӮр‘OӮЙҒA“ъ–{ҠCҢRӮНғҶғjҒ[ғNӮИҚмҗнӮрҲДҸoӮөӮЬӮ·ҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒAҒu•ВҚЗҚмҗнҒvӮЕӮ·ҒBҸoӮДӮұӮИӮўӮИӮзҒAүiү“ӮЙҸoӮзӮкӮИӮӯӮөӮДӮөӮЬӮЁӮӨҒAӮЖӮўӮӨҚмҗнӮЕӮ·ҒBӮВӮЬӮиҒAӢҢҺ®ӮМҸӨ‘D’cӮрҒAҳpҢыӮӘӢ·ӮӯӮДҗ…җ[ӮМҗуӮў—·ҸҮҚ`ӮМ“ьҢыӮЙ’ҫӮЯҒAӮаӮБӮД—·ҸҮҠН‘аӮрҚ`“аӮЙ••Ӯ¶ҚһӮЯӮД‘қүҮӮЖӮМҚҮ—¬Ӯр–WӮ°ӮжӮӨӮЖӮўӮӨҚмҗнӮИӮМӮЕӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒA3ҺҹӮЙ“nӮБӮД“WҠJӮіӮкӮҪӮұӮМҚмҗнӮНҒAғҚғVғAӮМҠCҠЭ–C‘дӮвӢм’ҖҠНӮМҠҲ–фӮЕҺё”sӮЙҸIӮнӮиӮЬӮ·ҒB—L–јӮИңAҗЈ•җ•v’ҶҚІӮӘҗнҺҖӮөӮҪӮМӮНҒAӮұӮМҚмҗн’ҶӮМҸo—ҲҺ–ӮЕӮөӮҪҒB ҒuӮұӮӨӮИӮБӮҪӮзҒA—ӨҸгӮ©ӮзҚUҢӮӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўҒv ‘е–{үcӮНҒA—·ҸҮҚ`Ӯр—Ө‘ӨӮ©ӮзҚUҢӮӮ·ӮйӮЧӮӯҒAҗVӮҪӮЙҒu‘ж3ҢRҒvӮр•Тҗ¬ӮөӮЬӮ·ҒBҺwҠцҠҜӮНҒA”T–ШҠу“T‘еҸ«ӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) ғVҒ[ғҢҒ[ғ“ӮМҚU–h
‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҒA“ъ–{ӮМғAғLғҢғXдFӮНғVҒ[ғҢҒ[ғ“ӮЕӮ·ҒBҺ‘Ң№ӮМ–RӮөӮўӮұӮМ“ҮҚ‘ӮНҒAғVҒ[ғҢҒ[ғ“ӮрҗШ’fӮіӮкӮҪӮзҺ©–ЕӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAғҚғVғAҢRӮаӮ»ӮМҺ–Ӯр’mҺ»ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAҠCҢRӮНҒA“ъ–{ҠCӮЙ–КӮөӮҪғEғүғWғIғXғgғbғNҚ`ӮЙӮаҠН‘аӮр•Ы—LӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҸ„—mҠН4җЗӮр’ҶҗSӮЖӮөӮҪҒuғEғүғWғIғXғgғbғNҠН‘аҒvӮЕӮ·ҒBӮұӮМҠН‘аӮНҸ¬ӢK–НӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{ҢRӮНӮ ӮЬӮиҸdҺӢӮөӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҸ¬•әӮӘҒAҺvӮнӮКӢәҲРӮЙҗ¬’·ӮөӮД“ъ–{ӮрӢкӮөӮЯӮйӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ҠCҢRӮМҺе—НӮӘҒA—·ҸҮү«ӮЕ“B•tӮҜӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮрҢ©ӮДҺжӮБӮҪғGғbғZғ“’с“ВӮНҒAҗПӢЙүКҠёӮЙғEғүғWғIғXғgғbғNҠН‘аӮр“®Ӯ©ӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮМҸ¬•әҠН‘аӮНҒA“ъ–{ҠCӮ©ӮзҢәҠE“еӮЦҒAӮіӮзӮЙӮН’ГҢyҠCӢ¬ӮрүzӮҰӮД–[‘Қ”ј“ҮӮ©Ӯз“ҢӢһҳpӮЦӮЖ“]Ӯ¶ҒA—с“ҮүҲҠЭӮМ“ъ–{ӮМҸӨ‘DӮв—A‘—‘DӮр•Р’[Ӯ©ӮзҢӮ’ҫӮөӮДүсӮБӮҪӮМӮЕӮ·(4ҢҺҒ`7ҢҺ)ҒB “ъ–{Қ‘–ҜӮНҒAҗkӮҰҸгӮӘӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМҸоҗЁӮрҠлӮФӮсӮҫ“ъ–{ҠCҢRӮНҒAҸг‘ә•F”VҸе’с“ВӮМҠН‘аӮрҺе—НӮ©Ӯз•Ә”hӮөӮД(‘ж2ҠН‘а)ҒAғEғүғWғIҠН‘аӮМ’ЗҢӮӮЙ“–ӮҪӮзӮ№ӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮкӮјӮкғҸғ“ғZғbғgӮМҠН‘аӮӘ’ЗӮўӮ©ӮҜӮБӮұӮрӮөӮДӮаҒAӮИӮ©ӮИӮ©‘ҳӢцӮЕӮ«ӮйӮнӮҜӮӘӮИӮўҒB“ъ–{—с“ҮӮЖӮўӮӨ–јӮМғeҒ[ғuғӢӮМҺьӮиӮрғOғӢғOғӢӮЖүсӮйҒAғgғҖӮЖғWғFғҠҒ[ӮЭӮҪӮўӮИ—l‘ҠӮр’жӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ‘D”•ӮМ”нҠQӮН“ъӮр’ЗӮБӮДҚLӮӘӮиҒAҚ‘–ҜӮМҗнҲУӮНҗҠӮҰӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{Қ‘ӮМҺқӮВ’v–Ҫ“IӮИҺг“_ӮНҒAҠJҗнҷң“ӘӮМҺһ“_ӮЕҒAҗн‘Ҳ‘S‘МӮрҠл–wӮЙҠЧӮзӮ№ӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(4) җўҠEҚЕӢӯӮМ—vҚЗ
ӮіӮДҒAӢTӮМҺqӮМӮжӮӨӮЙҚ`“аҗ[ӮӯӮЙ•ВӮ¶ӮұӮаӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮр“|Ӯ·ӮЧӮӯҒA“ъ–{—ӨҢR‘ж3ҢRӮН—Й“Ң”ј“ҮӮр“мүәӮөҒAӮ»ӮөӮД—·ҸҮҚ`Ӯр•пӮЭҚһӮЮӮжӮӨӮЙҚLӮӘӮйӢҗ‘еӮИ—vҚЗӮр•пҲНӮөӮЬӮөӮҪҒB —·ҸҮӮНӮҪӮўӮЦӮс”ьӮөӮўҠXӮЕӮ·ӮӘҒAӢҗ‘еӮИҢRҚ`ӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЙҒAҠX‘S‘МӮрҺжӮиҲНӮЮҺRҠx’n‘СӮрғRғ“ғNғҠҒ[ғgӮЖҸe–CӮЕ–„ӮЯҗsӮӯӮөӮҪҒAҗўҠEҚЕӢӯӮМ—vҚЗӮЕӮаӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ҢRӮМҚЕ‘еӮМҢлҺZӮНҒAӮұӮМ“sҺsӮӘ—vҚЗү»ӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮрҒu’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒvӮұӮЖӮЕӮ·ҒBҺQ–d‘Қ’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮИӮЗӮНҒAҒu—·ҸҮӮИӮЗҒA’|–о—ҲӮЕҲНӮБӮДӮЁӮўӮДҒA“G•әӮр•ВӮ¶ҚһӮЯӮкӮОӮ»ӮкӮЕҚПӮЮӮМӮҫҒvӮИӮЗӮЖҚӢҢкӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮаӮЖӮаӮЖ“ъ–{—ӨҢRӮНҒA—·ҸҮӮрҚUҢӮӮ·ӮйҢvүжӮрҺқӮБӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB—·ҸҮӮНҠCҢRӮЙ”CӮ№ӮДҒAҺ©•ӘӮҪӮҝӮН–һҸBүң’nӮМҺеҗнҸкӮЙ“Бү»ӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA—·ҸҮӮМҸуӢөӮЙӮВӮўӮД–і’mӮЕӮ ӮБӮДӮаҒAӮ»ӮкӮНӮ»ӮкӮЕҺd•ыӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒB ӮұӮМӮұӮЖӮ©ӮзӮа•ӘӮ©ӮйӮжӮӨӮЙҒA“ъ–{ӮМ—ӨҢRӮЖҠCҢRӮНҒAӮ·ӮЕӮЙӮұӮМ“–ҺһӮ©Ӯз•s’ҮӮЕҒAҢЭӮўӮМҸо•сӮӘ•Ә—§ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкӮӘ”ЯҢҖӮрҸөӮ«ӮЬӮ·ҒB Ӣ}‘ўӮМ‘ж3ҢRӮНҒAҸо•сӮа•ә—НӮа•җҠн’e–тӮаҒA‘SӮДӮӘ•s‘«ӢC–ЎӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҢ»ҸкӮр’mӮзӮИӮў‘е–{үcӮв–һҸBҢRҺi—Я•”ӮНҒA”T–ШҸ«ҢRӮЙ‘ҚҚUҢӮӮрӢӯ—vӮөӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAӮұӮкӮЙүҹӮөҗШӮзӮкӮҪ”T–ШҺi—Я•”ӮНӮұӮМ—vҚЗӮЙҗі–КҚUҢӮӮрҺdҠ|ӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB 7ҢҺ26“ъӮ©ӮзӮМ‘жҲкҺҹ‘ҚҚUҢӮӮНҒAҺrӮМҺRӮМ’ҶӮЕҺё”sӮЙҸIӮнӮиӮЬӮөӮҪҒB ҚUҢӮҢR5–ңӮМӮӨӮҝҒAҺҖҸқҺТҗ”ӮНӮИӮсӮЖ1–ң5җзҒI ‘SҗнҗьӮЕҳA”s’ҶӮМғҚғVғAҢRӮНҒAӮұӮМҸоҗЁӮЙӢУҠмӮөӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
| ҒЎ4ҒDҗн‘ҲҢoҚПӮЖ’і•сҗн | |
|
ҒЎ(1) җн‘ҲӮНғJғlӮӘӮ©Ӯ©Ӯй
“ъ–{ҢRӮЙӮЖӮБӮДӮНҺАӮЙ•s–{ҲУӮИӮӘӮзҒA—·ҸҮӮМҗнӮўӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҺҖ–ҪӮрҢҲӮ·ӮйҺеҗнҸкӮЦӮЖҸёҠiӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ—қ—RӮНҒAҒuҗн‘ҲҢoҚПҒvӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒB җн‘ҲӮНҒAҗ¶ҺYҗ«ҠF–іӮМ”jүуҚsҲЧӮИӮМӮЕҒAӮҪӮҫӮРӮҪӮ·ӮзӮЙғJғlӮӘӮ©Ӯ©ӮиӮЬӮ·ҒBӮЗӮӨӮөӮДҒAӮұӮМӮжӮӨӮИӢрӮ©ӮИҚsҲЧӮрӮ·ӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHҗlҠФӮЖӮўӮӨҗ¶•ЁҺнӮМ–{ҺҝӮЙӢ^ӮўӮрҠҙӮ¶ӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮНӮіӮДӮЁӮ«ҒAӮұӮМ“–ҺһҒA“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮНӮҪӮўӮЦӮсӮИ•n–RҚ‘ӮЕҒAҚаҗӯӮӘ”сҸнӮЙ•N”—ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒAӮұӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҒA—јҚ‘ӮЖӮаҠOҚ‘Ӯ©ӮзӮМҺШӢаӮЕҗн”пӮр’І’BӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮНҺеӮЙғCғMғҠғXҺsҸкӮЕҒAғҚғVғAӮНғtғүғ“ғXҺsҸкӮЕҠOҚВӮр”ӯҚsӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮӯҒAҺШӢаӮНҒuҗM—pҒvӮӘ–іӮҜӮкӮОӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсҒBғJғlӮр‘ЭӮ·‘ӨӮНҒA—ҳ‘§ӮрҠЬӮЯӮДүсҺыӮМ–ЪҸҲӮӘ—§ӮВӮ©Ӯз‘ЭӮ·ӮМӮЕӮ·ҒBӮаӮөӮа‘Э•tҗжӮӘ”j’]ӮөӮҪӮзҒA‘ЭӮөӮҪғJғlӮН•s—ЗҚВҢ ӮЖӮИӮиҒA‘е‘№ӮрӮұӮўӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB Ң»ҚЭӮМ“ъ–{ӮЕӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМ“sҺsӢвҚsӮӘ•s—ЗҚВҢ ӮЙӢкӮөӮсӮЕӮўӮЬӮ·ӮЛҒBҗӯҺЎүЖӮвғ}ғXғRғ~ӮМҳ_’ІӮЕӮНҒAӮ ӮҪӮ©ӮаҒu“VҚРҒvӮЭӮҪӮўӮЙҲөӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮН‘еӮ«ӮИҠФҲбӮўӮЕӮ·ҒB•s—ЗҚВҢ ӮЖӮўӮӨӮМӮНҒA’PӮИӮйҒuҢoүcӮМҺё”sҒvӮЕӮ·ҒBӢвҚsӮӘҒA‘ЭӮөӮДӮНӮИӮзӮИӮў‘ҠҺиӮЙғJғlӮр‘ЭӮөӮҪӮ©ӮзӮ ӮсӮИӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮИӮМӮЙҒAӮЗӮӨӮөӮДӢвҚsӮМ–і”\ӮИҢoүcҗwӮНҗУ”CӮрҺжӮзӮИӮўӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮЗӮӨӮөӮДҒA”ЮӮзӮМҗKӮр’@ӮўӮҪҚа–ұҠҜ—»ӮЗӮаӮНҗУ”CӮрҺжӮзӮИӮўӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHҢц“IҺ‘ӢаӮМ“Ҡ“ьӮЖӮ©Һиҗ”—ҝӮМ’lҸгӮ°ӮЖӮ©ҒA—vӮ·ӮйӮЙҒAҸҺ–ҜӮЙ‘SӮДӮрүҹӮө•tӮҜӮД’mӮзӮсҠзӮИӮМӮНӮўӮ©ӮӘӮИӮаӮМӮ©ҒHӮұӮМҚ‘ӮНҒAӮЬӮБӮҪӮӯ–іҗУ”CӮЕ‘К–ЪӮИҚ‘ӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪӮИҒB ӮЖӮаӮ ӮкҒA“ҠҺ‘ӮЖӮўӮӨӮМӮНҒAӮ»ӮкӮӯӮзӮўӮЙ“пӮөӮўӮаӮМӮИӮМӮЕӮ·ҒB ӮіӮДҒAҠOҚВҺsҸкӮЕӮНҒA“–ҸүӮНғҚғVғAҚВӮМ•ыӮЙҗlӢCӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮИӮәӮИӮзҒAҠOҚВӮрҚw“ьӮ·Ӯй“ҠҺ‘үЖӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA“ъ–{ӮжӮиӮағҚғVғAӮМ•ыӮӘӢӯӮўӮҫӮлӮӨӮ©ӮзҒAғҚғVғAӮЙ“ҠҺ‘ӮөӮҪ•ыӮӘӮжӮиҲА‘SӮҫӮЖҺvӮнӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМӮҪӮЯҒA“ъ–{ӮМҺ‘Ӣа’І’BӮНҒAҚӮӢҙҗҘҗҙӮзӮӘ–z‘–ӮөғCғMғҠғXҗӯ•{ӮМғoғbғNғAғbғvӮрҺуӮҜӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮё“пҚqӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМӮЖӮ«ҒAғAғҒғҠғJҺsҸкӮМғҶғ_ғ„Қа”ҙӮӘҸ•ӮҜҸMӮрҸoӮөӮДӮӯӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“–ҺһӮМғҚғVғAӮНҒAҚ‘“аӮМғҶғ_ғ„җlӮЙ‘е’eҲіӮрүБӮҰӮДӮўӮЬӮөӮҪӮ©ӮзҒA“Ҝ–EӮМӢкӢ«ӮЙ”YӮЮғҶғ_ғ„Қа”ҙӮНҒAӮЮӮөӮл“ъ–{ӮрүһүҮӮөӮД“ъ–{ӮЙҸҹӮБӮДӮаӮзӮўӮҪӮўӮЖҠиӮўҒAҠOҚВӮр‘е—КӮЙҲшӮ«ҺуӮҜӮДӮӯӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮДҒA“ъ–{ӮН“––КӮМҗн”пӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮкӮҫӮБӮДҺһҠФӮМ–в‘иӮЕӮ·ҒBӮаӮөӮа“ъ–{ӮӘҗнҸкӮЕ—тҗЁӮр‘ұӮҜӮйӮжӮӨӮИӮзҒA“ҠҺ‘үЖӮМӢ»–ЎӮНӮЬӮ·ӮЬӮ·ғҚғVғAҚВӮЙҲЪӮиҒA“ъ–{ӮНӮўӮёӮкҺ‘ӢағVғҮҒ[ғgӮЙҠЧӮйӮЕӮөӮеӮӨҒB ҚKӮўҒA“ъ–{ҢRӮНҗнҸкӮЕҳAҗнҳAҸҹӮЕӮөӮҪҒBғҚғVғAҠCҢRӮН—·ҸҮӮЙ•ВӮ¶ҚһӮЯӮзӮкҒAғҚғVғA—ӨҢRӮНӮЗӮсӮЗӮс–k•ыӮЙ“ҰӮ°ӮДҚsӮ«ӮЬӮ·ҒB ӮұӮМҢӢүКҒA“ъ–{ҚВӮНҚӮ“«ӮөҒAӢtӮЙҒAғҚғVғAҚВӮН”ғӮўҺиӮӘ•tӮ©ӮИӮӯӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒAғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮДҗн‘ҲҗӢҚsҸгӮМҺҖҠҲ–в‘иӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮсӮИ–оҗжҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҗнӮўӮӘӢNӮұӮиҒA“ъ–{ҢRӮН‘е‘№ҠQӮрҸoӮөӮДҢӮ‘ЮӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҗӯ•{ӮНӮұӮМҸҹ—ҳӮр‘еҒX“IӮЙҗй“`ӮөҒAҒu—·ҸҮ—vҚЗ–і“Gҗ_ҳbҒvӮр‘n‘ўӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮҪӮЯҒAҠOҚВҺsҸкӮЕӮНҚДӮСғҚғVғAҚВӮӘҗlӢCӮрҺжӮи–ЯӮөӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA“ъ–{ӮНғҚғVғAӮМҗн‘ҲҗӢҚs”\—НӮр”jүуӮ·ӮйӮҪӮЯҒAүҪӮӘүҪӮЕӮа—·ҸҮ—vҚЗӮрҠЧ—ҺӮіӮ№ҒAӮ»ӮМ–і“Gҗ_ҳbӮр“ЛӮ«•цӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮӯӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ҳк•”ӮМ—рҺjҸ¬җаӮЙӮНҒAҒu—·ҸҮ—vҚЗӮрҚU—ӘӮ·Ӯй•K—vӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB203ҚӮ’nӮҫӮҜӮр—ҺӮЖӮ№ӮО—ЗӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒvӮИӮЗӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮНҠФҲбӮўӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) ӢаҺq“БҺgӮЖ–ҫҗО‘еҚІ
ӮЖӮұӮлӮЕҒAӮЗӮсӮИӮЙҗнҸкӮЕҸҹ—ҳӮрҸdӮЛҒAӮЗӮсӮИӮЙҺ‘ӢаҢJӮиӮӘү~ҠҠӮЙӮИӮБӮДӮаҒAҗн‘ҲӮ»ӮМӮаӮМӮрҸIҢӢӮіӮ№Ӯй•ыҚфӮр—§ӮДӮЛӮОҲУ–ЎӮӘӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB “–ҺһӮМ“ъ–{җӯ•{ӮНҒA”сҸнӮЙ—pҲУҺь“һӮЕӮөӮҪҒB ӮЬӮёӮНғAғҒғҠғJӮЙҒAғZғIғhғAҒEғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғg‘е“қ—МӮМҠw—FӮЕӮ ӮБӮҪӢаҺqҢҳ‘ҫҳYӮрҒAҠOҢр“ҷ“БҺgӮЖӮөӮД‘—ӮиҚһӮЭӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮМ”C–ұӮНҒAғAғҒғҠғJ‘е“қ—МӮЙҗHӮў“ьӮБӮДҒAҺһӢXӮрҠOӮіӮёҳa•ҪӮМ’ҮүоӮрҚsӮнӮ№ӮөӮЯӮйӮұӮЖӮЕӮөӮҪҒBғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮНҒAӮұӮМҗн‘ҲӮМ‘SҠъҠФӮр’КӮ¶ҒAғ^ғCғ~ғ“ғOӮрҢ©ҢvӮзӮБӮДҳa•ҪүпӢcӮМҠJҚГӮрғҚғVғAҗӯ•{ӮЙ’сҲДӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМүeӮЙӢаҺq“БҺgӮМҠҲ–фӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӢаҺqӮНӮЬӮҪҒAғAғҒғҠғJҠe’nӮМғpҒ[ғeғBҒ[ӮЙҸoҗИӮөӮҪӮиҗV•·ӮЙ“ҠҚeӮрӮөӮҪӮиӮЖҒAғAғҒғҠғJҗўҳ_ӮМҗe“ъҠҙҸоӮр‘қҗiӮ·ӮйҸгӮЕ‘еҠҲ–фӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҒA“ъ–{җӯ•{ӮНҒAғXғEғFҒ[ғfғ“ӮЙ–ҫҗОҢі“сҳY‘еҚІӮр‘е—КӮМӢаүтӮЖӮЖӮаӮЙ‘—ӮиҚһӮЭӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮМ”C–ұӮНҒAғҚғVғAҚ‘“аӮМ”Ҫҗӯ•{ҠҲ“®үЖӮЙүҮҸ•Ӯр—^ӮҰҒAӮұӮкӮрӮаӮБӮДүўҸBӮМғҚғVғAҢRӮМ“ҢҗiӮрҗ§–сӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAғҚғVғA–ҜҸOӮМ”ҪҗнҠҙҸоӮрҗшӮи—§ӮДӮДҒAғҚғVғA’йҚ‘ӮЙ’·ҠъҗнӮМҗӢҚsӮр’f”OӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB–ҫҗО‘еҚІӮМҗЪҗG‘ҠҺиӮЙӮНҒAӮ ӮМғҢҒ[ғjғ“ӮаӮўӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAғyғeғӢғuғӢғNӮЕӮМ‘е–\“®(ҢҢӮМ“ъ—j“ъҺ–ҢҸ)ӮвҚ•ҠCҠН‘аӮЕӮМҗнҠНғ|ғ`ғҮғҖғLғ“ҚҶӮМ”Ҫ—җӮМүeӮЙӮНҒA–ҫҗО‘еҚІӮ©ӮзҢRҺ‘ӢаӮрӮўӮҪӮҫӮўӮҪҺРүпҺеӢ`ҠҲ“®үЖӮМҺpӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒuҠv–ҪҒvӮМ“с•¶ҺҡӮЙӢәӮҰҒAҺҹ‘жӮЙ“ъҳIҗн‘ҲӮМ‘ҒҠъҸIҢӢӮрҚlӮҰӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB–ҫҗО‘еҚІӮМҠҲ–фӮНҒAҒuҗ”ҢВҺt’cӮЙ‘Ҡ“–Ӯ·ӮйҒvӮЖҢҫӮнӮкӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкҲИҠOӮЙӮаҒA“ъ–{ӮНҗўҠEҠe’nӮЙ’і•сҲхӮвҠOҢрҠҜӮр‘—ӮиҚһӮЭҒAҗўҳ_‘ҖҚмӮвҸо•сҺыҸWӮЙ‘S—НӮрҗsӮӯӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮҪ‘җӮМҚӘӮМҠҲ–фӮӘҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ”sӮрҢҲӮ·ӮйҸd—vӮИғLҒ[ӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) •Я—ё—DӢцҗӯҚф
“ъҳIҗн‘Ҳ“–ҺһӮМ“ъ–{ҢRӮНҒAҚ‘ҚЫ–@ӮрӮжӮӯҠwӮСҒAӮ»ӮкӮЙҠ®‘SӮЙҸҖӢ’ӮөӮДҗн‘ҲӮрҗiӮЯӮЬӮөӮҪҒB —бӮҰӮОҒA“а’nӮЙҲЪ‘—ӮөӮҪғҚғVғAӮМ•Я—ёӮҪӮҝӮрҒA“ъ–{‘SҚ‘ӮЙҗЭ’uӮөӮҪ•Я—ёҺы—eҸҠӮЕҗl“№“IӮИ‘ТӢцӮЕҲөӮўҒAӮЬӮҪҒu“с“xӮЖҗн‘ҲӮЙҺQүБӮөӮИӮўҒvӮұӮЖӮрҸрҢҸӮЙҒA”ЮӮзӮр’иҠъ“IӮЙғҚғVғAӮЙ‘—Ӯи•ФӮ·ӮұӮЖӮЬӮЕҚsӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҸјҺRҺы—eҸҠӮЕӮНҒA“№Ңгү·җтӮЙҚsӮБӮҪӮиҸ—ҳYү®ӮЙ’КӮӨӮұӮЖӮ·ӮзӢ–ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҒAғҚғVғA•Я—ёӮНҒA“ъ–{ӮМ•ҪӢП“IӮИ–ҜҠФҗlӮжӮиӮа—ЗӮўҗ¶ҠҲӮӘҸo—ҲӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҺ–ҺАӮНҒA“ъ–{ӮрҒu—т“ҷӮМү©җFҗlҺнҒvӮЖҢДӮсӮЕ•ҺӮйҢXҢьӮӘӮ ӮБӮҪҗј—m—сӢӯӮЙҗ[ӮўҠҙ–БӮр—^ӮҰӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮзӮНҒAҺҹ‘жӮЙ“ъ–{ӮрҒu•¶–ҫҚ‘ӮМҲкҲхҒvӮЖӮөӮД”F’mӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮӘҒAҢгӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaҸр–сӮЕҒA“ъ–{ҠсӮиӮМҚ‘ҚЫҗўҳ_ӮрҠ«ӢNӮ·ӮйҸгӮЕӮМҸd—vӮИ—vҲцӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҒAҗнҸкӮМғҚғVғA•әӮЙӮұӮӨӮөӮҪү\ӮӘҚLӮӘӮйӮЖҒAӮҪӮҫӮЕӮіӮҰү}җнӢC•ӘӮМӢӯӮў”ЮӮзӮНҒAӢtӢ«ӮЙӮИӮйӮЖӮЮӮөӮлҠмӮсӮЕ“ъ–{ҢRӮЙ“ҠҚ~Ӯ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҒuғ}ғcғ„ғ}ҒAғ}ғcғ„ғ}ҒvӮЖӢ©ӮСӮИӮӘӮзҒB•Я—ё—DӢцҗӯҚфӮНҒAҗнҸкӮЕӮа“GӮМҺmӢCӮр—ҺӮЖӮ·җнҸp“IҢшүКӮр”ӯҠцӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ·ҒB ҲИҸгӮМӮұӮЖӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮйӮжӮӨӮЙҒAӮұӮМ“–ҺһӮМ“ъ–{җӯ•{ӮНҒA–һҸBӮМҗнҸкӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒA‘SҗўҠEӮМӢа—ZҺsҸкӮвҠOҢрҠҲ“®ӮвғeғҚҺxүҮҒAӮіӮзӮЙӮНҚ‘ҚЫ–@ӮЖҚ‘ҚЫҗўҳ_ӮрҺӢ–мӮЙҺыӮЯӮҪ‘s‘еӮИ‘еҗн—ӘӮр“WҠJӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮЕӮаҒAҗн‘ҲӮЙҸҹӮВӮҪӮЯӮЙӮНҒA•KӮёӮұӮӨӮўӮӨӮвӮи•ыӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮМӮұӮЖӮНҒAҒu‘·ҺqӮМ•ә–@ҒvӮ©ӮзӮа–ҫӮзӮ©ӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮҪғOғҚҒ[ғoғӢӮИҗн—ӘҗӢҚs—НӮӘҒAӮұӮМ40”NҢгӮМҗн‘ҲӮЕҠ®‘SӮЙҺёӮнӮкӮДӮўӮҪӮМӮНҠп–ӯӮЙҺvӮҰӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМ—қ—RӮНӮаӮҝӮлӮсҒA40”NҢгӮМҗн‘ҲӮӘҒAҗӯҺЎүЖ•sҚЭӮМҒuҢRҺ–ҠҜ—»ӮМ–\‘–ҒvӮЙӮжӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДҒAҢ»ҚЭӮМ“ъ–{ӮаҒuҠҜ—»ӮМ–\‘–ҒvӮЙӮжӮБӮДҺи‘«ӮӘғoғүғoғүӮЙ“®ӮўӮДӮўӮйҸу‘ФӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮрҗҘҗіӮЕӮ«ӮіӮҰӮ·ӮкӮОҒA“ъ–{ӮН’·ҲшӮӯ•sӢөӮ©ӮзӮа—eҲХӮЙ’EӢpӮЕӮ«ӮйӮЖҺvӮӨӮМӮЕӮ·ӮӘҒEҒEҒEҒBҒ@ |
|
| ҒЎ5ҒAү^–ҪӮМ8ҢҺ | |
|
ҒЎ(1) ү©ҠCҠCҗн
ӮіӮДҒAҳbӮрҗнҸкӮЙ–ЯӮөӮЬӮөӮеӮӨҒB ҠJҗн“–ҸүӮНҸБӢЙ“IӮҫӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮНҒA4ҢҺӮЙ“ьӮйӮЖҒAҺmӢCӮрҚӮ—gӮіӮ№ӮйӮҪӮЯӮЙӮөӮОӮөӮОҚ`ҠOӮЕ“ъ–{ҠН‘аӮЖ–CҗнӮрҚsӮӨӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҗV”CӮМғ}ғJғҚғt’с“ВӮӘ—L”\ӮҫӮБӮҪӮҪӮЯӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAғ}ғJғҚғtӮӘҚАҸжӮөӮДӮўӮҪҗнҠНғyғgғҚғpғ”ғҚғtғXғNӮӘӢ@—ӢӮЙҗGӮкӮДҚҢ’ҫӮөҒA’с“ВӮӘҗнҺҖӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ’ЦҺ–ӮӘҸo—ҲӮөӮҪӮҪӮЯӮЙҒAӮ©ӮҰӮБӮДҺmӢCӮӘүәӮӘӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪ(4ҢҺ13“ъ)ҒBүҪӮЖӮўӮӨ•sү^ҒBҢг”CӮМғEғCғgғQғtғg’с“ВӮНӮвӮйӢCӮрӮИӮӯӮөҒAӮұӮӨӮөӮД—·ҸҮҠН‘аӮНҒAҚДӮСҚ`“аӮЙ•ВӮ¶ӮұӮаӮБӮҪӮЬӮЬӮЖӮИӮиӮЬӮ·ҒB ӮвӮӘӮД8ҢҺӮЙ“ьӮйӮЖҒA—·ҸҮӮр•пҲНӮөӮҪ”T–Ш‘ж3ҢRӮЙӮжӮй–CҢӮӮЙӮжӮБӮДҒAҺRүzӮөӮЙ”тӮСҚһӮсӮЕ—ҲӮй–C’eӮМүJӮЙҸЕӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮНҒAӮұӮМҠлҢҜӮИҚ`Ӯр’EҸoӮөӮДғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙҢьӮ©ӮЁӮӨӮЖҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӢvӮөӮФӮиӮЙҸoҢӮӮөӮҪӮұӮМ‘еҠН‘аӮНҒAӮҪӮҝӮЬӮҝ“ъ–{ҠCҢRӮМҢxүъ–ФӮЙҲшӮБӮ©Ӯ©ӮиҒAӮЁӮБӮЖӮи“ҒӮЕӢмӮҜӮВӮҜӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY’с“ВӮМ‘ж1ҠН‘аӮЖ–CҢӮҗнӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮӘҒAҒuү©ҠCҠCҗнҒvӮЕӮ·(8ҢҺ10“ъ)ҒB “ҢӢҪ’с“ВӮНҒAӮөӮ©Ӯө—·ҸҮҠН‘аӮМҲУҗ}ӮрҗіӮөӮӯ”cҲ¬ӮөӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB“GӮӘҒAҢҲҗнӮр’§ӮЭӮЙ—ҲӮҪӮаӮМӮЖҠЁҲбӮўӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA—·ҸҮҠН‘аӮӘҒAҢ„ӮрҢ©ӮД“ъ–{ҠН‘аӮЖӮМ–CҢӮҗнӮр”рӮҜӮД–k•ыӮЙ‘S‘¬—НӮЕ“ҰӮ°ҸoӮ·ӮЖҒAҢг•ыӮЙ’uӮ«ӢҺӮиӮЙӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮЕӮаҒAҚQӮДӮД’ЗӮўӮ©ӮҜӮй“ъ–{ҠН‘аӮЙҒAҚKү^ӮМҸ—җ_ӮӘ”чҸОӮЭӮЬӮөӮҪҒB—yӮ©Ңг•ыӮ©Ӯз•ъӮБӮҪү“Ӣ——ЈҺЛҢӮӮӘғүғbғLҒ[ғpғ“ғ`ӮЖӮИӮиҒA“GӮМҗж“ӘӮрҗiӮЮҠшҠНғ`ғFғUғҢғrғbғ`ӮМҠНӢҙӮр”jүуӮөҒAғEғCғgғQғtғg’с“ВӮЩӮ©Һi—Я•”—vҲхӮр‘S–ЕӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМҢӢүКҒAғ`ғFғUғҢғrғbғ`ӮМҗiҳHӮН—җӮкҒAӮ»ӮМҢгӮлӮрҗiӮЮҸ”ҠН’шӮа‘еҚ¬—җӮЙҠЧӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮД’ЗӮўӮВӮўӮҪ“ъ–{ҠН‘аӮНҒAҚ¬—җҸу‘ФӮМ“GӮрҠeҢВҢӮ”jӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчҒBҗ¶Ӯ«ҺcӮБӮҪӮнӮёӮ©ӮИғҚғVғAҠН’шӮН—·ҸҮҚ`“аӮЙҲшӮ«•ФӮөҒAҺcӮиӮМ‘ҪӮӯӮӘҚ~•ҡӮ·ӮйӮ©ҢӮ’ҫӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮМҚKү^ӮНҒAӮ»ӮкӮҫӮҜӮЙ—ҜӮЬӮиӮЬӮ№ӮсҒB—·ҸҮҠН‘аӮМҠл“пӮр’mӮБӮҪғEғүғWғIғXғgғbғNҠН‘аӮӘҒAӢ~үҮӮМӮҪӮЯӮЙү©ҠCӮЙӢмӮҜӮВӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮр‘ТӮҝ•ҡӮ№ӮөӮДӮўӮҪӮМӮНҒAҸг‘ә’с“ВӮМ“ъ–{‘ж2ҠН‘аҒB”ЮӮНҒAӮВӮўӮЙҗбҗJӮрҗ°ӮзӮ·ӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮЬӮөӮҪҒB•KҺҖӮЙ“ҰӮ°ӮйғEғүғWғIҠН‘аӮЙҢң–ҪӮЙ’ЗӮўӮ·ӮӘӮБӮҪҸг‘әҠН‘аӮНҒAӮұӮМӢw“GӮрӮВӮўӮЙүу–ЕӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮӘҒuүUҺRү«ҠCҗнҒv(8ҢҺ14“ъ)ӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮДҒA“ъ–{ӮМғVҒ[ғҢҒ[ғ“ӮМҲА‘SӮНҒAӮжӮӨӮвӮӯҠm•ЫӮіӮкӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB ӮіӮДҒAҒuү©ҠCҠCҗнҒvӮМҢӢүКҒAғ{ғҚғ{ғҚӮЙӮИӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮМҗ¶Ӯ«ҺcӮиӮНҒA–һ‘«ӮИҸC—қӮаҺуӮҜӮзӮкӮёӮЙ—·ҸҮҚ`“аӮЙӢҸӮ·ӮӯӮЬӮиҒAҗн—НӮЖӮөӮДӮНҠ®‘SӮЙ–і—Нү»ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮӘҒuҢ’ҚЭҒvӮрғAғsҒ[ғӢӮөӮҪӮҪӮЯӮЙҒAҺА‘ФӮр’mӮзӮИӮў“ҢӢҪҠН‘аӮНҒA‘Ҡ•ПӮнӮзӮёҚ`ҠOӮЕӮМҢxүъ‘ФҗЁӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкҒA“ъ–{‘ж3ҢRӮН—vҚЗӮМ‘ҒҠъҚU—ӘӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB ғҚғVғAҢRӮНҒAҢ©Һ–ӮИҸо•сҗн—ӘӮЕ“ъ–{ӮМ‘е•ә—НӮр“м•ыӮЙ“B•tӮҜӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМҠФҒA–һҸBӮЕӮН‘еҢҲҗнӮӘҗнӮнӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) —Й—zӮМҗнӮў
Ӯ»ӮкӮЬӮЕ‘ЮӢpӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪғҚғVғA–һҸBҢRӮНҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМҸd—v“sҺsӮЕӮ Ӯй—Й—zӮЕӮ»ӮМ“®Ӯ«ӮрҺ~ӮЯӮЬӮөӮҪҒBғAғҢғNғZғCҒEғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮНҒAӮұӮМҠXӮр—vҚЗү»ӮөӮД“ъ–{ҢRӮрҢ}ӮҰҢӮӮЖӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМӮұӮлғҚғVғA–{Қ‘ӮЕӮНҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮӘ–іҲЧ–іҚфӮМӮЬӮЬӮЙ‘ЮӢpӮр‘ұӮҜӮйӮұӮЖӮр”б”»Ӯ·Ӯй“®Ӯ«ӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғA–һҸBҢRҺi—Я•”ӮЙӮНҒAӮ»ӮӨӮўӮӨғvғҢғbғVғғҒ[ӮаӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮіӮДҒA3ӮВӮМғӢҒ[ғgӮ©ӮзҗiҢӮӮөӮД—ҲӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒA—Й—zӮМҺи‘OӮЕҚҮ—¬ӮЙҗ¬ҢчӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮЬӮЬҒA—Й—zӮрҺO•ыӮ©Ӯз•пҲНӮөӮД’чӮЯ•tӮҜӮЬӮ·ҒB “ъ–{–һҸBҢRӮМ‘ҚҺi—ЯҠҜӮНҒA‘еҺRҠЮҢіҗғӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМҗlӮНҒA–{“–ӮНҸ¬җSӮЕҗ”ҺҡӮЙҚЧӮ©Ӯўҗl•ЁӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ӮӘҒA•”үәӮҪӮҝӮМ‘OӮЕӮНҚӢ•ъбы—ҺӮЕ‘й—gӮЖӮөӮҪҗl•ЁӮр‘•ӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҢҲҗнӮМҚЕ’ҶӮЙҒAҒuӮЗӮұӮјӮЕ‘е–CӮМү№ӮӘӮөӮЖӮйӮӘҒAҗн‘ҲӮЕӮаӮвӮБӮДӮўӮйӮМӮ©ӮМҒHҒvӮЖҺҷӢКҺQ–d’·ӮЙҸз’kӮр”тӮОӮөӮҪӮЖӮўӮӨҲнҳbӮӘҺcӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮНҒA“ҜӢҪӮМ‘еҗж”yӮЕӮ ӮйҗјӢҪ—Іҗ·ӮМ“қ—ҰҸpӮрҢ©ҸKӮБӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮЕӮаҒA”ЮӮНҸз’kӮр”тӮОӮөӮИӮӘӮзӮаҒA“Ә”]ӮМ’ҶӮЕӮНҢғӮөӮӯҗіҠmӮИҢvҺZӮрӮө‘ұӮҜӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{җlӮНҒAҲУҠOӮЖӮұӮӨӮўӮӨ‘еҸ«ӮМүәӮЕ“ӯӮӯӮЩӮӨӮӘҺА—НӮрҸoӮ№Ӯ»ӮӨӮИӢCӮӘӮөӮЬӮ·ҒB ҺQ–d’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮНҒA‘дҳp‘Қ“ВӮаӢОӮЯӮҪҗӯ•{—vҗlӮЕҒA–{—ҲӮИӮзҺҹҠъҺс‘ҠҢу•вӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮӘҒAҢR‘аӮМ’ҶӮЕҗ”ҠKӢүӮаҚ~ҠiӮЖӮИӮБӮД‘еҺRӮМҢRҺtӮЙӮИӮБӮҪ—қ—RӮНҒA”ЮӮМ’m—ӘӮИӮӯӮөӮДӮНғҚғVғAӮЙҸҹӮДӮИӮўӮЖҺvӮнӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ҢRӮНҒAҠҜ—»“IӮИ”NҢчҗlҺ–Ӯр‘Е”jӮөӮДҒAҒuҸҹ—ҳҒvӮр“ҫӮйӮҪӮЯӮЙҗs—НӮ·ӮйғXғ^ғ“ғXӮрҺжӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҒAҺF–ҖӮЖ’·ҸBӮМ“к’ЈӮиӮЖӮ©ҒAӮ»ӮӨӮўӮӨҗ§–сӮНӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМҳg“аӮЕӮНҠ„ҚҮӮЖғtғҢғLғVғuғӢӮИҗlҺ–ӮрҚsӮҰӮй‘gҗDӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮҪӮҫҒA”T–ШҸ«ҢRӮӘҒA’·ҸB”ҙӮМ”NҢчҗlҺ–ӮЕ‘ж3ҢRҺi—ЯҠҜӮЙӮИӮБӮҪӮұӮЖӮНҒA”ЮӮӘ–ўӮҫӮЙҲ«ӮӯҢҫӮнӮкӮйҸҠҲИӮМҲкӮВӮЕӮ·ӮЛҒB ‘еҺRҢіҗғӮМүәӮЙӮНҒA‘ж1ҢRӮМҚ•–Ш‘еҸ«ҒA‘ж2ҢRӮМүң‘еҸ«ҒA‘ж4ҢRӮМ–м’Г‘еҸ«ӮзҒA’@Ӯ«ҸгӮ°ӮМғxғeғүғ“ӮӘ‘өӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҺwҠцүәӮМҸ«•әӮҪӮҝӮаҒAҚ‘үЖӮМҒuҠлӢ}‘¶–SҒvӮрҺ©ҠoӮөӮДҒAӮ»ӮМҗнҲУӮНӢЙӮЯӮДҚӮ—gӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҒAғҚғVғAҢRӮНҚЎӮРӮЖӮВӢCҚҮӮӘ“ьӮзӮИӮўҒB‘еҸ«ӮҪӮҝӮНӮаӮҝӮлӮсҒA•ә‘аӮҪӮҝӮЙӮЖӮБӮДӮаҒAүҪӮМӮҪӮЯӮЙ•¶ҺҡӮаҢҫ—tӮа’КӮ¶ӮИӮў’ҶҚ‘ӮМҲкҠpӮЕҒA“ъ–{җlӮЖҺEӮөӮ ӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮМӮ©ҺЯ‘RӮЖӮөӮИӮўӮаӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA—Й—zӮМ‘O–КӮЕҲкҗiҲк‘ЮӮМҢғӮөӮўҚU–hҗнӮӘ“WҠJӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ·(8ҢҺ25“ъҒ`)ҒB“ъ–{ҢR13–ңӮЙ‘ОӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮН22–ңҒB “ъ–{ҢRӮНҒAҚ•–ШҸ«ҢR—ҰӮўӮй‘ж1ҢRӮӘҢ©Һ–ӮИҠҲ–фӮрҢ©Ӯ№ӮДҒAҢҜӮөӮўҺRҠx’n‘СӮр“Л”jӮөӮД“м•ыӮ©ӮзғҚғVғAҢRӮМ”wҢгӮЙүсӮиӮ©ӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМҸоҗЁӮрӢ°ӮкӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA’јӮҝӮЙ‘SҢRӮЙ‘ЮӢp–Ҫ—ЯӮрҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB ”ЮӮНҒAӮаӮЖӮаӮЖ—Й—zӮЕҚЕҸIҢҲҗнӮр’§ӮЮӮВӮаӮиӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBғҚғVғA–{Қ‘ӮЙҒuӮвӮйӢCҒvӮрҢ©Ӯ№ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAүҮҢR“һ’…ӮЬӮЕӮМҺһҠФүТӮ¬ӮӘӮөӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA—Й—zӮМҗнӮўӮНҒAӮ ӮБӮҜӮИӮӯҢҲ’…ӮөӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМҺҖҸқҺТӮН2–ң3җз–јҒAғҚғVғAҢRӮМҺҖҸқҺТӮН2–ңҒBғҚғVғAӮНҸl‘RӮЖ–k•ыӮЙҲшӮ«ҒAӮ»ӮөӮД”жӮкӮ«ӮБӮҪ“ъ–{ҢRӮН—LҢшӮИ’ЗҢӮӮрҚsӮҰӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМҗнӮўӮЕӮМ“ъ–{ҢRӮМ‘_ӮўӮНҒu—Й—zӮЕғҚғVғA–һҸBҢRӮр•пҲНҹr–ЕӮ·ӮйҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮөӮҪҒBҚ‘—НӮМ’бӮў“ъ–{ӮЖӮөӮДӮНҒAҸ\•ӘӮИ—]—НӮӘҺcӮБӮДӮўӮйӮӨӮҝӮЙҒAӮЖӮЙӮ©Ӯӯ‘ҒӮЯӮЙӮұӮМҗн‘ҲӮМҢҲ’…ӮрӮВӮҜӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAӮ»ӮМ–Ъҳ_Ң©ӮНҠ®‘SӮЙҺё”sӮөӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮӨӮўӮӨҲУ–ЎӮЕӮНҒA‘ҒҠъӮЙ‘ЮӢpӮрҢҲ’fӮөӮДҺе—НӮрү·‘¶ӮөӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒAҢгҗўӮЙҢҫӮнӮкӮйӮЩӮЗ–і”\ӮИҸ«ҢRӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсҒB “ъ–{–һҸBҢRӮНҒA‘ҒҠъҢҲ’…Ӯр’ъӮЯҒAғNғҚғpғgғLғ“Ӯр’ЗӮБӮДҚДӮС–һҸB–k•ыӮЙҗiҢӮӮрҠJҺnӮөӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ6ҒA“пҚU•s—ҺӮМ—·ҸҮ—vҚЗ | |
|
ҒЎ(1) –і–dӮИ“ЛҢӮҚмҗн
—Й—zӮМҗнӮўӮНҒA“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҚЕҸIҢҲҗнӮЖӮИӮйӮНӮёӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA–һҸBҢRӮНӮұӮМҗнҸкӮЙ•әҲхӮЖ’e–тӮр–іҗ§ҢАӮЙ“Ҡ“ьӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғAҢRӮЙ“ҰӮ°ӮзӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{ҢRӮМ•җҠн’e–тӮНҢНҠүӮөҒAӮөӮ©Ӯа‘е•қӮИ•әҲхӮМ‘№–ХӮр•шӮҰӮҪҸу‘ФӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮсӮИҸоҗЁӮЙӢк–гӮ·Ӯй–һҸBҢRҺi—Я•”ӮНҒA—·ҸҮӮМ‘ж3ҢRӮр“–ӮДӮЙӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB—·ҸҮ—vҚЗӮрҢyҺӢӮөӮДӮўӮҪ–Ӣ—»ӮҪӮҝӮНҒA‘ж3ҢRӮӘ—·ҸҮӮЙӮұӮкӮЩӮЗ’·ҠъӮЙӮнӮҪӮБӮДҚS‘©ӮіӮкҒAӮөӮ©Ӯаҗн—НӮЙӮ ӮкӮЩӮЗӮМ‘№–ХӮрҸoӮ·ӮЖӮН—\‘zӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB–һҸBҢRӮНҒA‘ж3ҢRӮӘ–kҸгӮөӮДӮӯӮкӮйӮЬӮЕҒAғҚғVғAҢRӮМ‘O–КӮЕ‘ТӢ@Ӯ·Ӯй•ыҗjӮрҚМӮйӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒA—·ҸҮӮМҗнӮўӮНӮұӮкӮ©ӮзӮӘ–{”ФӮЕӮөӮҪҒB ‘ж3ҢRӮМҺс”]•”ӮНҒA’e–т•s‘«Ӯр—қ—RӮЙ—vҚЗҚUҢӮӮрӮҪӮЯӮзӮӨӮОӮ©ӮиӮЕӮөӮҪӮӘҒAҠCҢRӮ©ӮзүҪ“xӮаүҪ“xӮаҚГ‘ЈӮіӮкӮДҒA‘Дҗ«ӮМӮжӮӨӮЙҚUҢӮӮрҚДҠJӮөӮҪӮМӮЕӮ·(9ҢҺ19“ъ)ҒBӮ»ӮМҢӢүКӮНҒA–іҺcӮИӮаӮМӮЕӮөӮҪҒB“ъ–{ӮМ•әҺmӮҪӮҝӮНҒA•sҸ\•ӘӮИ–CҢӮҺxүҮӮМҢгӮЕҸeҢ•Ӯр•шӮҰӮД“ЛҢӮӮөҒAӮ»ӮөӮДӢ@ҠЦҸe’eӮМүJӮЖӮШғgғ“(ғRғ“ғNғҠҒ[ғg)ӮМ•ЗӮМ‘OӮЙ—Э—‘ӮМӮжӮӨӮЙӮИӮ¬“|ӮіӮкӮДҚsӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB —·ҸҮ—vҚЗӮНҒAҠmӮ©ӮЙҢ©Һ–ӮИ—vҚЗӮЕӮөӮҪӮ©ӮзҒA’e–т•s‘«ӮМ“ъ–{ҢRӮМӢкҗнӮНҺd•ыӮИӮўӮЖҢҫӮҰӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒA‘ж3ҢRҺс”]•”ӮМ–іҲЧ–іҚфӮНӮРӮЗӮ©ӮБӮҪҒBҚUӮЯ•ыӮӘӮЖӮЙӮ©Ӯӯ’P’ІӮЕҒAӮўӮВӮа“ҜӮ¶ҸкҸҠӮр“ҜӮ¶—lӮЙҚUҢӮӮ·ӮйӮМӮҫӮ©ӮзҒAүҪ“xӮаүҪ“xӮа“ҜӮ¶Һё”sӮМҢJӮи•ФӮөӮЙҸIҺnӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҺmӢCӮМ’бӮў‘ж3ҢRӮМҺi—Я•”ӮНҒAҗнҸкӮ©Ӯз—ЈӮкӮҪҲА‘SӮИӮЖӮұӮлӮЙ–{үcӮр’uӮ«ҒAӮ»ӮөӮДҗнҸкӮрҺӢҺ@Ӯ·ӮйӮұӮЖӮ·ӮзӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҸоҗЁӮрҒAҠCҢRӮМӮЭӮИӮзӮё–һҸBҢRӮа—J—¶ӮөӮЬӮөӮҪҒB ҠCҢRӮЖӮөӮДӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮМғҚғVғAҠН‘аӮӘ—ҲӮй‘OӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮр‘S–ЕӮіӮ№ӮҪӮўҒB –һҸBҢRӮЖӮөӮДӮНҒAғҚғVғA—ӨҢRҺе—НӮрҹr–ЕӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙ‘ж3ҢRӮМҗн—НӮӘ—~ӮөӮўҒB Ӯ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAҒu—·ҸҮ–і“Gҗ_ҳbҒvӮрӮЬӮ·ӮЬӮ·җҒ’®ӮөӮДҠOҚВҺsҸкӮрҠҲҗ«ү»ӮіӮ№ӮҪӮҪӮЯҒAҺ‘ӢаҢJӮиӮӘ“ъӮЙ“ъӮЙ—ЗӮӯӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДҒA‘ҒҠъҚuҳaӮр‘_ӮӨ“ъ–{җӯ•{ӮЖӮөӮДӮНҒAғҚғVғAӮМ–і“G—vҚЗҗ_ҳbӮр•ІҚУӮөӮИӮўӮұӮЖӮЙӮНҒA”ЮӮрҢрҸВӮМғeҒ[ғuғӢӮЙҲшӮ«ҸoӮ·ӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮИӮўҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA—·ҸҮӮМҗнӮўӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҗі”OҸкӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) 203ҚӮ’n
ҠCҢRҢR—Я•”ӮНҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮМ“ЭҸdӮіӮЙҢғ“{ӮөӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮзӮЖӮөӮДӮНҒA—·ҸҮҠН‘аӮрӮЖӮЙӮ©Ӯӯ’ЧӮөӮДӮаӮзӮўӮҪӮўҒBҠCҢRӮМ—§ҸкӮ©ӮзӮНҒA—vҚЗӮИӮсӮ©ҚU—ӘӮЕӮ«ӮИӮӯӮҪӮБӮД—ЗӮўӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮұӮЕ”ЮӮзӮНҒA‘ж3ҢRӮЙҺҹӮМӮжӮӨӮИ’сҲДӮрӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғu—·ҸҮ—vҚЗӮрҚUҢӮӮ·ӮйӮМӮЕӮНӮИӮӯҒA—·ҸҮ–kҗјӮЙгЮӮҰ—§ӮВ203ҚӮ’nӮрҚU—ӘӮөӮДӮаӮзӮўӮҪӮўҒB203ҚӮ’nӮНҒA—·ҸҮҺsҠXӮЖ—·ҸҮҚ`ӮрҠП‘ӘӮ·ӮйӮЙҸ\•ӘӮИҚӮ“xӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮ©ӮзҒAӮ»ӮұӮ©Ӯз—·ҸҮҠН‘аӮМҲК’uӮр”cҲ¬ӮЕӮ«ӮйӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮӨӮИӮкӮОҒA—vҚЗүzӮөӮЙ–CҢӮӮрӮ©ӮҜӮДҠН‘аӮр’ЧӮ·ӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮйҒvҒB ӮөӮ©ӮөҒA‘ж3ҢRӮНҒuӮўӮЬӮіӮзҒA•”‘аӮМ”z’uҠ·ӮҰӮНӮөӮҪӮӯӮИӮўӮөҒA—·ҸҮҺsҺ©‘МӮр—ҺӮЖӮіӮИӮҜӮкӮОҲУ–ЎӮӘ–іӮўҒvӮЖҢҫӮБӮДҸaӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЕӮаҒAӮ ӮсӮЬӮиҠCҢRӮӘӮөӮВӮұӮўӮаӮМӮҫӮ©ӮзҒA•”‘аӮМҲк•”Ӯр203ҚӮ’nӮЙҢьӮ©ӮнӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA‘ж2Һҹ‘ҚҚUҢӮ(10ҢҺ26“ъҒ`)ӮЙҚЫӮөӮДҒAҸүӮЯӮД203ҚӮ’nӮНҗнҸкӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBғҚғVғAҢRӮНҒAӮӨӮ©ӮВӮИӮұӮЖӮЙҒAӮұӮМҚӮ’nӮМҸd—vҗ«ӮЙӢCӮГӮўӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA“ъ–{ҢRӮМҚUҢӮӮНҗ¬ҢчӮөҒA203ҚӮ’nӮНӮ»ӮМҺи’ҶӮЙ“ьӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒA•ә—НӮӘ’Ҷ“r”ј’[ӮҫӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒAӮ ӮБӮЖӮўӮӨӮЬӮЙғҚғVғAҢRӮМ”ҪҢӮӮЙӮжӮБӮД’DҠТӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA203ҚӮ’nӮМҸd—vҗ«ӮЙӢCӮГӮўӮҪғҚғVғAӮНҒAӮұӮМ’nӮрҢөҸdӮЙ—vҚЗү»ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“ъ–{ҢRӮМ’Ҷ“r”ј’[ӮИҚUҢӮӮНҒAӮўӮнӮОҒuӮвӮФҺЦҒvӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒA‘ж2Һҹ‘ҚҚUҢӮӮНҺеҗнҗьӮЕӮаҺё”sӮЙҸIӮнӮиҒA—vҚЗӮМ‘O–КӮН“ъ–{•әӮҪӮҝӮМҺrӮЕ–„ӮЯҗsӮӯӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ—vҚЗӮМ‘¶ҚЭӮНҒAҚЎӮв“ъ–{ӮМҗнӢЗӮЙӮЖӮБӮД’v–ҪҸқӮЙӮИӮиӮВӮВӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҺАӮН—·ҸҮ—vҚЗӮаӮ»ӮкӮЩӮЗ–іҸқӮЕӮН–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“ъ–{ҢRӮМҗ”ҺҹӮЙӮнӮҪӮй–Ҫ’mӮзӮёӮМҚUҢӮӮЙӮжӮБӮДҒAӮўӮӯӮВӮаӮМҗw’nӮН”jүуӮіӮкӮДӮўӮҪӮөҒA•әҲхӮМ‘№–ХӮЖ”жҳJӮа“ъ‘қӮөӮЙҚӮӮЬӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӢҮӮөӮҪғҚғVғAҢRӮНҒAҚЎӮв–р—§ӮҪӮёӮЖӮИӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аҺc“}ӮМ–C‘дӮрҺжӮиҠOӮөҒAӮұӮкӮр—vҚЗӮЙҗҳӮҰӮВӮҜӮйӮЩӮЗӮЙ’ЗӮўӢlӮЯӮзӮкӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮДҒAҚ`“аӮЙ•ӮӮ©ӮФ—·ҸҮҠН‘аӮМҺc“}ӮНҒA’PӮИӮйғIғuғWғFӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮаӮөӮа“ъ–{ҠCҢRӮӘӮ»ӮМҺ–ҺАӮр’mӮБӮДӮўӮҪӮИӮзҒAӮ ӮкӮЩӮЗ203ҚӮ’nӮЙӮұӮҫӮнӮйӮұӮЖӮа–іӮ©ӮБӮҪӮЕӮөӮеӮӨӮЙҒBӮұӮкӮұӮ»ҒA—рҺjӮМ”з“чӮЕӮ·ӮЛҒB ӮЕӮаҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМ–і“Gҗ_ҳbӮр•цӮіӮИӮўӮ©Ӯ¬ӮиҒAғҚғVғAӮӘҚuҳaӮЙүһӮ¶ӮйӮұӮЖӮН—LӮи“ҫӮЬӮ№ӮсҒBӮЬӮҪҒA‘ж3ҢRӮрӮұӮМ”Я‘sӮИ”C–ұӮ©Ӯзүр•ъӮөӮИӮўӮұӮЖӮЙӮНҒA–һҸBҢRӮӘғҚғVғAҢRӮр‘Е“|Ӯ·ӮйӮұӮЖӮаҸo—ҲӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒB ‘е–{үcӮНҒA”T–ШӮрҚX“RӮ·ӮйӮұӮЖӮрҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA–ҫҺЎ“VҚcӮӘ”Ҫ‘ОӮөӮҪӮҪӮЯӮЙҒAӮұӮМ•ыҗjӮН“PүсӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA–һҸBҢRӮ©ӮзҺQ–d’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘ”hҢӯӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) —·ҸҮӮМ—ҺҸй
‘ж3ҢRҺi—Я•”ӮМ–іҲЧ–іҚфӮФӮиӮрҢ©ӮҪҺҷӢКҺQ–d’·ӮНҒAҺ©ӮзӮӘҗw“ӘҺwҠцӮрҺ·ӮБӮДӮұӮМӢкӢ«ӮрҗШӮи”ІӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮ·ҒB”ЮӮНӮЬӮё203ҚӮ’nӮрҠm•ЫӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮДҒAҸaӮй‘ж3ҢRҺi—Я•”ӮМҗKӮр’@ӮўӮДҒA–C‘дӮв•әҲхӮр‘е—КӮЙӮұӮМҗн—Ә—v’nӮЙҲЪ“®ӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮД‘ж3Һҹ‘ҚҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮЬӮөӮҪ(11ҢҺ26“ъҒ`)ҒB203ҚӮ’nӮНӮВӮўӮЙ“ъ–{ҢRӮМҸ¶’ҶӮЙ“ьӮи(11ҢҺ30“ъ)ҒAӮ»ӮМҺR’ёӮЙҗwҺжӮБӮҪҠП‘ӘҲхӮӘ“IҠmӮИҺwҺҰӮрҸoӮөӮҪҢӢүКҒAҚ~Ӯи’ҚӮўӮҫ“ъ–{ҢRӮМ–C’eӮН—·ҸҮҠН‘а(Ӯ·ӮЕӮЙҺcҠ[“Ҝ‘RӮҫӮБӮҪӮӘ)Ӯр‘S–ЕӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮөӮҪ(12ҢҺ4“ъ)ҒBӮұӮкӮрҢ©ӮҪҺҷӢКӮНҒA‘еӢ}Ӯ¬ӮЕ–һҸBӮМҗнҗьӮЙӢAӮиӮЬӮ·ҒB ‘ж3ҢRӮНҒAҲшӮ«‘ұӮўӮД—·ҸҮ—vҚЗӮрҚUҢӮӮөӮЬӮөӮҪҒBҚЎүсӮНҒA–і–dӮИ“ЛҢӮӮрҢJӮи•ФӮ·ӮМӮЕӮНӮИӮӯҒA’nүәҚB“№ӮрҢ@ӮиҗiӮЯҒAӮ»ӮұӮЙ”ҡ–тӮрғZғbғgӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒA—vҚЗҺ{җЭӮр’nүәӮ©Ӯз•ў–ЕӮіӮ№ӮйҚмҗнӮрҺжӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМҚмҗнӮН‘еҗ¬ҢчӮрҺыӮЯҒA—vҚЗӮМҠOҠsҗw’nӮНҺҹҒXӮЙ’nүәӮ©ӮзҗҒӮ«”тӮОӮіӮкӮДҚsӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМүЯ’цӮЕҒAғҚғVғA‘ӨӮМ–јҸ«ғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮаҗнҺҖӮөҒAӮ·ӮЕӮЙҠН‘аӮрҺёӮБӮҪ—·ҸҮҺsӮМҗнҲУӮНғ[ғҚӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB 1905”N1ҢҺ1“ъҒA—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғӢӮНҒA”’ҠшӮрҢfӮ°ӮЬӮөӮҪҒB”T–ШҸ«ҢRӮНҒA”ЮӮрҗ…ҺtүcӮЙҢ}ӮҰӮЬӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒA‘ж3ҢRӮНӮВӮўӮЙ—·ҸҮӮрҚU—ӘӮөҒAӮ»ӮөӮДғҚғVғAӮМ–і“Gҗ_ҳbӮН•цӮкӢҺӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒA“ъ–{ҢRӮМҗнҺҖҸқҺТӮН4–ң–јҒBҺАӮЙӢкӮўҸҹ—ҳӮЕӮөӮҪҒB —·ҸҮӮМҗнӮўӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“ъ–{ҢR(ӮЖӮиӮнӮҜ”T–ШҸ«ҢR)ӮМ–і”\ӮФӮиӮОӮ©ӮиӮӘӢӯ’ІӮіӮкӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМҺһ‘гӮНҒA–мҗн’zҸйӮМӢZҸpӮӘ‘е•қӮЙҢьҸгӮөӮҪӮұӮЖӮЙүБӮҰӮДҒAӢ@ҠЦҸeӮМ”ӯ–ҫӮИӮЗӮЙӮжӮБӮДҒAӢ’“_Ӯр–hҢдӮ·Ӯй‘ӨӮМ”\—НӮӘҠi’iӮЙҗ¬’·ӮрҗӢӮ°ӮҪӮұӮЖӮЙ—ҜҲУӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҚUҢӮ‘ӨӮНҒAӮЬӮҫҗнҺФӮа”тҚsӢ@Ӯа–іӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒA–CҢӮӮ©ҸeҢ•“ЛҢӮӮөӮ©ҺжӮиӮӨӮй—LҢшӮИҺи’iӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©Ӯа”T–ШҢRӮНҒA–қҗ«“IӮИ–C’e•s‘«ӮЙ”YӮЬӮіӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМҗн‘ҲӮМ10”NҢгӮЙҺnӮЬӮБӮҪ‘жҲкҗўҠE‘еҗнӮЕӮНҒAғxғӢғ_ғ“ӮМҗнӮўӮЙ‘г•\ӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙҒA—vҚЗӮрҚUҢӮӮөӮҪ‘ӨӮӘ”ЯҺSӢЙӮЬӮиӮИӮў—¬ҢҢӮрҸdӮЛҒAҢӢӢЗҒAдP’…Ҹу‘ФӮр4”NӮа‘ұӮҜӮй”j–ЪӮЙҠЧӮиӮЬӮ·ҒBҒuҗн‘ҲӮМғvғҚҒvӮрҺ©”FӮ·ӮйғhғCғcҗlӮвғtғүғ“ғXҗlӮЕӮіӮҰӮұӮМ—LӮи—lӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒA—рҺjӮМҗуӮў“ъ–{ҢRӮМӢкҗнӮН“–‘RӮҫӮБӮҪӮЕӮөӮеӮӨҒB Ӯ»ӮкӮЕӮаҒA”T–ШҢRӮНҚЕҸI“IӮЙӮН—·ҸҮӮрҠЧ—ҺӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮЮӮөӮлӮұӮМ10”NҢгӮМғhғCғcҢRӮвғtғүғ“ғXҢRӮжӮиӮа—DҸGӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨ•]үҝӮр—^ӮҰӮйӮұӮЖӮаүВ”\ӮИӮМӮЕӮ·ҒB ӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒA”T–ШҢВҗlӮМҒu–і”\ҒvӮрӮ ӮЬӮиҢЦ‘еӮЙҺжӮиҸгӮ°ӮйӮЧӮ«ӮЕӮН–іӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
| ҒЎ7ҒDҚ•Қa‘дӮЖ•т“V | |
|
ҒЎ(1) ғҚғVғA–һҸBҢRӮМӢtҸP
Ӯ»ӮМӮұӮл“ъ–{–һҸBҢRӮНҒA—Й—z–k•ыӮМҚ№үНҺь•УӮЕғҚғVғAҢRӮЖ‘ОӣіӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮНҒA—Й—zӮМҗнӮўӮЕ•җҠн’e–тӮрҺgӮўүКӮҪӮөӮҪӮҪӮЯӮЙҒA•вӢӢӮр‘ТӮҪӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘е•қӮИ•әҲх•s‘«ӮЙҸPӮнӮкӮҪӮҪӮЯҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮМ“һ’…ӮрӮРӮҪӮ·Ӯз‘ТӮҝ‘ұӮҜӮйӮөӮ©–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA‘ОӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮ©Ӯз‘қүҮӮр“ҫӮД’ҳӮөӮӯӢӯү»ӮіӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҺ©җMӮр•tӮҜӮҪ”ЮӮзӮНҒA”ҪҢӮӮМӢ@үпӮрҢХҺӢбјҒXӮЖ‘_ӮӨӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ҒuҚ№үНүпҗнҒv(10ҢҺ10Ғ`17“ъ)ӮНҒAғҚғVғAҢRӮМҚЕҸүӮМ–Т”ҪҢӮӮЕӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮН‘еӮ«ӮИ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮИӮӘӮзҒAӮИӮсӮЖӮ©ӮұӮкӮрҢӮ‘ЮӮ·ӮйӮМӮЕӮөӮҪҒBғҚғVғAҢR22–ңӮМӮӨӮҝҺҖҸқҺТӮН4–ңҒB“ъ–{ҢR12–ңӮМӮӨӮҝҒAҺҖҸқҺТӮН2–ңҒB Ӯ»ӮМҢгҒAӢGҗЯӮӘ“~ӮЙӮИӮйӮЖҒA”жӮкӮ«ӮБӮҪ“ъ–{ҢRӮН–ы’fӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBғҚғVғAҢRӮӘӮұӮМҠҰӮіӮМ’ҶӮрҚUӮЯӮДӮӯӮйӮЖӮНҺvӮнӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҗіҠmӮЙҢҫӮӨӮИӮзҒAғҚғVғAҢRӮЙҚUӮЯӮД—ҲӮД—~ӮөӮӯӮИӮ©ӮБӮҪӮаӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮ»ӮӨӮўӮӨ•—ӮЙ–і—қӮвӮиӮЙҺvӮўҚһӮсӮҫӮМӮЕӮ·ҒBҠу–]“IҠП‘ӘӮЙгvӮи•tӮўӮД”І–{“I‘ОҚфӮрҚuӮ¶ӮИӮўҲ«•ИӮНҒAҢ»ҚЭӮЕӮаӮўӮҪӮйӮЖӮұӮлӮЙҢ©ӮзӮкӮй“ъ–{җlӮМ’ZҸҠӮЕӮ·ӮЛҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{җlӮЖғҚғVғAҗlӮЖӮЕӮНҒAҒuҠҰӮіҒvӮМҠT”OӮӘ‘SӮӯҲбӮўӮЬӮ·ҒB–һҸB“м•”ӮМ“~ӢGӮМӢCү·ӮНҒA•ҪӢПӮөӮД—лүә20“xӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{•әӮЙӮЖӮБӮДӢБҲЩ“IӮҫӮБӮҪӮұӮМҠҰӮіӮаҒA—лүә30“xӮМ’ҶӮЕҗ¶ҠҲӮөӮДӮ«ӮҪғҚғVғA•әӮЙӮЖӮБӮДӮНҠҰӮіӮМӮӨӮҝӮЙ“ьӮиӮЬӮ№ӮсҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAғҚғVғAҢRӮМӢtҸPӮӘҠJҺnӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB10–ңӮаӮМ‘еҢRӮӘ–k•ыӮ©ӮзүсӮиҚһӮЭҒAӮ»ӮөӮД“ъ–{ҢRӮр•пҲНҹr–ЕӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒuҚ•Қa‘дӮМҗнӮўҒv(1ҢҺ25Ғ`29“ъ)ӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮНҠ®‘SӮИҠпҸPӮЖӮИӮиҒA–ы’fӮөӮДӮўӮҪ“ъ–{ҢRӮНҠe’nӮЕҢӮ”jӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB –һҸBҢRҺi—Я•”ӮЕҒAҺҷӢКҺQ–d’·ӮЖҸј‘әҺQ–d’·ӮНғpғjғbғNӮЙҠЧӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ”ЮӮзӮНҒA“GӮЙ“Л”jӮіӮкӮҪ’n‘СӮЙҒA‘қүҮ•ә—НӮр’ҖҺҹ“Ҡ“ьӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӢрӮр”ЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮсӮИ•s—ҳӮИҸоҗЁӮҫӮБӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒA“ъ–{ҢRӮӘ‘S–ЕӮр–ЖӮкӮҪӮМӮНҒAҚKү^ҲИҸгӮМүҪҺТӮЕӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBғҚғVғAҢRҺi—Я•”ӮЕҒA”h”ҙҚR‘ҲӮӘ–u”ӯӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғӮғXғNғҸӮМғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAғNғҚғpғgғLғ“Һi—ЯӮӘ—ҠӮиӮИӮўӮаӮМӮҫӮ©ӮзҒAғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO‘еҸ«ӮрһҢ“ьӮкӮЙ”hҢӯӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAҚ•Қa‘дӮМ”ҪҢӮҚмҗнӮр—§ҲДҺw“ұӮөӮҪӮМӮНҒAӮұӮМҗVҺQҸ«ҢRӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮаӮөӮаӮұӮМҚмҗнӮӘҗ¬ҢчӮөӮҪӮзҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮНӮ»ӮМ’nҲКӮр’ЗӮнӮкӮДӮөӮЬӮӨӮұӮЖӮЕӮөӮеӮӨҒBҸЕӮБӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒAғOғҠғbғyғ“ғxғӢғOӮМ‘«ӮрҲшӮБ’ЈӮйӮжӮӨӮИ–Ҫ—ЯӮр—җ”ӯӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢӢүКҒAғҚғVғAҢRӮН“–ҸүӮМҠпҸPҢшүКӮрҗ¶Ӯ©Ӯ·ӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮёҒAӮ ӮҝӮұӮҝӮЕғӮғ^ғӮғ^ӮөӮДҚUҢӮӮрҺиҚTӮҰӮДӮўӮйӮӨӮҝӮЙҒA“ъ–{ҢRӮӘҗнҗьӮМҢҠӮр‘UӮӨӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB җg“аӮЙ‘«ӮрҲшӮБ’ЈӮзӮкӮДҚмҗнӮрҚБҗЬӮіӮ№ӮзӮкӮҪғOғҠғbғyғ“ғxғӢғOӮНҒAӮвӮйӢCӮрӮИӮӯӮөӮД–{Қ‘ӮЙҲшӮ«ҸгӮ°ӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮНӮ»ӮМ’nҲКӮр•Ы‘SӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB—ЗӮ©ӮБӮҪӮЛҒBӮЕӮаҒAҗнҸкӮНҲЈӮкӮИғҚғVғA•ә1–ң–јӮМҺҖ‘МӮЕӮўӮБӮПӮўӮҫҒB ӮұӮМӮЖӮ«ӮМғҚғVғAҢRӮМ—l‘ҠӮНҒA‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲӮМӮЖӮ«ӮМ“ъ–{ҢRӮЙ—ЗӮӯҺ—ӮДӮўӮЬӮ·ӮЛҒBӮ ӮМӮЖӮ«ӮМ“ъ–{ҢRӮаҒA—ӨҢRӮЖҠCҢRӮӘ”h”ҙҚR‘ҲӮЙ–І’ҶӮЙӮИӮБӮДҒAӢMҸdӮИҺ‘Ң№Ӯв•ә—НӮр•ӘҺUӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨӢрӮр”ЖӮөӮЬӮөӮҪҒB•…ӢҖҠҜ—»‘gҗDӮЖӮўӮӨӮаӮМӮНҒAӮўӮВӮМҺһ‘гӮЕӮаӮЗӮұӮМҚ‘ӮЕӮа“ҜӮ¶ӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮЬӮ№ӮсҒB җнҸкӮЕӮНҒAӮжӮиғ~ғXӮМҸӯӮИӮў•ыӮӘҸҹ—ҳӮр“ҫӮЬӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAғҚғVғAӮМғ~ғXӮӘ“ъ–{ӮМӮ»ӮкӮрҸгүсӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒAҒuҚ•Қa‘дӮМҗнӮўҒvӮН“ъ–{ҢRӮМүhҢхӮМҲкӮВӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAҚДӮСҗнҗьӮНдP’…Ҹу‘ФӮЙҠЧӮиӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) •вӢӢҳHӮрҸ„ӮйҗнӮў
–һҸBӮМ“ъҳI—јҢRӮНҒA—вӮҪӮўбЙӮЭҚҮӮўӮр‘ұӮҜӮИӮӘӮзҒAҢЭӮўӮМ•вӢӢҳHӮр”jүуӮөӮжӮӨӮЖ‘_ӮўӮЬӮ·ҒB—јҢRӮМҗ¶–ҪҗьӮНҒAҲк–{ӮМ“S“№ӮЕӮөӮҪҒB•әҲхӮаҲг–т•iӮа•җҠн’e–тӮаҒA“Ңҗҙ“S“№Ӯр—pӮўӮД—A‘—ӮіӮкӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъҳI—јҢRӮНҒAүх‘¬ӮМӢR•ә•”‘аӮр•Тҗ¬ӮөӮД“GӮМҢг•ыӮЙ‘—ӮиҚһӮЭҒA“S“№Ӯр”ҡ”jӮөӮжӮӨӮЖҺҺӮЭӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ ӮЬӮиҢшүКӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮМӢR•ә‘аӮНҒAӮөӮОӮөӮО•Ҫ–м•”Ӯр‘–Ӯй“S“№Ӯр”jүуӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{ӮМҚH•ә‘аӮНӮұӮкӮрҠИ’PӮЙҸC•ңӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒB Ҳк•ыӮМ“ъ–{ӮМӢR•ә‘аӮНҒAӮ»ӮӨӮИӮйӮҫӮлӮӨӮЖ—\‘zӮөӮДҒA“SӢҙ”ҡ”jӮрҗПӢЙ“IӮЙ‘_ӮБӮДҚsӮ«ӮЬӮөӮҪҒB“SӢҙӮИӮзҒAҠИ’PӮЙҸC—қӮЕӮ«ӮИӮўӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒA•ә—НӮЙӮдӮЖӮиӮӘӮ ӮйғҚғVғAҢRӮНҒA“SӢҙӮМӮжӮӨӮИҸd—vӢ’“_ӮЙӮНҒAҸнҺһ1–ң–јӮаӮМ•ә—НӮр“\Ӯи•tӮҜӮДҢ©’ЈӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮнӮёӮ©җ”Ҹ\–јӮМӢR•ә‘аӮЕӮН‘ҫ“Ғ‘ЕӮҝӮЕӮ«ӮёҒAӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ӮМ”jүуҚHҚмӮаӢуҗUӮиӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮМ“БҺк•”‘аӮМ’ҶӮЙӮНҒA’·ӢлғVғxғҠғAӮЙҗN“ьӮөӮДғVғxғҠғA“S“№Ӯр”ҡ”jӮөӮжӮӨӮЖ‘_ӮБӮҪҺТӮаӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮкӮа“GӮМҢөҸdӮИҢx”хӮЙӮжӮБӮДҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB җнҸкӮЙӮЁӮўӮДҒAӮаӮБӮЖӮаҸd—vӮИӮМӮН•вӢӢӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮұӮлӮМ“ъ–{ҢRӮНҒAӮ»ӮМӮұӮЖӮр—ЗӮӯ’mӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮӘҒAӮұӮМ40”NҢгӮМҗн‘ҲӮЕӮНҠ®‘SӮЙ–YӮкӮзӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮНҒAҺАӮЙҠп–ӯӮИҢ»ҸЫӮЕӮ·ӮЛҒB ӮЖӮұӮлӮЕҒAғҚғVғAҢRӮЙӮНҒAӮЬӮҫӮЬӮҫ“ъ–{ҢRӮМ•вӢӢҗьӮр”jүуӮ·Ӯйғ`ғғғ“ғXӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBғҲҒ[ғҚғbғpӮМҠН‘аӮӘҒAҒu‘ж2‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а(’КҸМғoғӢғ`ғbғNҠН‘а)ҒvӮЖӮИӮБӮД“ъ–{–ЪҺwӮөӮДҸoҚqӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮұӮМҠН‘аӮӘ–іҺ–ӮЙҗнҸкӮЙ“һ’…Ӯ·ӮкӮОҒA“ъ–{ӮМғVҒ[ғҢҒ[ғ“Ӯр’fӮҝҗШӮйӮұӮЖӮаүВ”\ӮҫӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ҮҚ‘ӮЕӮ Ӯй“ъ–{ӮНҒAҸнӮЙӮұӮӨӮўӮБӮҪ’nҗЁҸгӮМғnғ“ғfӮр”w•үӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) •т“Vүпҗн
ӮұӮМӮұӮлҒA“ъ–{ӮМҚ‘—НӮНҢАҠEӮЙ’BӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҗнҸкӮЕӮНҠҰӮіӮвүu•aӮЙӮжӮй•aҗlӮӘ‘ұҸoӮөҒA“а’nӮЕӮНҸdҗЕӮЙӢкӮөӮЮҚ‘–ҜӮМ”Я–ВӮӘӢҝӮ«ҒAӮ»ӮөӮДҚHҸкӮЕӮН•җҠн’e–тӮМ‘қҺYӮаҠФӮЙҚҮӮнӮИӮўҒBӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНғWғҠ•nӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB Ӯ»ӮсӮИ’ҶҒAӮжӮӨӮвӮӯ”T–Ш‘ж3ҢRӮЖӮМҚҮ—¬ӮрүКӮҪӮөӮҪ–һҸBҢRӮНҒAғҚғVғAҢRҺе—НӮЙҚЕҢгӮМҢҲҗнӮр’§ӮЭӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘҒu•т“VүпҗнҒv(2ҢҺ22“ъҒ`)ӮЕӮ·ҒB“ъ–{ҢR24–ң9җзӮЙ‘ОӮөҒAғҚғVғAҢR36–ң7җзҒBӮұӮкӮНҒAҗўҠEҗнҺjҸгҚЕ‘еӢK–НӮМҢғ“ЛӮЕӮөӮҪҒB •т“VӮЙҗwҺжӮйғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒAҺһҠФӮрӮ©ӮҜӮДӢЩ–§ӮИ—vҚЗӮр’zӮ«ҸгӮ°ҒAӮ»ӮөӮД–ң‘SӮМ‘ФҗЁӮЕ“ъ–{ҢRӮрҢ}ӮҰҢӮӮҝӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮНҒAҗV•Тҗ¬ӮМҠӣ—ОҚ]ҢRӮӘүE—ғӮ©ӮзҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮӘҚ¶—ғӮ©ӮзҗiҢӮӮөҒA•т“VҺsӮр—ј—ғӮ©Ӯз•пҲНӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚмҗнӮр—§ӮДӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ’nӮЕғҚғVғAҢRӮр•пҲНҹr–ЕӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA•ә—НӮНғҚғVғAҢRӮМ•ыӮӘ—yӮ©ӮЙҸгӮҫӮөҒA•т“VӮр’ҶҗSӮЙҢҳҢЕӮИҗw’nӮр•~ӮўӮДӮўӮЬӮ·ҒB“ъ–{ҢRӮНҒA“–‘RӮИӮӘӮзӢкҗнӮЙҠЧӮиӮЬӮөӮҪҒB Ҡӣ—ОҚ]ҢRӮНғҚғVғAҢRӮМҢъӮў•ЗӮЙ‘jӮЬӮкӮДӮ»ӮМ•а’ІӮрҠЙӮЯӮЬӮ·ҒBҗі–КҚUҢӮӮМ‘ж2ҢRӮЖ‘ж4ҢRӮаҒAӢӯ—НӮИ“GӮМ–hҚЗӮЙӮжӮБӮДӮИӮ¬•ҘӮнӮкӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮИӮБӮҪӮзҒA—ҠӮЭӮМҚjӮНҚ¶—ғӮМ”T–Ш‘ж3ҢRӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМ‘ж3ҢRӮаҒA•KҺҖӮЙҗiҢӮӮрҺҺӮЭӮйӮаӮМӮМҒAҢғӮөӮў‘№–ХӮрҺуӮҜӮДӮ»ӮМҗЁӮўӮН“ЭӮйҲк•ыӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМӮЖӮ«ҒAҠпҗХӮӘӢNӮ«ӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮӘҗнҲУӮр‘rҺёӮөҒAӮВӮўӮЙ‘ЮӢpӮрҠJҺnӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢҙҲцӮЙӮВӮўӮДӮН—lҒXӮИҗаӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒAғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮӘҢл’fӮрӮөӮҪӮЖӮўӮӨҗаӮӘҚЕ—L—НӮЕӮ·ҒB ӮЬӮёғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA“ъ–{ҢRӮМ—\”хҗн—НӮрүЯ‘е•]үҝӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮӘ‘№–ХӮрӢ°ӮкӮёӮЙ–і’ғӮИҚUӮЯ•ыӮрҢJӮи•ФӮ·ӮМӮНҒAҗl“IҺ‘Ң№ӮЙ—]—TӮӘӮ ӮйӮ©ӮзӮҫӮЖҺvӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA—·ҸҮӮр—ҺӮЖӮөӮҪ”T–Ш‘ж3ҢRӮМҺА—НӮЙӮВӮўӮДӮаүЯ‘е•]үҝӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ”ЮӮНҒAҗнӮўӮМҸүҠъ’iҠKӮ©Ӯз‘ж3ҢRӮрғ}Ғ[ғNӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮЖӮұӮлӮӘҒA”ЮӮНүE—ғӮМҠӣ—ОҚ]ҢRӮрҚ¶—ғӮМ‘ж3ҢRӮЖҠЁҲбӮўӮөҚ¬“ҜӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAҗнӮўӮМ’Ҷ”ХӮЙӮИӮБӮДӮ»ӮМӮұӮЖӮЙӢCӮГӮ«ҒAҢғӮөӮўғVғҮғbғNӮрҺуӮҜӮДҺvҚl’вҺ~Ҹу‘ФӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНҒAҚЎӮЬӮЕғmҒ[ғ}Ғ[ғNӮЙӮөӮДӮўӮҪ‘ж3ҢRӮЙүЎ• ӮрҸХӮ©ӮкӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒH ҺАҚЫӮЙӮНҒA“ъ–{ҢRӮНӮЩӮЖӮсӮЗ—\”хҗн—НӮрҺқӮБӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB•т“VүпҗнӮНҒAҲкӮ©”ӘӮ©ӮМ‘еҸҹ•үӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮЬӮҪҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮН—·ҸҮӮЕӮМғ_ғҒҒ[ғWӮ©Ӯзүс•ңӮөӮ«ӮкӮДӮЁӮзӮёҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮМҗS’_ӮрҠҰӮ©ӮзӮөӮЯӮйӮЩӮЗӮМҲР—НӮНҺқӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮЖӮаӮ ӮкҒAҺгӢCӮЙӮИӮБӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮМ–Ҫ—ЯҲкүәҒAғҚғVғAҢRӮН•т“VӮ©Ӯз“P‘ЮӮөҒA“ъ–{ҢRӮНӮұӮМүпҗнӮЙҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮМӮЕӮ·(3ҢҺ10“ъ)ҒB “ъ–{ҢRӮМҺҖҸқҺТҗ”7–ңҒBғҚғVғAҢRӮМҺҖҸқҺТӮН9–ңҒAӮ»ӮөӮД•Я—ё2–ң1җзҒB ӮұӮМҸҹ—ҳӮНҒAҒuғNғҚғpғgғLғ“ӮӘҺгӢCӮИҺwҠцҠҜӮҫӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨҲкҺ–ӮЙ‘еӮ«ӮӯҲЛ‘¶ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЗӮӨӮөӮД”ЮӮНҒAӮұӮсӮИӮЙҺгӢCӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒHӮ»ӮМ—қ—RӮНҒA”ЮӮӘӮ©ӮВӮДҒA—ӨҢR‘еҗbӮЖӮөӮД“ъ–{ӮрҺӢҺ@ӮөӮҪӮЖӮ«ӮЙҒAӮ»ӮМҚ‘—НӮр”сҸнӮЙҚӮӮӯ•]үҝӮөҒAӢӯӮўҗe“ъҠҙҸоӮр•шӮўӮҪӮұӮЖӮЙҢҙҲцӮӘӮ ӮйӮжӮӨӮЕӮ·ҒBғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒAӮаӮЖӮаӮЖ“ъ–{ӮЖӮМҗн‘ҲҺ©‘МӮЙ”Ҫ‘ОӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮЕӮНҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAӮЗӮӨӮөӮДӮ»ӮсӮИҗe“ъ“IӮИҗl•ЁӮр–һҸBҢRӮМҺi—ЯҠҜӮЙҗҳӮҰӮҪӮМӮ©ҒHӮ»ӮкӮНҒAӢЙӮЯӮДҠҜ—»“IӮИ”NҢчҗlҺ–ӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮөӮҪҒB•…ӢҖҠҜ—»‘gҗDӮЖ‘ВӮөӮҪғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒAӮаӮНӮвҒu“KҚЮ“KҸҠҒvӮЖӮўӮӨҠT”OӮр–YӢpӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮНҒA40”NҢгӮМ“ъ–{’йҚ‘ӮЖӮЬӮБӮҪӮӯ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{ҢRӮНҸҹ—ҳӮөӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒA•т“VүпҗнӮМҚЕ‘еӮМ–Ъ“IӮЕӮ ӮБӮҪҒuғҚғVғAҢRҺе—НӮМ•пҲНҹr–ЕҒvӮЙҺё”sӮөӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRҺе—НӮНҒAҢӢӢЗ“ҰӮ°ӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕҒAӮұӮМҗнӮўӮЕ’v–Ҫ“Iғ_ғҒҒ[ғWӮрғҚғVғAӮЙ—^ӮҰӮДҚuҳaүпӢcӮМғeҒ[ғuғӢӮЙҲшӮ«ӮёӮиҸoӮ·ӮЖӮўӮӨҗӯ—ӘӮНӢуҗUӮиӮЙҸIӮнӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғAғҒғҠғJ‘е“қ—МғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮНҒAҠщӮЙ—·ҸҮ—vҚЗҠЧ—ҺҺһӮЙғҚғVғAҗӯ•{ӮЙҒuҳa•Ҫ’ҮүоҒvӮрҗ\Ӯө“ьӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮкӮНӮ ӮҰӮИӮӯӢpүәӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮНҒA•т“VӮМҠЧ—ҺӮр’mӮБӮДҚДӮС“®ӮўӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒuүдӮӘҚ‘ӮНҒAӮЬӮҫҢЕ—LӮМ—М“yӮр’DӮнӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖҢҫӮБӮД“ЛӮБӮПӮЛӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAҢRӮН“S—дҒA‘ұӮўӮД’·ҸtӮЙ“P‘ЮӮөҒA“ъ–{ҢRӮНӮ»ӮкӮрҢң–ҪӮЙ’ЗҢӮӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮаӮНӮв—\”хҗн—НӮрҺgӮўүКӮҪӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮЙӮНҒAҚД“xӮМҢҲҗнӮр’§ӮЮ—НӮНҺcӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҢЭӮўӮЙҗw’nӮр’zӮўӮДбЙӮЭҚҮӮӨ—јҢRӮНҒAҢЭӮўӮМҠCҢRӮМҠҲ–фӮЙҠъ‘ТӮр’uӮӯӮөӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМҠФҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAҚҸҲкҚҸӮЖ“ъ–{–{“yӮЙ”—ӮиӮВӮВӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB ‘SҗўҠEӮМҺЁ–ЪӮӘҒAӮұӮМҠН‘аӮЙҸW’ҶӮөӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮӘҚuҳaӮМғeҒ[ғuғӢӮЙғҚғVғAӮрҲшӮ«ӮёӮиҸoӮ·ӮҪӮЯӮЙӮНҒAӮұӮМҠН‘аӮЖӮМҢҲҗнӮЙүҪӮӘүҪӮЕӮаҸҹ—ҳӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBҒ@ |
|
| ҒЎ8ҒA“ъ–{ҠCҠCҗн | |
|
ҒЎ(1) ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМүсҚq
ғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғp•ы–КӮЙ“сӮВӮМҠН‘аӮрҺқӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒAғoғӢғgҠCҠН‘а(ғoғӢғ`ғbғNҠН‘а)ӮЖҚ•ҠCҠН‘аӮЕӮ·ҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAғhғCғcҠCҢRӮМҚUҢӮӮ©ӮзғyғeғӢғuғӢғNӮрҺзӮйӮҪӮЯӮМ”хӮҰҒAҚ•ҠCҠН‘аӮНғgғӢғRӮЙ‘ОӮ·Ӯй”хӮҰӮЕӮөӮҪҒB ӮіӮДҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМ–u”ӯӮЙӮжӮБӮДҒA“ҢғAғWғAӮМҠCҢRӮӘӢҮ’nӮЙҠЧӮБӮҪӮұӮЖӮр’mӮБӮҪғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҒu‘ж2‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҒvӮЖүьҸМӮөҒAӮұӮкӮрӢЙ“ҢӮЙүсҚqӮіӮ№ӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮЬӮ·ҒBҺwҠцҠҜӮЙ‘IӮОӮкӮҪӮМӮНҒA‘еҠҜ—»ӮМғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМҠН‘аӮНҒA1904”N10ҢҺ15“ъҒAҚc’йӮЙҢ©‘—ӮзӮкӮДғNғҚғ“ғVғ…ғ^ғbғgҚ`ӮрҸoҢӮҒBғoғӢғgҠCӮ©Ӯз‘еҗј—mӮр“мүәӮөҒA“мғAғtғҠғJӮМҠм–]•фҢo—R(Ҳк•”ӮМҸ¬Ң^ҠНӮНғXғGғYү^үНҢo—R)ӮЕғCғ“ғh—mӮЙ“ьӮиҒAғ}ғүғbғJҠCӢ¬Ӯ©ӮзғxғgғiғҖү«Ӯр–kҸгӮөҒAӮ»ӮөӮД—·ҸҮӮЙ“ьӮй—\’иӮЕӮөӮҪҒBҗўҠEҺjҸгҒA—Ю—бӮрҢ©ӮИӮў’·ҠъӮМҗ퓬ҚqҠCӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮЙ•C“GӮ·ӮйӮМӮНҒAүF’ҲҗнҠНғ„ғ}ғgӮМғCғXғJғ“ғ_ғӢҗҜӮЦӮМҗ퓬ҚqҠCӮӯӮзӮўӮМӮаӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©(ҸО)ҒB ӮұӮМҠН‘аӮМҚqҠCӮНҒAӢк“пӮЙ–һӮҝӮҪӮаӮМӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМҚЕ‘еӮМ—қ—RӮНҒAҗўҠEҠe’nӮЙҗA–Ҝ’nӮрҺқӮВғCғMғҠғXӮӘ—lҒXӮИ–WҠQҚHҚмӮрҚsӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBғCғMғҠғX—МӮЦӮМҠсҚ`ӮрӢ‘”ЫӮіӮкӮҪғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAӮөӮ©ӮҪӮИӮӯҗ”ҸӯӮИӮўғtғүғ“ғX—МӮМҚ`ҳpӮЙ“ьӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮұӮЕӮа—lҒXӮИҒuҠOҢрҲі—НҒvӮӘӮ©ӮҜӮзӮкӮДҒA’Z“ъӮМӮӨӮҝӮЙҚ`ҠOӮЙ’ЗӮўҸoӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨҺn––ҒBӮұӮӨӮөӮДҒAӮлӮӯӮЙӢx—{ӮаҺжӮкӮёҒAҢP—ыӮаҺуӮҜӮзӮкӮИӮўӮұӮМҠН‘аӮМҗн—НӮНҒA“ъ‘қӮөӮЙ’бүәӮөӮДҚsӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҗ…•vӮМ’ҶӮЙӮНҒA”ӯӢ¶ҺТӮаҸoӮҪӮЖӮўӮўӮЬӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{җӯ•{ӮЙӮНҒAӮ»ӮМӮжӮӨӮИҺАҸоӮН•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМүeӮЙӢҜӮҰӮйҗӯ•{ӮӘҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮМҗKӮр’@ӮўӮД—·ҸҮӮрҺrӮМҺRӮЙ•ПӮҰӮҪӮМӮНҒAӮұӮкӮЬӮЕҸqӮЧӮҪӮЖӮЁӮиӮЕӮ·ҒB ӮіӮДҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒA—·ҸҮӮМҠЧ—ҺӮрғAғtғҠғJ“Ң•”ӮМғ}ғ_ғJғXғJғӢ“Ү(12ҢҺ29“ъ“ьҚ`)ӮЕ’mӮиӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮЖӮ«ҒA‘SҠНӮЙҸХҢӮӮӘ‘–ӮиӮЬӮөӮҪҒB—·ҸҮӮМҠЧ—ҺӮНҒAӮұӮМҗ퓬ҚqҠCӮМҚӘ–{“IҲУӢ`ӮрҢ©ҺёӮнӮ№ӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮИӮәӮИӮзҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒA—·ҸҮҠН‘аӮЖҚҮ—¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЕ“ъ–{ҠCҢRӮЙ‘ОӮөӮДҲі“|“IӮИҗ”“I—DҲКӮрҠm•ЫӮөӮДҒAғVҒ[ғҢҒ[ғ“Ӯр”jүуӮөҒA–һҸBӮМ“ъ–{ҢRӮрӢQӮҰӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒA—·ҸҮҠН‘аӮӘ‘S–ЕӮөӮҪҚЎӮЖӮИӮБӮДӮНҒA’P“ЖӮЕ“ъ–{ҠCҢRӮЖҗнӮнӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮөӮДҒAғCғMғҠғXҗ»ӮМҚӮҗ«”\ҠНӮр‘ҪӮӯ—iӮ·Ӯй“ъ–{ҠCҢRӮЖҗі–КҸХ“ЛӮөӮДҸҹӮДӮйӮЖӮНҺvӮҰӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒB ҠН‘аҺi—ЯғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮНҒA–{Қ‘ӮЙҚмҗн’ҶҺ~ӮрӢпҗ\ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮЬӮЬҗiӮЭ‘ұӮҜӮДӮаӢ]җөӮӘ‘қӮҰӮйӮҫӮҜӮҫӮЖҒB ӮөӮ©ӮөҒA–{Қ‘җӯ•{ӮНӮЬӮБӮҪӮӯҲбӮӨӮұӮЖӮрҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒB”ЮӮзӮНҒAғoғӢғgҠCӮМҺc‘¶ҠН‘аӮ©Ӯз‘Ю–рҠФӢЯӮМӢҢҺ®ҠНӮр’ҠҸoӮөҒAӮұӮкӮрҒu‘ж3‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҒvӮЖ–јӮГӮҜӮДғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮМҢгӮр’ЗӮнӮ№ӮЬӮөӮҪҒB‘қүҮӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЕҒA“ъ–{ҠCҢRӮЙ‘ОӮ·Ӯйҗ”“I—DҲКӮрҠm•ЫӮіӮ№ӮжӮӨӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҢvүжӮНҒA—қӢьӮМҸгӮЕӮН—ЗҚфӮМӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮЬӮ·ӮЛҒBӮөӮ©ӮөҒA‘Ю–рҠФӢЯӮМӢҢҺ®ҠНӮИӮЗҒAҗнҸкӮЕӮН‘«ҺиӮЬӮЖӮўӮЙӮөӮ©ӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮЬӮҪҒA‘қүҮӮМ“һ’…ӮрҗФ“№’јүәӮЕ‘ТӮВҗ”ғ–ҢҺҠФӮЕҒAғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ҠшүәӮМҸ«•әӮМ”жҳJӮНӮЬӮ·ӮЬӮ·ҢғӮөӮӯӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҗж‘c‘гҒXҢөҠҰӮМ’nӮЕ•йӮзӮөӮДӮ«ӮҪғҚғVғAӮМ”’җlҗВ”NӮҪӮҝӮӘҒA‘«Ҡ|ӮҜ3ғ–ҢҺӮаӮМҠФҒA”M‘СӮМ‘ҫ—zӮМүәӮЙ’uӮ«ӢҺӮиӮЙӮіӮкӮҪҸуӢөӮр‘z‘ңӮөӮДӮЭӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB Ҳк•ыҒAӮ»ӮМҗ”ғ–ҢҺҠФӮЕҒA‘јӮЙҺdҺ–ӮӘ–іӮӯӮИӮБӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮМҗ®”хӮЖӢx—{ӮЖҢP—ыӮНҒAҸ\•ӘүЯӮ¬ӮйӮЩӮЗӮЙҗ®ӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ‘қүҮҚфӮНҒAүпӢcҺәӮЙҳUӮБӮДҢ»ҸкӮр’mӮзӮИӮў•…ӢҖҠҜ—»ӮМҚlӮҰ•tӮ«Ӯ»ӮӨӮИӢрҚфӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ Ӯ ҒAӮИӮсӮЖ40”NҢгӮМ“ъ–{ҢRӮМ—l‘ҠӮЙҺ—ӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ҒB ӮөӮ©ӮөҒAӢр’јӮИғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’с“ВӮНҒA–{Қ‘ӮМ–Ҫ—ЯӮЙҸ]ӮнӮҙӮйӮр“ҫӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB”ЮӮНҒA‘қүҮӮМ“®Ӯ«ӮрҢ©җҳӮҰӮИӮӘӮзҒA3ҢҺ17“ъӮЙӮжӮӨӮвӮӯғ}ғ_ғKғXғJғӢӮрҸoҚ`ӮөҒAғCғ“ғh—mӮрҲкӢCӮЙ“Л”jҒBӮ»ӮөӮДғ}ғүғbғJҠCӢ¬Ӯр”ІӮҜӮДҒA4ҢҺ14“ъҒA•§—МғCғ“ғhғVғi(ғxғgғiғҖ)ӮЙ’HӮиӮВӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМ’nӮр—М—LӮ·Ӯйғtғүғ“ғXӮНҒA—бӮЙӮжӮБӮД—бӮМӮІӮЖӮӯҒAғCғMғҠғXӮМҠOҢрҲі—НӮЙӢьӮөӮДғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮр’ЗӮўҸoӮөӮЙӮ©Ӯ©ӮиӮЬӮ·ҒB ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’с“ВӮНҒAҺЧ–ӮҺТҲөӮўӮіӮкӮҪҠН‘аӮрғxғgғiғҖӢЯҠCӮЙңfңrӮіӮ№ӮВӮВҒAӮРӮҪӮ·Ӯз‘қүҮҠН‘аӮр‘ТӮҝ–]ӮЮӮМӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ”ЮӮНҒA5ҢҺ9“ъӮЙӮжӮӨӮвӮӯ‘қүҮӮЖӮМҚҮ—¬ӮЙҗ¬ҢчӮөҒAӮ»ӮМҗiҳHӮр“ъ–{ӮЦҢьӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮЖӮұӮлӮЕҒAғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮНҒAӮөӮОӮөӮО–і”\ҢДӮОӮнӮиӮіӮкӮЬӮ·ӮӘҒAҺ„ӮНӮ»ӮӨӮНҺvӮўӮЬӮ№ӮсҒBӮұӮкӮЩӮЗӮМүЯҚ“ӮИ‘еҚqҠCӮрҲкҗЗӮМ’E—ҺҺТӮа”Ҫ—җҺТӮаҸoӮіӮёӮЙҸжӮиҗШӮБӮҪ“қ—Ұ—НӮНҒAҺАӮЙ‘еӮөӮҪӮаӮМӮҫӮЖҺvӮӨӮМӮЕӮ·ҒB”ЮӮНҒAӮаӮөӮа“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮДӮўӮҪӮзҒAҒuҗl—ЮҺjҸгҚЕҚӮӮМ–ј’с“ВҒvӮЖҢДӮОӮкӮДӮўӮҪӮЕӮөӮеӮӨӮЛҒB —рҺjӮНҒAҸнӮЙ”sҺТӮЙ•s“–ӮЙҢөӮөӮўӮаӮМӮИӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҗiҳHӮНҒH
“ъ–{җӯ•{ӮНҒAғCғMғҠғXӮМ’і•с‘gҗDӮМҸ•ӮҜӮрҺШӮиӮДҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“®Ӯ«ӮрҢp‘ұ“IӮЙғӮғjғ^Ғ[ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғJғҖғүғ“ҳpҲИҚ~ӮНҒAӮ»ӮМ“®Ӯ«ӮрҢ©ҺёӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAҚqҠCӮМ”жӮкӮр–ьӮ·ӮҪӮЯӮЙҒAӮЬӮёӮНғEғүғWғIғXғgғbғNҚ`ӮЙ“ьҚ`Ӯ·ӮйӮЕӮөӮеӮӨҒBӮ»ӮөӮДҒA‘ҫ•Ҫ—mӮ©ӮзғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ“ьӮйӮМӮЙӮНҒA‘еӮ«Ӯӯ•ӘӮҜӮД2ӮВӮМғӢҒ[ғgӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBҲкӮВӮНҒA‘О”nҠCӢ¬Ӯр”ІӮҜӮйҗјӮжӮиӮМғӢҒ[ғgҒBӮаӮӨҲкӮВӮНҒAҗз“Ү—с“ҮӮр”ІӮҜӮй–kӮжӮиӮМғӢҒ[ғgҒB“ъ–{ҠCҢRӮНҒAӮұӮМӮӨӮҝӮМӮЗӮҝӮзӮ©ӮЕ‘ТӮҝ•ҡӮ№ӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB “ҢӢҪ’с“В—ҰӮўӮйҳAҚҮҠН‘аӮНҒAҚЕҸүӮНҒuҗјӮжӮиғӢҒ[ғgҒvӮЖҚlӮҰӮД’©‘N”ј“Ү“м•”ӮЙҠН‘аӮрҸWҢӢӮіӮ№ӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA‘ТӮДӮО‘ТӮВӮЩӮЗ•sҲАӮЙӮИӮйӮаӮМҒB“GӮМҸо•сӮӘ‘SӮӯ“ьӮзӮИӮўӮМӮҫӮ©Ӯз–і—қӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮЬӮҪҒAҸHҺRҺQ–dӮӘв¬’|җиӮў(ҸО)ӮрӮвӮБӮҪҢӢүКҒAҒu“ҢӮжӮиҒvӮМҢTӮӘҸoӮҪӮұӮЖӮаҠН‘аӮМҗS—қӮр•sҲАӮЙӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒBҸHҺRҗ^”VҺQ–dӮНҒAӮөӮОӮөӮОҸ¬җаӮИӮЗӮЕ”ьү»ӮіӮкүЯ‘е•]үҝӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ©ӮИӮиӮМ•ПҗlӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЙ—ҜҲУӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮөӮеӮӨҒB “®—hӮөӮҪ“ҢӢҪ’с“ВӮНҒA‘е–{үcӮЙ–і“dӮр‘ЕӮБӮДҒA–kҠC“№ӮЙ“]җiӮ·ӮйҺ|Ӯр’КҚҗӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA‘е–{үcӮМҲЙ“ҢҢR—Я•”’·ӮН—вҗГӮИ”»’f—НӮЕ“ҢӢҪӮр—GӮЯӮДүҹӮөҺ~ӮЯ‘ұӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ҳк•ыҒA–в‘иӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAҠщӮЙҒuҗјӮжӮиғӢҒ[ғgҒvӮМ“Л”jӮрҢҲӮЯӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—қ—RӮНҒA1җз“Ү—с“ҮӮН’Ә—¬ӮӘҢғӮөӮӯ“VҢуӮӘҲ«ӮўӮМӮЕҒA”жҳJӮөӮ«ӮБӮҪҠН‘аӮӘ–іҺ–ӮЙҚqҚsҸo—ҲӮйӮЖӮНҺvӮҰӮИӮўҒB2‘SҠН‘аӮӘғEғүғWғIғXғgғbғNӮЬӮЕӢx‘§ӮрҺжӮкӮё”R—ҝӮр•вӢӢӮЕӮ«ӮИӮўҺ–ҸоӮрҠУӮЭӮкӮОҒAҚЕ’ZғRҒ[ғXӮМҒuҗјӮжӮиғӢҒ[ғgҒvӮрҗiӮЮӮөӮ©ӮИӮўҒB ӮөӮ©ӮөҒAҒuҗјӮжӮиғӢҒ[ғgҒvӮЙӮНҒAӢӯ—НӮИ“ъ–{ҠCҢRӮӘ‘ТӮҝ•ҡӮ№ӮөӮДӮўӮйӮНӮёӮЕӮ·ҒBӮ»ӮұӮЕғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮНҒAӮўӮӯӮВӮ©ӮМӢU‘•ҚHҚмӮрҚsӮўӮЬӮөӮҪҒBҠН‘аӮрӮнӮҙӮЖү«“к(”ӘҸdҺR)ӮМ“Ң‘ӨӮЙҸoҢ»ӮіӮ№ҒAӢҢҺ®Ҹ„—mҠНӮрҸ¬Ҡ}Ңҙ•ы–КӮЙ•Ә—ЈӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBү^ӮӘ—ЗӮҜӮкӮОҒAӮұӮМ“®Ӯ«ӮЙ’ЮӮзӮкӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮНҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҗз“ҮғӢҒ[ғgӮр’HӮйӮаӮМӮЖҢл’fӮөӮДҒA‘О”nҠCӢ¬ӮрӮӘӮзӢуӮ«ӮЙӮөӮДӮӯӮкӮйӮҫӮлӮӨҒB ӮөӮ©ӮөҒAҚKү^ӮМҸ—җ_ӮНғҚғVғAӮЙӮН”чҸОӮЭӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB”ӘҸdҺRӮЙӮН–іҗьҗЭ”хӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘ“ҢҠЭӮЙҸoҢ»ӮөӮҪӮЖӮМ•сӮН“ҢӢһӮЬӮЕ“`ӮнӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҸ¬Ҡ}Ңҙ•ы–КӮЙ•Ә—ЈӮөӮҪҸ„—mҠНӮНҒAҢӢӢЗҒAӮЗӮұӮМҚ‘җРӮМ‘D”•ӮЙӮаҚsӮ«үпӮнӮёҒAӮөӮҪӮӘӮБӮДӮұӮкӮЙҠЦӮ·ӮйҸо•сӮа“ҢӢһӮЙӮН—¬ӮкӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЖӮНӢtӮЙҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮ©Ӯз•Ә—ЈӮіӮкӮҪ—A‘—‘D’cӮӘҸгҠCӮЙ“ьҚ`ӮөӮҪӮЖӮ«ҒAӮұӮкӮЙҠЦӮ·ӮйҸо•сӮӘ“ҢӢһӮЙ—¬ӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB‘е–{үcӮНҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒBҒu—A‘—‘D’cӮрҗШӮи—ЈӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAғҚғVғAҠН‘аӮНҚЕ’ZӢ——ЈӮМ‘О”nғӢҒ[ғgӮрҚМӮйӮЙҲбӮўӮИӮўҒvҒB ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮӘҺdҠ|ӮҜӮҪғtғFғCғ“ғgӮНҢ©Һ–ӮЙӢуҗUӮиӮөҒAӮ»ӮөӮД“ъ–{ӮНғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҲУҗ}Ӯр“ЛӮ«Һ~ӮЯӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAҢҲҗнӮМүОҠWӮӘҗШӮзӮкӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) “ъ–{ҠC‘еҠCҗн
ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAҢP—ы•sҸ\•ӘӮЕ”жҳJҚўңЮӮМҗ…•әӮЙүБӮҰҒA’ҷ‘ ҢЙӮЙ”[ӮЯӮ«ӮкӮИӮўҗО’YӮрҚb”ВӮЙ–һҚЪӮөӮҪҸу‘ФӮЕ‘О”nҠCӢ¬ӮЙ“ьӮБӮД—ҲӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮаҒAӮ»ӮМ’ј‘OӮЙҒAғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮМ•ӣҠҜӮЙ“–ӮҪӮйғtғFғҠғPғӢғUғҖҸӯҸ«ӮӘүЯҳJӮЕ•aҺҖӮ·ӮйӮЖӮўӮӨғnғvғjғ“ғOӮаӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮНҒAӮұӮМҗl–]ҲмӮкӮй—L”\ӮИ•ӣҠҜӮМҺҖӮрҒAҗ…•әӮҪӮҝӮЙ”й“ҪӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкҲИҸгӮМҺmӢCӮМ’бүәӮр”рӮҜӮҪӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДҒAӮұӮМғtғүғtғүӮЕғ{ғҚғ{ғҚӮМҠН‘аӮНҒAӮҪӮҝӮЬӮҝ“ъ–{ӮМҸЈүъ–ФӮЙҲшӮБӮ©Ӯ©ӮиӮЬӮөӮҪҒBҸЈүъ’шҒEҗM”ZҠЫӮ©ӮзӮМӢ}•сӮрҺуӮҜҒA“ҢӢҪ’с“В—ҰӮўӮй“ъ–{ӮМҳAҚҮҠН‘аӮНҒAҠШҚ‘“м•”ӮМ’БҠCҳpӮрҸoҢӮӮөӮЬӮөӮҪҒBҺһӮЙ1905”N5ҢҺ27“ъҢЯ‘O6ҺһҒB ҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvӮЙZҠшӮӘ•‘ӮўҸгӮӘӮиӮЬӮөӮҪҒBҲУ–ЎӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮНҒAҒuҚcҚ‘ӮМӢ»”pҒAӮұӮМҲкҗнӮЙӮ ӮиҒBҠeҲхӮўӮБӮ»ӮӨ•ұ—г“w—НӮ№ӮжҒvҒBҸHҺRҺQ–dӮНҒA‘е–{үcӮЙ–і“dӮр‘ЕӮҝӮЬӮөӮҪҒBҒu–{“ъҒA“VӢCҗ°ҳNӮИӮкӮЗӮа”gҚӮӮөҒvҒB •sү^ӮИӮұӮЖӮЙҒAҳAҚҮҠН‘аӮЙҺӢ”FӮіӮкӮҪғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAӢ·ӮўҠCӢ¬Ӯр’КӮйӮҪӮЯӮЙҗwҢ`Ӯр•ПҚXӮөӮДӮўӮй“r’ҶӮЕӮөӮҪҒB”ЮӮзӮНҒAҚЕҲ«ӮМғ^ғCғ~ғ“ғOӮЕҚЕӢӯӮМ“GӮЙҸPӮнӮкӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ҳAҚҮҠН‘аӮНҒAҒuTҺҡүс“ӘҒvӮрҠёҚsӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA“GӮМ’PҸcҗwӮЙ‘ОӮөӮДҗӮ’јӮЙӮИӮйҢ`ӮЙ–Ў•ыӮМ’PҸcҗwӮрҗiӮЯҒAӮ»ӮұӮ©Ӯз“GӮМ’ј‘OӮЕҲкҗДүс“ӘӮөҒA“ҜӮ¶•ыҢь(–k)ӮЙҠН‘аӮр‘–ӮзӮ№ӮИӮӘӮз–CҢӮӮр—ҒӮСӮ№ӮйӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ·ҒBӮжӮӯҢлүрӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮН–CҢӮҗнӮМҗн–@ӮЕӮНӮИӮӯӮДҒAҒuҗiҳHӮМҺжӮи•ыҒvӮЕӮ·ҒB“ҢӢҪ’с“ВӮЖҸHҺRҺQ–dӮНҒAҚр”N8ҢҺӮМү©ҠCҠCҗнӮМӮіӮўҒAӮаӮӨҸӯӮөӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮЙ–kӮЙ“ҰӮ°ӮзӮкӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪҢҷӮИҢoҢұӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒA“с“xӮЖ“ҜӮ¶Һё”sӮНӢ–ӮіӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮұӮЕҒAҒuҸнӮЙ“GӮЖ“ҜӮ¶•ыҢьӮЙ•АҚsӮөӮДҗiӮЮҒvӮҪӮЯӮЙҚlӮҰҸoӮіӮкӮҪӮМӮӘҒuTҺҡүс“ӘҒvӮЖӮўӮӨҚq–@ӮҫӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA“G‘OӮЕҗiҳHӮр•ПҚXӮ·ӮйӮЖӮ«ҒAҢRҠНӮМ“®Ӯ«ӮНҲкҺһ“IӮЙҗГҺ~ӮөӮЬӮ·ҒBӮ»ӮұӮр‘_ӮўҢӮӮҪӮкӮҪӮз’v–ҪҸқӮЙӮИӮиӮ©ӮЛӮЬӮ№ӮсҒBӮұӮМ–`ҢҜӮрӮ ӮҰӮДҺҺӮЭӮҪӮМӮӘҒA“ҢӢҪ’с“ВӮМ—EӢCӮЖҠoҢеӮЕӮ·ҒBҲДӮМ’иҒA‘SҠНӮМҗж“ӘӮЙ—§ӮВҗнҠНҒuҺOҠ}ҒvӮНҒAғҚғVғAҠН‘аӮМҸW’Ҷ–CҢӮӮрҺуӮҜӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҒuҺOҠ}ҒvӮНғCғMғҠғXҗ»ӮМҗўҠEҚЕӢӯӮМ‘•ҚbӮрҺқӮВҗVүsҠНӮЕӮ·ҒB’јҢӮӮрҺуӮҜӮДӮаҒAӮ»ӮМғ_ғҒҒ[ғWӮН’v–ҪҸқӮЙӮНӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBғҚғVғAҠН‘аӮӘҒAӮҪӮЬӮҪӮЬҗw•ПӮҰӮМ“r’ҶӮҫӮБӮҪӮҪӮЯӮЙ—LҢшӮИ–CҢӮӮрҚsӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮаҚKӮўӮөӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮјҒA“ъ–{ӮМҚKү^ҒAғҚғVғAӮМ•sү^ҒB ‘Ь’@Ӯ«ӮЙӮИӮиӮИӮӘӮзӮаҒA–іҺ–ӮЙүс“ӘӮрҸIӮҰӮД“GӮЖ•АҗiӮ·ӮйҢ`ӮЙӮИӮБӮҪҳAҚҮҠН‘аҒBҚЎ“xӮНҒA“ъ–{ӮӘӮЁ•ФӮөӮ·Ӯй”ФӮЕӮ·ҒB“ҢӢҪ’с“ВӮМҗнҠНҒuҺOҠ}ҒvҒu•~“ҮҒvҒu•xҺmҒvҒu’©“ъҒvӮЖ‘•ҚbҸ„—mҠНҒuҸt“ъҒvҒu“ъҗiҒvҒAҸг‘ә’с“ВӮМ‘•ҚbҸ„—mҠНҒu”ЦҺиҒvҒuҸoү_ҒvҒuҢбҚИҒvҒuҗуҠФҒvҒu”Әү_ҒvҒuҸн”ХҒvӮзӮӘҲкҗДӮЙ–C–еӮрҠJӮ«ӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮМҢRҠНӮНҒAҚДҺOӮЙӮнӮҪӮБӮДҸqӮЧӮҪӮжӮӨӮЙҒAҗўҠEҚЕӢӯӮМғCғMғҠғXҗ»ӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA“ъ–{ҠCҢRӮНҒA“ъ–{ғIғҠғWғiғӢӮМҲЙҸWү@җMҠЗӮвүәҗЈүО–тӮр—pӮўӮҪҚӮҗ«”\–C’eӮрҺg—pӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒA“GҠНӮМ‘•ҚbӮр‘ЕӮҝ”ІӮӯӮаӮМӮЕӮНӮИӮӯҒAҚb”ВӮЕ”ҡ”ӯӮөӮДҚӮ”MӮМүҠӮрҺTӮ«ҺUӮзӮ·ӮұӮЖӮЕҒA“Gҗ…•әӮМҠҲ“®Ӯр’вҺ~ӮіӮ№ӮДӮөӮЬӮӨӮЖӮўӮӨҗV•әҠнӮЕӮөӮҪҒB ғҚғVғAҠН‘аӮНҒAӮҪӮҝӮЬӮҝүҠӮрӮ Ӯ°ӮД’f–––ӮӮЙӮ ӮҰӮ¬ӮЬӮ·ҒB•sү^ӮИӮұӮЖӮЙҒAҠшҠНӮМғXғҸғҚғtӮӘҒAӮўӮ«ӮИӮи‘еғ_ғҒҒ[ғWӮрҺуӮҜҒA‘ҚҺi—ЯҠҜӮМғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮӘҸdҸқӮр•үӮўҗlҺ–•sҸИӮЙҠЧӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮНҒAӮұӮкӮрҺwӮөӮДҒuӮҫӮ©ӮзғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮН–і”\ӮИӮМӮҫҒIҒvӮЖ•]ӮөӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮНӮҝӮеӮБӮЖҚ“ӮИӮМӮЕӮНҒH ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ӮӘ“|ӮкӮҪӮзҒA•ӣҠҜӮМғtғFғҠғPғӢғUғҖӮӘҺwҠцӮрҲшӮ«ҢpӮӘӮЛӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮөӮ©ӮөҒA‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҒAӮұӮМ•ӣҠҜӮНҠщӮЙ•aҺҖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮаҒAӮ»ӮМҺ–ҺАӮНҲк•”ӮМ–Ӣ—»ӮЙӮөӮ©’mӮзӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮДҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҺwҠц–Ҫ—ЯҢn“қӮНҠCҗнҷң“ӘӮЕ–і—Нү»ӮөӮЬӮөӮҪҒBүҪӮЖӮўӮӨ•sү^ҒI “ъ–{ӮМҢRҠНӮНҒAғҚғVғAӮМӮ»ӮкӮжӮиӮаҒA–C—НҒAӢ@“®—НҒA‘•ҚbҒA‘SӮДӮЙӮЁӮўӮДҸҹӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҗ…•әӮМүsӢCӮЖҢP—ы“xӮНҒAӮ»ӮкӮұӮ»ҳbӮЙӮИӮзӮИӮўӮӯӮзӮўӮЙҢңҗвӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮДҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮНҲк•ы“IӮИӮаӮМӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҗ…•ҪӮИҠCӮМҸгӮЕҒA“ҜӮ¶Ӣ——ЈӮ©Ӯз‘е–CӮрҢӮӮҝҚҮӮӨӮМӮҫӮ©ӮзҒAҢRҠНӮМҗ«”\ӮЖҗ…•әӮМҳB“xӮНҒAӮ»ӮкӮұӮ»Ҹҹ”sӮр•ӘӮҜӮйҢҲ’и“IӮИ—v‘fӮЖӮИӮиӮЬӮ·ҒB җwҢ`Ӯа‘аҢ`ӮағYғ^ғYғ^ӮЙӮіӮкӮИӮӘӮзҒA•KҺҖӮЙ–kӮр–ЪҺwӮ·ғҚғVғAҠН‘аӮНҒA–йӮЙӮИӮБӮДҲАҗSӮөӮҪӮМӮаӮВӮ©ӮМҠФҒAӢӣ—ӢӮр•шӮҰӮҪ“ъ–{ӮМҗ…—Ӣ’шӮЙҸPӮўҠ|Ӯ©ӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB–йӮӘ–ҫӮҜӮҪӮзҒAҚДӮС–іҸқӮМ“ҢӢҪҠН‘аӮЙ’ЗӮўӮ©ӮҜӮЬӮнӮіӮкӮйӮМӮЕӮөӮҪҒB ‘Ю–рҠФӢЯӮМӢҢҺ®ҠН‘а(‘ж3‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а)ӮНҒAҠпҗХ“IӮЙ–іҸқӮМӮЬӮЬҒAҗнҸкӮЕүҪӮМ–рӮЙӮа—§ӮҪӮёӮЙ–kҸгӮө‘ұӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮВӮўӮЙ“ҢӢҪҠН‘аӮЙ”ӯҢ©ӮіӮк•пҲНӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҠН‘аӮр—ҰӮўӮйғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ӮНҒAӮВӮўӮЙҚ~•ҡӮрҢҲҲУӮөӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒAҸdҸқӮМғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ӮНҒAҠшҠНғXғҸғҚғtӮӘ’ҫ–vӮ·Ӯй’ј‘OӮЙҒA–Ӣ—»ӮҪӮҝӮЙҳAӮкӮзӮкӮДӢм’ҖҠНӮЙҸжӮБӮД’EҸoӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{ӮМӢм’ҖҠНӮЙ’ЗӮўүсӮіӮкҒAӮвӮНӮиҚ~•ҡӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҺһӮЙ1905”N5ҢҺ28“ъҒAҗўҠEҠCҗнҺjҸгҚЕ‘еӮМғҸғ“ғTғCғhғQҒ[ғҖӮНҒAӮұӮӨӮөӮДҸIҢӢӮөӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҠН‘аӮНҺ–ҺАҸг‘S–ЕӮөӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA“ъ–{ҠН‘аӮМ‘№ҠQӮНҠC“пҺ–ҢМӮЙӮ ӮБӮҪҗ…—Ӣ’шҗ”җЗӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ‘SҗўҠEӮӘҒAӮұӮМ“ъ–{ӮМ‘еҸҹ—ҳӮЙ•ҰӮ«Ӯ©ӮҰӮиӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAҲУӢCҸБ’ҫӮЕӮ·ҒBӮаӮНӮвҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМ‘ЮҗЁӮр”ТүсӮ·Ӯй•ыҚфӮНҠF–іӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ9ҒDғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢc | |
|
ҒЎ(1) Ҡ’‘ҫӮМҗи—М
ғAғҒғҠғJ‘е“қ—МғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮНҒAҚДӮСғҚғVғAҚc’йғjғRғүғC2җўӮЙҚuҳaӮрҺқӮҝӮ©ӮҜӮЬӮөӮҪҒB ғjғRғүғCӮНҒAҒuӮЬӮҫғҚғVғAӮМ—М“yӮӘҺёӮнӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖҢҫӮў•еӮБӮДҸaӮйӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМ“аҗSӮЕӮНҳAҗнҳA”sӮЙҲУӢCҸБ’ҫӮөҒAӮЬӮҪҒA‘«ҢіӮМҠv–ҪӮМүeӮЙӢәӮҰӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғtғүғ“ғXӮНҒA“Ҝ–ҝҚ‘ӮЕӮ ӮйғҚғVғAӮӘӮұӮкҲИҸгҺг‘Мү»Ӯ·ӮйӮЖҒAүј‘z“GҚ‘ӮЕӮ ӮйғhғCғcӮр—ҳӮ·ӮйӮОӮ©ӮиӮЖҚlӮҰӮДҒAғjғRғүғCӮЙҚuҳaӮрҠ©ҚҗӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМ—lҺqӮрҢ©ӮДӮўӮҪғhғCғcӮаҒAӮұӮкҲИҸгҗн‘ҲӮӘ’·ҲшӮӯӮЖҒAүј‘z“GҚ‘ӮЕӮ ӮйғCғMғҠғXӮӘ—L—ҳӮЙӮИӮйӮОӮ©ӮиӮҫӮЖҚlӮҰӮДҒAӮвӮНӮиғjғRғүғCӮЙҚuҳaӮрҠ©ӮЯӮЬӮөӮҪҒBҺҹ‘жӮЙҢXӮӯғҚғVғAҚc’йӮМҗSҒB Ӯ»ӮМҠФҒAғӢҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮНӢаҺq“БҺgӮр’КӮ¶ӮД“ъ–{җӯ•{ӮЙӮ Ӯй’сҲДӮрҺқӮҝҠ|ӮҜӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҒuғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒAӮЬӮҫҢЕ—LӮМ—М“yӮр’DӮнӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮЖҢҫӮБӮДҗн‘ҲӮрҢp‘ұӮ·ӮйӢCӮҫҒBӮҫӮБӮҪӮзҒAҢЕ—LӮМ—М“yӮЕӮ ӮйғTғKғҢғ“(ҒҒҠ’‘ҫ)Ӯр“ъ–{ҢRӮӘҗи—МӮөӮДӮөӮЬӮӨӮЧӮ«ӮҫӮЖҺvӮӨҒvҒB ҠщӮЙ“ъ–{ӮМҗн‘ҲҗӢҚs”\—НӮНҢАҠEӮЙ’BӮөӮВӮВӮ ӮиҒA‘е–{үcӮМҺQ–dӮМ‘ҪӮӯӮНҒAҚЕҸүӮМӮӨӮҝӮНӮұӮМ’сҲДӮМҺАҚsӮрҸaӮиӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҒuҗн‘ҲӮрҸIӮнӮзӮ№ӮйӮҪӮЯӮМҚЕҢгӮМҲк“ҘӮс’ЈӮиҒvӮЖҺе’ЈӮ·ӮйҺҷӢК‘еҸ«Ӯв’·үӘҺQ–dӮЙҗа“ҫӮіӮкӮДҒAӮВӮўӮЙҠ’‘ҫҚмҗнӮр”ӯ“®ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҠФҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҠ®‘SҢӮ”jӮөӮҪҳAҚҮҠН‘аӮНҒA“ъ–{ӢЯҠCӮМҗ§ҠCҢ ӮрҲкҺиӮЙҸ¶Ҳ¬ӮөҒAғEғүғWғIғXғgғbғNӮМӢЯҚxӮрҠН–CҺЛҢӮӮөӮДүсӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBҠ’‘ҫӮЦӮМ“nҠCҚмҗнӮНҒAӮұӮӨӮөӮҪҠCҢRӮМҠҲ–фӮр‘O’сӮЙӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӣӯ—НӮИҠCҢRӮЙҢмүqӮіӮкӮҪ“ъ–{—ӨҢRӮНҒAӮ ӮБӮЖӮўӮӨҠФӮЙҠ’‘ҫ‘S“yӮрҗи—МӮөӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮНҒAӮұӮМ’nӮЙ•”‘аӮрӮЩӮЖӮсӮЗ’uӮўӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҒAҒuҢЕ—LӮМ—М“yҒvӮрҺёӮБӮҪғҚғVғA’йҚ‘ӮНҒAӮЖӮӨӮЖӮӨҚuҳaүпӢcӮЙүһӮ¶ӮйҢҲҲУӮрҢЕӮЯӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ(2) ғ|Ғ[ғcғ}ғXӮМҠш
ғҚғVғA‘SҢ ғEғCғbғeӮЖ“ъ–{ӮМҠO‘ҠҒEҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮНҒAғAғҒғҠғJӮМҚ`ҳp“sҺsғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕ‘ОҢҲӮөӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮНҒA“ъ–{ӮӘ—vӢҒӮ·ӮйҒu’©‘N”ј“ҮӮЖ—Й“Ң”ј“ҮӮМҢ үvӮЖ“Ңҗҙ“S“№ӮМҠ„ҸчҒvӮЙӮВӮўӮДӮНҠИ’PӮЙҚҮҲУӮөӮЬӮөӮҪҒB ‘Ҳ“_ӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒAҒuғҚғVғA—МӮМҠ„ҸчӮЖ”…ҸһӢаҒvӮЙӮВӮўӮДӮЕӮ·ҒB“ъ–{ӮНҒAҠ’‘ҫӮМҠ„ҸчӮЖӢҗҠzӮМ”…ҸһӢаӮрӢҒӮЯӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮНҒuҗЎ“yӮМ—М“yӮаҠ„ҸчӮЕӮ«ӮИӮўӮө”…ҸһӢаӮаҺx•ҘӮҰӮИӮўҒvӮЖҢҫӮў•еӮиӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAӮНғPғ`ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮӯҒA–{“–ӮЙғJғlӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮаӮҝӮлӮсҒAӮұӮкҲИҸгӮМҚ‘үЖҲРҗMӮМ’бүәӮр”рӮҜӮҪӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨ—қ—RӮаӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒB ғҚғVғAӮНҒAӮаӮНӮвӮұӮкҲИҸгҗнӮҰӮйҸу‘ФӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёӢӯӢCӮИ‘Ф“xӮр•цӮіӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮНҒAҗӯ•{’Ҷҗ•ӮрӢҚҺЁӮй•…ӢҖҢRҗlҠҜ—»(ӢM‘°)ӮҪӮҝӮӘҒAҢiӢCӮМӮўӮўӮұӮЖӮрҢҫӮўӮУӮзӮөӮДғjғRғүғCҚc’йӮр‘ҖӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBҢRҗlҠҜ—»ӮҪӮҝӮНҒAҺ©•ӘӮҪӮҝӮМҲРҗMӮЖҠщ“ҫҢ үvӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЙҒAҚЕҢгӮЬӮЕҗн‘ҲӮр‘ұӮҜӮйӮВӮаӮиӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮіӮЙҒA40”NҢгӮМ“ъ–{ӮМ—l‘ҠӮЙӮ»ӮБӮӯӮиӮЕӮ·ӮЛҒB ӮаӮЖӮаӮЖҒA“ъ–{‘ӨӮМҚuҳaҸрҢҸӮНҒA“ъ–{ҢRҲі“|“I—DҲКӮМҗнӢөӮрҠУӮЭӮкӮОҒA”сҸнӮЙүё“–ӮИӮаӮМӮЕӮөӮҪҒB‘SҗўҠEӮМғvғҢғXӮӘҒAӮ»ӮМҗҪҺАӮіӮрҸЬҺ^ӮөӮҪӮЩӮЗӮЕӮ·ҒBӮЬӮҪҒAҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮМҢ©Һ–ӮИ•ЩҗгӮНҒAӮөӮОӮөӮОҠOҢрӮМ‘еүЖӮЕӮ ӮйғEғCғbғeӮрҲі“|Ӯ·ӮйӮЩӮЗӮЕӮөӮҪҒB ғEғCғbғeӮНӮЮӮөӮлҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮЙ“ъ–{‘ӨӮМҸрҢҸӮрҲщӮЮӮжӮӨӮЙҠ©Ҹ§ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғ^ғJ”hҢRҗlӮӘҺАҢ ӮрҲ¬Ӯй–{Қ‘ӮНҺПӮҰӮ«ӮлӮӨӮЖӮөӮИӮўӮМӮЕҒAғEғCғbғeӮМӢк–гӮНҗ[ӮЬӮйӮОӮ©ӮиҒBҒuӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНҒA‘cҚ‘ӮНҸҹӮҝ–ЪӮМ–іӮўҗн‘ҲӮрғ_ғүғ_ғүӮЖ‘ұӮҜҒAҠv–Ҫ–u”ӯӮЙӮжӮБӮДҚ‘үЖӮӘ“]•ўӮөӮДӮөӮЬӮӨӮҫӮлӮӨҒvҒB Ҳк•ыӮМ“ъ–{ҢRӮНҒAҗl“I‘№–ХӮӘҢғӮөӮӯҒAӮЬӮҪ–C’eӮМ‘қҺYӮаҠФӮЙҚҮӮнӮИӮўҸу‘ФӮЕӮөӮҪҒB‘OҗьӮЕӮМ’e–тҸБ”п—КӮНҒA“–ҸүӮМҢ©җПӮаӮиӮМҸ\”{Ӯр’ҙӮҰӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB–һҸBҢRҺi—ЯҠҜҒE‘еҺRҠЮӮНҒAҒuғnғӢғsғ“ӮЬӮЕҗiҢӮӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAӮ ӮЖ1”NҲИҸгӮМ’e–т”х’~Ӯр‘ТӮВ•K—vӮӘӮ ӮйҒvӮЖ–{Қ‘ӮЙӢпҗ\ӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЕӮаҒAҗнҸкӮМ“ъ–{ҢRӮНҒA’PҸғӮИҗ퓬ғҢғxғӢӮЕҚlӮҰӮкӮОҒAғҚғVғAҢRӮр‘Е“|ӮөӮДҗiҢӮӮЕӮ«ӮйүВ”\җ«ӮНӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮкҲИҸгҚ‘–ҜӮрҸdҗЕӮЕӢкӮөӮЯӮйӮнӮҜӮЙӮНӮўӮ©ӮИӮўӮөҒAӮұӮкҲИҸгҠOҚВӮр”ӯҚsӮөӮДҢгҗўӮМҗў‘гӮЙ•ү’SӮрӮ©ӮҜӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒB“VҚcӮаҗӯҺЎүЖӮаҢRҗlӮаҒAӮЭӮИҗSӮ©ӮзӮ»ӮӨҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒBӮИӮсӮЖӮўӮӨҢ©ҺҜӮМҗ[ӮіӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒH Ӯ»ӮұӮЕҒAҚuҳaүпӢcӮМҗ[ҚҸӮИ‘О—§Ӯр’mӮБӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXӮМҸ¬‘әӮЙҒu”…ҸһӢаӮа—М“yӮа’ъӮЯӮД—ЗӮўҒvӮЖҺwҺҰӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМ“d•сӮрҺуӮҜҺжӮБӮҪғ|Ғ[ғcғ}ғXӮМ“ъ–{ҠOҢр’cӮНҒAүчӮөӮіӮМӮ ӮЬӮиҡjҲфӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB ӮұӮМӮЬӮЬҚsӮҜӮОҒA“ъ–{‘ӨӮМҒuҠ®‘SҸч•аҒvӮЕҢҲ’…Ӯ·ӮйӮЖӮұӮлӮЕӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮН“y’dҸкӮЙӮИӮБӮД•^•ПӮөӮЬӮ·ҒBғjғRғүғCҚc’йӮӘҒAҒuҠ’‘ҫ“м•”ӮМҠ„ҸчӮр”FӮЯӮйҒvӮЖҗә–ҫӮр”ӯӮөӮҪӮМӮЕҒAӮ»ӮМ•ыҢьӮЕүпӢcӮНӮЬӮЖӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮНҒA”…ҸһӢаӮр’ъӮЯӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮНҒAҠ’‘ҫӮМ“м”ј•ӘӮрҠ„ҸчӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮЬӮөӮҪҒB ҺһӮЙ1905”N(–ҫҺЎ38”N)8ҢҺ29“ъҒBӮұӮӨӮөӮДҒA“ъҳIҗн‘ҲӮНҸIҢӢӮМ“ъӮрҢ}ӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(3) “ъ”д’JҸДӮ«“ўӮҝҺ–ҢҸ
”…ҸһӢаӮр“ҫӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒA“ъ–{ӮНҗн‘Ҳ–Ъ“IӮЕӮ ӮйҒu’©‘NӮЖ–һҸBӮ©ӮзӮМғҚғVғAҗЁ—НӮМӢм’ҖҒvӮрҠ®‘SӮЙ’Bҗ¬ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA‘еҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒA—\‘zҠOӮМҗl“I‘№ҠQӮЖҸdҗЕӮЙүҹӮөӮВӮФӮіӮкҒAҸeҢгӮМҗlҒXӮМӢкӮөӮЭӮН•MҗгӮЙҗsӮӯӮөӮӘӮҪӮўӮЩӮЗӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮсӮИ”ЮӮзӮНҒAҗнҸҹӮЙӮжӮБӮДӢҗҠzӮМ”…ҸһӢаӮЖҚL‘еӮИ—М“yӮр“ҫӮзӮкӮйӮаӮМӮЖ‘ҒҚҮ“_ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮӨҚlӮҰӮДҒAҺ©•ӘӮҪӮҝӮрҲФӮЯӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМҢҸӮЙӮВӮўӮДӮНҒAғ}ғXғRғ~•с“№ӮЙӮа–в‘иӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBҗV•·ӮвҺGҺҸӮНҒA“ъ–{җӯ•{ӮМӢкӮөӮў‘дҸҠҺ–ҸоӮр”й“ҪӮөҒAҢiӢCӮМ—ЗӮўҗнҸҹ•с“№ӮөӮ©—¬ӮіӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮҪӮҫӮөҒAӮ»ӮМ—қ—RӮНҒAҚЎ“ъӮМ“ъ–{ӮЕҚPҸн“IӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҒu–в‘иӮМүB•БҒvӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBғ}ғXғRғ~•с“№ӮЙӮжӮБӮДғҚғVғAӮЙ“ъ–{ӮМӢкӢ«Ӯр’mӮзӮкӮДӮөӮЬӮӨӮЖҒAҚuҳaӮЙүһӮ¶ӮДӮаӮзӮҰӮИӮӯӮИӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕҒA“ъ–{җӯ•{ӮНҒu“GӮрӢ\ӮӯӮҪӮЯӮЙ–Ў•ы(Қ‘–Ҝ)ӮрӢ\ӮӯҒvӮЖӮўӮӨӢкҸaӮМ‘I‘рӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҺ–ҺАӮр’mӮзӮИӮўҚ‘–ҜӮН”[“ҫӮөӮЬӮ№ӮсҒBӮ·ӮйӮнӮҜӮӘӮИӮўҒBҒu‘еҸҹ—ҳӮИӮМӮЙҒAӮұӮкӮҫӮҜ‘еӮ«ӮИӢ]җөӮр•ҘӮБӮҪӮМӮЙҒAӮЗӮӨӮөӮД”…ҸһӢаӮаҸoӮИӮўҸгӮЙ—М“yӮМҠ„ҸчӮаӮнӮёӮ©ӮИӮМӮҫҒIҒvҒuҗӯ•{ӮНӮаӮҝӮлӮсҒAҠOҢр’cӮӘҚҳ”ІӮҜӮИӮМӮЙҲбӮўӮИӮўҒIҒvӮЖӮўӮӨҗўҳ_ӮӘ‘SҚ‘ӮЙ•ҰӮ«ӢNӮұӮБӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮД“ъ–{‘SҚ‘ӮЕҲӨҚ‘ҸWүпӮӘҢҲӢNӮөҒAҢғӮөӮўғfғӮҠҲ“®ӮӘҢJӮиҚLӮ°ӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB“ъ”д’JҢцүҖӮЕӮМғfғӮӮН‘еӢK–НӮИ–\“®ӮЖӮИӮиҒAҢxҠҜ‘аӮЖҸХ“ЛӮөӮДҢр”ФӮӘҸДӮ«•ҘӮнӮкӮйҺ–‘ФӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪ(9ҢҺ5“ъ)ҒB Ҹ¬‘әҠO‘ҠӮНҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕӮМҺкҢMҺТӮЕӮ ӮБӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAҲГҺEӮрӢ°ӮкӮДӮЁ”EӮСӮЕӮРӮБӮ»ӮиӮЖӢAҚ‘ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮЙӮөӮДӮаҒAӮ ӮМ“–ҺһӮМ“ъ–{җlӮНғoғCғ^ғҠғeғBӮӘӮ ӮБӮҪӮсӮЕӮ·ӮЛҒBҚЎӮМ“ъ–{җlӮНҒAҗӯ•{ӮӘӮЗӮсӮИүЎ–\Ӯр’КӮөӮДӮағjғRғjғRӮөӮДӮўӮйӮөҒAӮ»ӮаӮ»Ӯа‘IӢ“ӮЙӮаҚsӮ«ӮЬӮ№ӮсҒBHҒEGҒEғEғGғӢғYӮМҸ¬җаҒwғ^ғCғҖғ}ғVғ“ҒxӮЙҸoӮДӮӯӮйғGғҚғC‘°ӮМӮжӮӨӮЙ‘Юү»ӮөӮҝӮбӮБӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒHӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНӮ«ӮБӮЖҒAүў•ДӮв’ҶҚ‘ӮЖӮўӮӨ–јӮМғӮҒ[ғҚғbғN‘°ӮЙҗHӮўҺEӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨӮЕӮөӮеӮӨҒBҸӯӮөӮНҒAӮұӮМ“–ҺһӮМ”eӢCӮрҺvӮўҸoӮөӮДӮаӮзӮўӮҪӮўӮЕӮ·ӮЛҒBҒ@ |
|
| ҒЎ10ҒD‘ҚҠҮ | |
|
ҒЎ(1) ҸҹҲцӮЖ”sҲц
ӮұӮӨӮөӮД“ъҳIҗн‘ҲӮН“ъ–{ӮМ‘еҸҹ—ҳӮЙҸIӮнӮиӮЬӮөӮҪҒB ҠmӮ©ӮЙҒAӢ]җөӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҠ„ӮЙӮН”…ҸһӢаӮрӮаӮзӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮөҒA“ҫӮзӮкӮҪ—М“yӮаӮнӮёӮ©ӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒAҗн‘Ҳ–Ъ“IӮрҠ®‘SӮЙ’Bҗ¬ӮөӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮұӮкӮН’NӮӘүҪӮЖҢҫӮЁӮӨӮЖ‘еҸҹ—ҳӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМҸҹҲцӮЙӮВӮўӮДҢҹ“ўӮөӮЬӮөӮеӮӨҒB үҪӮЖҢҫӮБӮДӮаҒAҺ©•ӘӮМ’·’ZӮрҢӘӢ•ӮЙ•ӘҗНӮөҒAҒuҸҹӮВӮҪӮЯҒvӮЙҚЕӮаҢ»ҺА“IӮЕҚҮ—қ“IӮИ•ыҚфӮр‘ЕӮБӮҪӮұӮЖӮӘ‘еӮ«ӮўӮЕӮөӮеӮӨҒB“ъ–{ӮНҒAҢRҺ–ӮМӮЭӮИӮзӮёҠOҢрӮвҢoҚПӮЙӮаҺь“һӮИ”z—¶ӮрҚsӮўҒAҗн‘ҲӮр—L—ҳӮЙ‘ҒҠъҸIҢӢӮіӮ№ӮйӮҪӮЯӮЙ–ң‘SӮМ‘[’uӮрҺжӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮНҒAҺ©ӮзӮМҒuҺгӮіҒvӮр—ЗӮӯҺ©ҠoӮөҒAӮ»ӮкӮрҚҺ•һӮ·Ӯй“№’цӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ‘·ҺqӮўӮнӮӯҒu”ЮӮр’mӮиҢИӮр’mӮкӮОҒA•SҗнӮөӮДҠлӮӨӮ©ӮзӮёҒvӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAӮМ”sҲцӮНҒAӮЬӮіӮЙӮұӮкӮЖ•\— Ҳк‘МӮЕӮөӮҪҒB”ЮӮНҒA“ъ–{Ӯр•ҺӮиҒAҺ©ӮзӮМҺА—НӮрүЯҗMӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӮРӮҪӮ·ӮзҗнҸкӮЕӮМҸҹ—ҳӮр’ЗӮўӢҒӮЯҒA‘җӮМҚӘӮМҠOҢрӮв’і•сӮрӮЁӮлӮ»Ӯ©ӮЙӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮұӮЖӮӘҒAҚ‘“аӮЕӮМ‘ӣҸпӮрҸөӮ«ҒAҚ‘ҚЫҗўҳ_Ӯр“GӮЙүсӮөҒAҸ”ҠOҚ‘Ӯ©ӮзҚuҳaӮрҠ©ҚҗӮіӮкӮйӮжӮӨӮИҗӯҺЎҸуӢөӮрҗ¶ӮсӮЕӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮкӮНҒAҢ»ҚЭӮЙӮа’КӮ¶ӮйӮҪӮўӮЦӮсӮЙҗ[ӮўӢіҢPӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ(2) Ӯ»ӮМҢгӮМ—јҚ‘
“ъҳIҗн‘ҲӮМҢӢүКӮНҒAӮ»ӮМҢгӮМ“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМҗiҳHӮЙӢЙӮЯӮД‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮЬӮөӮҪҒB ғҚғVғAӮЕӮНҒAҚc’йӮМҲРҗMӮӘ‘еӮ«Ӯӯ•цӮкҒAӮвӮӘӮДҠv–ҪӮӘӢNӮұӮиӮЬӮ·(1917”N)ҒBӮ»ӮөӮДҒAҗVҗӯ•{ӮМғҢҒ[ғjғ“ӮвғXғ^Ғ[ғҠғ“ӮНҒAғҚғVғAӮрӢӯҚ‘ӮЙүь‘ўӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒAҺРүпҺеӢ`җӯҢ ӮМғ\ғrғGғgҳA–MӮрҺч—§ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮвӮӘӮДғ\ҳAӮНҒAҚHӢЖ—НӮр‘қӢӯӮіӮ№ӮД“ъ–{ӮЙҗбҗJӮрүКӮҪӮө(1945”N)ҒAғAғҒғҠғJӮЖҗўҠEӮр“с•ӘӮ·Ӯй‘еҗЁ—НӮЙҗ¬’·ӮөӮЬӮөӮҪҒBғҚғVғAҗlӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМӢьҗJӮ©Ӯз‘ҪӮӯӮрҠwӮСҺжӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮЖӮұӮлӮӘ“ъ–{ӮНҒAӮұӮкӮЖӢtӮМҗiҳHӮр’HӮиӮЬӮ·ҒB –]ҠOӮМ‘еҗ¬ҢчӮЙ‘қ’·ӮөӮҪӮұӮМҚ‘ӮЕӮНҒAҢR”ҙӮӘ‘д“ӘӮөҒAӮ»ӮөӮДүЯҢғӮИҢRҚ‘ҺеӢ`ӮЙ‘–ӮиӮЬӮ·ҒBҺ©ӮзӮМ”\—НӮрүЯҗMӮөҒAҢoҚПӮвҠOҢрӮв’і•сӮр–іҺӢӮөҒAӮ»ӮөӮДӢБӮӯӮЧӮ«ӮұӮЖӮЙҒAҚ‘Ӣ«ӮрҗЪӮ·Ӯй‘SӮДӮМҚ‘ӮЙҗн‘ҲӮрҗҒӮБӮ©ӮҜӮйӮЙӮўӮҪӮйӮМӮЕӮ·ҒBӮЬӮіӮЙҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМӮЖӮ«ӮМғҚғVғA’йҚ‘ӮЖӮЬӮБӮҪӮӯ“ҜӮ¶•aҸуӮЙӣЖӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮЕҗhҸҹӮрҸҹӮҝ“ҫӮҪҗн—Ә“I—қ—RӮНҒAҗјүў—сӢӯ(үp•Д)ӮЖӮМҠOҢрӢҰ’ІӮЕӮ ӮиҒAҗнҸp“I—қ—RӮНҒAҗнҠНҒuҺOҠ}ҒvӮЙ‘г•\ӮіӮкӮйӢЯ‘г•әҠнӮМҲР—НӮЕӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҸәҳaӮМҢR”ҙӮНҒAӮ»ӮМӮұӮЖӮрҠ®‘SӮЙ–YӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒBҒuӮ©ӮВӮДғҚғVғAӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪҒvӮЖӮўӮӨҲкҺ–ӮЙ—L’ё“VӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢҙҲц•ӘҗНӮр‘УӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA–рӮЙ—§ӮҪӮИӮў“Ҝ–ҝӮрғiғ`ғXғhғCғcӮЖҢрӮнӮөҒAҺ‘Ң№ӮМ—A“ьҢіӮЕӮ ӮйғAғҒғҠғJӮЙҗн‘ҲӮр’§ӮЮӮЖӮўӮӨӢрӮрҚsӮўҒAӮіӮзӮЙӮН•әҠнӮМӢЯ‘гү»Ӯр‘УӮиҗl–ҪҢyҺӢӮМҗёҗ_ҳ_ӮЙ“ҰӮ°ҚһӮсӮҫҒB ӮіӮзӮЙӢ°ӮлӮөӮўӮМӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМ•үӮМҲвҺYӮр–YӢpӮөӮҪ“_ӮЕӮөӮеӮӨҒB“ъ–{ӮНҒAӮ ӮМҗн‘ҲӮЕӮўӮӯӮВӮаӮМүЯҺёӮр”ЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB—·ҸҮ—vҚЗӮЦӮМ–і–dӮИ“ЛҢӮӮвҒA—ӨҢRӮЖҠCҢRӮЖӮМҸо•сӮМ•Ә—§ҒAӮіӮзӮЙӮНҗнҸкҲг—ГӮМҢyҺӢ(Ӯ ӮМҗн‘ҲӮЕӮНҒAҗнҺҖҺТӮМҗ”ӮжӮи•aҺҖҺТӮМҗ”ӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪ)ҒBӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{ҢRӮНҒuҸҹ—ҳҒvӮМүhҢхӮЙҢ¶ҳfӮіӮкӮДҒAӮұӮкӮзӮМүЯҺёӮрҚҺ•һӮ·ӮйӮҪӮЯӮМ”І–{“Iүь‘PҚфӮрҚМӮлӮӨӮЖӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲӮЕӮНҒAӮұӮМүЯҺёӮӘӮжӮи‘еӮ«Ӯӯҗ[ҚҸӮИҺpӮЖӮИӮБӮДӮұӮМҚ‘ӮЙ”ЯҢҖӮрӮаӮҪӮзӮ·ӮМӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒA“ъ–{ӮН”pҡРӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪ(1945”N)ҒB ҒuҸҹӮБӮДҠ•ӮМҸҸӮр’чӮЯӮжҒvӮЖӮНҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЙӮұӮ»•щӮ°ӮйӮЧӮ«Ңҫ—tӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒB ӮұӮӨӮўӮБӮҪӮұӮЖӮЙҒA—рҺjӮМӢіҢPӮр“ЗӮЭҺжӮйӮЧӮ«ӮҫӮЖҺvӮӨӮМӮЕӮ·ҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎ(3) “ъ–{ӮЖғҚғVғA
“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮН’nҗЁ“IӮЙҢ©ӮДҒAӢЙӮЯӮДҲцүКҠЦҢWӮМҗ[Ӯў—ЧҚ‘“ҜҺmӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҚЎ“ъӮМ“ъ–{ӮЕӮНҒAғAғҒғҠғJӮЙҗи—МӮіӮкғAғҒғҠғJ•¶ү»ӮЙҗф”]ӮіӮкӮҪҺһҠъӮӘ’·Ӯ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAғ}ғXғRғ~ӮаҠwҺТӮаҺА–ұүЖӮаҒAӮЭӮсӮИғAғҒғҠғJӮОӮ©ӮиҢ©ӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҠmӮ©ӮЙҒAғAғҒғҠғJӮНҺ‘–{ҺеӢ`ӮМҗжҗiҚ‘ӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒAҢoҚП–КӮЕҺQҚlӮЙҸo—ҲӮй•”•ӘӮӘ‘ҪӮўӮұӮЖӮН•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ Ӯ»ӮұӮН—рҺjӮМҗуӮўҗ[ӮЭӮЙҢҮӮҜӮйҚ‘ӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒA•¶ү»–КӮЬӮЕӮЧӮБӮҪӮиӮИӮМӮНӮўӮ©ӮӘӮИӮаӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒH ӮұӮкӮЬӮЕӮМ“ъ–{җlӮНҒAҗнҢг•ңӢ»ӮЖӮ©ҢoҚП”ӯ“WӮОӮ©ӮиӮЙӢCӮрҺжӮзӮкҒAӮұӮМҗўҠEӮЙӮаӮБӮЖ‘еҗШӮИӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮр–YӮкӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮҫӮ©ӮзҒAҢoҚПҗжҗiҚ‘ӮМғAғҒғҠғJӮМҗKӮОӮ©Ӯи’ЗӮўҠ|ӮҜүсӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮөӮеӮӨҒBӮЕӮаӮұӮкӮНҒAҸәҳaӮМҢR”ҙӮӘӢ¶ӮБӮҪӮжӮӨӮЙҗн‘ҲӮөҒAғiғ`ғXғhғCғcӮМҗKӮр’ЗӮўүсӮөӮДӮўӮҪӮМӮЖ“ҜғҢғxғӢӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮЛҒB“ъ–{җlӮНҒA–{Һҝ“IӮЙӮНҗ¬’·ӮөӮДӮўӮИӮўӮМӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAӮНҒA“ъ–{ӮЖӮЬӮБӮҪӮӯҲЩӮИӮйҗ[Ӯў•¶ү»ӮрҺқӮБӮҪҚ‘ӮЕӮ·ҒBӮ№ӮБӮ©Ӯӯ—рҺjӮМҢГӮўӮЁ—Ч“ҜҺmӮИӮМӮҫӮ©ӮзҒAӮаӮБӮЖҢЭӮўӮМ•¶ү»ӮЕҺhҢғӮр—^ӮҰҚҮӮўҒAҢЭӮўӮМүҝ’lӮрҚӮӮЯӮДӮўӮӯӮЧӮ«ҺһҠъӮЕӮНӮИӮўӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒH(ҺАӮН•MҺТӮНғҚғVғAӮСӮўӮ«ӮИӮМӮЕӮ·)ҒB ӮұӮМ“ъҳIҗн‘Ҳҳ_ӮЕҒA‘ҪӮӯӮМҺбӮўҗlӮӘӮ»ӮӨӮўӮӨӢCҺқӮҝӮрӮаӮБӮДӮӯӮкӮҪӮзҠрӮөӮўӮЕӮ·ӮЛҒBӮаӮҝӮлӮсҒAӮ»ӮМ‘O’сӮЖӮөӮДҒAҒuҺ©ӢsҺjҠПҒvӮ©Ӯз’E”зӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒB Ғ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ4 | |
|
ҒЎ—рҺj“I”wҢi
“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA’ҙ‘еҚ‘’йҗӯғҚғVғAӮМӢЙ“ҢҗN—ӘӮЙ‘ОӮөӮДҒA“–ҺһҒA–ўӮҫ–і–јӮМҲкҸ¬Қ‘ӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪ“ъ–{ӮӘҚ‘үЖӮМ‘Қ—НӮрӮ Ӯ°ҺҖ—НӮрҗsӮӯӮөӮДҗнӮўӮКӮ«ҒAҗӢӮЙҒA“ҮҚ‘“ъ–{Ӯр•s”sӮМ‘ФҗЁӮЙҚмӮиӮ Ӯ°ӮДғҚғVғAӮМҢpҗнҲУҗ}Ӯр•ъҠьӮіӮ№ӮҪҗн‘ҲӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮаӮ»ӮаҒA’йҗӯғҚғVғAӮНҒA16җўӢIҲИ—ҲғVғxғҠғAӮМҢoүcӮЙ’…ҺиӮөҒA1730”NҚ ӮЬӮЕӮЙғAғWғA–k•ы’nҲжӮМҗиӢ’ӮрҸIӮнӮБӮДӢЙ“ҢӮ©ӮзӮМ“мүәӮрҠJҺnӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA1860”NӮЙӮНғEғXғҠҒ[ҲИ“ҢӮМүҲҠCҸBӮрҠl“ҫӮөҒAӮЬӮҪҒA1875”NӮЙӮНҠ’‘ҫ(ғTғnғҠғ“)ӮМҗк—LӮрүКӮҪӮөҒAүҲҠCҸBӮМ—v’nғEғүғWғIғXғgғNӮЙҠCҢRӮМҚӘӢ’’nӮр’zӮўӮДӢЙ“Ң—Y”тӮМ‘«Ҡ|Ӯ©ӮиӮрҚмӮБӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҢRҚ`ӮН“~ӢGҢӢ•XӮ·ӮйӮМӮЕҒAғҚғVғAӮНҒAӮИӮЁӮа•s“ҖҚ`ӮрӢҒӮЯӮДӮМ“мүәӮрүжҚфӮөӮДӮўӮҪҒBӮҪӮЬӮҪӮЬҒAҸCҚDҸр–сӮрҢӢӮС“ҫӮҪӮМӮрӢ@ӮЖӮөӮДҒAҠШҚ‘ӮМүҲҠЭӮЙ—ЗҚ`ӮрҺШӮиҺуӮҜӮжӮӨӮЖҚф“®ӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAӮМ“мүәӮрҚDӮЬӮКғCғMғҠғXӮМ–WҠQӮЙ‘ҳӮБӮД•sҗ¬ҢчӮЙҸIӮнӮБӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘҒA1895”N(–ҫҺЎ28)ӮМ“ъҗҙҚuҳaҸр–сӮЕ—Й“Ң”ј“ҮӮӘ“ъ–{ӮЙҠ„ҸчӮіӮкӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйӮвҒAғҚғVғAӮН•җ—НӮр”wҢiӮЙғhғCғcҒEғtғүғ“ғXӮЖӮЖӮаӮЙҸр–сӮЙҠұҸВӮрүБӮҰӮД“Ҝ”ј“ҮӮМҗҙҚ‘•ФҠТӮрӢӯ—vӮөҒA•ФҠТӮіӮкӮҪ“Ҝ”ј“ҮӮМ—v’nӮЕӮ Ӯй—·ҸҮӢyӮС‘еҳAӮр1898”NӮЙ‘dҺШӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮ©ӮӯӮөӮДҒAғҚғVғAӮН•s“ҖҚ`“ьҺиӮМ”OҠиӮрүКӮҪӮ·ӮЖӮЖӮаӮЙҒAҗжӮЙҠl“ҫӮөӮҪ“Ңҗҙ“S“№•~җЭҢ ӮЖҚҮӮнӮ№ӮДҒAӮұӮМҗVҢRҚ`ӮрғҚғVғA—МӮЖ’јҢӢӮ·ӮйӢӯ—НӮИҚӘӢ’’nӮЖӮөӮҪҒB ӮіӮДҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮНҒAҺг‘МӮр–\ҳIӮөӮҪҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯйҗјүў—сӢӯӮМҗN—ӘӮӘҳIҚңү»ӮөҒAғҚғVғAӮа–һҸBӮМҢoүcӮрӢӯ—НӮЙҗiӮЯӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮз—сӢӯӮМҗN—ӘӮЙ”Ҫ”ӯӮөӮДӢNӮБӮҪ–kҗҙҺ–•П(1900”N)ӮрҚDӢ@ӮЖӮөӮДҒAғҚғVғAӮН“S“№Ңx”хӮр–ј–ЪӮЙ‘еҢRӮр“ұ“ьӮөӮД–һҸBӮМ—v’nӮрҗиӢ’ӮөҒAҺ–•ПүрҢҲҢгӮаӮИӮЁ’“•әӮр‘ұӮҜӮД–һҸBӮМ—М“yү»ӮрҚфӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAҚXӮЙ“мүәӮөӮДҗGҺиӮрҠШҚ‘ӮЙҗLӮОӮөҒAӮвӮӘӮДӮНҲкҲЯ‘Сҗ…ӮМ“ъ–{Ӯа“ҜӮ¶ү^–ҪӮЙҠЧӮйҠлӢ@ӮрӮНӮзӮЮҢ`җЁӮЙӮЖ”ӯ“WӮөӮДӮўӮБӮҪҒB ӮұӮМ‘қ‘еӮ·ӮйғҚғVғAӮМӢәҲРӮЙ‘ОӮөӮДҒA“ъ–{ӮНҒA1902”N(–ҫҺЎ35)‘еҠCҢRҚ‘ғCғMғҠғXӮЖ“ъүp“Ҝ–ҝӮрҢӢӮСҒAӮ»ӮМ—}җ§ҢшүКӮрҠъ‘ТӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮҜӮҪҠOӮкӮМҢRҺ–—НӮЖҚа—НӮрҢЦӮйғҚғVғAӮНҒAҸ¬Қ‘“ъ–{ӮМҚRӢcӮ ӮйӮўӮН’k”»ӮЙҺЁӮаӮ©ӮіӮёҒAӮ©ӮҰӮБӮДӢЙ“ҢӮМ•ә—НӮр‘қӢӯӮөӮД“ъ–{ӮЦӮМҲі”—ӮрӢӯү»ӮөӮҪҒBӮҪӮЬӮиӮ©ӮЛӮҪ“ъ–{ӮНҒAӮИӮсӮЖӮөӮДӮЕӮаҒA‘еҚ‘ғҚғVғAӮМӢәҲРӮр”rҸңӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖҒAҗӢӮЙ1904”N(–ҫҺЎ37)2ҢҺ6“ъғҚғVғAӮЖӮМҚ‘Ңр’fҗвӮр’КҚҗӮ·ӮйӮМӮвӮЮӮИӮ«ӮЙ—§ӮҝҺҠӮБӮҪҒBӮ©ӮӯӮөӮДҒA2ҢҺ9“ъҗйҗнӮӘ•zҚҗӮіӮк“ъҳIҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠCҢRӮМҚмҗн•ыҗj
“ъ–{ҠCҢRӮНҒAҗнҠН6җЗҒE‘•ҚbҸ„—mҠН6җЗӮрҠоҠІӮЖӮ·ӮйӮаӮМӮЕҒAӮұӮкӮЙ–ўүсҚqӮМ‘•ҚbҸ„—mҠН2җЗӮӘӮўӮёӮк‘қҗЁӮіӮкӮй—\’иӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ‘SҗЁ—НӮНҗVӢҢҚҮӮнӮ№ӮДӮа–с26–ңғgғ“ӮЙүЯӮ¬ӮИӮўӮаӮМӮЕҒA51–ңғgғ“ӮМғҚғVғAҠCҢRӮЙ‘ОӮөӮД–с”ј•ӘӮМҗЁ—НӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮЬӮҪҒA“––КӮМ“GӮЕӮ ӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮНҒA–с19–ңғgғ“ӮЖӮўӮӨӮвӮв—тҗЁӮИӮаӮМӮИӮӘӮзҒAҗнҠН7җЗҒE‘•ҚbҸ„—mҠН4җЗӮр’ҶҺІӮЖӮ·ӮйҗVүsҠНӮЕҚ\җ¬ӮіӮкӮҪҗёүsӮЕ”сҸнӮИ‘е“GӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕ“ъ–{ҠCҢRӮНҒAҠпҸPӮЁӮжӮС•ӘҺU•ә—НӮМҠeҢВҢӮ”jӮИӮЗӮЙӮжӮиғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМ‘¬ӮвӮ©ӮИӮйҢӮ–ЕӮрҠъӮөҒAӮ»ӮМӮӨӮҰӮЕҒA—\ҠъӮіӮкӮйғҚғVғA–{Қ‘Ӯ©ӮзӮМ‘қүҮҠН‘аӮрҢ}ӮҰҢӮӮВӮМӮр•ыҗjӮЖӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҳAҚҮҠН‘аӮМҸo“®
1904”N(–ҫҺЎ37)2ҢҺ6“ъҢЯ‘O1ҺһҒAҗ^–й’ҶӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAҳAҚҮҠН‘аӮМҠeӢүҺwҠцҠҜӮӘҚІҗў•ЫҚЭ”‘’ҶӮМҠшҠНҺOҠ}ӮЙҸWӮЯӮзӮкӮҪҒB“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮНҒA’·ҠҜҢцҺәӮЕҠeӢүҺwҠцҠҜӮЙ’әҢкӮМ“`’BӮрҚsӮБӮҪҢгҒA“ъҳIҠJҗнӮЙ”әӮӨҸҠ—vӮМ–Ҫ—ЯӮрҺц—^ӮөҚмҗнӮМ”ӯ“®Ӯр—ЯӮөӮҪҒBҳAҚҮҠН‘аӮМҠe‘аҒEҠНӮНҒA–й–ҫӮҜӮр‘ТӮБӮДҒA—E–фҚІҗў•ЫӮр”ӯҗiӮөҗӘ“rӮЙӮВӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ1904.2.9 —·ҸҮҢыҠпҸP
—·ҸҮӮЬӮҪӮН‘еҳAӮЙҚЭ”‘’ҶӮЖ—\ҠъӮіӮкӮҪғҚғVғAҠН‘аҺе—НӮЙ‘ОӮөҒA2ҢҺ9“ъ–ў–ҫҒAӢм’ҖҠНӮЙӮжӮй–йҸPӮӘҠёҚsӮіӮкӮҪҒB —·ҸҮӮЙ‘ОӮөӮДӮНӢм’ҖҠН11җЗӮӘҢьӮҜӮзӮкҒAҠOҚ`•d”‘’ҶӮМғҚғVғAҠН‘аҺе—НӮрҠпҸPӮөӮҪӮӘҒAҸPҢӮҠН‘ҠҢЭӮӘҳAҢWӮрҺёӮөӮҪӮҪӮЯҒAҠeҠНӮМҠё“¬ӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҗ¬үКӮНҸ\•ӘӮЖӮНӮўӮў“пӮӯҒAҗнҠНғҢғgғEғBғUғ“ҒAғcғFғUғҢғEғCғ`ӢyӮС“с“ҷҸ„—mҠНғpғӢғүҒ[ғ_ӮЙ‘№ҸқӮр—^ӮҰӮҪӮӘҢӮ’ҫӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘еҳAҳpӮЙҗN“ьӮөӮҪӢм’ҖҠН8җЗӮНүп“GӮЕӮ«ӮёӮЙӢAҠТӮөӮҪҒB ӮұӮМ“ъҒAҗіҢЯҚ ҒAҳAҚҮҠН‘аӮНҗнүКҠg‘еӮМӮҪӮЯ—·ҸҮҢыҠOӮМғҚғVғAҠН‘аӮЙҠJҗн‘жҲкҢӮӮрүБӮҰҒAҠCҠЭ–C‘дӮМҺxүҮүәӮЙӮ ӮйғҚғVғAҺе—НӮЖҢғ—уӮИ–CҢӮҗнӮр“WҠJӮөӮҪҒB”ЮүдӮЖӮаӮЙ‘Ҡ“–ӮМ‘№ҠQӮрҗ¶Ӯ¶ӮҪӮӘҒAӮұӮкӮӘҺе—НҠНӮМӮНӮ¶ӮЯӮДӮМ‘ОҗнӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮИӮЁҒAғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҺi—Я’·ҠҜғXғ^ғӢғN’ҶҸ«ӮНҒA—·ҸҮӮӘҠпҸPӮіӮкӮҪҗУӮр•үӮнӮіӮкӮДҒAғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮЖҢр‘гӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ1904.2.9 җmҗмү«ҠCҗн
2ҢҺ8“ъ—[ҚҸҒAүZҗ¶ҠOӢgҸӯҸ«ӮМ—ҰӮўӮйҸ„—mҠНҗн‘аӮН‘•ҚbҸ„—mҠНҗуҠФӮр”әӮБӮДҗmҗмӮЙ“һ’…ӮөҒAҢмүqӮөӮДӮ«ӮҪ—ӨҢR•”‘аӮр–йӮМӮӨӮҝӮЙҗmҗмӮЙ—Ө—gӮөӮҪҒB“–ҺһҒAҗmҗмҚ`ӮЙӮНғҚғVғAҢRҠН2җЗ(ғҸғҠғ„Ғ[ғOҒAғRғҢҒ[ғc)ӮӘҚЭ”‘ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAҚ‘ҚЫҚ`ӮЕӮМҗ퓬Ӯр”рӮҜӮД—Ӯ9“ъҗіҢЯүЯӮ¬ӮЙҒAҚ`ҠOӮЙ—UӮўҒAҗв‘ОӮМ—DҗЁӮрӮаӮБӮДҲкӢ“ӮЙҢӮ–ЕӮөӮДҸҸҗнӮрҸьӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ1904.2.24-5.2 —·ҸҮҢы•ВҚЗ
—·ҸҮҢы•ВҚЗ ‘ж1үс•ВҚЗ —·ҸҮҢыӮМ•ВҚЗӮНҒAҳAҚҮҠН‘аҺQ–dӮМ—L”n—ЗӢk’ҶҚІӮӘ’ҶҗSӮЖӮИӮи•Дҗјҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйғTғ“ғ`ғғғSҚ`•ВҚЗҚмҗнӮрҺQҚlӮЙҢvүжӮрӮҪӮДҒAҠJҗн‘OӮ·ӮЕӮЙҒAҺg—pӮ·Ӯй•ВҚЗ‘D5җЗӮЖҸж‘DӮ·ӮйҺmҠҜ10–јӮӘ—\’иӮіӮкӮДҺАҚsӮМӢ@үпӮр‘ТӮБӮДӮўӮҪҒB ҠJҗнҸү“ӘӮМ—·ҸҮҠпҸPӮЕғҚғVғAҠН‘аӮӘҚ`“аӮЙҲЪ“®ӮөӮҪӮМӮЕҒAӮұӮМӢ@үпӮЙӮ»ӮМӮЬӮЬ•ВӮ¶ҚһӮЯӮДҒAҠCҸг—A‘—ӮМҲА‘SӮрҗ}ӮлӮӨӮЖ—·ҸҮҢы•ВҚЗӮӘҺАҚsӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBҢҢҸ‘ҺuҠиӮМӮаӮМ‘Ҫҗ”ӮрҠЬӮЮ2000—]–јӮМҺuҠиҺТӮ©Ӯз67–јӮр‘I”ІӮөҒAҗжӮЙ—\’иӮіӮкӮДӮўӮҪҺmҠҜӮЖҚҮӮнӮ№ӮДҒA—L”n’ҶҚІҲИүә77–јӮМҢҲҺҖ‘аӮӘ•Тҗ¬ӮіӮкҒA1904”N(–ҫҺЎ37)2ҢҺ24“ъ–ў–ҫҒA“V’ГҠЫҒA•сҚ‘ҠЫҒAҗmҗмҠЫҒA•җ—gҠЫҒA•җҸBҠЫӮМ5җЗӮӘҒAҗ…—Ӣ’шӮМҺxүҮүәӮЙ—·ҸҮҢыӮЦӮМ“Л“ьӮрҠёҚsӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғA‘ӨӮМҢғӮөӮў–WҠQӮЙ‘ҳӮБӮДҗN“ьӮНҚў“пӮрӢЙӮЯҒAҗhӮӨӮ¶ӮДҚLҗЈҸӯҚІӮМҺwҠцӮ·Ӯй•сҚ‘ҠЫӮЁӮжӮСҗД“Ў‘еҲСӮМҺwҠцӮ·ӮйҗmҗмҠЫӮМ2җЗӮӘҚ`Ңы•tӢЯӮЙ“һ’BӮөӮД”ҡ’ҫӮрүКӮҪӮөӮҪӮЙӮЖӮЗӮЬӮБӮҪҒBҺҖҸқҺТ4–јҒB ‘ж2үс•ВҚЗ ‘ж1үс•ВҚЗӮМҢшүКӮӘ•sҸ\•ӘӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮЕҚД“x•ВҚЗӮӘҢvүжӮіӮкҒAҗ”җзӮМҺuҠиҺТӮ©Ӯз—L”n’ҶҚІҲИүә68–јӮМҢҲҺҖ‘аӮр•Тҗ¬ӮөӮДҒA3ҢҺ27“ъ–ў–ҫҒAҗз‘гҠЫҒA•ҹҲдҠЫҒA–н•FҠЫҒA•ДҺRҠЫӮМ4җЗӮЙӮжӮй“Л“ьӮӘҢҲҚsӮіӮкӮҪҒBӮұӮМӮҪӮСӮНҒAғҚғVғA‘ӨӮМ–WҠQӮаҲк’iӮЖҢғӮөӮіӮрүБӮҰӮҪӮӘҒA‘OүсӮМҢoҢұӮрҗ¶Ӯ©ӮөӮДҒA’TҸЖ“”ӮМҢ¶ҳfӮр–hӮ¬ӮИӮӘӮз”т—ҲӮ·Ӯй‘Ҫҗ”ӮМ–C’eӮМ’ҶӮр–ТҗiӮөҒA‘S‘DӮӘҚ`Ңы•tӢЯӮЕӮМ”ҡ’ҫӮрүКӮҪӮ·ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҺҖҸқҺТҒAҚLҗЈ’ҶҚІҲИүә15–јҒB ‘ж3үс•ВҚЗ —ӨҢRӮМү–‘еҡТ(—Й“Ң”ј“Ү)Ҹг—ӨӮрүҮҢмӮ·ӮйӮҪӮЯҒAғҚғVғAҠН‘аӮМ“®Ӯ«Ӯр—}ҲіӮөӮжӮӨӮЖҳAҚҮҠН‘аҺе—НӮр—·ҸҮӮЙӢЯӮў— ’·ҺR—с“ҮӮЙҗiҸoӮіӮ№ӮҪӮӘҒAҚXӮЙҒAӮЕӮ«ӮкӮО—·ҸҮҚ`“аӮЙ•ВӮ¶ҚһӮЯӮДӮөӮЬӮЁӮӨӮЖ‘ж3үс•ВҚЗӮӘҢvүжӮіӮкӮҪҒB ӮұӮМӮҪӮСӮНҒA‘O2үсӮМҢoҢұӮЙӮ©ӮсӮӘӮЭҒAҸ¬ҸoӮөӮрӮвӮЯӮД12җЗӮЖӮўӮӨ‘еҸW’cӮрӮаӮБӮД5ҢҺ2“ъ–й”јӮ©Ӯзҗi“ьӮрҠJҺnӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҚr“VӮМӮҪӮЯ•ВҚЗ‘аӮМҚs“®ӮНҚў“пӮрӢЙӮЯҒAҗӢӮЙҚмҗн’ҶҺ~ӮӘ”ӯ—ЯӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒA–Ҫ—ЯӮМ“`’BӮӘ•—ҳQӮЙ–WӮ°ӮзӮкӮД“O’кӮрҢҮӮ«ҒA8җЗӮМ•ВҚЗ‘DӮӘ“Л“ьӮөӮҪҒBӢAҠТ‘аҲхӮН”јҗ”ӮЙ–һӮҪӮИӮў‘s—уӮИӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮИӮЁҒA3үсӮЙӢyӮФ—·ҸҮҢы•ВҚЗӮМҢӢүКҒA‘еҢ^ҠНӮМҚ`Ңы’КүЯӮНӢЙӮЯӮДҚў“пӮИӮаӮМӮЖӮИӮиҒAӮЩӮЪ–Ъ“IӮр’BӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ1904.8.10 ү©ҠCҠCҗн
1904”N(–ҫҺЎ37)8ҢҺ10“ъҢЯ‘O9ҺһҒAғEғBғgғQғtғgҸӯҸ«ӮМ—ҰӮўӮй—·ҸҮҠН‘а(җнҠН6ҒAҸ„—mҠН4ҒAӢм’ҖҠН8)ӮӘғEғүғWғIғXғgғNӮр–ЪҺwӮөӮД—·ҸҮӮр—ЈӮкӮҪҒBӮұӮМ“ъ‘Ғ’©Ӯ©ӮзғҚғVғAҠН‘аҸo“®ӮМӢC”zӮӘӮ ӮиҢx•сӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪ“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮНҒA•ӘҚЭ•ә—НӮМҸW’ҶӮр–Ҫ—ЯӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA’ј—ҰӮМҗнҠН4җЗӮрӮаӮБӮД“GҚqҳHҸгӮЦӮМҗiҸoӮрҠJҺnӮөӮҪҒB“r’Ҷ‘•ҚbҸ„—mҠНҸt“ъӢyӮС“ъҗiӮрҚҮ“ҜӮөӮДӢ}ҚsӮөҒAҢЯҢг1ҺһҚ ҒAӢцҠвӮМҗј18kmӮр“м“Ңҗi’ҶӮМғҚғVғAҠН‘аӮр–]Ң©Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB ӮұӮМӮҪӮСӮНҒAүЯӮ®ӮйҒA6ҢҺ23“ъӮМ‘ҳӢцҗнӮЕ“GҠН‘аӮр—·ҸҮӮЙҲнӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӢкӮўҢoҢұӮЙӮ©ӮсӮӘӮЭҒA“GӮМ‘ЮҳHӮрҺХ’fӮөӮДҲкӢ“ӮЙҢӮ–ЕӮөӮжӮӨӮЖҒAү“Ӣ——Ј–CҗнӮрӮаӮБӮДүҮҺЛӮөӮВӮВ—mҗSӮЦӮМ—UӮўҸoӮөӮрҺҺӮЭӮҪӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒAғҚғVғAҠН‘аӮМ’EҸoҲУҗ}ӮНҲУҠOӮЙҢҳӮӯҒA“ъ–{‘ӨӮМҸн—pӮ·Ӯй’ҡҺҡҗн–@ӮМҢг”цӮрӮ·Ӯи”ІӮҜҒAҲкҲУҒA‘S‘¬—НӮрӮаӮБӮД“мүәҲн‘–ӮрҠJҺnӮөӮҪҒB “ҰӮӘӮөӮДӮНҲк‘еҺ–ӮЖҒA“ъ–{ҠН‘аӮНҗw—eӮр—§ӮД’јӮөӮД’ЗҢӮӮөӮҪӮӘҒAҠшҠНҺOҠ}ӮӘ“Gҗн—сӮМ’ҶүӣӮЖ•АӮСҒAғҚғVғA‘ӨӮМҸW’Ҷ–CүОӮЙӮжӮи”нҠQӮН—ЭҗiӮөӮДӮўӮБӮҪҒBҗӢӮЙҢЯҢг3Һһ20•ӘҒAӮвӮЮӮИӮӯҺЛ’цҠOӮЙҸoӮД•АҗiӮөҢң–ҪӮЙ’ЗӮӨӮұӮЖ2ҺһҠФ—]ӮиҒAӮвӮБӮЖ“Gҗж“ӘӮЖӮМӢ——Ј7ӮӢӮҚӮЙ”—Ӯи“ҫӮД•sҸ\•ӘӮИ‘ФҗЁӮИӮӘӮз–CҗнӮрҠJҺnӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAҗнҗЁӮНҲкҢьӮЙҚD“]Ӯ№ӮёҒA”–•йӮӘ”—ӮиҒAӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮНҲГ–йӮЙ“GӮрҲнӮ·ӮйӢ°ӮкӮӘ”ZӮӯӮИӮБӮДӮўӮБӮҪҒBҢЯҢг6Һһ”јҚ ҒAҺOҠ}ӮМ”ӯҺЛӮөӮҪҺе–C–C’eӮӘҒAү^–ҪӮМҲк’eӮЖӮИӮБӮДҠшҠНғcғFғUғҢғEғBғ`ӮМҺi—Я“ғ•tӢЯӮЙ”j—фӮөӮДҺi—Я’·ҠҜӮзҺс”]•”Ӯр“|ӮөӮҪҒB”н’e‘ЗҢМҸбӮөӮҪ“ҜҠНӮНҚ¶ӮЙӢ}җщүсӮөӮДҺ©ҢИ‘а—с’ҶӮЙ“Л“ьӮөҒAғҚғVғAҗw—сӮНҺl•ӘҢЬ—фӮөӮДҚ¬—җӮЙҠЧӮБӮҪҒBӮұӮМӢ@ӮЙҸжӮ¶ӮДҒA“ъ–{Һе—НӮН•пҲНҚUҢӮӮЙӮӨӮВӮиҒA’ЗҢӮӮөӮДӮ«ӮҪҸ”ҠНӮа’ҖҺҹҗ퓬ӮЙүБ“ьӮөӮД“GӮЙ’Й‘ЕӮрүБӮҰӮҪҒB‘е‘ЕҢӮӮр–ЦӮиӮИӮӘӮзӮағҚғVғAҠН‘аӮНҒAҗ…—Ӣ•”‘аӮМ–йҸPӮрӮ©ӮнӮөӮДҺе—НӮН—·ҸҮӮЙҲшӮ«•ФӮөҒAҗнҠН1ҒEҸ„—mҠН3ҒEӢм’ҖҠН5ӮӘ•җ‘•үрҸңӮЬӮҪӮНҚАҸКӮЙӮжӮиҗЁ—НҢёӮЖӮИӮБӮҪҒB ү©ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮҜӮйӢкҗнӮӘ“ъ–{ҠCҠCҗнӮМ“O’к“IҗнҸҹӮЙӮВӮИӮӘӮйӮаӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҺOҠ}ӮМ”н’eӮН20—]”ӯҒAҺҖҸқҺТ125–јӮЕ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮҜӮй”н’e30—]”ӯҒAҺҖҸқҺТ113–јӮжӮиҺҖҸқҺТӮНӮнӮёӮ©ӮЙ‘ҪӮўҒBӮЬӮҪҒAҢг•”Һе–CӮЙ”н’eҒA•ҡҢ©Ӣ{”ҺӢұүӨ“aүәӮӘҗнҸқӮр•үӮнӮкӮҪӮМӮаӮұӮМҺһӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ1904.8.14 үUҺRү«ҠCҗн
‘•ҚbҸ„—mҠН3җЗӮрҠоҠІӮЖӮ·ӮйғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аӮНҒAҠJҗнҲИ—ҲҒA“ъ–{ӢЯҠCӮрҸcүЎ–іҗsӮЙҚs“®ӮөҒAҢң–ҪӮИ“ъ–{‘ӨӮМ‘{ҚхӮМ–ЪӮрҗцӮБӮД6ҢҺ’ҶҸ{ӮЙӮН‘О”nҠCӢ¬ӮЕҸoҗӘ“rҸгӮМ—ӨҢRҸ«•ә1000—]–јӮӘҸж‘DӮ·ӮйҸн—ӨҠЫӢyӮСҚІ“nҠЫӮрҸPӮБӮДҢӮ’ҫ”jӮөҒAӮЬӮҪ7ҢҺүәҸ{ӮЙӮНҺс“sӮМҢәҠЦҢыӮЕӮ Ӯй“ҢӢһҳpҠOӮЙҸoҢ»ӮөӮД–ТҲРӮрҗUӮйӮӨӮИӮЗҒAҗ_ҸoӢS–vӮМҚs“®ӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮМҠCҸгҢр’КӮЙ”сҸнӮИӢәҲРӮр—^ӮҰӮДӮ«ӮҪҒB ҳAҚҮҠН‘аӮН8ҢҺ10“ъ—·ҸҮҠН‘аӮрү©ҠCӮЙ”jӮБӮД“GҺе—НӮМғEғүғWғIғXғgғN’EҸoӮр‘jҺ~ӮөӮҪӮӘҒAҗнҸкӮр—Ј’E“мүәӮөӮҪҸ„—mҠНӢyӮСӢм’ҖҠНӮМ‘О”nҠCӢ¬’КүЯӮр—}ӮҰӮйӮҪӮЯҒAӮЬӮҪҚфүһӮөӮДҸo“®Ӯ·ӮйӮЖ—\ҠъӮіӮкӮйғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аӮЙӮа”хӮҰӮДҒA‘ж“сҠН‘аҺi—Я’·ҠҜҸг‘ә•F”VҸе’ҶҸ«ӮМ’ј—ҰӮ·Ӯй‘ж“сҗн‘а(Ҹoү_ҒEҢбҚИҒEҸн”ЦҒE”ЦҺи)Ӯр13“ъ–ў–ҫӮ©Ӯз‘О”nҠCӢ¬“Ң•ыӮЙҗжҚsӮіӮ№ӮД—vҢӮ”z”хӮЙӮВӮҜӮДӮўӮҪҒB 8ҢҺ14“ъҢЯ‘O5ҺһҒA“мҚq‘{Қх’ҶӮМ‘ж“сҗн‘аӮНҒAҗӢӮЙҒA‘O•ы–с10kmӮЙ“мүәӮ·ӮйҸh“GғҚғVҒ[ғ„ҒAғOғҚғӮғ{ғCҒAғҠғ…Ғ[ғҠғNӮМҠНүeӮр”FӮЯ‘S—НӮрӮаӮБӮД’ЗҗХӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҚ¶җЬӮөӮД“ҢҗiӮөҲн‘–ӮМӢ@ӮрӮӨӮ©ӮӘӮӨғҚғVғAҠН‘аӮЙ‘ОӮөҒA‘ж“сҗн‘аӮНҒAӮ»ӮМ–kҚqӮр–WӮ°ӮВӮВ5Һһ23•ӘӢ——Ј8400ӮҚӮЕ“aҠНғҠғ…Ғ[ғҠғNӮЙ‘ОӮө–CҢӮӮрҠJҺnӮөҒAҺҹӮўӮЕ•АҚsҗнӮЙӮжӮй–ТҢӮӮЙӮӨӮВӮБӮҪҒBҢғҗн30•ӘӮЙӮөӮДғҠғ…Ғ[ғҠғNӮНҢг—ҺӮөҺnӮЯҒAғҚғVҒ[ғ„ӢyӮСғOғҚғӮғ{ғCӮМ2ҠНӮНҒAҢЗ—§ӮөӮҪғҠғ…Ғ[ғҠғNӮрӢ~ҸoӮөӮжӮӨӮЖ”Ҫ“]ӮЬӮҪ”Ҫ“]ӮрҢJ•ФӮөӮИӮӘӮзғҠғ…Ғ[ғҠғNӮрӮ©ӮОӮБӮДүһҗнӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA—јҠНӮМ”н’eӮжӮӨӮвӮӯ—Э‘қӮ·ӮйӮЙӢyӮСҒAҗӢӮЙ8Һһ22•ӘҒAҚs“®•sҺ©—RӮЖӮИӮБӮҪғҠғ…Ғ[ғҠғNӮМӢ~ҸoӮр’f”OӮөӮД–k‘–ӮрҠJҺnӮөӮҪҒB Ҹг‘әҺi—Я’·ҠҜӮНҒA7Һһ50•ӘҚ Ӯ©ӮзҗнҸкӮЙ“һ’…ӮөӮДӮўӮҪҢyҸ„2җЗӮЙғҠғ…Ғ[ғҠғNӮрӮдӮҫӮЛҒA‘ж“сҗн‘аӮрӮаӮБӮД–k‘–Ӯ·Ӯй2ҠНӮМ’ЗҢӮҗнӮЙҲЪӮБӮҪҒB”н’eӮЙӮжӮиҲкҺһҗн—сӮр—ЈӮкӮйҠНӮрҗ¶Ӯ¶ӮИӮӘӮз’ЗҢӮӮ·ӮйӮұӮЖ1ҺһҠФ”јҒAӮөӮ©ӮағҚғVғAӮМ2ҠНӮЙӮНҢё‘¬ӮМ’ҘӮИӮӯҒAӢtӮЙҠшҠНҸoү_ӮМ’e–тҢҮ–RӮМ•сҚҗӮЙҗЪӮөӮҪҸг‘ә’·ҠҜӮНҒAҗӢӮЙ10Һһ4•Ә’ЗҢӮӮр’f”OӮөӮДҒAғҠғ…Ғ[ғҠғNӮрҸҲ•ӘӮ·ӮйӮҪӮЯ”Ҫ“]ӮөӮҪҒB ‘е”нҠQӮЙӮаӮЯӮ°ӮёҒAҢyҸ„ӮЖ‘ОҗнӮөӮДӮўӮҪғҠғ…Ғ[ғҠғNӮНҒAҗЪӢЯӮөӮДӮӯӮй‘ж“сҗн‘аӮр–]Ң©ӮөӮД’EҸoӮрӮ Ӯ«ӮзӮЯҺ©’ҫӮөӮДүКӮДӮҪҒBҸг‘ә’·ҠҜӮМ–ҪӮЙӮжӮиҒA”gҠФӮЙ•ӮӮ©ӮФғҠғ…Ғ[ғҠғNӮМҸжҲхӮМӢ~Ҹ•ӮӘҺАҺ{ӮіӮкӮҪӮӘҒAӮұӮМҚsҲЧӮН“ъ–{•җҺm“№ӮМҗёүШӮЕӮ ӮйӮЖҠCҠOӮЙҢ–“`ӮіӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮӮМҠЧ—Һ
1904”N(–ҫҺЎ37)8ҢҺ10“ъӮМү©ҠCҠJҗнӮМӮМӮҝҗнҠН5ҒEҸ„—mҠН1ҒEӢм’ҖҠН3ӮӘ—·ҸҮӮЙӢAӮБӮҪӮӘҒAӮўӮёӮкӮа‘е‘№ҸқӮр–ЦӮБӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪ14“ъӮМүUҺRү«ҠCҗнӮрҢoӮДғEғүғWғIғXғgғNӮЙӢA’…ӮөӮҪ‘•ҚbҸ„—mҠН2Ӯа‘№ҸқӮӘҗrӮҫӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒAҗӢӮЙғҚғVғA‘ӨӮНҒA—·ҸҮҠН‘аӮМғEғүғWғIғXғgғNүсҚqӮр’f”OӮөӮДҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзӮМ‘қүҮҠН‘аӮМ—Ҳ’…Ӯр‘ТӮВӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB “ъ–{‘ӨӮЖӮөӮДӮНҒAӮұӮМғҚғVғA‘қүҮҠН‘а“һ’…‘OӮЙҒAүҪӮЖӮөӮДӮЕӮа—·ҸҮҠН‘аӮрүу–ЕӮөӮДӮЁӮ©ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒA—ӨҠCҢRӮӘӢҰ—НӮөӮД—·ҸҮӮМҚU—ӘҒA“БӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮМҢӮ–ЕӮрӢ}ӮўӮҫҒB”T–Ш‘еҸ«ӮМ—ҰӮўӮй‘жҺOҢRӮНҒA“S•ЗӮМ—·ҸҮ—vҚЗӮЖӮМҺҖ“¬ӮрҢJ•ФӮөҒAҠCҢR”hҢӯӮМҸd–C‘аӮрӢмҺgӮөҒAҗӢӮЙ28cm—vҚЗ–CӮЬӮЕ“®ҲхӮөӮДӮМ”јҚОӮЙӢyӮФҲ«җнӢꓬӮМӮМӮҝҒA12ҢҺ5“ъҚ`“аӮрҲк–]ӮЙҺыӮЯӮй203ҚӮ’nӮМ’DҺжӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҗнҗЁӮНҲкӢ“ӮЙҚD“]ӮөҒA12“ъӮЬӮЕӮЙҚЭ”‘ӮМғҚғVғAҺе—НҠНӮр28cm—vҚЗ–CӮИӮЗӮЕҢӮ’ҫӮөҒAҺҹӮўӮЕ—Ӯ1905”N(–ҫҺЎ38)1ҢҺ2“ъ—·ҸҮ—vҚЗӮӘҠЧ—ҺӮө—·ҸҮҠН‘аӮаүу–ЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
| Ғ@ | |
|
ҒЎғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҸoҢӮ
ғҚғVғAӮН1904”N(–ҫҺЎ37)4ҢҺ30“ъҗV•ТҠН‘аӮМӢЙ“Ң”hҢӯҲУҗ}ӮрҢц•\ӮөҒAғҚғWғFғXғgғEғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ӮрҺi—Я’·ҠҜӮЖӮ·ӮйҒA‘ж2‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮр•Тҗ¬ӮөӮДҒA10ҢҺ15“ъғҠғoғEҚ`Ӯр”ӯҗiӮіӮ№ӮҪҒB11ҢҺ3“ъғӮғҚғbғRӮМғ^ғ“ғWғ…Ғ[ғӢӮЙӮЁӮўӮДғAғtғҠғJүIүсӮМҺе‘аӮЖғXғGғYү^үНҢo—RӮМҺx‘аӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҗiҸoӮөҒA—Ӯ1905”N(–ҫҺЎ38)1ҢҺ9“ъ•§—Мғ}ғ_ғKғXғJғӢ“ҮӮМғmғVғxӮЕҚҮ—¬ӮрҠ®—№ӮөӮҪҒB ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖӮНӮ»ӮМ”ӯҚq’nӮЕӮ ӮйғoғӢғgҠCӮЙӮҝӮИӮЭҒA“ъ–{‘ӨӮӘӮВӮҜӮҪ’КҸМӮЕӮ ӮйҒB ‘ҫ•Ҫ—m‘ж2ҠН‘аҒ@җнҠН7җЗҒCҸ„—mҠН9җЗҒCӢм’ҖҠН9җЗҒCҢvҗ퓬ҠН25җЗҒB Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ү^‘—‘D14җЗҒCҚHҚм‘D1җЗҒC“Б–ұ‘D1җЗҒCҚҮҢv41җЗҒB ‘ҫ•Ҫ—m‘ж3ҠН‘аҒ@җнҠН1җЗҒCҸ„—mҠН1җЗҒCҠC–hҠН3җЗҒCҢvҗ퓬ҠН5җЗҒB Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ҚHҚм‘D1җЗҒCү^‘—‘D3җЗҒCҚҮҢv9җЗҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҳAҚҮҠН‘аӮМҢ}ҢӮҸҖ”х
“ъ–{‘ӨӮЕӮНҒA—·ҸҮ•ы–КӮМҚмҗнҲк’i—ҺӮЙ”әӮўҒA‘е–{үcӢyӮСҠН‘аҺi—Я•”ӮМҚҮ“ҜӮЕҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮр‘S–ЕӮ·ӮйӮҪӮЯӮМҚмҗнӮӘҒAҳA“ъҗ^Ң•ӮЙҢӨӢҶӮіӮкӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒA1ҢҺ21“ъҒA“а’nӮЕҗ®”х’ҶӮМ‘SҠН’шӮЙ‘ОӮөӮДҒAҸC—қҠ®—№Һҹ‘ж’©‘NҠCӢ¬ӮМ‘OҗiҠо’n’БҠCҳpӮЦӮМҸIҢӢӮӘ”ӯ—ЯӮіӮкӮҪҒBӮ©ӮӯӮөӮДҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аҢӮ–ЕҺи’iӮЕӮ ӮйҺө’iҚ\ӮҰӮМҗн–@ӮМ–Т—уӮИҢP—ыӮӘүЫӮ№ӮзӮкҒAҒu‘ТӮВӮ ӮйӮрӮҪӮМӮЮҒvӮМ‘ФҗЁӮӘҸҮҺҹҚ\җ¬ӮіӮкӮДӮўӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠCҠCҗн
–ҫҺЎ38”N5ҢҺ27“ъ–ў–ҫҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘӢгҸBӮМҗј‘О”nҠCӢ¬ӮЙҢ»ӮкӮҪҒBҢЯ‘O9Һһ40•ӘҒA•tӢЯҸЈүъ’ҶӮМҸЈүъҠНҗM”ZҠЫӮ©ӮзӮМ•сҚҗӮЙӮжӮи“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮНҒAҒu“GҠНҢ©ӮдӮЖӮМҢx•сӮЙҗЪӮөҒAҳAҚҮҠН‘аӮНӮҪӮҫӮҝӮЙҸo“®ӮұӮкӮрҢӮ–ЕӮ№ӮсӮЖӮ·ҒB–{“ъ“VӢCҗ°ҳNӮИӮкӮЗ”gҚӮӮөҒvӮМ‘ж1•сӮр‘е–{үcӮЙ‘Е“dӮөӮДҠшҠНҺOҠ}Ӯр—ҰӮў’БҠCҳpӮ©ӮзҸoҢӮӮөӮҪҒB ӮвӮӘӮД“GҠН‘аӮр”FӮЯӮҪ’·ҠҜӮНҒAҠшҠНҺOҠ}ӮМғ}ғXғgҚӮӮӯҗ퓬ҠшӮрҒAӮВӮўӮЕ1Һһ55•ӘҒAҒuҚcҚ‘ӮМӢ»”pҚҹӮМҲкҗнӮЙҚЭӮиҒAҠeҲхҲк‘w•ұ—г“w—НӮ№ӮжҒBҒvӮМӮyҠшҗMҚҶӮр—gӮ°ҒA‘SҢRӮМҺmӢCӮрҢЫ•‘ӮөӮҪҒB —јҢRӮМӢ——ЈӮӘҒA8җзғҒҒ[ғgғӢӮЙӮИӮБӮҪҺһҒA’·ҠҜӮНүEҺиӮр‘еӮ«ӮӯҚ¶ӮЙҗUӮиҒAҺжӮи‘ЗҲк”tӮр—ЯӮөҒA“GҠН‘аӮЙҗЪӢЯӮөӮҪҒBҺһ2Һһ5•ӘҒAӮұӮкӮӘӮ©ӮМ—L–јӮИ“ҢӢҪ’·ҠҜӮМ“G‘O‘е”Ҫ“]ӮЕӮ ӮйҒB“GӮНҚDӢ@“һ—ҲӮЖӮОӮ©ӮиӮЙ–CҢӮӮрҺnӮЯӮҪӮӘҒAӮЬӮҫҲк—сӮМҗ퓬‘аҢ`(’PҸcҗw)ӮӘҸo—ҲҸгӮӘӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯ–Ў•ыӮӘҺЧ–ӮӮЙӮИӮиҒAҺvӮӨӮжӮӨӮЙҺЛҢӮӮӘҸo—ҲӮёҒAӮЬӮҪҢP—ы•s‘«ӮЖҗЬӮ©ӮзӮМҚr”gӮЕӮИӮ©ӮИӮ©–Ҫ’ҶӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB“GҠН‘аӮМҺЛҢӮҠJҺn2•ӘҢгӮМҒA2Һһ11•ӘҒA”ЮүдӮМӢ——Ј6500ғҒҒ[ғgғӢӮЙӮИӮБӮҪҺһҒA’·ҠҜӮНҒAҸүӮЯӮДҒu‘ЕӮҝ•ыҺnӮЯҒvӮр–ҪӮ¶ӮҪҒBҗўҠEӮМ’Қ–ЪӮрҸWӮЯӮҪҗўӢIӮМ‘еҢҲҗнӮНҒAӮұӮӨӮөӮДҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB —јҚ‘ӮМҠН‘аӮНҒAӢӨӮЙ‘cҚ‘ӮМ–Ҫү^Ӯр’SӮБӮД—НӮМҢАӮи•ұҗнӮөӮҪҒB—јҚ‘ӮМҺе—НҠНӮНҒA‘еҢыҢa–CӮрҺқӮБӮҪҗнҠНӮӘҒAүдӮӘ4җЗӮЙ‘ОӮөӮДҒA“GӮНҗVҺ®ӮӘ7җЗҒAӢҢҺ®4җЗӮЖӮНӮйӮ©ӮЙ—DҗЁӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAүдӮЙӮН‘¬—НӮЙҸҹӮй‘•ҚbҸ„—mҠНӮӘҚЭӮиҒAӮ»ӮМ•s—ҳӮр•вӮБӮДӮўӮҪҒB үдӮӘҠН‘аӮМҚIӮЭӮИҗнҸpӮЖҒA–ТҢP—ыӮЙӮжӮБӮД’bӮҰӮзӮкӮҪ–CҢӮӮЙӮжӮиҒA“GӮМ‘№ҠQӮНҗrӮҫӮөӮӯҒAҗн—сӮр—җӮөӮДүEүқҚ¶үқӮөӮҪҒBҠшҠНғXғҸғҚғtӮН2Һһ50•ӘӮВӮўӮЙҗ퓬—НӮрҺёӮўҒA“GҸ«ғҚғWғFғXғgғEғGғ“ғXғLҒ[’·ҠҜӮаҸdҸқӮр•үӮБӮДӢм’ҖҠНӮЙҲЪҸжӮөҒAҺwҠцҢ ӮрҺҹҗИҺwҠцҠҜӮМғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ӮЙҸчӮБӮҪҒBҗнҠНғIғXғүғrғAӮа3Һһ10•Ә’ҫ–vӮөҒAҗнӮўӮӘҺnӮЬӮБӮД30•ӘҢoӮБӮҪӮұӮлӮЙӮНҸҹ”sӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҢгҺе—Н•”‘аӮв•вҸ••”‘аӮӘ“ьӮи—җӮкҒAҗ”ҺһҠФӮЙ“nӮйҢғӮөӮўҗ퓬ӮӘ‘ұӮўӮҪҒB“GӮНҒAғ{ғҚғWғmғAғҢғLғTғ“ғhғӢҺOҗўӮЩӮ©3җЗҒAӮЬӮҪ‘ҠҺҹӮўӮЕ’ҫ–vҒAӮ»ӮМ‘јӮМҠН’шӮа‘е‘№ҠQӮрҺуӮҜҒAғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ“ҰӮ°ҚһӮаӮӨӮЖ•KҺҖӮМ“w—НӮр‘ұӮҜӮҪҒBӮвӮӘӮД“ъ–vӮӘӢЯӮГӮ«ҒAүдӮӘҺе—Н•”‘аӮН7Һһ28•ӘҒAҢгӮрӢм’ҖҠНӮвҗ…—Ӣ’ш‘аӮЙ”CӮ№ҒA—Ӯ’©ӮМҸWҚҮҸкҸҠӮЕӮ ӮйҹT—Е“ҮӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒBҢгӮрҺуӮҜҢpӮўӮҫүдӮӘ–йҗн•”‘аӮНҒA“{““ӢtҠӘӮӯ’ҶҒA–йүAӮЙӮЬӮ¬ӮкӮД“ч”–ӮөҒA‘sҗвӮИӢӣ—ӢҚUҢӮӮрҗ^–й’ҶӮЬӮЕҠёҚsӮөӮҪҒB –ҫӮҜӮД5ҢҺ28“ъҒA‘O“ъӮЖ‘ЕӮБӮД•ПӮнӮБӮДӢуӮНҗ°ӮкҸгӮӘӮиҒAғlғKғ{ғgғtҸӯҸ«—ҰӮўӮйҠшҠНғjғRғүғCҲкҗўҲИүә5җЗӮМҺc‘¶•”‘аӮаӮҪӮҝӮЬӮҝ”ӯҢ©•пҲНӮіӮкҒAҗӢӮЙ”’ҠшӮр—gӮ°ӮДҚ~•ҡӮөӮҪҒB•aҸ°ӮМ“GҸ«ӮрҸжӮ№ӮҪӢм’ҖҠНғxғhғEғBӮаүдӮӘӢм’ҖҠНҒuӮіӮҙӮИӮЭҒvӮМ’ЗҢӮӮЙ‘ҳӮўҒA”’ҠшӮрҢfӮ°ӮДҚ~•ҡӮөҒA’·ҠҜҲИүә•Я—ёӮЙӮИӮБӮҪҒB Ӯ»ӮМ‘јӮМҠН‘аӮаҺҹҒXӮЙҢӮ’ҫ–”ӮНқ\•ЯӮ ӮйӮўӮНҚ~•ҡӮөҒAӮұӮӨӮөӮД2“ъҠФӮЙ“nӮй—јҚ‘ҠН‘аӮМҢҲҗнӮНҸI—№ӮөӮҪҒB җнүКӮр‘ҚҚҮӮ·ӮйӮЖҒA38җЗӮМ“GҺе—НҠНӮМ’ҶҒA’ҫ–v21җЗҒAҚ~•ҡҒEқ\•Я7җЗҒA’Ҷ—§Қ‘ӮЙ“ҰӮ°ҚһӮЭ•җ‘•үрҸңӮіӮкӮҪӮаӮМ7җЗҒAҺcӮи3җЗӮМҸ¬ҠН’шӮӘ–Ъ“IӮМғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ“һ’BӮөӮҪӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB үдӮӘӮЩӮӨӮМ‘№ҠQӮНӮнӮёӮ©ӮЙҗ…—Ӣ’ш3җЗӮМӮЭӮЕӮ ӮйҒB ӮЬӮҪӮұӮМҠCҗнӮЕҒAғҚғVғA‘ӨӮНҗнҺҖҺТ4545–јҒA•Я—ё6106–јӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA“ъ–{‘ӨӮМҗнҺҖҺТӮН116–јӮЕӮ ӮБӮҪҒB җўҠEҠCҗнҺjҸгҒAӢHӮИӮйҠ®‘SҸҹ—ҳӮЕӮ ӮиҒAӮұӮкӮрҢ_Ӣ@ӮЙғAғҒғҠғJӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕ“ъҳIҚuҳaүпӢcӮӘҺАҺ{ӮіӮкӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮр“ұӮӯҸгӮЕҢҲ’и“IӮИ–рҠ„ӮрүКӮҪӮөҒA“ъ–{ӮЙ•ҪҳaӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҳZҳZҠН‘а
ғҚғVғAӮӘҒAғhғCғcӮЁӮжӮСғtғүғ“ғXӮр—UӮБӮДҒA1895”N(–ҫҺЎ28)4ҢҺӮМ“ъҗҙҚuҳaҸр–сӮЙүо“ьӮөҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМҗҙҚ‘•ФҠТӮрӢӯ—vӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮұӮМ•s“–ӮИҠұҸВӮЙ“ъ–{җlӮМ•®ҢғӮНӢЙ“xӮЙ’BӮөӮҪӮӘҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ҠCҢRӮНҺOҚ‘ӮМӢЙ“ҢҠН‘аӮЙӮ·Ӯз‘ОҚRӮөӮ©ӮЛӮйҸуӢөӮЕҒAҺc”OӮИӮӘӮзӮұӮМҠұҸВӮЙӢьӮ·ӮйӮМӮЩӮ©ӮИӮӯҒA‘ј“ъӮрҠъӮөӮДӮМүзҗdҸҰ’_ӮӘҺnӮЬӮБӮҪҒB “Ҝ”N7ҢҺҒA“ъ–{ӮНҒAҢR–ұӢЗ’·Ғ@ҺR–{Ң •әүqҸӯҸ«ӮМҲДүжӮЙӮИӮйҠCҢRҠg’Ј10”NҢvүжӮр”ӯ“®ӮөӮДҒAҗнҠН6җЗҒA‘•ҚbҸ„—mҠН6җЗ(ҳZҳZҠН‘а)ӮрҠоҠІӮЖӮ·ӮйӢЙ“Ңҗ…ҲжӮЕӮМҚЕӢӯҠН‘аӮМ•Ы—LӮр–ЪҺwӮөӮД•KҺҖӮМ“w—НӮрҠJҺnӮөӮҪҒB ‘жҲкҗн‘аӮрҚ\җ¬Ӯ·ӮйҗнҠНӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһҢҡ‘ў’ҶӮЕӮ ӮБӮҪ12000tӢүӮМ•xҺmҒA”Ә“ҮӮЙүБӮҰӮДҒA•~“ҮҒA’©“ъҒAҸүҗЈҒAҺOҠ}ӮӘүpҚ‘ӮЙ”ӯ’ҚӮіӮкҒA30cm–C14–еӮр”хӮҰӮй15000ғgғ“ӢүҒE18ғmғbғgӮМӢӯ—НҠНӮЖӮөӮДҸoҢ»ӮөӮҪҒB җнҠНҺOҠ}ӮНҒAӮ»ӮМҚЕҸIҠНӮЕҒA3”NӮМҚОҢҺӮЖ88–ңғ|ғ“ғh(“–Һһ880–ңү~)ӮМӢҗ”пӮр“ҠӮ¶ӮДҒA1902”N(–ҫҺЎ35)үpҚ‘ӮМғ”ғBғbғJҒ[ғX‘ў‘DҸҠӮЕҸvҚHӮөӮҪҗVүsҠНӮЕӮ ӮБӮҪҒB ‘ж“сҗн‘аӮрҚ\җ¬Ӯ·Ӯй‘•ҚbҸ„—mҠНӮНҒAҗуҠФҒAҸн”ЦҒAҸoү_ҒA”ЦҺиӮӘүpҚ‘ӮЙҒA”Әү_ӮӘғhғCғcӮЙҒAҢбҚИӮӘғtғүғ“ғXӮЙӮ»ӮкӮјӮк”ӯ’ҚӮіӮкҒA1901”N(–ҫҺЎ34)ӮЬӮЕӮЙҠ®җ¬ӮөӮД20cm–C4–еҒE15cm–C14–еӮр”хӮҰӮй9700ғgғ“ӢүҒE20ғmғbғgӮМҗVүsҠНӮЖӮөӮДҸoҢ»ӮөӮҪҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ5Ғ@–ҫҺЎ37”N2ҢҺ9“ъҒ`–ҫҺЎ38”N9ҢҺ5“ъ | |
|
“ъҳIҗн‘ҲӮНҗўҠEҺjӮр“]Ҡ·ӮіӮ№ӮҪҲк‘еҺ–ҢҸӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{ӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮӘ“ҢҗNҺеӢ`“IӮИғҚғVғAӮМҺиӮЙҠЧӮйӮұӮЖӮр–hҺ~Ӯ·ӮйӮҪӮЯҒAҚ‘үЖҲА‘SҸгҒAҗ^ӮЙҺ~ӮЮӮр“ҫӮёҚ‘ӮМ‘¶–SӮр“qӮөӮДҠJҗнӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮҪҒBғiғ|ғҢғIғ“ӮЕӮіӮҰ”s‘ЮӮіӮ№ӮҪҗўҠEӢьҺwӮМ‘еҚ‘ӮҪӮй’йҗ§ғҚғVғAӮЙ‘ОӮөҒAӢЙ“ҢӮМҗVӢ»Ҹ¬Қ‘“ъ–{ӮӘҸҹ—ҳӮөӮжӮӨӮЖӮНүдӮӘ“Ҝ–ҝҚ‘ӮЕӮ ӮБӮҪғCғMғҠғXӮЕӮ·ӮзҺvӮнӮёҒAҗўҠE’ҶӮӘ“ъ–{ӮМ”s–kӮр—\‘zӮөӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМ—\‘zӮНҢ©Һ–ӮЙ•ўӮйҒBҗӯҺЎӮЖҢRҺ–Ӯр“қҚҮӮөӮҪ–ҫҺЎ“ъ–{ӮМ—DӮкӮҪҗӯҗн—ӘӮНҒAҚЕҸI“IӮЙӮН“ъ–{ӮЙҸҹ—ҳӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪҒBӢЯ‘гҺjӮЙӮЁӮўӮДҸүӮЯӮД—LҗFҗlҺнӮӘ”’җFҗlҺнӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB
ӮұӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮНғAғWғAҒE’Ҷ“ҢҒE–kүўӮИӮЗӮМҸ”–Ҝ‘°ӮЙ—EӢCӮЖҠу–]Ӯр—^ӮҰҒAүӘ‘q“VҗSӮМҢҫӮӨҒeғAғWғAӮМӮЯӮҙӮЯҒfӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪҒB‘ҰӮҝҒA“ъ–{Ӯр”НӮЖӮөӮД”’җFҗlҺнӮМҺx”zӮ©Ӯз’EӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӢCү^ӮӘҗўҠE“IӮЙҺnӮЬӮБӮҪҒB “ъҗҙҒE“ъҳIӮМ—јҗн–рӮЙҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮҪ“ъ–{ӮНҒAҚ‘ҚЫҺРүпӮЙӮЁӮўӮДӮ»ӮМ’nҲКӮНҠm—§ӮіӮкӮҪӮ©ӮЙҢ©ӮҰӮҪҒBӮөӮ©Ӯөүў•Д—сӢӯӮН“ъ–{ӮМҺw“ұ“I’nҲКӮр”FӮЯӮИӮўӮОӮ©ӮиӮ©ҒAғAғWғA—BҲкӮМҗжҗiҚ‘ӮЖӮөӮДҢxүъӮМ–ЪӮрҢьӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮұӮЙүдӮӘҚ‘ӮМҚ‘–hӮНҗVӮҪӮИ“WҠJӮр—vӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB Ғ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ1 | |
|
ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМӢЙ“ҢҸоҗЁҒ@
“ъҗҙҗн‘ҲӮЙӮжӮБӮДҒAҚ‘ҚЫҺРүпӮЕӮМҒu–°ӮкӮйҺӮҺqҒvҗҙҚ‘ӮМҲРҗMӮН’бүәӮөҒA—сӢӯӮЖҗҙҚ‘ӮЖӮМ—НҠЦҢWӮН‘еӮ«Ӯӯ•Пү»ӮөӮҪҒBүБӮҰӮДҸd—vӮИӮұӮЖӮНҒAҗҙҚ‘ҚЕ‘еӮМҢRҺ–ҸW’cӮЕӮ ӮБӮҪ–k—mҢR”ҙ(ҢR’c)ӮӘ’Ч–ЕӮөҒA–һҸBӮ©ӮзүШ–kӮЙӮ©ӮҜӮДҢRҺ–“IӢу”’ӮӘҗ¶Ӯ¶ӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB–һҸBӮ©ӮзүШ–kӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ’nҲжӮНҒA–k—mҢR”ҙӮӘ‘¶ҚЭӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙ–ўӮҫ—сӢӯӮӘҗiҸoӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҚЕҢгӮМ–ўҠJ’nӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҢRҺ–“IӢу”’’n‘СӮМ”ӯҗ¶ӮНҒA—сӢӯӮЙӮжӮйҗVӮҪӮИҗЁ—НҢ—Ҡl“ҫӢЈ‘ҲӮрҸө—ҲӮ·ӮйӮұӮЖӮрҲУ–ЎӮ·ӮйҒBӮ»ӮМ’nҲжӮЙҗи—МҢRӮр’uӮўӮДӮўӮҪӮМӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮМҗнҸҹҚ‘“ъ–{ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA—сӢӯӮНҗVӢ»Қ‘“ъ–{ӮМ’“—ҜӮИӮЗӮИӮсӮз–в‘иӮЙӮөӮДӮЁӮзӮёҒAӮўӮВӮЕӮаӮұӮкӮр”rҸңӮЕӮ«ӮйӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮИ“ъ–{ҢyҺӢӮЖҢRҺ–“IӢу”’’n‘СӮЦӮМӢӯӮўҠЦҗSӮр•шӮўӮДӮўӮҪӮМӮНғҚғVғAҒAғtғүғ“ғXҒAғhғCғcӮИӮЗӮЕҒAҺOҚ‘ҠұҸВӮНӮ»ӮМҢ»ӮкӮЕӮ ӮйҒB’ҶӮЕӮағVғxғҠғA“S“№ӮрҢҡҗЭ’ҶӮЕ•s“ҖҚ`Ҡl“ҫӮМ•K—vӮӘӮ ӮБӮҪғҚғVғAӮӘӢЙӮЯӮДҗПӢЙ“IӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎғҚғVғAӮМ“ҢҗNҗӯҚфҒ@
ғҚғVғAӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮӘҸIӮнӮйӮЖҳIҗҙ–§–сӮрҢӢӮсӮЕ–һҸBҗiҸoӮрҗ}ӮиҒA–ҫҺЎ31”N(1898)“Ңҗҙ“S“№ӮМ•~җЭҢ ӮрҠl“ҫҒAӮіӮзӮЙҺOҚ‘ҠұҸВӮЕ“ъ–{Ӯ©ӮзҺжҸгӮ°ӮҪ—·ҸҮҒA‘еҳAӮМ‘dҺШӢҰ’иӮр’чҢӢҒA•s“ҖҚ`Ҡl“ҫӮМ”OҠиӮр’Bҗ¬ӮөӮҪҒBғҚғVғAӮНӮ»ӮМҢгҒA—·ҸҮҒA‘еҳAӮМҢoүcӮЙ—НӮр’ҚӮ¬ҒAҠШҚ‘җiҸoӮЙӮВӮўӮДӮНҲкҺһ“ъ–{ӮЖӢҰ’І“I‘Ф“xӮЙҸoӮДӮўӮҪӮӘҒA–ҫҺЎ33”N(1900)ӮЙӮИӮйӮЖҠШҚ‘ӮЙ”—ӮБӮД”nҺRӢЯ–TӮЙғҚғVғAӢЙ“ҢҠН‘аӮМ’ф”‘’nӮр‘dҺШӮөӮҪҒB ӮұӮкӮН—·ҸҮӮЖғEғүғWғIғXғgғNҢRҚ`ӮМ’ҶҢpҠо’nӮЕӮНӮ ӮиҒAҢ©•ыӮЙӮжӮБӮДӮН“ъҠШӮМҳA—ҚҗьӮрҺХ’fӮөҒAҠШҚ‘ӮрҺO•ыҢьӮ©Ӯзҗ§ҲіӮ·Ӯй‘ФҗЁӮЖӮа“ЗӮЭҺжӮкӮҪҒBӮЬӮҪҒAӢҗҚП“ҮӮЖӮ»ӮМ‘ОҠЭӮрғҚғVғAҲИҠOӮЙ‘dҺШӮіӮ№ӮИӮўӮЖӮўӮӨҳIҠШ–§–сӮрҢӢӮсӮҫҒBӮіӮзӮЙҠӣ—ОҚ]ӮМҺ‘Ң№ҠJ”ӯӮМ—ҳҢ ӮрҠl“ҫҒAӮ»ӮМҗЁ—НӮНҺҹ‘жӮЙ’©‘N”ј“ҮӮр“мүәӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮұӮМӮҪӮЯҒAҺOҚ‘ҠұҸВҢгӮНүзҗdҸҰ’_ӮРӮҪӮ·ӮзҚ‘—НӮМҸ[ҺАӮрҗ}Ӯй“ъ–{ӮЖҒAӢЙ“ҢҗN—ӘӮМҠйҗ}ӮрҳIҚңӮЙҢ»ӮөӮДӮ«ӮҪғҚғVғAӮЖӮӘҒAҠШҚ‘Ӯр•‘‘дӮЖӮөӮДҢғӮөӮӯ‘О—§Ӯ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB –kҗҙҺ–•ПӮМӮМӮҝғҚғVғAӮНҒA“Ңҗҙ“S“№Ӯр–hүqӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ–ј–ЪӮЕ‘еҢRӮрҸo•әӮөҒAҢХҺӢбјҒXӮЖ‘_ӮБӮДӮўӮҪ–һҸB‘S“yӮрӮҪӮҝӮЬӮҝҗи—МӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгӮа–һҸBӮЦӮМ•ә—НӮН‘қүБӮМҲк“rӮр’HӮиҒAғҚғVғAӮМ–һҸBҗи—МӮНүiӢv“IӮИӮаӮМӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘҲУҗ}ӮіӮкӮДӮўӮҪҒB–ҫҺЎ33”N11ҢҺӮЙӮНҒAӢЙ“Ң‘Қ“ВғAғҢғNғZҒ[ғGғtӮН•т“VҸ«ҢRҒE‘қҠыӮЙҲі—НӮрүБӮҰҒA‘жҲкҺҹҳIҗҙ–§–сӮрӢӯҲшӮЙҸі‘шӮіӮ№ӮҪҒB–ҫҺЎ34”N3ҢҺӮЙӮНғyғeғӢғuғӢғNӮЙӮЁӮўӮД‘ж“с–§–сӮӘ’ІҲуӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAүдӮӘҗӯ•{ӮНҒAӮұӮМ–§–сӮН“Ң—m•ҪҳaӮЙҠлҢҜӮИӮаӮМӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДғCғMғҠғXӮЖҗ}ӮБӮДғҚғVғAӮЙҚRӢcӮөӮҪҒB“–ҺһғҚғVғAӮНӮЬӮҫ“м–һ“S“№ӮМҚHҺ–ӮӘҠ®җ¬ӮөӮДӮўӮИӮўӮҪӮЯҸ\•ӘӮИҢR‘аӮрӢЙ“ҢӮЙ‘—ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒAҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй—vӢҒӮрҲкүһ“PүсӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМҢгӮағҚғVғAӮНҒA–һҸBҗи—МӮМҚҮ–@ү»Ғ^‘жҺOҺҹ–§–сӮрҗҙҚ‘ӮЙ”—ӮиҒA—сҚ‘ӮМҺxүҮӮрҺуӮҜӮД–§–сӮЙ’пҚRӮ·ӮйҗҙҚ‘ӮЖ’·ӮўҠФҢрҸВӮр‘ұӮҜӮҪҒB ӮұӮМғҚғVғAӮМҚs“®ӮНҒAғҚғVғAӮӘҠщӮЙҠШҚ‘ӮЕҢRҺ–Ҡо’nӮрҠl“ҫӮөҒA‘еҳAҒA—·ҸҮӮр‘dҺШҒAҹЭҠCҳpҒAү©ҠCӮМҺ–ҺАҸгӮМҗ§ҠCҢ Ӯр—LӮөҒA’©‘N”ј“ҮӮр’КӮ¶ӮДғEғүғWғIғXғgғNӮЖӮрҢӢӮФ’·‘еӮИҢRҺ–Ҡо’nӮрҠ®җ¬ӮөӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮЙҒAҸd‘еӮИӢәҲРӮЕӮ ӮБӮҪҒBҠШҚ‘ӮЙү—ӮҜӮй“ъ–{ӮМҢ үvӮӘҠлӮӨӮўӮЖӮўӮӨ–в‘иӮЕӮНӮИӮӯҒA“ъ–{ӮМ‘¶—§Ӯ»ӮМӮаӮМӮМҠлӢ@ӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғA–{“yӮНҒA“ъ–{Ӯ©ӮзӮНӮЖӮӨӮДӮўҸжӮиүzӮҰӮзӮкӮИӮўү“Ӯў”Ю•ыӮМӢ——ЈӮЙӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөҒA“ъ–{ӮНҒAӮ»ӮМ–{“yӮр’јҗЪғҚғVғAӮМ‘OҗiҢRҺ–Ҡо’nӮМ‘O–КӮЙӮіӮзӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүдӮӘҚ‘ӮрҸ„Ӯй“–ҺһӮМӢЙ“ҢҸоҗЁҒ@
–ҫҺЎ“ъ–{ӮМҺw“ұҺТӮЙӮЖӮБӮДҒA“ъ–{—с“ҮӮМҲА‘SӮр•ЫҸбӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮӘӢӯ‘еӮИ‘е—ӨҚ‘үЖӮМҺx”zү»ӮЙҠЧӮйӮМӮр–hҺ~Ӯ·ӮйӮұӮЖӮН•sүВҢҮӮМ—vҢҸӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢГӮӯӮН•¶үiҒAҚOҲАӮМҗМҒA“ъ–{ӮНҢіӣ„ӮЖӮўӮӨҚ‘“пӮЙ’ј–КӮөӮҪҒB–ЦҢГӮМҲіҗӯӮЙӮжӮй–Ҫ—ЯүәӮЖӮНү]ӮҰҒAҚOҲАӮМ–рӮҫӮҜӮЕӮаҠН‘D900дzӮМҢҡ‘ўӮЖҗіӢKҢR1–ңҗlҒAҗ…Һи15000җlӮМҸ]ҢRӮЙӮжӮи“ъ–{җN—ӘӮМҢvүжӮЙүЧ’SӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB’©‘NӮӘҺгҺТӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҢМӮМӢҰ“ӯҚsҲЧӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒAүдӮӘҚ‘ӮНҢіӣ„ӮМҢoҢұӮр’КӮ¶ӮДҒA’©‘N”ј“ҮӮӘ‘е—ӨҗЁ—НӮМҺx”zүәӮЙҠЧӮБӮҪҺһӮМ“ъ–{ӮЙ‘ОӮ·ӮйӢәҲРӮЙӮВӮўӮДҸ\•ӘӮИӢіҢPӮр“ҫӮҪӮМӮЕӮ ӮиҒAӮұӮМӢіҢPӮН–ҫҺЎӮМҺw“ұҺТӮЙӮаҺуӮҜҢpӮӘӮкӮДӮўӮҪҒB Ӯ»ӮМ’©‘NӮЖҗҙҚ‘ӮНҒA–ҫҺЎ“ъ–{ӮӘҚЕ‘еӮМҢoҚП“I—ҳҠQҠЦҢWӮр—LӮ·ӮйҚ‘үЖӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҗӯҺЎ“IӮЙӢЙӮЯӮД•sҲА’иӮИ—јҚ‘ӮӘҗјүў—сӢӯӮМҺx”zӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЖӮИӮкӮОҒA“ъ–{ӮМҲА‘SӮЖҢoҚП“IҢ үvӮНҠл–wӮЙ•mӮ·ӮйӮаӮМӮЖҚlӮҰӮзӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъүp“Ҝ–ҝӮ©“ъҳIӢҰҸӨӮ©Ғ@
Ӯ©ӮӯӮөӮДғҚғVғAӮН–һҸBӮрҢRҺ–җи—МӮөҒAӮ»ӮМ–өҗжӮНҠШҚ‘ӮМҸгӮЙӮаӢyӮСҒA“ъ–{ӮЖӮМ—ҳҠQӮНӮВӮўӮЙҸХ“ЛӮ№ӮЛӮОӮвӮЬӮИӮўҗЁӮўӮЙӮИӮБӮҪҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМҢR”хӮНҒAӮЬӮҫ—\’иӮМҠ®җ¬ӮрӮЭӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB“Ж—НӮЕӢӯ‘еӮИӮйғҚғVғAӮЙ‘ОҚRӮөҒAғҚғVғAӮМҗЁ—НӮрӢЙ“ҢӮ©Ӯз‘|“ Ӯ·ӮйӮұӮЖӮН“һ’к•sүВ”\ӮЕӮ ӮйҒBӮўӮ«ӮЁӮўғҚғVғAӮЖӢҰ’иӮМ“№ӮрӢҒӮЯӮДӮ»ӮМҗN—Ә“IҗӯҚфӮрҠЙҳaӮіӮ№ӮйӮ©ҒAӮЬӮҪӮН‘јӮМ—сӢӯӮЖ’сҢgӮөӮ»ӮМ—НӮрҺШӮиӮДғҚғVғAӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮ©ҒAҚ‘ҚфӮНӮ»ӮМӮўӮёӮкӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪҒB ‘OҺТӮНҒA–һҸBӮНғҚғVғAӮЙҸчӮБӮДҠШҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮй’nҲКӮНҠm•ЫӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨҒu’Іҗ®үВ”\ҳ_ҒvҒu–һҠШҢрҠ·ҳ_ҒvӮЕҒAҲЙ“Ў”Һ•¶ҒAҲдҸгҠ]ҒAҺRгp—L•ьӮзҢіҳVӢүӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢгҺТӮНҒA–c’ЈҺеӢ`җӯҚфӮрӢӯҚsӮ·ӮйғҚғVғAӮНҒA–һҸBӮрҗи—МӮөӮҪӮМӮҝҠШҚ‘Ӯа•KӮёҗи—МӮ·ӮйӮ©Ӯз’Іҗ®ӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮйӮЖӮ·ӮйҒu‘О—§•KҺҠҳ_ҒvӮЕҒAҢj‘ҫҳYҒAүБ“ЎҚӮ–ҫҒAҸ¬‘әҺх‘ҫҳYҒA—С“ҹӮзҢ»–р‘еҗbҢцҺgӢүӮЕӮ ӮБӮҪҒB “–ҺһӮМ“ъ–{җӯ•{ӮМҠо–{“IҠOҢр•ыҗjӮН“ъҳIӢҰ’ІҳHҗьӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғA’““ъҢцҺgғCғYғ”ғHғӢғXғLҒ[ӮзӮН‘еӮўӮЙ“ъҳI’сҢgӮрҸҘӮҰҒAҲЙ“Ў”Һ•¶ӮНҠO—VӮЙӮ ӮҪӮБӮД“ъҳIӢҰ’иӮрҺе’ЈӮөӮДӮўӮҪҒBӮаӮБӮЖӮа“ъҳIӢҰ’ІҳHҗьӮрҺе’ЈӮ·ӮйҲУҢ©ӮН“ъүp“Ҝ–ҝӮр–]ӮсӮЕӮўӮИӮўӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮИӮӯҒA“ъүp“Ҝ–ҝӮМҗ¬—§ӮНҚў“пӮЖ”»’fӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗўҠEҠeҚ‘ӮЙ‘®—МҒEҗA–Ҝ’nӮрҺқӮҝҒA“Ж—НӮЕҚ‘ҚЫҺРүпӮМғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЕӮ ӮлӮӨӮЖӮөӮҪҒuүhҢхӮ ӮйҢЗ—§ҺеӢ`ҒvӮр‘ұӮҜӮй‘еүp’йҚ‘ӮӘҒAҲк“]ӮөӮДӢЙ“ҢӮМҸ¬Қ‘“ъ–{ӮЖӮМ“Ҝ–ҝӮрҢӢӮФӮұӮЖӮИӮЗ–І‘zӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҒAӮжӮиҢ»ҺА“IӮИ“ъҳIӢҰ’ІӮрҺҺӮЭӮйӮМӮӘҺ©‘RӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҢj“аҠtӮМ’aҗ¶ӮЖ“ъүp“Ҝ–ҝ’чҢӢҒ@
ӮұӮМ“ъҳI’сҢgҳ_ӮНғCғMғҠғX‘ӨӮЙ“`ӮнӮиҒAҸӯӮИӮ©ӮзӮёғCғMғҠғXҗӯ•{Ӯрҗ_ҢoӮрҺhҢғӮөӮҪҒB–kҗҙҺ–•ПӮЕүдӮӘ—ӨҢRӮМҺА—НӮр–Ъ‘OӮЙӮөӮҪүpҚ‘ӮМ“–Һ–ҺТӮМ’ҶӮЙҒAӢЙ“ҢӮЕғҚғVғAӮЙ‘ОҚRӮЕӮ«ӮйӮМӮН“ъ–{ӮМ‘јӮЙӮИӮўӮЖӮўӮӨҠП”OӮӘҚӮӮЬӮБӮДӮ«ӮҪҗЬӮЕӮаӮ ӮиҒA“ъүp“Ҝ–ҝӮМ’чҢӢӮН—јҚ‘Ҹг‘w•”ӮЕҗ^Ң•ӮЙҚlӮҰӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮӯҒBүБӮҰӮДғҚғVғAӮЖ“ъ–{ӮӘӢҰ’иӮрҢӢӮФӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒAӮЖӮўӮӨӢ^ҳfӮНӮ©ӮҰӮБӮД“ъүp“Ҝ–ҝӮМ’чҢӢӮр‘ҒӮЯӮйҢӢүКӮЖӮИӮБӮҪҒB –ҫҺЎ34”N6ҢҺҗ¬—§ӮМҢj‘ҫҳY“аҠtӮНҒA’“үpҢцҺg—С“ҹӮрӮөӮДҒAүpҚ‘ӮӘ“ъүpҚUҺз“Ҝ–ҝӮЬӮЕҚlӮҰӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮБӮҪҒBүpҚ‘ӮНҒA“–Һһ“мғAҗн‘Ҳ(ғ{Ғ[ғAҗн‘Ҳ)ӮМӮҪӮЯӢЙ“ҢӮЙҺиӮрҗLӮОӮ·—]—НӮӘӮИӮӯҒAғҚғVғAӮӘӮ»ӮМӢ•ӮЙҸжӮ¶ӮДӢЙ“ҢӮЙҗiҸoӮөӮДӮ«ӮҪӮұӮЖӮрҢxүъӮөӮДӮўӮҪҺһӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢгҗ”ҺҹӮЙӮнӮҪӮйҲУҢ©ҢрҠ·ӮЖ“а—eӮМҸCҗіӮрҢoӮДҒA–ҫҺЎ35”N1ҢҺ30“ъғҚғ“ғhғ“ӮЙӮЁӮўӮД“ъүp“Ҝ–ҝӮН’чҢӢӮіӮкӮҪҒB “ъүp—јҚ‘ӮӘ–{“Ҝ–ҝӮЙ‘хӮөӮҪӮаӮМӮН—§ҸкӮМ‘ҠҲбӮЙӮжӮБӮДҲЩӮИӮБӮДӮўӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮНғҚғVғAӮЙ—DүzӮ·ӮйҢ үvӮМ•ЫҸШӮЖ‘еүp’йҚ‘ӮМ—`–]Ӯр“ҫӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮиҒAғCғMғҠғXӮНғҚғVғAӮМ“мүәӮрӢЙ“ҢӮЕ‘jҺ~Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮҫғҚғVғAӮМ–c’ЈҗӯҚфӮрӢӯӮӯҲУҺҜӮөӮҪ“_ӮЙӮЁӮўӮД—јҚ‘ӮНӢӨ’КӮөӮДӮЁӮиӮұӮкӮӘҒu‘ОҳI“Ҝ–ҝҒvӮЖӮўӮнӮкӮйҸҠҲИӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ОҳIҠOҢрҢрҸВҒ@
“ъүp“Ҝ–ҝӮНғҚғVғAӮМ‘ОҗҙҗӯҚфӮЙүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒB–ҫҺЎ35”N4ҢҺҒ@ғҚғVғAӮН–kҗҙҺ–•ПӮЕ–һҸBҗи—МӮМӮҪӮЯӮЙ”hҢӯӮөӮҪ–c‘еӮИ•ә—НӮр3үсӮЙ•ӘӮҜӮД“P‘ЮӮіӮ№ҒA–һҸBӮМҢ —ҳӮрҗҙҚ‘ӮЙ–ЯӮ·ӮұӮЖӮрҳIҗҙҸр–сӮЖӮөӮДҗҙҚ‘ӮЙ–сӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘҒA–ҫҺЎ35”N10ҢҺ8“ъӮМ‘жҲкҺҹ“P•әӮНҺАҚsӮөӮҪӮӘҒA‘ұӮӯ–ҫҺЎ36”N4ҢҺ8“ъӮМ‘ж“сүс“P•әӮНҒAҠъ“ъӮӘ—ҲӮДӮағҚғVғAӮН“P•әӮрҺАҺ{ӮөӮИӮўӮЗӮұӮлӮ©ҒAӢtӮЙ‘қ•әӮМӢC”zӮіӮҰҺҰӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҲк•ыӮЕӮНҗҙҚ‘ӮЙ“P•әӮМҸрҢҸӮЖӮөӮДҒA7ғ–ҸрӮЙӮМӮЪӮй–һҸBӮМ—ҳүv“ЖҗиӮМ—vӢҒӮрӮВӮ«ӮВӮҜӮҪҒB“ъүp—јҚ‘ӮНҒAҗҙҚ‘ӮЙғҚғVғAӮМ•s“–ӮИ—vӢҒӮрӢ‘җвӮ·ӮйӮжӮӨҢxҚҗҒA•ДҚ‘ӮағҚғVғAӮЙҚRӢcӮө–һҸBүр•ъӮМ–с‘©ӮрӮіӮ№ӮҪҒBҗҙҚ‘ӮНғҚғVғAӮМ—vӢҒӮрӢ‘җвӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮНғҚғVғAӮЙ–һҸBӮЙӢҸҚАӮйҢыҺАӮр—^ӮҰӮҪҒB‘жҲкҺҹ“P•әӮаҺАӮН—Й—zӮЙҲЪ“®ӮөӮҪӮҫӮҜӮЕҒA–һҸBӮМҢoүcӮрӮЬӮ·ӮЬӮ·җiӮЯҒAҗи—МӮМҺАҗСӮӘҠщҗ¬Һ–ҺАӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒB ӮұӮМғҚғVғAӮМ‘Ф“xӮЙ‘ОӮөӮДҒA4ҢҺ21“ъҒ@Ӣһ“sӮМҺRгp—L•ьҢіҗғӮМ•К“@–ізБҲБӮЕҒAҢjҺс‘ҠҒAҸ¬‘әҠO‘ҠҒAҲЙ“Ў”Һ•¶ҒAҺRгp—L•ьӮНӢҰӢcӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒu–һҸB–в‘иӮЙӮВӮўӮДӮНғҚғVғAӮМ—DҗжҢ ӮН”FӮЯӮйӮӘҒA’©‘N–в‘иӮНҸч•аӮөӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҠо–{•ыҗjӮрҠm”FӮөӮҪҒBӮўӮнӮдӮйҒu–һҠШҢрҠ·ҳ_ҒvӮМҠOҢрҗӯҚфӮЙ—§ӢrӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҠФҒAғҚғVғAӮМ–һҸBӮЙ‘ОӮ·Ӯй–мҗSӮНҳIҚңӮИ—l‘ҠӮр’жӮөӮДӮўӮҪҒA–PҷҖҸйҒAҲА“ҢҢ§Ҳк‘СӮрҺx”zүәӮЙӮЁӮіӮЯҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМ•вӢӯӮрҗiӮЯӮҪҒB7ҢҺӮЙӮН“Ңҗҙ“S“№ӮӘҠ®җ¬ӮөҒAҢR‘аӮМ‘е—КҲЪ“®ӮМҠо‘bӮНӮЕӮ«ӮДӮўӮҪҒB8ҢҺӮЙӮНӢЙ“Ң‘ҚҠД•{ӮӘҗЭ’uӮіӮкҒA“ъҳIҠФӮМҠЦҢWӮНӢ}‘¬ӮЙҲ«ү»ӮөӮДӮўӮБӮҪҒB 6ҢҺ12“ъҒ@ғҚғVғA—ӨҢR‘еҗbғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮӘӢЙ“ҢҺӢҺ@ӮМ“r’Ҷ—Ҳ“ъӮөӮҪҒBӢҺӮйҳI“yҗн‘Ҳ(1877Ғ`1878)ӮМҢчҗСӮ©ӮзүўҸBӮ«ӮБӮДӮМ‘еҗн—ӘүЖҒAҚc’й‘ӨӢЯӮМҸdҗbӮЖ–ЪӮіӮкӮДӮўӮҪӮЁӮиҒAүдӮӘҚ‘ӮНҚ‘•oӮЙҸҖӮ¶ӮД‘ТӢцӮөӮҪҒB“ъ–{ӮМҢіҳVӮ»ӮМ‘јҺс”]ӮЖүп’kӮөӮДӢAҚ‘ӮөӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮНӮМӮҝӮЙҒAҒu“ъ–{•ә3җlӮЙғҚғVғA•әӮН1җlӮЕҠФӮЙҚҮӮӨҒB“ъ–{ӮЖӮМҗн‘ҲӮНҒA’PӮЙҢRҺ–“IҺU•аӮЙӮ·Ӯ¬ӮИӮўҒBҒvӮЖҢкӮиҒA“ъ–{ӮМҗн—НӮр–в‘иӮЙӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB“–ҺһӮМғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮДҒA“ъ–{ӮНғgғӢғRӮжӮиӮа—yӮ©ӮЙҺгҸ¬ӮИҢгҗiҚ‘ӮЖӮөӮ©”F’mӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҗн‘ҲӮрҺ«Ӯ№ӮҙӮйҢҲҲУӮМүәӮЙ‘ОҳIҢрҸВҒ@
ғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮӘ—Ј“ъӮөӮДӮ©Ӯз1ҸTҠФҢгӮМ6ҢҺ23“ъҒ@‘ОҳI–в‘иӮЙӮВӮўӮДҢд‘OүпӢcӮӘҠJҚГӮіӮкӮҪҒBҲЙ“ЎҒAҺRгpҒA‘еҺRҒAҸј•ыҒAҲдҸгӮМ5ҢіҳVӮЖҒAҢj‘Қ—қҒAҸ¬—СҠO‘ҠҒAҺӣ“а—Ө‘ҠҒAҺR–{ҠC‘ҠӮЖӮӘ—сҗИӮөӮҪҒBҗИҸгҢjҺс‘ҠӮНҒAҗжӮМ–ізБҲБүпӢcӮЕҢҲ’иӮөӮҪ•ыҗjӮЙҠоӮГӮ«Ҹ¬‘әҠO‘ҠӮӘӢN‘җӮөӮҪ‘ОҳI•ыҗjӮрҗа–ҫҒAҢҹ“ўӮМҢӢүКҲИүәӮМ—vҺ|ӮӘҢҲ’иӮіӮкӮҪҒB 1Ғ@ғҚғVғAӮӘ–сӮЙӮ»ӮЮӮ«–һҸBӮ©Ӯз“P•әӮөӮИӮҜӮкӮОҒAӮұӮМӢ@үпӮр—ҳ—pӮө’©‘N–в‘иӮрүрҢҲӮ·ӮйӮұӮЖ 2Ғ@ӮұӮМ–в‘иӮрҢҲ’иӮ·ӮйҸкҚҮҒAӮЬӮёҠШҚ‘ӮНӮўӮ©ӮИӮйҺ–ҸоӮӘӮ ӮлӮӨӮЖӮаҒAӮ»ӮМҲк•”ӮЕӮағҚғVғAӮЙҸч—^ӮөӮИӮўӮұӮЖ 3Ғ@–һҸBӮЙӮВӮўӮДӮНҒAғҚғVғAӮӘҠщӮЙ—DҲКӮИ—§ҸкӮЙӮ ӮйӮМӮЕ‘ҪҸӯӮМҸч•аӮНӮ Ӯи“ҫӮйӮұӮЖ 4Ғ@’k”»ӮН“ҢӢһӮЕҠJҚГӮ·ӮйӮұӮЖ –ң“пӮр”rӮөӮДӮа’©‘NӮНҸч•аӮөӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAғҚғVғAӮЖӮМҸХ“ЛӮН–ЖӮкӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸ]ӮБӮД6ҢҺ23“ъӮМҢд‘OүпӢcӮНҒAҗн‘ҲӮрҺ«Ӯ№ӮҙӮйҢҲҲУӮрҢЕӮЯӮҪ“ъӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҢӢүКӮ©ӮзҢ©ӮкӮОҒA“ъҳIҠJҗн7ғ–ҢҺ”ј‘OӮЙӮ ӮҪӮиҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЕҗн‘ҲӮрҺ«Ӯ№ӮҙӮйҢҲҲУӮрҢЕӮЯӮҪӮМӮӘҠJҗн2ғ–ҢҺ‘OҒAӮМӮҝӮМ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮӘ3ғ–ҢҺ‘OӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮНҒAғҚғVғAӮӘӮ ӮЬӮиӮЙӢӯҲшӮЕ‘ГӢҰӮМ—]’nӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖҒA4ҢҺ21“ъӮМ–ізБҲБүпӢcӮЕҲЙ“ЎҒAҺRгpӮМ—јӢҗ“ӘӮӘҢҲҲУӮрҢЕӮЯӮҪӮұӮЖҒA‘еҺRҒAҢjҒAҺӣ“аӮз—ӨҢRҸoҗgҺТӮМ• ӮӘҢҲӮЬӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕҒA“аҠtӮЖӮөӮД“қҗғ•”ӮЖӮМ–ҖҺCӮаӮИӮӯҒAҺR–{ҠC‘ҠӮрҺnӮЯӮЖӮ·ӮйҠCҢRӮМ”Ҫ‘ОҲУҢ©Ӯа‘МҗЁӮр“®Ӯ©Ӯ·ӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮЖҒAҸd‘еӮИҢд‘OүпӢcӮЙҢіҳVӮМ’nҲКӮӘҚӮӮ©ӮБӮҪӮұӮЖҒA“ҷҒXӮӘӮМӮҝӮМ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЙ”дӮЧ’Қ–ЪӮіӮкӮйӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮлӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠJҗнҢoҲЬҒ@
Ӯ№ӮБӮ©Ӯӯ“ъҗҙҗн‘ҲӮЙӮжӮБӮДӮ ӮӘӮИӮБӮҪҠШҚ‘ӮМ“Ж—§ӮӘӢәӮ©ӮіӮкҒA’©‘N”ј“ҮӮМҲА’иӮрӮаӮБӮД“ъ–{‘¶—§ӮМ•ЫҸШ’nӮЖӮ·ӮйҚ‘җҘӮӘҗNҠQӮіӮкӮйҠлҢҜӮрҠҙӮ¶ӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮНҒA–ҫҺЎ36”N(1903)7ҢҺ28“ъҒ@’“ҳIҢцҺgҢI–мҗTҲкҳYӮрӮөӮДғҚғVғAӮЙ‘ОӮөӮД–һҸB“P•әӮМ—ҡҚsҒA–һҸBҒE’©‘N”ј“ҮӮЙӮЁӮҜӮй‘ҠҢЭҢ үvӮМҸі”F“ҷӮЙӮВӮўӮДҢрҸВӮрҠJҺnӮөӮҪҒBӮұӮМҺһ“ъ–{ӮЙӮНҒu38“x•tӢЯӮЕҗЁ—НҢ—Ӯр•ӘӮҜӮжӮӨҒvӮЖӮ·ӮйҲДӮЬӮЕҸoӮҪӮЖӮўӮӨҒB“ъ–{ӮНғҚғVғAӮЖӮМ•ҙ‘ҲӮрғMғҠғMғҠӮЬӮЕ”рӮҜӮжӮӨӮЖ“w—НӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөғҚғVғAӮНҗҪҲУӮрҺҰӮіӮёҒA8ҢҺ12“ъҒ@җПӢЙ”hӮМғAғҢғLғZҒ[ғGғtҠCҢR‘еҸ«Ӯр—·ҸҮӮМӢЙ“Ң‘Қ“В(‘ҫҺз)ӮЙ”CӮ¶ӮДҒAӢЙ“ҢӮМҢRҺ–ҒAҠOҢрҒAҚsҗӯӮрҲП”CӮөӮҪҒBғҚғVғAӮМ’““ъҢцҺgғҚҒ[ғ[ғ“ӮЖҸ¬‘әҠO‘ҠӮЖӮН10ҢҺ6“ъҒ@ҠO‘ҠҠҜ“@ӮЙӮЁӮўӮДүп’kӮрҠJҺnӮөҒAҲИҚ~8“ъҒA14“ъҒA26“ъӮЖӮұӮкӮр‘ұӮҜӮҪҒBӮөӮ©Ӯө”ЮүдӮМҺе’ЈӮМҢңҠuӮН‘еӮ«Ӯӯ‘ГӢҰӮМ—]’nӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯа10ҢҺ8“ъӮНғҚғVғAӮМ–һҸB“P•ә‘жҺOҠъӮМҚЕҸIҠъҢАӮЕӮ ӮБӮҪӮӘӮ»ӮМ“P•әӮМ’ӣҢуӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒB “ъҳIҠФӮМҠлӢ@ӮӘҚҸҲкҚҸӮЖӢЯӮГӮӯ’ҶӮЕҒA–ҫҺЎ37”NӮН–ҫӮҜӮҪҒB1ҢҺ6“ъғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgӮНҸ¬‘әҠO‘ҠӮЙ‘ОӮөҒAӢҺӮй12ҢҺ21“ъҸ¬‘әӮӘ’сӢcӮөӮҪҸCҗіҲДӮЦӮМүс“ҡӮрҺиҢрӮөӮҪҒB–ҫҺЎ36”N10ҢҺ3“ъҒA12ҢҺ11“ъӮЙ‘ұӮӯ‘жҺOҺҹҲДӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМүс“ҡӮНғҚғVғAӮМҚЕҸI’сҲДӮЖӮИӮБӮҪӮӘҠШҚ‘—М“yӮЙҠЦӮ·ӮйҺе’ЈӮНҒAҲЛ‘RӮЖӮөӮД12ҢҺ11“ъҲДӮр“ҘҸPӮөӮДӮўӮҪҒB Ҹ¬‘әҠO‘ҠӮН1ҢҺ13“ъҒ@Ңд‘OүпӢcӮЙҠоӮГӮӯ“ъ–{ӮМҚЕҸIҲДӮрғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgӮЙ’КҚҗҒA“Ҝ—lӮЙҢI–мҢцҺgӮЙ‘ОӮөӮДӮаҢP“dӮөӮҪҒBғҚғVғAӮЕӮН“ъ–{ӮМҚЕҸI’сҲДӮрҺу—МӮ·ӮйӮЖҒAғAғҢғLғZҒ[ғGғtӮӘҒA“ъ–{ӮМ’сҲДӮНҢк’ІӮа“а—eӮаҸ]—ҲӮжӮиҺ©ҚӣӮкӮД‘е’_ӮЕӮ ӮйҒAӮЖӮөӮДҢрҸВ‘ЕӮҝҗШӮиӮрҺе’ЈӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮ©“ъ–{Ӯ©ӮзӮМ“В‘ЈӮЙӮаҚSӮнӮзӮёғҚғVғAӮН1ҢҺ––ӮЙӮИӮБӮДӮаүс“ҡӮМҠъҢАӮ·Ӯз–ҫҺҰӮ№ӮёҒAүБӮҰӮДӢЙ“ҢӮЕӮМҢRҺ–Қs“®ӮНӮЬӮ·ӮЬӮ·Ң°’ҳӮЖӮИӮиҒA2ҢҺ3“ъӮЙӮНғҚғVғA—·ҸҮҠН‘аӮӘҸo“®ӮөӮДҚs•ы•s–ҫӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨӢ}•сӮ·Ӯз“ьӮБӮҪҒB 2ҢҺ 4“ъ ҢЯ‘OҒ@ҠJҗнӮрҠtӢcҢҲ’иҒBҢЯҢгҒ@Ңд‘OүпӢcӮЙӮДҠtӢcҢҲ’иӮр“VҚcҢдҚЩүВҒB –ҫҺЎ“VҚcӮНүпӢcҸI—№ҢгҒuҚЎүсӮМҗнӮН’ҪӮӘҺuӮЙӮ ӮзӮёҒA‘RӮкӮЗӮаҺ–ҠщӮЙдўӮЙҺҠӮйҒA ”VӮр”@үҪӮЖӮаӮ·ӮЧӮ©ӮзӮҙӮйӮИӮиҒvӮЖҠJҗнӮрҗ[Ӯӯ—J—¶ӮіӮкӮҪҒB 2ҢҺ 5“ъ Ҳҫ–мҢцҺgӮЙ‘ОӮөҒAҒuҚ‘Ңр’fҗвҒvӮМ’КҚҗӮрғҚҠO‘ҠӮЙ’сҸoӮр“d—Я 2ҢҺ 6“ъ 1600Ғ@Ҳҫ–мҢцҺgҒA“Ж—§Қs“®ӮМҚМ—pӮЖҚ‘Ңр’fҗвӮМҢц•¶ӮрғүғҖғXғhғӢғtҠO‘ҠӮЙҺиҢр 2ҢҺ 8“ъ Ҹ¬‘әҠO‘ҠҒ@ғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgӮЙҚ‘Ңр’fҗвӮр’К’m 2ҢҺ 9“ъ ғҚғVғA ‘О“ъҗйҗн•zҚҗ(ҠҜ•сҢfҚЪ10“ъ) 2ҢҺ10“ъ “ъ–{ ‘ОҳIҗйҗн•zҚҗ Ҳҫ–мҢцҺgҲИүәҢцҺgҠЩҲхҒ@ғҚғVғAӮрҲш—gӮ° 2ҢҺ11“ъ ғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgҲИүәҚЭ“ъҢцҺgҠЩӮр•ВҚҪ ҸЖҢӣҚc‘ҫҚ@ӮНҸ—ҠҜӮрҢӯӮнӮіӮкҒAғҚҒ[ғ[ғ“•vҗlӮЙ—ЯҺ|ӮрҺ’Ӯи ҒuҚ‘Ңрүс•ңӮМ“ъҒAҚДӮС•vҗlӮМӢA—ҲӮр‘ТӮВҒvӮЖӮөӮДҒAҢдйS•КӮЙӢвҗ»ӮМүФ•rҲк‘ОӮрүәҺ’ӮіӮкӮҪҒB ғҚҒ[ғ[ғ“•vҗlӮН—ЬӮөҒAҺbӮӯӮН”q“ҡӮМҺ«ӮрҸqӮЧӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB 2ҢҺ12“ъ ғҚҒ[ғ[ғ“ҢцҺgҲИүәҒ@үЎ•lҸo”ҝӮМғtғүғ“ғX—V‘Dғ„Ғ[ғүҚҶӮЙӮДӢAҚ‘ Ғu‘Ҫ”NӮМҗe—FӮЕӮ ӮйғxғӢғMҒ[ҢцҺgӮӘҲЙ“Ў”Һ•¶ӮМҺg–ҪӮр‘СӮСӮД—Ҳ–KӮөҒA ҲЙ“ЎӮӘҢцҗEҸгҗeӮөӮӯ•КҺ«ӮрҸqӮЧӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўӮМӮНҲвҠ¶ӮЕӮ ӮйӮӘҒA‘ј“ъҚ‘ҢрӮӘүс•ңӮө ҚДӮСҚДүпӮМ“ъӮӘ—ҲӮйҺ–ӮрҗШ–]ӮөӮДӮўӮйӮЖ“`ӮҰӮҪҒB(’Ҷ—Ә) Ңмүq•әҲк‘аӮӘүдӮӘҢцҺgҠЩӮЙ“һ’…ӮөҢмүqӮрҺуӮҜӮДҗVӢҙүwӮЙҢьӮ©ӮБӮҪӮӘҒA үҲ“№ӮЙӮНӢR•ә•”‘аҗ®—сӮөҒA(“ъ–{җlӮЙӮжӮй)•ҺҗJ–”ӮН”—ҠQӮЙ‘ОӮөүдӮзӮр•ЫҢмӮөӮҪ(’Ҷ—Ә) ғvғүғbғgғzҒ[ғҖӮЙӮНҠOҢр’c‘S•”ӮМ‘јҒAӢ{’ҶӮМҚӮҠҜӢyӮС•vҗlӮӘүдӮзӮр‘ТӮҝҺуӮҜҒAңҫңзӮЙ•КҺ«ӮрҸ–Ӯ·ҒB (’Ҷ—Ә)ӮұӮкҺАӮЙ”CӢ ӮИӮй“ъ–{ӮӘҒA“GҚ‘‘г•\ҺТӮЙ‘ОӮөӮД’vӮ№Ӯй‘—•КӮМ—зӮИӮиҒv ҲИҸгӮМӮжӮӨӮЙӮөӮД–ҫҺЎ36”N8ҢҺҲИҚ~ҒA–с6ғ–ҢҺӮЙӮнӮҪӮБӮҪ“ъҳIҢрҸВӮНҗӢӮЙ•s’ІӮМ—ЎӮЙ–ӢӮр•ВӮ¶ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB –ўӮҫҸdҚHӢЖ”ӯ’BӮМҲжӮЙ’BӮөӮДӮўӮИӮў“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДғҚғVғAӮНҒAҗlҢыӮЕ–с3”{ҒAҗО’Yҗ¶ҺY—КӮЕ1ҒD6”{ҒA‘L“SҒEҚ|ҚЮӮМҗ¶ҺY—КӮЕӮНҗ”Ҹ\”{ӮЙӮа’BӮ·Ӯй‘еҚ‘ӮЕӮ ӮйҒBғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзӢЙ“ҢӮЙҺҠӮйҗўҠEҚЕ‘еӮМҚ‘“yӮр—LӮөҒA—ӨҢRӮН“–ҺһҗўҠEҚЕӢӯӮЖӮМ—_ӮкӮӘҚӮӮӯҒAҠCҢRӮа‘еҠgҸ[ӮЙ’…ҺиӮөӮДӮЁӮиҒAҚ‘—НҒAҢRҺ–—НӮМ–КӮ©ӮзӮНӮЖӮӨӮДӮў“GӮөӮӘӮҪӮўҚ‘ӮЕӮ ӮйҒB ғҚғVғAӮЙҠ®ҸҹӮЕӮ«ӮйӮұӮЖӮр—\‘zӮ·ӮйӮаӮМӮНҒA“ъ–{ӮМҗУ”CӮ Ӯй“–ӢЗҺТӮМӮИӮ©ӮЙӮНҒAӮҫӮкҲкҗlӮЖӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ2 | |
|
ҒЎ—јҚ‘ӮМҢR”хҒ@
ғҚғVғAҢRӮНҗіӢKҢRӮЖғRғTғbғNҢRӮМ“сҺнӮ©ӮзӮИӮиҒA‘SғҚғVғA—ӨҢRӮМҢ»–р‘Қ•ә—НӮН207–ңҒA—\”хҒEҢг”х–рӮрҠЬӮЯӮҪ“®ҲхүВ”\•ә—НӮрүБӮҰӮйӮЖҒA400–ңҗlӮЖӮа500–ңҗlӮЖӮаҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮҪҒB–мҗн•”‘аӮН31ҢВҢR’cӮЙ•Тҗ¬ӮіӮкҒAӮұӮМ‘јӮЙ‘_ҢӮ•ә—·’cҒA“S“№•ә—·’cҒA—vҚЗ•әҒA‘е‘ ‘еҗb—күәӮМҢмӢ«•әӮӘ‘¶ҚЭӮөҒA“–ҺһҺ©‘јӢӨӮЙҒuғҲҒ[ғҚғbғpҚЕ‘еҚЕӢӯӮМ—ӨҢRҒvӮрҢЦӮБӮДӮўӮҪҒB ‘ОӮ·ӮйүдӮӘҢRӮНҒAҠJҗнҺһӮұӮ»ӢЙ“Ң”z”хӮМғҚғVғAҢRӮМ–с2ҒD3”{ӮЙ‘Ҡ“–ӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғA—ӨҢR‘S‘МӮМ•а•ә‘е‘аҗ”ӮЕ”дҠrӮ·ӮйӮЖӢНӮ©–с9Ғ“ӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘғҚғVғAӮНҒAҠJҗнҢг–с”ј”NӮЕӮЩӮЪ“ъ–{ҢRӮЙ•C“GӮ·ӮйӢK–НӮЬӮЕӢЙ“ҢҢRӮр‘қӢӯӮөҒAҗн‘Ҳ––ҠъӮЙӮН‘S–мҗнҢRӮМ4Ҡ„ҒA‘SҢRӮМ3Ғ^7ӮрүўҸBӮ©ӮзӢЙ“ҢӮЙ“WҠJӮөӮҪҒBүўҸBӮ©ӮзӮМ‘қүҮӮНҒAғVғxғҠғA“S“№ӮМҲк•ы’КҚsӮЙӮжӮБӮД—A‘——НӮрӢӯү»ӮөҒA‘е•ә—НӮМ—A‘—Ӯрҗ¬ӮөҗӢӮ°ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{ӮӘӮЩӮЖӮсӮЗ‘S•ә—НӮр–һҸBӮЙ“Ҡ“ьӮөӮҪӮМӮЙ”ҪӮөҒAғҚғVғAӮНүўҸB•ы–КӮМҚ‘ҚЫҸоҗЁӮЖҚ‘“аҺ–Ҹо(ӮўӮнӮдӮй”Ҫ‘Мҗ§Ҡv–ҪҗЁ—Н)ӮЙӮжӮБӮД•ә—НҺg—pӮЙҗ§ҢАӮрҺуӮҜӮҪӮМӮаҺ–ҺАӮЕӮ ӮйҒB ғҚғVғA‘SҠCҢRӮН–с80–ңғgғ“ӮЖҒA“ъ–{‘Ө–с26–ңғgғ“ӮЖ”дҠrӮөӮД–с3”{ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAғҚғVғAҠН‘аӮН’nҗЁҸгҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘а(ғoғӢғgҠCҠН‘а)ҒAҚ•ҠCҠН‘аҒA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а(“Ң—mҠН‘а)ҒA— ҠCҠН‘а(ғJғXғsҠCҠН‘а)ӮИӮЗӮЙ•ӘҺUӮіӮкӮДӮЁӮиҒA— ҠCҠН‘аӮНҢОҸгҒAүНҗмӮЕӮМҚs“®ӮөӮ©ӮЕӮ«ӮёҒAҚ•ҠCҠН‘аӮағӮғ“ғgғӢҒ[ӮМ’Ҷ—§Ҹр–сӮЙӮжӮБӮДҒAғgғӢғRӮӘғ_Ғ[ғ_ғlғӢғXҠCӢ¬ӮМ’КүЯӮрӢЦҺ~Ӯ·ӮйӮМӮЕҒA‘ҫ•Ҫ—mӮЦӮМүсҚqӮНҺ–ҺАҸг•sүВ”\ӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ӯ·ӮИӮнӮҝҒAҚЭӢЙ“ҢӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮЖҒA‘қүҮүВ”\ӮИғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖӮӘ“G‘ОӮө“ҫӮйӮаӮМӮЖҚlӮҰӮзӮкӮҪҒB ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮНҒA—·ҸҮҠо’nӮрӢ’“_ӮЖӮ·ӮйӮўӮнӮдӮй—·ҸҮҠН‘аӮЖҒAғEғүғWғIғXғgғNҠо’nӮрҚӘӢ’’nӮЖӮ·ӮйғEғүғWғIҠН‘аӮЖӮЕҚ\җ¬ӮіӮкҒAҲк•”ӮӘҗmҗмҒAҸгҠCӮрӢ’“_ӮЖӮөӮДӮўӮҪҒB ғҚғVғAҠН‘аӮН‘S‘МӮЕӮНҲі“|“IӮЙүдӮӘҠН‘аӮжӮиӮа—DҗЁӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒAӢЙ“ҢӮЙҢА’иӮ·ӮйӮЖӮвӮв—тҗЁӮЕӮ ӮБӮҪҒBҠН’шӮМҢ`Һ®Ӯа‘ҪҺн‘Ҫ—lӮЕҒAҗVҢ^ҠН’шӮЖӢҢҺ®ҠНӮӘҚ¬ҚЭӮөӮДӮўӮҪҒBҢгҸqӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ‘ҪӮӯӮӘҠO—mӮЕҚмҗнӮ·Ӯйғoғүғ“ғXӮЙҢҮӮҜҒA—ы“xӮН’бӮӯҒAҺАҗнӮЙ‘ОӮ·ӮйҸҖ”хӮӘ“ъ–{ӮжӮиӮаӮНӮйӮ©ӮЙҲ«Ӯ©ӮБӮҪҒB–C’eӮаҺҝ—КӮЖӮаӮЙ“ъ–{ӮжӮиӮа—тӮиҒA–CӮМӢВҠpӮМҗ§–сӮ©ӮзҺЛ’цӮа—тӮБӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—јҢRӮМҚмҗнҚ\‘zҒ@
ҒЎғҚғVғAҢRҚмҗнҚ\‘zҒ@ ӮаӮЖӮаӮЖғҚғVғAӮМҚмҗнҢvүжӮНүўҸB•ы–КӮрҺеҠбӮЖӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӢЙ“ҢӮЙӮНӢп‘М“IӮИӮаӮМӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮН’““ъ•җҠҜ“ҷӮ©ӮзӮМҢлӮБӮҪ•сҚҗӮЖҒAҚc’йҲИүәӮМҒuңҳҠ…Ӯ·ӮкӮО“Ң•ыӮМ–ўҠJ–Ҝ‘°“ъ–{ӮНӢьҸ]Ӯ·ӮйҒvӮЖӮўӮӨ“ъ–{•МҺӢӮМҢл”»’fӮӘ‘еӮ«ӮӯүeӢҝӮөӮДӮўӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМ–ҫҺЎ34”N(1901)‘О“ъҚмҗнҢvүжӮМҠT—vӮӘҚмӮзӮкҒA–ҫҺЎ36”N(1903)ӮНӮ¶ӮЯӮД“қҲк“IӮИҚмҗнҢvүжӮӘҚф’иӮіӮкӮҪҒB ҠCҢR ғҚғVғAӢЙ“ҢҠН‘аӮН—тҗЁӮЕӮНӮ ӮйӮӘҒA—·ҸҮ—vҚЗӮӘҢ’ҚЭӮИҢАӮиҢӮ”jӮіӮкӮйӮұӮЖӮИӮЗҚlӮҰӮзӮкӮёҒA“ъ–{ҠCҢRӮМү©ҠCҗiҸoӮЖ“ъ–{—ӨҢRӮМ’©‘N”ј“ҮӮЦӮМҸг—ӨӮр‘jҺ~Ӯ·ӮйӮұӮЖӮрҺе”C–ұӮЖӮөҒA“ъ–{ӮМүҲҠЭӮМҸ”Һ{җЭӮвүҲҠЭҚqҳH(ғVҒ[ғҢҒ[ғ“)ӮрҚUҢӮӮөғpғjғbғNӮрӢNӮұӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘ—vӢҒӮіӮкӮДӮўӮҪҒBүҮҢRӮЙҢьӮ©ӮӨғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖҚҮ—¬ӮөӮД“ъ–{ҠН‘аӮрҢӮ”jӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚЕҸI“IӮИҚмҗнҢvүжӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒA•Ы‘SҺеӢ`ӮЙҠЧӮиҚs“®ӮНҸБӢЙ“IӮЖӮИӮБӮҪҒB —ӨҢR ғҚғVғAӢЙ“ҢҠН‘аӮӘ‘¶ҚЭӮ·ӮйҢАӮиҸг—Ө’n“_ӮНҠШҚ‘үҲҠЭӮЕӮ ӮлӮӨӮЖ”»’fӮөҒAӢЙ“ҢғҚғVғAҢRӮр•т“VҒA—Й—z’nӢжӮЙҸWҢӢӮөҒA—·ҸҮӮЖғEғүғWғIғXғgғNӮрҠm•ЫӮөӮВӮВғnғӢғrғ“ӮЬӮЕӮМ’nҲжӮЕ“ъ–{ҢRӮМҚUҢӮӮр’x‘ШӮіӮ№ӮВӮВ‘қүҮӮр‘ТӮҝҒA“ъ–{ҢRӮЙ‘ОӮө•ә—Н“IӮЙ—DҲКӮЙӮҪӮБӮДӮ©Ӯз–һҸBӮЙӮЁӮўӮДҚUҗЁӮЙ“]Ӯ¶ӮйӮЖӮўӮӨҚмҗнӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҒЎ“ъ–{ҢRҚмҗнҚ\‘zҒ@ ғҚғVғAҢR‘Қ•ә—НӮНүдӮМ7”{Ӯ©Ӯз10”{ӮЙӮаӮ ӮҪӮйӮӘҒAғVғxғҠғA“S“№ӮМ—A‘——КӮ©ӮзҚlӮҰӮДӢЙ“ҢӮЙ“WҠJүВ”\ӮИ•ә—НӮН25–ң“аҠOӮЕӮ ӮлӮӨӮЖ”»’fӮөҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮаӢПҚt•ә—Н(ҺАҚЫӮЙӮНӮұӮМҢ©җПӮНүЯҸ¬ӮЕҒA‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҸIҗнҺһӮМғҚғVғAҢRӮН‘SҢRӮМ3Ғ^7Ғ@–с90–ңӮЙӮаӢyӮсӮҫ)ӮрӮаӮБӮДҢрҗнӮЕӮ«ӮйӮаӮМӮЖҚlӮҰӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМҚмҗнҢvүжӮМҸd“_ӮН‘ҒҠъҢҲҗнӮЙӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮМҚЭӢЙ“Ң•ә—НӮЙ‘ҒҠъӮЙҢҲҗнӮрӢӯӮўӮДҠeҢВҢӮ”jӮөҒAҺҹӮўӮЕ‘қүҮӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮр’ҖҺҹӮЙҠeҢВҢӮ”jӮөӮДҚuҳaӮМӢ@үпӮр‘ТӮВӮұӮЖӮөӮ©—L—ҳӮИҗн‘ҲҸI––ӮМҢ©ҚһӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB 1Ғ@3ҢВҺt’cӮЕ“GӮЙҗж—§ӮҝҠШҚ‘Ӯрҗи—МҒAҗ§ҠCҢ ӮИӮ«ҸкҚҮӮН1ҢВҺt’cӮЕӢһҸйӮрҗи—МҒB 2Ғ@–һҸBӮрҺеҚмҗн’nӮЖӮөҒAӮЬӮё—Й—zӮЙҢьӮ©ӮБӮДҚмҗнӮрҺАҺ{Ӯ·ӮйҒB 3Ғ@ғEғXғҠҒ[ӮрҺxҚмҗнӮЖӮөҒA1ҢВҺt’cӮЕ“GӮрҢЎҗ§Ӯ·ӮйҒB 4Ғ@ҠCҢRӮНҒA“GҠН‘аӮМҗн”х–ўҠ®ӮЙҸжӮ¶ӮДӢ}ҸPҢӮ”jӮөҒAӢЙ“ҢӮМҗ§ҠCҢ ӮрҠl“ҫӮ·ӮйҒB ҠJҗн‘OӮЙҚмҗ¬ӮіӮкӮДӮўӮҪҚмҗнӮЕӮНҒA‘жҲкҠъӮрҠӣ—ОүНҲИ“мӮМҚмҗнҒA‘ж“сҠъӮр–һҸBҚмҗнӮЖӮөӮҪӮӘҒA‘ж“сҠъӮЙӮВӮўӮДӮНҠJҗнӮЬӮЕӢп‘М“IӮИҢvүжӮНӮИӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДӮа“–ҺһӮМ“ъ–{ӮӘҒA’©‘N”ј“ҮӮМҠm•ЫӮЖӮ·ӮйҚ‘җҘӮӘҗNҠQӮіӮкҒA’ЗӮўӢlӮЯӮзӮкӮДҠJҗнӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮҪӮЖӮўӮӨҸуӢөӮрҺfӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮжӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҗmҗмү«ҠCҗнҒ@
–ҫҺЎ37”N2ҢҺ6“ъ0900Ғ@Қs“®ӮрҠJҺnӮөӮҪүдӮӘ—ьҚҮҠН‘аӮНҒAҺе—НҠН‘аӮН—·ҸҮҚ`ӮЙҢьӮ©ӮўҒAүZҗ¶ҠOӢgҸӯҸ«ҺwҠцүәӮМ‘ж4җн‘аӮНҗmҗмӮр–ЪҺwӮөӮҪҒBүZҗ¶ҠН‘аӮМ–Ъ“IӮН—ӨҢR‘ж12Һt’cӮМҗжҢӯ‘а(2200–ј)ӮрҢмүqӮө–іҺ–ӮЙ—g—ӨӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЖҒAҗmҗмҚЭ”‘’ҶӮМғҚғVғAҸ„—mҠНҒuғҸғҠғ„Ғ[ғOҒvӮЖ–CҠНҒuғRғҢҒ[ғcҒvӮМҢӮ–ЕӮЙӮ ӮБӮҪҒB 2ҢҺ8“ъҒ@1600Ӯ·Ӯ¬ҒAүZҗ¶ҠН‘аӮӘҗmҗмҚ`ӮМ“ьҢыӮЙӮіӮөӮ©Ӯ©ӮБӮҪҺһҒAҸoҚ`ӮөӮДӮ«ӮҪҒuғRғҢҒ[ғcҒvӮЙ‘ҳӢцӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮҝӮЙҚUҢӮ‘ФҗЁӮрӮЖӮБӮҪ“ъ–{ҠН‘аӮрҢ©ӮҪҒuғRғҢҒ[ғcҒvӮНҒA–C–еӮрҠJӮ«ӮВӮВӢ}зҜҗmҗмҚ`“аӮЦ”Ҫ“]ӮөӮҪҒB“ъҳI—јҢRӮӘӮНӮ¶ӮЯӮД–CүОӮрҢрӮҰӮҪӮМӮНҺАӮЙӮұӮМӮЖӮ«ӮЕӮ ӮйҒBӢ@җжӮрҗ§ӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒA—Ӯ9“ъҺOҗЗӮМ—A‘—‘DӮ©Ӯз—ӨҢR•”‘аӮрҸг—ӨӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBүZҗ¶Һi—ЯҠҜӮНғҚҠНӮрҠЬӮЮҗmҗмҚ`“аӮМҠOҚ‘‘DӮЙҒAғҚҠНӮӘ1300ӮЬӮЕӮЙҸoҚ`Ӯ·ӮйӮұӮЖӮр—vӢҒҒAҠOҚ‘‘DӮМӢҰ—НӮр—vҗҝӮөӮҪҒBғҚғVғAҠН’шӮНҒAҗmҗмҚ`ӮН’Ҷ—§Қ`ӮҫӮ©Ӯз•ЫҢмӮөӮД—~ӮөӮўӮЖ—ҠӮсӮҫӮӘ•·Ӯ«“ьӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮвӮЮӮИӮӯғҚғVғAӮМ—јҠНӮНҒA“ъ–{ҠН‘аӮМ‘ТӮҝҺуӮҜӮйҚ`ҠOӮЦӮЖҸoҢӮӮөӮҪҒB”ЮүдӮМӢ——ЈҒ@–с7000ӮlӮЙҗЪӢЯӮөӮҪ1220ҒA–Т‘RӮЖҗ퓬ӮМүОҠWӮӘҗШӮзӮкӮҪҒB ғҚғVғA‘ӨӮаӮжӮӯҗнӮБӮҪӮӘҒAүдӮӘҸW’Ҷ–CүОӮр—ҒӮСӮДҒuғҸғҠғ„Ғ[ғNҒvӮНүОҚРӮрӢNӮұӮө(–Ҫ’Ҷ’eӮНҗ„’и11”ӯ)ҒAҠНӮМҢг•”Ӯр’ҫүәӮіӮ№ӮИӮӘӮзӮУӮҪӮҪӮСҗmҗмҚ`“аӮЙ“ҰӮ°ӢAӮБӮҪҒBҒuғRғҢҒ[ғcҒvӮаӮ»ӮкӮЙҸ]ӮўҒA—јҠНӮНҢӢӢЗ‘SҸж‘gҲхӮр‘ЮӢҺӮіӮ№ӮҪӮМӮҝӮЙҺ©’ҫҒAҸӨ‘DҒuғXғ“ғKғҠҒ[ҒvӮаҺ©’ҫӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮНҒAҲк”ӯӮМ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮйӮұӮЖӮИӮӯҠ®ҸҹӮөӮҪҒB ӮұӮМҠCҗнӮЕ“ъ–{ҢRӮНҗmҗмҚ`ӮрҺи’ҶӮЙҺыӮЯӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAҲИҚ~“Ҝ’nӮ©ӮзӮМҸг—ӨҚмҗнӮӘ—eҲХӮЖӮИӮиҒAҗнӢЗӮр—L—ҳӮЙҗiӮЯӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҚ`Ӣ}ҸPҚмҗнҒ@
2ҢҺ9“ъ0030Ғ@‘ж1Ӣм’Җ‘а(Һi—ЯҗуҲдҗіҺҹҳY‘еҚІ)ҲИүәӮМӢм’ҖҠН10җЗӮНҒA—·ҸҮҚ`ӮЙ’в”‘Ӯ·Ӯй16җЗӮ©ӮзӮИӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а‘ОӮөӢӣ—Ӣ20Ӯр”ӯҺЛҒAӮӨӮҝҺO–{ӮӘ–Ҫ’ҶҒAҗнҠНҒuғcғFғUғҢғEғBғbғ`ҒvҒuғҢғgғ”ғBғUғ“ҒvҸ„—mҠНҒuғpғӢғүҒ[ғ_ҒvӮЙ‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰӮҪҒB ӮвӮӘӮД–йӮӘ–ҫӮҜӮҪӮӘҒAғҚғVғAҠН‘аӮН–йҸPӮМҚ¬—җӮМӮЬӮЬҚ`ҠOӮЙ’в”‘ӮөӮДӮўӮҪҒB1155Ғ@—ьҚҮҠН‘аҺе—НӮНҚUҢӮӮрҠJҺnҒAғҚғVғA‘ӨӮаӮ·Ӯ®ӮіӮЬүһҗнҒAӮұӮкӮЙ—·ҸҮ—vҚЗӮМ–C‘дӮаҺQүБӮөӮД–Т—уӮИ–CҢӮҗнӮЖӮИӮБӮҪҒBүдӮӘҗнҠНҒuҺOҠ}ҒvҒu•xҺmҒvҒu•~“ҮҒvӮИӮЗӮЙӮа”н’eӮөҒAҢӢӢЗӮНҗнӢ@ӮрҲнӮ·ӮйӮаҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМүҮҢмүәӮр“®Ӯ©ӮИӮўғҚғVғAҠН‘аӮЙ”дӮЧҒA—ьҚҮҠН‘аӮМҗПӢЙүКҠёӮИҚUҢӮӮНҚЫ—§ӮБӮДӮўӮҪҒB 2ҢҺ14“ъҒ@ғXғ^ғӢғN’ҶҸ«ӮЙ‘гӮнӮБӮДғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮӘ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮЙ”C–ҪӮіӮкӮҪҒBҗ…—ӢҗнӮМҢ ҲРӮЕ—EҸ«ӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮйғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮНҒAҒu‘№ҸқӮөӮҪҢRҠНӮӘ•ңӢҢӮ·ӮйӮЬӮЕӮНҒAӢ@—Ӣ•~җЭ“ҷӮЙӮжӮиҠН‘аӮМӢӯү»ӮЖ—Й“Ң”ј“ҮӮМҗ§ҠCҢ ӮрҠl“ҫӮөҒA“ъ–{ҢRӮМҠCҸгҢр’КҳHӮрӢәӮ©ӮөҒA“ъ–{—ӨҢRӮМҸг—ӨӮр‘jҺ~Ӯ·ӮйҒv•ыҗjӮЕ—ХӮЭҒAҠН‘аӮМҺmӢCҒAҗ퓬”\—НӮМҢьҸгӮЙ“wӮЯӮҪҒB ғҚғVғAҠCҢRӮМҚмҗнӮНӮвӮБӮ©ӮўӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ҠCҢRӮЙӮжӮй—U’vҚмҗнӮаҒAӢм’ҖҠНӮЙӮжӮйҠпҸPҚUҢӮӮаҢшүКӮНӮИӮӯҒAҢҲҗнӮр”рӮҜӮйғҚғVғAҠН‘аӮН—·ҸҮ—vҚЗӮМ’…’eӢ——ЈҲИҸгӮЙҸoҢӮӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{ӮӘҢxүъ‘Мҗ§ӮрүрӮӯӮЖҸoҢӮӮөҒA“ъ–{ҠН‘аҺе—НӮрҠm”FӮ·ӮйӮЖӮ·Ӯ®—·ҸҮҚ`“аӮЙ‘Ю”рӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮӘҢ’ҚЭӮИҢАӮиҒAүдӮӘ—ӨҢRӮМ—A‘—ӮНҗвӮҰӮёҠлҢҜӮЙӮіӮзӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮМӮҪӮЯ“ъ–{ҢRӮН“GҠН‘аӮр—·ҸҮҚ`“аӮЙ••Ӯ¶ҚһӮЯӮйҚмҗнӮрҚlӮҰӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҚ`•ВҚЗҚмҗнҒ@
—·ҸҮҚ`ӮЕ‘еҢ^‘D”•ӮӘҚqҚsүВ”\ӮИӮМӮН•қ91ғҒҒ[ғgғӢӮМ•”•ӘӮЙүЯӮ¬ӮИӮўҒBӮұӮМӢ·ӮўҠCҳHӮЙҳVӢҖӮМҸӨ‘DӮр’ҫӮЯҒAҚ`ҢыӮрҚЗӮІӮӨӮЖӮўӮӨ•ВҚЗҚмҗнӮӘҠйҗ}ӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“GҠН‘аӮЖ—vҚЗ–C‘дӮМ–Ъ‘OӮЕӮМҚмҗнӮНҗ¶ҠТӮНҠъӮө“пӮӯҒAҢҲҺҖӮМҚмҗнӮрҲУ–ЎӮөӮҪҒB 2ҢҺ24“ъҒ@‘жҲкүс•ВҚЗҚмҗн(ҺwҠцҠҜ—L”n—ЗӢk’ҶҚІ)ӮӘҠёҚsӮіӮкӮҪҒBүәҺmҒA•әӮр•еҸWӮөӮҪӮЖӮұӮлҒA56–јӮЙ‘ОӮөӮҪӮҝӮЗӮұӮлӮЙ2җз—]–јӮӘүһ•еӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB‘SҸж‘gҲх77–јӮ©ӮзӮИӮй5җЗӮНҒA—Ӯ25“ъ–ў–ҫ0415ҲкӢCӮЙҚ`“аӮЦӮЖ“Л“ьӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯөҗж“ӘӮрҗiӮсӮҫҒu“V’ГҠЫҒvӮӘ–CүОӮЖ’TҸЖ“”ӮЙӮжӮБӮДҚqҳHӮрҢлӮиқҰҚАӮөӮДӮ»ӮМӮЬӮЬ”ҡ’ҫҒAҒu•җҸFҠЫҒvӮНҚqҚs•s”\ӮЖӮИӮи—\’иҲК’uӮЙҚsӮ«’…Ӯ©Ӯё”ҡ’ҫҒAӮ»ӮкӮрҢ©ӮҪҒu•җ—zҠЫҒvӮН—\’иҲК’uӮрҢл”FӮөӮДҺё”sҒA–ТүОӮрӮВӮўӮДӮЩӮЪ—\’иҲК’uӮЬӮЕ’BӮөӮҪӮМӮНҒu•сҚ‘ҠЫҒvҒuҗmҗмҠЫҒvӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМҢӢүКӮр•sҸ\•ӘӮЖӮЭӮҪ—ьҚҮҠН‘аҺi—Я•”ӮЕӮН’јӮҝӮЙ‘ж“сҺҹҚмҗнҺАҺ{ӮрҢҲҲУҒA3ҢҺ27“ъ–й”јӮЙҺАҺ{ӮіӮкӮҪҒBҺwҠцҠҜӮН‘OүсӮЖ“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҸж‘gҲхӮНҚД“xӮМҺQүБӮНӢ–ӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB 3ҢҺ27“ъҒ@0300Ғ@‘D‘аӮН—·ҸҮҚ`“аӮЙ“ЛҗiӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөғҚғVғA‘ӨӮМҢxүъӮН‘OӮЙӮа‘қӮөӮДҢөҸdӮЕҒAҚЎүсӮаҠ®‘SӮИ••ҚҪӮЙӮНҺҠӮзӮёҚмҗнӮНҺё”sӮөӮҪҒBӮұӮМҚмҗнӮЕ•ҹҲдҠЫҺwҠцҠҜҒEҚLҗЈ•җ•vҸӯҚІӮНҒA•ҹҲдҠЫӮр”ҡ’ҫӮөӮҪӮЖӮ«ҸжҲхӮрғ{Ғ[ғgӮЙҲЪҸжӮіӮ№“_ҢДӮрӮЖӮБӮҪӮЖӮұӮлҒAҺwҠцҠҜ•tӮМҗҷ–м‘·ҺөҸг“ҷ•ә‘ӮӮӘҢ©“–ӮҪӮзӮёҒA’ҫӮЭӮдӮӯ‘D“аӮЕҺ©ӮзҺO“xӮЙӮнӮҪӮи‘D“аӮр‘{ҚхҒAҗӢӮЙ”ӯҢ©ӮЕӮ«ӮёҺ~ӮЮ–іӮӯғ{Ғ[ғgӮЙҸжӮиҲЪӮлӮӨӮЖӮөӮҪӮЖӮұӮлҒA“GҠНӮМ–ТҺЛӮрҺуӮҜ‘s—уӮИӮйҗнҺҖӮрҗӢӮ°ӮҪҒBҗ¶‘OӮМҢчҗСӮЖҚҮӮнӮ№ӮД’ҶҚІӮЙҸёҗiҒAҢRҗ_ӮЖӮөӮДжҗӮнӮкӮҪҒB Ӯ»ӮМҢгҒA5ҢҺ3“ъӮЙ‘жҺOҺҹ•ВҚЗҚмҗн(ҺwҠцҠҜ—СҺOҺq—Y’ҶҚІ)ӮӘҠйҗ}ӮіӮкӮҪӮӘҒA–\•—үJӮМӮҪӮЯ‘№ҠQӮӘ‘еӮ«ӮӯҚмҗнӮ»ӮМӮаӮМӮаҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪҒBҢӢүКӮНҸжҲх158–ј’ҶҒAҺы—eӮіӮкӮҪӮМӮН67–ј(“а20–ј•үҸқ5–јҗнҺҖ)ҒA•Я—ё17–јҒAҚs•ы•s–ҫ74–јӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮД—·ҸҮҚ`•ВҚЗҚмҗнӮНҗ¬ҢчӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒA“ъ–{ҢRӮМҢҲҺҖӮМҠё“¬җёҗ_ӮНғҚғVғAҠН‘аӮрҲі“|ҒAҠН‘аҸ«ҺmӮМҺmӢCӮНҚӮӮЬӮБӮҪҒBғҚғVғA‘ӨӮНӮЬӮ·ӮЬӮ·—·ҸҮҚ`“аӮЙҲшӮ«ҳUӮйӮұӮЖӮЖӮИӮиҒAү©ҠCӮМҗ§ҠCҢ ӮНӮЩӮЖӮсӮЗ“ъ–{ҢRӮМҸ¶’ҶӮЙӢAӮөӮҪҒBӮИӮЁӮұӮкӮЙӮНҒA—EҸ«ғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮМҗнҺҖӮа“ӯӮўӮҪҒB4ҢҺ13“ъғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮНҠшҠНӮЕӮ ӮйҗнҠНҒuғyғgғҚғpғEғҚғXғNҒvӮЙҸжӮиҒAүдӮӘ‘ж3җн‘аӮЦӮМ’ЗҢӮҗнӮМ“r’ҶӮЕ”Ҫ“]ӮөӮҪӮЖӮұӮлҗG—ӢӮөӮД”ҡ’ҫҒA•”үә650–јӮЖӢӨӮЙҗнҺҖӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгӮрҸPӮБӮҪғEғBғgғQғtғgҸӯҸ«ӮНҠН‘аӮМ•Ы‘SӮр‘жҲкӮЖӮөҒAҲИҚ~ӮМҚUҗЁӮНҸ„—mҠНӮЖҗ…—Ӣҗн‘аӮЙӮжӮйҲР—Н’гҺ@ӮЙҢА’иӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB ҚLҗЈҸӯҚІӮМ—EҗнӮНҠCҢRҢRҗlӮМӢTҠУӮЖӮИӮиҒAӮ»ӮМҢгӮМҠCҢRӮрҺxӮҰӮйҗёҗ_“IҺx’ҢӮЖӮИӮБӮҪӮұӮЖӮМҲУӢ`ӮНӢЙӮЯӮД‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪҒB‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй“БҺкҗцҚq’шӮЙӮжӮйҗ^ҺмҳpҠпҸPҚUҢӮҒAӮіӮзӮЙӮНҠCҸг“БҚUӮМҗёҗ_ӮНҒA–ҫҺЎҠCҢRӮЙӮЁӮўӮДӮ»ӮМҗж—бӮрҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠӣ—ОҚ]үпҗнҒ@
ҠCҢRӮМҠҲ–фӮЙӮжӮБӮДғҚғVғAҠCҢRӮМӢәҲРӮНӮИӮӯӮИӮиҒA—ӨҢRӮМ’©‘N“WҠJӮН—eҲХӮЖӮИӮБӮҪҒB ‘ж12Һt’c(ҲдҸгҢх’ҶҸ«)ӮН2ҢҺ16“ъҗmҗмӮЙҸг—ӨӮөӮД–kҸгӮрҠJҺnҒAҚ•–ШҲЧъй‘еҸ«ҺwҠцӮМ‘жҲкҢR(ӢЯүqҒA‘ж2Һt’cҠоҠІ)ӮНҒA3ҢҺ11“ъ’Б“мүYӮЙҸг—ӨӮөӮҪҒBӮұӮМ‘жҲкҢRҺе—НӮНҒA4ҢҺ29“ъӮЙӮН‘ҒӮӯӮаҠӣ—ОҚ]“nүНҚмҗнӮрҠJҺnӮөӮҪҒB ғҚғVғAҢRӮМҠӣ—ОҚ]–kҠЭӮМ–hүqӮНғUғXғҠҒ[ғ`’ҶҸ«ҺwҠцӮМ“Ң•”Һx‘аӮЕҒAҲА“Ң’nӢжӮЖӢгҳAҸй’nӢжӮЙ–hҢдҗнӮр•~ӮўӮДӮўӮҪҒBғҚғVғAҢRӮЙӮЖӮБӮДҺзӮйӮЙӮН—L—ҳӮИ’nҢ`ӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮЁ‘e––ӮИҡНҚҲӮӘ9ҢВ’Ҷ‘а•ӘҗЭӮҜӮзӮкӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮЕҒA–C•әӮН•а•әӮЖ“ҜҲкҗьҸгӮМӮЮӮ«ӮҫӮөӮМҗw’nӮЙ”z’uӮіӮкӢU‘•ӮаҢр’КҚҲӮаҸҖ”хӮіӮкӮёҒA•”‘аҠФӮМҳA—ҚӮаҸ[•ӘӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙғҚғVғAҢRӮМ–hҢдҸҖ”хӮЙ‘еӮ«ӮИҢҮҠЧӮӘӮ ӮБӮҪҸгӮЙҒA’гҺ@ӮӘҸ[•ӘӮЙӮЁӮұӮИӮнӮкӮёҒAғUғXғҠҒ[ғ`’ҶҸ«ӮН“ъ–{ҢRӮМҺеҚUҢӮӮНҲА“Ң’nӢжӮЙүБӮҰӮзӮкӮйӮаӮМӮЖҢл”»’fӮөҒAӢгҳAҸйӮЦӮМ‘қүҮӮр‘УӮБӮҪҒB “ъ–{ҢRӮНүE—ғӮМ‘ж12Һt’cӮр“nүНӮіӮ№ҒAиНүНҸг—¬Ӯ©Ӯз•пҲНӮіӮ№ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA‘ж2Һt’cҒAӢЯүqҺt’cӮЕӢгҳAҸйҗw’nӮрҚUҢӮӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒBӢгҳAҸй•tӢЯӮЕӮН“ъ–{ҢRӮН•ә—НӮЕ5”{ҒA–C•әӮЕ3”{ӮМ—DҗЁӮрҺқӮВӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB‘ОҠЭӮМ“GҸо‘{ҚхӮМӮЩӮ©“nүН“_ӮМ’ІҚёҒA–мҗнҸd–CӮМҗ„җiҒAҚH•әӮЙӮжӮйүЛӢҙҒAҠCҢRӮМ–CҠНӮМҗiҸoӮИӮЗӮМҸҖ”хӮМӮМӮҝҒA5ҢҺ1“ъ•ҘӢЕ3ҢВҺt’cӮН–C•әӮМүҮҢмҺЛҢӮӮМүәӮЙҲкҗДӮЙҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМ–м–CӮНӮЮӮ«ӮҫӮөӮМғҚғVғAҢR–C•әӮрҲі“|ӮөҒA‘ж3ҠН‘аӮМ–CҠНӮЙӮжӮйҠН–CҺЛҢӮӮаҺи“`ӮБӮДҒA1400Қ ӮЙӮНӢгҳAҸйҗј•ыҚӮ’nӮрҠm•ЫҒA2000ӮЬӮЕӮЙӮНӢгҳAҸйҗw’nӮрҗи—МӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮНӮнӮёӮ©1“ъӮЕҚў“пӮИ“nүНҚмҗнӮрҚsӮБӮҪҸгӮЙҚ‘Ӣ«ӮМ“GҗwӮр“Л”jӮөӮД–һҸBӮЙӢҙ“ӘҡЖӮрҠm—§ӮөӮҪҒB –{үпҗнӮН“ъҳI—ӨҗнӮМ–{Ҡi“IҸҸҗнӮЕӮ ӮиҒAҺmӢCҒA—ы“xӮЙҸҹӮиҒAҺь“һӮИҸҖ”хӮЖ–C•ә—НӮӘ—DҗЁӮИ“ъ–{ҢRӮӘүхҸҹӮөӮҪҒBҸҸҗнӮМҸҹ—ҳӮЙӮжӮБӮДҢRӢyӮСҚ‘–ҜӮМҺmӢCӮНҚӮ—gӮөҒAҗ§ҠCҢ ӮМҠm•ЫӮЖ‘ҠҳЦӮБӮДҺўҢгӮМ“м–һҸBҚмҗнӮӘ—L—ҳӮЙ“WҠJӮіӮкӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—Й—zӮЙҢьӮ©ӮӨ‘OҗiҚмҗнҒ@
‘ж1ҢRӮӘҸҮ’ІӮЙ’©‘N”ј“ҮӮр–kҸгӮөӮДҠӣ—ОҚ]“nүНӮМҺһҠъӮӘӢЯӮГӮӯӮЖӮЖӮаӮЙҒAҢЎҗ§ҢшүКӮрҺыӮЯӮйӮжӮӨ“ҜҺһҠъӮЙ—Й“Ң”ј“ҮӮЙҸг—ӨӮіӮ№ӮйӮҪӮЯҒA‘ж2ҢRӮӘ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪҒB—јҢRҢДүһӮөӮД“GӮр•пҲНҹr–ЕӮіӮ№ӮжӮӨӮЖҢvүжӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ү©ҠCӮМҗ§ҠCҢ Ҡm•ЫӮЙ”әӮўҒA‘ж2ҢRӮН—\’иӮр•ПҚXӮөӮД5ҢҺ5“ъӮ©Ӯз—Й“Ң”ј“ҮӮМ‘еҚ№үНүНҢы•tӢЯӮЙҸг—ӨӮөӮҪҒB“GҸ«ғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮН‘ж2ҢRӮМҸг—ӨӮр‘jҺ~Ӯ·ӮйӮжӮӨӮЙ–ҪӮ¶ӮҪӮӘҒAӮұӮМ–Ҫ—ЯӮНҺАҚsӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB—\”х•ә—НӮрҠЬӮЯӮйӮЖ9ҢВҺt’cӮаӮМ‘еҢRӮр“ъ–{ҢRӮӘҸг—ӨӮіӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨҺ–‘ФӮрҢ}ӮҰӮДҒA–WҠQӮМ•”‘аӮН“r’ҶӮ©ӮзҲшӮ«•ФӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB—g—ӨӮН5ҢҺ13“ъӮЬӮЕӮЙҸIӮнӮиҒA•әвӢ•”‘аӮМ—g—ӨҢгӮН‘ФҗЁӮрҗ®ӮҰӮД5ҢҺ16“ъӮЙӮН‘ж4Һt’cӮрӮаӮБӮДӢаҸBӮЖ—Й—zӮЖӮМҺХ’fӮЙҗ¬ҢчҒA5ҢҺ23“ъҒ@3ҢВҺt’cӮр•№—сӮөӮД“мҺRӮМҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“мҺRүпҗнҒ@
“мҺRҚU—ӘӮЙӮН“сӮВӮМҗнҸp“IҢшүКӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮё—Й“Ң”ј“ҮӮМҗж’[ӮЙ—·ҸҮ—vҚЗӮӘӮ ӮиҒA“мҺRӮрҚU—ӘӮөӮДҺХ’fӮөӮДӮөӮЬӮҰӮО—·ҸҮӮНҢЗ—§Ӯ·ӮйҒBӮіӮзӮЙ“мҺRҒE—·ҸҮӮрӮЁӮіӮ№ӮДӮөӮЬӮҰӮОҒAҢҲҗн’n“_ӮЖ—\‘zӮіӮкӮй—Й—zӮЦӮМ–kҗiӮЙ”wҢгӮрӢәӮ©ӮіӮкӮйҗS”zӮНӮИӮӯӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ‘ж1Һt’cӮӘҗі–КҒA‘ж3Һt’cӮӘҚ¶—ғҒA‘ж4Һt’cӮӘүE—ғ(“ҜҺt’cӮМ”ј•ӘӮНӢаҸBҸйҚUҢӮ)ӮЖӮўӮӨ•zҗwӮЕҒAӮЬӮё–C•ә‘аӮМҚUҢӮӮ©ӮзҠJҺnҒA–CҢӮӮМӮ ӮЖӮН•а•әӮМ“ЛҢӮӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөүдӮӘ–C•әӮЙӮНҸdүОҠнӮӘ•s‘«ӮөӮДӮЁӮиҒAҢшүК•sҸ\•ӘӮМӮЬӮЬ•а•әӮМ“ЛҢӮӮЖӮИӮБӮҪҒBүБӮҰӮДғҚғVғAҢRӮМ‘O–КӮН•Ҫ’R’nӮЕҗgӮрүBӮ·ӮЖӮұӮлӮНӮИӮўҒB“ЛҢӮӮ·Ӯй•а•әӮНӮіӮИӮӘӮз•W“IӮМӮжӮӨӮЙғoғ^ғoғ^ӮЖ“|ӮкӮҪҒBүҶҠWӢ@ҠЦҸeӮр—LӮ·ӮйҢҳҢЕӮИҗw’nӮЖ—·ҸҮӮ©ӮзҸoҢӮӮөӮҪғҚғVғAҠН‘аӮМҠН–CҺЛҢӮӮЙӮжӮиҒA‘ж2ҢRӮНӢкӢ«ӮЙҠЧӮБӮҪҒBӮҪӮЖӮҰӮО‘ж1Һt’cӮМ‘ж1—ь‘аӮЕӮНҒAҳA‘а’·Ҹ¬ҢҙҗіҚP‘еҚІҺ©Ӯз“ЛҢӮ‘аӮр—ҰӮўӮД“ЛҗiҒAҸdҸқӮр•үӮБӮҪӮЩӮЗӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҸуӢөӮЙ‘ОӮөүдӮӘ—ьҚҮҠН‘аӮНҒAҒuҗФҸйҒvҲИүә4җЗӮМҢRҠНӮЖ2җЗӮМҗ…—Ӣ’шӮӘӢаҸBҳpӮЙӮНӮўӮиҒAҠН–CӮЙӮжӮйҺxүҮҚUҢӮӮрҺАҺ{ҒAүңҢRҺi—ЯҠҜӮМӢӯҢЕӮИҲУҺuӮЙӮжӮиҒA‘S–ЕҠoҢеӮМ—[ҚҸ“ЛҢӮӮаҗ¬ҢчҒA1830‘ж4Һt’cӮМҲк•”ӮӘ“GҗwӮр“Л”jӮөӮДҲкҠpӮрҗи—МҒA1930Қ ӮЙӮНғҚғVғAҢRӮН—·ҸҮ•ы–КӮЦ”s‘–ҒAӮжӮӨӮвӮӯӮұӮкӮрҗи—МӮөӮҪҒB ғҚғVғAҢRӮМҗі–КӮнӮёӮ©300ғҒҒ[ғgғӢӮр2ҢВҺt’c”јӮМ•ә—НӮЕҚUҢӮӮөӮД14ҺһҠФӮ©Ӯ©ӮиҒAҺҖҸқҺТӮН4400–јӮЙӮаӢyӮсӮҫҒBӮұӮМ“мҺRӮМҚмҗнӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЖӮН‘SӮӯҲЩӮИӮйҗVӮөӮўҗ퓬ҒAӮұӮЖӮЙӮұӮМҢгӮМ—·ҸҮҚUҲНҗнӮрҺҰҚҙӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘҺc”OӮИӮұӮЖӮЙ“ъ–{ҢRӮНӮұӮМӢіҢPӮМҠҲ—pӮӘҸ\•ӘӮЖӮНӮўӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—Й—zӮЦӮМ‘OҗiҒ@
ғҚғVғAҢRӮН’xӮЬӮ«ӮИӮӘӮзҸ¬”ҪҢӮӮЙ“]Ӯ¶ӮҪҒBғVғxғҠғA‘ж1ҢR’c(ғVғ^ғPғҠғxғӢғO’ҶҸ«)ӮН—·ҸҮӮЙҢьӮ©ӮӨ“ъ–{ҢRӮМ“®Ӯ«ӮрҢЎҗ§Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЙ“мүәӮөҒA“ҫ—ҳҺӣӮЙ•zҗwӮөӮҪӮӘҒA6ҢҺ14ҒA15“ъҒ@‘ж2ҢRӮМҗжҗ§ҚUҢӮӮрҺуӮҜӮД”s‘ЮӮөӮҪҒBӮЬӮҪ“Ң•”•ә’c(ғUғXғҠғbғ`’ҶҸ«ӮМӮҝғPғӢғҢғӢ’ҶҸ«)Ӯа‘ж1ҢRҒA‘ж10Һt’cӮМҗі–КӮЙҢЎҗ§ҚUҢӮӮрҺҺӮЭӮҪӮӘҢӮ‘ЮӮіӮкӮҪҒB ғҚғVғAҢRӮМ•s“O’кӮИҸ¬”ҪҢӮӮН”s‘ЮӮрҢJӮи•ФӮ·ӮҫӮҜӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮД8ҢҺҸгҸ{ҒA“ъ–{ҢRӮН3•ы–КӮжӮи—Й—zӮр•пҲНӮ·ӮйҢ`ӮЖӮИӮБӮҪҒBҲк•ығҚғVғAҢRӮН”s‘ЮӮр‘ұӮҜӮҪӮЖӮНӮўӮҰ‘ЮӢpӮНҠTӮЛҢvүж“IӮЙҺАҺ{ӮіӮкҒA“ъ–{ҢRӮЙҸҹӮй‘еҢRӮр—Й—zӮЙҸWҢӢӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ3 | |
|
ҒЎү©ҠCҠCҗнҒ@
—·ҸҮӮМғҚғVғAҠН‘аӮНҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМ‘¶ҚЭӮЖӮЖӮаӮЙҠН‘а•Ы‘SӮрҗ}ӮиҒA—ҲӮйӮЧӮ«ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“Ң—mүсҚqӮр‘ТӮБӮДҲкӢ“ӮЙ“ъ–{ҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚмҗнӮМҠо–{ӮЖӮіӮкӮДӮўӮҪҒB җўҠE“IҗнҸpүЖӮЕӮ Ӯи—EҸ«ӮЕ’mӮзӮкӮҪғ}ғJғҚғt’ҶҸ«ӮЙӮжӮБӮДҲкҺһҒAҚUҗЁӮЙ“]Ӯ¶ӮҪҺһҠъӮаӮ ӮБӮҪӮӘҒAҢг”CӮМғEғCғgғQғtғgҸӯҸ«(—ХҺһҺi—Я’·ҠҜ)ӮНҸБӢЙҗн–@ӮрҚМ—pҒA“ъ–{ҠН‘аӮЖӮМҢҲҗнӮр”рӮҜӮДӮўӮҪҒBӢЙ“Ң‘Қ“ВғAғҢғNғZҒ[ғGғtӮНҒA—·ҸҮ—vҚЗӮӘӮўӮёӮкӮНҠЧ—ҺӮ·ӮйӮаӮМӮЖӮЭӮДӮЁӮиҒAҠН‘аӮМҸ«—ҲӮМӮҪӮЯӮЙ‘ҒҠъӮЙғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ’EҸoӮ·ӮйӮжӮӨҢө–ҪӮөӮҪҒB 8ҢҺ10“ъ0540Ғ@Ҹ„—mҠНҒuғmҒ[ғEғBғNҒvӮрҗж“ӘӮЙҒAҗнҠН6ҒAҸ„—mҠН4ӮрҠоҠІӮЖӮ·Ӯй—·ҸҮҠН‘аӮНҸoҚ`ҒAғEғүғWғIҠН‘аӮЦӮМҚҮ—¬Ӯрҗ}ӮБӮҪҒB “ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮНҒAӮұӮМ—·ҸҮҠН‘аӮр—mҸгӮЙ—U’vӮөӮДҢӮ”jӮөӮжӮӨӮЖ“GҠН‘а”ӯҢ©Ӯ©Ӯз4ҺһҠФ”јҢгӮЙ“GӮЙ’ЗӮўӮВӮ«ҒA1315ҺЛҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBүдӮӘҠН‘аӮН“GӮМҗж“ӘӮр—}ӮҰӮжӮӨӮЖ–k“ҢӮЙҗiҳHӮрӮЖӮиҒAҲк•ыӮМғҚғVғAҠН‘аӮН“ъ–{ҢRӮМҢг•ыӮ©Ӯз“Щ‘–Ӯрҗ}ӮБӮҪҒBғEғCғgғQғtғgҸӯҸ«ӮЙӮН“ъ–{ҠН‘аӮрҢӮ”jӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйҲУҺuӮН‘SӮӯӮИӮӯҒAӮҪӮҫҚc’й–Ҫ—ЯӮЙ“YӮБӮДғEғүғWғIғXғgғbғNүсҚqӮМҲк”OӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB’ЗҢӮӮ©Ӯз–с3ҺһҠФҒAӢ——Ј7000ӮlӮЖӮИӮБӮҪ1837Ғ@ҺЛ’eҲк”ӯӮӘҠшҠНҒuғcғGғUғҢғEғBғbғ`ҒvӮМҠНӢҙӮЙ–Ҫ’ҶҒAғEғCғgғQғtғgҸӯҸ«ҲИүә–Ӣ—»ӮНҗнҺҖҒAӮіӮзӮЙӢ@ҠЦҲхӮа“|ӮкӮҪӮҪӮЯҚ¶җщүсӮрҺnӮЯҒA—·ҸҮҠН‘аӮМ‘а—сӮН‘еҚ¬—җӮЖӮИӮБӮҪҒBҺе—НӮНҚДӮС—·ҸҮӮЦӮЖ“ҰӮ°ӢAӮи—ьҚҮҠН‘аӮН•пҲН‘ФҗЁӮрӮЖӮБӮҪӮӘҒA“ъ–vӮрҢ}ӮҰҒA“GҠН‘аӮНҺl•ӘҢЬ—фӮЖӮИӮБӮДҺlҺUӮөӮҪҒB 2000Ғ@“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮН–CҢӮӮр‘ЕӮҝҗШӮиҒAҗ…—Ӣҗн‘аӮЙ–йҸPӮр–ҪӮ¶“Щ‘–ӮөӮҪ“GҠН‘аӮМ‘{ҚхӮрҠJҺnӮөӮҪӮӘҒAӮЖӮаӮЙҗнүКӮрӢ“Ӯ°ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB ғҚғVғAҠН‘а’ҶҒA—·ҸҮҚ`ӮЬӮЕ–ЯӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮМӮНҒA5җЗӮМҗнҠНӮЖ1җЗӮМҸ„—mҠНӮҫӮҜӮЕҒA‘№ҸқӮӘҢғӮөӮўҠшҠНҒuғcғGғUғҢғEғBғbғ`ҒvӮНдPҸBҳpӮЕ•җ‘•үрҸңӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМ‘јҸ„—mҠН2җЗӮНҸгҠCӮЖғTғCғSғ“ӮЕ•җ‘•үрҸңӮіӮкҒA1җЗӮНҠ’‘ҫӮЬӮЕ—ҺӮҝү„ӮСӮ»ӮМҸкӮЕҚАҸКӮөӮҪҒBҢӢӢЗҒA—·ҸҮҠН‘аӮН1җЗӮа–Ъ“I’nғEғүғWғIӮЙ’BӮөӮҪӮаӮМӮНӮИӮӯҒAҺcӮйҠН‘аӮаӮіӮсӮҙӮсӮИ–ЪӮЙӮ ӮўҒAғҚғVғAӮМҚмҗнҢvүжӮНҚБҗЬӮөӮҪҒB “ъ–{ҠН‘аӮаҸӯӮИӮ©ӮзӮё”нҠQӮр”нӮБӮҪӮаӮМӮМҒAҗнҺҖ64–јҒAҗнҸқ161–јӮЙ—ҜӮЬӮБӮҪҒBӮұӮМү©ҠCҠCҗнӮНҒAӮМӮҝӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮМ‘OӮЙӮЖӮ©ӮӯҢyӮсӮ¶ӮзӮкӮӘӮҝӮЕӮНӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМҠCҗнӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҠН‘аӮНҺ–ҺАҸгҗн—НӮр‘rҺёӮөҒAҗ§ҠCҢ ӮрҲ¬ӮБӮҪӮнӮҜӮЕҒAӮ»ӮМҲУӢ`ӮНҢҲӮөӮДҸ¬ӮіӮИӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҒB“ҢӢҪ’·ҠҜӮӘҠъӮөӮҪҒu“GҢӮ–ЕҒvӮМҗнүКӮНӢyӮОӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮМӮЖӮ«—pӮўӮҪҒu’ҡҺҡҗн–@ҒvӮвҒu“G‘OҲкҗДүс“ӘҒvӮНҒAӮМӮҝӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЙҗ¶Ӯ©ӮіӮкӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүUҺRү«ҠCҗнҒ@
җ_ҸoӢS–vӮИғEғүғWғIҠН‘аӮЙ”YӮЬӮіӮкӮДӮўӮҪҸг‘әҠН‘аӮНҒA8ҢҺ10“ъҲИҚ~‘О”n•tӢЯӮЙӮ ӮБӮД“GҠН‘аӮМҢxүъӮЙӮ ӮҪӮБӮДӮўӮҪҒB ү©ҠCҠCҗнӮМ4“ъҢгҒA8ҢҺ14“ъ‘Ғ’©Ғ@ғCғGғXғZғ“ҸӯҸ«—ҰӮўӮйғEғүғWғIҠН‘аӮМҸ„—mҠН3җЗӮр”ӯҢ©ҒAүдӮӘ‘ж“сҗн‘аӮМҸ„—mҠН4җЗӮЖӮМҠФӮЙӮҪӮҫӮҝӮЙ–CҗнӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪҒBҸг‘әҠН‘аӮМҚUҢӮӮНҢғӮөӮӯҢрҗн30•ӘӮЕғҚғVғAҠН‘аӮН”н’eүҠҸгӮөҒA“БӮЙҒuғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒvӮН‘Җ‘ЗӢ@ӮӘҢМҸбҒAӮнӮӘҸW’Ҷ–CүОӮр—ҒӮСӮҪҒBҠшҠНҒuғҚғVғAҒvӮЖҒuғOғҚғҖғ{ғCҒvӮНҒA”н’eӮөӮҪӮӘӢ@ҠЦӮН–іҺ–ӮЕғEғүғWғIӮЙ“Ұ‘–ӮөӮҪҒBӮнӮӘ4ҠНӮа‘S—НӮЕ’ЗҢӮӮөӮҪӮӘҒAҢрҗн5ҺһҠФҢгҒAҠшҠНҒuҸoү_ҒvӮМ’e–тҢҮ–RӮЙӮжӮБӮДҠCҗнӮН–ӢӮр•ВӮ¶ӮҪҒB ҺcӮйҒuғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒvӮЙ‘ОӮөӮДҸг‘ә’·ҠҜӮНҒA—ҲүҮӮөӮДӮ«ӮҪҒuҳQ‘¬ҒvҒuҚӮҗз•дҒvӮЙҸҲ•ӘӮр”CӮ№ӮҪӮӘҒA“ҜҺһӮЙҒu“MӮкӮй“G•әӮрӢ~Ҹ•Ӯ№ӮжҒvӮЖ–Ҫ—ЯҒA“–ҺһғEғүғWғIҠН‘аӮр‘һҲ«ӮөӮДӮўӮҪүдӮӘҸ«•әӮЙҲЩ—lӮМҠҙӮр•шӮ©Ӯ№ӮИӮӘӮзӮаҸжҲх600—]–јӮӘӢ~Ҹ•ӮіӮкӮҪҒB ҠшҠНҒuғҚғVғAҒvӮЖҒuғOғҚғҖғ{ғCҒvӮНҒAҺg—pүВ”\ӮИҺе–CӮН3–еӮМӮЭӮЖӮИӮиҒAҗ퓬—НӮр‘rҺёҒAӮУӮҪӮҪӮСҸoҢӮӮ·Ӯй—НӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBғҚғVғAҠН‘а3җЗӮЙ‘ОӮө“ъ–{ҠН‘аӮН4җЗҒAӮ»ӮкӮдӮҰғҚғVғAӮНҠо–{“IӮЙ“Ұ‘–ӮрҠйҗ}Ӯ·ӮйӮаҒAҗ퓬ӢЗ–КӮЙӮЁӮўӮДӮНӢЙӮЯӮД—EҠёӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЮӮөӮлҸг‘әҠН‘аӮМҗнҸpҺwҠцӮНҗTҸdӮЕҒAҸҹӢ@ӮрҲнӮ·ӮйҸк–КӮ·ӮзҢ©ӮзӮкӮҪӮӘҚЕҸI“IӮЙӮН“GҠН1ӮрҢӮ’ҫҒA2җЗӮЙ‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰҒA“ъ–{ҠН‘аӮЙ’ҫ–vҠНӮНӮИӮӯҸҹ—ҳӮМҠCҗнӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ү©ҠCҠCҗнӮЖҒA‘ұӮӯӮұӮМүUҺRү«ҠCҗнӮЙӮжӮБӮДҒAғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮНҺАҺҝ“IӮЙ–і—Нү»ӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—Й—zүпҗнҒ@
“ъ–{ҢRӮН8ҢҺҸүӮЯ—Й—zүпҗнӮМҸҖ”х‘ФҗЁӮЙӮВӮўӮҪӮӘҒA—Й—z•tӢЯӮЙҸW’ҶӮөӮДӮўӮйғҚғVғAҢRӮНҠщӮЙүдӮМ1”{”јӮЙӢЯӮӯҒAӮіӮзӮЙ‘қүҮӮӘҲшӮ«‘ұӮ«“һ’…’ҶӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр’mӮиҒA‘¬ӮвӮ©ӮЙүпҗнӮМ‘ФҗЁӮЙӮӨӮВӮйӮұӮЖӮЖӮЖӮаӮЙҒAҢг‘ұ•”‘аӮМ“һ’…ӮЖӮаӮЙ‘SҢRӮрӢ“Ӯ°ӮДӮМҢҲҗнӮрҠJҺnӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒBҚмҗнҢvүжӮНҒA‘ж4ҢRҒA‘ж2ҢRӮЕҠCҸйҒ`—Й—z“№ӮЙүҲӮўҚUҢӮӮөҒA‘ж1ҢRҺе—НӮН‘ҫҺqүНүEҠЭӮЙ“nӮБӮД“GӮМ“Ң—ғӮр•пҲНӮ·ӮйҢvүжӮЕӮ ӮйҒBғҚғVғAҢRӮаҒAӢЯ“ъ’ҶӮЙ‘қүҮӮӘ“һ’…Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕҒA“–ҸүӮМ—\’иӮр•ПҚXҒA8ҢҺ21“ъҒ@ҳQҺqҺRҒ`ҲЖҺRвӢӮМҗьӮЕҢҲҗнӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒB ҚӢүJӮӘ‘ұӮўӮҪӮҪӮЯ‘OҗiҠJҺnӮӘ’xӮкӮДӮўӮҪ‘ж1ҢRӮН8ҢҺ23“ъ—[Ӯ©ӮзҚs“®ӮрҠJҺnҒAғҚғVғA“Ң•”•ә’cӮрҚUҢӮӮөӮҪҒBҢғҗнӮМӮМӮҝ26“ъӮЬӮЕӮЙ‘ж12Һt’cҒA‘ж2Һt’cӮЖӮаӢ’“_Ӯрҗи—МҒAӮіӮзӮЙҚUҗЁӮр‘ұҚsӮөӮҪӮҪӮЯғҚғVғA‘ж10ҢR’cӮН—Ӯ“ъӮ©Ӯз‘ЮӢpӮрҠJҺnҒAғҚғVғAҢRӮМҚ¶—ғӮЙ”j’]ӮӘҗ¶Ӯ¶ӮҪҒBӮЬӮҪ‘ж4ҢRӮаҲЖҺRвӢӮМ“GҗwӮЙ”—ӮБӮҪҒBғNғҚғpғgғLғ“ӮНҚ•–ШҢRӮМҗv‘¬ӮИӮйҗiҸoӮЙӮжӮБӮД“Ң•”•ә’cҚ¶—ғӮӘҠлҢҜӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕҒAҚДӮСҢvүжӮр•ПҚXҒAҲЖҺRвӢӮМҗьӮЕӮМҢҲҗнӮр’ҶҺ~ӮөҒA—Й—z“м‘ӨӮМҗw’nӮЙ‘Қ‘ЮӢpӮр–ҪӮ¶ӮҪҒB“xҸdӮИӮйҢvүж•ПҚXӮЖ‘ЮӢpӮНғҚғVғAҢRӮрҚ¬—җӮіӮ№ҒAҺmӢCӮр’бүәӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB ‘ЮӢpӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮр’ЗӮБӮД‘OҗiӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒA8ҢҺ30“ъӮ©Ӯз—Й—z“м‘ӨӮМҳIҢRҗw’nӮЙ‘ОӮөҒA‘ҚҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйӮаҒAҠжӢӯӮЙ’пҚRӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮМҸe–CүОӮЙӮжӮБӮД‘№ҠQӮӘ‘ұҸoӮөӮҪҒB–k‘еҺRӮМ‘Ҳ’DҗнӮЕӮНҒA•а•ә‘ж34—ь‘а‘ж1‘е‘аӮӘ—EҗнӮөҒAҗlҠiҚӮҢүӮЕ•¶•җӮЙҸGӮЕӮҪ‘е‘а’·ӢkҺь‘ҫҸӯҚІӮНҗнҺҖҢгӮНҢRҗ_ӮЖжҗӮнӮкӮҪҒB—DҗЁӮИғҚғVғAҢR–CҢӮӮМ‘OӮЙ‘ж2ҢRҒA‘ж4ҢRӮНӢкӢ«ӮЙҠЧӮи“ъ–{ҢRӮНҠлӢ@ӮЙ—§ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA31“ъ–ў–ҫӮ©Ӯз‘ҫҺqүНүEҠЭӮЙҗiҸoӮөӮҪ‘ж1ҢRҺе—НӮНғҚғVғAҢRӮМ“Ң—ғӮрҚUҢӮҒA9ҢҺ2“ъӮЙӮНй\“ӘҺRӮрҗи—МӮөӮҪҒB—\”х‘аӮрҺgӮўүКӮҪӮөӮДӮўӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA–hҢдҗнӮрҢг‘ЮӮіӮ№ӮҪҢгӮЙ•ә—НӮМҸW’ҶӮрҠйҗ}ӮөӮҪӮӘҒA–йҠФӮМ“Л‘RӮМҢг‘Ю–Ҫ—ЯӮЙӮжӮиғҚғVғAҢRӮМҚ¬—җӮНҲк‘wҗ[ӮЬӮБӮҪҒB9ҢҺ2“ъӮ©Ӯзй\“ӘҺRӮрҸ„ӮБӮДҢғӮөӮў‘Ҳ’DҗнӮӘ‘ұӮўӮҪӮӘҒA‘ж2Һt’cӮМүӘҚи—·’cӮНҒAҗ””{ӮМ“GӮрҢӮ”jӮөӮДҺR’ёӮрҚДҗи—МӮөӮҪҒB 9ҢҺ3“ъ’©ғNғҚғpғgғLғ“ӮН‘SҢRӮМ‘Қ‘ЮӢpӮЙҲЪӮБӮҪҒBҳA“ъӮМҗ퓬ӮЙ”жҳJӮМӢЙӮЙӮ ӮБӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒA’e–тӮаҢҮ–RӮө’ЗҢӮӮМ—]—НӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB—Й—zӮМҗи—МӮЬӮЕӮӘҢАҠEӮЕҒAғҚғVғAҢR‘ЮӢpӮЙҸжӮ¶ӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB –{үпҗнӮН“ъҳI—јҢRӮМҺе—НӮӘӮНӮ¶ӮЯӮДҚsӮБӮҪ–мҗнҢҲҗнӮЕӮ ӮиҒA—DҸGӮИғҚғVғAҢRӮр”jӮБӮҪүдӮӘҢRӮЙ‘ОӮөҒAҚ‘–ҜӮМҺmӢCӮНҸгӮӘӮиҚ•–ШҢRӮМ–јҗәӮНҠCҠOӮЙҚҢӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөҠъ‘ТӮөӮҪ“G–мҗнҢRҺе—НӮМҢӮ–ЕӮНӮЕӮ«ӮёҒAҺҖҸқҺТӮа“ъ–{ҢRӮМ•ыӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҒBғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒu‘ЮӢpӮН—\’иӮМҚs“®ҒvӮЖҢц•сҒAҲшӮ«‘ұӮӯ‘ж1үс—·ҸҮ‘ҚҚUҢӮӮМҺё”sӮЖӮЖӮаӮЙүдӮӘҢRҺс”]ӮМ—J—¶ӮНҗ[ӮЬӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚ№үНүпҗнҒ@
“ъ–{ҢRӮН—Й—zӮрҗи—МӮө‘жҲкҠъӮМҚмҗн–Ъ•WӮр’Bҗ¬ӮөӮҪӮӘҒAҸ«•әӮМ‘№ҠQӮЖ”жҳJӮӘ‘еӮ«ӮӯҒA’e–тӮаҢҮ–RӮөӮҪӮҪӮЯ’ЗҢӮӮ·Ӯй—]—НӮИӮӯҒA—Й—zӮМ–k•ыӮЙӮД’вҺ~Ӯөҗн—НӮМүс•ңӮЙ“wӮЯӮДӮўӮҪҒBҲк•ығҚғVғAҢRӮН’ҖҺҹүўҸBӮ©ӮзӮМ‘қүҮ•”‘аӮӘ“һ’…ӮөӮДӮЁӮиҒAҗнӢЗӮМ‘O“rӮНҠyҠПӮЕӮ«ӮйҸуӢөӮЙӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘е–{үcӮЕӮНҗl”nҒA’e–тӮМ•вҸ[ӮЙ“wӮЯӮйӮЖӮЖӮаӮЙ•ә”хӮМӢЩӢ}‘қҗЭӮЙ’…ҺиӮөӮҪӮӘҒA–һҸBҢRӮМҗl”nҒA’e–т•вҸ[ӮН10ҢҺҸгҸ{ӮЬӮЕҒA‘nҗЭҺt’cӮМ•Тҗ¬ӮН10ҢҺ––ӮЬӮЕӮ©Ӯ©ӮйҢ©ҚһӮЭӮЕӮ ӮиҒAҺўҢгӮМ–kҗiӮЙӮНҗTҸdӮИӮй”z—¶ӮӘ—vҗҝӮіӮкӮҪҒB–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮЕӮНҒAҚ‘—НӮМҢАҠEӮрҚl—¶ӮөҒAҚЎҢгӮНҗн—ӘӢ’“_ӮМҗи—МӮжӮиӮаҒAҸ¬ӮіӮў‘№ҠQӮЕӮжӮи‘ҪӮў“G•ә—НҢӮ–ЕӮрҗ}ӮйӮұӮЖӮрҺеҠбӮЖӮөҒAҚмҗнӮМҚH•vӮЖ–kҗiҸҖ”хӮЙ“wӮЯӮҪӮӘҒAҚUҗЁҠJҺnҺһҠъӮр’иӮЯӮзӮкӮИӮўӮЬӮЬҺҷӢК‘ҚҺQ–d’·ӮН—·ҸҮҚU—ӘҗнӮМҚмҗнҺw“ұӮЙҸo”ӯӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB ғҚғVғA–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮНҒA—Й—zүпҗнҢгҲкӢ“ӮЙ“S—дӮЬӮЕӮМҢг‘ЮӮрҠйҗ}ӮөӮҪӮӘҒAӢЙ“Ң‘Қ“ВӮМҚҮҲУӮӘ“ҫӮзӮкӮё“ъ–{ҢRӮМ’вҺ~ӮаӮ ӮБӮДҚ№үН•tӢЯӮЙ’вҺ~ӮөӮҪҒB9ҢҺүәҸ{ӮЙӮН‘ж1ҢR’cҒAғVғxғҠғA‘ж6ҢR’c“ҷӮМ‘қүҮӮа“һ’…ӮөӮД“ъ–{ҢRӮжӮиӮа’ҳӮөӮӯ—DҗЁӮИ•ә—НӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕғҚғVғAӢ{’мӮМҲУҢьӮаҚl—¶ӮөӮДҚUҗЁӮрҢvүжӮөҒA10ҢҺ5“ъӮ©ӮзҚs“®ӮрҠJҺnӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮНҠeҺнҸо•сӮ©ӮзғҚғVғAҢRӮМҚUҗЁӮӘӢЯӮўӮұӮЖӮНҺ@’mӮЕӮ«ӮҪӮӘҒA1Ң»җw’nӮЕҢ}ҢӮӮөӮД‘№ҠQӮр—^ӮҰӮҪӮМӮҝӮЙҚUҗЁӮЙ“_ӮёӮйӮ©ҒH2Ӯ ӮйӮўӮНӢ@җжӮрҗ§ӮөӮДҚUҗЁӮрӮЖӮйӮ©ҒHӮМ—јҳ_ӮӘ‘О—§ӮөҒAҢӢҳ_ӮНӮЕӮИӮ©ӮБӮҪҒBҚЕүE—ғ‘O•ыӮЙ“ЛҸoӮөӮДӮўӮҪ”~‘т—·’cҗі–КӮЦӮМ“G•әӮӘ‘қүБӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮЕҒA‘ж1ҢRҺi—ЯҠҜӮН10ҢҺ7“ъ–йҒA”~‘т—·’cӮрҢг‘ЮӮіӮ№ӮйӮЖӮЖӮаӮЙ‘ж1ҢRҺе—НӮрүE‘ӨӮЙҠсӮ№ӮД‘ФҗЁӮрҗ®ӮҰӮҪҒB8“ъӮ©ӮзғҚғVғAҢRӮН–{ҹвҢО“ҷӮЙ–ТҚUӮрҠJҺnӮөҒAүE—ғӮЙӮДҢғҗнӮӘӮНӮ¶ӮЬӮБӮҪҒB ҺҷӢК‘ҚҺQ–d’·ӮН6“ъ—·ҸҮӮжӮи–ЯӮБӮҪӮӘҚUҗЁ“]ҲЪӮЙҠЦӮ·Ӯй–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮМӢcҳ_ӮНӮИӮ©ӮИӮ©ҢҲӮ№ӮёҒAҠeҢRҺQ–d’·ӮМҲУҢ©Ӯр•·Ӯ«ҒA9“ъ–й”јҚUҗЁ“]ҲЪӮМ–Ҫ—ЯӮӘ”ӯӮ№ӮзӮкӮҪҒB10“ъӮ©Ӯз‘ж2ҢRҒA‘ж4ҢRӮӘҒA11“ъӮ©Ӯз‘SҢRӮӘҚUҗЁӮрҠJҺnӮөҒA’ҶүӣӢyӮСҚ¶—ғӮ©ӮзғҚғVғAҢR—ј—ғӮЙҢьӮ©ӮБӮДҺеҚUӮӘҺwҢьӮіӮкӮҪӮӘҗнӢЗӮНҗi’»Ӯ№ӮёҒAӮұӮМҠФүдӮӘ•ыүE—ғ•ы–КӮЕӮНӢкҗнӮӘ‘ұӮўӮҪҒBҢғ“¬ӮӘ‘ұӮӯҠФӮЙ12“ъӮрҢ}ӮҰӮҪҒB‘ж4ҢRӮМҺOүтҗОҺRӮМ–йҸPӮЖӮұӮкӮЙҳAҢgӮ·Ӯй‘ж2ҢRӮМҚUҢӮӮӘҗ¬ҢчӮөҒAғҚғVғAҢR“Ң•”•ә’cӮМ‘ҚҚUҢӮҺё”sӮЖӮЖӮаӮЙ“]Ӣ@ӮӘ–KӮкӮҪҒB“Ҝ“ъҒA–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮНҚ№үНҚ¶ҠЭӮЙҢьӮ©ӮӨ’ЗҢӮӮр–Ҫ—ЯӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAҢRӮМ’пҚRӮНҠжӢӯӮЕҒAӮИӮЁҗнҗьӮН”g—җӮЖҢғ“¬ӮӘ‘ұӮўӮҪҒB –һҸBҢRҺi—Я•”ӮМ–Ӣ—»ӮНҒAҲшӮ«‘ұӮ«–k•ыӮЙҢьӮ©ӮӨҚUҗЁӮМ‘ұҚsӮрҺе’ЈӮөӮҪӮӘҒAҺRгp—L•ьҺQ–d‘Қ’·Ӯ©ӮзҒuҚ‘—НӮМҢАҠEӮ©ӮзҗнҗьҠg‘еӮр”рӮҜӮйҒvҺ|ҳA—ҚӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪ‘ҚҺi—Я•”Һс”]ӮЙӮжӮБӮДҗ§Һ~ӮіӮкӮҪҒB18“ъҚ№үНҚ¶ҠЭӮЙҗw’nӮрҗи—МӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҢҲӮөҒAғҚғVғAҢRӮЖ•tӢЯӮЙ‘ОҗwӮөӮҪӮЬӮЬӮЕ“~үcӮМҸҖ”хӮЙ“ьӮБӮҪҒBҚ№үНӮМ‘ОҗwӮН–ҫӮӯӮйҸtӮЬӮЕ‘ұӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚ•Қa‘дүпҗнҒ@
Қ№үНүпҗнҢг“ъҳI—јҢRӮНҒAҚ№үНӮрӮНӮіӮсӮЕҗw’nҚ\’zӮЖҗ퓬—НӮМүс•ңӮЙ“wӮЯӮИӮӘӮзҒAҚUҗЁӮМӢ@үпӮрӮӨӮ©ӮӘӮБӮДӮўӮҪҒB—Ӯ”NӮМүр•XҠъӮЬӮЕӮЙғҚғVғAҢRӮН30ҢВҺt’cҲИҸгӮМ•ә—НӮрӢЙ“ҢӮЙҸW’ҶӮ·ӮйӮаӮМӮЖ—\‘zӮөӮДӮўӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒAғҚғVғAӮМҚUҢӮӮрҢӮ‘ЮӮ·Ӯй‘ФҗЁӮрҗ®ӮҰӮИӮӘӮзҒA—·ҸҮҠЧ—ҺҒA‘ж3ҢRӮМ–kҸгӮр‘ТӮҝӮИӮӘӮзүz“~Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮӘҚUҗЁӮЙҸoӮйҸкҚҮҒAҢҳҢЕӮИүдӮӘҗі–КӮр”рӮҜҒA—ј—ғӮрҸХӮӯӮаӮМӮЖ—\‘zӮөҒAӮұӮкӮЙ‘ОүһӮ·ӮйӮҪӮЯ‘ж8Һt’c(Һt’c’·—§Ң©Ҹ®•¶’ҶҸ«)ӢyӮС‘ж5Һt’cӮр—\”хӮЖӮөӮДҚT’uӮөӮҪҒB –ҫҺЎ38”N1ҢҺҒ@—·ҸҮӮНҠЧ—ҺҒA‘Т–]ӮМ‘ж3ҢRӮН–kҗiӮрҠJҺnҒA“һ’…ӮН2ҢҺ17“ъӮЖ—\‘zӮіӮкӮҪҒBӮЬӮҪ‘е–{үcӮНҠШҚ‘Ӯр–hүqӮөҠҺӮВ–һҸBҢRӮМ“Ң‘ӨӮЙ“WҠJӮіӮ№ӮйӮҪӮЯҒAҗVӮҪӮЙҠӣ—ОҚ]ҢRӮр•Тҗ¬ӮөӮҪҒB 10ҢҺ26“ъӢЙ“ҢҢR‘Қ“ВғAғҢғLғZҒ[ғGғtҠCҢR‘еҸ«ӮНүр”CӮіӮкҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮӘӢЙ“Ң—ӨҠCҢR‘ҚҺi—ЯҠҜӮЖӮИӮиҒAғҚғVғA–һҸBҢRӮН‘ж1Ғ`‘ж3ҢRӮЙҚД•Тҗ¬ӮіӮкӮҪҒB ‘ж1ҢRҺi—ЯҠҜҒ@ғҠғlғEғBғbғ`‘еҸ«(11/8•т“V’…)ҒA‘ж2ҢRҺi—ЯҠҜҒ@ғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO‘еҸ«(12/8•т“V’…)ҒA‘ж3ҢRҺi—ЯҠҜҒ@ғJғEғҠғoғӢғX‘еҸ«(12/15•т“V’…)ӮЕӮ ӮйҒBғNғҚғpғgғLғ“ӮН“–ҸүҒA–{Қ‘Ӯ©ӮзӮМ‘қүҮ“һ’…ӮрӮЬӮБӮДҲк‘еҚUҗЁӮрҚsӮӨ—\’иӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA—·ҸҮҠЧ—ҺӮЙӮжӮБӮД‘ж3ҢRӮӘ–kҸгӮ·ӮйӮұӮЖӮр’mӮи‘ж3ҢR“һ’…‘OӮЙҚUҗЁӮрӮЖӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB1ҢҺ25“ъҒ@ғҚғVғAҢRӮНҚUҢӮӮрҠJҺnҒA‘ж1ҒA‘ж3ҢRӮЕ“ъ–{ҢRӮрҗі–КӮЙҚS‘©ҒA‘ж2ҢRӮЕ“ъ–{ҢRӮМҗј—ғӮр•пҲНҚUҢӮӮ·ӮйҚмҗнӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{ҢRӮН“ъ‘қӮөӮЙ‘қ‘еӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮЙҲі”—ӮіӮкӮДӮўӮҪӮӘҒA24“ъ–йӮ©ӮзҚЕҚ¶—ғӮМӢR•ә‘ж2—·’cӮв‘ж2ҢR•әвӢҸ”•”‘аӮНҢӮ‘ЮӮіӮкҒAҚ•Қa‘дӮаҗи—МӮіӮкӮҪҒB җVҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮД’…”CӮөӮҪғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO‘еҸ«ҺwҠцӮМғҚғVғA‘ж2ҢRӮМҚUҗЁӮЙӮжӮБӮДүдӮӘҗј—ғӮЙҠлӢ@ӮӘ–KӮкӮҪҒB ‘еҺR‘ҚҺi—ЯҠҜӮН25“ъҒ@‘ж8Һt’c’·ӮЙҚ•Қa‘д•ы–КӮМ“GҢӮ–ЕӮр–ҪӮ¶ҒA26“ъ–йҲИҚ~ӮіӮзӮЙ‘ж5ҒA‘ж2ҒA‘ж3Һt’cӮМҺе—НӮрӮа‘ж8Һt’c’·ӮЙ”z‘®ӮөӮД—ХҺһ—§Ң©ҢRӮЖӮөӮД”ҪҢӮӮіӮ№ӮҪҒBҲк•ығҚғVғAҢRӮНҚ•Қa‘дҗи—МҢгҒA’ҫ’UҡЖӮрҸd“_ӮЖӮөӮДҸHҺRҺx‘аӮМҗі–КӮЙ–ТҚUӮрүБӮҰӮҪӮӘҒAҸHҺRҺx‘аӮН•ұ“¬ӮөӮұӮкӮрҺзӮи”ІӮўӮҪҒBӮЬӮҪғҚғVғAҢRӮНҒA—ХҺһ—§Ң©ҢRӮМҚUҢӮӮа‘jҺ~ӮөҒAҚ•Қa‘дҺь•УӮЕҢөҠҰӮМ’nӮЙҳA‘ұҺO’Ӣ–йӮЙӮнӮҪӮБӮДҢғҗнӮӘ“WҠJӮіӮкӮҪҒB 28“ъ–йӮЙӮИӮиғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA’ҫ’UҡЖҚUҢӮӮМҗ¬ҢчӮМҢ©ҚһӮЭӮӘӮИӮӯҒAӢtӮЙ“ъ–{ҢRӮӘ‘еҚUҗЁӮрӮЖӮиӢЙӮЯӮДҠлҢҜӮИ‘ФҗЁӮЖӮИӮйӮұӮЖӮрӢ°ӮкҒAҚUҗЁӮМ’ҶҺ~Ӯр–ҪӮ¶ӮДғҚғVғA‘ж2ҢRӮрҹУүНүEҠЭӮЙҢг‘ЮӮіӮ№ӮҪҒBҢчӮрӢ}ӮўӮҫғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO‘еҸ«ӮӘғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮМҲУҢ©Ӯр–іҺӢӮөӮДӢӯҚsӮ·ӮйӢЗ–КӮӘ”wҢiӮЙӮ ӮБӮҪӮЖӮаӮіӮкӮДӮўӮйҒB“сҗlӮН‘еҸ«ҸёҗiӮН“ҜҠъӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA10ҚО”N’·ӮМғOғҠғbғyғ“ғxғӢғOӮМ•ыӮӘӢ{’ҶӮЕӮМ”ӯҢҫҢ Ӯа‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪҒB ғҚғVғAҢRӮӘҢөҠҰҠъӮЙ‘еӢK–НӮИҚмҗнӮрӮ·ӮйӮНӮёӮӘӮИӮўӮЖҺvӮўҚһӮЭҒA•sҲУӮр“ЛӮ©ӮкӮҪ“ъ–{ҢRӮНҺwҠцӮаҺx—Ј–Е—фӮЖӮИӮиҒAҚ¬—җӮөӮҪӮӘҒAӮұӮМҠлӢ@ӮН•әҺmӮМ—EҗнӮЖғNғҚғpғgғLғ“ӮЖғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO—ј‘еҸ«ӮМ•sҳaӮЙӮжӮБӮДҗhӮӨӮ¶ӮДӢ~ӮнӮкӮҪҒBғҚғVғA‘ж2ҢRҺi—ЯҠҜғOғҠғbғyғ“ғxғӢғO‘еҸ«ӮНҒAүпҗнҢг•aӢCӮЖҸМӮөӮДӢAҚ‘ӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ4 | |
|
ҒЎ—·ҸҮ—vҚЗӮМҸуӢөҒ@
—·ҸҮӮЙӮНӮ©ӮВӮДҗҙҚ‘ӮӘҚ\’zӮөӮҪӢҢҺ®ӮМ—vҚЗӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгғҚғVғAӮӘҺOҚ‘ҠұҸВӮМ‘гҸһӮЖӮөӮД‘еҳAӮЖӮЖӮаӮЙӮұӮкӮр‘dҺШӮөӮДӮ©ӮзӮНҒAүжҠъ“IӮЙӢӯү»ӮіӮкӮҪ‘е—vҚЗӮЙүь’zӮ·ӮйҚHҺ–ӮрҗiӮЯӮДӮўӮҪҒB1901”NӮЙӮИӮБӮД“–ҺһӮМғNғҚғpғgғLғ“—Ө‘ҠӮЙӮжӮйҚ\’zҢvүжӮӘҢҲ’иӮөҒA1909”NҠ®җ¬Ӯр–Ъ“rӮЖӮөӮД‘ҚҚH”п159–ңғӢҒ[ғuғӢӮр“ҠӮ¶ӮД‘ж1ҠъҚHҺ–ӮӘҗiӮЯӮзӮкҒAҚHҠъӮМ“r’ҶӮЕ“ъҳIҠJҗнӮрҢ}ӮҰӮДӮўӮҪҒB “–ҸүғҚғVғAҚ‘–hҲПҲхүпӮвғSғӢғoғbғLҒ[Ҹ«ҢRӮЙӮжӮБӮД’сҲДӮіӮкӮҪӮаӮМӮ©ӮзӮНҸkҸ¬ӮіӮкҒAҺе–hҢдҗьӮН‘O–КӮМҚӮ’nӮ©ӮзҢ©үәӮлӮіӮкҒAҺе–hҢдҗьӮМҠO‘ӨӮ©ӮзҺs“аҒAҚ`“аӮӘ–CҢӮүВ”\ӮЕӮ ӮйӮИӮЗӮМҺг“_ӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒA‘Ҫҗ”ӮМӢЯ‘г“IҡЖ—ЫӮЖ–C‘дӮр’ҶҠjӮЖӮөҒAӮ»ӮМҠФҢ„Ӯр—ХҺһҡЖ—ЫҒAҲН•ЗҒA–мҗнҗw’n“ҷӮЕ•вӮўҒA“SҸр–ФӮрӮЯӮ®ӮзӮ№ӮҪҢҳҢЕӮИӢЯ‘г—vҚЗӮЖӮИӮйӮНӮёӮЕӮ ӮиҒA“БӮЙҠCҗі–КӮН‘Ҫҗ”ӮМ–C‘дӮӘ‘ўӮзӮкӮҪҒB ҠJҗн“–ҸүӮН–ўӮҫҚHҠъӮМ“r’ҶӮЕӮ ӮиҒAҠCҗі–КӮМ–C‘дӮНҠTӮЛҠ®җ¬ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA—Өҗі–КӮНҲк•”ӮрҸңӮўӮДҠ®җ¬ӮөӮДӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө3ҢҺ’ҶҸ{ӮЙ—vҚЗӮЙӮВӮўӮДҢoҢұӮМҗ[ӮўғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«(“Ң‘_•ә‘ж7Һt’c’·)ӮМҠҲ—НӮ ӮйҺw“ұӮМүәӮЙӢ}‘¬ӮЙүь‘PӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҺе–hҢдҗьӮМүiӢvҡЖ—ЫӮМ–h”хӮрҠ®җ¬Ӯ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA‘Ҫҗ”ӮМ—ХҺһҡЖ—ЫҒAӢ@ҠЦҸeҚАҒA–мҗнҗw’n“ҷӮӘҗЭӮҜӮзӮкӮҪҒB ҠЦ“ҢҢRҢRҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ҒA—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜғXғ~ғӢғmғtҸӯҸ«ҲИүәҺз”х•ә—НӮН“Ң‘_•ә‘ж4Һt’cҒA“Ҝ‘ж7Һt’cӮр’ҶҗSӮЙ–с47000–јӮрҗ”ӮҰҒAӮМӮҝӮЙҠCҢR—Өҗн‘аҒAӢ`—E•ә“ҷӮӘүБӮнӮиҒA”T–Ш‘ж3ҢRӮрҢ}ӮҰҢӮӮВ‘ФҗЁӮрҢЕӮЯӮДӮўӮҪҒB–{Қ‘Ӯ©ӮзӢ~үҮӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘ—ҲҚqӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҳA—ҚӮНҠщӮЙ“`ӮҰӮзӮкӮДӮЁӮиҒAҺз”х‘аӮМҺmӢCӮНӢЙӮЯӮДҚӮӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҢRӮМҗн—ӘҚ\‘zҒ@
“ъ–{ҠCҢRӮМҗн—Ә“IҢ©’nӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзӮМ‘қүҮ“һ’…‘OӮЙ—·ҸҮӮЙӮ ӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮр’Ч–ЕӮөӮДӮЁӮӯӮұӮЖӮӘҗв‘ОӮЙ•K—vӮҫӮӘҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМ”ЭҢмӮМүәӮЙҢ’ҚЭӮрҗ}ӮлӮӨӮЖӮ·ӮйғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮіӮ№ӮйӮЙӮНҒA—Өҗі–КӮ©ӮзӮМ—vҚЗҠЧ—ҺӮөӮ©Һи’iӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB “ҜҺһӮЙӮ»ӮМӮұӮЖӮНҒA“ъ–{—ӨҢRӮМҗн—Ә“IҢ©’nӮ©ӮзӮ·ӮйӮЖҒAӢЙ“ҢғҚғVғAҢRӮЖӮМ–мҗнҢҲҗнӮЙҗЁ—НӮрҸW’ҶӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒA—vҚЗӮрҚUҢӮӮ·ӮйӮжӮиӮа—ӨҸгӮЕ••ҚҪҠДҺӢӮЙ—ҜӮЯӮй•ыӮӘ—L—ҳӮЕӮ ӮиҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҚU—ӘӮЙ‘еӮ«ӮИҗн—НӮрҠ„ӮӯӮұӮЖӮНҒAӢЙ“ҢғҚғVғAҢRӮМҠeҢВҢӮ”jӮМӮҪӮЯӮМҗн—НӮрҺгӮЯӮДӮөӮЬӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB—ӨҢRӮМӮЭӮМҗн—ӘӮЕӮ ӮкӮОҒA—·ҸҮ—vҚЗӮНҒA—·ҸҮӮЙҺҠӮй“S“№ӢyӮСҠCҸгӮрҺХ’fӮ·ӮкӮО‘ЬӮМ‘lӮЕӮ ӮиҒA‘еӮ«ӮИӢ]җөӮр•ҘӮБӮДӮЬӮЕӮаҚU—ӘӮ·Ӯй•K—vӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAүдӮӘ—ӨҠCҢR“қҗғ•”ӮЖӮөӮДӮМҚмҗнҸгӮНӮ»ӮкӮрӢ–ӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒB —vҚЗҗнӮрҢyҺӢӮөӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨҒA“c’ҶӢ`Ҳк’ҶҚІ(ҢгӮМ‘еҸ«)ҒAҚІ“ЎҚ|ҺҹҳY’ҶҚІ(ҢгӮМ’ҶҸ«)ҒA—R”дҢхүqҸӯҚІ(ҢгӮМ‘еҸ«)ӮзӮМҗiҢҫӮНҗПӢЙ“IӮЙҚМ—pӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB—eҲХӮЙҚU—ӘӮЕӮ«ӮҪӮЖӮўӮӨ“ъҗҙҗн‘ҲӮЕӮМҢoҢұӮЖғҚғVғAҢRӮМҢөӮөӮўӢ@–§•ЫҺқӮЖ‘ҠӮЬӮБӮДҒA—·ҸҮӮӘҚЕҗVҺ®‘е—vҚЗӮЙ•ПҗgӮөӮВӮВӮ ӮйӮұӮЖӮр’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒAӢЯ‘г“IҚUҸйҗн–@ӮМ”FҺҜӮӘ•sҸ\•ӘӮМӮЬӮЬҚмҗнӮЙ—ХӮЮӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚUҢӮҸҖ”хҒ@
ҠJҗн•Й“ӘӮМ—·ҸҮҚ`ҠOҠпҸPӮМҗнүКӮНҸӯӮИӮӯҒA3үсӮЙӮнӮҪӮй•ВҚЗҚмҗнӮаҒAҚLҗЈ’ҶҚІ“ҷӮМ•ұҗнӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҸ\•ӘӮИҗ¬үКӮЙҺҠӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠН–CӮЙӮжӮйғҚғVғAҠН‘аӮЦӮМҠФҗЪҺЛҢӮӮаҺvӮнӮөӮӯӮИӮӯҒA’јҗЪ“I—·ҸҮҚ`••ҚҪӮМ’·ҠъҢp‘ұӮН—ьҚҮҠН‘аӮЙӮЖӮБӮДҸdӮў•ү’SӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮіӮзӮЙӮНғEғүғWғIғXғgғbғNӮМғҚғVғA•К“ӯҠН‘аӮН“ъ–{ӢЯҠCӮЙҸo–vӮөҒA—ьҚҮҠН‘аӮНҠН‘аӮр•ӘҢӯӮ№ӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮБӮҪҸгӮЙҒA4ҢҺ––ӮЙӮНғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“ҢҚqҢҲ’иӮӘ•сӮ¶ӮзӮкӮҪҒBӮұӮМ‘ФҗЁӮЕғҚғVғA‘қүҮҠН‘аӮрҢ}ӮҰӮкӮО“ъ–{ӮНҠлӢ@ӮЙ—§ӮВҒBӮ©ӮӯӮөӮД5ҢҺ––ҒA—ӨҸгӮ©ӮзӮМ—·ҸҮ—vҚЗӮЦӮМҚUҢӮӮНҢҲ’иӮіӮкӮҪҒB 5ҢҺ29“ъҒ@ҲИүәӮМӮжӮӨӮИҗ퓬Ҹҳ—сӮӘ”ӯ—ЯӮіӮкҒAҢRҺi—Я•”ӮН6ҢҺ1“ъүFҺЎҚ`ӮрҸoҚ`ҒA“r’ҶӮЕ—ьҚҮҠН‘аӮЖ‘ЕӮҝҚҮӮнӮ№ӮрҢoӮД8“ъ‘еҳAҗј–kӮЙ“һ’…ӮөӮҪҒB 6ҢҺ26“ъҒ@Ң•ҺR“ҷӮМ“Gҗw’nӮрҚU—ӘӮөӮД‘OҸЈҗнӮрҗ„җiҒA—vҚЗ•вӢӯӮМҺһҠФӮр“ҫӮжӮӨӮЖӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮМ’DүсҚUҢӮӮрҢӮ‘ЮӮөӮДӮұӮкӮрҗи—МӮөӮҪҒBӮіӮзӮЙ‘ж9Һt’cӮИӮЗӮМ‘қүҮ•”‘аӮМ“һ’…ҢгҚUҢӮӮрҚДҠJҒA7ҢҺ30“ъӮЙӮН—vҚЗӮЙ‘ОӮ·ӮйҚUҲНҗьӮЙҗiҸoӮөӮҪҒB—ӨҢRӮМ—vҗҝӮЙӮжӮйҠCҢRӮМ—ӨҗнҸd–C‘аӮНҒA8ҢҺ7“ъӮЙӮН—·ҸҮҺsҠXӮр–CҢӮӮөӮДүОҚРӮр”ӯҗ¶ӮіӮ№ҒAӮұӮМӮҪӮЯ—·ҸҮҠН‘аӮНҸoҚ`ӮөӮДғEғүғWғIӮЙҢьӮ©ӮБӮҪӮӘҒA“r’ҶӮЕ‘ТӮҝҺуӮҜӮҪ“ъ–{ҠН‘аӮЖү©ҠCҠCҗнӮрҚsӮўҒAӮ»ӮМ‘ҪӮӯӮН—·ҸҮҚ`ӮЙ“ҰӮ°ӢAӮБӮҪҒBғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮНҚДӮСҸoҚ`Ӯ·ӮйӮұӮЖӮИӮӯҒAҗ…•әӮв–CӮМ‘Ҡ“–•”•ӘӮр—g—ӨӮөӮД—ӨҸг–h”хӮрӢӯү»ӮөӮҪҒB 8ҢҺ9“ъӮЙӮН“Ңҗі–КӮМ‘Oүqҗw’nӮрҚU—ӘҒAҚUҸй–C•әӮЖ’e–тӮНҒAүдӮӘҢRӮЙӮжӮБӮДҸC•ңӮөӮҪ“S“№ӮЙӮД“WҠJӮрҸIӮҰӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮД‘ҚҚUҢӮӮМҸҖ”хӮНҗ®ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж1үс‘ҚҚUҢӮҒ@–ҫҺЎ38”N8ҢҺ19“ъҒ`24“ъҒ@
8ҢҺ16“ъҒ@”T–Ш‘еҸ«ӮНҢRҺgӮрҺgӮБӮДҒu”сҗ퓬ҲхӮМ”р“пӮЖҠJҸйҠ©ҚҗҒvӮр‘—•tҒB“GҸ«ғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ӮНӮаӮҝӮлӮсӮұӮМҠ©ҚҗӮрӢ‘”ЫӮөӮҪҒB 8ҢҺ19“ъҒ@0600Ғ@үдӮӘҚUҸй–CӮМ–CҢӮӮЖӮұӮкӮЙ‘ұӮӯ“ЛҢӮӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮ‘ҚҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪҒB 8ҢҺ21“ъҒ@‘ж11Һt’cӮӘ“ҢҢ{ҠҘҺR‘ж2ҡЖ—ЫӮрҗи—МӮ·ӮйӮаҸW’Ҷ–CүОӮр—ҒӮСӮД’DүсӮіӮкӮҪҒB22“ъӮЙӮН”Х—іҺR“ҢҡЖ—ЫӮМҺО–КӮЙ’ЈӮи•tӮўӮДӮўӮҪ•P–мҚH•әҢR‘ӮӮЩӮ©җ”–јӮӘҒAҡЖ—ЫӢЯӮӯӮМӢ@ҠЦҸeҚАӮр”ҡ”jӮөӮДҺз•әӮӘҸӯӮИӮўӮұӮЖӮр•сҚҗҒAӮұӮкӮЙҸжӮ¶ӮД•а•ә‘ж7—ь‘аӮМҺc‘¶•”‘аӮӘ“ЛҢӮӮөӮД“ҜҡЖ—Ыҗј–k“ЛҠpӮрҗи—МӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮМҚДҺOӮЙ“nӮйӢtҸPӮЙ‘ОӮөӮДҒA“ъ–{ҢRӮа‘қүҮӮр‘—ӮиҒAҗӢӮЙӮНҗјҡЖ—ЫӮаҗи—МӮөӮҪҒB24“ъӮа”Х—іҺR“ҢҒAҗјҡЖ—ЫӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҗнүКӮМҠg‘еӮЙ“wӮЯӮҪӮӘҒA’e–т•s‘«ӮМӮҪӮЯ’ҫ–ЩӮіӮ№ӮзӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB24“ъ’©Ғ@”T–Ш‘еҸ«ӮзӮӘ‘oҠбӢҫӮЕӮМӮјӮўӮДӮўӮйӮЖҒA–ҫӮҜҚsӮӯҢхӮМ’ҶӮЙҺҹҒXӮЖҺpӮрҢ»Ӯ·ӮЙӮНҒAҺО–КӮЙӮЖӮиӮВӮўӮД“|ӮкӮҪ–іҗ”ӮМ“ъ–{•әӮМҺrӮОӮ©ӮиӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗVҺ®•әҠнӮЕӮ ӮйӢ@ҠЦҸeӮрӢмҺgӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮМ‘OӮЙҒA‘ж3ҢRҺi—Я•”ӮНӮВӮўӮЙҚUҢӮ’ҶҺ~Ӯр–ҪӮ¶ӮҪҒBҺе–hҢдҗьӮЕӮН”Х—іҺR“ҢҒAҗјҡЖ—ЫӮрҗи—МӮ·ӮйӮЙ—ҜӮЬӮБӮДҺё”sӮөӮҪҒBӮ Ӯй—ь‘аӮЕӮНҢRҠшҢмүq•әҺбҠұӮрҸңӮўӮДҒA—ь‘а’·ҲИүә‘SҲхӮӘҗнҺҖӮ·ӮйӮЖӮўӮБӮҪҸуӢөӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘OҗiҡЖ—ЫӮЦӮМҗiҢӮҒ@
‘ж1үс‘ҚҚUҢӮӮМҗнҢPӮЙҠУӮЭҒAӢӯҸPӮЙ‘ЦӮҰӮДҗіҚU–@ӮЙӮжӮйҚмҗнӮрҚМӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB‘ҰӮҝҒAҡЖ—Ы•ыҢьӮЙҚҲӮрҢ@ӮиҗiӮЭҒAӮ»ӮМҗж’[ӮЙ‘ж2ҚUҢӮҗw’nӮрҚ\’zҒA–hҢд‘ӨӮМ—LҢшҺЛ’цӮЙ“ьӮБӮДӮ©ӮзӮМ‘OҗiҒA“ЛҢӮҸҖ”х“ҷӮМӮ·ӮЧӮДӮрҚUҢӮ‘ӨӮМ’zҸйӮЙӮжӮйүҮҢмүәӮЙҚsӮӨӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAҺһҠФӮНӮ©Ӯ©ӮйӮӘӢ]җөӮрҸӯӮИӮӯӮжӮиҠmҺАӮЙ“Л“ьӮЕӮ«Ӯй•ы–@ӮЕӮ ӮйҒB ‘ж3ҢRӮНҺе–hҢдҗьӮМҡЖ—ЫӮЙҗЪӢЯӮ·ӮйҚҲӮрҢ@ҚнӮөӮД‘ж2үс‘ҚҚUҢӮӮМҸҖ”хӮрӮ·Ӯ·ӮЯӮВӮВҒA‘O•ыӮЙҺcӮй‘Oүqҗw’nӮМҚU—ӘӮЙ“wӮЯӮҪҒB9ҢҺ20“ъҒ@ҢғҗнӮМӮМӮҝӮЙ—іҠб–k•ыҡЖ—ЫҒAҗ…ҺtүcҡЖ—ЫӮИӮЗӮрҚU—ӘӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAҢRӮМҸW’Ҷ–CүОӮЙӮжӮБӮДүдӮӘ‘№ҠQӮаҸӯӮИӮӯӮИӮӯҒAӮ©ӮМ203ҚӮ’nӮаҲк’Uҗи—МӮМӮМӮҝӮЙ’DҠТӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж2үс‘ҚҚUҢӮҒ@–ҫҺЎ38”N10ҢҺ26“ъҒ`31“ъҒ@
10ҢҺ1“ъӮ©Ӯз28ғZғ“ғ`һЦ’e–C6–еӮМҚЕҸүӮМ–CҢӮӮӘҚsӮнӮкӮҪҒB“а’nӮМҠCҠЭ—vҚЗӮ©ӮзҺжӮиҠOӮөӮД—A‘—ӮөӮДӮ«ӮҪӮаӮМӮЕӢҢҺ®ӮдӮҰӮЙ•s”ӯ’eӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒA—\ҠъҲИҸгӮМ–Ҫ’Ҷҗё“xӮЖҲР—НӮр”ӯҠцӮөҒAҸdүОҠн•s‘«ӮЙ”YӮЮ“ъ–{ҢRӮЙӮЖӮБӮДӮН—LҢш“IӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ҢRӮӘҚҲӮМҢ@ҚнӮЙӮжӮБӮДҡЖ—ЫӮЙӢЯҗЪӮ·ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮД,ғҚғVғAҢRӮН–CүОӮМҸW’ҶӮЙӮжӮБӮД–WҠQӮөӮҪҒB–йҠФҚмӢЖӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮЖ’TҸЖ“”ӮрӮВӮ©ӮБӮД–WҠQҒAҗӢӮЙ“ъ–{ҢRӮН’nүәҚB“№ӮрҢ@ӮиҗiӮсӮЕҡЖ—ЫӮЙҗЪӢЯӮөӮҪҒB 10ҢҺ26“ъҒ@–k“Ңҗі–КӮЙ‘ОӮ·Ӯй‘ж2үс‘ҚҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪҒBҚЎүсӮМҺе–Ъ•WӮН—vҚЗ–k‘ӨҺе—v3ҡЖ—ЫӮЕӮ ӮйҒB“Ҝ“ъ”Х—іҺR–kҡЖ—ЫӮр’DҺжӮөҒA–CҢӮӮЖҚB“№ҚмӢЖӮр‘ұӮҜӮҪҢгӮЙҒA30“ъ•а•ә“ЛҢӮӮрҠёҚsҒA’КҸМҲкҢЛҡЖ—ЫӮЖ“ҢҢ{ҠҘҺR–kҡЖ—ЫӮМҲк•”Ӯрҗи—МӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҸјҺчҺRҒA“с—іҺRҒA“ҢҢ{ҠҘҺRӮМ3ҡЖ—ЫӮЙ‘ОӮ·ӮйҚB“№ҚмӢЖӮМҠ®җ¬ӮЙӮНҺһҠФӮӘӮ©Ӯ©ӮйӮҪӮЯҒA‘ҚҚUҢӮӮр’ҶҺ~ҒA3ҡЖ—ЫӮЦӮМҚB“№ҚмӢЖӮЦӮМҗi’»ӮЙ“w—НӮрҢp‘ұӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҺеҚU“]Ҡ·ҳ_‘ҲҒ@
ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“ҢҚqӮӘҚҸҒXӮЖ”—ӮиҒAҠCҢRӮЖӮөӮДӮНҠН’шӮМҗ®”хҒEҸC—қӮМӮҪӮЯҸӯӮИӮӯӮЖӮа2ғ–ҢҺҠФӮМҸҖ”хӮр•K—vӮЖӮ·ӮйҒBӮөӮҪӮӘӮБӮД11ҢҺ––(ғoҠН‘а“һ’…ӮН–ҫ”N1ҢҺӮЖ—\‘ӘӮөӮДӮўӮҪ)ӮЙӮНҠCҸг••ҚҪӮрҠЙӮЯӮД“а’nӮЙӢAҚ`ӮөӮИӮӯӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒB‘ҒҠъҚU—ӘӮМӮҪӮЯӮЙӮаҚUҢӮ–Ъ•WӮр203ҚӮ’nӮЙҲЪӮөҒAӮұӮұӮрҗи—МӮөӮДҠП‘ӘҸҠӮрҗЭӮҜҒA–CҢӮӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҚ`“аӮМ“G‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрҢӮ”jӮіӮкӮҪӮўҒAӮЖ—ӨҢRӮЙҗ\Ӯө“ьӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢ»’nӮМ–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮЖ‘ж3ҢRҺi—Я•”ӮНҒA203ҚӮ’nӮрҚU—ӘӮөӮДӮа—·ҸҮ—vҚЗӮӘҠЧ—ҺӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮНӮИӮзӮИӮўҒAӮЖӮөӮДҒA”сҗн—Ә“IӮИҺеҚU“]Ҡ·ӮЙӮН”Ҫ‘ОӮЕӮ ӮБӮҪҒB ”T–ШҢRҺi—ЯҠҜӮЙ‘ОӮ·Ӯй”б”»ӮӘҚӮӮЬӮй’ҶҒA11ҢҺ23“ъӮЙӮНҒAӮЖӮӯӮЙ‘ж3ҢRӮЙ‘ОӮөҢғ—гӮМ’әҢкӮрҺ’ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҺRҢ§ҺQ–d‘Қ’·Ӯ©ӮзӮаҚUҢӮҗ¬ҢчӮрӢFӮйҠҝҺҚӮӘ‘—ӮзӮкӮҪҒB‘SҚ‘–ҜӮМҠҙҸоӮаӮЬӮҪҢғӮөӮӯҒAҒu”T–ШҸ«ҢRӮж• ӮрҗШӮкҒvӮЖӮМҚҢҒXӮҪӮй”с“пҒAҲҪӮўӮНҢғ—гӮ·Ӯй“d•сӮӘҲшӮ«ӮаҗШӮзӮё‘ж3ҢRҺi—Я•”ӮЦҺE“һӮөӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж3үс‘ҚҚUҢӮҒ@–ҫҺЎ38”N11ҢҺ26“ъҒ`12ҢҺ6“ъҒ@
11ҢҺӮЙ“ьӮиҒA‘ж3ҢRӮЙӮН‘ж7Һt’cӮЖҚH•ә3ҢВ’Ҷ‘аӮӘ‘қүБӮіӮкӮҪҒBҸЕ‘ҮӮМҗFӮӘ”ZӮў‘ж3ҢRӮНҒAӮ ӮӯӮЬӮЕҸүҠъӮМҢvүжӮрҠС“OӮ·ӮЧӮӯҒA—vҚЗҗі–КӮ©ӮзӮМҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҠJҺnӮЙҗж—§Ӯҝ”T–ШҢRҺi—ЯҠҜӮНҒuҢRҺi—ЯҠҜҺ©ӮзҒAҢR—\”хӮМ‘ж7Һt’cӮр—ҰӮўӮД“ЛҗiӮөӮжӮӨҒvӮЖӮЬӮЕҸqӮЧҒAӮ»ӮМҠoҢеӮМ’цӮӘӮӨӮ©ӮӘӮнӮкӮҪҒB11ҢҺ26“ъ1300Ғ@Ҡe‘аӮН‘Ҫ‘еӮИӮй‘№ҠQӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮё“ЛҢӮӮр”Ҫ•ңӮөӮД“GҗwӮМҲкҠpӮЙ“Л“ьӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAҢRӮМ–Т—уӮИ–CүОӮЖӢtҸPӮМ”Ҫ•ңӮЙӮжӮиӮұӮкӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒAҗнӢөӮНҲкҗiҲк‘ЮӮЕӮ ӮБӮҪҒB җ…ҺtүcӮМ’JӮМ’ҶӮ©Ӯз“GӮМ–hҢдҗьӮМҲкҠpӮр•Ә’fӮөӮД—vҚЗ“аӮЙ“Л“ьӮө“а•”Ӯрқҳ—җӮ·ӮкӮОҒA“GӮМҺwҠцҢn“қӮЙҚ¬—җӮрҗ¶Ӯ¶ӮйҒBӮ»ӮӨҚlӮҰӮҪ•а•ә‘ж“с—·’c’·’Ҷ‘әҠoҸӯҸ«ӮНҒA”T–ШҢRҺi—ЯҠҜӮЙ’ј‘iӮөӮДҢҲҺҖ‘аӮр•Тҗ¬ӮөӮҪҒBҠe•”‘аӮжӮи‘I”ІӮіӮкӮҪ“Б•КҺx‘а6ҢВ‘е‘а3җз•S—]–јӮНҒA–йҸPӮЙ—ХӮЭ‘ҚҲх”’ӮўӮҪӮ·Ӯ«ӮрӮ©ӮҜӮҪҒB—L–јӮИ”’жF‘аӮЕӮ ӮйҒB11ҢҺ26“ъ—[ҚҸҒA”T–Ш‘еҸ«ӮМҢ©‘—ӮиӮрҺуӮҜ’Ҷ‘әҸӯҸ«Ӯрҗж“ӘӮЙҸo”ӯӮөӮҪ”’жF‘аӮҫӮБӮҪӮӘҒA“r’ҶӮЕ’n—ӢӮЙҗЪҗGӮөӮДӮ©ӮзӮНғҚғVғAҢRӮМғTҒ[ғ`ғүғCғgӮЙҸЖӮи•tӮҜӮзӮк–CүОӮӘҸW’ҶҒA—·’c•ӣҠҜҲИүә‘Ҫҗ”ӮМҺҖҸқҺТӮрӮҫӮөҒA’Ҷ‘әҸӯҸ«Һ©җgҸdҸқӮр•үӮБӮҪҒBӮ©ӮӯӮөӮДӢҮ—]ӮМҲкҚфӮЖӮөӮДҒAҗнҸpҸнҺҜӮЖӮөӮДӮН–і–dӮЙӢЯӮў–йҠФӮМҠпҸPҗн–@ӮНҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪҒB 11ҢҺ27“ъҒ@ӢҮ’nӮЙ’ЗӮўҚһӮЬӮкӮҪҢRҺi—ЯҠҜӮНҒAҺеҚUӮрӮВӮўӮЙ203ҚӮ’nӮЙ•ПҚXҒAҺxүҮ–CҢӮӮЙ‘ұӮўӮД“Ҝ–йӮжӮи‘ж1Һt’cӮЙӮжӮй203ҚӮ’nӮЙ‘ОӮ·ӮйҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪҒBҲк’UӮНҚӮ’nӮМ’Ҷ• ӮЬӮЕ“ЛҗiӮөӮҪӮаӮМӮМҒAғҚғVғAҢRӮМ–ТҺЛӮр—ҒӮС•әӮМ‘е”јӮрҺёӮБӮД‘ЮӢpӮөӮҪҒB—Ӯ28“ъ0800Ғ@җј“м•ы–КӮМ“ЛҢӮ‘аӮН–Т—уӮИҗЁӮўӮЕ“ЛҗiҒAӮұӮкӮрҢ©ӮҪүE—ғ‘аӮНүҮҢRӮр‘—ӮиҺҖӮЙ•ЁӢ¶ӮўӮЕҺR’ёӮЙ“Л“ьҒAҢғҗнӮМӮМӮҝӮЙҺR’ёҗј“м•”ӮрҲк’Uҗи—МӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМ’јҢгҒA“м‘ӨӮ©ӮзӮМғҚғVғAҢRӮМ‘еӢtҸPӮрҺуӮҜӮйҒBҺRҸгӮ©ӮзӮНӢӣ—ӢӮр”ӯҺЛҒAҺ©ҢRӮМ”’•әҗw’nӮЙӮ·Ӯз–CҢӮӮрүБӮҰӮйҗҰӮЬӮ¶ӮіӮЕҒAҗҰҺSӮИ‘Ҳ’DҗнӮӘ“WҠJӮіӮкӮҪҒB29“ъӮЙӮН“һ’…ӮөӮҪӮОӮ©ӮиӮМ‘ж7Һt’cӮр“Ҡ“ьҒA30“ъ–йӮЙӮН203ҚӮ’nӮрҗи—МӮ·ӮйӮаҒA—Ӯ’©ӮЙӮНғҚғVғAҢRӮЙӮжӮБӮД’DүсӮіӮкҒAҗОӮр“ҠӮ°“GӮЙҠҡӮЭ•tӮ«ҒAҗн—FӮМҺrӮр“ҘӮЭүzӮҰҺrҺRҢҢүНӮМҸC—…ҸкӮӘҒA203ҚӮ’nӮМ‘Ҳ’DӮрҸ„Ӯй”ЮүдӮМҺҖ“¬ӮЙӮжӮБӮДҢ»ҸoӮөӮҪҒB җнӢөӮр—J—¶ӮөӮҪ‘еҺR‘ҚҺi—ЯҠҜӮНҒAҺҷӢК‘ҚҺQ–d’·ӮрҚмҗнҺw“ұӮМӮҪӮЯӮЙ”hҢӯҒAҺҷӢК‘еҸ«ӮН’јҗЪ‘ж3ҢRҺQ–dӮр“қҠҮӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB12ҢҺ3“ъӮ©ӮзҚUҢӮӮӘҚДҠJӮіӮкҒA12ҢҺ5“ъӮЙӮНӮВӮўӮЙ203ҚӮ’nӮрҗи—МҠm•ЫӮөӮҪҒBҠщӮЙғҚғVғAҢRӮаӢtҸPӮМӮҪӮЯӮМ—\”х‘аӮрҸБ–ХӮөҗsӮӯӮөӮДӮЁӮиҒA203ҚӮ’nӮНӮЬӮіӮЙ‘SҺRӮұӮЖӮІӮЖӮӯ“ъ–{ҢRҸ«•әӮМҺrӮрӮаӮБӮД–„ӮЯҗsӮӯӮ·ӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҠJҸйҒ@
203ҚӮ’nҠЧ—ҺҢгҒAғҚғVғAҢRӮНӢ}‘¬ӮЙҗнҲУӮрҺёӮўӮНӮ¶ӮЯӮҪҒBӮўӮБӮЫӮӨ“ъ–{ҢRӮНҒAҲшӮ«‘ұӮ«ҚB“№ҚмӢЖӮЙӮжӮйҡЖ—ЫҚUҢӮӮр‘ұӮҜҒA12ҢҺ18“ъӮ©Ӯз28“ъӮЬӮЕҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҡЖ—Ы–C‘дӮМ’ҶҗSӮЕӮ ӮБӮҪ3‘еҡЖ—ЫӮрҗи—МӮөӮҪҒB–ҫҺЎ38”N1ҢҺ1“ъҢЯҢгӮЙӮНҒA—vҚЗҗь’јҢгӮМ’ҶҠjҗw’nӮЕӮ Ӯй–]‘д’ёҸг•tӢЯ(185ҚӮ’n)Ӯрҗи—МӮөӮҪҒBӮЬӮіӮЙҺsҠXӮЙ“Л“ьӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪ1530Ғ@ғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ӮНҠJҸйӮМӮҪӮЯӮМҢRҺgӮр”hҢӯҒAғҚғVғAҢRӮНҚ~•ҡӮөӮҪҒB 12ҢҺ15“ъӮЙӮНҚмҗнҺw“ұ’ҶӮМғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮӘ“ъ–{ҢRӮМ28ғTғ“ғ`–C’eӮЕҗнҺҖӮөӮҪӮұӮЖӮаҒAғҚғVғAҢRҸ«•әӮМҺmӢCӮМ’бүәӮЙҢqӮӘӮБӮҪҒB1ҢҺ2“ъҢЯҢгҒ@җ…ҺtүcӮЙӮДҠJҸйӢK–сӮр’ІҲуҒA–ҫҺЎ38”N1ҢҺ5“ъҗіҢЯӮЙӮНүдӮӘүqҗ¶‘а–{•”ӮЙҸ[ӮДӮзӮкӮДӮўӮҪ–ҜүЖӮЙӮДҒA—јҢRҺi—ЯҠҜӮМҢҖ“IӮИүпҢ©ӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМ“ъӮН’©Ӯ©Ӯз”ьӮөӮӯҗ°Ӯк“nӮиҒAҗ”“ъ‘OӮЬӮЕӮМҢғҗнӮӘүRӮМӮжӮӨӮИүёӮ©ӮИ“ъҳaӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДғҚғVғAҢRӮМҠJҸйӮЖ•җ‘•үрҸңӮЙӮжӮи—·ҸҮҚU—ӘҗнӮНҸI—№ӮөӮҪҒB ӮИӮЁӮұӮМҺһ–ҫҺЎ“VҚcӮНҒAғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ӮӘ‘cҚ‘ӮМӮҪӮЯӮЙҗsӮӯӮөӮҪ’үҗЯӮрҸdӮсӮ¶ҒA•җҺmӮМ–ј—_Ӯр•ЫӮҪӮөӮЯӮйӮжӮӨӮЙҒAӮЖҠу–]ӮіӮкӮҪҒB“VҚcӮМҗ№Һ|ӮН”T–Ш‘еҸ«ӮЙ“`ӮҰӮзӮкҒAӮіӮзӮЙӮНғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ӮЙӮа“`’BӮіӮкӮҪҒBүдӮӘҚ‘ӮӘ•җҺm“№җёҗ_Ӯр”ӯҠцӮөӮҪҲк—бӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҗнүКӮЖ‘№ҠQҒ@
–ҫҺЎ37”N7ҢҺ31“ъ‘Oҗiҗw’nӮрҗи—МӮөӮДӮ©Ӯз155“ъӮМ“ъҗ”Ӯр—vӮөҒAҢг•ы•”‘аӮрҠЬӮЯӮДү„ӮЧ–с13–ңҗlҒAҗ퓬ҺQүБҚЕ‘еҗlҲх6–ң4җз(‘ж3үс‘ҚҚUҢӮҺһ)ӮМ•ә—НӮЙӢyӮсӮҫҒB –мҗнӮЙӮЁӮўӮДӮН”sҗнҒ|—\’иӮМ‘ЮӢpҒ|Ӯр‘ұӮҜӮҪғҚғVғAҢRӮаҒAҗкҺз–hҢдӮЙ“OӮөӮҪғXғeғbғZғӢ’ҶҸ«ҲИүәӮНҒAҒuҗўҠEҚЕӢӯӮМғҚғVғA—ӨҢRҒvӮМ–јӮрҗJӮЯӮйӮұӮЖӮИӮӯҒAӮ»ӮМ“`“қӮрҲвҠ¶ӮИӮӯ”ӯҠцӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ—·ҸҮ—vҚЗӮМҚU—ӘҗнӮНҒAӢӯҸPӮЙӮВӮ®ӢӯҸPӮрҢJӮи•ФӮ·–ў‘\—LӮМ‘еҢғҗнӮЖӮИӮиҒAӮЬӮіӮЙӢКҚУӮЖҗёҗ_“Iҗ«ҠiӮр“ҜӮ¶ӮӯӮ·Ӯйҗ퓬ӮЕӮ ӮБӮҪҒB —·ҸҮӮМҠЧ—ҺӮЙӮжӮБӮДҒA—ьҚҮҠН‘аӮНғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙ”хӮҰӮДҗ®”хҒAҢP—ыӮрҚsӮӨ—]—TӮр“ҫҒA–һҸBҢRӮНҺҹӮМ•т“VүпҗнӮЙ‘ж3ҢRӮрҺg—pӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиҒAҠOҚВ•еҸWӮЙӮаҚDүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮұӮМҗнӮўӮНҒAҸ«—ҲҗнӮЙӮЁӮҜӮйүИҠwӢZҸpӮМҸd—vҗ«ӮЙҠЦӮ·ӮйҲк‘еҢxҸаӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ5 | |
|
ҒЎүпҗн‘OӮМҚ‘ҸуҒ@
—Й—zҒEҚ№үНӮМ—јүпҗнӮЖ—·ҸҮҚU—ӘӮМ5–ң—]ӮЖӮ ӮнӮ№ӮйӮЖҒA10–ңӮр’ҙӮҰӮйҸ«•әӮӘӮұӮМ1”NӮЕқЛӮкӮДӮўӮҪҒB–C’eӮМҢҮ–RӮЙ“зӮвҠҳӮр’ЧӮөӮД’eҠЫӮрҚмӮзӮЛӮОӮИӮзӮИӮўӮЩӮЗ•nҺгӮИҗ¶ҺY—НӮөӮ©ӮИӮў“ъ–{ӮНҒAӮ·ӮЕӮЙ•еҸWӮөӮҪ3үӯӮМҠOҚВӮаҸБ”пӮөӮДӮўӮҪҒBҺQ–dҺҹ’· ’·үӘҠOҺjҸӯҸ«ӮНҒA’e–тӮӘ•вҸ[ӮіӮкӮйӮЬӮЕ2ҒA3ғ–ҢҺӮМӢxҗнӮаӮвӮЮӮр“ҫӮИӮўҒAӮЖҗiҢҫӮөӮҪӮЩӮЗӮҫӮБӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДғҚғVғAӮНҒA“Ҝ’ц“xӮМ‘№ҠQӮр–ЦӮБӮҪӮЖӮНӮўӮҰҗVӮҪӮЙүўҸBӮ©Ӯз10җ”–ңӮМ•ә—НӮрғVғxғҠғA“S“№ӮЕ‘—ӮиҚһӮЭҒAҠCҢRӮН“ъ–{ӮМҺе—vҠН’шӮЙ•C“GӮ·ӮйӢK–НӮМ‘ҫ•Ҫ—m‘ж“сҠН‘а(ӮўӮнӮдӮйғoғӢғ`ғbғNҠН‘а)ӮрӢЙ“ҢӮЙ”hҢӯӮөӮВӮВӮ ӮБӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘а•АӮСӮЙ•т“VӮЙҸWҢӢӮ·Ӯй—Ө•ә40–ңӮМӮ ӮйҢАӮиҚuҳaӮЙӮНүһӮ¶ӮзӮкӮИӮўӮЖҗә–ҫӮөӮҪғҚғVғAӮЙ‘ОӮөҒA“ъ–{ӮН”ЫүһӮИӮӯ—ӨҠCӮЕҢҲҗнӮр’§ӮЬӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүпҗн‘OӮМҗнӢөҒ@
—·ҸҮӮрҠЧ—ҺӮіӮ№ӮҪ‘ж3ҢRӮНҒA–ҫҺЎ38”N1ҢҺүәҸ{ӮжӮи–kҸгӮрҠJҺnҒAҠӣ—ОҚ]ҢRӮа•әвӢӮМҚў“пӮрҚҺ•һӮөӮВӮВ–һҸBҢRӮМ“ҢӮЙҗiҸoӮөӮВӮВӮ ӮБӮҪҒB‘е–{үcӮЕӮНҒA—ҲӮй–һҸBӮЕӮМҲк‘еҢҲҗнӮЙ”хӮҰӮД3ҢВҺt’cӮМ‘қҗЭӮЖ’e–тҒAүО–CӮМ‘қҺYӮЖҠOҚ‘Ӯ©ӮзӮМҚw“ьӮИӮЗҒA•ә”хӮМҠg’ЈӮЙ“wӮЯӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA’“•ДҢцҺg ҚӮ•ҪҸ¬ҢЬҳYӮрӮөӮД•ДҚ‘‘е“қ—МӮЙ‘ҒҠъҚuҳaӮМҲҙҗщӮЙӮЮӮҜӮДҢҹ“ўӮөҺnӮЯӮДӮўӮҪҒB –һҸBҢRӮЕӮН—б”NӮжӮиӮа‘ҒӮўүр•XҠъӮЙҗж—§ӮБӮД•т“V•tӢЯӮМғҚғVғAҢRӮЙҢҲҗнӮрӢҒӮЯӮйӮұӮЖӮЙҢҲӮөӮҪҒBҠШҚ‘’“ҷ•ҢR—күәӮМҠӣ—ОҚ]ҢR(Һi—ЯҠҜ җм‘әҢi–ҫ‘еҸ«)ӮЙ“GӮМ“Ң—ғӮр•пҲНӮөӮДӮұӮМ•ы–КӮЙҢЎҗ§Ӯ·ӮйӮжӮӨ—vҗҝӮөҒA‘ж1(Һi—ЯҠҜ Қ•–ШҲЧъй‘еҸ«)ҒA‘ж4(Һi—ЯҠҜ –м’Г“№ҠС‘еҸ«)ҒA‘ж2ҢR(Һi—ЯҠҜ үң •ЫиЭ‘еҸ«)Ӯр•А—сӮөӮД–kҗiҒA‘ж3ҢR(Һi—ЯҠҜ ”T–ШҠу“T‘еҸ«)ӮН“GӮМҗј—ғӮр•пҲНӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒB –һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜ ‘еҺRҠЮ‘еҸ«ӮН–ҫҺЎ38”N2ҢҺ20“ъҒAӮұӮМ–Ҫ—ЯӮрүә’BӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAҒu–{үпҗнӮН“ъҳIҗнӮМҠЦғ–ҢҙӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМүпҗнӮМҢӢүКӮр‘Sҗн–рӮМҢҲҸҹӮЖӮ·ӮйӮжӮӨ“wӮЯӮжҒvӮЖӮөӮДҒAҗі–КӮ©ӮзӮМ—НҚUӮр”рӮҜҒA‘Ө”wҚUҢӮӮЖҸӯӮИӮў‘№ҠQӮЕ‘е‘ЕҢӮӮр—^ӮҰӮйӮжӮӨҢPҺҰӮөӮҪҒB Ҳк•ығҚғVғA‘ӨӮЕӮНҒA‘ж3ҢRӮМҚs“®ӮН’ҚҺӢӮөӮДӮЁӮиҒAҚ•Қa‘дӮМ”sҗнҢгӮа‘ҒҠъӮМҚUҗЁӮӘҢҹ“ўӮіӮкӮҪӮӘҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮН–АӮБӮҪҢг2ҢҺ21“ъ“ъ–{ҢRӮМҗј—ғӮр•пҲНӮ·ӮйҚUҗЁӮМҠJҺnӮр–ҪӮ¶ӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМҚUҗЁӮН“ъ–{ҢRӮЙӮжӮБӮДҸo’[ӮрӮӯӮ¶Ӯ©ӮкҒAҚUҗЁӮМ’ҶҠjӮЖӮИӮйғҚғVғA‘ж2ҢRӮН24“ъӮЙӮНҚUҗЁӮр’f”OӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ•т“Vүпҗн‘ж1ҠъҒ@–ҫҺЎ39”N2ҢҺ26“ъҒ`2ҢҺ28“ъҒ@
–ҫҺЎ38”N2ҢҺ26“ъҒ@Ҡӣ—ОҚ]ҢRӮНҢЎҗ§Қs“®ӮМӮҪӮЯҚвҸйӣ№ӮЙҒA‘ж1ҢRӮНҚӮ—дҺq“м•ыҚӮ’nӮЙӮ»ӮкӮјӮкҗiҸoҒA—Ӯ27“ъ—јҢRӮНӮ»ӮкӮјӮк‘O–КӮМғҚғVғAҢRӮрҚUҢӮӮөӮҪӮӘҒAғҚғVғAҢRӮа“O’кӮөӮДҚRҗнӮөҒAӮўӮёӮкӮМҗі–КӮаӮЩӮЖӮсӮЗҗi“WӮрҢ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB ‘ж3ҢRӮН28“ъӮЬӮЕӮЙҗј—ғӮЙ“WҠJҒA‘ж2ҢRӮЖ‘ж4ҢRӮНҒA–CҗнӮрҚsӮБӮДҠйҗ}ӮМ”й“ҪӮЙӮВӮЖӮЯӮҪҒBғҚғVғA‘ж2ҢRӮНҒA“ъ–{ҢRӮМҚ¶—ғӮЙ‘ОӮөӮДҚUҗЁӮЙҸoӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAүдӮӘ‘ж3ҢRӮМ“®ҢьӮр“ЗӮЭҲбӮҰҒAҚUҗЁӮр’ҶҺ~ӮөӮДӮөӮЬӮӨҒB28“ъӮЙӮИӮиҒAҚ•Қa‘д•ы–КӮ©ӮзғҚғVғAҢRӮрҢӮ”jӮөӮВӮВҗҙүНҸйӮрҗи—МҒA•т“Vҗј•ыӮЙҸoҢ»ӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮЙ‘ОӮөҒAүКҠёӮИҚs“®Ӯ©Ӯз”T–Ш‘жҺOҢRӮЕӮ ӮлӮӨӮЖ”»’fҒAӮұӮкӮрҢӮ‘ЮӮ·ӮйӮҪӮЯ—\”х‘аӮр•т“V•tӢЯӮЙҸWҢӢӮіӮ№ӮҪҒB ӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮН”T–Ш‘ж3ҢRӮЕӮИӮӯҒAҗм‘әҢi–ҫ‘еҸ«—ҰӮўӮйҠӣ—ОҚ]ҢR(‘ж11Һt’cҒAҢг”х‘ж1Һt’cҒAҢг”х‘ж16—·’cҒ@‘ј)ӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAҢRӮН“ъ–{ҢRҺе—НӮӘ•т“VӮМ“Ң•ыӮ©ӮзҗiҸoӮөӮДӮӯӮйӮаӮМӮЖ‘z’иӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ•т“Vүпҗн‘ж2ҠъҒ@–ҫҺЎ39”N3ҢҺ1“ъҒ`3ҢҺ7“ъҒ@
3ҢҺ1“ъҒ@‘Ғ’©Ӯ©Ӯз‘SҗнҗьӮЙ“nӮБӮД“ъ–{ҢRӮМ‘ҚҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAҡНҚҲӮрҢ@ӮиҒAҸбҠQ•ЁӮрҗЭӮҜӮҪғҚғVғAҢRӮМҗw’nӮНҢҳҢЕӮЕҒA‘ж2ҢRҗі–КӮНҚUҢӮӮӘҗiӮЬӮёҒA1“ъӮЕ4679–јӮМ‘№ҠQ(ӮӨӮҝҗнҺҖ1089)ӮЙӢyӮсӮҫҒB‘ж4ҢRҒA‘ж1ҢRӮЖӮаӮЙҚUҢӮӮНҗiӮЬӮёҒAүх’ІӮҫӮБӮҪӮМӮН‘ж3ҢRӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘ж3ҢRӮН1“ъӮЙҗV–Ҝ•{ҒAҺl•ы‘дӮрҗи—МӮөҒA3“ъӮЙӮНғҚғVғAҢRӮМ”ҪҢӮӮрҢӮ‘ЮӮөҒA4“ъӮЙӮН•т“VӮЬӮЕ10җ”ӮjӮҚӮМ’n“_ӮЬӮЕҗiҸoӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙҳAҢgӮөӮД‘ж2ҢRӮМҚ¶—ғӮа‘OҗiӮЕӮ«ӮҪӮӘ3ҢҺ6“ъӮЬӮЕ‘ж3ҢRӮрҸңӮӯҠeҢRӮНҒAүҹӮөӮВүҹӮіӮкӮВӮМҸу‘ФӮЕҗнӢөӮЙ’ҳӮөӮўҗi“WӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘ж3ҢRӮМ‘O–КӮМ’пҚRӮаӢӯӮӯӮИӮиҒA‘ж3ҢRӮНҚXӮЙ–k•ыӮЙүIүсӮөӮДғҚғVғAҢRӮМ‘ЮҳHӮр’fӮЖӮӨӮЖӮөӮҪҒB Ҳк•ыӮМғҚғVғAҢRӮМ3ҢҺ5“ъӮМ”ҪҢӮӮН•s”ӯӮЙҸIӮнӮБӮҪҒBғVғxғҠғA‘ж1ҢR’cӮМҸWҚҮӮӘ’xӮкҒAӮЬӮҪүдӮӘ‘ж2ҢRӮМ‘ж5ҒA‘ж8Һt’cӮМҚUҢӮӮЕҒAүE—ғ‘аӮМҲк•”ӮрҚ¶—ғҗі–КӮЙ“]—pӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©Ӯө‘ж3ҢRӮӘ•т“VӮМит•”ӮЙ“Л“ьӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪ3ҢҺ7“ъҒ@җнӢ@ӮН“®Ӯ«ҺnӮЯӮҪҒBҢг•ыӮЙ•sҲАӮрҠҙӮ¶ӮДӮўӮҪғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮНҒAғҚғVғA‘ж1ҒA‘ж3ҢRӮрҹУүНӮМҗьӮЬӮЕ“P‘ЮӮіӮ№ҒAҗVӮҪӮИ•ә—НӮр’ҠҸoӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ•т“Vүпҗн‘ж3ҠъҒ@–ҫҺЎ39”N3ҢҺ8“ъҒ`3ҢҺ10“ъҒ@
–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮӘғҚғVғAҢRӮМҢг‘ЮӮр’mӮБӮҪӮМӮНҒA3ҢҺ8“ъ0120Ғ@‘ж1ҢRҺi—Я•”Ӯ©ӮзӮМ“d•сӮЙӮжӮйҒB‘ҚҺi—ЯҠҜ‘еҺRҠЮҢіҗғӮНүьӮЯӮД‘SҢRӮЙ‘ОӮөӮД’ЗҢӮ–Ҫ—ЯӮр’BӮөӮҪҒB ‘ж1ҢRӮНӢ}җiӮөӮДғҚғVғA‘ж1ҢRӮр•т“V•tӢЯӮЙӮ ӮБӮҪғҚғVғA‘ж2ҒA‘ж3ҢRӮ©Ӯз•Ә’fӮөҒA‘ж2ҢRҒA‘ж4ҢRӮН‘O–КӮМғҚғVғAҢRӮЙ‘ОӮөӮД–ТҚUӮрҠJҺnҒA‘ж3ҢRӮН“S—дӮЙҺҠӮй“S“№ҒA“№ҳHӮрҺХ’fӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒBғҚғVғAҢRӮН‘SҢRӮМ•цүуӮр”рӮҜӮйӮҪӮЯҒA3ҢҺ9“ъүдӮӘ‘ж3ҢRӢyӮС‘ж5Һt’cҗі–КӮЙ‘ОӮө–Т—уӮИӢtҸPӮрҺАҺ{ҒAӮұӮМҗі–КӮМ“ъ–{ҢRӮНҲкҺһӢкӢ«ӮЙ—§ӮҝҒAҢг”х‘ж1—·’cӮИӮЗӮМҲк•”ӮЙӮНүу–ЕӮ·Ӯй•”‘аӮаӮ ӮБӮҪҒB ”ҪҢӮ•”‘аӮНғҖғCғҚғt’ҶҸ«ӮМҺwҠцӮ·Ӯй•а•ә29ҢВ‘е‘аҒAүО–C–с100–еӮЕҒA’ӢҠФҚUҢӮӮЙ‘ұӮ«–йҸPӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ҢRӮрӢкӮөӮЯӮҪҒB 3ҢҺ9“ъ1915ҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮН“S—дӮЙҢьӮ©ӮӨ‘ЮӢp–Ҫ—ЯӮр”ӯ—ЯҒA10“ъ–йӮЙ“ьӮиҒAүпҗнӮН“ъ–{ҢRӮМ‘еҸҹӮрӮаӮБӮДҸIӮнӮиҒA•т“VӮНүдӮӘҺи’ҶӮЙ—ҺӮҝӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ•т“VүпҗнҢгӮМғҚғVғAҢRҒ@
•т“VӮ©ӮзҺl•ҪҠXӮЙ‘ЮӢpӮөӮҪ’јҢгӮМ3ҢҺ15“ъҒ@“GҸ«ғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮН–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜӮр”л–ЖӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөҢR’c’·ӮЕӮа—ЗӮўӮ©Ӯз–һҸBҢRӮЙ—ҜӮЬӮиӮҪӮўӮЖӮўӮӨ”MҲУӮӘ”FӮЯӮзӮкҒA3ҢҺ21“ъҗVӮҪӮЙ‘ҚҺi—ЯҠҜӮЖӮИӮБӮҪғҠғlғEғBғbғ`‘еҸ«ӮМҢг”CӮЖӮөӮД‘ж1ҢRҺi—ЯҠҜӮЙ”CӮ¶ӮзӮкӮҪҒBҢүӮӯҚ~ҠiҗlҺ–ӮрҠГҺуӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮҪӮөӮ©ӮЙғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ«ӮМҺwҠцӮөӮҪҚмҗнӮНҒA‘O”N5ҢҺ1“ъӮМҠӣ—ОҚ]үпҗнҲИ—ҲӮЩӮЖӮсӮЗӮ·ӮЧӮДӮЙ”s–kӮөҒA—·ҸҮ—vҚЗӮаҺёӮБӮДӮўӮҪҒBғҚғVғA’ҶүӣӮӘғNғҚғpғgғLғ“Ӯр‘ҚҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮД•s“KҠiӮЖ”FӮЯӮҪӮұӮЖӮНҺсҚmӮіӮкӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҒAғiғ|ғҢғIғ“җн‘ҲӮЕӮаӮіӮзӮЙӮНҢгӮМ“Жғ\җнӮЕӮаҒA”s–kӮЖҢг‘ЮӮМҳA‘ұӮ©ӮзҚL‘еӮИғҚғVғAҚ‘“аӮЕ“GҢRӮр”ж•ҫӮіӮ№ҚЕҸI“IӮЙҸҹ—ҳӮр’НӮЮҒAӮЖӮўӮӨӮМӮӘғҚғVғAҢRӮМ“`“қ“I—U’vҗн—ӘӮЕӮ ӮйҒB •т“VүпҗнӮЬӮЕӮН”s–kӮЖҢг‘ЮӮМҳA‘ұӮҫӮБӮҪӮӘҒAҠщӮЙ“ъ–{ҢRӮНҚUҗЁҢАҠE“_ӮЙ’BӮөӮДӮўӮҪҒBӮіӮзӮЙҸҹӮБӮҪҚмҗнӮЕӮ ӮБӮДӮа“ъ–{ҢRӮМ‘№ҠQӮМ•ыӮӘ‘ҪӮўӢЗ–КӮа‘¶ҚЭӮ·ӮйҒBҲкӮВҲкӮВӮМ–hҢдҗ퓬ҒA‘S‘МӮЖӮөӮДӮМ’x‘ШҚs“®ӮЖӮөӮДҢ©ӮкӮОғҚғVғAҢRӮМҚмҗнӮНҗ¬ҢчӮөӮҪӮЖӮўӮҰӮжӮӨҒBӮҪӮҫӮө–hҢдӮҫӮҜӮЕӮНҚЕҸI“IӮИҸҹ—ҳӮр’НӮЮӮұӮЖӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҫӮЬӮҫ—]—НӮМӮ ӮйғҚғVғAҢRӮЙӮЖӮБӮДҒAӮЬӮіӮЙӮұӮкӮ©ӮзӮӘҗі”OҸкӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘ—\‘zӮр—yӮ©ӮЙүzӮҰӮДҠжӢӯӮИ“ъ–{ҢRҒAҺРүп•sҲАӮр‘қ‘еӮөӮДӮўӮҪҚ‘“аҺ–ҸоӮИӮЗӮ©ӮзҒA—IҒXӮЖ“`“қ“Iҗн—ӘӮр“WҠJӮ·ӮйӮМӮр‘ТӮБӮДӮЁӮкӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒBғNғҚғpғgғLғ“•АӮСӮЙғҚғVғA’ҶүӣӮМ‘еӮўӮИӮйҢлҺZӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҢг“ъ–{ҢRӮН“S—дҒA•т“VҠФӮЙҒAӮЬӮҪғҚғVғAҢRӮНҺе—НӮрҢцҺе—д•tӢЯӮЙ“WҠJҒAӮ»ӮкӮјӮкҺўҢгӮМҚмҗнӮрҸҖ”хӮөӮВӮВҒAӢxҗнӮрҢ}ӮҰӮҪҒB —ӨҗнӮНӮұӮМүпҗнӮрӮаӮБӮДҺ–ҺАҸгҸI—№ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүпҗнӮМҢӢүКҒ@
–{үпҗнӮНҒA•ә—Н—тҗЁӮИ“ъ–{ҢRӮӘ•ъ’_ӮИ•пҲНӮрҠёҚsӮөӮД‘еҸҹӮр“ҫӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒAҚЕҢгӮМ’iҠKӮЕ•пҲН–ФӮрҠ®җ¬ӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒA‘еӢҷӮр“ҰӮөӮҪҢ`ӮЙӮИӮБӮҪҒBҗlҲхҒAүО–CҒA’e–тӮМ•s‘«ӮӘӮ»ӮМ’v–Ҫ“IӮИҢҙҲцӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAүпҗнҠъҠФӮӘ24“ъҠФҒA—јҢRҚҮҢv–с60–ңӮЙӮаӢyӮФ‘еҢRӮМҗ퓬ӮНҒAҗўҠE—ӨҗнҺjҸгӢу‘OӮМ‘еүпҗнӮЕӮ ӮиҒAҗўҠEӮМ•әҠwҠEӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA“ъҳIҗн‘Ҳ‘OӮМҗн‘ҲӮЕӮНҒA“ъ–vӮМ‘ҒӮў“~ӢG“с“ъҠФӮЙӮнӮҪӮБӮҪ—бҠOӮрҸңӮ«“ъ–vӮЬӮЕӮЙҸҹ”sӮНҢҲӮөӮДӮўӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЕҚмҗнӮМ—рҺjӮӘ‘еӮ«Ӯӯ•ПӮнӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB –һҸBҚ‘ҢR‘ҚҺi—ЯҠҜ‘еҺRҠЮҢіҗғӮНҒA•т“VүпҗнҢгӮМ3ҢҺ13“ъҒ@ҺRҢ§—L•ьҺQ–d‘Қ’·ӮЙҒAҗн—ӘӮЖҗӯҺЎ(җӯ—Ә)ӮЖӮӘҲк’vӮөӮИӮҜӮкӮОҚмҗнӮН–іҲУ–ЎӮЕӮ ӮйӮЖҸгҗ\ҒAӮұӮкӮрҺуӮҜӮҪҺRҢ§ҺQ–d‘Қ’·ӮН3ҢҺ23“ъҒu‘жҲкӮН“GӮНӮИӮЁ–{Қ‘ӮЙӢӯ‘еӮИ•ә—НӮр—LӮ·ӮйӮМӮЙ”ҪӮөҒAүдӮНӮ ӮзӮсҢАӮиӮМ•ә—НӮр—pӮўҗsӮӯӮөӮДӮўӮйҒB‘ж“сӮЙҠщӮЙ‘Ҫҗ”ӮМҸ«ҚZӮрҺёӮўҒAҚЎҢг—eҲХӮЙ•вҸ[Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒBҒvӮЖӮМ—қ—RӮ©ӮзҒuҺзҗЁӮрӮЖӮйӮаҚUҗЁӮрӮЖӮйӮа—eҲХӮЙ•ҪҳaӮрүс•ңӮ·Ӯй–]ӮЭӮӘӮИӮўҒvӮЖӮМҲУҢ©Ҹ‘ӮӘҲЙ“ЎҺс‘ҠҲИүәӮМҠt—»ӮЙҺҰӮіӮкӮҪҒB ӮөӮ©ӮөғҚғVғA‘ӨӮЙӮНҲЛ‘RӮЖӮөӮДҚuҳaӮЙүһӮ¶ӮйӢC”zӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙӮжӮБӮДҗ§ҠCҢ Ӯр’DӮҰӮОҒA–һҸBӮМ“ъ–{ҢRӮЦӮМ•вӢӢҳHӮӘҺХ’fӮЕӮ«ҒAҚЕҸI“IӮЙӮНғҚғVғAӮӘҸҹ—ҳӮ·ӮйӮЖҠmҗMӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB ’ҳӮөӮӯ—DҗЁӮИғҚғVғAҢRӮЙ‘ОӮ·Ӯй•т“VӮЕӮМ—ӨҸгҢҲҗнӮЕӮМҸҹ—ҳӮНҒA—сҚ‘ӮМҸЬҺ^ӮрҸWӮЯҚuҳaӮр‘ЈӮ·ӢCү^ӮрҗiӮЯӮҪӮӘҒAҢҲ’и“I‘ЕҢӮӮр—^ӮҰӮйӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮзӮёҺс”]•”ӮМ—J—¶ӮНҲЛ‘Rҗ[Ӯ©ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮөӮД–{җн‘ҲӮМҺ“—YӮрҢҲӮ·ӮйҚЕҢгӮМҢҲҗнӮӘҒAҚЎ“xӮНҠCҸгӮЙӮЁӮўӮД“WҠJӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ6 | |
|
ҒЎғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ‘қҢӯҢҲ’иҒ@
“ъҳIҗн‘ҲӮНҗўҠE’ҶӮМ—\‘zӮЙ”ҪӮөӮДғҚғVғAҢRӮМ”s–kӮЙӮВӮ®”s–kӮЙҸIӮнӮБӮДӮўӮҪҒB—ӨҗнӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAҸ¬Қ‘“ъ–{ӮМ—ӨҢRӮӘҗўҠEҚЕӢӯӮЖҢДӮОӮкӮйғҚғVғA—ӨҢRӮЙ“O’к“IӮИ‘ЕҢӮӮр—^ӮҰӮДӮўӮҪҒBӮЬӮҪғҚғVғAҠCҢRӮа“ъ–{ӮМ—ьҚҮҠН‘аӮЙӮжӮБӮД‘е‘ЕҢӮӮрҺуӮҜӮДӮўӮҪҒB–ҫҺЎ37”N8ҢҺӮЙӮЁӮұӮИӮнӮкӮҪү©ҠCҠCҗнӮЖүUҺRү«ҠCҗнӮЙӮжӮБӮДғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМҗн—НӮН’ҳӮөӮӯ’бүәҒAҺc‘¶•ә—НӮаҗhӮӨӮ¶ӮД—·ҸҮҚ`“аӮЙ•ВӮ¶ҚһӮЯӮзӮкӮДӮўӮҪҒB Ӯ»ӮӨӮөӮҪҸуӢөӮр—J—¶ӮөӮҪғҚғVғAҚc’йғjғRғүғC“сҗўӮНҒAҗнӢЗӮрҲкӢ“ӮЙ”ТүсӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒA‘ж“с‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а(ҲИүәғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖӢLӮ·)Ӯр•Тҗ¬ҒAҺi—Я’·ҠҜӮЙӮНҒAҺҳҸ]•җҠҜҒEҢR—Я•”’·ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[ҸӯҸ«(ҢгӮЙ’ҶҸ«)Ӯр”C–ҪӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМҗw—eӮНҒAҗVүsҗнҠН5җЗӮЖӢҢҺ®җнҠНӮрҺе—НӮЙ•вҸ•ҠН’ш‘Ҫҗ”Ӯр”zӮөӮҪӢӯ—НӮИӮйҠН‘аӮЕҒA“r’ҶӮЙҲкӮВӮаҠо’nӮМӮИӮў18000ҠC—ўӮр’ҙӮҰӮД’·Ӣл—·ҸҮӮЙҢьӮ©ӮӨӮЖӮўӮӨү“‘еӮИҚмҗнӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҢҲ’иӮН4ҢҺ––ӮЙ”ӯ•\ӮіӮкӮҪӮӘҒAҠН’шӮМҗ®”хӮЙҺиҠФҺжӮиҒAҺАҚЫӮЙӮН7ҢҺ4“ъӮЙӮИӮБӮД“ҜҠН‘аӮӘ•Тҗ¬ӮіӮкҒAғҠғoғEҢRҚ`ӮМҸo”ӯӮН–ҫҺЎ37”N10ҢҺ15“ъӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҠeҠН‘DӮНҒAӮ»ӮМ–јӮМӮЖӮЁӮиғoғӢғgҠCӮМӮжӮӨӮИ“аҠCӮЕӮМү^—pӮрҚl—¶ӮөӮДҢҡ‘ўӮіӮкӮҪӮҪӮЯҒA•ңҢі—НӮӘҺгӮӯҒAҠНҺс•”ӮМ‘•ҚbӮӘҺгӮўӮЖӮўӮӨӢӨ’КӮМҺг“_ӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙӮНҸЖҸҖӢ@Ӯв‘ӘӢ—ӢV“ҷӮМ‘•”хӮЙӮаҢҮҠЧӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҒBүБӮҰӮДҸж‘gҲхӮаҒAӢ}зҜ”_‘ә•”Ӯ©Ӯз’Ҙ”ӯӮіӮкӮҪҺТӮӘ‘ҪӮӯҒAҸoҚ`Ӯр‘OӮЙҗнҸp“IӢіҲзӮрҺАҺ{Ӯ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮиҒAҚqҠC“r’ҶӮЙӮЁӮўӮДӮа‘ҖҠНҢP—ыӮв–CҸpҢP—ыӮр”Ҫ•ңӮіӮ№ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB ‘SҚqҳHӮр‘–ҚqӮ·ӮйӮЙӮН90“ъҒAӮіӮзӮЙҗО’YҒAҗ…җПҚһӮЭӮИӮЗӮМӮҪӮЯӮЙ60“ъӮМ“ъҗ”ӮӘ—\’иӮіӮкҒA’©‘NҠCӢ¬ӮЙ’BӮ·ӮйӮМӮН150“ъҢгҒAӮВӮЬӮиҸҮ’ІӮЙҚqҠCӮЕӮ«ӮкӮОҒA3ҢҺ’ҶҸ{ӮЙӮН“ъ–{–{“yӢЯӮӯӮЙ“һ’BӮЕӮ«ӮйӮұӮЖӮӘ—\‘zӮіӮкӮҪҒB җ”Ҹ\җЗӮЙӮаӮМӮЪӮй‘еҠН‘аӮМҚqҠCӮНҒA”R—ҝӮЖӮМӮҪӮҪӮ©ӮўӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBҗО’YӮНӢЙӮЯӮД”R—ҝҢш—ҰӮӘҲ«ӮӯҒAӮЁӮЁӮЮӮЛ3ҒA4“ъӮІӮЖӮЙ•вӢӢӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒB‘еҚqҠCӮЙ”пӮвӮіӮкӮйҗО’YӮМ—КӮНҒA–с24–ңғgғ“ӮЖӮўӮӨӢБӮӯӮЧӮ«—КӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮзӮНҒAҚqҳH“r’ҶӮМҚ`ӮЙ”z’uӮіӮкӮДӮўӮйҠOҚ‘Ӯ©ӮзҢЩӮў“ьӮкӮҪҗО’Y‘DӮ©Ӯз•вӢӢӮрҺуӮҜӮйӮӘҒAҠН‘аҺ©җgӮа‘ҪӮӯӮМҗО’Y‘DӮрҸ]ӮҰҒAҗH—ҝҒAҗ…Ӯр–һҚЪӮөӮҪү^‘—‘DӮа“ҜҚsӮіӮ№ӮДӮўӮҪҒB •вӢӢҗMҚҶӮӘ”ӯӮ№ӮзӮкӮйӮЖҒA‘еҢ^ӮМҗО’Y‘DӮӘҠН’шӮЙҗЪӢЯӮө‘D‘МӮрүЎ•tӮҜӮ·ӮйҒB”gӮЙ—hӮкӮй’ҶӮЕӮМҗЪҢҪӮН”сҸнӮЙҠлҢҜӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA”gӮМүёӮ©ӮИ“ъӮНҒAҸn—ыӮөӮҪ‘Җ‘ЗӮЙӮжӮБӮДӮ»ӮкӮрүВ”\ӮЙӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҗО’Y‘DӮМғNғҢҒ[ғ“ӮЕ’ЭӮиҸгӮ°ӮзӮкӮҪҗО’YӮМ•UӮвҗ…ӮӘҚb”ВӮЙҲЪӮіӮкҒAӢ@ҠЦ•”ҲхӮҪӮҝӮӘҠН“аӮЙү^ӮСҚһӮЮҒBӮұӮМҗО’YӮМ—mҸг•вӢӢӮНҒAғҚғVғAҠCҢRӮӘҗ¶ӮЭҸoӮөӮҪүжҠъ“IӮИҚмӢЖ•ы–@ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAӮӨӮЛӮиӮв”gӮМҚӮӮў—mҸгӮЕӮМҚмӢЖҺһӮНҒAғnғVғPӮвғJғbғ^Ғ[ӮЙҗО’YӮрҗПӮЭ‘ЦӮҰҒAӮіӮзӮЙӮ»ӮкӮр•вӢӢӮ·ӮйҠН’шӮЙҲЪӮіӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮёҒA”сҸнӮИҚў“пӮр”әӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҠЧ—Һ‘OӮМӢЙ“ҢҸоҗЁҒ@
ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ”hҢӯӮр”ӯ•\ӮөӮҪ‘OҢгҒAӢЙ“ҢӮЕӮН—·ҸҮҚ`•ВҚЗҚмҗнӮрӮЁӮұӮИӮБӮДӮўӮҪүдӮӘҠН’шӮӘҺҹҒXӮЖҗG—ӢҒAҸХ“ЛӮЕҺёӮнӮкӮйӮЖӮўӮӨҺ–ҢҸӮӘ–u”ӯӮөӮДӮўӮҪҒB–ҫҺЎ37”N5ҢҺ14“ъӮЙҒA“с“ҷҸ„—mҠНҒuӢg–мҒvӮӘ”Z–¶ӮМӮҪӮЯ‘•ҚbҸ„—mҠНҒuҸt“ъҒvӮЖҸХ“ЛҒAҒuӢg–мҒvӮН’ҫ–vӮө317–јӮӘҺҖ–SҒAҒuҸt“ъҒvӮН‘№ҸқӮөӮҪҒBӮЬӮҪӮ»ӮМ—Ӯ“ъӮЙӮНҗVүsҗнҠНҒuҸүҗЈҒvӮӘ“с“xҗG—ӢӮө’ҫ–vҒA•ӣ’·ҲИүә492–јӮӘҗнҺҖҒAӮ»ӮМ’јҢгҒAҗнҠНҒu”Ә“ҮҒvӮаҗG—ӢӮөӮД’ҫ–vӮөӮҪҒB —ьҚҮҠН‘аӮМҺе—НӮЕӮ Ӯй6җЗӮМҗнҠНӮН4җЗӮЙҢғҢёҒAҗн—НӮМ1Ғ^3ӮӘҺёӮнӮкӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ—ҲҚqӮӘ“`ӮҰӮзӮкӮйҚЕ’ҶӮЙӮ ӮБӮДҠCҢRӮМ”Я’QӮН‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮМҚ ғҚғVғA“Ң—mҠН‘аӮНҒAҸC—қ’ҶӮрҠЬӮЯӮД5җЗӮМҗнҠНӮӘ—·ҸҮҚ`“аӮЙҗцӮсӮЕӮўӮҪҒBӮ»ӮМҸгғҚғVғA–{Қ‘Ӯ©Ӯз“ҢҚqӮ·ӮйғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙӮНҒAҗнҠН7җЗӮӘҺе—Н(ҺАҚЫӮН8җЗ)ӮЕӮ ӮйӮЖ“`ӮҰӮзӮкҒAӮұӮкӮзӮӘҚҮ—¬Ӯ·ӮкӮОғҚғVғAӮН12җЗӮМҗнҠНӮр—LӮ·Ӯй‘еҠН‘аӮЖӮИӮйҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө—ьҚҮҠН‘аӮНҒAӮнӮёӮ©4җЗӮМҗнҠНӮЕ‘ОҚRӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBҸ„—mҠНҲИүәӮМҠН’шӮН—ьҚҮҠН‘аӮМ•ыӮӘҸҹӮБӮДӮўӮйӮЖӮНү]ӮҰҒAҺе—НҠНӮМҗДҺЛӮЕҠН‘аҲкҢҲӮМ‘еҗЁӮНҢҲӮ·ӮйҒAӮЖӮўӮӨ“–ҺһӮМҠCҗнӮМҸнҺҜӮ©ӮзҚlӮҰҒAӮұӮМӮЬӮЬӮЕӮН“ъ–{ҠCҢRӮМ”s–k•KҺҠӮН’NӮМ–ЪӮЙӮа–ҫӮзӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪҒB –ҫҺЎ37”N12ҢҺ5“ъҒ@—·ҸҮӮМ203ҚӮ’nӮӘҠЧ—ҺӮөӮҪҒBӮ»ӮМҺR’ёӮ©ӮзӮН—·ҸҮҚ`“аӮЖҺsҠXӮЖӮӘҲк–]ӮМӮаӮЖӮЙҢ©үәӮлӮ·ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBүдӮӘҸd–CӮН“GҠНӮЙ‘ОӮөӮД–CҢӮӮрҠJҺnҒAҗнҠН5җЗ’Ҷ4җЗҒAҸ„—mҠН2җЗӮЩӮ©ӮӘҢӮ’ҫҒAҺcӮйҗнҠНҒuғZғ”ғ@ғXғgғ|ғҠҒvӮаүдӮӘҗ…—Ӣ’ш‘аӮЙӮжӮБӮД‘е”j’…’кӮөҒA—·ҸҮҠН‘аӮН‘S–ЕҒA—ьҚҮҠН‘аӮНғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙ‘Қ—НӮрӢ“Ӯ°ӮД—§ӮҝҢьӮ©ӮӨ‘ФҗЁӮрӮЖӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“ҢҚqҢoүЯ 1Ғ@
ғҠғoғEҢRҚ`Ӯр4ҸW’cӮЙӮнӮ©ӮкӮДҸo”ӯӮөӮҪҠН‘аӮНҒAҸoҚ`’јҢгӮМҲГ–йӮМ–kҠCӮЕүpҚ‘Ӣҷ‘D’cӮр“ъ–{ӮМҗ…—Ӣ’шӮЖҢл”FӮөӮД–CҢӮӮ·ӮйҺ–ҢҸ(ғhғbғKҒ[ҒEғoғ“ғNҺ–ҢҸ)ӮрӢNӮұӮөӮҪҒB‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҒAӢ}‘ўӮМҠН‘аӮЙӮжӮй—ы“xӮМ’бӮіӮЖҺwҠцҢn“қӮМҺгӮіӮр–\ҳIӮөӮҪҢ°’ҳӮИҺ–—бӮЕӮ ӮиҒAҺь•УҸ”Қ‘ӮМ•ЁҸОӮўӮЖӮИӮБӮҪӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҠJҗнӮМү\ӮӘӮіӮіӮвӮ©ӮкӮҪӮЩӮЗүpҳIҠЦҢWӮрҲ«ү»ӮіӮ№ӮҪҒB ӮұӮМүeӢҝӮаӮ ӮиҒA“ъ–{ӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ӮЕӮ ӮйүpҚ‘Ӯ©ӮзӮНҠН‘аӮМҺҰҲРү^“®ҒAғtғүғ“ғXӮМҚ`ҳp—ҳ—pӮМҗ§Һ~ҒAҗО’YҚw“ьӮМ–WҠQ“ҷӮрҺуӮҜӮДү“җӘӮМӢк“пӮНҲк‘wүБҸdӮіӮкӮҪҒBӢx—{Ӯв•вӢӢӮЙ“KӮөӮҪҚ`ҳpӮНғҚғVғAӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ғtғүғ“ғXӮМҗЁ—НүәӮЙӮ Ӯй2ҒA3ӮрҸңӮўӮДҒA“r’ҶӮЗӮұӮЙӮаӮИӮӯҒAү“‘еӮИҚqҳHӮМ‘е”јӮНғCғMғҠғXҠCҢRӮМҗЁ—НүәӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA—mҸг•вӢӢӮЖӮўӮӨҚў“пӮИҚмӢЖӮрҢJӮи•ФӮіӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB •§—Мғ}ғ_ғKғXғJғӢ“Ү–kҠЭӮМғmғVғx”‘’nӮЖғCғ“ғhғVғi”ј“ҮғJғҖғүғ“ҳpӮҫӮҜӮӘҒA40җ”җЗ12000–јҸ«•әӮМ‘еү“җӘӮМӢx—{ҒE•вӢӢ’nӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМҠН‘аӮЙ‘ОӮөӮДғtғүғ“ғXҗӯ•{ӮМ‘Ф“xӮНҒAүp•§ҠЦҢWӮрҚl—¶ӮөӮД—вӮҪӮ©ӮБӮҪҒBҲ«үuӮМӮНӮСӮұӮйҺЬ”MӮМ–ўҠJ’nғmғVғx”‘’nӮЕӮНҒA“–Ҹү2ҸTҠФӮМ’в”‘—\’иӮӘ2ғ–ҢҺӮЙӮаү„ӮСҒAҸ«•әӮМҢ’ҚNҸу‘ФӮНӢ}‘¬ӮЙҲ«ү»ҒAҢRӢIӮНӢЙ’[ӮЙҠЙӮсӮҫҒBғAғtғҠғJҠCҠЭүҲӮўӮМҠCҗ}ӮН•sҗіҠmӮИӮаӮМӮӘ‘ҪӮӯҒAҠН‘DӮМҢМҸбӮа‘ҠҺҹӮўӮҫҒBғҚғVғAҗlӮЙӮЖӮБӮДҺЬ”MӮМ’nӮН‘ПӮҰӮӘӮҪӮўӮаӮМӮӘӮ ӮиҒAү^‘—‘DҒuғ}ғүғCғAҒvӮЕӮН–\“®ӮӘӢNӮұӮБӮҪ’цӮЕӮ ӮБӮҪҒB –ҫҺЎ38”N1ҢҺ1“ъҒ@–{Қ‘Ӯ©ӮзҗіҺ®ӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮӘ‘S–ЕӮөӮҪӮұӮЖӮӘ“`ӮҰӮзӮкҒA—·ҸҮҠН‘аӮЖҚҮ—¬ӮөӮДҲі“|“IӮИҗн—НӮЕҢҲҗнӮЙ—ХӮЮӮЖӮўӮӨ–Ъҳ_Ң©ӮН’ЧӮҰӢҺӮйҒBҚ“”MӮЖҢғҳQӮМғCғ“ғh—mӮрҢoӮДҒA4ҢҺ14“ъӮҪӮЗӮи’…ӮўӮҪ•вӢӢ’nҒ@ғxғgғiғҖӮМғJғҖғүғ“ҳpӮЕӮаҒAғtғүғ“ғXӮМ‘Қ“ВӮН–{Қ‘ӮМҺwҺҰӮЙҠоӮГӮўӮД3ғJғCғҠ—МҠCҠOӮЦӮМ’в”‘ӮрҺе’ЈҒAӮіӮзӮЙӮНҗО’YӮМӢҹӢӢӮаӢ‘”ЫӮөӮҪҒBӮ»ӮМҚ ғXғGғYү^үНӮрҢoӮДҚҮ—¬ӮөӮҪҺx‘аҺi—ЯҠҜ(‘ж2җнҠНҗн‘аҺi—ЯҠҜ)ғtғFғҠғPғӢғUғҖҸӯҸ«ӮӘ”]ҲмҢҢӮЕ“|ӮкҒAҗёҗ_җҠҺгӢC–ЎӮМғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜӮНҒA’xӮкӮД“һ’…Ӯ·ӮйӮНӮёӮМғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ҺwҠцӮМ‘ж3ҠН‘аӮр‘ТӮҝӮИӮӘӮз4“ъҠФӢЯҠCӮЙ—VңTҒA4ҢҺ26“ъғJғҖғүғ“ҳp–k•ы60ҠC—ўӮЙӮ Ӯйғ”ғ@ғ“ҒEғtғHғ“ҳpүҲҠЭӮрңfңrӮөӮДҒAӮұӮұӮЕӮа20җ”“ъ‘ТӢ@Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB ҢӢӢЗғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒAӮұӮМ”сҸнҺҜӮИӮЬӮЕӮМ’·ҠъҒE’·“rӮМ‘еү“җӘӮЕҒAӮ·ӮЕӮЙҢ’ҚNӮрҠQӮөҺmӢCӮНҹң‘rӮөҢRӢIӮН’oҠЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҒAҺАҗн—НӮӘ’ҳӮөӮӯ’бүәӮөӮҪҸу‘ФӮМӮЬӮЬҒAү^–ҪӮМ‘О”nү«ӮЦӮЖҢьӮ©ӮӨӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠН‘аӮМҢ}ҢӮ‘ФҗЁ 1Ғ@
—·ҸҮҠЧ—ҺҢгҒA—ьҚҮҠН‘аӮНҲк•”ӮЕғEғүғWғIҠН‘аӮМҠДҺӢҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҸо•сҺыҸW“ҷӮрҚsӮўӮИӮӘӮзҒA’ҖҺҹ“а’nӮМҠCҢRҚHҸұӮЕҠН’шӮМҗ®”хҒE•вӢӯҒEӢx—{ӮрҚsӮўүsӢCӮрүс•ңӮөӮҪҒBӮұӮкӮзӮМҠН’шӮНҒA“ъҳIҗн‘Ҳ–u”ӯҲИҚ~ҒAҗmҗмҚ`ҠOӮМҠCҗнҒA—·ҸҮҚ`ҠпҸPҒAү©ҠCҠCҗнӮМ‘§ӮВӮ®ҠФӮаӮИӮўҠCҗнӮЙӮжӮБӮД‘№ҸқӮвҢМҸбҢВҸҠӮӘ‘ұҸoӮөҒA–һҗg‘nбwӮЙӢЯӮўҸу‘ФӮЕҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҢ}ӮҰҢӮӮВ‘ФҗЁӮЙӮН’цү“Ӯ©ӮБӮҪҒB —ьҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY‘еҸ«ӮНҒA12ҢҺ30“ъ–ҫҺЎ“VҚcӮЙҸг‘tҢгҒA—Ӯ”N2ҢҺ6“ъ“ҢӢһӮр—сҺФӮЕҸo”ӯҒAҢаҢRҚ`Ӯ©ӮзҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvӮЙҸжӮиҚһӮсӮҫҒB2ҢҺ14“ъҒ@ҠН’шӮр—ҰӮўӮДҢаҢRҚ`Ӯр”І•dҒA21“ъӮЙӮН’©‘N“мҠЭӮМ’БҠCҳpӮЙҸWҢӢӮө–ТҢP—ыӮрҚsӮБӮҪҒB“ҢӢҪ’·ҠҜӮНӢZ—КӮМ–КӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҗёҗ_ӮМҢP—ыӮа‘УӮзӮёҒAҒuӢ@җжӮрҗ§Ӯ·ӮйӮНҗнӮўӮМҸн–@ӮИӮиҒvӮЖ—@ӮөҒu•S”ӯ•S’ҶӮМ–CҲк–еӮН•S”ӯҲк’ҶӮМ–C•S–еӮЙҸҹӮйҒvӮЖҢPҺҰӮөӮҪҒB ҢP—ыӮН–Т—уӮрӢЙӮЯӮҪҒBҗwҢ`ү^“®ӮӘҢJӮи•ФӮөҚsӮнӮкҒA“G”ӯҢ©Ӯ©Ӯз—vҢӮҗнҒA–йҠФӮМҸPҢӮҒA’ЗҢӮӮ©ӮзҢӮ–ЕӮЦӮЖҲкҳAӮМҚUҢӮҢP—ыӮН’Ӣ–йӮрӮнӮ©ӮҪӮКҢғӮөӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB10“ъҠФӮЙ•ҪҺһӮМ1”NҠФ•ӘӮаӮМҢP—ы—p–C’eӮрҸБ”пӮөӮҪӮЩӮЗӮЕҒAӮұӮМҠФӮЙ–CҢӮӮМӢZ—КӮН–с3”{ӮЙҢьҸгӮөӮҪӮЖӮўӮнӮкҒA’БҠCҳpӮМ“аҠOӮЙӮНҺАҗнӮіӮИӮӘӮзӮМҢөӮөӮўҢP—ыӮӘ“WҠJӮіӮкӮҪҒB—ьҚҮҠН‘аӮНҗнҠНӮМҗ”ӮЕӮН—тӮБӮДӮўӮҪӮӘҒA‘¬—НӮЖ’ҶҸ¬ҢыҢaӮМ–Cҗ”ӮЕҸҹӮиҒAҺmӢCӮЖӢZ”\ӮИӮзӮСӮЙүәҗЈүО–тӮМҲР—НӮЕӮН’ҳӮөӮӯҸҹӮБӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠН‘аӮМҢ}ҢӮ‘ФҗЁ 2Ғ@
ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҚМӮйӮЧӮ«“№ӮН“сӮВҚlӮҰӮзӮкӮҪҒB 1Ғ@җ퓬ӮрҠoҢеӮМҸгӮЕ1“ъӮа‘ҒӮӯғEғүғWғIғXғgғbғNҢRҚ`ӮЙ’јҚqҒAӮұӮұӮрӢ’“_ӮЙүьӮЯӮДҚмҗнӮрҠJҺnӮ·ӮйҒB 2Ғ@‘дҳpҒEҗҙҚ‘“мҠЭӮЬӮҪӮНӮіӮзӮЙ“м•ыӮЙҚӘӢ’’nӮрҠl“ҫӮөҒA”ҪҢӮӮМҺһҠъӮр‘_ӮўӮИӮӘӮз“ъ–{ӮМ”wҢгӮрӢәӮ©Ӯ·ҒB ү“җӘӮМ“r’ҶӮЕӮ·Ӯз”R—ҝ•вӢӢӮЙ”YӮЬӮіӮкӮҪғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҒAүьӮЯӮД“м•ыӮЙӢ’“_ӮрӮВӮӯӮиҒAӮ»ӮұӮЕ•вӢӢӮрҚsӮӨӮЖӮНҚlӮҰ“пӮӯҒAҢӢӢЗӮН1ҲДӮрҚМ—pӮ·ӮйӮаӮМӮЖ”»’fӮөӮҪҒB ӮЕӮНҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒA‘О”nҠCӢ¬ҒA’ГҢyҠCӢ¬ӮМӮўӮёӮкӮр’КүЯӮ·ӮйӮМӮ©ҒAӮіӮзӮЙӮНҸ@’JҠCӢ¬Ӯ©ӮзүIүсӮ·ӮйӮМӮ©ҒB 1Ғ@ҚЕ’ZғRҒ[ғXӮЕӮ Ӯй‘О”nҠCӢ¬(’©‘NҠCӢ¬)Ӯр’КүЯӮ·ӮйҒB 2Ғ@“ъ–{ҠН‘аӮМҲУ•\ӮрӮВӮӯҚмҗнӮ©ӮзҒA’ГҢyҠCӢ¬ӮЬӮҪӮНҸ@’JҠCӢ¬Ӯр’КүЯӮ·ӮйҒB ’ГҢyҠCӢ¬ӮвҸ@’JҠCӢ¬Ӯ©ӮзӮНҠmӮ©ӮЙҚs“®ӮНүBӮ№ӮйӮӘҒAӮұӮМҺһҠъӮН—јҠCӢ¬ӮЖӮа”Z–¶ӮӘ—§ӮҝҚһӮЯӮйҒB’n—қӮЙ•sҲД“аӮЕ’·ӮўҚqҠCӮЕ”ж•ҫӮөӮДӮўӮй‘еҠН‘аӮӘ’КүЯӮ·ӮйӮМӮНӢЙӮЯӮДҚў“пӮЕӮ ӮйҒBҸХ“ЛӮвҚАҸКӮМҠлҢҜӮр–`ӮөӮДӮЬӮЕҒAҗTҸdӮИғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜӮӘӮұӮМғRҒ[ғXӮр‘I‘рӮ·ӮйӮЖӮНҺvӮҰӮИӮўҒB ”\“o”ј“Үү«ӮЙӮД‘ТӢ@ӮөӮўӮёӮкӮ©ӮзӮа‘ОүһӮЕӮ«ӮйҲДӮаҢҹ“ўӮіӮкӮҪӮӘҒA“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮМҢҲҗSӮЙӮжӮиҒAҚЕҸI“IӮЙӮН‘О”nҠCӢ¬ӮЙӮД‘ТӢ@Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB —ьҚҮҠН‘аӮМҢ}ҢӮҚмҗнӮНҒAҚмҗнҺQ–dҸHҺRҗ^”VӮӘҚlҲДӮөӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҳA‘ұ4’Ӣ–йӮЙӮнӮҪӮйҺө’i”х(Ӯ©ӮЬӮҰ)ӮМҗн–@ӮЕҒAҳAҢgӮөӮҪ”gҸуҚUҢӮӮЙӮжӮБӮДғEғүғWғIғXғgғbғN“һ’…‘OӮЙ“GҠН‘аӮМҠ®‘Sҹr–ЕӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ“ҢҚqҢoүЯ 2Ғ@
ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜҲИүәӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙӮЖӮБӮДҒA‘О”nҠCӢ¬Ӯр’КүЯӮ·ӮйӮұӮЖӮӘғEғүғWғIғXғgғbғNҢRҚ`ӮЙҢьӮ©ӮӨҚЕ’ZғRҒ[ғXӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҸ\•ӘҸі’mӮөӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮкҢМҒAӮ ӮҰӮД‘ҫ•Ҫ—mҸгӮрүIүсӮөӮДҒA’ГҢyҒAҸ@’JӮМӮўӮёӮкӮ©ӮМҠCӢ¬Ӯр’КүЯӮ·ӮйғRҒ[ғXӮаҸ\•ӘҚlӮҰӮзӮкӮҪӮӘҒA‘ҚҚҮ“IӮЙҢҹ“ўӮөӮҪҢӢүКҒAҗіҚU–@ӮрӮЖӮйӮұӮЖӮЙҢҲӮөӮҪҒB ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аҺi—Я•”ӮНҒA‘О”nҠCӢ¬ӮЙ“ъ–{ҠCҢRӮМҺе—НӮӘ‘ТӮҝҚ\ӮҰӮДӮўӮйӮЙҲбӮўӮИӮўҒAӮЖӮөӮИӮӘӮзӮаҒAҠо–{“IӮЙ“ъ–{ҠН‘аӮНҺOҠCӢ¬ӮЙ•ӘҺU”z’uӮіӮкӮДӮўӮйӮаӮМӮЖҗMӮ¶ӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөғҚғVғAҠН‘аӮМҗн—НӮН“ъ–{ҠН‘аӮр‘еӮ«Ӯӯ—ҪүнӮөӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҠmҗMӮр•шӮўӮДӮЁӮиҒA•ӘҺUӮөӮҪ’ҶӮМҲкҠН‘аӮЖӮМҢҲҗнӮНӮЮӮөӮл–]ӮЮӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӢӯӮўҺ©җMӮӘ‘О”nҠCӢ¬“Л”jӮМҢЕӮўҢҲҲУӮр•шӮ©Ӯ№ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ‘О”nҠCӢ¬җi“ьӮр‘OӮЙҒAҠН‘аӮМҲк•”ӮрҠ„ӮўӮД‘ҫ•Ҫ—mҸгӮЙҗiҸoӮіӮ№Ӯй—z“®ҚмҗнӮрҠйҗ}ӮөӮҪҒB“ҢӢҪ’·ҠҜҲИүәӮМ“ъ–{ҠН‘аҺе—НӮӘ‘О”nҠCӢ¬Ӯр—Ј’EӮөӮҪҢ„ӮрӮВӮўӮДҒA“ҜҠCӢ¬Ӯр“Л”jӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМӮҪӮЯүј‘•Ҹ„—mҠН2җЗӮЖ•ЯҠlүpҚ‘ҸӨ‘D1җЗӮрӢгҸBҒEҺlҚ‘ӮМү«ҚҮӮўӮЙҸo“®ӮіӮ№ӮҪҒBӮіӮзӮЙ5ҢҺ24“ъӮЙӮНҒAҗО’Yү^”АӮМ”CӮрҸIӮҰӮҪү^‘—‘D6җЗӮӘүј‘•Ҹ„—mҠН2җЗӮЖӮЖӮаӮЙҸгҠC•ы–КӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМҚs“®ӮағҚғVғAҠН‘аӮӘү©ҠC•ы–КӮЕҚs“®’ҶӮр‘•ӮӨ—z“®ҚмҗнӮМҲкҺнӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӢpӮБӮД‘О”nҠCӢ¬Ӯр’КүЯӮ·ӮйӮұӮЖӮрҲГҺҰӮіӮ№ӮйҢӢүКӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъ–{ҠCҠCҗн ҢoҲЬҒ@
Ғuғlғ{ғKғgғtҠН‘аӮЖҚҮ—¬ӮөӮҪғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҒA5ҢҺ14“ъ(ғJғҖғүғ“ҳp–k•ы)ғzғ“ғRҒ[ғwҳpӮрҸo“®ҒA“Ң•ыҠCҸгӮЙҢьӮ©ӮӨҒvӮұӮМӢЩӢ}“d•сӮЙҗЪӮөӮҪ—ьҚҮҠН‘аӮНҒAғCғ“ғhғVғiӮ©ӮзӮМӢ——ЈӮ©ӮзҚlӮҰҒA5ҢҺ22“ъӮЙӮНғҚғVғAҠН‘аӮӘ‘О”nҠCӢ¬•tӢЯӮЙ“һ’BӮ·ӮйӮНӮёӮЕӮ ӮйӮЖҗ„’иӮөӮҪҒBғҚғVғA‘Ө’і•сӢ@ҠЦӮМӢU‘•“d•сӮӘ”тӮСҢрӮӨ’ҶҒAүдӮӘ—ьҚҮҠН‘аӮН‘О”nҠCӢ¬ӮЙҸWҢӢӮөӮҪӮЬӮЬ“®Ӯ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө24“ъӮЙӮИӮБӮДӮаүдӮӘҸЈүъҗьӮЙҢ»ӮкӮёҒAғҚғVғAҠН‘аӮМҸБ‘§ӮН•s–ҫӮҫӮБӮҪҒB—ьҚҮҠН‘аҺi—Я•”ӮЕӮНҒA’ГҢyҠCӢ¬ӮЙүIүсӮөӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҸЕ‘ҮӮөҒA5ҢҺ25“ъҒ@ҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvӮЙӮЁӮҜӮйҸ«ҠҜҒEҺQ–d’·үпӢcӮЕӮНҒA“Ҝ“ъҢЯҢг3ҺһӮЙ’ГҢyҠCӢ¬ӮЙҢьӮҜӮДӮМҲЪ“®ӮӘҢҲӮЬӮиӮ©ӮҜӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA’xӮкӮДҸoҗИӮөӮҪ‘ж2ҠН‘аҺQ–d’·“ЎҲдҠrҲкҸӯҸ«ӮЖ“ҜҺi—ЯҠҜ“Ү‘ә‘¬—Y’ҶҸ«ӮӘ”Ҫ‘ОӮөӮҪӮҪӮЯҒA“Ҝ“ъӮМҲЪ“®ӮН’ҶҺ~ӮЖӮИӮиҒAҗЬ’ҸҲДӮЖӮөӮД26“ъӮЬӮЕ“GҠН‘аӮМ“®ҢьӮрҢ©ӢЙӮЯӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB26“ъӮЙӮНғҚғVғAҠН’шӮМҲк•”ӮӘ“ҢғVғiҠCӮЙӮўӮйӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮиҒAӮЬӮҪ“VҢуӮӘҲ«ү»ӮөӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAҚДӮСҲЪ“®ӮН’ҶҺ~ӮЖӮИӮБӮҪҒBҢӢүК“IӮЙӮНӮұӮкӮӘ“ъ–{ӮЙ”сҸнӮИҚKү^ӮрӮаӮҪӮзӮ·ӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB 0245 5ҢҺ27“ъ ҸЈүъ’ҶӮМүј‘•Ҹ„—mҠНҒuҗM”ZҠЫҒv(ҠН’·җ¬җмқ„‘еҚІ)Ғ@ғoғӢғ`ғbғNҠН‘а”ӯҢ© –kҲЬ33“x10•ӘҒ@“ҢҢo128“x10•Ә 0445 ҒuҗM”ZҠЫҒvҒ@“GғmҠН‘а203’n“_ғjҢ©ғҶҒ@‘Е“d 0505 —ьҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜ “ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY‘еҸ«Ғ@‘SҠН‘аӮЙҸo“®–Ҫ—Я 0600 “ҢӢҪ’·ҠҜҒ@Ғu“GҠНҢ©ғҶғgғmҢx•сғjҗЪғV —ьҚҮҠН‘ағn’јғ`ғjҸo“® ”Vғ’ҢӮ–ЕғZғ“ғgғXҒvӮМҲГҚҶ“d•¶ ––”цӮЙҒu–{“ъ“VӢCҗ°ҳNғiғҢғh”gҚӮғVҒvӮМ•Ҫ•¶“d•¶Ӯр‘е–{үcӮЙ”ӯҗM 0605 —ьҚҮҠН‘аҠшҠНҒuҺOҠ}Ғv(ҠН’·ҲЙ’n’m•FҺҹҳY‘еҚІ)Ғ@’БҠCҳpӮрҸoҚ` 0645 Ҹ„—mҠНҒuҳaҗтҒv(ҠН’·җО“cҲкҳY‘еҚІ)ҒAҒuҗM”ZҠЫҒvӮЖҸЈүъ”C–ұӮрҢр‘гҒAҠДҺӢҚs“®Ӯр‘ұҚs 0900 Ӣ{ҢГ“ҮӮМҒuӢvҸјҢЬ—EҺmҒvғoғӢғ`ғbғNҠН‘аҗЪӢЯӮМӢ}•сӮр“а’nӮЙ’mӮзӮ№ӮйӮЧӮӯ100km—ЈӮкӮҪҗОҠ_“Ү“dҗMӢЗӮЙғNғҠ‘DӮЕҢьӮ©ӮӨ 0950 ‘ж3ҠН‘а(Һi—Я’·ҠҜҒ@•РүӘҺөҳY’ҶҸ«)Ғ@‘О”nҗ_Қи“м“Ң12ғLғҚӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮр”ӯҢ© 1030 ‘ж3җн‘а(Һi—ЯҠҜҒ@ҸoүHҸdү“’ҶҸ«)Ғ@‘О”nҗ_Қи“м“Ң25ғLғҚӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮр”ӯҢ© 1140 җнҠНҒuғIғҠғҮҒ[ғӢҒvҒ@Ӣ——Ј8000ӮЕ‘ж3җн‘аӮМҸ„—mҠН4җЗӮЙ‘ОӮө–CҢӮҠJҺn ‘ж3җн‘аӮН‘Ю”рҚs“®ӮЦ 1339 ҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvҒ@ғoғӢғ`ғbғNҠН‘а”ӯҢ© Қ¶ҢҪ“м”чҗјҒAғj—сҸcҗwӮЕ–kҸг’ҶӮрҠm”F 1340 “ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜҒ@‘SҠНҗ퓬ҠJҺnӮр”ӯ—Я 1355 ҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvӮЙӮyҗMҚҶҠшӮӘ—gӮӘӮйҒ@ҒuҚcҚ‘ғmӢ»”pҚҹғmҲкҗнғjғAғҠ ҠeҲхҲк‘w•ұ—г“w—НғZғҲҒvӮЖүә—Я 1402 Ӣ——Ј–с10000Ғ@—ьҚҮҠН‘а‘¬—Н15ғmғbғgҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘а‘¬—Н–с11ғmғbғgӮЖҗ„’и 1405 Ӣ——Ј8000Ғ@Қ¶180“x“G‘OҲкҗДүс“ӘӮр–Ҫ—Я(ӮўӮнӮдӮй“ҢӢҪғ^Ғ[ғ“) 1408 ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[Һi—Я’·ҠҜҒ@‘SҠНҚUҢӮҠJҺnӮр–Ҫ—Я 1410 Ӣ——Ј6500Ғ@“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜҒ@‘SҠНӮЙ–CҢӮӮр–Ҫ—Я 1438 җнҠНҒuғIғXғүғrғAҒvҒ@”н’e‘Ҫҗ”Ғ@Қ¶ҢҪӮЙҢXҺО 1440 ҠшҠНҒuҺOҠ}ҒvҒ@”н’e20”ӯҲИҸг •ӣ’·Ҹј‘ә’ҶҚІҒAҗ…—Ӣ’·җӣ–мҸӯҚІҒAҠН‘аҺQ–d”С“cҸӯҚІӮЩӮ©ҺҖҸқҺТ100–ј 1452 ҠшҠНҒuғNғjғғҒ[ғWҒEғXғҸғҚғtҒvҚqҚs•s”\Ғ@ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜҒAғCғOғiғ`ғEғXҠН’·ҸdҸЗ 1500 •aү@‘DҒuғIғҠғҮҒ[ғӢҒvҒuғJғXғgғҚғ}Ғ[ҒvҚS‘©ӮіӮкӮй 1506 җнҠНҒuғIғXғүғrғAҒv’ҫ–vҒ@504–јҗнҺҖ 1520 ғҚғVғAҠН‘а”Z–¶ӮМ’ҶӮЦ‘Ю”рҒ@‘жҲкҺҹҗ퓬ҸI—№ 1540 ҠшҠНҒuғNғjғғҒ[ғWҒEғXғҸғҚғtҒvҗнҗь’E—Һ 1606 ‘ж“сҺҹҗ퓬ҠJҺn 1730 ҸdҸЗӮМғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜҒ@Ӣм’ҖҠНҒuғuғCғkғCҒvӮЙҲЪҸжҒAҠН‘аҺwҠцӮрғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ӮЙҲПҸч 1900 ҠшҠНҒuғNғjғғҒ[ғWҒEғXғҸғҚғtҒv’ҫ–vҒ@925–јҗнҺҖ 1930 җнҠНҒuғAғҢғNғTғ“ғhғӢҺOҗўҒv“]•ўҒ@Ҹж‘gҲх867–ј‘SҲхҗнҺҖ(’ҫ–vӮН2130Қ ) 1923 җнҠНҒuғ{ғҚғWғmҒv’ҫ–vҒ@865–јҗнҺҖҒ@җ¶‘¶ҺТҗ…•ә1–јӮМӮЭ 1928 “ъ–vҒ@“ҢӢҪ’·ҠҜҒ@–CҢӮ’ҶҺ~Ӯр–Ҫ—Я 2000 Ӣм’ҖҠНҒAҗ…—Ӣ’шӮМ–йҸPҠJҺn 2200 җнҠНҒuғiғҸғҠғ“ҒvӢӣ—ӢҚUҢӮӮрҺуӮҜ”нҠQҗr‘еҒ@700–јҗнҺҖ(’ҫ–vӮН—Ӯ’©–ў–ҫ) 2300 Ӣм’ҖҠНҒAҗ…—Ӣ’шӮМ–йҸPҸI—№ 0300 5ҢҺ28“ъ җнҠНҒuғVғ\ғCҒEғEғFғҠҒ[ғLҒ[Ғv”нҠQҗr‘еӮМӮҪӮЯ—ӨҠЭӮЦҗЪӢЯ 0520 ‘ж5җн‘а(Һi—ЯҠҜ•җ•x–M“CҸӯҸ«)Ғ@“GҺc‘¶ҠН‘а”ӯҢ© 0830 җнҠНҒuғVғ\ғCҒEғEғFғҠҒ[ғLҒ[ҒvҒ@үј‘•Ҹ„—mҠНҒuҗM”ZҠЫҒvҒu‘д“мҠЫҒvӮЙҚ~•ҡ 0900 Ҹ„—mҠНҒuғAғhғ~ғүғӢҒEғiғqғӮғtҒv’ҫ–vҒ@ҸжҲх101–јӮН‘О”nӮЙҸг—ӨҢг•Я—ёӮЖӮИӮйҒBғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜҲИүәҒ@Ӣ@ҠЦҢМҸбӮМӢм’ҖҠНҒuғuғCғkғCҒvӮ©ӮзӢм’ҖҠНҒuғxғhҒ[ғ”ғBғCҒvӮЙҚДҲЪҸж 1043 ҺwҠцҢ ӮрҢpҸіӮөӮҪғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«Қ~•ҡҒAҠшҠНҒuғjғRғүғCҲкҗўҒvӮУӮӯӮЮ5җЗӮН•ЯҠl 1102 җнҠНҒuғVғ\ғCҒEғEғFғҠҒ[ғLҒ[ҒvҒ@ҸжҲх613–јҺы—eҢг’ҫ–v 1337 ғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ҒAҺOҠ}ҠНҸгӮЕҚ~•ҡ•¶Ҹ‘ӮЙ’ІҲу 1500 Ӣм’ҖҠНҒuғxғhҒ[ғ”ғBғCҒvҒAӢм’ҖҠНҒu—шҒv(ҠН’·‘ҠүHҚPҺOҸӯҚІ)ӮЙҚ~•ҡҒAғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ҲИүәӮН•Я—ёӮЖӮИӮйҒB 1810 ‘•ҚbҸ„—mҠНҒuғAғhғ~ғүғӢҒEғEғVғғҒ[ғRғtҒv’ҫ–vҒ@ҠН’·ғ~ғNғҚғX‘еҚІҲИүә83–јҗнҺҖ ӮұӮкӮЙӮжӮи“с“ъӮЙӮнӮҪӮБӮҪҠCҗнӮНҸI—№ 1245 5ҢҺ29“ъ ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’·ҠҜҲИүәӮМ–Ӣ—»ӮрҸжӮ№ӮҪӢм’ҖҠНҒuғxғhҒ[ғ”ғBғCҒvҒ@ҚІҗў•Ы“ьҚ` 1430 •ЯҠlӮіӮкӮҪҗнҠНҒuғjғRғүғCҲкҗўҒvҒ@ҚІҗў•Ы“ьҚ` ғҚғVғA–{Қ‘ӮЙ“ҰӮкӮҪӮМӮН“Б–ұ‘D(ү^‘—‘D)ҒuғAғiғhғDғCғҠҒv1җЗӮМӮЭҒA–Ъ“IӮМғEғүғWғIғXғgғbғNҢRҚ`ӮЙ“һ’BӮөӮҪӮМӮНғҲғbғgҺ®Ҹ¬Ң^Ҹ„—mҠНҒuғAғӢғ}Ғ[ғYҒvҒAӢм’ҖҠНҒuғuғүҒ[ғ”ғBғCҒvҒuғOғҚҒ[ғYғkғCҒvӮМҺOҗЗӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB “ъ–{ҠН‘аӮМ‘№ҺёӮНҒA‘ж34ҚҶ’шҒA‘ж35ҚҶ’шҒA‘ж69ҚҶ’шӮМҗ…—Ӣ’шҺOҗЗӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎӮ»ӮМҢгӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аҺс”]җwҒ@
Һi—Я’·ҠҜ ғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ӮНҒA“Ә•”ӮЙҸdҸЗӮр•үӮўҒAҺQ–d’·ғRғҚғ“‘еҚІҒAғZғ~ғҮҒ[ғmғt’ҶҚІҲИүәӮМ–Ӣ—»ӮЖӮЖӮаӮЙӢм’ҖҠНҒuғxғhҒ[ғ”ғBғCҒvӮМҚ~•ҡӮЙ”әӮў•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪҒB’јӮҝӮЙҚІҗў•ЫҠCҢR•aү@“Б“ҷҺәӮЙ“ьү@ҒAҲЯҗHӮЖӮаӮЙ“ъ–{ҠCҢRӮМҸ«ҠҜӢүӮжӮиӮаӮНӮйӮ©ӮЙҚӮ‘ТӢцӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҺҹҗИҺwҠцҠҜӮҪӮйғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ӮНҒAҠшҠНҒuғjғRғүғCҲкҗўҒvӮЙҚҝҸжӮөҒAҗнҠНҒuғIғҠғҮҒ[ғӢҒv‘ј3җЗӮМ5җЗӮрӮаӮБӮДғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙҢьӮ©ӮБӮҪӮӘҒA5ҢҺ28“ъҢЯ‘O10ҺһүЯӮ¬ҒAүдӮӘҠН‘аӮЙ•пҲНӮіӮкӮҪӮМӮрҢ©ӮДҗнӮӨӮұӮЖӮИӮӯҚ~•ҡӮрҢҲҲУҒBҺQ–d’·ғNғҚғbғc’ҶҚІҒAҒuғjғRғүғCҲкҗўҒvҠН’·ғXғ~ғӢғmғt‘еҚІӮзӮЖӮЖӮаӮЙ•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҸ„—mҠНҒuғCғYғҖғӢҒ[ғhҒvӮҫӮҜӮНҚ~•ҡ–Ҫ—ЯӮЙ•®ҢғӮө“Ң•ыӮЙ“Ұ‘–ҒAғҚғVғA—М“ағEғүғWғ~Ғ[ғӢҳpӮЕҚАҸКӮМӮҝҺ©”ҡҒAҠН’·ғtғFғӢғ[ғ“’ҶҚІҲИүәӮМҸжҲхӮН“k•аӮЕғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒBҸ„—mҠНҒuғIғҢҒ[ғOҒvҒuғAғ”ғҚғүҒvҒuғWғFғҖғ`ғ…Ғ[ғOҒvӮМ3җЗӮНҒAғGғ“ғNғDғCғXғgҸӯҸ«ӮЙ—ҰӮўӮзӮкӮД”д“Үғ}ғjғүӮЬӮЕ“Ұ‘–ҒAӮ»ӮұӮЕ•Дҗӯ•{ӮЙ—}—ҜӮіӮк•җ‘•үрҸңӮіӮкӮҪҒB “ҢӢҪ‘еҸ«ӮНҒA”s–kӮөӮҪ“GҢRҗlӮЙ•җҗlӮЖӮөӮДӮМ–ј—_Ӯр‘ёҸdӮөҒAғҚғWғFғXғgғ”ғFғ“ғXғLҒ[’ҶҸ«ӮЖғlғ{ғKғgғtҸӯҸ«ӮЙ‘ОӮөӮДғҚғVғAҚc’йӮЦӮМҗнӢө•сҚҗӮМ‘ЕҗfӮрӢ–үВӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҗнҺһүәӮЙӮ ӮБӮДӢЙӮЯӮДҲЩ—бӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮҪ•Я—ёӮЙ‘ОӮ·Ӯй‘ТӢцӮаҗl“№“IӮИӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAӮұӮұӮЕӮа•җҺm“№җёҗ_ӮӘ”ӯҠцӮіӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠCҗнӮМҢӢүКӮЖҗўҠEҠeҚ‘ӮМ”ҪүһҒ@
‘ў‘DӢZҸpҗ…ҸҖӮӘҚӮӮӯҒAҗVүsҗнҠНӮр‘ұҒXӮЖҺ©Қ‘ӮЕҗiҗ…ӮіӮ№ӮДӮўӮйҗўҠEҲк—¬ӮМҠCҢRҚ‘ғҚғVғAӮӘҒAҺе—vҢRҠНӮМ‘ҪӮӯӮрҠOҚ‘ӮЙ”ӯ’ҚӮөӮДӮўӮйӢZҸpҢгҗiҚ‘“ъ–{ӮЙ‘е”sӮөӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮНҒAӮЬӮіӮЙҠпҗЦ“IӮИ‘еҺ–ҢҸӮЕӮ ӮиҒA•т“VӮЕӮМ—ӨҸгҢҲҗнӮЕӮМҸҹ—ҳӮЙ‘ұӮӯҠCҸгҢҲҗнӮЕӮМҸҹ—ҳӮНҒA“ъ–{ҢRӮМ’к’mӮкӮКӢӯӮіӮрҺҰӮ·ӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮМ“ъ–{ҲіҸҹӮМғjғ…Ғ[ғXӮНҗўҠEӮрӢБңұӮіӮ№ҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМҚ‘ӮӘҚҶҠOӮЕ•сӮ¶ӮҪҒB ҠeҚ‘ӮМ•с“№Ӯр”дҠrӮ·ӮйӮЖҒAӮЁӮИӮ¶—LҗFҗlҺнӮЖӮөӮДҺ©Қ‘ӮМҸҹ—ҳӮМӮжӮӨӮЙӢ¶ҠмӮөӮҪғAғWғAӮвғAғүғuҠeҚ‘ҒAғҚғVғAӮМ“мүәӮр‘jҺ~ӮөӮҪӮ©ӮБӮҪүдӮӘ“Ҝ–ҝҚ‘ӮМүpҚ‘ӮвғAғҒғҠғJӮМҗV•·ӮНҒA“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮрҺи•ъӮөӮЕҸМӮҰӮҪҒBҲк—бӮрӢ“Ӯ°ӮйӮЖҒuғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNҒEғTғ“ҒvӮНҺРҗаӮЕҒAҒu20җўӢIӮМӮӨӮҝӮЙ“ъ–{ӮНҒAҠФҲбӮўӮИӮӯҗўҠEӮМғgғbғvӮЙ—§ӮВӮҫӮлӮӨҒvӮЖӮЬӮЕҸqӮЧӮҪҒB Ҳк•ығҚғVғAӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ғtғүғ“ғXӮНҒAӮұӮкҲИҸгҗн‘ҲӮр‘ұӮҜӮкӮОғҚғVғAӮМҚ‘ҚЫ“I’nҲКӮӘ’бүәӮ·ӮйӮұӮЖӮрҠлңңӮөҒAҚuҳaӮЙүһӮ¶ӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒAӮЖҸ]—ҲӮМҺе’ЈӮрӢ}•ПӮіӮ№ӮҪҒBғhғCғcӮНҒAҒuҗнҢгӮМҢЗ—§ҒvӮр”рӮҜӮжӮӨӮЖҸҷҒXӮЙ“ъ–{ҠсӮиӮЙҗӯҚфӮр“]Ӯ¶ӮДӮўӮҪӮӘҒAӮұӮМҠCҗнӮрӢ@ӮЙ‘О“ъҗЪӢЯӮр–ҫҠmӮЙӮөӮҪҒBӮЬӮҪғIҒ[ғXғgғүғҠғAӮвғtғBғҠғsғ“ӮМҗV•·ӮЙӮНҒAҒuӢӯҚ‘ӮЖӮИӮБӮҪ“ъ–{ӮӘҗNҚUӮөӮДӮӯӮйҒvӮЖҒAҢxүъҗSӮрӢӯӮЯӮйҳ_’ІӮӘ–Ъ—§ӮҝҺnӮЯӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮрӢ«ӮЙҚ‘ҚЫҠЦҢWӮН‘еӮ«Ӯӯ•П“®ӮөҒAҠeҚ‘ӮМҗV•·ӮаҺ©Қ‘ӮМҚ‘үvӮрӢҒӮЯӮД‘еӮ«Ӯӯҳ_’ІӮр•ПӮҰӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB ‘ј•ығҚғVғAҚ‘“аӮЕӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮМ”s–kӮН5ҢҺ30“ъӮЙҸүӮЯӮДҢц•\ӮіӮкҒAҒuҠCҗнӮЙӮН”sӮкӮҪӮӘғҚғVғAӮМҲР—НӮНҸнӮЙ—ӨҢRӮЕӮ ӮйҒB–һҸBӮЙӮН50–ңҗlӮМ•әӮӘӮ ӮиҚuҳaӮЙүһӮ¶ӮйӮЧӮ«ӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖӮ·Ӯй“а—eӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҒuҗн‘ҲӮМҚs•ыӮНҢҲӮөӮҪҒvӮЖӮ·Ӯйҳ_’ІӮаҢ»ӮкӮҪҒB “ъ–{ҠCҠCҗн(җўҠE“IҢДҸМ ‘О”nү«ҠCҗн)ӮНҒAҠН‘аҢҲҗнҺеӢ`Ӯр•s“®ӮМӮаӮМӮЖӮөҒA‘еҠНӢҗ–CҺеӢ`Һһ‘гӮМ–ӢҠJӮҜӮрҚҗӮ°ҒA‘SҗўҠEӮМҠCҢRҗнҸpӮвҢҡҠНҗӯҚфӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒB 1805”NӮМғgғүғtғ@ғӢғKҒ[ү«ҠCҗнӮрҸгүфӮй‘еҸҹ—ҳӮНҒAҒuғpҒ[ғtғFғNғgҒEғQҒ[ғҖҒvҒu“Ң—mӮМҠпҗЦҒvӮЖҗвҺ^ӮіӮкӮҪҒBҗўҠEҠCҗнҺjҸгӮМӮЭӮИӮзӮёҗўҠEҺjҸгӮЙҺcӮйӮұӮМ‘еҲМӢЖӮЙӮжӮБӮДҒA“ҢӢҪҺi—Я’·ҠҜӮНғlғӢғ\ғ“ӮЙ•C“GӮ·ӮйҲМ‘еӮИ’с“ВӮЖӮөӮДҒAҗўҠEӮЙӮ»ӮМ–јӮрҚҢӮ©Ӯ№ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҳIҗн‘Ҳ7 | |
|
ҒЎҺxҚмҗнҒ^–kҠШ•ы–КҚмҗнҒAҠ’‘ҫ•ы–КҚмҗнҒ@
–ҫҺЎ37”NҸtҲИ—ҲҒAғEғXғҠҒ[•ы–КӮМғҚғVғAҢRӮНҒAҠШҚ‘“Ң–k•”ӮМҷчӢҫ(Ӯ©ӮсӮ«ӮеӮӨ)“№ӮЙҗi“ьӮөӮДӮўӮҪҒB“ъ–{‘ӨӮЕӮН‘ҒӮӯӮ©ӮзӮұӮМ“GӮрҚ‘Ӣ«ҠOӮЙӢм’ҖӮөҒAӮ ӮйӮўӮНғEғүғWғIғXғgғbғNӮЬӮЕҗiҢӮӮөӮДӮұӮкӮрҗи—МӮ·ӮйҢvүжӮӘӢcҳ_ӮіӮкӮДӮўӮҪӮӘҒA–һҸBӮЕӮМҺеҚмҗнҸdҺӢӮМӮҪӮЯӮЙҢ©‘—ӮзӮкӮДӮўӮҪҒBҠШҚ‘’“ҷ•ҢR(Һi—ЯҠҜ ’·’JҗмҚD“№‘еҸ«)ӮНҒA•т“VҗнӮМҸIӮнӮБӮҪ–ҫҺЎ38”N5ҢҺҲИҚ~ҒA‘қүБӮіӮкӮҪҢг”х‘ж2Һt’cӮр“–ҠY•ы–КӮЙҚs“®ӮіӮ№ӮҪҒBҢг”х‘ж2Һt’cӮН9ҢҺ1“ъүп”JӮЬӮЕҗiҸoҒAҚuҳaҸр–сӮМҗ¬—§ӮЙӮжӮБӮДҚмҗнӮрҸI—№ӮөӮҪҒB Ҡ’‘ҫӮЙ‘ОӮөӮДӮаҒA“Ҝ—lӮЙ‘ҒӮӯӮ©ӮзҚU—ӘӮ·ӮйҲДӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒA–kҠШҚмҗнӮЖ“ҜӮ¶—қ—RӮЕҢ©‘—ӮзӮкӮДӮўӮҪҒB•т“Vҗн’јҢгӮМ3ҢҺ31“ъ“®ҲхӮіӮкӮҪҗVҗЭӮМ‘ж13Һt’c(Һt’c’· ҢҙҢыҢ“ҚП’ҶҸ«)ӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮӘҸIӮнӮиҒAҗн‘ҲҸIҢӢӮӘӢЯӮӯ—\‘zӮіӮкӮйӮЙҺҠӮиҒAҚuҳaҸрҢҸӮр—L—ҳӮЙӮ·Ӯй–Ъ“IӮМӮҪӮЯҠ’‘ҫҗи—МӮЙҺg—pӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB“Ж—§‘ж13Һt’cӮНҒA7ҢҺҸгҸ{Қs“®ӮрӢNӮұӮөҒA7ҢҺ8“ъҲк•”ӮрӮаӮБӮД‘е”‘ӮЙҒA7ҢҺ24“ъҺе—НӮрӮаӮБӮДғAғӢғRғҸӮЙҸг—ӨӮ»ӮкӮјӮк“––КӮМ“GӮрҚUҢӮҒAғҠғ„ғuғmғt’ҶҸ«ҺwҠцӮМ•а•ә–с4000ҒA–C8–еӮрҺе—НӮЖӮ·ӮйҚЭҠ’‘ҫғҚғVғAҢRӮМҚ~•ҡӮЙӮжӮиҒA8ҢҺ1“ъҠ’‘ҫ‘S“ҮӮрҗи—МҒAҚuҳaӮрҢ}ӮҰӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸIҗнҺw“ұӮЖҗӯҗн—ӘҒ@
ғҚғVғA—ӨҢRӮНҒAҚ‘“аӮМҠv–ҪҗЁ—НӮЙ”хӮҰӮД•ә—НӮрү·‘¶ӮөӮДӮўӮҪӮӨӮҰӮЙҒA“ъ–{ҢRӮМҗн—НӮрҢyҺӢӮөӮҪӮҪӮЯӢЙ“ҢӮЦӮМ•ә—Н”hҢӯӮрзSзOӮөӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘ҠҺҹӮ®”sҗнӮЙҚ‘“аӮМҗlҗS“®—hӮӘҚӮӮЬӮйӮұӮЖӮрӢ°ӮкӮДҒA‘еҒX“IӮИ•ә—Н‘қӢӯӮЙ“ҘӮЭӮ«ӮБӮДӮўӮҪҒB’PҗьӮМғVғxғҠғA“S“№ӮрҲк•ы’КҚsӮЖӮөӮДҺg—pӮөҒAӮҪӮҝӮЬӮҝӢЙ“ҢғҚғVғA—ӨҢRӮМ•ә—НӮН“ъ–{ҢRӮМ3”{ӮЙ”—ӮБӮДӮўӮҪҒB“ъҳI—јҚ‘ӮМ•ә—НӮМҚ·ӮН“ъӮр’ЗӮБӮДҠg‘еӮөӮДӮўӮБӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮө•т“VүпҗнӮЕ—DҗЁӮИғҚғVғAӮМ‘еҢRӮрүу‘–ӮіӮ№ӮҪӮЖӮНӮўӮҰҒA“ъ–{ҢRӮЙӮНӮ»ӮкҲИҸгҗiҢӮӮ·Ӯй—НӮНҺcӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯа“ъ–{—ӨҢRӮНҒA•әӮМ•вҸ[ӮрӢ}Ӯ®—]ӮиҒA—ӨҢRҸИ—Я‘жҢЬҚҶӮЕ’Ҙ•әҢҹҚёӮМҗ…ҸҖӮрҒAҗg’·ҺlҺЪӢгҗЎҢЬ•Ә(–с147ӮғӮҚ)ӮЬӮЕүәӮ°ӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҸг“ъ–{ӮМҚаҗӯӮа”ЯҠП“IҸуӢөӮЕӮ ӮБӮҪҒBҠJҗнҢг1”N3ғ–ҢҺ—]ӮМҠФӮЙ“Ҡ“ьӮіӮкӮҪҗн”пӮН20үӯү~ӢЯӮӯҒAӮ»ӮкӮНҗн‘OӮМҚ‘үЖ—\ҺZӮМ8”{ӮЙӮаӮ ӮҪӮйӢҗҠzӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗӯ•{ӮНҒA‘қҗЕҒAҗVҗЕӮМ‘nҗЭӮрӮНӮ¶ӮЯ5үсӮЙӮнӮҪӮйҚ‘ҚВҒA4үсӮМҠOҚВӮЙӮжӮБӮД•вӮБӮДӮ«ӮҪӮӘҒAҚаҗӯҗӯҚфҸгҒAӮұӮкҲИҸгӮМ”PҸoӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮИҸоҗЁӮМ’ҶӮЕҒAүдӮӘҗӯ•{ҒE“қҗғ•”ӮЙӮНҚuҳaӮр—ХӮЮҗәӮӘҚӮӮЬӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮаӮ»Ӯа“ъ–{ӮӘ‘¶–SӮр“qӮҜӮДҗн‘ҲӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮҪӮМӮНҒAғҚғVғAӮМҳIҚңӮИҗN—ӘҗӯҚфӮЖ’§”ӯҚsҲЧӮЙ‘ОӮ·ӮйҺ©үqҚ‘–hӮМӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{ӮМҺw“ұҺТӮҪӮҝӮН—М“y“I–мҗSӮр•шӮӯӮұӮЖӮаӮИӮӯҒAғҚғVғA—М“аҗ[ӮӯҗiҢӮӮ·ӮйҚ‘—НӮМӮИӮўӮұӮЖӮрҺ©ҠoӮөӮДӮўӮҪҒBҗӯ•{ӮаҢR•”ӮаҒAҠJҗнҺһӮ©Ӯзҗн‘ҲӮН’ZҠъҠФӮЕҸI—№ӮөҒAғҚғVғAӮЖҚuҳaҸр–сӮр’чҢӢӮ·ӮйӮұӮЖӮрҗ^Ң•ӮЙҚlӮҰӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢcҒ@
—ӨӮМ•т“VүпҗнҒAҠCӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕ“ъ–{ҢRӮӘ‘еҸҹӮр“ҫӮҪҢгҒA6ҢҺ2“ъ•Д‘е“қ—МғӢҒ[ғYғxғӢғgӮНҒA’“•ДғҚғVғA‘еҺgғJғVғjҒ[ӮрҸөӮўӮДҚuҳaӮрҠ©ҚҗӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮөӮ©ӮөғJғVғjҒ[‘еҺgӮНҒA5ҢҺ30“ъӮМҳIҚ‘Ӣ{’ҶҢRҺ–үпӢcӮӘҢpҗнӮЙҢҲ’иӮөӮҪҺ|ӮМ“d•сӮрҺҰӮөӮИӮӘӮзҺҹӮМӮжӮӨӮЙ“ҡӮҰӮҪҒB Ғu“ъ–{ҢRӮӘ–ўӮҫғҚғVғA—М“yӮМҗЎ’nҺЪ“yӮрӮаҗи—МӮ№ӮҙӮйҢ»ҸуӮЙӮДҚuҳaӮ·ӮйӮНҒAғҚғVғAӮМ–ј—_ӮрҺё’ДӮ·ӮйӮаӮМӮИӮиҒB—]ӮН–ўӮҫҚuҳaӮМҢP—ЯӮЙҗЪӮ№ӮёҒA–ўӮҫүһӮёӮйӮр“ҫӮёҒBҒv ӮөӮ©Ӯө6ҢҺ7“ъӮұӮлӮ©ӮзӮжӮӨӮвӮӯғҚғVғA“а•”ӮЙӮаҚuҳaӮМ“®Ӯ«ӮӘҢ©ӮҰҺnӮЯҒAүьӮЯӮД6ҢҺ10“ъ•Д‘е“қ—МғӢҒ[ғYғxғӢғgӮНҒA“ъҳI—јҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҚuҳaӮрҠ©ҚҗӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮіӮзӮЙӮН“ЖҒA•§ӮЕӮ·ӮзғҚғVғAӮЙҳaӮрҚ\ӮёӮЧӮ«ӮрҠ©ӮЯҒAҚuҳaӮМҗәӮН‘SҗўҠEӮЙҹыӮБӮҪҒB 8ҢҺ9“ъӮ©Ӯз“ъҳI‘SҢ ҲПҲхӮН•Дғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЙӮЁӮўӮДҚuҳaүпӢcӮрҠJӮ«ҒA8ҢҺ29“ъҚuҳaҸр–сӮМӢҰ’иӮрҸIӮҰҒA9ҢҺ5“ъҒ@ҢЯҢг3Һһ47•ӘҒ@ғ|Ғ[ғcғ}ғXҠCҢRҚHҸұӮЙӮЁӮўӮД“ъҳIҚuҳaҸр–сӮӘ’ІҲуӮіӮкӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮНҠJҗнҲИ—Ҳ20ғ–ҢҺӮрӮаӮБӮДҒAӮұӮұӮЙҸIҢӢӮрҢ©ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҢӢүК–һҸBҢRӮН9ҢҺ16“ъҗіҢЯӮ©ӮзӢxҗнӮЙ“ьӮБӮҪҒB–ҫҺЎ38”N10ҢҺ14“ъҒ@ҚuҳaҸр–сӮМ”бҸyӮӘҚsӮнӮкҒA“ъҳIӮМҗн‘ҲӮНҗіҺ®ӮЙҸIҢӢӮөӮҪҒB ҚuҳaҸр–сӮМҺе—v“а—eӮНҲИүәӮМӮЖӮЁӮиҒB ғҚғVғAӮНҒAҠШҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМҗӯҺЎҢRҺ–ӢyӮСҢoҚП“I—DҲКӮр”FӮЯӮйҒB ғҚғVғAӮНҒA–һҸBӮ©Ӯз“P•әӮ·ӮйҒB ғҚғVғAӮНҗҙҚ‘ӮМҸі‘шӮр“ҫӮДҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМ‘dҺШҢ Ӯр“ъ–{ӮЙҠ„ҸчӮ·ӮйҒB ғҚғVғAӮНҗҙҚ‘ӮМҸі‘шӮр“ҫӮДҒA“м–һҸB“S“№ӮЙҠЦӮ·ӮйҢ —ҳӮЖҚаҺYӮр“ъ–{ӮЙҠ„ҸчӮ·ӮйҒB ғҚғVғAӮНҒAҠ’‘ҫ“м•”Ӯр“ъ–{ӮЙҠ„ҸчӮ·ӮйҒB –і”…ҸһҒAҠ’‘ҫӮМ“м”ј•ӘӮМӮЭ“ъ–{ӮЦҒBӮұӮкӮӘҗSҢҢӮр’ҚӮўӮЕҚuҳaүпӢcӮЙ—ХӮсӮҫ“ъ–{‘SҢ ҒEҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮМ“w—НӮМҺ’•ЁӮЕӮ ӮиҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙҗhҸҹӮөӮҪ“ъ–{ӮӘ“ҫӮҪӮ·ӮЧӮДӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©Ӯө“ҜҺһӮЙғҚғVғAӮМғAғWғAҗN—ӘӮр—}ӮҰҒA“ъ–{ӮМҚ‘ҚЫ“I’nҲКӮрҠm—§ӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB ”…ҸһӢаӮӘӮИӮӯҒAҗи—МӮөӮҪҠ’‘ҫӮа”ј•ӘӮЙҚнӮзӮкӮҪӮұӮМҸр–сӮНҒAҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮҪ“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДӢЙӮЯӮД•s–һ‘«ӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҲк•ыҒA—ӨҢRӮМ‘е”јӮрү·‘¶ӮөӮДӮўӮҪғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮДӮаҒAӮұӮМҸр–сӮН•s–{ҲУӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{ӮМ“®Ҳх”\—НҒAҗн”п’І’BӮН•Ҙ’кӮөӮДӮЁӮиҒAғҚғVғAӮНҚ‘“аӮЙҠv–ҪӢCү^ӮӘ”RӮҰҸгӮӘӮБӮД—ҲӮДӮЁӮиҒAӮЖӮаӮЙҗн‘ҲҢp‘ұӮНҚў“пӮИҺ–ҸоӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮіӮзӮЙ•Д‘е“қ—МӮМ’Үүо“w—НӮаӮ ӮБӮДӮұӮМӮжӮӨӮИ‘ГӢҰҲДӮӘҗhӮӨӮ¶ӮДҗ¬—§ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Қ‘“аӮЕӮНҚuҳaҸр–сӮр•s–һӮЖӮ·Ӯй–ҜҸOӮӘҠOҢрӮМҺё”sӮЖӮөӮДҗӯ•{ӮрҚUҢӮӮөҒA‘ӣ—җӮӘ“ъ”д’J•tӢЯӮ©Ӯз”ӯҗ¶ҒA9ҢҺӮ©Ӯз10ҢҺӮЙӮ©ӮҜӮД“ҢӢһӮЙүъҢө—ЯӮӘ•zҚҗӮіӮкӮйҺ–ҢҸӮӘӢNӮұӮБӮҪҒBҒuүзҗdҸҰ’_ҒvӮМӢкҳJӮЖҒAҗr‘еӮИӮйӢ]җөӮЙ‘ОӮ·Ӯй•сӮўӮМҸӯӮИӮўӮұӮЖӮЙ‘ОӮ·Ӯй•®ҢғӮ©ӮзӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮНҚ‘“аҺ–ҸоӮв“а•”ӮМ•sҳaӮИӮЗӮЙӮжӮБӮДӮўӮнӮО“ъ–{ӮЙҸҹ—ҳӮрҸчӮБӮҪӮӘҒAӮаӮөҢpҗнҲУҺvӮрҢҳҺқӮөӮДғnғӢғsғ“•tӢЯӮЕ”ҪҢӮӮЙӮЕӮДӮўӮҪӮИӮзӮОүКӮҪӮөӮДӮЗӮӨӮИӮБӮҪӮўӮҪӮ©ҒBӮұӮМӮұӮЖӮНүдӮӘ’Ҷүӣ“қҗғ•”ӮЕӮН“–‘R’mӮиҗsӮӯӮөӮДӮўӮҪҒBӮЁӮ»ӮзӮӯҢг”NӮМ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҒAҸҸҗнӮМҸҹ—ҳӮЙ‘ОӮ·ӮйӮ»ӮМҢгӮМ•ДүpҢRӮМ”ҪҚRӮЖ“Ҝ—lӮМҢoүЯӮрӮҪӮЗӮБӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮлӮӨҒB ӮөӮ©ӮөӮұӮМҗ^‘ҠӮНҲк”КӮЙӮН—қүрӮіӮк“пӮӯҒAҚ‘–ҜӮМ‘ҪӮӯӮНҳAҗнҳAҸҹӮМ•с“№ӮМӮЭӮЙҠбӮр’DӮнӮкҒAҚ‘—НӮМҢАҠE“_ӮЙ’BӮөӮДӮўӮҪӮнӮӘҚ‘ӮМҢ»ҸуӮЙӮНӢCӮГӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢӢүКҒAӮўӮҪӮёӮзӮЙҗнҸҹӮЙӮҪӮ©ӮФӮиҚ‘–hӮМҗЖҺгҗ«Ӯр’mӮзӮёӮөӮДҒA–қҗSӮӘҗ¶Ӯ¶ӮҪӮұӮЖӮН”Ы’иӮЕӮ«ӮИӮўҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҗнүКӮЖ‘№ҠQҒ@
ҒЎ“ъ–{ҢR ҺҖ–SӢyӮС•һ–р–ЖҸң –с118000–ј •Я—ё –с2000–ј ҢR”n –с38350“Ә ҢRҠН‘№Һё 12җЗ җ…—Ӣ’шҒE•ВҚЗ—pҠН‘D“ҷ 25җЗ —A‘—‘D“ҷ 54җЗ —ӨҢRҒ@—ХҺһҢRҺ–”п 128328–ңү~ ҠCҢRҒ@—ХҺһҢRҺ–”п 23993–ңү~ ҒЎғҚғVғAҢR җнҺҖ –с115000–ј •Я—ё 79454–ј •ЯҠl”n 3983“Ә кbҠlүО–C 957–е кbҠlҸ¬Ҹe 140904’ҡ ҢӮ’ҫҒE•ЯҠlҠН‘D 98җЗ —}—ҜҒE•җ‘•үрҸңҠН‘D 7җЗ җ„’иҢRҺ–”п 218000–ңү~ҲИҸгҒ@ |
|
|
ҒЎҠeҚ‘ӮМ”ҪүһҒ@
“ъ–{җlӮНҒAҗl“№ӮМӮҪӮЯ”…ҸһӢаӮМҢ —ҳӮр•ъҠьӮөӮҪҒBӮұӮМҲМ‘еӮИҚDҲУӮН“ъ–{җlӮӘ—EҠёӮИӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAҠ°‘еӮИҚ‘–ҜӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺҰӮөӮҪҒBҒҒғҸғVғ“ғgғ“ҒEғXғ^Ғ[ҺҶҒҒ “ъ–{ӮНҗн‘ҲӮЕҺҰӮөӮҪҲМ‘еӮіӮрҚuҳaҸр–сӮЕ— •tӮҜӮҪҒBӮұӮМ“ъ–{ӮМҠ°‘еӮіӮНҗўҠEҺjҸг—бӮрҢ©ӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҒҒғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNҒEғTғ“ҺҶҒҒ “ъ–{ӮНҗўҳ_Ӯр—eӮкӮДҗіӮөӮӯҚs“®ӮөӮ»ӮкӮЙӮжӮБӮД“ҫӮҪ’nҲКӮНҒAӮўӮ©ӮЙӢҗ‘еӮИҠzӮМ”…ҸһӢаӮЙӮаҸҹӮйӮаӮМӮӘӮ ӮйҒBҒҒғfғCғҠҒ[ҒEғjғ…Ғ[ғXҺҶҒҒ “ъ–{җӯ•{ӮӘ”…ҸһӢа•ъҠьӮЙ‘ОӮ·ӮйҚ‘–ҜӮМ•s–һӮЙҠё‘RӮЖ‘ОҢҲӮөӮжӮӨӮЖӮ·Ӯй—EӢCӮНҒA“ъ–{ӮМ—ӨҠCҢRҢRҗlӮӘ“GӮЙ‘ОҢҲӮөӮҪҺһӮМ—EӢCӮЙ”дӮЧ‘»җFӮӘӮИӮўҒBҒҒғӮҒ[ғjғ“ғOҒEғ|ғXғgҺҶҒҒ “ъ–{ӮМҢГӮӯӮ©ӮзӮМӢRҺm“№(•җҺm“№)җёҗ_ӮӘҒA’PӮИӮйӢа‘K“I”z—¶ӮМӮҪӮЯӮМҗн‘ҲҗӢҚsӮр’pӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB(’Ҷ—Ә)ғTғҖғүғCӮМ“`“қӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAӮаӮөҚЎҒAү©ӢаӮМӮҪӮЯӮЙҗнӮӨӮұӮЖӮр–ҪӮ¶ӮзӮкӮйӮЖӮ·ӮкӮОҒA”ЮӮзӮМ–ј—_ӮНүҳӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒBҒҒғ^ғCғҖғXҺҶҒҒ “ъ–{ӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮйӮЖҒAҗўҠEӮН“ъ–{ӮМҸҹҲцӮрҲӨҚ‘җSҒAҺ©—ҘҗSӮИӮЗӮЖӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҠо”ХӮӘ•җҺm“№ӮЙӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮҪҒBӮ»ӮкӮНҗV“nҢЛҲо‘ўӮМҒu•җҺm“№Ғv(Bushido-The Soul of Japan)ӮӘҒA6”NҠФӮЕ10”ЕӮрҸdӮЛӮҪӮұӮЖҒAӢаҺqҢ«‘ҫҳYӮ©ӮзҒu•җҺm“№ҒvӮр‘ЎӮзӮкӮҪғӢҒ[ғYғxғӢғg‘е“қ—МӮӘ30ҚыӮрҚw“ьӮөҒA3ҚыӮр‘§ҺqӮҪӮҝӮЙҒAҺcӮиӮрҗӯ•{—vҗlҒAҢRҠwҚZ“ҷӮЙ”z•zӮөӮҪӮұӮЖӮ©ӮзӮаҒAӮЬӮҪғJғCғ[ғӢҒEғEғBғӢғwғӢғҖҺOҗўӮНғhғCғcҢRӮЙҢьӮ©ӮБӮДҒu“рӮзӮН“ъ–{ҢR‘аӮМҗёҗ_ӮЙӮИӮзӮҰҒvӮЖҢPҺҰӮөӮҪӮұӮЖӮИӮЗӮ©ӮзӮаҒA“–ҺһӮМҗўҠEӮӘ“ъ–{ӮМ•җҺm“№ӮЙӢӯӮӯҠЦҗSӮрҺқӮҝҒA•җҺm“№Ӯр•]үҝӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘ—қүрӮЕӮ«ӮжӮӨҒB ӮұӮМҒu•җҺm“№ҒvӮЕҚЕӮаӢӯ’ІӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮӘҒuӢ`ҒvӮЕӮ ӮиҒAҗlӮӘӮўӮӯӮзҚЛҠoӮӘӮ ӮБӮДӮаҒuӢ`ҒvӮӘӮИӮҜӮкӮО•җҺmӮЕӮНӮИӮўӮЖҗаӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮД‘ҪӮӯӮМҺбҺТӮӘҒAӮМӮҝӮМ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЕӮНҒu—IӢvӮМ‘еӢ`ҒvӮЖӮўӮӨғAғWғAүр•ъӮМҒuӢ`(—қ‘zҒEҗіӢ`)ҒvӮМӮҪӮЯӮЙҗ¶–ҪӮр•щӮ°ӮҪҒB –ҫҺЎҲЫҗVӮ©ӮзӮнӮёӮ©30—]”NӮЙӮөӮДҗјүў“IӢЯ‘гү»Ӯр’Bҗ¬ӮөӮҪҚӮ“xӮИӢZҸp—НҒAҸ¬җlӮМӮжӮӨӮИ“ъ–{ҢRҸ«•әӮМӢБӮӯӮЩӮЗ—EҠёӮЕ•sӢьӮМҗёҗ_—НҒAӮұӮкӮзӮНүў•ДҗжҗiҚ‘Ӯ©ӮзҠҙ’QӮЖҲШ•|ӮрӮаӮБӮДҢ}ӮҰӮзӮкӮҪҒB•xҚ‘Ӣӯ•әҚфӮрҢoӮДӮМ“ъҗҙҗн‘ҲҒAүзҗdҸҰ’_ӮМҢгӮМ“ъҳIҗн‘ҲҒAӮ»ӮкӮНүдӮӘ—ӨҠCҢRӮӘ‘SҚ‘–ҜӮМҢгүҮӮМӮаӮЖӮЙ“oӮиӮВӮЯӮҪҲкӮВӮМү©ӢаҺһ‘гӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲӮМ—рҺj“IҲУӢ`Ғ@
“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҒA—LҗFҗlҺнӮМҲкҸ¬Қ‘ӮӘ”’җFҗlҺнӮМӢӯҚ‘ғҚғVғAӮр‘ЕӮҝ”jӮБӮҪӮұӮЖӮНҒAӮЬӮіӮЙ13җўӢIӮМ–ЦҢГ’йҚ‘ҲИ—ҲҗвӮҰӮДӢvӮөӮўӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBғAғWғAӮМҠҙҢғӮН‘еӮ«ӮӯҒAғVғӢғNғҚҒ[ғhӮМҸhҸкӮМ‘ҪӮӯӮЙӮНҒA–ҫҺЎ“VҚcӮМӮІҗ^үeӮЖ“ҢӢҪҢіҗғӮМҺКҗ^ӮӘҸьӮзӮкӮҪӮЩӮЗӮЕҒAғCғ“ғhӮМғlҒ[ғӢӮНҒAҒuҗВ”NҺһ‘гҚЕ‘еӮМҠҙҢғӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЕ“ъ–{ӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒvӮЖӢLӮөӮДӮўӮйҒB—LҗFҗlҺнӮМҺuӢCӮрҢЫ•‘ӮөҒA–Ҝ‘°ҲУҺҜӮрҚӮӮЯӮҪӮұӮЖӮНҳ_Ӯр‘ТӮҪӮИӮўҒB ғAғWғAӮМ“Ж—§ҒAғAғWғAӮМ–Ҝ‘°ү^“®ӮНӮұӮұӮЙүиӮрӮУӮўӮҪҒBҗҙҚ‘ӮЙҗhҲеҠv–ҪӮӘӢNӮұӮБӮҪӮМӮаҠФӮаӮИӮўҢгӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{Ӯр”НӮЖӮөҒA”’җFҗlҺнӮМҺx”zӮ©Ӯз’EӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӢCү^ӮӘӮжӮӨӮвӮӯ“®Ӯ«ҸoӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪҒBӮ»ӮМүeӢҝӮН’Ҷ“ҢӮвғҚғVғAӮМҗЁ—НҢ—“аӮЙӮ ӮБӮҪғ|Ғ[ғүғ“ғhҒEғtғBғ“ғүғ“ғhӮИӮЗӮЙӮЬӮЕӢyӮсӮҫҒB‘OҸqӮМғlҒ[ғӢҺс‘ҠӮрӮНӮ¶ӮЯҒA—LҗFҗўҠEӮМ‘ҪӮӯӮМҗӯҺЎ“IҺw“ұҺТӮӘҒA“ъҳIҗн‘ҲӮрҢ_Ӣ@ӮЙӢNӮҝҸгӮӘӮиҒAүў•Д—сӢӯӮМ’йҚ‘ҺеӢ`“IҺx”zӮЙүКҠёӮЙ’§җнӮөҒAҗӢӮЙӮН—рҺjӮМӢAҗ–Ӯр•ПӮҰӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB“–ҺһӮЙӮЁӮўӮД“ъ–{–Ҝ‘°ӮМүКӮҪӮөӮҪ–рҠ„ӮНҒAҺАӮЙҲМ‘еӮИӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮжӮӨҒB җјүўӮМҺjҸ‘ӮЕӮНҒAғtғүғ“ғXҠv–ҪӮӘҚ‘–ҜҚ‘үЖӮрҗ¬—§ӮіӮ№ӮҪӮЖӮөӮДӮўӮйӮӘҒA–Ҝ‘°Қ‘үЖӮМ“Ж—§ӮрғAғWғAӮвғAғүғuҒAғAғtғҠғJҸ”Қ‘ӮЙ–ЪҠoӮЯӮіӮ№ӮҪӮМӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМү^“®ӮЙүОӮрӮВӮҜҒA—LҗFҗlҺнӮМ–Ҝ‘°Қ‘үЖӮрҢҡҚ‘ӮіӮ№ӮҪӮМӮӘҒAӮМӮҝӮМ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ҒBҒ@ |
|
| Ғ@ | |
| ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲӮЖҢRҗl | |
|
ҒЎ–һҸBҢR/“ҢӢһ‘е–{үc
ҺR–{Ң •әүq/‘еҺRҠЮ/ҺҷӢКҢ№‘ҫҳY/Ҹјҗм•qҲы/—§Ң©Ҹ®•¶ ҒЎ‘жҲкҢR Қ•–ШҲЧъй/“ЎҲд–О‘ҫ/”~‘т“№ҺЎ ҒЎ‘ж“сҢR үң•ЫиЭ/—ҺҚҮ–LҺOҳY/ӢkҺь‘ҫ ҒЎ‘жҺOҢR ”T–ШҠу“T/ҲЙ’n’mҚKүо/‘е’л“сҳY/’Г–м“cҗҘҸd/ҲкҢЛ•әүq/’Ҷ‘әҠo ҒЎ‘жҺlҢR –м’Г“№ҠС/ҸгҢҙ—EҚм ҸHҺRҺx‘а-ҸHҺRҚDҢГ Ҡӣ—ОҚ]ҢR-җм‘әҢi–ҫ ҒЎ‘жҲкҠН‘а “ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY/үБ“Ў—FҺOҳY/ҸHҺRҗ^”V/ҺOҗ{Ҹ@‘ҫҳY/ҸoүHҸdү“/—L”n—ЗӢk/—й–ШҠС‘ҫҳY/ҚLҗЈ•җ•v ҒЎ‘ж“сҠН‘а Ҹг‘ә•F”VҸе/ҚІ“Ў“S‘ҫҳY/“Ү‘ә‘¬—Y/“ЎҲдҠrҲк/үZҗ¶ҠOӢg/”Ә‘гҳZҳY ҒЎ‘жҺOҠН‘а •РүӘҺөҳY ҒЎғҚғVғA ғXғeғtғ@ғ“ҒEғ}ғJғҚғt/ғJҒ[ғӢҒEғyғgғҚғ”ғBғ`ҒEғCғFғbғZғ“Ғ@ |
|
| ҒЎ–һҸBҢR/“ҢӢһ‘е–{үc | |
|
ҒЎҺR–{Ң •әүq 1852-1933 ҺF–Җ”Л үБҺЎү®’¬
“ъҳIҠJҗн“–ҺһӮМҠCҢR‘еҗbҒB үў•Д—сӢӯӮЙ”дӮөӮДӮ ӮЬӮиӮЙӮаҗЖҺгӮЕӮ ӮБӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮрҒA‘еҚ‘ғҚғVғAӮЙ‘ОҚRӮө“ҫӮйӮЬӮЕӮЙ‘қӢӯӮөӮҪҢчҗСӮ©ӮзҒA“ъ–{ҠCҢRӮМҗ¶ӮЭӮМҗeӮЖӮМҲЩҸМӮаӮ ӮйҒB ҚЎӮЙҺcӮйӮўӮӯӮВӮ©ӮМҺКҗ^ӮМ•—–eӮӘҺҰӮ·ӮЖӮЁӮиҒAҺб”NӮМҚ ӮжӮи—E–ТӮИҗ«ҠiӮЕӮ ӮиҒAӮ©ӮВҢbӮЬӮкӮҪ“ч‘МӮ©ӮзҒAҺF–ҖӮМ’ҶӮЕӮа’ҶҗS“IӮИҗl•ЁӮҫӮБӮҪҒB—cӮўҚ Ӯ©ӮзҒwҗlӮЙӮИӮ©ӮИӮ©ӢьӮөӮИӮў–\ӮкӮс–VӮМӢCҺҝҒxӮӘӮ ӮиҒA”ЮӮМ•ғҗeӮИӮЗӮНҒuҢ •әүqӮНӮжӮӯӮдӮҜӮО—§”hӮИҗl•ЁӮЙӮИӮйӮӘҒAҲк•аҢлӮйӮЖӮЗӮсӮИҗlҠФӮЙӮИӮйӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒvӮЖҗS”zӮөӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМҢгҒAҸ\‘г‘O”јӮ©Ӯз’№үH•ҡҢ©Ғ`•и’Cҗн‘ҲӮЙҸ]ҢRҒAҗнҢгӮН—НҺmӮЙӮИӮлӮӨӮЖӮөӮҪӮЖӮ©ҒAҠCҢR•әҠw—ҫӮМҺҺҢұӮЙ—ҺӮҝӮкӮОӮвӮӯӮҙҺТӮЙӮИӮйҠoҢеӮҫӮБӮҪӮЖӮ©ҒAӮўӮ©ӮЙӮаҺF–ҖӮзӮөӮў–іҚңӮЕаЦ–ТӮИғGғsғ\Ғ[ғhӮӘҺcӮБӮДӮўӮйӮӘҒAҺАҚЫӮЙӮНӢЙӮЯӮДӢӯӮў—қҗ«ӮЕҢЕӮЯӮзӮкӮҪҗl•ЁӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒB ҺF–Җ”ҙӮМ“ӘӮЕӮ ӮБӮҪҗјӢҪ—Іҗ·ӮӘҒA–ҫҺЎҗӯ•{ӮЙ‘ОӮ·Ӯй”Ҫ—җҢRӮМҗeӢКӮЖӮөӮД•s•Ҫ•ӘҺqӮзӮЙ’SӮ¬ҸгӮ°ӮзӮкӮҪҚЫҒA‘ҪӮӯӮМҺF–ҖҗlӮзӮНҗјӢҪ‘ӨӮЙ’…ӮӯӮЧӮӯҗEӮрӮИӮ°ӮӨӮБӮДҺF–ҖӮЦӮЖӢAҠТӮөӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҢ •әүqӮа—бҠOӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAҠщӮЙҸ«—ҲӮМ—L–]Ҡ”ӮЖӮөӮДҢ •әүqӮМҚЛҠoӮрҢ©ҸoӮөӮДӮўӮҪҗјӢҪӮНҒAҢ •әүqӮрҗа“ҫӮөӮД“ҢӢһӮЦ•ФӮйӮжӮӨӢӯӮӯҢҫӮў•·Ӯ©Ӯ№ӮҪҒBҗјӢҪӮМӮаӮЖӮЙҺcӮБӮҪ“Ҝ–EӮзӮрүЎ–ЪӮЙҒAҢ •әүqӮНӢғӮӯӢғӮӯ“ҢӢһӮЙҲшӮ«•ФӮөҺmҠҜҠwҚZӮЦ•ңӢAҒAӮ»ӮМӮЬӮЬҠCҠO—ҜҠwӮЦӮЖ—·—§ӮҝҒAғhғCғcӮМ‘D”•ҸгӮЕҗјӢҪӮМҺҖӮр’mӮзӮіӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒBҺR–{Ң •әүqӮМҗlҗ¶ӮЙӮЁӮўӮДӮұӮМҺһӮЩӮЗ”ЯӮөӮЭӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪҸo—ҲҺ–ӮН–іӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮ ӮзӮ©Ӯ¶ӮЯ—\‘zӮіӮкӮҪӮұӮМҢӢ––ӮрҠГӮсӮ¶ӮДҺуӮҜ“ьӮкӮҪӮМӮНҒAҲкҺһӮМҠҙҸоӮЙ—¬ӮіӮкӮёӮЙҚ‘ӮМҸ«—ҲӮрҢ©җҳӮҰӮҪ”»’fӮМҢӢүКӮЕӮ ӮиҒAҢ •әүqӮӘҒuҸоӮжӮи—қҗ«ӮЙҸҹӮйҗlҒvӮЕӮ ӮБӮҪҺ–ӮрҸШ–ҫӮ·Ӯй•ӘӮ©ӮиӮвӮ·Ӯў—бӮЖҢҫӮҰӮйҒB“Ҝ—lӮМғPҒ[ғXӮЖӮөӮД‘жҺlҢRҺi—ЯҠҜӮМ–м’Г“№ҠСӮӘӮўӮйҒB’ZӢCӮЕӢ°ӮлӮөӮўӮЖҺvӮнӮкӮҪ”ЮӮаҒAҺАҚЫӮЙӮНҗlҲк”{ӮМ—қҗ«ӮЕ•ЁҺ–Ӯр”»’fӮ·Ӯйҗl•ЁҒBӮжӮБӮД–м’ГӮаҢ •әүqӮЖ“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙҗјӢҪӮМҗа“ҫӮрҺуӮҜ“ьӮкҒAҗј“мҗн‘ҲӮЕҗјӢҪ‘ӨӮЙӮВӮӯҺ–ӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҺR–{Ң •әүqӮӘҠCҢR”ЁӮМ’ҶӮЕ“ӘҠpӮрҢ»ӮөӮҪ—қ—RӮЖӮөӮДҒAҗl•АӮЭҠOӮкӮҪӢLүҜ—НӮвҒA•ЁҺ–Ӯр—қҳHҗ®‘RӮЖ“`ӮҰӮй”\—НӮӘҗlҲк”{—DӮкӮДӮўӮҪҺ–ӮӘӮ Ӯ°ӮзӮкӮйҒBӮЬӮҪ”сҸнӮЙҠМӮӘҗҳӮнӮБӮДӮЁӮиҒA‘еӮ«ӮИҢрҸВӮЕ•Ё•|Ӯ¶ӮөӮИӮўӮЖӮ©ҒA‘ҠҺиӮМҲУ•\ӮрӮВӮўӮДҺ©•ӘӮМғyҒ[ғXӮЙҺқӮҝҚһӮЮӮИӮЗҒAҺбӮўҺһ•ӘӮЙҠщӮЙ‘Ҡ“–ӮМҳVаФӮіӮа•№Ӯ№ҺқӮБӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮұӮЙҢҷӮзӮөӮіӮӘ–іӮӯҒAӮдӮӯӮдӮӯӮН–ҫҺЎ“VҚcӮЙӮаҲӨӮіӮкӮҪӮжӮӨӮЙҒA”сҸнӮЙӢCҺқӮҝӮМӮўӮўҗl•ЁӮЕӮ ӮБӮҪҺ–Ӯа“Б•MӮ·ӮЧӮ«ӮҫӮлӮӨҒB Ӯ»ӮсӮИҢ •әүqӮӘӮўӮжӮўӮж“ъ–{ҠCҢRӮЙғҒғXӮр“ьӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB“ъҳIҠJҗнӮМ10”N‘OҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМҺOҚ‘ҠұҸВӮНҒAӢЯ‘г“ъ–{ӮӘ–ЎӮнӮБӮҪҚЕҸүӮМҚ‘җJӮҫӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮрҠъӮЙҚ‘үЖ‘қӢӯӮЙ”ҸҺФӮӘӮ©Ӯ©ӮБӮҪӮМӮНҠФҲбӮўӮИӮўҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕҸ«—Ҳ“Ң—mӮЕ“ъ–{ӮЖҸХ“ЛӮ·ӮйүВ”\җ«ӮМӮ ӮйӮМӮНғҚғVғAӮҪӮҫҲкҚ‘ӮЕӮ ӮиҒAҢ •әүqӮЖӮөӮДӮНӮұӮкӮЙ‘ПӮҰӮӨӮйӮҫӮҜӮМҠCҢRӮрҺd—§ӮДӮйӮМӮӘҺҠҸг–Ҫ‘иӮҫӮБӮҪҒBӮұӮұӮЕ—§ӮҝҸгӮ°ӮзӮкӮҪӮМӮӘ–ҫҺЎ29”NӮ©ӮзҺАҺ{ӮіӮкӮҪҸ\ғ•”NҢvүжӮЕӮ ӮйҒB 10”NӮЕҢRҠН‘ҚҢv5–ңtҒЛ25–ңtҒAҠCҢRҢRҗl12,000җlҒЛ36,000җlӮЦӮМ‘е‘қӢӯӮНҒAҚ‘үЖ—\ҺZӮМӮ©ӮИӮиӮМ•”•ӘӮӘ’ҚӮӘӮкӮҪ‘еҺ–ӢЖӮЕҒAҚ‘–ҜӮЦӮМҗЕ•ү’SӮНҗ¶ҠҲӮрӮ©ӮИӮиҲі”—ӮөӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮӘҒAӮұӮұӮЕҚЎ“ъӮМ“ъ–{ӮЖҢҲ’и“IӮЙҲЩӮИӮйӮМӮНҒA‘ҪӮӯӮМҚ‘–ҜӮӘӮұӮМҸdҗЕӮр‘OҢьӮ«ӮЙҺуӮҜҺ~ӮЯӮҪҺ–ӮЕӮ ӮиҒAҺһӮЙҒuҲк‘МӮўӮВӮЙӮИӮБӮҪӮзҢRҠНӮӘӮЕӮ«Ӯ ӮӘӮйӮсӮҫҒHҒvӮЖӮЮӮөӮлҚГ‘ЈӮМҗәӮИӮЗӮа•·Ӯ©ӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒBҺOҚ‘ҠұҸВӮЕҒwүзҗdҸҰ’_ҒxӮӘҚ‘үЖғҢғxғӢӮЕӮМғXғҚҒ[ғKғ“ӮЖӮИӮБӮДҲИҢгҒA“ъ–{–Ҝ‘°җlҺқӮҝ‘OӮМ”E‘П—НӮӘҚЕ‘еҢАӮЙ”ӯҠцӮіӮкҒA’·ӮӯӢкӮөӮўҸdҗЕҒE•nҚўӮМ10”NӮрҸжӮиүzӮҰӮДүў•Д—сӢӯ•АӮЭӮМҠCҢRӮӘҗ¬—§Ӯ·ӮйӮЙҺҠӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB –ЪӮМ‘OӮЙ–ҫҠmӮИ“GӮМҺpӮӘӮ ӮиҒAҸdҗЕӮМҺg“rӮӘӢЙӮЯӮД•ӘӮ©ӮиӮвӮ·ӮўӮЖӮўӮӨҸуӢөӮӘҚ‘–ҜӮМ”E‘ПӮЖҗёҗ_ӮрҺқ‘ұӮіӮ№ҒAҚ‘үЖӮӘҗN—ӘӮіӮкӮйӢ°•|ӮЖүў•Д—сӢӯӮЦӮМҲШ•|ҒE“ІңЫӮӘүдӮӘҚ‘ӮМ”т–ф“Iҗ¬’·ӮМ—ЖӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙҗж—§ӮВҗ”Ҹ\”N‘OҒA—ЧӮМҗҙҚ‘ӮЕӮНҺ—ӮҪӮжӮӨӮИҸуӢөӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮёҒAӮұӮМӮжӮӨӮЙӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМҚ·ӮНҚ‘–Ҝҗ«ӮМҲбӮўӮаӮ ӮйӮҫӮлӮӨӮӘҒA—DӮкӮҪҺw“ұҺТӮМ—L–іӮЖӮўӮӨ“_ӮНӮвӮНӮи–іҺӢӮЕӮ«ӮИӮўҒB ҺR–{Ң •әүqӮНҠCҢRӮМ‘е‘қӢӯӮжӮиҲИ‘OӮЙҒAҠCҢRҗlҺ–ӮМ‘еҗ®—қӮрҚsӮБӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAҢR•”ӮМҚӮҠҜӮзӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮӘ•и’Cҗн‘ҲӮЕҠҲ–фӮөӮҪӢҢҺһ‘гӮМүp—YӮЕӮ ӮиҒA“ҜҺһӮЙҺһ‘г’xӮкӮМҗн‘Ҳү®ӮҫӮБӮҪҒB‘ҪӮӯӮНҢ •әүqӮМ“ҜӢҪӮЕӮ ӮйҺF–ҖҗlӮЕӮ ӮиҒAҢ •әүqӮМҗж”yӮЙ“–ӮҪӮйҗlҠФӮа‘Ҫҗ”ҒB”ЮӮНӮұӮкӮзӮр‘SӮД—\”х–рӮЦӮЖ’ЗӮўӮвӮиҒAҗіӢKӮМҢRҗlӢіҲзӮрҺуӮҜӮҪҺбҺиӮзӮрҸd—pӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҢгӮЙ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМҺQ–d’·Ғ`‘Қ—қ‘еҗbӮЖӮИӮйүБ“Ў—FҺOҳYӮИӮЗӮа”h”ҙӮр’ҙӮҰӮДҢ •әүqӮЙҢ©ҸoӮіӮкӮҪҲнҚЮӮЕӮ ӮиҒAӮЬӮҪ•aҺгӮЕ—\”х–рҚsӮ«ӮӘ”ZҢъӮҫӮБӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYҺ©җMӮаҒAӮұӮұӮЕӮМҢ •әүqӮМ”»’fӮЕҢ»–рӮЙӮЖӮЗӮЯӮзӮкӮҪҢoҲЬӮӘӮ ӮйҒBҸоӮжӮи—қҗ«ӮЕ•ЁҺ–Ӯр”»’fӮ·ӮйӢCҺҝӮӘҺw“ұҺТӮМҺ‘ҺҝӮЖӮөӮД”ӯҠцӮіӮкӮҪҲкӮВӮМ—бӮЕӮ ӮиҒA“–ҺһӮМҗV•·ӮЕӮа‘Ҡ“–•ЁӢcӮрӮ©ӮаӮөӮҪӮзӮөӮўӮӘҒAҢӢүК“IӮЙҚ‘үЖ‘еҢvӮҫӮБӮҪҺ–ӮӘҸШ–ҫӮіӮкӮДӮўӮйҒB ҺR–{Ң •әүqӮНҗӯҺЎӮрҠЬӮЮҗн—ӘүЖӮЖӮөӮДӮа—DӮкӮДӮЁӮиҒA‘ҒӮў’iҠKӮЕҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮЮҲИҠOӮЙӮұӮМҗн‘ҲӮЙҸҹӮҝ–ЪӮНӮИӮўӮЖҚlӮҰӮҪҒB‘SӮДӮМҢoҲЬӮвҢӢүКӮр’mӮйүдҒXӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA—L—ҳӮЙҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮЮҚ\‘zӮН“–ӮҪӮи‘OӮЙҺvӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮөӮ©ӮөҒAҺ©ӮзӮМҺиӮЕ—сӢӯӮЙ•АӮФҢRҠНӮр—КҺYӮөҒAӮ»ӮМҲР•—Ӯр’ӯӮЯӮкӮОҒwӮЁӮ©ӮөӮИӢCҒxӮрӢNӮұӮөӮДӮөӮЬӮӨӮМӮӘҗlҠФӮЖӮўӮӨӮаӮМҒBҺ–ҺАҚ‘–ҜӮНҺ©Қ‘ӮМүh’BӮЙҠҙ“®ӮөӮҪҒBӮўӮжӮўӮж“ъҳIҠJҗнӮӘ”ZҢъӮЙӮИӮиҺnӮЯӮҪҺһҒAӮИӮсӮЖӮ©җн‘ҲӮрүс”рӮөӮжӮӨӮЖӮ·Ӯйҗӯ•{ӮрҒAҗўҳ_ӮНҺгҚҳӮЖ”с“пӮөӮҪҒBҢгӮМ“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДӮНҢRҺс”]•”ӮӘӮұӮМ‘еҸOҗўҳ_ӮЙ•ЦҸжӮөҒAҢӢүКӮЖӮөӮД–Е–SҗЎ‘OӮЬӮЕ’@Ӯ«ӮМӮЯӮіӮкӮйӮМӮҫӮӘҒA–ҫҺЎҚ‘үЖӮЙӮЁӮўӮДӮН—қҗ«ӮМҗlҒAҺR–{Ң •әүqӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҒAҠфҗlӮ©ӮМ—DӮкӮҪҺw“ұҺТӮЙӮжӮиҒAӮ»ӮМ“пӮрүс”рӮЕӮ«ӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨҒB ҺR–{Ң •әүqӮӘҺеҺІӮЖӮИӮБӮД’zӮ«ҸгӮ°ӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAӮұӮМҺһ‘гӮЕҚlӮҰ“ҫӮйҚЕҚӮӮМ“ӯӮ«ӮЕ”C–ұӮр‘SӮӨӮөӮҪҒBӮұӮМҗн‘ҲӮМҢгҒAҢ •әүqӮНҒA‘ў‘DӢЖӮр–ҜҠФӮЙҲП‘хӮ·Ӯй•ыҗjӮрҚМ—pӮөҒAҺO•H‘ў‘DӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй–ҜҠФӮМ‘ў‘DӢZҸpӮр”т–ф“IӮЙҚӮӮЯҒAҢгӮМ‘ў‘D‘еҚ‘ӮҪӮй“ъ–{ӮМ‘bӮр’zӮӯӮЙҺҠӮйҒBҢгӮЙӮ©ӮМҗнҠН‘еҳaӮӘ‘ў‘DӮіӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮйҢаҠCҢRҚHҸұӮМ‘ў‘DғhғbғOӮаӮұӮМ—¬ӮкӮЕҢҡ‘ўӮіӮкӮҪӮаӮМӮЕҒAӮұӮМ“–ҺһҒAҗўҠEӮЕӮаҢQӮр”ІӮӯӢҗ‘еӮИғhғbғOӮҫӮБӮҪҒBӮұӮМғhғbғOӮМӢLҳ^ӮН‘ж“сҺҹ‘еҗнҢгӮМӢЯ‘гӮЬӮЕ‘ұӮ«ҒA60”N‘гӮМғ^ғ“ғJҒ[ӮМҺһ‘гӮЙӮИӮБӮДӮжӮӨӮвӮӯҗўҠEҗ…ҸҖӮЖӮөӮД’и’…ӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮ©ӮзҒAҢ •әүqӮМҗжҢ©ӮМ–ҫӮН–}җlӮМӢyӮФӮЖӮұӮлӮЕӮНӮИӮўҒB Қ‘үЖӮЙӮЖӮБӮД—LүvӮИӮұӮМҗl•ЁӮӘ•\•‘‘дӮ©Ӯз‘ЮҸкӮ·Ӯй—vҲцӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҗӯҺЎӮӘӮзӮЭӮЕӮМғSғ^ғSғ^ӮҫӮБӮҪҒB‘Қ—қ‘еҗbҚЭ”CҺһӮМғVҒ[ғҒғ“ғXҺ–ҢҸ(ҢR•”—ҚӮЭӮМүҳҗE)ӮвҒAӮ©ӮЛӮДӮжӮиҒwҢ •әүqӮЙӮўӮўҠҙҸоӮрҺқӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒx”Ә‘гҳZҳYҠCҢR‘еҗbӮМҺvҳfӮИӮЗҒAҢ •әүqӮЙӮЖӮБӮДғ}ғCғiғXӮЖӮИӮй—vҲцӮН–{җlӮМҗУ”CӮЖӮНҠЦҢWӮИӮӯҢ •әүqӮрүЯӢҺӮМҗlӮЖӮөӮҪҒBҢӢүК“IӮЙҚ‘үvӮр‘еӮ«Ӯӯ‘№ӮИӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAҗнҸҹҚ‘ӮӘӮ»ӮМүhүШӮЙӮжӮБӮДӮЭӮёӮ©Ӯз“]—ҺӮөҺnӮЯӮДӮўӮҪҲкӮВӮМ’ӣӮөӮЖҢҫӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB Ң •әүqӮН“ъ•ДҠJҗнӮМ8”N‘OҒA1933”NӮМ12ҢҺ8“ъӮЙ–vӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘еҺRҠЮ 1842-1916 ҺF–Җ”Л үәүБҺЎү®’¬
–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҺАҺҝӮМ‘ҚҺi—ЯҠҜӮЕӮ ӮйҒB ҢҢӢШӮНҗјӢҪ—Іҗ·ӮМҸ]ҢZ’нӮЙӮ ӮҪӮиҒAҗјӢҪӮМ’нӮМҸ]“№ӮЖӮЖӮаӮЙҠнӮМ‘еӮ«ӮіӮЕ’mӮзӮкӮйҒB‘еӮзӮ©ӮЕғfғ“ӮЖҚ\ӮҰҒAӮЗӮұӮ©”ІӮҜӮҪӮжӮӨӮИ•—–eӮИӮӘӮзҒA–Ӣ––ӮМ“®—җҠъӮр‘OҗьӮЕӮ©ӮўӮӯӮ®ӮБӮДӮ«ӮҪ–ТҺТӮЕӮ ӮиҒA“–Һ–ӮНҸнӮЙҗјӢҪӮМӮ»ӮОӮЕ•вҚІӮ·Ӯй—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҒB‘еҺRӮМҒAҺF–Җ•җҺmӮМҺс—МӮЖӮөӮДӮМҗUӮй•‘ӮўӮНҗјӢҪӮМүeӢҝӮрҗF”ZӮӯ”ҪүfӮөӮҪӮаӮМҒB–ҫҺЎҸүҠъӮЙӮНўҺF–ҖӮНғoғJӮҫЈӮЖӮўӮӨүAҢыӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮӘҒAӮұӮкӮНҗјӢҪӮрҺnӮЯӮЖӮ·ӮйҺF–ҖӮМҺе—vҳA’ҶӮМҺ–ӮрҺwӮөӮДӮЁӮиҒAҚЧҺ–ӮЙӮұӮҫӮнӮзӮёҒAӮЬӮҪ—Y•ЩӮрҢҷӮӨҺF–ҖҺ®ӮМғҠҒ[ғ_Ғ[‘ңӮӘҒA‘ј”ЛӮ©ӮзҢ©ӮкӮОӮМӮлӮЬӮЙҢ©ӮҰӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮМҺF–ҖҺ®ӮМ–{—¬ӮрҚsӮӯ‘еҺRӮӘҒA“–Һ–ӮМҗјӢҪӮ»ӮМӮЬӮЬӮМ‘ңӮЕҒAҚ‘ү^ӮрӮ©ӮҜӮҪҗнӮМ‘ҚҺi—ЯҠҜӮЖӮИӮБӮҪҒB ‘еҺRӮНҠJҗн‘OӮЙҒAӮЖӮ Ӯйҗl•ЁӮЙўҸҹӮБӮДӮўӮйҺһӮНҺҷӢКӮіӮсӮЙ‘SӮДӮрӮЬӮ©Ӯ№ӮйҒBӮўӮжӮўӮж”sӮҜҗнӮЙӮИӮйҺһӮЙӮНҺ©•ӘӮӘҸoӮДҚsӮ©ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўЈӮЖҢкӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҒA“ъҳIҗн‘Ҳ’ҶӮН‘SӮДӮрҺQ–d‘Қ’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮзӮЙҲПӮЛӮйҢ`ӮрӮЖӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAҢ`Һ®ҸгӮНҸҹӮҝ‘ұӮҜӮҪӮҪӮЯҒA‘еҺRӮМҸoӮй–ӢӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮжӮӯҒA‘гӮнӮиӮЙҢғҗн’ҶӮЕӮМ‘еҺRӮМғ{ғPӮҪғGғsғ\Ғ[ғhӮОӮ©ӮиӮӘҺcӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮӘҒAҗј“мҗн‘ҲӮМӮұӮлӮжӮиҒA‘еҺRӮӘ(ҲУҗ}“IӮЙ)ғ{ғPӮДҢ©Ӯ№ӮйӮМӮНҗнӢөӮӘ”сҸнӮЙҢөӮөӮўҺһӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкҒAӮ·ӮИӮнӮҝ‘еҺRӮМҒw–{“–ӮМҲУ–ЎӮЕӮМҸo”ФҒxӮНӮ·Ӯ®Ӯ»ӮұӮЬӮЕ—ҲӮДӮўӮҪҸШӮЕӮаӮ ӮйҒB ӮҝӮИӮЭӮЙҒA‘еҺRӮӘҢкӮБӮҪҒAҗжҸqӮМҒgӮЖӮ Ӯйҗl•ЁҒhӮЖӮНҠCҢR‘еҗbӮМҺR–{Ң •әүqӮҫҒBҺR–{ӮНҠJҗнӮЙҗж—§ӮҝҒA‘ОҳIӮМ’вҗнҢрҸВӮұӮ»ӮӘ“ъ–{ӮМҗ¶–ҪҗьӮЕӮ ӮйҺ–Ӯр‘еҺRӮЙ”OүҹӮөӮЙҚsӮБӮҪҚЫҒAҸгӢLӮМ‘дҺҢӮрҺуӮҜҺжӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮМҺһҺR–{ӮНҒA‘еҺRӮЙҚ‘“а‘е–{үcӮЙҺcӮйӮжӮӨ’сҲДӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮӘҒAӮ ӮБӮіӮиӮЖ’fӮзӮкӮДӮўӮйҒB‘еҺRӮӘҢҫӮӨӮЙӮНў”ЮӮзӮНҗнӮНҺ„ӮжӮиӮаӮёӮБӮЖҸгҺиӮҫӮӘҒA•KӮёүдӮр’ЈӮБӮДҚмҗнӮЙҺxҸбӮрӮ«ӮҪӮ·ЈӮЖӮўӮӨҺ–ӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBӮҫӮ©ӮзҺ©•ӘӮӘҢ»ҸкӮЕ‘ҚҺwҠцӮрӮЖӮзӮЛӮОӮИӮзӮИӮўӮЖҒBӮұӮұӮЕӮўӮӨ”ЮӮзӮЖӮНҒA‘жҲкҢRӮМҚ•–ШӮЖ‘жҺlҢRӮМ–м’ГӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӢӨӮЙҺF–Җ•җҺmӮМҸгӮӘӮиӮЕӮ ӮиҒAҚ•–ШӮИӮЗӮН‘еҺRӮЖ“ҜӢҪӮМүәүБҺЎү®’¬ӮМҸoӮҫӮ©Ӯз—cҺһӮМҚ Ӯ©Ӯз’mӮБӮДӮўӮйҠФ•ҝӮҫӮлӮӨҒB ӮЖӮұӮлӮЕ‘еҺRӮНҒA–CҸpӮМ‘жҲкҗlҺТӮҫҒB‘cҗжӮМ‘гӮ©ӮзүҪӮ©ӮЖ”тӮС“№ӢпӮЙүҸӮӘӮ ӮиҒA•ғӮМүeӢҝӮаӮ ӮБӮДҺбӮўҚ Ӯ©Ӯз‘е“ӣӮМҢӨӢҶӮЙ—]”OӮӘ–іӮ©ӮБӮҪҒB–Ӣ––ӮМ•и’Cҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДӮН–CҸp’·ӮЖӮөӮДҠҲ–фҒBҺ©ӮзӮМ–јӮМӮВӮўӮҪҒw–нҸ•–CҒxӮЖӮўӮӨӮаӮМӮаҠJ”ӯӮөӮДӮўӮйӢШӢа“ьӮиӮМ–C•әүЖӮЕӮ ӮйҒB–ҫҺЎӮЙ“ьӮБӮДӮ©ӮзӮНғhғCғc—ҜҠwӮЕӮіӮзӮЙ–ҒӮ«ӮрӮ©ӮҜӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪӮұӮМҺһӮЙ•Ғ•§җн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйғҒғbғc—vҚЗӮМҚU—Әҗн(“ЖӮМҸҹ—ҳ)ӮЙҠПҗн•җҠҜӮЖӮөӮДҸ]ҢRҒBӢЯ‘г—vҚЗӮЙӮЁӮҜӮйҗ퓬ӢK–НӮМӮ·ӮіӮЬӮ¶ӮіӮрҺ©ӮзӮМҠбӢ…ӮЙҸДӮ«•tӮҜӮДӮ«ӮҪҗlӮЕӮаӮ ӮйҒBӮұӮкӮзӮМҢo—рӮ©Ӯз•ӘӮ©ӮйӮжӮӨӮЙҒAҲкҢ©ӮМӮлӮЬӮЕӮӨӮ·ғ{ғPӮМҗl•ЁӮН‘SӮӯҲИӮБӮД•\–КҸгӮМӮаӮМӮЕӮөӮ©ӮИӮӯҒAў‘еҺRӮіӮсӮМҲМӮіӮНҒAүәӮЕҺgӮнӮкӮҪҺТӮөӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўЈӮЖӮўӮӨҒA“–Һ–ӮМҢjҺс‘ҠӮМҢҫ—tӮӘҢ»ҺА–ЎӮр‘СӮСӮДӮӯӮйӮнӮҜӮҫҒB ӮЖӮНҢҫӮҰҒAӮаӮҝӮлӮс‘еҺRӮа–ң”\ӮЕӮНӮИӮўҒBҢӢүКӮ©ӮзҢ©ӮкӮО“KҗШӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪ”»’fӮаӮ ӮйҒB—·ҸҮ—vҚЗӮМ203ҚӮ’nӮЕӮ ӮйҒBҠCҢRӮМҸHҺRҗ^”VҺQ–dӮжӮиҒAҚU—ӘӮМҺеҠбӮр203ҚӮ’nӮЙҸW’ҶӮ·ӮЧӮ«ӮЖӮМҲДӮӘҸoӮҪҚЫҒA“ҢӢһӮМ‘е–{үcӮНӮ»ӮМ“№—қӮЙҺ^“ҜӮөҒAӮ·ӮЭӮвӮ©ӮЙӮұӮкӮрҺАҚsӮЙҲЪӮ·ӮЧӮ«ӮЖ”»’fӮөӮҪҒBӮҫӮӘҒAҢ»’nӮЕӮМҢҲ’иҢ ӮрҺқӮВ‘еҺRӮНӮұӮкӮЙ”Ы’и“IӮҫӮБӮҪҒB203ҚӮ’nӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҚU—ӘӮр’S“–Ӯ·Ӯй”T–ШӮЖҒAӮ»ӮМҺQ–d’·ӮМҲЙ’n’mӮӘ”с“пӮМ‘ОҸЫӮЖӮИӮиӮӘӮҝӮҫӮӘҒAҺАҚЫӮЙҢ»ҸкӮЕ“GӮЖ‘ОӣіӮөӮДӮўӮйҗlҠФӮЙӮНҒAӮўӮЬӮРӮЖӮВӮ»ӮМҚU—ӘӮМҲУҗ}ӮӘӮВӮ©ӮЯӮИӮўӮаӮМӮҫӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮаӮөӮӯӮН–CҸpӮМҗк–еүЖӮЕӮ ӮйҲЙ’n’mӮӘӮ»ӮӨӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЙҒA–CӮМғGғLғXғpҒ[ғgӮЕӮ Ӯй‘еҺRӮаүҪӮзӮ©ӮМҢЕ’иҠT”OӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮӘ—vҚЗҚU—ӘӮМҗі–К“Л”jӮЙӮұӮҫӮнӮиӮрҺқӮҪӮ№‘ұӮҜӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒB ӮЖӮаӮ ӮкҒA‘еҺRӮМ“пҗFӮӘ—·ҸҮҚU—ӘӮЙҲк’иӮМүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҺ–ӮНҠmӮ©ӮЕӮ ӮиҒAҢг“ъҺҷӢКҺQ–d‘Қ’·Ӯр—·ҸҮӮЙҢӯӮйҺ–(ӢyӮСӮ»ӮкӮЙ”әӮӨӮўӮӯӮВӮ©ӮМүp’f)ӮЙӮжӮБӮД‘еӮўӮЙ”ТүсӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮБӮҪҒB җнҢгӮН“Яҗ{ӮЕ”_ӢЖӮИӮЗӮөӮИӮӘӮзҗГӮ©ӮЙ•йӮзӮөӮҪӮӘҒAҢМӢҪӮМҺӯҺҷ“ҮӮЦӮНҗӢӮЙӢAӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҺ©ӮзӮӘӢӯӮӯ•зӮБӮҪҗјӢҪӮр“ў”°Ӯ№ӮҙӮйӮрӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҗј“мҗн‘ҲӮМҠҙҸқӮЙӮжӮйӮаӮМӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBүҪ“xӮ©Һс‘ҠӮЙҗ„ӮіӮкӮИӮӘӮзӮ»ӮМ“s“x’fӮи‘ұӮҜӮҪӮМӮНҒAҗјӢҪӮрӢt‘ҜӮЖӮөӮДжИӮЯӮҪ–ҫҺЎҗӯ•{ӮЙ‘ОӮ·Ӯй’пҚRӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйҒBӮ»ӮМ‘еҺRӮаӮўӮжӮўӮж—ХҸIӮӘ”—ӮБӮҪҚЫҒAўҢZӮіӮҹ(җјӢҪӮМҺ–)ЈӮЖӮӨӮнҢҫӮр•ъӮБӮДӮЁӮиҒAҚЕҢгӮЬӮЕӮ»ӮМҗёҗ_ӮМҺx’ҢӮӘҗјӢҪӮЕӮ ӮйҺ–ӮрҺьҲНӮЙ’mӮзӮөӮЯӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҺҷӢКҢ№‘ҫҳY 1852-1906 “ҝҺR”Л
“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй–һҸBҢRҺQ–d‘Қ’·ҒB –ҫқрӮИ“Ә”]ӮЖҒAҚLӮўҺӢ–мӮЕ•ЁҺ–Ӯр‘ЁӮҰӮзӮкӮйӢMҸdӮИҗlҚЮӮЖӮөӮДҒAҲі“|“I•s—ҳӮИ“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮЙ‘еӮўӮЙҚvҢЈӮ·ӮйҒB ҺҷӢКӮНҚмҗн—§ҲДӮЙӮЁӮўӮД“VҚЛ“IӮИ”\—НӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйӮӘҒA“ҜҺһӮЙҚ‘ҚЫҸоҗЁӮвҗӯҺЎ—НҠwӮрҢ©ӢЙӮЯҒAҗжӮрҢ©’КӮ№Ӯй”\—НӮЙӮа’·ӮҜӮДӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB–ҫҺЎҚаҠEӮМ‘е•ЁҒAҸa‘түhҲкӮЖӮўӮҰӮОҒAҢ»ҚЭӮЕӮаҸ‘“XӮЙ’ҳҸ‘ӮӘ•АӮФӮЩӮЗӮМҗl•ЁӮҫӮӘҒAҗн”п’І’BӮМҲЧӮЙӮұӮМҚаҠEӮМғtғBғNғTҒ[Ӯрҗа“ҫӮөӮ«ӮБӮҪӮМӮНҺҷӢКӮМҺи•ҝӮЙӮжӮйӮаӮМҒBҲк“x–ЪӮЙ–е‘O•ҘӮўӮрӮӯӮзӮБӮҪӮМӮҝҒA“с“x–ЪӮМ–K–вӮЙӮЁӮўӮДғ{ғҚғ{ғҚӮЖ—ЬӮрӮұӮЪӮөӮИӮӘӮз“ъ–{ӮМҚsӮӯ––ӮрҢкӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМҚмҗн‘S‘МӮМҗЭҢvӮНҺҷӢКӮЙӮжӮБӮД‘gӮЭ—§ӮДӮзӮкӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҲЧҒAҺQ–d‘Қ’·ӮЙӮН“–‘RҺҷӢКӮӘ“K”CӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒA•¶–ҫҠJү»Ӯа40”NӮҪӮВӮЖ‘O—бӮЙ”ӣӮзӮкӮй•ҫҠQӮӘҢ»ӮкҺnӮЯӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒw‘еҗb(“–Һ–ҺҷӢКӮН“а–ұ‘еҗb)ӮӘҢ»ҸкӮМҺQ–dӮрӮвӮйӮМӮНӮЁӮ©ӮөӮўҒxӮЖӮўӮӨҳbӮЕӮ ӮйҒBҠйӢЖӮЕҢҫӮҰӮОҒwҸг‘w•”ӮӘҢ»ҸкӮЙӮЕӮйӮМӮНӮЁӮ©ӮөӮўҒxӮЖӮўӮӨӮМӮЖ“ҜӮ¶ӮҫӮлӮӨҒBҳ_ӮМҗҘ”сӮНӮіӮДӮЁӮ«ҒAҢӢӢЗҺҷӢКӮНҺ©ӮзҚ~ҠiҗlҺ–Ӯрҗ\ӮөҸoҒA–һҸBҢRӮМҺQ–d‘Қ’·Ӯр–ұӮЯӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB“–Һ–ӮМҗўҳ_ӮЕҒuӮжӮӯӮаҸAӮ«ӮҪӮиҒA–”ӮжӮӯӮаҸAӮ©ӮөӮЯӮҪӮиҒvӮЖҸЬҺ^ӮіӮкӮҪҺҷӢКӮМүp’fҗlҺ–ӮНҒA“ъ–{ҢRӮЙӮЁӮўӮДҚЕҸүӮМғPҒ[ғXӮЕӮ ӮиҒA“ҜҺһӮЙҚЕҢгӮМғPҒ[ғXӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBғҒғ“ғcӮвғvғүғCғhӮжӮиӮаҚ‘үvӮр—DҗжӮіӮ№ӮйҺ–ӮӘӮўӮ©ӮЙ“пӮөӮўӮ©ӮМҲк—бӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB ҠJҗнӮЙҗж—§ӮҝҒAҸо•сҗнӮМҸd—vӮіӮрҲн‘ҒӮӯҸdҺӢӮөӮҪҺҷӢКӮНҒAӮұӮМҺһ‘гӮЙҠщӮЙҠC’кғPҒ[ғuғӢӮЖӮўӮӨ’…‘zӮр“ҫӮДӮЁӮиҒAҺАҚЫӮЙ“ъ–{ҠCҠC’кӮЙӮ»ӮкӮр’ЈӮиҸ„ӮзӮ№ӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA—·ҸҮҚU—ӘӮЙӮЁӮўӮДӮНҒA–C•әүИӮМҸнҺҜӮр–іҺӢӮөӮҪ–C‘д”z’uӮЙӮжӮБӮД—vҚЗҠЧ—ҺӮЙҚvҢЈӮөӮДӮўӮйҒBҗжӮМҗlҺ–ӮМ—бӮЙҢАӮзӮёҒAҺҷӢКӮЖӮўӮӨҗlӮНҗж“ьҠПӮв‘O—бҒAҢЕ’иҠП”OӮЙӮжӮйҚd’јҺvҚlӮЙҠЧӮзӮИӮў“_ӮЕ—]җlӮжӮиҲі“|“IӮЙ—DӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮйҒB Қмҗн—§ҲДҺТӮМ—§ҸкӮ©ӮзҒAҗн–рӮНҚЕ’·ӮЕӮа2”NӮЖҢ©ҢАӮБӮДӮЁӮиҒAҸнӮЙҚuҳaӮМҗЭ’uғ^ғCғ~ғ“ғO–НҚхӮр‘O’сӮЖӮөӮҪҚмҗнү^—pӮр“WҠJӮөӮДӮўӮҪ“_ӮЕҒA‘јӮМҗl•ЁӮзӮЖҢҲ’и“IӮЙҲЩӮИӮБӮДӮўӮйҒB‘S‘МӮр‘еӮ«ӮӯҳлбХӮөӮИӮӘӮзҒAҢ»ҸкӮЕз…ҳrӮрҗUӮйӮў‘ұӮҜӮйҗlҚЮӮӘҒAӮұӮМҺһ‘гӮМӮұӮМҸкҸҠӮЙӮўӮҪӮұӮЖӮН“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҚKү^ӮИҺ–ӮЕӮ ӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒBҢіҒX“ъҳIҗн‘ҲӮМҚмҗнӮН‘O”CӮМ“c‘әң}—^‘ўӮЙӮжӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪӮӘҒA“c‘әӮӘҗн‘OӮЙӢ}ҺҖӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ‘еӮ«ӮИ•sҚKӮМҲЧӮЙҒAҺҷӢКӮӘӮ»ӮкӮрҲшӮ«ҢpӮ®ҢoҲЬӮӘӮ ӮБӮҪҒBғtғ^ӮрӮ ӮҜӮДӮЭӮкӮО“VҚЛӮЖӮіӮкӮҪ“c‘әӮМҚмҗнӮЙӮНӮўӮӯӮВӮ©ӮМ•s”хӮӘҢ©ӮВӮ©ӮиҒAӮ©ӮИӮиӮМ•”•ӘӮӘҺҷӢКӮЙӮжӮБӮД‘gӮЭ’јӮіӮкӮҪҒB“c‘әӮМҺҖӮНҢR•”ҠЦҢWҺТӮӘҗВӮҙӮЯӮй”ЯҢҖӮҫӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҺҖӮӘҢӢүК“IӮЙҗнҸҹӮЙҢӢӮСӮВӮўӮҪҺ–ӮЙӮИӮйҒB ҺҷӢКӮН’ZӢCӮЕ“{–ВӮиӮвӮ·ӮўҢғҸоүЖӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBҚU—Ә“пҚqӮ·Ӯй—·ҸҮӮЙ•ӢӮўӮҪҚЫӮИӮЗӮНҒAҢғӮ·ӮйӮ ӮЬӮиҒAӮЖӮ ӮйҺQ–dӮМӢ№ӮЙӮВӮўӮҪҒu“V•Ы‘K(ғGғҠҒ[ғgӮМӮ Ӯ©Ӯө)ҒvӮрҲшӮ«ӮҝӮ¬ӮБӮҪӮЖӮўӮӨғGғsғ\Ғ[ғhӮӘӮ ӮйҒBӮӘҒA“ҜҺһӮЙҸоӮЙҢъӮӯҒA—·ҸҮӮЕӢкҗнӮөӮҪ“ҜӢҪӮМ”T–ШҠу“TӮЖӮНҸIҗ¶җeӮөӮўҠФ•ҝӮҫӮБӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲҢгҒA–ҫҺЎ“VҚcӮЦӮМҠMҗщ•сҚҗӮМҚЫҒA”T–ШҠу“TӮНҺ©ӮзӮМ”сӮрҗФ—ҮҒXӮЙ•¶ӮЙӮөӮҪӮҪӮЯӮДҸг‘tӮөӮҪӮӘҒAӮұӮМҢүӮі(җlӮЙӮжӮБӮДӮНүЯ“xӮЙ”Я‘sӮЖӮаҺуӮҜҺжӮй)ӮЖҢҖ“IӮИ”T–ШӮМҲк–КӮрҺҷӢКӮНҲӨӮөҒAӮөӮОӮөӮОҢRҠЦҢWҺТӮзӮЙҒuҢ©ӮлҒAӮұӮкӮӘ”T–ШӮҫҒvӮЖҺ©ӮзӮМҺ©–қӮМӮжӮӨӮЙҢкӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB Ғu—қ‘zӮМ“V•ӘӮЙҢbӮЬӮкӮДӮўӮйҒvӮЖӮНҒAғhғCғcӮ©ӮзҸөӮ©ӮкӮҪҢRҺtғҒғbғPғӢӮЙӮжӮйҺҷӢК•]ӮҫӮӘҒA‘ҪӮӯӮМҗlӮӘӮұӮкӮЖҺ—ӮҪӮжӮӨӮИҸШҢҫӮрҺcӮөӮДӮўӮйӮМӮрҢ©ӮйҢАӮиҒA”ЮӮМҚЛӮНӮвӮНӮиҗ¶ӮЬӮкҺқӮБӮҪӮаӮМӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBӮӘҒAҲк•ыӮЕҺҷӢКӮМ•кҗeӮН—cҸӯӮМҚ ӮМҺҷӢКӮМ“ӘӮМҲ«ӮіӮрҠлңңӮөӮҪӮзӮөӮўҒBӮ»ӮұӮЕ“ӘӮр—вӮвӮ·ҲЧӮЙҲдҢЛӮМҗ…Ӯр“ӘӮ©ӮзӮ©ӮФӮйҒuҗ…—ҒӮСҒvӮрӮ·Ӯ·ӮЯӮҪӮМӮҫӮӘҒA7ҚОӮЕҺnӮЬӮБӮҪӮұӮМҸKҠөӮНҒAҲИҢг50”NӢЯӮӯ‘ұӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲҢгӮМҺҷӢКӮНӢ}‘¬ӮЙ”eӢCӮӘҗҠӮҰҒAғ{Ғ[ӮБӮЖӮЗӮұӮ©Ӯр’ӯӮЯӮДӮўӮйӮжӮӨӮИҺ–ӮӘӮөӮОӮөӮОӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB“ъҳIҠФӮМҚuҳaҸр–с’чҢӢӮ©Ӯз2”NӮр‘ТӮВ‘OӮЙҒAҺҷӢКӮН”]ҲмҢҢӮЙӮжӮиҗГӮ©ӮЙ‘§ӮрҲшӮ«ҺжӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB‘’ӢVӮЙӮЁӮўӮДӮНҒA”T–ШҠу“TӮӘҚ~үJӮМ’ҶӮЕҠ»ӮЙӮжӮиӮ»ӮӨҺpӮӘ”FӮЯӮзӮкӮДӮўӮйҒB Ҹ®ҒA—]’kӮҫӮӘҒAҸГ“мҚ]ғm“ҮӮЙӮ ӮйҺҷӢКҗ_ҺРӮЖӮНҒAӢLҺТӮИӮЗӮМ—Ҳ–KҺТӮ©Ӯз“ҰӮкӮйҲЧҒAҠJҗн‘OӮЙҺҷӢКӮӘүB“ЩӮөӮҪ•К‘‘ӮҫӮӘҒAҢӢӢЗҸZ–ҜӮЙӮОӮкӮДӮөӮЬӮўҒAӮ»ӮМҢгҗ_ҺРӮЖӮөӮДҚХӮзӮкӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸјҗм•qҲы 1859-1928 җе‘д”Л
–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ҺQ–dҒBҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮМүщ“ҒӮЖӮаҢҫӮнӮкҒA–һҸB•Ҫ–мӮЕӮНҚмҗн—§ҲДӮМ’ҶҗSӮЖӮөӮДӮ»ӮМ”\—НӮрӮУӮсӮҫӮсӮЙ”ӯҠцӮөӮҪҒB “ъҳI—ӨҢRӮМҺ–ҺАҸгҚЕҢгӮМҸХ“ЛӮЖӮИӮБӮҪ•т“VүпҗнӮЙӮЁӮҜӮйҒw‘s‘еӮИ’Ҷүӣ“Л”jҚмҗнҒxӮНҸјҗмӮМҲДӮЖӮіӮкҒAҸјҗмӮМҢчҗСӮӘҢгҗўӮЙҢкӮзӮкӮй—vҲцӮМҲкӮВӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮӘҒA”ЮӮМ•]үҝӮЙҠЦӮөӮДӮНҺ^”Ы—јҳ_Ӯ ӮйҒB“ъҳIҗн‘Ҳ‘S‘МӮр’КӮөӮД“ъ–{ҢRӮЙӮЖӮБӮДҚЕ‘еӮМҠлӢ@ӮНӮМҚ•Қa‘дүпҗнӮҫӮӘҒAӮұӮМҺһӮМ‘е‘ЕҢӮӮНҸјҗмӮЙӮжӮйҗlҚРӮЖҢ©ӮйҺ–ӮаӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB Қ•Қa‘дүпҗнӮНғҚғVғAҢRӮЙӮжӮй‘еӢK–НӮИӢ}ҸPӮЙӮжӮБӮДҠJ–ӢӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒAӮұӮМҺһӮМ“ъ–{ҢRӮН‘SӮӯӮМ–і–h”хӮЕӮ ӮБӮҪҲЧҒA“–ҸүӮМҗнӢөӮНүу‘–ӮЙҺҹӮ®үу‘–ӮЕӮ©ӮИӮи”ЯҺSӮИӮаӮМҒB–і–h”хӮҫӮБӮҪ—қ—RӮНҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮаҠЬӮЮҺQ–d–{•”ӮӘҒAҢө“~Ҡъ(-30ҒҺҲИүә)ӮЕӮМҠпҸPӮН–іӮўӮҫӮлӮӨӮЖҸҹҺиӮЙҠmҗMӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫӮӘҒA“ъ–{җlӮМҠҙҠoӮ©ӮзҢ©ӮкӮОҒAӮЬӮ ӮұӮкӮНҺd•ыӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB –в‘иӮНҒAӮ»ӮсӮИҢө“~ӮМ’ҶӮЕҚх“GӮЙҸoӮДӮўӮҪҸHҺRҺx‘аӮ©ӮзҒAҳIҢRӢӯҸPӮрҺfӮнӮ№ӮйҸо•сӮӘүҪ“xӮаӮ Ӯ°ӮзӮкӮДӮўӮҪҺ–ӮҫҒBҸHҺRҺx‘аӮМҺwҠцҠҜҒAҸHҺRҚDҢГӮН•сҚҗӮӘҸWӮЬӮкӮОҸWӮЬӮйӮЩӮЗҳIҢRӮМӢӯҸPӮНӢ^ӮўӮжӮӨӮӘӮИӮўӮЖҠmҗMӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAӮұӮкӮзӮМҺ–ҺАӮр–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮЙӮўӮӯӮз•сҚҗӮөӮжӮӨӮЖӮаҒA•”‘аӮМҲЪ“®Ӯвҗw’nӮМҚ\’zҒA•ЁҺ‘ӮМ•вҸ[ӮИӮЗӮМ–Ҫ—ЯӮНҸoӮіӮкӮйҺ–ӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺ–ҺАҸгҸHҺRӮМ•сҚҗӮНҒw–ЩҺEҒxӮіӮкӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮұӮМӮ ӮҪӮиӮНҸјҗмӮЙӮжӮй”»’fӮЖҢҫӮнӮкӮДӮЁӮиҒA”ЮӮМ•]үҝӮӘғOғҢҒ[ӮЕӮ ӮйҸҠҲИӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМ–ЩҺEӮЙӮжӮБӮДҒA“ъ–{ҢRӮНҠ®‘SӮЙ‘ЕӮҝӮМӮЯӮіӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮйӮМӮҫӮӘҒAҺ–‘OӮЙ“пӮрҺ@’mӮөӮДӮўӮҪҸHҺRҺx‘аӮӘӢ@ҠЦ–CӮЕҺқӮҝӮұӮҪӮҰӮҪҺ–ӮЕӮЗӮӨӮЙӮ©үу–ЕӮр–ЖӮкӮҪҒBҸHҺRӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA“ҖҸқӮЕҺwӮв•@ӮӘӮҝӮ¬ӮкӮДӮөӮЬӮӨӮЩӮЗӮМӢЙҠҰӮМ’ҶӮЕҒAүҪӮМӮҪӮЯӮМҚх“GӮҫӮБӮҪӮМӮ©ӮЖӮЮӮИӮөӮўҢАӮиӮҫӮБӮҪӮНӮёӮҫҒBғҚғVғAҢRӮМ–CҢӮӮЙӮжӮБӮДҒAҸHҺRӮӘ’·”NҲзӮДӮДӮ«ӮҪӢR•әӢyӮСҒAӢMҸdӮИӢR”nӮӘ‘ҪӮӯҸБҺёӮөӮҪҒBӮұӮМҺһҸHҺRӮӘ”с–}ӮҫӮБӮҪӮМӮНҒuӮ№ӮЯӮДӢR”nӮҫӮҜӮЕӮа”р“пӮрҒvӮЖӮМҗiҢҫӮр–іүәӮЙӢpүәӮөӮДӮўӮйӮЖӮұӮлҒBҒuӢR•әӮҪӮйӮаӮМ”nӮЖӮЖӮаӮЙҺҖӮЛҒvӮЖӮМҗM”OӮЕӮ ӮиҒAҸHҺRӮӘҚЕҢгӮМ•җҺmӮЖҲШ•|ӮіӮкӮйҚ„’јӮіӮМҢ»ӮкӮЖҢҫӮҰӮйҒBҲк•аҠФҲбӮҰӮО–і‘КӮИҗнҺҖҒEҸБ–ХӮрҗ„Ҹ§ӮөӮДӮўӮйӮЖӮаҺжӮзӮкӮйӮӘҒAӮұӮМүпҗн‘OҢгӮМҸHҺRӮМ“ӯӮ«Ӯвҗ¶Ӯ«—lӮрҢ©ӮкӮОҒAҢгҗўӮЙҢ©ӮзӮкӮйӮжӮӨӮИҲАӮБӮЫӮўҗёҗ_ҳ_ӮЖӮН•КҢВӮМӮаӮМӮЖ”»’fӮЕӮ«ӮйҒB Қ•Қa‘дӮЕӮМҺёҚфӮЙӮВӮўӮДҺQ–d–{•”ӮЕӮЗӮМӮжӮӨӮИҳbӮөҚҮӮўӮӘҚsӮнӮкӮҪӮ©ӮН’иӮ©ӮЕӮНӮИӮўӮӘҒA–іҳ_ҸјҗмӮНҺ©ӮзӮрҚUӮЯӮҪӮҫӮлӮӨҒBӮ»ӮМҲк•ыӮЕҒAҸјҗмӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺQ–dҳA’ҶӮНҒAҗнӮўӮЙҠФӮЙҚҮӮнӮИӮ©ӮБӮҪ”T–ШҢRӮрҚҰӮЯӮөӮӯҺvӮБӮДӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB—·ҸҮҚU—ӘӮӘ“пҚqӮөӮДӮўӮҪҚ Ӯ©ӮзҒAҸјҗмӮН”T–ШҢRҺi—Я•”Ӯр’Й”lӮөӮДӮЁӮиҒA”T–ШҠу“TҚX“RӮМӢ}җж–NӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮЬӮҪҒAҸнӮЙҗTҸdҳ_ӮрҸҘӮҰӮй‘ж“сҢRӮМ—ҺҚҮ–LҺOҳYҺQ–d’·ӮрҠҙҸо“IӮИ—қ—RӮЕ”rҸңӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮДӮўӮйӮЖӮұӮлӮИӮЗӮрҢ©ӮДӮаҒAҸјҗмӮН—L”\ӮИҺТӮЙӮ ӮиӮӘӮҝӮИҒw‘ҠҺиӮМ—§Ҹк(ӢкӢ«)ӮӘ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҗlҠФҒxӮҫӮБӮҪӮУӮөӮӘӮ ӮйҒBҠJҗнӮжӮиҲИ‘OӮЙӮН‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘еҺRҠЮӮвҒAҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮМ‘O”CҺТҒA“c‘әң}—^‘ўӮрҚ“•]Ӯ·ӮйӮИӮЗҒA”дҠr“IҗуӮў•”•ӘӮҫӮҜӮЕҗlӮр”»’fӮ·ӮйҢXҢьӮаҢ©ӮзӮкҒAҗжӮЙҗGӮкӮҪ—ҺҚҮ–LҺOҳYӮИӮЗӮаҒuҢҲ’fӮИӮҜӮкӮО‘еҺ–Ӯрҗ¬Ӯө“ҫӮй”\ӮНӮёҒvӮЖҗШӮиҺМӮДӮзӮкӮДӮўӮйҒB Ҳк•ыӮЕ•КӮМ‘Ө–КӮрҺfӮнӮ№ӮйғGғsғ\Ғ[ғhӮаӮ ӮйҒBҚU—ӘӮӘ‘еӮўӮЙ“пҚqӮөӮҪ—·ҸҮ—vҚЗҠЧ—ҺҢгҒA‘ҚҺi—Я•”ӮЙӢAҠТӮөӮҪҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘӮ»ӮМҢгӮМҸҲ—қӮрҚsӮБӮДӮўӮҪҚЫӮЕӮ ӮйҒBҲЙ’n’mҚKүоӮрӮНӮ¶ӮЯҒA‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮМ‘ҪӮӯӮНҸҲ•ӘӮМ‘ОҸЫӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒA”T–ШӮЙ‘ОӮөӮДӮаҗlҺ–ӮрҠЬӮЯӮҪҒwҸҲ•ӘҒxӮМ—\’иӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮкӮЙҠЦӮ·ӮйҸ‘—ЮӮЙҒAҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘӮИӮсӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮИӮӯғTғCғ“ӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮМӮрҢ©ӮДҒAҸјҗмӮНӮ ӮнӮДӮДҗ§Һ~ӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМҸҲ•ӘӮӘҺАҚsӮіӮкӮкӮО”T–ШӮӘ•KӮёҗШ• Ӯ·ӮйӮЖӮМҠmҗMӮӘӮ ӮБӮҪҲЧӮзӮөӮўҒBҺҷӢКӮНӮӨӮБӮ©ӮиӮөӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒAӮ·ӮсӮИӮиӮЖ”[“ҫӮөӮДӮұӮМҸҲ•ӘӮНҢ©‘—ӮиӮЖӮИӮБӮҪҒBҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҺ–ҺАҠЦҢWӮЙҢлӮиӮӘӮ ӮйүВ”\җ«ӮаӮ ӮйӮӘҒAӢӯҚdҳ_ӮрӮФӮҝҸгӮ°ӮйҲк•ыӮЕ•qҠҙӮЙ”z—¶ӮрҺҰӮ·“с–Кҗ«ӮНҗlҠФ–ЎӮӘӮ ӮБӮДӢ»–Ўҗ[ӮўҒBҺҷӢКҢ№‘ҫҳY“Ҝ—lӮЙғJғbӮЖӮИӮиӮвӮ·ӮӯҒAӮөӮ©ӮөҲк•ыӮЕӮНғEғFғbғgӮЙӮ»ӮкӮрҲшӮ«ӮёӮйғ^ғCғvӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒEҒEҒB ҸIҗнӢAҚ‘ҢгҒAҸјҗмӮНӢcүпӮЕ—ӨҢRӮМҗн’Ҷ•сҚҗӮр’S“–ӮөӮҪӮӘҒA2ҺһҠФӮЙӮаӮнӮҪӮйӮ»ӮМ•сҚҗӮМ“а—eӮӘҺАӮЙҢ©Һ–ӮЕ—қҳHҗ®‘RӮЖӮөӮДӮўӮҪӮЖӢLҳ^ӮЙӮ ӮйҒB‘ОӮ·ӮйҠCҢRӮМ•сҚҗӮНҒAӮвӮНӮи—қҳHҗ®‘RӮЖӮөӮҪҳ_ӮМ“WҠJӮЙ’и•]ӮМӮ ӮйҸHҺRҗ^”VӮӘ’S“–ӮөӮҪӮӘҒAҸHҺRӮЖӮўӮӨ”дҠr‘ОҸЫӮӘӮ ӮиӮИӮӘӮзҺьҲНӮЙҢ©Һ–ӮЖҢҫӮнӮөӮЯӮйҸјҗмӮМ“Ә”]ӮНӮвӮНӮи“–‘гӢьҺwӮМӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒB ‘еҗіӮМҸIӮнӮиӮЙ—\”х–рӮЦӮЖ•Т“ьӮіӮкҒAҸәҳaӮЙ“ьӮБӮҪ3”N–ЪӮЙ–vӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—§Ң©Ҹ®•¶ 1845-1907 ҢK–ј”Л
‘ж”ӘҺt’cҺi—ЯҠҜҒB “ъ–{ӮӘүу–ЕҗЎ‘OӮЬӮЕ’ЗӮўҚһӮЬӮкӮҪҚ•Қa‘дүпҗнӮЙӮЁӮҜӮйҠҲ–фӮЕ’mӮзӮкӮйҒB —§Ң©Ҹ®•¶ӮН–цҗ¶җVүA—¬ӮМ–јҺиӮЕӮ ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAӮ©ӮМ—L–јӮИҸ№•ҪҚвҠw–вҸҠӮЕ•ЧҠwӮЙ–ұӮЯӮҪ•¶•җ—ј“№ӮМҚЛҗlӮҫҒB‘еҗӯ•тҠТҢгӮМ–Ӣ•{ӮМ’ҶӮЙӮ ӮБӮДҺеҗнҳ_ӮрҸҘӮҰ‘ұӮҜӮҪӢӯҚd”hӮЕҒA•и’Cҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДӮНҺF’·ӮрҺеӮЖӮ·ӮйҠҜҢRӮр“O’к“IӮЙӢкӮөӮЯӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҢRҸг‘w•”ӮМ‘ҪӮӯӮН•и’Cҗн‘ҲӮрҢoҢұӮөӮДӮўӮйӮӘҒA“–Һ–Һб”NӮЕӮ ӮБӮҪ”ЮӮзӮӘ”дҠr“I––’[ӢЯӮӯӮЕҸ]ҢRӮөӮДӮўӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒA—§Ң©ӮНҠщӮЙҺwҠцҠҜӮЖӮөӮД–Ӣ––ӮрҗнӮБӮҪҒBӮдӮҰӮЙҺF’·Ҹг‘w•”ӮЙӮН—§Ң©ӮЙӮжӮБӮДӢкӮөӮЯӮзӮкӮҪҗl•ЁӮӘ‘Ҫҗ”ҒBҺRгp—L•ьӮИӮЗӮаӮ»ӮМҲкҗlӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮ»ӮсӮИ‘ҜҢRӮМҺе—vҗl•ЁӮӘ–ҫҺЎ—ӨҢRӮЙҸөӮ«“ьӮкӮзӮкӮҪӮМӮНҚЛ”\ӮМ–L•xӮіӮдӮҰӮЕӮ ӮиҒA‘жҺlҢRӮМ–м’Г“№ҠСӮИӮЗӮН’C–ӨӮрҺwӮөӮДҒu“Ң—mҲкӮМ—p•әүЖҒvӮЖ•]ӮөӮДӮўӮйҒB “ъҳIҠJҗн“–ҺһҒA—§Ң©ӮМ‘ж”ӘҺt’cӮН—\”хҗн—НӮЖӮөӮДҚ‘“а‘ТӢ@ӮМҸу‘ФӮЙӮ ӮБӮҪҒBғNғҚғpғgғLғ“ӮМ“P‘ЮҗнҸpӮЙӮжӮБӮД“¬ӮўӮӘ’·Ҡъү»Ӯ·ӮйӮЙҸ]Ӯў“ъ–{ҢRӮН•ЁҺ‘ӮвҗlҲхҢҮ”@ӮМ•ҫҠQӮӘҢ°’ҳӮЙҒBҚҮ—¬Ӯ·ӮйӮНӮёӮҫӮБӮҪ”T–ШҠу“TӮМ‘жҺOҢRӮӘ—·ҸҮӮЕӮўӮжӮўӮждP’…Ҹу‘ФӮЙҠЧӮБӮҪ10ҢҺҒA—§Ң©ӮМҺt’cӮН–һҸBӮМҚr–мӮЙҸг—ӨӮөӮҪҒBӮұӮМҺһӮвӮв’xӮкӮДҚ№үНүпҗнӮЙҺQүБӮөҒAӮ»ӮМҢг–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”•tӮҜӮМ—\”хҢRӮЖӮөӮДҚTӮҰҒAӮ»ӮМӮЬӮЬҢө“~ӮрҢ}ӮҰӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒB ҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮвҸјҗм•qҲыӮз‘ҚҺi—Я•”ӮМ–КҒXӮӘ“~ӢGӮМҸPҢӮӮН–іӮўӮЖ“ҘӮсӮЕӮўӮҪ1ҢҺ”јӮОҒAғҚғVғAҢRӮН10–ңҗlӮр’ҙӮҰӮй•ә—НӮр“ъ–{‘ӨҚ¶—ғҒAҚ•Қa‘дӮЙӮФӮВӮҜӮДӮ«ӮҪҒB–ТҸ«ӮЕ’mӮзӮкӮйғOғҠғbғyғ“ғxғӢғNҸ«ҢRӮЙ—ҰӮўӮзӮкӮҪҺmӢCҚV—gӮҪӮй•ә—НӮЙӮжӮБӮДҒAҢ„Ӯр•tӮ©ӮкӮҪ“ъ–{‘ӨӮНҲкӢCӮЙ•цӮкӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҚЕӮа”sҗнӮӘҗ^ҺА–ЎӮр‘СӮСӮҪҸuҠФӮЕӮ ӮиҒAӮұӮұӮЕҗнҗьӮӘ•цүуӮөӮДӮўӮкӮОҢгӮМ•т“VүпҗнӮНӮЁӮлӮ©ҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮ·ӮзӮа‘¶ҚЭӮөӮИӮ©ӮБӮҪҺ–ӮЙӮИӮйҒB •цүуӮрҗHӮўҺ~ӮЯӮДӮўӮҪӮМӮНҸHҺRҚDҢГӮӘ—ҰӮўӮйӢR•ә—·’c(ҸHҺRҺx‘а)ӮЕӮ ӮиҒAӮұӮМ•”‘аӮН—BҲк“ҘӮЭӮұӮҪӮҰӮҪӮӘҲЧӮЙҒAӮдӮӨӮЙ10”{Ӯр’ҙӮҰӮй•ә—НӮЙҺжӮиҲНӮЬӮкӮйҺ–‘ФӮЙ’ЗӮўҚһӮЬӮкӮДӮўӮҪҒBҸHҺRҺx‘аӮӘӮұӮұӮЕҠё“¬ӮЕӮ«ӮҪӮМӮНҒA’гҺ@ӮЙӮжӮБӮДҸPҢӮӮрҺ–‘OӮЙҺ@’mӮөӮДӮўӮҪҺ–ҒAӮЬӮҪӢ@ҠЦ–CӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҸdүОҠнӮрҸd“_“IӮЙ”z”хӮөӮДӮўӮҪҸHҺRӮМҗжҢ©ӮМ–ҫӮЙӮжӮйҒBӮӘҒAӮаӮҝӮлӮс•цүуӮНҺһҠФӮМ–в‘иӮҫӮБӮҪҒB ҳIҢRӮМӢӯҸPӮӘҺеҗн—НӮр—pӮўӮҪ‘еӢK–НӮИӮаӮМӮЕӮ ӮйӮЖӮжӮӨӮвӮӯҺ@’mӮөӮҪ–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮНҒA’xӮЬӮ«ӮИӮӘӮзӮа‘қүҮ•”‘аӮр”hҢӯӮөӮҪҒB—VҢRӮЖӮөӮДҚTӮҰӮДӮўӮҪ—§Ң©Һt’cӮҫҒBӮұӮМҺһ—§Ң©ӮНҠщӮЙ61ҚОҒB—\”хҢRӮЖӮөӮДҢг•ыӮЙ’uӮ©ӮкӮҪӮМӮН”\—НӮвҗ¶Ӯў—§ӮҝӮ©ӮзӮЕӮНӮИӮӯҒAӮҪӮҫӮ»ӮМ”N—оӮЙӮжӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪҒBүҮҢRӮЖӮөӮДҚ•Қa‘д”h•әӮМ–Ҫ—ЯӮӘҸoӮіӮкӮҪҺһҒAҠщӮЙҗнӢөӮНҲкҚҸӮМ—P—\ӮӘ–ҪҺжӮиӮЖӮўӮӨҸуӢөӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒB—§Ң©ӮН–с2–ңҗlӮМ•ә—НӮр—ҰӮўӮДҢө“~ӮМ–һҸB•Ҫ–мӮЙҸoҗӘҒBҲкҺһӮр‘ҲӮӨҺ–‘ФӮЙ—§Ң©ӮНӢx‘§ӮМ‘I‘рӮр”rҸңҒA–йҠФӮЙӮЁӮўӮДӮаҗQӮёӮМӢӯҚsҢRӮрҠёҚsӮөӮҪҒBӮұӮМҺһӮМӢCү·ӮНҒ|30ҒҺӢЯӮӯӮЬӮЕ—вӮҰҚһӮсӮҫӮЖҢҫӮнӮкҒAҸ«•әӮзӮӘҺқҺQӮөӮҪҲ¬Ӯи”СӮӘҠвҗОӮМӮжӮӨӮЙ“ҖӮБӮДӮЖӮДӮаҗHӮЧӮзӮкӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМҒAӮЬӮё–{ҸBӮЕӮНӮ ӮиӮҰӮИӮўӢCҢуӮЙӮЁӮўӮДҒA‘ж”ӘҺt’cӮН•цӮкӮйҺ––іӮӯҲЕ–йӮМҠO’nӮрҸc’fҒA–йӮӘ–ҫӮҜӮҪҢгӮЙӢБӮӯӮЧӮ«‘ҒӮіӮЕҢ»ҸкӮЬӮЕӮҪӮЗӮи’…ӮўӮДӮўӮйҒB”ЮӮзӮНҗВҗXҢ§ӮМҚO‘OӮЕҸўҸWӮіӮкӮҪ•”‘аӮЕӮ ӮиҒA“ъ–{’ҶӮЕҚЕӮа‘ПҠҰҗ«ӮЙ—DӮкӮҪ•”‘аӮҫӮБӮҪҒB ‘ж”ӘҺt’cӮӘҚ•Қa‘дӮЙӮҪӮЗӮи’…ӮўӮҪҺһҒAҠщӮЙҚ•Қa‘дӮНғҚғVғAҢRӮМҺиӮЙ—ҺӮҝҒA“ъ–{‘ӨӮНүу‘–’ј‘OӮМӢкӢ«ӮЙӮ ӮБӮҪҒB—§Ң©ӮзӮМ“һ’…ӮЙӮжӮиҒAҗнҗьӮНӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮДҲЫҺқӮіӮкӮйӮаҒAҗн—Н”дӮНҲЛ‘RӮЖӮөӮД‘еӮ«ӮИҠJӮ«ӮӘӮ ӮиҒAӮіӮзӮИӮйүҮҢRӮМ“һ—ҲӮЬӮЕҺқӮҝӮұӮҪӮҰӮйӮМӮӘ—§Ң©Һt’cӮМҺАҺҝӮМ”C–ұӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҺһӮМүпҗнӮН‘Ҡ“–ӮЙүХ—уӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкҒA–с2–ңӮМ—§Ң©Һt’cӮМ”јҗ”ҲИҸгӮрҺёӮӨӮЩӮЗӮМ‘ЕҢӮӮрӮұӮӨӮЮӮБӮҪҒBӮұӮМҺһҒA•цӮкӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪҺt’cӮЙ‘ОӮө—§Ң©ӮӘ“{““ӮМүүҗаӮрӮФӮБӮДҗнҲУӮрҢЫ•‘ӮіӮ№ӮҪӮМӮН—L–јӮИ‘}ҳbӮЕӮ ӮйҒB —§Ң©Һt’cҒAҸHҺRҺx‘аӮӘҳIҢRӮрҗHӮўҺ~ӮЯӮДӮўӮйҠФӮЙ“ъ–{‘ӨӮН‘жҲкҢRҒA‘ж“сҢRӮжӮи•ә—НӮр—фӮўӮДҚ•Қa‘д•ы–КӮр‘қҲхҒAӮ»ӮӨӮұӮӨӮөӮДӮўӮйҠФӮЙҳIҢRӮМғNғҚғpғgғLғ“ӮӘҗнӢөӮр“ЗӮЭҲбӮҰ“P‘ЮӮМ•ыҗjӮр‘ЕӮҝҸoӮөӮҪҒBӮұӮМҺһғҚғVғAҢR•”“аӮЕҺwҠцҢn“қӮЙҚ¬—җӮӘӮ ӮБӮҪӮзӮөӮӯҒAҚмҗнӮрҺwҠцӮөӮДӮўӮҪғOғҠғbғyғ“ғxғӢғNӮНӮұӮкӮр•s•һӮЖӮөӮДҸҹҺиӮЙ–{Қ‘ӮЙӢAӮБӮДӮөӮЬӮӨ‘МӮҪӮзӮӯӮҫӮБӮҪҒB “ъ–{ҢRӮЙӮЁӮўӮДӮНҺwҠцҠҜӮӘ•әҺmӮзӮрҺq’нӮМӮжӮӨӮЙүВҲӨӮӘӮиҒAҚ‘үЖ–hүqӮМҲУҺvӮЖҗнҲУӮӘ––’[ӮМ•ә‘ІӮЙӮЬӮЕҚsӮ«“НӮўӮДӮўӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒAғҚғVғA‘ӨӮМ•а•әӮзӮНҒAҺt’c’·ӮМ–ј‘OӮ·Ӯз’mӮзӮёҒAүҪӮМҲЧӮЙ“¬ӮБӮДӮўӮйӮМӮ©Ӯа•ӘӮ©ӮзӮёҒA–{Қ‘ӮЕ”_ҚмӢЖӮрӮөӮДӮўӮҪӮзӮўӮ«ӮИӮиҗн‘ҲӮЙҲшӮБ’ЈӮзӮкӮДӮ«ӮҪҒAӮЖӮўӮӨ—L—lӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBӮөӮ©Ӯа“–Ҹү–с‘©ӮіӮкӮҪ’АӢаӮНӮЩӮЖӮсӮЗҺx•ҘӮнӮкӮёҒAҗH—ҝӮа”ј•Ә’ц“xӮөӮ©ҺxӢӢӮіӮкӮИӮўҒB•Ә”z‘OӮЙҺmҠҜӮзӮӘғlғRғoғoӮөӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮҪӮМӮҫҒBҳV•әӮМ—§Ң©ӮӘ•и’Cҗн‘ҲӮМҚ ӮЖ•ПӮнӮзӮКӢCҠTӮЕ•әҺmӮзӮрҢЫ•‘Ӯө‘ұӮҜӮҪӮМӮЙ‘ОӮөҒAғҚғVғA‘ӨӮНӮ ӮЬӮиӮЙӮЁ‘e––ӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮӨӮөӮ©ӮИӮўҒBҳIҢRӮНҸҹӮДӮйҗнӮЙ•үӮҜ‘ұӮҜӮҪҢӢүКҒAҗ””NҢгӮМ’йҗӯ•цүуӮЙҺҠӮБӮҪҒB—§Ң©ӮМӮжӮӨӮИҗlҚЮӮМҗв‘Оҗ”ӮӘҲі“|“IӮЙ•s‘«ӮөӮДӮўӮҪӮМӮНҢҫӮӨӮЬӮЕӮаӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҲкҢR | |
|
ҒЎҚ•–ШҲЧъй 1844Ғ|1923 ҺF–Җ”Л үәүБҺЎү®’¬
‘жҲкҢRҺi—ЯҠҜҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮй—ӨҗнӮМ‘жҲкҗнӮрҸьӮБӮҪ–ТҸ«ӮҪӮйҗl•ЁӮЕӮ ӮйҒB ҺmҠҜҠwҚZӮЕҗіӢKӮМҢRҗlӢіҲзӮрҢoӮДӮ«ӮҪғGғҠҒ[ғgӮӘҠщӮЙҺе—¬ӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҠJҗн“–ҺһҒA”сҗіӢKҠX“№Ӯр•аӮЭ‘ұӮҜӮДӮ«ӮҪҒw’@Ӯ«ҸгӮ°ҒxӮМҒwҺҳҸгӮӘӮиҒxӮӘҲЩ—бӮМ”І“FӮрҺуӮҜӮҪҒBӮұӮМ—қ—RӮЖӮөӮДҒA‘жҲкҗнӮЖӮИӮй‘жҲкҢRӮЙӮН‘Ҡ“–ӮИҸdҲіӮӘӮ©Ӯ©ӮйҲЧҒAӮЮӮөӮлҢ»ҸкӮЕҸC—…ҸкӮрҗцӮи”ІӮҜӮДӮ«ӮҪ–ТҺТӮӘ“K”CӮЖ”»’fӮіӮкӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB Қ•–ШҢRӮМ”C–ұӮНҠӣ—ОҚ]Ӯр“nүНӮөҒA–һҸBӮМғҚғVғAҢRӮр’@ӮӯҚЕҸүӮМҲкҢӮӮрүБӮҰӮйҺ–ӮҫӮБӮҪӮӘҒAӮұӮМ”C–ұӮНҒAҸүҗнӮЕҲіҸҹӮөӮДҒwҠOҚВ•еҸWӮр—L—ҳӮЙҗiӮЯӮйҒxӮЖӮӨҗӯҺЎ“IӮИҲУ–ЎҚҮӮўӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЕӮМҗ¬”ЫӮӘҗн‘Ҳ‘S‘МӮрҚ¶үEӮ·ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮаүЯҢҫӮЕӮНӮИӮӯҒAҗ¶”јүВӮИҸҹӮҝ•ыӮЕӮНӢ–ӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЖ•\Ң»ӮөӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB Ӯ»ӮсӮИ”wҢiӮрҺқӮБӮДӮМҸҸҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAҚ•–ШҢRӮНҠъ‘ТӮЗӮЁӮиӮМҺdҺ–ӮрӮөӮДӮЭӮ№ӮҪҒB“G‘OӮЕӮМ–і–h”хӮИ“nүНӮЕӮН‘Ҫҗ”ӮМӢ]җөӮӘ—\‘zӮіӮкӮҪӮӘҒAҚL”НҲНӮрҺз”хӮ·ӮйҳIҢRӮЙ‘ОӮөҒAҲк“_ӮЙҗн—НҸW’ҶӮӘүВ”\ӮИҚ•–ШҢRӮН–hҢдӮМҗЖҺгӮИ’n“_ӮрҗіҠmӮЙҢ©”ІӮӯҒBҳIҢRӮМ3”{ӮМ•ә—НӮрҲкӢCӮЙ“Ҡ“ьӮ·ӮйҺ–ӮЕҲі“|ӮөҒAҗбүрӮҜӮЕ‘қҗ…ӮөӮҪҠӣ—ОҚ]ӮМ“nүНӮЙҺҠӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҺһӮМҒwүЛӢҙӢZҸpҒxӮНҒAҺгҚ‘“ъ–{ӮӘ–ҫҺЎӮМҠJүФӮЖӮЖӮаӮЙ’n“№ӮЙҠwӮсӮЕӮ«ӮҪӢZҸpӮМҲкӮВӮЕӮ ӮиҒA’·”NӮМ“w—НӮӘ–ЪӮЙҢ©ӮҰӮйҢ`ӮЕ•сӮнӮкӮҪ•ӘӮ©ӮиӮвӮ·ӮўғPҒ[ғXӮЖҢҫӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB “nүНҢгӮаҒA4–ңӮрүzӮҰӮйҢR‘аӮЕ–йҸPӮрҚsӮБӮДҳIҢRӮр“O’к“IӮЙ’ЙӮЯӮВӮҜӮйӮ ӮҪӮиҒA’@Ӯ«ҸгӮ°ӮМҺАҗнҢoҢұҺТӮЖӮөӮДӮ»ӮМ”\—НӮ𑶕ӘӮЙ”ӯҠцӮөӮДӮўӮйҒBҳIҢR(ӮЖҢҫӮӨӮ©ҸнҺҜ)Ӯ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA‘еҢRӮрҲИӮБӮДӮМ–йҸPӮИӮЗҗіӢKӮМү^—p–@ӮЕӮНӮ ӮиӮҰӮИӮў–\Ӣ“ӮҫӮБӮҪӮнӮҜӮЕҒAғҚғVғAӮӘ—ӨҢRӮМҗжҗiҚ‘ӮЕӮ ӮБӮҪҺ–ӮӘҒAӮұӮұӮЕӮНӢwӮЖӮИӮБӮҪӮЖӮаҚlӮҰӮзӮкӮйҒBҠӣ—ОҚ]ӮЕҗнӮБӮҪҳIҢRӮЙӮНҒAҚ•–ШӮЙ‘ОӮөӮД‘Ҡ“–ӮИӢ°•|җSӮӘҗAӮҰӮВӮҜӮзӮкҒAҢгҒXӮЬӮЕүeӢҝӮрӢyӮЪӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮкӮИӮЗӮаүҪӮрӮөӮЕӮ©Ӯ·Ӯ©•ӘӮ©ӮзӮИӮўҚ•–ШӮМ’к’mӮкӮИӮіӮЦӮМӢ°ӮкӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮжӮӨҒB Қ•–ШҢRӮМҸҸҗнҸҹ—ҳӮЙӮжӮБӮДҒwҠOҚВӮЙӮжӮйҺ‘Ӣа’І’BҒxӮН”gӮЙҸжӮиҒAҚ•–ШӮНҗн–р‘S‘МӮЙ‘ОӮөӮД”сҸнӮЙ‘еӮ«ӮИҢӢүКӮрҺcӮөӮҪҺ–ӮЙӮИӮйҒBҲИҢгӮа—Г—zүпҗнӮЕӮМ‘ҫҺqүН“nүНӮЙӮжӮйҢ^”jӮиӮИҠпҸPӮрҗ¬ҢчӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒAҚ‘үЖ–hүqӮЙ‘еӮўӮЙҚvҢЈӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAҚЕҢгӮЬӮЕҺҳӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮ©ҒAҗнҢгӮаҸoҗў—~ӮЙӮН–RӮөӮӯҒAҢіҗғӮЙҸ–Ӯ№ӮзӮкӮйҺ–ӮаӮИӮӯ—\”х–рӮЦӮЖ•Т“ьӮіӮкҒAҗГӮ©ӮЙҢRҗlӮЖӮөӮДӮМ–ӢӮр•ВӮ¶ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘ж“сҢR | |
|
ҒЎүң•ЫиЭ 1847-1930 –L‘OҸ¬‘q”Л
‘ж“сҢRҺi—ЯҠҜҒB ‘SҳWӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘ’®ҠoӮЙҸбҠQӮӘӮ ӮиҒAҺQ–dӮЖӮМӮвӮиҺжӮиӮа‘е”јӮӘ•M’kӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB•и’Cҗн‘ҲӮЕӮН–Ӣ•{‘ӨӮЙӮВӮўӮҪҒAӮўӮнӮдӮй‘ҜҢRӮМҸ¬‘q”ЛҺmӮҫӮБӮҪӮӘҒA“ъҳIҠJҗнӮЙӮ ӮҪӮБӮДӮНӮ»ӮМ”\—НӮМҚӮӮіӮдӮҰӮЙҒuүңӮҫӮҜӮНҠOӮ№ӮИӮўҒvӮЖҒA‘ж“сҢRӮМҺi—ЯҠҜӮЙ”І“FӮіӮкӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮМ—ӨҢRҺi—ЯҠҜӮМ’ҶӮЕҒuҚмҗнҺQ–dӮМ•вҚІӮӘӮИӮӯӮДӮаҚмҗнҢvүжӮр—§ҲДҸo—ҲӮйӮМӮНүңӮҫӮҜҒvӮЖ•]ӮіӮкӮҪӮМӮНӮ ӮЬӮиӮЙӮа—L–јӮИҳbҒB •и’Cҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAҸe’eӮЕ–jӮрҠСӮ©ӮкӮҪӮЬӮЬҺwҠцӮрҺ·ӮБӮД“G’ҶӮр“Л”jӮ·ӮйӮИӮЗӮМ—E–ТӮіӮ𑶕ӘӮЙ”ӯҠцӮөӮҪӮӘҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҚ ӮЙӮЁӮўӮДӮН•ЁҗГӮ©ӮЕҒAҢҲӮөӮД•”үәӮЙ‘ОӮөӮДҲРӮрҺҰӮ·ӮжӮӨӮИҺ–ӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBҠо–{“IӮЙӮНҺQ–dӮМҲУҢ©Ӯр‘ёҸdӮөҒAҚмҗнүпӢcӮЙӮЁӮўӮДӮа–ЩӮБӮД’БҚАӮ·ӮйҺpҗЁӮЕҲкҠСҒB–Ӣ—»ӮзӮМҸoӮөӮҪҢӢҳ_ӮЙ‘ОӮөӮДӢ–үВӮрҸoӮ·ӮЖӮўӮӨ—¬ӮкӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB ӮұӮМӮ ӮҪӮиӮНҒAҲЛ‘RҢҢӢCҗ·ӮсӮИ–ТҸ«ҒAҚ•–ШҲЧъйӮЖӮН‘ОҸЖ“IӮЖҢҫӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮЖӮНҢҫӮҰҒAӮ ӮйҺһҒAүңҢRӮМҺw—Я•”ӮӘ–йҸPӮЙүпӮБӮҪҚЫӮЙӮНҒAҸe’eӮЙҠөӮкӮДӮўӮИӮўҺQ–dӮзӮӘӮӨӮлӮҪӮҰӮй’ҶҒAҲкҗl“°ҒXӮЖҚ\ӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨғGғsғ\Ғ[ғhӮаӮ ӮиҒAҺбӮўҚ ӮЙ”|ӮнӮкӮҪ’_—НӮӘ”NҳVӮўӮДҸ®ҒAӮ»ӮМҗёҗ_ӮрҚӘ–{Ӯ©ӮзҺxӮҰӮДӮўӮҪҺ–ӮрӮӨӮ©ӮӘӮнӮ№ӮйҒB Ӯ»ӮсӮИүңӮӘ—ҰӮўӮй‘ж“сҢRӮӘҚЕҸүӮЙӮФӮҝ“–ӮҪӮБӮҪ“пҠЦӮӘҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМ•tӮҜҚӘ•tӢЯӮЙӮ ӮйӢаҸBҒE“мҺRӮЕӮМҚU—ӘҗнӮҫҒBӮұӮМ“мҺRӮНғҚғVғAҢRӮЙӮжӮБӮДҒwҸ¬ӢK–НӮИ—vҚЗҒxӮЖӮөӮДҢЕӮЯӮзӮкӮДӮЁӮиҒA‘еҸ¬ӮМ–C–еӮН131–еҒAҺз”х•ә—НӮН2–ң8000–јӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮұӮұӮЕ“ъ–{ҢRӮНҸүӮЯӮДӢЯ‘гҗнӮМҗф—зӮрҺуӮҜӮйӮұӮЖӮЖӮИӮиҒA131–еӮМӢ@ҠЦ–CӮЙӮжӮйҲкҗД‘|ҺЛӮЕӮұӮЖӮІӮЖӮӯӮИӮ¬“|ӮіӮкӮҪҒB5ҢҺ26“ъ‘Ғ’©ӮЙҠJҺnӮіӮкӮҪҚмҗнӮЕӮНҒAҢЯ‘O’ҶӮҫӮҜӮЕ3000җlӮр’ҙӮҰӮйҺҖҸқҺТӮӘҸoӮҪӮӘҒAӮұӮкӮНҸ]—ҲӮМҗн‘ҲҠПӮЕӮНӮ ӮиӮҰӮИӮўҗ”ҺҡӮҫӮБӮҪҒB‘е–{үcӮӘ“–ҸүҒuғ[ғҚӮӘҲкӮВ‘ҪӮўӮМӮЕӮНҒHҒvӮЖҒA‘Е“dғ~ғXӮрӢ^ӮБӮҪӮЩӮЗӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB ‘O‘г–ў•·ӮМҺSҸуӮЙӮЁӮўӮДҒAӮұӮМҺһүЗ–ЩӮИҳVҸ«ӮӘҲк‘МүҪӮрҺvӮБӮҪӮ©ӮНҢкӮзӮкӮДӮўӮИӮўҒBӢ°ӮзӮӯ•Ғ’iӮЗӮЁӮиҒAҢҫ—tӮр”ӯӮ№ӮёӮ»ӮМҸкӮЙҚ\ӮҰӮДӮўӮҪӮаӮМӮЖҺvӮнӮкӮйҒB‘ж“сҢRҺi—Я•”ӮНӮӨӮлӮҪӮҰӮёӮЙҚUҢӮӮр‘ұӮҜҒAҢЯҢг5ҺһӮЙ“ЛҢӮӮрҠёҚsҒAҢЯҢг8ҺһӮЙҗhӮӨӮ¶ӮД“мҺRӮМҚU—ӘӮЙҗ¬ҢчҒAғҚғVғAҢRӮН—·ҸҮӮЦ“P‘ЮӮ·ӮйӮЙҺҠӮйҒBӮ»ӮМ—·ҸҮҚU—ӘӮН‘жҺOҢRӮМ”T–ШҠу“TӮЙҲшӮ«ҢpӮӘӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮйӮМӮҫӮӘҒAӮаӮөүјӮЙӮұӮМҺһ“_ӮЕ‘е–{үcӮӘ—vҚЗҗнӮЙӮЁӮҜӮй”FҺҜӮрҚӘ–{“IӮЙүьӮЯӮДӮўӮкӮОҒAҢгӮЙ‘ұӮӯ”T–ШҢRӮМ—·ҸҮҚU—ӘҗнӮНҒAӮЬӮҪҲбӮБӮҪ“WҠJӮрҢ©Ӯ№ӮДӮўӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖӮаҺvӮнӮкӮйҒB “мҺRҢгӮНҒA—Г—zүпҗнӮЙӮЁӮҜӮйҺсҺRҡЖӮМ‘Ҳ’DҗнӮИӮЗҢғҗнӮрҢJӮи•ФӮөҒA•т“VӮЕғҚғVғAҢRӮр‘ЕӮҝ•ҘӮӨӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮіӮ·ӮӘӮЙӢ]җөҺТӮМ‘ҪӮіӮН–ЪӮр•ўӮӨӮОӮ©ӮиӮМӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪҒBҗнҢгҒAүңӮНҒuӮ ӮкӮЩӮЗӮМ‘еӮ«ӮИӮўӮӯӮіӮНҺ©•ӘӮаҸүӮЯӮДӮЕӮ ӮБӮҪҒvӮЖҢкӮБӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮұӮЙӮН‘еӮ«Ӯ·Ӯ¬ӮҪӢ]җөӮЙ‘ОӮөӮДӮМҠҙҸқӮаҠЬӮЬӮкӮДӮўӮҪӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒH“ъ–{’ҶӮӘ•ӮӮ©ӮкӮҪҠMҗщғpғҢҒ[ғhӮЙӮЁӮўӮДӮНҺУҚЯӮМҢҫ—tӮрӮВӮФӮвӮўӮҪҲнҳbӮӘҺcӮБӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮМӮ ӮҪӮиӮН”T–ШҠу“TӮЙҸdӮИӮйӢCҺҝӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB ‘OҺһ‘гӮ©ӮзӮМҗ¶Ӯ«ҺcӮиӮЕӮ Ӯй‘јӮМҺi—ЯҠҜӮз“Ҝ—lҒAҗӯҺЎӮЙӮНҠЦ—^ӮөӮИӮўҺpҗЁӮрҠСӮ«ҒA“БӮЙҸoҗўӮа–]ӮЬӮёҒAҗГӮ©ӮИ—]җ¶Ӯр‘—ӮБӮҪҒBҺF’·”ҙҲУҠOӮЕӮНҸүӮМҢіҗғӮЙҸ–Ӯ№ӮзӮкӮИӮӘӮзӮаҒAҺ©ӮзӮМ•җ—EӮрҲкҗШҢЦҺҰӮөӮИӮўҢӘӢ•ӮіӮН•җҺm“№ӮМҚЕҢгӮМ–јҺcӮЕӮ ӮиҒA”ЮӮзӮМҺһ‘гӮрҲИӮБӮДӢҢ“ъ–{ӮНҠ®‘SӮИҸIӮнӮиӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҺOҢR | |
|
ҒЎ”T–ШҠу“T 1849-1912 ’·ҸB”Ӣ”ЛҸoҗg
—·ҸҮ—vҚЗӮрҚU—ӘӮ·ӮЧӮӯ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪ—ӨҢR‘жҺOҢRӮМҺi—ЯҠҜҒB–м’ГӮвүңӮз‘јӮМҺi—ЯҠҜӮзӮЙ”дӮЧҒAӢPӮ©ӮөӮўҢo—рӮӘ–іӮўӮЙӮаҠЦӮнӮзӮё”І“FӮіӮкӮҪӮМӮНҒA’·ҸB”ҙӮМ’·ҳVҒAҺRҢң—L•ьӮЙӮжӮй”h”ҙҗlҺ–ӮЙӮжӮйӮаӮМӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒBҢӢүКӮЖӮөӮД—·ҸҮ—vҚЗӮМҚU–hӮЕӮН”T–ШӮМ–і”\ӮіӮОӮ©ӮиӮӘ–Ъ—§ӮҝҒA5–ңӮрүzӮ·ҺҖҸқҺТӮӘҲк‘СӮр–„ӮЯҗsӮӯӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮӘҒAӮұӮМҳ_ӮНӮўӮнӮдӮйҢӢүКҳ_ӮЕӮ ӮиҒAӮўӮіӮіӮ©—җ–\ӮЕӮаӮ ӮйҒB ӮұӮұӮЕӮНӮ ӮҰӮД”T–Ш—iҢмӮрҺеҺІӮЖӮөӮДҳ_Ӯр‘gӮЭ—§ӮДӮДӮЭӮҪӮўҒB ҒЎҗlҺ–ӮМ–в‘и1 Ң»ҚЭҒA”T–ШӮНҗнүәҺиӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҳ_ӮӘҺе—¬ӮЖӮИӮБӮДӮўӮйӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮйҒBӮұӮкӮЙӮВӮўӮДӮНҗк–еүЖӮЖ•]ҳ_үЖӮМҠФӮЕҲУҢ©ӮӘӮФӮВӮ©ӮБӮДӮЁӮиҒA—eҲХӮЙӮН’f’иӮЕӮ«ӮИӮўӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒAӮЗӮҝӮзӮЙӮөӮлҒA–в‘иӮМ–{ҺҝӮНӮ»ӮМ”T–ШӮрҺi—ЯҠҜӮЙ”C–ҪӮөӮҪ‘е–{үcӮМӮ Ӯи•ы(ҢҫӮўҠ·ӮҰӮкӮОҺF’·”ҙҗlҺ–ӮӘүЎҚsӮөӮҪҺһ‘г”wҢi)ӮЙӮ ӮиҒA‘Ҫ‘еӮИӢ]җөӮрҸoӮөӮҪҗУ”CӮМҸҠҚЭӮНҒAҚӘ–{“IӮЙӮН’·ҸB”ҙӮМ’·ӮҪӮйҺRгpӮЙӢAӮ·ӮйӮЖҢҫӮҰӮйҒBҒw”T–Ш–і”\ҳ_ҒxӮр’и’…ӮіӮ№ӮҪҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮИӮЗӮНҒAҺRгpӮЙ‘ОӮөӮДӮаҺиҢөӮөӮў•]үҝӮр—^ӮҰӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAҲк”Кҳ_ӮЕӮНӮвӮНӮиҒw”T–Ш–і”\ҳ_ҒxӮҫӮҜӮӘҲкҗl•аӮ«ӮөӮДӮўӮйҠҙӮӘӮ ӮйҒB ҒЎҗlҺ–ӮМ–в‘и2 ӢЯ‘гҗнӮЙӮЁӮҜӮйҺQ–dӮЖӮНҒAҺАҚЫӮМҚмҗн—§ҲДҺТӮЕӮ ӮиҒAҗн‘ҲӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮНҺi—ЯҠҜӮЕӮНӮИӮӯҺQ–dӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮБӮДӮаүЯҢҫӮЕӮНӮИӮўҒBӮ»ӮкӮрҚЕӮа‘МҢ»ӮөӮДӮўӮйӮМӮӘ‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘еҺRҠЮӮЕӮ ӮиҒAҢ»ӮЙ—ӨҢRӮМҚмҗнӮН‘е”јӮӘҺQ–d‘Қ’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЙӮжӮйҗ}ҲДӮМҸгӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДӮНҠeҢRҺi—ЯҠҜӮМүәӮЙӮН—L”\ӮИҺQ–d’·ӮӘ’uӮ©ӮкӮй”ЦҗОӮИҗlҺ–ӮӘҚsӮнӮкӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒcҒB ”T–ШӮМ‘жҺOҢRӮЙӮЁӮўӮДӮНҒAҒwҢӢүК“IӮЙҒxӮ»ӮӨӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB—vҚЗӮрҚUӮЯӮй”T–ШҢRӮМҺQ–d’·ӮЙӮНҒA–C•әүИӮМ‘жҲкҗlҺТӮЖӮөӮД—ҜҠw‘gӮМҲЙ’n’mҚKүоӮӘҚМ—pӮіӮкӮҪӮӘҒAҲкӮВӮМҚмҗнӮЙӮұӮҫӮнӮи‘ұӮҜӮҪҠж–АӮіӮвҒA‘OҗьӮ©ӮзӮНӮйӮ©Ңг•ыӮЙҺi—Я•”Ӯр’uӮӯӮЖӮўӮӨ’v–Ҫ“IӮИ‘I‘рғ~ғXӮНҒAӮұӮМҺQ–d’·ӮМ”сӮӘ–вӮнӮкӮйӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨҒB ”T–ШӮМҗн‘ҲүәҺиӮрҺw“EӮ·ӮйҗәӮНӮ ӮБӮДӮаҒAҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮДӮМ”T–ШӮМҗlҠiӮр”Ы’иӮ·ӮйҺТӮНӮЁӮзӮёҒAӮаӮөӮаҺQ–d’·ӮӘ•КӮМҗl•ЁӮЕӮ ӮкӮОҒAҢ»‘гӮЙӮЁӮҜӮй”T–ШҠу“TӮМ•]үҝӮНӮаӮӨҸӯӮөүёӮвӮ©ӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўҒB —·ҸҮҚU—ӘӮӘ“пҚq’ҶҒA”T–ШҢR(“БӮЙҲЙ’n’mҺQ–d)ӮМҠж–АӮіӮЖҚмҗнӮМӮЬӮёӮіӮН‘е–{үcӮЕӮаҺw“EӮіӮкӮДӮўӮҪӮӘҒA’NӮаӮӘҢр‘гҗlҺ–ӮЙӮНҢыӮр•ВӮ¶ӮҪҒBӮұӮкӮНҲЙ’n’mӮӘ‘еҺR‘ҚҺi—ЯӮМҗeҗКӢШӮЙӮ ӮҪӮйҲЧӮЕӮ ӮиҒAӮұӮкӮр•ъ’uӮөӮҪҺ–ӮӘ‘е—КӮМҗнҺҖҺТӮЙӮВӮИӮӘӮБӮҪ‘Ө–КӮӘӮ ӮйӮМӮҫӮ©ӮзҒAҢц•ҪӮЙҚlӮҰӮДӮаҗУ”CӮр”T–ШҲкҗlӮЙӢAӮ·ӮйӮМӮН‘Г“–ӮЕӮНӮИӮўҒB ҒЎ”FҺҜӮМҢлӮи1 ”T–ШҢR•Тҗ¬ӮМ“–ҸүҒA—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘӮМҸd—vҗ«ӮНӮ»ӮұӮЬӮЕҚӮӮўӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮӘҒAғNғҚғpғgғLғ“ӮМ“P‘ЮҗнҸpӮЙӮжӮБӮДҗн‘ҲӮӘ’·ҲшӮӯӮЙӮВӮкҒAғҚғVғA–{Қ‘ӮМғoғӢғeғBғbғNҠН‘а”hҢӯӮӘҢ»ҺА–ЎӮр‘СӮСҺnӮЯҒAҺ–‘OӮЙ—·ҸҮӮМҠН‘аӮрҲкҗЗҺcӮзӮё’ҫӮЯӮй•K—vҗ«ӮӘӢiӢЩӮМүЫ‘иӮЖӮөӮД•ӮҸгӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA•УӢ«җнӮМҲкӮВӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪ—·ҸҮҚU—ӘӮӘҒAӮўӮВӮМҠФӮЙӮ©җн‘Ҳ‘S‘МӮМҚsӮӯ––ӮрҚ¶үEӮ·ӮйғLҒ[ғ|ғCғ“ғgӮЦӮЖү»ӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮаӮ»ӮаӮМ‘O’сҸрҢҸӮӘ•ПӮнӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҲЧӮЙҒAҢRӮМ•Тҗ¬Ӯ©Ӯз•вӢӢӮМӮ Ӯи•ыҒA’e–тӮМҠ„ӮиҗUӮиӮИӮЗӮрҢ©’јӮ·•K—vӮӘӮ ӮйӮМӮҫӮӘҒA‘е–{үcӮНҒAӮҪӮБӮҪ1“ъӮЕ—·ҸҮӮрҠЧӮЖӮөӮҪҒw“ъҗҙҗн‘ҲӮМ‘O—бҒxӮЙӮЖӮзӮнӮкҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҗн—НӮрҢyҺӢӮөӮө‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒBӮұӮМҗн—Ә“I”»’fғ~ғXӮНҺҖҸқҺТӮМ—КҺYӮЖӮўӮӨҢӢүКӮЙӮжӮБӮД•сӮнӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮйӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҗУ”CӮрҒu”T–ШӮМ–і”\ҒvӮЕ•Р•tӮҜӮДӮөӮЬӮӨӮМӮНҚ“ӮЖҢҫӮӨ‘јӮН–іӮўҒB ‘жҺOҢRӮМҢR”хӮМ’ҶӮЙӮНҒA–Ӣ––ӮЙҺgӮнӮкӮҪҗВ“әӮМ–CӮа‘Ҫҗ”ҠЬӮЬӮкӮДӮўӮҪҺ–ӮИӮЗӮНҒA”FҺҜӮМҠГӮіӮрҳI’жӮ·ӮйҚЕӮҪӮйҸШӢ’ӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮұӮкӮрҺқӮҪӮ№ӮҪ‘Ө(‘е–{үc)ӮжӮиҒAҺқӮҪӮіӮкӮҪ‘ӨӮМ•ыӮӘ”с“пӮіӮкӮйӮМӮНӮўӮіӮіӮ©ӮЁӮ©ӮөӮИҳbӮЕӮаӮ ӮйҒBӮұӮӨӮўӮӨ•sҸр—қӮЙ‘ОӮөҒA”T–ШӮӘҲкҗШ•s•ҪӮрӮұӮЪӮіӮИӮўҗ«ҠiӮҫӮБӮҪҺ–ӮаҒAҢгӮМ”T–Ш–і”\ҳ_ӮМҸ¬ӮіӮИҲкҲцӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB —·ҸҮҚU—ӘҗнӮМҢг”јҒA–һҸBӮ©Ӯз—·ҸҮӮЙ”hҢӯӮіӮкӮҪҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘҲЙ’n’mҺQ–d’·ӮЖҢыҳ_ӮЙӮИӮБӮҪҚЫҒu–C’eӮа–іӮөӮЙҗн‘ҲӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·Ӯ©!!ҒvӮЖ•®ӮйҲЙ’n’mӮЙ‘ОӮөҒAҺҷӢКӮНҒu–C’eӮӘ–іӮўӮМӮНӮЗӮұӮа“ҜӮ¶ҒvӮЖҗШӮБӮДҺМӮДӮҪҒBӮұӮМҸкҚҮҒAҲ«ӮўӮМӮНӮЗӮҝӮзӮЕӮаӮИӮӯҒA‘е–{үcӮЙӮЁӮҜӮйҚӘ–{“IӮИ”FҺҜӮМҢлӮиӮЖҢ©ӮйӮЧӮ«ӮҫӮлӮӨҒB ҒЎ”FҺҜӮМҢлӮи2 ҸгӢLӮЕӮаҗGӮкӮҪӮжӮӨӮЙҒA“–Ҹү—·ҸҮ—vҚЗӮМҗн—НӮНүЯҸ¬•]үҝӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҠЧ—ҺӮЬӮЕ”ј”NӮаӮ©Ӯ©ӮйӮЖҢҫӮнӮкӮИӮӘӮзӮаҒAӮҪӮБӮҪӮМ1“ъӮЕҠЧ—ҺӮіӮ№ӮҪ“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһӮМҺАҗСӮӘӮ ӮБӮҪҲЧӮЕҒAӢtӮЙҢҫӮҰӮО“ъ–{ҢRӮЙүЯҗMӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮҪ•ыӮӘӮўӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮў(ӮұӮМ“_ӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮЕ—·ҸҮӮрҢoҢұӮөӮҪ”T–ШҒAҲЙ’n’mӮМ—јҺТӮа“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮй)ҒB ӮӘҒAҺАҚЫӮМ—·ҸҮ—vҚЗӮНҒA10”N‘OӮЖӮН‘SӮӯ•К•ЁӮМӢЯ‘г—vҚЗӮЖү»ӮөӮДӮЁӮиҒA“ъҗҙҗн‘ҲҺһӮМҗнҸpӮН‘SӮӯ’К—pӮөӮИӮӯӮИӮБӮДӮўӮҪҒB”T–ШҸг—ӨӮЙҗж—§ӮҝҒA—·ҸҮӮжӮиӮНӮйӮ©ӮЙӢK–НӮМҸ¬ӮіӮИӢаҸB“мҺRӮМ—vҚЗӮЕӮНҒAүңҢRӮӘҳIҢRӮМҲі“|“IӮИүО—НӮр‘OӮЙҒw’ZҺһҠФӮЕ4000Ӯр’ҙӮҰӮйҺҖҸқҺТҒxӮрҸoӮөӮҪҒBӮұӮМ‘O‘г–ў•·ӮМҢӢүКӮрҺуӮҜҒA‘е–{үcӮНҚӘ–{“IӮИ”FҺҜӮрүьӮЯӮй•K—vӮӘӮ ӮБӮҪӮНӮёӮИӮМӮҫӮӘҒAӮ»ӮӨӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBӮ»ӮөӮДҗ”ҸTҠФҢгҒA‘OҗьӮЙӮ Ӯй”T–ШҢRӮӘҒA‘е–{үcӮМ”FҺҜӮМҢлӮиӮрҗgӮрҲИӮБӮДӮр’ЙҠҙӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB ҒЎ–{“–ӮЙӢрҚфӮ© ”T–ШӮӘ”с“пӮіӮкӮй—қ—RӮМҚЕӮҪӮйӮаӮМӮЖӮөӮДҒA‘е—КӮМҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮҪҺOҺҹӮЙӮнӮҪӮйҲкҗДҚUҢӮӮӘӢ“Ӯ°ӮзӮкӮйӮӘҒAӮұӮкӮр”с“пӮ·ӮйӮМӮНҒwҢгҸoӮөӮ¶ӮбӮсӮҜӮсҒxӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAҲк•ы“IӮИ’fҚЯӮЖҢҫӮӨӮөӮ©ӮИӮўҒBҗн‘ҲӮМҺd•ыӮӘҢҖ“IӮЙ•Пү»ӮөӮДӮўӮҪ“–ҺһҒAӢЯ‘г—vҚЗҚU—ӘӮрҢoҢұӮөӮҪ•”‘аӮН”T–ШҢRӮӘҺАҺҝҸүӮЯӮДӮЕӮ ӮиҒA’NӮаӮ»ӮМҚU—ӘӮМҺd•ыӮр’mӮзӮИӮўӮЗӮұӮлӮ©ҒAҢ»ҸкӮЕҸүӮЯӮД—vҚЗӮр–ЪӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ—L—lӮҫӮБӮҪ(“–ҺһҠщӮЙҒA—vҚЗӮЙӮНҚH•әӮр—pӮўӮйҺ–Ӯр—vӮЖӮ·Ӯйҳ_ӮӘүўҸBӮЕ’и’…ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAӮұӮМҺһ“_ӮМ“ъ–{ӮЕӮН—vҚЗӮрҚU—ӘӮЕӮ«ӮйӮЩӮЗӮМҚH•әӢZҸpҺ©‘МӮӘҲзӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ)ҒB ”T–ШӮНҺO“xӮа“ҜӮ¶ҚмҗнӮрҢJӮи•ФӮөӮҪӮЖ’Й”lӮіӮкӮйӮӘҒA•КҗlӮЕӮ ӮкӮОӮЗӮӨӮҫӮБӮҪӮ©ҒHҚ•–ШӮҫӮБӮҪӮзҒHүңӮҫӮБӮҪӮзҒHҢӢүК“IӮЙҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЙӮжӮйҠпҚфӮЙӮжӮБӮДҠЧ—ҺӮөӮҪ—·ҸҮ—vҚЗӮҫӮӘҒAӮұӮМҠпҚфҺ©‘МҒAҗіҚU–@ӮЕӮН’К—pӮөӮИӮўӮЖӮўӮӨ”T–ШҢRӮМӢіҢPӮӘӮ ӮБӮҪҸгӮЕӮМ—§ҲДӮЕӮ ӮйҒBҚЕӮаҺҖҸқҺТӮМ‘ҪӮ©ӮБӮҪ‘жҲкүсҲкҗДҚUҢӮҗнӮМ‘OӮМҺһ“_ӮЕҒAҗі–К“Л”jӮрӢрҚмӮЖ’kӮ¶ӮйҺ–ӮӘӮЕӮ«ӮҪҗlҠФӮӘүКӮҪӮөӮДүҪҗlӮўӮҪӮҫӮлӮӨӮ©ҒHӮ»ӮкӮр’mӮБӮДӮўӮҪӮМӮНӮЁӮ»ӮзӮӯ—vҚЗӮр’zӮўӮҪғҚғVғAҢRӮМӮЭӮЕӮ ӮиҒAӮҫӮ©ӮзӮұӮ»—vҚЗҺi—ЯҠҜӮМғXғeғbғZғҠӮН”T–ШӮрҒwӮҪӮБӮҪӮМ”ј”NӮЕ—·ҸҮӮрҠЧӮЖӮөӮҪҒxӮЖ•]үҝӮөӮҪӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ҒB ӮаӮҝӮлӮсҒA”T–ШҢRӮа‘SӮӯ–іҚфӮЕӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒB“с“x–ЪҒAҺO“x–ЪӮМҲкҗДҚUҢӮӮЕӮНҒAҗжӮМ”ЯҢҖӮрӢіҢPӮЖӮөӮДҒAҡНҚҲӮрғMғҠғMғҠӮЬӮЕү„җLӮ·ӮйӮИӮЗӮўӮӯӮзӮ©ҚH•vӮӘүБӮҰӮзӮкӮДӮЁӮиҒAҺ–ҺАҺҖҸқҺТӮМҗ”ӮН‘жҲкҺҹӮЙ”дӮЧ‘е•қӮЙҢёӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮМ“сҺҹҒAҺOҺҹҚUҢӮӮЕӮНғҚғVғAҢRӮМҺҖҸқҺТҗ”ӮМ•ыӮӘҸгүсӮБӮДӮўӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкҒAӮҫӮЖӮ·ӮкӮОҒw–і‘КҺҖӮЙҒxӮЖҗШӮБӮДӮ·ӮДӮйӮМӮНӮ ӮЬӮиӮЙӮа”EӮСӮИӮўҒB ҒЎҲА‘SӮИҸкҸҠӮ©ӮзҺҖ’nӮЙ’ЗӮўӮвӮБӮҪӮЖӮўӮӨҢлүр ”T–ШҢRӮМҚмҗнӮМӮЬӮёӮіӮЖӮөӮДҒA‘OҗьӮ©Ӯз—ЈӮкӮ·Ӯ¬ӮҪҸкҸҠӮЙҺi—Я•”Ӯр’uӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪ“_ӮӘӮ Ӯ°ӮзӮкӮйҒBӮұӮкӮӘүРӮЖӮИӮБӮД•K—vҲИҸгӮЙҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪ–КӮӘӮ ӮйӮМӮН”ЫӮЯӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBӮұӮМ“_ӮіӮҰүь‘PӮЕӮ«ӮДӮўӮкӮО‘жҲкүсҲкҗДҚUҢӮӮЙӮжӮБӮД—vҚЗӮНҠЧ—ҺӮөӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҗәӮаҲк—қӮ ӮйӮжӮӨӮЙҺvӮҰӮйҒBӮӘҒAӮұӮұӮЕҺw“EӮөӮДӮЁӮ«ӮҪӮўӮМӮНҒA”T–ШӮӘҒwүдӮӘҗgӮМҲА‘SӮр—DҗжӮөӮДҢг•ыӮЙҺi—Я•”ӮрӮЁӮўӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўҒxӮЖӮўӮӨҺ–ҒB Ңг•ыӮЙҺi—Я•”ӮӘ’uӮ©ӮкӮҪӮМӮНҒAҺQ–d’·ҒEҲЙ’n’mӮЙӮжӮйҒuҸe’eӮМ”тӮСҢрӮӨ‘OҗьӮЙӮЁӮўӮДӮН“IҠmӮИҚмҗн”»’fӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨ•ыҗjӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAӮұӮкӮрҚМ—pӮөӮҪ”T–ШӮЙҗУ”CӮӘӮ ӮйӮЖӮНҢҫӮҰҒA•ЫҗgӮЖӮўӮӨ•s–ј—_ӮЖҚ¬“ҜӮ·ӮйӮЧӮ«ӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB Һ–ҺАҒA”T–ШӮН’PҗgӮЕҠлҢҜӮИ‘OҗьӮЦӮМҺӢҺ@ӮрүҪ“xӮаӢӯҚdӮөӮДӮЁӮиҒAӮіӮзӮЙҢҫӮҰӮОҒAҺбӮўҚ ӮЙҺw“EӮіӮкӮДӮўӮҪҺҖ’nӮр’TӮ·ҒwҺ©ҺEҠи–]ҒxӮӘӮұӮұӮЕӮа“ӘӮрӮаӮҪӮ°ӮДӮіӮҰӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB”T–ШӮН“ъҳIҗн‘ҲҸoҗӘӮЙӮ ӮҪӮиҒAҠщӮЙҗн’nӮЙҚңӮрӮӨӮёӮЯӮйӮВӮаӮиӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйӮӘҒAӢаҸBӮЕ’·’jӮрҒA—·ҸҮӮЕҺҹ’jӮрҺёӮБӮДҲИҚ~ӮНҒAӮіӮзӮЙӮ»ӮМҢXҢьӮЙ”ҸҺФӮӘӮ©Ӯ©ӮБӮҪүВ”\җ«ӮН”Ы’иӮЕӮ«ӮИӮўҒB ҒЎӢрҗlӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒH ‘е—КӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪ”T–ШӮНҒAҺһӮЖӮөӮД•ОӢ·ӮИӢрҗlӮЖӮөӮД•`Ӯ©ӮкӮйҺ–ӮӘӮ ӮйҒB•\Ң»ӮМҺ©—RӮЖҢҫӮБӮДӮөӮЬӮҰӮОӮ»ӮкӮЬӮЕӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮӘҚ‘үcғҒғfғBғAӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҸкҚҮҒAӮұӮМ•ОҢ©ӮМӢпҚҮӮНүҪӮ©ӢЙҚ¶“IӮИ“хӮўӮӘӮөӮДӮ Ӯ«ӮкӮДӮөӮЬӮӨҒBҺь’mӮМҺ–ҺАӮҫӮӘҒA”T–ШӮНҲк•”ӮМӢҢ“ъ–{ҢRӮМӮжӮӨӮЙҸoҗўӮМҲЧӮМҺ„—ҳҺ„—~ӮЙ‘–ӮБӮҪҺ–ӮНӮИӮӯҒA”сҸнӮЙ•”үәӮр‘zӮўҒAүЯҸиӮИӮЬӮЕӮЙҺ©•ӘӮЙҢөӮөӮӯҗ¶Ӯ«ӮҪҗlҠФӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮұӮлӮӘҒAӮЗӮӨӮўӮӨғtғBғӢғ^Ғ[Ӯр’КүЯӮөӮҪӮМӮ©ҒAҺһӮЖӮөӮДӮ Ӯ©ӮзӮіӮЬӮЙӢ¶җlӮЯӮўӮҪ•`ҺКӮрӮіӮкӮйҺ–ӮіӮҰӮ ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB —·ҸҮӮМҺҖҸқҺТӮЙ‘ОӮөӮДӮМҗУ”CӮНҒAӮаӮҝӮлӮсҺi—ЯҠҜӮЕӮ Ӯй”T–ШӮЙӢAӮ№ӮзӮкӮйӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮұӮМҢӢүКӮрҲк”Ф’pӮ¶ӮДӮўӮҪӮМӮН”T–ШҺ©җgӮЕӮ ӮиҒAҠFӮӘ•ӮӮ©ӮкӮҪҠMҗщӮМҚЫӮЙ–ҫҺЎ’йӮЙҗШ• Ӯрҗ\ӮөҸoӮДӮўӮйҺ–Ӯр’mӮБӮДӮЁӮ©ӮЛӮОӮИӮзӮИӮўҒB “ъҳIҗн‘ҲӮЕӮН—·ҸҮҲИҠOӮЕӮа‘Ҫҗ”ӮМҺҖҸқҺТӮӘҸoӮДӮЁӮиҒA’ҶӮЙӮН“–‘RҚмҗнӮМӮЬӮёӮіӮЙӢNҲцӮ·ӮйӮаӮМӮаӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮ»ӮӨӮўӮБӮҪҸ”ҒXӮНҗнҸҹӮМҢӢүКүқ—ҲӮЙӮжӮБӮДӮ Ӯй’ц“xҗ…ӮЙ—¬ӮіӮкӮДӮўӮйҠҙӮН”ЫӮЯӮИӮўҒBӮЖӮ·ӮкӮОҒAӮЭӮёӮ©ӮзҗУ”CӮр”ғӮБӮДҸoӮйҢүӮіӮНӢрҗlӮЙӮНҗ^Һ—ӮМӮЕӮ«ӮИӮўҗ¶Ӯ«—lӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮрӮаӮБӮДӮаҸ®ҒAӢ¶җlӮЯӮўӮҪ•`ҺКӮрӮ·ӮйҲк•”ҚмүЖӮвғҒғfғBғAӮИӮЗӮЙӮВӮўӮДӮНҒAӮ»ӮМүҝ’lҠПӮұӮ»ӮӘ•ОӢ·ӮЖҢҫӮӨ‘јӮН–іӮўҒB“БӮЙӮ»ӮкӮӘҚ‘үcғҒғfғBғAӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮкӮОҒAӮаӮНӮвҠлӢ@ӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒB ҒЎ‘Қҳ_ӮЖӮөӮД ‘е—КӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAҠCҢRӮМ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЖ•АӮсӮЕ”T–ШӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮМүp—YӮЖӮөӮДҚХӮиҸгӮ°ӮзӮкӮҪ—қ—RӮЖӮөӮДҒAӮөӮОӮөӮО–ҫҺЎӮЖҢ»‘гӮМҒuҸҺ–ҜҠҙҠoӮМҚ·ҒvӮӘҺw“EӮіӮкӮйҒBҢүӮіӮвҚҺҢИҗSӮр”ь“ҝӮЖӮ·Ӯй‘OҺһ‘гӮМ“ъ–{–Ҝ‘°ӮМҠҙҠoӮӘҒAҗgӮр–ЕӮөӮДҚ‘ӮЙҗsӮӯӮөӮҪ”T–ШӮрүp—YӮЖӮөӮД•]үҝӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAӢtӮЙҢҫӮҰӮОҒwҗ¬үКҺҠҸгҺеӢ`ҒxӮЙҠЧӮБӮДӮўӮйҢ»‘гӮМ“ъ–{җlӮМҠҙҠoӮӘҒA”T–ШӮрӢрҸ«ӮЖӮөӮДҒAӮ»ӮМ–ј—_Ӯр’nӮЙжИӮЯӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҺ–ӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒB ӮіӮзӮЙӮаӮӨҲкӮВӮМҸd—vӮИ“_ӮЖӮөӮД‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙҗGӮкӮИӮўӮнӮҜӮЙӮНӮўӮ©ӮИӮўҒB”T–ШӮМ”ЖӮөӮҪҺёҚф(Ҳк”Кҳ_Ӯ©ӮзӮ ӮҰӮДҺёҚфӮЖҢДӮФ)ӮМ—ЮҺ——бӮНҗжӮМ‘еҗн’ҶҒAӮ ӮзӮдӮйҸк–КӮЕҢJӮи•ФӮіӮкӮҪҒBҸүҠъӮМ•ыҗjӮвҗж“ьҠПӮЙӮұӮҫӮнӮйӮ ӮЬӮиҚЕҢгӮЬӮЕҗі–К“Л”jӮрҗҘӮЖӮөӮҪҠо–{•ыҗjӮрӮНӮ¶ӮЯҒAҸо•сҢyҺӢҒAҲА‘SӮИӮЖӮұӮлӮ©Ӯз–і—қ“п‘иӮрүҹӮө•tӮҜӮйҸг‘w•”ӮМ–і”\ҒE•…”sӮНҒA–SҚ‘ӮЙҺҠӮйӮа“–‘RӮМҸX‘ФӮҫӮБӮҪӮМӮНҠФҲбӮўӮИӮўҒB“–ҺһӮМҺс”]•”ӮМҒw–іҚфҒxӮрҗі“–ү»Ӯ·ӮйҲЧӮЙҒwҗёҗ_ҳ_ҒxӮӘ•K—vҲИҸгӮЙӢӯ—vӮіӮкҒAӢрҚмӮрҳA”ӯӮөӮҪҸг‘w•”ӮЙ‘гӮнӮБӮДҒA‘OҗьӮЕ•Д•әӮМ10”{Ӯр’ҙӮҰӮй•әҺmӮӘҺUӮБӮҪӮнӮҜӮҫҒB ӮұӮМҺһҒAҗgӮрӢ]җөӮЙӮөӮДҚ‘ӮЙҗsӮӯӮөӮҪ”T–ШӮМҒw”ь“ҝҒxӮЖҒwҗ¶Ӯ«—lҒxӮӘҗнҲУҚӮ—gӮЙ‘еӮўӮЙ—ҳ—pӮіӮкҒAӮұӮкӮЙӮжӮБӮД‘ж“сҺҹ‘еҗнҢoҢұҺТӮМ’ҶӮ©Ӯз”T–Ш”б”»ӮМҗәӮӘҸoӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒBӮӘҒAҳ_“_Ӯр“ҘӮЭҲбӮҰӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒBӮұӮұӮЕ”б”»ӮіӮкӮйӮЧӮ«ӮНҒA”T–ШӮМҲРӮрҺШӮиӮДүЎ–\ӮрҗUӮйӮБӮҪ–}җlӮМҺmҠҜӮзӮЕӮ ӮиҒAҗgӮр—ҘӮөӮДҢИӮЙҢөӮөӮӯҗ¶Ӯ«ӮҪ”T–ШӮрӮвӮиӢКӮЙӮ Ӯ°ӮйӮМӮНӢШҲбӮўӮЕӮөӮ©ӮИӮўҒB ‘ж“сҺҹ‘еҗнӮМ”sҗнӮН“ъ–{Қ‘–ҜӮЙӮЖӮБӮД”сҸнӮЙүЯҚ“ӮИҸo—ҲҺ–ӮЕӮ ӮиҒAӢЗҸҠӮЙӮЁӮҜӮй”sҺcғpғ^Ғ[ғ“ӮӘ—·ҸҮҚU—ӘҗнӮЖҸd•ЎӮ·Ӯй“_ӮН”Ы’иӮЕӮ«ӮИӮўҒBӮҫӮ©ӮзӮЖӮўӮБӮДҒA‘ж“сҺҹ‘еҗнӮЙӮЁӮҜӮйҺс”]•”ӮМҸX‘ФӮрҒAӮіӮзӮЙ40”NӮіӮ©ӮМӮЪӮБӮД”T–ШӮЙ“K—pӮ·ӮйӮМӮНӮвӮНӮи—қ•sҗsӮҫҒB”T–ШӢрҸ«ҳ_ӮрҚ‘–ҜӮЙҚLӮЯӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮа—ӨҢRӢіҲзӮв‘ж“сҺҹ‘еҗнӮЕӮРӮЗӮў–ЪӮЙӮ ӮБӮДӮЁӮиҒAҺҒӮМҗцҚЭ“IӮИҠҙҸоӮЙӮжӮБӮД”T–ШӮЦӮМ•]үҝӮӘҗhҢыӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮНҺd•ыӮМӮИӮўҺ–ӮҫӮлӮӨӮӘҒAҗн‘ҲӮрҢoҢұӮөӮДӮўӮИӮў‘е‘Ҫҗ”ӮМҗў‘гӮМҗlҠФӮНҒAӮжӮи‘еӢЗӮ©Ӯз•]үҝӮрүәӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮ ӮиҒAҲАҲХӮИҗёҗ_ҳ_ӮМ”Ы’иӮЙ‘–ӮйӮЧӮ«ӮЕӮНӮИӮўҒB–{—Ҳҗёҗ_ҳ_ӮЖӮНҒAҢИӮрҢөӮөӮӯ—ҘӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮ ӮйӮЖ’mӮБӮДӮЁӮӯ•K—vӮӘӮ ӮйӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҲЙ’n’mҚKүо 1854-1917 ҺF–Җ”Л
‘жҺOҢRҺQ–d’·ҒB—·ҸҮҚU—ӘӮМҚмҗнӮНҠо–{“IӮЙӮНҲЙ’n’mӮӘҺеӮЖӮИӮБӮД—§ҲДҒAҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҠу“TӮӘҸі”FӮМҢ`ӮрӮЖӮБӮҪҒB”T–ШӮЙ‘ОӮөӮДӮНҺ^”Ы—јҳ_ӮӘӮ ӮйҲк•ыӮЕҒAҲЙ’n’mӮЙ‘ОӮөӮД—iҢмӮ·ӮйҗәӮН“–ҺһӮаҚЎӮаҢҲӮөӮД‘ҪӮӯӮНӮИӮўҒB—·ҸҮҚU—ӘӮӘҸIӮнӮБӮҪҢгҒAҲЙ’n’mӮНҺQ–d’·Ӯрүр”CӮіӮк—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜӮЙҸAӮўӮҪӮӘҒAӮұӮкӮНҺ–ҺАҸгӮМҚX“RӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒB Һi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЕӮНҠж–АӮЕ–і”\ӮИҲ«ӢКҺQ–d’·ӮЖӮөӮД•`Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮаӮ»ӮаҲЙ’n’mӮӘҺQ–d’·ӮЙ”C–ҪӮіӮкӮҪ—қ—RӮЖӮөӮДӮНҒAғhғCғc—ҜҠw‘gӮЕӮ ӮйҸгҒA“ҜҠъӮЕӮа“ЛҸoӮөӮҪҸGҚЛӮФӮиӮр”ӯҠцӮөӮДӮўӮҪ”wҢiӮӘӮ Ӯй(‘жҺOҢRҺQ–d’·”C–Ҫ‘OӮН‘е–{үcӮМҚмҗнҺQ–d)ҒBӮЬӮҪҗк–еӮӘ–C•әүИӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒA—vҚЗҚU—ӘӮЙ“K”CӮЖҚlӮҰӮзӮкӮҪҺ–ӮвҒA”T–ШҺi—ЯҠҜ“Ҝ—l“ъҗҙҗн‘ҲӮЕ—·ҸҮҚU—ӘҗнӮрҢoҢұӮөҢ»’nӮЙ–ҫӮйӮ©ӮБӮҪҺ–ҒAӮіӮзӮЙӮНүўҸB—ҜҠwҺһ‘гӮЙ”T–ШӮЖ–КҺҜӮӘӮ ӮБӮҪҺ–ӮИӮЗӮа”C–ҪӮМ—vҲцӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB‘ҚҺi—ЯҒE‘еҺRҠЮӮМҗe‘°(–ГӮМ•v)ӮЕӮ ӮБӮҪ“_ӮЕ—DӢцӮіӮкӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮаӮ»ӮаӮМ‘O•]”»ӮЖӮөӮД”\—Н“IӮЙ‘жҺOҢRӮМҺQ–d’·ӮЙ“K”CӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮҪҲЧҒAӮұӮкӮНҢг•tӮҜӮМ•—•]ӮЖҢ©ӮҪ•ыӮӘӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB ҲЙ’n’mӮМҗlӮЖӮИӮиӮЙӮВӮўӮДӮНӮжӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҒBӮӘҒA—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘҗнӮӘ”ЯҺSӮИ—l‘ҠӮр’жӮөӮҪҺ–ӮЙӮжӮБӮДҲЙ’n’mӮМҗlҠiӮНӮЩӮЪҢЕ’иӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒB”T–ШҢRӮМҺi—Я•”ӮЙӮЁӮўӮДҒAҠO•”Ӯ©ӮзӮМҗiҢҫӮрҚДҺOӢpүәӮө‘ұӮҜӮҪҠж–АӮИҺQ–d’·ҒBҚӮ–қӮЕӢр—тӮЕҒAҢг•ыӮ©Ӯз–і—қӮрүҹӮө•tӮҜӮй”ЪӢҜҺТҒBӮұӮкӮзӮНҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЙӮжӮБӮД’и’…ӮөӮҪғCғҒҒ[ғWӮҫӮӘҒA—вҗГӮЙҢ©ӮДӮЗӮӨӮҫӮлӮӨӮ©ҒB ӮұӮұӮЕ“БӮЙҲЙ’n’mӮрҚDҲУ“IӮЙҢ©ӮйӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮӘҒAӢqҠП“IӮЙҢ©ӮДҲЙ’n’mӮӘ–і”\ӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮжӮиҒAӮЮӮөӮлҒwҺd•ыӮӘ–іӮ©ӮБӮҪҒxӮЖӮўӮӨӮМӮӘҺА‘ФӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒB—·ҸҮҚU—ӘҗнӮМҢӢүКӮр’mӮйүдҒXӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAҺ©ӮзӮМҚмҗнӮЙӮұӮҫӮнӮи‘ұӮҜӮҪҲЙ’n’mӮНҠmӮ©ӮЙ–і”\ӮИҸ¬–рҗlӮЙҢ©ӮҰӮДҺd•ыӮӘ–іӮўҒBӮӘҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮаҲЙ’n’mӮН–CҸpӮМҗк–еүЖӮЕӮ ӮиҒA(ҲЙ’n’mӮМ’mҺҜӮӘ—·ҸҮ—vҚЗӮЙ’К—pӮөӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДӮа)җк–еүЖӮЖӮөӮД”C–ҪӮіӮкӮҪҲИҸгҒAҺ©Ӯз‘gӮЭ—§ӮДӮҪҚмҗнӮрҗ„ӮөҗiӮЯӮйҺ–Һ©‘МӮНҢҲӮөӮДӢрӮЕӮНӮИӮўҒBӮӘҒAғtғ^ӮрӮ ӮҜӮДӮЭӮкӮО‘е–{үcӮЙ—·ҸҮ—vҚЗӮМҸо•сӮӘ–іӮӯҒA‘жҺOҢRӮЙӮаӮ»ӮкӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢӢүКҒAӢNӮұӮйӮЧӮӯӮөӮДӢNӮұӮБӮҪ”ЯҢҖӮЖҢҫӮӨ‘јӮНӮИӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒB —·ҸҮҚU—ӘӮӘ“пҚqӮөӮДӮўӮйҚЫҒAҚ‘“аӮЕӮН“ҢӢһҳpӮрҺзӮй28ғTғ“ғ`–CӮрҺжӮиҠOӮөӮД—·ҸҮӮЙҲЪӮ·ӮЖӮўӮӨҸнҺҜӮНӮёӮкӮМҲДӮӘ•ӮҸгӮөӮҪӮӘҒA“–Ҹүҗк–еүЖӮМҲЙ’n’mӮНӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДүщӢ^“IӮҫӮБӮҪҒBҲЙ’n’mӮЙҢАӮзӮёҒAҺQ–d•ӣ’·ӮМ‘е’лӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҢ»ҸкӮМ“Ә”]ӮҪӮҝӮНӮұӮМҲДӮрӮұӮЖӮІӮЖӮӯ–і—қӮҫӮЖ•]ӮөӮҪҒBӮЬӮҪҺАҚЫӮЙ28ғTғ“ғ`–CӮӘ—·ҸҮҚU—ӘӮЙ”z”хӮіӮкӮҪҢгӮаҒAғ}ғjғ…ғAғӢ’КӮиӮМ“KӢ——ЈӮр•ЫӮБӮД–CҢӮӮөӮДӮўӮҪҲЧҒAӮ»ӮМҢшүКӮрҚЕ‘еҢАӮЙ”ӯҠцӮ·ӮйҺ–ӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМ’в‘ШӮр‘ЕӮҝ”jӮБӮҪӮМӮНҒA–CҸpӮМ‘fҗlӮЕӮ ӮйҺQ–d‘Қ’·ҒEҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЕӮ ӮиҒAҲА‘SӢ——ЈӮр‘SӮӯ“xҠOҺӢӮөӮҪ–C”z”хӮЕҒAҢӢүКӮЖӮөӮД—·ҸҮҠЧ—ҺӮЙ‘еӮ«ӮӯҚvҢЈӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB ҢӢүКӮ©ӮзҢ©ӮкӮОҲЙ’n’mӮзӮН–і”\ӮЖҢ©ӮзӮкӮДҺd•ыӮӘӮИӮўӮӘҒAҠwӮсӮЕӮ«ӮҪғ}ғjғ…ғAғӢ’КӮиӮЙҗк–еӢZҸpӮр”ӯҠцӮ·ӮйӮМӮӘҲЙ’n’mӮзҗк–еүЖӮМ–рҠ„ӮЕӮ ӮиҒAӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮз—·ҸҮ—vҚЗҺ©‘МӮӘғ}ғjғ…ғAғӢӮМ’К—pӮ·ӮйғXғPҒ[ғӢӮр‘еӮ«Ӯӯ’ҙӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҢ»ҺАҒBӮ·ӮИӮнӮҝӮұӮкӮұӮ»ӮӘҒA”ЯҢҖӮМҚӘ–{“IӮИҢҙҲцӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒB “ъҳIҗн‘Ҳ‘S‘МӮрҢ©ӮкӮОҒAғRғTғbғNӢR•әӮр‘ҠҺиӮЙ–C•әӮрҠҲ—pӮөӮДҗнӮБӮҪҸHҺRҺx‘аҒAӢЯ‘г—p•әӮЕӮНӮ ӮиӮҰӮИӮў‘еӢK–НӮИ–йҸPӮрӮ©ӮҜӮҪҚ•–ШӮв–м’ГҒAҸ]—ҲӮМҠН–CҺЛҢӮӮМӮ Ӯи•ыӮрҚӘ’кӮ©ӮзүьӮЯӮҪ“ҢӢҪҠН‘аӮИӮЗҒAҗіҚU–@ӮЕӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮұӮ»‘еӮ«ӮИҢшүКӮр”ӯҠцӮЕӮ«ӮҪ•”•ӘӮНҸӯӮИӮӯӮИӮўҒBғ}ғjғ…ғAғӢӮМ’КӮ¶ӮИӮў—vҚЗӮЙҗк–еүЖӮзӮр”z’uӮөҒAӮөӮ©Ӯа—vҚЗӮМҸо•сӮрҺ–‘OӮЙ”cҲ¬ӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪ‘е–{үcӮМ•sү^ҒB–SӮӯӮИӮБӮҪ•ыҒXӮЙӮНҗ\Ӯө–уӮИӮўӮӘҒAӮұӮұӮНҲЙ’n’mҲкҗlӮрғ„ғҠӢКӮЙӮ Ӯ°ӮйӮМӮЕӮНӮИӮӯҒAҒwҺd•ыӮИӮ©ӮБӮҪҒxӮЖҚlӮҰӮйӮМӮӘ‘Г“–ӮЖҺvӮҰӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘е’л“сҳY 1864-1935 ’·ҸB”Л
‘жҺOҢRҺQ–d•ӣ’·ҒB ’·–еҸoҗgӮМүpҚЛӮМ’ҶӮМҲкҗlӮЕӮ ӮиҒA’·ҸB”ҙӮМ’·ӮЕӮ ӮйҺRгp—L•ьӮМ•ӣҠҜӮр–ұӮЯӮҪҢo—рӮаӮ ӮйҒB‘жҺOҢRӮЙ•Тҗ¬ӮіӮкӮйӮЬӮЕӮНҺQ–d’·ӮМҲЙ’n’mҚKүо“Ҝ—lӮЙ‘е–{үcӮМҺQ–d–{•”ӮЙӮЁӮиҒA—·ҸҮҚU—ӘӮЙӮЁӮҜӮй“Ә”]ӮМ’Ҷҗ•ӮЖӮөӮДӮ»ӮМ”\—НӮрҠъ‘ТӮіӮкӮҪҒB —·ҸҮҚU—ӘӮЙӮЁӮҜӮйҚU–hӮМ’ҶӮЕҚЕ‘еӮМ‘№ҠQӮрҸoӮөӮҪӮМӮН‘жҲкүсҲкҗДҚUҢӮӮМҺһӮҫӮӘҒAӮұӮМҚмҗнӮр—§ҲДӮөӮҪӮМӮН‘е’лӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҚЕҗVҺ®ӮМӢ@ҠЦ–CӮЙ‘ОӮөӮДҸeҢ•“ЛҢӮӮрҢJӮи•ФӮ·ҚмҗнӮНҒAҢгҗўӮ©ӮзҢ©ӮкӮОӢрҚм’ҶӮМӢрҚмӮЕӮ ӮиҒAҢӢүКӮЖӮөӮДӮН–ЪӮа“–ӮДӮзӮкӮИӮўҗ”ӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮ·ӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҸeҢ•“ЛҢӮӮрӢрҚмӮЖҗШӮБӮДҺМӮДӮйүдҒXӮМҺvҚlүсҳHӮНҒAӮЁӮ»ӮзӮӯ‘ж“сҺҹ‘еҗнӮЕҢJӮи•ФӮіӮкӮҪ”ЯҢҖӮМӢLүҜӮЙ—R—ҲӮөӮДӮўӮйӮЖҺvӮнӮкӮйҒBӮұӮМҠҙҠoӮр–ҫҺЎҠъӮМ—·ҸҮҚU—ӘҗнӮЙ“–ӮДӮНӮЯӮйӮМӮНҢцҗіӮИ”»’fӮЖӮНҢҫӮўӮГӮзӮўӮМӮаҠmӮ©ӮҫӮлӮӨҒB ҺАҚЫӮМӮЖӮұӮлҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҺь•УӮНӢ}ҸsӮИҠRӮаӮөӮӯӮН“Ю—ҺӮМҗ[’JӮЙҲНӮЬӮкӮДӮЁӮиҒAӮұӮМ—vҚЗӮрҚUӮЯӮйӮЖӮ·ӮкӮОҠЙӮвӮ©ӮЙ‘ұӮӯҺО–КӮМғӢҒ[ғgӮөӮ©ҺcӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB“–‘R“GӮМӢ@ҠЦ–CӮНӮұӮұӮЙҸd“_”z”хӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒA”T–ШҢRӮӘ–і—қӮНҸі’mӮЕҗі–КӮ©ӮзҚUӮЯӮҪӮМӮН’vӮө•ыӮМӮИӮўӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨҒB—vҚЗҚU—ӘӮН•Ё—КӮЕүҹӮөҗШӮйӮМӮӘ“–ҺһӮМҗіҚU–@ӮЕӮ ӮиҒAӮЬӮҪ–һҸBҢRӮв‘е–{үcӮ©ӮзҒwҚU—ӘҚГ‘ЈҒxӮМ“`—ЯӮӘӮҪӮСӮҪӮС“НӮўӮДӮўӮҪҺ–ҸоӮаӮ ӮиҒA•K‘R“IӮЙ‘еӢK–НӮИ•Ё—КҚмҗнҒAӮ·ӮИӮнӮҝ’ZҠъҢҲҗнӮрҢ©ҚһӮсӮҫҲкҗДҚUҢӮӮрҺdҠ|ӮҜӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮҫҒB ӮұӮМҲкҗДҚUҢӮӮН–і–dӮ©ӮВ–іҚфӮИҗі–К“Л”jӮЖҺvӮнӮкӮДӮўӮйӮУӮөӮӘӮ ӮйӮӘҒAҺАҚЫӮЙӮН”T–ШҢRӮНүЯӢҺӮЙ—бӮМ–іӮў11–ң3җз”ӯӮаӮМ–CҢӮӮр—·ҸҮ—vҚЗӮЙ’@Ӯ«ӮВӮҜҒAүВ”\ӮИҢАӮи’ҫ–ЩӮіӮ№ӮҪҸгӮЕҸ«•әӮр“ЛҢӮӮіӮ№ӮДӮўӮйҒBҢӢүКӮЖӮөӮДӮН“ъ–{җнҺjӮЙҺcӮйҺSҢҖӮЙӮИӮБӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAӢ@ҠЦ–CӮрҺАҗн”z”хӮөӮҪ‘еӢK–Нҗ퓬Һ©‘МӮӘҒAҗўҠEӮЕҸүӮЯӮДӮМҺ–ӮЕӮ ӮиҒAҢӢүКҳ_ӮҫӮҜӮЕҲк•ы“IӮЙҗШӮиҺМӮДӮйӮМӮЬӮёӮўҒBӮұӮМҺһӮМҲкҗДҚUҢӮӮЕӮНҲкҢЛ•әүqӮМ—ҰӮўӮй‘жҳZ—·’cӮӘ—·ҸҮҺsҠXӮМҢ©үәӮлӮ№Ӯй–]‘дӮЬӮЕ“һ’BӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAӮұӮкҲИ‘OӮаӮұӮкҲИҚ~ӮаҒA—vҚЗҚU—ӘӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙӮөӮД“S•ЗӮЙӢaҢҠӮрӮӨӮӘӮБӮДӮўӮӯӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAҲкҢЛӮзҢ»ҸкҸ«ҚZӮаӮ»ӮкӮр”O“ӘӮЖӮөӮҪҚsҢRӮҫӮБӮҪӮНӮёӮҫҒB –в‘иӮНӮұӮМҢгӮҫҒB“ҜӮ¶Ӯӯ–]‘д•tӢЯӮЬӮЕ“һ’BӮөӮҪ‘жҸ\Ҳк—·’cӮЖӮЖӮаӮЙҒAҲкҢЛӮӘҳIҢRҗw’nӮЦҲкҗДҚUҢӮӮрӮ©ӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮЖӮұӮлӮЕҒA”T–ШҢRҺi—Я•”ӮӘ‘ЮӢpӮМ–Ҫ—ЯӮрҸoӮөӮДӮөӮЬӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮЙҗж—§ӮВ“мҺRӮМҚU—ӘӮЙӮЁӮўӮДҒAүң•ЫиЭӮӘ—ҰӮўӮй‘ж“сҢRӮМҺҖҸқҺТҗ”ӮН‘Ҡ“–ӮИҗ”(ҚЕҸI“IӮЙ6,000җl’ҙ)ӮЙҸёӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAүәҠЦӮЦӮМҚsҢR—сҺФ“аӮЕӮұӮкӮр•·ӮўӮҪҲЙ’n’mҺQ–d’·ӮИӮЗӮНҒuҗ”ҺҡӮӘ‘ҪӮ·Ӯ¬ӮйҒBҠФҲбӮўӮЕӮНӮИӮўӮМӮ©ҒvӮЖӮИӮ©ӮИӮ©җMӮ¶ӮзӮкӮёӮЙӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮӘҒAҺАҚЫӮЙ“мҺRӮ·ӮзӮНӮйӮ©ӮЙҸгүсӮйҗ”ҺҡӮр–ЪӮМӮ ӮҪӮиӮЙӮөӮҪҺһҒAҲЙ’n’mӮМӮЭӮИӮзӮёҒAҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҠу“TҒAӮіӮзӮЙӮНҚмҗнӮр—§ҲДӮөӮҪ‘е’лӮИӮЗӮН‘Ҡ“–ӮЙӢ°ӮкҗнӮўӮҪӮНӮёӮҫӮлӮӨҒBӮЁӮ»ӮзӮӯӮН“®—hӮӘҸ[–һӮөӮҪҺi—Я•”ӮӘҺvҚlӮрҸЕӮБӮҪӮМӮН•K‘RӮИӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҗнӢөҸ¶Ҳ¬ӮӘӢlӮЯӮзӮкӮДӮўӮИӮўҸуӢөүәӮЕ‘ЮӢpӮрүә—ЯҒAӮұӮкӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҚU—ӘҗнӮНҸoҢыӮӘҢ©ӮҰӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҲИҢгҒA”T–ШҢRӮНҚмҗнү^—pӮЙҗTҸdӮЙӮИӮйҒBҲкҗДҚUҢӮӮНӮұӮМҢгӮа‘ж“сүсҒA‘жҺOүсӮЖ‘ұӮўӮҪӮӘҒAҡНҚҲӮр—vҚЗғMғҠғMғҠӮЬӮЕҢ@ӮиҗiӮЯӮДӮ»ӮұӮ©ӮзҸoҢӮӮ·Ӯй•ыҗjӮр“O’кӮөӮҪҲЧҒAҲИҢгӮМ‘№ҠQӮН‘е•қӮЙҢёҸӯҒAғҚғVғA‘ӨӮМ•ыӮӘ”нҠQӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮЖӮНҢҫӮҰ—vҚЗӮНҲкҢьӮЙҠЧ—ҺӮөӮИӮўҒBӮұӮМҠФҒA“ъ–{Ӯ©Ӯз28ғTғ“ғ`–CӮӘ—A‘—ӮіӮкҒA—vҚЗҚU—ӘӮЙү^—pӮіӮкҺnӮЯӮҪӮӘҒA‘е’л“сҳYӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺi—Я•”ӮН“–Ҹү“пҗFӮрҺҰӮөӮДӮўӮҪӮзӮөӮўҒBҢӢүКӮЖӮөӮД—·ҸҮ—vҚЗӮӘҠЧӮЖӮ№ӮҪӮМӮН28ғTғ“ғ`–CӮЙӮжӮйӮЖӮұӮлӮӘ‘еӮ«ӮўӮМӮҫӮ©ӮзҒA‘е’лӮМӮұӮМҺһӮМҺpҗЁӮНҢӢүК“IӮЙғGғҠҒ[ғgӢCҺҝӮМ•ҫҠQӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB ҲкҢьӮЙҠЧ—ҺӮөӮИӮў—·ҸҮҚU—ӘҗнӮЙӢЖӮрҺПӮвӮөӮҪҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘҒA–һҸB‘ҚҺi—Я•”Ӯ©ӮзӮНӮйӮОӮйғeғR“ьӮкӮЙӮвӮБӮДӮ«ӮҪҚЫҒA‘е’лӮНҺҷӢКӮ©Ӯзҗl‘OӮЕ‘еҠ…ӮрҺуӮҜӮДӮўӮйҒBғGғҠҒ[ғgӮЙӮЖӮБӮД‘ПӮҰ“пӮўӢьҗJӮҫӮБӮҪӮӘҒA”T–ШҒAҲЙ’n’mӮзӮЙ‘гӮнӮБӮД‘е’лӮӘҺҷӢКӮМ”lҗәӮр—ҒӮСӮйҺ–ӮЕҢRӢKӮӘ•ЫӮҪӮкӮҪӮЖӮМҢ©•ыӮаӮЕӮ«ӮйҒB“БӮЙ‘е’лӮЦӮМ•—“–ӮҪӮиӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪ“_ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺҷӢКӮЖ“ҜӢҪӮЕӮ ӮБӮҪҺ–ӮЙүБӮҰҒAҺҷӢКӮӘҸү‘гҚZ’·ӮрӢОӮЯӮҪ—ӨҢR‘еҠwҚZӮМҸoҗgӮЕӮ ӮБӮҪҺ–ӮаӮ ӮйӮЖҺw“EӮіӮкӮйҒB Һi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЕӮНҒAӮўӮ«Ӯи—§ӮБӮҪҺҷӢКӮӘ”T–ШҢRҺiҺQ–dӮМ“V•Ы‘KӮрҲшӮ«ӮҝӮ¬ӮБӮҪғGғsғ\Ғ[ғhӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮаӮөӮұӮкӮӘҺjҺАӮЕӮ ӮкӮОӮұӮМҺһӮМ”нҠQҺТӮН‘е’лӮҫӮБӮҪӮЖӮаҗ„‘ӘӮЕӮ«ӮйҒBӮИӮЁҒA“V•Ы‘KӮН‘ж“сҺҹ‘еҗнӮЙҺҠӮйӮЬӮЕҺQ–dӮМҸЫ’ҘӮ©ӮВ‘г–јҺҢӮЕӮ ӮиҒAҒu–{•”Ӯ©Ӯз“V•Ы‘KӮӘҺӢҺ@ӮЙ—ҲӮҪҒvӮИӮЗӮЖӮўӮӨҺgӮнӮк•ыӮрӮөӮҪҒB ҺҷӢКӮМ“oҸкҢгҒA—·ҸҮҚU—ӘӮНҸҮ’ІӮЙҗiӮЭҺnӮЯҒAҗӢӮЙӮНҠJҸйӮ№ӮөӮЯӮйӮнӮҜӮҫӮӘҒAҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШӮЖҺQ–dӮМ’Г–м“cӮрҸңӮӯҺi—Я•”Һе—vғҒғ“ғoҒ[ӮНӮұӮЖӮІӮЖӮӯҸҲ•ӘӮМ‘ОҸЫӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҲИҢг‘е’лӮМҸoӮй–ӢӮН–іӮӯӮИӮйҲк•ыҒAҗнҢгӮНҸҮ’ІӮЙҸoҗўӮрҸdӮЛ—ӨҢR‘еҸ«ӮЬӮЕҸгӮиӢlӮЯӮДӮўӮйҒB—·ҸҮҚU—ӘӮМүЯ’цӮНӮЖӮаӮ©ӮӯӮЖӮөӮДҒA‘е’лӮМ”\—НӮӘҢRӮЙ•K—vӮЖӮіӮкӮҪӮЖҢ©ӮйҺ–ӮаӮЕӮ«ӮйӮөҒAӮаӮөӮӯӮНҒuҺQ–dӮНҸҲ”ұӮіӮкӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҢгӮМҲ«ҸKӮӘҠщӮЙӮұӮМҚ Ӯ©Ӯзүиҗ¶ӮҰҺnӮЯӮДӮўӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’Г–м“cҗҘҸd 1873-1930 ҢF–{”Л
‘жҺOҢRҺQ–dҒBҠOҢр“IӮЕүхҠҲӮИҗ«ҠiӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB–{ү№ӮрүBӮіӮё—Ұ’јӮЙ”ӯҢҫӮ·Ӯйҗ«ҠiӮЕӮ ӮиҒAӮЬӮҪ’ZӢCӮИ–КӮИӮЗӮ©ӮзӮөӮОӮөӮОҺьҲНӮЖӮМзaзҖӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҠу“TӮЙӮ©ӮнӮўӮӘӮзӮкҒAҢг”NӮа”T–ШӮЙӮВӮўӮДүщӮ©ӮөӮ»ӮӨӮЙҢкӮйҺ–ӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB ”T–ШӮЙ‘ОӮөӮДӮа•Ё•|Ӯ¶ӮөӮИӮўҢыӮМ—ҳӮ«•ыӮЕӮ ӮБӮҪҲЧҒAӮөӮОӮөӮОҺQ–d’·ӮМҲЙ’n’mҚKүоӮ©Ӯз’ҚҲУӮрҺуӮҜӮҪҒBӮ ӮйҺһӮИӮЗӮНҺQ–d“ҜҺmӮЕ—·ҸҮҚU—ӘӮЙӮВӮўӮДӢcҳ_ӮөӮДӮўӮҪҚЫҒAҢыӮрӢІӮсӮҫ”T–ШӮЙ‘ОӮөӮДҺvӮнӮёҒuҠtүәӮН–ЩӮБӮДӮўӮДӮӯӮҫӮіӮўҒvӮЖҢы‘–ӮиҒAӮұӮкӮрҢ©ӮҪҲЙ’n’mӮӘҢғҚVҒB’Г–м“cӮНҢRӢ@Ҳб”ҪӮЕҚ‘“аӮЙ‘—Ӯи•ФӮіӮкӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪҺ–ӮаӮ ӮйҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮД”T–ШӮНҸОӮўӮИӮӘӮзҒu‘ҠҺиӮрҢ©ӮД”ӯҢҫӮөӮИӮўӮЖҸ«—Ҳ‘№ӮрӮ·ӮйӮјҒvӮЖӮўӮБӮҪӮжӮӨӮИ“а—eӮЕ—@ӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҢг”NӮЙӮИӮйӮӘҒAӮұӮМҗ«ҠiӮӘҚРӮўӮөӮД’Г–м“cӮН—ӨҢRӮр’ЗӮнӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮй(ҸгҢҙ—EҚмӮЖӮМзaзҖӮӘҢҙҲцӮИӮЗӮЖҢҫӮнӮкӮй)ӮМӮҫӮӘҒAӮұӮұӮЙӢyӮсӮЕ”T–ШӮМҢҫ—tӮрҺvӮўҸoӮөҒuҚЎӮМҺ©•ӘӮМҗgӮрҢ©ӮкӮОӮ ӮМҺһӮМҠtүәӮМҢҫ—tӮӘҠҙҠS–і—КҒvӮЖӮМҸҠҢ©ӮрҳRӮзӮөӮДӮўӮйҒB “ъҳIҗн‘Ҳ’ҶӮЙӮЁӮўӮДӮНҠOҢр“IӮИҗ«ҠiӮ©ӮзӮ©ҸВҠO“IӮИ–рҠ„ӮаүКӮҪӮөӮДӮЁӮиҒA”ЮӮЖҗЪӮөӮҪүpҚ‘ҠПҗн•җҠҜӮМғnғ~ғӢғgғ“’ҶҸ«ӮИӮЗӮНҒu“ъ–{җlӮЙӮН’ҝӮөӮӯ–ҫҳNӮИҗВ”NҸ«ҚZҒvӮЖ•]ӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAӢtӮЙҢҫӮҰӮО“–ҺһӮМ“ъ–{җlӮМ’ҶӮЕӮа•ӮӮ«ӮвӮ·Ӯўҗ«ҠiӮЕӮ ӮБӮҪҸШӮЖҢҫӮБӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒBҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҠу“TӮНҒAҺ©җgӮа—cҸӯҺһӮжӮи•ӮӮўӮҪ‘¶ҚЭӮЕӮ ӮиҒAҸнӮЙҺьҲНӮЖ—nӮҜҚһӮЯӮёҒAҸҠ‘®Ӯ·ӮЧӮ«ҸW’cӮрӮВӮўӮЙҢ©ӮВӮҜҸoӮ·Һ–ӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBҚЎӮЕӮ ӮкӮОҒwҢВҗ«ҒxӮЖӮўӮӨҢҫ—tӮЕҸЬҺ^ӮіӮкӮй“ЖҺ©җ«ӮӘҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДӮНҒwҗ¶Ӯ«ӮГӮзӮіҒxӮМ‘еӮ«ӮИ—vҲцӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮМӮҫӮӘҒA‘§ҺqӮЩӮЗ”NӮМӮНӮИӮкӮҪ’Г–м“cӮМ’ҶӮЙӮаҒA”T–ШӮНҺ©ӮзӮЖ—ЮҺ—ӮөӮҪӢCҺҝӮрҢ©ҸoӮөӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB ‘жҺOҢRҺQ–d–{•”ӮМ’ҶӮЕӮаҺб”NӮЕӮ ӮБӮҪ’Г–м“cӮӘ–ҪӮ¶ӮзӮкӮҪ‘еӮ«ӮИ”C–ұӮЙҒA—·ҸҮҠЧ—ҺҢгӮМ“GҢRҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғҠӮЖӮМҢрҸВӮМ–рӮӘӮ ӮБӮҪҒB“GҢRҚ~•ҡҢгӮЙ“ъ–{‘ӨӮ©Ӯз‘—ӮзӮкӮҪҚЕҸүӮМҺgҺТӮЖӮўӮӨ—§ҸкӮҫӮӘҒAҚ~•ҡ’јҢгӮҫӮҜӮЙӮ»ӮкӮрҺуӮҜ“ьӮкӮИӮўҳIҢRӮМ•s–һ•ӘҺqӮЙӮжӮйҸPҢӮӮНҸнӮЙҠлңңӮіӮкӮйӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҸуӢөӮЙ‘ОӮөҒAҺQ–d’·ӮМҲЙ’n’mӮзӮНӢR•әҲкҢВ’Ҷ‘аӮрҢмүqӮЙӮВӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҒA’Г–м“cӮНҸn—¶ӮөӮҪҸгӮЕӮұӮкӮр’fӮБӮДӮўӮйҒB“GӮМҺc“}ӮН–сҲк–ңҒBӮұӮкӮзӮӘӮўӮБӮ№ӮўӮЙҢьӮ©ӮБӮДӮӯӮкӮОҲкҢВ’Ҷ‘аӮИӮЗҸҠ‘FӮН–і—НҒAӢMҸdӮИҗн—НӮӘ–і‘КӮЙӮИӮйӮЖӮМ”»’fӮЕӮ ӮйҒBҢӢӢЗӮҪӮБӮҪ2җlӮМ•”үәӮМӮЭӮрҳAӮкӮД—·ҸҮҺsҠXӮЙҸжӮиҚһӮЮҺ–ӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮМӮ ӮҪӮиӮМҠ„ӮиҗШӮиӮМ—ЗӮіӮН’Г–м“cӮМҺқӮВҢүӮіӮЕӮ ӮиҒA‘јӮМ“ъ–{җlӮжӮиӮа—DӮкӮДӮўӮҪ“_Ӯ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB —·ҸҮҺsҠXӮЙ“ьӮБӮҪ’Г–м“cӮНҒAҚKӮўҳIҢRҺc“}ӮМ”ҪҢӮӮЙүпӮӨҺ–ӮаӮИӮӯғXғeғbғZғҠӮМ“@‘оӮЙ“һ’…Ӯ·ӮйӮМӮҫӮӘҒAӮұӮұӮЕғXғeғbғZғҠ–{җlӮрҸўҺgӮЖҠФҲбӮҰӮҪӮиҒAғXғeғbғZғҠ•wҗlӮрүәҸ—ӮЖӮөӮДӮ ӮөӮзӮӨӮИӮЗҒA’Г–м“c“Б—LӮМ•sҺиҚЫӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒB”ЮӮНҢгӮМ•т“VүпҗнӮЙӮЁӮўӮДӮаҒAҗи—М‘OӮМ“Gҗw’nӮр“ъ–{ӮМҗw’nӮЖҠЁҲбӮўӮөӮДҗiҸoҒAҳIҢRӮЙ•пҲНӮіӮкӮДҺҖӮЙӮ©ӮҜӮйӮИӮЗҒAӮ©ӮИӮиҢy—ҰӮИ–КӮрҳI’жӮіӮ№ӮДӮўӮйҒBҲЙ’n’mӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺQ–dӮзӮМғGғҠҒ[ғg“IҺvҚlӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA’Г–м“cӮМӮұӮӨӮўӮБӮҪ“_ӮНҠхӮЮӮЧӮ«ӮаӮМӮ ӮБӮҪӮлӮӨӮөҒAҲк•ыӮЕӮұӮМҠлӮӨӮіӮр”T–ШӮНҲӨӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBӮИӮЁҒA’Г–м“cӮӘӮӨӮБӮ©ӮиҳIҢRӮЙ•пҲНӮіӮкӮҪҚЫҒA•”үәӮМҠЫҺRӮЖӮўӮӨ“`ӢRӮӘ“GӮМ•Я—ёӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮҫӮӘҒAҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЙӮжӮкӮОҒAҳIҢRӮЙҗq–вӮіӮкӮҪҚЫӮМҠЫҺRӮӘҒAҳ_•¶ӮМӮжӮӨӮИ—қҳHҗ®‘RӮЖӮөӮҪ“ҡ•ЩӮр“°ҒXӮЖ“WҠJӮөҒAғҚғVғA‘ӨӮрҒAӮРӮўӮДӮНғҲҒ[ғҚғbғpӮМ•әҠwүпӮрӢБӮ©Ӯ№ӮҪӮЖӮўӮӨҒBҸ«ҚZғNғүғXӮИӮзӮЬӮҫӮөӮаҒAӮҪӮ©ӮӘҲк•ә‘ІӮМӢі—{ӮМҚӮӮіӮӘүўҸBӮМҸнҺҜӮЖӮНӮ©ӮҜ—ЈӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ӮзӮөӮўҒB “ъҳIҗн‘ҲҸIҢӢҢгҒA’Г–м“cӮНҲкҺһ—ӨҢR‘еҠwӮЕӢіҠҜӮЖӮөӮДӢі•ЪӮрӮУӮйӮӨӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҺһӮМҗ¶“kӮМ’ҶӮЙҒAӮ©ӮМ“ҢһҠүpҺчӮӘӮўӮҪҒBҢг”NҒA“ҢһҠӮН’Г–м“cӮМ‘§ҺqӮМ’mҸdӮЙ‘ОӮөҒuүҙӮНӢіҠҜӮМ’ҶӮЕӮЁ‘OӮМҗe•ғӮіӮсӮӘҲк”ФҚDӮ«ӮҫӮБӮҪҒvӮЖҸqүщӮөӮҪӮӘҒA“ҢҸрӮӘ’Г–м“cӢіҠҜӮМӮЗӮМ•”•ӘӮЙҚDҠҙӮрҺқӮБӮҪӮМӮ©ӮЬӮЕӮНҢкӮзӮкӮДӮўӮИӮўҒBҸ®ҒA—Ө‘еӢіҠҜӮрҢoӮҪҢгҒA’Г–м“cӮНҸӯҸ«ӮЬӮЕҸёӮйӮМӮҫӮӘҒAӮ·Ӯ®ӮЙ—\”х–р“ьӮиӮр–ҪӮ¶ӮзӮкҒAҗжҸqӮМӮжӮӨӮЙӮұӮұӮЕҢRҗlӮЖӮөӮДӮМҗlҗ¶ӮрҸIӮҰӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒB ’Г–м“cӮМӮжӮӨӮИҗlҠФӮӘҢR‘аӮЙӮЖӮБӮД—LүvӮ©–іүvӮ©ӮН”»’fӮӘӮВӮҜ“пӮўҒBӮӘҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа“ъҳIҗнҸҹҲИҢгӮМ“ъ–{ҢRӮН’Г–м“cӮМӮжӮӨӮИ‘¶ҚЭӮр—e”FӮөӮИӮў‘Мҗ§ӮЦӮЖҲЪӮи•ПӮнӮБӮДӮўӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮНҚЕҸI“IӮЙ–\‘–ӮөӮДҚ‘үЖӮІӮЖүу–ЕӮ·ӮйҢR•”ӮӘҒAҸӯӮөӮёӮВҗ¬—§Ӯ·ӮйүЯ’цӮМҒAӮІӮӯҸүҠъӮМ’iҠKӮҫӮБӮҪӮМӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҲкҢЛ•әүq 1855-1931 ҚO‘O”Л
•а•ә‘ж6—·’c’·ҒBӮаӮөӮаҲкҢЛ•әүqӮӘҒAҺw—ЯӮр–іҺӢӮөӮД“Ж’fӮЕ“®Ӯӯҗl•ЁӮЕӮ ӮБӮҪӮИӮзҒA—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘҚмҗнӮМҚs•ыӮН‘еӮ«Ӯӯ•ПӮнӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB “ъҳIҗн‘ҲӮЕҚЕӮа‘е—КӮМӢ]җөҺТӮМҸoӮҪ—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘҚмҗнҒB’ҶӮЕӮа‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮМ”нҠQӮН‘Ҡ“–ӮЙ”ЯҺSӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB—vҚЗӮЙ”z”хӮіӮкӮҪҚЕҗVҺ®ӮМӢ@ҠЦ–CӮвҠфҸdӮЙӮа“hӮиҢЕӮЯӮзӮкӮҪӮЧғgғ“ӮНҸ]—ҲӮМҗнҸpӮЕӮН‘ҫ“Ғ‘ЕӮҝӮЕӮ«Ӯй—ЮӮМӮаӮМӮЕӮНӮИӮӯҒAӮұӮМҚU—ӘӮЙӮ ӮҪӮБӮҪ‘жҺOҢRӮНҗTҸdӮЙҺ–Ӯрү^ӮФ•K—vӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙҗж—§ӮВ“мҺRӮЙӮЁӮўӮДҒAүң•ЫиЭӮМ‘ж“сҢRӮӘҚU—ӘӮөӮҪ—vҚЗӮЕӮНҒAҸ]—ҲӮМҸнҺҜӮ©Ӯз—\‘zӮіӮкӮҪҺҖҸқҺТӮрҲкҢ…ҸгүсӮйӢ]җөӮӘҸoӮД‘е–{үcӮрӢБңұӮіӮ№ӮҪӮӘҒA“мҺRӮрӮіӮзӮЙҸгүсӮйӢK–НӮМ—·ҸҮ—vҚЗӮНӢҘҲ«Ӯ»ӮМӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB ӮұӮМҚU–hӮЙӮЁӮўӮДҒA”T–ШҢRҺi—Я•”ӮӘүәӮөӮҪ‘I‘рӮНҸ]—ҲӮЗӮЁӮиӮМҗі–К“Л”jҒBӢ@ҠЦҸeӮМҺЛ’цӮӘҠфҸdӮЙӮаҸdӮИӮйҚЕӮаҢөӮөӮўғӢҒ[ғgӮЙҗ^җі–КӮ©ӮзҠЫҚҳ“Ҝ‘RӮЕ‘е—КӮМҸ«•әӮр‘—ӮиҚһӮЮҺ–ӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB2–ңӮр’ҙӮҰӮйӮЖӮіӮкӮй—·ҸҮҚU—ӘҚмҗнӮМӢ]җөӮМ‘е”јӮНҒAӮұӮМ‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮМҺһӮМӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA–іҲЧӮЙ‘е—КӮМҸ«•әӮрҺҖӮЙ’ЗӮўӮвӮБӮҪ”T–ШҠу“TӮзӮМ–і”\ӮрҗУӮЯӮйҗәӮН“БӮЙҢгҗўӮЙӮЁӮўӮДҸӯӮИӮӯӮИӮўҒB Ҳк•ыӮЕҲЩҳ_ӮаӮ ӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҚU—ӘӮЙӮНҗі–К“Л”jҲИҠOӮЙӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҲУҢ©ӮҫҒB—·ҸҮҚU—ӘҗнҲИҚ~ӮаҗўҠE’ҶӮЕ—vҚЗҚU—ӘҗнӮӘҚsӮнӮкӮҪӮӘҒAҠо–{“IӮЙӮНҗі–КӮ©ӮзҚUӮЯӮй•Ё—КҚмҗнӮӘҗі“қӮЕӮ ӮиҒAҗS—қ“IҒA•ЁҺҝ“IӮЙҺз”х‘ӨӮр’ЗӮўӢlӮЯӮДӮўӮӯӮЖӮўӮӨӮаӮМҒBҺ–ҺАҒA“–Ҹү“ъ–{ҢRӮҫӮҜӮӘ–і‘КҺҖӮЙӮөӮҪӮЖҺvӮнӮкӮҪҚU—ӘҚмҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAғҚғVғA‘ӨӮМҺуӮҜӮҪҸdҲіӮНҢӢҚ\ӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBҢгӮМ203ҚӮ’nҚU—ӘӮЙӮЁӮўӮДҒAҗ”ғ–ҢҺ‘ұӮӯҚU–hӮМ”жҳJӮӘғҚғVғAҢRӮЙ’~җПӮіӮкӮҪҺ–ӮЕӮжӮӨӮвӮӯҗ¬ҢчӮЙҺҠӮБӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ҺАӮӘӮ ӮйҒB ҢӢүК“IӮЙӮНҺё”sӮЕӮ ӮиҒAӢрҚмӮЖӮіӮкӮй—·ҸҮ—vҚЗ‘ҚҚUҢӮӮҫӮӘҒAҺАӮН‘жҲкүсҚUҢӮӮМҺһҒAҲкҢЛ•әүqӮМҺwҠцӮ·Ӯй‘жҳZ—·’cӮМҲк•”ӮӘ—·ҸҮҺsҠXӮрҢ©үәӮлӮ№Ӯй–]‘дӮЬӮЕ“һ’BҒAҗӢӮЙӮНӮұӮұӮМҳIҢRҗw’nӮрҚU—ӘӮө“ҫӮйӮЬӮЕӮЙ”—ӮБӮДӮўӮҪҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕҺҖҸқҺТҗ”ӮӘ‘Ҡ“–ӮИҗ”ӮЙ–cӮзӮсӮЕӮўӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮ»ӮМҗ¬үКӮЖӮөӮДҒAҲкҢЛ•әүqӮзӮМ•”‘аӮМ–фҗiӮӘҺАҢ»ӮөӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBӮөӮ©Ӯа—FҢRӮЕӮ Ӯй‘жҸ\ҲкҺt’cӮаӮ·Ӯ®ӢЯӮӯӮЬӮЕ‘OҗiӮөӮДӮ«ӮДӮўӮйҒBҲкҢЛӮН‘МҗЁӮӘҗ®ӮўҺҹ‘жҒA—ј—·’cӮЙӮжӮйҲкҗДҚUҢӮӮЙ“ҘӮЭҗШӮй• җПӮаӮиӮҫӮБӮҪӮӘҒAӮұӮұӮЙ—ҲӮД”T–ШҢRҺi—Я•”ӮжӮи“P‘Ю–Ҫ—ЯӮӘ’К’BӮіӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒB ҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮМ’ҳҺТҒAҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮЙӮжӮкӮОҒAҲкҢЛӮНҒuӮўӮЬӮЙӮөӮДҚUҢӮӮр’ҶҺ~Ӯ·ӮкӮОӮұӮкӮҫӮҜӮМҺҖҸқӮрӮҫӮөӮҪӮұӮЖӮӘӮ·ӮЧӮДӮЮӮҫӮЙӮИӮйҒB–]‘дӮНӮЖӮкӮйҒBӮнӮӘ—·’c“Ж—НӮрӮаӮБӮДӮаҚUҢӮӮр‘ұҚsӮөӮҪӮўҒvӮЖ”Я’ЙӮИҲУҢ©Ӣпҗ\ӮрӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAҗӢӮЙӮНҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮёҒA“P‘ЮӮЙҠГӮсӮ¶ӮйҺ–ӮЙҒBӮұӮұӮЕ“`—Яғ~ғXӮИӮЗӮрӢU‘•Ӯ·ӮйӮИӮЗӮөӮДҚUҢӮӮрӢӯҚsӮЕӮ«ӮДӮўӮкӮОҒA—·ҸҮӮНӮ ӮҰӮИӮӯҠЧ—ҺӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮӘҒAҚKӮ©•sҚKӮ©ҲкҢЛӮНҚЧҚHӮрҳMӮ·ӮйҚфҺmӮМ—ЮӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB Ҳк•ыӮМ”T–ШҢRҺi—Я•”ӮҫӮӘҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮаӮұӮМҺһ“_ӮЕӮНҗнӢөҸ¶Ҳ¬”\—НӮЙҢҮҠЧӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮӨӮөӮ©ӮИӮўҒB”T–ШҠу“TӮЁӮжӮСӮ»ӮМҺi—Я•”ӮӘҗУӮЯӮзӮкӮйӮЖӮ·ӮкӮОҒAҚмҗнӮ»ӮМӮаӮМӮМ“а—eӮЕӮНӮИӮӯҒAӮЬӮіӮЙӮұӮМҺһӮМҸуӢөҸ¶Ҳ¬ӮМҠГӮіӮЙӮ ӮйҒBӮаӮҝӮлӮс”T–ШҢRҺi—Я•”Ӯ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAҺҹҒXӮЖӮ ӮӘӮБӮДӮӯӮйҒwӮ ӮиӮҰӮИӮўҗ”ҺҡҒxӮЙ‘Ҡ“–ӮЙҠМӮӘӮВӮФӮіӮкӮҪӮНӮёӮЕӮ ӮиҒAҢгӮ©Ӯз’fҚЯӮ·ӮйӮМӮН•sҸр—қӮЖҢҫӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮаӮөӮа”T–ШӮӘ‘@ҚЧӮИҠҙҗ«ӮрҺқӮҪӮИӮў–іҚңҠҝӮЕӮ ӮБӮҪӮИӮзҒAӮаӮөӮаҲЙ’n’mӮзӮМҺQ–dӮӘҒwҸнҺҜӮр”хӮҰӮҪғGғҠҒ[ғgӢCҺҝҒxӮЕӮИӮҜӮкӮОҒAӮ ӮйӮўӮНӮіӮзӮЙҚUӮЯҚһӮЬӮ№ӮДҚU—ӘҗнӮМҢӢүКӮр•ПӮҰӮДӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮӘҒA”T–ШӮаҲЙ’n’mӮаҒAӮіӮзӮЙӮНҚмҗнӮр—§ҲДӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҺQ–d•ӣ’·ӮМ‘е’л“сҳYӮа—ЗҺҜӮЙҠоӮГӮўӮҪ”»’fӮрүәӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB җнҢгҒAҲкҢЛӮНҗнҺһӮМҠҲ–фӮ©ӮзҢВҗlҠҙҸуӮрҺуӮҜӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮМ‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮМ“ӯӮ«ӮӘ•]үҝӮіӮкӮҪӮЖҚlӮҰӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB‘Ю–рҢгӮНӮ©ӮВӮД”T–ШҠу“TӮа–ұӮЯӮҪҠwҸKү@ӮМү@’·җEӮЙҸAӮ«ҒAҚc‘°ӮзӮМҺt’нӮМӢіҲзӮЙӮ ӮҪӮБӮҪҒBҲкҢЛӮНҺб”NҺһҒA—ӨҢR•әҠw—ҫӮЙ“ьҠwӮ·ӮйҲЧӮЙ–{ҸBҚЕ–kӮМҚO‘OӮ©Ӯз“ҢӢһӮЬӮЕ“k•аӮЕҸгӢһӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮНӮйӮОӮйү“ҳHӮМ—·ҳHӮМүКӮДҒAғtғ^ӮрҠJӮҜӮкӮОҺҺҢұҠҜӮМҺҝ–вӮЙӮНүҪҲкӮВ“ҡӮҰӮзӮкӮИӮўҒBӮ Ӯ«ӮкӮҪҺҺҢұҠҜӮӘҒuӮЁ‘OӮНүҪӮрӮөӮЙӮ«ӮҪӮМӮҫҒvӮЖҺ¶җУӮ·ӮйӮаҒAҲкҢЛӮНӮРӮйӮЬӮёҒuҗl•ЁӮрҢ©ӮД—~ӮөӮўҒvӮЖҺе’ЈҒBҒuӮИӮзӮОҚDӮ«ӮИҠҝҺҚӮр“ЗӮсӮЕӮЭӮлҒvӮЖүһӮ¶ӮҪҺҺҢұҠҜӮЙ‘ОӮөҒAҺ©ҚмӮМҠҝҺҚӮр”вҳIҒBӮ»ӮМҸкӮЕҚҮҠiҲөӮўӮЙӮИӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйӮЩӮЗӮМҗl•ЁӮҫӮБӮҪҒB—·ҸҮӮЕӮМҢч–јӮН—EҠёӮИ‘sҺmӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйӮӘҒAҢі—ҲӮМ•ЧӢӯүЖӮЕӮ Ӯиҗ¶ҠUҸ‘•ЁӮр’К“ЗӮө‘ұӮҜӮҪҒBӢіҲзҺТӮЖӮөӮДҢ}ӮҰӮҪ”У”NӮНҗl•АӮЭҲИҸгӮЙҚK•ҹӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮлӮӨӮ©ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’Ҷ‘әҠo 1854-1925 •FҚӘ”Л
—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘҗнӮЙӮЁӮҜӮй”’жF(ӮҪӮ·Ӯ«)‘аӮМҺwҠцҠҜҒB ”’жF‘аӮЖӮНҒA‘жҺOүсҲкҗДҚUҢӮӮЙӮЁӮҜӮйҠпҸP•”‘аӮЕӮ ӮйҒB‘жҲкүсӮМҲкҗДҚUҢӮӮЕӮ Ӯи“ҫӮИӮўӢ]җөӮрҸoӮөӮДҢгҒA”T–ШҢRҺi—Я•”ӮНҚмҗнӮрҸCҗіҒAүВ”\ӮИҢАӮиҚҲӮрҢ@ӮиҗiӮЯӮйҺ–ӮЕ‘ж“сүсҲкҗДҚUҢӮӮМӢ]җөҺТҗ”Ӯр‘е•қӮЙҢёӮзӮөӮДӮўӮйҒBӮӘҒA—vҚЗӮўӮЬӮҫҠЧ—ҺӮ№ӮёҒB“~ӮӘ–Ъ‘OӮЖӮИӮБӮҪ11ҢҺҒA‘жҺOүс–ЪӮМҚUҢӮӮЙҺҠӮБӮДҺi—Я•”ӮНӮаӮНӮвҺиӢlӮЬӮиӮМҠҙӮаӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМҢӢүКӮЖӮөӮДҒA3100җlӮЙӮжӮй‘еҠ|Ӯ©ӮиӮИҠпҸPҚмҗнӮӘ—§ҲДӮіӮкҒAӮұӮкӮӘҺАҚsӮЙҲЪӮіӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮМ•”‘аӮН–йҸPӮр”C–ұӮЖӮөӮДӮўӮҪҲЧҒAӮЁҢЭӮўӮМҺҜ•КӮМҲЧӮЙ”’жFӮрӮВӮҜӮДӮўӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAҢӢүКӮЖӮөӮДӮұӮкӮӘҺҖӮЙ‘•‘©ӮЖӮИӮиҒAҠҙҸо“IӮЙҚмҗнӮМ–і–dӮіӮрҲшӮ«—§ӮДӮйҲкҲцӮЖӮаӮИӮБӮДӮўӮйҒB ҢR“а•”ӮМҸг—¬ӮЙҲК’uӮөӮҪ’Ҷ‘әӮЖӮөӮДӮНҒAӮұӮМҚмҗнӮМҲУҗ}ӮӘҒAӮ·ӮИӮнӮҝ”јӮОӮвӮҜӮБӮПӮҝӮМӢӯҚs“Л”jӮЙӮ ӮйҺ–ӮрҺ@ӮөӮДӮўӮҪӮЖҺvӮнӮкӮйҒBҚмҗнӮЙҗж—§ӮҝҒu‘еҗЁӮМ•әҺmӮӘҺҖӮсӮЕӮўӮйҒBӮ»ӮлӮ»ӮлҸгӮМҺТӮӘҺҖӮИӮИӮўӮЖҗ\Ӯө–уӮӘ—§ӮҪӮИӮўӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒvӮЖӮМ‘дҺҢӮӘҺcӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӮұӮМ•”‘аӮМҲУӢ`ӮӘҚU—ӘӮжӮиӮа•җҺm“№җёҗ_“IӮИӮаӮМӮЙ’uӮ©ӮкӮДӮўӮҪҢ»ҺАӮрӮЩӮМӮЯӮ©ӮөӮДӮўӮйҒB ‘жҺOүсҲкҗДҚUҢӮӮӘҠJҺnӮіӮкӮҪӮМӮН11ҢҺ26“ъӮМҢЯ‘O8ҺһҒB”’жF‘аӮНӮ»ӮМ“ъӮӘ•йӮкӮҪ20ҺһӮ©ӮзӮМҺn“®ӮЕӮ ӮйҒB’Ҷ‘әӮз‘жҺOҢRӮМ•әҺmӮӘ—Й“Ң”ј“ҮӮЙҸг—ӨӮөҒA‘е—ӨӮМ”M”gӮЙӮЬӮЭӮкӮҪҚ Ӯ©ӮзӮНҠщӮЙҗ”ғ–ҢҺӮӘҢoүЯӮөӮДӮўӮҪҒBҸг—ӨҠФӮаӮИӮў’iҠKӮЕүң•ЫиЭӮМ‘ж“сҢRӮӘ“мҺRӮрҚU—ӘҒAүБҗЁӮөӮҪ‘жҺOҢRӮМҲк•”ӮЙ’Ҷ‘әҠoӮаҠЬӮЬӮкӮДӮўӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮ»ӮұӮЕӮЁӮСӮҪӮҫӮөӮўҗ”ӮМҺҖҸқҺТӮрҺnӮЯӮД–ЪӮМ“–ӮҪӮиӮЙӮөҒA‘жҺOҢRӮМҸ«•әӮзӮНӮ»ӮМҗҰҺSӮіӮЙ“xҠМӮр”ІӮ©ӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒBҲИҚ~ҒA“Г“ӘҺRӮвҢ•ҺRҒAӮіӮзӮЙӮН“мҺRӮЙ•C“GӮ·ӮйӮМ‘е—КӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪ‘ҫ”’ҺRҒAӮ»ӮөӮД‘жҲкүсҒA‘ж“сүсӮМҲкҗДҚUҢӮӮрҢoӮҪ”T–ШҢR•әҺmӮзӢк”YӮМ––ӮЙҒA”’жF‘аӮӘӢ@ҠЦ–CӮЙ–Е‘Ҫ‘ЕӮҝӮЙӮіӮкӮйҢӢ––ӮӘ—pҲУӮіӮкӮҪҺ–ӮЙӮИӮйҒB ҠпҸPӮМ–Ҫү^Ӯр•ӘӮҜӮҪӮМӮНҲк”ӯӮМ’n—ӢӮҫҒBҲЕ–йӮЕаy—фӮөӮҪ’n—ӢӮН”’жF‘аӮМҲК’uӮрҳIҢRӮЙ’mӮзӮөӮЯҒA’TҸЖ“”ӮМҢхӮӘҲкҗДӮЙҸWӮЬӮйҒBҢ©ӮкӮО”’ӮўжFӮӘӮжӮӯ”ҪҺЛӮөӮДҠiҚDӮМ“IӮЙӮИӮБӮДӮўӮйӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒBӮұӮұӮЙҳIҢRӮӘҢЦӮйӢ@ҠЦ–CӮӘҲкҗДӮЙүОӮр•¬ӮӯҺSҺ–“һ—ҲӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҲк•ӘҠФӮЕӮЁӮжӮ»600”ӯӮаӮМҸe’eӮр”ӯӮ·Ӯй‘г•ЁӮЕҒAҲк•bӮЙҠ·ҺZӮ·ӮкӮОҺАӮЙ10”ӯҒBҲк“xҗҘӮрҗHӮзӮӨӮЖ“ҜӮ¶ҸкҸҠӮЙ2”ӯҒA3”ӯӮЖ”н’eӮ·ӮйҲЧҒAҸқҢыӮӘҲкӢCӮЙҚLӮӘӮиҒA‘ҰҚАӮЙ’v–ҪҸқӮЙӮИӮйҒB’ҶӮЙӮН60”ӯҒA70”ӯӮЖӮӯӮзӮБӮҪҲв‘МӮаӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкҒAҢ»ҸкӮМҗҰҺSӮіӮН—eҲХӮЙ‘z‘ңӮө“пӮўӮаӮМӮӘӮ ӮйҒBҢRҲгӮЙӮжӮБӮДҒw‘Sҗg–I‘ғҸe‘nҒxӮЖӮўӮӨҗVӮөӮўҒwҺҖҲцҒxӮӘ–Ҫ–јӮіӮкӮҪӮЩӮЗӮҫҒB ӮұӮМ•¶Һҡ’КӮиҺEҗl“IӮИӢ@ҠЦ–CҺЛҢӮӮрҸW’Ҷ“IӮЙҺуӮҜҒA3000җlӮр’ҙӮҰӮй‘аӮНҗ”ҸuӮМҢгӮЙүу–ЕҒBҢҲҺҖӮЕ—ХӮсӮҫ’Ҷ‘әҠoҺ©җgӮНӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮДҲк–ҪӮрӮЖӮиӮЖӮЯӮйӮаҒAҸdҸЗӮЙӮжӮиӮ»ӮМӮЬӮЬ–{Қ‘ӮЦ‘—ҠТӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҚмҗнҠJҺnӮЙҗж—§ӮҝҒA’Ҷ‘әӮНҺ©•ӘӮӘҗнҺҖӮөӮҪҢгӮМҺwҠцҢn“қӮМӮ Ӯи•ыӮр•”үәӮЙ’сҺҰӮөҒAӮіӮзӮЙӮНҢгӮлӮЙүәӮӘӮйҺТӮрҺaӮкҒAӮЖӮЬӮЕ–ҪӮ¶ӮДӮўӮйӮЩӮЗӮЕҒAҗ¶Ӯ«ӮДӢAӮйҲУҺvӮН–С“Ә–іӮ©ӮБӮҪӮНӮёӮЕӮ ӮйҒB‘аӮӘ‘S–ЕӮөӮДҢгҒA–{Қ‘ӮЕ—Г—{Ӯр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪ’Ҷ‘әӮМҗёҗ_ӮМҗҰҺSӮіӮНҺ@ӮөӮД—]ӮиӮ ӮйҒB ‘жҺOҢRӮМҸ«•әӮзӮЙӮЖӮБӮД”’жF‘аӮМүу–ЕӮНӮвӮНӮиҸЫ’Ҙ“IӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮӯҒA”ЮӮзӮМ—Һ’_ӮН‘Ҡ“–ӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮЙӮаҠЦӮнӮзӮё’Ҷ‘әӮНӮұӮМҺһӮМҗнӮўӮФӮиӮр•]үҝӮіӮкҒAҚЕҸI“IӮЙ—ӨҢR‘еҸ«ӮЙӮЬӮЕҸёӮиӢlӮЯӮДӮўӮйҒBҢӢүКӮНӮЗӮӨӮ Ӯк’Ҷ‘әӮМҺwҠц“қ—ҰӮвҠё“¬ӮФӮиӮӘ•]үҝӮіӮкӮҪӮаӮМӮҫӮлӮӨӮӘҒAҲк•ыӮЕҒA—·ҸҮҚU—ӘӮЖ”T–ШҠу“TӮр“ъҳIҗнҸҹӮМғVғ“ғ{ғӢӮЙҚХӮиҸгӮ°ӮҪ“ъ–{ҢR•”ӮМҺ–ҸоӮЖӮөӮДҒA’Ҷ‘әӮМ‘¶ҚЭӮН“sҚҮӮӘ—ЗӮ©ӮБӮҪӮЖҢ©ӮйҺ–ӮаӮЕӮ«ӮйҒB ӮЁӮ»ӮзӮӯ“ъҳIҗнҢгӮМҺһ“_ӮЕӮНҒA“ъ–{ҢR•”ӮНҸғҗҲӮЙҸҹӮҝҗнӮрҠмӮСҒAӮ»ӮМҢчҳJҺТӮЖӮөӮД’Ҷ‘әӮв”T–ШҒAӮіӮзӮЙӮНҠфҗlӮ©ӮМҢRҗ_ӮрҚХӮиҸгӮ°ӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBӮӘҒAҢӢүК“IӮЙӮНҢгӮЙӮұӮкӮзӮӘ”ьү»ӮіӮкҒA‘ёӮФӮЧӮ«‘O—бӮЖӮөӮДӢіүИҸ‘ӮИӮЗӮЙҢfҚЪӮіӮкӮйӮЙҺҠӮйҒBӮ»ӮМҢг100”NӮрҢoӮДҒAүдҒXӮМҗў‘гӮМҠҙҠoӮЕ”»’fӮ·ӮкӮОҒAҺҖӮрҺ^”ьӮ·ӮйҲ«ӮөӮ«‘O—бӮЖҢҫӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮйӮЬӮЕӮЙ•ПҺҝӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҺlҢR | |
|
ҒЎ–м’Г“№ҠС 1841-1908 ҺF–Җ”Л
‘жҺlҢRҺi—ЯҠҜҒBҗнҗьӮМ’Ҷүӣ•”•ӘӮр’S“–ӮөӮҪҒB ‘жҲкҢRӮМҚ•–ШҲЧъй“Ҝ—lӮМ–ТҸ«ғ^ғCғvӮЕӮ ӮиҒAҸoҗgӮвҗн—рҒAӢCҺҝӮИӮЗӮаӢЯӮўҲЧӮ©ҒA‘o•ыӢӨӮЙғүғCғoғӢҺӢӮөӮДӮўӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB“ъҳIҠJҗнӮЙҗж—§ӮҝҒAҠCҢR‘еҗbӮМҺR–{Ң •әүqӮӘ‘еҺRҠЮӮЙ‘ОӮөҒu“қҗғӮМ’Ҷҗ•ӮЙҺQүжӮ·ӮЧӮӯҚ‘“а‘е–{үcӮЙҺcӮБӮҪ•ыӮӘ—ЗӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒHҒvӮЖ–вӮўӮ©ӮҜӮҪӮЖӮұӮлҒA‘еҺRӮНҒuҗн‘ҲӮЙӮВӮўӮДӮНҺ©•ӘӮжӮиӮа–м’ГӮзӮМ•ыӮӘҸгҺиӮЕӮ ӮйҒvӮЖ“ҡӮҰӮДӮўӮйҒBӮіӮзӮЙҒu”ЮӮзӮНҸoҗжӮЕҢЭӮўӮЙӢӯҸоӮр’ЈӮиҒAҲУҢ©ӮӘҲк’vӮөӮИӮўҺ–ӮӘ‘ҪӮўӮҫӮлӮӨҒvӮЖ‘ұӮ«ҒAҒuӮ»ӮМҺһӮЙҲУҢ©ӮрӮЬӮЖӮЯӮйӮМӮӘҺ„ӮМ”C–ұҒvӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮйҒBӮұӮұӮЕҢҫӮӨҒg–м’ГӮзҒhӮЖӮўӮӨӮМӮӘ–м’Г“№ҠСӮЖҚ•–ШҲЧъйӮЕӮ ӮйӮМӮН‘z‘ңӮЙ“пӮӯӮИӮўҒB Ӯ»ӮсӮИ–м’ГӮҫӮӘҒA‘жҲкҢRӮМҚ•–ШҲЧъйӮӘ—ОҠӣҚ]“nүНӮМҚмҗнӮр’S“–Ӯ·ӮйҺ–ӮӘҢҲ’иӮөӮҪҚЫҒAҺ©ӮзҚ•–ШҺi—Я•”ӮрҗqӮЛҒAҺ©•ӘӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲҺһӮЙҺgӮБӮДӮўӮҪҠӣ—ОҚ]Һь•УӮМ’nҗ}Ӯр“ЎҲдҺQ–d’·ӮЙҺи“nӮөӮДӮўӮй(Қ•–ШӮН•sҚЭӮҫӮБӮҪҲЧ)ҒBӮЬӮҪҒAҚ№үНүпҗнӮЙӮЁӮўӮДӮНҸӯҗlҗ”ҒEҢy‘•ӮӘ“S‘ҘӮЖӮіӮкӮй–йҸPӮрҒA–м’ГҢR‘SҢR(2ҢВҺt’c/–с3–ңҗl)ӮЕӢӯҚsӮ·ӮйҚrӢЖӮрҢ©Һ–җ¬ҢчӮіӮ№ҒAғҚғVғAҢRӮН’Ч‘–ӮЙҺҠӮйҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҢ^”jӮиӮМ–йҸPӮМ‘O—бӮЖҢҫӮҰӮОҒAҗ”ғ–ҢҺ‘OӮМҚ•–ШҢRӮМғPҒ[ғXӮҪӮҫҲк—бӮМӮЭӮЕӮ ӮиҒAӮұӮұӮЙӮа—јҺТӮМӢCҺҝӮМ—ЮҺ—җ«ӮӘҺfӮнӮкӮйҒBӮұӮМҺһӮМ–м’ГӮМҗSӮЬӮЕӮНӢLҳ^ӮЙҺcӮБӮДӮўӮИӮўӮӘҒA–йҸPҢҲҚsӮЙӮ ӮҪӮБӮДҚ•–ШӮЙ‘ОӮ·ӮйӢӯ—уӮИ‘ОҚRҗSӮЖғҠғXғyғNғgӮӘ‘еӮўӮЙ‘¶ҚЭӮөӮҪӮЖҚlӮҰӮйӮМӮа–К”’ӮўӮҫӮлӮӨҒB ӮЖӮаӮ ӮкҒAҺбӮўӮұӮлӮ©Ӯз—E–ТӮ·Ӯ¬ӮД–\‘–ӮЖ—ЧӮиҚҮӮнӮ№ӮҫӮБӮҪ–КӮН”ЫӮЯӮёҒA”ЮӮрӮўӮ©ӮЙҗ§ҢдӮ·ӮйӮ©ӮӘҺQ–dӮзӮМҸd—vӮИ–р–ЪӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBӮұӮұӮЕҚKү^ӮҫӮБӮҪӮМӮНҒAҺQ–d’·ӮЙӢЙӮЯӮДҗTҸdӮИҗ«ҠiӮМҸгҢҙ—EҚмӮӘҸAӮўӮҪҺ–ӮҫҒB”ЮӮН–м’ГӮМ–ә–№ӮЖӮўӮӨҺ–ӮаӮ ӮиҒA–м’ГӮрҗ§Һ~ӮЕӮ«ӮйӮаӮБӮЖӮа“IҠmӮИҗlҚЮӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBҢӢүКӮЖӮөӮД•т“VүпҗнӮМҺһ“_ӮЕҚЕӮаҗн—НӮрү·‘¶ӮөӮДӮўӮҪӮМӮН–м’ГҢRӮЕӮ ӮиҒA(“ъ–{ҢRӮЙӮЖӮБӮДӮМ)ҚЕҸIҢҲҗнӮЙӮЁӮўӮДҚ•–ШҢRӮЙ‘гӮнӮБӮДӮМҺе—НӮЖӮИӮБӮҪҒB–м’ГӮНӮ»ӮкӮЬӮЕӮМғNғҚғpғgғLғ“ӮМ“P‘ЮҗнҸpӮрҒwҢ©Һ–ӮИҗнҸpҒxӮЖӮөӮДҸМӮҰҒAҢҲӮөӮДҗ[’ЗӮўӮіӮ№ӮйҺ–ӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМ—вҗГӮИ”»’fӮНҸгҢҙҺQ–d’·ӮЖӮМ—ЗҚDӮИҠЦҢWӮЖӮа–іүҸӮЕӮНӮИӮўӮЖҺvӮнӮкӮйҒB Ӯ»ӮМғNғҚғpғgғLғ“ӮМҚXӮИӮй“P‘ЮҗнҸpӮЙӮжӮБӮДҒA“ъ–{ҢRӮНҗhӮӨӮ¶ӮД•т“VүпҗнӮЙҸҹ—ҳҒB‘ұӮӯ“ъ–{ҠCҠCҗнӮМҲіҸҹӮЙӮжӮБӮДҒwҸҹӮҝ“ҰӮ°ҒxӮМҚ\җ}ӮЕҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮЮҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮ·ӮйӮМӮҫӮӘҒA“GҸ«ӮЕӮ ӮБӮҪғNғҚғpғgғLғ“ӮӘ”sҗнӮМҗУ”CӮрҺжӮБӮДҢR–@үпӢcӮЙӮ©ӮҜӮзӮкӮйҺ–Ӯр•·ӮўӮҪ–м’ГӮНҒuӮ»ӮаӮ»ӮаҠtүәӮНҠJҗнӮЙ”Ҫ‘ОӮҫӮБӮҪӮЖ•·ӮӯҒBӮ»ӮкӮЕӮа–һҸBӮЕҺwҠцӮрҺжӮБӮД—§”hӮЙҗнӮБӮҪӮМӮЙ•үӮҜӮҪӮ©ӮзӮЖҢҫӮБӮДҸҲ”ұӮіӮкӮйӮМӮНӮ ӮЬӮиӮЙӮаӢCӮМ“ЕҒvӮЖҒAӮ»ӮМ—қ•sҗsӮіӮЙ•®ҠSӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮұӮкӮН“GҸ«ӮЦӮМҲШҢhӮМ”OӮМ•\ӮкӮЖӮаҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨӮӘҒAҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮӘҺw“EӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҒA“ъҳIҗн‘ҲӮНҒwҗн‘ҲӮМ’ҶӮЙӮЬӮҫӢRҺm“№(үдӮӘҚ‘ӮЕӮН•җҺm“№)җёҗ_ӮӘүоҚЭӮөӮДӮўӮҪҚЕҢгӮМғPҒ[ғXҒxӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸHҺRҚDҢГ 1859-1930 ҸјҺR”Л
“ъ–{ӢR•әӮМ•ғӮЖҢДӮОӮкӮйҒB “ъ–{җl—ЈӮкӮөӮҪ•—–eӮЕ“ӘӮаӮжӮӯҒA“–ҺһӮЖӮөӮДӮН’·җgӮЕ•wҗlӮ©ӮзӮМҗlӢCӮаҢъӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBҚ]ҢЛҠъӮМҺҝҺАҚ„Ң’ӮИ•җҺmӮМҗ¶Ӯ«•ыӮрҗF”ZӮӯҺcӮөӮДӮЁӮиҒAҗҙ•nӮр—ЗӮөӮЖӮ·ӮйҲк•ыӮЕ•АҠOӮкӮҪҺрҚӢӮЖӮөӮДӮМҲк–КӮаӮ ӮБӮҪҒB ӢR•әӮЖӮН•¶Һҡ’КӮиӢRҸжӮөӮҪ•ә‘аӮҫӮӘҒAӮұӮкӮНҺҳҺһ‘гӮМӢR”nӮЖӮН‘SӮӯ•КӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӢR”nӮНҒA’PӮЙ•җҺmӮӘ”nӮЙҸжӮБӮДҢВҗlӢZӮЕ“GӮЙҗШӮиҚһӮЮӮаӮМӮЕӮ ӮйӮМӮЙ‘ОӮөҒAӢR•әӮНҚх“GӮвҠпҸPӮрҺе”C–ұӮЖӮөӮҪӮаӮМҒBӮжӮБӮДӮұӮМҠT”OӮМ‘¶ҚЭӮөӮИӮ©ӮБӮҪ–ҫҺЎҸү“ӘӮЙӮЁӮўӮДӮНӢR•ә‘аӮЙӮ©ӮҜӮзӮкӮйҠъ‘ТӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМ—¬ӮкӮр•ПӮҰӮҪӮМӮӘҒAғtғүғ“ғX—ҜҠwҒEғҚғVғA’“ҚЭӮЕӢR•әӮрҠwӮсӮҫҸHҺRҚDҢГӮЕӮ ӮиҒAҸг‘w•”ӮЙӢR•әӮМҸd—vҗ«ӮрҗаӮӯӮЖӮЖӮаӮЙҒAғtғүғ“ғXҺ®ӮМҸж”nӮрҺжӮи“ьӮкӮйҺ–ӮЙ’Қ—НӮөӮҪҒB“–ҺһӮМ—ӨҢRҚӮҠҜӮМ‘ҪӮӯӮӘғhғCғcӮ©ӮФӮк(ҢRҺtғҒғbғPғӢӮМүeӢҝ)ӮҫӮБӮҪҺ–ӮрҚlӮҰӮкӮОӮұӮкӮН‘Ҡ“–•—“–ӮҪӮиӮМӢӯӮўҚrҚsӮҫӮБӮҪӮНӮёӮЕӮ ӮиҒAҢгӮМ“ъ–{ӢR•әӮНҺАҺҝҸHҺRҲкҗlӮЙӮжӮБӮДҲзҗ¬ӮіӮкӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮаӮўӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB ’·ҠъӮМғҚғVғA‘ШҚЭҢoҢұӮ©Ӯз‘ОҳIҺ–ҸоӮЙҸЪӮөӮ©ӮБӮҪҸHҺRӮНҒAӮ©ӮМҚ‘ӮӘүј‘z“GҚ‘ӮЖӮөӮД•ӮҸгӮөӮҪ’iҠKӮЕҒwғRғTғbғNӢR•әӮЖӮМҗ퓬Ӯр‘z’иӮөӮҪӢR•әҲзҗ¬ҒxӮЙ’…ҺиӮөӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮ©Ӯз“ъҳIҗн‘ҲӮЬӮЕӮМ10”NҠФӮЕ“ъ–{ӢR•әӮМҺҝӮН‘еӮ«ӮӯҢьҸгӮөӮҪӮӘҒA”n‘МӮМҺҝӮв‘•”хҒA•әӮМ‘wӮМҢъӮіӮЕӮНғҚғVғA‘ӨӮЙ•ӘӮӘӮ ӮйҒBҠJҗнӮЙҗж—§ӮҝҒAҸHҺRӮӘӢR•әӮМҸdүОҠнӮрӢӯү»ӮөӮҪӮМӮНҸ_“оӮИҺvҚl—НӮМҺ’•ЁӮЖҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨӮөҒAҒwҢ©ӮҪӮӯӮИӮўҢ»ҺАҒxӮр—вҗГӮЙҺуӮҜҺ~ӮЯӮДүрҢҲӮрҗ}ӮБӮҪ“_ӮН‘ҪӮӯӮМҺw“ұҺТӮӘҢ©ҸKӮӨӮЧӮ«”ь“ҝӮҫӮлӮӨҒB “ъҳIӮӘҠJҗнӮөӮҪ’јҢгӮНҒAҸг‘w•”ӮӘӢR•әӮМ“Бҗ«Ӯр—қүрӮөӮ«ӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҺ–ӮаӮ ӮиҒAӢR•әӮМҺқӮВӢ@“®—НӮрҠҲӮ©ӮөӮ«ӮкӮИӮў–Ҫ—ЯӮӘ‘ұӮӯӮаҒAҗн‘ҲӮӘ’·ҲшӮӯӮЙӮВӮкҒAҚL‘еӮИ–һҸBҚr–мӮЙӮЁӮҜӮйҚх“G”C–ұӮӘҢшүКӮр”ӯҠцӮөҺnӮЯӮҪҒBҸHҺRӮӘ•ыҒXӮЙ•ъӮБӮҪ•”‘аӮвҠФ’іӮӘҠmҺАӮЙӢ@”\ӮөҒAҳIҢRӮМҚs“®ӮНҠTӮЛҸHҺRҺx‘аӮМҺ@’mӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB “ъ–{ҢRӮӘүу–ЕӮөӮ©ӮҜӮҪҚ•Қa‘дӮМүпҗнӮЙӮЁӮўӮДӮаҒAҸHҺRҺx‘аӮНҺ–‘OӮЙҳIҢRӮМ‘еӢK–НӢӯҸPӮМ’ӣӮөӮр”FҺҜҒA‘ҚҺi—Я•”ӮЙүҪ“xӮа•сҚҗӮрҸгӮ°ӮДӮўӮйҒBӮӘҒAӮұӮМҺһӮМ•сҚҗӮЙҠЦӮөӮДӮНҒA‘ҚҺi—Я•”ҺQ–dӮМҸјҗм•qҲы(ҸHҺRӮМҢг”yӮЙ“–ӮҪӮй)ӮЙӮжӮБӮД–ЩҺEӮіӮкҒA–һҸBҢRӮН’Ч‘–җЎ‘OӮЬӮЕ’ЗӮўӢlӮЯӮзӮкӮйӮЖӮўӮӨҗhҺ_ӮрӮИӮЯӮҪҒBӮ»ӮкӮЕӮаүу–ЕӮр–hӮ°ӮҪӮМӮНҒA“Б•КӮЙ”z”хӮіӮкӮҪӢ@ҠЦ–CӮрӮУӮсӮҫӮсӮЙҠҲ—pӮөӮҪҸHҺRҺx‘аӮӘҒA“P‘ЮӮ№ӮёӮЙҗw’nӮЕҺқӮҝӮұӮҪӮҰӮҪҺ–ӮӘ‘еӮ«ӮўҒBӢtӮЙӢ@ҠЦ–CӮМӮИӮў‘јӮМ•”‘аӮНӮұӮЖӮІӮЖӮӯҢг‘ЮӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮДӮЁӮиҒAҸHҺRҺx‘аӮӘҚЕҢгӮМҚФӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ҢRӮрүу–ЕӮ©Ӯз–hӮўӮҫӢ@ҠЦ–CӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҸHҺRҺ©җgӮӘ‘ҒӮӯӮ©ӮзҸг‘w•”ӮЙҺ·қXӮЙҠ|ӮҜҚҮӮБӮҪҢӢүКҒA“Б•КӮЙҸHҺRҺx‘аӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA”ЮӮМҗжҢ©ӮМ–ҫӮН—рҺjӮрҚ¶үEӮөӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB Қ•Қa‘дүпҗнҢгҒAҸHҺRҺx‘аӮН”T–ШҠу“TӮМ‘жҺOҢRӮЙ•Т“ьӮіӮкҒAҚ¶—ғӮ©ӮзҳIҢRӮМӮНӮйӮ©Ңг•ыӮЬӮЕҗiҸoҒAӮөӮОӮөӮОҳIҢRҺi—ЯҠҜӮМғNғҚғpғgғLғ“ӮрӢ^җSҲГӢSӮЙӮЁӮЖӮөӮўӮкӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBҸHҺRӮНӮ»ӮкӮЬӮЕӮа‘Ҫҗ”ӮМӢR•ә‘аӮрҚх“GӮЦӮЖ•ъӮБӮДӮўӮҪӮМӮҫӮӘҒA–һҸB•Ҫ–мӮМ“~ӮНҒ|30“xӮЙӮаӮИӮйҢө“~ӮЕӮ ӮйҒBҢ»’nӮМҗlҠФӮЙӮжӮкӮОҒA“ъ–{ӮМҗ^“~’…ӮӯӮзӮўӮМ‘•”хӮМҸгӮЙ•ӘҢъӮўҸг’…ӮрүHҗDӮиҒAӮіӮзӮЙ•ӘҢъӮўҗ^–ИӮМ“Бҗ»ғRҒ[ғgӮр’…ҒAӮ»ӮМҸгӮЕ•ӘҢъӮў–СҺ…Ӯв–ИӮМ–XӮЕҠз‘S‘МӮр•ўӮӨӮЖӮМҺ–ӮҫҒBү®“аӮЕӮ·ӮзҺиӮӘ“ҖӮиҒAҸ‘Ӯ«•ЁӮа—eҲХӮЕӮИӮӯ‘SӮӯҺdҺ–ӮЙӮИӮзӮИӮўӮзӮөӮўҒBӮ»ӮсӮИҠҰӮіӮМ’ҶӮЕ’·Ӣ——ЈӮЙӮнӮҪӮйҚх“GӮрҢJӮи•ФӮөҒA“GҸо”cҲ¬ӮЙҚvҢЈӮөӮҪҺ–ӮНӮЬӮіӮЙҠҙ’QӮҫӮӘҒAҚф“G•”‘аӮМ’ҶӮЙӮН1000kmҲИҸгӮМӢ——ЈӮрҲЪ“®ӮөӮҪӮаӮМӮаӮ ӮиҒAӮНӮҪӮөӮДҗ^“~ӮМ–һҸBӮЕӮЗӮӨӮвӮБӮДӮ»ӮМӮжӮӨӮИ‘еҺ–ӮӘҗ¬Ӯө“ҫӮҪӮМӮ©ҒAҢ»‘гӮЙҗ¶Ӯ«ӮйүдҒXӮЙӮН‘z‘ңӮМӮөӮжӮӨӮаӮИӮўҒBҸ«•әӮМҗgӮЙӮИӮБӮДӮаҒA”nӮМҗgӮЙӮИӮБӮДӮаӮҪӮҫӮҪӮҫӢ°Ӯк“ьӮйӮОӮ©ӮиӮЕӮ ӮиҒAҺ–ҺАҒA‘е–{үcӮМӮЭӮИӮзӮёҒAҠCҠOӮМҸ]ҢRӢLҺТӮзӮаӮұӮкӮзӮМҲМӢЖӮрҲШ•|ӮөӮҪӮзӮөӮўҒB ӮаӮҝӮлӮсӢЙҠҰӮЙ‘ПӮҰӮҪӮМӮНӢR•әӮЙҢАӮзӮИӮўҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ҢRӮМ–hҠҰӢпӮНғҚғVғAҢRӮЙ”дӮөӮДӮ©ӮИӮи‘e––ӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕҒAҳIҢR•әҺmӮзӮНҒw“ъ–{ҢRӮНҠҰӮіӮЕ’·ҠъҗнӮЙ‘ПӮҰӮзӮкӮИӮўҒxӮЖ“ҘӮсӮЕӮўӮҪҒBӮӘҒAҺАҚЫӮЙӮНӮ»ӮӨӮНӮИӮзӮёҒAҳIҢR•әҺmӮзӮНҒu•n‘ҠӮИ–hҠҰӢпӮМӮЬӮЬҗбӮМ’ҶӮЕ–°ӮиҒA—Ӯ’©ӮЙӮНӢNӮ«ҸгӮӘӮБӮД—§ӮҝҢьӮ©ӮБӮДӮӯӮйҒvӮЖ“ъ–{•әӮМҺқӢv—НӮЙӢБңұӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBҢөҠҰӮЙҠөӮкӮҪғҚғVғAҗlӮЖҢy‘•ӮМ“ъ–{җlӮӘ‘О“ҷӮЙ“¬Ӯў“ҫӮҪӮМӮНҒA•әҺmӮМҺmӢCӮМҲбӮўӮаӮ ӮйӮҫӮлӮӨӮӘҒA•Ғ’iӮ©Ӯзҗҙ•nӮрҗSӮӘӮҜӮДӮ«ӮҪҗёҗ_“IӢӯҗxӮіӮа‘еӮ«ӮИ—vҲцӮЖҢҫӮҰӮйӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒB ҸHҺRҺ©җgҒA•Ғ’iӮ©ӮзжТ‘тӮрҢҷӮўҒAҺҝ‘fӮрҗSӮӘӮҜҒAҢR•”“аӮЙӮЁӮўӮДӮаҚЕҢгӮМ•җҺmӮЖӮөӮДҲк–ЪӮЁӮ©ӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮөҒAҸHҺRӮЙҢАӮзӮё‘јӮМ’ҳ–јӮИҗl•ЁӮзӮа—ЮҺ—ӮМӢCҺҝӮМҺқӮҝҺеӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЙҺvӮнӮкӮйҒB”T–ШҠу“TӮЖҸHҺRҚDҢГӮНүҝ’lҠПӮЙӮЁӮўӮДӢӨ’КӮөӮҪ•”•ӘӮӘ‘ҪӮӯҒAҺ–ҺА—јҺТӮЖӮаӢCӮӘҚҮӮБӮҪӮМӮ©җeҢрӮНҗ[Ӯ©ӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйҒBӮЬӮҪҒA‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘еҺRҠЮӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺF–Җ•җҺmӮЙӮН•nӮөӮўҺ–ӮӘӮЮӮөӮл”ь“ҝӮЖӮўӮӨүҝ’lҠПӮӘ“`“қ“IӮЙӮ ӮиҒA—cҸӯӮМӢЙ•nӮрҒA’pӮ¶ӮйӮЗӮұӮлӮ©”ь’kӮЖӮөӮДҺьҲНӮЙҢЦӮйӮЩӮЗӮҫӮБӮҪҒBҢгӮМҗўӮЕҢҫӮӨҗёҗ_ҳ_ӮӘ“–ӮҪӮи‘OӮМ“ъҸнӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮӘҒAӮұӮМӢCҺҝӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮН‘јӮМғAғWғAҸ”Қ‘ӮЖӮНҲЩӮИӮБӮҪ—рҺjӮр•аӮсӮҫӮЖ’fҢҫӮөӮДӮўӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒB ҸHҺRӮН‘Ю–рҢгҒAҢМӢҪҸјҺRӮЕӢі•ЪӮрҺжӮйҒB•җҢMӮрҢЦӮйҺ–ӮӘҲкҗШ–іӮӯҒAҸIҗнӮ©Ӯз26”NҢгӮЙҗГӮ©ӮЙ‘§ӮрҲшӮ«ҺжӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸHҺRҚDҢГ2Ғ@(Ӯ Ӯ«ӮвӮЬӮжӮөӮУӮй)
“ъҳIҗн‘ҲӮрҸҹ—ҳӮЙ“ұӮўӮҪ—§–рҺТӮМҲкҗlҒAҸHҺRҚDҢГҒB”ЮӮНҢRҗlӮЖӮўӮӨӮжӮиҒA•җҺmӮЕӮ ӮиҒA•җҺm“№ӮЖӮўӮӨ“ъ–{җёҗ_ӮМ‘МҢ»ҺТӮМҲкҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ӢR•әӮр—{җ¬Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨӮҪӮБӮҪҲкӮВӮМ–Ъ“IӮМӮҪӮЯӮЙҺ©•ӘӮМҗlҗ¶Ӯр•щӮ°ӮҪҒBғtғүғ“ғXӮЦӮМ—ҜҠwҢгҒAӢR•ә—{җ¬ӮМҺg–ҪҠҙӮр–ҫҠmӮЙҺ©ҠoӮөӮДӢAҚ‘ӮөӮҪҒB ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲӮЕҠҲ–ф ҸHҺRҚDҢГӮЖӮўӮӨ–ј‘OӮр•·ӮўӮДҒAӮўӮ©ӮИӮйҗl•ЁӮ©Ӯр‘Ұ“ҡӮЕӮ«ӮйҺТӮН“ъ–{җlӮМ’ҶӮЕӮаҒAӮ»ӮӨ‘ҪӮӯӮНӮ ӮйӮЬӮўҒB“–‘RҒA—ҜҠwҗ¶ӮЙӮЖӮБӮДӮа“йҗхӮЭӮМӮ Ӯйҗl•ЁӮЕӮНӮИӮўҒB”ЮӮН–ҫҺЎҺһ‘гӮМҢRҗlӮЕӮ ӮиҒA“ъҳIҗн‘ҲӮр“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮЙ“ұӮўӮҪ—§–рҺТӮМҲкҗlӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮ·ӮкӮОҒAғAғWғAӮМ—ҜҠwҗ¶ӮМ’ҶӮЙӮНҒA–{ҚeӮЕӮұӮМҗl•ЁӮрҺжӮиҸгӮ°ӮйӮұӮЖӮЙ•sүхҠҙӮр•шӮӯҗlӮаӮўӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮұӮМҗн‘ҲӮМҢгҒA“ъ–{ӮН’©‘N”ј“ҮӮр“ъ–{ӮМҗA–Ҝ’nӮЖӮөӮДҺx”zүәӮЙ’uӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB ӮөӮ©ӮөҒA–{ҚeӮЕ“ъҳIҗн‘ҲҺһӮЙҠҲ–фӮөӮҪҢRҗlӮрҺжӮиҸгӮ°ӮйӮМӮНҒAҗн‘ҲӮр”ьү»Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЕӮаҒAҗA–Ҝ’nҗӯҚфӮрҗі“–ү»Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЕӮаӮИӮўҒBҸHҺRҚDҢГӮЖӮўӮӨҲкҗlӮМ“ъ–{җlӮӘҒAӮЗӮМӮжӮӨӮИҗёҗ_ӮЕ–ҫҺЎӮМҺһ‘гӮрҗ¶Ӯ«”ІӮўӮДӮўӮБӮҪӮ©ӮрҸРүоӮөӮДӮЭӮҪӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЙүЯӮ¬ӮИӮўҒB”ЮӮНҢRҗlӮЖӮўӮӨӮжӮиҒA•җҺmӮЕӮ ӮйҒB•җҺm“№ӮЖӮўӮӨ“ъ–{җёҗ_ӮМ‘МҢ»ҺТӮМҲкҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҗl•ЁӮМҗEӢЖӮӘӮҪӮЬӮҪӮЬҢRҗlӮЕӮ ӮиҒAҗEҸкӮӘҗнҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒB 1904”NӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA“Ң—mӮМҲкҠpӮЙӮ Ӯй•Р“cҺЙӮМ“ъ–{ӮӘӮНӮ¶ӮЯӮДғҲҒ[ғҚғbғp•¶–ҫӮЖҢҢӮЭӮЗӮлӮМ‘ОҢҲӮрӮөӮҪҗн‘ҲӮЕӮ ӮБӮҪҒBҠпҗЦӮЖӮаҢҫӮнӮкӮҪҸҹ—ҳӮрҸҹӮҝҺжӮБӮҪ—vҲцӮНҒAӮўӮӯӮВӮ©ҸгӮ°ӮзӮкӮйӮӘҒAҺеӮИ—vҲцӮНҗўҠEҚЕӢӯӮМӢR•әӮЖҢҫӮнӮкӮҪғҚғVғAӮМғRғTғbғNӢR•әҸW’cӮрҢӮӮҝ”jӮБӮҪӮұӮЖҒBӮ»ӮкӮЖғҚғVғAҠCҢRӮМҺе—НҠН‘аӮр“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕҢӮ”jӮөӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB ҸHҺRҚDҢГӮНҗўҠEҚЕӢӯӮМғRғTғbғNӢR•әҸW’cӮЖҗнӮБӮҪ“ъ–{ӢR•әӮМ‘а’·ӮЕӮ ӮБӮҪҒB”ЮӮНӮРҺгӮИ“ъ–{ӢR•әӮр—ҰӮўӮД—EҠёӮЙҗнӮўҒAӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮД“GӮрӮвӮФӮБӮҪҒBӮЬӮҪӮаӮӨҲкӮВӮМҸҹ—ҳҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮН“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY—ҰӮўӮйҳAҚҮҠН‘аӮМҚмҗнҸҹӮҝӮЖӮаҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮұӮМҚмҗнӮр—§ҲДӮөӮҪҗl•ЁӮӘҚDҢГӮМ’нҸHҺRҗ^”VӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚмүЖӮМҺi”n—Й‘ҫҳYӮНҒAӮұӮМ“сҗlӮМҢZ’нӮЖҗіүӘҺqӢKӮМҺOҗlӮрҺеҗlҢцӮЙӮөӮҪҸ¬җаҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮрҸ‘Ӯ«ҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕҒuӮұӮМҢZ’нӮӘӮўӮИӮҜӮкӮО“ъ–{ӮНӮЗӮӨӮИӮБӮДӮўӮҪӮ©ӮнӮ©ӮзӮИӮўҒvӮЖҢкӮБӮДӮўӮйҒB ҒЎ—ӨҢRҺmҠҜҠwҚZӢR•әүИӮЦ Ңг”NҒAҒu“ъ–{ӢR•әӮМ•ғҒvӮЖҢДӮОӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҸHҺRҚDҢГӮМӢR•әӮЖӮМҠЦӮнӮиӮНҒAӮҪӮнӮўӮМӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB—ӨҢRҺmҠҜҠwҚZ“ьҠwҺһӮЙҒAӢR•әүИӮН–C•әүИӮвҚH•әүИӮжӮиҸCӢЖ”NҢАӮӘ1”N‘ҒӮўӮұӮЖӮЕҢҲӮЯӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB‘ІӢЖӮӘ‘ҒӮҜӮкӮОҒAӢӢ—ҝӮа‘ҒӮӯӮаӮзӮҰӮйҒBүЖӮӘ•n–RӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮЕҒAӮұӮМ‘I‘рӮЙ–АӮўӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҚDҢГӮӘҺmҠҜҠwҚZӮЙ“ьӮБӮҪӮМӮНҒA1877”N(–ҫҺЎ10”N)ӮМ5ҢҺҒA19ҚОӮМ”NҒBҺmҠҜҠwҚZӮӘӮЕӮ«ӮДӮЬӮҫ3”NӮаҢoӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB—ӨҢRӮ»ӮкҺ©‘МӮаӮ«ӮнӮЯӮДҗЖҺгӮИҠо”ХӮөӮ©ҺқӮҝҚҮӮнӮ№ӮДӮўӮИӮўҺһҠъӮЕӮ ӮиҒAӢR•әүИӮИӮЗ—LӮБӮД–іӮ«ӮӘӮІӮЖӮ«‘¶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМ”ЮӮӘҒA•nҺгӮИӢR•әӮМүь‘PӮЖҗi•аӮЙ”MӮўҸо”MӮрҢXӮҜҒAӢR•әӮМ—{җ¬ӮЙ–{Ҡi“IӮЙҺжӮи‘gӮЮӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮМӮНҒAғtғүғ“ғX—ҜҠwӮӘӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒuүҙӮӘ“ъ–{ӮМӢR•әӮрҚмӮйҒvҒBҚDҢГӮН–ҫҠmӮИҺg–ҪӮрҺ©ҠoӮөӮДҒAғtғүғ“ғXӮ©ӮзӢAҚ‘ӮөӮҪҒB ҒЎғtғүғ“ғX—ҜҠw ҚDҢГӮӘғtғүғ“ғXӮЙ—ҜҠwӮөӮҪӮМӮН1887”NӮМӮұӮЖӮЕҒA29ҚОӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBҸјҺR”Л(Ң»ҲӨ•QҢ§)ӮМӢҢ”ЛҺеҒEӢvҸј’иж•ӮӘӮ»ӮМ‘O”NӮЙғtғүғ“ғXӮЙ—VҠwӮөӮДӮЁӮиҒA87”NӮЙғtғүғ“ғXӮМҺmҠҜҠwҚZӮЙ“ьҠwӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ“ҜӢҪӮМҢRҗlӮр•вҚІ–рӮЖӮөӮД”hҢӯӮ·ӮйҳbӮӘӢҪ—ўӮЕҺқӮҝҸгӮӘӮиҒAҚDҢГӮӘ”І“FӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҺһ‘гҒAӮЬӮҫ•җҺmӮМҺеҸ]ҠЦҢWӮНҚӘӢӯӮӯҺcӮБӮДӮўӮҪҒBҸHҺRүЖӮНҗж‘c‘гҒXҒA”ЛҺеӢvҸјүЖӮЙҺdӮҰӮДӮ«ӮҪӢҢҗbӮЕӮ ӮйҒBбпӮрҗHӮсӮЕӮ«ӮҪү¶ӮрӮ ӮҫӮЕ•ФӮ·ӮнӮҜӮЙӮНҚsӮ©ӮИӮўҒBҚDҢГӮН–АӮӨӢCҺқӮҝӮрҗUӮиҗШӮБӮДҒAғtғүғ“ғXҚsӮ«ӮрҢҲ’fӮөӮҪҒB “–ҺһҚDҢГӮН“ҢӢһ’Б‘дҺQ–dӮЖӮўӮӨҢRӮМ—vҗEӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМ’nҲКӮрҺМӮДӮДӮМ—ҜҠwӮЕӮ ӮйҒBҢRӮМ—vҗҝӮ©ӮзҸoӮҪӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҲИҸгҒAҢRӮЕӮМүh’BӮрӮ Ӯ«ӮзӮЯӮйӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҸгҒAӮ»ӮМ“–ҺһҒA—ӨҢRӮМҢRҗ§ӮНғhғCғcҺ®ӮЙҲкҗVӮіӮкӮДӮЁӮиҒAғtғүғ“ғX—ҜҠwӮНҺһ‘гҚцҢлӮМҠҙӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮдӮҰӮЙ”ЮӮМ—ҜҠwӮрӮЖӮЯӮжӮӨӮЖӮ·ӮйҺТӮаҸӯӮИӮӯӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA”ЮӮНҢҲӮөӮД—Һ’_ӮөӮДӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBғtғүғ“ғXӮЙӮНӢR•әӮМ“`“қӮӘӮ ӮиҒAҠwӮФӮЧӮ«“_ӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮйӮНӮёӮЖҠҙӮ¶ӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB ғpғҠӮЙ’…ӮўӮҪҚDҢГӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғp•¶–ҫӮМӢҗ‘еӮИ•xӮЖӢZҸpӮМҸWҗПӮЙҒAӮөӮОӮөӮЪӮӨ‘RӮЖӮ·ӮйҒB“Ң—mӮМҢгҗiҚ‘“ъ–{Ӯ©ӮзҒAҲкӢCӮЙҗўҠEӮМ•¶ү»“sҺsғpғҠӮЙ‘«Ӯр“ҘӮЭ“ьӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҢ©Ӯй•ЁҒA•·Ӯӯ•ЁӮ·ӮЧӮДӮӘӢБӮ«ӮЕҒA“–ҸүҲкҗlӮЕҠXӮр•аӮҜӮИӮўӮЩӮЗӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB ҒЎӢR•әӮЙҠЦӮ·Ӯй‘SӮДӮрҠwӮФ ҚDҢГӮМғtғүғ“ғX—ҜҠwӮН4”N”јӮЙӢyӮсӮҫҒB“–ҸүҒA”ЮӮМ—ҜҠwӮНҸгӢLӮМӮўӮ«ӮіӮВӮ©ӮзҺ„”п—ҜҠwӮЖӮўӮӨ—§ҸкӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө2”N”јӮЩӮЗҢoӮБӮҪҚ ҒAҠҜ”п—ҜҠwӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮЖӮўӮӨ–Ҫ—ЯӮрҺуӮҜҺжӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBҸ«—ҲӮрҸъ–]ӮіӮкӮҪҢ»–рҸ«ҚZӮӘҺ„”п—ҜҠwӮЕӮНҒAӮ©ӮнӮўӮ»ӮӨӮҫӮЖӮўӮӨ“ҜҸоҳ_ӮӘ—ӨҢR“а•”Ӯ©ӮзӢNӮұӮБӮДӮ«ӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮМӮҪӮЯӮЙ”ЮӮЙүәӮіӮкӮҪ–Ҫ—ЯӮНҒAғtғүғ“ғXӢR•әӮМҗнҸpҒA“а–ұҒAҢo—қҒAӢіҲзӮИӮЗӮр’ІҚёӮөҒAҢӨӢҶӮ№ӮжӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮВӮЬӮи“ъ–{ӮМӢR•әҢҡҗЭӮЙҠЦӮ·Ӯй’ІҚёӮрӮ·ӮЧӮДҒAҚDҢГӮЙҲПӮЛӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮИӮМӮЕӮ ӮйҒB ҚDҢГӮӘ“w—НӮөӮҪӮұӮЖӮНҒAӮЬӮёғtғүғ“ғX”nҸpӮМҗ^җ‘ӮрҗgӮЙӮВӮҜӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮИӮҜӮИӮөӮМӢаӮрӮНӮҪӮўӮД”nӮрҲк“ӘҚw“ьӮөӮҪӮЩӮЗӮЕӮ ӮйӮ©ӮзҒA”ЮӮМҸK“ҫҲУ—~ӮН“O’кӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮұӮЙҲкӮВӮМ–в‘иӮӘӮ ӮБӮҪҒBҗжӮЙҸqӮЧӮҪӮжӮӨӮЙ“ъ–{—ӨҢRӮМҢRҗ§ӮӘғtғүғ“ғXҺ®Ӯ©ӮзғhғCғcҺ®ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮзӮкҒAӢR•әӮМ•Ә–мӮа—бҠOӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮЖ”nҸpӮЙҠЦӮөӮДӮНғhғCғcҺ®ӮЖғtғүғ“ғXҺ®ӮЕӮНҒAӮЬӮйӮЕҲбӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ғhғCғcҺ®ӮНҚd’ј”ьӮр’ЗӢҶӮ·ӮйӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒAғtғүғ“ғXҺ®ӮНҸ_“оҒAӮ©ӮВҺ©‘R‘МӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр–{‘ҘӮЖӮөӮДӮўӮҪҒBӮҪӮЖӮҰӮОғhғCғcӮЕӮН”nӮЙҸжӮБӮҪӮЖӮ«ҒA•GӮрҢгӮлӮЙҲшӮ«ҒA•GӮ©ӮзүәӮНӮ»ӮкӮжӮиӮіӮзӮЙҢгӮлӮЙҲшӮўӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮӨӮИӮйӮЖӢRҺиӮНӢ|ӮИӮиӮЙӮИӮиҒAҢ©ӮҪ–ЪӮЙӮНҷzҒXӮөӮӯҒAҲР•—“°ҒXӮҪӮйҺpӮЖӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөӮұӮкӮЕӮНҗlҠФӮМҺpҗЁӮЖӮөӮДӮН•sҺ©‘RӮЕҒA’·ҺһҠФӮМӢRҸжӮЙӮЗӮӨӮөӮДӮа–і—қӮӘӮ©Ӯ©ӮиҒA”жҳJӮӘӮНӮИӮНӮҫӮөӮўҒB Ҳк•ығtғүғ“ғXӮНҒAӢRҺиӮМҺpҗЁӮр”nӮМү^“®ғҠғYғҖӮЙүҲӮӨӮжӮӨӮЙӮөӮДӮЁӮиҒA‘«ӮаҢгӮлӮЙҲшӮӯӮЖӮўӮӨ–і—қӮИҺpҗЁӮрҺжӮзӮёҒAҺ©‘RӮЙҗӮӮкӮіӮ№ӮДӮўӮйҒB’·ҺһҠФӮМӢRҸжӮЙӮЕӮ«ӮйӮҫӮҜ‘ПӮҰӮйӮжӮӨӮЙҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ҚDҢГӮМ—ҜҠw–Ъ“IӮНҒA’PӮЙғtғүғ“ғXӢR•әӮЙҠЦӮ·Ӯй’ІҚёҢӨӢҶӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢAҚ‘ҢгҒA“ъ–{ӮМӢR•әҢҡҗЭӮЙӢп‘М“IӮЙҗУ”CӮрҺқӮБӮДҺжӮи‘gӮЬӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBҒuӮ»ӮкӮрӮвӮкӮйӮМӮНҒAҺ©•ӘӮөӮ©ӮўӮИӮўҒvӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒBҲАҲХӮИ‘ГӢҰӮНӢ–ӮіӮкӮИӮўӮМӮЕӮ ӮйҒBғtғүғ“ғXҺ®ӮЕӮа—ЗӮўӮаӮМӮН—ЗӮўҒBғhғCғcҺ®ӮЕӮаҲ«ӮўӮаӮМӮНҲ«ӮўҒB ”ЮӮНҒAүўҸBҺӢҺ@ӮЕғtғүғ“ғXӮЙ—§ӮҝҠсӮБӮҪ“а–ұ‘еҗbӮМҺRҢ§—L•ьӮЙ’ј‘iӮөӮДӮЬӮЕҒAғtғүғ“ғXҺ®”nҸpӮМ—DҲКҗ«ӮрҺе’ЈӮөӮҪҒBҺRҢ§ӮМ•ФҺ–ӮНҒuҚlӮҰӮДӮЁӮӯҒBӮ»ӮМӮұӮЖӮрӮіӮзӮЙҢӨӢҶӮөӮДӮЁӮӯӮжӮӨӮЙҒvӮЖӮўӮӨ‘fӮБӢCӮМӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҸHҺRҚDҢГӮЖӮўӮӨҗl•ЁӮЙ’Қ–ЪӮөӮҪӮұӮЖӮҫӮҜӮНҠmӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҚDҢГӮӘ—ҜҠwӮрҸIӮҰӮДӢAҚ‘ӮөӮҪҢгҒAҺбҠұ33ҚОӮМ”ЮӮЙ“ъ–{ӮМӢR•әҢҡҗЭӮМ‘SӮДӮр”CӮ№ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ҒЎҗ¶ҠUҲкҺ– Ғu’jҺqӮНҗ¶ҠUҲкҺ–ӮрӮИӮ№ӮО‘«ӮйҒvӮЖӮНҒAҸHҺRҚDҢГӮМҢы•ИӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҲкҺ–ӮЖӮНҒA”ЮӮЙӮЖӮБӮД“ъ–{ӢR•әӮМҲзҗ¬ӮЙ‘јӮИӮзӮИӮўҒBүў•Д—сӢӯӮЙҲшӮҜӮрҺжӮзӮИӮўӢR•әӮрҚмӮиҸгӮ°ӮйӮұӮЖҒBӮұӮМӮҪӮБӮҪҲкӮВӮМ–Ъ“IӮӘ”ЮӮМ‘Sҗlҗ¶ӮрҺx”zӮөӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮаҢҲӮөӮДүЯҢҫӮЕӮНӮИӮўҒB”ЮӮМүҝ’lҠПӮНҺАӮЙ’PҸғ–ҫүхӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМҲкҺ–ӮӘ‘SӮДӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮкҲИҠOӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAүҪҺ–ӮЙӮаҺАӮЙ’W”‘ӮЕӮ ӮиҒA•ЁӮвӢа‘KӮЙӮН—~ӮвҺ·’…җSӮӘ‘SӮӯӮЖӮўӮБӮДӮўӮўӮЩӮЗӮИӮўҒB “ъҗҙҗн‘ҲҸI—№ҺһҒAӢӨӮЙҗнӮБӮҪ•”үәӮҪӮҝӮЖ—A‘—‘DӮЙҸжӮиҚһӮЭҒA“r’ҶҚL“ҮӮЕҸhүcӮөӮҪӮЖӮ«ӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB”ЮӮН•ӣҠҜӮрҢДӮСӮҫӮөҒA”ЮӮМҚs—ӣӮрҠJӮҜӮіӮ№ӮҪҒB’ҶӮЙӮНҒA”ЮҺ©җgӮМӢӢ—ҝ‘Ьҗ”ғ–ҢҺ•ӘӮӘӮ»ӮМӮЬӮЬҺиӮВӮ©ӮёӮЕ“ьӮБӮДӮўӮҪҒBҗн’nӮЕӮНӮЩӮЖӮсӮЗӢаӮМҺgӮў“№ӮӘӮИӮўӮ©ӮзӮҫҒB•ӣҠҜӮЙҒuӮҫӮўӮФӮ ӮйӮИҒBӮЭӮсӮИӮЕҠMҗщҸjӮўӮЕӮаӮвӮйӮӘӮўӮўҒvӮЖҢҫӮБӮД‘SҠz“nӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB •ЁӮвӢа‘KӮЙ–і“Ъ’…ӮИӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBҺ©•ӘӮМ–ҪӮЙ‘ОӮөӮДӮа“Ҝ—lӮЕӮ ӮБӮҪҒB“GӮМ’eҠЫӮӘ”т—ҲӮ·Ӯй’ҶӮЕҒA”ЮӮНҗgӮрүBӮ·ӮұӮЖӮаӮИӮӯ‘SҢRӮМҺwҠцӮрҺ·ӮБӮҪҒB“GҗwӮЙ50ғҒҒ[ғgғӢӮЩӮЗӮЬӮЕӢЯӮГӮўӮДӮМ“GҸоҺӢҺ@ӮИӮЗҒA‘а’·ӮЕӮ ӮйҚDҢГҺ©ӮзӮӘӮөӮОӮөӮОҚsӮБӮҪҒB‘O•ыӮЙӮНҺХӮй•ЁӮӘүҪӮаӮИӮў•Ҫ’nӮЕӮ ӮйҒB“–‘R•”үәӮН•KҺҖӮЙҺ~ӮЯӮйҒBӮөӮ©Ӯө”ЮӮНҢyӮӯӮӨӮИӮёӮӯӮҫӮҜӮЕҒA’eүJӮМ’ҶӮЙ”тӮСҚһӮсӮЕӮўӮӯӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB ”У”NҒAҚDҢГӮНҢоӮнӮкӮДӢҪ—ўӮМ’ҶҠwҚZӮМҚZ’·ӮрӢОӮЯӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB—ӨҢR‘еҸ«ӮЬӮЕҸёӮиӮВӮЯӮҪҗl•ЁӮӘҒA’n•ыӮМ’ҶҠwҚZӮМҚZ’·ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒA“–ҺһӮМҸнҺҜӮЕӮНӮ Ӯи“ҫӮИӮўӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA–ј—ҳӮв–КҺqӮИӮЗӮЖӮЩӮЖӮсӮЗ–іүҸӮИӮұӮМ’jӮНҒAҒuүҙӮН’ҶҠwӮМӮұӮЖӮНүҪӮа’mӮзӮсӮӘҒA‘јӮЙҗlӮӘӮўӮИӮҜӮкӮОҒAҚZ’·ӮМ–јӮрҸoӮөӮДӮаӮўӮўҒB“ъ–{җlӮНҸӯӮө’nҲКӮр“ҫӮД‘ЮҗEӮ·ӮйӮЖҒA—VӮсӮЕү¶ӢӢӮЕҗHӮӨӮұӮЖӮрҚlӮҰӮйҒBӮ»ӮкӮНӮўӮ©ӮсҒBүҙӮЕ–рӮЙ—§ӮВӮИӮзүҪӮЕӮа•тҢцӮ·ӮйӮжҒvӮЖҢҫӮБӮҪҒB ҚDҢГӮМҚZ’·ҚЭҗEӮН6”NҲИҸгӮЙӢyӮсӮҫҒBӮөӮ©ӮөҢҲӮөӮД–ј‘OӮҫӮҜӮМҚZ’·ӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҠФҒAҲк“ъӮаӢxӮсӮҫӮұӮЖӮНӮИӮӯҒA’xҚҸӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮӮМ72”NҠФӮМҗ¶ҠUӮНҒAҲкҺ–ӮМ‘еҗШӮИӮұӮЖӮМӮҪӮЯӮЙӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрҢгҗўӮЙҺҰӮөӮҪҗlҗ¶ӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ғ@ |
|
|
ҒЎҗм‘әҢi–ҫ 1852-1933 ҺF–Җ”Л
—ӨҢRӮЙӮЁӮҜӮйҚЕҸIҢҲҗнӮЖӮИӮй•т“VүпҗнӮЙҗж—§ӮБӮДҢӢҗ¬ӮіӮкӮҪҠӣ—ОҚ]ҢRӮМҺi—ЯҠҜҒBҺFүpҗн‘ҲҒE•и’Cҗн‘ҲӮрҗнӮў”ІӮўӮҪҒAҺF–ҖҢnҚӮҠҜӮМ“TҢ^“IӮИҢo—рӮрҺқӮВҒB Ҡӣ—ОҚ]ҢRӮЖӮНӮ»ӮМ–јӮМӮЖӮЁӮиҒA’Ҷ’©Қ‘Ӣ«Ӯр—¬ӮкӮй‘еүНҒAҠӣ—ОҚ]•ы–КӮЙ”z”хӮіӮкӮҪҢRӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМ–Ъ“IӮН•т“VүпҗнӮЕӮНӮИӮӯ’©‘N•ы–КӮМҢx”хӢyӮСҠ’‘ҫ•ы–КӮЦӮМӮҜӮсҗ§ҒAҚU—ӘӮЙӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ӮЙӮНҠщӮЙҗVӮҪӮЙҢRӮр•Тҗ¬Ӯ·Ӯй—]—НӮН–іӮӯҒAҠщ‘¶ӮМ•ә—НҒEҺеӮЙ”T–ШӢH“TӮМ‘жҺOү^Ӯ©Ӯз—рҗнӮМ•”‘аӮрҲшӮ«”ІӮӯӮИӮЗӮөӮДӢӯҲшӮЙ•ә—НӮрҸWӮЯӮҪҒB–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”ӮЕӮНҚЕҸIҢҲҗнӮЖӮөӮДҲК’uӮГӮҜӮДӮўӮҪ•т“VӮМүпҗнӮӘ–Ъ‘OӮЙ”—ӮБӮДӮЁӮиҒAӮұӮМ’iҠKӮЕӢMҸdӮИ•ә—НӮр‘јӮЙӮЬӮнӮ·Һ–ӮЙ‘ОӮөҒA‘еҺRҠЮӮзӮН“–‘RӢӯӮўҢң”OӮрҺҰӮөӮҪҒBӮЕӮНҒAӮИӮәӮ»ӮұӮЬӮЕӮөӮДӮұӮМҢRӮН•Тҗ¬ӮіӮкӮҪӮМӮ©ҒH ӮұӮМҲДӮМ’сҸҘҺТӮН‘е–{үcӮМ’·үӘҠOҺ‘ӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйҒBҠщӮЙҸIҗнӮӘӢЯӮў’iҠKӮЕҒAӮ ӮнӮжӮӯӮОғҚғVғA—МӮМҲк•”ӮЕӮаҗи—МӮөҒAҗнҢгӮМҚ‘үЖү^үcӮр—L—ҳӮЙү^ӮСӮҪӮўҲУҗ}ӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮўҒAӮұӮкӮНӮЬӮіӮЙүў•Д—сӢӯӮМ’йҚ‘ҺеӢ`Ӯ»ӮМӮЬӮЬӮМ”ӯ‘zӮҫҒBӮұӮМӢЙӮЯӮДҗӯҺЎ“IӮИ’·үӘӮМ”»’fӮЙӮжӮБӮДҒA‘OҗьӮМ–һҸBҢRӮНҗн—НҚнҢёӮМ’К’BӮрҺуӮҜӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAҺАҚЫӮЙӮұӮкӮН•K‘RӮМ‘[’uӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB “–Һ–үдӮӘҚ‘ӮН•ДҚ‘ӮМғӢҒ[ғYғxғӢғgӮЙ’вҗнҚuҳaӮМ’ҮүоӮр‘ЕҗfӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAғҚғVғA‘ӨӮЙӮ»ӮкӮрҺуӮҜ“ьӮкӮйӢуӢCӮН”чҗoӮаӮИӮӯҒAүјӮЙҚuҳaӮЙҺқӮҝҚһӮЯӮҪӮЖӮөӮДӮаҢрҸВӮНӢЙӮЯӮДҢөӮөӮўӮаӮМӮЙӮИӮйӮЖ—\‘zӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒwӮұӮұӮНҺ–‘OӮЙҠ’‘ҫӮ ӮҪӮиӮрҗи—МӮөҒAҗнҸҹҒE—М“yҠl“ҫӮМҠщҗ¬Һ–ҺАӮрҗПӮЭҸгӮ°ӮДӮЁӮӯӮЧӮ«ҒxӮЖӮўӮӨғӢҒ[ғYғxғӢғgӮ©ӮзӮМ’сҲДӮӘӮ ӮиҒAӮұӮкӮрҺА‘HӮ·ӮйҺ–ӮӘғӢҒ[ғYғxғӢғgӮЙ’І’в–рӮрүКӮҪӮөӮДӮаӮзӮӨҲЧӮМ”јӮО‘O’сҸрҢҸӮЖӮўӮӨҸуӢөӮЙӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒBҲкҢ©‘е–{үcӮӘӢрҚмӮр‘ЕӮҝҸoӮөӮҪӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйҠӣ—ОҚ]ҢR•Тҗ¬ӮЙӮНӮ»ӮкӮИӮиӮМҺ–ҸоӮӘӮ ӮБӮҪӮнӮҜӮҫҒBӮаӮҝӮлӮсӮұӮӨӮөӮҪ“а•”Һ–ҸоӮН‘OҗьӮЕ—қүрӮЕӮ«ӮйҺнӮМӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҒBӮ»ӮаӮ»Ӯа•т“VӮЕ•үӮҜӮДӮөӮЬӮҰӮО’вҗнҢрҸВӮаүҪӮа–іӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҸуӢөӮЙӮЁӮўӮДҒAҗм‘әҢi–ҫӮНҗlҗ¶ӮЕҚЕӮа‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҸd—vӮИҢҲ’fӮрӮ·ӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝ‘е–{үc–Ҫ—ЯӮМ–іҺӢӮЕӮ ӮйҒB–һҸBӮЙӮЁӮҜӮй—ӨҢRӮМ‘ҚҺwҠцҢ ӮН“ҢӢһӮМ‘е–{үcӮЕӮНӮИӮӯҒA–һҸB‘ҚҺi—Я•”ӮМ‘еҺRӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮӘҒAӮ»ӮкӮЙ•s•ЦӮрҠҙӮ¶ӮҪ‘е–{үcӮӘҒAӮЭӮёӮ©ӮзӮМ’јҠҚӮМҺwҠцүәӮЕ“®ӮҜӮйӮжӮӨ•Тҗ¬ӮөӮҪӮМӮӘҠӣ—ОҚ]ҢRӮЕӮ ӮиҒA“–‘Rҗм‘әӮа“ҢӢһӮМҺwҺҰӮЕ“®ӮӯӮЧӮ«ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮӘҒAӮұӮкӮрӮ ӮБӮіӮиӮЖҸRӮБӮДҢ©Ӯ№ӮҪӮМӮӘҗм‘әӮМҢүӮўӮЖӮұӮлӮҫӮлӮӨҒBҢR•Тҗ¬ҢгҒA‘еҺRӮЖӮМүп’kӮЙҚЫӮөӮД‘ҒҒXӮЙў‘ҚҺi—Я•”(‘еҺR)ӮМҺwҠцӮЙҸ]ӮӨЈҲУҺvӮр•\–ҫӮөӮДӮўӮйҒBҢгӮМ“ъ–{ҢRӮЕӮ ӮкӮОҢR–@үпӢcӮЕӮЯӮБӮҪҗШӮиӮЖӮИӮйҸdҚЯӮИӮнӮҜӮҫӮӘҒAӮ ӮйӮўӮНӮұӮМҢҲ’fӮЙӮжӮБӮД•т“VүпҗнӮН‘еӮўӮЙ“®ӮўӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўҒB ҺһӮЙҳIҢRҺwҠцҠҜӮМғNғҚғpғgғLғ“ӮНҒA—·ҸҮӮрҠЧӮЖӮөӮҪҒwӢ°ӮйӮЧӮ«”T–ШҢRҒxӮМҸҠҚЭӮрӮВӮ©ӮЭӮ©ӮЛӮДӮЁӮиҒAҸнӮЙӮ»ӮМ“®ҢьӮрӢCӮЙӮ©ӮҜӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮсӮИҗЬҒAғҚғVғAӮМ’і•с–ФӮӘҚ¶—ғ•ы–К(“ъ–{ӮМүE—ғ•ы–К)ӮЙ”T–ШҢRӮМҲк•”‘аӮр”ӯҢ©ҒB”T–ШҢRӮНҠӣ—ОҚ]•ы–КӮЕҗiҢR’ҶӮЖӮМ•сӮрӮ Ӯ°ӮҪҒBӮұӮМҲк•”‘аӮНҒAҠщӮЙҗм‘әӮМҺwҠцүәӮЙ“ьӮБӮҪҒgҢіҒh”T–ШҢRӮМ•”‘аӮЕӮ ӮиҒAӮұӮМҠЁҲбӮўӮЙӮжӮБӮДғҚғVғAҢRӮН•”‘аӮМү^—pӮрҚӘ–{Ӯ©ӮзҢлӮБӮҪӮЖӮўӮҰӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒAҺе—НӮрҠӣ—ОҚ]ҢRӮМ•ы–КӮЦӮЖҚ·ӮөҢьӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ҡӣ—ОҚ]ҢRӮНҒAӢ}•Тҗ¬ӮМҸгҒAӢK–НӮаҸ¬ӮіӮӯҒAӮЬӮҪҒAҺе—НӮӘҳV•әӮЕӮ ӮБӮҪҺ–ӮаӮ ӮиҒAӮ»ӮМ”\—НӮН‘јӮМҢRӮЙ”дӮЧӮД’ҳӮөӮӯ—тӮйӮЖҢ©ӮзӮкӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮсӮИӮЖӮұӮлӮЙҺе—НӮр’@Ӯ«ҚһӮЬӮкӮкӮО‘ҰҺһ•ІҚУӮаӮ Ӯи“ҫӮйӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒcҒBҺАҚЫӮЙӮНӮ»ӮӨӮНӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЙӮНҗм‘әӮМҗl•ҝӮӘӢӯӮӯүeӢҝӮөӮДӮўӮҪӮЖӮМ•]ӮӘҸӯӮИӮ©ӮзӮёӮ ӮйҒBҠӣ—ОҚ]ҢRӮМ•әҺmӮНӮЭӮ¶ӮЯӮҫӮБӮҪҒB”N—о‘wӮӘҚӮӮўӮМӮНҢг”хӮМҗlҠФӮӘ‘ҪӮўӮ©ӮзӮЕӮ ӮиҒAӮ·ӮИӮнӮҝғXғyғAӮЕӮ ӮйҒB”T–ШҢRӮ©Ӯз—рҗнӮМ•‘‘дӮрҲшӮ«”ІӮўӮДӮ«ӮДӮўӮйӮЖӮНҢҫӮҰҒAӮұӮҝӮзӮНҒwҢгӮЙҗёҗ_Ӯр•aӮЮӮЩӮЗӮМҺҖҗьҒxӮрӮӯӮ®ӮБӮДӮ«ӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМ”жҳJӮаӮНӮИӮНӮҫӮөӮўҒBӮ»ӮМҸг”T–ШҢRӮЙ‘ОӮ·Ӯй•]үҝӮНҚӮӮӯӮИӮўӮМӮҫӮ©ӮзҒAҠӣ—ОҚ]ҢRӮӘҺьҲНӮМ•”‘аӮ©ӮзҒuҠсӮ№ҸWӮЯҒvӮЖҡ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҸуӢөӮЙҒAҢ»Ҹк•әҺmӮНӮжӮЩӮЗ‘ПӮҰ“пӮ©ӮБӮҪӮНӮёӮҫҒB ‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘еҺRӮЖҒAӮіӮөӮДҗн—рӮМ•ПӮнӮзӮИӮўҗм‘әӮНӮұӮкӮрҺ@ӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBҺ©Ӯз‘OҗьӮЙӮЁӮаӮЮӮўӮД–јӮа–іӮўҳV•әӮзӮЙҗәӮрӮ©ӮҜӮДӮЬӮнӮБӮҪҒBӮұӮМҺһҒA”зӮМҢRҢCӮ©ӮзӮнӮҙӮнӮҙ‘җиЬӮЙ—ҡӮ«‘ЦӮҰӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйҒB“–ҺһӮМ“ъ–{җlӮМ—ҡ•ЁӮН‘җиЬӮЕӮ ӮиҒAҢR‘аӮЙ“ьӮйӮЬӮЕҢCӮ·ӮзҢ©ӮҪҺ–ӮаӮИӮўҗlҠФӮӘ‘е”јӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBҗм‘әӮН’PӮЙӢ@”\“IӮҫӮ©Ӯз‘җиЬӮЙ—ҡӮ«‘ЦӮҰӮҪӮЖӮМҗаӮаӮ ӮйӮӘҒA––’[ӮМ•әҺmӮзӮЙӮЖӮБӮДӮНҗeӮөӮЭӮвӮ·Ӯў•—–eӮЕӮ ӮБӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒB‘җиЬҺpӮЕӮвӮаӮ·ӮйӮЖҠлҢҜӮИ‘OҗьӮр•аӮ«үсӮиҒAӮЁӮ»ӮзӮӯӮН“ҜӮ¶–ЪҗьӮЕ•әҺmӮзӮЖҗәӮрҢрӮнӮөӮҪҒBӮұӮМҢгҒAғҚғVғAҢRӮМ–ТҚUӮрҺуӮҜӮҪҠӣ—ОҚ]ҢRӮМҳV•әӮзӮНҒAүә”n•]ҲИҸгӮМ“ӯӮ«ӮрӮөӮҪҒB–{“–ӮМ”T–ШҢRӮӘҚ¶—ғ•ы–КӮЙӮўӮйҺ–ӮЙҳIҢRӮӘӢCӮГӮӯӮЬӮЕҺқӮҝӮұӮҪӮҰҒAӮұӮМҠФӮЙ–м’Г“№ҠСӮзӮМҺе—НӮӘҗ–җЁӮрҲ¬ӮйҺ–ӮЙҗ¬ҢчӮөҒA•т“VӮЕӮМҸХ“ЛӮрӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮДҗhҸҹӮЙӮЬӮЕҺқӮҝҚһӮЮҺ–ӮӘүВ”\ӮЖӮИӮБӮҪҒBҲкҳAӮМҚs“®Ӯ©Ӯз”»’fӮ·ӮкӮОҒAҗм‘әӮН‘Ҡ“–ӮЙҒwҗl•ЁҒxӮЕӮ ӮйӮЖҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҲкҠН‘а | |
|
ҒЎ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY 1848-1934 ҺF–Җ”ЛүәүБҺЎү®’¬
“ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДғҚғVғAӮМғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрүу–ЕӮіӮ№ӮҪҒA“ъ–{ҳAҚҮҠН‘аӮМҺi—Я’·ҠҜҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМүp—YӮЖӮөӮДҗўҠE’ҶӮЙҚLӮӯ’mӮзӮкӮйӮӘҒAҢі—ҲүЗ–ЩӮИғ^ғ`ӮҫӮБӮҪҸгҒA•aҺгӮҫӮБӮҪҺ–ӮаӮ ӮБӮДҺьҲНӮ©ӮзӮМ•]үҝӮНҢҲӮөӮДҚӮӮўӮЖӮНҢҫӮҰӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘҒA“ъҳIҗн‘ҲҠJҗнӮЙҗж—§ӮҝҒA“ъ–{ҠCҢRӮМҲзӮДӮМҗeӮЖӮаҢҫӮҰӮйҠCҢR‘еҗbҺR–{Ң •әүqӮЙӮжӮй‘е”І“FӮрҺуӮҜҒAҠХҗEӮЕӮ ӮБӮҪ•‘’Я’БҺз•{Һi—Я’·ҠҜӮ©ӮзҒAҲк–ф•\•‘‘дӮЦӮЖ“oҸкӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB Ӯ»ӮкӮЬӮЕҒA“ъҳIҠJҗнҺһӮМҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮНҒA“–ҺһӮМҸн”хҠН‘а(•ҪҺһӮМҠН‘а)Һi—Я’·ҠҜӮЕӮ ӮБӮҪҚӢҢҶҒA“ъҚӮ‘s”VҸе’ҶҸ«(ҺF–Җ”Л)ӮӘӮ»ӮМӮЬӮЬ”C–ҪӮіӮкӮйҺ–ӮЙӢ^–вӮрӢІӮЮҺТӮНӮЁӮзӮёҒA“–ӮМ“ъҚӮ’ҶҸ«ӮаҺ©ӮзӮӘ“ъ–{ҠCҢRӮр—ҰӮўӮДғҚғVғAӮрҢ}ӮҰҢӮӮВҗSӮГӮаӮиӮҫӮБӮҪҒBӮӘҒA—c“йҗхӮЕӮаӮ ӮиҒA–ҝ—FӮЕӮаӮ ӮйҺR–{‘еҗbӮӘ•ъӮБӮҪӢt“]җlҺ–ӮЕҒA“ъҚӮӮНғҚғVғAҢ}ҢӮӮМ‘еҺdҺ–Ӯ©ӮзҠOӮіӮкӮйҢӢүКӮЖӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮұӮкӮр•·ӮўӮДҢғҚVӮөӮҪ“ъҚӮӮНҒA’ZҢ•Ӯр”ІӮўӮДҒuҢ •әүqҒAӮұӮкӮЕүҙӮрҺhӮ№!!ҒvӮЖҺR–{‘еҗbӮЙӢlӮЯҠсӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB “ъҚӮӮЙҢАӮзӮёҒAҠCҢRҠЦҢWҺТӮМ‘ҪӮӯӮНҸнӮЙ–іҢыӮИ“ҢӢҪӮМҺА—НӮрӮВӮ©ӮЭ‘№ӮЛӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМ”\—НӮНҠTӮЛҒw–ў’mҗ”ҒxӮЖӮўӮӨҺ–ӮЕҲк’vӮөӮДӮўӮҪҒB’ҶӮЙӮНҺR–{ӮМҢҲ’fӮр—җ–\ӮИҗlҺ–ӮЖӮөӮДҳIҚңӮЙ”ыӮрӮРӮ»ӮЯӮҪҺТӮаӮўӮӯӮзӮ©ӮЁӮиҒAӮұӮМҺһ“_ӮЕӮНҒAҚЎ“ъҗўҠФӮЕҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮжӮӨӮИүp—Y“ҢӢҪӮНӮЬӮҫ‘¶ҚЭӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB ӮұӮМҗlҺ–ӮЙӮВӮўӮДӮНӢ{’ҶӮЕӮаҳb‘иӮЙӮИӮБӮҪӮзӮөӮӯҒAӮ ӮйҺһ–ҫҺЎ“VҚcӮӘҺR–{‘еҗbӮЙ“ҢӢҪ”І“FӮМ—қ—RӮрӮЁҗqӮЛӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҺR–{‘еҗbӮНҒu“ҢӢҪӮНү^ӮМ—ЗӮў’jӮЕӮІӮҙӮўӮЬӮ·Ӯ©ӮзҒvӮЖҒAӮ ӮЬӮиӮЙӮа—L–јӮИҲкҢҫӮрҢЈҸгӮөӮДӮўӮйҒB үКӮҪӮөӮДҺR–{ӮНҒAү^ӮҫӮҜӮЕ“ҢӢҪӮрҚМ—pӮөӮҪӮМӮҫӮлӮӨӮ©ҒHҺR–{ӮӘ“ҢӢҪӮрҚМ—pӮ·ӮйӮЙӮ ӮҪӮиҒA“ҢӢҪӮМҒwҸn—¶ӮЙҸn—¶ӮрҸdӮЛӮҪҸгӮЕҺАҚsӮЙҲЪӮ·ҒxӮЖӮўӮӨҗTҸdӮИҗ«ҠiӮр•]үҝӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМҗ«ҠiӮр”@ҺАӮЙӮ ӮзӮнӮ·—бӮӘҒA“ъҳIҠJҗнӮМ10”N‘OҒA“ъҗҙҗн‘ҲҺһӮЙӮЁӮҜӮйүpҚ‘җР‘D”•ӮМҢӮ’ҫҺ–ҢҸӮҫҒB “ҢғVғiҠCӮМҠCҸгӮЕҒwҗҙӮМ•әҺmҒxӮр–һҚЪӮөӮҪүpҚ‘җРӮМү^”А‘DӮЙ‘ҳӢцӮөӮҪ“ҢӢҪӮНҒA’вҺ~–Ҫ—ЯӮр–іҺӢӮ·ӮйүpҚ‘‘DӮЦӮМ‘ОүһӮЙ‘еӮўӮЙ–АӮБӮҪҒBӮЖӮНҢҫӮҰ‘I‘рҺҲӮНӮҪӮБӮҪӮМ2 ӮВҒAҒwҢӮ’ҫҒxӮ©Ғw•ъ’uҒxӮМӮЭҒB“–ҺһӮНӮЬӮҫ‘DҸгӮ©Ӯз’ҶүӣӮЦҳA—ҚӮрӮЖӮйҺи’iӮӘ”ӯ’BӮөӮДӮЁӮзӮёҒAҚ‘ҚЫ–@ӮЙ‘ҘӮБӮҪҒw“KҗШӮИ‘ОүһҒxӮН‘SӮД“ҢӢҪҲкҗlӮЙӮдӮҫӮЛӮзӮкӮҪҒBғGғҠҒ[ғg‘өӮўӮМҠCҢRӮЙӮЁӮўӮДҒA“ҢӢҪӮНҢҲӮөӮД“ӘӮМүс“]ӮӘ‘ҒӮў•ыӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮӘҒA“–ӮМ“ҢӢҪҺ©җgӮӘӮ»ӮМҺ–Ӯрҗ[Ӯӯ”FҺҜӮөӮДӮЁӮиҒAҗlҲк”{ҺһҠФӮрӮ©ӮҜӮДҚlӮҰҒAҚlӮҰ”ІӮўӮҪ––ӮЙҢҲ’fӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҢӮ’ҫӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҢӢҳ_ӮЙҺҠӮйӮЬӮЕҒA“ҢӢҪӮНҗҙӮМ•әҺmӮзӮрҠб‘OӮЙҒAҺАӮЙ4ҺһҠФӮаҸn—¶ӮрҸdӮЛҒAӮұӮМҸуӢөүәӮЙӮЁӮҜӮйҢӮ’ҫӮӘҚ‘ҚЫ–@ҸгҒAүҪӮз–в‘иӮИӮўҺ–ӮрҠmӮ©ӮЯӮ Ӯ°ӮҪҸгӮЕҺАҚsӮЙҲЪӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҺ–ҢҸӮНҲкҺһҚ‘“аҠOӮр‘ӣ‘RӮЖӮіӮ№ӮҪӮӘҒAҢӢүК“IӮЙ“ҢӢҪӮМҚs“®ӮН“№—қӮЙүҲӮБӮҪӮаӮМӮЖӮөӮДҒAүpҚ‘ӮЖӮМҗӯҺЎ–в‘иӮЙ”ӯ“WӮ·ӮйҺ–ӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBҺR–{Ң •әүqӮНӮұӮМҺһӮМ“ҢӢҪӮМүp’fӮрҚӮӮӯ•]үҝӮөӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮкӮӘҳAҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮЦӮМ”І“FӮЙӮВӮИӮӘӮБӮҪҺ–ӮНҠФҲбӮўӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBӮЬӮҪҒA•КӮМ—vҲцӮМҲкӮВӮЖӮөӮДҒAҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЙӢ»–Ўҗ[ӮўғGғsғ\Ғ[ғhӮӘӢLҚЪӮіӮкӮДӮўӮйҒB ҠT—ӘӮ·ӮкӮОҒAҒuҒcҺR–{Ң •әүqӮНҺбӮўҚ ӮН”сҸнӮЙӢCҗ«ӮӘҚrӮӯҒA“Ҝ—»ӮзӮЙ•РӮБ’[Ӯ©ӮзҢ–үЬӮрӮУӮБӮ©ӮҜӮДӮўӮҪ(ӮұӮкӮНҺF–ҖӮМ•—ҸKӮЕӮаӮ Ӯй)ҒB—ҜҠwӮ©ӮзӢAҚ‘ҢгӮЙ”z‘®ӮіӮкӮҪҠНӮЕӮіӮіӮўӮИҺ–Ӯ©Ӯз“ҢӢҪӮЖҢыҳ_ӮЙӮИӮиҒAӮұӮұӮЕ“ҢӢҪӮр‘ЕӮҝ•үӮ©ӮөӮДӮвӮлӮӨӮЖҒA“ҫҲУӮМғ}ғXғgҸёӮиӮЕӢЈ‘ҲӮө”’Қ••tӮҜӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒB“ҢӢҪӮаӮұӮкӮЙүх‘шӮ·ӮйӮӘҒAҢӢүКӮН“ҢӢҪӮӘ”ј•ӘӮа“oӮзӮИӮўӮӨӮҝӮЙҺR–{ӮӘғ}ғXғgӮМ’ёҸгӮЬӮЕҸёӮиӮ«ӮйӮЖӮўӮӨҲіҸҹӮҫӮБӮҪҒBӮӘҒA•үӮҜӮӘҠm’иӮөӮҪҢгӮа“ҢӢҪӮНғmғҚғmғҚӮЖғ}ғXғgӮМ’ёҸгӮЬӮЕҸёӮиӢlӮЯҒAӮ»ӮұӮЕҸүӮЯӮДҒwӮЁӮўӮМ•үӮҜӮҪӮў!!ҒxӮЖҠҙ•һӮөӮДҢ©Ӯ№ӮҪҒcҒBҒv“r’ҶӮЕғTғWӮр“ҠӮ°ӮёҒAҚЕҢгӮЬӮЕӮвӮиҗӢӮ°ӮҪҸгӮЕ“°ҒXӮЖ•үӮҜӮр”FӮЯӮй—lӮЙҒAҺR–{ӮН“ҢӢҪӮМүщӮрҠҙӮ¶ҒA‘еӮўӮЙҠЦҗSӮөӮҪӮЖӮМҺ–ӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮӨӮўӮБӮҪҢoҲЬӮаӮ ӮБӮДҳAҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮЖӮИӮБӮҪ“ҢӢҪӮНҒAү©ҠCӮМҠCҗнӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮЙ‘ЕҢӮӮрүБӮҰҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕҺе—НӮМғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрҹr–ЕҒBҺjҸг—ЮӮМ–іӮўҗнүКӮЕҲИӮБӮДҠCҢRӮМүp—YӮЖӮИӮйӮМӮҫӮӘҒAү©ҠCҠCҗнҲИҢгҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЬӮЕӮМҗ”ғ–ҢҺӮМҠФӮНҒAӮРӮҪӮ·Ӯз’n“№ӮЙҺЛҢӮҢP—ыӮрҢJӮи•ФӮөҒAүpҚ‘ӮМҠПҗн•җҠҜӮ©ӮзҒuҗЩ—тӢЙӮЬӮиӮИӮўҒvӮЖҚ“•]ӮіӮкӮҪҠН–CӢZҸpӮрҒuҠпҗХ“IӮИ–Ҫ’Ҷ—ҰҒvӮЖҡXӮзӮ№ӮйӮЬӮЕӮЙҲзӮДҸгӮ°ӮҪҒBҠCҗнӮЕӮНҒu‘ҪӮӯӮМ’eӮр“–ӮДӮҪ•ыӮӘҸҹӮВҒvӮЖӮўӮӨғVғ“ғvғӢӮИҢҙ—қӮрҗMҸрӮЖӮ·ӮйҲк•ыӮЕҒAҒuҠCҸгӮЕӮМ‘е–CӮНӮ»ӮӨӮ»ӮӨ“–ӮҪӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҢ»ҺАӮрҺFүpҗн‘ҲҲИҢгҒAҗgӮрӮаӮБӮД’ЙҠҙӮөӮДӮўӮҪ“ҢӢҪӮӘҒAӮ»ӮМҗ«ҠiӮӘ•\Ӯ·ӮӘ”@Ӯӯ’n“№ӮЙҒAӮРӮҪӮ·Ӯз’n“№ӮЙҳAҚҮҠН‘аӮрҢӨ–ҒӮөӮҪҢӢүКҒA—рҺjӮЙ—ЮӮрҢ©ӮИӮўҲіҸҹӮЙӮВӮИӮӘӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB”ЮӮМҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮДӮМҚЕ‘еӮМҗ¬үКӮНҒA’n–ЎӮИӮӘӮзӮаӮұӮұӮЙӮ ӮБӮҪӮМӮНҠФҲбӮўӮИӮўҒB “ҢӢҪӮЙӮН—L–јӮИ‘}ҳbӮӘӮ ӮйҒBғҚғVғA–{Қ‘ӮжӮи”hҢӯӮіӮкӮҪҺе—НӮМғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрҢ}ҢӮӮ·ӮйӮЙӮ ӮҪӮиҒA“ъ–{ҠCҢRӮНҒuғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮН‘О”nҠCӢ¬Ӯр’КүЯӮ·ӮйҒvҺ–Ӯр‘е‘O’сӮЖӮөӮҪҸгӮЕҚмҗнӮр—§ҲДӮөҒAӮ»ӮкӮЙҸ]ӮБӮД‘SӮДӮӘҗiҚsӮөӮДӮўӮҪҒBӮӘҒAҠМҗSӮМғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮН5ҢҺӮМ14“ъӮЙғtғBғҠғsғ“ӮрҸo”ӯӮөӮДҲИҚ~ҒAӮўӮВӮЬӮЕӮҪӮБӮДӮа“ъ–{ӮМҸЈүъ–ФӮЙӮРӮБӮ©Ӯ©ӮзӮИӮўҒBҠCҢR“аӮНӮЁӮлӮ©‘е–{үcӮЕӮаҒuғҚғVғAӮНҠщӮЙ‘ҫ•Ҫ—m‘ӨӮр’КӮБӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒHҒvӮЖӮМӢ^”OӮӘ“ъ‘қӮөӮЙҚӮӮЬӮБӮДӮўӮБӮҪҒBӮаӮөӮ»ӮкӮӘ–{“–ӮЕӮ ӮкӮО“ъ–{ҠCҢRӮМҚмҗнӮН‘SӮДӮӘҗ…–AӮЙӢAӮ·ӮЗӮұӮлӮ©ҒAҢҲҗнӮӘҗжү„ӮОӮөӮЙӮИӮйҺ–ӮЕҗн‘ҲӮӘ’·Ҡъү»ӮөҒAҚuҳaӮЗӮұӮлӮ©”ж•ҫӮөӮҪ–һҸBӮМ—ӨҢRӮӘүу–ЕӮіӮ№ӮзӮкӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝ”sҗнҒЛ‘®Қ‘ү»ҒЛҚ‘“yҸБҺёҒЛ“ъ–{–Е–SӮҫҒB ҒuӮаӮөӮа‘О”nӮр’КӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮзҒcҒvӮұӮМғvғҢғbғVғғҒ[ӮЙ‘ПӮҰӮ©ӮЛҒAҚмҗн—§ҲДӮМ’Ј–{җlӮЕӮ ӮйҺQ–dҸHҺRҗ^”VӮӘҒAҺ©ӮзҒu‘О”nҢ}ҢӮҲДҒvӮМ•ъҠьӮрҺе’ЈӮөҺnӮЯӮйӮИӮЗҒAҠCҢR“аӮМҳT”ӮӮН–ЪӮЙ—]ӮйӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМҸуӢөӮрҢ©Ӯ©ӮЛӮҪ‘ж“сҠН‘аӮМ“Ү‘ә‘¬—Y(ҸHҺRҺQ–dӮМҢіҸгҺi)ӮНӮнӮҙӮнӮҙғ{Ғ[ғgӮрӮұӮўӮЕҠшҠНҺOҠ}ӮМ“ҢӢҪӮр–KӮЛӮҪҒB•”ү®ӮЙ“ьӮйӮИӮиҲҘҺAӮа”ІӮ«ӮЕҒu’·ҠҜӮНҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮНӮЗӮұӮр’КӮйӮЖӮЁҚlӮҰӮЕӮ·Ӯ©ҒvӮЖ’P’јӮЙҗqӮЛӮҪҒB“Л‘RӮМ–K–вҒEҺҝӢ^ӮЙӢБӮўӮҪ•—Ӯа–іӮӯҒAҸӯӮөҚlӮҰӮҪ“ҢӢҪӮНӮҪӮБӮҪҲкҢҫ“ҡӮҰӮДһHӮӯҒA ҒuӮ»ӮкӮН‘О”nҠCӢ¬ӮжҒv “ҢӢҪӮМӢЙ’[ӮЙ–іҢыӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйӮӘҒAҺб”NҺһӮНӮжӮӯҢyҢыӮр’@ӮўӮДҺё”sӮөӮДӮўӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкҒAҲИҢг”ӯҢҫӮЙӮЬӮЕҸn—¶ӮрүБӮҰӮҪ’·”NӮМҸKҠөӮЙӮжӮБӮДҒAҢгӮМ–іҢыӮИҗ«ҺҝӮӘӮЕӮ«Ӯ ӮӘӮБӮҪӮаӮМӮЖҗ„Һ@ӮЕӮ«ӮйҒB“Ү‘әӮЖӮМ‘О–КҢгҒAӮ»ӮМӮЬӮЬ“ҢӢҪӮНҠН‘аӮр‘ТӢ@ӮіӮ№‘ұӮҜҒAҠCҗнҺjҸгҚЕҸүӮЕҚЕҢгӮМ‘еҺdҺ–ӮрҗӢҚsӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB“ҢӢҪӮМҺpҗЁӮЖҲМӢЖӮНҒAҚ‘“аӮМӮЭӮИӮзӮёҠCҠOӮМҠCҢRҠЦҢWҺТӮзӮ©ӮзӮаҚӮӮӯ•]үҝӮіӮкӮҪҒB‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲҺһӮМ•ДҚ‘‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮМғ~ғjғbғc’с“ВӮНҒAҚЕӮа‘ёҢhӮ·ӮйҢRҗlӮЖӮөӮД“ҢӢҪҢіҗғӮМ–јӮрӢ“Ӯ°ӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪ’йҗӯғҚғVғAӮЙӢкӮөӮЯӮзӮкӮДӮўӮҪғtғBғ“ғүғ“ғhӮЙӮЖӮБӮДӮа“ҢӢҪӮНүp—YӮЕӮ ӮиҒAҲкҺһҠъҺqӢҹӮЙTogoӮМ–ј‘OӮӘ•p”ӯӮөӮҪӮЖӮМ“`җаӮаӮ ӮйҒB җнҢг“ҢӢҪӮНҗ¶Ӯ«ӮИӮӘӮзӮЙӮөӮДҢRҗ_ӮЙҚХӮиҸгӮ°ӮзӮкҒA‘Ю–рҢгӮаҠCҢRӮМӮІҲУҢ©”ФӮЖӮИӮйҒBҢ»–рӮМҠCҢRҸd–рӮӘҒAҸd—vҺ–ҚҖӮрҢҲ’иӮМҚЫӮЙ•KӮё“ҢӢҪӮМҲУҢ©Ӯр•·ӮӯҺ–ӮӘҸKҠөү»ҒAҢӢүКӮЖӮөӮД“ъ–{ӮНҺе—НӮӘҚqӢуӢ@ӮЙҲЪӮи•ПӮнӮйҺһҗЁӮЙҸжӮи’xӮкҒAҸәҳaӮЙ“ьӮБӮҪҢгӮа‘еҠНӢҗ–CҺеӢ`ӮМҺф”ӣӮЙӮЖӮзӮнӮк‘ұӮҜӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒBҒwҗжҗlӮрҢhӮӨҒxӢV—зӮНүдҒXӮМҚ‘–Ҝҗ«ӮЙӮЁӮҜӮй‘ёӮў•”•ӘӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮН“ҜҺһӮЙҒw‘O—бҺҠҸгҺеӢ`ҒxӮЙӮжӮйҺvҚl’вҺ~ӮЖҺҶҲкҸdӮМҗ«ҺҝӮрҺқӮВҒBӮ»ӮМҢгӮМ“ъ–{ҠCҢRӮМҚsӮ«’…ӮӯҗжӮН—рҺjӮМҺҰӮ·ӮЖӮЁӮиӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүБ“Ў—FҺOҳY 1861-1923 ҚL“Ү”Л
“ъ–{ҠCҠCҗнҺһӮЙӮЁӮҜӮйҳAҚҮҠН‘аҺQ–d’·ҒBҢгӮЙҠCҠOӮМӢLҺТӮ©ӮзғҚғEғ\ғNӮЖӮ Ӯҫ–јӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙҚЧҗgӮМ•—–eӮҫӮБӮҪҒB ҺmҠҜҠwҚZҺһ‘гӮНҒA“Ү‘ә‘¬—Y(‘ж“сҠН‘аӮЦ“]Ҹo)ӮЖҺеҗИӮр‘ҲӮӨ—DҸGӮФӮиӮрҢ©Ӯ№ӮҪӮӘҒAҗlҠФ–ЎӮЙӮ ӮУӮкҺьҲНӮ©ӮзӮМҗM—ҠӮаӮ ӮВӮ©ӮБӮҪ“Ү‘әӮЖӮНҗ«ҠiӮМ–КӮЕ‘ОҸЖ“IӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB ҺF–ҖҒE’·ҸBӮМҗlҠФӮӘҸd—vӮИғ|ғXғgӮр“ЖҗиӮөӮДӮўӮҪ“–Һ–ӮЙӮЁӮўӮДҒAҺF’·”ҙӮЕӮИӮўӮЙӮаҠЦӮнӮзӮё’…ҺАӮЙ’nҲКӮрҸгӮ°ӮДӮўӮБӮҪӮМӮН“Ә”]ӮМ–ҫқрӮіӮЙӮжӮйӮаӮМӮҫӮӘҒA“Б•MӮ·ӮЧӮ«“_ӮНүБ“ЎӮМҚЛӮрҚӮӮӯ”ғӮБӮҪҺF–ҖӮМҺR–{Ң •әүqӮЙӮжӮйҢгүҹӮөӮҫӮлӮӨҒBҺF–Җ”ҙӮМҸoҗgӮИӮӘӮзӮа”h”ҙӮЙӮұӮҫӮнӮзӮИӮўҗlҺ–ӮрҚsӮБӮДӮўӮҪҺR–{ӮНҒA‘ҒӮӯӮ©ӮзүБ“ЎӮр”І“FӮөҒAҺ©ӮзӮМҢгҢpҺТӮМҲкҗlӮЖӮөӮДҸ\җ””NӮЙ“nӮБӮДӢіҲзӮрӮЩӮЗӮұӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮ»ӮМүБ“ЎӮӘҳAҚҮҠН‘аӮМҺQ–d’·ӮЖӮөӮД—E–фӮөҒAҢгӮЙӮН‘Қ—қ‘еҗbӮЙӮЬӮЕҸгӮиӢlӮЯӮйӮМӮҫӮ©ӮзҒAҺR–{Ң •әүqӮМӢіҲзӮЖҗжҢ©ӮМ–ҫӮЙӮНүьӮЯӮДҠҙ’QӮ·ӮйӮөӮ©ӮИӮўҒB “ъҳIӮӘҠJҗнӮ·ӮйӮЙӮ ӮҪӮиҒA“–ҸүҒAҳAҚҮҠН‘аӮМҺQ–d’·ӮН“Ү‘ә‘¬—YӮҫӮБӮҪҒBӮұӮкӮН‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМҲУҢьӮаӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкҒAҺQ–d’·ӮЙ“а’иӮөӮДӮўӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйүБ“ЎӮНҸг‘ә•F”VҸе—ҰӮўӮй‘ж“сҠН‘аӮМҺQ–d’·ӮЙҒBҸг‘әҠН‘аӮӘғEғүғWғIҠН‘а•в‘«ӮЙҺё”sӮөҒA“{ӮБӮҪҚ‘–ҜӮ©Ӯз—ҜҺз‘оӮӘ“ҠҗОӮіӮкӮҪҚЫҒAҺQ–d’·ӮМүБ“Ў‘оӮа“ҜӮ¶Ӯӯ“ҠҗОӮрҺуӮҜӮДӮўӮйҒBӮӘҒAүUҺRү«үпҗнӮЕҗбҗJӮрҗ°ӮзӮөӮҪҢгӮЙҳAҚҮҠН‘аӮМҺQ–d’·ӮЖӮөӮД“]”CҒA‘гӮнӮиӮЙ“Ү‘әҺQ–d’·ӮӘ‘ж“сҠН‘аӮМ‘ж“сҗн‘аҺwҠцҠҜӮЖӮөӮД“]ҸoӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮБӮҪҒB җ¶җ^–К–ЪӮИүБ“ЎӮЖӮөӮДӮНҒAҳAҚҮҠН‘аӮМ–TҺб–іҗlӮИҸHҺRҗ^”VҺQ–dӮӘ–ЪҸбӮиӮҫӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйӮӘҒAүБ“ЎӮаҸHҺRӮМҚЛ”\ӮНҚӮӮӯ”ғӮБӮДӮЁӮиҒAҚмҗн‘S”КӮНҸHҺRҺе“ұӮЕ“WҠJӮ·ӮйҺ–ӮЙҒB“ъ–{ҠCҠCҗн‘OӮЙӮНҒAӮ»ӮМҸdҲіӮ©ӮзҸHҺRҺQ–dӮӘ‘еӮўӮЙӮвӮВӮкӮҪҳbӮӘ—L–јӮҫӮӘҒAҺQ–d’·ӮҪӮйүБ“ЎӮаҲЭӮӘ‘Ҡ“–ӮЬӮўӮБӮДӮўӮҪӮзӮөӮӯҒAҢRҲгӮЙӮ©Ӯ©ӮиӮ«ӮиӮМ“ъҒXӮӘ‘ұӮўӮҪҒBҢіҒXүБ“ЎӮНӮ©ӮИӮиӮМҺрҚӢӮЖӮөӮД’mӮзӮкӮДӮЁӮиҒA—cҸӯӮМҚ ӮжӮиҠщӮЙҢZӮМ”УҺЮӮМ‘ҠҺиӮрӮөӮДӮўӮҪӮЖӮМҲнҳbӮӘҺcӮйҒBӮұӮМҺһӮМҲЭ’ЙӮНӮ»ӮӨӮөӮҪ’·”NӮМ•ү’SӮЖ–іүҸӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮНҒA“ҢӢҪҒAҸHҺRӮЖ•АӮСҒA–і–h”хӮИҠНӢҙӮЕӮҪӮҫ3җlҚЕҢгӮЬӮЕ—§Ӯҝ‘ұӮҜӮ»ӮМҗE–ұӮр‘SӮӨӮөӮҪҒBҗнҢгҒAҢа’БҺз•{Һi—Я’·ҠҜҒA‘жҲкҠН‘аҺi—ЯҠҜӮИӮЗӮр—р”CӮ·ӮйӮӘҒAӮ»ӮМҠФҒA”Ә‘гҳZҳYӮӘҠCҢR‘еҗbӮЙҸA”CӮөҒAҺR–{Ң •әүqӮМ’zӮўӮДӮ«ӮҪҠCҢRӮМ•ыҗjӮӘҗн‘OӮЖӮНҸҷҒXӮЙҲбӮБӮҪӮаӮМӮЙӮИӮиӮНӮ¶ӮЯӮҪҒBҢгӮЙүБ“ЎӮӘ‘Қ—қ‘еҗbӮЙҸA”CӮ·ӮйӮЙ“–ӮҪӮиҒAҗlҺ–Ӯвҗ§“xӮЙӮЁӮўӮДҺR–{Ң •әүqӮМҲУҺvӮрҢpҸіӮ·ӮйҳHҗьӮрҺжӮйӮаҒAӮұӮМҺһ“_ӮЕҠCҢRӮНҗцҚЭ“IӮИӢT—фӮр“а•пҒBүБ“ЎӮМҺһ‘гӮЙӮЁӮўӮДӮН—ЗҺҝӮИҠCҢRӮӘҲЫҺқӮіӮкӮйӮаҒAҸәҳaӮЙ“ьӮБӮДӮ©ӮзӮН–ҫҺЎӮМҚ ӮЖӮНҲЩҺҝӮМҠCҢRӮЦӮЖ•П–eӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB үБ“ЎӮН•ДҚ‘ӮЖӮМҗн‘ҲӮМүВ”\җ«ӮрҠщӮЙ”FҺҜӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAҢRҸkӮвҠOҢрӮЙӮжӮБӮДӮұӮкӮрүс”рӮ·ӮйҺ–ӮӘҚЕ‘PӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒBҒuҚ‘–hӮНҢRҗlӮМҗк—L•ЁӮЙӮ ӮзӮёҒvӮЖӮаҸqӮЧӮДӮЁӮиҒAҠщӮЙҚ‘ӮрҺ„•Ёү»ӮөӮНӮ¶ӮЯӮҪҢR‘аӮрҠлӮФӮсӮЕӮўӮҪӮЖӮаҢҫӮҰӮжӮӨҒBүБ“ЎӮМҠлңңӮӘӢпҢ»ү»Ӯ·ӮйӮЬӮЕҒAӮ»ӮӨ’·ӮӯӮНӮ©Ӯ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҺ–ӮНҺь’mӮМӮЖӮЁӮиӮЕӮ ӮйҒB —\’fӮҫӮӘҒAҢгӮМ‘еҗнӮМҚЫҒAҚL“ҮӮЙӮ ӮБӮҪүБ“ЎӮМ“ә‘ңӮНҸe’e—pӮМӢа‘®ӮЖӮөӮД’Ҙ—pӮіӮкҒA‘дҚАӮҫӮҜӮӘҺcӮіӮкӮйӮЖӮўӮӨ—JӮ«–ЪӮЙүпӮБӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМ‘дҚАӮа‘еҗн––ҠъӮЙҗўҠEҸүӮМҢҙҺq”ҡ’eӮЙӮіӮзӮіӮкҒAҚЎӮИӮЁҺе–іӮ«‘дҚАӮЖӮөӮДҢ»’nӮЙҺc‘¶ӮөӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸHҺRҗ^”V 1866-1942 ҸјҺR”Л
Ғu’q–dҒA—NӮӯӮйӮӘ”@ӮөҒvӮЖӮН“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЙӮжӮй•]ӮЕӮ ӮйҒBҳAҚҮҠН‘аҺQ–dӮЖӮөӮДҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮМ‘е•”•ӘӮр—§ҲДӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB•—–eӮНҚЫ—§ӮҝҒA–ЪӮВӮ«ӮМүsӮіӮвҚs“®—lҺ®ӮМ“ЖҺ©җ«Ӯ©ӮзҒAҠCҢR“аӮЕӮаҲкҚЫҲЩҚКӮр•ъӮВ‘¶ҚЭӮҫӮБӮҪҒBҗlҲк”{ӮМҸW’Ҷ—НӮЙ’·ӮҜҒAҲк“xҚlӮҰҺnӮЯӮйӮЖ’kҳb’ҶӮЕӮ ӮлӮӨӮЖ‘ҠҺиӮМ‘¶ҚЭӮрҸБӮөӢҺӮБӮДҺvҚlӮЙ–v“ӘӮЕӮ«ӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒB —cҸӯӮжӮиӢCҗ«ӮӘҢғӮөӮӯҒAҸнӮЙҺqӢҹӮзӮМҲ«Һ–ӮМҗж“ӘӮЙ—§ӮВӮжӮӨӮИҗ«ҠiӮҫӮБӮҪӮзӮөӮўҒBӮөӮОӮөӮОҢ–үЬ‘ӣ“®ӮИӮЗӮаӢNӮұӮөҒA—јҗeӮМҗS”zӮНҗsӮ«ӮИӮўғ^ғCғvҒBҗ¬җlӮөӮДӮ©ӮзӮағMғғғ“ғuғӢҸгӮМғgғүғuғӢӮЕҠOҚ‘җlӮМғ`ғ“ғsғүӮрӢәӮөӮВӮҜӮҪғGғsғ\Ғ[ғhӮӘҺcӮйӮжӮӨӮЙҒAҗ¶—ҲӮ»ӮӨӮўӮӨӢCҺҝӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮё•АҠOӮкӮҪ“Ә”]ӮрҺқӮҝҚҮӮнӮ№ӮДӮўӮй“_ӮНҠCҢR‘еҗbӮМҺR–{Ң •әүqӮЖ—ЮҺ—ӮөӮДӮЁӮиҒA—јҺТӮӘҗЪӮөӮҪҚЫӮЙӮЗӮМӮжӮӨӮИӮвӮиӮЖӮиӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮ©”сҸнӮЙӢ»–Ўҗ[ӮўӮЖӮұӮлӮЕӮаӮ ӮйҒB ҸHҺRӮМ“Ә”]ӮМ–ҫқрӮіӮЙӮЁӮўӮДӮНүБ“Ў—FҺOҳYҺQ–d’·ӮзӮрҺnӮЯ‘ҪӮӯӮӘӮ»ӮкӮр”FӮЯӮДӮўӮйӮӘҒA”ЮӮӘ”дҠr“IҺ©—RӮЙҗUӮй•‘ӮҰӮҪӮМӮНҠJҗн“–Һһ‘жҲкҠН‘аҺQ–d’·ӮЕӮ ӮБӮҪ“Ү‘ә‘¬—YӮМ‘¶ҚЭӮӘ‘еӮ«ӮўӮжӮӨӮҫҒBҗнҢгӮЙ“Ү‘әӮНҒu“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҠCҸгҚмҗнӮНӮ·ӮЧӮД”ЮӮМ“Ә”]Ӯ©ӮзҸoӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒvӮЖӮМҸШҢҫӮрҺcӮөӮДӮўӮйӮӘҒAҺАҚЫӮМӮЖӮұӮлӮН“Ү‘әӮӘҒwҸHҺRӮӘ‘SӮДӮрҸoӮ№ӮйӮжӮӨҒxӮЁ‘V—§ӮДӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮ©Ӯа’mӮкӮИӮўҒB “ъҳIҠJҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAҠCҢRӮЙӮЁӮҜӮйҚЕҸүӮМҺRӮН—·ҸҮҢыӮМ•ВҚЗҚмҗнӮҫӮӘҒAӮұӮкӮНҗжӮЙ•Дҗјҗн‘ҲӮЕ•ДҢRӮӘҚsӮБӮҪҚмҗнӮрҺQҚlӮЖӮөӮҪҸHҺRӮЙӮжӮБӮДҺеӮЙ—§ҲДӮіӮкӮҪӮаӮМӮҫҒBҠПҗн•җҠҜӮЖӮөӮД•Дҗјҗн‘ҲӮЙҺQүБӮөӮҪҸHҺRӮН•ДҢRӮМӮұӮМ”ӯ‘zӮЙҠҙ’QӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮӘҒAҺ–ҺАҒA“ъ–{ӮЕӮаҳAҚҮҠН‘а“аӮЕҚмҗн—vҲхӮр•еҸWӮөӮҪҚЫҒA”сҸнӮЙ‘ҪӮӯӮМ•әҺmӮӘӮұӮМҚмҗнҺQүБӮЙҺuҠиӮөҒA‘IӮЙҳRӮкӮҪҺТӮӘҸгҠҜӮЙӢғӮ«ӮВӮўӮДҚмҗнҺQүБӮрҚ§ҠиӮ·ӮйӮЩӮЗӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮҫӮҜҚмҗнӮЖӮөӮД–Ј—Н“IӮЕӮ ӮиҒAӮ©ӮВ‘ҪӮӯӮМ•әҺmӮр–Ј—№Ӯ·ӮйӮҫӮҜӮМҗнүКӮӘҠъ‘ТӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ӮҫӮлӮӨҒBӮӘҒA—§ҲДӮөӮҪҸHҺRҺ©җgҒAӮўӮҙӮ»ӮкӮӘ“®Ӯ«ҺnӮЯӮй’iҠKӮЙӮИӮиҒu•әҲхӮЙҠлҢҜӮӘ‘ҪӮ·Ӯ¬ӮйҒvӮЖӮөӮДӢ}зҜҸБӢЙ“IӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒBӮұӮМ•sҲА’иӮіӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮвҗнҢгӮМҗёҗ_җўҠEӮЦӮМҢX“|ӮЖ’КӮ¶ӮйӮаӮМӮӘӮ ӮйӮӘҒAӢЙӮЯӮДҠҙҗ«ӮӘ–LӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮМ’jӮМғӮғҚӮў•”•ӘӮӘҒAҗнҸкӮМҢ»ҺАӮЙ—hӮіӮФӮзӮкӮДӮўӮҪӮЖүрҺЯӮаӮЕӮ«ӮйҒB —·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнӮНҒAӮўӮҙӮУӮҪӮрҠJӮҜӮДӮЭӮйӮЖӮ»ӮМҗнүКӮН–FӮөӮӯӮИӮӯҒAҲк•ыӮЕҺҖҸқҺТӮӘӮ¶ӮнӮ¶ӮнӮЖ—ЭҗПӮөҺnӮЯӮҪҒBҚмҗнҺwҠцӮрҺжӮБӮҪ—L”n—ЗӢkӮНҺvӮўӮВӮЯӮД‘М’ІӮр•цӮөӮДҗнҗь—Ј’EҒBҸHҺRӮМҗe—FӮЕӮ ӮБӮҪҚLҗЈ•җ•vӮН—·ҸҮ—vҚЗӮМ–C’eӮЙҗgӮрҚУӮ©ӮкҒAҲИҢг“ъ–{ӮЕҚЕҸүӮМҢRҗ_ӮЦӮЖҚХӮиҸгӮ°ӮзӮкӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB ҢӢӢЗӮҪӮўӮөӮҪҗ¬үКӮрҺcӮ№ӮИӮўӮЬӮЬҚмҗнӮН’вҺ~ҒBӮ»ӮМҢгҒAү©ҠCӮМҠCҗнӮИӮЗӮрҢoӮДҳAҚҮҠН‘аӮМҺеҠбӮНӮўӮжӮўӮж—ӨҢRӮЦӮЖҢьӮҜӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮ·ӮИӮнӮҝ203ҚӮ’nӮЕӮ ӮйҒBҢӢүКӮр’mӮйүдҒXӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒA203ҚӮ’nӮрҢyҺӢӮөӮҪғҚғVғAҢRӮв”T–ШҠу“TӮз‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮН–і”\ӮЖҺvӮўӮӘӮҝӮЕӮ ӮйӮӘҒA‘ж“сҺҹ‘еҗнӮрҢoҢұӮөӮҪҢі“ъ–{ҠCҢRҢRҗlӮМҗз‘Ғҗі—ІҺҒӮИӮЗӮНҒA’ҳҸ‘ӮЕҸHҺRҺQ–dӮМүp’mӮрҗвҺ^ӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМҚӮ’nӮЙӮ©ӮИӮи‘ҒӮў’iҠKӮЕ–ЪӮр•tӮҜӮҪҸHҺRӮМҗ_ҠбӮЙҠҙ•һӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮМӮҫҒB ҠmӮ©ӮЙҒAҚqӢуӢ@ӮМ‘¶ҚЭӮөӮИӮў–ҫҺЎҠъӮЙӮЁӮўӮДӮН“сҺҹҢіӮМҠC–К(’n–К)ӮӘ‘SӮДӮЕӮ ӮйҒBҺOҺҹҢіӮМҺӢ“_ӮЕ–{ҺҝӮрҢ©”ІӮӯӮМӮН•АҠOӮкӮҪҠб—НӮМҸШӮҫӮлӮӨҒBғhғCғcӮ©ӮзҸөгЩӮіӮкӮҪ—ӨҢRӮМҢRҺtғҒғbғPғӢӮӘҸ«ҚZӮЙ•K—vӮИҺ‘ҺҝӮЖӮөӮДҒw‘z‘ң—НҒxӮрӢ“Ӯ°ӮДӮўӮйӮӘҒAҸHҺRӮНӮұӮМҚЛӮЙӮЁӮўӮДӮа‘еӮўӮЙ—DӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBӮЖӮаӮ ӮкҒAӮұӮМ203ҚӮ’nӮӘ—·ҸҮҚU—ӘҚмҗнӮЙӮЁӮҜӮйғLҒ[ғ|ғCғ“ғgӮЖҢ©ӮҪҸHҺRӮНҒAҳA“ъҒA—ӨӮ©Ӯз—·ҸҮӮрҚU—ӘӮ·Ӯй”T–ШҠу“TӮМ‘жҺOҢR•ы–КӮЙ–оӮМӮжӮӨӮИ“В‘ЈҸуӮр‘—Ӯи‘ұӮҜӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМ“а—eӮН—қҳHҗ®‘RӮЖӮөӮҪ’·•¶ӮЕӮ ӮиҒAҗжҸoӮМҗз‘ҒҺҒӮНҒAҺQ–dҗEӮМҢғ–ұӮМҚҮҠФӮЙӮ ӮкӮЩӮЗӮМ•¶ҸНӮрҸ‘Ӯ«ҸгӮ°ӮйӮЖӮНӮЗӮӨӮўӮӨҸҲ—қ”\—НӮИӮМӮ©ӮЖӢБӮ«ӮрүBӮіӮИӮўҒB Һi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЕӮНҒA203ҚӮ’nӮЦҺе—НӮрҢьӮҜӮИӮў”T–ШҢRӮЙ‘ОӮөӮДҠCҢRӮӘ‘Ҡ“–ӮўӮзӮҫӮБӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮжӮӨӮИӢLҸqӮӘӮ ӮйӮӘҒAҸHҺRӮМ“В‘ЈҸуӮрҢ©ӮйҢАӮиӮЕӮНҒAӮ»ӮӨӮўӮБӮҪ—ЮӮМ•\Ң»ӮНӮИӮўҒB”T–ШҢRӮМ‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮМҺSӮҪӮйҢӢүКӮрӮЛӮ¬ӮзӮўӮВӮВӮаҒAӮҪӮҫӮРӮҪӮ·Ӯз203ҚӮ’nӮӘ“VүӨҺRӮЕӮ ӮйҺ|Ӯрҳ_Ӯ¶‘ұӮҜӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB12ҢҺӮЙ“ьӮиӮжӮӨӮвӮӯ203ҚӮ’nӮӘҗи—МӮіӮкӮҪ—Ӯ“ъӮМҚГ‘ЈҸуӮЙӮНҒAҳAҚҮҠН‘аҺi—Я•”ӮӘҸ¬–фӮиӮөӮДҠмӮсӮҫҺ|ӮЬӮЕӢLҚЪӮөӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМҗЁӮўӮЕ‘¬ӮвӮ©ӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮЦӮМ–CҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйӮжӮӨҢғ—гӮөӮДӮўӮйҒB—·ҸҮ—vҚЗҠЧ—ҺҢгҒA—·ҸҮҚ`ӮЙ“ьҚ`ӮөӮҪ“ҢӢҪӮЖ”T–ШӮМ–КүпӮӘҗЭӮҜӮзӮкӮҪӮӘҒAҢ»ҸкӮЬӮЕ•tӮ«“YӮБӮҪҸHҺRӮНӮұӮМҺһӮМ–КүпӮр‘еӮўӮЙҠҙ“®“IӮИҸк–КӮЖӮөӮДҺуӮҜҺ~ӮЯӮҪӮЖҢҫӮнӮкҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮа”T–ШҢRӮЙ‘ОӮ·ӮйҚҰӮЭӮӘӮЬӮөӮіӮИӮЗӮНҺҰӮіӮкӮДӮўӮИӮўҒB —·ҸҮҠЧ—ҺҢгҒA“ъ–{ҢRӮНҗ§ҠCҢ ӮрҠ®‘SӮЙҸ¶Ҳ¬ҒAҠщӮЙғҚғVғAӮр”ӯӮөӮҪғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрӮўӮ©ӮЙ—L—ҳӮИ‘Мҗ§ӮЕҢ}ҢӮӮЕӮ«ӮйӮ©ӮӘҺеҠбӮЖӮИӮБӮҪҒBҲИҢгҒAҳAҚҮҠН‘аӮНҠНӮМҗ®”хӮЖ–CҢӮӮМҸC—ыӮЙ‘SӮДӮр”пӮвӮ·ӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҠФӮМҸHҺRӮНҸIҺnҠCҗнӮМғVғ…ғ~ғҢҒ[ғVғҮғ“ӮЙ–v“ӘӮөӮДӮўӮҪӮжӮӨӮҫҒB“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕӮН7’iҚ\ӮҰӮМҚмҗнӮв“ҢӢҪғ^Ғ[ғ“ӮӘ—L–јӮҫӮӘҒAӮ»ӮкҲИ‘OӮМ–в‘иӮЖӮөӮДҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮНҒgӮўӮВӮЗӮұӮр’КӮйӮМӮ©ҒhӮЖӮўӮӨҺ–ӮӘҠCҢRҺс”]•”Ӯр”YӮЬӮ№ӮҪҒBӮ»ӮМ’Ҷҗ•ӮЙӮўӮҪ’jӮӘҸHҺRӮЕӮ ӮиҒAҺQ–d’·ӮМүБ“ЎӮҫӮБӮҪҒB—јҺТӮЖӮаӮұӮМҠФӮЙ‘Ҡ“–ӮвӮВӮкҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮӘғtғBғҠғsғ“Ӯр”ӯӮөӮҪӮЖӮМҸо•сӮӘ“ҫӮзӮкӮДҲИҚ~ҒA”ЮӮзӮМҗҠҺгӮФӮиӮН–ЪӮа“–ӮДӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBӮұӮұӮЙ—ҲӮДҸHҺRӮНҗёҗ_ӮМ•sҲА’иӮіӮрҳI’жӮөҺnӮЯҒAҠщӮЙҢҲ’иӮіӮкӮҪҒw‘О”nӮЕӮМҢ}ҢӮҒxӮр”jҠьӮ·ӮйҺ|ҒAҸҹҺиӮЙ‘е–{үcӮЙ‘—җMӮ·ӮйӮИӮЗҒAӮИӮ©ӮИӮ©ӮМҠлӮӨӮіӮр—рҺjӮЙҚҸӮсӮЕӮўӮйҒB 5ҢҺ27“ъ‘Ғ’©ҒAҒu“GҠНҢ©ӮдҒvӮМ•сӮрҺуҗMҢгҒAҸHҺRӮНҲкҗlҸ¬–фӮиӮөӮДӮўӮйҺpӮр–ЪҢӮӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮМҗ”ҺһҠФҢгӮЙӮ©ӮМ—L–јӮИҒu–{“ъ“VӢCҗ°ҳNӮИӮкӮЗӮа”gҚӮӮөҒvӮМ“dҗMӮӘ‘ЕӮҪӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒBӮўӮжӮўӮжҠCҗнӮӘҺnӮЬӮБӮДӮ©ӮзӮНҒA“ҢӢҪҒAүБ“ЎӮМ—јҺТӮЖӮЖӮаӮЙҠлҢҜӮИҠНӢҙӮЙ—§Ӯҝ‘ұӮҜҒA“ъӮӘ•йӮкӮйӮЬӮЕҗӢӮЙӮ»ӮұӮр“®Ӯ©ӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъ–vҢгӮЙӢм’Җ‘аӮЙӮжӮй‘|“ўҗнӮЙ“ьӮБӮДӮ©ӮзӮНҒAӮРӮҪӮ·Ӯз•сҚҗҸ‘ӮМҚмҗ¬ӮЙ–ұӮЯҒA—Ӯ“ъӮМ’ЗҢӮӮЙӮВӮўӮДҺvӮўӮрӮЯӮ®ӮзӮ№ӮҪҒBҺi”n—Й‘ҫҳYҺҒӮМҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЕӮНҒAҠCҗнҸҳ”ХӮЙ‘еүҠҸгӮөӮҪғҚғVғAҗнҠНҒwғIғXғүҒ[ғ”ғBғAҒxӮМҺSӢөӮр–ЪӮМ“–ӮҪӮиӮЙӮөӮҪҸHҺRӮӘҗ[ӮӯҸХҢӮӮрҺуӮҜӮҪҺ|ӢLҚЪӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҺ–ҺАӮұӮМҗнҠНӮМүҠҸгӮНӮұӮМҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮаҸЫ’Ҙ“IӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB җнҠНӮМ‘•ҚbӮНҒuүјӮЙҺ©ӮзӮМҺе–CӮЕҺ©ӮзӮМ‘•ҚbӮр‘ЕӮҝ”ІӮўӮҪӮЖӮөӮДӮаӮ»ӮкӮЙ‘ПӮҰӮзӮкӮйҒvӮаӮМӮЖ’иӢ`ӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӮұӮМҸрҢҸӮр–һӮҪӮ№ӮИӮўӮаӮМӮНҗнҠНӮЖӮіӮкӮИӮўҒBӮЬӮҪҒA•Ё—қ“IӮЙӮа’ҫӮЬӮИӮўҗЭҢvӮЕӮ ӮиҒA“–Һһ‘z’иӮіӮкӮҪҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДҗнҠНӮӘ’ҫ–vӮ·ӮйҺ–‘ФӮНӮ Ӯи“ҫӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҗнҠНӮӘ–ЪӮМ‘OӮЕ“сҗЗӮаүҠҸгӮөӮДӮўӮйҒB’e–тӮЙҲшүОӮөӮҪҒwғIғXғүҒ[ғ”ғBғAҒxӮМүҠӮЖҚ•үҢӮН“VӮЬӮЕ“НӮ«ҒA“r’ҶҺӢҠEӮӘҲ«Ӯ·Ӯ¬ӮД–CҢӮӮрҺ~ӮЯӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўӮЩӮЗӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮ»ӮөӮДҒAҢҲӮөӮД’ҫӮЬӮИӮўӮЖҢҫӮнӮк‘ұӮҜӮҪӮҪҗнҠНӮНҒAӮвӮӘӮДӮ ӮБӮҜӮИӮӯ’ҫӮсӮҫҒBӮөӮ©ӮаӮұӮМҠCҗнӮр’КӮөӮД’КҺZҳZҗЗӮаӮМҗнҠНӮӘӮұӮЖӮІӮЖӮӯҠC–КӮЙ–vӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB —қҳ_үЖӮЕ”ҺҠwӮҫӮБӮҪҸHҺRӮЖӮөӮДӮНҒAҠН–CӮЕӮМ’ҫ–vӮИӮЗ‘z’иӮөӮҪӮНӮёӮаӮИӮӯҒAӮҫӮ©ӮзӮұӮ»Һ·қXӮИ–йҠФӮМӢӣ—ӢҚUҢӮӮаҠЬӮЯӮҪ7’iҠKӮаӮМҢ}ҢӮ–ФӮрӢкҗSӮөӮДҚ\’zӮөӮҪӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ҒBҸHҺRӮӘӮЗӮМ’iҠKӮЕ•§–еӮрҺuӮөӮҪӮ©ӮН’иӮ©ӮЕӮНӮИӮўҒBӮӘҒAҲкҳAӮМҒwҸo—ҲҺ–ҒxӮӘҸHҺRӮрғLғҠғLғҠӮЖ’чӮЯҸгӮ°ҒAҢӢүКӮЖӮөӮДҢгӮМҗёҗ_җўҠEӮЦӮМҢX“|ӮӘҗ[ӮЬӮБӮҪӮМӮНҠe“`ӢLӮӘ“`ӮҰӮйӮЖӮЁӮиӮҫҒBҸIҺn”ч“®ӮҫӮЙӮ№ӮёҒAҠMҗщҢгӮаҠзҗF•ПӮҰӮёӮөӮОӮөӮО—ҝ’аӮЕ—VӮС“|ӮөӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЖӮНӢЙӮЯӮД‘ОҸЖ“IӮИ––ҳHӮЖҢҫӮҰӮйҒB җнҢгӮНӮ©ӮВӮДӢіҠҜӮЕӮ ӮБӮҪ”Ә‘гҳZҳYӮЖӢЯӮўҲК’uӮЙӮ ӮиҒAӮ©ӮМ—й–ШҠС‘ҫҳYӮрҢR•”Ҹг‘wӮЦҲшӮ«ҸгӮ°ӮйӮИӮЗӮМ“ӯӮ«ӮрҢ©Ӯ№ӮйӮӘҒAҠщӮЙ—ӨҠCҢRӮМҺе“®ӮӘҗӯ‘ҲӮМҗFӮрӢӯӮӯ‘СӮСҺnӮЯӮДӮўӮҪӮұӮМҚ ӮЙӮЁӮўӮДҒAҸHҺRӮМ‘¶ҚЭүҝ’lӮНҺҹ‘жӮЙ”–ӮЬӮБӮДӮўӮБӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒBҲИҢгҒA‘§ҺqӮ𕧖еӮЙ“ьӮкҒAҺ©ӮзӮа“Б’иӮМҸ@ӢіӮЙҢX“|ӮөҒAӢЙӮЯӮДҗГжҚӮЙ—рҺjӮМ•\•‘‘дӮ©Ӯз—§ӮҝӢҺӮБӮДҚsӮБӮҪҒB ҢRҗ_ӮҪӮй“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМүAӮЙүBӮкҒAҚ‘–ҜӮ©ӮзӮН–ЪӮЙӮВӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮМҢчҳJҺТӮаҒAӮаӮҝӮлӮсҠCҢR“аӮЙӮЁӮўӮДӮН’·Ӯӯ“`җа“IӮИҺQ–dӮЖӮіӮкҒA“ъҳIҠJҗнӮ©Ӯз70”NӮрҢoӮҪҢгӮЙҒwҚвӮМҸгӮМү_ҒxӮЙӮжӮБӮДҲк”КӮЙӮаҚLӮӯ–јӮр’mӮзӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҺOҗ{Ҹ@‘ҫҳY 1855-1921 •FҚӘ”Л
‘жҲкҠН‘аҸҠ‘®ҒA‘жҲкҗн‘аҺi—ЯҠҜҒB ‘жҺOҗн‘аӮМҸoүHҸdү“ӮЙ‘ұӮ«ҒAҺF’·”ҙҲИҠOӮЕ‘еҸ«ӮЙӮЬӮЕҸёӮиӢlӮЯӮҪҗl•ЁӮЕӮ ӮйҒBғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮМҸW’Ҷ–CүОӮЙӮжӮБӮД•үҸқҒAҢгӮЙҠCҢRӮМҒw“ЖҠб—іҒxӮМҲЩ–јӮЖӮИӮйҒB җ¶ӮЬӮкӮН•FҚӘ”ЛӮҫӮӘҒAӮұӮұӮМ”ЛҺеӮНҚч“c–еҠOӮМ•ПӮЕ“ўӮҪӮкӮҪҲдҲЙ’ј•JӮЕӮ ӮйҒBҺOҗ{Ҹ@‘ҫҳYӮМҒwҸ@ҒxӮМҺҡӮНҲдҲЙ’ј•JӮМүъ–јӮЕӮ ӮйҒuҸ@ҠПү@–цӢЕҠoүҘӢҸҺmҒvӮЙӮ ӮвӮ©ӮБӮД–Ҫ–јӮіӮкӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA–{җlӮаҲдҲЙ’ј•JӮЙ‘ОӮөӮД‘ёҢhӮМ”OӮр•шӮўӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҲдҲЙ’ј•JӮН‘ёҚcқөҲО”hӮр‘е’eҲіӮөӮҪ’Ј–{җlӮЕӮ ӮиҒAҺF’·ӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй“|–Ӣ”hӮ©ӮзӮЭӮкӮО•¶Һҡ’КӮиӮМҒwӢwҒxӮЕӮ ӮйҒBҠCҢR•әҠw—ҫҺһ‘гӮМҺOҗ{ӮМҢЁҗgӮМӢ·ӮіӮӘ—eҲХӮЙ‘z‘ңӮЕӮ«ӮжӮӨҒBӮұӮМҺһӮМ“ҜҠъӮЙҒAҺF’·”ҙҲИҠOӮЕҸүӮЯӮДҠCҢR‘еҸ«ӮЙҸёӮиӢlӮЯӮҪҸoүHҸdү“ӮӘӮўӮйӮӘҒAӮ©ӮкӮзӮМүh’BӮНӮұӮМҺһҠъӮМӢtӢ«ӮМҸгӮЙҗ¬Ӯи—§ӮВӮаӮМӮҫҒB “ъҳIҠJҗн“–ҸүҒAҺOҗ{ӮН‘ж“сҠН‘аҸҠ‘®ӮМ‘ж“сҗн‘аҺwҠцҠҜӮМҚАӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҲөӮўӮӘӢЙӮЯӮД“пӮөӮўҸг‘ә•F”VҸе’·ҠҜӮМ‘¶ҚЭӮӘ‘O’сӮЙӮ ӮиҒA’ҶүӣӮЕҗlҺ–ӮМ•”ҸҗӮЙӮўӮҪҺOҗ{ӮӘҒAҺ©ӮзҸг‘әӮМүәӮЙ”z‘®ӮіӮкӮйҺ–Ӯр‘I‘рӮөӮҪҺ–ӮЙӮжӮйҒB‘ж“сҠН‘аӢyӮСҸг‘ә’·ҠҜӮӘғEғүғWғIҠН‘аӮЙ–|ҳMӮіӮкҒAҚ‘“аӮЕҒwҳI’TҒxӮжӮОӮнӮиӮіӮкӮДӮўӮҪҚ ҒAҺOҗ{ӮНҸг‘әӮМб’бӣӮр‘SҗgӮЕҺуӮҜҺ~ӮЯӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҲК’uӮЙӮ ӮиҒAҸнӮЙ”lҗәӮМ“IӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮаҗ„‘ӘӮіӮкӮйҒBӮұӮМӢкӢ«ӮНүUҺRү«ҠCҗнӮМҠ®ҸҹӮЙӮжӮБӮД•сӮнӮкҒAӮұӮМҢгӮЙҺOҗ{ӮН‘жҲкҗн‘аӮМҺwҠцҠҜӮЙ“]ҸoӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒB ‘жҲкҗн‘аӮНҒAҠшҠНӮМҒwҺOҠ}ҒxӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·ӮйҺе—НҗнҠНӮ©Ӯзҗ¬Ӯй‘аӮЕӮ ӮиҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДҺOҗ{Һ©җgӮН“a(ӮөӮсӮӘӮи)ӮЖӮИӮйҗнҠНҒw“ъҗiҒxӮЙҸжҠНӮөӮҪҒB“ъ–{ҠCҠCҗнҸү“®ӮЙӮЁӮҜӮйҒw“ҢӢҪғ^Ғ[ғ“ҒxӮНҗўҠE’ҶӮМ’mӮйӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒAӮұӮМҺһғҚғVғA‘ӨӮӘҚЕӮа–CҢӮӮрҸW’ҶӮіӮ№ӮҪӮМӮӘҠшҠНӮМҒwҺOҠ}ҒxӮЕӮ ӮиҒAҺҹӮМ–Ъ•WӮЖӮИӮБӮҪӮМӮӘ‘аӮМҚЕҢг”цӮЙҲК’uӮөӮҪҒw“ъҗiҒxӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМ2ҠНӮН“ъ–vӮЬӮЕҸIҺnғҚғVғA‘ӨӮМ–Ъ•WӮЖӮіӮкҒAҺ–Ӯ ӮйӮІӮЖӮЙ”н’eӮ·ӮйҚР“пӮЙҢ©•‘ӮнӮкӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒB Ғw“ъҗiҒxӮӘ–іҺ–ғ^Ғ[ғ“ӮрҸIӮҰӮҪҢгҒA‘•ҚbӮМ”–Ӯў‘ж“сҠН‘аӮН”дҠr“IҲА‘SӮИӢ——ЈӮр•ЫӮБӮДғ^Ғ[ғ“ӮрҠ®җӢҒAӮұӮМҚ ӮЙӮН‘жҲкҗн‘аӮЙӮжӮБӮДҠщӮЙғҚғVғA‘ӨӮМ“ӘӮрүҹӮіӮҰҚһӮЮҗwҢ`ӮӘҸo—ҲҸгӮӘӮБӮДӮЁӮиҒAҳAҚҮҠН‘аҺе—НҠНӮМ‘Ө–КӮЖӮўӮӨ‘Ө–КӮӘҲкҗДӮЙ–C–еӮрҠJӮӯӮЙҺҠӮйҒBҠJҗнӮ©ӮзҲкҺһҠФӮаӮҪӮҪӮИӮўҠФӮЙғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮМҠшҠНҒwғXғҸғҚғtҒxӮНүҠҸгҒAӮЬӮаӮИӮӯҒwғIғXғүҒ[ғ”ғBғAҒxӮӘ‘еүОҚРҒAҗӢӮЙӮНҗнҠНӮМҸнҺҜӮр‘ЕӮҝ”jӮБӮД’ҫ–vӮ·Ӯй”ЯҢҖӮрҺАүүӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҢгҢ`җЁӮӘӢt“]Ӯ·ӮйҺ–ӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҲЛ‘R–CҢӮӮМ–Ъ•WӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҒwҺOҠ}ҒxӮЖҒw“ъҗiҒxӮНӮөӮОӮөӮО”н’eҒA“ъӮаҢXӮӯ16ҺһүЯӮ¬ҒAҺOҗ{ӮМӢЯӮӯӮЙӮа’…’eӮӘӮ ӮиҸ«ҚZӮМ‘ҪӮӯӮӘҺҖҸқӮөӮҪҒBӮұӮМҺһ”j•РӮМҲк•”ӮӘҺOҗ{ӮМҠз–КӮр’јҢӮӮөҒA–`“ӘӮЙҸqӮЧӮҪҒw“ЖҠб—іҒxӮМҸҠҲИӮЖӮИӮйҸdҸЗӮЙӮИӮБӮҪҒB“ъ–vӮӘӢЯӮГӮӯӮЙӮВӮкӮДҠCҗнӮМҺе–рӮНӢм’Җ‘аӮЦӮЖҲЪӮи•ПӮнӮиҒAҲИҢгҒw“ъҗiҒxӮНҢг•”8ғCғ“ғ`–C“ғҚ¶–CӮЙ–C’e’јҢӮӮрӮӯӮзӮӨӮаҒA’v–Ҫ“IӮИ”нҠQӮр”нӮзӮИӮўӮЬӮЬ—рҺj“IӮИҠCҗнӮр–іҺ–ҸIӮҰӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB ҠCҗн’ҶӮЙҠз–КӮЙҗHӮўҚһӮсӮҫ”j•РӮНҒAҗнҢгӮа‘М“аӮЙҺcӮБӮДҺЁ•@үИҢnӮМҸбҠQӮЕҺOҗ{Ӯр”YӮЬӮ№ӮҪӮӘҒAҸ\җ””NӮМҢгҒAӮжӮӨӮвӮӯ•@ҚoӮ©ӮзҺ©‘RӮЙ—ҺүәӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB”У”NӮНҢМӢҪӮЙӮЩӮЗӢЯӮў•‘’Я’БҺз•{Һi—Я’·ҠҜӮМҗE–ұӮр‘SӮӨӮөҒA66ҚОӮЕ–vӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҸoүHҸdү“ 1856-1930 үп’Г”Л
‘жҲкҠН‘аӮЙ‘®Ӯ·Ӯй‘жҺOҗн‘аӮМҺwҠцҠҜҒBҺF–Җ”ҙҲИҠOӮЕҠCҢR‘еҸ«ӮЬӮЕҸёҗiӮөӮҪҚЕҸүӮМҗl•ЁӮЕӮ ӮйҒB •и’Cҗн‘ҲҺһӮЙ‘ҜҢRӮМ—vӮЖӮИӮБӮҪүп’Г”ЛӮМҸoҗgӮҫӮӘҒAӮұӮМҺһӮЙ”’ҢХ‘аӮЖӮөӮДҗн‘ҲӮЙҺQүБҒB‘јӮМ‘ҜҢRҸгӮӘӮиӮЖӮН•КӮМ“№Ӯр•аӮсӮҫӮМӮНҒAҒw”’ҢХ‘аӮМ”ь’kҒxӮӘүeӢҝӮөӮҪӮЖҢ©ӮйҺ–ӮаӮЕӮ«ӮйҒB ‘жҺOҗн‘аӮЖӮНҒAҸ„—mҠНӮМҒwҠ}’uҒxӮрҠшҠНӮЖӮ·Ӯй•Тҗ¬ӮЕҒAҲИүәӮЙҒwҗзҚОҒxҒAҒwү№үHҒxҒAҒwҗVҚӮҒxӮ©Ӯзҗ¬ӮйҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮД‘жҲкҗн‘аӮН“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮӘҸжҠНӮ·ӮйҒwҺOҠ}ҒxӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй4җЗӮМҗнҠНӮЖ2җЗӮМ‘•ҚbҸ„—mҠНӮ©Ӯзҗ¬ӮйҒBӮұӮкӮЙӢм’Җ‘аӮвҗ…—Ӣ’шӮИӮЗӮрҠЬӮЯӮД‘жҲкҠН‘аӮЖӮўӮӨӮЬӮЖӮЬӮиӮЙӮИӮйҒB “ъ–{ҠCҠCҗн’ј‘OӮМ’iҠKӮЙӮЁӮўӮД‘жҺOҗн‘аӮН‘О”nӢЯ•УӮЕҸЈүъ”C–ұүәӮЙӮ ӮиҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрҚЕҸүӮЙ”ӯҢ©ӮөӮҪҒwҗM”ZҠЫҒxӮ©ӮзӮМ‘Е“dӮрҺуӮҜҢ»ҸкӮЙ’јҚsҒAҠН‘аӮМҠДҺӢӮрҚsӮБӮҪҒB”ЮӮзӮӘҢ»ҸкҠCҲжӮЙ“һ’…ӮөӮҪҺһ“_ӮЕҒAҠщӮЙ•РүӘҺөҳYӮМ‘жҺOҠН‘аӮӘ“GҠН‘аӮЖ•№‘–ӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮНүОҠWӮрҗШӮзӮёӮЙӮұӮкӮзӮр–ЩҺEӮө‘ұӮҜӮДӮўӮйҸу‘ФӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМ”wҢiӮЙӮН‘а—сӮМ—җӮкӮв’e–тӮМ–і‘КҢӯӮўӮрӢ°ӮкӮҪғҚғWғFғXғgғEғFғ“ғXғLҒ[’с“ВӮМ”»’fӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйӮӘҒA–C–еӮҫӮҜӮНғLғbғ`ғҠӮЖ“ъ–{‘ӨӮЙҢьӮҜӮзӮкӮДӮЁӮиҒA“аҸоӮр’mӮзӮИӮў‘жҺOҠН‘аӮЖӮөӮДӮНғMғҠғMғҠӮМӢ——ЈӮЕҚqҚsӮ·Ӯй“пӮөӮўҺһҠФ‘СӮӘ‘ұӮўӮДӮўӮҪҒB ӮұӮМӢЩ’ЈҸу‘ФӮЙӮЁӮўӮД“GҠН‘аӮ𒧔ӯӮөӮҪӮМӮӘҸoүHӮМ‘жҺOҗн‘аӮЕӮ ӮйҒB•РүӘӮМ‘жҺOҠН‘а(‘жҢЬҒE‘жҳZҗн‘а)ӮӘҺЛ’цӢ——ЈӮМ•ЈӮрҸo“ьӮиӮөӮДӮўӮйӮМӮЙ‘ОӮөҒAҸoүHӮНҲкӢCӮЙ“GҠН‘аӮМүщӮЬӮЕӮаӮ®ӮиӮұӮЮ–\Ӣ“ӮЙҸoӮҪҒBӢ——Ј7,000ӮрҗШӮкӮОҢЭӮўӮЙҸ\•ӘӮИ–CҢӮӮӘүВ”\ӮЙӮИӮйӮӘҒA‘жҺOҗн‘аӮНӮіӮзӮЙӮ¶ӮнӮ¶ӮнӮЖӢ——ЈӮрӢlӮЯҒA3,000mӮ ӮҪӮиӮЬӮЕҗЪӢЯӮөӮДҢ©Ӯ№ӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮұӮМҺһҒAҚЕӮаӢ——ЈӮрӢЯӮГӮҜӮзӮкӮҪҗнҠНғAғҠғҮҒ|ғӢӮМҲк•әӮӘ‘ПӮҰҗШӮкӮё–\”ӯҒAҺw—ЯӮМ–ҪӮр‘ТӮҪӮёӮЙ–C–еӮрҠJӮўӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҚҮҗ}ӮЙҚҶ—ЯӮр‘ТӮҝӮ©ӮЛӮДӮўӮҪ‘јӮМҠН‘DӮзӮӘҺҹҒXӮЖ–CҢӮӮрҠJҺnҒAҸoүHӮМ‘жҺOҗн‘аӮНҸW’Ҷ–CүОӮМ“IӮЖӮИӮБӮҪҒBӮаӮөӮұӮМҺһ”gӮӘ’бӮҜӮкӮОҒAӮўӮӯӮВӮ©ӮМ–Ҫ’Ҷ’eӮЙӮжӮБӮД‘жҺOҗн‘аӮН‘еӮ«ӮИ‘№ҠQӮрӮұӮӨӮЮӮБӮДӮўӮҪүВ”\җ«ӮӘӮ ӮиҒAҢгӮМҚмҗнӮЙҗS—қ“IӮИ–КӮЕүeӢҝӮр—^ӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮаҗ„‘ӘӮЕӮ«ӮйҒB ӮЗӮӨӮЙӮ©ҺЛ’цҢ—ҠOӮЬӮЕ“ҰӮкӮҪ‘жҺOҗн‘аӮҫӮӘҒAӮұӮМ–`ҢҜӮМ— ӮЙӮНҒw‘ҜҢRҒxӮЖӮөӮДӮНӮўӮВӮӯӮОӮБӮДӮ«ӮҪҸoүHӮМҠCҢRҗlҗ¶ӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB“–ҺһӮМҢR‘аҸг‘w•”ӮНӮұӮЖӮІӮЖӮӯҺF’·”ҙӮӘ“ЖҗиҒBӮЖӮӯӮЙҠCҢRӮНҺF–Җ’P“ЖӮМ“VүәӮЕӮ ӮиҒAҒw‘ҜҢRҸoҗgҒxӮМҗlҠФӮН‘ҪӮ©ӮкҸӯӮИӮ©Ӯк—қ•sҗsӮИҲөӮўӮрҺуӮҜӮДӮ«ӮҪҒBҸoүHӮИӮЗӮа—бҠOӮЕӮНӮИӮӯҒAӮ Ӯй’ц“xӮМ’nҲКӮр“ҫӮДӮ©ӮзӮаҒAӮ»ӮМӮ№ӮўӮЕӢtӮЙ•—“–ӮҪӮиӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪҺ–ӮН‘z‘ңӮЙ“пӮӯӮИӮўҒB’·”N‘ПӮҰ”EӮсӮҫ––ӮМ”ҪҚңҗSӮӘҒA“GӮМ‘еҠН‘аӮр‘OӮЙҸoүHӮр–\”ӯӮіӮ№ӮҪӮЖҚlӮҰӮйӮМӮНҒAҢҲӮөӮДҺЧҗ„ӮЕӮНӮИӮўӮҫӮлӮӨҒB “ъҳIҗн‘ҲҸIҢӢҢгҒAҚІҗў•Ы’БҺз•{ӮМҺi—Я’·ҠҜӮвӢіҲз–{•”’·Ӯр—р”CӮөҒA–`“ӘӮЙӮаҗGӮкӮҪӮжӮӨӮЙҠCҢR‘еҸ«ӮЦӮЖҸёҗiҒB“–ҺһӮаҗV•·ӮИӮЗӮЕӮа‘еӮ«ӮӯҲөӮнӮкӮҪҒBӮ ӮӯӮЬӮЕүҜ‘ӘӮЕӮөӮ©ӮИӮўӮӘҒAӮұӮМҸuҠФӮЙҸoүHӮМҠCҢRҗlҗ¶ӮНӢЙӮЬӮБӮҪӮаӮМӮЖҺvӮнӮкӮйҒBҲкҗlӮЙӮИӮБӮҪҢгҒA’jӢғӮ«ӮЙӢғӮўӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—L”n—ЗӢk 1860-1930 ӢIҸB”Л
‘жҲкҠН‘аҺQ–dҒB—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнӮМҺwҠцҠҜҒB җ¶ӮЬӮкӮМӢIҸBӮН“ҝҗм–Ӣ•{ҢдҺOүЖӮМҲкӮВӮЕӮ ӮиҒA•Ўҗ”ӮМҸ«ҢRӮр”yҸoӮөӮДӮ«ӮҪ—рҺjӮӘӮ ӮйҒB•и’Cҗн‘ҲҢгӮМ–ҫҺЎӮЙӮЁӮўӮДӮН‘ҜҢR’ҶӮМ‘ҜҢRӮЖҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨҒB—L”nӮМ•ғҗeӮНӢIҸB“ҝҗмүЖӮМүЖҗbӮЕӮ ӮБӮҪҲЧӮЙҲЫҗVҢгӮМ•—“–ӮҪӮиӮӘ‘Ҡ“–ӮЙӢӯӮӯҒA—ЗӢkҺ©җgӮа—cҸӯӮжӮиӢкҳJӮрҸdӮЛӮДӮ«ӮҪӮзӮөӮўҒBӮұӮМүeӢҝӮаӮ ӮБӮДӮ©җ¶ҠUӮр’КӮөӢЙ’[ӮИӮЩӮЗӮЙҺҝ‘fӮИҗ¶ҠҲӮрҗҘӮЖӮөҒA“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮ©ӮзӮМҗM—ҠҢъӮӯҒA‘ӨӢЯ’ҶӮМ‘ӨӢЯӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМҸҳ”ХӮЙӮЁӮўӮДҒAҠCҢRӮЙӮЖӮБӮДҚЕҸүӮМ‘еҠ|Ӯ©ӮиӮИҚмҗнӮЖӮИӮБӮҪ—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнҒBӮұӮкӮНҳpҢыӮМӢ·Ӯў—·ҸҮҚ`ӮМҸoҢыӮЙ‘D”•Ӯр’ҫӮЯӮДҚ`Ӯр–і—Нү»Ӯ·ӮйҺaҗVӮИӮаӮМҒBҢҙҲДӮН•Дҗјҗн‘ҲӮрҺӢҺ@ӮөӮҪҺQ–dҸHҺRҗ^”VӮЙӮжӮйӮаӮМӮҫӮӘҒA•әҺmӮМҠлҢҜӮӘҚӮӮ·Ӯ¬ӮйҺ–Ӯ©ӮзӮўӮҙҺАҚsӮЙҲЪӮ·’iҠKӮЕҒAҸHҺRҺ©җgӮӘӢyӮСҚҳӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮаҒAҗ¶ҠТӮӘҗв–]“IӮИҚмҗнӮНҚмҗнӮЕӮНӮИӮўӮЖӮөҒAҠTӮЛ”Ҫ‘ОӮМҲУҢьӮрҺҰӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAӮұӮкӮЙ”ҪӮөӮДҚмҗнҺQүБӮЦӮМҺuҠиҺТӮН‘Ҫҗ”ҒBҗ””{ӮМ’Ҡ‘IӮрҲИӮБӮДҚмҗн—vҲхӮӘ‘IӮОӮкӮйӮЖӮўӮӨ—L—lӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҸHҺR“Ҝ—lҒAҲИ‘OӮ©Ӯз—·ҸҮҚ`ҢыӮН•ВҚЗӮіӮ№ӮйӮөӮ©ӮИӮўӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪ—L”nӮЖӮөӮДӮНҒAҗв‘ОӮЙҗ¬ҢчӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨӢCҠTӮӘӮ ӮБӮҪӮҫӮлӮӨӮөҒAӮЬӮҪдP’…Ӯ·Ӯй—·ҸҮҠН‘аҚU—ӘҚмҗнӮЙӢЖӮрҺПӮвӮөӮДӮўӮҪҺ–ҸоӮаӮ ӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒB—L”nӮН“ҢӢҪӮМҲУҢьӮр”јӮО–іҺӢӮ·ӮйҢ`ӮЕҚЧҺ–ӮрҗiӮЯҒAҺ©’ҫӮіӮ№Ӯй‘DӮМ‘I•КҒAӮіӮзӮЙӮН”ҡ–тӮМҗПӮЭҚһӮЭӮЬӮЕҸIӮҰӮҪҸу‘ФӮЕҢ»ҸуӮр•сҚҗҒBҠщҗ¬Һ–ҺАӮрҗжҚsӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҚмҗнҺАҚsӮЬӮЕ‘ҶӮ¬’…ӮҜӮҪҒBҲкҺQ–dӮӘ“Ж’fӮЕҳbӮрҗiӮЯӮДӮөӮЬӮБӮҪҠiҚDӮҫӮӘҒAҺ©ӮзӮӘҚмҗнӮЙҺQүБӮөҒAҗж“ӘӮЙ—§ӮБӮДҺҖ’nӮЙ•ӢӮӯҺ–ӮЕҒAӮ»ӮМҗУ”CӮрҺҰӮөӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB ӮЖӮұӮлӮӘӮўӮҙҚмҗнӮӘҺnӮЬӮБӮДӮЭӮйӮЖҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМ–CҢӮӮӘҢғӮөӮ·Ӯ¬ҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМҠН‘DӮӘҳpҢыӮЬӮЕӮҪӮЗӮиӮВӮҜӮИӮўҒBҺҖӮрҠoҢеӮЕ–]ӮсӮҫ—L”nӮЙӮЖӮБӮДӮН’f’°ӮМҢӢүКӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA“БӮЙ‘ж“сүс–ЪӮМҚмҗнӮЕӮНҒA•ҹҲдҠЫӮрҺwҠцӮ·ӮйҚLҗЈ•җ•vҸӯҚІӮӘӢ]җөӮЙӮИӮйӮИӮЗҒAӮўӮжӮўӮж”нҠQӮӘҗ[ҚҸӮЙӮИӮБӮДӮ«ӮҪҒBүҪҺ–ӮЙӮаҺА’јӮИҗ«ҠiӮМ—L”nӮҫӮҜӮЙҒAӮұӮМҢӢүКӮр’ЙҚҰӮМӢЙӮЭӮЖҺуӮҜҺ~ӮЯҗӢӮЙ•aҗgӮЦҒB–і”OӮМҗнҗь—Ј’EӮЖӮИӮБӮҪҒBҸ®ҒA—L”nӮӘҠOӮкӮҪҢгӮМ‘жҺOүс•ВҚЗҚмҗнӮН•КӮМҺwҠцҠҜӮӘҚмҗнӮр’S“–Ӯ·ӮйӮаҒAҢӢӢЗ–FӮөӮўҗ¬үКӮрҸгӮ°ӮйӮЙҺҠӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҳAҚҮҠН‘аӮЖӮөӮДӮН”сҸнӮЙҢөӮөӮўҢӢүКӮИӮӘӮзҒAҲк•ыӮЕҲкҳAӮМҢoҲЬӮрҢ©ҺзӮБӮДӮ«ӮҪүў•ДӮМҠПҗн•җҠҜӮвғ}ғXғRғ~ӮНӮұӮкӮзӮМҚмҗнӮрҠTӮЛҚDҲУ“IӮЙ‘ЁӮҰӮҪӮзӮөӮўҒB”ЮӮзӮМӢLҺ–Ӯв•сҚҗӮЙӮжӮБӮДүў•ДӮМҒAҳAҚҮҠН‘аӮЙ‘ОӮ·Ӯй•]үҝӮӘҸгӮӘӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйҒBҺwҠцҠҜӮӘҺ©ӮзҺҖ’nӮЙ•ӢӮӯҺpҗЁӮвҒAҚмҗнӮЙ‘ОӮ·ӮйҸ«•әӮзӮМҺmӢCӮМҚӮӮіӮӘҒA“–ҺһӮМүў•ДӮМҠҙҠoӮаӮөӮӯӮН“ъ–{ӮЙ‘ОӮ·Ӯйҗж“ьҠПӮЖ‘еӮ«ӮӯҲЩӮИӮБӮДӮўӮҪӮМӮӘҢҙҲцӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮнӮкӮйҒBӮіӮзӮЙӮұӮМҺһҠъҒA—ОҠӣҚ]ӮЕӮНҚ•–ШҲЧъйӮМ‘жҲкҢRӮӘҸүҗнӮрҲіҸҹӮөӮДҢ©Ӯ№ҒAӮұӮкӮзӮМҸo—ҲҺ–ӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮЙ‘ОӮ·ӮйҗўҠEӮМҢ©•ыӮӘҲк•ПҒB“–Ҹү‘SӮӯ”„ӮкӮйӢC”zӮМ–іӮ©ӮБӮҪҠOҚВӮӘ”тӮФӮжӮӨӮЙ”„ӮкҺnӮЯҒAҗн–рҢp‘ұӮМҺ‘ӢаӮрӮЗӮӨӮЙӮ©Ҡl“ҫӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒB —L”nӮНҢі—ҲҒAҗӯҺЎ“IӮИӮаӮМӮЙӮНҢыӮрӢІӮЬӮёҒAҗнҢгӮаҸ]—ҲӮЗӮЁӮиҺА’јӮИҗ¶Ӯ«•ыӮрҠСӮўӮҪҒBҺR–{Ң •әүqҺёӢrӮМҢҙҲцӮЖӮИӮБӮҪғVҒ[ғҒғ“ғXҺ–ҢҸӮЕӮНҒAҗӯҺЎӮЙүо“ьӮөӮҪҢR”ҙҠЦҢWҺТӮзӮМҺvҳfӮӘ‘еӮўӮЙүQҠӘӮўӮҪӮӘҒA’ІҚёҲПҲхӮЕӮ ӮБӮҪ—L”nӮНӮ»ӮӨӮөӮҪҺGү№ӮЙҲкҗШҢрӮнӮзӮёҒAӮҪӮҫҺ–ҺАӮЙҠоӮГӮ«Ңц•ҪӮИ”»’fӮрүәӮөӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB ӮҝӮИӮЭӮЙҒAӮұӮМҺһҺёӢrӮөӮҪҺR–{Ң •әүqӮНҺ–ҢҸӮЖӮН‘SӮӯ–іҠЦҢWӮЕҒAҺ–ҢҸ”ӯҠoҺһӮЙӮҪӮЬӮҪӮЬ‘Қ—қ‘еҗbӮМ–рҗEӮЙӮўӮҪӮЙӮ·Ӯ¬ӮИӮўҒBӮӘҒA—Y•ЩӮЕ’mӮзӮкӮйҢ •әүqӮНҲкҗШӮМҢҫӮў–уӮаӮ№ӮёҒA–м“}ӮМҢҫӮӨӮЬӮЬӮЙҗУ”CӮрӮЖӮй“№Ӯр‘IӮсӮҫҒB—L”nӮЙӮөӮлҺR–{Ң •әүqӮЙӮөӮлҒAӮұӮӨӮөӮҪҢW‘ҲӮЖӮН–іүҸӮЕӮ ӮиӮҪӮ©ӮБӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒB”ЮӮзӮЙҢАӮзӮёҒA–Ӣ––Ӯ©Ӯ瓬Ӯў‘ұӮҜӮДӮ«ӮҪ‘ҪӮӯӮМҺwҠцҠҜӮзӮНҗӯҺЎӮЖӮН–іүҸӮМ“№Ӯр‘IӮсӮҫҒBӮӘҒA’ҶӮЙӮНӢмӮҜҲшӮ«ӮвҢ —НӮӘ‘еҚDӮ«ӮИҗl•ЁӮаӮЁӮиҒA—сӢӯӮЙ–фӮиҸoӮҪҢгӮМ“ъ–{ӮНӮұӮӨӮўӮБӮҪҳA’ҶӮЙӮжӮБӮДҢЎҲшӮіӮкӮДӮўӮӯҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—й–ШҠС‘ҫҳY 1868-1948 ҠЦҸh”Л(җз—tҢ§)
‘ж“сҠН‘аӮЙҸҠ‘®Ӯ·Ӯй‘жҺlӢм’Җ‘аҺi—ЯҒBҢгӮЙ‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲӮрҸIҢӢӮЙ“ұӮўӮҪ‘Қ—қ‘еҗbҒA—й–ШҠС‘ҫҳYӮЖ“ҜҲкҗl•ЁӮЕӮ ӮйҒB180cmӮр’ҙӮҰӮйӢҗ‘МӮЕ–Ъ—§ӮҝҒAҠН’·Һһ‘гӮМҺR–{Ң •әүqӮ©ӮзӮа–ЪӮрӮ©ӮҜӮзӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒB“O’кӮөӮҪҢP—ыӮрҚsӮӨҢөӮөӮіӮ©ӮзҒA•”үәӮЙӮНӢSӮМҠС‘ҫҳYҒAӢSҠСӮИӮЗӮЖҢДӮОӮкӮҪҒB җнҺһӮЙӮЁӮҜӮйӢм’ҖҠНӮМҺе—v”C–ұӮНҸdӮЙӢӣ—ӢӮЙӮжӮй“GҠНҸPҢӮӮЕӮ ӮйҒBҗнҠНҺOҠ}ӮӘ15,000t‘OҢгӮИӮМӮЙ‘ОӮөҒAӢм’ҖҠНӮНӮ»ӮМ30•ӘӮМ1ҲИүә(400tҺг)ӮМ‘еӮ«ӮіӮЕӮ ӮиҒAҗgӮр’рӮөӮДӢӣ—ӢӮр”ӯҺЛӮ·ӮйҺ–ӮӘҺg–ҪӮҫӮБӮҪҒBӢм’ҖҠН‘аӮӘҚЕҸүӮЙ–ф“®ӮөӮҪӮМӮНҗйҗн•zҚҗ‘OҢгӮМ—·ҸҮҚ`ҠпҸPҚмҗнӮҫӮӘҒAӮұӮМҚмҗнӮН–FӮөӮўҗ¬үКӮрӮ Ӯ°ӮДӮўӮИӮўҒB‘ұӮӯү©ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮНҒA“GӮМҺc‘¶•ә—НӮр’@Ӯӯ”C–ұӮӘүәӮБӮҪӮӘҒAӮвӮНӮиӢм’Җ‘аӮНҗ¬үКӮрӮ Ӯ°ӮйҺ–ӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢҙҲцӮЖӮөӮДҒAҠeӢм’ҖҠНӮӘ“GӮМ”ҪҢӮӮрӢ°ӮкҒA”дҠr“Iү“ӮўӢ——ЈӮ©ӮзӢӣ—ӢӮр”ӯҺЛӮөӮДӮўӮҪҺ–ӮӘҺw“EӮіӮкӮДӮЁӮиҒAҸHҺRҗ^”VӮрӮНӮ¶ӮЯҳAҚҮҠН‘аӮМҺi—Я•”ӮН‘Ҡ“–ӢЖӮрҺПӮвӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮкӮз•sҚb”гӮИӮўӢм’Җ‘аӮМ’ҶӮЙ—й–ШҠС‘ҫҳYӮНӮ ӮБӮҪҒB “ъҗҙҗн‘ҲӮрҢoҢұӮөӮҪ—й–ШӮМҺқҳ_ӮНҒuҚӮ‘¬ӢЯӢ——ЈҺЛ–@ҒvҒB“ЗӮсӮЕҺҡӮМӮЬӮЬҚӮ‘¬ӮЕүщӮЙ”тӮСҚһӮсӮЕӢӣ—ӢӮр”ӯҺЛӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚlӮҰӮЕӮ ӮиҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДӮНҠцүәҠН’шӮЙӮұӮМ“_Ӯр“O’кӮөӮДӢӯү»ӮіӮ№ӮҪҒBӮӘҒAү©ҠCҠCҗнӮЕӮНҒAӮЬӮіӮЙ—й–ШӮМҺқҳ_ӮЖҗ^ӢtӮМү^—pӮӘҚsӮнӮкӮҪҲЧӮЙ“–ҸүӮМҗнүКӮНҺSҒXӮҪӮйӮаӮМҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДӢм’Җ‘аӮМ–јӮНүҳ“DӮЙӮЬӮЭӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮкӮНӢtҗаӮЖӮөӮД—й–ШӮМҺқҳ_ӮӘҚm’иӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨҺ–ӮЕӮаӮ ӮйӮӘҒAӮЖӮаӮ ӮкҲкҳAӮМҚмҗнӮЙҺQүБӮөӮҪ—й–ШӮНӢьҗJӮЕ–йӮа–°ӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒB –{—ҲӮИӮзӮО–і–јӮЕҸIӮнӮйӢм’Җ‘аӮМ—й–ШӮӘҒA—рҺjӮМ•\•‘‘дӮЙ“oҸкӮ·ӮйӮМӮНғoғӢғeғBғbғNҠН‘аҢ}ҢӮӮМ’ј‘OӮЕӮ ӮйҒBҳAҚҮҠН‘аӮЙӮжӮБӮД“ҢғVғiҠCӮЙ“WҠJӮіӮкӮҪҚх“G–ФӮӘғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮр•ЯӮзӮҰӮҪӮМӮН5ҢҺ27“ъӮМ–ў–ҫӮЕӮ ӮиҒAҚх“GӮрҺе”C–ұӮЖӮөӮҪ‘жҺOҠН‘аӮрҺеҺІӮЙҗ”ҺһҠФӮЙӢyӮФ“GҠН‘аӮМ’З”цӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBҺi—ЯҠҜ•РүӘҺөҳYӮӘ—ҰӮўӮй‘жҺOҠН‘аӮН“GҠН‘аӮМҚ\җ¬Ӯ⑬“xҒA‘а—сҒAҗiҚs•ыҢьӮИӮЗӮр’ҖҺҹ‘Е“dӮө‘ұӮҜӮҪӮӘҒA”Z–¶ӮвҚӮӮЯӮМ”gӮЙӮжӮБӮДҗіҠmӮИҚqҳHҠ„ӮиҸoӮөӮЙҺбҠұҺиҠФҺжӮБӮҪҒBӮұӮМҺһ•РүӘӮНҠлҢҜӮрҸі’mӮЕҠН‘аӮМҗ^җі–КӮЙҠН’шӮрҸoӮөҒAғoғӢғeғBғbғNҚqҳHӮрҢv‘ӘӮ·Ӯй•ыҗjӮрҢҲ’иҒBҠлҢҜ”C–ұҺАҚsӮЙӮ ӮҪӮи‘Ҡ“–ӮИҠoҢеӮЕ’§ӮсӮҫӮНӮёӮҫӮӘҒEҒEҒB •РүӘӮӘӮұӮкӮрӮвӮй’ј‘OҒA‘ж“сҠН‘аҸҠ‘®ӮЖӮИӮй—й–ШӮМ‘аӮӘ“Ж’fӮЕӮұӮкӮрӮвӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҺOҢiҠН(Ңө“ҮҒEҸј“ҮҒEӢҙ—§)ӮИӮЗӮМӢҢҺ®ҠНӮЕ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪ‘жҺOҠН‘аӮЙӮЖӮБӮДғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮНӢәҲРӮ»ӮМӮаӮМӮҫӮӘҒAӮіӮзӮЙӢK–НӮМҸ¬ӮіӮИ—й–ШӮМӢм’Җ‘аӮӘ“GҠН50җЗҺгӮМҗ^җі–КӮЙ“WҠJҒAҗіҠmӮИҚqҳHҠ„ӮиҸoӮөӮЙӮ ӮҪӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB—й–ШҺқҳ_ӮМҒuҚӮ‘¬ӢЯӢ——ЈҺЛ–@ҒvӮЙ•K—vӮИӮМӮНӢ°•|ӮЙ‘ПӮҰӮӨӮй’_—НӮҫӮӘҒAӢSҠСӮӘӮөӮІӮ«ҸгӮ°ӮҪӢм’Җ‘аӮМҗ¬үКӮӘӮұӮӨӮўӮӨҸк–КӮЕҲкӢCӮЙ•\–Кү»Ӯ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮұӮМҺһӮМ—й–ШӮМҚs“®ӮНғҚғVғA‘ӨӮЙӮЖӮБӮДӮа‘z’иҠOӮЕӮ ӮБӮҪӮзӮөӮӯҒAӮЬӮіӮ©ӮұӮкӮӘҚqҳHҢv‘ӘӮМҲЧӮМҚs“®ӮЖӮНҺvӮнӮИӮўҒBғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮМҺi—Я•”ӮНҚqҳHӮЙ‘е—КӮМӢ@—ӢӮӘӮЬӮ©ӮкӮҪӮЖ”»’fӮөҒAӮЁӮ©Ӯ°ӮЕ‘а—сӮӘ‘еӮ«Ӯӯ—җӮкӮйҺ–ӮЙҒB—§ӮД’јӮөӮЙҺҠӮзӮКӮЬӮЬҺеҗнҸкӮЙ“Л“ьӮЖӮИӮБӮҪҒB Һе—НҠН“ҜҺmӮМҢғ“ЛӮЙӮЁӮўӮДӢм’Җ‘аӮМҸoӮй–ӢӮНӮИӮўҒBҸү“ъӮМ—јҠН‘аҢғ“ЛӮМҢгҒA—[•йӮкӮӘӢЯ•tӮӯӮЖӮЖӮаӮЙҚД“xӢм’Җ‘аӮМҸo”ФӮЖӮИӮйҒB17Һһ‘OҒA—й–ШӮӘ—ҰӮўӮй‘жҺlӢм’Җ‘аӮЙ“ҢӢҪӮ©Ӯз”ӯ“®ӮМ–Ҫ—ЯӮӘҸoӮҪҒB–Ъ•WӮНғoғӢғeғBғbғNҠН‘аҠшҠНӮМҒwғXғҸғҚғtҒxӮҫҒBҠeҠНҒA—й–ШӮМҺқҳ_ӮЗӮЁӮи600mӮЩӮЗӮЬӮЕӢЯ•tӮ«Ӣӣ—ӢӮр”ӯҺЛӮ·ӮйӮаҚӮ”gӮЙӮжӮБӮД–Ҫ’ҶӮ№ӮёҒBӢЖӮрҺПӮвӮөӮҪӮМӮ©ҒA—й–ШӮНҺ©ӮзӮӘҸжҠНӮ·ӮйҒw’©–¶ҒxӮр300mӮЬӮЕҗЪӢЯӮіӮ№ҒAҺҠӢЯӮ©ӮзӢӣ—ӢӮр•ъӮБӮДӮўӮйҒBҺc”OӮИӮӘӮзӮұӮкӮа“IӮрҠOӮ·Ҳк•ыҒAҒw’©–¶ҒxӮЙ’ЗҸ]ӮөӮД“ҜӮ¶Ӯӯ300mӮЬӮЕҗЪӢЯӮөӮҪҒw‘әүJҒxӮМӢӣ—ӢӮӘҒwғXғҸғҚғtҒxӮЙ–Ҫ’ҶӮөӮДӮўӮйҒBҢӮ’ҫӮЙҺҠӮзӮИӮ©ӮБӮҪҲЧӮЙ‘еӮ«ӮИҗ¬үКӮЖӮНӮЖӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮМҚUҢӮӮЙӮжӮБӮДҒwғXғҸғҚғtҒxӮНҠшҠНӮЖӮөӮДӮМӢ@”\ӮрҠ®‘SӮЙҺёӮӨҺ–ӮЙӮИӮБӮҪҒB –йҠФӮЙ“ьӮиҚД“xӢм’Җ‘аӮЙҸoҢӮӮМҺw—ЯӮӘҸoӮіӮкҒAҲк”УӮрӮЖӮЁӮөӮД—й–ШӮМӢм’Җ‘аӮН3җЗҢӮ’ҫӮМҗ¬үКӮрӢ“Ӯ°ӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮұӮкӮН‘SӢм’Җ‘аӮМ’ҶӮЕӮаҚЫ—§ӮВүхӢ“ӮЕӮ ӮиҒAӮ©ӮВӮД—·ҸҮҚ`•ВҚҪҚмҗнӮвү©ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮұӮ«үәӮлӮіӮкӮҪҚ ӮМӢм’Җ‘аӮ©ӮзӮ·ӮкӮОӮЬӮіӮЙҗбҗJӮҫӮБӮҪӮлӮӨҒB‘жҺlӢм’Җ‘аӮМ“ӯӮ«ӮрҢ©ӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮН‘еӮўӮЙҠмӮСҒA‘|“ўҗнҢгӮЙҠшҠНҺOҠ}Ӯр–KӮкӮҪ—й–ШӮЙ‘ОӮө30•ӘӮаӮМҠФҗнӢөӮМҗ„ҲЪӮЙӮВӮўӮДҢкӮи‘ұӮҜӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB–іҢыӮЕ’mӮзӮкӮй“ҢӢҪӮМй`җгӮФӮиӮрҸүӮЯӮД–ЪӮМ“–ӮҪӮиӮЙӮөӮҪ—й–ШӮНҒAҢгӮЙҒwҠtүәӮӘӮ ӮкӮЩӮЗӮөӮбӮЧӮйӮМӮрҢ©ӮҪӮМӮНҸүӮЯӮДӮҫҒxӮЖҢкӮБӮДӮўӮйҒBҸ®ҒAӮұӮМ‘|“ўҗнӮЙӮЁӮўӮД‘жҺlӢм’Җ‘аӮМҠҲ–фӮӘ”тӮСӮКӮҜӮДӮўӮҪҲЧҒAҺQ–dӮМҸHҺRҗ^”VӮӘҢӮ’ҫӮМҗ¬үКҲкҗЗӮр‘јӮМ‘аӮЙҸчӮБӮД—~ӮөӮўӮЖ”—ӮБӮҪӮМӮН—L–јӮИҳbҒBӢSҠС—й–ШӮЖҲИүәҒAҚң“чӮрҚнӮБӮҪ‘аҲхӮзӮЙӮЖӮБӮДҠҙ–і—КӮМүh—_ӮЕӮ ӮБӮҪӮЙҲбӮўӮИӮўҒB ҒEҒEӮұӮМҗўҠEҠCҗнҺjҸгӮМүхӢ“Ӯ©ӮзҺАӮЙ41”NҢгҒA—й–ШӮН•ДҢRӮМҸДҲО’eӮЙӮжӮБӮДҸЕ“yӮЖү»ӮөӮҪ“ҢӢһӮЕҒAҺёӢrӮөӮҪ“ҢһҠүpҺчӮЙ‘гӮнӮБӮД“аҠt‘Қ—қ‘еҗbӮЙҸA”CӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB”й–§— ӮЙҸIҗнӮр”C–ұӮЖӮөӮҪ“аҠtӮЕӮ ӮиҒAҺ«‘ЮӮө‘ұӮҜӮҪ—й–ШӮЙ‘ОӮөҸәҳa“VҚcӮӘӮИӮ©ӮОӮЁҠиӮўӮ·ӮйҢ`ӮЕӮжӮӨӮвӮӯҗ¬—§ӮөӮҪ“аҠtӮҫӮБӮҪҒB‘жҺlӢм’Җ‘аҺһ‘гӮЙҢ©ӮҪҚ‘үЖӮМҺpӮНҠщӮЙ–іӮӯҒAҲГҺEӮрҢxүъӮөӮИӮӘӮзӮМҚ‘үЖү^үcӮНҗlҗ¶ҸI”ХӮМ—й–ШӮЙӮЖӮБӮДҺcҚ“Ӯ·Ӯ¬Ӯй•‘‘дӮЖҢҫӮӨӮөӮ©ӮИӮўҒB•\—§ӮБӮҪҚs“®ӮрҺжӮкӮИӮў—й–ШӮЙ‘ОӮөҒAҺьҲНӮНҢҲ’f—НӮМ–іӮіӮрҺw“EӮөӮҪҒBҸIҗнҚHҚмӮМҺһҠФӮрүТӮ®ҲЧӮЙҒwғ|ғcғ_ғҖҗйҢҫҒxӮрӮвӮиүЯӮІӮөӮҪ—й–ШӮрҒAғ}ғXғRғ~ӮНҒwғ|ғcғ_ғҖҗйҢҫ–ЩҺEҒxӮЖӮөӮД‘еӮўӮЙ‘ӣӮ¬ҒAӮұӮкӮр’mӮБӮҪ•ДҚ‘ӮНҗӢӮЙҢҙҺq”ҡ’e“ҠүәӮрҢҲ’иӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB ‘О•Дҗн‘ҲҸIҢӢҢгҒA—й–ШӮН“ъ–{ӮМ•җҺm“№җёҗ_ӮМҢНҠүӮрҗSӮ©ӮзүчӮвӮсӮҫӮЖҢҫӮнӮкӮйҒBӮҪӮБӮҪӮМ40”NӮЕҗўҠEӮМ—сӢӯӮЙ’ЗӮўӮВӮўӮҪ“ъ–{ӮНҒA“ҜӮ¶Ӯӯ40”NӮЕ’nӮЙ–vӮөӮҪҒB—й–ШӮЙҢҫӮнӮ№ӮкӮОҒAӮ»ӮМҚЕ‘еӮМҢҙҲцӮН“ъ–{җlӮМҗёҗ_ӮМ‘В—ҺӮЖӮўӮӨҺ–ӮҫӮБӮҪӮМӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚLҗЈ•җ•v 1868-1904 үӘ”Л
—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнӮЙӮЁӮҜӮйҢ»ҸкҺwҠцҠҜҒB“–ҚмҗнӮЙӮЁӮҜӮйҗнҺҖӮМҢӢүКҒA“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДӮЁӮ»ӮзӮӯӮНҸүӮМҢRҗ_ӮЖӮөӮДҚХӮиҸгӮ°ӮзӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒB ”N—оӮӘҲкӮВҲбӮўӮМҸHҺRҗ^”VӮЖӮНҢр—¬ӮӘҗ[ӮӯҒAҲкҺһҠъӮНҸZӢҸӮрӮЖӮаӮЙӮөӮДӮўӮҪҠФ•ҝӮЕӮ ӮиҒA“Ҝ”N‘гӮрҢ©үәӮөӮӘӮҝӮИҸHҺRӮӘ’ҝӮөӮӯ‘О“ҷӮЙ•tӮ«ҚҮӮБӮҪҗ”ҸӯӮИӮўҗl•ЁӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB—јҺТӮНҒAҢгӮМҠCҢR‘еҗbҒA”Ә‘гҳZҳYӮр’КӮ¶ӮД’mӮиҚҮӮБӮҪӮзӮөӮӯҒAҸHҺRӮЙӮЖӮБӮДӮ©ӮВӮДӮМӢіҠҜӮҫӮБӮҪ”Ә‘гӮМҺ©‘оӮЙҒAҚLҗЈӮӘ“ъҒXҸ_“№ӮМ—ыҸKӮЙ’КӮБӮДӮўӮҪҺ–ӮӘүҸӮҫӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒB •Дҗјҗн‘ҲӮЙҠПҗн•җҠҜӮЖӮөӮДҺQүБӮөӮҪҸHҺRӮНҒAҗVӢ»Қ‘ӮМ•ДҚ‘ӮӘӮ©ӮВӮДӮМҠCҢRүӨҚ‘ӮМғXғyғCғ“Ӯр’@Ӯ«ӮМӮЯӮ·—lӮр–ЪӮМ“–ӮҪӮиӮЙӮөҒA“БӮЙ•ДҚ‘ҠН‘аӮМҳpҢы•ВҚЗҚмҗнӮЙҠҙ’QӮөӮҪҒB”ЮӮӘӢAҚ‘ӮөӮДҢгҒAҚLҗЈӮЙ‘ОӮөҒuҚЎүсғAғҒғҠғJӮӘғXғyғCғ“ӮЙ‘ОӮөӮДӮвӮБӮҪӮМӮЖ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрӮаӮБӮЖ‘еӢK–НӮЙӮвӮкӮОҒAғҚғVғAӮҫӮБӮД‘ЬӮМӮЛӮёӮЭӮҫҒvӮЖҢкӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮөӮДӮ»ӮкӮ©Ӯзҗ””NҢгҒAҚLҗЈӮНҺАҚЫӮЙӮ»ӮМҚмҗнӮЙҺQүБӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB —·ҸҮҢыӮМ•ВҚЗҚмҗнӮӘ—\‘zҲИҸгӮМ“пҚqӮөӮҪҲкҲцӮНӢӯ—НӮИ—vҚЗ–CӮҫҒB“ҜӮ¶ӮӯӢӯ—НӮИ’TҸЖ“•ӮӘҸнӮЙ–йӮМҠCӮрҸЖӮзӮөӮДӮЬӮнӮиҒA‘DүeӮр”FӮЯӮжӮӨӮаӮМӮИӮз—eҺНӮИӮӯ–C’eӮрҳA”ӯӮ·ӮйҒBӮ©ӮВӮД“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһӮЙ“ъ–{ҢRӮӘҠЧ—ҺӮіӮ№ӮҪ—·ҸҮ—vҚЗӮЖӮН‘SӮӯ•К•ЁӮМӢЯ‘г—vҚЗӮЕӮ ӮиҒAҺOҚ‘ҠұҸВҲИҢгҒAғҚғVғAӮӘҺАӮЙҸ\”NӮаӮМҢҺ“ъӮр”пӮвӮөӮДҚ\’zӮөӮҪүеҸйӮҫӮБӮҪҒB•Дҗјҗн‘ҲӮЕҸHҺRӮӘғXғyғCғ“ҠН‘аӮЙҢ©ӮҪҒwҗЖҺгӮіҒxӮН—·ҸҮӮМғҚғVғAҢRӮЙӮН”чҗoӮа–іӮӯҒAӮҪӮҫӮҪӮҫҚ|“SӮМҺRӮ©Ӯз“ъ–{‘ӨӮЙ‘ОӮөӮД“O’к“IӮИ‘ЕҢӮӮӘүБӮҰӮзӮк‘ұӮҜӮҪӮМӮҫӮБӮҪҒB ҚLҗЈӮН‘жҲкүс•ВҚЗҚмҗнӮЙӮЁӮўӮДҒw•сҚҗҠЫҒxӮМҺwҠцҠҜӮЖӮөӮДҺQүБҒBҺmҠҜҠwҚZӮЕӮМҗ¬җСӮНүәӮ©Ӯзҗ”ӮҰӮҪӮЩӮӨӮӘ‘ҒӮ©ӮБӮҪҚLҗЈӮНҒAӮөӮ©Ӯөҗ…—ӢҸpӮЙӮЁӮўӮДӮН•АӮФҺТӮӘӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҚLҗЈӮрҠЬӮЮ“ъ–{ӮМҗ…—Ӣ’шӮӘ—·ҸҮӮМҚ`ҢыӮр–ЪҺwӮ·ӮаҒAӮ»ӮМҺи‘OӮЕ–Т—уӮИ–CҢӮӮЙ’@Ӯ«ӮМӮЯӮіӮкҒA–Ъ“IӮр’BӮ·ӮйҺ–Ӯ©ӮИӮнӮё“P‘ЮӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮДӮўӮйҒB ‘ж“сүсӮМҚмҗнӮЕӮНҒwҚK•ҹҠЫҒxӮМҺwҠцҠҜӮЖӮөӮД’§ӮЮӮаҒAӮұӮұӮЕӮағҚғVғA‘ӨӮЙҺ@’mӮіӮкҒAӮ ӮҰӮИӮӯҸW’Ҷ–CүОӮМ“IӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒBҗhӮӨӮ¶ӮДҳpҢыӢЯӮӯӮЙ‘D”•Ӯр’в”‘ӮіӮ№ҒA”ҡ–тӮрҺdҠ|ӮҜӮҪҢгӮЙ’EҸoӮрӮНӮ©ӮйӮаҒAӮўӮҙ”р“п—pӮМғ{Ғ[ғgӮЙҸWӮЬӮБӮДӮЭӮкӮО•”үәӮӘҲкҗl‘«ӮиӮИӮўҒB•Ўҗ”ӮМ—vҚЗ–CӮМҺЛ’ц“аӮЙӮ ӮБӮДҠщӮЙҺҖҗьғXғҢғXғҢӮМӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮиӮИӮӘӮзҒAҚLҗЈӮН3“xҒAҺАӮЙ3“xӮа‘D“аӮЙ–ЯӮиҒAҚs•ы•s–ҫӮМ•”үәӮр’TӮөӮҪӮзӮөӮўҒB“ҰӮ°’xӮкӮҪ•”үәӮӘҲкҗlӮҫӮҜ”ҡ–тӮЖӮЖӮаӮЙҠCӮЙ’ҫӮЮӮМӮӘӮЗӮӨӮөӮДӮаҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮЕӮаӮўӮжӮўӮж–CҢӮӮӘҢғӮөӮӯӮИӮиҒAҗӢӮЙғ{Ғ[ғgӮЕҢ»ҸкӮ©Ӯз’EҸoӮрӮНӮ©ӮБӮҪҺһҒAҚLҗЈӮНӮұӮМҗўӮ©ӮзҸБӮҰӮҪҒB‘јӮМ•”үәӮҪӮҝӮӘӢCӮГӮӯӮЬӮаӮИӮўӮЩӮЗҲкҸuӮМҺ–ӮҫӮБӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒBҚLҗЈӮМ‘МӮНғ{Ғ[ғgӮМҸгӮ©ӮзҸuҺһӮЙҸБӮҰӢҺӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮҫ ҚLҗЈ•җ•vӮЖӮНӮұӮӨӮўӮӨ’jӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸнҒX•”үәӮМ–К“|Ң©ӮӘӮжӮӯҒAӮўӮвӮИҺdҺ–ӮрҺ–Ӯр—ҰҗжӮөӮДӮұӮИӮ·ӮИӮЗҒAҺьҲНӮ©ӮзӮМҗl–]ӮӘҢъӮӯҒAӮ»ӮМҗ¶Ӯ«•ыӮМү„’·ӮЙӮжӮБӮДҗӢӮЙӮНҺ©ӮзӮМ–ҪӮр—ҺӮЖӮөҒA•”үә‘zӮўӮМӮұӮМ”ь’kӮЙӮжӮБӮДҢгӮЙҒwҢRҗ_ҒxӮЙҚХӮиҸгӮ°ӮзӮкӮҪҒBҚLҗЈӮН—vҚЗ–CӮМ’јҢӮӮрҺуӮҜӮҪӮЖҗ„‘ӘӮіӮкҒAӮ»ӮкӮдӮҰӮЙҒwҗ”•УӮМ“ч•РӮрҺcӮөӮДҸБӮҰӢҺӮБӮҪҒxӮЖӮўӮБӮҪӮжӮӨӮИ•`ҺКӮрӮіӮкӮйӮӘҒAҺАҚЫӮЙӮНӮ»ӮӨӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB2010”NӮМ2ҢҺҒAғҚғVғA‘ӨӮМҺ‘—ҝӮЙӮжӮБӮДҒAҚLҗЈӮМҲв‘МӮӘғҚғVғAҠCҢRӮЙӮжӮБӮДҠC’ҶӮ©ӮзҲшӮ«ҸгӮ°ӮзӮкӮДӮўӮҪҺ–ӮӘ•ӘӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҚLҗЈӮНҢR•”“аӮЙӮЁӮўӮДҗ”ҸӯӮИӮў’mҳI”hӮЕӮ ӮиҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМғҚғVғA’“ҚЭӮЙӮжӮБӮДӮ©ӮМҚ‘ӮЙ‘ҪӮӯӮМҗl–¬Ӯр’zӮўӮҪҒBҺmҠҜ“ҜҺmӮМҠЦҢWӮМӮЭӮИӮзӮёҒAҠCҢRҸd–рӮМ–әҒAғAғҠғAғYғiӮЖӮМҗe–§ӮИҠЦҢWӮН—L–јӮИӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮиҒA—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗн‘OӮЙӮағAғҠғAғYғiӮЦҺиҺҶӮрҸ‘Ӯ«‘—ӮБӮДӮўӮйҒBҚLҗЈӮМҲв‘МӮӘӮнӮҙӮнӮҙҠC’кӮ©ӮзҲшӮ«ҸгӮ°ӮзӮкӮҪӮМӮНҒAӮұӮӨӮўӮБӮҪҗl–¬ӮЙӮжӮБӮДҒAғҚғVғAҢR•”“аӮЕүҪӮзӮ©ӮМ“ӯӮ«Ӯ©ӮҜӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮНҠФҲбӮўӮИӮўӮҫӮлӮӨҒBҺ‘—ҝӮЙӮжӮкӮОҒAҲшӮ«ҸгӮ°ӮзӮкӮҪҚLҗЈӮН“Ә•”ӮрҸңӮҜӮОӮЩӮЪ–іҸқӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМҢг‘’ӢVӮрҲИӮБӮД’ҡҸdӮЙ‘’ӮзӮкӮҪӮЖӮіӮкҒAӮ»ӮМҺһӮМҲкҳAӮМҺКҗ^ӮНғҚғVғA‘ӨӮЙҢ»‘¶ӮөӮДӮўӮйӮЖӮМҺ–ӮЕӮ ӮйҒB Ң»‘гӮЙҗ¶Ӯ«ӮйүдҒXӮЙӮЖӮБӮДҢRҗ_ӮЖҢҫӮҰӮОҒAҗнҲУҚӮ—gӮЙ—ҳ—pӮіӮкӮйғlғKғeғBғ”ӮИғCғҒҒ[ғWӮӘҗжҚsӮөӮӘӮҝӮҫӮӘҒAӮ»ӮкӮНӮұӮұӮ©ӮзӮаӮӨҗ”Ҹ\”NҗжӮМҳbӮҫҒBғҚғVғAҠCҢRӮМҢRҗlӮ©ӮзӮ·ӮзӮа•К’iӮМҢhҲУӮЖӮЖӮаӮЙӢцӮіӮкӮҪҚLҗЈӮМҺ–—бӮрҢ©ӮкӮОҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮаүдӮӘҚ‘ҚЕҸүӮМҒwҢRҗ_ҒxӮНҸғҗҲӮЙҚLҗЈӮЖӮўӮӨҢчҳJҺТӮЙ‘ОӮ·ӮйҒAҲФҳJӮЖ‘ёҢhӮЙӮжӮБӮДҚХӮзӮкӮҪӮЖ—қүрӮ·ӮйӮМӮӘҗіүрӮҫӮлӮӨҒB ҚLҗЈ•җ—YӮӘҢ}ӮҰӮйҺ–ӮМӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪ37ҚОӮМҗ¶’aӮМ“ъҒA5ҢҺ27“ъҒB“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY—ҰӮўӮйҳAҚҮҠН‘аӮН‘О”nү«ӮЙӮДғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮрҢ}ҢӮҒB‘OӮЙӮаҢгӮЙӮа•АӮФ—бӮМ–іӮўҒAҠCҗнӮЙӮЁӮҜӮйҠ®‘SҸҹ—ҳӮЙӮжӮБӮД‘cҚ‘–hүqӮМҗУ–ұӮрүКӮҪӮ·Һ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘ж“сҠН‘а | |
|
ҒЎҸг‘ә•F”VҸе 1849-1916 ҺF–Җ”Л
‘ж“сҠН‘аҺi—Я’·ҠҜҒBҗнҠНӮр’ҶҗSӮЙ•Тҗ¬ӮіӮкӮй‘жҲкҠН‘аӮЙ‘ОӮөҒA‘•ҚbҸ„—mҠНӮЕ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪӮМӮӘ‘ж“сҠН‘аӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМӢ@“®—НӮрҠҲӮ©ӮөҒAҠCҗн“–ҸүӮНғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аҢӮ”jӮМ”C–ұӮр•үӮӨҒBҸг‘әӮН”сҸнӮЙ’ZӢCӮЕӢCҗ«ӮӘҚrӮўҺ–ӮЕ’mӮзӮкҒA“ҜӢҪӮМ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮрӮөӮДҒuӮ ӮкӮЩӮЗҠҙҸоӮМҢғӮөӮў’jӮНӮЁӮзӮсҒvӮЖӮЬӮЕҢҫӮнӮөӮЯӮДӮўӮйҒB Ҹг‘әӮӘҢӮ‘ЮӮ·ӮЧӮӯӮЖӮұӮлӮМғEғүғWғIҠН‘аӮНҒA•¶Һҡ’КӮиғEғүғWғIғXғgғNӮЙҸн’“Ӯ·ӮйғҚғVғAҠН‘аӮЕҒA•ЁҺ‘Ӯрү^ӮФ“ъ–{ӮМ—A‘—ғүғCғ“ӮрӢ}ҸPӮөӮДӮН’ҫӮЯӮйҚмҗнӮр”C–ұӮЖӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒA“ъ–{ӮНҸ«•әӮрӮНӮ¶ӮЯӮЖӮ·Ӯй•ЁҺ‘ӮрӮөӮОӮөӮО’ҫӮЯӮзӮкҒAӮЬӮіӮЙҗн—ӘҸгӮМ’Й“_ӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗ§ҠCҢ ӮМҠm•ЫӮНҒAҠщӮЙҠJҗнӮжӮиӮёӮБӮЖҲИ‘OӮ©ӮзҺR–{Ң •әүqҠCҢR‘еҗbӮЙӮжӮБӮДӢӯӮӯҺе’ЈӮіӮкӮДӮўӮҪҺ–ӮЕӮ ӮиҒAӮжӮБӮДӮнӮҙӮнӮҙ‘ж“сҠН‘аӮӘ•Тҗ¬ӮіӮкӮДӮўӮҪӮнӮҜӮҫӮӘҒAҠJҗнҢгӮөӮОӮзӮӯӮНӮұӮМ”C–ұӮрүКӮҪӮ№ӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮӘ‘ж“сҠН‘аҸг‘ә’·ҠҜӮМ•sү^ӮҫӮБӮҪҒB ‘ж“сҠН‘аӢкҗнӮМ—қ—RӮЖӮөӮДҒA‘ҠҺиӮМғEғүғWғIҠН‘аӮӘӢ@“®җ«ӮЙ—DӮкӮҪҠН‘DӮМҸWӮЬӮиӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖҒAӮ»ӮкӮзӮӘӮ ӮӯӮЬӮЕ—A‘—‘DӮМҠпҸPӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮЁӮиҒAҸг‘әҠН‘аӮЖҗнүОӮрҢрӮҰӮйҲУҺvӮӘҠF–іӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖҒAӮЬӮҪ“ъ–{ҠC“Б—LӮМ”Z–¶ӮӘғEғүғWғIҠН‘аӮМ“Ұ–SӮЙ—L—ҳӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘӢ“Ӯ°ӮзӮкӮйҒBӮұӮМҲЧҒAҸг‘әҠН‘аӮНүҪ“xӮ©ғEғүғWғIҠН‘аӮр•в‘«ӮөӮВӮВӮаҒAӮ ӮЖҲк•аӮЕ“ҰӮ°ӮзӮкӮйҸX‘ФӮрҢJӮи•ФӮөӮДӮўӮҪҒBҚ‘“аӮЕӮНҸг‘әӮЦӮМ”l“|ӮӘҗҒӮ«ҚrӮкҒAӢcүпӮЕӮаҸг‘әӮрҳIҚңӮЙ–і”\ҲөӮўӮ·ӮйҗәӮЬӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМҠФҒAҚИӮӘҺзӮйҸг‘әӮМҺ©‘оӮЙӮН“ҠҗОӮӘҢJӮи•ФӮіӮкҒA‘OҗьӮМҸг‘әӮЙӮНҸг‘әӮр’Й”lӮ·ӮйҺиҺҶӮвҸ‘–КӮӘҺE“һӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB–ңҗlӮМҠФӮЕӮаҢQӮр”ІӮўӮДҠҙҸоӮМҢғӮөӮў’jӮӘҒAҗҒӮ«ҸгӮӘӮйҺ©ӮзӮЦӮМҚ“•]ӮЙ‘ОӮөӮЗӮкӮЩӮЗӮМҗSҸқӮрҠіӮБӮҪӮ©ӮНҺ@ӮөӮД—]ӮиӮ ӮйҒBӮұӮМҠФҸг‘әӮНҲкҗШӢCӮЙӮөӮИӮўӮ»ӮФӮиӮЕ’КӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮӘҒAҚІ“Ў“S‘ҫҳYҺQ–dӮЙӮНҸг‘әӮМ”w’ҶӮӘҸ¬ӮіӮӯҢ©ӮҰӮҪӮЖӮўӮӨҒB Ӯ»ӮсӮИҺ“•ҡӮМҺһӮрҢoӮДҒAҸг‘әҠН‘аӮНӮжӮӨӮвӮӯ”C–ұӮрӮЬӮБӮЖӮӨӮ·ӮйӢ@Ӯр“ҫӮйҒB“ъ–{Һе—НӮМ“ҢӢҪҠН‘аӮЖғҚғVғAӮМ—·ҸҮҠН‘аӮӘҢғ“ЛӮөӮҪү©ҠCҠCҗнӮӘҚsӮнӮкӮҪӮМӮНҠJҗнӮМ”NӮМүДҒA8ҢҺ10“ъҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮМ4“ъҢгҒAғEғүғWғIҠН‘аӮН—·ҸҮҠН‘аӮӘүу–ЕӮөӮҪӮЖӮН’mӮзӮёӮЙҚҮ—¬—\’и’n“_ӮЙҗiӮЭҸoӮҪҒBӮұӮұӮЕ‘ҳӢцӮөӮҪӮМӮӘҸг‘әҠН‘аӮЕӮ ӮиҒA‘ЮҳHӮр’fӮҝӮВӮВ‘SҠНӮӘӮ ӮиӮБӮҪӮҜӮМ–C’eӮр“fӮ«ҸoӮөӮҪҒBҗўӮЙ–јҚӮӮўүәҗЈүО–тӮӘү©ҠCҠCҗнӮЙ‘ұӮўӮДӮұӮұӮЕӮа‘еүОүӢӮрҸгӮ°ҒAӮұӮМҺһӮнӮёӮ©3җЗӮМғEғүғWғIҠН‘аӮНҺUӮиҺUӮиӮЖӮИӮБӮҪҒBҸг‘әӮН—]җlӮрҠсӮ№•tӮҜӮИӮўӮЩӮЗӮМҢғҸоӮрӮФӮҝӮЬӮҜӮИӮӘӮз–C’e”ӯҺЛӮМҺw—ЯӮрҸoӮө‘ұӮҜҒAҗӢӮЙӮНғEғүғWғIҠН‘аүу–ЕҗЎ‘OӮЙ’ЗӮўӢlӮЯӮИӮӘӮзӮа’eҗШӮкӮЙҺҠӮй(ӮұӮкӮНҢл•сӮҫӮБӮҪӮЖӮМҗаӮаӮ Ӯй)ҒBӮұӮМҺһҸг‘әӮН“`Ңҫ—pӮМҚ•”ВӮр’@Ӯ«ӮВӮҜӮД–\ӮкӮйӮжӮӨӮЙүчӮөӮӘӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйӮӘҒAӮ»ӮМҗ”ҺһҠФҢгӮЙӮН”ј’ҫӮМ“GҠНғҠғ…Ғ[ғҠғbғNӮ©ӮзҸж‘gҲхӮрӢ~Ҹ•Ӯ·Ӯй—вҗГӮіӮрҺжӮи–ЯӮөӮДӮўӮйҒB Ҹг‘әӮӘҗ”ғ–ҢҺӮаӮМҠФҺфӮў‘ұӮҜӮҪғEғүғWғIҠН‘аӮЙ‘ОӮөҒAӢ~ҚПӮрҺ{ӮөӮҪӮМӮН”ЮӮМҗl•ЁӮрҢ©ӮйҸгӮЕӢ»–Ўҗ[ӮўӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҸг‘әҠН‘аӮЙ“O’к“IӮЙ’@Ӯ©ӮкӮҪғҚғVғAӮМғҠғ…Ғ[ғҠғbғNӮНҒA’NӮМ–ЪӮЙӮаҗ퓬•s”\ӮН–ҫӮзӮ©ӮЕҒAҸжҲхӮН’ҫ–vӮЙ”хӮҰӮД‘ҒӢ}ӮЙ”р“пӮ·ӮйӮЧӮ«Ҹу‘ФӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAӮЗӮсӮЗӮсҢXӮўӮДӮўӮӯ‘D‘МӮЙӮЁӮўӮДҒAғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҸжҲхӮН–CӮр‘ЕӮҝ‘ұӮҜӮДӮЁӮиҒA—»ҠНӮӘҗнҗь—Ј’EӮөӮҪҢгӮаҗнҲУӮр“rҗШӮкӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮўҒBӮұӮМ—EҠёӮіӮӘҸг‘әӮМӢХҗьӮЙҗGӮкӮҪӮжӮӨӮИӮМӮҫҒB ҺF–Җ•җҺmӮЙӮЖӮБӮДҒw—EҠёӮЕӮ ӮйҺ–ҒxӮЖҒwҺгҺТӮрӮўӮҪӮнӮйҺ–ҒxӮНҚЕ‘еӮМ”ь“ҝӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкӮйҒBҺF–ҖҢ^ӮМ“TҢ^“IӢCҺҝӮЕӮұӮМ’nҲКӮЬӮЕ“oӮБӮДӮ«ӮҪҸг‘әӮӘҒA“GҠНҸж‘gҲхӮМӢ~ҚП–Ҫ—ЯӮрҸoӮөӮҪӮМӮНҒAӮЬӮіӮЙ•K‘RӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBҢгӮЙӮұӮМҚsҲЧӮН“ъ–{Қ‘–ҜӮЙ‘еӮўӮЙғEғPҒA’ј‘OӮЬӮЕҒw–і”\ҒxӮЖӮМ’ҶҸқӮр—ҒӮСӮ№ӮДӮ«ӮҪҗўҠФӮМ•]үҝӮНҲк•ПҒA•җҺm“№ӮМҠУӮЖӮөӮД‘еӮўӮЙҸЬҺ^ӮіӮкӮйҺ–ӮЖӮИӮйҒB ”l“|ӮЖҸЬҺ^ӮӘҗҒӮ«ҚrӮкӮҪҸг‘әӮЖ—ЮҺ—ӮМғPҒ[ғXӮЖӮөӮДӮН”T–ШҠу“TӮМ—бӮӘӮ ӮйҒB”T–ШӮӘ—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘӮЙҺиҠФҺжӮБӮҪҚЫӮЙӮаҒA”T–Ш“@ӮЙӮН“ҠҗОӮӘҢJӮи•ФӮіӮкҒA—ҜҺзӮрҺзӮйҚИӮНӮҪӮўӮ»ӮӨҗSҚЧӮў‘zӮўӮрӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAҗнҢгӮЙӮИӮБӮДӮЭӮкӮОҗўҠФӮНҺиӮМӮРӮзӮр•ФӮөӮҪӮжӮӨӮЙ”T–ШӮрҸЬҺ^ҒAҢRҗ_ӮЙҚХӮиҸгӮ°ӮҪҒBҺё”sӮөӮҪҺТӮЙ‘ОӮөӮДүAӮ©Ӯз“O’к“IӮЙ‘ЕҢӮӮрүБӮҰӮйҗ«ҺҝӮНҒAүдҒX“ъ–{Қ‘–ҜӮӘҺқӮВүAҺјӮИӮй•”•ӘӮМҚЕӮҪӮйӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒAҲк•ыӮЕ•ЁҺ–ӮЙҲкӢCӮЙ”MӢ¶ӮөҒA—қҗ«ӮрҺёӮўӮ©ӮҜӮйӮМӮаӮвӮНӮиүдҒXӮМ(ҺһӮЙ•үӮМҗ«ҺҝӮрҺқӮВ)Қ‘–Ҝҗ«ӮЖҢҫӮБӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB ӮіӮДҒAғEғүғWғIҠН‘аҢӮ‘ЮӮ©Ӯз9ғ•ҢҺҢгӮМ“ъ–{ҠCҠJҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAҸг‘әӮНҚДӮСҸd—vӮИ“ӯӮ«ӮрӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒBҗнҗь—Ј’EӮрҺҺӮЭӮйғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮМҗiҳHӮрҢ©ҢлӮБӮҪ“ҢӢҪӮзӮМҺw—ЯӮр–іҺӢӮөҒA“Ж’fӮЕӢt•ыҢьӮЦ“]җiҒA‘ЮҳHӮрӮУӮіӮ®Һ–ӮЕ“GҠН‘аӮМ“Ұ–SӮрҠ®‘SӮЙ–hӮ¬Ӯ«ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮӘӮИӮҜӮкӮОғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮНҗнҗьӮ©Ӯз–іҺ–ӮЙ—Ј’EҒAғEғүғWғIҚ`ӮЦӮМ‘Ю”рӮрүКӮҪӮ№ӮҪӮНӮёӮЕӮ ӮиҒAҢӢүКӮЖӮөӮДҚЎӮМ“ъ–{ӮН–іӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB җнҢгҒAҺQ–dӮМҚІ“Ў“S‘ҫҳYӮН•ДҢRҺmҠҜӮзӮЙ‘ОӮ·ӮйҢцүүӮЙӮЁӮўӮДҒAӮұӮМҺһӮМ“а—ЦҺ–ҸоӮр’kҳbӮЖӮөӮДҸqӮЧӮҪӮМӮҫӮӘҒAҗ^‘ҠӮр’mӮБӮҪӮЖӮ Ӯй•ДҢRҸ«ҠҜӮӘҸг‘әӮМҒw—EӢCӮ Ӯй“Ж’fҒxӮЙ‘ОӮөӮДҒuғuғүғ{Ғ[ҒvӮрӢ©ӮсӮҫҒBҠщӮЙүј‘z“GҚ‘ӮЙӮИӮиӮВӮВӮ ӮБӮҪ•ДҚ‘ӮМҺdҠҜӮр‘OӮЙҚІ“ЎӮНҒuҢҫӮӨӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒcҒvӮЖҗ[ҚҸӮЙҢгүчӮөӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒA“ҢӢҪӮзӮӘ“GҠНӮМҗiҳHӮрҢ©ҢлӮБӮҪҺ–ӮНҗнҢгӮа’·ӮўҠФ”й–§ӮЙӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҢRҗ_ӮӘҠФҲбӮўӮр”ЖӮөӮҪӮЖӮўӮӨӢLҳ^ӮН’fӮ¶ӮДҠOӮЙҳRӮкӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮҫҒB ӮұӮМҗн‘ҲӮЙҸҹӮБӮҪҺһ“_ӮЕҒA“ъ–{ӮНӮаӮӨ“]—ҺӮөҺnӮЯӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҺOҠН‘а | |
|
ҒЎ•РүӘҺөҳY 1854-1920 ҺF–Җ”Л
‘жҺOҠН‘аҺi—ЯҠҜҒBҗ«ҠiӮНү·ҢъӮЕ”h”ҙӮЙ‘®ӮіӮёҒA–і—~ӮИҗlҠiҺТӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB Ңа’БҺз•{Һi—ЯҠҜҒAҢаҠНҗӯ•”’·ӮИӮЗӮМ—vҗEӮрҢoӮД‘жҺOҠН‘аҺi—ЯҠҜӮЖӮИӮйҒB ‘жҺOҠН‘аӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮрҗнӮБӮҪҳVӢҖҠНӮ©Ӯзҗ¬ӮиҒAҺе—НҢҲҗнӮЙӮЁӮўӮДӮН“–ҸүӮ©Ӯзҗн—НҠOӮМ‘¶ҚЭӮЖӮөӮДҢ©ӮзӮкӮДӮўӮҪҒBҲк•ыӮЕ‘«ӮМ‘¬ӮўҸ„—mҠНӮӘ’ҶҗSӮМҚ\җ¬Ӯ©ӮзҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕӮНҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮМҗiҳHҠm”FӮӘҺе”C–ұӮҫӮБӮҪҒB•РүӘӮНҒA“–ҸүҳAҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮЙҚЕ—L—НҺӢӮіӮкӮДӮўӮҪҺF–ҖӮМ“ъҚӮ‘s”VҸеӮЖҺmҠҜҠwҚZ(ӮМ‘Oҗg)ӮМ“ҜҠъӮЕӮ ӮиҒAҠCҢRӮЙӮЁӮўӮДӮ»ӮкӮИӮиӮМ“№Ӯр•аӮ«‘ұӮҜӮДӮ«ӮҪӮҫӮҜӮЙҒAҸoӮй–ӢӮМ–іӮўҗн—НҠOӮМ—лҚЧҠН‘аҺi—ЯҠҜӮЖӮўӮӨ—§Ҹк(ӮөӮ©ӮаҺе—НҠНӮН‘жҲкҠН‘аӮЙҲшӮ«”ІӮ©ӮкӮй)ӮНҗSҠOӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBӮӘҒA•РүӘӮНҺ©ӮзӮМ”C–ұӮЖ—§ҸкӮЙ‘ОӮөҒAӢЙӮЯӮД’үҺАӮИҗl•ЁӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB ”––¶ӮӘ“ъ–{ҠCӮр•ўӮӨ5ҢҺ27“ъ‘Ғ’©ҒAҸЈүъҠНҒwҗM”ZҠЫҒxӮ©ӮзӮМҒu“GҠНҢ©ӮдҒvӮМ‘Е“dӮЙӮжӮиҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮӘӮўӮжӮўӮжҠJҗнӮЦӮЖҢьӮ©ӮӨӮнӮҜӮҫӮӘҒA“ъ–{‘ӨӮМҗнҸҹҸрҢҸӮН“GҠН‘аҹr–ЕҒBҠCҗнӮМҸнҺҜӮЕӮНҒAӮЬӮёҺАҢ»•sүВ”\ӮЖӮіӮкӮйҚӮӮўғnҒ[ғhғӢӮӘүЫӮ№ӮзӮкӮДӮўӮҪҒBӮұӮкӮрғNғҠғAӮ·ӮйӮЙӮН“ъ–{‘ӨӮЙӮЖӮБӮДҒwҲі“|“IӮЙ—L—ҳӮИҸуӢөҒxӮЕҗнүОӮрҠJӮӯ•K—vӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮМҲЧӮМүә’nҚмӮиӮЖӮөӮДҒA“GҠН‘аӮМҒwҗiҳHҠm”FҒxӮНӮұӮМҸгӮИӮӯҸd—vӮҫӮБӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝ‘жҺOҠН‘аӮМ”C–ұӮұӮ»ӮӘҒgӮ»ӮкҒhӮЕӮ ӮиҒAӮұӮМҸd—vҗ«Ӯр–ҫҠmӮЙ”F’mӮөҒA‘S—НӮЕӮЬӮБӮЖӮӨӮөӮҪӮМӮӘҒA•РүӘҺөҳYӮЖӮўӮӨ’jӮМҗ^үҝӮҫӮлӮӨҒB ҒwҗM”ZҠЫҒxӮМ‘Е“dӮЙӮжӮиғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮр•в‘«ӮөӮҪ‘жҺOҠН‘аӮН’ЗҗХӮМ”C–ұӮрҢpҸіӮөӮҪҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕғҚғVғA‘ӨӮМҗiҳHӮНҠTӮЛ“Б’иӮЕӮ«ӮДӮЁӮиҒAӮИӮзӮОӮ»ӮМҗё“xӮрҠmҺАӮИӮаӮМӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ’iҠKӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮұӮұӮЕ•РүӘҺөҳYӮӘүәӮөӮҪ–Ҫ—ЯӮӘҒA“GҠНӮМ‘OӮр“ЛӮБҗШӮйӮЖӮўӮӨ—НӢZӮҫҒB‘D”•ӮӘҒA‘јӮМ‘D”•ӮМҗіҠmӮИҗiҳHӮр’f’иӮ·ӮйҚЫҒAҚЕӮаҠmҺАӮИӮМӮН‘ҠҺиҠНӮМҗ^җі–КӮЙҸoҒAӮ»ӮұӮ©ӮзҠp“xҒAӮ·ӮИӮнӮҝ•ыҠpӮрҠ„ӮиҸoӮ·•ы–@ӮЕӮ ӮйҒBӮаӮҝӮлӮсҸW’Ҷ–CүОӮЙүпӮӨғҠғXғNӮНӮұӮМҸгӮИӮӯҚӮӮўҒB•РүӘӮНӮ»ӮкӮрҢҲҚsӮ·ӮЧӮ«ӮЖ”»’fӮөӮҪҒB‘жҺOҠН‘а‘S–ЕӮМғҠғXғNӮЖҒA“GҸоӮМ“`’BӮрӮНӮ©ӮиӮЙӮ©ӮҜӮкӮОҒAҠФҲбӮўӮИӮӯҢгҺТӮӘҸd—vӮЖӮМүp’fӮЖҢҫӮҰӮйҒB “G‘OӮМүЎ’fӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҺАҚЫӮЙӮНӮұӮМҺһӢЯӮӯӮЙӮўӮҪ‘жҺlӢм’Җ‘а(‘ж“сҠН‘аҸҠ‘®)ӮӘ—EҠёӮЙӮаҗжӮЙ“ҜӮ¶ӮұӮЖӮрҢҲҚsӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҸ„—mҠНӮМҗ”•ӘӮМҲкӮМ‘еӮ«ӮіӮЕҒAӮ©ӮВӢ@“®—НӮа“с”{ӮрҢЦӮйӢм’ҖҠН‘аӮӘӮ»ӮМҗ^үҝӮр”ӯҠцӮөӮҪӮнӮҜӮҫҒBӮұӮМӢм’ҖҠН‘аӮМҺi—ЯҠҜӮӘҒA—й–ШҠС‘ҫҳY’ҶҚІӮЕӮ ӮиҒA‘ж“сҺҹ‘еҗн––ҠъӮЙ“ҢҸрүpӢ@Ӯ©ӮзҗӯҢ ӮрҲшӮ«ҢpӮўӮҫҒAҢгӮМ—й–Ш‘Қ—қ‘еҗbӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮМҢгҒAғҚғVғAҠН‘аҺе—НҠНӮ©ӮзӮМ–CҢӮӮМ“IӮЖӮИӮиӮИӮӘӮзӮа‘жҺOҠН‘аӮНҸо•сӮМ‘Е“dӮр‘ұӮҜҒAҢӢүК“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮрӮөӮДҒu“GӮрҢ©Ӯй‘OӮЙ“GӮМҗwҢ`Ӯ»ӮМ‘јӮр’mӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒvӮЖҢҫӮнӮөӮЮӮйӮЙҺҠӮйҒB’КҗMҺи’iӮӘ”ӯ“W“rҸгӮЙӮ ӮБӮҪ“–ҺһӮЙӮЁӮўӮДҒA“GӮМҗiҳHӮвҗн—НҒA‘а—сӮЬӮЕҺ–‘OӮЙҸ¶Ҳ¬ӮЕӮ«ӮҪҗ¬үКӮНҒAӮұӮМҺһ“_ӮЕҗўҠEӢьҺwӮҫӮБӮҪҒBҢВҗlӮМ•җҢMӮҫӮҜӮӘҸdҺӢӮіӮкӮҪ•җҺmӮМҺһ‘гӮМҗнӮ©ӮзӢЯ‘г“IӮИҸW’cҗнӮЦӮЖҢ`ӮӘ•ПӮнӮй’ҶҒA•РүӘӮзӮрҺnӮЯӮЖӮ·Ӯй•‘‘д— ӮМҗlҚЮӮМӢMҸdӮіӮН•MҗгӮЙҗsӮӯӮөӮӘӮҪӮўҒBӮЖӮаӮ ӮкҒAӮұӮМҺһӮМҗнҸкӮЕӮНҒA“ъ–{җlӮӘҺқӮВҒA’n–ЎӮЕ’…ҺАӮИӢО•ЧӮіӮӘҚЕӮа‘еӮ«Ӯӯ”ӯҠцӮіӮкҒAҚЕ‘еӮМҗ¬үКӮрҸгӮ°ӮҪӮЖ’fҢҫӮөӮДӮаӮўӮўӮҫӮлӮӨҒB“ъ–{ҠCҠCҗнҢгҒA•РүӘӮН’вҗнӮМҚuҳaҸр–сӮр—L—ҳӮЙҗiӮЯӮйҲЧӮМҠ’‘ҫҗи—МӮЙ”hҢӯӮіӮкҒAӮ»ӮұӮЕӮа”C–ұӮр–іҺ–ӮЬӮБӮЖӮӨӮ·ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒB җнҢгӮН—ӨҠCҢRӮр’ҶҗSӮЖӮ·Ӯйҗӯ‘ҲӮЙӮНҠЦӮнӮзӮёҒA•РүӘӮЖӮН‘ОҸЖ“IӮЙҠCҢR‘еҗbӮЙӮЬӮЕҸгӮиӢlӮЯӮҪ”Ә‘гҳZҳY(‘•ҚbҸ„—mҠНҒwҗуҠФҒxҠН’·:‘ж“сҠН‘а)ӮӘҒA‘дҳp‘Қ“ВӮМғ|ғXғgӮрҸ„ӮйғSғ^ғSғ^(—ӨҠCҢRӮМӮўӮҙӮұӮҙ—ҚӮЭ)ӮрҺқӮҝҚһӮсӮЕӮ«ӮҪҺһӮИӮЗӮаҒA–іүәӮЙҲкҸRӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮкӮН•РүӘӮМҗ«ҠiӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮҫӮлӮӨӮӘҒA“ҜҺһӮЙҺF–Җ•җҺmӮМ”ь“ҝӮМҲкӮВӮЖӮіӮкӮйҒwҢүӮіҒxӮЙӮжӮй•”•ӘӮа‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒBҒ@ |
|
| ҒЎғҚғVғA | |
|
ҒЎғXғeғtғ@ғ“ҒEғ}ғJғҚғt 1813-1878 ғEғNғүғCғi
‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аҒAӮўӮнӮдӮй—·ҸҮҠН‘аӮМҺi—ЯҠҜҒB 1877-78”NӮМғҚғVғAҘғgғӢғRҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҒAҗ…—ӢҚмҗнӮЕ“G•ыӮрӢкӮөӮЯӮҪҠCҢRӮМ–јҸ«ӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҺһӮМҗнӮўӮНӢӣ—ӢӮрҺg—pӮөӮҪҚмҗнӮЕӮНҗўҠEӮЕӮаҚЕӮа‘ҒӮўҺһҠъӮМӮаӮМӮЕҒAҠCҢRӢZҸpҠvҗVӮМҚЕҗж’[ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBӮұӮМҺһҠъӮЙғҚғVғAӮӘҠJ”ӯӮөӮҪ“OҚb’eҠЫӮӘғ}ғJғҚғtғLғғғbғvӮЖҢДӮОӮкӮйӮжӮӨӮЙҒAғ}ғJғҚғtҺ©җgҒAҠН‘аӮМӢ@”\ӮрҢьҸгӮіӮ№ӮйӮҪӮЯӮЙ‘•ҚbӮвҚqҠCӢ@”\ҒAӢyӮСҠC—mҢӨӢҶӮИӮЗӮЙҗs—НӮөҒA’ҶӮЙӮН—LҠQӮИҢӨӢҶӮаӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйӮӘҒA‘S‘МӮЖӮөӮДҠCҢR—Н‘қҗiӮЙӮ©ӮИӮиҚvҢЈӮөӮҪӮзӮөӮўҒB ӮЬӮҪҒAҗўҠEҲкҺьҚqҠCӮр2“xӮаҚsӮБӮДӮЁӮиҒAҠCӮМ’jӮЖӮөӮДӮМ–`ҢҜүЖ“IҲк–КӮрӮЭӮ№ӮИӮӘӮзӮаҒAӮұӮМҺһӮМҢӨӢҶҗ¬үКӮрҒuғ”ғBҒ[ғ`ғғғVҚҶӮЖ‘ҫ•Ҫ—mҒvӮЙ’ҳӮөӮД”ӯ•\Ӯ·ӮйӮИӮЗҒAҢӨӢҶүЖӮЖӮөӮДӮМҚӘҗ«Ӯа‘Ҡ“–ӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB“ъҳIҠJҗн’ј‘OӮЙӮаҒA“–ҺһҚЕҗVүsӮМ•XҚУҠНҢҡ‘ўӮЙҢgӮнӮиҒAӮұӮМҚ ӮМғҚғVғAӮЙӮЖӮБӮДӮМMr.ҠCҢRӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйӮҫӮлӮӨҒB Ӯ»ӮсӮИғ}ғJғҚғtӮӘӢЙ“ҢӮЙҸжӮиҚһӮсӮЕӮ«ӮҪҒB “ъҳIҠJҗнӮМ’iҠKӮЕҒA—·ҸҮҠН‘аӮМҺi—ЯҠҜӮНғIғXғJғӢҒEғ”ғBҒ[ғNғgғҚғ”ғBғ`ҒEғXғ^ғӢғN’с“ВӮҫӮБӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮМҳAҚҮҠН‘аӮЙҠпҸPӮіӮкӮҪҗУ”CӮр–вӮнӮкӮД‘Ю”CҒA‘гӮнӮБӮДғ}ғJғҚғt’с“ВӮӘҸA”CӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒBҢі—ҲҠCҢRӮЙӮЁӮўӮД‘еӮўӮЙғҠҒ[ғ_Ғ[ғVғbғvӮр”ӯҠцӮөҒA”ЮӮМҗM•тҺТӮН‘Ҫҗ”ӮЙӮМӮЪӮБӮҪӮЖӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӮұӮМҢр‘гҗlҺ–ӮЕғҚғVғA‘ӨӮМҺmӢCӮНӮ·ӮұӮФӮйҸгҸёӮөӮҪӮжӮӨӮҫҒB “–ҸүҒA—·ҸҮҚ`ӮМүңҗ[ӮӯӮЕҗн—Нү·‘¶Ӯрҗ}ӮБӮДӮўӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮНҒAғ}ғJғҚғtӮМҸA”CӮЙӮжӮБӮДҗПӢЙ“IӮЙҠO—mӮЙҸo–vӮөҺnӮЯҒAӮөӮ©Ӯө—vҚЗ–CӮМҺЛ’цӢ——ЈғMғҠғMғҠӮ©ӮзҠOӮЙҸoӮйҺ–ӮНӮИӮӯҒA“ъ–{‘ӨӮр—UӮБӮДӮНҲшӮБҚһӮЮӮЖӮўӮӨӮ©ӮҜӮРӮ«ӮӘҳA“ъҚsӮнӮкӮҪҒBӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮағ}ғJғҚғtӮМӢCҗ«ӮЖӮөӮДӮНҒAӮаӮБӮЖҠO—mӮЕғhғ“ғpғ`ӮвӮиӮҪӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮЕҒAӮөӮОӮөӮО—vҚЗ–CӮМүҮҢмӮМ“НӮ©ӮИӮўғGғҠғAӮЬӮЕү“ҸoӮөҺnӮЯҒA“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮзҳAҚҮҠН‘а‘ӨӮЙ•tӮҜ“ьӮйҢ„Ӯр—^ӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB —·ҸҮҚ`•ВҚЗҚмҗнӮӘ–FӮөӮўҗ¬үКӮрӮ Ӯ°ӮёҒAҺиӢlӮЬӮиҠҙӮМӮ ӮБӮҪ“ҢӢҪӮзӮЖӮөӮДӮНҒAӮөӮ«ӮиӮЙҚ`Ӯ©ӮзҸoӮДӮ«ӮДӮН’§”ӯӮрҢJӮи•ФӮ·ғ}ғJғҚғtӮМҗ«ҺҝӮНӮЮӮөӮлҚD“sҚҮӮҫӮБӮҪӮлӮӨҒBӮұӮҝӮзӮ©Ӯз’§”ӯӮ·ӮкӮОӮ·Ӯ®ӮЙ”MӮӯӮИӮйҺ–ӮӘӮнӮ©ӮйӮЙӮВӮкҒAҒuӮЕӮНҒAӮЁӮСӮ«ҸoӮөӮДӢ@—ӢӮЙӮФӮҝ“–ӮДӮкӮОӮЗӮӨӮ©ҒvӮЖӮўӮӨҲДӮӘ•ӮҸгҒBӮіӮ·ӮӘӮЙҢҙҺn“IӮ·Ӯ¬ӮйҚмҗнӮЙҒAҳAҚҮҠН‘аҺi—Я•”ӮаӮ»ӮұӮЬӮЕ‘еӮ«ӮИҗ¬үКӮНҠъ‘ТӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮйҒBӮӘҒAӮУӮҪӮрӮ ӮҜӮкӮОҒAӮЁӮСӮ«ҸoӮіӮкӮҪғ}ғJғҚғtӮНҒAӮЬӮсӮЬӮЖ“ъ–{‘ӨӮМӢ@—ӢӮЙҗЪҗGӮөҒAҠшҠНғyғgғҚғpғtғҚғtғXғNӮНӮ ӮҰӮИӮӯҚҢ’ҫҒBӮұӮұӮЕғ}ғJғҚғtӮН’EҸoӮМ“№Ӯр‘IӮОӮёҒAҠНӮЖӮЖӮаӮЙҠCӮЙҸБӮҰӮҪҒBӮұӮМӮ ӮҪӮиӮНҒAӢrҗFӮаӮ ӮлӮӨӮӘҒAҠCӮМ’jӮЖӮөӮДӮМҗ¶Ӯ«—lӮӘ‘O–КӮЙҸoӮДӮўӮДҸгҺҝӮМүp—Y’kӮЖҢҫӮҰӮйҒB ӮіӮДҒAғ}ғJғҚғtӮрӢ@—ӢӮЕҢӮ’ҫӮіӮ№ӮҪҳAҚҮҠН‘аӮЖӮөӮДӮНҒAҺvӮнӮКҗнүКӮЙҗFӮЯӮ«—§ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBӮӘҒAӮұӮкӮӘӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮӘҚ`ӮМүңҗ[ӮӯӮЬӮЕӮаӮ®ӮиӮұӮсӮЕӮөӮЬӮӨ•ӣҚм—pӮӘ”ӯҗ¶ҒAӮіӮзӮЙӮН•ңҸQӮЙ”RӮҰӮҪғҚғVғA‘ӨӮӘҒAҺ©•Ә’BӮӘӮвӮзӮкӮҪӢ@—ӢҚмҗнӮр“ъ–{‘ӨӮЙҺdҠ|ӮҜҒAӮИӮсӮЖ“ъ–{‘ӨӮаҒw”Ә“ҮҒxӮЖҒwҸүҗЈҒxӮӘӮұӮкӮрӮЬӮЖӮаӮЙӮӯӮзӮӨӮЖӮўӮӨ‘еҺё‘ФӮрҢ©Ӯ№ӮДӮўӮйҒBӮұӮМҺһҒAҲк”ӯӮМ–C’eӮа‘ЕӮҪӮёӮЙҒAӮЬӮіӮЙҢХӮМҺqӮМҗнҠНӮӘ2җЗӮаҺёӮнӮкҒA’NӮаӮӘҚ‘үЖ‘¶‘ұӮМҠлӢ@ӮрҠҙӮ¶ӮйӮЩӮЗӮМҸХҢӮӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB ӮұӮМӮ ӮҪӮиӮНҒA“ъҳI‘o•ыӮЖӮаӮЙҒAӢЯ‘гҗнӮМ–ўҸnӮіӮӘҳI’жӮөӮҪғPҒ[ғXӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйӮӘҒAӮжӮиӮЙӮжӮБӮДҠшҠНӮвҗнҠНӮӘғsғ“ғ|ғCғ“ғgӮЕ”н—ӢӮ·ӮйӮИӮЗҒAү^–Ҫ“IӮИ“WҠJӮӘҺ–‘ФӮрӮжӮиҢҖ“IӮЙӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМҺ–ҢҸӮЕ‘е–{үcӮНҢғ“{ӮөҒA“ҢӢҪҚX“Rҳ_ӮаӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮҫӮӘҒAҚЕҸI“IӮЙӮН“ҢӢҪҺ©җgӮМ”л–ЖӮНҚsӮнӮкӮёҒAӮұӮкӮӘҚ‘ү^Ӯр•ӘӮҜӮҪӮЖӮаҢҫӮҰӮйҒB ӢtӮЙғҚғVғA‘ӨӮЕӮағ}ғJғҚғtҗнҺҖӮЕҗнҲУӮМ’бүәӮӘ’ҳӮөӮӯҒAӮұӮҝӮзӮаӮұӮұӮЕҚ‘ү^ӮӘҢҲӮЬӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮўӮўӮҫӮлӮӨҒBҒ@ |
|
|
ҒЎғJҒ[ғӢҒEғyғgғҚғ”ғBғ`ҒEғCғFғbғZғ“ 1852-1918 ғүғgғrғA
ғEғүғWғIғXғgғNҠН‘аҺi—ЯҠҜҒB“ъ–{ҠCӮЙӮЁӮўӮД’КҸӨ”jүуҗнӮрҚsӮўҒA“ъ–{ҢRӮМ•вӢӢӮрӢәӮ©ӮөӮҪҒB “ъҳIҠJҗн“–ҸүӮН—·ҸҮҚ`ӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮЙҸҠ‘®ҒBҠJҗнҢгӮЙғ}ғJғҚғt’с“ВӮМ–ҪӮЙӮжӮиҒAғEғүғWғIҠН‘аҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮД“ъ–{ҠCӮЙӮЁӮҜӮй’КҸӨ”jүуҚмҗнӮЙҸ]Һ–Ӯ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮйҒB“ъ–{‘ӨӮ©ӮзҢ©ӮкӮОҒAғoғӢғeғBғbғNҠН‘аӮұӮ»ӢәҲРӮЖӮўӮБӮҪҠҙӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒAғҚғVғAӮЕӮН—·ҸҮҠН‘аӮұӮ»ӮӘғҚғVғAҠCҢRӮМҗёүsӮЕӮ ӮиҒAҺ–ҺАҒAҠCҗн“–ҸүӮМ”ЮӮзӮМҺmӢCӮНҸнӮЙҚӮӮўҗ…ҸҖӮЙ•ЫӮҪӮкӮДӮўӮҪҒBӮұӮМҲЧҒAҠCҗн’јҢгӮМҗmҗмү«ҠCҗнӮрҸңӮҜӮОҒA“ъ–{ӮМҳAҚҮҠН‘аӮНҸнӮЙӢкҗнӮрӢӯӮўӮзӮкӮДӮЁӮиҒAҗhҸҹӮөӮҪү©ҠCү«ҠCҗнӮИӮЗӮЕӮаҒuӮЗӮӨӮөӮДҸҹӮДӮҪӮМӮ©•ӘӮ©ӮзӮИӮў(ҸHҺRҗ^”VҺQ–d)ҒvӮЖӮўӮӨӮМӮӘҺАҸоӮҫӮБӮҪҒB ғEғүғWғIҠН‘аӮН4җЗӮМҸ„—mҠНӮр’ҶҗSӮЖӮөӮҪҸ¬ӢK–НҠН‘аӮЕӮ ӮиҒAӢ@“®—НӮрҗ¶Ӯ©ӮөӮД—A‘—‘DӮИӮЗӮрҸPҢӮҒA’ZҺһҠФӮЕҗнҗьӮр—Ј’EӮ·ӮйҗнҸpӮрҢJӮи•ФӮөӮД“ъ–{‘ӨӮрӢкӮөӮЯӮҪҒBӮұӮМғEғүғWғIҠН‘аӮр•Я‘ЁӮ·Ӯй”C–ұӮЙӮ ӮҪӮБӮҪӮМӮӘ‘ж“сҠН‘аӮМҸг‘ә•F”VҸе’·ҠҜӮҫӮӘҒA’…”CӮ©Ӯзҗ”ғ–ҢҺҒAҲкҢьӮЙғEғүғWғIҠН‘аӮр‘ЁӮҰӮйҺ–ӮӘӮЕӮ«ӮёӮЙ–і”\ҢДӮОӮнӮиӮіӮкӮҪӮМӮН—L–јӮИҳbӮҫҒB “ъ–{‘ӨӮр–|ҳMӮө‘ұӮҜӮҪғEғүғWғIҠН‘аӮӘӮжӮӨӮвӮӯ•Я‘ЁӮіӮкӮҪӮМӮНҒAҠCҗнӮ©Ӯз”ј”NӮрҢoӮҪүUҺR(ӮӨӮйӮіӮс)ү«ҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮЬӮЕҚI–ӯӮЙҸг‘әҠН‘аӮрӮ©ӮнӮөӮДӮ«ӮҪғCғFғbғZғ“ӮӘӮ ӮБӮҜӮИӮӯ•в‘«ӮіӮкӮҪӮМӮНҒAү©ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮҜӮйҒu‘z’иҠOҒvӮЙӢNҲцӮ·ӮйҒBүUҺRү«ҠCҗнӮЙҗж—§ӮҝҒA—·ҸҮҠН‘аӮӘғEғүғWғIғXғgғNӮЦӮЖҲЪ“®Ӯ·ӮйӮЖӮМ•сӮрҺуӮҜӮҪғCғFғbғZғ“ӮНҒAӮұӮкӮрҢ}ӮҰӮйҲЧӮЙ“ъ–{ҠCӮр“мүәҒA—\’иғGғҠғAӮЕ—\’иҺһҚҸӮрүЯӮ¬ӮДӮаҲкҢьӮЙҚҮ—¬ӮЕӮ«ӮИӮўӮҪӮЯӮЙҠCҸгӮрӮіӮЬӮжӮБӮДӮўӮҪӮЖӮұӮлӮрҒAҸг‘әҠН‘аӮЙ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪҒBӮұӮМҺһҒAғCғGғbғZғ“ӮӘӮ·Ӯ®ӮЙ–kҸгӮөӮДӮўӮкӮОҸг‘әҠН‘аӮЙӮНӮҝҚҮӮнӮ№ӮйҺ–ӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAӮЬӮіӮ©—·ҸҮҠН‘аӮӘүу–ЕӮ·ӮйӮЖӮНҺvӮнӮИӮўҒBӮ»ӮМҗж“ьҠПӮЙӮжӮБӮД”»’fӮӘ“ЭӮБӮҪӮжӮӨӮИӮМӮЕӮ ӮйҒBӮіӮ·ӮӘӮЙӮЁӮ©ӮөӮўӮЖӢCӮГӮ«ҒA–kҸгӮрҠJҺnӮөӮҪӮЖӮұӮлӮЕҸг‘әҠН‘аӮЙ‘ҳӢцҒAӮ ӮиӮБӮҪӮҜӮМ–C’eӮр’@Ӯ«ҚһӮЬӮкӮй“пҺ–ӮЙ‘ҳӢцӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮұӮМҺһӮМҸг‘ә’·ҠҜӮН‘Ҡ“–ӮЙүБ”MӮөӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮнӮкҒAҢғҸоүЖӮЖӮөӮДӮМғGғsғ\Ғ[ғhӮӘӮўӮӯӮВӮ©“`ӮнӮйӮӘҒAҲк•ыӮМғCғFғbғZғ“ӮН•үӮҜҗнӮИӮӘӮзӮаҢгӮЙ•кҚ‘ӮЕҸЬҺ^ӮіӮкӮй“ӯӮ«ӮрҢ©Ӯ№ӮйҒBӮұӮМҺһӮМғEғүғWғIҠН‘аӮНҒwғҚғVғAҒxҒwғOғҚғӮғ{ғCҒxҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮМ3җЗӮМӮЭӮМ•Тҗ¬ӮЕҒAҸг‘әҠН‘аӮМ–CҢӮӮЙӮжӮБӮДҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮН‘е”jҒBҺcӮй2җЗӮаҸг‘әӮМ“S’ЖӮрӢтӮзӮўӮИӮӘӮзӮМ–hҗнӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕҳAҚҮҠН‘аӮМҒwүәҗЈүО–тҒxӮЙӮВӮўӮДӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗғҚғVғA‘ӨӮЙ’mӮзӮкӮДӮЁӮзӮёҒAғEғүғWғIҠН‘аӮНӮ»ӮМ–ТүОӮрҗgӮрҲИӮБӮДҺvӮў’mӮзӮіӮкӮҪҒBғCғGғbғZғ“ӮМ—§ҸкӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAҺc‘¶ӮМҠН‘DӮрғEғүғWғIғXғgғNӮЬӮЕ‘Ю”рӮіӮ№ӮкӮОҒAҲшӮ«‘ұӮ«’КҸӨ”jүуҚмҗнӮНүВ”\ӮИӮнӮҜӮЕҒAӮұӮМӢкӮөӮўҸуӢөүәӮЕӮМҺҠҸг–Ҫ‘иӮНҒw“Ұ‘–ҒxӮЙӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒBӮӘҒAғCғFғbғZғ“ӮНҗнҸкӮрӮИӮ©ӮИӮ©—Ј’EӮөӮжӮӨӮЖӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮЕӮ ӮйҒB ҠН‘аү^“®Ӯ©Ӯз’E—ҺӮөӮҪҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮН“ъ–{‘ӨӮЙӮЖӮБӮД•ҙӮкӮа–іӮў•W“IӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҺһ–ТӮиӢ¶ӮБӮДӮўӮҪҸг‘ә•F”VҸе’·ҠҜӮЙӮжӮБӮДҒAӮұӮМ‘•ҚbҸ„—mҠНӮНҸДӮ«җsӮӯӮіӮкӮйӮМӮаҺһҠФӮМ–в‘иӮҫӮБӮҪӮҫӮлӮӨҒBӮӘҒAғCғFғbғZғ“ӮНҗнҸкӮр—Ј’EӮ·ӮйӮаҚДҺOҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮрҸ•ӮҜӮЙ–ЯӮиҒAүәҗЈүО–тӮМ–C’eӮрӢтӮзӮБӮДӮН“Ұ‘–ҒB“ҰӮ°җШӮБӮҪӮ©ӮЖҺvӮӨӮЖӮЬӮҪ—»ҠНӮрӢ~ӮўӮЙӮӯӮйӮЖӮўӮӨҚs“®ӮрҢJӮи•ФӮөӮҪҒBӮұӮМҲкҳAӮМҚs“®ӮЙӮжӮБӮДҒAғEғүғWғIҠН‘аӮН–Ғ–ХӮЙ–Ғ–ХӮрҸdӮЛҒAҲИҢгҺgӮў•ЁӮЙӮИӮзӮИӮў’цӮЙ”jүуӮіӮкҗsӮөӮҪӮМӮҫӮӘҒAӮ»ӮұӮЬӮЕӮвӮиҗШӮБӮҪғCғFғbғZғ“ӮЙ“G–Ў•ы–вӮнӮёҢгӮЙҸЬҺ^ӮӘҸWӮЬӮБӮҪӮМӮН•K‘RӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB җhӮӨӮ¶ӮДҺ©‘–ӮөӮДӮўӮҪҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮН‘ҠҺҹӮ®’…’eӮЙӮжӮБӮДҗZҗ…ҒBҗӢӮЙӮНғCғFғbғZғ“ӮаҗнҸкӮрҢгӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҺһҒAҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮМ–C“ғ•”ӮЕӮН’ҫ–vӮөӮИӮӘӮзӮаҸ®ҒA–CҢӮӮр‘ұӮҜӮДӮЁӮиҒAҸг‘ә’·ҠҜӮЙҒu“GӮИӮӘӮзӮ ӮБӮПӮкҒvӮЖҢҫӮнӮөӮЯӮҪӮзӮөӮўҒBҗ”ҚҸӮМҢгҒAҒwғҠғ…Ғ[ғҠғbғNҒxӮНҗӢӮЙ“ъ–{ҠCӮЙ–vӮ·ӮйҺ–ӮЙӮИӮйӮМӮҫӮӘҒAҸг‘әҠН‘аӮНҗ¶Ӯ«ҺcӮБӮҪҸж‘gҲхӮзӮрӢ~ҸoҒB’ҡҸdӮЙҲөӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪ”ЮӮзӮНӮ»ӮМҢгҒA“ъ–{Қ‘“аӮМҺы—eҸҠӮЦ‘—ӮзӮкӮҪӮӘҒA“ъҳIҗн‘Ҳ‘S‘МӮрӮЖӮЁӮөӮД•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪғҚғVғA•әӮМҲөӮўӮНҒAҢгҗўӮМ“ъ–{ҢRӮЖӮН”дҠrӮЙӮИӮзӮИӮўӮЩӮЗӮМҢъӢцӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҸ®ҒAғEғүғWғIҠН‘аӮӘ“ъ–{ӮМ—A‘—‘DӮИӮЗӮрҢӮ’ҫӮөӮДӮўӮҪҚ ҒA”gҠФӮЙ•ӮӮ©ӮФҗl”nӮН‘SӮДҢ©ҺEӮөӮЙӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕҒAҢ©ҺEӮөӮЙӮөӮҪ“–Һ–ҺТӮЕӮ ӮйғEғүғWғIҠН‘аҸж‘gҲхӮзӮНҒAҺ©ӮзӮӘӢ~Ҹ•ӮіӮкӮй—§ҸкӮЙӮИӮиҒA“ъ–{‘ӨӮМҲөӮўӮЙ‘еӮўӮЙҚўҳfӮөӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮйҒB ”sҢRӮМҸ«ӮЖӮИӮБӮҪғCғFғbғZғ“ӮНҗнҢгҒAӮ»ӮМҗУ”CӮЙӮжӮБӮДҚ¶‘JӮіӮкӮйӮаҒAҢгӮЙ–ј—_Ӯрүс•ңҒBҲИҢгҠCҢR“аӮМ—НҠwӮЙ–|ҳMӮіӮкӮйҢ`ӮЕ‘Ю–рӮЖӮИӮиҒA‘ў‘DҠйӢЖӮМҢ»ҸкҠД“ВӮЖӮөӮД”дҠr“I•ҪҳaӮИ—]җ¶Ӯр‘—ӮйҺ–ӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲҒE“ъҳIҗн‘ҲҒE‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗн ҠOҠП | |
| ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲҒ@ | |
|
“ъҗҙҗн‘ҲӮНҒAҚЎӮ©Ӯз120”NӢЯӮӯ‘OҒA1894”NӮЙҺnӮЬӮБӮҪҗн‘ҲӮЕӮ·ҒB‘ҠҺиҚ‘ӮМҗҙӮНҒAҚ]ҢЛҺһ‘гӮМҒuҠCҠOҢр—¬ӮМҺА‘ФҒvӮрҠwҸKӮөӮҪӮЖӮ«ӮЙҸoӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһӮаҗҙүӨ’©ӮӘ’ҶҚ‘ӮрҺx”zӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮН–ҫҺЎӮЙӮИӮБӮДӮ©Ӯз“ъ–{ӮӘҸүӮЯӮДҢoҢұӮөӮҪ–{Ҡi“IӮИҠOҚ‘ӮЖӮМҗн‘ҲӮЕӮ·ҒB
Қ¶ӮМҺКҗ^ӮНҒA–јҢГү®ҺsҗзҺнӢжӮЙҺcӮйҗнҺҖҺТӮМҒuӢL”O”иҒvӮЕӮ·ҒBҚӮӮіӮН22ғҒҒ[ғgғӢӮЕҒAҚЕҸг•”ӮН‘е–CӮМ–C’eӮрӮ©ӮҪӮЗӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮұӮЙӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһӮЙҗнҺҖӮөӮҪ•әҺm726җlӮМ–ј‘OӮӘҚҸӮЬӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМүәӮЙӮНҒA“–ҺһӮМ•әҺmӮӘҗнҸкӮЕҗgӮЙӮВӮҜӮДӮўӮҪ“№ӢпӮМғҢғҠҒ[ғtӮӘ’ӨӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB”w”XӮЖӮўӮӨғҠғ…ғbғNӮМӮжӮӨӮИ•ЁӮЙҢCӮрӮВӮҜӮДӮўӮЬӮ·ҒBғsғXғgғӢӮаӮ ӮиӮЬӮ·ҒB–јҢГү®ӮМ•”‘аӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮЕӮҪӮӯӮіӮсӮМҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӢL”O”иӮНҒA1903”NҒAӮ»ӮМҢчҗСӮрҺ]ӮҰӮйӮҪӮЯӮЖӮөӮДҒA•җҠнӮИӮЗӮр’’’јӮөӮДҚмӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB ҺҹӮМҚ¶ӮМҺКҗ^ӮНҒA‘еҚгҺs“VүӨҺӣӢжӮЙӮ ӮйӢҢҗ^“cҺR—ӨҢR•ж’nӮЕӮ·ҒB–ҫҺЎҺһ‘гӮМҸүӮЯӮМҗј“мҗн‘ҲӮ©Ӯз‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲӮЬӮЕӮМҗнӮўӮЕҗнҺҖӮөӮҪ—ӨҢRӮМ•әҺmӮИӮЗӮМ•ж’nӮЕҒA5000ҠоҲИҸгӮМ•жҗОӮӘҺcӮБӮДӮўӮДҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҗнҺҖҺТӮМӮаӮМӮӘ‘ҪӮӯҺcӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB•жҗОӮМ‘Ө–КӮЙӮНҒA–SӮӯӮИӮБӮҪ“ъ•tӮвҸкҸҠӮӘӢLӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮМ•ж’nӮЙӮНҒAҢR•vӮМ•жӮаҺcӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBҢR•vӮЖӮНҒA•ә‘аӮЖӮЖӮаӮЙҗнҸкӮЦҚsӮБӮДүЧ•ЁӮМү^”АӮИӮЗӮрӮөӮҪҗlӮҪӮҝӮМӮұӮЖӮЕӮ·ҒB•жҗОӮрҢ©ӮйӮЖҗОҚHӮИӮЗӮМҗEҗlӮв•aҗlӮМҠЕҢмӮрӮ·ӮйҗlӮИӮЗҒAҢRҗlҲИҠOӮМҗlҒXӮаҗнҸкӮЕ–SӮӯӮИӮБӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB (1)“ъҗҙҗн‘ҲӮМҢҙҲц “ъҗҙҗн‘ҲӮНӮИӮәӢNӮұӮіӮкӮҪӮМӮ©ҒBӮЬӮҪҒAҗн‘ҲӮМ–Ъ“IӮЙӮВӮўӮДӮаҚlӮҰӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB (2)җн‘ҲӮМҢoүЯӮЖҢӢүК җн‘ҲӮМҢӢүКӮЖӮЖӮаӮЙҒA“–ҺһӮМҗlҒXӮӘҗн‘ҲӮрӮЗӮМӮжӮӨӮЙӮЖӮзӮҰӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒA“–ҺһӮМҗнҸкӮМҺКҗ^ӮвҠGӮИӮЗӮ©ӮзҒAҗн‘ҲӮМ—lҺqӮаҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB (3)җнҢгҢoүc җн‘ҲӮМҢӢүКӮЖӮөӮДҒAӮ»ӮМҢгӮМ“ъ–{ӮНӮЗӮМӮжӮӨӮИҗiҳHӮрӮЖӮБӮҪӮМӮ©Ӯр’ЗӮўӮЬӮ·ҒB ҒЎҠJҗнӮМҢoҲЬ 1860”N‘г”јӮОҲИҚ~ҒAғtғүғ“ғXӮвғAғҒғҠғJӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮрҺx”zӮөӮДӮўӮҪ’©‘NүӨ’©ӮЙҠJҚ‘Ӯр”—ӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ӮаҒA’©‘NӮЙ‘ОӮөӮДҸр–с’чҢӢӮЖҠJҚ‘Ӯр”—ӮиҒA1876”NӮЙ“ъ’©ҸCҚDҸрӢKӮрҢӢӮсӮЕ’©‘NӮрҠJҚ‘ӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМҲк•ыӮЕҒAҗҙҚ‘Ӯа’©‘NӮЦӮМүо“ьӮрӢӯӮЯӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ’©‘NҚ‘“аӮЕӮНҗҙҚ‘ӮрҺxҺқӮ·ӮйҗЁ—НӮЖ“ъ–{ӮрҺxҺқӮ·ӮйҗЁ—НӮӘ‘О—§ӮөӮЬӮөӮҪҒB 1884”NҒA“ъ–{ӮМӢҰ—НӮр“ҫӮДҚ‘“аӮрүьҠvӮөӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӢаӢКӢП(ғLғҖҒEғIғbғLғ…ғ“)ӮзӮМғOғӢҒ[ғvӮӘғNҒ[ғfғ^Ғ[ӮрӢNӮұӮөӮЬӮ·ҒBҒuҚbҗ\Һ–•ПҒvӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөҗҙҚ‘ӮН’©‘NӮЙҢR‘аӮр‘—ӮиҒA’БҲіӮөӮЬӮөӮҪҒB —Ӯ1885”NҒA“ъ–{ӮНҗҙӮЖӮМҠЦҢWӮрҸC•ңӮ·ӮйӮҪӮЯҲЙ“Ў”Һ•¶ӮрҗҙӮЙ‘—ӮиҒu“V’ГҸр–сҒvӮрҢӢӮСӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҸр–сӮЕҒAҚЎҢгҒA’©‘NӮЙҸd‘еӮИҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮДҸo•әӮ·ӮйҸкҚҮӮЙӮНҢЭӮўӮЙҳA—ҚӮөӮ ӮӨӮұӮЖӮрҢҲӮЯӮЬӮөӮҪҒB 1894”NҸtҒA’©‘N“м•”ӮЕ‘еӢK–НӮИ”_–ҜӮМ”Ҫ—җӮӘӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒBҒuҚbҢЯ”_–Ҝҗн‘ҲҒvӮЕӮ·ҒB–рҗlӮЙӮжӮй•s“–ӮИүЫҗЕӮИӮЗӮЙ‘ОӮөӮД–ҜҸOӮӘ“{ӮиҒAӮ»ӮМӮұӮл’©‘NӮЕҚLӮЬӮБӮДӮўӮҪҗVӢ»Ҹ@ӢіҒu“ҢҠwҒvӮМҺw“ұҺТӮр’ҶҗSӮЙ•җ—Н–IӢNӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ’©‘Nҗӯ•{ӮНӮұӮМ’БҲіӮМӮҪӮЯҒAҗҙҚ‘ӮЙҸo•әӮр—vҗҝҒBҗҙҚ‘Ӯ©ӮзӮН2000җl—]ӮиӮМҢR‘аӮӘ”h•әӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮД“ъ–{ӮНҒA’©‘NӮЙӮўӮй“ъ–{җlӮр•ЫҢмӮ·ӮйӮҪӮЯӮЖӮөӮДҒA’©‘NӮЦӮМҸo•әӮрҢҲ’иҒAӮЁӮжӮ»4000җlӮр‘—ӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘҒA“ъҗҙ—јҚ‘ҢRӮМүо“ьӮЙҠлӢ@ҠҙӮрӮаӮБӮҪ’©‘Nҗӯ•{ӮЖ”_–ҜҢRӮНҳa–сӮрҢӢӮСҒA”Ҫ—җӮНӮўӮБӮҪӮсҺыӮЬӮиӮЬӮ·ҒBӮ»ӮұӮЕҒA“ъ–{җӯ•{ӮНҗҙҚ‘ӮЙӢӨ“ҜӮЕ’©‘NӮМ“аҗӯүьҠvӮрҚsӮИӮӨӮұӮЖӮр’сҲДӮөӮЬӮөӮҪӮӘҒAҗҙҚ‘ӮНӮұӮкӮрӢ‘”ЫӮөӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{җӯ•{ӮН“Ж—НӮЕ’©‘NӮМ“аҗӯүьҠvӮЙӮ ӮҪӮйӮЖӮөӮДҒAӮ»ӮМӮЬӮЬ•әӮр’uӮӯӮұӮЖӮрҢҲӮЯӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA’©‘NүӨӢ{Ӯрҗи—МҒBҗҙҚ‘ҠсӮиӮМҗӯҢ Ӯр“|ӮөҒAҚ‘үӨӮМ•ғӮЕ“ъ–{ӮрҺxҺқӮөӮДӮўӮҪ‘еү@ҢN(ғeғEғHғ“ғOғ“)ӮрҗӯҢ ӮМҚАӮЙӮВӮҜӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮДҒAҗҙҚ‘ҢRӮр’З•ъӮрӮөӮДӮЩӮөӮўӮЖҒA’©‘NүӨ’©Ӯ©Ӯз“ъ–{ӮЙҲЛ—ҠӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ2“ъҢгӮМ1894”N7ҢҺ25“ъҒAғvғ“ғh(–L“Ү)ү«ӮЕҗӢӮЙ“ъҗҙ—јҢRӮМҠН‘аӮӘҗнӮўӮЙ“Л“ьҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ19җўӢI––ӮМ“ҢғAғWғAҸоҗЁӮЖҗн‘ҲӮМҢҙҲцҒE–Ъ“I ӮИӮә“ъ–{ӮНҗҙӮЖ‘О—§ӮөӮДӮЬӮЕ’©‘N”ј“ҮӮЙӮұӮҫӮнӮБӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒBӮ»ӮкӮрҚlӮҰӮйӮҪӮЯӮЙӮұӮМӮұӮлӮМ“ҢғAғWғAӮМҸуӢөӮрҗ®—қӮөӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ’ҶҚ‘ӮНҗҙүӨ’©ӮӘҺx”zӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB 19җўӢI––ҒAҗўҠEӮМӢӯҚ‘ӮЖӮөӮДғCғMғҠғXӮЖ‘О—§Ӯ·ӮйғҚғVғAӮӘ“ҢғAғWғAӮЙӮаҗЁ—НӮрҗLӮОӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮҪ‘О—§ӮЙ”ҸҺФӮрӮ©ӮҜӮҪӮМӮӘҒA1891”NӮЙҺnӮЬӮБӮҪҒAғҚғVғAӮЙӮжӮйғVғxғҠғA“S“№ҢҡҗЭӮЕӮ·ҒBӮұӮМ“S“№ӮМҸI“_ӮНғEғүғWғIғXғgғNӮЕӮ·ҒB “–Һһ“ъ–{җӯ•{ӮМ—vҗEӮЙӮўӮҪҺRҢ§—L•ьӮНҒAғVғxғҠғA“S“№ӮӘҠ®җ¬Ӯ·ӮкӮОҒAғҚғVғAӮМ’©‘NҗiҸoӮӘ—eҲХӮЙӮИӮйӮЖҠлӢ@ҠҙӮр•еӮзӮ№ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA“ъ–{ӮМҲА‘SӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЙӮНҚ‘Ӣ«ӮрҺзӮйӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAӮ»ӮМҠO‘Ө(ҺьҲН)ҒAӮВӮЬӮи’©‘NӮМҲА‘SӮрҠm•ЫӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒB Ҳк•ыҒAҚbҗ\Һ–•ПҢгҒA’©‘NӮЦӮМүeӢҝ—НӮрӢӯӮЯӮйӮЙӮНҗҙҚ‘Ӯр“ўӮҪӮИӮҜӮкӮОӮЖӮўӮӨҺе’ЈӮағҒғfғBғAӮЙҸoӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮўӮӨҸуӢөӮЕ1894”NӮЙӢNӮ«ӮҪҒuҚbҢЯ”_–Ҝҗн‘ҲҒvӮӘҲшӮ«ӢаӮЖӮИӮБӮД“ъҗҙҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮӘҗн‘ҲӮЙҗiӮсӮҫ”wҢiӮН2ӮВӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ҲкӮВӮНҒAҚ‘“аӮМҺ–ҸоӮЕӮ·ҒBҠJҗн‘OӮМ1894”NӮЙӮНҗӯ•{ӮНҸOӢcү@ӮМҗӯ“}җЁ—НӮЖ‘О—§ӮөӮД’ЗӮўӢlӮЯӮзӮкҒAҸOӢcү@Ӯр2үсӮаүрҺUӮ·ӮйӮЩӮЗӮЕӮөӮҪҒBҚ‘“а“IӮЙӮНҒAӮаӮӨҲкӮВҒAҗҙҚ‘ӮЖҗнӮҰӮйҢRҺ–—НӮӘӮұӮМҺһҠъӮЙӮИӮБӮДҗ®”хӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ӮЬӮҪ‘ОҠO“IӮЙӮНҒAғCғMғҠғXӮЖӮМҠЦҢWӮЕӮ·ҒB1894”N7ҢҺ16“ъҒAҠJҗнӮМ’ј‘OӮЙҒAғCғMғҠғXӮЖ“ъүp’КҸӨҚqҠCҸр–сӮӘҢӢӮОӮкӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҒAҗҙӮЖҗн‘ҲӮЙӮИӮБӮДӮаҚЕӢӯӮМҚ‘ғCғMғҠғXӮӘҗн‘ҲӮЙүо“ьӮ·ӮйӮЁӮ»ӮкӮӘӮИӮӯӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB 8ҢҺ1“ъӮЙҸoӮіӮкӮҪҒAҒuҗйҗнӮМ’ә—@ҒvӮЙӮұӮМҗн‘ҲӮМ–Ъ“IӮӘҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB Ғu’©‘Nғn’йҚ‘ғJ‘ҙғmҺnғjҢ[—UғVғe—сҚ‘ғmҢЮ”әғjҸAғJғVғҒғ^ғӢ“Ж—§ғmҲкҚ‘ғ^ғҠҒBҒ`үAғj—zғj‘ҙғm“аҗӯӮЙҠұҸВғVҒEҒEҒEҒv Ғu“ъ–{ӮӘ’©‘NӮрҚ‘ҚЫҺРүпӮЙҲшӮ«“ьӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөҗҙӮӘ“Ж—§Қ‘ӮЕӮ ӮйӮНӮёӮМ’©‘NӮЙҠұҸВӮөӮДӮўӮйӮМӮЕӮ»ӮкӮр”rӮ·ӮйҒvҒ|ӮұӮкӮӘҚЕҸI“IӮИҗн‘ҲӮМ–ј–ЪӮЕӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҒAҒu’©‘NӮМ“Ж—§ҒvӮМӮҪӮЯӮЙҒAҗҙҚ‘ӮМҗЁ—НӮр’©‘NӮ©Ӯз’ЗӮўҸoӮөӮҪӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮұӮЕ“ъ–{ӮНҒu’©‘NӮМ“Ж—§ҒvӮЖҢҫӮБӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮұӮЕӮМҒu“Ж—§ҒvӮЖӮНӮ ӮӯӮЬӮЕҗҙ’©ӮЦӮМҸ]‘®ҠЦҢWӮр’fӮҝҗШӮйӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮЕӮ·ҒB ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲӮМҢoүЯ 1894”N9ҢҺҒA“ъ–{ӮМ—ӨҢRӮН’©‘N–k•”ӮМ“sҺsҒAғsғҮғ“ғ„ғ“Ӯрҗи—МҒBҠCҢRӮНү©ҠCҠCҗнӮЙҸҹ—ҳҒA11ҢҺӮЙӮН—ӨҢRӮӘҒAҗҙҚ‘ӮМҸd—vӮИҢRҺ–Ӣ’“_ҒE—·ҸҮӮрҗи—МҒB—Й“Ң”ј“ҮӮрҗ§ҲіӮөӮЬӮөӮҪҒB —Ӯ95”NӮЙӮН’ҶҚ‘ҒEҺR“Ң”ј“ҮӮМҲРҠCүqӮрҚUҢӮӮөҒAҗҙӮМ–k—mҠН‘аӮрҚ~•ҡӮіӮ№ӮЬӮ·ҒB “ъ–{ӮӘ—DҗЁӮИ’ҶӮЕҒAҗҙӮНҚuҳaӮр‘ЕҗfӮөӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒB 1895”N3ҢҺҒA‘ҚҗЁ100җlӮр’ҙӮҰӮйҗҙҚ‘ӮМҺgҗЯӮӘҚuҳaүпӢcӮМӮҪӮЯҺRҢыҢ§ӮМүәҠЦӮЙӮвӮБӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮұӮұӮЙӮНҚuҳaүпӢcӮМ—lҺqӮр“`ӮҰӮйӢL”OҠЩӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮМӢL”OҠЩӮЙӮНҒAҚuҳaүпӢcӮЙҠЦӮ·ӮйҺ‘—ҝӮӘ“WҺҰӮіӮкӮДӮўӮй‘јҒAүпӢcӮӘҚsӮИӮнӮкӮҪ•”ү®ӮӘ“–ҺһӮМ’І“x•iӮ»ӮМӮЬӮЬӮЙҚДҢ»ӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB җҙҚ‘‘ӨӮМ‘SҢ ӮН—ӣҚғҸНҒB“ъ–{‘ӨӮМ‘SҢ ӮНҲЙ“Ў”Һ•¶Һс‘ҠӮЖ—ӨүңҸ@ҢхҠO‘ҠӮЕӮ·ҒB ҢрҸВӮЕ“ъ–{ӮНҒA ҒE“ъ–{ӮМҚ‘үЖ—\ҺZӮМ4”{ҲИҸгӮЙӮ ӮҪӮйҒu3үӯ—јӮМ”…ҸһӢаҒvҒB ҒEҒu—Й“Ң”ј“ҮҒE‘дҳpҒEаOҢОҸ”“ҮӮр“ъ–{ӮЙҸчӮйӮұӮЖҒvҒB ҒEүБӮҰӮДҒuҗҙӮМҸd—vӮИҚ`ӮрҠJҚ`Ӯ·ӮйҒvӮұӮЖӮр—vӢҒӮөӮЬӮөӮҪҒB 4ҢҺҒA”…ҸһӢаҲИҠOӮНӮЩӮЪ“ъ–{ӮМ—vӢҒ’КӮиӮЕҚҮҲУӮЙ’BӮөҒA“ъҗҙҚuҳaҸр–сҒAӮўӮнӮдӮйүәҠЦҸр–сӮӘҢӢӮОӮкӮЬӮөӮҪҒB ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲӮМ“сӮВӮМӮЖӮзӮҰ•ы ӮұӮұӮЕҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЖӮНӮЗӮсӮИҗн‘ҲӮҫӮБӮҪӮМӮ©ӮаӮӨҲк“xҚlӮҰӮДӮЭӮжӮӨӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB2ӮВӮМҚlӮҰ•ыӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ҲкӮВӮНҒAҒuӢ·ӮўҲУ–ЎҒvӮМ“ъҗҙҗн‘ҲӮЕӮ·ҒBҗнӮўӮӘҺnӮЬӮБӮҪ1894”N7ҢҺӮ©ӮзҚuҳaҸр–сӮӘ’чҢӢӮіӮкӮҪ95”NӮМ4ҢҺӮЬӮЕҒB җнҸкӮЖӮИӮБӮҪӮМӮНҒA’©‘NӮ©ӮзҗҙҚ‘ӮМ“Ң–k•”ҒAҗн‘ҲӮМ––ҠъӮЙӮН“ъ–{ҢRӮН‘дҳpӢЯӮӯӮМаOҢО“ҮӮрҚUҢӮӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮнӮёӮ©10Ӯ©ҢҺ’ц“xӮМҗн‘ҲӮрҺwӮөӮЬӮ·ҒB ӮаӮӨҲкӮВӮНҒAҒuӮжӮиҚLӮўҲУ–ЎҒvӮЕӮЖӮзӮҰӮйҢ©•ыӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮНҒA’©‘NүӨӢ{ӮМҗи—МӮв“ҢҠw’БҲіҗн‘ҲӮЬӮЕҠЬӮЯӮйӮаӮМӮЕӮ·ҒB “ҢҠwӮНҒuҚbҢЯ”_–Ҝҗн‘ҲҒvӮрӢNӮөӮҪҸ@Ӣі’c‘МӮЕӮөӮҪҒB”_–ҜҢRӮНӮўӮБӮҪӮс“P‘ЮӮөӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“ъҗҙҗн‘Ҳ’ҶӮЙҚДӮС–IӢNӮөӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮН’©‘Nҗӯ•{ҢRӮЖӮЖӮаӮЙӮ»ӮМ’БҲіӮЙҢJӮиҸoӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮД‘дҳpҗӘ•һӮМҗн‘ҲӮЕӮ·ҒBүәҠЦҸр–сӮЕ“ъ–{ӮНҗҙӮ©Ӯз‘дҳpӮрҠl“ҫӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө‘дҳpӮЕӮНҒA“ъ–{ӮМ—М“yӮЙӮИӮйӮұӮЖӮЙ”Ҫ”ӯӮөӮД’пҚRү^“®ӮӘӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ӮНҢR‘аӮр”hҢӯӮөӮДӮұӮкӮр’БҲіӮөӮДҒA‘дҳpӮрҗӘ•һӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮұӮЬӮЕӮр“ъҗҙҗн‘ҲӮЖӮЖӮзӮҰӮйҚlӮҰ•ыӮаӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲӮЖ“ъ–{Қ‘–Ҝ “ъҗҙҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮйӮЖҒAҗV•·ҒAҺGҺҸҒAүүҢҖҒAӢСҠGҒA•әҺmӮҪӮҝӮМҺиҺҶӮИӮЗӮіӮЬӮҙӮЬӮИғҒғfғBғAӮӘҗн‘ҲӮр“`ӮҰӮЬӮөӮҪҒB —бӮҰӮОӮұӮкӮНҒu“ъҗҙҗ퓬үж•сҒvӮЖӮўӮБӮДҒAҗн‘ҲӮМҢoүЯӮрҠG“ьӮиӮЕ“`ӮҰӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAҲкӮВҲкӮВӮМҗ퓬ӮрҠGӮЕ•`Ӯ«ҒAҸЪӮөӮўүрҗаӮрӮВӮҜӮДӮўӮЬӮ·ҒB җV•·ҺРӮНӢЈӮБӮДҸ]ҢRӢLҺТӮвҸ]ҢRүжүЖӮр‘—ӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮіӮДҒAӮұӮМ“ъҗҙҗн‘ҲӮЙҗӯ•{ӮНӮЁӮжӮ»24–ңҗlӮМ•ә—НӮр“Ҡ“ьӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҝҒAҠCҠOӮМҗн’nӮЙҚsӮБӮҪӮМӮӘ17–ңҗl—]ӮиӮЕӮөӮҪҒBҗнҺҖҺТӮН‘дҳpҗӘ•һӮМҗн‘ҲӮЬӮЕҠЬӮЯӮйӮЖӮЁӮжӮ»1–ң3000җlӮЕҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ‘дҳpӮЕғRғҢғүӮвғ}ғүғҠғAӮИӮЗӮЙӮ©Ӯ©ӮБӮД•aҺҖӮөӮҪҗlӮӘ1–ңҗlӮаӮўӮЬӮөӮҪҒBҗн‘ҲӮНҺАӮН•aӢCӮЖӮМ“¬ӮўӮЖӮаҢҫӮҰӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮЕӮН“–ҺһӮМҺКҗ^ӮвҠGӮ©ӮзҒAҗнҸкӮМҺА‘ФӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ӮұӮкӮНҒAӢTҲддў–ҫ(ӮұӮкӮ Ӯ«)ӮЖӮўӮӨҸ]ҢRғJғҒғүғ}ғ“ӮӘ—·ҸҮҚxҠOӮЕӮЖӮзӮҰӮҪҒA–С•zӮрҺқӮБӮД”р“пӮ·ӮйҸ—җ«ӮЖҺqӢҹӮҪӮҝӮЕӮ·ҒBҗн‘Ҳ‘ҠҺиҚ‘ӮМҲк”КӮМ–ҜҠФҗlӮҪӮҝӮЙӮаӮҪӮзӮ·”ЯӮөӮЭӮрҺКӮөӮҪӢMҸdӮИҺКҗ^ӮЕӮ·ҒB ӮаӮӨҲкӮВҒAҗGӮкӮДӮЁӮ«ӮҪӮўӮұӮЖӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҺҹӮМҠGӮрҢ©ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB ӮұӮкӮНҒA•—ҺhүжӮЕ—L–јӮИғrғSҒ[ӮӘҗнҸкӮр•`ӮўӮҪҠGӮЕӮ·ҒB Ҡ}ӮрӮ©ӮФӮБӮҪӮи‘җ—ҡӮрӮНӮўӮҪҗlӮӘӮҜӮӘҗlӮрү^ӮсӮЕӮўӮйӮЖӮұӮлӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮМҗнҸкӮЙҺ—ӮВӮ©ӮнӮөӮӯӮИӮўҠiҚDӮМҗlӮҪӮҝӮӘҒAҢR•vӮЖӮўӮнӮкӮйҗlҒXӮЕӮ·ҒB ҢR•vӮН–ҜҠФӮМӢЖҺТӮӘҸWӮЯӮДҒAҸ\җ”–ңҗlӮӘҗнҸкӮЙҸoӮ©ӮҜӮҪӮЖӮўӮнӮкӮЬӮ·ӮӘҒA7000Ӯ©Ӯз8000җlӮӘҺҖ–SӮөӮЬӮөӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮНҒu•әҺmӮЖҢR•vӮМҗн‘ҲҒvӮЖҢҫӮнӮкӮйӮЩӮЗӮЕӮ·ҒB ҒЎҒu•¶–ҫӮМҗн‘ҲҒvӮЖӮўӮӨҢ©•ы ӮіӮДҒA•әҺmӮҪӮҝӮНӮЗӮсӮИҚlӮҰ•ыӮвҺvӮўӮЕҗн’nӮЙҚsӮБӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨӮ©ҒH Ӯ»ӮМҺһӮЙғLҒ[ғҸҒ[ғhӮЖӮИӮйӮМӮӘҒu•¶–ҫҒvӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ӮН•¶–ҫӮЖӮўӮӨ—§ҸкӮЙ—§ӮБӮДҗҙӮЖҗнӮӨӮМӮҫӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ—бӮЖӮөӮДҒA“–ҺһҒAғLғҠғXғgӢі“kӮЖӮөӮД—L–јӮҫӮБӮҪ“а‘әҠУҺOӮЖӮўӮӨҗlӮӘҒAӮұӮМӮжӮӨӮИҒAҗн‘ҲӮрҗі“–ү»Ӯ·Ӯйҳ_•¶ӮрҒwҚ‘–Ҝ”V—FҒxӮЖӮўӮӨҺGҺҸӮЙ”ӯ•\ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҗlӮНҢгӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮМҠJҗн‘OӮЙӮН”сҗнҳ_ҒAҗн‘Ҳ”Ҫ‘ОӮрҺе’ЈӮөӮҪҗlӮЕӮ·ҒB ҢіӮНҒuJustification of the Corean WarҒvӮЖӮўӮӨғ^ғCғgғӢӮМүp•¶ӮЕҸ‘Ӯ©ӮкӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB“–ҺһӮМҗнҸкӮӘҺеӮЙ’©‘N”ј“ҮӮҫӮБӮҪӮМӮЕҒAӮұӮӨӮўӮӨғ^ғCғgғӢӮӘӮВӮҜӮзӮкӮЬӮөӮҪҒBүp•¶ӮЕҸ‘ӮӯӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAүў•ДҗўҠEӮЙ“ъ–{ӮМҗн‘ҲӮМҗі“–җ«Ӯр‘iӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ’ҶӮЕҒu“ъ–{ӮН“Ң—mӮЙү—ӮҜӮйҗi•аҺеӢ`ӮМҗнҺmӮИӮиҒvӮЖӮөӮДҒAҗi•аӮМ“GӮЕӮ Ӯй’ҶҚ‘ҲИҠOӮМҗўҠE’ҶӮ·ӮЧӮДӮӘ“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮр–]ӮЮӮҫӮлӮӨӮЖҢҫӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB “ъ–{ӮНүў•Д—¬ӮМ•¶–ҫӮрҺжӮи“ьӮкҒAӢЯ‘гү»Ӯрҗ}ӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҺ©•үӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮіӮзӮЙҒu“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮН“Ң—mҳZүӯҗlӮМҺ©—RҗӯҺЎҒ@Һ©—RҸ@ӢіҒ@Һ©—RӢіҲзҒ@Һ©—RҸӨӢЖӮрҲУ–ЎҒvӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӢLҸqӮӘҢ©ӮзӮкӮЬӮ·ҒB ӮұӮМҳ_•¶Ӯ©ӮзӮНҒAҗiӮсӮҫ“ъ–{ӮӘғAғWғAӮМ–ҝҺеҒAӮ·ӮИӮнӮҝғAғWғA’nҲжӮМ’ҶҗSӮЖӮИӮйӮұӮЖӮрҚ\‘zӮөӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЙ“ЗӮЭҺжӮкӮЬӮ·ҒB ӮұӮМҗн‘ҲӮН“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҒu•¶–ҫӮЙҠоӮГӮӯҒA•¶–ҫӮМӮҪӮЯӮМҗн‘ҲҒvӮИӮМӮҫӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮНҒA“а‘әҠУҺOӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒA“–ҺһҒA•ҹ‘т—@ӢgӮӘҺеҚЙӮ·ӮйҗV•·ҒuҺһҺ–җV•сҒvӮИӮЗҒAӮіӮЬӮҙӮЬӮИғҒғfғBғAӮЕҗ·ӮсӮЙҺе’ЈӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮкӮӘҚ‘–ҜҒA•әҺmӮҪӮҝӮЙӮаҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкӮДӮўӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎҗнҢгҢoүc ӮұӮМҒuҗнҢгҢoүcҒvӮЖӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМҢR”хҠg’ЈӮр’ҶҗSӮЖӮөӮҪ“ъ–{ӮМҗӯҚфӮрҺwӮ·Ңҫ—tӮЕӮ·ҒB “ъҗҙҗн‘ҲҢгҒAүәҠЦҸр–сӮӘҢӢӮОӮкҒA“ъ–{ӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAӮЩӮЪ—vӢҒ’КӮиӮЙ2үӯ—јҒҒ3үӯү~ӮЖӮўӮӨ‘ҪҠzӮМ”…ҸһӢаӮЖҒA—Й“Ң”ј“ҮҒA‘дҳpҒAаOҢОҸ”“ҮӮИӮЗӮМ—М“yӮр“ҫӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҗҙӮНҒA’©‘NӮӘ“Ж—§Қ‘ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр”FӮЯӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAҗ”“ъҢгҒAғҚғVғAҒAғhғCғcҒAғtғүғ“ғXӮӘҒu—Й“Ң”ј“ҮӮӘ“ъ–{ӮМӮаӮМӮЙӮИӮйӮұӮЖӮНҒA’©‘NӮМ“Ж—§Ӯр—L–ј–іҺАҒAӮВӮЬӮи–ј‘OӮҫӮҜӮЕҺА‘ФӮМӮИӮўӮаӮМӮЙӮ·ӮйҒvӮЖӮөӮДҒA“ъ–{ӮЙ•ъҠьӮрӢҒӮЯӮЬӮөӮҪҒBӮўӮнӮдӮйҒuҺOҚ‘ҠұҸВҒvӮЕӮ·ҒB ҢӢӢЗҒA“ъ–{ӮНҺOҚ‘ӮЙ‘ОҚRӮ·Ӯй•җ—НӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAӮұӮкӮрҺуӮҜ“ьӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД—Й“Ң”ј“ҮӮрӮЁӮжӮ»4500–ңү~ӮЕҗҙҚ‘ӮЙ•ФҠТӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМҺOҚ‘ҠұҸВӮМҢгҒA“ъ–{ӮНҒuүзҗdҸҰ’_(ӮӘӮөӮсӮөӮеӮӨӮҪӮс)ҒvӮрғXғҚҒ[ғKғ“ӮЙҒAҢR”хӮМҠg’ЈӮрҗiӮЯӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒA“GӮЙ•ңҸQӮ·ӮйӮЬӮЕҒAҗdӮМҸгӮЙҗQӮДҗgӮрӢкӮөӮЯҒAӮЙӮӘӮўҠМӮрӮИӮЯӮД“G“ўӮҝӮМҺuӮр–YӮкӮИӮўӮжӮӨӮЙӮөӮҪҒAӮЖӮўӮӨ’ҶҚ‘ӮМҢМҺ–ӮЕӮ·ҒBӮұӮМғXғҚҒ[ғKғ“ӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМҒuҗнҢгҢoүcҒvӮЙ‘еӮ«ӮӯүeӢҝӮөӮЬӮ·ҒB Ӣп‘М“IӮЙӮНҒA•әҠнӮИӮЗӮрҚмӮйӮМӮЙҢҮӮ©Ӯ№ӮИӮў“SӮМҗ¶ҺYӮр‘қӮвӮ»ӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЙӮВӮўӮДҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҒЎҠҜүc”Ә”Ұҗ»“SҸҠ 20җўӢIҸүӮЯӮЙҺBүeӮіӮкӮҪҒA•ҹүӘҢ§ӮМ”Ә”Ұҗ»“SҸҠӮМүf‘ңӮЕӮ·ҒB “ъ–{ҚЕҸүӮМ–{Ҡi“IӮИҗ»“SҸҠӮЕӮ Ӯй”Ә”Ұҗ»“SҸҠӮМҢҡҗЭӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮӘҸIӮнӮБӮД3”NҢгӮМ1897”NӮМӮұӮЖӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЬӮЕ“ъ–{ӮНҒA“SӮМ‘е•”•ӘӮрғCғMғҠғXӮИӮЗӮ©ӮзӮМ—A“ьӮЙ—ҠӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB “ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМ“ъ–{ӮНҒAҢR”хҠg’ЈӮМӮҪӮЯӮМ•әҠнҚмӮиҒAҢRҠНӮМҢҡ‘ўҒA“S“№ӮМҢҡҗЭҒAӮ»ӮөӮДҚHӢЖӢ@ҠBӮМҗ»‘ўӮИӮЗӮМӮҪӮЯӮЙ‘ҪӮӯӮМ“SӮр•K—vӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕҗӯ•{ӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМ”…ҸһӢаӮр“ҠӮ¶ӮДҒA•ҹүӘҢ§”Ә”Ұ‘әҒAҢ»ҚЭӮМ–kӢгҸBҺsӮЙҠҜүcӮМҗ»“SҸҠӮрҢҡҗЭӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ғhғCғcӮМӢZҸpӮрҺжӮи“ьӮкӮҪҗ»“SҸҠӮН1901”NӮЙ‘ҖӢЖӮрҺnӮЯҒA15”NӮЩӮЗӮЕ“SӮМҚ‘“аҗ¶ҺYӮМ80Ғ“ӮрҗиӮЯӮйӮЬӮЕӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкҲИҚ~ҒA”Ә”Ұҗ»“SҸҠӮНҒA“ъ–{ӮМҸdҚHӢЖӮМ’ҶҗSӮЖӮИӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ҒЎӢа–{ҲКҗ§ӮМҚМ—p ҒuҗнҢгҢoүcҒvӮМ‘еӮ«ӮИғ|ғCғ“ғgӮЖӮөӮДҒA“ъ–{ӮН”…ҸһӢаӮрҢіӮЙӢа–{ҲКҗ§ӮрҚМ—pӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮНӢаӮрӮЁӢаӮМӮЁӮЁӮаӮЖӮЖҚlӮҰӮйҗ§“xӮЕӮ·ҒBҒuӢа–{ҲКҒvӮЖӮўӮБӮДӮаҒAӮаӮҝӮлӮс•Ғ’iӮНҺҶ•јӮвҚdүЭӮрӮЁӢаӮЖӮөӮДҺgӮӨӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮӘӮЁӢаӮЖӮөӮДҲАҗSӮөӮДҺgӮҰӮйӮМӮНҒAӮўӮВӮЕӮаӢаӮЖҢрҠ·ӮЕӮ«ӮйӮ©ӮзӮҫҒAӮЖҚlӮҰӮйӮМӮЕӮ·ҒB ҺКҗ^Қ¶ӮӘӢа–{ҲКҗ§ӮЕҺgӮнӮкӮҪҺҶ•јӮЕӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮЙӮНҒAҒuӮұӮМҺҶ•јӮЕӢаүЭҸEү~ӮЖҢрҠ·ӮЕӮ«ӮйҒvӮЖҸ‘ӮўӮДӮ ӮиӮЬӮ·ҒB 19җўӢIӮЙғCғMғҠғXӮӘӮұӮМҗ§“xӮр’иӮЯҒAӮ»ӮМҢгғҲҒ[ғҚғbғpӮМ‘јӮМҚ‘ҒXӮаӢа–{ҲКҗ§ӮрҚМӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮЬӮЕӮМ“ъ–{ӮНҲбӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲӮЕ“ъ–{ӮНҗҙӮ©ӮзҒA“–ҺһӮМҚ‘үЖ—\ҺZӮМӮЁӮжӮ»3”N•ӘӮЙӮаӮ ӮҪӮй”…ҸһӢаӮрғCғMғҠғXӮМӮЁӢаҒEғ|ғ“ғhӮЕӮаӮзӮўӮЬӮөӮҪҒBғ|ғ“ғhӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒA“–ҺһӮНӢаӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮЖ“ҜӮ¶ӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕ“ъ–{ӮНӮ»ӮМ”…ҸһӢаӮрҺgӮБӮДғҲҒ[ғҚғbғpӮМҚ‘ҒXӮЖ“Ҝ—lӮЙҒuӢа–{ҲКҗ§ҒvӮрҚМӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮӨӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒA“ъ–{ӮМү~ӮӘҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮМҚ‘ҒXӮЕҗM—pӮМӮ ӮйӮЁӢаӮЖҢ©ӮИӮіӮкӮЬӮ·ҒB ӮЬӮҪӢа–{ҲКҗ§ӮЖӮўӮӨ“ҜӮ¶җ§“xӮрҚМӮБӮДӮўӮйӮМӮЕҒA–fҲХӮИӮЗӮЕӮМҺжҲшӮағXғҖҒ[ғYӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB“ъ–{ӮӘӢа–{ҲКҗ§ӮрҚМ—pӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНҒAүў•ДӮЖҢoҚП“IӮЙ‘О“ҷӮЙӮИӮйҲк•аӮҫӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮМ—lҺqӮрҺҰӮөӮҪғrғSҒ[ӮМҠGӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB Ғu1897”NӮМ“ъ–{ҒvӮЖӮўӮӨҠGӮЕӮ·ҒBүў•Д—сӢӯӮМҚ‘ҒXӮӘҸWӮЬӮБӮДӮўӮй’ҶӮЙ“ъ–{ӮӘ“ьӮБӮДӮўӮӯ—lҺqӮЕӮ·ҒB—сӢӯӮМҚ‘ҒXӮНҒAӢБӮўӮҪӮиҒA—вӮвӮвӮ©ӮИ–ЪӮЕҢ©ӮДӮўӮйӮМӮӘ“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЙ‘ОӮ·ӮйҢ©•ыӮр•\ӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҚЎ“ъӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮӘӮЗӮМӮжӮӨӮИҗн‘ҲӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮрҠwҸKӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕӮНҒu•¶–ҫҒvӮЖӮўӮӨӮМӮӘҸd—vӮИғLҒ[ғҸҒ[ғhӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМ•¶–ҫӮЖӮўӮӨҚlӮҰ•ыӮӘӮўӮ©ӮЙӢЯ‘гӮМ“ъ–{ӮрӮЖӮзӮҰӮДӮўӮҪӮМӮ©ҒAӮ»ӮМӮұӮЖӮр’mӮйҸгӮЕҒA“–ҺһӮМҢҫҳ_ҠEӮрғҠҒ[ғhӮөӮҪ•ҹ‘т—@ӢgӮМҒw•¶–ҫҳ_”VҠT—ӘҒxӮр“ЗӮЮӮұӮЖӮрӮЁӮ·Ӯ·ӮЯӮөӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲҒ@ | |
|
“ъҳIҗн‘ҲӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮ©Ӯз10”NҢгҒA1904”NӮЙҺnӮЬӮБӮҪҗн‘ҲӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗн‘ҲӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮМүҪ”{ӮаӮМӢK–НӮЕҚsӮИӮнӮкҒAӮ»ӮМҢӢүК“ъ–{ӮНғAғWғA‘е—ӨӮМҲкҠpӮЙҗЁ—НҢ—ӮрҺқӮВҚ‘үЖӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгӮМ—рҺjӮЙӮа‘еӮ«ӮИүeӢҝӮрӢyӮЪӮөӮҪ“ъҳIҗн‘ҲӮрҒAҚЎ“ъӮНҠфӮВӮ©ӮМ–КӮ©ӮзҚlӮҰӮДӮўӮ«ӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
Ӯ»ӮкӮЕӮНҒAҚЎ“ъӮМғ|ғCғ“ғgӮЕӮ·ҒB (1)җн‘ҲӮМ”wҢi “ъҳIҗн‘ҲӮӘӮИӮәӢNӮұӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮ»ӮМ”wҢiӮрҚlӮҰӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB“БӮЙҒA“ъ–{ӮЖғCғMғҠғXӮЖӮМ“Ҝ–ҝҒҒ“ъүp“Ҝ–ҝӮӘ‘еӮ«ӮИҢгүҹӮөӮЙӮИӮБӮҪӮұӮЖӮрҢ©ӮДӮўӮ«ӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB (2)Қ‘–ҜӮЖҗн‘Ҳ “ъҳIҗн‘ҲӮН•әҺmӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҚ‘–Ҝ‘S‘МӮЙ‘еӮ«ӮИӢ]җөӮрӢӯӮўӮйҗн‘ҲӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕҒAҗн‘ҲӮЙ”Ҫ‘ОӮ·ӮйҺе’ЈӮӘӮіӮЬӮҙӮЬӮИ—§ҸкӮ©ӮзӮИӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҝғLғҠғXғgӢіӮМҗMҺТӮМ“а‘әҠУҺOӮрҺжӮиҸгӮ°ӮДӮЭӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒAҗн‘ҲӮЙҸ—җ«ӮҪӮҝӮНӮЗӮӨҠЦӮнӮБӮҪӮМӮ©ӮаҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB (3)җн‘ҲӮМҢӢүК җн‘ҲӮМҢӢүКҒA“ъ–{ӮНҠШҚ‘Ӯр•ЫҢмҚ‘ӮЖӮөҒAӮвӮӘӮДҗA–Ҝ’nӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪ“ъ–{ӮМҗЁ—НҢ—ӮЖӮИӮБӮҪ–һҸBӮрӮЯӮ®ӮБӮДғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJӮЖӮМ‘О—§Ӯаҗ¶Ӯ¶ӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮ ӮҪӮиӮрҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB ҒЎҗн‘ҲӮМ”wҢi җҙҚ‘ӮН“ъҗҙҗн‘ҲҢгҒAғhғCғcӮвғҚғVғAҒAғCғMғҠғXҒAғtғүғ“ғXӮИӮЗӮМ—сӢӯӮМҚ‘ҒXӮӘӮ»ӮкӮјӮкӮЙҗЁ—НҢ—ӮрҗЭӮҜҒA”јӮОҗA–Ҝ’nӮМӮжӮӨӮИҸу‘ФӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҗҙҚ‘“аӮЕӮНҒA–ҜҸOҸ@ӢіӢ`ҳa’cӮр’ҶҗSӮЙҒu•}җҙ–Е—mҒҒҗҙ’©ӮрҸ•ӮҜҒAҗј—mӮр–ЕӮЪӮ№ҒvӮрҢfӮ°ӮҪҠOҚ‘җlҸPҢӮү^“®ӮӘӢNӮұӮиӮЬӮ·ҒBҗҙ’©җӯ•{ӮаӮұӮкӮрҺxҺқӮөҒA1900”NҒA—сӢӯӮЙҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҒAғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJҒA“ъ–{ӮИӮЗ8Ӯ©Қ‘ӮӘҸo•әӮөҒA—җӮр’БҲіӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҺ–ҢҸӮНӢ`ҳa’cҺ–ҢҸӮЖҢДӮОӮкӮЬӮ·ҒB ӮЖӮұӮлӮӘҸo•әӮөӮҪҚ‘ӮМҲкӮВғҚғVғAӮН–һҸBҒҒ’ҶҚ‘“Ң–k•”ӮрҺ–ҺАҸгҗи—МӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB Ӯ»ӮМ–ј–ЪӮНҒAғҚғVғAӮӘ–һҸB’nҲжӮЕ’ҶҚ‘Ӯ©Ӯз‘dҺШӮөӮДӮўӮҪ“S“№ӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮөӮҪҒB –һҸBӮЙ’“•әӮр‘ұӮҜӮйғҚғVғAӮНҒA“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДӮа‘еӮ«ӮИӢәҲРӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA’ҶҚ‘ӮЙ‘еӮ«ӮИ—ҳҢ ӮрҺқӮБӮДӮўӮҪғCғMғҠғXӮаҒAҺ©Қ‘ӮМҢ үvӮЖҸХ“ЛӮ·ӮйӮЖҚlӮҰӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮҪ’ҶҒA1902”NҒA“ъ–{ӮЖғCғMғҠғXӮН“ъүp“Ҝ–ҝӢҰ–сӮрҢӢӮСӮЬӮ·ҒB Ҹр–сӮЙӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮЖ’ҶҚ‘‘е—ӨӮЕҢЭӮўӮМ—ҳҢ Ӯр”FӮЯҚҮӮӨ“а—eӮӘҗ·ӮиҚһӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ“Ҝ–ҝӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮЕӮНҒAғҚғVғAӮЖҗнӮЁӮӨӮЖӮўӮӨҗўҳ_ӮӘҚӮӮЬӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB 1903”NҒAғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮрүс”рӮөӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҢіҺс‘ҠӮМҲЙ“Ў”Һ•¶ӮӘғҚғVғAӮЙ•ӢӮ«ҒAҚc’йғjғRғүғC2җўӮЖүпҢ©ӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҢрҸВӮНҺё”sӮЙҸIӮнӮиӮЬӮ·ҒB “ъ–{ӮМҲА‘SӮМӮҪӮЯӮЙӮНҒA’©‘N”ј“ҮӮ©ӮзғҚғVғAӮрӢм’ҖӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮйӮЖӮөӮДҒAҸ¬‘әҺх‘ҫҳYҠO‘ҠӮНҒA1904”N2ҢҺ6“ъҒAғҚғVғAӮЙҚ‘Ңр’fҗвӮрҢҫӮў“nӮөӮЬӮөӮҪҒB 2ҢҺ8“ъҒA“ъ–{ҢRӮНҒAҠШҚ‘ӮЖ’ҶҚ‘ӮМ—·ҸҮӮЕҢRҺ–Қs“®ӮрҠJҺnҒB2ҢҺ10“ъҒA‘o•ыӮӘҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮДҒA“ъҳIҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ’©‘N”ј“ҮӮрӮЯӮ®Ӯй“®Ӯ« ҠJҗнӮЙӮўӮҪӮйҢoүЯӮр”N•\ӮЕ’ЗӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮеӮӨҒB ӮЬӮёҒA’©‘NӮрҸ„Ӯй“®Ӯ«ӮЕӮ·ҒB 1895”N4ҢҺҒA“ъҗҙҗн‘ҲҢгӮМүәҠЦҸр–сӮЕҗҙҚ‘ӮН’©‘NӮМҒu“Ж—§Һ©ҺеҒvӮр”FӮЯӮЬӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҒA“ъ–{ӮЖӮөӮДӮНҒAҗҙҚ‘ӮМҗЁ—НӮр’©‘NӮ©Ӯз’ЗӮўҸoӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМ–Ъ“IӮрҲкүһ’Bҗ¬ӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ӮЖӮұӮлӮӘӮ»ӮМ’јҢгӮЙҺOҚ‘ҠұҸВӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ӮМ—НӮӘҢг‘ЮӮөӮҪӢ@үпӮЙ’©‘NӮЕӮНҒAҗe“ъ”hҗӯҢ ӮӘ“|ӮіӮкҒAғҚғVғAҠсӮиӮМҗӯҢ ӮӘ’aҗ¶ӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{ӮН1895”N10ҢҺҒA’©‘NӮМүӨӢ{ӮрҸPӮБӮДҒA’©‘NӮМ’ҶӮЕғҚғVғAҠсӮиӮМҗЁ—НӮМ’ҶҗSӮҫӮБӮҪи{”Ь(ғ~ғ“ғr)ӮрҺEҠQӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮМҢӢүК”Ҫ“ъ“¬‘ҲӮӘҚӮӮЬӮиҒAӮЬӮ·ӮЬӮ·“ъ–{ӮМ—§ҸкӮНҲ«ӮӯӮИӮиҒAғҚғVғAӮМүeӢҝ—НӮӘӢӯӮЬӮиӮЬӮөӮҪҒB Ҳк•ыӮЕ1897”N10ҢҺҒA’©‘NӮНҚ‘ҚҶӮр‘еҠШ’йҚ‘ӮЙүьӮЯӮЬӮ·ҒBҗҙӮв“ъ–{ӮЖ“ҜӮ¶Ғu’йҚ‘ҒvӮЖӮўӮӨҚ‘ҚҶӮЕҒAҺ©Һеҗ«ӮрҺҰӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮ©ӮзӮнӮёӮ©җ””NӮЕҒAҗн‘ҲӮМҗ¬үКӮрҸБ–ЕӮіӮ№ӮДӮөӮЬӮӨҢ`ӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮаӢ`ҳa’cҺ–ҢҸӮМҢгӮағҚғVғAӮӘ–һҸBӮ©Ӯз“P•әӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮНҒA“ъ–{ӮМҠШҚ‘ӮЕӮМ—НҠЦҢWӮрӮіӮзӮЙҺгӮЯӮй–в‘иӮЖӮөӮД–іҺӢӮЕӮ«ӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҒAғҚғVғAӮМҗЁ—НӮрҠШҚ‘Ӯ©Ӯз”rҸңӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҚЕҸd—vүЫ‘иӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ҳк•ығCғMғҠғXӮН“–ҺһғҚғVғAӮЖ‘О—§ӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒA“мғAғtғҠғJӮЕғ{Ғ[ғAҗн‘ҲӮЖӮўӮӨҗн‘ҲӮрӮөӮДҒAӮ»ӮкӮӘ‘еӮ«ӮИ•ү’SӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒAӢЙ“ҢӮЕғҚғVғAӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҒA“ъ–{ӮМ—НӮр—ҳ—pӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ҒB “ъүp“Ҝ–ҝӮМ“а—eӮНҒAҒuғCғMғҠғXӮМҗҙӮЙӮЁӮҜӮй—ҳүvҒA“ъ–{ӮМҗҙӮЙӮЁӮҜӮй—ҳүvӮЖҠШҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮйҗӯҺЎҸгҸӨӢЖҸгҚHӢЖҸгӮМ—ҳүvӮр‘жҺOҚ‘ӮМҒuҗN—Ә“IҚs“®ҒvӮ©ӮзҺзӮйӮҪӮЯ•K—vӮИ‘[’uӮрӮЖӮйҒBҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ·ҒBӮұӮМ‘жҺOҚ‘ӮЖӮНғҚғVғAӮМӮұӮЖӮИӮМӮЕӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМҢгҒA“ъ–{ӮН–һҸB–в‘иӮвҠШҚ‘–в‘иӮЙӮВӮўӮДғҚғVғA‘ӨӮЖҢрҸВӮрҸdӮЛӮЬӮөӮҪӮӘӮЬӮЖӮЬӮзӮёҒAҗӢӮЙ1904”N2ҢҺӮЙҠJҗнӮЙ“ҘӮЭҗШӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮМ–Ъ“IӮНҒA (1)ҠШҚ‘ӮЙ‘ОӮ·Ӯй“ъ–{ӮМҺx”zҢ ӮрғҚғVғAӮЙ”FӮЯӮіӮ№Ӯй (2)–һҸBӮ©ӮзғҚғVғAҢRӮр“P‘ЮӮіӮ№Ӯй ӮұӮЖӮЕӮөӮҪҒB ӮЬӮҪғCғMғҠғXӮвғAғҒғҠғJӮЙ“ъ–{ӮМ—§ҸкӮр—қүрӮөӮДӮаӮзӮЁӮӨӮЖҒA“БҺgӮр”hҢӯӮөӮЬӮөӮҪҒBғAғҒғҠғJӮЙ”hҢӯӮіӮкӮҪӮМӮӘӢаҺqҢҳ‘ҫҳYӮЕӮ·ҒB”ЮӮН–ҫҺЎӮМҸүӮЯӮЙғAғҒғҠғJӮМғnҒ[ғ”ғ@Ғ[ғh‘еҠwӮЙ—ҜҠwӮөҒA‘е“қ—МӮМғZғIғhғAҒEғҚҒ[ғYғ”ғFғӢғgӮЖӮа–КҺҜӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB 1904”N4ҢҺҒAӢаҺqӮНҒAғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғNӮЕҗӯҚаҠEӮМ’ҳ–јҗlӮЙ‘ОӮөӮДҚsӮИӮБӮҪғXғsҒ[ғ`ӮЕҺҹӮМӮжӮӨӮЙҸqӮЧӮЬӮөӮҪҒB ҒuғyғҠҒ[’с“ВӮНҒAҺ„ӮҪӮҝӮЙ–еҢЛҠJ•ъӮрҺцӮҜӮДӮӯӮкӮЬӮөӮҪҒBҚЎҒAүдӮӘҚ‘ӮНҒAӮ»ӮМ–еҢЛҠJ•ъӮМӮҪӮЯӮЙҗнӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ҒBҒv ’ҶҚ‘‘е—ӨӮЕӮМ–еҢЛҠJ•ъҒAӮВӮЬӮиӮЗӮМҚ‘Ӯа’ҶҚ‘ӮЕҢoҚП“IӮИ—ҳүvӮр’ЗӢҒӮЕӮ«ӮйҒAӮЖӮўӮӨӮМӮӘҒAғAғҒғҠғJӮМ’ҶҚ‘җӯҚфӮМҠо–{•ыҗjӮЕӮөӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘғҚғVғAӮӘ–һҸBӮрҗи—МӮөҒA–еҢЛҠJ•ъӮр–WӮ°ӮДӮўӮйӮМӮЕҒA“ъ–{ӮНӮ»ӮкӮрүьӮЯӮйӮҪӮЯӮЙҗнӮӨӮМӮҫӮЖҢҫӮБӮДӮўӮйӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ”сҗнҳ_ җн‘ҲӮӘҺnӮЬӮй’ј‘OҒA“ъ–{Қ‘“аӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮМғҒғfғBғAӮНҒAҒuғҚғVғAӮрҢӮӮВӮЧӮ«ӮҫҒvӮЖҺе’ЈӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮрҒuҺеҗнҳ_ҒvӮЖҢҫӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮөҒAҲк•”ӮЕӮ·ӮӘҒAҠJҗнӮ·ӮйӮЧӮ«ӮЕӮИӮўӮЖӮўӮӨ”сҗнҳ_ӮвҒA–ҫҠmӮИ”Ҫҗнҳ_ӮаҺе’ЈӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМ”сҗнҳ_ҒA”Ҫҗнҳ_ӮЙӮНӮіӮЬӮҙӮЬӮИ—§ҸкӮМӮаӮМӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮұӮЕӮНғLғҠғXғgҺТӮМ“а‘әҠУҺOӮрҺжӮиҸгӮ°ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB “а‘әҠУҺOӮЖӮўӮҰӮОҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҺһӮЙӮНҗіӢ`ӮМҗн‘ҲӮҫҒAӮЖҺе’ЈӮөӮҪҗl•ЁӮЕӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲӮМҢӢүКӮрҢ©ӮДҒA“а‘әӮН‘еӮ«Ӯӯ”ҪҸИӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ”ЮӮӘҸ‘ӮўӮҪҒuҗн‘Ҳ”pҺ~ҳ_ҒvӮр“ЗӮсӮЕӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҒuӮ»ӮМ(ҒҒ“ъҗҙҗн‘ҲӮЕӮМ“ъ–{ӮМ)–Ъ“IӮҪӮиӮө’©‘NӮМ“Ж—§ӮНӢpӮДҺгӮЯӮзӮкҒAҺx“Я•ӘҠ„ӮМ’[ҸҸӮНҠJӮ©ӮкҒA“ъ–{Қ‘–ҜӮМ•Ә’SӮН”сҸнӮЙ‘қүБӮіӮк“Ң—m‘S‘МӮрҠл–wӮМ’nҲКӮЙӮЬӮЕҺқӮҝ—ҲӮВӮҪӮЕӮНӮИӮўҢБҒvҒ@(Ғw–ң’©•сҒx1903.6.30) ӮВӮЬӮи“ъҗҙҗн‘ҲӮМҢӢүКҒA“Ң—m‘S‘МӮӘҠлӮӨӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ·ҒB ”ЮӮН•КӮМ•¶ҸНӮЕҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮНҢӢӢЗҒu—ҳ—~ӮМӮҪӮЯӮМҗн‘ҲҒvӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮҪ”ҪҸИӮ©ӮзҒAҗн‘ҲӮНҒuҗlӮрҺEӮ·ӮұӮЖҒvӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮНҒu‘еҚЯҲ«ҒvӮЕҒAҺ©•ӘӮНҒuҗн‘Ҳҗв‘О“I”pҺ~ҳ_ҺТҒvӮЙӮИӮБӮҪӮЖҢҫӮўҗШӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө“а‘әӮНҒAҺАҚЫӮЙҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮйӮЖҒA•Ҫҳaүс•ңӮрӢFӮйҚs“®ӮЙғVғtғgӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB”ҪҗнӮНҒAҚK“ҝҸHҗ…ӮзҺРүпҺеӢ`ҢnӮМҗlҒXӮЙӮжӮБӮДҺе’ЈӮіӮк‘ұӮҜӮЬӮөӮҪҒB ӮЕӮНҺҹӮЙҒAҺАҚЫӮМҗн‘ҲӮМӮжӮӨӮ·ӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҒЎҗн‘ҲӮМҺА‘Ф “–ҺһҒA’ҶҚ‘ҒE—Й“Ң”ј“Үҗж’[ӮМ—·ҸҮҚ`ӮНҒAғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМ–{Ӣ’’nӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB —ӨҢRӮНӮұӮМғҚғVғAӮМҠН‘аӮр—ӨӮ©ӮзҚUҢӮӮ·ӮйӮҪӮЯҒA—·ҸҮӮрҢ©үәӮлӮ·ӢuӮрҗи—МӮөӮжӮӨӮЖҒAҚUҢӮӮрҢJӮи•ФӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөғҚғVғAӮНӢӯҢЕӮИ—vҚЗӮр’zӮўӮД“ъ–{ӮрҚДҺOҢӮ‘ЮӮөӮЬӮ·ҒB“ъ–{ӮМ•әҺmӮН“ЛҢӮӮрҢJӮи•ФӮөӮЬӮөӮҪӮӘҒA—vҚЗӮ©ӮзӮМ–C’eӮр—ҒӮСҒAҺҹҒXӮЖ“|ӮкӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ҚUҢӮҠJҺnӮ©ӮзӮЁӮжӮ»”ј”NҢгӮМ1905”N1ҢҺҒA“ъ–{ҢRӮН‘еӮ«ӮИӢ]җөӮр•ҘӮБӮҪ––ӮЙӮжӮӨӮвӮӯӮұӮМ’nӮрҗи—МӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮөӮҪҒB 1905”N3ҢҺӮЙӮНҒA–һҸBӮЕ•т“VүпҗнӮӘҚsӮИӮнӮкӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮЖғҚғVғAҢRҒAҚҮӮнӮ№ӮД60–ңҗlӮр’ҙӮҰӮйҸ«•әӮӘҒA18“ъҠФӮЙӮнӮҪӮБӮДҢғӮөӮўҗнӮўӮрҢJӮиҚLӮ°ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҚЕҢгӮЙғҚғVғAҢRӮӘ“P‘ЮӮрҺnӮЯӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{‘ӨӮН•т“VӮрҗи—МӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮНҗ¬ҢчӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөғҚғVғAҢRӮЙҢҲ’и“IӮИ‘ЕҢӮӮр—^ӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮНҺё”sӮөҒAӮЬӮҪ“ъ–{ҢRӮН•әҺmӮа•ЁҺ‘ӮаҢАҠEӮЙ’BӮөӮЬӮөӮҪҒB ҒЎҗн‘ҲӮЖҚ‘–Ҝ ғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮН•¶Һҡ’КӮиҚ‘ӮМ‘Қ—НӮрӢ“Ӯ°ӮДӮМҗнӮўӮЕӮөӮҪҒBҗн”пӮҫӮҜӮЕӮа–с18үӯү~ӮЕҒAӮұӮкӮНҗн‘Ҳ‘OӮМ“ъ–{ӮМҚ‘үЖ—\ҺZҒA–с3үӯү~ӮМ6”{ҲИҸгӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ӮұӮкӮрӮЬӮ©ӮИӮӨӮҪӮЯӮЙҚsӮИӮБӮҪӮМӮӘҒAӮЬӮё‘қҗЕӮЕӮ·ҒB”сҸн“Б•КҗЕӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҒA’n‘dӮИӮЗӮМҗЕӮр‘қҗЕӮ·ӮйӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒAүҢ‘җӮвү–ӮМҗк”„җ§“xӮр–{Ҡi“IӮЙҺnӮЯӮЬӮөӮҪҒB”„ӮиҸгӮ°ӮНҚ‘ӮМӮаӮМӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ҺҹӮЙҚ‘ҚВӮр”ӯҚsӮөӮЬӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҺШӢаӮЕӮ·ҒBҚ‘“аӮЕӮЁӮжӮ»6үӯ7җз–ңү~’І’BӮөӮЬӮөӮҪӮӘҒAҚ‘–ҜӮМ‘ҪӮӯӮН‘қҗЕӮЕ•ү’SӮӘ‘қӮҰӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒAҚ‘ҚВӮрҗiӮсӮЕ”ғӮҰӮйҸуӢөӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBҺs’¬‘әӮИӮЗӮЕӢӯӮӯҚw“ьӮрӮ·Ӯ·ӮЯӮҪӮЖӮўӮӨ—бӮӘҸӯӮИӮӯӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҠOҚВӮЖӮўӮБӮДҒAғCғMғҠғXӮвғAғҒғҠғJӮ©ӮзӮаҺШӢаӮрӮөӮЬӮөӮҪҒBӮЁӮжӮ»8үӯү~ӮЖӮўӮӨӢҗҠzӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМҺШӢаӮӘҗнҢгӮМҚаҗӯӮр‘еӮ«ӮӯӢкӮөӮЯӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪӮұӮМҗн‘ҲӮЕҸ]ҢRӮөӮҪ“ъ–{ӮМ•әҺmӮНӮЁӮжӮ»109–ңҗlӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB“–ҺһӮМҗlҢыӮӘ–с5000–ңҗlӮЕҒAӮЁӮжӮ»”ј•ӘӮӘ’jҗ«ӮҫӮЖӮ·ӮйӮЖҒA109–ңҗlӮН’jҺq22Ғ`23җlӮЙ1җlӮЖӮўӮӨҢvҺZӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮҫӮҜӮМ•ә‘аӮрҸWӮЯӮйӮЙӮНҒA20‘гӮМҺбҺТӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒA30‘гӮв40‘гӮМ’jҗ«Ӯа“®ҲхӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB’ҶӮЙӮНҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЙ‘ұӮўӮД“с“x–ЪӮМҸoҗӘӮЙӮИӮБӮҪ•әҺmӮаӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДӮ»ӮМӮӨӮҝҒAӮЁӮжӮ»88000җlӮМ•әҺmӮӘ–SӮӯӮИӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪӮҜӮӘӮв•aӢCӮЙӮИӮБӮҪ•әҺmӮН40–ңҗlӮр’ҙӮҰӮЬӮ·ҒBӮВӮЬӮиҸoҗӘӮөӮҪ•әҺmӮМ”јҗ”ӮӘүҪӮзӮ©ӮМӢ]җөӮр”нӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ҒЎҗн‘ҲӮЖҸ—җ«ӮҪӮҝ ҲкҗlҲкҗlӮМ•әҺmӮЖӮ»ӮМүЖ‘°ӮЙӮНӮіӮЬӮҙӮЬӮИғhғүғ}ӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮұӮЕӮН•vӮрҗнҸкӮЙ‘—ӮиҸoӮөҒAүЖӮрҺзӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҚИӮМӮұӮЖӮрҢ©ӮДӮўӮ«ӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB җн‘ҲӮӘҺnӮЬӮйӮЖҒAҸ—җ«ӮМҗsӮӯӮ·ӮЧӮ«”C–ұӮЖӮөӮДҒA—бӮҰӮОҺҹӮМӮжӮӨӮИӮұӮЖӮӘҢҫӮнӮкӮЬӮөӮҪҒB (1)ҸoҗӘҺТӮрӮөӮД“аҢЪӮМ—JӮИӮ©ӮзӮөӮЮӮЧӮө (2)ҸОӮБӮДҢR–еӮЙ•vӮр‘—ӮйӮЧӮө (3)ҸoҗӘҺТӮМүЖ‘°ӮрҲФ•ҸӮ·ӮйӮұӮЖҒ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@ Ҹ—җ«Ӯаҗн‘ҲӮЙүҪӮ©–р—§ӮҝӮҪӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҒAҲӨҚ‘•wҗlүпӮЖӮўӮӨҒAүпҲхӮӘ45–ңҗlӮаӮўӮҪ’c‘МӮӘҒA•әҺmӮҪӮҝӮЙҲФ–в•iӮр‘—ӮБӮҪӮиҒAҸoҗӘ•әҺmӮМүЖ‘°Ӯр—гӮЬӮөӮҪӮиӮЖҗ·ӮсӮЙҠҲ“®ӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғu“аҢЪӮМ—JҒvӮЖӮНҚИӮЖӮөӮД•vӮЙүЖ’лӮМӮұӮЖӮЕ—]ҢvӮИҗS”zӮрӮ©ӮҜӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢҲҲУӮМ•\ӮкӮЖӮөӮДҒAӢп‘М“IӮЙӮНҚИӮҪӮҝӮӘҺ©•ӘӮМ”ҜӮМ–СӮрҗШӮБӮҪӮиӮөӮЬӮөӮҪҒB ’ҶүӣӮМҺКҗ^ӮрҢ©ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӮұӮкӮНҗз—tҢ§ӮМүд‘·ҺqҺsӮЙӮ ӮйҒuҚ•”Ҝ’ЛҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ·ҒB’nҢіӮМҸ—җ«ӮҪӮҝ11җlӮӘҚ•”ҜӮрҗШӮБӮДҗн‘Ҳ’ҶӮМүЖӮрҺзӮиҒAҗн‘ҲӮӘҸIӮнӮБӮД–іҺ–•vӮҪӮҝӮӘҠMҗщӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAӮ»ӮМӢL”OӮЖӮөӮДҢҡӮДӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©Ӯө–іҺ–ӢAӮБӮДӮ«ӮҪҸкҚҮӮНӮжӮ©ӮБӮҪӮЕӮөӮеӮӨӮӘҒAҗнҺҖӮөӮҪҗlӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮ·ҒB үEӮМҠGӮрҢ©ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBӮұӮкӮН–һ’JҚ‘ҺlҳYӮЖӮўӮӨҗlӮМ•`ӮўӮҪҒuҢRҗlӮМҚИҒvӮЖӮўӮӨҠGӮЕӮ·ҒB ӮұӮұӮЕӮНҸ—җ«ӮӘ•әҺmӮМ–XҺqӮЖ“ҒӮрҺқӮБӮДҒA”ЯӮөӮ»ӮӨӮЙҢ©ӮВӮЯӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҺАӮН•vӮНҗнҺҖӮөӮДҒAҢ`Ң©ӮЖӮөӮД–XҺqӮЖ“ҒӮӘ–ЯӮБӮДӮ«ӮҪҒAӮ»ӮкӮрҺиӮЙӮөӮДӮўӮйҸк–КӮЕӮ·ҒBҚИӮМ–ЪӮЙӮН—ЬӮӘӮҪӮҪӮҰӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҗн‘ҲӮМ”ЯӮөӮЭӮӘҗГӮ©ӮЙ“`ӮнӮБӮДӮӯӮйҠGӮЕӮ·ҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙ•vӮрҺёӮБӮҪҚИӮр“–ҺһӮНҒu–ў–SҗlҒvӮЖҢҫӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮӨӮөӮҪҸ—җ«ӮӘӮҪӮӯӮіӮсҸoӮйӮЖҒA–ў–SҗlӮӘҚДҚҘӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ—ЗӮўӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮӘ‘еӮ«ӮИҳb‘иӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҒuҚ‘ӮМӮҪӮЯӮЙ–ҪӮр—ҺӮЖӮөӮҪ•vӮМӮұӮЖӮр‘еҗШӮЙҺvӮӨӮИӮзҚДҚҘӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҲУҢ©ӮӘӢӯӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{ӮЙғҚғVғA•¶ҠwӮрҸРүоӮөӮҪҚмүЖӮМ“с—t’аҺl–АӮНҒAҒuҚДҚҘӮ·ӮЧӮөҒvӮЖӮ«ӮБӮПӮиӮЖҺе’ЈӮөӮЬӮөӮҪҒB ҒЎҗн‘ҲӮМҸIҢӢ ӮіӮДғ|ғCғ“ғg(3)җн‘ҲӮМҢӢүКӮЕӮ·ҒBӮЬӮёҒA“ъҳIҗн‘ҲӮӘӮЗӮӨҸIӮнӮБӮҪӮМӮ©ҒAҲкҸҸӮЙҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB 1905”N5ҢҺҒA“ъ–{ӮНҒAҗнҠНҺOҠ}ӮӘ—ҰӮўӮйҳAҚҮҠН‘аӮӘҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮр‘О”nү«ӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕ”jӮиӮЬӮөӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҗн—НӮМ‘е”јӮрҺёӮӨӮЖӮўӮӨҒA“ъ–{ӮМҲі“|“IӮИҸҹ—ҳӮЕӮөӮҪҒB үEӮН“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЖғҚғVғAӮМҗнӮўӮр•`ӮўӮҪ•—ҺhүжӮЕӮ·ҒBҸҹ—ҳӮӘ‘ұӮўӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒA“ъ–{ӮНҚаҗӯ“IҢRҺ–“IӮЙӮаҢАҠEӮрҢ}ӮҰҒAӮұӮкҲИҸгӮМҗн‘ҲҢp‘ұӮНҚў“пӮЙӮИӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮҪҸуӢөүәҒA‘еҚ‘ғҚғVғAӮЙҸҹ—ҳӮ·Ӯй“ъ–{ӮМҗЁӮўӮЙҠлӢ@ҠҙӮрҠoӮҰӮҪғAғҒғҠғJӮӘ—јҚ‘ӮМ’ҮүоӮЖӮИӮиҒAӢxҗнӮЦӮМ“®Ӯ«ӮӘӢӯӮЬӮиӮЬӮөӮҪҒB ҒЎғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaүпӢc Ӯ»ӮөӮД1905”N8ҢҺӮ©Ӯз9ҢҺӮЙӮ©ӮҜӮДҒAғAғҒғҠғJӮМғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕҚuҳaүпӢcӮӘҠJӮ©ӮкӮЬӮөӮҪҒB ’ҮүоӮөӮҪӮМӮНғAғҒғҠғJӮМғZғIғhғAҒEғҚҒ[ғYғ”ғFғӢғg‘е“қ—МҒB“ъ–{ӮМ‘г•\ӮНҸ¬‘әҺх‘ҫҳYҠO‘ҠҒAғҚғVғAӮМ‘г•\ӮНғEғBғbғeӮЕӮөӮҪҒB үпӢcӮМҢӢүКҒA“ъҳIӮМҚuҳaҸр–сҒAғ|Ғ[ғcғ}ғXҸр–сӮӘ’ІҲуӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB ҒЎҚuҳaӮМ“а—e ҚЕҸI“IӮЙӮЬӮЖӮЬӮБӮҪҚuҳaҸр–сӮНҺҹӮМӮжӮӨӮИ“а—eӮЕӮөӮҪҒB (1)ғҚғVғAӮНҒA“ъ–{ӮӘҠШҚ‘ӮЙӮЁӮўӮД•K—vӮИҒuҺw“ұ•ЫҢмӢyӮСҠД—қ(ҠД“ВӮөҒAҸҲ—қӮ·ӮйӮұӮЖ)ӮМ‘[’uҒvӮрӮЖӮйӮұӮЖӮр–WҠQҠұҸВӮөӮИӮў (2)—·ҸҮ‘еҳAӮМ‘dҺШҢ ҒA—·ҸҮҢыҒ|’·ҸtӮМ“S“№ӮЖ•t‘®ӮМҢ —ҳ(—бӮҰӮО•ҸҸҮ’YҚzӮИӮЗ)Ӯр“ъ–{ӮЙҸч“n (3)–kҲЬ50“xҲИ“мӮМҠ’‘ҫӮр“ъ–{ӮЙҸч“n ӮҪӮҫӮө”…ҸһӢаӮНҺx•ҘӮнӮкӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ӮМҚ‘–ҜӮНҒAҗн‘ҲӮЕ•ҘӮБӮҪӢ]җөӮЙ‘ОӮөӮДҠl“ҫӮөӮҪӮаӮМӮӘӮ ӮЬӮиӮЙҸӯӮИӮўӮЖӮөӮДҒAҚuҳaҸр–сӮӘҢӢӮОӮкӮҪ“ъӮЙ“ҢӢһӮИӮЗҠe’nӮЕ–\“®ӮрӢNӮөӮЬӮөӮҪҒB“ъ”д’JҸДӮ«‘ЕӮҝҺ–ҢҸӮИӮЗӮЕӮ·ҒBҢR‘аӮӘҸo“®ӮөӮД’БҲіӮЙ“–ӮҪӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЩӮЗӮЕӮөӮҪҒB ӮіӮД“ъ–{ӮНӮұӮМҢгҒA1910”NӮЙҠШҚ‘Ӯр•№ҚҮӮөӮДҗA–Ҝ’nӮЖӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢoүЯӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҒЎҠШҚ‘•№ҚҮӮМ•аӮЭ “ъҳIҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮБӮҪ’јҢгӮМ1904”N2ҢҺ23“ъҒA“ъ–{ӮНҠШҚ‘ӮЖӮМҠФӮЙ“ъҠШӢc’иҸ‘Ӯр’ІҲуӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮБӮДҒAҒuҠШҚ‘Ӯр‘јӮМҚ‘Ӯ©ӮзҺзӮйӮҪӮЯҒvӮЖҢҫӮӨ–ј–ЪӮЕҒAҠШҚ‘“аӮЕҢRҺ–Ҹг•K—vӮИӮіӮЬӮҙӮЬӮИҢ —ҳӮр“ҫӮЬӮөӮҪҒB —·ҸҮӮЕҢғҗнӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪ8ҢҺӮЙӮНҒA‘жҲкҺҹ“ъҠШӢҰ–сӮрҢӢӮСҒAҠШҚ‘ӮЙҒA“ъ–{ӮӘҗ„‘EӮ·ӮйҠOҢрҒEҚаҗӯҢЪ–вӮрҺуӮҜ“ьӮкӮйӮұӮЖӮр”FӮЯӮіӮ№ӮЬӮ·ҒB ҚuҳaӮМҢгҒA1905”N11ҢҺӮЙӮНҠШҚ‘ӮЖӮМҠФӮЕ‘ж“сҺҹ“ъҠШӢҰ–сӮр’чҢӢҒBҺс“sӮЙҠШҚ‘“қҠД•{ӮрҗЭ’uӮөӮДҒAҠШҚ‘ӮМҠOҢрҢ Ӯр’DӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮөӮДҠШҚ‘ӮМҚc’йҒEҚӮҸ@(ғRғWғҮғ“)ӮНҒA1907”N6ҢҺӮЙғIғүғ“ғ_ӮМғnҒ[ғOӮЕҠJӮ©ӮкӮҪ•ҪҳaүпӢcӮЙ–§ҺgӮр‘—ӮиҒA“ъ–{ӮМҺx”zӮӘ•s“–ӮҫӮЖ‘iӮҰӮжӮӨӮЖӮөӮЬӮөӮҪӮӘҒAҺё”sӮЙҸIӮнӮиӮЬӮ·ҒBӮўӮнӮдӮйғnҒ[ғO–§ҺgҺ–ҢҸӮЕӮ·ҒB ӮұӮМҺ–ҢҸӮрӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЙ“ъ–{ӮН1907”N7ҢҺҒAҚӮҸ@ӮрҺёӢrӮіӮ№‘жҺOҺҹ“ъҠШӢҰ–сӮр’чҢӢҒB “ъ–{ӮНҠШҚ‘ӮМ“аҗӯҢ ӮрҗЪҺыҒAҠШҚ‘ӮМҢR‘аӮрүрҺUӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒBүрҺUӮіӮкӮҪҢR‘аӮ©ӮзӮНҢіҢRҗlӮӘҒAӢ`•ә“¬‘ҲӮЖҢДӮОӮкӮй“ъ–{ӮЦӮМ’пҚRү^“®ӮЙҺQүБӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB 1909”N10ҢҺӮЙӮНҒA’ҶҚ‘ғnғӢғrғ“үwҚ\“аӮЕҒAҠШҚ‘ӮМ–Ҝ‘°ү^“®үЖҒEҲАҸdҚӘ(ғAғ“ғWғ…ғ“ғOғ“)ӮӘҠШҚ‘“қҠДӮҫӮБӮҪҲЙ“Ў”Һ•¶Ӯр‘_ҢӮҒAҲЙ“ЎӮНҺҖ–SӮөӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮН—Ӯ1910”N8ҢҺҒAҠШҚ‘•№ҚҮҸр–сӮЙӮжӮБӮДӮВӮўӮЙҠШҚ‘Ӯр•№ҚҮӮөҒA“ъ–{—МӮМҒu’©‘NҒvӮЖӮөӮЬӮөӮҪҒB’©‘NӮЙӮН’©‘N‘Қ“В•{Ӯв“ъ–{ӮМҢR‘аӮӘ’uӮ©ӮкҒA1945”NӮЬӮЕҗA–Ҝ’nҺx”zӮӘ‘ұӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ–һҸB–в‘и җA–Ҝ’nҺһ‘гӮМ’©‘NӮЙӮВӮўӮДӮНӮҪӮӯӮіӮсӮМ–{ӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮұӮЙӮ ӮйғCҒEғTғ“ғNғҖӮМҒw”ј•ӘӮМӮУӮйӮіӮЖҒxӮвғnғҖҒEғ\ғNғzғ“ӮМҒwҺҖӮКӮЬӮЕӮұӮМ•аӮЭӮЕҒxӮИӮЗӮНҒAҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘӮЗӮӨӮўӮӨҢoҢұӮИӮМӮ©ӮӘӮҪӮўӮЦӮсӮжӮӯ•ӘӮй–{ӮЕӮ·ҒB ӮЖӮұӮлӮЕғ|Ғ[ғcғ}ғXҚuҳaҸр–сӮЕ“ъ–{ӮНҒAғҚғVғAӮӘҺқӮБӮДӮўӮҪ–һҸBӮЕӮМ—ҳҢ ӮрҠl“ҫӮөӮЬӮөӮҪҒB “S“№ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA—·ҸҮҢыҒ|’·ҸtҠФӮМ“S“№ӮрҺиӮЙ“ьӮкҒA1906”NӮЙҒu“м–һҸB“S“№Ҡ”Һ®үпҺРҒvҒҒӮўӮнӮдӮйҒu–һ“SҒvӮрҗЭ—§ӮөҒAҢoүcӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB —Й“Ң”ј“ҮӮМ—·ҸҮҒE‘еҳA’nҲжӮНҒuҠЦ“ҢҸBҒvӮЖҢДӮОӮкҒA—·ҸҮӮЙӮНҺx”zӮМӮҪӮЯӮЙҠЦ“Ң“s“В•{ӮӘ’uӮ©ӮкӮЬӮөӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮӘҺnӮЬӮйҚЫҒA“ъ–{ӮН–һҸBӮМ–еҢЛҠJ•ъӮрғAғҒғҠғJӮвғCғMғҠғXӮЙғAғsҒ[ғӢӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒAғAғҒғҠғJӮМ“S“№үӨӮЖҢҫӮнӮкӮҪғnғҠғ}ғ“ӮЖӮўӮӨҗlӮӘҒAӮіӮБӮ»Ӯӯ–һ“SӮМ“ъ•ДӢӨ“ҜҢoүcӮрҗ\Ӯө“ьӮкӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ъ–{ӮНҸ¬‘әҠO‘ҠӮМҲУҢ©ӮЕӮұӮкӮр’fӮиӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮЙ‘ОӮөӮДғAғҒғҠғJӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙ“ъ–{ӮЙӢкҢҫӮр’жӮөӮЬӮөӮҪҒBҒ@Ғ@ ҒuҳIҚ‘ғJҠY’n•ығjү—ғeҺА—ҳғmҚ‘үЖ“I“Жҗиғ’ҲЧғTғ“ғgғVғeҺё”sғVғ^ғӢғmҠйҗ}ғjжщғL–һҸBғjү—ғe”VғgӢПғVғL“ъ–{ғm—ҳүvғm”r‘ј“I•}җAғn’ЙҗШғiғӢҺё–]ғmӢNҲцғ^ғӢғwғVҒv ӮВӮЬӮиҒAӮ©ӮВӮДғҚғVғAӮӘӮөӮҪӮМӮЖ“ҜӮ¶”r‘ј“IӮИҚs“®Ӯр“ъ–{ӮӘ–һҸBӮЕӮөӮДӮўӮйҒAӮЖ”б”»ӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮҪӮұӮЖӮЙҲЙ“Ў”Һ•¶ӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙ—J—¶ӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғuүд“–ӢЗҺТғjғVғe–еҢЛҠJ•ъҒAӢ@үпӢП“ҷғmҺеӢ`ғ’‘ёҸdғZғXҗШғҠғj—ҳҢИҺеӢ`ғj‘–ғҢғnүў•ДҸ”–MғnүдҗҪҺАғ’Ӣ^ғqҗMғ’Ңбғj‘[ғJғTғӢғjҺҠғӢғwғVҒvҒu–һҸBғjү—ғPғӢ—ҳҢИҗӯҚфғmҺАҺ{ғnҗЁғqҗҙҗlғm”ҪҚRғ’ҸөғNғn–Ьҳ_ҒvҒuҗўҠEғm‘еҗЁғn–wғg“ъ–{ғ’ҢЗ—§ғZғVғҒғXғ“ғnӣЯғ}ғTғӢғmҢXҢьҒvҒ@(1907”N) ғҚғVғAӮЙҸҹӮВӮұӮЖӮЕ“ъ–{ӮН“–ҺһҒAҗўҠEӮМҲк“ҷҚ‘ӮЙӮИӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮҫӮҜӮЙ—сӢӯӮМа•—у(ӮөӮкӮВ)ӮИ‘ҲӮўӮЙ‘ОүһӮөӮДӮўӮ©ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮӯӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮЬӮҪ’ҶҚ‘Ӯ©ӮзӮМ”Ҫ”ӯӮаӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМҺһ‘гӮНҒA—сӢӯӮЖӮўӮнӮкӮҪүў•ДҸ”Қ‘ӮӘ”eҢ Ӯр‘ҲӮӨҺһ‘гҒAҺг“чӢӯҗHҒA—М“yӮвҢ үvӮрҠg‘еӮөӮДӮўӮӯӮұӮЖӮӘ“–‘RӮЖӮіӮкӮҪҺһ‘гӮЕӮөӮҪҒB“ъ–{ӮНӮ»ӮӨӮөӮҪүў•Д•¶–ҫҚ‘ӮрӮЯӮҙӮөӮД’·ӮўҚв“№Ӯр“oӮБӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД“ъҳIҗн‘ҲӮЕ“–ҺһҢҫӮнӮкӮҪҒuҲк“ҷҚ‘ҒvӮМ’ҮҠФӮЙ“ьӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМүЯ’цӮЙӮНҚЎӮЙӮЬӮЕӮВӮИӮӘӮй‘еҗШӮИ–в‘иӮӘӮ ӮйӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBӮЭӮИӮіӮсӮа—рҺjӮЖ‘ОҳbӮөӮДӮўӮБӮДӮӯӮҫӮіӮўҒBҒ@ |
|
| ҒЎ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнҒ@ | |
|
“ъҳIҗн‘ҲӮ©Ӯз10”NҢгҒA1914”NӮЙҺnӮЬӮБӮҪ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМӮұӮлӮМ—рҺjӮрҠwӮсӮЕӮўӮ«ӮЬӮөӮеӮӨҒBӮұӮМ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮМҚr”pҒAғAғҒғҠғJӮМ‘д“ӘҒAғ\ҳAӮМҸoҢ»ӮИӮЗӮМ“Б’ҘӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮМҲУ–ЎӮЕҗўҠEҺjӮМ’ҶӮМ‘еӮ«ӮИ“]Ӣ@ӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ҒB
ғCғMғҠғXӮМ—рҺjүЖғzғuғXғ{Ғ[ғҖӮНҒAҗн‘ҲӮЖҠv–ҪҒAӮ»ӮөӮД•ҪҳaӮӘҢрҚцӮ·Ӯй20җўӢIӮӘӮұӮұӮ©ӮзҺnӮЬӮБӮҪӮЖӮўӮӨҢ©•ыӮрӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB Ҳк•ы“ъ–{ӮНҒA‘еҗнӮр’КӮөӮДғAғWғAҒE‘ҫ•Ҫ—mӮЙӮіӮзӮЙ–c’ЈӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиӮжӮи‘еӮ«ӮИ’йҚ‘ӮЦӮЖҠg‘еӮөӮДӮўӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҚЎ“ъӮМғ|ғCғ“ғgӮЕӮ·ҒB (1)“сҸ\ҲкӮ©Ҹр—vӢҒ “ъ–{ӮӘӮИӮә‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙҺQҗнӮөӮҪӮМӮ©ҒAӮЬӮҪӮ»ӮМ’ҶӮЕ’ҶҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҸoӮөӮҪ—vӢҒӮрҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB (2)ғҸғVғ“ғgғ“‘Мҗ§ ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮр’КӮөӮДҒA“ъ–{ӮН’ҶҚ‘Ӯв‘ҫ•Ҫ—mӮЕӮіӮзӮЙҢ үvӮр–cӮзӮЬӮ№ӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮЙ‘ОӮөӮДӢNӮ«ӮҪ”Ҫ”ӯӮвҒAӮ»ӮМҢӢүКӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҚ‘ҚЫ“IӮИ‘Мҗ§ӮаҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB (3)‘еҗнҢiӢCҒ@җ»Һ…ӢЖӮМ”ӯ“W ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМҢӢүКҒA“ъ–{ҢoҚПӮНӢ}җ¬’·ӮрҗӢӮ°ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—lҺqӮр‘@ҲЫҺYӢЖӮр’ҶҗSӮЙҢ©ӮДӮўӮ«ӮЬӮ·ҒB ҒЎҗн‘ҲӮМ”wҢiӮЖҠJҗн ғ|ғCғ“ғg(1)ӮЬӮё‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙӮВӮўӮДӮЭӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB 1914”N6ҢҺҒBғҲҒ[ғҚғbғp“Ң•”ҒAғ{ғXғjғAӮМҺс“sғTғүғGғ”ғHӮЕҺ–ҢҸӮӘӢNӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМ’nӮр–KӮкӮДӮўӮҪғIҒ[ғXғgғҠғAӮМ’йҲКҢpҸіҺТ•vҚИӮӘҒA—ЧӮМҚ‘ғZғӢғrғAӮМҗВ”NӮЙҲГҺEӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“–ҺһҒA–Ҝ‘°•ҙ‘ҲӮЕӢЩ’ЈӮөӮДӮўӮҪ“ҢғҲҒ[ғҚғbғpӮЕӮНҒAӮұӮМҺ–ҢҸӮрӮ«ӮБӮ©ӮҜӮЙҒAғIҒ[ғXғgғҠғAӮЖғZғӢғrғAӮӘҗн‘ҲӮрҺnӮЯӮЬӮ·ҒB ӮұӮкӮЙ‘јӮМ‘еҚ‘ӮМ—ҳҠQӮӘ—ҚӮЭҚҮӮўҒAғCғMғҠғXҒAғtғүғ“ғXҒAғhғCғcҒAғҚғVғAӮИӮЗӮаҺҹҒXӮЖҺQҗнӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҒu‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнҒvӮЕӮ·ҒB ғҲҒ[ғҚғbғpӮН“–ҸүҒAғIҒ[ғXғgғҠғAҒEғnғ“ғKғҠҒ[ҒAғhғCғcҒAғCғ^ғҠғAӮр’ҶҗSӮЖӮ·Ӯй“Ҝ–ҝҚ‘‘ӨӮЖғCғMғҠғXҒAғtғүғ“ғXҒAғҚғVғAӮр’ҶҗSӮЖӮ·ӮйҳAҚҮҚ‘‘ӨӮӘҗнӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМҗнӮўӮНҒAҚ‘үЖӮӘӮ·ӮЧӮДӮМ—НӮрҗн‘ҲӮЙӮВӮ¬ҚһӮЮҒA‘Қ—НҗнӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮіӮзӮЙҒAӮұӮкӮЬӮЕӮИӮ©ӮБӮҪҗVӮөӮў•әҠнӮӘҺgӮнӮкӮЬӮөӮҪҒB ”тҚsӢ@ӮвҗнҺФҒBҗцҗ…ҠНӮв“ЕғKғXӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮНҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮЕӮНҒAҢRҗlӮМҗнҺҖҺТӮӘӮЁӮжӮ»900–ңҒAӮіӮзӮЙ400–ңӮЖҢҫӮнӮкӮйҲк”КҺs–ҜӮӘӢ]җөӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨҒA”ЯҺSӮИҗн‘ҲӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ҒЎ“ъ–{ӮМҺQҗн “ъ–{ӮНҒAғCғMғҠғXӮЖ“ъүp“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮЕӮўӮҪӮұӮЖӮрҚӘӢ’ӮЙҒAӮұӮМҗн‘ҲӮЙҺQҗнӮөӮЬӮ·ҒB “–ҺһҒAғhғCғcӮН’ҶҚ‘ӮМҺR“Ң”ј“ҮӮЙ“S“№ӮвҚzҺRӮИӮЗӮМҢ үvӮрҺқӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ӮНҒAғhғCғcӮрҚUӮЯҒAӮұӮкӮзӮМҢ үvӮрҺиӮЙ“ьӮкӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮД1914”N8ҢҺҒAғhғCғcӮЙҗйҗнӮр•zҚҗӮөӮЬӮөӮҪҒB 9ҢҺӮЙӮНҒAҺR“Ң”ј“ҮӮЙ“ъ–{ҢRӮӘҸг—ӨӮөҒAғAғWғAӮЕӮМғhғCғcӮМӢ’“_ӮҫӮБӮҪҗВ“ҮӮрҗи—МӮөӮЬӮөӮҪҒB ҒЎ“ъ–{ӮМҺQҗнӮМ”wҢi “ъ–{ӮӘҺQҗнӮөӮҪ—қ—RӮрҚlӮҰӮйӮҪӮЯҒA‘еҗн‘OӮМ“ъ–{ӮМҸуӢөӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҺАӮН“ъ–{ӮН“сӮВӮМ‘еӮ«ӮИүЫ‘иӮр•шӮҰӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ҲкӮВӮНҒAҒuҲк“ҷҚ‘ҒvӮЖӮөӮДҢR”хҠg’ЈӮр‘ұӮҜӮҪӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢӢүКҒA‘қҗЕҳHҗьӮаҢp‘ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪӮӘҒAҚ‘–ҜӮ©ӮзӮНҗЕӮМ”pҺ~ӮвҢёҗЕӮрӢҒӮЯӮйү^“®ӮӘҚӮӮЬӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮөӮД‘ж“сӮНҒAғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJӮИӮЗӮЦӮМ•үҚВҒAӮВӮЬӮиҺШӢаӮӘ‘қӮҰҒAӮЬӮҪ–fҲХҗФҺҡӮЙӮаӢкӮөӮсӮЕӮўӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒB ӮұӮӨӮөӮДҚsӮ«ӮГӮЬӮБӮДӮўӮҪ“ъ–{ӮМ‘OӮЙӢNӮ«ӮҪӮМӮӘ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB —бӮҰӮОҒA“–Һһ78ҚОӮҫӮБӮҪҢіҳVӮМҲдҸгҠ]ӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙҢҫӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB ҒuҚЎүсүўҸBӮМ‘еүР—җӮНҒA“ъ–{Қ‘ү^ӮМ”ӯ“WӮЙ‘ОӮ·Ӯй‘еҗіҗVҺһ‘гӮМ“V—CҒBҒvҒ@Ғ@ Ғu“Ң—mӮЙ‘ОӮ·Ӯй“ъ–{ӮМ—ҳҢ ӮрҠm—§Ӯ№ӮҙӮйӮЧӮ©ӮзӮёҒv “V—CӮЖӮН“VӮМҸ•ӮҜӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮЕӮ·ӮӘҒA‘еҗнӮЙҺQҗнӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҚ‘ӮМ“аҠOӮМӮіӮЬӮҙӮЬӮИ–в‘иӮрҲкӢ“ӮЙ‘ЕҠJӮөӮДӮўӮұӮӨҒAӮ ӮйӮўӮН‘ЕҠJӮЕӮ«ӮйӮЖҚlӮҰҒAӮ»ӮМҲУ–ЎӮЕ“V—CӮЖҢҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAғAғWғAӮЙӮіӮзӮЙ‘еӮ«ӮӯҗiҸoӮөӮДӮўӮӯӮЧӮ«ӮҫӮЖӮаҢҫӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB “–ҺһғhғCғcӮН’ҶҚ‘ӮЕӮНҺR“Ң”ј“ҮӮМдPҸBҳp(ӮұӮӨӮөӮгӮӨӮнӮс)’nҲжӮр1898”NӮ©Ӯз‘dҺШӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪ‘ҫ•Ҫ—mӮЕӮНҒA19җўӢI––ӮЙғXғyғCғ“Ӯ©ӮзҚw“ьӮөӮҪғ}Ғ[ғVғғғӢҸ”“ҮҒAғJғҚғҠғ“Ҹ”“ҮҒAғAғҒғҠғJ—МӮМғOғAғҖӮрҸңӮӯғ}ғҠғAғiҸ”“ҮӮИӮЗӮрҺx”zӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮМҢR•”ӮвүБ“ЎҚӮ–ҫҠO‘ҠӮНҒAҳAҚҮҚ‘‘ӨӮЙ—§ӮБӮДҺQҗнӮ·ӮйӮұӮЖӮЕҒAӮұӮкӮзӮМ’nҲжӮрҺиӮЙ“ьӮкӮжӮӨӮЖӢӯӮӯ–]ӮсӮЕӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъүp“Ҝ–ҝӮМҺпҺ|Ӯ©ӮзӮ·ӮйӮЖ•KӮёӮөӮаҺQҗнӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮнӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB“ъ–{ӮМҺvҳfӮЙӮВӮўӮДӮНҒAғCғMғҠғXӮвғAғҒғҠғJҒAӮ»ӮөӮД’ҶҚ‘Ӯ©ӮзҢң”OӮӘҸoӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{ӮН“ъүp“Ҝ–ҝӮрҸӮӮЙӮЖӮйҢ`ӮЕҒA1914”N8ҢҺҒAҠJҗнӮ©Ӯз1Ӯ©ҢҺҢгӮЙҒAӮ©ӮИӮиӢӯҲшӮЙғhғCғcӮЙҗйҗн•zҚҗӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮНӮЬӮёҺR“Ң”ј“ҮӮЙ•әӮр‘—ӮиҒAҗВ“ҮӮМғhғCғcҢRӮрҚ~•ҡӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒBӮЬӮҪғhғCғcӮӘҢoүcӮөӮДӮўӮҪҺR“Ң“S“№Ӯаҗи—МӮөӮЬӮөӮҪҒBҲк•ыҠCҢRӮН“м—mҸ”“ҮӮЙҠН‘аӮр”hҢӯӮөӮД10ҢҺӮЙӮНҗи—МӮөҒAӮұӮМ’nҲжӮЙҢRҗӯӮр•~Ӯ«ӮЬӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҢRӮӘ“қҺЎӮЙ“–ӮҪӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДӮаӮӨҲкӮВӮМ‘еӮ«ӮИҸo—ҲҺ–ӮӘҒAғ|ғCғ“ғgӮЙӮ Ӯй’ҶҚ‘ӮЦӮМҒu“сҸ\ҲкӮ©Ҹр—vӢҒҒvӮЕӮ·ҒB ӮұӮкӮЙӮВӮўӮДҢ©Ӯй‘OӮЙҒA“–ҺһӮМ’ҶҚ‘ӮМҸуӢөӮрҠm”FӮөӮДӮЁӮ«ӮЬӮөӮеӮӨҒB ҒЎ’ҶҚ‘ӮМҸуӢөӮЖ21Ӯ©Ҹр—vӢҒ 20җўӢIҸүӮЯӮМ’ҶҚ‘ӮЕӮНҒA—сӢӯӮМҚ‘ҒXӮӘҢ үvӮрӮўӮБӮ»ӮӨҠg‘еӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB 1911”N1ҢҺҒA‘·•¶—ҰӮўӮйҠv–Ҫ”hӮӘҒAҗҙ’©ӮМ‘Е“|Ӯр–ЪҺwӮөӮДҒA’ҶҚ‘“м•”ӮЕ•җ‘•–IӢNӮөӮЬӮөӮҪҒBҒuҗhҲеҠv–ҪҒvӮМҺnӮЬӮиӮЕӮ·ҒBӮұӮМ“®Ӯ«ӮНҒA’ҶҚ‘Ҡe’nӮЙҚLӮӘӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB —Ӯ1912”N1ҢҺҒB‘·•¶ӮН’ҶүШ–ҜҚ‘ӮМҺч—§ӮрҗйҢҫҒBҒu—ХҺһ‘е‘Қ“қҒvӮЙҸA”CӮөӮЬӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөҒAҗҙ’©ӮЙ‘гӮнӮБӮД‘S“yӮрҺx”zӮЕӮ«ӮйӮЬӮЕӮЙӮНҺҠӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBҗҙ’©ӮЕҺАҢ ӮрҲ¬ӮБӮДӮўӮҪеНҗўҠM(ӮҰӮсӮ№ӮўӮӘӮў)ӮӘ‘·•¶ӮМ‘OӮЙ—§ӮҝӮНӮҫӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB еНҗўҠMӮНҒAҗҙ’©ӮМҚc’йӮр‘ЮҲКӮіӮ№ӮЬӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДӮ»ӮкӮЖҲшӮ«Ҡ·ӮҰӮЙҒAҺ©ӮзӮӘ‘·•¶Ӯр—}ӮҰӮДҒA’ҶүШ–ҜҚ‘ӮМҸү‘гҒE‘е‘Қ“қӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB еНҗўҠMӮНҒAҗВ“ҮӮрҗи—МӮ·Ӯй“ъ–{ҢRӮЙ“P‘ЮӮрӢҒӮЯӮЬӮ·ҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{ӮНӮ»ӮкӮрӢ‘”ЫҒB 1915”N1ҢҺҒAеНҗўҠMӮЙ‘ОӮөӮДҒu“сҸ\ҲкӮ©ҸрӮМ—vӢҒҒvӮр“ЛӮ«ӮВӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ“сҸ\ҲкӮ©Ҹр—vӢҒӮМ“а—e Ӯ»ӮкӮЕӮН“сҸ\ҲкӮ©ҸрӮМ—vӢҒӮМҺеӮИ“а—eӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB (1)ҺR“ҢҸИӮМғhғCғcҢ үvӮМ“ъ–{ӮЦӮМҲш“nӮө (2)—·ҸҮҒE‘еҳAӮМ‘dҺШҠъҢАӮЖ“м–һҸB“S“№ӮМҢ үvӮМҠъҢАӮрӮ»ӮкӮјӮк99Ӯ©”NҠФӮЙү„’·Ӯ·ӮйӮұӮЖҒBӮұӮкӮНӮўӮёӮкӮа“ъҳIҗн‘ҲӮЕ“ъ–{ӮӘғҚғVғAӮ©ӮзҠl“ҫӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB (3)Ҡҝ–идКҢцҺi(Ӯ©ӮсӮвӮРӮеӮӨӮұӮсӮ·)ӮМ“ъ’ҶӢӨ“ҜҢoүc Ҡҝ–идКҢцҺiӮН1908”NӮЙҗЭ—§ӮіӮкӮҪ’ҶҚ‘ҚЕ‘еӮМҗ»“SҠйӢЖӮЕӮ·ҒBӮұӮМҢoүcӮЙ“ъ–{ӮаҺQүБӮіӮ№ӮлӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ·ҒB (4)’ҶҚ‘үҲҠЭӮМҚ`ҳpҒE“ҮӮөӮе(ҒҒ“ҮҒX)ӮМ‘јҚ‘ӮЦӮМ•sҠ„Ҹч (5)“ъ–{җlӮМҗӯҺЎҒEҚаҗӯҒEҢRҺ–ҢЪ–вӮрҚМ—pӮ·ӮйӮұӮЖҒAҢxҺ@Ӯр“ъ’ҶҚҮ“ҜӮЙӮ·ӮйӮұӮЖ ӮіӮ·ӮӘӮЙӮұӮМҢЬҚҶ—vӢҒӮЙӮНҚ‘ҚЫ“IӮЙӮаҒAӮЬӮҪ“ъ–{Қ‘“аӮМҗӯҺЎүЖӮ©ӮзӮа”б”»ӮӘҸoӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮНӮұӮМҢЬҚҶ—vӢҒҲИҠOӮМҺеӮИ—vӢҒӮрҒA’ҶҚ‘‘ӨӮЙҚЕҢг’К’«ӮрӮВӮ«ӮВӮҜӮДҺуӮҜ“ьӮкӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “–ҺһӮМ’ҶҚ‘ӮЕӮНҒAҺу‘шӮөӮҪ5ҢҺ9“ъӮрҚ‘’pӢL”O“ъҒAӮВӮЬӮиҚ‘ӮМ’pӮрҗSӮЙҚҸӮЮ“ъӮЖӮөӮҪӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒA“ъ–{җ»•iӮМ•s”ғү^“®ӮаӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪ’ҶҚ‘ӮМҗV•·Ғu–kӢһ“ъ•сҒvӮНҺҹӮМӮжӮӨӮЙҸ‘Ӯ«ӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮМ—vӢҒӮНҒu—сӢӯғmҺ№“iғ’ҸөғL“ағnҺx“Яҗlғm•®җSғ’ҢғҒvӮ·ӮйӮаӮМӮЕҒA“ъ–{ӮНҒuҗўҠEғmҢц“GҒvӮЖӮИӮиҒAҒu‘ј“ъ•KғX–Ҫғ’“qғXғӢ“ъғAғӢғiғҠҒv ’ҶҚ‘Ӯ©ӮзҒuҗўҠEӮМ“GҒvӮЖҢҫӮнӮкӮйӮЬӮЕӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮБӮҪӮжӮӨӮЙҒA’ҶҚ‘ӮМ–в‘иӮрӮЯӮ®ӮБӮД“ъ–{ӮН‘еӮ«ӮИүЫ‘иӮр”w•үӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎғ”ғFғӢғTғCғҶҸр–сӮЖҢЬҺlү^“® ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМҢӢүКҒAӮЗӮӨӮИӮБӮДӮўӮБӮҪӮМӮ©ӮӘҒAҺҹӮМғ|ғCғ“ғg(2)ӮЕӮ·ҒB 1919”N6ҢҺҒA‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮрҸIӮнӮзӮ№ӮйҚuҳaҸр–сӮӘҒAғtғүғ“ғXӮМғpғҠҚxҠOҒAғ”ғFғӢғTғCғҶӢ{“aӮЕ’ІҲуӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB “ъ–{ӮНҒAғAғҒғҠғJҒAғCғMғҠғXҒAғtғүғ“ғXҒAғCғ^ғҠғAӮЖӮЖӮаӮЙ5‘еҚ‘ӮМҲкҲхӮЖӮөӮДҺQүБҒBҢіҺс‘ҠӮМҗјүҖҺӣҢц–]ӮзӮӘҸoҗИӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮМҸр–сӮЕ“ъ–{ӮНҒAдPҸBҳpӮМ“қҺЎҢ Ӯв“S“№ӮИӮЗҒAҺR“Ң”ј“ҮӮЙӮЁӮҜӮйғhғCғcӮМҢ үvӮрҲшӮ«ҢpӮ®ӮұӮЖӮр”FӮЯӮзӮкӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA’ҶҚ‘ӮНӮұӮМҸр–сӮЙ’ІҲуӮөӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ҒЎҢЬҺlү^“® ҚuҳaүпӢcӮМҚЕ’ҶӮМ1919”N5ҢҺ4“ъҒB“ъ–{ӮӘҺR“Ң”ј“ҮӮМҢ үvӮрӢҒӮЯӮҪӮұӮЖӮЕҒA’ҶҚ‘ӮЕӮН‘еӢK–НӮИ”Ҫ“ъү^“®ӮӘӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒBҠwҗ¶ӮИӮЗӮӘ“VҲА–еҚLҸкӮЕҸWүпӮрҠJӮ«ҒA”Ҫ“ъӮМғXғҚҒ[ғKғ“ӮрҢfӮ°ӮД—§ӮҝҸгӮӘӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҒuҢЬҺlү^“®ҒvӮЕӮ·ҒB ’ҶҚ‘Ҡe’nӮЕҒAҠwҗ¶ӮМҺцӢЖғ{ғCғRғbғgҒAҳJ“ӯҺТӮМғXғgғүғCғLҒAҸӨ“XӮМ•В“XӮв“ъ–{ҸӨ•iӮМ•s”ғү^“®ӮИӮЗӮӘӢNӮұӮиӮЬӮөӮҪҒB ҒЎ“м—mҸ”“ҮӮМ“қҺЎ ‘жҲкҺҹ‘еҗн’ҶҒA“ъ–{ӮН’ҶҚ‘ӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒA‘ҫ•Ҫ—mӮМ“ҮҒXӮЙӮаҗiҸoӮөӮЬӮөӮҪҒB1914”NҒAғhғCғc—МӮҫӮБӮҪғ}ғҠғAғiҸ”“ҮҒAғpғүғIҸ”“ҮҒAғJғҚғҠғ“Ҹ”“ҮҒAғ}Ғ[ғVғғғӢҸ”“ҮӮИӮЗ“м—mӮМ“ҮҒXӮрҗи—МӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB 1920”NӮЙӮНҒAғ”ғFғӢғTғCғҶҸр–сӮЙҠоӮГӮўӮД“ъ–{ӮӘ“қҺЎӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ғpғүғIҸ”“ҮӮМғRғҚҒ[ғӢ“ҮӮЙҒu“м—m’ЎҒvӮӘҚмӮзӮкҒA“ҮҒXӮЙ6ӮВӮМҺx’ЎӮӘ’uӮ©ӮкӮЬӮөӮҪҒB ҲИҚ~ҒA“ъ–{ӮНҗlҒXӮМ•йӮзӮөӮвӢіҲзӮИӮЗӮрҒu“ъ–{ү»ҒvӮ·ӮйҗӯҚфӮрӮЖӮиӮИӮӘӮзҒA20”NҲИҸгӮЙӮнӮҪӮБӮД“қҺЎӮр‘ұӮҜӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ҺАӮН’ҶҚ‘Ӯа“r’ҶӮ©ӮзҺQҗнӮөӮДҗнҸҹҚ‘ӮМҲкҲхӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—§ҸкӮЕҚuҳaүпӢcӮЙҺQүБӮөҒAҺR“Ң”ј“ҮӮЕғhғCғcӮӘҺқӮБӮДӮўӮҪҢ үvӮН“–‘RҒA’ҶҚ‘ӮЙ•ФҠТӮіӮкӮйӮЧӮ«ӮҫӮЖҺе’ЈӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{ӮНҒA“ъ–{ӮМҺиӮрҢoӮД’ҶҚ‘ӮЙ•ФҠТӮ·ӮйӮЖҗә–ҫӮөӮДҒAӮўӮБӮҪӮс“ъ–{ӮӘҲшӮ«ҢpӮ®Ң`ӮрҺуӮҜ“ьӮкӮіӮ№ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮӨӮ·ӮйӮЖҒAҚЎҢ©ӮҪӮжӮӨӮЙҢЬҺlү^“®ӮЖҢДӮОӮкӮй”Ҫ“ъү^“®ӮӘӢNӮ«ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮ ӮиҒA’ҶҚ‘‘г•\ӮНҚuҳaҸр–сӮЙҢӢӢЗҒA’ІҲуӮөӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҺR“Ң–в‘иӮН’ҲӮЙ•ӮӮўӮҪҢ`ӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ӮЬӮҪ“ъ–{ӮӘҗи—МӮөӮҪҗФ“№ӮжӮи–kӮМғhғCғc—МӮМ“м—mҸ”“ҮӮЙӮВӮўӮДҒA“ъ–{ӮНҒAҚ‘ҚЫҳA–ҝӮ©Ӯз“қҺЎӮр”CӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮрҒuҲП”C“қҺЎҒvӮЖӮўӮўӮЬӮ·ҒB 1920”NӮЙ“м—mҸ”“ҮӮМҲП”C“қҺЎӮӘҺnӮЬӮиҒA“ъ–{ӮМ–@—ҘӮЙҠоӮГӮўӮД“қҺЎӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB(ӮҪӮҫӮөҢRҺ–Һ{җЭӮМҗЭ’uӮНӢЦҺ~ӮіӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB) 1922”NӮЙӮНғpғүғIҸ”“ҮӮМғRғҚҒ[ғӢ“ҮӮЙ“м—m’ЎӮЖӮўӮӨ–рҸҠӮӘҗЭ’uӮіӮкҒA–ҜҗӯӮЙҲЪҚsӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮД“м—m’ЎӮНҒAҲЪ–ҜӮМҸ§—гҒAҺYӢЖӮМҗUӢ»ҒAӢіҲзӮМҸ§—гӮрҗiӮЯӮЬӮөӮҪҒB ҺYӢЖӮЖӮўӮӨӮЖҒAғTғgғEғLғrӮвҒA–ыӮӘҺжӮкӮйғRғRғ„ғV(җОӮҜӮсӮМҚЮ—ҝ)ӮМҚН”|ҒAӮ©ӮВӮЁӮФӮөӮМҗ»‘ўӮИӮЗӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBҲЪ–ҜӮЖӮөӮДӮНҒAү«“кӮ©ӮзӮҪӮӯӮіӮсӮМҗlӮӘ“м—mҸ”“ҮӮЙӮнӮҪӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ӢіҲзӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAӮұӮҝӮзӮрҢ©ӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB ӮұӮкӮНҒwҚ‘Ңк“З–{ҒxӮЖӮўӮӨ“ъ–{ҢкӮМӢіүИҸ‘ӮЕӮ·ҒBҲП”C“қҺЎӮӘҢҲӮЬӮй‘OӮЙҠщӮЙ“ҮӮМҺҷ“¶ӮЙ“ъ–{ҢкӮрҒuҚ‘ҢкҒvӮЖӮөӮДӢіӮҰӮжӮӨӮЖӮөҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮұӮМӢіүИҸ‘ӮрҚмӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҠӘ2ӮМ‘ж5үЫҒuғKғbғRғEҒvӮМғyҒ[ғWӮЙӮНӮұӮӨҸ‘ӮўӮДӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ҒuғZғ“ғZғCғmғIғVғGғ’ғ}ғӮғbғeҒ@ғCғbғVғҮғEғPғ“ғҒғCғjғxғ“ғLғҮғEғXғҢғoҒ@ғnғ„ғNғҲғCғjғzғ“ғWғ“ғjҒ@ғiғӢғRғgғKғfғLғ}ғXҘҘҘҒv ӮҪӮҫӮөҒA“ъ–{ҢкӮНӢіӮҰӮзӮкӮДӮа“ъ–{Қ‘җРӮН—^ӮҰӮзӮкӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ҒЎғҸғVғ“ғgғ“‘Мҗ§ ғ|ғCғ“ғgӮЙӮ ӮБӮҪғҸғVғ“ғgғ“‘Мҗ§ӮЙӮВӮўӮДӮЕӮ·ӮӘҒA‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮр’КӮөӮД“ъ–{ӮӘ’ҶҚ‘Ӯв‘ҫ•Ҫ—mӮЙҗiҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЙ‘ОӮөҒAҸ”ҠOҚ‘Ӯ©ӮзӮНӮұӮкӮЬӮЕҢ©ӮҪӮжӮӨӮЙӮіӮЬӮҙӮЬӮИ•sҲАӮв”б”»ӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAғAғWғAҒE‘ҫ•Ҫ—m’nҲжӮЕ“ъ–{ӮрҠЬӮЯӮҪҠЦҢWҚ‘ӮӘ—ҳҠQӮр’Іҗ®ӮөҒAҚs“®ӮЙҳgӮрҗЭӮҜӮйӮҪӮЯӮЙҠJӮ©ӮкӮҪӮМӮӘҒA1921Ғ`22”NӮЙӮ©ӮҜӮДӮМғҸғVғ“ғgғ“үпӢcӮЕӮөӮҪҒB ғҸғVғ“ғgғ“үпӢcӮЕӮН’ҶҚ‘ӮЙҠЦӮөӮДӮЬӮёӢгӮ©Қ‘Ҹр–сӮӘҢӢӮОӮкӮЬӮөӮҪҒB ’ІҲуӮөӮҪӮМӮНҒA•ДҒEүpҒE•§ҒEҲЙҒE—–ҒE’ҶҚ‘ҒEғxғӢғMҒ[ҒAғ|ғӢғgғKғӢҒA“ъ–{ӮМ9Ӯ©Қ‘ӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМ“а—eӮНҒA’ҶҚ‘ӮМҺеҢ ҒA“Ж—§ӮИӮзӮСӮЙ—М“y“IҒAҚsҗӯ“I•Ы‘SӮр‘ёҸdӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҗ·ӮиҚһӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮН’ҶҚ‘ӮМ“Ж—§Қ‘ӮЖӮөӮДӮМ—§ҸкӮр‘ёҸdӮөҒAӮ»ӮМ—М“yӮвҒA—М“y“аӮЕӮМҺx”zҢ Ӯр‘ёҸdӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮөӮДӮаӮӨҲкӮВ‘еӮ«ӮИ“а—eӮӘҒA’ҶҚ‘ӮЙӮЁӮҜӮйҠeҚ‘–ҜӮМӢ@үпӢП“ҷҺеӢ`ӮрҲЫҺқӮ·ӮйӮұӮЖҒAӮЕӮөӮҪҒBӮВӮЬӮиҒAӮ ӮйҚ‘ӮҫӮҜӮӘ’ҶҚ‘ӮЕ“Жҗи“I—ҳҢ Ӯр“ҫӮйӮұӮЖӮНҒAӢ@үпӢП“ҷӮЙ”ҪӮ·ӮйӮЖӮөӮД”Ы’иӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЙӮұӮМҸр–сӮМҚЕ‘еӮМҲУ–ЎӮӘӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ҒB ӮұӮМҸр–сӮМҺпҺ|ӮЙүҲӮБӮД’ҶҚ‘ӮЖ“ъ–{ӮМ‘SҢ ӮӘҢрҸВӮөҒAҺR“ҢҸИӮМӢҢғhғCғcҢ үvӮН’ҶҚ‘ӮЙ•ФҠТӮ·ӮйӮұӮЖҒA“ъ–{ҢRӮН“P•әӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҢҲӮЯӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҒA‘ҫ•Ҫ—mҠCҲжӮЕ—сӢӯӮМ—ҳҢ ӮрӮЁҢЭӮўӮЙҗNӮіӮИӮўӮжӮӨӮЙӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҒAҺlӮ©Қ‘Ҹр–сӮаҢӢӮОӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮН“ъ–{ҒAғAғҒғҠғJҒAғtғүғ“ғXҒAғCғMғҠғXӮМҠФӮЕҢӢӮОӮкӮҪӮаӮМӮЕҒA‘ҫ•Ҫ—mӮМҢ»ҸуҲЫҺқӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ҒЎҗОӢҙ’XҺRӮМҒuҸ¬“ъ–{ҺеӢ`Ғv ӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ӮНғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJӮЖӢҰ’ІӮөӮДҒAҠCҠOӮМ—ҳҢ ӮрҲЫҺқӮ·Ӯй•ыҢьӮрӮЖӮйӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBӮҪӮҫҒAӮұӮӨӮөӮҪүp•ДӮЖӢҰ’ІӮөӮжӮӨӮЖӮўӮӨӮ ӮиӮ©ӮҪӮЙ‘ОӮөӮДҒAҢR•”ӮМ’ҶӮЙӮНүp•ДӮЖ‘ОҢҲӮөӮВӮВ’ҶҚ‘ӮЕӮМ—ҳҢ Ҡg‘еӮрӮНӮ©ӮйӮЧӮ«ӮҫӮЖӮўӮӨҚlӮҰӮрҺқӮВҗlҒXӮӘӮўӮДҒAҚ\‘zӮр—ыӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮұӮӨӮөӮҪҢRӮМҲк•”ӮМҚlӮҰӮЖӮНҗі”Ҫ‘ОӮЙҒAӮ»ӮаӮ»Ӯа“ъ–{ӮӘҠCҠOӮЙ—ҳҢ ӮрҺқӮВӮұӮЖӮрҗ^ӮБҢьӮ©Ӯз”б”»ӮөӮҪҗlӮӘӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМ‘г•\“IӮИҗl•ЁӮӘҗОӢҙ’XҺRӮЕҒA”ЮӮНҒuҸ¬“ъ–{ҺеӢ`ҒvӮрҺе’ЈӮөӮЬӮөӮҪҒB ӮұӮкӮНҒA“ъ–{ӮНҸ¬ӮіӮИҚ‘ӮЕӮўӮўӮЕӮНӮИӮўӮ©ҒAӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒB —бӮҰӮО”ЮӮМҒu‘е“ъ–{ҺеӢ`ӮМҢ¶‘zҒvӮЖӮўӮӨ•¶ҸНӮЙӮНҺҹӮМӮжӮӨӮИҲкҗЯӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB Ғu’©‘NҒA‘дҳpҒAҠ’‘ҫҒA–һҸBӮЖү]ӮӨ”@Ӯ«ӢНӮ©ӮОӮ©ӮиӮМ“y’nӮрҠьӮВӮйӮұӮЖӮЙҲЛӮиҚL‘еӮИӮйҺx“ЯӮМ‘S“yӮрүд—FӮЖӮөҒAҗiӮсӮЕ“Ң—mӮМ‘S‘МҒA”ЫҒAҗўҠEӮМҺгҸ¬Қ‘‘S‘МӮрүд“№“ҝ“IҺxҺқҺТӮЖӮ·ӮйӮұӮЖӮНҒA”@үҪӮОӮ©ӮиӮМ—ҳүvӮЕӮ ӮйӮ©ҢvӮи’mӮкӮИӮўҒBҒcҒv ӮВӮЬӮиҗОӢҙ’XҺRӮНҒu“ъ–{җlӮНҗј—m—сӢӯӮМҗ^Һ—ӮрӮ·ӮйӮМӮрӮвӮЯӮДҒAҗA–Ҝ’nӮвҗЁ—НҢ—Ӯр•ъҠьӮ·ӮйӮұӮЖӮрҺе’ЈӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮӨӮ·ӮкӮОҢR”хӮа•s—vӮЙӮИӮйӮЖӮўӮӨ’Қ–ЪӮ·ӮЧӮ«ӮұӮЖӮаҸqӮЧӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮНӮЖӮДӮаҸ¬ӮіӮИҗәӮЕ“–ҺһӮНӮЩӮЖӮсӮЗ–іҺӢӮіӮкӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮӨӮөӮҪҺе’ЈӮӘӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮа–YӮкӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB ҒЎ‘еҗнҢiӢC ҚЕҢгӮМғ|ғCғ“ғgҒA‘еҗнҢiӢCӮЕӮ·ҒBӮ»ӮкӮЕӮНӮұӮкӮЙӮВӮўӮДүf‘ңӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙӮжӮБӮДҒA“ъ–{ӮНӮ»ӮкӮЬӮЕӮЖҲк•ПӮөӮДҚDҢiӢCӮЖӮИӮиӮЬӮөӮҪҒBҒu‘еҗнҢiӢCҒvӮЕӮ·ҒB җўҠE“IӮИ‘DӮМ•s‘«Ӯ©ӮзҒA‘ў‘DӢЖӮвҠCү^ӢЖӮӘ’ҳӮөӮӯҗLӮСӮЬӮөӮҪҒB ”Ә”Ұҗ»“SҸҠӮИӮЗӮр’ҶҗSӮЖӮөӮҪ“SҚ|ӢЖӮвӢ@ҠBҚHӢЖҒBӮ»ӮкӮЬӮЕ—A“ьӮЙ—ҠӮБӮДӮўӮҪү»ҠwҒA–т•iҚHӢЖӮИӮЗӮа”ӯ’BҒBҚHӢЖҚ‘ӮЖӮөӮДӮМҠо‘bӮр’zӮ«ӮЬӮөӮҪҒB •xҺRҢ§“Ң•”Ӯр—¬ӮкӮйҚ••”җмӮЕӮ·ҒBӮұӮұӮЕӮН‘еҗіҺһ‘гӮЙҗ…—Н”ӯ“dҸҠӮӘҢҡҗЭӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҺһ‘гҒAӢ@ҠBӮМ“®—НӮНҒAҸцӢCӮ©Ӯз“dӢCӮЙ•ПӮнӮиҒAӮ»ӮкӮӘ“dҢ№ӮМҠJ”ӯҒA“БӮЙҗ…—Н”ӯ“dӮЙ”ҸҺФӮрӮ©ӮҜӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎҗ»Һ…ӢЖӮМ”ӯ“W ‘еҗнҢiӢCӮЙӮжӮБӮДҒAӮЯӮҙӮЬӮөӮўҗЁӮўӮЕҗ¬’·ӮөӮҪӮМӮӘҒAҗ¶Һ…ӮрҚмӮйҗ»Һ…ӢЖӮЕӮ·ҒB“ъ–{Ҡe’nӮЕ—AҸoӮЙҢьӮҜӮҪҗ¶Һ…ӮМҗ¶ҺYӮӘҗ·ӮсӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB үEӮМҺКҗ^ӮНҒA’·–мҢ§ӮМҗz–KҢО”ИӮЙ—§Ӯҝ•АӮФҗ»Һ…ҚHҸкӮЕӮ·ҒB ӮұӮұӮНҒA–ҫҺЎҺһ‘гӮ©Ӯзҗ»Һ…ӢЖӮӘҗ·ӮсӮИ’nҲжӮЕҒAҒuҗz–Kҗз–{ҒvӮЖҢҫӮнӮкӮйӮЩӮЗҒAҚHҸкӮМүҢ“ЛӮӘ—§Ӯҝ•АӮсӮЕӮөӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕӮНҒAҺеӮЙ”_‘әӮМ•nӮөӮўҸ—җ«ӮҪӮҝӮӘҸ—ҚHӮЖӮИӮиҒAҗ»Һ…ҚHҸкӮЕӮЬӮдӮ©ӮзҺ…ӮрӮЖӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBҳJ“ӯӮНҒA1“ъ14ҺһҠФӮЙӮаӢyӮФӮаӮМӮЕӮөӮҪҒB Ҹ—ҚHӮМ’АӢаӮМӢLҳ^ӮӘҺcӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒB’АӢаӮНҒAӮЖӮБӮҪҺ…ӮМҺҝӮв—КӮЙӮжӮБӮДҢҲӮЬӮиӮЬӮөӮҪҒB100ү~ҲИҸгӮрүТӮ®Ҹ—ҚHӮНҒAҚHҸк“ҜҺmӮЕҺжӮиҚҮӮўӮЙӮИӮйӮұӮЖӮаӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒAүЯҚ“ӮИҳJ“ӯӮЕ•aӢCӮЙӮИӮБӮДҢМӢҪӮЙӢAӮіӮкӮҪӮиҒA–ҪӮр—ҺӮЖӮ·Ҹ—ҚHӮҪӮҝӮаҸӯӮИӮӯӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB ҒЎҗ»Һ…ӢЖ ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнҠъӮМ“ъ–{ӮМҢoҚП”ӯ“WӮЙӮВӮўӮДҒAҚ¶ӮМғOғүғtӮрҢ©ӮйӮЖ•ӘӮ©ӮйӮжӮӨӮЙҒA1915”NӮІӮлӮ©Ӯз‘қӮҰҒA15”NӮ©Ӯз18”NӮЬӮЕӮН—AҸoӮӘ—A“ьӮрҸгүсӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮМҺһҠъӮНӮҝӮеӮӨӮЗ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮМҠФӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮЬӮЕӮМ“ъ–{ӮМ–fҲХӮНҒA–ИүФӮрғAғҒғҠғJӮвҒAғCғMғҠғX—МӮҫӮБӮҪғCғ“ғhӮ©Ӯз—A“ьӮөӮҪӮиҒA“SӮвӢ@ҠBӮр—A“ьӮөӮҪӮҪӮЯӮЙҗФҺҡҢXҢьӮӘ‘ұӮўӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө‘еҗнӮӘҺnӮЬӮйӮЖҒAғAғWғAҢьӮҜӮМ–ИҺ…Ӯв–ИҗD•ЁҒAӮ»ӮөӮД“ъ–{ҲИҸгӮЙ‘еҗнҢiӢCӮЙ•ҰӮўӮҪғAғҒғҠғJҢьӮҜӮМҗ¶Һ…ӮМ—AҸoӮӘ‘еӮ«ӮӯҗLӮСҒA–fҲХҚ•ҺҡӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҢӢүК“ъҳIҗн‘ҲҲИҚ~ӮМҚВ–ұӮНүрҸБӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB –Ӣ––ҲИ—ҲҒAҗ¶Һ…ӮН—AҸo•iӮМғgғbғvӮр‘–Ӯи‘ұӮҜӮДӮ«ӮЬӮөӮҪҒBҗ¶Һ…ӮНҢҙ—ҝӮрҚ‘“аӮЕӮЬӮ©ӮИӮҰӮЬӮ·Ӯ©ӮзҒA—AҸoӮ·ӮкӮОӮ·ӮйӮЩӮЗҒAҠOүЭӮрүТӮ®ӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮөӮҪҒB“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДӢMҸdӮИ—AҸo•iӮҫӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎҸ—ҚHӮМҳJ“ӯҠВӢ« Ҹ—ҚHӮҪӮҝӮМҳJ“ӯҺһҠФӮЕӮ·ӮӘҒA•\ӮЙҺҰӮөӮҪӮМӮН–ҫҺЎ––ҠъӮМ’·–мҢ§ӮМҸкҚҮӮЕҒA’©5Һһ15•ӘӮЙӢNҸ°ӮөӮДҒA5Һһ40•ӘӮЙҸAӢЖӮөӮЬӮ·ҒB“r’ҶҗHҺ–ӢxҢeӮрӢІӮЭӮИӮӘӮзҒA–йӮН9ҺһӮЬӮЕҺdҺ–ӮЕӮ·ҒB ‘SҚ‘“IӮЙӮНҲк“ъ10Ғ`14ҺһҠФӮЖӮўӮБӮҪӮЖӮұӮлӮЕҒAҢ»ҚЭӮМҠҙҠoӮ©ӮзӮ·ӮйӮЖ’·ҺһҠФҳJ“ӯӮЕӮөӮҪҒB Ҳк•ыҒA–ИүФӮ©ӮзҺ…ӮрҚмӮй–aҗСҚHҸкӮМҸ—ҚHӮҪӮҝӮЙӮНҒAҗ[–йҳJ“ӯӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB”ЮҸ—ӮҪӮҝӮМӮұӮЖӮНҒAӮұӮұӮЙӮ ӮйҒwҸ—ҚHҲЈҺjҒxӮЖӮўӮӨ–{ӮЙ•`Ӯ©ӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮН1925”NӮЙҚЧҲдҳaҠм‘ ӮЖӮўӮӨҗlӮӘ’ҳӮөӮҪ–{ӮЕӮ·ҒB ӮұӮМ–{ӮМҚЕҢгӮМӮЖӮұӮлӮЕ”ЮӮНҒuҸ—ҚH–в‘иӮұӮ»ӮНҺРүпҒAҳJ“ӯҒAҗl“№ҸгӮ ӮзӮдӮйүр•ъ–в‘иӮМҚЕӮаҗж’[ӮЙҒA’ҶҗSӮЙ’uӮўӮДҚlӮЦӮзӮкӮЛӮОӮИӮзӮК–}ӮДӮМҸрҢҸӮрӢп”хӮөӮДӢҸӮйҒBҒvӮЖӮўӮБӮДӮўӮЬӮ·ҒBӮұӮӨӮөӮҪҸ—ҚHӮҪӮҝӮӘ“–ҺһӮМ“ъ–{ҢoҚПӮрҺxӮҰӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB ҒЎ“sҺsӮМӢߑ㕶ү» ‘еҗнҢiӢCӮЖӮЖӮаӮЙҒA“sҺsҗlҢыӮН‘қүБӮөҒA“ҢӢһӮН200–ңӮрүzӮҰӮйӮЩӮЗӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB“sҺsӮЕӮНғTғүғҠҒ[ғ}ғ“ӮвӮ»ӮМүЖ’лӮр’SӮӨҺе•wҒAӮ ӮйӮўӮНҒuҗEӢЖ•wҗlҒvӮЖҢДӮОӮкӮйҺ––ұҗEӮИӮЗӮМҸ—җ«ӮӘ‘қӮҰӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB‘еҗіӮМҸIӮнӮиӮ©ӮзҸәҳaӮМӮНӮ¶ӮЯӮЙӮ©ӮҜӮДӮМ“sҺsӮМӮжӮӨӮ·ӮрҢ©ӮДӮЭӮЬӮөӮеӮӨҒB ҺКҗ^ӮН‘еҗіҺһ‘гӮМ“ҢӢһӮЕӮ·ҒB “sҺsӮЕӮНҒAҺ©“®ҺФӮвғfғpҒ[ғgӮЖӮўӮБӮҪҗј—mӮМӢߑ㕶ү»ӮӘҗgӢЯӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB үШӮвӮ©ӮИ—m•һӮрҗgӮЙӮВӮҜӮДҠXӮр•аӮӯҸ—җ«ӮҪӮҝӮНҒAғӮғ_ғ“ғKҒ[ғӢҒEҒuғӮғKҒvӮЖҢДӮОӮкӮЬӮөӮҪҒB үEӮНҒAғҢғXғgғүғ“ҒBӮұӮМӮұӮлҒAҗј—m—ҝ—қӮНғҢғXғgғүғ“ӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒAүЖ’лӮМҗH‘мӮЙӮаҚLӮӘӮБӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒB ‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮр’КӮөӮД“ъ–{ӮН–c’ЈӮөӮДӮўӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮ»ӮМҚЫҒAғCғMғҠғXҒAғAғҒғҠғJӮЖӮМ—ҳҠQӮМ’Іҗ®ӮӘ•K—vӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒA–c’ЈӮөӮДӮўӮБӮҪҗжӮМ’ҶҚ‘ӮИӮЗӮЖӮМ–ҖҺCӮӘ”рӮҜӮзӮкӮИӮў–в‘иӮЕӮаӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮсӮИ’ҶӮЕҒAҗжӮЩӮЗҢ©ӮҪӮжӮӨӮЙ“ъ–{ӮН”’җlӮМҗ^Һ—ӮрӮвӮЯӮДҒAҗA–Ҝ’nӮв’ҶҚ‘ӮЕӮМ—ҳҢ ӮрҺМӮДӮйӮЧӮ«ӮҫӮЖӮМҺе’ЈӮа‘¶ҚЭӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪ‘Ҫ—lӮИҲУҢ©ӮвүВ”\җ«ӮӘ‘¶ҚЭӮөӮҪӮЖӮұӮлӮЙҒA‘еҗіӮЖӮўӮӨҺһҠъӮрҠwӮсӮЕӮдӮӯҚЫӮМ–Ј—НӮӘӮ ӮйӮжӮӨӮЙҺvӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҗҙҗн‘ҲҒ@–ҫҺЎ27”N8ҢҺ1“ъҒ`–ҫҺЎ28”N3ҢҺ10“ъ | |
|
җјүў—сӢӯӮМ“Ң—mҗN—ӘӮМҚЕ’ҶӮЙӮ ӮБӮДҒA“ъҗҙ—јҚ‘ӮМҠp’ҖӮНӮ©ӮкӮзӮЙӢҷ•vӮМ—ҳӮр—^ӮҰӮйӮЙүЯӮ¬ӮИӮўҒB“ъҗҙӮӘ‘P—Ч’сҢgӮМӮҪӮЯӮЙӮН’©‘NӮЙӮЁӮҜӮй“ъҗҙ—јҚ‘ӮМ•ҙ‘ҲӮрҚӘҗвӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘӢ}–ұӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ–ҫҺЎ18”N4ҢҺӮЙҒu“V’ГҸр–сҒvӮӘ’чҢӢӮіӮкӮҪӮӘҒA’чҢӢӮ©Ӯз–с10”NҢгӮЙҗ¶ӢNӮөӮҪ“ъҗҙҗн‘ҲӮНҒAҗҙҚ‘ӮӘӮұӮМҸр–сӮЙҲб”ҪӮөӮҪӮұӮЖӮӘҢҙҲцӮЖӮИӮБӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB
‘ҰӮҝҒAҸ@ҺеҢ ӮрҲЫҺқӮө’©‘NӮН‘®Қ‘ӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮө‘ұӮҜӮйҗҙҚ‘ӮЖҒA’©‘NӮр“Ж—§ӮіӮ№ӮұӮкӮЖ’сҢgӮөӮД”ӯ“WӮМ“№ӮрҠJ‘сӮөӮжӮӨӮЖӮ·Ӯй“ъ–{ӮЖӮМҚ‘ҚфӮМҸХ“ЛӮЕӮ ӮйӮЖ“ҜҺһӮЙҒAҺ©—НӮЕҺыҸEӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪ’©‘N“а•”ӮМҚ¬—җӮЙӮжӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ©ӮӯӮөӮД–ҫҺЎ27”NӮЙ–u”ӯӮөӮҪ“ъҗҙҗн‘ҲӮНҗVӢ»Қ‘“ъ–{ӮӘҺnӮЯӮДҢoҢұӮөӮҪ‘ОҠOҗн‘ҲӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯа‘ҠҺиӮНҳVӮўӮҪӮиӮЖӮНӮўӮҰҒu–°ӮкӮйҺӮҺqҒvӮЖӢ°ӮкӮзӮкҒAҗlҢыҒE”Еҗ}ӮЖӮаүдӮМ10”{ӮНӮ ӮлӮӨӮ©ӮЖӮўӮӨ’ҙ‘еҚ‘ӮМҗҙӮЕӮ ӮйҒBҚ‘–ҜӮН•sҲАӮЙңЙӮ«ӮИӮӘӮзӮаҲЫҗVӮЕ’zӮўӮҪӮОӮ©ӮиӮМҗVҗ¶Қ‘үЖӮМ–Ҫү^Ӯр“qӮөӮДҸгүәҒEҠҜ–ҜҗSӮрҲкӮВӮЙӮөӮДҚ‘“пӮЙӮ ӮҪӮиҒAҳAҗнҳAҸҹӮМӮӨӮҝӮЙҗн‘Ҳ–Ъ“IӮрҠ®җӢӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҗнӮўӮНӮұӮкӮЕҸIӮнӮБӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBҸh”NӮМ‘z’и“GҚ‘ғҚғVғAӮЖӮН‘Ғ”УҗнӮнӮҙӮйӮрӮҰӮИӮўү^–ҪӮӘ‘ТӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ғu‘еҠШҚ‘ҒvӮМҚ‘ҚҶӮНҒAҗј—п1897”N(–ҫҺЎ30”NҒEҢх•җҢі”N)10ҢҺ12“ъӮМҚc’й‘ҰҲКҺ®Ӣ“ҚsӮМ“ъӮ©ӮзӢNӮұӮйҒBӮ»ӮкҲИ‘OӮНҒu’©‘NҒvӮЕӮ ӮйҒBҸ]ӮБӮДҒuҗӘҠШҳ_ҒvӮЖӮ©ҒA–ҫҺЎ9”N2ҢҺ’ІҲуӮМҸCҢрҸрӢKӮрҒu“ъҠШҸCҢрҸрӢKҒvӮЖҢДӮФӮМӮНҢө–§ӮЙӮНҗіӮөӮӯӮИӮўҒB–{ҚҖӮЕӮНҸгӢLӢNҢ№ӮЙҠоӮГӮ«Ғu’©‘NҒvҒuҠШҚ‘ҒvӮрӢж•КӮөӮДҢДҸМӮ·ӮйҒBҒ@ |
|
| “ъҗҙҗн‘Ҳ1 | |
|
ҒЎҗӘҠШҳ_ӮМ‘д“ӘӮЖ‘дҳpҸo•ә
“ъ–{ӮН–Ӣ––ҠъӮЙҗј—m11ғJҚ‘ӮЖҸр–сӮрҢӢӮсӮЕӮўӮИӮӘӮзҒAӢЯ—ЧӮМ’ҶҚ‘ҒE’©‘NӮЖӮНҗіҺ®Қ‘ҢрӮр’чҢӢӮөӮДӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB –ҫҺЎҲЫҗVӮМӮМӮҝҗVҗӯ•{ӮН’©‘NӮЖӮМҸCҢрӮрҗ}ӮлӮӨӮЖӮөҒA–ҫҺЎҢі”N12ҢҺҒ@‘О”n”ЛҺеҒE‘vӢ`’BӮЙ–ҪӮ¶ӮДҸ‘Ӯр’©‘NӮЙ‘—ӮБӮҪӮӘҒAҺһӮМҗЫҗӯӮЕӮ Ӯй‘еү@ҢNӮНҚҪҚ‘ҺеӢ`ӮрҚМӮБӮД“ъ–{ӮМ—vӢҒӮрӢ‘ӮсӮҫҒBӮИӮЁӮаҗӯ•{ӮН’©‘NӮЖӮМҸCҢрӮр–]ӮсӮЕҠOҢр“IҢрҸВӮрҸdӮЛӮйӮаҸнӮЙ”сӢҰ’І“IӮИ‘Ф“xӮЕүдӮЙ‘ОӮөӮҪҒBӮұӮМӮҪӮЯ’©‘NӮМ–і—зӮрӢ–Ӯө“пӮўӮЖӮ·ӮйҗӘҠШҳ_ӮӘҠӘӮ«ӢNӮұӮиҒAӮМӮҝӮМҗј“мӮМ–рӮЙҢqӮӘӮБӮҪҒBӮҫӮӘ“––КӮМ“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДӮН”ј“Ү–в‘иӮжӮиӮа–k•ыүЪҲО’nӮЕӮМ‘ОғҚғVғA–в‘иӮМ•ыӮӘҸd—vӮЕӮ ӮиҒAүҪӮжӮи•s•Ҫ“ҷҸр–сӮМүьҗіӮӘҚ‘ҚфӮЖӮөӮДҚЕҸd—vүЫ‘иӮЕӮ ӮБӮҪҒB –ҫҺЎ4”N11ҢҺҒ@—®Ӣ…ӮМ–Ҝ69–јӮӘ‘дҳp“м’[’n•ыӮЙ•Y’…ӮөҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ54–јӮӘҗ¶”Ч(“y–Ҝ)ӮМӮҪӮЯӢsҺEӮіӮкҒA3–јӮН“MҺҖҒA12–јӮМӮЭӮӘҗhӮӨӮ¶ӮД“ҰӮкӢҺӮБӮҪҒBӮЬӮҪ–ҫҺЎ6”N3ҢҺӮЙӮН”х’ҶҒEүӘҺRӮМ–Ҝ4–јӮӘ‘дҳp“Ң“мҠЭӮЙ•Y’…ӮөӮД—Ә’DӮіӮкӮйҺ–ҢҸӮӘӢNӮұӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҺуӮҜӮДҗӯ•{ӮНҒAҠO–ұӢЁ•ӣ“ҮҺнҗbӮрҗҙҚ‘ӮЙ”hҢӯӮө’k”»ӮіӮ№ӮҪӮЖӮұӮлҗҙҚ‘ӮНҒA‘дҳpӮНҗҙҚ‘ӮМ—МҲжӮЕӮНӮИӮӯҒAү»ҠOӮМ–ҜӮЕӮ ӮиҠЦ’mӮ·ӮйӮЖӮұӮлӮЕӮНӮИӮўҒAӮЖӮөӮДүдӮӘҚRӢcӮЙӮНүһӮ¶ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ–ҫҺЎ7”N4ҢҺ4“ъҒ@җӯ•{ӮН—ӨҢR’ҶҸ«җјӢҪҸ]“№Ӯр‘дҳp”Ч’nҺ––ұ“s“ВӮЙ”CӮ¶ҒA—ӨҢRҸӯҸ«’JҠұҸйҒAҠCҢRҸӯҸ«җФҸј‘Ҙ—ЗҲИүә3658–јӮрҲИӮБӮДҸoҗӘӮМҢRӮр‘дҳpӮЙ‘—ӮБӮҪҒBҚ“”MӮЖ•a–ӮӮЖҗнӮўӮВӮВҗ¶”ЧӮМ–{Ӣ’ӮрҸХӮ«ҒA‘ҠҺҹӮўӮЕ“GӮрҚ~ӮөӮВӮўӮЙ‘дҳp‘S“ҮӮр•Ҫ’иӮөӮҪҒBҗҙҚ‘ӮН“ъ–{ӮМҸo•әӮр”с“пӮө—јҚ‘ӮМҠФӮНҢҜҲ«ӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒAүp•§ӮМ’І’вӮЙӮжӮБӮДҗҙҚ‘ӮН“ъ–{ӮМҸo•әӮрӢ`Ӣ“ӮЖ”FӮЯӮҪҒBүдӮӘҚ‘ӮН‘дҳp—М—LӮНҲУҗ}Ӯ№ӮёҒA‘SҢRӮр“PҺыҢг12ҢҺүәҸ{ӮЙ’й“sӮЙҠMҗщӮөӮҪҒB–{җн–рӮМ“ъ–{ҢRӮМ‘№ҠQӮНҒAҗнҺҖ12ҒAҗнҸқ17ҒAҗн•aҺҖ531ӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМ‘дҳpҗӘ“ў(җӘ”ЧӮМ–р)ӮНҠg‘еӮ·ӮйӮұӮЖӮаӮИӮӯҸ¬җн‘ҲӮЕҸIӮнӮБӮҪӮӘҒA“ъҗҙӮМҸХ“ЛӮНҠщӮЙ–ҫҺЎҸү“ӘӮЙ‘kӮБӮДҢ»ӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚ]үШ“ҮҺ–ҢҸҒ@
җӘҠШҳ_‘ҲӮӘҲк’i—ҺӮөӮҪӮМӮҝӮа“ъ–{җӯ•{ӮНӮИӮЁҸCҚDӮМҠу–]ӮрҺМӮДӮИӮ©ӮБӮҪҒB–ҫҺЎ8”NҒ@’©‘NҚ‘үӨ—ӣаҶ‘еүӨӮН23ҚОӮЙӮИӮиҒAҺ©ӮзҚ‘җӯӮрӮЭӮй—§ҸкӮЖӮИӮБӮҪҒB•ЫҺзҺеӢ`ҺТӮЕқөҲОҳ_ҺТӮМ—ӣ‘еүӨӮМҗ¶•ғҒEҗЫҗӯ‘еү@ҢNӮМүeӢҝ—НӮа’бүәӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮи’©‘NӮМҠOҢр•ыҗjӮаҲк•ПҒAҸCҚDӮМҲУӮр’КӮ¶ӮйӮЬӮЕӮЙӮИӮБӮҪҒB—јҚ‘ӮМҸCҚDӮӘҺnӮЬӮйӮ©ӮЙҢ©ӮҰӮҪ–оҗжҒAүB“ЩӮөӮДӮўӮҪ‘еү@ҢNӮНӢһҸйӮЙӮНӮўӮиҒAҚДӮСҗӯҺЎӮМҺАҢ ӮрҲ¬ӮБӮҪӮМӮЕҒAҠOҢр•ыҗjӮН“с“]ӮөҒAҸCҚDӮӘӮЕӮ«ӮИӮӯӮИӮБӮҪӮОӮ©ӮиӮЕӮНӮИӮӯҒA•sҚKӮЙӮөӮДҚ]үШ“ҮҺ–ҢҸӮӘ“Л”ӯӮөӮҪҒB –ҫҺЎ8”N5ҢҺ20“ъҒ@ҢRҠНҒuү_—gҒv(ҠН’·ҲдҸг—ЗҠ]ҸӯҚІ)ӮӘ’©‘NӢЯҠCӮМҗ…ҳHӮр‘Ә—К’ҶҒAҚ]үШ“Ү–C‘дӮМ’©‘N•әӮ©Ӯз–CҢӮӮрҺуӮҜӮҪҒBҒuү_—gҒvӮН’fҢЕүһҗнӮөӮД–C‘дӮрҗи—МҒAүiҸ@ҸйӮрҸДӮ«’©‘N•ә30—]–јӮр“|ӮөҒAүО–C38–еӮ»ӮМ‘јӮр’DӮБӮДӢA“ҠӮөӮҪҒBӮұӮМҗ퓬ӮЕ‘№ҠQӮНҗ…•ә1–јҗнҺҖҒA2–јӮӘ•үҸқӮөӮҪҒB–ҫҺЎ9”N1ҢҺҒ@ҺQӢc—ӨҢR’ҶҸ«Қ•“cҗҙ—ІӮр“Б–Ҫ‘SҢ ӮЖӮөӮД’©‘NӮЙ”hҢӯҒA’©‘NӮЖҢрҸВӮр‘ұӮҜӮҪҒBҢрҸВӮН“пҚqӮөӮҪӮӘ2ҢҺ27“ъҒ@’©‘Nҗӯ•{ӮНҚЯӮрҺУӮөҒA“ъ–{ӮМ—vӢҒӮр—eӮкӮДҚ]үШ“ҮҸр–с12ҸрӮрҢӢӮСҒAӮЖӮаӮ©ӮӯҸCҚDӮН•ңҠҲӮөӮҪҒB“ъ‘NӮӘҸCҚDӮрҗвӮБӮҪ•¶ү»8”N(1811)Ӯ©Ӯз65”N–ЪӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМҸр–сӮМҚңҺqӮНҒA’©‘NӮӘ“Ж—§Һ©ҺеӮМҚ‘үЖӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҠm”FӮөҒA“ъ‘N—јҚ‘ҳaҗeӮМҺАӮр•\Ӯ·ӮйӮұӮЖӮр–сӮөӮҪӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮйӮЙҗҙҚ‘ӮН’©‘NӮН‘®Қ‘ӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮөҒA“ъ–{ҒE’©‘N—јҚ‘ҠФӮМҸр–сӮр”jҠьӮ·ӮйӮжӮӨӮЙ—vӢҒӮөӮДӮ«ӮҪҒB“ъ–{ӮНӮұӮкӮрӢ‘”ЫӮөӮҪӮӘҒAүҪӮзӮМүрҢҲӮрҢ©ӮИӮўӮЕҺһҠФӮӘҢoүЯӮөӮДӮўӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’©‘NӢһҸйӮМ•ПҒ^җpҢЯӮМ•ПҒ@
–ҫҺЎ9”NӮМҚ]үШ“ҮҸр–сӮЙӮжӮБӮД“ъ–{ӮН’©‘NӮрҺ©Һе“Ж—§ӮМҚ‘үЖӮЖ”FӮЯӮҪҒB’©‘NӮЕӮМҸр–с’чҢӢӮМҢҙ“®—НӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮӘҠJү»“}ӮЖӮўӮӨӢЯ‘гү»ӮЙҲУ—~“IӮИҗЁ—НӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮН“ъ–{ӮЙӮИӮзӮБӮД“аҗӯӮрүьҠvӮөҒAӢЯ‘гҚ‘үЖӮЦӮМ’E”зӮрҗ}ӮлӮӨӮЖӮ·ӮйӮаӮМӮЕҒA•КҺ}‘аӮЖҢДӮОӮкӮй“ъ–{ҢRҗlӮМҺw“ұӮЙӮжӮйҗVҺ®ҢR‘аӮМҲзҗ¬Ӯв“ъ–{ӮЦӮМҺӢҺ@’cӮИӮЗӮӘҗПӢЙ“IӮЙҚsӮнӮкҒA‘еү@ҢNӮз•ЫҺз”hӮр’ЗӮўҒAүӨӮМдnүЖҒEи{ҺҒҲк‘°ӮЖҢӢӮсӮЕҗӯ•{ӮМҸd—vӮИ’nҲКӮрҗиӮЯҒAҺАҢ ӮрҲ¬ӮиӮВӮВӮ ӮБӮҪҒB •КҺ}‘аӮӘ—DӢцӮіӮкӮй‘гӮнӮиӮЙӢҢҺ®ҢR‘аӮӘ—вӢцӮіӮкӮйӮМӮН’vӮө•ыӮӘӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙ”әӮӨ”ЮӮзӮМ•s–һӮМ‘қ’·ӮЙүБӮҰҒAӢӢ—^ӮМ•s•ҘӮўҒA—ЖҗHӮМ•sҗіҺ–ҢҸӮӘҸdӮИӮБӮДҒA–ҫҺЎ15”N(1882)7ҢҺ20“ъҗpҢЯӮМ•П(ӢһҸйӮМ•П)ӮӘ–u”ӯӮөӮҪҒB200—]–јӮМ’©‘N•әӮЙӮжӮйғNҒ[ғfғ^Ғ[ӮН–\–ҜӮӘүБӮнӮи2000җlҲИҸгӮМҗЁ—НӮЖӮИӮиүӨӢ{ӮЙ—җ“ьҒAүӨӮЖүӨҺqӮрҗ¶ӮҜ•ЯӮиӮЙӮөҒAи{ҺҒҲк‘°ӮрӢsҺEӮөӮҪҒB‘еү@ҢNӮНӮұӮМӢ@Ӯр“ҰӮіӮё“ъ–{җlӮМ’З•ъӮрҗ}ӮиҒA”hҢӯӢіҠҜҒE–x–{—з‘ўҚH•ә’ҶҲСӮрӮНӮ¶ӮЯ6җlӮМ“ъ–{җlӮӘҺEҠQӮіӮкӮҪҒB“ъ–{ҢцҺgҠЩӮаҸДӮ©ӮкҒAүФ–[Ӣ`ҺҝҢцҺgӮзӮНҸdҲНӮр“Л”jӮөӮДҗmҗмӮЙ“ҰӮкҒAүpҚ‘ҢRҠНӮЙҺы—eӮіӮкӮДҗhӮӨӮ¶ӮДӢAҚ‘Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB үФ–[ҢцҺgӮ©ӮзӮМ•сҚҗӮрҺуӮҜӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮНҒAҚ•“cҗҙ—ІӮМӢӯҚdҳ_ӮЖҺRгp—L•ьӮМҗTҸdҳ_ӮӘӮФӮВӮ©ӮиҒAҢӢӢЗҠOҢрҢрҸВӮрүҮҢмӮ·ӮйӮҪӮЯҸӯҗ”ӮМ•ә—НӮМӮЭ”hҢӯӮ·ӮйҗTҸdҳ_ӮрҚМӮБӮҪҒB8ҢҺ20“ъӢһҸйӮЙ–ЯӮБӮҪүФ–[ҢцҺgӮНҒAҢцҺ®ҺУҚЯҒA‘№ҠQ”…ҸһҒA”ЖҗlҠЦҢWҺТӮМҸҲ”ұӮИӮЗ6Ӯ©ҸрӮр—vӢҒӮөӮҪҒBҚДӮСҺАҢ ӮрҲ¬ӮБӮҪ‘еү@ҢNӮНүҮ•әӮрҗҙҚ‘ӮЙӢҒӮЯӮДӮЁӮиҒAүс“ҡӮН’xӮкӮҪҒBӮЬӮҪҺR’ҶӮЙ“ҰӮкӮДӮўӮҪи{”ЬӮНҒAҺR’ҶӮ©Ӯз–§ҺgӮр‘—ӮиӮ·ӮЭӮвӮ©ӮЙҗҙҚ‘ӮЙӢ~ҚП•ЫҢмӮрҗҝӮӨӮжӮӨӮЙҠ©ӮЯӮҪҒBи{ҺҒҲк‘°ӮНҒA‘еү@ҢNӮЖ‘О—§ӮөӮҪӮ©ӮзӮұӮ»“ъ–{Ӯр”wҢiӮЖӮ·ӮйҠJү»“}ӮЖ’сҢgӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҗЁ—НҲЫҺқӮМӮҪӮЯӮЙӮН“ъ–{ӮжӮиӮаӢӯ‘еӮИҗҙҚ‘ӮМ—НӮЙҲЛ‘¶ӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒBҢҫӮўҠ·ӮҰӮкӮОҒAҗҙҚ‘ӮН‘еү@ҢNӮЖи{ҺҒҲк‘°ӮрҚIӮЭӮЙӮ ӮвӮВӮиҒAҺАҺҝҸгӮМ‘®Қ‘ӮЖӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮМҗҙҚ‘ӮНҒA’©‘NӮ©ӮзӮМ—vҗҝӮрҺуӮҜӮД—Ө•әӮЖҢRҠН6җЗӮр”hҢӯӮөҒAӢЩ’ЈӮӘҚӮӮЬӮБӮҪӮӘҒA8ҢҺ30“ъҒ@ҒuҚП•Ё•Я(ӮіӮўӮаӮВӮЩ)Ҹр–сҒvӮӘ’ІҲуӮіӮкҒA“ъ–{ӮН’©‘NӮ©ӮзҺУҚЯ”…ҸһӮМ‘јӮЙҢцҺgҠЩҢмүqӮМӮҪӮЯӮМ’“•әҢ Ӯр“ҫӮҪҒBҢрҸВӮЙӮ ӮҪӮиҗҙҚ‘ӮНҒAҲЛ‘RҠШҚ‘ӮН‘®Қ‘ӮЕӮ ӮйӮЖҺе’ЈӮө•әӮр’©‘NӮЙ’““ФҒA‘еү@ҢNӮр—}—ҜҒEҲш‘ЮӮіӮ№ҒA‘еӮўӮЙ’©‘NӮМ“аҗӯӮЙҠұҸВӮөӮҪҒBӮұӮМҺ–ҢҸӮЙӮжӮиҒAүдӮӘҗӯ•{“БӮЙҢR“–ӢЗҺТӮН‘ОҠOҢрҸВӮМ—eҲХӮЕӮИӮўӮұӮЖӮрӢӯӮӯ”FҺҜӮіӮ№ӮзӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’©‘NӢһҸйӮМ•ПҒ^Қbҗ\ӮМ•ПҒ@
җpҢЯӮМ•ПҢгӮМ’©‘NӮНҒAӢһҸй“аӮЕӮН“ъ–{•әӮЖҗҙҚ‘•әӮӘ‘Ҡ‘ОӣіӮөӮДӮЁӮиҒAҗӯ•{“аӮЕӮН•ЫҺз”hӮЖүьҠv”hӮМ‘О—§ӮӘ‘ұӮўӮДӮўӮҪҒB•ЫҺз”hӮНҒAҠJү»“}ӮЖӮЮӮ·ӮсӮЕ‘еү@ҢNӮр’З•ъӮөӮҪи{ҺҒҲк‘°Ӯр’ҶҗSӮЖӮ·ӮйҺ–‘е“}ӮЕҒAҗpҢЯӮМ•ПӮЕҗҙҚ‘ӮМүҮҸ•ӮЕҗӯҢ ӮЙүс•ңӮ·ӮйӮЖӮЬӮ·ӮЬӮ·‘еҚ‘ӮЙҲЛ‘¶Ӯ·Ӯй•K—vӮрҠҙӮ¶ҒAҺзӢҢ”hӮЙ“]Ӯ¶ӮДӮўӮҪҒB•\–КҸгӮНҗҙҚ‘ӮМҺxҺқӮрӢВӮ¬ҒA— –КӮЕӮНҗҙҚ‘ӮМӮЭӮЙҲЛ‘¶Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘ•ЫҗgӮЙӮН•s—ҳӮИӮұӮЖӮрҢеӮиҒAҗiӮсӮЕғҚғVғAҲИҠOӮМ—сӢӯӮЖ’КӮ¶ӮжӮӨӮЖӮ·ӮзӮөӮДӮўӮҪҒBүьҠv”hӮНӢаӢКӢПҒA–pүjҚFӮзӮр’ҶҗSӮЖӮ·Ӯй“Ж—§“}ӮЖҢДӮОӮкӮй–ҫҺЎҲЫҗVӮЙ”НӮрӮЖӮйҠJ–ҫ“IҸӯ‘sҸW’cӮЕӮ ӮйҒBи{ҺҒҲк‘°ӮЖҢӢӮсӮЕ‘еү@ҢNӮр’З•ъӮөӮҪӮӘҒAҚЎ“xӮНүьҠvӮрӮЯӮ®ӮБӮДи{ҺҒӮЖ‘О—§ӮөҒA“ъ–{ӮЖӮМҳAҢgӮрӢӯӮЯӮжӮӨӮЖҚlӮҰӮДӮўӮҪҒB и{ҺҒҲк‘°Ӯр’ҶҗSӮЖӮ·ӮйҺ–‘е“}ӮН’©‘N“а•”ӮЕҗЁ—НӮрҠg‘еӮөӮДӮНӮўӮҪӮӘҒAҲ«җӯӮФӮиӮӘӮРӮЗӮӯҗlҗSӮНи{ҺҒҲк‘°Ӯ©Ӯз—Ј”ҪӮөӮВӮВӮ ӮБӮҪҒB’©‘NҚ‘үӨӮМҗSӢ«ӮЙӮа•Пү»ӮӘҢ©ӮзӮкӮҪӮӘҒAҚ‘җӯӮрҲкҗVӮ·ӮйӮҫӮҜӮМҢҲҲУӮНӮИӮӯҒA—DҸ_•s’fӮИ‘Ф“xӮЙҸIҺnӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪҚ‘үӨӮМ‘Ф“xӮЙҒA“Ж—§“}ӮНҲкӢ“ӮЙҚ‘җӯүьҠvӮр’fҚsӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҢҲӮөҒA–ҫҺЎ17”N(1884)12ҢҺ4“ъҒ@ӢһҸй—X•ЦӢЗҠJҗЭӮМҸjүғӮЙҠeҚ‘ҢцҺgӮЖҗӯ•{ҚӮҠҜӮӘҲк“°ӮЙүпӮөӮҪ–йҒA“Ж—§“}ӮМҚ^үpҗAҒA–pүjҚFҒAҸҷҚL”НҒAӢаӢКӢПӮзӮЙӮжӮБӮДҺ–‘е“}ӮМҚӮҠҜи{үjгВӮрҸқӮВӮҜүӨӢ{ӮЙ”—ӮБӮҪҒB—Ӯ12ҢҺ5“ъҒ@Қ‘үӨӮр—iӮөӮҪ“Ж—§“}ӮН‘еҗӯҲкҗVӮр•zҚҗҒAүӨӢ{Һз”хӮМӮҪӮЯ“ъ–{ҢцҺgҒE’|“YҗVҲкҳYӮЙүҮҢRӮр—vҗҝӮөӮҪҒB’|“YҢцҺgӮН100–ј—]ӮМ•әӮЙӮжӮБӮДүӨӢ{ӮрҢмүqҒAҗӯҢ ӮН“Ж—§“}ӮЙӢAӮөҒAғNҒ[ғfғ^Ғ[ӮНҲкүһҗ¬ҢчӮөӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘӮұӮМҚbҗ\ӮМ•П(ҠҝҸйӮМ•П)ӮӘӢNӮұӮйӮЖи{ҺҒҲк‘°ӮН’јӮҝӮЙҗҙҚ‘•әӮЙӢ~үҮӮрӢҒӮЯҒAеНҗўҠMӮНҗҙҚ‘•ә2000ӮрӮаӮБӮДҢRҺ–үо“ьӮөүӨӢ{ӮЙ”—ӮиҒAүӨӢ{“аӮМ’©‘N•әӮЖӢ~үҮӮМ“ъ–{•әӮЙҢьӮ©ӮБӮДҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҚ‘“а“с”hӮМҗӯ‘ҲӮӘҲк“]ӮөӮД“ъҗҙ—јҚ‘•әӮМҗ퓬ӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB“ъ–{ҢRӮНҗ”ӮӘҸӯӮИӮӯ”сҸнӮИӢкҗнӮЙҠЧӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮаҚ‘үӨӮН—тҗЁӮМ“ъ–{ҢRӮрҢ©ҢАӮиҒA–§Ӯ©ӮЙүӨӢ{Ӯр“ҰӮкӮДҗҙҚ‘ҢRӮЙҗgӮр“ҠӮ¶ӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҗ¬ҢчӮөӮҪӮ©ӮЙӮЭӮҰӮҪ“Ж—§“}җӯҢ ӮНҲк–йӮМ“VүәӮЕ’ЧӮҰҒA“ъ–{ҢRӮНҢмӮйӮЧӮ«үӨӮрҺёӮБӮҪӮӨӮҰӮЙҚЭ—Ҝ–MҗlӮрҠЬӮЮ40–јӮрүzӮ·ҺҖҺТӮрҸoӮөӢһҸйӮр“PҺыҒAҗmҗмӮЙ“ҰӮкӮҪҒB–MҗlӢ]җөҺТӮМ’ҶӮЙӮН–\ӢsӮИӮйҗҙҚ‘•әӮЙӮжӮБӮДӢ]җөӮЖӮИӮБӮҪ•wҸ—ҺqӮаӮ ӮБӮҪҒB “ъ–{җӯ•{ӮНҒA’©‘NӮЙ‘ОӮөӮДӮНҺУҚЯ”…ҸһӮрҒAҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДӮНҚ‘үӨӮрҢмүqӮөӮДӮўӮҪүдӮӘ•әӮрҚUҢӮӮөӮҪҚЯӮрӢҠӮөҒAҚДӮС–вҚЯҺgӮр‘—ӮБӮҪҒB–ҫҺЎ18”N1ҢҺ9“ъҒ@“ъ‘NҠФӮЙҒuӢһҸйҸр–сҒvӮӘ’ІҲуӮіӮкӮҪҒBӮЬӮҪҲЙ“Ў”Һ•¶ӮзӮр“V’ГӮЙӮЁӮӯӮБӮДҗҙҚ‘ӮЖ’k”»ӮөҒA4ҢҺ18“ъӮЙҺҠӮиҒA“ъҗҙӮЖӮаӮЙ’©‘NӮ©Ӯз“P•әӮ·ӮйӮұӮЖҒAҸ«—Ҳ’©‘NӮЙҲЩ•ПӮӘӢNӮұӮи—јҚ‘ӮЬӮҪӮНҲкҚ‘ӮӘ”h•әӮр—vӮ·ӮйӮЖӮ«ӮНҒA‘ҠҢЭҺ–‘O’К’mӮМ•K—vӮрҢҲӮЯӮҪҒu“V’ГҸр–сҒvӮр’чҢӢӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ъҗҙ‘О—§ӮЙ‘ОӮ·ӮйҸоҗЁҒ@
“с“xӮМӢһҸйӮМ•ПӮрҸdӮЛҒAҗҙҚ‘ӮЖӮМҠЦҢWӮН”NӮЖӮЖӮаӮЙҲ«ү»ӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДүдӮӘҗӯ•{“БӮЙҢR“–ӢЗӮМ‘ОҠOҠП”OӮр‘еӮ«ӮӯҺhҢғӮөҒA‘ОҗҙҢR”хӮрӢ}‘¬ӮЙҚӮӮЯӮйҢҲҲУӮрӮіӮ№ӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ъ–{ӮНҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮөӮДҗн‘ҲӮр—~ӮөӮДӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮН—сӢӯӮЖӮМ•s•Ҫ“ҷҸр–сӮМүьҗіӮЙ“w—Н’ҶӮЕҒA“ъүpҸр–сӮМҚXүьӮұӮ»Ҹр–сүьҗіӮМҠо‘bӮЙӮИӮйӮЖӮЭӮДүpҚ‘ӮЙ“ӯӮ«Ӯ©ӮҜӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМүpҚ‘ӮН‘ОҳI•§ӮМҚ‘ҚЫҠЦҢWӮ©Ӯз“ъҗҙҗн‘ҲӮЙӮН”Ҫ‘ОӮөҒAӮ»ӮкӮЗӮұӮлӮ©үpҗҙ“Ҝ–ҝҗаӮіӮҰӮаү\ӮіӮкӮҪ’цӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸ]ӮБӮД“ъҗҙӮМҠJҗнӮНӢN“®ӮЙӮМӮБӮДӮ«ӮҪ•s•Ҫ“ҷҸр–сүьҗіӮрҗ…–AӮЙӢAӮіӮИӮўӮЖӮаҢАӮзӮИӮўҒBҺһӮМҠO‘Ҡ—ӨүңҸ@ҢхӮН”сҸнӮИӢк”YӮӘӮ Ӯи‘ОҗҙҠOҢр•ыҗjӮН’ҳӮөӮӯӢҰ’І“IҒE•Ҫҳa“IӮЕӮ·ӮзӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМҗӯ•{“–ӢЗӮМ•ҪҳaҺеӢ`“IӢҰ’І•ыҗjӮЙ‘ОӮөӮДҒAҺеҗнҳ_Ӯр“WҠJӮөӮҪӮМӮНҢR•”ӮЕӮ ӮБӮҪҒB—ӨҢRӮНҸ””КӮМҢ`җЁӮ©Ӯз“ъҗҙӮН‘Ғ”УҗнӮнӮЛӮОӮИӮзӮКӮаӮМӮЖ”»’fӮөҒAҲкҲУ‘Оҗҙҗн‘ҲӮМҢҲҲУӮрҢЕӮЯӮДӮўӮҪҒBӮҫӮӘҠCҢRӮНҺе“®“IӮИ—§ҸкӮ©ӮзҠJҗнӮрҳ_Ӯ¶ӮҪӮаӮМӮНӮИӮӯ—ӨҢRӮМҲУҢ©ӮЙ’ЗҸ]Ӯ·ӮйӮЖӮўӮӨҢ`ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮЙӮНҠCҢRҢR”хӮӘ’xӮкӮД‘ОҗҙҠCҗнӮЙҺ©җMӮӘӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮаҲкҲцӮЕӮ ӮйӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙҚ‘ҳ_ӮН“с•ӘӮөҒA‘ОҗҙҗӯҚфӮН—eҲХӮЙҲк’vӮөӮҰӮИӮўҸуӢөӮЙӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎӢаӢКӢПӮМ‘ҳ“пӮЖҚ‘“аҗўҳ_ӮМ•Ұ“«Ғ@
–ҫҺЎ17”NӮМҚbҗ\ӮМ•ПӮМ”s–kӮЙӮжӮБӮД–S–ҪӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪ’©‘N“Ж—§“}ҠІ•”ӮНҒA“ъ–{ӮвғAғҒғҠғJӮЙҚЭӮБӮДҚДӢNӮМӢ@үпӮр‘ТӮБӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕӮа“ъ–{ӮЙӮ«ӮҪӢаӢКӢПӮв–pүjҚFӮНҒAҺзӢҢ”hӮЙӮжӮй’©‘Nҗӯ•{Ӯ©ӮзҚЕӮағ}Ғ[ғNӮіӮкӮДӮўӮҪҠлҢҜҗl•ЁӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ӮНҚ‘Һ–”Ж–S–ҪҺТӮЖӮөӮД•ЫҢмӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAӮвӮӘӮДҠOҢрҸгӮМ–в‘иӮЖӮИӮйӮМӮрӢ°ӮкҚ‘ҠO‘ЮӢҺӮр–ҪӮ¶ҒAҺАҚsӮіӮкӮИӮўӮЖҢ©ӮйӮв•ЫҢмӮр—қ—RӮЙҸ¬Ҡ}ҢҙӮв–kҠC“№ӮИӮЗӮМү“Ҡu’nӮЙҲЪӮөӮҪҒBӮ»ӮМҠФӢаӢКӢПӮН‘cҚ‘үьҠvӮМ‘е–]Ӯр–YӮкӮйӮұӮЖӮНӮИӮӯҒA“ъ–{җlӮМҺxүҮҺТӮа•ҹ‘т—@ӢgҒA’ҶҚ]’ӣ–ҜҒAҢг“ЎҸЫ“сҳYӮз‘Ҫҗ”ӮЙӮМӮЪӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМӮжӮӨӮИҸуӢөӮМ’ҶӮЕ–ҫҺЎ27”N3ҢҺ27“ъҒ@’©‘Nҗӯ•{ӮНҺhӢqҚ^ҸаүFӮр“ъ–{ӮЙӮЁӮӯӮиӮұӮЭҒAҚЕҸI“IӮЙӮНҸгҠCӮЙӮДӢаӮрҺЛҺEҒAҲв‘МӮр’©‘NҢRҠНӮЕ—A‘—ӮөӮҪҸгӮЙҺlҺҲӮрҗЎ’fҒA“ӘӮЖ“·ӮНӮіӮзӮөӮаӮМӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮБӮҪ–\Ӣ“ӮЙҸoӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҺcӢsӮИҺ–ҢҸӮӘ•сӮ¶ӮзӮкӮйӮЖ“ъ–{ӮМҚ‘–ҜӮН’©‘NӮМҺcӢsӮФӮиӮЖ“ъ–{җӯ•{ӮМ“оҺгӮіӮрӮИӮ¶ӮиҒAҺ–ҢҸӮМ”wҢгӮЙҲГ–фӮ·ӮйҗҙҚ‘ӮМҲ«з…ӮіӮЙҢғ“{ӮөӮҪҒBҗўҳ_ӮНӢӯҚdҠOҢр•ыҗjӮЦӮЖҲЪӮиҒA“ъ–{Қ‘“аӮЙӮН”Ҫ’©ҚRҗҙӢCү^ӮӘҗ·ӮиҸгӮӘӮБӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ҢҠw“}ӮМ—җҒ@
ӢаӢКӢПӮМҲГҺEӮЙҢДүһӮ·ӮйӮ©ӮМӮжӮӨӮЙ–u”ӯӮөӮҪӮМӮӘ“ҢҠw“}ӮМ—җӮЕӮ ӮйҒB“ҢҠwӮЖӮНҗјүўӮМҠw–вӮЙ‘ОҚRӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮЕҒA–{—ҲғLғҠғXғgӢіӮр”rҗЛӮ·ӮйҗVӢ»Ҹ@ӢіӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҚLӮӯ’©‘N–ҜҸOӮЙҗZ“§Ӯ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҗӯҺЎ“IҗFҚКӮр‘СӮСҒAҗӯ•{ӮМҺёҗӯҒA’n•ыҗӯҺЎӮМҲ«җӯӮЙҚRӮөӮД“аҗӯүьҠvӮр•WһФӮөҒAӮВӮўӮЙӮН—җӮрӢNӮұӮ·ӮЙҺҠӮБӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB –ҫҺЎ27”N(1894)4ҢҺҒ@‘S—…–k“№ӮМҲкӢчӮЙӢNӮұӮБӮҪ“ҢҠw“}ӮМ—җӮНӮҪӮҝӮЬӮҝ’©‘N‘S“yӮЙ”gӢyҒA6ҢҺӮЙӮН‘SҸFҲИ“мӮӘӮ·ӮЧӮД”Ҫ—җҗЁ—НӮМҺи’ҶӮЙҠЧӮиҒAӮіӮИӮӘӮзҠv–Ҫ‘O–йӮМҸу‘ФӮЖӮИӮБӮҪҒB’©‘Nҗӯ•{ӮНҺ©—НүрҢҲӮНҚў“пӮЖ”»’fҒA6ҢҺ3“ъӮЙҗҙҚ‘ӮЙӢ~үҮӮрӢҒӮЯӮҪҒBҗҙҚ‘ӮН’јӮҝӮЙӮұӮкӮЙүһӮ¶ҒA6ҢҺ7“ъӮЙӮНҗҙҚ‘ҢR‘ж1җw–с1000–јӮМүеҺRҸг—ӨӮрҠJҺnӮөӮҪҒB“ъ–{ӮЙ‘—ӮБӮҪ’К’mӮЙӮНҒu‘®–M•ЫҢмӮМӮҪӮЯӮМҸo•әҒvӮЖӮ ӮиҒA–ҫӮзӮ©ӮЙ“V’ГҸр–сҲб”ҪӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗҙҚ‘Ӯ©ӮзӮМ’К’mӮрҺуӮҜӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮНҒAҒu’©‘NӮрӢMҚ‘ӮМ‘®–MӮЖ”FӮЯӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒvҺ|Ӯрүс“ҡӮөҒAҒuӢҸ—Ҝ–Ҝ•ЫҢмӮМӮҪӮЯ’©‘NӮЙ”h•әӮ·ӮйҒvӮЖ’К’mҒA6ҢҺ9“ъӮЙӮН‘ж5Һt’cӮМҲк•”ӮрүF•iӮ©ӮзҸoҚ`ӮіӮ№ӮҪҒB “ъ–{ӮНҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮөҒAӢҰ“ҜӮөӮД’©‘NӮМ“а—җӮр’БҲіӮө“аҗӯүьҠvӮрӮ·Ӯ·ӮЯӮжӮӨӮЖҗ\ӮөҚһӮсӮҫӮӘҗҙҚ‘ӮНӮұӮкӮрӢ‘җвӮөӮҪҒBҸ@‘®ҠЦҢWӮМӢӯү»Ӯр–ЪҺwӮ·ӮұӮЖӮӘҗҙҚ‘ӮМҠо–{•ыҗjӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBҚbҗ\ӮМ•ПҢг’©‘NӮМүьҠv”hӮӘүу–ЕҸу‘ФӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯ’©‘N‘ӨӮ©ӮзӮМүьҠvӮНҺ–ҺАҸг•sүВ”\ӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮӨӮИӮйӮЖ“ъ–{ҢRӮӘ’©‘NүӨӢ{ҒAҗӯ•{Ӯр—}ӮҰӮҪӮМӮҝӮЙҸгӮ©ӮзүьҠvӮрҺw“ұӮ·Ӯй‘јӮИӮӯҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮНҗҙҚ‘ӮМ‘vҺеҢ ӮМ”rҸңӮӘ”рӮҜӮзӮкӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBүp•ДғҚҺOҚ‘ӮНҒAӮ»ӮкӮјӮкӮМ—§ҸкӮ©Ӯз’І’вӮрҲҙҗщӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪӮӘҗҙҚ‘ӮНҒA“ъ–{ӮМ“P•әҢгӮЕӮИӮҜӮкӮОүҪҺ–ӮМӢҰӢcӮЙӮаүһӮ¶ӮИӮўӮЖӮўӮӨ‘Ф“xӮрҢЕҺқӮөӮҪӮҪӮЯӮўӮёӮкӮаҺё”sӮөҒAҠeҚ‘ӮЖӮаӮЙ–TҠПӮМ—§ҸкӮрӮЖӮйӮЙҺҠӮБӮҪҒB 7ҢҺ12“ъҒ@“ъ–{җӯ•{ӮН‘ж“сҺҹҗвҢрҸ‘ӮЖӮўӮнӮкӮйҗйҢҫӮр”ӯӮөҒAҗн‘ҲӮаҺ«ӮіӮИӮўҢҲҲУӮрҺҰӮөӮҪҒB7ҢҺ19“ъӮЙӮН‘е“ҮҢцҺgӮӘ’©‘Nҗӯ•{ӮЙҗҙҚ‘ҢRӮМ“PӢҺ—vӢҒӮрӢҒӮЯӮйҒuҚЕҢг’К’«ҒvӮрҺиҢрӮөӮҪҒB6ҢҺ’ҶҸ{ҲИ—Ҳ•җ—НӮрӮаӮБӮДӢһҸйӮр—}ӮҰӮДӮўӮҪ“ъ–{ӮНҒAи{ҺҒҲк‘°ӮЙ‘гӮнӮйӮаӮМӮЖӮөӮДүBҗұ’ҶӮМ‘еү@ҢNӮЙҸo”nӮр‘ЈӮөүьҠvӮЙ’…ҺиӮөӮҪҒB7ҢҺ23“ъҒ@‘еү@ҢNӮН“ъ–{•әӮЙҢмӮзӮкӮДүӨӢ{ӮЙ“ьӮии{ҺҒҲк‘°ӮрҲк‘|ӮөӮДҗӯҢ ӮрҲ¬ӮиҒA‘О“ъӢҰ—НӮМ‘Ф“xӮр–ҫӮзӮ©ӮЙӮөӮҪҒBӮұӮұӮЙӮЁӮўӮД’©‘NӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{ӮМ—§ҸкӮНҲкӢ“ӮЙҚD“]Ӯ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒAҗҙҚ‘ӮЖӮМҗн‘ҲӮНӮўӮжӮўӮж”рӮҜӮӘӮҪӮўӮаӮМӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’ҶүШҺv‘zӮЖҗўҠEҠПӮМ‘ҠҲбҒ@
’©‘NӮН’·Ӯў“`“қӮр—LӮ·Ӯй’ҶүШҺv‘zӮЙҠоӮГӮӯ’©Қv‘МҗЁӮЙ‘gӮЭҚһӮЬӮкҒAҗҙҚ‘ӮрҺеҢNҒA’©‘NӮрҗbүәӮЖӮ·ӮйҺеҸ]ҠЦҢWӮрҢӢӮСҒAҗҙҚ‘ӮрҸ@ҺеҚ‘ӮЖӢВӮ®‘®Қ‘ӮМ—§ҸкӮрҺзӮБӮДӮўӮҪҒBҺ©Ӯз’ҶүШӮЖҸМӮө4000”NӮМ•¶ү»ӮрҢЦӮйҗҙҚ‘ӮНҒAҗVӢ»Қ‘“ъ–{Ӯр’ҶүШ’ҒҸҳӮМ”jүуҺТӮЖӮөӮДӮЖӮзӮҰҒA’ҶүШҗўҠEӮМ–hүqӮрҢR”хӢӯү»ӮМ–Ъ“IӮЖӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{ӮНҒAҗҙҚ‘Ӯрүў•Д—сӢӯӮМ‘OӮЙ•ъ’uӮіӮкӮҪ‘OӢЯ‘гҚ‘үЖӮЖҲК’u•tӮҜҒAҲў•Рҗн‘ҲҲИ—ҲҺ©Қ‘ӮМ“Ж—§Ӯ·ӮзҠлӮӨӮў”јҗA–Ҝ’nҚ‘үЖӮӘ—ЧҚ‘’©‘NӮМ•ЫҢмӮрӮЬӮБӮЖӮӨӮЕӮ«ӮйӮЖӮНҺvӮҰӮёҒAӮаӮөӮұӮкӮӘ”j’]Ӯ·ӮкӮО’©‘NӮаӮЬӮҪҗјүў—сӢӯӮМ‘җҠ ҸкӮЖӮИӮиҒA“ъ–{ӮМ‘¶—§ӮаӢәӮ©ӮіӮкӮйӮұӮЖӮН•K’иӮЕӮ ӮБӮҪҒB “–ӮМ—ӣҺҒ’©‘N‘ӨӮ©ӮзӮ·ӮкӮОҒAӮЗӮҝӮзӮ©Ҳк•ыӮЙӮВӮҜӮО•KӮё‘ј•ыӮМ”Ҫ”ӯӮрҸөӮ«ҒA‘еҚ‘җҙҚ‘ӮЖҗVӢ»Қ‘“ъ–{ӮМҠФӮЕҢгҗiҚ‘ӮЖӮөӮДҚ¬–АӮр‘ұӮҜӮДӮўӮҪҒB“ъ–{ӮН’©‘NӮЙ‘ОӮөҺ©—RӮИ“Ж—§Қ‘ӮЖӮИӮйӮұӮЖӮрҠъ‘ТӮөӮҪӮӘҒAҺ©—НӢ~ҚП”\—НӮӘӮИӮӯ‘јҚ‘ӮЙҲЛ‘¶Ӯр‘ұӮҜӮй‘ј—Н–{Ҡи“IҗӯҚфӮрӮЖӮйҚ‘ӮНүқҒXӮЙӮөӮДҺё”sӮөҒAҚ‘үЖӮрҠлҢҜӮИ—§ҸкӮЙ—§ӮҪӮ№ӮйӮұӮЖӮНҺjҸгӮЙ—бӮӘҸӯӮИӮӯӮИӮўҒBӮұӮМҸкҚҮӮМ’©‘NӮНӮЬӮіӮЙӮұӮкӮЕӮ ӮБӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙӢҢ‘Мҗ§Қ‘үЖӮМҠұҸВӮр”rҸңӮөҒAүў•ДӮМҗNҸoӮ©ӮзүдӮӘҚ‘ӮРӮўӮДӮН“Ң—m‘S‘МӮМ•ҪҳaӮрҠm•ЫӮөӮӨӮйӢЯ‘гҚ‘үЖӮМҢҡҗЭӮр–ЪҺwӮөӮДӮўӮҪӮМӮӘ“ъ–{ӮЕӮ ӮйҒBҗVӢҢӮМҲЩӮИӮйҗўҠEҠПӮЖ’ҒҸҳӮрӮЯӮ®ӮБӮДҗ„җiӮіӮкӮҪ“ъҗҙ—јҚ‘ӮМҢR”хӢӯү»ӮНҒAӮ»ӮМҚlӮҰӮр•ПҚXӮөӮИӮўҢАӮиҸХ“ЛӮН•sүВ”рӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҗҙҗн‘Ҳ2 | |
|
ҒЎ—ӨҸгҗн—НҒ@
ҒЎ“ъ–{ҢR •ҪҺһ•Тҗ¬ӮН‘ҚҲх7–ң–јӮЕ7ҢВҺt’cӮЙ•ӘӮҜӮДӮўӮҪҒBҗнҺһ•Тҗ¬ӮЙӮжӮкӮО“®Ҳх•ә—НӮНҺз”х•”‘аӮрҠЬӮЯӮД–с23–ң–јӮЕӮ ӮиҒAҺQүБҺАҗ”ӮН24–ңӮр’ҙӮҰӮҪҒBҚ‘ҢRӮЖӮөӮДӮМ•Тҗ¬ҒE‘•”хӮа“қҲкӮіӮкҢP—ыҒEҺmӢCӮЖӮаӮЙҚӮӮӯҒAҺҝ“IӮЙӮНҗҙҚ‘ҢRӮр’ҳӮөӮӯ—ҪүнӮөӮДӮўӮҪҒB ҒЎҗҙҚ‘ҢR җҙҚ‘–{—ҲӮМҗіӢKҢRӮН”ӘҠшӮЖ—ОүcӮЕӮ ӮБӮҪҒB”ӘҠшӮН–һҸB‘°ӮМҗўҸPҢRӮЕ•ҪҺһӮНҚsҗӯ’PҲКӮЕҗнҺһӮМӮЭҢR‘а•Тҗ¬ӮМ’PҲКӮЕӮ ӮиҒAҗҙ’©ӮМҺx“ЯҺx”zӮЙ”әӮў•җ—НӮрӮаӮБӮДҠҝ–Ҝ‘°ӮрҺx”zӮ·Ӯй’nҲКӮЙӮ ӮБӮҪҒB–с29–ңҗlӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒB—ОүcӮНҠҝҗlӮМӮЭӮЕ•Тҗ¬ӮөҒAҠeҸИӮЙ’““ФӮіӮ№ӮДҺЎҲАӮМҲЫҺқӮЙ“–ӮҪӮзӮ№ӮДӮўӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA–с54–ңҗlӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒBӮұӮкӮзӮНҗҙ’©ҢҡҚ‘“–ҺһӮМҗ§“xӮрӮ»ӮМӮЬӮЬҺуӮҜҢpӮ¬‘nҗЭҲИ—Ҳ–с200”NҲИҸгҢoӮДӮЁӮиҒA‘е–CӮЖӢ@ҠЦҸeӮМҺһ‘гӮЙӢ|ӮЖ‘ҫ“ҒӮМӢZҸpӮЙӮжӮБӮДҸ«ҚZӮрҚМ—pӮөӮДӮўӮҪҒBҢRҗ§ӮН—җӮкҗёҗ_“IӮЙӮа•…”s‘В—ҺӮөӮДӮЁӮиҒAҒuҲў•Рҗн‘ҲҒvӮвҒu‘ҫ•Ҫ“VҚ‘ӮМ—җ(’·”Ҝ‘°ӮМ—җ)ҒvӮИӮЗӮЕӮаӮНӮвҢR‘аӮЖӮөӮДӮМҺА‘ФӮрҺёӮБӮДӮўӮйӮұӮЖӮрҳI’жӮөӮДӮўӮҪҒB ӮұӮкӮзӮЙ‘гӮнӮБӮДҗҙҚ‘ҢRӮМҺАҗн—НӮЖӮИӮБӮҪӮМӮН—EҢRӮЖ—ыҢRӮЕӮ ӮйҒB —EҢRӮНҒAҲў•Рҗн‘ҲӮИӮЗӮЕҗіӢKҢRӮӘ–і—НӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙүһӢ}“IӮЙ•Тҗ¬ӮөӮҪҺ„•әҸW’cӮЕҒA—b•ә“IӮИҗFҚКӮрҺқӮБӮДӮўӮҪҒB—ыҢRӮНҒA”ӘҠшӮМ’ҶӮ©Ӯз‘I”ІӮіӮкӮҪӮаӮМӮЕҠOҚ‘җlҸ«ҚZӮМҢP—ыӮрҺуӮҜӮҪҗVҺ®ҢR‘аӮЕӮ ӮйҒBҠJҗн“–ҸүӮМ—EҢRҒE—ыҢRӮМ‘ҚҲхӮН–с35–ң–јҒAҗнҺһӮЙҗVӮҪӮЙ•еҸWӮө‘Қҗ”–с98–ңӮЙӮа’BӮөӮҪӮӘҒA–{җн‘ҲӮЙҺg—pӮіӮкӮҪӮМӮН’ј—кҸИӢЯӮӯӮЙӮ ӮБӮҪ•”‘аӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮЕӮа“ъ–{ҢRӮжӮиӮаӮНӮйӮ©ӮЙ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ‘ҪӮӯӮН•Тҗ¬ҒE‘•”хҒEҢP—ыӮа“қҲкӮіӮкӮДӮўӮИӮўҺG‘ҪӮИҢR‘аӮЕӮ ӮБӮҪҸгӮЙҒA“қҗғ‘gҗDӮЙҢҮ“_Ӯр•шӮҰӮДӮЁӮи‘SҢRӮрҸW’Ҷ“IӮЙү^—pӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮИӮ©ӮЕ—ӣҚғҸН’ј—ҰӮМ–k—m—ӨҢR–с3–ңӮЖ“Ң–kҺOҸИӮМ—ыҢR5җз–јӮНҗёүs•”‘аӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠCҸгҗн—НҒ@
ҒЎ“ъ–{ҢR җҙҚ‘ҠН‘аӮЙ‘ҚҗЗҗ”ҒA‘Қғgғ“җ”ӮЙӮЁӮўӮД—тӮиҒA’иү“ҒA’Бү“ӮМӮжӮӨӮИӢҗ‘еҗнҠНӮН—LӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAүх‘¬ӮЖ‘¬ҺЛ–CҺе‘МӮМҗVүsҠНӮр•Ы—LӮөҢRӮМҺmӢCҒAӢZ”\ҒAҺwҠц“қ—Ұ–КӮЙӮЁӮўӮДӮНҗҙҚ‘ҠCҢRӮжӮиӮа—yӮ©ӮЙ—DӮкӮДӮўӮҪҒB ҒЎҗҙҚ‘ҢR җҙҚ‘ӮН–ҫҺЎ8”NӮЙ‘•ҚbҠНӮрҚw“ьӮөӮДҲИ—ҲӢЯ‘гҠCҢRӮМ”ӯ“WӮЙ“wӮЯӮДӮўӮҪҒBүpҒE“Ж—јҚ‘ӮЙҢRҠНӮр”ӯ’ҚӮөҚҒҚ`ӮЙ“Ң—mҠН‘аҺi—Я•”Ӯр’uӮӯүpҚ‘ӮЖӢЩ–§ӮИҠЦҢWӮрҺқӮҝҒAҢЪ–вғүғ“ғO‘еҚІӮМҺw“ұӮМӮаӮЖҠCҢR—НӮМҠg‘еӮрҗ}ӮБӮДӮўӮҪҒBҸгӢLӮМӮжӮӨӮЙҗ”ӮЕӮНҸҹӮйҗҙҚ‘ҠCҢRӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӢҢҢ^ҠН’шӮӘ‘ҪӮӯҒAҢP—ыҒEҺmӢCӮЙ—тӮйӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ—ӨҢR“Ҝ—l“қҗғ‘gҗDӮЙҢҮҠЧӮӘӮ ӮБӮҪҒBҚмҗнӢж•ӘӮЖӮөӮД–k—mҒA“м—mҒA•ҹҢҡҒAҚL“ҢӮМҠeҗ…ҺtӮЙ•ӘӮ©ӮкҒAӮ»ӮкӮјӮкӮӘҸҠҠЗӮМ‘еҗbҒE‘Қ“ВӮЙ—к‘®ӮөӮДӮЁӮиҒAҺwҠцҢ ӮаҢP—ыӮа“қҲкӮіӮкӮДӮЁӮзӮёҚҮ“ҜӮЕҚмҗнӮ·Ӯй‘ФҗЁӮЙӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB’ҶӮЕӮа–k—mҗ…ҺtӮНҳB“xӮаҚӮӮӯ•КҠiӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA‘јӮМ3җ…ҺtӮНҲк•”ӮрҸңӮ«ҠO—mӮЕӮМҚмҗнӮ·ӮзҚў“пӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮіӮкӮйҒBҺАҚЫӮЙ“ъҗҙҗн‘ҲӮЙҺQүБӮөӮҪӮМӮН–k—mҗ…ҺtӮЖҚL“Ңҗ…ҺtӮМӮӨӮҝӮМ3җЗӮМӮЭӮЕҒAҢRҠН25җЗҒAҗ…—Ӣ’ш12җЗҒA‘ҚҢv44000ғgғ“ӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪҒB ӮұӮМ’ҶӮЕҒu’иү“ҒvӮЖҒu’Бү“ҒvӮНҒA“Ң—mҲкӮМҢҳҠНӮЖӮөӮДӮ»ӮМҲР—eӮрҢЦӮБӮДӮўӮҪӮӘҒAҠН—оӮН10җ””NӮӘҢoүЯӮөӮДӮўӮҪҒB‘јӮМҠНӮа“ъ–{ҠН‘аӮЖ”дҠrӮөӮДҲк”КӮЙ‘¬—НӮа’xӮӯҒAҗVҺ®‘¬ҺЛ–CӮр”хӮҰӮҪҢRҠНӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮНҗҙҚ‘ӮМ“аҗӯӮӘ—җӮкӢЯ‘гү»ӮрҲЫҺқӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯӮЕҒA–{—ҲӮНҠCҢR—НҠg’ЈӮЙҸ[ӮДӮзӮкӮйӮЧӮ«—\ҺZӮӘҒAҗј‘ҫҚ@ӮМҠТ—пҸjӮўӮМӮҪӮЯ–ңҺхҺRӮМ‘е’лүҖӮМҢҡҗЭ”п—pӮЙ—¬—pӮіӮкӮҪӮҪӮЯӮЖӮўӮнӮкӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҚмҗнҚ\‘zҒ@
‘е’йҚ‘ӮҪӮйҗҙҚ‘ӮНӮ©ӮЛӮДӮжӮи“ъ–{ӮрҺгҸ¬Қ‘ҺӢӮөӮДӮЁӮиҒA–ҫҺЎҲЫҗVҢгӮМ“ъ–{ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҢyҳН•Ӯ”–ҒAӮЭӮҫӮиӮЙҗј—m•¶–ҫӮМӮЬӮЛӮІӮЖӮрӮөӮҪҲкҸ¬Қ‘ҲОӮЖҡ}ӮиҒA—DҗЁӮИ—ӨҠCҢRӮрӮаӮБӮДӮ·ӮкӮОҗнӮнӮёӮөӮДӢь•һӮөӮӨӮйӮ©ҒAҗнӮБӮҪӮЖӮөӮДӮаҲкҢӮӮМӮаӮЖӮЙ•ІҚУӮөӮӨӮйӮаӮМӮЖҗMӮ¶ӮзӮкӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮкҲИ‘OӮЙҒA“ъ–{ӮМҗӯ‘ҲӮ©ӮзҳaҗнҚ‘ҳ_ӮМҲк’vӮӘ“ҫӮзӮкӮёҒAӮҪӮЖӮҰҗнӮӨӮа“а•”•цүуӮМҠлҢҜӮрӮНӮзӮЮҗЖҺгӮИҚ‘үЖӮЕӮ ӮйӮЖ”»’fӮөӮДӮўӮҪҒBҗўҠEҠeҚ‘ӮаҒA“Ҝ—lӮЙҚ‘“y–КҗПҒEҢoҚП—НӮ»ӮМ‘јӮ ӮзӮдӮй–КӮ©ӮзҢ©ӮДҗҙҚ‘ӮМҸҹ—ҳӮНҺnӮЯӮ©ӮзӢ^ӮӨ—]’nӮӘӮИӮўӮЖӮ·ӮйҠП‘ӘӮӘҺx”z“IӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮӨӮөӮҪ’ҶӮЕ“ъ–{ҢRӮМҚмҗнҢvүжӮНҒAҒw—ӨҢRӮМҺе—НӮрҺRҠCҠЦ•tӢЯӮЙҸг—ӨӮ№ӮөӮЯҒA’ј—к•Ҫ–мӮЙӮЁӮўӮДҗҙҚ‘–мҗнҢRӮЖҢҲҗнӮ·ӮйӮЙӮ ӮиҒAӮұӮкӮӘҲЧҗжӮё‘ж5Һt’cӮр’©‘N•ы–КӮЙҗiӮЯҠCҢRӮрӮөӮД‘¬ӮвӮ©ӮЙү©ҠCӢyӮСҹЭҠCҳpӮМҗ§ҠCҢ ӮрҺыӮЯӮөӮЮҒxҒ@ӮЖҗн‘ҲҸI––ӮМҸуӢөӮр‘z’иӮөҒAҗ§ҠCҢ Ҹ¶Ҳ¬ҢгӮМ“G–мҗнҢRҺе—НҢӮ–ЕӮрҚмҗнӮМҺеҠбӮЙ’uӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ–L“Үү«ҠCҗнҒ@
—·ҸҮҗјҠCҠЭӮМҗ§ҠCӮМ‘е–{үcҢP—ЯӮрҺуӮҜӮҪ—ьҚҮҠН‘аӮНҒA7ҢҺ23“ъ1100ҚІҗў•ЫӮрҸoҚ`ҒA’©‘N‘S—…“№җј–k’[ӮМҢSҺRү«ӮЦҢьӮ©ӮБӮҪҒB‘ж1—VҢӮ‘а(Һi—ЯҠҜҒ@’ШҲдҚqҺOҸӯҸ«)ӮМҒuӢg–мҒvҒuҳQ‘¬ҒvҒuҸH’Г“ҮҒvӮМҺOҗЗӮНҒA25“ъ–L“Үү«ӮЕҗҙҚ‘ҢRҠНҒuҚПү“ҒvҒuҚLүіҒvӮЖүпҚҮӮөӮҪҒB ҠJҗн‘OӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯ—з–CҸҖ”хӮрӮөӮДӮўӮҪӮЖӮұӮлҒA0750Ғ@Ӣ——Ј3000ӮlӮЙӮДҒuҚПү“ҒvӮӘ“Л”@–CүОӮрҠJӮўӮҪҒB“ъ–{ӮМ3ҠНӮН’јӮҝӮЙүһҗнҒAҢрҗнҗ”•ӘҢгҒuҚПү“ҒvӮНҗј•ыӮЙ“Щ‘–ӮрҠJҺnҒAҒuӢg–мҒvҒuҳQ‘¬ҒvӮНӮұӮкӮр’ЗҢӮ’ҶҒAҗҙҚ‘ҢRҠНҒu‘ҖҚ]ҒvӮЖүpҚ‘ҸӨ‘DҠшӮрҢfӮ°ӮҪӢD‘DҒuҚӮиһҚҶҒvӮЖ‘ҳӢцӮөӮҪҒBҒuҚӮиһҚҶҒvӮНҗј•ыӮЙ‘Ю”рӮөӮҪӮӘ“ҜҸӨ‘DӮНҗҙҚ‘•ә–с1200–јӮр“ӢҚЪӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕҒA—VҢӮ‘аҺi—ЯҠҜӮНҒuҳQ‘¬ҒvҠН’·ҒE“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY‘еҚІӮЙүp‘DӮМҸҲ’uӮр–ҪӮ¶ӮҪҒB“ҢӢҪҠН’·ӮНүp‘DӮЙ’в‘DӮр–ҪӮ¶ҒA—ХҢҹҢг‘DҲхӮЙ‘ЮӢҺӮр–ҪӮ¶ҢxҚҗҗMҚҶӮМҢгӮЙӮұӮкӮрҢӮ’ҫҒAҗҙҚ‘•әӮр•Я—ёӮЖӮөӮҪҒB’Ҷ—§Қ‘ӮЕӮ ӮйүpҚ‘‘D”•ӮрҢӮ’ҫӮөӮҪӮұӮЖӮЕҚ‘ҚЫ–в‘иӮЖӮИӮиӮ©ӮҜӮҪӮӘҒA“ҢӢҪҠН’·ӮМҸҲ’uӮН“KҗШӮЕӮ ӮйӮЖҒAҗўҠE“IҚ‘ҚЫ–@ҠwҺТғzҒ[ғүғ“ғhҒEғEғFғXғgғҢҒ[ғL—ј”ҺҺmӮ©ӮзӮа•]үҝӮіӮкӮҪӮҪӮЯүpҚ‘җўҳ_ӮН’ҫҗГү»ӮөӮҪҒBүеҺRӮЦӮМ‘қүҮ•”‘аӮрҸжӮ№ӮҪҒuҚӮиһҚҶҒvӮМҢӮ’ҫӮНҒAӮұӮМҢгӮМ—ӨҢRӮЙӮжӮйҗ¬ҠҪҒEүеҺRҚмҗнӮЙ‘еӮ«ӮӯҚvҢЈӮөҒAӮұӮМ—E’fӮН“ҢӢҪӮМ–јӮрҚ‘ҚЫ“IӮЙӮа—L–јӮЙӮөӮҪҒB ӮИӮЁӮұӮМҠCҗнӮЕ“ъ–{‘ӨӮЙҺҖҸқҺТӮНӮИӮӯҒAҒuҚПү“ҒvӮЙ‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰҒA‘ҒҒXӮЙҚ~•ҡӮөӮҪҒu‘ҖҚ]ҒvӮНүдӮӘҒuҸH’Г“ҮҒvӮЙ•ЯҠlӮіӮкҒAҒuҚLүіҒvӮНҚАҸКӮөӮҪӮМӮҝүО–тҢЙӮӘ”ҡ”ӯӮөҺcҠ[ӮрҺcӮ·ӮМӮЭӮЖӮИӮБӮҪҒBӮұӮМҠCҗнӮНҒAҗн—Н“IӮЙ“ъ–{ӮНҗҙҚ‘‘ӨӮЙҗ””{ӮөҒAҸҹ”sӮНҺnӮЯӮ©Ӯз–ҫӮзӮ©ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҸҸҗнӮМүхҸҹӮНҠCҢRӮМӮЭӮИӮзӮё—ӨҢRҒAӮ»ӮөӮДҚ‘–ҜӮЙӮаҺ©җMӮр—^ӮҰҺmӢCӮрҚӮ—gӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҗ¬ҠҪҒEүеҺRҚмҗнҒ@
’©‘Nҗӯ•{Ӣ~үҮӮр–ј–ЪӮЖӮөӮДҸo•әӮөӮҪҗҙҚ‘ҢRӮН6ҢҺ9“ъҒ@—tҺu’ҙӮр‘ҚҺwҠцҠҜӮЖӮөӮД2465–јӮЖ–C8–еӮМ•”‘аӮӘӢһҸй“м•ы–с100ӮjӮlӮМүеҺRӮЙҸг—ӨҒAӮ»ӮМҢгӮа‘қүҮӮрҢJӮи•ФӮө7ҢҺ23“ъӮЙүеҺRӮЙӮ ӮйҗҙҚ‘ҢRӮН4165–јӮрҗ”ӮҰӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘OҸqӮМӮжӮӨӮЙҒuҚӮиһҚҶҒvӮЙҸжҠНӮөӮДӮўӮҪ1200–јӮЖ–C12–еӮМ‘қүҮ•”‘аӮН–L“Үү«ӮЕҢӮ’ҫӮіӮкӮДӮўӮҪҒBүеҺRӮЙҸWҢӢӮөӮҪҗҙҚ‘ҢR–kҸгӮМҸо•сӮӘӮөӮОӮөӮО“`ӮҰӮзӮкҒA•ҪҸл•tӢЯӮЙҸWҢӢӮөӮВӮВӮ ӮйҗҙҚ‘ҢRҺе—Н(–с10000)ӮЖӮЖӮаӮЙӢһҸй•tӢЯӮМ“ъ–{ҢRӮӘӢІҢӮӮіӮкӮйӢ°ӮкӮӘӮ ӮиҒAҗн—ӘҸгӮ©ӮзӮНҗҙҚ‘ҢRҺе—НӮМ•ҪҸлҸW’ҶҒE“мүәӮЙҗж—§ӮҝӢ@җжӮрҗ§ӮөӮДүеҺR•tӢЯӮМҗҙҚ‘ҢRӮрҢӮ”jӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ–]ӮЬӮөӮ©ӮБӮҪҒB7ҢҺ25“ъҒ@’©‘Nҗӯ•{Ӯ©ӮзүеҺRӮМҗҙҚ‘ҢRҢӮ‘ЮӮМ—vҗҝӮрҲЛ—ҠӮіӮкӮҪ‘е’№ҢцҺgӮНҒA—Ӯ26“ъҒ@‘ж9•а•ә—·’c’·ҒE‘е“ҮӢ`Ҹ№ҸӯҸ«ӮЙӮ»ӮМҺ|Ӯр’К’BӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮұӮл–L“Үү«ҠCҗнҸҹ—ҳӮМ•сӮӘ“`ӮнӮиҒA‘SҢRӮЭӮИ—E–фҒAҺmӢCӮН‘еӮўӮЙҸгӮӘӮБӮҪҒB ‘е“Ү—·’c’·ӮНҗҙҚ‘ҢRӮМҺе—Н–с3000—]ӮӘҗ¬ҠҪ–k•ыӮЙҗw’nӮрҗи—МӮөӮД–hҗнҸҖ”хӮрӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮр’mӮиҒAӮұӮкӮр–Ъ•WӮЖӮөӮД29“ъ‘ҒӢЕӮ©ӮзҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮөӮҪҒB7ҢҺ29“ъ0200Ғ@Қ¶үE—ј—ғӮЙ•КӮкӮД‘SҢRӮНҲкҗДӮЙҚs“®ӮрҠJҺnӮөӮҪҒBүE—ғ‘аӮН–һ’ӘӮЙӮ ӮҪӮи“№ҳHӮЖҗ…“cӮМӢж•КӮӘӮЕӮ«ӮёҚsҢRӮНҚў“пӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮұӮлҒA‘Oүq’Ҷ‘аӮӘҲАҸйҗмӮр“nӮБӮҪ•УӮиӮЕ“Л”@“GҸPӮрҺуӮҜҒA‘ж12’Ҷ‘а’·ҸјҚи’јҗb‘еҲСҗнҺҖӮМӮЩӮ©җ”–јӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘ“ъҗҙҗн‘ҲҚЕҸүӮМӢ]җөҺТӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢғҗн30•ӘӮМӮМӮҝ“GӮрҢӮ‘ЮҒAҗ¬ҠҪӮр–ЪҺwӮөӮДҚsҢRӮр‘ұҚsӮөӮҪҒB0520Ғ@—·’c’·’ј—ҰӮМҺе—НҚ¶—ғ‘аӮНҒAҗ¬ҠҪӮМ“Ң–kҚӮ’nӮЙ“һ’…ҒAӮҪӮҫӮҝӮЙ“GҗwӮЙҢьӮ©ӮБӮДҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒB—јҢRӮМҸ¬ҸeҒE–C•әүО—НӮМүһҸVӮНҢғ—уӮрӢЙӮЯӮҪӮӘүE—ғ‘аӮаӮвӮӘӮД“һ’…ҒA“GҡЖ—ЫӮр‘ұӮҜӮДҠЧӮкӮҪҒB0700“GҺе—НӮН‘ЮӢpӮрҺnӮЯӮҪӮМӮЕ—·’cӮН“GҗwӮЙ“Л“ьҒAҢғҗн2ҺһҠФӮЕҗ¬ҠҪӮМ“Gҗw’nӮрҗи—МӮөӮҪҒB —·’cӮН‘ФҗЁӮрҗ®ӮҰӮУӮҪӮҪӮСҚ¶үE—ј—ғӮЙ•КӮкӮД’ЗҢӮӮЙҲЪӮиҒA“м–kӮ©ӮзүеҺRӮрҸХӮұӮӨӮЖӮөӮҪҒBӮаӮЖӮаӮЖүеҺRӮНҗҙҚ‘ҢRӮӘӮ»ӮМ–{Ӣ’ӮЖӮөӮД’·Ӯӯ•zҗwӮөӮДӮўӮҪҸҠӮИӮМӮЕҒAҗ¬ҠҪӮМ”s•әӮНӮ·ӮЧӮДӮұӮұӮЙҸWҢӢӮөҠжӢӯӮЙ’пҚRӮ·ӮйӮаӮМӮЖҚlӮҰӮзӮкҒA“ъ–{ҢRӮНҢғҗнӮрҠoҢеӮөӮДҗiҢӮӮөӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘ—[ҚҸҒAүE—ғ‘OүqӮӘӮ»ӮМ’nӮЙ“һ’…Ӯ·ӮйӮЖ“GӮН‘ЮҺUӮөӮҪҢгӮЕҗҙҚ‘•әӮМҺpӮНӮЗӮұӮЙӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒB–іҢҢӮМӮӨӮҝӮЙүеҺRӮрҗи—МӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢгҸӯҗ”ӮМ–йҸPӮрҺуӮҜӮҪӮӘӮұӮкӮрҢӮ‘ЮҒAҗн—ҳ•iӮНҢRҠшҒAҸe–CҒA’e–тӮ»ӮМ‘ј‘Ҫҗ”ӮЙӮМӮЪӮиҚмҗнӮН“ъ–{ҢRӮМүхҸҹӮЙҸIӮнӮБӮҪҒBӮұӮМӮМӮҝӮөӮОӮөӮОҢ©ӮзӮкӮҪӮжӮӨӮЙҗҙҚ‘•әӮНӮ ӮЬӮиӮЙӮаҺгӮӯҒA“ҰӮ°‘«ӮҫӮҜӮН‘¬Ӯ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗ¬ҠҪӮМ”sҺc•ә2000—]ӮН‘Ҫҗ”ӮМҸ¬ҸW’cӮЙ•ӘӮ©ӮкҒA‘ҪӮӯӮН•П‘•ӮөӮДҺR–мӮр“Ҙ”jӮөҒA“GҸ«ҒE—tҺu’ҙҲИүәӮН300ғ}ғCғӢӮаүКӮДӮМ•ҪҸлӮЬӮЕ”s‘–ӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮИӮЁҲАҸй“nӮМҗ퓬ӮЕ‘ж21—ь‘а‘ж9’Ҷ‘аӮМҡhҷЪҺи”’җ_Ң№ҺҹҳYҲк“ҷ‘ІӮӘҒAӢ№•”Ӯр“G’eӮЙҢӮӮҪӮкӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёғүғbғpӮрҢыӮ©Ӯз•ъӮіӮёҗҒӮ«ӮВӮГӮҜӮҪҒAӮЖӮўӮӨ’ү—E”ь’kӮӘ“–ҺһӮМҚ‘–ҜӮМҺmӢCӮрҢЫ•‘ӮөӮҪҒBӢЯ‘г“ъ–{ӮМ’ү—E’k1ҚҶӮЕӮ ӮБӮҪҒB(ӮМӮҝӮЙ‘ж5Һt’cӮН“–ҠYҡhҷЪҺиӮр‘ж12’Ҷ‘аӮМ–ШҢыҸ¬•Ҫ“с“ҷ‘ІӮЕӮ ӮйҒAӮЖ’щҗіҒAҸCҗgӢіүИҸ‘ӮЙӮа–ШҢыӮМ–ј‘OӮЕҢfҚЪӮіӮкӮҪҒB)Ғ@ |
|
|
ҒЎҗйҗн•zҚҗҒ@
–L“Үү«ҠCҗнҒAҗ¬ҠҪҒEүеҺRҚмҗнӮЕҺ–ҺАҸгҗн‘ҲҸу‘ФӮЙ“ьӮБӮДӮНӮўӮҪӮӘҒA–ҫҺЎ27”N8ҢҺ1“ъҒ@–ҫҺЎ“VҚcӮНҗйҗнӮМҸЩ’әӮра…”ӯӮөҒAҗӯ•{ӮНҠJҗнӮрҠeҚ‘ӮЙҚҗӮ°ӮҪҒBҗҙҚ‘’“ҚЭ‘г—қҢцҺgҒEҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮНҢцҺgҠЩҲхӮвӢҸ—Ҝ–ҜӮЖӮЖӮаӮЙ–kӢһӮрҲшӮ«—gӮ°ҒAӢAҚ‘ӮМ“rӮЙӮВӮўӮҪҒB“ҜӮ¶“ъӮЙҗҙҚ‘Қc’йӮаҗйҗнӮр•zҚҗҒAӮұӮкӮрҺуӮҜӮДҗјүўҸ”Қ‘ӮНӢЗҠO’Ҷ—§ӮрҗйҢҫӮөӮҪҒB“ъ–{җӯ•{ӮМҠ©ҚҗӮр—eӮкӮДҸ”җӯҚьҗVӮр’fҚsӮөӮҪ’©‘NҗVҗӯ•{ӮНҒA8ҢҺ26“ъҒ@“ъ‘N—јҚ‘“Ҝ–ҝҸр–сӮЙ’ІҲуӮөҒA“ъ–{ӮЖҚUҺз“Ҝ–ҝӮрҢӢӮсӮҫҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ•ҪҸлҚмҗнҒ@
8ҢҺүәҸ{Ғ@•ҪҸл•tӢЯӮЙҸW’ҶӮөӮҪҗҙҚ‘ҢRӮН12000–јҒA–мҺR–C32–еҒAӢ@ҠЦ–C6–еӮЙ’BӮөҒAҗ¬ҠҪӮМ”sҸ«—tҺu’ҙӮМҺwҠцүәӮЙҒA”sҺc•ә3000ӮӘүБӮнӮиӢһҸйӮрҲРҲіӮ·ӮйҗЁӮрҺҰӮөӮҪҒB8ҢҺ19“ъҒ@ӢһҸйӮЙ“һ’…ӮөӮҪ‘ж5Һt’c’·–м’Г“№ҠС’ҶҸ«ӮНҒAҺt’c‘S—НӮМ“һ’…ӮЖӮЖӮаӮЙ–kҗiӮрҢҲҲУӮөӮД•ҪҸлӮЙҢьӮ©ӮӨ‘OҗiӮр–ҪӮ¶ӮҪҒB Ғ@1Ғ@Қ¬җ¬‘ж9—·’c(’·ҒE‘е“ҮҸӯҸ«Ғ@3600–ј)Ғ@Ӣ`ҸBҠX“№ӮЙүҲӮБӮД–kҗiҒA“GӮрҢЎҗ§ Ғ@2Ғ@Қс”JҺx‘а(’·ҒE—§Ң©ҸӯҸ«Ғ@3600–ј)Ғ@Ӣ`ҸBҠX“№“Ң‘ӨӮр•ҪҸл–k‘ӨӮЙ‘OҗiҒA“G‘Ө–КӮрҚUҢӮ Ғ@3Ғ@ҢіҺRҺx‘а(’·ҒEҚІ“Ў‘еҚІҒ@4700–ј)Ғ@Қс”JҺx‘аӮЖӮЖӮаӮЙ“GӮМҚ¶—ғӮЙӮ ӮҪӮй Ғ@4Ғ@Һt’cҺе—Н(Һt’c’·’ј‘ІҒ@5400–ј)Ғ@‘Қ—\”хӮЖӮөӮДҚ¬җ¬—·’cӮМҢг•ыӮр–kҗiӮМӮҝ“GӮМ‘ЮҳHӮЙ”—Ӯй Ҡe•”‘аӮНҢг•ыӮ©ӮзӮМ’З‘—•вӢӢӮМ•s‘«ӮрҺ©ӮзӮМ—ЖвaҺыҸWӮв’S‘—ӮИӮЗӮЕ•вӮўӮВӮВ‘OҗiҒA9ҢҺ15“ъ‘Ғ’©Ӯ©ӮзҲкҗДӮЙҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒB Қ¬җ¬—·’cӮНҠжӢӯӮИ“GӮМ’пҚRӮрҺуӮҜҗнӢөӮНҗi“WӮөӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA“GӮрҢЎҗ§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮНҗ¬ҢчӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҝҚс”JҺx‘аӮЖҢіҺRҺx‘а•ы–КӮМҗнӢөӮН—L—ҳӮЙҗi“WӮөҒA•ҪҸлӮМ”wҢгӮ©Ӯз“Л“ьҒA•ұҗнӮМҢӢүКҚс”JҺx‘аӮН0600Қ ӮЙӮНүІ’O‘дӮМҢҜ—vӮрҗи—МҒAӮұӮұӮЙ–CӮрҲЪӮөӮД“GӮр–ТҺЛӮөӮҪҒBӮұӮкӮЖҳAҢgӮөӮҪҢіҺRҺx‘аӮНҒA–ТҸ«ҚІ“Ўҗі‘еҚІӮМҺwҠцӮЕ“GӮМ”wҢгӮЙүфӮиҺҹҒXӮЖ“GҡЖ—ЫӮрҗи—МӮөӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМҲкҠpӮЙҢә•җ–еӮӘӮ ӮБӮҪҒBҺO‘ә’ҶҲСӮМҺwҠцӮ·Ӯй16–јӮМҢҲҺҖ‘аӮНҢә•җ–еӮЙӢЯӮГӮ«ҠJ–еӮрҺҺӮЭҒAҢҙ“cҸdӢgҲк“ҷ‘ІӮЩӮ©ӮӘ’рҗgӮө12ғҒҒ[ғgғӢӮМҸй•З“аӮ©Ӯз”тӮСҚ~ӮиӮД–е”аӮрҠJӮўӮДҢә•”–еҗи—МӮМ’[ҸҸӮрҚмӮБӮҪҒB“GӮНӢR•әӮрҠЬӮЮҗ”“xӮМӢtҸPӮрҺҺӮЭӮҪӮӘүдӮӘ”ҪҢӮӮЙӮжӮБӮД‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰӮДҢӮ‘ЮӮөӮҪҒBҗнӢөӮНҲкҗiҲк‘ЮӮМӮӨӮҝӮЙ‘ұӮҜӮзӮкҒA“ъ–vӢЯӮӯӮИӮБӮҪ1640Ғ@Қс”JҺx‘аӮМ‘O–КҸй•ЗӮМ“G•әӮН“Л”@”’ҠшӮрҢfӮ°ӮҪҒBҢрҸВӮМҢӢүК–ҫ’©ӮМҠJҸйӮр–с‘©ӮөҒAҢіҺRҺx‘аҗі–КӮМ“GӮа”’ҠшӮрҢfӮ°—Ӯ“ъӮМҠJҸйӮр–с‘©Ӯө’вҗнӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮЖӮұӮлӮӘӮұӮкӮНҗҙҚ‘ҢRӮМ–d—ӘӮЕӮ ӮБӮҪҒB2100Ғ@“GӮН–с‘©ӮрҲбӮҰ•—үJӮЖ–йүAӮЙ•ҙӮкӮД‘еӢ“ӮөӮД“Ұ‘–ӮөӮДӮўӮ«ҒAҺЛҢӮӮрӮ·ӮйӮЖ’пҚRӮ·ӮйӮұӮЖӮИӮӯ“Щ‘–ӮөӮДӮўӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҢ©ӮҪ“ъ–{ҢRӮН15“ъ2400Ӯ©ӮзҸй“аӮЙ“ЛҢӮӮөӮҪӮӘҠщӮЙ“GӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮН”s‘–ӮөӮДӮЁӮиҒAӮЩӮЖӮсӮЗ’пҚRӮИӮӯ•ҪҸлҸй“аӮр‘|“ўӮөҗи—МӮөӮҪҒBҗ¬ҠҪҒEүеҺRӮМ”sҸ«—tҺu’ҙӮН•sҗн‘ЮӢpҲДӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮЖү]ӮнӮкҒAӮ©Ӯ©ӮйҺгҸ«ӮМӮаӮЖӮЕӮНҚUҢӮҗёҗ_ӮНҠъ‘ТӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎү©ҠCҠCҗнҒ@
9ҢҺ16“ъҒ@—ьҚҮҠН‘аӮН–L“Үү«ӮрҸoҚ`ҒA“r’ҶҗҙҚ‘ҠН‘аӮр‘{ҚхӮөӮВӮВҠC—m“ҮӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒB—Ӯ17“ъ1030Ғ@ҠC—m“Ү–k“ҢӮЙ”ҒүҢӮрҠm”FҒAҗҙҚ‘ҠН‘аӮЕӮ ӮБӮҪҒB–ҫҺЎ27”N9ҢҺ17“ъ1250Ғ@Ӣ——Ј5700ӮlӮЕ“GҠшҠНҒu’иү“ҒvӮӘҚUҢӮӮрҠJҺnҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҚЕ‘еӮМҠCҗнӮМ–ӢӮНҠJӮ©ӮкӮҪҒB “ъ–{‘Ө•ә—НӮН—ьҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜҲЙ“Ў—SӢң’ҶҸ«—ҰӮўӮйҠшҠНҒuҸј“ҮҒvҲИүә12җЗҒAҗҙҚ‘ҠН‘аӮН’ҡҸ—Ҹ№’с“В—ҰӮўӮйҒu’иү“ҒvҒu’Бү“Ғv“ҷ14җЗӮЖҗ…—Ӣ’ш4җЗӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗҙҚ‘ҠН‘аӮН—A‘—‘D5җЗӮрҢмүqӮөҠӣ—ОҚ]ӮЙ’в”‘’ҶӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮҝӮзӮа“ъ–{ҠН‘аӮМ”ҒүҢӮр”FӮЯӮД“мүәӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҗҙҚ‘ҠН‘аӮМҗwҢ`ӮНҒA’ҶүӣӮЙҒu’иү“ҒvҒu’Бү“ҒvӮр”zӮөҒAҚ¶үEӮЙҠeҠНӮр”zӮ·ӮйҢг—ғ’P’тҗwҢ`(ҺOҠp‘аҢ`)ӮЕ“ъ–{ҠН‘аӮМ‘Ө–КӮЙҸХ“ЛӮ·ӮйӮжӮӨӮЙҚqҗiӮөӮДӮ«ӮҪҒBӮұӮкӮЙ‘ОӮө“ъ–{ҠН‘аӮНҒA‘ж1—VҢӮ‘аҒE–{‘аӮМҸҮӮЙ’PҸcҗwҒEҲк—сҸc‘аӮЕ—ХӮсӮҫҒBӮұӮкӮНү^“®ӮМҺ©—RӮӘӮ ӮиҒA‘¬“xӮЙҸҹӮй“ъ–{ҠН‘аӮНҗщүсӮөӮВӮВӢ——Ј3000MӮЙӢЯҗЪӮөӮДӮ©Ӯз–Т—уӮИӮй–CҢӮӮр—ҒӮСӮ№ӮҪҒB җ퓬ҠJҺn’јҢгӮ©Ӯз“GӮМҗwҢ`ӮН—җӮкҺnӮЯҒAҠшҠНҒu’иү“ҒvӮН‘Җ‘З’КҗMӢ@”\Ӯр‘№үуӮөҒAҠН‘аӮМҺwҠцӮрӮЖӮкӮИӮӯӮИӮиҠeҠНӮІӮЖӮМҚUҢӮӮЙӮИӮБӮҪҒBүE—ғӮМҒu—gҲРҒvҒu’ҙ—EҒvӮН‘ҒҒXӮЙүОҚРӮрӢNӮұӮөӮДӮЁӮиҒA“ъ–{ҠН‘аӮНҗЁӮўӮЙҸжӮ¶ӮДҗЪӢЯӮөӮД–ТҢӮӮрүБӮҰӮҪҒBҗ퓬ӮН“ъ–vӮЬӮЕ‘ұӮ«ҒAҢғҗн5ҺһҠФҒA“GҠНҒu’ҙ—EҒvҒu’vү“ҒvҒuҢoү“ҒvӮрҢӮ’ҫҒAҒu—gҲРҒvҒuҚLҚbҒvӮрқҰҚАӮіӮ№ҒA‘јӮМҠНӮЙӮа‘е‘№ҠQӮр—^ӮҰӮҪҒBҲк•ыӮМ“ъ–{ҠН‘аӮЙӮа‘Ҡ“–ӮМ‘№ҠQӮӘӮ ӮиҒAҠшҠНҒuҸј“ҮҒvӮНҺҖҸқҺТ90–јӮЙӢyӮС—EҠёӮИӮйҗ…•әӮұӮЖҺOүYҢХҺҹҳYҺO“ҷҗ…•әӮаҗнҺҖӮөӮҪҒB–{‘аҚЕҢг”цӮМҒu”дүbҒvӮНҒAҒu’иү“ҒvҒu’Бү“ҒvӮзӮЙ•пҲНӮіӮкҸW’Ҷ–CүОӮр—ҒӮСҺҖҸқҺТ50–јӮрҸoӮөҒAӮЩӮЖӮсӮЗҢҙҢ^ӮрӮЖӮЗӮЯӮИӮўӮЬӮЕ”jүуӮіӮкӮҪҒB‘¬—НӮМ’xӮўҒuҗФҸйҒvӮа“Ҝ—lӮЕҒAҠН’·ҚвҢі”ӘҳY‘ҫҸӯҚІӮНҗнҺҖӮөӮҪҒB җҙҚ‘ҠCҢRӮМҢЪ–в•җҠҜӮЖӮөӮДҒu’Бү“ҒvӮЙҸжӮиҚһӮсӮЕӮўӮҪғ}ғbғMғtғBғ“•ДҸӯҚІӮНҒAҒu“ъ–{ҠCҢRӮНҸIҺnҗ®‘RӮЖ’PҸcҗwӮрҺзӮиҒAүх‘¬Ӯр—ҳӮөӮД—L—ҳӮИӮйҢ`ӮЙӮЁӮўӮДҚUҢӮӮр”Ҫ•ңӮөӮҪӮМӮНӢБ’QӮЙ’lӮ·ӮйҒBҒvӮЖ“ъ–{ҠCҢRӮМҲкҺ…—җӮкӮК‘ҖҠНӮрҚӮӮӯ•]үҝӮөӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮЙҹr–ЕӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҗҙҚ‘ҠН‘аӮЙ‘е‘ЕҢӮӮр—^ӮҰҒAӮ»ӮМҢгӮНҲРҠCүqӮЙ•ВӮ¶ҚһӮЯү©ҠCҒE’©‘NӮМҗ§ҠCҢ ӮрӮЩӮЪҸ¶’ҶӮЙ“ьӮкӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBҺўҢгүдӮӘ—ӨҠCҢRӮМҚмҗнӮНӢЙӮЯӮД—L—ҳӮЖӮИӮиҒAҗнӢЗӮМ‘O“rӮЙ–ҫӮйӮў’ӣӮөӮӘҢ©ӮҰӮҪҒBҒ@ |
|
| “ъҗҙҗн‘Ҳ3 | |
|
ҒЎҠӣ—ОҚ]Қмҗн
•ҪҸлҗи—МҢгҒAҺRгp—L•ь‘еҸ«ӮМҺwҠцӮ·Ӯй‘ж1ҢRӮН‘ж3Һt’cҒA‘ж5Һt’cӮрҠоҠІӮЖӮөӮД9ҢҺ––ӮЬӮЕӮЙҸWҢӢӮрҠ®—№ҒAӮҪӮҫӮҝӮЙ–kҗiӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҢҲӮөҒA‘ж2ҢR(‘еҺRҠЮ‘еҸ«)ӮМ—Й“Ң”ј“ҮҸг—ӨӮЖҢДүһӮөӮДҠӣ—ОҚ]“nүНҚмҗнӮрҺАҺ{Ӯ·ӮйҸҖ”хӮрҗ®ӮҰӮҪҒBҲк•ыҗҙҚ‘ҢRӮН•ҪҸлӮМ”sҗнҢгҒAҲАҸFҒEӢ`ҸBӮЕ“ъ–{ҢRӮМ–kҗiӮЙ”ҪҢӮӮөӮҪҢгӮЙҒA‘vҢcӮр‘ҚҺwҠцҠҜӮЖӮөҒA–с18000ӮЕӢгҳAҸйӮр’ҶҗSӮЙ“с—ўӮЙӮнӮҪӮБӮД‘еҸ¬50ӮаӮМҢҳҢЕӮИҗw’nӮрҗи—МҒA15ғLғҚҸг—¬ӮМҗ…Ңы’Б‘ОҠЭ•tӢЯӮЙҲЛҚҺ“ӮҲў(ӮўӮұӮӯӮЖӮӨӮ )ӮМҺwҠцӮ·Ӯй–с5500Ӯр”z”хӮөӮДҠӣ—ОүEҠЭӮр–hҢдӮөӮҪҒB 10ҢҺ25“ъ•ҘӢЕҒ@‘ж1ҢRҺе—НӮН“G‘Oҗiҗw’nӮМҢХҺRӮЙ‘ОӮ·Ӯй“nүНҚмҗнӮрҠJҺnӮөӮҪҒB‘O“ъ–й”јӮ©Ӯз–§Ӯ©ӮЙҗiҸoӮөӮДӮўӮҪҚІ“ЎҺx‘аӮИӮЗҲк•”‘Oүq•”‘аӮНҒA“м‘ӨӮ©ӮзҢХҺRӮрҚUҢӮҒA“GҺе—НӮМ‘Ө”wӮЙ”—ӮБӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМ–йҠФҢRӢҙҚ\’zӮЖ“nүНҸҖ”хӮЙӢCӮГӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪҗҙҚ‘ҢRӮНҢХҺR•tӢЯӮрҢЕҺзӮөҒA0800Қ Ҡeҗw’nӮ©Ӯз“ъ–{ҢRӮЙ‘ОӮөӮД”ҪҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҢХҺRӮМҺеҸ«ӮН”nӢКӣАӮЕҒA‘еӮўӮЙ•ұҗнӮөҠжӢӯӮИ’пҚRӮрҺҰӮөӮД‘ж6—ь‘аӮМҲк•”ӮӘӢкӢ«ӮЙҠЧӮй’цӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺxӮҰӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёӮЙӢгҳAҸй•ы–КӮЙҢг‘ЮӮөӮҪҒB25“ъ–йҒA‘ж3Һt’cӮНүIүсӮөӮДӢгҳAҸйҚUҢӮӮМ•zҗwӮЕҳIүcҒA‘ж5Һt’cӮН”nҚaӮ©ӮзҢХҺRӮЙӮнӮҪӮй’nҲжӮЙҳIүcӮөӮДӢгҳAҸйҚUҢӮӮрҸҖ”хӮөӮҪҒB10ҢҺ26“ъ0600Ғ@•а•ә‘ж11—ь‘аӮӘӢгҳAҸй–k‘Ө‘д’nӮЙҗiҸoӮөӮДӮЭӮйӮЖ“GӮМ’пҚRӮНӮИӮӯҒAҸй“аӮНҠХҺUӮЖӮөӮДӮўӮДҗlүeӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗҙҚ‘ҢRӮНҢХҺRӮМҗ퓬ӮЙ”s‘ЮӮ·ӮйӮЖҒAҳVҸ«‘vҢcӮН25“ъ–й”ј–PҷҖҸйӮЙ‘ЮӢpӮөҒAӮұӮкӮр’mӮБӮҪҗҙҚ‘ҢRҸ”•”‘аӮа—бӮЙӮжӮБӮДҗнӮнӮёӮөӮДӢгҳAҸйӮр•ъҠьӮөӮД“Щ‘–ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМҚмҗнӮЕ“ъ–{ҢRӮНӮНӮ¶ӮЯӮД“G’nҗҙҚ‘—М“аӮЙҗи—М’nӮр“ҫӮҪҒBӮ»ӮөӮДҚ‘Ӣ«ӮМ—vҸХӢгҳAҸйӮМҸҹ•сӮӘӮаӮҪӮзӮіӮкӮйӮЖҒA–ҫҺЎ“VҚcӮН‘ж1ҢRӮЙ’әҢкӮрҺ’ӮБӮҪҒB ӮИӮЁ‘ж1ҢRӮНӢгҳAҸйӮМ–іҢҢҗи—МҢгҒA’јӮҝӮЙ’ЗҢӮӮө–PҷҖҸйӢyӮС‘е“ҢҚaӮрҗи—МҒAҗҙҚ‘ҢRӮНӮЩӮЖӮсӮЗ’пҚRӮрҺҰӮіӮёӮЙҺO•ы–КӮЙ”s‘–ӮөӮҪҒB“GҸ«‘vҢcӮаҺе—НӮЖӮЖӮаӮЙ•т“V•ы–КӮЙ“ҰӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—·ҸҮҚU—Әҗн
ү©ҠCҠCҗнӮЕҗ§ҠCҢ Ӯр“ҫӮҪүдӮӘҢRӮНҒA‘еҺRҠЮ‘еҸ«ӮМҺwҠцӮ·Ӯй‘ж2ҢRӮр•Тҗ¬ҒA—·ҸҮ—vҚЗӮрҚU—ӘӮ·ӮйӮҪӮЯ10ҢҺ24“ъӮ©ӮзӢаҸB”ј“ҮӮМүФүҖҢыӮЙҸг—ӨӮөӮҪҒB“G‘OҸг—ӨӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҗҙҚ‘ҢRӮМ’пҚRӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯҒA‘ж1Һt’cӮН11ҢҺ6“ъӮЙӮН”ј“ъ‘«ӮзӮёӮМҚUҢӮӮЕӢаҸBҸйӮрҗи—МҒA“G•ә3500ӮН—·ҸҮҢыӢyӮС‘еҳAҳp•ы–КӮЙ‘ЮӢpҒAүдӮӘҺҖҸқҺТӮН25–јӮЙ—ҜӮЬӮБӮҪҒB”s‘–Ӯ·ӮйҗҙҚ‘ҢRӮр’ЗҢӮӮ·Ӯй‘ж1Һt’cӮН11ҢҺ8“ъӮЬӮЕӮЙ‘еҳAҳpҸ”–C‘дӮрӮ·ӮЧӮДҗи—МҒAҗнҲУӮрҺёӮБӮҪҗҙҚ‘ҢRӮНӮұӮұӮЕӮа—·ҸҮҢыӮЬӮЕ”s‘–ӮөӮҪҒB11ҢҺ17“ъ‘ж2ҢRӮНӢаҸBӮрҸo”ӯҒA“r’Ҷ‘OүqӮМҲк•”ӮӘҗҙҚ‘•”‘аӮМ”ҪҢӮӮЙӢкҗнӮөӮҪ‘јӮН‘еӮ«ӮИ’пҚRӮаӮИӮӯ20“ъӮЙӮН—·ҸҮ”w–К–hҢдҗьӮЙҗiҸoӮөӮҪҒB —·ҸҮӮНҗҙҚ‘–k—mҠН‘аӮМҚЕҸd—vҢRҚ`ӮЕӮ ӮиҒAӢҗ–ңӮМҚаӮЖ10җ””NӮМҺһ“ъӮр”пӮвӮөӮД“–ҺһӮМҗVҺ®–C‘дӮрҚ\’zӮөӮҪ“Ң—mҲкӮМ—vҚЗӮЕҒA13ӮМүiӢv–C‘дӮЖ4ӮВӮМ—ХҺһ–C‘дӮЙӮНҒAғJғmғ“–CҒAҺR–CӮИӮЗҠeҺн–с100–еӮӘ”z”хӮіӮкӮДӮўӮҪҒB—ӣҚғҸНӮН‘қүҮӮЙ“wӮЯӮҪӮӘҒAүдӮӘ—ӨҠCҢRӮЙ‘jӮЬӮкӮДҸ\•ӘӮИ‘қүҮӮӘӮЕӮ«ӮёҒA—vҚЗҺз”х‘а–с8000ӮЖ‘еҳAӮМ”sҺc•ә–с4000ӮӘҺз”хӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮМӮӨӮҝ–с9000ӮНҗVӢK’Ҙ•е•әӮЕӮ ӮиҒAҺз”х‘аҺwҠцҢn“қӮН•ЎҺGӮЕҒAҺАҺҝ“IӮИ‘ҚҺwҠцҠҜӮН•¶ҠҜӮЕӮ ӮиҺзҸ«ӮМҢҲҲУӮНӮИӮӯ—Н—КӮЙҢҮӮҜӮҪҒB”zүәӮМҸ«•әӮҪӮҝӮа“ъ–{ҢRӮМ‘еҳAҗи—МӮЙҳT”ӮӮөӮД“Ұ–SӮ·ӮйӮаӮМӮӘ‘ҠҺҹӮ¬ҒA‘ў‘DҸҠӮМҠҜ—ҷӮаӢMҸd•iӮр“җӮсӮЕ“Ұ‘–ӮөҒA—·ҸҮҺsҠXӮН‘еҚ¬—җӮЖү»ӮөӮДӮўӮҪҒB 11ҢҺ21“ъ–ў–ҫҒ@—·ҸҮҢыҚUҢӮӮМүОҠWӮӘҗШӮзӮкӮҪҒB‘ж1—·’cҒA‘ж12—·’cӮӘҗј•ы“Ң•ыӮ©ӮзӮ»ӮкӮјӮкҢЎҗ§Ӯ·Ӯй’ҶҒA‘ж1Һt’cӮН—·ҸҮӮМҺг“_ӮЕӮ Ӯйҗј–kҗі–КӮ©ӮзҒA‘ж2—·’cӮНҲДҺqҺR–C‘дҢSӮМҚU—ӘӮрҠJҺnӮөӮҪҒB0800ӮЙӮНҲЦҺqҺRӮрҗи—МҒAҸјҺчҺRҒA“с—іҺRӮМ–C‘дӮаҺҹҒXҠЧ—ҺҒA”ј“ъӮМҗ퓬ӮЕҗі–КӮМ–C‘дӮНӮұӮЖӮІӮЖӮӯ“ъ–{‘ӨӮЙӢAӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮӘ–C‘дҢQӮрҚU—ӘӮөӮД—·ҸҮҺsҠXӮЙ”—ӮйӮМӮр’mӮйӮЖҒAҗҙҚ‘ҢR•”‘аӮН’Ч—җӮөӮ ӮйҺТӮНҢR•һӮр’EӮўӮЕҺs–ҜӮр‘•ӮБӮД“Ұ‘–ӮөӮҪҒBҢЯҢгӮЙӮИӮиҠCҠЭ–C‘дӮМҚUҢӮӮЙ’…ҺиӮөҒAү©ӢаҺR–C‘дӮЙ“Л“ьҒAҷгҡ^ҚUҢӮӮЙӮжӮБӮД“пӮИӮӯӮұӮкӮрҗи—МӮөӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДҠCҗі–К–h”хӮМ–C‘дҢQӮаӮұӮЖӮІӮЖӮӯүдӮӘҸ¶’ҶӮЙҠЧӮиҒA1700ӮЙӮН‘еҗЁӮНҢҲӮөӮҪҒB“Ң—mҲкӮМ‘е—vҚЗӮНҗўҠEӮМҢRҺ–җк–еүЖӮМ—\‘zӮр— җШӮиӮнӮёӮ©Ҳк“ъӮЕҠЧ—ҺӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМүхҸҹӮН—·ҸҮ—vҚЗӮМҢyҺӢӮЖӮИӮиҒAӮМӮҝӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮД—·ҸҮҚUҢӮҚмҗнӮМҺё”sӮЙҢqӮӘӮйӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҲРҠCҚtҚмҗн
—·ҸҮҠЧ—ҺҢгӮа–k—mҠН‘аӮНҲРҠCүqҢRҚ`“аӮЙҲшӮ«ҳUӮиҹЭҠCҳpҢыӮр–hҢмӮөӮДҸoҢӮӮМӢC”zӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҠCҸгӮ©ӮзҢӮ–ЕӮ·ӮйӮұӮЖӮаҳpҢыӮрҠ®‘SӮЙ••ҚҪӮ·ӮйӮұӮЖӮаҚў“пӮЕӮ ӮиҒA‘ж2ҢR‘еҺRҺi—ЯҠҜӮЖ—ьҚҮҠН‘аҲЙ“ҢҺi—Я’·ҠҜӮНҳA–јӮЙӮДҺR“ҢҚмҗнҒ^ҲРҠCүqҚU—ӘӮМҲУҢ©Ӣпҗ\ӮрҚsӮБӮҪҒB‘ҰӮҝҗҙҚ‘–k—mҠН‘аӮрүу–ЕӮіӮ№ҒA’ј—к•Ҫ–мӮЕӮМҢҲҗнӮМ‘O’сӮрӮВӮӯӮиҗҙҚ‘ӮЙҚuҳaӮрҗҝӮнӮөӮЯӮй–Ъ“IӮЕҺАҺ{ӮөӮҪҚмҗнӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҲРҠCүqӮНҺR“ҢҸИӮМ–kҠЭӮЙӮ ӮБӮДҠCӢ¬ӮрӮЦӮҫӮДӮД—·ҸҮҢыӮЖ‘Ҡ‘ОӮ·Ӯй’ј—кҳpҚД—vӮМ—vҚЗӮЕӮ ӮйҒB—·ҸҮӮЙ•C“GӮ·Ӯй10”N—]ӮМҚОҢҺӮЖӢҗ”пӮр”пӮвӮөӮДҚ\’zӮіӮкӮҪ—vҚЗӮЕҒA24ғZғ“ғ`ғJғmғ“–CҲИүә161–еӮМүО–CҒEӢ@ҠЦ–CӮр”хӮҰӮДӮўӮҪҒBӮұӮұӮЕӮаҺwҠцҠҜӮН•¶ҠҜӮЕӮ ӮиҒAҺз”х•әӮМ‘ҪӮӯӮНҗVӢK’Ҙ•еӮМҺТӮӘ‘ҪӮӯ‘ҠҺҹӮ®”sҗнӮЙҺmӢCӮН’бүәӮөӮДӮўӮҪҒB —ӨҸгҗ퓬 1ҢҺ20“ъӮ©Ӯз“ъ–{ҢRӮНүhҸйҳpӮЙҸг—ӨӮрҠJҺnҒA—ьҚҮҠН‘аӮМҺxүҮ–CҢӮӮМүәӮЙӮЬӮё—Өҗн‘аӮӘҸг—ӨҒAӮВӮўӮЕ‘ж6ҒA‘ж2Һt’cӮӘҸг—ӨӮөӮҪҒBҠe‘аӮН26“ъӮрҠъӮөӮДҗiҢӮӮрҠJҺnҒA“r’Ҷ•SҺЪҠRӮЙӮЁӮўӮД•а•ә‘ж11—·’c’·‘еҺӣҲАҸғҸӯҸ«ӮНҗнҺҖҒAҸ«ҠҜӮМҗнҺҖҺТӮН‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮЬӮЕ‘еҺӣҸӯҸ«ӮҪӮҫҲкҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒB2ҢҺ1“ъҒ@‘еҺRҢRҺi—ЯҠҜӮН‘ҚҚUҢӮӮрҠJҺnҒAҚ~җбӮр–`ӮөӮД–k‘Ө—vҚЗӮЙҢьӮ©ӮБӮД‘OҗiӮөӮҪӮӘҒAҗҙҚ‘ҢRӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮНҠщӮЙ‘ЮӢpӮөӮДӮЁӮи‘еӮ«ӮИ’пҚRӮрҺуӮҜӮйӮұӮЖӮИӮӯ2“ъӮЬӮЕӮЙҲРҠCүqҺsҠXӮЖҡЖ—ЫҢQӮрҚU—ӘӮөӮҪҒB ҠCҸгҗ퓬 2ҢҺӮМҲРҠCүqӮНҠҰӢCӮН•X“_үәӮрҺҰӮөҒAҠН‘МӮН•XӮЕ•ўӮўҗsӮӯӮіӮкҸ¬ҠН’шӮНҚqҚs•s”\ӮМҸу‘ФӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@2ҢҺ3“ъ–ў–ҫҒ@үдӮӘҗ…—Ӣҗн‘аӮНҚrӮкӢ¶ӮӨҚ`“аӮЙҗi“ьҒAҢҲҺҖ“IӮИҠпҸPҚUҢӮӮрҠёҚsӮөӮҪҒBҠпҸPҚUҢӮӮН5“ъӮЙӮаҺАҺ{ӮіӮкҒB0320Ғ@“GҠшҠНҒu’иү“ҒvӮр‘е”jҒAҒu—Ҳү“ҒvҒuҲРү“ҒvӮЩӮ©ҲкҗЗӮрҢӮ’ҫӮөӮҪҒBҒ@2ҢҺ7“ъҒ@ҲЙ“Ң’·ҠҜӮН‘SҠН‘аӮрӮаӮБӮД“G–C‘дӮМ–hҢд—НӮЙ’v–Ҫ“I‘е‘ЕҢӮӮр—^ӮҰҗҙҚ‘ҠCҢRӮМҗнҲУӮр’ҳӮөӮӯ‘rҺёӮіӮ№ӮҪҒB9“ъӮЙӮНҒu–хү“ҒvӮӘҢӮ’ҫҒA‘е”jӮөӮҪҠшҠНҒu’иү“ҒvӮНҺ©’ҫӮөҠН’·ӮНҺ©ҢҲӮөӮҪҒB2ҢҺ10“ъҒ@ҠeҠН’·ӮзӮН’ҡ“рҸ№’с“ВӮЙҚ~•ҡӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӢӯ—vҒAҠщӮЙҚ~•ҡӮМӢCӮӘҗҙҚ‘‘SҠН’шӮЙ– ү„ӮөӮДӮЁӮи’ҡ’с“ВӮНҚ~•ҡӮМҢҲҲУӮЙҺҠӮБӮҪҒB’ҡ’с“ВӮЖҗeҢрӮМӮ ӮБӮҪҲЙ“ҢҺi—Я’·ҠҜӮНҒA•’“ёҺрӮЖҢНҳIҠ`Ӯр‘ЎӮиӮ»ӮМҳJӮрҲФӮЯӮҪӮӘҒA12“ъ’ҡ’с“ВӮНҒAҲЙ“Ў’·ҠҜӮМ—FҸоӮрҗ[ӮӯҺУӮөҒA•”үәҸ«•әӮМҸ•–ҪӮрҢоӮӨӮД–Ӣ—»“с–јӮЖӮЖӮаӮЙҺ©ҢҲӮөӮҪҒBҲЙ“Ң’·ҠҜӮН’ҡӮМҺҖӮр“үӮЭҒA—зӮрҗsӮӯӮөӮДӮ»ӮМҲв‘МӮрҗҙҚ‘ӮЙ‘—ҠТӮөӮҪҒBӮұӮМҢoҲЬӮН“ъҗҙ—јҚ‘ӮЙҗ[ӮўҠҙ–БӮр—^ӮҰӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮДҲРҠCүqӮНҠЧ—Һ–k—mҠН‘аӮН‘S–ЕӮөҒAҗ§ҠCҢ ӮНӮ·ӮЧӮД“ъ–{ӮЙӢAӮөҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМ’ј—кҚмҗнӮрҸҖ”хӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж2ҠъҚмҗнҢvүж
үдӮӘҢRӮН—ӨҠCӮЙ‘SҸҹӮрҺыӮЯҒA—Й“Ң”ј“Ү“аӮМ“GӮрҢӮ”jӮө‘еҳA•ы–КӮЙ“]җiӮөӮҪ‘ж1ҢRӮНҒA3ҢҺ5“ъҒ@ӢҚ‘‘Ӯрҗи—МҒA9“ъӮ©ӮзӮН“cҸҜ‘д•tӢЯӮМ“GӮр•пҲНҚUҢӮӮөӮұӮкӮрҗи—МҒA–һҸB“аҚмҗнӮрҸI—№ӮөӮҪҒBӮЬӮҪ3ҢҺ26“ъӮЙӮН—ӨҢRӮМ”дҺu“ҮҺx‘аӮЙӮжӮБӮДаOҢО“ҮӮрҗи—МҒAҺx“ЯҠC•ы–КӮЙӮЁӮҜӮйҠCҢRҚӘӢ’’nӮЖӮ·Ӯй–Ъ“IӮр’Bҗ¬ӮөӮДӮўӮҪҒB ‘е–{үcӮНҺҹӮМҺеҚмҗнӮЕӮ Ӯй’ј—к•Ҫ–мӮЕӮМ–мҗнҢRҢҲҗнӮМӮҪӮЯҒA‘ж2ҠъҚмҗнҢvүжӮӘҺАҢ»ӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB’ј—кҚмҗнӮЙҺQүБ—\’иӮМ•ә—НӮНҠщӮЙҸoҗӘӮөӮҪ4ҢВҺt’cӮЙүБӮҰҒAӢЯүqҒA‘ж4Һt’cӮЩӮ©ӮЕ‘SҢR–с20—]–ңӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮН“–Һһ“®ҲхӮӘ—\‘zӮіӮкӮйҗҙҚ‘ҢR–с20–ңҗlӮЙ”дӮЧӮвӮв—DҗЁӮЕӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮзӮкӮҪҒBӮұӮкӮр“қ—ҰӮ·ӮйӮҪӮЯҒAҺQ–d‘Қ’·ҒEҸ¬ҸјӢ{ҸІҗm‘еҸ«ӮрҗӘ“ў‘е‘Қ“ВӮЙҒAҗмҸг‘ҖҳZ’ҶҸ«ӮЖҠ’ҺRҺ‘ӢI’ҶҸ«Ӯр‘ҚҺQ–d’·ӮЙ”CӮ¶ҒAҚмҗнҸҖ”х’ҶӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA4ҢҺ17“ъӮЙҚuҳaҸр–сӮӘ’ІҲуӮіӮкӮҪӮҪӮЯҒAҗҙҚ‘ҢRӮЙ‘ОӮ·ӮйҚмҗн’вҺ~ӮӘ”ӯ—ЯӮіӮкӮҪҒB—Й“Ң”ј“ҮӮЖҲРҠCүqӮЙҺз”х•”‘аӮрҺcӮөҒA•”‘аӮН’ҖҺҹ“а’nӮЙҠMҗщӢAҚ‘ӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүәҠЦҚuҳaҸр–с
“ъҗҙҠJҗнҲИ—ҲҳAҗнҳA”sӮМҗҙҚ‘ӮНҒA–ҫҺЎ27”NҸү“~Ӯ©ӮзҲк“ъӮа‘ҒӮўҗн‘ҲҸIҢӢӮр–]ӮсӮЕӮўӮҪҒBӮҫӮӘ‘еҚ‘ӮМ‘М–КӮрӢCӮЙӮ·ӮйҗҙҚ‘ӮН”sҗнҚ‘ӮЖӮөӮДҗнҸҹҚ‘ӮҪӮй“ъ–{ӮЙҳaӮрҚuӮ¶ӮжӮӨӮЖӮ·ӮйӮЩӮЗӮМҢҲҲУӮаӮИӮӯҒA–§Ӯ©ӮЙүў•ДҠeҚ‘ӮЙ‘ОӮө’ҮҚЩӮМҳJӮрӮЖӮБӮД—~ӮөӮўӮЖҚ§ҠиӮөӮҪӮӘҗјүўҠeҚ‘ӮНӮўӮёӮкӮаӮұӮкӮЙүһӮ¶ӮжӮӨӮЖӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB 12ҢҺ17“ъҒ@“V’ГҠCҗЕ–ұҺiӮМғfғgғҠғ“ғOӮЖӮўӮӨғhғCғcҗlӮӘ—ӣҚғҸНӮ©ӮзҲЙ“Ў”Һ•¶Һс‘ҠӮЦӮМҸЖүпҸ‘ӮрҺқӮБӮДҗ_ҢЛӮЙҢ»ӮкӮҪҒBӮұӮкӮН“ъ–{җӯ•{ӮМҚlӮҰӮДӮўӮйҚuҳaҸрҢҸӮр’TӮйӮҪӮЯӮЖҺvӮнӮкҒAӮ»ӮМҺ‘ҠiӮЙӮа•sҗRӮИ“_ӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕ“ъ–{җӯ•{ӮН–КүпӮрҺУҗвӮөӮҪҒBҗҙҚ‘җӯ•{ӮНӮ»ӮМҢгӮаҗ”“xӮЙӮнӮҪӮи•ДҚ‘ҢцҺgӮр’КӮ¶ӮДҚuҳaӮрҗ\ӮөҚһӮсӮЕӮ«ӮҪӮӘҒAҚuҳa’сӢcӮЙӮВӮўӮДӮ»ӮМҗҪҲУӮЙӢ^–вӮрҺқӮБӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮНҒAҗҙҚ‘җӯ•{ӮЙ“ъ–{ӮМҲУҗ}Ӯр’mӮзӮөӮЯӮйӮҪӮЯҒA•ДҚ‘ҢцҺgӮр’КӮ¶ӮДҒA ҒwҢRҺ–”…ҸһӮЖ’©‘N“Ж—§ӮрҠm”FӮ·ӮйӮЩӮ©ҒA“y’nӮМҠ„ҸчӮЖҸ«—ҲӮМҚ‘ҢрӮр—ҘӮ·ӮйҸр–с’чҢӢӮрҠо‘bӮЖӮөӮДҒA‘SҢ Ӯр—LӮ·ӮйҺgҗЯӮр”hҢӯӮөӮИӮҜӮкӮОүҪӮзӮМҚuҳaӮа–іҢшӮЕӮ ӮйҒBҒxӮЖҗйҢҫӮөӮҪҒB 2ҢҺ18“ъҒ@җҙҚ‘җӯ•{ӮН•ДҚ‘ҢцҺgӮр’КӮ¶ӮД—ӣҚғҸНӮр‘SҢ ‘еҗbӮЙ”C–ҪӮөӮҪӮМӮЕүпҚҮҸкҸҠӮрҺwҺҰӮіӮкӮҪӮўҒAӮЖӮ·Ӯйҗ\Ӯө“ьӮкӮрҚsӮБӮҪҒB3ҢҺ14“ъҒ@—ӣҚғҸНӮН“V’ГӮрҸo”ӯӮөӮДүәҠЦӮЙҢьӮ©Ӯў3ҢҺ20“ъӮ©ӮзҸt”ҝҳOӮЕ‘ж1үсүпҚҮӮрҠJӮўӮҪҒBҗҙҚ‘‘SҢ ӮНҚuҳaүпӢcӮМ‘OӮЙ‘ҰҺһӢxҗнӮр—vҗҝҒA“ъ–{‘Ө‘SҢ ӮЖӮНӢxҗнҸрҢҸӮЕ“пҚqӮөӮДӮўӮҪӮЖӮұӮлҒA3ҢҺ24“ъҒ@“ъ–{’ҶӮрҗkқһӮіӮ№ӮҪҸ¬ҺRҳZ”VҸ•(–L‘ҫҳY)ӮЙӮжӮй—ӣҚғҸН‘_ҢӮҺ–ҢҸӮӘ”ӯҗ¶ӮөӮҪҒBӮұӮМҺ–ҢҸӮЙӮжӮи“ъ–{ӮМҚuҳaҠOҢрӮНҲкӢCӮЙӢкӢ«ӮЙҠЧӮиҒA–ҫҺЎ“VҚcӮМҗ№Һ|ӮЙӮжӮБӮД’јӮҝӮЙ‘S6ҸрӮ©ӮзӮИӮйӢxҗнҸр–сӮӘ’чҢӢӮіӮкӢxҗнӮӘҗ¬—§ӮөӮҪҒBҢҫӮнӮО—ӣҚғҸН‘ҳ“пҺ–ҢҸӮМ‘гҸһӮЖӮөӮДӢxҗнӮӘҗ¬—§ӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҢгӮаҚuҳaҸр–сӮЙӮВӮўӮДӢҰӢcӮрҸdӮЛҒAҗҙҚ‘‘Ө‘SҢ ӮМҗҪҲУӮМӮИӮўӢмӮҜҲшӮ«ӮЙ‘ОӮөҒA“ъ–{‘Ө‘SҢ ӮӘ•®ҢғӮөӮДӢә”—“IҢҫҺ«ӮЕүһҸVӮ·ӮйҲк–ӢӮаӮ ӮБӮҪӮӘҒA4ҢҺ17“ъӮЙӮН“ъҗҙҚuҳaҸр–сӢyӮС•t‘®Ӣc’иҸ‘ӮМ’ІҲуӮрҸIӮҰӮҪҒB –ҫҺЎ28”N4ҢҺ17“ъ’ІҲуӮМҚuҳaҸр–сӮМҺеӮИ“а—eӮНҲИүәӮМӮЖӮЁӮиҒB Ғ@Ғ@ҒE’©‘N“Ж—§ӮМҠm”F Ғ@Ғ@ҒE—Й“Ң”ј“ҮҒA‘дҳpҒAаOҢО“ҮӮМҠ„Ҹч Ғ@Ғ@ҒE”…ҸһӢа2үӯғeҒ[ғӢӮМҺx•Ҙ Ғ@Ғ@ҒE’КҸӨӮЙҠЦӮөҒAҗјүў—сӢӯӮЖӢП“ҷӮМҢ —ҳӮМҺц—^ Ғ@Ғ@ҒEҠJҚ`ҸкӮЖҠJҺsҸкӮЙӮЁӮҜӮйҚHӢЖҠйӢЖҢ ӮМҠm—§ Ғ@Ғ@ҒEҸр–с—ҡҚsӮМ’S•ЫӮЖӮөӮДҲРҠCүqӮМҗи—МҒ@ |
|
|
ҒЎҺOҚ‘ҠұҸВ
“ъҗҙӮМҚuҳaӮӘҗ¬—§ӮөҒA‘SҚ‘–ҜӮӘҗнҸҹӮЙҗҢӮБӮДӮўӮҪӮЖӮ«ҒAӢ}“]’јүәҒA‘SҚ‘–ҜӮрӮөӮДҗFӮрҺёӮнӮөӮЯӮҪӮМӮНҒAғҚғVғAҒAғhғCғcҒAғtғүғ“ғXӮЙӮжӮйҺOҚ‘ҠұҸВӮЕӮ ӮйҒB4ҢҺ23“ъҒ@ҚЭӢһӮМҺOҚ‘ҢцҺgӮНҠO–ұҸИӮЙҠO–ұҺҹҠҜӮр–KӮЛҒAҒw“ъ–{ӮӘ—Й“Ң”ј“ҮӮрҸҠ—LӮ·ӮйӮұӮЖӮНҒA“Ң—mүiү“ӮМ•ҪҳaӮЙҠQӮӘӮ ӮйӮ©Ӯ瑬ӮвӮ©ӮЙӮұӮкӮр•ъҠьӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒxӮЖҠ©ҚҗӮөӮҪҒBӮВӮўӮЕҗҙҚ‘җӯ•{ӮаӮұӮМҠұҸВӮрҢыҺАӮЙҚuҳaҸр–сӮМ”бҸyү„ҠъӮр—vӢҒӮөӮДӮ«ӮҪҒB җјүў—сӢӯӮӘҠұҸВӮЙӮЕӮйӮұӮЖӮНҲИ‘OӮ©ӮзӮ Ӯй’ц“x—\‘zӮіӮкӮҪӮұӮЖӮЕҒA•KӮёӮөӮа“Ӯ“ЛӮМҸo—ҲҺ–ӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢЙ“ҢӮЦӮМ“ҢҗNҗӯҚфӮрӮЖӮБӮДӮўӮҪғҚғVғAӮНӮ©ӮЛӮДӮжӮи“ъҗҙ–в‘иӮЙӮНҠЦҗSӮрҺҰӮөҒAҺb’и“IҢ»ҸуҲЫҺқҗӯҚфӮ©Ӯзҗн‘Ҳ’ҶӮНҲкүһҗГҠПӮМ—§ҸкӮрӮЖӮБӮДӮўӮҪҒBӮЖӮұӮлӮӘ—\‘zӮЙ”ҪӮө“ъ–{ӮӘ‘еҸҹӮр”ҺӮ·ӮйӮЖҢ©ӮйӮвҒA‘е—ӨҠ„ҸчӮНҢ»Ҹу•ПҚXӮЙӮИӮйӮұӮЖӮ©ӮзғҚғVғAӮМ‘Ф“xӮНҗПӢЙ“IӮЖӮИӮиҒAҗN—Ә“IҲУҗ}Ӯр”ҚӮ«ҸoӮөӮЙӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ғtғүғ“ғXӮНҒA“–ҺһӮМҠOҢрҠЦҢWӮ©ӮзӮЭӮДӮ»ӮМҗ¶‘¶ҸгғҚғVғAӮЖӮМ–§җЪӮИҠЦҢWӮӘӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮӘҠұҸВӮрҢҲҲУӮөғhғCғcӮӘӮұӮкӮЙүһӮ¶Ӯй“®Ӯ«ӮрҺҰӮ·ӮЖҒAҗЁӮўӮұӮМ“сҚ‘ӮЙҸ]ӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮў—§ҸкӮЙӮ ӮБӮҪҒBӮЬӮҪғhғCғcӮНҠJҗн“–ҸүӮ©Ӯз“ъ–{ӮЙҚDҲУ“IӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘӮ»ӮМҚs“®ӮНӮ ӮўӮЬӮўӮИ“_ӮӘҸӯӮИӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB–§Ӯ©ӮЙҗҙҚ‘ӮЙ‘ОӮөҗнҺһӢЦҗ§•iӮр—AҸoӮөӮҪӮи‘Ю–рҸ«ҚZӮрҗҙҚ‘ӮЙҠЦҢWӮіӮ№ӮҪӮиӮөӮДҺ©Қ‘ӮМ—ҳүvӮрҗ}ӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB“Ң—mӮМ—ҳҠQҠЦҢWӮӘ”дҠr“IҸӯӮИӮўғhғCғcӮЙӮЖӮБӮДҒAҳI•§“Ҝ–ҝӮНӢәҲРӮЕӮ ӮиӮұӮМӢ@үпӮЙҳI•§“сҚ‘ӮЙҗЪӢЯӮрҗ}ӮиҒAғҚғVғAӮМҗЁ—НӮрүўҸBӮ©ӮзӢЙ“ҢӮЙҢьӮҜӮй•K—vӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮўӮёӮкӮаҚ‘ҚЫҠЦҢWӮМ•ЎҺGӮіӮӘ—ҚӮсӮҫҢӢүКӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮМҠO–ұ“–ӢЗӮНӮұӮМ•ЎҺGӮИҚ‘ҚЫҸоҗЁӮрҗіӮөӮӯ—қүрӮөӮДӮНӮЁӮзӮёҒA—ӨҢRӮӘ‘nҗ¶ҠъӮЙӢіҺtҚ‘ӮЖӮөӮДӮўӮҪ“ЖҒE•§ӮМ“Ҝ’ІӮрҸХҢӮ“IӮЙҺуӮҜҺ~ӮЯӮҪҒB ’ҶӮЕӮаҢц‘RӮЖҠұҸВӮМ“xӮрӢӯӮЯӮҪӮМӮНғҚғVғAӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ъ–{ӮЙ’в”‘’ҶӮМҠН‘DӮЙҸoҚ`ҸҖ”хӮр–ҪӮ¶ӮҪӮи—\”х•әӮрҸўҸWӮ·ӮйӮИӮЗӮЖӮўӮБӮҪ‘О“ъңҳҠ…ӮрӢп‘Мү»ӮіӮ№ӮДӮЁӮиҒAҺOҚ‘ҠұҸВӮМ’Ј–{җlӮӘғҚғVғAӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮН–ҫ”’ӮЕӮ ӮБӮҪҒB 4ҢҺ24“ъҒ@ҚL“Ү‘е–{үcӮЕҺOҚ‘ҠұҸВӮМӮұӮЖӮрӢcӮ·ӮйҢд‘OүпӢcӮӘҠJӮ©ӮкӮҪҒBҲЙ“Ў”Һ•¶Һс‘ҠӮНҚМӮйӮЧӮ«ҲДӮЖӮөӮД3ҲДӮр’сҺҰӮөӮҪҒB Ғ@1Ғ@ӮҪӮЖӮҰҗVӮҪӮЙ“GҚ‘ӮӘ‘қүБӮ·ӮйӮаҺOҚ‘ӮМҠ©ҚҗӮр’fҢЕӢ‘җвӮ·Ӯй Ғ@2Ғ@—сҚ‘үпӢcӮрҠJҚГӮө—Й“Ң”ј“Ү–в‘иӮрӢҰӢcӮ·Ӯй Ғ@3Ғ@Ҡ©ҚҗӮр—eӮкҗҙҚ‘ӮЙү¶Ңb“IӮЙҠТ•tӮ·Ӯй ҲИҸг3ҲДӮЙӮВӮўӮД“ўӢcӮрҗsӮӯӮөӮҪӮӘҒA1ҲДӮНҒA—ӨҠCҢRӮМҗн—НҸг“һ’кҸҹӮҝ–ЪӮНӮИӮўҒB2ҲДӮНҒA—сҚ‘үпӢcӮӘӮ©ӮҰӮБӮДҗVӮҪӮИҠұҸВӮр“ұӮӯҠлҢҜҗ«ӮӘӮ ӮиҒAҢӢӢЗҺOҚ‘ӮМҠ©ҚҗӮр—eӮкӮҙӮйӮр“ҫӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъ–{ҠOҢрӮМ”s–kӮЕӮ ӮБӮҪҒB–ҫҺЎ28”N5ҢҺ10“ъҒ@—Й“Ң”ј“ҮҠТ•tӮМҸЩ’әӮӘүәӮиҒA‘SҚ‘–ҜӮН–ңқНӮМ—ЬӮр“ЫӮсӮЕҺOҚ‘ӮМ•җ—НҠұҸВӮМ‘OӮЙӢьӮөӮҪҒBӮвӮӘӮДҒAғҚғVғAҢӮӮВӮЧӮөӮЖӮМҗәӮӘҠъӮ№ӮёӮөӮД•ҰӮ«ӢNӮұӮиҒAҒuүзҗdҸҰ’_ҒvӮН‘SҚ‘–ҜӮМҚҮҢҫ—tӮЖӮИӮБӮД•xҚ‘Ӣӯ•әӮЙ“wӮЯӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮұӮМӮЖӮ«Ӯ©Ӯз“ъҳIҗн‘ҲӮЬӮЕӮМ10”NҠФӮНӢЯ‘г“ъ–{ҺjҸгҚЕӮа–Ҝ‘°“IҲУҺҜӮМ”ӯ—gӮөӮҪҺһҠъӮЖӮИӮиҒAҒuүзҗdҸҰ’_ҒvӮН“ъҳIҗн‘ҲӮЕҗhӮӨӮ¶ӮДҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮйҢҙ“®—НӮЖӮИӮБӮҪҒB ӮИӮЁ‘е“ҢҲҹҗн‘ҲӮМ“®ҲцӮМҲкӮВӮНҒAҺx“ЯҺ–•ПӮЙ‘ОӮ·Ӯй—сҚ‘ӮМҸУүоҗОӮЦӮМүҮҸ•Ғ|ӮўӮнӮдӮйүҮҸУҒ|ӮМ”rҸңӮЙӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺx“Я‘е—ӨӮЙ‘ОӮ·ӮйүдӮӘҗЁ—НӮМҠg‘еӮр‘jҺ~ӮөҒA–WҠQӮөӮжӮӨӮЖӮ·Ӯй—сӢӯӮМ“®Ӯ«ӮНҒAҠщӮЙӮ»ӮМ45”N‘OӮЙӮЁӮўӮДҢ©ӮзӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ—·ҸҮҚUҲНҗн | |
| –ҫҺЎ37”N-–ҫҺЎ38”N(1904/8/19〜1905/1/1)ӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮҜӮйҗ퓬ӮМҲкӮВҒBғҚғVғA’йҚ‘ӮӘ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМ•кҚ`ӮЖӮөӮДӮўӮҪ—·ҸҮҚ`ӮрҺзӮй—·ҸҮ—vҚЗӮр“ъ–{ҢRӮӘҚU—ӘӮөҠЧ—ҺӮіӮ№ӮҪҒBҒ@ | |
| ҒЎ”wҢi | |
|
ғҚғVғAӮНҒA1898”NӮМ—Й“Ң”ј“Ү‘dҺШҲИҚ~ҒA—·ҸҮҢыӮрҚӘӢ’’nӮЖӮ·Ӯй—·ҸҮҠН‘а(‘ж1‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а)ӮрӢЙ“ҢӮЙ”z”хӮөҒA—·ҸҮҢыӮрҲНӮЮҺRҒXӮЙ–{Ҡi“IӮИүiӢv—vҚЗӮрҢҡҗЭӮөӮДӮўӮҪҒB“ъ–{ӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒA“ъ–{–{“yӮЖ’©‘N”ј“ҮӮЖӮМҠФӮМ•вӢӢҳHӮМҲА‘SӮМҠm•ЫӮӘҢҮӮ©Ӯ№ӮёҒAӮөӮҪӮӘӮБӮД’©‘N”ј“ҮҺь•УҠCҲжӮМҗ§ҠCҢ ӮрүҹӮіӮҰӮйӮұӮЖӮӘ•Kҗ{ӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮН—·ҸҮҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮ·Ӯй•K—vӮӘӮ ӮйӮЖ‘z’иӮөӮДӮўӮҪҒBӮЬӮҪҚЕҸI“IӮЙ—·ҸҮӮЙ—§ӮДвДӮБӮҪғҚғVғA—ӨҢRҗЁ—Н(2ҢВҺt’c)ӮН“ъ–{ҢRӮМ•вӢӢӮЙӮЖӮБӮДҸd—vӮИ‘еҳAҚ`ӮЙ‘ОӮ·ӮйӢәҲРӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB
1903”N12ҢҺ30“ъӮЙ—ӨҠCҢRҠФӮМҚмҗнӢҰӢcӮӘҚsӮнӮкҒAҒu—·ҸҮҚ`ҠOӮЙ’в”‘ӮөӮДӮўӮй—·ҸҮҠН‘аӮЙ‘ОӮ·ӮйҠпҸPӮр—DҗжӮ·ӮЧӮ«ҒvӮЖӮМҠCҢR‘ӨӮМҺе’ЈӮЖҒu—ХҺһҠШҚ‘”hҢӯ‘аӮМ”hҢӯӮр—DҗжӮ·ӮЧӮ«ҒvӮЖӮМ—ӨҢR‘ӨӮМҺе’ЈӮМҠФӮЕ’Іҗ®ӮӘҢvӮзӮкҒA—ӨҢR‘ӨӮӘҸчӮБӮДҢҲ’…ӮөӮҪҒBҠCҢR‘ӨӮН‘жҲк’iҠKӮЖӮөӮДҚ`ҠOҠпҸPӮрҚsӮўҒA‘ж“с’iҠKӮЖӮөӮДҚ`ҢыӮр••ҚҪӮөҒA‘жҺO’iҠKӮЖӮөӮДҚ`ҠOӮ©ӮзӮМҠФҗЪҺЛҢӮӮЙӮжӮБӮДҚ`“аӮМҠН’шӮрҢӮ”jӮ·ӮйӮұӮЖӮр‘z’иӮөӮДӮўӮҪӮЖӮіӮкӮйҒB‘жҲк’iҠK(ҠпҸP)ӮМӢ@–§•ЫҺқӮрҸdҺӢӮөӮДҒA30“ъӮЙҸүӮЯӮДӮұӮМҚ\‘zӮр—ӨҢRӮЙ’mӮзӮ№ӮҪҒBҠCҢR‘ӨӮЖӮөӮДӮНҒA—ӨҢRӮМүҮҸ•ӮИӮөӮМҠCҢR“Ж—НӮЙӮжӮй—·ҸҮӮМҸҲ—қӮр–]ӮсӮҫӮжӮӨӮЕҒAҺ–‘O’Іҗ®ӮМ’iҠKӮ©Ӯз—ӨҢRӮМҢгүҮӮр—vӢҒӮөӮИӮўҺ|ӮрӮөӮОӮөӮОҢыҠOӮөӮҪ‘е–{үcҠCҢR–Ӣ—»ӮаӮўӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйҒB ҠJҗнҢгҒAҚ`ҠOҠпҸPӮЖҚ`Ңы••ҚҪҚмҗнӮӘҺАҚsӮіӮкӮҪӮӘҒAҺё”sӮаӮөӮӯӮН•sҸ\•ӘӮИҢӢүКӮЕҸIӮнӮиҒA—·ҸҮҠН‘аӮМҗн—НӮН•Ы‘SӮіӮк‘ұӮҜӮҪҒB2ҢҺ––Қ Ӯ©ӮзғEғүғWғIғXғgғNҸ„—mҠН‘аӮӘҠҲ“®ӮрҺnӮЯҒA3ҢҺҲИҚ~ӮН‘ж“сҠН‘аӮр‘ОғEғүғWғIғXғgғNҸ„—mҠН‘аҗк”CӮЙ—фӮ©ӮЛӮОӮИӮзӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҠCҢRӮНӮИӮЁӮаҒuҠCҢR“Ж—НӮЙӮжӮй—·ҸҮҠН‘аӮМҸҲ’uҒvӮЙҚSӮиҒAҲИҢгӮаҚ`ҢыӮМ•ВҚЗӮр–Ъ“IӮЖӮөӮҪҚмҗнӮӘ‘ұӮҜӮзӮкӮҪҒB 3ҢҺ27“ъҒA‘ж“сүс•ВҚЗҚмҗнӮӘҺАҚsӮіӮкӮҪӮӘҒA•ВҚЗӮНүКӮҪӮ№ӮИӮ©ӮБӮҪҒB4ҢҺӮЙӮНӢ@—ӢӮЙӮжӮй••ҚҪҚфӮЙ“]Ҡ·ӮіӮкҒA12〜13“ъӮЙҺАҺ{ӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢг5ҢҺ3“ъӮЙ‘жҺOүс•ВҚЗҚмҗнӮӘҺАҺ{ӮіӮкӮҪӮӘҒAӮұӮкӮа•sҗ¬ҢчӮЙҸIӮнӮБӮҪҒB5ҢҺ9“ъӮжӮиҒA“ъ–{ҠCҢRӮНҒA—·ҸҮҠН‘аӮМҚs“®ӮМҺ©—RӮрҗ§ҢАӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҚ`ҢыӢЯӮӯӮЙҠН’шӮр—VңTӮіӮ№Ӯй’јҗЪ••ҚҪҚфӮЙ“]Ҡ·ӮөӮҪӮӘҒA15“ъӮЙӮН“–Һһ“ъ–{ҠCҢRӮӘ•Ы—LӮ·ӮйҗнҠНӮМҳZҗЗӮМӮӨӮҝ2җЗӮрҗG—ӢӮЙӮжӮиҲкӢ“ӮЙҺёӮӨҗ[ҚҸӮИҺ–‘ФӮаҗ¶Ӯ¶ӮҪҒBҢ»ҸуӮЕӮН—·ҸҮҠН‘аӮМҚs“®ӮМҺ©—RӮрҗ§ҢАӮ·ӮйӮҪӮЯҒA“ъ–{ҠCҢRӮН—·ҸҮҚ`ҢыӮЙ“\Ӯи•tӮ©ӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮиҒA—ӨҸгӮ©Ӯз—·ҸҮӮрҚUҢӮӮ·Ӯй•K—vҗ«ӮӘ‘қӮөӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB ӮұӮМӮжӮӨӮИҸуӢөӮЙүБӮҰӮДҒAғҚғVғAӮӘғoғӢғgҠCҠН‘а(ғoғӢғ`ғbғNҠН‘а)ӮМҺе—НҠН‘DҢQӮрӢЙ“ҢӮЙ”hҢӯӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ—\‘zӮіӮкӮҪҒBӮўӮЬӮҫҢ’ҚЭӮМ—·ҸҮҠН‘аӮЙӮұӮкӮзӮӘ‘қ”hӮЕүБӮнӮкӮОҒA“ъ–{ҠCҢRӮМ”{ӢЯӮўҗн—НӮЖӮИӮйҒBӮаӮөӮұӮМҚҮ—¬ӮрӢ–ӮөӮҪҸкҚҮҒAӢЙ“ҢӮМҗ§ҠCҢ ӮНғҚғVғA‘ӨӮЙ’DӮнӮкҒA“ъ–{–{“yӮЖ’©‘N”ј“ҮҠФӮМ•вӢӢҳHӮНҗвӮҪӮкҒA–һҸBӮЕӮМҗн‘ҲҢp‘ұӮНҗв–]“IӮЙӮИӮйҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ“ъ–{ҢRӮНҒAӮұӮМ‘қ”hҠН‘аӮӘӢЙ“ҢӮЙ“һ’…Ӯ·Ӯй‘OӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮ·Ӯй•K—vӮЙ”—ӮзӮкӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҢoҲЬӮ©ӮзҠCҢRӮНҒAҠJҗн“–ҸүӮ©ӮзӢ‘ӮЭ‘ұӮҜӮДӮ«ӮҪ—ӨҢRӮМ—·ҸҮҺQҗнӮр”FӮЯӮҙӮйӮр“ҫӮИӮӯӮИӮБӮҪҒB ‘ОӮөӮД—ӨҢRӮНҒAҠCҢR‘ӨӮМҲУҢьӮаӮ Ӯи—vҚЗҚU—ӘӮЙ‘ОӮөӮДҠJҗнҸү“ӘӮМ3ҢҺҸгҸ{ӮЬӮЕӮНҠДҺӢӮЕҸ[•ӘӮЕӮ ӮйӮЖ”»’fӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA’ҶҸ{ӮЙ“ьӮиҒAҠCҢRӮМҸҸҗнӮМҚмҗнӮӘҺё”sӮө—·ҸҮҠН‘аӮӘ–ўӮҫҢ’ҚЭӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮ©Ӯз3ҢҺ14“ъҒA2ҢВҺt’cӮ©ӮзӮИӮйҚUҸйҢRӮр•Тҗ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮрҢҲ’иӮ·ӮйҒB ӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҠCҢRӮНӮ»ӮМҢгӮаҠCҢRӮҫӮҜӮЙӮжӮй—·ҸҮҠН‘аӮМ–і—Нү»ӮЙҢЕҺ·ӮөҒA4ҢҺ6“ъӮМ‘еҺRҠЮҺQ–d‘Қ’·ҒAҺҷӢКҢ№‘ҫҳYҺҹ’·ӮЖҠCҢRҢR—Я•”Һҹ’·ҲЙҸWү@ҢЬҳYӮЖӮМҚҮӢcӢcҢҲ•¶ӮЙӮаҒu—ӨҢRӮӘ—vҚЗҚU—ӘӮрӮ·ӮйӮұӮЖӮНҠCҢRӮМ—vҗҝӮЙӮ ӮзӮёҒvӮЖӮўӮӨ1•¶ӮӘӮ ӮйӮИӮЗ—ӨҢRӮЖӮМӢӨ“¬ӮрӢ‘ӮЭ‘ұӮҜӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҢoҲЬӮЙӮжӮиҚUҸй“БҺк•”‘аӮр—iӮ·Ӯй‘ж3ҢRӮМ•Тҗ¬ӮН’xӮкҒAҗ퓬Ҹҳ—сӮН5ҢҺ29“ъӮЙ”ӯ—ЯӮЖӮИӮБӮҪҒBҢRҺi—Я•”ӮН“ҢӢһӮЕ•Тҗ¬ӮіӮкҒAҺi—ЯҠҜӮЙӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮЕ—·ҸҮҚU—ӘӮЙҺQүБӮөӮҪҢo—рӮӘӮ ӮБӮҪ”T–ШҠу“T‘еҸ«ӮӘҒAҺQ–d’·ӮЙӮН–CҸpӮМҗк–еүЖӮЕӮ ӮйҲЙ’n’mҚKүоҸӯҸ«ӮӘ”C–ҪӮіӮкӮҪҒBҢRҺQ–dӮзӮЙӮНҒAҠJҗнҢгӮЙҠCҠO•Ӣ”CҗжӮ©ӮзӢAҚ‘ӮөӮДӮ«ӮҪҺТӮӘүБӮнӮБӮДӮўӮйҒB“–ҺһӮМҗж’[’mҺҜӮрҠwӮсӮЕӮўӮҪҗlҚЮҒA“БӮЙғhғCғcӮЕ—vҚЗҗнӮрҠwӮсӮЕӮўӮҪҲдҸгҠф‘ҫҳYӮӘҺQ–dӮЖӮөӮДүБӮнӮБӮДӮўӮйҺ–ӮНҒA—·ҸҮ“пҗнӮМ‘ЕҠJӮЙ‘еӮ«ӮӯҚvҢЈӮөӮҪҒBҢRҺi—Я•”ӮН6ҢҺ1“ъӮЙ–{“yӮр”ӯӮҝҒA8“ъӮЙ‘еҳAӮЙ“һ’…ӮөӮҪҒB“–ҺһӮ·ӮЕӮЙ‘ж1ҢRҒA‘ж2ҢRӮӘ‘е—ӨӮЙҸг—ӨӮөӮДӮЁӮиҒAӢаҸBҸйҚU—ӘҗнӮрҸIӮҰ–kҸгӮ·Ӯй‘ж2ҢRӮ©Ӯз2ҢВҺt’c(‘ж1Һt’cҒA‘ж11Һt’c)ӮӘ’ҠҸoӮіӮкҒA‘ж3ҢRӮМҺе—НӮЖӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎ—·ҸҮ—vҚЗ | |
|
—·ҸҮӮНӮаӮЖӮаӮЖӮНҗҙҚ‘ӮМҢRҚ`ӮЕҒAҳIҚ‘ӮӘ—·ҸҮӮрҺи’ҶӮЙҺыӮЯӮҪҺһ“_ӮЕӮ Ӯй’ц“xӮМҸ”җЭ”хӮрҺқӮБӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©Ӯө–hҢдҺ{җЭӮИӮЗӮӘӢҢҺ®ӮЕ•sҸ\•ӘӮЖ”»’fӮөҚXӮИӮйӢӯү»ӮрҚsӮБӮҪҒB1901”NӮжӮиҠJҺnӮіӮкӮҪӮұӮМҚHҺ–ӮНҒA203ҚӮ’nӮв‘еҢКҺRӮаҠЬӮЯӮҪҚLӮў”НҲНӮЙ–hҢдҗьӮрҗЭ’uӮөҺз”х•ә2–ң5000ӮрҸн’“ӮіӮ№ӮйӮаӮМӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө—\ҺZ•s‘«ӮЕӢK–НӮрҸkҸ¬ӮіӮк–hҢдҗьӮН203ҚӮ’nӮв‘еҢКҺRӮжӮиҚ`ҳp‘ӨӮЙҒAҺз”х•әӮа1–ң3000ӮМҸн’“ӮЙ•ПҚXӮіӮкӮҪҒBҠ®җ¬ӮН1909”NӮМ—\’иӮЖӮіӮкӮҪӮӘ1904”NӮЙҠJҗнӮЖӮИӮи—vҚЗӮН–ўҠ®җ¬ӮМӮЬӮЬҗн‘ҲӮЙ“Л“ьӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB
—vҚЗӮМҺе–hҢдҗьӮНғxғgғ“ӮЕҺьҲНӮрҢЕӮЯӮҪ”јүiӢvҡЖ—Ы8ҢВӮр’ҶҗSӮЙҡЖ—Ы9ҢВҒAүiӢv–C‘д6ҢВҒAҠp–КҡЖ4ҢВӮЖӮ»ӮкӮрҢqӮ®ҡНҚҲӮ©ӮзӮИӮиӮ ӮзӮдӮй•ыҠpӮ©ӮзӮМҚUҢӮӮЙ”хӮҰҒAҢг•ыӮМҚӮ‘дӮЙ–C‘дӮр‘ўӮиҺxүҮ–CҢӮӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBҚXӮЙ“Л”jӮіӮкӮҪҸкҚҮӮЙ”хӮҰӮДҡЖ—ЫӮЖҡНҚҲӮЖ–C‘дӮрҳAӮЛӮҪҸ¬ӢK–НӮИ•ӣҠsӮӘ—·ҸҮӢҢҺsҠXӮрҺжӮиҲНӮсӮЕӮўӮҪҒBҠCҸг•ы–КӮа220–еӮМүО–CӮр–C‘дӮЙ”z”хӮөӮДҠН‘DӮМҗЪӢЯӮр–WҠQӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЕӮаҚHҺ–ӮМ“rҸгӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҺ{җЭӮМ•s”хӮӘӮ ӮБӮҪҒB–C‘дӮМҸг•”ӮН”ҚӮ«ҸoӮөӮЕӮ»ӮМ–wӮЗӮӘ–hүqҗьҸгӮЙӮ ӮиҒA“ъ–{‘ӨӮМ–CҢӮӮЙҺNӮіӮкӮйүВ”\җ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪҺг“_Ӯр•вӢӯӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙ–hүqҗьӮрҚXӮЙҠOҺьӮЙҗЭ’uӮ·ӮйҢvүжӮаӮ ӮБӮҪӮӘҠJҗнӮЙҠФӮЙҚҮӮнӮё203ҚӮ’nӮв‘еҢКҺRӮИӮЗӮЙ–мҗнҗw’nҒE‘OҸЈҗw’nӮрҗЭӮҜӮйӮЙӮЖӮЗӮЬӮБӮҪҒBӮұӮкӮзӮМҗw’nӮН‘жҺOҢRӮМ‘ҚҚUҢӮ‘OӮЙ’DҺжӮіӮкӮҪӮиӮөӮҪӮӘ‘ж7Һt’c’·ғҚғ}ғ“ҒEғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮМҗё—Н“IӮИӢӯү»ҚHҺ–ӮЕӮ©ӮИӮиӮМӢӯ“xӮрҢЦӮйӮаӮМӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB ҠJҗнҺһҒAҳIҢRӮӘ–һҸBӮЙ”z”хӮ·Ӯйҗн—НӮН6ҢВҺt’cӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ3•ӘӮМ1ӮЙ“–ӮҪӮй2ҢВҺt’c–с3–ң–јӮӘ—·ҸҮӢyӮС‘еҳA’nҲжӮЙ”z”хӮіӮкӮҪҒBӮұӮкӮЙ—vҚЗҢЕ—LӮМҺз”х•ә—НҒAҚH•әҒA—vҚЗ–C•әӮИӮЗӮаҠЬӮЯҚЕҸI“IӮЙ4–ң4җз–ј(ӮұӮкӮЙҢR‘®‘ј7җз–јҒAҠCҢRҸ«•ә1–ң2җз–ј)ӮӘ—§ӮДвДӮи‘жҺOҢRӮрӢкӮөӮЯӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎҢoүЯ | |
|
ҒЎ‘OҸЈҗн
ҳIҢRӮЕӮНҒAӮұӮМ—vҚЗӮрҠЬӮЯӮҪ’nҲжҲк‘СӮр–hүqӮ·ӮйғҚғVғAҠЦ“ҢҢRӮӘҗVҗЭӮіӮкҢRҺi—ЯӮЖӮөӮДғAғiғgҒ[ғҠғCҒEғXғeғbғZғҠ’ҶҸ«ҒA—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜӮЙғRғ“ғXғ^ғ“ғ`ғ“ҒEғXғ~ғӢғmғt’ҶҸ«ӮӘҸA”CҒBҺз”х•”‘аӮЖӮөӮД“ҢғVғxғҠғA‘ж7‘_ҢӮ•әҺt’c(Һt’c’·ҒFғҚғ}ғ“ҒEғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«)ӮЖ“Ҝ‘ж4Һt’c(Һt’c’·ҒFғAғҢғNғTғ“ғhғӢҒEғtғHҒ[ғNҸӯҸ«)ӮұӮМ‘јҒA“ҢғVғxғҠғA‘ж5‘_ҢӮ•әҳA‘аӮв—vҚЗ–C•ә‘аҒAӢR•әҒEҚH•әӮИӮЗ‘ҚҗЁ4–ң4җз–јҒAүО–C436–е(ҠCҠЭ–CӮНҸңӮӯ)ӮӘвДӮБӮДӮўӮҪҒB ҠCҢRӮНҒA’P“ЖӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮр–і—Нү»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮр’f”OӮөҒA1904”N7ҢҺ12“ъӮЙҲЙ“Ң—SӢңҠCҢRҢR—Я•”’·Ӯ©ӮзҺRгp—L•ьҺQ–d‘Қ’·ӮЙҒA—·ҸҮҠН‘аӮр—·ҸҮҚ`ӮжӮи’ЗӮўҸoӮ·Ӯ©үу–ЕӮіӮ№ӮйӮжӮӨҗіҺ®ӮЙ—vҗҝӮөӮҪҒBӮ»ӮМҚ ‘жҺOҢRӮНҒA6ҢҺ26“ъӮЬӮЕӮЙ—·ҸҮҠOү„•”ӮЬӮЕҗiҸoҒB6ҢҺ31“ъҒA‘е–{үcӮ©ӮзӮа—ӨҢRӮЙ‘ОӮөӮД—·ҸҮ—vҚЗҚU—ӘӮрӢ}Ӯ®ӮжӮӨ’К’BӮӘҸoӮДӮўӮҪҒB ӮөӮ©ӮөҒA—·ҸҮ—vҚЗӮрҚU—ӘӮ·ӮйӮұӮЖӮр“–Ҹү”O“ӘӮЙ’uӮўӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒA—ӨҢRӮНӮұӮкӮз—vҚЗӮМҸо•сӮӘ•s‘«ӮөӮДӮўӮҪҒBҳIҢRӮМӢӯү»ӮөӮҪ—vҚЗҗЭ”хӮЙҠЦӮ·ӮйҺ–‘OҸо•сӮН–wӮЗӮИӮӯ‘жҺOҢRӮЙ“nӮіӮкӮҪ’nҗ}ӮЙӮН—vҚЗ–hҢдҗьӮМ‘OӮЙӮ Ӯй‘Oҗiҗw’n(—іҠб–k•ыҡЖ—ЫҒAҗ…Һtүc“м•ыҡЖ—ЫҒA—іүӨ•_ҺRҒA“мҺR”вҺRҒA203ҚӮ’nӮИӮЗ)ӮӘ‘SӮӯӢLҚЪӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB–hҢдҗьӮЕӮа“с—іҺRҒA“ҢҢ{ҠҘҺR—јҡЖ—ЫӮН—ХҺһ’zҸйӮЖҸ‘ӮўӮДӮўӮйӮИӮЗҢлӢLӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҒB ӮұӮӨӮөӮҪ’ҶӮЕ—vҚЗҚU—ӘӮМҺеҺІӮрӮЗӮМ•ыҢьӮ©ӮзӮЙӮ·ӮйӮ©ӮӘӢc‘иӮЖӮИӮБӮҪҒBҗн‘OӮМҗ}ҸгҢӨӢҶӮЕӮНҗјҗі–КӮ©ӮзӮМҚU—ӘӮӘ—L—ҳӮЕӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮН‘еҳAҸг—Ө‘OӮМҺ–‘OҢӨӢҶӮЙӮжӮиӮ»ӮМ•ы–КӮ©ӮзӮМҚU—ӘӮЙӮН“Gҗw’nӮр‘Ҫҗ”ҚU—ӘӮөӮДӮўӮӯ•K—vӮӘӮ ӮиҒA“S“№Ӯв“№ҳHӮаӮИӮўӮМӮЕҚUҸй–CӮИӮЗӮМ•”‘а“WҠJӮЙҺһҠФӮр—vӮөҒu‘ҒҠъҚU—ӘҒvӮӘӮЕӮ«ӮИӮўӮЖҚlӮҰ“Ң–k•ы–КӮМҺеҚUӮЙ•ПҚXӮ·ӮйҒBӮҫӮӘҗVӮҪӮЙҢR—Я•”Һҹ’·ӮЖӮИӮБӮҪ’·үӘҠOҺjӮвҒA–һҸBҢRҺQ–dҲдҢыҸИҢбӮзӮӘҗј•ыҺеҚUӮрҺxҺқӮөӢcҳ_ӮЖӮИӮй(’ҚҲУӮ·ӮйӮМӮНӮұӮМҒuҗј•ыҺеҚUҒvҗаӮНӮ ӮӯӮЬӮЕ—vҚЗҚU—ӘӮМҺеҺІӮрӮЗӮМ•ы–КӮЙӮ·ӮйӮ©ӮМҳbӮЕӮ ӮиҒAҢгӮЙҸoӮй203ҚӮ’nҚU—ӘӮЖӮН‘SӮӯ•КҺҹҢіӮМӢcҳ_ӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ Ӯй)ҒB ҢӢӢЗӮұӮМӢcҳ_ӮН‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮӘҢ»’nӮЙ“һ’…Ӯ·Ӯй7ҢҺӮІӮлӮЬӮЕҺқӮҝүzӮіӮкӮйҒBӮ»ӮМҚ ‘жҺOҢRӮНҒA6ҢҺ26“ъӮЬӮЕӮЙ—·ҸҮҠOү„•”ӮЬӮЕҗiҸoӮөӮДӮўӮҪҒB7ҢҺ3“ъҒAғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҺt’cӮМҲк•”ӮӘӢtҸPӮЙ“]Ӯ¶ӮйӮӘҡНҚҲӮЙ‘ТӮҝҚ\ӮҰӮй“ъ–{ҢRӮМ”ҪҢӮӮЙ“P‘ЮӮөӮДӮўӮйҒB Ӯ»ӮМҢг‘жҺOҢRӮЙ‘ж9Һt’cӮвҢг”х‘ж1—·’cӮӘ‘ҠҺҹӮўӮЕҚҮ—¬Ӯөҗн—НӮӘ‘қӢӯӮіӮкӮҪҒBӮұӮМӮ ӮЖ”T–ШӮНҢңҲДӮҫӮБӮҪҺеҚU•ы–КӮр—vҚЗ“Ң–k•ы–КӮЖҢҲ’иӮ·ӮйҒBҗј•ыҺеҚUҲДӮр’f”OӮөӮҪ—қ—RӮНҒA 1. “WҠJӮЬӮЕӮЙ“G‘OӮМҠJӮҜӮҪ•Ҫ’nӮр’·ӢмҲЪ“®Ӯ№ӮЛӮОӮИӮзӮёҠлҢҜ 2. “S“№ӮаҚUҸй–CӮИӮЗӮМ–CӮрҲЪ“®ӮіӮ№ӮкӮй“№ҳHӮаӮИӮўӮМӮЕ–C•ә“WҠJӮӘ“пӮөӮў 3. —vҚЗӮМҺҖ–ҪӮрҲкӢ“ӮЙҗ§Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«Ӯй–]‘дӮӘ“Ң–k•ы–КӮЙӮ Ӯй 4. 203ҚӮ’nӮв“мҺR”вҺRӮИӮЗӮМ‘Oҗiҗw’nӮӘ‘ҪӮӯӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮзӮрҚU—ӘӮөӮҪҸгӮЕ—vҚЗ–hҢдҗьҚU—ӘӮЖӮИӮйӮМӮЕҺһҠФӮӘҠ|Ӯ©Ӯй ӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҸҖ”хӮрҗ®ӮҰӮҪ‘жҺOҢRӮН7ҢҺ26“ъ—·ҸҮ—vҚЗӮМҸ”‘Oҗiҗw’nӮЦӮМҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйҒB—vҚЗӮМ‘Oҗiҗw’nӮНҒAҺеӮЙҗј•ыӮЙ203ҚӮ’nӢЯ•УҸ”җw’nҒA–k•ыӮЙҗ…ҺtүcӢЯ•УҸ”җw’nҒA“Ң•ыӮЙ‘еҸ¬ҢПҺRҸ”җw’nӮӘ‘¶ҚЭӮөӮДӮЁӮиҒA“––КӮМҺе–Ъ•WӮН“Ң•ыӮМ‘еҢКҺRӮЖӮіӮкӮҪҒBӮұӮкӮзӮМ–hҢдҺ{җЭӮН–ўҠ®җ¬ӮҫӮБӮҪҒB3“ъҠФ‘ұӮўӮҪҗ퓬ӮЕ“ъ–{ҢR2,800–јҒAғҚғVғAҢR1,500–јӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөҒA30“ъӮЙҳIҢRӮН—vҚЗ“а•”ӮЙҢг‘ЮӮөӮҪҒBӮұӮМҚ ”T–ШӮНҒA‘қүҮӮМ–C•ә‘аӮМ“һ’…ӮрҢoӮҪ8ҢҺ19“ъӮЬӮЕ‘ҚҚUҢӮӮрү„ҠъӮ·ӮйҢҲ’fӮрӮөӮДӮўӮйҒB 8ҢҺ7“ъҒAҚ•Ҳд’оҺҹҳYҠCҢR’ҶҚІ—ҰӮўӮйҠCҢR—ӨҗнҸd–C‘аӮӘ‘еҢКҺRӮЙҠП‘ӘҸҠӮрҗЭ’uӮөҒA—·ҸҮҚ`ӮЦӮМ–CҢӮӮрҠJҺnҒB9“ъ9Һһ40•ӘӮЙҗнҠНғҢғgғEғBғUғ“ӮЙ–Ҫ’Ҷ’eӮр—^ӮҰӮҪҒB—·ҸҮҠН‘аӮЙ”нҠQӮӘҸoҺnӮЯӮҪӮұӮЖҒAӮЬӮҪӢЙ“Ң‘Қ“ВғAғҢғNғZғCғGғtӮМ“xҸdӮИӮйғEғүғWғIғXғgғNӮЦӮМүсҚq–Ҫ—ЯӮаӮ ӮиҒAғҚғVғA—·ҸҮҠН‘а(‘жҲк‘ҫ•Ҫ—mҠН‘а)Һi—Яғ”ғBғgғQғtғgӮН8ҢҺ10“ъҒAғEғүғWғIғXғgғNӮЦүсҚqӮөӮжӮӨӮЖ—·ҸҮҚ`ӮрҸoҢӮӮөӮҪҒBҠCҢR‘ӨӮӘ—ӨҢRӮЙ—vҗҝӮөӮҪҒu—·ҸҮҠН‘аӮр–CҢӮӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҚ`ӮжӮи’ЗӮўҸoӮ·ҒvӮұӮЖӮНҒAӮұӮкӮЙӮжӮБӮД’Bҗ¬ӮіӮкӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө“ъ–{ҳAҚҮҠН‘аӮНү©ҠCҠCҗнӮЕ“с“xӮЙ“nӮи–CҢӮҗнӮрҚsӮӨӢ@үпӮр“ҫӮВӮВӮа1җЗӮа’ҫ–vӮ№ӮөӮЯӮйӮұӮЖӮИӮӯҒA”–•йӮЙҺҠӮиҢ©ҺёӮўҒAҚXӮЙ—·ҸҮҚ`ӮЦӮМӢAҠТӮрӢ–ӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBӢAҚ`ӮөӮҪҠН’шӮМ–wӮЗӮНҸг•”Қ\‘ўӮр”jүуӮөӮВӮӯӮіӮк—·ҸҮҚ`ӮМҗЭ”хӮЕӮНҸC—қӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҸуӢөӮҫӮБӮҪҒBҢӢӢЗҚЕӮа‘№ҠQӮӘҢy”чӮҫӮБӮҪҗнҠНғZғ”ғ@ғXғgғ|ғҠ ӮМӮЭӮӘҠO—mҚqҚsүВ”\ӮЙӮЬӮЕҸC—қӮөӮҪӮМӮЭӮЕҒA—·ҸҮҠН‘аӮНӮ»ӮМҗ퓬—НӮрӮЩӮЪ‘rҺёӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮ(–ҫҺЎ37”N8ҢҺ19“ъ〜24“ъ)
‘ҚҚUҢӮӮр‘OӮЙ‘жҺOҢRӮНҢRҺi—Я•”Ӯр–цҺч–[Ӯ©Ӯз–PҷҖҺR“Ң“мҚӮ’nӮЙҗiҸoӮіӮ№ӮҪҒBҚXӮЙ’cҺRҺq“Ң–kҚӮ’nӮЙҗ퓬ҺwҠцҸҠӮрҗЭӮҜҗ퓬ӮМҸуӢөӮр’ҖҲк”cҲ¬ӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙӮөӮҪҒBӮұӮұӮНҢғҗн’nӮЖӮИӮБӮҪ“ҢҢ{ҠҘҺR•Ы—ЫӮ©Ӯз3ғLғҚӮЖӮўӮӨҸкҸҠӮЕӮөӮОӮөӮО“G’eӮЙҢ©•‘ӮнӮкӮйҸкҸҠӮЕӮ ӮБӮҪҒBҲИҚ~ҒAҚUҲНҗнӮНҺеӮЙӮұӮұӮЕҺwҠцӮӘҺжӮзӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB 8ҢҺ18“ъҗ[–йҒA‘жҺOҢR(ҺQүБ•ә—Н5–ң1җз–јҒAүО–C380–е)ҠeҺt’cӮН‘ҙҒX–Ъ•WӮЖӮіӮкӮй“Gҗw’nӮМҺЛ’цҢ—ҠOӮЬӮЕҗЪӢЯӮө‘ҚҚUҢӮӮЙ”хӮҰӮҪҒB —Ӯ8ҢҺ19“ъҒAҠeҗі–КӮЙӮЁӮўӮД‘Ғ’©ӮжӮиҸҖ”хҺЛҢӮӮӘҺnӮЬӮйҒBҺg—p’eҠЫҗ”11–ң3җз”ӯӮЖӮўӮӨ‘O—бӮМ–іӮў‘е–CҢӮӮӘ1ҺһҠФӢӯӮЙ“nӮБӮДүБӮҰӮзӮкҢЯ‘O6ҺһҒA“ъ–{‘жҺOҢRӮН—·ҸҮ—vҚЗӮЙ‘ОӮөӮД‘ҚҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҢг”х‘ж11—·’cӮН–Ъ•WӮМ‘е’ёҺqҺRӮр3“ъҳA“ъӮМ–ТҚUӮМ––22“ъӮЙҗи—МҒBӮөӮ©Ӯөҗ…Һtүc•ы–КӮр’S“–ӮөӮҪ‘ж1Һt’cӮЖ“ҢҢ{ҠҘҺR•ы–КӮМ‘ж11Һt’cӮНҗiҢӮӮЕӮ«Ӯё‘е‘№ҠQӮр”нӮБӮҪҒB ‘ж9Һt’cӮН“ҜӮ¶Ӯӯ‘е‘№ҠQӮр–ЦӮиӮИӮӘӮзӮаҚ¶—ғӮМ‘ж6—·’c(—·’c’·ҒFҲкҢЛ•әүqҸӯҸ«)ӮӘ‘PҗнҒA”zүәӮМ•а•ә‘ж7ҳA‘аӮЕӮНҳA‘а’·ӮӘҗнҺҖӮ·Ӯй’цӮМҺҖ“¬ӮЖӮИӮБӮҪӮӘ20“ъӮЙ”Х—іҺR“ҢҗјҡЖ—ЫӮМҗи—МӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪҒBӮұӮұӮН”јӮО—vҚЗӮМ‘ж“с–hүqҗьӮЙҗHӮўҚһӮсӮҫ—v’nӮЕ‘ж“с–hүqҗьӮЕҚЕӮа•WҚӮӮӘҚӮӮӯ—·ҸҮҚ`‘SӮДӮрҢ©“nӮ№Ӯй–]‘дӮМҠб‘OӮҫӮБӮҪҒB ”T–ШӮНҗи—М’nӮрҲЫҺқӮөҒA–]‘дӮрҗи—МӮ·ӮЧӮӯ‘ж1Һt’cҒE‘ж11Һt’cӮа”Х—іҺR•ы–КӮЙ“Ҡ“ьӮ·ӮйҒB‘ж6—·’cӮа–]‘дҚU—ӘӮМӮҪӮЯҒA”ж•ҫӮөӮҪ‘ж7ҳA‘аӮрүәӮ°җжҢҺ30“ъӮЙҳA‘а’·ӮӘҗнҸқӮМӮҪӮЯҢр‘гӮөӮҪӮОӮ©ӮиӮМ•а•ә‘ж35ҳA‘аӮр“Ҡ“ьӮ·ӮйҒBӮөӮ©ӮөҢғҗнӮЖӮИӮи22“ъӮЙӮНҳA‘а’·ӮӘҗнҺҖӮөӮДӮөӮЬӮӨҒB23“ъӮЙӮН‘ж6—·’cӮЙ‘ЦӮнӮи•а•ә‘ж12ҒE22ҒE44ӮМҢv3ҳA‘аӮӘ“Ҡ“ьӮіӮкӮйӮӘҒAӢ·Ӯў”Х—іҺRӮЙҸW’ҶӮөӮҪӮҪӮЯҺьҲНӮМ•Ы—ЫӮ©ӮзӮМ–CҢӮӮЖ—\”х•ә—НӮМӢtҸPӮЙ‘ҳӮўҲкҺһ“IӮЙ–]‘дӮрҗи—МӮЕӮ«ӮҪӮМӮЭӮЕҠm•ЫӮЙӮНҺё”sӮөӮҪҒB —Ӯ24“ъҒA”T–ШӮН‘ҚҚUҢӮӮМ’ҶҺ~ӮрҺwҺҰҒA‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮЖҢДӮОӮкӮҪӮұӮМҚUҢӮӮЕ“ъ–{ҢRӮНҗнҺҖ5,017–јҒA•үҸқ10,843–јӮЖӮўӮӨ‘е‘№ҠQӮр–ЦӮиҒA‘ОӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮМ”нҠQӮНҗнҺҖ1,500–јҒA•үҸқ4,500–јӮҫӮБӮҪҒB‘жҺOҢRӮНӮЩӮЪҲкҢВҺt’c•ӘӮМ‘№ҠQӮрҸoӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮ‘OҸЈҗн(–ҫҺЎ37”N9ҢҺ19“ъ〜22“ъ)
ҢRҺi—Я•”ӮНҒA‘е–{үcӮ©ӮзӮМҒu‘¬ӮвӮ©ӮИӮй‘ҒҠъҚU—ӘҒvӮМ—vҗҝӮМӮҪӮЯҒA‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮр•а•әӮМ“ЛҢӮӮЙӮжӮйӢӯҸP–@ӮЕҚsӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“ЛҢӮӮЙӮжӮйҚUҢӮӮЕӮН—vҚЗӮНҠЧ—ҺӮЕӮ«ӮИӮўӮЖ”»’fӮөҒA—vҚЗ‘O–КӮ¬ӮиӮ¬ӮиӮЬӮЕҡНҚҲӮрҢ@ӮиҗiӮсӮЕҗiҢӮҳHӮрҠm•ЫӮ·ӮйҗіҚU–@ӮЖҢДӮОӮкӮй•ыҺ®ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮй(җіҚU–@•№—pӮЙӮжӮйҚUҢӮҢvүжӮМҚф’и)ҒBғҚғVғAҢRӮЙӢЯҗЪӮ·ӮйӮҪӮЯӮМҡНҚҲҢҡҗЭӮрҠJҺnӮөӮҪҒB30“ъӮЙӮНғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮМ“Ж’fӮЙӮжӮй”Х—іҺRӮЦӮМҚUҢӮӮӘҚsӮнӮкӮҪӮӘ“ъ–{ҢRӮМ”ҪҢӮӮЕ3Ҡ„ӮрҺёӮўҺё”sӮөӮҪҒB 9ҢҺ15“ъҒA‘ОҚҲҢҡҗЭӮрҸIӮҰӮҪ‘ж3ҢRӮН19“ъҒAҗи—МӮөӮҪ”Х—іҺRӮЖ‘е’ёҺqҺRӮ©ӮзҺь•УӮЦҗw’nӮрҠg‘еӮөҲА’иү»Ӯр–ЪҺwӮөӮҪҚUҢӮ(‘ж2үс‘ҚҚUҢӮӮЙҢьӮҜӮДӮМ‘OҸЈҗн)ӮрҚsӮБӮҪҒB17ҺһҚ ӮжӮи“мҺR”вҺRӮЖ203ҚӮ’nӮЦ2ҢВҢг”хҳA‘а4,000–јӮЙӮжӮйҚUҢӮӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBӮ»ӮМ”УӮНҢҺ–йӮЕғҚғVғAҢRӮМҚUҢӮӮНҗіҠmӮрӢЙӮЯ‘OҗiӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮёҒA—Ӯ20“ъӮЙ“ЛҢӮӮНү„ҠъӮіӮкӮҪҒB20“ъ5ҺһӮжӮиҺnӮЬӮБӮҪ“ЛҢӮӮЕ“мҺR”вҺRӮНӮнӮёӮ©10•ӘӮЕҺз”х‘аӮӘҢг‘ЮӮөҗи—МҒBӮөӮ©Ӯө203ҚӮ’nӮЕӮНҢғҗнӮЖӮИӮи20“ъӮМ—[ҚҸӮЙӮНҗј“мҡЖ—ЫӮрҗи—МӮ·ӮйӮӘ“Ң–kҡЖ—ЫӮМҳIҢRӮЖҺЛҢӮҗнӮЖӮИӮйҒB21“ъӮЙӮН‘o•ы‘қүҮӮрҸoӮ·ӮӘ“ъ–{‘ӨӮН—\”х‘аӮМ”z’uӮӘҢг•ыӮ·Ӯ¬ӮҪӮҪӮЯҒAҗiҢӮ’ҶӮЙҢғӮөӮўҸeүОӮр—ҒӮС“һ’…ӮН–йҠФӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮМӮЬӮЬ22ҺһӮЙ“Ң–k•Ы—ЫӮЦҚUҢӮӮрҠ|ӮҜӮйӮӘҺё”sҒB22“ъӮМ10ҺһӮЬӮЕӮЙ6“xӮЙҳjӮй“Ң–kҡЖ—ЫӮЦӮМҚUҢӮӮН‘SӮДҺё”sӮө“ъ–{ҢRӮН“P‘ЮӮр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮҪҒB—ҙҠб–k•ыҡЖ—ЫӮвҗ…ҺtүcҺь•УӮМҡЖ—ЫҢQӮИӮЗӮНҗ§ҲіӮЙҗ¬ҢчӮө203ҚӮ’nҲИҠOӮМҗн—Ә–Ъ•WӮМҗи—МӮЙӮНҗ¬ҢчӮөӮҪҒB ӮұӮМҗнӮўӮЕӮМ‘№ҠQӮН“ъ–{ҢRӮНҗнҺҖ924–јҒA•үҸқ3,925–јҒBғҚғVғAҢRӮНҗнҺҖ–с600–јҒA•үҸқ–с2,200–јӮҫӮБӮҪҒB ‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮӘҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪҢгҒA“ҢӢһҳp—vҚЗӮЁӮжӮСҢ|—\—vҚЗӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮҪ“с”ӘcmһЦ’e–C(“–ҺһӮН“сҸ\”Ә‘W–CӮЖҢДӮОӮкӮҪ)ӮӘҗнҗьӮЙ“Ҡ“ьӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB’КҸнӮНғRғ“ғNғҠҒ[ғgӮЕ–CүЛ(–CӮМ‘дҚАӮМӮұӮЖ)ӮрҢЕ’иӮөӮДӮўӮйӮҪӮЯҗн’nӮЙҗЭ’uӮ·ӮйӮМӮНҚў“пӮЖӮіӮкӮДӮўӮҪӮӘҒAӮұӮкӮзҢң”OӮНҚH•әӮМ“w—НӮЙӮжӮБӮДҚҺ•һӮіӮкӮҪҒB “с”ӘcmһЦ’e–CӮНҒA9ҢҺ30“ъӢҢҺsҠX’nӮЖҚ`ҳp•”ӮЙ‘ОӮөӮД–CҢӮӮрҠJҺnҒB20“ъӮЙҗи—МӮөӮҪ“мҺR”вҺRӮрҠП‘Ә“_ӮЖӮөӮДҳp“аӮМҠН‘DӮМ‘ҪӮӯӮЙ–Ҫ’Ҷ’eӮр—^ӮҰ‘№ҠQӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҠН‘аҺ©җgӮНү©ҠCҠCҗнӮЕӮ·ӮЕӮЙҗн—НӮр‘rҺёӮөӮДӮЁӮиҒAӮұӮМ–CҢӮӮӘғҚғVғAҸ«•әӮМҗнҲУӮЙӢӯӮўҸХҢӮӮрүБӮҰӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB–CҢӮҺ©‘МӮН—ЗҚDӮИҗ¬үКӮрҺыӮЯӮҪӮҪӮЯ’ҖҺҹ‘қүБӮіӮкҒAҚЕҸI“IӮЙҢv18–еӮӘ‘ж3ҢRӮЙ‘—ӮзӮкӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮ(–ҫҺЎ37”N10ҢҺ26“ъ〜30“ъ)
10ҢҺ15“ъҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘғEғүғWғIғXғgғNӮЙҢьӮ©ӮБӮДҸoҚqӮөӮҪӮЖӮўӮӨ•сӮрҺуӮҜҒA—ӨҢRӮНҠCҢRӮ©Ӯз–оӮМӮжӮӨӮИҚГ‘ЈӮрҺуӮҜӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒBӮ»ӮМӮжӮӨӮИ’ҶӮЕ10ҢҺ26“ъҒA“с”ӘcmһЦ’e–CӮр”z”хӮөӮДҒA‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйҒB–Ъ•WӮН“ЛӢN•”ӮрҢ`җ¬ӮөӮДӮўӮй”Х—іҺRӢyӮС—іҠб–k•ы•Ы—ЫӮМҺь•УӮрҗи—МӮөҲА’иү»ӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB 4“ъҠФӮЙҳjӮй“с”ӘcmһЦ’e–CӮМҲР—НӮНҗҰӮЬӮ¶ӮӯҒA–Ъ•WӮЖӮИӮБӮҪ“с—іҺRҡЖ—ЫӮН•әҺЙӮӘ”jүуӮіӮк“ҢҢ{ҠҘҺRҡЖ—ЫӮЕӮНүО–тҢЙӮӘ”ҡ”ӯӮ·ӮйӮИӮЗӮМ‘е‘№ҠQӮр–ЦӮБӮҪҒB29“ъӮЙӮНғҚғVғAҢRӮӘ”ҪҢӮӮЙ“]Ӯ¶ӮйӮӘҺё”sӮөҒA30“ъӮЙҚЎ“xӮН“ъ–{ҢR‘ж9Һt’cӮӘ–і–јӮМҡЖ—Ы(’КҸМPҡЖ—Ы)ӮрҚUҢӮӮөҒA‘ж6—·’cӮӘӢꓬӮМ–––й”јӮЙӮНҗи—МӮ·Ӯй(ҢгӮЙPҡЖ—ЫӮНҲкҢЛҡЖ—ЫӮЖүьҸМӮ·Ӯй)ҒB“ъ–{ҢRӮНҗнҺҖ1,092–јҒA•үҸқ2,782–јӮМ‘№ҠQӮрҸoӮ·ӮӘҒAғҚғVғAҢRӮаҗнҺҖ616–јҒA•үҸқ4,453–јӮЖ“ъ–{ҢRҲИҸгӮМ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮҪҒB“ъ–{ҢRӮНҚмҗн–Ъ“IӮН’Bҗ¬ӮөӮДӮўӮҪӮӘҗи—МӮөӮҪӮМӮНPҡЖ—ЫӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒA‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮӮНҺё”sӮЖҚlӮҰӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘жҺOүс‘ҚҚUҢӮ(–ҫҺЎ37”N11ҢҺ26“ъ〜12ҢҺ6“ъ)
11ҢҺ14“ъҒA203ҚӮ’nҺеҚUӮЙҢЕҺ·Ӯ·ӮйҺQ–d–{•”ӮНҢд‘OүпӢcӮЕҒu203ҚӮ’nҺеҚUҒvӮрҢҲ’иӮ·ӮйҒBӮөӮ©Ӯө–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜ‘еҺRҠЮҢіҗғӮНӮұӮкӮр—eӮкӮёҒA‘ҚҺQ–d’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳY‘еҸ«ӮНҒA10ҢҺӮЬӮЕӮМҠП‘Ә–CҢӮӮЕ—·ҸҮҠН‘аҢRҠНӮМӢ@”\ӮНҺёӮнӮкӮҪӮЖ”»’fӮөӮДҠН‘DӮЦӮМ–CҢӮӮаӢЦҺ~Ӯр–ҪӮ¶ӮҪҒBӮұӮӨӮўӮБӮҪҸг‘w•”ӮМҲУҢ©ӮМҗHӮўҲбӮўӮН”T–ШӮЖ‘ж3ҢRӮрҚ¬—җӮіӮ№ҒA‘жҺOүс‘ҚҚUҢӮҲДӮН—јҺТӮМҲУҢ©Ӯр‘S•”ҺжӮи“ьӮкӮҪҗЬ’ҸҲДӮЖӮИӮБӮҪҒB 11ҢҺ’ҶҸ{ӮЙ”Х—іҺRҒEҲкҢЛ—ј•Ы—ЫӮ©Ӯз—ј‘ӨӮМ“с—іҺRӮЖ“ҢҢ{ҠҘҺR•Ы—ЫӮМ’јүәӮЬӮЕҡНҚҲӮрҢ@ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөҚXӮЙ’Ҷ• Ӯ©Ӯзғgғ“ғlғӢӮрҢ@ӮиӢ№•ЗӮЖҠOҠЭ‘Ө–hӮр”ҡ”jӮ·ӮйӮұӮЖӮрҢvүжҒBҺQ–d–{•”ӮН“а’nӮЙҺcӮБӮДӮўӮҪҚЕҢгӮМҢ»–р•әҺt’cӮМҗёүsҒA‘ж7Һt’cӮр“Ҡ“ьҒA•”‘аӮр‘ж1ҒA‘ж9Һt’cӮМҠФӮЙ”z’uӮө203ҚӮ’nҚUҢӮӮЙӮа”хӮҰӮҪ•zҗwӮрӮ·ӮйҒB 11ҢҺ26“ъҒA“ҢҢ{ҠҘҺR–kҡЖ—ЫӮЖ“с—іҺRҡЖ—ЫӮЦӮМҸҖ”х–CҢӮӮрҠJҺnҒBҢЯҢгӮЙӮН‘ж11Һt’cӮӘ“ҢҢ{ҠҘҺR–kҡЖ—ЫӮрҒA‘ж9Һt’cӮӘ“с—іҺRҡЖ—ЫӮрӮ»ӮкӮјӮкҚUҢӮӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯөҗ””gӮЙҳjӮйҚUҢӮӮНҺё”sӮЙҸIӮнӮиҒA–й”јӮЙӮН—LҺuҺuҠиӮЙӮжӮй“ЛҢӮ‘аӮрҒA’Ҷ‘әҠoҸӯҸ«ӮМҺwҠцӮМӮаӮЖӮЙҚUҢӮӮрҚsӮӨҒBӮұӮМ“ЛҢӮ‘аӮН–йҠФӮМ“G–Ў•ыӮМҺҜ•КӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДҒA‘аҲх‘SҲхӮӘ”’жFӮр’…—pӮөӮҪӮМӮЕ”’жF‘аӮЖҢДӮОӮкӮҪҒB”’жF‘аӮН—vҚЗӮЦҢҲҺҖӮМҠпҸP“ЛҢӮӮрҺҺӮЭӮйӮӘҒAҺi—ЯҠҜӮӘӢЗҸҠҚUҢӮӮЙ–v“ӘӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮұӮЖӮвҒA—\”х•ә—НӮМҸӯӮИӮіҒAӢЗҸҠ“IӮЙ“ъ–{ҢRӮӘ–§ҸWӮөӮДӮөӮЬӮБӮҪӮұӮЖӮИӮЗӮМҢӢүКҒA‘е‘№ҠQӮр–ЦӮиҺё”sӮөӮҪҒB “–ҸүӮМҚUҢӮҢvүжӮӘ“ЪҚБӮөӮҪӮұӮЖӮЕ‘ж3ҢRӮН27“ъҒAҚUҢӮ–Ъ•WӮр—vҚЗҗі–КӮ©Ӯз203ҚӮ’nӮЙ•ПҚXӮөӮҪҒB28“ъӮжӮи‘ж1Һt’cӮЙӮжӮйҚUҢӮӮрҺnӮЯӮйӮӘҒA—ҠӮЭӮМ“с”ӘcmһЦ’e–CӮа203ҚӮ’nӮМ“DӮЙҺhӮіӮйӮҫӮҜӮЕҢшүКӮНҸӯӮИӮӯ1500–ј’цӮЙӮЬӮЕҸБ–ХӮөӮДӮўӮҪ‘ж1Һt’cӮН‘OҗiӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB29“ъӮЙҗV’…ӮМ‘ж7Һt’cӮӘ“Ҡ“ьӮіӮкҒA30“ъ17ҺһҚ ӮЙҗј“мҡЖ—ЫӮрҗи—МҒAҗ”ҺһҠФҢгӮЙӮН“Ң–kҡЖ—ЫӮаҗи—МӮ·ӮйӮӘҳIҢRӮМҢғӮөӮў”ҪҢӮӮрҺуӮҜ—Ӯ12ҢҺ1“ъ‘Ғ’©ӮЙӮНҗј“м•”ӮМҲкҠpҲИҠOӮр’DҠТӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨҒB 11ҢҺ29“ъӮЙ—·ҸҮӮЦҢьӮ©ӮБӮҪҺҷӢК–һҸBҢR‘ҚҺQ–d’·ӮӘ12ҢҺ1“ъӮЙ“һ’…ҒB“rҸгҒA203ҚӮ’nҠЧ—ҺӮМ•сӮрҺуӮҜӮҪӮӘҢгӮЙ’DҠТӮіӮкӮҪӮұӮЖӮр’mӮБӮҪҺҷӢКӮН‘еҺR–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜӮЙ“d•сӮр‘ЕӮҝҒA–k•ыҗнҗьӮЦҲЪ“®’ҶӮМ‘ж8Һt’cӮМ•а•ә‘ж17ҳA‘аӮр“мүәӮіӮ№ӮйӮжӮӨӮЙ—vҗҝӮөӮҪҒB “ъ–{ҢRӮН12ҢҺ1“ъӮ©Ӯз3“ъҠФӮрҚUҢӮҸҖ”хӮЙҸ[ӮДҒAҚUҢӮ•”‘аӮМҗ®—қӮв‘е–CӮМҗw’n•ПҠ·ӮрҚsӮБӮҪҒB12ҢҺ4“ъ‘Ғ’©Ӯ©Ӯз203ҚӮ’nӮЙ–ТҚUӮрҠJҺnӮөҒA5“ъ9ҺһүЯӮ¬ӮжӮи‘ж7Һt’c•а•ә27ҳA‘аӮӘҺҖҺзӮөӮДӮўӮҪҗј“м•”ӮМҲкҠpӮрӢ’“_ӮЙ‘ж7Һt’cҺc—]ӮЖ‘ж1Һt’cӮМҲк•”ӮЕҚ\җ¬ӮіӮкӮҪҚUҢӮ‘аӮӘҗј“м•Ы—Ы‘SҲжӮрҚUҢӮӮө10ҺһүЯӮ¬ӮЙӮНҗ§ҲіҒB‘ФҗЁӮрҗ®ӮҰ13Һһ45•ӘҚ ӮжӮи“Ң–kҡЖ—ЫӮЦҚUҢӮӮрҠJҺnӮө22ҺһӮЙӮНғҚғVғAҢRӮН“P‘ЮҒA203ҚӮ’nӮрҠ®‘SӮЙҗи—МӮөӮҪҒB—Ӯ6“ъӮЙ”T–ШӮН“k•аӮЕ203ҚӮ’nӮЙ“oӮиҸ«•әӮрҳJӮӨӮӘҒAҚUҢӮ‘аӮН900–ј’цӮЙҢғҢёӮөӮДӮўӮҪҒB ӮұӮМҚUҢӮӮЕӮМ‘№ҠQӮН“ъ–{ҢRӮНҗнҺҖ5,052–јҒA•үҸқ11,884–јҒBғҚғVғAҢRӮНҗнҺҖ5,308–јҒA•үҸқҺТӮН12,000–јӢЯӮӯӮЙ’BӮөӮҪҒBғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮМ‘S–ЕӮӘҠm”FӮіӮкҒAҺҷӢКӮНүҢ‘дӮЙӮ Ӯй–һҸBҢRҺi—Я•”ӮЦӮЖ–ЯӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ—vҚЗҗі–К“Л”jӮЖғҚғVғAҢRӮМҚ~•ҡ
12ҢҺ10“ъҒA‘ж11Һt’cӮЙӮжӮй“ҢҢ{ҠҘҺR–kҡЖ—ЫӮЦӮМҚUҢӮӮрҠJҺnҒB15“ъӮЙҢMҸНҺц—^ӮМӮҪӮЯ•әҺЙӮр–KӮкӮДӮўӮҪғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮӘ“с”ӘcmһЦ’e–CӮМ’јҢӮӮрҺуӮҜҗнҺҖӮ·ӮйҒB18“ъӮЙӮН“ъ–{ҢRҚH•әӮӘӢ№•ЗӮЙҺжӮи•tӮҜӮҪ2ғgғ“ӮаӮМ”ҡ–тӮЙӮжӮй”ҡ”jӮЕӢ№•ЗӮӘ•цүуҒAғҚғVғAҢRӮНӢНӮ©150–јӮМҺз”х•әӮөӮ©ӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮӘүКҠёӮЙ”ҪҢӮӮө‘ж11Һt’cӮНҗнҺҖ151–јҒA•үҸқ699–јӮаӮМ‘№ҠQӮрҺуӮҜҺҖ“¬ӮМ–––й”јӮЙҗи—МӮ·ӮйҒBғҚғVғA‘ӨӮН150–ј’Ҷ92–јӮӘҗнҺҖӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӢКҚУӮЙӢЯӮў’пҚRӮҫӮБӮҪҒB ӮұӮМӮҪӮЯҒA”T–ШҺi—Я•”ӮНӢ№•ЗӮвҡНҚҲӮрҠ®‘SӮЙ”jүуӮөӮДӮ©Ӯз“ЛҢӮӮЙҲЪӮй•ыҗjӮрҢЕӮЯҒA28“ъӮЙӮН‘ж9Һt’cӮЙӮжӮй“с—іҺRҡЖ—ЫӮЦӮМҚUҢӮӮӘҺnӮЬӮйҒBӢ№•ЗӮЙҗЭ’uӮіӮкӮҪ3ғgғ“ҺгӮМ”ҡ–тӮЙӮжӮи300–јӮМҺз”х•әӮМ”јҗ”ӮӘҗ¶Ӯ«–„ӮЯӮЖӮИӮйӮӘҺc•әӮӘҢғӮөӮӯ’пҚRҒAҗ…•әӮМ‘қүҮӮаӮ Ӯи‘o•ыҺЛҢӮҗнӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©ӮөҢг•ыӮЙүсӮиҚһӮсӮҫ•а•ә‘ж36ҳA‘аӮрҢ©ӮҪҺз”х‘а’·ӮӘ“P‘ЮӮрҢҲ’fӮөӮҪӮМӮЕ29“ъ3ҺһӮЙӮНҗи—МӮ·ӮйҒB‘ж9Һt’cӮНҗнҺҖ237–јҒA•үҸқ953–јӮМ‘№ҠQӮр”нӮиҒAғҚғVғAҢRӮа300–јҲИҸгӮМҺҖҺТӮрҸoӮөӮДӮўӮйҒB 31“ъҒA‘жҲкҺt’cӮЙӮжӮйҸјҺчҺRҡЖ—ЫӮЦӮМҚUҢӮӮӘҺnӮЬӮиғҚғVғAҢRҺз”х•ә208–јӮМӮӨӮҝҚB“№”ҡ”jӮЕ”јҗ”ӮӘҺҖ–SҒAҗиӢ’ӮөӮҪ“с—іҺR•Ы—ЫӮ©ӮзӮМүҮҢмҺЛҢӮӮаӮ ӮиҢг•ыӮрҺХ’fӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчҒA11ҺһӮЙҚ~•ҡӮөӮҪҒB‘жҲкҺt’cӮНҗнҺҖ18–јҒA•үҸқ169–јӮМ‘№ҠQӮр”нӮиғҚғVғAҢRӮаҗ¶‘¶ҺТӮН103–јӮҫӮБӮҪҒB 203ҚӮ’nҚU–hӮЕ—\”хҗн—НӮӘҢНҠүӮөҒAҗі–КӮМҺе—v•Ы—ЫӮӘ—ҺӮҝӮҪӮұӮЖӮЕғҚғVғAҢRӮМҺmӢCӮН”сҸнӮЙ—ҺӮҝҚһӮЭҒAҺс”]•”ӮЙӮЁӮўӮДӮаҚRҗн”hӮНҗЁӮўӮрҺёӮӨҒB1ҢҺ1“ъ–ў–ҫӮжӮи“ъ–{ҢRӮНҸd—vӢ’“_ӮЕӮ ӮйҢХ“ӘҺRӮв–]‘дӮЦӮМҚUҢӮӮрҠJҺnҒA16Һһ”јӮЙғҚғVғAҢRӮНҚ~•ҡӮрҗ\Ӯө“ьӮкӮҪҒB 5“ъӮЙ—·ҸҮ—vҚЗҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғҠӮЖ”T–ШӮН—·ҸҮӢЯҚxӮМҗ…ҺtүcӮЕүпҢ©ӮөҒAҢЭӮўӮМ•җ—EӮв–h”хӮрҸМӮҰҚҮӮўҒAғXғeғbғZғҠӮН”T–ШӮМ2җlӮМ‘§ҺqӮМҗнҺҖӮр“үӮсӮҫҒBӮЬӮҪҒA”T–ШҸ«ҢRӮН•җҺm“№җёҗ_ӮЙ‘ҘӮиҚ~•ҡӮөӮҪғҚғVғAҸ«•әӮЦӮМ‘СҢ•ӮрӢ–ӮөӮҪҒBӮұӮМ—lҺqӮНҢгӮЙ•¶•”ҸИҸҘүМҒuҗ…ҺtүcӮМүпҢ©ҒvӮЖӮөӮДҚLӮӯүМӮнӮкӮҪҒBӮұӮӨӮөӮД—·ҸҮҚUҲНҗнӮНҸI—№ӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМ“Ҡ“ь•ә—НӮНү„ӮЧ13–ң–јҒAҺҖҸқҺТӮН–с6–ң–јӮЙ’BӮөӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎүeӢҝ | |
|
—·ҸҮ—vҚЗӮМҚU—ӘӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҠН‘аӮНҢӮ–ЕӮіӮкӮҪҒB
“ъ–{ҢRӮН–{Ҡi“IӮИҚUҸйҗнӮМҢoҢұӮӘҸӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB—ӨҢR‘S‘МӮЙӢЯ‘гҗнӮЕӮМ—vҚЗҗнӮрҸn’mӮөӮҪҗlҠФӮӘӮЁӮзӮёҒAҺQ–d–{•”ӮМҺw“ұғ~ғX“ҷӮаҸdӮИӮи‘ж1үс‘ҚҚUҢӮӮЕӮНӢу‘OӮМ‘е‘№ҠQӮрҗ¶Ӯ¶ӮДӮөӮЬӮБӮҪҒB—vҚЗҚU—ӘӮЙ•K—vӮИҚB“№җнӮМӢі”НӮМҢҮ”@ӮЙҠЦӮөӮДӮНҒAҸгҢҙ—EҚмҸӯҸ«ӮӘҗн‘OҚH•әҠДӮЖӮөӮДҗ®”хӮөӮжӮӨӮЖӮөӮДӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒAӮұӮМҗнӮўӮМӢкҗнӮӘӮ ӮйӮЖҺvӮнӮкҒAҸгҢҙҸӯҸ«ӮНӮұӮМ”ҪҸИӮ©Ӯз–ҫҺЎ39”NҚB“№Ӣі”НӮрҚмҗ¬ӮөҒAҸ¬‘qӮЙ’““ФӮөӮДӮўӮҪҚH•ә‘аӮЙӮжӮБӮДҒAҸүӮЯӮДӮМҚB“№җнҢP—ыӮӘ“G–Ў•ыӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДҺАҺ{ӮіӮкӮДӮўӮйҒB Ңy—Кү»ӮӘҗ}ӮзӮкӮҪҸгӮЙ–Ҳ•Ә500ҳA”ӯӮЖҺА—pҗ«ӮМҚӮӮўӢ@ҠЦҸeӮЕӮ Ӯйғ}ғLғVғҖӢ@ҠЦҸeӮНҒAӮұӮМҗ퓬ӮЕҗўҠEӮЕҸүӮЯӮД–{Ҡi“IӮЙү^—pӮіӮкҲР—НӮр”ӯҠцӮөӮҪҒBӢ@ҠЦҸeҗw’nӮ©ӮзӮМҸ\Һҡ–CүОӮЙ‘ОӮөҒAҸ]—ҲӮМ•а•әӮЙӮжӮй“ЛҢӮӮН–і—НӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮрҺАҗнӮЕҸШ–ҫӮөӮҪҒBӮұӮМҸуӢөӮр‘ЕҠJӮ·ӮйҚUҢӮ–@Ӯр“ъҳIҗн‘ҲҢгӮаҺbӮӯӮНҢ©ӮўӮҫӮ·ӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB “–ҺһӮМ“ъҳI—јҢRӮНҗўҠE“IӮЙҢ©ӮДӮа—бҠO“IӮЙӢ@ҠЦҸeӮр‘е—К”z”хӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA‘ҒӮӯӮ©Ӯз–hүq•әҠнӮЖӮөӮДӮМү^—pӮрҚlӮҰҸoӮөӮҪғҚғVғAҢRӮЙ‘ОӮөҒA“ъ–{ҢR‘ӨӮНӮ ӮӯӮЬӮЕӮа–мҗнӮМ•вҸ••әҠнӮЖӮөӮДҚlӮҰӮДӮўӮҪӮМӮЕҒAҸүҠъӮЙӮНҢшүК“IӮИү^—pӮНҚsӮнӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBҢгӮЙ“ъ–{‘ӨӮағҚғVғA‘ӨӮМү^—p–@Ӯрүһ—pӮөӮДӮўӮйҒB “ҜҺһ‘гӮМғҲҒ[ғҚғbғpҠeҚ‘ӮЕӮНҒAӢ@ҠЦҸeӮрӮІӮӯҸӯҗ””z”хӮөӮДӮўӮҪӮҫӮҜӮЕү^—p–@ӮаҠm—§ӮіӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМҗ퓬ӮЙӮЁӮҜӮйӢ@ҠЦҸeӮМҲР—НӮНҠeҚ‘ҠПҗн•җҠҜӮЙӮжӮБӮД–{Қ‘ӮЙ•сҚҗӮіӮкӮҪӮӘҒA•УӢ«ӮМ“БҺкҺ–—бӮЖӮөӮДӮЩӮЖӮсӮЗ–ЩҺEӮіӮкӮҪҒBғҲҒ[ғҚғbғpҠeҚ‘ӮӘӮұӮМҺ–ҺАӮЙӢCӮГӮ«ҒAӢ@ҠЦҸeӮМҚUҢӮӮЙ‘ОӮөӮД—LҢшӮИүрҢҲҚфӮӘҚlӮҰҸoӮіӮкӮйӮМӮН‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЙӮЁӮҜӮйҗнҺФӮМ”ӯ–ҫӮЬӮЕ‘ТӮВӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎ—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙҠЦӮ·Ӯйҳ_“_ | |
|
ҒЎ203ҚӮ’n
203ҚӮ’nӮН—vҚЗҺе–hҢдҗьӮМҠO‘ӨӮЙҲК’uӮөӮДӮЁӮиҒAӮұӮұӮМ–hҢдҺ{җЭӮНӮўӮнӮдӮй‘Oҗiҗw’nӮЖӮөӮД’zӮ©ӮкӮҪҒB–{ҚӮ’nӮ©Ӯз—·ҸҮҚ`“аӮӘ“W–]ӮЕӮ«ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНғҚғVғA‘ӨӮаҠJҗн‘OӮ©ӮзҸі’mӮөӮДӮўӮҪӮӘҒA—\ҺZ•s‘«ӮЕӢK–НӮӘҸkҸ¬ӮіӮкӮҪӮұӮЖӮаӮ Ӯи–hҢдҗьӮЙӮН‘gӮЭҚһӮЬӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠJҗнҢгӮЙғRғ“ғhғүғ`ғFғ“ғRҸӯҸ«ӮЙӮжӮиҒA‘ҚҚUҢӮҠJҺnӮЬӮЕӮЙӮ©ӮИӮиӮМ–hҢдӮр—LӮ·ӮйӮЬӮЕӮЙӮИӮБӮДӮНӮўӮҪӮӘҒA‘јӮМҳIҢRҗw’nӮ©ӮзӢ——ЈӮӘӮ Ӯи—\”х•ә—НӮМ“Ҡ“ьӮЙ•ү’SӮӘӮ ӮйӮМӮЕҸ]—Ҳ’КӮи‘Oҗiҗw’nӮЖӮөӮДү^—pӮ·Ӯй—\’иӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮзҗ퓬ӮрҢoӮДҳIҢRӮН•ыҗjӮр•ПҚXӮөӮД203ҚӮ’nӮрҢЕҺзӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮи—\”х•ә—НӮрҺҹҒXӮЖӮұӮұӮЙ’ҚӮ¬ҚһӮсӮЕӮўӮБӮҪҒB“ъ–{‘ӨӮЖӮөӮДӮЭӮҪӮз—\”х•ә—НӮМҸБ–ХӮр—UӮӨҸгӮЕӮНҚЕ“KӮМҗнҸкӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB 203ҚӮ’nҚU–hҗнӮМҸIӢЗҢгҒAғҚғVғA‘ӨӮМ’пҚR—НӮН’ҳӮөӮӯҢёҗҠӮөӮДӮЁӮиҒA12ҢҺ’ҶҸ{ӮжӮиҚsӮнӮкӮҪ“Ң–k–КӮМҺе–hҢдҗьҸгӮМҚU–hҗнӮЕӮНҺе—vҺO•Ы—ЫӮЖ–]‘дӮЖӮўӮӨҸd—vӢ’“_ӮӘ—§ӮД‘ұӮҜӮЙҠЧ—ҺӮөӮҪҒB—vҚЗҺi—ЯҠҜғXғeғbғZғҠӮӘҚ~•ҡӮрҢҲ’fӮөӮҪ—қ—RӮНҒA—\”х•ә—НӮрҸБ–ХӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҗнҗьӮрҺxӮҰӮзӮкӮИӮӯӮИӮБӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB203ҚӮ’nӮНҒAӮұӮМҲУ–ЎӮЕ—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙӮЁӮўӮДҸd—vӮИҸкҸҠӮЕӮ ӮБӮҪҒB 203ҚӮ’nӮМҚU–hҗнӮЙӮВӮўӮДӮНҒA—lҒXӮИҢ©үрӮӘҢкӮзӮкӮДӮўӮйҒB“БӮЙ203ҚӮ’nӮМҠП‘ӘҸҠӮЖӮөӮДӮМүҝ’lӮрҸdҺӢӮ·ӮйҢ©үрӮӘ‘ҪӮўҒB–{–hҢдҗьӮМҠOӮ©Ӯз—·ҸҮҚ`“аӮМғҚғVғAҠН’шӮр–CҢӮӮ·ӮйҸкҚҮӮМҠП‘ӘҸҠӮЖӮөӮД–{ҚӮ’nӮНҚЕ“KӮИҸкҸҠӮЕӮ ӮиҒAҚU—ӘӮН‘ҒҠъӮЙҚsӮнӮкӮйӮЧӮ«ӮҫӮБӮҪӮЖӮ·ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮҫӮӘ‘жҺOҢRӮМҚмҗн–Ъ“IӮН—vҚЗӮМҚU—ӘӮЕӮ Ӯи—·ҸҮҠН‘аӮМҹr–ЕӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮҪ‘ҚҚUҢӮҠJҺnҺһ“_ӮЕ‘жҺOҢRӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮйҸd–CӮНҚЕ‘еӮЕ15cmһЦ’e–CӮЕӮ ӮиҒA”\—Н“IӮЙҠП‘ӘҺЛҢӮӮЙӮжӮйҠН‘аҢӮ–ЕӮИӮЗ‘жҺOҢRӮЙӮН•sүВ”\ӮҫӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒAҠП‘ӘҸҠӮМҗЭ’uҺ©‘МӮН–{ҚӮ’nҲИҠOӮЕӮаүВ”\ӮЕӮ ӮиҒAҚUҲНҗнӮМ‘ҒҠъӮ©ӮзҢшүК“IӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮҪҒB‘ж1үс‘ҚҚUҢӮҲИ‘OӮМ7ҢҺ30“ъӮЙҒAӮ·ӮЕӮЙҗи—МӮөӮДӮўӮҪ‘Oҗiҗw’nӮМҲкӮВӮЕӮ Ӯй‘еҢЗҺRӮЙҠП‘ӘҸҠӮӘҗЭ’uӮіӮкӮДӮўӮйҒB‘еҢЗҺRӮрҠП‘ӘҸҠӮЖӮ·Ӯй–CҢӮӮЙ‘ПӮҰӮ©ӮЛӮҪӮҪӮЯӮЙҒA—·ҸҮҠН‘аӮН—·ҸҮҚ`ӮрҸoӮДү©ҠCҠCҗнӮЙҺҠӮБӮҪҒBҠCҗнҢгӮЙ—·ҸҮҚ`ӮЙ•‘Ӯў–ЯӮБӮҪ—·ҸҮҠН‘аӮНҒAҲИҢгҗнӢЗӮӘҗiӮЮӮЙӮВӮкӮДҸ”ҸҲӮЙ‘қҗЭӮіӮкӮҪҠП‘ӘҸҠҢQӮЙӮжӮБӮДҺҹ‘жӮЙ’в”‘ҸҠӮр’DӮнӮкӮДӮўӮ«ҒAҗӢӮЙӮН—ҙүНүНҢыӮМҗуҗЈ(Ҡұ’ӘҺһӮЙӮНҚ»ҸBӮЙҚАҸКӮөӮД‘D‘МӮрҸқӮЯҚs“®•s”\ӮЙӮИӮйӮұӮЖӮр–ЖӮкӮИӮў)ӮЙ’ЗӮўҚһӮЬӮкӮҪҒB —·ҸҮҚ`ӮЙӮН‘еҠНӮрҺы—eӮЕӮ«ӮйғhғbғNӮӘӮИӮӯҒA–CҢӮӮЙӮжӮй‘№ҸқӮМҸC—қӮаӮЬӮЬӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒAҠН‘DӮМҸж‘gҲхӮр—Өҗн‘аӮЖӮөӮД’nҸгҗнӮЙ“Ҡ“ьӮ·ӮйӮұӮЖӮНҚUҲНҗнӮМҸүҠъӮ©ӮзҚsӮнӮкӮДӮЁӮиҒA203ҚӮ’nӮӘҗи—МӮіӮкӮйҲИ‘OӮжӮи—·ҸҮҠН‘аӮМҗн—НӮН’ҳӮөӮӯ’бүәӮөӮДӮўӮҪҒB–{ҚӮ’nӮӘҚЕ“KӮИҠП‘ӘҸҠӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮНҺ–ҺАӮЖӮөӮДӮаҒAҗнӢөӮМҗi“WӮЙ”әӮБӮДҒAҗи—М“–ҺһӮЙӮНӮ»ӮМүҝ’lӮН‘Ҡ“–ӮЙҢёӮ¶ӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB 203ҚӮ’nӮМҠП‘ӘҸҠӮЖӮөӮДӮМүҝ’lӮрҸdҺӢӮ·ӮйҸкҚҮҒA203ҚӮ’nӮӘҚU—ӘӮіӮкӮД—·ҸҮҠН‘аӮӘүу–ЕӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮ—vҚЗӮа‘¶ҚЭҲУӢ`ӮрҺёӮБӮДҚ~•ҡӮөӮҪӮЖӮўӮӨҢ©үрӮЙҢqӮӘӮйӮМӮҫӮӘҒA ҺАҚЫӮЙӮН12ҢҺ6“ъӮМ203ҚӮ’nҗи—МӮ©Ӯз1ҢҺ1“ъӮМ—vҚЗҚ~•ҡӮЬӮЕӮН25“ъӮаӮМ“ъҗ”ӮӘ‘¶ҚЭӮ·ӮйҒB—·ҸҮ—vҚЗӮМ‘¶ҚЭҲУӢ`ӮрӮўӮӨӮМӮИӮзӮОҒAҠН‘аӮМ—L–іӮЙҠЦӮнӮзӮёҒA‘ж3ҢRӮрүВ”\ӮИҢАӮи’·Ӯӯ—·ҸҮҚU—ӘҚмҗнӮЙҚS‘©Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮа‘еӮ«ӮИҲУӢ`ӮӘӮ ӮйӮнӮҜӮЕҒA—·ҸҮҠН‘аӮМ‘¶”ЫӮӘғҚғVғAҢRӮӘҚ~•ҡӮрҢҲ’fӮөӮҪӮұӮЖӮМҺе—vҲцӮЖӮНҢҫӮҰӮИӮўҒB ‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮНҒAҚUҲНҠ®җ¬ҲИҢгӮМҢp‘ұ“IӮИ–CҢӮӮЙӮжӮБӮД—·ҸҮҠН‘аӮМҗ퓬—НӮНҺёӮнӮкӮВӮВӮ ӮйӮұӮЖӮр”FҺҜӮөӮДӮЁӮиҒA‘е–{үcӮЙӮаӮ»ӮМ•сҚҗӮрҚsӮБӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөӮИӮӘӮз‘е–{үcӮН203ҚӮ’nӮЙҺ·’…ӮөӮДӮЁӮиҒAӮұӮұӮЦӮМҚUҢӮӮр—vӢҒӮө‘ұӮҜӮҪҒB‘жҺOҢRӮНӮұӮкӮЙҸ]ӮнӮёҒAӮЬӮҪ‘жҺOҢRӮӘҸҠ‘®Ӯ·Ӯй–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”Ӯа‘е–{үcӮ©ӮзӮМ—eҡ[ӮЙӢӯӮӯӢ‘җвӮМҲУӮрҺҰӮөӮҪҒB‘еҺR‘ҚҺi—ЯӮЖҺҷӢК‘ҚҺQ–d’·ӮНӮ»ӮкӮјӮк‘е–{үcӮЖҺRҢ§ҺQ–d‘Қ’·ӮЙ“d•сӮр‘—Ӯи203ҚӮ’nҺеҚUӮЙ•s“ҜҲУӮр“`ӮҰӮДӮўӮйҒB ‘е–{үcӮӘӮұӮМӮжӮӨӮЙӢӯҚdӮЙ—·ҸҮҗнӮЙүо“ьӮөӮДӮ«ӮҪӮМӮНҒAҠCҢR‘ӨӮМҲУҢ©Ӯр—eӮкӮҪӮаӮМӮЖҺvӮнӮкӮйҒBӮұӮМӮұӮЖӮ©ӮзҳA‘zӮіӮкӮҪӮаӮМӮ©ҒA203ҚӮ’nӮМҚU—ӘӮр—ӨҢRӮЙҗiҢҫӮөӮҪӮМӮНҠCҢRӮМҸHҺRҗ^”VҸӯҚІӮЕӮ ӮйӮЖӮ·ӮйҗаӮӘӮ ӮйӮӘҒAҚӘӢ’ӮЙ–RӮөӮӯ(Ҹ‘ҠИӮНҺһҠъӮӘ’xӮ·Ӯ¬Ӯй)ҒAҢ»ҚЭӮЕӮН”Ы’иӮіӮкӮДӮўӮйҒB ‘ж1үс‘ҚҚUҢӮӮЕӮН‘ж3ҢRӮН203ҚӮ’nӮрҺе–Ъ•WӮЖӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠCҢRӮ©ӮзӮұӮМҺһ“_ӮЕ203ҚӮ’nҚU—ӘӮМ—vҗҝӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҸ¬җаӮИӮЗӮЕ•`Ӯ©ӮкӮйӮұӮЖӮа‘ҪӮўӮӘҺАҚЫӮЙӮНҒAӮұӮМҺһ“_ӮЕ203ҚӮ’nҚU—ӘӮрҳ_Ӯ¶ӮзӮкӮҪӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘е–{үcӮӘ‘ҚҚUҢӮ‘OӮЙҸҘӮҰӮДӮўӮҪӮМӮНҺе–Ъ•WӮрҗј–kӮМҲЦҺqҺRҒA‘еҲДҺqҺRӮМ“Л”jҒAӮаӮөӮӯӮН’nҢ`ӮӘ•Ҫ’RӮЕҗiҢRӮөӮвӮ·ӮўӮЖ—\‘zӮіӮкӮйҗј•ыӮ©ӮзӮМҚUҢӮӮЙӮжӮй—vҚЗӮМҚU—ӘӮЕӮ Ӯи203ҚӮ’nү]ҒXӮНҚl—¶ӮіӮкӮДӮўӮИӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮзӮН“S“№җьӮ©Ӯз—ЈӮкӮДӮўӮДҚфҢ№’nӮ©Ӯзү“Ӯӯ•вӢӢӮЙ“пӮӘӮ ӮйҒBҚXӮЙ•Ҫ’R•”ӮНҲЪ“®’ҶӮЙ“GӮЙҺpӮр”ҳӮҜҸoӮө”нҠQӮр‘қӮ·ҠлҢҜӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕӢpүәӮіӮкӮҪҒBүјӮЙҒA‘ж1үс‘ҚҚUҢӮӮМҺһ“_ӮЕ‘ж3ҢRӮӘ203ҚӮ’nӮрҺе–Ъ•WӮЙҠЬӮЯҒAӮұӮкӮрҗи—МӮЕӮ«ӮҪӮЖӮөӮДӮаҒAҺҠӢЯӮЙҗФҚгҺRҒE“ЎүЖ‘еҺRӮЖӮўӮӨ–hҢдҗw’nӮӘҚ\’zӮіӮкӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪ”wҢгӮЙҚ\’zӮіӮкӮҪҺе–hҢдҗь“аӮМ‘Ҫҗ”ӮМ•Ы—ЫҒE–C‘дӮ©Ӯз–Т—уӮИ–CҢӮӮрҺуӮҜӮйӮұӮЖӮН—eҲХӮЙ‘z‘ңӮЕӮ«ҒAҗи—МӮрҲЫҺқӮ·ӮйӮұӮЖӮНҚў“пӮЕӮ ӮБӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮйҒB ҚӮ’nӮМҗи—МӮрҲЫҺқӮЕӮ«ӮҪӮЖӮөӮДӮаҸгӢLӮМ’КӮи‘жҺOҢRӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮ·ӮйӮҫӮҜӮМҸd–CӮНӮұӮМҺһ“_ӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮМҺһ“_ӮЕ‘жҺOҢRӮӘҸҠҺқӮ·ӮйҸd–CӮН15cmһЦ’e–C16–еӮЖ12cmһЦ’e–C28–еҒAӮұӮкӮЙҠCҢR—ӨҗнҸd–C‘аӮМ12cmғJғmғ“–C6–еӮҫӮҜӮЕӮ Ӯи‘•ҚbӮЕ•ўӮнӮкӮҪҗнҠНӮрҢӮ’ҫӮЕӮ«ӮйҲР—НӮНӮИӮўҒBҚЕ‘еӮМ15cm–CӮЙӮөӮДӮаӮұӮкӮНҠCҢRӮЕӮНҗнҠНӮв‘•ҚbҸ„—mҠНӮМ•ӣ–C’ц“xӮМ‘еӮ«ӮіӮЕӮөӮ©ӮИӮўӮөҠНҚЪ–CӮжӮи–CҗgӮӘ’ZӮўӮаӮМӮИӮМӮЕҸү‘¬ҒAҠС’К—НӮН—тӮйҒBӮ»ӮкӮЕӮаүјӮЙ—·ҸҮҠН‘аӮрҹr–ЕҸo—ҲӮҪӮЖӮөӮДӮаҒA—vҚЗҺз”х‘аӮрҚ~•ҡӮіӮ№ӮзӮкӮИӮҜӮкӮО‘жҺOҢRӮН–k•ыӮМҗнҗьӮЙҢьӮ©ӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒBҠН‘аҹr–ЕҢгӮЙӮвӮНӮиҗіҚU–@ӮЙӮжӮй—vҚЗҚU—ӘӮрҠ®җӢӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҲИҸгҒA•пҲНҗн‘S‘МӮЙ”пӮвӮіӮкӮйҠъҠФӮЖ‘№ҠQӮН•ПӮнӮзӮИӮўӮЖ—\‘zӮіӮкӮйҒBӮЮӮөӮлҺjҺАӮЩӮЗ•ә—НӮрҸБ–ХӮ·ӮйӮұӮЖӮИӮӯҺе–hҢдҗьӮрҢҳҢЕӮЙҺзӮзӮкӮДӮөӮЬӮўҒA—vҚЗӮМҚU—ӘӮНҒAӮжӮи’xӮкӮҪүВ”\җ«Ӯ·ӮзӮ ӮйҒB —·ҸҮҚU—ӘӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҠeҳ_ӮЖӮөӮД—ӨҢRҒA“БӮЙ”T–Ш‘ж3ҢRӮМ•ӘҗНӮӘ‘ҪӮўӮӘҒAҠCҢRӮМҺё”sӮр—ӨҢRӮӘ”ТүсӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮӘ‘Қҳ_ӮЖӮөӮДӢЯ”N’и’…ӮөӮДӮўӮйҒB ҠJҗн‘OӮМҢvүж’iҠKӮ©Ӯз—ӨҢRӮМ—·ҸҮҺQҗнӮрӢ‘ӮЭ‘ұӮҜӮҪҠCҢRӮМҲУҢьӮЙҗUӮиүсӮіӮкҒA—ӨҢRӮМ—·ҸҮҚUҢӮҠJҺnӮН‘е•қӮЙ’xӮкӮҪҒBҠJҗнӮ©Ӯз—vҚЗҚU—Әҗн’…ҺиӮЬӮЕӮМҠъҠФӮӘ’·Ӯ·Ӯ¬ӮҪӮҪӮЯӮЙ—vҚЗ‘ӨӮЙҸҖ”хҠъҠФӮр—^ӮҰӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮұӮЖӮНҒA—·ҸҮ“пҗнӮМ‘еӮ«ӮИ—vҲцӮЖӮөӮДҺw“EӮіӮкӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӢЯ‘гҗнӮЙӮЁӮҜӮй—vҚЗҚU–hҗнӮМүҪӮҪӮйӮ©Ӯр’mӮзӮИӮ©ӮБӮҪ“–ҺһӮМҺ–ҸоҒAӮЬӮҪӮ»ӮаӮ»Ӯа“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМҚ‘—НҒE•җ—НӮрҚlӮҰӮкӮОҒAҢӢӢЗӮМӮЖӮұӮл–і—қӮрҸі’mӮЕӮұӮМӮжӮӨӮИҚмҗнӮрҚsӮнӮҙӮйӮр“ҫӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮаҢҫӮҰӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ”T–ШҠу“T
Һ^”Ы—јҳ_ӮЖӮаӮЙӮ ӮиҒAӮ»ӮкӮзӮӘҳ_Ӯ¶ӮзӮкӮДӮ«ӮҪӮЁӮжӮ»ӮМҢoҲЬӮНҺҹӮМ’КӮиҒB “ъҳIҗн‘Ҳ–u”ӯҺһӮМ”T–ШӮНӢxҗE’ҶӮҫӮБӮҪӮӘҒA“ъҗҙҗн‘ҲӮМҗнҗСӮ©Ӯз–мҗнӮӘ“ҫҲУӮИҸ«ҢRӮЖ•]үҝӮіӮкӮДӮЁӮиҒAҲк”К“IӮЙӮаҚӮӮӯ•]үҝӮіӮкӮДӮўӮҪҒB—·ҸҮҚU—ӘҗнӮӘ“пҚqӮ·ӮйӮЖҒA“ҢӢһӮМ”T–Ш“@ӮЙ“ҠҗОӮіӮкӮҪӮиҒAҢRҺi—Я•”ӮЙ”б”»ӮМ“ҠҸ‘ӮӘ‘Ҫҗ”ҠсӮ№ӮзӮкӮйӮИӮЗҢғӮөӮӯ”б”»ӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҚU—ӘҗнӮӘҸҹ—ҳӮЙҸIӮнӮиҒAҗ…ҺtүcүпҢ©ӮИӮЗӮМ”ь’kӮӘҢ–“`ӮіӮкӮҪӮұӮЖӮвҒA•т“VүпҗнӮЙӮЁӮҜӮйҠҲ–фӮ©ӮзҒAҠMҗщӢAҚ‘ҺһӮЙӮН”сҸнӮЙҚDҲуҸЫӮрӮаӮБӮДҢ}ӮҰӮзӮкӮҪҒB“ъҳIҗнҢгӮаҠTӮЛ•]үҝӮНҚӮӮӯҒA–ҫҺЎ“VҚc‘е‘’ӮМҚЫӮЙҸ}ҺҖӮ·ӮйӮЙӢyӮсӮЕҗ_Ҡiү»ӮіӮкӮҪҒB Ӯ»ӮМҢгҒAҲЙ’n’mҚKүо‘ж3ҢRҺQ–d’·ӮЖҢўүҺӮМ’ҮӮЕӮ ӮБӮҪҲдҢыҸИҢб–һҸBҢRҺQ–dӮӘ—ӨҢR‘еҠwҚZ’·ӮрҳZ”N”ј(1906”N(–ҫҺЎ39”N)2ҢҺ〜1912”N(‘еҗіҢі”N)11ҢҺ)ӮЖ’·ҠъӮЙӢОӮЯҒAӮЬӮҪӮ»ӮМҢгҒA—ӨҢR“а•”ӮЙӮЁӮўӮД’·ҸB”ҙ”rҗЛӮМӢCү^ӮӘҚӮӮЬӮиҒA—ӨҢR‘еҠwӮМӢіҠҜӮӘҢӢ‘©ӮөӮДҺRҢыҢ§ҸoҗgҺТӮр“ьҠwҺҺҢұӮЙҚҮҠiӮіӮ№ӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮИӮЗӮӘӮ ӮБӮҪҒBҲдҢыӮӘ—ӨҢR‘еҠwҚZ’·Ӯр–ұӮЯӮДӮўӮҪҺһҠъӮЙ“ьҚZӮө—D“ҷӮЕ‘ІӢЖ(1909”N(–ҫҺЎ42”N)〜1912”N(‘еҗіҢі”N))ӮөӮҪ’JҺх•vӮӘҒAҢгӮЙ—Ө‘е•әҠwӢіҠҜӮЖӮИӮБӮҪҚЫӮЙ“ъҳIҗн‘ҲӮМҗӯҗн—ӘӢ@–§җнҺjӮр’ҳӮөӮҪҒBӮўӮнӮдӮйҗн‘ҲҺw“ұҺjӮЕӮ Ӯи‘ӯӮЙҒu’JҗнҺjҒvӮЖҢДӮОӮкӮйҒBҒu’JҗнҺjҒv’ҶӮМ—·ҸҮҗнӮЙҠЦӮ·ӮйӢLҸqӮНҒAҲЙ’n’m‘ж3ҢRҺQ–dӮЖҲУҢ©ӮрҲЩӮЙӮөӮҪ’·үӘҠOҺjҺQ–dҺҹ’·ҒAҲдҢыҸИҢб–һҸBҢRҺQ–dӮМҸ‘ҠИӮрҢҙҺ‘—ҝӮЖӮөӮҪӮаӮМӮӘ‘е•”•ӘӮрҗиӮЯҒAҺАҚЫӮМ“–Һ–ҺТӮЕӮ Ӯй‘ж3ҢRҺQ–d•”(ҲЙ’n’mҚKүоҒA‘е’л“сҳYҒA”’Ҳд“сҳYҒA’Г–м“cҗҘҸdӮз)ӮЙӮжӮйӢLҳ^ӮЙӮжӮйӮаӮМӮӘӮИӮӯҒAҲк•ы“IҢ©’nӮЙ•ОӮБӮҪҺ‘—ҝӮӘ—pӮўӮзӮкӮДӮЁӮиҒAӮЬӮҪҢлӮиӮа‘ҪӮўҒB ҲИҸгӮМӮжӮӨӮИҢoҲЬӮӘҒAҢгҗўӮМ‘ж3ҢRӮМҗн‘ҲҺw“ұӮИӮзӮСӮЙ”T–ШҒEҲЙ’n’mӮзӮМ•]үҝӮЙүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒB ‘ҫ•Ҫ—mҗн‘ҲҢгӮМҸәҳa40”N‘гӮЙҒu’JҗнҺjҒvӮӘҒuӢ@–§“ъҳIҗнҺjҒvӮЖ‘иӮөӮДҢҙҸ‘–[Ӯ©ӮзҠ§ҚsӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAҸ¬җаүЖҺi”n—Й‘ҫҳYӮӘҒA—·ҸҮҚUҲНҗнӮЕ“ъ–{ҢRӮӘ–c‘еӮИҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮҪӮМӮН‘ж3ҢRҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШӮЖҺQ–d’·ӮМҲЙ’n’mҚKүоӮМ–іҲЧ–іҚфӮӘҢҙҲцӮЖӮ·ӮйҚlӮҰӮЙҠоӮГӮўӮДҸ¬җаӮр”ӯ•\ӮөӮҪҒB Һi”nӮМӮўӮнӮдӮйӢрҸ«ҳ_ӮНҲк”К“IӮЙҺуӮҜ“ьӮкӮзӮкҒAӮұӮкӮЖ“ҜӮ¶ҚlӮҰӮЙҠоӮГӮӯҸ‘җРӮӘ‘ҪӮӯҸo”ЕӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮкӮзӮЙӮНҢлүрҒE•ОҢ©ӮрҚӘ’кӮЖӮөӮҪҢлӮиӮӘ‘ҪӮӯҢ©ӮзӮкҒAҢц•ҪӮИ•]үҝӮЖӮНҢҫӮў“пӮўӮаӮМӮҫӮБӮҪҒBӮұӮкӮзӮМ“_ӮрҚlҺ@Ӯө’јӮөӮД“–ҺһӮМҸуӢөӮрҚl—¶Ӯ·ӮйӮЖҒAҺjҺА’ц“xӮМ‘№ҠQӮНҒAӮұӮкӮрӮвӮЮӮр“ҫӮИӮўӮаӮМӮЖ—iҢмӮ·ӮйҲУҢ©ҒAӮЬӮҪӮ»ӮМ’ц“xӮЕ–Ъ“IӮр’BӮөӮҪҺ–ӮНӮЮӮөӮл•]үҝӮ·ӮЧӮ«ӮаӮМӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҲУҢ©ӮаҸoӮДӮўӮйҒBҲк•ыӮЕҒAҗlӢCӮМҚӮӮўҺi”nҸ¬җаӮНүрҗаҒEғKғCғh–{ӮМ—ЮӮӘ”ӯҚsӮіӮкӮйҸкҚҮӮӘ‘ҪӮӯҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕӮНҸ¬җаӮМӢLҸqӮрҺ–ҺАӮЖҢ©ӮИӮөӮДҸ‘Ӯ©ӮкӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўӮҪӮЯҒAҢлүрҒE•ОҢ©ӮрҚӘ’кӮЖӮөӮҪҢлӮиӮЙҠоӮГӮӯ•]үҝӮаҚДҗ¶ҺYӮіӮкҒA–ўӮҫӮЙҚӘӢӯӮӯҺxҺқӮіӮкӮДӮўӮйҒBҲИҸгӮМӮжӮӨӮЙҢ»ҚЭӮаҺ^”Ы—јҳ_ӮӘӮ Ӯи•]үҝӮН’иӮЬӮБӮДӮўӮИӮўҒB Ң»ҚЭҒAҚUҸйҗнҠФӮЙ”T–ШӮӘӢLӮөӮҪ“ъӢLӮМ“а—eӮӘҲк•”ҢцҠJӮіӮкҒAӮЬӮҪ•ҹ“ҮҢ§—§җ}Ҹ‘ҠЩӮМҚІ“Ў•¶ҢЙӮЙӮНҒuҺиҚe–{“ъҳIҗнҺj(үјҸМ)ҒvӮМ—·ҸҮҗнҠЦҳA•”•ӘӮӘҸҠ‘ ӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ–ҫӮзӮ©ӮЙӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҲИ‘OӮ©Ӯз–hүqҢӨӢҶҸҠҺ‘—ҝҺәӮЙ‘жҺOҢRҺQ–d‘е’лҺҹҳYӮМ“ъӢLӮӘҸҠ‘ ӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮН’mӮзӮкӮДӮўӮҪӮӘҒA’·ӮӯҢӨӢҶҺ‘—ҝӮЖӮДҠҲ—pӮіӮкӮИӮўӮЬӮЬӮЕӮўӮҪҒBӮұӮкӮзӮМҚlҺ@ӮӘҗ[ӮЬӮйӮЙӮВӮкҒAҲИҢгӮа•]үҝӮН•Пү»ӮөӮДӮўӮӯӮЖҺvӮнӮкӮйҒB ‘ж3ҢRӮЕӮН‘ҪӮӯӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAҚЕҢгӮЬӮЕҺwҠцӮМ—җӮкӮвҺmӢCӮМ’бүәӮӘҢ©ӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮЬӮҪ”T–ШӮӘҺ©ӮзҺёҚфӮрүчӮвӮЭҒAӮ»ӮкӮЙ‘ОӮ·Ӯй”с“пӮрҠГҺуӮөӮҪӮұӮЖӮНҒA”T–ШӮМ“ҝӮЖӮўӮӨҢ©•ыӮЖ–і”\ҢМӮМҸҠҚмӮЖӮўӮӨҢ©•ыӮӘӮЕӮ«ӮйҒB Һi”n—Й‘ҫҳYӮМӮжӮӨӮИ”T–Ш–і”\ҳ_ӮЖҗіӢtӮМ—§ҸкӮ©Ӯз”T–ШӮМҚмҗнӮр•]үҝӮ·ӮйҗәӮЖӮөӮДҒA“–ҺһӮМҸ]ҢRӢLҺТҒAғXғ^ғ“ғҢҒ[ҒEғEғHғVғ…ғoғ“(Stanley WashburnҒA1878〜1950)ӮМӢLҳ^ӮӘӢ“Ӯ°ӮзӮкӮйҒBғEғHғVғ…ғoғ“ӮМҺw“EӮЕӮНҒA‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮМҢгҒA”T–ШӮН‘ҰҚАӮЙӢӯҸPҚфӮМ–іүvӮіӮрҢеӮиҒAҚH•әӮЖҲк”КҺm‘ІӮЙҒAҸeҢ•ӮЙ•ПӮнӮБӮД’Яҡ{ӮЖӮЖғVғғғxғӢӮЖӮўӮӨҢ©үhӮҰӮНӮөӮИӮўӮӘҢшүК“IӮИ•җҠнӮрҺжӮзӮ№ҒAҡНҚҲӮрӮИӮйӮЧӮӯҚUҢӮ–Ъ•WӮЙҢьӮ©ӮБӮДү„җLӮөҒA—]Ӯ·ӮЖӮұӮл200-30ғ„Ғ[ғhӮЙӮИӮБӮҪ’n“_Ӯ©ӮзҒA–C•әӮМүҮҢмҺЛҢӮӮМӮаӮЖӮЙҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҚUҢӮ•ыҗjӮЙ•ПҚXӮөӮҪӮЖӮөӮДӮўӮйҒBӮіӮзӮЙҒA203ҚӮ’nӮМҸd—vҗ«ӮрҺw“EӮө‘ж7Һt’cӮрҸW’Ҷ“IӮЙ“Ҡ“ьӮ·Ӯй•ыҢьӮЕ‘жҺOҢRӮМҢRӢcӮрӮЬӮЖӮЯӮҪӮМӮа”T–ШӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮөӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘жҺOҢRҺi—Я•”
Һi”nӮМҚм•iӮрҠЬӮЯ–ҫҺЎ“–ҺһӮ©ӮзҢ»‘гӮЙҺҠӮй–і”\ҳ_ӮМҺеӮИҚӘӢ’ӮЙӮНҲИүәӮМӮаӮМӮӘӮ ӮйҒB 1. ’PҸғӮИҗі–КҚUҢӮӮрҢJӮи•ФӮөӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйӮұӮЖҒB 2. •ә—НӮМ’ҖҺҹ“Ҡ“ьҒA•ӘҺUӮЖӮўӮӨӢЦҠхӮрҢJӮи•ФӮөӮҪӮұӮЖҒB 3. ‘ҚҚUҢӮӮМҸо•сӮӘғҚғVғA‘ӨӮЙҳRӮкӮДӮўӮДҒAҸнӮЙ–ң‘SӮМҢ}ҢӮӮрӢ–ӮөӮҪӮұӮЖҒB 4. —·ҸҮҚU—ӘӮМ–Ъ“IӮНғҚғVғA—·ҸҮҠН‘аӮр—ӨҸгӮ©ӮзӮМ–CҢӮӮЕүу–ЕӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪӮЙӮаҠЦӮнӮзӮёҒA—vҚЗ–{‘МӮМҚU—ӘӮЙҢЕҺ·Ӯө–і‘КӮИ‘№ҠQӮрҸoӮөӮҪӮұӮЖҒB 5. ҸүҠъӮМ’iҠKӮЕӮНҒAғҚғVғAҢRӮН203ҚӮ’nӮМҸd—vҗ«Ӯр”FҺҜӮөӮДӮЁӮзӮё–h”хӮН”дҠr“IҺи”–ӮЕӮ ӮБӮҪҒB‘јӮМӢ’“_ӮЙ”дӮЧӮДҠИ’PӮЙҗи—МӮЕӮ«ӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒA•ә—НӮрҸW’ҶӮіӮ№ӮёҒAғҚғVғAҢRӮӘ203ҚӮ’nӮМҸd—vҗ«Ӯр”FҺҜӮө—vҚЗү»ӮөӮҪӮҪӮЯҒA‘Ҫҗ”ӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪӮұӮЖҒB 6. —·ҸҮӮрҺӢҺ@ӮЖӮўӮӨ–ј–ЪӮЕ–KӮкӮҪҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮӘҢ»ҸкҺwҠцӮрҺжӮиҒA–Ъ•WӮр203ҚӮ’nӮЙ•ПҚXӮөҒAҚмҗн•ПҚXӮрҚsӮБӮҪӮЖӮұӮлҒA4“ъҢгӮЙ203ҚӮ’nӮМ’DҺжӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮЖ“`ӮҰӮзӮкӮйӮұӮЖҒB ӮИӮЗӮӘ‘ҪӮӯҸqӮЧӮзӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҚЕӢЯӮЕӮНҗVҺ‘—ҝӮМ”ӯҢ©Ӯв“–Һ–ҺТӮЕӮ Ӯй‘жҺOҢRҠЦҢWҺТӮМҸШҢҫҒEӢLҳ^ӮИӮЗӮ©ӮзҺ–ҺАҢл”FҒA’mҺҜ•s‘«ӮЙӮжӮйҢлӮБӮҪҢӢҳ_ӮИӮЗӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮБӮДӮ«ӮДӮўӮйҒBҸгӢLӮМ6“_ӮЙ‘ОӮөӮДӮа 1. ‘жҲкҺҹ‘ҚҚUҢӮҲИҚ~ӮНҚUҢӮ–@ӮрӢӯҸP–@Ӯ©ӮзҡНҚҲӮрҢ@ӮиҗiӮсӮЕ—FҢRӮМ‘№ҠQӮр—}ӮҰӮйҗіҚU–@ӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮДӮЁӮиҒA’PҸғӮИҗі–КҚUҢӮӮрҢJӮи•ФӮөӮҪӮЖ•\Ң»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНҺ–ҺАӮЕӮНӮИӮўҒBҗі–КӮЖӮўӮӨӮМӮаҒA—·ҸҮ—vҚЗҺ©‘МӮН‘SҺьҲНӮр–hҢдӮөӮДӮўӮй—vҚЗӮЕӮ Ӯиҗі–КӮЖӮ©‘Ө–КӮИӮЗӮЖӮўӮӨӮМӮН‘¶ҚЭӮөӮИӮўҒB–k“Ң•ы–КӮа203ҚӮ’nӮМӮ Ӯй–kҗј•ы–КӮа“Ҝ“ҷӮМ–hҢдӢ@”\ӮрҺқӮБӮДӮўӮйӮМӮЕҒAҺ©ҢRӮМ•”‘а“WҠJӮв•вӢӢ–КӮЕ—L—ҳӮИ“Ң–k•ы–КӮрҺеҚUӮЙ‘IӮсӮҫ”»’fӮНҢлӮиӮЕӮНӮИӮўҒB 2. •ә—НӮр•ӘҺUӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮМӮНӢ@ҠЦҸeӮвһЦҺU’eӮӘ–{Ҡi“IӮЙ“Ҡ“ьӮіӮкӮҫӮөӮҪӮұӮМҺһ‘гӮЕӮНӢtӮЙ•Kҗ{ӮИӮұӮЖӮЕҒAҸW’ҶӮ·ӮйӮЖӮ©ӮҰӮБӮДӢ]җөӮр‘қӮвӮ·ӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒBҡНҚҲҗнӮМ“Л”j–@ӮЖӮөӮД‘жҲкҺҹҗўҠE‘еҗнӮЕ•ТӮЭҸoӮіӮкӮҪҗZ“§җнҸpӮа•а•әӮӘҸ¬‘аӮв•Ә‘аӮЙҺUӮзӮОӮБӮД–Ъ•WӮЙҚUӮЯҚһӮЮӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA‘жҺOҢRӮНӮўӮҝ‘ҒӮӯӮ»ӮкӮрҺжӮи“ьӮкӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB 3. ‘ҚҚUҢӮӮМҸо•сӮӘ“GӮЙҳRӮкӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҠmҺАӮИҸШӢ’ӮН‘¶ҚЭӮөӮИӮўҒB“–ҺһӮМ•ЁҺ‘—A‘—–КӮ©ӮзӮөӮД‘ҚҚUҢӮӮЙҸҖ”хӮӘ1ғ–ҢҺӮНҠ|Ӯ©ӮйӮҪӮЯҒAҒu–ҲҢҺ26“ъҚ ӮЙҚUҗЁӮрӮ©ӮҜӮйӮМӮЕҳIҢRӮаӮ»ӮкӮЙӢC•tӮўӮДҸҖ”хӮөӮДӮўӮҪҒvӮЖӮўӮӨҳbӮН‘ҒҠъҚU—ӘӮр”—ӮзӮкӮДӮўӮй‘жҺOҢRӮЖӮөӮДӮН’vӮө•ыӮИӮў–КӮаӮ ӮйҒB 4. —·ҸҮҚU—ӘӮМ–Ъ“IӮНҸIҺn—vҚЗҚU—ӘӮЕӮ ӮиҠН‘аҢӮ–ЕӮЕӮНӮИӮўҒuҠН‘аҢӮ–ЕӮӘ–Ъ“IӮҫӮБӮҪҒvӮЖӮўӮӨӮМӮНҢлӮиҒBӮЬӮҪ‘жҲкҺҹ‘ҚҚUҢӮҺһ“_ӮЕ‘жҺOҢRӮЙӮНҸd–CӮЙӮ»ӮМ—lӮИ”\—НӮНӮИӮўӮМӮЕҒAҠН‘DӮМҢӮ–ЕҺ©‘М•sүВ”\ӮҫӮБӮҪҒB‘жҺOҢRӮӘҠН‘аҹr–ЕӮр–Ъ“IӮЙ•Тҗ¬ӮіӮкӮҪ•”‘аӮЕӮИӮўҺ–ӮӘ•ӘӮ©ӮйҒB–Ҫ—ЯӮӘ—vҚЗҚU—ӘӮЕӮ ӮйҲИҸгҒAӮ»ӮкӮЙүҪӮзҠс—^ӮөӮИӮў203ҚӮ’nҚU—ӘӮН‘жҺOҢRӮН‘I‘рӮЕӮ«ӮИӮўӮМӮН“–ӮҪӮи‘OӮЕӮ ӮйҒB11ҢҺӮЙ‘е–{үcӮӘҢд‘OүпӢcӮрҠJӮўӮДӮЬӮЕ203ҚӮ’nҺеҚUӮрҢҲӮЯӮҪӮӘҒA‘жҺOҢRӮМҸгӢүҺi—Я•”ӮҪӮй–һҸBҢRӮӘ”Ҫ‘ОӮөӮДӮўӮйӮМӮЕ‘жҺOҢRӮЖӮөӮДӮНҸ]—Ҳ’КӮиӮМҚUҢӮӮр‘ұӮҜӮҪӮұӮЖӮН“–‘RӮЕӮ ӮйҒBҗҘ”сӮНӮЖӮаӮ©ӮӯҒAҢЕҺ·ӮөӮҪ“_Ӯр–в‘иҺӢӮ·ӮйӮИӮз‘жҺOҢRӮЕӮНӮИӮӯ–һҸBҢRӮМ•ыӮӘҸгӢүҺi—Я•”ӮЕӮ ӮйҲИҸгҗУ”CӮӘ‘еӮЕӮ ӮйҒB 5. 203ҚӮ’nӮӘҸүҠъӮМ’iҠKӮЕ–hҢдӮӘҺи”–ӮҫӮБӮҪҺ–ҺАӮНӮИӮӯҒA‘ж“сҢRӮМ“мҺRҚU—ӘҗнҢгӮ©ӮзӮ·ӮЕӮЙ–hҢдӢӯү»ӮМҚHҺ–ӮӘҺnӮЯӮзӮкӮДӮўӮйҒB‘жҲкҺҹ‘ҚҚUҢӮҺһ“_ӮЕ‘жҺOҢRӮМ12cmһЦ’e–CӮМ–CҢӮӮЙ‘ПӮҰӮӨӮйӢӯҢЕӮіӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮө(ҚUҸй–C•әҺi—Я•”ҺQ–dҚІ“ЎҚ|ҺҹҳY’ҶҚІ’k)ҒAҺз”х•ә—НӮа9ҢҺҺһ“_ӮЕ613–јӮҫӮБӮҪ203ҚӮ’nӮН12ҢҺӮМҚЕҸIҚUҢӮҺһӮЕ516–јӮЕӮ Ӯи‘қӢӯӮіӮкӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮаӮИӮўҒBӮаӮөүјӮЙ“–ҸүӮжӮиҚUӮЯӮйӮЙӮөӮДӮаҒA—vҚЗ–kҗј•ы–КӮН“S“№ӮаӮИӮӯҺе—vӮИ“№ҳHӮаӮИӮўӮМӮЕ•”‘а“]Ҡ·ӮӘӮөӮёӮзӮӯҒA‘ҒҠъӮЙҚUҗЁӮЙҸoӮйӮжӮӨ—vҗҝӮ·ӮйҠCҢRӮв‘е–{үcӮМ—vҗҝӮЙӮН“ҡӮҰӮзӮкӮИӮўҒB 6. –Ъ•WӮр203ҚӮ’nӮЙ•ПҚXӮөӮҪӮМӮНҺҷӢКӮӘ—ҲӮйҲИ‘OҒA‘жҺOҺҹ‘ҚҚUҢӮ’ҶӮЕ”»’fӮөӮҪӮМӮН”T–ШӮЕӮ ӮйҒBҺҷӢКӮЕӮНӮИӮў(ҺҷӢКҺ©җgӮН203ҚӮ’nҚU—ӘӮЙ”Ҫ‘ОӮ·ӮзӮөӮДӮўӮй)ҒBҚмҗнӮаҺҷӢКӮӘ—ҲӮДӮ©Ӯз•ПҚXӮіӮкӮҪ“_ӮН–wӮЗӮИӮӯҒAҸ]—ҲӮМ‘жҺOҢRӮМғvғүғ“ӮМӮЬӮЬҺАҚsӮіӮкӮДӮўӮйҒBҸd–CӮМ”z’u“]Ҡ·ӮН12cmһЦ’e–CӮЖ9cmүP–CӮӘҗ”10–еӮҫӮҜӮЕӮ ӮиҒAҺе—НӮМ28cmһЦ’e–CӮН“®ӮўӮДӮўӮИӮўҒB“®ӮўӮҪҸd–CӮа–Ъ•WӮр203ҚӮ’nӮЕӮНӮИӮӯ—yӮ©Ңг•ыӮМҗw’nӮЙӮөӮДӮЁӮиҒA203ҚӮ’nҚUҢӮӮЙ’јҗЪҠс—^ӮөӮДӮўӮИӮўҒB‘јӮЙӮа“ҜҺm“ўҠoҢеӮМҳA‘ұ–CҢӮӮНӮ·ӮЕӮЙҚUҸй–C•әҺi—Я•”ӮЙӮжӮБӮДҚsӮнӮкӮДӮўӮҪҒAӮЖ”Ҫҳ_ӮіӮкӮДӮўӮйҒB ‘јӮЙӮаҒA—vҚЗҚ\’zӮЙ’·Ӯ¶ӮйғҚғVғAӮӘ—·ҸҮ—vҚЗӮр–{Ҡi“IӮИӢЯ‘г—vҚЗӮЖӮөӮДҚ\’zӮөӮДӮўӮҪӮМӮЙ‘ОӮөӮДҒA“ъ–{ҢRӮЙӮНӢЯ‘г—vҚЗҚU—ӘӮМғ}ғjғ…ғAғӢӮНӮИӮӯҒAӢ}зҜҒAүўҸBӮ©ӮзӢі–{ӮрҺжӮиҠсӮ№–|–уӮөӮДӮўӮҪҒB—·ҸҮ—vҚЗӮрҠГӮӯҢ©ӮДӮўӮҪӮМӮН‘жҺOҢRӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯҒA‘е–{үcӮа–һҸBҢRӮаҠCҢRӮа“Ҝ—lӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒA—ӨҢRӮӘҺи–{ӮЙӮөӮҪ•§“Ж—ј—ӨҢRӮ©ӮзӮөӮД—vҚЗҚU—ӘӮМҠо–{ӮНҠпҸPӮ©ӢӯҸPӮрҠо–{ӮЖӮөӮДӮЁӮиҒA“–ҺһӮМҠҙҠoӮЕӮНӢӯҸP–@ӮӘҒuӢрҚфҒvӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒBӢtӮЙӮұӮМҗнӮўӮЕҸүӮЯӮД–в‘и’сӢNӮіӮкӮҪӮЖӮ·ӮзҢҫӮҰӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠCҢRӮМ–в‘и
ҠCҢRӮН“ъҳIҠJҗнҲИ—Ҳ—ӨҢRӮМ—·ҸҮҺQҗнӮрӮіӮ№ӮёҒAҠCҢR’P“ЖӮЕӮМ—·ҸҮҠН‘аӮМ–і—Нү»ӮЙҢЕҺ·ӮөӮҪҒBӮ¬ӮиӮ¬ӮиӮЬӮЕ—ӨҢRӮМ—·ҸҮҺQҗнӮрӢ‘ӮЭ‘ұӮҜҒA—ӨҠCҢRӮМӢӨ“ҜҳaҚҮӮрҢyҺӢ–іҺӢӮөӮҪҠCҢRӮМ•ыҗjҒA”T–Ш‘ж3ҢRҺQҗн(‘ж1үс‘ҚҚUҢӮ)ӮЬӮЕӮМ—·ҸҮҚU—ӘӮЙӮЁӮҜӮйҠCҢRӮМҚмҗнҺё”sӮМҳA‘ұӮЖӮўӮБӮҪҒAҠCҢRӮМ•sҺиҚЫӮаҚU—ӘӮМҚў“пӮіӮМҺеҲцӮЖӮөӮД–іҺӢӮЕӮ«ӮИӮўҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҢR’Ҷҗ••”ӮМ–в‘и
“ъҳIҠJҗнҢгӮЙҢ»’n—ӨҢRӮМ‘ҚҺi—Я•”ӮЖӮөӮДҗЭ’uӮіӮкӮҪ–һҸBҢRӮМ•ыҗjӮЖ‘е–{үcӮМ•ыҗjӮӘҲЩӮИӮиҒAӮ»ӮкӮјӮкӮӘ”T–Ш‘жҺOҢRӮЙҺw—Я’К’BӮрҸoӮөӮДӮўӮҪӮЖӮўӮӨҢR—ЯҸгӮМҚ\‘ў“IӮИ–в‘иӮа‘жҺOҢRӮН”YӮЬӮіӮкҚмҗнӮЙүeӢҝӮр—^ӮҰ‘ұӮҜӮҪҒBӮЬӮҪ’e–тӮМ”х’~—КӮр—ӨҢRҸИӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮрҠоҸҖӮЙҢvҺZӮөӮҪӮҪӮЯҒA‘жҺOҢRӮМӮЭӮИӮзӮё‘SҢRӮЕ–қҗ«“IӮИүО—Н•s‘«ҒA“БӮЙ–C’e•s‘«ӮЙ”YӮЬӮіӮкӮДӮўӮҪҒBҗVҺj—ҝӮр—pӮўӮҪ’·“мҗӯӢ`ҺҒӮМҢӨӢҶӮЙӮжӮкӮОҒA—бӮҰӮОүўҸBӮЙӮЁӮўӮД—vҚЗҚU—ӘӮЙҚЫӮөҒA•K—vӮИ–C’eҗ”ӮН1–еӮЙӮВӮ«җз”ӯӮӘҠо–{ӮҫӮБӮҪӮӘ‘жҺOҢRӮМ1–е800”ӯӮМ—vҗҝӮЙ‘ОӮө—ӨҢRҸИӮН‘Ҡ’kӮИӮөӮЙ1–е400”ӯӮЖҸҹҺиӮЙ•ПҚXӮөҢғҳ_ӮЖӮИӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB’·“мҗӯӢ`ҺҒӮНҢRҗӯ‘ӨӮМ–C’e”х’~ӮМҢ©җПӮМҠГӮіӮаҗУ”CӮЖӮөӮД‘еӮ«ӮўӮҫӮлӮӨҒAӮЖҺw“EӮөӮДӮўӮйҒBӮИӮЁҒAҠCҢRӮМ—vҗҝӮрҺуӮҜӮДҒA—·ҸҮҚUҢӮӮрҺе–Ъ•WӮЖӮөӮВӮВӮаҒAҠЧ—ҺӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘ•sүВ”\ӮИҸкҚҮӮНҚ`“аӮрҳлбХӮЕӮ«ӮйҲК’uӮрҠm•ЫӮөӮДҒAҠН‘DҒA‘ў•әҸұӮЙҚUҢӮӮрүБӮҰӮйӮЖӮўӮӨ•ыҗjӮЕүҢ‘д‘ҚҺi—Я•”(‘еҺRҺi—ЯҠҜ)ӮЖ‘е–{үcҠФӮМ’Іҗ®ӮӘ•tӮўӮҪӮМӮНҒAҢд‘OүпӢcӮрҢoӮД11ҢҺ”јӮОӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҺҷӢКҢ№‘ҫҳY
—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙӮЁӮўӮДӮНҺҷӢКҢ№‘ҫҳY–һҸBҢR‘ҚҺQ–d’·ӮМҢчҗСӮӘҢкӮзӮкӮйӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒB“ъ–{ҢRӮӘ203ҚӮ’nӮрҚU—ӘӮөӮҪӮМӮНҺҷӢКӮӘ—·ҸҮӮЙ“һ’…ӮөӮҪ4“ъҢгӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҒAҺҷӢКӮМҢчҗСӮЙӮжӮБӮДӮнӮёӮ©4“ъҠФӮЕҚU—ӘӮіӮкӮҪӮЖӢ@–§“ъҳIҗнҺjӮЕҸРүоӮіӮкҺi”n—Й‘ҫҳYӮМҚм•iӮИӮЗӮЕҗўҠФӮЙҚLӮЬӮБӮҪҒBӮҪӮҫӮөҒAӢ@–§“ъҳIҗнҺjӮН—·ҸҮҗнӮЙү—ӮўӮД‘жҺOҢRӮМ•ыҗjӮЖ”Ҫ”ӯӮөӮҪ‘е–{үc‘ӨӮМҗlҠФӮМҸШҢҫӮрҺжӮи“ьӮкҢ»ҸкӮМ‘жҺOҢR‘ӨӮМҸШҢҫӮр–wӮЗҚМ—pӮөӮДӮўӮИӮў•ОӮБӮҪ“а—eӮМҺ‘—ҝӮЕӮ ӮиҢлӮиӮа‘ҪӮўӮұӮЖӮӘ•КӢ{’gҳYҒA’·“мҗӯӢ`ҒAҢҙҚ„ӮИӮЗӮМҢӨӢҶ’ІҚёӮЕ”»–ҫӮөҸ‘җРӮИӮЗӮЕ”ӯ•\ӮіӮкӮДӮўӮйҒB ӮЬӮёҒAҺi”nӮМҚм•iӮИӮЗӮЕҺҷӢКӮзӮН203ҚӮ’nҚU—ӘӮрҺxҺқӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮМӮжӮӨӮЙ•`Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҺҷӢКҺ©җgӮН‘жҺOҢRӮМҗіҚU–@ӮЙӮжӮй–]‘дҚU—ӘӮрҸIҺnҺxҺқӮөӮДӮўӮйҒBҗіҚU–@ӮМ“r’Ҷ’iҠKӮЕ‘е–{үcӮвҠCҢRӮЙӢ}Ӯ©ӮіӮкҺАҺ{ӮөӮҪ2үсӮМ‘ҚҚUҢӮӮЙӮН”Ҫ‘ОӮЕҒAҸҖ”хӮрҠ®‘SӮЙҗ®ӮҰӮҪҸгӮЕӮМ“Ң–k•ы–КҚU—ӘӮрҺwҺҰӮөӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮНҚ`ҳp•”ӮвҺsҠXӮЦӮМ–CҢӮӮа’e–тҗЯ–сӮМ“_Ӯ©Ӯз”Ҫ‘ОӮөӮДӮЁӮиҒA“–‘R203ҚӮ’nҚU—ӘӮа”Ҫ‘ОӮҫӮБӮҪҒB –һҸBҢRҺ©җgӮаҺҷӢКӮЖ“ҜӮ¶Ӯӯ“Ң–k•ы–КҚU—ӘӮрҺxҺқӮөӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©Ӯө‘жҺOҢRӮН‘жҺOҺҹ‘ҚҚUҢӮӮМҗ¬ҢчӮМҢ©ҚһӮЭӮӘӮИӮӯӮИӮйӮЖҢҲҗSӮр•ПҚXӮө203ҚӮ’nҚU—ӘӮрҢҲҲУӮ·ӮйҒBӮұӮкӮЙ–һҸBҢR‘ӨӮМ•ыӮӘ”Ҫ‘ОӮөҒA‘ҚҺi—Я•”Ӯ©Ӯз”hҢӯӮіӮкӮДӮўӮҪҺQ–d•ӣ’·ӮМ•ҹ“ҮҲАҗіҸӯҸ«Ӯр‘жҺOҢRӮМ”’ҲдҺQ–dӮӘҗа“ҫӮөӮҪ’цӮҫӮБӮҪҒB ҺҷӢКӮӘ—Ҳ–KҺһӮЙ‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮМҺQ–dӮЙ‘ОӮөӮДҢғ“{ӮөҲЙ’n’mҺQ–d’·ӮзӮрҳ_”jӮөӮҪӮЖӮаҢҫӮнӮкӮДӮўӮйӮӘҒA‘жҺOҢRӮМҺQ–dӮН–wӮЗӮӘҺҷӢКӮЖүпӮБӮДӮЁӮзӮё“dҳbҳA—ҚӮЕҚПӮЬӮөӮДӮўӮйӮМӮЕҺ–ҺАӮЕӮНӮИӮўҒB’nҗ}ӮМӢLҚЪғ~ғXӮЕҺҷӢКӮЙ—Ө‘е‘ІӢЖӢLҸНӮрӮаӮ¬ҺжӮзӮкӮҪӮМӮН‘жҺOҢRҺQ–dӮЕӮНӮИӮӯ‘ж7Һt’cӮМҺQ–dӮЕӮ ӮйӮөҒAҗ퓬ҺӢҺ@ҺһӮЙ‘жҺOҢRҺQ–dӮрҺ¶җУӮөӮҪҳbӮаҺ–ҺАӮЕӮНӮИӮў(ӮұӮМҚЫ“ҜҚsӮөӮДӮўӮҪӮМӮНҸј‘ә–ұ–{‘жҲкҺt’c’·ӮЖ‘е”—Ҹ®•q‘жҺөҺt’c’·)ҒB ӮЬӮҪҺҷӢКӮӘ–ҪӮ¶ӮҪӮЖӮіӮкӮйҚUҸй–CӮМ24ҺһҠФҲИ“аӮМҗw’n•ПҚXӮЖ–Ў•ыҢӮӮҝӮрҠoҢеӮөӮҪҳA‘ұ–CҢӮӮаҒAҺҷӢКӮНҺАҺҝ“IӮЙӮНүҪӮаӮөӮДӮўӮИӮўҒBӮ·ӮЕӮЙ28cmһЦ’e–CӮН‘жҺOҢRӮЙ”z”хӮіӮкӮДӮўӮҪ‘S–C–еӮӘ203ҚӮ’nҗнӮЙ‘ОӮөӮДҺg—pӮіӮкӮДӮўӮйӮөҒAҺҷӢК—Ҳ’…Ӯ©ӮзҚUҢӮҚДҠJӮМ5“ъӮЬӮЕӮМҠФӮЙҗw’n•ПҚXӮ·ӮйӮұӮЖӮН“–ҺһӮМӢZҸpӮЕӮН•sүВ”\ӮЕӮ ӮйҒBҺАҚЫӮМӮЖӮұӮлӮН12cmһЦ’e–C15–еӮЖ9cmүP–C12–еӮр203ҚӮ’nӮЙӢЯӮўҚӮҚиҺRӮЙҲЪӮөӮҪӮҫӮҜӮЕӮ ӮйҒB–Ў•ыҢӮӮҝҠoҢеӮЕҢӮӮВӮжӮӨҺҷӢКӮӘ–ҪӮ¶ӮҪӮЖӢ@–§“ъҳIҗнҺjӮЕӮНӢLҸqӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҚUҸй–C•әҺi—Я•”ӮЙӮўӮҪ“Ю—З•җҺҹҸӯҚІӮНҒu—FҢRӮӘӮўӮДӮа–C•әӮӘҺЛҢӮӮөӮДҚўӮйҒvӮЖӢtӮЙҺҷӢКӮЖ‘е”—Һt’c’·ӮӘҚUҸй–C•әӮЙҚRӢcӮөӮҪӮЖҸqӮЧӮДӮўӮйҒB“Ю—ЗҸӯҚІӮМҒuғҚғVғAҢRӮМҚs“®Ӯр‘jҺ~Ӯ·ӮйӮҪӮЯӮЙӮН’vӮө•ыӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨҗа–ҫӮЙҺҷӢКӮН”[“ҫӮөӮҪӮӘҒA‘жҺOҢRӮМ’Г–м“cҺQ–dӮаҒu“ъ–{ӮМҺR–C‘аӮН“®ӮӯӮаӮМӮӘҢ©ӮҰӮҪӮз”ӯ–CӮөӮДӮўӮҪҒvӮЖҸШҢҫӮөӮДӮЁӮиҒAҺҷӢКӮЕӮНӮИӮӯ‘жҺOҢR‘ӨӮМ”»’fӮЕ–Ў•ыҢӮӮҝҠoҢеӮЕ”ӯ–CӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйҒB ҚUҢӮ•”‘аӮМҗw’n•ПҚXӮИӮЗӮаӮИӮіӮкӮДӮЁӮзӮёҒAҸгӢLӮМ—lӮЙҸ]—ҲҢҫӮнӮкӮйҺҷӢКӮМҺwҠцүо“ьӮа‘еӮ«ӮИӮаӮМӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҢ©ӮДҒA203ҚӮ’nӮН–wӮЗҸ]—ҲӮМҚмҗнҢvүж’КӮиӮЙҚUҢӮӮӘҚДҠJӮіӮк‘жҺOҢRӮМҚмҗнӮЕ1“ъӮЕҠЧ—ҺӮөӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮБӮДӮўӮйҒB ӢЯ”NҒA‘жҺOҢRҺQ–d”’Ҳд“сҳYӮв“Ж—§–C•ә‘е‘а’·Ҹг“Ү‘PҸdӮМүс‘zӮЖӮўӮБӮҪ‘жҺOҢRҺi—Я•”‘ӨӮМҺj—ҝӮ©ӮзҒAҺҷӢКӮӘ—·ҸҮӮЕҺАҚЫӮЙ‘жҺOҢRӮМҚмҗнӮЙҺwҺҰӮр—^ӮҰӮДӮўӮҪӮұӮЖӮрҺw“EӮ·ӮйҢӨӢҶӮӘҗVӮөӮӯҸoӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮҪӮҫӮөҒAӮұӮкӮЙӮжӮйӮЖҺҷӢКӮНҚмҗн—§ҲДҺ©‘МӮНҲЙ’n’mҚKүо‘жҺOҢRҺQ–d’·ҲИүәӮМ‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮЙҚsӮнӮ№ӮДӮЁӮиҒAҺҷӢКӮМ”ӯҲДӮҫӮҜӮЕҚмҗнӮӘҢҲӮЬӮБӮҪӮЖӮНҸqӮЧӮзӮкӮДӮўӮИӮўҒBҸгӢLӮМ’КӮиҚмҗнҺ©‘МӮЩӮЖӮсӮЗ•ПҚXӮӘҢ©ӮзӮкӮИӮў“_Ӯ©ӮзҢ©ӮДӮаҒAҺҷӢКӮМҺw“ұӮӘӮ ӮБӮҪӮЙӮ№Ӯж“а—e“IӮЙӮНӢЙӮЯӮДҸӯӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ’·үӘҠOҺj
—·ҸҮҚU—Әҗн“–ҺһӮЙҺQ–d–{•”ҺQ–dҺҹ’·ӮМҗEӮЙӮ ӮБӮҪҒBҠJҗнҺһӮМ‘еҺRҺQ–d‘Қ’·ӮЖҺҷӢКҺQ–dҺҹ’·ӮӘҒA–һҸBҢR‘ҚҺi—Я•”җЭ’uӮЙ“–ӮҪӮи“а’nӮр—ЈӮк‘е—ӨӮЙҲЪ“®Ӯ·ӮйӮЙӢyӮсӮЕҺҷӢКҺҹ’·ӮМҢгӮр”CӮіӮкӮҪҒB’·үӘӮНӮМӮҝӮЙҒu’·үӘҠOҺjүсҢЪҳ^ҒvӮр“ZӮЯҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕ—·ҸҮҚU—ӘҗнӮЙӮВӮўӮДӮМҠҙ‘zӮрҺcӮөӮДӮўӮйҒB’·үӘӮМӢLҸqӮНҒu’JҗнҺjҒvӮИӮЗӮЙҲш—pӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҢгҗўӮМ—·ҸҮҚU—ӘҗнҢӨӢҶӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮр—^ӮҰӮҪҒB“–ҺһӮМ—ӨҢR’Ҷүӣ•”ӮЙҲК’uӮөӮҪҗl•ЁӮМӢLҳ^ӮЕӮ ӮиӢMҸdӮИӮаӮМӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҠФҲбӮўӮИӮўӮӘҒAӮ»ӮМ“а—eӮЙӮН–ҫӮзӮ©ӮИҢлӮиӮӘ”FӮЯӮзӮкӮйҒB —бӮҰӮО9ҢҺӮМҚUҢӮӮНҒAҺе–hҢдҗьӮжӮиҠO‘ӨӮМ‘Oҗiҗw’nӮрҚU—Ә‘ОҸЫӮЖӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиҒA—ҙҠб–k•ы•Ы—ЫӮвҗ…ҺtүcҺь•У•Ы—ЫӮЬӮҪ203ҚӮ’nҺь•УӮМӢ’“_ӮМҗи—МӮЙҗ¬ҢчӮөӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAҒu‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮЖ“Ҝ—l–wӮЗүдӮЙӮИӮсӮзӮМҺыҠnӮИӮөҒvӮЖҢлӮиӮрҸqӮЧӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪ10ҢҺӮМ—·ҸҮҚUҢӮӮӘҺё”sӮЙҸIӮнӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮВӮўӮДӮНҒuӮЬӮҪ‘SӮӯ‘OүсӮМӮЖ“ҜҲкӮМ”ЯҺSҺ–ӮрҢJӮи•ФӮөӮДҺҖҸқҺOҗз”Ә•S—]–јӮр“ҫӮҪӮМӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮаӮ»ӮМӮНӮёӮЕҒAҲкҒA“сҒAҺOүсӮЖӮа–wӮЗ“ҜҲкӮМ•ы–@ӮЕ“ҜҲкӮМҢҳ—ЫӮр–і—қүҹӮөӮЙҚUӮЯ—§ӮДӮҪҒvӮЖҸqӮЧӮДӮЁӮиҒAҺе–hҢдҗьӮЦӮМҚUҢӮӮЖ‘Oҗiҗw’nӮЦӮМҚUҢӮӮМӢж•КӮаӮИӮіӮкӮёҒAӮЬӮҪӢӯҸP–@Ӯ©ӮзҗіҚU–@ӮЦӮЖҗн–@Ӯр•ПҚXӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮВӮўӮДӮаҗGӮкӮДӮўӮИӮўҒB 203ҚӮ’nӮЙӮВӮўӮДӮНҒu9ҢҺ’ҶҸ{ӮЬӮЕӮНҺR• ӮЙӢНӮ©ӮМҺU•әҚҲӮӘӮ ӮйӮМӮЭӮЙӮДҒA“GӮНӮұӮұӮЙӮИӮсӮзӮМҗЭ”хӮрӮаҗЭӮҜӮИӮ©ӮБӮҪҒvӮЖҸqӮЧҒAӮұӮкӮрҚӘӢ’ӮЖӮөӮДҒuӮдӮҰӮЙ9ҢҺ22“ъӮМ‘жҲкҺt’cӮМҚUҢӮӮЙӮЁӮўӮДҚЎӮРӮЖ‘§•ұ”ӯӮ·ӮкӮОҠ®‘SӮЙҗи—МӮө“ҫӮй”ӨӮЕӮ ӮБӮҪҒvӮЖӮМҢ©үрӮрҸqӮЧӮДӮўӮйҒBӮұӮМ’·үӘӮМҢ©үрӮН‘ҪӮӯӮМ’ҳҚмӮЙҲш—pӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮкӮНҢ»ҚЭӮМҢӨӢҶӮЙӮжӮкӮО”Ы’иӮіӮкӮйҒB 28cmһЦ’e–CӮМ—·ҸҮ”hҢӯӮЙӮВӮўӮДӮаҒAҺ©ҢИӮМҠЦ—^ӮӘ‘еӮ«Ӯ©ӮБӮҪӮұӮЖӮрҸqӮЧӮДӮўӮйӮӘ(ӮұӮМҢҸӮЙҠЦӮөӮДӮН‘ж3ҢRӮМҲЙ’n’mҺQ–d’·ӮӘҒu(Ӣҗ–CӮН)‘—ӮйӮЙӢyӮОӮёҒvӮЖ“d•сӮөӮҪӮЖӮўӮӨҳbӮӘ—L–јӮҫӮӘҒAӮұӮкӮрҠЬӮЯӮД)ҒAҢ»ҚЭӮЕӮН’·үӘӮМ‘nҚм(—iҢмӮ·ӮйӮЖӮөӮДӮаӢLүҜҲбӮў)ӮЕӮ ӮйӮЖҢӢҳ_•tӮҜӮзӮкӮДӮўӮйҒB28cm—Ъ’e–CӮр—·ҸҮ—vҚЗҚUҢӮӮЙ—pӮўӮйӮұӮЖӮНҒA‘ж3ҢR•Тҗ¬ҲИ‘OӮМ5ҢҺ10“ъӮЙ—ӨҢRҸИӢZҸpҗRҚё•”ӮӘ–C•әүЫ’·ӮЙӢпҗ\Ӯө—ӨҢR‘еҗbҲИүәӮаӮұӮкӮр”FӮЯҺQ–d–{•”ӮЙҗ\Ӯө“ьӮкӮДӮўӮҪӮӘҒAҺQ–d–{•”ӮН’ҶҸ¬ҢыҢa–CӮМ–CҢӮӮЙҺҹӮ®ӢӯҸPӮрӮаӮБӮДӮ·ӮкӮО—·ҸҮ—vҚЗӮрҠЧ—ҺӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЖ”»’fӮөӮДӮұӮМ’сҲДӮрҺжӮи“ьӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢг8ҢҺ21“ъӮМ‘ҚҚUҢӮҺё”sӮМӮМӮҝҒAҺӣ“аҗіӢB—ӨҢR‘еҗbӮНӮ©ӮЛӮДӮжӮи—vҚЗҚUҢӮӮЙ28cm—Ъ’e–CӮрҺg—pӮ·ӮЧӮ«ӮЖҺе’ЈӮөӮДӮўӮҪ—LҚвҗ¬ҸНӢZҸpҗRҚё•”’·ӮрҸөӮўӮД25°26“ъӮЖҲУҢ©Ӯр•·ӮўӮҪӮМӮҝҚМ—pӮ·ӮйӮұӮЖӮрҢҲ’fӮөҒAҺQ–d–{•”ӮМҺRгpҺQ–d‘Қ’·ӮЖӢҰӢcӮөӮДӮ·ӮЕӮЙ’БҠCҳpӮЙҲЪҗЭӮМӮҪӮЯҲЪҗЭҚHҺ–ӮрҠJҺnӮөӮДӮўӮҪ28cm–CҳZ–еӮр—·ҸҮӮЙ‘—ӮйӮұӮЖӮрҢҲ’иӮөӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮӘҺАҚЫӮМ“®Ӯ«ӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©Ӯө’·үӘ’kҳbӮЙӮжӮкӮОҒAҺQ–d–{•”‘ӨӮМ’·үӘҺQ–dҺҹ’·ӮӘҒA‘ҚҚUҢӮҺё”sӮМӮМӮҝӮЙ28—Ъ’e–CӮМ—·ҸҮ—vҚЗҚUҢӮӮЙ—pӮўӮйӮЧӮ«ӮЖӮўӮӨ—LҚвҸӯҸ«ӮМҲУҢ©Ӯр•·ӮўӮД“ҜҲУӮөҒA—ӨҢR‘еҗbӮрҗа“ҫӮөӮҪӮЖҒAӮЬӮБӮҪӮӯӢtӮМӮұӮЖӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB ӮұӮкӮзӮМҢлӮБӮҪҢ©үрӮЬӮҪ‘nҚмӮіӮкӮҪҳbӮрҚӘ–{ӮЖӮөӮД‘жҺOҢR”б”»ӮМ‘е•”ӮӘҢ–“`ӮіӮкҒAҢ»ҚЭӮаӮ»ӮкӮН‘ұӮўӮДӮўӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳY
”T–ШӮЖӢӨӮЙ“ъҳIҗн‘ҲҢгӮЙүp—Yү»ҒEҗ_Ҡiү»ӮіӮкӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЙӮВӮўӮДӮНҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮМӢPӮ©ӮөӮўҗнүКӮМүeӢҝӮ©ӮзӮ©ҒA—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙӮЁӮҜӮй•ӘҗНӮЁӮжӮС•]үҝӮӘҒA”T–ШӮЙ”дӮөӮДҲі“|“IӮЙҸӯӮИӮўҒB“ъҳIҠJҗн’јҢгӮМ‘О’n–CҢӮҚмҗн”s‘ЮҒA3үсӮЙӢyӮФҚ`Ңы•ВҚЗҚмҗнҺё”sҒA”s‘ЮӮЕӮНӮИӮўӮӘӢlӮЯӮӘҠГӮӯҺё”sӮЖ•]ӮіӮкӮйү©ҠCҠCҗнҒAҠCҢRӮМҚмҗн‘S”КӮрҺwҠцӮөӮҪ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮа—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙӮЁӮўӮДӮН–Ъ—§ӮБӮҪҗнҗСӮНӮИӮўҒB—ӨҢRӮМ”T–ШӮМ•]үҝӮЖӢӨӮЙҒA—·ҸҮҚUҲНҗнӮЕӮМҠCҢRӮМ“ҢӢҪӮМ•]үҝӮа•K—vӮЖӮўӮӨҗәӮаҲк•”ӮЙ‘¶ҚЭӮ·ӮйҒBӮЬӮҪ•]үҝӮНӮЗӮӨӮ ӮкҒA—·ҸҮ—vҚЗӮЙ”T–Ш(—ӨҢR)Ӯа“ҢӢҪ(ҠCҢR)ӮаӢкӮөӮЯӮзӮкӮҪӮұӮЖӮНҺjҺАӮЖӮөӮДҺcӮйҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҲнҳb
ғҚғVғAҢRӮМ”sҲцӮЖӮөӮДҒAғrғ^ғ~ғ“C•s‘«ӮӘҢҙҲцӮМүуҢҢ•aӮЙӮжӮйҗнҲУ‘rҺёӮӘҲкҲцӮЖӮөӮДӢ“Ӯ°ӮзӮкӮДӮўӮйҒB—·ҸҮ—vҚЗ“аӮМ”х’~җH—ҝӮЙӮН‘е“ӨӮИӮЗӮМҚ’•Ё—ЮӮӘ‘ҪӮӯҒA–мҚШ—ЮӮНҸӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB‘е“ӨӮрҗ…ӮЙ’РӮҜӮД”ӯүиӮіӮ№ӮкӮОғrғ^ғ~ғ“–L•xӮИӮаӮвӮөӮӘӮЕӮ«ӮйӮӘҒAғҚғVғAӮЙӮНӮаӮвӮөӮрҚмӮБӮДҗHӮЧӮйҸKҠөӮӘ–іӮ©ӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҰғrғ^ғ~ғ“CӮӘ”ӯҢ©ӮіӮкӮҪӮМӮН1920”NӮЕӮ ӮиҒAӮіӮзӮЙҒAӮаӮвӮөӮЙғrғ^ғ~ғ“ӮӘҠЬӮЬӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ”ӯҢ©ӮіӮкӮйӮМӮНӮаӮБӮЖҢгӮМҺһ‘гӮҫӮБӮҪҒBҲк•ыҒA“ъ–{—ӨҢRӮМҗнҺһ•әҗHӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮЖ“ҜӮ¶Ӯӯ”’•Д”С(җё”’•Д6ҚҮ)ӮЕӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮаӮ ӮиҒAӢrӢCӮӘ‘е—¬ҚsӮөӮДӮўӮҪҒB —^ҺУ–мҸ»ҺqӮНҒA—·ҸҮ•пҲНҢRӮМ’ҶӮЙҚЭӮй’нвФҺOҳYӮр’QӮӯ“а—eӮМҒwҢNҺҖӮЙӮҪӮЬӮУӮұӮЖӮИӮ©ӮкҒxӮр1904”N9ҢҺӮЙҒw–ҫҗҜҒxӮЕ”ӯ•\ӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҺАҚЫӮЙӮН’нӮН‘ж4Һt’cҸҠ‘®ӮЕӮ ӮиҒA—·ҸҮҚUҲНҗнӮЙӮНҺQүБӮөӮДӮўӮИӮўҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ203ҚӮ’n | |
|
’ҶҚ‘–k“Ң•”ӮМ—Й“Ң”ј“Ү“м’[ӮЙҲК’uӮ·Ӯй—·ҸҮ(Ң»ҚЭӮМ‘еҳAҺs—·ҸҮҢыӢж)ӮЙӮ ӮйӢu—ЛӮЕӮ ӮйҒB1904 - 1905”NӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮНғҚғVғAҠCҢRӮМҠо’nӮМӮ ӮБӮҪ—·ҸҮҚ`ӮрҸ„Ӯй“ъҳIӮМ‘Ҳ’DҗнӮЙӮжӮйҢғҗн’nӮЖӮИӮБӮҪҸкҸҠҒBӢҢҺsҠX’nӮ©Ӯз–kҗј2kmӮЩӮЗӮМӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮйҒBҠC”І203mӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮ©ӮзӮұӮМ–јӮӘ•tӮҜӮзӮкӮҪҒB
ҒЎ“ъҳIҗн‘Ҳ “ъҳIҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮДҒA—·ҸҮҚU—ӘӮН•K—v•sүВҢҮӮЙӮИӮиҒA“ъ–{—ӨҢRӮН‘жҺOҢRӮр•Тҗ¬Ӯө—·ҸҮ—vҚЗӮрҚUҢӮӮөӮҪҒB 203ҚӮ’nӮНҒA“–ҸүӮ ӮЬӮиҸd—vҺӢӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъ–{‘ӨӮНҠП‘ӘӮЕӮ«Ӯй’n“_ӮН203ҚӮ’nӮМ‘јӮЙӮаӮ ӮиҒAҠщӮЙ‘ҚҚUҢӮ‘OӮЙҗи—МӮөӮҪ‘еҢЗҺRӮ©ӮзҠП‘ӘҺЛҢӮӮрҺАҺ{ӮөӮДӮўӮҪҒB–CҢӮҠJҺn2“ъ–ЪӮЙӮНҗнҠНғҢғgғ”ғBғUғ“ӮЙ–Ҫ’Ҷ’eӮр—^ӮҰҒA—·ҸҮҠН‘аӮЙҠлӢ@ҠҙӮр•шӮ©Ӯ№ҒAү©ҠCҠCҗнӮЦӮМ’[ҸҸӮЙӮИӮБӮДӮаӮўӮйҒB ғҚғVғAҢR‘ӨӮаҒA203ҚӮ’nҲк‘СӮН—vҚЗҺе–hҢдҗьӮ©Ӯз—ЈӮкӮДӮЁӮиҚUҢӮ‘ӨӮ©ӮзӮ·ӮйӮЖҲЪ“®ӮЙҺһҠФӮӘӮ©Ӯ©ӮйӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAӮ»ӮМҚЫӮН‘јӮМ–hҢд•Ы—ЫӮ©ӮзӮНӮЬӮйҢ©ӮҰӮЕҢ}ҢӮӮр”нӮйӮЖӮўӮӨҚUӮЯӮйӮЙ•s—ҳӮИ’n“_ӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯҒAҢxүъҗw’nҒE‘Oҗiҗw’nӮЖӮөӮДү^—pӮөӮДӮўӮҪҒB ӮөӮ©Ӯө“мҺRӮМҗнӮўҢгӮжӮи–hҢдӢӯү»ӮМҚHҺ–ӮӘӮИӮіӮкӮДӮЁӮиҒA‘жҺOҢRӮМ•пҲНҠ®—№Һһ“_ӮЕӮ©ӮИӮиӢӯҢЕӮИҗw’nӮЖӮИӮБӮДӮўӮҪҺ–ӮӘҚUҸй–C•әҺi—Я•”ҺQ–dӮМҸШҢҫӮЙӮ ӮйҒB ӮұӮӨӮўӮБӮҪ—қ—RӮЙӮжӮи‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮӮЕӮН–Ъ•WӮЖӮіӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҚUҢӮҺё”sҢгӮЙҠCҢRӮӘ—·ҸҮҚ`’в”‘’ҶӮМғҚғVғAҠН‘аӮр–CҢӮӮ·ӮйҚЫӮМ’e’…ҠП‘Ә“_ӮЖӮөӮДҚD“KӮЕӮ ӮйӮЖӮөӮДҚU—ӘӮрҗiҢҫ(ҸHҺRҗ^”VӮӘҗiҢҫӮөӮҪӮЖӮаӮўӮнӮкӮйӮӘ’иӮ©ӮЕӮНӮИӮў)ӮөҒAӮұӮкӮЙ“–ҸүӮ©Ӯз—vҚЗҗј•ыҺеҚUҗЁҳ_ӮҫӮБӮҪ’ҶүӣӮМ‘е–{үcӮӘ“Ҝ’ІӮөӮД203ҚӮ’nҚU—ӘӮрҺxҺқӮ·ӮйҒB ӮұӮкӮЙ‘ОӮө–һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘еҺRҠЮӮв‘ҚҺQ–d’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYҒAҢ»’nҢRӮЕӮ Ӯй‘ж3ҢRҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҠу“TӮзӮН 1. ҠщӮЙ‘еҢЗҺRӮ©ӮзӮМҠП‘Ә–CҢӮӮвү©ҠCҠCҗнӮЕ—·ҸҮҠН‘аӮНүу–ЕӮөӮДӮЁӮиҒAҠП‘Ә“_ӮИӮЗ•K—vӮЖӮөӮИӮўҒB 2. ҠН‘аӮрҹr–ЕӮөӮДӮа—vҚЗҺз”х‘аӮНҚ~•ҡӮ№ӮёҒAҚ~•ҡӮөӮИӮўҢАӮи‘ж3ҢRӮН–kҸгӮ·ӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮНҒA—vҚЗҗі–КӮЦӮМҚUҢӮӮЙӮжӮйҸБ–ХҗнӮөӮ©ӮИӮўҒB ӮЖ”»’fӮөҒAҠCҢRӮв‘е–{үcӮМ203ҚӮ’nҚUҢӮ—vҗҝӮрӢpүәӮө‘ұӮҜӮҪҒB җнҺФӮвҚqӢуӢ@ӮМӮИӮў“–ҺһӮЖӮөӮДӮНҒA‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗнӮЕӮМ“dҢӮҗнӮМӮжӮӨӮИ‘ҒҠъ“Л”jӮНӮЕӮ«ӮИӮўҲИҸгҒAҡНҚҲӮЙвДӮи“SҸр–ФӮЖӢ@ҠЦҸeӮЕҺзӮБӮДӮўӮй“G—vҚЗӮр—ҺӮЖӮ·ӮЙӮНҸБ–ХҗнӮөӮ©ӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮөӮ©Ӯө‘е–{үcӮ©ӮзӮМҲі—Н(–{—ҲҒA‘ж3ҢRӮН–һҸBҢRӮМҸҠ‘®ӮЕҒA‘е–{үcӮМ’јҗЪҺwҠцүәӮЙӮИӮў)ӮЙ‘ж3ҢRӮӘӢьӮө1904”N11ҢҺ28“ъӮЙ203ҚӮ’nҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·ӮйҒBҲк“xӮН’DҺжӮЙҗ¬ҢчӮ·ӮйӮағҚғVғAҢRӮӘ”ҪҚUӮөӮД’DҠТӮіӮкҒAҲкҗiҲк‘ЮӮМҢғҗнӮЖӮИӮйҒB ҢӢӢЗ12ҢҺ5“ъӮЙ203ҚӮ’nӮНҠЧ—ҺӮ·ӮйҒBҢӢүК“IӮЙӮұӮМҗнӮўӮЕ—vҚЗӮМ—\”хҗн—НӮӘҢНҠүӮөҒA‘ұӮӯ—vҚЗҗі–КӮЕӮМҚU–hӮЕ—LҢшӮИҢ}ҢӮӮӘӮЕӮ«ӮёҒAҗі–К–hҢдҗьӮМ“ҢҢ{ҠҘҺR•Ы—ЫҒA“с—ҙҺR•Ы—ЫӮИӮЗӮӘ‘ҠҺҹӮўӮЕҠЧ—ҺҒA—Ӯ1905”N1ҢҺ1“ъӮЙ—vҚЗӮНҚ~•ҡӮөӮҪҒB –{‘Ҳ’DҗнӮНҒA‘ҪӮӯӮМҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮҪҒB‘ж7Һt’c(Ҳ®җм)ӮНҒA15,000җlӮЩӮЗӮМ•ә—НӮӘ5“ъҠФӮЕ–с3,000җlӮЙӮЬӮЕҢёҸӯӮөӮҪҒBғҚғVғA‘ӨӮМ”нҠQӮа‘еӮ«ӮӯҒAӮ ӮиӮЖӮ ӮзӮдӮй—\”х•әӮв—ХҺһӮЙҠCҢRӮ©Ӯз—ӨҢRӮЦҲЪӮіӮкӮҪҗ…•әӮЬӮЕӮаӮӘҒAӮұӮМҚӮ’nӮЕ–ҪӮр—ҺӮЖӮөӮҪҒB”T–ШҠу“TӮНҒAҺ©ҚмӮМҠҝҺҚӮЕ203ҚӮ’nӮр“сҒZҺO(ӮЙҒEӮкӮўҒEӮіӮс)ӮМ“–ӮДҺҡӮЕҺў—мҺR(ӮЙӮкӮўӮіӮс)ӮЖүrӮсӮҫҒB ҒЎ203ҚӮ’nӮ©ӮзӮМҠП‘ӘҺЛҢӮӮЙӮВӮўӮД 1904”N12ҢҺ5“ъӮЙ“ъ–{ҢRӮӘҗи—МӮөҒAүi–мҸCҗgҠCҢR‘еҲСӮӘҺwҠцӮөӮҪ—ӨҸгӮ©ӮзӮМ–CҢӮӮЕғҚғVғA“Ң—mҠН‘аӮрүу–ЕӮіӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮӘ’КҗаӮҫӮӘҒAҠЧ—ҺҢгӮМ—ӨҠCҢRӮЙӮжӮй’ҫҠНӮЦӮМ’ІҚёӮЕӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМҠНӮН–Ҫ’ҶӮөӮДӮаҠН’кӮЙ‘№ҠQӮрҺуӮҜӮДӮЁӮзӮёҒAҗZҗ…ӮИӮЗӮНӢNӮұӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪ(—ӨҢRҸИҢR–ұӢЗ–C•әүЫҗОҢхҗ^җbӮв•җ“cҺOҳYҒAҸг“cҚvӮзӮӘ’ІҚёӮрҠJҺnҒA1906”N11ҢҺҚЕҸI•сҚҗ)ҒB Һg—pӮөӮҪ“сҸ\”Ә‘W–CӮМ–C’eӮӘҢГӮӯҒAҗMҠЗӮМ“®Қм•s—ЗӮаӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕ•s”ӯ’eӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪҒB•сҚҗӮрҺуӮҜӮҪ—ӨҢRҸИӢZҸpҗRҚё•”’·—LҚвҗ¬ҸНӮН–C’eӮМ‘S–К•ПҚXӮрҺwҺҰӮөӮДӮўӮйҒBҠCҢR‘ӨӮМ’ІҚёӮЕӮНҒA‘ҪӮӯӮМҠН’шӮӘғLғ“ғOғXғgғ“•ЩӮрҠJӮўӮДӮўӮҪҺ–ӮӘҠm”FӮіӮкӮДӮўӮҪӮжӮӨӮЕҒA•сҚҗӮЕӮНҺ©’ҫҸҲ—қӮіӮкӮҪӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB ӮЬӮҪ‘жҲкҺҹ‘ҚҚUҢӮ‘OӮЙҚsӮнӮкӮҪү©ҠCҠCҗнӮЕҒA—·ҸҮҠН‘аӮНҠщӮЙҗ퓬•s”\ӮИ’цӮМ‘е‘№ҠQӮр”нӮБӮДӮЁӮиҒA—·ҸҮҚ`ӮМҺ{җЭӮЕӮНҸC•ңӮН•sүВ”\ӮҫӮБӮҪҒBҢӢӢЗҒAҗнҠНғZғ”ғ@ғXғgғ|ғҠӮҫӮҜӮӘҠO—mҚqҚsүВ”\ӮИ’ц“xӮЬӮЕҸC•ңӮіӮкӮҪ(Ӯ»ӮМҢгғZғ”ғ@ғXғgғ|ғҠӮНҗнҠНӮМ’ҶӮЕ—BҲкҠП‘ӘҺЛҢӮӮрӮМӮӘӮкӮҪӮӘҒA“ъ–{ҠCҢRӮМҗ…—Ӣ’шӮМ—ӢҢӮӮЙӮжӮи‘е”jӮөҺ©’ҫӮөӮҪ)ӮӘҒA‘јӮМҠН’шӮНҗ퓬•s”\ӮИӮЬӮЬ•ъ’uӮіӮкҒAҚЕҢгӮНҺ©’ҫҸҲ—қӮіӮкӮҪҒB203ҚӮ’nӮМҒu—·ҸҮҠН‘аҹr–ЕӮМӮҪӮЯӮМҠП‘Ә“_ҒvӮЖӮөӮДӮМүҝ’lӮНҒAҺАҚЫӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮҰӮйҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ203ҚӮ’nӮрҢ©Ӯй | |
|
—·ҸҮҚ`ӮрҸ„Ӯй“ъҳIӮМ‘Ҳ’DҗнӮЕҢғҗн’nӮЖӮИӮБӮҪҠC”І203ӮҚӮМҺR
ҒЎ“ЛҢӮӮЖ‘ЮӢpӮӘҢJӮи•ФӮіӮк‘ҪӮӯӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪҗнҸк —·ҸҮҒ@Ғ|Ғ@–ҫҺЎӮрҗ¶Ӯ«ӮҪ“ъ–{җlӮЙӮЖӮБӮДҒAӮұӮМ“с•¶ҺҡӮН’n–јҲИҸгӮЙҒA—lҒXӮИҲУ–ЎӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒBӮ»ӮкӮНҗўҠEҚЕӢӯӮМғҚғVғAҢRӮЙҸҹ—ҳӮөӮҪӮЖӮўӮӨҠҙ“®ӮҫӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB—·ҸҮҠЧ—ҺӮМ•сӮЙҗЪӮөҒA“ъ–{’ҶӮӘ•ҰӮ«Ӯ©ӮҰӮиҒAҠXӮЙӮН’с“”Қs—сӮӘҸoӮДҸҹ—ҳӮрҸjӮБӮҪӮЖ•·ӮўӮДӮўӮйҒB Ӯ»ӮМҲк•ыӮЕҒAҗMӮ¶ӮзӮкӮИӮўӮЩӮЗ‘ҪӮӯӮМҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮҪҒBғҚғVғA‘ӨӮМ—·ҸҮ—vҚЗҺз”х•ә—НӮН35ҒA600–јҒAӮұӮкӮрӮрҚUҲНӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮНү„ӮЧ12–ң–јҒAҗ퓬ҠъҠФӮН155“ъӮҫӮБӮҪӮӘҒA—·ҸҮҠJҸйӮМҺһ“_ӮЕ“ъ–{ҢRӮМҺҖҸқҺТӮН–с6–ңҒAғҚғVғAҢRӮМӮ»ӮкӮН3–ңӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНҒAӢЯ‘г“ъ–{ӮМҗнҺjӮМ’ҶӮЕҚЕӮа”ЯҲЈӮрӮаӮБӮДҢкӮзӮкӮйӮұӮЖӮӘ‘ҪӮўӮӘҒA—·ҸҮҚUҲНҗнӮНӮ»ӮМ”ЯҲЈӮрҸЫ’ҘӮ·ӮйҗнӮўӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕӮаҒA1904”N(–ҫҺЎ37)ӮМ11ҢҺ26“ъӮ©Ӯз12ҢҺ6“ъӮЬӮЕ‘ұӮҜӮзӮкӮҪ203ҚӮ’nҚU—ӘҗнӮЕҒA“ъ–{ҢRӮН–с6–ң4җзӮМ•әҺmӮр“Ҡ“ьӮөҒAҗнҺҖҺТ5ҒA052–јҒA•үҸқҺТ11ҒA884–јҒAҚҮҢv16ҒA936–јӮЖӮўӮӨҗMӮ¶ӮӘӮҪӮўҗ”ӮМӢ]җөҺТӮрҸoӮөӮҪҒB —·ҸҮ”Һ•ЁҠЩӮрҢ©ҠwӮөӮҪҢгҒA—·ҸҮҢыӢжӮЙӮ ӮйғzғeғӢӮМғҢғXғgғүғ“ӮЕ’ӢҗHӮрӮЖӮБӮҪҒBӮ»ӮМҢг–KӮкӮҪӮМӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМҺеҗнҸкӮМҲкӮВӮҫӮБӮҪ203ҚӮ’nӮЕӮ ӮйҒB203ҚӮ’nӮНҒAӢҢҺsҠX’nӮ©Ӯз–kҗј2ҒD2ӮӢӮҚӮЩӮЗӮМӮЖӮұӮлӮЙӮ Ӯй•WҚӮ203ӮҚӮМҺRӮЖӮаҢҫӮҰӮИӮўӢu—ЛӮЕӮ ӮйҒB’ёҸгӮЙҢьӮ©ӮӨҺФ‘ӢӮ©ӮзҒA—·ҸҮҚ`ӮӘҲк–]ӮЕӮ«ӮйӮМӮЕӮНӮЖҠъ‘ТӮөӮҪӮӘҒAҺc”OӮИӮӘӮзҺФ“№ӮМ—јҳeӮЙҗ¶Ӯў–ОӮйҺч–ШӮӘҺӢҠEӮрҺХӮБӮДҒA—·ҸҮҚ`ӮН’ёҸгӮЙ’…ӮӯӮЬӮЕ’ӯӮЯӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮрҲөӮБӮҪҸ‘җРӮЙӮНҒA—·ҸҮ—vҚЗӮв203ҚӮ’nӮМҚU—ӘӮрҸ]ҢRӢLҺТӮӘғҢғ“ғYӮЕӮЖӮзӮҰӮҪҺКҗ^ӮӘҢfҚЪӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮкӮрҢ©ӮйӮЖғҚғVғAҢRӮӘүiӢv—vҚЗӮр’zӮўӮД“ъ–{ҢRӮрҢ}ӮҰҢӮӮБӮҪ“ҢҢ{ҠҘҺRӮв“с—ҙҺRҒAҸј–ШҺRӮМҡЖ—Ы•tӢЯӮаҒA203ҚӮ’nӮМҺО–КӮаҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮӘӮНӮ°ҺRӮЕӮ ӮйҒB“–ҺһӮНӮаӮЖӮаӮЖҚrӮк’nӮҫӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮ»ӮкӮЖӮа—јҢRӮ©ӮзҢӮӮҝҸoӮіӮкӮй–C’eӮЙӮжӮБӮДҒA’n•\ӮӘ•ПӮҰӮзӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮЖӮаӮ©Ӯӯ“–ҺһӮНӮұӮМ•tӢЯӮаҚr—БӮЖӮөӮҪҗнҸкӮҫӮБӮҪҒB ғoғXӮЙ—hӮзӮкӮйӮұӮЖ10•ӘӮЩӮЗӮЕҒA203ҚӮ’nӮМ’“ҺФҸкӮЙ’…ӮўӮҪҒB’“ҺФҸкӮМ‘OӮЙҒu“сҒӣҺOҢiӢжҒvӮЖ’ӨӮиҚһӮсӮҫҠвҸкӮӘӮ ӮиҒAҺR’ёӮЬӮЕӮНӢ}ҚвӮӘӮ»ӮМҚ¶Ӯ©Ӯз‘ұӮўӮДӮўӮйҒB“k•аӮЕӮМ“o’ёӮӘ–і—қӮИҠПҢхӢqӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒA—L—ҝӮЕғ}ғCғNғҚғoғXӮӘ•КӮМғӢҒ[ғgӮЕҺR’ёӮЬӮЕү^ӮсӮЕӮӯӮкӮйҒB ҢЯҢгӮМ“ъҚ·ӮөӮНӢӯӮ©ӮБӮҪӮӘҒAӢ}ҚвӮрӮҪӮЗӮБӮДҺR’ёӮЬӮЕ“oӮБӮДӮЭӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB–ЪӮМ‘OӮЙ‘ұӮӯӢ}ҚвӮНҚЎӮН•Ь‘•ӮіӮкӮ·ӮБӮ©Ӯи—V•а“№ӮЖӮөӮДҗ®”хӮіӮкӮДӮўӮйӮӘҒAҚЎӮ©Ӯз105”N‘OҒAӮұӮМҺRӮМ’ёҸгӮрҗи—МӮ·ӮйӮҪӮЯӮЙҺАӮЙ‘ҪӮӯӮМ“Ҝ–EӮМҢҢӮӘ—¬ӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮкӮН•ҙӮкӮаӮИӮў—рҺj“IҺ–ҺАӮЕӮ ӮйҒB ҒЎғҚғVғAҢRӮМүiӢv—vҚЗӮМ‘OӮЙҺrӮМҺRӮр’zӮўӮҪ“ъ–{ҢR ҺАӮНҒA203ҚӮ’nҚU—ӘӮН“ъҳIҗн‘ҲӮМ“–ҸүӮМҚмҗнӮЙӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB1904”N(–ҫҺЎ37)2ҢҺ6“ъҒAғҚғVғAҗӯ•{ӮЙҚ‘Ңр’fҗвӮр’КҚҗӮөӮҪӮ»ӮМ“ъҒA“ъ–{җӯ•{ӮНҳAҚҮҠН‘аӮрҗi”ӯӮіӮ№ҒA‘S–Кҗн‘ҲӮЦӮМүОӮФӮҪӮрӮ«ӮБӮҪҒB‘е–{үcӮӘҠJҗн‘OӮЙҢҲӮЯӮҪҚмҗнӮМҠо–{ӮНҒA 1 —ӨҢRӮМҺеҚмҗнӮр–һҸBӮЙӮЁӮ«ҒAғҚғVғAӮМ–мҗнҢRӮрӢҒӮЯӮДҚUҢӮҒAү“Ӯӯ–k•ы’nӢжӮЙ‘|“ўӮ·Ӯй 2 ҠCҢRӮНҗПӢЙ“IӮЙғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрҚUҢӮӮөҒAӮұӮкӮрҢӮ–ЕӮөӮДӢЙ“ҢӮЙӮЁӮҜӮйҗ§ҠCҢ ӮрҠm—§Ӯ·ӮйҒA ӮЖӮўӮӨӮаӮМӮҫӮБӮҪҒB “–ҺһҒAғҚғVғAӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮН—·ҸҮҚ`ӮрӢ’“_ӮЖӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮМҠН‘аӮрүу–ЕӮіӮ№ӮИӮҜӮкӮОҒA“ъ–{ҠCӮвү©ҠCӮЕӮМүдӮӘҚ‘ӮМҗ§ҠCҢ ӮН•ЫҸШӮіӮкӮИӮўҒBӮЖӮұӮлӮЕҒA—·ҸҮҚ`ӮМ“ьӮиҢыӮН—·ҸҮҢыӮЖҢДӮОӮкӮДӮўӮйҒBҳVҢХ”ц”ј“ҮӮМ“Л’[ӮЖ‘ОҠЭӮМү©ӢаҺRҺRҳ[ӮЙӢІӮЬӮкӮҪҗ…ҳHӮНҒA•қӮӘ270ӮҚӮЩӮЗӮөӮ©ӮИӮӯҒAӮөӮ©ӮаҒAҗ…җ[ӮМҠЦҢWӮ©Ӯз‘еҢ^җнҠНӮӘҚqҚsӮЕӮ«ӮйӮМӮНҒAӮ»ӮМӮӨӮҝӮМ91ӮҚӮЙӮ·Ӯ¬ӮИӮўҒBӮ»ӮұӮЕҒAҳAҚҮҠН‘аӮН—·ҸҮҢыӮЙүЭ•Ё‘DӮИӮЗӮМ”p‘DӮр”ҡ”jӮөӮД’ҫӮЯҒAғҚғVғAӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮӘҠO—mӮЙҸoӮзӮкӮИӮӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҠпҚфӮрӮЖӮБӮҪҒBӮұӮкӮрҒu—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнҒvӮЖӮўӮӨҒB ӮұӮМ–і–dӮ«ӮнӮЬӮиӮИӮўҒu—·ҸҮҢы•ВҚЗҚмҗнҒvӮНҺO“xҺҺӮЭӮзӮкӮҪӮӘҒAӮўӮёӮкӮаҺё”sӮөӮҪҒBӮҪӮЬӮҪӮЬ“VҢуӮЙҢbӮЬӮкӮИӮ©ӮБӮҪӮиҒA”p‘DӮр–Ъ“I’n“_ӮЙү^ӮФ‘OӮЙ”ӯҢ©ӮіӮкӮДҸW’Ҷ–CүОӮр—ҒӮСӮҪӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBҲк•ыҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘү“ӮӯғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзҸ„ҚqӮөӮДӮӯӮй“®Ӯ«ӮрӮЭӮ№ӮДӮўӮҪҒB“ъ–{ӮМҳAҚҮҠН‘аӮӘғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҢ}ӮҰҢӮӮВ‘OӮЙҒA—·ҸҮӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрүу–ЕӮіӮ№ӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBӮіӮаӮИӮўӮЖҒAӢІӮЭҢӮӮҝӮіӮкӮйҠлҢҜҗ«ӮӘӮ ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮұӮЕҒA—ӨҢRӮЙ—·ҸҮӮМҚӮ’nӮМҲкӮВӮр’DҺжӮіӮ№”wҢгӮ©Ӯз—·ҸҮӮр’xӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB‘е–{үcӮН‘жҺOҢRӮрӢ}зҜ•Тҗ¬ӮөӮДҒAӮ»ӮМҺi—Я’·ҠҜӮЙ”T–ШҠу“T(ӮМӮ¬ӮЬӮкӮ·ӮҜ)Ӯр”C–ҪӮөӮҪҒB”T–ШҸ«ҢRӮМ—ҰӮўӮй‘жҺOҢRӮН6ҢҺ6“ъҒA—Й“Ң”ј“ҮӮМү–‘еаS(ӮҰӮсӮҪӮўӮЁӮӨ)ӮЙҸг—ӨӮ·ӮйӮЖҒA—·ҸҮӮМғҚғVғAҢR—vҚЗӮЦӮМҚUҢӮӮрҠJҺnӮөҒAҲИүәӮМӮжӮӨӮЙҺOүсӮМ‘ҚҚUҢӮӮрҚsӮБӮҪҒB Ғң‘жҲкүс‘ҚҚUҢӮҒF8ҢҺ19“ъӮЙ“с—ҙҺRҒA“ҢҢ{ҠҘҺRӮЙӮ ӮБӮҪ—·ҸҮ–k“Ң•”ӮМғҚғVғA—vҚЗӮЦӮМҚUҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҗ퓬ӮН8ҢҺ26“ъӮЬӮЕ6“ъҠФӮЙӢyӮсӮҫҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғAҢRӮМҠжӢӯӮИ”ҪҢӮӮЙӮ ӮўҒAҺё”sӮЙҸIӮнӮй(ӮұӮМҗ퓬ӮЙ5–ң765–јӮӘҺQүБӮөҒAӮ»ӮМӮӨӮҝ15ҒA860–јӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөӮҪ)ҒB Ғң‘ж“сүс‘ҚҚUҢӮҒF9ҢҺ9“ъӮ©Ӯз—ҙҠб–kҡЖ—ЫӮЁӮжӮСҗ…Һtүc“м•ыҡЖ—ЫӮЦӮМҚB“№ӮМҢ@ҚнӮрҢ@ӮиҗiӮЭҒA10ҢҺ26“ъӮ©Ӯз6“ъҠФҒA“ЛҢӮ‘аӮН“GӮМҸeҢӮӮр”рӮҜӮДҡЖ—ЫӮЙҗЪӢЯӮөҒAҺҠӢЯӢ——ЈӮ©Ӯз”’•әҗнӮр’§ӮсӮҫҒBӮҫӮӘҒAҚЎүсӮағҚғVғAҢRӮМҠжӢӯӮИ’пҚRӮЙӮ ӮБӮДҚмҗнӮНҗ¬ҢчӮ№Ӯё(ӮұӮМҗ퓬ӮЕҒA1ҒA092–јӮМҗнҺҖҺТҒA2ҒA728–јӮМ•үҸқҺТӮрҸoӮөӮҪ)ҒB Ғң‘жҺOүс‘ҚҚUҢӮҒF11ҢҺ26“ъӮЙҠJҺnӮіӮкҒA“с—ҙҺRҲИ“ҢӮМҲкҢЛҡЖ—ЫҒA“ҢҢ{ҠҘҺRҒAҸјҺчҺRӮЙӮўӮҪӮйӢҢҲН•ЗӮЦӮМҚUҢӮӮрҢJӮи•ФӮөӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮМҠeҺt’cӮНӮұӮЖӮІӮЖӮӯ–Ъ•WӮр’Bҗ¬ӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъҳIҗнҺjӮЙҺcӮйҒA“Б•К—\”х‘а2600—]–јӮ©ӮзӮИӮй”’жF‘аӮМҠпҸPҚUҢӮӮаӮұӮМӮЖӮ«ҚsӮнӮкӮҪ(“ъ–{‘ӨӮН4ҒA500–јӮМҺҖҸқҺТӮрҸoӮөҒBғҚғVғAҢRӮаҗнҺҖҺТӮрҸoӮөӮҪ)ҒB ӮИӮәӮ©‘жҺOҢRҺi—ЯҠҜӮМ”T–ШҸ«ҢRӮНҒA—·ҸҮ—vҚЗӮМҗі–КҚUҢӮӮЙҢЕҺ·ӮөӮДӮўӮйҒB‘е–{үcӮӘ—·ҸҮҚ`ӮрҢ©үәӮлӮ№Ӯйҗј‘ӨӮМ“сҒZҺOҚӮ’nӮЙҚUҢӮӮМ–Ъ•WӮрҗШӮи‘ЦӮҰӮйӮжӮӨӮҪӮСӮҪӮСҢP—ЯӮр”ӯӮөӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA”T–ШҸ«ҢRӮН203ҚӮ’nӮЙҗUӮиҢьӮұӮӨӮЖӮаӮ№ӮёҒA“S•ЗӮМ—vҚЗӮЦҗ^ӮБҗі–КӮ©Ӯз’§ӮЭҒAҲ«җнӢꓬӮ·ӮйӮОӮ©ӮиӮҫӮБӮҪҒB ”T–ШҸ«ҢRӮӘӮЖӮБӮҪҚмҗнӮНҒAҲкӢCҷиҗӯӮЙ“GӮМ–{җwӮрӮВӮӯӮЖӮўӮӨ“ъ–{ҢГ—ҲӮМ–мҗнҢьӮ«ӮМҗн–@ӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBӮҫӮӘҒA10”N‘OӮМ“ъҗҙҗн‘Ҳ“–ҺһӮЖӮНҒA—·ҸҮӮМ—vҚЗӮНӮЬӮБӮҪӮӯ—l•ПӮнӮиӮөӮДӮўӮҪҒBғҚғVғAҢRӮН’nҢ`ӮрҚIӮЭӮЙҗ¶Ӯ©ӮөҒAӢҗ”пӮр“ҠӮ¶ӮД“SҚңӮЖғxғgғ“(ғRғ“ғNғҠҒ[ғg)ӮЕҢЕӮЯӮҪ–C‘дӮЖҸeҚАӮр–іҗ”ӮЙҚ\’zӮөӮДӮўӮҪҒBӮұӮМүiӢv—vҚЗӮрҺжӮиҲНӮЮ–hҢдҗw’nӮН25ғLғҚӮЙӮаӢyӮсӮҫҒBҳAӮЛӮзӮкӮҪ700–еӮМ–C‘дӮЖҺOҸ\“сҢВ‘е‘аҒA–с4–ң2җзҗlӮМҺз”х‘аӮӘ“ъ–{ҢRӮр‘ТӮҝӮ©ӮЬӮҰӮДӮўӮҪҒBүКҠёӮЙҚUҢӮӮ·Ӯй“ъ–{ҢRӮӘҺrӮМҺRӮр’zӮӯӮҫӮҜӮҫӮБӮҪӮМӮН“–‘RӮЕӮ ӮйҒB ҒЎ5–ңӮМӢ]җөҺТӮрҸoӮөӮҪ––ӮЙӮвӮБӮЖ203ҚӮ’nӮр’DҺж ”T–ШҸ«ҢRӮӘ203ҚӮ’nҚU—ӘӮЙҚмҗнӮрҗШӮи‘ЦӮҰӮҪӮМӮНҒA‘жҺOүс‘ҚҚUҢӮӮЕҗr‘еӮИ”нҠQӮрҺуӮҜӮҪҢгӮЕӮ ӮйҒB203ҚӮ’nӮЦӮМ–CҢӮӮНҒA11ҢҺ28“ъӮМ’©Ӯ©ӮзҠJҺnӮіӮкҒA–й”јӮЬӮЕӮЙ203ҚӮ’nӮМҗј“мҺR’ёӮрҗи—МӮөӮҪҒB“ъ–{ҢRӮМҚUҢӮ–Ъ•WӮӘ203ҚӮ’nӮЙ•ПӮнӮБӮҪӮұӮЖӮрҺ@’mӮөӮҪғҚғVғAҢRӮНҒA—vҚЗӮ©Ӯз‘қүҮ•”‘аӮрҸoӮөӮДӢtҸPӮЙӮЕӮДӮ«ӮҪҒB“ЛҢӮӮЖ‘ЮӢpӮӘҢJӮи•ФӮіӮкӮйҗнҸкӮЕӮНҒA“G–Ў•ыӮМҺҖ‘МӮӘҺlҸdӮЙӮаҢЬҸdӮЙӮаҸdӮИӮБӮДӮўӮҪҒBҗи—МӮөӮҪ’n“_ӮЙҗw’nӮрҚ\ӮҰӮйӮМӮЙҒA“ъ–{ҢRӮН“yҸлӮӘ•s‘«ӮөӮҪӮҪӮЯҺҖ‘МӮрҗПӮЭҸгӮ°ӮДҗнӮБӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒBӮ»ӮкӮЕӮаҗи—М’nӮрҺxӮҰӮ«ӮкӮёҒA29“ъӮМ–йӮЙӮН’DҠТӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨҒB ӮұӮӨӮөӮҪҸуӢөӮЙӮөӮСӮкӮрҗШӮзӮөӮҪӮМӮНҒA–һҸBҢR‘ҚҺQ–d’·ӮҫӮБӮҪҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЕӮ ӮйҒB”ЮӮН11ҢҺ30“ъӮЙ‘жҺOҢRҺi—Я•”ӮЙӢ}ҚsӮ·ӮйӮЖҒA‘еҺR‘ҚҺi—ЯҠҜӮМ‘г—қӮЖӮөӮДҒA”T–ШҸ«ҢRӮ©ӮзҲкҺһ“IӮЙ‘жҺOҢRӮМҺwҠцҢ ӮрҺжӮиҸгӮ°ҒAӮЭӮёӮ©Ӯз‘жҺOҢRӮрҺwҠцӮөӮД“сҒZҺOҚӮ’nӮрҸW’Ҷ“IӮЙҚUҢӮӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҗнӢөӮНҲкҗiҲк‘ЮӮрҢJӮи•ФӮөӮҪҒB 12ҢҺ5“ъҒA“ъ–{ҢRӮН203ҚӮ’nҗј“м•”ӮрҚДӮСҗи—МӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪӮӘҒA“ъ–{ҢRӮЙ‘ОӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮМ”ҪҢӮӮН‘sҗвӮрӢЙӮЯӮҪҒB’eҠЫӮӘҢҮ–RӮө’v–Ҫ“IӮИҸуӢөӮЙ’ЗӮўҚһӮЬӮкӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒAҗОүтӮвҚ»вIҒA–Ш•РӮЬӮЕ•җҠнӮЙ•ПӮҰӮДүһҗнӮөҒA•KҺҠӮЕғҚғVғAҢRӮрҢӮ‘ЮӮөӮҪҒB—тҗЁӮӘ•KҺҠӮЖӮИӮБӮҪғҚғVғAҢRӮН12ҢҺ6“ъ•ҘӢЕӮЬӮЕӮЙҒAҗб•цӮр‘ЕӮБӮД”s‘–ӮөҒA203ҚӮ’nӮНӮжӮӨӮвӮӯ“ъ–{ҢRӮМҺиӮЙ—ҺӮҝӮҪҒB 203ҚӮ’nӮрҠm•ЫӮөӮҪ“ъ–{ҢRӮНҒAӮҪӮҫӮҝӮЙ–CҢӮӮМҠП‘ӘҸҠӮрҗЭӮҜҒAӮ»ӮМҠП‘ӘҺwҠцӮЙӮөӮҪӮӘӮБӮДҚ`“аӮМғҚғVғAҗнҠНӮЙ‘ОӮөӮД28cm–CӮМ–CҢӮӮрҠJҺnӮөӮҪҒBҢЯҢг2ҺһҒAҺl•ыӮрҲіӮ·Ӯй–CҗәӮрҚҢӮ©Ӯ№ҒAҚЕҸүӮМ28cm–C’eӮӘҺR—ЕӮрүzӮҰӮДҳp“аӮМғҚғVғAҠН‘аӮЙҸPӮўӮ©Ӯ©ӮБӮҪҒB–CҢӮӮНҲИҢгӮа‘ұӮҜӮзӮк12ҢҺ8“ъӮЬӮЕӮЙғҚғVғAӮМ‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮрӮұӮЖӮІӮЖӮӯҢӮ’ҫӮөӮДӮўӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮДғҚғVғA‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮНҲк“xӮа“ъ–{ӮМҠН‘аӮЖ–CүОӮрҢрӮҰӮйӮұӮЖӮИӮӯҸБӮҰӢҺӮБӮҪҒB ҒЎ 11ҢҺ28“ъӮ©Ӯз12ҢҺ6“ъӮЬӮЕӮМ203ҚӮ’nҚU—ӘҗнӮЕҒA“ъ–{ҢRӮН–с6–ң4җзҗlӮр“Ҡ“ьӮөҒAҗнҺҖҺТ5ҒA052–јҒA•үҸқҺТ11ҒA884–јҒAҚҮҢv16ҒA936–јӮЖӮўӮӨҗMӮ¶ӮӘӮҪӮўӢ]җөҺТӮрӮҫӮөӮҪҒBҚЎ•аӮўӮДӮўӮйҺR’ёӮЦӮМ“№•tӢЯӮаҒA“G–Ў•ыӮМ–C’eӮӘаy—фӮөӮДҺRӮМҺО–КӮНҢҺ–КӮМӮжӮӨӮИ–іҺSӮИҺpӮЙ•ПӮнӮиүКӮДӮДӮўӮҪӮНӮёӮЕӮ ӮйҒBӮ№ӮБӮ©Ӯӯҗи—МӮөӮҪҗw’nӮрҺзӮлӮӨӮЖӮөӮДӮаҒA“ъ–{•әӮНӮ·ӮЕӮЙ’eҠЫӮрҢӮӮҝӮВӮӯӮөӮДӮўӮҪҒB”—Ӯи—ҲӮй“G•әӮЙ‘ОӮөӮДҒAҗОүтӮвҚ»вIҒA–Ш•РӮЬӮЕ•җҠнӮЙ•ПӮҰӮДүһҗнӮөӮДҢӮ‘ЮӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮӨӮөӮҪҢхҢiӮр“ӘӮМӢчӮЕ•`ӮӯӮҫӮҜӮЕҒAҺьҲНӮМҢiҠПӮНҺ_•@ӮрӢЙӮЯӮҪҗнҸкӮЙ•ПӮнӮиҒA”wӢШӮЙ—вӮҪӮўӮаӮМӮӘ‘–ӮБӮҪҒB ғ|Ғ[ғcғ}ғXӮЕ“ъҳIҚuҳaӮӘҗ¬ӮБӮД10”NҢгӮЙҒAғҚғVғAӮМҗўҠE“IҗәҠyүЖғVғғғҠғAғsғ“ӮӘ203ҚӮ’nӮр–KӮкӮҪӮЖӮ«ӮМҳbӮӘ“`ӮнӮБӮДӮўӮйҒBҗЬӮ©ӮзүJҸгӮӘӮиӮЕҒAҚӮ’nӮМҺО–КӮЙӮН•ыҒXӮЙ”’ӮўҠLҠkӮӘҺUӮзӮОӮБӮДӮўӮйӮМӮӘҢ©ӮҰӮҪҒBҺАӮНҠLҠkӮЕӮИӮӯӮДҗlҚңӮМӮ©ӮҜӮзӮҫӮБӮҪҒBғVғғғҠғAғsғ“ӮНҺR’ёӮЙ—§ӮБӮД’БҚ°ӮМүМӮрүМӮБӮҪҒBӮУӮЖ–ЪӮрҠJӮҜӮйӮЖҒAҺО–КӮ©ӮзҠф•SҠфҗзӮМҗВӮў•һӮрӮЬӮЖӮБӮҪғҚғVғA•әӮӘҒAӢaӮМӮІӮЖӮӯҺR’ёӮЦӮНӮўҸгӮӘӮБӮДӮӯӮйӮМӮӘҢ©ӮҰӮҪӮЖӮўӮӨҒB“ъ–{җlӮЙӮЖӮБӮДӮҫӮҜӮЕӮИӮӯҒAғҚғVғAҗlӮЙӮЖӮБӮДӮа203ҚӮ’nӮН‘ҪӮӯӮМ“Ҝ–EӮӘ–°Ӯйҗн’nӮИӮМӮҫҒB ‘еҠҫӮрӮ©Ӯ«ӮИӮӘӮзӮжӮӨӮвӮӯҺR’ёӮЙӮҪӮЗӮиӮВӮўӮҪҒBҚLҸкӮМ’ҶүӣӮЙӮНҸe’eӮМҢ`ӮрӮөӮҪҠп–ӯӮИ’үҚ°”иӮӘ—§ӮҝҒAҺў—мҺR(ӮЙӮкӮўӮіӮс)ӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒB203ҚӮ’nҚU—ӘҗнӮЕӢ]җөӮЖӮИӮБӮҪҸ«•әӮМ—мӮрҲФӮЯӮйӮҪӮЯӮЙҒA“ъҳIҗн‘ҲӮӘҸIӮнӮБӮҪ1905”NӮЙҢҡӮДҺnӮЯҒA1913”NӮЙҠ®җ¬ӮөӮҪ’үҚ°”иӮЕӮ ӮйҒBҸe’eӮМҢ`ӮМ“ғӮНҒA203ҚӮ’nӮЕҸEӮўҸWӮЯӮзӮкӮҪ’eҠЫӮЖ–C’eӮМ–тд°ӮрҸWӮЯӮД“ъ–{җ»ӮМғүғCғtғӢ’eӮМҢ`ӮЙ’’’јӮөӮҪӮаӮМӮҫҒBҺўиЛҺR(ӮЙӮкӮўӮіӮс)ӮНҒA203Ӯр’ҶҚ‘Ңк“ЗӮЭӮ·ӮйӮЖҺў—мҺRӮЖӮИӮйӮҪӮЯӮЙҒA”T–ШҠу“TҸ«ҢRӮӘ–ј•tӮҜӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮҝӮИӮЭӮЙҒA”T–ШҸ«ҢRӮНҒuҺўиЛҺRҒvӮЖ‘иӮ·ӮйҠҝҺҚӮаҺcӮөӮДӮўӮйҒB Ғ@ҺўиЛҺRӣУжҜ“пқі (Һў—мҺRҒkӮЙӮкӮўӮіӮсҒl ӣУҒkӮҜӮсҒlӮИӮкӮЗӮаҒ@жҜҒkӮ ҒlӮЙқіҒkӮжҒlӮА“пҒkӮӘӮҪҒlӮ©ӮзӮсӮв) Ғ@’jҺqҢч–јҠъҚҺд… (’jҺqҢч–јҒ@д…ҒkӮ©ӮсҒlӮЙ ҚҺҒkӮ©ҒlӮВӮрҠъӮ·) Ғ@иcҢҢ•ўҺRҺRҢ`үь ( “SҢҢҺRӮр•ўӮРӮДҒ@ҺRҢ`үьӮЬӮй) Ғ@дЭҗlкҺӢВҺўиЛҺR (–ңҗlҗДҒkӮРӮЖҒlӮөӮӯӢВӮ®Ғ@Һў—мҺR ) ”T–ШҸ«ҢRӮМҺҚӮЙӮ ӮйӮжӮӨӮЙҒA203ҚӮ’nҚU—ӘҗнӮНҺRҢ`Ӯр•ПӮҰӮДӮөӮЬӮӨӮЩӮЗ‘sҗвӮИҚU–hҗнӮҫӮБӮҪҒBҢ»ҚЭӮМ203ҚӮ’nӮМ•WҚӮӮН200ӮҚӮөӮ©ӮИӮўҒB“ъҳIҗн‘ҲӮЕ3ӮҚҺRӮӘ’бӮӯӮИӮБӮҪӮЖӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМҺR’ёӮр’DҺжӮөӮҪӮЖӮ«ӮМ“ъ–{ҢRӮМҠҪҠмӮНӮўӮ©ӮОӮ©ӮиӮҫӮБӮҪӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҠбүәӮЙҒA—·ҸҮҚ`ӮрҢ©үәӮлӮ№ҒAҳp“аӮЙ’в”‘ӮөӮДӮўӮйғҚғVғAӮМҠН‘DӮӘҺиӮЙҺжӮйӮжӮӨӮЙҢ©ӮҰӮйҒBӮЬӮіӮЙӮұӮМҸкҸҠӮН—·ҸҮҚ`ӮЙ–CҢӮӮрүБӮҰӮвӮ·Ӯў—v’nӮҫӮБӮҪҒB ҚLҸкӮМӢЯӮӯӮЙҒAғҚғVғAҺ®150ғ~ғҠғJғmғ“–CӮӘ2–е“WҺҰӮөӮДӮ ӮБӮҪҒBҗа–ҫҸ‘Ӯ«ӮЙӮжӮйӮЖҒA203ҚӮ’n‘Ҳ’DҗнӮЕҚӮ’nӮЙ’““ФӮ·ӮйғҚғVғAҢRӮН150ғ~ғҠғJғmғ“–C2‘дӮЖ76ғ~ғҠ‘¬ҺЛ–мҗн–C2‘дӮрҗЭӮҜҒAҺU•әҡНҚҲҒA•а•әҡНҚҲҒAүҶ‘МӮИӮЗӮрҢ@ӮБӮДҒA“ъ–{ҢRӮ©ӮзӮМҗiҢӮӮрӮЛӮОӮиӢӯӮӯ‘jҺ~ӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲӮЖғxғ“ғ`ғғҒ[ӮМҺ‘Ӣа’І’B | |
|
Ғu“ъҳIҗн‘ҲҒAҺ‘Ӣа’І’BӮМҗнӮў - ҚӮӢҙҗҘҗҙӮЖүў•Дғoғ“ғJҒ[ӮҪӮҝҒv(”В’J•q•F’ҳҒAҗV’Ә‘IҸ‘)ӮЖӮўӮӨ–{ӮЙӮВӮўӮДҺжӮиҸгӮ°ӮДӮЭӮҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB
“ъҳIҗн‘ҲҺһӮЙ“ъ–{ӮӘҚ‘ҚЫҺ‘–{ҺsҸкӮ©Ӯз‘е—КӮМҺ‘Ӣа’І’BӮрҚsӮҰӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҲИ‘OӮжӮиҒuҲк‘МӮЗӮӨӮвӮБӮҪӮсӮҫӮлӮӨҒHҒvӮЖӮўӮӨӢ^–вӮЖӢӯӮўӢ»–ЎӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮҫӮБӮДҒAүpҢкӮМ•ъ‘—ӮвғRғ“ғeғ“ғcӮаҚJ(ӮҝӮЬӮҪ)ӮЙӮ ӮУӮкӮДүҪ”NӮаүpҢкӢіҲзӮрҺуӮҜӮйҢ»‘гӮМ“ъ–{ӮЕӮіӮҰҒAҒuҠCҠOӮМ“ҠҺ‘үЖӮ©ӮзҺ‘ӢаӮр’І’BӮөӮДӮұӮўҒvӮЖҢҫӮнӮкӮҪӮзҒA•А‘е’пӮМӮұӮЖӮ¶ӮбӮИӮўӮЕӮ·ӮжӮЛҒHҒ@Ӯ»ӮкӮрҒA–ҫҺЎҲЫҗVӮ©Ӯз40”NӮаӮҪӮБӮДӮЁӮзӮёҒAӮЬӮҫҸdҚHӢЖӮаӮлӮӯӮЙ—§ӮҝҸгӮӘӮБӮДӮўӮИӮў–ҫҺЎҠъӮМ“ъ–{җlӮӘӮвӮйӮЖӮўӮӨӮМӮН‘е•ПӮИӮұӮЖӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒBӮ»ӮкӮаҒAҒu‘еҚ‘ғҚғVғAӮЖҗн‘ҲӮөӮЬӮ·ӮМӮЕҒvӮЖӮўӮӨҒAӮ©ӮИӮиҗ¬ҢчӮӘүцӮөӮў–Ъ“IӮМӮҪӮЯӮЙҒAӮЕӮ·ҒB ӮаӮҝӮлӮсҒAӮҝӮеӮБӮЖ—рҺjӮрӮІ‘¶Ӯ¶ӮМ•ыӮНҒAҒu“–ҺһӮН’йҗӯғҚғVғAӮЙӮжӮйғҶғ_ғ„җl”—ҠQ(ғ|ғOғҚғҖ)ӮӘғqғhӮ©ӮБӮҪӮМӮЕҒAғҶғ_ғ„Һ‘–{ӮН“ъ–{ӮЙҚDҲУ“IӮҫӮБӮҪӮсӮҫӮжҒvӮЖӮўӮБӮҪғEғ“ғ`ғNӮр”вҳIӮіӮкӮйӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒBҠmӮ©ӮЙӮ»ӮӨӮөӮҪҺ–ҺАӮаӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAӮЕӮНӮ»ӮМҗlӮӘ(ӮЬӮҪӮНӮ ӮИӮҪӮӘ)Ӯ»ӮМ“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЙғ^ғCғҖғXғҠғbғvӮөӮДҒAҒuӮҝӮеӮБӮЖҠOҚ‘ӮЙҚsӮБӮДҚ‘үЖ—\ҺZ•АӮЭӮМӢаҠzӮр’І’BӮөӮДӮ«ӮДӮӯӮкҒvӮЖҢҫӮнӮкӮҪӮзҸo—ҲӮЬӮ·Ӯ©ҒHӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҸӯӮИӮӯӮЖӮаҺ„ӮН(“ъҳIҗн‘ҲӮӘӮЗӮӨӮўӮӨҢӢүКӮЙӮИӮйӮ©Ӯр’mӮБӮДӮЁӮиҒA“–ҺһӮМҲк”К“IӮИ“ъ–{җlӮжӮи“–ҺһӮМҗўҠEҸоҗЁӮвӢа—ZӮМ’mҺҜӮаӮ ӮйӮЖӮНҺvӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮа)Ӯ ӮЬӮиҺ©җMӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB ӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕҒAӮұӮМ–{ӮНҒAҲкҢ©ғxғ“ғ`ғғҒ[ӮЙҠЦҢWӮИӮўӮжӮӨӮЕӮ·ӮӘҒAҺ‘Ӣа’І’BӮрҚlӮҰӮДӮўӮйӢNӢЖүЖӮвғxғ“ғ`ғғҒ[ӮМCFOӮМ•ыҒXӮӘ“ЗӮсӮЕӮа”сҸнӮЙҺQҚlӮЙӮИӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮБӮҪҺҹ‘жӮЕӮ ӮиӮЬӮ·ҒBҒuҚвӮМҸгӮМү_ҒvӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮрҗі–КӮ©Ӯз•`ӮўӮҪ–{ӮҫӮЖӮөӮҪӮзҒAӮұӮМ–{ӮН“ҜӮ¶“ъҳIҗн‘ҲҠъӮрғtғ@ғCғiғ“ғX“IӮИ‘Ө–КӮ©Ӯз•`ӮўӮҪ–{ӮҫӮЖҢҫӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB ғxғ“ғ`ғғҒ[ӮМҗlӮӘӮұӮМ–{Ӯр“ЗӮсӮЕғcғ{ӮЙӮНӮЬӮй‘жҲкӮМғ|ғCғ“ғgӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙҚЫӮөӮДӮМҺ‘Ӣа’І’BҠzӮМҢ…ӮӘҒAӮҪӮЬӮҪӮЬҢ»‘гӮМғxғ“ғ`ғғҒ[ӮМӮ»ӮкӮЖҺ—ӮДӮўӮйӮЖӮұӮлӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒB“ъ–{ӮМғxғ“ғ`ғғҒ[ӮӘҸгҸк‘OӮЙ’І’BӮ·ӮйӢаҠzӮНҒAӮҫӮўӮҪӮўҗ”үӯү~‘OҢгӮМҸкҚҮӮӘ‘ҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҚӮӢҙҗҘҗҙӮҪӮҝӮЙӢҒӮЯӮзӮкӮҪ’І’BӮМӢаҠzӮаҒuүӯү~ҒvӮМ’PҲКӮЕӮөӮҪҒB ӮаӮҝӮлӮсҒAӮ»ӮМ“–ҺһӮ©ӮзҢ»ҚЭӮЬӮЕӮМғCғ“ғtғҢӮӘӮ ӮйӮМӮЕҒA“–ҺһӮМ1үӯү~ӮЖҚЎӮМ1үӯү~ӮМүҝ’lӮӘ“ҜӮ¶ӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAҚЎӮЬӮіӮЙҗ”җз–ңү~Ӯ©Ӯзҗ”үӯү~ӮМ’І’BӮр–ЪҺwӮөӮД“®ӮўӮДӮўӮйғxғ“ғ`ғғҒ[Ӯа‘ҪӮўӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮөҒA“ҜӮ¶(–ј–Ъ)ӢK–НӮМҺ‘Ӣа’І’BӮЙғgғүғCӮ·ӮйҳbӮЙӮНҲшӮ«ҚһӮЬӮкӮйҗlӮӘ‘ҪӮўӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB ӮаӮӨҲк“_ӮНҒA“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЖӮўӮӨҚ‘ӮМҒuғxғ“ғ`ғғҒ[ӮБӮЫӮіҒvӮЙӮВӮўӮДҒB ӮұӮМҺ‘Ӣа’І’BӮМ’ҶҗSӮЖӮИӮБӮҪҚӮӢҙҗҘҗҙӮӘ“ъӢв‘ҚҚЩҒA‘е‘ ‘еҗbҒA‘Қ—қ‘еҗbӮИӮЗӮр—р”CӮөӮҪҗlӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮНӮжӮӯ’mӮзӮкӮДӮўӮйӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮМүШ—нӮИҢo—рӮ©ӮзҒA–Ӣ––ӮМӮ»ӮкӮИӮиӮМүЖҢnӮЙҗ¶ӮЬӮкӮҪғGғҠҒ[ғg“IӮИҗl•ЁӮҫӮЖҺvӮБӮДӮўӮйҗlӮа‘ҪӮўӮсӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBҺАҚЫӮМҚӮӢҙҗҘҗҙӮНҒA–Ӣ•{Ңд—pҠGҺtӮМҗм‘әҸҜүEүq–еӮМ”с’„ҸoҺqӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒB3ҚОӮЕҗе‘д”ЛӮМ‘«ҢyҒAҚӮӢҙүЖӮЙ—{ҺqӮЙҸoӮіӮкҒA12ҚОӮ©ӮзүЎ•lӮМҠOҺ‘ҢnӢвҚsӮЕғ{Ғ[ғCӮЖӮөӮД“ӯӮўӮДӮЁӮиҒAҒuғGғҠҒ[ғgҒvӮЖӮўӮӨӮжӮиӮНҒAҺ–ӢЖӮаҺиӮӘӮҜӮйҒuғxғ“ғ`ғғҒ[Ғv“IӮИҗlӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB“–ҺһӮН“ъ–{ӮЖӮўӮӨҚ‘‘S‘МӮаҚвӮМҸгӮМү_Ӯр–ЪҺwӮ·Ғuғxғ“ғ`ғғҒ[ҒvӮЭӮҪӮўӮИӮаӮсӮЕӮөӮҪӮөҒAӮ»ӮкӮрҺxӮҰӮйҗlҚЮӮағxғ“ғ`ғғҒ[“IӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒB ҺOӮВ–ЪӮЙҒAӮұӮМ–{ӮН“–ҺһӮМҗўҠEӮМҢoҚПӮвӢа—ZҺsҸк‘S”КӮрҳлбХ(ӮУӮ©Ӯс)Ӯ·ӮйҸгӮЕӮа–р—§ӮВӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB Ң»ҚЭӮМҗўҠEӮНҒAҸо•сӮрү^ӮФғCғ“ғ^Ғ[ғlғbғgӮвғӮғoғCғӢ’КҗMӮӘҗўҠEӮМӢчҒXӮЬӮЕ•ҒӢyӮөӮВӮВӮ ӮйғtғFҒ[ғYӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒA“–ҺһӮМҗўҠEӮНҒAғӮғmӮрү^ӮФ“S“№ӮӘӮЬӮіӮЙғCғ“ғtғүӮЖӮөӮД•ҒӢyӮөӮВӮВӮ ӮйҺһҠъӮЕӮ ӮиҒAӮ»ӮұӮЕғxғ“ғ`ғғҒ[“IӮИ“ҠҺ‘Ӯв”ғҺыҢҖӮӘҢJӮиҚLӮ°ӮзӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҒAҺ„ӮНҒAҢ»‘гӮМҗф—ыӮіӮкӮҪҺ‘–{ҺsҸкӮЖӮўӮӨӮМӮНҸҷҒXӮЙҢ`җ¬ӮіӮкӮДӮ«ӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAҢ»ҚЭӮМғAғҒғҠғJӮМҸШҢ”ҺжҲш–@ӮЙӮ ӮҪӮйҒu1933”NҸШҢ”–@ҒvӮвҒu1934”NҸШҢ”ҺжҲшҸҠ–@ҒvҲИ‘OӮМҒA1920”N‘гҲИ‘OӮМғAғҒғҠғJӮМҺ‘–{ҺsҸкӮИӮсӮДӮаӮМӮНҒAҢҙҺn“IӮИ–і–@Ҹу‘ФӮҫӮБӮҪӮМӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮБӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөӮұӮМ–{ӮЙҒA“ъ–{ӮӘүp•ДӮЕӮМҚ‘ҚВ”ӯҚsӮрҺ„•еӮ©ӮзҢц•еӮЙҗШӮи‘ЦӮҰӮйҚЫӮЙҒA•ЩҢмҺm“ҷӮЙҲЛ—ҠӮөӮДғhғLғ…ғҒғ“ғeҒ[ғVғҮғ“ӮӘ”сҸнӮЙ‘е—КӮЙ‘қӮҰӮҪҒAӮЖӮўӮБӮҪӢLҸqӮӘҸoӮДӮ«ӮДҒAҒuӮЁӮБҒvӮЖҺvӮБӮҪҺҹ‘жӮЕӮ·ҒB “БӮЙ“ъ–{ӮМӢа—Zҗ§“xӮНғAғҒғҠғJ“ҷӮМҗ§“xӮрғRғsҒ[ӮөӮД“ұ“ьӮөӮҪ•”•ӘӮӘ‘ҪӮўӮМӮЕҒAҢ»‘гӮМғKғ`ғKғ`ӮЙӢKҗ§ӮіӮкӮҪӢа—ZӮМҗўҠEӮөӮ©’mӮзӮИӮўӮЖҒAҒuӢа—ZӮНӢKҗ§ӮӘ–іӮўӮЖҗ¬—§ӮөӮИӮўӮөҒAӢKҗ§ӮЙҸ]ӮӨӮМӮӘӢа—ZӮИӮМӮҫҒvӮЖҺvӮўӮӘӮҝӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAҒuҺsҸкғҒғJғjғYғҖҒvӮЖӮўӮӨӮМӮНҒAҢВҗlӮв–@җlҠФӮМҢ_–сӮИӮЗӮЙӮжӮБӮДҒAӮЁҢЭӮўӮЙғҒғҠғbғgӮМӮ ӮйҺжҲшӮр”ӯҢ©Ӯ·ӮйҺ©—Ҙ“IӮИӮөӮӯӮЭӮЕӮ ӮиҒAӮЁӢаӮрҲөӮӨҒuҺ‘–{ҺsҸкҒvӮНӮ»ӮМҺsҸкғҒғJғjғYғҖӮМ’ҶӮЕӮаҚЕ‘еӢK–НӮМӮаӮМӮЕӮ·ҒBҒuҸо•сӮЙғEғ\ӮӘӮ ӮБӮҪӮиҢ_–сҲб”ҪӮӘӮ ӮБӮҪӮиӮөӮҪӮзҒAӮ»ӮкӮЙғyғiғӢғeғBӮр—^ӮҰӮйҒvӮЖӮўӮБӮҪғҒғJғjғYғҖӮӘ‘¶ҚЭӮөӮИӮўӮЖҒAғRғҸӮӯӮД“ҠҺ‘ӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйӮнӮҜӮаӮИӮўӮМӮЕҒAҢц“IӮИӢKҗ§ӮӘҗф—ыӮіӮкӮДӮўӮИӮўҺһ‘гӮЙӮаҒAҺАӮНӮ©ӮИӮиӮМӮЖӮұӮлӮЬӮЕҺ©—Ҙ“IӮЙ“®ӮўӮДӮўӮҪӮМӮ©Ӯа’mӮкӮЬӮ№ӮсҒB(Ӣа—ZӮЙҠЦӮ·ӮйӢKҗ§ӮМ’ҶӮЙӮНҒAҢoҚП—қҳ_“IӮЙ•KӮёӮөӮа•K—vӮҫӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўӮӘҒAҚ‘–ҜӮМҒuҲАҗSҒvӮМӮҪӮЯӮЙ(ӮВӮЬӮиҒuҗӯҺЎ“IӮЙҒv)“ұ“ьӮ№ӮҙӮйӮр“ҫӮИӮ©ӮБӮҪӮаӮМӮа‘ҪӮўӮМӮЕӮөӮеӮӨҒB) “ъ–{ӮМҚ‘ҚВӮрҲшӮ«ҺуӮҜӮй’ҶҗS“I–рҠ„ӮрүКӮҪӮөӮҪғNҒ[ғ“ҒEғҚҒ[ғuҸӨүпӮНӮ»ӮМҢгғҠҒ[ғ}ғ“ӮЙӢzҺыӮіӮкӮДҚЎӮЕӮНҺpӮрҸБӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAғӮғӢғKғ“ҒAғxғAғҠғ“ғOҒAҚҒҚ`ҸгҠCӢвҚsҒAғEғHҒ[ғoҒ[ғOӮЖӮўӮБӮҪҢ»‘гӢа—ZӮМҺе—vғvғҢғCғ„Ғ[’BӮӘҒAӮ·ӮЕӮЙӮұӮМ–ҫҺЎҠъӮ©Ӯ瑶ҚЭӮөӮҪӮМӮҫӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮаӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒB ӮаӮҝӮлӮсҒAҗн‘ҲӮН‘ҠҺиӮЖӮМҚҮҲУӮЙҠоӮГӮ©ӮИӮў–\—НҚsҲЧӮЕӮ ӮиҒAғxғ“ғ`ғғҒ[ӮНҢЪӢqӮЖӮМҚҮҲУ(Ң_–с)ӮИӮЗӮЙҠоӮГӮӯ”с–\—Н“IӮИҚsҲЧӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨ“_ӮЕ‘SӮӯҲЩӮИӮйӮаӮМӮЕӮ·ӮөҒA“ъҳIҗн‘ҲӮр—зҺ^ӮөӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮаӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮМӮЕ”OӮМӮҪӮЯҒBӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМ–ҫҺЎҠъӮМ“ъ–{ӮӘҒAғAғWғAҗlӮӘҗјүўҚ‘үЖӮЙҗнӮўӮр’§ӮЮӮЖӮўӮӨ’NӮаӮвӮБӮҪӮұӮЖӮӘӮИӮўӮұӮЖӮрҒAҚ‘ҚЫ“IӮЙҺ‘ӢаӮрҺи“–ӮДӮөӮДҗ¬ӮөҗӢӮ°ӮҪӮЖӮўӮӨ•ЁҢкӮНҒAӢNӢЖӮрҺuӮ·җl’BӮМҺhҢғӮЙӮа‘еӮўӮЙӮИӮйӮсӮ¶ӮбӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲҺОӮЯҳ_Ғ@ | |
|
“ҝҗм–Ӣ•{Ӯр“|ӮөҗVӮөӮўҗӯ•{Ӯр‘ЕӮҝ—§ӮДӮҪҲЫҗVӮМҺuҺm’BӮНҒA•xҚ‘Ӣӯ•әҒEҗBҺYӢ»ӢЖӮрҚҮӮўҢҫ—tӮЙӢЯ‘гҚ‘үЖӮр–ЪҺwӮөӮДҗVӮөӮўҚ‘ҚмӮиӮрҺnӮЯӮЬӮөӮҪҒB
–ҫҺЎҗӯ•{ӮМҚ‘үЖ–Ъ•WӮНүў•Д—сӢӯӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮзӮИӮўӮұӮЖӮЕӮөӮҪҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ӮрҺжӮиҠӘӮӯ’nҲжӮНӮ·ӮЕӮЙӮЩӮЖӮсӮЗүў•ДӮМҗA–Ҝ’nӮЙӮіӮкӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӮұӮЖӮрҸнӮЙ“ҘӮЬӮҰӮД“ъ–{ӮМҚs“®ӮрҢ©ӮИӮҜӮкӮО“ъ–{ӮМҚs“®Ӯр—қүрӮЕӮ«ӮИӮӯӮИӮБӮДӮөӮЬӮўӮЬӮ·ҒB ҚЎӮМҺһ‘гӮЙҗ¶Ӯ«ӮйҗlӮМҠҙҠoӮЕ“–ҺһӮМ—рҺjӮр’ӯӮЯӮйӢрӮрҗNӮөӮДӮНӮИӮзӮИӮўӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӮВӮЬӮи“–ҺһӮМҚ‘ҚЫҸоҗЁӮЖ“ъ–{ӮМ’uӮ©ӮкӮДӮўӮйҸуӢөӮр‘O’сӮЙӮөӮДҢҹҸШӮөӮИӮҜӮкӮОүҪӮаҢ©ӮҰӮДӮ«ӮЬӮ№ӮсҒB Қ‘ҚЫҺРүпӮЙҺQ“ьӮөӮҪ–ҫҺЎҗӯ•{ӮНҒA“ҢғAғWғAҗўҠEӮМ’ҶӮЕӮЗӮМӮжӮӨӮЙ•аӮЭҒAӮ»ӮөӮДғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮрҺnӮЯӮйӮЙҺҠӮБӮҪӮМӮ©ҒAӮ»ӮөӮД“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮӘҗl—ЮӮМ—рҺjӮЙҲМ‘еӮИӮйүeӢҝӮр—^ӮҰ,җl—ЮӮМ—рҺjӮрүжҠъ“IӮЙ‘е“]Ҡ·ӮіӮ№ӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮНҒu‘Sҗl—ЮӮМ—рҺjӮрғRғyғӢғjғNғX“IӮЙ‘е“]Ҡ·ӮіӮ№ӮҪҒvӮИӮЗӮМӢLҸqӮрҢ©ӮкӮОҒAӮИӮсӮЖҒu‘еӮ°ӮіӮИҒvӮЖҺvӮӨӮМӮНҚЎӮМҺһ‘гӮМҠҙҠoӮЕҢ©ӮйӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB“–ҺһӮН”’җlӮҫӮҜӮӘҗlҠФӮЕӮ ӮБӮДҒAҚ•җlӮвү©җFҗlҺнӮНҗlҠФӮЙӮ ӮзӮёӮЖҚlӮҰӮҪӮМӮӘҗўҠEӮМҸнҺҜӮЕӮөӮҪҒB җҙҚ‘ӮМҒu‘еҢц•сҒvӮЙӮНү©җFҗlҺнӮЖ”’җFҗlҺнӮЖӮМҠФӮМ—D—тӮН“VӮМ’иӮЯӮҫӮЖӮўӮӨӮУӮӨӮЙҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBғAғWғAӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮМҚ‘ӮН”’җlӮМ’m”\”\—НӮНғAғWғAҗlӮжӮиӮНӮйӮ©ӮЙҸгӮЕӮ ӮйҒA”’җlӮЙӮНүiӢvӮЙҸҹӮДӮИӮўӮЖҗMӮ¶ӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ӯ»ӮкӮр“ъ–{җlӮН“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮМҸҹ—ҳӮЕӮРӮБӮӯӮи•ФӮөӮҪҒAҗl—ЮӮМ—рҺjӮНӮұӮұӮ©Ӯз•ПӮнӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB “ъҳIҗн‘Ҳ’ј‘OӮМғҚғVғA‘ӨӮМ“ъ–{ӮЦӮМ”FҺҜӮрҸ‘ӮўӮДӮЭӮЬӮ·ҒB Ғu“ъ–{ҢRӮӘғҲҒ[ғҚғbғpӮМҚЕҺгҸ¬Қ‘ӮЙ‘ҫ“Ғ‘ЕӮҝҸo—ҲӮйӮЬӮЕӮЙӮНҒAҗ”Ҹ\”NҒAӮЁӮ»ӮзӮӯ100”NӮНӮ©Ӯ©ӮйӮЕӮ ӮлӮӨҒv—ӨҢR•җҠҜғQҒEғoғmғtғXғLҒ[’ҶҚІ ҒuғҚғVғAҢRӮН“ъ–{ҢRӮМ3”{ҲИҸгӮЕӮ ӮйҒB—ҲӮйӮЧӮ«җн‘ҲӮН’PӮЙҢRҺ–“IҺU•аӮЙүЯӮ¬ӮИӮўҒvғNғҚғpғgғLғ“‘еҸ« ҒuҸ¬үҺӮӘӮ ӮҰӮД’ҪӮЙҗн‘ҲӮрҺdҠ|ӮҜӮйӮИӮјӮЖҒAҲкҸuӮҪӮиӮЖӮа‘z‘ңҸo—ҲӮИӮўҒB–XҺqӮМҲкҗUӮиӮЕӮ©ӮҪӮГӮҜӮДӮөӮЬӮӨӮіҒvғcғAҒ[ҒEғjғRғүғCҚc’й ҒuүдҒXӮЙ‘ОӮ·Ӯй“ъ–{ӮМҗн‘ҲӮН“ъ–{ӮЙӮЖӮБӮДҺ©ҺEҚsҲЧӮЕӮ ӮлӮӨҒB”ЮӮзӮМҠу–]ӮМ‘SӮДӮМ”jүуӮЖӮИӮлӮӨҒvғmғ{ғGҒEғ{ғҢғ~ғ„ҺҶ Ғu“ъ–{ҠCҢRӮНҠOҚ‘Ӯ©ӮзҠН’шӮрҚw“ьӮөҒA•ЁҺҝ“I‘•”хӮҫӮҜӮНҗ®ӮҰӮҪҒBӮөӮ©ӮөҠCҢRҢRҗlӮЖӮөӮДӮМҗёҗ_ӮН“һ’кӮнӮкӮнӮкӮЙӮНӢyӮОӮИӮўҒBӮіӮзӮЙҢRҠНӮМ‘ҖҸcӮвү^—pӮЙҺҠӮБӮДӮНӢЙӮЯӮД—c’tӮЕӮ ӮйҒvҸ„—mҠНғAғXғRғҠғbғhҠН’· ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAғҚғVғAӮНҒuҗlҺн“I—DүzҠҙҒvӮ©Ӯз“ъ–{җlӮрӮұӮЖӮІӮЖӮӯ•МҺӢӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮжӮӯӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBүҪӮағҚғVғAҗlӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ‘јӮМ”’җlӮа—LҗFҗlҺнӮа“ҜӮ¶ӮжӮӨӮЙҚlӮҰӮДӮўӮЬӮөӮҪҒB“ҜҺһӮЙ“ъ–{‘ӨӮМ‘ҪӮӯӮМҸ«ҚZӮа“һ’кҗн‘ҲӮНҸҹӮҝ–ЪӮӘӮИӮўӮЖҚlӮҰӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©Ӯө“–ҺһӮМғAғWғAӮМҠВӢ«ӮЕӮНҗн‘Ҳүс”рӮМ“№ӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒB “ъҳIҗн‘ҲӮНӢqҠП“IӮЙҢ©ӮДӮа‘еҗlӮЖҺqӢҹӮМҗн‘ҲӮЕғҚғVғAӮМ‘S•ә—Н–с300–ңҗlӮЙ‘ОӮөӮД“ъ–{ӮМ•ә—НӮН–с20–ңҗlҒAҢRҠН–с60–ңғgғ“ӮЙ‘ОӮөӮД“ъ–{ӮН26–ңғgғ“ӮЕӮөӮҪҒB Ӯ»ӮкӮЕӮНүҪҢМҒAғiғ|ғҢғIғ“ӮЕӮіӮҰ”s‘ЮӮіӮ№ӮҪҗўҠEӢьҺwӮМ‘еҚ‘ғҚғVғAӮЙ‘ОӮөӮДӢЙ“ҢӮМҸ¬Қ‘“ъ–{ӮӘҸҹ—ҳҸo—ҲӮҪӮМӮ©ҒAӮ»ӮкӮН’PӮИӮйҚKү^ӮҫӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҺ„ӮМҢ©үрӮН“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮН•K‘RӮМҸҹ—ҳӮҫӮБӮҪӮЖҢ©ӮДӮўӮЬӮ·ҒB “–ҺһҗўҠEҲкӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖҗнӮБӮҪ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕӮНҺjҸгӢHӮЙҢ©ӮйҲк•ы“I‘еҸҹ—ҳӮЕӮөӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҗн—НӮМ‘е”јӮр1үсӮМҠCҗнӮЕӮӨӮөӮИӮБӮҪӮӘҒA“ъ–{ӮМ‘№ҠQӮНҗ…—Ӣ’ш3җЗӮМӮЭӮЖӮўӮӨҗMӮ¶ӮзӮкӮИӮў‘еҸҹ—ҳӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮМ“ъ–{ҠCҠCҗнӮМҸҹ—ҳӮрҚмҗнӮМ–ӯӮЕӮ ӮйӮЖүрҗаӮөӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҺ„ӮМҢ©—§ӮДӮНӢZҸp—НӮМҚ·ӮЕӮ ӮйӮЖӮ ӮҰӮД’fҢҫӮөӮЬӮ·ҒB ҒuӢZҸp—НӮМҚ·ҒvӮИӮЗӮЖҢҫӮҰӮО‘ЬӮҪӮҪӮ«ӮЙӮ ӮўӮ»ӮӨӮЕӮ·ӮӘҒA“ъ–{ҠCӮМҚмҗнӮрүВ”\ӮЙӮөӮҪӮМӮНҒA“ъ–{ҠCҢRӮМҚӮ‘¬ү»ӮЙӮжӮиӮЬӮ·ҒBҒuӢ{ҢҙҺ®ҒvӮМҗ«”\ӮЖҢҫӮБӮДӮаӮ ӮЬӮи’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮ№ӮсӮӘҒA“–Һһ“ъ–{ҠН‘аӮМ‘DӮМғXғsҒ[ғhӮНҗўҠEҚЕҚӮӮЕӮөӮҪҒBӮұӮМҗўҠEҚЕҚӮӮМғGғ“ғWғ“Ӯр”ӯ–ҫӮөӮҪӮМӮӘҒAҠCҢRӮМӢ{Ңҙ“сҳYӮЕӮ·ҒB Ӣ{ҢҙҺ®ғGғ“ғWғ“ӮНүҝҠiӮаҲАӮӯҒAӢӢҗ…ӮӘҠyӮЕҒA‘|ҸңӮаҠyҒAғGғlғӢғMҒ[Ңш—ҰӮӘҚӮӮӯҒA”n—НӮӘӢӯӮўҒAҸ¬Ң^ӮИӮМӮЕҒAғXғyҒ[ғXӮрӮЖӮзӮИӮўҒB–ҫҺЎ30”NғCғMғҠғXӮЙ“БӢ–Ӯрҗ\җҝӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМӢZҸp—НӮЙ“Ҝ–ҝҚ‘ӮМғCғMғҠғXӮӘӢБ’QӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮкӮӘ“ъ–{ҠCҢRӮМҚӮ‘¬ү»ӮрӮаӮҪӮзӮөҒAғҚғVғAӮрӢБӮ©Ӯ№ӮҪ“ъ–{ҠCҠCҗнӮМҚмҗнӮрүВ”\ӮЙӮөӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ң»ҚЭҗўҠEӮМғnғCғeғNҗ»•iӮМ•”•iҒAҺ‘ҚЮҒAҚHҚмӢ@ҠBӮИӮЗӮМҒAӮўӮнӮдӮйҺ‘–{ҚаӮМ–с80Ғ“ӮӘ“ъ–{җ»ӮЕӮ ӮйӮжӮӨӮЙҒAҒuӢZҸp—§Қ‘Ғv“ъ–{ӮМ–GүиӮНӮ·ӮЕӮЙ100”N‘OӮ©Ӯ瑶ҚЭӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒB —бӮҰӮОғAғҒғҠғJӮМҺ©“®ҺФҺYӢЖӮМӢZҸpӮрҒA“ъ–{ӮМӢ@ҠBҚHӢЖӮЙҠ®‘SӮЙҲЛ‘¶ӮөӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮұӮкӮНҒuҚ‘ҚЫ•ӘӢЖҒvӮИӮЗӮЖҢДӮЧӮйғҢғxғӢӮЕӮИӮӯҒAӮаӮНӮвӮ»ӮМӢZҸpӮӘ“ъ–{ӮЙӮөӮ©ӮИӮўҸуӢөӮИӮМӮЕӮ·ҒB ғҚғVғAӮӘ“ъ–{Ӯр“Ң—mӮМ’xӮкӮҪ–Ҝ‘°ӮЖӮөӮДӮөӮ©Ң©ӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA“ъ–{җlӮМ•¶ү»ӮНӮ·ӮЕӮЙғҚғVғAӮрӮНӮйӮ©ӮЙ—ҪүнӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ·ҒBӮ»ӮМҸШӢ’ӮЙ“–ҺһӮМ“ъ–{Қ‘–ҜӮМҺҜҺҡ—ҰӮН75Ғ“ӮЖүў•ДҸ”Қ‘ӮжӮиҲі“|“IӮЙҚӮӮ©ӮБӮҪҒBӮҫӮ©Ӯз•ЎҺGӮИ•әҠнӮМҺжӮиҲөӮў•ы–@ӮӘҺҶӮМҗа–ҫҸ‘ӮЙӮжӮй“`’BӮӘүВ”\ӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒAҢP—ыӮМғXғsҒ[ғhӮрҸгӮ°ӮйҺ–ӮӘҸo—ҲӮҪӮМӮЕӮ·ҒB Ҳк•ығҚғVғA‘ӨӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЕ•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪғҚғVғAҗlӮМ’ҶӮЕҺ©•ӘӮМ–ј‘OӮ·ӮзҸ‘ӮӯҺ–ӮМҸo—ҲӮИӮўҺТӮӘүЯ”јҗ”ӮаӮўӮЬӮөӮҪҒB–ј‘OӮӘҸ‘ӮҜӮДӮа•¶ҸНӮӘ“ЗӮЯӮйҗlӮНҠІ•”ғNғүғXӮҫӮҜӮҫӮЖӮўӮӨҢ»ҸуӮЕӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒAӢM‘°ӮЦӮМӢіҲзҗ§“xӮөӮ©ӮИӮў“–ҺһӮМүў•ДӮМҺҜҺҡ—ҰӮМ’бӮіӮӘӮаӮҪӮзӮөӮҪ“–‘RӮМҢӢүКӮЕӮ·ҒB ӢtӮЙғҚғVғAӮМ•Я—ёӮЖӮИӮБӮҪ“ъ–{•әӮМҸ‘ӮўӮҪҳ_•¶ӮӘүў•ДӮМҗV•·ӮЙҸРүоӮіӮкӮйӮЖҲк•ә‘ІӮ·Ӯзҳ_•¶ӮӘҸ‘ӮҜӮй“ъ–{ӮМ•¶ү»“xӮЙүў•ДӮМҺҜҺТӮНӢБңұӮөҒAӮ»ӮМҢгӢM‘°’ҶҗSӮМӢіҲзҗ§“xӮ©ӮзҒAҸҺ–ҜӮрҠЬӮЯӮҪӢіҲзҗ§“xӮЦӮМҺРүпүьҠvӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪӮЩӮЗӮЕӮөӮҪҒB ӮұӮкӮрҢ©ӮДӮа“ъ–{ӮМ•¶ү»“xӮМҚӮӮіӮН“–ҺһҗўҠEҲкӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮҰӮЬӮ·ҒBӮВӮЬӮиҺ„ӮӘҢҫӮўӮҪӮўӮМӮНҒAғҚғVғAӮжӮиҲі“|“I•¶ү»“xӮМҚӮӮўӢZҸp—§Қ‘“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮН—рҺjӮМ•K‘RӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ·ҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎӢZҸpӮӘҗ§ӮөӮҪ“ъҳIҗн‘Ҳ | |
|
ҒЎ–іҗьӢ@
–ҫҺЎ38”N(1905)5ҢҺ27“ъҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘а”ӯҢ©ӮМ•сҚҗӮрҺуӮҜӮҪҗнҠНҺOҠ}ӮНҒA‘е–{үcӮЙҲ¶ӮДӮД“d•¶Ӯр”ӯҗMӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮкӮӘ—L–јӮИҒAҒu“GҠН‘аҢ©ғҶғgғmҢx•сғjҗЪғVҒA—ьҚҮҠН‘ағn’јғ`ғjҸo“®ҒAғRғҢғ’ҢӮ–ЕғZғ“ғgғXҒB–{“ъ“VӢCҗ°ҳNғiғҢғhғӮ”gҚӮғVҒv ӮұӮМ“d•¶ӮНҒA“–ҺһҒAҗўҠEҚЕҚӮӮМҗ«”\ӮрҢЦӮБӮҪ–іҗьӢ@ӮЙӮжӮБӮД‘Е“dӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮкӮӘ–ҫҺЎ36”NӮЙҠJ”ӯӮіӮкӮҪҺOҳZҺ®–іҗь“dҗMӢ@ӮЕӮ·ҒBӮұӮМ“dҗMӢ@ӮНҒA’ьҗMҸИӮМӢZҺtҒEҸј‘гҸј”VҸ•ӮӘҚмӮиҸгӮ°ӮДӮўӮҪҺАҢұӢ@ӮрҒAҠCҢRӢZҺtҒE–Ш‘әҸxӢgӮӘ‘е•қӮЙүь—ЗӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ·ҒB150kmҲИҸгӮМ’КҗMӮӘүВ”\ӮҫӮБӮҪӮұӮЖӮЕҒA’КҗMӢZҸpӮЙ—тӮБӮҪғҚғVғAҢRӮжӮи—DҲКӮЙ—§ӮВӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЕӮөӮҪҒB ӮЬӮҪҒA–іҗьӢ@ӮМ“dҢ№ӮНҒA“Ү’Гҗ»ҚмҸҠӮӘҚ‘ҺY‘ж1ҚҶӮЖӮөӮДҠJ”ӯӮөӮҪ’~“d’rӮЕӮөӮҪҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮМҸҹ—ҳӮНҒAҒu“G‘Oүс“ӘҒvӮвҒuTҺҡҗн–@ҒvӮИӮЗҒAғtғHҒ[ғҒҒ[ғVғҮғ“ӮМҸҹ—ҳӮЖӮіӮкӮЬӮ·ӮӘҒAҺАӮН“ъ–{ӮМҚӮӮўӢZҸp—НӮӘҸҹ—ҳӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪ‘Ө–КӮӘӢӯӮўӮМӮЕӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎүО–т
“ъҳIҗн‘ҲӮЕ“ъ–{ӮӘҸҹ—ҳӮөӮҪ—қ—RӮНӮўӮӯӮВӮ©Ӯ ӮиӮЬӮ·ӮӘҒA“БӮЙ‘еӮ«ӮИ—қ—RӮМ1ӮВӮЙҒA“ъ–{ҠCҢRӮӘҗўҠEҚЕҚӮӮМүО–тӮрҺқӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘӮ Ӯ°ӮзӮкӮЬӮ·ҒB ӮаӮҝӮлӮсүО–тҺ©‘МӮНҗМӮ©ӮзӮ ӮиӮЬӮөӮҪӮӘҒA“ъ–{ҢRӮМүО–тӮНҲі“|“IӮИ”jүу—НӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮёӮН”jүуӮіӮкӮҪғҚғVғAҠНғAғҠғҲҒ[ғӢӮМҺКҗ^ӮрҢ©ӮДӮӯӮҫӮіӮўӮИҒBҚb”ВӮӘӮЩӮЖӮсӮЗ•цӮкҒAҸДӮ«җsӮӯӮіӮкӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘӮнӮ©ӮиӮЬӮ·ҒBӮЗӮкӮЩӮЗ”jүу—НӮӘӢӯӮўӮ©Ҳк–Ъ—Д‘RӮЕӮ·ҒB ӮұӮМүО–тӮМ”ӯ–ҫҺТӮНҒA“ъ–{ҠCҢRӢZҺmӮМүәҗЈүлҲт(ӮөӮаӮ№ӮЬӮіӮҝӮ©)ӮЕӮ·ҒBүәҗЈӮНҲАҗӯ6”NҒAҚL“ҮӮМ“S–C’¬ӮЕҗ¶ӮЬӮкӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМҸкҸҠӮН–ј‘OӮМ’КӮиҒA“S–CӮрҚмӮБӮДӮўӮҪҸкҸҠӮЕӮ·ҒB үәҗЈӮН—cӮўҚ ӮНӢ•Һг‘МҺҝӮЕӮЬӮЖӮаӮЙ•ЧӢӯӮаӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮўӮЬӮ·ӮӘҒAӮ»ӮкӮИӮМӮЙҚH•”‘еҠw(Ң»ҒA“Ң‘еҚHҠw•”)ӮЙ3”ФӮЕҚҮҠiӮ·ӮйҸrүpӮЕӮөӮҪҒB ‘ІӢЖҢгҒAҲуҚьӢЗӮЙӢО–ұӮөҒAӮұӮұӮЕҺҶ•ј—pӮМғCғ“ғNӮрҠJ”ӯӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮМғCғ“ғNӮЙӮжӮиҒAҗёҚIӮИҲуҚьӮӘүВ”\ӮЖӮИӮиҒAӢUҺD–hҺ~ӮЙ‘еӮўӮЙ–р—§ӮҝӮЬӮөӮҪҒB Ӯ»ӮМҢгҒAүәҗЈӮНҠCҢRҸИӮМӢZҠҜӮЖӮИӮиҒAӮұӮұӮЕғpғҸғtғӢӮИүО–тӮр”ӯ–ҫӮ·ӮйӮМӮЕӮ·ҒB “–ҺһӮМүО–тӮНҠЈ‘ҮӮөӮДӮўӮйӮЖӮ·Ӯ®”ҡ”ӯӮөӮДӮөӮЬӮӨӮҪӮЯҒA15〜20Ғ“’ц“xӮМҗ…•ӘӮрҠЬӮЬӮ№ӮДӮўӮЬӮөӮҪҒBӮЕӮ·ӮӘӮұӮМ’Іҗ®ӮӘ”сҸнӮЙ“пӮөӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ·ҒB“–ӮҪӮи‘OӮЕӮ·ӮӘҒAҗ…•ӘӮӘ‘ҪӮ·Ӯ¬ӮйӮЖ”ҡ”ӯ—НӮН—ҺӮҝӮйӮөҒAӮ©ӮЖӮўӮБӮДҸӯӮИӮ·Ӯ¬ӮйӮЖҠлҢҜӮҫӮ©ӮзӮЕӮ·ҒB –ҫҺЎ26”N(1893)ҒAүәҗЈӮНҗх—ҝӮЙҺgӮнӮкӮҪғsғNғҠғ“Һ_ӮЙғҸғbғNғXӮрҚ¬ӮәӮйӮұӮЖӮЕҒAӮ«ӮнӮЯӮДҲА‘Sҗ«ӮМҚӮӮўүО–тӮрӮВӮӯӮиҸoӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМүО–тӮН—вӮвӮ·ӮЖҢЕӮЬӮиҒAү·ӮЬӮйӮЖүt‘МӮЖӮИӮйӮМӮЕҒA•Ы‘¶Ӯа—eҲХӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ӮаӮҝӮлӮсүО–тӮҫӮҜӮЕӮН‘еӮ«ӮИ”ҡ”ӯ—НӮН“ҫӮзӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮЕӮ·ӮӘҒAҲЙҸWү@ҢЬҳYҒEҠCҢR‘еҸ«ӮӘҚӮ•iҺҝӮМҲЙҸWү@җMҠЗӮрҠJ”ӯҒBӮұӮӨӮөӮД“ъ–{ҢRӮН–ҫҺЎ27〜28”NӮМ“ъҳIҗн‘ҲӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҢӮ”jҒA‘еҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮйӮМӮЕӮ·ҒB үәҗЈүО–тӮМҗ»‘ў–@ӮНӢЙ”йӮЖӮіӮкҒAҗўҠE’ҶӮ©ӮзӮЁӮ»ӮкӮзӮкӮЬӮөӮҪҒBҠCҢRӮЕӮН‘ж2ҺҹҗўҠE‘еҗнӮЕӮаҺgӮБӮДӮўӮҪӮЩӮЗӮЕӮ·ҒB ӮҝӮИӮЭӮЙӮұӮМҢчҗСӮЕүәҗЈӮНҠCҢRҸИӮ©Ӯз1200ү~ӮМҸЬӢаӮр“ҫӮЬӮөӮҪҒB–JҸуӮЙӮНҒuүд•әҠнӮЙҲк‘wӮМүs—ҳӮрүБӮЦ’йҚ‘ҠCҢRӮЙейүv(=Ҹ•ӮҜ)Ӯр—^ӮУӮйҸӯӮ©ӮзӮҙӮйӮМӮЭӮИӮзӮё‘ҙӢОҳJ“ҷӮЙ‘еӮИӮиӮЖӮ·ҒvӮЖӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘DӮМғXғsҒ[ғh
үО–тӮаҸd—vӮЕӮөӮҪӮӘҒA“ъ–{ҠН‘аӮН‘DӮМғXғsҒ[ғhӮаҗўҠEҚЕҚӮғҢғxғӢӮЕӮөӮҪҒB“–ҺһҒAҢRҠНӮНҗО’YӮЖҗ…ӮЙӮжӮйҗ…ҠЗҺ®ӢDгЈӮрҗПӮсӮЕӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒA“–ҺһҚЕҚӮ•фӮМӢDгЈӮр”ӯ–ҫӮөӮҪӮМӮӘҒAҠCҢRӮМӢ{Ңҙ“сҳYӮЕӮ·ҒB ҲАҗӯ5”Nҗ¶ӮЬӮкӮМӢ{ҢҙӮНҒAҠCҢR•әҠw—ҫӢ@ҠЦүИӮр—DҸGӮИҗ¬җСӮЕ‘ІӢЖӮөӮҪӮҪӮЯҒAҠCҢRҸИӮ©ӮзғCғMғҠғXӮЦ”hҢӯӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӢ{ҢҙӮНӮМӮЧ16”NӮағCғMғҠғXӮЙӮўӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮМҠФҒAғOғүғXғSҒ[ӮМ‘ў‘DүпҺРӮвғOғҠғjғbғ`ҠCҢR‘еҠwӮИӮЗӮЕҢӨӢҶӮрҸdӮЛҒA–ҫҺЎ29”NҒAӮВӮўӮЙ“ЖҺ©ӮМӢ@ҠЦӮр”ӯ–ҫӮөӮЬӮ·ҒB –ҫҺЎ30”NғCғMғҠғXӮЖ“ъ–{ӮЕ“БӢ–ӮрҺж“ҫҒA–ҫҺЎ33”NӮЙҢRҠНҒuҢө“ҮҒvҒuҸј“ҮҒvӮЙ“ӢҚЪӮіӮкҒAҺАҢұҚqҠCӮӘҚsӮнӮкӮЬӮөӮҪҒBҢӢүКӮНҗО’YӮаҗ…ӮаӮНӮйӮ©ӮЙҸӯӮИӮӯӮДҚПӮЭҒA”сҸнӮЙӮўӮўҗ¬җСӮрҺыӮЯӮЬӮөӮҪҒB Ӣ{ҢҙҺ®ӮМҗ«”\ӮН”ІҢQӮЕҒA ҒEҠOҚ‘җ»ӢDгЈӮӘ90–ңү~ӮИӮМӮЙҒAӢ{ҢҙҺ®ӮН40–ңү~ӮЖүҝҠiӮӘҲАӮӯҒAӮөӮ©ӮаӮЗӮМҚHҸкӮЕӮаҚмӮкӮйӮЩӮЗҗ»ҚмӮӘ—eҲХ ҒEӢӢҗ…ӮӘғүғNӮЕҒA‘|ҸңӮағүғNҒB—җ–\ӮЙҲөӮБӮДӮаҲА‘S ҒEғGғlғӢғMҒ[Ңш—ҰӮӘҚӮӮӯҒA”n—НӮӘӢӯӮў ҒEҸ¬Ң^ӮИӮМӮЕҒAғXғyҒ[ғXӮрӮЖӮзӮИӮў ӮЖғCғMғҠғXҗlӮағrғbғNғҠӮМҚӮҗ«”\ҒBӮұӮкӮӘ“ъ–{ҠCҢRӮМҚӮ‘¬ү»ӮрӮаӮҪӮзӮөӮҪӮМӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎӢ{Ңҙ“сҳY
1858”N(ҲАҗӯ5”N)-1918”N “ъ–{ҠCҢRӮМҢRҗlҒBҚЕҸIҠKӢүӮНҠCҢRӢ@ҠЦ’ҶҸ«ҒB’jҺЭҒBҚHҠw”ҺҺmҒAӢ{ҢҙҺ®җ…ҠЗҠКӮМ”ӯ–ҫҺТҒBӢ{Ңҙҗ¬ҸfӮМ’·’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкҒA–ӢҗbӢ{Ңҙ–ШҗОӮМ—{ҺqӮЖӮИӮйҒBҗГүӘҠw–вҸҠӮрҢoӮДҒA1872”NҒAҠCҢR•әҠw—ҫ—\үИӮЙ“ьҠwҒBӮ»ӮМҢгҒAғCғMғҠғXӮЙ—ҜҠwӮөҒAғOғҠғjғbғ`ҠCҢR‘еҠwҚZ3”NүЫ’цӮЕҠwӮсӮҫҒB1883”N3ҢҺҒA’ҶӢ@ҠЦҺm”CҠҜҒBҺе‘DӢЗӢ@ҠЦүЫҒAғCғMғҠғX’“ҚЭҒAҠНҗӯӢЗӢ@ҠЦүЫ’·ҒAҢ““ҢӢһ’йҚ‘‘еҠwҚHүИ‘еҠwӢіҺцҒAүЎҗ{үк’БҺз•{‘ў‘D•”ҢvүжүИ’·ҒA‘ў‘D‘ў•әҠД“ВҠҜ(ғCғMғҠғXҸo’Ј)ӮИӮЗӮр—р”CӮөҒA1896”N4ҢҺҒA‘ў‘D‘еҠДӮЙҗiӢүҒB ҠCҢRҸИҢR–ұӢЗ‘ў‘DүЫүЫ—»ӮИӮЗӮрҢoӮДҒA1900”N5ҢҺҒAӢ@ҠЦ‘ҚҠДӮЙҗiӢүҒBҠНҗӯ–{•”‘ж4•”’·ӮрӢОӮЯҒA1906”N11ҢҺҒAҠCҢRӢ@ҠЦ’ҶҸ«ӮЖӮИӮиҒA1909”N8ҢҺҒA—\”х–рӮЙ•Т“ьӮіӮкӮҪҒBӮМӮҝҒAӢM‘°ү@ӢcҲхӮЖӮИӮйҒB1899”N3ҢҺҒAҚHҠw”ҺҺmҚҶӮрҺж“ҫҒB1907”N9ҢҺҒA’jҺЭӮМҺЭҲКӮрҺцҺЭӮөүШ‘°ӮЖӮИӮйҒB ҒЎ ‘жҢЬүс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпҺ––ұӢЗ•Т Ғw‘жҢЬүс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпҗRҚё•сҚҗҒx(1904) Ӣ{Ңҙ“сҳYҸo•iӮМҗ…ҠЗҺ®ӢDгЈ ӢDгЈӮЖӮНҸцӢCӮр”ӯҗ¶ӮіӮ№Ӯйғ{ғCғүҒ[ӮЕҒAӢ{Ңҙ“сҳYӮНҠCҢRӢZҸpҺТҒBҸd—vӮИҗ…ӮМҸzҠВ–@ӮЙ•s‘«ӮӘӮ ӮБӮҪҸ]—ҲӮМҗ…ҠЗҺ®ӢDгЈӮрүь—ЗӮөӮҪҒBҲУҸ ҺaҗVӮЕҸцӢC”ӯҗ¶ӮМ—ҰӮаҚӮӮӯҒAүў•ДӮМ—D“ҷҚHҸкӮЕҗ»ҚмӮөӮҪӮаӮМӮЙӮа—тӮзӮИӮўӮЖӮМ•]үҝӮрҺуӮҜӮҪҒB ҒЎ Ӣ{ҢҙҺ®җ…ҠЗӢDгЈӮМ”ӯ–ҫ(Ӣ{Ңҙ“сҳY) “WҺҰҺ‘—ҝӮНҒA–ҫҺЎ37”NҒAҒuӢ{ҢҙҺ®җ…ҠЗӢDгЈҒv(“БӢ–‘ж3014ҚҶ)ӮМ”ӯ–ҫӮМҢчҗСӮЙӮжӮиҒAӢ{Ңҙ“сҳY(1858Ғ\1918)ӮЙҢM“с“ҷҲ®“ъҸdҢхҸНӮӘүәҺ’ӮіӮкӮҪҚЫӮМ•¶Ҹ‘ӮЕӮ·ҒBҠCҢRӢZҸpҸ«ҚZӮҫӮБӮҪӢ{Ңҙ“сҳYӮНҒA’КҺZ16”NӮЙӮаӮЁӮжӮФүpҚ‘ӮЦӮМ—ҜҠwӮЕ“ҫӮҪӢZҸpӮЖҢoҢұӮрҠҲӮ©ӮөҒA–ҫҺЎ29”NҒuӢ{ҢҙҺ®җ…ҠЗӢDгЈҒvӮр”ӯ–ҫӮөӮЬӮөӮҪҒBӢDгЈӮЖӮНғ{ғCғүҒ[ӮМӮұӮЖӮЕӮ·ҒBӢ{ҢҙӮМӢDгЈӮНҒA–Ш’YӮр”R—ҝӮЖӮөӮҪҸцӢC‘DӮҫӮБӮҪ“–ҺһӮМҢRҠНӮвҸӨ‘DӮЙҚМ—pӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӢ{ҢҙӮМӢDгЈӮНҒAүҝҠiӮӘ“–ҺһӮМҗўҠE•WҸҖӮМ”ј•ӘӮЕӮ ӮиҒAӢӢҗ…ҒE‘|ҸңӮӘ—eҲХӮЕҒA‘ПӢvҗ«ӮЙ•xӮЭҒAӮіӮзӮЙ”R”пӮӘӮжӮӯҒAҸ¬Ң^ӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҚӮ”n—НӮЕӮ Ӯй“_ӮЕҒAүжҠъ“IӮИ”ӯ–ҫӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӢ{ҢҙҺ®җ…ҠЗӢDгЈӮЕҚӮ‘¬ү»ӮөӮҪ“ъ–{ҠCҢRӮМҠҲ–фӮӘ“ъҳIҗн‘ҲӮМҸҹ—ҳӮЙҚvҢЈӮөӮҪӮұӮЖӮЕҒAӮ»ӮМҗ«”\ӮНҗўҠEӮ©ӮзӮа’Қ–ЪӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎҠCҢR‘ўӢ@ӢZҸpҺ©—§үЯ’цӮЖҸa’J—І‘ҫҳY
ҢRҠНӮҫӮҜӮЕӮИӮӯ‘ў‘DҸҠӮЬӮЕӮЬӮйӮІӮЖ—A“ьӮЕҸo”ӯӮөӮҪ“ъ–{ӮМҠCҢRӮҫӮӘҒAҗlҚЮ—{җ¬Ӯр’ҶҗSүЫ‘иӮЖӮөӮВӮВӢZҸpӮМҺ©—§ӮЙ“wӮЯӮҪҢӢүКҒAҠCҢRӮН‘ҒӮӯӮа–ҫҺЎҺһ‘гӮЙҺ©ҺеҠJ”ӯӮМӢ{Ңҙғ{ғCғүӮрҺе—НҠНӮЙ“Жҗи“IӮЙҚМ—pӮөӮҪҺһҠъӮӘӮ ӮйҒB Ӯ»ӮМӢ{Ңҙ“сҳYҺҒӮНҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“ӮМҚМ—pӮЙӮаҗПӢЙ“IӮЕҒA1906(–ҫҺЎ39)”NҒAҠНҗӯ–{•”‘жҺl•”’·ӮҫӮБӮҪ“ҜҺҒӮМҢҲ’fӮЙӮжӮиҸ„—mҠНҲЙҗҒӮМҢvүжӮр•ПҚXӮөҒAҢRҠН—pӮЖӮөӮД“–ҺһҗўҠEҚЕ‘еӮМғ^Ғ[ғrғ“Ӯр•ДҚ‘ғtғHғAғҠғoҒ[үпҺРӮЙ’Қ•¶ӮөҒA—Ӯ”N9ҢҺӮЙҠН“аӮЙ“ӢҚЪӮөӮҪҒB 1912(‘еҗі1)”NҒAҠCҢRӮНӢ{Ңҙғ{ғCғүӮ©ӮзғCҚҶҠН–{Һ®ғ{ғCғүӮЙ“]Ҡ·ӮөӮҪҒBҲИ—ҲҒAҠOҚ‘ҺYғ{ғCғүӮМ—A“ьҒA“ӢҚЪӮаӮ ӮиӮНӮөӮҪӮӘҒAҸa’J—І‘ҫҳYҺҒӮӘӮ»ӮМӢZҸpҺТӮЖӮөӮДӮМҢo—рӮрҠJҺnӮіӮкӮҪҺһӮЙӮНҒAғ{ғCғүӢZҸpӮЖғҢғVғvғҚҸцӢCӢ@ҠЦӢZҸpӮр’ҶҠjӮЖӮ·Ӯй‘ўӢ@ӢZҸpӮЙӮЁӮўӮДҠCҢRӮНӮЩӮЪҺ©—§Ӯр’Bҗ¬ӮөҒAҚ‘“аӮЕ–ўҢoҢұӮМҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“ӮЙӮВӮўӮДӮаҒAҗжҗiҸ”Қ‘Ӯ©ӮзӮМҸо•сӮр‘еӢШӮЕҗіҠmӮЙ”»’fӮөӮДӮўӮҪҒBҸa’J—І‘ҫҳYҺҒҺ©җgӮӘҒuӢҢҠCҢRӢZҸpҺ‘—ҝҒv(җ¶ҺYӢZҸpӢҰүпҒA1970)ӮМ‘ж2•ӘҚы(ӮұӮМҸa’J•¶ҢЙӮЙҺы”[ҒA50Ғ|002)ҒAPҒD35ӮЙҺҹӮМӮжӮӨӮЙҸ‘ӮўӮДӮЁӮзӮкӮйҒB ҒuҺ„ӮН‘еҗі9(1920)”NӮЙӢҢҠCҢR‘еҠwҚZҗкүИҠwҗ¶ӮЖӮөӮДҒAҸцӢCҗ„җiӢ@ҠЦӮрҗкҸCӮөӮҪҚЫҒA“–Һһ•ДҠCҢRӮМҸ„—mҗнҠНғҢғLғVғ“ғgғ“(“dӢCҗ„җi)ӮЖ“ҜҲк”n—НӮМҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“‘•’uӮМҗЭҢvӮрүЫӮ№ӮзӮк1ғJ”NӮ©Ӯ©ӮБӮДӢ@ҠЦҺәӮМ”z”хҗ}ӮрҚмҗ¬ӮөӮҪҒBҠН–{ҢЬ•”’·ӮМҺӢҺ@ӮӘӮ ӮБӮДҒA“Ҝ”N12ҢҺ1“ъӮ©ӮзҒAҠН–{ҢЬ•”ӮЙӢО–ұӮ·ӮйӮұӮЖӮЖӮИӮБӮҪҒB“–ҺһҺе—НҠНӮМҢҡ‘ўӮЖӮЖӮаӮЙҒAҸ„—mҠНӢм’ҖҠН“ҷӮа‘Ҫҗ”Ңҡ‘ў’ҶӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸ„—mҠНҒAӢм’ҖҠНӮМғ^Ғ[ғrғ“ӮЙҢМҸб•p”ӯҒAӮ»ӮМүQ’ҶӮЙҠӘӮ«ҚһӮЬӮк”сҸнӮЙ’bӮҰҸгӮ°ӮзӮкӮҪ(үә—Ә)ҒvҒB ӮұӮМҲш—p•¶’ҶӮЙӮа•Р—ШӮӘҸoӮДӮўӮйӮӘҒA“–ҺһҗўҠEҠeҚ‘ӮЕӢNӮұӮБӮДӮўӮҪғ^Ғ[ғrғ“ӮМҢМҸбӮН‘е•ПӮИӮаӮМӮҫӮБӮҪҒBҲк”КӮЙҗ^ӮМҠvҗV“IӢZҸpӮНғgғүғuғӢӮрҚҺ•һӮөӮВӮВ”ӯ’BӮ·ӮйӮМӮЕӮ ӮиҒAҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“Ӯа—бҠOӮЕӮНӮ Ӯи“ҫӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢҢҠCҢRғ^Ғ[ғrғ“ӮМ1ҒA2ҚҶӢ@ӮН“–ҺһӮМҚЕ—LғJғҒҒ[ғJӮ©ӮзӮМ—A“ьӢ@ӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮзӮН“–ҺһӮМҗўҠEҚЕ‘еӢ@ӮҫӮБӮҪӮ©Ӯз“–‘RӮЙ•pҒXӮЖҢМҸбӮөӮҪҒBӮҪӮҫӮөӮ»ӮкӮзӮрҺgӮўӮұӮИӮ·ӮҫӮҜӮМӢZҸp—НӮрӢҢҠCҢRӢZҸpҗwӮНӮ·ӮЕӮЙ”хӮҰӮДӮЁӮиҒAӮ»ӮМҸгӮЙғJҒ[ғ`ғXғ^Ғ[ғrғ“ӮЖғpҒ[ғ\ғ“ғXғ^Ғ[ғrғ“ӮМҗ»‘ўҢ Һж“ҫӮЙӮжӮйӢZҸpҸC“ҫӮрҗПӮЭҸdӮЛӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҸгӢLӮМҺһҠФ“IҢoүЯӮЙӮжӮкӮОҒAӢҢҠCҢRӮМғ^Ғ[ғrғ“ӢZҸpҺ©—§үЯ’цӮМҸd—v•”•ӘӮЖҸa’JҺҒӮМӢZҸpҺТӮЖӮөӮДӮМҢo—рӮН’ҡ“xҸdӮИӮБӮДӮўӮйҒBӢҢҠCҢRӮНҒA‘еҗі4(1915)”N“xҢvүжӮМ“с“ҷӢм’ҖҠН“ҚӮЖҠ~(2Ӣ@2ҺІҒA16700”n—Н)ӮЙҠНҗӯ–{•”“ЖҺ©җЭҢvӮМ’PғVғҠғ“ғ_’јҢӢғ^Ғ[ғrғ“Ӯр‘•”хӮ·ӮйӮЬӮЕӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒB1923”NӮЙғJҒ[ғ`ғXғ^Ғ[ғrғ“ҒA1928”NӮЙғpҒ[ғ\ғ“ғXғ^Ғ[ғrғ“ӮЖӮМҗ»‘ўҢ Ң_–сҠъҢАӮМ“һ—ҲӮЖӮЖӮаӮЙҢ_–сӮр‘ЕӮҝҗШӮиҒAҠOҚ‘“БӢ–Ӯ©ӮзҺ©—§ӮөӮҪҠН–{Һ®ғ^Ғ[ғrғ“ӮӘ–јҺАӮЖӮаӮЙҗ¬—§ӮөӮҪҒB ӮұӮМӢZҸpҠJ”ӯғ`Ғ[ғҖӮМ’Ҷҗ•ӮЙҸa’J—І‘ҫҳYҺҒӮН1920”NӮЙҠНҗӯ–{•”ҲхӮЖӮөӮДҺQүБӮіӮкҒAҲИ—Ҳғ^Ғ[ғrғ“ӢZҸpӮМҺ©—§ӮЙ‘еӮ«ӮӯҚvҢЈӮіӮкҒA1944”N11ҢҺҲИҚ~ҸIҗнӮЬӮЕӮНҠНҗӯ–{•”’·ӮМ—vҗEӮЙӮ ӮиҒAҗнҢгӮа1973”N4ҢҺ8“ъӮЙҗАӢҺӮіӮкӮй’ј‘OӮЬӮЕҒA“ъ–{ӢZҸpӮМ”ӯ“WӮМӮҪӮЯӮЙҗs—НӮіӮкӮҪҒB ҠН–{Һ®ғ{ғCғүҒAғ^Ғ[ғrғ“Ӯр’ҶҗSӮЖӮөӮҪӢҢҠCҢRӮМ‘ўӢ@ӢZҸpӮНҠН–{Һ®ғ^Ғ[ғrғ“ӮМҗ¬—§ҠъҲИҢгҸҮ’ІӮЙ”ӯ’BӮөҒA1940”NӮұӮлҸvҚHӮМҺе—НҠНӮЕӮНҒA1Ӣ@2ҠКҒA1ҺІ1Ӣ@4–ң”n—НҒA4ҺІҒAғ^Ғ[ғrғ““ьҢыӮЕ30ӢCҲі350ҒҺ’ц“xӮЕӮ ӮБӮҪҒB“а”RӢ@ҠЦӮЕӮаҗцҗ…ҠН—pӮЙҠН–{Һ®ӮӘҠJ”ӯҒAҺА—pӮіӮкҒAӮЬӮҪҒA‘еҳaҒA•җ‘ ӮЙ“ӢҚЪӮр–Ъ•WӮЙҠJ”ӯӮіӮкӮҪ‘еҢ^•Ў“®ғfғBҒ[ғ[ғӢӢ@ҠЦӮНҒA‘еҳaҒA•җ‘ ӮЙӮН•sҚМ—pӮЖӮИӮБӮҪӮӘҒAҺҹҠъҢvүжҗнҠН—pӮЖӮөӮДӮМҺА—pҺҺҢұ–Ъ“IӮЕҗ…ҸгӢ@•кҠН“ъҗi(3Ӣ@1ҺІҒA2ҺІӮЕ47000”n—Н)ӮЙҚМ—pӮіӮкӮДӮўӮйҒBӢҢҠCҢRӮМӢ@ҠЦӮНҒA“а”RӢ@ҠЦҒA•вӢ@ҒAҺІҢnҒAғvғҚғyғүҒA“dӢCҒAҢv‘•ҒA“ҷӮаҠЬӮЯӮДҒA1941”NҲИ—Ҳ4ғ•”NӮЙҳiӮйҗн‘Ҳ’ҶӮр’КӮ¶ӮДҒAӢ@ҠЦӮМҢМҸбӮЙӮжӮиҚмҗнӮЙҺxҸбӮр—ҲӮөӮҪӮұӮЖӮН–wӮЗӮИӮўҚDҗ¬җСӮрӮ Ӯ°ӮДӮўӮйҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъҳIҗн‘ҲҺһӮМ–і“d–]ҳOҗЬҸХӮЙӮЁӮҜӮйҠO–ұҸИӮМӢрӮ©Ӯі | |
|
ҒЎ1ҒDӮЬӮҰӮӘӮ«Ғ@
“ъҳIҗн‘ҲӮМҺһ‘гӮМҠO–ұҸИӮЙӮНҒAҸ¬‘әҺх‘ҫҳYӮМӮжӮӨӮИҲӨҚ‘ӮМ—L”\ҠOҢрҠҜӮӘӮўӮДҒA“ъ–{ӮМҚ‘үvӮМӮҪӮЯӮЙҠҲ–фӮөӮҪӮұӮЖӮӘ’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ӮӘҒAҠO–ұҸИӮ»ӮМӮаӮМӮМ‘МҺҝӮЙӮНҒAӮ·ӮЕӮЙӮ ӮМҺһ‘гӮ©ӮзҒAҢ»ҚЭӮМҒuҺ––ЬӮк‘МҺҝҒvӮМ–GүиӮӘҢ©ӮзӮкӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮұӮӨӮўӮӨ–в‘иӮЙӮНӮЬӮБӮҪӮӯӮМ‘fҗlӮЕӮ·ӮӘҒA–іҗьӢZҸpӮМ—рҺjӮр’ІӮЧӮДӮўӮйҠФӮЙ’mӮБӮҪӮұӮЖӮрҒAҲИүәӮЙӢLӮөӮЬӮ·ҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ2ҒD–і“d–]ҳOӮМӢЩӢ}җ«Ғ@
“ъҳIҗн‘ҲӮМҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДҒA“ъ–{җlӮӘҗ»‘ўӮөӮҪ–і“d‘•’uӮӘ‘еҠҲ–фӮөҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮИӮЗӮрҸҹ—ҳӮЙ“ұӮўӮҪӮұӮЖӮНҒA(”N”yҺТӮЙӮН)ӮжӮӯ’mӮзӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒB“ъ–{ҠCҢRӮӘ–і“dӮр‘•”хӮ·ӮйӮЙҺҠӮБӮҪҢoҲЬӮрҠИ’PӮЙӢLӮ·ӮЖҒAҲИүәӮМӮЖӮЁӮиӮЕӮ·ҒB “ъҳIҗн‘ҲӮМҺһ‘гӮНҒAғ}ғӢғRҒ[ғjӮӘ–і“dӮр”ӯ–ҫӮөӮДӮЬӮаӮИӮўӮұӮлӮЕҒAҗўҠEӮМӮЗӮМҢR‘аӮаҒA–і“dӮМ‘•”хӮЙӮН–ў’…ҺиӮЕӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮжӮӨӮИӮЖӮ«ҒA“VҚЛ“IӮИҗжҢ©җ«ӮрӮаӮБӮҪҠCҢRӮМҸHҺRбБ”V(“ъҳIҗн‘ҲҺһӮМҠшҠНҺOҠ}ӮМҺQ–d)ӮӘҒu–і“dӮМҺА—pү»ӮЖ‘е—Ө”ј“ҮүҲҠЭӮЙӮЁӮҜӮй–і“d–]ҳO(*1)ӮМҢҡҗЭҒvӮрҢRҺс”]ӮЙ’сҲДӮөӮЬӮөӮҪҒBӮвӮНӮи“VҚЛӮҫӮБӮҪҺR–{Ң •әүqҠCҢR‘еҗb(ӮМӮҝӮМ‘Қ—қ)ӮНҒAӮұӮМҺбӮўҺmҠҜӮМ’сҲДӮМҸd—vҗ«ӮрӮўӮҝ‘ҒӮӯҢ©”ІӮ«ҒAҚҶ—ЯӮрӮ©ӮҜӮЬӮөӮҪҒBӮНӮ¶ӮЯӮНғ}ғӢғRҒ[ғjӮМ–і“d‘•’uӮрҚw“ьӮ·ӮйҢvүжӮаӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ӮӘҒAӮ ӮЬӮиӮЙӮаҚӮҠzӮҫӮБӮҪӮМӮЕ’ҶҺ~ӮөҒA•KҺҖӮЕҺ©—НҠJ”ӯӮрӢ}Ӯ¬ӮЬӮөӮҪҒBӢZҸpӮрҺуӮҜҺқӮБӮД“w—НӮөӮҪӮМӮНҒAҚЕҸүҠъӮНҠw—рӮМ–іӮў“VҚЛӢZҸpҺТҒEҸј‘гҸј”VҸ•ӮЕҒA–{Ҡiү»ӮөӮДӮ©ӮзӮНҒA–Ш‘әҸxӢgӮЕӮөӮҪҒB –Ш‘әҸxӢgӮНҒAҸҹҠCҸMӮв•ҹаV—@ӢgӮрӮМӮ№ӮҪҷч—ХҠЫӮМҚЕҚӮҗУ”CҺТӮҫӮБӮҪ–Ш‘әҗЫ’ГҺзӮМҺҹ’jӮЕҒA“Ң‘е—қҠw•”ӮМ‘еҠwү@ӮрҸoӮДғAғҒғҠғJӮМғCғGҒ[ғӢ‘еӮЕ”ҺҺmҚҶӮoӮҲӮcӮр“ҫӮҪҠwҺТӮЕӮөӮҪҒBӮаӮЖӮаӮЖӮН—қҳ_үЖӮЕӮөӮҪӮӘҒAҚ‘үЖ‘¶–SӮМҠлӢ@ӮЕӮ ӮйӮҪӮЯҒAҚDӮ«ӮИ—қҳ_Ӯр••ҲуӮөӮДҒAҗн‘ҲҺһӮЙ‘fҗlӮЕӮаҺg—pүВ”\ӮИҒAүуӮкӮЙӮӯӮӯҲөӮўӮвӮ·Ӯў–і“d‘•’uӮМҠJ”ӯӮЙ‘S—НӮр’ҚӮ¬ҒAӮ©ӮлӮӨӮ¶ӮДҠФӮЙҚҮӮнӮ№ӮЬӮөӮҪҒB Ғm“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЕ–і“dӮМӢZҸpӮрҢoҢұӮөӮДӮўӮйҗlӮНҲкҗlӮаӮЁӮзӮёҒAҺҶӮМҸгӮМ’mҺҜӮр‘ҪҸӯӮНҺқӮБӮДӮўӮйҗlӮаӮҪӮ©ӮҫӮ©җ”җlӮЕӮөӮҪӮ©ӮзҒAӮ¶ӮВӮЙӮжӮӯӮвӮБӮҪӮЖҺvӮўӮЬӮ·ӮөҒAҠJ”ӯӮр’сҲДӮөӮҪҸHҺRбБ”VӮМ’BҺҜӮаҲуҸЫ“IӮЕӮ·Ғn ҢRӮЕӮНҒAӮұӮМ–і“d‘•’uӮрҢRҠНӮЙ‘•”хӮ·ӮйӮЖӮЖӮаӮЙҒA‘SҚ‘ӮЙ–]ҳOӮрӮВӮӯӮБӮДӮ»ӮұӮЙҗЭ’uӮ·ӮйҢvүжӮрӮҪӮДҒA‘еҺФ—ЦӮЕҺАҚsӮЙҲЪӮөӮЬӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAғҚғVғAӮМҠН‘аӮрҢ}ӮҰҢӮӮВӮҪӮЯӮЙӮНҒA“ъ–{ӮМүҲҠЭӮҫӮҜӮМ–]ҳOӮЕӮН•sҸ\•ӘӮЕӮ·ҒB“ҢғVғiҠCӮв“ъ–{ҠCӮЕӮМҠCҗнӮЙ”хӮҰӮйӮҪӮЯӮЙӮНҒAӮЗӮӨӮөӮДӮаҒA’©‘N”ј“ҮӮвғVғi‘е—ӨӮМүҲҠЭӮЙ–і“d–]ҳOӮрӮВӮӯӮй•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮөӮҪҒB—ӨҠCҢRӮНӮұӮМӮұӮЖӮЙ•KҺҖӮЙӮИӮиӮЬӮөӮҪҒB ҒmҲИүәӮНҒA“cҠЫ’јӢgҒu“ъ–{ҠCҢRғGғҢғNғgғҚғjғNғX”йҺjҒvӮ©ӮзӮМ”ІҗҲӮЕӮ·ҒB“cҠЫҺҒӮНҒAҗн’ҶӮЙғhғCғcӮМӢZҸpҸо•сӮр“ъ–{ӮЙ’mӮзӮ№ӮйӮҪӮЯӮЙҒAҗцҗ…ҠНӮЕ–§Ӯ©ӮЙғhғCғcӮрӮЯӮҙӮөӮДҠпҗХ“IӮЙғhғCғcӮЙ“һ’…ӮөҒAҠпҗХ“IӮЙғhғCғcӮМ”sҗнӮрҗ¶Ӯ«”ІӮ«ҒAҗнҢгӮаҠҲ–фӮөӮЬӮөӮҪҒBӮұӮМ”йҺjӮНҒAғhғCғcӮЙҚsӮӯ‘OӮЙҠCҢRӮМ“ъҳIҗн‘ҲҺһӮМҺj—ҝӮрҢ©ӮйӢ@үпӮӘӮ ӮБӮДҒAӮ»ӮМҗЬӮиӮЙғҒғӮӮөӮҪӢЙ”йӮМғmҒ[ғgӮрҢіӮЙӮөӮДӮўӮйӮ»ӮӨӮЕӮ·Ғn Ғm*1Ғ@“–ҺһӮН–іҗьӮЙӮжӮй“dҳbӮНӮЬӮБӮҪӮӯ–ўҠJ‘сӮЕҒA–іҗь“dҗM(–і“d)ӮӘӮвӮБӮЖҸo—ҲӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮЖӮўӮӨҺһ‘гӮЕӮөӮҪҒnҒ@ |
|
|
ҒЎ3ҒD—ӨҠCҢRӮМҠO–ұҸИӮЦӮМ—v–]Ғ@
Ӯ»ӮұӮЕ—ӨҠCҢRӮНҒAҠO–ұҸИӮЙӮ ӮДӮД•¶Ҹ‘ӮрҸoӮөҒA‘е—ӨӮМҗҙҚ‘җӯ•{ӮЖ”ј“ҮӮМҠШҚ‘җӯ•{ӮЙҒA–і“d–]ҳO—pӮМ“y’nҺШ—pӮМҗЬҸХӮрҲЛ—ҠӮөӮЬӮөӮҪҒBӮ·ӮИӮнӮҝҒA ҒuҗҙҚ‘“м•”ӮЙӮЁӮўӮДҒv ҲкҒA•ҹҢҡҸИүҲҠЭӮМҸd—vӮИӮйҺs—WӢyҠJҚ`Ҹк“ҷӮЙ“dҗMӢЗҗЭ’u•А”VӮрҗЭ’uӮ·ӮЦӮ«“y’nӮМҺg—pҢ ҒB ҲкҒA•ҹҸBӮжӮи•ҹҢҡҸИ“аҸd—vӮИӮйҺs—W“ҷӮЙ“dҗMӢЗҗЭ’u•А”VӮрҗЭ’uӮ·ӮЦӮ«“y’nӮМҺg—pҢ ҒB ҒuҠШҚ‘ӮЙӮЁӮўӮДҒv ҲкҒAүҲҠЭӮЙү—ӮҜӮйҸd—vӮИӮйҺs—WӢyҠJҚ`Ҹк“ҷӮЙ“dҗMӢЗҗЭ’u•А”VӮрҗЭ’uӮ·ӮЦӮ«“y’nӮМҺg—pҢ ҒB “ҷӮрҺж“ҫӮ·ӮйҢҸӮМҠtӢcҗҝӢcҲДӮр’сҸoҒA’јӮҝӮЙҢрҸВӮрҠJҺnӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҠtӢcӮМҢҲ’иӮрҢ©ӮҪҒB ҒEҒEҒEӮЖӮўӮӨӮнӮҜӮЕҒAүәӢLӮМӮжӮӨӮИ‘Қ—қ‘еҗbӮ ӮДӮМ•¶Ҹ‘ҒAӮЁӮжӮСҠO–ұ‘еҗbӮ ӮДӮМ•¶Ҹ‘ӮӘҸoӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ4ҒD‘Қ—қ‘еҗbҲ¶ӮМ•¶Ҹ‘Ғ@
ҒuҒ@ҠҜ–[‘ж3656ҚҶғm2 ӢЯ—Ҳ–іҗь“dҗMӮМҢӨӢҶҗңӮй‘ҙӮМ•аӮрҗiӮЯ”VӮрҢRҺ–Ҹг‘ҙӮМ‘јӮЙүһ—pӮ·ӮйӮЙ‘ҙӮМҢш—НҗңӮй‘еӮИӮйӮаӮМӮ ӮиҒAҺкӮЙ”VӮрҗҙҚ‘“м•”ӢyҠШҚ‘үҲҠЭӮЖ’йҚ‘—М“yӢyҠН‘DӮЖӮМҠФӮЙҗЭ’uӮ·ӮйӮр“ҫӮНҒA•ҪҺһӮН–Ьҳ_җнҺһӮЖҲа’КҗMӮрҠmҺА•qҠҲӮИӮзӮөӮЯҢRҺ–Ҹг‘ҙӮМ‘јӮЙ•ЦүvӮр—^ӮУӮйӮұӮЖҺҠ‘еӮИӮйӮЦӮ«ӮЙ•tҸ”ҠOҚ‘ӮЙҗжӮсӮө‘OӢLӮМҗҙҚ‘“м•”ӢyҠШҚ‘үҲҠЭӮЙ–іҗь“dҗMҢрҠ·ҸҠӮрҗЭ’uӮ·ӮйӮМ“БҢ Ӯр’йҚ‘җӯ•{ӮЙҺж“ҫӮө’uӮ©ӮсӮұӮЖҚЕ•K—vӮЖ”FӮЯдўӮЙҠtӢcӮрҗҝӮУ –ҫҺЎ32”N9ҢҺ4“ъ ҠCҢR‘еҗbҒ@ҺR–{Ң •әүq / —ӨҢR‘еҗbҒ@ҺqҺЭҒ@Ңj‘ҫҳY / “аҠt‘Қ—қ‘еҗbҒ@ҢтҺЭҒ@ҺRгp—L•ьҒ@“a ҒvҒ@ |
|
|
ҒЎ5ҒDҠO–ұ‘еҗbҲ¶ӮМ•¶Ҹ‘Ғ@
ҒuҒ@ҠҜ–[Ӣ@–§‘ж219ҚҶғm2 ҚЎ”КҗҙҚ‘“м•”ӢyҠШҚ‘үҲҠЭӮЙ–іҗь“dҗMҢрҠ·ҸҠӮрҗЭ’uӮ·ӮйӮМ“БҢ Ӯр’йҚ‘җӯ•{ӮЙҺж“ҫӮө’u“xҢҸӮЙҠЦӮөҗҝӢcӮЙӢyӮР’uҢуҸҲ•КҺҶҚbҚҶҺКӮМ’КҠtӢcҢҲ’и‘Ҡҗ¬ҢуӮЙ•tӮДӮН•КҺҶүіҚҶ—v—МӮЙҲЛӮиүE“БҢ Һж“ҫ•ыүВ‘RҢдҺжҢv‘Ҡҗ¬“xҚҹ’iӢyҢдҸЖүпҢу–з –ҫҺЎ32”N11ҢҺ14“ъ ҠCҢR‘еҗbҒ@ҺR–{Ң •әүq / —ӨҢR‘еҗbҒ@ҺqҺЭҒ@Ңj‘ҫҳY / ҠO–ұ‘еҗbҒ@ҺqҺЭҒ@җВ–ШҺь‘ Ғ@“a •КҺҶҚbҚҶ(ҸИ—Ә) •КҺҶүіҚҶ(ҢрҠ·ҸҠҗЭ’uӮМ“БҢ ӮрҺж“ҫӮө“xҗьҳHҒBҲИүә3ҒDӮЖ“ҜҲк“а—e)Ғ@ |
|
|
ҒЎ6ҒD’S“–‘ӢҢыӮМҗжҢ©җ«ӮМ–іӮіҒ@
ӮұӮМҠtӢcҢҲ’иӮЙҠоӮГӮӯҢP—ЯӮЙ‘ОӮөӮЬӮөӮДҒAҗҙҚ‘“Б–Ҫ‘SҢ ҢцҺg’jҺЭҗј“ҝ“сҳYӮНҒAҠO–ұ‘еҗbҲ¶ӮЙҒAҲИүәӮМӮжӮӨӮИҒyӢ°ӮйӮЧӮ«ҲУҢ©Ҹ‘ҒzӮр‘—ӮБӮДӮ«ӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB—v–сӮўӮҪӮөӮЬӮ·ҒB (1)–іҗь“dҗMӮН–ўӮҫҺАҢұ’iҠKӮИӮМӮЕҒA’јӮҝӮЙҗҙҚ‘ӮЙҗЭ’uӮ·ӮйӮМӮНҢyӢ“ӮЕӮ ӮйҒB (2)ӮөӮ©Ӯа—ӨҸгӮЕӮН—Lҗь“dҗMӮМ•ыӮӘ—ЗӮўҒB (3)җҙҚ‘ӮӘӢ‘җвӮ·ӮйӮМӮН•K‘RӮИӮМӮЕҒA—]ҢvӮИғgғүғuғӢӮрӢNӮұӮ·•K—vӮНӮИӮўҒB (4)“S“№•~җЭӮМӮжӮӨӮИ–в‘иӮИӮзӮЬӮҫӮөӮаҒA“ъ–{ӮМ—ҳүvӮЙӮИӮзӮИӮў–в‘иӮЕҗҙҚ‘ӮМҗSҸШӮрҠQӮ·ӮйӮМӮН“ҫҚфӮЕӮНӮИӮўҒB “cҠЫҺҒӮНҒAӮұӮМ‘ӢҢыӮМ‘Ф“xӮЙ‘ОӮөӮДҒA Ғu“–ҺһғҚғVғAӮМҗN—ӘҲУҗ}ӮНҺ@’mӮіӮкӮДӮЁӮиҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМүсҚqӮЙ”хӮҰӮДҠCҢRӮӘ–ң‘SӮМ‘ОҚфӮрӮЖӮзӮЛӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҸoҗжӢ@ҠЦӮЙӮНӮ»ӮкӮрҺ@’mӮ·Ӯй”\—НӮӘ–іӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮўҒvӮЖӢLӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB“ъ–{Ӯ»ӮМӮаӮМӮӘҺҖӮКӮ©җ¶Ӯ«ӮйӮ©ӮМҗЈҢЛҚЫӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮМӮЙҒAӮ»ӮМӮ ӮЬӮиӮМ“ЫӢCӮіӮЙҲ ‘RӮЖӮөӮЬӮ·ҒB“cҠЫҺҒӮНҸ‘ӮўӮДӮЁӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAҠCҢRӮНҢғ“{ӮөӮҪ–Н—lӮЕӮ·ҒBӮ»ӮөӮДҒAҺҹҗЯӮМӮжӮӨӮЙҒAӮаӮБӮЖӢп‘М“IӮЙ15ӮМ’n“_ӮрҺwҺҰӮөӮДҒAӮіӮзӮИӮйҗЬҸХӮрӢӯӮӯҲЛ—ҠӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғm“–ҺһӮМҠO–ұ‘еҗbӮМҗВ–ШҺь‘ ӮНҒA—бӮМғyғӢҒ[җlҺҝҺ–ҢҸӮМӮЖӮ«ҒA”’”Ҝҳь–қ‘еҺgӮЖҢҫӮнӮкӮҪҗlӮМ‘\‘c•ғӮЕӮ·ҒBҺi”n—Й‘ҫҳYӮНҗВ–ШҺь‘ ӮМӮұӮЖӮрҒAҒuүҪӮрӮөӮҪӮМӮ©ӮжӮӯ•ӘӮ©ӮзӮИӮўҗl•ЁҒvӮЖ”б”»ӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒnҒ@ |
|
|
ҒЎ7ҒDӢп‘М“IӮЙҺwҺҰӮөӮҪ15ӮМ’n“_Ғ@
•ҹҸBҺsҠXҺбӮН‘ҙӮМ•ҚӢЯ / ҢЬҢХ“ҮҺбӮН—…җҜ“Ү•d’n•ҚӢЯ / “ҢҸд“Ү / үс‘D“Ү / үGқf“Ү / ғsғүғ~ғbғhҠp / ғ`ғ“ғӮҠp / ғPғӮғC“Ү“м“Ң•” / ӣъ–еҺsҠXҺбӮН‘ҙӮМ•ҚӢЯ / ғ`ғғғyғӢ“Ү / ғ^ғIғ“ғqҒ[ғӢ / ғWғҮғJғRҠp / “ҢҲш“ҮҺбӮН—–ӣЧ / ҺO“s“Ү“м“Ң•” / ғqғ…Ғ[ғ„ғ““Ү ҒmӮұӮкӮзӮМҸкҸҠӮӘӮЗӮұӮ©ӮЙӮВӮўӮДӮНҒA’mҺҜӮӘӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘ’КӮиӮ»ӮӨӮИүҲҠЭӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮНҠmӮ©ӮЕӮ·Ғn ҠCҢRӮЖӮөӮДӮНҒAӮұӮкӮзӮр‘еҺgӮЙҸ‘Ӯ«‘—ӮйӮұӮЖӮЙӮжӮБӮДҒAӮәӮРҗЬҸХӮ·ӮйӮжӮӨҲі—НӮрӮ©ӮҜӮҪӮМӮЕӮөӮеӮӨҒBӮөӮ©ӮөҒAғ_ғҒӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ8ҒDҺSӮЯӮҫӮБӮҪҗҙҚ‘ӮЖӮМҗЬҸХҢӢүКҒ@
Ӯ»ӮМҢгҒA–ҫҺЎ33”NӮМӢ`ҳa’cӮМҺ–ҢҸӮИӮЗӮӘӮ ӮБӮДҗЬҸХӮӘ’xӮкӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮЕӮаҢ`Һ®“IӮЙӮНҗ\Ӯө“ьӮкӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒBӮөӮ©ӮөҒAҢҫӮрҚ¶үEӮ·ӮйӮИӮЗҒAӮўӮўӮ©Ӯ°ӮсӮИ•ФҺ–ӮөӮ©“ҫӮзӮкӮёҒA‘МӮжӮӯӢ‘җвӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒB“cҠЫҺҒӮНҒAӮВӮ¬ӮМӮжӮӨӮЙ•]ӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB Ғu“ъҗҙҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮрҺыӮЯӮҪҢгӮЕӮаӮ ӮиҒAӮаӮБӮЖ—L”\ӮИҠOҢрҠҜӮр“ҫӮДӮЁӮкӮОҒAӮ»ӮМҢг‘еӮ«ӮИүeӢҝӮӘӮ ӮБӮҪӮаӮМӮрӮЖҗЙӮөӮЬӮкӮйҒv ӮЬӮБӮҪӮӯӮ»ӮМ’КӮиӮЕӮ·ҒBҠМҗSӮМҗЬҸХ’S“–ӮМҢцҺgӮӘҒuҚЕҸүӮ©ӮзӮвӮйӢCӮӘ–іӮўҒvӮМӮЕӮ·Ӯ©ӮзҒAӮӨӮЬӮӯӮўӮӯ”ӨӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒB ҒmҢ»ҚЭ’ҶҚ‘ӮвҠШҚ‘ӮЙӮўӮйҠOҢрҠҜӮЖ“ҜӮ¶ӮЕӮ·ӮЛҒn ӮұӮМҠO–ұҠҜ—»ӮМӮҫӮзӮөӮМӮИӮіӮЙӮжӮиӮЬӮөӮДҒAҠCҢRӮН—]ҢvӮИӢкҳJӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ9ҒDӮЗӮӨӮөӮжӮӨӮаӮИӮ©ӮБӮҪҠШҚ‘ӮЖӮМҗЬҸХҢӢүКҒ@
‘ј•ыҠШҚ‘ӮЕҗЬҸХӮЙӮ ӮҪӮБӮҪ“Б–Ҫ‘SҢ ҢцҺg—СҢ Ҹ•ӮНҒAӮ Ӯй’ц“xӮНҗЬҸХӮөӮҪӮзӮөӮўӮМӮЕӮ·ӮӘҒA“K“–ӮИҢыҺАӮЕӢ‘җвӮіӮкӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҺШ’nӮрҠҳҺRӮЙӮөӮЪӮБӮДҗ\Ӯө“ьӮкӮЬӮөӮҪӮӘҒAӮұӮкӮаҺу‘шӮіӮкӮёҒBҢӢӢЗҒA ҚbҒFҢRҺ–—НӮр”wҢiӮЙӢӯҚdӮЙҗ\Ӯө“ьӮкӮйҒB үіҒFҗЬҸХӮрҢp‘ұӮөӮИӮӘӮзҒAҺ–ҺАҸгӮНҢҡҗЭӮөӮДӮөӮЬӮӨҒB Ғ\Ғ\ӮМ“сҲДӮөӮ©ӮИӮўӮҫӮлӮӨҒAӮЖӮўӮӨҢӢҳ_ӮЙӮИӮиҒA‘o•ыӮЖӮаӮЙ•sүВ”\ӮҫӮЖӮөӮДҒAҠШҚ‘ӮЦӮМ–і“d–]ҳOҢҡҗЭӮаҸБ–ЕӮөӮДӮөӮЬӮўӮЬӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ10ҒDҢӢӢЗҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮНӮЗӮӨӮөӮҪӮМӮ©Ғ@
җҙҚ‘ӮаҠШҚ‘ӮаҒA—vҗlӮҪӮҝӮНҒAғҚғVғAӮЙвД—ҚӮіӮкӮДӮөӮЬӮБӮДҒAӮұӮкӮӘӢЙ“ҢӮӘҗA–Ҝ’nӮЙӮИӮБӮДӮөӮЬӮӨӮ©ӮЗӮӨӮ©(ғVғiҒA’©‘N”ј“ҮҒA“ъ–{ӮМҗlӮҪӮҝӮӘғҚғVғAӮМ“z—кӮЙӮИӮБӮДҸБ–ЕӮөӮДӮөӮЬӮӨӮ©ӮЗӮӨӮ©)ӮМҗЈҢЛҚЫӮЕӮ ӮйӮЖӮМ”FҺҜӮаҗУ”CҠҙӮаӮИӮӯҒA“ъ–{ӮҪӮҫҲкҚ‘ӮӘ‘Ҫ‘еӮИӢ]җөӮр•ҘӮБӮДҗнӮў”ІӮ«ӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒA’©‘N”ј“ҮӮӘҗнҸкӮЙӮИӮБӮДӮ©ӮзҒAӮўӮӯӮВӮ©ӮМ”ј“ҮүҲҠЭӮМ“ҮӮЙ•KҺҖӮЕ–і“d–]ҳOӮрҢҡҗЭӮөӮДҒAғҚғVғAҠН‘аӮЖӮМҗнӮўӮЙҠҲ—pӮөӮЬӮөӮҪҒBҲк•ығVғiӮМ‘е—ӨүҲҠЭӮМ•ыӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗҢҡҗЭӮЕӮ«ӮёӮЙҸIӮнӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·ҒB ӮөӮ©ӮөӮ»ӮкӮЕӮаҒA“ъ–{ҠCӮЙ•ӮӮ©ӮФ“ъҠШ‘o•ыӮМҸ¬“ҮӮИӮЗӮЙ‘ҪӮӯӮМ–і“d–]ҳOӮрҚмӮиҒA“ъ–{ҠCҢRӮНӮ»ӮкӮзӮрҚЕ‘еҢАӮЙҠҲ—pӮөӮДҒAғҚғVғAҠН‘аӮрҢӮ–ЕӮөӮЬӮөӮҪҒB Ғm—L–јӮИ’|“ҮӮЙӮаҗЭ’uӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮМ’|“Ү’ІҚёӮӘ‘ҪӮӯӮИӮіӮкӮДӮЁӮиҒA“–ҺһӮ©ӮИӮиӮМҗ”ӮМ“ъ–{җlӮӘӢҸҸZӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘҒA“ъҳIҗнҺjӮЙӢLӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·ҒBҠ®‘SӮЙ“ъ–{җlӮӘҠҲ–фӮөӮДӮўӮҪ“ҮӮЕӮ ӮиҒAҠШҚ‘ӮЖӮН–іҠЦҢWӮЕӮөӮҪҒBҒn Ғm–і“d–]ҳOӮН–ЪҺӢӮЙӮжӮБӮД“GҸоӮр’TӮиҒAӮіӮзӮЙ–і“dӮЙӮжӮБӮД“GӮМҸо•сӮрғLғғғbғ`ӮөҒA–Ў•ыӮМҢRҠНӮвҚ‘“аӮМҺi—Я’Ҷҗ•ӮЖҳA—ҚӮөӮЬӮ·ӮӘҒAӮЩӮЖӮсӮЗӮМ–і“d–]ҳOӮНҚ‘“а—vҸҠӮЖ—LҗьӮЕҳAҢӢӮіӮкӮЬӮөӮҪҒBӢЯӮӯӮН—Lҗь“dҳbҒAү“•ыӮН—Lҗь“dҗMӮЕӮ·ҒBӮұӮМ—Lҗь–ФӮЙӮжӮБӮДҒA•K—vӮИҸо•сӮӘ“ҢӢһӮМ‘е–{үcӮвҢR—Я•”ӮЙ‘—ӮзӮкӮЬӮөӮҪҒB“ҮӮМҸкҚҮӮЙӮНӮұӮМ—Lҗь–ФӮНҠC’кғPҒ[ғuғӢӮЕӮөӮҪҒBҢ»ҚЭӮМӮжӮӨӮЙ–іҗьӮЙӮжӮйҺ©ҚЭӮИ’КҗMӮНҸo—ҲӮЬӮ№ӮсӮЕӮөӮҪҒBӮЬӮҪҲГҚҶӮа–ў”ӯ’BӮЕӮөӮҪҒBӮИӮЁ“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮМ•Ә–мӮЕ“ъ–{ӮМӢZҸpӮӘҸгӮЕӮөӮҪӮӘҒAҲГҚҶӮМүр“ЗӮНғҚғVғAӮӘҸгӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ·(ӮЖӮўӮӨӮжӮиӮа“ъ–{җlӮӘӢкҺиӮЖӮ·Ӯй•Ә–мӮЕӮ·)ҒnҒ@ |
|
|
ҒЎ11ҒDӮЮӮ·ӮСҒ@
ҲИҸгӮНҒAҗжҢ©җ«ӮӘӮИӮӯҺ––ЬӮкҺеӢ`ӮЕҚ‘үvӮр‘№ӮЛӮйҠO–ұҸИӮМ‘МҺҝӮН“ъҳIҗн‘ҲӮМ‘OӮ©ӮзӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒ\Ғ\ӮЖӮўӮӨӢЯ‘гҺjӮМҺ–—бӮЕӮ·ҒB“мӢһ‘еӢsҺEӮМӢL”OҠЩӮӘ–іҗ”ӮЙӮЕӮ«ӮДӮаҚRӢcӮРӮЖӮВӮөӮИӮў“ъ–{ҠO–ұҸИӮМ–GүиӮрҢ©ӮйҺvӮўӮЕӮ·ҒB ҒuҚ‘ҚЫ’КҗMӮМ“ъ–{ҺjҒv(“ҢҠC‘еҠw)ӮЙӮаҸ‘Ӯ«ӮЬӮөӮҪӮӘҒAҗн‘Oҗн’ҶӮаҒAғҚғVғAӮрҺhҢғӮөӮҪӮӯӮИӮўҒ\Ғ\ӮЖӮўӮӨҠO–ұҸИӮМҺгҚҳӮӘҒA“ъ–{ӮМҚ‘ҚЫ’КҗMӮМҗA–Ҝ’nҸу‘ФӮ©ӮзӮМ—Ј’EӮр‘е•қӮЙ’xӮзӮ№ӮҪӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB Ғmҗн‘ҲӮЙӮИӮБӮДҠO–ұҸИӮӘ–ZӮөӮӯӮД’КҗMҠЦҢWӮМ‘ОҠOҗЬҸХӮЙҸoҗИӮөӮИӮӯӮИӮБӮҪҺһ‘гӮЙӮИӮБӮДҒAӮНӮ¶ӮЯӮДҒAзЁҗMҸИӮМ‘ОҠOҗЬҸХӮӘӮӨӮЬӮӯӮўӮӯӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒ\Ғ\ӮЖӮўӮӨ”з“чӮИҳbӮӘҒAзЁҗMҸИ‘ӨӮМҺj—ҝӮЙӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮЬӮ·Ғn ӮұӮМҺ–ҢҸӮ©Ӯз‘ҪӮӯӮМӢіҢPӮӘ“ҫӮзӮкӮЬӮ·ӮӘҒAӮЁӮ»ӮзӮӯҗмҢыҠO–ұ‘еҗbӮИӮЗӮНҒAӮЬӮБӮҪӮӯ–іҠЦҗSӮҫӮЖҺvӮўӮЬӮ·ҒB Ғm“ъ–{ӮМ–ј—_ӮМӮҪӮЯӮЙ•tӢLҒBҠO–ұҠҜ—»ӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAғAғҒғҠғJҗўҳ_Ӯр“ъ–{ӮМ–Ў•ыӮЙӮВӮҜӮйӮҪӮЯӮЙҒAҺӮҺq•ұҗvӮМҠҲ–фӮрӮөӮҪҗl•ЁӮӘӮўӮЬӮөӮҪҒBӢаҺqҢҳ‘ҫҳYӮвҚӮ•фҸчӢgӮЕӮ·ҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҗl•ЁӮМҠҲ–фӮӘ“ъ–{ӮрӢ~ӮўӮЬӮөӮҪҒBҗн”п’І’BӮМӮҪӮЯӮЙҗSҢҢӮр’ҚӮўӮҫҚӮӢҙҗҘҗҙӮаӮ»ӮӨӮЕӮ·ҒnҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎҺR–{Ң •әүq | |
|
ҺR–{Ң •әүqӮНҒA“ъ–{ҠCҢRӮМӢЯ‘гү»ӮМӮҪӮЯҒAҺ„ҸоӮрҠ®‘SӮЙҺМӮДӮ«ӮБӮДүьҠvӮр’fҚsӮөӮҪҒBүҪ“xӮ©үў•ДӮрҢ©ӮДүсӮиҒAӮ»ӮкӮЙ”дҢЁӮ·ӮйҠCҢRӮӘ•K—vӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр’ЙҠҙӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBүьҠvӮНӮўӮВӮМҗўӮаҒA–ҪӮӘӮҜӮЕӮ ӮйҒBҠщ“ҫҢ үvӮЖӮМзaзҖҒA’пҚRҗЁ—НӮМ–WҠQҒAӮұӮкӮзӮрӮЗӮӨҸҲ—қӮ·ӮйӮ©ҒBӮұӮұӮЙӮ»ӮМғӮғfғӢӮӘӮ ӮйҒB
ҒЎ“ъ–{ҠCҢRӮМ•ғ ҺR–{Ң •әүqӮНҠCҢRҺmҠҜӮЕӮ ӮиҒAҠCҢR‘еҗbҒAҺс‘ҠӮр–ұӮЯӮҪҗӯҺЎүЖӮЕӮаӮ ӮйҒBҒu“ъ–{ҠCҢRӮМ•ғҒvӮЖҢҫӮнӮкӮҪҒBҠCҢRӮр‘nҗЭӮөӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBҠCҢRӮМӢЯ‘гү»ӮМӮҪӮЯӮЙҒA”Ш—EӮрӮУӮйӮБӮДҸ”җ§“xӮМүьҠvҒAҗlҺ–ӮМҚьҗVӮр’fҚsӮөӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМүьҠvӮӘҚsӮнӮкӮДӮўӮИӮҜӮкӮОҒA“ъҗҙҒA“ъҳIӮМ—јҗн‘ҲӮЙ“ъ–{ӮНҸҹӮДӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB“ъҳIҗн‘ҲҺһӮМ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМҠҲ–фӮаҒAҺR–{ӮӘӮўӮИӮҜӮкӮОӮ Ӯи“ҫӮИӮ©ӮБӮҪҒB ”ЮӮрҒuҗјӢҪ—Іҗ·ӮЖ‘еӢv•Ы—ҳ’КӮМ’·ҸҠӮрҢ“ӮЛӮҪӮжӮӨӮИ’jҒvӮЖҸМӮ·ӮйҺТӮаӮўӮҪҒBҗјӢҪӮМ“ҝҒA‘еӢv•ЫӮМ’mҗ«ӮЖ’_—Н(“xӢ№)ҒAӮұӮкӮзӮр—LӮ·ӮйӮЖӮўӮӨӮМӮЕӮ ӮйҒBҠCҢRӮМүьҠvӮрӮИӮ·ӮЙ“–ӮҪӮиҒA”ЮӮНҲкҗШӮМҺ„ҸоӮр”rӮөҒAӮ»ӮкӮр’fҚsӮөӮҪӮ©ӮзӮҫҒBүьҠvӮНӮўӮВӮМҗўӮЕӮа’ЙӮЭӮӘ”әӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB“–‘RҒAҠф‘ҪӮМ’пҚRҗЁ—НӮӘҺR–{ӮМ‘OӮЙ—§ӮҝӮУӮіӮӘӮйҒBӮөӮ©Ӯө”ЮӮНҲкҗШ‘ГӢҰӮрӢ–ӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗҙҚ‘(’ҶҚ‘)ҒAғҚғVғAӮЙҸҹӮДӮйҠCҢRӮрҚмӮйӮЖӮўӮӨҺҠҸг–Ъ“IӮӘӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB ҒЎҗјӢҪ—Іҗ·ӮЙҗSҗҢ ҺR–{Ң •әүqӮӘҗ¶ӮЬӮкӮҪӮМӮН1852”N10ҢҺ15“ъҒAҺF–Җ”Л(ҺӯҺҷ“Ү)ӮМүБҺЎү®’¬ӮЕӮ ӮйҒBҺF–ҖҸoҗgӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮМҺТӮӘӮ»ӮӨӮЕӮ ӮйӮжӮӨӮЙҒAҺR–{ӮаҗјӢҪ—Іҗ·Ӯр‘ёҢhӮөҒA”ЮӮЙҗSҗҢӮөӮДӮўӮҪҒB ҺR–{ӮН—cӮўҚ Ӯ©ӮзҒAӢCҗ«ӮӘҢғӮөӮӯҒAҢ–үЬӮӘ‘ҒӮўӮұӮЖӮЕ—L–јӮҫӮБӮҪҒBҢ–үЬӮөӮДӮўӮйҺqӢҹӮҪӮҝӮМӮЖӮұӮлӮЙ”ЮӮӘҢ»ӮкӮйӮЖҒAҒuҢ •әүqӮӘ—ҲӮҪҒIҒvӮЖҢҫӮБӮДҠFҲк–ЪҺUӮЙ“ҰӮ°ӮҪӮЖӮўӮӨҒBҺqӢҹӮҪӮҝӮ©ӮзӢ°ӮкӮзӮкӮ鑶ҚЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮөӮҪҚrӮБӮЫӮў’jӮӘҒAҗјӢҪӮЙҗSҗҢӮө”ЮӮ©Ӯз“ҝӮрҠwӮФӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB‘е’_–і”дӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзӮаҺv—¶–И–§ҒAӮ»ӮМҸгҲӨҸо–LӮ©ӮИҗlҠiӮМҺқӮҝҺеӮЙӮИӮБӮДӮўӮӯӮМӮЕӮ ӮйҒB –ҫҺЎӮМҗVҗӯ•{ӮӘӮЕӮ«ӮҪ’јҢгҒA16ҚОӮМҺR–{ӮНҗјӢҪӮМҺ©‘оӮр–KӮЛӮДҒAҺ©•ӘӮМҗiҳHӮЙӮВӮўӮД‘Ҡ’kӮөӮҪҒBҗјӢҪӮМүс“ҡӮНҒAҒuҠCҢRӮЙҚsӮӯӮМӮӘӮўӮўҒvҒBҺR–{ӮМҠCҢRҚsӮ«ӮӘҢҲ’иӮөӮҪҸuҠФӮЕӮ ӮйҒBҒuӮ ӮиӮӘӮЖӮӨӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒvӮЖ—зӮрҸqӮЧӮҪҺR–{ӮЙҒAҗјӢҪӮНҸҹҠCҸMӮЦӮМҸРүоҸуӮрҸ‘ӮўӮДӮӯӮкӮҪҒBҸҹӮН“ҝҗм–Ӣ•{ӮМ–ӢҗbӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҗVҗӯ•{ӮМҗ¬—§ӮЙҚvҢЈӮөӮҪҗl•ЁӮЕӮ ӮиҒAҠCҢR•тҚs(ҠCҢR‘еҗb)ӮрҢoҢұӮөӮДӮўӮҪҒBҠCҢRӮЙҗё’КӮөӮДӮўӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB җјӢҪӮМҸРүоҸуӮрҢgӮҰӮДҒA“ҢӢһӮМҸҹҠCҸM‘оӮр–K–вӮөӮДҸҹӮЙүпӮБӮДӮЭӮйӮЖҒA—\‘zҠOӮМ•Ф“ҡӮӘ•ФӮБӮДӮ«ӮҪҒBҒuҠCҢRӮНӮвӮЯӮҪӮЩӮӨӮӘӮўӮўҒBҠCҢRӮМҸCӢЖӮИӮсӮД•А‘е’пӮМӮаӮМӮ¶ӮбӮИӮўҒvҒBҸҹӮЙ”Ҫ‘ОӮіӮкҒAӮ»ӮМ“ъӮНӮўӮБӮҪӮсҲшӮ«—gӮ°ӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҠCҢRҚsӮ«ӮНҗјӢҪӮЖӮМ–с‘©ӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮӨҠИ’PӮЙ’ъӮЯӮзӮкӮйӮаӮМӮЕӮНӮИӮўҒBҸҹ‘оӮЦӮМ“ъҺQӮӘҺnӮЬӮБӮҪҒBӮжӮӨӮвӮӯҸҹӮӘҗЬӮкҒAҸҹ‘оӮЙӢҸҢуӮрӢ–ӮіӮкӮҪҺR–{ӮНҒA“ҢӢһҠJҗ¬ҸҠ(“ҢӢһ‘еҠwӮМ‘Oҗg)ӮЕҠCҢRӮМҠо‘bҠwӮЖӮаӮўӮӨӮЧӮ«ҚӮ“ҷ•Ғ’КҠw(җ”ҠwҒAҠOҚ‘ҢкҒAҚ‘ҢкҒAҠҝ•¶ҒA—рҺjҒA•Ё—қҒAү»ҠwҒA’n—қӮИӮЗ)ӮрҠwӮФӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҒЎғhғCғcҠCҢRӮМғӮғ“ғcҠН’· ҺR–{Ң •әүqӮӘҗSӮ©Ӯз‘ёҢhӮөӮДӮўӮҪҗl•ЁӮНҒAҗјӢҪ—Іҗ·ӮМ‘јӮаӮӨҲкҗlӮўӮҪҒBғhғCғcҗlӮМғOғүғtҒEғӮғ“ғcӮЕӮ ӮйҒBӮұӮсӮИӮұӮЖӮрҸqӮЧӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒBҒu“ъ–{җlӮЕӮНҗјӢҪ“мҸF(—Іҗ·)ҒAҠOҚ‘җlӮЕӮНғOғүғtҒEғӮғ“ғcҒAӮұӮкӮӘҗўҠEҚLӮөӮЖӮўӮҰӮЗӮа‘еҗl•ЁӮҫҒvҒB ӮұӮМғOғүғtҒEғӮғ“ғcӮНғhғCғcҠCҢRӮМ—ыҸKҠНҒuғ”ғBғlғ^ҒvӮМҠН’·ӮЕӮ ӮйҒBҺR–{ӮН24ҚОӮМӮЖӮ«ҒA‘јӮМҠCҢRҸӯҲС•в7–јӮЖӢӨӮЙҒAӮұӮМ—ыҸKҠНӮЦӮМҸжӮи‘gӮЭӮр–ҪӮ¶ӮзӮкҒA10ғ–ҢҺӮЙӢyӮФҗўҠE”јҺьӮМҚqҠCӮЙҸoӮҪҒBӮұӮМҠФҒAҺR–{ӮНғOғүғtҒEғӮғ“ғcӮ©Ӯз‘ҪӮӯӮрҠwӮсӮҫҒB‘DӮМ‘ҖҸcӮвҢRҺ–ӢZҸpӮНӮаӮҝӮлӮсӮМӮұӮЖҒAҗӯҺЎҒAҢoҚПҒA–@—ҘҒA“NҠwӮИӮЗ‘ҪҠтӮЙӮнӮҪӮйҒBӮ»ӮкӮОӮ©ӮиӮЕӮНӮИӮўҒBғӮғ“ғcӮНҒA•һ‘•ҒAҗ¶ҠҲ‘Ф“xҒA—зӢVҒAҺп–ЎӮИӮЗӮаҒAҺңҲӨӮЙ–һӮҝӮҪ‘Ф“xӮЕҗҪҺАӮЙӮ«ӮЯҚЧӮ©ӮӯӢіӮҰӮҪҒB ғӮғ“ғcӮНғhғCғcӮМӢM‘°ҸoҗgӮЕҒAҚӮӮўӢі—{ӮЖҚӮҢүӮИҗlҠiӮМҺқӮҝҺеӮҫӮБӮҪҒBү·ҸоҲмӮкӮйҗl•ҝҒAӮ»ӮМ’ҶӮЙ“SҚңӮМӮжӮӨӮИҚҮ—қҗ«ӮӘ–өҸӮӮИӮӯҠСӮ©ӮкӮДӮўӮҪҒBҒuҺ„ӮМҚЎ“ъӮ ӮйӮМӮНҒAӮЬӮБӮҪӮӯғӮғ“ғcҠН’·ӮМҠҙү»ӮЙӮжӮйҒvӮЖҺR–{ӮӘҢкӮБӮДӮўӮйӮЩӮЗӮЙүeӢҝӮрҺуӮҜӮҪҒBҢRҗlӮЖӮөӮДҒAҗlҠФӮЖӮөӮДҒAӮЬӮҪғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЖӮөӮДҒAҺR–{ӮНғӮғ“ғcӮрғӮғfғӢӮЖӮ·ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ҒЎҚИғgғLӮЖӮМҸoүпӮў ғӮғ“ғcӮ©ӮзҠwӮсӮҫӮұӮЖӮН‘јӮЙӮаӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮНҚИӮЙ‘ОӮ·ӮйҺpҗЁӮЕӮ ӮйҒBғhғCғcӮМ—ыҸK‘DҒuғ”ғBғlғ^ҒvӮЙҸжӮй’ј‘OҒAҺR–{ӮН17ҚОӮМҸӯҸ—ғgғLӮЖҸoүпӮБӮҪҒBҸкҸҠӮНҒAҠCҢRҺmҠҜҚҮҸhҸҠӮМҢьӮ©ӮўӮЙӮ ӮБӮҪҸ—ҳYү®ҒBҗVҠғӮМӢҷҺtӮМ–әӮЕҒAүЖӮӘ•nӮөӮӯӮДҒAҚЕӢЯ”„ӮзӮкӮД—ҲӮҪӮОӮ©ӮиӮЕӮ ӮйӮЖӮўӮӨҒBҺR–{ӮНғgғLӮМҗgӮМҸгӮр•·Ӯ«ҒAҗSӮ©ӮзӮўӮЖӮЁӮөӮӯҺvӮўҒAүҪӮЖӮөӮДӮЕӮаӮұӮМӢкӢ«Ӯ©Ӯз”ЮҸ—ӮрӢ~ӮўҒAҺ©•ӘӮМҚИӮЙӮөӮжӮӨӮЖҢҲҗSӮөӮҪҒB ҺR–{ӮН“Ҝ—»ӮМӢҰ—НӮр“ҫӮДҒAҸ—ҳYү®ӮМ“сҠKӮ©ӮзӮРӮ»Ӯ©ӮЙғgғLӮрҚjӮЕүәӮлӮөӮДҒA’mӮиҚҮӮўӮМүәҸhӮЙӮ©ӮӯӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBғgғLӮрҗ¶ҠUӮМ”ә—өӮЖҢҲӮЯӮҪҺR–{ӮНҒAӮ»ӮМҢгғhғCғcӮМҢRҠНҒuғ”ғBғlғ^ҒvӮЙҸжӮиҚһӮЭҒAҲк•ығgғLӮНҠCҢRҺmҠҜӮМҚИӮЖӮөӮДӮМ•K—vӮИҗS“ҫӮрҠwӮСӮИӮӘӮзҒA”ЮӮМӢAҚ‘Ӯр‘ТӮВӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒB ҢӢҚҘӮөӮДӮөӮОӮзӮӯӮөӮДҒAҚИӮӘҺR–{ӮМҸжӮйҢRҠНӮрҢ©ҠwӮЙ—ҲӮҪӮЖӮ«ӮМӮұӮЖҒB’ҶҲСӮЕӮ ӮБӮҪҺR–{ӮНҺ©•ӘӮЕҠН“аӮрҲД“аӮөӮҪҒBӮ»ӮМӢAӮиҒBҢRҠНӮ©Ӯзғ{Ғ[ғgӮЙҸжӮиҒAӮ»ӮМғ{Ғ[ғgӮ©ӮзҺVӢҙӮЙҲЪӮлӮӨӮЖӮ·ӮйӮЖӮ«ҒAҺR–{ӮНҚИӮМ—ҡӮ«•ЁӮрҺқӮБӮДҗжӮЙҺVӢҙӮЙ“nӮиҒAҚИӮМ‘OӮЙӮ»ӮкӮрӮ»ӮлӮҰӮД’uӮўӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮұӮкӮрҢ©ӮДӮўӮҪ‘јӮМҸ«•әӮҪӮҝӮНҒAҺR–{Ӯр—вҸОӮөӮҪҒB“–ҺһӮМ“ъ–{ӮЕӮұӮсӮИӮұӮЖӮрӮ·ӮйҺТӮНӮЩӮЖӮсӮЗӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBҚИӮрҢRҠНӮЙҲД“аӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҒAӮЬӮёӮ Ӯи“ҫӮИӮўҒBӮЬӮөӮДҚИӮМ—ҡӮ«•ЁӮр•vӮӘӮ»ӮлӮҰӮД’uӮӯӮИӮЗҒA’jӮЖӮөӮД’pӮёӮЧӮ«ҚsҲЧӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҺR–{ӮНҲУӮЙүоӮіӮИӮ©ӮБӮҪҒBҒuҢhҚИ(ҚИӮрҢhӮӨӮұӮЖ)ӮНҲкүЖӮЙ’ҒҸҳӮЖ•ҪҳaӮрӮаӮҪӮзӮ·ҒvӮЖҢҫӮБӮДӮНӮОӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮкӮағӮғ“ғcҠН’·Ӯ©ӮзҠwӮсӮҫҗј—mӮМ”ь•—ӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒB ҒЎ‘еүьҠvӮМ’fҚs ҺR–{Ң •әүqӮӘҢгӮЙҒuҠCҢRӮМ•ғҒvӮЖҢДӮОӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮй–{Ҡi“IӮИҺdҺ–ӮрҺnӮЯӮҪӮМӮНҒA38ҚОӮЕҠCҢR‘еҗbҠҜ–[ҺеҺ–(ҢгӮМҠCҢRҸИҺеҺ–)ӮЙ”І“FӮіӮкӮДӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB“–ҺһӮМҠCҢR‘еҗbӮНҗјӢҪҸ]“№ҒAҗјӢҪ—Іҗ·ӮМ’нӮЕӮ ӮйҒB үў•ДӮЙ”дҢЁӮөӮӨӮйҗёӢӯӮИӢЯ‘гҠCҢRӮрҚмӮзӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒB6”N‘OӮМ1887”N10ҢҺӮ©Ӯз”ЮӮН1”NҠФүў•ДӮЙ“nӮиҒAҠeҚ‘ӮМҠCҢRҗ§“xӮрҺӢҺ@ӮөӮДҲИ—ҲҒA“БӮЙӮ»ӮМҠҙӮрӢӯӮӯҺқӮВӮЙҺҠӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙӮНҒAҠCҢRҸ”җ§“xӮМүьҠvӮЖ•s—vӮИҗlҲхҗ®—қӮН•sүВ”рӮЕӮ ӮйӮЖҚlӮҰӮҪҒB үьҠvҲДӮр—ыӮиҸгӮ°ҒAҠCҢR‘еҗbӮМҗјӢҪӮЙ’сҸoӮөӮҪӮЖӮ«ҒA•ЁҺ–ӮЙ“®Ӯ¶ӮИӮўҗјӢҪӮа“xҠМӮр”ІӮ©ӮкӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҸ«ҠҜ(ӢЗ’·ҒA•”’·Ӣү)8–јҒAҚІҠҜ(үЫ’·ҒAүЫ’·•вҚІӢү)ӮЖҲСҠҜ(ҢW’·ҒAҺе”CӢү)89–јҒAҚҮҢv97–јӮМҺmҠҜӮрғNғrӮЙӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ“а—eӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗјӢҪӮӘӢБӮўӮҪӮМӮНҒAӮ»ӮкӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮ»ӮМ’ҶӮЙҺF–ҖҸoҗgҺТӮа‘еҗЁ–јӮрҳAӮЛӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB ҒuӮұӮсӮИӮЙҗ®—қӮөӮҪӮзҒA—LҺ–ӮМҚЫӮЙҒAҺxҸбӮНӮИӮўӮ©ҒvӮЖҗјӢҪҒBҺR–{ӮНҒAҒuҗVӢіҲзӮрҺуӮҜӮҪҺmҠҜӮӘ‘қӮҰӮДӮЁӮиӮЬӮ·ҒBҗS”zӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҗн‘ҲӮЙӮИӮБӮҪӮзҒAҗ®—қӮөӮҪ—\”х–рӮМҗlӮрҸўҸWӮ·ӮкӮОҸ\•ӘӮЕӮ·ҒvӮЖүһӮҰӮҪҒBҗјӢҪӮНҺR–{ҲДӮЕӮўӮӯ• ӮрҢҲӮЯӮҪҒB ҺR–{ӮМҗlҲхҗ®—қҲДӮЙӮНҒA–ҫҠmӮИ•ыҗjӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮҪӮЖӮҰ“ҜӢҪҸoҗgӮМҗж”yӮЕӮаҒA–ҫҺЎҲЫҗV“–ҺһӮ©ӮзӮМҢMҢчӮрҗПӮсӮЕӮўӮДӮаҒAҢ»ҚЭҸ«ҠҜӢүӮМ’nҲКӮЙӮ ӮБӮДӮаҒAӮ ӮйӮўӮНҺ©•ӘӮЖҗeҢрӮӘӮ ӮБӮДӮаҒAҠCҢRӮМҸ«—ҲӮМҢvүжӮЙ‘ОӮөӮДҒA“‘‘ҝӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮЖ”FӮЯӮйҺТӮН“‘‘ҝӮ·ӮйҒBӮЬӮҪҒAҺ©•ӘӮЙ‘ОӮөӮДҒAӮҪӮЖӮҰҲ«ҢыӮрҢҫӮӨҺТӮЕӮаҒAҸ«—ҲҚ‘үЖӮЙӮЖӮБӮД—L—pӮИҗlҚЮӮЖ”FӮЯӮйҺТӮНҺcӮ·ҒB ҺR–{ӮНӮұӮМ•ыҗjӮрҢөҠiӮЙҺзӮи”ІӮўӮДҒAҲкҗШӮМҲЩӢcҗ\Ӯө—§ӮДӮр”FӮЯӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮӨҒBҺ„ҸоӮрҺEӮөҒAҸ«—Ҳ—\‘zӮіӮкӮйҗҙҚ‘ҒAғҚғVғAӮЖӮМҗнӮўӮЙҸҹӮДӮйҠCҢRӮрҚмӮйӮұӮЖӮрҺҠҸг–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB ҒЎ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮрҺi—Я’·ҠҜӮЙ‘IӮФ 1898”NҒAҺR–{ӮН‘ж“сҺҹҺRҢ§—L•ь“аҠtӮМҠCҢR‘еҗbӮЙҸA”CӮөӮҪҒB‘ОғҚғVғAҗнӮр‘z’иӮөӮҪҠCҢRҚмӮиӮЙз…ҳrӮрӮУӮйӮӨ’ҶӮЕҒAҚЕӮа‘еӮ«ӮИҢҲ’fӮНҸн”хҠН‘а(ҢгӮМҳAҚҮҠН‘а)ӮМҺi—Я’·ҠҜӮЖӮөӮД“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮр‘IӮсӮҫӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҢгӮЙӮұӮМҗlҺ–ӮНҒA—ӨҢRӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮМҺQ–dҺҹ’·ҸA”CӮЖ•АӮФ“с‘еҢҶҚмӮЖҸМӮіӮкӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҺR–{ӮЙӮЖӮБӮДӮұӮкӮНҗhӮўӢкҸaӮМҢҲ’fӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢ»’·ҠҜӮЕӮ Ӯй“ъҚӮ‘s”VҸеӮрүр”CӮ·ӮйӮұӮЖӮрҲУ–ЎӮөӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒB“ъҚӮӮНҺR–{ӮМ’|”nӮМ—FӮЕӮ ӮиҒAҠCҢR•әҠw—ҫӮЙҲкҸҸӮЙ“ьӮиҒAҗe—FӮЖҢҫӮБӮДӮаӮўӮўҠФ•ҝӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒBҺR–{ӮНҒAӮұӮұӮЕӮаҺ„ҸоӮрҺМӮДӮҪҒB “ъҚӮӮН—L”\ӮИҠCҢRҺmҠҜӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮН”FӮЯӮДӮўӮҪӮӘҒAҺ©•ӘӮМҚЛӢCӮЙ“MӮкҒA“Ж’fҗкҚsӮМҢXҢьӮӘҢ©ҺуӮҜӮзӮкӮҪҒB‘ОғҚғVғAҗнӮНҒAҚ‘ү^Ӯр“qӮҜӮҪҗн‘ҲӮЙӮИӮйҒBӮ»ӮМҺi—Я’·ҠҜӮНҸгӮМ•ыҗjӮЙ”ҪӮ·ӮйҺТӮЕӮ ӮБӮДӮНӮИӮзӮИӮўҒBӮ»ӮМ“_ҒA“ҢӢҪӮЙӮН•sҲАӮНӮИӮўҒBӮ»ӮМҸгҒAҚҮ—қ“IӮ©ӮВ—вҗГ’ҫ’…ӮИ”»’fӮЖҚs“®ҒAӮ»ӮкӮЙӮ«ӮнӮЯӮДӢӯү^ӮЕӮ ӮйҒBҺR–{ӮН“ҢӢҪӮұӮ»Һi—Я’·ҠҜӮЙ‘ҠүһӮөӮўӮЖ”»’fӮөӮҪҒB ҺR–{Ӯ©Ӯзүр”CӮр’КҚҗӮіӮкӮҪ“ъҚӮӮНҒAҚҳӮМ’ZҢ•Ӯр”ІӮўӮДҒAҒuҢ •әүqҒAүҪӮаҢҫӮнӮсҒBӮұӮкӮЕүҙӮрҺhӮөҺEӮөӮДӮӯӮкҒvӮЖҢҫӮБӮҪҒB’|”nӮМ—FӮ©ӮзӮМ’КҚҗӮЙҒAҢЦӮиҚӮӮ«ҢRҗlҒA“ъҚӮӮМ“{ӮиӮЖҺё–]ӮНҺ@ӮөӮДӮ ӮЬӮиӮ ӮйӮаӮМӮЕӮ ӮйҒBҺR–{ӮН“ъҚӮӮМҗSӮӘ’ЙӮўӮЩӮЗӮнӮ©ӮБӮҪҒB”ЮӮН“ъҚӮӮМҗ«ҠiӮӘҚ‘үЖӮМ‘еҺ–ӮЙҚЫӮөӮДҒA•sҢьӮ«ӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒA“ҢӢҪӮр‘IӮОӮҙӮйӮр“ҫӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮржxҒXӮЖҗаӮўӮД•·Ӯ©Ӯ№ӮҪҒBӮ»ӮөӮДҚЕҢгӮЙҢҫӮБӮҪҒBҒu“сҗlӮН’|”nӮМ—FӮҫӮөҒAҸӯӮөӮа•ПӮнӮзӮК—FҸоӮрҚЎӮЕӮа•шӮўӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҚ‘үЖӮМ‘еҺ–ӮМ‘OӮЙӮНҒAҺ„ҸоӮНҗШӮиҺМӮДӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўӮМӮҫҒvҒB “ъҚӮӮаҲӨҚ‘ҺТӮЕӮ ӮБӮҪҒB–ЪӮЙ—ЬӮр•ӮӮ©ӮЧӮДҒAӮӨӮИӮёӮўӮҪҒBҒuҢ •әүqҒAӮжӮӯӮнӮ©ӮБӮҪҒBӮжӮӯҢҫӮБӮДӮӯӮкӮҪҒvҒBҺR–{ӮаӢғӮўӮҪҒBӮ»ӮөӮД“ъҚӮӮМҺиӮр—јҺиӮЕҢЕӮӯҲ¬ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBүp—YҒA“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМ’aҗ¶ӮМ”wҢгӮЙӮНӮұӮӨӮөӮҪғhғүғ}ӮӘӮ ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB 1933”N12ҢҺ8“ъҒAҺR–{Ң •әүqӮН81ҚОӮМ‘еүқҗ¶ӮрҗӢӮ°ӮҪҒBӮ»ӮМ”NӮМ3ҢҺ30“ъӮЙӮНҒA73ҚОӮЙӮИӮйҚИ“oҠмҺq(ғgғLӮрүь–ј)ӮрҺёӮБӮДӮўӮҪҒB“oҠмҺqӮМҚЕҠъӮМӮЖӮ«ҒAҺR–{Ӯа•aҸ°ӮЙүзӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAҚИӮМӮўӮй2ҠKӮЙү^ӮсӮЕӮаӮзӮўҒAҚИӮМҺиӮрҲ¬ӮБӮДҢҫ—tӮрӮ©ӮҜӮҪҒBҒuӮЁҢЭӮўӢкҳJӮөӮДӮ«ӮҪӮӘҒAӮұӮкӮЬӮЕүҪҲкӮВӢИӮӘӮБӮҪӮұӮЖӮрӮөӮҪҠoӮҰӮНӮИӮўҒBҲАҗSӮөӮДҚsӮБӮДӮӯӮкҒBӮўӮёӮкү“Ӯ©ӮзӮёҒAҢгӮр’ЗӮБӮДӮўӮӯӮ©ӮзҒvҒB“oҠмҺqӮН–ЪӮ©Ӯзғ|ғҚғ|ғҚӮЖ—ЬӮрӮИӮӘӮөӮД•vӮМҺиӮрҲ¬Ӯи•ФӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМ“ъҒA“oҠмҺqӮН•vӮМҲӨӮрӢ№ӮЙ•шӮ«ӮИӮӘӮзҒAӮ ӮМҗўӮЙ—·—§ӮБӮҪҒBҺR–{ӮӘ‘јҠEӮөӮҪӮМӮНҒAӮ»ӮМ”NӮМ•йӮкӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҺR–{Ң •әүqӮМҗ¶ҠUӮНҒAҠCҢRӮМ‘еүьҠvӮр’fҚsӮөӮДҒA“ъ–{ӮрҠлӢ@Ӯ©ӮзӢ~ӮБӮҪӮұӮЖӮЕҸМӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAӮ»ӮкӮЖӢӨӮЙҚИӮрҠлӢ@Ӯ©ӮзӢ~ӮўҸoӮөҒAҗ¶ҠUҲӨӮө‘ұӮҜӮҪӮ»ӮМҗlҗ¶ӮрӮаӮБӮДҒAӮ»ӮМҲМ‘еӮіӮрҢгҗўӮЙҺcӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYҒ@ | |
|
“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮНҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙӮД‘мүzӮөӮҪғҠҒ[ғ_Ғ[ғVғbғvӮр”ӯҠцӮөҒA“ъ–{ӮрҸҹ—ҳӮЙ“ұӮўӮҪҒB“ъ–{ӮМҠлӢ@ӮрӢ~ӮБӮҪӮұӮМ•sҗўҸoӮМүp—YӮНҒAҢRҗlӮЙӮИӮйӮВӮаӮиӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB”ЮӮМҗlҗ¶Ӯр•ПӮҰӮҪӮМӮНҒA7”NҠФӮМғCғMғҠғX—ҜҠwӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМ—ҜҠwӮНҒAҠCӮМ’jҒE“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮрҚмӮиҸгӮ°ӮҪҒB
ҒЎҗн‘ҲӮрҢҷӮБӮҪҢRҗl “ъҳIҗн‘ҲӮМ—ӨҗнӮМүp—YӮӘҒA”T–ШҠу“TҒAҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЕӮ ӮйӮЖӮ·ӮкӮОҒAҠCҗнӮМүp—YӮН“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЕӮ ӮйҒB‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗнҲИ‘OӮМ“ъ–{ӮЙӮЁӮўӮДҒAҚЕӮа‘ёҢhӮіӮкӮҪҢRҗlӮМҲкҗlӮЕӮ ӮБӮҪҒB”T–ШӮЖ“Ҝ—lӮЙҢRҗ_ӮЖӮ ӮӘӮЯӮзӮкҒA“ҢӢҪҗ_ҺРӮЬӮЕ‘¶ҚЭӮ·ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAҗнҢгӢіҲзӮМҢ»ҸкӮЕ“ҢӢҪӮМ–јӮр•·ӮӯӮұӮЖӮӘӮЩӮЖӮсӮЗӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBҢRҗlӮрүp—YҺӢӮөҗ_Ҡiү»Ӯ·ӮйӮұӮЖӮНҒAҢRҚ‘ҺеӢ`ӮЙӮВӮИӮӘӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕғ^ғuҒ[ҺӢӮіӮкӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBҚЎӮв“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМ–јӮНҒA“ъ–{җlӮЙӮЁӮўӮД–YӮкӮзӮкӮВӮВӮ ӮйӮМӮЕӮ ӮйҒB ӮөӮ©ӮөҒA“ҢӢҪӮМҗёҗ_ӮЖӮ»ӮМҗ¶Ӯ«•ыӮНҒAҢRҚ‘ҺеӢ`ӮЖӮН’цү“ӮўӮЖӮұӮлӮЙӮ ӮйҒBӮ»ӮаӮ»Ӯа”ЮӮНҗн‘ҲӮӘҢҷӮўӮЕӮ ӮБӮҪҒB–Ӣ––ҒAҺF–Җ(ҺӯҺҷ“ҮҢ§)”ЛҺmӮЖӮөӮД‘ҪӮӯӮМҗн‘ҲӮЙҺQүБӮөҒAӮ»ӮМ”ЯҺSӮіӮрӮўӮвӮЖҢҫӮӨӮЩӮЗ–ЎӮнӮБӮҪҒBҺ©•ӘӮНҢRҗlҢьӮ«ӮМҗlҠФӮЕӮНӮИӮўҒA“S“№ӢZҺtӮЖӮөӮДҚ‘үЖӮЙ•тҺdӮөӮҪӮўҒBӮұӮкӮӘҺбӮўҚ ӮМ“ҢӢҪӮМ–ІӮЕӮ ӮБӮҪҒB “ҢӢҪӮНҗн‘ҲӮрҢҷҲ«ӮөӮҪҒBҺcҚ“–і”дӮИҗн‘ҲӮМҢ»ҺАӮр’mӮи”ІӮўӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫҒB•”үәӮӘҺҹҒXӮЖҺҖӮсӮЕӮўӮӯҒBӮ»ӮсӮИҗнҸкӮМҢ»ҺАӮЙ•Ҫ‘RӮЖӮөӮДӮўӮзӮкӮйғ^ғCғvӮМҗlҠФӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮөӮ©Ӯө”ЮӮНҸнӮЙҚ‘үЖӮЦӮМ’үҗЯҒAҲӨҚ‘җSӮЙҲмӮкӮйҗlҠФӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒBҚ‘үЖӮӘҗ¶Ӯ«ӮйӮ©ҺҖӮКӮ©ӮМҗЈҢЛҚЫӮЕӮМ—EӢCӮЖҢҲ’f—НӮНҚЎӮИӮЁҢкӮи“`ӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒBҺң”ЯӮМ’ҶӮЙ—EӢCӮӘӮ ӮиҒA—вҗГ’ҫ’…ӮЕӮ ӮиӮИӮЁ‘е’_ӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮН—қ‘z“IғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЖӮөӮД‘ёҢhӮіӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҒЎ” ҠЩҗн‘ҲӮЕҢ©ӮҪ•җҺmӮМҗS “ҢӢҪӮМҗВҸtҺһ‘гӮНҗн‘ҲӮМҳA‘ұӮЕӮ ӮБӮҪҒBҺӯҺҷ“ҮҳpӮЕӮМғCғMғҠғXӮЖӮМ–CҢӮҗнҒB–Ӣ•{•цүуҢгҒAҠҜҢRӮЖӮөӮД—ХӮсӮҫӢҢ–Ӣ•{җЁ—Н(үп’Г”ЛӮрӮНӮ¶ӮЯ“Ң–kҸ””Л)ӮЖӮМҗн‘ҲҒBӮ»ӮөӮДү|–{•җ—gҢRӮЖӮМҗнӮў(” ҠЩҗн‘Ҳ)ҒB –ӢҗbӮЕӮ ӮБӮҪү|–{•җ—gӮНҠН‘аӮр—ҰӮўӮДҒAүЪҲО’n(–kҠC“№)ӮМ” ҠЩ(”ҹҠЩ)ӮЙ—§ӮДӮұӮаӮиҒAӢӨҳaҚ‘ӮМҗЭ—§ӮрҗйҢҫӮөӮҪҒBҗӯ•{ӮНҒAү|–{ҢR’БҲіӮМӮҪӮЯӢ}зҜҒAҢRӮр”hҢӯӮ·ӮйӮұӮЖӮЙӮөӮҪҒB“ҢӢҪӮНҺO“ҷҺmҠҜӮЖӮөӮДҗӯ•{ҢRӮМҢRҠНҒuҸt“ъҒvӮЙҸжӮиҚһӮЮӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB–ҫҺЎ2(1869)”NҒA22ҚОӮМҺһӮЕӮ ӮйҒB ” ҠЩҚ`ӮЦӮМ‘ҚҚUҢӮӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮЖӮ«ӮМӮұӮЖҒB–Ў•ыӮМҢRҠНӮМҲкӮВӮЙ“GӮМ–C’eӮӘ–Ҫ’ҶӮөҒA‘е”ҡ”ӯӮрӢNӮұӮөӮҪҒB‘D‘МӮНҗ^ӮБ“сӮВӮЙҗЬӮкҒA“ҢӢҪӮМҸжӮйҒuҸt“ъҒvӮМ–ЪӮМ‘OӮЕҢӮ’ҫӮөӮҪҒBҠўвIӮЖү»ӮөӮҪҢRҠНӮМҺcҠ[ҒBҺи‘«ӮӘҲшӮ«—фӮ©ӮкӮҪҲв‘МҒBҸ•ӮҜӮрӢҒӮЯӮйүцүдҗlӮМҗвӢ©ҒBҠCӮНҸC—…ҸкӮЖү»ӮөӮДӮўӮҪҒB“ҢӢҪӮН–іүд–І’ҶӮЕүцүдҗlӮМӢ~Ҹ•ӮЙ“–ӮҪӮБӮҪҒB“GҠНӮрҢ©Ӯй—]—TӮНӮИӮўҒB ӮұӮӨӮөӮҪҸC—…ҸкӮМ’ҶӮЕ—BҲкӮМӢ~ӮўӮҫӮБӮҪӮМӮНҒAү|–{ҢRӮЙӮжӮБӮДҺҰӮіӮкӮҪ•җҺmӮМҚ°ӮЕӮ ӮБӮҪҒBү|–{ҢRӮМҢRҠНӮН’ҫ–v’n“_ӮЙҗЪӢЯӮөӮДӮўӮҪӮӘҒAҚUҢӮӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ҢӢҪӮҪӮҝӮМӢ~Ҹ•ҠҲ“®ӮӘ‘ұӮҜӮзӮкӮДӮўӮйҠФҒAӮ»ӮкӮрӮ¶ӮБӮЖҢ©ҺзӮБӮДӮӯӮкӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB“ҢӢҪӮН“GӮЕӮ Ӯйү|–{ҢRӮЙ•§ӮМҗSҒA•җҺmӮМҗSӮрҢ©ӮҪҒB ҒЎғCғMғҠғX—ҜҠw ҢRҗlӮЙӮИӮйӮВӮаӮиӮМӮИӮ©ӮБӮҪ“ҢӢҪӮӘҠCҢRӮЙ“ьӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪӮМӮНҒAҗјӢҪ—Іҗ·ӮМҗа“ҫӮЙӮжӮйҒBҗјӢҪӮН“ҜӢҪӮМҗж”yӮЕӮ ӮиҒA–ҫҺЎҲЫҗVӮМ—§–рҺТӮЕӮ ӮБӮҪҒB“S“№ӢZҺtӮЙӮИӮлӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪ“ҢӢҪӮНҒAҗјӢҪӮр–KӮЛӮДғCғMғҠғX—ҜҠwӮр‘Ҡ’kӮөӮҪҒBӮөӮ©ӮөҗјӢҪӮМ•ФҺ–ӮНҒAҒu“S“№ӢZҺtӮЕӮН“––КҒA—ҜҠwӮМҢvүжӮНӮИӮўҒvӮЖӮўӮӨӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒBҗјӢҪӮНҒA“ъ–{ӮӘӮұӮкӮ©ӮзҗўҠEӮЙҢЮӮөӮДҚsӮӯӮЙӮНҠCҢR—НӮӘ•sүВҢҮӮЕӮ ӮйӮұӮЖҒAӮіӮзӮЙӮұӮМҠCҢRӮЙ“ҢӢҪӮӘ•K—vӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮр’fҢЕӮҪӮйҢы’ІӮЕҗа“ҫӮөӮҪҒB “ҢӢҪӮМҗSӮН—hӮкӮҪҒBғCғMғҠғXӮЙ—ҜҠwӮөӮҪӮўҒBӮөӮ©ӮөҒA“S“№ӢZҺtӮЙӮұӮҫӮнӮБӮДӮўӮДӮНҒAӮ»ӮМғ`ғғғ“ғXӮрҲнӮ·ӮйҒB“ҢӢҪӮНҺvӮў”YӮсӮҫ––ҒA‘ёҢhӮ·ӮйӢҪ—ўӮМҗж”yҒAҗјӢҪӮЙҗlҗ¶Ӯр—aӮҜӮжӮӨӮЖҺvӮБӮҪҒBӮ»ӮөӮДӮұӮМҺһӮЙҠCҢRӮрҗ¶ҠUӮМҺdҺ–ӮЖӮ·ӮйҢҲ’fӮрӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB –ҫҺЎ4(1871)”N3ҢҺҒA“ҢӢҪӮНүЎ•lҚ`ӮрҸo”ӯӮөҒAғCғMғҠғXӮЙҢьӮ©ӮБӮҪҒB23ҚОӮМҺһӮЕӮ ӮйҒB“–ҸүғJғҢғbғWӮЙӮДҒAүpҢкӮрҺnӮЯҒAҗ”ҠwҒA—қүИӮИӮЗӮМҠо‘b’mҺҜӮрҠwӮСҒA2”NҢгҒA“ьҠwӮрӢ–ӮіӮкӮҪҠwҚZӮНҒAҒuғEҒ[ғXғ^Ғ[ҒvӮЖӮўӮӨҸӨ‘DҠwҚZӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮұӮНҚZҺЙӮаҸhҺЙӮаӮИӮӯҒAҒuғEҒ[ғXғ^Ғ[ҒvӮЖӮўӮӨ–јӮМ—ыҸK‘DӮӘӮ ӮйӮҫӮҜҒBҠwҗ¶ӮНӮұӮМ‘DӮЕҺцӢЖӮрҺуӮҜҒAҗQ”‘ӮЬӮиӮ·ӮйҒB‘DӮӘҚZҺЙӮЕӮ ӮиҒAҸhҺЙӮЕӮ ӮБӮҪҒBҸнӮЙҺА‘HӮр”әӮӨ‘DҸгӮЕӮМҺцӢЖӮНҺАӮЙҢөӮөӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA2”NҢг—DҸGӮИҗ¬җСӮЕҒuғEҒ[ғXғ^Ғ[ҒvӮр‘ІӢЖӮөӮҪҒBӢіҠҜӮвҠwҗ¶’ҮҠФӮ©ӮзӮМ“ҢӢҪӮМ•]үҝӮНҒAҒuҠwҸp—DҸGҒA•iҚs•ыҗіҒA—зӢVҗіӮөӮўҒvӮЖӮўӮӨ”сҸнӮЙҚӮӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB ‘ІӢЖҢгҒAҚP—бӮЙҸ]ӮБӮД“ҢӢҪӮН”ҝ‘DҒuғnғ“ғvғVғғҒ[ҒvӮЙҸжӮиҚһӮсӮЕҗўҠEҲкҺьӮМү“—mҚqҠCӮМ“rӮЙӮВӮўӮҪҒBҠwӮсӮҫ’mҺҜӮрҺАҚЫӮМҸкӮЕҺҺӮ·ӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒB7ғ–ҢҺӮЙӢyӮФҚqҠCӮЕҒA“ҢӢҪӮНӮ·ӮБӮ©ӮиҠCӮМ’jӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBғ}ғXғgӮЙ“oӮкӮОҒA•—ӮМӢӯӮіӮЖ•ыҢьӮр‘ҰҚАӮЙ”»’fӮөҒA“VҢуӮв”gӮМ•Пү»Ӯр—\‘ӘӮөӮҪҒB‘Җ‘DӮЙҠЦӮөӮДӮаҒAӮұӮұӮЬӮЕ’@Ӯ«ҚһӮЬӮкӮҪ’jӮНҒA“ъ–{ҠCҢRӮЙӮНӮўӮИӮўӮЖӮЬӮЕҢҫӮнӮкӮҪҒB ғCғMғҠғX—ҜҠwӮЕ“ҫӮҪӮаӮМӮНҒA’PӮЙҠCӮЖ‘DӮЙҠЦӮ·Ӯй’mҺҜӮвӢZҸpӮОӮ©ӮиӮЕӮНӮИӮўҒBғCғMғҠғXӮМ‘DҸжӮиӮЖҗ¶ҠҲӮрӢӨӮЙӮөӮДҒA”ЮӮзӮМғvғүғCғhӮрҠ_ҠФҢ©ӮйӮұӮЖӮаӮөӮОӮөӮОӮҫӮБӮҪҒB”ЮӮзӮНҲӨҚ‘җSӮЙҲмӮкҒAҚ‘үЖӮЙ’үҗҪӮрҗsӮӯӮ·җSҚ\ӮҰӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮҪҒBӮҪӮЖӮҰҸӨ‘DӮЖӮўӮҰӮЗӮаҒAӮРӮЖӮҪӮСҗн‘ҲӮЖӮИӮкӮОҗнҸкӮЙ•ӢӮӯӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҲӨҚ‘җSӮӘ”ЮӮзӮМғvғүғCғhӮМҢ№ӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮҫҒB ҒЎҳAҚҮҠН‘аҺi—Я’·ҠҜӮЙ ғҚғVғAӮМӢәҲРӮӘҢ»ҺА“IӮИӮаӮМӮЖӮИӮиҒA“ъ–{ӮНҚ‘үЖ‘¶–SӮМҠлӢ@ӮЙӮ ӮйҒBӮұӮкӮН“–ҺһӮМғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЙӢӨ—LӮіӮкӮДӮўӮҪ”FҺҜӮЕӮ ӮБӮҪҒBғҚғVғAӮЖӮМҗн‘ҲӮр‘z’иӮөӮДҒAҠCҢR‘еҗbӮМҺR–{Ң •әүqӮНҒAҳAҚҮҠН‘аӮМҺi—Я’·ҠҜӮЖӮөӮД“ҢӢҪӮр–АӮўӮИӮӯ‘I‘рӮөӮҪҒB“ҜӮ¶ҺF–ҖӮМҸoҗgӮЕӮ ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮНӮИӮўҒBҺR–{ӮНҒA“ъ–{ҠCҢRӮМ—рҺjӮМ’ҶӮЕӮұӮкӮЩӮЗӢӯ—НӮИ‘еҗbӮНӮўӮИӮўӮЖӮЬӮЕҢҫӮнӮкӮҪҲнҚЮӮЕӮ ӮБӮҪҒB”NҢчҸҳ—сӮвҺF’·ӮМ”h”ҙҗlҺ–Ӯр”rҸңӮөҒA”\—НӮМӮ ӮйҗlҚЮӮр“o—pӮөӮҪӮұӮЖӮЕ’mӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮМ”ЮӮӘӮ ӮҰӮД“ҜӢҪӮМ“ҢӢҪӮр‘IӮсӮҫӮМӮНҒA“ҢӢҪӮМғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЖӮөӮДӮМҺ‘ҺҝӮр•]үҝӮөӮДӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮБӮҪҒB “ҢӢҪӮр‘IӮсӮҫҺR–{ӮМ”»’fӮНҠФҲбӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъҳIҗн‘ҲӮМҚЕ‘еӮМҺRҸкҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЖӮМ“ъ–{ҠCҢҲҗнӮЙӮЁӮўӮДҒAӮ»ӮкӮНҸШ–ҫӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB1904”N10ҢҺҒAғҚғVғAӮМғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНғtғBғ“ғүғ“ғhӮ©Ӯз“ъ–{ӮЙҢьӮ©ӮӨ1–ң8җзғLғҚӮМ‘еҚqҠCӮЙҸo”ӯҒBӮұӮкӮр“ҢӢҪӮМҳAҚҮҠН‘аӮН“ъ–{ҠCӮЕҢ}ӮҰҢӮӮБӮҪҒB—Ӯ”NӮМ5ҢҺ27“ъӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒB ӮұӮМҠCҗнӮНҒAҳAҚҮҠН‘аӮМҲі“|“IӮИҸҹ—ҳӮЕҢҲ’…ӮӘӮВӮўӮҪҒB“ҢӢҪҺ©җgӮМҢҫ—tӮЙӮжӮкӮОҒAҒuӮұӮМҠCҗнӮНҗ퓬ҠJҺn30•ӘӮЕҢҲӮЬӮБӮҪҒBӮнӮкӮЙ“Vү^Ӯ ӮиҒAҸҹ—ҳӮөӮҪӮМӮҫҒvҒBҗ”ҺҡӮрҢ©ӮкӮОҲк–Ъ—Д‘RӮЕӮ ӮйҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҺҖҺТ1–ң1җзҗl(“ъ–{‘Ө”ӯ•\)ӮЙ‘ОӮөҒAҳAҚҮҠН‘аӮМҺҖҺТӮН116–јӮЙӮ·Ӯ¬ӮИӮўҒB Ҹҹ—ҳӮМ—vҲцӮНүҪӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮ©ҒBҚӮ“xӮИҗн—ӘҗнҸpҒB”ј”NҲИҸгӮМ’·—·ӮЙӮжӮйғҚғVғA‘ӨӮМҗнҲУӮМ‘rҺёҒB–CҢӮӮМ–Ҫ’Ҷ—ҰӮМҚ·ӮИӮЗӮўӮлӮўӮлӮ Ӯ°ӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮөӮ©ӮөҒAүҪӮЖҢҫӮБӮДӮаҢҲ’и“IӮИҚ·ӮНҺmӢCӮМҚ·ӮЙӮ ӮБӮҪӮұӮЖӮНҠФҲбӮўӮИӮўҒB“ҢӢҪӮЙӮЖӮБӮДҒAӮұӮМҗнӮўӮН’PӮЙҺ©ҢИӮМ–ј—_ӮЙҠЦӮнӮй–в‘иӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒB“ъ–{ӮӘҸБ–ЕӮ·ӮйӮ©ӮЗӮӨӮ©ӮМҗнӮўӮЕӮ ӮиҒA–ҪӮр“ҠӮ°ҸoӮ·ҠoҢеӮӘӮЕӮ«ӮДӮўӮҪҒB “ъ–{ӮМ–Ҫү^Ӯр”w•үӮӨҺi—Я’·ҠҜ“ҢӢҪӮМӢЩ”—ҠҙӮНҒAӮұӮМҗнӮўӮЙ—ХӮЮ‘SӮДӮМҸ«•әӮЙ“`ӮнӮБӮДӮўӮҪҒBҒuӮұӮМҗн‘ҲӮНҚ‘үЖӮМҲА”ЫӮЙҠЦӮнӮйҢҲҗнӮЕӮ ӮиҒAҸ”ҢNӮЖӢӨӮЙ•ІҚңҚУҗgҒA“GӮрҢӮ‘ЮӮөӮД“VҚcӮМҢдҗSӮрҲАӮсӮ¶•тӮзӮсҒvҒBҢҲҗнӮЙҚЫӮөҒAҠН‘аӮМҸ«•әӮЙҢкӮБӮҪ“ҢӢҪӮМҢҫ—tӮЕӮ ӮйҒBҢөҸlӮЙӮөӮДҒAҢҲ‘RӮҪӮйӮұӮМҢҫ—tӮНҠН“аӮЙҷzӮЖӮөӮДӢҝӮ«“nӮиҒA—ЬӮр—¬Ӯ·ҺТӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBҚ‘үЖӮрҸБ–ЕӮМҠлӢ@Ӯ©ӮзҺзӮйӮҪӮЯҒAҸ«•әӮЖү^–ҪӮрӢӨӮЙӮөӮеӮӨӮЖӮўӮӨҠoҢеӮӘ“`ӮнӮБӮҪҒB җ퓬ӮМҠФҒA“ҢӢҪӮН“GӮМ–C’eӮӘ—җӮк”тӮСҒAҗҒӮ«ӮіӮзӮөӮМҠНӢҙӮЙ—§Ӯҝ‘ұӮҜӮҪҒBӮўӮӯӮз•”үәӮӘӮ·Ӯ·ӮЯӮДӮаҒA•ӘҢъӮўҚ|”ВӮЕҢЕӮЯӮзӮкӮҪҲА‘SӮИҺi—Я“ғӮЙ“ьӮлӮӨӮЖӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB–ҪӮМҠлҢҜӮЙ’јҗЪӮіӮзӮіӮкӮДӮўӮй•әҺmӮҪӮҝӮЖү^–ҪӮрӢӨӮЙӮөӮҪӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮўӮ©ӮЙ–C’eӮМүJӮӘҚ~ӮлӮӨӮӘҒAҠНӢҙӮ©ӮзӮНҗв‘ОӮЙ‘Ю”рӮөӮИӮўҒB“ҢӢҪӮНӮұӮӨҢҳӮӯҗҫӮБӮДӮўӮҪҒB‘SҢRӮМ•әҺmӮНҒA”gӮөӮФӮ«ӮрҺуӮҜӮИӮӘӮзҒAҠНӢҙӮЕүКҠёӮЙҺwҠцӮрҺ·Ӯй“ҢӢҪӮМҺpӮрҢ©ӮД•ұӮў—§ӮБӮҪҒBҚ‘үЖӮМӮҪӮЯӮЙ–ҪӮрҢңӮҜӮДҗнӮЁӮӨӮЖӮөӮДӮўӮйҺi—Я’·ҠҜӮМҺpӮрҢ©ӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB•әҺmӮН“ҢӢҪӮЖӢӨӮЙҗнӮӨӮұӮЖӮрҢЦӮиӮЙҺvӮўҒA”ЮӮЖӢӨӮЙҚ‘үЖӮМӮҪӮЯӮЙ–ҪӮр“ҠӮ°ҸoӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB “ҢӢҪӮМҲМ‘еӮіӮНҒAӮұӮМҠCҗнӮЙӮЁӮўӮДӮМӮЭҺҰӮіӮкӮҪӮнӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBҸн“ъҚ ӮМӢО–ұӮФӮиӮНҒAҠCҢR“аӮЕӮН’mӮзӮКҺТӮНӮўӮИӮ©ӮБӮҪҒBҠCҢRӮМҠІ•”ӮЙӮМӮЪӮиӮВӮЯӮДӮаҒA’NӮжӮиӮа‘ҒӮӯӢNӮ«ӮД‘f‘«ӮЕҚb”ВӮрҗфӮўҒA•ЦҸҠ‘|ҸңӮЬӮЕҚsӮБӮҪҒB–\•—үJӮМҺһӮИӮЗӮаҒAҺ©ӮзҗQӮёӮЙҢxүъӮЙ“–ӮҪӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB•”үәӮҫӮҜӮЙҗhӮўҺvӮўӮрӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB ҲкӮВӮМ‘DӮЙҸжӮйҠCӮМ’jӮНҒAү^–ҪӢӨ“Ҝ‘МӮЕӮ ӮйҒBӮРӮЖӮҪӮС‘DӮӘ’ҫ–vӮ·ӮкӮО•”үәӮаҸгҠҜӮаӮИӮӯҒAӮЭӮИҠCӮЙ“ҠӮ°ҸoӮіӮкӮйҒBҺҖӮКӮаҗ¶Ӯ«ӮйӮаҲкҸҸӮЕӮ ӮйҒBҳAҚҮҠН‘аӮНҒAҺi—Я’·ҠҜ“ҢӢҪӮр’ҶҗSӮЖӮөӮДҒAҲкҺ…—җӮкӮК‘gҗDӮЖӮИӮБӮДҗнӮБӮҪӮМӮҫҒB “ҢӢҪӮМӮаӮЖӮЕҒA•”үәӮНҺ©ӮзӮМ”\—НӮрҚЕ‘еҢА”ӯҠцӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB“ҢӢҪӮНҺ©ҢИӮрҢөӮөӮӯ—ҘӮөӮИӮӘӮзӮаҒA•”үәӮЦӮМҗҪҺАӮИ‘Ф“xҒAҺvӮўӮвӮиӮЙҲмӮкӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮҫҒB“ъ–{ҠCҠCҗнӮНҒA“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮЖӮўӮӨҲкҗlӮМҲМ‘еӮИғҠҒ[ғ_Ғ[Ӯр“ъ–{җlӮМҗSӮЙҚҸӮЭӮВӮҜӮҪҗн‘ҲӮЕӮаӮ ӮБӮҪҒB ҒЎҒuҸҹӮБӮДҠ•ӮМҸҸӮр’чӮЯӮжҒv “ҢӢһҳpӮЕҚsӮнӮкӮҪҳAҚҮҠН‘аӮМүрҺUҺ®ӮЕҒA“ҢӢҪӮНҒuҸҹӮБӮДҠ•ӮМҸҸӮр’чӮЯӮжҒvӮЖҢкӮБӮДҒAӮ»ӮМүүҗаӮр’чӮЯӮӯӮӯӮБӮҪҒBӮұӮМҢҫ—tӮМ’КӮиҒA“ҢӢҪӮЙӮНҸҹҺТӮМйҒӮиӮНӮЬӮйӮЕҢ©ӮзӮкӮИӮўҒBӮаӮЖӮаӮЖүЗ–ЩӮЕӮ ӮБӮҪ“ҢӢҪӮНҒAҗнҢгӮіӮзӮЙүЗ–ЩӮЙӮИӮБӮҪҒBҗV•·ӮИӮЗӮМҺжҚЮӮЙҲкҗШүһӮ¶ӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB”ЮӮНҢі—ҲӮӘҗн‘ҲӮрҢҷӮБӮҪҗlҠФӮЕӮ ӮйҒBӮҪӮЖӮҰ–hүqӮЖӮўӮӨҲУ–ЎӮӘӮ ӮлӮӨӮЖӮаҒAҗ¶җgӮМҗlҠФӮӘҺEӮөҚҮӮӨӮМӮӘҗн‘ҲӮЕӮ ӮйҒBҸҹ—ҳӮөӮҪӮ©ӮзӮЖӮўӮБӮДҒAҺ©–қӮ·ӮЧӮ«ӮаӮМӮЖӮНҺvӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒB ”У”NӮМ“ҢӢҪӮМҗ¶ҠҲӮНҒAҚ‘үЖӮМҠлӢ@ӮрӢ~ӮБӮҪүp—YӮЖӮНӮЁӮжӮ»Ӯ©ӮҜ—ЈӮкӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB“ҢӢҪ‘е–ҫҗ_ӮИӮЗӮЖҸМҺ^ӮіӮкӮйӮұӮЖӮрӢЙ’[ӮЙҢҷӮБӮҪҒBҗҙ•nӮИҗ¶ҠҲӮрҠСӮ«ҒAӮўӮВӮаҺьҲНӮЙҺvӮўӮвӮиӮрҠсӮ№ӮҪӮЖӮўӮӨҒBҸн“ъҚ ҒA”ЮӮӘҢкӮБӮДӮўӮҪҢҫ—tӮӘӮ ӮйҒBҒuҗlҠФӮЙҲк”Ф‘еҗШӮИӮМӮНҗ^–К–ЪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕӮ ӮйҒBҸӯӮөӮОӮ©ӮиӮМҚЛӢCӮИӮЗҒAүҪӮМ–рӮЙӮа—§ӮҪӮИӮўӮаӮМӮҫҒBӮҪӮЖӮҰӢр’јӮЖ”оӮзӮкӮДӮаҒAҢӢӢЗӮНҗ^–К–ЪӮИҺТӮӘҸҹ—ҳӮрӮЁӮіӮЯӮйӮМӮҫҒvҒB 1934”N5ҢҺ30“ъҒA87ҚОӮМ“ҢӢҪӮНүЖ‘°ӮЙҢ©ҺзӮзӮкӮИӮӘӮзҗГӮ©ӮЙ‘§ӮрҲшӮ«ҺжӮБӮҪҒBҚ‘үЖӮЙ’үҗЯӮрҗsӮӯӮөҒAҗ^–К–ЪӮЙӮ»ӮөӮДҗҪҺАӮЙҗ¶Ӯ«ӮҪӮ»ӮМҗ¶ҠUӮНҒAҚЎӮИӮЁӢPӮ«ӮрҺёӮБӮДӮўӮИӮўҒB Ғ@ |
|
| ҒЎ“ъ–{ҠCҠCҗнӮЖ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYҒ@ | Ғ@ |
|
”T–ШҠуҸ•—ҰӮўӮй‘жҺOҢRӮӘ—·ҸҮ—vҚЗӮЙ‘ОӮ·Ӯй‘ж2үс‘ҚҚUҢӮӮрҠJҺnӮ·Ӯй11“ъ‘OӮМҒA–ҫҺЎ37”N(1904)10ҢҺ15“ъӮЙғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНғҠғoғEҢRҚ`Ӯ©ӮзҸoҚqӮөӮДӮўӮйҒBғҚғVғAҠCҢRӮНҒAғoғӢғ`ғbғNҠCӮЙӮ ӮйҗёүsӮМҠН‘аӮрӢЙ“ҢӮЙ”hҢӯӮөӮДҒA—·ҸҮҚ`ӮЙӮ Ӯй‘ҫ•Ҫ—mҠН‘аӮЖӮЖӮаӮЙ“ъ–{ҠCҢRӮЖҗнӮҰӮОҒA“ъ–{ҠН‘аӮМӮЩӮЪ2”{ӮМҗн—НӮЖӮИӮйӮМӮЕҒAҸҹ—ҳӮөӮДҗ§ҠCҢ ӮрҠm•ЫӮЕӮ«ӮйӮЖӮМҚlӮҰӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAғoғӢғ`ғbғNҠCӮ©ӮзӢЙ“ҢӮЙҢьӮ©ӮӨҚqҠCӮН’nӢ…Ӯр”јҺьӮ·ӮйӮЩӮЗӮМӢ——ЈӮӘӮ ӮйүХҚ“ӮИӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB
Ӯ»ӮаӮ»ӮаҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҸoҚqӮөӮДҠФӮаӮИӮӯғgғүғuғӢӮрӢNӮұӮөӮДӮўӮйҒBҚ‘—§Қ‘үпҗ}Ҹ‘ҠЩӮМҒwӢЯ‘гғfғWғ^ғӢғүғCғuғүғҠҒ[ҒxӮЙҒAҚІ“ЎҺsҳYҺҒӮМҒwҠCҢRҢЬҸ\”NҺjҒxӮЖӮўӮӨ–{ӮӘҢцҠJӮіӮкӮДӮўӮйҒBӮ»ӮұӮЙӮНӮұӮӨҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒB ҒuҸo”ӯ‘OӮжӮиҒA“ъ–{ҢRӮН’ҡ–•(ғfғ“ғ}Ғ[ғN)ҠCӢ¬ӮЙӢ@—ӢӮр•~җЭӮөӮҪӮЖӮ©ҒA–kҠCӮЙӮН“ъ–{җ…—ӢҠН’шӮӘӮРӮ»ӮсӮЕӮўӮйӮЖӮ©ӮЖҒAӮўӮлӮўӮлү\ӮӘӮЖӮсӮЕӮўӮҪӮМӮЕҒA”Я‘sӮИҢҲҲУӮрӮаӮБӮД‘s“rӮЙӮНҸAӮўӮҪӮаӮМӮМҒAҗ…’№ӮМү№ӮЙӮаҠМӮрӮВӮФӮөҒA”–•XӮр“ҘӮЮҺvӮўӮЕӮ ӮБӮҪҒBүКӮҪӮөӮД–kҠCҚqҳHӮМҚЫӮЙӮНҒAүpҚ‘Ӣҷ‘DӮМ“•үОӮрҢ©ӮДҒAӮ·ӮНӮұӮ»“ъ–{җ…—Ӣ’ш‘аӮМҸPҢӮӮЖҒA–У(ӮЯӮӯӮз)–Е–@ӮЙ–CҢӮӮөӮДӢҷ‘DӮр’ҫӮЯӮҪҸгӮЙҒAҸ„—mҠНғAғEғҚғүӮН“ҜҺu“ўӮҝӮЙӮ ӮўҒAҗ…җьҸгӮЙҺl’eӮрӮӨӮҜӮйӮЖӮўӮӨ”ЯҠмҢҖӮрүүӮ¶ҒAүpҚ‘ӮМ•®ҢғӮЖҗўҠEӮМҡ}ҸОӮЖӮрҸөӮўӮҪҒBҒv —vӮ·ӮйӮЙғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҚ\җ¬ӮНҗўҠEҚЕӢӯӮрҢЦӮБӮДӮўӮҪӮӘҒAӢЙ“ҢӮЦӮМҸoҚqӮӘӢ}зҜҢҲ’иӮіӮкӮД”_–ҜӮзӮр’ҘҸWӮө5ғJҢҺ’ц“xӮМҸҖ”хҠъҠФӮӘӮ ӮБӮҪӮаӮМӮМҒA”ЮӮзӮМ‘ҪӮӯӮНҗ퓬ҲхӮЖӮөӮДҸ[•ӘӮЙҢP—ыӮіӮкӮҪғҢғxғӢӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB үpҚ‘ӮНҺ©Қ‘ӮМӢҷ‘DӮӘ–CҢӮӮіӮкӮҪӮұӮЖӮрӢӯӮӯҚRӢcӮөҒAҢгӮЙ”…ҸһӢаӮрҸҹӮҝҺжӮБӮҪӮҫӮҜӮЕӮНӮЖӮЗӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒBӢe’rҠ°ӮМҒw‘еҸO–ҫҺЎҺjҒxӮЙӮжӮйӮЖҒA ҒuүpҚ‘ӮНҒAӮЖӮЙӮ©ӮӯғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҠлҢҜӮҫӮЖӮўӮӨҢыҺАӮЕҒAҸ„—mҠН10җЗӮр”hӮөӮДҒAҠН‘аӮМҢгӮр’ЗӮБӮДҒAҠДҺӢӮМ–ЪӮрҢхӮзӮ№ӮДҒAғXғyғCғ“үҲҠЭӮЬӮЕ•№ҚqӮөӮҪҒBӮаӮҝӮлӮсҒA“ҜҠН‘аӮМ•Тҗ¬ӮЖҚs“®ӮНҒAҸЪҚЧӮЙүpҚ‘җӯ•{ӮЖҒA“Ҝ–ҝҚ‘“ъ–{җӯ•{ӮЙ‘Е“dӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮЕӮ ӮйҒBҒvӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒB ӮЬӮҪҒA“–ҺһӮМҠН‘DӮМ”R—ҝӮНҗО’YӮЕҒA”R—ҝҢш—ҰӮӘҲ«Ӯ©ӮБӮҪӮұӮЖӮ©ӮзҒAҚqҠCӮЙӮН‘е—КӮМҗО’Y•вӢӢӮрүҪ“xӮаүҪ“xӮаҢJӮи•ФӮіӮЛӮОӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮр’mӮй•K—vӮӘӮ ӮйҒBҗО’YҺ‘Ң№ҠJ”ӯҠ”Һ®үпҺРӮМ‘е’ОҸd”VҺҒӮМҒwҗО’YӮрӮдӮӯҒxӮЖӮўӮӨғTғCғgӮЙӮНҒA ҒuҠН‘аӮМҲк“ъӮМҗО’YҺg—p—КӮНҺOҗзғgғ“ҒAғtғӢғXғsҒ[ғhӮМҸкҚҮӮНҲк–ңғgғ“ӮЖӮўӮӨҗ”ҺҡӮӘӢLҳ^ӮіӮкӮДӮўӮйҒBҗО’Y’ҷ‘ ҢЙӮМ—e—КӮМҸ¬ӮіӮў‘DӮНҗ”“ъӮЁӮ«ӮЙ•в’YӮөӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮёҒAӮ»ӮМ“s“xҒA‘е‘D’cӮН’в‘ШӮрӮжӮ¬ӮИӮӯӮіӮкӮҪҒBҗО’YҗПҚһӮЭҚмӢЖӮНҗ…•әӮЙ‘е•ПӮИҳJ—Н•ү’SӮЙӮИӮБӮҪҒB‘DҠФӮЙ“nӮөӮҪ”ВӮМҸгӮрҗО’YвДӮр“V”үӮЕӮ©ӮВӮўӮЕү^ӮФҒBҚмӢЖӮМӮҪӮЯ”gӮМҸ¬ӮіӮў“ъӮр‘IӮФӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮН•K‘R“IӮЙүҠ“VүәӮМҚмӢЖӮЙӮИӮйҒBүҪӮкӮЙӮөӮлғҚғVғAҗ…•әӮӘҠөӮкӮДӮўӮйӮНӮёӮМӮИӮў”M‘СӮМҠCҸгӮЕӮ ӮйҒB”M•aӮЕҺҖӮКҗ…•әӮӘ‘ҠҺҹӮўӮҫҒBҒvӮЖҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйҒB ӮұӮМ•¶ҸНӮр“ЗӮЮӮЖҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҗ…•әӮН”R—ҝӮЕӮ Ӯй‘е—КӮМҗО’YӮрү^ӮФӮЖӮўӮӨҸdҳJ“ӯӮрҠCӮМҸгӮЕӮвӮБӮДӮўӮҪӮұӮЖӮӘ•ӘӮ©ӮйӮМӮҫӮӘҒA“–ҺһӮМҗўҠEҚqҳHӮМҗО’Y•Ы—LҚ`ӮНүpҚ‘ӮӘҺx”zӮөӮДӮЁӮиҒAү“‘еӮИҚqҳHӮМ‘е”јӮНүpҚ‘ҠCҢRӮМҗЁ—НүәӮЙӮ ӮБӮҪҒBүpҚ‘ӮН“ъ–{ӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ӮЕӮ ӮйӮ©ӮзҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНүpҚ‘ӮӘҺx”zӮ·ӮйҚ`ӮЕӮНҗО’YӮр•вӢӢӮ·ӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮёҒAҢцҠCҸгӮЕҗО’Y‘DӮр’TӮөӢҒӮЯӮДӮМҚqҠCӮӘ‘ұӮўӮҪӮжӮӨӮИӮМӮҫҒB“–‘R—ЗҺҝӮМҗО’YӮНҺиӮЙ“ьӮзӮИӮўҒB ӮЬӮҪҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҚqҳHӮрҢ©ӮйӮЖғXғGғYү^үНӮр’КӮБӮҪ‘DғӢҒ[ғgӮЖҒAғAғtғҠғJ“м’[ӮМҠм–]•фӮрҢo—RӮөӮҪғӢҒ[ғgӮЖҒA“сҺиӮЙ•ӘӮ©ӮкӮДӮўӮйӮМӮЙӮаӢБӮӯҒB”R—ҝҢш—ҰӮӘҲ«ӮӯӮ©ӮВҒA”R—ҝӮӘҺиӮЙ“ьӮиӮЙӮӯӮ©ӮБӮҪӮМӮҫӮ©ӮзҒAҚЕ’ZӢ——ЈӮЕҗiӮЮӮұӮЖӮӘ—DҗжӮіӮкӮйӮНӮёӮИӮМӮҫӮӘҒA“сҺиӮЙ•ӘӮ©ӮкӮҪӮМӮНҒAӢhҗ…ӮМҗ[ӮўҗнҠНӮН“–ҺһӮМғXғGғYү^үНӮр’КӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮИӮ©ӮБӮҪӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮӘӮ»ӮМ—қ—RӮМӮжӮӨӮҫҒB ғҚғVғAӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ӮЕӮ Ӯйғtғүғ“ғX—Мғ}ғ_ғKғXғJғӢ“ҮӮМғmғVғxҚ`ӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҚҮ—¬ӮөҒA•ЁҺ‘ӮМ•вӢӢӮрҚsӮИӮБӮҪҢг1905”N3ҢҺ16“ъӮЙғmғVғxҚ`ӮрҸoҚ`ӮөӮҪӮӘҒAӮұӮМҺһ“_ӮЕӮН”T–ШҢRӮМҠҲ–фӮЕҠщӮЙ—·ҸҮ—vҚЗӮНҠЧ—ҺӮөӮДӮЁӮиҒA—·ҸҮҚ`ӮЙ’в”‘ӮөӮДӮўӮҪҠН‘DӮаүу–ЕӮөӮДӮўӮҪӮҪӮЯҒA“ъ–{ҠН‘аӮЙ‘ОӮ·ӮйҲі“|“I—DҲКӮрҠm•ЫӮ·ӮйӮЖӮўӮӨ“–ҸүӮМ–Ъ“I’Bҗ¬ӮНҚў“пӮИҸуӢөӮЙӮИӮБӮДӮўӮҪҒBӮ»ӮМӮӨӮҰҒAғCғ“ғh—m•ы–КӮЕӮНғҚғVғAӮМ—FҚDҚ‘ӮНҸӯӮИӮӯҒAҸ«•әӮМ”жҳJӮН’~җПӮөҒAҗ…ҒEҗH—ҝҒEҗО’YӮМ•s‘«ӮНӮ©ӮИӮиҗ[ҚҸӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮөӮД1905”N4ҢҺ14“ъӮЙ“Ҝ–ҝҚ‘ғtғүғ“ғX—МғCғ“ғhғVғi(Ң»ғxғgғiғҖ)ӮМғJғҖғүғ“ҳpӮЙ“Ҡ•dӮөҒAӮ»ӮұӮЕҗО’YӮИӮЗӮМ•вӢӢӮрҚsӮИӮўҒA5ҢҺ9“ъӮЙӮНғ”ғ@ғ“ғtғHғ“ү«ӮЕ’ЗүБӮЙ”hҢӯӮіӮкӮҪ‘ҫ•Ҫ—m‘жҺOҠН‘аӮМ“һ’…Ӯр‘ТӮҝҒAӮўӮжӮўӮжғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙҢьӮҜӮД50җЗӮМ‘еҠН‘аӮӘҸoҚqӮөӮҪҒB Ҹ¬Ҡ}Ңҙ’·җ¶ ’ҳҒwҢӮ–Е : “ъ–{ҠCҠCҗн”йҺjҒxӮЖӮўӮӨ–{ӮӘӮ ӮйҒBӮИӮәғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҠН‘DӮӘҠИ’PӮЙ’ҫ–vӮөӮҪӮ©ӮЙӮВӮўӮДҸ‘Ӯ©ӮкӮДӮўӮйӮӘҒAӮ»ӮМ—қ—RӮНҒA—ЧӮМҚ‘ӮМӢq‘DғZғEғHғӢҚҶ’ҫ–vӮЖӮжӮӯҺ—ӮҪӮЖӮұӮлӮӘӮ ӮБӮДӢ»–Ўҗ[ӮўҒB ҒuҒc5ҢҺ23“ъӮН‘Ғ’©ӮжӮиҠeҠНӮЙҚЕҢгӮМҗО’Y“ӢҚЪӮрҚsӮнӮөӮЯҒAҸo—ҲӮӨӮйӮҫӮҜ‘Ҫ—КӮЙҗПӮЭ“ьӮкӮйӮжӮӨ–Ҫ—ЯӮөӮҪӮМӮЕҒA’ҶӮЙӮН’и—КӮМ”{ҲИҸгӮЙӮаӢyӮсӮҫӮаӮМӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮұӮкӮӘӮМӮҝҢғҗнӮЖӮИӮБӮҪҚЫҒAҗЖӮӯ“]•ўӮ·ӮйҠНӮӘ‘ұҸoӮөӮҪҲкӮВӮМҢҙҲцӮрӮИӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҳIҚ‘‘s”NҸ«ҚZ’ҶӮМҳr—ҳӮ«ӮЖӮўӮнӮкӮҪғNғүҒ[ғh’ҶҚІӮНҒAӮ»ӮМ’ҳҒw‘О”nү«үпҗнҳ_Ғx’ҶӮЙҒAҒwүдӮӘ—ЗҗнҠНғXғEғHҒ[ғҚғtҒBғ{ғҚғaғmҒBғIғXғүҒ[ғrғ„ӮМҺOҗЗӮН–CүОӮрҲИӮДҢӮ’ҫӮ№ӮзӮкӮҪҒBӮ©ӮӯӮМ”@Ӯ«ӮНӢЯҗўӮМҗ퓬ӮЙӮЁӮўӮДҗrӮҫӢH—LӮМӮұӮЖӮЕӮ ӮйӮӘҒAӮ»ӮМҢҙҲцӮҪӮйӮв–ҫ”’ӮҫҒB‘ҰӮҝӮұӮМҺOҠНӮНүЯ‘еӮМҗПҚЪӮрӮИӮөҒA•ңҢі—НӮӘҢҮ–RӮөӮДӮўӮҪӮ©ӮзӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮкӮаҗГүёӮМ“VҢуӮЕӮ ӮБӮҪӮИӮзҒAӮ Ӯ ӮЬӮЕӮИӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮлӮӨӮӘҒA”gҳQҚӮӮӯҠН‘аӮӘ“®—hӮөӮҪӮМӮЕҒAҗ…–КӢЯӮў’eҚEӮжӮиҺ©—RӮЙҗZҗ…ӮөӮҪҢӢүКӮҫӮЖҺvӮӨҒBҒxӮЖҳ_Ӯ¶ӮДӮўӮйҒBӮМӮЭӮИӮзӮёҗПҚЪүЯ‘ҪӮМӮҪӮЯҒAҗ…ҚЫӮМ‘•ҚbзеӮНҗ…’ҶӮЙ–vӮөҒA‘SӮӯ–hҢдӮМ–рӮЙ—§ӮҪӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮаҢ©“ҰӮ№ӮИӮўҲкҺ–ӮЕӮ ӮлӮӨҒBүҪӮЙӮөӮДӮаӮұӮӨӮЬӮЕӮ·ӮйӮұӮЖҲЧӮ·ӮұӮЖҺиҲбӮўӮЙӮИӮБӮДӮдӮӯӮМӮНҒA”Яү^ӮЖӮўӮнӮО”Яү^ӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮМҒAҚ‘ҢрӮЙҗMӢ`Ӯр–іҺӢӮөӮҪ“VжўӮЕӮНӮ ӮйӮЬӮўӮ©ҒBҒcҒv ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҗО’YӮМ’І’BӮЙӢкҳJӮөӮҪҳbӮНҲИ‘OӮЙ“ЗӮсӮҫӮұӮЖӮӘӮ ӮйӮӘҒAғCғMғҠғXӮҫӮҜӮЕӮИӮӯғAғҒғҠғJӮаҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮЙ•ЁҺ‘ӮрӢҹӢӢӮөӮҪҚ‘ӮЙҚRӢcӮөӮҪӢLҳ^ӮӘӮ ӮиҒAӮ»ӮМӮҪӮЯӮЙғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМ•әҺmӮНӮЩӮЖӮсӮЗ—ӨҸгӮЙҸгӮӘӮйӮұӮЖӮӘҸo—ҲӮёҒAҠCҸгӮЕӮМ”R—ҝү^”АҚмӢЖӮИӮЗӮЕҳJ—НӮрҚнӮӘӮкҒA”ј”NӮЙӮаӮнӮҪӮй‘еҚqҠCӮЙ‘Ҡ“–”ж•ҫӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖӮНҸd—vӮИғ|ғCғ“ғgӮҫӮЖҺvӮӨҒB ӮұӮұӮЕ“ъҳIӮМҗн—НӮр”дҠrӮөӮДӮЁӮұӮӨҒB “ъ–{ҠCҢRӮНҒAҗнҠН4ҒA‘•ҚbҸ„—mҠН8ҒA‘•ҚbҠC–hҠН1ҒAҸ„—mҠН12‘ј ғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮНҗнҠН8ҒA‘•ҚbҸ„—mҠН3ҒA‘•ҚbҠC–hҠН3ҒAҸ„—mҠН6‘ј ӮЕҗнҠНӮМҗ”ӮЕӮН“ъ–{ҠCҢRӮНғҚғVғAӮМ”ј•ӘӮЙүЯӮ¬ӮИӮ©ӮБӮҪҒB ӮаӮө“ъ–{ҠCҢRӮӘҒAӮұӮМҠН‘аӮрҲк’UғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙӢAҚ`Ӯ·ӮйӮұӮЖӮрӢ–ӮөӮДӮөӮЬӮҰӮОҒAғҚғVғAҢRӮН–ң‘SӮМҸҖ”хӮрӮөӮДҗнӮҰӮйӮМӮЕҒAҗнҠНӮӘ“ъ–{ҢRӮМ”{ӮаӮ ӮйғҚғVғAӮЙ•ӘӮӘӮ ӮБӮҪӮЕӮ ӮлӮӨҒB“ъ–{ҠCҢRӮЖӮөӮДӮНҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ–ЯӮй‘OӮЙҢҲҗнӮЙҺқӮҝҚһӮЮӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮкӮОҒA‘Ҡ“–”ж•ҫӮөӮҪҠН‘аӮЖҗнӮӨӮұӮЖӮЙӮИӮйӮМӮЕҒAҸҸҗнӮМ—DҗЁӮӘҠъ‘ТӮЕӮ«ӮйҒB ӮөӮ©ӮөҒAӮұӮМҺһ‘гӮЙӮНҚЎӮМғҢҒ[ғ_Ғ[ӮМӮжӮӨӮИӮаӮМӮН‘¶ҚЭӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘҚЎӮЗӮМӮ ӮҪӮиӮрҚqҠCӮөӮДӮўӮйӮ©ӮНӮВӮ©ӮЯӮёҒAғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ–ЯӮйӮМӮЙҒA‘О”nҠCӢ¬Ӯр’КӮйӮМӮ©ҒA’ГҢyҠCӢ¬Ӯр’КӮйӮМӮ©ҒAҸ@’JҠCӢ¬Ӯр’КӮйӮМӮ©ӮаӮнӮ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮұӮЕӮаӮөҒAӮ»ӮкӮјӮкӮМүВ”\җ«ӮрҚlӮҰӮД“ъ–{ҠCҢRӮМҗн—НӮр•ӘҺUӮіӮ№ӮДҗ”ғ•ҸҠӮЕ‘ТӮҝҚ\ӮҰӮДӮўӮҪӮЖӮөӮҪӮзҒA“ъ–{ҢRӮӘҸҹ—ҳӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪүВ”\җ«ӮӘҚӮӮ©ӮБӮҪӮЖҺvӮӨҒB ӮұӮұӮӘ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮМҲМӮўӮЖӮұӮлӮҫӮӘҒA“ҢӢҪӮНҒAҲЩҸнӮИ’·—·ӮМүКӮДӮЙӮнӮҙӮнӮҙ‘ҫ•Ҫ—m‘ӨӮрҢo—RӮ·ӮйүВ”\җ«ӮН’бӮӯҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮМҗн—НӮЙҺ©җMӮӘӮ ӮйӮИӮзӮО•KӮёҚЕ’ZӢ——ЈӮМ‘О”nҠCӢ¬Ӯр’КӮйӮЖҠmҗMӮөҒA‘SҠНӮӘ‘О”nҠCӢ¬ӮЕ‘ТӮҝ•ҡӮ№ӮөӮДӮўӮҪӮМӮҫҒBҗжӮЩӮЗҸРүоӮөӮҪҒwҢӮ–Е : “ъ–{ҠCҠCҗн”йҺjҒxӮЙӮНҒA“ъ–{ҢRӮӘ‘О”nҠCӢ¬ӮЙ‘SҗЁ—НӮрҸWӮЯӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘ‘z’иҠOӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӮМғҚғVғA‘ӨӮМҠҙ‘zӮӘҸРүоӮіӮкӮДӮўӮйҒB ҒuҒcӮЬӮіӮ©ӮЙҸ@’JҒE’ГҢyӮМ“сҠCӢ¬ӮрӮ Ӯк’цҺvӮўҗШӮБӮД•ъқұ(ӮЩӮӨӮДӮ«)ӮөҒA’©‘NҠCӢ¬ӮЙӮМӮЭ‘SҗЁ—НӮрҸWӮЯӮДӮўӮҪӮЖӮНҺvӮнӮИӮ©ӮБӮҪӮзӮөӮўҒBғNғүҒ[ғh’ҶҚІӮНӮұӮкӮЙ‘ОӮөҒAҒwҚЕӮаӢБӮӯӮЧӮ«ӮНҒAүдӮӘҠН‘аӮЙӮ ӮБӮД‘S“ъ–{ҠН‘аӮЖ‘ҳӢцӮ·ӮйӮӘ”@Ӯ«ӮНҒA‘SӮӯ—\‘zҠOӮЕ•sҲУӮЙҸжӮ№ӮзӮкӮҪӮжӮӨӮИӮаӮМӮҫҒBӮЖҢҫӮӨӮДӮўӮйҺ–ӮҫҒBҒxӮЖ—в•]ӮөҒcҒvӮЖҸ‘ӮўӮДӮ ӮйҒB Ӯ»ӮөӮДҒAү^–ҪӮМ5ҢҺ27“ъӮМ’©ӮрҢ}ӮҰӮҪҒB Ҹ„—mҠНӮ©Ӯз“GҠН”ӯҢ©ӮМҳA—ҚӮрҺуӮҜҒA“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮНҢЯ‘O6Һһ21•ӘӮЙҒAҒu“GҠНҢ©ӮдӮЖӮМҢx•сӮЙҗЪӮөҒAҢбҠН‘аӮН’јӮҝӮЙҸo“®ҒA”VӮрҢӮ–ЕӮ№ӮсӮЖӮ·ҒBҚҹӮМ“ъҒA“VӢCҗ°ҳNӮИӮкӮЗ”gҚӮӮөҒvӮЖ‘е–{үcӮЙ‘Е“dӮөӮДӮўӮйҒB —јҠН‘аӮНӢ}‘¬ӮЙҗЪӢЯӮөҒAӢ——Ј8000mӮЙӮЬӮЕӮИӮБӮҪӮЖӮ«ҒA“ҢӢҪӮНҚ¶ӮЙ‘ЗӮрҗШӮйӮұӮЖӮр–ҪӮ¶ҒA’ҡҺҡҢ^ӮЙ“GӮМҗж“ӘӮрҲі”—ӮөӮжӮӨӮЖӮөӮҪҒBҢRҠНӮНҒAӮ»ӮМҚ\‘ўҸгҒA“GӮНҗі–КӮЙӮўӮйӮжӮиӮаҚ¶үEӮЗӮҝӮзӮ©ӮЙӮўӮҪ•ыӮӘҒA–Ъ•WӮЙ‘ОӮөӮДҚUҢӮӮЕӮ«Ӯй‘е–CӮМҗ”ӮӘ‘ҪӮӯӮИӮйҒBӮ»ӮМ”Ҫ–КҒAүс“]ү^“®’ҶӮНҺ©ҢRӮ©ӮзӮМҚUҢӮӮН“пӮөӮӯӢtӮЙ“GҠНӮМҗі–КӮМ‘е–CӮМҺЛ’цҢ—ӮЙӮЖӮЗӮЬӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBӮөӮ©Ӯөүс“]ү^“®’ҶӮМ“ъ–{ҠCҢRӮМҲК’uӮНҒA“GҠНӮМҺЛ’цҢ—ӮМғMғҠғMғҠӮМӮЖӮұӮлӮЕӮ ӮиҒA“–‘R–Ҫ’Ҷҗё“xӮН’бӮўҒB ӮұӮМҺһ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYҺi—Я’·ҠҜӮМҚмҗн’S“–ҺQ–dӮЕӮ ӮБӮҪҸHҺRҗ^”VӮНҒAҺ©’ҳӮМҒwҢR’kҒxӮЙӮұӮӨҸ‘ӮўӮДӮўӮйҒB Ғu“GӮМҠН‘аӮӘҒAҸүӮЯӮДүОҠWӮрҗШӮБӮД–CҢӮӮөӮҪӮМӮӘҒAҢЯҢг“сҺһ”Ә•ӘӮЕҒAүдӮӘ‘жҲкҗн‘аӮӘҒAҺbӮӯӮұӮкӮЙ‘ПӮҰӮДҒAүһҗнӮөӮҪӮМӮӘҺOҺl•Ә’xӮкӮД“сҺһҸ\Ҳк•ӘҚ ӮЕӮ ӮБӮҪӮЖӢLүҜӮөӮДӮўӮйҒBӮұӮМҺOҺl•ӘӮЙ”тӮсӮЕӮ«ӮҪ“G’eӮМҗ”ӮНҒAҸӯӮИӮӯӮЖӮаҺO•S”ӯҲИҸгӮЕҒAӮ»ӮкӮӘҠFүдӮӘҗж“ӘӮМҠшҠНҒwҺOҠ}ҒxӮЙҸW’ҶӮіӮкӮҪӮ©ӮзҒAҒwҺOҠ}ҒxӮН–ўӮҫҲк’eӮрӮа‘ЕӮҝҸoӮіӮКӮӨӮҝӮЙҒA‘ҪҸӯӮМ‘№ҠQӮаҺҖҸқӮаӮ ӮБӮҪӮМӮҫӮӘҒAҚKӮўӮЙӢ——ЈӮӘү“Ӯ©ӮБӮҪӮҪӮЯҒA‘еүцүдӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒcҢЯҢг2Һһ12•ӘҒAҗнҠН‘аӮӘ–CҢӮӮрҠJҺnӮөӮДҒA“GӮМҗж“Ә“сҠНӮЙҸW’eҒcҒAҢЯҢг“сҺһҺlҸEҢЬ•ӘҒA“GӮМҗн—с‘SӮӯ—җӮкӮДҒAҸҹ”sӮМ•ӘӮ©ӮкӮҪҺһӮМ‘ОҗЁӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮМҠФҺАӮЙҺOҸ\ҢЬ•ӘӮЕҗі–ЎӮМӮЖӮұӮлӮНҺOҸ\•ӘӮЙӮ·Ӯ¬ӮИӮўҒBҒcҗЁ—НӮНӮЩӮЪ‘О“ҷӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮҪӮҫӮвӮвүдӮӘҢRӮМҗнҸpӮЖ–CҸpӮӘ—DӮкӮДӮЁӮБӮҪӮҪӮЯӮЙҒAӮұӮМҢҲҸҹӮржХ(Ӯ©)Ӯҝ“ҫӮҪӮМӮЕҒAҚcҚ‘ӮМӢ»”pӮНҒAҺАӮЙӮұӮМҺOҸ\•ӘҠФӮМҢҲҗнӮЙӮжӮБӮД’иӮЬӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBҒv ҠCҗнӮНҺАӮНӮұӮМ“ъӮМ–йӮЬӮЕ‘ұӮўӮҪӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҗнӮўӮЕғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮрҚ\җ¬ӮөӮДӮўӮҪ8җЗӮМҗнҠНӮМӮӨӮҝ6җЗӮӘ’ҫ–vӮө2җЗӮӘ•ЯҠlӮіӮкӮҪҒB‘•ҚbҸ„—mҠН5җЗӮӘ’ҫӮЭ1җЗӮӘҺ©’ҫҒAҸ„—mҠНғAғӢғ}Ғ[ғYӮӘғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙҒAҠC–hҠН3җЗӮӘғ}ғjғүӮЙ“ҰӮ°ҒAӢм’ҖҠНӮН9җЗ’ҶӮМ5җЗӮӘҢӮ’ҫӮіӮкҒA2җЗӮӘғEғүғWғIғXғgғbғNӮЙ“ҰӮ°ӮҪҒBғҚғVғA‘ӨӮМҗl“I”нҠQӮНҗнҺҖ5046–јҒA•үҸқ809–јҒA•Я—ё6106–јҒBҲк•ы“ъ–{‘ӨӮМ‘№ҠQӮНҒAҗ…—Ӣ’ш3җЗҒAҗнҺҖҺТ116–јҒA•үҸқ538–јӮЕӮ ӮБӮҪҒBҢӢүКӮН“ъ–{ҢRӮМҲіҸҹӮЕӮ ӮиҒA“ъ–{ҢRӮМӮұӮМҸҹ—ҳӮЕ“ъҳIҗн‘ҲӮМҗ–җЁӮНҢҲ’и“IӮЖӮИӮБӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮЁӮҜӮй“ъ–{Ҹҹ—ҳӮМғjғ…Ғ[ғXӮНҗўҠEӮрӢБ’QӮіӮ№ҒA–wӮсӮЗӮМҚ‘ӮӘҚҶҠOӮЕ•сӮ¶ӮҪӮЖӮўӮӨҒB—LҗFҗlҺнӮЖӮөӮДҺ©Қ‘ӮМӮұӮЖӮЙӮжӮӨӮЙӢ¶ҠмӮөӮҪғAғWғAӮвғAғүғuҸ”Қ‘ҒAғҚғVғAӮМ“мүәӮр‘jҺ~ӮөӮҪӮ©ӮБӮҪүp•ДӮН“ъ–{ӮМҸҹ—ҳӮрҺ]ӮҰҒAғҚғVғAӮМ“Ҝ–ҝҚ‘ғtғүғ“ғXӮНғҚғVғAӮЙҚuҳaӮр‘EӮЯҒAғhғCғcӮНӮұӮМҠJҗнӮМҸҹ—ҳӮрӢ@ӮЙ‘О“ъҗЪӢЯӮрӢӯӮЯӮҪӮжӮӨӮҫҒB ӮЖӮұӮлӮЕҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕ–Ҫ—ЯӮЙҲб”ҪӮөӮДҗнҸкӮ©Ӯз—Ј’EӮөӮДғ}ғjғүӮЙҢьӮ©ӮБӮҪғҚғVғAӮМҸ„—mҠНӮӘ3җЗӮ ӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМӮӨӮҝӮМӮРӮЖӮВӮӘҒuғAғEғҚғүҒvӮЕӮ ӮйҒBӮұӮМӢLҺ–ӮМҚЕҸүӮЙҒAғoғӢғ`ғbғNҠН‘аӮӘғҚғVғAӮМғҠғoғEҢRҚ`ӮрҸo”ӯӮөӮҪ’јҢгӮЙүpҚ‘Ӣҷ‘DӮрҢл”ҡӮөӮҪӮұӮЖӮрҸ‘ӮўӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҺһӮЙ“ҜҺu“ўӮҝӮЙӮ ӮўҒAҗ…җьҸгӮЙ–Ў•ыӮ©ӮзҺl’eӮрӮӨӮҜӮҪӮМӮӘӮұӮМҒuғAғEғҚғүҒvӮЕҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮМҺһӮНҠН’·ӮӘҗнҺҖӮ·ӮйӮИӮЗ‘№ҸқӮрҺуӮҜӮҪӮМӮҝӮЙ“Ұ–SӮөӮДҒA’Ҷ—§Қ‘ӮЕӮ ӮйғAғҒғҠғJ—МғtғBғҠғsғ“ӮЙ’HӮиӮВӮ«ғ}ғjғүӮЕ—}—ҜӮіӮкӮҪӮМӮҫӮӘҒAӮұӮМҸ„—mҠНӮМӮ»ӮМҢгӮМү^–ҪӮӘӢ»–Ўҗ[ӮўҒB1906”NӮЙҒuғAғEғҚғүҒvӮНғoғӢғgҠCӮЙ–ЯӮиҒA1917”NӮЙ‘еүь‘•ӮМӮҪӮЯӮЙғyғgғҚғOғүҒ[ғhӮЙүсҚqӮіӮкӮйӮЖҒA“сҢҺҠv–ҪӮӘӢNӮұӮБӮДҠН“аӮЙҠv–ҪҲПҲхүпӮӘҗЭӮҜӮзӮкҒA‘ҪӮӯӮМҸж‘gҲхӮӘғ{ғӢғVғFғrғLӮЙ“Ҝ’ІӮөӮҪӮ»ӮӨӮҫҒB11ҢҺ7“ъ(ҳI—п10ҢҺ25“ъ)ӮЙӮН—ХҺһҗӯ•{ӮӘ’uӮ©ӮкӮДӮўӮҪ“~Ӣ{Ӯр–CҢӮӮөҒAӮіӮзӮЙғAғEғҚғүӮМҗ…•әӮҪӮҝӮӘҒAҗФүq‘аӮв”Ҫ—җ•әҺmӮЖӮЖӮаӮЙҒA“~Ӣ{ҚU—ӘӮЙҺQүБӮөӮД10ҢҺҠv–ҪӮМҗ¬ҢчӮЙҠс—^ӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB 1923”NӮЙӮНҠv–ҪӢL”OҠНӮЙҺw’иӮіӮкӮДҒAғҚғVғAҠv–ҪӮМғVғ“ғ{ғӢӮМӮРӮЖӮВӮЖӮөӮДғTғ“ғNғgғyғeғӢғuғӢғOӮМғlғ”ғ@үН”ИӮЙҚЎӮаҢW—ҜҒE•Ы‘¶ӮіӮкӮДӮўӮйӮЖӮўӮӨҒB Ҳк•ыҒA“ъ–{ҠCҠCҗнӮЕ“ҢӢҪ•Ҫ”ӘҳYӮӘҚАҸжӮөӮҪҒAҳAҚҮҠН‘аҠшҠНӮМҗнҠНҺOҠ}ӮНӮ»ӮМҢгӮЗӮӨӮўӮӨү^–ҪӮр’HӮБӮҪӮМӮ©ҒB1921”NӮМғҸғVғ“ғgғ“ҢRҸkҸр–сӮЙӮжӮБӮД”pҠНӮӘҢҲ’иӮөҒA1923”NӮМҠЦ“Ң‘еҗkҚРӮЕҠЭ•ЗӮЙҸХ“ЛӮөӮҪҚЫӮЙҒAүһӢ}ҸC—қ’ҶӮЕӮ ӮБӮҪ”j‘№•”ҲКӮ©ӮзҗZҗ…ӮөӮ»ӮМӮЬӮЬ’…’кӮөӮДӮөӮЬӮӨҒBүр‘МӮіӮкӮй—\’иӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҚ‘“аӮЕ•Ы‘¶ү^“®ӮӘӢNӮұӮи1925”NӮЙӢL”OҠНӮЖӮөӮДүЎҗ{үкӮЙ•Ы‘¶Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘҠtӢcҢҲ’иӮіӮкӮҪҒB‘ж“сҺҹ‘еҗнҢгӮМҗи—МҠъӮЙӮНҒAғҚғVғAӮ©ӮзӮМҲі—НӮЕүр‘МҸҲ•ӘӮЙӮіӮкӮ»ӮӨӮЙӮИӮБӮҪӮӘҒAғEғBғҚғrҒ[ӮзӮМ”Ҫ‘ОӮЕӮ»ӮкӮр–ЖӮкӮҪҢгҒAғAғҒғҠғJҢRҗlӮМӮҪӮЯӮМҢвҠyҺ{җЭӮӘҗЭ’uӮіӮкӮДҒAҲкҺһӮНҒuғLғғғoғҢҒ[ҒEғgҒ[ғSҒ[ҒvӮӘҠНҸгӮЕҠJӮ©ӮкӮҪӮЖӮўӮӨҒBӮ»ӮМҢгҒA•ЁҺ‘•s‘«ӮЕӢа‘®—ЮӮвҚb”ВӮМ‘ҪӮӯӮӘ“җӮЬӮкӮДҚr”pӮ·ӮйҲк•ыӮҫӮБӮҪӮӘҒAүpҚ‘ӮМғWғҮғ“.S.ғӢҒ[ғrғ“ҒA•ДҠCҢRӮМғ`ғFғXғ^Ғ[ҒEғjғ~ғbғc’с“ВӮМҗs—НӮЙӮжӮи•Ы‘¶ү^“®ӮӘҗ·ӮиҸгӮӘӮБӮДҸәҳa36”N(1961)ӮЙҸC—қ•ңҢіӮіӮкҒAҢ»ҚЭӮНҗ_“ЮҗмҢ§үЎҗ{үкҺsӮМҺOҠ}ҢцүҖӮЙӢL”OҠНӮЖӮөӮДҢцҠJӮіӮкӮДӮўӮйҒB ӮнӮӘҚ‘ӮМ—рҺjҲвҺYӮЖӮөӮДҠфҗў‘гӮЙӮаӮнӮҪӮБӮДҺcӮіӮкӮйӮЧӮ«‘DӮӘҒAҗи—МҢRӮЙӮжӮБӮДҢвҠyҺ{җЭӮЙӮіӮкӮ»ӮМҢгҚrӮкӮйӮЙ”CӮіӮкӮҪӮұӮЖӮНҒA“ъ–{җlӮМҢЦӮиӮр’DӮӨӮҪӮЯӮЙҗи—МҢRӮӘүҹӮө•tӮҜӮҪҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМүp—YӮЕӮ Ӯй”T–ШӮв“ҢӢҪӮрҢ°ҸІӮөӮИӮў—рҺjҠПӮЖ–іҠЦҢWӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҺvӮӨӮМӮҫҒB ҒuҺOҠ}ҒvӮН“ъҳIҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮөӮнӮӘҚ‘ӮМ“Ж—§ӮрҺзӮБӮҪҸЫ’ҘӮЖӮөӮД—LҺuҺТӮЙӮжӮиҢмӮзӮкӮДӮ«ӮДҒAҢ»ҚЭӮНҺOҠ}ӢL”OүпғҒғ“ғoҒ[ӮМүп”пӮЖҢ©ҠwҺТӮМҠП———ҝӮЙӮжӮиҲЫҺқҒEҠЗ—қӮіӮкӮДӮўӮйӮМӮҫӮӘҒAҠП——ҺТӮӘҸӯӮИӮӯӮДӮНҒAӮ»ӮкӮа“пӮөӮӯӮИӮй“ъӮӘӮўӮёӮк—ҲӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўҒB “ъ–{ҠCҠCҗнӮЙӮаӮөӮнӮӘҚ‘ӮӘ”sӮкӮДӮўӮҪӮзҒA“ъ–{ҠCӮМҗ§ҠCҢ ӮӘғҚғVғAӮЙ’DӮнӮкӮДҒA–һҸBӮв’©‘N”ј“ҮӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮӯ“ъ–{—с“ҮӮМ–kӮМҲк•”ӮаҒAғҚғVғAӮМ—М“yӮЙӮИӮБӮДӮўӮДӮЁӮ©ӮөӮӯӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBҚЎӮМ‘ҪӮӯӮМ“ъ–{җlӮНҒAӮнӮкӮнӮкӮМ‘cҗжӮӘ–ҪӮрҢңӮҜӮДҗнӮБӮДҸҹ—ҳӮөҒAӮнӮӘҚ‘ӮрҺзӮБӮДӮӯӮкӮҪӮұӮЖӮЙҠҙҺУӮ·ӮйӮұӮЖӮрҒA–YӮкӮДӮөӮЬӮБӮДӮНӮўӮИӮўӮҫӮлӮӨӮ©ҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ‘еҺRҠЮ | |
|
‘ж“сҺҹҗўҠE‘еҗн’јҢгҒA‘ҪӮӯӮМҢRҗlӮМ“ә‘ңӮӘ“PӢҺӮіӮкӮй’ҶҒA‘еҺRҠЮӮМ“ә‘ңӮҫӮҜӮН“PӢҺӮр–ЖӮкӮҪҒB“ъ–{Ӯр“қҺЎӮөӮҪғ}ғbғJҒ[ғTҒ[ҢіҗғӮӘҒAҺ©ҺәӮЙ‘еҺRҠЮӮМҸС‘ңүжӮрҸьӮБӮДӮўӮҪӮЩӮЗӮМ‘еҺRғtғ@ғ“ӮҫӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒBғ}ғbғJҒ[ғTҒ[ӮрҗSҗҢӮіӮ№ӮҪүp—Y‘еҺRҠЮӮрҚмӮиҸгӮ°ӮҪӮаӮМӮНҒAүҪӮЕӮ ӮБӮҪӮМӮ©ҒB
ҒЎҗјӢҪ—Іҗ·ӮЖӮМӮВӮИӮӘӮи –ҫҺЎҺһ‘гҒA“ъ–{ӮН“ъҗҙҗн‘ҲҒA“ъҳIҗн‘ҲӮЙҸҹ—ҳӮөҒAҗўҠEӮМҗжҗiҚ‘үЖӮМ’ҮҠФ“ьӮиӮрүКӮҪӮөӮҪҒBӮ»ӮМ—§–рҺТӮМҲкҗlӮӘ‘еҺRҠЮӮЕӮ ӮйҒBҢRҗlӮЖӮөӮДҢіҗғӮЙӮЬӮЕ“oӮиӮВӮЯҒAӢЯ‘гҚ‘үЖ“ъ–{ӮМҢҡҗЭӮМ’ҢӮЖӮөӮДҠҲ–фӮөӮҪӮ»ӮМҢчҗСӮЕҢцҺЭӮМ’nҲКӮЙӢPӮўӮДӮўӮйҒB—рҺjүЖӮН‘еҺRҠЮӮрҸМӮөӮДҢҫӮӨҒBҢRҗlӮЕӮ ӮиӮИӮӘӮзҒAҢRҗlҲИҸгӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйӮЖҒBӮ»ӮМҲкҗ¶ӮН–ҫҺЎҲЫҗVӮМүp—YҒAҗјӢҪ—Іҗ·ӮМҚД—ҲӮЖӮЬӮЕҢҫӮнӮкӮҪҒBӮаӮөҗјӢҪӮӘҗј“мҗн‘ҲӮЕҺҖӮИӮёӮЙҗ¶Ӯ«ӮДӮўӮкӮОҒAӮұӮсӮИҗ¶ҠUӮр‘—ӮБӮДӮўӮҪӮМӮЕӮНӮИӮўӮ©ӮЖҺvӮнӮ№Ӯйҗl•ЁӮҫӮБӮҪҒB 1842”NҒA‘еҺRҠЮӮНҺF–Җ”ЛӮМҺӯҺҷ“ҮҸйүәӮМүәүБҺЎү®’¬ӮЕҒA•F”ӘӮЖӢЈҺqӮМҠФӮМҺҹ’jӮЖӮөӮДҗ¶ӮЬӮкӮҪҒB•ғӮМ•F”ӘӮНҗјӢҪ—Іҗ·ӮМ•ғӮМ’нӮЕ‘еҺRүЖӮЙ—{ҺqӮЙ“ьӮБӮҪҗl•ЁӮЕӮ ӮйҒBӮВӮЬӮи—Іҗ·ӮЖӮНҸ]ҢZ’нӮМҠЦҢWҒB“сҗlӮН”ZӮўҢҢүҸҠЦҢWӮЕҢӢӮОӮкӮДӮўӮҪҒB ‘еҺRӮН6ҚОӮМҚ Ӯ©ӮзҒAҺF–ҖӮМӢҪ’ҶӮЖҢДӮОӮкӮҪ’nӢж•КӮМҗВҸӯ”NӮМҢRҺ–ҒEӢіҲз‘gҗDӮЙ“ьӮиҒAӢҪ’Ҷ“ӘӮМҗјӢҪ—Іҗ·Ӯ©Ӯз“ЗӮЭҸ‘Ӯ«ӮИӮЗӮрӢіӮнӮБӮҪҒB‘еҺRӮжӮи15ҚОӮа”N’·ӮМҗјӢҪӮНҒAҢZӮЕӮ ӮиҒA•ғӮЕӮаӮ ӮйӮжӮӨӮИ‘¶ҚЭӮҫӮБӮҪҒBӮұӮМӢҪ’ҶӢіҲзӮМ’ҶӮЕҒA‘еҺRӮНҺF–Җ•җҺmӮМҗ_җ‘ӮрҠwӮСҒAӮ»ӮкӮрҗgӮЙ•tӮҜӮҪҒB”ЪӢҜӮрҢҷӮўҒAҺҖӮрҠoҢеӮөӮДӮұӮЖӮЙ—ХӮЮҢүӮіӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮөӮДҒAғҠҒ[ғ_Ғ[ӮМӮ ӮйӮЧӮ«ҺpӮНҒAҗgӢЯӮИҗјӢҪӮ©ӮзӢzҺыӮөӮҪҒBҢгӮМүp—Y‘еҺRҠЮӮНҒAҺF–ҖӮИӮөӮЙӮаҒAҗјӢҪӮИӮөӮЙӮаҒA‘¶ҚЭӮөӮҰӮИӮ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB ҒЎ•әҠнҢӨӢҶӮМӮҪӮЯ—ҜҠw ‘еҺRҠЮӮНҒAӮ»ӮМҗ¶ҠUӮЕ3үсӮаҠCҠO“nҚqӮрҢoҢұӮөӮДӮўӮйҒBҚЕҸүӮМ“nүўӮН1870”N8ҢҺҒA–ҫҺЎҗVҗӯ•{ӮӘӮЕӮ«ӮҪ2”NҢгӮМӮұӮЖҒBғAғҒғҠғJҒAғҲҒ[ғҚғbғpӮр–K–вӮөҒA–с”ј”NӮЙӮнӮҪӮй—·ӮЕӮ ӮБӮҪҒB”ЮӮӘҺеӮЙҢ©ӮДүсӮБӮҪҗжӮНҒAҠCҢRӮМ‘ў‘DҸҠҒA•җҠнҚHҸкҒA‘е–Cҗ»‘ўҸҠӮИӮЗӮЕӮ ӮйҒBӮИӮәҒAӮұӮсӮИӮаӮМӮӘӮЕӮ«ӮйӮМӮ©ҒBӮ»ӮМӢK–НӮЖӮўӮўҒAҗёҚIӮіӮЖӮўӮўҒA“ъ–{ӮМ”дӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮұӮӨӮўӮӨҚ‘ӮЖҗн‘ҲӮөӮҪӮзҒA“ъ–{ӮНӮРӮЖӮҪӮЬӮиӮаӮИӮўҒBӢЯ‘гү»ӮрӢ}ӮӘӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBҒuҚ‘ӮМ“Ж—§ӮН•әҠнӮМ“Ж—§ӮҫҒvӮЖӮўӮӨӢCҺқӮҝӮр•шӮўӮДҒA1871”N3ҢҺӮЙӢAҚ‘ӮөӮҪҒB –{Ҡi“IӮИ•әҠнӮМҢӨӢҶӮрӢ}ӮӘӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮИӮўҒBҸЕ‘ҮҠҙӮрҺқӮБӮДӢAҚ‘ӮөӮҪ‘еҺRӮНҒAҚД“nҚqӮрҠиӮўҸoӮҪҒBӢAҚ‘ӮөӮД8ғ–ҢҺҢгӮМ11ҢҺҒA‘еҺRӮНҚД“xүўҸBӮЙҢьӮҜӮД—·—§ӮБӮҪҒB29ҚОӮМӮ©ӮИӮи’xӮў—ҜҠwӮЕӮ ӮйҒB‘еҺRӮӘғҲҒ[ғҚғbғpӮ©ӮзҠwӮЪӮӨӮЖӮөӮҪӮМӮНҒA’PӮЙ•әҠнӮМӮұӮЖӮҫӮҜӮЕӮНӮИӮўҒBӮұӮӨӮөӮҪ•әҠнӮрҗ¶ӮЭҸoӮ·‘f’nҒAӮВӮЬӮиӢߑ㕶–ҫӮ»ӮМӮаӮМӮЙҠЦҗSӮӘҢьӮҜӮзӮкӮДӮўӮҪҒBғIҒ[ғXғgғҠғAӮМғEғBҒ[ғ“ӮЕҠJҚГӮіӮкӮҪ–ңҚ‘”Һ——үп(1873”N8ҢҺ)ӮЙӮНҒAүҪӮЖ1ғ–ҢҺӮМ‘ШҚЭ’Ҷ26үсӮаүпҸкӮр–KӮкӮДӮўӮйҒBӮжӮЩӮЗӢӯӮўҺhҢғӮрҺуӮҜӮҪӮМӮЕӮ ӮлӮӨҒB ҒЎҗјӢҪӮМүә–мӮЕӢAҚ‘ —ҜҠw’ҶӮМ‘еҺRӮЙҺF–ҖӮМҗж”yӮЕӮ ӮйӢgҲд—FҺАӮ©ӮзҒAӢБӮӯӮЧӮ«ҺиҺҶӮӘ“НӮўӮҪҒBҗјӢҪ—Іҗ·ӮӘүә–мӮөҒAҺӯҺҷ“ҮӮЙӢAӮБӮДӮөӮЬӮўҒAӮұӮкӮЙ‘Ҡ“–җ”ӮМҺF–Җ”ЛҺmӮӘ“Ҝ’ІӮөӮДӢAӢҪӮөӮҪӮЖҢҫӮӨҒBҗVҗӯ•{ӮМҚЕ‘еҠлӢ@ӮЕӮ ӮйҒBҺиҺҶӮНҒAӮұӮМ‘О—§ӮМүрҢҲӮМӮҪӮЯҒAӮ·Ӯ®ӢAҚ‘ӮөӮДӮЩӮөӮўӮЖҢӢӮсӮЕӮўӮҪҒB ҺиҺҶӮрҺуӮҜҺжӮБӮДӮ©Ӯз2ғ–ҢҺҢгҒAӢgҲд—FҺАҺ©җgӮӘүўҸBӮЙҸжӮиҚһӮсӮЕӮ«ӮҪҒB‘еҺRӮрҳAӮк–ЯӮ·ӮҪӮЯӮЕӮ ӮйҒBҺ–‘ФӮНҒA‘z‘ңҲИҸгӮЙҗ[ҚҸӮҫӮБӮҪҒB1874”N10ҢҺҒA‘еҺRӮНҗјӢҪӮрҗӯҢ ӮЙ•ңӢAӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨҸdҗУӮр’SӮБӮДӢAҚ‘ӮөӮҪҒB 3”NӮФӮиӮЙҺӯҺҷ“ҮӮЙ–ЯӮБӮҪ‘еҺRӮНҒAӮ»ӮМ‘«ӮЕҗјӢҪӮМӮаӮЖӮр–KӮкӮҪҒBҗVҗӯ•{ӮЙ–ЯӮБӮД—~ӮөӮўӮЖӮўӮӨ‘еҺRӮМ•KҺҖӮМҗа“ҫӮаӢуӮөӮӯҒAҠвӮМӮжӮӨӮИҗјӢҪӮМҗSӮр•ПӮҰӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮ©ӮБӮҪҒBӮИӮзӮОҒA‘еҺRӮМ‘I‘рӮНҲкӮВӮЕӮ ӮйҒBҗјӢҪӮМӮаӮЖӮЕ•…”sӮөӮҪҗVҗӯ•{ӮМ—§ӮД’јӮөӮрҗ}ӮйӮЬӮЕӮМӮұӮЖҒBҗјӢҪӮЖү^–ҪӮрӢӨӮЙӮөӮҪӮўӮЖҗ\ӮөҸoӮҪҒBҗјӢҪӮМҺь•УӮр•s•Ҫ•җҺmӮӘҺжӮиҲНӮсӮЕӮўӮҪҒB”ЮӮзӮӘ–\”ӯӮ·ӮкӮОҒAҗјӢҪӮН–ҪӮМҠлҢҜӮЙӮіӮзӮіӮкӮйҒBҗјӢҪӮрҺзӮйӮҪӮЯӮЙӮаҒA‘еҺRӮНҗјӢҪӮЖҚs“®ӮрӢӨӮЙӮ·ӮЧӮ«ӮҫӮЖҚlӮҰӮҪҒB ‘еҺRӮМҗ\ӮөҸoӮЙ‘ОӮөҒAҗјӢҪӮНҺсӮрүЎӮЙҗUӮБӮҪҒBҒuӮЁӮНӮс(ӮЁ‘O)ӮНҒAӮұӮкӮ©ӮзӮМ“ъ–{ӮЙ•K—vӮИҗlҚЮӮ¶ӮбҒB“ҢӢһӮЙӮЁӮБӮДҒA“VҚc•ГүәӮМӮЁ–рӮЙ—§ӮҪӮЛӮОӮИӮзӮсҒBӮЁӮў(үҙ)ӮМ–рӮЙӮНҒA—§ӮҪӮсӮЕӮаӮўӮўҒvҒBҒuӮЁӮўӮМ–ҪҒAҢZӮіӮҹӮЙӮЁ—aӮҜӮөӮЬӮ·ҒvҒBҗјӢҪӮНӢ}ӮЙ—§ӮҝҸгӮиҒAҒuӮИӮзӮсҒA’fӮ¶ӮДӮИӮзӮсҒBӢAӮкӮБҒA“ҢӢһӮЙӢAӮкӮБҒvӮЖ“{–ВӮБӮҪҒB җјӢҪӮН–Е‘ҪӮИӮұӮЖӮЕҗlӮрҺ¶ӮиӮВӮҜӮйӮұӮЖӮМӮИӮўҗlҠФӮЕӮ ӮйҒB‘еҺRӮНҒAҗјӢҪӮМ“{җәӮМ’ҶӮЙӮ»ӮМ”Я‘sӮИӮйҢҲҲУӮрҠҙӮ¶ҺжӮБӮҪҒB•s•Ҫ•җҺmӮҪӮҝӮМ‘ӨӮЙҗgӮр’uӮ«ӮИӮӘӮзҒA”ЮӮзӮЖү^–ҪӮрӢӨӮЙӮ·ӮйҒBӮ»ӮөӮД”ЮӮзӮЖӢӨӮЙҺҖӮКҒBҗVӮөӮӯ’aҗ¶ӮөӮҪҗӯ•{ӮрҺзӮйӮЙӮНӮұӮкӮөӮ©ӮИӮўҒBҗјӢҪӮМҒuҚ‘үЖӮЦӮМӮІ•тҢцҒvӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМҒuӮІ•тҢцҒvӮЙ‘еҺRӮрҠӘӮ«“YӮҰӮЙӮөӮҪӮӯӮИӮ©ӮБӮҪӮМӮҫҒB‘еҺRӮЙӮНҒAӮ»ӮсӮИҗјӢҪӮМӢCҺқӮҝӮӘ’ЙӮўӮЩӮЗӮнӮ©ӮйҒB‘еҺRӮНҗјӢҪӮМӮаӮЖӮрӢҺӮиҒAҺАүЖӮЙӮаҠсӮзӮёӮЙ“ҢӢһӮЦӮЖӢ}ӮўӮҫҒBӮұӮкӮӘҗјӢҪӮЖӮМҚЎҗ¶ӮМ•КӮкӮЖӮИӮйӮ©ӮаӮөӮкӮИӮўӮЖҺvӮӨӮЖҒA—ЬӮӘҲмӮкҸoӮДҺ~ӮЬӮзӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҒЎҗјӢҪӮМҺҖ ‘еҺRӮӘӢ°ӮкӮДӮўӮҪҚЕҲ«ӮМҺ–‘ФӮӘӢNӮ«ӮДӮөӮЬӮБӮҪҒBҗјӢҪӮр—i—§ӮөӮДҒAӮВӮўӮЙҺӯҺҷ“ҮӮМ•җҺmӮҪӮҝӮӘ–\”ӯӮөӮҪҒBҗј“мҗн‘Ҳ(1877”N)ӮЕӮ ӮйҒB‘еҺRӮЙӮаҒA’БҲіӮМӮҪӮЯҺӯҺҷ“ҮӮЙҢьӮ©ӮӨ–Ҫ—ЯӮӘүәӮіӮкӮҪҒB‘еҺRӮНҢRҗlӮЕӮ ӮйҒBҗнҸкӮЙӮ ӮБӮДӮНҒA–Ў•ы(җӯ•{ҢR)ӮМҸҹ—ҳӮЙҚЕ‘PӮрҗsӮӯӮіӮҙӮйӮр“ҫӮИӮўҒBҚЕӮаҗhӮўҗнӮўӮЖӮИӮБӮҪҒB”ј”NҲИҸгӮЙ“nӮйҢғҗнӮМ––ҒAҗјӢҪӮӘ—§ӮДвДӮаӮБӮҪҸйҺRӮЦӮМ–CҢӮӮМҺһӮӘ—ҲӮҪҒBӮ»ӮМ”CӮНҒA”сҸоӮЙӮа‘еҺRҠЮӮЙүәӮБӮҪҒB ‘Ғ’©4ҺһӮЙҺnӮЬӮБӮҪҚUҢӮӮНҒA–ҫӮҜ•ыӮЙӮН‘еҗЁӮӘҢҲӮЬӮБӮҪҒBҗјӢҪҺ©җnҒBҲв‘МӮӘҸтҢхҺӣӮЙү^ӮОӮкӮҪҒB‘еҺRӮНҒAҢҲӮөӮДӮ»ӮкӮрҢ©ӮжӮӨӮЖӮНӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗјӢҪ•vҗlӮЙ’ўҲФӢа(Ҳв‘°ӮЙ‘ЎӮйӮЁӢа)Ӯр“nӮ»ӮӨӮЖӮөӮҪӮӘ“ЛӮ«•ФӮіӮкҒAҠЮӮМҺoӮНӢғӮ«ӮИӮӘӮзҠЮӮрҗУӮЯ—§ӮДӮҪҒBӢ№ӮӘ’ЈӮи—фӮҜӮйӮжӮӨӮИҗhӮў—§ҸкӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA”ЮӮНҲкҗШ•ЩүрӮрӮөӮИӮ©ӮБӮҪҒB—қүрӮөӮДӮаӮзӮҰӮйӮЖҺvӮБӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮ©ӮзӮҫҒBҒuҢZӮіӮҹӮҫӮҜӮӘҒAӮнӮ©ӮБӮДӮӯӮкӮкӮОӮ»ӮкӮЕӮўӮўҒvҒBҗјӢҪӮМҗVҗӯ•{ӮЦӮМҒuӮІ•тҢцҒvӮрҢ©“НӮҜӮйӮМӮҫҒBӮ»ӮсӮИҺvӮўӮӘҒA”ЮӮМҗSӮрӮ¬ӮиӮ¬ӮиӮМӮЖӮұӮлӮЕҺxӮҰӮДӮўӮҪҒB җј“мҗн‘ҲӮМ—Ӯ”NҒA–ҫҺЎ“VҚcӮӘ–k—ӨҒE“ҢҠC’n•ыӮрҸ„ҚKӮіӮкӮҪӮЖӮ«ҒA‘еҺRҠЮӮНӮ»ӮМ“ҜҚsӮр–ҪӮ¶ӮзӮкӮҪҒB“VҚcӮӘ‘еҺRӮЙҢкӮиҺnӮЯӮҪҒBҒuҺ„ӮНҒAҗјӢҪӮЙҲзӮДӮзӮкӮҪҒBҚЎҒAҗјӢҪӮНҒw‘ҜҒxӮМүҳ–јӮр’…Ӯ№ӮзӮкҒAӮіӮјүчӮөӮ©ӮлӮӨӮЖҺvӮӨҒBҺ„ӮаүчӮөӮўҒBҗјӢҪ–SӮ«ҢгҒAҺ„ӮНӮ»ӮМ•ыӮрҗјӢҪӮМҗg‘гӮнӮиӮЖҺvӮӨӮјҒvҒB ‘еҺRӮНҠҙҢғӮЕҗgӮӘҗkӮҰӮҪҒBҒuӮаӮБӮҪӮўӮИӮўӮЁҢҫ—tӮЕӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒB‘Sҗg‘S—мӮр•ГүәӮЙ•щӮ°ӮйҸҠ‘¶ӮЕӮІӮҙӮўӮЬӮ·ҒvӮЖ“ҡӮҰӮйӮМӮӘӮвӮБӮЖӮҫӮБӮҪҒBҗјӢҪӮрҺёӮБӮДҲИ—ҲҒA‘еҺRӮНҢіӢCӮрҺёӮБӮДӮўӮҪҒBүҪӮрӮ·ӮйӮЙӮаҒAӢCҚҮӮўӮӘ“ьӮзӮИӮўӮМӮҫҒBӮұӮМҺһӮМ“VҚcӮМӮЁҢҫ—tӮЕҒAҗјӢҪ–SӮ«ҢгӮМҺ©•ӘӮМҗ¶Ӯ«•ыӮӘҢ©ӮҰӮДӮ«ӮҪҒBҒuҺ©•ӘӮНҢZӮіӮҹӮМ‘гӮнӮиӮЖӮИӮлӮӨҒvҒBҗјӢҪӮМҗlҗ¶Ӯрҗ¶Ӯ«ӮкӮОӮўӮўӮМӮҫҒB‘еҺRӮМ–ЪӮ©ӮзҒA”MӮў—ЬӮӘӮЖӮЯӮЗӮИӮӯ–jӮрӮВӮҪӮБӮҪҒB ҒЎ‘еҺR—¬ӮМ“қ—ҰҸp “ъ–{ӮӘҗжҗiҚ‘ӮМ’ҮҠФ“ьӮиӮрүКӮҪӮ·ӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪ“ъҗҙҗн‘Ҳ(1894”N)ҒA“ъҳIҗн‘Ҳ(1904”N)ӮМҸҹ—ҳӮНҒA‘еҺRҠЮӮМ‘¶ҚЭ”ІӮ«ӮЙҢкӮйӮұӮЖӮНӮЕӮ«ӮИӮўҒB‘ж“сҢRӮМҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮДҺQҗнӮөӮҪ“ъҗҙҗн‘ҲӮМҸoҗwӮЙҚЫӮөҒAҒu“GҚ‘–ҜӮЖӮўӮҰӮЗӮаҗmҲӨӮрҺқӮБӮДҗЪӮ·ӮЧӮөҒvӮЖҢPҺҰӮөӮҪҒBҢPҺҰӮрҗӮӮкӮй‘еҺRӮМҺpӮЙҒAҒu—EҺТӮНӢ`ӮЙ“ДӮӯӮИӮҜӮкӮОӮИӮзӮсҒvӮЖҢкӮБӮДӮўӮҪҗјӢҪ—Іҗ·ӮрҢ©ӮҪҺТӮНҒAҢҲӮөӮДҸӯӮИӮӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB“G•әӮ©ӮзӮаҸМҺ^ӮіӮкӮҪ“ъ–{ҢRӮМӢK—ҘҗіӮөӮіӮНҒAҢгҒXӮЬӮЕҢкӮиҺнӮЙӮИӮБӮДӮўӮйҒB –һҸBҢR‘ҚҺi—ЯҠҜӮЖӮөӮДҗнӮБӮҪ“ъҳIҗн‘ҲӮЕӮаҒA‘еҺRҠЮӮМ‘¶ҚЭҠҙӮНҲі“|“IӮҫӮБӮҪҒB‘еҺRҠЮӮМӢ–үВӮр“ҫӮҪҚмҗнӮИӮзӮОҒAӮ«ӮБӮЖҸҹӮДӮйҒBӮ»ӮӨҺvӮнӮ№Ӯй—НҒAҗl“ҝӮӘ‘еҺRӮЙӮНӮ ӮБӮҪҒBҒuӮұӮМҗн‘ҲӮНҒA‘еҺRҠЮӮЕҢҲӮЬӮйҒvӮЖҢкӮБӮҪӮМӮНҒAҺQ–dҺҹ’·ӮМҺҷӢКҢ№‘ҫҳYӮЕӮ ӮйҒB—ӨҢRӮМҸҹ—ҳӮНҒAӮұӮМ“сҗlӮМ“сҗlҺOӢrӮЙ•үӮБӮДӮўӮҪҒB‘еҺRӮНҺҷӢКӮМҚмҗнӮр‘S–К“IӮЙҗM—ҠӮө”CӮ№җШӮБӮҪҒB”CӮ№ӮҪҲИҸгӮНҢыҸoӮөӮрӮөӮИӮўҒBӮ»ӮөӮДӮ»ӮМҢӢүКӮЙ‘ОӮөӮДӮНҒAҺ©•ӘӮӘҗУ”CӮрҺжӮкӮОӮўӮўҒB‘еҺRӮНӮұӮМғXғ^ғCғӢӮрҠСӮўӮҪҒB ҸHҺRҚDҢГҸӯҸ«—ҰӮўӮйӢR•ә‘жҲк—·’cӮӘғҚғVғAҢRӮЙ•пҲНӮіӮкӮйӮЖӮўӮӨ•сҚҗӮӘҒAҺi—Я•”ӮЙ”тӮСҚһӮсӮЕӮ«ӮҪҒBҸHҺR—·’cӮӘ•цӮкӮкӮОҒA‘SҢRӮӘ•Ә’fӮіӮкӮйҒBҺi—Я•”ӮЙҗнңЙӮӘ‘–ӮБӮҪҒBҸо•сӮӘҚц‘ҺҒBҺҷӢКӮМ“{җәӮӘ”тӮФҒBӮҪӮҫӮІӮЖӮЕӮНӮИӮў•өҲНӢCӮӘ‘еҺRӮМ•”ү®ӮЙӮа“`ӮнӮБӮДӮ«ӮҪҒB‘еҺRӮНҒAӮұӮМҺһҒuӮЁӮўӮӘҒAҺwҠцӮрӮЖӮйҒvӮЖҢҲ’fӮөӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮөӮ©ӮөҷтҡlӮЙҺvӮБӮҪҒBҢZӮіӮҹ(җјӢҪ)ӮҫӮБӮҪӮзӮЗӮӨӮ·ӮйӮҫӮлӮӨӮ©ҒBӮ»ӮӨҺvӮў•ФӮөӮҪӮЖӮҪӮсҒA‘еҺRӮНҢR•һӮр’EӮ¬ҒAӮнӮҙӮЖҗQӮйҺx“xӮрӮөӮДҒA–°Ӯ»ӮӨӮИҠзӮЕғhғAӮМғmғuӮЙҺиӮрӮ©ӮҜӮҪҒBӮ»ӮөӮДҒAӮЖӮЪӮҜӮҪ’ІҺqӮЕҒAҒuӮНҒ[ҒAӮИӮсӮ¶ӮбҒAӮЙӮ¬ӮвӮ©Ӯ¶ӮбӮМӮӨҒvҒBӮЭӮсӮИӮ ӮБӮҜӮЙӮЖӮзӮкӮДҒAҗQҠФ’…ҺpӮМ‘еҺRӮЙ–ЪӮрҢьӮҜӮҪҒBҒuӮіӮБӮ«Ӯ©ӮзҒA‘е–CӮМү№ӮӘӮөӮҝӮеӮиӮЬӮ·ӮӘҒAҚЎ“ъӮНӮЗӮұӮјӮЕҒAӮўӮӯӮіӮЕӮаӮвӮБӮДӮІӮҙӮйӮМӮ©ҒHҒvҒB ‘еҺRӮМҠФӮМ”ІӮҜӮҪҗәӮЙҲкҗlӮӘҸОӮБӮҪҒBӮ»ӮкӮӘҲшӮ«ӢаӮЖӮИӮБӮДҒAҺi—Я•”ӮМ‘SҲхӮӘҸОӮўҸoӮөӮҪҒBҺi—Я•”ӮЙ•YӮБӮДӮўӮҪӢЩ’ЈҠҙӮӘҲкӢCӮЙҳaӮзӮ¬ҒA—вҗГӮіӮӘ–ЯӮиҒAҸуӢө”cҲ¬ӮӘ“IҠmӮЙӮИӮіӮкӮйӮжӮӨӮИӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB‘еҺRӮНҒAҢҲӮөӮДӢр“ЭӮИғҠҒ[ғ_Ғ[ӮЕӮНӮИӮўҒBӮЮӮөӮл“ӘӮМүс“]ӮНӮ·ӮұӮФӮ鑬ӮўҒBҸуӢө”FҺҜӮа“IҠmӮЕӮ ӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA’mӮБӮДӮўӮИӮӘӮзҒA’mӮзӮИӮўӮУӮиӮрӮ·ӮйҒBӮұӮкӮН”E‘П—НӮЖ’_—НӮӘӮИӮҜӮкӮОҒAӮЕӮ«ӮИӮўӮұӮЖӮИӮМӮҫҒB‘еҺR—¬“қ—ҰӮМҗ^җ‘ӮЕӮ ӮБӮҪҒB ҒЎҲӨҚИүЖӮЕҺq”П”Y “ъҳIҗн‘ҲҢгҒA‘еҺRӮН“Яҗ{(“И–ШҢ§)ӮМ•К“@ӮЕ”_ҚмӢЖӮИӮЗӮЙ‘ЕӮҝҚһӮЮ—IҒXҺ©“KӮМҗ¶ҠҲӮЙ“ьӮБӮҪҒB”ЮӮр‘Қ—қ‘еҗbӮЙҗ„‘ХӮөӮжӮӨӮЖӮ·Ӯй“®Ӯ«ӮаӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮкӮрҢЕҺ«ҒBҗӯҺЎ“IӮИ–мҗSӮЖӮН–іүҸӮМ’jӮҫӮБӮҪҒBүЖҗlӮЙ‘ОӮөӮДӮаҒA•”үәӮЙ‘ОӮөӮДӮаҒAҲР’ЈӮйӮұӮЖӮӘӮИӮўҒBҗlӮМҲ«ҢыӮрҢҫӮӨӮұӮЖӮаӮИӮўҒBҗжҚИӮМҺҖҢгҒAҢгҚИӮЙ“ьӮБӮҪҺМҸјӮНҒAӮ»ӮӨӮўӮӨӮЖӮұӮлӮӘ‘еҺRӮрҚDӮ«ӮЙӮИӮБӮҪ—қ—RӮМҲкӮВӮҫӮБӮҪӮЖҢҫӮБӮДӮўӮйҒBҺ„җSӮИӮӯҒAҠCӮМӮжӮӨӮЙҚLӮўҗSӮрҺқӮҝҒA’NӮЙ‘ОӮөӮДӮаҢӘӢ•ӮИ‘еҺRӮМҺpӮНҗјӢҪ—Іҗ·ӮрңfңiӮЖӮіӮ№ӮҪҒB ҲӨҚИүЖӮЕҺq”П”YӮаҒA‘еҺRӮМ“Б’·ӮМҲкӮВӮЕӮ ӮБӮҪҒBҺdҺ–ӮрҸIӮҰӮйӮЖҠсӮи“№ӮрӮ№ӮёҒAӮЬӮБӮ·Ӯ®ӮЙүЖ‘°ӮМӮаӮЖӮЙӢAӮйҸKҠөӮНҗ¶ҠU‘ұӮўӮҪҒBҢ|ҺТ—VӮСӮИӮЗӮрҚDӮЬӮёҒAүЖ‘°ӮЖүЯӮІӮ·ҺһӮр‘еҗШӮЙӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮйҒBӮ»ӮсӮИүЖ‘°ӮЙҢ©ҺзӮзӮкӮИӮӘӮзҒA1916”N12ҢҺ10“ъҒA‘еҺRҠЮӮН74”NӮМҗ¶ҠUӮрҸIӮҰүi–°ӮөӮҪҒBҚИӮМҺМҸјӮНҒA‘еҺRӮӘҲУҺҜһNһOӮМ’ҶҒAҒuҢZӮіӮҹҒvӮЖӮӨӮнӮІӮЖӮрҢҫӮӨӮМӮр•·ӮўӮДӮўӮйҒBҒuӮвӮБӮЖҗјӢҪӮіӮсӮЖүпӮҰӮҪӮМӮЛҒvҒBҺМҸјӮН•vӮЙӮ»ӮӨҢкӮиӮ©ӮҜӮҪҒBҒ@ |
|
| Ғ@ | |
| Ғ@ | |
| ҒЎ–ҫҺЎҺһ‘г –ң”ҺӮЙҢ©ӮйҚЕҗVӢZҸp | |
| ҒЎ”MғGғlғӢғMҒ[ӮМ—ҳ—p | |
|
Ғ`ҸцӢCӢ@ҠЦӮ©ӮзғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ӮЬӮЕҒ`
үж‘ңӮНҒA1876”NӮМғtғBғүғfғӢғtғBғA–ң”ҺӮМӢ@ҠBҠЩӮЕҒAӢ@ҠBӮҪӮҝӮр“®Ӯ©ӮөӮДӮўӮҪӢҗ‘еӮИҸцӢCӢ@ҠЦҒB“ҜӮ¶үпҸкӮЙӮНғKғXғGғ“ғWғ“ӮаҸo“WӮіӮкҒAӮұӮМҗ””NҢгӮЙӮНғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ӮӘ“oҸкӮ·ӮйҒB үО—НҒA“d—НҒAҗ…—Н“ҷӮМғGғlғӢғMҒ[ӮрҢp‘ұ“IӮЙ“®—НӮЙ•ПҠ·Ӯ·Ӯй‘•’uӮрҢҙ“®Ӣ@ӮЖӮўӮӨҒB’ҶӮЕӮа”MғGғlғӢғMҒ[Ӯр—ҳ—pӮ·ӮйӮаӮМӮӘҒu”MӢ@ҠЦҒvӮҫӮӘҒAӮұӮкӮНҺҹӮМ2ӮВӮЙ•Ә—ЮӮЕӮ«ӮйҒB 1ҒDҠO”RӢ@ҠЦ”R—ҝӮМ”RҸДӮжӮи”ӯҗ¶ӮөӮҪ”MӮӘ”}‘МӮЖӮИӮиҒAҠФҗЪ“IӮЙ“®—НӮрҗ¶ӮЮҒB —б)ҸцӢCӢ@ҠЦҒAҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“ӮИӮЗ2ҒD“а”RӢ@ҠЦ”R—ҝӮМ”RҸДӮЕ”ӯҗ¶ӮөӮҪғKғXӮ»ӮМӮаӮМӮӘ’јҗЪ“®—НӮрҗ¶ӮЮҒB —б)ғKғXғGғ“ғWғ“ҒAғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ҒAғfғBҒ[ғ[ғӢғGғ“ғWғ“ӮИӮЗ ҒЎүО–тӮ©ӮзҸцӢCӮЦҒ|ҠO”RӢ@ҠЦӮМ’aҗ¶ ‘еӮ«ӮИ“®—НӮрҗ¶ӮЭҸoӮ·Ӣ@ҠBӮЖӮөӮД”MӢ@ҠЦӮМ–{ҠiҺg—pӮӘҺnӮЬӮБӮҪӮМӮНҺYӢЖҠv–ҪҲИҚ~ӮЕӮ ӮйӮӘҒA17җўӢIӮЙӮаҒAүО–тӮвҸцӢCӮр—ҳ—pӮөӮҪҠO”RӢ@ҠЦӮЕҗ…ӮрӢӮӮЭҸгӮ°ӮйҺҺӮЭӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBӮұӮМҚ ҒA’YҚzӮЕӮН”rҗ…ӮӘ”YӮЭӮМҺнӮҫӮБӮҪҒB1712”NҒAғjғ…Ғ[ғRғҒғ“(T. Newcomen)ӮӘҗО’YӮр”RӮвӮөӮДҗ…Ӯрҗ…ҸцӢCӮЙӮөҒAӮ»ӮкӮӘ—вӮҰӮДҗ…ӮЙ–ЯӮйҺһӮЙ‘еӢCҲіӮӘғVғҠғ“ғ_Ғ[(“ӣ)“аӮМғsғXғgғ“ӮрүәӮ°ӮД“®—НӮЙӮ·Ӯй—gҗ…Ӣ@ӮрҠJ”ӯӮ·ӮйӮЖҒA‘ҪӮӯӮМҚzҺRӮЕҺg—pӮіӮкӮҪҒB ҒЎҸцӢCӢ@ҠЦӮМ“oҸк ғjғ…Ғ[ғRғҒғ“ӮМҸцӢCӢ@ҠЦӮНҒA”MҢш—ҰӮМҲ«ӮўӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮМҢгҒA•ңҗ…ҠнӮр—pӮўӮДҢш—ҰӮжӮӯ“®—НӮр”ӯҗ¶ӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЙҗ¬ҢчӮөӮҪӮМӮӘҒAғҸғbғg(J. Watt)ӮЕӮ ӮйҒB”ЮӮӘ1776”NӮЙүь—ЗӮөӮҪҸцӢCӢ@ҠЦӮН”MҢш—ҰӮӘ‘е•қӮЙҢьҸгӮөӮДӮЁӮиҒA1780”N‘гӮЙ—gҗ…ғ|ғ“ғvӮМ“®—НҢ№ӮЖӮөӮДӢ}‘¬ӮЙ•ҒӢyӮөӮҪҒBғҸғbғgӮНҚXӮЙүь—ЗӮрҸdӮЛҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮМ“®—НӮНҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗ…ҺФӮЙ‘ЦӮнӮБӮД*ҚHҸкӮЕӮаҺgӮнӮкҒAҗ»“SҸҠӮЕӮНҸцӢCғnғ“ғ}Ғ[ӮӘҠҲ–фӮөӮҪҒB1803”NӮЙӮНҗўҠEҸүӮМҸцӢCӢ@ҠЦҺФӮӘҠ®җ¬ӮөҒA1807”NӮЙӢD‘DӮӘҺА—pү»ӮіӮкӮйҒB1884”NӮЙӮНғpҒ[ғ\ғ“ғY(C. A. Parsons)ӮӘҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“(үHҚӘҺФӮӘүс“]Ӯ·Ӯй)ӮМ“БӢ–ӮрҺж“ҫӮ·ӮйӮЖҒA‘D”•Ӯв”ӯ“dӮМҚЫӮМ“®—НӮЙҺgӮнӮкӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮНҒAҚzҺRҒAҗ»“SӢЖҒA•Ё—¬ӮИӮЗ—lҒXӮИ•Ә–мӮЕүһ—pӮіӮкӮДҺYӢЖҠv–ҪӮМҢҙ“®—НӮЖӮөӮД”ӯ“WӮрҗӢӮ°ӮҪӮӘҒA19җўӢIҢг”јӮЙӮНҒA‘еҢ^ӮЕҲЪ“®—pӮЙӮН•sҢьӮ«ҒAғ{ғCғүҒ[”ҡ”ӯҺ–ҢМӮӘ‘Ҫ”ӯҒA”MҢш—ҰӮӘ’бӮўӮИӮЗҢҮ“_ӮӘ–Ъ—§ӮҝҺnӮЯӮйҒB“БӮЙҒAҢр’К—A‘—Ӣ@ҠЦӮЙӮНҢyӮӯӮДӮжӮиҢш—ҰӮМӮжӮў“®—НҢ№ӮӘӢҒӮЯӮзӮкҒAӮ»ӮкӮЙүһӮҰӮД“oҸкӮөӮҪӮМӮӘ“а”RӢ@ҠЦӮЕӮ ӮйҒB *ӮИӮЁҒAҗ…—НӮМ—ҳ—pӮаҚH•vӮӘҺҺӮЭӮӘ‘ұӮҜӮзӮкҒA–ң”ҺӮЙӮаҗ…—НӢ@ҠЦӮӘҸo“WӮіӮкӮҪҒB ҒЎ“а”RӢ@ҠЦӮМ’aҗ¶ –§•ВӢуҠФӮЕҚ¬ҚҮӢCӮр”RӮвӮөӮД“®—НӮр”ӯҗ¶ӮіӮ№ӮйҢ»ҚЭӮМ“а”RӢ@ҠЦӮНҒA1794”NӮЙғXғgғҠҒ[ғg(R. Street)ӮӘҚlҲДӮөӮҪӮЖӮўӮнӮкӮйҒBӮ»ӮМҢгҒA1860”NӮЙғӢғmғAҒ[ғӢ(J. J. E. Lenoir)ӮӘғKғXғGғ“ғWғ“ӮрҺА—pү»ӮіӮ№ҒAҗўҠEҸүӮМ“а”RӢ@ҠЦӮӘ’aҗ¶ӮөӮҪҒBӮұӮкӮНҒAҗО’YғKғXӮЖӢуӢCӮМҚ¬ҚҮӢCӮрҺg—pӮөӮҪҒu2ғTғCғNғӢҒv(2Қs’ц)ӮМғGғ“ғWғ“ӮЕҒA”MҢш—ҰӮНҸцӢCӢ@ҠЦӮМ–с3”{ӮаҢьҸгӮөӮҪҒB”ЮӮМғGғ“ғWғ“ӮН1867”N‘ж2үсғpғҠ–ң”ҺӮЕҸo•iӮіӮкӮДӮўӮйҒB“ҜӮ¶ғpғҠ–ң”ҺӮЕӮНҒAғIғbғgҒ[(N. A. Otto)ӮЖғүғ“ғQғ“(E. Langen)ӮӘҒAғKғX”RҸДҺһӮЙғsғXғgғ“ӮӘҸгӮӘӮиҒAӮ»ӮМҢг‘еӢCҲіӮЕүәӮӘӮйӮЖӮўӮӨҒA”R”пӮМ—ЗӮўҒuғtғҠҒ[ҒEғsғXғgғ“Ӣ@ҠЦҒvӮЕӢаҸЬӮрҺуҸЬӮөӮДӮўӮйҒB1876”NӮЙӮНҒAғIғbғgҒ[ӮНӢz“ьҒEҲіҸkҒE–c’ЈҒE”rӢCӮМҒu4ғTғCғNғӢҒvӮМғKғXғGғ“ғWғ“ӮрҺҺҚмӮөҒA—Ӯ”N“БӢ–ӮрҺж“ҫӮөӮҪҒB”ЮӮМғGғ“ғWғ“ӮНҸo—НҒE”MҢш—ҰӮЙ—DӮкҒA‘ӣү№ӮаҸӯӮИӮ©ӮБӮҪҒB ҒЎ”R—ҝӮМ•П‘JҒ|җО’YӮ©ӮзҗО–ыӮЦ ӮұӮкӮзӮМ“а”RӢ@ҠЦӮМ”R—ҝӮНӮўӮёӮкӮаҗО’YғKғXӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҒAҲЪ“®—pӮЙӮНҸdӮўғKғX”ӯҗ¶ҠнӮИӮЗӮӘ•K—vӮҫӮБӮҪҒBӮ»ӮұӮЕҒA—eҗПӮ ӮҪӮиӮМ”ӯ”M—КӮӘҚӮӮӯү^”АӮӘ—eҲХӮИ”R—ҝӮЖӮөӮДҒAҗО–ыӮрҗёҗ»ӮөӮҪғKғ\ғҠғ“Ӯр—pӮўӮйҢӨӢҶӮӘҗiӮЯӮзӮкӮҪҒB 1883”NҒAғ_ғCғҖғүҒ[(G. Daimler)ӮӘғKғ\ғҠғ“—pӮМӢCү»ҠнӮр”хӮҰӮҪ4ғTғCғNғӢӮМғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ӮрҠJ”ӯӮөҒAғGғ“ғWғ“ӮМҸ¬Ң^ү»ҒEҚӮҗ«”\ү»ӮЙҗ¬ҢчӮ·ӮйҒB“а”RӢ@ҠЦӮН“_үО‘•’uӮа‘еҗШӮҫӮӘҒA”ЮӮН”MҠЗӮрғVғҠғ“ғ_Ғ[ӮЙҺhӮөҒAҺ©‘R’…үОӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨ“БӢ–ӮаӮЖӮБӮДӮўӮйҒB1886”NӮЙӮНғxғ“ғc(C. F. Bentz)ӮӘҗўҠEҚЕҸүӮМҺА—p“IӮИғKғ\ғҠғ“Һ©“®ҺФ(3—ЦҺФ)Ӯрҗ»ҚмӮөӮҪҒB2ғTғCғNғӢӮМғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ӮаҚмӮзӮкҒA1881”NӮЙғNғүҒ[ғN(D. Clerk)ӮӘҺА—pү»‘жҲкҚҶӮр”ӯ–ҫҒA1891”NӮЙғfғC(J. Day)ӮӘ”ӯ–ҫӮөӮҪғGғ“ғWғ“ӮН4ғTғCғNғӢӮМӮаӮМӮжӮиғRғ“ғpғNғgӮЕҒA20җўӢIӮЙғIҒ[ғgғoғCӮвғӮҒ[ғ^Ғ[ғ{Ғ[ғgӮЙ•ҒӢyӮөӮҪҒB1887”Nғ{ғbғVғ…(R. A. Bosch)ӮӘҺҘҗО”ӯ“dӢ@Ӯр—pӮўӮҪүОүФ“_үО•ыҺ®ӮрҠ®җ¬ҒA1893”Nғ}ғCғoғbғn(W. Maybach)ӮӘ–¶җҒӮ«Һ®ӮМӢCү»ҠнӮр”ӯ–ҫӮ·ӮйӮИӮЗғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“ӮМҠJ”ӯӮӘҗiӮсӮҫҒB ҲИҢгҒAғKғ\ғҠғ“ӮЙ‘гӮнӮи’бҺҝ–ыӮр”R—ҝӮЖӮ·ӮйғGғ“ғWғ“ҠJ”ӯӮЦӮМҺщ—vӮаҚӮӮЬӮиҒA1893”NҒAғfғBҒ[ғ[ғӢ(R. Diesel)ӮӘҢy–ыӮр”R—ҝӮЖӮөӮҪҲіҸkӢуӢC’…үОҺ®ғGғ“ғWғ“(ғfғBҒ[ғ[ғӢғGғ“ғWғ“)Ӯр”ӯ•\ҒA1895”NӮЙҠ®җ¬ӮіӮ№ҒAҲАүҝӮИҢy–ыӮвҸd–ыӮМ—ҳ—pӮЙ“№ӮрҠJӮўӮҪҒB 1870”N‘гӮ©Ӯз1890”N‘гӮНҢ»ҚЭӮМғGғ“ғWғ“ӢZҸpӮМҠо‘bӮӘҠm—§ӮіӮкӮҪү©ӢаҺһ‘гӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮөӮД2“xӮЙӮнӮҪӮйҗўҠE‘еҗнҠъӮрҢ}ӮҰӮйӮЖҒAҢR—pӢ@Ӯв•әҠнӮЦӮМүһ—pӮМӮҪӮЯӮЙӢZҸpҠJ”ӯӮӘүБ‘¬ӮөҒA”MӢ@ҠЦӮНӮіӮзӮИӮйҗi•аӮрҗӢӮ°ӮДӮўӮӯӮұӮЖӮЙӮИӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎ“dӢCғGғlғӢғMҒ[ӮМ—ҳ—p | |
|
үж‘ңӮНҒA1893”NғVғJғS–ң”ҺӮМ“dӢCҠЩӮЙҗЭ’uӮіӮкӮҪҸцӢCӢ@ҠЦғAғҠғXғGғ“ғWғ“ӮЕӮ ӮйҒBӮұӮкӮЕ”ӯ“dӢ@ӮрүсӮөӮД”ӯ“dӮөҒAүпҸк“аӮЙ“dӢCӮрӢҹӢӢӮөӮҪҒBғVғJғS–ң”ҺӮЕӮН“dӢCӮр—ҳ—pӮөӮҪ—lҒXӮИ”ӯ–ҫ•iӮӘ“WҺҰӮіӮкҒA“dӢCӮМҺһ‘гӮМ“һ—ҲӮрҲуҸЫӮГӮҜӮҪҒB
18җўӢIҲИ‘OӮНҒA“dӢCӮЖӮўӮҰӮО–ҖҺCӮЙӮжӮи”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҗГ“dӢCӮҫӮБӮҪҒB1800”NӮЙғ”ғHғӢғ^(A. Volta)ӮӘҒA—nүtӮрүоӮөӮДҲЩҺнӢа‘®ӮрҗЪҗGӮіӮ№ӮҪӮЖӮ«ӮЙ“dӢCӮӘ”ӯҗ¶Ӯ·ӮйҢ»ҸЫӮр”ӯҢ©ӮөӮДўғ”ғHғӢғ^ӮМ“d‘Н(“d’r)ЈӮр”ӯ–ҫӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҺқ‘ұ“IӮЙ“dӢCӮМ—¬ӮкӮрӢNӮұӮ·ӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЖӮИӮБӮҪҒB”ЮӮМ”ӯ–ҫӮНҒAӮЩӮЗӮИӮӯҒAғNғӢҒ[ғNғVғғғ“ғN(W. Cruikshank)ӮЙӮжӮБӮДҺА—p“IӮИ“d’rӮЙүь—ЗӮіӮкӮҪҒB 1821”NӮЙӮНғtғ@ғүғfҒ[(M. Faraday)ӮӘӮНӮ¶ӮЯӮД“d“®Ӣ@(ғӮҒ[ғ^Ғ[)ӮМҢҙ—қӮрҚlҲДӮ·ӮйҒBӮұӮкӮНҒA“d—¬Ӯр—¬ӮөӮҪҗjӢаӮрҺҘҗОӮЙӢЯӮГӮҜӮйӮЖ—НӮрҺуӮҜӮйӮЖӮўӮӨҢ»ҸЫӮр—ҳ—pӮөӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪҒB”ЮӮН1831”NӮЙӮНӢtӮЙҒA“SҗSӮЙҠӘӮўӮҪғRғCғӢӮЙүiӢvҺҘҗОӮрҸoӮө“ьӮкӮ·ӮйӮЖ“dӢCӮӘҗ¶Ӯ¶ӮйҒAӮВӮЬӮиҺҘӢCӮЙӮжӮБӮД“dӢCӮрҚмӮкӮйӮЖӮўӮӨў“dҺҘ—U“ұӮМ–@‘ҘЈӮр”ӯ•\ӮөӮҪҒBҢ»ҚЭӮМ”ӯ“dӢ@ҒA•ПҲіҠнӮНӮ·ӮЧӮДӮұӮМүһ—pӮЕӮ ӮйҒB—Ӯ”NҒAғsғNғVҒ[(H. Pixii)ӮӘӮұӮкӮрүһ—pӮөӮДҗўҠEҸүӮМ”ӯ“dӢ@(ғ_ғCғiғӮ)Ӯр”ӯ–ҫӮөӮҪҒB“d“®Ӣ@ӮЖ”ӯ“dӢ@ӮНҒA“ҜӮ¶Ңҙ—қӮр—ҳ—pӮөӮДӮўӮйӮӘҒA‘OҺТӮН“dӢCғGғlғӢғMҒ[ӮЙӮжӮиӢ@ҠBӮрҚм“®ӮіӮ№ҒAҢгҺТӮНӢ@ҠBӮМҚм“®ӮЙӮжӮйүс“]—НӮЕ“dӢCғGғlғӢғMҒ[Ӯр”ӯҗ¶ӮіӮ№ӮйӮЖӮўӮӨ“ӯӮ«ӮрӮ·ӮйҒB 1860”N‘OҢгӮЙӮИӮйӮЖҒAғAҒ[ғN“”ӮМҺА—pү»ҒA“dҗMӢ@ӮМ“oҸкӮИӮЗӮЕ“d—НҺщ—vӮӘҚӮӮЬӮиҒAғWҒ[ғҒғ“ғX(W. von Siemens)ӮвғOғүғҖ(Z. T. Gramme)ӮМҗ»•iӮЙ‘г•\ӮіӮкӮйҺА—p“IӮИ”ӯ“dӢ@ӮӘ‘ұҒXӮЖҗ»ҚмӮіӮкӮйҒB1882”NӮЙӮНҒAғCғMғҠғXӮЕҲк”КҸБ”пҺТҢьӮҜӮЖӮөӮДӮНҸүӮМ”ӯ“dҸҠ(ғzғӢғ{Ғ[ғ“ҒEғ”ғ@ғCғAғ_ғNғgHolborn Viaduct)ӮӘүТ“®ӮөӮҪҒBҲк•ыҒA“d“®Ӣ@ӮӘҺА—pү»ӮіӮкӮҪӮМӮН”ӯ“dӢ@ӮжӮиӮаҸӯҒX’xӮкӮҪ1870”N‘гҲИҚ~ӮЕӮ ӮйҒB1873”NӮЙӮНҒAғEғBҒ[ғ“–ң”ҺӮЕҗжӮМғOғүғҖӮӘ’ј—¬“d“®Ӣ@ӮрҸo“WӮөӮҪҒBӮұӮМҚ ӮМ“d—НӢZҸpӮН’ј—¬ӮӘҺе—¬ӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA1880”N‘гҢг”јҲИҚ~ҒAғtғFғүҒ[ғҠғX(G. Ferraris)ӮЙӮжӮй“с‘ҠҢ𗬓d“®Ӣ@ӮМ”ӯ–ҫҒAғEғFғXғeғBғ“ғOғnғEғX (Westinghouse) ҺРӮЙӮжӮйҢ𗬕ыҺ®ӮМҚМ—pҒAғtғFғүғ“ғeғB(S. Z. de Feranti)ӮЙӮжӮйҢ𗬑—“d•ыҺ®ӮМ”ӯ“dҸҠҢҡҗЭӮИӮЗҢр—¬ӮМ‘д“ӘӮӘҺnӮЬӮйҒBӮұӮкӮЙ”әӮўҒAҢ𗬕ыҺ®ӮМ“d“®Ӣ@ӮМ“oҸкӮӘ‘ТӮҪӮкӮҪҒB1887”NӮЙғeғXғү(N. Tesla)ӮӘҺА—p“IӮИҢ𗬓d“®Ӣ@(“с‘Ҡ—U“ұ“d“®Ӣ@)Ӯр”ӯ–ҫӮ·ӮйҒB ”ӯ“dӢ@ӮМ“oҸкӮЖӮ»ӮМҢгӮМүь—ЗӮНҒA‘е—КӮМ“d—НӢҹӢӢӮрҺАҢ»ӮөҒA“d“”ҒA“d“®Ӣ@ҒA“dҗMҒE“dҳbӮМ”ӯ’BӮр‘ЈӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒAҺи“®ӮЕӮ ӮБӮҪ”_Ӣ@ӢпӮвҗ¶ҠҲ—p•iӮИӮЗ—lҒXӮИ•Ә–мӮЕ“dӢCӮӘ—ҳ—pӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB“БӮЙҒAӮұӮкӮЬӮЕҸцӢCӮр—ҳ—pӮөӮДӮўӮҪӢ@ҠЦҺФӮӘ“d“®ӮЙӮИӮйӮИӮЗҒA19җўӢIҢг”јӮЙӮЁӮўӮДӮНҸцӢCӮ©Ӯз“dӢCӮЦӮМ“®—НӮМ‘еӮ«ӮИ•Пү»ӮӘӮ ӮБӮҪӮЖҢҫӮҰӮжӮӨҒBҲг—ГҒAҗ¶ҠҲ—p•iӮИӮЗ—lҒXӮИӢZҸp•Ә–мӮЕӮа“dӢCӮМ—ҳ—pӮӘҺҺӮЭӮзӮкӮҪҒB ҒЎ ғGғҢғxҒ[ғ^ / ғGғҢғxҒ[ғ^ӮМ—рҺjӮНҲДҠOҢГӮӯҒA19җўӢIҸү“ӘӮЙӮНҒAҗ…ҲіӮр—ҳ—pӮөӮҪғGғҢғxҒ[ғ^ӮӘҠJ”ӯӮіӮкӮДӮўӮҪҒB1853”NӮМғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғN–ң”ҺӮЕӮНҒAҸцӢCӮр“®—НӮЖӮөӮҪғIҒ[ғeғBғXҺРҗ»ӮМғGғҢғxҒ[ғ^ӮӘҸo“WӮіӮкҒAғIҒ[ғeғBғX(E. G. Otis)Һ©җgӮӘҺАүүӮөӮДӮ»ӮМҲА‘Sҗ«ӮрҺҰӮөӮДӮЭӮ№ӮҪӮЖҢҫӮӨҒBӮЬӮҪҒA1867”NғpғҠ–ң”ҺӮЕӮНҗ…ҲіҺ®ғGғҢғxҒ[ғ^ӮӘҸo“WӮіӮкӮДӮўӮҪҒB ӮұӮМүж‘ңӮНҒA1893”NӮМғVғJғS–ң”ҺӮМүпҸкӮЙҗЭ’uӮіӮкӮҪғGғҢғxҒ[ғ^ӮЕӮ ӮйҒBҲі“|“IӮИ“dӢCӮМ—НӮӘҺҰӮіӮкӮҪғVғJғS–ң”ҺӮЕӮНҒAғGғҢғxҒ[ғ^Ӯа“d“®ӮЙӮИӮБӮҪҒBҒ@ |
|
| ҒЎҲуҚьҠЦҳAӢ@ҠBҒ@ | |
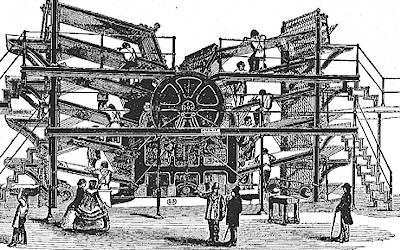 үж‘ңӮНҒA1862”N‘ж2үсғҚғ“ғhғ“–ң”ҺӮЕ“WҺҰӮіӮкӮҪҒAғzҒ[Ң^10•ыӢӢҺҶ—Ц“]Ӣ@ӮЕӮ ӮйҒBғzҒ[Ң^Ӣ@ӮН1860ҒA70”N‘гӮЙ‘ҪӮӯӮМҗV•·ҺРӮЕҺg—pӮіӮкӮҪҒBҲуҚьӢ@ӮМ”ӯ“WӮНҒAҠҲҺҡ’’‘ўҒAҗAҺҡӢ@ҒAҗ»ҺҶӢZҸp“ҷӮМ”ӯ“WӮЖӮаӮ ӮўӮЬӮБӮДҒA’ZҺһҠФӮЙӮЁӮҜӮй‘е—КӮМҲуҚьӮрүВ”\ӮЙӮөӮҪҒB ҒЎҺиҲшӮ«•ҪҲіӢ@Ғ`ү~ҲіҲуҚьӢ@ ӢЯ‘гҲуҚьӢZҸpӮНҒA15җўӢI”јӮОӮМғOҒ[ғeғ“ғxғӢғN(J. H. Gutenberg)ӮЙӮжӮйҠҲ”ЕҲуҚьӮМҚlҲДӮЙ’[Ӯр”ӯӮ·Ӯй(“dҺq“WҺҰүпўғCғ“ғLғ…ғiғuғүҒ|җј—mҲуҚьӢZҸpӮМкt–ҫЈ)ҒBҺһӮрҢoӮД1798”NӮЙӮНҒAғCғMғҠғXӮМғXғ^ғ“ғzҒ[ғv(C. Stanhope)ӮӘҒAӮДӮұӮМҢҙ—қӮрүһ—pӮөӮҪ‘Қ“Sҗ»ӮМҺиҲшӮ«ҲуҚьӢ@ӮрҠJ”ӯӮөҒAғҚғ“ғhғ“ӮМғ^ғCғҖғYҺҶӮМҲуҚьҚHҸкӮЕҚЕҸүӮЙҺg—pӮіӮкӮД–ҲҺһ•Р–К250–ҮӮрҲуҚьӮөӮҪҒB 19җўӢIӮЙ“ьӮйӮЖҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮМүһ—pҒAҗн‘ҲӮЙӮжӮйҗV•·Һщ—vӮМҚӮӮЬӮиӮЖӮЖӮаӮЙҗ¶ҺYҗ«ӮМҚӮӮўҲуҚьӢ@ӮӘҢ»ӮкӮйҒBӮЬӮҪҒAӮұӮМҚ ҒA•Ҫ”ЕҲуҚь(җО”ЕҲуҚьҒAғҠғgғOғүғt)ӮӘҚlҲДӮіӮкҒAӮұӮкӮЬӮЕӮМ“ә”ЕӮв–Ш”ЕӮЙ”дӮЧ•`үжӮӘ—eҲХӮЙҚДҢ»ӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒA‘ҪҗFҚьӮиӮаҠJ”ӯӮіӮкӮйҒBӮЩӮЪ“ҜҺһҠъӮМҺКҗ^ӢZҸpӮМҠJ”ӯҒAҗ»ҺҶӢZҸpӮМ”ӯ“WӮЖӮЖӮаӮЙҒAӢЯ‘гҲуҚьӮМ”ӯ“WӮЙ‘еӮ«ӮӯҠс—^Ӯ·ӮйӮұӮЖӮЙӮИӮйҒB 1812”NӮЙғhғCғcӮМғPҒ[ғjғq(F. Konig)ӮЖғoғEғAҒ[(A. Bauer)ӮЙӮжӮиҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮЕүТ“®Ӯ·Ӯйү~ҲіҲуҚьӢ@(”ЕӮЖҺҶӮрү~“ӣӮЕғvғҢғXӮ·ӮйӮаӮМ)ӮӘ’aҗ¶ӮөҒAӮ»ӮМҢгғ^ғCғҖғYҺРӮМҲЛ—ҠӮрҺуӮҜӮДүь—ЗӮрҸdӮЛҒAү~“ӣӮр2ӮВ—pӮўӮД“ҜҺһӮЙ2–ҮӮМ•Р–КҚьӮиӮӘүВ”\ӮЖӮИӮиҒA–ҲҺһ1,100–ҮӮЩӮЗӮрҲуҚьӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB ҒЎҠҲҺҡ’’‘ўҒEҗAҺҡ ҠҲҺҡ’’‘ўӮвҗAҺҡӮМ•Ә–мӮЕӮаҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮМ“oҸкӮр”wҢiӮЙҗl—НӮ©ӮзӢ@ҠBү»ӮЦӮМ“®Ӯ«ӮӘҗiӮЮҒB1838”NӮЙғAғҒғҠғJ“БӢ–ӮрҺж“ҫӮөӮҪғuғӢҒ[ғX(D. Bruce)ӮЙӮжӮйҺиүсӮөҺ®ҠҲҺҡ’’‘ўӢ@ӮНҒA2ҢВӮМLҺҡҢ^ӮМ’’Ң^ӮрҚҮӮнӮ№ҒAғ|ғ“ғvӮЕ’nӢаӮр’’Ң^ӮЙ—¬ӮөҚһӮЮӮаӮМӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӮ»ӮкӮЬӮЕӮМ’’Ң^ӮЖӮРӮөӮбӮӯӮЙӮжӮйҠҲҺҡ’’‘ўӮЙ”дӮөӮДҠi’iӮЙ‘ҒӮӯ’’‘ўӮ·ӮйӮұӮЖӮӘүВ”\ӮЙӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒAҠҲҺҡ’’‘ўӮвҲуҚьӢ@ӮМүь—ЗӮЖӮЖӮаӮЙҒAҠҲҺҡӮр”Е–КӮЙ‘gӮЮҗAҺҡҚмӢЖӮМӢ@ҠBү»ӮаӢҒӮЯӮзӮкӮҪҒB1820”N‘гӮ©Ӯзғ`ғғҒ[ғ`ӮвғJғXғeғ“ғoғCғ“ӮзӮЙӮжӮиҗ”ҒXӮМҗAҺҡӢ@ӮӘҠJ”ӯӮіӮкӮДӮ«ӮҪӮӘҒAүжҠъ“IӮҫӮБӮҪӮМӮНҒAғAғҒғҠғJӮМғ}Ғ[ғQғ“ғ^Ғ[ғүҒ[(O. Mergenthaler)ӮӘ1886”NӮЙ”ӯ–ҫӮөӮҪҒA1ҚsӮрӮЬӮйӮІӮЖҠҲҺҡӮЙӮ·ӮйғүғCғmғ^ғCғvӮМ“oҸкӮЕӮ ӮйҒBғ^ғCғvғүғCғ^Ғ[ӮМғLҒ[ғ{Ғ[ғhӮр’@ӮӯӮжӮӨӮЙҢҙҚe’КӮиӮЙғLҒ[Ӯр‘ЕӮВӮЖҒAӢ@ҠBӮӘҠҲҺҡӮМ•кҢ^Ӯр‘IӮСҸoӮөҒA1Қs•Ә•АӮЧӮДҠҲҺҡӮМҢЕӮЬӮиӮр’’‘ўӮ·ӮйҒBӮұӮкӮЬӮЕ3–јӮЕҚsӮБӮДӮўӮҪ‘ҖҚмӮӘ1–јӮЕүВ”\ӮЙӮИӮиҒAҚмӢЖҢш—ҰӮӘҢьҸгӮөӮҪҒB 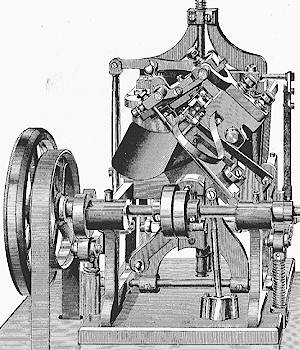
Johnson & MackellarӮМҠҲҺҡ’’‘ўӢ@ ҒЎ—Ц“]Ӣ@ӮЙӮжӮй”ӯ“W җV•·ӮвӮ»ӮМ‘јӮМ’иҠъҠ§Қs•ЁӮМ”ӯҚs•”җ”ӮӘ‘қ‘еӮ·ӮйӮЙӮВӮкҒAӮіӮзӮЙҚӮ‘¬ӮМҲуҚьӢ@ӮӘӢҒӮЯӮзӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB1846”NӮЙӮНҒAғAғҒғҠғJӮМғzҒ[(R. M. Hoe)ӮӘ—Ц“]Һ®ҲуҚьӢ@ӮрҺА—pү»Ӯ·ӮйҒBҠҲҺҡӮМҠФӮЙһ¶Ң`ӮМӢа‘®”ВӮр•tӮҜӮДү~“ӣҢ`ӮМў”Е“·ЈӮЙҢЕ’иӮөҒAӮ»ӮМҺьҲНӮЙ4–{ӮМўҲі“·ЈӮрҺжӮи•tӮҜҒAҠФӮЙҺҶӮр’КӮөӮДҳA‘ұҲуҚьӮ·ӮйӮаӮМӮЕҒAү~ҲіҲуҚьӢ@ӮЖҲбӮБӮД”ЕӮрӮаӮЖӮМҸкҸҠӮЙ–ЯӮ·•K—vӮӘӮИӮўӮҪӮЯҺһҠФ’ZҸkӮЙӮИӮБӮҪҒB1857”NӮЙӮНғ^ғCғҖғYҺРӮ©Ӯз”ӯ’ҚӮрҺуӮҜӮДҒAҲі“·10–{ҒA10җlӮЕҺҶӮр’КӮ·ӮЖӮўӮӨӢҗ‘еӮИӢ@ҠBӮӘҗ»ҚмӮіӮкӮҪҒB–ҲҺһ2–ң–ҮӮаӮМҲуҚьӮӘүВ”\ӮҫӮБӮҪӮЖӮўӮӨҒB ӮЬӮҪҒA1851”NғҚғ“ғhғ“–ң”ҺӮЕӮНҒAғtғHғXғ^Ғ[(J. Foster)ӮӘҗV•·—pҗЬӮиӮҪӮҪӮЭӢ@ӮрҸo•iӮөӮДӮўӮйҒBҢгҗўҒAҗЬӮиӮҪӮҪӮЭӢ@ӮМүь—ЗӮӘҲуҚьӮМҚӮ‘¬ү»ҒAҺ©“®ү»Ӯрҗ„ӮөҗiӮЯӮйҲкӮВӮМҸd—vӮИ—v‘fӮЖӮИӮБӮҪҒB —Ц“]ҲіҺ®ҲуҚьӢ@ӮНҒAҠҲҺҡӮӘү~“ӣӮ©Ӯз—ҺӮҝӮвӮ·ӮўҢҮ“_ӮӘӮ ӮБӮҪӮӘҒAҺҶҢ^ӮМ’’Ң^Ӯ©Ӯзү””ЕӮрҚмӮй•ы–@ӮрҺgӮБӮДҒAү~“ӣӮ»ӮМӮаӮМӮр”ЕӮЙӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB1865”NҒAғoғҚғbғN(W. Bullock)ӮӘҳA‘ұҠӘҺжҺҶӮЙҲуҚьӮ·ӮйҗўҠEҸүӮМ—Ц“]Ӣ@Ӯрҗ»ҚмӮ·ӮйӮЖҒAӮұӮкӮЬӮЕӮМӮжӮӨӮЙҗlӮӘҺҶӮр‘}Ӯ·•K—vӮӘӮИӮӯӮИӮБӮҪҒBҠӘҺжҺҶӮрҗШ’fҢгӮЙ2–{ӮМ”Е“·Ӯр’КӮөӮД—ј–КӮӘҲуҚьӮіӮкҒA”rҺҶҺуӮҜӮЙ”rҸoӮіӮкӮйҺd‘gӮЭӮЕҒAҢ»ҚЭӮМ—Ц“]Ӣ@ӮЖҠо–{Қ\‘ўӮН“ҜӮ¶ӮЕӮ ӮйҒB Ҳк•ыҒAғCғMғҠғXӮЕӮНҒA1862”NӮМ‘ж2үсғҚғ“ғhғ“–ң”ҺӮЕ—Ц“]Ӣ@ӮМғӮғfғӢӮЙҠҙ–БӮрҺуӮҜӮҪғ^ғCғҖғYҺРӮМҺР’·(J. Walter ҮV)ӮМҺwҺҰӮЙӮжӮиҒA1866”NҒAғEғHғӢғ^Ғ[—Ц“]Ӣ@ӮӘҗ»ҚмӮіӮкӮйҒBӮұӮкӮНҒAҠӘҺжҺҶӮӘ‘—ӮиҸoӮіӮкӮДүБҺј‘•’uӮр’КүЯӮөҒAҸг•”ӮМ”Е“·ӮЕ•\–КҒAүә•”ӮМ”Е“·ӮЕ— –КӮрҲуҚьҢгӮЙҚЩ’fӮіӮкҒAҗUӮи•ӘӮҜӮзӮкӮйӮЖӮўӮӨҺd‘gӮЭӮЕӮ ӮБӮҪҒBҲк“xӮЙ4ғyҒ[ғWӮрҲуҚьҒA–ҲҺһ12,000–ҮӮМ—ј–КҚьӮиӮрүВ”\ӮЖӮөӮҪҒB 1870”N‘гӮНҒAҠeҚ‘ӮМҺе—vӮИҲуҚьӢ@җ»‘ўүпҺРӮӘ—Ц“]Ӣ@ӮМҗ»ҚмӮрҚsӮӨҺһ‘гӮЖӮИӮБӮДӮўӮӯҒBғAғҒғҠғJӮМғAҒ[ғӢҒEғzҒ[ (R. Hoe) ҺРҒAғhғCғcӮМғ}ғVҒ[ғlғ“ғtғ@ғuғҠғbғNғAғEғOғXғuғӢғO (Maschinenfabrik Augusburg) ҚҮҺ‘үпҺРҒAғPҒ[ғjғbғqҒEғoғEғAҒ[ (Konig-Bauer) ҺРӮИӮЗӮӘ—Ц“]Ӣ@ӮМҗ»ҚмӮЙҺжӮи‘gӮсӮҫҒBғtғүғ“ғXӮЕӮНҒA1872”NҒA“ъ–{ӮЙ“йҗхӮЭӮМҗ[Ӯўғ}ғҠғmғj (Marinoni) ҺРӮӘҠӘҺжҺ®ҲуҚьӢ@Ӯрҗ»ҚмӮөӮДӮўӮйҒBҸ]—ҲӮМӮаӮМӮЙ”дӮЧӮДҚ\‘ўӮӘҠИ•ЦӮЕҒAҚӮҗ«”\ӮЕӮ ӮйӮұӮЖӮӘ“Б’ҘӮҫӮБӮҪҒB1889”N‘ж4үсғpғҠ–ң”ҺӮЕҗV•·ӮМҚӮ‘¬ҲуҚьӮрҺАүүӮөҒA1890”NӮЙӮНҒA“ъ–{ӮМ“аҠtҠҜ•сӢЗӮЕ“ұ“ьҒA‘ж1үс’йҚ‘ӢcүпӢcҺ–‘¬ӢLҳ^ӮрҠҜ•с•tҳ^ӮЖӮөӮДҲуҚьӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA“ҢӢһ’©“ъҗV•·ҺРӮЙӮа—A“ьӮіӮкӮҪҒB 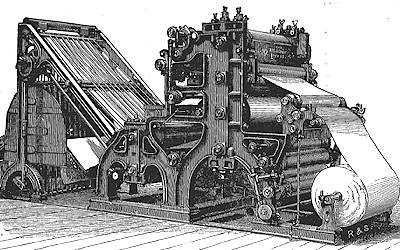 Walter PressӮМ—Ц“]Ӣ@Ғ@ 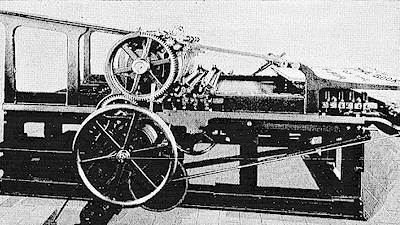
ғ~Ғ[ғҢҺРҸo•iӮМү~’ҢҲуҚьӢ@ 1880”NӮЙӮИӮйӮЖҒA—Ц“]Ӣ@ӮМӮіӮзӮИӮйҚӮ‘¬ү»Ӯр–ЪҺwӮөӮДҗЬӮиӮҪӮҪӮЭ•”•ӘӮМҠJ”ӯӮӘҠҲҗ«ү»ӮөӮДӮўӮ«ҒAӮ»ӮМҢгӮМ—Ц“]Ӣ@ӮвҲуҚьӢ@ӮНҒAҗШ’f•”ӮвӢӢҺҶ•”ӮИӮЗӮМӢ@Қ\ӮМүь—ЗӮрҸdӮЛӮДҚӮ‘¬ү»ӮөӮДӮўӮБӮҪҒB1893”NӮЙӮНҒAғAғҒғҠғJӮМғ~Ғ[ғҢ(R. Miehle)ӮЙӮжӮи1ҚH’цӮЕҲі“®ӮӘҚ¶үEӮЙ1үс“]ӮёӮВҢv2үс“]Ӯ·Ӯй2үс“]Һ®ҲуҚьӢ@ӮӘ”ӯ–ҫӮіӮкӮҪҒBҸ]—ҲҢ^ӮМ1ҚH’цҲі“®1үс“]ӮЙ”дӮЧӮДҲуҚь”\—НӮӘ”т–ф“IӮЙҢьҸгӮ·ӮйҒB“Ҝ”NӮМғVғJғS–ң”ҺӮЙғ~Ғ[ғҢҺРӮМҗ»•iӮӘҸo•iӮіӮкӮДӮўӮйҒB1904”NӮЙғӢғxҒ[ғӢ(I. W. Rubel)ӮМ”ӯ–ҫӮЙӮжӮйғIғtғZғbғgҲуҚьӮМҺи–@(”ЕӮ©ӮзғSғҖ•zӮЙ“]ҺКӮөӮДӮ©ӮзҲуҚьӮ·Ӯй)ӮӘҠm—§ӮіӮкӮДӮ©ӮзӮНҒAғIғtғZғbғg—Ц“]Ӣ@ӮМҺһ‘гӮЦӮЖ•Пү»ӮөӮДӮўӮӯҒB  —Ц“]Ӣ@
—Ц“]Ӣ@
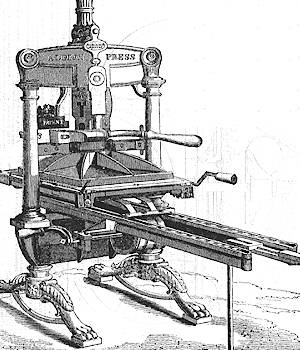
HopkinsonӮЖCope”ӯ–ҫӮМғAғӢғrғIғ“ҲуҚьӢ@ 1822”NӮЙR. W. CopeӮЙӮжӮБӮД”ӯ–ҫӮіӮкӮҪғAғӢғrғIғ“(Albion)Ң^ҺиҲшӮ«ҲуҚьӢ@ҒBӮұӮМҺн—ЮӮМҲуҚьӢ@ӮН–ҫҺЎҺһ‘гӮЙ“ъ–{ӮЙ‘Ҫҗ”—A“ьӮіӮкӮҪҒB 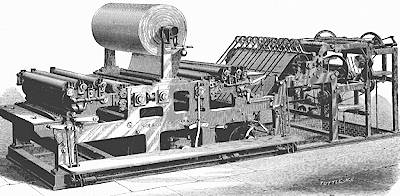 Hoe PressӮМ—Ц“]Ӣ@ ғzҒ[ҺР(Hoe press)ӮМ—Ц“]ҲуҚьӢ@ҒB—ј–КҲуҚьӮӘүВ”\ӮЕӮ ӮиҒA“ҜҺһӮЙҲуҚьӮөӮҪҗV•·Ӯр“сӮВҗЬӮиӮЙӮ·ӮйӢ@”\ӮаӮ ӮБӮҪҒB 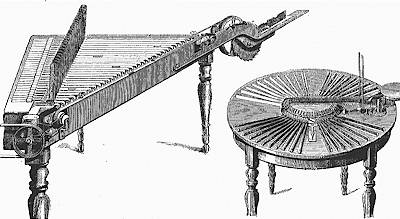
W.H. Mitchell”ӯ–ҫӮМҗAҺҡӢ@ҒEүр”ЕӢ@ W. H. MitchellӮЙӮжӮи”ӯ–ҫҒAҸo•iӮіӮкӮҪҗAҺҡӢ@ҒEүр”ЕӢ@ӮЕғҒғ_ғӢӮрҺуҸЬӮөӮҪҒBҚ¶‘ӨӮӘ•K—vӮИҠҲҺҡӮр‘—ӮиҸoӮ·‘ҖҚмӢ@ӮЕҒAғLҒ[ӮрүҹӮ·ӮЖҸҮ”ФӮЙҠҲҺҡӮӘҸoӮДӮӯӮйҒBүр”ЕӢ@ӮЖӮНҠҲҺҡӮрҺd•ӘӮҜӮ·Ӯй‘•’uҒBҺd•ӘӮҜӮөӮҪҠҲҺҡӮрҗAҺҡӢ@ӮЙ–ЯӮ·ҒB 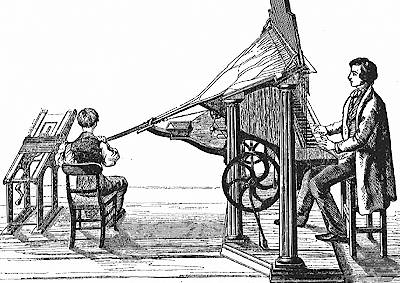 җAҺҡӢ@
җAҺҡӢ@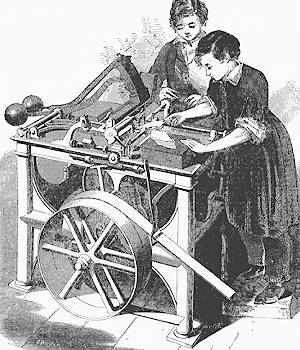 Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@••“ӣҗЬӢ@
Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@Ғ@••“ӣҗЬӢ@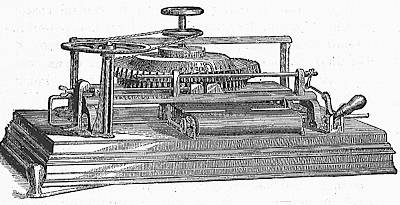 ғ^ғCғvғүғCғ^Ғ[
ғ^ғCғvғүғCғ^Ғ[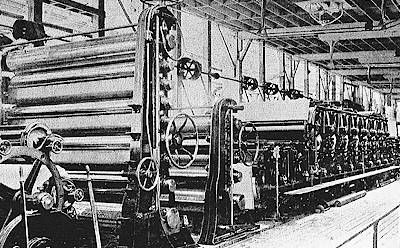 җ»ҺҶӢ@Ғ@ җ»ҺҶӢ@Ғ@ |
|
| ҒЎ‘D”• | |
|
үж‘ңӮН1889”N‘ж4үсғpғҠ–ң”ҺӮ©ӮзҒAҸцӢC‘DӮМ’f–Кҗ}ҒB’ҶүӣӮЙҸцӢCӢ@ҠЦҒA‘D”ц(Қ¶’[)ӮЙӮНғXғNғҠғ…Ғ[ҒEғvғҚғyғүӮӘӮВӮўӮДӮўӮйҒBҚЎ“ъӮЕӮаҒA‘DӮМҗ„җiӢ@ӮЖӮўӮҰӮОӮЩӮЖӮсӮЗӮӘғXғNғҠғ…Ғ[ӮЕӮ ӮйҒB
18җўӢIӮЙҸцӢCӢ@ҠЦӮӘ”ӯ–ҫӮіӮкӮйӮЖҒAҺи‘ҶӮ¬Ӯв”ҝӮЙӮ©ӮҰӮД‘D”•ӮМ“®—НҢ№ӮЖӮ·ӮйҺҺӮЭӮӘҺnӮЬӮйҒB1783”Nғtғүғ“ғXӮЕҒAғ{Ғ[ғg—ј‘DҢҪӮМҗ…‘~Ӯ«ҺФ—Ц(ҠO—Ц)ӮрҸцӢCӢ@ҠЦӮЕүфӮөҗмӮр15•ӘҚqҚsӮөӮҪӮМӮӘҒAҗўҠEҸүӮМҸцӢC‘DӮМҺА—pү»ӮЖӮўӮнӮкӮйҒB1807”NӮЙӮНҒAғAғҒғҠғJӮМғnғhғ\ғ“җмӮЕҠO—ЦҺ®ҸцӢC‘DӮӘ—·Ӣqү^‘—ӮрҠJҺnӮөҒAҸӨӢЖ“IӮЙҗ¬ҢчӮрҺыӮЯӮйҒB үНҗмӮвҢОӮЕҠҲ–фӮөӮҪҸцӢC‘DӮНҠCҸг—A‘—ӮЦӮаҗiҸoӮөҒA‘D”•ӮМ‘еҢ^ү»ӮЙ”әӮўҒA1820”N‘гҲИҚ~ҒA–Шҗ»ӮЙӮ©ӮнӮй“S‘DӮМҢҡ‘ўӮаҺnӮЬӮйҒB1840”NӮЙӮН‘еҗј—m’иҠъҚqҳHӮӘҠJҗЭӮіӮкӮйӮИӮЗҒAҠO—ЦҺ®ҸцӢC‘DӮӘ”ҝ‘DӮЙ‘гӮнӮй—A‘—Һи’iӮЖӮИӮБӮДӮўӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮұӮлӮЙӮНҒAҗ„җi—НӮрүБ‘¬ӮіӮ№ӮйғXғNғҠғ…Ғ[ҒEғvғҚғyғүӮМҠJ”ӯӮаҗiӮЭҒAғOғҢҒ[ғgҒEғuғҠғeғ“ҚҶӮЖӮўӮӨҒAғXғNғҠғ…Ғ[ӮӘҗ„җiӢ@ӮМҠO—mҚqҠC—pӮМ“S‘D(ҸүӮМӢЯ‘г‘D”•)ӮМ“oҸкӮрӮЭӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB ҸцӢCӢ@ҠЦӮНҚLӮўҗЭ’uғXғyҒ[ғXӮӘ•K—vӮИӮҪӮЯҒAҢRҠНӮЙӮН•sҢьӮ«ӮЖӮіӮкӮДӮўӮҪӮӘҒA“Sҗ»ҸӨ‘DӮвғXғNғҠғ…Ғ[ҒEғvғҚғyғүӮМ•ҒӢyӮЙ”әӮўҒAҸцӢCӢ@ҠЦҚМ—pӮӘҢҹ“ўӮіӮкҒA1845”NӮЙғCғMғҠғXҠCҢRӮНҠO—Ц‘DӮЖғXғNғҠғ…Ғ[‘DӮМҚjҲшӮ«ҺАҢұӮрӮөӮДҒAғXғNғҠғ…Ғ[‘DӮрҚМ—pӮ·ӮйҒB1853”NӮЙ–u”ӯӮөӮҪғNғҠғ~ғAҗн‘ҲӮНҢRҠНӮМҗ«”\ҢьҸгӮЙ”ҸҺФӮрӮ©ӮҜҒA1859”NӮЙғtғүғ“ғXҠCҢRӮӘ–Ш‘ўӮМ‘D‘МӮр“S”ВӮЕ–hҢмӮөӮҪҢRҠНғOғҚғҸҒ[ғӢҒA—Ӯ”NӮЙғCғMғҠғXҠCҢRӮӘҗўҠEҸүӮМ‘S“Sҗ»‘D‘МӮрӮаӮВҢRҠНғEғHҒ[ғҠғAӮрҗiҗ…ӮіӮ№ӮйӮИӮЗҒA‘•ҚbҠНҢҡ‘ўӮӘҺnӮЬӮйҒB “м–kҗн‘ҲӮЕӮНҸүӮЯӮД‘•ҚbҠН“ҜҺmӮМҗ퓬ӮӘҚsӮнӮкӮҪҒBҢRҠНӮМ•әҠнӮНҒA–CҲИҠOӮЙӢӣ—ӢӮИӮЗӮМ‘•”хӮӘүБ‘¬“x“IӮЙҗiӮЭҒA’гҺ@ӮвҸӨ‘DӮМҢмүqӮрҚsӮӨҸ„—mҠНӮӘ”ӯ’BӮөӮДӮўӮӯҒB ҸцӢC‘DӮМғGғ“ғWғ“ӮНҒA2ӮВӮМғVғҠғ“ғ_Ғ[ӮЕҚӮҲіҸцӢCӮЖ’бҲіҸцӢCӮр—ҳ—pӮ·Ӯй•ЎҚҮӢ@ҠЦӮ©ӮзҒA3ӮВӮМғVғҠғ“ғ_Ғ[ӮЕҚӮҲіҒE’ҶҲіҒE’бҲіӮМҸцӢCӮрҠҲ—pӮ·ӮйҺO’i–c’ЈҺ®Ӣ@ҠЦӮЦӮЖҗiү»ӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгҒAғpҒ[ғ\ғ“ғY(C. A. Parsons)ӮӘҠJ”ӯӮөӮҪҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“ғGғ“ғWғ“(ҸцӢCӮЕүHҚӘҺФӮӘүс“]Ӯ·Ӯй)ӮМ“oҸкӮЕӮіӮзӮИӮйҗiү»ӮрҗӢӮ°ӮйҒB1897”NӮЙӮНҒAғ”ғBғNғgғҠғAҸ—үӨ‘ҰҲК60”NӢL”OҚХӮЙҺQүБӮөӮҪ”ЮӮМғ^Ғ[ғrғjғAҚҶӮӘ34ғmғbғgӮЕ‘–ҚsӮөҒAҗlҒXӮрӢБӮ©Ӯ№ӮҪ(“–ҺһӮМӢм’ҖҠНӮӘ27ғmғbғg)ҒBҸцӢCғ^Ғ[ғrғ“ӮНҒAӮ·Ӯ®ӮЙӢм’ҖҠНӮЙ“ӢҚЪӮіӮкҒAҸӨӢЖ—p‘D”•ӮЙӮаҚМ—pӮіӮкӮйҒBӮ»ӮөӮДҒA20җўӢIӮЙӮНҠO—mҚqҠC’иҠъ‘DӮ©ӮзҢRҠНӮЙҺҠӮйӮЬӮЕ—L–ј‘D”•ӮМҺе“®—НҢ№ӮЖӮИӮйҒBҒ@ |
|
| ҒЎғJғҒғү | |
|
үж‘ңӮНҒA1862”NӮМғҚғ“ғhғ“–ң”ҺӮЙҸo•iӮіӮкӮҪғpғmғүғ}ғҢғ“ғYӮЖҺOӢrғJғҒғүӮЕӮ ӮйҒBҗўҠEӮЕҸүӮЯӮДӮМҺКҗ^ӮНҳIҸoӮЙ8ҺһҠФӮаӮ©Ӯ©ӮБӮҪӮӘҒAӮұӮМҚ ӮЙӮНҳIҸoҺһҠФӮа’ZӮӯӮИӮиҒAү®ҠOӮв—·җжӮЙҺКҗ^Ӣ@ӮрҺқӮҝӮҫӮөҒAҺBүeӮ·ӮйӮұӮЖӮӘ‘z’иӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮБӮҪҒB
ғҢғ“ғYӮЙүfӮБӮҪүf‘ңӮрү»ҠwҚм—pӮЙӮжӮБӮДҢЕ’иӮөӮҪҚЕҸүӮМҗlӮНҒAғtғүғ“ғXӮМғjғGғvғX(J. N. Niépce)ӮЕӮ ӮйҒB1826”NӮЙ‘ӢӮМҠOӮМ•—ҢiӮрҺBүeӮөҒAҳIҸoҺһҠФӮН–с8ҺһҠФӮаӮ©Ӯ©ӮБӮҪӮЖҢҫӮнӮкӮДӮўӮйҒBҠҙҢх•ЁҺҝӮЖӮөӮД—pӮўӮҪӮМӮНғAғXғtғ@ғӢғgӮМҲкҺнӮЕҒAҢхӮЙ“–ӮҪӮйӮЖҚdү»Ӯ·Ӯйҗ«ҺҝӮр—ҳ—pӮөӮҪҒB ғjғGғvғXӮЖӢӨ“ҜҢӨӢҶӮрҗiӮЯӮДӮўӮҪғ_ғQҒ[ғӢ(L. J. M. Daguerre)ӮНҒAғjғGғvғXӮМҺҖҢгҒA1837”NӮЙҒAӢвғҒғbғLӮрҺ{ӮөӮҪ“ә”ВӮр—pӮўӮйӢв”ВҺКҗ^(ғ_ғQғҢғIғ^ғCғv)ӮрҠ®җ¬ӮөӮҪҒBҢ»‘ңӮрҚsӮӨӮұӮЖӮЙӮжӮиҳIҸoҺһҠФӮрҗ”Ҹ\•ӘӮЖ’ZӮӯӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBӮЖӮНҢҫӮБӮДӮа“®ӮӯӮаӮМӮЙӮНҺgӮҰӮёҒAҚ¶үE”Ҫ“]ӮөӮҪүж‘ңӮЕҒA“ҫӮзӮкӮйҺКҗ^ӮНҲк–ҮӮ«ӮиӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ӯ»ӮМҢгҒAғCғMғҠғXӮМғgҒ[ғӢғ{ғbғg(W. H. F. Talbot)ӮӘғJғҚғ^ғCғvӮЖӮжӮОӮкӮйғlғKҒҒғ|ғW–@Ӯр”ӯ–ҫӮөҒAүҪ–ҮӮаӮМҺКҗ^ӮрҚмӮйӮұӮЖӮрҺАҢ»ҒBӮЬӮҪҒAғtғүғ“ғXҗӯ•{ӮНӢв”ВҺКҗ^–@ӮМ“БӢ–Ӯр”ғӮўҺжӮиҲк”КҢцҠJӮөӮҪӮҪӮЯҒAғҲҒ[ғҚғbғpҠe’nӮЕҠҙҢхҚЮ—ҝӮЖғҢғ“ғYӮМүь—ЗӮӘҗiӮЭҒAҳIҸoҺһҠФӮаҗ”•ӘӮЖ’ZӮӯӮИӮБӮҪҒBӮ»ӮМӮҪӮЯҒA’ҶҺYҠKӢүӮМҠФӮЕҸС‘ңҺКҗ^ҺBүeӮӘ‘е—¬ҚsӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA1839”NӮЙӮНҺЦ• Һ®ҢgҚsҢ^Ӣв”ВғJғҒғүҒAҺOӢrӮИӮЗӮа”ӯ–ҫӮіӮкҒA1844”NӮЙӮНӮ·ӮЕӮЙҒA150“xӮМҠp“xӮрҺКӮ·ғpғmғүғ}ҺКҗ^ӮаҺBӮзӮкӮДӮўӮйҒBҸЕ“_Ӣ——ЈӮМ’ZӮўғҢғ“ғYӮМҺсӮрҗUӮиҒA–`“Әүж‘ңӮМӮжӮӨӮЙҳpӢИӮөӮҪ”ЕӮЙҺBүeӮөӮҪҒB ғJғҚғ^ғCғvӮНғlғKӮЙҺҶӮрҺgӮБӮДӮўӮҪӮҪӮЯүж‘ңӮӘӮ ӮЬӮи‘N–ҫӮЕӮНӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒA1851”NӮЙӮНғCғMғҠғXӮМғAҒ[ғ`ғғҒ[(F. S. Archer)ӮӘғKғүғX”ВӮЙғRғҚғWғIғ“ӮЖӮўӮӨүt‘МӮМҠҙҢхҚЮ—ҝӮр“h•zӮөҒAҺјӮБӮҪҸу‘ФӮЕ—pӮўӮйҺј”ВҺКҗ^Ӯр”ӯ•\ӮөҒA‘N–ҫӮИҺКҗ^Ӯр’б—хӮЙҚмҗ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮрүВ”\ӮЙӮөӮҪҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒAҗV•·ӮМ•с“№ҺКҗ^ӮИӮЗҒAҗўҠEӮМ—lҒXӮИҸкҸҠӮӘҺBүeӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAҗнүРӮМ—lҺqӮвғsғүғ~ғbғhӮЖӮўӮБӮҪ–јҸҠҒAӮ»ӮөӮД‘ж1үсғҚғ“ғhғ“–ң”ҺӮМүпҸкӮЕӮ Ӯйҗ…Ҹ»Ӣ{ӮМҢҡҗЭҸуӢөӮМҺBүeӮаӮИӮіӮкӮҪҒB –`“Әүж‘ңӮМғJғҒғүӮНӮұӮМҚ ӮМӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB Ӯ»ӮМҢг1871”NӮЙғ}ғhғbғNғX(R. L. Maddox)ӮЙӮжӮБӮДҒAғKғүғX”ВӮЙғ[ғүғ`ғ“Ӯр—pӮўӮҪҠЈ”ВҺКҗ^ӮӘ”ӯ–ҫӮіӮкӮҪҒBҠЈ”ВӮН•Ы‘¶ӮӘӮ«ӮӯӮҪӮЯҸӨ•iӮЖӮөӮД”М”„ӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAҺКҗ^ӮМҲк”КӮЦӮМ•ҒӢyӮӘҗiӮсӮҫҒBӮіӮзӮЙ1888”NҒAҢ»ғRғ_ғbғN(Kodak)ҺРӮМ‘nӢЖҺТӮЕӮ ӮйғAғҒғҠғJӮМғCҒ[ғXғgғ}ғ“(G. Eastman)ӮӘҒAҸdӮӯҠ„ӮкӮвӮ·ӮўғKғүғX”ВӮЙӮ©ӮнӮБӮДҒAҢyӮӯҸ_ӮзӮ©ӮўғZғӢғҚғCғhҗ»ӮМғҚҒ[ғӢғtғBғӢғҖӮрҠJ”ӯӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮиҒAҢ»ҚЭӮМӮжӮӨӮИҒA‘fҗlӮЕӮағVғғғbғ^Ғ[ӮрүҹӮ·ӮҫӮҜӮЕҺBүeӮЕӮ«ӮйғJғҒғүӮӘҺАҢ»ӮөӮҪҒBӮҝӮИӮЭӮЙҒA1893”NӮМғVғJғS–ң”ҺӮЕӮНҺКҗ^ҺBүeӮМ“ЖҗиҢ ӮрғRғ_ғbғNҺРӮӘ—LӮөӮДӮЁӮиҒA1“ъ100ғhғӢӮЕӢ–үВҸ‘Ӯр”ӯҚsӮөӮДӮўӮҪҒBҒ@ Ғ@ |
|
| ҒЎ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпҒ@ | |
|
ҒЎ‘ж1үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп / җBҺYӢ»ӢЖӮМӮҪӮЯӮЙ
ҠJҚГҠъҠФҒF1877(–ҫҺЎ10)”N8ҢҺ21“ъҒ`11ҢҺ30“ъҸкҸҠҒF“ҢӢһҸг–мҢцүҖ“ьҸкҺТҗ”ҒF454,168җl 1877(–ҫҺЎ10)”NӮМ8ҢҺҒAҗј“мҗн‘ҲҠJҗнӮМ’ҶҒA“ъ–{ӮЕҸүӮЯӮДӮМ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮМҠJҸкҺ®ӮӘҚsӮнӮкӮҪҒB–{үпӮНҒA“ъ–{ӮӘҺQүБӮөӮҪ1873”NӮМғEғBҒ[ғ“–ңҚ‘”Һ——үпӮрҺQҚlӮЙҒAҸү‘г“а–ұӢЁ‘еӢv•Ы—ҳ’КӮӘҗ„ӮөҗiӮЯӮҪӮаӮМӮЕӮ ӮйҒB ”Һ——үпӮЖ–Б‘ЕӮБӮҪӮаӮМӮНҒAҲИ‘OӮЙӮа‘¶ҚЭӮөӮҪӮӘҒAӮ»ӮМӮЩӮЖӮсӮЗӮӘ–ј•уӮв’ҝ•iӮрҸWӮЯӮДҠП——ӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮӘ–Ъ“IӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМ”Һ——үпӮНҒA“БӮЙҒuҠ©ӢЖҒvӮМ“с•¶ҺҡӮрҠҘӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮ©ӮзӮа–ҫӮзӮ©ӮИӮжӮӨӮЙҒAҸo•i•ЁӮМ’ҶӮ©ӮзҗBҺYӢ»ӢЖҗ„җiӮЙӮН•s•K—vӮИ"Ң©җў•Ё"ӮМғCғҒҒ[ғWӮрҢөҠiӮЙ”Ы’иӮөҒAүў•ДӮ©ӮзӮМӢZҸpӮЖҚЭ—ҲӢZҸpӮМҸoүпӮўӮМҸкӮЖӮИӮйҺYӢЖҸ§—гүпӮЖӮөӮДӮМ–КӮр‘O–КӮЙүҹӮөҸoӮөӮДӮўӮйҒB –с10–ң•Ҫ•ығҒҒ[ғgғӢӮМүпҸкӮЙӮНҒA”ьҸp–{ҠЩҒA”_ӢЖҠЩҒAӢ@ҠBҠЩҒAүҖҢ|ҠЩҒA“®•ЁҠЩӮӘҢҡӮДӮзӮкҒAҠ°үiҺӣӢҢ–{–VӮМ•\–еӮМҸгӮЙӮН‘еҺһҢvӮӘҢfӮ°ӮзӮкӮҪҒBӮЬӮҪҒAҢцүҖ“ьӮиҢыӮЙ‘ўӮзӮкӮҪ–с10ғҒҒ[ғgғӢӮМғAғҒғҠғJҺ®ӮМ•—ҺФ(’nүәҗ…ӢӮӮЭҸгӮ°—p)ӮвҸг–м“ҢҸЖӢ{‘OӮ©ӮзҢцүҖӮЙӮ©ӮҜӮДӮМҗ”җзҢВӮМ’с“”ӮӘҚКӮр“YӮҰӮҪҒB ‘SҚ‘Ӯ©ӮзҸWӮЯӮзӮкӮҪҸo•i•ЁӮНҒA‘O”NӮМғtғBғүғfғӢғtғBғA–ң”ҺӮЙӮИӮзӮБӮД‘еӮ«Ӯӯ6ӮВӮМ•”(ҚzӢЖӢyӮС–иӢаҸpҒAҗ»‘ў•ЁҒA”ьҸpҒAӢ@ҠBҒA”_ӢЖҒAүҖҢ|)ӮЙ•Ә—ЮӮіӮкҒA‘fҚЮҒEҗ»–@ҒE•iҺҝҒE’Іҗ®ҒEҢш—pҒEүҝ’lҒEүҝҠiӮИӮЗӮМҠоҸҖӮЕҗRҚёӮӘҚsӮнӮкӮҪҒB—DҸGҚмӮЙӮНҸЬ”vҒE–JҸу“ҷӮӘҺц—^ӮіӮкҒAӮўӮнӮО•Ё•i’ІҚёӮЖҺYӢЖҸ§—гӮӘ“ҜҺһӮЙҚsӮнӮкӮДӮўӮҪӮЖҢҫӮҰӮйҒB ӮұӮМ”Һ——үпӮЕӮНҒA–aҗDҺYӢЖӮӘ‘ҪӮӯӮМҠ„ҚҮӮрҗиӮЯӮҪӮӘҒAӮ»ӮМ’ҶӮЕҚЕҚӮӮМҸЬ”vҒA–P–дҸЬ”vӮр—^ӮҰӮзӮкӮҪүзү_’C’vӮНҒA“ъ–{ӮМ“БӢ–җ§“xӮрҢкӮйҸгӮЕӮаӮжӮӯӢ“Ӯ°ӮзӮкӮйҗl•ЁӮЕӮ Ӯй(ғRғүғҖҒ@–ҫҺЎӮМ“БӢ–җ§“x)ҒB ҒЎ ‘ж1үсӮНҒAҗBҺYӢ»ӢЖӮр’S“–Ӯ·Ӯй“а–ұҸИҠ©ӢЖ—ҫӮМҗЭ—§(1874”N)Ӯ©Ӯз3”NӮЖӮўӮӨғXғsҒ[ғhҠJҚГӮЕҒA“WҺҰ•iӮНҗӯ•{ӮЙӮжӮйӮаӮМӮӘҚЕӮа‘ҪӮ©ӮБӮҪҒBҗӯ•{ӮН’ZҠъҠФӮЕ‘Ҫҗ”ӮМҚ‘“аҸo“W•iӮр•еӮйӮҪӮЯҒAҸo•iҗlҸ•җ¬–@ӮрҚмӮБӮДү^”А”пҸ•җ¬“ҷӮрҚsӮўҒAҸo•iӮр‘ЈӮөӮҪҒB“WҺҰ•iӮН•{Ң§•КӮЙ“WҺҰӮіӮкҒAӢЈ‘ҲҗSӮрҗшӮБӮҪҒB ҠOҚ‘җ»•iӮНҗӯ•{Қw“ь•iӮМӮЭӮӘҸo“WӮіӮк(‘ж4үс“аҚ‘”ҺӮЬӮЕӮұӮМҸу‘ФӮНҢp‘ұ)ҒA“а–ұҸИҠ©”_ӢЗҸo•iӮМ•—ҺФӮвӢа‘®җ»ӮМ”_Ӣ@ӢпӮИӮЗӮӘ“WҺҰӮіӮкӮҪҒB ҠOҚ‘ӮМ–Н•нӮЖӮөӮДҒAҠOҚ‘җ»•iӮр•ӘүрӮөӮД–Н‘ўӮөӮҪӮЖӮўӮӨғ~ғVғ“ӮвҲуҚьӢ@ӮМҸo“WӮаӮ ӮБӮҪҒB ҚH•”ҸИҚHҚмӢЗӮМҗщ”ХҒAӢһ“sҗјҗwӮМҚr–ШҸ¬•ҪӮМ–Шҗ»ғWғғғKҒ[ғhҗDӢ@ӮМӮжӮӨӮЙҗјүўӮМӢZҸpӮр“ъ–{ӮМҺYӢЖӮЙҚҮӮӨҢ`ӮЕҺжӮи“ьӮкӮҪҗ»•iӮӘҸo“WӮіӮкӮДӮўӮй“_ӮН’Қ–ЪӮ·ӮЧӮ«ӮЕӮ ӮйҒBӮЬӮҪҒAғEғBҒ[ғ“–ң”ҺӮМӢZҸp“`ҸKҗ¶ӮЙӮжӮйҸo“WӮаҢ©“ҰӮ№ӮИӮўҒB‘Ә—КӢZҸpӮрҠwӮсӮҫ“Ў“ҮҸнӢ»ӮӘҚHҚмӢЗҺһ‘гӮЙҗ»ҚмӮөӮҪҺЪ“xҠcҗьӢ@(ӮаӮМӮіӮөӮЙ–Ъҗ·ӮрҚҸӮЮӢ@ҠB)ӮНҒAӮ»ӮМҲк—бӮЕӮ ӮйҒBҲк•ыҒAүзү_’C’vӮМ–aҗСӢ@(ғKғү–a)ӮМӮжӮӨӮЙҚЭ—ҲҺYӢЖӮ©Ӯзҗ¶ӮЬӮкӮҪҗ»•iӮаӮ ӮиҒAӮұӮкӮНҸ]—ҲӮМ–ИҺ…җ¶ҺY‘МҢnӮр•ПӮҰӮйӮұӮЖӮИӮӯҺg—pӮЕӮ«ӮҪӮҪӮЯҒAӢ}‘¬ӮЙ•ҒӢyӮөӮҪҒB —К“IӮЙӮНҒA–aҗСӮв”_ӢЖҠЦҢWӮМҸo“W•iӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҒB”_ӢЖӢ@ҠBӮЕӮНҒAҗ_‘ә•ҪүоӮМүҢ‘җҗШӮиӢ@Ӯв”dҺнӢ@ӮӘҗl—НӮрҸИӮўӮҪӮЖӮўӮӨ“_ӮЕҚӮ•]үҝӮр“ҫӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҚӮҠzӮҫӮБӮҪӮҪӮЯ•ҒӢyӮНҗiӮЬӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒB ҚHӢЖ”ӯ“WӮМҠо‘bӮЖ–ЪӮіӮкӮйҢҙ“®Ӣ@—ЮӮЕӮНҒAүЎ•lҗ»“SҸҠӮМҗҷҺR“ҝҺOҳYӮӘҸo•iӮөӮҪҸцӢCӢ@ҠЦӮӘ2“ҷҸЬӮрҺуҸЬӮөӮДӮўӮйӮӘҒAҺА—pӮЙӮН“KӮіӮИӮўӮЖӮМҲУҢ©ӮаӮ ӮБӮҪҒBҠOҚ‘ӮЕӮНӮЬӮҫҗ…—Н—ҳ—pӮаҗ·ӮсӮЕӮ ӮиҒAҗ…Һ‘Ң№ӮМ–L•xӮИүдӮӘҚ‘ӮЕӮНҒAӮЬӮёӮ»ӮМ—ҳ—pӮӘҺҺӮЭӮзӮкӮҪҒB ‘ж1үсӮЕӮНӮұӮМӮжӮӨӮЙҒAҚ‘“аҗ»•iӮНҒAҠOҚ‘җ»•iӮМ–Н•нҒAүь—ЗӮЖӮўӮБӮҪ’iҠKӮЙ—ҜӮЬӮБӮДӮўӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж2үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп / •sӢөүәӮЕӮа‘еҗ·Ӣө
ҠJҚГҠъҠФҒF1881(–ҫҺЎ14)”N3ҢҺ1“ъҒ`6ҢҺ30“ъҸкҸҠҒF“ҢӢһҸг–мҢцүҖ“ьҸкҺТҗ”ҒF823,094җl ‘ж2үсӮМ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮНҒAҗј“мҗн‘ҲӮМҗн”п”PҸoӮрҢ_Ӣ@ӮЖӮ·ӮйғCғ“ғtғҢҒ[ғVғҮғ“ҒA–Ӣ––ҠJҚ`ҲИ—ҲӮМ–fҲХ•sӢПҚtӮЙӮжӮйҗіүЭ—¬Ҹo“ҷӮЙӮжӮй•sӢөүәӮЕҠJӮ©ӮкӮҪ”Һ——үпӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAҸo•iҗ”ӮН‘ж1үсӮМ4”{ӮЙӮа‘қӮҰҒA“ьҸкҺТҗ”“ҷӮЩӮЖӮсӮЗӮМ•Ә–мӮЕ‘ж1үсӮМ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮМӢK–НӮр—ҪӮ®ҢӢүКӮЖӮИӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘ж1үсӮМҸҠҠЗӮН“а–ұҸИӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA‘ж2үсӮЕӮНӮіӮзӮЙ‘е‘ ҸИӮаүБӮнӮиҒAҗӯ•{ӮЖӮөӮДӮаҠ©ӢЖ”Һ——үпӮЙҲк‘w’Қ—НӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮӘҺfӮҰӮйҒB үпҸк–с14–ң3,000•Ҫ•ығҒҒ[ғgғӢӮЙҒA–{ҠЩӮЩӮ©6ҠЩӮМ’В—сҠЩӮӘҢҡҗЭӮіӮкӮҪҒBҸг–мӮМҺRӮМүФҢ©ӢqӮрҠъ‘ТӮөӮД3ҢҺӮЙҠJүпӮөӮҪӮұӮЖӮӘҢчӮр‘tӮөӮҪӮМӮ©ҒAүпҠъ’ҶӮМ“ьҸкҺТӮН82–ңҗlӮЕҒAҲк“ъ•ҪӢП6,740җlӮЖҒA‘ж1үсӮМ”{ӢЯӮӯӮМҗlӮрҸWӮЯ‘еҗ·ӢөӮҫӮБӮҪҒBӮЬӮҪҒA–ҫҺЎ“VҚcӮаҚcҚ@ӮЖҚsҚKӮөҒA”MҗSӮЙҠП——ӮөӮҪҒB ‘ж1үсӮЙ‘ұӮ«‘ж2үсӮМ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮЙӮЁӮўӮДӮаҺw“ұҺТ“I–рҠ„ӮрүКӮҪӮөӮҪӮЁҢЩӮўҠOҚ‘җlғҸғOғlғӢ(G. Wagener)ӮНҒA“ъ–{җӯ•{ӮЦӮМ•сҚҗҸ‘ӮМ’ҶӮЕ“ъ–{ҺYӢЖӮМҢ»Ҹу•ӘҗНӮЖҸ«—ҲӮЦӮМ’сҢҫӮрҚsӮўҒA—бӮҰӮО“ъ–{”_ӢЖӮрҠOҚ‘ӮМҺ‘–{ӮвӢZҸp“ҷӮр“ұ“ьӮөӮД”ӯ“WӮіӮ№ӮйӮЧӮ«ӮҫӮЖҸqӮЧӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮкӮН”_ҸӨ–ұҸИӮЕӮЁҢЩӮўҠOҚ‘җlӮр”pҺ~Ӯ·ӮйӮИӮЗӮөӮДӮўӮҪ“ъ–{җӯ•{ӮЦӮМ’пҚRӮЕӮ ӮиҒAҠOҚ‘җlӢZҸpҺТҲЛ‘¶Ӯ©ӮзӮМҺ©—§Ӯр–ЪҺwӮөӮДӮўӮҪ“–ҺһӮМ“ъ–{ӮМҗӯҚфӮЖӮМ‘ОҸЖӮӘ•ӮӮ«’ӨӮиӮЖӮИӮБӮДӮўӮйҒB ӮИӮЁҒA‘ж1үсӮЕӮНҸo•i•ЁӮр•{Ң§•КӮЙ’В—сӮөӮҪӮӘҒA‘ж2үсӮЕӮНҸo•iҺТ‘ҠҢЭӮМӢЈ‘ҲҗSӮрҗшӮйӮұӮЖӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДҺн•КӮЙ’В—сӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA‘ж1үсҲИҢгӮМүь—З”ӯ“WӮрҠъ‘ТӮөҒA‘OүсӮЖ“Ҝ—lӮМӮаӮМӮМҸo•iӮрӢЦӮ¶ӮҪҒB ҒЎ җј“мҗн‘ҲӮрҢ_Ӣ@ӮЖӮөӮҪғCғ“ғtғҢҒ[ғVғҮғ“ӮЙӮжӮиҒAҠ©ӢЖҗӯҚфӮМҸkҸ¬Ӯр—]ӢVӮИӮӯӮіӮкӮйҸуӢөӮЕҠJҚГӮіӮкӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒAӢK–НӮН‘ж1үсӮр—ҪӮ®ӮаӮМӮҫӮБӮҪҒBҠe•{Ң§ҢQӢжӮЙҗЭ’uӮіӮкӮҪҗўҳbҠ|ӮЙӮжӮйҸo“WҠ©—UӮӘҲкҲцӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮЕӮ ӮйҒBҸo“W•iӮНҺн•КӮЙ“WҺҰӮіӮкҒAҗ»•iӮр”дҠrӮ·ӮйӮұӮЖӮЙҸd“_ӮӘ’uӮ©ӮкӮҪҒBӮұӮұӮЕӮаҗӯ•{ӮМҸo“W•iӮӘҚЕӮа‘ҪӮӯҒAҠ©”_ӢЗ(”Һ——үпҸI—№ҺһӮН”_ҸӨ–ұҸИ”_–ұӢЗ)ӮЖҚH•”ҸИӮМӮаӮМӮӘ’ҶҗSӮЕӮ ӮБӮҪҒB Ҹo“Wҗ”ӮНҒA–aҗСҠЦҢWӮӘ–с3•ӘӮМ1ӮрҗиӮЯӮҪӮӘҒAүзү_’C’vҗ»ҚмӮМүь—З”ЕғKғү–aҲИҠOӮНҒAӮЩӮЖӮсӮЗғKғү–aӮМ–Н‘ў•iӮҫӮБӮҪҒB“БӢ–җ§“xӮӘӮИӮўҺһҠъӮҫӮБӮҪӮҪӮЯҒAүь—З”ЕғKғү–aӮЖ–Н‘ў•iӮМ—ј•ыӮӘҺуҸЬӮөӮДӮўӮй(ғRғүғҖҒu–ҫҺЎӮМ“БӢ–җ§“xҒvҺQҸЖ)ҒBӮЩӮ©ӮЙҒA‘ж1үсӮМҗ…ҺФҺ®җD•ЁӢ@ҠBӮЕҺуҸЬӮөӮҪ“n•УӢұҒEҺД“c“ҝ‘ ҢZ’нӮӘҒAӮ»ӮМҚЫ“ьҺиӮөӮҪғAғҒғҠғJҗ»•iӮМҗ}Һ®ӮрҢіӮЙүь—ЗӮрҸdӮЛӮДҒA‘«“ҘӢ@ӮЕҚД“xҺуҸЬӮөӮДӮўӮйҒB ҺҹӮўӮЕ‘ҪӮ©ӮБӮҪӮМӮНҒA”_ӢЖӢ@ҠBӮЕӮ ӮйҒBҠ©”_ӢЗ(ҺO“c”_Ӣпҗ»ҚмҸҠ)ӮӘ–аҗ Ӣ@Ӯвғ|ғ“ғvӮИӮЗӮЕҺуҸЬӮөӮДӮўӮйӮӘҒAӮ·ӮЧӮДҠOҚ‘җ»•iӮМ–Н‘ўӮҫӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒAҠCҠOӮМ‘е”_ҸкҢьӮҜӮМӢ@ҠBӮН“ъ–{ӮЕӮ»ӮМӮЬӮЬҺgӮӨӮЙӮН•s“K“–ӮЕҒA”_ӢЖӢ@ҠBӮНӮ»ӮМҢгӮаҠOҚ‘ӢZҸpӮр—A“ьӮ·ӮйӮМӮЕӮНӮИӮӯҒA“ъ–{“ЖҺ©ӮМ•ыҢьӮЙ”ӯ“WӮөӮДӮўӮӯҒB Ңҙ“®Ӣ@—ЮӮЕӮНҒA–ҜҠФӮ©ӮзӮМҸo•iӮаҸҷҒXӮЙ‘қӮҰҒAҸцӢC“®—Н—ҳ—pӮМ–GүиӮӘүMӮҰӮй(ӮұӮМ2”NҢгӮЙӮНҒAҸцӢCӢ@ҠЦӮрҺgӮБӮҪ‘еӢK–НӮИ–aҗСӢЖӮЖӮөӮД—L–јӮИ‘еҚг–aҗСүпҺРӮа‘ҖӢЖӮрӮөӮДӮўӮй)ҒB Ҡ©ӢЖҗӯҚфӮМ–КӮЕӮНҒA”Һ——үпӮЙӮжӮиҚ‘“аҠe’nӮ©ӮзҸo“W•iӮӘҸWҗПӮіӮкӮйӮҪӮЯҒAҠe’nӮМҺYӢЖҸу‘ФӮр”cҲ¬Ӯ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA–ҜҠФӮЙӮНҒA”Һ——үпҸo“WӮӘ—ҳүvӮрҗ¶ӮЮӮЖӮўӮӨ”FҺҜӮНӮЬӮҫҗZ“§ӮөӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж3үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп / җўҠEӮЦғAғsҒ[ғӢ
ҠJҚГҠъҠФҒF1890(–ҫҺЎ23)”N4ҢҺ1“ъҒ`7ҢҺ31“ъҸкҸҠҒF“ҢӢһҸг–мҢцүҖ“ьҸкҺТҗ”ҒF1,023,693җl “–ҸүӮНҒAғEғBҒ[ғ“–ң”Һ•ӣ‘ҚҚЩӮЕӮ ӮБӮҪҚІ–мҸн–ҜӮр’ҶҗSӮЖӮөӮДҒAҸ«—ҲӮМ–ң”ҺҠJҚГӮр–ЪҺwӮөӮДҸӯӮөӮЕӮаӢK–НӮрҠg‘еӮөӮҪҒuғAғWғA”Һ——үпҒvӮрҒAҚcӢI2550”NӮЙӮ ӮҪӮй1890”NӮЙҠJҚГӮ·ӮйҲДӮӘҚ\‘zӮіӮкӮДӮўӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA‘е‘ ‘еҗbҸј•ыҗіӢ`ӮзӮМ”Ҫ‘ОӮЙӮжӮБӮДҒAҸғ‘RӮҪӮй“аҚ‘”ҺӮЖӮөӮД‘ж3үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮӘҠJҚГӮіӮкӮйӮұӮЖӮЙӮИӮБӮҪҒBӮұӮМӮжӮӨӮИҢoҲЬӮЙӮжӮиҒA“аҚ‘”ҺӮЕӮНӮ ӮБӮҪӮӘҸo“W•iӮМ”МҳHҠg‘еӮМӮҪӮЯӮЙҠOҚ‘җlӢqӮМ—U’vӮЙ—НӮӘ“ьӮкӮзӮкҒAҗўҠEҠeҚ‘ӮЙҸө‘ТҸуӮӘ‘—ӮзӮкӮҪҒBҚЕҸI“IӮЙӮНҒAҠOҚ‘Ӯ©Ӯз246җlӮМ“ьҸкҺТӮӘӮ ӮБӮҪҒB •sҢiӢCҒEғCғ“ғtғӢғGғ“ғUӮМ—¬ҚsҒEҳA“ъӮМүJҒA7ҢҺ1“ъӮЙӮН’йҚ‘ӢcүпҸOӢcү@‘IӢ“ӮӘӮ ӮБӮҪӮИӮЗӮМүeӢҝӮ©ӮзҒA‘S‘МӮМ“ьҸкҺТҗ”ӮНҗLӮС”YӮсӮҫҒBӮ»ӮМӮЩӮ©ӮЙӮаҒA’PӮЙҗј—mӮМ•¶•ЁӮЖӮўӮӨӮҫӮҜӮЕӮН–һ‘«ӮЕӮ«ӮИӮӯӮИӮиӮВӮВӮ Ӯй–ҜҸOӮЙ‘ОӮөӮДҒAҗӯ•{ӮНӮ ӮӯӮЬӮЕҒA‘ж1үсҲИ—ҲӮМҢвҠyӮр”rҸңӮ·Ӯй•ыҗjӮрҠСӮўӮҪӮұӮЖӮаҒAүeӢҝӮөӮДӮўӮҪӮЖҚlӮҰӮзӮкӮДӮўӮйҒB үпҸкӮМҢҡ’ШӮН9,725’Ш(3–ң2,000•Ҫ•ығҒҒ[ғgғӢ)ӮЕҒA–{ҠЩӮМӮЩӮ©ӮЙҒA”ьҸpҠЩҒA”_—СҠЩҒA“®•ЁҠЩҒAҗ…ҺYҠЩҒAӢ@ҠBҠЩҒAҠOҚ‘җ»•iӮр•АӮЧӮйҺQҚlҠЩӮ©ӮзӮИӮиҒAҢҡ•Ё‘S‘МӮМ–КҗПӮНҒA‘ж2үсӮМ–с1.3”{ҒAҸo“W•iҗ”ӮН441,458“_ӮЖ‘қүБӮөӮҪҒB“ҢӢһ“d“”үпҺРӮӘүпҸк“аӮЙҒA“ъ–{ӮЕӮНӮ¶ӮЯӮДӮМ“dҺФӮЖӮИӮйҳH–К“dҺФӮр‘–ӮзӮ№ӮҪӮұӮЖӮӘ“Б•MӮЙүҝӮ·ӮйҒB ҠҜ’ЎҸo•i•ЁӮН–JҸЬӮМҗRҚёӮМ‘ОҸЫҠOӮЖӮіӮкӮҪӮМӮЕҒA–ҜӢЖӮрҗUӢ»Ӯ·ӮйҲУҗ}ӮӘ–ҫҠmӮЙӮИӮБӮҪҒBӮөӮ©ӮөҒA–JҸЬӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҗRҚёӮМҢӢүКҺҹ‘жӮЕӮНҸӨ•iӮМ”„ӮкҚsӮ«ӮЙ‘еӮ«ӮИүeӢҝӮӘҸoӮҪӮҪӮЯҒA“ҷҗ”ӮЙ•s–һӮрӮаӮБӮҪҸo“WҺТӮ©Ӯз‘iҸЧӮӘӢNӮұӮйӮұӮЖӮаӮ ӮБӮҪҒBҲк•ыҒAӮұӮМ”Һ——үпӮН1888”NӮ©ӮзӮМҲУҸ “oҳ^җ§“xӮр‘ЈҗiӮөӮҪӮұӮЖӮа’Қ–ЪӮіӮкӮйҒBҗӯ•{ӮНҲУҸ Ҹр—бӮрҺРүпӮЙ”F’mӮіӮ№ӮйҲУҗ}ӮМӮаӮЖҒAҸo“W•ЁӮЙҢАӮиҸoҠиҺиҗ”—ҝӮЖ“oҳ^—ҝӮр’ҘҺыӮөӮИӮўӮұӮЖӮЙӮөӮҪӮМӮЕҒAҸoҠиҗ”ӮӘӢ}‘қӮөӮҪҒB ӮұӮМӮжӮӨӮЙ—lҒXӮИҗVӮөӮў“®Ӯ«ӮӘӮ ӮБӮҪ‘ж3үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA•sҢiӢCӮИӮЗӮаҸdӮИӮиҒAҸo•iҗ”ӮМ‘қүБӮЙ‘ОӮөӮДҒA‘е—КӮМ”„ӮкҺcӮиӮӘҸoӮйҢӢүКӮЖӮИӮБӮҪҒB ҒЎ “аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮа3үсӮрҗ”ӮҰҒAҺҹ‘жӮЙҺРүпӮЙ’и’…ӮөӮДӮўӮӯҒBҗӯ•{Ҹo“W•iӮӘҗRҚё‘ОҸЫҠOӮЖӮіӮкҒAӮұӮұӮ©Ӯз–ҜӢЖҗUӢ»ӮМҗ«ҠiӮӘ–ҫҠmӮЖӮИӮБӮҪҒB–JҸЬӮМ“ҷӢүӮӘҸӨ•iүҝ’lӮрҚ¶үEӮ·ӮйӮҪӮЯҒAҗRҚёӮЙ‘ОӮ·Ӯй•s–һӮаҸoӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB1884”NӮМҸӨ•WҸр—бӮр”зҗШӮиӮЙ“БӢ–җ§“xӮМҗ®”хӮаҗiӮЭӮВӮВӮ ӮБӮҪҒBҸo“W•iҗ”ӮН‘OүсӮр—ҪӮ¬ҒAӮ»ӮМҺн—ЮӮа‘Ҫ—lү»ӮөҒAӢ@ҠBҗ»•iӮМ•Ә—ЮӮӘҸЪҚЧү»ӮіӮкӮйҒB –ҜҠФҸo•iӮН‘OүсӮМ–с4”{Ӯа‘қүБӮөӮҪӮаӮМӮМҒA‘еҢ^Ӣ@ҠBӮЙӮВӮўӮДӮНҺQҚlӮЖӮөӮД“WҺҰӮіӮкӮҪҠҜҗ»•iӮМӮЭӮЕҒAҚЕӮаҸo“Wҗ”ӮӘ‘ҪӮ©ӮБӮҪҒuӢCӢ…ҒEӢDҺФҒEӢD‘D“ҷҒvӮМ•”–еӮЕӮаҒA‘е”јӮН”nӢпӮЕҒAҸцӢCҺФӮв“dҺФӮМҸo“WӮНҲк•iӮаӮИӮ©ӮБӮҪҒBүпҸк“аӮЙ“ҢӢһ“d“•Ҡ”Һ®үпҺРӮМ“ЎүӘҺsҸ•ӮӘ—A“ьӮМ“dҺФӮр‘–ӮзӮ№ӮДӮНӮўӮҪӮӘҒA“БӮЙ“S“№ҠЦҢWӮНӮЬӮҫҠҜүcӮӘ’ҶҗSӮЕӮ ӮБӮҪӮҪӮЯӮЙӮұӮМӮжӮӨӮИҸу‘ФӮҫӮБӮҪҒB‘ў‘DӢЖӮН‘ҒӮӯӮ©ӮзҺYӢЖү»ҒE–Ҝүcү»ӮіӮкӮДӮЁӮиҒAҗмҚи‘ў‘DҸҠӮӘ‘е–C—A‘—‘D–НҢ^ӮрҸo“WӮөӮДӮўӮйҒB“Sҗ»ӮМҸцӢC‘DӮЕӮ ӮйҒBҺQҚlҸo•iӮЕӮНҠCҢRҸИӮМҢRҠН–НҢ^ӮӘӮ ӮБӮҪҒB –aҗСҠЦҢWӮМҸo“WӮН‘Ҡ•ПӮнӮзӮё‘ҪӮ©ӮБӮҪӮӘҒAҠi’iӮМҗi•аӮНҢ©ӮзӮкӮИӮ©ӮБӮҪҒBҗ”ҸӯӮИӮўҺуҸЬҺТӮМ’ҶӮЙӮНҒAҲИҚ~ҺуҸЬӮрҸdӮЛӮйҢд–@җм’јҺOҳYӮМ–ј‘OӮӘӮ ӮйҒB ”_ӢЖӢ@ҠBӮЕӮНҒA“n•У–ңӢgӮМҢy•Ц‘Е”фҠн(”n—Н’EҚ’Ӣ@Ӯрҗl—pӮЙүь‘ў)ӮӘҺуҸЬӮөӮДӮўӮйҒBҗl—НӮМҸИ—Нү»Ӯрҗ}ӮлӮӨӮЖӮөӮДӮўӮҪ”_ҸӨ–ұҸИӮМҲУҗ}ӮЖӮНӢtҚsӮ·ӮйӮӘҒAҗlҠФӮМ’АӢаӮМ•ыӮӘ”nӮМҺg—pӮжӮиҲАүҝӮҫӮБӮҪ“–ҺһӮМҢ»ҸуӮрӮУӮЬӮҰӮДӮўӮҪҒB Ңҙ“®Ӣ@•”–еӮМҸo•iӮН17“_ӮЙ—ҜӮЬӮБӮҪӮӘҒA“ҢӢһ“d“•Ҡ”Һ®үпҺРӮӘғGғWғ\ғ“ҒEғ_ғCғiғӮ(”ӯ“dӢ@)ӮМ–Н‘ў“ҷӮрҸo•iӮөҒA“d—НӮМҺһ‘гӮМ“һ—ҲӮрҺҰӮөӮҪҒB’Ҷүӣ”ӯ“dӮЙӮжӮй“d—НҺ–ӢЖӮМӮНӮ¶ӮЬӮиӮНҒAӮұӮМ“ҢӢһ“d“•Ҡ”Һ®үпҺР(1886”NҗЭ—§)ӮЕҒA”’”M“”ӮрӢҹӢӢӮөӮҪҒBӮ»ӮМҢгҺҹҒXӮЙҒA‘еҚгҒAӢһ“sӮИӮЗӮЕ“d“”үпҺРӮӘҚмӮзӮкӮДӮўӮйҒBҸo“W•iӮЕӮНҒAӮЩӮ©ӮЙҒAҗОҗм“Ү‘ў‘DҸҠӮӘҒu”•—pҚӮҲіҸцӢCӢ@ҠBҒvӮЕҸЬӮр“ҫӮДӮўӮйҒB–ҜҠФӢ@ҠBҚHӢЖӮӘӮЯӮОӮҰӮВӮВӮ ӮБӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж4үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп / Ӣһ“sӮМҠӘӮ«•ФӮө
ҠJҚГҠъҠФҒF1895(–ҫҺЎ28)”N4ҢҺ1“ъҒ`7ҢҺ31“ъҸкҸҠҒFӢһ“sҺsүӘҚиҢцүҖ“ьҸкҺТҗ”ҒF1,136,695җl ”Һ——үпҠJҚГӮӘ—ҳүvӮрӮӨӮЮӮұӮЖӮӘҺь’mӮіӮкӮҪӮҪӮЯҒA—U’vҠҲ“®ӮӘҚsӮнӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒA‘ж4үсӮМҠJҚГ’nӮНҒA“ҢӢһ‘J“sҲИҚ~ӮМ’б–АӮрҠҲҗ«ү»ӮөӮҪӮўӢһ“sӮЙҢҲӮЬӮБӮҪҒB“–ҸүҒA‘ж4үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮН1894”NӮЙҠJҚГӮіӮкӮй—\’иӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒAӢһ“sҺs–ҜӮНӢһ“sӮМҢҡ“s1100”NӮМӢL”OҺ–ӢЖӮЖӮөӮДҒA1895”NӮЙҠJҚГӮ·ӮйӮұӮЖӮрӢӯӮӯ–]ӮсӮҫҒB1894”NӮЙӮН“ъҗҙҗн‘ҲӮӘ–u”ӯӮөӮҪӮӘҒAҗӯ•{ӮНҗBҺYӢ»ӢЖҗӯҚфӮНҗнҺһ’ҶӮЕӮ ӮБӮДӮаҸd—vӮЕӮ ӮйӮЖӮөҒA—\’и’КӮиӮМҠJҚГӮрҢҲӮЯӮҪҒB үпҸкӮН•ҪҲАҗ_Ӣ{ӮМ“мӮЙ“–ӮҪӮиҒAүпҸк–КҗПӮН17–ң8,000•Ҫ•ығҒҒ[ғgғӢҒAҢҡ•Ё•~’n‘Қҗ”ӮН4–ң7,000•Ҫ•ығҒҒ[ғgғӢӮЕӮ ӮБӮҪҒBүпҸкӮМҗі–КӮЙӮН‘е—қҗОҗ»ӮМ•¬җ…ӮӘҢҡӮҝҒAӮ»ӮМҚ¶үE—ј‘ӨӮЙ”„“XӮӘ•АӮсӮҫҒB Ңҡ•ЁӮНҒA”ьҸpҠЩҒAҚHӢЖҠЩҒA”_—СҠЩҒAӢ@ҠBҠЩҒAҗ…ҺYҠЩҒA“®•ЁҠЩӮМ6ҠЩӮӘҺе—vӮИӮаӮМӮЕӮ ӮиҒAӢ@ҠBҠЩӮМ“®—НҢ№ӮНӮ»ӮкӮЬӮЕӮМҗО’YӮ©Ӯз“d—НӮЙ•ПӮнӮБӮҪҒB җ…ҺYҠЩӮМ‘OӮЙӮНҗ…ҺYҺәҒAҚЎ“ъӮЕӮўӮӨҗ…‘°ҠЩӮӘӮ ӮиҒAүVӮвҢпҒA•©ӮИӮЗӮрҢ©Ӯ№ӮҪҒBӮұӮұӮЕӮНӢӣӮрҸгӮ©ӮзҢ©ӮйӮЖӮўӮӨӮ»ӮкӮЬӮЕӮМ•ы–@ӮЖӮНҲЩӮИӮиҒA‘Ө–КӮ©ӮзҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮЕ’ҝӮөӮӘӮзӮкӮҪҒBӮҪӮҫӮөҠCҗ…ӢӣӮНӮұӮұӮЕӮНҢ©ӮзӮкӮёҒA•әҢЙҢ§ӮМҳa“c–ҰӮЙӮ Ӯй—VүҖ’nҳaҠyүҖ“аӮЙҗЭӮҜӮҪҗ¶ӮҜвЕӮЕҢ©ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮҪҒB ӮЬӮҪҒA”ьҸpҠЩӮЕӮНғtғүғ“ғXӮ©ӮзӢAӮБӮҪҚ•“cҗҙӢPӮӘҸo•iӮөӮҪҒw’©ӣBҒxӮЖ‘иӮөӮҪ—Ү‘Мүж(ӮМӮҝӮЙҸДҺё)ӮӘҒA•—‘ӯҸп—җӮМ‘е‘ӣ“®ӮрӢNӮұӮөӮҪҒBҢӢӢЗҒAҠGӮМҲк•”Ӯр•zӮЕ•ўӮБӮД’В—с‘ұҚsӮЙ—ҺӮҝ’…ӮўӮҪӮӘҒAғrғSҒ[(G. Bigot)ӮМ•—Һh–ҹүжӮЙӮаӮұӮМҺ–ҢҸӮӘ“oҸкӮөӮДӮўӮйҒB ӮЩӮ©ӮЙ‘еӮ«ӮИҳb‘иӮЖӮөӮДҒAүпҸкӮМҠOӮЙҗіҺ®ӮИҢр’КӢ@ҠЦӮЖӮөӮД“ъ–{ӮЕӮНӮ¶ӮЯӮДҺsҠX“dҺФӮӘ“oҸкӮөӮҪӮұӮЖӮӘӮ ӮйҒBү^ҚsӮНҒAӢһ“sҺөҸрӮ©ӮзүпҸкӮМ•ҪҲАҗ_Ӣ{•tӢЯӮЖ”ъ”iҢО‘`җ…ӮМӮЩӮЖӮиӮЬӮЕҒA“мӮМ•ҡҢ©•ы–КӮЙӮа‘–ӮиҒA“d—НӮН‘aҗ…ӮМҗ…—Н”ӯ“dӮЕӮЬӮ©ӮИӮБӮҪҒB“d—НҺһ‘гӮМ–ӢҠJӮҜӮрҸЫ’ҘӮ·ӮйӮаӮМӮЖҢҫӮҰӮжӮӨҒB үҪӮ©ӮЖҳb‘иӮМ‘ҪӮў”Һ——үпӮЕӮ ӮБӮҪӮӘҒA7–ң3,781җlӮМҸo•iҗlӮ©Ӯз16–ң9,098“_ӮМҸo•iӮр“ҫӮДҒA“ьҸкҺТҗ”Ӯа113–ң6,695җlӮЙ’BӮөҒA‘е•ПӮИ“цӮнӮўӮМ’ҶӮЕҸI—№ӮөӮҪҒBӮЬӮҪҒA“№ҳHҒE—·ҸhӮМҗ®”хӮӘҗiӮЭҒAӢһ“sӮМҠПҢх“sҺsӮЖӮөӮДӮМҠо‘bӮӘҚмӮзӮкӮҪҒB ҒЎ ӮұӮұӮЙӮ«ӮДҒAҚHӢЖ•”—ЮҲИҠOӮНҒAҢ¬•АӮЭҸo“W•iӮӘҢёҸӯӮ·ӮйӮЖӮўӮӨҺ–‘ФӮӘӢNӮ«ӮҪҒB“ъҗҙҗн‘ҲӮМүeӢҝӮЙӮжӮй‘ў‘DҸҠӮМ”Й–ZҒA—A‘—‘D’Ҙ—pӮЙӮжӮйү^‘—Һи’iӮМҢҮ”@ӮИӮЗӮӘҲкҲцӮЖӮўӮнӮкӮйҒB ’Қ–Ъ“xӮМҚӮӮўҢҙ“®Ӣ@•”–еӮМҸo“WӮН7“_ӮЙ—ҜӮЬӮиҒAҺЕүYҗ»ҚмҸҠ(Ң»Ғu“ҢҺЕҒv)җ»ӮМ•—ҺФӮв“ЎҲд‘Қ‘ҫҳYӮМ’Ң•tҢұҗ…Ҡн(ғ{ғCғүҒ[ӮМӢCҲіҸгҸёӮЙӮжӮйҺ–ҢМӮр–hҺ~Ӯ·Ӯй‘•’u)ӮӘҺуҸЬӮөӮДӮўӮйҒB ӮөӮ©ӮөҒAҗVӮөӮўҺYӢЖӮН’…ҺАӮЙҲзӮБӮДӮЁӮиҒA”ӯ“dҒE“dӢCүһ—pӮМ•”ӮӘҗVҗЭӮіӮкӮДӮўӮйҒB‘O”NӮЙҗЭ—§ӮіӮкӮҪӢһ“s“dӢC“S“№ӮЙӮжӮйҒA“ъ–{ҸүӮМүcӢЖ—p“dҺФӮаӢһ“sҺs“аӮр‘–ҚsӮөӮДӮўӮҪ(ғӮҒ[ғ^Ғ[ӮНҒAҚ‘ҺYӮЖ—A“ьӮМ—ј•ы)ҒB“dӢCӮМ•Ә–мӮН—A“ьӮЙ—ҠӮй•”•ӘӮаҸӯӮИӮӯӮИӮ©ӮБӮҪӮӘҒAү«үе‘ҫҳY(Ң»Ғuү«“dӢCҚHӢЖҒvӮМ‘nҺnҺТ)ӮӘ“dҗMӢ@Ӯв“dҳbӢ@ӮрҒAҺЕүYҗ»ҚмҸҠӮӘ•ПҲіҠнӮвғAҒ[ғN“”ӮИӮЗӮрҸo•iӮөӮДҺуҸЬӮөӮДӮўӮйҒB –aҗСҠЦҢWӢ@ҠBӮНҒAҸo•iҗ”ӮҫӮҜ‘ҪӮў’б–АӮМҸу‘ФӮЕӮ ӮБӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕҒAүпҸк“аӮЕү^“]ӮіӮкӮҪҢд–@җм’јҺOҳYҸo“WӮМҗ»Һ…Ӣ@(ҺlҸрҢJҺ…Ӣ@ҒҒҗ¶Һ…ӮрҠӘӮ«ҺжӮйҸ¬ҳgӮрӮұӮкӮЬӮЕӮМ“сӮВӮ©ӮзҺlӮВӮЙ‘қӮвӮөӮДҗ¶ҺYҗ«ӮрҢьҸгӮіӮ№ӮҪ)ӮНҚD•]Ӯр“ҫӮДҒAӮ»ӮМҢг‘SҚ‘ӮЙҗЭ’uӮіӮкӮДӮўӮБӮҪҒB ‘јӮЙ“Б•MӮ·ӮЧӮ«Ҹo“W•iӮНӮ ӮЬӮиӮИӮўӮӘҒAҗуҸА“ЎӢg(җуҸАҸӨүп)ҒAҗҷүYҳZүEүq–е(ӮМӮҝӮМҒuғRғjғJҒv)ҒAҺR“c—^Һө(Ң»ҒuҢГүН“dӢCҚHӢЖҒv)ӮзҒAҚЎӮЙ‘ұӮӯҠйӢЖӮМ‘nҺnҺТ’BӮМҸo“WӮӘ–ЪӮрҲшӮӯҒB“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮНҸӨ•iҗй“`ӮМҸкӮЖӮөӮДӮМ’nҲКӮр“ҫӮДҒA–ҜҠФӮЙӮаҠҲ—pӮіӮкӮВӮВӮ ӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ‘ж5үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп / ҚЕҢгӮЙӮөӮДҚЕ‘еӮМ“аҚ‘”Һ
ҠJҚГҠъҠФҒF1903(–ҫҺЎ36)”N3ҢҺ1“ъҒ`7ҢҺ31“ъҸкҸҠҒF‘еҚгҺs“VүӨҺӣҚЎӢ{“ьҸкҺТҗ”ҒF4,350,693җl 1903(–ҫҺЎ36)”NӮЙ‘еҚгӮЕҠJҚГӮіӮкӮҪ”Һ——үпӮЕӮ ӮйҒB‘ж5үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮН“–ҸүҒA1899”NӮЙҠJҚГ—\’иӮҫӮБӮҪӮӘҒA1900”NӮМғpғҠ–ң”ҺҒA1901”NӮМғOғүғXғSҒ[–ң”ҺӮЦӮМҺQүБҸҖ”хӮМӮҪӮЯү„ҠъӮіӮкӮҪӮЖӮўӮӨҢoҲЬӮӘӮ ӮйҒB“ъҗҙҗн‘Ҳ(1894-95”N)ӮМҸҹ—ҳӮЙӮжӮиҠeҠйӢЖӮӘҠҲ”ӯӮЙҺsҸкӮрҠg‘еӮөӮДӮўӮҪӮұӮЖҒA“S“№–ФӮӘӮЩӮЪ“ъ–{‘SҚ‘ӮЙӮнӮҪӮБӮҪӮұӮЖӮИӮЗӮӘӮ ӮиҒA”Һ——үпӮЦӮМҠъ‘ТӮН‘еӮ«ӮӯҒA•~’nӮН‘OүсӮМ“с”{—]ҒAүпҠъӮаҚЕ’·ӮМ153“ъҠФӮЕҒAҚЕҢгӮЙӮөӮДҚЕ‘еӮМ“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпӮЖӮИӮБӮҪҒB үпҸкӮЙӮНҒA”_ӢЖҠЩҒA—СӢЖҠЩҒAҗ…ҺYҠЩҒAҚHӢЖҠЩҒAӢ@ҠBҠЩҒAӢіҲзҠЩҒA”ьҸpҠЩҒA’Кү^ҠЩҒA“®•ЁҠЩӮМӮЩӮ©ҒA‘дҳpҠЩҒAҺQҚlҠЩӮӘҢҡҗЭӮіӮкӮҪ(ҺКҗ^)ҒBҢҡ•ЁӮНӮұӮкӮЬӮЕӮМүјҗЭӮЕӮНӮИӮӯҺҪӢт“hӮиӮЕҒA”ьҸpҠЩӮН‘еҚгҺs–Ҝ”Һ•ЁҠЩӮЖӮөӮДӮ»ӮМҢгҺgӮнӮкӮДӮўӮйҒB‘ж“сүпҸкӮЖӮөӮДҒAҚдӮЙҗ…‘°ҠЩӮаҢҡӮДӮзӮкӮҪҒB Ҹ«—ҲӮМ–ң”ҺӮрҲУҺҜӮөӮДҢҡӮДӮзӮкӮҪҺQҚlҠЩӮНҒAӮ»ӮкӮЬӮЕ”FӮЯӮзӮкӮДӮўӮИӮ©ӮБӮҪҸ”ҠOҚ‘ӮМҗ»•iӮр’В—сӮөӮДӮЁӮиҒAғCғMғҠғXҒAғhғCғcҒAғAғҒғҠғJҒAғtғүғ“ғXҒAғҚғVғAӮИӮЗҸ\җ”Ӯ©Қ‘ӮӘҸo•iӮөӮҪҒBӮ»ӮМ’ҶӮЕҗVӮөӮўҺһ‘гӮрӢӯӮӯҲуҸЫ•tӮҜӮҪӮМӮНғAғҒғҠғJҗ»ӮМ8‘дӮМҺ©“®ҺФӮЕӮ ӮБӮҪҒB“аҚ‘”Һ——үпӮЖӮўӮҰӮЗӮаҒA”OҠиӮМ–ңҚ‘”Һ——үпӮЙӢЯӮГӮўӮДӮўӮйӮЖҢҫӮҰӮжӮӨҒB ҸүӮЯӮДӮМ–йҠФҠJҸкӮӘҚsӮнӮкҒAүпҸкӮЙӮНғCғӢғ~ғlҒ[ғVғҮғ“ӮӘҺжӮи•tӮҜӮзӮкӮҪҒB‘啬җ…Ӯа5җFӮМҸЖ–ҫӮЕғүғCғgғAғbғvӮіӮкҒAғGғҢғxҒ[ғ^Ғ[ӮВӮ«ӮМ‘е—СҚӮ“ғӮаҗlӢCӮрҢДӮсӮҫҒBӮұӮкӮзӮНҒA“ъ–{ӮЙӮа–{Ҡi“IӮИ“d—НҺһ‘гӮӘ“һ—ҲӮөӮҪӮұӮЖӮрҺҰӮөӮДӮўӮйҒBӮЬӮҪҒA’ғүPҺRӮМ’rӮМӮЩӮЖӮиӮЙҗЭӮҜӮзӮкӮҪ”т’шӢY(ғEғHҒ[ғ^Ғ[ғVғ…Ғ[ғg)ҒAғҒғҠҒ[ғSҒ[ғүғEғ“ғhҒAғpғmғүғ}җўҠEҲкҺьҠЩҒA•sҺvӢcҠЩ(“d“”ӮвүО–тӮр—pӮўӮҪҢ¶‘z“IӮИ•‘“ҘҒA–іҗь“dҗMҒAXҗьҒAҠҲ“®ҺКҗ^ӮИӮЗӮрҢ©Ӯ№ӮҪ)ҒA‘еӢИ”nӮИӮЗҒAҢвҠyҺ{җЭӮӘҗlӢCӮрҢДӮсӮҫҒBҚдӮМҗ…‘°ҠЩӮН“сҠKҢҡӮДӮМ–{Ңҡ’zӮЕҒA•ВүпҢгӮНҚдҗ…‘°ҠЩӮЖӮөӮДҺs–ҜӮЙҗeӮөӮЬӮкӮҪҒBҠeҠЩӮН–йҠФӮН•ВҠЩӮөӮДӮўӮҪӮЙӮаӮ©Ӯ©ӮнӮзӮёҒA‘ҪӮӯӮМ“ьҸкҺТӮНӮұӮкӮзӮМғCғӢғ~ғlҒ[ғVғҮғ“Ӯв—]Ӣ»–Ъ“–ӮДӮЕ—ҲҸкӮөҒA“ьҸкҺТӮН“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үпҺnӮЬӮБӮДҲИ—ҲӮМҗ”ӮрӢLҳ^ӮөӮҪҒB –{—ҲҒAҚ‘“аӮМҺYӢЖҗUӢ»Ӯр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮҪ“аҚ‘”ҺӮНҒA“ьҸкҺТӮМҸБ”п“ҷӮЙӮжӮйҢoҚПҢшүКӮЙҸd“_ӮӘ’uӮ©ӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮиҒAҺ–ҺАҒA‘еҚгҺsӮН”ң‘еӮИҢoҚПҢшүКӮрҺуӮҜӮҪҒB”Һ——үпӮН“sҺsӮрҠҲҗ«ү»ӮіӮ№ӮйҺи’iӮЖӮөӮДҸd—vҺӢӮіӮкҒA–ңҚ‘”Һ——үпӮМ“ъ–{ҠJҚГӮЦҠъ‘ТӮӘҚӮӮЬӮиҒA1907”NӮЙ—\’иӮіӮкӮҪ‘ж6үсӮр–ңҚ‘”Һ——үпӮЙҒAӮЖӮўӮӨҗәӮаҸгӮӘӮйҒBӮөӮ©ӮөҒA“ъҳIҗн‘ҲӮМӮМӮҝҚаҗӯ“пӮЙҠЧӮйӮЖҒAҺYӢЖҗUӢ»ӮМ”п—p‘ОҢшүКӮрӢ^–вҺӢӮіӮкӮД‘ж6үсӮНү„ҠъҒAӮВӮўӮЙӮН’ҶҺ~ӮіӮкӮДӮөӮЬӮӨҒBӮ»ӮМҢгҒA•{Ң§ӮЙӮжӮй”Һ——үпӮНҠJӮ©ӮкӮйӮаӮМӮМҒAҚ‘үЖ“I”Һ——үпӮМ“ъ–{ӮЕӮМҺАҢ»ӮНҒAҗнҢгҒA1970”NӮМ‘еҚг–ң”ҺӮЬӮЕ‘ТӮВӮұӮЖӮЖӮИӮйҒB ҒЎ ‘ж5үсӮЕӮНҒAҸгҲКҺуҸЬҺТӮМ”јҗ”ҲИҸгӮрҠйӢЖӮӘҗиӮЯӮДӮЁӮиҒAҚ‘“аҠйӢЖӮМҗ¬’·ӮрүMӮӨӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒBҚHӢЖҠЦҢWӮМҸo•iӮН‘S‘МӮМүЯ”јҗ”ӮЙӮаҸгӮБӮҪҒB “ъҗҙҗн‘ҲӮЙӮЁӮўӮД‘D”••s‘«Ӯр’ЙҠҙӮөӮҪҗӯ•{ӮНҒA1890”N‘гҢг”јӮ©Ӯз‘ў‘DӢЖӮрҸ§—гӮөҒAүў•ДӮЖҢЁӮр•АӮЧӮйӮЬӮЕӮЙӮН“һӮзӮИӮўӮаӮМӮМҒAҺYӢЖӮЖӮөӮДӮМ”ӯ“WӮрӮЭӮйҒBҺO•H‘ў‘DҸҠҒAҗмҚи‘ў‘DҸҠҒA‘еҚг“SҚHҸҠӮМ‘D–НҢ^ӮИӮЗӮӘҺуҸЬӮөӮДӮЁӮиҒAҺуҸЬ—қ—RӮЖӮөӮДҒAҸo“W•iӮМ•]үҝҲИҠOӮЙҒAҗ»ҚмӮМӮҪӮЯӮМӢ@ҠBҗЭ”хӮМҗ®”хҒAӢZҸpҺТ—{җ¬“ҷҒAӢЖҠE‘S”КӮЙӮнӮҪӮйҚvҢЈӮӘҗGӮкӮзӮкӮДӮўӮйҒBӮЩӮ©ӮЙҒAҸцӢCӢ@ҠЦҺФӮЕӮМҺуҸЬӮаҢ©ӮзӮкӮйҒBҺ©“®ҺФӮНҒA—A“ь•iӮМғfғӮғ“ғXғgғҢҒ[ғVғҮғ“ӮрӮөӮДӮўӮй’iҠKӮҫӮБӮҪҒB “dӢC•Ә–мӮЕӮНҒAү«үе‘ҫҳYӮМ“dӢC’КҗMӢ@ҒA“ъ–{“dӢCҠ”Һ®үпҺР(•ДҚ‘ғEғFғXғ^ғ“ҒEғGғҢғNғgғҠғbғNҺРӮЖӮМҚҮ•ЩӮЕ1899”NҗЭ—§)ӮМ“dҳbӢ@ҒA“ҢӢһ“dӢCҠ”Һ®үпҺР(ӮМӮҝӮЙҒu“ҢҺЕҒv)Ҹo“WӮМҠeҺн“dӢ…ӮӘҒAҗ»•iӮМҗ«”\ӮЖӮЖӮаӮЙ’бүҝҠiӮӘ•]үҝӮіӮкӮДҸЬӮр“ҫӮДӮўӮйҒB“ҜӮ¶ӮӯҺуҸЬӮөӮҪү®Ҳдҗж‘ ӮМҠЈ“d’rӮН“–ҺһҠCҠOӮЙ—AҸoӮіӮкӮДӮўӮҪҢчҗСӮӘ•]үҝӮМғ|ғCғ“ғgӮҫӮБӮҪӮжӮӨӮҫҒBҺЕүYҗ»ҚмҸҠӮЙӮжӮй”ӯ“dӢ@ӮаҺуҸЬӮөӮДӮўӮйӮӘҒAӮұӮҝӮзӮМ“а•”•”•iӮН—A“ь•iӮЕӮ ӮБӮҪҒB –aҗСӮМ•Ә–мӮЕӮНҒAҢд–@җм’јҺOҳYӮМҸ\“сҸрҢJҺ…Ӣ@ӮӘҸo•iӮіӮкӮйҒBҗ»Һ…ҚмӢЖҢш—ҰӮрҢьҸгӮіӮ№ӮйӮаӮМӮЕҒAҗ»Һ…Ӣ@ҠBҚ‘ҺYү»ӮЦӮМ“№ӮрҠJӮўӮҪҒB Ңҙ“®Ӣ@•”–еӮМҸo“WӮН76“_ӮЙӮаӢyӮСҒAҠCҢRӢZҸpҺТӮМӢ{Ңҙ“сҳYҸo“WӮМҗ…ҠЗҺ®ӢDгЈ(ғ{ғCғүҒ[)ӮӘҸЬӮр“ҫӮйҒBҗ«”\ӮаӮіӮйӮұӮЖӮИӮӘӮзҒA—nҗЪӮвҲЫҺқӮӘ—eҲХҒAҚ‘“аӮЕҸC—қҒEҗ»‘ўӮӘүВ”\ӮЖӮўӮӨӮМӮӘ‘еӮ«ӮИ—ҳ“_ӮЕҒAӮЩӮЗӮИӮӯҢRҠНӮЙ“ӢҚЪӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB ӮИӮЁҒAҠOҚ‘җ»•iӮЙӮВӮўӮДӮНҒAӮұӮМ”Һ——үпӮЕӮжӮӨӮвӮӯҺ©—RӮИҸo•iӮв”М”„ӮӘӢ–үВӮіӮкҒAҺQҚlҠЩӮЕ“WҺҰӮӘҚsӮнӮкӮҪҒB“ъ–{ӮН1899”NӮЙҚHӢЖҸҠ—LҢ ӮМҚ‘ҚЫ“I•ЫҢмӮр’иӮЯӮҪғpғҠҸр–сӮЙүБ–ҝӮөӮҪӮМӮЕҒA‘z’иӮрҸгүсӮйҸ\җ”Ӯ©Қ‘ӮаӮМҸo“WӮӘӮ ӮБӮҪҒBӮұӮМүБ–ҝӮНҒA“ҜҺһӮЙҒA“ъ–{ӮӘӮаӮНӮвҠOҚ‘ӮМ–Н‘ўӮЙӮН—ҠӮкӮИӮўҒAӮЖӮўӮӨӮұӮЖӮрҲУ–ЎӮөӮҪҒBҒ@ |
|
|
ҒЎ“ҢӢһҠ©ӢЖ”Һ——үп / җV•·ӢLҺ–”ІҗҲ
(–ҫҺЎ40”N3Ғ`7ҢҺҒAҺеҚГ“ҢӢһ•{ҒE“ҢӢһҸг–мүпҸкӮЙӮДҠJҚГ) ҒЎ–ҫҺЎ40”N6ҢҺ17“ъ(“З”„җV•·)/Ғu”Һ——үп”„“XӮМӮјӮ«Ғv ҒңӢЈ‘ҲӮМҲА”„ӮиҒ@үпҸкҠOӮМ”„“XӮНүҪӮкӮаӢЈ‘ҲӮМҢ`ӮЕ‘е•ЧӢӯ‘еҲА”„ӮиӮрӮөӮДӢҸӮйӮ©ӮзӮЁ“yҺYӮМ”ғӮў•ЁӮН–}ӮД‘ҙҸҲӮЙҢАӮйӮЖ“ЖӮиӮЕ’иӮЯӮД‘ж“сүпҸкҠП——ӮМӢA“rҠПҢҺ–еӮжӮиҸoӮЕ’rӮМҗј”ИӮИӮй•\–КӮжӮиҸ„ҺӢӮ·ӮкӮО Ғң•һ•”Һө•у“X(—Ә) ҒңүӘҺRҢ§•ЁҺY”„“X(—Ә) ҒңғAғCғkҠЩҒ@ҠЩӮЖү]ӮӨӮЖӮЗӮӨӮвӮз‘еҢUҚҫӮЙҺvӮнӮкӮйӮӘ‘ҙӮМҺАҸ¬ӮіӮИ”„“XӮЙүЯӮ¬ӮКӮМӮЕғAғCғkҗlҺнӮМҗ»Қм•iӮЖҸМӮө–ШҚЧҚHҒAҚbҠ|ӮҜҒA’№”зӮМ—ЮӮрҠ|ӮҜ—сӮЛ–TӮЙ’ғҲщӮЭҸҠӮИӮЗӮаҗЭӮҜӮДӮ ӮиӮЬӮҪб°ӮӯӮҝӮбӮМӮЁ”kӮіӮсӮӘ“XҗжӮЙҚTӮҰӮДғcғҢғbғvӮЖ–јӮГӮӯӮйғAғCғkғmүЩҺqӮрҲк‘ЬҢЬ‘KӮЕ•pӮиӮЙ”ғӮҰ”ғӮҰӮЖ‘EӮЯӮДӮўӮйӮӘҠF‘ЬӮЦ“ьӮкӮБӮ«ӮиӮЕҢ©–{ӮЖү]ӮӨ•ЁӮӘҲкӮВӮаҸoӮДӮЁӮзӮКӮҪӮЯҢ•“ЫӮӘӮБӮД”ғӮӨҗlӮӘӮўӮИӮў Ғң”ҹҠЩ–јҺY”„“XҒ@ӮЙӮНҠұӮөйЖ(Ӯ·ӮйӮЯ)ӢyӮСҚ©•zҒAүЩҺqҒAҚ©•z’ғҒAҚ©•zҠКӢlӮМ—ЮӮӘӮ Ӯи”VӮН—ЧӮЖҲбӮўҲкҢыӮГӮВӮНүҪӮЕӮаҢ©–{ӮрӮВӮЬӮЬӮ№ӮйӮМӮЕ’ҶҒX”Йҗ·ӮөӮДӮўӮй(ҲИүә—Ә) ҒЎ–ҫҺЎ40”N4ҢҺ25“ъ(“ҢӢһ’©“ъҗV•·)/ҒuҸ”Қ‘–јҺY”„“XӮЯӮ®Ӯи(Ҳк)Ғv –wӮЗ‘SҚ‘Ӯр–Ф—…Ӯ№Ӯй–јҺY‘өӮўҒA’ҝӮөҒAӢCӮЙ“ьӮкӮиҒA“yҺYӮЙ’јӮ®ӮЖ”ғӮнӮсӮЖӮНҺvӮҰӮЗӮа’В—сҸкӮЙӮДӮНғIғCғ\ғҢӮЖӮаҺQӮзӮЛӮО’rӮМ’[ӮИӮй‘Ұ”„“XӮМҸdӮИӮйӮаӮМӮрҸРүоӮ·ӮЧӮө ҒңғAғCғkҚм•i”„“XҒ@ҠПҢҺ–еӮрҸoӮЕӮДҒAҺlҢЬҢ¬ҚsӮӯӮЖүE‘ӨӮЙғAғCғkӮМ“XӮӘӮ ӮйҒAҚм•iӮНҗ”‘ҪӮ©ӮзӮЛӮЗҒAзлҒA–~ҒAгNҢһӮ«ӮИӮЗ—бӮМ•s“ҫ—v—МӮМ’ӨӮӘӮ ӮБӮДҗжӮёҢГүлӮЖҢ©ӮкӮОҢ©ӮйүВӮөӮЕӮ ӮйҒAҺҹӮЙӢrгJ• ҠӘ—lӮМ•ЁӮаӮ ӮиӮДӣx(ӮўӮёӮк)Ӯа“йҳH(ғNғVғҚ)ҒAҸtҚМ(ғnғӢғgғҠ)ҒA•W’ғ(ғVғyғ`ғғ)ҒA”’“ң(ғVғ’ғ^ғE)ӮМ“yҗlӮМҺиӮЙҗ¬ӮБӮҪӮЖү]ӮӨӮұӮЖӮҫӮӘ’иүҝӮӘ”»‘RӮЖӮ№ӮКӮМӮЕ”ғӮўҺиӮӘҲкҗЎзSзOӮ·ӮйҒA–ЮӮағ`ғүғҠғzғүғҠ—…”nҗ”ҺҡӮЕ450ӮИӮЗӮЖү]ӮӨҸ¬ҺDӮӘ–іӮўӮЕӮаӮИӮўӮӘҺlҸ\ҢЬ‘KӮвӮзҺl‘KҢЬ—РӮвӮзҗңӮйһB–ҶӮЕӮ ӮйҒA‘Ұ”„“XӮНҚЕӮаҗv‘¬ӮрӮҪӮБӮЖӮФӮМӮЙӮұӮсӮИҺ–ӮЙӮДӮНғXғOӮЖ‘ҙӮМҠФӮЙғAғCғk‘г•Ё(ӮөӮлӮаӮМ)ӮЖӮИӮй(Ңҙ•¶ғ}ғ})ҒA’ҚҲУӮ·ӮЧӮөӮҫҒAӮ»ӮкӮЙҚҹӮМ“XӮЙӮДӮНғAғCғkӮМҺиҗ»ӮЖҸМӮөғcғҢғbғvӮЖӮ©ү]ӮӨӮЁӮұӮөӮМ”@Ӯ«•ЁӮр”„ӮБӮДӢҸӮйӮӘҒAӮұӮсӮИ•ЁӮН“Ң–kӮЙҚsӮҜӮО“һӮйҸҠӮЙ‘тҺRӮ Ӯй ҒЎ–ҫҺЎ40”N6ҢҺ17“ъ (“З”„җV•·)/ҒuҠШҚ‘—¬ӮМ•wҗlүр•ъҒv ”Һ——үп‘жҲкүпҸк“аӮИӮйҗ…Ҹ»ҠЩӮӘҸкҸҠ•ҝӮМҲ«ӮөӮ«ҲЧӮ©ҲкҢь•sҢiӢCӮИӮйӮжӮиҒAҢДӮС•ЁӮЖӮ№ӮсӮЖӮДӮ©Ҳк–јӮМ’©‘N•wҗlӮрҢЩӮў“ьӮкӮұӮкӮрҠyҠн(ғIғӢғSҒ[ғӢ)ӮМ”PҠӘ(ӮЛӮ¶ӮЬ)Ӯ«ӮЖӮөӮДҺgӮўӢҸӮиӮөӮӘҒAӮұӮкӮЙӮжӮиӮД’[ӮИӮӯӮаҠШҚ‘—ҜҠwҗ¶ӮМҢғҚVӮрҸөӮ«–Ъүә•ҙ‘Ҳ’ҶӮИӮй—RҒBӮіӮД•·ӮӯҸҲӮЙӮжӮкӮОҢі—Ҳҗ…Ҹ»ҠЩӮМӢNҢ№ӮЖӮаү]ӮӨӮЧӮ«ӮНҸүӮЯ”Һ——үп‘жҲкүпҸк“аӮЙ’©‘NҠЩӮМ–јӮЙӮДҠJҸкӮ№ӮсӮЖӮөӢа–ЧӮҜӮЙ”ІӮҜ–ЪӮИӮ«җlҒXӮН’иӮЯӮДҚҹҸҲӮЙӮа‘ҪӮӯӮМ“ьҸкҺТӮӘӮ ӮйӮИӮзӮсӮЖҚlӮҰҒA‘ҙӮМҸкҸҠӮНүпҸк’ҶӢЙӮЯӮД•УзҝӮИӮйҸҲӮИӮкӮЗӮаҸ\ҢЬҳZҢ¬ӮМҲщҗH“XҢ¬Ӯр•АӮЧӮДҠJӢЖӮөӮҪӮйӮӘӮўӮжӮўӮж”Һ——үпӮМҠJүпӮіӮйҒTӮвӮұӮМ•УӮНҲкҢьӢqӮИӮӯҺАӮЙҺв”ңӮҪӮй—L—lӮИӮйӮжӮиҲщҗH“XӮМүcӢЖҺТӮНӮұӮкӮЕӮНӮИӮзӮКӮЖ”Һ——үпӮЙ’©‘NҠЩӮМ”ӯ“W•ы–@ӮрҠиӮўҸoӮЕӮҪӮйӮаҒAҲкҢьҺПӮҰҗШӮзӮҙӮйӮжӮи‘RӮзӮОӮЖ’№–”ҺеҗlҺӣ“Ү–”Ӣg“ҷӮЙӮД”ьҸpҠwҚZӮЙҲЛ—ҠӮөүҪӮ©ӢqҠсӮ№ӮМ•ы–@ӮрҚlҲДӮ№ӮсӮЖӮ№ӮөҢӢүКӮӘ‘ҰӮҝҚЎӮМҗ…Ҹ»ҠЩӮЙӮДҒA”Һ——үпӮжӮиӮН’©‘NҠЩӮМ•t‘®ӮЖӮөӮДӢ–үВӮөӮҪӮйӮИӮиҒB‘RӮйӮЙ‘ҙӮМҢгҚҹӮМҗ…Ҹ»ҠЩӮжӮиүә’JҢд“k’¬ҺO’ҡ–ЪҺlҸ\“с”Ф’nӮМ”С“c“S”VҸ•ӮЖү]ӮӨҗlӮЙҲЛ—ҠӮөӮД’©‘N•wҗl“A–Ҫҗж(“сҸ\)ӢyӮС’К•ЩӮрҢЩӮў“ьӮкҒAӢҺҢҺ“сҸ\“ъӮжӮи“ҜҠЩ“а•уӢК“a’ҶүӣӮЙҠyҠнғIғӢғSҒ[ғӢӮМ”PҠӘӮ«ӮЙҺg—pӮөӮҪӮйӮЙҒA‘ҙӮМҢгҺlҢЬ“ъӮНүҪӮзӮМ•ПӮнӮиӮҪӮйҺ–ӮаӮИӮ©ӮиӮөӮЙ“сҸ\ҢЬҳZ“ъӮІӮл“сҺOҗlӮМҠШҚ‘—ҜҠwҗ¶—ҲӮҪӮиӮДҚҹӮМ—L—lӮрҢ©ӮйӮвҲкҢы“сҢыүҪӮЖӮ©ү]ӮўӢҸӮиӮөӮӘҒA‘ҙӮМҢгӮН“ъҒX•KӮёҗ”Ҹ\җlӮМҠШҚ‘җl—ҜҠwҗ¶—ҲӮҪӮиӮДҒA•pӮиӮЙҒuҺ©Қ‘ӮМҸKҠөӮЖӮөӮД•wҗlӮрӢqӮЙҗЪҢ©Ӯ№ӮөӮЮӮйӮұӮЖҒAҲҪӮўӮНҺzӮӯӮМ”@Ӯ«Ң©җў•ЁӮЙҺ©Қ‘ӮМ•wҗlӮрҺg—pӮ·ӮйӮН–і—зӮИӮиҒA‘¬ӮвӮ©ӮЙӢAҚ‘Ӯ№ӮөӮЮӮЧӮөҒvӮИӮЗӮЖҺ––ұҲхӮЙӢкҸоӮрҺқӮҝҚһӮЭӮөӮжӮиҒA“ҜҠЩӮЙӮДӮНӮӨӮйӮіӮӯҺvӮўӮДҗӢӮЙҸүӮЯҺьҗщӮрҺуӮҜӮҪӮй”С“cҺҒӮЙҲЛ—ҠӮөӮД’І’вӮрҗҝӮўӮҪӮйӮжӮиҒA”С“cҺҒӮаҺМӮД’uӮ©ӮкӮёӮЖ—ҜҠwҗ¶ӮЙҢьӮ©ӮўҒuҢҲӮөӮДҠШҚ‘•wҗlӮр•ҺҗJӮөӮҪӮйӮЙӮНӮ ӮзӮёҒB”JӮлҠШҚ‘ӮМҲЧӮЙҒAӮұӮкӮрӢ@үпӮЖӮөӮД•wҗlӮМҠҲ“®Ӯр—UӮнӮсӮЖ—~ӮөҒA“O“Ә“O”ц‘PҲУӮрҲИӮБӮДӮИӮөӮҪӮйҺ–ӮИӮиҒvӮЖҗаӮ«—@ӮөӮҪӮйӮаҒA”Ю“ҷӮНӮИӮ©ӮИӮ©•·Ӯ«“ьӮкӮёҒAҗӢӮЙ–ЪүәҺЕӢжҹN“c–{ӢҪ’¬ӮМҗҙҢхҠЩӮЙ‘ШҚЭ’ҶӮИӮйҠШҚ‘“а–ұҺQҠҜҢ“’йҺәүпҢvҗRҚёҲПҲх“ъ–{Қ‘Ӣ{“аҸИҺ––ұҺӢҺ@ҲхҗіҺO•iӮЖү]ӮӨ’·Ӯ«ҢЁҸ‘Ӯ«Ӯр—LӮ·Ӯйи{ҢіҗAӮЖү]ӮҰӮйҗlӮжӮиҗ…Ҹ»ҠЩӮЙ‘ОӮө•\ҢьӮ«ӮМҢрҸВӮрҺnӮЯӮіӮ№ӮҪӮйӮжӮиҒA”С“cҺҒӮНӢҺӮйӢг“ъ–{ӢҪҸt–Ш’¬Ҳк’¬–ЪҺlҸ\Һl”Ф’nӮМҠШҚ‘—ҜҠwҗ¶ҠсҸhҺЙӮЙ“һӮии{ҺҒ—§үпӮўӮМҸгҚДӮС”Ю“ҷӮЙҢьӮ©ӮўӮДҚ§ҒXҢPҺ«“IӮМүүҗаӮрҺҺӮЭӮөӮаүҪ“ҷӮМҢшүКӮИӮӯҒA”Ю“ҷӮМ”ҪҚRү^“®ӮНүvҒXҗЁӮўӮр‘қӮө—ҲӮҪӮйӮЙӮјҗ…Ҹ»ҠЩӮЙӮДӮа–wӮЗҺқӮДӮ ӮЬӮөҒAҚҹӮМҸгӮНҺ~ӮЮӮр“ҫӮёӮЖӮДҠщӮЙҢЩӮў“ьӮкӮҪӮйҠШҗlӮМҲЧӮЙ“ҠӮ¶ӮҪӮй”п—pӮр•ЩҸһӮ·ӮкӮО“A–ҪҗжӮрӢAҚ‘Ӯ№ӮөӮЮӮЧӮөӮЖҸч•аӮөӮҪӮйӮа”Ю“ҷӮН—TӮИӮзӮҙӮй—ҜҠwҗ¶ӮМҺ–ӮЖӮДӢаӮМ—pҲУӮа–іӮ«ӮжӮиҒAӣБҺаүДҒAӢаүiҺЭ“ҷӮМҠwҗ¶Ӯр‘Қ‘гӮЖӮөӮДҸ®ӮаӮўӮлӮўӮлӮЖ(Ңҙ•¶ӮўӮлӮЖҒT)ӮұӮкӮЙ‘ОӮ·ӮйӢкҸоҺқӮҝҚһӮЭ—ҲӮйӮжӮиҗ…Ҹ»ҠЩӮЙӮДӮНүvҒXӮӨӮйӮіӮӘӮи‘RӮзӮО•ЩҸһӢаӮН“eӮЙҠp“A–ҪҗжӮрӢAҚ‘Ӯ№ӮөӮЮӮйӮЙ—vӮ·Ӯй—·”п‘ҙӮМ‘јӮҫӮҜӮрҠШҗlӮМҺиӮЙӮД—pҲУӮ№ӮөӮЮӮйӮұӮЖӮЖӮөӮД’k”»ӮН‘QӮӯҗiҚsӮ№ӮөӮа”Ю“ҷӮЙӮН‘Ҫ•Ә‘ҙӮМӢаӮаӮ ӮзӮҙӮйӮЧӮҜӮкӮОҒA•Lинҗ…Ҹ»ҠЩӮЙӮД‘№–ХӮрү}ӮнӮё”Ю“ҷӮМ—vӢҒ’КӮи“сҺO“ъ’ҶӮЙ“A–ҪҗжӮрӢAҚ‘Ӯ№ӮөӮЮӮйӮұӮЖӮЖӮИӮйӮЧӮөӮЖү]ӮӨҒB’AӮө“A–ҪҗжҺ©җgӮН—]ӮиӢAҚ‘ӮрҠмӮСӢҸӮзӮёӮЖӮМӮұӮЖӮИӮиҒBҲцӮЭӮЙӢLӮ·”@үҪӮЙҸӨ”„ӮМҚ°’_ӮЙҸoӮЕӮҪӮйӮЙӮаӮ№ӮжҒAғIғӢғSҒ[ғӢӮМ”PҠӘӮ«ӮЖӮДҲкҢВӮМ—§”hӮИӮйҗEӢЖӮИӮиҒA•wҗlӮӘҗEӢЖӮр“ҫӮД“ӯӮ«ӮВӮВӮ ӮйӮаӮМӮрӮнӮҙӮнӮҙ–іҗEӢЖӮЖӮИӮзӮөӮЯӮДӢAҚ‘Ӯ№ӮөӮЯӮсӮЖӮ·ӮйӮӘҠШҚ‘—¬ҒA”Ы(ӮўӮИ)“Ң—m—¬ӮМ•wҗlеӯӢҸҺеӢ`ӮМ“№“ҝӮИӮкӮОҒA”Ю“ҷӮМҸKҠөӮЖӮөӮДҢғҚVӮ·ӮйӮа–і—қӮИӮзӮКӮұӮЖӮИӮкӮЗӮаҒAҲк•ыӮЙӮН•wҗlӮр’jҺqӮМҗЁ—НӮжӮи’EӮ№ӮөӮЯӮДҒAеӯӢҸӮр–ЖӮкӮөӮЯӮсӮЖӮ·Ӯй•wҗlүр•ъү^“®Ӯ ӮйӮ©ӮЖҺvӮҰӮОҒAҲк•ыӮЙӮНӮЬӮҪӮұӮкӮрӢtӮЙҚsӮӯ•wҗl–іҗEӢЖү^“®ӮаӮ ӮиҒAҗўӮН—lҒXӮЖү]ӮӨӮЧӮөҒBҠМҗSӮМ–{җlӮӘӢAҚ‘ӮрҠмӮОӮёӮЖү]ӮӨӮЙҺҠӮБӮДӮНӮўӮжӮўӮж–К”’ӮөҒB (’ҚҒ@җ…Ҹ»ҠЩӮЖӮНҒA’©‘NҠЩӮМӢЯӮӯӮЙ—]Ӣ»“IӮИӮаӮМӮӘ–іӮӯҒAӢq‘«ӮӘ—ЗӮӯӮИӮўӮМӮрҗS”zӮөӮҪ•tӢЯӮМ”„“X“XҺе’BӮӘҒAӢӨ“ҜӮЕҢҡҗЭӮөӮҪ—]Ӣ»ҸкҒBӢҫӮр’ЈӮиҸ„ӮзӮ№ӮҪ–АҳHҒAғ~ғүҒ[ғnғEғXӮМӮұӮЖӮЕӮ·ҒB“ҢӢһ’©“ъҗV•·Ғ@–ҫҺЎ40”N4ҢҺ10“ъӢLҺ–ӮрҢіӮЙ•в‘«)Ғ@ |
|
| ҒЎ”Һ——үпҲк——Ғi”N•\Ғj | |
| җўҠEҸүӮМ–ңҚ‘”Һ——үпӮНҒA1851”NӮЙғҚғ“ғhғ“ӮЕҠJҚГӮіӮкӮҪҒBӮ»ӮкӮр”зҗШӮиӮЙҒAүў•ДҸ”Қ‘Ӯр’ҶҗSӮЙ–ң”ҺғuҒ[ғҖӮӘӢNӮұӮиҒAҠeҚ‘ӮЕ‘ұҒXӮЖҠJҚГӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB“ъ–{ӮӘҸүӮЯӮДҗіҺ®ӮЙҺQүБӮөӮҪ–ң”ҺӮНҒA1867(Ңcүһ3)”NӮМғpғҠ–ң”ҺӮЕӮ ӮйҒB–ҫҺЎҺһ‘гӮЙ“ьӮйӮЖҒAҚ‘“аӮЕӮа”Һ——үп(“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп)ӮӘҠJҚГӮіӮкӮйӮжӮӨӮЙӮИӮйҒB | |
| Ғ@ | |
|
Ғ@ҒЎ–ЯӮйҒ@Ғ@ҒЎ–ЯӮй(ҸЪҚЧ)Ғ@Ғ@Ғ@ҒЎ KeywordҒ@Ғ@Ғ@Ғ@ |
|
 Ҹo“T•s–ҫ / Ҳш—pӮрҠЬӮЮ•¶җУӮНӮ·ӮЧӮД“–ӮgӮoӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒB
Ҹo“T•s–ҫ / Ҳш—pӮрҠЬӮЮ•¶җУӮНӮ·ӮЧӮД“–ӮgӮoӮЙӮ ӮиӮЬӮ·ҒB
ҒЎ”Һ——үпҲк——Ғi”N•\Ғj
| ”N | ҠCҠOӮМ–ңҚ‘”Һ——үп | “ъ–{ӮМ”Һ——үп | ҠCҠOҺ–Ҹо | “ъ–{Һ–Ҹо |
| 1851(үГүi4) | ‘ж1үсғҚғ“ғhғ“–ң”Һ | –т•iүпҒA–{‘җүпҒA•ЁҺYүп | Ғ@ | Ғ@ |
| 1852(үГүi5) | Ғ@ | ғtғүғ“ғX‘ж“с’йҗӯ(Ғ`1870) | Ғ@ | |
| 1853(үГүi6) | ғjғ…Ғ[ғҲҒ[ғN–ң”Һ | ғNғҠғ~ғAҗн‘Ҳ(Ғ`1856) | ғyғҠҒ[—ҲҚq | |
| 1854(ҲАҗӯ1) | Ғ@ | Ғ@ | “ъ•ДҳaҗeҸр–с | |
| 1855(ҲАҗӯ2) | ‘ж1үсғpғҠ–ң”Һ | Ғ@ | ’·ҚиҠCҢR“`ҸKҸҠҠJҗЭ | |
| 1856(ҲАҗӯ3) | Ғ@ | ғxғbғZғ}Ғ[җ»Қ|–@ | Ғ@ | |
| 1858(ҲАҗӯ5) | Ғ@ | Ғ@ | “ъ•ДҸCҚD’КҸӨҸр–с(—–ҒEҳIҒEүpҒE•§ӮЖӮа) | |
| 1861(•¶Ӣv1) | Ғ@ |
“м–kҗн‘Ҳ(Ғ`1865)/ғҚғVғA”_“zүр•ъ—Я ғCғ^ғҠғAүӨҚ‘җ¬—§ |
’·Қиҗ»“SҸҠҸvҚH | |
| 1862(•¶Ӣv2) | ‘ж2үсғҚғ“ғhғ“–ң”Һ | Ғ@ | ғҚғ“ғhғ“ҠoҸ‘(ҠJҺsҠJҚ`ү„Ҡъ) | |
| 1866(Ңcүһ2) | Ғ@ | •ҒҡТҗн‘Ҳ | Ғ@ | |
| 1867(Ңcүһ3) | ‘ж2үсғpғҠ–ң”Һ | Ғ@ | ‘еҗӯ•тҠТ | |
| 1868(–ҫҺЎ1) | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ |
•и’Cҗн‘ҲҒE–ҫҺЎүьҢі ҚӮ“Ү’YҚzӮЙ“ъ–{ҸүӮМҸцӢCғ|ғ“ғvӮрҗЭ’u |
| 1870(–ҫҺЎ3) | Ғ@ | Ғ@ | •Ғ•§җн‘Ҳ(Ғ`1871)/ғtғүғ“ғX‘жҺOӢӨҳaҗ§ | |
| 1871(–ҫҺЎ4) | Ғ@ | Ӣһ“s”Һ——үп | ғhғCғc’йҚ‘җ¬—§ | ”p”Л’uҢ§/Ҡв‘qҢӯҠOҺgҗЯ’c”hҢӯ(Ғ`1873)/җк”„—ӘӢK‘ҘҢц•z(—Ӯ”N’вҺ~)/үЎҗ{үк‘ў‘DҸҠ(җ»“SҸҠӮ©ӮзүьҸМ) |
| 1872(–ҫҺЎ5) | Ғ@ | “’“Үҗ№“°”Һ——үп | Ғ@ | үЎ•l-җVӢҙ“S“№ҠJ’К/Ҡwҗ§Ңц•z/ҠҜүc•xүӘҗ»Һ…ҸкҠJӢЖ |
| 1873(–ҫҺЎ6) | ғEғBҒ[ғ“–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | ’Ҙ•ә—Я/җӘҠШҳ_”jӮкҗјӢҪ—Іҗ·Ӯзүә–м |
| 1876(–ҫҺЎ9) | ғtғBғүғfғӢғtғBғA–ң”Һ | Ғ@ | ғxғӢӮӘ“dҳbӮр”ӯ–ҫ | ”p“Ғ—Я/җ_•—ҳAӮМ—җҒAҸHҢҺӮМ—җҒA”ӢӮМ—җ |
| 1877(–ҫҺЎ10) | Ғ@ | ‘ж1үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп |
ҳI“yҗн‘Ҳ(Ғ`1878) ғCғMғҠғX—МғCғ“ғh’йҚ‘ӮМҗ¬—§ |
җј“мҗн‘Ҳ |
| 1878(–ҫҺЎ11) | ‘ж3үсғpғҠ–ң”Һ | Ғ@ | ғGғfғBғ\ғ“ӮӘ”’”M“dӢ…Ӯр”ӯ–ҫ | Ғ@ |
| 1879(–ҫҺЎ12) | ғVғhғjҒ[–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ |
| 1880(–ҫҺЎ13) | ғҒғӢғ{ғӢғ“–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | ҚHҸк•ҘүәҠT‘ҘӮЕҠҜүcҺ–ӢЖӮр–ҜҠФ•ҘүәӮ° |
| 1881(–ҫҺЎ14) | Ғ@ | ‘ж2үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп | Ғ@ | –ҫҺЎ14”NӮМҗӯ•П/Ҹј•ыҗіӢ`ӮӘ‘е‘ ӢЁӮЙҸA”C |
| 1883(–ҫҺЎ16) | Ғ@ | Ғ@ | ҚHӢЖҸҠ—LҢ ӮМ•ЫҢмӮЙҠЦӮ·ӮйғpғҠҸр–с/ғ_ғCғҖғүҒ[ӮӘ4ғTғCғNғӢғKғ\ғҠғ“ғGғ“ғWғ“Ӯр”ӯ–ҫ | |
| 1884(–ҫҺЎ17) | Ғ@ | Ғ@ | җҙ•§җн‘Ҳ | Ғ@ |
| 1885(–ҫҺЎ18) | Ғ@ | Ғ@ | ғҢғ“ғgғQғ“ӮӘXҗьӮр”ӯҢ© | “аҠtҗ§“x/җк”„“БӢ–Ҹр—б |
| 1887(–ҫҺЎ20) | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ | “ҢӢһ“d“•(“d—НүпҺР)үcӢЖҠJҺn |
| 1888(–ҫҺЎ21) | ғoғӢғZғҚғi–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ |
| 1889(–ҫҺЎ22) | ‘ж4үсғpғҠ–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | ‘е“ъ–{’йҚ‘Ңӣ–@”ӯ•z |
| 1890(–ҫҺЎ23) | Ғ@ | ‘ж3үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп | Ғ@ | ‘жҲкүс’йҚ‘ӢcүпҠJҚГ |
| 1893(–ҫҺЎ26) | ғVғJғS–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ |
| 1894(–ҫҺЎ27) | Ғ@ | Ғ@ | ҳI•§“Ҝ–ҝ | “ъҗҙҗн‘Ҳ(Ғ`1895) |
| 1895(–ҫҺЎ28) | Ғ@ | ‘ж4үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп | Ғ@ | ҺOҚ‘ҠұҸВ/Ӣһ“s“dӢC“S“№ҠJӢЖ |
| 1897(–ҫҺЎ30) | ғuғҠғ…ғbғZғӢ–ң”Һ | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ |
| 1898(–ҫҺЎ31) | Ғ@ | Ғ@ | •Дҗјҗн‘Ҳ | Ғ@ |
| 1899(–ҫҺЎ32) | Ғ@ | Ғ@ | ғ{Ғ[ғAҗн‘Ҳ(Ғ`1902) | ҚHӢЖҸҠ—LҢ ӮМ•ЫҢмӮЙҠЦӮ·ӮйғpғҠҸр–сүБ–ҝ |
| 1900(–ҫҺЎ33) | ‘ж5үсғpғҠ–ң”Һ | Ғ@ | Ӣ`ҳa’cҺ–ҢҸ | Ғ@ |
| 1901(–ҫҺЎ34) | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ | ҠҜүc”Ә”Ұҗ»“SҸҠ‘ҖӢЖҠJҺn |
| 1902(–ҫҺЎ35) | Ғ@ | Ғ@ | Ғ@ | “ъүp“Ҝ–ҝ |
| 1903(–ҫҺЎ36) | Ғ@ | ‘ж5үс“аҚ‘Ҡ©ӢЖ”Һ——үп | Ғ@ | Ғ@ |
| 1904(–ҫҺЎ37) | ғZғ“ғgғӢғCғX–ң”Һ | Ғ@ | ғӢғxҒ[ғӢӮӘғIғtғZғbғgҲуҚьӮр”ӯ–ҫ | “ъҳIҗн‘Ҳ(Ғ`1905) |
| 1907(–ҫҺЎ40) | Ғ@ | “ҢӢһҠ©ӢЖ”Һ——үп | үp•§ҳIҺOҚ‘ӢҰҸӨҗ¬—§ | Ғ@ |