�����ΐ����_�E���� / ���_�ւ̋^�O�E���_�̌��1�E���_�̌��2�E�r�b�O�o���F����u���b�N�z�[���͐��������E���_�����̌���E���ΐ����_�Ǝ��p���E���_�̌��3�E���_�̌��4�EGPS�Ƒ��ΐ����_�EGPS���q���v�Ƒ��ΐ����_�E�d�͏��E���ΐ��������ʊ��E���_�̌��5�E�E�E
�@
�G�w�̐��E�E��l
�@�@�@


| ����̋N�� | |
|
����̋N�� / �_�[�E�B���̔���
�`���[���Y�E�_�[�E�B���́u��̋N���v�͏ȗ�������A��ʓI�ɒm���Ă��鏑���ł��B�����ȏ����́A�u���R�I���Ɋ�Â���̋N��(On the Origin of Species by Means of Natural Selection)�v����сA�u���������Ōb�܂ꂽ�i��̕ۑ�(the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life)�v����R�����Ă��܂��B�C�M���X�̎��R��`�ҁA�`���[���Y�E�_�[�E�B��(1809-1882�N)��1842�N�A(�ނ̉^���I��5�N�Ԃɂ킽��r�[�O�����̑D������߂������傤��6�N��)�Ɏ�̋N���������n�߂܂����B1859�N�ɏo�ł����u��̋N���v�́A�`���[���Y�E���C�G������́u�n���w�̌���(��O���ɋy�ԁF1830-1833�N)�v����сA�g�[�}�X�E�}���T�X����́u�l���_�v(1798�N)������ȉe����^���Ă��܂��B ����̋N�� / ���R�I��� �`���[���Y�E�_�[�E�B���́u��̋N���v�̒��Ŏ��R�I����̊T�O���Љ�Ă��܂��B���̂����݂́A�ǐ��̈�`�q�ψق�ۑ����A�~�ς���Ƃ����T�O���琬�藧���Ă��܂��B�Ⴆ�A�����̐������H�₵�A��ԋ@�\�B�������Ƃ��܂��傤�B���̎q���́A���̔\�͂������p���ŁA�܂����̎q���ֈ�`�������n���܂��B���R�I����͂��D�ꂽ�\�͂������A���������ɐ������т�̂���Ƃ��Ďc���Ă䂭�ƒ�߂Ă��܂��B�����I���̊ԁA�l�Ԃ͉ƒ{��A���Ȃǂ̌�z(�u���[�h)�Ō��I�ȕω��������炵�Ă��܂����B���X�ɁA�s���v�ȓ��F��}�����A�]�܂������F�̈�`�q��ۑ�����ђ~�ς��Ă����̂ł��B���R�I����Ɛl���ɂ��u���[�_�[�Ƃ̈Ⴂ�́A�q�g���ǐ���`�̕ۑ��𑀍삷��̂��A���R�������I������̂��̈Ⴂ�ł��B �_�[�E�B���̂��ǂ蒅�������_�́A�ނ̉s���ώ@�ɂ��Ă͕s���S�Ȃ��̂ł����B�ނ͎��R���������ׂĂ̐����l���̐i���ƃo���G�[�V����������ł���ƍl���Ă��܂����B����ɂ��̃o���G�[�V�����ɂ͍ŏI�I�ɂ��ׂĂ̎킪�A��������Ƃ̐�c������ƁA���̂悤�Ɍ��_�t���Ă��܂��B�u�ώ@�\�Ŏ�����������A���ׂĂ̐����͈�̑傫�ȉƑ��Ƃ������Ƃ��m�M�ł���v1 �_�[�E�B�j�X�g�͌��݂̐����̐�c�͔�����i�������Ƙ_���Ă��܂��B�@���A�o�i�i�A���A�ԂȂǂ̐��������̂���i�������Ƃ����l����1800�N��ł͂����Ƃ��炵���v������������܂���B�����̐����w�͏����̒i�K�ŁA�����̍זE�͈�H�̌��`�����Ƃ����l�����Ă��܂���ł����B���̍��̓O���K�[�E�����f��(1822-1884�N)����`�̃R���Z�v�g�̌������n�߁A1850�N�㔼�Ƀ��C�X�E�p�X�c�[��(1822-1895�N)�͎��R�����_�̌��ɑ��_�����悤�Ǝ��݂Ă��܂��B�����̉Ȋw�҂̌���(�_�[�E�B���̐i���_�̔��Ύ�)��ߋ�50�N�Ԃɂ킽�鐶���w�A�����w�A����ш�`�w�̕������i���ɂ��A�_�[�E�B���̗��_�͂��ׂĂ��������Ȃ����Ƃ͖��m�ł��B�Ⴆ�A��`�q�̃o���A�����݂��邱�Ƃ��m����܂���(����āA�͔�Ԃ��Ƃ��ł��Ȃ�)�B��̒��Ő����̈Ⴂ�����邱�Ƃ͊m���ł�(�قȂ锧�̐F�����A��̓����A�����Ȃ�)�B�傫���A�т̒�����������A�������т̒Z���������܂��B�������A�@���Ȃ��ނ̌��ł����ȊO�͎Y�݂܂���B���ƃo�i�i�͉��ʂł͂���܂���I���R�����̃��J�j�Y���͉Ȋw�I�ɏؖ�����Ă��܂����A�m���Ȃ��Ƃ́A���鎩�R�����͉��w�I�ȋK���ŕs�\���Ƃ������Ƃ��B ����̋N�� / �w���Y���[�����̏��� �_�[�E�B���̗��_�A�u��̋N���v�̔w�i�ɂ̓W�����E�X�e�B�[�u���X�E�w���Y���[����(1796-1861)�̏d�v�ȏ��������������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�܂���B�w���Y���[�����̓P���u���b�W��w�̃_�[�E�B���̋����̂ЂƂ�ł����B������A���̃r�[�O�����̑D���A���o�[�g�E�t�B�c���C(1805-1865�N)�Ƀ_�[�E�B�����Љ���̂��A�w���Y���[�����ł����B�`���[���Y�͍q�C�O�ɁA�w���Y���[��������`���[���Y�E���C�G��(1797-1875)����́u�n���w�����v������邱�Ƃ�i�߂��Ă��܂��B�w���Y���[�����́u�����̂��߂ɕK�������ǂ݂Ȃ����A�������A��ȗ��_�������ĐM���Ȃ悤�ɁB�v�Ə������Ă��܂��B2 �y�r���z 1 Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 1859, p. 109. 2 Richard Milner, The Encyclopedia of Evolution, p.286. �@ |
|
|
���_�[�E�B���i���_ / �O��
�_�[�E�B���i���_�́A���ׂĂ̐��� �E���A�o�i�i�A����ԂȂǂɂ́A�֘A�t�������c(common ancestor)������Ƃ��ĕ��L��������Ă��闝�_�ł��B�_�[�E�B���̊�{�I���_�́A�����͔��̂��甭���A���B�A����я����Ȏ��R��`�̋���(�ˑR�ٕ�)��O��ɂ��Ă��܂��B�܂�A��蕡�G�ō��x�Ȑ����ł����P���ȑg�D�̂���i������A�悤����ɐV������͈�`�q�̓ˑR�ψق��甭�������D�ꂽ�ψق��ێ�����(���R�I����Ƃ��Ēm���Ă���)�����̗ǐ��ψق͎�����Ɍp�����ƒ��Ă���̂ł��B����ɒ����N���������A�ǐ��ψق͒~�ς��A�S���قȂ�����̐����ƂȂ�܂��B(�I���W�i���̕ό`�̂ł͂Ȃ��A���S�ɈقȂ��������ɂȂ�B) ���_�[�E�B���i���_ / ���R�I��� �_�[�E�B���i���_�͔�r�I�V�������^�ł���̂ɑ��A�i���_�̐��E�ώ��̂̓A���e�B�[�N�̂悤�ɌÂ��T�O�ł��B�A�i�N�V�}���h���X�Ȃǂ̌Ñ�M���V���̓N�w�҂͔��̂��i���������ցA�����Đl�ނɐi�������Ɖ��肵�Ă��܂��B���̌�A�`���[���Y�E�_�[�E�B���́u���R�I���v�̃��J�j�Y�������o�ꂵ�܂����B���̃��J�j�Y���́A�ǐ��̈�`�q�ψق�ۑ����Ē~�ς���Ƃ����T�O���琬�藧���Ă��܂��B�Ⴆ�A�����̐����ɉH���o�Ĕ�Ԃ��Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B����Ƃ��̎q���͓�����`�q�������p���ōs���܂��B�̈�`�q���������q���͓r�₦�D�ꂽ��`�q���������q���͔ɐB���A���������ɐ������т�v�f����������̂������������т�ƌ����������R�I����ł��B���R�I����͎��R�ɏ]���Ă̔ɐB����l�H�I�ɗǂ��i������u���[�_�[�̂悤�Ȃ��̂ł��B�����I���̊ԁA�l�Ԃ͉ƒ{��A���Ȃǂ̌�z(�u���[�h)�Ō��I�ȕω��������炵�Ă��܂����B�u���[�_�[�͏��X�ɖ]�܂����Ȃ����F����菜���܂��B���R�I����������l�ɗ�������͔̂r�������ƒ�`���Ă���̂ł��B ���_�[�E�B���i���_ / ������肾���m���Ɂc �_�[�E�B���̐����i���_�͂������Ƃ����C�̉����Ȃ�悤�ȉߒ��ł��B�_�[�E�B���͎��̂悤�ɏ����Ă��܂��F�u���R�����́A�킸���Ȍp�������ǐ��ٕς𗘗p���邱�Ƃɂ���č�p����B����́A�ˑR�A�Z���ԂŋN���邱�Ƃ͂Ȃ��A�������ƒ����N�����|�����v���Z�X�ł���B�v1�@����ă_�[�E�B���́A�u�����A���R��������̋N���łȂ��Ƃ����玄�̗��_�͐��藧���Ȃ��v�ƔF�߂Ă��܂��B2�@���̂悤�ȕ��G�Ȋ튯�́u�Ҍ��o���Ȃ����G�������V�X�e��(irreducibly complex system)�v�ƌĂ�Ă��܂��B���̃V�X�e���͕����̌������Ȃ��v�f���琬�藧���A�ꕔ���������������őS���̓�������~����̂ł��ׂĂ̗v�f���s���ł��B3�@�]���āA���̂悤�ȃV�X�e����1��1���X�ɍ��ꂽ�Ƃ����l���͐��藧���܂���B��ʓI�Ƀl�Y�~��肪�A���I�ȁu�Ҍ��ł��Ȃ����G���v�̗�Ƃ��ċ������܂��B�l�Y�~����5�̗v�f���琬�藧���Ă��܂��F1)���A2)���͂ȃX�v�����O�A3)�u�n���}�[�v�ƌĂ��ׂ��_�A4)�n���}�[���Œ肷�鉄�ז_�A����сA5)�y��ƂȂ�v���b�g�z�[���B���̒��ł�������̕��i�ł�������Ί��S�ɓ����܂���B���̂悤�Ƀl�Y�~�߂�̂��ׂĂ̕��i���s���ł��B�l�Y�~���@�͊Ҍ��ł��Ȃ����G��������Ă���̂ł��B4 ���_�[�E�B���̐i���_ / ��@�ɕm����i���_ �_�[�E�B���̐i���_�͉ߋ�50�N�Ԃɂ킽�鐶���w�A�����w�A����ш�`�q�w�̕������i���ɂ��A����������@�ɕm���Ă��܂��B���ݎ������͊Ҍ��ł��Ȃ����G�������V�X�e�����זE�ɑ��݂��邱�Ƃ������Ă��܂��B���肳�ꂽ���G�����������̐����w�I���E���o�����܂��B���q�����w�҂̃}�C�P���E�f���g�����͂��������Ă��܂��F�u�ŏ��̃o�N�e���A�̍זE�́A�d��10-12�O�����łƂĂ��Ȃ����������A���ꂼ��͐^�Ƀ~�N���ŏ��^�����ꂽ�H��̐����P�ʂł��B�e�זE�͐l�ނ����������@���Ȃ�@�B�����͂邩�ɕ��G�Ŋ���ɋy�ԕ��q�@�B�Őv���ꂽ1000���ɋy�Ԍ��q�Ő��藧���Ă��܂��B���E�ɂ͂��̂悤�Ȑ����P�ʂ͐�Α��݂��Ȃ��ƒf���ł��܂��v�B5 �����āA���̍ו����ł��Ȃ����G�����ώ@����ɂ͌�������K�v�Ƃ��܂���B�_�[�E�B���̎���ɂ͔F������Ȃ������A�Ҍ��ł��Ȃ����G����������ǂ��Ⴊ�ځA���A�S���̓����ł��B�@�������Ȃ���_�[�E�B���������F�߂Ă��܂��F�u�ڂ̈قȂ��������ɏœ_�����A���̋��e�߂���ڂ̋����ׂ����u�A����ѐF�ʍ������Ȃ��悤�ɏC�����鑕�u�����R�����ɂ���Č`�������Ȃǂƍl����̂́A�^�ɂƂ�ł��Ȃ��s�����̂悤�Ɏv����v�B6 �y�r���z 1 Charles Darwin, \"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life,\" 1859, p. 162. 2 Ibid. p. 158. 3 Michael Behe, \"Darwin\'s Black Box,\" 1996. 4 \"Unlocking the Mystery of Life,\" documentary by Illustra Media, 2002. 5 Michael Denton, \"Evolution: A Theory in Crisis,\" 1986, p. 250. 6 Charles Darwin, \"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life,\" 1859, p. 155. �@ |
|
|
���c�m�`�j�d�点�� / �ƂĂ��Ȃ��c��ȕ��G���̔���
�c�m�`�j�d�点��͍��܂ł̉Ȋw�E�S�̂�ʂ��čł��̑�Ȕ����̈�ł���Ƃ����܂��B1953�N�A�W�F�[���X�E���g�\���ƃt�����V�X�E�N���b�N�ɂ���āA�c�m�`�͈�`�q�ɂ���ĕ����I�������`��鐶���̂̍ł��d�v�ȕ��q�ł���ƒ���܂����B2001�N�̒����ɂȂ�ƁA�q�g�Q�m���v���W�F�N�g�ƃZ�����E�W�F�m�~�b�N�X�Ђ���g���Ăc�m�`�ɓ��݂���{���ƕ��G���ɂ��Ē��܂����B���ݐl�Ԃ̂c�m�`���q��3�~���I���̉��w�����ŖȖ��ɔz��Ă��邱�Ƃ͒m���Ă��܂��B�c�m�`���q�̒��̒P��זE�ł���o�N�e���A�̂d�D�ۂɂ��Ă����̒��Ɋ܂܂�Ă�����͐��E���̐}���قɂ���ł��������{��S���W�߂������c��ƂȂ�܂��B ���c�m�`��d�点�� / ��� �c�m�`(�f�I�L�V���{�j�_)�͂点��K�i�̂悤�ȉQ���`�ɂ˂��ꂽ��{���̕��q�ł��B���ꂼ��̍��́A�ɂȂ铜�����_���̃o�b�N�{�[���Ƒ����̉���琬�����Ă��܂��B���̂点��K�i�̕����̓A�f�j��(A)�ƁA�`�~��(T)�ƁA�V�g�V��(C)�ƃO�A�j��(G)��4�̉���琬�����Ă��܂��B�����̉���̓A���t�@�x�b�g�̂悤�Ȗ����������A�P��A���́A����ђi���Ȃǂ��`�����A�זE�̐����Ɠ����𐬂��܂��B����̓R���s���[�^�[�́u0�v��u1�v�Ȃǂ̃o�C�i���[�R�[�h(����)�Ɣ�r�I���Ă��܂��B�\�t�g�E�F�A�[����R���s���[�^�[�֓`�B����悤�ɁA�c�m�`�R�[�h�͏���L�@�זE�ɓ`�����`�q�̌���ł��B �c�m�`�R�[�h�̓t���b�s�[�f�X�N��2�i�R�[�h�̂悤�ɋɂ߂ĒP���ɑɂȂ��č\������Ă��܂��B���������x�ȕ��G���͂��̋@�\�Ɉˑ����Ă���̂ł��B���݁A���ː������w�̂悤�ȋߑ�Z�p�ɂ���čזE�́u��H�̌��`���v�ł��邾���ł͂Ȃ��A�������łȂ���Ίώ@���鎖�̏o���Ȃ��قǔ����ŃX�y�[�X�V���g����萸���ŕ��G�ȍ\���ł��B ���̂悤�ɂc�m�`�R�[�h�͋��ٓI�ȕ��G��������Ă��܂����A����ɉȊw�҂����Q�������̂��R�[�h�̕ϊ��V�X�e���ł����B�ǂ�Ȍ���ł�������P��͓���̌���̗̈���łȂ�����̈Ӗ��𐬂��Ȃ��悤�ɁA����͋ߑ�I���w���̊�ՂȂ̂ł��B�P����2�i�R�[�h�Ɋւ��Ắu�|�[������r�A�̐^�钆�̃h���C�u�v�����p���鎖���ł��܂��B�L���Ȃ��̘b�̒��Ń~�X�^�[���r�A�͔ނ̗F�l�ɁA�C�M���X�l�����������痈���Ȃ�Έ�{�̂낤�����ɉ��Ėk������̑��ɒu���A�����ނ炪�C���痈���Ȃ��2�{�̂낤�����ɉ��悤�ɂƈ˗����܂����B�|�[���E���r�A�ƗF�l�̊Ԃɓ�����ƂȂ錾�ꂪ�Ȃ���A���̒P���ȓ`�B�@�͈Ӗ��𐬂��܂���B�ł͂��̒P���ȗ�ƈ��q���g�債�Ă݂܂��傤�B �c�m�`���q�͕��G�ȃ��b�Z�[�W�V�X�e���ł��B�c�m�`������ׂȕ����͂ɂ���Ēz���ꂽ�Ȃ�A��������ׂȕ����͂ɂ���Ēz�����͂��ł��B�����̉Ȋw�҂͉��w�������\�������P�ʂ͎��R�I�i���̃v���Z�X��ʂ��Ăł���ƌ����Ă��܂��B�������A�ޗ��̏��͊��S�ɌX�Ɨ������`�B���ʂł��邱�Ƃ�F�����Ȃ���Ȃ�܂���B�]���ĉ��w�����̒P�ʂ͕��G�Ȃc�m�`���̌`���Ƃ͖��W�Ȃ̂ł��B�Ⴆ�A�u���R�͑n�����ꂽ�v�Ƃ�����C���N�A�N�������A����Ƃ��y���L�ŏ����ꂽ���͑S�����łȂ��悤�ɁA���2�i�R�[�h��[���X�R�[�h�A�܂��͕����ŏ����ꂽ�Ƃ��Ă��}�̎��͓̂Ɨ����Ă��āA�܂܂�Ă�����̈Ӗ��͑S���ς��Ȃ��A���Ɠ`�B�ޗ������W�ł��邱�Ƃ������ł��܂��B����Ȋw�҂́A�ŏ��̂c�m�`���q�̒��ɂ��鎩�ȑg�D�̗̈���͉��w�������̂��\���������̂ł���Ɖ��߂��Ă��܂��B�܂����ɂ��O�����������g�D���ŏ��̂c�m�`���`�������Ƃ������߂�����܂��B�������A�ޗ��x�[�X���`�B�����A�܂��͂��ꎩ�̂������\�������Ƃ������_�͔�_���I�ł��B�@�i���_�̈�`�q���Ƃ͑������Ăc�m�`���q�̉Ȋw�g�D�\���͊��S�ɓƗ����Ă���̂ł��B ���c�m�`��d�点�� / �i���_���������� �����̋N���͉����Ȃ��Ƃ���ɉ��炩�̕����͂�������Ĕ��������ƌ����c�m�`��d�点��̉Ȋw�I���߉����͐l�̗͂�K�v�Ƃ����Ɏ�菜����܂��B�@�S���E�͎��R���ۂŋ����I�Ɂg�����h�����̂ł���f�U�C�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��Ƒ����̐l�X�ɐM�����܂��Ă���̂��i���_�ł��B�������A�����������z�u���ꂽ�c�m�`���q����������A�����̗L�@�̂Ə��R�[�h�����ɕ��G�ł���ƒm�������A�i���_���͔ے肳��A�F�����i��f�U�C�i�[�̑��݂�F��������Ȃ��̂ł��B �@ �@ |
|
| ���l�Ԃ̐i���E�i�� | |
|
���v��
�`���[���Y�E�_�[�E�B���ƃe�C���[���E�h�E�V�����_���́A�Ƃ��ɓƎ��̐i���_�������钆�ŁA�u�i���̉ߒ��ɂ���l�ԁv�Ƃ������݂��݂߂��B���̎��_�́A�����̐l�ނɂƂ��ċ}���̉ۑ�ł���n�������ɑΏ����邤���ŁA�d�v�Ȏ�����^���Ă����ƍl������B�_�[�E�B���́A�l�Ԃ̎Љ�|�����I�Ȑi���_��ʂ��āA�l�Ԃ̓������́A�Љ�{�\�Ƌ����\�͂ɋN�����Đi�����Ă������̂��Ƃ��A�����̔��B�����ƂŁA���̑Ώۂ͐l�ԎЉ�ɂƂǂ܂炸�A�����E�A�n���S�̂ɂ��y�Ԃ��̂ł���Ƃ����B�܂��A�e�C���[���́A�F���̔�����_�̑��݂�����܂���s��ȃL���X�g���I�i���_��W�J���钆�ŁA�l�Ԃ͌��݁A�i���Ƃ����s�t�̗���̒��ɂ���A����܂łɂ��ǂ��Ă������ɎU�݂��邠����v���G�ɗ��܂��Ă��̗��j���`�����Ă����Ƃ����B�ނ�͂Ƃ��ɁA�����E�ɂ�����Ȃ����A�l�ԎЉ�̗��j�A�F������a���̗��j�Ƃ������A���ԓI�ɂ���ԓI�ɂ��L��ȗ���̒��̈�_�ɁA���݂̐l�Ԃ͒u����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă����B �M�҂̌����́A���V���g�����ɂ�����A�t���J�]�E�̏ۉ����Ɋւ��āA����c���x���Ō��肳�ꂽ���Ƃ��A�n��Љ�ɂǂ̂悤�ȉe�����y�ڂ��̂��A���̑��݂̊֘A���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����݂���̂ł���B���V���g�����́A���ێ���̋K���݂̂��s�����ł��邪�A����ł̂����ꂩ��ی삷��Ƃ������̖ړI��B�����邽�߂ɂ́A����݂̂Ȃ炸�A�n��Љ�ł̕ۑS���߂��鏔���⍑�ۊW�ȂǁA���̑����̗v������������K�v������B����́A�����E�ɂ�����l�Ԃ̈ʒu��F�����邱�ƁA�l�Ԃ�F���̗��j�̒��ō��l�Ԃ͂ǂ̂悤�Ȓn�_�ɂ��鑶�݂Ȃ̂������o���邱�Ƃɂ܂ŋy�ԁB��l�̐i���_�҂́u�i���̉ߒ��ɂ���l�Ԃ����߂�ځv�́A���̓_�ɂ����āA�n�������̉����̂��߂ɐl�Ԃ����ׂ����_�ɑ傢�Ȃ�q���g��^���Ă������̂ł���B |
|
| ��1�D�͂��߂� | |
|
�n����̐����́A�������l�Ԃ́A���̐�ǂ��ւނ����̂��낤���B���̖����́A��̂ǂ̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�̂��낤���B19���I����20���I�̊ԂɊ�����l�̊w�ҁA�`���[���Y�E�_�[�E�B���ƃe�C���[���E�h�E�V�����_���́A���ꂼ��ɐ����Ɛl�Ԃɂ��Ă̐i���_�݂������B��l�͎��g�̘_��W�J���钆�ŁA�u�i���̉ߒ��ɂ���l�ԁv�Ƃ������݂����߂��B���̖ڂɐl�Ԃ̎p�͂ǂ��f�����̂��낤�B
����́A�n���⍷�ʁA�푈�Ƃ������l�ԎЉ�̖��̂ق��ɁA�n���̑����Ɛl�ނ̑����Ƃ�������܂łɂȂ��X�P�[���̑���\�n������肪�A�l�X�̊Ԃŋ��ʂɁA�傫���ӎ������悤�ɂȂ�������ł���B�����̉����̂��߂ɁA�l�Ԃ͂��̂�����̉�������悢�̂��B�ǂ̂悤�ɕ��ނ��Ƃ��A�����̎����ւƂȂ���̂��B���̖���ɓ������o�����߂ɂ́A��l�̊w�҂��i���_��ʂ��Ē����A�i���̉ߒ��ɂ���l�ԁA�n���₻�̐����Ƃ̂Ȃ���₩�����������݂Ƃ��Ă̐l�Ԃ����߂�ڂ��s���ł���悤�Ɏv���B �{�e�ł́A�_�[�E�B���ƃV�����_�����ꂼ��̐i���_���T�ς�����A�M�҂̌����Ώۂł��郏�V���g�����ɂ�����쐶����(�����ɃA�t���J�]�E)�̕ۑS��͍����鎖�Ⴉ��A���ɋ��߂��Ă���ω����l�@����B���̂����ŁA���������n���������l����ɂ�����A��l�̎��_�ɂǂ̂悤�Ɋw�Ԃ��Ƃ��ł���̂��ɐG��Ă݂����B �@ |
|
| ��2�D�_�[�E�B���̐i���_�E�e�C���[���̐i���_ | |
|
��2�|1�D�w��̋N���x�Ɏn�܂�_�[�E�B���̐i���_
�`���[���Y�E���o�[�g�E�_�[�E�B��(1809�`1882)�͉p���̔����w�҂ł���A��w���ƌ�A�C�R�����D�r�[�O�����ɏ�荞�ݓ�ẴK���p�S�X������I�[�X�g�����A�Ȃǂ�T�����A�������̓��A�����ώ@�����B�����āA���̌o���Ǝ��̗��Â��Ɋ�Â��Â�����݂�ꂽ�����w��̐i���_��̌n�����A1859�N�A���̗L���ȁw��̋N���x�\����B �w��̋N���x�ɂ����ēW�J���ꂽ���R�������̂��킵�������͖{�_�ł͏ȗ����邪�A�ʐ��ɂ��A���̒���ɂ����ă_�[�E�B���͐l�Ԃ̐i�������Ƃ��邱�Ƃ͂Ȃ������Ƃ���Ă���1�B�L���X�g���ɒ[����n�������l�X�̊Ԃň�ʓI�ł��������[���b�p�Љ�ɂ����āA�ْ[�I�Ƃ�������Ȃ�����ƂƂ��邱�Ƃ��ꂽ�_�[�E�B���́A�l�Ԃ̐i���ɂ��Ď�藧�ĂĂ܂Ƃ߂邱�Ƃ͂��Ȃ��������̂́A��̐i���̒��ɐl�Ԃ̐i�������R�܂܂�邱�Ƃ͂͂�����ӎ����Ă����Ƃ����Ă���2 �B ���]�d�g3 �ɂ��A�_�[�E�B�����A���������l�Ԃ̐i���Ɋւ��ċ�̓I�ɘ_���n�߂��̂́A1871�N���\�́w�l�Ԃ̗R���x����ł���B�����Ŕނ́A�l�Ԃ̐����I�i���ƎЉ�|�����I�i���Ƃ����i���_�ɂ������̃��x���m�ɋ�ʂ��A�l�Ԃ̎Љ�|�����I�i��(���Ȃ킿�������̐i��)�Ƃ́A�����\�͂ƎЉ�{�\�ɋN��������̂ł���A���ꂷ��i���_�I�ɐ����ł���A�܂蓮���ɂ܂ł��̗R�������ǂ邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���B�_�[�E�B���́A������W�c�����Ƃ������p���Ĉȉ��̂悤�ɐ������Ă���B�u�����́A�������ɏ���������肠���Ă��铮�����ׂĂɂƂ��āA����߂ďd�v�Ȃ��̂̈�Ȃ̂ŁA���̊���ǂ�Ȃɕ��G�Ȃ������ŋN�������Ƃ��Ă��A���R�����ɂ���ċ��߂�ꂽ�ł��낤�B�Ƃ����̂́A����߂ċ����ɖ������̂������W�܂��Ă���悤�ȋ����̂́A�悭�h���A�����̎q������Ă邾�낤����ł���v4�B ���]�́A�����������_�W�J���āA�u�l�Ԃ̏ꍇ�A�Љ�{�\�͓����Ɠ����������������ē���W�c�̒��Ԃɂ̂��肳��Ă����B�Ƃ��낪�A�����̔��W�ɉ����āA���肳�ꂽ�W�c�̘g�����̂Ǐ��z���āA�Љ�{�\�⋤�����L�����Ă������v�B5�Ƃ��A���̒���̒��Ől�Ԃ̓������̑Ώۂ�������n�����ɂȂ���\�����������Ă���6�B �ȏ���A�_�[�E�B���́A�l�Ԃ��P�ɑ��̓������܂߂���A�̐����w�I�Ȑi���̓r��ɂ���Ƃ��������łȂ��A���̓������ɂ����Ă������ߒ������ǂ��Đi���𑱂��Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���B�����ɂ����āA�l�Ԃ́A���̓����Ɛ��Ă��藣���Ȃ������w�I�ȂȂ���̒��ɑ��݂��Ă���ƂƂ��ɁA���g���Ƃ�܂����A������ɂ��ڂ��ނ��Ă䂭�ߒ��ɂ��鑶�݂ł���Ɖ�����Ă���Ƃ�����B�@ |
|
|
��2�|2�D�e�C���[���ɂ��L���X�g���I�i���_
�e�C���[���E�h�E�V�����_��(1881�`1955)�́A�t�����X�̃C�G�Y�X��m�ł���ƂƂ��ɁA�Ð����w�ҁE�n���w�҂ł�����A�����w�≻�w�A�N�w�ɂ����ʂ������j�[�N�Ȑl���ł���B�ނ́A�C�G�Y�X��̏C���m�A���t�Ȃǂ��o�Ē����ȂǃA�W�A�ł̌��������ɏ]�����A�k�����l�̔����Ȃǂ̈̋Ƃ𐬂��B�����������Łw���ۂƂ��Ă̐l�ԁx�����M���A�Ǝ��̃L���X�g���I�i���_��ł����Ă�B �F���̔�������A���������A�l�ޔ����Ƒ����ߒ��́A�l�ނ̉b�q���m������邱�Ƃɂ���Ē��_�ւƎ��ʂ��Ă����Ƃ������̑s��Ȑ��́A�_�[�E�B���ɂ��i���_�Ƃ����Ȋw�I�Ȏ��ۂƁA�L���X�g���Ƃ����v�z�����т���͂��炫�������B�e�C���[���́A���q�Ȃǂ̗��p���Ď��g�̐����ڍׂɐ������Ă���A�N���[�h�E�g�������^��7�ɂ��A�u�Ȋw�Ƃ����̈�A���ۂƂ������x���ɗ����āA�n���̂킴���l�ނ̐i����ʂ��Ăǂ̂悤�Ɍp������Ă��邩�A�������Ă���v8 �Ƃ����B �e�C���[�������̐����q�ׂ钆�ŏd�����Ă���_�̈�ɁA���݂��l�Ԃ͐i���̉ߒ��ɂ���A�i���Ƃ������̗̂���͑����Ă���s�t�ł���A�Ƃ������Ƃ�����B�܂��A�i���̒��_�ւƂނ����Ă��邱��܂ł̗��j���ӂ肩�����āA�u�܂��܂��f�ГI�ɂȂ�ӎ��̗v�f���܂��܂��������ȕs�����ԂɂȂ��ĕY���̂��]���ł���v9�Ƃ��āA�ߋ��ɎU�݂��Ă������܂��܂̎��ۂ����G�ɗ��ݍ����A�W�����Č��݂▢��������̂��Ƃ��Ă���B�����������_�ɗ����A�e�C���[���́A���݂���l�ԂƂ������̂��A�s�t�̗���̒��ŗe�Ղɂ͂قǂ��Ȃ��A�ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����G�ȑ����̗v������������Ȃ���A���������ڎw���ĕ���ł�����́A�Ɖ����Ă����̂ł͂Ȃ����A�ƍl������B�@ |
|
| ��3�D���V���g�����ɂ�����A�t���J�]�E�_���ƒn��Љ�ւ̉e�� | |
|
�����܂ł́A�_�[�E�B���ƃe�C���[�����҂̐i���_����A���ꂼ��́u�i���̉ߒ��ɂ���l�Ԃ����߂�ځv���l�@���Ă����킯�����A�M�҂̌����ɂ����Ă��A�l�Ԃ�����P�̂Ƃ��đ�����̂ł͂Ȃ��A�����̗���⑼�̂��̂Ƃ̂������̒��ő����邱�Ƃ��d�v�ƂȂ��Ă���B�ȉ��ł́A�����̊T�����Љ��Ȃ��ŁA���̓_�𖾂炩�ɂ��Ă����B
�M�҂̌����́A���V���g�����ɂ�����A�t���J�]�E�̏ۉ������߂������c�ł̘_���ƁA�n��Љ�ł̐l�ԂƃA�t���J�]�E�Ƃ̋����̎���(�]�E�̕ۑS�E�ی��]�E�Ɛl�Ƃ̏Փ˂Ȃ�)�Ƃ�����̈قȂ鎟���ɂ����錻�ۂɂ��āA���̑��ݍ�p��֘A�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����݂���̂ł���B���̖���́A�˂��l�߂�ƁA�l�Ԃ��쐶�����Ƃ̋�����}�邱�Ƃ��s���ł��邱�Ƃ����o������ŁA�ǂ̂悤�ɂ��Ă�������H���Ă����̂��A�������������Ɍ����Đl�Ԃ͉������ׂ��Ȃ̂��A�Ƃ����₢�ƂȂ�B�@ |
|
|
��3�|1�D�A�t���J�]�E�̌����Əۉ�̑S�ʗA�o�֎~���߂��铮��
���V���g�����10(��ł̂�����̂���쐶���A���̎�̍��ێ���Ɋւ�����)�Ƃ́A��ł̂�����̂���쐶���A����̍��ێ�����K�����邱�ƂŁA�������ł̂����ꂩ���邱�Ƃ�ړI�Ƃ������ۏ��ł���B ���̏��̑ΏۂƂȂ�쐶������́A�����Ƃ��ď��Ǝ�����֎~����镍�����T�A������̏��������Ώ��Ǝ�����F�߂��镍�����U�A�����ɂ����ĕی삵������ɂ��đ����Ɏ���K���̋��͂����߂����Ƃ��Ɍf�ڂ��镍�����V�A�̎O�̕������Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł���B�ǂ̕������ɂǂ̎���f�ڂ��邩�́A��N�Ɉ�x�J�Â���������c�ɂ����āA�Q�����ɂ���ċc�_����Č��܂�B�������āA�������Ɍf�ڂ��ꂽ���A�o�A�A���A�ėA�o�A�C����擾����ȂǁA�u����v����Ƃ����s�ׂ��֎~�������͐��������B 1973�N�ɏ�ł��A1976�N�ɏ��߂Ă̒���c���J�Â��ꂽ�Ƃ��A�A�t���J�]�E�͕������U�Ɍf�ڂ��ꂽ�B�A�t���J�]�E�̓A�t���J�嗤�S�y�ɐ������Ă������A�����ɂ��A���n�x�z�̓����ƂƂ��ɏۉ��ړ��Ăɑ�ʂɎE�C����A�k���A�����A�������ł͌̌Q�̋K�͂͏������Ȃ��Ă����B���̈���ŁA�����ł͕ی��ł̃T�t�@���ȂNJό������Ƃ��ďd�v������Ă���A�암�ɂ����Ă��Ԉ����Ȃnjv��I�ȊǗ��̉��A�L�x�Ȍ̌Q���ۂ���Ă����B�������A1976�N�ɂ͑嗤�S�̂�130����11�����]�E�́A�ۉ�̎��v�����E�I�ɍ��܂钆�ő�K�͂Ȗ��ɂ����A1987�N�ɂ�76����12�ɂ܂Ō�������B���ɁA�P�j�A��^���U�j�A�Ȃǂł͕ی��⍑���������ɂ����Ė����}�������A�]�E�̐��͌�������13�B���̂��Ƃ́A�����̍��X�̊ό��Ƃɂ���Ō���^�����B �����������Ԃ��A�A�t���J�]�E�̐������́A���ɂ���đ����̏̈Ⴂ�͂���A�A�t���J�]�E�Ƃ�����������ɐ�ł̂����ꂩ���邩�ɂ��āA����c�őS�̂ł̍��ӂ��`�����悤�Ƃ���B�������A�A�t���J�]�E�Ƃ����N�����m��쐶�����̌����Ȍ��������܂�ɃV���b�L���O�Ȏ����ł��������߁A�ߏ蔽�������A�����J��t�����X�̓����ی�E����n��NGO�́A�]�E�����̌����ł��閧�������N�����ۉ�������؋֎~���ׂ�(�܂�A���ׂĂ̍��ɐ�������A�t���J�]�E�����T�Ɍf�ڂ��ׂ�)�ł���A�Ƃ����[�I�Ș_����p���đ�K�͂ȃL�����y�[���𐢊E���ŊJ�n����14�B���̉e�����A�A�����J��t�����X�Ɏn�܂�A�P�j�A�A�^���U�j�A�A���A�t���J�����Ȃǂ̊֘A�����A�����ւ���ɐ����I�Ȉ��͂Ȃǂ�����������ʁA�A�t���J�]�E�̎�����Δh���������߂�1989�N�̒���c�ł́A�암�A�t���J�����ȂǁA�ꕔ�̍��̌̌Q���i�グ������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�S�̌Q�͕������T�ւƌf�ڂ���邱�ƂɂȂ����B ���̉e���͌��n�ɂ����Ă������Ɍ���邱�ƂƂȂ�B�^���U�j�A�ɂ����ẮA���̎���肪����ɋ�������A����܂ŕی��ߕӂ̑��Ɍ���ẮA���l�ɋ������������Ă����o�C���[�̎p�������Ȃ��Ȃ����B�܂��A�e�ی��Ŋ�����W�J���鉢�Ă�NGO�ɂ̓L�����y�[���ɂ�鑽�z�̊�t�������������߁A����炪������]�E�̕ی슈���ɏ[�Ă��A�K���͈�w�����ɂȂ����B�����Ă���]�E����o�ϓI�ȗ��v��ό��Ƃ��d������P�j�A��^���U�j�A�ɂƂ��āA�A�t���J�]�E�̕������T�f�ڂ́A���̂悤�ɖ��ɑR�����i�Ƃ��Ċ��҂ł�����̂ł������BNGO�̓��������͂������ɂ���A�P�j�A��^���U�j�A�������~���w�������̂��A�����������ʂ�������ł̂��Ƃ��傫�������B ����������ŁA�n�惌�x���ł́A����܂Ŗ@�K���͂��������̂́A�����I�ɂ͕��C����Ă����ی��ɗאڂ��鑺�̏Z���ɂ�鐶���̂��߂̎���܂ł����i�ɐ�������錋�ʂƂȂ�A�[���Ȗ��ƂȂ�B�܂��A�Ǘ�����̐����ɂ��]�E�̓��������肵�Ă���A�ό��Ƃɉ����āA�ۉ����A��Ȃǂ������Ƃ��ė��p���邱�ƂŌo�ϓI���v�邱�Ƃ��d������암�A�t���J�����ł́A���̂��Ƃ͏d��Ȍo�ϓI�����Ǝ~�߂�ꂽ�B�����̍��X�ł́A�쐶�����̏��L���◘�p����������n���ɈϏ����A�n��Љ�n���̖쐶���������𗘗p���邱�Ƃŕn��������_���Ȃǂ̃v���O���������{����Ă���A���̏d�v�Ȏ������Ƃ��Ă̏ۉ�������~����邱�Ƃ͑傫�ȒɎ�ł������B�����������������A1989�N�̒���c�ł́A�������T�f�ڊ�𖾂炩�ɖ������Ă��Ȃ����X�ɂ��āA���̌̌Q�̊i����������ȍ~�̉�c�Ō������邱�Ƃ����肳�ꂽ15�B�@ |
|
|
��3�|2�D�ۉ�̑S�ʗA�o�֎~�[�u�������ĊJ�Ɍ����Ă̓���
1989�N�̑S�ʗA�o�֎~���A�W���o�u�G�A�{�c���i�A�i�~�r�A�𒆐S�Ƃ����암�A�t���J�����́A1992�`1997�N�ɂ����ĊJ�Â��ꂽ�O��̒���c�ŁA���炽�߂āA�e���̏̈Ⴂ�ɉ��������_��ȃA�t���J�]�E�������E�֘A���ɂ�鍇�ӌ`����ڎw���ׂ����g�݂��s��16�B�ނ�͂܂��A����܂ŞB���ł������������̌f�ڊ���ڍׂɒ�߂邱�Ƃ���c��ŋ��߁A1994�N�̉�c�ɂ����ĐV���������߂�ꂽ�B���ɁA���̊�ɏƂ炵���킹�Ď����̃]�E�̌Q���������T�ł͂Ȃ��������U�Ɍf�ڂ����ׂ��ł���|���ؖ������B����ɁAEU�̋��͂̂��ƂŊJ�Â��ꂽ�A�A�t���J�����̊ԂŌ݂��̏ɂ��Ă킩�肠�����߂̌��n���@���܂߂��A�t���J������c�ɂ����āA�e���̑�\�҂ɗ��������߂��B ���������w�͂̌��ʁA1997�N�̒���c�ɂ����āA�ۉ����͉�c�ŔF�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ̂ݎ��{����A����������c�ŔF�߂�ꂽ���݂̂Ƃ���A�ۉ�̈�@����ƃ]�E�̈�@�ߎE�ɂ��Ẵf�[�^�x�[�X�����蓮���������葱����Ȃ�17�A�����̏������ł͂��邪�A�W���o�u�G�A�{�c���i�A�i�~�r�A�O�����̌̌Q���������U�f�ڂ���邱�ƂƂȂ����B������A1999�N�ɂ͓��{�Ƃ��̎O�����̊Ԃň�����̏ۉ��������{���ꂽ�B �Ȍ�A2000�`2004�N�ɂ����ẮA2000�N�̉�c�œ�A�t���J�̌̌Q���V���ɕ������U�Ɍf�ڂ��ꂽ���̂́A�ˑR�Ƃ��āA�P�j�A����͑S�̌Q�̕������T�f�ڂ����߂������ŁA�암�A�t���J��������͂���Ȃ������{�����߂鐺��������A�c�_�͕��s�������ǂ��Ă����B����������A2007�N�̉�c�ɂ����āA������Δh�A������i�h�����̈ӌ������ݎ��`�ŁA2008�N�ɐV���ȏۉ����������{�������9�N�Ԏ�����~����A���X��̉�c�܂ł�(9�N���߂������)�ۉ������{�̂��߂̈ӎv����v���Z�X���쐬����A�Ƃ�������18���A�t���J�����S�̂Ō`�����ꂽ���ƂŁA�ꉞ�̏I���ƂȂ����B�����ɂ����ẮA�����ی�E����n��NGO��A�����J�A�t�����X�Ȃǂ̑卑�⌳�@�卑�Ȃǂɂ�鈳�͂��قƂ�lj�����邱�Ƃ��Ȃ������B �܂��A2007�N�̉�c�ɂ����ē��M���ׂ��_�Ƃ��āA1989�N�̎��_�ł͏ۉ������Δh�ł������^���U�j�A���A�����̌̌Q�̕������U�ւ̌f�ڂ����Ƃ߂����Ƃ�����19�B�^���U�j�A�ł̓]�E�̓��������Ă���A����ɔ����A�암�A�t���J�����̏ꍇ�Ɠ��l�Ƀ]�E�ɂ��_�앨��Q�Ȃǂ��N���A�l�ƃ]�E�̏Փ˂��������Ă����Ƃ����w�i���������B�@ |
|
|
��3�|3�D���ɂ�����c�_�ƒn��Љ�ł̎���Ƃ̊W���ǂ��l���邩
���V���g�����́A��������̍��ێ���̋K���Ɋւ��Ă̂ݒ�߂���ł��邪�A���̖ړI�ł���u��ł̂�����̖h�~�v�ɂ́A���ۂɂ��̒n��őΏێ�Ƃ������������ׂĂ̐l�ԁA���ׂĂ̍s�ׂ��g�݂��W���Ă���B�����āA����c�ɂ���Č��肳�ꂽ��̕������ւ̊i�グ�E�i�����Ȃǂ̌���́A���ێ���Ƃ����s�ׂ݂̂ɂƂǂ܂炸�A���n�ł̋K����n��Z���̐����ȂǍL�͈͂ɉe�����y�ڂ����Ƃ́A��L�ł��G�ꂽ�Ƃ���ł���B�t�ɁA����c�ł̒��ɂ�鍇�ӌ`����ӎv����́A�Ώێ�̍��ێ���f�[�^�݂̂Ȃ炸�A��ł̂�����̖h�~�Ɋւ�邷�ׂĂ̗v���ɏ�ɍ��E����Ă���Ƃ����邾�낤�B ���������������l����������A�Ώێ���߂��邠���郌�x���ł̓��������A�������Ƃ炦�邽�߂̘g�g�̌`�������߂��Ă���B�A�t���J�]�E����������n��ł́A�l�Ԃƃ]�E�̊Ԃɂǂ̂悤�Ȗ�肪�����Ă���̂��B���̖��ɂ́A���̒n��̐l�ԎЉ�ɂ�����ǂ̂悤�ȗv�f�A���E�ۑ肪�֘A���Ă���̂��B�����̂́A���́A�����������̔����Ɖ����ɂǂ̂悤�ɂ�������Ă���̂��B�����āA���̂悤�Ȏ�������ꂼ��ɕ��������X�ƁA���̏ۉ��]�E���i�𗘗p���鍑�X�̊Ԃɂ́A�ǂ̂悤�Ȗ��E�ۑ肪���݂��Ă���̂��B�n��⎩���́A���A���ێЉ����i�K�ɂ����āA�����߂������Ƃ����߂��Ă���̂��B����炷�ׂĂ��܂ޑS�̑���`���o������ŁA���ێ�����K�����郏�V���g�����ɂ͉����ł���̂����l���Ă������Ƃ��d�v�ł���B �@ |
|
| ��4�D�܂Ƃ� / �����\�Ȕ��W�Ɍ��������_�̍\�z��ڎw���� | |
|
�쐶���A���Ƃ����P�̂́u��v���A��ł̂����ꂩ����Ƃ������Ƃɑ��āA���V���g�����Ƃ�������E���ێ���Ƃ������삩��ǂ̂悤�ȃA�v���[�`���\�Ȃ̂��B�����N���ɂ���ɂ́A�ȉ��̓�_���l�����������ł́A����c�ɂ�����e���́A�o�ρE�Љ�E�����ȂǑ�����ɂ܂�����c�_���K�v�ł���B���Ȃ킿�A�쐶�����̒u����Ă���ɂƂ��āA���ێ�����ǂ̂��炢�̋��ЂƂȂ�̂��A�쐶�����̈�ԋ߂��ɕ�炵�A�����Ƃ����������n��Љ�ɂƂ��āA���ێ���͂ǂ̂悤�ȉe���͂����̂��B
���������ϊv�����V���g�����ɔ�����̂Ƃ��āA�������l�����Ɓu�����\�Ȕ��W�v�Ƃ����T�O20 �̓o�ꂪ����B�������l�����́A�������l���̕ۑS�Ƃ��̎����\�ȗ��p�A��`�����̗��p���瓾���闘�v�̍t���Ȕz����ړI�Ƃ��āA1992�N�ɒ������ꂽ���ł���B�����āA���̑Ώ۔͈͂̕��L������A���V���g�����⑼�̖쐶�����A���R���Ɋ֘A������̏�ɗ����A�����𑩂˂�g�g���ƈʒu�Â����Ă���B���V���g�����́A���������ɂ́A���̖ړI�������Ƃ���A�쐶���A����ی�E�ۑ����邱�Ƃ�ڎw�����ł������B�������A�쐶���A���ɑS��������Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����������I�ɗ��p���邱�Ƃł��̕ۑS��}�낤�Ƃ���p�������������l�����̘g�g�݂ɑg�ݓ����ꂽ���Ƃɂ���āA���̖ڎw�������m�ɏC�����邱�Ƃ����߂���悤�ɂȂ����̂ł���B �������̂��Ƃ́A�ˑR����ꂽ�]���Ȃǂł͂Ȃ��A�A�t���J�]�E�_���Ƃ������ۂ̂����ɂ��A�L�x�Ȍ̌Q�����암�A�t���J�����ɂ��ۉ嗘�p�������Ɉ�@����▧��U�����Ȃ��`�ł����Ȃ����A�ۉ����Ƃ����A�t���J�]�E�̗��p���W���͂ǂ��l���Ă䂭�̂��A�Ƃ����₢�Ƃ��Č���Ă������̂ł���B�܂��A�������l�����́A�u�����̖@�߂ɏ]���A�����̑��l���̕ۑS�y�ю����\�ȗ��p�Ɋ֘A����`���I�Ȑ����l����L���錴�Z���̎Љ�y�ђn��Љ�̒m���A�H�v�y�ъ��s�d���A�ۑ����y�шێ����邱�Ɓv�L���Ă���21�B���̓_�Ɋւ��Ă��A�n��Љ�ł̖쐶�����̎�����Ȃǂ��A���V���g����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ď����オ���Ă��Ă���B���V���g�����͂܂��ɁA�����\�Ȕ��W�ɓK�����Ă������Ƃ����߂��Ă���B �Ƃ���ŁA�����\�Ȕ��W��ڎw���l�Ԃ́A�͂����Đi���E�i���̓r��ɂ���l�ԂƂ�����̂��낤���B�_�[�E�B���̂����������̐i�����炷��ƁA�n���̊��ɂ܂Ŗڂ������n�߂��l�Ԃ͂��̓_�ɂ����Ă͐i�����Ă���̂�������Ȃ��B�������A�����Ƃ������܂��܂̗v�������G�ɗ��ݍ��������ۂ���������A�s�t�ȓ���i�ސl�Ԃ̕��݂́A�`�Ԃ����e�C���[���̂����i���ɋ߂����̂͂��邪�A�I���_�������Ȃ������ɁA�i�����Ă���Ƃ͌����������ʂ�����B �����A�_�[�E�B���ƃe�C���[���̓�l�̐i���_������Ƃ��A�d�v�Ȃ̂͂��̐i���̍s���������ł͂Ȃ��A�������l�Ԃ����̉ߒ��̒��ɁA�F������A���R�Ƃ̂�������Ȃ�������������̂Ƃ��đ��݂��Ă���Ƃ������Ƃł���B�s��Ȏ��Ԏ��⑼�Ƃ̊֘A�Ƃ����S�̂̒��́A�ǂ��ɍ��l�Ԃ͈ʒu���Ă���̂��B�����₦���ӎ�����ڂ��l�̘_�҂���w�Ԃ��Ƃ��A�n�������̉����ɁA�����\�Ȕ��W�̌`���ɁA�d�v�ȈӖ������Ƃ�����B�@ |
|
|
1�@���]�d�g�w�_�[�E�B�j�Y���̐l�Ԙ_�x�A26�ŁB
2�@���]�E�O�f��(1)45�ŁB 3�@���]�d�g�́A���ݏ��R��w�o�ϊw�������ł���(�N�w�A�G�R���W�[�_)�B 4�@���]�E�O�f��(1)204�ŁB 5�@���]�E�O�f��(1)208�ŁB 6�@���킵���́A���]�E�O�f��(1)�I�͎Q�l�̂��ƁB 7�@�N���[�h�E�g�������^���́A�N�w�A�����ߋ`�w�A���R�Ȋw�ɐ��ʂ����t�����X�̎v�z�Ƃł���B 8�@�N���[�h�E�g�������^���w�e�C���[���E�h�E�V�����_���x54�A55�ŁB 9�@�g�������^���E�O�f��(8)�A85�ŁB 10�@1973�N����1975�N�����B���E175�J�����������Ă���(2009�N11�����_)�B 11�@������w�n�����K�o�i���X�ƃ��W�[���̔��W�v���Z�X�x86�ŁB 12�@����E�O�f��(11)�A91�ŁB 13�@���킵���́A�C�A�����I���A�E�_�O���X���n�~���g���w�ۂ̂��߂̓����x���Q�l�̂��ƁB 14�@���킵���́A����E�O�f��(11)�A��5�͎Q�Ƃ̂��ƁB 15�@���V���g������7�����c���c7.9�B 16�@���킵���́APhiyllis Mofson , in Jon Hutton and Barnabas Dickson, Threatened Convention: The Past, Present and Future of CITES(EARTHSCAN,2000), Zimbabwe and CITES: Influencing the International Regime, pp.105-119 ���Q�Ƃ̂��ƁB 17�@���V���g������10�����c���c10.9�y��10.10�B 18�@���V���g������14�����c����14.75�`14.79�B 19�@���V���g������14�����c��ď��ACOP14Prop.7�B 20�@�u�����\�v�Ƃ����l�����́A���Ƃ��Ǝ��R�ی앪��ɂ����Ĕ��B���Ă����T�O�ł���B1980�N�AIUCN�AUNEP�AWWF�������Ŕ��\�����w���E�ۑS�헪�x�ɂ́A�u���R�����̕ۑS��ʂ��Ď����\�ȊJ���̒B���𑣐i�������邱�Ɓv���ړI�Ƃ��ď�����A���ڂ��ꂽ�B���̌�A1984�N�ɍ��ۘA���ɐݒu���ꂽ�A���ƊJ���Ɋւ��鐢�E�ψ���(�ʏ̃u�����g�����g�ψ���)�̕��wOUR COMMON FUTURE�x(1987�N)�̒��ŁA�����\�Ȕ��W(�J��)�Ƃ́A�u�������オ����̗~�����[������\�͂Ȃ����ƂȂ��A�����̐���̗~���������Ɓv�Ɛ������ꂽ�B�����ł������W(�J��)�Ƃ́A�n��J���A�y�؊J���A�o�ϋK�͂̊g��Ƃ������Ӗ������A�u���L���ȏ�Ԃ�ڎw�����サ�Ă����v�Ƃ������Ӗ�������L���Ă���_�ɗ��ӂ���K�v������B�Q�l�����^���䐳�O�ҁw�n�������x(�L��t�A2005)�ȂǁB 21�@�������l�����攪��(j)���B �@ �@ |
|
| ���t���C�g1 �u�����́v | |
| �t���C�g�ɂ��A���͐l�Ԃ̊�]�������߂̂��̂ł���A�킽�������̌��閲�͂��ׂĉ��炩�̈Ӗ��̂�����̂��Ƃ��Ă��܂��B�����Ė��ɂ͊�]�����̂܂܂̌`�Ō����ꍇ�ƁA���ݓI�Ȋ�]���`��ς��c�Ȃ���Č����ꍇ������Ƃ��Ă��܂��B��҂̐��ݓI�Ȋ�]�Ƃ͖������Ă���{�l�ɂ�������Ȃ��悤�ȗ}�����ꂽ���ӎ��I�Ȋ�]�̂��ƂŐ����I�Ȋ�]����Ɋ܂܂�Ă���Ƃ����Ă��܂��B���̂悤�Ȗ��̕ϑ������j��B���ꂽ��]��T��o�����߂ɂ̓t���C�g�̐������l�̖��̐����u�s���v�u�ލs�v�u�}���v�u���{�v�ɂ��Ēm���Ă����K�v������ł��傤�B | |
|
���u�s���v�s���̑傫���l�قǑ傫�Ȗ�������
���̃t���C�g�S���w�ł悭���グ�����\�I�Ȗ��ɁA�ҏb�ɒǂ��ē����܂���Ă���̂�����܂��B���̂悤�Ȗ���������͋��|�̂��܂�т��肵�Ėڂ��o�܂����ł悩�����Ƌ����Ȃł��낷�ł��傤�B���̖��͗c�����ɐe��������͂����ݓI�ȕs���ƂȂ��Č������̂Ƃ���Ă��܂��B �܂��C�̋����ł��炢���߂���Ƃ������悤�Ȗ������邱�Ƃ����邱�Ƃ���A���̖��͕K�������c�����̕s���̌��ꂾ���Ƃ͌����܂���A�v����ɋ������̂ɂ����߂��鎞�̕s���������ɕ\���Ƃ����̂������ł���Ƃ����܂��B �s���͑��ɂ����낢��Ȗ��ɂȂ��ĕ\������܂��B�Ⴆ�Ύ��������閲�┯�̖т������閲�������ł��B���̃t���C�g�S���w�ł́A���̂悤�Ȏ��������閲�┯�̖т������閲�𐫓I�Ȕ\�͂ւ̕s����I�Ȋ����ɂ��s���ƌ��т��ĕ��͂��Ă��܂��B�������A���̂悤�ȁu�s�����v�͌J��Ԃ����邱�Ƃɂ���Ă��̊Ԃɂ��s������������Ă��܂����Ƃ���������Ă��܂��B���ɂ͂��������s�v�c�ȏ����p�̐��������Ă��܂��B |
|
|
���u�ލs�v���̃^�C���X���b�v�͓����s
����Љ�ł͌l�̎��R�����܂�ɂ����d����Ă��邽�߂ɁA��������ɂ��Ă��A�������Ăǂ������炢���̂����f���Ă��܂��l�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���A�Ⴆ�Η������y���ގ��R������Η��Ȃ�Ă��Ȃ����R������܂��B�������鎩�R������Ό������Ȃ����R������A���܂��܂Ȏ��R�̒��Ŏ�҂͂Ȃ��Ȃ��S�����邱�Ƃ��o�����A�s���⊋���ɔY�܂���Ă��܂����Ƃ��������̂ł��B���̐S�̕s���⊋���ْ͋������߂ăX�g���X�ւƂȂ��Ă����܂��B����ƐS�͗���͂��߁A���ɂ͂��ׂĂ�������Ďq���̂悤�ɂ��������˂āA�܂��������R�łȂ��Ȃ����悤�ɋ������ԏ�ԂɊׂ�Ƃ���̐S���w�ł����ލs���ۂ�������l�����܂��B ��ʓI�ɂ��̂悤�ȏ�Ԃ̎��͖������₷���Ƃ������Ƃ������܂��B�܂�O���u�s���v�ł��������܂����悤�ɁA�s���⊋���ɂ��S�̃o�����X�������A������s���������₷����ԂɂȂ��Ă���̂ł��B �Ƃ���ŁA���̑ލs�͖��̒��ł��N����܂��B���̒��ł́A�^�C���X���b�v���ĉߋ��̏o��������݂������Ă��錻�ۂƂ��ĕ\��܂��B�܂��ɈȑO�̏�Ԃɋt�߂肵�čs���̂ł��A���Ƀi���V�X�g�I�Ȏ��Ȉ��̋����l�⎩�Ȓ��S�I�Ȑl���s�����ȕs���ɏP��ꂽ�肷��Ɩ��̒��Ŏ����̗c�����ɓ������邩�̂��Ƃ��A���̂悤�Ȗ������₷���悤�ł��B�������ŋ߂̖��̐��_�����ɂ��ƌ����̏o��������퐶���̈ꕔ�����ɕ\��邱�Ƃ����|�I�ɑ����ލs�̌`�ŕ\��邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ł��B |
|
|
���u�}���v�ǂ����Ė��̒��̂킽���͗���s�\�Ȃ�
�O�q�̂Ƃ���t���C�g�͖��͐l�Ԃ̊�]�������߂ɑ��݂�����̂��Ɛ����܂����B���̊�]�Ƃ͓��퐶���̒��Ŗ�������Ȃ��������̂ŁA�������Ȃ��̂���A�ߐe�����Ȃǂ̐��I�~����l�ɂ���Ă͎E�l�Ȃǂ��܂��ܖ��ł��B�l�X�͂��̂悤�Ȋ�]���S�̒��ɕ����Ă��Ă��A����炪�����ł��Ȃ����̂ł������肷��ƁA�Ȃ�Ƃ�������Y��悤�Ƃ��Ė��ӎ��̐��E�ɕ����߂Ă��܂��̂ł��B�܂����Ƃ����Ĕ��Ɋ���I�ɋ��������苰�|�ɋ������茙�������������肵�����ƂȂǂ��A�L���Ƃ��ăC���v�b�g���ꂸ�{���͖Y��Ă��܂����Ǝv������ł������Ƃ��A���ӎ��̐��E�ɉ������܂�Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɗ}�����ꂽ���ӎ��̒��̊�]�⊴��͖��ƂȂ��Ă��܂��܂Ȍ`�ŕ\��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ疰���Ă��鎞�͐��_�I�ْ������݁A���܂ŗ}������Ă������̂���C�Ɉ��o��Ƃ�����������܂��B�܂�}������Ă�����]�����݂̒��Ŗ��������Ƃɂ���ĐS�̃o�����X�����܂��ۂ��Ă���̂ł��B ���������ۂɌ��閲�̓��e�͎x���ŗ�łǂ�ȈӖ�������̂��������ς�킩��Ȃ��悤�Ȃ��̂�����̂́A�F����̌o�����瑽���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�Ⴆ�Ε��e����D���ȏ��̎q���A���̋C�����ӎ��̒��ʼn������悤�Ƃ��Ė��̒��ő吨�̐l���܂��ɂ���O�ŕ��e�Ɣh��ȃP���J�����Ă���Ƃ����̂������������̈�ł��傤�B ���͖����Ă���Ԃ̐S�����ۂł����A���e���͂����肵�Ȃ����Ƃ��������߂ɁA�Y��Ă��܂��Ă�����̂����Ȃ�����܂���B |
|
|
���u���{�v���ɂ͉f�ς̂悤�Ɍ��{�̃`�F�b�N������
�����ł͖��̋����ׂ���ʂ��Љ�܂��傤�B�Ȃ�Ɩ��͂��Ȃ����g�̓��Ȃ�\��ł���Ȃ���A���Ȃ����g���C�Â��Ȃ��Ƃ���œ��e�������ĕҏW���Ă��܂��Ă���̂ł��B�Ⴆ����ǂ����`�ʂ̖��Ƃ��Q���łт������Ȃ�悤�ȋ��낵�����������Ƃ��܂��B���������͐��`�ʂ��ꂽ���͖̂��ӎ��̐��E�ł͂����ƃO���e�X�N�Ȉӎ��ł�������A���̒��̂ƂĂ��Ȃ����|�͎��͋C���̈������Q�ł������肷��̂ł��B�܂��������ł͂����܂Ŏv���Ă����Ƃ͐M�����Ȃ��悤�ȐS�̓��������ӎ��̐��E�ł͂���̂ł��B �Ƃ��낪�A�����Ɂu���{�v�Ƃ�����p�������Ă��邽�߂ɖ��ӎ��̐��E�ɔ�߂�ꂽ���e�͖��̒��ɕ\��Ă������悤�ȓ��e�ɒu���������Ă��܂��Ă���̂ł��B�܂茟�{�Ƃ͗}�����ꂽ��]�����ƂȂ��ĕ\��Ă���O�ɁA���̊�]���`�F�b�N���āA���܂�ɂ������������s�s���Ȋ�]�Ƀu���[�L���������ڂ����Ă���̂ł��B���̌��ʂƂ��Ċ�]�͂Ђǂ��c�Ȃ���p�������ƕς��Ė��ɕ\���̂ŁA�����Ӗ����Ă���̂��A�ǂ����Ă���Ȗ�������̂������ς�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B���̂��߁A���̐l�Ƃ��Ă���قǏd�v�łȂ����Ƃ����̒��S�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�ł����疲���͂ő�Ȃ��Ƃ͌��{���ꂽ���̎��{���̈Ӗ������j�邱�ƂȂ̂ł��B�@ �@ |
|
| ���t���C�g2 �u�����f�v | |
|
(Die Traumdeutung, The Interpretation of Dream)�@1900�N�ɔ��\���ꂽ�A�I�[�X�g���A�̐��_�Ȉ�W�[�N�����g�E�t���C�g�ɂ�閲�Ɋւ��鐸�_���͊w�̌����ł���B
�t���C�g��1856�N�ɐ��܂�A�E�B�[����w�ň�w���w�ԁB�]��U�̐���Ƃ��ăE�B�[�������a�@�ɋΖ����A�t�����X�̃T���y�g���G�[���a�@�ł��w�ԁB1893�N�ɗF�l�̈�t���[�[�t�E�u���C�A�[�Ƌ����Łw�q�X�e���[�����x�\����B�{���͈�t�Ƃ��ĒS����������Ɋւ��錤���̐��ʂł��������A�o�œ����͕]������Ȃ��������߂ɏ���600�����������邽�߂�8�N�Ԃ��������B ���ɂ��Ă̍l�@�͌Ñォ��s���Ă������A�S���w�I�Ȋϓ_����̌����͑����Ȃ��B���������Ė��̌����ɂ��Ă��_�w�I�Ȑ������Ȃ���Ă����B�₪�ĐS���w�I�Ȑ��������݂��A�������̊��o�̎h���ɂ���Ė��ɂ��̎h�������f�����Ƃ����������Ȃ����悤�ɂȂ����B�������t���C�g�́A���̊��o�h�������ł͂Ȃ����Ƃ��w�E���A���̓��e�_��ԂƊ֘A�t����c�_�����܂��܂Ȏ��ጤ���Ɋ�Â��ēW�J�����B �����̍\�� �t���C�g�ɂ��Ζ��̑f�ނ͋L����������o����Ă���A���̑I����@�͈ӎ��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ӎ��I�ł���B���������Ĉꌩ����Ɨ��G�Ȗ��̓��e�ɂ����Ă����ӎ��Ɋ�Â�����������������Ă���A���܂��܂ȏo��������̕���Ƃ��ĘA����������̂ł���B����ɂ͂��܂��܂ȑ_�������邪�A��ʓI�ɂ͖��Ƃ͐��ݓI�Ȋ�]���[����������̂ł���B�܂薲�͖��ӎ��ɂ�鎩�ȕ\���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B �����Âւ̉��p �t���C�g�͖��ɂ����ď[�������悤�Ƃ����]���C���[�W�ɂ��B���ɕ\������Ă��邩�ɂ��Ē��ӂ��Ă���B���̗��R�Ƃ��Ă͊�]�m�����邱�Ƃ�W���悤�Ƃ���ӎ��ɂ���Ė����c�Ȃ���邱�Ƃ������Ă���B�ӎ��ɂ�閲�̌��{��������邽�߂ɖ��ӎ��͊�]���ԐړI�ȕ\�������p����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ʏ�ł͈ӎ��I�ɗ}�������ׂ��ƌ��Ȃ���Ă��鐫�~�����̒��ł͊�]�Ƃ��Ĕ������邽�߂ł���B�t���C�g�͕����Љ�̐����ɂ��l�Ԃ̖{�\����������Ă�����̂́A����͏��ł����킯�ł͂Ȃ��A���̐��~�͈Úg�I�ȕ\���ɂ���Ė�����������̂Ƒ����邱�Ƃ��ł���Ƙ_����B�@ �@ |
|
| ���t���C�g3 �u�����f�v | |
|
�����̖��̊w��I����
�{���ł́A�����ڊo�߂Ă��鎞�̐S�̓����̒��ɁA������̈ʒu�ɐ����u�����Ƃ̂ł���悤�ȐS�̏��Y���Ƃ������ƁA�����Ė����Ȃ���ȂƂ�Ƃ߂��Ȃ����̂Ȃ̂��A����𖾂炩�ɂ������Ǝv���B�Ñ�M���V�A�A���[�}�ɂ����ẮA���͐_��f�[�����̂��������ƍl�����A�O���̕ʐ��E�������Ă������̂Ƃ���Ă����B���̌�A�A���X�g�e���X�͖������̓������ƍl���A���݂̖��Ɋւ��錤���̒[�����J�������A�{�i�I�Ȗ��̌������n�܂�̂͋ߑ��҂��˂Ȃ�Ȃ������B�ȉ��A���̊w��I��������ʂɂ܂Ƃ߂Ă����B ���`�@�o����Ԃɑ��閲�̊W �q���f�u�����g�ɂ��A���͌����̐�������藣���ꂽ�A���ꎩ�̂ł܂Ƃ܂������݂Ȃ̂����A���̍ޗ��͌����̐�������̂��Ă���ꂽ���̂ł���A���ǂ͌����̐��E���犮�S�ɗV�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B ���a�@���̍ޗ��\�\���̒��ł̋L�� �����o�����ɂ͊o���̂Ȃ��悤�ȋL���⌾�t���ޗ��Ƃ��ċ�g���邱�Ƃ́A�����̕�������Ă���B�q���f�u�����g��V���g�������y���́A�����o�����ɂ����ĈӋ`�̂�����̂ł͂Ȃ��A�ǂ��ł������悤�ȍ��ׂȂ��̂��ޗ��ɂ��邱�Ƃ��������A���ɖY��Ă����c�N����̐������ޗ��ɂȂ�̂��Əq�ׂĂ���B�����炱���A�ꌩ�A���͈ӎ������ƌq���肪�Ȃ��悤�Ɍ�����̂ł���B ���b�@���̎h���Ɩ��̌��� ���̌���ɂ́A�O�I���o�h���A���I���o�����A���I�g�̎h���A�����ɐS�I�Ȏh����4������B�O�I���o�h���͐������ɊO�������h���ŁA���炩�ɖ��̌���ƂȂ��Ă���B���I���o�����͎�ϓI�Ȏh���ɂ����̂ŁA�Ⴆ�Ό��o���݂���Ŗ��Ɍ��o�̓��e���o�Ă���悤�ɁA������܂����̌���ƍl������B���I�g�̎h���͐g�̊튯���甭������̂ł���A�S����x�������ƕs���Ȗ������邵�A������n���̏�Q�ł͓f�����肷�閲������B�Ō�ɐS�I�h�������A����͊o�����ɂ�����S�ł���A���̌`�ۂ̗R���������������d�v�Ȗ��̌���Ȃ̂����A����܂ł̌����ł͏d������Ă��Ȃ��B ���c�@�Ⴊ�o�߂�Ɩ���Y��Ă��܂��̂͂Ȃ��� �V���g�������y���ɂ��A���ɂ͒������Ȃ���Θ_�����Ȃ����߁A�������̏u�ԃo���o���ɕ���Ă��܂��悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���A�L������邽�߂̏����������Ă���B�������Ⴊ�o�߂�ƊO���̊��o���E�̂��ƂɖZ�E����A�킸���Ɋo���Ă������̋L�������R����ɘc�߂��A�Y����Ă��܂��̂ł���B ���d�@���̐S���w�I�ȏ����ِ� �t�F�q�i�[�́A���̕���͊o�����̕\�ې����̕���Ƃ͕ʕ����Ǝ咣���Ă���B�Ⴆ�Ίo�����̎v�l�͊T�O�ɂ���čs����̂����A���͊T���Ď��o�I�`�ہA���o�I�`�ۂɂ���Ďv�l����B�ܘ_�A�������ɂ͊O�E�ɑ��Ĕw�������Ă��邽�߁A����͎v�l�Ƃ��������ۂ̑̌��Ƃ��ĐM�����Ă���B�����������̕\�ۂ��݂��Ɍ��т���A�z��p�͊o�����̘A�z��p�Ƃ͈Ⴂ�A����Ȃ��̂ł���B ���e�@���̒��ɂ�����ϗ��I���� �s�����ȏՓ��͊o�����ɂ�����̂����A���ۂ̍s���ɂȂ�Ȃ��悤�ɕ��i�͗}�~����Ă���B�������A�q���f�u�����g��[���ɂ��A�������ɂ͂��̗}�~���Ȃ��Ȃ�A���͉B���ꂽ�ϗ��I���ׂ������ɒm�点�邱�ƂɂȂ�B ���f�@�����_�Ɩ��̋@�\ �����_�͎�Ɏ���3�̐��ɕ�������B1)�o�����̊��S�ȐS�I�����͖��̒��ł��p�������Ƃ������B���̐��ł͖��̊�ȘA�z�̐������ł��Ȃ��B2)���ł͐S�I�������ቺ���A���֘A���o�ɂ��A�ޗ����n��ɂȂ�Ƃ������B����͖����I�o���ƍl������ŁA���ɂ������ȘA�z�̐������ł���̂����A���̂��߂ɖ�������̂��͂킩��Ȃ��B3)�o�����ɂ����Ă͕s���S���S���s���Ȃ��悤�ȐS�̎d���ւ̔\�͂����ɂ͂���Ƃ�����B����Ȃ�A���͊o�����̕s���S�Ȃ��̂�₤���߂ɂ���A�ƍl���邱�Ƃ��ł���B ���g�@���Ɛ��_�a�Ƃ̏��W �O���[�W���K�[�́A��]�[���Ɛ��_�a�ɋ��ʂȕ\�ۍs�ׂ��Əq�ׂĂ���B���Ɛ��_��Q�͈�v����_�������A�����A���_��Q�̃��J�j�Y�����𖾂����ł��傫�ȈӖ������ł��낤�B�@ |
|
|
�������f�̕��@ / ���閲����̕���
�u�������߂���v�Ƃ͖��Ɂu�Ӗ��v��^���邱�Ƃł���A�S�I���s�ׂ̘A���ɁA�����i�̂��̂Ƃ��đg�ݓ���邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���ɈӖ���^��������ɂ́A�ے��I�����f(������̑S�̂Ƒ����ėގ��̓��e�ɒu����������@)�A��ǖ@(��ǂ̃L�[�𗊂�ɁA�����Í����̂悤�ɂ݂���@)�Ȃǂ��̂��炠�������A�w��I�ɂ͖�������Ă���B�������A���ɂ͎��ۂɈӖ�������A�w��I�Ȗ����f�̕��@���\���Ƃ������Ƃ��A���͐��_���͂̎��Â̒��Ŋm�M����悤�ɂȂ����B�a�I�\�ۂ́A���ꂪ���҂̐��_��������o�Ă������v�f�֊Ҍ������ƁA���҂͂��̕\�ۂ����������B�ł́A������a�I�Ǐ�̂悤�Ɉ����A���_���͂̋Z�@��K�p���Ă݂���ǂ����ƍl���n�߂��̂��B���_���͂��������邩�ǂ����́A���҂������̓��̒��ɕ������ƈ���݉B���������Ă���邩�ǂ����Ɍ������Ă���B�����ŁA���܂�d�v�łȂ��������Ƃ��A�W�Ȃ��Ǝv���Ă��A�����}�������A�ᔻ�����Ɋώ@���A����悤�w������̂ł���B�ӎ��I�Ȕᔻ����i�ɑނ��A�u�~����ꂴ�鏔�ϔO�v�������яオ���Ă��邱�ƂɂȂ�B���̕��@���f�ɂ������悤�ɓK�p����̂ł���B ���C���}�̒��˂̖� �傫�ȃz�[���ɑ����̋q������A���̒��ɃC���}������B���̓C���}�Ɂu�܂��ɂނƂ��������āA����͎��ۂɌN���g�̙�Ȃ̂��v�ƌ����ƁA�C���}�́u�����ǂ�قǒɂ����Ă��邩�A��A�݁A�����Ȃ��ǂ�Ȃɒɂ����A���킩�肩����B�܂�Œ��߂�����悤�Ȃ�ł��v�ƌ����B���͂т����肵�ăC���}���Î�����ƁA�������A�ނ���ł���B����͓����튯�W�̂��Ƃ������Ƃ��Ă������ȂƎv���A�A��f�悤�Ƃ���ƁA�C���}�͂�����Ƃ��₪��B���₪�邱�Ƃ͂Ȃ��̂Ɂc�c�B�E���ɑ傫�Ȕ��_�A�ʂ̏ꏊ�ɕ@�b���̏k�ꂽ�`�̔��D�F�̌��o������B�h�N�^�[�E�l���Ă�Őf�Ă��炤�ƁA�ԈႢ�Ȃ��Ƃ����B�F�l�̃I�b�g�[�����[�I�|���g���T�ɂ���B�l�́u����͓`���a�����A�������S�R���ɂȂ�Ȃ��B���̏�A�ԗ��ɂȂ�Ǝv�����A�ŕ��͔r������邾�낤�v�ƌ������B�ǂ����炱�̓`���a�����������������Ă���B�I�b�g�[���A�C���}���a�C�ɂȂ��ĊԂ��Ȃ����Ƀv���s���[�����܂𒍎˂����̂��B�c�c�v���s�����c�c�v���s�I���_�c�c�g�����`���~��(���̉��w�������̓S�V�b�N�̂Ō�����)�c�c���̒��˂͂����ȒP�ɂ͂��Ȃ����̂Ȃ̂����c�c�����炭���ˊ�̏��ł��s���S�������̂��낤�B ���� / �ŏ��̃C���}�Ƃ̉�b�́A�܂��C���}���ɂ݂������Ă���Ƃ��Ă��A����ɑ��ăt���C�g�͐ӔC�����������Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�܂��A�������A�ނ���ł������鏗���ƁA�f�B�t�e���A�Ɛf�f����Ă����C���}�̐e�F(�������_�̓f�B�t�e���A���Ӗ�����)��2�l���A�C���}�Ƃ���ւ����Ă���B�����āA��ɂ̌������f�B�t�e���A�̂悤�Ɋ펿�I�Ȃ��̂Ȃ�A�t���C�g�͂܂����Ă����̎����ɐӔC���Ȃ����ƂɂȂ�B�������A�C���}���f�B�t�e���A�Ƃ����d�a�ɂ����܂܂ł͗ǐS�ə�߂邽�߁A�u�S�R���ɂȂ�Ȃ��v�Ƃ����l�̈Ԃ߂̌��t���K�v�ƂȂ����̂��B�I�b�g�[�ƃ��[�I�|���g��2�l���o�ꂷ��̂́A�p�S�[�����[�I�|���g���^���A�v���s���[�����܂𒍎˂����I�b�g�[��ᔻ���邽�߂ł��낤�B�O���A�t���C�g�̓C���}�ɂ��ẴI�b�g�[�̔����̒��ɁA�����ւ̔��������Ă����̂ł���B�g�����`���~���͐��I�V��ӂ̎Y�����ƃt���C�g�͕��������Ƃ����邽�߁A�S�V�b�N�ŋ�������Ă����̂́A���I�v�f�̗D�ʂɑ���Î����Ӗ����Ă���̂��낤�B������܂��A�t���C�g���g�̗��_(���~���d���������_)�𐳓������邱�ƂɌq�����Ă���B �� �ȏオ���͌��ʂ����A�t���C�g�͂��̕��͂̐��s�ɂ������āA���܂�ɂ������̎v�����������яオ���Ă���̂ŁA�����ǂ������̂ɋ�J�����Əq�ׂĂ���B���̖��́A���̓��̖�̂������̎���(�I�b�g�[�̕A�a�����M)�ɂ���Đ�������]���[�����Ă���B�܂薲�̌��_�́A���݂̃C���}�̋�ɂɑ��Ă͎��̐ӔC�ł͂Ȃ��I�b�g�[�ɐӔC������A�Ƃ������ƂɂȂ�̂ł���A�t���C�g�̊�]���[�����Ă���̂ł���B���͎��ۂɈӖ��������Ă���A���̓��e�͊�]�[���Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
�����͊�]�[���ł���
��]�[�������̗B��̈Ӑ}�ł��邩��A���͊��S�ɗ��Ȏ�`�I�ł���B�钆�ɍA�����킯�A�������ޖ�������B�܂��A�q�ǂ��̖����P���Ȋ�]�[���������Ă���A��J���ĉ����ׂ�������Ȃ��B�q�ǂ��͐��I�~�]�Ɋւ��閲�͑����Ȃ���������Ȃ����A�H�ׂ������َq���o�Ă���ȂǁA�H�~�Ɋւ��閲�͑����A������]�[�����Ӑ}���Ă��邱�Ƃ�[�I�ɋ����Ă����̂ł���B�@ |
|
|
�����̘c��
�u���͊�]�[���ł���v�Ƃ�������̈�ʉ��́A��ɖ��⋰�|���ɂ���Ĕے肳���悤�Ɏv����B�������A���̌��ݓ��e����ɂ�s���������Ă��Ă��A���͂��Ă݂�A���̐��ݓ��e�͂�͂��]�[�����ł��邱�Ƃ��킩��B�C���}�̒��˂̖��ɂ��Ă��A����ׂ͂��肰�Ȃ����e�ł������̂ɁA���ݓ��e�͊�]�[�����Ӑ}���Ă����B�ł́A�Ȃ����߂����]�[���Ƃ������i�������Ȃ��̂��낤�B���͂Ȃ����͂��Ă݂�܂ł��̈Ӗ����킩��Ȃ��قǘc�Ȃ���Ă���̂��낤���B����ɂ��ăt���C�g�͎��̂悤�Ȗ����ɂ��Đ������Ă���B ���t���C�g�̋����C���Ɋւ�閲 ���̖��̑O���A�t���C�g�͏������ɔC������邩������Ȃ��Ƃ����\���Ă������A����͏@����̗��R����l���Ă��A���Ȃ������Ƃł������B���̓��e�́A�F�l�q�������ł���A���Ȃ�̐e���̏�������Ă��邱�ƁA�F�l�q�̊���������ƈ���Ă��邱�ƂȂǂ��v���o���ꂽ�B�n���������̂悤�Ɏv�������A�t���C�g�͂���������̒�R�̌��ꂾ�ƋC�Â��A���͂Ɏ�肩����B�t���C�g�̔������[�t�͍߂�Ƃ��čق��������Ƃ�����A�����u������Ƒ���Ȃ��Ƃ��낪����v�ƌ����Ȃ���S�z���Ă������Ƃ��v���o���B�q�������ł���Ȃ�A�t���C�g�́u�q�ɂ͏�������Ȃ��Ƃ��낪����v�ƍl���Ă��邱�ƂɂȂ�A����͏��F���������s�����Ȃ��Ƃ��Ƃ����B�܂��A�����̂m���������ɂȂ��Ă������A�ނ͍��i���ꂽ���Ƃ����邽�߁A�����̏��i�͓���ƌ����Ă������Ƃ��v���o���B�܂�A���̒��̔����͂q�Ƃm��2�l�Ƃ���ւ���Ă���̂��B�q�Ƃm�̋����C�����x�����Ă���̂��@����̗��R�ł���Ȃ�A����̓t���C�g�ɂ��������Ƃ��l������B�������A�x���̗��R���A�q���n���҂łm���ߐl�ł��邽�߂Ȃ�A�t���C�g�̋������i�ɂ͏\���Ȍ����݂����邱�ƂɂȂ�B�������A�����������ɂȂ邽�߂�2�l�̗F�l�����Ƃ��߂��̂��Ƃ���A����͔[�������������Ƃ��ƃt���C�g�͎v���B���A�ނ͖��̒��ł��q�ɐe���̏�������Ă���̂��B�Ƃ��낪�A���̐e���������q���n�����Ƃ��������̎咣���B�����̂ł���A���ݓ��e���c��(�U��)���ꂽ���̂Ȃ̂ł���B�ŏ��ɔn�����������Ǝv�����̂��A���̕s�����Ȏ����̎咣�ɒ��ʂ������Ȃ������̂��ƌ����邾�낤�B �����܂ł̍l�@����A���̌`���ɂ�2�̐S�I�͂��ւ���Ă��邱�Ƃ��킩��B��]���`������͂ƁA���̊�]�Ɍ��{�������A���̕\����c�Ȃ���͂ł���B���̌��⏊�̌��{�����́A�ӎ��ւ̓���������邩�ǂ����Ƃ����_�ɂ���A�D�s���ɕύX(�c��)������łȂ���A���⏊�̒ʉ߂��������Ƃ͂Ȃ��B�����炱���A��ɓ��e�͉��y���e�̋U���Ƃ��Ė��̕���Ɍ����̂ł���A�����閲�̈Ӗ��͊�]�[���Ȃ̂ł���B(�����l���Ă݂�ƁA�u�ӎ�����v�Ƃ́A�u�\�ۂ���v�ߒ��Ƃ͕ʎ�́A�u�\�ۂ���v�ߒ�����͓Ɨ������Ɠ��̐S�I�s�ׂł���悤�Ɏv����B�ӎ��͕ʂ̂Ƃ��납��^����ꂽ���e��m�o����A��̊��o�튯�̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂�������Ȃ��B) ���t���C�g�̊��҂̖� ���̕w�l���҂̖��́A�l��[�тɏ��҂��悤�Ǝv�������A�O���̍�����������ق��͉��̒������Ȃ������̂Œf�O�����A�Ƃ������̂ł���B�������ɍs�����Ǝv�������A���j�̌ߌ�Ȃ̂œX�͕܂��Ă��邵�A�o�O���d�b�̌̏�łł��Ȃ������̂��B���͂̌��ʁA���̖��̑O���A���҂͏��F�B��K�₵�Ă������ƁA�ޏ��́u���܂��[���тɂ��ʼn�����H�v�u�����Ɣ�肽���v�ƌ����Ă������Ƃ��킩�����B���̏����̂��Ƃ�v�͗_�߂��₵�Ă������A�ޏ��͑����Ă���A�v�͖L���ȏ������D�݂ł���B�t���C�g�͂��̖����A�[�т����y���������Ȃ���]�̏[�����Ƃ����B�[�т����y������A���F�B�̐g�̂͂ӂ�����Ƃ��A�v�̍D�݂̏����ɂȂ��Ă��܂����炾�B���������̊�]�́A�[�тɏ��҂����������̂ɂł��Ȃ������A�Ƃ����悤�Șb�ɘc�Ȃ���Ă���B�܂��A���҂͏��F�B�̑���Ɏ������g�ɓo�ꂳ���A�����̊肢���[������Ȃ��������Ă��邱�ƂɂȂ�̂ŁA����͏��F�B�ւ̓��ꉻ�������Ă���ƍl������B���ꉻ�̓q�X�e���[�I�v�l�ɂ����̂ł���A���҂͎��������F�B�̈ʒu�ɒu�����ƂŁA�v�ɗ_�߂��₳�ꂽ���Ɗ���Ă���̂ł���B �t���C�g�͗l�X�Ȋ��҂���u�����̖��͊�]�[���ł͂Ȃ��v�Ƃ������_���Ă��邪�A�ނ͂�������Ƃ��Ƃ���]�[���̖��Ƃ��ĕ��͂��Ă݂���B�Ⴆ�A�t���C�g�̌����Ă��邱�Ƃ��Ԉ���Ă��Ăق����A�Ƃ�����]�̏[�����������҂�����B�q�ǂ��̎���߂��ޖ����݂����҂ɑ��ẮA������l��(������)��邩�炾�ƕ��͂��Ă���B�u��]�ɔ����閲�v�̑����́A�t���C�g(���͈�)�̌������Ƃ��Ԉ���Ă��邱�Ƃ��肤�悤�Ȋ�]���A�}�]�L�Y���I�v�f(�U���I�E�T�f�B�Y���I�v�f���]����������)�ɂ���]�̂����ꂩ�ł���B��҂̓}�]�L�Y���I��]���u�s���Ȗ��v�ɂ���ď[�����悤�Ƃ�����̂��B������ɂ���A�����傫���c�Ȃ���Ă���̂́A���̖��̊�]�ɑ��錙���E�}���Ӑ}�����݂��邩��ł���A�u���́A����(�}������E�r�˂��ꂽ)��]�́A(�U������)�[���ł���B�v�@ |
|
|
�����̍ޗ��Ɩ��̌���
���`�@���̒��ɏo�Ă���ŋ߂̂��̂ƍ��ׂȂ��� �ǂ�Ȗ��̒��ɂ��A�O���̏��̌��ւ̌��т��������������B��A�O���O�̈�ۂ��o�Ă��邱�Ƃ����邪�A�O���ɂ��̈�ۂ��v���o���Ă��邱�Ƃ��قƂ�ǂŁA��ӂ��o���Ă��Ȃ��悤�ȏ��̌��������̍ޗ��̒��S�ƂȂ�̂��B�������A�O���̏��̌��������Ɖ����ߋ��̏��̌��Ɍ��т��Ă������ł́A���̍ޗ���l���̂����Ȃ鎞��������I�ю���Ă��邱�Ƃ��ł���B�܂��A���Ɋւ��鏔��ۂ̑��̂��̂́A�ǂ��ł������悤�ȁA�t���I�Ȏ���ł���A�������ׂȂ��̂����̍ޗ��ƂȂ�̂ł���B���̏d��Ȃ��̂��獱�ׂȂ��̂ւ̐S�I�A�N�Z���g�́u�ړ��v�́A���̌��{�ɂ���Ċ�]���B���悤�ɘc�Ȃ��ꂽ���Ƃɂ����̂��B�����炱���A�����ďd�v�ł͂Ȃ����̌��̎c�悪���Ɏg����̂ł���B�܂��A���̍�Ƃɂ́A���݂��閲�̎h������̂ւƂ܂Ƃߏグ��A���̋����͂�����B�O���̓�̈قȂ����̌����A���̒��ł͈�̂��̂ɂȂ�̂ł���(���k)�B �����Ŗ������F���������X�̏���������ƁA1)���̒��֒��ڏo�Ă���ŋ߂̏d�v�ȑ̌�(�C���}�̒��˂̖��A�����C���Ɋւ�閲)�A2)���ɂ���ĂЂƂ̓���̂Ɍ�������鐔�����̍ŋ߂̏d�v�ȑ̌��A3)�����e���ɍ��ׂł��邪�����������̌���ʂ��ĕ\��������Ȃ����͂���ȏ�̍ŋ߂̏d�v�ȑ̌��A4)���̒��ŕK������ŋ߂́A���������ׂȈ�ۂɂ���đ㗝�������I�ȏd�v�ȑ̌��A��4�ɕ����邱�Ƃ��ł���B�܂��A�����Ȃ閳�Ӗ��Ȗ��h�������Ȃ��A���C�Ȗ����Ȃ��B���C�Ȗ��̒��ɂ́A���I�v�f�����{�ɂ���Ęc�Ȃ���A���ׂȂ��̂Ɉړ�(�U��)���Ă�����̂������B�����͍����̂��߂ɐ����̎ז��͐�����Ȃ����̂Ȃ̂ł���B ���a�@���̌���Ƃ��Ă̗c���I�Ȃ��� ���ݏo������]���̂́A�c�N����ɗR�����邱�Ƃ������B�Ⴆ�ΐ�ɋ������u�����C���Ɋւ�閲�v�Ȃǂ��A�c�N����(�̂��l���ɂȂ�Ǝ��͂��猾���Ă���)�̗~�]�Ɍq�����Ă���̂ł���B���Ƃ����݂̊�]�ł����Ă��A�����c���̎v���o���狭�͂ȉ�����Ă��邱�Ƃ������B�ǂ�Ȗ��̌��ݓ��e�ɂ��A�����ŋߑ̌��������Ƃւ̌q����͂��邪�A����ɔ����Đ��ݓ��e�̒��ɂ́A���݂ɂ�����܂Łu�ŋ߂̂��́v�Ƃ��ĕۑ�����Ă����悤�ȁA���ɌÂ��̌��ւ̌q���肪����B�������̊�]�[������̖��ɓ��ꂳ��Ă������łȂ��A��̈Ӗ��A��̊�]�[�������̂��̂��B�����Ă��āA���̈߂��͂��ł����ƁA��ԉ��̂Ƃ���Ŕ��ɑ����c������̊�]�̏[�������ɂԂ��邱�Ƃ����ɑ����B����́u�K���v�ƌ���������������������Ȃ��B ���b�@�g�̓I������ �g�̓I�h�����ɂ́A1)�O���̏��Ώۂ���o�Ă���q�ϓI���o�h���A2)��̓I�ɂ̂݊�b�Â�����Ƃ���̊��o�튯�̓��I������ԁA3)�g�̓������甭����g�̎h����3��ނ�����B����炪���ɉe����^���邱�Ƃ́A�����̊ώ@�A�����ɂ���Ċm���߂��Ă���B�������A���̂悤�ȊO�I�h����(�����I�h����)�����Ŗ����\�����������킯�ł͂Ȃ��B�����������铮�@���g�̓I�h�����ȊO�̂Ƃ���ɂȂ���A���`���Ƃ������Ƃ͂��蓾�Ȃ��̂ł���B���łɏq�ׂ��悤�ɁA���͍ŋ߂̍ޗ��Ɨc�����̍ޗ����D�ނ̂����A�����ɐ������ɂ�����V���������ޗ�(�g�̓I�h��)�������ƁA������ꏏ�ɂȂ��Ė��`����(���ׂȈ�ۂƂ���)�ޗ������B���ɐg�̓I�h����������W�Q���A���𒆒f�����邱�ƂɂȂ肻���ȏꍇ�́A���̍ޗ��ɂ��肰�Ȃ��D�荞�ނ��ƂŁA�����𑱂��邱�Ƃ��\�ɂ��Ă���B�ڊo�܂����v���苿���Ă��A���̉������̒��ŃT�C�����ɋU������Ă���A�����𑱂��邱�Ƃ��ł���B���葱�������Ƃ�����]�͂˂ɖ��`���̓��@�ƂȂ�̂ł���A�������邱�Ǝ��̂����̊�]�̏[���ƂȂ�̂ł���B ���c�@�ތ^�I�Ȗ� �N�ɂł������悤�Ɍ���Ă��閲�́A����̌���o�Ă���Ɛ����ł��邽�߁A���̌���������������̂ɓs�����悢�B��������������Ă݂悤�B ����)���ō��f���閲 ���l�̑O�ŗ���������A���l�ȕ����ł����肷�閲�ŁA㵒p�ƍ��f���o���A���̏ꂩ�瓦���o�������Ƃ��ł��Ȃ��B�������A���͂͂���ɑ��Ė��S�ł���A�Ƃ������ł���B�c������́A���͏������p�����������̂ł͂Ȃ��������A�����p����������K�v�̂Ȃ��p���_�C�X�ł������B���̖��͂��̃p���_�C�X�ւƘA��߂����ƂŁA��]�[�����Ӑ}���Ă���B�������A�I�o��ʂ͑��̐S�I�g�D�ɂ���ċ��ۂ���Ă��邽�߁A���̕\�ۂ�㵒p�ƍ��f��������̂ł���B���{�̗v���ɏ]���A���̘I�o�͒��f���ׂ����̂Ȃ̂��B�Ȃ��A�����I�o�̖��ł��A���f��㵒p�������Ȃ��ꍇ�͗ތ^���ł͂Ȃ��B ����)�ߐe�҂����ʖ� ����͖��̒��Ŕ߂��݂�������ꍇ�Ɗ����Ȃ��ꍇ������̂����A��҂͗ތ^���Ƃ͌�����B���̂Ȃ�A���̎��ɂ���Ĉ��l�ƍĉ�ł����Ƃ����悤�Ȗ��́A���̎�����]����Ƃ���]���Ȃ��Ƃ��́A�����Ȗ��ł��邩�炾�B���̂��Ƃ���A���̒��̊���͐��ݓ��e�ɑ�������̂ł���A�\�ۓ��e�̂悤�ɂ͘c�Ȃ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��킩��B����Ƃ͋t�ɁA�ތ^���Ƃ��Ă̋ߐe�҂̎��͋�ɂɖ����Ă���A�������ߐe�҂̎�����]���Ă�����̂ł���B�ܘ_�A�����������_�ł��̐l�̎�������Ă��邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��B�����́A�c������̂��鎞���ɕ�������]�Ȃ̂ł���B �q�ǂ��͗��ȓI�ł���A�������ł������̗~���������悤�Ƃ���B����킪���܂��A�e�̈���������痣��Ă��܂��̂ŁA���̐��ɂ��Ȃ�������Ɗ����邾�낤�B�������A�q�ǂ����y�X�����u���Ⴆ�v�ƌ������Ƃ��Ă��A���̎q�͂܂����̔ߎS�⋰�|�ɂ��Ă͉����m��Ȃ��̂��B�q�ǂ��ɂƂ��āu���v�Ƃ������Ƃ́A�u�s���Ă��܂����v�Ƃ������炢�̈Ӗ��Ȃ̂ł���B�܂��A�e�̏ꍇ�͎����Ɠ����̐e�����ʖ�������B����́A�j�̎q�͕�e�ɁA���̎q�͕��e�ɍŏ��̈���������A�����̐e�������̗��w�ƌ��Ȃ����߂ł���B����ɂ͕��e����������������A��e�����q�ɉ��S����Ƃ������悤�ȁA�e�̑ԓx�ɂ��Ƃ��낪�傫���B�q�ǂ��͎������������Ă���Ȃ����̐e�ɔ��R����̂ł���B(���̌������x������悤�ȓ`���Ƃ��āA�G�f�B�v�X���`���ƃ\�|�N���X�̓����̌�������B�܂��A�V�F�C�N�X�s�A�́u�n�����b�g�v�́A���̖S�삪�����������E�����Ȃ��Ȃ����s���Ȃ��B����́A�n�����b�g�̗c������̊�]�������Ɠ����ł��邽�߁A���̍߈������甌���E���𐋍s�ł��Ȃ��̂��B)�ߐe�҂����ʖ��́A���̓r�����Ȃ���]�䂦�Ɍ��{��Ƃ�A�c�Ȃ��ꂸ�Ɍ����B�����炱����ɂ��Ƃ��Ȃ��Ă���̂ł���B ����)�����̖� ���̗ތ^���́A�����ɗ��悵�āA������x�J��Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ł���B�����ɗ��悷�閲�́A�c�N����ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ����Ď����ւ́A�������肪�����L�������ƂɂȂ��Ă���B���̋L�����A���i�Ȏ����̓��ɂ����āA�S�̒��ɖ߂��Ă���̂ł���B�@ |
|
|
�����̍��
�{�͂̉ۑ�́A���v�z(���ݓ��e)�������Ȃ�ߒ���ʂ��Ė����e(���ݓ��e)�ւƕς���Ă����̂��A�����T�����邱�Ƃɂ���B���ݓ��e�͈��̏ی`�����ŒԂ��Ă��āA���̈�����ݓ��e�̌��t�ɖ|�Ă݂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̏ی`�������L���W�ɏ]���ēǂ����Ƃ����ɁA���̌`�ۉ��l�ɏ]���ēǂ�ł��܂��A�K�����H�ɓ��ݍ��ނ��ƂɂȂ�̂ł���B ���`�@���k�̍�� ���̈��k��ƂƂ́A���v�z�ɂ����镡���̐l���╨�̗v�f�������I������A�����l���⍬�����ȂǁA�V���ȓ���I�`�ۂ����グ�邱�Ƃł���B�Ⴆ�u�C���}�̒��˂̖��v�ɂ����ẮA�C���}�̓t���C�g�̖���ȁA���ł̂��߂Ɏ���ł��܂����������ҁA�����{�Ï��̎q�ǂ����A�����̐l���̓�������������A��̑����l�������グ���Ă���B�܂��A���k��Ƃ�������D�̍ޗ��Ƃ��āA���ɂ����錾��`����(������)������B���̍�Ƃ����k���悤�Ƃ���ΏۂɌ��t�Ɩ��̂Ƃ�I�ї^���鎞�A���m�ȁA�����Ċ�ȑ��ꂪ�����̂��B�Ⴆ�A���鏗�����҂̖��ɂ�����uMaistollmutz�v(�}�C�X�g���~���b�c)�Ƃ����Ԃ莚�́AMais(��冋o)�Atoll(���s�C����)�Amanstoll(�j������)�AOlmutz(�I���~���b�c���n��)�Ȃǂ����k���ꂽ���̂ł���B�܂��A������������̕ϑ��́A�ϑz�ǂ�q�X�e���[�ǁA�����ϔO�ɂ�������B ���@�ӎ��ɂ����錾��͕��\�ۂƌ�\�ۂ̓����Ȃ�̂����A���ӎ��ł͕��\�ۂ����Ȃ����߁A���ł͌ꂪ���̂悤�Ɍ���āA���k���ꂽ�蕪�����ꂽ�肷��B ���a�@�ړ��̍�� ���v�z�̒��ŋ����S�̂������v�f�́A���l�x�̒Ⴉ�����ʂ̗v�f�ɕϊ�����Ė����e�Ɍ���A�܂�ʼn��l�Ȃ��v�f�̂��Ƃ���舵���邱�Ƃ�����B���̍�Ƃɓ����Ă���S�I�ȗ͂́A����ł͐S�I�ɉ��l�̍������v�f����G�l���M�[�D���A�����ł͑��ʓI����(�����ʂɌq�����Ă��邱��)�̓r��ʂ��āA���l�x�̒Ⴂ���v�f�����l����v�f�ɍ��ς��A���̐V�������v�f�������e�ɓ����Ă���̂��B���̂悤�ɁA���`���ɂ����Ă͌X�̐S�I���x�̓]�ڂ���шړ�(�u������)���s����B ���b�@���̕\����i�̂��낢�� ���́A�X�̖��v�z�̊Ԃɂ���_���I���W��\�����ׂ���i���������킹�Ă��Ȃ��B�u�������v�u�c�c���䂦�Ɂv�u���傤�ǁc�c�̂悤�Ɂv�u�Ƃ����ǂ��v�u�c�c���A���邢�́c�c���v�Ƃ������悤�ȑO�u���́A���̒��ł͖�������A��̓I�ȓ��e���������H�����̂ł���B���������āA���̍�Ƃ��ł��������̊֘A������̂́A�����f�̎�Ɉς˂��邱�ƂɂȂ�B���̊O����̎v�l�ɂ���ĕ\������Ă�����̂́A���v�z�̍ޗ��̑����Ȃ̂ł����āA���v�z�Ԃ̊W�A���ɂ�����m�I��Ƃ̕\���ł͂Ȃ��̂��B�������A���̘_���I�ȑg���Ă��ł��邾���Î����悤�Ɠw�߂閲������B�ȉ��A���̗�������悤�B 1�D���̒��œ�̂��̂��ߐڂ��ďo�Ă���ꍇ�́A���v�z�ɂ�����ٖ��Ȋ֘A�������Ă���B2�D�Z�����`�ƒ������a�ɕ������Ă���A�u�`�ł��邩��A�a�ł���v�Ƃ����悤�ɁA���҂̈��ʊW���Ӗ����邱�Ƃ�����B3�D�u�c�c���c�c���v�Ƃ�����ґ���̕\���͖��ɂ͂Ȃ��B���̘b���肪�u�납�������ǂ������ł����v�ƌ����ꍇ�A����́u��ƕ����v�Ƃ����A�P�Ȃ����ƌ���ׂ��ł���B4�D���Ɂu�ہv�͑��݂��Ȃ��̂ŁA���̔��Ε��ɂ���Ă����\������Ȃ��B5�D���͗ގ����A���v�A�u���傤�ǁc�c�̂悤�Ɂv�Ȃǂ̘_���I���W�ɂ��ẮA���łɂ��閲�ޗ��ɓ��ꉻ���邩�A�V���ȓ���ւƍ��������邱�Ƃɂ���Č����ɕ\������B�u�`�́c�c�����A�a���c�c���v�Ƃ����ꍇ�A�a�̂悤�ȍs�����Ƃ�`���o�Ă�����A�`�Ƃa�����킹�������l�����o�Ă���B6�D���̌`���́A�����ΉB�����ꂽ���e�\���̂��߂ɗ��p�����B�Ⴆ�Ζ��ɕs���Ăȉӏ�(���@)������A���q����(�y�j�X�̌��@)���Ӗ����铙�B �� ���ɂ����ẮA�v�l�`���͕��̂悤�Ɍ`�ۉ����A�v�l�ΏۂƂȂ�B�Ⴆ�A�u2�{2��4�v�ɂ�����u�{�v��u���v�̂悤�Ȍ`�����A���ɂ����Ắu2�{�{��4�v�̂悤�Ɂu2�v��u4�v�̂悤�ȗv�f�Ƃ��Č����B���ӎ��ɂ͎v�l�`���Ǝv�l�Ώۂ̏s�ʂ͂Ȃ��̂ł���B ���c�@�\���\���ւ̌ڗ� ���v�z�̕��Œ��ۓI�ȕ\���́A�����e�ɂ����Ă͌`�ۓI�ŋ�ۓI�ȕ\���ƒu����������B���̍ޗ��ɂ͎��o�I�`�ۂ��D��I�ɍ̂�グ���A����ɂ���Ė��̗l�X�ȕ\�����\�ɂȂ��Ă���̂ł���B ���d�@���ɂ�����ے��I�\�� / ���E�ތ^�� ���͗l�X�ȏے����U���I�\���ɂ������ė��p����̂����A�����̏ے��̒��ɂ͕K���Ƃ����Ă����قǓ���̈Ӗ���L������̂�����B�����Ƃ���������͒j������A������e��ނ͏��́A�K�i�ł̏��~�͐��s�ׁA���X�B�����͓��ɗތ^���̕��͂ɂ͗L���ł���B�ތ^���́A�u���̎h���̖��v(����~�]�������Ă���)�̂悤�ɂ��������Ӗ��������̂ƁA��s������ė����閲�̂悤�ɁA���e������ł��S�R�Ӗ����Ⴄ���̂�2�ɕ�������B�������A�ے��̈Ӌ`���ߑ�Ɍ��ς���ׂ��ł͂Ȃ��A���������{�l�̎��R�A�z�ɂ�������I�ȈӋ`������B ���e�@���� / ���ɂ�����v�Z�Ɖ�b ���̍�Ƃ͌v�Z�Ȃǂ��Ȃ��B���Ɍv�Z�����ʂ��o�Ă��Ă��A����͕\���ł��Ȃ��ޗ��ւ̈Î��ƂȂ鐔������ׂĂ���ɂ����Ȃ��̂��B�܂��A���͕�����b��V���ɑn��������͂��Ȃ��B�̒ʂ�����b�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���ۂ̉�b�⏬���ɂ͂�����̐�[�v�z�̒�����ؗp���A�{���̕����Ƃ͖��W�Ȍ`�ɑg�ݍ��킹����A���ܐ�ɂ��Ă��邾���ł���B ���f�@�r�����m�Ȗ� / ���ɂ�����m�I�Ɛ� �����e�̍r�����m���͕\�ʂ����̂��̂ɂ����Ȃ��B����́A��]�ƚ}���������Ă���{�l�̖��ӎ��@�Â��Ă���ꍇ�A�u���������Ƃ��A���Ӗ����v�Ƃ����ᔻ���A���̍r�����m���Ƃ��Č���Ă��邾���Ȃ̂��B����A�����e�ɂ�����ᔻ�̂悤�Ȋ����́A����Ƃ̎v�l�����ł͂Ȃ��A���v�z�̍ޗ��ɑ����Ă���B����͖��v�z�ɂ�����ᔻ�̌J��Ԃ��ł���A���ꂪ�d�グ�̍ς`�����Ƃ��Ė����e�ɓ����Ă���̂ł���B�܂��A�ЂƂ��o����ɖ��ɉ����ᔻ�A���̍Č����ĂыN����������Ȃǂ́A���̑啔�������ݖ��ɑ����Ă���B ���g�@���̒��̏ ��͕\�ۂƂ̌����ɂ����Ă̂ݍl������̂����A���ɂ����ẮA�댯�ȕ\�ۂł����Ă��S���|���Ȃ�������A���ׂȂ��ƂɌ��{���Ă���ꍇ������B���̂悤�ɁA���ɂ����ď�ƕ\�ۂ��K�����Ȃ��̂́A��̕��͌��̂܂܂ł���̂ɁA�\�ۓ��e�̕������͈ړ��Ƒ㗝�Ƃ�������Ƃ��Ă��邩��ł���B��͌��{�̍�p�ɋ������Ȃ����߁A�\�یQ���痣�E���Ė����e�Ɍ����B�������A����S�������{�̉e�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�}�����ꂽ��A���Ε��ɕς����邱�Ƃ�����B�܂��A���̒��̏���P��̌���ɂ����̂Ƃ͌��炸�A�����̏������Ƃɂ����ē���̏���`�����Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B(���̏�ƕ\�ۂ̊W�́A�������_�o�ǂɂ����Ă͂����茻���B�q�X�e���[���҂⋭���_�o�NJ��҂́A���ׂȂ��Ƃ�|��������A���Ȕ��̂��������ɂ��Ă��܂��A����Ȏ������g��s�R�Ɏv�����̂��B�_�o�ǎ҂ɂ������͂˂ɖ{���Ȃ̂ł���A���_���͂͂��̏�ɒނ荇���Ă����͂��́A�}�����ꂽ�\�ۂ�T�����߂�̂ł���B) ���h�@����H ���̌��⏊�͖����e�𐧌�������폜�����肷�邾���ł͂Ȃ��A�����e�ɐV�������̂�Y�����A�s�����Ŏx���ŗ�Ȃ��̂��̒ʂ����̌��ɉ��H����@�\������B���̂��߁A���͂��̉��H���ꂽ�ؗ��ĂɈӖ�������悤�Ɍ�����̂����A����͎��ۂ̖��̈Ӗ�����Ђǂ���������Ă���B���̖����`�������l�̌_�@�����H�Ƃ����B �� �ȏ�A����܂ł̖����`������_�@��4�ɂ܂Ƃ߂�ƁA1�D���{�̖ڂ�悤�Ƃ���v��(�ړ�)�A2�D�S�I�ޗ��̈��k�A3�D���o�I�`�ۂɂ��\���\���ւ̌ڗ��A4�D�����I�O�ςւ̌ڗ�(����H)�A�ƂȂ�B�@ |
|
|
�������ۂ̐S���w
���`�@����Y���Ƃ������� ���̖Y�p�͂��̑啔������R�̎d�Ƃł���B���������āA�����͂ɍۂ��ĖY���ꂽ���̉ӏ��͋U��(�����)�̐������Ȃ������ӏ��ł���A���ꂪ�ˑR�v���o���ꂽ�ꍇ�A���ꂱ�������̍ł��d�v�ȕ������ƍl���Ă悢�B(�������A���ɂ͂ǂ����Ă������Ȃ����ы�(�����`)������A����ɂ��Ă͕��u���Ă�������Ȃ�)�B��R�͓����������Ă��邪�A��̊Ԃ͂��̗͂̈ꕔ�������Ă���A���̂��Ƃ����̌`�����\�ɂ��Ă���B������Ԃ͌��{�̈З͂����ނ����邱�ƂŖ��`�����\�ɂ��Ă���̂ł���B�����f�͖ڕW�̂Ȃ��\�ۂɐg���ς˂Ă���Ƃ����ᔻ�����邪�A���ӎ��̖ڕW�\�ۂ����\�ۂ̗�������肵�Ă���̂ł���A�ڕW�\�ۂ̂Ȃ��v�l�Ƃ������̂͂Ȃ��B�ӎ��I�ȖڕW�\�ۂ͒�R�̎x�z���ɂ���̂����A��R����܂�Η}������Ă����ڕW�\�ۂ֓�����A�ꌩ�s�����ɂ��v����悤�ȘA�z�Ɍ��т��̂ł���B ���a�@�ލs �S�Ƃ������u����̑g���ē���(��������ʐ^�@�̂悤�Ȃ���)�Ƃ��čl����ƁA���ꂼ��̉f��(�\��)���ǂ̂悤�ɂ��Đ��藧���Ă���̂����l���邱�Ƃ��ł���B�܂��A�S�I���������炩�̎h�����甭���Ĕ����֎�����̂��Ƃ���A��1�}(442��)�̂悤�ɁA�S�I�ߒ��͒m�o�����g�D(�m�o���[)����g�̓I�������N�����g�D(�^�����[)�ւƌo�߂���B���̍ہA���m�o���S�̒��ɍ���(�L������)���c�����Ƃ́A�A�z�������邱�Ƃ�������炩�ł���B���Ƃ���A�L���͂������Ȃ��m�o���[�̔w��ɂ́A�L������g�D�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B�������A����̋���(�m�o�h��)���l�X�Ȓ蒅�����Ă���ƍl������̂ŁA�L���g�D�͕�������̂��Ɖ���ł���(��2�}�F443��)�B�܂��A�L�����l�X�Ȓ�R���Ȃ���^�����[�ɒB����̂��Ƃ���A�^�����[�̒��O�ɂ͔ᔻ��������g�D(���⏊)������̂��Ƒz��ł���(�O�ӎ�)�B�����āA�O�ӎ��̔w��ɂ́A�O�ӎ���ʉ߂���ȊO�Ɉӎ��ɒʂ���r�������Ȃ��g�D(���ӎ�)������(��3�}�F445��)�B ���̐S�I���u�Ŗ����l����ƁA�����͊o�����̂悤�ɉ^�����[�̕��ֈړ�����̂ł͂Ȃ��A�t�ɒm�o���[�̕��ֈړ�����̂��ƍl������B����͕��G�ȕ\��(�ϔO)����A���ꂪ���ďo�Ă����Ƃ���̊����I�`�ۂt�߂肵�Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B�����͒m�o���[����^���͂������ė���钪�����A��Ԃ͒�R�̗͂���܂�A�ӎ��ւƋt������̂ł���B�O�ӎ��ɂ����閲�v�z�̍\���͉�̂��A���v�z�͌��̑f�ނɊ҂��Ă��܂��B���͑ލs�I���i�����̂ł���B����́A�����c������ʂ̑�p���ł����邱�Ƃ����������B�܂��A�q�X�e���[��ϑz�ǂ̌��o�A����l�̌��e�Ȃǂ��ލs�ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B ���b�@��]�[���ɂ��� �v�l�����ɂ���ďՓ��𐧌䂷��悤�ɂȂ�ƁA�q�ǂ��Ɍ�����悤�ȋ���Ȋ�]�̌`���͒f�O�����B���̂��߁A����̈ӎ��I��]�͓����e�̖��ӎ��I��]�ɂ���ċ�������Ȃ���A�������o�������̏\���ȗ͂������Ȃ��B���̖��ӎ��I��]�Ƃ́A���{���܂����݂��Ȃ��������̗c������]�Ȃ̂ł���B�������A�ӎ��I��]�����ӎ��I��]�ƍ��v���Ȃ��ꍇ������A�}������Ă������ӎ��I��]�̏[���ɑ��āA����͋�ɂȊϔO�ɓo�ꂳ���Ē�R���悤�Ƃ���B���ꂪ�s������Y�����ł���B����́A����Ӗ��Ŏ���̊�]�[��(������])�������Ă���B���������āA���̊�]�́A�u�ӎ��v�u���ӎ��v�Ƃ����Η����A�u����v�u�}�����v�Ƃ����Η��ɂ���čl���������킩��₷���B(����́A��ɏ�ʎ���̋c�_�Ɍq�����Ă���)�B�q�X�e���[�ǂ̏Ǐ�����Ɠ����ŁA��̑Η��I��]�[������̕\���ɂ����ďo��ꍇ�ɂ̂ݐ����Ă���B ���Ƃ��Ɛl�Ԃ̐S�́A�ŏ��͂ł��邾�������h���ȏ�Ԃɒu�����Ƃ�����̂������ɈႢ�Ȃ��B�����炱���A�O������̎h���E�������ɉ^���Ƃ��ĕ��o����Ƃ����A��̐}�����̗p�����̂��B�����A���I�~���ɔ����鋻��(�Ⴆ�ΐH�~)�́A�P�Ɏ葫���o�^�o�^����Ή����ł�����̂ł͂Ȃ��B���̂��߁A���̊�]����x���������A���̋���(�~��)��������x�ɁA������������悤�Ƃ������n�I�v�l�����̎��̒m�o�̋L�������ĂыN�������ƂɂȂ�̂��B�������A���̒m�o�̍Đ��͖����������炳�Ȃ����߁A��荇�ړI�I�Ȏv�l�������n�܂�A�����̗}�����\�ɂ��Ă������̂ł��낤�B���͌��n�I�v�l�ւ̑ލs�ł���A�c�����ɗR�����閳�ӎ��I��]�̏[���A���̊�]�Ɍ��������L�����̍Đ�(�m�o�̍ďo��)��ڎw���Ă���̂ł���B ���c�@���ɂ��o�� / ���̋@�\ / �s�����|�� ���ߒ��͂܂����ӎ��̊�]�[���Ƃ��ċ��e����邪�A�O�ӎ��͂��̊�]�����ۂ��}������B�܂�A��������l�ɂƂ��Ă��̊�]�͋C�ɓ���Ȃ��̂ł���A�����炱���A����̊�]�͖��ɕs���Ƃ����`���Ō����̂ł���B ���d�@��ꎟ����ё�ߒ� / �}�� �����̎��R�ȗ��o��ڎw���S�I�ߒ����ꎟ�ߒ��A���̑�ꎟ�ߒ��̕\�ۂɂ���ĕs���������ȏꍇ�A�����j�~������}������ߒ����ߒ��Ƃ���B��ꎟ�ߒ��͒m�o���ꐫ�����o�����߂ɋ������o�֓w�͂��A��ߒ��͂��̈Ӑ}��������A���̑���Ɏv�l���ꐫ���l�����悤�Ƃ���̂��B�ŏ�����^�����Ă����ꎟ�ߒ��ɑ��A��ߒ��͏��X�Ɍ`������A�₪�ėc�����̊�]�Ƃ͖�������悤�ȖڕW�\�ۂ���邱�Ƃ������B���̏ꍇ�A�c�����̊�]�[���͕s�����邱�ƂɂȂ邽�߁A�u�}���v����邱�ƂɂȂ�B ���e�@���ӎ��ƈӎ� / ���� �N�w�҂͖��ӎ����ӎ��I�Ȃ��̂̑Η����Ƃ����Ӗ��ŗp���Ă��邪�A�S���w�I�ȈӖ��ł́A���ӎ��͈ӎ�������Ȃ����ӎ��ƁA�ӎ����ł��閳�ӎ�(�O�ӎ�)�̓�ɂ킯�邱�Ƃ��ł���B���ӎ��I�Ȃ���̂́A�O�E�̌����Ɠ����悤�ɖ��m�Ȃ��̂ł���A�O�E�����o�튯�̕ɂ���Ă͕s���S�ɂ����������Ȃ��悤�ɁA�ӎ��̃f�[�^�ɂ���Ă͕s���S�ɂ����������Ȃ��悤�ȁA�{���A�����I�ȐS�I�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B�@ �@ |
|
| ���t���C�g4 �u����ƃG�X�v | |
|
���ӎ��Ɩ��ӎ��I�Ȃ���
���_���͂ł́A�S�I�Ȃ��̂��ӎ��I�Ȃ��̂Ɩ��ӎ��I�Ȃ��̂ɕ�����B�Ⴆ�A����Ƃ��Ɉӎ����ꂽ�\�ۂ́A���̏u�Ԃɂ͏�����̂����A����͍Ăшӎ����ꂤ��B����͂��̕\�ۂ����݂��Ă���(���ӎ�������)�Ƃ������Ƃł���A���̐��ݓI�ȕ\�ۂ͈ӎ�����Ȃ��܂܁A���_�����ɂƂ��ĉe����^���邱�Ƃ��ł���B�ӎ�����Ȃ��̂͂����̗͂�����ɔ����邩��ł���A���̈ӎ�����Ȃ���Ԃ�}���Ƃ����A�}�����N�����Ă�����x�����Ă���͂��A���_���͂ł́u��R�Ƃ��Ċ�����v�Ǝ咣����B�}�����ꂽ���̂́A���ӎ��I�Ȃ��̂̌��^�ł���A���ӎ��̊T�O�͗}�����_���瓾��ꂽ���̂Ȃ̂��B �������A�u���ݓI�ł͂��邪�ӎ����ꂤ����́v������A�L�q�I�ȈӖ��ł͖��ӎ��͓��ނ��邱�ƂɂȂ�B������(�L�q��̍���������邽�߂�)�A�͓��I�ȈӖ��ł͂����O�ӎ��I�Ɩ��Â��邱�Ƃɂ��A���ӎ��I�Ƃ������O�́u�}������Ĉӎ�����Ȃ����́v�ɂ����邱�Ƃɂ���B����ŁA�ӎ�Bw�A�O�ӎ�Vbw�A���ӎ�Ubw��3�̏p�ꂪ���������ƂɂȂ�B���̋�ʂ͔��ɗL���Ȃ��̂ł��邪�A����Ɍ�����i�߂Ă����ƕs�\���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ�B �����͌l�̐��_�ߒ��̖��������̐�������Ɩ��Â������A����͐��_�̖@��ł���A���_�̂����镔���ߒ��̒��߂��s�Ȃ��A��̊Ԃł������̌��{�𑱂��Ă���B���_�̂���X���͎���ɂ���ė}������A�ӎ�����ߏo�����̂ł���A���_���͂ɂ����Ă��A�A�z���}�����ꂽ���̋߂Â��ƁA����̒�R�ɂ���ĘA�z�͒���Ă��܂��B�������A���҂͒�R�ɍ��E����Ă��邱�Ƃ�������Ȃ��B�܂�A����̒��ɂ͈ӎ�����Ȃ����̂�����̂ł���A�}�����ꂽ���̂Ɠ����悤�ɁA�ӎ����邱�ƂȂ��ɋ�����p�������̂��B���ǁA�_�o�ǂ͈ӎ��I�Ȃ��̂Ɩ��ӎ��I�Ȃ��̂̊����ł͂Ȃ��A�u�������鎩��v�Ɓu�������ꂽ�}�����ꂽ���́v�Ƃ̑Η����l���˂ΐ����ł��Ȃ��B������u�}�����ꂽ���́v�͖��ӎ��I�ł��邪�A���ӎ��I�Ȃ��̂͑S�Ă��}������Ă���̂ł͂Ȃ��A����̈ꕔ���܂����ӎ��I�Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
������ƃG�X
��������ӎ��I�ɂȂ낤�Ƃ�����̂́A�L���̍��Ղɂ���ĉ\�ɂȂ�B�L���̌n���m�o���ӎ��̌n�ɒ��ڌ��т��Ƃ���A�L���̎c�����������Ă�������̔����́A�m�o���ӎ��̌n�̗v�f�ւƗe�ՂɈ����p�����ƍl������B���̋L�����Ղ̔������m�o�v�f�������������łȂ��A���S�ɒm�o�v�f�Ɉڍs���Ă��܂��ƁA�m�o�Ƌ�ʂ����������o�ƂȂ�\��������̂��B�����āA�������ӎ������(�O�ӎ��I�ɂȂ�)�̂͌���\�ۂƂ̌����ɂ��̂ł���A����\�ۂ͕����ꂽ����̋L���́A���o�I�Ȏc�����Ȃ̂ł���B����A���o�I�ȋL���̎c�����́A�v�l�̋�̓I�ȑf�ނƂ��Ĉӎ�����Ă��A�v�l������Â���悤�ȑf�ފԂ̏��W�ɂ��ẮA���o�I�\����^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߁A����ɂ��v�l�������ӎ��I�ȉߒ��ɋ߂��ƌ�����B���_���͂ł́A�O�ӎ��I�Ȓ���҂����o�����ƂŁA�}�����ꂽ���̂��ӎ��I�ɂ���̂ł���B �� �t���C�g�́A�ӎ��͕��\�ۂƌ�\�ۂ̓����Ȃ邪�A���ӎ��͕��\�ۂ����Ȃ��Əq�ׂĂ���B�Ⴆ�Ζ��ɂ͑f�ނƂ��Ă̕��\�ۂ���������A�v�l�Ƃ��Ă̑f�ފԂ̊W�����o�I�ȕ\�ۂƂȂ��Č����B ���ƕs���̌n��̓����m�o�́A�O������R������m�o�����͂邩�ɍ����I�ł���B���̂悤�ɓ������璼�ړ`�B���銴�o�̏ꍇ�A���ӎ��I�\�ۂ�O�ӎ��ɂ����炷��������́A���ɕK�v�ł͂Ȃ��B���o�͈ӎ��I�����ӎ��I���̂ǂ��炩�ł���A���Ƃ����o������\�ۂƌ�������Ƃ��ł����A�ӎ��I�ƂȂ邽�߂ɂ͒��ڂ����Ȃ�̂ł���A�ӎ��ƑO�ӎ��̑���͈Ӗ��������Ȃ��̂��B ���̂悤�ɁA�O���Ɠ����̒m�o�ƒm�o���ӎ��̕\�ʑ̌n�̊W�����炩�ɂȂ�ƁA����̂��Ƃ���薾�炩�ƂȂ�B����͂��̊j�S�ł���m�o�̌n����R�����Ă���A�L���̎c�����Ɉˑ����Ă���O�ӎ����܂�ł��邪�A���ꎩ�g�͈ӎ�����Ȃ��B����A���䂪���̒��ő������鑼�̐S���I�Ȃ���(���ӎ��I�ɂӂ�܂�����)���A�O���f�b�N�ɂȂ���ăG�X�Ɩ��Â��悤�B����͒m�o���ӎ��̒���̂��ƂŁA�O�E�̉e���ɂ���ĕω�����G�X�̕����ł���A���̎��䂩��m�o�̌n���j�S�Ƃ��Ĕ��W����B����͒m�o�̌n���\�ʂ��`�����Ă��镔�ʂɌ��ǂ���Ă���A����ƃG�X�͉��̂ق��ō������Ă���B�������A�}�����ꂽ���̂��G�X�̈ꕔ�ł���A�}���̒�R�ɂ���Ď���Ƃ͕�����Ă��邪�A�G�X��ʂ��Ď���ƘA�����邱�Ƃ��ł���̂��B�����}�Ŏ�����(273��)�A�u���o�X�v������̏�Ɏ߂ɂ̂��Ă���悤�ɂȂ�B ����̓G�X�ɑ���O�E�̉e���ƃG�X�̈Ӑ}��L���ɔ���������悤�ɓw�͂��A���������̗���Ɍ����������������Ɠw�͂��Ă���B����͗������\���A��M���܂ރG�X�Ƃ����z�n�䂷��R��̂悤�Ȃ��̂��B�������A�M�S�ȏn����K�v�Ƃ���m�I��Ƃł��A�ӎ��ɂ̂ڂ炸�ɑO�ӎ��I�ɍs���邱�Ƃ�����B���ꂾ���łȂ��A���Ȕᔻ�ƗǐS�̂悤�ɁA����߂ĉ��l�̍������_�����ł������ӎ��ɍs���A�d�v�ȉe�����y�ڂ����Ƃ�����B����́A���͒��ɒ�R���ӎ�����Ȃ����Ƃ���������邵�A���̂悤�Ȗ��ӎ��I�߈��������_�o�ǂɌ���I�Ȗ����������Ă���̂��B����͈ӎ��I����ł���O�ɁA�g�̂̊��o�����˂��ꂽ�g�̎���Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
������ƒ�����(���䗝�z)
�������R���[(�T�a)�̋�Y�́A����ꂽ�Ώۂ�����̒��ɍČ����A�Ώ۔����ꎋ�ɂ���đ㏞����Ƃ������̂ł��邪�A���̂悤�ȑ㏞�͎���̌`���ɏd��ȍv�������Ă���B�����������O���ɂ����Ă͑Ώ۔����Ɠ��ꎋ�͋�ʂ���Ă��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���I�Ώۂ����Ă��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ��A���O���ւ̈��̑ލs��������A����̒��ɑΏۂ����邱�ƂŁA����͑Ώۂ����Ă邱�Ƃ��\�ɂȂ�̂ł��낤�B���̎�����Ƃ����ߒ��͏����̔��B�i�K�ł͂����N����̂ŁA����̐��i�͊��Ă�ꂽ�Ώ۔����̒��a�ł���A�ΏۑI���̗��j���܂�ł���̂ł���B �����ΏۑI��������ω��ɓ]���邱��(�Ώۂ̓����������̐��i�Ɏ�����邱��)�́A���䂪�G�X���x�z���A�G�X�Ƃ̊W��[�߂��̕��@�ł���B���䂪�Ώۂ̐����g�ɂ���Ƃ��A����̓G�X�ɑ��Ă�������������(���Ȃ�������悤�ɂ��ނ���)�̂��B���̂悤�ɁA�Ώۃ��r�h�[�����Ȉ����r�h�[�ɕς�邱�Ƃ́A���I�ڕW�̕����������炵�A���A���Ȃ킿���̏��������炷�B �� ����̑Ώۓ��ꎋ�������Ȃ�A�����Ȃ肷���ĕs���a�ɂȂ�ƁA�X�̓��ꎋ���݂��Ɋu�₵�A����̕�������\��������B���̋ɒ[�ȗႪ�A�X�̓��ꎋ����ւ��Ȃ���A�ӎ����̂��������Ƃ��A�����鑽�����l�i�ł��낤�B �c������ɋN���������ꎋ�̌��ʂ͉i���I�ł��邽�߁A���䗝�z�̔w��ɂ͍ŏ��̍ł��d�v�ȓ��ꎋ�A���ɕ��Ƃ̓��ꎋ����������Ă���B���̊W�ɂ́A�G�f�B�v�X�W�̎O�p�W�I�ȑf���ƁA�̗̂����I�f���̓���ւ���Ă���B�j���̏ꍇ�A�ŏ��͕�ɑ���ˑ��^�̑Ώ۔������͂��܂����A���ꎋ�ɂ���ĕ����킪���̂ɂ���B�������A��ւ̐��I��]�������Ȃ�ƁA�������̊�]�̖W�Q�҂ł��邱�Ƃ�F�߁A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X����B�����ŕ��Ƃ̓��ꎋ�́A�G�ӂ̒��q��тт�悤�ɂȂ�A��ɑ��镃�̈ʒu���߂邽�߂ɁA�������O�������Ƃ�����]�ɕς��B�����āA��Ƃ̓��ꎋ�����Ƃ̓��ꎋ���������邱�ƂŁA(��Ƃ̊W��ۂ��Ȃ���)��ւ̑Ώ۔�����������A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�͕���B���ʂ͕��Ƃ̓��ꎋ���������A���Ƃ̊W�̓A���r���@�����g�ɂȂ�A�j���̒j�炵���͌��łȂ��̂ɂȂ�B �������A���ƕ�A�ǂ���̓��ꎋ�ɏI��邩�́A�����I�f���̑��ΓI�ȋ��x�Ɉˑ����Ă���B�Ⴆ�A�j���͕�ɑ��鈤��̑ΏۑI�������łȂ��A�����̂悤�ɂӂ�܂��A���ɑ��ď����I�ԓx���A��ɑ��Ď��i�[���G�ΓI�ԓx�������ꍇ������B�����̏ꍇ���A���ʂ͕�Ƃ̓��ꎋ�̋����ɂ���ď��炵���Ȃ�̂����A���Ƃ̓��ꎋ�ɂ���Ēj�炵�����������Ƃ�����B���ڍׂɌ�������A���S�ȃG�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�̏ꍇ�A�z���ƉA���̓�d�̃R���v���b�N�X�������āA���̗����I�f�����݂��Ɋ����Ă���ƍl���Ă悢���낤�B �G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�Ɏx�z����鐫�I�i�K�̌��ʂƂ��āA�݂��Ɍ���������̓��ꎋ���ݗ�����A����̒��ɒ��a���N����B���̎���ω��͓���ȗ����ۂ��A���䗝�z���邢�͒�����Ƃ��āA����̑��̓��e�ɑΗ����邱�ƂɂȂ�B�������A������̓G�X���ŏ��ɑΏۂ�I�������ۂ̒P�Ȃ�c�����ł͂Ȃ��A���̑ΏۑI���ɑ��鐸�͓I�Ȕ����`���̈Ӗ��������Ă���A����Ƃ̊W�́u���O�͕��̂悤�ł���˂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������������ł͂Ȃ��A�u���O�͕��̂悤�ł��邱�Ƃ͂�邳��Ȃ��v�Ƃ����������܂�ł���B����́A���䗝�z���G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�̗}���ɂ���Đ��܂ꂽ����ł���A���̗}����(���ЁA�@������A���Ƃ̉e����)�����x�I�ɍs����قǁA������͗ǐS�A���ӎ��I�߈����Ƃ��Ď�������i�Ɏx�z����̂ł���B ���䗝�z�Ƃ̓G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�̈�Y�ł���A���䂪�{���A�O�E�����̑�\�҂ł���̂ɑ��āA������͓��I���E�A�܂�G�X�̑㗝�l�Ƃ��Ď���ɑΗ�����B����Ɨ��z�̊Ԃ̊����́A�����ƐS���́A�O�E�Ɠ��E�̑Η����ʂ����̂Ȃ̂ł���B���̌�̐����ߒ��ł́A���t�̖��߂�֎~�������䗝�z�Ɏc��A�ǐS�Ƃ��ē����I�Ď����s�Ȃ��A����̍s�ׂƂ̊Ԃْ̋��͍߈����Ƃ��Ċ������邱�ƂɂȂ�B�܂��A�Љ�I����́A���ʂ̎��䗝�z�ɂ��ƂÂ����l�Ƃ̓��ꎋ�ɂ���Đ��藧�B�@ |
|
|
�����ނ̖{�\
�{�\�ɂ̓G���X(���{�\�A���ȕۑ��{�\)�Ǝ��̖{�\�����邪�A���̓��ނ̏Փ��͍������邱�Ƃ�����A�𗣂���\��������B�Ⴆ�ΐ��Փ��̃T�f�B�Y���͏Փ����������Ă��邪�A�Ɨ������T�f�B�Y���͉𗣂̓T�^�ł���B��ʂɁA�����̒i�K���琫����ւ̐i���̓G���X�����������̂����A���������T�f�B�Y�������ւ̑ލs�͏Փ����𗣂���ƍl�����A�_�o�ǂł͏Փ��𗣂Ǝ��̏Փ��̔�����������(��ɏq�ׂ鋭���_�o�ǂȂ�)�B���̓��ނ̖{�\�̑Η��́A���Ƒ����݂̑Η��Œu�������邱�Ƃ��ł���B�l�X�Ȏ���ɂ���āA���͑����݂ɕς��B�A���r���@�����g�ȑԓx�͍ŏ����炠����̂ŁA�ϓ]�́A�G�l���M�[�������I�������痣��ēG�ΓI�G�l���M�[�Ɉڂ邱�Ƃɂ��̂ł���B ���̈ړ��G�l���M�[�͔��������r�h�[�ł���A����̓��r�h�[�̈�蕔�����A���ȂƂ��̖ړI�̂��߂ɏ����A����ɂ���ċْ����x�z����G�X�̎d����������̂��B���������̏��߂ɁA�����郊�r�h�[�̓G�X�̒��ɒ~�ς��ꂽ���A����͂܂��`�����ł����̂ł������B�G�X�͂��̃��r�h�[�̈ꕔ�����G���X�I�Ώ۔����ɂ�����A���ɋ������ꂽ����͂��̑Ώۃ��r�h�[���L(�킪���̂�)���A���Ȃ��G�X�ɑ��鈤�̑Ώۂ��炵�߂悤�Ƃ���B����̎��Ȉ��͑ΏۂƂ����I�Ȃ��̂���P�ނ������̂Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
������̈ˑ���
����͑啔�����A�������ꂽ�G�X�̑Ώ۔����̑���ɂȂ铯�ꉻ����`������Ă���B���̓��ꉻ�̍ŏ��̎����ɑ����钴����́A����̒��œ��ʂ̋@�ւƂ��Ăӂ�܂��A���̌�A�������ꂽ����ƑΗ�����悤�ɂȂ�̂��B������́A���䂪�܂��ア�����ɋN�����ŏ��̓��ꉻ�ł���A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�̈�Y�Ƃ��ċ���ȑΏۂ������ꂽ���ʂł��邽�߁A���U�ɂ킽���ċ����x�z�͂�ێ����邱�ƂɂȂ�B�q�������e�ɏ]���悤�ɁA����͒�����̖��߂ɕ��]����̂��B�����āA�G�X�̂����ɐ[�����荞������́A����ɑ��ăG�X�̑�\�Ƃ��Ăӂ�܂��A�ӎ����牓������Ă���̂ł���B �����̊W�������Տ��I����������B�Ⴆ�A���͒��Ɏ��Â̌��ǍD�ł��邱�Ƃ���������A�����I����������ꂽ�肷��ƁA���܂����悤�ɏ�Ԃ�����������l�X������B������A�����Ô����Ƃ������A���͓����I�ȗv�f�A�߈����ɂ���̂��B���̖��ӎ��I�߈����̌����́A���Ă̕������ꂽ����W�A���̉e�����Ɍ`�����ꂽ������(���䗝�z)�ɂ���B�߈�������菜���ɂ́A�}�����ꂽ���������X�Ɏ�菜���A�ӎ��I�ȍ߈����ɕς��悤�ɂ��邵���Ȃ��B�܂��A���͎҂����䗝�z�̈ʒu�ɒu����邩�ǂ������A���Ì��ʂ����E���邾�낤�B �����_�o�ǂƃ������R���[�ł́A�߈����͔��ɋ����ӎ�����A���䗝�z�͓��ʂȌ��i���������B�������R���[�̏ꍇ�͒����䂪�ӎ���Ɛ肵�Ă���A�ᔻ�Ώۂ͓��ꎋ�ɂ���Ď���Ɏ�������Ă���̂ŁA������͎���ɑ��ăT�f�B�Y��������B���̏ꍇ�A���̖{�\����������x�z���Ă���A����͎��ɋ�藧�Ă���̂�h�����߂ɂ��N�a�ɓ]����ق��Ȃ��B����ɑ��ăq�X�e���[�ł́A������̔ᔻ�͗}������A�߈����͖��ӎ��Ȃ܂܂ɂƂǂ܂�B�����������_�o�ǂł́A����͍߈������W����f�ނ��������}���ł��Ȃ����߁A�}�����ꂽ�Փ��ɂ���č߈����͐�����̂����A����ɂ���Đ��F����邱�Ƃ͂Ȃ��B �����_�o�ǂł́A�O����I�̐��ւ̑ލs�ɂ���āA���̏Փ���(�Փ��𗣂ɂ����)�U���Փ��ɂ����̂����A�������R���[�ƈ���đΏۂ͕ێ�����Ă��邽�߁A���̍U���Փ������Ȃ��������Ƃ͂Ȃ�(�܂莩�E�Փ��͂Ȃ�)�A�Ώۂ�łڂ����Ƃ���B���̍U���Փ��̓G�X�ɂƂǂ܂�A����ɑ��Ď���͔����`����\�h����u����̂����A����ł�������͂��̍U���Փ��ɑ��Ď�������B�����āA������̔��ɂ���čU���䂷�����قǁA�U���Փ��͎������������ꂽ���ƂɂȂ�B���̖{�\�́A���r�h�[�䂷��͂�^���邪�A����͎��Ȃ̐����������댯�����Ƃ��Ȃ��Ă���̂ł���B �� �Փ��𗣂̓G���X�I�����̏��Ɣj�̉���������炷�̂ł���A������̏ꍇ�����Ƃ̓��ꎋ�ɂ���ďՓ��𗣂������A���̎c�E�������߂邱�ƂɂȂ����̂ł��낤�B ����͊O�E�̋��ЁA�G�X�̃��r�h�[����̋��ЁA������̋��ЂƂ����A�O�l�̕s���ɂ��т₩����Ă���B������ɑ��鎩��̕s���A�܂�ǐS�̕s���͋����s����������p���ꂽ���̂ł���A���̕s���������s���̉��H���ꂽ���̂��ƍl������B�_�o�ǓI�s���́A����ƒ�����Ƃ̂������̕s��(�����́A�ǐS�́A���̕s��)�ɂ���ċ��߂���̂ł��낤�B����̓G�X�̖��ӎ��I�Ȗ��߂����������A�G�X�ƌ����⒴����Ƃ̊������������悤�Ƃ���̂ł���A���_���͎͂���̃G�X���������������߂�̂ɖ𗧂̂ł���B�@ �@ |
|
| ���t���C�g5 �u����c�����_�o�ǂ̕a�����v(�Ǘ� / �T�j) | |
|
�{�_���͏Ǘ�u�T�j�v�ƌĂ�Ă���A���銳��(�ȉ��A�T�j�ƌĂ�)�̗c�����̐_�o�ǂɊւ��Ă̂ݕ��ꂽ���̂ł���B�T�j�̗c�����_�o�ǂ́A�܂�4���ɕs���q�X�e���[(�������|��)�Ƃ��Ďn�܂�A����ɋ����_�o�ǂւƕς���āA10�܂ő����Ă���B�ŏ��A�T�j�͂Ђǂ����S�ȏ�Ԃ������Ă������߁A���͂ɋ��͂����邽�߂ɁA�t���C�g�͓]�ڂƊ����ݒ�@�𗘗p�����B�z���]�ڂ��N����A�s������R�����a����A���_�I���t����������B����ɁA���̊����������玡�Â�ł���|�������A���҂̕a�C�ւ̎�������߂��̂ł���B�������Ė{�i�I�ȕ��͎��Â��n�߂��邱�ƂɂȂ����B
�����ƕa���̊T�� �� �Ƒ��̍\���́A���A��A�o�A����B��e�͕a�C�����B���e�͗}�T�ǁB ����(3��)�c�c1�Δ��Ō����i�B�Ȍ�A�o�̗U�f����܂ł��ƂȂ������i�B ����(3�`4��)�c�c���i�ω��̎���(�o�̗U�f��A�\��A�������сA�C���C������)�B ��O��(4�`4�Δ�)�c�c�������|�ǂ̎���(�s�����Ȍ�)�B ��l��(4�Δ�����10��)�c�c�����_�o�ǂ̎���(�@���̓�����)�B ���U�f����т��̒��ڂ̌��� 3�̍�����o�̐��I�U�f(���K��������������A�y�j�X��͂�ŘM��)���n�܂�A���ꂪ�j���Ƃ��Ă̎��Ȋ���ɕs����^���邱�ƂɂȂ�B�o�͒m�I�ɂ��D��Ă���A�T�j�͎o�Ɉ��|���ꂽ�������߂����Ă����B���̎o�ɑ��ĎI�ł����������́A�o�ɑ���\���I�ȑԓx��������z(�o�̈ߕ����͂���铙)�ɂ���ĉB������邱�ƂɂȂ�B�o�̗U�f�����₵���T�j�́A�����̐����G���Ă��炢�����Ƃ����I�Ȑ��ڕW���i�[�j��(����)�Ɍ����A���킢������n�߂��B�������A�i�[�j���́u����Ȃ��Ƃ�����q�͂����̏�(����)�Ɂ��������܂���v�ƌ���(�����Њd)�B���̂��߁A�ނ̐������͐���ȑO�̐��I�̐��ɑލs���A�T�f�B�Y���I����判�I�X����тт邱�ƂɂȂ�B�������āA�{����ۂ��Ȃ�A�s���������A�����ȓ����ɑ��Ă��c�s�ɂȂ����B�܂��A�T�f�B�Y���̓}�]�q�Y���ɂ��]�����A�o�ɂ���ĐA������ꂽ�I�ȑԓx�͕��e�Ɍ������A�}�]�q�Y���I�ȈӐ}�̑ΏۂƂ��ꂽ�B�@ |
|
|
�����ƌ����i
�o�̗U�f�ɂ���Ďn�܂������s�Ɛ��I�|���X���́A4�Έȍ~�A�_�o�ǂւƕς��B���̂��������ɂȂ����̂́A����s�����ł���B���̓��e�́A����~�̖�A�����ЂƂ�łɊJ���A�O�ɂ͑傫�Ȗ�����A�����Ɋ��C���̔����T�������Ă����A�Ƃ������̂ł���B���̖����`��������ԋ�����]�́A������(�������I)���I�����邱�Ƃł������ɈႢ�Ȃ��B���̊�]�́A1�Δ��̎��Ɋ�ɂ������e�̐����̋L��(�����i)��h�点�A�U������Ė��ƂȂ����̂��B���������̌��i�́A�i�[�j���̈Њd�A�������������Ă��鏭�����������ƂȂǁA���R�Ɗ����Ă����������A���ۂɋN���肤�邱�Ƃ��m�M�����邱�ƂɂȂ�B��e�̂悤�Ȗ����邽�߂ɂ́A��������˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����킯���B���̕��̋��Ђ��瓦��邽�߂ɁA�ނ͕��e�ւ̎I�ԓx��}�����A�T�����e�ɑ��ĕ|�������悤�ɂȂ����̂ł���(�������|��)�B�@ |
|
|
����A�O�̓��_
�����c�����̋L���́A�����̂ł����Ƃ̍Č��ł͂Ȃ��A��z�`�����ł��邩������Ȃ��B�������A�{�Ǘ�̂悤�ɁA�u���̌�a���ɑ��Ē������Ӌ`�����悤�ȓ��e��L������i�́A�ʗ�͋L���Ƃ��čĐ��������̂ł͂Ȃ��A�ނ��됔�����̕W���𑍍����Ȃ��獜��܂��Ĉ���������\�\����˂Ȃ�Ȃ��v(���͂ɂ��\��)�B�@ |
|
|
�������_�o��
4�Δ��̍��A�ނ̕q���ŕs���ȏ�Ԃ����P���邽�߂ɁA��e�͐����������n�߂�B���̌��ʁA�������|�ǂ͉������ꂽ�̂����A�V���������Ǐ���n�߂邱�ƂɂȂ�B�ނ́A�_�̎��ɑς���L���X�g�ɓ��ꉻ���A���ɑ���}�]�q�Y���I�ԓx���������B���ɐM�S�[���Ȃ�A���ɂ��O�ɂ͕K���������F������A�ی��Ȃ��\�����A�[���ɂ͐����̈��ɐڕ�����悤�ɂȂ�B�������A����ł̓L���X�g�Ɏ���^�����_�����ւ̃T�f�B�Y���I�ȓG�ӂ������A�u�_���v�u�_����ցv�Ƃ����A�z���ǂ����Ă������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�t���C�g�ɂ��A���̃A���r���@�����c�Ȋ�������判�ɊW���Ă���B�܂��A��H��s��ҁA�V�l������Ƒ傫������f���o���A���̏����ł͑����z�����܂˂Ȃ�Ȃ������B����́A�����f���o���A������z�����ނƂ����Ӗ�������A�a�C�ł�ꂽ�������āA�����Ȃ肽���͂Ȃ��Ƃ�����]�̌���ł������B���̌�A�h�C�c�l�ƒ닳�t�̉e���ŐM���̂āA�I(�������I)�ԓx(�}�]�q�Y��)��E�p���A���Ȃ萳��Ȕ��B����ނ��ƂɂȂ�(���̂��Ƃ��A���͎��Âɂ�����]�ڂɂ����Ė𗧂��ƂɂȂ����ƃt���C�g�͏q�ׂĂ���)�B�@ |
|
|
����判�ƃR���v���b�N�X
�����_�o�ǂ͉��s�I�E��判�I�f���̏�ɔ������Ă���B�ނ͗c�������環��Q�ɋꂵ��ł���A���͎��Â��鍠�ɂ��������^�����Ȃ���Δr�֊������ł��Ȃ���Ԃɂ������B���̒���Q�͋����_�o�ǂ̍���ɂ��镔���I�ȃq�X�e���[�ł���B�s�����ɂ���ė}�����ꂽ���ւ̏����I�ԓx�́A���Ǐ�ɑލs���A�c�����̉�����֔�A���ɂƂȂ��ĕ\�����ꂽ�B��ւ͐g�̂��番���\�ȑ����ł���A�q�ǂ��A�y�j�X���Ӗ����Ă���B�r�֍s�ׂ͉����ƈ��������ɐg�̂̈ꕔ��������邱�Ƃł���A��e�̂悤�ɋ���������ĕ�������y��^�����A�q�ǂ��e�ɑ��邱�ƂȂ̂ł���B�������|�ǂƂ��ė}������Ă���������������A�����_�o�ǂɂȂ����킯���B�@ |
|
|
������������̒lj� / ����
�T�j�̋L���ɁA���F���Ȃ̓������傫�Ȓ��ɕs�����������A�Ƃ������̂�����B���̋L���̔w��ɂ͎q�疺(�O���[�V���Ƃ����A���F���Ȃ̂��關�Ɠ������O)�̋L�����B������Ă���B�ނ͎q�疺���������Ă��鎞�A���ւ�R�炵�Ă��܂����̂ł���B�r�A�s�ׂ͐��I�ȗU�f���Ӗ����Ă���B�q�疺�̎p��(���̉H�̂悤�ɁA�r���u���ɂȂ��Ă����H)�Ɏh�����ꂽ���ւ́A�q�疺�ɂ�����ꂽ�̂ł��낤(�����Њd)�B���̃O���[�V���Ƃ̌��i�̕��͂ɂ���āA���҂̒�R�͂Ȃ��Ȃ�A��͂����A�z���W�߂č\�����邾���ɐ�S����悩�����B�@ |
|
|
�������Ə����
���O�I�̐��͐ېH�{�\�Ɉˑ��������I�����ł��邽�߁A���̓��䂪���܂������Ȃ���ΐېH��Q�ƂȂ�B�₪�Č��O�I�̐�����判�̐��ɔ��B���A�o�̗U�f�ɂ���Đ���I�̐��ɖڊo�ߎn�߂邪�A�i�[�j���̋����Њd�ɂ���āA�ĂуT�f�B�X�e�B�b�N����判�̐��ɑލs����B�����ăT�f�B�Y���̓}�]�q�Y���ɓ]�����A�A���r���@�����c�Ȋ�����������ށB���ɕs�����ɂ�錴���i�̊������ɂ���āA����I�̐����Ăъ������n�߂�̂����A�����s���ɂ���ċ��|�ǂƂȂ�B���̂��߁A���ӎ��I�������͒���Q(�q�X�e���[)�������A��判�̃T�f�B�Y���A�}�]�q�Y���͂��̌�����a���Ċ������p���B�₪�ė}���Ƃ������x�Ȍ`��(�@���ɂ��)�ɂ���ċ��|�ǂ͉������邪�A����ɋ����_�o�ǂƂȂ�A���ݓI�Ɋ������Ă����T�f�B�Y���A�}�]�q�Y���́A�_�ւ̖`���A���ȁ��L���X�g�̎��Ƃ����`�ł͂�����B�₪�ăh�C�c�l�ƒ닳�t�̉e�����ɁA�\�ʓI�ɂ͐���I�̐��ւƈڍs���A���l�ƂȂ�B�������A�ҕa�ɂ���ċ����s�����������A�j���I���Ȉ������܁B�_�o�ǂƂȂ��ăt���C�g�̕��͂��邱�ƂɂȂ����̂ł���B�@ �@ |
|
| ���t���C�g6 �u���~�A�Ǐ�A�s���v | |
| ���~�Ƃ͎���@�\�̐����̕\���ł���A����ƃG�X�܂��͒�����Ƃ̊���������邽�߂ɋN����@�\�ቺ�ł���B���̋@�\�ُ̈�ȕω���V���ȍ�p�����ƂȂ����Ƃ��A����͏Ǐ�ƌĂ�邪�A����͒��f���ꂽ�Փ������̒���Ƒ㏞�ł���A�}���ߒ��̌��ʂȂ̂��B����͂��������Ǐ�Ɠ������߂ɁA�l�X�Ȗh�q�����݂邱�ƂɂȂ�B���̖h�q�ɂ͗}���̑��ɁA�u�������A�ލs�A�����`���ȂǁA�l�X�Ȏ�ނ�����A���̈Ⴂ�ɂ���Đ_�o�ǂނ��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�h�q�͎���ƃG�X�̋�ʈȑO�ł͂��̕��@���قȂ�A������̌`���ȑO�ƈȌ�ł��قȂ��Ă���B�@ | |
|
�����|�ǁA�q�X�e���[�A�����_�o�ǂ̖h�q
���|��1(�Ǘ�n���X)�F�@�n���X�͔n�Ɋ��܂��Ƃ����s��(�Ǐ�)�̂��߂ɁA�X��������Ƃ��ł��Ȃ�����(���~)�B�n�͕��e���u��������ꂽ���̂ł���A�����̓G�f�B�v�X�ɂ����鋎���s���ł���B�c���N��ł͓����Ɛl�̈Ⴂ���܂�������Ȃ��̂ŗe�Ղɒu���������A�������|�ǂ��₷���B�ނ͕��ɑ��Ĉ���ƌ����Ƃ����������̊���������A����ł͕��e�Ɉ����ꂽ���Ɗ����A���ꂪ�n�Ɋ��܂��A�܂蕃�e�ɐH�ׂ���Ƃ����A�I(�����I)�ȏ�Փ��������Ă���B�����A����ȏ�ɕ�e�ւ̏�Փ��������A��Ƃ̊W���ז����鑶�݂Ƃ��āA���e�ނ��ƂɂȂ�B�������A���e�ւ̈���炱�̍U���Փ��͗}������A�t�ɕ��e����̍U���Ƃ������Ε��ɓ]�����A����ɂ���͔n����̍U���ɒu����������B����͓����ɋ����s���������Ă���̂ł���B ���|��2(�Ǘ�T�j)�F�@�T���|�ǂ̃��V�A�l���N�̏ꍇ�A�ނ��n���X�Ɠ����悤�ɋ����s�������������A����͕�e���߂��郉�C�o���S����ł͂Ȃ��A��e�̂悤�ɕ��Ɉ����ꂽ���Ƃ����~�]�������B�܂�A�n���X�ƈ���āA�������̊����ɂ����ĕ��e�ւ̈����苭�������̂��B�������A��e�̂悤�Ɉ�����邽�߂ɂ́A�������������ꂽ���݂łȂ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�B���̋����s�����A�ނ̋��|�ǂ������N�����Ă���̂ł���B �q�X�e���[�F�@�]���q�X�e���[�ł́A�s���͐����Ȃ�����ɁA�^����ჁA�s���Ӑ��̉^�����z���A�ɂ݂⌶�o�ȂǁA�Ǐ�͉^���@�\�Ɍ����(�]������)�B���̌����́A�}�������������̒��Œɂ݂��������A���o�͂��̏ł̒m�o�ł������A��Ⴢ��Ă���^���͂��̏Ő��s�����͂��ł������A�Ȃǂ��l������B�܂�A�g�̓I�ȋ�ɂ͂���̂����A���̑���ɕs���͊��S�ɗ}������Ă���B �����_�o��1�F�@�����_�o�ǂ̏Ǐ�ɂ́A�܂��֎~�A�x���A�����Ȃǂ̔ے�I�Ȑ����̂��̂�����A���̌�A����Ɣ��̑㏞������������ꍇ������B�����̓q�X�e���[�Ɠ����悤�ɏ�Փ������A������I�Ґ����ア���Ƃ�����A�}���͕s���S�ɂȂ炴��Ȃ�(�߈������W����f�ނ��������}���ł��Ȃ�)�B���̌��ʁA����̖h�q�͏����̃T�f�B�Y���I�����ւ̑ލs�Ɍ����A�Փ��𗣂ɂ���ď�Փ��͍U���Փ��ւƕς��A�Ώۂւ̔j��Փ��Ɠ����ɁA������̔j�����߂邱�ƂɂȂ�B�����āA����͌��i������������ɕ��]���邠�܂�A���x�Ȕ����`���W�����A�ɓx�ɗǐS�I�A����I�A���ȂƂȂ�B�������A������̉ߍ��Ȕᔻ���Î�(�֎~�����)���Ƃɂ���āA����͍߈��������o�����ɂ��ނƂ����㏞�����邱�Ƃ��ł���B�t�Ɍ����A�q�X�e���[�ƈႢ�A�s����߈����������邩�炱���A������������Ƌ֎~�����̂ł���B �����_�o��2�F�@�����_�o�ǂɂ͎���ƕ����Ƃ�����̎�i������B����͔ے�����ƂƂ��閂�p�I�ȋV���ł���A�^���̏ے��ɂ���ĕs���ȏ��N����Ȃ��悤�ɂ��A���̏��̂𐁂������Ă��܂����Ƃ���h�q�����ł���B�܂��A�����_�o�ǂł̓q�X�e���[�̂悤�ɕs���ȑ̌���Y�ꋎ�邱��(���S�ȗ}��)�͂ł��Ȃ����A���̏�������A�A�z�I�ȊW�𐧈������蒆�f���邱�Ƃ͂ł���B������Ƃ����A����҂��s���̈������Ƃ�����������A���ӂ���炵���肷��̂Ɗ�{�I�ɂ͓����ł���B�܂��A�U���Փ��Ə�Փ��͂ǂ�����g�̓I�ȐڐG�⌋�����ւ�邽�߁A�����_�o�ǂł͓��ɐڐG�⌋�����֎~�����s�ׂƂȂ�₷���B�@ |
|
|
���s���̖��
�s���͊��҂Ɩ��ĂȊW�������A���R�Ƃ��Ă��邱�ƂƁA�Ώۂ��Ȃ��Ƃ�������������B�Ώۂ�����ꍇ�͋��|�ƌĂ�邱�ƂɂȂ邾�낤�B�s���̍���ɂ͋����̍��܂肪����A����ł͂��ꂪ�s���̐��������肾���A�����łْ͋������ɂ���Čy�������B�s���͊댯�ȏ�Ԃւ̔����Ƃ��ċN����A����������ԂɍĂт������ƁA���܂��čĐ������B���̂��߁A�s���͊댯�ւ̐M���Ƃ��Ă̖�����S���Ă���A���̐M���ɂ���Ď���̐��~���N����A���_�_�o�ǂ̌����Ƃ��Ȃ�B�Ⴆ�A����̏ꍇ�A���Ƃ��������s�ׂ́A�s���̏P�����ӂ����Ƃ����Ӑ}�������Ă���B����A�댯�ȏ��Ŏ����I�ɕs�������������ꍇ������A����͌����_�o�ǂ̌����ƂȂ�B�s���͐_�o�ǂ̊�{���ۂł���A�Ǐ�`���͂��ׂĕs��������邽�߂Ɋ�Ă�ꂽ���̂ł���B�Ƃ����Ă��A���̕s���̌����͎��o����͂��Ȃ��B�����̕s���͕������Ă���댯�ɑ���s�������A�_�o�ǓI�s���͕�����Ȃ��댯�ɑ���s���Ȃ̂ł���B �q���̕s���́A������l(��e)���������Ƃ����B��̏����ɊҌ��ł���B�ŏ��͏o�Y�Ƃ��������w�I�ȈӖ��ł̕�e�Ƃ̗��ʂ�����(�����N)�A���ɒ��ڂ̑Ώۑr���Ƃ����Ӗ��ŕꂩ��̗��ʂ�����B��e�������Ȃ��Ȃ�����A���Ȃ��Ȃ����肵���Ƃ��̕s��������ł���B�����͕�e����x�ڂ̑O���������ƁA������x�ƌ����Ȃ����̂悤�Ɏv�����ނ̂ł���A���ꂪ�܂������Ƃ������Ƃ͊w�K���Ă͂��߂ĕ����邱�Ƃł���B�u���Ȃ����Ȃ����v�Ƃ����V�Y�́A���̑�Ȓm������������̂ł�����̂��B�₪�āA�Ώۂ������Ƃ��邱�Ƃ��������Ă��A���x�͑Ώۂ���̈���������댯�����A�s���̏����ƂȂ�̂ł���B�����s�����܂��A���l����Ώ�(����)�̑r�����Ӗ����A���ꂪ������̌`���ɂ���āA�ǐS�̕s����Љ�I�ȕs���ɔ��W����B���̏ꍇ�A������̏�����{�肪����̕s���������N�����킯�����A����͒�����(���e)�̈���������s���ł�����̂��B�����āA������ɑ���s���̍Ō�̕ω��́A���̕s���ł���B�@ �@ |
|
| ���t���C�g7 �u�i���V�V�Y������v | |
|
�l�b�P�ɂ��A�u�i���V�V�Y���v�Ƃ����q��́A����l�Ԃ������̓��̂�Ώۂ̂悤�Ɉ����A���I�ȊS������Ă���߁A������A�������āA���ɂ͊��S�Ȗ����ɒB����s�ׂ�\�����̂ŁA���̐��ڕW�|�����Ӗ�����B�������A�i���V�V�Y���I�ȑԓx�͔��ɍL�͈͂ɂ킽���ĔF�߂��邽��(�Ⴆ�ΐ_�o�ǎ҂̓i���V�V�Y���I�ԓx�ɂ���Đ��_���͂�����ɂ���)�A���ڕW�|���ł͂Ȃ��A���ȕۑ��{�\�̃G�S�C�Y�������r�h�[�ʂŕ⑫������̂ł��낤�B
�Ⴆ�A�p���t���j�A����(���_�����a)�֑͌�ϑz�ƁA�O�E�̐l���⎖������̊S�̗���������Ƃ��Ă���A���Ȃ̃��r�h�[���O�E����P�����Ă���B�֑�ϑz�͑Ώۃ��r�h�[�̋]���ɂ���Đ��������̂ł���A�O�E����P�����ꂽ���r�h�[�͎���ɋ�������A�i���V�V�Y���I�ԓx�ɂȂ�(�I�ȃi���V�V�Y��)�B�܂��A���l�ȃi���V�V�Y���I�ԓx�͌��n�l�⎙���ɂ�������B���̂悤�ɁA���䃊�r�h�[�ƑΏۃ��r�h�[�ɂ͈�̑Η�������A������]�v�Ɏg����A���ꂾ�������������Ă䂭�B��҂̔��W�i�K�������ł���A���̋t���Ύ��a�҂̐��E�v���̋�z�ł���B�����āA����ɌŗL�̃��r�h�[(���䃊�r�h�[)�ƁA�Ώۂɕt������郊�r�h�[(�Ώۃ��r�h�[)����ʂ��邱�Ƃ́A���~���Ǝ���~���Ƃ��݂��ɋ�ʂ���Ƃ�������(���r�h�[���_)�Ɋ�Â��Ă���B �� ����]�ڐ_�o��(�q�X�e���[�A�����_�o��)���~���̃��r�h�[�I�ȓ����̒Nj����\�ɂ����悤�ɁA�������s����p���m�C�A�͎���S���ւ̓��@���\�ɂ���B�܂��A�펿�I������q�|�R���f���[�A��������ώ@���邱�Ƃ��A�i���V�V�Y�������ɂ͏d�v�ł���B����ǂ��ďq�ׂĂ݂悤�B �펿�I�Ȓɋ��s���ɋꂵ�߂��Ă���҂́A���r�h�[�I�S�����̑Ώۂ�������グ�A�����邱�Ƃ���߂Ă���B�a�l�̓��r�h�[�̊�����ނ̎���ւƈ����߂��A�S����ɍĂт���𑗂�o���̂��B�����悤�ɁA�q�|�R���f���[(�S�C�ǁF�������Ȃ��̂ɐg�̓I�ȋꂵ�݂�i����)���A�S�ƃ��r�h�[���O�E�̑Ώۂ���������߂āA�������C������Ă���튯�ɏW������B����]�ڐ_�o�ǂ��Ώۃ��r�h�[�̟T�ςɂ���ċN����悤�ɁA�q�|�R���f���[�͎��䃊�r�h�[�̟T�ςɂ���ċN����̂ł���B�q�|�R���f���[�̓p���t���j�A�ɂ����Ă������A���̊W�́A�����_�o��(�s���_�o�ǁA�_�o�����)������]�ڐ_�o�ǂɑ���W�Ɠ����ł���B�܂�A����]�ڐ_�o�ǂɂ�����s���ɑ�������̂��A�p���t���j�A�ɂ�����q�|�R���f���[�ł���A�s�����������邽�߂̋�z�`��(�]���A�����`���Ȃǂ̐S�I���H)�ɑ�������̂��A�p���t���j�A�֑̌�ϑz�Ȃ̂ł���B�p���t���j�A������]�ڐ_�o�ǂƋ�ʂ����_�́A���ۂɂ���Ď��R�ɂȂ������r�h�[���A��z���̑ΏۂɂƂǂ܂炸�A����ɉ�A���Ă��邱�Ƃɂ���B �i���V�V�Y�������̑�O�̕��r�͐l�Ԃ̈�����ł���B�ŏ��̎��̈��I�Ȑ��I�����́A���ȕۑ��ɖ𗧂@�\�Ƃ��đ̌�����A���b�����Ă�����e(�܂��͂��̑㗝��)�Ɉˑ����Ă���B���ꂪ��Ɏ����������̗~���ƂȂ�A��e�͍ŏ��̐��I�ΏۂƂȂ�̂�(�ˑ��^)�B�������A���r�h�[���B�ɏ�Q�������ނ����ꍇ�A���̑Ώۂ��e�ł͂Ȃ��������g��I�Ԃ��Ƃ�����(�i���V�V�Y���^)�B�a�C�ł͂Ȃ��Ƃ��A�S�Ă̐l�Ԃ͈ꎟ�I�i���V�V�Y�������Ȃ��Ă���A���ꂪ�ΏۑI���̍ۂɗD���Ɍ���Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B�j�����r���Ă݂�ƁA�j����(��e�ւ̓]�ڂɂ����)�ˑ��^�ɂȂ�₷���A�Ώۈ��̂��߂Ɏ��䃊�r�h�[���R�����Ȃ�₷���B�����̏ꍇ�́A�v�t���ɂȂ�ɂ��(��������̔��B�̂��߂�)�i���V�V�Y�������܂�A�Ώۈ����\�������������̂ɂ���̂ŁA�������舤����邱�Ƃ����߂₷���B�܂��A�q�ǂ����ł���ΑΏۈ��͋����Ȃ�̂����A�i���V�V�Y�������������(���ꎋ)�A�q�ǂ��́u�Ԃ�V�É��v�Ƃ��ĊÂ₩����邱�ƂȂ�B �� ���r�h�[�I�ȗ~�������́A���ꂪ�����I����їϗ��I�ȏ��ϔO�ƏՓ˂���ƁA�����̊ϔO�������ɑ���K�͂Ƃ��ĔF�߁A����炪�v������Ƃ���Ɏ���]�����Ƃ���B�܂�A����̎����S����}����������̂ł���B����̑�����݂��}���̏����́A���Ȃ̂����Ɉ�̗��z���������āA����Ɍ����̎�������킹�邱�Ƃɂ���B���̂悤�ȁu���z����v�ɂ��Ă͂܂�̂��A�c���ɂ͌����̎��䂪���Ă������Ȉ��Ȃ̂��B�i���V�V�Y���́A�c���̎���Ɠ��l�Ɋ��S�������Ȃ��đ��݂���A���̐V���ȗ��z�I�Ȏ���ɕψʂ������̂Ƃ��Ďp�������B�������A���̗��z����̊��S���͌����̗l�X�ȋK�͂ɂ���ĕ�����A�₪�āu���䗝�z�v�Ƃ����V�����`���̂Ȃ��ɁA������x���S�����l�����悤�Ƃ���B�ނ����Ȃ̗��z�Ƃ��Ă��̊�O�ɓ��e������̂́A�c���̎���ꂽ�i���V�V�Y���̑㗝���Ȃ̂ł���B�܂��A�����������z�`���͎���̏��v�������߂�Ƌ��ɗ}�����x��������̂ł���A���̂悤�ɕʂ̖ڕW�ɗv�������������邱�Ƃł͂Ȃ�(���͗}�����Ȃ�)�B �i���V�V�Y���I�������m�ۂ��邽�߂Ɍ����̎����₦���Ď����A���z�ɍ��킹�悤�Ƃ���悤�ȐS�I�@�삪����Ƃ���A���Ӗϑz��ώ@�ϑz�𐳂����������邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�ނ�͎��������̍l�����S�Ēm���Ă��邵�A���������̍s�ׂ͊ώ@����A�Ď�����Ă���̂��Ƒi���A�u���ܔޏ��͂܂����̎����l���Ă���v�ƁA���̐��̑��݂��咣����B���ہA�����̈�̈Ӑ}���ώ@���A�֒m���A�ᔻ���邱�̂悤�ȗ͎͂������݂��Ă���A����Ȑ������c��ł�������ɂ�������B����A���̐S�I�@��ɂ͗ǐS�����̔Ԑl�Ƃ��ė��Ă��Ă���̂��B�ǐS�Ƃ����|�́A���ɂ͗��e�̔ᔻ�́A���ŎЉ�(���t�A���E�A���_)�̔ᔻ�̋�̉����ꂽ���̂ł���A�͂��߂͊O������̋֎~�܂��͖W�Q�ɂ���āA�}���X���������Ă���ۂɔ�������錻�ۂł������B���̗͂��ލs����ƁA�ώ@�ϑz�̂悤�ɐ�����̓I�ɕ������A�ǐS�̔��B�j���t�s�I�ɍĐ����邱�ƂɂȂ�B���Ȋώ@�̏�ɒz���ꂽ�ǐS�̎��Ȕᔻ�́A���E�T���̖�ڂ��ʂ����A���̓��E�T�����N�w�I�v�l�ɍޗ�����Ă���B���̂��Ƃ́A�p���m�C�A���҂̎v�ٓI�̌n�`��(�ϑz)�Ƃ����W�ł͂Ȃ����낤�B ���䊴��͂܂�����֑�Ƃ����`�Ō����(�����S�̂悤�Ȃ���)�B�l�����ɏ��L���܂��͂���܂łɒB��������̂��́A�o���ɂ���ė��������ꂽ�f�p�ȑS�\����̂�����c�������A���䊴��̍��g��������̂��B�܂��A���䊴��̓i���V�V�Y���I���r�h�[�ɋٖ��Ɉˑ����Ă���B�Ⴆ�p���t���j�A�ɂ����Ă͎��䊴����߂��A����]�ڐ_�o�ǂɂ����Ă͒ቺ���Ă��邵�A������Ȃ����Ƃ͎��䊴���ቺ�����A������邱�Ƃ͎��䊴������߂�̂ł���B�Ώۂւ̃��r�h�[�����͎��䊴������߂Ȃ����߁A������Ώۂւ̈ˑ�������͎��䊴���ቺ������B���������āA�������Ă���l�͎��Ȃ̃i���V�V�Y���̈ꕔ��r�����A�ڋ��ɂȂ�̂ł���A������Ȃ���Ύ��䊴������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B������Ȃ��܂��䊴����Ăэ��߂�ɂ́A�Ώۂ��烊�r�h�[�������グ�邵���Ȃ��̂��B ����̔��B�͈ꎟ�I�i���V�V�Y�����狗�����Ƃ邱�Ƃɂ���Đ��藧���A���̃i���V�V�Y�����Ăъl�����悤�ƌ������w�͂ݏo���A���䗝�z���`������B�܂�A���r�h�[�����䗝�z�ɁA���z�̎����ɂ���ē����閞�����Ɉړ�������̂ł���B�����ɁA����͑Ώۊ����̃��r�h�[�𑗂�o���Ă������̂ł���A����͂��̂悤�Ȋ����Ǝ��䗝�z�̂��߂ɕn���ɂȂ�̂����A�Ώۖ����◝�z�����ɂ���čĂіL�x�ɂȂ�B���䊴��̈ꕔ�͈ꎟ�I�Ȃ��̂ł���A�����i���V�V�Y���̖��c�����A���̕����͌o���ɂ���ė��������ꂽ�S�\��(���䗝�z�̎���)�ɗR�����A��O�̕����͑Ώۃ��r�h�[�̖����ɗR�����Ă���B�܂��A���I���z�͎��䗝�z�ɑ��ĕ⏕�W�ɂ���A����ɗ��z�Ƃ��Č����Ă��钷�������L����҂͈�����₷���B���䗝�z�̎���������Ȑl�́A���I���z�ɂ���Ď��䊴������߂悤�Ƃ���̂ł���B�Ō�ɁA���䗝�z�͎Љ�I�ȕ�����L���Ă���A�Ƒ���K���A�����̋��ʂ̗��z�ł�����B���̗��z����������Ȃ��ƍߐӂ̈ӎ���������̂����A����͌����A���e�̈����������Ƃւ̕s������A��ɕs���葽���҂ւ̍ߐӊ��ɂȂ����̂��B�@ �@ |
|
| ���A���i�E�t���C�g8 �u����Ɩh�q�v | |
| �����ҁ@�h�q�@�\�̗��_�@ | |
|
��1�� ����̈ʒu�Ɩ���
�t���C�g�����_���͂��n�߂����́A����͖��ɂ��ꂸ�A�[�w�̖��ӎ��𖾂炩�ɂ��邱�ƁA�}�����ꂽ�Փ��⊴��A��z���������邱�Ƃ��d�v�ł������B�܂�A���_���͂͐[�w�S���w�Ɠ������̂ƌ��Ȃ���Ă����̂��B�������A���ۂɊ��҂����Â��悤�Ƃ���Ύ���̍����ɒ��ʂ��邽�߁A���ُ̈킳����菜���Ď���̌��N�����߂����Ƃ��K�v�ƂȂ�B1920�N�A�u���������̔ފ݁v�Ɓu�W�c�S���w�Ǝ���̕��́v�ɂ����āA�t���C�g�͎���̌����̒[�����J�����B���݂̐��_���͂̉ۑ�́A�l�i���\������G�X�A����A������ƌĂ��O�̕���(�R��)�̑��݊W�A�O�E�Ƃ̊W���������邱�Ƃɂ���B1920�N�ȑO�̐��_���͂ł̓G�X(���ӎ�)�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ۑ肾�������A�Ȍ�ɂ����Ă͎���̍\���𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��V�����ۑ�ƂȂ����̂ł���B �������������A�G�X�⒴����͎����}��ɂ��ĊԐړI�ɒm�邱�Ƃ��ł���B�G�X�͈ӎ��Ɍ��ꂽ�Ƃ��ɊԐړI�ɐ����ł��邾���ł���A��������͂�����ӎ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B����̕ω��̎d��������A�ǂ̂悤�ȃG�X�̏Փ�������̂��A�ǂ̂悤�Ȓ�����̖��߂������Ă���̂������炩�ɂȂ�̂��B �u�G�X�̗̈�́A������s�ꎟ�ߒ��t�Ƃ���悤�Ȑ������������̈�ł���B���Ȃ킿�A���̖��ӎ��I�ȗ̈�ɂ����ẮA�ϔO�̓o���o���ŁA�_���I�ȓ��ꂪ�Ȃ��A����ϔO�͑��̊ϔO�ƒu���������₷���A�݂��ɑΗ����Ă�����̂��r���I�ɂȂ炸�A���������ɕ������Ă���B�v(p.9)�B�u����ɔ����āA����̗̈�ɂ����ẮA�ϔO�͌��i�ȋK���ɂ��������ĘA�������B�_���I�ɗ��H���R�Ƃ��Ă���B���ꂪ������s�ߒ��t�ƌĂ�Ă�����̂ł���B���Ȃ킿�A�ߒ��́A�Փ����ȒP�ɖ��������Ȃ��悤�ɂ���B���������悤�Ƃ���Ȃ�A����̏��F�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v(p.10)�B�����̃��[�������ďՓ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B���̏�A�����䂪�ϗ��I�A�����I�K�͂ɂ���Ď�������Ă��邽�߁A���̋K�͂Ɉ�v���Ȃ���ΏՓ��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �u�Փ��͎��䂩��ᔻ����A�ϗe�����܂���̂ŁA�q��ȕ��@�����ĂāA��P����������݁A��������|���A�����悤�Ƃ���B�Փ������̂悤�ȓG�ӂɂ݂����N�������邩��A����͋^���Ԃ����Ȃ�B����͔��U����������݁A�t�ɃG�X�̗̈�̂Ȃ��ɐN�����Ă䂱���Ƃ���B����̔��U���̖ړI�́A�Փ����i�v�ɒ��ق����邱�Ƃł���B����͓K���Ȗh�q�@�𗘗p���āA�Փ��̐N�����ӂ����A�������g���ێ����悤�Ƃ���B�v(p.10-11)�B�u����ꂪ�m�邱�Ƃ̂ł���̂́A�c�߂��Ȃ��A���Ƃ̂܂܂̃G�X�̏Փ��ł͂Ȃ��A���䂪���U���ɂ����h�q�@�ɂ���ĕό`����A����̐F�ʂ�������ꂽ�G�X�̏Փ��ł���B���͎҂̌����ۑ�́A�S���ߒ����G�X�A����A������̊Ԃɂ���ꂽ�Ë��̉ߒ��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃł���B�v(p.11)�B�@ |
|
|
��2�� �G�X�A����A������͕��͓I�ɂ����Ɍ�������邩
���_���͗Ö@�����������ȑO�̍Ö��@�ɂ����ẮA���ӎ��I�Ȃ��̂𗝉����悤�Ƃ͂��Ă������A����̖����͂قƂ�Ǎl�����Ă��Ȃ������B�ނ���A����͍Ö���W������̂ł��邽�߁A�Ö��͎���̖W�Q���������A�[�w�̖��ӎ��𖾂炩�ɂ�����̂ł������B���ӎ������҂ɐ����������A�ӎ���������ΏǏ�͏�����A�Ƃ����킯���B�������A�����Ɉӎ��I���ꂽ�G�X�̏Փ��ɑ��āA����͐V���Ȏ��Ȗh�q�̍R�����n�߂邽�߁A�Ö��@�̌��ʂ͈ꎞ�I�Ȃ��̂ł����Ȃ��B 1895�N�A�t���C�g�ƃu���C�A�[�́u�q�X�e���[�����v�ɂ����Ė��炩���ꂽ���R�A�z�@�ł́A����������ď������邱�Ƃ͂Ȃ������B���̂����A����͘A�z��]��������_���I�W�ɋC��z�邱�Ƃ��ւ����A�G�X���b���₷���Ȃ�悤�Ɏ��������߂���B�������A�Ö��ƈ���Ď���͌��C�ł��邽�߁A�l�X�Ȗh�q�@���g���ĘA�z�̗�����ז����A����̓G�X�ɑ��ās��R�t�������B���͂̋K�������炳���悤�Ƃ��邱�Ƃ��A�ނ��늋���ݏo���̂��B�����ŁA���͎҂̒��ӂ͘A�z�����R�ɁA�G�X�̓��e���玩��̊����Ɉڂ����B�A�z�ɋy�ڂ��e������A�ǂ�Ȗh�q�@���g�����̂��𖾂炩�ɂ��A������č\������̂��B���������āA���͎҂̔C���͖h�q�@�\��m�邱�Ƃł���A���ɖh�q�@�\�ɂ���Ęc�߂�ꂽ���̂����ʂ�ɂ��邱�Ƃł���B�u��������ꂽ���̂��C�����A�������ꂽ���̂�^�̕����ɖ߂��A�ؒf���ꂽ�W��������B�����ŁA������x���䕪�͂���G�X���͂ɒ��ӂ��ڂ��̂��B���_���͈͂�����I�ȍÖ��@�ƈႢ�A����ƃG�X�̓�����Ɍ��݂ɒ��ӂ������Ȃ��玡�Â�����@�Ȃ̂ł���B ���҂����͂̍��{�K���ɏ]���Ă��鎞�́A�Ӑ}�I�Ɏ���̋@�\���~���Ă���̂����A�������Ă��鎞�́A����ɂ���Ď���̋@�\�͎����I�ɒ�~���Ă���B���������āA���̉��߂́A���ݖ��̎v�z�𖾂炩�ɂ������ł̓G�X�̌����ɖ��ɗ��B���ɂ�����ے������߂���A�G�X�̓��e�����炩�ɂȂ�̂ł���B����A���ɂ�����c�Ȃ�u����������́A����̖h�q��m�邱�Ƃ��ł���B �]�ڂ̉��߂����䕪�͂ƃG�X���͂ɕ����邱�Ƃ��ł���B�u���҂����͎҂ɑ��Čo�����邠����Փ��������A�]�ڂƂ�����̂ł���B���̋����͂��̂Ƃ��̕��͏ɂ������ĐV�������肾���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B���̋����͏������Ƃ��\�\�ق�Ƃ��ɑS���c������̑ΐl�W�ɋN���������A���͒��ɔ��������̂��߂ɍĐ����ꂽ���̂ɂ����Ȃ��B�v(��.24)�B���̂��߁A�]�ڂ͊��҂̉ߋ��̏�I�o����m��̂ɓs�����悢�B�]�ڂ͎���3�ɕ�������B ���D����]�ځF�@���҂͕��͎҂ɑ��āA���A�����݁A���i�A�s���̂悤�Ȍ��������������A�����̊������������Ă���Ǝv���B�����̊���̌���́A�c�����̊���W�A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�⋎���R���v���b�N�X�̒��ɂ���B���̓]�ڂ���A�c�����̏Փ������𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���B ���D�h�q�̓]�ځF�@�c�����̏Փ������łȂ��A���̎��̖h�q�@�܂ŋ����I�ɔ�������B���̏ꍇ�A���͂̏œ_���Փ��������̏Փ��h�q�̋@�\�ɁA�܂�G�X���玩��Ɉڂ��ق����悢�B���̓]�ڂ����߂��邱�Ƃ́A�G�X�̓��e�����łȂ�����̊��������炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���̂��B ���D�s�ׂɈڂ��ꂽ�]�ځF�@���퐶���ł͎���̕��������̂����A���͏ł̓G�X�̕��������Ȃ�悤�ɂ��ނ�����B�]�ڂ������Ȃ�ƁA�]�ڂ̊���Ɋ܂܂�Ă���Փ���h�q���A���퐶���̍s�ׂɌ����͂��߂�B���̍s�ׂ����߂���A�����G�X�ɋ������ꂽ���ۂ̃G�l���M�[�ʂ����炩�ɂ��邱�Ƃ��ł��邪�A����͖h�q�̓]�ڂ�舵���ɂ����A���ÓI�ɗ��v�̏��Ȃ����̂ł���A�������˂Ȃ�Ȃ��B �����̐��_���͂ɂ����ẮA����̑啔�������ӎ��I�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��킩��A���䕪�͂��d�v�Ȃ��̂ƂȂ��Ă����B�������A����̒�R����͂��Ă���A�G�X�̓��e�͋]���ɂ��ꂴ��Ȃ����A���x�̓]�ڂ͑����̍ޗ�����邪�A�s�ׂɈڂ����Ε��͏��z�������̂ɂȂ�A���ÊW���C�����邱�Ƃ�����ɂȂ�B���䕪�͂ƃG�X���͂̃o�����X���厖�Ȃ̂ł���B�@ |
|
|
��3�� ���͂̑ΏۂƂ��Ă̎���̖h�q����
�u���͎҂̉ۑ�́A���ӎ��I�Ȃ��̂��ӎ��I�ɂ��邱�Ƃł���B���ӎ��I�Ȃ��̂́A�G�X�A����A������̂�����̗̈�ɂ��ӂ��܂�Ă���B�ǂ�ȗ̈�ɂӂ��܂�Ă��悤�ƁA�Ƃɂ����A���ӎ��I�Ȃ��̂��ӎ��I�ɂ��邱�Ƃ����͂̉ۑ�ł���B���͎҂͂�����̗̈�ɂӂ��܂�Ă��閳�ӎ��I�Ȃ��̂ɂ��A�����ɁA�q�ϓI�ɒ��ӂ��ނ���K�v������B�v(p.36)�B �������R�͎���̖h�q�H�삩��N���Ă��邽�߁A��R�Ƃ��Ă��������̂͂��ׂĎ��䕪�͂ɖ𗧂B�܂��A����͏Փ��ɂƂ��Ȃ��Ă������ɑ��Ă��A�}���A�u�������A�]�|�̂悤�Ȗh�q�@�𗘗p���ď�̕\�o��h�����Ƃ���B���������āA��̕ω����玩���m�邱�Ƃ��ł���̂��B����̖h�q�������ł�����������́s���i�t�ł���B���i�͉ߋ��ɂ����ĉ����ł������h�q�ߒ��̖��c��ł���A����h�q�ߒ����J��Ԃ���邱�Ƃʼni��������A�����ɖh�q���ׂ����痣��ās���i�̑��b�t(���C�q)�ɂ܂Ŕ��W����̂��B���i�̑��b�͂���ꍇ�A�h�q�@�͋Ìł����p�ł�����������Ȃ����A�ӎ��ɂ����炷���Ƃ͓���B ����̐_�o�ǂƓ���Ȗh�q�@�̊Ԃɂ͋K���������W������B�Ⴆ�A�q�X�e���[���҂͏Փ��̐N���ɑ��āA�}���ɂ���ĊϔO�\�ۂ��ӎ�����r������B�����_�o�ǂ̏ꍇ�́A�Փ���S�̂̕�������藣���A�ϔO�\�ۂƏ���u�����Ă��܂��B �������͂ɂ����Ă͎��R�A�z���g���Ȃ��Ƃ������_������B�G�X�̏��͎��R�A�z�łȂ��Ƃ��A�Ⴆ�Ζ���V�Y�A�`��Ȃǂ��痝�����邱�Ƃ��ł��邪�A���R�A�z���g��Ȃ����͂́A���͂̍��{�K��(����̎���)�ɂ���Đ����銋���ݏo�����Ƃ��ł��Ȃ��B���̊�����������ɒ�R�������A�h�q�����𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��ł���̂ł���B�܂�A�������͂̓G�X���͂ɂ͋������A���䕪�͂ɂ͎ア�A�Ƃ������Ƃ��B�C�M���X�w�h�͎����̗V�Y���l�̎��R�A�z�Ɠ��i�Ɉ�������ƍl���A�V�Y�̒��f�����R�A�z�̒��f�Ɠ����悤�Ɍ��Ȃ��A����̖h�q�𖾂炩�ɂł���Ǝ咣���Ă���B�������A����͏ے����߂��ɒ[�ɂ܂ł��������߂�댯������̂œK���ł͂Ȃ��B���R�A�z���g���Ȃ��Ƃ������_�́A��̕ω��̕��͂ɂ���ĕ₦�悢�B�Ⴆ�Η��_���邩�Ǝv���Ɩ��S�ł�������A���i���邩���ɐe�ł���ꍇ�A�ʏ�̏�̕ω���W���鎩��̖h�q�������Ă���ƍl������̂��B�@ |
|
|
��4�� �h�q�@�\
�t���C�g���h�q�Ƃ������t���ŏ��Ɏg�����̂́u�h�q�����_�_�o�a�v(1894)�����A���̌�A�h�q�Ƃ������t�͂��܂�g�p���ꂸ�A�}���Ƃ������t���g����悤�ɂȂ����B�������A�u���~�A�Ǐ�A�s���v(1926)�̕⒍�ŁA�t���C�g�͖h�q�Ƃ����T�O���������A���䂪���p�����i��ʂ�h�q�ƌĂق����悢�A�}���͖h�q�̈�킾�Əq�ׂĂ���B�����āA����̏Ǐ�Ɠ���̖h�q�@�ɂٖ͋��ȊW�����邱�Ƃ��A���łɃt���C�g�ɂ���Ď�������Ă���̂ł���B�Ⴆ�A�q�X�e���[�ɂ͗}���A�p���m�C�A�ɂ͓��e�A�����_�o�ǂɂ͓]�|�����p�����̂��B����̖h�q�@�́A�ލs�A�}���A�����`���A�u���A�ŏ����A���e�A������A���r�h�[�̎��Ȃւ̌��������A�]�|�A�����邢�͒u�������A�Ƃ����\��ނ��l�����Ă���B �Ⴂ�w�l�̎���F�@�ޏ��͌Z��̉e���Œj���A�]�ɋꂵ�߂��A���i�S�����e�Ɍ������G�ӂ������Ă����B�������A����ł͈���������������߂ɁA���̓G�ӂ͕�e�������s���������N�����A�������������ᔻ����悤�ɂȂ�B���̈����̖��������������������邽�߂ɁA�ޏ��͑����݂̊�����ȊO�̑��l�Ɍ�����(�u������)�B�������A���̒u�������ł͊����͏\���ɉ�������Ȃ��������߁A�����݂���Ɍ�����悤�ɂȂ�(���r�h�[�̎��Ȃւ̌�������)�B���x�͎��s�I�X���������Ȃ������߁A���������l��ł���̂ł͂Ȃ��A���l��������ł���̂��A�Ɗm�M����悤�ɂȂ�(���e)�B�������Ĕޏ��͍߈������������ꂽ�̂����A������Ă���Ƃ��������������Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ����B���e�Ƃ����h�q�@�\�𗘗p�������Ƃ́A�ޏ��̐��i�Ƀp���m�C�A�̍�����������ƂɂȂ����̂ł���B �����ޏ��������݂�}���ɂ���ĉ������A�g�̓I�Ǐ�ɓ]������Ă����Ȃ�A�q�X�e���[�ƂȂ��Ă������낤�B�����悤�ɑ����݂��}������Ă��Ă��A�}�����ꂽ���̂��t�߂肵�Ȃ��悤�ɔ����`��������Ă�����(�܂��ɉߓx�ɂ₳�����Ȃ��Ă�����)�A�����ċ����I�ȋV���ɂ���čU���Փ����������Ȃ��悤�ɖh�q����Ă�����A�����_�o�ǂƂȂ��Ă�����������Ȃ��B���䂪�}���𗘗p����Ȃ�A�����͉�������邪�q�X�e���[�⋭���_�o�ǂɂȂ��Ă��܂��B�}���͑��̖h�q�@�ɔ�ׂ�ƓƓ��Ȉʒu���߂Ă���A����ȏՓ����������������邱�Ƃ��ł���̂����A��I�A�Փ��I��������ӎ��I�Ȃ��̂͒Ǖ�����A����̓����͂Ȃ��Ȃ�A�i�v�ɐl�i�̓����j��댯��������B���̂��߁A�_�o�ǂɂȂ�₷���̂ł���B ���łɃt���C�g���w�E���Ă����悤�ɁA�G�X�A����A�����䂪���������S�I�̐��ŗ��p�����h�q�@�ƁA����ȑO�̖h�q�@�ł͈Ⴂ������B����ƃG�X���������Ă��Ȃ���Η}���͖��ɂȂ�Ȃ����A�}���⏸�͔��B�ߒ��̌���Ɏg�p�����B�ލs�A�]�|�A���r�h�[�̎��Ȃւ̌��������́A�����炭���B�I���قɊւ��Ȃ��A�Փ��Ɠ������炢�Â����̂ł��낤�B���e�������́A����ƊO�E���������Ă��Ȃ���Η��p�ł��Ȃ��ƍl������B�������A�C�M���X�w�h�ɂ��A���䂪�O�E���番������͓̂��e�������̋@�\�ɂ����̂ł���B�@ |
|
|
��5�� �s����댯�ɂ��ƂÂ��h�q�ߒ��̊T��
��l�̐_�o�ǂ̏ꍇ�A���䂪�Փ��������̂͒����������Ă���̂ł���A����̖h�q�͒�����ɂ��ƂÂ��s���ɂ���Đ����Ă���B������͗��z�I����\���A���̊�ɏƂ炵�Đ��~���֎~���A�U���Љ�I�ł���ƌ��߂���B����͓Ɨ����������A������̊�]�𐋍s���铹��̈ʒu�Ɋi���������̂ł���B����͕K��������]��F�߂Ȃ��킯�ł͂Ȃ����A�����䂪�Փ��̖������֎~���Ă��邽�߁A���̖��߂ɕ��]���āA�G�X�ƍR��������Ȃ��̂��B �u�����A�_�o�ǂ�������̏s���������������̂ł���Ȃ�A�q�ǂ��̗{��������Ă���l�X���A�����A�ߓx�Ɍ��i�Ȓ�������`������悤�Ȃ��Ƃ́A�ǂ�Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤�ɂȂ�悢�A�Ƃ������ƂɂȂ�B�v(p.70)�B�q�ǂ��͓��ꎋ�ɂ���āA���e����{�ɂ��Ē���������̂ŁA���e�͎q�ǂ��ɑ��A�ɒ[�Ɍ��i�ȓ����I�|����������ׂ��ł͂Ȃ��B�U�����ɂ��Ă��A�O�E�ւ̂͂������K�v�ł���B��������A�q�ǂ��͑�l�ɂȂ��Ă��c�E�Ȓ�����̕s���ɋ������ɂ��݁A�_�o�ǂɂȂ�S�z���Ȃ��A�Ƃ����l����������B�������A��������(���C�q��ꕔ�̋���҂ɂ��)���z�́A�����I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ۂɂ͒�����ɊW�Ȃ��_�o�ǂɂȂ�ꍇ���邱�Ƃ́A�c���_�o�ǂ�����Ζ��炩�ł���B �q�ǂ��̐_�o�ǂ̏ꍇ�A�Փ��ɑ���h�q�͒�����̕s���ł͂Ȃ��A�����̕s���ɂ���ċN�������B�c���̎���́A�{�炵�Ă���l�������Փ��̖������֎~���邽�߁A�������������I�Ȕ�(���ɋ���)�������̂ł���B�d�v�Ȃ̂́A�O�E����̕s���ł��낤�ƁA������̕s���ł��낤�ƁA�s���ɂ���Ėh�q�ߒ����N����Ƃ������Ƃ��B�܂��A������◼�e�̉������Ȃ��Ɗ�����ꍇ�A�����ďՓ����ߓx�ɋ����ꍇ�ɂ����Ă��A����̕s���������A�_�o�ǂɂȂ邱�Ƃ�����B����̕s���́A�ǐS�̕s���⌻���̕s���ɂ���āA���i�͉B����Ă���̂ł���B �u���͂Ƃ������ẤA���҂̖h�q���Ƃ�̂����A����܂Ŗh�q����Ă����Փ��̋����������炽�߂Ĉӎ��ɂ����炵�A���䂪�������Փ����Ƃ����Ƃ����S�Ȃ������Řa���ł���悤�ɂ��邱�Ƃł���B�v(p.79)�B�h�q��������̕s���ɂ���ċN���Ă���ꍇ�́A�����͑S���S���I�Ȗ��ł��邩��A�����䂪�����Ȃ��̂ɂȂ�Θa���͗e�Ղł���B�c���_�o�ǂ̂悤�Ɍ����̕s�������ł���ꍇ�́A�{��҂̑ԓx�ύX���K�v�ł���B���͎͂�������߂�ꍇ������Ύ�߂邱�Ƃ�����B��������߂邱�Ƃ��ł���A���Â͐����Ɍ������Ă���̂ł���B�@ |
|
| �����ҁ@�����̕s���⌻���̊댯��������� / �c�����̖h�q | |
|
��6�� ��z�ɂ����錻���۔F
�h�q�̐��_���͓I�����́A�G�X�Ǝ���̊���(�q�X�e���[�A�����_�o�ǂ̕���)�ɂ͂��܂�A���Ɏ���ƒ�����̊���(�������R���[�̕���)�A����ƊO�E(����)�̊���(�������|�ǂ̕���)�ւƁA���̌�����i�߂Ă����B���ɗc�����͐g�̓I�Ɏキ�A�N���ɗ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�����̕s����댯�ɂ��炳��₷���B�ł́A�c���͂ǂ̂悤�ɊO�E�ɑ��Ėh�q����̂��낤���B �n���X�̓������|�ǁF�@�n���X�͕�������A���ɂ͎��i�̂��߂ɍU���I�ł������B�������A���������Ă������̂ŁA�U���I�Փ��̔��Ƃ��āA�����͋��������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����s�����������B���̋����s���������̕s���Ɠ����悤�ɋ��낵���������̂ŁA�܂��s�u�������t�Ƃ����h�q�@�����p���ꂽ�B���ɑ���s���͓����ւ̕s���ɒu���������A���ɑ��鋰�|���s�]�|�t���āA�����甗�Q����Ă���Ƃ����s���Ɋ������B����ɁA���O���̓����ł���A���ݐ���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����s���ɂ܂Łs�ލs�t�����B�������āA��ւ̋֎~���ꂽ����A���ɑ���U���Փ��͈ӎ�����������̂����A�����s���̓E�}�ւ̋��|�Ƃ��Ďc��A�ˊO�֏o�邱�Ƃ�f�O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�n���X�̋��|�ǂ��������߂ɂ́A�s�����E�}�Ƃ͊W�Ȃ����Ƃ������A���̌�ŕ��������K�v���Ȃ����Ƃ������K�v������B�������A�n���X�͋��|�ǂ�����������A�����g��(����)�����������ƂŁA���ւ̎��i�A�U�����͎c���Ă����B���̂��߁A�n���X�́u���ǍH���B�����ŐK�Ɛ�����ʂ��Ƃ�A���傫���A��藧�h�Ȃ��̂ɂ�������v�Ƃ�����z(���Ɠ������������z)�ɂ���āA������۔F���A�����̊�]�������̂ł���B ��l�Ɠ����ꎋ���邱�Ƃ́A����Ȏq�ǂ��ł��悭������B����7�̏��N�́A�n���X�Ɠ����悤�ɕ��e��(���C�I��)�Ɠ��ꎋ���邱�ƂŁA���ւ̕s�����ɒu�������A��z�̒��Ń��C�I�����������炷���Ƃŕs�����������Ă���B�܂�A��z�ɂ���Č����̕s����۔F���邱�ƁA���ɓ�����z�ɂ���ĕ��ւ̕s�����������邱�Ƃ́A�q�ǂ��ł͂悭���邱�ƂȂ̂��B���������������́A�₪�Ď���̌��������̗͂������Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����A�������̏������߂��鍠�ɂ͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�@ |
|
|
��7�� ���t��s�ׂɂ����錻���۔F
��l���q�ǂ��ɗ^�����т̂����A�����̂��̂͌����̔۔F�ɂ���Ă���o�����B�������q�ǂ��Ɂu�Ȃ�Ƒ傫����ł��傤�v�ƌ����A�����͋t�ł���̂ɁA�u��������̂悤�Ɂv�����A�u�����̂悤�Ɂv�E�����A�Ȃǂƌ����B�q�ǂ������������Ɓu�����悭�Ȃ����v�ƌ����A�q�ǂ��������ȐH�ו����Ɓu�����Ƃ��܂����Ȃ��v�Ƌ����A�N�������Ȃ��Ȃ��Ď₵����Ɓu�����A���Ă���v�ƌ����B�q�ǂ��̂ق����A���������Ԃߕ��𗘗p����悤�ɂȂ�A�ꂵ�����Ƃ�����Ɓu�Ȃ�Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������܂��Č����A��e���������炢�Ȃ��Ȃ�Ɓu�}�}�A��������v�ƙꂢ���肷��B�������A���������q�ǂ��̋����I�����۔F�́A���̊����瓦��悤�Ƃ�����̂ŁA���ꎩ�g�a�I�Ȑ��i�������̂ł͂Ȃ��B �����_�o�ǂɂ����ẮA�����`�����֎~���ꂽ�Փ��������t�]���A�}���͔����`���ɉ�������Ĉ��肷��B�q�ǂ�����z�A���t�A�s�ׂɂ���Č�����]�|����ꍇ���A�����悤�ȕs���̉������ł���B(�����A�_�o�ǂ̏ꍇ�͓��݉����ꂽ��������肾���A�q�ǂ��̏ꍇ�͊O�E�ւ̖h�q�ł���Ƃ���ɈႢ������)�B���t��s�ׂɂ�錻���۔F�̖h�q���@�́A��z�ɂ����錻���۔F�Ɠ��l�A����̌��������̗͂������Ȃ鍠�ɂ͗��p�ł��Ȃ��Ȃ�B�������A��z�Ȃ�N�ɂ��m���邱�Ƃ��Ȃ����A���t��s�ׂ͊O�E�ɕ\�o����邽�߁A�O�I�����ɂ���Ă�萧�������̂ł���B�@ |
|
|
��8�� ����@�\�̐���
�����۔F�Ɨ}���A��z�Ɣ����`���̊Ԃɂ͗ގ��_������B�O�E�̕s���Ɠ��E�̕s��������悤�Ƃ�����@�̊Ԃɂ́A���镽�s�W������̂��B�q�ǂ������������������Ă���ƁA�����۔F�̂悤�ȕ��@��p���Ȃ��Ă��A�O�E�̕s��������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B���ۂɕs���ɂȂ�悤�ȏ�ʂ�����邱�Ƃ��ł��邩�炾�B���ɑ��l�̗D�ꂽ���т����邱��(�V�т�^���A���Ȃ�)�́A���e(���̎q�̏ꍇ�͒j��)�ւ̗��A�������傫�Ȑ���ւ̎��i�Ɍq�����Ă��邽�߁A���̊������~�߂邱�ƂɂȂ�B(�� �A���i�E�t���C�g�͋����R���v���b�N�X�̍l���P���Ă��邽�߁A����̗���������s����y�j�X�A�]�ɊҌ�����X��������A���G�ɂ��Ă��܂��Ă���)�B�����̊����𐧌����A�s���Ȃ��Ƃɑ������Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁA���������@�\�̐����Ƃ����B ����@�\�̐����́A�_�o�ǂ̐��~�Ƃ̊Ԃɕ��s�W��������B�_�o�ǂ̐��~�͋֎~���ꂽ�Փ����s�ׂɈڂ���Ȃ��悤�ɖh�q���Ă���̂ł���A����͊����ς���Ă��ω����Ȃ����A����@�\�̐����͊O�E�ɑ���h�q�ł��邽�߁A���̏����ɂ���ĕω�����B���~�̔w��ɂ͏Փ��I��]�����邽�߁A�P���Ȑ��~�ŊԂɍ���Ȃ��Ȃ�Ɛ_�o�ǂɂȂ�̂����A����@�\�̐����̏ꍇ�A���~�̂悤�Ȋ����͋N���Ȃ��B����͊O�E�̕s��������邱�Ƃ��ړI�Ȃ̂ł���A���䔭�B�̐���ȉߒ��Ȃ̂ł���B�������A�ߓx�ɓ������肵�Ă���A����͎���̕n�����A�_�o�ǓI�Ȑ��~�Ɍq�����Ă��܂��B���̂��߁A�ŋ߂̋���w�̂悤�Ɏ��R�����^��������́A�����čD�܂������Ƃł͂Ȃ��B�@ |
|
| ����O�ҁ@�h�q�̓�̗ތ^ | |
|
��9�� �U���҂Ƃ̓��ꎋ
�s���ꎋ�t�͒�����̌`���ɕK�v�ȋ@�\�ł���Ɠ����ɁA�Փ��̍����ɖ𗧂��Ă���B�Ⴆ����`�b�N�Ŋ炪�Ђ��鏭�N�́A�����ނ�{���Ă����搶�̊���ɂ�������ł��������A�H�������Ă������鏭���́A�H��̊i�D�����ĕs�����������Ă����Ƃ������Ⴊ����B�����ɂ͍U���҂Ƃ̓��ꎋ��������B�q�ǂ��͕s����^����l�̑�����������A�U����͕킷�邱�ƂŁA���|��^������҂��狰�|��^����҂ɕω����A�s������������̂��B �U���҂Ƃ̓��ꎋ�͒�����̔��B�ɕK�v�ȑO�i�K�ł���A�����̍s�ׂɑ��鑼�l�̔ᔻ����݉����邱�ƂɌq�����Ă���B�u�q�ǂ��͂��������̓��݉��̉ߒ������A���������炵�Ă����l�̓����������̂��̂ɂ���悤�ɂƂ����A���̐l�����̑�����ӌ��������̂��̂Ƃ��A��������`������ɕK�v�ȍޗ������炩���ߏ������Ă���̂ł���v(p.144)�B�������A���̓��݉������ł͎��Ȕᔻ�̔\�͂͌`������Ȃ��̂ŁA�q�ǂ��͔ᔻ���O�E�Ɍ����Ă��܂��B�ᔻ�����ꂽ�u�ԂɁA�����̍߂𑼐l�ɂȂ�����Ă��܂��̂��B���̖h�q�@�\���s���e�t�Ƃ����B �ᔻ���錠�Ђ���Ƃ��Ď�����A�ւ���ꂽ�Փ������𑼐l�ɓ��e���邽�߁A����́A�ŏ��͑��l�ɑ��Ă̂��i�ɂȂ�B���l�ւ̔��͍߈����̐��Ȃ̂��B�u�^�̈Ӗ��ł̓����́A������̔ᔻ�Ɠ����悤�ȈӖ������悤�ɁA�Ƃ�����ꂽ�ᔻ�����݉����A���̂��߂ɁA���䂪�����̉ߌ�����o����悤�ɂȂ�Ƃ��ɂ͂��߂Ă����Ă���B���̍�����A������̌������͊O�łȂ��A���Ɍ������A���l�ɑ���s���e���͎���ɂȂ��Ȃ��Ă䂭�B�v(p.148)�B��������������̔��B�ߒ��ɂ����āA���l�ւ̍U�������c���Ă���ꍇ�́A�������R���[���҂̒����䂪����ɑ��ė⍓���ł���̂Ɠ��l�A���l�ɑ��Ă��⍓�ɂȂ�B�܂��A���e���������I�Փ��ɑ���h�q�ƂȂ�ꍇ�́A���͑����݂Ɂs�]�|�t����A�p���m�C�A�I�Ȗϑz���N��������B�@ |
|
|
��10�� �@������`
���e�́A�댯�ȏՓ��������ӎ�����ƁA���̊댯������Ƃ͊W�̂Ȃ����̂Ƃ��Ă��܂��B�C�M���X�w�h�ɂ��A�܂��}���̐����Ă��Ȃ����㐔�����̍��A�c���͂��łɍŏ��̍U���I�������O�E�ɓ��e����Ƃ����B���̎����ɂ͂܂������̋�ʂ��͂����肵�Ă��Ȃ����߁A���e�����p����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ����낤�B���e�ɂ���āA����͎�����ᔻ�������ɑ��l�����悤�ɂȂ邽�߁A�l�ԊW�͑��Ȃ���B�������A�����̏Փ������𑼐l�Ɂu�����I�ɏ��n�v�����ꍇ�A�t�ɐl�ԊW�����łɂ��邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A�Փ���������㗝�l�ɓ��ꎋ�����ꍇ�A�㗝�l�̊�]�ɑ��Ă͗����������Ċ���ƂȂ�A�����ɑ��Ă͔����`���ɂ���Č������Ȃ邱�Ƃ�����B�����̏Փ��𑼐l�ɂ���Ė��������悤�Ƃ��邽�߁A�����I�s���ƂȂ�̂ł���B�Ⴆ�A�j���̖��̂��߂ɉߏ�ɐs���������A���z���q�ǂ��ɋ��߂�e�A�����̎��P�ƁA���X�^���̋Y�ȁu�V���m�E�h�E�x���W�����b�N�v�ȂǁB�@ |
|
| ����l�ҁ@�Փ��̋����ɂ��ƂÂ��s���̖h�q / �v�t�����Ƃ��� | |
|
��11�� �@�v�t���ɂ����鎩��ƃG�X
���_���͂ł́A�������͗c�������炷�łɎn�܂��Ă���ƍl���邽�߁A�v�t������ɖ��ɂ��邱�Ƃ͏��Ȃ��B�����A�v�t���͗c�������A�X�N���ƂƂ��ɁA�G�X����������A���䂪��̉�����鎞���Ƃ��čl����K�v������B����́A�G�X�͐��U��ʂ��ĂقƂ�Ǖω����Ȃ��̂����A���䂪�ω����邽�߂ł���B �c���̏ꍇ�A����͎����̊�]�����o���A�Փ��ɑ��鎩���̗͂Ȃł���قNj����͂Ȃ��B�G�X�ɑ��鎩��̑ԓx�́A�O�E���疽�߂��ꂽ���̂ɉ߂��Ȃ��̂��B�O�E�̉e���𑽂���u�悢�v�q���ƌ����A�Փ��𐧌����悤�Ƃ��Ȃ��Ȃ�u��邢�v�q�ƌ�����̂ł���B�₪�āA�Փ��̗v�����傫���Ȃ�A�����̕s���������Ȃ��Ă���ƁA���I�Ȋ�����������悤�ɂȂ�B���̊����ɂ���āA�Փ����������悤�Ƃ��鎩��̋@�\���`�������B����͂�����x�܂ŏՓ���}���ł���悤�ɂȂ�̂��B���݊��ɂȂ�ƁA����͐V�������e�A�m���A�\�͂��l�����A�O�E�ɑ��Ă�苭���Ȃ��Ă���B���e�ւ̈ˑ��ɑ����ē��ꎋ������A���e�⋳�t�̊�]�◝�z�͂܂��܂�����Ɏ��������B�������Ċ��̗v���Ɉ�v����i���I�ȑg�D�̐��A�����䂪�`�������̂ł���B �v�t���ɂȂ�ƁA�g�̓I���n�ɂ���Ċ��C��^����ꂽ�Փ��́A���Փ��Ƃ��ĐS���I�Ȃ��̂ɂȂ�B�����Ď���ƃG�X�̊ԂɐV�������I������������̂ł���B����ł������O�I�A���I�S�͍Ăѕ\�ʂɌ���A�l������Ă��������̏K���͏����A�������̂�~������A���炵�Ȃ����������A�I�o�X����c�E���������B�������A�c�������̐��~���������Ă��A���łɎ���͋����Ȃ��Ă��邽�߁A�ȒP�ɂ̓G�X�ɏ������Ȃ��B����ɁA�O����I�������������Փ��͌������A����I�����ړI�A����Ɋւ���ϔO���d�v�ɂȂ��Ă���ŁA�O����I�ȍU������c���I�|���͏�������B�����Ƃ��A���̏Փ������킩�ُ킩�͑�l�̉��l���f�ł����āA�{���͎���Ƃ͊ւ�肪�Ȃ��B�����āA�v�t���̓{���̂悤�ȏՓ��ɒ�R���Ă�������̑g�D�̐��́A��ʂɐ��U��ʂ��ĕς��Ȃ��قNj��łɂȂ�B�@ |
|
|
��12�� �@�v�t���ɂ�����Փ��̕s��
�v�t���ɂ����鎩��̏Փ��ɑ���ԓx�ɂ́A�֗~�ƒm�����������Ɍ�����B�v�t���̋֗~�́A�Փ��̂��鐫���ł͂Ȃ��A���̗ʓI�ȋ����ɑ���s�����琶���Ă���B�Փ����u���́c�c�������v�Ƃ����A����́u���O�́c�c���ׂ��łȂ��v�Ɠ�����̂��B�������A���̋֗~�����Q�ȏՓ���K�v�ł�������悤�ȏՓ��܂ŋ��ۂ���Ȃ�A�Ⴆ�ΐg�̓I�����͑S�Ĉ����ƍl���ċ��ۂ���Ȃ�A�ނ���댯�ł���B�_�o�ǂ̂悤�ȑ㏞�I�������Ȃ��̂ŁA�ˑR�ɋ֗~���̂ĂďՓ��^�M�ɕς�邱�Ƃ��������Ȃ����A�����ł��Ȃ���ΐ��_�a�Ɏ���ꍇ��������B �N�̒m�I�ߒ�����������ƁA�N���S������Ă�����́A�����̐S�̒��ɐ����Ă���S���I�����Ɠ������ł��邱�Ƃ������B���Փ��ɐg��C�����A�����������邩�A���R�Ƒ����A���Ђɑ��锽�R�Ƌ��]�A�Ƃ��������ł���B�Փ����n�l���邱�ƁA���Ȃ킿�m�����́A�֗~�ȏ�ɏՓ���}�������i�ƂȂ�B�N�̐��E�ρA�Љ�ϊv�̎v�z�́A�G�X�̏Փ��I�~�]�̒��ɐV�����~�]�������邽�߂ɍ����B�m���̋����͏Փ����������悤�Ƃ��鎩��̓w�͂ɂ����̂ł���A����I�ɕ\�����A�ӎ��I�ɓ������邱�Ƃ��\�ɂ���B�����炱���A���_���͂ɂ����Ċ����Փ��ߒ�������I�ɕ\�����邱�Ƃ����ÂɌq����̂ł���B �v�t���ɂ�����ΐl�W�͌��n�I�ȓ��ꎋ�ɂ��ƂÂ����̂������A�^�̈Ӗ��ł̑���Ƃ������̂͂��Ȃ��B���ꎋ�͎��X�ƑΏۂ�ς��邱�Ƃ��ł���̂ŁA�M��I�ɒN�����������萒�q�������Ǝv���ƁA�����ɕʂ̐l�ւƐS�ς�������̂��B�@ |
|
|
������Ɩh�q�@��
(The Ego and the Machanisms of Defense)�@1936�N�ɔ��\���ꂽ�A���i�E�t���C�g�ɂ�鐸�_���͊w�̌����ł���B���_���͂̊T�O�Ɨ��_���m�������W�[�N�����g�E�t���C�g�̖��ł���A���i�E�t���C�g�͎���Ǝ����S���ɂ��Ă̌����҂ł������B�{���͕��t���C�g�̎���Ɩh�q�̊T�O���Q�l�ɂ����咘�ł���A�t���C�g�h�̐��_���̗͂��_�W���������̂ł���B �t���C�g�h�̗��_�ɂ��A�h�q�Ƃ͂��܂��܂ȐS���I��p�ɑ��鎩��̋ꓬ�ł���B����͐l�Ԃ̐��_�ɂ����Ė��ӎ��ƊO�����Ƃ�����悤�ɓw�͂���B�h�q�@���͎��䂪���Ȉӎ�������p�ł���A�s���ɑ��Ėh�q�@�������ʓI�ɋ@�\����Ύ���A�C�h�����Ē�����Ƃ����O�̋@�ւɏ������邱�Ƃ��ł���ƍl����B�O�̋@�ւ̊W���ɂ��Đ�������A����Ƃ͎v�l���i��ӎ��̗̈�ł���A�C�h�Ƃ͖��ӎ��̗̈�A�����Ē�����Ƃ͎Љ�ʔO�⓹���K�͂��i��̈�ł���B �{�\�ł��鐫�~��\�͐�������͖��������Ƃ��邪�A������͂����W����B���̂��ƂŎ���ƒ�����͏Փ˂��邱�ƂɂȂ邽�߁A�h�q�@�����@�\�����Ď����[�������Ă���B���鏗���̎���ɂ��A�ޏ��͎���̉����Ȗ{�\�Փ��𐬐l��ɂ͈�]���Ă�������S�ɗ}������悤�ɂȂ����B����������A���l�ɂ���Ď����̗~�]�����o�������ƂŁA���l��ʂ��Ď����̗~�]��������Ƃ����h�q�@�����@�\�����̂ł���B ���̎���ł̖h�q�@�����ʂ����Ă���S���I�@�\�Ƃ͎���̗~�]�𑼎҂ɓ��e���邱�Ƃł��邪�A����Ƃ͕ʎ�ɗ}���Ƃ����h�q�@���̐S���I�@�\������B���鏭���̎���ɂ��A�ޏ��͎����̕�e�ɑ���ے�I�Ȋ����}���������߂ɔ����Ƃ��ĉߓx�ȗD�����������悤�ɂȂ�A�ƒ���ɂ͓K���ł��������_�̐����ߒ��ɖ�肪�������B�B�ʂ̎���ł͕��e�̐�������ݐ肽���Ƃ�����z����ېH��Q�ɂȂ���������������Ă���B�����̎���ł͐S���I����������������@�Ƃ��Ėh�q�@�����}�����s�������߂ɑ����ʂɖ�肪�]�ڂ����Əq�ׂ�B �t���C�g�͖h�q�@���̊ώ@�܂��Ď����̐S���ɂ��ďq�ׂĂ���A�������V�т������̒u����Ă��閳�͂ȏ�Ԃ����z�I�ɕω���������̂ł��邱�Ƃ��w�E�����B�܂��z�I�ȕ����ʂ��Ďq���͌��͂��l�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B�v�t���ɂ������҂̔��Љ�I�s�������̉�����Ɉʒu�Â��邱�Ƃ��ł���S���I�����ł���A�������I�Փ��ɑ��ēK�ɏ������邱�Ƃ��ł��Ȃ���ΐ��_�����Ɍq����Ƙ_����B�@ |
|
| �@ | |
| ���t���C�g9 �u���������̔ފ݁v | |
| ���_���͗��_�ł͐S�I�ߒ����u���������v�Ɏx�z����Đi�s������̂ƍl����B�o�Ϙ_�I�Ȋϓ_���炷��A���͋����ʂ̌����ɁA�s���͋����ʂ̑����ɑΉ�����̂ŁA�S�I���u�͋����ʂ��߂ɁA���邢�͍P��ɕۂƂ��Ƃ���(���������͍P�팴���ɗR������)�B�������A���������͎��Ȃ����ۂɂ͖��p�ł���A�댯�ł������邽�߁A����̎��ȕۑ��{�\�̉e�����āu���������v����サ�A�����������܂��͒f�O�����邱�ƂɂȂ�B�Փ��v���Ɗ댯�Њd�ɑ��锽���́A�����������A������C�����錻�������ɂ���ē������̂ł���B | |
|
�u�O���_�o�ǁv�Ƃ͐����̊댯�ƌ��т����ЊQ(�푈�⎖��)�̌�ɐ�����a�ł���A��ϓI�ȋ�ɁA����A�����Ȃǂ̒��݂��A�ЊQ�̉�z�ɐS��D����B���̏ꍇ�A����̑Ώۂւ́u���|�v���x�z���Ă���̂ł����āA�댯�̗\���ł���u�s���v�������Ƃ͂����Ȃ��B
�����N���̒j���ɂ�鎅�����V�т̗�B���̎q�͎������𓊂��Ắu�I�[�I�[�I�[�v�ƌ����A�Ђ������������Ď��������p�������Ɓu�_�[�vDa(����)�ƌ����Ȃ���A���x��������J��Ԃ����B���̗V�т͕�e�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃƌ���邱�ƂɊW���Ă���B�������������Ɓu�_�[�v�ƌ����̂́A��e������邱�Ƃւ̊��т��Ӗ����Ă���B�������A�������𓊂��邱�Ƃ͕�e�������邱�Ƃ��Ӗ����Ă���̂ŁA������J��Ԃ����Ƃ͋�ɂ��Ƃ��Ȃ��͂��ł���B����͉��������Ɉ�v����̂��H |
|
|
�u���҂͗}�����ꂽ���̂���t���]�ނ悤�ɁA�ߋ��̈�ЂƂ��ĒǑz���邩���ɁA���݂̑̌��Ƃ��Ĕ�������悤�ɗ]�V�Ȃ������B���̍Č��́A�]�܂����͂Ȃ������Ƃ������ɓo�ꂵ�āA���������̐����A���������ăG�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�ƁA���ꂩ��̔h�����Ƃ̊���������e�Ƃ��Ă���A�܂��t�ɑ���W�Ƃ����]�ڂ̗̈�ŋK���I�ɉ�������B���Â������܂Ői�߂A�ȑO�̐_�o�ǂ́A���܂�V�����]�ڐ_�o�ǂɂƂ��Ă����ꂽ�̂��Ƃ������Ƃ��ł���B�v(p.159)
��t�͊��҂ɖY�ꂽ�ߋ����đ̌������A�O����̌������Y�ꂽ�ߋ��̔��f�ł��邱�Ƃ����Ƃ点�˂Ȃ�Ȃ��̂ł���A���̈Ӗ��ł͓]�ڐ_�o�ǂɈڍs����i�K�������킯�ɂ͂����Ȃ��B���̂悤�ɔ��������̌�(��������)�́A�}�����ꂽ�Փ�������������̂ŁA����ɕs���������炷�͂��Ȃ̂����A���̖�����^������̂ł����邽�߁A���������ɂ͖������Ȃ��B�������A���������������̌����݂̂Ȃ��̌����Č�����ꍇ������B��ɂɖ������l�ԊW�����x���J��Ԃ��l�����A���邢�͍ЊQ�_�o�ǎ҂�q�ǂ��̎������V�т��l����A���������̚��O�ɂ��锽�����������݂���̂ł͂Ȃ����Ƃ������肪���藧�B�u���������̉���𐳓��Â���]�n�͏[���ɂ���A���������͉������������̂��ŁA���ȏ�ɍ����I�A�ꎟ�I�A���Փ��I�ł���悤�Ɏv����B�v(p.163) |
|
| ��������L�@�̂ɂƂ��āA�O�E�̉e���ɑ���h���ی�͎h����e�ȏ�ɏd�v�ȉۑ�ł���B�h���ی�ɂ���ĊO�E�̉e���ɂ�鋻���ʂ͗}������̂����A���̎h���ی��˔j����قNj��͂ȋ����͊O�����ƌĂԂ��Ƃ��ł���B�O�����_�o�ǂ��h���ی�̔j�]�̌��ʂ��Ɖ����Ă悢�B�O���_�o�ǂ̌����͕s���̔������r�₦�����Ƃɂ���̂ŁA�O����ʂ̋ꂵ����������̂́A�s��(�댯�̗\���Ƃ����h�q����)�W�����h���̓��������邽�߂ł���A����́u���͊�]�����v�ł���Ƃ�������̗�O�Ƃ�����(�s�����⏈���̖��͗�O�ł͂Ȃ�)�B���̖��͔��������ɂ����������̂ł���A����́u���������̔ފ݁v�����݂��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B | |
|
�{�\�Ƃ͐�������L�@�̂ɓ��݂���Ք��ł����āA�ȑO�̏�Ԃ����悤�Ƃ�����̂��ƍl����Ȃ�A���ǂ���͎��ւƌq�����Ă��邱�Ƃ��킩��B�u������O�Ȃ��̌o���Ƃ��āA�����鐶���͓��I�ȗ��R���玀��Ŗ��@���Ɋ҂�Ƃ������肪��邳���Ȃ�A�����͂����A�����鐶���̖ڕW�͎��ł���Ƃ��������Ȃ��v(p.174)�B����A���I�{�\�͖{���u���̖{�\�v�ł���A���ɓ������̖{�\�ƑΗ�����W�ɂ���B����{�\�͎����A���I�{�\�͐��̌p����������̂ł���B
�������ł́A����{�\�Ɛ��I�{�\�̑Η��́A�u���̖{�\�vTodestrieb�Ɓu���̖{�\�vLebenstrieb�̑Η��ɒu���������A�����w�I�ϓ_����̌������Ȃ���Ă���B���̌��ʁA�����w�ł͎��̏Փ���ے肵����Ȃ����Ƃ��킩�����ƃt���C�g�͏q�ׂĂ���B ���r�h�[���̔��W���T�ς��Ă݂�ƁA�܂��]�ڐ_�o�ǂ̕��͂ɂ���āu���I�{�\�v�Ɓu����{�\�v�̑Η����l����������Ȃ������B�u���v�̊T�O�͐��B�@�\�ɑ����Ȃ������̂��̂��܂��邱�ƂɂȂ������A����{�\�̂ق��͂܂����ȕۑ��ɖ𗧂{�\�Ƃ��āA�}�����A���{������̂��ƍl�����Ă����ɂ����Ȃ��B�₪�āA���r�h�[������Ɍ������邱�Ƃ����ڂ��W�߁A����𐫓I�ΏۂƂ��鎩�Ȉ��I���r�h�[�͐��I�{�\�̕\���ł���A���ȕۑ��{�\�Ɠ��ꎋ�����ɂ悤�Ȃ�̂����A����ɂ���Ď���{�\�Ɛ��I�{�\�̑Η��͕s�\���Ȃ��̂ɂȂ����B����{�\�̈ꕔ�����r�h�[�I�ł���Ƃ݂Ȃ��ꂽ����ł���B���Ƃ���A���r�h�[�I�{�\�ȊO�ɑ��̖{�\�͂Ȃ����ƂɂȂ�̂��낤���H�@�u�ہv�ƃt���C�g�͓�����B�����Ɂu���̖{�\�v�Ɓu���̖{�\�v�̑Η��Ƃ����V�����l�������o�ꂷ�邱�ƂɂȂ�B ���̖{�\�Ǝ��̖{�\�̑Η��́A�Ώۈ����̂��̂Ɍ���������B����͈�(�)�Ƒ�(�U��)�Ƃ̑Η��ł���B�ȑO���琫�I�{�\�̃T�f�B�Y���I�v�f�͔F�߂Ă������A�T�f�B�Y���͎���̎��Ȉ��I���r�h�[�̉e���ɂ���āA���䂩��͂ݏo���āA�ΏۂɌ������Ă͂��߂Č���鎀�̖{�\���Ɖ��肷�邱�Ƃ��ł��邩������Ȃ��B�܂��A�}�]�q�Y�������̖{�\�̒��ړI�Ȍ���Ƃ��āA�ꎟ�I�Ȃ��̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B �u�����͐��_�����́A����A�����炭�͐_�o������ʂ̎x�z�I�ȌX���Ƃ��āA���������ɂ����Ă���������悤�ɁA���I�Ȏh���ْ������������A���̓x�����ɂ������A�܂��͂�������̂����X��������̂�m�����B(�o�[�o���E���E�̕\���ɂ�韸�ό���Nirvanaprinzip)�B���̂��Ƃ��A����ꂪ���̏Փ��̑��݂�M��������Ƃ��L�͂ȓ��@�̈�ł���B�v(p.187) |
|
|
���������͐S�I���u�ɋ������N����Ȃ��悤�ɂ��邩�A�����̗ʂ����ɕۂ̂����A����͖��@�I���E�̐Î~��Ԃɂ��ǂ�Ƃ����A�S�����̕��ՓI�w�͂̈ꗃ��S���Ă���B���I�s�ׂ̉����͍��x�ɂ����܂��������̏u�ԓI�ȏ��łƌ��т��Ă��邪�A�Փ������́u�S���v�͏����I�ȋ@�\�ł����āA��������o�̉����ɂ����ĉ�������悤�ɒ��߂���B�����ɉ������������̖{�\�ɊW����\�����F�߂���̂ł���B�u���������́A�܂��Ɏ��̖{�\�ɕ�d������̂̂悤�Ɏv����v(p.194)�B�@ �@ |
|
| ���t���C�g10 �u�}���v | |
|
�Փ�(�~��)���ɂ��悤�Ƃ����R�ɂԂ���̂��A�Փ��̉^���ł���B�Փ��͂�������̂��Ƃŗ}���̏�Ԃɂ������B�O�I�Ȏh����p�����Ȃ�u�����v����悢�̂����A�Փ��̏ꍇ�ɂ͓����Ƃ������@�͖𗧂��Ȃ��B�u�����ŁA�̂��ɂ͔��f�̉��(����)�Ƃ����Փ��ɑR����ǂ����@�������邾�낤���A���̑O�i�K�A�܂蓦���Ƌ��ۂ̒��ԕ����}���ł���A���̊T�O�͐��_���͂̌����ȑO�ɂ͐ݒ�ł��Ȃ������v(p.78)�B
�u�}���v���N����ɂ́A�Փ��ړI��B�����邱�Ƃ������ł͂Ȃ��s������^���Ă��܂��A�Ƃ����������K�v�ł���B�}���̂��Ƃɂ���Փ��͖����̉\�����[���ɂ��邵�A���ꎩ�͉̂����ɖ����Ă��邪�A���̗v����Ӑ}�ƈ�v���Ȃ��B����͈���ł͉������A�����ł͕s���ނ̂ł���A�s���̓��@�������̉������������͂������Ƃ��}���̏����ƂȂ��Ă���B�܂��A���_���͂̌o�����炷��A�u�}���͂��Ƃ��Ƒ��݂���h�q�@���ł͂Ȃ��A�ӎ����ꂽ���_�����Ɩ��ӎ��̐��_�����Ƃ̂͂����肵����ʂ��ł���ȑO�ɂ͂��肦�Ȃ��Ƃ������ƁA�}���̖{���͈ӎ�����̋���Ɗu���ɂ����Ă̂ݐ��藧�Ƃ������Ƃł���v(p.79)�B�}���̋@����������ȑO�́A���Ε��ւ̓]���A�������g�ւ̌��������Ȃǂ��Փ���h�q���Ă����̂��B�u���_�̐R�������̍\����A���ӎ��ƈӎ��̋�ʂ������ƌo������܂ŁA�}���̖{���̐[�݂ɓ��荞�ނ̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�B�����ɂł���̂́A�}���̓�A�O�̓������L�q�I�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃ����ł���B �u�����ɂ͌��}��Urverdrangung�A�܂�Փ��̐S���I(�\�ۓI)�ȑ�\���ӎ��̒��ɓ��荞�ނ̂����ۂ���Ƃ����A�����̗}�������肷�鍪��������B����Ɠ����ɒ蒅���s�Ȃ���B�Ƃ����̂́A���̑�\�͂���Ȍ�s�ς̂܂ܑ������A����ɏՓ������т��̂ł���B����͌�ŏq�ׂ閳�ӎ��I�ȉߒ��̓����̌��ʂ�����̂ł���v�B�u�}���̑��i�K�A�܂�{���̗}���́A�}�����ꂽ��\�̐S���I�Ȕh�����Ɋ֘A���邩�A�����Ȃ��A�N���͕ʂ������̑�\�ƌ��т��Ă��܂��悤�ȊW�ɂ���v�l�X���Ɋ֘A���Ă���B���������W���炱�̕\�ۂ͌��}�������������̂Ɠ����^�������ǂ�B���������Ė{���̗}���Ƃ͌���̗}���ł���v�B���}���������̂́A����Ɗ֘A����\���̂��邷�ׂĂ̂��̂Ɉ��͂��y�ڂ��̂��B �}���͈ӎ��̑̌n�ւ̊W���������W���Ȃ��̂ŁA�}�����ꂽ���͖̂��ӎ��̒��ő������A�g�D������A�h�����݁A���т����ł�����B�Փ��̑�\���}���ɂ���Ĉӎ��̉e�����܂ʂ����ƁA���ӎ��ɂ����Ď��R�ɔ��W����̂��B����͈ł̒��ŋɒ[�ȕ\���`���������Ă͂т��邽�߁A�_�o�ǎ҂̐S�̒��ň�ƁA���҂ɂƂ��Ă͈ٕ��ɂ��������Ȃ��B�u�_�o�ǂ̏Ǐ�͗}�����ꂽ���̂̔h�����v�ł���A���₳��Ă����ӎ��ւ̒ʘH���Ǐ�`���ɂ���čŏI�I�ɏ�����������̂Ȃ̂��B(���_���͂ł́A�}�����ꂽ���̂̔h�������o���悤�ɗv�����Ă���̂ł���A���̔h�����͊u����c�Ȃ̂��߂ɁA�ӎ��̌��{��ʉ߂ł���)�B �}���͌ʓI�ł��邾���łȂ��A�����I�ł�����B�u�}���Ƃ͂������͂̏����K�v�Ƃ�����̂ł���A���̏���𒆎~������d��Ȍ��ʂ��܂˂��ł��낤����A�V�����}���̓������K�v�ƂȂ�v(p.81)�B�}�����ꂽ���͈̂ӎ����ꂽ���̂ɂ��������͂������Ă��āA����ɂ͂��������Έ��͂������A���t���ۂ���Ă���B�}���������邱�Ƃ͗͂̏�����Ӗ�����̂��B�܂��A�}���̗������́A���̌`���ɂ�������Ă���B�Փ�������������ƁA���ڂɗ}�����������̂ł͂Ȃ��A��蓹�����Ȃ���ӎ��ɓ��荞�����Ƃ���B�������A�������ɂ���ĕs���ȕ\�ۂ�������x�ȏ�ɋ����Ȃ�Ɨ}����������B�}���͕s�������炰�邱�Ƃɂ��̑㏞��������̂��B �����܂ł����́A�Փ���\���Փ����狂����ʂ̐��_�I�G�l���M�[(���r�h�[)�ł݂�����Ă���\��(�\�یQ)�Ƃ��ė������Ă������A�\�ۈȊO�ɂ��Փ����\������̂Ƃ��āu����v������B���̂��Ƃ���A�Փ��̉^���͎O��ނ��邱�Ƃ��킩��B�u�܂�A�Փ��͂܂�������������Č����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����A�Ȃ�炩�̎��I�ȐF�ʂ����т�����Ƃ��Č����邩�A�܂��͕s���ɓ]�����邩�ł���B�Ō�̓�̉\���́A�Փ��̐��_�I�ȃG�l���M�[������A�Ƃ��ɕs���ɒu�������邱�Ƃ��Փ��̐V�����^���Ȃ̂��Ɨ�������悤�ɋ����Ă���v(p.82)�B�u�����͗}���̓��@�ƈӐ}���s���������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ����Ƃ��o���Ă���B���������āA�Փ���\�̊���̉^���́A�\�ۂ̉^����肸���Əd�v�ł���A���ꂪ�}���ߒ��̕]�������肷��̂ł���B�}�����s����s���̋N����̂�h���̂Ɏ��s������A���Ƃ����ꂪ�\�ۂ̕����ł��̖ړI��B�����Ƃ��Ă��A����͎��s���Ƃ����Ă悢���낤�v(p.83)�B �}���Ƃ͈�ʂɑ㗝�`���ݏo�����̂��B�ł́A�㗝�`���ƏǏ�`������v�����Ă悢�̂��낤���B�Ǐ�`���̃��J�j�Y���Ɨ}���̃��J�j�Y���͈�v����̂��낤���B���������茾����̂́A�u���̗��҂͂܂������Ⴄ���̂ł���A�㗝�`����Ǐ�`���������̂͗}�����ꎩ�̂ł͂Ȃ��āA�܂������ʂȉߒ����甭������}�����ꂽ���̂̍Č��̒���Ȃ̂��Ƃ������Ƃł���v�B�����A�}���̃��J�j�Y���͑㗝�`���̃��J�j�Y���ƈ�v���Ȃ��B�㗝�`���̃��J�j�Y���ɂ͗l�X�Ȏ�ނ�����A���̂�����͗}���̃��J�j�Y���ɋ��ʂ���_������B����̓G�l���M�[�[��(���Փ�����ɂ���Ȃ烊�r�h�[)�̏����ł���B �s���q�X�e���[�̏ꍇ(��G�������|)�B�}���̂��Ƃɂ���Փ������́A���ɑ���s�����Ƃ��Ȃ������r�h�[�I�ԓx�ł���A�}����A���̋����͈ӎ���������Ă������A�㗝�Ƃ��āA�s���̑ΏۂɓK�������������Ɠ����ʒu���߂Ă����B�\�ە���(���r�h�[�ΏۂƂ��Ă̕��e)�̑㗝�`���́u�u�������v(����)�̓������ǂ�A���̌��ʁA���ɑ��鈤��v���͘T�ւ̕s���ɂȂ����̂��B���̏ꍇ�A�}���͎��s�������̂ƍl���Ă悢�B�}���̍�Ƃ͕\�ۂ��������Ēu�������������ł���A�s���̌y���͐������Ă��Ȃ����炾�B���̂��ߐ_�o�ǂ̊����͂����܂炸���i�K�ɐi�݁A�s���̔�����h�������̉�����s�Ȃ���B �]���q�X�e���[�̏ꍇ�B�}���ɂ���āu����v�͂܂����������Ă��܂��B(���̏ꍇ�ɂ́A�}���͂���قNJ��S�ł͂Ȃ��A��ɂȊ��o�̈ꕔ���Ǐ̂ƌ��т�����A�����炩�̕s���̔������������Ȃ��Ȃ�A���|�ǂ̃��J�j�Y��������B)�]���q�X�e���[�ł́A�Փ���\�̕\�ۓ��e�͈ӎ����犮�S�ɏ�������A�㗝�`���Ƃ��āA�_�o�x�z���N����A���ɂ͊��o���A���ɂ͉^�����̐����������A�����܂��͐��~�Ƃ��Č�����B�ߓx�ɐ_�o�x�z���ꂽ�ꏊ�́A�}�����ꂽ�Փ��̑�\���̂̈ꕔ�Ȃ̂��B�u�q�X�e���[�̗}���́A���ꂪ�[���ȑ㗝�`���ɂ���Ă̂݉\�ł��邩����A���S�Ȏ��s���Ɣ��f����Ă��d�����Ȃ��B�������}���̖{���̉ۑ�ł������̏����Ƃ����_�ł́A�q�X�e���[�͈�ʂɊ��S�Ȍ��ʂ������߂Ă���B���̏ꍇ�]���q�X�e���[�̗}���ߒ��́A�Ǐ�`���ŏI�����āA�s���q�X�e���[�̂悤�ɓ�i�K�Ɂ\�\�܂��͖����Ɂ\�\�Â��K�v���Ȃ��v(p.85)�B �����_�o�ǂ̏ꍇ�B�u�ލs�v�ɂ���āA��I�ȗ͂��T�f�B�Y���I�ȗ͂ɂ�����Č����邽�߁A�}�����ɂ���̂����r�h�[�I�ȗ͂Ȃ̂��G�ӂ��������͂Ȃ̂��͂����肵�Ȃ��B������l�ɑ���G�ӂɖ������Փ����}�����ɂ���̂��B�u�܂��}���̎d���͊��S�Ȑ��ʂ������߁A�\�ۓ��e�͋��₳��ď�͏������Ă��܂��B�㗝�`���Ƃ��Ď���̕ω��A�܂�A�Ǐ�Ƃ͂����Ȃ��悤�ȗǐS�̍��܂肪������B�����ő㗝�`���ƏǏ�`���͕������Ă��܂��v�B�}���̓��r�h�[�̏����������炵�����A���̖ړI�̂��߂ɁA�����`���A���Ε��̑����Ƃ������@���g�����̂��B�u�������A���߂͂��܂��䂭�}���������������A�o�߂��i�ނɂ�Ď��s�������Ȃ��Ă���B�����`���ɂ���ė}�����������������́A�}�����ꂽ���̂��Č��ł���ꏊ�ł�����B���ł�����́A�Љ�I�s���A�ǐS�̕s���A�e�͂Ȃ����Ȃǂɕω����Ăӂ����ь����Ă���v�B���ۂ��ꂽ�\�ۂ͒u�������ɂ���đ㗝�����B�������A���̕\�ۂ͈ӎ��ɂ���Ď��X�ɋ��ۂ��ꑱ����B�u�����ŋ����_�o�ǂ̗}���̎d���́A�Ȃ����ʂ̂Ȃ��A�I��邱�Ƃ̂Ȃ��ւ�`���̂ł���v�B�@ �@ |
|
| ���t���C�g�Ɛ��_���� | |
| ��1.���_���͑O�j�@ | |
|
�����X�����Y���Ɠ������C
�t�����c�E�A���g���E���X����Franz Anton Mesmer �@1734�`1815�B�X�C�X�ƃh�C�c�̍����߂��Ő��܂ꂽ�B�������C�ɂ�鎡�Ö@�ł��郁�X�����Y���̑n�n�ҁB���߁A�_�w���w�сA��ɁA�E�B�[����w�ɓ����Ĉ�w���w�сA�E�B�[���ň�҂ƂȂ�B(�w�ʘ_���̃^�C�g��-�u�l�̂̎����ɋy�ڂ��f���̉e���ɂ��āv)���X�����͈�҂��J�Ƃ��A���������S�l�ƌ������A�傫�ȉ��~�����܂����B�����l�Ԃ̉^�����x�z����Ƃ����萯�p�̌��������̗͂ɂ���Đ������悤�Ƃ��āA����p���Đl�Ԃ̑̂�����������Ȃł��肵�Ă��邤���ɁA�Ö���Ԃ��N�������Ƃ������B�����āA������l�Ԃɂ����̓����Ɏ�����p�����u�������C�v������ƍl����悤�ɂȂ�B���������̍l�����́A�E�B�[���Ŕ�����A1778�N�p���ɍs�����B(����ɁA�u�������C�Ö@�v���Z�N�n���^�f��������ꂻ�ꂪ�X�L�����_���ƂȂ����v�Ƃ��A�A)�u�Ȋw�u�[���v�ɕ�����Ă����p���ł́A�����Z��n�̐^�ɐf�Ï����J���A�ނ́u�v���I�V��p�́v�͑哖����A�M����u���W��������𐬂��ĉ����������B��l�ЂƂ�����Â��Ă���ɂ̂Ȃ��Ȃ������X�����̓o�P(�傫�ȃJ�V�̉�)���g�����W�c���Â��n�߂��B���̓������o�P�̒������ɃK���X��A�S�̕t���i�����Ă����B���̉������20�{�قǂ̓S�_���o�Ă��āA���҂����͂��������B�a�l(�q�X�e���[���ғ�)�������A�R�Ō��э��킹�A�d�C��H�̂悤�Ȃ��̂�����B���̉�H�����C�������A�Ƃ������̂������B���y��Ɩ��A���Ȃǂ̒��x�i�A�ގ��g�̊�ȕ���(���c�̂悤��)��ԓx�Ȃǂɂ���āA���҂͔�����N�����A�����Ă��̔��삪�����܂�ƏǏ����Ă���̂������B(���̂悤�ɐl�H�I�ɔ�����N�����Ǐ�����ł����鎡�Ö@���u�����@�v�Ƃ����B)�t�����X���{�́A�w�҂Ȃǂ���Ȃ���ʂ̒����@�ւ�݂��Ē��ׂ����ʁA�Î��ɂ��Ö���Ԃ̑��݂͔F�߂�ꂽ���A�������C�Ɠ����悤�ȍ�p�����������C�̑��݂͔ے肳��u�y�e���v������������ꂽ�B�ނ̂ق�����ϋɓI�ɓ������C�̑��݂𗧏ł��Ȃ��������߁A����ɕs�]���ɂȂ�A�X�C�X�ɋA���ĖS���Ȃ����B�Î��Ö@�̑n�n�҂Ƃ����B ���X�����́A���Ǝ҂��Ɏ����g���Č��ʂ��������b���Ď����ł����Ɏ����ꂽ�킯�ł��邪�A���Ì��ʂ������炷�͎̂��C�ł͂Ȃ��A���m�Ō����u�C�v�̂悤�Ȃ��̂��낤�ƍl���A������u�������C�v�Ɩ��Â����B�u�������C�͉F�������Ă��āA���ꂪ�l�ԁE�n���E�F�����A�����Đl�Ԃǂ�����}��Ƃ��Ă���A�l�̓����ɂ��闬�̂̕��z���s�ύt�ɂȂ�ƕa�C�ɂȂ�B���������āA�������C�Ö@�ɂ���āA���C���̂̋ύt������Εa�C�͎���v�̂ł���B ���̂悤�ȉ��z���̂��S�����Ă���Ƃ������z�́A�t���C�g�̃��r�h�[�̊T�O�ւƌp�������B�@ |
|
|
�����X�����Y��������p��
���X�����͖��m�ɂ͂��Ȃ��������A�u�l�Ԃ��l�Ԃ������v�Ƃ������_�Ö@�̑O���̎���ɔF������n�߂��B ���z���́��u�������C�v�@�u���C�́v�������E�e�� ���C�͂̋����l���������Âł��� ���X�����̔����́A���̒�q�s���C�[�M���[�����݂��p�����B �s���C�[�M���[���́A�ċz�����ɔY��ł����N�Ɏ��C�Ö@���قǂ������B����ƐN�͊�Ȑ�����ԂɊׂ����B�u�������悤�ȁv�A�u�o�����Ă���悤�ȁv�A�u�ʂ̐l�i�v�������ꂽ�̂��m�F�����B�����Ă��̏�Ԃɂ���Ƃ��́A���݂́u������܂܂Ɂv�s�����A���̏�Ԃ���o�߂�ƁA�u���C�����v��Ԃɂ����Ƃ��̋L���͈�Ȃ������B ���݂͂��̎��C������Ԃ��u�l�����V�a�v�Ɩ��������B (��ɁA�C�M���X�̈�t�u���C�h�͂�����u�Ö��@hypnotism�v�Ɩ����B)�@ |
|
|
���V�����R�[�ƃq�X�e���[
�p���̃T���y�g���G�[���a�@(�t���C�g�����w�����a�@)�́A�������̐��_�a�@�ł���Ɠ����ɁA�z�[�����X���e���ł��������B�����A4��l�ȏ�̏��������e����Ă���A����500�l�ɂ���t��l�A��������10���ȉ��A�N��200�l�`300�l�̐��_�a���҂��S���Ȃ��Ă����B �����̉@���W�����E�}���^���E�V�����R�[�́A�������d���ǂ�؈ޏk�������d����(�V�����R�[�a)�̌����Ȃǂő����̋Ɛт��c�����l�ł��邪�A�����ɍÖ��Ö@�̑�Ƃł���A�q�X�e���[�̐��Ƃł��������B �V�����R�[�@Jean Martin Chrcot�@1825�`93�N�@�t�����X�̐��_��w�ҁ@�q�X�e���[����эÖ��p�Ɋւ���u�`�ɂ���Đ��E�I�ɒm��ꂽ�B�ނ́A�k�����(�̂��k����a�C�Ŕގ��g������ɂ�����n�߂Ă���)�̔����A�������d���ǁA�V�����R�[�a(�V�����R�[�͔]�Ґ��d���ǂƂ���؈ޏk�������d����)(�Ґ��𒆐S�ɁA�]�玿����ؓ��ɂ�����^���_�o�H�̕ϐ�������a�C)���́A�Ǐ���D �V�����R�[���킭�u��Âɂ����Ĉ�t���A���łɂ킩���Ă�����̂����ɒ��ڂ���̂͂������Ȃ��̂��v�A�u�V�����A�܂�V�����a�C(�Ƃ����Ă����ۂ͐l�ޓ��l�ɌÂ����̂���)�Ɋ��������Ƃ������Ƃ͂��炵���v ���_�a���w�A�S���Ö@�A���_���͂Ȃǂɑ傫�ȉe����^�����B�ނ̖剺�ɂ́A�r�l�[�A�t���C�g�A�W���l�[��������B�@ |
|
| ��2.�Ö��p���琸�_���͂ց@�@ | |
| ���w����A�����t���C�g�́A�A�p�[�g�����g����ĊJ�ƁA�Ö��p��p���Ď��Âɂ��������B(���҂͂قƂ�ǂ��������̏����ł������B)�������A�Ö��p�͂�����₷���l�Ƃ�����ɂ����l������B����̓t���C�g�ɂƂ��Ă��Ȃ�d�v�Ȗ��ł������B(�Ö��p�Ŏ��Âɂ������t�ɂƂ��āA�Ö��p�ɂ�����Ȃ��l�����āA���ꂪ�\�ɂȂ�ƒv���I�Ō���������B)�������ăt���C�g�͂������ɍÖ��p���牓������A���_���͗Ö@���a������ɂ��������B�t���C�g�u���_���͂̐����j�̂Ȃ��ōÖ����ۂ��ʂ����������́A�ǂ�Ȃɍ����]�����Ă��]���������邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B���_���͂́A���_�ʂł����Öʂł��A�Ö����ۂ���p��������Y����g���Ă���̂ł���v�@ | |
|
���A���i�EO (�x���^�E�{�b�y���n�C��)�ƃu���C�A�[
���_���͎j��A�ł��L���Ȋ��҂́A�A���i�EO�ł���B �A���i.O(�x���^�E�p�b�y���n�C��) �t���C�g�̗F�l�u���C�A�[�̊��ҁB �u���C�A�[�ɂ��A���i �u�m�\�������v�E�u�L���͔��Q�v�E�u�l���݂͂��ꂽ���{�ƍ˔\�̎�����v�E�u�S�D�������P�Ɓv �u�����قljs���m���Ɖs�����ϗ͂�����A���̂��߂ɔޏ������܂����Ƃ��Ă��K�����s����v �u�P���Ȑ����̂��߂ɒm�I�~���s���Ɋׂ�A�������ɒ^��X�����������v �u�ޏ��̃q�X�e���[�𑣐i�������͕̂��e���s���̕a�ɂ����������Ɓv �u���g�I�Ȋŕa�̌��ʁA�H�~���ނ�����A�_�o���̊P���n�܂����B�v �u���̑��A�Ύ��A���ɁA���o��Q�A���o�r���A�Ǖ���ჁA�ӎ����r���v �u�܂������ւ̌��o������A�����Q�A�l�i���͂��܂�A���̎��コ��Ɉ����v�v ��ɁA�x���^�E�p�b�y���n�C���Ƃ������I�ȃ\�[�V�����E���[�J�[�ƂȂ�B �w�l�Q�����^���̓��m�ł������B �A���i�͖��[�A�u���C�A�[�̉��f���B�f�@�̎��ԂɂȂ�ƃA���i�͎���Ö���ԂɊׂ�A���R�ɘb�������B �u���C�A�[�́A�b������ƏǏy���Ȃ��Ă���A���i�������B�A���i�͎����������������̕��@���u�k�b�Ö@�v(�ӂ����āu���ˑ|���v)�ƌĂB���ꂪ�A���t��B��̎��Î�i�Ƃ��鐸�_���͗Ö@�̉萶���ł���B�@ |
|
|
���A���i�̏Ǐ�ƒk�b����
�|�ǂ�Ȃɂ̂ǂ������Ă��������ނ��Ƃ��ł��Ȃ��| �A���i�̒k�b�̗v�� �|�A���i�̉ƂɃC�M���X�l�ƒ닳�t���Z�ݍ���ł���(�A���i�̘b������Ƃ���)�B�A���i�͂��̏����������������B������A���̏������A���i�̎����Ă��錢�ɃR�b�v�Ő������܂���̂�ڌ����A�����������������ڂ����B�������߂Ȃ��Ȃ����̂͂��ꂩ��B�| �A���i�͂��̘b������܂ŁA�Y��Ă����̂����A�v���o���Ęb�����Ƃ���A�������߂�悤�ɂȂ����B �|���y���ƊP���o��| �|�A���i�́A���e�̊ŕa�����Ă���Œ��ɗׂ���_���X���y���������Ă����Ƃ��A�u�����Ȃ��A���͈�������e�̊ŕa�����Ă���Ƃ����̂ɁA�݂�Ȃ͊y��������Ă���v�Ǝv�����B���A���̏u�ԁA�u����Ȃ��Ƃ��l���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����߈����ɏP��ꂽ�B����ȗ����y���ƊP���o��悤�ɂȂ����B����́A���̂Ƃ����l��A���Ȃ̂��B�| �������ăA���i�͎����玟�ւƏǏ���u�b���ď������v�B �������A�A���i�̓u���C�A�[�ɂ���āA�X�C�X�̃T�i�g���E���ɑ���ꂽ�B �|���ׂĂ̏Ǐ������������̂悤�Ɍ���������ӁA�u���C���[�̓A���i�ɌĂт����ꂽ�B�s���Č���ƁA�A���i�͉��������z�������āu�搶�̎q�����܂��v�Ƌ���ł����B�z���D�P�ł������B�u���C���[�͓��]���A�|���Ȃ�A�A���i�̎��Â�������Ă��܂����B�ޏ��̓T�i�g���E���ł��ǏĔ������B�|�@ |
|
|
���}���Ǝ��R�A�z�@
�t���C�g�́A�p�����w�O�ɁA�A���i�̘b���u���C���[���畷���Ĕ��ɋ������������B�V�����R�[�ɂ��b�������A�ނ͋����������Ȃ������B�t���C�g���A�u�k�b�Ö@�v�����ÂɎ����ꂽ�B �u�q�X�e���[���҂͋L��(���ӎ��I�L��)�ɋꂵ�߂��Ă���v�|�w�q�X�e���[�����x1895(�u���C�A�[�Ƃ̋���) �u���ȑ̌��v�́A���ӎ��̒��ցu�}���v�����B�}�����ꂽ���͈̂ӎ�����Y�ꋎ����B����������(���ȑ̌�)�́A���ӎ��̒��ɗ��܂�A��ɂȂ��ďǏ�������N�����B���҂����̗}�����ꂽ�L�����v���o�����Ƃɂ���ďǏ�����B���́u�}���v�̊T�O�����_���͂̏o���_�ƂȂ�A�u�b���ƏǏ�����v�Ƃ����u�@�v���邢�́u�J�^���V�X�@�v�����_���͂̊�{�ł���B ���}���@repression ���_���͂ɂ�����ł��d�v�ȊT�O�B�}���Ƃ͈ӎ����邱�Ƃɑς����Ȃ����̂ŁA�g�Փ���㗝���Ă�����́h�g�Փ���\�����t�h���ӎ�����Ǖ����A�r�����邱�Ƃ��Ӗ�����B������t���C�g�́u�ӎ����牓�����邱�Ɓv�Ƃ����B�q�X�e���[�A�_�o�ǂɍł��T�^�I�ɔF�߂���h�q�@�\�Ƃ݂Ȃ����B�ӎ�����Ǖ����ꂽ���̂����ӎ��I�Ȃ��̂ł��邪�A��x�����ӎ�����Ǖ�����A����͖��ӎ��I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��A�Ăшӎ��Ɍ���Ȃ��ƌ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�����略���̂��Ă��Փ��̂������A�}���ɂ���ďՓ��͖��E����Ă��܂��킯�ł͂Ȃ�����A�ς�������͈̂ӎ��Ɍ���Ă���B������₦���}���̂��߂ɃG�l���M�[������邱�ƂɂȂ�A��J������Ȃ��B���̕s�o�ςȃG�l���M�[������Ȃ��Ă����ނ悤�ɗ}�����������邽�߂ɂ͂��܂��܂ȐS�I�ߒ������肷��K�v������B�Ⴆ�A���{�Ƃ����ߒ��ɂ���đς����Ȃ����̂́A���e��������̂ɕς����Ă��܂��Ƃ������̂ł���B���������}���̍l�����̒��ōł��d�v�Ȃ��̂͌��}���ł���B����́A�ӎ��I�ɑς����Ȃ����̂�r������}�����ȑO�Ɋ��Ɍ��}�����N���Ă���A���ӎ��I�Ȃ��̂������A���̖��ӎ��I�Ȃ��̂��ς����Ȃ����̂��Ђ����悤�Ƃ��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B���̈Ӗ��łӂ��ɗ}���Ƃ�����̂́A��}���Ƃ���B���}���Ƃ������̂��ǂ�Ȃ��̂��A�t���C�g�͕K�����������ł͂Ȃ��B���J���́u�ے��I�Ȃ��̂����肠����[���v�Ƃ݂Ȃ��A���}�����N����ȑO�Ɉӎ�����r�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��o�������邱�Ƃ��琸�_�a�����������B������ɂ��Ă��A�}�����ǂ�ȐS�I�ߒ��ł��邩�́A�}�����������ꂸ�A���ӎ��I�Ȃ��̂��ӎ��Ɍ����Ƃ��ł���B�}�����ꂽ���̂��Ǐ�Ƃ��Č���邾���łȂ��A���퐶���ɂ����Ă��A�����ԈႢ�A�v���Ⴂ�A�߂��A���ȂǂɌ���邱�Ƃ��t���C�g�͎����Ă���B �����R�A�z�@free�@association �t���C�g�ɂ���Ďn�߂�ꂽ�S���Ö@�̋Z�p�B(��@���̂̓S���g�����ŏ��ɕ��Ă���)�t���C�g�́A�ŏ��Ö��ɂ�鎡�Â����݂����A���҂����قǂ̌��ʂ�ꂸ�A�Ö��ɑ����̂Ƃ��Ď��R�A�z���n�߂��B���Ȃ킿�A�Ö����ɗ^����ꂽ�Î����Ö��҂͂��ׂĎv���o�����Ƃ��ł��邪�A����炪�Ö����ɗ^����ꂽ�Î��ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��B����������������ɂ��ăt���C�g�͊��҂ɐS�ɕ����Ԃ��Ƃ��A�ǂ�Ȃ܂�Ȃ����Ƃł��A�����ɂ������Ƃł��c�炸�v���o���悤�ɂ������B�������Ď��R�Ɏv���o������ƁA���̒��ɏǏ�̌��ɂȂ��Ă���S���I�����ɍs�������邱�Ƃ��������B�������A�o����ςނɂ�āA���R�Ɏv���o�����Ƃ͔��ɍ���ŁA���R�Ɏv���o�����Ƃ�W���Ă��鏔�������������m�ɂ����ׂ����̂ƍl���A���_���͂Ƃ����p�ꂪ�g����悤�ɂȂ����B����������͎��R�A�z���Z�@�Ƃ��Ė����l�ł���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�@ |
|
|
���q�X�e���[�Ɨc�����̐��I�s�҂ƃG�f�B�v�X(�I�C�f�B�v�X)�E�R���v���b�N�X
�t���C�g�̓u���C�A�[�̊��҃A���i�̏Ǐ�́A���~�Ɗւ�肪���邱�Ƃ��͂����茩�������B�܂��A�u�������߂Ȃ��Ǐ�v�̌������^�����B�ӎ��Ɍ��ꂽ�����u�����R�b�v���琅�����v���Ƃ̑��Ɍ���������̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂ł���B������k��ΐ^�̌����ɒH�蒅���ƍl�����B �܂��t���C�g�́A�����̏������҂��������������邱�Ƃ�������ɒ��ڂ����B �t���C�g�u���͂ɂ���Ė��炩�ɂ����A�z�L���̘A�������ǂ��Ă����ƁA�A�A�A�A�Ō�ɂ͕K�����I�̌��̗̈�ɓ��B����B���̐��I�̌��Ƃ́A�w�������鐫�I�o���x�ł���B�v�|���e�������͐g�߂Ȓj������̐��I�s�ҁ| �������A�t���C�g�͎���Ɋ��҂̍������^��n�߂��B�����Ă���܂ł̎咣�u�q�X�e���[�̌����͗c�����̐��I�s�҂ł���v�Ƃ����u�U�f���_�v���������ɂ��������B�|���I�s�҂͊��҂̋�z�ł��� �u���̋�z���ǂ����Ċ��҂����͕����̂��v�ˁu�ِ��̐e�ւ̈���v�ˁu���̈���͕��ՓI�Ȃ��̂ł���v �������Ă܂Ƃ߂��̂��t���C�g�̃G�f�B�v�X(�I�C�f�B�v�X)�E�R���v���b�N�X�̗��_�ł���B �|�c���������̐e��S�����āA�ِ��̐e�ƌ��ꂽ���Ƃ����~�]�Ƃ��̗~�]���߂���S�̊��� �j�̎q�̏ꍇ�|�j�̎q�͕�e�ƌ��ꂽ���Ǝv�����A�����Ƀy�j�X���Ȃ����Ƃ����A�������ꂽ�ɈႢ�Ȃ��Ɛ�������B�����āA��e��������Ǝ�������������邩������Ȃ��Ƃ����s���ɋ����(�����s��)�B���������āA��e�ւ̈����f�O����B�܂����ۂɃ}�X�^�[�x�[�V������e�Ɍ������āw����Ȃ��Ƃ����Ă���ƁA����������x�Ƃ����A�����s�����点��B���e���由�����邩������Ȃ��Ƃ������|�S�́A�₪�Ē�����ƂȂ�ނ̐S�ɏZ�ݑ�����B ���̎q�̏ꍇ�|���̎q�͊��Ɏ�������������Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����B����̓y�j�X�A�]���������B�����āA���������̂悤�ȁu�s���S�ȁv�`�ɎY��e�����ށB��e���������ƒz�������̎q�́A���e�Ɉ���������Ă��A��e������͂��Ȃ��B�₪�Ďv�t���ɂ́A��e�Ƙa�����A���e���������B���Ȃ킿�j���Ƃ̌����̊ϔO�������悤�ɂȂ�B�@ |
|
|
�����ӎ��Ƒ��d�l�i
�t���C�g���Ö��p����w�̂́u�l�Ԃ̐S�̒��ɂ͎����ł��m��Ȃ�����������v�Ƃ������ƁA���Ȃ킿�u���ӎ��v�ł���B���̒��ɂ͕ʂ̐l�i(����)������ł���ꍇ������B���ꂪ�\�ʂɌ���ꂽ�ꍇ�𑽏d�l�i�Ƃ����B �u�t���C�g�ɂƂ��Ė��ӎ������肷�邱�Ƃ͕K�R�I�ł������B�Ȃ��Ȃ����ꂪ����I�Ɍo�����铮�@�̕s���ĂȎv�����A�r���̌o�߂��s���ĂȎv�l�̌���(�Ђ�߂�)�A������Ƃ��������ԈႢ�A�����Ⴂ�A���A�_�o�ǂ̏Ǐ�A�����͂��ׂāA�w�ӎ��ɏ��Ȃ����̍�p��O��Ƃ��Ȃ�������������Ȃ��x�̂ł���A�w���ӎ��������ɑ}�����Ă݂�ƁA�����̈ӎ����ꂽ�͂��炫�́A�͂����肵���֘A�̂��Ƃɒ����Â��邱�Ƃ��ł���x�̂ł���B�v �t���C�g�u���ӎ��ɒ��ڃA�N�Z�X���邱�Ƃ͕s�\���v�@ �����ӎ��@unconscious(Ucs) ���ӎ��I�Ƃ����`�e���Ƃ��Ă̗p�@�́A�Ӗ����L���B�����I�A�@�B�I�ňӎ�����Ȃ����ƁA���ӂ͈̔͂��Ă��邽�߂ɋC�Â����Ƃ̂ł��Ȃ����ƁA�v���o�����Ƃ̂ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ�����B�ӎ�����Ȃ����̂����ׂĖ��ӎ��I�Ƃ����B�t���C�g�̏ꏊ�_(topographical�@viewpoint)�ɂ��ƁA�S�I���u�́A�ӎ��n�A�O�ӎ��n�A���ӎ��n�̂��ꂼ��̌n����Ȃ�A�����I�Ɏg����B���ӎ��̓��e���Ȃ����̂́A�ӎ��ɓ���A�Ƃǂ܂邱�Ƃ̂ł��Ȃ��}�����ꂽ�ϔO�ł���B���̈Ӗ��ł́A���ӎ��͗}�����ꂽ���̂Ɠ��`�ɂȂ�B�������A�}���͌n�������I�ɍl������Ƃ��납�炢���A�}�����ꂽ���̂ƌ�����Ȃ��Ƃ��������B��N�ɂȂ��āA�S�I���u�́A�C�h�A����A������̌n�Ƃ��čl������悤�ɂȂ邪�A�قږ��ӎ��̓C�h�ɑΉ�����B�������A����A������͑O�ӎ��A�ӎ��ɑΉ�������̂ł͂Ȃ��B���ӎ��͌����ɑ���z���������A���]�s���̌����ɂ��������n�Ƃ��čl�����A�}�����ꂽ�ϔO�͑��݂Ɏ��R�ɒu���������A���k���ꂽ�肷�邵�A���Ԃ��������A�j�����̂ł��Ȃ��A�ꎟ�I�ߒ��Ƃ��Ă̓����������Ă���B������g�I�ɂ����A�}�����ꂽ�ϔO�̌����ɂ���Ă��肠�������z�I�����̋؏����Ƃ��Ă̍��q�����肠���Ă�����̂ł���B�����N�ɂ����ẮA�l�I���ӎ��ƏW���I���ӎ�����ʂ���A���ӎ��͑n���I�����̕�ق��Ȃ��Ă���ƍl������B�����܂ł��Ȃ��A���ӎ��͒��ڂɊώ@�������̂ł͂Ȃ��A�Ǐ�▲���肪����Ƃ��č\�����ꂽ���̂ł���B���̈Ӗ��Ŗ��͖��ӎ���m�邽�߂̉����ł���Ƃ�����B�@ |
|
|
�����A���̎d���A���̕���
���ɑ���S�͌Ñォ�炠��A���̃J�^���O���Ñォ�炠�����B �u���A���͏����̏ے��ł���v�|�A���e�~�h���X�w���̏��x �t���C�g�́A���̃J�^���O����邱�Ƃ����A�u���̐��ݓ��e�v���u���ӎ��I�~�]�v�ƌ��т��āA�u�����f�v�������B���̉��߂́A�����o���_�Ƃ������R�A�z�ɂ���Ă����Ȃ���B�t���C�g�́A�u���Y����̂́A���ӎ��I�~�]�ł���v�Ƃ����Ă������A���ׂĂ̖����~�]�[���̖��ł���͂����Ȃ��A��N�A�u�����_�v���C�����u���������v�̊T�O�������B �w�����f�x����(1900�N)�ȗ��A�t���C�g�̖����͂̌����́A���_���͂̊�b�I�����Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����B��{�I�ɂ͗}�����ꂽ��]���[�������A�o���ɂ���Đ����𒆒f�����Ȃ��悤�ɂ���@�\�������̂ƍl����ꂽ�B����ɑ��āA1953�N�ȗ��A�N���C�g�}���̎w�����鐇���̌����ɂ��REMS�̔����ȗ��A���̎����I�������s����悤�ɂȂ�A���̌����͑傫�Ȕ������Ă����B�ӂ�����ꂪ���Ƃ��ł��鎋�o�I�\�ۂ�REMS�ɂ����Č�����̂ł���A�������A���邢�͊o�����Ɍ��鎋�o�I�\�ہA���邢��NREM�Ɍ��閲�Ƃ͋�ʂ���Ă���B���������������炢���A�t���C�g�̖��̗��_�͂��̂܂����I�Ɋm��������̂Ƃ͍l�����Ȃ��B �����̎d���@dream�@work ���ӎ��I�Ȏv�l�@�́A�t���C�g�̂����ꎟ�I�ߒ��ŁA�����ł̍����I�E�ӎ��I�Ȏv�l�l���Ƃ͂��Ȃ�قȂ�B ���܂��܂Ȏv�z���e�����k���ꂽ��A�u��������ꂽ�肷��B �Ⴆ�A A,B,C��3�l�̓�����A�ɋÏk����AA��B�̂悤�Ȓ��������AC�̂悤�Ȍ��t�����������肷��悤�Ȃ��̂ł���B���������ꎟ�I�v�l�l���͖���Ȃǂɂ��g���Ă���B�u�������́A����ł���Ƃ��ɁA���e�̗m���������Ƃ����悤�ɁA�����I�\���ɂ���đS�̂��Î����悤�Ƃ�����̂ł���B����ɐ��ݓ��e�́A�ȏ�̂悤�Ȗ��̎d���ɂ���Ď��o�I�A���邢�͒��o�I�C���[�W�ɕϗe����邪�A�����̃C���[�W�͌X���œ��ꐫ�������Ă��Ȃ��B������܂Ƃ߁A��̕���ɂ��肠����̂��A�I���H(����)(secondary�@elaboration)�ł���B �����̕��́@analysis�@of�@dreams ���_���͂ɂ����ẮA���R�A�z�̕��͂Ɠ����ɖ��̕��͂��s�Ȃ���B�v���o���ꂽ���̏����ɏ]���A�X�̓��e�ɂ��Ď��R�A�z�����Ă����A���S�̂̓���I�ȉ��߂��s����B�����Ώے��I���߂����p�����B �Ⴆ�A�i�C�t�A���M�Ȃǂ̂悤�ɐ�������̂́A�j��������ے����邱�Ƃ���A�B�������疲�̉��߂͗e�ՂɂȂ�B�������A��ɂƂ��������̂��j��������ے�����Ƃ͂�����Ȃ��B�l�̉ߋ��o���̂�����ɂ���āA���̏ے��I�Ӗ����قȂ�̂Ŏ��R�A�z�ɂ���ĈӖ��͖��炩�ɂ����B�@ |
|
|
�����~�̕ϑJ
�t���C�g�̂����u�c�����~�v�̊T�O�́A�������E�����B�Ȃ��Ȃ�A����܂ł͎v�t���ȑO�̎q�ǂ��͖��C�ŁA���I�Ȃ��ƂƂ͖����ƍl�����Ă�������B �t���C�g�u���̂悤�Ȕ��́A�w���I�x�Ɓw����I�x�̍����Ɋ�Â��Ă���B�v�t���ȑO�ƈȌ�ł͓������~�ł��Ӗ����Ⴄ�B����ǁA�c�������~��������Ƃ͕ς��Ȃ��B�c���͑��`�|���I�ł���B�����͂܂�����ɏW�����Ă��炸�A�����т͑̒��Ɋg�U���Ă���B���ꂪ�܂����O���ӂɏW������B��e�̓��[���z���Ă���i�K�ł���B�������ɏW������B����̓g�C���b�g�g���[�j���O�̎����ɏd�Ȃ邪�A���̎��C�Ɏ��䂪�`������A�T�f�B�Y���͂��̎����ɋN��������B�j�����ɂ�����ƁA�j���̗L�����d�v�ȈӖ��������Ă���B����܂ŕ�e�Ƃ̑o���W�ɂ������q�ǂ��́A��-��-�q�Ƃ����O�p�W�̒��Ɏ������ʒu�Â��A�����͎����̎����Ă��Ȃ�(������)�j���������Ă��镃�e�ɗ~�]�������A�j���͕�e�������̂��̂ɂ������Ɗ肢�A����G������B�������ăG�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�����܂��B�����s���ɂ���āA�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�͊O����͉�������A�������ɓ���A�₪�Đ�����ɂ������āA���~�͐���̗D�ʂ̂��Ƃɓ��������B�v �����I�|���@sexual�@pervesion�@ �c���͐��I�ɕ������Ă��Ȃ����߁A���I�~�]�͕s��ő��ʓI�ł���A����̑ΏۂƓ���̖ړI�������Ȃ����I�W�������Ƃ݂Ȃ���A�������Ă����̌X�����ۂ���Ă��邱�Ƃ𐫓I�|���Ƃ����B���I�|���́A���̗c���I��]�������Ƃ�����̂ł���̂ɑ��āA�_�o�ǂ͂��̊�]��ނ��悤�Ƃ�����̂ł���ƃt���C�g�͉������B���I�|���Ƃ݂Ȃ������̂́A����ɍU���������ċꂵ�߂邱�Ƃɂ���Ė����������悤�Ƃ�����s�����A�������ꂵ�߂邱�Ƃɂ���Ė����悤�Ƃ����s���A�������A���O�Ɛ���̐ڐG�����߂���o�����A���ɂ�鐫�s�ׁA�����Ƃ̐��s�ׁA�q�ǂ��Ƃ̐��s�ׂɂ���Đ��I���������߂鈤���ǁA�������ߏǂȂǂ�����B�@ |
|
|
������ƃG�X
�l�Ԃ̐S���ǂ�ȍ\�������Ă���̂��A�t���C�g�͍l�����B���̏����ɂ����ăt���C�g�́A�ӎ��Ɩ��ӎ����l�����B���ɒ����̂��u����v�Ɓu�G�X�v�́u�_�v�ł���B�G�X�Ƃ̓j�[�`�F�ɗR������T�O�ŁA�u�����̂Ȃ��ɂ͂��邪�A�����Ƃ͍l����ꂸ�A�w����x�Ƃ����l�����Ȃ������v�ł���B�t���C�g�̂����Ƃ���̃G�X�́u�������̗~�]���痈��G�l���M�[�ŏ[�����Ă��邪�A�����Ȃ�g�D���������A�����Ȃ�S�̓I�ӎu���������A���������̌���̂��Ƃɂ����~���~���������悤�Ƃ����������������Ă����A�G�X�͍��ׂł���A�����������ɖ��������v�ł���@����̓G�X�Ɠ����A�Ë����A����Ƃ��͗D���ɗ����ăG�X���]�������A����Ƃ��̓G�X�ɐU����B�u����̃G�X�ɑ���W�́A�z�n�䂷��R��v�݂����Ȃ��́B�A���A����͂�����ӎ��I�ɂ���킯�ł͂Ȃ��B����͎����̂��Ă��邱�Ƃ�m��Ȃ��B�Ⴆ�A�}���B����͂�����ӎ�����Ƌ�ɂ�߈��������ڂ���悤�ȊϔO��L����}�����Ă��܂����A�����ł͗}���������Ƃ�m��Ȃ��B�}���̑��A�۔F(�m�o���������������Ƃ��ĔF�߂Ȃ�)�A�����A�����`���A�������A���ꉻ�A���e�Ȃǂ́u�h�q���J�j�Y���v����g���Ȃ���(�J��Ԃ����A�����܂ł��ޖ����o�I��)�A�����̐g������Đ����Ă����B(�t���C�g�̎��㖖���A���i�͂��̎���̖h�q���J�j�Y���̌�����i�߂�-����S���w) ������@ego ����Ƃ����T�O�́A�ł��L�͈͂ɂ킽��Ӌ`�������A���{�I�ɂ́A�l�ԂƂ͉����Ƃ������ɓ����悤�Ƃ���Ƃ��̒��S�I�ȊT�O�ł���B���������āA������ǂ̂悤�ɍl���邩���A�S���w�̗��_�̊�{�ƂȂ�B�����w�I�A�s����`�I�Ȍ����҂́A����Ƃ����T�O�͂��܂�p�����A�̂Ƃ��l�Ƃ����T�O���g���A�l�Ԃ��Љ�I���݂Ƃ��Ă݂悤�Ƃ���Ƃ��́A�����A�ԓx�Ƃ����T�O���d������B���_���͓I�A�N�w�I�ȗ��_��g�ݗ��Ă悤�Ƃ���l�����́A�D��Ŏ���Ƃ����T�O���g���X��������B�������A����̊T�O�͈�l�ł͂Ȃ��B�����Ƃ������܂��Ȃ͎̂���Ǝ��Ȃ̊T�O�ł���B�����Ƃ���ʓI�ɂ́A����͎�̂Ƃ݂Ȃ���A���Ȃ͋q�̂Ƃ݂Ȃ����B����́A���鎩���ƌ����鎩���A���Ȃ��鎩���Ɣ��Ȃ����ΏۂƂȂ��Ă��鎩������ʂ�����̂ł���B�o�������ΏۂƂȂ��Ă��鎩�Ȃ̂��Ƃ����ۓI���ȂƂ����B���̈Ӗ��Ōo�������̂Ƃ��Ă̂͒��z�I����Ƃ�����B���Ȃɂ��Ă͊����A�m�邱�Ƃ��ł��邪�A����ɂ��Ă͒m�邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���B�������A���ȂƎ��䂪�������̂悤�ɋ�ʂ���Ă���Ƃ͌���Ȃ��B���������҂ł��A�����S��������Ӗ��Ŏg�����Ƃ�����B�t���C�g�̏ꍇ�A����Փ��Ƃ����Ƃ��̎���͐����I�̂̈Ӗ��������A���䃊�r�h�[�Ƃ����Ƃ��͋q�̂ɑ����̂̈ӂ������B�������A�ꏊ�_�Œ�����ƃG�X�ɑ���Ӗ��Ŏ���Ƃ����p����g���Ƃ��ɂ͐S���I�@�\�̂��Ƃ������Ă���B����̌`���A���B�ɂ��Ă������܂��ł���B����Ƃ��ɂ̓G�X�����B�I�ɕ������Ď��䂪�l�����邩�Ǝv���ƁA���ꎋ�ɂ���Ď��䂪�`�������Ƃ��l������B�����B���ɂ����Ă͐�����Ԃ�������������ł��邩�̂悤�ɂ݂Ȃ���邪�A���̏�Ɏ��䂪�lj�����A���_�I�ɂ͕s���m�ȊT�O�ƂȂ��Ă��Ă���B���̂悤�ȍ������N���Ă��鍪���́A��{�I�Ɏ�̂Ƌq�̂Ƃ��čl���悤�Ƃ���Ƃ���ɂ���B�����ł��Ƃ��Ǝ�̂Ƌq�̂̋�ʂ͂Ȃ��A��̂͋q�̂ł���A�q�͎̂�̂ł���Ƃ����l������������B���J���̋����i�K�̊T�O�͂��������l������[�I�Ɏ������̂ł���A�t���C�g�̓��ꎋ�̍l������W�J�������̂Ƃ�����B����̓C�f�I���M�[�̎Y���ɉ߂��Ȃ����e�Ƃ݂Ȃ����B(�c������v�t���ɂ̓C�h�̏Փ��������A����͂��܂苭���Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA�C�h�⒴����Ƃ̊ԂɊ����������Ă���B�A���i�E�t���C�g�͓��Ɏ���̖h�q�@�\�ɂ��Ę_���A�t�F�����c�B�͎���̔��B�ɂ��ďڍׂȋL�q�����݂Ă���B�n���g�}���̓t���C�g���s���m�Ȃ܂܂Ɏc���Ă�������@�\�m�ɂ��Ă���B���Ȃ킿�A�t���C�g�͑O�q�̎���̈ӎ��I�@�\�ɂ��Ă͏����ɊȒP�ɐG�ꂽ�����Ł|���̕��́|����Ȍ゠�܂蕁�y���Ȃ������B���̂��߁A����͂����ς�s���⊋������`�������ƍl�����₷���������A�����Ƃ͊W�Ȃ������I�@�\�������Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���̍l���́A�s�A�W�F�Ȃǂ̒m�I���B�̍l���ƋO����ɂ�����̂ł���B ���G�X(Es��)�@�C�h(id��it) �O���[�f�b�N�ɂ���ē������ꂽ���_���̗͂p��B�O����̎O�l�̂̑㖼���ɂ́A�J���~��Ƃ����Ƃ��@it�@rain�@�Ƃ����悤�ɁA�J���~�点���̂̈Ӗ�������B�l����ƌ����Ƃ��@es�@denkt�@in�@mir�@�̂悤�ɃG�X���l�����̂Ƃ��Ďg����B�����������Ƃ���As��F�̑㖼��(���e����ŃC�h)�͍s�����N����������̂��Ӗ�����悤�ɂȂ����B�t���C�g�͐l�̑S�̍\�����l����Ƃ��A������O�̕����A���Ȃ킿�A�C�h�A����A������ɋ�ʂ��A�C�h�͑S�����ӎ��I�ȐS�I�G�l���M�[�̌���ƍl�����B�{�\�I�Փ��ƌĂ����̂́A���̃C�h�̏d�v�ȕ����ł���B���̂ق��c�����̑̌��������Ă�����]�����ׂĊ܂܂��B�@ |
|
|
���g�[�e���ƃ^�u�[
�t���C�g�͌l�̐S������W�c�̐S���ցA����ɂ͐l�ޑS�̂̐S���w�ւƂ��̗��_���L�����B �u�����A�l�ނ͈�l�̓ƍٓI�ȉƒ��Ɏx�z����鏬���ȕ����P�ʂŐ������Ă����B�������̏����͂��ׂĉƒ����Ɛ肵�Ă����B������A���q�������c�����Ĕ������N�����A���e���E���ĐH�ׂĂ��܂����B�����ޓ��͕��e�ނƂƂ��Ɉ����Ă������̂ŁA���̌�A�߈����ɉՂ܂�A�g�[�e�����E�����Ƃ��ւ��A���R�̐g�ɂȂ����������������̂��̂ɂ��邱�Ƃ�����ւ����B�������ă^�u�[���o���オ�����B�^�u�[�̗��ɂ͕��e�E���ƕ�e�̐����Ƃ�����̍����I��]������B ���̌����E���v�́A�l�ލŏ��̔ƍ߂Ƃ��Đl�ނ̗��j�ɂʂ������������Ղ��c���A�����镶���ɐZ�����Ă���B���̌����E���͕����̊�b�ł���A�l�ނ͂��̔ƍ߂���o�����Ă����镶�������肠�����B�v ���t���C�g�̂��̉����́A���݂ł͋�z�����Ƃ݂Ȃ���Ă���B ���^�u�[�@�@taboo �֊��̈ӁB�ꌹ�̓|���l�V�A�A�~�N���l�V�A�A�����l�V�A�̌���ɂ���A�T���ƃN�b�N���p��ɓ��������Ƃ�����B �ꌹ�I�ɂ͋ւ���ꂽ���́A�G��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂��Ӗ�����B�g�[�e�~�Y���̎Љ�Ɍ����镗�K�ŁA����̐l�A����������邱�ƁA������ꏊ�ɋߊ��Ȃ����ƁA����ȍs�ׂ�����A����̌��t���g��Ȃ��悤�ɂ��邱�ƁA�����͑��ׂĂ̐l�ɓK�p����邱�Ƃ����邵�A����̌l�ɂ̂ݓK�p����邱�Ƃ�����B�펞���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂����邵�A����̂Ƃ��̂ݎ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��^�u�[������B��������Ȃ��ƁA�Ђ��A�댯�����̐l��Љ�N����ƐM�����Ă���B�^�u�[�ɐG���Ɛ��߂̎����K�v�ƂȂ�B�����Љ�ɂ����Ă��ގ��̌��ۂ�������B �^�u�[�Ɋ�Â��^���I�����̂��ߐ_�o�ǂ��N����B�^�u�[�͐G��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��Ő_���Ȃ��̂��Ӗ����邱�Ƃ�����B ���g�[�e�~�Y���@�@totemisim �g�[�e���̐M�̂��Ƃ������B�g�[�e�~�Y���͏@���I�M���������̂ł�������A���̊�@���~�����̂ƍl������B���邢�͒P���Ɏ�������ʂ��邽�߂̋L���ɉ߂��Ȃ����Ƃ�����B ���g�[�e���@totem �A���S���L�A����(�k�Ă̓y���C���f�B�A��)�̌�Ŏ��_�̈Ӗ������B�ޓ��̐M�ɂ��ƁA�g�[�e���ƌĂ�铮���A�A���A���R��(�Ȃ�)�́A���������Ƌߐe�̊W�������Ă���ƍl������A�g�[�e�������������̐�c�Ƃ݂Ȃ��Ă���B���镔���ł͎v�t���ɖɂ�錶�z�▲�̒��Ɍ������̂��X�l�̃g�[�e���Ƃ݂Ȃ��Ă���B�I�[�X�g�����A��A�t���J�ł͎����̃g�[�e��������A������E���ĐH�ׂ邱�Ƃ͋ւ����Ă���B�����̖��O���͂Ƃ��Ă��g����B���̂悤�ȐM�̓��[���b�p�A�A�W�A�ł��F�߂���B���������������ǂ����_������ł���B�@ |
|
|
�����z�̖���
�u���z�v�Ƃ͏@���|�L���X�g��(�t���C�g�̓��_���l�����O�ꂵ�����_�_��)�������B�t���C�g�u�@���͗c�����́w���ׂȂ��x���琶�܂��B�c���͕��e�ɗ��낤�Ƃ��邪�A���̕��e�̑㗝���@���v�@ |
|
|
���~���Ƃ��̉^��
�~�����l�Ԃ����G�l���M�[ �����͖{�\�ɂ������Đ����Ă���B�{�\�Ƃ͂��̎�̂��ׂĂ̌ő̂ɋ��ʂ���s���l���ł���B�����͉����l���Ȃ��Ă������Ă�����B�����̖{�\�͐��܂ꂽ�Ƃ����łɈ�`�q�ɏ������܂�Ă���B�l�Ԃ͖{�\�����Ă��܂����B�����͕s���B�������s���͂��߂��l�Ԃ̑�]�͔����I�i�������B���̂�����������Ȃ��A�͂��܂��A�l�I�e�j�[�̂�����������Ȃ��B�Ƃɂ����{�\�����Ă��܂����A�Ƃ����̂��t���C�g�l���B�t���C�g�͐l�Ԃɂ�����{�\�Ɏ������̂��u�~���v�Ƃ�сA�����̖{�\�Ƌ�ʂ����B�~�����t���C�g�́A��ɕ������B �k1�u���̗~���v���u2���ȕۑ��~���v�l����ɁA�i���V�V�Y���̊T�O�� ���~���ɂ͑ΏۂɌ������~���ƁA���Ȏ��g�Ɍ������~���Ƃ�����B�������ŏI�I�ɂ́A���̗~�](�G���X)�Ǝ��̗~��(�^�i�g�X)�̓_��B(���̗~���͐V�@���̏W�c�����△���ʎE�l�Ȃnj���̂��܂��܂Ȍ��ۂ��𖾂���d�v�ȊT�O�ł���B)�@ |
|
|
���i���V�V�Y���@narcissism(���Ȉ�)
�G�R�[�̈������₵�Đ��ʂɈڂ��������̎p�Ɍ��Ƃ�v�������i���V�X���ꌹ�ɂ�������B���r�h�[���O�̑ΏۂɌ�����ꂸ�A�������g�̎p�Ɍ���������́B�������łِ͈��̈������₵�A�����̈������߂邪�A���̓����͎������g�̎p�Ɏ������̂ł���Ƃ����Ӗ��Ŏ��Ȉ��Ɋ�Â��ΏۑI���ł���B�֑�ϑz�������_�a�ł́A�O�̑ΏۂɌ������Ă����Ώۃ��r�h�[�́A�����Ɍ������鎩�䃊�r�h�[�ƂȂ�B���Ƃ��Ƃ͎��䃊�r�h�[�������I�Ȃ��̂ŁA���傤�lj����������U�����o���ĊO�̑ΏۂƐڐG���A�K�v�ɉ����ċU����̓��ɂ��܂����ނ̂Ɠ��l�ɍl������B ���̂��߁A�Ώۃ��r�h�[����ɂ��܂������̂�I���Ȉ��Ƃ����A�����I�Ȏ��䃊�r�h�[�ɂ��ƂÂ����̂��ꎟ�I���Ȉ��Ƃ����B���B�I�ɂ́A���̈��ɓ��ʂȐS�I��p�������A���Ȉ��ɔ��W����ƍl������B ���̓��ʂȐS�I��p�͓��ꎋ�Ƃ݂Ȃ����B���̈��ɂ����Ă͎��䂪�������Ă��Ȃ����A���҂Ƃ̓��ꎋ�ɂ���Ď��䂪�������邱�Ƃɂ���āA�����̐g�̂łȂ������̎����������悤�ɂȂ�B���J���̔��B�I�i�K�Ƃ��Ă̋����i�K�́A���̓��ꎋ���l�����悤�Ƃ�����̂ł���B���Ȉ��͎����̂��Ƃ����ɊS�������A���l�ɑ���z���������Ă�ł͗��Ȏ�`�Ǝ��Ă���B���Ȉ�����������ƌ������{��A���܂莩�Ȉ���������㵒p�S�������Ȃ�B���B�I�ɂ́A���Ȉ���r�����邱�Ƃɂ��A���̑㗝�Ƃ��Ď��䗝�z��������Ă���B�@ |
|
|
�����䃊�r�h�[�@ego�@libido
�_�o�ǂ̎��Â��琸�_�a�̎��ÂɊႪ��������Ƃ��A���_���͂Ɏ��Ȉ��̍l��������������A���r�h�[���䃊�r�h�[�ƑΏۃ��r�h�[�ɕ�������B���Ȉ��ɂ����ẮA�܂����r�h�[�͎���ɕt�����Ă�����̂ƍl������B������ꎟ�I���Ȉ��Ƃ�ԁB���Ȃ킿�A���r�h�[�͂܂�����ɕt�����Ă���A��ɂȂ��đΏۂɌ�������B�����Ώۃ��r�h�[�Ƃ����B�Ώۂɕt�����Ă������r�h�[���Ăю���Ɍ����ς���ꂽ�Ƃ��́A�I���Ȉ����N����ƍl������B ����͐��_�a�֑̌�ϑz�A�q�|�R���f���[�ȂǂɌ����Ɍ�������̂ł���B ���䃊�r�h�[����ɂȂ�A���ꂾ���Ώۃ��r�h�[�͏������Ȃ�B �Ώۃ��r�h�[���傫���Ȃ�A���ꂾ�����䃊�r�h�[�͏������Ȃ�B �t���C�g�̗��_�\�����猾���A�������r�h�[�Ǝ���Փ��͑S���قȂ���̂ł��邪�A����Ƃ����T�O�̞B��������A���������댯��������B���䂪���r�h�[�̒����ɂł��邩�̂悤�ɏq�ׂ��邱�Ƃ����邪�A���܂��܂Ȍ���̌��ɂ��Ȃ�B�@ |
|
|
���G���X�@eros
�w�V�I�h�X�ɂ���čŏ��ɋL�ڂ��ꂽ�ŌÂ̍ł�����Ȑ_�B�������̒����璲�a�̂Ƃꂽ���������o���B���̌�A���I�Ȉ��̐_�Ƃ݂Ȃ���A���g�I�A�I�Ȉ��A�K�y�[(Agape)���邢�̓J���^�X(Cartas)�ɑΗ�������̂Ƃ݂Ȃ����B�t���C�g�̌���̏Փ��_�ł́A�G���X�͎��̏Փ��ɑΗ�������̂ŁA���I�Փ�������I�Ŏ��ȕۑ��̏Փ������܂߂��Ӗ��ōl������B�@ |
|
|
���t���C�g�̊��҂���
���h�[�� �h�[���͓���18��(�t���C�g44��)�̏����ŁA�t���C�g�ɕ��͎��Â������r�����Â���߂����҂ł���B �h�[���̓u���W���A�̖��ŗ��e�ƌZ�ƕ�炵�Ă���A�ƂƐe�������Ă����B�ޏ��̏Ǐ��16�̂Ƃ�����n�܂����B������q�X�e���[���́g�P�h�ł������B�P������Ɓg�����o�Ȃ��Ȃ�h�g�T��ԁh�Ɋׂ�g���E��]�h�܂ŕ����悤�ɂȂ����B�h�[����K������Z�N�n�����Ă���A�h�[���̕��e��K�̍Ȃƕs�ϊW�ɂ������B�h�[���B�w����K�w�l�Ƃ̊W�𑱂��邽�߂ɁA������K���ɍ����o�����̂��x�ƍl���Ă����B�t���C�g�̓h�[���̃q�X�e���[�Ǐ���gK���ւ̒W�����S�h�g���e�ւ̋ߐe�����I����h�gK�w�l�ւ̓���������h�Ȃǂ��番�͂����B�������A3�������炸�Ńh�[��������I�ɕ��͂���߂Ă��܂����B�t���C�g�́w���̉��߂�����Ȃ����炵�����߁x�Ə����Ă���@���̍��̃t���C�g�͂܂��A���_���͉ƂƂ��Ă͖��n�ŁA�]�ځA�t�]�ڂ𗝘_������ȑO�������B�h�[���̕��͂̎��s��ʂ��A���͎��Â̋Z�@���m�����Ă������Ƃ������Ƃł���B �������ȃn���X �n���X�̕��͂́A�ނ̕��e(�}�b�N�X�E�O���[�t,���y�w��)��ʂ��čs�Ȃ�ꂽ�B �n���X��5�̂Ƃ��A�w�n�Ɋ��܂�邩��x�ƌ����A�O�ɏo��̂�������悤�ɂȂ���(�n���|��)�B�܂��הn�Ԃ������Ă���n���|���Ƃ������|�������Ă����B���_���͂̐M��҂ł��镃�e�́A�u�n���X�͑傫�ȃy�j�X���������Ă���̂��v�Ɖ��߂������A�t���C�g�́u�n���X�͎����̃y�j�X�������̂�����Ă���v�Ɖ��߂���(�������|)�B�w�n�Ɋ��܂��x�Ƃ������N�̋��|�́A���e���由�����邱�Ƃւ̋��|���]�����ꂽ����(���̕��͕E�������킦�Ă���A�n�Ɏ��Ă���ƃt���C�g�͎v����)�ł���B�ǂ����ĕ��e�ɔ�������̂��B����͏��N����e�ɑ��Đ������������Ă��邩��ŁA�w�n���|���x�Ƃ����͕̂��e�̎��ɑ����]�̂�����ł���B �������āA�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�̗��_���ł��������Ă����B ���˂��ݒj �˂��ݒj�̕��͂́A���Â����������B��̎���Ƃ����Ă���B �ނ͎��������̂́A��ꎟ���Ő펀�����B �˂��ݒj�Ƃ���(�t���C�g���Ă�)�����_�o�NJ��҂́A����29�̖@���ƂŁA�����̕��e�Ǝ����̈����鏗���̐g�ɋ��낵�����Ƃ������������Ƃ������|�ɂ��т��Ă����B�܂��N�����E�������Ƃ����Փ��ƁA�䓁�Ŏ����̂̂ǂ��������肽���Ƃ����Փ��ɋꂵ�߂��Ă����B����ɁA���z�̎؋���Ԃ��ׂ����ǂ����Ƃ��������߂����Ď��ʂقǔY��ł����B�ނ͐��I�ɂ͑��n�ŁA6�̂Ƃ����łɁA�����̗����������Ƃ����~��������ƕ��e�ɕs�K���~�肩����Ƃ��������ϔO�ɋꂵ�߂��Ă����B29�ɂȂ��Ă����̋����ϔO�ɋꂵ�߂��Ă����̂����A���̂Ƃ����e�͂��łɖS���Ȃ��Ă����B �g�˂��ݒj�h�ƃt���C�g���ĂЂƂ̗��R�́A�w�l�Y�̂͂Ȃ��x�������痣��Ȃ��Ƃ������҂̑i������B(�l�Y�Ƃ́A�ݔC�̐K�̏�ɑl�̓������������Ԃ���Ƃ������̂ŁA�l�͏o�J���T��������H���j���ē����̒��ɓ��荞�ނƂ����B)�ނ̋����ϔO�̊j�͂��̑l�Ƃ����ے��ł��������Ƃ��t���C�g�͎w�E����B �t���C�g�́A���e�̐g���Ă���C���������͕��ւ̈�����łȂ��A���͕��e�̎����肤�C�����̂������ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���˂��ݒj�͎������̂ł���B ���V�����[�o�[ �p���m�C�A���҃V�����[�o�[�́w����_�o�a���҂̉�z�^�x(�ϑz)���o�ł����B�僌�[�o�[�͐_���琢�E���~���Ƃ����C����^����ꂽ���A���̔C���𐋍s����ɂ͏����ɓ]�����邱�Ƃ��K�v�ł������B �t���C�g�͂��̖ϑz�͂����B ���`�O�Ȉ�ł��蒘�q�ƁA������v�҂Ɏ��V�����[�o�[�́A�c������茵�i�ȕ��Ɍ�������Ă�ꂽ�B�ނ͍ō��ٔ����̔����ɂ܂łȂ������A���_�a�@��10�N�ȏ���߂������l���ł���B��z�^�̒��ŏd�v�ȈӖ������̂͑��z�A���̑��z�͕��e�̏ے��ł���B�t���C�g�̓V�����[�o�[�̖ϑz�̍��ɕ��e�ɑ���A���r���@�����c�ƁA�����ɂȂ��Ēj���������܂��j�����爤���ꂽ���Ƃ����g�������h������邱�Ƃ�˂��~�߁A���̉�z�^���u�E�Č��̊�āv�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B ���T�j ���V�A�l�M���̃Z���Q�C�E�p���P�[�G�t�ŁA1909�N���Ƀt���C�g�̂��Ƃւ���Ă����B �ނ̕��͂�4�N�ȏ㑱�������A�t���C�g�ɂ���đł���ꂽ�B�ނ͌����ł���قǂɉ������A�����͂��Ȃ������B�ނ̓��V�A�v���ł��ׂĂ̍��Y�������A��ꎟ����ɂ܂��t���C�g�̂��Ƃ�K��o�ϓI�������������B�ނ͐��U�t���C�g���h�������B�ނ̓t���C�g�̊��҂ł��邱�Ƃ������ł������B �T�j�ƌĂ��̂́A�ނ̖��ɂ��B�|3�̃p���P�[�G�t�͑��ۂŐQ�Ă����B�����ЂƂ�łɊJ�����̂ł����邨����O������ƁA�傫�Ȗ̎}��6,7�C�̘T�������Ă����B�ނ͐H�ׂ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ������|�ɋ���A�ߖ��グ�Ėڂ��o�܂����B ���̗c�����̈ꌏ����A�ނ͐_�o�I�Ȑ��s���|��w�ʐ������D�݁A�q�b�v�̑傫�ȏ������D�݁A�g���̒Ⴂ���������߂�|�ɑ������B�t���C�g�͘T�̖��̔w��ɁA�Ռ��I���������邱�Ƃ��m�M���A�ނ�1�Δ��̂Ƃ��ɗ��e�̐�����ڌ������ɈႢ�Ȃ��Ɖ��߂����B�����ė��e��3���Đ������A����1��͌�w�ʂŌ�������ƌ��_�����B 1920�N�㔼�ɁA�p���m�C�A�I�ȏǏ��悵�A�u�����Y���B�b�N�̕��͂��Ă���B�@ |
|
|
���l�Êw�Ɛ��_����
�t���C�g���Ñ�╨�̏N�W���n�߂��͕̂��e�̎��ゾ�����B �����E�K���E�F�C-�����ҞH�� �u�t���C�g�̓G�W�v�g��M���V���Ɏ����̕����c�恁���[�c�����߂��H�I�v �u�t���C�g���N�W���n�߂��̂́A�t���C�g�����Ǝ҂�������ł��j�Q����Ă�������ŁA�ނ͒�����������ׂĎ��@����(���كZ��)���O�Ɍ����ĂāA����̐S���Ԃ߂Ă����̂ł͂Ȃ����v �t���C�g�͂��̂悤�ɂ����Ă���B �u�w�q�X�e���[�����x�̂Ȃ���R��̎���́A�����肪�����ŏ��̊��S�ȃq�X�e���[���͂ł��������A����ɂ���Ď��͈�̏��u�������B���͌�ɂ�����k���_���͎��ÂƂ����l�ЂƂ̎��Ö@�܂ō��߁A�ړI�ӎ��������Ă������g����悤�ɂȂ����B���̏��u�Ƃ́A�a���ƂȂ�S�I�f�ނ������ɑw���ƂɎ��o���ď���������@�ŁA�����͍D��ł�����Ñ�̖��v�s�s�̔��@�Z�p�ɂ��Ƃ������̂��B�v �u���_���͉Ƃƌ������̂́A���@�Ɏ��g�ލl�Êw�҂Ɠ������A��Ԑ[���Ƃ���ɂ���ł��M�d�ȕɓ��B����ɂ́A���҂̐S�̑w�����@��N�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�ƘT�j�Ɍ���� �����_���͂̍l���ł́A�_�o�ǂ̌����͑S�ėc�����̑̌��ɂ���B���������Đ��_���͎��ÂƂ́A���݂̏�ԁA���Ȃ킿�Ǐ�o�����āA�l�Êw�҂��������̒n�w���@��N�����Ă����悤�ɁA�S�̑w���ЂƂЂƂ@��N�����Ă����āA�Ǐ�̌����ł���c�����̑̌���T�蓖�Ă��ƂȂ̂ł���B�@ |
|
|
���]��(����)sference
�S�����Â��i�݁A���҂����Î҂ɑ��Ď����̕s�����]�Ȃǂ����R�ɘb���悤�ɂȂ��Ă���ƁA���҂͗c�����ɐe�Ȃǂɑ��ĕ����Ă������ӎ��I�Ȋ���⊋�������Î҂Ɉڂ��悤�ɂȂ��Ă���B���Ȃ킿�A���҂͗c�����̊��������Î҂Ƃ̊W�Ō����I�ɍČo�����邱�ƂɂȂ�B�S�����Â��������邩�ۂ��́A���������W�������邩�ۂ��ɂ������Ă���B���̓]�ړI�W���N�����Ƃ��A���҂͓]�ڐ_�o�ǂɂȂ��Ă���Ƃ�����B���҂����Î҂Ɋ��ԓx�Ȃǂ�]�ڂ���Ƃ��A���̓]�ڂƁA���̓]�ڂ��N����B���̓]�ڂ͊��҂����Î҂ɍs�ׂ∤�������Ƃ��ł���B ���̂Ƃ��A���҂͎��R�ɘb���A�M���������A���Î҂ɂ�艈���悤�ɋߊ��A���̒��Ɏ��Î҂����ꂽ���Ƃ���A�g�����Ȃ݂�ǂ�����悤�ɂȂ�A���̊��҂Ɏ��i���������A�Ǐ}�ɂȂ��Ȃ����肷��B���̓]�ڂ��N����Ƃ��ɂ́A���҂͎��Î҂ɓG�ӂ������A���Â��L�W���Ȃ����Ƃ����ڂ�����A���Î҂������A�s�������Ƃ����ĂȂ���B���R�ɘb�����Ƃ��ł����A�����v���o���Ęb�����Ƃ����Ȃ��B���ɂ͎��Â𒆎~������Ȃ���Ԃɂ��Ȃ�B���̂悤�ȕ��̓]�ڂ��N����̂́A���Î҂����}�ɁA���҂ɂƂ��Ĕ��ɋ�ɂȎ����ȂǂɌ��y������A�����b�����悤�Ƃ��邩��ł���B���Î҂́A�ŏ��A���҂ɑ��čD�ӂ������Ă��Ă��A���Â��i�ނɂ�āA�D�ӂ�����ɔ���A�G�ӂ����債�A���҂Ɩʐڂ���̂����ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����B����͔��Γ]�ڂƂ�����̂ł���B�����̓]�ړI����́A���Ï�ʂ݂̂ŋN����Ƃ͌���Ȃ��B���퐶���ɂ����Ă��N���Ă���B ���]�ڐ_�o�� �t���C�g���ŏ��ɓ]�ڐ_�o�ǂƂ����p����g�����Ƃ��ɂ́A���_���͂ɂ���Ď��Âł���_�o��(�q�X�e���[�A�s���q�X�e���[�A�����_�o��)�������Ӗ��������Ă����B���݂ł͎��Ò��Ɋ��҂����͎҂Ɋ����]�ڂ���Ƃ��̂��Ƃ������B ���]�ڒ�R ���͂��Ă��銳�҂��_�Ӓ��Ɍ���悤�Ƃ��銴���Փ��̂�����̂�}�����Ă������Ƃ���X���̂��ƁB���҂́A�Ⴆ�A�e�ɑ���ȑO�̊���͎҂ɓ]�ڂ��Ă��邪�A���̓]�ڊ���̒��ɂ́A���ł����ꂪ�������̂����邩��A����͗}������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�����̊��҂��j���̕��͎҂ɑ��Ă₫�������₭�̂́A�ޏ��̒��ɕ��e�ɑ���G�f�B�v�X��R���v���b�N�X�������āA���I�ȊS�������ɕ\�o�����Ȃ�����ł���B�@ |
|
|
�����_�a�@psychosis
��ʂɐ��_��Q���ʂ��āA�_�o�ǂƐ��_�a�ɕ�����B�_�o�ǂ͏�Q�̒��x���y�����A���_�a�́A���̒��x�̏d�����Ƃ������B�_�o�ǂƐ��_�a�̋����f�f�I�ɖ��m�ɂ��邱�Ƃ͕K�������e�Ղł͂Ȃ��B���o��ϑz�����邩�琸�_�a(�����a)�ł���Ƃ����悤�ɁA�P��ȏǏ�͐f�f�ł��Ȃ��B���_�a�́A�펿�I��Q�ɂ����̂Ƌ@�\�I��Q�ɂ����̂Ƃɑ�ʂ����B�O�҂͔~�Ő��̐i�s��ჁA�]��ᇁA�����d���ǂȂǂɕt�����ċN���鐸�_�a�ł���B��҂́A����I��Q����Ƃ����N�T�a�A�v�l�l���ɏ�Q�̂��镪���a�A�ϑz�ǂȂǂł���B��ʂɋ@�\��Q�͑̎��I��S���I�v���ɂ���ċN����Ƃ���Ă��邪�A��`��_�o������Ȃǂ̉e���ɂ��Ă����܂��܂Ȍ������s���Ă���B �t���C�g�͐_�o�w�Ɛ��_�a�̈Ⴂ�����̂悤�ɗ��������B �u�_�o�ǁv�@�Փ�(�C�h)���}�������Ƃ��A�}�����ꂽ�Փ��͈ӎ��ɕ����яオ�낤�Ƃ���B���̂Ƃ�����͂��̏Փ������̂܂܂̎p�ňӎ��ɕ����яオ��Ȃ��悤�ɘc�Ȃ��A�h�q������B���ꂪ�Ǐ�ƂȂ��Č����Ƃ��_�o�ǂƂȂ�B �u���_�a�v�@�����Ƃ̐ڐG���Ւf���ꎩ�Ȉ��ɗ��܂��Ă��邪�A����ꂽ���������߂����Ƃ���Ƃ��A�Փ������܂�ɋ���Ŏ���̖h�q�����|���Ă��܂��A�Փ��ƌ������Փ˂��A������c�Ȃ��邩��z�I�ɔj����ق��ɂȂ��Ȃ��Ă�����̂ƍl���Ă���B ���_�o�ǁ@neurosis �_�o�ǂ͐��_�_�o�ǂƌ����_�o�ǂɋ�ʂ����B ���_�_�o�ǁ|���|�ǁA�����_�o�ǁA�q�X�e���[�Ȃ� �����_�o�ǁ|�s���_�o�ǁA�_�o����Ȃ� ���Ƃ��Ɛ_�o�ǂ͌����_�o�ǂ̂��Ƃ��Ӗ����A�����I�ȋ@�\��Q(�����_�o�A�_�o������)�ɗR��������̂ƍl�����Ă������A�����ł͐_�o�ǂƐ��_�_�o�ǂ́A�قƂ�Ǔ����Ӗ��ŗp������B�@ |
|
|
���p���m�C�Aparanoia(�ϑz��)
�ꌹ�I�ɂ͗�������͂���Ă���̈ӁB 1863�N�J�[���o�[������Q�ϑz��֑�ϑz�Ȃǂ��L�q����Ƃ��g�p�����p��B �ϑz�ǂ͏��X�ɔ��W���A���łɑg�ݗ��Ă��A�ς��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��_���I�ɑ̌n�����ꂽ�ϑz�����d�����_��Q�ł���B�ϑz�I�ȐM�O�������Ă���ق��́A��ʂɂ͌����Ȉُ�͂Ȃ����A���̖ϑz�̂��ߎv�l�l���͑傫�ȏ�Q���Ă���B�������ϑz�ǂƐf�f����銳�҂͂܂�ŁA�ϑz�ǂɗގ��̖ϑz���������������̂������B�a���Ƃ��ẮA�S���I�ɍ�����S�������Ȃ��玸�s���邽�߁A�߈������������肷��ꍇ�A�Ⴆ�A�e�����܂�ɍ����]�݂������A���Ў�`�I�Ō��i�ȏꍇ�ȂǁA���̎q�͖ϑz�ǓI�X���W�����Ă����B�܂��A�ِ��̐e���ߓx�ɓ��ꎋ�����q�ǂ��Ȃǂ��A���̌X���������悤�ɂȂ�B���̖h�q�@���̓t���C�g�ɂ���Ď�����Ă���悤�ɁA���f�����S���Ȃ��Ă���B ���ϑz�@delusion �����ɑ����Ȃ�������M�O�B������x�܂ł͒N�ł��ϑz�������Ƃɂ���Đl�i�I�Ȉ���Ă���B�s���ɑ��Ď���������ȗ͂������Ă���悤�Ȗϑz�́A�p�Y����₨�Ƃ��b�ȂǂɈ�ʂɌ�����B�����͎����̊�]�����悤�Ɏ�����c�Ȃ��ď�I����悤�Ƃ�����̂ł���B�ł��邩��A�ϑz�͗����I�v�l�ɂ���Ďx�z����Ă���̂ł͂Ȃ�����ɂ���Ďx�z����Ă���B�ϑz�ǂ͑̌n�I�ɋ��ݏグ��ꂽ�ϑz�������Ă��邪�A����͘_���I�ł͂Ȃ��A����Ɏx�z���ꂽ�h�q�ł���B��ʂɗ~������ϑz�́A�֑�ϑz�A��Q�ϑz�A�W�ϑz�Ȃǂł���B�����̖ϑz�͊O�̐��E�ɑ��čU���I�ł��邪�A�������g�ɑ��čU���I�ɂȂ�ƁA�}���I�ϑz���N����B�Ⴆ�A���ӁA�߁A�n���Ȃǂ̖ϑz�ł���B ���ϑz�I�l�i�@paranoid�@personality ���̐l�i�̌����ȓ����́A��łŎ��i�[���A���l�ɑ��^���[���s�R�̔O�������A����I�E�U���I�ŁA�Ë���m��Ȃ��B�����S�������A�����̔\�͂����ڕW��Nj�����B�ᔻ������Ȃ����A���l��ᔻ���A�y�̂���B�����̗D�ꂽ�Ƃ�����������悤�Ƃ���B���͂̍��ɂ��ΐꐧ�I�ɂȂ�B�h�q�@�\�Ƃ��Ă͓��f�𗘗p���₷���B�Ⴆ�A�킽���͔ނ����炵���A�Ƃ�������ɁA�ނ͂킽����ł��邩��A�������ނ��U������̂͐����ł���Ƃ����悤�ɁA�����̓G�ӂ�U���𑼐l�ɂ��Ԃ���B���������l�i�I�����́A����ȏ�ɔ��W���Ȃ�����A�a�I�Ƃ͂����Ȃ��B���A�}�����ꂽ�������Ȃǂ����ƂŐ��_�a�ɂ����W����B�܂��A�Ȋw��|�p�Ȃǂōv������悤�Ȏd���������邱�Ƃ�����B�@ |
|
| ���t���C�g�E�G�b�@ | |
|
���t���C�g�ƃ����O
�[�w�S���w�̃p�C�I�j�A�ł��郆���O�́A1875�N�n�����q�t�̑��q�Ƃ��ăX�C�X�ɐ��܂ꂽ�B�c���������z�ɒ^��A�����������邱�Ƃ��������炵���B�����O�͐S�쌻�ۂ̌����Ŋw�ʂ��擾���A1900�N�Ƀ`���[���b�q�̐��_�a�@�ɋ߂��B�����ʼn@�������Ă����̂��A�����a�̌����Œm����I�C�Q���E�u���C���[�ł������B(���_�����a�A�A���r���@�����c-����������A���ǂȂǂ͔ނ̑���)�u���C���[�Ƀt���C�g�́w�����f�x��ǂ�ő��̈�t�ɐ�������悤�ɖ�����ꂽ�����O�́A�[���������A���̘_�����ǂ���A�t���C�g�̍l���������̌����Ɏ����ꂽ�B�w�������s���̐S���w�x(1906�N)�ł̓t���C�g�����p���A�^�����Ă���B1906�N�����O�͎��������M��ҏW�����_���W�w�f�f�w�I�A�z�����x���t���C�g�ɑ������B���̖{�́A�t���C�g�̎��R�A�z�������ؓI�ɗ��t������̂ŁA�t���C�g�̓����O�ɗ��𑗂����B���N�A�t���C�g�͐_�o�Ǘ��_�Ɋւ���_���W�������O�ɑ������B���̗��̒��Ń����O�́u�킽���̓t���C�g�̗i��҂ł��萸�_���͂̓`���҂ł��v�Ɛ錾�����B�������ē�l�̌�F�͎n�܂����B���N�����O�̓t���C�g��K�˂Ă���B(���̂Ƃ��A��l��13���Ԃ��b���������炵���B)�����O�̓t���C�g�e�̂悤�ɂ������A�t���C�g�̓����O�𑧎q�̂悤�ɉ��������B�t���C�g�̓����O�_���͉^���̌�p�҂ɂ������ł����B�������A�E�B�[���ɂ͂��łɃt���C�g�̐M��҂����̃O���[�v���ł��Ă���A1910�N�ɍ��ې��_���͊w����ݗ����ꂽ�Ƃ��A�t���C�g�̓����O�������ɏA�C���������̂�����A�E�B�[���h�ƃ`���[���b�q�h�̑Η��͌������A�����O�͋����E�ނ��Ă��܂����B ��1909�N�̃G�s�\�[�h ���̔N�A�t���C�g�ƃ����O�̓A�����J�̃N���[�N��w����u���˗������B(�t���C�g�͒��O������}�X�R�~������劽�}���A�����A���_���͂��A�����J�ʼnh���邱�Ƃ�\���������B) �o���̑O���A�ꏏ�ɐH���������Ƃ��A �����O�u�k�h�C�c�̓D�Y�n�тŐ�j����̐l�����@���ꂽ�v �t���C�g�u�ǂ����ČN�́A���̂ɂ���Ȃɋ��������̂ł����H�v�ƋC��A�A�A�u�N�����̘b��ɂ������͎��̎���]��ł��邩�炾�v ���̗��s�̊Ԓ��t���C�g�ƃ����O�͖����s�����Ƃ��ɂ��݂��̖��͂��������B ����郆���O�͎��̂悤�Ȗ��������B �u�ނ͌Â��Ƃ̓�K�ɂ����B���̕����ɂ͌����ȉƋ����A���炵���G���ǂɂ������Ă����B���֍~��Ă����ƁA�����ƌÂ��Ƌ�������B�ނ͉ƒ���T�����Ă݂悤�Ǝv�����B���ׂĂ݂�Ɛłł��Ă����B����ꖇ�̐ΔɊ����Ă��Ă���������ƈ�t�������オ��A�K�i���������B������~��Ă����Ɗ�̒��ɂ���ʂ��ꂽ���A������A�����ɂ͍����ꂽ���킪�U����Ă����B���n�����̖��c�ł������B�����Đl�Ԃ̓��W�����ӂ��������B�v �t���C�g�͂��̖����āA���̓��W�����N�̂��̂��Ƃ������Ƃɋ������������B �t���C�g�u�����O�͂��̓��W���̎�����ɑ��Ď��̊�]������Ă���̂��v �����O�͂���́A�S���̓I�O�ꂾ�Ǝv�����B�u���̒��ɏo�Ă����Ƃ͐S�̃C���[�W�ł���A��K�͎��̃C�ӎ��A��K�͌l�I���ӎ��A�n���͏W���I���ӎ��Ȃ̂��B���W���͐l�ނ̑c��̂��̂ł���A���̊�]�Ƃ͉��̊W�������v �܂��t���C�g�̌������ɂ��āA�����O�́A�t���C�g�̎������̂��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��Ăق����Ɗ�����B�������A�t���C�g�u����Ȃ��Ƃ�����A���̌��Ђ��낤���Ȃ��Ă��܂��v�ƁA�A�A �����O�u�t���C�g�͌l�I���Ђ�S��������ɂ����Ă���B�v�ƃt���C�g�Ɍ��ŁA�A�A ���_���`�A�I�J���g�ɂ��ă����O���������Ƃ� �����O�u�_���`��I�J���g�ɂ��Ăǂ��l���邩�v �t���C�g�u�Y�����v -�����O�͎����̉��u�����^���ԂɏĂ����S�̂悤�Ɋ������B���̏u�ԁA��l�̋߂��ɂ������{���̒��ő傫�Ȕ��������B��l�́w�т����肵�ė����オ�����B �����O�u���ꂪ�܂��ɒ��팻�ۂł���v �t���C�g�u���������v �����O�u�������A���Ȃ��͊Ԉ���Ă���B���̌������Ƃ����������Ƃ��ؖ����邽�߂ɁA ���炭����Ƃ�����x�������Ɠ�����������͂��ł��v -�����O�̌����Ƃ���ł������B�t���C�g�͐��_���͉^���̎w���҂̒n�ʂ�D���邱�Ƃɋ����Ă����H�I �A�A�A�A�A�̂��낤�A�A�A�A�Ƃ����̂������O�̕��͂������A�A�A �����ē�l�͌��� �����O�́A�t���C�g�́u�l�Ԃ̖��ӎ��I�~�]�͑��ׂĐ��I�Ȃ��́v�Ƃ����咣�Ɏ^���ł��Ȃ������B �����O�u�S�I�G�l���M�[�́A�����ƍL����ʓI�Łw�����́x�Ƃ����ׂ����̂ŁA���~�͂��̈ꕔ�ɂ����߂��Ȃ��B �����āA�t���C�g�̂������ӎ��̉����ɂ͂����Əd�v�ȑw-�w���ӎ��W���I�x������v �t���C�g�ƌ��ʂ��������O�͐��_�I��@�Ɋׂ�A�������甲���o���̂ɐ��N�������������ȁB (�t���C�g�ƌ��ʂ�����q�����́A�قƂ�Ǘ�O�Ȃ����_�I��@�Ɋׂ��Ă���B���C�q�͐��_�a�ɁA�^�E�X�N�͎��E����)�@ |
|
|
���t���C�g�ƕ��w
�Ⴂ���́A�V�F�[�N�X�s�A�A�Q�[�e�A���͂��߁A�M���V���E���e���̌ÓT�ɂ�����܂œǂ������B ���A������̕��w�A���ɑO�q���w�ɂ͉��̋����������Ȃ������B �ӔN�́A�����������D���������B ���C�ɓ���̓V���[���b�N�z�[���Y��A�K�T�E�N���X�e�B�ȂǂŁA���͈�ӂœǂ�ł��܂����B�@ |
|
|
���Ɛ��w
�u�搶�͂قƂ�ǂ����Ɛl���N�����킩���Ă��܂������A�������ꂪ����Ă���ƁA�����������������ł����B�v�@ |
|
|
�����퐶���ŁA�������͐l�̖��O����������ԈႦ����A���͂������ԈႦ���肷��B����ȂƂ��A�قƂ�ǂ̐l���u���́A�܂��������̂��v��[���l�����肵�Ȃ��B�������A�t���C�g�͂��������g��������h�̗��R���l�����B
����Ƃ��t���C�g�́A�����̎����Ă������F�l�Ƀv���[���g���邱�Ƃɂ��A����ɓY����J�[�h���������B�Ƃ��낪�Afur(�E�����[�g���o�܂��A�E�E�E�E�̂��߂�)�Ə����ׂ��Ƃ�����Abis(�E�E�E�܂�)�Ə����Ă��܂��������ȁB����ɂ��ăt���C�g�́A�ufur�̌J��Ԃ�������邽�߂ɕʂ̌��t��p�����̂��B�Ȃ��Abis�Ƃ����S���Ӗ��̈Ⴄ���t��p�����̂��Ƃ����ƁA����̓h�C�c��ł͂Ȃ��A���e�����bis(������x�̈�)�ł���A�������p���Ă͂����Ȃ��Ƃ����ӎ����������B�v���̉��߂������́u�����������悤�Ƃ����̂͒P��̌J��Ԃ��ł͂Ȃ��āA�s�ׂ̌J��Ԃ�����Ȃ��́B�O�ɓ��������ɓ������̂��v���[���g�������Ƃ�����̂ł́H�I�v�Ǝw�E�����B���̎w�E���ăt���C�g�́u���͂��̕���C�ɓ����Ă��āA�{���͑��肽���Ȃ������̂��v�Ƃ������_�ɒB�����B �t���C�g���ɂ����A������Ƃ������s���A�����̑O���͓��I�Ȍ���v���ɂ���ĂȂ����̂ł���B�@ |
|
|
���t���C�g�̓��[�}���D���ł��т��іK��A�K���w���[�[���x�����ɍs�����B�t���C�g�͂��̗��ɂȂ��Ă��܂��A����قǂ̖��͂͂ǂ����炭��̂��𖾂炩�ɂ����̂��A�w�~�P�����W�F���̃��[�[���x(1914)�B�ނ͂�������p���͂̎G���w�C�}�[�S�l�ɓ����Ŕ��\�����B����قǂ̎��M�ƃt���C�g�������Ǝ��M���Ȃ������̂ł��傤�B
�t���C�g�u�~�P�����W�F���́A�����Đ����̋L�q�ɋt����ė��j�I�E�`���I�ȃ��[�[����i��̃��[�[�����肠�����̂��B�������邱�Ƃɂ���ă~�P�����W�F���́A���[�[���ɉ����V�������́A���l�ԓI�Ȃ��̂�D�荞�̂��B���̐Α��̋���ȓ��̗͂ɖ�����ꂽ�ؓ��̑S�̂́E�E�E�E�E�l�Ԃ̂Ȃ�����ő���̐��_�I�s�ׂ�\�����Ă���B�v �����[�[�̓G�W�v�g���疯���~���o�����̂ł����A���̔ޓ�������(�����̎q��)�𐒔q���A�����ɂ�������Ă���̂����Č��{���܂����B�t���C�g�ȑO�̔��p�j�Ƃ����́u�~�P�����W�F���́A�{��������钼�O�̃��[�[��`�����v�Ɖ��߂��Ă����̂ł��B�������A�t���C�g�́u�~�P�����W�F���͓{�����߂悤�Ƃ��Ă��郂�[�[��\�����悤�Ƃ����̂��v�Ɖ��߂��܂����B�@ |
|
|
���t���C�g�́A���_���͂Ƃ���������g���āA�䑽���l���|���I�i���h�E�_�E���B���`�̓�ɒ��킵���B(�k�_�E���B���`�̗c�����̋L���x1910�|���_���͓I�`�L)
�|�u�ǂ����킽���͍ŏ�����Ñ�Ɋւ��^���ɂ������悤���B�܂��h�肩���̒��ɂ������A��H�̓Ñ邪�����~��Ă��āA���Ŏ��̌����J���A���̐O�����x�����̔��œ˂������̂������B�v�|���I�i���h ���Ñ�͓̌��ł��邱�Ƃ��������Ă���B �|�t���C�g�́����A�L���ł͂Ȃ���N�̋�z���Ɗm�M�����B�u���͒j���̏ے��ł��邩��A���̏�ʂ̓t�F���`�I��\���Ă���B�Ȃ��Ȃ�Ñ�͌Ñ�G�W�v�g�ł́u��v��\���ی`�����ł������B�������×��A�Ñ�ɂ͎��������炸�A���ɂ���ĉ�C����ƐM�����Ă����̂ŁA�L���X�g���̓`���ł͏������ق̏؋��Ƃ��Đ���Ɉ��������ɏo���ꂽ�B���I�i���h�͂����m���Ă����ɈႢ�Ȃ��B�Ñ�ɂ͏����������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A���I�i���h�ɂ͕��e�����Ȃ��������Ƃ��Ӗ����Ă���B�����ă��I�i���h�́A���̕�e�ւ̈������瓯�����҂ɂȂ����B���������I�i���h�͐��I�Ȃ��Ƃɂ͂قƂ�Nj������Ȃ������B�v�| �|�ꕔ�̓������҂́A��e�ƈ�̉����A���̈���ŁA�����Ɏ����j�����̑ΏۂɑI�сA���ĕ�e�������������Ă��ꂽ�悤�ɁA���̒j��������B�|�c�����~���_ �����I�i���h�͎������Ƃ���3�N�ԉ߂����A���e�̍č�����Ɉ�Ă��܂����B �����Ĕނ̒�q�͔��������N���������������ł��B ���w���i���U�̔��݁x�|���̔��݂́u���I�i���h�̒��ł܂ǂ��ł������́A�����L�����Ăъo�܂�������ł͂Ȃ����v �@ |
|
| �����l�T���X�̖��\�l���I�i���h�E�_�E���B���`�� �@�w�Ñ��z�x�Ɠ������C���̐��_���͓I���� |
|
|
�V�O�����h�E�t���C�g���z���I�ɍs�������I�i���h�E�_�E���B���`�̗c�����̐��_���͂Ɍ��y���܂������A���̐��_���͂́w���I�i���h�E�_�E���B���`�̗c�N���̂���v���o(1910)�x�Ƃ����_���ɋL�ڂ���Ă��܂��B���I�i���h�E�_�E���B���`(1452-1519)�́A�����̗D�ꂽ�|�p�ƁE���w�ҁE�Z�p�҂ݏo�����C�^���A�E���l�T���X�̐����ɂ����āA�~�P�����W�F��(1475-1564)��t�@�G���E�T���e�B�Ƒo�����ׂ��ō��̓V�˂ƌ�����l���ł��B
�~�P�����W�F���̍ō�����́A�V�X�e�B�[�i��q����F�ʖL���ɏ���L�s�ȓV���ł���A�T���E�s�G�g���吹���̃s�G�^����t�B�����c�F�̃_���B�f�������j�I�ȍ�i�Ƃ��ėL���ł��B�~�P�����W�F���͖��\�l�ł��������I�i���h�E�_�E���B���`�Ɣ�r����ƁA������G��Ƃ������`���p�̕���ŋ��ٓI�ȍ˔\�������܂����B���I�i���h�E�_�E���B���`�́w�Ō�̔ӎ`�x�Ɓw���i�E���U�x�Ƃ����N�����m���Ă�����j�I����𐧍삵�܂������A�G��E�����̌|�p���삾���łȂ����݁E�y�E�H�w�E�Ȋw�Ƃ������Z�p����ł������Ƃ��Ă͗ޗ�̂Ȃ��ٍ˂����܂����B �Ñ�M���V�A��[�}�̌ÓT���������悤�Ƃ��郋�l�T���X(���|����)���ɂ��̍˔\���⊶�Ȃ������������I�i���h�E�_�E���B���`�́A�|�p�E�Z�p�E�w��̂����镪������S�ɖԗ����閜�\�l��ڎw���܂������A�t�Ɍ����A����̕���ɑS�Ă̏�M�Ɣ\�͂��X���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������߂ɁA�w�|�̏�����ɂ����Ė����̍�i�E�_�l�E�A�C�f�A�𐔑����c�����ʂƂȂ�܂����B���I�i���h�E�_�E���B���`�͖��s���̒m�I�D��S�Ɗ��S��`�̗~�����������āA�w�|�̍L�͂ȕ���ɂ����āw������\�����錤���E����E���z�x���s���܂����B�������A��i�̌v���Z�p�I�ȃA�C�f�A���]��ɑs��ł���A����̎Y�ƋZ�p���ǂ����Ȃ��قǂɐ�i�I�ł��������߁A���̑���������(����)�ɓ������Ƃ��ł��Ȃ������ƌ����܂��B S.�t���C�g�͌Ñ�G�W�v�g�̗��j��l�Êw�����ɐ[���S���Ă���A�t���C�g�̐f�Î��ɂ̓X�t�B���N�X��A�u�E�V���x���_�a�̊G���|�����A�f�X�N�̏�ɂ̓G�W�v�g�̐_�X�̏����ȗ���(����)�������ɒu����Ă����Ƃ����܂��B�t���C�g�́A�G�W�v�g�̓Ñ�̏��_���g�ƃ��I�i���h�E�_�E���B���`���c�������玝���Ă����w�Ñ��z�x�̘A�z����A�_�E���B���`�̓������C�����w�E���āw���I�i���h�E�_�E���B���`�̗c�N���̂���v���o(1910)�x�̘_�l�������グ�܂����B �_�E���B���`�́A���e�ƌ������Ă��Ȃ���������J�^���[�i�̎������Ƃ���5�܂ň�Ă��܂������A�w�h���Ă̒��ɂ��鎩��(�Ԃ����)�̌��Ɉ�C�̓Ñ�(�͂�����)�������~��Ă��āA���̔��Ō����J���ĉ��x���O��˂������x�Ƃ����c�����L���������Ă��܂����B�t���C�g�͂��̗c�����L�����q�ϓI�Ȍ����ł͂Ȃ��A�_�E���B���`�̖��ӎ��I�Ȋ�](�������ւ̑ލs)�f�����S�I���A���e�B�Ɖ��߂��āw�Ñ��z�x�ƌĂт܂����B �t���C�g�̓_�E���B���`�̍�i�ł���w�O�l�Â�̐��A���i(���A���i�Ɛ���q�Ə��r)�x�ɁA�_�E���B���`�̓Ñ��z�ɏے������u���O���I�ȕ������~�v�����f����Ă���Ƃ��āA�����̃_�E���B���`�̌���˕t�����Ñ�̔��́u��e�̓��[(�j����)�v�̒u�������ł���ƌ����܂����B�w�O�l�Â�̐��A���i�x�ɕ`����Ă��鐹�A���i�̈ߕ��̑��̕������Ñ�̗֊s�Ɍ�����Ǝ咣�����̂́A���_���͉Ƃ̃I�X�J�[�E�v�C�X�^�[�ł����A�t���C�g�͂��̊G��̓��قȍ\������A�_�E���B���`�̖��ӎ��I�ȑލs�~���Ɠ��c�����̐������ǂݎ��܂����B �Ñ�G�W�v�g�l�͓Ñ��ꐫ���ے����钹�ƍl���A�Ñ�̓��������ꐫ�_���g��M���Ă��܂������A�_�E���B���`���g�������Ă�����z�ɏo�Ă������́A��L�̋L�^�ɂ��Ɩ{���́u�Ñ�v�ł͂Ȃ��u��(�Ƃ�)�v�ł������Ƃ����܂��B�����s���w���i�����Ă��Ȃ������̃��[���b�p�ł́A�Ñ�ɂ̓I�X�����݂������X�����������Ȃ��Ƃ������M���M�����Ă��܂����B�t���C�g�̓G�W�v�g�̕ꐫ�_���g�ƃh�C�c��̃��b�^�[(��)������I�A�z�Ō��т�����A���X�������Ȃ��Ñ邪���ɂ���ĔD�P����Ƃ����z���{�����̖��M���A����}���A���������قŃC�G�X�E�L���X�g���Y�G�s�\�[�h�ƌ��ѕt���Ă��܂��B �w�O�l�Â�̐��A���i�x�ɂ́A�C�G�X�̕�ł��鐹�}���A�ƃ}���A�̕�̐��A���i���`����Ă��邪�A���҂̔N����������Ȃ��قǂɓ�l�Ƃ��Ⴍ�`����Ă���A���}���A�Ɛ��A���i�̐g�̂����G�ɗ��ݍ����ē�l�̐g�̂��Z�����Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^���Ă��܂��B�t���C�g�̐��_���͓I�ȊG����߂ł́A���}���A�̓��I�i���h�E�_�E���B���`�̎Y�݂̕�e�ł���J�^���[�i���ے����A���A���i�͈�Ă̕�e�ł���A���r�G�����ے����Ă���Ƃ���܂����B�w�O�l�Â�̐��A���i�x�́A�_�E���B���`�̓�l�̕�e(���e�Ɨ{�e)�ɑ��鈤��Ƒ����̊�����\�����Ă��āA�X�ɁA�_�E���B���`���Ƒ��W�̍����̒��ŏ[���ł��Ȃ�����������(������)�̗~���s����\���Ă���̂ł��B �t���C�g�́A�����j�[�E�N���C�����w�E�������n�I�h�q�@���̈�ł���w���e���ꎋ(projective identification)�x�̍l������p���āA�_�E���B���`�̓������C���̊l����������܂����B��e�ƕ�e�Ɉ�����Ă��鎩���ꉻ���ĕ�e�̗��ꂩ�玩��(���N)�����邱�ƂŁA�c�����̎����Ɨގ��������N�������铯�����̌X�������܂��Ƃ����̂ł����A���́u���e���ꎋ�ɂ�铯�����v�̍l�����ł́A�������͎q������̎������g���������Ƃ��鎩�Ȉ��ɋߎ��������̂ƂȂ�܂��B �i���V�V�Y��(���Ȉ�)����Ώۈ��ւ̔��B�ߒ��̓r��ŁA��e�Ǝ��Ȃꎋ����h�q�@�����ߏ�ɓ����ƁA�����Ɠ���̐������Ώۂ�I�����铯�����C�����l������Ƃ����̂��t���C�g�̐S���I�ȓ������_�ł����B�������I�ȑΏۑI���̌����Ƃ��Č��݂łَ͑����̃A���h���Q���V�����[�̂悤�Ȑ����w�I����(���̃z��������)���L�͂ł����A�ÓT�I�Ȑ��_���͂ł́A��e�ւ̓��e�����ꉻ(���e���ꎋ)�⎩�����g�Ɨގ������Ώۂ������鎩�ȑΏۓI(���Ȉ��I)�ΏۑI���ɂ���Đ�������Ă��܂����B �_�E���B���`�̓������X�����t�B�N�V�����Ƃ��čČ������ǂ݂₷�����j�����Ƃ��ē��{�ЂƂ݂́w�t���̃��f�B�`�x������܂����A���̏����ł̓_�E���B���`��������������A���W�F���ւƒu�������ăt�B�����c�F����̋֒f�̒j�F�����Ƃ������炷��������Ă��܂��B����́A�w�O�l�Â�̐��A���i�x�̍\�}����Ñ��z(���r�h�[�̑ލs)��ǂݎ��A�S���_�̓������X���͂���t���C�g�̘_�l�ɂ��Ęb�����܂����B�@ �@ |
|
| �������f / ���c�ЕF | |
|
�F�l�����Ȗ��������Ɖ]���Ęb���ĕ��������B����͓c�ɂ̔_�ƂŔ������ӂ̂��Ƃł���B�S�g�����т�A�����s�������傭�t���ē����Ȃ��Ȃ������A���ꂪ�u�d�C�̂����v���Ǝv��ꂽ�B������p���𒅂�����炵���j��������ɂ���������������Ă���������Ă���悤�Ƃ���̂����A����b���ځs�����߁t���Ȃ��̂ō���ʂĂ��Ƃ���ŊႪ���߂��̂��Ƃ����B���߂Č����疍�����Łs�ނ�݁t�Ɍł��Ď��Ⴡs���сt��Ă��������ł���B
���͂��̈ꗼ���O�̐V���L���ɏ������������̐�Đ��ꉺ�����Ă���̂����̂��悤�Ƃ��Ċ��d�������Ƃ��ڂ��Ă������̂��v���o�����̂ŁA�F�l�ɂ����ǂ��ƕ�������ǂƂ����B����Ȃ炻�ꂪ���̖����ďo������̎킾�낤�Ƃ������ƂɂȂ����B�Q���������^�ÂŁA�d�������悤�Ǝv������d�����O�����Ă����������ŁA���̂Ƃ��ɗF�l�͓V�䂩�琂�ꉺ�������R�[�h��ڌ������ł��낤���A�܂��\�P�b�g�ɘI�o�����d�ɂ̓d���̊댯�ӎ��Ɉӎ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B���ꂪ���̖��̑��̑f���炵���v����B���ɏ���̏o�Ă���̂��S���肪����B���̗F�l�ɂ͗��H�ȕ��ʂ̗F�B�͏��Ȃ��Ď�Ɏ������炻���������ʂ̘b���̂ł��邪�A���̎������̍��͎��g�ł͂��܂��B������͂��Ȃ��Ŏ�ɏ���̎����ĐF�X�̎d��������Ă��邱�Ƃ����̗F�l�����X�̘b�̐ܐ߂ɕ�������Ēm���Ă���̂ł���B ����Ō������A��s���сt��Ⴢ�A�V���L���̊��d�A�d�C���������Ă���F�l�A���̏���Ɖ]�����悤�ȏ����ɂ��̖��̔��W�̌a�H���i�s�����̂ł͂Ȃ����Ƒz�������B ���łɎ����g�̋ߍ��������ɂ���Ȃ̂�����B ���m�l�̋Ȕn�t�炵���̂����Ă��ꂪ�悸�Z����e���A���ꂩ�疭�Ȍ���s�������ˁt�̂悤�ɂ����n���������𑀂�Ƃ��ꂪ���C�I���̂悤�Ɍ����ė���B���̂����Ƀ��C�I���Ƃ��ՂƂ����ʓ���������ė��Ď����ɋߊ��A�������Ď����̊�̂����O�ɕ@�ʁs�͂ȂÂ�t��ڋ߂�����B�U�Ԃ��Č���Ɛ��m�l�͂������Ȃ��B�ǂ����������́u�I�[�C�����َq�������ė����v�Ƒ吺�ʼn]�����Ƃ��邪�オ����ĉ]���Ȃ��B�����ŊႪ���߂����A���������Ȃ���ĚX�s���ȁt���Ă��������ł���B ������O�����O�X���̑̌����ɖ������炵�����̂����t����B�H��ł�����Ǝ��o���ꂽ�_���e���p�c�̘b�ƁA�F�l�ƍ��t�̂Ƃ��ɏo���t�H�C���[�}���̃Z�����t��̉\�Ƃł��̖��̐��m�l�����������B���p���Ȕn�ɕό`���Ă��ꂪ�ҏb���ďo�����Ǝv����B���ꂩ���͂�O��̐H��ʼn����̂��ł���A�����ƑO�ɓ������̖ҏb�����o�������̂������b�������B���ꂪ�ҏb�����̏�ʂ��ďo������������Ȃ��B�u��َq�������ė����v���ǂ�������Ȃ����A���������̑O�X��ł���������͂�H��̎G�k�������ɂ��铞�����̂̒������َq����Ɏw�肵�Ď����ė����������Ƃ͂������̂ł���B �����̗��s������t�����C�I���ɂȂ錏�����͉��߂̎��������t����Ȃ��B����Ȃ̂���������t���C�h�ɂł���������ƁA�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ邩������Ȃ��Ƃ����C������̂ł���B ��L�̖������Ă����ƌ�����ɔ����قŊ�y�s�������t���y�\�y�̖ʂ̓W��������Č��ɍs�����B��i�̒��Ɏ��q���̎��q�̖ʂ���_���������A���̖ʂɕ����Ă��鐅�F�ɔ������ʂ���o�����z�Ђɑ����b饁s���Ă��݁t��\�킷���߂ł��낤�A�����̑������ɖD�����Ă���B���̖����̗��`�ɕ����܂��A�����̖��Ɍ��������̗��Ƃ�قǂ悭���Ă���̂ł�����Ƌh���s�т�����t������ꂽ�B ���̕����͑������R��������Ȃ����A������������������A�ȑO�ɗގ��̂����q���ǂ����Ō������̋L�����ӎ��̒�Ɏc�����Ă�����������Ȃ��Ƃ����\����ے肷�邱�Ƃ�����ł���B ����ɂ��Ă����p�t�Ȃ����Z���X�g�Ɩ����Ƃ̊W�͂�͂蕪��Ȃ��B���ɂ��Ƃ��̖��������̋������痈�Ă��邩������Ȃ����A�����������̋L���ɂ͋����Ɩ��p�t�܂����y�҂Ƃ̗��z�͈ӎ�����Ȃ��B(���a�\�N�ꌎ)�@ �@ |
|
| �����ː��ƉȊw�� | |
|
���x�N�����ƕ��ː��@ �A�����E�x�N����(1852�`1908) ���ː�����˔\���������ꂽ�͖̂�100�N�O�ŁA���͂��Ȃ�ŋ߂̏o�����Ȃ̂ł��B1896�N�A�����E�x�N�����́A�������d���g�̒��Ԃł�������z���������ɁA�����d���g�ł���X�����o���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��������Ă��܂����B�����A�w���̓��B���w�����E�����g�Q���ɂ���Ĕ������ꂽ���̕��ː��ł������A�܂����ː���������˔\�̑��݂͊m�F����Ă��܂���ł����B�x�N�����͌����̂��߂ɃE�������܂ގ��������ɓ��ĂȂ���Ȃ�܂��A���R�܂�̓������������߂Ɏ��������ɓ��Ă邱�Ƃ��ł��܂���ł����B�x�N�����������ɂ��̎������w�����o���Ă��Ȃ����ǂ������ׂĂ݂�ƁA���ĂĂ��Ȃ��͂��̎������A�w���ł͂Ȃ��ʂ̕��ː����o���Ă��邱�Ƃ����܂����B�����̌��ʁA���ː��̓E�����̔Z�x�ɔ�Ⴕ�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B ���L�����[�v�Ȃƃ��W�E�� �}���[�E�L�����[(1867�`1934) 1898�N�}���[�E�L�����[�͕v�̃s�G�[���E�L�����[�ƈꏏ�ɁA���ː��̓d����p���ώ@�ɂ���ăg���E�������܂����B�܂��A�E�����̍z�Β��ɃE�����ȊO�̕��ː����f���܂܂�Ă���Ɨ\�����A�|���j�E���E���W�E�������܂����B���Ƀ��W�E���̔����͑����̉Ȋw�҂̒��ڂ��W�߂܂����B�Ȃ��Ȃ�A�ƂĂ��������˔\�������Ă������߁A�l�X�ȕs�v�c�Ȑ����������Ă�������ł��B���Ƃ��A��ɐ������Ă���悤�Ɍ�������A�т�ɓ��ꂽ���W�E�����|�P�b�g�ɓ���Ă����ƁA�Ώ������悤�ȉ��ǂ��N�������肵�܂����B���������ڂ��W�߂��̂́A���W�E�����G�l���M�[���o�����������Ƃł��B���ː������͂������ː����o���Ȃ��Ȃ�܂����A���W�E���͔���������1602�N�Ɣ��ɒ��������̂ŁA�����͉i���ɕ��ː����o��������悤�Ɏv���܂����B �������ɎQ���������{�l�A�R�c���j �����U�t�H�[�h�ƐV�������q�\�� �A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h(1871�`1937) ���q�́A���q�j�̎����d�q������Ă���ƌ����Ă��܂����A���̍\�������������͕̂��˔\�̌���������������ł��B1902�N�A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�́A���ː��͌��q�����ĕʂ̌��q�ɂȂ�Ƃ��ɕ��o�������̂ł���Ƃ����A�����̏펯���悤�ȉ���\���܂����B�Ȃ��Ȃ�A���q�͕����̍����ł���A����ȏ㕪��������A�ω����邱�Ƃ��Ȃ��Ǝv���Ă�������ł��B1905�N�ɂ̓A���t�@���̐��̂��w���E���Ƃ������q�̌��q�j�ł��邱�Ƃ���܂����B1911�N�ɂ́u���q�͌��q�j�Ɠd�q���琬�藧�v�Ƃ����A�����������M���Ă��錴�q�\������܂����B���U�t�H�[�h�͂��ꂾ���ɂƂǂ܂炸�A�����E�����̔����A�����q�̑��݂̗\���ȂǑ���Ȍ��т��Ȋw�j�Ɏc���܂����B�@ |
|
| ���A���g���[�k�E�A�����E�x�N���� | |
|
(Antoine Henri Becquerel, 1852-1908)�@�t�����X�̕����w�ҁB���ː��̔����҂ł���A���̌��тɂ��1903�N�m�[�x�������w�܂���܂����B�p�����܂�B���q�̃W�����E�x�N����(�t�����X���)�������w�҂ł���B
�u��������w�̌����҃A���N�T���h���E�G�h�����E�x�N�����̑��q�A�Ȋw�҃A���g���[�k�E�Z�U�[���E�x�N�����̑��ŁA�����҂̓��ɐi�B�G�R�[���E�|���e�N�j�[�N�Ŏ��R�Ȋw���A�����y�؊w�Z�ōH�w���w�B 1903�N�A�m�[�x�������w�܂��s�G�[���E�L�����[�A�}���E�L�����[�Ƌ��Ɏ�܂����B 1908�N�A�u���^�[�j��������Le Croisic��55�̎Ⴓ�ŋ}���B�}���E�L�����[���l�A���ː���Q���������ƍl������B ���˔\��SI�P�ʂ̃x�N����(Bq)�̓A�����E�x�N�����ɂ��Ȃ�ł���B 1896�N�A�E�������̌u�����������ɁA�E���������o�������ː�(�A���t�@��)���ʐ^����I�������邱�Ƃ������B�x�N�����͋��R���ː��������Ƃ͂����A�����܂ł��u���̌����Ɍ��т��������ł������B�ŏ��̂���������1895�N11���Ƀh�C�c�̃����g�Q������������X���ł���B�x�N�����̓����ł������|�A���J����1������ɓ��肵�������g�Q���̘_�����x�N�����Ɏ�n���B���̂Ƃ��|�A���J���́uX�����u������Ȃ�A�u�����牽�炩�̕��ː����������邩������Ȃ��v�ƃx�N�����ɘb���Ă���B �������n�߂�ƁA���z���ɓ��Ă��E�����̗��_�J���E�������ӌ����邱�Ƃ������Ɋm�F�ł����B����ɁA���z���ɂ��炵���E���������������ŕ��ł��ʐ^�����������邱�Ƃ��A1896�N2���ɔ������Ă���B�Ō�̍K�^�͓ܓV(�ǂ�Ă�)�������������ł��Ȃ��������Ƃ������B�����ĊJ�ɔ����A�x�N�����̓E�������Ɗ����ꏏ�ɂ��܂��Ă������B�Ƃ��낪�������ĊJ����O�Ɋm�F����ƁA�������Ɋ������Ă��邱�ƂɋC�Â����̂������B�E�����������Ă���̂����炩�̕��ː��ł��邱�Ƃ́A��C�̓d���ɂ���Ċm�F�����B�E�����̔Z�x�ɑ�����ː��̋��x�̕��͂�A�E�����ȊO�̕��ː����f�̔����̓s�G�[���E�L�����[�ƃ}���E�L�����[�ɂ��B�@ |
|
| ���}���A�E�X�N�E�H�h�t�X�J���L�����[ | |
| (Maria Skłodowska-Curie, 1867-1934)�@���݂̃|�[�����h(�|�[�����h��������)�o�g�̕����w�ҁE���w�ҁB�t�����X�ꖼ�̓}��(�}���[)�E�L�����[(Marie Curie)�B�����V�������܂�B�L�����[�v�l(Madame Curie)�Ƃ��ėL���ł���B���ː��̌����ŁA1903�N�̃m�[�x�������w�܁A1911�N�̃m�[�x�����w�܂���܂��A�p����w���̏��������E�ɏA�C�����B���˔\ (radioactivity) �Ƃ����p��͔ޏ��̔��Ăɂ��B�@ | |
| �� | |
|
���c����
���a���̖��O�̓}���A�E�T�����E�X�N�E�H�h�t�X�J(�X�N���h�t�X�J)(Maria Salomea Skłodowska)�B���u���f�B�X�J�E�X�N�E�H�h�t�X�L(�X�N���h�t�X�L�[)�͉����M���K���o�g�ŁA�鐭���V�A�ɂ���Č����⋳�d�ɗ����Ƃ𐧌������܂ł̓y�e���u���N��w�Ő��w�ƕ����̋��ڂ��������Ȋw�� �B�����̑c�����[�t�������E���w�̋����ł���A���u�����ŎႢ���̃{���X���t�E�v���t(en)���t�������B��u���j�X���o�E�{�O�X�J�������M���K���o�g�ŁA���w�Z(�{�[�f�B���O�X�N�[��)�̍Z���߂鋳��҂������B �}����5�l�Z��̖����q�ŁA�o�]�t�B�A(1862�N��)�A�u���X�j���o(��Ɠ����A1865�N��)�A�w��(1866�N��)�A�Z���[�t(�c���Ɠ����A1863�N��)�B���̒��ł��}���A�͗c���̍����瑏���ŁA4�̎��ɂ͎o�̖{��N�ǂł��A�L���͂����Q�������B ���������A�|�[�����h�̓E�B�[����c�ɂĕ�������A�����V���������̓|�[�����h���������Ƃ��Ď�����鐭���V�A�ɕ������ꂽ��Ԃɂ���A�Ɨ����Ƃ̑̂��Ȃ��Ă��Ȃ������B�鐭���V�A�͒m���w���Ď����čs���ɐ�����������B�}��6�̎��A���u���f�B�X�J�������ɍu�`���s���Ă������Ƃ����o���ĐE�ƏZ�����������B����ɕ�u���j�X���o���g�̂��Ă��܂����B���@�ւ̎��s���d�Ȃ�n��������Ƃ͈ڂ�Z�Ƃŏ����Ȋ�h�w�Z���J�������A1874�N�ɐ��k���늳�����`�t�X����ƂɈڂ�A�o�]�t�B�A���S���Ȃ����B1878�N�ɂ͕�u���j�X���o�����j�ő��E�����B14�̃}���͐[���ȟT��ԂɊׂ�A��ɕ�����J�g���b�N�̐M���̂āA�s�m�_�̍l�������悤�ɂȂ����Ƃ����B�@ |
|
|
���ƒ닳�t�̃L�����A�Ɣj�ꂽ��
1883�N6���ɃM���i�W�E����D�G�Ȑ��тő��Ƃ����B �����������A�����ɂ͐i�w�̓��͊J����Ă��Ȃ������B���́A�}����e�ʂ₩�Ă̋����q���Z�ޓc�ɂő����������A�ޏ��͎��R�̒��ł̂�т肵�����������\�����B ���̌ハ���V�����ɖ߂��ă`���[�^�[�Ȃǂ߂Ă������A�s���Z�c�J�Ƃ����������t�̏Љ�Ŕ@�́u���܂悦���w(en)(�����V�����ړ���w)�v�Ŋw�ԋ@����B���̍��A�o�u���X�j���o���p���Ŗ�w�C�w�̂��߂ɒ��������Ă������A�}���͐\���o�ē����A�o���������邱�Ƃ����߂��B1885�N����}���͏Z�ݍ��݂̉ƒ닳�t���n�߂��B�ŏ��̓N���N�t�̖@���ƈ�ƂŁA���̌�`�F�n�k�t(en)�Ŕ_�Ƃ��c�ޕ����̐e�ʋɓ���]���t�X�L�ƂŃK���@�l�X�ƂȂ����B�����ŕw�ɑł����ޏ��ɁA�����V������w�Ő��w���w��ł�����Ƃ̒��j�J�W���~�F�V���E�]���t�X�L(en)���䂩��A�ӂ���͗����ƂȂ����B�������A�J�W���~�F�V���������̊�]�𗼐e�ɍ�����ƁA�Љ�I�n�ʂ̈Ⴂ�𗝗R�ɖҔ����ꂽ�B�ޏ��͎��ӂ̂܂܌_���2�N�Ԃ��I����ƃ`�F�n�k�t������A�o���g�C���݂ɂ���\�|�g�̒��ɏZ�ރt�b�N�X�Ƃł����1�N�ԉƒ닳�t�̎d���𑱂����B 1890�N3���A�������O�Ɉ�t�J�W���~�F�V���E�h�E�Y�L�ƍ����o�u���X�j���o���p���ňꏏ�ɏZ�ނ悤�U���莆���}���ɓ͂����B�����ޏ��͒f��B����o�̌��ɂ���ƌ��߂����ƁA�����V�����̉ƒ닳�t�̎d���������ŁA�����V�����ړ���w�ł̕w�Ɋy�����������Ă��邱�ƁA���w����ɂ͒~�����[���ł͂Ȃ����ƁA�����ăJ�W���~�F�V���E�]���t�X�L��Y���ꂸ�ɂ������Ƃ��������B�ޏ��͉ƒ닳�t������T��A�I�[���h�^�E���ߍx�̃N���N�t�x�O�ʂ�(en) 66�ɂ���_�H������(en)�̎������ʼnȊw�����̋Z�\�K���ɓw�߂��B���̎������̓T���N�g�y�e���u���N�Ń��V�A�̒����ȉ��w�҃h�~�g���E�����f���[�G�t�̏���߂����Ƃ����邢�Ƃ��̃��[�t�E�{�O�X�L�[���Ǘ����Ă���A�܂����[�x���g�E�u���[���Ɋw��N. Milicer���ޏ����w�������B �]�@��1891�N�H�ɁA�ޏ��ɂƂ��Č����čK���ł͂Ȃ��`�ŖK�ꂽ�B�����͔F�߂��Ȃ��������A�J�W���~�F�V���E�]���t�X�L�ƃ}���͘A������荇���Ă����B������9���A��l�̓U�R�p�l�Ŕ����̗��s�����ɂ����B��������24�ɂȂ�}�����P�������l���ɕω������҂������A�ނ͗D�_�s�f�ʼn������f�ł����ɂ����B���̂��ߓ�l�͌��ܕʂꂵ�Ă��܂��A�}���͎���t�����X�s�������ӂ����B ����̃J�W���~�F�V���E�]���t�X�L�́A���m���擾��ɐ��w�҂Ƃ��Ă̗�����ς݁A�܂����M�F�E�H��w�̊w���A�����V�������璡�̒����܂ŏ��l�߂��B�����ӔN�ɂ́A1935�N�Ɍ��Ă�ꂽ�}���E�L�����[�̓����̑O�ɍ��荞��ʼn����̑z���ɂӂ���A�����V�����H�ȑ�w(en)�̘V�����ƂȂ����ނ̎p������ꂽ�Ƃ����B�@ |
|
|
���p���ł̋�w
3���Ԃ̋D�Ԃ̗����o�āA1891�N10���A�}���̓p���Ɉڂ�Z�B�����A�����ł��Ȋw�������u�\�Ȑ����Ȃ��@�ւ�1�ł������\���{���k(�p����w)�̓o�^�p���ɂ͖��O���u�}���A�v����t�����X�ꕗ�Ɂu�}���[�v�Ə����A�����A���w�A���w���w�ԓ��X���n�܂����B�X���u�n�̔������痧���ɖ��邢�u�����h�A�O���[�̓��̃}���͊w���ł��l�ڂ������A�ޏ����g���`�Z��ʂ��ĎႫ�C�O�i�c�B�E�p�f���t�X�L�Ȃǃp���ݏZ�|�[�����h�l��Ƃ��e�����������B �������A�����̓|�[�����h�ɖ߂�ƌ��߂Ă��������ɂ͎��Ԃ��������ƂɋC�Â��A�o�v�w�̌��𗣂�ăp���ɂ悭������7�K���Α���A�p�[�g�̉�������������Ĉ����z�����B�}���͒��Ɋw�сA�[���̓`���[�^�[�߂����𑗂����B������Ɏ������ĐH�����낭�Ɏ�炸�A�g�[���Ȃ��������ߊ������ɂ͎����Ă��镞���ׂĂ𒅂ĐQ����X���߂����Ȃ���w�ɑł����B���ɂ͓|��Ĉ�t�ł���`�Z�̖ʓ|�ɂȂ������Ƃ����������A�w�͂��d�˂�����1893�N�ɂ͕����w�̊w�m���i���B���̔N�A���~���������x�͒��߂����A�����̊w�F���ޏ��̂��߂ɏ��w����\�����w�𑱂��邱�Ƃ��ł����B�@ |
|
|
���s�G�[���E�L�����[
�w�m���l����A����܂ł̒~���ɗ��鐶����ς��ă}���̓t�����X�H�ƐU������̎���������s���A�킸���Ȃ����������悤�ɂȂ����B���ς�炸�������̕n�R�����͑��������A���̒��Œ��~�����w����S�z�Ԕ[�����B �������A��������|�S�̎��C�I�����̌����͑�w��߂Ă����K�u���G���E���b�v�}���̍H�Ǝ�����ōs���ɂ͎苷�ō����Ă����B����ȍ��A�`�F�n�k�t����ɒm�荇�����������V�����s�Ńp���ɗ��āA�}����K�˂Ă����B�ޏ��̕v�ł���t���u�[����w(en)�����w�����̃��[�t�E�R���@���g�X�L���Y�݂��A�ꏊ�̒𗊂߂����Ȑl�����Љ��^�тƂȂ����B���ꂪ�A�t�����X�l�Ȋw�ҁE�s�G�[���E�L�����[�������B �s�G�[���E�L�����[�͓���35�B�p���s���H�ƕ������w��������w (EPCI) �̋��E�ɏA���Ă����B�����̃s�G�[���̓t�����X�ł͖����ɋ߂��������A�ނ̓C�I�������̗U�d���ɂȂǓd�ׂ⎥�C�̌����Ő��ʂ������Ă���A�L�����[�V���J�����ɃL�����[�̖@���q�����{�����Ȃǂ��𖾂��Ă����B1893�N�ɂ̓C�M���X�̃E�B���A���E�g���\��(�P�����B����)���킴�킴�ʉ�ɖK�˂���A�t�����X���O�ł͊��ɓV�˂̌Ăѐ������������B �������ގ��g�͏o���⏗���Ƃ̌��ۂȂǔO���ɒu���Ă��Ȃ������B�M�͂�f��A�����Ƒe���Ȍ��C�ݔ��ɊÂȂ��疳�S�Ɍ����ɑł����ޓ��X�𑗂��Ă����B�ِ��ςɂ��āA�s�G�[���͓��L�Ɂu�����̓V�˂Ȃǂ߂����ɂ��Ȃ��v�ƁA���g�̊w��I�T���S�𗝉����Ă͂���Ȃ��ƍl���Ă����B 1894�N�t�A���Ζʂ̃s�G�[������������ۂ��A�}���́u���g�œ��͐��݁A�����ŗD�����l���Ȃ���A�ǂ����z���Ȗ��z�Ƃ̕��͋C��X���Ă����v�ƐU��Ԃ�A�Ȋw��Љ�̂��Ƃ���荇�����ۂɂ͎����Ƌ��ʂ���Ƃ���𑽂��������Ƃ����B�����ăs�G�[���������悤�Ɋ����Ă���A�ނ̓}���Ɏ䂩�ꂽ�B��ɖ��v�w��������ƉƑ��ŒʎZ5�x�̃m�[�x���܂���܂��邱�ƂɂȂ�L�����[�v�Ȃ͂������ďo�����A���C�ƃR���@���g�X�L��������l�̓V�˂��������킹���L���[�s�b�g���ƂȂ����B �s�G�[���͈�O���N���Ċw�ʎ擾��ڎw���A�d�グ���u�Ώ̐��ۑ��̌����v(�L�����[�̌���)�_���̎ʂ���ޏ��ɑ���A��l�̋����͏k�܂����B�����ă}���͎����̉����������ɔނ����҂��A�s�G�[���͕n�����T�܂����ޏ��ɑł��ꂽ�B���݂��ɑ��h���M���������e���Ȋԕ��ɂȂ�����l�����A�}���͂����|�[�����h�ɋA��Ɛ����Ă����B1894�N�ɐ��w�̊w�m���i���}���͉ċG�x�ɂ𗘗p���ă����V�����ɗ��A�肵�����A�ӂ����уt�����X�ɖ߂邩�ǂ������߂��˂Ă����B�ޏ��͓�������T���Ă݂����A���M�F�E�H��w�͏������ق�����Ȃ������B���̊ԁA�s�G�[���̓}���ɁA�����̎莆�����x������A10���Ƀ}���̓p���ɋA���Ă����B�s�G�[���͔M�ӂڃ}���Ɍ��A�ꏏ�Ƀ|�[�����h�ɍs���Ă��悢�Ƃ܂œ`�����B�ޏ����ނ̃v���|�[�Y����������̂�1895�N7���ɂȂ����B 1895�N7��26���A���f�Ȍ��������s��ꂽ�B�V�w�̃h���X�͋`�Z�̕ꂪ���������́B����ł̐������A�w�ւ��A�����������ɂ̓|�[�����h���畃��o���������������B�j���̒��Ŏ����I������l�́A�j�����ōw���������]�Ԃɏ���ăt�����X�c���n�т�����V�����s�ɏo�������B�������ă}���́A�V�������A�l���̔����A�����ė��������Ȋw�����̓��u���B�@ |
|
| �� | |
|
�����˔\
�O���V�G�[���ʂ�̃A�p�[�g�ŐV�������n�܂����B�}����EPCI�Ō����𑱂��Ȃ���Ǝ������Ȃ����B�ٖD�͑O���瓾�ӂ��������A�Ɛg�̍��͂낭�ɂ��Ȃ������������ǂ�ǂ�r���グ���B�����������邽�߂ɒ��E�������狳���̎��i���擾�����B1897�N9��12���ɂ͒����C���[�k�Ɍb�܂�A���̏o�Y�ƈ玙�ɂ͋`���ň�t�̃E�W���[�k�E�L�����[���ޏ����������B���N���ɂ͓S�|�̎����ɂ��Ă̌����_�����d�グ���B �}���͕v�Ƙb�������A���m���擾�Ƃ������̒i�K�i�ތ����ɓ������B��l�͂����ŁA1896�N�Ƀt�����X�̕����w�҃A�����E�x�N�����������A�E���������������˂���X���Ɏ������ߗ͂��������ɒ��ڂ����B����͗ӌ��ȂǂƈقȂ�O������̃G�l���M�[����K�v�Ƃ����A�E�������̂����R�ɔ����Ă��邱�Ƃ������ꂽ���A���̐��̂⌴���͓�̂܂܃x�N�����͌�����������Ă����B�}���ƃs�G�[���́A�_���쐬�̂��߂��̌�����ڕW�ɐ������B �s�G�[�����m�ۂ���EPCI�̎�����͑q�Ɍ��@�B���𗬗p�����g�[���������e���Ȃ��̂ŁA�K�₵������w�҂́u�W���K�C���q�ɂƉƒ{�����𑫂���2�Ŋ������悤�ȁv�ƗႦ����������B�����Ƀs�G�[���ƌZ�̃W���b�N��15�N�O�ɔ����������e�R�𗘗p���鍂���x�̏ی��d���v�ƁA�s�G�[���J���̐����s�G�]�f�q�d�C�v�ȂNj@����������݁A�E�����������̎��͂ɐ�����d�����v�������B�����Ă����ɁA�T���v���̕��ˌ��ۂ����ۂ̃E�����ܗL�ʂɍ��E����A���≷�x�ȂNJO�I�v���ɉe�����Ȃ��Ƃ������ʂ��B�܂�A���˂͕��q�Ԃ̑��ݍ�p���ɂ����̂ł͂Ȃ��A���q���̂��̂Ɍ��������Ƃ������B����́A�v�Ȃ����炩�ɂ������̂̒��ōł��d�v�Ȏ����ł���B���Ƀ}���́A���̌��ۂ��E�����݂̂̓������ǂ����^��������A���m�̌��f80�ȏ�𑪒肵�g���E���ł����l�̕��˂����邱�Ƃ������B���̌��ʂ���A�}���͂����̕��˂ɕ��˔\�ƁA���̂悤�Ȍ��ۂ��N�������f����ː����f�Ɩ��Â����B �ޏ��͔����������e���ɔ��\���邱�Ƃ������ӎ����A�Ȋw�ɂ������挠(en)�������Ƃɕq���������B2�N�O�Ƀx�N���������g�̔������Ȋw�A�J�f�~�[�Ɍ��\�������������Ɨ����ɐL���Ă�����A�����҂̉h�_���A�����ăm�[�x���܂��V���o�i�X�E�g���v�\��(en)�̂��̂ɂȂ��Ă����\��������B�v�Ȃ��ނƓ������f������i�����A�}���͌������e���Ȍ��ɗv���_�����쐬���A�K�u���G���E���b�v�}����ʂ���1898�N4��12���ɉȊw�A�J�f�~�[�֒�o�����B�������A�v�Ȃ̓g���v�\�����l�A�g���E���̕��˔\���������ł͔s�ꂽ�B2�����O�Ƀx�������ŃQ�A�n���g�E�V���~�b�g(en)���Ǝ��ɔ����E���\���Ă����B�@ |
|
|
���V���f�̐����ƌ���
�}���̒T���S�͎~�܂邱�Ƃ�m�炸�A����EPCI�ɂ���l�X�ȍz���T���v���̕��˔\�]�����n�߂��B�₪�āA2��ނ̃E�����z�ɂ��Ē��ׂ����ʁA�g���x���i�C�g(�ӓ��E�����z)�̓d�����E�����P�̂���2�{�ɂȂ�A�s�b�`�u�����h�ł�4�{�ɑ������邱�Ƃ�������A�����������̓g���E�����܂�ł��Ȃ������B���肪��������A�����̍z�ɂ̓E���������y���Ɋ����ȕ��˂��s����������̕��������ʂ��܂܂��Ɣޏ��͍l�@�����B�}���́u�ł��邾�����}�ɂ��̉������m���߂����Ȃ�M��Ȋ�]�ɂ���ꂽ�v�ƌ�ɏq�ׂ��B 1898�N4��14���A�v�Ȃ̓s�b�`�u�����h�̕��͂ɂ�����A100�O�����̎�������_�Ɠ����ł���ׂ���Ƃɒ��肵���B�s�G�[���̓}���̍l�@�̐��������m�M���A�₪�Ď��g��ł��������Ɋւ��錤���𒆒f���Ĕޏ��̎d���ɉ�������B1898�N7���A�L�����[�v�Ȃ͘A���Ř_���\�����B����̓|���j�E���Ɩ��Â����V���f�����Ɋւ�����̂������B�����12��26���ɂ́A���������ː����郉�W�E���Ɩ��������V���f�̑��݂ɂ��Ĕ��\�����B �v�Ȃ̔��\�Ɋw��̔����͗�W�������B�����w�҂͐V���f�̕��ː����ǂ̂悤�Ȍ��ۂ��琶����̂����s���ȏ�Ԃł͎^�����Â炭�A���w�҂͐V���f�Ȃ���̌��q�ʂ����炩�łȂ���Ȃ�Ȃ��ƍl���Ă����B���̂��߂ɂ͏����ȐV���f�̉�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�}���͂���ɒ��ތ��ӂ������B�������s�b�`�u�����h�͔��ɍ����ŁA�������肷�鎑���Ȃǖ��������B�n�l�̖��A�K���X�������ɒ��F�ړI�Ŏg���E�������𒊏o������̔p�����𗘗p������@���v�����A�吶�Y�n�ł���I�[�X�g���A�̃{�w�~�A�E�U���N�g�E���A�q���X�^�[���z�R�֓`�𗊂��Ė₢���킹���Ƃ���A�����Œ����邱�ƂɂȂ����B�������^����͕v�Ȃ����S���Ȃ���Ȃ炸�A�ƌv����������v���ƂȂ����B ���ɕK�v�Ȃ��̂́A�����ɕK�v�ȍL���ꏊ�������B�s�G�[����EPCI�Ɋ|�����������A��l�͌�������邱�Ƃ��ł������A�ȑO�͈�w���̉�U���Ɏg���Ă����A���������������������A�������L�����[�v�Ȃ̗l�X�ȋƐтޕ���ƂȂ�B �s�b�`�u�����h�͕��G�ȉ��w�g�����������z���ł���A���������͔��ɓ�����̂������B�������A�v�Ȃ̓��W�E���������Ȍ�����(���ʌ����@)�������Ď��o���Ƃ������@�ɒ����A����͉ߍ��ȓ��̘J����v�������B���L���P�ʂ̍z���������قŎϕ��E���a�E�n���Ⓘ�a�E��߂Ȃǂ̕��@�ŕ������A�n�t�����������邱�Ƃ����i�K���J��Ԃ��B�����ɂ͉��˂������A�傫�ȉ��g����Ƃ͉��O�ōs�����B���s���ĕ��˔\�̌������s��Ȃ���Ȃ炸�A�₪�ĕv�w�ԂŎd�������S����A�ׂ��Ȍ������s�G�[�����A������Ƃ��}�����s���悤�ɂȂ����B�������ŏ��Ɏ�ɓ��ꂽ1�g�����������Ă��S������Ȃ������B�v�Ȃ͐V���f�̊ܗL����1/100���x�Ɩژ_��ł��������ۂɂ�1/1000000�����ł����Ȃ��A�L�ӂȗʂ邽�߂ɕK�v�ȍz�Ηʂ͉��g���ɂ��Ȃ邱�Ƃ͂܂��킩���Ă��Ȃ������B �v�Ȃɂ͎��Ԃ�����Ȃ������B�����ɂ�����o��̕��S�A�Ȃ�S�������`���E�W���[�k�E�L�����[�̓����ʼnƑ��������Ĉ����z������ˌ��Ẳƒ��Ȃǐ�������҂����߁A�ӂ���Ƃ����E�𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�s�G�[���͎������グ�悤�ƃ\���{���k�����E�̋ɉ��債�����A�t�͊w�Z���o�Ă��Ȃ����ƂȂǂ𗝗R�ɗ��I�����B����Ȑ܂�1900�N�A�X�C�X�̃W���l�[����w����v�Ȃ֍D�����̋����E�I�t�@�[�����������A�����𒆒f���Ȃ��Ă͂Ȃ炸���ނ����B�����`�����������w�҃A�����E�|�A���J���́A�D�G�ȓ��]�̍��O���o��h�����߂ɍ���܂��ăs�G�[�����\���{���k��w���̕����E���w�E�����w�ے�(PCN) �����ɏ��ق��A�܂��}�����Z�[�u���̏��q�����t�͊w�Z�̏������t�ƂȂ����B�������Ď����͏����������������ɂ͏Ă��ɐ����x�������B�@ |
|
|
�����W�E���̐���
�|���j�E���͉��w�I�������r�X�}�X�ɋ߂��A�z�̒��Ńr�X�}�X�l������T�����ƂŔ�r�I�ȒP�ɂ��ǂ�����B���������W�E�������͈�ؓ�ł͂����Ȃ������B���w�I�������߂����f�Ƀo���E�������邪�A�z�Β��ɂ̓o���E���ƃ��W�E���̗������ܗL���Ă����B1898�N�̒i�K�ŕv�Ȃ̓��W�E���̍��Ղ�͂�ł������A�����ȏ�Ԃŏ[���ȗʂ��m�ۂ���ɂ͎���Ȃ������B �Ȋ��Ɖߍ��ȍ�ƁA�N�������ƌv��d�����߂̋��E�̑��Z���䂦�A�v�Ȃ̌��N��Ԃɂ܂ň��e�����y�ڂ��A�s�G�[���͐������ꎞ���f���ׂ��Ƃ��l�����B�������}���͏��������X�Ɛi�ލ�ƂɊ�]�����o���Ă����B1�g���̃s�b�`�u�����h���番�������ł������W�E����������1/10�O�����ɂ����Ȃ�Ȃ��������A���ː����f�͒��X�ƔZ�k����A�₪�Ď����ǂ�����M���甭����������悤�ɂȂ������炾�B�}���͂�����u�d���̂悤�Ȍ��v�ƌ`�e���Ă���B1902�N3���ɂ͔Z�k�Ɍ��ʓI�Ȏ�������A�����p���Đ������������̃X�y�N�g�������W�E���ŗL�̂��̂ł��邱�Ƃ�˂��~�߁A�v�Ȃ͏������W�E�����̐����Ɋ������o�����B�v�Ȃ́A�L�ӂȏ������W�E������܂ł�11�g���̃s�b�`�u�����h�����������B ���������̍��A�x�d�Ȃ�s�K���v�Ȃ��P���B1902�N5���A�}���̕��u���f�B�X�J��Ă̒m�点���͂��A�A���̂��Ȃ��]������B�ޏ��͐e�s�F�Ȏ�����ӂ߂����A�ӔN�̃u���f�B�X�J�͓͂��}���̘_�����y���݂ɓǂ݁A����3���Ƀ��W�E�����������̎莆�ɂ͑傢�Ɋ�сA�����ւ�Ɏv���Ă����B����̃s�G�[���ɗF�l�����̓A�h�o�C�X�𑗂�A�J�f�~�[����ɂȂ�悤�E�߂����A7���̑I���ŗ��I����B���������̂悤�Ȋ������h�_�ł͂Ȃ������̂��߂̂��̂ŁA�t�Ƀ��W�I���h�k�[���M�͂̌��ƂȂ������ɂ͌��������Ɋ�^���Ȃ��ƒf���Ă���B�v�Ȃ͌����ɖ߂邪�̂ɕϒ����������A�s�G�[���̓��E�}�`�������������т��є���ɋꂵ�݁A�}���͐_�o�𐊂������������V�s�ǂ��N�����悤�ɂȂ����B��1903�N�ɂ͑Җ]�̑��q�𗬎Y���Ă��܂��A�}���͔߂��݂ɂ��ꂽ�B ���̂悤�ȋꋫ�̒��Ői�߂�ꂽ�������ʂ�v�Ȃ͒���w��ɒm�炵�߁A1899�N����1904�N�ɂ�����32�̌������\���s�����B�����͑��̊w�҂����ɕ��˔\����ː����f�ɑ���F���ɍ��V�𔗂�A�����Ɍ����킹���B���ː����f�̒Nj��͂������̓��ʑ̔����Ɍq����A����ɃE�B���A���E�����[�[�ƃt���f���b�N�E�\�f�B�̃��W�E������ɂ��w���E�������̊m�F�A�A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�ƃ\�f�B�̌��f�ϊ����Ȃǂ������炳�ꂽ�B�����́A�����̊T�O�ł������u���f�͕s�ρv�ɕϊv�𔗂�A���q�����w�Ɉꑫ��т̐i���������炵���B ����ɁA1900�N�Ƀh�C�c�̈�w�҃��@���N�z�b�t�ƃM�[�[��(en)���A���ː��������g�D�ɉe����^����Ƃ������Ȃ��ꂽ�B�����s�G�[���̓��W�E����r�ɓ\��t���A�Ώ��̂悤�ȑ������m�F�����B��w������Ƌ��������������ʁA�ώ������זE��j����ʂ��m�F����A�畆�����∫����ᇂ����Â���\�����������ꂽ�B����͌�ɃL�����[�Ö@�ƌĂ��B�������ă��W�E���́u����v�Ƃ��Ēm����悤�ɂȂ����B��ꎟ����A�Ȋw�҂̊Ԃŕ��ː��픘(en)�ɂ��l�̉e���ւ̊댯�����X�ɂł͂��邪�F�m����Ă��āA�����̕��ː���������舵���Ȋw�҂�͉���p�������ː��h��A���߂̎g���̂ĂȂǂ̑������Ă���A�}���͌���������Ɏ�܂ł̖h�������悤�������w�����Ă������{�l�͕��ː�������f��ň������Ƃ������A�h����w�Ǎs��Ȃ������B���̂��߃}���̎�̓��W�E���Ώ��̍����炯�Ŋ����X�����̂悤��ᰂ��c���Ă����Ƃ����B �V���f���W�E���́A�w��ΏۂɎ~�܂炸�A�Y�ƕ���ł��L�p�������X�Ɩ��炩�ɂȂ����B�L�����[�v�Ȃ́A���W�E�������@�ɑ���������擾�������J�����B����͒��������Ƃ����A���̂��߂ɑ��̉Ȋw�҂����͉��̖W�����Ȃ����W�E�����g�p���邱�Ƃ��ł����B�t�����X�̎��ƉƃA�����E�h�E���[��(Emile Armet de Lisle)�̓��W�E���̍H�ƓI���Y�ɏ��o���A�v�Ȃ̋��͂����A��Õ���ւ̒��n�߂��B���W�E���͐��E�ōł������ȕ����ƂȂ����B�@ |
|
|
���h�_�̌��Ɖe
���ː������̌����͌��X�}���̔��m���擾��ړI�Ɏn�߂�ꂽ���A���Z�̂��߂Ȃ��Ȃ����̏����ɂ�����Ȃ������B���������������ƓZ�߂��A�A�����E�x�N�������㉟������1903�N6���ɘ_���R�������B�v�Ƌ`���A�o�A�����q����������钆�A3�l�̘_���R�������w�́A�}���Ƀp����w�̗��w���m (DSc)���������B���̓��̗[�H��ɂ́A�m�荇���̑��ɂ��܂��܃p���ɗ��Ă��ĖK�₵���A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h�v�Ȃ�������Ă����B �v�Ȃ̋Ɛт��ł������]�������̂̓C�M���X�������B1903�N6���A�����������͕v�Ȃ𐳎��Ƀ����h���֏��҂��A�u�����˗������B�s�G�[���͎������������u���Ŋ��т𗁂сA�}���͌�������ɏ��߂ďo�Ȃ��������ƂȂ����B�P�����B������E�B���A���E�N���b�N�X�A�W�����E�E�B���A���E�X�g���b�g(���C���[��)��Ƃ��e�����������B�����11���ɂ͉��������f�[�r�[���_�������^���ꂽ�B������1903�N12���A�X�E�F�[�f�������Ȋw�A�J�f�~�[�̓s�G�[���ƃ}�������ăA�����E�x�N������3�l�Ƀm�[�x�������w�܂����^���錈����������B���̗��R�́u�A�����E�x�N���������������������ˌ��ۂɑ��鋤�������ɂ����āA���M���ׂ��������܂�Ȍ��т����������Ɓv�ł������B�������ă}���́A�������̃m�[�x���܂����^���ꂽ�l���ƂȂ����B�v�Ȃ̓X�g�b�N�z�����̎����ɂ͏o�Ȃł��Ȃ��������A����7���t�����̏܋��͈�Ƃ̌o�Ϗ�Ԃ��~���������łȂ��A���K�I�Ɍb�܂�Ȃ��m�l��w�������̂��߂ɂ��𗧂Ă�ꂽ�B ���̃m�[�x���܂̐R�����s��ꂽ�ہA�A�J�f�~�[�͕����w���^�Ō�����i�߂Ă������A�I�l�ψ���̒��ɂ͐V���f�����͉��w�܂��Y������̂ł͂Ƃ����^��̐������������B���̂��߁A1903�N�x��ܗ��R����̓��W�E���ƃ|���j�E���̔����͂����ĊO����A�����̎��^�Ɋ܂݂���������Ή����s��ꂽ�B �m�[�x����܂́A��l����C�ɗL���l�ɂ����B����������͕v�Ȃ̖]�ނ��̂ł͂Ȃ������B���X�̎�ނ�ʉ�̈˗��A�������ޑ��ʂ̎莆�ȂǂɎ��Ԃ�����A���܂�����Ƃ̎���⌤�����ɂ܂œ��ݓ��낤�Ƃ���}�X�R�~��焈Ղ��A����茤��������]�T���D��ꂽ�B1904�N�A�p����w�̓s�G�[�����w�����E�Ɍ}����Őf���s�������A���������p�ӂ���Ȃ����Ƃ�m�����s�G�[���͂�������ނ��悤�Ƃ����B��w���͐܂�A�c��Ɋ|�������Č�����Ɛݔ����P�o���A����ƃs�G�[���̏������B ���̔N�A�}���͔D�P���Ă������Ƃ�����A��Ƃ͒i�X�B�ٓI�Ȑ����𑗂�悤�ɂȂ����B�����͂ł����A��O�ɒǂ���邽�߂ɋU�����g���ău���^�[�j���̓c�ɂ֔��邱�Ƃ��������B����ȕv�Ȃ́A1904�N12��6���Ɏ����G�[�����Y�܂ꂽ���Ƃŗ������������߂��n�߂��B1905�N�ɂ͋��E�ɕ��A���A�������ɓ��鎞�������n�߂��B���ς�炸�p�[�e�B�[�Ȃǂ͔����Ă������A�S�ɗ]�T���ł���Ɖ����ӏ܂Ȃǂɂ��o��������A�����ƃ��C�E�t���[�⒤���ƃI�[�M���X�g�E���_���A�Ȋw�ҊW�łׂ͗ɏZ�ރW�����E�y�����v�ȁA�W�����W���E�����o����V�������E�G�h�D�A�[���E�M���[���ȂǂƂ��e���������A���т��щƂɏ������B�����ɂ͋����q�����������邱�Ƃ�����A���̒��ɂ̓s�G�[���̐��k�|�[���E�����W���o���������B�@ |
|
|
��1906�N4��19��
1906�N�ɓ���A�����E�ƂƂ��ɓ����V�����L�����B�G�ʂ�̎������������n�߂��B�苷�Ō�ʂɕs�ւȍx�O���������A����Ǝ�`�������������Ɏ�����C�ɂ̓}�����C������A���^���x����ꂽ�B�v�Ȃ͑��ς�炸���Z�������B�}���̓Z�[�u�����q�w�Z�̋��t�𑱂��A�s�G�[���͉Ȋw�҂����đ�w�����Ƃ��Ă̗l�X�ȎG���ɒǂ��Ă����B �����4��19���ؗj���ɋN�������B�J�͗l�̓��s�G�[���͗l�X�ȗ\������Ȃ��A�n�Ԃ��s�����������h�t�B�[�k�ʂ�(en)�����f���Ă����ۂɂԂ������הn�Ԃ�瀂���A���̎������B�쎟�n�͔�Q�҂��L���ȉȊw�҂��ƋC�Â����B������w�ɓd�b�A�����Ȃ���A�w�����Ƌ����̃W�����E�y�������L�����[�ƂɌ��������B���̎��}���͕s�݂ŁA�`�����ނ����������Ē��ɂȎ���҂����B�ߌ�6���A�C���[�k��A��ċA����}���͂��̒m�点�ɓ�����A�b���͒N�̖₢�����ɂ����̔����������Ȃ������B��̂��i�����ꂽ�}�����Ƃ߂ǂȂ��܂𗬂����̂́A�����ɋ삯�����`�Z�W���b�N�̎p�������Ƃ��������B���̕s���̎��̂͐��E���ɕ��ꂽ�B�������A21���ɐ��Ƃ̃\�[�ōs��ꂽ���V�ł́A��\�c�̔h�����������傰���ȍs����}���͒f��A���f�Ȏ��ƂȂ����B�`����`�Z�W���b�N��́A��������������悤�Ȕޏ���S�z���Ă����B���̓����̃}���͓��L�Ɂu�����^���������n�Ԃ͂��Ȃ��̂��낤���v�Ƃ܂ŏ����Ă���B���̌���ޏ��͒��قɒ��܂܁A���ɔߖ��グ��ȂǕs����Ȑ��_��Ԃɂ���A���L�ɂ͔ߒɂȌ��t�����B 5��13���A�p����w(�\���{���k)�����w���̓s�G�[���ɗp�ӂ����E�ʂƁA�������ɂ����鏔�������}���̂��߂Ɉێ����邱�Ƃ����߂��B���V�̗����ɐ\�������ꂽ���̈⑰�N���͂����ς�ƒf�����}�����������A���̌��͉�ۗ������B�F�X�Ȃ��Ƃ������悬�������A�₪�Ĕޏ��́u�d����Y�v���p���A�s�G�[���ɂӂ��킵������������邱�Ƃ������̂��ׂ����Ƃƌ��f���A��w�̐E�ʂƎ������̌�C����������B�������āA�p����w���̏����������a�������B �Ă̊��ԁA�Z�����s�G�[���̎��Ƃł���\�[�Ɉڂ��đ�w�u�`�̏����ɔ�₵���B������11��5���ߌ�1��30���A�}���͖����̔�����ă\���{���k�̋��d�ɗ������B�ǂ�Ȉ��A�������̂��Ƌ����ÁX�̐��k�⒮�O�����̑O�ŁA�}�����ŏ��ɘb�������t�́A�s�G�[�����Ō�ƂȂ����u�`����߂��������ꕶ�������B�W�X�Ƃ��Ȃ���A�ނ̎u���p���}���ɊϏO�͊������o�����Ƃ����B�@ |
|
|
����掂̉Q���ɓ�����x�ڂ̉h�_
�����ɕ��A�����}�����ŏ��Ɏ��g���Ƃ́A���N�s�G�[�����x�������P�����B�����̘_�j�������B�����āw�����h���^�C���Y�x��I�є��\�����P�����B�����̗��_�Ƃ́A���W�E�������f�ł͂Ȃ����������Ƃ������̂������B�ޏ��͎������ʂŔ��_���悤�ƁA�v�Ȃ̓�����ƂƂ��ɃE�����̖�300�{�̕��˔\���������ȃ��W�E������0.0085�O�����̕����Ɏ��g�݁A1910�N�ɐ��������ċ��̌��𗧏����B���N2��25���A�`���E�W���[�k�E�L�����[���S���Ȃ����B���q���A��Ă����n�R�Ȉٍ��̏������̕Ό�����������A�l�X�ȍ���ɑ������Ƃ��Ɏx���A����薺�����̗ǂ������������ł������ނ̎��ɉƑ��͔߂��݂ɒ��B ��������1907�N����A���h�����[�E�J�[�l�M�[�̎�������������A10�l���̌������������܂łɂȂ����B���̔N�ɂ͂���܂ł̌�����Z�߂��w���˔\�T�_�x���o�ł��A�܂����W�E�����˔\�̍��ۊ�P�ʂ��`����d�����s�����B1911�N�Ɍ��肳�ꂽ���̒P�ʂ́A�v�Ȃ̐�����u�L�����[�v(�L���FCi)�Ɩ��Â���ꂽ�B �������N�A���͂��琄����ĉȊw�A�J�f�~�[����̌��ɂȂ������Ƃ��}����ς킵�����ԂɊ������B��Ȃ������đΗ����ƂȂ����G�h�A�[���E�u�������[�Ƃ̊ԂŁA�x���҂ɂ���̐w�c���o���オ���Ă��܂����B���R��`�҂̃}���ƌh�i�ȃJ�g���b�N�̃u�������[�A�|�[�����h�l�t�����X�l�A�����ď����Βj���B���ɂ���1902�N�Ƀs�G�[�������ĉ���ƂȂ����l�����A�����̉���ɖҔ������B����ɂ́A�J�g���b�N�̓��[���ҒB�ɑ��ă}�������_���l���Ƃ����f�}�܂ŗ��ꂽ�B�G�N�Z���V�I�[����(fr)�Ȃǂ͈�ʂŃ}�����U�����A�E���n�V���ɂ͔ޏ��̉h�_�̓s�G�[���̋Ɛтɏ�������������Ƃ����L���܂ōڂ����B 1911�N1��23���A�A�J�f�~�[����̑I�o���[���s��ꂽ���A�l�ߊ|�����L�҂�����쎟�n�ʼn��͍����̒��ɂ������B�[���ɔ����������ʂ͍͋��Ńu�������[���I��A�������̖ʁX�̓}���{�l�������ė��_�ɕ�ꂽ�B���̎��ɂ́A�}���͐����Ċ��ɂ������̊O���̃A�J�f�~�[����ɂȂ��Ă����B�ޏ������₵���t�����X�����̏��������I�o����̂�1979�N�ł������B�W�X�Ƃ����}�����������A��L�ɂ̓t�����X�A�J�f�~�[�̌Â����K�������Ă������Ƃ�������Ă���A��x�ƌ��ɂȂ�Ȃ��������肩�A�@�֎��ւ̘_���f�ڂ����ۂ��A�Ȋw�A�J�f�~�[�Ɗ��S���Ԃ����B��̂��ƂɂȂ邪�A�t�����X�̌��I�@�ւ������ȉh�_��^�����̂́A1922�N�Ƀp����w�A�J�f�~�[����Âւ̍v���Ƃ������R�ŁA�O����Ĕޏ�������ɑI�o�������������B �}���͌����ɖ߂�A�w�C�P�E�J���������O�E�I�l�X�Ƌ����Œቷ���ł̃��W�E�����ː������̍\�z��������B�Ƃ��낪�L���l�̃X�L�����_����ɍw���~��~�����ĂĂ��������̐V�����A11��4���t���L���Ń}���̕s�ϋL�����X�I�Ɍf�ڂ����B�����5�ΔN���ŁA�s�G�[���̋����q�|�[���E�����W���o���B�ނ͊������������v�w�Ԃ͗�߂ĕʋ����A�ٔ������ɂ܂łȂ��Ă����B�}���͎������̖��ŔY�ރ����W���o���̑��k�������ɐe���ɂȂ��Ă����B1911�N10�����Ƀu���b�Z���ŊJ���ꂽ�\���x�[��c�ɂ͓�l�����ďo�Ȃ��A�}���͘_���\�����Ⴋ�A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���փ`���[���b�q��w���E�ւ̐��E����������肵�Ă���B���̍Œ��́̕A�����W���o���Ɉ��Ă��}���̎莆��\�I���A���l�̉ƒ���s�����ȏ��ƃ}�������e�����B���̌���͑����A�܂����ޏ������_���l���A�s�G�[���͍Ȃ̕s�ς�m���Ď��E�����̂��ƁA����ʂ��Ƃ�A���������Ă��B���ɂ͋L�҂��u�����b�Z���܂ʼn����A�}���͉�c�̕���҂����ɋ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B �\�[�̎���ɋA��ƁA�����͌Q�W�Ɏ��͂܂�A������y�܂ł����B�}���͎q��������A��ĒE�o���A�e�����G�~�[���E�{�����v�Ȃ���Ƃ����B���{�̌��������b�̓{�����Ƀ}����݂��Ȃ��w���Ƃ���Ɣ��������A�v�Ȃ͈�Ђ�܂Ȃ������B�{�����v�l�}���O���b�g�̓W�����E�x���������̖��ŁA�ޏ��̓}���Ȃ��Ȃ�2�x�Ɗ�����킹�Ȃ��ƕ����t�ɋ������B�����͂��낢��ȂƂ���֔�щ��Ă����B ���̑����̉Q����11��7���A�X�E�F�[�f������m�[�x�����w���^�̓d�������B���R�́u���W�E���ƃ|���j�E���̔����ƁA���W�E���̐�������т��̉������̌����ɂ����āA���w�ɓ��M���ׂ��������܂�Ȍ��т����������Ɓv�ƁA�V���f���������グ�ĕ]�����Ă����B�}���́A���߂�2�x�̃m�[�x����҂ƂȂ�A�܂��قȂ镪��(�����w�܁E���w��)�Ŏ��^���ꂽ�ŏ��̐l���Ƃ��Ȃ����B�����A�Q���̃X�L�����_���𗝗R�ɁA�X�E�F�[�f������������^�������킹�Ă͂ǂ����Ƃ����������������B�������}���͋B�R�Ǝ�܂���ӎv�������A���x�̓X�g�b�N�z�������������B�L�O�u���Ń}���́A�s�G�[���̋ƐтƎ����̎d���𖾗Ăɋ�ʂ�����ŁA���̐��ʂ̔��[�͂ӂ���̋��������ɂ������Əq�ׂ��B ��܌��12��29���A�}���͂��a�Ɛt���œ��@�����B�ꎞ�މ@������1912�N3���ɂ͍ēx���@���t���̎�p�����B���̌�x�O�ɉƂ���ė×{������6���ɂ̓T�i�g���E���ɓ������B8���ɂ͏��X�̉������A���������w�҃n�[�T�E�G�A�g���̏��҂ɉ����ăC�M���X�֓n�����B2�����ԉ߂��������10���Ƀp���֖߂������A�\�[�̉Ƃ͂�����ߐV���ɃA�p�[�g���肽�B���̊ԁA�}���͂����ƃX�N�E�H�h�t�X�J�̐����g���Ă����B�}�X�R�~�͑��ς�炸�����l�^�������Ă̓}����@�����Ƃ������������A���̈���ő������}����]������ƃt�����X�̐�i���̏ے��ɍՂ�グ��ȂǓs���̂悢�L������ڂ��A�}���̓W���[�i���Y�������������B �}���ɂƂ��ċꂵ�����ԁA�ޏ����x�����̂͑����̒m�l�F�l�A�����ĉƑ������������B1912�N5���ɂ́A�w�����N�E�V�F���L�F���B�`��c���Ƃ���|�[�����h�̋����A��\�c���}����K�₵�A�����V�����ɕ��˔\��������ݗ����Ĕޏ��ɏ����߂Ă��炢�����ƑŐf�����B1905�N�̃��V�A���v���Ȍ�A�鐭���V�A�̂��т����ɂ݁A�����}���̖��������E�I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă������Ƃ��傫�������B���̐\���o���}���͏n�l���A�{���������ڎw���Ă������ƁA���Ȃ킿�s�G�[������p������������ނɑ����������̂ɂ��邱�Ƃ��v���o�����B�������ă|�[�����h�A���͒f�������A�ޏ��̓p������w�����邱�Ƃ���������B1913�N�A�����V�����̌������J�����ɏo�Ȃ����}���́A���߂ă|�[�����h��ʼnȊw�̍u�����s�����B �č��ɂ͌��N�����A��ƂŃX�C�X�𗷍s����ȂǍD���ȓc�ɂŋx�������ƁA�}���͂܂��ϋɓI�ɓ����͂��߂�B1914�N7���ɂ́A�v�̖���������s�G�[���E�L�����[�ʂ�Ƀ��W�E���������̐V���������L�����[�������������B���������ɂ͎��|����Ȃ������B7��28���A��ꎟ���E��킪�u���������߂ł���B�@ |
|
| �� | |
|
����ꎟ���E���
�푈�͌������̃X�^�b�t���������m�Ƃ��ď��W���A�j���Ŏc�����҂͎��a�������@�B�Z�t�����������B���������u���^�[�j���Ɏ~�߁A�}���̓p���Ɏc���Ă����B9��2���ɂ̓h�C�c�R�̋��p���ɋy�сA�}���͐��{�̗v���Ō����������L����M�d�ȏ������W�E���������{���h�[�ɑa�J�����邽�߂ɋD�Ԃɏ�����B�������ޏ��͂��̔�펖�ԂɎ��������ׂ����Ƃ����o���A�����p���ɕ����߂����B ���B���w�����E�����g�Q����1895�N�ɔ�������X���͂��ł�X���B�e�ɂ���Âւ̍v�����\�ƂȂ��Ă����B�������t�����X�ɂ͂�������{����ݔ������ɏ��Ȃ����Ƃ��}���͒m���Ă����B��p�ɂ����āA�e�e��j�ЂȂǐl�̂ɐH�����ٕ������O�Ɋm�F�ł���A�����҂̐������͏オ��B�ޏ���X�������Ɍg������o�����������������A��w�̍u�`�ŋ����邽�߂ɒm���������Ă����B�}���͑�w����Ǝ҂Ȃǂ�����ĕK�v�ȋ@�ނB���A�����̕a�@�ɂ�����ݒu������A������Z�t�����Ɉ˗����đ�����s�����B �����ɕ��Â��Ȍ����҂̎p�͖��������B�}���͌R��X���B�e�ݔ����[���Ɏ����Ă��Ȃ����Ƃ�m���Ă���A�ړ����\�ɂȂ鎩���Ԃɐݔ��Ɣ��d�@�𓋍ڂ��āA1914�N8��������a�@�����n�߂��B�}���k���̕����Ҏ��ÂɈЗ͂��������̈ړ������g�Q���Ԃ́A�R�̒��Łu�v�`�E�L�����[�v(���уL�����[)�̖��ŌĂꂽ�B��������ǂ̒������ɂ����1��ł͕s������ƁA�}���͌��I�E���L�̎Ԃ���������{�����B�L�͎ҕv�l�����͋��͓I���������A�R��s���@�ւ͓�F�������Ƃ��낪���������B�}���͖�l�����������Ē��B��ʍs�̋����A�@�ޒ��B�̂��߂ɐ��{����ԏ\�����ː��ǒ��Ƃ�����E�����Ċ��������B���n�ȗ��p�҂̂��߂ɐݔ��g�p�}�j���A����p�ӂ��A�����҂̎��Âɖ𗧂Ă��B �}�����ݒu���������g�Q���ݔ��́A�a�@���w�Ȃ�200�ӏ��ɉ����A������20��ƂȂ����B�}�����g���A�Z�p�Ҏw���̍u�`�ƕ��s���Ă���X���Ǝˎ�1��ɏ�荞��Ŋe�n��������B���̂��߂Ɏ������U�w������A�����Ԃ̉^�]�Ƌ����擾���A�̏�ɑΉ����邽�ߎ����Ԑ����ɂ��Ă��K�������B�C���[�k�͂���ȕ�̎p�Ɏ��������̊����ɉ���肽���Ɛ\���o�āA�}���͂����F�߂��B����ɕ�q�͒��~�̑����z���w���ɏ[�āA����Ƀm�[�x���܂��܂ސ��������_������t���悤�Ƃ����B��������҂͗��ɖ����̒S�������ꑽ���Ƌ��ۂ����B �����g�Q�����u�ɂ́A�������I�ȃ��h�����g���悤�ɂȂ�A�{���h�[���玝���A�������W�E���������g���ă}���̓`���[�u�Ƀ��h���C�̂��l�߂��Ƃ��s�����B����̓}����X���픘���N�����A��̌��N��ԂɈ��e�����y�ڂ����̂ł͂ƍl�����Ă���B 1918�N11���A�푈�͏I�������B��͎��N�Y���R�ƂȂ��Ĉ�Ƃ͒��~�����Ȃ莸�������A���X�o�債�Ă����B����Ȃ��Ƃ��}��������Ƃ́A1919�N�Ɍ̋��������̎x�z����E���|�[�����h��a�����������ꂽ���Ƃ������B���̏���́A�p���w������̋��F�A�C�O�i�c�B�E�p�f���t�X�L�������B�@ |
|
|
���A�����J�K��
�������͍ĊJ�������A����͐ݔ��������ɂ���������Ԃł������B1920�N�Ƀ��X�`���C���h�Ƃ��o�������L�����[���c���ݗ�����A���ː����Â̌������x���������A�����≻�w�̌����ɂ͂قƂ�ǔ�p�����Ȃ������B ���̔N��5���A�A�����J�̏����G���w�f�B���j�G�^�[ (Delineator)�x�ҏW���̃E�B���A���E�u���E���E�����j�[����̐\��������āA�}���̓C���^�r���[�ɉ������B���̐Ȃō������~�������Ƃ�������ɁA1�O�����̃��W�E�������Ɠ������B���̉��i�͊���10���h���ɑ����������A�A�����J�̌b�܂ꂽ�Ȋw��������m�郁���j�[�ɂƂ��ċ����̉������B�ޏ��͋A����ɃL�����y�[�����s���A�}���Ƀ��W�E���悷�鎑�����W�߂��B �ޏ��̋��߂ɉ����A1921�N�}���͖��ӂ���ƃA�����J�n�q�����߂��B���̃X�P�W���[���ɑ����̑�w�Ȃǂւ̗�K����A�A�����J�哝�̂Ƃ̎��T�܂ł�����������Ă���ƒm�����t�����X���{�͍Q�āA���������疼�_��^���Ă��Ȃ��s�H����₨���Ƃ܂������W�I���h�k�[���M�͂����^���悤�Ƃ����B�������ȑO�Ɠ������R�Ń}���͒f�����B�������痣�ꂽ���̐�`�����͋C�̐i�܂Ȃ����̂��������A�}���͊e�n�ő劽�}���A�哝�̃E�H�����E�n�[�f�B���O���璼�X�Ƀ��W�E�����^���s��ꂽ�B�������ޏ��͂�����l�ւ̑��^�ł͂Ȃ��������ւ̊ƈ����Ă��炢�A�l�̍����ɂ͂��Ȃ������B 1929�N�ɂ͍ēn�Ă��A�}����1925�N�Ƀ����V�����Ɏo���Ɛݗ������L�����[�������ɓ�������@��ނ̎�����̂ɐ��������B�@ |
|
|
��������
�A�����J�̗��͑听�����C�߁A�������̓��W�E���ȊO�ɂ������̍z�T���v���╪�͋@��ށA�����Ď������B�����ޏ��͂��̗��ŁA�����̖�����e���͂��z���ȏ�ɑ傫���Ȃ��Ă��܂��A���͂⌤��������ɖv�����邱�Ƃ͋�����Ȃ����Ƃ�������B�Ȃ�ƁA�}���̓p���̃��W�E���������𗧔h�ȕ��˔\�����̒��S�Ɉ�Ă悤�Ƃ����B �܂��A1922�N�ɂ̓��l�X�R�̑O�g�ɓ��鍑�ےm�I���͈ψ��� (International Committee on Intellectual Cooperation, ICIC) �����o�[12�l�̂ЂƂ�ɉ�������B���ς�炸�����邱�ƂȂǂ��Ȃ��������߁A�V�n�ˈ�͑�1�����̔ޏ��̈�ۂ��u���h�������Ȃ����z�̖����l���v�Ǝ����Ɏc�����B �������͐��ʁE���Ђ���Ȃ����l�ȃX�^�b�t������A�}���͔ނ�̎w���ɑ����̎��Ԃ��������B�����̂悤�ɔޏ��̎���ɂ͌���������̎w�j��i���𑊒k���A�_���̍Z���Ȃǂ��肤�������炪�W�����B�}���͓K�Ȏw����w����^���A���ʂ��オ�����ۂɂ͏j���̂�������J���Ȃǔނ���A���̎��͂�L�����B�A���t�@���q�̃G�l���M�[�����ł͂Ȃ����Ƃ��������T�������E���[�[���u�����A�^��X���ώ@���s�����t�F���i���E�I���E�F�b�N�A�t�����V�E���������}���O���b�g�E�y���[�Ȃǂ�����������o���B���̒��ł��ۗ��������̂́A���C���[�k�Ƃ��̕v�t���f���b�N�E�W�����I���L�����[�̐l�H���˔\�̌����ł���A�v�Ȃ�1935�N�Ƀm�[�x�����w�܂���܂����B1919�N����1934�N�̊ԁA���������甭�\���ꂽ�_����483���ɂȂ����B �����A���˔\�����N�֗^���鈫�e��������ɖ��炩�ƂȂ��Ă����B���{�̎R�c���j��1923�N����2�N���A���W�E���������ŃC���[�k�̏���Ƃ��ăA���t�@�����x�̌������s���A�}���̎x�����Ȃ���5�̘_���\�����B�����������s���̑̒��s�ǂ��N�����ċA�����A���N�S���Ȃ����B�}���͂��̕�ɐG�꒢�ӂ�\���莆�𑗂��Ă���B1925�N1���ɂ͕ʂ̌����������Đ��s�ǐ��n���Ŏ��S�B����Ɍl����������a�ŖS���Ȃ����B�����������Ȉ��ʊW��Ώ��@�ɂ͂����Ɍq����Ȃ������B�@ |
|
|
������
1932�N�A�]�|�����}���͉E�������܂������A���̕������Ȃ��Ȃ������Ȃ������B���ɂ⎨��Ȃǂ������A���N�s�ǂ��������B1933�N�ɂ͒_��������������p�����������B�t�Ƀ}���̓|�[�����h��K�₵�����A���ꂪ�Ō�̗��A��ƂȂ����B1934�N5���A�C�����D�ꂸ�������𑁂���ɂ����B���̂܂ܐQ���ނ悤�ɂȂ����}���͌������A���j�̋^��������Ƃ����f�f���������B �×{�ɓ��邱�Ƃ����߁A�G�[���̓}�����t�����X�����̃I�[�g���T���H�����p�b�V�[(en)�ɂ���T���Z������(en)�Ƃ����T�i�g���E���֘A��čs�����B�����������Ŏ��f�@�ł͔x�Ɉُ�͌����炸�A�W���l�[������Ăꂽ��t���s�������t�����̌��ʂ́A�Đ��s�ǐ��n���������B 7��4�����j���A�}���̓t�����X�ŖS���Ȃ����B7��6���ɕv���l�ߐe�҂�F�l�����������Q�����V���s���A�}���́A�v�s�G�[��������\�[�̕�n�ɁA�v�ƕ���Ŗ������ꂽ�B �ޏ��̎������̓p���̃L�����[�����قƂ��āA���̂܂܂̎p�ŕۑ�����Ă���B�}���̎c�������M�̘_���Ȃǂ̂����A1890�N�ȍ~�̂��͕̂��ː��������܂܂��舵�����댯���ƍl�����Ă���B���ɂ͔ޏ��̗����̖{��������ː������o���ꂽ�B�����͉��ŕ����ꂽ���Ɏ��߂ĕۊǂ���A�{������ɂ͖h�앞���p���K�{�ƂȂ�B�܂��A�L�����[�����ق��������͕��˔\��������Č��w�ł��Ȃ��������A�ߔN�����������{����Č��J���ꂽ�B���̕����ɂ͎������Ȃǂ������̂܂ܒu����Ă���A�����Ɏc���ꂽ�}���̎w�䂩������ː������m�����Ƃ����B 60�N���1995�N�A�v�Ȃ̋Ɛт��̂��A�ӂ���̕�̓p���̃p���e�I���Ɉڂ���A�t�����X�j�̈̐l�̂ЂƂ�ɗꂽ�B�}���́A�p���e�I�����J���鏉�̏����ł���B���̍ہA�}���̊������̕��˔\���肪�s��ꂽ�B���̌���360Bq/cc�͎���߂Ȃ��狖�e�Z�x��5%���x�ɂƂǂ܂�A���W�E���̔���������l���ĕ��ː��픘���ɂ͋^�₪���܂ꂽ�B���̑���ɁA�v�`�E�L�����[���Ŋ������ɗ��т�X���픘���a�C���N�������̂ł͂Ƃ�����������Ă���B�@ |
|
| ���R�c���j | |
|
(1896-1927)�@���{�̉Ȋw�ҁB�t�����X�̃��W�E��������(fr)(��̃L�����[������)�ŕ����w�҂ł���}���E�L�����[�Ɏt�����A���̒����̕����w�҃C���[�k�E�W�����I���L�����[��Ƌ��ɕ��˔\�̌����ɍv���B�����ɔ������ː���Q�ɂ��A31�̎Ⴓ�Ŏ��������B���W�E���������ɗ��w�����ŏ��̓��{�l�ł���A���ː����w�����̋]���ƂȂ��Ď��������ŏ��̓��{�l�Ƃ����B
1896�N(����29�N)�A���Ɍ��_�ˎs�ɐ��܂��(�{�Вn�͊��s�ؓc)�B���e�̎d���̓s���ŏ��w�Z���狌�����w�Z�܂ł��p�ʼn߂����A�w�Z�ł̐��т͏�Ɏ�Ȃł������B��ɓ��{�{�y�Ɉڂ�A1916�N�ɓ��������H�Ɗw�Z(��̓����H�Ƒ�w)�𑲋ƌ�A���k��w���w���ɓ��w���ĉ��w���U�B��w�ł����Q�̐��т������߂��B��w���ƌ�͓���w�̍u�t�Ƃ��Ă̋Ζ���A�����鍑��w(��̓�����w)�q�����ɏ������Ƃ��ĕ��C�B������w�o�g�łȂ��҂Ƃ��Ă͈ٗ�̏o���ł������B�����A���������͌R���ɖ𗧂��������i����Ă������Ƃ�����A1923�N(�吳12�N)�A�R�c��27�ɂ��ē��{�����{�ɂ��A�t�����X�֔h�����ꂽ�B �t�����X�ł̎R�c�́A���W�E���������Ń}���E�L�����[�Ɏt���B���������Ŏ�������ł������}���̒����C���[�k�̋��������҂ƂȂ�A�g���E���ƃ|���j�E��������o�������ː��̔���̌����Ȃǂ��s���A�P�Ƙ_�����������ƁA�C���[�k�Ƃ̋����_���������グ���B���̌����Ԃ�̓}����C���[�k�炩��A�����]�������B 1926�N�ɓ��{�A���B�t�����X�ŋz�������ŐV�Z�p�ɂ����{�����ł̊����҂���Ă������A2�N���̊Ԃ̕��ː������ɂ����ː���Q(��q)�ɑ̂�N����Ă����R�c�́A�A�����_�ł��łɌ��N�Ȃ��Ă���A�A������ɓ��@�B�a���ɂ���Ȃ�����t�����X�؍ݒ��̌������o�������ƂŁA�����鍑��w�̗��w���m�����ٗ�̎Ⴓ�Ŏ��^���ꂽ�B���̌�����A��ڎw���ĕK���ɓ��a�����𑗂������A���̍b����Ȃ���1927�N(���a2�N)�A31�̎Ⴓ�Ŏ��������B���̑O���ɂ͓����鍑��w�̋����ɔC������A�]�Z�ʂ��������Ă���B ��O�̓��{�͕��˔\�����͈̔͂������������߁A���{�����ł̓}���E�L�����[�̈̋ƂƂ͑ΏƓI�ɁA�R�c�̗��w�⎀�ɂ��ĂقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������B��ɎR�c�̑��q�̎R�c���j(���{��j�w��)���A1990�N��ȍ~�ɕ��̌l�j�𖾂ɖ{�i�I�Ɏ�g���ƂŁA��L�̂悤�ȏڍׂȐ��U�����炩�ƂȂ����B�@ |
|
|
���Ɛ�
���W�E���������ŎR�c���s�Ȃ��������́A��Ƀg���E���ƃ|���j�E��������o�������ː��̔���̌����Ȃǂł���A���̗D�G�ȓ��]�Ɛ��m�ȋZ�p�ɂ��A�}���E�L�����[���獂���]�������ƌ�����B�C���[�k���R�c�̎d���Ԃ�ɂ͊������Ă���A�R�c�̎肪�����N���ȃE�B���\�������ɂ��āA��}�����Ă̎莆�Łu�R�c�̓E�C���\�����u(����)�̓S�̔���Ƒn�I���@�ō��A���܂Ŏg�p���Ă����������9�{�ȏ�ɋ��͂Ō̏Ⴕ�Ȃ��������u�����������v�u���̂܂ܖʓ|�Ȃ��Ƃ��N����Ȃ���A���ʂ̗l�����݂�ɂ́A���}�_���B�������̂ŏ\���ł��傤�v�Ɠ`���Ă���B���̃C���[�k�̎莆�̌����́A�p���̃L�����[������(en)�ɕۑ�����Ă���B ���ɂ��R�c�́A�|���j�E��������o�����A���t�@����A�g���E���A���W�E���Ɋւ���_�����A�C���[�k��ق��̌������͎҂����ƂƂ��ɏ����グ�A�t�����X�̉Ȋw�A�J�f�~�[�@�֎��ɔ��\���Ă���A�����́̕A���W�E���������̐^���Ȍ������т̑b�ɂȂ������̂ƌ����Ă���B�C���[�k���w�ʂ��擾�����ۂ̔��m�_���ɂ́A�R�c�̐��O�ɃC���[�k���R�c�Ƃ̘A���Ŕ��\�����|���j�E���̌������e�����p����Ă���B ���{�A�������R�c���a���ɂ�����ł��A���W�E���������ł͔ނ̓Ƒn���������]������A���̏d�v�ȋƐтɑ��ĕ\�����s���Ă���B�R�c�̎��ɂ������ẮA�}���͂������ɒ��ӂ����߂��莆�������A�ނ̑f�����^���Ă���B���1995�N�ɃA�����J�Ŋ��s���ꂽ�}���E�L�����[�̓`�L�w�}���[�E�L�����[�x�ɂ́A�R�c���}������̂��̗�^�������Ƃ��u�m�u�E���}�_�v�̖��ŐG����Ă���B�����̎R�c�̌������ʂ́A�R�c�̎����1935�N�ɃC���[�k���m�[�x�����w�܂���܂������ƂŌ����Ɏ������B �R�c�̎������80�N���2006�N�A�t�����X�̉Ȋw�j������ Jean-Pierre Poirier���A�����̌��q�Ȋw�����j���܂Ƃ߂��Ȋw���wMarie Curie-et les conquerants de l��atom 1896-2006�x���ɂ�����A�O�q�̎R�c�̑��q�E�R�c���j�̕��Q�l�ɁA�R�c�ɂ��ēƗ�����4�y�[�W��1�͂������A���̐l�ƂȂ��Ɛтɂ��ĉ�����Ă���B ���{�����ł͎R�c�̎����̗�12���A�ނ̕�Z�ł��铌�k��w�̓��k���w�������ɁA�R�c���a���ŗ��w���m�̊w�ʂ��擾�����ۂ̘_�����f�ڂ���A���̎������ʂ������]������Ă���B�����w���_�����̍�㐳�M�́A�R�c�̌������C���[�k�̃m�[�x����܂ɐ�삷��A���t�@���ɂ��O�O�Ȍ������Əq�ׂĂ���A���w���m�̑�v�ۖΒj���A�C���[�k����Ƀm�[�x�����w�܂���܂��Ă��邱�Ƃ���A�R�c�������ł�����̋Ɛт��]������Ă������낤�ƈӌ����Ă���B2006�N�ɂ͓��{���ˉ��w��ŕ��ˉ��w���_��50���N�L�O���ƂƂ��āw���ˉ��w�p�ꎫ�T�x�����s���ꂽ�ہA���ˉ��w�����Ɍ����Ȍ��т̂��������{�l16�l�̒��ɁA���ˉ��w�̐�B��1�l�Ƃ��ĎR�c�̖����������Ă���B�@ |
|
|
�����ː���Q
�R�c�̌����Ώۂ̂����A�|���j�E���͔��ɕ��˔\�̋��͂Ȍ��f�ł���A�̓��ɓ���Ɛ����w�I�e�������ɑ傫���A���S�i�m�O�����̐ێ�Ŏ��S����\��������A�g���E�����܂����W�E�����������Ƌ��͂ȕ��˔\������f�ł���B�����������̕��ː��h��̒m���ƋZ�p�͂܂��s�\�����������߁A�������̎R�c�͕��˔\�ɑ���h�����قƂ�Ǎs�Ȃ��Ă��炸�A�������s���Ă��������ɂ͊��C���u��h��X�N���[����������t�����Ă��Ȃ������B���W�E���������ł̌������̎ʐ^��1�������c����Ă��邪�A��ɂ�����������Ƃ������F�u����Ȍy���ł́A�ǂ�قǂ̕��ː��𗁂т����Ƃ��v�ƘR�炷�قǂ̖��h����Ԃł̌����ł������B �A�����_�ŎR�c�͂��łɁA�Ƒ��������قǑ����Ă���A���މ@���J��Ԃ������ɁA���т������Ȃ�A�畆���{���{���Ɣ����A���ڂ������ɋ߂��Ȃ�A�����������ɂ����Ȃ�A�t���Y���Ȃ��ł͕����Ȃ��قǂ̕a��ƂȂ��Ă����B�����͕��˔\��������Ԃ��Ȃ��������߁A���ː���Q�ɂ��Ă̈�w�F�����Ⴍ�A���l�̏ǗႪ���Ȃ����Ƃ������āA��t�̐f�f�ł��a�C�̌����͕s���ł���A�e����������́u��a�v�Ƃ��Ă�����ꂽ�B�������Ȃ���R�c���g�͎����̕a�C�ƕ��˔\�Ƃ̊W���^���Ă���A�C���[�k�ɑ��A���ː��ɂ�钆�Ŋ��҂̏ǗႪ�t�����X�ɂ�������Ăق����Ƃ̎莆�������Ă���B���q�̌��j���A���̎��̓�����3�̎Ⴓ���������߂ɕ��̋L�����قƂ�ǂȂ��A��̘Q�]����ɍč��������߂ɍč���ւ̔z������R�c�̂��Ƃ��قƂ�ǘb���Ȃ��������Ƃ�����A���j�͕��̎�������a�Ǝ��͂���`�����Ă����B �R�c�̎������琔�\�N���o���ĕ��ː���w�������������ݗ����ꂽ��A���W�E���������ł̎R�c�̌����̗l�q��A�A����̎R�c�̏Ǐ�A�R�c�͓T�^�I�ȕ��ː���Q�ƕ��͂����悤�ɂȂ����B�w�p�ɂ����ẮA�R�c�̎�������30�N�ȏ���1959�N�A���˔\�����҂ł���ѐ������������ɂāA�R�c���������ɋ������ː��𗁂ё��������Ƃɂ�鈫���]�ǂŎ��������Əq�ׂĂ���A����͓��{�̊w�p�Ɍ��ꂽ���ː���Q�̍ŏ��̌����ƍl�����Ă���B���̌��1994�N�A���w���m�E�Ð�H���������ɂāA���˔\��Q�̊댯���̗������\���łȂ���������ɋ]���ƂȂ����҂Ƃ��āA�R�c�̖��������Ă���B 1998�N�A���{�ŊJ�Â��ꂽ���W�E�������S���N�̋L�O�u������@�ɁA�R�c�̈�i�ނ̎c�����˔\�̑��肪�s��ꂽ�B��i�ނ͍ȁE�Q�]�̗��e�ɂ��A�a�C�����q�ɓ`�����Ȃ��悤�ɂƂ̔z�����炷�ׂĔp������Ă������A���낤���ĘQ�]�������ɕۊǂ��Ă����p�X�|�[�g������˔\��������������A���ː������̕t�������w�Ńp�X�|�[�g����ɂ������Ղ��c����Ă����B���̃p�X�|�[�g�͖v�ォ��80�N�ȏ���o�Ă��Ȃ����͂ȕ��˔\��тт���ԂŁA�p���̃L�����[�������Õ����قɕۊǂ���Ă���B�@ |
|
| ���A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h | |
|
(Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson, OM, FRS, 1871–1937)�@�j���[�W�[�����h�o�g�A�C�M���X�Ŋ��������w�ҁA���w�ҁB�}�C�P���E�t�@���f�[�ƕ��я̂������������w�̑�Ƃł���B�����ƃ����̔����A���U�t�H�[�h�U���ɂ�錴�q�j�̔����A���q�j�̐l�H�ϊ��Ȃǂ̋Ɛтɂ��u���q�����w�̕��v�ƌĂ��B1908�N�Ƀm�[�x�����w�܂���܁B�܂��A���U�t�H�[�h�w���̂��ƃ`���h�E�B�b�N�������q�̔����A�R�b�N�N���t�g�ƃE�H���g������������g�������f�ϊ��̌����A�G�h���[�h�E�A�b�v���g�����d���w�̌����Ńm�[�x���܂���܂��Ă���B
�����q�����w�̕� ���̏̍��͉Ȋw�j�̒������ł͂Ȃ��A���̐l���ɂ���Ă��������������B���U�t�H�[�h�͎����S�ɖ����A�Ⴂ���������������A�{�[�C�Y(���q����)�ƌĂB�P���u���b�W�̃L�����F���f�B�b�V���������́A�ݔ���v���@���J�����Ȃ���傫���Ȃ�A���ʂ��グ�čs�����B ���̊J���⌤���Ɏ��g�ނ̂́A�Ⴂ���������ł������B���ʑI�ʊ�ŃA�C�\�g�[�v�̕����ɐ��������t�����V�X�E�A�X�g���A�����Ō��q�O�����B�e�����������Y�A��������Ɍ��q�O�����J�������p�g���b�N�E�u���P�b�g�ȂǁA���E�������ނ��l�ߊĂ���B ���U�t�H�[�h�͒��g�ŁA���i������A�Ẵr�[�`�ł��W���P�b�g��E���Ȃ��p���a�m�ł������B�ނ͎����ō��E�����t�����āA�������̗\�Z���l�{�ɂ܂ŐL�����B ���Ə̂���Ȃ���A��Ԓ�q�Ƃ͐��ʁE���ʂ�]�V�Ȃ�����Ă���B�t�ɁA����̂ɕ������ۗ��Ƃ�������B�����\�����A�������̌��q��\�������w�����[�E���[�Y���[�́A�u�肵�ď]�R���A�K���|������Ŗ��𗎂Ƃ����B����ŃC�M���X�́A���q�����̈������ނ����ƌ�����B �L�����F���f�B�b�V���������ł̂��C�ɓ���́A���V�A���痈�������w�҃s���[�g���E�J�s�b�c�@�ł������B�ނ͎n�߁A�\�r�G�g�ƃC�M���X�Ƃ����R�ɍs�������Ă����B�������A1934�N�A�����w�҂̏d�v���ɋC�t�����\�r�G�g���{�́A�ނ�n�q�֎~�ɂ����B���U�t�H�[�h�͂���ɍR�c�̎莆���o�����B����ɑ���Ԏ��ɂ́A�u�C�M���X���J�s�b�c�@��~�������Ă���̂͗����ł���B��X������Ɠ������炢���U�t�H�[�h�����߂Ă���v�Ƃ������̂������B�p�{�[���h�E�B���̏��͂𗊂��A���ʂ������B�J�s�b�c�@�̐e�ނ̏������A���p�\�r�G�g��g�}�C�X�L�[�Ɍ������āA�u�����̃s���[�g���͊�Ŏ҂��v�Ƌ����ƁA��g�́A�u���̃��V�t�͂����Ɗ�Ŏ҂��v�ƕԂ����B���������B�����Ń��U�t�H�[�h�͂ǂ�Ȏ�ɑł��ďo�����B�ނ̓J�s�b�c�@�ׂ̈ɁA�O�̍��c�̗\�Z���g���Č��݂��A�P���u���b�W�̎O�̔��d���̏o���d�͂���x�Ɏg�������̎������u���A�Ȃ�ƁA�\�r�G�g�ɑ���t�����̂��B����ɂ̓\�r�G�g���A�O���|���h�̑㏞���x�������݂̂Ȃ炸�A�J�s�b�c�@���Ԃ߂�ׁA���X�N���ɉp���l���̐V���������������Ă��B�J�s�b�c�@���ϔO���āA�u��X�͉^���Ƃ�����͂̒��𗬂�������q�ɉ߂��Ȃ��v�ƃ��U�t�H�[�h�Ɉ��Ă��B�@ �@ |
|
| �����ː��E�G�b | |
|
�����R���˔\�̔���
�t�����X�̃x�N�����́A1896�N�A�V�R�̕���������w���Ɠ����l�ȕ��ː������o����邱�Ƃ������B���̔����ɋ������������s�G�[���E�L�����[�A�}���[�E�L�����[�v�Ȃ́A�V�R�����̒�������ː����f Ra(���W�E��)�� Po(�|���j�E��)�������B ���R���˔\�A�������R�E�ɑ��݂�����ː������́A���݂܂łɐ������̎�ނ���������Ă���B�{���ł́A�V�R�̕���������ː������o����邱�Ƃ������x�N�����̋Ɛыy�сA�V�R�����̒�������ː����f Ra(���W�E��)�� Po(�|���j�E��)�������L�����[�v�Ȃ̋Ɛтɂ��ďq�ׂ�B ��1�D�x�N�����ɂ����˔\�̔��� 1895�N�̃����g�Q��(Roentgen)�ɂ��w���̔����̌�A�t�����X�̃|�A���J��(H.Poincare)��1896�N1���A�w�����u����тт��K���X����o�邱�ƁA�܂��u�����������点�鐫�������邱�Ƃ���A�u��������o�������͕��ʂ̌��̑��ɂw�����o���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̍l�����������B������đ����̎������s���A������������ʂ��������ꂽ�B ���̂悤�Ȓ��ŁA1896�N2���A�t�����X�̃x�N����(H.Becquerel)�́A�u���������o���E����������(���_�J���E���E���j��)�̌������A���������ŎՌ������ʐ^����ɂ����Đ����ԓ����ɂ��Ă��Ƃ���A�����������Ă���A���̌�������w���Ǝ������̂����o���ꂽ�ƍl������B�v�ƕ����B���̎��_�ł́A�x�N�������g�E��������������o����ː��Ɠ���(�܂��͗�)�Ƃ̊Ԃɉ��炩�̊W������ƍl���Ă����B �Ƃ��낪���̌�A���l�̎������d�˂邽�߂Ɋ���ɂ̂��������������������A�V�s����Ȃ��߂ɉ����ԓ����ɓ��Ă��̂��͂����肵�Ȃ��Ȃ����B���̊����������Ă݂�Ɠ����ɓ��Ă����̂��������������Ă����B�E��������������ɓ��Ă����Ԃł͂Ȃ��A����ɏ悹�Ă��鎞�Ԃ������ɊW����Ƃ��������́A�����Ɩ��W�ɉ��炩�̕��ː����E��������������o�Ă��邱�Ƃ������Ă���B���̌ケ�̕��ː��̐��������ׂ��A���̕��ː����o�������́A�E�������f���܂�ł�������悭�A���ꂪ�E�����̒P�̂ł��낤�Ɖ������ł��낤�ƁA�����ł��낤�Ɛ��n�t�ł��낤�ƁA���������������I�A���w�I��Ԃɂ͑S�����W�ł��邱�ƁA���ߐ��̋����͎������̃E�����̊ܗʂɔ�Ⴗ�邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B ����ɁA���̕��ː��͂w���Ɠ��l�ɋ�C��d�����邱�Ƃ����炩�ɂ���A�d���d���̑���ɂ��E�������̐����̌������s��ꂽ�B�V�R�̕�������w���̂悤�ȕ��ː��������I�ɕ��o����邱��(���̍�p�͌�N�L�����[�v�Ȃɂ���āu���˔\�v�Ɩ��t����ꂽ)�������x�N�����͂��̕��ː����u�E�������v�Ɩ��t����(�u�x�N�������v�Ƃ��Ăꂽ)���A���̍�p�͂w�������ォ�������߂��̔����̏d�傳�͓����w�ǔF������Ȃ������B ��2�D�L�����[�v��(�t�����X�A�|�[�����h)�ɂ�郉�W�E���ƃ|���j�E���̔��� ���ꂩ��2�N��A�}���[�E�L�����[(Marie Curie)�ƃs�G�[���E�L�����[(Pierre Curie)�v�Ȃ́A�E�������Ɋւ���x�N�����̘_���ɋ����������A�E�������̌������n�߂��B�ޓ��͏]���p�����Ă����ʐ^���������m�ȕ��ː����x������s�����߁A�d�����A�L�����[���d�C�v�A�s�G�]�d�C�v�Ȃǂ�p����(���܂�m���Ă��Ȃ����Ƃł��邪�A�s�G�[���E�L�����[�̓s�G�]�d�C���ۂ̔����҂ł���A����d������ɗp���鐅���s�G�]�d�C�v�����Ă���)�B����ɂ��10E�|11�A���y�A�I�[�_�[�̓d��������\�Ƃ��A�ޓ��̌����̋�������ƂȂ����B�}���[�E�L�����[�͂����̑��u��p���Č������s���A�E�������̋����̓E�������������Ɋ܂܂��E�����̗ʂɔ�Ⴗ�邱�ƁA�E�������̓E�����������̉��x�∳�͓��̏�Ԃɍ��E���ꂸ�A�₦�������I�ɕ��˂���Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B�܂��A�E�������ȊO�̉������ɂ��Ă����ׁA�g���E�����������E�����������Ɠ��l�̕��ː����o�����Ƃ����A���̗l�ȕ��ː����o���������u���˔\�v�Ɩ��t�����B ��X�̉������̎����˔\�����Ă����}���[�́A�V�R���E�����z���������E�����z���������Ƌ������˔\�������Ƃ��������B���̂��Ƃ���A�E�������������E�����ȊO�̕��ː��������܂�ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���A�s�b�`�u�����h(�l�E�����z)�Ƃ����z�����������˔\�������Ƃ�˂��~�߂��B�ޓ��͂���ɁA�����̕����A���˔\������J��Ԃ��A1898�N7���� Bi(�r�X�}�X)�ɐ��������Ă���V�������f�������B���̐V���f�̓}���[�̑c���|�[�����h�Ɉ���Łu�|���j�E���v�Ɩ������ꂽ�B2�l�͂��̌���s�b�`�u�����h�̕��͂�i�߂��B�s�b�`�u�����h�̒��ɂ́A���̒��Ɋ܂܂�Ă���E������|���j�E���������˔\�̋�������������ƍl����2�l�́A������1898�N12�� Ba(�o���E��)�ɐ������������ː�����������Ɣ��\�����B���̐V���f�́m���˂�����́n�Ƃ����Ӗ��́A�uRa�G���W�E���v�Ɩ������ꂽ�B���������̎��_�ł͖��������̃��W�E���͒��o����Ă��炸�A���̔��\�Ɏ^�����Ȃ��Ȋw�҂������B2�l�̎��̎d����1�������������ȃ��W�E���𒊏o���邱�Ƃł������B���W�E�����o��Ƃ͑����̍�������B�T���łȂ��ޓ��́A���z�̓I�[�X�g���A���{�������A�������w�w�Z����肽���u���������ɂ��āA�Ă̏����Ɠ~�̊����ɑς��Ȃ����Ƃ𑱂����B������4�N���1902�N3���A���ɏ������W�E�����𒊏o�����B���\�g�����̌��z���瓾��ꂽ���W�E���͂�����0.1 �O�����̔��������ł������Ƃ����B�����̋Ɛтɂ��A�}���[�̓m�[�x�������w��(1903�N)�y�уm�[�x�����w��(1911�N)���A�s�G�[��(1906�N�Ɏ��̎�)�̓m�[�x�������w��(1903�N)�����܂����B �}���[�E�L�����[�͂܂��A�ÓT���w�I�Ȏ�@��p����Ra�̎��ʐ������߁A�u225(���݂ł�226.03�Ƃ���Ă���)�v�Ƃ����l���B�Ȃ��A�}���[�E�L�����[�̐e�F�ł���A���h���E�h�D�r�G���k(A.Debierne�G�\���{���k��w)��1899�N�ɁA�L�����[�v�Ȃ��p�����s�b�`�u�����h�̎c�Ԃ̒��ɑ�3�̐V���ː����f�����邱�Ƃ����A�u�A�N�`�j�E���v�Ɩ��t�����B�@ |
|
|
�����ː��̕��ނƂ��̐���
�d�����ː�����ʂɂ͕��ː��Ə̂��Ă���B���ː��ɂ͗��q���Ɠd���g������B���q���ɂ͓d�ׂ����דd���q���Ɣ�דd���q��������B�d���g�̓G�l���M�[�͈͂��߂Ȃ��g������������A�G�b�N�X����K���}���̂悤�ȓd���g�͎��O�������G�l���M�[�������g����ł���B���ː��̐����ɂ͕��ː����ʌ��f�̕���A���q�j�����A���ː��ǂ����̓]���Ȃǂ�����B���ː��͌��q�F�������̂悤�Ȑl�H�I�ȑ��u�ō�肾�����Ƃ��ł��邪�A���R�E�ɂ��������̕��ː��������݂���B�����ł́A���ː�����ނƐ����ʂɕ��ނ��A���̊T�v��v�Ă���B ��1�D���ː� �����͂��܂��܂Ȍ��q�E���q����\������Ă���B���q�E���q�͌��q�j�Ɠd�q���琬��B���q�j�̌������i�W���A���G�l���M�[�̕��ː������p�����悤�ɂȂ������ʁA�f���q�̗̈������݂ɏo�Ă����B���ː��Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ŁA�ǂ����猻���̂ł��낤���B ���ː��ɂ͗��q��(���q�̗���)�Ɠd���g�Ƃ�����B�f���q�̂Ȃ��ŁA�����ɂ�茟�o���\�Ƃ������̂ɁA�d�q(�d�q�Ɨz�d�q)��˗��q(�~���[�I��)�̂悤�ȃ��v�g���Ɨz�q�⒆���q�̂悤�ȃn�h����������B���q�j�̍\�����q�ł���z�q�ƒ����q�́A�j�q�Ƃ��Ă�Ă���B ���q�j�Ƃ́A�����̊j�q���j�͂ŏW���������̂ł���A���q�Ƃ́A���q�j�ɌŗL�̐��d��(���q��)���A�d�q�Ɠd���͂Œނ荇���Ĉ��艻������Ԃł���B���q�͂��낢��Ȍ��q�ǂ������A���w�I�Ȍ�����(�d�q�̏W���̂��܂��܂ȏ�Ԃ��琶����d���I�ȑ��ݍ�p)�ŏW��������Ԃł���B ��ʂɁu���ː��v�Ƃ́A�������Ō��q�E���q���猋���͂��ł��ɂ��d�q�����R�d�q�Ƃ��Ĉ��������A���q�╪�q�̃C�I�������邽�߂ɏ\���ȃG�l���M�[�������Ă���d�����ː����Ӗ�����B�d�����ː��̃G�l���M�[�ɂ͏�����Ȃ��B ���q���͉דd���q���Ɣ�דd���q���ɕ��ނ����B���q���ɂ͑����̎�ނ�����B�Ⴆ�A���h���̕���Ő�����w���E���̌��q�j���琬��A���t�@���A�d���f�̌��q�j���琬��d�z�q���A���ː����ʌ��f�̕���Ŕ�������x�[�^��(�z�d�q�����܂�)�A�d�����f���C�I���������d�C�I���Ȃǂł���B���G�l���M�[������̌��݂ɂ���āA�Β��Ԏq��~���[�I���̂悤�ȃ��v�g���̗��p���\�ɂȂ����B�z�q�͌��q�ʂ��ق�1�ł��鐅�f(�y���f)�̌��q�j�ł���B�d�ׂ������Ă��Ȃ���דd���q���ɒ����q��������B�����q�͓d���͂ɂ�锽�������Ɍ��q�j�ɐڋ߂ł���B�x�������q�͉דd���q���ɔ�ׂČ��q�j����(���q�j�ǂ������Փ˂��ċN���锽��)�̊m���������B �d���g�̂Ȃ��ŁA���q�ɗR��������̂��G�b�N�X���A���q�j�ɗR��������̂��K���}���Ƌ�ʂ��Ă���B����ɂ���ẮA�G�b�N�X�����X�ɓ�G�b�N�X���ƍd�G�b�N�X���ɋ�ʂ��Ă���B�����͂�������A���O�����������G�l���M�[�̓d���g�ł���B�ŋ߂ł͒P�ɁA�g���A�g���̂悤�ȓd���g�̐����ɂ���Č������Ƃ������Ȃ��Ă���B ��2�D���˔\ ���ː�����o����\�͂��A���˔\������Ƃ��A���邢�͕��ː��ł���Ƃ����B���˔\��L���镨���̂��Ƃ���ː������Ƃ����A���˔\��L���錳�f�͕��ː����ʌ��f(���ː��j����Ӗ�������A���ː����ʑ̂Ƃ������Ƃ�����)�ƌĂ�Ă���B ���q��(���q�ԍ�)�͌��f�ɌŗL�ł���A�������f�̌��q�j�ǂ����͗z�q�����������B�������f�ł����Ă����q�ʂ��قȂ���̂ʌ��f(���ʑ�)�Ƃ����B�َ�̓��ʌ��f�̌��q�j�ɂ́A�����̗z�q�����邪�����q���͈قȂ��Ă���B ��ʂɁA���f�͕����̓��ʌ��f���������琬����̂������B���f���قȂ�Ή��w�I�Ȑ������قȂ�B���Ƃ��A���f�Ƃ������f�́A����ȓ��ʌ��f�ł���y���f(�z�q��1�A���ݔ�99.9885��)�Ɠ���������ȏd���f(�z�q��1�A�����q��1�A���ݔ�0.0115��)���琬��B�s����ŁA���̎����ŕ��铯�ʌ��f�����ː����ʌ��f(���ː��j��Ƃ�����)�ł���B�O�d���f(�g���`�E���Ƃ�����)�͐��f�̕��ː����ʌ��f�ł���B�y���f�A�d���f�A�O�d���f�̉��w�I�����́A���ʂ̑���ɔ�ׂ�A�قƂ�Ǖς��Ȃ��Ƃ����ėǂ��B ���q�j�̈��萫�ɂ́A�j���̗z�q���ƒ����q���̃o�����X���W���A���q����20�ȉ��̂悤�Ȍy�����q��ʂɂ���A��ʂɊj���̒����q���͗z�q���ɔ�ׂđ����B��ʂɁA����ȓ��ʌ��f�̐��́A���f�ɉ����ĒP���̂���������A�����̂���������B���ː����ʌ��f�̑����́A�z�q���ƒ����q���̊������A����Ȃ��̂Ɣ�ׂăA���o�����X�ɂȂ�Ȃ�قǁA�������Z���Ȃ�X��������B ���q����1�`83�̊Ԃɂ����Ă��A���q��43�̃e�N�l�`�E��(Tc)�̂悤�Ɉ���ȓ��ʌ��f��������݂��Ȃ����f������B���q�����傫���Ȃ��Č��q��83�̑���(Bi)����ƁA���蓯�ʌ��f�͑S�����݂��Ȃ��Ȃ�B���q�����E����(U)�̂悤�ɑ傫���ƁA���R�Ɍ��q�j�����āA������ȏ�Ԃł��钆�Ԃ̌��q���ł����̌��f�Q�ƕ����̒����q�Ƃ����������̌��q�j�ɕ��錻�ۂ������B����������j����Ƃ����B ��3�D���ː��̐��� ���ː��̐����͕��ː����ʌ��f�̌��q�j�̕���A���q�j����(���˕��ː��ɂ�錴�q�j�̔����A�j���������A�j�Z��������j�j�Ӕ����Ȃǂ��܂܂��)�ɂ����̂Ɛ������˂̂悤�ɕ��ː��ǂ����̓]���ɕ�������B�܂��A�j���������𗘗p���錴�q�F��������p����l�H�I�ȕ��ː����ƒn����F���̂悤�Ȏ��R�E�̕��ː����ɕ����邱�Ƃ�����B ���ː����ʌ��f�̌��q�j�͕s����ł��邩��A���ː�����o���Ă�����ȓ��ʌ��f�ɕς��B�������ː����͕��ː���ςƂ����B�P�ɕ��͉�ςƂ������Ƃ������B�����������ʌ��f�̌��q�j���ˑR�Ƃ��Ė����s����ł���ꍇ�ɂ́A���蓯�ʌ��f�ɂȂ�܂ł���ɕ�����J��Ԃ��B���̂������o�������ː��́A��Ƀx�[�^��(�z�d�q���͒����q���̃o�����X�����Ȃ��Ƃ��ɕ��o�����)��K���}���ł��邪�A�d�����q�j���邢�͂��̑�����̕��ː����ʌ��f����A���t�@�������o����邱�Ƃ�����B ���ː��͌��q�j�����ɂ���Ă����o�����B���q�j�������������ꂽ�����A�V�R�̕��ː����ʌ��f�̕���Ŕ�������A���t�@���𗘗p���Č��q�j���������ׂ�ꂽ�B���̌�A���q������Ƃ��̕t���V�X�e���𗘗p����Ƃ��A�j�����A�������𗘗p���錴�q�F�ɂ���āA�G�l���M�[�����߂��l�X�ȗ��q����d���g�����p�ł���悤�ɂȂ����B�����̕��ː����ɏƎ˂���ƁA���q�j�����ɂ�葽�푽�l�̕��ː������o����A���܂��܂ȕ��ː����ʌ��f����������B������𗘗p���ĉ������闱�q�ɂ́A�z�q�A�d�z�q�A�A���t�@���A���̑��̏d�דd���q(�d�C�I��)��d�q�Ȃǂ�����B���q�j�����̎�ނ����܂��܂ŁA���q�j�����ɂ����o�������ː��̎�ނ��A�������q�̃G�l���M�[�̈�ɂ���ĕω�����B���G�l���M�[�̕��ː��𗘗p����ƁA���q�j�����ɉ���j�j�Ӕ������N����B300MeV����z�q�����ɏƎ˂��Ē��Ԏq����o������Ƃ��A�j���[�g���m�̌����p�Ƃ���30GeV���x�ɉ��������z�q�����p�����Ă���B �G�b�N�X����K���}���̂悤�ȓd���g�͌��q�̑����d�q�Ƒ��ݍ�p(���d���ʂ�R���v�g���U��)���āA�d�q�ɂ��̃G�l���M�[�̂��ׂĂ��������͈ꕔ��^����B�܂��A1.02MeV�����傫�ȃG�l���M�[�̓d���g��������ʉ߂���Ɠd�q�Ɨz�d�q��(�d�q�Αn���Ƃ�����)���āA���̕������d���g�̃G�l���M�[��������B����Ƃ͔��̌��ۂł��邪�A�דd���q����������ʉ߂���ƁA���q�j�̓d�ׂƂ̐Ód���ݍ�p�ɂ��d���g�����o�����B����𐧓����˂ƌĂԁB �n�\�ʂɂ͎��R�E�̕��ː�����т����Ă���B��Ȕ������͉F��������щ�X�̐����������邢�͒n�\�Ƃ��̋ߖT�ɑ��݂�����ː����ʌ��f�̕���ł���B�����̋��x�́A��������n��̏�������ɂ���đ傫���قȂ��Ă���B �F���ɂ͒��V�������̂悤�ȍ��G�l���M�[���ː��̔������ƍl�����Ă�����̂�����B�n���̑�C���ɔ���F����(�ꎟ�F�����Ƃ���)�̐����́A�z�q(���f�̌��q�j)��90�������߁A���̑��̐����́A5�����x�̃w���E��(He)�Ə��ʂ̃��`�E��(Li)����S(Fe)�܂ł̏d�C�I���ł���B�ꎟ�F�����͑�C�Ƃ̌��q�j�����ɂ���ēF�����A����ɂ́A�z�q�A�����q�Ȃǂɕϊ����A�啔������C����ʉ߂���Ԃɕ��邩�z�������B�Β��Ԏq�̕���Ő�����~���[�I���Ȃ�тɌ��q�j�����������ł���g���`�E��(3�g)�Ƃ����ː��Y�f(14�b)�̂悤�ȕ��ː����ʌ��f���A�n�\�Ŋϑ������F���R���̕��ː��ƕ��˔\�̗�ł���B �n�k�ɂ͒n���̔N��������邢�͂�������钷�����̕��ː����ʌ��f�����������݂���B�����̂����̎�Ȃ��̂ɁA�����j���������ł���E������g���E��������B�E������g���E���͂���������ː����ʌ��f�ŁA�A���t�@�[����x�[�^���Ȃǂ���o���Ȃ��玟�X�ɕ���B�����̎q���j��ɂ̓��h����g�����̂悤�ɁA�q�g�ɂƂ��čł��傫�Ȏ��R���ː�������y�ڂ��A���ː���K�X���܂܂��B�܂��A�q�g�̐����ێ��Ɍ������Ȃ��J���E���ɂ��A���ː��J���E��(40�j)���܂܂�Ă���A�J���E���Ɠ����̃��r�W�E��(Rb)�ɂ����ː����ʌ��f���܂܂�Ă���B�@ |
|
|
�����˔\
���˔\�Ƃ͕s����Ȍ��q�j������Ȍ��q�j�ɕς��(��ςƌĂ�)�Ƃ����ː�����o����\�͂������B���ː�����o����悤�ȕs����Ȍ��f(���q�j)���܂ޕ������܂��A���˔\��L����Ƃ����A���ː������ƌĂԁB���ː��j��̉�ό��ۂɔ������˔\�̋����͖��b��ς��銄����������ϒ萔�ɂ��邢�͔������s�ŕ\�킳���B�����͂��ꂼ��̌��q�j�ɌŗL�̗ʂł���B���˔\�ɂ́A���R���˔\�Ɛl�H���˔\������B�l�H���˔\�͐F�X�ȂƂ���ŗ��p����Ă���B ��1�D���˔\�̒�` ���˔\�Ƃ́A�s����Ȍ��q�j������Ȍ��q�j�ɕς���ό��ۂɂ����ĕ��ː�����o����\�͂܂��͂��̋����������B���̂悤�Ȍ��f(����̈���Ȍ��f�Ɣ�r����Ƃ��ɁA���ː����ʌ��f�܂��͕��ː����ʑ̂ƌĂ�)���܂ޕ������܂��A���˔\��L����Ƃ����A���ː������ƌĂԂ��Ƃ�����B �u��ρv�Ƃ́A�s����Ȍ��q�j(���ː����q�j)�����ĂȂ��Ȃ邱�ƂƁA���f�����̌��f�ɕς�邱��(�ϊ�)�������B���̓�������ɋN���邱�Ƃ�\���Ă���B �u���˔\�v��1896�N2���A�t�����X�̃x�N����(�g�DBecquerel)�ɂ���Ĕ������ꂽ�B�x�N�����͂��̕��ː����u�E�������v�Ɩ��t�����B���ꂩ��2�N��A�}���[�E�L�����[(Marie Curie)�̓s�G�[���E�L�����[(Pierre Curie)�̍�����A����d������ɗp���鐅���s�G�]�d�C�v��p���ăE�������̌������s���A�E�������̋����̓E�������������Ɋ܂܂��E�����̗ʂɔ�Ⴗ�邱�ƁA�E�������̓E�����������̉��x�∳�͓��̏�Ԃɍ��E���ꂸ�A�₦�������I�ɕ��˂���Ă��邱�Ƃ��m�F�����B�܂��A�E�����ȊO�̉������ɂ��Ă����ׁA�g���E�����������E�����������Ɠ��l�̕��ː����o�����Ƃ����A���̗l�ȕ��ː����o���������u���˔\�v�Ɩ��t�����B1898�N7����Bi(�r�X�}�X)�ɐ��������Ă���V�������f�������B���̐V���f�̓}���[�̑c���|�[�����h�Ɉ���Łu�|���j�E���v�Ɩ������ꂽ�B2�l�͂��̌���s�b�`�u�����h(�ꂫ�����E�����z)�̕��͂�i�߂��B�s�b�`�u�����h�̒��ɂ́A���̒��Ɋ܂܂�Ă���E������|���j�E���������˔\�̋�������������ƍl����2�l�́A������1898�N12��Ba(�o���E��)�ɐ������������ː�����������Ɣ��\�����B���̐V���f�́m���˂�����́n�Ƃ����Ӗ��́A�uRa�F���W�E���v�Ɩ������ꂽ�B ��2�D������ ���ː��j��̉�ς́A�j��ɌŗL�̊m���ŋN����B�j���Â��Ƃ�A�K��������ςɂ����鎞�Ԃ͈�肵�Ă��Ȃ����A�����̓����j��̏W�܂�ɂ��ẮA��ς̊����͊j��ɌŗL�ł���B���鎞�������ςɂ���ĕ��ː��j��̐��������Ɍ�������܂łɗv���鎞�Ԃs�����Ɖ]���B������j��ɌŗL�ł���B �܂�1�b�Ԃɉ�ς��銄������ϒ萔�Ƃ����B�ɂƂs�ɂ͎��̊W������B �Ɂ�0.693/T ��3�D���R���˔\�Ɛl�H���˔\ ���˔\�ɂ́A�l�Ԃ̊����ɊW�Ȃ����݂��鎩�R���˔\�ƁA�l�Ԃ̊����ɋN������l�H���˔\������B���R���˔\�ɂ́A�n�����a�����������炠�����V�R���˔\(���n���˔\)�ƒn���ɍ~�肻�����F�������N���Ƃ�����˔\������B�l�H���˔\�́A�l�H�I�ɍ��o���ꂽ���̂ł��邪�A�g�p����ړI�ɉ����Ă��낢��̎�ނ�����B ��4�D���R���˔\ ��4-1�D�V�R���˔\ �n�k���ɂ́A�n���̒a�����ɂł��������̕��ː��j�킪�L�����z���Ă���B�����͓V�R���˔\�ƌĂ�A�y���A�����A�A���A�؍ށA���ޓ��̐��������̂��낢��̕����Ɋ܂܂�Ă���B���˔\�́A�l�̓��ɂ����݂���B��\�I�Ȃ��͓̂V�R�̃J���E�����Ɋ܂܂����ː����ʌ��f(40�j)�Ɋ�Â����̂ł���B ��4-2�D�F�����N���̕��˔\ �F�������n���y�т��̑�C�ɓ˓�����Ƃ��ɁA��X�̕��ː���������������B���̑�\�I�Ȃ��̂�3�g�A14�b������B�����̕��˔\�́A����ł͐�������A����ł͉�ς�����Ȍ��f�ɕς��̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͑����邱�Ƃ����邱�Ƃ��Ȃ��A�n����ɂ͂��ꂼ��قڈ��ʂ̕��˔\�����݂��邱�ƂɂȂ�14�b�̓��ʑ̔�𑪒肵�A14�b�̕��˔\�̌�������|����ɁA���j�l�Êw��̈╨�̔N��𐄒肷����@���ǂ��m���Ă���B ��5�D�l�H���˔\(��) �l�H���˔\�́A���ː��̃G�l���M�[��L���ɗ��p���邽�߂ɁA���o�������̂ł���B ��5-1�D���q�͔��d�ɊW������˔\ ���ː��̂��G�l���M�[�́A���q�͔��d�Ƃ��đ�K�͂ɗ��p����Ă���B���q�͔��d�ɔ�����ʂ̕��˔\�́A�\�����S�ɊǗ�����Ă���B���q�͔��d�̔��W�ƂƂ��ɁA����܂ňȏ�Ɍ��q�͂̈��S���v�X�d�v�ɂȂ��Ă��Ă���B ��5-2�D�j�����ɋN��������˔\ �j�����ɂ���đ�C���ɕ��o���ꂽ���˔\�ɋN��������ː��~�����̓t�H�[���A�E�g�ƌĂ�Ă���B�ă\����C�����j������ł�����1962�N�̗��N1963�N���ō��Ƃ��ĔN�ԍ~���ʂ��������A���̑啔�������łɍ~���������Ă���Ɛ��肳��Ă���B ��5-3�D��×p���˔\(��) ����܂�100�N�ȏ�ɂ킽���ēd�����ː��͂܂��܂���Â̒��ŗ��p����Ă���A���ł͐f�f�A���Â���юE�ۂȂǂɌ������Ƃ��ł��Ȃ�����Ƃ��Ă�������蒅���Ă���B���q�͕S�Ȏ��TATOMICA�̒����ڕ��ށu���ː��̈�w���p�v�̏����ڕ��ށu�f�f�v�A�u���Áv�A�u�E�ہE�ŋہv�A�u���i�E��Ñ��u�E�@��v�Ȃǂɂ��낢��ȗ��p�Ⴊ�Љ��Ă���B ��5-4�D���H�w�p���˔\(��) �v���A�����𖾁A�����̍\����́A�V�f�ނ̊J���A�G�l���M�[���Ȃǂł̗��p�́A���q�͕S�Ȏ��TATOMICA�̒����ڕ��ށu���ː��̗��H�w���p�v�̏����ڕ��ށu�����w���p�v�A�u�H�Ɨ��p�v�A�uRI�̗��p�v�ɏЉ��Ă���B ��5-5�D�_�Ɨp���˔\(��) �i����ǁA�Q���쏜��H�i�̕ۑ��A���ۑS�Z�p�Ȃǂł̗��p�́A���q�͕S�Ȏ��TATOMICA�̒����ڕ��ށu���ː��̔_�ѐ��Y�Ɨ��p�v�̏����ڕ��ށu�i����Ǔ��v�A�u�H�i�̕ۑ����v�A�u���ː��ɂ����ۑS�v�ɏЉ��Ă���B�@ |
|
|
�����ː��̎ʐ^��p
���ː��̎ʐ^��p�́A��������������ː����o�@�Ƃ��ė��p����Ă����B����́A���̓����A���łɎʐ^�Z�p����ʂɂ����p�����قǕ��y���Ă������߂ł���B���ː��̎ʐ^��p�̓����́A�L�^�E�ۑ����\�ȁA���ː��̉����ɂ���B���̌�A���̓����𗘗p���āA��Â̕���ł͐f�×p�G�b�N�X���ʐ^���͂��߂Ƃ�����ː��f�f���A���q�͂̕���ł͎ʐ^�t�B������p�����t�B�����o�b�W���s���Ȃ��̂ƂȂ����B���ː��̎ʐ^��p�́A�I�[�g���W�I�O���t�B��W�I�O���t�B�ȂNJ�b����Y�ƕ���܂ŁA�L�͂ɗ��p����Ă���A�ʐ^���̃C���[�W��������u����p�̕��p�ɂ���āA����ɗp�r���L�܂��Ă���B�����ł́A���ː��̎ʐ^��p�̗��p���@�Ǝ�ȗ��p����Љ�A���p��̉ۑ�ɂ����y����B ��1�D�ʐ^��p�ɂ����ː��̌��o�Ǝʐ^�Z�p �E�����̕��˔\�̔���(�t�����X�̃x�N�����A1896�N)�ɗp����ꂽ�͎̂ʐ^���ł������B�ʐ^�Z�p�͂��ł�18���I����19���I�ɂ����Ĕ��W���Ă������߁A���������ł̎ʐ^�B�e�́A�����A�킪���ł���ʗp�Ƃ��Ă̕��y���n�܂��Ă����B�ʐ^���܂̊��x�A�I�o���ԁA�����E�蒅�p����̐��\�Ȃǂ����݂̂����Ɣ�r����A�����I�Ȃ��̂ł������Ƃ��Ă��A�������������Ō������������A��������o�I�ɔ��ʉ\�ȏ�Ԃɂ܂ő������錻�������A������ɓ��ܒ��Ɏc������s�v�Ȋ�������������������蒅�����́A�������łɎ��p�\�Ȉ�ɂ܂Ő����Ă����킯�ł���B �ʐ^���܂Ƃ��Ăӂ��킵���������͐����������ꂽ���A���ݎg�p����Ă���ʐ^���܂́A���ʂ̗�������܂ޏL����ő̗��q���[���`�����ɋψ�ɕ��U�������̂���̂ł���A�������Ƃ��ẮA���g�[���A�n�C�h���L�m�����邢�̓t�F�j�h���Ȃǂ��A�蒅�t�ɂ̓`�I���_�i�g���E���������p�����Ă���A�����̑��������ː��̎ʐ^�B�e�ɗ��p�ł���B ��2�D���ː��ɂ��ʐ^��p�Ƃ��̓��� ���ː��̓n���Q��������܂ގʐ^���ܒ��̌��q�E���q�ɓd����p���y�ڂ��āA���R�d�q�A�C�I�����N���������B����炪��C�I�����Ҍ����Đ�������B�����͈���ŁA����������A�蒅����ƕ��ː��̎ʐ^���ł���B���̌����͌��̎ʐ^��p�Ƒ傫�ȑ���͂Ȃ��B���̔Z�W�ɑ���������ː��̏ڍׂȕ��ʑ��������邱�ƁA���F��掆��̍������ł���ʐ^���̂��̂̋L�^�E�ۑ����\�Ƃ������A�ʐ^�{���̓����͂���������p�ł���B�������A���ː��͉����ƈ���Ď��o�I�ɂ͑S���������Ȃ����߁A���m�̔�ʑ̒��̕��ː��̋��x�́A�ʐ^�@�ɂ��ꍇ�͗\�������ŁA�������d����p��u����p�̂悤�Ȃ��̑��̕��ː�����@�����p�ł���A�����𗘗p���ĕʓr���肷��K�v������B�܂��A���ː��̎�ނ͑��l�ŁA���̃G�l���M�[���ʏ�ɂ߂đ傫���B���ː��̎ʐ^�B�e�ɂ́A���ː��̎�ނɉ����āA�ʐ^���܂�t�B�����E���̂Ȃ�����œK�Ȃ��̂�I�肷��Ɠ����ɁA�����Č���������O���ɂ������œK�I�o�����̌���Ƃ����O����ȏ�����Ƃ��K�v�ł���B��ʑ̎������̕��˔\���z����˔\�ʂ����߂�I�[�g���W�I�O���t�B�A���ː��̓��ߐ��𗘗p����G�b�N�X���f�f��W�I�O���t�B�Ȃǂ́A���ː��̓����������ʐ^�B�e�@�ł���B ��3�D�I�[�g���W�I�O���t�B�ƃ��W�I�O���t�B ���̎������邢�͋����ޗ����̂ɕ��˔\�������ʑ̂̏ꍇ�́A�ʐ^���܂�h�z�����t�B�����܂��͊��Ɣ�ʑ̂Ƃ̊Ԃɕ��̂�u�����ɎB�e����B������I�[�g���W�I�O���t�B�Ƃ����B����ɂ������Đl�̂̈ꕔ��q��@�G���W���̂悤�Ȕ�ʑ̂��A���ː����Ǝʐ^���܂Ƃ̊Ԃɋ���Ԃ̓K���Ȉʒu�ɔz�u���āA���ː��̓��ߑ����B�e������@�����W�I�O���t�B�ƌĂ�ł���B����ȏꍇ�������āA�����̖ړI�Ɏg�p�����ʐ^����t�B�����A�����t�A�蒅�܂Ȃǂ͑���ނ̂��̂��s�̂���A�e�Ղɓ���\�ł���B ��ʑ̂͑��푽�l�ł���A�B�e�Z�p���X�ɍH�v��v���邩��A�����ł͑�\���2�C3�Љ��Ɏ~�߂�B ��3-1. �I�[�g���W�I�O���t�B ����͂��ׂĎՌ����̗D�ꂽ�Î��ōs���B�t�B�����̎�舵���́g���Ԃ�h���Ȃ��悤�ɉ�������(���w�I�e��)�A�܂�Ȃ�����(�@�B�I�e��)�������Ӑ[���s���B�܂��A��ʑ̂�������u�����Ղւ����A�t�B�����̕��˔\������h�~���邽�߁A�������������̂悤�Ȕ����ŕ����ăt�B����������B�I�o���Ԃ͌����������l�����ĕʓr�A�ړI�ɉ������œK���Ԃ����炩���ߋ��߂Ă����A�K���ȑ���������܂ł̈�莞�ԈÎ����ɐÒu����B���̌�A�t�B�������ʑ̂�����O���A�����A�蒅����Ɣ����ʐ^�̍�������������B��ʑ̎������ƂɎB�e�A����������I�ԁB���Ƃ��č��G�l���M�[���q����������ƁA�n���Q����������q�����Z�x�ɕ��U�������������܂�I�ԁB�����ɂ͓��ʂ̏K�����K�v�ł���B�I�[�g���W�I�O���t�B�̗��p�ړI�ɉ����āA���̂悤�ȎO��ނ̕��@�ŕ��ː��ʐ^(�I�[�g���W�I�O���t)���ώ@�E�]������B���Ȃ킿�A(1)�����I�ȍ����x�������x�v��p���ċ��߂���@(�}�N���I�[�g���W�I�O���t�B)�A(2)�����I�ȍ����x���������Œ��ׂ���@(�~�N���I�[�g���W�I�O���t�B)�����(3)��Ղ��������Œ��ׂ���@(��ՃI�[�g���W�I�O���t�B)�ł���B������̕��@�ɂ��Ƃ��Ă��A���ː��ɂ����܂̍��������ː��̋��x�ɔ�Ⴗ��̈��I�肵�Ă����A�I�o���Ԓ��ɓ��܂�����������ː��̐ϕ��ʁA���Ȃ킿�A�ʐ^�̍����x������ː�������ʂ����߂���B�}�N���I�[�g���W�I�O���t�@�ɂ��A�������̕��˔\�̖ʕ��z���T���I�ɔ��ʂł���B�~�N���I�[�g���W�I�O���t�ł́A���̕��ʑ�������ɏڍׂɊώ@�ł���B�����ŁA��҂͓��ɁA���A���̔��Ђ�p�����זE���O�̕��ː����ʌ��f(RI)�̕��z�⏔��̍ޗ�����RI�̐��ׂȕ��z������̂ɗp�����Ă���B(3)�̔�Ղׂ���@�́A�������ܖ���p����F�����̑���Ƃ��A���˔\�̎�ނ肷��Ƃ������A�������̕��˔\�̔��ʂɓK���Ă���B���ː���Ə]���҂��g�т�����ː��Ǘ��p�̃t�B�������ʌv(�t�B�����o�b�W)�́A�ėp�I�ȃI�[�g���W�I�O���t�B�̉��p��ł���B�t�B�����o�b�W�͍�Ə]���҂̕��ː�����Ǘ��ɂƂ��ċɂ߂ėL�p�ł���A���ː��̎�ނɉ����āA���ꂼ��̔��(���ː��̕������̓��B����)���l�����āA���ː��z���p�̌�������ёg�����قȂ�t�B���^��p����Ȃǂ��āA��X�̕��ː���Ώۂɂ������ʑ��肪�s����B ��3-2. ��j���p���W�I�O���t�B ��j���p���W�I�O���t�B�̎�ȖړI�́A��ʑ̂̌������ł���B���̖ړI�ɂ̓R���g���X�g�̗ǂ��I�o�E���������̑I�肪�d�v�ł���B���W�I�O���t�B�p�̕��ː����͎�Ƃ��ăK���}�����ł���A�Œ莮�Ɖ����Ƃ�����B���ː��̓����͌X��RI�ɓ��L�̂��̂ł���A��ʂɁA�������̒���RI�̂Ȃ�����R���g���X�g���ő�ƂȂ�悤�ȕ��ː��j���I�����ĕ��ː����Ƃ���B�ėp�I�ȃK���}�����̗��\�Ɏ����B�G�b�N�X�����ɂ͎s�̂̃G�b�N�X���������u�����p�ł���B�K�v�ȘI�o���Ԃ́A���ː����̎�ށA���x�A�����̌����Ǝ�ށA�ʐ^���܂̊��x�A���������A�����Ɠ��܊Ԃ̋����������Ă��Č��߂�B�B�e�̂����́A�ʐ^�t�B���������J�Z�b�g�Ɏ��߂Č����Ւf���A���������g�p���ĘI�o���Ԃ�Z�k����B���W�I�O���t�B�͍q��@�G���W���A�Y�Ɨp�ł͋����n�ڕ����̌������p�ɐ������p�����Ă���B ��3-3. ��Õ���ɂ����闘�p ��Õ���ɂ����郉�W�I�O���t�B�̑�\��́A�f�f�ɗ��p����Ă���G�b�N�X���ʐ^�ł���B�j��w�̕���ł́A���҂ɓ��^����C���r�{���ː����i��p���āA�V���`�O���t(�V���`���[�V�����J�����ɂ��B�e�����ʐ^)��f�f�ɗ��p���Ă���B��Õ���ɂ����闘�p�ł́A�R���g���X�g�̑N�����ɉ����āA���̂ւ̕��ː�����ʂ̒ጸ�����d�v�ł���B�R���g���X�g�̑N�����ɂ��ẮA��j���p���W�I�O���t�B�Ɠ��l�̑K�v�ł���B�R���g���X�g�̑N�����̎���́ACT(�R���s���[�e�b�h�E�g���O���t�B)�̂悤�ȃC���[�W�����Z�p�̉��p�ł���B������ʂ̒ጸ���ɂ̓t�B�������x�̌��オ�L���ȑ�ł���B�ʐ^���܂Ƃ��Ă̓n���Q�����◱�q�a�̑��傪���ł���A���̂ق����܂̃t�B�������ʂւ̓h�z(��d���t�B����)�A�������̗��p�Ȃǂ�����B ��4�D�ʐ^��p���p��̉ۑ� ���ː��ɂ��ʐ^��p�𗘗p���邳���̉ۑ�́A�Î����삪�s���Ȃ��Ƃł���B���Ƃ��ăt�B�����o�b�W���ʌv���ɋ�����A�]���̎ʐ^�t�B�����ɑ����ĈÎ����삪����ł��A�L�����ː��G�l���M�[�̈�ɂ����ċz�����ʂ̑��芴�x���ǂ��M���~�l�b�Z���X���ʌv(�s�k�c)���邢�͂s�k�c�Ɣ�ׂĂ�����x�������A�����������g�p���\�Ȏ��O���p���X��N�̋P�s���u���������琬��K���X���ʌv(Radiophotoluminescence)�����p�����悤�ɂȂ��Ă���B����ɁA��Ðf�f�p�̃G�b�N�X���t�B�����ɕς���āA�킪���ŊJ�����ꂽ�P�s���u��������p����C���[�W���O�v���[�g���o�����A��������p�����G�b�N�X���ʐ^�ɔ�ׂāA�����2�����x�̔���ʒጸ�����������Ă���B�@ |
|
|
�����ː��̌u����p
�����̌u����p�͌ő̗��_�̔��W�A���A�ޗ��A����E�v�����A�e��Z�p����̋}���Ȑi�����W�ɔ����A���̗����͂܂��܂��[�܂��Ă���B���ː��̌u����p���A�ő̂̓d�q��Ԃ��l�����邱�Ƃɂ��M���邢�͌����~�l�Z���X�̗̈悪�J��A���ꂪ���ː��̌��o��z�����ʂ̑���ɍL�����p�����悤�ɂȂ��Ă���B�Ȃ��ł��u���𗘗p������Ðf�f�p�G�b�N�X���̕��ː�����ʒጸ���́A�u����p�̉���I�ȉ��p��ł���B�����ł́A���ː��ɂ��u����p�̌����Ƃ��̓������ȒP�ɏЉ�A��ɕ��ː��̌��o�Ɛ��ʌv�ւ̗��p����L���B ��1�D���ː��̌u����p �����ɊO�����牽�炩�̃G�l���M�[��������ꂽ�Ƃ��A�������o����錻�ۂ����~�l�Z���X�Ƃ����B�����Ă͊O������̗�N���������Ă���Ԃ����������o�����ꍇ���u���A��N���f���ꂽ������̕��o�������ꍇ���������ƌĂ�ŋ�ʂ��Ă����B��ʂɂ̓��~�l�Z���X���u���ƌĂ�ł���B��������(ZnS)���听���Ƃ���z���Ɍ����Ǝ˂����Ƃ��̌u���͓���Ŋώ@�ł���B�u�����镨�����u������(�܂��͌u����)�Ƃ����B�u���̂Ƃ͉��̈�̌��̔����������傫�������������B�u���̂����o������̔g���A���x�⎝�����Ԃ͕����ɌŗL�Ȃ��̂ł���B �����ɓ��˂������ː�(�d�����ː�)�̃G�l���M�[�ɂ���āA���q�E���q�̓d�q��Ԃ͗�N���(�������)�ɕω�����B���ꂪ��ɂȂ��ēd���g�̕��o���N����B���ː����u���̂ɓ��˂�����ƁA���̈�̔g���̌�(���~�l�Z���X)�����o�����B���̌��ۂ��V���`���[�V�����Ə̂��Ă���A�V���`���[�^�Ƃ͌u���̂̕ʖ��ł���B�V���`���[�^�͕��ː��̑����w���ɂ���Ðf�f�̌���ł����Η��p����Ă���B �\�ɕ��ː��̑���ɗp�����Ă����ȃV���`���[�^�������B���ː����V���`���[�^��ʉ߂��邳���ɔ�������V���`���[�V�������́A�����ʂ��������A�������Ԃ͒Z���B���ː�����p�Ƃ��ċ��߂���V���`���[�^�́A���ː����Ռ������u�Ԃɉ���(300�`600nm)����o(���������Ƃ���)���A���������������A�����œ������ɗD��Ă��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���ʂ̃^���E��(Tl)��s�����Ƃ��Ċ܂�NaI(Tl)���邢��CsI�̂悤�Ȗ��@�V���`���[�^�́A�K���}���ɑ��锭�������������V���`���[�^�ł���B����ɑ��A�L�@�V���`���[�^�͌������Ԃ��Z���̂������ł���B�L�@�V���`���[�^�͕��˔\�Z�x�̍��������̑���ɓK���Ă���B�L�@�V���`���[�^�ɂ̓A���g���Z���������тɃ|���X�`������|���r�j���g���G���Ȃǂ̗L�@�ő�(�v���X�`�b�N�V���`���[�^)������B�x�[�^���̃G�l���M�[���Ⴂ�A�g���`�E��(3�g)��Y�f�̕��ː����ʑ�(14�b)���܂ޗL�@���́A�g���G���̂悤�ȗn�}�ɗn�����A�����ȃK���X�܂��̓v���X�`�b�N�e��ɋl�߂đ��肷��B������t�̃V���`���[�^�Ƃ����B �V���`���[�V�������o��̕��ː����o���́A�}�Ɏ����悤�ł���B������̏ꍇ���V���`���[�^�����d�q���{�ǂɖ�����������Ԃɔz�u���đ��肷��B�V���`���[�V�������͔����ʂ����Ȃ��B�����ŁA�V���`���[�V�����������A�d�q�@��Ōv���\�ƂȂ�悤�ɂ������u�����d�q���{�ǂł���B���d�q���{�ǂ̌��d�ʂɓ��B�����V���`���[�V�������́A108�`1010�{���x��������A���̏o�͂��d�q�@��Ōv�������B ��2�D�M���~�l�Z���X�������͔M�u�����ʌv(�s�k�c) �n���Q��������܃t�B�����������t�B�������ʌv(�t�B�����o�b�W)�́A���ː���Ə]���҂̍�Ɗ��Ԓ��̔�����ʂ��L�^���邱�Ƃ��ł��A�ʐ^�͒����Ԃ̕ۑ��ɑς��邽�߁A���ː�����Ǘ��p�Ƃ��ĕ��y���Ă���B�������A�t�B�����o�b�W�͔����g�p���ł��Ȃ��ق��A�ʐ^�t�B�����̑����A�g�p�A��������蒅�܂ł̑S������A�Ռ����̗ǂ��Î��ōs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����Z��������B ���ː��ŏƎ˂��ꂽ���������M���������ɔ�������u��(�M���~�l�Z���X)�����ɂ����āA���̔����ʂ������̕��ː��z�����ʂɔ�Ⴕ�A�Ȃ��ł������������������̂�M���~�l�Z���X����(�s�k�c����)�Ƃ����B���Ƃ��Ώ��ʂ̊�������������������LiF�́A���q�ԍ����l�̑g�D�ɑ������Ă���A�M���~�l�Z���X�����Ƃ��ė��p�ł���B�������ʌv�̌`�Ōg�юg�p�����̂��A��߂�ꂽ���x�܂ň�葬�x�ʼn��M���A�����ʂ����d�q���{�ǂ���Čv������B�s�k�c�͎ʐ^�t�B���������L���G�l���M�[�̈�̑��肪�\�ł���A�����̕K�v���Ȃ��A�ēݏ�������ΐ��ʌv�̔����g�p���\�ł���B�~�ς����L�^�����ԂƂƂ��ɋ͂��ɑމ�����t�F�[�f�C���O���s�k�c�̌��_�ł��邽�߁A�މ��̏��Ȃ��s�k�c���ʌv�̊J�����s���Ă���B ��3�D�P�s�����Ƃ��̗��p �s�k�c�����𗘗p����ہA�M�̑���ɓd���g�Ōu������������̂��P�s����(Optically Stimulated Luminescence��OSL)�Ƃ����B�P�s������1980�N�ォ��A�����Ⓑ�̂悤�ȓV�R�z���⎥��̂悤�ȍl�Êw�I�����Ŋϑ�����͂��߁A���R���ː��̒~�ϐ��ʂ𑪒肷�邱�Ƃɂ���āA�����̔N���ސ��E���肷��Z�p�Ƃ��ĊJ���A���p����Ă����B�P�s�������M���~�l�Z���X�̂悤�ɐ��ʌv�Ƃ��ė��p�ł���B�P�s���������̊J���ƕ����Č��Ǝ˂ɂ��ǂݏo���ɂ���X�̉��ǂ��{����Ă���A���萫�ɗD�ꂽ���@���J������Ă���B�ǂݏo���ɂ̓��[�U���邢�͔����_�C�I�[�h���g�p����A�A���g���邢�̓p���X�g�ŗ�N����������B�M���~�l�Z���X�@�ɔ�ׂăt�F�[�f�C���O�̋��ꂪ�Ȃ��P�s�����̗��p�́A���ɂ킪���Ō������E�߂��Ă���A���O���p���X�𗘗p����K���X���ʌv�͕��ː���Ə]���җp�̔���Ǘ��Ɏg�p����Ă���B���`�E�����ʑ�(6Li)���g�p����ΔM�����q�������x�ő���ł���B�s�k�c�����̋P�s�����ǂݏo���@�����p���ĊJ�����ꂽ�A�C���[�W���O�v���[�g(�ʒu�q���^���ː����o��)�͑�^�ł���A��Ðf�f�p�G�b�N�X���ɂ�銳�҂̕��ː�����ʂ��A�]���̎ʐ^�t�B�����Ɣ�ׂĒ������ጸ�\�Ƃ����B���̕��@�͑���͈͂��ʐ^�t�B���������L���A�����g�p���\�ł��邽�ߕ��y���Ă���B ��4�D�����Ƃ��Ă̗��p �������������߂邽�߁A���ʂ̊���������������������������(ZnS)����ː������ƍ������A�u���h���Ƃ��ėp�������j�͌Â��B���̌�A���ː��h��̌��n���炻���̎g�p�͌�������A�@�߂Œ�߂���˔\�̏���l�������͈͂ŁA�g���`�E��(3�g)��v�����`�E��(147Pm)��p��������h���̐��Y�E�g�p���s���Ă����B�������A����ː�����h���̊J���ɔ����A�����ł̐��Y�����͊��S�ɒ�~���A���̎g�p����������Ă���B�@ |
|
|
���F�����̔���
�F�����́A�d�����̓d�ׂ����X�ɕ��d���Ă��������̋����̉ߒ��ł��̑��݂����炩�ɂȂ��Ă���(20���I����)�B�w�X(Hess)�́A1911-1912 �N�ɁA�C����p�����n���I�Ȋϑ��ɂ��A�F�����̑��݂��������B ��1�D�d�����̎��R���d�̌��� �������d�����ɗ^�����d�ׂ́A���Ԃ��o�Ə��X�ɕ��d���Ă��܂��B���̌��ۂ͓����A�≏�̕s���S�ɂ����̂ƍl�����Ă������A�K�C�e��(Geitel�G1900)�� C.T.R.�E�C���\��(Wilson�G1900) �́A�≏���s���S�Ȃ��߂ł͂Ȃ��A�d�������̋�C�̓d���ɋN�����邱�Ƃ����o�����B ����ł͂��̓d���͉��̐�����̂��H�悸�A�d�����̓��ǂ�[�U�K�X(�Ɋ܂܂��V�R���ː��j��)����o�Ă�����ː����l����ꂽ�B�m���ɕǍނ�[�U�K�X��T�d�ɑI�сA��舵�����ƂȂǂɂ���ĕ��d�͒��������������B���������S�ł͂Ȃ������B���ɓd�������ӂ̕���(��C��y��)����o����ː����d���������̋C�̂�d�����邱�Ƃ��l����ꂽ���A�d�����S�̂𐅂≔�ŎՕ����Ă����A�d�������S�ɂȂ������Ƃ͂ł��Ȃ������BC.T.R.�E�C���\��(1901)��`���[�h�\��(Richardson�G1906) �́A���̓d���̌������n���O�������Ă��铧�ߗ͂̋������炩�̕��ː��ł͂Ȃ����Ɛ������A�l�X�Ȓ������s�����B 1910�N�O��ɂȂ�ƁA���̐������x������悤�Ȍ������ʂ��łĂ����B��C�̓d���̍��x���z���A�y�뒆���ː��j��ɂ��d�������ł͐����ł��Ȃ������̂ł���B�d������n�ォ�珙�X�Ɏ����グ�Ă����ƁA�y�납��̕��ː��͋�C�ɋz������邽�ߓd�����̓d���͌������Ă����͂��ł���B�x���O�E�B�b�c(Bergwitz�G1910) ��}�N�����i(Mclenna) ����у}�b�J����(Macallum)(1911)�͂��̂悤�Ȏ������������A���̌����̂������͗\�z���������������B�܂��A�����t(Wulf�G1909) ���G�b�t�F�����œ��l�̎������s�����Ƃ���A�y�납��̕��ː�����C�ŋz�������Ƃ��ė\�z�����d���̖�6�{���̓d�����ϑ����A�ނ̓����̌�����C��w���ɂ��邩�A�܂��͋�C�̋z�����\�z�ȏ�ɏ������̂ł͂Ȃ����ƍl�����B �S�b�P��(Gockel�G1910) �͂��̊ϑ�������i�߂āA�C���ɂ̂����d������p���č��x4500���܂ł̓d���𑪒肵���B����ƁA�d���͍������x�łނ��둝�����Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�y�납����o�������ː������̂悤�ȍ����x�܂ŒB����͂��͂Ȃ�����A����ȊO�̕��ː������ɑ��݂��邱�Ƃ��������̂ł���B�S�b�P���͂��̕��ː����Ƃ��āA���ː��j�킪���Ăł������ː��̃K�X����C�̏�w�ɒ~�ς������̂��l�������A����ł͊ϑ����ʂ��������ɂ͏��Ȃ������B ��2�D�C���ɂ��ϑ� �����̊ϑ����ʂ܂��A�F�����̑��݂𖾂炩�ɂ����̂̓w�X(Hess�A�I�[�X�g���A)�ł������B�ނ͋C���ɓd�������̂��ăS�b�P���Ɠ��l�̊ϑ����s�����B�悸1070m�܂ł̍��x���z�𑪒肵(1911)�A���ː��̋��x���n��Ƒ卷�Ȃ����Ƃ��������B����5350m�܂ł̍��x���z�𑪒肵(1912)�A�ፂ�x�ł͓d�������������� 800m�t�߂��瑝�����n�߁A4000m�ł͖�6�{�ɁA5000m�ł͖�9�{�ɂȂ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B���̂悤�Ȍ��ʂ́A���ː��K�X�̒~�ςƂ������Ƃł͓�������ł����A�ǂ����Ă��n���O������̕��ː������Ă���ƍl������Ȃ��Ƃ̌��_�ɒB�����B���������ł���A���̕��ː��͋ɂ߂ċ������ߗ͂������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�n���O����n�㍂�x5000m�܂ł͐��Ɋ��Z����5�`6m�A�n��܂ł͓��l�ɖ�10m�̋�C�w�����݂��Ă���A���̒n���O����̕��ː��͂��̌����w���ђʂ��ē��B����̂ł���B���ʂ̂w��������͐�1m�̌���������Ζw�Njz������Ă��܂����Ƃ��l����A���̒n���O���ː��̊ђʗ͂̋���������B ���̂悤�ɂ��Ĕ������ꂽ�n���O����̕��ː��̓h�C�c�ł́u�������ː��v�A�u�w�X���ː��v�A�u�����ː��v�ȂǂƌĂꂽ���A�p�Ăł́u�F����(cosmic ray)�v�ƌĂ�A���݂ł́u�F�����v�Ƃ����ď̂��蒅���Ă���B ���̌�A���̍����G�l���M�[���������F�����͐��E���̕����w�҂̊S���W�ߑ����̌������J�n���ꂽ�B ��3�D�F�����̐����̊ϑ� �R�[���w���X�^�[(Kolhoerster�G1913�C1914) �́A9300m�܂ł̍��x���z�̐���������s���A�n��ł̉F�����d�����x��50�{�ɒB���邱�Ƃ��������B�܂��F�����̋�C�ɑ���z���W�������߁A1.0E�|5/cm(Ra-C�����̖�5����1)�̒l���B 1925�N�ɂ́A�~���J��(Millikan)����уL��������(Cameron) ���~���A�[��(�W��3900m)�ƃA���E�w�b�h��(�W��2060m)�ł̊ϑ�����F�����̐��ɑ���z���W��������(1.8�`3.0)E�|3/cm �A�R�[���w���X�^�[�̒l(2.5E�|3/cm)�ƈ�v�������Ƃ���F�����̑��݂��m�F�����B�g���l���A�B���A����ł̊ϑ����s���A�R�[���w���X�^�[(1933)�́A���[1000m�����̐[���łf�l�ǂɂ��F�����̑��݂��m�F���Ă���B �N���C(Clay�G1927) ��R���v�g��(Compton�G1930-)�́A�n����L���F�������x���ϑ����A�ԓ��߂��ŋ��x���ɏ��ɂȂ邱��(�u�F�������x�̈ܓx���ʁv)���m�F�����B����ɁA�ܓx�Ƃ��āu�n���C�ܓx�v���Ƃ�����F�������x�Ƃ̑��ւ��ǂ����Ƃ���A�n����C�ɓ��˂���1���F�������d�ׂ������A�n������ɂ���ĉ^���ʂ̏��������q�͒��˕Ԃ���邩��ł���Ɖ��߂��ꂽ(�X�g�[�}�[(Stormer�G1930)�A�����g��(Lemaitre)����у��@�����^(Vallarta�G1933))�B�F�����ɑ���n���C�̉e���̊T�O��}�Ɏ����B ��4�D�V�������q�̔��� 1927�N�ɂ̓X�R�x���c�B��(Skobelzyn)���E�C���\�������ɂ��F�����̔�Ղ����߂Ċϑ������B�����ŃA���_�[�\��(Anderson�G1932) �͋������ꒆ�ŃE�C���\���������쓮�����A�F�����̐i�s������p�Ȃ����āA�ʐ^�B�e���邱�Ƃɂ���Ă��̃G�l���M�[�𑪒肵���B���̍ہA�ނ͎��ꒆ�œd�q�̋O���Ƃقړ����x�ł��邪���Ε����ɋȂ����Ă���F�������q�̋O�Ղ��ϑ������B���ꂪ�z�d�q�̔����ł���A�����f�B���b�N(Dirac) �����Ă����ʎq�_����b�Â��A���Θ_�I�ʎq�d���͊w�̔��W�ɍv�������B �܂��A�X�g���[�g(Street) ����уX�e�B�[�u���\��(Stevenson�G1937)��1947�N�A������������������ŋȂ�Ȃ���~�������q�̔�Ղ����o���A���̎��ʂ�d�q�̖�100�{�Ƒ��肵���B���ꂪ���Ԏq�̔����ł���B�����1934�N�ɓ���G�����j�͂̌��Ƃ��Ē������q�ł���A���Ԏq������100������1�b�Ń����ɕ���Ƃ����u���b�P�b�g(Blackett)�̐��_(1938)�ƕ����ē���̗��_�𗠕t������̂ł������B ���̂悤�ɉF�����́A�s�v�c�ȓd�������̒T�������������ɔ������ꂽ�B���̌�A�l�X�Ȍ����҂ɂ���Ă��̐������𖾂���A���ꂾ���ł͂Ȃ��A���q�j���_�A�f���q�_��d�v�Ȏ����̔����̕�ɂƂȂ�A����ɂ͉F���_�̔��W�ɂ�����ȍv�������Ă����̂ł���B�@ |
|
|
���w���ƕ��˔\�̔���
�A�ɐ��̌��������Ă��������g�Q���͉A�ɐ��̐����ׂ悤�Ƃ��Ăw���������B�x�N�����͌u���Ƌ��ɂw�����������Ă��鎖���m���߂悤�Ƃ��ĕ��˔\�������B�L�����[�v�Ȃ̓E�����z�̒����獂�����˔\�����V���f�|���j�E���A���W�E���������B19���I���A������A�̑唭�����Ȃ���A��X�̕����ɑ���m���͑傫�Ȑi���𐋂����B ��1�D�w���̔��� 1895�N���h�C�c�̃������c�u���O(Wuerzburg)��w�̕����w�����ł���A�w�����������Ă��������g�Q��(�����`�F���FWilhelm Conrad Roentgen�A�ƁA1845�`1923)�͉A�ɐ���(�N���b�N�X��)�̎�����M�S�ɍs���Ă����B�A�ɐ��ǂ������{�[�����ŕ����Еt�����āA�Ǔ��Ŕ�����u�����O�֘R��Ȃ��悤�ɂ��A�܂������̃J�[�e����߂Ď�����^�Âɂ��A�A�ɐ���������ƁA�ӊO�Ȃ��Ƃ��ϑ����ꂽ�B�e�[�u���̏�ɒu���Ă���u����(�����V�A�����o���E���h�z)���Èł̒��Ō���n�߂��̂ł���B�u�����ǂ��牓�����Ă������͂Â��Ă����B�u���͊ǂ���1m�ȏ㗣�����Ƃ��ł����ς�炸�����Ă����B�����m���Ă��Ȃ����ː����A�ɐ��ǂ��甭�������̌u�������点�Ă���ɂ������Ȃ��ƃ����g�Q���͍l�����B���̕��ː��͖��m�̐��Ƃ����Ӗ��łw���ƌĂ��悤�ɂȂ����B 1895�N�̕��A�����g�Q���͂w���̌����ɂ�����1�l�Ŗv�������̐����グ�A���̔N�̂����ɕɂ܂Ƃ߂��B�w���̐����Ƃ��Ď��̂��Ƃ����ꂽ(�v�_���L��)�B �C) �w���́A�A�ɐ����Ǖǂ̃K���X�ɓ�����ł������u������ꏊ�����ɕ��o�����B ��) �u�����甭������̋��x�́A�w���̔����_����u���܂ł̋����̓��ɋt��Ⴕ�Č�������B2m���x�܂Ōu�����������Ă����������m�����B �n) �w����1000�ł̖{�ł����߂��邪�A1.5mm���̉��ł͖w�ǎՒf�����B���������̔ł́A���x���傫���قǎՕ�����͂��傫���B �j) �w���͎ʐ^��������������B�܂��ӌ������Ƃ��Ēm���Ă���J���V�E���������A�E�����K���X�A���ʂ̃K���X�A����A�≖������������B �z) �ʐ^���̏�Ɏ��u���Ăw�����Ǝ˂���Ǝ�̍��̎ʐ^���B���B���u�̊T�O�}��}1�A���̎��B��ꂽ��̍��̎ʐ^��}2�Ɏ����B �w) �w���͎��͂ɂ���Đi�H���Ȃ���Ȃ��B(���ߗ͂����邱�ƂƎ���ɂ����Ȃ̂Ȃ����Ƃ��A�w�����A�ɐ��Ƒ��ق�_�ł���B) �w���ɂ��Ẵ����g�Q���̑�1��̓������c�u���O������w�����1895�N�ł�132�`141�łɋL�ڂ��ꂽ�B1896�N��������ƃ����g�Q���͕̕ʍ���L���Ȋw�ҒB�ɔ��������B �w���͎��ɂ���ċȂ����Ȃ��̂ʼnA�ɐ��Ƃ͈قȂ邱�Ƃ͕������Ă������A���̓����͋��܁A���A��܌��ۂ��ł��Ȃ������B���̂��߂w���̖{���ɂ��Ă͗��q���Ɣg�������Η����Ă����B���q����W.H.�u���b�O(Bragg)�Ȃǂ��A�g�����̓X�g�[�N�X(Stokes)�A�o�[�N��(C.G.Barkla)�Ȃǂ��������B��������g�����̕��������̐l�X�ɂ���Ďx������Ă������A1912�N���E�G(Max von Laue)�ɂ���Č����ɂ��w���̉�܌��ۂ���������A�₪�Ăw�����d���j�ł��邱�Ƃ��F�߂���悤�ɂȂ����B1922�N�R���v�g��(Compton)�͎U���w���̌�������R���v�g�����ʂ����A�w���̌�������d���g�̗��q���Ɣg�����Ƃ�����d�����m�F����邱�ƂɂȂ����B ��2�D�E�����̕��˔\�̔��� �����g�Q���́̕A�����t�����X�̎w���I�Ȋw�҂ł������|�A���J���ɂ����1896�N��1���A�p���̊w�m�@�ɏЉ�ꂽ�B�����̊w�m�@�L���ɂ́u�����u�����镨���́A�����Ƌ��ɂw�������o���Ă���\��������B�v�Ƃ����|�A���J���̗\�����c����Ă���B ���z���Ȃǂ̎h���ɂ���Ču����ӌ����镨���͐������m���Ă����B�p���̉Ȋw�����ق̕����w�����ł������x�N����(Antoine Henri Becquerel�A�ŁA1852�`1908)�́A������m�F���悤�Ǝv���������B�x�N�����Ƃ͑c���̑ォ��Ȋw�����ق̕����w�����E�ɂ���A�x�N�����̕��͌u�������̌����҂ł������B���̎��W�����u���������g���Ē��������ɂƂ肩���邱�Ƃ��ł����B �x�N�����́A�ʐ^���������z�ƃA���~�łł������̒��Ɏ��߁A���z���ɎN���Ă��������Ȃ��悤�ɂ����B�܂Â��̃A���~���̏�ɃE�������̔��Ђ�u�����o���h�ŌŒ肵�đ��z�ɐ����ԎN���Ă��犣�����������B���z���̎h���ŃE����������w�������o�����A�����z�ƃA���~�߂����w���͎ʐ^��������������ɂ������Ȃ��B�\�z�ʂ茻�����ꂽ���͍������Ă����B �������A�܂�����ӊO�Ȃ��Ƃ��N�������B������̓����Â������߁A���̊ԁA��L�̎ʐ^���z���ɎN�����Ƃ��ł��Ȃ������B�x�N�����͂�����������āA���z���ɎN���Ȃ���Ί��͍������Ȃ����Ƃ��m���߂Ēu�����ƍl���A��������������B�������ʐ^���͑��z���ɎN���Ȃ��Ă��������Ă����̂ł���B�x�N�����͂��̎�����1896�N3���ɔ��������B ���낢��ȕ������ʐ^���̏�ɒu���Ď������Ă݂�ƁA�u�����鐫���≻�w�`�Ƃ͖��W�ɁA�E�������܂����ł�����ׂĊ������������邱�Ƃ����������B���ɋ����E�����̏ꍇ�ɍ����x�͑傫�������B�E��������͂w���Ɏ���������p�������ː����o�Ă���ƍl����ꂽ�B���̕��ː��͂��炭�̊ԁA�x�N�������ƌĂ�Ă����B �x�N�������Ƃw���̋��ʓ_�́A��L�̎ʐ^���ɑ��銴����p�̂ق��A��C�̉����鐫��(��C�ɑ���d����p)�ł���B�d����p�́A�ѓd���̂��w���ŏƎ˂��ꂽ��A�E�����ɐڋ߂���ƕ��d���N���邱�Ƃ��画�������B ��3�D�|���j�E���A���W�E���̔��� �s�G�[��(Pierre Curie�A�ŁA1859�`1906)�ƌ������A�����҂Ƃ��ăX�^�[�g���悤�Ƃ��Ă����L�����[�v�l(Marie Sklodowska Curie�A�|�[�����h�A�ŁA1867�`1934)�́A�w�ʎ擾�̃e�[�}�Ƃ��ăx�N�������̌������n�߂��B�s�G�[��(���ɕ��������w�̈ꗬ�̌����҂ł������B)�͕v�l�������悤�ƁA�}3�Ɏ����悤�ȐV��������d���v���l�Ă����B�����̃R���f���T�[�`�a�ɂ́A�ɔa�̏�Ɏ������悹���ċ���A��������o����ː��ɂ���Ă`�a�Ԃ̋�C���d������d����������B����A�E���̈��d�f�q�p�ɂ͕����M�g�̏�ɏ悹��ꂽ���ɂ���Ĉ������A�����ɂ��d����������B���̑傫���߂���Η����ɐ�����d�������E����d�ʌv�d�̎w���͓����Ȃ��B���̑��u���g���A�V���Ŏ��ʂ𑪂�̂Ɠ����悤�ɁA����������o�������ː��̗ʂ���ʂł���B �L�����[�v�l�͐V�^�̔���d���v����g���āA����ł��邠���镨���̕��˔\(���ː�������\��)���ʓI�ɑ��肵�Ă������B�E�������g���E�����܂ޕ������������˔\���������B���̒�ʑ���ɂ���āA���˔\�̓E�������f�܂��̓g���E�����f�̗ʂɔ�Ⴕ�A�����̉��x�A���w�`�Ȃǂ̉e���͎Ȃ����Ƃ����������B �������A�����ł��ӊO�ȗ�O���ϑ����ꂽ�B���ނ̃E�����z�A�s�b�`�u�����h(�_���E����)�ƃV�����R���b�g(���ƃE���j���̗ӎ_��)�͂��̒��ɊܗL����E�����̗ʂ���͐����ł��Ȃ��傫�ȕ��˔\���������̂ł���B�V�����R���b�g���莝���̍ޗ��ō������đ��肵�����A���˔\�̓E�����̊ܗL�ʂ̕������������݂��Ȃ������B���̎�����1898�N4���A�p���̉Ȋw�A�J�f�~�[�ɕ��ꂽ�B�L�����[�v�l�́A�V�R�̃E�����z�ɂ͕��˔\�����������m�̌��f�����ʂɍ������Ă���A���ꂪ�z�̕��˔\���������Ă���̂��ƍl���A���m�̕��ː����f�̒T�����n�߂��B�s�G�[�������������̌����𒆒f���v�l�Ƌ��ɐV���f�̒T���ɋ��͂��邱�ƂɂȂ���(�s�G�[����1906�N�̎��̎��܂ŕ��˔\�̌������Â��邱�ƂɂȂ�)�B��ʂ̍z���ӂ���n������āA���w���͂̎�@�ɂ���Đ����ɕ�������Ă������B�����̕��˔\�͔���d���v�ő��肳��A�����˔\�̐������Z�k���ꂽ�B���m�̕��ː����f�̓r�X�}�X�Ɏ��������������A�����r�X�}�X�ƕ��ː��������̍������Ƃ��Ď�o���ꂽ�B�r�X�}�X�Ɩ��m���f�̕����́A���ؓ����̂���������\�Ȃ��Ƃ��킩�����B�������̍�������^�ň�U700���ɔM����������ƁA250�`300���͈̔͂ŕ��ː��������͍����h���̂悤�Ȍ`�ŕǂɕt�������B���m�̕��ː����f�̈�́A���̂悤�ɂ��Ĕ������ꂽ�B1898�N7���A�v�ȘA���̕��Ȋw�A�J�f�~�[�ɒ�o���ꂽ�B���̒̕��ŁA���f���̓L�����[�v�l�̐��܂ꂽ���̖��|�[�����h�Ɉ���ŁA�|���j�E���Ɩ��t����悤��Ă���Ă���B �܂��A���͂̍ۂɃo���E�����̒��ɂ��������˔\�����o���ꂽ�B���w�����ł̓o���E���Ɠ������������邪�A���A���ƃA���R�[���̍����t�A���_�n�t���ł̉������̗n��x�̍��𗘗p���ĕ��˔\���������ʌ����@�ɂ�蕪�����ꂽ�B���̂悤�ɂ��Ă�����̕��ː��V���f���W�E�����������ꂽ�B���̔�����1898�N9���A�L�����[�v�ȂƓ����̃y�����̋��������Ƃ��Ĕ��\���ꂽ�B�@ |
|
|
�������A�����A�����̔���
1898�N���A���U�t�H�[�h�́A�E������g���E���Ȃǂ̓V�R�̕��ː���������o�Ă�����ː��ɂ͐����̈قȂ鏭�Ȃ��Ƃ�2��ނ̂��̂����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���ߗ͂̎ア�����u�����v�A���ߗ͂̂�苭�������u�����v�Ɩ��������B���̑��Ƀ�����������ɓ��ߗ͂��傫�����ː������݂��邱�Ƃ�����A������u�����v�Ɩ��t�����B ��1�D�����̈قȂ���ː��̔��� J.J.�g���\��(Joseph John Thomson)�́A�P���u���b�W��w�L���x���f�B�b�V���������ɂ����ĉA�ɐ��̎������s���A�d�C�̉^�ю�ł���S�Ă̕����̊�{�I�\���v�f��1�ł���d�q������(1897�N)�B1895�N�A����J�DJ�D�g���\���̉��ɂ���ė����̂́A�j���[�W�[�����h���܂�̉p���ږ��̎q�A�[�l�X�g�E���U�t�H�[�h(Ernest Rutherford)�ł������B���U�t�H�[�h�͂܂��A���˔\�Ƃw�����C�̂̓d�C�`���ɋy�ڂ����ʂɋ������������B���ː�����������o���ꂽ���G�l���M�[���q(���ː�)�́A�C�̒��̌��q����d�q���������o���A���ꂪ�d���̉^�ю�Ƃ��Ă͂��炭�̂ł���B1898�N�A���U�t�H�[�h�́A�C�̂̓d�C�`���ɋy�ڂ��w���̌��ʂɂ���J�DJ�D�g���\���Ƃ̋����������s������A�w���ƕ��ː�����������o�������ː��͖{���I�ɓ����U�镑�������邱�Ƃ��������B�܂��A�ނ́A�t(�E����)��Th(�g���E��)�Ȃǂ̓V�R�̕��ː���������o�Ă�����ː��̕����ɂ��z���̑��肩��A�t��s��������o�������ː��ɂ͐����̈قȂ鏭�Ȃ��Ƃ�2��ނ̂��̂�����A1�͓d���\�͂����ɑ傫���A���̂��ߕ����ɋz������₷���A�������ł��~���Ă��܂����A����1�́A��������d���\�͂��������A���ߗ͂��傫�����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�M���V����̃A���t�@�x�b�g�̍ŏ���2������p���āA�O�҂������A��҂������Ɩ��������B���̑��Ƀ�����������ɓ��ߗ͂��傫�����ː������݂��邱�Ƃ�����A����������Ɩ��t�����B����(�A���t�@��)�A����(�x�[�^��)�A����(�K���}��)�̐����̊T�O��}�Ɏ����B�܂��A���t�@���͎��ꖇ�ŁA�x�[�^����1mm���̃A���~�j�E���ŁA�K���}����1.5cm���̉��ŕ��ː����Ղւ��ł���B ��2�D�����̐��� ������d�C�⎥��ŋȂ��邱�Ƃ́A�d�q�̏ꍇ���͂邩�ɍ���ł������B�������A���U�t�H�[�h(�����}�M����w)�͂��̎����ɐ�����(1903�N)�A�����̎��ʁ^�d�ה�����߂�[�����J�����B���萸�x���グ��w�͂𑱂������ʁA1906�N�ɂ��̔䂪���f�C�I���̒l�̖�2�{�ł��邱�Ƃ��������B���q�ʂ�2�̌��f�͑��݂��Ȃ�����A���f�Ɏ����y�����f�ŁA�d�ׂ�2�A���q�ʂ�4�̃w���E���C�I���ƍl����Β��낪�����B�������ă����q�����̓d�ׂ����w���E�����q�j�ł��邱�Ƃ��������B�Ȃ��A1903�N�ɁA�����̕��ː���������w���E������������邱�Ƃ����o����(�����[�[�ƃ\�f�B�[�G�}�M����w)�A���U�t�H�[�h��́A���W�E���̎���������˂��ꂽ�����q���W�߂Ă��̌��X�y�N�g�����w���E���Ɠ����ł��邱�Ƃ��m�F���Ă���(1907-1908�N)�B ��3�D�����̐��� �x�N����(Antoine Henri Becquerel)�́A�u�E�����ɂ���ĕ��o�������ː��̈ꕔ(���U�t�H�[�h�ɂ���ă����ƌĂꂽ���ː�)�́A����ɂ���ċȂ����A���̕����͉A�ɐ��Ɠ��������ł���v�Əq�ׂ�(1899�N)�B���U�t�H�[�h�ƓƗ���F�D�M�[�[�������̂��Ƃ����Ă���B�x�N�����́A�g���\���Ɠ����悤�ȕ��@���g���āA�����̎��ʁ^�d�ה�𑪒肵�A�g���\���̑��肵���d�q�̒l�ɋ߂����Ƃ����o�����B���̂悤�ɁA���������̓d�ׂ����d�q�ł��邱�Ƃ͖��炩�ƂȂ����B���������̑��x�͉A�ɐ��̑��x���͂邩�ɑ��������̂ł���B ��4�D�����̐��� �����́A�������ߐ��������A����ɂ���ėe�ՂɋȂ����Ȃ������B���̕��ː��̓t�����X��P.���B���[��(Paul Ulrich Villard)��1900�N�Ɋϑ����A���U�t�H�[�h���u�����v�Ɩ��t����(1903�N) �B���U�t�H�[�h�́A�������w���̂悤�ɔg���̒Z�����ł���ƍl�������A���̂��Ƃ́A�����������ɓ��Ă��Ƃ��̎U�����ϑ����āA���ꂩ������̔g���𑪒肷�邱�Ƃɂ���ďؖ����ꂽ(1914�N�A���U�t�H�[�h�y��E�DN.�_�R�X�^�E�A���h���[�h)�B�@ |
|
|
���l�H���˔\�̔���
�l�H�I�Ȍ��q�j�j������́A1919�N�C�M���X�̃��U�t�H�[�h�ɂ���čŏ��ɍs��ꂽ�B�C�^���A�̕����w�҃G�~���I�E�Z�O���́A1937�N�A�T�C�N���g�����ŏƎ˂��������u�f������l�H�I�ɍ��ꂽ�ŏ��̕��ː����f�u�e�N�l�V�E���v(�u�l�H�v�Ƃ����Ӗ�)�������B 1938�N�A�h�C�c�̃n�[���ƃV���g���X�}���́A�E�����ƒ����q�Ƃ̊j�����������̒�����A�]���̍l�����ł͗\������Ȃ������j��������B�}�C�g�i�[�ƃt���b�V���͂��̔�������j����̍l����������B �u�l�H���˔\�v�Ƃ͐l�H�I�ɍ��ꂽ���ː������̑��̂ł���A�l�X�Ȋj��A�����`�Ԃ����邽�߁A���������āu�l�H���˔\�̔����v�Ƃ��邩����肷�邱�Ƃ͓���B�����ł́A�ŏ��̐l�H�j�ϊ��A�ŏ��̐l�H���f�A�j����̔�����3�_�ɂ��ďq�ׂ�B ��1�D�ŏ��̐l�H�j�ϊ� �l�H�I�Ȍ��q�j�ϊ������́A1919�N���U�t�H�[�h�ɂ���čŏ��ɍs��ꂽ�B�ނ́APo(�|���j�E��)����̃����𒂑f�K�X���ɒu���āA�����̓��B�����̎��������Ă����B���̂Ƃ��APo������o����郿���̓��B������1�C����C���Ő�cm���x�ł���ɂ�������炸�APo��������40cm�ȏ�̋����Ɍu���X�N���[��(��������������h�����K���X)��u���Ă��Ƃ��ǂ����ꂪ�P����(�V���`���[�V����)�A���炩�̗��q���u���ɏՓ˂��Ă��邱�Ƃ��ϑ����ꂽ�B���U�t�H�[�h�́A���̗��q�̎���̒��ł̕Ό����������āA�V���`���[�V�������N�������Ă��闱�q�����f�̌��q�j(�z�q)�ł���ƌ��_�����B�܂��A�K�X�̋C�����グ����u���X�N���[���̑O�ɋ�������u���ƃV���`���[�V�����������邪�A�K�X��������C�ɂ���ƃV���`���[�V��������������Ƃ����������ʂ���A���f14 (14�m)�̌��q�j�Ƀ���(4He�̌��q�j)���Փ˂��A�_�f17(17�n)�̌��q�j�Ɨz�q�ɕς��A�z�q���u�������点�邱�Ƃ������B���ꂪ�l�H�I�Ɍ��q�j�𑼂̌��q�j�ɕϊ������ŏ��̎����ł������B ��2�D�ŏ��̐l�H���f �����f���G�t(�����f���[�t�A���V�A)���ŏ��̎������\�\�����̂�1869�N�̂��Ƃł������B����܂łɔ�������Ă������f���A����Ȍ�ɔ������ꂽ���f���A�S�Ă��̎������\(��N�ꕔ���ǂ��ꂽ)�̗\�z�ǂ���ɂ����܂��Ă����B���������ĐV�������f�̔����͎������\���肪����ɂ��Đi�߂��Ă������B1925�N��Re(���j�E��)����������ĈȌ�A�������\�ɂ͂܂�4�̋��c����Ă������ARe�̔����Ȍ�10�N�ȏ���V�������f�͔�������Ȃ������B����A���U�t�H�[�h�́u���q�̓v���X�d�ׂ�������1�̌��q�j�Ƃ��̎��͂���鑽���̓d�q����ł��Ă���v���Ƃ̔������_�@�ɔނ̒�q�����͂��̌��q�j�̐����ɂ��Č�����i�߁A���q�j�͗z�q�ƒ����q����ł��Ă���A���f�̐����͗z�q�̐��Ō��܂邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�܂�z�q�̐���l�H�I�ɕς��Ă��ΐV�������f���ł���͂����A�ƍl�����Ȋw�҂����́A���q�ɍ����G�l���M�[��^���Č��q�j�����߂̑��u(�T�C�N���g����)���l�Ă���(1929�N)�B ���āA�������\��4�̋ɑ������錳�f�͂Ȃ��Ȃ���������Ȃ������B�������ɕ��ː����o���đ��̌��f�ɕς���Ă��܂����f�����邱�Ƃ������Ă���A���R�E�ɂȂ���ΐl�H�I�ɍ���Ă݂悤�ƍl�����Ȋw�҂������B�C�^���A�̕����w�҃G�~���I�E�Z�O���́A1936�N�̉ăA�����J�̃J���t�H���j�A��w�̃T�C�N���g�����Ō��q�ԍ�42��Mo(�����u�f��)�ɏd�z�q(�z�q1�ƒ����q1����Ȃ鐅�f�̌��q�j)���Ǝ˂��C�^���A�Ɏ����A�����BMo�̌��q�j���z�q��1��荞�߂A�z�q��43(���q�ԍ�43)�̖��������f���ł���͂��ł������B����43�Ԍ��f�̉��w�I�����͎������\�̐^��ɂ���Mn(���q�ԍ�25)�Ɛ^���ɂ���Re(���q�ԍ�75)�Ɏ��Ă���͂��ł���A�Z�O���́A�Ǝ˂��������̒�����Mn��Re�ɉ��w�I�����̎������������o����Ƃ��s�����B�����Ă��ɔނ́A�����ԉ��w�҂������ł��Ȃ������V�������f�̑��݂��m�F�����B���q�ԍ�43�̕��ː����f�ł������B�ނ́A�l�H�I�ɍ��ꂽ�ŏ��̌��f�ł��邩��A�u�l�H�v�Ƃ����Ӗ��́u�e�N�l�V�E���v�Ƃ������O��V���f�ɂ����B1937�N�̂��Ƃł������B���ꂪ�ŏ��̐l�H���ː����f(�l�H���˔\)�ł���B ��3�D�j����̔��� 1938�N12���A�h�C�c�̃n�[���ƃV���g���b�X�}��(�V���g���X�}��)�́A�t(�E����)��x�������q�ŏՌ�����ۂ�(���A��)�����Ő����邩������Ȃ����E�������f(���q�ԍ���92)��T���ړI�ŁA���̂Ƃ��ɐ�������ː����f�̏ڍׂȌ������s���Ă����B�ޓ��́A�E������x�������q�ŏՌ������ۂɐ����鐔�����̕��ː����ʌ��f�̒�����A�]��Ra(���W�E��)�̓��ʑ̂ƍl�����Ă���������86���̌��f���ARa�ł͂Ȃ����q�ԍ�56��Ba(�o���E��)�ł��邱�Ƃ��m�F�����B����܂ł́A�j�����ŐV�����ł��錴�q�j�͏��߂̌��q�j�ɋ߂���ނ̂��̂Ɍ�����ƍl�����Ă���A�ޓ��̔����͂��̍l�������S�ɕ������̂ł������B �����ŁA�}�C�g�i�[�ƃt���b�V���͂��̌��ۂ����̂悤�ɍl�����B�t����Ba���ł����Ƃ���ƁA�j�̓d�ׂ�36e�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A����炪�����̃����q��z�q�̕��o�ɂ��^�ы�������́A�Ⴆ�Ό��q�ԍ�36(Kr�G�N���v�g��)�̂悤�ȑ傫�ȗ��q�ɂ���Ĉ�C�ɉ^�ы���ꂽ�ƍl��������G�l���M�[�I�ɂ��Ⴍ�Ȃ�Ó��ł���B���Ȃ킿�A�t�������q�̍�p��Ba��Kr�̂悤��2�̊j�Ɋ��ꂽ�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����Ă��̂悤�ɍl����ƁA���ʌ�������l���Ė�200 �l���u �̃G�l���M�[�����o�����͂��ł���B���̃G�l���M�[�͎�Ɋ��ꂽ2�̔j�Ђ̉^���G�l���M�[�ɂȂ�ƍl������̂ŁA���̂悤�ȃG�l���M�[��������2�̔j�З��q�����ː������Œ��ڊϑ������͂��ł���B�����̍l���͂��ׂČ����Ɋm�F����āA�����̌��q�͗��p����̖��J���ƂȂ����B ���̂悤�Ɍ��q�j���������x�̑傫�Ȕj�ЂɊ���錻�ۂ́u�j����v�Ɩ��t����ꂽ�B����Ăł����������u�j�����������v�ƌĂԁB235�t���x�������q�ɂ���Ċj����ƁA��40��̊j�������������ł��A�����͎��X�Ƀ����Ȃ���ŏI�I�ɂ͈���Ȋj�ɂȂ�B���̉ߒ��Ŕ�������j��� 160��ɂ��B����B�����̓��ŕ��ː��̂��̂́u�l�H���˔\�v�ł���B �Ȃ��A�A�t���J�E�K�{�����a���I�N���n��̃E�����z�����ŁA��20���N�O�Ɏ��Ȏ������̊j�����A�������������������Ղ���������A�l�דI�ɂł͂Ȃ��A�V�R���ۂƂ��Ċj���N�����邱�Ƃ��m�F���ꂽ(1972�N)�B���̌��ۂ́u�V�R���q�F�v�ƌĂ�Ă��邪�A�V�R���q�F�̑��݂ɂ��ẮA1956�N���{�l�̉��w�ҍ��c�a�v���\�����Ă����B�@ |
|
|
���d�����ː�
�d�����ː��Ƃ́A�����ɓd����p���y�ڂ����ː��ł���B��ʂɂ́A�d�����ː���P�ɕ��ː��Ə̂��Ă���B�d�����ː��ɂ͉דd���q(�A���t�@����d�q���Ȃ�)�̂悤�Ɍ��q�E���q�ړd�����邱�Ƃ��ł��钼�ړd��(��)���ː��ƁA�G�b�N�X���⒆���q���̂悤�ɁA�������q�̑����d�q�⌴�q�j�Ƒ��ݍ�p���ĉדd���q���������A�I�ɔ��������דd���q���������ɓd����p���y�ڂ��Ԑړd��(��)���ː�������B�����ł́A�d�����ː��̐����Ɨ��p�ɂ��Ă��G���B ��1�D�d�����ː� �d�����ː��Ƃ́A�����ɓd����p���y�ڂ����Ƃ��ł�����ː��̂��Ƃł���B ��ʂɂ́A�d�����ː���P�ɕ��ː��Ə̂��Ă���B��d�����ː��ɂ͎��O���������d����p���Ȃ��B �d�����ː��������ɓ��˂���ƁA�U����z���ɂ�肻�̃G�l���M�[�������ɗ^������B�d�����ː��̕����ւ̃G�l���M�[�ڍs�ߒ����A���ː��ƕ����̑��ݍ�p�Ƃ����B���ݍ�p�̎�ނ͑����A�����������݂͌��Ɋ֘A���Ă���B �d�����ː��͒��ړd��(��)���ː��ƊԐړd��(��)���ː��ɑ�ʂ����B�����ŁA���ړd��(��)���ː��Ƃ́A�דd�������q��(�A���t�@���A�x�[�^���Ȃ�)�ł����āA���ꎩ�̂����ځA���q�̋O���d�q���邢�͕��q�ɑ������ꂽ�d�q�ɓd�C�I�ȗ͂��y�ڂ��ēd�����N��������A�דd���q���ː��̂��Ƃł���B ����ɑ��A�G�b�N�X(�w)���A�K���}���Ȃǂ̓d���g(�w����K���}���Ȃǂ̓d���g�̗��q���ɒ��ڂ����Ƃ��ɂ́A���������q�Ƃ���)���邢�͓d�ׂ������Ȃ������q���́A���q���邢�͌��q�j�Ƃ̑��ݍ�p����ĉדd���q���������A�I�ɔ��������דd���q�����d����p�ɂ�������B�����ŁA�������Ԑړd��(��)���ː��ƌĂԁB ��ʓI�ɂ悭�m���A���A�����̗��p�p�x�������דd���q���ɂ́A�A���t�@���A�d�z�q���A�z�q���A���̑��̏d���q��(�d�C�I���Ƃ�����)�A�x�[�^��(�d�q�����܂�)���A��דd���q���ɂ͒����q�����A�d���g�ɂ́A�K���}���y�уG�b�N�X��(�����G�b�N�X�����܂�)������B ��Ɍ����ΏۂƂȂ��Ă�����ː��ɁA�Β��Ԏq�A�ʗ��q(�~���[�I��)��j���[�g���m�Ȃǂ�����B�����V���ȕ��ː����o�ꂷ�邱�ƂɂȂ낤�B ��2�D�d�����ː��̐����Ƃ��̗��p �d�����ː��̃G�l���M�[�́A��C��d���\�ȁA�܂��͂���ȏ�ł���B��C��d�����Ĉ�̐��C�I���Ǝ��R�d�q�����镽�σG�l���M�[�̒l���v�l�Ƃ����B�C�̂̂v�l�́A�G�l���M�[��1MeV���x�̉דd�d���q���̏ꍇ�A30�`35eV�ł���B �d�����ː��͕������\�����錴�q�╪�q�Ƒ��ݍ�p���āA���̃G�l���M�[�̈ꕔ���邢�͑S���������ɋz�������B���ː��̕����Ƃ̑��ݍ�p�́A�Љ�̗l�X�ȕ���ɗ��p����Ă���B �d�����ː��̎�Ȉ�ʓI�������L����ƁA (1) �G�l���M�[�͈͂��L���B (2) ���o���x���������������̂������B (3) ��ނ������A���̂��̂ɂ͓��L�̐���������B �̂悤�ł���B���ː��̓����ɂ́A�q�g�̌܊��ŔF�m����邱�Ƃ��قƂ�ǂǂȂ��Ƃ����ʂ����邪�A���̓��������p����Ă���Ƃ͌�����B��L�̂悤�ȓ����͒P�Ƃŗ��p�����ꍇ�����邪�A���ː��̎�ނƂ��̐���<08-01-02-02>�ɋL����Ă���悤�ɁA���ː��̔������̓����ƕ����ė��p����邠��B ���ː��̔������̎�Ȃ��̂ɂ́A (1) ���ː����ʌ��f�F�V�R�ɑ��݂��錳�f�̑啔���ɊW���Ă���A���Ɍ��q��(�܂��͌��q�ԍ�)���������A���q�j���s����Ȃ��� (2) ���ː�������A���q�F�F�l�H�I�ɕ��ː��̃G�l���M�[�𗘗p�������u�Ȃǂ�����B ���ː��̕������ł̓d�����ݍ�p�𗘗p���āA�דd���q�̃G�l���M�[�����߂鑕�u��������ł���A���x�̒x����דd���q���ł��钆���q���A���q�j�ɐڋ߂��ăE������v���g�j�E���̂悤�ȏd�����q�j�ɍ�p���Ղ����Ƃ𗘗p�������u�����q�F�ł���B �דd���q���̓��ߑ��́A���ː��̕������̎U���A�z���f���Ă���B����𗘗p�����Z�p�����W�I�O���t�B(�f�f�p�G�b�N�X�������܂�)�ł���B�v������ɗ��p����Ă�������v��x���v�Ȃǂ����ނł���B �d����p�𗘗p�����u�����̃O���[���d�ǂ́A���p�i�Ƃ��ĉƒ�ł������p�����Ă���B�u����p�͐f�f�p�G�b�N�X���ʐ^�̑���������ː��ʂ̕]���ɗL�p�����F�߂��Ă����B ���ː��̃G�l���M�[���A���w�G�l���M�[��ꡂ��ɏ��邱�Ƃ���A���w�����̐ؒf�A�O���t�g�d�������̂悤�ȕ��ː����w�����̗U�N��ʂ��āA�L�@���̉����ɗ��p����Ă���A�����ԗp���W�A���^�C����ϔM���d���핢�ނ̋����Ȃǂɗ��p�����ق��A�p�K�X�̕��ː������ɂ��L�Q�������̌��������łɎn�܂��Ă���B ���ː��̐�����p�́A���ː��̒��ڍ�p�ƕ����āA�V����ɂ��Ԑڍ�p�̗��p�����ڂ���A��×p���H�i�̎E(��)�ہA����h�~�A�i����ǁA�Q���쏜�Ȃǂ̂ق��A���ÁA�u�ɒጸ���Ȃǂɗ��p����Ă���B ���ː��̌��o���x�́A���w�I�Ȍ��f���͂̊��x��啝�ɏ�����̂������B�����Ō��q�͕���ł̌��o��Ƃ��Ċ��p�����͖̂ܘ_�A���ʌ��f���͂ɉ��p����Ă���B�������̔N�㌈��ɗ��p����Ă���J�[�{���f�[�e�B���O�Y�f(14�b)�́A���ː��̓����ƉF������ђn�����̍P�퐫���ɗ��p�����A���x�̍�����@�ƂȂ��Ă���B ��d�������ː��ɕ��ނ���Ă��鎇�O���͑��z�����ɂ��܂܂�Ă���B���O���̎E�ی��ʂ́A���ː����p�ɐ悾���Ă����B�d���g���t��(����)�͂悭�m��ꂽ���ۂł���B�@ |
|
|
�������
���q�j�������q����˂��āA���q�ԍ���2�A���ʐ���4�����������ʂ̎�ނ̌��q�j�ɕς��ߒ�������ςƂ����B�����q�̓w���E���̌��q�j�ł���B����ς����鐫�������������q�j�������ː��j�܂��̓����ˑ̂Ƃ����B�����ˑ̂ɂ̓��W�E���A�E�����A�g���E�����A�V�R�ɑ��݂�����̂̑��ɁA�J���z���j�E���̂悤�ɐl�H�I�ɍ�肾�������̂�����B ��1�D����� ����ς͌��q�ԍ��y�A���ʐ��`�̌��q�j�������q����o���Č��q�ԍ��y-2�A���ʐ��`-4�̌��q�j�ɕς��ߒ��������B����������A�z�q2�A�����q2����ł��Ă��郿���q����яo���Ă��������Ƃɂ́A�z�q��2�����āA���q�ԍ���2�������������q�j���c��B�܂��A�����q��2����̂Ŏ��ʐ��͍��v��4������������B1909�N���U�t�H�[�h(Ernest Rutherford)�ƃ��C�Y(Thomas Royds)�́A�����q���w���E��(4He)���q�j�ł��邱�Ƃ��ؖ������B�������͂��ꂼ��̊j��ɓ��L�ŁA�Z�����̂�214Po �� 210Pb��1.64�~10�|4�b�A�������̂�238�t �� 234Th��4.47�~10�{9�N�ȂǗl�X�ł���B ��2�D����ς̃G�l���M�[ ����ς��N���邽�߂ɕK�v�ȃG�l���M�[�̏����́A �p���m�lZ�CN�|(�lZ-2�CN-2�{�l2�C2)�n��2��0�@�@�@�@�@�@�@�@(1) �ł���B�����ŁA�lZ�CN�A�lZ-2�CN-2�A�l2�C2�́A�e�j�A���j�A�����q�̂��ꂼ��̎��ʐ��ŁA���͌��̑��x�ł���B�p�͂��̉�ςɂ���ĉ�������G�l���M�[�ŁA��σG�l���M�[�Ƃ����A�����q�y�є������ꂽ���j�̉^���G�l���M�[�̘a�A �p��(1/2)�E�l2�C2 ��2�{(1/2)�E�lZ-2�CN-2 �u2�@�@�@�@�@(2) �ɓ������B�����ŁA���̓����q�̑��x�A�u�͖��j��̑��x�ł���B�����̉^���ʕۑ��� �l2�C2 v���lZ-2�CN-2 �u�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (3) ��p���āA(2)���������A�����q�̉^���G�l���M�[�d���́A �d����(1/2)�E�l2�C2 ��2���p/�m1�{�l2�C2�^�lZ-2�CN-2�n�@�@(4) �ŗ^������B ����ς�����j��̎��ʐ��lZ�CN�́A��ʂɃ����q�̎��ʐ��l2�C2��4�ɔ�ׂċɂ߂đ傫���̂ŁA(4)���̂l2�C2/�lZ-2�CN-2����1�ƂȂ�A�p�͖w�ǃ����q�̉^���G�l���M�[�ɓ������Ȃ�B���Ȃ킿�A����ς̏ꍇ�A�����q�̃G�l���M�[�͈��ł���(����ς̏ꍇ�ɂ́A�d�q�ƃj���[�g���m�����˂���邽�߁A�����q�Ƃ����o�G�l���M�[�͋ψ�ł͂Ȃ�)�B �} ��210Po������˂���郿���q�̔�Ղ��E�C���\��(C.T.R�CWilson)�̖����ŎB�e�������̂ł���B�C�̒��̔�Ղ̒������������������ł���̂̓G�l���M�[���ψ�ł��邱�Ƃ������Ă���B���̋����̂��Ƃ����Ƃ����B�����q�̋�C���̔��(�q cm)�ƃG�l���M�[(�d�� �l���u)�Ƃ̊Ԃɂ́A �q�����d��3/2�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (5) �̊W������B���������āA��C���̔�����킩��A�����q�̃G�l���M�[�𐄒�ł���B�܂��t�ɁA�����q�̃G�l���M�[������ł���A���̋�C���ł̔�����킩��B ����ꍇ�ɂ́A1��ނ̃G�l���M�[�̃����q�����łȂ��A2��܂��͂���ȏ�̎�ނ̃G�l���M�[�������������q����o����j�킪����B �\��228Th�̖��j212Bi��208Tl�Ƀ���ς���Ƃ��ɕ��o����郿���q�̃G�l���M�[�X�y�N�g�������������̂ł���B����͖��j(212Bi)�������Ɋ����(208Tl)�Ɉڂ炸�A��X�̗�N��ԂɑJ�ڂ��A���̃G�l���M�[���ʂɑΉ������G�l���M�[����o���邽�߂ł���B���̏ꍇ�p�����ꂾ���������Ȃ�A�����q�̃G�l���M�[���������Ȃ�B���̎�����ςɑ����ă����̕��˂��N����B���o���������̃G�l���M�[�͂p�̏������Ȃ������ɓ������B ��3�D����Ɖ�ϒ萔(�K�C�K�[�E�k�b�^���̖@��) 212Po������o����郿���q�̔���͖�8.6cm�A232Th�̂���͖�2.8cm�ł���B����ς̔������́A�O�҂�3.04�~10�|7�b�A��҂�1.41�~10�{10�N�ł���B�K�C�K�[�ƃk�b�^���́A�����q�̔���������قǃ���ς̔������͒Z���Ƃ��������I�����ɒ��ڂ��A1911�N�ɔ��(�q)�ƂƉ�ϒ萔(��)�Ɋւ��鑽���̑���l�����A�����̊W�������B log�Ɂ����Elog�q�{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(6) �����ł�����т��͂Ɖ�όn��ɂ���Ă��܂�萔�ł���B�ɂ̓Ɂ�(ln2)/T�Ȃ鎮�Ŕ�����(�s)�ƊW���Ă���B(6)�����K�C�K�[�E�k�b�^��(Geiger-Nuttall)�̖@���Ƃ����B ����̓����q�̃G�l���M�[�������قǒ����B���������āA�����q�̃G�l���M�[�������قlj�ϒ萔���傫���Ƃ�����B����͑傫���G�l���M�[�������������q�͌��q�j�����яo���͂��傫�����A�܂��j���ł̐U���������̂ŁA�j�O�ɔ�яo���@��傫���Ȃ�Ɖ��߂ł���B �����q���j�̒�����O�֏o��ɂ́A�y��82�̊j�ɂ��Ă�20MeV�ȏ�̍����̃N�[������ǂ�ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��Ƃ̓G�l���M�[����MeV�̃����q�ɂƂ��ẮA�ÓT�͊w�I�ɂ͕s�\�ł���ƍl����ꂽ�B1928�N�A�K���t(George Gamow)���́A��ǂ̒��������q�����ݏo��������g���l�����ʂƂ����T�O�����A�ʎq�͊w�I�戵���ɂ���Ă�������߂����B�@ |
|
|
�������
�e�j�킩��d�q(���|)�����o�����ꍇ�A�܂��͗z�d�q(���{)�����o�����ꍇ�A���邢�͐e�j��Ɋj�O�̋O���d�q���ߊl�����ꍇ(�O���d�q�ߊl)��3�̌��ۂ�����ςƂ����B����ςł́A�j��̎��ʐ��͕ς��Ȃ����A���|��ςł͌��q�ԍ���1�����������A���{��ς�O���d�q�ߊl�ł͌��q�ԍ���1������������B���o�����d�q�̃G�l���M�[�͂���͈͂ɂ킽���ĘA���I�ɕ��z���Ă���B�܂��A����ς̏ꍇ�A�����̕��o���ꍇ�������B ��1�D����� ����ς́A���q�j�܂��͑f���q�����|(�d�q)���邢�̓��{(�z�d�q)����o���āA����̌��q�j�܂��͑f���q�ɕω����錻�ۂł���B���Ƃ��A �����q�@�@���@���|�@�{�@�z�q 64Cu�@ ���@���|�@�{�@64Zn 24Na�@ ���@���|�@�{�@24Mg 11�b�@�@ ���@���{�@�{�@11�a �Ȃǂ�����ł���B �܂��A�z�d�q����o���邩���Ɍ��q�j���O�����܂��d�q���z�����ėz�q�������q�ɕς�錻�ۂ�����B����ƍ�c�́A���̂悤�Ȍ��ۂ̋N����\�����ŏ��ɗ\������(1935�N)�B������O���d�q�ߊl�Ƃ����A�����I�ɂ��ؖ�����ă���ς̈��ł��邱�Ƃ��킩�����B ����ς����鐫���́A�ŏ����W�E����g���E�����̎��R���ː��j��Ŕ������ꂽ���A���q�j�����ɂ�錴�q�j�̐l�H�I�ȓ]���⌴�q�j����̎������i�߂���ɂ�āA�����̌��q�j������ς����邱�Ƃ��킩�����B ����ςł́A�j��̎��ʐ��͕ς��Ȃ��B���|��ςł͌��q�ԍ���1�����������A���{��ς�O���d�q�ߊl�ł͌��q�ԍ���1������������B ��2�D����ς̃G�l���M�[ ����ςŕ��o����郿���q�̃G�l���M�[�͈��ł���̂ɑ��āA����ςŕ��o���������q(�d�q�A�z�d�q)�̃G�l���M�[�́A �} �Ɏ����悤�ɂ��ꂼ��̊j��ɌŗL�ȏ���l�����������镪�z(�A���X�y�N�g��)�������Ă���B���̂��ƂɋC�t�����̂̓`���h�E�B�b�N(Sir J.Chadwick�C1914�N)�ł���B ���q�j�́A���ꂼ��ɌŗL�̗��U�I�ȃG�l���M�[���ʂ������Ă���B���������āA����ςŕ��o���������q�̃G�l���M�[���A���ł��邱�Ƃ��ǂ����߂��邩��1920�N��㔼�̑傫�Ȗ��ł������B �G���X(C.D. Ellis)�ƃE�[�X�^�[(W.A. Wooster)�́ARaE(210Bi)��M�ʌv�̒��ɓ���A����ςŕ��o���������q���܂ޑS�Ă̕��ː��̃G�l���M�[�𑪒肵��(1927�N)�B���̌��ʁA1��RaE���q�j�̉�ςɂ���āA���o�����G�l���M�[�͕���350�}40keV�Ƃ����l���B���̒l�́ARaE������o���������q�̃G�l���M�[�X�y�N�g���̍ő�l1050keV��菬�����A�ނ���X�y�N�g���̕��ϒl390�}40keV�ɂقړ������B���̂��Ƃ͕��o���������q���A�j�𗣂��u�Ԃ���ϑ�����Ă���悤�ȘA���X�y�N�g���������Ă���Ƃ������ƂɂȂ�B���̌�A32�o�Ȃǂɂ��Ă����l�̂��Ƃ��m���߂�ꂽ�B�����Ń���ς̏ꍇ�ɂ̓G�l���M�[�̕ۑ����͐������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ����o�Ă����B 1932�N�Ƀ`���h�E�B�b�N(Sir J. Chadwick)�������q�����A�n�C�[���x���O(W. Heisenberg)�����q�j�͗z�q�ƒ����q���琬�藧���Ă���Ƃ������_�\�����B�����Ń���ς͎��̂悤�Ȍ��q�j�����ł̊j���j�q�̕ϊ��ƍl����ꂽ�B �����q �� �z�q �{ ���| ���̔����ł́A3�̗��q�͋��Ƀt�F���~���q�Ȃ̂ŁA���ӂ̊p�^���ʂ͔���A�E�ӂ͐����ƂȂ�A�����̑O��Ŋp�^���ʂ̕ۑ������藧���Ȃ��B 1931�N�p�E��(V. Pauli)�́A����ς̍ۂɓd�q�ƂƂ��ɓd�C�I�ɒ����ȂقƂ�ǎ��ʂ̂Ȃ����q�����o����A�S�̂Ƃ��Ă̓G�l���M�[���ۑ������Ɖ��肵�A����ςɂ�����G�l���M�[�Ɗp�^���ʂ̕ۑ��Ɋւ�����ɓ�����^�����B���̗��q���j���[�g���m�Ƃ����A�d�q�ƂƂ��ɕ��o����闱�q�j���[�g���m�A�z�d�q�ƂƂ��ɕ��o����闱�q���j���[�g���m�Ɩ��t�����B �����q �� �z�q �{ ���| �{ �ˁh(���j���[�g���m) �z�q �@�� �����q �{ ���{�{ �{ ��(�j���[�g���m) 1934�N�A�t�F���~(E. Fermi)�͗ʎq�͊w�I�ɂ��̖������߂��A�j���[�g���m�̓X�s��1/2�A�f�B���b�N�̕����������A�d�C�I�ɒ����A�t�F���~���v�ɏ]���A���ʂ�0�܂��͓d�q�ɔ�ׂċɂ߂ď��������q�ł���Ƃ����B�j���[�g���m�Ƃ������q�́A���̗��q�Ƃ̑��ݍ�p�����Ɏア���߁A���o������ł��邪�A���݂ł͂��̑��݂������Ŋm�F����Ă���B ��3�D����σG�l���M�[ ����σG�l���M�[�p�́A�d�q�ƃj���[�g���m�̉^���G�l���M�[�̘a�ł���B �p �� �de �{ �d�ˁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (1) �de�Ƃd�˂́A���ꂼ��Ɨ��ɂ͒�܂�Ȃ��B���������ĕ��o�����d�q�̃G�l���M�[�́A�}�Ɏ����悤�ɂ���͈͂ɂ킽���ĘA���I�ɕ��z���A���̍ő�l�dmax�͂d�ˁ�0�̂Ƃ��ł���B �z�q�y�A�����q�m�̒������q�̎��ʂ��lZ�CN�Ƃ��A�d�q�̎��ʂ����Ƃ���ƁA���|��ς̍ۂ̃G�l���M�[�ۑ��̎��́A �lZ�CN ��2 �� �lZ�{1�CN�|1 ��2 �{ �p�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ (2) ���������āA���|��ς��N���邽�߂̃G�l���M�[�����́A �p ��(�lZ�CN�|�lZ�{1�CN�|1)��2 �� 0�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(3) ���l�ɁA���{��ςɑ��ẮA �p ��(�lZ�CN�|�lZ�|1�CN�{1 �|2��)��2 �� 0 �@�@�@�@�@�@�@�@(4) �O���d�q�ߊl�ɑ��ẮA �p ��(�lZ�CN�|�lZ�|1�CN�{1)��2 �|�h �� 0�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (5) �ƂȂ�B�����łh�͋O���d�q�̑����G�l���M�[�ł���B ��4�D����ςƃ��� ����ςɂ����ẮA�����̕��o���ꍇ�����ɑ����B����ό�̖��j��A�܂��͊j�����Ő������ꂽ�c���j�́A�����Η�N��Ԃɂ���B��N��Ԃɂ���j�́A������ȒႢ�G�l���M�[��Ԃփ�������˂��đJ�ڂ���B�Ȃ��A���̃����̕��˂̓���ς��̂��̂ɒ��ڊW�͂Ȃ��B ����j�� �} �Ɏ������悤�ȉ�ό^(��σX�L�[��)�ŕ���ꍇ�A�����̃G�l���M�[���z�͕��G�ɂȂ�B�`����a���ւ̑J�ڂƂ`����a�ւ̑J�ڂ͕ʂ̂��̂ł���A���̊e�X�ɃG�l���M�[��1�A��2�̃������t������B���������đS�̂̃G�l���M�[���z�� �} �Ɏ����悤�ɂ��̍����ɂȂ�B�a�Ƃa���̃G�l���M�[�̍����ÂƂ��A�lB�A�lB�����j������Ԃa�ɂ���Ƃ��ƁA��N��Ԃa���ɂ���Ƃ��̎��ʂƂ���� �lB�� ��2 �| �lB ��2 �� �� �ƂȂ�A��1�̂dmax�ƁA��2�̂dmax�͒��x�Â����قȂ�B��1�ƃ�2�̊����́A�e��ς̋N����m���ɂ���Č��܂�B ��5�D����萔 ����ςɂ��������萔�ɂ܂��͔������s�́A�����ŗ^������B �Ɂ�(ln2)�^�s��(�萔�~�}�g���b�N�X�v�f)�E����C�Ef�@�@�@�@�@(6) �����́A�����̐l�ɂ��v�Z����A�\���邢�̓O���t�ŗ^�����Ă���BC�͑J�ڂ̊m��������킷�}�g���b�N�X���܂ސ��ł���B (6)�������������āAf�s��0.693/C�Ƃ���Ƃ킩��悤�ɁAf�s���������قǁA����m�����傫�����Ƃ������Ă���B�@ |
|
|
�����ː��ƕ����̑��ݍ�p
���ː��ƕ���(�}���Ɠ��`�Ɉ���)�Ƃ̑��ݍ�p�ɂ́A���ː��̎�ނƃG�l���M�[���W����B�����̎�ނ��W���邪�A���ݍ�p���l���邳���́A�ނ��댴�q�̍\���v�f(���q�j�Ƒ����d�q)�̂悤�Ȕ����I���ʂ���̗������K�v�ł���B�ł���b�I�ȍ�p�ߒ��ł��錴�q�̑����d�q�Ƃ̑��ݍ�p�ł́A���ː��̎U����z������ȉߒ��ł���B���̉ߒ��ŕ������ɂ͌��q�E���q�̓d���A��N�A�����o�Ȃǂ̍�p���N����B���q�j�Ƃ̑��ݍ�p�ɂ����Ă͎�Ɍ��q�j���������グ��B�������A���ː��ƕ����Ƃ̑��ݍ�p�̎�ނ͋ɂ߂đ����A�������A���̃G�l���M�[�ˑ������傫�����߁A2�C3�̍��ڂ̊T�v�����Ɏ~�߂�B ��1�D�܂����� ���ː�(�d�����ː�)�ƕ���(�����ł͔}���Ɠ��`�Ɉ���)�Ƃ̑��ݍ�p�̊�́A�O�����������ː��Ƃ����~�N���ȗ��q(���˗��q)���A�������\�����Ă���~�N���ȗ��q(�W�I���q)�ƌ݂��ɍ�p���y�ڂ��������Ƃɂ���B�܂���˗��q���W�I���q�ƏՓ˂��ċN���錻�ۂ̐����ł���B���q�ǂ����̏Փ˂̂����A���˗��q���W�I���q�ɋy�ڂ��͂́A���q�╪�q�̌����͂ɔ�ׂĈ��|�I�ɑ傫���B���q�j�Ɠd�q�̌����͂͌��q�╪�q�̌����͂����i�i�ɑ傫�����߁A���ː��ƕ����̑��ݍ�p����舵�������ɁA���ꂪ���S�I�ȉۑ�ɂȂ�B�j�q�Ԃɓ����j�͂͂���Ɉ�i�Ƒ傫�����߁A���G�l���M�[�̕��ː������������ɖ��ɂȂ�B�����G�l���M�[�Ƃ͔��ɁA��p���y�ԋ�ԓI�ȋ����́A���q�ƕ��q�A���q�j�Ɠd�q�A���q�j�����̊j�q�Ɗj�q�̏��ɋɒ[�ɏ������Ȃ�B ���ː��ɂ͗��q���Ɠd���g(���q)������A���q���ɂ͉דd��L����דd���q���Ɖדd�̂Ȃ���דd���q��������B���ː��̃G�l���M�[�͂��܂��܂ł���B�����ŁA�܂����ː����ʌ��f������o�������x�̃G�l���M�[��L������ː�(10MeV�ȉ�)�ɓI���i���čl���邱�Ƃɂ���B ��2�D���ː����ʌ��f�̕���ɂ����o�������x�̃G�l���M�[(keV�`10MeV)�̕��ː��ƕ����Ƃ̑��ݍ�p ���q�E���q�n�̊O�k�d�q�̌����G�l���M�[�͐�eV�̒��x�ł���̂ɑ��A���˗��q����MeV�̃G�l���M�[��L����דd���q�̏ꍇ�́A���ː��̃G�l���M�[���S���{���傫���B�����ŁA�������̓d�q�Ɉꖜ��ȏ���Փ˂��J��Ԃ��āA���X�ɃG�l���M�[�������B�דd���q�ƕ����̑��ݍ�p�̊T�O�}��}�Ɏ����B����ɂ������d�ׂ������Ȃ������q����q�́A1��̏Փ˂ɂ���đ傫�ȃG�l���M�[�������āA���̌��ʉדd���q��������B���̂��߁A�דd���q�ł͒P�ʒ���������̃G�l���M�[���������ɂȂ�A��דd���q�ł͏Փ˒f�ʐς����ɂȂ�B ��2-1. �דd���q�̃G�l���M�[���� �דd��L������˗��q�̃G�l���M�[�����ߒ��ɂ́A�e���U���A��e���U���A���q�j�����Ɛ������˂�����B���q�ǂ����̏Փ˂ɂ����āA���˗��q�Ɠ������q���Ăѕ��o�����ꍇ�ƁA���˗��q���W�I���q�ɋz�������ꍇ������B�P�Ƃ̗��q�ǂ����̋@�B�I�ȏՓ˂��e���U���ł���B�ǂ��炩�̗��q�ɓ����\��������ꍇ�́A�Փ˂ɂ���ē����V�X�e���ɕω��������A�^���G�l���M�[�̈ꕔ���ڍs����B���ꂪ��e���U���ł���B�d�q�̏ꍇ�Ɍ���A���q�j�̋߂��ʼn����x���ĕ��˂���鐧�����˂��L�ӂɋN����B�W�I���q�̌��q�j�ɁA�G�l���M�[���z������ċN����ߒ������q�j�����ł���B���˗��q�̈ꕔ�͕�����ʂ蔲����B�������ː��̓��߂Ƃ����B�����̒P�ʒ���������̃G�l���M�[������j�~�\�Ƃ����B���˗��q�̃G�l���M�[�����ɂ͏Փ˂ɂ����̂ƕ��˂ɂ����̂Ƃ�����B�P�ʒ���������̌��㗦(������W���Ƃ���)�����ʂŏ������l�����ʋz���W���mcm2/g�n�Ƃ����B�P�ʒ���������̓d�������d���ƌ����B�}��212Po������o�����A���t�@���̃u���b�O�Ȑ�(��d��������)�ł���B���ː����ʌ��f(RI)�̕���ɂ����o�������ː��̃G�l���M�[�́AkeV���x����10MeV���x�܂łł���BkeV�ȉ��̕��ː��̃G�l���M�[�����́A��ɒe���U�����x�z�I�ł���BkeV�ȏ�ɂȂ�Ɣ�e���U�����x�z�I�ɂȂ�B����ȗ�������A���q�j�����ɂ��G�l���M�[�����̊����͏������B�U�����ꂽ���q���ˑR�Ƃ��č����G�l���M�[��Ԃɂ���ƁA���������ĎU�����J��Ԃ��A���SeV�ȉ��Ɍ��������ƁA�I�ɔ��������d�q�ɂ��d����p���N��p���x�z�I�ɂȂ�B�C�̂ɂ����錴�q�E���q�̕��ϓd���G�l���M�[�̑傫����30eV���x�A�����̂̓d���G�l���M�[�͐�eV���x�ł���B�����ߒ��ɂ͏�ɕ����ɓ��L���t�˂����A���ɂ͔M�G�l���M�[���n�S�̂ɓ`�B�����B�d�q�͉דd���q�ł��邪�A�W�I���q�ƏՓ˂����Ƃ��̃G�l���M�[�������傫���A�ЂƂ��ь��q�̑����d�q�ɏՓ˂���A���˓d�q�Ƃ̋�ʂ��Ȃ��Ȃ�_�ŁA���̑��̉דd���q(�דd�d���q�Ƃ���)�Ƃ͈قȂ��Ă���B�ׁ[�^���͓d�q���ł��邪�A���̃G�l���M�[��0����ő�G�l���M�[�܂ł̘A���X�y�N�g���ł���B�x�[�^���̕������ł̋z���Ȑ��̗��}�Ɏ����B�d�q�̑��x�͓����G�l���M�[�̉דd���q�̂Ȃ��Œ������傫���B���˗��q�����q�j�̋߂��ʼn������ĕ��˂����ߒ��𐧓����˂Ƃ������A�������˂̕��˗��͕W�I���q�̎��ʂ�2��ɔ���Ⴗ��B�d�q�̎��ʂ�d�ׂ̓������z�q�̎��ʂƔ�ׂ�ƕ��˗��͗z�q��340���{�ł���B�d�q�̏ꍇ�ɐ������˂ɂ��G�l���M�[�������d����p�̂���Ɠ������Ȃ�̂́A���Ł`20MeV���x�A���Ł`200MeV���x�ł���B ��2-2. ��דd���q�̃G�l���M�[���� �d���g�̗ʎq�ł�����q�́A�������ł͎�ɂ�����\������דd���q�Ƒ��ݍ�p����B��v�Ȃ��̂Ɍ��d���ʁA�R���v�g���U���A�d�q�ΐ����̎O�҂�����B�}�ɉ��ɂ�������q�̑j�~�\�ƃG�l���M�[�̊W�𗼑ΐ��l�Ŏ����B���d���ʂ̊�^�ƃR���v�g���U���̊�^�������ɂȂ�̂͂��悻0.7MeV�A�R���v�g���U���Ɠd�q�ΐ����̏ꍇ�͂��悻4MeV�ł���B�������œd�q�Ɨz�d�q������ɂ͌��q�̃G�l���M�[�͏��Ȃ��Ƃ�1.02MeV������K�v������B�����I�Ɍ������q�̎U���A�z���̗l�q��}�Ɏ����B�R�����[�g�������q�̓��˕����̌��q�����v������ƁA�w���@���ɏ]������̑��肪�ł��邪�A��ʂɁA����������ʉ߂���L�������𑪒肷�邳���ɂ́A�w�I�����Œ�܂�r���h�A�b�v�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�r���h�A�b�v�W���͓���̔z�u���Ƃɋ��߂�K�v������B���q�͌���U������B����ԑS�̂̌���U�����������q���A���x�h�܂��̓G�l���M�[�A���x�h�Ƃ����B�U���̂̌����������ƃA���x�h�͖O�a����B�����q�ƕ����̑��ݍ�p�ł͑����d�q�Ƃ̑��ݍ�p�͏������B���̂����͌��q�j�Ƃ̑��ݍ�p����ɂȂ�B�e���U���A��e���U���A�ߊl�y�ь��q�j���������̗�ł���B�����q�̃G�l���M�[��1MeV�ȉ��ł́A�e���U�����D���ł���B�U�������q�̕������z�����ΏۂƂ��ċ��߂��Փˌ�̒����q�G�l���M�[�́A���Փ˂��Ƃɏ����G�l���M�[��1/���̂ɂȂ�B���̊W��p����Ə���1MeV�ł����������q���M�����q�ɂȂ�܂łɕK�v�ȏՉ͌y���f��17.5��ɂȂ�B1MeV�`��MeV�̒����q�͒e���U���Ɣ�e���U���Ō�������B����ɒ����q�̃G�l���M�[���傫���Ȃ�ƒ����q���z�����ėz�q�A�A���t�@���̂悤�ȉדd���q��1���o���錴�q�j�������N����B���q�j�����ł͗��q�̕��o�ɔ����Č��q�̕��o���N���邱�Ƃ������B�M�����q�̕ߊl�����f�ʐς͌��q�j�̎�ނɂ���Ē������傫�����̂�����B113Cd��157Gd�Ȃǂ͂��̗�ł���B�M�����q���z�����Č��q����o����(n�C��)�������N����B��דd���q�̎U���┽���Ő������דd���q�̕����Ƃ̑��ݍ�p�́A���ː��̎�ނƃG�l���M�[�ɉ����āA1�D�ŋL�������̂Ɠ��l�̉ߒ��Ō������A�ގ��̉ߒ��ŃG�l���M�[�������Ɉڍs����B���q�j�����ɂ��G�l���M�[�̏o�����N����B���̂��߁A�X�̔����̃G�l���M�[���x�����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ARI�̕���Ŕ�������G�l���M�[�͈͂ł́A���ʂȗ�������G�l���M�[�����ɐ�߂錴�q�j�����̊�^�͑傫���Ȃ��B ��3�D���G�l���M�[�̕��ː��ƕ����Ƃ̑��ݍ�p ���G�l���M�[�̗̈�ł͓��˗��q�̑��x�������Ȃ�B�דd���q�̓d���ɂ��C�I���̐������͑��x�ɔ���Ⴗ��B����ɔ����Č��q�j�����͎�ނ��������A���̏Փ˂Ō��q�j������o�����דd���q�̎�ނ␔����������B�܂��A�d�����q�j�ȊO�̊j���������A�j�j�Ӕ����A���Ԏq�̕��o�Ȃǂ��N����B���̌��ʁA���ː��ƕ����̑��ݍ�p�ɐ�߂�d����p�̊����́A���G�l���M�[�̗̈�ł͌������A���q�j�����̊�������������B�G�l���M�[��2GeV�̗z�q���A����2.45cm�̉��ŋz�������G�l���M�[�����̗�ł́A�d����p�̊�����3���ȉ��ł���̂ɑ��A���q�j�����̊�����15���ł������Ƃ����B��דd���q���̏ꍇ�����Ԃ͓��l�ł���B �����G�l���M�[�̉דd���q���̂Ȃ��ŁA�d�q�̑��x�͍ł��傫���B3MeV�̓d�q�̑��x�́A�^�ł̌�����99���ɒB���邪�A�z�q�ł�5.7GeV�̑��x�ɑ�������B �\�ɓd�q�̑��x�Ɣ�d���\�������B���Θ_�I�ɗL�ӂȍl�����K�v�ȗ̈�ł́A�������ˑ��������x�ƂƂ��ɑ傫���Ȃ�B�@ �@ |
|
| ���A�C���V���^�C���@ | |
|
���͂��߂�
20���I---�����́A�ߌ��I�ŋ�Y�ɖ�������̐��E�푈���o�������B����͐l�ގj��l�Ԃ��Ƃ����ő�̍߈��ł���A�����āA�ł������ȍs�ׂł������B�����A20���I�ɂ�����Ȋw�Z�p�ƈ�w�̐i���́A�߂��܂������̂ł������B�����͌��݁A���̉��b�ɗ����Ă���B�Ȋw�Z�p�̐i���́A�l�Ԃ̐�����L���A�����K�ɂ��A��w�̐i���́A���āu�s���̕a���v�Ƃ���ꂽ�a�C�̎��Â��\�Ȃ炵�߂��B�������Ȃ���Ȋw�̐i���ɂƂ��Ȃ��}���ȋZ�p�v�V�͂����ɉ��b�����ł͂Ȃ��Q�����������炵���B���Ȃ킿�A�Ȋw�Z�p�̐i���͎��R��j�A�����́A���܂�n���K�͂̊����ɒ��ʂ��Ă���B 20���I�́A���E��]�̐��I�ł�����A�s���E���ׂ̐��I�ł��������B���̐��I�̏��߁A�A�C���V���^�C���́u���ΐ����_�v�ɂ���āA���l�̉F���ς�ς����B�ނ̗��_�́A���_�����w�̕���ɂƂǂ܂炸�A�v�z�A�N�w�ɂ܂ʼne�����y�ڂ��A�ނ����ĐV��������̗a���҂��炵�߂��B�A�C���V���^�C���́A�����ɂ��āA�ނ̗��_�����グ�����H�@�܂��A�A�C���V���^�C���́A��l�̐l�ԂƂ��āA�ǂ̂悤�ɐ��������H�@���̃T�C�g�́A�A�C���V���^�C���̓`�L�𒆐S�ɁA�ނ̉Ȋw�A�v�z�������������A�����āA�A�C���V���^�C���̐l�ԑ��ɂ�������̂ł���B �Ȃ��A�{�y�[�W�́u���������v����u���H�̏I���v�܂ł̓��e�́A�u�_�͘V��(�낤����)�ɂ��āc�^�A�C���V���^�C���̐l�Ɗw��@�A�u���n���E�p�C�X(Abraham Pais)1982�N�v�y�сu�A�C���V���^�C���@�C�M���X�@BBC����@1996�N�vetc.�����ƂɕҏW�������̂ł���B �@ |
|
| �����ꑊ�ΐ����_�ƈ�ʑ��ΐ����_ | |
|
�����ꑊ�ΐ����_(special relativity)
�^�����Ă��镨�̂̑��x�́A�Î~���Ă���l�������ꍇ�ƈ�葬�x�ő����Ă���Ԃ̒�����݂��ꍇ�ł́A���R�A�قȂ��Č�����B�Ƃ��낪���̑��x�́A�Î~���Ă���l�����肵�Ă��A�����Ă���Ԃ̒��ő��肵�Ă��A�܂����������ł���B���̖������������邽�߁A�A�C���V���^�C���́A1905�N�ɔ��\�������ꑊ��(����)�_�ŁA����ꂪ�����ȂɎg���Ă��鎞�ԂⒷ���̊T�O���A���{�I�ɕς��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������B���Ȃ킿�A�Î~���Ă���l�ɂƂ��Ă̎��ԂⒷ���ƁA�����Ă���l�ɂƂ��Ă̎��ԂⒷ���́A�ʂ̂��̂��Ƃ������̂ł���B���ꂩ��A�����̈ꌩ��Ȍ��_�������ꂽ���A�����͂��ׂĎ����Ŋm���߂�ꂽ�B���̒��ł́A�����̑O��ŕ����̎���(�d��)����������ƁA���̕������^���G�l���M�[�͑�������Ƃ����A���ʂƃG�l���M�[�̓��������A���ɗL���ł���B���݂ł́A���ꑊ�Θ_�͕����w�҂̌���̈ꕔ�ƂȂ��Ă���B ����ʑ��ΐ����_(general relativity) �Î~���Ă鎞�v�╨�����ƁA���̑��x�ő����Ă��鎞�v�╨�����Ƃ̊W����ɂ���̂����ꑊ�Θ_�ł��邪�A�A�C���V���^�C���́A1916�N�ɒ�����ʑ��ΐ����_�ŁA�����x�^�������Ă��鎞�v�╨�����ɂ܂ŁA������ʉ������B���ꂩ��j���[�g���̖��L����(�d��)�����R�ɓ������B��ԂƉ^������Ȃ�l������Ԃ́A���Ƃ��Ă������ʂ̏�̂悤�ȋȂ�������ԂŁA���̋Ȃ�������d�͂�\���Ă���B���̗��_�́A�A�C���V���^�C���̒��ۓI�v�l�̎Y���ł��������A���̌ア�����̎����Ŏ����ꂽ�B�A�C���V���^�C���̕������̉�����A��Ԃ̒��ɁA�u���b�N�z�[���Ƃ�����ȏꏊ�����邱�Ƃ������ꂽ�B�F�������w�͈�ʑ��ΐ����_�Ɋ�Â��Ę_������B�@ |
|
| ���A�C���V���^�C�����Ăǂ�Ȑl�H | |
|
�A�C���V���^�C���̃C���[�W�Ƃ����u�e���݂₷�����ڂ��v���グ����B�ނ̓t�H�g�W�F�j�b�N(photogenic�F�ʐ^����̂悢)�Ȃ̂��낤�B�ł��{���ɁA�e���݂₷���l�������̂��낤���B
����Ȉ�b������B ������A����q�����A�u�ߏ��ɗL���Ȑ��w�̐搶���Z��ł���v�ƕ����āA�����������̐��w�̐搶(���̓A�C���V���^�C��)�̂��Ƃ�K�ˁA�Z���̏h�����`���Ă�������B�{���ɁA����Ȃ��Ƃ��������̂��ǂ����͕�����Ȃ��B �l�ԒN�����A�����ʂƈ����ʂ��������킹�Ă���Ǝv���邪�A�A�C���V���^�C���̏ꍇ�������ł���B�@ �܂��A�����ʂƂ��ẮA�ȉ��̂��Ƃ��������悤�B�@ ���ނ́A�w�͉Ƃł������B�ނ́w��ʑ��ΐ����_�x�̊�����A�����ɑł����݂����Ė����������������A���ڂ����ς��قǂ̑�a�������Ă���B ���ނɂ́A���[���A�̃Z���X���������A�ȉ��́A1921�N�A�A�C���V���^�C���̃A�����J���K��̍ۂ̃j���[���[�N�`�ł̐V���L�҂Ƃ̂��Ƃ�ł���B �L�� / ���ΐ����_�̓��e������Ő�������Ƃǂ��Ȃ�܂����B �A�C���V���^�C�� / �����A���Ȃ����A���̕Ԏ����A���܂肭���܂��߂ɍl���Ȃ��ŁA��k�����ł����Ă�������Ȃ�A���͎��̂悤�ɓ����邱�Ƃ��ł��܂��B���܂ł̗��_�ł́A�����F������A���ׂĂ̕��������������Ă��܂����Ƃ��Ă��A�Ȃ����ԂƋ�Ԃ͎c���Ă���Ƃ���Ă��܂������A���ΐ����_�ɂ��A�����F������A���ׂĂ̕��������������Ă��܂��A���ԂƋ�Ԃ�����ƈꏏ�ɏ��������Ă��܂��̂ł��B �L�� / ���ΐ����_��{���ɗ������邱�Ƃ��ł���l�́A���E���ɏ\���l�������Ȃ��Ƃ������Ƃł����A����͂ق�Ƃ��ł���(���F�A�C���V���^�C���́A��ʑ��ΐ����_�̍Ō�̌��e���o�ŎЂɓn�����Ƃ��Ɂw����𗝉��ł���l���͐��E����12�l��葽���Ȃ��x�Ƃ������Ƃ��A����Ȃ������Ƃ�)�B �A�C���V���^�C�� / ���ΐ����_�̐����������������w�҂͂���ł�����𗝉�����ł��傤�B���Ɏ������ΐ����_���u�`�����x��������w�̊w���́A�݂�Ȃ�����A�悭�������Ă܂����B �L�� / ��ʑ�O�ɂ́A�Ƃ��Ă������ł��Ȃ��悤�ȍ��x�̕����w�̗��_�ɑ��āA��ʑ�O���A�������M���I�ɂȂ�̂͂Ȃ��ł��傤�B �A�C���V���^�C�� / ����͐��_�a���w�̖��ł��傤�B �����̎��₪�悤�₭�I������Ƃ���ŁA �A�C���V���^�C�� / ���ɑ��鎎���́A����ō��i�ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B ���ނ́A���E���̐l�X���犽�}�����悤�ȓƓ��̕��͋C�����l���ł������B�@ �����A�����ʂƂ��ẮA�ȉ��̂��Ƃ��������悤�B�@ ���ނ̔���ƌ��̈����B �o�[�i�[�h�E�V���[(���̐l�����̈������L��) / �킪�e���Ȃ�A�C���V���^�C���N�A���݂͂��݂̏������Ƃ��A�ق�Ƃ��ɁA�悭�������Ă���̂��ˁB�ЂƂ����Ɍ����Ă݂Ă���ˁB �A�C���V���^�C�� / ���Ȃ����A���Ȃ��̏������̂𗝉����Ă�������x�ɂ͂ˁA�o�[�i�[�h����B ���ނ́u���v������ --- ����͂܂��A�����ʂł����� --- �m���ɁA������Ȃ��Ɓu��ʑ��ΐ����_�v�݂����ȑ�d�����ƂĂ������ł��Ȃ��������낤�B�ނ͂܂��A���ɂ����U�̍Ō��30�N(30�N���̊�)���u����ꗝ�_�v�̌����ɔ�₵�A���̓V�˂̎��ԂƘJ�͂��g���ʂ��������A���̐��ʂ����邱�Ƃ͂Ȃ������B�����āA�ނ́A�u�ʎq�͊w�v���A�Ō�܂ŔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��������A����́A�{�l���F�߂邪���������B ���ނɂ͌Ǎ��Ȃ�������---�A�C���V���^�C���H���u���́A�P�Ƃő��鑕���������n�̂悤�Ȃ��̂ł��B���Ă�W�c�͂��߂Ȃ�ł��v�ނ͉Ȋw�҂Ƃ��Ă͌Ǘ��I�ł������B�����āA�����炭�l�ԓI�ɂ������������B ���ނ͎����̗��_����ɐ������Ǝv���Ă��� --- �ނ͈�ʑ��ΐ����_���A�F�����H�̊ϑ��ɂ���ďؖ����ꂽ�Ƃ��A��������Ă���B�w�C�M���X�̊ϑ������A���Ƃ��������Ȃ������Ƃ��Ă��A���͂����_���C�̓ł��Ǝv�������ł��B���̗��_�͐������̂ł��B��ʑ��ΐ����_�́A�ԈႢ�Ƃ���ɂ͂��܂�ɔ��������܂��B�ϑ����ʂƖ�������͂�������܂���x--- �ނ͂܂��A�ʎq�͊w�Ƃ̘_���̒��Ř����ɂ��w�_�̓T�C�R�����ӂ�Ȃ��x�Ƃ������t���͂��Ă���B ���ނ́A���a��`�҂Ƃ��Ă͎��Ȗ������Ă��� --- �Ȃ��Ȃ�ނ́A���[�Y�x���g�哝�̈��̌����J���𑣂��莆�ɃT�C�������B ���ނ͉Ƒ��ɗ₽������ --- �ނ͓�x�������A��x�Ƃ����s���Ă���B�ނ́A�Ȋw�̒T���̂��߂ɂ́A�Ƒ���������݂��A�Ƒ����]���ɂ����G�S�C�X�g�ł������B�u���͗\���s�\�̐l�ԊW����g�������A�Ǘ�����邷�ׂ��w�т܂����B�l���́A���f����A������݂��肪�����Ă����܂��B�Ƃ��ɁA�����Ȃǂ́c�v �A�C���V���^�C���́A20���I���\����V�� --- �_����m�b�������������҂ł���A�������A�w�͂̐l�������B�܂��A�펯�ɂƂ���Ȃ����R�l�ł���A�ϐl�ł��������B�����āA�A�C���V���^�C���́A�X�s�m�U�̐_�A�܂�F�����̂��̂�_�Ƃ��ĐM���Ă����B �@ |
|
| ���������� | |
|
�u224�ԁB�E����(���F�~�����w�����琼�֖�130km)�A3��15���A1879�N�B�{���A���l�w���}���E�A�C���V���^�C���A�Z���E�����s�o���z�t�ʂ�135�A�M���_�����A�l�I�ɂ͒m���Ă���A�͉��ɏ�������o�^���̑O�Ɍ���A�j�q�̏o�����������B���O�̓A���o�[�g�A�E�����̔ނ̏Z���Ő��܂�A��e�̓p�E���[�l�E�A�C���V���^�C���A�����R�b�z�A���_�����̂��Ƃɐ��܂ꂽ�B3��14���A1879�N�A�ߑO11��30���B�Ǘ��A�m�F�A�����F�w���}���E�A�C���V���^�C���B�o�^���A�n���g�}���B�v
1944�N�A�o���z�t�ʂ�̉Ƃ͋�P�Ŕj�ꂽ���A�o���ؖ����͍��ł��E���������قŌ����o�����B�A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���́A1879�N3��14���ߑO11��30���A�h�C�c�̏��s�s�E�����ɐ��܂ꂽ(1999�N�����a120�N�ɓ�����)�B�A���o�[�g�̓w���}���ƃp�E���[�l�̓�l�̎q���̂����ŏ��̎q���ł������B1881�N11��18���A�ނ�̖��A�܂�A���o�[�g�̖��A�}�������܂ꂽ�B��l�͒��̗ǂ��Z���������B(���F���̎ʐ^�͖��}���ƃA�C���V���^�C��) �A�C���V���^�C���Ƃ́u������`�˓I�X���v(�܂�A���_���l�ł���Ȃ���A�h�C�c�l�ɓ������悤�Ƃ���X��)�������Ă����B�A���o�[�g�́A�b���n�߂�܂łɈُ�Ɏ��Ԃ����������̂Łu�m�b�x��v���Ƃ͂��߂͐S�z���ꂽ�B�������A��ɂ́A���̐S�z�͂����ɏ����������B ���e�w���}���́A�H���ԂƂ�̏��������Ă����B�A���o�[�g�Ɨ��e�̊W�͒��a�̂Ƃꂽ�A����ӂ����̂ł���A��e���A��苭�����i������Ă����B�ޏ��͍˔\����s�A�j�X�g�ʼnƒ���ɉ��y���������݁A�q�������̉��y����͑�������n�܂����B�}���̓s�A�m���t���K�����B�A���o�[�g��6�ˍ�����13�ˍ��܂Ńo�C�I�����̎w�������B�o�C�I�����͔ނ̑�D���Ȋy��ƂȂ����B���Ȃ݂ɁA�A�C���V���^�C���̍D���ȍ�ȉƂ́A�V���[�x���g�A���[�c�@���g�A�o�b�n�A�r�o���f�B�A�R���b���A�X�J�����b�e�B�ł���A�x�[�g�[�x���̏d�����I�ȕ����ɂ͎䂩��Ȃ������B�u���[���X�͓��ɍD���ł͂Ȃ��A���[�O�i�[�͌����������B���łɁA�ނ̍D���ȉ�Ƃ́A�W���b�g�A�t���E�A���W�F���R�A�s�G���E�f���E�t�����`�F�X�J�A�����u�����g�ŁA�L���[�r�Y���A���ۊG��ɂ͖��S�ł������B ����ɁA�ނ��D���w�ɂ��Ă������Ă������B�A�u���n���E�p�C�X�͎��̂悤�ɋL���Ă���B�u���w�ɂ��ẴA�C���V���^�C���̏K���ƍD�݂ɂ��Ă͎��́A�͂����肵���`���������Ă��Ȃ��B���̃��X�g�͔ނ̍D��Ƃ��肠���肵�����ɕ��ׂ����̂ł��邪�A�ǂ̂��炢���S���A�ǂ̂��炢��\�I�Ȃ��̂ł��邩�͕s���ł���B�n�C�l�A�A�i�g�[���E�t�����X�A�o���U�b�N�A�h�X�g�G�[�t�X�L�[(�w�J���}�[�]�t�̌Z��x)�A���W�[���A�f�B�b�P���Y�A���[�Q�����t�A�g���X�g�C(���b)�A�J�U���c�A�L�X�A�u���q�g(�w�K�����C�̐��U�x)�A�u���b�z(�w���B���M���E�X�̎��x)�A�K���W�[(�����`)�A�S�[���L�[�A�n�[�V�[(�w�A�_�m�̏��x)�A�t�@���E���[��(�w�����u�����g�̐��U�Ǝ���x)�A���C�N(�w��O�̎��ŕ����x)�v ���w���}���E�A�C���V���^�C���́A����C�̂Ȃ��S�̂₳�����A�����Ăǂ��炩�Ƃ����Ǝg�I�Ȑl�ԂŁA���ׂĂ̒m�l���爤����A���w���D�݁A�[���ɂ́A�悭�V���[��n�C�l���Ƒ��ɘN�ǂ��Ă��������B�w���}���̒�A���R�u�f������́A���w�̖����o���Ă��ꂽ�B���������Ɓu(�A���o�[�g)���N�͐[���K�����𖡂�����v�B�A���o�[�g��10�˂���15�˂܂ŋK���I�ɉƒ��K���}�b�N�X�E�^�����[�g���A�ނ̋���ɏd�v�ȍv���������B�^�����[�g�́A�n�R�Ȉ�w���ŁA���T�ؗj���A��A�A�C���V���^�C���Ƃ̗[�H�ɂ���Ă����B�ނ́A�A���o�[�g�ɉȊw�̒ʑ�����ǂ܂��A��ɁA�J���g�̒�����^�����B��l�́A�Ȋw�ƓN�w��_���ĉ����Ԃ��߂������B�A���o�[�g�͂܂��A�������g�Ő��w�̕��𑱂����B12�˂̂Ƃ��A�ނ̓��[�N���b�h�ɂ��Ă̏����Ȗ{����������B��ɔނ́A���̖{��_���Ȋ̖{�ƌĂ�ł���B�u���̓��e�̖��𐫂Ɗm�����́A���Ɍ����\���悤�̂Ȃ���ۂ�^�����B�v12�˂���16�˂܂ŁA�ނ͓Ɗw�Ŕ����Ɛϕ����w�B �w���}���̉H���ԂƂ�̎��Ƃ͂��܂萬�������Ƃ͂����Ȃ������B�A���o�[�g�̒a���̂��炭��ɁA�w���}���̒탄�R�u(���ƉƓI�Ő��͓I�Ȓ킾����)�́A�~�����w���ŁA�����ȃK�X�����H���X���n�߂悤�ƒ�Ă����B�w���}���́A������������A�����ƍȃp�E���[�l�̎��Y�̑啔�������̎��Ƃɓ������邱�ƂɂȂ����B1880�N(�A���o�[�g1�˂̂Ƃ�)�ɁA�w���}���Ƃ��̉Ƒ��̓~�����w���Ɉڂ����B����2�`3�N��A���R�u�͂����Ƒ傫�Ȗ�S�������āA�~�����w���̔��d���ƏƖ��V�X�e���p�̔��d�@�A�A�[�N���A�d�C���葕�u������d�@�H����n�߂悤�ƒ�Ă����B�����̌v���1885�N�A�Ƒ�����́A���Ƀp�E���[�l�̕��e����̎��������ɂ���Ď�������A���̉�Ђ�1885�N5��6���ɐ����ɓo�L���ꂽ�B �A�C���V���^�C���̉�z�u4�˂�5�˂̍��A���́A�R���p�X�������Ă���܂����B�ǂ�Ȃɓ������Ă��j�͏�Ɉ��̕��p�������Ă��܂��B������ŏ��Ɍ����Ƃ��A�R���p�X������قNJm���ȓ���������Ƃ����������A���E�ɑ��鎄�̍l������ς��܂����B����܂Ŏ��́A�������̂����ɂ́A����ɐG��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂����B�������A���̏u�ԁA �����̔w��ɂ͐[���B���ꂽ�������A���݂���͂����Ƃ������ƂɋC�������̂ł��B�v ��߂������̉����Ƃ́u�d���C�v�ƌĂ����̂������B���R�E�ɂ���A��{�I�ȗ͂Ƃ��Ă̓d���C�̔����́A19���I�����w�ɂ�����ő�̐i���ł���A�܂��Ȃ��傫�ȋZ�p�v���������炷���ƂɂȂ����B�@ |
|
| ���Ⴋ���̃A�C���V���^�C�� �@ | |
|
5�˂̎��A�ނ͉ƒ�ŏ��߂ċ�������B���̑}�b�́A�A�C���V���^�C�����ᛂ��������āA�ƒ닳�t�Ɉ֎q�𓊂������̂ŁA���̏�ŏI�����������B6�˂ɂȂ��Ĕނ͍����w�Z(Grundschule)(���F���{�̏��w�Z�ɂ�����@������4�N��)�ɓ��w�����B�ނ́A�M���ł���A�����Ȃ������i�ގ����ŁA���w�̖���[�����Ȃ�����������A�v�Z�ԈႢ���Ȃ������킯�ł͂Ȃ������B�ނ̐��т͗ǂ������B1886�N8��(�A�C���V���^�C��7��)�A��p�E���[�l�͔ޏ��̕�e�ɏ����Ă���w���̂��A���o�[�g�͐��т����炢�܂����B�܂����т͈�ԂŁA�ނ̒ʐM��͂��炵�����̂ł����B�x�������A�A���o�[�g�͈ˑR�Ƃ��ĐÂ��Ȏq���ŁA�w�Z�F�����ƈꏏ�ɗV�Ԃ��Ƃɂ͊S���Ȃ������B�ނ̈�l����̃Q�[���͔E�ςƂ˂��K�v�Ƃ��Ă����B�J�[�h�ʼnƂ�����̂����C�ɓ���̈�������B
1888�N10��(�܂�9�˂̂Ƃ�)�A�����w�Z����A���C�g�|���g�E�M���i�W�E��(���FGymnasium�F�����������w�Z�BGrundschule�l�N�ԏI���㎎�����Ă͂���B9�N���A���Ƃ���Ƒ�w���w���i��������) �ɓ��w�����B �~�����w������̘b�ŃA�C���V���^�C�����A���x���悭��@���Ō�����b������B��̃M���i�W�E���ŁA���鋳�t���A�A�C���V���^�C���Ɍ������āu�����A���݂��N���X�ɂ��Ȃ�����������ƍK�����낤�Ɂv�ƌ������B�A�C���V���^�C���͓������B�u���͉����������Ƃ����Ă��܂���B�v�搶�̓����́u����͂��̂Ƃ��肾�B���������݂͂�����̗�̂����ɍ����āA�ɂ�ɂ₵�Ă��邪�A����͎����A�N���X�S�̂��瓾��K�v�����鑸�h�̔O���������Ă���̂��B�v ���N����̃A�C���V���^�C���ɂ��Ă̘b���W�߂Ă݂�ƁA�ނ̍ł������I�ȂЂƂƂȂ肪�A��V�I�ȂłȂ��A�����̂��̂ł��邱�Ƃ��A���ɂ悭������Ă���B���̎q�́A�b���n�߂͒x���������A���w�Z�ł͈�ԂɂȂ����B�ނ̐��т����������ƍL���M�����Ă��邪�A����͍������Ȃ��B���̎q�͐��l���āA�����Â��Ȍ`�������o�āA������Ȋw�I�Ȑ����𐬂��������B�����ɍ����āA�ɂ�ɂ₵�Ă������N���A�V�l�ɂȂ��āA�u�w�I�b�y���n�C�}�[����(���A�A�����J�̊j�J���ɔ������I�b�y���n�C�}�[�̓X�p�C�e�^�ŃA�����J���{���獐�����ꂽ)�x����舵�����ǎ҂͔n�����v�ƍl���ď�������B�ӔN�ɂ́A�ނ̕��a��`�I�Ȋm�M�̂������ŁA�ǂ�Ȍ��Ў҂ɂ��A�͋������̔����������B�������A�ނ̌l�I����щȊw��̍s�ׂɂ����ẮA�ނ͌��Ђɒ�R����d���l�ł��A�܂��A���Ђ�]�����悤�Ƃ���v���Ƃł��Ȃ������B�ނ���A�ނ͔��Ɏ��R�ł������̂ŁA�����ȊO�̂����Ȃ�`�̌��Ђ��A�ނɂƂ��Ă͔n�����Č������̂ł���B�ʂ̌��ɂ��Ă����A�ނ̒Z���@���I�M�������Ղ��c���Ȃ������̂Ɠ����悤�ɁA��N�A�ނ́A�����A����Ȋw�I�l�����ɋɓx�ɔM�����A���ꂩ��A��������ʂ��c�����̂Ă��̂ł���B�����̏@���I�M�����Ԃɂ��āA�A�C���V���^�C�����g�͌�ɁA���������Ă���B�u�t���̂��̎���ꂽ�@���I�y���́w�B��ҁx����A�����g��������邽�߂̍ŏ��̎��݂��������Ƃ��A���ɂ͖��炩�ł���B�v���̗~���͔ނ̐��U�ɂ킽���đ������B60�Α�ɂȂ��āA�ނ͎������A�g���S���Ȋw�ɔ���n�����Ƃɂ���āA�w���x����сw�����x����w����x�ւƓ��ꂽ�̂��Ƃ��������Ƃ�����B�������A�ނ͎������g�Ƒ��̐l�����Ƃ̊Ԃɋ�����u�����Ƃ����̂ł͂Ȃ������B�l�Ɨ���邱�Ƃ́A�ނ̐S�̓����̂��Ƃł���A���̂������ŁA�ނ͎v���̒��ɖ�����Đl��������ʂ����Ƃ��ł����B�������A���̐l���ɂ��āA���Ƃɔ�}�Ǝv����̂́A�������Ȃ���A�����ɔނ��A���E�ƐڐG��f�����킯�ł͂Ȃ��A�܂����E���璴�R�Ƃ��Ă����킯�ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł���B ������́A�����čł��d�v�ȃA�C���V���^�C���̐��i�́A��l�ŐÂ��ɗV��ł���q�ǂ��̒��ɂ��łɖ��炩�ł���B���Ȃ킿�ނ́w���E�x�ł���B���̂��Ƃ͂܂��A�ƒ�ł̌o���̕����A�����̊w�Z��������d�v���������ƂɌ��邱�Ƃ��ł��邵�A�܂��w������A�Ɗw�������ł̎��Ƃ��D�悵�����ƁA�x�����̓����ǎ���ɁA�����w�ҎЉ�ƂقƂ�njl�I�ȐڐG�Ȃ��ɁA�ނ̍ł��n���I�������s�������Ƃɂ����邱�Ƃ��ł��邾�낤�B����͂܂��A���̐l�Ԃ⌠�Ђɑ���W�ɂ����Ă�������Ă���B�w���E�x�͂܂��A�ނ̂Ђ��ނ��ȓƗ͂̌����A�ł������Ȃ̂́A���ꑊ�ΐ����_�����ʑ��ΐ����_�ւ̔ނ̉ߒ��ł��A�悭�ނɖ𗧂����B���̐����͂܂��A�ނ̌㔼���ɂ����Ă����m�ł����āA�ނ͗ʎq�͊w�ɑ��č��{�I�ɉ��^�I�ł��葱�����̂������B�Ō�ɁA�w���E�x�́A�ނɂƂ��āA�`���ƃJ���X�}�ɋQ�������E����A�ނ̑�ȃv���C�o�V�[����邽�߂Ɏ��ۏ�K�v�Ȃ��Ƃł������B �~�����w������ɖ߂낤�B1894�N(15�˂̂Ƃ�)�A�h�C�c�ł̋����ɔs�ꂽ���w���}���́A�H����C�^���A�̃p���B�A(�~���m������40km)�Ɉڂ���Ƃ������z�����B�����A�w�Z�̂���A���o�[�g�����́A�ЂƂ�Ń~�����w���Ɏc�����B �A�C���V���^�C���̉�z�u���̓~�����w���̊w�Z���A����ł��܂�܂���ł����B���i�ȋK���ƌ��Ў�`�B���t�͌R�l�̂悤�ɁA�ނ���U����āA�����g�܂��܂��B���͓����o�����@��T�����߁A����ƌ��������܂����B�܂�A���ƍ��ӂ�������҂̂Ƃ���Ɍ����āA��ʂ̐f�f����������Ă����̂ł��B���́A�_�o����ɋꂵ�݁A�����ɂ��w�Z�𗣂��K�v������Ƃ������e�ł����B�v �����Ԃ��Ȃ��h�C�c�鍑�̌R����`����́A���R�ɂ���舒B(��������)�ȃA�C���V���^�C�����N�̋C���ɂ͍���Ȃ������B �A�C���V���^�C���́A�A���������ˑR�A�C�^���A�́u�p���B�A�v�̉Ƃ̌��ւɌ���A���e�ɁA���������������ł���B�u�S�z���Ȃ��ł���A���Q�҂ɂȂ����͂Ȃ�����B�ڂ��ɂ́A�����ƌv�悪����B�v���ꂪ�A15�˂̂Ƃ�����������ł���B�ɂ��ẮA�����Ԃ����肵�Ă����B(���̎ʐ^�F15�˂̃A�C���V���^�C��) ���[���b�p�ł��ō��̃��x�����ւ�A�X�C�X�́u�`���[���b�q�A�M�H�ȑ�w(Eidgenössische Technische Hochschule, ETH)�v�ɐi�ނ̂��A�ނ̌v�悾�����B�h�C�c�́u�M���i�W�E���v��������ƏI���Ă���A�������œ��ꂽ�̂����A�r���ł�߂Ă��܂������߁A���w������˔j���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����̃A�C���V���^�C���́A���Ə؏����A����ɍ��Ђ��Ȃ������B������邽�߁A�h�C�c���Ђ���������Ă����̂������B���ǁA��w�̓����͕s���i������(���w�ɂ����Ă͗D�G�Ȑ��т����������A�����Ɠ����ƐA���Ŏv�킵���_�������Ȃ�����)�B�A�C���V���^�C���́A���e�̂����߂������āA�X�C�X�̃A�[���E�Ƃ������̃M���i�W�E���ɕғ����邱�Ƃɂ����B����́A���܂ł͂Ȃ����ւ̑����������B�A�[���E�̃M���i�W�E���́A�����ꂽ����V�X�e���������A�ŐV�̕����w�������������Ă����B���̌������ŁA�A�C���V���^�C���͓d�C�Z�p�̔w��ɂ���A�����@���̑��݂��A�͂��߂Ċm�F�����B�ނ́A�R���p�X�̐j��d�r�Ɠd���ɋ߂Â��A�d�������E��U���ł��邱�Ƃ��m���߂��B���̓�Ƃ��A�d���C�ƌĂ�铯�����ۂ́A���ꂼ��̑��ʂł���B�܂��A�ނ́A�P���Ȗ_�����g���āA���S�����͐��ɉ����ďW�܂�`���p�^�[�������������肵���B�����āA�A�C���V���^�C���́A�u���v�Ƃ������̂��A��Ԃ��ړ�����d���g�ł��邱�Ƃ�������ꂽ�B�@ |
|
| ���~���[�o�Ƃ̏o� | |
|
�X�C�X�̃A�[���E�̃M���i�W�E�������Ƃ����A�C���V���^�C���́A�`���[���b�q�ɂ���O��́u�`���[���b�q�A�M�H�ȑ�w(ETH)�v�ɓ��w�����B�uETH�v�́A���[���b�p���w�̍H�Ȍn��w�ł���A�����ݔ����ō��ɏ[�����Ă����B�������A�A�C���V���^�C���́A���܂�M�S�Ȋw���ł͂Ȃ��A���C�ɓ���̃J�t�F�ɓ���Z�肾�����B
�A�C���V���^�C���̉�z�u�V����������@���A��҂̍D��S�����S�ɉ����Ԃ��Ȃ������̂́A�܂��Ɋ�Ղł��B������D��S�Ƃ����A���̑@�ׂȐA���́A�h����ʂɂ���A��Ɏ��R��{���ɂ��Ĉ�̂ł��̂ł�����B�v�A�C���V���^�C���́A�R�[�q�[��������Ȃ���A�����Ԃ��N���X���[�g�ƌ�荇�����B���̒��ɁA�����R�[�X��I��ł��鏗�q�w���������B�ޏ��̖��O�́A�~���[�o�E�}���b�`�B�����A�uETH�v�̓��[���b�p�ł������Ȃ��A�����ɂ���˂��J���Ă����w�������B���т���ϗǂ������~���[�o�́A�n���K���[���炱�̑�w�ɓ��w���Ă����B�����āA�A�C���V���^�C���Ɠ��������̋��E�ے��Ŋw��ł����̂��B�ނɂƂ��āA�~���[�o�͖��̑̌��҂������̂����m��Ȃ��B�Ƒ��̑����͂Ȃ��A�������Ă��āA�A�C���V���^�C�������A�����Ǝ��R�������̂ł���B�A���o�[�g�ƃ~���[�o�́A�������ɁA���������͓����^�C�v�̐l�Ԃ��ƍl����悤�ɂȂ����B�����̃A�C���V���^�C���ɂƂ��āA�~���[�o�ƂƂ��Ɋw�сA�̂قƂ������A�����āA�����w�ɂ��čl����̂́A�ǂ���������炢��Ȃ��Ƃ������B�@ |
|
| ���w������̃A�C���V���^�C���̐��� | |
|
�w������̃A�C���V���^�C���̎p�́A�ŐV�̌����ł����炩�ɂȂ��Ă���B�uETH�v�̋L�^���c���Ă���B�ނ�3�N�̂Ƃ��ɁA�����[�����Ƃ��N�����Ă���B1899�N��3���A��w���ǂ́A�����Ɋw���̃A�C���V���^�C�������ӂ����B���R�́A�Εׂ��̌��@�ƂȂ��Ă���B����́A�܂�A�C���V���^�C���������������ł̎�����ӂ��Ă����ƌ������Ƃ��B���̏؋��ɐ��ѕ\������ƁA���ɂ͂�����A�����������ł̎����́A�Œ�̐��сu1�v�Ə�����Ă���B�Ƃ��낪�����N�A�u�d�C�Z�p�v�̌����ł́A�D�G�Ȑ��т́u6�v���Ƃ��Ă���B�������łɁA�A�C���V���^�C���́A�����̍D���ȕ��삾���ɏ�M���X���A���̑��̕���́A���������������Ă������Ƃ�������B
�����Ƃ�A�����Ɍ�����A�C���V���^�C���̑ԓx�́A�Ƃ��Ƀg���u���B��w�̕����w�����A�n�C�����b�q�E�E�F�[�o�[�͂����������Ɠ`�����Ă���B�u���݂͌����q���A�A�C���V���^�C���B���Ɍ����B�������A���݂͒N�̌������Ƃ������Ȃ��Ƃ����傫�Ȍ����A�������Ă���B�v �A�C���V���^�C���̉�z�u������́A�E�F�[�o�[�̌������ƂȂ����܂���ł����B���̐l�̂��Ă��镨���w�́A70�N�O�̂��̂ł��B�����A�����̎����̂��Ƃ�b�����Ƃ��Ă��A���̐l�͎���݂��Ȃ��B�K���ɂ����炤�̂��őP�̍�ł����B�v 1912�N�ɃE�F�[�o�[�����ʂƁA�A�C���V���^�C���͗F�l�ɁA����߂ĔނɂƂ��ĈٗႾ���u�E�F�[�o�[�̎��́wETH�x�̂��߂ɂȂ�v�Ə����Ă���B�@ |
|
| ���A�E����сu�A�J�f�~�[�E�I�����s�A�v | |
|
�uETH�v�ɂ�����A�A�C���V���^�C���̍ŏI�I�Ȑ��т́A���_�����w�A���������w�A�V���w�ɂ��āu5�v�A���_�u5.5�v�A�M�`���ɂ��Ă̏��_���u4.5�v�A(���Â���ō��_��6)�ł������B�������A�F�l�̃}���Z���E�O���X�}�����A���ꂢ�Ȋ��S�ɐ������ꂽ�u�`�m�[�g���A�݂��Ă��ꂽ���A�ł������B
1900�N8��(�A���o�[�g21��)�A�A�C���V���^�C���͑�w�𑲋Ƃ��A��勳�t�̎��i���A����3�l�̒��Ԃƈꏏ�ɂƂ����B����3�l�͂��ꂼ��uETH�v�̏���̒n�ʂ��������ɗ^����ꂽ�B5�l�ڂ̊w���A�~���[�o�́A���Ǝ����ɍ��i���Ȃ������B�����āA�A�C���V���^�C�����g�́A�E���Ȃ������B����́A�A�C���V���^�C���ɂƂ��Ď�ɂ����Ƃ������B�E�F�[�o�[���A����̐E����Ă����̂ɁA���̖�j�����B(�E�F�[�o�[�Ƃ̑Η����킴�킢�����̂��B)�A�C���V���^�C���́A�E�F�[�o�[�������ċ����Ȃ������B �������Ƃ͏d�Ȃ�A�C�^���A�̃p���B�A�ł́A���e�̉�Ђ��|�Y�����B�A�C���V���^�C���́A�K���Ŏd����T���B�������Ȃ�Ƃ��Ă��K�v�������B���e�w���}�������q�̏A�E�ɗ͂�s�������B���̂悤�Ȏ莆���c���Ă���B �u�q�[�@�����@���q�̂��߂ɁA���肢�ɏオ��}�X�������e���A�ǂ����������������B���q�́A�E�̂Ȃ����݂̏�[���Q���Ă���܂��B���⎩���ɂ́A���̊�]���Ȃ��Ƃ����v�������ɓ��ɋ��܂�A����ɁA���q�͍��̖͂R�����Ƒ��ɂƂ��āA�����͏d�ׂȂ̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ����s���ɂ����Ȃ܂�Ă��܂��B�����A���q�ɏ���̎d���������Ē�����A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B�@�w���}���E�A�C���V���^�C���v �A�C���V���^�C���́A�k�͖k�C����A��̓C�^���A�̓�[�܂ŁA�����镨���w�҂ɗ��s�����āA�A�E���̖₢���킹�������B�ǂ��Ԏ��͈���Ȃ������B�������A����ƁA�A�C���V���^�C���́A�Վ��̐E���������B1901�N5��19������A�ނ̓��B���^�[�c�[���̍����w�Z��2�����Ԃ̑㗝�����ƂȂ����B���B���^�[�c�[���̌�A������Վ��E����������ł����B1901�N9������1�N�ԁA�V���t�n�E�[���̎����w�Z�ɔC�p���ꂽ�B ����A1900�N���A�F�l�̃}���Z���E�O���X�}�����A�Ƒ��ɃA�C���V���^�C���̖��E�̏�Ԃɂ��āA�b�������Ƃ��K�������B���̘b���āA�O���X�}���̕��e�̓x�����̘A�M�����ǒ����t���[�h���q�E�n���[�ɁA�A�C���V���^�C���𐄑E�����B�A�C���V���^�C���́A���̐�����[�����ӂ����B���̌��́A1901�N12��1���ɂȂ��ē����ǂ̋�Ȃ��X�C�X�A�M����ɍL�������ɋy��Ŏ������邱�ƂɂȂ����B�A�C���V���^�C���́A�����ɉ���̎莆�𑗂����B�r���ň�x�A�ނ̓n���[�̖ʐڂ����B�����炭�ނ͂��̂Ƃ��A�̗p�̉��炩�̕ۏ����̂ł��낤�B������ɂ���A�ނ̓V���t�n�E�[���̐E�����߁A�C�p�����O�ł͂��������A1902�N2���ɃX�C�X�̎�s�x�����ɗ����������B���ߔނ͉Ƒ�����̏��Ȃ��d����ƁA���w����ѕ����w�̉ƒ닳�t�̎����Ő��v�𗧂Ă��B�ނ̋����q�̈�l�͔ނ��A���̂悤�ɋL�q�����B �u�w��(�g��)�͖�5�t�B�[�g10�C���`(1.76m)�ŁA�����͂Ђ낭�A�����O�����݂ŁA�����̕��A���\�I�Ȍ����A�����Ђ�������A�@�͏����킵�@�ŁA�P�����F�̊�A�������A�t�����X��𐳂����b���������a�肪����B�v ���[���X�E�\�����B�[�k�Əo������̂͂��̎����ł���B�u�P�ǂȃ\���v�͏��߂͉ƒ닳�t�Ƃ��ăA�C���V���^�C���̋����q���������A�I���̗F�l�ƂȂ����B�A�C���V���^�C���A �\�����B�[�k�A����т�����l�̗F�l�A�R�����b�g�E�n�r�q�g�͒���I�ɉ�A�N�w�A�����w�A���w���A�v���g������f�B�b�P���Y�܂Ř_�����B�ނ�͌��l�Ɂu�A�J�f�~�[�E�I�����s�A�v(��̎ʐ^)�̑n���҂ŗB��̃����o�[�ł���Ɛ錾���A�ꏏ�ɐH��(�T�^�I�Ȃ̂̓\�[�Z�[�W�A�`�[�Y�A�ʕ��A�g������)�����A�T���Ă��炵�������߂������B ��������������ɁA�X�C�X�A�M�]�c��ɂ��A�C���V���^�C���̔C���̎葱�������B1902�N6��16���A�ނ͓����ǂ�3���Z�p���E�ɏA���A�N���3500�X�C�X�E�t�����ł������B �A�C���V���^�C���̉�z�u�ӊO�ł��傤���A���ɂƂ��ē����ǂ́A��w��肸���Ƃ悢�A�E���ł����B�����A��w�̐E���ɂȂ��Ă�����A�����_�����d�グ��ƁA�������ꂽ���Ƃł��傤�B�����킢�ɂ��A�����������Ƃ���͎��R��������ł��B�v�@ |
|
| �������A�����A���̎� | |
|
�u�������l��A���݂ɏo��O�A�ڂ��͈�l�ŁA�ǂ�����āA�����Ă���ꂽ�̂��낤�B���݂Ȃ��ł́A�ڂ��͎��M���Ȃ��d���ւ̏�M���A�l���ւ̂�낱�т�����͂��Ȃ��B�܂�A���݂Ȃ��ł́A�ڂ��̐l���͐l���ł͂Ȃ��B�v
�A�C���V���^�C���̃~���[�o�ւ̃��u���^�[�ł���B �u1898�N2���@�q�[�@�莆�����������Ƃ����v�������A�ŏI�I�ɁA���Ȃ��̌�������]�̖ڂɎ��������炷�܂��Ƃ������ӎ��́A�������Ă�����������Ă��܂��܂����B�v �A���o�[�g�ƃ~���[�o�͎���Ɏ��������́A�����^�C�v�̐l�Ԃ��ƍl����悤�ɂȂ�B �u1899�N8���@�ڂ������̐��_�I�����w�I�����́A�Ȃ�Ɩ��ڂȂ��Ƃ��B�ڂ������́A�������̈Â����܂������A�悭�����������B�������A�R�[�q�[���̂�A�\�[�Z�[�W��H�ׂ��肷��̂��ꏏ���B�v �A�C���V���^�C�����A�A�E���������Ă������A�~���[�o�Ƃ̗������A���e�����ɂ��n�߂�B �A�C���V���^�C���̗��e�́A�~���[�o�Ƃ̌����ɋ����������B�~���[�o�͎����������Ă����̂��B��e(���̎ʐ^)�͂����炭�A���������l�́A����{����ǂ�ŁA�H������炸�A�C�����������������Ȃ��Ƃł��������̂��낤�B�ꏏ�ɂȂ�Ȃ�A���͎��ʂȂǂƁB�܂��A��e�͂����Ă������������Ƃ��������̂����A�Ƃɂ����A�~���[�o�Ƃ̌����́A������ɔ����ꂽ�B �u1900�N7���@������l��@�ڂ��̗��e�̌��������ɂ́A�����䖝���ł��Ȃ��B���݂����Ǝ����ɗ������Ƃ��̂��Ƃ��A�ꂪ�A�w���Ȃ��̉����~���[�o�́A�Ȃ�ɂȂ����H�x�Ƃ����̂ŁA�ڂ��̍Ȃ��Ɠ����Ă�����B����ƁA��̓x�b�h�ɐg�𓊂��o���A�w���O�͎����̏�����䖳���ɂ��Ă���B�q���ł��ł��Ă����B�Ȃɂ������߂��Ⴍ�����x�ƌ����A����ŁA�ڂ��̊��E�܂̏����ꂽ�B�ڂ���̊W�J���邱�Ƃ͋����Ȃ��B�v 1901�N�̏t�A��l�͖k�C�^���A�̒��R��(�~���m�̖k��50km)�ňꎞ���߂����B���̎����́A�����̃��u���^�[����A�����ŋ߁A���炩�ɂȂ����B �u���������Ȗ�����@�R���ɗ��Ă�����B���݂ɂƂ��āA�ق�̂킸���Ȏ��Ԃ���������Ȃ����A�ڂ��ɂƂ��ẮA�V�ɂ����銽�тȂ̂�����B�������肽���邢�S�ƁA���̖����ȓ��]�������Ă��Ă�����B���炵���Ƃ���Ɉē����邩��B�v �~���[�o�̕��́A���̂悤�ɏ����c���Ă���B �u�킽���̓R���֍s�����B���̐l���r���L���A�������ǂ点�đ҂��B�����Ŕ����߂����A�~���J�����b�^(�ق̖��O)��K�ꂽ�B�����̂��ɁA�����̂��߂ɁA������l�����Ă���āA�ǂ�ȂɍK�����������Ƃ��B�������A�ނ������K���������Ă��邱�Ƃ��킩��B�v ��l���K�ꂽ�فA�~���J�����b�^�̓�����L�Ԃɂ́A�����w�G���X�ƃv�V���P�x�̒�����������Ă���B��l�����̑��߂����Ƃł��낤�B ���T�Ԍ�A�A���o�[�g�̂��ƂɁA�~���[�o���D�P�����Ƃ����m�点���͂����B���ꂩ�琔�����A�~���[�o�̓`���[���b�q�ő�w���Ƃ̎������鏀����i�߂�B�A���o�[�g�͗Վ��̋����̐E�āA�X�C�X�����т܂���Ă����B �u������l��@����������A�ꏏ�ɉȊw�̌����𑱂��悤�B���{�̂Ȃ������Ƃ��āA�N���Ƃ肽���Ȃ�����ˁB���A���݈ȊO�̐l�͂��ׂāA�ڂɌ����Ȃ��ǂ̌������ɂ���悤�ŁA�悻�悻����������B�v ��L�ŏq�ׂ��Ƃ���A�A�C���V���^�C���́A1901�N9���A�`���[���b�q�ߍx�̃V���t�n�E�[���̎����w�Z�ɗՎ��I�ɔC�p���ꂽ�B����̃~���[�o�́A�`���[���b�q���o�āA�ʂ̒��ɉB���悤�Ɉڂ�Z�B�͂��߂ɂ��A�D�P��������悤�ɂȂ��Ă������߁A�������ŁA�ނƈꏏ�ɂ���Ƃ�����A������킯�ɂ͂����Ȃ���������ł���B���C����̑��K���ό��q�ɕ���āA��l�͂Ђ����ɉ�����Ȃ������B���ǁA�~���[�o�͑��ƍĎ����ɂ����s���A�Ȋw�҂ɂȂ閲�͏������B�ޏ��́A�n���K���[�̗��e�̂��Ƃŏo�Y���邽�߁A�X�C�X���������B�A���o�[�g���A������ƏA�E���Ȃ���Γ�l�́A�����ł��Ȃ������B���炾�����̂钆�A�悤�₭�N�͂����B �u�������l��@����A�F�l�̃}���Z��(�O���X�}��)����莆�������B�ނ̘b�ɂ��ƁA�x�����̒��ł̂ڂ��̏A�E���A�{���܂�ɂȂ����炵��B��тł߂܂������������B�ł��A�����Ƃڂ������A���݂̊�т̕����A�傫�����낤�ˁB�v �A�C���V���^�C���͂������܁A�X�C�X�̎�s�x�����Ɍ��������B�����ǂɏA�E�����܂����̂��B �x�����ŁA�ނ��^���ɁA�����w�̌������ĊJ�������A�~���[�o�́A���e�̂��Ƃŏo�Y�����B1902�N1���̂��Ƃ������B�q���͏��̎q�Łu���[�[���v�Ɩ��t����ꂽ�B����́A�����ŋ߁A���炩�ɂȂ��������ł���B���[�[�����A���܂ꂽ��ɋN������A�̏o�����́A�A�C���V���^�C���ɂƂ��āA����܂Ōo���������Ƃ̂Ȃ��傫�Ȏ����ł���A��������ɂ������炵���B�~���[�o�ɂƂ��Ă͂���ɁA�炢�̌��������ł��낤�B �A�C���V���^�C���̎莆�u������l��@���݂��]�ʂ�A���̎q�����������H�@���N���ȁH�@�����Ă���H�@����ȂɈ����Ă���̂ɁA�ڂ��͂܂�����Ă����Ȃ��ˁB�ڂ��������A�܂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����́A�ǂ�����A���[�[�����茳�ɒu���邩�Ƃ������Ƃ��B�ڂ��͂��̎q���A��Ɏ���������Ȃ��B�v �������A�X�C�X�̌������ɂȂ�������̃A�C���V���^�C���ɂƂ��āA����͐E���������˂Ȃ��X�L�����_���������B��l�́A�������ԁA���̖��Ɗi�����A���Ɍ��S�����B���[�[������������Ƃɂ����̂������B�A�C���V���^�C���́A��x�����[�[���ɉ���Ƃ͂Ȃ������B���[�[���́A�܂��Ȃ��a�C�ɂȂ�A���̌�A���ׂĂ̋L�^�������Ă���B ���[�[�������܂ꂽ�����N�A�A�C���V���^�C���́A�C�^���A�̎��ƂɋA�����B���w���}��(���̎ʐ^)���A�a�Ď��̏��ɂ������̂��B�A�C���V���^�C���ƕ��e�̊W�́A�ƂĂ����G�������B�A�C���V���^�C���́A���e�̎��Ƃ��X�����鎞���ɁA���z�̊w��S�����Ă������ƂɁA�����߈���������Ă����B�܂��A�A�C���V���^�C���́A�����͕��e�̂悤�ɁA���s�������͂Ȃ��Ǝv���A�����ł��Ȃ��������e���}�킵�����������A�N�����������e�������Ă������̂��B �A�C���V���^�C���̉�z�u���͕��̍Ŋ������Ƃ肽�������B����ŁA�����ɓ���A�����b�����܂����B���̂Ƃ����́A�����������Ă��ꂽ�̂ł��B�ł������ɁA�����s���Ă���Ƃ����āA�ǂɊ�����ނ��܂����B���̓��A���͎��ɂ܂����A��������l�ŁB�v �A�C���V���^�C���́A�ǂ����l�ԗ��ꂵ���l���Ƃ��āA�������ꂪ���ł���B�����ے肵�A���ׂĂz�����悤�Ȋ������B�������A���e�̎��́A��͂�傫�ȃV���b�N�������B����ȗ��A����2�x�Ƃ���Ȏv���͂������Ȃ��ƁA�l�����̂����m��Ȃ��B �A�C���V���^�C���̉�z�u ���ꂪ�A���ɂƂ��Ă̓]���_�ł����B�l�ԂƂ����̂́A�͂��Ȃ����݂ł����A�����������ƂɁA���܂ł��߂���Ă��Ă͂����Ȃ��ƁA���̂Ƃ�������̂ł��B���̂悤�ȃ^�C�v�̐l�Ԃ̐^���́A�l���邱�Ƃɂ���܂��B�����邱�Ƃł͂Ȃ���ł��B�v ���w���}���̎�����A���J���o����1903�N1���A�A�C���V���^�C���́A�~���[�o�ƌ��������B�@ |
|
| �����ꑊ�ΐ����_(1905�N�F��Ղ̔N) | |
|
1905�N(�A�C���V���^�C��26��)���̔N�̓A�C���V���^�C���ɂƂ��āu��Ղ̔N(miracle year)�v�ƌĂ�Ă���B���̔N�A�ނ́u���v�̗��q�Ƃ��Ă̐������瓾��ꂽ�u���ʎq�����v���q�̑��݂�T�����ē���ꂽ�u�u���E���^���̗��_�v�����āu���ꑊ�ΐ����_�v�������������̂��B
�A�u���n���E�p�C�X�́A���̂悤�Ɍ���Ă���B �u1905�N�̃A�C���V���^�C���̂悤�ɁA����قǒZ���Ԃɕ����w�̒n�����g�����l�͑O�ɂ���ɂ���l�����Ȃ��B�v �A�C���V���^�C���̉�z�u16�˂̂Ƃ��A���߂Ă��̃C���[�W�������т܂����B�w���x�ɏ������A���������ǂ�Ȃӂ��ɂȂ�̂��낤���B16�˂̎��ɓ����͌�����܂���ł������A���ꂩ��10�N�A�����₢�𑱂��܂����B�P���Ȏ��₱�����ł�����̂ł��B�܂��A���ɉ����˔\������Ƃ���A����́w���o�̂悤�ȋ���x�ł��B�v �ނ́u���v�̐����𗝉����邽�߂ɁA�l���̂��ׂĂ��₵���ƌ���Ă���B �A�C���V���^�C���́A16�˂̂Ƃ��u���ɏ��v�Ƃ����C���[�W���v�������ׂ��B����́A �ނ̓��̒��ōs����L���Ȏ���(�v�l����)�̍ŏ��̂��̂ł���B���G����܂�Ȃ��T�O�𗝉����邽�߂̔��ɒP���ȃV�i���I�B���Ƃ��A�����u���v���u�g�v�ł���Ƃ���A���ꂪ�A���Ƃ��ǂ�Ȃɑ����ړ����悤�Ƃ��A�g�̒�����J�Ԃɒǂ������Ƃ͉\�ɈႢ�Ȃ��B�u�������v�ƃA�C���V���^�C���͑�����B���̎�������������������̂��낤�B�u���v�͎~�܂��Č�����̂��B���Ԃ��~�܂��Ă��܂��̂��B�u���v�̔g�̒����ɁA�����Ə�葱�����Ƃ�����A ���������u���A�����܌�����̂��낤���B16�˂̃A�C���V���^�C���́A���������������Ȃ������B�ނ͂܂��A�P�����ꂽ�Ȋw�҂ł͂Ȃ������̂������B �u�`���[���b�q�A�M�H�ȑ�w(ETH)�v�ŁA�A�C���V���^�C�����s�����Ƃ��Ă��������́A�������́u���v�̖��Ɋւ�����̂������B�u���v�ɏ��Ƃ����C���[�W�́u���v�̑��x�ł́A���Ɋ�Ȏ��Ԃ�������ɈႢ�Ȃ��Ƃ����������琶�܂ꂽ���̂������B ������̐l�́u���v�́u�g�v�Ƃ��ē`����Ă����ƍl���Ă����B�u���v���u�g�v�Ȃ�A��Ԃ̒��ł��́u�g�v�������玟�ւƓ`����Ă������߂̕������K�v�ł���B�����A���̕����́u�G�[�e���v�ƌĂ�Ă����B�u�G�[�e���v�̑��݂́A19���I�����w�̂܂��ɓy��ł���펯�ł������B�Ȃ��Ȃ�A���ΐ����_�ȑO�̕����w�ɂ����Ắu�j���[�g���v���u���ԁv���u�G�[�e���v�ł��������炾�B �u�G�[�e���v�Ƃ��������́A�������Ԃɖ����Ă���ƍl�����Ă����B�u���v�̓��������̌o���ƈ�v�����邽�߂ɍl���o���ꂽ�̂��u�G�[�e���v�������B���ʂ̏ł���A�����͂���̂͊ȒP�ł���B���Ƃ��u�D�̑��x�v�́A�����Ȃ��݂̊Ɣ�r����A�ȒP�ɑ��邱�Ƃ��ł���B���l�ɁA�D�̃f�b�L�ɂ���u��g���v�̑��x�����邱�Ƃ��ł���B ���́u��g���v���A�w��(�ւ���)�Ɍ������ĕ����Ă���A�D�̑��x���A��⑬���A�D���Ɍ������Ă���A�D�����x���B���̒n����ł́u���x�v�͑��ΓI�Ȃ��̂ł���B���̓������̂ɑ��āA�ǂ���̕����ɓ������ɂ���āA���x�𑫂�����������肷��悢�B�������u���v���u�G�[�e���v�ɑ��ē��l�ɂӂ�܂����ǂ����́A�傫�ȓ䂾�����B�u���v�̑��x�����ΓI�ł���A�����Ȃ�����x���Ȃ����肷��̂��낤���B�����҂����́u�G�[�e���v���Ƃ���u���v�̑��x�𑪂낤�Ǝ��݂��B�n���́A���z�̎����b�����悻30km�ł܂��A�����Ɂu�G�[�e���v�̒���җ�Ȑ����œ����A�u�G�[�e���v�̕���������B�u���v�̑��x���ω�����Ȃ�A�u�G�[�e���v�̒���ǂ����Ői�ށu���v�́A���Ɂu�G�[�e���v�̒������������Ői�ށu���v���������Ȃ�͂��ł���B �������u���v�̑��x�̕ω��𑪒肷������́A�S�Ď��s�����B�ǂ̎����ł��u���v�̑��x�́A��ɓ����������̂��B�A�C���V���^�C���́A���̕����w�҂��������A�͂邩�ɑ��������Ɂu�G�[�e���v�Ƃ����l�������̂ċ����Ă����B�u�G�[�e���v�����݂��Ȃ��ƂȂ�A���̈Ӗ�����Ƃ���͈�ł���B�u���v�̑��x�͈��ł���s�ςł���B�u���v�́A�n����̏o�������x�z���邠����^���@���̗B��̗�O�Ȃ̂��B 1905�N�A�A�C���V���^�C���́A�u���v�̑��x�́u���s�ρv�ł���Ɗm�M����B�^���̖�肪�A�܂��c���Ă����B�n����ŁA�ʏ�̑��x�̉^���͂��邱�Ƃ́A���̓�����Ƃł��Ȃ��B���Ƃ��A�o�q�̌Z��̃W���O���[(juggler�F����ڂ��A�i�C�t�A�s���Ȃǂ��œ�������~�߂��肷��Ȍ|�t)������Ƃ���B����ɂ���o�q�̌Z�̃W���O���[�͓����Ă͂��Ȃ����A�D�̏�ɂ���o�q�̒�̃W���O���[�́A5�m�b�g�̑��x�œ����Ȃ���A�W���O�������Ă���B�D�̒�̃W���O���[���猩��A���Ԃ͋t�ł���B�����͓����Ă��Ȃ����A�ݕӂ̂���ɂ���Z�̃W���O���[�́A5�m�b�g�̑��x�Ō���ɓ����Ă���B���ꂪ�u���ΐ����_�v�̊�{�������B�o�q�̃W���O���[�́A�����Ă���s���̉^�����q�ׂ�̂ɁA���������@�����g�����Ƃ��ł���B�Ƃ��낪�u���v�͕ʂł���B�~�܂��Ă�W���O���[�ƁA�����Ă���W���O���[�̗������u���v���ʂ�߂��Ă��A�A�C���V���^�C���ɂ��u���v�ɑ��邻�ꂼ��̑��x�́A�܂����������Ȃ̂��B �Ȃ��A����Ȃ��ƂɂȂ�̂��낤���B�u���x�v�Ƃ́A���鎞�ԓ��ňړ����������̂��Ƃ��B�����ŃA�C���V���^�C���͋C�Â����B�u���v�̑��x���s�ςł���Ȃ�A���̉������ω����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�A�C���V���^�C���͎��⎩������B�u���v�̑��x�́A���s�ςŁA���Ԃ̗��ꂱ�����ω�����̂��B�u���Ԃ̐i�ݕ����ω�����v����͂܂��ɁA���{�����������悤�Ȕ��z�������B�A�C���V���^�C���ȊO�̂��ׂĂ̐l�ɂƂ��āA���ԂƂ͐�ΓI���s�ς̗���ł���A�����ɍ��܂��F���̌ۓ��ł������B���Ԃ̈ꍏ�݂��A�L�яk�݂�����A��炢���肷��Ƃ����l���́A�ŏ��A�A�C���V���^�C�����g�ɂƂ��Ă����A�������̂������B �A�C���V���^�C���̉�z�u��ςȓ��̂�ł����B�w���x�Ɋւ���ŏ��̋^�₩��A���́w���ΐ����_�x�ɂ��ǂ蒅���܂�10�N���������킯�ł��B�����鐸�_�I�����������蔲���A���̉ʂĂɁA�ˑR�����������т܂����B�悭���ꂽ���ł����B�F�l�̃~�P�[���E�x�b�\�ƁA�U���ɏo�����܂����B����ׂ�̂́A�����ς玄�Łw���݂̏������K�v�Ȃx�ƃx�b�\�Ɍ����Ă�����ł��B���̎��A������������ł��܂����B���́A�ق��ĉƂ삯�߂�܂����B�����A�x�b�\��K�˂āA���������܂����B�w���肪�Ƃ��B���S�ɖ�������������x�v �ǂ�ȉ����Ȃ̂��B���Ԃ��s�ςł͂Ȃ��Ƃ�����---�����Ă���l�Ǝ~�܂��Ă���l�ɂ́A���ꂼ��Ⴄ�����Ŏ��Ԃ��߂��Ă��邱�ƂɂȂ�B�A�C���V���^�C���́A��������̂悤�ȃp���h�b�N�X��p���ďؖ������B��̏o�������A���m�ɓ������_�ŋN�����Ƃ��A���ׂĂ̐l���A��������ƔF�߂邾�낤���B���͔F�߂Ȃ��̂��B�A�C���V���^�C���̓��̒��ŁA�����̕���͐��H���I�ꂽ�B���H�����ɓ�{�̖_�����āA���̊Ԃ̋����𑪂�B���ɁA���Ԃ̒n�_�������āA�����Ɉ������B�K�Ȋp�x�̂��������g���A���Ԓn�_�ɂ���ώ@�҂͓�{�̖_���A��x�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B ���āA������{�̖_�ɓ����ɗ�����A���ł�������邱�Ƃ��ł���B�ώ@�҂́A��̏o�������A�܂����������ɋN�����̂��ƔF�߂邱�Ƃł��낤�B �������A�������Ƃ��Ԃ̒����猩���ꍇ�́A�ǂ����낤�B�ނ��������������Ă���B ��{�̖_�̒��ԓ_�ɗ����Ƃ��A�����悤�ɗ���������B �����Ă���ώ@�҂ɂ́A�����ɂ͌����Ȃ��B�O���ɂ���_�ɗ����������Ɍ���̂��B�u���v�͖_���狾�܂ł̋������ړ�����̂ɁA���Ԃ�������B���̊ԂɁA��Ԃ͑O���̖_�Ɍ������Ĉړ�����B �܂�A�O���̖_����́u���v�́A�ڂɓ͂��܂ł̋������Z���Ă��ނ킯���B��������ƁA�~�܂��Ă���ώ@�҂Ɠ����Ă���ώ@�҂ł́A�������������̂��ӌ�����v���Ȃ��B���Ԃ́u���ΓI�v�Ȃ��̂Ȃ̂��B �A�C���V���^�C���̉�z�u��̕s����������܂��B���̗��_�́A���Ԃ͎��������ꂼ��ɁA��������x�ŗ���Ă���Ƃ������Ƃ������������ł��B����߂ĒP���Șb�Ȃ̂��Ɛ������Ă��A�M����l�́A�قƂ�ǂ��܂���ł����B�v ���Ԃ͕ω�����Ƃ����ŏ��̒�������A���݁u���ꑊ�ΐ����_�v�Ƃ��Ēm���銮�������`�܂Ŏ����Ă����̂�5�T�Ԃ��������B���̃A�C���V���^�C���̗��_�́A���������Γ����قǁA�Î~�����ꍇ�ɔ�ׂāA���Ԃ̗���͒x���Ȃ邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�ނ͍ŏ��̘_���ŁA�����ɂƂ��đ��ΓI�ɓ����Ă��鎞�v�́A�������猩��ƒx���Ȃ��Ă���͂����Əq�ׂĂ���B����ɁA�ԓ��ɂ��������v�Ƌɓ_���������v���ׂ�A�ԓ��̎��v�̕����A�x���Ȃ�Ƃ��q�ׂĂ���B1905�N�ɔނ͂��ׂĂ����ʂ����̂��B �M�����������Ƃ����A�Ԃɏ���Ďd���ɍs���Ƃ��́A���Ɍ������Ă���Ƃ������A���Ԃ͂������i�ށB���x���オ��ƒ������k�܂�B����50km�ő���Ԃ̒��ł́A���Ԃƒ����̕ω��́A�܂�����������Ȃ����A�����A�Ԃ��u���v�̑��x��90���̑����ő���A�����猩�Ă���҂ɂƂ��āA�����͒ʏ��44���ɏk�܂��Ă��܂��̂��B�����ŁA�悤�₭�u���v�Ɋւ���A�C���V���^�C���̍ŏ��̋^��ɓ������o��B�����u���v�ɏ�邱�Ƃ��ł����牽���N����̂��낤��---����---�����N���Ȃ�---�Ȃ��Ȃ�A����́A�s�\������B�u���v�̑��x�ɒB�����Ƃ��A�����̓[���ɏk�܂�A���Ԃ͒�~����B �ŏ��́A�قƂ�ǁA�����Ă���Ǝv����---����Ȃ��Ƃ��蓾�Ȃ��A����݂͂�Ȃł���߂�---�ƁB�������A�悭�l����Ǝ����т��A���������a���A�����̂�������Ȃ��B���ꂪ�u���ꑊ�ΐ����_�v�Ȃ̂��B 1905�N6��30���A�A�C���V���^�C���́A�h�C�c�̈ꗬ�w�p���ɁA�u�^�����镨�̂̓d���C�w�v�Ƒ肷��_���\����B���̘_���ɂ́A�Q�l�������r�����A���������t���Ă͂��Ȃ������B�A�C���V���^�C���́A�_�����M�܂łɁA�悭�b���Ă��ꂽ�F�l�~�P�[���E�x�b�\�Ɏӎ�������Ă���B�������A�ȃ~���[�o�̖��O�͏o�Ă��Ȃ��B���āA�A�C���V���^�C���ƃ~���[�o�́A�u���v�Ɖ^���̖��ɂ��Ĉꏏ�Ɍ������悤�Ɩ��Ă����B�����̎莆�ɁA���̂��Ƃ͂͂�����Ə�����Ă���B �A�C���V���^�C���̎莆�u�����q�L�����@���݂́A�ڂ��ɂƂ��Ă̐_�a�ł��B�ق��̐l�́A���̐_�a�ɋ߂Â����Ƃ͂ł��܂���B���݂͒N�����A�ڂ��������A��������ڂ��𗝉����Ă����B�ڂ������́w���ΐ��^���x�Ɋւ��錤�����A���炵�����_���Ȃ�A�ڂ��͊�тƌւ�ɖ�������邱�Ƃł��傤�B�v �u���ꑊ�ΐ����_�v�Ɋւ��āA�ȃ~���[�o�́A�ǂ̂悤�ȍv�����������B�٘_�͂��邾�낤���A�~���[�o�́A�����I�ȍv�������Ă��Ȃ��ƍl������B�ޏ��́A�A�C���V���^�C���̍l�����A�������邱�Ƃ��]���邱�Ƃ͂ł����B�������A�ޏ����g�̐V�������z�Ƃ������̂͂Ȃ������B�c���ꂽ�莆�����Ă��A�ޏ��͈�x���m�I�Ȗ�������Ă��Ȃ��B�������ē�N�A�~���[�o�̖����͕ς���Ă����B�ޏ��́A�Ǝ���q���̐��b�ɂ����Ă����̂������B �u���ꑊ�ΐ����_�v�\����4������A�lj��̒Z���_�����o���ꂽ�B�����ɂ́A���̍ł��L���Ȍ������o�ꂷ��B�uE=mc2(���̎ʐ^�̓A�C���V���^�C���̒��M)�v�����镨�̂Ɋ܂܂�邠����G�l���M�[�́A���ʁ~�u���̑��x�v�̓��Ƃ����A�r�����Ȃ������ɂȂ邱�Ƃ����炩�ɂ��ꂽ�B�킸���A1g�̕����ɂ��A����ȃG�l���M�[����߂��Ă���B�������A�����A���̃G�l���M�[�����o����Ȃ��Ȃ�A���̃G�l���M�[�́A�܂������ϑ�����Ȃ��B���傤�ǁA�����āA�������g��Ȃ���������̂悤�Ȃ��̂ł���B�ǂ�قǒ��ߍ���ł��邩�A�N�ɂ�������Ȃ��B ���E�́A�͂��߁A�A�C���V���^�C���̔����̋����ׂ��Ӗ��ɂ́A�܂������C�Â��Ȃ����̂悤�������B�����ǂɂƂ߁A�]�ɂɕ�������������26�˂̎�҂��A�F���S�̂Ɋւ���F�����A���S�ɕς��Ă��܂����̂��B �A�C���V���^�C���̉�z�u�Ȃ����ɁA���ꂪ�ł�����ł��傤�B���ʂ̑�l�͌����ė����~�܂��āw���ԁx��w��ԁx�ɂ��čl�����肵�܂���B�q���������A�����������Ƃ����܂��B���̔閧�́A�q���̂܂܂ł������Ƃł��B���́A�P������܂�Ȃ�����𑱂��Ă��܂����B�����č����A�₢�����Ă��܂��B�v�@ |
|
| �����ꑊ�ΐ����_(�����̔���) | |
|
�}���E�A�C���V���^�C���ɂ�闪�`�́A6���_�����u�����w�N��v�Ɏ��ꂽ������̌Z�̋C�����������₩�ɕ`�ʂ��Ă���B�u���̎Ⴂ�w��(�A�C���V���^�C��)�́A�L���Ȃ悭�ǂ܂��G���ւ̔��\�͂����ɒ��ڂ��W�߂邾�낤�Ǝv�����B�ނ͉s�����Ƃ��т����ᔻ�����҂����B�������ނ͂Ђǂ����]�����B�ނ̔��\�̌�ɂ͗₽�����ق��������B�����̎��̐����͔ނ̘_���̂��ƂɑS���G��Ȃ������B���ƒ��Ԃ͐ÊϓI�ԓx���Ƃ����B�_���̊��s��A���炭���āA�A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���̓x�����������ʂ̎莆��������B����͗L���ȃ}�b�N�X�E�v�����N(���̎ʐ^)���瑗��ꂽ���̂ŁA�����ɂƂ��ĕs���m�Ȃ������̓_�𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ����Ƃ߂Ă����B�����ԑ҂�����́A���ꂪ�ނ̘_�����Ƃ��������ǂ܂�Ă����Ƃ����ŏ��̂��邵�ł������B�Ⴂ�Ȋw�҂̊�т́A�ނ̊�����F�߂�m�点�������̍ō��̕����w�҂̈�l����͂����̂ŁA���ɑ傫�������B�v
���ꑊ�ΐ����_�������܂��̂����ɓ��_�E�����̃g�s�b�N�ɂȂ����̂́A�v�����N�̏����̊S�ɕ����Ƃ��낪��ł���B�v�����N�́A����̉Ȋw�I�����`�̒��ŁA�A�C���V���^�C���̗��_�ɂ���߂ċ�����������ꂽ���R���q�ׂ��B�u���ɂƂ��Ă��̗��_�̖��͂́A���̊�{�藝����A��������ΓI���s�ςȐ��_�������œw�͂��ē����o�����Ƃ��ł���Ƃ��������ł������B�v��ΐ��̒T��----�i���ɁA�v�����N�̉Ȋw��̎�v�ȖڕW�ł�����----�͐V�����œ_�����o�����B�u�ʎq�_�ɂ������p�ʎq�̂悤�ɁA�w���x�̑��x�͑��ΐ����_�̐�ΓI�Ȓ��S�_�ł���B�v1905�`6�N�̓~�w���̊ԂɁA�v�����N�̓x�������̕����R���L�E���ŃA�C���V���^�C���̗��_���Љ���B���̍u�`�ɔނ̏���t�H���E���E�G���o�Ȃ��Ă����B���̌��ʁA�t�H���E���E�G�͑��Θ_�ւ̂�����l�̏����̓]���҂ƂȂ�A1907�N�Ƀt�B�]�[�̎����ɂ��Ă̌����ȃm�[�g���o�ł��A���ꑊ�ΐ����_�Ɋւ��Ă���ɂ悢�d�������A�����ē��ꑊ�Θ_�̍ŏ��̃��m�O���t�̒��҂ɂȂ����B�v�����N���܂��A1906�N9���ɊJ�Â��ꂽ�Ȋw�W��ŁA�u���ΐ����_�v�̈Ӗ�����Ƃ��낢�����c�_�����B���Θ_�Ɋւ���ŏ��̔��m�_���́A�ނ̎w���̂��ƂɊ��������B�@ |
|
| ���x��������`���[���b�q�����ăv���n�� | |
|
1905�N�A�A�C���V���^�C���ƍȂ̃~���[�o�́A�c�����q�ƂƂ��ɁA�X�C�X�̃x�����ŐÂ��ɕ�炵�Ă����B�u���ꑊ�ΐ����_�v�̔��\����ނ͑��ς�炸�A�x�����̓����ǂœ����Ă����B
�A�C���V���^�C���̎莆�u�e���Ȃ�F�ցB���͖����ɃX�C�X�̌������Ƃ��āA�C���N������Ă��܂��B�����͂܂��܂��ł��B�����ǂŖ���8���ԓ����܂����A��w�ł�����������悤�ɂȂ�܂����B�v 1907�N12���ɂȂ��Ă܂��Ȃ��A�A�C���V���^�C���͊w���Ƃ��Ă̐l���̃X�^�[�g������B �ނ̑����́A�����Ƃ��ĕ��ʂ̂��ƂŁA��w�̎��u�t���o�肷�邱�Ƃł������B����͋����E�ł͂Ȃ��A�����đ�w���邢�͉������̌��I�c�̂ɂ���ĕ���x��������̂ł͂Ȃ������B���u�t�ł��邱�Ƃ͔C�����ꂽ��w�ŋ����錠���������Ƃ��Ӗ�����ɂ����Ȃ������B�B��̋����͊e�R�[�X�̏o�Ȏ҂̎x�������z�̎��Ɨ��ł������B��w�l�Ƃ��Ă̌o�����l������̂́A���̐l�l���x�T�ł��邩�A�܂��͗T���Ȑl���ƌ������Ă���ꍇ�������Ɠ��������Ό���ꂽ���̂ł���B�ǂ�����ނɂ͂��Ă͂܂�Ȃ������B�������ꂪ�A���̂悤�ȐE��{�����߂�ӎu���������炠��Ȃ���A�Ȃ��������N���Ȃ������̂��̗��R�ł���B 1907�N�A����ɂ�������炸�A�ނ͓����ǂ̐E�ɏA�����܂܂ŏo�肷�錈�S�������B6��17���ɔނ̓x�����̏B���ǂɁAPhD�w�ʘ_���A17�̔��\�ςݘ_��(�������A1905�N�̐��ʂ��܂�)�A�����ė������Ƃ������莆�𑗂����B�������A�K���͋K���ł���B�Ƃ����̂́A���R�͉��ł���A�A�C���V���^�C���́A�u��w���E�A�C�_���v�Ƃ��Ė����\�̉Ȋw�_�����A�\�����ɓY���đ���Ƃ����v���ɏ]���̂��Ȃ��Ă��܂����̂ł������B1908�N�̏��߂ɔނ͂���Ɓu��w���E�A�C�_���v�����A������2��28���ɁA�Ⴂ�A�C���V���^�C�����m�ɁA�ނ̐\��������A�����ċ������������ꂽ�B�A�C���V���^�C���͏��߂Ċw��I���E�̈���ƂȂ����B 1909�N7���A�A�C���V���^�C���͍ŏ��̖��_���m�����W���l�[�u��w�Ŏ��^���ꂽ�B10���ɂ́A�`���[���b�q��w�̏������Ƃ��ē����͂��߂��B �u���͏\������A��������Ă����肸���Ɨǂ���Ő������ɂȂ�悤�ɂƂ����A����傫�ȑ�w����̏����ɉ����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B���ꂪ�ǂ��̑�w�ł��邩�b���̂��܂�������Ă���܂���B�v�����A�C���V���^�C������Ɉ��Ăď������̂́A�`���[���b�q�ŏ������E�ɂ��Ă܂����N�������Ȃ�1910�N4��4���̂��Ƃł������B�ނ����҂������ق́A�v���n�ɂ���h�C�c�n��w�A�J�[��=�t�F���f�B�i���h��w���痈�邱�ƂɂȂ�Ǝv���Ă����B1���ɏ��W���ꂽ�����ψ���͋�����ɒ�Ă��邱�Ƃ����A�܂����ĂȂ������̂ŁA�ނ͐T�d�łȂ���Ȃ�Ȃ������B�ψ���̈ψ����ł��A�C���V���^�C���̋��͂Ȏx���҂ł����������ƃA���g���E�����p�́A���炩���ߔނ̈ӌ���Őf���Ă����B1910�N4��21���t�̈ψ���́A3�l�̌��҂��Ă��A�ނ�͊F�����̐\���o���������ӌ��ł���Əq�ׂ��B�A�C���V���^�C���͑�1�ʂɑI�ׂ�Ă����B���̓̕v�����N�̔M��Ȑ��E������p���Ă���B�u���Θ_�Ɋւ���A�C���V���^�C���̎d���́A�����炭�A���܂łɏ����_�I�Ȋw����ɂ͔F���_�ɂ����āA�����Ƃ���ꂦ�����ׂĂ̂��Ƃ��_�ɗ��킵�Ă���B�[�N���b�h�w�́A����ɔ�r����Ύq�ǂ��̗V�тł���B�v�ނ͑����āA�A�C���V���^�C�����R�y���j�N�X�ɂ��Ƃ����B ���̌�A���]�Ȑ܂͂��������A1911�N1��6���A�u�c��E���c�t�����c�E���[�t�É��v��4��1���t�̔C���𐳎��ɏ��F�����B�A�C���V���^�C����1��13���t�̎莆�Œʒm�����B�C���̔��߂ɐ旧���āA�ނ͎����̏@���̋A���F���o�^���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ނ́u���[�[���v�Ə������B3���ɔނƉƑ��̓v���n�ɓ��������B�@ *(�v���n��w�Ƃ��̋����E�ɂ���) ���[���b�p�ōł��Â���w�̈�ł���v���n�̑�w�́A�h�C�c�l�̋����ƃ`�F�R�l�̋����������Ă���A�����̋����́A���ꂼ�ꎩ���̌��t�ōu�`���Ă����B�������A�h�C�c�l�̓`�F�R�l�ɑ��āA�����D�G�����ł���Ǝ咣���ă`�F�R�l��̎����A�h�C�c�l�ƃ`�F�R�l�́A���������I�ȑ������N�����A���ꂪ�v���n�̑�w���ɕ����A���̈���h�C�c��w�A�����`�F�R��w�ƌĂB���̃h�C�c��w�̏���̑����́A�G�����X�g�E�}�b�n�ł������B ���̃v���n�̃h�C�c��w�̗��_�����w�̍u�`�̍u���ɁA1910�N�Ɉ�̋�Ȃ��ł����B���̂Ƃ��A�����I�o��C����Ă����̂́A�A���g���E�����p�ł��������A�����p�́A�}�b�n�̎��ؓN�w��M��}�b�n�̔M���I�Ȑ��q�҂ł������B�����ŁA�����p�́A���̃}�b�n�̐��_�ŕ����w���������鋳���F���āA��l�̌��҂������������B ���̈�l�̓A�C���V���^�C���A���̓O�X�^�t�E���E�}���ł������B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���҂̖��O�ƁA���̉Ȋw�I�ƐтƂ���w���ǂ֒�o����銵��ł��������A1905�N�Ƀx�����Ŕ��\���ꂽ�_���ƁA���ꂩ��1910�N�܂łɔ��\���ꂽ�_���Ƃɂ���āA���łɖ����̍��܂�������A�C���V���^�C�����A���̌��Ƃ���A���E�}���͑��̌��҂Ƃ���Ă����B �������Ȃ���A�I�[�X�g���A�̐��{�́A�O���l(�܂�I�[�X�g���A���Ђ������Ȃ��l)���A�v���n�̃h�C�c�l��w�̋����ɔC�����邱�Ƃ��D�܂Ȃ������̂ŁA�h�C�c��w���ǂ́A�܂����̒n�ʂ����E�}���̕��\�����B�Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C�������̌��ɂ������Ă��邱�Ƃ�m�������E�}���́A�A�C���V���^�C���̂悤�ɁA�V���������m��Ȃ����A�킯�̂킩��ʂ��Ƃ������҂���̌��ɂ����āA�����̎d���̐^�̕]����F�߂Ȃ��悤�ȑ�w�̋����ɂ͂Ȃ肽���Ȃ��ƁA���̐\������������Ă��܂����B�����ŃI�[�X�g���A���{�ƃh�C�c��w���ǂ́A�������O��u�O���l�����v�������Ă������āA���̒n�ʂ��A�C���V���^�C���ɐ\�����̂ł������B �A�C���V���^�C���́A�ނ̌̋��ƂȂ����`���[���b�q�̒�����Ɉ����Ă����B�����āA���̒����͂Ȃ�ĊO���̒��ɍs�����Ƃɕs���������Ă������A�ނ̍ȃ~���[�o���A���̃`���[���b�q�̒������邱�Ƃ��A�̂��܂Ȃ������B�������A�ނ��A���̃`���[���b�q�̑�w����Ƃ��Ă�����V�ƁA�ނ��v���n�̃h�C�c��w�Ŏ��ׂ���V�Ƃ̊Ԃɂ́A���܂�ɑ傫�ȍ����������̂ŁA�ނ́A���ɂ��̐\���o��������āA�v���n�֍s�����S�������̂ł������B ���̃v���n�̃h�C�c��w�̋����̒n�ʂ́A���̍c��t�����c�E���[�[�t�ɂ���ĔC������邱�ƂɂȂ��Ă������A�c��́A�F�肳�ꂽ����(�J�g���b�N�A�v���e�X�^���g�A���_������Ȃ�)�ɁA������l�����������A��w�̋����ɂȂ鎑�i�����ƐM���Ă����̂ŁA�����łȂ��悤�Ȑl���w�̋����ɔC�����邱�Ƃ�����ł����B�Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C���́A�~�����w���̃M���i�W�E��������Ƃ��ɁA���_���l�̏@�h�ɑ����鐳�K�̋A�˂��̂ĂĂ��܂��Ă����̂ŁA�����͂����Ȃ�@���c�̂ɂ������Ă��Ȃ������B�������A�A�C���V���^�C���́A�F�l�����̒����ɂ��������āA�ނ̒������ɔނ̏@���̓��[�[�̏@���ł���Ə�������ŁA�c��t�����c�E���[�[�t�ɂ��C�������ɂ��܂����̂ł������B �@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_(�l���ōō��̎v�����F�d��) | |
|
�A�C���V���^�C���̉�z�u�������U��ʂ��Ă�낤�Ƃ����̂́A�����A�₢�����邱�Ƃł����B�_�͂��̉F�����A�ʂȕ��ɍ�邱�Ƃ��ł����̂��낤���B����Ƃ��A������邵���Ȃ������̂��낤���B�����āA�����`�����X���������Ȃ�A���͂ǂ�ȕ��ɉF������������낤���B�v
�u�_�̈Ӑ}��ǂ݂Ƃ낤�v�Ƃ����̂́A�A�C���V���^�C���̑s��Ȗ�S�������B�ނ́A���x�����̎��݂ɐ������A��ԂƎ��ԂƁu���v�Ɋւ��邻��܂ł̍l������傫���ς����̂��B �A�C���V���^�C���́A�܂�20�ゾ�������A�}�b�N�X�E�v�����N�ȂǁA�����ł����Ђ̂����������w�҂����ƌ𗬂��Ă����B�����w�S����������A�C���V���^�C���̗��_�ɂ����̂���͂܂����������B�d�͂ł���B �A�C���V���^�C���̉�z�u�}�b�N�X�E�v�����N�͎��Ɂw�d�́x�̗��_�ɂ��Ă͌�������Ȃƌx�����܂����B���̖��͓�����āA���Ƃ��𖾂��Ă��A�����l�M���Ȃ����낤�Ɣނ͌����̂ł��B����ł��A���͌������܂����B�l���̒��ł���قnj����ɍl���������͂���܂���B�ŏ��̑��ΐ����_�Ȃǁw�d�́x�̖��ɔ�ׂ�Ύq�ǂ��̗V�тł��B�v �u�d�́v�͈ꌩ���ɒP���ł���B1kg�̓ؓ��A1kg�̃T�N�����{�A���ł��낤��1kg�̂��̂́A���������������B�Ȃ��Ȃ�A�n���́u�d�́v��������S�������悤�Ɉ������邩��ł���B�������A���̒n���̓����̍��{�ɂ͉�������̂��́A�N�ɂ�������Ȃ������B�j���[�g���́u�d�́v�����z�n�̓������x�z���Ă��邱�Ƃ��������B�������A�ǂ̂悤�ɂ��āH�@���ꂪ������Ȃ������B�܂��A�V�̂��O���ɉ����ē����̂́A�ǂ����ĂȂ̂��H�@�F����S�̂Ƃ��Ē������ĂĂ���̂́A�����������Ȃ̂��H�@�u�d�́v�́A��������̂��Ɉ����B�Ȃ�ŁA�ł��Ă��悤�ƁA�ǂ�قǑ傫���낤�Ɨ�O�͂Ȃ��B�������o���_�������B �A�C���V���^�C���̉�z�u����͓ˑR�̂��Ƃł����B����l�����Ђ�߂����̂ł��B�l���ōō��̎v����(glücklichste Gedanke meines Lebens)�Ƃ����Ă����������m��܂���B�����A�l���������痎������A���̐l�͎����̏d���������Ȃ����낤�ƍl�����킯�ł��B�v �A�C���V���^�C���́A���̃A�C�f�A���A�ʂ̗�Ő��������B�N�����A�G���x�[�^�[�ɏ���Ă��鎞�A�P�[�u�����ꂽ��ǂ��Ȃ邾�낤���H�@���̐l�͕����オ�薳�d�͂ɂȂ�B�ނƃG���x�[�^�[�́A�ǂ�����n���́u�d�͏�v�ɂ����ē������x�ŁA���R�������邩��ł���B�ł́A���̐l���F�����P�b�g�̒��ɂ�����ǂ��Ȃ邩�H�@����ł���͂�A�����Ă���B���ɑ�����������u�d�͏�v���Ȃ�����ł���B����ł́A���P�b�g�������n�߂���ǂ��Ȃ邩�H�@��������ɂ�A���P�b�g�̏��͏㏸���A����Ă���l�ɂԂ���B���̐l�ɂƂ��ẮA�u�d�́v�ɂ���āA�������ɒ����Ă���悤�Ɋ������邾�낤�B�u�����v�Ɓu�d�́v�������悤�Ɋ�������Ȃ�A����������ƁA��͓������̂ł͂Ȃ����낤���H�@�A�C���V���^�C���́A�����l�����̂ł���B�u�����v�Ɓu�d�́v�������ł��邱�Ƃ́A�v���I�ȐV���_�̊�b�ƂȂ邩���m��Ȃ��B�A�C���V���^�C���́A�������������B(��������) �ނ͂����₢�������B�����u�����ɂ���Đ��܂��́v�Ɓu�d�́v�������Ȃ�A�����̍Œ��ɉ����N����ł��낤���B���P�b�g����������ƁA����������Ă����u���v�́A���������̕ǂɓ����鎞�A�����Ă����ʒu���Ⴍ�Ȃ��Ă���B����Ă���l�ɂ́u���v���Ȃ������悤�Ɍ�����B�����ɂ���āu���v���Ȃ���Ȃ�u�d�́v���u���v���Ȃ���͂����B����͔��ɏd�v�Ȏ肪����ł������B (���������ƌ����x�s�ς̖@��) �u�������� / �A�C���V���^�C������ʑ��ΐ����_�̊�{�ɂ����������̈�B��n�̉����x�I�^���ɂ���Đ�����͂͏d�͂Ɠ����̌��ʂ����Ƃ����B�j���[�g���͊w�ɂ͂Ȃ������咣�B�v �G���x�[�^�̎v�l�����́A��N�A�C���V���^�C�����u�l���ō��̎v�����v�Ƃ��������̂ł���B�܂�A���̎v�l��������A�C���V���^�C���́u���������v�������̂������B�G���x�[�^���n���̏d�͂ɂ���Ď��R����(�����x�^��)����ƁA�G���x�[�^�[�̓����ɂ���ώ@�҂́u���d�ʏ�ԁv���o������ --- �܂�A���̐l�͂ӂ��ӂ��ƕ����B�܂��A�F���ŃG���x�[�^���Î~�܂��͓����x�^�����Ă���ƁA���ɂ���ώ@�҂͓������u���d�ʏ�ԁv���o������ --- ���̐l���������A�ӂ��ӂ��ƕ����B����́A���Ƃ��X�y�[�X�V���g���̒��ŏ�������Ԃ肵�Ă����Ԃł���B����A�G���x�[�^���F���ʼn����x�^��������ƁA�����̊ϑ��҂́u�d�͂Ƌ�ʂł��Ȃ��́v�������� --- ���Ƃ��A�X�y�[�X�V���g������������Ƃ��ł���B�܂��n���ŃG���x�[�^���Î~�܂��͓����x�^�����Ă���ꍇ�A�����̊ϑ��҂́u�d�́v��������B���̊ώ@�҂��`����Ƃ��悤�B�������G���x�[�^��������Ă��ĊO�̏�Ԃ������Ȃ��ꍇ�A�`����́u�G���x�[�^���n���̏d�͂ɂ���Ď��R����(�����x�^��)���Ă����ԁv�Ɓu�G���x�[�^���F���ŐÎ~�܂��͓����x�^�����Ă����ԁv����ʂł��Ȃ��B�`����ɂƂ��āA�����́A�Ƃ��Ɂu���d�ʏ�ԁv�܂�A�ӂ��ӂ�蕂���Ă����Ԃł��邩��ł���B�܂��`����͓������u�n���ŃG���x�[�^���Î~�܂��͓����x�^�����Ă����ԁv�Ɓu�F���ŃG���x�[�^�������x�^�����Ă����ԁv����ʂł��Ȃ��B������̏ꍇ���`����́u�d�́v����сu�d�͂Ƌ�ʂł��Ȃ��́v�������邩��ł���B�܂�A�n���ɂ����ĐÎ~�܂��͓����x�^�����Ă���G���x�[�^�ɂ�����u�d�́v�ƁA�F���ɂ����āu�����v���Ă���G���x�[�^�ɂ�����u�́v�͋�ʂł��Ȃ��B���ꂪ�u���������v�ł���B �b�͂���ɑ����B�n���ŁA���R����(�����x�^��)���Ă���G���x�[�^���A�n���ŁA�O���猩�Ă���ϑ��҂́A�G���x�[�^�̒��̌����Ȃ����Đi��Ō�����B�܂�A���R����(�����x�^��)���Ă���G���x�[�^�̒��̊ϑ��҂b����ɂ́A���̕ǂ��甭�������͉E�̕ǂɌ������Ē��i���Č�����̂ɁA�G���x�[�^�̊O�̊ϑ��҂c����ɂ́A���͋Ȃ����Č�����B�b����Ƃc����̈Ⴂ�́A���R����(�����x�^��)���Ă��邩�A���ĂȂ����̈Ⴂ�����ł���B����Ȃ̂ɁA���̋O�Ղ͈���Č�����B�����Ȃ�Ɓu���������v�Ɓu�����x�s�ς̖@���v�͖������邱�ƂɂȂ�B�Ƃ����̂́A���́A�������ԂɁA�b����Ƃc����Ƃł́A�Ⴄ������i�ނ���ł���B��������o�Ă������_�́A�d�͂ɂ���āA���c�ނƂ������Ƃł������B���Ƃ��Ώd�͂ɂ���āA���Ԃ͂������i�ށB����ŁA��ʑ��ΐ����_�̊�b�͒z���ꂽ�B�c��́A�����ɂ��āA����𐔊w�I�ɋL�q���邩�ł������B�@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_(����) | |
|
1912�N�A�A�C���V���^�C���́A�����ƍȃ~���[�o�̕�Z�ł���u�`���[���b�q�A�M�H�ȑ�w�v�̋����ƂȂ����B�d�͂̌����𑱂���A�C���V���^�C���́A�����ňȑO�A����������t���珕�͂��B
�A�C���V���^�C���̉�z�u���w�̋��t�ł���~���R�t�X�L�[(���̎ʐ^)�́A�w������̎����w�ӂ��҂̌��x�ƌĂ�ł܂����B�����炸�Ƃ������炸�ł��B�������A���ΐ����_�͔ނɊ�����^�����悤�ł����B�ނ͂���𐔊w�I�\���ɒu�������Ă��ꂽ��ł��B�v ���w�҃~���R�t�X�L�[�́A�[�����@�͂������A�A�C���V���^�C���ɏd�v�Ȍ���^�����B����́A��ԂƎ��Ԃ�Z��������4�����̐}���ł������B���Ƃ��A�L��ȕ�����v�������ׂė~�����B�����ł�4�̐����ŁA������o�������L�^�ł���B�܂��A3�̐���������A���̂̈ʒu��\����B�@�̓��ł��낤��ꡂ��ȋ�͂ł��낤�ƁA3�̐����u�����v�Ɓu���v�Ɓu�����v����ł����镨�̂̈ʒu���L�^�ł���B����Ɂu���ԁv��������A����4�Ԗڂ̎����ɂ���āA�F���̂�����o�������L�^�ł���̂��B���̔����ł��낤�Ɠy�j�̖�̃f�[�g�ł��낤�ƁB�u�f�[�g�̑҂����킹�v�Ƃ����̂́A���ԂƋ�ԂɊւ��邲���g�߂Ȍo���̈���B�܂��A����̏ꏊ�����߂���B��̓�����������Ƃ���B�����āA���m�Ȏ��������߂���E�E�E���Ƃ���10��10���B�~���R�t�X�L�[���F�߂��悤�ɁA������o�����́u����v�̂Ȃ��ŒP��̐��w�I�}�����`���B���ԂƋ�Ԃ����킳�����u����v�Ƃ����T�O�āA�A�C���V���^�C���͂���ɐ�Ɍ������B 4�����́u����v�Ƃ����~���R�t�X�L�[�̐��ʂ�������āA�A�C���V���^�C���́A���̐V�������z��B����́u����Ƃ����̂́A�܂������ł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ������z�ł���B����͗l�X�ɋȂ����Ă���͂����Ɣނ͍l�����B���ԂƋ�Ԃ��A��������Ȃ������肵����ǂ��Ȃ邾�낤���H�@�����N���邾�낤���H�@�A�C���V���^�C�������������F�d�͂���������B �A�C���V���^�C���̑f���炵�����z�̗v�́A���ԂƋ�Ԃ��Ȃ��Ă���̂́A�u�����v�Ɓu�G�l���M�[�v�ł���Ƃ��������ł���B���Ƃ��A��r�ɓ������Ƃ���B�g�����B�r�ɔg�𗧂Ă��̂͐ł���B���l�ɁA�͎��ԂƋ�Ԃ̒��ɁA�d�͂Ƃ����g�𗧂Ă�̂ł���B �������Ȃ���A����͕���ł���B�������A���������ω�������B����������Ȏ��ʂ́A����ɑ傫�Ȃ��ڂ݂����B�߂���ʂ邠���镨�́A���̂��ڂ݂̒��ɁA�]���藎������A���͂�������肷��B���ꂪ�d�͂ł���B�����ƃG�l���M�[�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ����̂䂪�݂��A�ʂ蔲���邽�߂́A����͒����I�ȓ��ł���B�������āA�A�C���V���^�C���͏d�͂ƓV�̂̋O���̊W�ɋC�Â����B���Ƃ��A�n���́A�P�ɑ��z��������䂪�݂ɂ����āA�����Ă��邾���������̂��B�A�C���V���^�C���́A1913�N�ɏd�͂Ɋւ���V�������_�̊�b�\�����B ���̌�A1914�N8���A��ꎟ���E��킪�u�������B �A�C���V���^�C���̉�z�u���[���b�p�͐��C�������M�����������Ƃ��n�߂Ă��܂��܂����B���́A������̑�Ȏ���ɐ����āA���́A�������A�����������ŕ�������ɑ����Ă��邱�Ƃ��A�ǂ����Ă��M�����܂���B���̎�͎��������̎��R�Ȉӎu�▽�߂ɂ��p�Y�I�s�ׁA���Ӗ��Ȗ\�́A�����Ĉ����S�̖��̂��Ƃɍs���邷�ׂĂ̕s�����Ŕ�펯�ȍs�ׂ���������̂ł��B�v �A�C���V���^�C���́A�x�������x�O�Ɉ����������ČǓƂɕ�炵�A�d�̗͂��_�ɖv�������B�ނ͍Ō�̃n�[�h���ɒ��ʂ��Ă����B�Ȃ���������̐��w�I��肪�����Ȃ������̂ł���B �����̂Ђ�߂��Łu��ʑ��ΐ����_�v���a�������̂ł͂Ȃ��B�A�C���V���^�C���́A���w�I��������z���˂Ȃ炸�A���ɂ͐�]���āA������߂������قǂ������B�����̃A�C���V���^�C���̃m�[�g(���̎ʐ^�̓A�C���V���^�C���̒��M�̃m�[�g)����������ƁA1912�N�ȍ~�̔ނ̋ꓬ���A�y�[�W����`����Ă���ƌ�����B ���͂�A�ǂ��i�炢���̂�������Ȃ��Ƃ����Ƃ���܂ŁA�ǂ��߂��āA�ނ͐��w�҂̗F�l�ɏ��������߂��B���̗F�l�Ƃ́A��w����̃N���X���[�g�������}���Z���E�O���X�}��(���̎ʐ^)�������B�ނ̎菕���ŁA�d�͂̐V�������_�͊��������B�A�C���V���^�C���́A�O���X�}�����畡�G�ȁu�Ȗʊw�v�ɂ��ċ��������B�c���ꂽ�m�[�g�����Ă����ƁA�ނ́A���̐��w�I�ȐV����������A��T��Ŏg���͂��߂����Ƃ��悭������B���������ꓬ���A�₪�Ď������сu��ʑ��ΐ����_�v�ƂȂ����B�����ȕ����܂ŁA���ׂă}�X�^�[����܂łɂ́A3�N���������B1915�N�̏H�܂łɁA�����͐������B �����A�f���̋O���͐��m�ɗ�������Ă������A���O���������B�����̋O�����A���N�킸���ɂ���錴����������Ȃ������̂ł���B�A�C���V���^�C�����ق���ƁA�ނ͂����������Ǝv����B�u���E���A�Ȃ�ƌ������ƍ\��Ȃ��B�_���A���ɐ����̋O�����v�Z���Ă݂�ƍ������̂��B�v�ނ́A���̒ʂ���s���A�����āA���ʂ��o���B �A�C���V���^�C���̉�z�u�����̌v�Z���A�����̓����𐳊m�ɗ\�����Ă���ƋC�Â����Ƃ��A���������̒��Œe���܂����B���̊��o�́A���܂�ɋ���ł����B���́A�������d������ɒ������A���Y��Ă��܂����B����قǂ̊�т����������Ƃ́A���ɂ���܂���B�v �u����͋Ȃ����Ă���v�Ƃ����A�A�C���V���^�C���̑�_�Ȕ��z�́A�����ł��ؖ�����邱�ƂɂȂ�B�����́A���z�ɍł��߂��f���ŁA���z�̋���Ȏ��ʂ����o��������̂��ڂ݂����ɘA��āA���̋O��������Ă���(�����̋ߓ��_�ړ�)�B �A�C���V���^�C���̗��_�́A�F���̒a���ɂ��ẲȊw�I�����ɂ܂ł���ԁB�u�r�b�O�o���v�ł���B�c������F���B��͂̍\���B����F���_�̑傫�Ȕ��W�́A �@�@�@ �Ƃ�����̌������瓱����Ă���B���ӂ́u���ԂƋ�ԁv�E�ӂ́u�����̃G�l���M�[�v�B���ꂪ�A�d�͂Ɋւ��āA�A�C���V���^�C�����A���ǂ蒅�������_�F�u��ʑ��ΐ����_�v�ł���B |
|
| ���A�C���V���^�C���̐��w�ɑ���l���� | |
|
�A�C���V���^�C���ƃQ�I���O�E�s�b�N
�A�C���V���^�C���́A��x�͐��w���U���悤�ƍl�������Ƃ����������B���������āA�ނ͂܂��A�`���[���b�q�̍H�|�w�Z�̐��w�ƕ����̋��t��{�����邽�߂̃R�[�X������̂ł������B �������A���̂Ƃ��A�K���s�K���A���w�̕����̋����̒��ɁA���V�A���܂�̃w���}���E�~���R�t�X�L�[�������B���̂Ƃ��~���R�t�X�L�[�́A�����Ⴍ���ēƑn�I�Ȑ��w�҂̈�l�Ƃ݂Ȃ���Ă������A�ނ̍u�`�́A�����ď��ȍu�`�Ƃ͌����Ȃ������B�����āA�A�C���V���^�C�����A�u�������w�v�ɑ��鋻���������Ă��܂����̂́A���傤�ǂ��̍��ł������B�ނɂ́A�ނɋ����̂��镨���w�̖@����莮������ɂ́A����Ȃɕ��G�Ȑ��w�͕K�v�Ƃ����A�ȒP�Ȑ��w�̌��������ŏ\���ł���Ǝv���Ă����̂ŁA�u�������w�v����͂Ȃ�āA���_�����w�̕������������̂ł������B �A�C���V���^�C���́A���炭�A���̍l�����A���������Ă����B ���ɃA�C���V���^�C�����A���̓��ꑊ�ΐ����_�\����1905�N����O�N��A1908�N�ɁA�A�C���V���^�C���̂��Ƃ̐��w�̐搶�~���R�t�X�L�[���A�l�����̊w��p���āA���̌����Ȑ��w�I�莮����^�����Ƃ��ɂ��A�A�C���V���^�C�����g�́A������A���ΐ����_�̐^�ɕ����w�I�ȈӖ������ނ��Ƃ��ނ��덢��ɂ��閳�p�ŕ��G�Ȍ`����`�̓����ƌ��Ȃ������炢�ł������B�܂��A�}�b�N�X�E�t�H���E���E�G���A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�𐔊w�I�ɁA�܂Ƃ߂������ȏ����\�����Ƃ��ɂ��A�A�C���V���^�C���́A �u���E�G�̂��̖{�́A�����g(��������̂�)���ɓw�͂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ə�k�������Ă���B �A�C���V���^�C���̑��ΐ����_���]���ɂȂ�����������̃h�C�c�ɂ����鐔�w�����̒��S�́A�Q�b�e�B���Q����w�ł������B�~���R�t�X�L�[�̓`���[���b�q�̍H�|�w�Z����A���̃Q�b�e�B���Q����w�ֈڂ��Ă������A�ނ��A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�̐��w�I�莮�����n�߂��̂́A���̃Q�b�e�B���Q����w�ɂ����Ăł������B �A�C���V���^�C���́A���̃Q�b�e�B���Q���̐��w�҂������A���w��傢�Ɋ��p���������w�̘_���\����̂����āA �u�Q�b�e�B���Q���̐l�����́A�Ƃ��ǂ�������������B���̐l�����́A���w��p���ĕ����w���n�������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A���̐l�������A�ǂ�Ȃɓ����悢�����A����ꕨ���w�҂Ɏ������Ɠw�͂��Ă���悤�Ɏ��ɂ݂͂���v�Ə�k�������Ă���B ���̃Q�b�e�B���Q����w�ɂ́A�����I�����̑吔�w�҃_�[�t�B�b�g�E�q���x���g�������B�q���x���g�́A�A�C���V���^�C������ɏq�ׂ��悤�ɍl���Ă����ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���̂��Ƃ��A���w���K�v�ȏꏊ�ł͐��w���A�����ɗp����ׂ������\���ɂ悭�m�����l�ł���ƍl���Ă����B �q���x���g�́A���Ă��̂悤�ɂ����Ă���B �u�����̒��Q�b�e�B���Q���ł́A�X���s���w���ł������A�l�����̋�ԂƂ������̂��A�C���V���^�C�������A�悭�������Ă��邩���m��Ȃ��B����ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���́A�����w�ɂ�����f���炵���d�����ǂ�ǂĂ���̂ł���v ���̂悤�ɃA�C���V���^�C���́A�ꎞ�́A�����w�̊�b�I�ȗ��_��W�J����̂ɁA�������G�Ȑ��w�͕K�v�Ȃ��ƍl���Ă����̂ł��邪�A�ނ��v���n�ŁA���̑��ΐ����_���d�͂̂���ꍇ�Ɋg�����悤�Ɠw�͂��A����ɑ��Đ��w�҂̃Q�I���N�E�s�b�N���A�A�C���V���^�C���̍l���W�����邽�߂̐��w�I����́A�C�^���A�̃��b�`�ƃ��r�E�`�r�^�̑n�n�����e���\����͊w�ɑ��Ȃ�ʂ��Ƃ��w�E���A���̃s�b�N�̏��͂ɂ���ăA�C���V���^�C�����A���̃e���\����͊w���}�X�^�[���A�����́A���w�҂ɂƂ��Ă��V�����w��ł��������̃e���\����͊w���c���ɋ�g���Ĉ�ʑ��ΐ����_�W�����Ĉȗ��A�A�C���V���^�C���́A���̍l���������Ă���B ���������āA�A�C���V���^�C���́A����ȍ~�������w�Ɋ��\�ȎႢ�l������ɂ��Ă���B ���Ƃ��A�R���l���E�X�E�����`���X(Cornelius Lanczos)�A���@���^�[�E�}�C���[�A���I�|���g�E�C���t�F���g�A�y�[�^�[�E�x���N�}���A�o�����e�B���E�o�[�O�}���ȂǁA����������w�I�˔\�ɂ߂��܂ꂽ�l����������Ƃ������A�����̐l�����́A����������ł͗��h�Ȓn�ʂĂ���B �@ (�A�C���V���^�C���ƃQ�I���O�E�s�b�N) �A�C���V���^�C�����v���n�œ��������̂Ȃ��ɁA���w�҃Q�I���O�E�s�b�N(Georg Pick 1859-1942)�������B�M��(�� / ��쌒���Y)�̍l���ł́A���̃Q�I���O�E�s�b�N���炢�A�C���V���^�C���̎d���ɑ��đ傫�ȉe����^�����l���͂Ȃ��Ǝv���̂ł��邪�A���̂��Ƃ������������Ƃ͂ǂ��ɂ�������Ă��Ȃ��̂ŁA���̃s�b�N�ɂ��Ƃ��A�����ڂ����L�����Ƃ������Ă����������B ���ʏ�̋Ȑ��̐�����_���悤�Ǝv���Ƃ��ɂ́A���̕��ʏ�Ɉ�̒�������ݒ肵�A�Ȑ���̓_�����̒������Ɋւ�����W�ŕ\���Ă����̂��ӂ��ł���B �Ƃ���ŁA1896�N�ɁA�i�|����w�̃c�F�U���́A�Ȑ���̈�_�l�ɂ�����ڐ�����̎��Ƃ��A�l�ɂ�����@������̎��Ƃ���悤�ȍ��W���Ȑ��Ɍ��т��A�Ȑ��ɂ����ē����Ă������̂悤�ȍ��W���Ɋւ��ċȐ���̓_��\�킵�A�����p���ċȐ��̐�������������Ƃ������Ƃ��͂��߂��B�c�F�U���̒����́A1901�N�ɃR�����t�X�L�[�ɂ���ăh�C�c��ɖ|��u���R�w�u���v�Ƒ肵�Ĕ������ꂽ�B����ȗ����̕��@�ɂ��w�͎��R�w�Ƃ��Ă���B ���̃s�b�N�́A�Ⴂ�Ƃ��ɁA�v���n��w�̎��������w�҂̋����ł������G�����X�g�E�}�b�n�̏�����������Ƃ�����A���������ăA�C���V���^�C������\���N��ł��������A�A�C���V���^�C���̓s�b�N�̑f���炵�����w�I�˔\�ɂقꂱ�݁A�ނ����̗��_�����w�̌����ɂ����Ē��ʂ������w�I���Ɋւ��ẮA�������̃s�b�N�ɑ��k�������̂ł������B �����A�C���V���^�C���́A�ނ��x������1905�N�ɔ��\�������ΐ����_���A������d�͏ꂪ����ꍇ�Ɋg�����悤�Ƃ������Ƃ�M�S�Ɏ��݂Ă����B���������ăA�C���V���^�C���́A�������̃s�b�N�ɉ�A�ނ��ނ̑��ΐ����_�̊g���ɂ����ďo����Ă��鐔�w�I��������ׂăs�b�N�ɑł������A����ɂ��ăs�b�N�̍l���������Ă����B �A�C���V���^�C���̒��ʂ��Ă�����̈Ӗ���I�m�ɂ��s�b�N�́A�������łɁA�A�C���V���^�C�������̗��_��W�J���邽�߂ɕK�v�ȕ���́A�J�[���E�t���[�h���q�E�K�E�X(1777-1855)�A�Q�I���O�E�t���[�h���b�q�E�x�����n���g�E���[�}��(1826-1866)�ɂ͂��܂�A�N���o�X�g���E�O���S���I�E���b�`(1853-1925)�ƃg�D���I�E���r�E�`�r�^(1873-1941)�ɂ���Ċ������ꂽ��Δ����w�ł��邱�Ƃ����j���Ă����B ���ʊw�́A�������A���ʂ��ꎩ�g�̐����ƁA���̕��ʂ̏�ɉ�������Ă���}�`�̐�������������w�ł���B ���ʏ�̑��قȂ��_�����Ԑ��̂����ŁA���������Ԑ�������ԒZ�������������Ă���Ƃ����A����͂��̕��ʎ��g�̐����ƁA���ʏ�̒����̐����������\���Ă���B �܂��A���ʏ�ɂ����ꂽ�C�ӂ̎O�p�`�ɂ����ẮA���̓��p�̘a�͓p�ɓ������Ƃ����A����͕��ʂ��̂��̂̐����ƁA���̕��ʂ̏�ɂ���O�p�`�Ƃ����}�`�̐����������\���Ă���B ���̕��ʊw����������ɂ́A���ʏ�ɐ}��`���Ē��ڂ��̐}�ɂ��Č���������@�ƁA���ʏ�ɒ�������ݒ肵�āA�������͊w�̎�@��p�����ʂ�̕��@���l������B ���̉�͊w�I�Ȏ�@��p����ꍇ�ɂ́A���ʏ�̓_����̐��̑g�ŕ\������Ƃ���������p���邪�A����䂦�ɕ��ʂ͓��̂��̂ł���Ƃ�����B ���āA���l�E�f�J���g(1596-1650)�ƃs�G�[���E�h�D�E�t�F���}�[(1601-1665)�ɂ���͊w�̔����ɂÂ��āA�j���[�g���ƃS�b�g�t���[�g�E�E�B���w�����E���C�v�j�b�c(1646-1716)�ɂ���Ĕ����ϕ��w�����������ɂ����ŁA�Ȑ���Ȗʂ̌����ɔ����ϕ��w�̎�@��p����Ƃ������Ƃ��͂��߂�ꂽ�B �w�̌����ɔ����ϕ��w�̎�@��p����ꍇ�A����͔����w�Ƃ��邪�A���̔����w�́A�J�[���E�t���[�h���q�E�K�E�X�ɂ���Ă͂��߂đg�D�I�ɓW�J���ꂽ�B �K�E�X�͎�Ƃ��ċȖʂ̐���������w��p���Č����������A���̋Ȗʂ̐����ɓ��ނ��邱�Ƃ��킩��B ���Ƃ����ʂ��ɂƂ��Ă݂�A���S�Ƃ��̋��ʏ�̈�_�����Ԓ����́A���̓_�ɂ�����ڕ��ʂɐ����ł���Ƃ����A����́A�����̋�Ԃ̂Ȃ��ɓ����Ă��鋅�Ƃ��Ă̐������ׂ̂Ă���B ����ɑ��āA���ʏ�̓�_�����ԋ��ʏ�̋Ȑ��̂����ŁA�ł��Z�������������Ă���̂́A�����̓�_�����ԑ�~(�����̓�_�ƒ��S�ƂŒ�܂镽�ʂŋ��ʂ�����ꍇ���̐���Ɍ����~)�ł���Ƃ����A����́A���̋����܂�ł���O�̋�ԂƂ͊W�̂Ȃ��A���ʂ��̂��̂̐�����\���Ă���B �K�E�X�́A���̋Ȗʂ��̂��̂̐�������������w���A�Ȗʏ�̊w�Ɩ��Â����B ���ʏ�̓_�̈ʒu��\�����Ǝv���A�n����̈ܓx�ƌo�x�̂悤�ɁA��̐���K�v�Ƃ��邩��A���ʂ͓��̂��̂ł���B���l�ɁA�Ȗʂ����̂��̂ł���B ���̌������ɂ��A���ʂ͓��̕���ȋ�Ԃł���A�Ȗʂ͓��̋Ȃ�������Ԃł���Ƃ������Ƃ��ł���B ���������ăK�E�X�̋Ȗʏ�̊w�́A���̋Ȃ�������Ԃɂ�����w�ł���Ƃ������Ƃ��ł��邪�A����́A���[�}���ɂ���āA��ʂ̂������̋Ȃ�������Ԃ̊w�֊g�����ꂽ�B���[�}���̂͂��߂����̂������̋Ȃ�������Ԃ̊w�́A���݃��[�}���w�Ƃ��Ă���B ���̃��[�}���w�́A�������������̂ɓ��L�̕��@��K�v�Ƃ��邱�Ƃ��킩���Ă������A���̕��@�́A�C�^���A�̃N���o�X�g���E�O���S���I�E���b�`�ƃg�D���I�E���r�E�`�r�^�ɂ���Č��������ꂽ���A���̕��@�͔ނ�ɂ���Đ�Δ����w�Ɩ��Â���ꂽ�B ���������̐�Δ����w�́A���݂ł́A���b�`�v�Z�@�Ƃ��A�e���\����͊w�Ƃ����Ă���B �A�C���V���^�C������A���̑��ΐ����_�g���̒��z�������A����W�����邽�߂̐��w�I�Ȏ�i�ɂ��đ��k�����s�b�N�́A����͂��̃��b�`�ƃ��r�E�`�r�^�ɂ���č���Ă����Δ����w���̂��̂ł��邱�Ƃ����j���āA�A�C���V���^�C���ɂ�����������邱�Ƃ������߂��̂ł������B �A�C���V���^�C���ƃs�b�N�����Ԃ��̂�������������B�A�C���V���^�C�����q�ǂ��̂Ƃ�����o�C�I�������K���͂��߁A�ŏ��͂��₢��ł��������A����Ƀo�C�I�����̂����͂ɂЂ����悤�ɂȂ����̂͂��łɂׂ̂��B �Ƃ��낪�A���̃s�b�N���܂��o�C�I�������悭�����̂ŁA�A�C���V���^�C���̓s�b�N�ƃo�C�I�����̍��t�����̂��݁A�܂��A�v���n�̉��y���D�Ƃ̃O���[�v�ɂ������A����I�Ɍ��y�l�d�t�����y���ނ悤�ɂȂ����B �܂��A�C���V���^�C���́A�v���n�Őe�����Ȃ����T���X�N���b�g��̋��������b�c�E�E�B���e���j�b�c�����̋`���̔��t�ł悭�o�C�I������e�����B�@ |
|
| ���~���[�o�̔Y�݁A�x�������� | |
|
�A�C���V���^�C���̉�z�u���͗\���s�\�̐l�ԊW����g�������A�Ǘ�����邷�ׂ��w�т܂����B�l���́A���f����A������݂��肪�����Ă����܂��B�Ƃ��ɁA�����Ȃǂ́c�c�v
�A�C���V���^�C���́A�Ђ������ʑ��ΐ����_�̌����ɑł����݁A���̂��ׂĂ̂��Ƃ��]���ɂ����B�ȃ~���[�o�ɂ��A�قƂ�NJS�������Ȃ��Ȃ����B���Ĉ��������Ă�����l�́A�Ȋw�̌�����i�߂�p�[�g�i�[�ɂȂ낤�Ɩ��Ă����B�������A�͉ʂ�����Ȃ������B �A�C���V���^�C���̉�z�u���́A�l�t�����������ł����A�ƒ���ɂ���j�ł�����܂���B�~�����͎̂����g�̕��a�ł��B�l�Ƃ����͖̂��Ӗ����Ǝv���ƈ��S�ł��܂���B�v 1911�N�A�A�C���V���^�C���́A�v���n�̑�w�̋����ɂȂ����B�傫�ȏo���������B�������A����A�A�p�[�g�ɂ������āA��l�ڂ̑��q�̐��b�ɂ�����ȃ~���[�o�ɂƂ��ẮA�v���n�͗��Y�n�̂悤�Ɋ�����ꂽ�B�ޏ��́A�����������c����āA�i���ɋ��ɒǂ�����Ă��܂��Ɗ������B�A�C���V���^�C�����A�Ȋw�̌��������A�~���[�o���Ǝ�������Ɩ������S�����܂����Ƃ��A��l�����N���̊ԁA�ۂƂ��Ƃ��Ă������������̊W�����S�ɂ���ꂽ�̂ł������B�~���[�o�́A�����̖�]���ʂ������Ƃ��o���Ȃ������B���̖�]�Ƃ́A���͂���ɓ����ȂǂƂ����悤�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�j���Љ�̒��ŐV�����^�C�v�̏����ɂȂ邱�Ƃł������B���ꂪ�A���S�ɂ����������B�ŋߔ������ꂽ�~���[�o�̎莆�ɂ́A���̂悤�ɏ�����Ă���B �u�ނ���������ɂ������Ƃ��A���͑�ρA���ꂵ���v���܂��B���̖]�݂́A���̐������ނ̐l�ԓI���ʂɗL�Q�ȉe����^���Ȃ��ŗ~�����Ƃ������Ƃ����ł��B�v �~���[�o�́A���̂悤�ɂ������c���Ă���B �u�ނɂ́A�����̍Ȃ̂��߂Ɋ������Ԃ͎c���Ă��Ȃ��Ƃ����킯�ł��B���Ƃ����l�Ԃ͊����₷���̂ŁA����ŋꂵ��ł���̂ł͂Ȃ����Ƃ��l���܂��B���͈���ɋQ���Ă���A���ׂĂ͂��̊��܂킵���Ȋw�������Ȃ��̂��ƐM�����ސ��O�ɂ܂ŗ��Ă��܂��B�v 1911�N�A�����̉Ȋw�҂��W�܂��1��\���x�C��c���A�u�����b�Z���ŊJ���ꂽ�B�A�C���V���^�C���͏o�Ȏ҂̒��ōŔN���������B�������A�ȃ~���[�o�ɂƂ��āA�v�̉h���͉������E�̏o�����������B �A�C���V���^�C���Ɉ��Ă��~���[�o�̎莆�B�u�����Ƒf���炵����c�������͂��ł��B�����Q���ł�����A�ǂ�Ȃɗǂ������ł��傤�B���Ȃ��Ƃ́A���炭����Ă��܂��A�܂��A���̊�����ڂ��Ă��܂����B�v �A�C���V���^�C���́A�����m�I�ȃp�[�g�i�[�����߂Ă͂��Ȃ������B�ȃ~���[�o�̌ǓƂ́A�[�܂����������B �A�C���V���^�C���́A�h�C�c��K�₷�闷�̓r���A���Ƃ��̃G���U�ɉ�B�G���U�́A�A�C���V���^�C���Ɠ����悤�Ȓ��A�����悤�Ȋ��ň�����l�������B�����āA�A�C���V���^�C���́A�G���U�ƂȂ�A���S���A�����������Ȃ��ƒ됶���𑗂��̂ł͂Ȃ����ƍl�����B�l���̒P���ȉc�݂ɂ܂��A�����̊�сA���Ƃ��A�H�ׂ�����肷�邱�Ƃ̊y�����A�A�C���V���^�C���́A�����������̂��A�G���U�ƕ��������������Ɩ]�B �A�C���V���^�C���̎莆�u�e���Ȃ�G���U�B�莆���ǂ������肪�Ƃ��B�f�l�ɂ������鑊�ΐ����_�̖{�Ƃ����̂͂���܂���B�ł��A�N�ɂ͖l�Ƃ����A���Ƃ������܂��B�����A�`���[���b�q�ɗ��邱�Ƃ���������A�Ȃʂ��ŁE�E�E�Ȃɂ���A�ޏ��͂ƂĂ����i�[�����̂ł�����E�E�E��l�����ŎU�����y���݂܂��傤�B�v �u�e���Ȃ�G���U�B�l�����́A�Ƃ��Ɉ���Ȑl�Ԃł��B�e�͂Ȃ��`���ɔ����Ă��܂��B�������A������x�����܂��B�N�������Ă��܂��B�N�̉�������邾���ŁA�K���ɂȂ�܂��B�l���ꂵ��ł���̂́A���邱�Ƃ���������Ȃ��l���A����������ł��B�v ���ʂ́A����ȏ�A�i�W���Ȃ������B 1913�N�A�A�C���V���^�C���́A�d�͂Ɋւ���V�������_�̊�b�\�����B����Ɋ��������̂��A�h�C�c�̑�\�I�ȕ����w�҃}�b�N�X�E�v�����N�������B�ނ́A�A�C���V���^�C�����A�x��������w�̋����Ɍ}���悤�ƁA�݂�����`���[���b�q�ɏo�������B �A�C���V���^�C���̉�z�u�v�����N�ɂƂ��Ď��́A���J���̎����݂����Ȃ��̂ł����B�������A������^�}�S�߂邩�ǂ����E�E�E�����l�������̂ŁA�����A�w�ʼn���Ƃɂ��܂����B���f�肷��Ȃ�A�݂ɔ����Ԃ������Ă����ƁA�ނɌ����܂����B�������A�Ԃ��Ԃ�������A����́A�x�������s�������m����Ƃ����Ӗ��ł��B�v �����āA�A�C���V���^�C���́A�Ԃ��Ԃ�I�B �A�C���V���^�C���̌o���́A���_�ɒB���悤�Ƃ��Ă����B�����A�x��������w�́A���_�����w�̐��E�I���S�������̂��B�������A�ȃ~���[�o�ɂƂ��ẮA�v�̏o�������Ӗ��������B�d�͂̌����ɂ̂߂荞�ރA�C���V���^�C���̉ƒ됶���͔j�]���O�������B�A�C���V���^�C���́A���̍��A���Ƃ��̃G���U�ƁA�܂��A�A�������n�߂�B �A�C���V���^�C���̎莆�u1913�N12���B�e���Ȃ�G���U�B��������ɂ́A������̗����x���ؖ�������̂��Ȃ���A�e�Ղł͂���܂���B�����ŁA���͍Ȃ��A�N�r�ɂł��Ȃ��ق��l�̂悤�Ɉ����Ă��܂��B�Q���͕ʂŁA�ޏ��Ɠ�l����ɂȂ�̂�����Ă��܂��B�N�ƐT�܂����ƒ�����Ă���A�ǂ�Ȃɑf���炵���ł��傤�B�v 1914�N4���A��Ƃ̓x�������Ɉڂ������A7���ɂ̓~���[�o�́A�q�ǂ���A��āA�`���[���b�q�ɖ߂��Ă��܂����B �A�C���V���^�C���̉�z�u���q�����Ƃ̕ʂ�́A��͂�h�����Ƃł����B���j�n���X�E�A���o�[�g�̗{�猠���咣���悤���Ƃ��l���܂������A�ǂ����A���ʂ������ł��傤�B�~���[�o�́A���q�������A���������ɂȂ�悤�Ɏd�����Ă����̂ł��B�ޏ��́A�ꏏ�ɕ�点��悤�ȏ����ł͂Ȃ������E�E�E�Ƃ��Ă��A���i�[���������E�E�E�Ȃ��A����������ł��傤���B�v�@ |
|
| ���a�C�A�č��A��̎� | |
|
1915�N12���A�A�C���V���^�C���͗F�l�x�b�\�[�Ɉ��ĂāA�����́u�������Ă��邪�A���Ȃ���͂Ă��v�Ə������B����ǂ��A�ނ͋x�{���Ƃ�Ȃ������B1916�N�ɔނ́A10�҂̉Ȋw�_�������������A���̒��ɂ́u��ʑ��ΐ����_�̏��̏d�v�ȊT�_�v�u���R����їU�����o�̗��_�v�u�d�͂Ɋւ���ŏ��̘_���v�u�G�l���M�[-�^���ʂ̕ۑ����ɂ��Ă̘_���v�u�V�����@���c�V���g�̉��ɂ��Ă̘_���v�u�A�C���V���^�C��-�h�D�E�n�[�X���ʂ̑���̂��߂̐V������āv���܂܂�Ă���B�ނ͂܂��A���ΐ����_�Ɋւ��鏉�߂Ắu���ʑ��I�Ȓ���v�����������B�ߓx�̌������������A�K�Ȓ��ӂ����������ƂƂ����܂��āA1917�N�̂��鎞�Ɏn�܂��āA���N�������a�C�̎傽�錴���ł������ɈႢ�Ȃ��B
���̎��������n�܂������͐��m�ɂ͂킩��Ȃ��B�������A1917�N2���ɁA�A�C���V���^�C���̓G�[�����t�F�X�g���ɁA�̑������̂��߂Ɍ������H���Ö@�����A����߂Ĉ��ÂȐ����𑗂邱�Ƃ��������Ă���̂ŁA�I�����_��K�˂邱�Ƃ͏o���Ȃ����낤�Ə������B�������A���̈��ÂȐ����́A�������ɔނ���ʑ��Θ_�I�F���_�̊�b�I�_�����A���M���邱�Ƃ�W���Ȃ������B���[�����c�́A�A�C���V���^�C�����A�����Ȃ����ƂɎ��]��\�������B����ǂ��A�ނ͏������F�u�������N�̐��͓I�Ȏd���̌ゾ����A���Ȃ����x�{���Ƃ�͓̂��R�̂��Ƃł��B�v�A�C���V���^�C���̕Ԏ��́A�ނ̕a�C�����ׂȂ��Ƃł͂Ȃ������Ƃ������Ƃ������Ă���B�펞���ɂ����āA�ނ́A�x�������ɂ��鎩���̐g�����A��h�C�c�̐e�ނƕۂ��Ă���Ȃ���̂������ŁA�����͂�����ׂ��H������ɓ���邱�Ƃ��ł���Əq�ׁA�u���̉������Ȃ�������A���������ɂƂǂ܂邱�Ƃ́A�قƂ�Ǖs�\�������ł��傤�B�܂��A���Ԃ����̏�Ԃ̂܂ܑ������ǂ����A���ɂ͂킩��܂���B�v�ƕt���������B�ނ́A�X�C�X�ŁA�a�̉��͂��邱�Ƃ�M�S�ɂ����߂���t�̒����ɏ]��Ȃ������B ���̎����ɁA�G���U�E�A�C���V���^�C���E���[���F���^�[�����������Ƃ肵�������B1876�N�Ƀz�[�G���c�H�������̃w�b�q���Q���Ő��܂ꂽ�G���U�́A�A���o�[�g�̏]�o�ł���A���u�܂����Ƃ��v�ł��������B�ޏ��̕����h���t�́A�A���o�[�g�̕��w���}���̏]�Z��ł������B�ޏ��̕�t�@�j�[�́A�A���o�[�g�̕�p�E���[�l�Ǝo���ł������B�G���U���悭�~�����w���̐e�ʂ�K��A�A�C���V���^�C�����w�b�q���Q���ɂ���ė��Ă����c�N����ȗ��A�G���U�ƃA���o�[�g�͂��݂���m���Ă����B�ނ�͂��݂����D���ɂȂ��Ă����B20��̏��߂ɁA�G���U�̓��[���F���^�[���Ƃ������̏��l�ƌ������A�ނ̂��Ƃœ�l�̖��A�C���[�ƃ}���S�b�g�����������B���̒Z�������͗����ŏI������B�A�C���V���^�C�����x�������ɓ��������Ƃ��A�G���U�Ɣޏ��̖������́A�n�[�o�[�����h�ʂ��5�Ԃ̏�K�̃A�p�[�g�ɏZ��ł����B�ޏ��̗��e�́A���������̉��̊K�ŕ�炵�Ă����B�G���U���x�������ɂ������Ƃ́A�A�C���V���^�C�������̒��Ɉ������v���̈�ł������B 1917�N�āA�A�C���V���^�C���́A�G���U�ׂ̗̃A�p�[�g�Ɉ����z�����B�u�G���U�̐e�Ȑ��b�̂��A�ŁA���͍�N�̉Ă���4�|���h�̏d�������܂����B�G���U�́A���̂��߂ɕK�v�Ȃ��ׂĂ̗���������Ă����B�v����ǂ��A���̔N�̏I���߂��A�ނ̌��N�͂������������Ȃ����B�ނ͈ݒ�ᇂ������Ă��邱�Ƃ��A�͂����肵���B���̐������ԁA�ނ͏��ɂ��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B1918�N4���A�ނ͊O�o���邱�Ƃ������ꂽ�B�������A�܂��A�p�S���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�u�ŋ߁A���́A�Ђǂ�������N�����܂����B����́A�����o�C�I������1���Ԓe�����Ƃ����A���������ꂾ���̂��ƂŁA�N�����̂ł��B�v5���ɁA�ނ͍ĂсA���x�́A���t�ŏ��ɂ����B12���ɂ͔ނ́A�G�[�����t�F�X�g���ĂɁA���S�Ȍ��N�����߂����Ƃ́A�����Ȃ������m��Ȃ��Ə������B ���̎��܂łɁA�A���o�[�g�ƃG���U�͌������悤�ƌ��ӂ��Ă����B����䂦�A�A�C���V���^�C���́A�~���[�o�Ɨ�������葱�����n�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������́A1919�N2��14���ɉ����ꂽ�B�����(���Ƃ������ɂ�����)�~���[�o���A�A�C���V���^�C���́u�m�[�x���܁v�̏܋������Ƃ������Ƃ��A��茈�߂Ă����B�~���[�o�́A���̌ジ���ƁA���ʂ܂ŁA�`���[���b�q�ɂƂǂ܂����B���ߔޏ��́A�ޏ��̐��A�}���b�`�𖼏�����B�������A1924�N�A�ޏ��̓A�C���V���^�C���Ƃ������ɖ߂邱�Ƃ������ꂽ�B���܁A�q�ǂ�������K�˂�ۂɁA�A�C���V���^�C���́A�ޏ��̉Ƃɑ؍݂����B�ޏ���1948�N�Ɏ��B���̐��N��ɁA�A�C���V���^�C���́A�ޏ��ɂ��ď������B�u�ޏ��͕ʋ��Ɨ����Ɍ����ĊÂȂ������B�����āA���̋C���́w���f�B�A�x��A�z��������̂ɂȂ��Ă����B���̂��Ƃ��A��l�̒j�̎q�����Ƃ̊W���Â����̂ɂ������A���͔ނ���A�₳���������Ă����B���̐l���ɂ�����A���̔ߌ��I�l���́A��������ɂȂ�܂ő����A�������邱�Ƃ͂Ȃ������B�v �A���o�[�g�ƃG���U�́A1919�N6��2���Ɍ��������B�ނ�40�ˁA�ޏ���43�˂ł������B�ނ�̓G���U�̃A�p�[�g�ɋ����\�������A�A�C���V���^�C���̌����Ƌx���̏ꏊ�Ɏg����̊K��2�������A����ɉ�����ꂽ�B���܁A�}�Ɉݒɂ��N���邱�Ƃ��܂����������A�������A1920�N�ɔނ̓x�b�\�[�ɁA�ƂĂ��悢���N��Ԃɖ߂��ό��C���Ə������B���Â��ŁA�g���݂�����A��̂悤�ŁA���T�^�I�Ȓ��Y�K���ł���G���U�́A�ޏ��̃A���o�[�g�̐��b������̂��D�B�ޏ��͔ނ̖������ւ炵���Ɋ�B �A���o�[�g�ƃG���U���������āA���N��ɁA�ނ̕ꂪ�x�������ɂ���ė��āA���q�̉ƂŎ��B �A���o�[�g�̕�A�p�E���[�l�̈ꐶ�͈��y�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B1902�N�ɕv������ꂽ���Y�Ɩ������̂܂ܔޏ����c���Ď���A�ޏ��͍Ȏq�w�b�q���Q���ɂ���o���̃t�@�j�[�̂��Ƃɍs���A�؍݂����B���̌�A�ޏ��͒������ԃn�C���u�����ōȂ��Ȃ������I�b�y���n�C�}�[�Ƃ������O�̋�s�Ƃ̉ƂɏZ�ݍ��݁A��Ƃ̐萷��Ɣޏ���炤���l�̗c���q�ǂ������̋���Ƃ����d�����B��ɔޏ��́A�ꎞ���A�ޏ��̂���߂̌Z�탄�R�u�E�R�b�z�̉Ƃ̐��b�����A���ꂩ��A���c�F�����Ɉڂ�A���}���Ƃ��̕v�p�E���E���B���e���[�̉ƂɈꏏ�ɏZ�B ���̂��Ƃɑ؍݂��Ă���ԂɁA�p�E���[�l�͕����̃K���ŏd�a�ɂȂ�A���[�[�i�E�E�T�i�g���E���ɓ��@���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���̌�A�܂��Ȃ����āA�ޏ��͑��q�ƈꏏ�ɂ������Ƃ������Ƃ���Ɋ�]�����B1920�N�̏��ߍ��A�}���A��t�A�����ĊŌ�w�ɕt���Y���ăp�E���[�l���A�x�������ɓ��������B�ޏ��̓A�C���V���^�C���̏��ւɐQ�����ꂽ�B�ޏ���2���Ɏ��������B �A�C���V���^�C���̎莆�B�u�ꂪ�S���Ȃ����E�E�E�������͊F������������Ă���B���̂Ȃ���̏d�݂��F�A���̐��܂Ŋ����Ă���B�v |
|
| ���ˑR�L���ɂȂ����A�C���V���^�C��(1919�N5��29�� / ���H�̊ϑ�) | |
|
1919�N�̏��H�A��p�E���[�l�E�A�C���V���^�C�����A�T�i�g���E���ɂ����Ƃ��A�ޏ��͑��q����A�͂�������������A����͎��̂悤�ȏ����o���ł������B�u��������A�����͂��ꂵ���j���[�X�ł��B���[�����c���A�p���̊ϑ��������z�ɂ����̕Ό������ۂɗ������Ɠd��Œm�点�Ă��܂����B�v�����O�ɁA�A�C���V���^�C���ɁA���̃j���[�X��m�点���d��́A�u�G�f�B���g�������z�̉��Ő��̕ψق������B�\���I�Ȓl�́A0.9�b�ƁA����2�{�Ƃ̊Ԃł���B�h��B���[�����c�B�v�ƂȂ��Ă����B����́A������̒ʐM�ł������B�������m�肵�Ă��Ȃ������B����ł��A�A�C���V���^�C���́A�������Ă����B
���̘p�Ȃɑ���A�C���V���^�C���̗����̐i�����A��Z���ɗv�悤�B1907�N�A�x�����̓����ǂ̎��������u���������v�����A���̌����́A���ꂾ���Ō����������Ȃ��邱�Ƃ��Ӗ�����ƒm��B�������A���̌��ʂ́A���܂�ɏ������āA�ƂĂ��ϑ��ł��Ȃ��Ǝv���B1911�N�A�v���n�̋�������A�ނ́A���̌��ʂ͊F�����H�̍ۂɁA���z�������߂Ēʂ鐯�̌��ɂ��Č��o�\�Ȃ��ƁA�����Ă��̏ꍇ�A�p�Ȃ̑傫���́A0.87�b�ł��邱�Ƃ����o���B�������A�u��ԁv���Ȃ����Ă��邱�ƁA�����āA����䂦�ɁA�ނ̓������Ԉ���Ă��邱�Ƃ�ނ͂܂��m��Ȃ��B�ނ͂܂��A�j���[�g���ɋ߂��B��Ԃ����R�ł���ƐM���Ă����j���[�g���́A����̏d�̖͂@���ƌ��̗��q������A0.87�b --- ���݃j���[�g���̒l�ƌĂ�Ă��� --- �������Ōv�Z�ł����͂��ł���B1912�N�A�`���[���b�q����A�u��ԁv�͋Ȃ����Ă��邱�Ƃ�����B���N�o���āA�ނ͋�Ԃ̋ȗ������̘p�Ȃ̒l��ς��邱�Ƃ𗝉�����B1915�N�A�ނ́A��ʑ��ΐ����_�ɂ��A���z�ɂ����̘p�Ȃ́A1.74�b --- �A�C���V���^�C���̒l�ŁA�j���[�g���̒l��2�{ --- �ɓ������Ȃ邱�Ƃ�����B����2�{�Ƃ������q�́A�j���[�g���ƃA�C���V���^�C���̑Ό��̂��V���Ă�����B �A�C���V���^�C����������������ȑO��1914�N�ɁA�ނ̓x�b�\�[���ɔނ炵�����M�������ď����Ă����B�u���H�̊ϑ����������悤�Ƃ��܂��ƁA���͎��̗��_�̌n�����͂�A�܂������^��Ȃ��B�v ���j�̂������̋C�܂���̂������ŁA�ނ͌�������ʂ̏�ɗ��_��ςݏグ��Ƃ������f����~��ꂽ�B�܂�A1912�N�A�u���W���ɏo�������A���[���`���̓��H�ϑ����́A���̕Ό��������v��ɉ����Ă����ɂ�������炸�A�J�̂��ߊϑ��𒆎~�����B�܂��A1914�N�̉ĂɁA�G�����B���E�t���C���g���b�q���������h�C�c�̊ϑ������A8��21���̓��H���ϑ����邽�߂ɃN���~�A�����ɂނ��������A��ꎟ��킪�u���������߂ɁA�����߂�悤�ɑ��͌x�����A���l���͂��������B�S�O�����҂͑ߕ߂��ꂽ���A�Ō�ɂ͈��S�ɁA�������A�������̂��Ƃ����A���̌��ʂ��������ɋA�������B1916�N�̃x�l�Y�G���ɂ�������H���ϑ�����@��͐푈�̂��߂Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�ߋ��̓��H�̍ۂɎB�����ʐ^�ŕΌ���T���Ƃ��������̎��݂���́A���������Ȃ������B1918�N6���̓��H�̊��ԂɁA���̌��ʂ��v�낤�Ƃ���A�����J�̓w�͂��A����I�Ȍ��ʂ������炳�Ȃ������B 1919�N5��29���̓��H���ϑ����邽�߂ɁA�G�f�B���g��������ϑ����́A��吼�m�A�X�y�C���̐ԓ��M�j�A�̊C�݉��A�v�����V�y���֏o�������B�o���ɐ旧���āA�G�f�B���g���͏������B�u���̓��H�ϑ����́A���߂Č��̏d��(���Ȃ킿�A�j���[�g���̒l)�𗧏��邩���m��Ȃ��B���邢�́A�[�N���b�h��ԂƂ����A�C���V���^�C���́A�˔�ȗ��_�̊m�邩���m��Ȃ��B���邢�́A�Ȃ�������������ȋA��---�Ό��Ȃ��Ƃ������ʂɓ��B���邩���m��Ȃ��B�v 5��29���A�吼�m��́A������܂��Ă����B�������A�₪�ċ�͐���A���H�̉e�̒��ŁA���̘p�Ȃ͊ϑ����ꂽ�B11���ɂȂ��āA���̌��ʂ������ɔ��\���ꂽ�B 1919�N�t�A��ʑ��ΐ����_��������閳���f�悪�A���J����Ă����B��̎ʐ^�͂��̉f��̈�R�}�ł���B �@ |
|
| ���ˑR�L���ɂȂ����A�C���V���^�C��(�����̒a��) | |
|
���H�̊ϑ����ʂ́A1919�N11���ɔ��\���ꂽ�B�܂������A���ɂ��āA�A�C���V���^�C���́A���E�̗L���l�ɂȂ����B20���I�ŏ��́u�X�^�[�Ȋw�ҁv�̒a���ł���B���̂Ƃ��A�����Ƃ��ẴA�C���V���^�C�����A�ł����������B�u�m���̉��g�v�u�e���݂₷���������ɂ������ҁv
���́A1919�N�A��ꎟ���E��킪�I���A���E�͍������Ă����B���X�͔��ʂāA�h�C�c�鍑�͕��ꋎ�����B�����ɁA�A�C���V���^�C���Ƃ����j������āA�����������킯�ł���B�u���́A�����ɁA�F���ɂ͐V�����@�������邱�Ƃ�錾����B�v����́A���j�I�u�Ԃ������B���ׂƂ��������̒��ŁA���ɂ���������ꂽ�B���[�[���A�Δ������āA�R����~��Ă����悤�������B �h�C�c�̊w�҂ł���A�C���V���^�C�����A�t�����X�̑�w����A�w�ʂ����Ƃ��A�ނ͂��łɁA�w����z�������݂ƂȂ��Ă����B�A�C���V���^�C���́A���a�ւ̊�]��\���V���{���������̂��B���āA����قǁA��O�̐l�C���Ȋw�҂͂��Ȃ������B������l�̃X�[�p�[�E�X�^�[�F�`���b�v�����Ƃ̉�B�`���b�v�����H���u���ɐl�C������̂́A�N�ł����𗝉��ł��邩��ł��B�Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C������A���Ȃ��ɐl�C������̂́A��O�̒N�����A���Ȃ��𗝉��ł��Ȃ�����ł��B�v �A�C���V���^�C���̉�z�u�������܂��ɘA��āA���́A�ǂ�ǂ�����ɂȂ��Ă����܂����B�������A����́A���ɂ���ӂꂽ���ۂŁA�I�݂ȃ��[���A�ƂƂ��ɁA���ׂĂ�����Ȃ���Ȃ�܂���B�`���b�v�����́A���ꂪ�o���Ă��܂����B�ނƉ�����Ƃ��A�������́A��l�̖����ĂԌQ�O�Ɉ͂܂�܂����B�w����́A�ǂ������Ӗ����낤�x�Ɣނɐq�˂�ƁA�`���b�v�����́w�Ӗ��͂Ȃ��̂��x�Ɠ����܂����B�v �@ 1920�N��A�ȃG���U�́A�㏸�������̕v�̒n�ʂ�傢�Ɋy���B�������A�A�C���V���^�C���́A��l�̊ԂɁA��������Ƃ��������Ђ��Ă����B�Q���͕ʁX�A���ւɂ͗������点�Ȃ��B�����āA�ނ͊O�ŁA�N�Ⴂ���������Ƃ������Ă����B �A�C���V���^�C���̉�z�u�����Ƃ́A���R�̌��ʂ��������悤�Ƃ���A�����̌����݂̂Ȃ���Ăł��B�����͂��ׂĊ댯�ł��B�v �A�C���V���^�C���́A�킸��킵�����Ƃ̂Ȃ��Z�b�N�X��]��ł����B�ƒ�ł��A�ɗ́A�킸��킵��������Ă����B�A�C���V���^�C���́A�����̋`�����ŏ����ł��ނ悤�Ȍ`�ŁA������ǂ����߂��B���y�̒Nj��͑��������A�������A�����w�̌����������ŗD�悾�����B �A�C���V���^�C���̉�z�u�F�l�̃~�P�[���E�x�b�\�́A��l�̏����Ƃ����ƈꏏ�ɁA�K���ɕ�炵�܂����B���́A2�x���s���܂����B������A���Ȃ�s���_�Ȍ`�ŁE�E�E�B���́A�l�Ԃ�������Ǝv���܂����A�j���Ԃ̌l�I�ȂȂ���Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B���́A�P�Ƃő��鑕���������n�̂悤�Ȃ��̂ł��B2�����Ă�W�c�͂��߂Ȃ�ł��B�v �@ |
|
| �����{�K��ƃm�[�x���� | |
|
�吳����Ɉꐢ���r���������G���u�����v�̔��s�������Ђ̎В��R�{���F(���˂Ђ�)���́A���s��w�̓N�w�������c�E���Y�A���k��w�̗��_�����w�����Ό��������̂����߂ɂ���āA�A�C���V���^�C������{�֏��҂���v��𗧂Ă��B
�A�C���V���^�C���͐��E�e�n�𗷍s�������A�����̗��s�͂��ł��A�����I�ȋْ��Ɍ��т����Ă���A���������Ĕނ́A�ނ̌������ނ̓G�ɂ���Ĉ��p����Ȃ��悤�ɂƂ����C��z���Ă��Ȃ���Ȃ炸�A���̂��߂Ɋe�n�̒��������i��K����S����y���ނƂ����]�T�������Ƃ��ł��Ȃ������B �������A�ɓ��̓��{�𗷍s����ꍇ�ɂ́A���̂悤�ȋْ�����͂܂������������āA�S���炻�̗��s���y���ނ��Ƃ��ł���ł��낤�A�C���V���^�C���͍l�����B ���̂Ƃ��̎�����A�C���V���^�C���́A������T�Ԍ�ɏ������u���{�ɂ����鎄�̈�ہv�Ƃ������͂̒��ł��̂悤�ɂׂ̂Ă���B �u������A�O�N���͐��E�̊e�n�𗷍s�����B����͈�l�̊w�҂ɂƂ��Ă͑��������B���̂悤�Ȏ�ނ̐l�Ԃ́A�������ɂƂǂ܂��ĐÂ��ɕ����Ă���ׂ����̂��ƍl���Ă����B�����玄�͂����A���s�ɑ���\����܂��͗��R���l���o���āA����ň��S���Ă����̂��B���܂܂ł̑����̗��s�ɂ́A���傤�Ǔs���̂悢�\�����������̂�����A���قǕq���łȂ����̗ǐS���A�����܂����̙�ӂ���Ƃ꓾���悤�Ȏ���ł������B�Ƃ��낪����R�{������w���{�֗��Ă݂���ǂ����x�Ƃ̏��҂��������Ƃ����̍l�������\����́A���܂܂ł̂Ƃ͑S�R���̐������قɂ��Ă����B�Ƃ����̂́A�w�������̋@����������Ȃ�A�������{�֍s���@��͗��Ȃ������m��Ȃ��B���̋@�����O�Ɍ��Ȃ��炻��𗘗p���Ȃ������A�Ƃ�������͈ꐶ�Y����܂��x�Ƃ����������A��A���ǂ��납�A���N����N�����̎��Ԃ��Ԃ��Ȃ���Ȃ�ʓ��m�ւ̗��s�����S���������R�ł������B �������{���珵�҂��ꂽ�Ƃ������Ƃ������Đl�X�͔��ɑA�܂��������B�x�������ɏZ��ł��Ă���قǑA�܂�����ꂽ���Ƃ͂͂��߂Ăł������B���ǂ��ɂƂ��ẮA���{�Ƃ������́A�����x�[���ɕ�܂ꂽ�s�v�c�ȍ��Ǝv���Ă���B���̖��̍��Ɏ��͂�ꂽ�̂��B���{�l---�h�C�c�ł͗҂������炵�A�M�S�ɕ����A�e�ɏ��Ă���A���̓��{�l�̏Z��ł��鍑�Ɏ��͂�ꂽ�̂��B���{�l�̂��̔��I�@���̔��̔w��ɂ́A�����̐S�Ƃ͎��ƌ`���قɂ����₳�������{�̐S�������Ђ���ł���B�����Ȃ��킢�炵�����{�̊���A�Ƃ��ǂ����s������{���̓ǂݕ��Ɍ���Ă�����{�̋C�����ǂ�Ȃɂ����̂���ƈقȂ��Ă��邱�Ƃł��낤���v �����ŃA�C���V���^�C���́A1922�N��9���Ƀ��C�v�`�b�q�ŊJ����鎩�R�Ȋw�҉�c���I������Ȃ�A���̂��Ɠ��{��K�₵�����Ƃ����Ԏ����A�����ЎВ��̎R�{���F���ɂ����̂ł������B �������ăA�C���V���^�C���́A1922�N��10��8���A�}���Z�[���o���̓��{�X�D�̖k��ۂɁA�v�l�����ŋq�ƂȂ����̂ł���B �A�C���V���^�C���v�Ȃ��̂����k��ۂ́A�ꃖ���ȏ�ɂ킽��q�C�̂̂��ɁA11��13���ɏ�C�ɒ����A11��17���ɂ͐_�˂ɓ��`���邱�ƂɂȂ��Ă����B ���̖k��ۂ���C�Ɍ������ċ}���ł���11��10���̂��Ƃł��������A�X�G�[�f���̉Ȋw�A�J�f�~�[�̃m�[�x���܈ψ���́A�A�C���V���^�C���ɑ��ăm�[�x�������w�܂�^����Ƃ������Ƃ\�����B ���łɂׂ̂��悤�ɃA�C���V���^�C���́A1905�N�ɁA19���I�܂ł̕����w�����������A20���I�̕����w���x�z����Ǝv������ꑊ�ΐ����_���d�͏�̑��݂���ꍇ�֊g�����邱�Ƃ����݁A����1916�N�ɂ������ʑ��ΐ����_���������A���̗��_�́A1919�N�̓��H�ϑ��ɂ���Č����Ɏ�����Ă����̂ł���B ����قǂ̎d���������A�C���V���^�C���ɑ��āA�X�G�[�f���̃m�[�x���܈ψ���m�[�x���܂�^����̂ɂ������������Ԃ�v���Ă��܂����̂́A���̂悤�ȗ��R�ɂ����̂ł���B �܂����ɁA�A���t���b�h�E�m�[�x���́A���̃m�[�x�������w�܂�ݒ肷��ɓ����āA�܋��́A����ɂ���Đl�ނ����ɑ傫�ȗ��p���l��悤�ȁA�����w�̍ŋ߂̔����ɑ��ė^������ׂ��ł���Ƃ������Ƃ��K�肵�Ă���B �Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�́A�ŏ��́A�V�������ۂ��咣������̂ł͂Ȃ��A����܂łɒm���Ă��������̌��ۂ�I�ɁA���ȒP�ɗ��������̌�����^������̂ł������B���������Ă��ꂪ�ʂ����āu�����v�ł��邩�ǂ����́A�l�X�ɂ���Ĉӌ����킩���Ƃ���ł������B�܂��Ă�A���ꂪ�l�ނɂƂ��đ傫�ȗ��p���l�̂�����̂��ǂ������A�l�X�̈ӌ��ɂ܂������ׂ����ł������B ���ɁA�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�́A�����ɗ��_�����w�̗��_�ł���ɂ�������炸�A���Ԃ����ɂ�āA����͐����I�Ș_���̓���Ɏg����悤�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B���̎����������悤---�����̔M���I�ȃh�C�c���Ǝ�`�҂����́A��ꎟ���E���ɂ�����h�C�c�̔s�k�́A�h�C�c�̍��͂�R���͂͐��E����ɂ��Ă������ĂЂ����Ƃ���̂ł͂Ȃ������ɂ�������炸�A���_���l�ƕ��a��`�҂��h�C�c�𗠐������ƂɌ������������ƐM���Ă���---�Ƃ���ŁA�A�C���V���^�C���͂��̃��_���l�ł���A���������a��`�҂ł������B�����Ă��̃A�C���V���^�C���́A�h�C�c�̓G�C�M���X�̊w�҂������F�߂����䂦�ɗL���ɂȂ������ΐ����_�ɂ�閼���𗘗p���āA�����A���_���l�ƕ��a��`�̂��߂̉^����W�J���Ă���---�ȏ�̎���炵�āA�����X�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[�̃m�[�x���܈ψ���A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�ɑ��ăm�[�x���܂�^����Ƃ������Ƃ�����A����̓X�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[���A�����I�ɃA�C���V���^�C���̑��ɗ����ƂɂȂ�A�X�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[���܂��A�����I�_���̉Q�Ɋ������܂�Ă��܂������ꂪ����B �ȏ����A�X�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[�̃m�[�x���܈ψ���A�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�ɑ��ăm�[�x���܂�^���邱�Ƃ����߂���Ă����傫�ȗ��R�ł������B �Ƃ��낪�A�X�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[�́A�ȏ��̂��Ƃ��I�݂ɂ����āA�A�C���V���^�C���Ƀm�[�x���܂�^������@���v�������B ����́A�A�C���V���^�C���ɁA���̑��ΐ����_�ɂ�����Ɛтł͂Ȃ��A���̌��ʎq�̗��_�ɂ�����Ɛтɑ��ăm�[�x���܂�^����Ƃ������Ƃł������B �A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�́A�w�҂̊Ԃ���łȂ��A���E�̑�O�̊ԂŘb��ɂ����قǗL���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��A���ꂪ�����̋�ɋ������Ƃ������Ԃ܂ł܂˂��Ă��܂��Ă������A�A�C���V���^�C���̌��ʎq�̗��_�́A�w�҂̊Ԃ����Œm���Ă���A���ΐ����_�ɂ��Ƃ炸�����ꂽ���_�ł������B ���������̌��ʎq�̗��_�ɂ����ẮA�������Ɏ�������������Ă����B �����ŃX�G�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[�́A�u1921�N�x�̃m�[�x���܂́A���d���ʂ̖@���Ɨ��_�����w�̗̈�ɂ�����d���ɑ��āA�A�C���V���^�C���ɗ^����ꂽ�v�Ƃ������Ƃ��A1922�N��11��10���ɔ��\�����B �A�C���V���^�C���͂��̒m�点���A��C�������������k��ۂ̑D��ł������킯�ł��邪�A���̖k��ۂ́A11��13���̌ߑO11���̏�C�ɓ��`�����B ���̎��̗l�q���A11��14���t�̓ǔ��V���͂��̂悤�ɓ`���Ă���B �D���ɃA�C���V���^�C�����m��K�˂�ƁA���������m�[�x���܂����^���ꂽ�Ƃ̕�ɐڂ��A���f�̑�(�Ă�)�ŁA�����̊w���͂���قǂɒl������̂ł͂Ȃ��ƌ������A���E��12�l�������̊w���𗹉���������̂͂Ȃ��Ƃ�������ے肵�A�ӂ��̉Ȋw�I�m���̂���l�Ȃ�Ή��l���悭����������ł��낤�Ƃׁ̂A�Ȃ��{�N�N���X�}�X���ł̓��H�̎����́A�V���������̂ōD���ʂ͓����Ȃ������ƌ�����B���m�͎��f�Ȕw�L���ŁA�@���Ƃ̂悤�ȉ��a�ƌ����̑ԓx�Őڂ������A���{�l�Ƃ͊w�K�I�e�a�������Ă���Ƃׂ̂Ă����B �@ |
|
| �����{�ɂ�����A�C���V���^�C�� | |
|
���āA�A�C���V���^�C���v�ȂƁA��C�܂ŏo�}���������ЎЈ���_��펁�Ƃ��̂����k��ۂ́A11��14���̒���C���o�����Đ_�˂Ɍ��������B
�k��ۂ��_�˓��`�\���11��17���́A�������̉J������āA���t���a�̓��ł������B���̂Ƃ��̗l�q���A�A�C���V���^�C�����g�͂��̂悤�ɂׂ̂Ă���B �u�F�X�Ƒz���͂��Ă������̂́A���{�Ƃ������̂m�ɓ��ɂ����ׂĂ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�k��ۂ����˓��C�ɓ����ė̓��X�������ɏƂ炳��Ă���̂������Ƃ��A���̍D��S�͋ɓx�ɋْ������B�D�q�ƑD���̊�͊�тɂ����₢�Ă����B�����Ȃ璩�H�̑O�ɂ͊���݂��Ȃ��₳�������{�̕w�l�������A���̘Z���Ƃ����̂ɁA�����f�b�L�ɂƂяo�āA�ꎞ�������̍��̓y�����悤�ƕ�������Ă����B�����������ӂ��Ă����ɂ�������炸�A�l�X���������������ڂ��Ă���̂��݂Ď��̐S�͓������ꂽ�B���{�l�͂��̍��y�Ƃ��̍����������Ă���B�����炭���{�l�قLj����S�̋��������͑��ɂȂ��ł��낤�B���{�l�͊O������悭�b���A�O���̎���ɑ��đ傫�Ȍ����S�������Ă���B����ɂ�������炸���{�l�́A�O���ł͂��������̋q�ł���Ƃ�����������̂���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̗��R�͂Ȃ�ł��낤���ƁA���͍l���Ă݂��B�v �k��ۂ́A�ߌ�ɁA�_�ˍ`�̘a�c���ɂ��̎p���������B �A�C���V���^�C�����o�}���邽�߂ɐ_�˂ւ��Ă����A������w�̒��������Y�����A���k��w�̈��m�h�ꋳ���A��B��w�̌K�؈��Y(���₨)�����A���k��w�̐Ό��������A�����Ђ̎R�{���F�v�ȁA����ɑ����̐V���L�҂́A�����o�}���̃����`�Ŗk��ۂ��������B �A�C���V���^�C���́A�o�}���̐V���L�҂����ɂ��̂悤�Ɍ���Ă���B �u���́A���_�̒����ɂ���Ă͂��߂ē��{��m��A���̍������ɂ͂ӂ��������Ă��܂��B���{����x�K�₵�Ă݂����Ƃ͎v���Ă���܂����B���̂��щ����Ђ̏����ł��悢����{��K�₷�邱�ƂɌ��܂�܂����̂ł����A���͑��ΐ����_�̒m������{�̐l�ɗ^����ƂƂ��ɁA�܂����{������������ċA�肽���Ǝv���Ă��܂��B���̊w���͂��ׂĊm�M�̏�ɗ����Ă��܂����A����ł��ǂ����ł���ɐV�������������邩���m��Ȃ��Ƃ������āA���܂Ȃ��ӂ炸�ɂ���������������Ă��܂��B���͓��{�Ɉꃖ���]��؍݂���\��ł����A���̊Ԃ������ɔ�₵�����Ǝv���܂��v �A�C���V���^�C���v�ȂƏo�}���̐l�������̂����k��ۂ́A�ߌ�l�������_�ˍ`�̑�O�˒�ɉ��Â����ꂽ���A�_�˂̍`�́A���̗L���ȃh�C�c�̗��_�����w�҂���ڌ��悤�Ƃ���l�����ł��ӂ�Ă����B �A�C���V���^�C���v�Ȉ�s�́A�_�˂̃I���G���^���E�z�e���ŏ��e�̂̂��A�ߌ���A�O�m�{���̗�Ԃŋ��s���������B�r�����w�ł́A�V����ٓ��̔���q�̂�ѐ���ʔ��������A�C���V���^�C���v�l�́A����͈��̓��{���y���Ƃ��̒��q��^���Ă���ɋ������B ���̓��A�C���V���^�C���v�Ȃ́A���s�̒������肵�����ƁA�ڂ�ڂ�̂Ƃ����Ă���s�z�e���ŁA���������ڂ̖�����������B ��11��18���́A�ӂ����ы��s�������Ԃň��肵���̂��A�A�C���V���^�C���v�Ȃ͋D�Ԃœ������������B���̓��͉_��Ȃ��H����ŁA�A�C���V���^�C���v�Ȃ́A���i�A�փ����A�l���̏H�i�F�A�����Đ�������������x�m�R�ȂǁA�ԑ�������{�̌i�F���\���Ɋy���ނ��Ƃ��ł����B �������āA�A�C���V���^�C���v�ȂƂ��̈�s���̂������}��Ԃ́A11��18���̌ߌ�7��20���ɓ����w�ւ��ׂ荞�B ���̓����w�̃v���b�g�z�[���́A���S�̏o�}���̐l�����Őg�������ł��ʂقǂł������B �����̎ʐ^�ǂ̂����}�O�l�V���[���̉��Ɛl�����������킯�ĕv�Ȃ����D�������ƁA����ɂ܂������Ă�������̐l�����́A�X�q��U��A����������̊��Ă����т��A���������ĕS���̂悤�Ȗ��̐������������B �A�C���V���^�C���v�Ȃ́A�X�e�[�V�����E�z�e���ŏ��e�̂̂��A�����w����鍑�z�e�����������B���̒鍑�z�e���ɂ́A���}�̉ԑ��ł�����ꂽ�������v�Ȃ̂��߂ɗp�ӂ���Ă����B�A�C���V���^�C���́A�u���̕����͂��܂肺�����������܂��B���̃z�e���͑�w���̋C�ɓ���܂������A�����Ǝ��f�ȕ����ƂƂ肩����悤�R�{���ɓ`���ĉ������v�ƌ��������A�R�{���F���́A�u���͗��s�����āA�ł��邩����̂��Ƃ����Ȃ����ɕ���������]�������Ă��܂��A���̐��ӂ����͐������Ă������������Ǝv���܂��v�Ƃ����咣�ɂ�����������Ă��܂����B ���̗�����11��19���ɃA�C���V���^�C���́A�c��`�m��w�̑�u���ŁA�u���ꂨ��ш�ʑ��ΐ����_�ɂ��āv�Ƃ�������ōu�����s�����B �A�C���V���^�C���͂܂��A�a���p�̐Ό������m�̒ʖ�ŁA�ꎞ������l�����܂ł̎O���Ԃ��A���ꑊ�ΐ����_�ɂ����x�X(������)�Ɛ����Ă������B �����āA�ꎞ�Ԃ̋x�e�̂̂��A����Ɍ������玵���܂ł̓ԁA����ǂ͈�ʑ��ΐ����_�ɂ��Ęb�������B �������ăA�C���V���^�C���́A��������ڂ̍u����́A�ʖ���܂߂Č��Ԃ��������킯�ł��邪�A�Ō�܂ł����M�S�ɂ������A��琔�S�l�ɂ���ԓ��{�̑�O�̑ԓx�́A�A�C���V���^�C���ɐ[��������^�����B ���̂��Ƃ���ǔ��V���̋L���́A���̍Ō���u���O�͂Ȃ����Ȃ����Ԉ�l�����h�����ɐÂ��ɂ����Ă����B�A�C���V���^�C�����̐��͋�����ӂ�悤�ɉ��y�I�ł���A�Ό����m�̐����͏��q�ǂ��ɂ���������錾�t�g���ł���B��琔�S�̒��O�́A�����͂킩��˂ǁA�܂�������킳�ꂽ�B���傤�ǃA�C���V���^�C�����̍Ö��p�ɂł����������悤�Ɂv�Ƃ������t�Ō���ł���B ��11��20���̌ߌ�́A�A�C���V���^�C���v�Ȃ́A���ΐ�̐A�����ŊJ���ꂽ�w�m�@�̌������}��ɏo�Ȃ����B�����Ė�͖������œ��{�̎ŋ������������B �A�C���V���^�C���̓����ɂ��������ڂ̍u����́A11��24���ɁA�_�c�̐N��قŊJ���ꂽ�B���̂Ƃ��̉���́u�����w�ɂ������ԂƎ��Ԃɂ��āv�ł��������A������A�[���̌�������A�r���ꎞ�Ԃ̋x�e�����ď\���܂ő������B���̂Ƃ��͒��O�͑O��ɂ��܂��ē��ɂ��ӂ�A����ł��Ȃ������l�̐������������B �ȏ�́A���ΐ����_�ɊS�������Ă����ʑ�O�̂��߂̈�ʍu���ł��������A�A�C���V���^�C���̊w�p�u���́A11��25������A���j���x���12��1���܂ł̘Z���ԁA�����ߌ����ꎞ�Ԕ��A������w���w�������w�����̒����u���ōs��ꂽ�B �A�C���V���^�C���͂��̍u�`�̑����ڂɂ͋�ԂƎ��Ԃ̑��ΐ�������A�����ڂɂ͎��R�@���̓��[�����c�ϊ��ɑ��ĕs�ςł���ׂ���������A�~���R�t�X�L�[�̎l�������E�ɂ�����e���\���㐔�w��W�J�����B�����đ�O���ڂɂ́A�e���\���̔��������āA�}�N�X�E�F���̓d���������ɋy�B ��l���ڂ���͈�ʑ��ΐ����_�̐����ɓ���A��l���ڂ́A���[�}���w�ƃe���\����͊w�̐����ɔ�₳�ꂽ�B��ܓ��ڂɂ́A�d�̗͂��_�ɓ����āA�d�͏�ł̌��̕Θ߁A�܂������̋ߓ��_�ړ��Ȃǂ̎������������ꂽ�B �����čŌ��12��1���́A�F���_�I�Ȗ��̐����ɔ�₳�ꂽ�B �������āA�A�C���V���^�C���ɂƂ��ẮA�����ȗ���w�Z�������������Ă������킯�ł��邪�A11��30���t�̓ǔ��V���ɁA�A�C���V���^�C�����m�̃z�e�������Ƃ����L���������Ă��邩��ȉ��Ɉ��p���Ă݂悤�B �u�����ȗ��̃A�C���V���^�C�������́A�����Ԃ�Z�������[���߂����Ă���B�[�H�Ȃǂ͂����Ă��z�e���ŐH�ׂȂ��قǂŁA�v�l�����ʼn���牃��A���҂��珵�҂Ƃ��Â��āA���߂���o�Ă����ƃz�e���ւ͖�\���O�ɂ͂قƂ�ŋA�������Ƃ��Ȃ��B���͔������ɂ͂�����悤�����A�㎞������܂ł͐�Ε������̋��d����ꂸ�A�h�A�̏�ɂ́w�m�b�N�����Ă͂����Ȃ��x�Ə������D�������Ă���B���̂킸���ꎞ�Ԃ��炢�������̂����錤���ɂӂ����Ȏ��Ԃł���炵���B�㎞����͕v�l�ƂƂ��ɕ����֔��ȊȒP�ȐH�����^���Ă������߂Ȃ���A�莆���K��q���̖��h������B�������X�̂����ɂ͂����Ԃ�K��q�����������A�����v�Ȃ̓̂ق��ɁA�����Ђ��ꎺ���肫���ĖK��q�̒��掟������Ă���̂ŁA���̂���͂���ȂɖK��q�ɂ͐ڂ��Ȃ��B���H�͕����ł������H���֏o���肷�邪�A�����ł��Ƃ��͈�i����i�A�ق�̂����邵�̕����Ƃ�A���ׂȂ��������ʂɂ��Ȃ��A�������킾��������Ԃ肪�ڗ��Ƃ����B�A���R�[�������܂ނ��̂͐�ɂ����āA�����Â��Ȏ������������A�����������͔��ɂ������Ɨ������������̂ŁA���̑��̂悤�ȓ������قƂ�ǎ��������Ȃ��������B�Ȃɂ�����d�ɏ����Ȃ��Ƃ����Ă�����Ă��A��X���J�ɗ�̕��₳�������q�ł���������A�����͂�����ƕЂÂ���Ƃ����ӂ����B�z�e�����̑��̔��܂�q�͂�������h�ӂ�\���Ă��邪�A�v�l�����ɋߊ�Ȃ̂ŁA�Ƃ��ǂ��܂������đ��l�̕����֓������肵�ď����Ȋ��m���̂����B���̂܂��v�l�̍s���ɐM���������Ă��锎�m�́A���̂܂ܕv�l�ɂ��Ă��̕����ɓ��荞�݁A�w��̗E�҂��������ɂ����Ԃ鋰�k���āA�����ӂ��Ɠ����������Ƃ��Ƃ��ǂ�����B �����C����ύD���ƌ����A�ǂ�Ȃɂӂ��Ă������Ƃ����ɂ͂��邪�A�\�����đł��Ƃ��ĕv�l�ƌ��Â��Ă��邱�Ƃ�����Ƃ����B�ו��Ƃ����Ă��v�w�Ńg�����N���܂ŁA���낢��̕����������Ă��Ă���悤�����A�ǂ��������т����肷��قǎ��f�Ȃ��̂ł���Ƃ����B�����͐Q���ւ͂���ƁA�����Ȃ邱�Ƃ������Ă��A�ǂ�ȋߐe�҂������˂Ă��Ă��A���˂Ă����h�A���J���ʐl�Ƃ��ĕ]���ł���B�����́w�������Q���ɓ���Ƃ��́A���̒��̂��ׂĂ��犮�S�ɂ܂ʂ����Ƃ��ŁA���������̎��������l���Ȃ��B���ׂĂ�Y��Ă��������݂̂�S������B���̊w�҂͖��̂Ȃ��ŕ��������l�����ȂǂƂ������A�����͂��ׂĂ�Y��Ă������炩�ɖ���Â��邾���ł���x�Ƃ����Ă��邻���ł���v ���āA�A�C���V���^�C���̓��{�ɂ�����X�P�W���[���͂��Ȃ肫�����̂ł������B 11��17���ɐ_�˂ɒ����A11��18���ɓ������肵�Ă���A12��1���܂łɁA��̈�ʍu���ƘZ���ɂ킽��w�p�u�����s�������A�����12��2���ɂ́A�������Đ����������B �����Ă��̗�����12��3���ɂ́A�ߑO�㎞����A���s����ŁA�������̒��O��O�ɂ��āA���m�h�ꎁ�̒ʖ�ŁA�ߌ���܂ŁA���������ΐ����_�Ɋւ����ʍu�����s�����B�����́A���s���͂������A�ߌ�����A�܂��������璮�u�ɂ����l�������A�u����͔��Ȑ���ł������B �u����́A�A�C���V���^�C���v�Ȃ͌ߌ�O����䔭�̗�Ԃŏ����Ɍ������A������V�����A�����ė�12��4���̒��������ɐ����o�����ē����������A�����ŗ����ȗ��͂��߂ē���Ԃ̐Â��ȋx�{�̎��Ԃ��Ƃ����B �������A12��6���ɂ͓����ɋA��A�����������������A12��8���ɂ͖��É��ŁA10���ɂ͋��s�ŁA11���ɂ͑��ŁA13���ɂ͐_�˂ŁA���ꂼ���ʍu�����s�����B ���̌�A�C���V���^�C���v�Ȃ͓͂ޗǂƋ{�����������āA12��23�����i�ɓ������A����͖�i�̎O��N���u�Ɉꔑ�����B �����Ă��̗����A12��24���́A�����s�̑唎����ň�ʍu�����s���A25���ɂ͋�B��w��K�₵���B �������Ĕ��m�v�Ȃ͖�i�œ��{�ł̍Ō�̐������߂��������A���̍Ō�̖�12��28���̖�ɂ́A��i�N���u�ɂ����钷��O�䕨�Y�x�X���̏��҉�ɏo�Ȃ����B ���̂Ƃ��A�C���V���^�C�����m�́A�Ȃɂ����{�̑�\�I�ȉ̂����������Ƃ������Ƃ߂ɉ����āA��Ȃ̐l�������A�`���v�A�w�ȁA���S�A�����сA����ɂǂ��傤�������ɂ�����B���|���o���āA���m�v�Ȃ���낱�����B ���̂Ƃ��A�C���V���^�C���́A����Ƀo�C�I�������O�ȑt���Ă���B �������ăA�C���V���^�C���v�Ȃ́A12��29���ߌ�O���A�����̐l�Ɍ������Ȃ���A�Y���ۂœ��{������A�A���̓r�ɂ����̂ł������B�@ |
|
| �������_����`�ɑ���A�C���V���^�C���̑ԓx | |
|
�h�C�c�ŁA�����_����`���L�܂�A�A�C���V���^�C���̕����w�́u���_���I�v�ŕs�������Ƃ����ᔻ�����ꂽ�Ƃ��A�ނ͌Ǘ������Ƃ����ނ̐M����j��A���_���Љ�̈���Ƃ��ĐU�镑���悤�ɂȂ�B�A�C���V���^�C���́A���R�ƃ��_���l�Ƃ��čs�������B
���_�������̏h���ւ̃A�C���V���^�C���̐ϋɓI�ȊS�́A�x����������Ɏn�܂����B�ނɂƂ��āA���̊S�́A�����Ǝ�`(�C���^�[�i�V���i���Y��)�I���z�ƁA�����Ė���������̂ł͂Ȃ������B1919�N��10���ɔނ́A�����w�҃|�[���E�G�v�V���^�C���ɏ������B�u�l�Ԃ́A�����̕����̒��Ԃւ̋C�Â��������킸�ɁA���ۓI�ȊS�������Ƃ��ł�����̂ł��B�v12���ɁA�ނ̓G�[�����t�F�X�g�ɏ������B�u������(�x������)�́A�����_����`�������A�����I�����X���͌��������̂ł��B�v�ނ́A���̍��ɁA�|�[�����h����у��V�A�ɂ������w�ߍ��ȉ^�����瓦��Ă������_���l(�����ނ�̗����́A�x�������œ��Ɍ����ł������B1900�N�ɂ́A92,000�l�̃x�������̃��_���l�̂���11,000�l���w�������_���l�x�ł������B1925�N�ɂ́A172,000�l����43,000�l�ƂȂ���)�ɑ���A�h�C�c�l�̔����ɓ��Ɍ��{�����B�u�����̕s�^�ȓ��S�҂����̂ւ̔����������肽�Ă邱�Ƃ́c�c���ʓI�Ȑ�����̕���ƂȂ�A������A�f�}�S�[�O(�������)�ɂ���āA���܂����p����Ă��܂��B�v�������̂����̖S���҂������A�����ʂ菕�������߂āA�ނ̉Ƃ��m�b�N���ɗ����̂ŁA�A�C���V���^�C���́A�ނ�̋���̂��Ƃ��A���ɂ悭�m���Ă����B�ނɂƂ��āA�ǂ��郆�_�������Ɋւ��邩����A�����Ǝ�`�́A���炭�����Ă����Ă悩�����B ���炢��̎킪������������B�u�i�ʂ��������������_��(�h�C�c�l�Ƃ̓������咣����҂���)�̔M�]�ƕ����ƂɁA���́A�I�n�Y�܂���Ă��܂����B������A���ɑ����̎��̃��_���l�̗F�l�����̒��ɂ݂Ă��܂����B�����́A�����āA����Ɏ����悤�ȗl�X�ȏo�������A���̒��Ƀ��_�������̊�����ĂыN�����܂����B�v�A�C���V���^�C���́A�Ȋw�ɂ��A�����Ƃ������A�C�f���e�B�e�B�̍����́A���_���l���邱�Ƃł���A����́A�N���o�߂���ɂ�āA�܂��܂������Ȃ����ɈႢ�Ȃ��B�������A���̒����S�́A�@���I�Ȃӂ��݂�S���L���Ȃ��B1924�N�ɁA�ނ́A�Ƃ��Ƃ��x�������̃��_���l�W��̉��[������ɂȂ����B�������A����ɘA�ъ��̍s�ׂƂ��Ăł������B�V�I�j�Y��(���_�������̑c���Č��^��)�́A�ނɂƂ��āA���̉��ɂ������āA�l�̑����ւ̌����ȓw�͂̈�`�Ԃɂ����Ȃ������B�ނ́A�V�I�j�X�g�̑g�D�ɂ͉����Ȃ������B �A�C���V���^�C���̉�z�u���̓��_���l�ł����A���_���̋��������H���Ă���킯�ł͂���܂���B�m���ɁA�q�ǂ��̍��͐M�S�������A�w�Z�ɍs���Ƃ��ɂ́A���_���̉̂��̂��Ă����قǂł��B�������A���̍����߂ĉȊw�̖{��ǂ݁A����ŁA���̐M�͏I���܂����B�����A�����o��ƂƂ��ɁA���鎖���ɋC�Â��悤�ɂȂ�܂����B����́A��������̂̔w��ɂ́A���������ԐړI�ɂ����A�����܌����Ȃ�����������Ƃ������Ƃł��B����͐M�ɂ��ʂ��܂��B���̈Ӗ��ŁA���͏@���I�Ȑl�Ԃł�����̂ł��B�v�@ |
|
| ���ʎq�͊w�A����ꗝ�_ | |
|
�u���v�̓䂩��u���ꑊ�ΐ����_�v�ցA�����āu�d�́v�̒Nj�����u��ʑ��ΐ����_�v�� ---- ���R�̒�����[���M�������炱���A�A�C���V���^�C���́A�̑�Ȏd���𐬂��������̂ł������B�������A���̊m�ł���M�O�́A�����w�ɐ��܂ꂽ���̐V���ȗ��_�ƁA�Փ˂��邱�ƂɂȂ����B1927�N�A��5��̃\���x�C��c�ŁA�A�C���V���^�C���́u�ʎq�͊w�v�̊w�҂����Ɠ��Ȃ����B�u�ʎq�͊w�v�́A�������ۂ��u���q�v��u�f���q�v�ȂǁA�����Ƃ������ȃ��x���ŒNj�����w��ł���B���F���i�[�E�n�C�[���x���N(1901-1976)��j�[���X�E�{�[�A(1885-1962)�ɑ�\�����ʎq�͊w�̉Ȋw�҂����́A�~�N���̐��E�̕������ۂ́A�s�m�����Ƌ��R�ɂ���Ďx�z����Ă��邱�Ƃ𗝘_���Ă��B�F���Ƃ����ł��傫�ȍ\���ɏœ_�ĂĂ����A�C���V���^�C���́A���R�E�ɁA�s�m���Ȃ��̂�����Ƃ����u�ʎq�͊w�v�̍l�������A�Ђǂ��������B
�j�[���X�E�{�[�A�ƃA�C���V���^�C�� �A�C���V���^�C���̉�z�u�ʎq�͊w�́A�����I�ɂ͗L���ł��傤�B�������A�m���Ƃ��A���R�ŁA���ׂĂ����肳���Ƃ����j�S�̌����ɂ́A�[���ł��܂���B�����Ɛ[���A�{���̌���������͂��ł��B�{�����Ɍ������悤�ɁA�_�̓T�C�R�����ӂ�Ȃ���ł��B�v�u�ʎq�͊w�͑�ψ�ۓI�ł��B���������A���̓��Ȃ鐺�́A����͂܂��{���ł͂Ȃ��Ǝ��Ɍ����Ă���܂��B���̗��_�́A���Ȃ葽���̂��̂������炵�܂��B�������A������n����̐_��ɂقƂ�Nj߂Â��Ă���܂���B������ɂ��Ă��A���͐_�̓T�C�R���U������Ȃ��Ɗm�M���Ă���܂��B �v �A�C���V���^�C���́w�_�̓T�C�R�����ӂ�Ȃ��x�Ƃ����L���Ȍ��t�ɂ́A����������������B�Ȃ��A�ނɂ��ꂪ�킩��̂��B�_�����̒��ɁA�����B���Ă��邩�́A�킩��Ȃ��B �A�C���V���^�C���́A���U�A�{�[�A�Ƙ_���𑱂����B�����āA�ʎq�͊w���x�����邱�Ƃ͂Ȃ������B�����āA�A�C���V���^�C���́A�u���ΐ����_�v�Ɓu�ʎq�͊w�v���A��ɂ܂Ƃ߂�s��ȗ��_��ł����Ă悤�Ɩڎw���̂ł������B �A�C���V���^�C���̉�z�u��������́A�٘_���������Ŏ҂��ƁA������悤�ɂȂ�܂����B���N�̊ԂɁA�ڂ������@�\���Ȃ��Ȃ������̂悤�ȑ��݂ł��B���������Ă��A����ȋC�͂��܂���ł����B���̋C�����A�悭�\���Ă��܂�������E�E�E�v �ɏ�����ɑ�܂ŁA���ׂĂ̕������ۂ��������������_�A����́u����ꗝ�_�v�ƌĂ��B�A�C���V���^�C���́A�u����ꗝ�_�v�����߂āA�ǓƂȒ������̂�ɓ��ݏo�����B �A�C���V���^�C���̉Ȋw��̊����̍Ō�̊��Ԃ́A�����ƁA����ꗝ�_�ɂ���Ďx�z���ꂽ�B�܂��A�ʎq�_���A�ނ̐S����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��Ȃ������B����30�N�Ԃɂ킽���āA�����̖ړI��B�����邽�߂̕��@�ɂ��ẮA�Ò��͍��ł��������A���̖ړI���̂́A�ނɂƂ��ẮA�͂����肵�Ă����B��ʑ��ΐ����_�Ȍ�̉Ȋw��̗��H�ŁA�ނ́A�ړI�̍`�ɓ������邽�߂ɁA�A���̕��@�ŁA�����̕ύX���A�����������闷�s�҂̂悤�ł������B�ނ́A���ɁA���ǂ���Ȃ������B���̔N���ɂ�����ނ̌������@�̍ł������������́A����قǁA�]�O�̂��̂ƈ���Ă���킯�ł͂Ȃ��F�q�C�ւ̌X�|�A�M��A�����āA��ɁA����A���邢�͎v�ĂȂ��ɁA��̐헪����߁A�قƂ�Njx�ފԂ��Ȃ��A�ʂ̕���Ɏ�肩����\�́B20�N�̊ԁA�ނ́A�ق�5�N�Ɉ�x���A5�����̕��@�����݂��B���̌�́A�������̂��ƁA���̊��Ԓ��ɂ��A�ނ́A�܂���̎�ނ́A�����Ď��ɂ͕ʂ̎�ނ́A4�����A���ɂ���āA�ړI�ɓ��B���铹��T�����B�ނ͂܂��A��ʑ��ΐ����_�̖��Ɏ��Ԃ������邱�Ƃ��������낤���A���邢�́A�ʎq�_�̊�b���n�l�����ł��낤�B ����ꗝ�_�ɂ�����ނ̖ړI�͊m�łƂ������̂ł������B�ނ̕��@�͑��l�ł������B�����Ĕނ̓w�͓͂k�J�ł������B�@ (�d�͏�Ɠd����̓���ꗝ�_) ��Ԃɕ��������݂���A����́A���̋�Ԃɏd�͂̏���Ђ��������B�����āA���̏d�͂̏�͑��̕��̂ɓ����āA���̕��̂ɓ����͂������N�����B �A�C���V���^�C���́A���̎�����L�q���邽�߂ɁA�܂��l�����̋�Ԃ��l���A���̋�Ԃ́A�d�͏�ɂ���Ē�܂�ȗ��������Ă���ƍl�����B���ꂪ�A�ނ̈�ʑ��ΐ����_�́A�͂��߂ɂ���l���ł��邪�A���̍l�����ɂ��A��ʑ��ΐ����_�́A����Ɍ����ďd�͏�̗��_�ł���A�l�����̋ȗ�����������Ԃ́A�����\�����邽�߂ɍł��K������Ԃł���Ƃ������Ƃ��ł���B ���āA��Ɠ�������A�d�ׂ����������q�ɑ��Ă����݂���B�d�ׂ����������q�̑��݂́A��ԂɈ�̓d������Ђ��������B�����āA���̓d����́A���̓d�ׂ����������q�ɓ����āA����ɓ����͂��Ђ��������B �A�C���V���^�C���̈�ʑ��ΐ����_�́A�����̑��݂ɂ���āA�Ђ����������d�͂̏�́A��Ԃ̋ȗ��Ƃ����`�ōl���ɓ���Ă��邪�A�d�ׂ����������q�̑��݂ɂ���āA�����N�������d������A��Ԃ̐����Ƃ����`�ōl���ɓ����Ƃ������Ƃ͂��Ă͂��Ȃ��B ���̂��Ƃ��A���˂��˕s���Ɏv���Ă����A�C���V���^�C���́A�x�������ɋA���Ă���(1924�N)�́A�����ς�A���̖��ƂƂ肭�B���̂悤�ɁA�d�͏�̑��݂ƁA�d����̑��݂Ƃ���Ԃ̐����Ƃ��čl���ɓ��ꂽ���_�́A���݂ł͓���ꗝ�_�Ƃ��Ă���B ��̘b������킩��悤�ɁA���̓���ꗝ�_�́A���Ȃ萔�w�I�ȗ��_�ł���B ���āA�A�C���V���^�C�����A���̈�ʑ��ΐ����_�ŗp������ԂƁA�A�C���V���^�C�������̓���ꗝ�_�ŗp������Ԃ̈Ⴂ�́A���̂悤�ł���B ��Ԃ͕���łȂ��Ƃ����A��Ԃ͋Ȃ����Ă���ƍl����̂����ʂł��邪�A��Ԃ͋Ȃ����Ă���Ɠ����ɁA�˂���Ă��邢�邱�Ƃ�����̂ł���B���̏ꍇ�A��Ԃ��ǂ̂��炢�Ȃ����Ă��邩��\���ʂ͋ȗ��A��Ԃ��ǂ̂��炢�˂���Ă��邩��\���ʂ͝���(�ꂢ���)�Ƃ��Ă���B �����̌��t���g���A�A�C���V���^�C�����A���̈�ʑ��ΐ����_�ŗp������ԂƁA����ꗝ�_�ŗp������Ԃ̈Ⴂ�́A����ŁA���̂悤�ɂׂ̂邱�Ƃ��ł���B �A�C���V���^�C���́A���̈�ʑ��ΐ����_�ł́A�ȗ��͂����Ă��邪�A�����͂����Ă��Ȃ���Ԃ��l�����B�������A���̓���ꗝ�_�ł́A�ȗ��͂����Ă��Ȃ����A�����������Ă����Ԃ��l�����B ���āA�A�C���V���^�C�����A���̏d�͏�Ɠd����̗������l���ɓ��ꂽ����ꗝ�_������������Ƃ����\�́A1929�N��3��14���Ƃ����A�A�C���V���^�C���̑�\��ڂ̒a�������߂Â��ɂ�āA���E���ɂЂ�܂����B �A�C���V���^�C���́A���̑��ΐ����_�ɂ���āA�F���̓�̈���������l�ł���B���̃A�C���V���^�C�����A��\��ڂ̒a�����������āA���̉F���̓���ŏI�I�ɉ�������ꗝ�_�\����ł��낤�Ƃ����\�́A�W���[�i���Y���ɂƂ��ẮA�����Ă����̃j���[�X�ł���B ���������Ĕނ́A���E���̐V���Ђ�G���Ђ���A�ނ����̑�\��ڂ̒a�����������Ĕ��\���悤�Ƃ��Ă��铝��ꗝ�_�̊T�v��N�ɂł�������悤�Ȍ��t�ŋ����Ăق����Ƃ����v�������B�����Ĕނ̃x�������̉Ƃ́A�����吨�̐V���L�҂�G���L�҂ɂ���Ď��͂܂�邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B ���̃A�C���V���^�C���̐V��������ꗝ�_�́A�v���C�Z���̉Ȋw�A�J�f�~�[�̋I�v�ɔ��\����邱�Ƃ����������̂ŁA���̈�����֎���āA���̘_����������\�����̂�҂��d���Ȃ��������A����A�����J�̐V���L�҂́A�������ꂪ���\���ꂽ�Ȃ�A���̂ǂ̐V���Ђ�������������A�����J�֒m�炻���Ƃ��āA�A�����J�ւ̓d���ʐ^��p�ӂ����قǂł������B ���̑����̒��ŁA�A�C���V���^�C���̐V��������ꗝ�_�́A���Ƀv���C�Z���̉Ȋw�A�J�f�~�[�̋I�v�ɔ��\���ꂽ���A����́A���w�A���ƂɃe���\����͊w�̌����Ŗ������ꂽ���y�[�W�̘_���ł������̂ŁA�V���L�҂�G���L�҂ɂƂ��ẮA����͑S���̂���Ղ�Ղ�ł������B �������A���[�}���w�̌��ʂ𗘗p�����A�C���V���^�C���̈�ʑ��ΐ����_���A�t�ɁA���̃��[�}���w�̌������h�������̂ƑS�����l�ɁA���[�}���w�̊g���𗘗p�����A�C���V���^�C���̓���ꗝ�_���A�t�Ƀ��[�}���w�̊g���̌������h�������͎̂����ł������B�@ |
|
| ���A�����J�ցA�G���U�̎� �@ | |
|
�A�C���V���^�C����1933�N10������A�����J�ɉi�Z�����B�����Ƃ��A�h�C�c�����낤�Ƃ����ނ̍l���́A����2�N�قǑO�����̉����n�߂Ă����B1931�N12���A�ނ͎����̗��s�����ɏ����Ă���B�u�����A���͎��̃x�������ł̒n�ʂ��A��{�I�Ɏ�Ȃ����Ƃ����S�����B�v���̂Ƃ��A�ނ̓p�T�f�i(���T���W�F���X�ߍx)�ɏ��߂đ؍݂��邽�߂̗��H�̓r���ł������B�h�C�c�̍ŋ߂̎������A�悭�l���Ă݂������͋C�ł������B1�N�O�ɁA�i�`�X�́A���ٓI���𐋂��A�h�C�c���a���c��̋c��12����107�ɐL���Ă����B
�v�����X�g��(�j���[�W���[�W�[�B)�ɈڏZ���悤�Ƃ����A�C���V���^�C���̌���́A�A�u���n���E�t���N�X�i�[�Ƃ�3��̉�̌��ʂł������B�ŏ��̉�͗\�肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ������B1932�N�̏��߁A�t���N�X�i�[�́A�����w�p�������Ƃ����V���������Z���^�[(��̃v�����X�g������������)�����Ƃ����ނ̊��ɂ��āA�J���t�H���j�A�H�ȑ�w�̋��������Ƌc�_���邽�߂ɁA�p�T�f�i��K��Ă����B���̋@��ɁA�ނ̓A�C���V���^�C���ɏЉ�ꂽ�B��l�͌������v��ɂ��Ĉ�ʓI�ɋc�_�����B1932�N�̏t�A�I�b�N�X�t�H�[�h�œ�l���ĊJ�����ہA�t���N�X�i�[�̓A�C���V���^�C�����g���������ɎQ������C�������Ȃ����ǂ����q�˂��B1932�N6���A�J�v�[�g(�A�C���V���^�C����1929�N�Ƀx�������ߍx�J�v�[�g�ɉƂ��Ă���)�ł�3�x�ڂ̉�̍ہA�A�C���V���^�C���́A�ނ̏���Ƃ��ă��@���^�[�E�}�C���[��A��Ă�����Ȃ�A�Q����M�]����Əq�ׂ��B �A�C���V���^�C���́A�����A1�N�̂���5�������v�����X�g���ŁA�c��̎��Ԃ��x�������ʼn߂�������ł������B�������A�����Ă����͂����Ȃ������B1932�N7���̐V�����I���ŁA�i�`�X��230�̋c�Ȃ邱�ƂɂȂ����B�A�C���V���^�C�����A�ȂɁA���O�͓�x�ƃJ�v�[�g�̒������邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Əq�ׂ��̂́A���̔N��12���̂��Ƃł������B1932�N12��10���A�A�C���V���^�C����Ƃ�30�̉ו��ƂƂ��ɁA���C�D�I�[�N�����h�Ńu���������n�[�t�F�����o�����A�ĂуJ���t�H���j�A�Ɍ��������B�������ꂪ�ނ�ɂƂ��ăh�C�c�Ƃ̉i���̕ʂ�ɂȂ����B1933�N1��30���A�q�g���[�����͂��ɂ������B3����ɁA�A�C���V���^�C���́A�v���V�A�E�A�J�f�~�[�̎����Lj��A�����̕�̎�茈�߂ɂ��Ď莆�������Ă���B�������A���Ԃ͋}���Ɉ������A1933�N3��28���t�̎莆�ŁA�A�C���V���^�C���͎��\���x�������̃A�J�f�~�[�֑������B����1�T�ԑO�A�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�́A�u�ŋ߂̃h�C�c�j��A�ł����S�ȉƑ�{�����s��ꂽ�v�ƕ��B�i�`�X�ˌ����́A�A�C���V���^�C���̃J�v�[�g�̉Ƃ��A�B������{���̂��߂ɉƑ�{���������̂ł���B�w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x�ɂ��ƁA�ނ炪���������̂́A�p����1�{�����ł������B �x�������ɂ������A�C���V���^�C���̘_���́A�`���̑��q���h���t�E�J�C�U�[�̎�ɂ���āA�����ɋ~�o����A�t�����X�̊O��p�X�֑܂ŁA�t�����X�O���Ȃɑ���ꂽ�B �A�C���V���^�C���̂��Ƃɂ́A�ÎE��\�����鋺����܂œ͂��Ă����B���N�̓��A��x���������悤�ɁA�ނ͍ĂсA�h�C�c���瓦���B �A�C���V���^�C���̉�z�u���́A�����Ȃ鍑�Ƃɂ��A�܂��A�F�l�����T�[�N���ɂ��A�����������Ƃ͂���܂���B�����̉Ƒ��Ƃ���������ۂ��܂����B�������g�̒��ɁA����������K�v���́A�N�X�����܂����B�Ǘ�������������ŁA�����A�ꂢ�v�������܂������A����������Ƃ́A��x������܂���B���l�̗����⓯����t���Ȃ���A�ނ�̈ӌ���A�Ό���������R�ł����܂��B�v 1933�N�A�A�C���V���^�C���ƍȃG���U�́A�A�����J�ɓn��A��x�ƃh�C�c�ɂ͖߂�Ȃ������B �Â��ȑ�w���v�����X�g���ɗ��������ƁA�����ɓ��ۂ���܂����B�����A�����āu�v�����X�g�������������v�ɒʂ��A�ߌ�ɂȂ�ƁA�}�[�T�[�ʂ�̂�����܂肵������ɋA���Ă����B �ނ́A�����ĎԂ̉^�]���o���Ȃ������B�A�C���V���^�C���́A�����O�̕��ς��Ȑ��i���A�����ɔ��������B�A�����J�s���ƂȂ鎮�T�ɁA�C���𗚂����ɏo�Ȃ����̂��A���̈��ł������B�펯�I�ȑ�w�����Ƃ����������A�ނ͌����āA�����悤�Ƃ��Ȃ������B�����݂ȁA���[���A�̉e�ɂ́A�[�܂�s���ǓƂ��A�B����Ă����B 1936�N�A�ȃG���U�́A�Z���a�C�̌�A�S���Ȃ����B�G���U�̎���u�F�̂悤�ȌǍ��̐����́A�x�𑝂����v�ƁA�ނ́A�F�l�ւ̎莆�ɏ����Ă���B �ŏ��̍ȁA�~���[�o�Ƃ́A��x�Ɖ���Ƃ͂Ȃ��A�ޏ���1949�N�ɖS���Ȃ�B���j�̃G�h���@���g�́A���_�̕a�āA�X�C�X�̕a�@�ŁA1966�N�ɖS���Ȃ����B���j�̃n���X�E�A���o�[�g�́A�J���t�H���j�A�ōH�w�̋����ɂȂ邪�A���e�Ƃ͖ő��ɉ��Ȃ������B�u����ꗝ�_�v�̒Nj��͑������B�������A�A�C���V���^�C���́A������ł��Ȃ������B �A�C���V���^�C���́A�u����ꗝ�_�v��ǂ����߂����߂ɁA���U�̍Ō��30�N�ʂɂ����Ƃ����ӌ�������B�������A�������́A�ނ̉��b���A�傢�ɎĂ���̂��B�ނ́A���_�̓���̂��߂̓����A�����Ă��ꂽ�̂��B�����A�����̕����w�҂��A�j�̗͂��A�d�͂�d���͂ƁA�������悤�Ƃ��Ă���B�N�����A�A�C���V���^�C���̈�Y���p���ł���̂��B�@ |
|
| ���A�C���V���^�C���̕��a�v�z�ƃ��[�Y�x���g�哝�̂ւ̎莆 | |
|
1930�N12���A�A�C���V���^�C���́A�A�����J��K�₵���Ƃ��ɁA�ނ̕��a�v�z��������B���̒��ŁA�A�C���V���^�C���́A�푈��j�~���邽�߂̋�̓I�ȕ��@���������B
�A�C���V���^�C���H���u���݁A���܂��܂ȍ��̐l���A���Ƃ̂��߂ɁA�E�l�̍߂�Ƃ��Ă��邱�ƂɋC�Â��Ăق����Ǝv���܂��B�����Ȃ�ł��A�����͋��ۂ��ׂ��Ȃ̂ł��B�������w�����ꂽ�l��2�����푈���ۂ𐺖�����A���{�͖��͂ƂȂ�܂��B�Ȃ��Ȃ�A�ǂ̍�������2�����z����l�����e����Y�����̃X�y�[�X���Ȃ�����ł��B�v ���̉����́A�A�����J�l�ɁA�M���I�Ɍ}�����A��҂݂̋��u2���v�Ə����ꂽ�o�b�W�������Ă������B 1933�N�A�A�C���V���^�C���́A�i�`�X�̔��Q��āA�A�����J�ɖS�������B���̎��A�A�C���V���^�C���́A����܂ł̕��a�v�z���A�ˑR���������A�i�`�X�ւ̑R��i�����B �A�C���V���^�C���́A���}���E�������ƕ��a��`�̓��u�Ƃ��Ē����𗬂𑱂��Ă����B���̃��}���E�������ɃA�C���V���^�C���́A���̂悤�Ȏ莆�𑗂����B�u�������`�����邱�Ƃ́A���Ȃ����������ł��傤�B�����A�������ۂ��L���Ȏ���͏I���܂����B�������A���������ė����オ��ׂ��ł��B�v �A�C���V���^�C���̑ԓx�̕ω��ɑ��āA���}���E�������́A���L�ɁA�����������B�u�����鐸�_�̎コ���A��l�̉Ȋw�҂̐��_�Ɍ�����Ƃ́E�E�E�B�A�C���V���^�C���̒m���́A���R�Ȋw�̕���ł͓V�˓I�ł��邪�A����ȊO�ł́A�����܂��ŁA���Ȗ������Ă���B�v 1939�N8��2���A���I�E�V���[�h�̗v�����āA�A�C���V���^�C���́A���[�Y�x���g�哝�̈��̌����̊J�������Ȃ����莆�ɏ��������B�A�C���V���^�C���́A�V���[�h���莆�������Ă��Ă���A2�T�ԔY�����ɁA���������̂������B���e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B �e�E�c�E���[�Y�x���g ���O���哝�� �q�[ ���e�Ŏ��ɓ`�B���ꂽ�d�E�t�F���~�Ƃk�E�V���[�h�̍ŋ߂̂������̌����́A�E�������f���A�߂������A�V�����A���d�v�ȃG�l���M�[���ƂȂ�Ƃ������҂����ɕ������܂��B���ݐ����Ă���́A����ʂŏ\�����Ӑ[��������邱�Ƃ��v������A����ɕK�v�Ƃ���A���{���ǂƂ��āA�����A�s���Ɉڂ����Ƃ�v������Ă���悤�Ɏv���܂��B���������āA���́A�ȉ��̎����Ȃ�тɊ����ɂ��āA���Ȃ��̒��ӂ����Ȃ������Ƃ����̋`���ł���ƐM���܂��B ����4�����Ԃɂ�����t�����X�̃W�����I�ƃA�����J�̃t�F���~�ƃV���[�h�̌����ɂ���āA��ʂ̃E���j�E�����Ɋj�A���������N�������Ƃ��\�ɂȂ�A�����āA����ɂ���āA����ȗ͂ƁA���ʂ̐V�������W�E���l�̌��f�ݏo�����Ƃ��\�ɂȂ����܂��B�����Ă��܂�A���ꂪ�߂������Ɏ��������̂́A�قƂ�NJm���Ȃ悤�Ɏv���܂��B ���̐V�������ۂ͂܂��A���e����邱�Ƃ��\�ɂ��܂��B�����āA�V�����^�C�v�̔��ɋ��͂Ȕ��e�������Ƃ������Ƃ� --- �m���Ƃ����قǂłȂ��ɂ��Ă� --- �\���ɍl�����邱�Ƃł�����܂��B���̃^�C�v�̒P�̔��e���{�[�g�ʼn^��A�`�Ŕ�������A����͍`�S�̂�j�Ă��܂�����łȂ��A���̎��Ӓn������j�Ă��܂��ł��傤�B�������A���̔��e�́A��s�@�ł̗A���ɂ́A�d�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ�ł��傤�B�@ �č��ō̌@�ł���E�����z�́A���Ɏ��������A�������̌@�ʂ������͂���܂���B�J�i�_�Ƌ��`�F�R�X���o�L�A�ł́A�ǎ��̃E�����z���A�����炩�̌@����܂��B����A�ł��d�v�ȃE�������́A�x���M�[�̃R���S�ł��B ���̏��ӂ݂�A�哝�̂ɂ�����܂��ẮA���{��(�j�����)�A�������̌��������Ă���A�����J�l�����w�ҒB�Ƃ́A�����I�ڐG�𖧂ɂ��邱�Ƃ��]�܂����ƁA���l���ɂȂ��Ă���낵���ł��傤�B�����B�����邱�Ƃ��\�ɂ����̕��@�́A���Ȃ����A�������̐M���ł���l���A���A������̗���ŕ�d���邱�Ƃ��ł���l���ɁA���̎d����������Ƃ����m��܂���B���̎d���́A�ȉ��̂��Ƃ��܂݂܂��B ��)���{�̏Ȓ��ɐڋ߂��āA����Ȃ�J���Ɋւ��Ď��m���邱�ƁA�č��̂��߂ɁA�E�����̊m�ۂ��m���ɂ��錏�ɂ��ē��ʂȒ��ӂ����Ȃ������e�́A���{�̍s���ɂނ����������Ă��邱�ƁB ��)���݁A�����́A��w�̎������̌���ꂽ�\�Z�Ŏ��{����Ă��܂����A�K�v�Ȃ�A�����Ȃ闝�R�ŁA��t��ɂ��܂Ȃ����l�Ƃ̐ڐG��ʂ��āA�����p�ӂ��邱�ƂƁA�����Ă܂��A�K�v�Ȑݔ��������Ă���Y�Ɗe�Ђ̎������̋��͂邱�ƂŁA������Ƃ𑬂߂邱�Ƃł��B ���́A�h�C�c����̂����`�F�R�X���o�L�A�̍z�R����̃E�����̔̔����A�h�C�c���������~�������Ƃ̈Ӗ��𗝉����Ă��܂��B�h�C�c���A���̂悤�ȑ��}�ȍs�����Ƃ������Ƃ́A�����A�ȉ��̂悤�ȗ��R�ŗ����ł��܂��B���Ȃ킿�A�h�C�c�̎����̎q���A�t�H���E���@�C�c�[�b�J�[���A�x�������̃J�C�U�[�E���B���w�����������ɔz������A�����ł̓A�����J�̃E���������̂��������A�ǐՌ�������Ă���̂���ł��B �h�� �A���o�[�g�E�A�C���V���^�C�� ���B�e���ꂽ��ȃt�B�������c���Ă���B�V���[�h���A�A�C���V���^�C������A�����J���̃T�C�������炤��ʂ��A�킴�킴�A�Č��������̂ł���B�Ȃ��A�A�C���V���^�C�����A���̃t�B�����̎B�e�ɋ��͂����̂�---�B�e�̖ړI�͕s���ł���B�������A�A�C���V���^�C�����A�����J���𑣂��莆�ɃT�C���������s�ׂ̐��������m�M���Ă��Ȃ���A���A���̎B�e�ɋ��͂��邱�Ƃ͂Ȃ������͂���(���̎ʐ^)�B �A�C���V���^�C���̕ʑ����V���[�h�ƂƂ��ɖK�ꂽ�̂��A�G�h���[�h�E�e���[(���̎ʐ^)�ł������B�e���[�́A���X�A�����X�������ŁA�����J���ɂ��������A���́A���f���e���������āu�����̕��v�ƌĂ��悤�ɂȂ����B����A�A�����J�̌R�������̎���ƂƂ��ɕ��l���ł���B �e���[�̉�z�u�A�C���V���^�C���́A�莆�𒍈Ӑ[���ǂ݂܂����B�����Ă���́A�j�G�l���M�[���A���ځA�����Ɏg�p�����ŏ��̎����낤�ƌ����܂����B�����́A�j�G�l���M�[�ł��鑾�z�̃G�l���M�[���A����܂ŁA�ԐړI�Ɏg���Ă�������ł��B���ꂪ�A�A�C���V���^�C���̗B��̊��z�ł����B�T�C�����ꂽ�莆�́A�V���[�h����������A�哝�̂ɓ͂�����܂łɂ́A3����������܂����B�v �A�C���V���^�C���̎莆�ɂ́A�h�C�c�̌����J���̒��S�ƂȂ����w�҂̖��O��������Ă���B����̓t�H���E���@�C�c�[�b�J�[�ł���B�����A�J�C�U�[�E���B���w�����������̐V�i�����w�҂������B���݁A�h�C�c�ō��̕����w�҂ł���Ɠ����ɁA�L���X�g���̗��ꂩ�畽�a�^����i�߂�N�w�҂ł�����B ���@�C�c�[�b�J�[�̉�z�u���́A�A�C���V���^�C�����Ƃ����s���́A�����������Ǝv���܂��B���������A����������\���͂���������ł��B�������A�Z���ԂŌ����邱�Ƃ́A�s�\�ł��邱�Ƃ����܂����B����́A�������ɂƂ��āA�K���Ȃ��Ƃł����B�A�����J���A�������J�������ƕ����āA�{���ɋ����܂�����B�������A���������A�A�����J���l�ɓw�͂��Ă��A�����͊������Ȃ������ł��傤�ˁB�A�����J�́A�h�C�c�̐�{���̗\�Z�𓊓������̂ł�����B�v �����J���̂��߂́u�}���n�b�^���v��v�������n�߂��B�l�����ꂽ��n�Ɂu���X�T�����X�������v�����ꂽ�B���łɁA�V���[�h�̃A�C�f�A�Ŋj�A�����������͐������A�����̕���Ƃ��Ă̎��p�����A���̌������̎g���������B���_���l�S���҂��͂��߁A���E������A���_�����w�A���������w�̊w�҂��W�߂��A���Ԃ���u������A���������𑗂����B�Ȋw�҂͐��ʂɍׂ������f����āA���̕���ɂ��Ă͈�ؒm�炳��Ȃ������B�A�C���V���^�C�������z�Ƃ��������̐��ʂ̎��R�Ȍ𗬂́A�����ɂ͂Ȃ��A�������x�z����̂́A�Ȋw�҂ł͂Ȃ��A���Ƃł������B�������A�Ȋw�҂́A���̖{���ɋC�Â��Ȃ��܂܁A�����ɔM�����Ă������B�����̓��ނ̌����̂����A�v���g�j�E���́A���V���g���B�̃n���t�H�[�h�ŁA�Z�k�E�����́A�e�l�V�[�B�̃I�[�N���b�W�ŁA�}�s�b�`�Ő��Y����Ă����B���X�T�����X�A�n���t�H�[�h�A�I�[�N���b�W�̎O�J���́A�ٖ��Ɍ��т��A�閧�̂����ɁA�j�G�l���M�[�̉���ւƌ������Ă����̂ł������B 1945�N�A�h�C�c�S�y�́A�A���R�ɂ�錃������P�ɂ��炳��A��v�ȓs�s�́A��œI�ȑŌ������B5��7���A�i�`�X�E�h�C�c�͘A�����ɑS�ʍ~�������B�������A�h�C�c�~������A���{�R�͘A�����Ɛ킢�����Ă����B�A�����J�R�̉���㗤�ɂ���āA���{�̍~���͖ڑO�Ǝv��ꂽ���A�������A���̂܂܁A�A�����J�R�����{�{�y�㗤�����s����A�A�����J�R�ɂ��A�����̎����҂��ł邱�Ƃ͖��炩�������B �A�C���V���^�C���ɂƂ��Ă̓G�ł������i�`�X�E�h�C�c�́A���S�ɖłB��b�̏W�c����b�ɂӂ��킵�����苎��ꂽ�̂��B�ނ̐S�́A���������������̂ɖ������ӂ�Ă����B�������A���̌�̓��X�A�A�C���V���^�C���́A���낵���\���ɂ����Ȃ܂ꂽ---�u���{���܂��~�����Ă��Ȃ��B�A�����J�̌��������́A�܂������Ă���B�������{��K�ꂽ�̂́A1922�N11���������B�`����Ԗڂ������{�l�A���R�Ɛl�Ԃ���Ɍ��ꂽ���{�A�����ɂ́A�������̗F�l������B�m���ɁA���̐푈���A���{���A�W�A�ōs�����ȍs�ׂ́A�i�`�X�E�h�C�c�ɂ���ׂĂ��A�܂��Ƃ͂����܂��B�����A���{�́A���Ǝ��̉Ƒ����A�E�����Ƃ͂��Ȃ������B���̓��{���A���������̊�@�ɂ��炳��Ă���B�v �h�C�c�~�����ڑO�ƂȂ������A�����̊J���ɁA������������Ȋw�҂̒�����A�����̎g�p�ɔ����铮�����o�Ă����B�哝�̈��̌����������̐��菑������A�����̉Ȋw�҂̏������W�܂����B �i�`�X�ח���2�����O�A�V���[�h�́A�A�C���V���^�C���Ɖ�A�ӂ����сA�哝�̂ւ̎莆�ɃT�C������悤���߂��B�����̓��{������j�~���悤�ƁA�V���[�h�́A�哝�̂ɓ�����������肾�����B�����J����i�߂�ɂ��A�����������~�߂�ɂ��A�A�C���V���^�C���̖������K�v�������̂ł���B�A�C���V���^�C���́A�ӂ����сA�V���[�h�̈ӌ��ɓ������T�C�������B�������A���̎莆��ǂ܂Ȃ��܂܁A���[�Y�x���g�哝�͎̂��S�����B�@ �uO weh!(�����߂����I)�v�A�C���V���^�C���́A�L���Ɍ������������ꂽ���Ƃ�m�����Ƃ��A�������Ɠ`������B�@ ���A�悤�₭�A�����̔�Q�ʐ^�����\���ꂽ���A�A�C���V���^�C���ɁA�莆�����������{�l�������B�A�C���V���^�C������A�Ԃ��Ă������Ȃ́A���܁A�����̒n�����ɂɕۑ�����Ă���B�Ȃ��A���a��`�҂̃A�C���V���^�C�����A�����̊J����i�߂郋�[�Y�x���g�̎莆�ɁA���������̂�---�A�C���V���^�C���̕��a�v�z�̍��{���s���₢���������̂́A�G���w�����x�ҏW�҂̎����l(���̂͂点������)�������B ���̎莆�u���̑��̖ړI���A�l�ނ̕����ƍK���ɕ�d���ׂ��Ȋw���A�Ȃ��ɂ��̂悤�ɋ��낵�����ʂ��A�����炷�悤�ɂȂ����̂��B�̑�ȉȊw�҂Ƃ��āA���������ɏd�v�Ȗ�����������ꂽ���Ȃ��́A���{�����̐��_�I��ɂ��~�����i������v �A�C���V���^�C���́A��V�ɔ����āA�����āA���̎莆�̗��ɕԎ��������āA����Ԃ��Ă����B�����ĒǐL�ɂ́A�u�l��ᔻ����Ƃ��́A�悭����̂��ƂׂĂ���ɂ��ׂ����v�ƁA�{��������ɂ��Ă����B�A�C���V���^�C���̕ԐM�ɂ͎��̂悤�ɂ���B�u�������A�l�ނɂƂ��ċ���ׂ����ʂ������炷���Ƃ��A���͒m���Ă��܂����B�������A�h�C�c�ł��A�����J���ɐ������邩���m��Ȃ��Ƃ����\�����A���ɃT�C���������̂ł��B�v�����āA�A�C���V���^�C���́A�푈���������������������B�u���ɓG�������āA���̖������̖ړI���A���Ǝ��̉Ƒ����E�����Ƃł���ꍇ�ł��B�v�@ |
|
| �����E���{ | |
|
����E���̏I���Ɉ����������N�قǁA�A�C���V���^�C�����A��������^���ɁA�̂߂肱��ł������Ƃ��͂Ȃ������B�u�푈�ɂ͏����������a�͂܂����v�ƁA1945�N12���A���O�Ɍ���Ă���B�ނ́A���̐��E�́A��@�I�ɕs����ł���Ƃ݂Ȃ��A�V���������`�Ԃ��A�v������Ă���ƐM���Ă����B�A�C���V���^�C���H���u�ŐV�̌��q���e�́A�L���̓s�s�ȏ�̂��̂�j�Ă��܂����B�����ɁA���т��������x��̐����ϔO�����A����������̂ł���B�v1945�N��9���Ƃ������������ɔނ́A���̂悤�ɒ��Ă���B�u�����Ɛl�ނ��~�ς���B��̕��@�́A�@���Ɋ�Â����Ƃ̈��S��ۏႷ��w���E���{�x�̌`���ł���B�v
�ނ̍l���ɂ��ƁA���̎�̐��E���{�́A�\�����𑩔����邱�Ƃ��ł��錈�茠���A�^�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ނ́A���̂悤�Ȍ��������������ۘA���ɂ͉��^�I�ł������B���E���{�́A�ނ̎c���ꂽ�N���ɁA�ނ��ĎO�Ďl�A���낢��Ȍ`�ŗ����߂��Ă����e�[�}�ł������B1950�N�ɂ��w�Ȋw�҂̓����I�`���ɂ��āx�̃��b�Z�[�W�̒��Ŕނ͌J��Ԃ��Ă���B�u�\�͓I��i��r�����邽�߂ɁA�@���Ɋ�Â��āA�����ƓI�g�D���n�݂���邱�Ƃɂ���Ă̂݁A�l�ނ͋~����̂ł��B�v���̂悤�ȗ��z�Ɍ������āA���Ƃ��A���͂������悤�Ƃ��A�����́A�w�͂��ׂ��ł���Ɣނ͐M���Ă����B�u�����A���R�ŗǐS�I�Ȑl�́A�łڂ����Ƃ����̂́A�^�������m��Ȃ����A���̂悤�Ȍl�͌����ēz��ɂ��ꂽ��A�ӖړI�ȓ���Ƃ��Ďd����������悤�Ȃ��Ƃ��A�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�v�����A�����̋@��(�ǐS�I�������ێ҂Ɋւ���莆��A�c��̔��Ċ��������ψ���֊��₳�ꂽ���Z���t�A�E�B���A���E�t���E�G���O���X�ւ̎莆)�ɁA�ނ͎s���I�s���]������B�u�����ƓI�̐��̂��ƂɁA���E�ɕ��a���A�����炻���Ƃ��邤���ł̖��́A�K���W�[�̕��@���K�͂Ɏ�����邱�Ƃ̂���Ă̂݁A���������Ƃ����̂��A���̐M�O�ł���܂��E�E�E�E�m���l�̏����h���w����̎��R��}������x���ɑR����ɂ͉����Ȃ��ׂ��ł��낤���B�����ɂ����āA�K���W�[�̈Ӗ��ł̔͐���Ƃ����v���I�ȕ��@�������o�����Ȃ��B�v���ނׂ��}�b�J�[�V�[����̓��t�������̕��͂́A�����Ƃ��Ă͂ނ���A�܂�Ȃ��̂ł������B ����ɁA�A�C���V���^�C���́u���q�̓G�l���M�[�̗��p��l�ނɖ𗧂`��(������)����ɂ��Ă̒m���Ə��y�����߂���@�Ői�߂Ă����v�K�v����Ɋ����Ă����B�u�E�E�E�E����́A������肵����ʎs�����A���g�Ɛl�ނ̗��v�ɖ𗧂`�ł̍s���𗝐��I�Ɍ��肵�A�`���ł��邽�߂ɕK�v�ł���v�ƁA���̒Z�����݊��ԂɃA�C���V���^�C�����c���߂����q�Ȋw�ҋً}�ψ���Ƃ����c�̂̌��͂ɏq�ׂĂ���B1954�N�A�A�C���V���^�C���́A�閧�ی���ŁA�I�b�y���n�C�}�[��e�N���悤�Ƃ���A�����J���O���̍s�����A���I�ɔᔻ���錴�q�͉Ȋw�҂̈��|�I�����Ɏ^�ӂ�\�������B ���̃A�C���V���^�C���̐����I�S�́A��ɏq�ׂ��e�[�}�ɏW������Ă����悤�Ɏv����B�ނ̒�Ă̂������́A�����A���I�ł���A�܂����̂��̂́A�܂����������ł������B�����A�����̒�Ă��A�����_�Ƌ��������I�M�O���琶�܂�Ă������Ƃ͊m���ł���B �A�C���V���^�C���̐����I�����ɂ��āA�����Ɛ[�����ŁA���Ƃ̓�̌����q�ׂ˂Ȃ�Ȃ��B�ނ́A�����ăh�C�c�l�������Ȃ������B�u�h�C�c�l���A�킪���E���_���l�̑�ʋs�E������Ă���́A���͍���A�h�C�c�l�Ƃ͈�̂�����荇�����A������͂Ȃ��E�E�E�B�\�Ȕ͈͂Ŏ����̗ǐS��ۂ����A�ق�̐����ɂ��Ă͗�O�ł���B�v�ނɂƂ��āA��O�̐����Ƃ́A�I�b�g�[�E�n�[���A�}�b�N�X�E�t�H���E���E�G�A�}�b�N�X�E�v�����N�A����ɃA�[�m���h�E�]���}�[�t�F���g�ł������B �A�C���V���^�C���́A�C�X���G�����{�ɂ��āA�����I�ɔᔻ�I�ȏꍇ�����������A�C�X���G���̑�V�̂��߂Ɍ��g�I�ł������B�ނ́A�C�X���G���̂��Ƃ��uus(�����)�v�A���_���l�̂��Ƃ��uMy people(�킪���E)�v�ƌĂB�A�C���V���^�C���̃��_���l�Ƃ��Ă̓��E�ӎ��͔N���Ƃ�ƂƂ��ɋ����Ȃ��Ă������悤�Ɏv����B�ނ́A�^�Ɏ����̌̋��ƂȂ�ꏊ�������������Ȃ������̂����m��Ȃ��B�������A�ނ͎����̑�����푰�͔����ł����̂ł���B�@ |
|
| ���v�����X�g���ɂ�����A�C���V���^�C�� | |
|
�A�C���V���^�C�����A�v�����X�g�������������̋����Ƃ��Ē��C�����̂́A1933�N�̓~�̂��Ƃł������B�������A���̂Ƃ��A�C���V���^�C���́A�P�Ȃ闷�s�҂̍��������ăA�����J�ɓ������̂ł������B
�������Ȃ���A�A�C���V���^�C���́A�ނ��A�����J�ֈڏZ���Ă���O�N�ڂ�1936�N�ɔނ̍ȃG���U���������B �A�C���V���^�C���ƃ~���[�o�̊Ԃɐ��܂ꂽ���j���A�A�C���V���^�C���ƂƂ��ɃA�����J�ֈڏZ�������A���̐l�͋Z�t�Ƃ��ēƗ������B �܂��A�G���U�̂�Ă�����l�̖��̂�����l�̓h�C�c�������Ă���A�܂��Ȃ��S���Ȃ������A������l�̃}���S�b�g�́A���̕v�Ɨ������Ĉȗ��̓A�C���V���^�C���ƈꏏ�ɏZ��ł����B���̃}���S�b�g�́A���������ƂƂ��ĕ��������l�ł������B �A�C���V���^�C���ɂ́A�}���Ƃ����l�̖����������A�ޏ��́A�A�C���V���^�C�����w���Ƃ̂���A�[���E�̏B���M���i�W�E���̐搶�̎q���ƌ������āA�C�^���A�̃t�B�����c�F�ɏZ��ł������A�C�^���A�ɂ�����i�`�̉e���ɕs���������āA�ޏ��̕v�̓X�C�X�ɋA��A�ޏ��͌Z��������ăv�����X�g���֗��Ă����B���̃}���̐��Ƙb���Ԃ�́A�Z�̃A�C���V���^�C���̂���ƁA��������ł���A�ނ��K�˂�l���������������B �j���[�W���[�W�[�B�A�v�����X�g���̃}�[�T�[�E�X�g���[�g112�Ԓn�̃A�C���V���^�C���̉Ƃɂ́A���̖��A�}���S�b�g�A���̖��}���̂ق��ɁA1929�N�ȗ��A�C���V���^�C���̔鏑���Ƃ߁A�̂��A�C���V���^�C���̃n�E�X�E�L�[�p�[�ƂȂ����w�����E�f���J�X�삪�������Ă����B���̃f���J�X��́A�A�C���V���^�C���Ɠ����V�����@�[�x���̐��܂�ł���A�G���U�E�A�C���V���^�C���Ɠ��������Ȓ��̏o�ł����āA���͓I�ɃA�C���V���^�C���̐g�̉��̎d����ЂÂ��Ă��ꂽ�B ���łɂׂ̂��悤�ɁA1933�N�̓~�ɃA�C���V���^�C�����A�A�����J�ɗ����Ƃ��ɂ́A�ނ͒P�Ȃ闷�s�҂Ƃ��Ă̍����������Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�A�A�����J�̈ږ��ǖ@�ɂ��A�A�����J�ɉi�Z���鋖��^������̂́A�A�����J�̎������ł������B�����āA���̗̎��́A�A�����J���O�ɂ������Ȃ��̂ł��邩��A�A�����J�ɉi�Z���鋖�悤�Ƃ���l�́A��x�A�����J�̊O�֍s���āA�����ŃA�����J�̎����炻�̂悤�ȋ���������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B �����ŁA�A�C���V���^�C���́A�o�~���[�_�̃C�M���X�̐A���n�֍s���A�����̗̎�����A�����J�։i�Z���鋖�悤�Ƃ����B �������A�A�C���V���^�C���̂悤�Ȑl�̂��̓��ւ̖K��́A���ȕ]������сA���́w���Ղ肳�킬�x�ɂ܂�Ă��܂����B���̒n�̃A�����J�̎��́A�A�C���V���^�C���̂��߂Ɋ��}�p�[�e�B�[�Â��A�A�C���V���^�C���ɁA�A�����J�ɉi�Z���鋖��^�����̂ł������B �������ăA�C���V���^�C���́A�A�����J�ɉi�Z���鋖��ƂƂ��ɁA�A�����J�̎s���ɂȂ肽���Ƃ�����]��\�����āA���̐\�����݂̂��߂̗p���邱�Ƃ��ł����̂ł������B �������A�A�C���V���^�C�����A�A�����J�̎s���ƂȂ邽�߂ɂ́A�܂��ܔN�ԑ҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�����āA���̂Ƃ��ɂ́A�A�����J�̌��@�ƁA�A�����J�̎s���̋`���ƌ����Ɋւ��鎎�������邱�ƂɂȂ��Ă����B���������ăA�C���V���^�C���́A���̎����̂��߂̕�����ɔM�S�ɍs�����Ƃ����Ă���B �A�C���V���^�C���́A1940�N��10���ɁA���̃}���S�b�g�A�鏑�̃w�����E�f���J�X�ƂƂ��ɁA�A�����J�s�������̂ł������B �������ăA�C���V���^�C���Ƃ��̈�Ƃ́A�v�����X�g���ł̐����ɂƂ�����ł������B�v�����X�g�������������̋����Ə����A�v�����X�g����w�̋����Ɗw���A�����ăv�����X�g���̒��̂��ׂĂ̐l�������A�A�C���V���^�C�����D�����B �����A�v�����X�g����w�̊w�������́A �@ The bright boys, they all study math And Albie Einstein points the path Although he seldom takes the air We wish to God he'd cut his hair �@ �G�˂ǂ��́@�������w������� �����ā@�A���r�[�E�A�C���V���^�C���͂��̕��j���w������ �ނ͖ő��ɊO�ɏo�Ȃ������ �����_�l�@�ނ��U�������܂��悤�� �@ �Ƃӂ����ĉ̂����B �܂��A�A�C���V���^�C���́A���̐l���瑊�ΐ����_�̒�`��������āA�ӂ����Ď��̂悤�ɓ������Ƃ����B �u�����j�̎q���A���ꂢ�ȏ��̎q�ƈꎞ�ԕ���ō����Ă����Ƃ���A���̈ꎞ�Ԃ͈ꕪ�̂悤�Ɏv����ł��傤�B�������A�����ނ��M���X�g�[�u�̂��Ɉꕪ�ԍ����Ă�����A���̈ꕪ�Ԃ͈ꎞ�Ԃ̂悤�Ɋ�����ł��傤�B���ꂪ���ΐ��ł��v �܂��A�A�C���V���^�C�����A���̂܂��̐l�����ɗ^������ۂɂ��ẮA���I�|���g�E�C���t�F���g�����̂悤�Ɍ����Ă���B �u�v�����X�g���ɂ����鎄�̓����̈�l�͎��ɂ��̂悤�ɂ����˂��B�w�����A�C���V���^�C�����A�ނ̖��������炢�A�ނ̃v���C�o�V�[����낤�Ƃ���̂Ȃ�A�Ȃ��ނ͕��ʂ̐l������悤�Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��낤���B�Ȃ��ނ͔����̂��A�������Ȕ�̏㒅�𒅁A�C�����͂����A�T�X�y���_�[�������A�J���[�������A�l�N�^�C�����߂Ă��Ȃ��̂��낤���x--- ����ɑ��铚���͊ȒP�ł���B�ނ̍l���́A�ނ̓��p�𐧌����A��������Ȃ����邱�Ƃɂ���Ĕނ̎��R��傫�����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɂ���B�����́A���ɑ����̕����̓z��ɂȂ��Ă���B�����́A���オ��ɒ��钅���A�d�C�①�ɁA�����ԁA���W�I�A�����Ă��̑��̑����̎����̓z��ɂȂ��Ă���B�A�C���V���^�C���́A�������ŏ��ɂ��悤�Ǝ��݂��̂ł���B�������́A�U�����֍s���K�v���ŏ��ɂ����A�C���͂͂��Ȃ��Ă����ށA��̔�̏㒅������A����͐��N�Ԃɂ킽���ď㒅�̖�����������B�T�X�y���_�[�́A�Q���̒��V���c��p�W���}�̂悤�ɗ]�v�Ȃ��̂ł���v �v�����X�g���̐l�����́A�A�C���V���^�C���Ɋւ��đ����̈�b������Ă���B���̂Ȃ��ɂ��̂悤�Ȃ̂�����B �A�C���V���^�C���̋ߏ��Ɉ�l�̏������Z��ł������A���̏����̕�e�͂���Ƃ��A�������A�Ƃ��ǂ��A�C���V���^�C���̉Ƃ�K�₷�邱�ƂɋC�������B�����ŕ�e���s�v�c�Ɏv���āA���̗��R�������˂�ƁA�����͕��C�Ȋ�ŁA���̂悤�ɓ������B �u�킽������Ƃ����w�̏h��̒��ɉ����Ȃ���肪�����č����Ă����́B��������F�������w���Ȃ��̋ߏ���112�Ԓn�ɂ́A�A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���Ƃ������E�I�Ȑ��w�҂��Z��ł���x���ċ����Ă��ꂽ�́B�����ł킽���A���̃A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���搶���������˂��āA���̍����Ă���h��������ĉ�����悤����ł݂��́B��������A���̐l�́A�Ƃ��Ă��悢�l�ŁA��낱��ł킽���̍����Ă������������ĉ��������́B�ƂĂ��e�ɋ����ĉ��������̂ŁA�w�Z�ŏK�����A�悭�킩������B���������̐l�́A���������肪��������A�܂����ł��A��������Ⴂ�ƌ����ĉ��������̂ŁA�����肪����Ƌ����Ă��炢�ɂ����̂�v ���̏����̕�e�́A���̘b�ɂт����肵�Ă��܂��āA�����A�C���V���^�C���̏��֘l�тɍs�������A�A�C���V���^�C���́A �u���₢��A����Ȃɂ��l�тɂȂ�K�v�͂���܂���B���͂��Ȃ��̂��삳��Ƙb�����邱�Ƃɂ���āA���삳������w���ƈȏ�̂��Ƃ��A���삳��w�ɂ������Ȃ�����ł��v�Ɠ������Ƃ����B �A�C���V���^�C�����A���̂��삳��ɖ��̉�@����������Ƃ��ɏ����������c���Ă��邪�A���̖��̈�́A�^����ꂽ��̉~�n1�Ƃn2�ɑ��ċ��ʐڐ��������A�Ƃ����̂ł������B�@ |
|
| �����H�̏I��� | |
|
��2�����E���̊ԁA�A�C���V���^�C���́A�Â��ɉ߂������B���[�Y�x���g�哝�̂ɁA�j�̌��������Ȃ����莆�����������A�����̐����ɂ͊ւ��Ȃ������B�푈���I���ƁA�A�C���V���^�C���́A�������`�E�咣�Ɋւ��Č��������߂�ꂽ�B�V�������ƃC�X���G���̑哝�̂ɂȂ��ė~�����Ƃ̗v�������������A�������A���ނ����B�ނɂƂ��āA�����܂ōŗD��͉Ȋw�������B
�ӔN�̃A�C���V���^�C���ɂ��Ĉꌾ�����ӂ�Ă������B�v�����X�g���̔ӔN�̃A�C���V���^�C���ɏo��������Ƃ�����Ƃ�����l�̘V�����A���̎��̈�ۂ���������Ă���---�w�܂�ŗH��݂�����������x---���̘V���̌����A�C���V���^�C���̎p---����́A�g���ɖ��������U�����A�C���V���^�C���̐^���̎p�������̂����m��Ȃ��B 1955�N�̏t�A�A�C���V���^�C���̐S���́A�s���������������B�����āA�ނ͓��@�����B�ނ́A�a���ɁA�鏑���ĂсA���N�M�Ɗዾ�Ə��������̌��e������Ă���Ɨ��B�������A�����������Ă��邱�Ƃ�m���Ă����B����ł��A�d�����C�ɂȂ�u���͌v�Z�������v�ƌ������B��������āA�v�Z���Ă��A���̐��ʂ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƁA�ނ͒m���Ă����B�ނɂ́A����ł��ǂ������B1955�N4��18���ߑO1��15���A�A���o�[�g�E�A�C���V���^�C���́A�����Ђ��Ƃ�B���N76�ˁB�ނ́A��Ԃ⎞�ԁA�F���̍\���ɂ��Ă̔F�����A�i���ɕς��āA�����āA�����Ă������B �A�C���V���^�C���̌��t�u���́A���U�A���R�̒��ɉB��Ă��钁�����A�킸���ł��A�����܌��悤�Ƃ��Ă��܂����B���ׂẲȊw�́A���E�̒��ɑ��݂��钲�a���A�M����K�v������܂��B�����������Ƃ����������̎v���́A�i���̂��̂ł��B�v �A�C���V���^�C���̕�͂Ȃ��B�v�����X�g���̑��V�p�[���[�ōs��ꂽ�ނ̑��V�́A�킸��12�l���Q�����������̊ȑf�Ȃ��̂������B�ނ̓��e�ł́A���j�̃n���X�E�A���o�[�g�������A����������B�ނ̍ŏ��̍ȁA�~���[���@���A��l�ڂ̃G���U���A���łɐ��������Ă����B���V�́A�F�l�ٌ̕�m�I�b�g�[�E�l�[�T�����A�Q�[�e�̎��u�V���[�̏��ւ̃G�s���[�O�v�̈�߂��Ï����������ŏI������B���̒ʒm���o�����A�ԗւ����y���T����悤�ɁA�A�C���V���^�C���́A�⏑�ɂ������߂��̂������B�o�Ȏ҂̂����A��l�̏����������A�J�g���b�N���k�������̂ŁA�ޏ��́A��ւ̃J�[�l�[�V�������A�C���V���^�C���ɕ������B�u�P���Ȃ��̂����������v�A�C���V���^�C���́A���U�A�����M���Ă����B ��̂�䶔��ɂӂ���A��u�ɏ]���āA�D�͋߂��̃f���E�F�A��ɗ����ꂽ�B�@ |
|
| �������� | |
|
�����́A�A�C���V���^�C���̋Ɛт��A�ǂ��]�����ׂ��ł��낤���H�@�A�C���V���^�C���́u��ʑ��ΐ����_�v�́A�����̉F���_�̓y���z�����B�������A�����Ɂu���ΐ����_�v��---�A�C���V���^�C�����g�������悤�Ɂu�d�v�Ȑi���́A�����V�������������N�����܂��v---�����̓���c�����B�����̉F���_�́A���͂�A�ϑ��Ŋm���߂���͈͂��͂邩�ɒ����Ă���B�ǂ̗��_���ؖ����邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł���B�����́A���邢�́u��ʑ��ΐ����_�v��m��Ȃ�����---�܂�A�j���[�g���̗͊w�̂悤�ɁA�u���ԁv�͐�ʼni���ł���u��ԁv�́A�܂������ʼnʂĂ��Ȃ����̂ł���Ƃ������E�ς��A���̂܂ܐM���Ă�������A�悩�����̂����m��Ȃ��B����u�ʎq�͊w�v�́A�ǂ����낤�B���Ƃ��A���̍��{�������������낤���������Ȃ��낤���u21���I�̉Ȋw�̐i���́A�ʎq�͊w�Ȃ��ɂ͍l�����Ȃ��v�ƌ����Ă���قnj��݂̉Ȋw�Z�p�ɍv�����Ă���B�����܂ł́u�ʎq�͊w�v�̋}���Ȑi���́A���̎��p���ɗv�����������̂��낤�B���̓_���炢���u�ʎq�͊w�v�́u��ʑ��ΐ����_�v�����A�����̐����ɐړ_�������B
�A�C���V���^�C���̒T���́u���R�𗝉��������v�Ƃ����Ȋw�҂̗~���������߂̂��̂ɉ߂��Ȃ������̂��B����A�Ȋw�̐i�����A�Ȋw�҂̗~�������ɔC�����邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�A�C���V���^�C���̋Ɛт́A�����������������̂��B�����݁A�����́A�����P���Ɍ����\�����͂ł��Ȃ��B�������A������A�������������m��Ȃ����A���̓����͕K���o��ƐM���悤�B�@ �@ |
|
| ���A�C���V���^�C��2 / ���c�ЕF�@ | |
|
����
���̊ԓ��{�֗�������o�[�g�����h�E���b�Z�����A�u�����E���ň�Ԃ��炢�l�Ԃ̓A�C���V���^�C���ƃ��j�����v�Ƃ����悤�ȈӖ��̎���N���ɘb���������ł���B���́u���炢�v�Ƃ����̂��ǂ������Ӗ��̂��炢�̂ł��邩�����������̂ł��������A�⊶�Ȃ��烉�b�Z���̎g����������k�炵���B �Ȃ�قǓ�l�Ƃ��Ɋv���Ƃł���B�������j���̎d���͂ǂ��܂ł������ł��邩���s�ł��邩�A�����炭�͂���͒N�ɂ��悭����Ȃ����낤���A�A�C���V���^�C���̎d���͏��Ȃ����啔���������ɐ����ł���B����ɂ��Ă͐��E���̐M�p�̂���w�҂̍ő命�������������Ă���B�d�����Ȋw��̎��ł��邾���ɂ��̐��ʂ͋ɂ߂đN���ł���A�]���Ă�����d�������l�̉Ȋw�҂Ƃ��Ă̂��炳���܂����ꂾ���͂����肵�Ă���B ���j���̎d���͉Ȋw�łȂ������ɁA���̐l�̂��̎d���̐��s�҂Ƃ��Ă̂��炳�͕K�������ڑO�̐��ʂ݂̂Ōv�ʂ��鎖���o���Ȃ��B����ɂ�������炸���j���̂��炳�͈�ʂ̐��l�ɕ���₷����ނ̂��̂ł���B�戵���Ă�����̂��l�Ԃ̎Љ�ŁA�g���Ă�����̂���������ł���B��������Ȋw�I�ɂ͖�̕���Ȃ����̂ł��邪�A�������l�̐����ɒ��ڂȂ��̂ł��邾���ɁA�������N�ɂ�����₷���悤�Ɏv����B ����ɔ����ăA�C���V���^�C���̎戵�����Ώۂ͒��ۂ��ꂽ���Ƌ�Ԃł����āA�g��������͐��w�ł���B���ׂĂ��_���I�ɖ��ĂȂ��̂ł���ɂ�����炸�A�g���Ă���u����v�����l�ɐe�����Ȃ����߂ɁA���̍���ɏn���Ȃ��l�ɂ͗e�ՂɐH���t���Ȃ��B����Ŕނ̎d���𐳓��ɗ������A�ނ̂��炳��@���ɘĉ��s�����t����ɂ́A��ʂ�̐��w�I�f�{�̂���l�ł�������ƍ����܂��B ���ꕪ��Ȃ��悤�ȕ��G�Ȏ��͐��l�ɕ���₷���A��r�I�ȒP���ĂȎ��̕����p�s�����t���ĕ���ɂ����Ƃ����������Ȍ��_�ɂȂ��ł��邪�A����́u����v�Ƃ������t�̈Ӗ��̎g�������ł��鎖�͖ܘ_�ł���B �A�C���V���^�C���̎d���̈̑�Ȃ��̂ł���A�ނ̓��]����ї���Ă��炢�Ƃ������͑�������ꕔ�̊w�҂̊Ԃɂ͔F�߂��Ă����B��������ʐ��ԂɎ��s���t�Ě��s�͂�t�����悤�ɂȂ����͍̂����̎��ł���B�����P���̌������z�̋߂���ʉ߂���ۂɁA���ꂪ�d�͂̏�̉e���̂��߂ɋɂ߂Ă킸���Ȃ邾�낤�Ƃ����A�N���v���������Ȃ������������A�ނ̗��_�̕K�R�̌��ʂƂ��ĉ��M�̂����Ŋ���o���A�����\�������B���ꂪ�]��ΓG���̉p���̊w�҂̓��I�ϑ��̌��ʂ��炠����x�܂Ŋm���߂�ꂽ�̂ŁA�����͐��l�̊�Ɉ��̃��}���`�b�N�ȐF�ʂ�тт�悤�ɂȂ��ė����B�����Đl�X�͂��������}�ɓV����ِl���~���ė������̂悤�ɋ��ق̊�s�܂Ȃ��t��ނ̐g�ӂɏW�������B �ނ̗��_�A���Ƃɏd�͂Ɋւ���V�������_�̎����I�؍��́A���ꂪ��������ɂ߂ċ@���Ȃ��̂ł��邾���ɂ܂��ɓx�܂Ŋ��S�Ɋm�肳�ꂽ�Ƃ͉]���Ȃ���������Ȃ��B���������ꏫ���̎�����ϑ��̌��ʂ��A�ނ̌��݂̗��_�ɑ����ł��s���Ȃ悤�Ȏ����������Ƃ��Ă��A�ނ̕����w�҂Ƃ��Ă̂��炳�ɂ͂��̂��߂ɏ������r�s�����t�����Ȃ����낤�Ƃ������́A�ނ̎d���̋ؓ�����ʂ�ł����Ēʂ����l�̓��������F���Ȃ���Ȃ�Ȃ����ł��낤�B �����w�̊�b�ɂȂ��Ă���͊w�̍��{�Ɉ����_�̂���Ƃ������͑�������F�߂��Ă����B�������ވȑO�̑����̊w�҂ɂ͂�����ǂ������炢����������Ȃ������B���邢�͑命���̐l�͈��P�I�̑Ë��ɓ��ĕʂɂǂ����悤�Ƃ��v��Ȃ������B�͊w�̋��ȏ��͂��̋}���ɐG��Ȃ��悤�ɒm��������Ă��܂��Ă����B����ł����p��̑����̖��ɂ͎��ۍ��x�����Ȃ������̂ł���B�Ƃ��낪�ߑ�ɂȂ��ēd�q�ȂǂƂ������̂���������A������d���C����M�̌��ۂ͂��̕s�v�c�ȕ��̍�p�ɋA�[�����悤�ɂȂ����B�����Ă��̕������ʂȏ����̉��ɋ����ׂ������x�ʼn^�����鎖�������ė����B�����������̉^���ɊW�������ɐG�ꏉ�߂�Ɠ����ɁA���܂ł����Ƃ��Ă������͊w�̋}�������낻��ɂ݂�������悤�ɂȂ��ė����B�������c�̂��Ƃ��D�ꂽ�V��Ƃ͎��s�͂�t�����炱�̖��Ɏ���āA�F�X�Ȗ����̒ɂ݂��Ǖ��I�̎�p�Ŏ��Â��悤�Ƃ��č��܂��Ă���ԂɁA���̎Ⴂ�����̊w�҂̓X�C�X�̓����ǂ̈���ɂ�����āA�����Ƃ����ƍ��{�I�ȑ��p���l���Ă����B�a�̍��͓d���C����������ƍ��{�I�Ȏ��Ƌ�Ԃ̊T�O�̒��ɐ������Ă��鎖�Ɋ�������B�������Ă��̕��肩�������A�Ԃɍ��킹�̎��Ƌ�Ԃ�����Ď̂ĂāA�V�������S�Ȃ��̂����̑��ɐA�����B���̎�p�ŕ����w�͈��Ɏ�Ԃ����B�����ēd���C����Ɋւ��闝�_�̑����̕a�}�s�т傤�����t�͂ЂƂ�ł��Y��ɏ��ł����B �a�����������̂����̂��炳�ŁA�������p������ہs�Ă���t�͑��̂��炳�łȂ���Ȃ�Ȃ��B �������a�C�͂��ꂾ���ł͂Ȃ������B���̎�p�Łu���x�̑��ΐ��v��Еt����ƁA�K�R�̐��s���Ƃ��āu�d�͂Ɖ����x�̖��v���N���ė����B���̋}���̒ɂ݂́A���̋}���̒ɂ݂����������߂Ɉ�w�s���������ė����B���������̕��̎�p�͈�w�ʓ|�Ȃ��̂ł������B���Ɏ�p�Ɏg�����ݗ��̓���͂������ɗ����Ȃ������B�ᓙ�̑c�悩����N���g����ꂽ���[�N���b�h�w�ł͎n�����t���Ȃ������B���̑��ɂȂ�ׂ��V������������߂Ă���ނ̎�ɐG�ꂽ�̂́A�O���I�̒����ɐ��w�҃��[�}�����A���̂悤�ȉ��p�Ƃ͉��̊W���Ȃ��ɏ����Ȑ��w��̗��_�I�̎d���Ƃ��Ďc���Ă������╨�ł������B�����B�s�����t�������đ������V�����s���ȃ��X�ŁA����N���l�Ԃ̔]�̒��ɂւ�t���Ă���������펯�I�Ȏ���̊ϔO�����F�s���������t��������B�����Ă����荏��ŐV�����g���Ă��u����̐��E���v�������Ɉ��u�����B����ŏd�͂̔閧�͎����I�ɉ��߂����Ɠ����ɌÂ��͊w�̈Ïʂł����������^���̕s�v�c�͖����Ȃ��ɐ�������A���Əd�͂̊W�ɑ�������ׂ��\���͓I�������B������̗\���͂ǂ��Ȃ邩����Ȃ����A�Ƃ����������܂ŕБ������������鎖�̏o���Ȃ��������E�́A���������ɒu���Ĉӂ̂܂܂ɔC�ӂ̑�����ς鎖���o����悤�ɂȂ����B�ώ҂Ɋւ��邠�����ΐ���Ŕj���鎖�ɂ���Č��o���ꂽ�q�ϓI���݂́A����Ӗ��ŋp���Đ�Ȃ��̂ɂȂ����Ɖ]���Ă��悢�B ���̎d�����d�����邽�߂ɕK�v�ł������ނ̓O��I�Ȏ��M�͂����鍢��𗽉�s��傤���t�������悤�Ɍ�����B�������̂��炳�ł���B�����钼�ڌo�����痈��펯�̌��e�ɘf�킳�ꂸ�ɏ����̓��̂́A���w�Ƃ�����B�̌���ł���Ƃ��Ă��A�S�����ۓI�Ȑ��w�̘g�ɖ��ۂ̎����E�𐡕��̌��Ԃ��Ȃ���͂߂��N�₩�Ȏ�ۂ͕����w�҂Ƃ��Ă��̔�}�Ȃ��炳�ɂ����̂ƍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ����������тʂ������]�������Ă��āA�����Ĕ�r�I�Z���N���̊Ԃɂ��ꂾ���̎d�����d�����邾���̊��͂������Ă���l�Ԃ́A�u�l�v�Ƃ��Ă̐����s�������t����A���퐶����A���͑����̐l�̒m�肽���Ǝv���Ƃ���ł��낤�B ����Ŏ��͗L�荇���̎�߂ȍޗ�����m�蓾���邾���̎��������ɏ������ׂāA���̊w�҂̖ʉe��O�C�s���ڂ낰�t�ɂł��Љ�Ă݂����Ǝv���̂ł���B��ȍޗ��̓��X�R�t�X�L�[�̒����ɋ���O�͂Ȃ������B�v����ɑf�l��Ɓs���낤�Ƃ����t�̃X�P�b�`�̂悤�Ȃ��̂��Ǝv���ēǂ�ł��炢�����̂ł���B�@ |
|
|
����
�A���x���g�E�A�C���V���^�C���͈ꔪ����N�O���̏o���ł���B���{�Ȃ�Ζ����\��N�K�̐���Ő����N�l�\�O(�吳�\�N)�ɂȂ��ł���B���ꂽ�ꏊ�͓�h�C�c�Ńh�i�E�̗���ɉ��������s�s�E�����ł���B���̃h�C�c�ň�ԍ����S�`�b�N�̎����̂���Ƃ����O�ɂ͊i�ʐ��E�Ɍւ�ׂ����������L�s���t���Ȃ��炵�����̎s���͋��R�ɂ��̉Ȋw�҂̏o���ƌ��ѕt�����鎖�ɂȂ����B���̓y�n�ɂ�����ނ̗c�N����ɂ��Ēm�蓾���鎖���͈⊶�Ȃ���ɂ߂ď��Ȃ��B������̈�b�Ƃ��ē`�����Ă���̂́A�ނ��܍̎��ɁA�������̗��j�Ղ�������ꂽ��������A���̎��ɁA���璼�ڂɐڐG������̂̂Ȃ����j���A��������͂̍�p�œ����̂����Ĕ��ɋ�����ۂ����Ƃ������ł���B���̎��̈�ۂ��ނ̌�N�̎d���ɂ���e����^�����Ƃ��������ގ��g�̌�����`����Ă���B ���x���̍��A�ނ̕��͉Ƒ��������ă~�����w���Ɉړ]�����B���x�̉Ƃ͑O�̂��܂��邵���Z���Ƃ������čL���뉀�Ɉ͂܂�Ă����̂ŁA�����ŏ��߂Ď��R�ɐڂ��邱�Ƃ̏o�������R�E�̈�ۂ��ނ̐��U�Ɍ����Ė��Ӗ��ł͂Ȃ������ɑ���Ȃ��B �ނ̉Ƒ��Ƀ��_���l��̌�������Ă���Ƃ������͒��ڂ��ׂ����ł���B��N�̔ނ̎d����A�Љ�l���ςɂ́A���̎����Ǝv�������ď��߂ė��������_�����Ȃ��Ȃ��悤�Ɏv���B����͂Ƃɂ����ނ��~�����w���̏��w�Ŏ����[�}�J�g���b�N�̋��`�Ɖƒ�ɂ����郆�_�����̋��`�Ƃ̑��ΓI�Ȗ����\�\���P�I�ȓƒf�Ɠƒf�̔w�y�s�͂����t���ނ̗c���S�ɂǂ̂悤�Ȕ������N���������A������{�l�ɕ����Ă݂������ł���B ���̎���̔ނ̊O�ςɂ͉���̉s���V�˂̑M���͌����Ȃ������B���̂��]�������o����̂����ʂ��x���A���̂��߂ɗ��e���S�z�������炢�ŁA�傫���Ȃ��Ă���͂���d�ł������B���A����̔ނ͂ނ���T���ڂŁA���܂�l�D���̂��Ȃ��A�Ƃ�ڂ����̒��ԊO��̊ς��������B�������̍�����^�Ɛ��`�ɑ���ɒ[�ȕΎ����ڂɗ������B����Ől�X�́u�n�������s�r�[�_�[�}�C�A�[�t�v�Ƃ����Ӗ��s�����ȁt��ނɗ^�����B���́u�n�������v��O�ꂳ�������̂������̔ނ̎d���ɂȂ낤�Ƃ́A�N�����ɂ��l���Ȃ��������ł��낤�B ���y�ɑ���n�D�͑��������o�߂Ă����B�Ƃ�Ŏ]���̂̂悤�Ȃ��̂�����āA�Ƃ�ł�������̂��Ă������A�p�����������ė��e�ɂ�����͉B���ĕ������Ȃ����������ł���B�r���ȗV�Y�Ȃǂ��牓���������Ƃ�ڂ����̎q���̓��ȓI�ȌX���������ɂ��F�߂���B ��N�܂Ŕނɂ��܂Ƃ������_���l�ɑ���V���[���B�j�Y���̔��Q�́A�������̍�����ނ̗c���S�ɏ����Ȕg���𗧂ď��߂��炵���B�����Ă��̕s���`�ɑ��锽�R�S���ނ̐��i�ɉ����̍��Ղ��c���Ȃ���ɂ͍s���Ȃ������낤�Ǝv����B�u���_���l�͂��̐E�Ə�̊��▯���̉ߋ��̂��߂ɁA�l����M�p�����Ƃ����o���ɖR�����B���̓_�Ɋւ��ă��_���l�̊w�҂ɒ��ڂ��Č��邪�����B�ޓ��͘_���Ƃ������̂ɗ�ᎁs�����炱�ԁt������B���Ȃ킿���@�ɂ���đ��̏��������v����B�����I��������͐M�p�������Ȃ��l�ł��A�_���̑O�ɂ͋������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����m���Ă��邩��B�v�����]�����j�[�`�F�̂ɂ��ɂ��������t�����X�ɋ�����X�̎��ɋ����悤�Ɏv����B �ނ̊w�Z���т͂��܂�悭�Ȃ������B���Ɍ���Ȃǂ��@�B�I�ɈËL���鎖�̉���Ȕނɂ͓����̌R�����ȋl�ߍ�����͍H�������������B����ɔ����Đ��w�I�����̔\�͂͑����������o�����߂��B�v�Z�͏��łȂ��Ă��l���������ɍI���ł������B���鎞�ނ̔����ɓ���l�ŁA�H�ƋZ�t�����Ă��郄�[�R�u�E�A�C���V���^�C���ɁA�㐔�w�Ƃ͈�̂ǂ�Ȃ��̂��Ǝ��₵�������������B���̎��ɔ������u�㐔�Ƃ����̂́A����͕s�����̂̂��邢�v�Z�p�ł���B�m��Ȃ������w�Ɩ��Â��āA�����Ă����m���Ă���悤�Ȋ�����Ď戵���āA����ƒm���Ă�����̂Ƃ̊W���������B�������炱�̂w���߂�Ƃ������@���v�Ɖ]���ĕ��������B���̙��y�s�Ђ傤����t�ȁA�������v�������͎q���̓��ɖ����Ă��関�m�̑㐔�w���Ăъo�܂��ɂ͏[���ł������B���ꂩ��F�X�̑㐔�̖��͂ЂƂ�Ŋy�ɉ�����悤�ɂȂ����B�n�߂āA�w�̃s�^�S���X�̒藝�ɑŁs�ԁt���������ɂ͂���ł��O�T�ԓ����Ђ˂������A�����܂��ɂ͐��ɂ��̏ؖ��ɐ��������B�_���I�Ɋm���Ȃ��镨��߂����т́A�������̍�����ނ̂���Ⴂ���ɟ��ݓn���Ă����B�����Ɋւ���ނ̏����͊w�Z�̋����ȂǂƂ͖��W�ɋ����ׂ����x�ő��債���B�\�܍̎��ɂ͂�����w�ɓ���邾���̎��͂�����Ƃ��������W��̋��t���錾�����B �����������w�Z�𑲋Ƃ��Ȃ������Ɋw�Z�������ꎞ���f����悤�ɂȂ����Ƃ����̂́A�ނ̉Ƒ��ꓯ���C�^���A�ֈڏZ���鎖�ɂȂ����̂ł���B�ޓ��̓~�����ɗ��������B�����ł��炭���R�̐g�ɂȂ������N�͂悭���s�������B���鎞�͒P�g�ŃA�y�j�����z���ĕY�Q�����肵���B�Ԃ��Ȃ��ނ̓`���[���q�̃|���e�L�j�N���֓��w���Đ��w�ƕ����w���C�߂�ړI�ŃX�C�X�ւ���ė����B�����������L�ډȊw�̑f�{������Ȃ������̂ŁA���炭�A�[���E�̎��Ȓ��w�ɂ͂����Ă����B�킸���ɏ\�Z�̏��N�͊��ɂ��̎�������u�^���̂̌��w�v�Ɋ��t�����߂Ă����Ƃ������ł���B��N���E�����������d���͂������̎�����o�t�s�ӂ��t���o�����߂Ă����̂ł���B �ނ̌��l�Ƃ��Ă̐��U�̖]�݂͋����ɂȂ鎖�ł������B����Ń`���[���q�̃|���e�L�j�N���̎t�͉Ȃ̂悤�ȕ���֓��w���ď\�������\��܂ŕ������B���ƌ�ނ��ǂ����̑�w�̏���ɂł����b���悤�Ƃ���҂����������A���Ђ�l��̖�肪�ז��ɂȂ��Ďv�킵�����������Ȃ������B�������ƒ�̌o�ς͊y�łȂ���������A�Ƃ������������œ����ĐH��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�V���t�n�E�[����x�����Ŏ����t���߂Ȃ���Â��ɐ[�������w��������B���Ȃ�ɕn�����邵�����Ă����炵���B���̎����̌��w�̒��Ԃɓ샍�V�A���痈�Ă��鏗�w���������āA���̌���Z�O�N�ɂ��̐l�ƌ������������N��ɗ��������B�����ƌ�ɏ]���s���Ƃ��t�̃G���[�E�A�C���V���^�C�����}���čK���ȉƒ������Ă���Ƃ������ł���B ���Z��N�A�X�C�X�؍ܔN�̌�Ƀ`���[���q�̌������Ă���ƌ��E�ɏA�����i���o�����B�����̗F�O���X�}���̎����s���イ����t�œ����ǂ̋Z�t�ƂȂ��āA�����Ɉ��Z��N������Z��N�܂ŋ߂Ă����B�ނ̂悤�Ȓ��ۂɒ��������_�Ƃ��ɂ߂Ĕڋ߂Ȕ����̐R��������Ă����Ƃ������͖ʔ������ł���B�ގ��g�̌��t�ɂ��Ƃ��̐E���ɂ������ȋ����������ē����Ă����悤�ł���B ���Z�ܔN�ɂȂ��Ĕނ͉i���Ԃ̌����̌��ʂ\���n�߂��B���̒��ɂ����ς��ɂ��܂��Ă������̂���͂̒���������悤�Ȑ����ň��o�����B�w�����N�Ӂx�ɏo�����_�������ł��l�ł��̊O�Ɋw�ʘ_�������������B����������h�Ȃ��̂ł��邪�A���̒��̈�����Θ_�̌��c�Ə̂�����u�^�����镨�̂̓d�C�͊w�v�ł������B�h�C�c�̑�ƃv�����N�͂��̘_�������ċ����Ă��̖����̐N�Ɏ莆���A���̔�}�Ȓ��z�̐������j�������B �x�����̑�w�͔ނ�������Ƃ����S�O�s���イ����t���Ă����B����Ɣނ̈֎q���o����ƊԂ��Ȃ��A�`���[���q�̑�w�̕��ŗ��_�����w�̏������Ƃ��ď��فs���傤�ւ��t�����B���ꂪ���Z��N�A�ނ��O�\��̎��ł���B�����ǂɉB��Ă������|�����N�̒n���ȕ��a�̐����́A�����炭�ނ̂Ƃ��Ă͈Ӌ`�̐[�����̂ł������ɑ���Ȃ����A�Ƃ��������O�\��ɂ��Ĕނ͗����Ďn�߂Ė{����ɏ��o������ł���B�����N�ɂ̓v���[�O�̐������ɏ��ق���A�����N�ɍĂу`���[���q�̃|���e�L�j�N���̋����ƂȂ����B���̎n�܂�������l�N�̏t�x�������Ɉڂ��Ă����Ŏd����听�����̂ł���B �x��������w�ɂ���ނ̒��u���̐��͏]���̃��R�[�h��j���Ă���B���N���}�ɐ��E�I�ɗL���ɂȂ��Ă���V���G���L�҂͖ܘ_�A��ƒ����Ƃ܂ł��ނ̖�ɉ����悹�āA�ё���`�����당������炵�Ă���Ƃ����ށB�u�`�����܂��ĘL���֏o��Ɗw�������������Ď��������B��s�����t�A��Ɛ��E���̊w�҂�f�l�s���낤�Ɓt����F�X�̎���⒐���̎莆�����Ă���B����ɑ��Ĉ�X���Ƃ��Ԏ����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B�O������u�������ɗ��Ă���Ɨ��܂��B���̂悤�ȗv���͌����ɔM�S�Ȋw�҂Ƃ��Ă̔ނɂ͖��f�Ȃ��̂ɑ���Ȃ����A�ނ͊i�ʁb�}�s����t�Ȋ�����Ȃ��ŋC�i�ɐe�ɒN�ɂł�������^���Ă���悤�ł���B �ނ̖������}�ɗg�������ŁA�ނɑ��锗�Q�̉̎�������Ȃ����B���_���l��r�˂Ƃ������{�l�ɂ͂�����ƕ���Ȃ��A�����������̃h�C�c�l�ɂ͕���₷�������ɁA�����͕ʂ̖��ȓ��@��������āA��c�̃A�C���V���^�C���r�˓����̂悤�Ȃ��̂��o�����B�ܘ_�命���͕����w�҈ȊO�̐l�ŁA���ɂ͂����Ԃ����킵���l���������Ă���悤�ł���B���ꂪ����x�������̃t�B���n�[���j�[�Ō��J�̒e�N����������Ė��Łs�ނ�݁t�Ȉ�������ׂ��B���ɕ����w�҂Ɩ��̂��l����l���āA����͂������ɒ��ڂ̐l�g�U���͂��Ȃ��ő��Ό����̔ᔻ�̂悤�Ȏ����q�ׂ����A����͂قƂ�ljȊw�I�ɂ͖����l�Ȃ��̂ł������B�v����ɂ��̉�����͏����Ȉ�����̕\���ɏI���Ă��܂����B�C�̉i���A�C���V���^�C�������Ȃ�s�������������ƌ����āA�}�Ƀx������������Ɖ]���o�����B����ƃx��������w�ɋ�����w�̏���Ƃ́A����A�C���V���^�C�����Ȃ��߂�Ɠ����ɁA�A���ŐV���ٖ֕������o���A�ނɑ���U���̕s���Ȏ��𐳂��A�ނ̉Ȋw�I�v���̈̑�Ȏ���ۏ����B�܂��A�C���V���^�C���͐i�܂Ȃ������炵���̂��A�����߂Ď��g�ٖ̕������������A������V���Ɍf�����B���̒Z�����͂͗�̒ʂ�L�r�L�r�Ƃ��ċɂ߂ėv�Ă���͖̂ܘ_�ł��邪�A���̍s���̊Ԃɔڋ��Ȕ��Q�҂ɑ����X�������������Ă���悤�ł���B�ނɑ��铯��҂͉�������d����悱�����肵���B���̒��ɂ̓}�N�X�E���C���n���g�̖����������Ă����B ���̌�i�E�n�C���ʼnȊw�ґ��̂��������A���ɂ��̒��̈���𑊑Θ_�̘_�]�ɂ��Ă������B���̎��̉��͉��ƂȂ��ْ����Ă��������l�̃A�C���V���^�C���͋ɂ߂ēۋC�s�̂t�Ȋ�����Ă����B���i�[�h�������̔����q�ׂĂ���ԂɁA���ăt�B���n�����j�[�Ŕނ̐l�g�U����������j�����̕��̐Ȃ��甏��������肵���B���������i�[�h�̋}�s���t��������́A��ÂȁA�������s�����قŌy�������ꂽ�B ���i�[�h�u�������ۂ���ȏd�͂́w��x������Ȃ�A���������ƌ��₷��(anschaulich)���ۂ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�v �A�C���V���^�C���u���₷���Ƃ����₷���Ȃ��Ƃ��������͎���ƂƂ��ɕς���̂ŁA�]��Ύ��̔����ł���܂��B�K�����[�̎���̐l�ɂ͔ނ̗͊w�͂�قnj��₷���Ȃ����̂������ł��傤�B�����錩�₷���ϔO�ȂǂƏ̂�����̂́A��́w�펯�x�w���S�ȗ��m�x(gesunder Menschenverstand)�Ə̂�����̂Ɠ��l�ɂ����Ԃ��炯�Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�v ���̕ԓ��Œ��O�����o�����Ɠ`�����Ă���B���̓��_�͓��ꑊ�o�ɂȂ�Ȃ��ŏI�������炵���B ���N�͕č��֏�����ču���ɍs�����B���̋A��ɉp���ł��u����������B���̓����̔ނ̒n�̐V���͔ނ̕��тƍu���Ԃ�����̂悤�ɓ`���Ă���B �u�c�c�B������ƌ����Ƃ���ł͕ʂɓ��X�Ƃ����l�q�Ȃǂ͂Ȃ��B���w�ŁA����Ă��āA�������肵�Ă���B�l�\�O�ɂ��Ă͂ӂ��Č�����B�畆�͑����ɉ�����тсA���͍��ɊD�F������̞��s���������t��Ȃ��c��ł���B�z�ɂ�ᰁs����t�A��̂܂��ɂ͔�J�̐������Ă���B�������Ⴛ�ꎩ�g�͎��̂悤�Ɍ��s�Ёt���t�����ł���B����͖�������l�̊�ł����āA�₽���ŎZ�I�ȃA�J�f�~�b�N�Ȋ�łȂ��A���ʂ̎��o�̉��ɉB�ꂽ������̂����������l�n���҂̊�ł���B��̒��ɂ͈ٗl�Ȍ�������B�ǂ����Ă������̐S�̓����ɐ������Ă���l�̊�ł���B�v �u�ނ��d��ɗ��ƒ��O�͂��������ɔނ̗͂�������B�h�C�c�ꂪ�킩�镪��ʂ͖��łȂ��B�Ƃ��������͋����l�ɔ��邠�镨��������B�v �u�d��Ȏ�����b�����Ƃ���l�ɂӂ��킵���悤�ɁA�������A�����Ĉ������͂��������Ęb���B�������������C������悤�ȂƂ���͂Ȃ��B�����s����t�ŁA�������܂��Ă��āA�����ĕq���ł���B�����b�������ɓ����ė���Ƒ����̐g�U�����������B�����g��������A�v�_�����߂邽�߂ɕИr�����o������A�܂��w�̒[��O�ɐG�ꂽ�肷��B�������g�̂͌����ē������Ȃ��B�܁X�ނ̊Ⴊ���ȕ\������ďu�s�܂����t����������B����ƃh�C�c��̕���Ȃ��l�ł��F�ނ荞�܂�ď��o���B�v �u�s�v�c�ȁA�l�����s�Ёt���t����l���ł���B������т�������v���t�F�b�T�[�Ƃ͂����Ԏ�ނ��������Ă���B���y�ƂƂł������悤�ȗl�q�����邪�A�ނ͎��ۂɂ����ł���B���w���o����Ɠ������x�Ƀ��@�C�I�������o����B�[���ȏ�Ɨ����������ă��U���g�A�V���[�}���A�o�b�n�Ȃǂ����t����c�c�B�v �������߂ăA�C���V���^�C���̎ʐ^�������̂͂j�N�̂Ƃ���łł������B���̎��Ɏ��B�́u���̊�͖�������|�p�Ƃ̊炾�v�Ƃ����悤�Ȏ���b���������B�Ƃ��낪���̉p���̐V���L�҂������悤�Ȏ����]���Ă���̂�����ƁA���̈�ۂ͂����炩���ʂȂ��̂�������Ȃ��B���۔ނ̂悤�Ȕj�V�r�̎d���́A�u���v�����Ȃ���ނ̐l�ɂ͎v���t�������Ɏv���Ȃ��B�����������������邾���ł͕��ɂȂ�Ȃ��B���̍��ɘ_���̋����˂����̂��ނ̎d���ł������B �A�����J�̃X���b�\���Ƃ����V���L�҂̂����������̌��G�ɂ���ʐ^�͂�����Ƃ�������������^����B�ǂ�������ȁA���ɂ���̐l���킹�����������ȂƂ��낪����B�܂��ŋ߂Ƀ^�C���X�T���̉��ɏo���A�ނ��L���O�X�E�J���b�W�ōu�������Ă��鉡���������ƕς��Ă���B��ʂɑ��Ă��Ȃ�傫�Ȋp�x�����ē˂��o���O�p�`�̑傫�ȕ@����ɕt���B �A�C���V���^�C���́u�|�p�����悤�Ȑ��_�I�K���͑��̕��ʂ���͂ƂĂ������Ȃ����̂��v�Ɛl�ɘb���������ł���B�Ƃ��������ނ͌|�p��n���ɂ��Ȃ���ނ̉Ȋw�҂ł���B�A�C���V���^�C���̌|�p���ʂɂ������̒��ōł������Ȃ��͉̂��y�ł���B�ނ̒e�����@�C�I��������l�O�̂��̂��Ƃ������͒�]�ł���炵���B���Ȃ�e�q�j�[�N�̘Z�s�ނt�������u���[���X�̂��̂ł��N�₩�ɒe�����Ȃ������ł���B�Z�p����łȂ��đ����ȗ������������|�p�I�̉��t���o����炵���B ���ꂩ��A�q���̎��ɏ��̂�������Ɠ����悤�ɁA���X�s�A�m�̌��Ղ̑O�ɍ����đ����I�̃t�@���^�W�[�����̂��l�m��ʊy���݂̈�������ł���B���̘b���Ǝ��͉��ƂȂ��{���c�}�����v���o���B�������{���c�}���͉A�C�ŃA�C���V���^�C���͖��邢�B ���y�̒��ł͌ÓT�I�Ȃ��̂��D�ނ����ł���B���ɃS�`�b�N�̌��z��栁s���Ɓt������o�b�n�̂��̂�ނ��D�ނ̂͋��R�ł͂Ȃ���������Ȃ��B�x�[�g�[���F���̍�i�ł��傫�ȃV���t�H�j�[�Ȃǂ��A�ނ���J���}�[���W�[�N�̗ނ��D�ނƂ�������A�V���p���A�V���[�}�����̑��b�Q���h�s�낤�܂�́t�̍�҂�A�܂����O�i�[���̑��̊y���ɂ��܂蓯��Ȃ����Ȃǂ��A���ƂȂ��ނ̖ʖڂ�z��������B �G��ɂ͑S�����S�������ł���B�l���̐��E�߂Ă���ނɂ͓̌|�p�͂��邢�͂��܂�Ɏ��Y�ɋ߂���������Ȃ��B���ۂ����Ƌ�Ԃ̗v�f�ɐ�߂��ނɂ͐F�ʂ̔������Ȃǂ͂��܂�ɋȌ��ɉ߂��Ȃ���������Ȃ��B �O���I�Ȓ����ɂ͑����̓������B���Ɍ��z�̔��ɂ͒V����ɂ��܂Ȃ������ł���B �����]���Ή��y�͂�����|�p�̒��ŗB��̎l���I�̂��̂Ƃ��]���Ȃ����͂Ȃ��B���̌|�p�ɂ͈��́u�^���v���{���I�Ȃ��̂ł���B�������̎��ƂƂ��ɉ^������u���́v�Ƌ�ԂƂ������I�łȂ������ł���B ���w�ɂ����S�ł͂Ȃ������ł���B�����Z�����ނɂ͑�R�F�X�̂��̂�ǂމɂ��Ȃ��̂ł��낤�B�V�F�[�N�X�s�A�h���ăQ�[�e������قǂɎv��Ȃ��炵���B�h�X�g�G�t�X�L�[�A�Z���o���e�X�A�z�[�}�[�A�X�g�����h�x���q�A�S�b�g�t���[�h�E�P���[���A����Ȗ��O���D���ȕ��̑��ɁA�]����C�u�Z���Ȃǂ��D���Ȃ����̑��ɋ������Ă���B���̖�����F�X�̈Ӗ��Ō�X�ɂ͖ʔ�����������B ���@�S�b�g�t���[�h�E�P���[�Ƃ͂ǂ�Ȑl���Ǝv���ď��{�N�ɕ����Ă݂�ƁA���̐l(�ꔪ���\�ꔪ��Z)�̓X�C�X�`���[���q�̐���ŁA�`�ʂׂ̍����A�������R��I�C���ɕx�ʎ������Ƃ������ł���B �N�w�҂̎d���ɑ���ނ̑ԓx�͑z������ɓ�Ȃ��B���b�N��q���[����J���g�ɂ͑����̎������Ă��A�w�[�Q����t�B�q�e�͖��ɂȂ�Ȃ��炵���B����͂������肻���Ȏ��ł���B�Ƃɂ��������̓N�w�҂͔ނ��瑽�����w�˂Ȃ�܂��B�V���[�y���n�E�A�[�ƃj�[�`�F�͕��w�҂Ƃ��Đ��܂���̂������ł���B�������j�[�`�F�͂���܂�M���M�����Ă���(glitzernd)�Ɖ]���Ă���B �ނ����̉����ȁs���ւ��t�������Ă��鎖�͏��N����̃C�^���A���s�������o���Ă���悤�Ɍ�����B�������ނ̗��s�͒P�Ɍ����Ȗ�����i�F������ǂ��āA�D�Ԃ̒��ł͋����肷�鈟�ނ̂ł͂Ȃ��āA���̖ړI���Ȃ���ɎR�ɊC�l�ɜf�r�s�ق������t����̂��D�����Ƃ������ł���B�������ނ����̖�����悤�Ȋ�����āA���������������܂悢�����Ă���ԂɁA�ǂ�Ȋ������ނ̔]���s�̂���t�ɋN���Ă��邩�Ƃ������͒N�ɂ�����Ȃ��B �������ɂ͈�،������Ȃ��B�N�W�Ȃ��F���ł���B�w�҂̒��ŔނقǏ����̏��L�ɗ�W�Ȑl�����Ȃ��Ɖ]���Ă���B�ނ��ނ̂悤�ȍ��{�I�ɐV�����d���ɎQ�l�ɂȂ镶���̐��͔�r�I�ɂ߂ď����ł��鎖�͓��R�ł���B������I�[�\���e�B�͔ގ��g�̓��W���ȊO�ɂ͂ǂ��ɂ����Ȃ��̂ł���B �ނ̓��퐶���͂����炭���f�Ȃ��̂ł��낤�B�w�҂̒��ɐ܁X����悤�ȋ��K�ɖ��S�Ȑl�ł͂Ȃ��炵���B�ނ̒��҂̖|��҂ɂ͈�ł̂��Ȃ�ȕ����O��v�����ė���Ƃ����悤�ȉ\���������B�����̓��{�l�ɂ͑����ςȊ��������邪�A�h�C�c�l�Ƃ����҂�m���Ă���l�ɂ͕ʂɂ����s�v�c�Ƃ͎v���Ȃ��B���ɔނ̐l��̎��܂ł���藧�Ăčl����قǂ̎��ł͂Ȃ��Ǝv����B ��͂悭���邻���ł���B�_�o�̂��炢�炵���҂��A�ނ̂悤�Ȏd�������āA�����Ă��ꂪ�����ɋ߂Â����Ƃ�����Ȃ苻������ɂ������Ȃ��B����Ɏd����r���Œ��~���Ă̂Ɉ�������Ƃ������͑��O�Z�P�������ł���ɑ���Ȃ��B�������ނ͓K���Ȏ��ɂ������Ɛ�グ�ď��ɂ��A�����Ďd���̎��͑S���Y��Ĉ������o����Ɣގ��g�l�ɘb���Ă���B������ԍŏ��̑��Ό����Ɏ��t�����������͂������ɂ����͂䂩�Ȃ������炵���B�������r�S�҂̂悤�ɂȂ��Ĝf�r�����Ɖ]���Ă���B��͔N�̎Ⴉ���������ł����낤���A���̎��̐S���͂����炭�����I�ꂽ���������̊w�Ҍ|�p�Ƃ��邢�͏@���Ƃɂ��Ďn�߂Ė��킢�������ނ̂��̂ł������낤�B�@ |
|
|
���O
�A�C���V���^�C���̐l���ς͌�X�̒m�肽���Ɗ肤�Ƃ���ł���B�������ގ��g�̕M�ɂ��Ȃ����肻�̈���s�����ς�t�����M�s�������t�����͂����炭�s�\�Ȏ��ɑ���Ȃ��B�ނ̉�b�̒f�Ђ���ɂ����W���[�i���X�g�̕]�_��A�܂�����̉���Ȏ�ɂǂꂾ���̐M�p���[�s���t���邩�͋^��ł���B�������̏オ�鏈�ɉ�����Ƃ������܂肠�ĂɂȂ�Ȃ���Ȋw�I�@���𗊂݂ɂ��āA��������̍ޗ��������ɏЉ��B �ނ̐l�Ԃɑ���ԓx�͔����I�l���I�̂��̂ł���炵���B�ނ̍җ��s������t�Ȋ�ɂ͂����炭�l�Ԃ̂�����Ό���s������ɂ��߂��č��邾�낤�Ƃ������͑z������ɓ�Ȃ��B�H�ɔނ̌�����k���h煁s�����t���~悁s�������Ⴍ�t�͖��炩�ɂ���������̂ł���B��_�����j���͂̓j�[�`�F�Ɠ������x��������Ȃ��B�������j�[�`�F��]���ăM���M�����Ă���Ɖ]�����ނ͂����̎�_�ɑ��Ă��Ȃ�C�̉i�����e�������Ă���B���Q�҂ɑ��Ă͏�ɎI�ł���A��������҂ɂ͂ǂ�Ȕn���Ȏ���ɂł��^�ʖڂɐe�ɓ����Ă���B �q�\�̐��E�ɂ����Ă̋M���ł���ނ͎Љ�̈���Ƃ��Ă͐����s���������t�̃f���N���b�g�ł���B���ƂƂ������̂́A�ނɂƂ��Ă͂��ꎩ�g���ړI�ł����ł��Ȃ��B���̗͂����_�Ȃ�ł��Ȃ��B�������Ɖ]���Ĕނ͗L��ӂ�̎Љ��`�҂ł��Ȃ�����Y�}�ł��Ȃ��B�ނ̐����Ƃ����̂ɋ���A�Љ�̏j�����P�ɐ��x���ǂ����Ă݂��Ƃ���ł���ʼni�v�I�ɓ�������̂ł͂Ȃ��B�������X�̉�|�̐ߐ��Ƒ��݂̐l�Ԉ��ɂ���Ă̂ݗ��z�̎Љ�ɓ��B���鎖���o����Ƃ����̂ł���炵���B �ܘ_�ނ͐��E���a�̊��]�҂ł���B���������̕��a�邽�߂ɂ͕K�������َ�̖����̓��������p���Ȃ��Ă������Ƃ����l���������ł���B���_���������W�����č��y�𗧂Ă悤�Ƃ����U�C�I�j�Y���̎咣�҂Ƃ��Ă������肻���Ȏ��ł���B�K�ؗ��w���m�����Ĕނ��x�����ɐq�˂����ɁA���m�͓��m�ŕʎ�̕��������B���Ă���͖̂ʔ����Ƃ������悤�Ȏ���b���������ł���B���̓_�ł��ނ͈��̃����`���B�X�g�ł���Ƃ��]���悤�B����ɂ��Ă��ނ��c�N���ォ��S������̍����܂łɁA�ӖړI�ȕs�����ȃV���[���B�j�Y����������Q���@���ɔނ̎v�z�ɉe�����Ă��邩�́A���邢�͔ގ��g�ɂ����f����@���Ȗ��ł��낤�B �K�ؔ��m�ƑΘb�̒��ɁA���C�@�ւ���������Ȃ�������l�Ԃ͂��������K���������낤�Ƃ����悤�Ȏ����������悤�ɋL�����Ă���B�܂����̐l�ƐΒY�̃G�l���M�[�̖���_���Ă��钆�ɁA�u����ɓ���ʂ̐ΒY���瓾����G�l���M�[�������Ƒ������Ƃ���A���݂�葽���̐l�Ԃ������������邩������Ȃ����A�����Ȃ����Ƃ����ꍇ�ɁA���ꂪ���߂ɐl�ނ̍K�����������ǂ�������͋^��ł���v�Ɖ]�����Ƃ���B�������ꂾ���̒f�Ђ���ނ̕����ς���㈁s�����t����̂͑��v�ł��낤���A���Ȃ����ނ��u�ΒY�����v�̖�������搉̎҂łȂ��������͑z�������B���Ȃ����ނ̓����S�ƐΒY����ŋl�܂��Ă��Ȃ��؋��ɂ͂Ȃ邩�Ǝv���B �ނ͂܂����ꂩ�炪��������ł���B�ނ��d�̗͂��_�Ŏ���Ȃ������d���C�_�́A���C���ɂ���Ĕނ̈�ʑ��ΐ������̌����ɕ������ꂽ�悤�ł���B���ꂪ�����ł���Ƃ��Ă��A�܂��ނ̖ڑO�ɂ͑傫�Ȗ�肪�c����Ă���B����͂�����u�f�ʁs�N�A���^���t�v�̖��ł���B���̖��ɂ��ނ͋v�����O������t���Ă���B����ނ�������ǂ���舵�����������̌����̂ł��낤�B�G�W���g���̉]���Ƃ�����ƁA��ʑ��Ό����͂قƂ�ǂ��ׂĂ̂��̂����ΐ��D�����B���ׂĂ͊ϑ��҂̎ړx�ɂ��B������c���ꂽ���̂��u��p�s�A�N�V�����t�v�Ə̂�����̂ł���B���ꂾ������Εs�ςȁu�����̐��v�ł���B�f�ʐ��Ȃ���͎̂������������̍�p�Ɉ��̒P�ʂ�����Ƃ����錾�ɉ߂��Ȃ��B���́u�����v�������炭����o�����́u�m���s�v���o�r���e�B�t�v�ƌ��ѕt��������̂ł��낤�Ɖ]���Ă���B����ɑ���A�C���V���^�C���̍l���͕s�K�ɂ��Ă��܂��m��@��Ȃ��B�����ނ���N�̌܌����C�f���̑�w�ŏq�ׂ��u���̏I��̕��ɁA�u�f�ʐ��Ƃ��ēZ�s�܂Ɓt�߂�ꂽ���������邢�́w�͂̏�s�t�F���h�t�x�̗��_�ɉz��������^���鎖�ɂȂ邩������Ȃ��v�Ɖ]���Ă���B���̓�̂悤�Ȍ��t�̉��߂�ގ��g�̌����畷�����̏o�����������A����͕����w�̗��j�ł����炭�ł��L�O���ׂ����̈�ɂȂ邩������Ȃ��B(�吳�\�N�\��)�@ �@ |
|
| ���A�C���V���^�C���̋���� / ���c�ЕF�@ | |
|
�ߍ��p���ɋ���m�l����A�A���L�T���_�[�E���X�R�t�X�L�[���w�A�C���V���^�C���x�Ƃ��������𑗂��Ă��ꂽ�B�u��ԏ�ȂǂŔ����Ă��鑭�������A�ދ����̂��Ɂc�c�v�ƒf���Ă悱���Ă��ꂽ�̂ł���B
���Ăɂ���������̃A�C���V���^�C���̐����͔��Ȃ��̂ŁA�ނ̖���u���Ό����v�Ƃ������t�Ȃǂ��F�X�ȑ�I�ȈӖ��̗��s��ɂȂ��Ă���炵���B�����h������̕ւ�ł́A�V����ʑ��G�����炢���������Ă��Ȃ��X��ɂ��A�����ƃA�C���V���^�C���̒���(�p��)�����͕��ׂĂ��邻���ł���B�V���̖�������Ă���ƁA��ǂ̂ނ������e��s���₶�t�̋����떂���s���܂��t���Ă����āA���ꂪ�����`���B�e�B���Ȃǂƍς܂��Ă���̂�����B�����Ȃ��Ă͂������̃A�C���V���^�C�����ꂢ������Ă��鎖�ł��낤�B ��M�s�킪���Ɂt�ł͂܂�����قǂł��Ȃ����A����ł��ނ̖��O�͗��w�҈ȊO�̕��ʂɂ��ߍ������Ԋg�܂��ė����悤�ł���B�����Ĕނ̎d���̓��e�͕���Ȃ��܂ł��A���ꂪ���ɏd�v�Ȃ��̂ł����āA������d�������ނ����ȗD�ꂽ���]�̏��L�҂ł��鎖��F�ߐM���Ă���l�͂��Ȃ�ɑ����ł���B�������Ĕނ̎d���݂̂Ȃ炸�A�ނ́u�l�v�ɂ��ē��ʂȋ���������Ă��āA���̖ʉe��m�肽�����Ă���l�����Ȃ�ɑ����B���������l�X�ɂƂ��Ă��̃��X�R�t�X�L�[�̒����͐r�������̂�����̂ł��낤�B ���X�R�t�X�L�[�Ƃ͂ǂ������l�����͒m��Ȃ��B����l�̘b�ł̓W���[�i���X�g�炵���B���g�̏����ɂ������炵�������鎖�������Ă���B������ɂ��Ă����q�ƂƂ��đ����F�߂��A�����Ȋw��������A�Ȋw�ɑ��Ă����Ȃ�ȗ�����L�s���t���Ă���l�ł��鎖�́A���̏��̓��e������������鎖���o����B ���̐l�̃A�C���V���^�C���ɑ���W�́A�ꌩ�{�X�E�F���̃W�����\���A�Ȃ����G�b�J�[�}���̃Q�[�e�ɑ���悤�Ȃ��̂�������Ȃ��B�ގ��g����҂̗ޗ��������x�܂ŏ��F���Ă���B�u���߁s���͂��t�̒��̔��s�͂��t�v�ȂǂƎ����ʼn]���Ă��邪�A�P�Ȃ�{�X�E�F���Y���łȂ����͖��炩�ɔF�߂���B ���X�A�C���V���^�C���ɉ���ĎG�k������@�����̂ŁA���̎��X�̒k�Ђ��ڂƂ��A����̒��߂�c�q�A���邢�͂���Ɋւ���]�_�����������̂��Z�s�܂Ɓt�܂��������ɂȂ����Ƃ����̍قł���B���_�L���̑S�ӔC�͋L�҂��Ȃ킿���҂ɂ��邱�Ƃ����ɒf���Ă���B ��̐l�̒k�b���Đ����ɂ����`����Ƃ������́A���ꂪ�����ȉȊw��̒藝������łȂ�����A�����ɉ]���قƂ�Ǖs�\�ȂقǍ���Ȏ��ł���B���Ƃ����t�����͐����ɏ������߂Ă��A���̎��̊�̕\���̃j���A���X�͑S�R�����Ă��܂��B���ꂾ���炠��l�̉]���������A���̊O�`�����������`���邱�Ƃɂ���āA�b�����{�l�𑼐l�̑O�Ɋׂ�邱�Ƃ��g���邱�Ƃ�����ɏo����B����͖��ӔC�Ȃ������ӂ���S�V�b�v�ɂ���ē���s���Ă��錻�ۂł���B ����ł��̏����̓��e�����ǂ̓��X�R�t�X�L�[�̃A�C���V���^�C���ςł����āA����������`����̂�����A�X�Ɉ�w�A�C���V���^�C�����牓���Ȃ��Ă��܂��A�r���S�ׂ���ł���B���������ǁu�l�v�̐^�������ΐ��̂��̂�������Ȃ�����A�����������Ƃ���ƁA���̈�т̋L������͂��́u�^�v�̑���������Ȃ��B�����łȂ��ꍇ�ł��A��������l���鎖�̎�q���炢�ɂ͂Ȃ�Ȃ����͂���܂��B �]�k�͂��Ă����A���̏����̈�͂ɃA�C���V���^�C���̋���Ɋւ���ӌ����Љ�_�]�������̂�����B����͑����̐l�ɐF�X�ȈӖ��ŐF�X�Ȍ����̋���������Ǝv���邩��A���̒������̗v�_�����������ɏЉ�����Ǝv���B�A�C���V���^�C�����g�̌��t�Ƃ��ďo�Ă��镔���͂Ȃ�ׂ������ɖ����ł���B����ɑ��钘�҂̘_�c�͂킴�Ƒ啔�����ȗ����邪�A�������ނ̖ʖڂ�`�����ނ̋L���͕ۑ����邱�Ƃɂ���B �A�C���V���^�C���̓w�����z���c�ȂǂƔ��ōu�`�̂��܂��^�̊w�҂ł���B�݂̂Ȃ炸�u�`�u���ɂ���Đl�ɋ�����Ƃ������ɋ����ƔM�S�������Ă��邻���ł���B����Ŋw����w�҂ɑ��Ă݂̂Ȃ炸�A��ʐl�̒m���|�������鎖��ς킵���v��Ȃ��B�Ⴆ�ΘJ���҂̏W�c�ɑ��Ă��A����₷���u��������ĕ�������Ƃ���B����ȕ��ł��邩��A�Ƃ��������ނ�����Ƃ������ɖ��S�Ȑ�l���łȂ����͑z�������B �A�C���V���^�C���̍l���ł́A�Ⴂ�l�̎��R���ۂɊւ��铴�@�̊���J����Ƃ��������ł���Ȏ��ł��邩��A�]���Ď��ȋ�����\���ɗ^���邽�߂ɁA�ÓT�I�Ȍ�w�݂̂Ȃ炸�u�����Ȃ��]���v��w�̋���Ȃǂ͊����]���ɂ��Ă��ɂ����Ȃ��Ƃ����l���炵���B����ɂ��Ď��o���ꂽ So viele Sprachen einer versteht, so viele Male ist er Mensch. �Ƃ����J�[���ܐ��̌��t�ɑ��Ĕނ́A�u��w���Z�ҁs�V���v���n�E�A�g���[�e���t�v�͕K�������u�l�ԁv�̐擪�ɗ����̂ł͂Ȃ��A�������i�҂ł���F���̑��i�҂���ׂ��l�̑��ʐ��͌�w�m���̍L�����ł͂Ȃ��āA�ނ��낻��Ȃ��̂̋L���̂��߂ɕΐ��s�ւ�ρt�ɓ��]���g��Ȃ��ŁA���̒����J�����Ă������ɂ���A�Ɖ]���Ă���B �u�l�Ԃ́w�s�q�ɔ�������x(subtil zu reagieren)�悤�ɋ��炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]��w���_�I�̋ؓ��x(geistige Muskeln)�Ă����{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���߂ɂ͌�w�̌P���s�h�����t�͂��܂�K���Ȃ��B������͎����ŕ����l����悤�ȏC���ɏd����u������ʓI���炪�L���ł���B�v �u�ށs�����Ɓt�����k�̌��I�X���͖��_�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ʗႻ�̂悤�ȌX���́A���Ȃ�ɑ������猻������̂ł���B���ꂾ���玩���̈Ăł́A�����w�Z�s�M���i�W�E���t�̎O�N�����炻�ꂼ��̕��ʂɕ��h�����邪�����Ǝv���B���̑O�ɋ����鎖�͋ɂ߂Ċ�b�I�ȂƂ��낾�����A���Ȃ����̐܂�Ȃ����x�Ɏ~�s�Ƃǁt�߂����������B����ł������k�����w�I�̌X��������Ȃ�A����ɂ̓��e���A�O���[�L���\���ɂ�点�āA���̑�萫�ɍ���Ȃ��w�Ȃł����߂�͎̂~�s��t�������������c�c�v ����͖��炩�ɐ��w�Ȃǂ��w�������̂ł���B���w�����̐��k�͓��{�Ɍ���Ȃ��ƌ����āA���X�R�t�X�L�[�̉]���Ƃ���ɋ���ƁA���Ȃ�͂����������ł���Ȃ���A���w�ɂ����Ă͂܂�Œ�\�ŁA�w�Z�������ɏP��ꂽ���w�̈����ɐ��U���t����Ă��Ȃ����l�������炵���B���̂����鐔�w�I��\�҂ɂ��ăA�C���V���^�C���͎��̂悤�Ȏ����]���Ă���B �u���w�����̌������ʂ��Đ��k�̖��\�ɂ݂̂�邩�ǂ��������ɂ͂悭����Ȃ��B�ނ��뎄�͑����̏ꍇ�ɂ��̐ӔC�����t�̖��\�ɂ���悤�ȋC������B��T�̋��t�͂����ȉ���Ȃ����k�ɂ������Ď��Ԃ����Ă���B���k���m��Ȃ������ɕ����Ă���B�{���̋^��̂��������́A���肪�m���Ă��邩�A���邢�͒m�蓾�鎖���o�����łȂ���Ȃ�Ȃ��B����ŁA���������߉߂̍s����Ƃ���ł͑�T���t�̕�����ș�s�Ƃ��t��ցs�����ށt��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�w���̏o���h���͋��t�̔\�͂̎ړx�ɂȂ�B��̊w���̏o���h���ɂ͎���������̕��ϒl�������Ă��̏㉺�Ɏ�̏o���肪����B���̕��ς�������A����ł��Ȃ茋�\�Ȗ�ł���B��������������w���̐i�������ψȉ��ł���Ƃ����ꍇ�ɂ́A�����w�N���Ƃ������A�ނ���搶�������Ɖ]�������������B���̏ꍇ�ɋ��t�͕K�v�Ȏ����͂悭���������A�܂����ނƂ��Ď��R�ɂ��Ȃ������̗͂͂���B�����������ʔ�������͂��Ȃ��B���ꂪ�قƂ�ǂ��ł��Ёs�킴�킢�t�̌��ɂȂ�̂ł���B�搶���ދ��̌ċz�s�����t�𐁂����������ɂ͐��k�͒������Ă��܂��B������\�͂Ƃ����͖̂ʔ��������鎖�ł���B�ǂ�Ȓ��ۓI�ȋ��ނł��A���ꂪ���k�̐S�̋Ր��ɋ����N������悤�ɂ��A�D��S�������������Ă����˂Ȃ�Ȃ��B�v ����͑����̐l�ɂƂ��Ď��̒ɂ��b�ł���B ���̗��z������������Ƃ��āA���Ă𗧂Ă�ۂɍޗ��ƕ��z���ǂ����邩�Ƃ�����ɑ��ẮA��̓I�̘b�͌���ɏ���Ɖ]���āA�b�����������x�̖��ɓ]���Ă���B �u�v�͎��Ԃ̌o�ςɂ���B����ɂ͖��ʂȐ��k�����߂̌P���I�Ȏ��͈�ؔp���邪�����B�����ł���̗��K�̍Ō�̖ړI�͑��Ǝ����ɂ���悤�Ȏ��ɂȂ��Ă���B���̎�����p���Ȃ�������Ȃ��B�v�u����͏C�w���̍Ō�ɂ����鋰�낵���䕐���Z�̂悤�ɁA�y���̎�O�܂ł����̈Ée�𓊂���B���k���搶���s�f�ɂ��̋����I�ɒ�߂�ꂽ����̓��̏����ɂ����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂����̎����Ƃ����̂��l�H�I�ɖ��Łs�ނ�݁t�ɒ��x�������P�s�ˁt����グ�����̂ŁA����Ɏ�̓͂��悤�ɕڝ��s�ׂt���ꂽ�҂͂���Ɛ����Ԃ����͎����������Ă��Ă��A��ł͂�������Y��čĂю�肩�������͂Ȃ��B�����Y��Ă��܂��Ζ��ȋL���̌P���̌��ʂ͏����Ă��܂��B�����������߂ΐ��J����ɂ͑��v�Y��ɖY��Ă��܂��悤�ȁA�܂��Y��đR��ׂ��悤�Ȏ����A���N���������ċl�ߍ��ޕK�v�͂Ȃ��B��X�͎��R�ɋA�邪�����B�����čŏ��̎d�����₵�čő�̌��ʂ�Ƃ��������ɏ]�������������B���Ǝ����͐��ɂ��̌����ɔ�������̂ł���B�v ����ł͑�w���w�̎��i�͂ǂ����Ă��߂邩�Ƃ̖�ɑ��āA �u���R�Ɏx�z�����悤�ȉ̎����s�t�H�C�A�v���[�x�t�łȂ��A��̂̐��тɂ������B����͋��t�ɂ͂悭������̂ŁA��������Ȃ���߂͂�͂苳�t�ɂ���B���Ă����k����������x�����Ȃ���Ώ��Ȃ��قǁA���k�͑��Ƃ̎��i�₷�����낤�B����Z���ԁA���̂����l���Ԃ͊w�Z�A�Ԃ͑�ŗ��K����Α�R�ŁA���ꂷ��ő���ł���B��������ŏ��ȉ߂���Ǝv���Ȃ�A�܂��l���Ă݂邪�����B�Ⴂ���͉̂ɂȎ��Ԃł����������w�͂��o�����Ă���B���̂Ɖ]���A�ޓ��͑S���E��m�o���F�����ۂݍ��܂Ȃ���Ȃ�Ȃ�����B�v �u���Ԃ����炵�āA���̑�肠�܂�K�{�łȂ��Ȗڂ���邪�����B�w���E���j�x�Ə̂�����̂Ȃǂ�����ł���B����͒ʗኣ�������ȕ\�ɋl�ߍ����炵�̂Ȃ����̂ł���B����Ȃǂ͎v�����Đ�l�߁A�N�ア����Ȃǂ͔����ɂ��čj�̂����Ɏ~�߂����B���ɌÂ�����̗��j�Ȃǂ͂����Ԃ����Ă��܂��Ă���l�̐����ɑ債���e���͂Ȃ��B���͊w�����A���L�T���_�[�剤���̊O���_�[�X���̐����҂̎����������m��Ȃ��Ă��A�債���s�K���Ƃ͎v��Ȃ��B���������l�����c�����Õ����I�̈�Y�́A���ʂȃo���X�g�Ƃ��ċL���̏d�ׂɂȂ����ł���B�ǂ����Ă��Ñ�ɟ�s�����̂ځt�肽���Ȃ�A���߂ăT�C���X��A���^�Z���L�Z�X�Ȃǂ͐ߖāA�����ɍv�������A���L���[�f�X�A�v�g�����C�X�A�w�����A�A�|���j�E�X�̎��ł������b���Ă��炢�����B�S�ے���`���҂◬���҂̍s��ɂ��Ȃ����߂ɔ����Ƃ┭���Ƃ�����Ă��炢�����B�v ���j�̎��Ԃ̈ꕔ�������āA���ۂ̍��Ƒg�D�Ɋւ��鎖���A�Љ�w��@���Ȃǂ������Ă͂ǂ����Ƃ�����ɑ��Ă͂ނ���s�^�����Ɠ����Ă���B�ގ��g�l�Ƃ��Ă͌������̑g�D�Ɋւ��Ă��Ȃ�ȋ����������Ă��邪�A�w�Z�Ő����I�f�{����鎖�͖ʔ����Ȃ��Ɖ]���Ă���B���̗��R�͑�ꂱ����������͊��ӂ̉e���̂��߂ɖ{���I�s�U�n���q�t�ɏo���ɂ������A�܂����̐��n���Ȃ����̂�������̎��ɂ��������͈̂�̑��߂���Ƃ����̂ł���B���̑�萶�k�ɉ���������p�ɂȂ��H��K�C�����A�w���s�������́t�Ȃ萻�{�Ȃ���O�Ȃ�Ƃɂ������ɂȂ邾���Ɏd����ł�肽���Ƃ����l���ł���B����ɑ��ă��X�R�t�X�L�[���A��̂���͘r���d���ނ̂���ӂ��A����Ƃ����O��ʂƂ̎Љ�I�A�т̊������������邽�߂��ƕ����ƁA �u�����Ƃ����ɂ͏d�v�Ɏv����B���̏�Ɏ��̂��̊�]�𐳓��Ǝv�킹�������̌��n������B��H�͖ܘ_����������邽�߂̉��n�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ł��A�l��(�ksittliche Perso:nlichkeit�l)�Ƃ��ė��ׂ��n�Ղ��g�����߂邽�߂ɖ��ɗ��B���ʊw�Z�ő��Ɏd���Ă�ׂ����͖̂����̊����A�w�ҁA�����A���q�ƂłȂ��āu�l�v�ł���B�����́u�]�v�ł͂Ȃ��B�v�����g�C�X���ŏ��ɐl�Ԃɋ������͓̂V���w�ł͂Ȃ��ĉł���A�H��ł������c�c�v ����ɘa���ă��X�R�t�X�L�[�́A�����ɗ��h�Ȓb��s�����t�Ńu���L�E�ł����ČC���ł������̖̂��̎�s�}�C�X�e���W���K�[�t���������ɏo���āA�L��s�Ђ����傤�t�͉Ȋw�����R�|�p�̈�ł���Ɖ]���Ă���B�������A�C���V���^�C�����A�Ȋw���ꎩ�g�͎��p�Ƃ͖��W�Ȃ��̂��ƌ������Ȃ���A��H�̕K�C���咣���Ď��p�d����̂������Ɖ]���̂ɓ����Ď��̂悤�Ȏ����]���Ă���B �u�������p�ɖ��W�Ɖ]�����̂́A�����Ȍ����̋��ɖړI�ɂ��Ăł���B���̖ړI�͂����ɂ߂ď����̐l�ɂ̂ݔF�ߓ�������̂ł���B����ł��������Ȋw�̏������炢�̂Ƃ���܂ł��̍l���������čs���̂͌����Ⴂ�ł���B�ނ��딽�Ɏ��͊w�Z�ŋ����闝�Ȃ͍�������Ă����肸���Ǝ��p�I�ɏo����Ǝv���B���̂͂��܂�ɔ���ۓI�s�h�N�g���l�[�A�t�߂���B�Ⴆ�ΐ��w�̋������ł��A�����Ǝ��p�I�����̂���悤�ɁA�����Ƃ����Ɉ��s���t�܂��悤�ɁA�����Ɗ�Ɍ�����悤�ɂ��ׂ��̂��A�������Ȃ����玸�s�������ł���B�q���̓��ɍl�����ד����鎖�������Ȃ��ł��̑��ɘZ�s�ނt�������u��`�v�Ȃǂ����Ă����B��̓I���璊�ۓI�Ɉڂ铹�𖾂��Ă��Ȃ��ŁA�����Ȃ菃���Ȓ��ۓI�ϔO�̗�����������͖̂����ł���B�����������������܂��s����B�悸��Ԃ̊�b�I�Ȏ����͋���ł��Ȃ��ŌˊO�Ŏ�������������B�Ⴆ����q��̖ʐς𑪂鎖�A�����s�悻�t�̂Ɣ�r���鎖�Ȃǂ������B�������w���Ă��̍����A���̉e�̒����A���z�̍��x�ɒ��ӂ𑣂��B��������A���t�Ɣ��n�s�͂��ڂ��t�̐��Ƃɂ���āA�傫����p�x��O�p�����Ȃǂ̊T�O�𒍂����ނ����y���ɑ����m���ɁA���܂��ɖʔ��������̐��w�I�W��ۂݍ��܂��鎖���o����B��̂��������w��̎��ۂ̋N���͂����������p���ł������ł͂Ȃ����B�Ⴆ�^���[�X�͎n�߂ċ������̍����𑪂邽�߂ɁA���̉e�̏I�_�̕ӂ֏����Ȗ_����{���Ă��B����Ŏq���ɃX�e�b�L���������ėV�Y�̂悤�Ȏ�������点��A�悭�悭�q���̓����B�t���s�t�F���i�[�Q���g�t�łȂ�����A���͂ЂƂ�łɉ����čs���B���ɝ��s��t�����Ȃ��ł��̍����𑪂蓾���Ƃ������͎q���S�Ɋ������낤�B���̊�т̒��ɂ͑����O�p�`�Ɋւ��鑪�ʓI�F���̊��삪�Ă��Ă���B�v �u�����w�̏����Ƃ��ẮA�����I�Ȃ��́A��Ɍ����Ėʔ������̊O�͎����Ă͂����Ȃ��B���̌����Ȏ����͂��ꂾ���ł������̏��Y�r�s���g���g�t�̒��ŏo���������̓�\���炢���͂����ƗL�v�ȏꍇ�������B����ƌ��ۂ̐��E�Ɋ�̂����������Ⴂ���̂̓��Ɍ����Ȃǂ͈�ؗe�͂��Ă��˂����Ȃ��B�����́A���x���E���j�̔N��̐����Ɠ��l�ɁA�ޓ��̕����w�̒��ɐ��ދC���̈����|�낵���H��ł���B�悭��̂킩�����I�҂Ȏ����Ƃ̋��t��������Ȃ�Β����̊w��������n�߂Ă����B�������Ă����e�����@�̗��K�Ȃǂł͂߂����ɏo����Ȃ��悤�Ȉ�ۂƗ��������҂��鎖���o���邾�낤�B�v �u���łȂ���ߍ�����Ǝ����I�Ɋw�Z�ōs���o���������̎�i�ŁA�����Ɗg�������サ�����̂�����B����͋���p�̊����t�B�����ł���B�����ʐ^�̏����̐i�R�͋���̓꒣��ɂ����ݍ���ł���B�����Ă����Ŏn�߂āA�����̌��J�ϗ��������s�Ђ킢�t�Ȃ��̂₠���ǂ��ە��s������́t�ő������Ă���̂ɑ��āA�����I�Ȃ��̂������đR������@��邾�낤�B�����p�t�B�����ɊȒP�Ȍ����ł����p����A�]���͂������t�̋L�ڂŒ����炵������Ă���n���w�Ȃǂ̋����́A���E���V�̐������̌��ɂ��������C�������ď[������邾�낤�B�����Ēn�}��̂����̐��ł��A�����̎��i����s�܁t�̓���Ɍo������A����܂łƂ͂܂�ň�������̂Ɍ����ė���B�܂����Ƀt�B�����̌J��o�����𑁂߂��邢�͊ɂ߂Č����鎖�ɂ���ĐF�X�̒m���������鎖���o����B�Ⴆ�ΐA���̐����̖͗l�A�����̐S���̌ۓ��A�����̉H�̉^���̎d���Ȃǂ������ł���B���������w�d�v���Ǝv���̂́A���l�̒m���Ă���ׂ��͂��̎�v�ȍH�ƌo�c�̏��t�B�����ŏЉ�鎖�ł���B���͍H��̐��藧���A�@�֎ԁA�V�����A���ЁA�F���}��͂ǂ����č���邩�A���d���A�K���X�H��A�K�X�������ɂ͂ǂ�Ȃ��̂����邩�B����Ȏ��͂킸���̎��Ԃň�ې[���ς��鎖���o����B�X�Ɏ��R�Ȋw�̕��ʂŁA���ʂ̊w�Z�Ȃǂł͓������Č������Ȃ��悤�ȍ���Ȏ����ł��A�t�B�����Ȃ�Ηe�ՂɁA���������ۂƓ������炢���ĂɎ������Ƃ��o����B�v����ɋ��玖�Ƃ��~���̓��͂������Łu�����Ɗ�ɕ��Ԃ悤�ɂ���v(�kdie erho:hte Anschaulichkeit�l)�Ƃ������ł���B�o�������͒m��(Erlernen)���̌���(Erleben)�ɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B���̍��{���j�͖����̊w�Z���v�ɓO�ꂳ����ׂ����̂ł���B�v ��w������̍�������ɂ��Ă͂��܂藧�������b�͂��Ȃ����������ł���B�������A�C���V���^�C���͏A�w�̎��R���ɒ[�܂Ŏ咣������ŁA���u���i�̂������܂��������P�p�������Ƃ����ӌ��炵���B���K�Ȃ���K�Ȃ�ł���u�`�𗝉����鉺�n�̏o�������͎̂��R�ɓ���Ă���āA���ʊw�̑f�{�Ȃǂ͋��v���Ȃ��B���Ƃɔނ̌o���ł͗L�ׂȓO��I�Ȑl�Ԃ͉��X����ɕ���X��������Ƃ����̂ł���B�]���Ē����w�Z�ł͐��k���������Ȑ��ɓ��邾���̑f�{���o�����悻�̊w�Ȃɑ��邾���̖Ə����鎖�ɂ�������B�O�ɒ��w���Ǝ����S�p���������̂́A�܂肱�����č�������֖̊��Ŕj����Ӗ��Ǝv����B�ށs�����Ɓt���ނ��S�R������\�͌������߂�Ƃ����̂ł͂Ȃ��B��Ȋw���ɂȂ邽�߂̗\�������Ȃǂ͎~�߂������������A�������������t�ɂȂ낤�Ƃ����l�ŁA�����̂Ȃ��悤�Ȃ̂͑������o���Ă�߂�������������Ɖ]���Ă���B����͐��k�Ɋ��ŋ��t�Ɍ��ȔނƂ��Ă�������ׂ����Ƃ��ƒ��҂��]���Ă���B �����Œ��҂͂��炭�A�C���V���^�C�����͂Ȃ�āA�����̖��ɑ��邱�̗��w�҂̌��Ђ̔@���ɂ��Ę_���Ă���B���_�����̂悤�ȏ펯�ɉ����Z�����������u�`���āA�����Ē��O�𐌂킹����̂́A�ގ��g�̓����ɔR����M��Ȃ��̂�����o�邽�߂��Ɖ]���Ă���B�ނ̍u�`�ɂ͑��̒��ۊw�҂ɋH�Ɍ������̗v�f�A��ƈ��g���Ă��Ă���A�Ƃ��̒��҂͉]���Ă���B�u�`�̂��ƂŎ���҂����������Ă��Ă��A�}�Ȋ�����Ȃ��Ŋy�������ɋ����Ă��邻���ł���B�ނ̒��u�҂͐��S�l�Ƃ������R�[�h�j��̑����ɒB�����B�ނ̍u�`���͕����܂ł��Ȃ���������B�݂�Ȃ̍s�����ւ��čs�������A�Ɖ]���邭�炢�������ł���B���̐l�C�ɑ��Ĉ��̕s���̐F���ނ̔��ڂ̊Ԃɓǂ܂��B�݂̂Ȃ炸�u�͂����̂��ȁv�Ƃ������t���ނ̌�����k�ꂽ�B����������͈�������Ă͂����Ȃ��A�����̂Ȃ��Ƃ��������ƒ��҂��ٌ삵�Ă���B ���ꂩ��ÓT����Ɋւ��钘�҂̒����c�_�����邪�A���{�l�����X�ɂ͋������������痪���鎖�ɂ��āA���ɏ��q������Ɉڂ�B �w�l�̏C�w�͂��Ȃ�܂Ŏ��R�ɂ�点�鎖�Ɉًc�͂Ȃ��悤�����A���������܂�句�����シ����ł��Ȃ��炵���B �u���̊w�ȂƓ��l�ɉȊw�̕����A�Ȃ�ׂ����������Ă��˂Ȃ�܂��B���������̌��ʂɂ��Ă͑����̋^��������Ă���B���̍l���ł͕w�l�Ƃ������̂ɓV���̂����Q�������āA�j�q�Ɠ������҂̎ړx�Ă��ɂ͂����Ȃ��Ǝv���B�v �L�����[�v�l�Ȃǂ�����ł͂Ȃ����Ƃ����R�c�ɑ��ẮA �u�����������h�ȏ��O��͂܂��O�ɂ����낤���A���ꂩ�Ƃ����Đ��I�Ɏ��������܂��Ă���W���͓�������Ȃ��B�v ���X�R�t�X�L�[�͎l�\�N�O�̕w�l�ƍ��̕w�l�Ƃ̒�����������l����ƁA�m���̕��y�ɏ]���ĒǁX�͕w�l�̓V�˂��y�o����悤�ɂȂ�͂��Ȃ����A�Ɖ]���ƁA �u�M���s���Ȃ��t�͗\������D���̂悤�����A���������̊��҂͏������������ゾ�Ǝv���B�P�ɑf�{�������q�\�������Ƃ����w�ʓI�x�̑O��A�V�˂������Ƃ����悤�ȁw���I�x�̌�������_����̂͏��������ł͂Ȃ����B�v�����]�������ɃA�C���V���^�C���̊炪��Ȃ̂悤�ɂ�����ƂЂ������̂ŁA����������o��ȂƎv���Ă���ƁA�ʂ��āu���R���]���X�̂Ȃ��w���x��n�������Ƃ����������O�����Ƃ͌���Ȃ��v�Ɖ]�����B����͖��_�b�Βk�s���傤����t�ł��邪�ނ̐^�ӂ͒j���̓����̍��ق�F�߂�ɂ���炵���B���X�R�t�X�L�[�͂����~���s�ӂ���t���āu�w�l�͔����w��n�����鎖�͏o���Ȃ��������A���C�v�j�b�c��n�������B���������ᔻ�͎Y�߂Ȃ����A�J���g���Y�ގ����o����v�Ɖ]���Ă���B �b���͓]���āA������u�V�ˋ���v�̖��ɂ͂���B���ʂ̓V��������̂�I��œ��ʂɋ��炷��Ƃ������́A�����Ƃ��Ă͑����̏��F����Ƃ���Ŗ��͒��x�@���ɂ���B����͌����_�[�E�B���̎��R�������ɉ����Ђ��Ă��āA���R�̑I����l�H�I�ɏ�������ɂ���B�ނ����̍l���̓I�����s�A�̐̂���A�����鎎�����x�ɒʂ��Č����Ă���̂ŁA���ꎩ�g�ʂɐV�������Ƃł͂Ȃ����A���͐��x�̗͂ŐϋɓI�ɂǂ��܂Ői�߂邩�ɂ���A�ƒ��҂͉]���Ă���B����ɑ���A�C���V���^�C���̍l���͎��������̔ނɑ����������̂ł���B�u���Z�s�X�|���g�t���Ȃ̂悤�ɂ��V�˗{���v(�kquasisportma:ssig gehandhabte Begabetenzu:chtung�l)�͂����Ȃ��Ɖ]���Ă���B���ʂ͂������̂����s���ł���B���������̑I�����K�x�ɂ��D���ʂ��Ȃ����͂���܂��B����܂ł̌o���ł͂܂���̓I�ȈĂ͓����Ȃ����A�K���ɂ��A�]���Ȃ���e�ł������Ă��܂��悤�ȓV�˂�����s�ЂȂ��t�֏o���Ĕ��B�����鎖���o���悤�Ƃ����̂ł���B ���҂͂���ɂÂ��āA�V�˂����t���鎖�̍����_���A�܂��⏕����ƓV�ˏo���Ƃ͕K���������s���Ȃ����Ȃǂ�����ɂ��Ę_���Ă���B�����Ĉ�̓V�˂̏o�������ɖ]�ނ̂��������������Ƃ������{���ɐG�ꂽ�Ƃ���ŁA�A�C���V���^�C���̓Ɠ��ȎЉ�ς��ق̂߂����Ă���B�����������̓_�̏Љ�͑��̋@��ɏ��邱�Ƃɂ������B(�吳�\�N����)�@ |
|
| �@ | |
| ����ʑ��ΐ����_�E���� | |
| �@ | |
| ����ʑ��ΐ����_�ւ̋^�O | �@ |
| �����Ԃƒ����Ɋւ���]�������͑��������Ă���@ | |
|
�u���ԁv�Ɓu�����v�Ɋւ��āA�]�����瑊�ΐ����_�̉�����ɂ����Ă��܂��܂Ȑ������Ȃ���Ă��܂������A���̐����ɂ͘_���I�ɖ���������܂��B�ȉ��ɂĎw�E���܂��B
�m�����n �܂����ԂɊւ��Ăł����A���銵���n����A���̌n�ɑ��Ă����葬�x�ʼn^�����Ă���ʂ̊����n������ƁA�u���Ԃ�������肷����ł���悤�Ɍ�����v�Ɠ��ꑊ�Θ_�ł͐������܂��B ���Ԃ�������肷���ނ��Ƃ̌���I�؋��Ƃ��āA�]�����炠�����Ă������̂Ƀ~���[���q�̎����̉��т̌��ۂ�����܂��B�F�������獂���łӂ肻�����~���[���q�͒ʏ�̂��̂ɔ�ׂĎ��������ۂɉ��т邪�A����͍����ʼn^�����Ă��闱�q�̌n�̎��Ԃ�������肷���؋��ł���Ɛ�������Ă��܂����B ���̐������炷��ƁA�u���Ԃ�������肷����ł���悤�Ɍ�����v�Ƃ����̂́A�g������h�݂̂Ȃ炸���̌n�ł͎��ۂɎ��Ԃ��������i����ł���Ƃ������ƂɂȂ�A�������ł͂Ȃ��A�����I�Ȏ��Ԃ̒x�ꂪ����Ƃ������ƂɂȂ�܂�(�Ȃ��Ȃ�A���ۂɎ��������т��̂ł�����)�B���ꑊ�Θ_�̐������������؋��̈�Ƃ��Đ̂��炠�����Ă����̂͂����m�̒ʂ�ł��B ���Ɂg�����h���l���Ă݂܂��B ���銵���n����A���̌n�ɑ��Ă����葬�x�ʼn^�����Ă���ʂ̊����n������ƁA�u���̂̒������k��ł���悤�Ɍ�����v�Ƒ��Θ_�ł͐������܂��B �����Ŋ�Ȃ��ƂɋC�t���܂��B �g�����h�̕��́A���Ԃƈ���āu���ۂɒ������k�؋��͂���ł���I�v�Ƃ������Ⴊ�Ȃ����������Ă��Ȃ��̂ł�(���̓_�́A�㓡�����������u���ΐ����_�̓�Ƌ^��v�̒��ł������w�E���Ă��܂���)�B���ԂŒx�ꂪ����Ȃ�A�����Ɋւ��Ă��A�u�i�s�����ɏk���̂��������ꂽ�I�v�Ƃ����j���[�X�������Ă��悳�����Ɏv���܂����A���������Ƃ�����܂���B ����͂ǂ��������Ƃł��傤���H ���Ԃ͎��ۂɒx�ꂪ�ϑ�����Ă���̂ɁA�����̕��͂����܂Ō������ōς܂��悢�Ƃ������ƂȂ̂ł��傤���H �������A����͂������Ȃ��Ƃł��B ���Θ_�̘_���W�J���l����ƁA���Ԃƒ���(���)�́A�{���I�ɋ�ʂ��Ă������Ă��Ȃ��̂ŁA��̂悤�Ɉ���͎����I�ɕω�������̂ɁA��������́g�������h�ɂ����Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͋N����͂�������܂���B �����Ƃ��g�����̕ω�������h���܂��͗����Ƃ��g�������ɂ����Ȃ��h�Ƃ������ƂȂ�Θb�͂킩��̂ł����A����́u�����I�E�E�v�Ƃ����A��������́u�������ɂ����Ȃ��v�ȂǂƂ����̂͘_���I�ȋ��ʂ��Ă��炸�A�������邱�Ƃ͂ł��܂���B ���ΐ����_�̋��ȏ����ŁA���ԂƋ�Ԃ̐��������ꂼ��Ɨ��ɓǂ�ł�����ɂ͋C�Â��Ȃ��������Ƃ��A��������2����ׂ�ƁA�d��Ȗ����ӂ���ł��邱�Ƃ��킩��̂ł��B ���ꑊ�ΐ����_�̌��ׂ��܂���I�悵���Ƃ�����ł��傤�B�@ |
|
| �������v�̍l�@���瑊�Θ_�ɂ����鎞�Ԙ_�̊ԈႢ�������� | |
|
���Ԃɂ��Ắu���ԁE��Ԃ̔��Ȃƕ����w�̐V������{�����̒�āv�ł��ڂ����_���܂������A�ʂ̎��_����݂Ă����ΐ����_�̎��Ԙ_�ɂ͎v�l��̌�肪���݂��Ă��܂��B�A�C���V���^�C���̎��Ԙ_�̓f�^�����ł���Ƃ�����̂ł����A�d��ȓ_�ł��̂ŁA���L�ɂĎw�E���܂����B
�m�v��n �܂��͂��߂ɗv�_�����q�ׂ܂��ƁA���ՓI�Ȏ��Ԃ̗���������v�Ƃ������̂ő�ւ��Ă��܂������Ƃ����ΐ����_�ɂ����錈��I�ȊԈႢ�ł���܂����B�����v�̐i�݂͎��Ԃ��̂��̂ł͂Ȃ��ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���́u�����v�̐i�݁����ՓI���Ԃ̗���v�Ƌ����ɃC�R�[���Ō���ł��܂������Ƃ��A20���I�����w�����ꂩ���������ւƓ����Ă��܂��������̈�Ƃ�����̂ł��B �m�����n ���ΐ����_�ł́A�����v���x�����̌n�S�̂̕��ՓI�Ȏ��Ԃ܂Œx���Ǝ咣���܂��B�����v���x���ƁA���̌n���̌����v�݂̂Ȃ炸�A����܂����v�Ȃǂ̋@�B�����v��U��q���v�A�����̐U���𗘗p����N�I�[�c���v�A�͂��܂������v�܂ł��x��A����ɐ������̐S���̌ۓ��������̓x�����܂ł��Ȃɂ������x���Ɛ������܂��B �������A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B �����v�̐i�s�������ꂽ��A�Ȃ��͊w�I�ɓ����@�B�����v�܂Œx��͂��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��H�x��闝�R���܂������Ȃ��̂ł��B ����͂��������v���x��Ă��邾���ł���A����ȏ�̈Ӗ��͂���܂���B�����v���x�ꂽ��ԂƂ����̂́A��(�d���g)���]�v�ȋ����������ނ��߂ɂ�葽���̎��Ԃ�����������Ԃ������̂ł����A����Ȃӂ��Ɍ��̉^�����ω�������A�Ȃ��n�̕��ՓI���Ԃ܂Œx��邱�ƂɂȂ�̂��A���͂��̍������Ȃɂ��Ȃ��̂ł��B �����v�ɍ��킹�ċ@�B�����v�A�N�I�[�c���v�܂Œx��͂��߂邱�ƂȂǂȂ����A�܂��ĐS���̌ۓ��܂ł������ɂȂ邱�Ƃ�����܂���B�̂́A�����v�A�����v���v�A���E�\�N���v�A�������v�A�����v�Ȃǂ��܂��܂Ȏ��v���������̂ł���B �����ŁA�����v�Ƃ͂Ȃɂ����͂����肳���Ă����܂��傤�B �u���ԁA��ԁA�����ĉF���v������p���܂��B �����v �u���̋����ɂ��������s�ȃj���̋��̊Ԃ�����������̃p���X���������Ƃ���ƁA����͓d�����ۂ�p�����ł��ȒP�Ȏ��v�Ƃ��Ďg���܂�(���}�`)�B����������v�Ƃ������Ƃɂ��܂��傤�B���̃p���X������̋����瑼���̋��֍s�����Ԃ��u�`�N�v�Ɛ����C�A�鎞�Ԃ��u�^�N�v�Ɛ�����A�����v�̃`�N�E�^�N�Ŏ��Ԃ�����܂��B�����������v���l����ƁA���ΐ����_���c�_����̂ɂ����ւ�֗��ł��B���ׂĂ̕������ۂ́A(���Ƃ����Ƃ�Ƃ��������ۂ��܂߂�)�d���C�̖@���ɂ�āA���������Č����v�̎��Ԃɂ�Đi�s���܂��B���������Č����v�̎������Ԃ͓��ʂȎ��Ԃł͂Ȃ��āA���ՓI�Ȏ��Ԃ��\������̂ł��B�v ���ΐ����_�ɂ����鎞�ԂƂ������̂������ɐ�������Ă��܂��B �������A��ɂ��q�ׂ��悤�ɏ�L�̓��e�͊Ԉ���Ă��܂��B �u���ׂĂ̕������ۂ́A(���Ƃ����Ƃ�Ƃ��������ۂ��܂߂�)�d���C�̖@���ɂ�āA���������Č����v�̎��Ԃɂ�Đi�s���܂��B�v�ȂǂƂȂ�������̂��H ���������鍪�������������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�����ɓ���̕��ՓI�Ȏ��ԂɌ��ѕt���Ă��܂��Ă���̂��킩��܂�(���̑S�Ă̋��ȏ��ł������ł���)�B�V�̂̉^�s�́A�Ȃ�̗͂ɂ���ĉ^�s���Ă���̂��H�����v�͂Ȃ�̗͂ɂ���ē����Ă���Ƃ����̂ł��傤���H �����Ă���n�ł͉��̐}�a�̂悤�Ɍ��͐i�s��(��)�A�n�ォ��݂��炱�̎��v�͂�����肷����ł���悤�Ɍ�����ł��傤���A���������ꂪ�@�B�����v�A�����v�A�����v�A�l�Ԃ̐������ɂȂ��e����^������̂łȂ����Ƃ��܂������Ȃ��Ƃł��B �n�ォ��݂Ă��A���P�b�g�̒��̋@�B�����v�̐i�s�͒n��̂��̂Ƃ܂����������ł��邵�A�܂����P�b�g���̐l�̐S���̌ۓ����n��ƂȂ��ς�肠��܂���B���ۂ͒n�ォ��݂�������v���x���Ƃ��������̂��ƁA�������ꂾ���̂��ƂȂ̂ł��B (��)���͂��̌����v�̌��̐i�s���Ԉ���Ă��܂��B�ڂ����� �����Ԃ̒x��̃J���N���𖾂炩�ɂ��� ���������������B ��L�̖{�ł́A�}�`�̌����v���n��̊ϑ��҂̎��v�A�}�a�̌����v�����P�b�g�ɂ̂��������v�̉^�s�Ƃ��Đ�������Ă��܂��B ��L�̖{�ł͂���� �u���p���X�����̊Ԃ���������ԂɁA�n��ϑ��҂���݂���̓��P�b�g�ƈꏏ�ɉ��ɓ����܂�����A���P�b�g���~�܂��Ă���Ƃ��������p���X�͎߂ɒ��������������ł��Ői�܂Ȃ���Ȃ�܂���B����͒n��̊ϑ��҂��猩��ƁA�����Ă��郍�P�b�g�̎��v�̕����������Ǝ������ނ��Ƃ��Ӗ����܂��B���ꂪ�^���ɂ�鎞�v�̒x��ƌĂ�錻�ۂł��B����͂�����P�b�g�Ɍ���܂���B�q��@��d�Ԃɏ悹�����v���A�n��ɂ��������v�ɔ�ׂ�Ƃ�����莞�����ނ̂ł��B�v�ƋL�q����Ă��܂��B ���܂�����Ă͂����Ȃ��̂́A�u�E�E�n��ɂ��������v�ɔ�ׂ�Ƃ�����莞�����ނ̂ł��B�v�Ƃ������ł��B�����ł��A�����v�̎��Ԃ��A���ՓI�Ȏ��Ԃ̗��ꂷ�Ȃ킿���̍��݂ɂ�������ƒu�������悤�Ƃ����Ӑ}���ǂ݂Ƃ�邱�Ƃł��B ����͂��ׂĂ̑��Θ_�̋��ȏ��ɋ��ʂ��������ł���A�����v���}�`����}�a�̂悤�ɕς�邩�炻�̌n�̎��Ԃ܂Œx��͂��߂�A���Ȃ킿�A�����v���x�����̌n�̋@�B�����v�A�����v���琶���̐S���̌ۓ��A�l�̐����ɂ�����܂ł��ׂĂ��x���Ǝ咣����B �܂������ނ��Ⴍ����Ȑ����ł��B���Ƃ����d���g�̋������n�̂��ׂẲ^�����K�肵���肵�Ȃ��B���Θ_�̖{��ǂލۂ́A���̓_���\�����ӂ��ēǂ�ł��������B �a�}�̌��ۂȂǁA�n�ォ��݂���u�������̂悤�ɉ^�����Ă���̂��ȁv�Ƃ����Ӗ��ł����Ȃ��A�{���I�Ȏ��ԂƂ͑S�����W�Ȍ��ۂł���Ƃ������Ƃ��厖�ȃ|�C���g�ł��B ���ԂƂ͐l�Ԃ��l���������T�O�ł���A����́u���ł����Ē�`����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������㕨�ł͂���܂���B ���ł����Ď��ԂƂ������̂��`���Ă��܂��������߂ɁA���Ԃ͌��Ƃ��������I���̂̐����ɂ�����߂ɔ�����Ƃ����s���R�ɂ܂�Ȃ����Ԃɔ��W���Ă��܂����̂ł��B ���ΐ����_�ł͎��Ԃ��܂�Ŏ��̂̂悤�ɂ������Ă��܂����A����͌��ł����Ď��Ԃ��`���Ă��܂������Ƃ���̓��R�̋A���������킯�ł��B ���㕨���w�Ōn���ƂɌŗL�̎��Ԃ��l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������������ƂɂȂ��Ă���̂��A���Ƃ��������A�C���V���^�C�������Ԃ�����ɖ��������Ɍ��т������Ƃ��������Ă��܂��B �����g�������Ȃ�܂��߂͐����̂ł���(������~�X�ł���)�A������u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�Ƃ����݂��ɖ������������̏�ɑł����Ă����̂ł�����A���ΐ����_�̎��Ԃ͓x�������Ă������Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂����B ����ɁA���̂������Ȏ��ԊT�O��p���āA����(���)���`�������̂�����A��Ԃ̕��܂ł������Ȃ��ƂɂȂ�A�u�������ł͏k�܂Ȃ����A�������̌n���猩��Ώk��Ō�����B�v�ȂǂƂ�����Șb���܂���ʂ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B ���ԂƂ����̂͐l�ԂɂƂ��Ă킩��ɂ������̂̈�ł��̂ŁA���Ƃ����ꌩ���ɂ��Ȃ����悤�Ɍ�������̂Ő��������ƁA������u����Ȃ��̂��E�E�E�v�Ƃ��܂�����Ă��܂����̂������͂Ȃ��Ǝv���܂����B �ł̓A�C���V���^�C�����Ȃ����Ԃ����ł����Ē�`���Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��B 1900�N���������A�G�[�e�����ǂ�����Ă���������Ȃ����R(��Όn�������Ȃ��i���������Ă�������Ȃ����R)���A�C���V���^�C���͂ǂ����Ă��P���Ȍ������瓱��������������Ǝv���܂��B �����A�G�[�e���̖��͕����w�̑���ł���A�G�[�e����������Ȃ����ƁA�܂�������Ȃ����Ƃɑ��邤�܂����R�t�����ł��Ȃ����Ƃɕ����w�҂͑傫�ȉ����������Ă��܂����B �������D�u�Ɠo�ꂵ���A�C���V���^�C���Ƃ�����N���A�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v��p�����Ԃ̒�`��ύX����Ƃ����Ђ˂�Z��������A���[�����c���������̂Ƃ͈Ⴄ���@�ŁA���[�����c�ϊ��������邱�ƂɋC�t���܂����B�G�[�e���Ƃ������̂ɒ��ڐG��邱�ƂȂ��A�}�C�P���\���E���[���[�����̊�Ȍ��ʂ��A���ɂ�������Ɛ������Ă��܂����̂ł��B ���̂��܂�ɊȌ��Ō���(�H)�ȉ����̂����ɁA�����w�҂��Ƃт����̂́A�����̏��l������ȂÂ��܂��B �������A���̉����̎d���́A�S���̌�肾�����̂ł��B�A�C���V���^�C���́A�d��ȃ~�X���������Ƃ��܂����B ���̃~�X�Ɋւ��ẮA�u�������A���ʗ��A�^�L�I���A�^�C���}�V���A�o�q�p���h�b�N�X�̖��Ɋ��S����������v���̑��ŏڂ����q�ׂ܂����̂ł������������B�Ƃ������A�l�ނ̓A�C���V���^�C���̍I���Ȑ����Ɍ������x����Ă��܂����B���̂��܂������������Ȃ������킯�ł��B �����Ȃ�Ƃ������A21���I�̍��Ɏ����Ă��A�C���V���^�C���̔����������Ԃ��Ɏ��Â��Ă���̂ł�����A���̌���ɂ͌��t������܂���B�����ȒP�Ɍ����A���Θ_�̎��Ԃ́A�u��Όn�ȂǂȂ��A�S�Ă͑��ł���v�𐳓������邽�߂ɐ��ݏo����܂����B�����v�̎��ԂƉ�X�̎��ԂƂ͂Ȃ�̊W������܂���B �w�҂́A�u���Θ_�̎��Ԃ������{���̎��ԁv�̂悤�Ɍ���Ȃ��Ƒ̍ق����Ȃ�����A���܂ł����̂悤�Ɍ����Â��Ă��邾���ł��B�������A���[�����c���k���U��ł��B ���Θ_�ł̎��Ԃ���X�̌����̎��ԂƂ܂��������т��Ȃ��Ƃ������ƂɋC�Â����Ɍ���܂ł��Ă��܂������Ƃ́A�����w�̗��j�ɂ����錈��I�ȃ~�X�������Ƃ��킴������܂���B 21���I�����Ɏ����Ă��A�w�҂͂܂��C�Â��Ȃ��E�E�E�B�@ |
|
| �����Θ_�̌����ɂЂ��ޗ���s�\�Ș_���W�J�𖾂炩�ɂ��� | |
|
�����ł́A�����v�Ɋւ���]�������̌��ƁA���Θ_�̔j�]��������܂��B
�m�����n �܂��͂��߂ɁA���ꑊ�ΐ����_�̌����ƂȂ��Ă���u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v���L���܂��B �����x�s�ς̌��� 1�u�^�̌��̑����͌����̉^����Ԃɂ�炸���ł���B�v ���ꑊ�ΐ����� 2�u�����@���́A���ׂĂ̊����n�ɑ��ē����`�ł���킳���B�v �A�C���V���^�C���́A����1��2���w�������Ƃ��č̗p�����ꑊ�Θ_�����グ�܂����B �Ƃ���ŁA1��2���l���ɓ����ƁA���̂悤�ɂ��\������܂��B �����x�s�ς̌����̕ʕ\�� 3�u�����Ȃ銵���n(�ϑ���)���猩�Ă��A���̑����͈��l���ł���B�v ���āA�u�����x�s�ς̌����v�̎����I�؋��Ƃ��Ă悭����������̂ɁA�A������̌��̑����̑��肪����܂��B �u���ΐ����_�v(���쓟�v��)�ɂ͂��̂悤�ɋL����Ă��܂��B �^�����Ă������ �u�����s�ς̌����ɂ��ƁA���̑����͌����̉^���ɖ��W�ł���B���̌����̌��́A�܂��V�̂̊ϑ��ɂ���čs��ꂽ�B�^�̐Î~�����ɂ����������A�ϑ��҂̕��֑������ʼn^�����Ă����������̌��̑����������Ə����������� �{�����Ƃ����B2�̐����݂��̂܂�����]���Ă����d���ł́A������n���ɋ߂Â��Ă���Ƃ��́A�����̐��͉��������Ă���B�����̐����炭������ϑ������Ƃ���A����10^-6�ł��邱�Ƃ��m���Ă���B(�r����)���̂悤�Ȃ��Ƃ���A����0�ł���A�����x�s�ς̌����͐������ƍl������B�v ���̂悤�Ɍ����x�s�ς̌����̏؋����������Ă���킯�ł����A�����������l����Ƃ킩��ʂ�A����́u���͐��Ԃi����v�Ƃ����}�N�X�E�F���̍l���̐��������m�F�������̂ɂȂ��Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃł��B������Όn����ɐi�s���邱�Ƃ𖾗ĂɎ����Ă���(�����̉^���ɉe�����Ȃ����Ƃ������Ă���)�A���ΐ����_�̔j�]�̗�Ƃ�����̂ł��B ���Θ_�́A���L�̌����v�̌��i�s�����Ă��킩��ʂ�A����ł͌��͂܂�Ŋ����̖@���ɏ]�����̂悤�ɐi�s����Ǝ咣���闝�_(�����̉^���ɉe�����Đi�s����̂��Ǝ咣)�ł��̂ŁA��̎��������g�̎咣��^��������ے肵�Ă��邱�Ƃ��l����A���Θ_�̓��������ɋC�Â��̂͗e�Ղł��B �}�̐����́A��Όn�̑��݂��x�����Ă��邾���ł���A���̘A���̌��ʂ�3�̈Ӗ��́u�����x�s�ς̌����v�̏؋��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�}�ł́A�A���������n�����~�܂��Ă���Ƃ����`�ƂȂ��Ă��āA����ł�3���ؖ����邱�Ƃ͂ł��܂���B 3���ؖ�����ɂ́A�n�����߂Â��Ă����ꍇ�Ɖ�������ꍇ�̓�d������̌��̑������ׂȂ���Ȃ�Ȃ�����ł��B ���̓�d������̌��̋����́A���Θ_�a���ȑO�ɊF���}�N�X�E�F���������Ɋւ��ĔF�����Ă����u�d���g�͐�Όn����ɑ������ő���v�Ƃ����d���g�̋������̂��̂ƂȂ��Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ă��������B 1�͌��㕨���w�ɂ����Ă����������̂ł��B����̓}�N�X�E�F�����d���C�w�����������Ƃ�����F���F�����Ă������ƂŁA����1�̕\���ɂ́A�Ȃ�瑊�Θ_�I�ȗv�f�͂���܂���B�����x�s�ς̌����̐��������ؖ�����ɂ́A1�ł͂Ȃ��A3�̕������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����炠�����1�A2�A3�̂���܂����悭�������Ă��Ȃ��Ɗw�҂̐����ɂ��܂�����Ă��܂��܂��̂ŏ\�����ӂ��Ă��������B ��̓�d���̎����́A�u���͐�Όn����Ɍ������ő���v�Ƃ������Ƃ��x�����A��Όn�̑��݂����͂Ɏ咣������e�̂��̂ł����āA���͓��ꑊ�Θ_��ے肷�����ł������̂ł��B �����w�҂́A���ꑊ�Θ_�̔j�]����u���Θ_�̐������̏؋��v�Ƃ��ċ��ȏ����ł����Â��Ă���킯�ł��B ���ǁA�����w�҂́A���Θ_�ɂ����čł��{���I��3�̏ꍇ�̏؋��������悤�ɂ�������ꂸ�A1�̐��������咣���āA���܂��������肪�Ȃ���ԂȂ̂ł��B ���Ȃ݂ɁA�����A�����v�̂悤�ɁA�����̖@���ɏ]�����悤�Ȑi�s��������̂ł͂Ȃ��A��Όn����ɑ�����̂ł��邱�Ƃ́A���̗�ł�������Ă��܂��B �m�����A�����̖@���ɏ]�킸�A��Όn����ɑ��邱�Ƃ���������n ���u�����x�s�ς̌����������I�Ɏ�����Ă���v�͑�R�ł��� �����[�U�[�W���C���ɂ��A��Όn�̑��݂͊m���ƂȂ��� ���ꑊ�Θ_�̌����ɂ������ȓ_���������Ă݂܂��B�����Ō����v�������o���Ă݂܂��傤�B �}�`�ɂ����āA�����nS���ɌŒ肳�ꂽ�����������������ɔ�����ꉝ���^�����Ă���Ƃ��܂��B�����ЂƂ̊����nS���l���A���܌nS���͌nS�ɑ��ĉE�����ɑ��x���œ����Ă���Ƃ��܂��B�nS���璭�߂�A���͐}�a�̂悤�Ɏߏ���̋���ǂ�������悤�ɉ^������Ƒ��Θ_�ł͎咣���܂��B �����ł����A�����nS���Όn�ɂ���������ǂ��ł��傤���B�}�N�X�E�F���������ɂ��Ό��͐�Όn�i����Ƌ����܂�����}B�̂悤�Ɏ߂ɂ͐i�܂��A�^��ɂ������ƂɂȂ苾�ɂ͓�����Ȃ����ԂɂȂ��āA��̌����v�̐����͂��������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A���㕨���w�ł́A�u��Όn�Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��v�ƂȂ��Ă��܂�����A����ȉ��߂͋�����Ă��܂���B �Ƃ��낪�A���͐�Όn����ɐi�s���邱�Ƃ́A�q��@�ɓ��ڂ���Ă��郌�[�U�[�W���C���ɂ���Ď�����Ă��܂����A�܂���̓�d�����݂Ă����炩�ł��B��Όn�͎��݂��܂��B ���Č����v�ł́A���ǁA��������̌��͎��̐}1(�u���ΐ����_�v(���쓟�v��)�̐})�̂悤�ɐi�s����Ƃ��������ׂ����Ƃ������Ă���̂Ɠ����ł��B ����́A���̓{�[���Ɠ����悤�Ȑi�s������Ǝ咣������̂ł����A�͂����Č�(�d���g)�������ɂ���Ȑi�s��������̂Ȃ̂��ǂ����B ���͖{���ɂ���Ȑi�ݕ�������̂ł��傤���H ���ΐ����_��K���Ŏ�낤�Ƃ��镨���w�҂́A���͐�ɂ��̂悤�ɐi�s����Ǝ咣���܂��B �Ȃ��Ȃ�A���㕨���w�҂͓��ꑊ�ΐ������Ƃ�����������ȂɎ��K�v�����邩��ł��B�����A������A������̂悤�Ȑi�s�����Ȃ��Ɣ��������Ȃ�A������̕������炿����Ƃł��Y���Đi�ނ��Ƃ����������Ȃ�A�d���C�w�����͌n�ɂ���ċL�q�����ʉ�����邱�ƂɂȂ��āA�u�S�Ă̕������_�͂ǂ�Ȋ����n�ł������v�Ƃ����匴�����j��邱�ƂɂȂ�A���Θ_�݂̂Ȃ炸�A���㕨���͑����ꂵ�Ă��܂�����ł��B ���́A���́A�����v�̂悤�Ȑi�s�̎d�������Ȃ��̂ł��B ���̗��R���q�ׂ܂��B ��̓�d���ł̌��̋��������Ă��������B���́A�����̉^���̉e�����Ȃ����Ƃ�������Ă��܂��B ������ɁA��̌����v(�v�l��̎Y���I)�ł́A�����̉^���̉e������(�܂�Ŋ����̖@���ɏ]���悤��)�i�s����Ƃ��Ă���B�����ł��B �ȏ���A�����v�̌��̋����͉R�ł���ƒf���ł��邩��ł��B ���ΐ����_����R�̋�_�ł��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B �����v�����A�����x�s�ς̌����Ɠ��ꑊ�ΐ�����������������̂ł���A���ꑊ�Θ_�̓y��ł��邱�Ƃ���������ƔF�����Ă��������B �����āA���ꂪ�A�C���V���^�C���̂Ƃ�ł��Ȃ��\�Ԃ��甭�����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��I�@ |
|
| �������x�s�ς̌����ɂ�����V�p���h�b�N�X�̒� | |
|
�����ȑO����S�̒�ŁA������Ƌ^��Ɏv���Ă�����肪����܂��B�ǂ̋��ȏ��ł��c�_����Ă��炸�A�܂������Ȍ��t�Ƃ��ĂƂ�o�����Ƃ��ł��܂����̂ŁA�����ɐV�����p���h�b�N�X�Ƃ��Ē��A�F�l�̈ӌ���₢�����Ǝv���܂��B�ȉ��ŒP�Ɂh�n�h�ƌ������ꍇ�́A���ׂāh�����n�h���Ӗ����܂��B
�m�p���h�b�N�X�̒n ���܁A�����̊����n�l���Ō����E�����ɑ������Ői��ł���Ƃ��܂��B ���̂`�͉E�����ɑ������Ői��ł���A�܂����̂a�͍������ɑ������Ői��ł���Ƃ��܂��B ���܂`�Ƃa�͊����n�l�̒��̕��̂ł�����A���̂`�ɑ�����̑����͂��|v�ł���A�܂����̂a�ɑ�����̑����͂��{v�ƂȂ�܂��B�l�Ƃ�����̊����n�̒��ŋc�_���Ă��邱�Ƃł�����A���R���������v�Z�ƂȂ�܂��B ����́A���̂`�ɑ�����̑��Α��x�����|���ɂȂ�A���̂a�ɑ�����̑��Α��x�����{���ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B ���̏ꍇ����1�Ƃ��܂��傤�B ���܁A���̂`�ƕ��̂a�����ꂼ��ϑ��҂`�A�ϑ��҂a�ɒu��������Ƃ��܂��B����ƁA�r�[�ɏ��ς���Ă��܂��B �ϑ��҂�����ʌn�̑�\�҂ƍl����ƁA�����x�s�ς̌����̓K�p�ł��鏊�ƂȂ�A�ϑ��҂`�ɂƂ��Č��̑����͂��Ɍ����A�܂��ϑ��҂a�ɂƂ��Ă����ƂȂ�܂��B���̏ꍇ����2�Ƃ��܂��傤�B ���ď�1�Ə�2���ׂ��ꍇ�A���Ɋ�Ȃ��ƂɋC�Â��܂��B ��1�ł́A�`�Ƃa�������̊����n�̒��ɂ��镨�̂Ƃ��čl�@���܂����B����A��2�ł͂`�Ƃa���ϑ��҂Ƃ�������ōl���܂����B�ǂ�����A���̂ł���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��ӎ��������Ă��邩�����Ă��Ȃ����̍��ɂ����܂���B ��1�ł͕��̂`���猩������͂��|���ő����Ă���悤�Ɍ����A���̂a�ł͂��{���ł���悤�Ɍ�����B�Ƃ��낪�A��2�̂悤�ɕ��̂��ϑ��҂Ƃ��ĂƂ炦���r�[�A�ǂ���̊ϑ��҂ɂ����͂��ł���Ă���悤�Ɍ�����B �܂������s���Șb�ł��B ����[���ł���b�ł͂���܂���B�u���̂��猩���E�E�v���u�ϑ��҂��猩���E�E�v���{���I�ɓ����ł��邱�Ƃ͖��炩������ł��B �����ŁA���Θ_�҂͂��̂悤�ɔ��_���邩������܂���B �u����A��̋c�_�͊Ԉ���Ă���B���ΐ����_�ɂ��A�ǂ�ȕ��̂���݂Ă����̑����͂��Ɍ�����̂��I�v�ƁB �������A�����ł��傤���B ��1�͈�̌n���ɂ����镨�̂ƌ��̉^���̊W�ƍl���Ă��܂��̂ŁA���ɑ��镨�̂̑��Α��x�́A���̂`�̏ꍇ�A���R���|���ƂȂ�܂��B�u���̕��̗̂��ꂩ�猩���Ƃ��̑��x(���̂��猩�����x)�v�Ƃ����̂��A�����w�ɂ����鑊�Α��x�̒�`������ł��B����āA��1�ő��Α��x�����|���₃�{���ɂȂ�̂́A�܂��������R�ȋc�_�Ȃ̂ł��B ��������2�̂悤�ɁA���Ɗ����n(�ϑ���)�̊Ԃ̊W�Ƃ��ĂƂ炦���Ƃ��A���Θ_�̌����x�s�ς̌����ɂ��A��2��(�ϑ��҂�ʂ̂���n�̑�\�҂ƍl�����)�ϑ��҂`�ɂ��a�ɂ����͂��Ői��ł���悤�Ɍ����邱�ƂɂȂ�B ���ӁF���Θ_�Łh�ϑ��ҁh�ƌ������ꍇ�́A�h���銵���n�̑�\�ҁh(���邢�́u���銵���n�ɐÎ~������W�̌��_�v�ƌ����Ă��悢)�Ƃ����Ӗ��������܂��B �u��̌n���̕��̂Ƃ��Ă݂���|���ƂȂ�A���̕��̂��ϑ���(�ʌn�̑�\��)�ƌ�����ς��������ł��ɂȂ�v�ȂǂƂ����̂́A�܂��������������b�ł͂���܂��B�u�^���͂ǂ��������H�v�ƌ�ŕ��̌N�ɕ�������ǂ�������̂ł��傤�H �܂��Ƀp���h�b�N�X���������Ă���̂ł��B (���킸�����Ȃ̒��ӂł����A��1�����R���Θ_���g���Ă̋c�_�ł��̂ŁA���̓_�͌�����Ȃ��ł�������) ������l�̐l���A��̕������ۂ����|���ƌ�����A�܂�������(�I)���ƌ����肷��B���̊���͂Ȃ�Ȃ̂��A���Θ_�͌��o�Ǐ�̗��_�Ȃ̂ł��傤���H����Ȃ��ƂɂȂ�̂́A���_�����{�I�ɂ����������Ƃ̏؋��ł��傤�B ���Θ_�ɂ����ẮA���́A�n�A�ϑ��҂̎O�����ɂ����܂��Ɏg�p����Ă����悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B ����Ȃ������Șb�ɂȂ�̂��A�u�ǂ�Ȋϑ��҂ɂ����̑����͂��ł���v�Ƃ��������x�s�ς̌������Ԉ���Ă��邩��ł��B�݂Ȃ��܂͂ǂ��v���܂����H ����ɁA�������x�̊ϓ_������V�����p���h�b�N�X�����o���܂����B����̃p���h�b�N�X�ƍ��킹�čl���Ă݂Ă��������B �@ |
|
| �������x�s�ς̌����́A���Ԃ�O��ɂ������̂ł��� | |
|
����́A�����x�s�ς̌����́A���Ԃ�O��Ƃ��Ȃ���Ή��߂ł��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ��܂������܂��B
����ɁA�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�݂͌��ɖ���������̂ł���A���̓��Z�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ𖾂炩�ɂ��܂��B(��̌������������邱�Ƃ͌E�c���������̒��Ō��y����Ă��܂����ؖ��܂ł͋L����Ă��Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA�����ł͎������o�����ؖ����L���܂���) �m�����n �܂��u�����x�s�ς̌����v�Ɓu���ꑊ�ΐ������v���͂��߂ɏ����܂��Ƃ��̂悤�ɂȂ�܂��B �����x�s�ς̌����T 1�u�^�̌��̑����́A�����̉^����Ԃɖ��W�Ȉ��l���ł���B�v ���ꑊ�ΐ����� 2�u�������ɓ����x�^�������Ă��邷�ׂĂ̊����n�ɂ����āA���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�܂����������`�� �\����A�����̊����n�̂Ȃ�������ʂȂ��̂�I�яo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �A�C���V���^�C���́A����1��2����{�I�Ȍ����Ƃ��č̗p�����ꑊ�ΐ����_�����グ�܂����B �Ƃ���ŁA2���l���ɓ����ƁA1�̌����x�s�ς̌����͂��̂悤�ɂ��\������܂��B �����x�s�ς̌����@�U 3�u�����Ȃ銵���n(�ϑ���)���猩�Ă��A���̑����͈��l���ł���B�v (��)���1�`3�́u���ΐ����_�̍l�����v(����d�M��)���Q�l�ɂ��܂����B �ȉ��A�����̌��������킵�����Ă����܂��B ��X�͂��ܑ��Θ_�̒a�����钼�O1904�N�ɗ����Ă���Ƃ��܂��傤�B�����ăA�C���V���^�C���̍l�@���Âɒǂ��Ă����A���Θ_�ɂ�����l�@�̌����݂����Ǝv���܂��B �g�����h�Ƃ����Ƃ��́A�����u���ɑ��鑬�����H�v�Ƃ������Ƃ����ɂȂ�܂��B��������5�����^���ŕ����A�Ƃ����Ƃ��́A�n�ʂɑ��Ă̑����������Ă���킯�ł��B�ł�����A1�́A�u�����̉^����Ԃɖ��W�ɁA���������l���ƂȂ�悤�ȓ��ʂȌn�����݂���̂��v�Ƃ������Ƃ����͂Ɏ咣���Ă���ƌ��������邱�Ƃ��ł��܂�(����́A���Θ_�a���ȑO�̃}�N�X�E�F���������̉��߂��̂��̂ł��I)�B �������̂悤�Ȍn������Ȃ��Ȃ�A1�̎咣�����邱�Ǝ��̖��Ӗ��ł�����A1�͂��������Ӗ��Ȃ̂ł��B���̌n�̐��́A�������E�E���邢�͂����Ƃ�������̂��m��Ȃ����A�Ƃɂ������̂悤���ʂȌn�̑��݂�1�͎咣���Ă���B �������A�������݂���Ƃ���A���̓��ʂȌn�͂��͈�����Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ��ȉ��ɏؖ����܂��B �m�ؖ��n ���܉��ɁA���̑��������l���ƂȂ�悤�ȓ��ʂȌn�Ƃ��Čn�`�����݂����Ɖ��肵�܂��傤�B ���܌n�a�͌n�`�ɑ��A�����葬�x���œ����Ă���Ƃ��܂��B ����ɂ��A�n�`�̍��W�ɐÎ~�����l���猩��ƌ��͈��l���Ői��Ō�����͖̂��炩�ł��B���āA�n�a�͌n�`�ɑ��Ĉ�葬�x�œ����Ă���̂ł�����A�n�a���ɐÎ~�����l��������݂�ƁA���̑����͓��R���Ƃ͂Ȃ�܂���B����Čn�a�͓��ʂȌn�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ����Ƃ��킩��܂��B �n�`�ɑ��鑬�x��0�ȊO�̗l�X�Ȓl���Ƃ鑼�̌n���l���Ă��A�����̂����Ȃ�n���u���ʂȌn�v�ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ����Ƃ͂����ɂ킩��܂��B ����āA���ʂȌn����ȏ㑶�݂��邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��A��������Ƃ���A����͂�����ł���A�Ƃ������Ƃ��ؖ�����܂���(�����܂ł��Ȃ����Ƃł����A���̐�Όn�ɐÎ~�������w�I�ȍ��W�n�͖����ɐݒ�ł��܂�)�B �I���B 1 �́A�u������̓��ʂȌn�����̐��ɂ���̂��v�ƁA���̑��݂�ϋɓI�Ɏ咣���Ă���B �����A���̓��ʂȌn�́A���Ԃ܂��͐�Όn�ƌĂ�Ă��܂�������A�����ł����̌Ăѕ��ɂȂ炢�܂��ƁA1�͐��Ԃ̑��݂����͂Ɏ咣���Ă���B 1 �́A���Ԃ̑��݂��咣���Ă���B 2 �́A���Ԃ̑��݂�ے肵�Ă���B ���̂悤�Ɍ����邱�Ƃ́A����̖ڂɂ����炩�ɂȂ�܂����B1��2�͑S�������̂��Ƃ��咣���Ă���B ���āA�����̗���ōl����ƁA���̂悤�ɂ܂������܂荇��Ȃ���̌������̗p���ė��_���\�z���悤�Ȃǂ�����v��Ȃ����ƂȂǂ����ɂ킩��܂��B1��2�͖������Ă���̂ł�����B �Ƃ��낪�A��l�A�C���V���^�C���������Ⴂ�܂����B �ނ́A�Ȍ�������I�Ȍ`���Ƃ������̂��ُ�ȂقǍD���������̂ł��傤�B1��2���Ȃ�Ƃ��Z���������������B 1 �̓}�N�X�E�F���������̐�����\���������́A2�̓j���[�g���͊w���ӎ��������̂Ƃ����܂����A�P���Ȍ����̂Ƃ���ŁA����2���`���̏�œ���I�ɕ\�������������̂ł��B�`���Ƃ������̂Ɉُ�ɂ���������̂��A�C���V���^�C���ł����B 1 �� 2 �̗Z�����琶�܂ꂽ3�ȂǁA���ꂪ���Ă����Ȃ̂͂����炩�ł��B�������A�A�C���V���^�C���́u�͊w�̖@���͂��ׂĂ̊����n�ɁE�E�v�ł͂Ȃ��A�u���ׂĂ̕����@���͂��ׂĂ̊����n�ɁE�E�E�v�Ƃǂ����Ă������������B 1 �� 2 �Ȃǂ��ꂪ���Ă��������Ă��邵�A3�ȂǏ��w�����݂Ă��R�Ƃ킩��܂��B �������A3 ���Ȃ�Ƃ��������������B�ǂ�����������E�E�E�B �u�������B����A�҂Ă�B�������B���ԂƂ͂����������Ƃ�����i�ł����\���ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����H���Ԃ��A�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v����b�Ƃ��A�����g���Ē�`�������Ă݂�ƁE�E�E�����A���̃��[�����c�ϊ������o�Ă���ł͂Ȃ����I���[�����c��̂悤�ɐl�H�I�ȉ�����݂��ē������@���A������̕�����قǂ������肵�Ă���I�����͂����肻�����B�v�ƁA���̂悤�Ȍo�܂��ւāA�L���ȁu�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v��1905�N�ɏ������Ƒz������܂��B ���ԂƂ͂킩��ɂ������̂ł��B ���̂킩��ɂ������̂��A���ł����Ă��̂悤�ɕ\�������ƁA������u���Ԃ��āE�E����Ȃ��̂Ȃ̂��E�E�E�v�ƂȂ��Ă��܂��Ă�������������܂���B ����������1��2���ǂ����Ă����_�̊�b�ɂ����������߂ɁA�A�C���V���^�C���͖��������������m�̏�ŁA���̖����̘_����p���Ď��ԂƂ������̂��Ē�`�����̂ł��B ���Ԃ�O��I�ɂ˂��Ȃ���邱�ƂŁA�Ȃ�Ƃ����܂����킹�A�ł����������̂����Θ_�ł��B�����Ƃ����y��Ŗ��������Ă���̂ł�����A�ǂ����ɂ��̂�������邱�Ƃ͓��R�̂��Ƃ������̂ł��B �{�[�A��}�C�P���\���Ȃǂ͑��ΐ����_�ɑ唽�������悤�ł����A�u��V�ˌ���I�j���[�g���ȗ��̑�v���I�v�Ƃ����A�}�X�R�~���܂߂Ă̐��Ԃ̑升�����������������Ă��܂����̂ł��傤�B�������Θ_���悭�u���܍��킹�̗��_�v�ƌĂԂ͈̂ȏ�̂悤�ȗ��R����ł��B �A�C���V���^�C���͗��j�I�_���u�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v�̒��ŁA�u�����x�s�ς̌����v�Ɓu���ꑊ�ΐ������v���������Ă��Ȃ����Ƃ̏ؖ���^���Ă���̂ł����A���̏ؖ����S���̋U��ł��邱�Ƃ��A�����Ŏ����܂����B����͋����ׂ��\�Ԃ̏ؖ��ƂȂ��Ă��܂��B �ȏ�̋c�_����A���ꑊ�ΐ������ƌ����x�s�ς̌����͖����������̂ł��邱�Ƃ��������܂����B �����̋��ȏ��ł͂悭�u���Θ_�̗��_�`���̊Ȍ����A�������v�Ƃ������Ƃ���������܂��B �������ɁA�����w�ɂ����Ă������̏d�v�ȗv�f�ł͂���܂����A������������Ȍ��ł��낤�Ɗ�b�ɂ�������̌������������Ă���̂ł�����A���̏�ɍ\�z���ꂽ���_�����������̂ƂȂ邱�Ƃ͐�ɂȂ��A�Ƃ������Ƃ�F�����邱�Ƃ���ł��B ���Θ_�̒a�����j���[�g���ȗ��̑�v���ȂǂƂ�����̂́A�u���ԁE��ԁv�̊T�O�����ꂩ��ς��Ă��܂�������ł����A�A�C���V���^�C���̎��Ԃɑ���l�@���Ԉ���Ă����̂́A���̗l�X�ȉӏ��Ŏ������Ƃ���ł��B���́A���Ԃ́A�F���S�̂ɋ��ʂɗ���Ă���Ɩ���A�Ƃ��������̂��̂������̂ł��B�����w�҂͂��C�Â��̂ł��傤���E�E�E �@ |
|
| ���u�����x�s�ς̌����v�ł͂Ȃ��u���ꑊ�ΐ������v�ɒ��ڂ��ׂ� | |
|
���Θ_�ŁA���������v���Ă��邱�Ƃ�����܂��B����́h�����x�s�ς̌����h�Ɋւ��Ă̂��Ƃł��B
���ꑊ�Θ_�̂��ƂɂȂ�ƁA�u�����x�s�ς̌������������A�����x�s�ς̌����͂������v�Ƃ��낢��Ȑl���咣����̂ł����A����Ȃ��Ƃ������Ă邩��A�j�S�����������s�m���ȏ�ԂɂȂ��Ă���C�����܂��B �݂Ȍ����x�s�ς̌����Ƃ������������܂ЂƂ����܂��ɂ������߂Ă��Ȃ��̂łȂ��ł��傤���B ���ꑊ�ΐ����_�͌����x�s�ς̌�����������\������Ă���̂ł͂���܂���B �u�����x�s�ς̌����v�ƂƂ��ɁA������̒��ł���u���ꑊ�ΐ������v�����킹�č\������Ă��܂��B ���Ȃ킿�A���ꑊ�Θ_�́A 1 �����x�s�ς̌��� 2 ���ꑊ�ΐ����� �Ƃ�������w�������Ƃ��č���Ă���̂ł��B �A�C���V���^�C���̌����͂�����ƔF������ɂ́A�Y�o��2���ꑊ�ΐ������ɂ������ڂ��Ȃ���Ȃ炢�B �����x�s�ς̌������茩�Ă��Ă̓_���ł�(�{�����ڂ₯�Ă��܂�)�B ��� �����Θ_�̌����ɂЂ��ޗ���s�\�Ș_���W�J�𖾂炩�ɂ��� �ł��������܂������厖�ȓ_�ł��̂ŁA����܂ł̋L�q���܂Ƃ߂�`�ōēx�������܂��B ���Θ_�̋��ȏ��ɂ悭�o�Ă���1�A2�A3��������x�����܂��B �����x�s�ς̌���1�u�^�̌��̑����͌����̉^����Ԃɂ�炸���ł���v ���ꑊ�ΐ�����2�u�����@���́A���ׂĂ̊����n�ɑ��ē����`�ł���킳���v 1 �� 2 ���l���ɓ����ƁA���̂悤�ɂ��\������܂��B �����x�s�ς̌����̕ʕ\��3�u�����Ȃ銵���n(�ϑ���)���猩�Ă����̑����͈��l���ł���v �͂����茾���܂��B 1 �͐��������A2 �� 3 ���Ԉ���Ă���̂ł��B ��� 1 �́A�̂��獡���܂Ŋ����ɐ������B�������A2 ���Ԉ���Ă���̂́A���ł��w�E�����ʂ葽���̎���Ŗ��炩�ł��B �����Θ_�̌����ɂЂ��ޗ���s�\�Ș_���W�J�𖾂炩�ɂ��� ���u�����x�s�ς̌����������I�Ɏ�����Ă���v�͑�R�ł��� �����[�U�[�W���C���ɂ��A��Όn�̑��݂͊m���ƂȂ��� 2 �͊��S�Ɍ���������ł��B����āA1��2��Z��������3�����ƂȂ�͓̂��R�ł���܂��B 2 �̂悤�Ȍ��������܂ł���ΓI�����Ƃ��ĐM�Ă��邩��A���㕨���͂ǂ��܂ł��������Ȃ��ƂɂȂ��Ă����̂ł��B ���ꑊ�ΐ������̂悤�ȊԈ���������ȂǁA���}�Ɏ̂ċ���Ȃ���Ȃ�܂���B�w�҂͂͂₭�C�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA���̂��ƂɋC�t�����Ƃ��A�̂ċ���E�C���������Ƃ��A�䂪���㕨���͂܂Ƃ��ȏ�ԂւƋA�邱�Ƃ��ł��܂��B �@ |
|
| �����[�U�[�W���C���ɂ��A��Όn�̑��݂͊m���ƂȂ��� | |
|
�q��@��P�b�g�ɓ��ڂ���Ă��郌�[�U�[�W���C���ɂ��A�����x�s�ς̌������j��Ă��邱�Ƃ��E�c����㓡�����ɂ�����Ă��܂��B
�Ƃ��낪�A���Θ_�w�҂́A���ΐ����_�������čI���ɔ��_���A���[�U�[�W���C���������Θ_���x��������̂��Ǝ咣���Ă���A�o������Ȃ���Ԃ̂܂܂��Ă���悤�Ɏv���܂��B ���̖����l���Ă��邤���ɁA���Θ_�h�����{�̂Ƃ���ő傫�Ȋ��Ⴂ�����Ă��邱�ƂɋC�Â��܂����B�����ł͑��Θ_�h�̊��Ⴂ�𖾂炩�ɂ��܂��B �m�����n �܂��c�_�̖{���I�ȏœ_���A�_�_�Ƃ����`�ł܂��ꌾ�ŕ\�����Ă����܂��B ���_�_�� ���[�U�[�W���C���̌��̋����́A��Όn��O��ɂ��Ȃ���ΐ��藧���Ȃ����̂ł���B ���́��_�_�������������ۂ����A�ő�̏œ_�ɂȂ��Ă��܂��B �����Θ_�h�́A��̘_�_�͐������ƌ����A����đ��ΐ����_�͊Ԉ���Ă���Ǝ咣���܂�(�������_�_������������Ό��ʓI�ɂ��̂悤�ɂȂ�܂�)�B �������A���Θ_�h�͏�̎咣�ɑ��Ă܂��^����ɑ��ΐ����_�������o���A���̂悤�ɔ��_���܂��B ���Θ_�h�̔��_ ��]�̏�̌��̊ϑ��_�́A��]�n���Ȃ킿�����x�n�ɂ���̂�����A����͓��ꑊ�Θ_�̓K�p�͈͂ɂ͑����Ȃ��B����āA���̂��Ƃœ��ꑊ�Θ_�����ۂ��c�_������̂͂��������B����͉����x�n�ł��邩��A��ʑ��Θ_��p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��ʑ��Θ_�Ōv�Z����E�E�E�Ƃ��Ă��낢��ƌv�Z���A�u�ق�A�܂������������Ȃ��B���Θ_�͐������̂��B�v �Ƃ��āA���߂�����B �����āA���̈�ʑ��Θ_�ł̌v�Z�������Ă��鍇���Ă��Ȃ��ŁA�܂����܂��܂ȋc�_������L�����Ă��܂��B �������A�悭�l���Ă݂�E�E�E�E���Θ_�h�̎咣�͂��������Ƃ������ƂɋC�Â��܂��B �����ł̋c�_�̒��S�́A���[�U�[�W���C���̌��̋�������Όn��O��ɂ��Ȃ���ΐ��藧���Ȃ����̂Ȃ̂��ۂ��A�Ƃ������Ƃł��B��́��_�_���̐��ۂ��݂̂���ɂ��Ă���B �����W���C���̌��̓������A��Όn���l���Ȃ���ΐ����̂��Ȃ����̂Ȃ�A���ꑊ�ΐ������͊ԈႢ�Ƃ������ƂɂȂ�A���Θ_�͕��܂��B����A������Όn�ƂȂ��W�̂Ȃ����̂Ȃ�A���̌��ۂ��瑊�Θ_���ے肳��邱�Ƃ͂���܂���B ���Ȃ݂ɁA��Όn�ƃG�[�e���͖��W�ł��B ���̋c�_�ł́A���̌��ۂ���K�R�I�ɐ�Όn���o�Ă��邩�ۂ����ő�̏œ_�Ȃ̂ł��B �����܂ŗ���ƁA�C�Â����Ƃ�����ł��傤�B ����́A���̌��ۂ��������̂ɁA���Ȃ炸�������Θ_�������o���K�v�ȂǂȂ��A�Ƃ������Ƃł��B ���ꂪ���Θ_�h�̔��_�͂��������Ǝ����͂��߂ɏq�ׂ����R�ł��B ���Θ_�ȊO�̊ϓ_�����������A���̌��ʁA��Όn�̑��݁E�݂����炩�ɂȂ�A���̋c�_�͂܂���������ɏI���܂��B�����āA���̌��ʁA���̒i�K�Ƃ��đ��Θ_�̐��ۂ����f�����Ƃ������ꂾ���̂��Ƃł��B ���Θ_�������o����ΓI�ȕK�v���A�K�R���ȂǂȂ��̂ł��B �ɂ�������炸�A��́��_�_�����ؖ�����̂ɁA���Θ_�h�́A�܂��^����ɑ��Θ_�������o���A����₱���Ɛ�������B���Θ_�łȂ���A���_�_���̐��ۂ������͖̂����Ƃł��v���Ă��邩�̂悤�ł��B�������A�����o���Ă���̂́A�܂��\���ɂ͎�����Ă��Ȃ���ʑ��Θ_�ł���A�����͂ȂǂȂ����Ƃ͖��炩�ł����A�܂����������̊ϓ_�����ʑ��Θ_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ́A��ʑ��ΐ����_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ̏ؖ��Ŏ����ؖ������Ƃ���ł��B ��������A�܂�����������ϓ_���疾���ɏؖ��ł���̂ł��B �m�ؖ��n ���[�U�[�W���C���́A���̂̉�]�p���x�����o���鑕�u�ł��B �q��@�̋@�̂ɉ����x�v�ƂƂ��ɂƂ����A�W���C������͋@�̂̌X���̏�A�܂������x�v����͈ʒu�̏�����A�������q��@�̐������p����i�s�����𒀎�����o���܂��B ���[�U�[�W���C���Ɖ����x�v�����킹�āA�����Z���T�Ƃ����܂��B �@�̂��X����������Ƃ̎p���ɂ��ǂ��A�������͂��ꂻ���ɂȂ�@��𐳂��������ɂ��ǂ��B�����Z���T�́A�܂��ɍq��@�̓��]�̖�����S���Ă��܂��B ���[�U�[�W���C���ɂ́A�����O�E���[�U�[�W���C���ƌ��t�@�C�o�[�W���C����2��ނ�����܂����{���I�Ȍ����͓����ł��B���[�U�[�W���C���́A���u�S�̂���]����ƌ��H���ɉ��������g�������������ꂩ�甭�����銱�Ȃ������o��œǂ݂Ƃ�A���̏���]�p���x�����o���܂��B ���[�U�[�W���C�����g���ƁA�@�̂̌X�������o�����̏���`���邱�ƂŁA�q��@�͂˂Ɉ��肵���悢�p�����������Ƃ��ł��܂�(���ۂ�3�������̂̉�]�p�����A���^�C���Ɍ��o���A3�����I�ȏ��ɂ��p����������܂�)�B ���[�U�[�W���C���͂܂������̃u���b�N�{�b�N�X�̒��ɒu����Ă��Ȃ���A�q��@�ɐ���Ȏp�����w�����A�����x�v�ł̈ʒu���Ƃ����킹�邱�ƂŁA�@�̂𐳂����ړI�n�܂ŗU�����Ă����B ���̎������̂��A��Όn�̑��݂��m���ɂ��Ă��邱�Ƃ͖����ł��B �Ȃ��Ȃ�A������Όn�ȂǂƂ������̂��Ȃ����ɂƂ��āg�S�Ă̊����n����h�ȂǂƂ������ƂɂȂ�A�܂��q��@�̓��]�Ƃ��ėp����Ƃ������z���̂������т܂���B�v���悤�ɂ��ł��Ȃ�����ł�(����ƂȂ��ΓI�Ȋ���W��݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��I)�B ��������̐�Όn�Ƃ�����������Ƃ�������(����W)�����邩��A�@�̘̂A���I�ȌX�����̏��l�𒀎��������킹�邱�Ƃ��ۏ���A���m�Ȏp���E�ʒu�����肾����B�ŏ��̏o�����̏����p�����[���ɃZ�b�g���A�������珇���X�V���Ă������v�������ׂĂ��������B ��Όn�Ƃ����m�ł��鑫�ꂪ���邩�炱���A���n�_�ł̌v�Z�l���ۏ����B ������Όn�Ƃ������̂�z�肵�Ȃ���A��s�@�̓��]�ł��銵���Z���T�̐v����ł��܂���B���̂��Ƃ̓��[�U�[�W���C���̐v���̂��A��ΓI��n�𑫏�Ɍ����i�s���邱�Ƃ�O��ɑg�ݗ��Ă��Ă���؋��Ȃ̂ł��B�܂��v��̌v�Z�����ۂɂ݂Ă��A��Όn��z�肵���v�Z���Ȃ���Ă���B ����ɁA���̑��u�̐v�ɂ����ẮA�����n�A�����x�n(��]�n)�ȂǂƂ�����ʂ��Ȃ����K�v���Ȃ����Ƃ��킩��܂��B�u��]�n�͈�ʑ��Θ_�ŁA�����n�͓��ꑊ�Θ_�ŁE�E�v�ȂǂƂ���ȕ��ɐv�����Ă���̂ł͂Ȃ��A����Ȃ��Ƃɂ͂����܂��Ȃ��ɁA�Z�p�҂͐�Όn�Ƃ������ΓI�Ȋ���W��p���āA�ÓT�����w�̔��e�Ń��[�U�[�W���C���Ƃ������u��v������Ă��܂��B�����āA�����ɂ��̑��u�͒������Ȑ��x�œ��삵�Ă���B ���ǁA����̋Z�p�҂����́A�}�N�X�E�F�����������A���Θ_�a���ȑO�̏펯�I�ϓ_����f���ɉ��߂����Ƃ������Ƃł��B �^�̃}�N�X�E�F���������̓�̂������̎��@�������d(��)���|�݂a(��)�^�݂� �Ɓ@��^2��������a(��)���݂d(��)�^�݂��@����g����������������܂����A����������Ƃ��̔g�̑��x�͂��ƂȂ�܂��B���ꂱ�����u�d���g�����Ƃ������x�ő����Όn�Ƃ������ʂȑ��ꂪ����v�Ɖ�X�ɋ����Ă���Ă����ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���́u���ʂȌn�ȂǂȂ��B�S�Ă̌n�͓������I�v�Ƃ�����������ꑊ�ΐ�����������ɑł����āA�d���C�w�̊�{���߂��ꒃ�ɂ��Ă��܂����B �������A����Z�p�̑O�ɁA���ꑊ�ΐ������Ƃ��������̉R���������Ȃ��I�悵�Ă��܂��܂����B ���ǁA���Ƃ͐�Όn����ɑ������ő�����̂ł���A���̉^���n���猩���ꍇ���ȊO�̑����ɂȂ�Ƃ����A���Θ_�a���ȑO�̕����w�҂Ȃ�N�����l�������߂ɋZ�p�҂͑f���ɏ]�����Ƃ������Ƃł���A���̉��߂ɑ����ă��[�U�[�W���C����v���听�����݂��킯�ł��B �u���b�N�{�b�N�X�̒��ɂ��Ȃ���A���[�U�[�W���C���́A�q��@������ɔ�Ԃ��߂̏��M���Â��Ă���A�Ƃ���������������x�悭�l���Ă݂Ă��������B ������Όn����ɐi�s���Ă��邱�Ƃ��A���̎������͂�����킩�邩��ł��B �ؖ��I���B ��̐����Ŋ����n�A�����x�n�܂������W�Ȃ��A�܂����ΐ����_�������o�����Ɍ����g���Đ�Όn�����ꂽ���Ƃɒ��ڂ��Ăق����Ǝv���܂��B �ȏォ��A�`���̘_�_�́A�������Ǝ��͔��f���܂��B ���ꑊ�ΐ������̔j�]�͖��炩�ŁA���Θ_���ے肳��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��ł��傤�B ����ɁA�㓡�����A�E�c����̃��[�U�[�W���C���Ɋւ���ڍׂȐ�������܂�邱�Ƃ������߂��܂��B���[�U�[�W���C���́A���݁A��s�@�݂̂Ȃ炸���P�b�g�A�~�T�C���A�l�H�q���A�w���R�v�^�A�����͂Ȃǂ���Ƃ�������̂ɓ��ڂ��ꂻ�̎p������ɋ��͂ȈЗ͂����Ă��܂��B ���㓡�����ɂ��A���܂��܂Ȗ{�ŁA�{�_���������������ړI�ȕ��@�Ō����x�s�ϑ��j��̏ؖ����Ȃ���Ă��܂��B �ؖ��́A�㓡�����̐����ɔ�ׂ�A���ԐړI�ȕ��@�Ƃ����邩������܂���B�������A��Όn�̑��݂������ɂ͂���ŏ\���Ȃ̂ł��B�㓡�����͉�]�n�A�����n�̋�ʂɂ���������������c�_������Ă��܂����A��̏ؖ����A ���̕K�v���Ȃ����Ƃ��킩��ł��傤�B �@ |
|
| �����Ǝ��Ԃ̍l�@�ŃA�C���V���^�C����3�d�̃~�X��Ƃ��Ă��� | |
|
���ΐ����_�ł͌��������������킯�ł����A�����v�̍l�@�ɂ����ăA�C���V���^�C����3�d�̃~�X��Ƃ��Ă��܂��B
����͂���܂ł̌��Ǝ��ԂɊւ���l�@���܂Ƃ߂�`�ŁA���̃~�X���q�ׂ����Ƃ������܂��B �m�����n ����܂Ń}�C�P���\���E���[���[����(�ȉ��l�l����)������v�ł̌��̍l�@�Ɋւ��Č��㕨���w������Ă���_�����낢��w�E���܂������A���̒��S�I�Ȗ��_���Ȍ��ɐ�������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B ��}���݂Ă��������B ����́A�u���ΐ����_�v(���쓟�v��)�̌����v�̐}�Ƃقړ������̂ł��B �����n�r���ɌŒ肳�ꂽ�C���������Ɍ������������鑕�u���l���A�r���͊����n�r�ɑ��Ă������ɑ��x�u�œ����Ă���Ƃ��A���̌��ۂ��r����ϑ����Ă��܂��B �n�r�����n�r�ɑ��Ăǂ�ȑ��x�ő����Ă��銵���n�ł������Ƃ��Ă��A�^��ɔ��˂��ꂽ���͂҂����苾�l�ɓ��B����B��������Ȃ��ƂɁA�u�x�N�g����������āA�E�}�ō��}���x�N�g���̒����������Ȃ��Ă���̂ɁA���̃x�N�g���̑傫���́A�ˑR���l���ł���v�Ƃ��������ׂ����Ƃ������Ă���̂���}�ł��B �܂����ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�́A�͂����Č��͐}�̂悤�Ȑi�s������̂��H�Ƃ������Ƃł��B �w�҂́u���͏�}�̂悤�ɂ܂�Ŋ����̖@���ɏ]�����̂悤�ɐi�s����v�Ǝ咣���܂��B���́u��̂悤�Ȑi�s�͂��Ȃ��B �}�N�X�E�F�������������͐�Όn�𑫏�ɐi�s���邩��A�^��ɕ����ꂽ���͐^��ɐi��ł��܂��̂ŋ��l�ɂ͓�����Ȃ��B�v�Ǝ咣���܂��B ���́A��}�̂悤�Ȑi�s�͂��܂���B�����v�̌��̋����͌��Ȃ̂ł��B ���̗��R�́A���͏�}�̂悤�Ȋ����̖@���ɏ]�����悤��(�܂�����̉^���ɉe����������悤��)�i�s�͂����A��Όn����ɐi�ނ��Ƃ����Ɏ����Ŏ�����Ă��邩��ł��B���L�Ŏ����Ă��܂��B �m���������̖@���ɏ]�킸�A��Όn����ɑ��邱�Ƃ���������n ���u�����x�s�ς̌����������I�Ɏ�����Ă���v�͑�R�ł��� �����Θ_�̌����ɂЂ��ޗ���s�\�Ș_���W�J�𖾂炩�ɂ��� �����[�U�[�W���C���ɂ��A��Όn�̑��݂͊m���ƂȂ��� ���āA�Ȃ������w�҂��}1�̌��̐i�s���x�����邩�Ƃ����ƁA���Θ_�̍��{�����ł�����ꑊ�ΐ����������邩��ł��B�������A���̌���������Ă��邱�Ƃ́A��L����Ŏ����ꂽ�ʂ�ł����A����ɂ��̌����������Ɋ�Ȃ��̂ł��邩�́A ���u���ΐ������v�ɂ܂�����̏�Ȃ����j�̌o�܂𖾂炩�ɂ��� �ŏڂ����q�ׂ܂����̂Ō��Ă��������B ���c�����͂��̒����u�Ȃ��Ƃ����鑊�ΐ����_�v�ŁA�����Ȃ��}1�̂悤�ɐi�s���邩�̗��R��������Ă��܂����A���̐��������ł��邱�Ƃ́A�u�Ȃ��Ƃ����鑊�ΐ����_�v�̏d��~�X�̎w�E�Ŏ������Ƃ���ł��B�����ŁA���ӂ��Ăق����̂́A�}1�̌��̐i�s�Ƃl�l�����̏c�����̌��̐i�s�Ƃ́A�{���I�ɓ����ł���Ƃ������Ƃł��B ���̂Ƃ���͋������悭��������Ă���A����䂦�Ɂu�Ȃ��Ƃ��E�E�v��p.45�Ń��[�U�[���u��p���Đ�������Ă���̂ł����A���ꂪ�S���̒ʂ�Ȃ������ƂȂ��Ă���̂͂܂������c�O�ł��B 100�N�O�Ȃ�A�����w�҂́A�}�N�X�E�F�����������݂Ȏ��Ɠ����l���łƂ炦�Ă��܂����B�u�d���g�͐�Όn����ɂ��ő���̂��v�ƁB �������A���ΐ����_���a�������������ŁA�}�N�X�E�F�����������Ԉ������Ղ̏�łƂ炦��悤�ɂȂ��Ă��܂����B ����́A����(����ɋ��)��O��I�ɂ˂��Ȃ��邱�ƂŎ��s����܂����B �����܂łŁA����3�d�̃~�X�̂���2�̃~�X��������Ă���̂ł������C�Â��ł��傤���B �܂��A�}1�ɂ����āA�^��ɕ����ꂽ���͂ق�Ƃ��͂��̂܂ܐ^��������ɐi�s����̂ɂ�������炸�A���ꑊ�ΐ��������犵���̖@���ɏ]�����悤�ɐi��(���Ɍ����Ă����悤�ɐi��)�ƂƂ炦�Ă��܂������Ƃ��܂���1�Ԗڂ̃~�X�B �����2�ԖڂƂ��āA�����}1�̂悤�Ɍ����i�s��(���̂Ɠ����̂悤�ɐi��)�r�n�̂悤�ȃx�N�g����`���̂Ȃ�A�c�����Ɖ������̑��x�x�N�g������������Ă���̂ł�����A�E�}�̂r�n�ł͑����͓��R�����傫���Ȃ�Ȃ���Ȃ�܂���B�Ƃ��낪�A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�r���n�̑傫�����̃x�N�g�����r�n�ł͒����x�N�g����`���Ă����Ȃ���A���x�͂����Łu�����x�s�ς̌����v�Ƃ������������������A���͂ǂ̌n�ɂ����Ă����Ȃ̂ŁA�E�}(�r�n)�ł̃x�N�g���̑傫���܂ł����Ƃ��Ă��܂������ƁA���ꂪ��2�Ԗڂ̃~�X�ł����B �}1��肃�łȂ��͖̂��炩�ł����A����͒P���ȃ~�X�Ȃ̂ł��B ���w�A�����w�ɂ����āA�u���x�x�N�g���̒����͑����ɔ�Ⴓ���ĕ`���v�Ƃ����̂͊�{�I�ȋK���ł�����B ����͏����Ȑ��w�̃~�X�ł���A��ɋ������ׂ����̂ł͂���܂���B �������A���낤���Ƃ��A�A�C���V���^�C���͎��Ԃ̒�`���˂��Ȃ��邱�ƂŁA�u����ŗ����͍����Ă���̂��I�v�Ǝ咣���A�����Ă���ɂ݂���x����Ă��܂����B�����Ă���͂����Ȃ��̂ł��B ���Ԃ��ǂ̂悤�ɔP���Ȃ���ꂽ���A��̓I�Ȍv�Z�ɂ��ẮA �����Ԃ̒x��̃J���N���𖾂炩�ɂ��� ���������������B ���āA����3�Ԗڂ̃~�X�ł��B ����(�����܂ł����ɁI)�A1�Ԗڂ̃~�X��2�Ԗڂ̃~�X���~�X�łȂ��}1�̌����v�̌��̐i�s�����������̂������Ƃ��Ă��A���̌����v�̎��Ԃ���X�̓���̕��ՓI�Ȏ��ԂƃC�R�[���Ƃ��Ă��܂������Ƃ��A�v���I�ȃ~�X�ł����B ���Θ_�̎��Ԃ��A����̕��ՓI�Ȏ��ԂƂ܂��������т��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A����܂ōĎO�q�ׂĂ����Ƃ���ł��B ���Ȃ킿 �u�����v�̎��ԁv���u����̕��ՓI�Ȏ��ԁv �Ƃ��Ă��܂������Ƃ��A��3�Ԗڂ̃~�X�������킯�ł��B�����I���B �ȏオ�A�`���ɂׂ̂�3�d�̃~�X�ł��B ���ΐ����_�́A���̂悤�ɂ��܂��܂ȃ~�X���܂�d�Ȃ��Ēa���������̂Ȃ̂ł��B�@ |
|
| ���j���������̃G�l���M�[��E������^2�����`�̌����ł͂Ȃ� | |
|
���q���e�⌴�q�͔��d�̃G�l���M�[�́A�L���Ȏ��d�������O2�́u���ʂƃG�l���M�[�̓������v�������ł���ƁA�]����茾���Ă��܂����B����͂܂�ő��Θ_�Ƃ������_�����������猴�q���e���ł������̂悤�ɂ��\������A���Θ_�̐������̌���I�؋��̂悤�Ɍ��`����āA����ɂ������Ă���̂͏��m�̂Ƃ���ł��B
�Ƃ��낪�A�����͈���Ă���̂ł��B �j����̋���ׂ����o�G�l���M�[�́A�ŏ��Ƀ}�C�g�i�[�ƃt���b�V�ɂ���ė��_�I�Ɍv�Z����܂������A����ɂ͑��Θ_�Ȃǂ܂������p�����ɂȂ���܂���(�d�C�|�e���V�����E�G�l���M�[�ɂ��v�Z�ł���)�B��ɂȂ��āA�ނ�́A���Θ_�̂d������^2��p���Ă������悤�Ȓl���ł�ƋC�Â����Ƃ������ƂȂ̂ł��B�d�C�|�e���V�����E�G�l���M�[�ł̌v�Z�͌���ł��\���ʗp���܂��B ���̎����́A����u���q���e�v(�R�c���ƒ�)��ǂ�ł͂��߂Ēm�������ƂȂ̂ł����A����́A���q�͔��d�⌴�q���e�́A���ΐ����_������������a���������̂ł͂Ȃ��I�Ƃ��������ׂ��������A��L�{�����p���������܂��B �m�����n 1938�N(���a13�N)12���X�g�b�N�z�����x�O�̐Â��ȓc�ɒ��Ń}�C�g�i�[�ƃt���b�V�����������悤�ɁA�E�������q�j���O������̒����q���z�����錴�q�j�͂��̒����q�̎����Ă����G�l���M�[�����炢��̂Ō��q�j�̃G�l���M�[�͏オ��A���q�j�͐U�����J�n����B ���̌��ʁA�^��������ɃX�^�C���̗ǂ������̃E�G�X�g�̂悤�ȁu���т�v�������A���̌��q�j�͂��т�����ɓ�̕����ɕ�����A���q�j�͊j�̂���܂܂̃s�[�i�b�c�̂悤�Ȍ`�ɂȂ�A��́u�ӂ���݁v��������B���q�j�S�̂̓v���X�ɑѓd���Ă��邩��A���̓�̂ӂ���݂̊Ԃɂ͓d�C�����͂ɂ��˗͂������A���݂��ɗ���悤�Ƃ���B �������j�͂ɋN������\�ʒ��͂����q�j�̕\�ʂɓ����Ă���A���ꂪ�j�̕\�ʐς��ŏ��ɂ��悤�Ɠ������ߊj��(�\�ʒ���)�̓s�[�i�b�c�^�ɂȂ������q�j��\�ʐύŏ��̋��`�Ɉ����߂����Ƃ���B�������j�͎͂��ߍ�p�������Ȃ��̂ŁA�j�͂ɋN������\�ʒ��͂́A��̂ӂ���݂����т��ʂ��Ă��������܂܂ł�����x�ȏ�ɗ���Ă��܂��ƁA�}���Ɏ�܂��Ă��܂�(���ߍ�p�݂̂Ȃ炸��������p��������d�C�����͂͂��قǎ�܂�Ȃ�)�B ���̎������s�[�i�b�c�^�����`�Ɉ����߂����Ƃ���\�ʒ��͂���̂ӂ���݂������������Ƃ���d�C�����͂ɑł������Ƃ��ł��Ȃ�������A�j�͂��т�����ɂ��ĂЂ���A�j�͕���̕����ЂƂȂ邪�A���̕����ЊԂɑ��݂���d�C������(�˗�)�͏����邱�Ƃ͂Ȃ��̂œ�̕����Ђ͐����悭���݂��ɔ��Ε����ɉ^���G�l���M�[�������Ă������ł����B���炩�ɓd�C�����͂��j����̌����ł���B���̓d�C�����͂͌��q�j���ɒ�����ꂽ�d�C�|�e���V�����E�G�l���M�[�Ƃ��ĕ\�����Ƃ��ł���̂ŁA�j������o�����G�l���M�[�̌��͂��łɊj���ɒ������Ă���d�C�|�e���V�����E�G�l���M�[�ł���B ���������Ċj����@�\�͉����A�C���V���^�C���̗L���Ȃd�������O2(���ʌ���)�Ȃǎg�킸�ɐ����ł���B���ꂪ�}�C�g�i�[�ƃt���b�V���^�����j��ŏ��̊j����̕����I���߂ł������B����Ƀ}�C�g�i�[�͂d�������O2���g���Ă��j�������������B���̐����͑�2�����E���u�����O�ɂȂ��ꂽ���̂ł���A�E�E�E�E�E ���̂悤�Ɋj����ɂƂ��Ȃ��G�l���M�[�́A�d�C�|�e���V�����G�l���M�[(�d�C�͂ƌ����Ă������ł���)�������ł���A��L�̍Ō�̕��̂悤�ɂd�������O2�ł̉��߂Ƃ����̂́A��ɂȂ��ĂȂ��ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��ł��傤�B �� ���q���e���y������A������u�̋ʁv���`�������B���q���e�̑��G�l���M�[�̖�35�p�[�Z���g�͔M�G�l���M�[�Ƃ��ĕ��o�����B�y������̉̋ʂ̒��a��100���[�g�����炢�ɂȂ�B�������O����̌��q���e�̉��x�́A���z�̓������x(���S���x����1000���x)�ɂ܂ŏオ��A���q���e���̂��̑S������������ɃK�X�ɂȂ��Ă��܂��B���������Ȃ�����ȂƂĂ��Ȃ����x�ɂ܂ŏオ��̂��H ���q�j1�̑傫���͂��悻10������1�Z���`���[�g���ł���B���̂悤�ȋɔ��Ȍ��q�j������1����ɕ���������2���d�q�{���g�̃G�l���M�[�����o�����̂ł���B2���d�q�{���g�̂����A����80�p�[�Z���g�ł���1��6000���d�q�{���g�͓�̕����Ђ��^�ԉ^���G�l���M�[�Ƃ��Č����B���q�j��������N�����Ɛ^����ɕ�����(���q�j)�����������B������1�̉^�ԉ^���G�l���M�[�́A���̎��ʂɑ��x�̃j����|���ē�Ŋ��������̂Ƃ��ĕ\�����(�����O2/2�F���͎��ʂ̒l��\�����͑��x��\��)�B ���������ĕ����Ђ̑��x����{�ɂȂ�Ƃ��̉^���G�l���M�[�͎l�{�ƂȂ�A���x���O�{�ɂȂ�Ɖ^���G�l���M�[�͋�{�A���x���l�{�ɂȂ�ƃG�l���M�[��16�{�ƂȂ�A�Ƃ�����ɑ��x�����������������ł��^���G�l���M�[�͌�������I��������̕����Ђ̃X�s�[�h�͕��ϕb��1000�����[�g��(����3600���L�����[�g���I)�Ō����x�̖�30����1�ł���B��������̕�����1�̉^���G�l���M�[�͂��̑��x(�b��1000�����[�g��)���j�悵���l�ɔ�Ⴗ��(1000�����j�悷��Ƃ����ɂȂ邩�H)�B���q�j1�������ہA���̓�̕����Ђ̉^�ԉ^���G�l���M�[��1��6000���d�q�{���g�Əo��͉̂E�̌v�Z�Ɋ�Â��Ă���B���̌v�Z�ɂ͂��łɑ��x���g���Čv�Z���Ă���̂ŁA�A�C���V���^�C���̎��d�������O2�͂��������g���Ă��Ȃ��B�E�E�E�E ���̂悤�ɁA���̂������^���G�l���M�[�������Ђ́A���̌㑽���̕����ЂƂԂ��葬�x��ω���������ȓd���g(�w���A�K���}�[���A�M��)����o���邱�ƂɂȂ�܂��B(�d�ׂ������x�^������Γd���g����o���A���̍ۉ^���G�l���M�[�͓d���g�̃G�l���M�[�ɓ]������Ă������Ƃɒ���) ���̂悤�ɍl����A�d�C�����͂���^���G�l���M�[�ւ����ēd���g���o�ւƂ������̓��ɂ����߂������Ƃ����R���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B�d�������O2�ł̉��߂́A�u���̂悤�ȉ��߂��\�ł���v�ƌ�ŒN�����C�t�����Ƃ����Ӗ����������Ă��܂���B���Θ_�Ƃ͂܂������W�̂Ȃ��Ƃ��납�猴�q���e�����܂ꂽ���Ƃ��킩��ł��傤�B �ȏ���A�̂��猾���Â��Ă����u���ΐ����_���a���������A�ŁA���q�̓G�l���M�[�̗��p���\�ƂȂ����I�v�Ƃ��������͊��S�Ɍ��ł���ƌ����܂��B����͑��ΐ����_�����Ă�(�܂��Ȃ��m���ɕ��܂���)�A���݂̌��q�͔��d�́A���ȏ��̋L�q�͑����C��������A�������Ȃ��Ɏ�����ƂȂ��A���̂܂c���Ă����Ƃ������Ƃł��B �u���q���e�v(�u���[�o�b�N�X)�́A�j�����������猴�������܂ł��A�Տꊴ���ӂ��^�b�`�ł����������̂ŁA�ǂ�ł���Ǝ��������j�̕���ɗ����Ă��邩�̍��o�����ڂ������Ă���閼���ł��B�@ |
|
| ���������x�̐V�p���h�b�N�X | |
|
���Θ_�ɂ����鑊�Α��x�Ɋւ��ẮA �������x�s�ς̌����ɂ�����V�p���h�b�N�X�̒� �Ńp���h�b�N�X������̖������w�E���܂������A�������x�̖ʂ�����V�����p���h�b�N�X�����o���܂����B��̂��̂Ɩ{���͓����ł����B ���ΐ����_�������܂Ő������Ǝ咣�������́A���̓��ɒ��킳��Ă͂������ł��傤���B �m�ڍׁn �}�̂悤�ɑ�n(�j�n�Ƃ���)�ɗ������l�ɑ��đ��x���Ŕ��ł��郏�V�`�ƁA����ɂ��̃��V�`�ɑ��Ă��̑��x�Ŕ��ł��郏�V�a������Ƃ��܂��B ���܁A������j�n�̒��ł̕��̂̉^���ƍl���A�l�ɑ��鑊�Α��x�����߂Ă݂܂��B�j�n�Ƃ�����̌n���ōl���Ă��܂�����A�l����݂����V�a�̑��x���͂�+���ƂȂ邱�Ƃ͎����ł��B���Ȃ킿�A�l�́A���V�a��������+���Ŕ��ł���Ɗϑ�����킯�ł��B���̏ꍇ����1�Ƃ��܂��傤�B ���āA���Ƀ��V�`���j�L�n�̑�\(�j�L�n�̌��_�ɌŒ肳��Ă���Ƃ���)�Ƃ��A����Ƀ��V�a���j�L�L�n�̑�\�ƌ��܂��B ����ƁA���x�͂j�n�A�j�L�n�A�j�L�L�n�Ƃ���3�n�Ԃ̉^����_����`�ƂȂ�A���ΐ����_�ł̌n�Ԃ̍������x�̌v�Z����A�l����݂����V�a�̑��x���́A ����(��+��)�^(1�{����/��^2) �ƂȂ�܂��B���̏ꍇ����2�Ƃ��܂��傤�B���̏ꍇ�A�l�́A���V�a������(��+��)�^(1�{����/��^2)�Ŕ��ł���Ɗϑ�����킯�ł��B ��Ȃ��ƂɂȂ�܂����B �Ȃ�ƁA��1��2�ŁA�l���猩�郏�V�a�̑��Α��x�����قȂ��Ă���̂ł��B �^���͈�ł�����A����͑S�����������킯�ŁA�܂��Ƀp���h�b�N�X���������Ă���̂ł��B��1��2�́A�����I�ɂ͑S�������ȏł��邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B (���킸�����Ȃ̒��ӂł����A1�����R���Θ_���g���Ă̋c�_�ł��̂ŁA���̓_�͌�����Ȃ��ł��������ˁB) ���̂悤�ɂȂ�疳���Ȑݒ�������Ƃ��A���ΐ����_��K�p����ƁA���R�Ɍ���I�ȃp���h�b�N�X���������Ă��܂����ƂɂȂ�܂��B���̃p���h�b�N�X�͑S���v���I�ŁA�����]�n�͂Ȃ��悤�Ɏ��̖ڂɂ͂���̂ł����A�F�l�͂ǂ̂悤�ɍl������ł��傤���B���̃p���h�b�N�X���u�������x�̐V�p���h�b�N�X�v�Ɩ��t���A�u�����x�s�ς̌����ɂ�����V�p ���h�b�N�X�v�ƂƂ��ɍ���l�X�ɋc�_����邱�Ƃ�]�݂܂��B (����) �Ȃ��n�Ԃł̍������x����L�̂悤�Ȍ��ʂɂȂ�̂��A�O�̂��ߏ��������Ȍv�Z�Ŏ����Ă����܂��B �m�������Α��x�̌v�Z�n ��2�̏ꍇ�A�@���ꑊ�Θ_�ɂ��A�j�n�Ƃj�L�n�̕ϊ��͎��̃��[�����c�ϊ��Ō���Ă��܂��B ������(���|����)�^��(1�|(��/c)^2)�A�@���������A�@�@���������A�@�@������(���|�����^��^2)�^��(1�|(��/c)^2)�@�E�E�E�E1 ���l��K�L�n��K�L���n�̊Ԃ̕ϊ��́A���̂悤�ɂȂ�܂��B ���L�L��(�����|������)�^��(1�|(��/c)^2)�A�@���L�L�������A�@���L�L�������A���L�L��(�����|�������^��^2)�^��(1�|(��/c)^2)�E�E2 2�̉E�ӂ�1�������Đ�������ƁA ���L�L���m���|((���{��)�^(1�{�����^���O2))���n�^��(1�|(1�^��^2)((���{��)�^(1�{�����^��^2)))�E�E�E3 �ƂȂ�܂�(���L�L�͗����܂����A�ȉ��̌��ʂ͓����ɂȂ�܂�)�B ���āA�j�L�L�n�̂j�n�ɑ��鑬�������Ƃ���ƁA�j�L�L�n�Ƃj�n�̊Ԃ̃��[�����c�ϊ��͎��ƂȂ�܂��B ���L�L��(���|����)�^��(1�|(���^��)�O2)�A�@���L�L��(���|����)�^��(1�|(���^��)^2)�E�E�E4 3��4�̂��L�L�͓������Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A��r���邱�Ƃɂ��A ����(���{��)�^(1�{�����^���O2) �ƂȂ�A��2�ł̍������x�������܂�܂��B�@ |
|
| ���u���ΐ������v�ɂ܂�����̏�Ȃ����j�̌o�܂𖾂炩�ɂ��� | |
|
���ꑊ�ΐ������^��ʑ��ΐ������Ƃ����������w���̗p���Ă����ߒ��߂�ƁA���炩�ɂ��������Ǝv���_������������܂��B�ȉ��A�v�����܂܂ɋ^��_���q�ׂĂ����܂��B
�m�����n �܂����ꑊ�ΐ������Ƃ͉����H�����Ă݂܂��傤�B �u���ΐ����_�̍l�����v(����d�M��)�ɂ́A���̌��������̂悤�ɕ\������Ă��܂��B ���ꑊ�ΐ����� �u�������ɓ����x�^�������Ă��邷�ׂĂ̊����n�ɂ����āA���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�܂����������`�ŕ\����A�����̊����n�̂Ȃ�������ʂȂ��̂�I�яo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �����Œ��ڂ��ׂ��́A�u�E�E�E�E���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�܂����������`�ɁE�E�E�v�́u���ׂẮv�Ƃ������t�ł��B �A�C���V���^�C���͓��ꑊ�Θ_�\���������A��{�I�����@���́A�S���ŎO�����ł����B 1 �j���[�g���̉^���@���A2 �j���[�g���̖��L���̖͂@���A3 �}�N�X�E�F���̓d���C�w�̖@�� ���̎O�ł��B �����A���̌������{���ɐ��������̂Ȃ�A��̎O�̖@�����A���ꑊ�ΐ����������Ă��邱�ƂR�ؖ����Ȃ���Ȃ�܂���B�����āA�悭�����̋��ȏ��ŏ�����Ă���悤�ɁA1�̉^���@����3�̓d���C�w�́A1����ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ���ƁA�������Ƀ��[�����c�ϊ���p����ΑS�Ă̊����n�ɂ����Ă܂����������`�ɕ\�����邱�Ƃ��ł��܂��B �A�C���V���^�C����1��3�ł���ɐ��������킯�ł��B���̎��_�ŁA1�̃j���[�g���͊w�́A���ꑊ�ΐ����_�Ƃ����͊w���_�̋Ɍ��Ƃ��Ă̈Ӗ��������ƂɂȂ�܂����B �������A2�̖��L���̖͂@��(�d�͗��_)�����́A�������ꑊ�ΐ������ɂ��ƂÂ��`��(���Ȃ킿���[�����c�ϊ��s�ς̌`��)�����ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���Ȃ킿�A�����ւ��Ɏ��s�����̂ł��B ���āA���̎��s�����Ƃ��������ɒ��ڂ���K�v������܂��B �ʏ�Ȃ�����ŕ����w�҂́u���ꑊ�ΐ������͊Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����H�v�ƍl����̂����ʂł���A�u�����w�ł͂���Ȍ����͍̗p�ł��Ȃ��B�v�Ƃ���̂�����Ȏv�l�ɂ��ƂÂ����f�Ƃ������̂ł��B �Ȃ��Ȃ猴���Łu���ׂẮE�E�E�v�Ǝ咣���Ă���̂ł�����A�O�̂�����ł悢�ȂǂƂ������Ƃ��������͂����Ȃ�����ł��B�������A�ǂ������킯���K�^�ɂ������c���Ă��܂����B �����������ł��邱�Ƃ��������߂ɂ́u�d�͗��_�ł����ꑊ�ΐ������ɉ������`�̂��̂��ł����B�����Ă��̏d�͗��_�̐������������ꂽ�B����āA����ŎO�̑S�Ă̕����@���͂������ɓ��ꑊ�ΐ������������Ƃ��ؖ�����A���̌����̐������������ꂽ�B�v�Ƃ����`�őS���̏��F�Ȃ���Ȃ�܂���B ����������Ȃ��Ƃ͈�x���Ȃ������̂ł��B ����Ԃ��܂����A���ꑊ�ΐ��������w�̊�{�����Ƃ��邽�߂ɂ́A�܂����ׂĂ̕����@�������̌����ɑ������`�ɏ����ւ������̖@���͂������ɐ������Ǝ����Ă���A���̃X�e�b�v�ɐi��ł����Ȃ���Ȃ�܂���B �������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ꂽ���Ƃ��Ȃ������B �Ȃ��A���̂��Ƃ��d�v�����邱�ƂȂ��A�����w�҂͐�ւƐi��ł��܂����̂��H���ɂ͕s���łȂ�܂���B ���̂��Ƃ������ɐ�i�Ƃ������Ƃ́A���ꑊ�ΐ������͈�x�����̐����������j�I�Ɏ����ꂽ���Ƃ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B ��x�������ꂽ���Ƃ��Ȃ��̂ɁA���̌��������㕨���w�̊�{�����Ƃ��ČN�Ղ��A���̋�̓I�K���h���[�����c�ϊ��s��(����)���h�����ׂĂ̕������_�ɗv�������B �����������Ă���Ƃ��������悤���Ȃ��B �����āA�A�C���V���^�C���́A���x�́A�n���ꋓ�ɉ����x�n�܂Ŋ܂߂��`�Ɋg��������ʑ��ΐ�����������ɍ��o��(���������̍l�@����ł��傤��)�A����ɂ��ƂÂ��d�͗��_����肠���Ă��܂��܂����B ��L�{�ɂ́A��ʑ��ΐ����������̂悤�ɕ\������Ă��܂��B ��ʑ��ΐ����� �u���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�C�ӂ̍��W�n�œ����`�ŕ\�����B�v �悭�l����ƁA�A�C���V���^�C���͂����ł����ɂ������Ȃ��Ƃ����Ă��܂��B ���̈�ʑ��ΐ������ł��u���ׂẮE�E�E�v�ƕ\������Ă��܂����A�����̂��ׂĂ̕����@�������̌����ɑ����Đ����������ւ����邩�ۂ��ȂǁA�܂�����������Ȃ������̂ł��B ���܂��܃A�C���V���^�C���͂��̌�����p���āA��ʑ��Θ_�Ƃ����d�͗��_����邱�Ƃɐ������܂������A�t�Ɍ����Ώd�͗��_����(���܂��ɁI)�������Ă��Ȃ��̂ł��B��ʑ��Θ_�͏d�͗��_�ł��B �ɂ�������炸�A�R�������m�߂����Ƃ��Ȃ������C�ō�肾���āA���ꂪ�������������������ł��邩�̂悤�ɁA�Ȃ��A�C���V���^�C���͎咣����̂ł��傤���H ��ʑ��ΐ������̐��������ؖ������̂́A���ׂĂ̕����@�������̌����ɑ����Đ���ɏ����ւ����S�Ă̗��_�̐������������ꂽ��ł������肦�Ȃ��̂ł��B �����āA���̐�������������Ă͂��߂āA���̌��������_�̊�b�Ƃ��č̗p���邱�Ƃ��������B���̎葱�����o���ɁA����ɂ��̌����𗝘_�̊�b�ɍ̗p���Ă͂����Ȃ��B�u���ׂĂ̕����@�����A�����x�n�܂Ŋg�����ꂽ�C�ӂ̍��W�n�œ����`�ɂ��܂������ւ���ꂽ�B�����āA���̏���������ꂽ���_�̐������������Ŋm�F���ꂽ�B�v�Ƃ����b�����������Ƃ�����܂���B���̏ꍇ���A���ꑊ�ΐ������̂Ƃ��ƑS���������o�����Ă���̂ł��B ����ŁA�Ȃ��u�����v�Ȃǂƌ�����̂ł��傤���H ����ɂ������Ȃ��Ƃ�����܂��B ��ʑ��ΐ������́A���ꑊ�ΐ�����������ʂ̌`�Ɋg���������̂ł�����A���͂����E�E�ɂ������K�v�͂Ȃ��A���ׂĂ̕������_�́A��ʁE�E�ɑ������`�ŕ\������Ȃ���Ȃ�܂���B�ɂ�������炸�A�d�͈ȊO�̗��_�ł́A�����w�҂��s�ό`���ɂ����Ă����͈̂�ʁE�E�̕��ł͂Ȃ��A�ǂ������킯����������E�E�̕�(���[�����c�ϊ����ϐ��̗v��)�Ȃ̂ł��B �S���s���ł���A�s���R�Ȃ��Ƃ�����Ă���Ƃ��������܂���B �A�C���V���^�C���́A��������ɉˋ�̌�������肾���Ă͂��̉ˋ�̌�������b�Ƃ������_������Ă����B ����قǁA�����w�̋K���E�K�͂Ƃ������̂������ԓx�͂���܂���B ����w�E�������Ƃ��A���㕨���w�ŁA�Ȃ����ɂ���Ȃ��̂ł��傤���H ����Ȃ��Ƃ͎��łȂ��Ƃ��A���ꂾ���ċC�t�����Ƃł��B�����炭�ߋ����l���̐l���C�t���Ă������Ƃł��傤�B�������A����������o���Ȃ��B�Ȃ����H ����́A���㕨���w�ɂ����ăA�C���V���^�C���͐_�l�ɍՂ�グ���Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B �A�C���V���^�C���_�b�������w�S�̂��x�z���Ă��āA���̖��͂̈Î��ɂ�����A���ΐ����_�̋^��_�Ɋւ��Ă͊w�҂͎v�l���X�g�b�v���Ă��܂�����ł��B���܂����ڂ���������ƊJ���ăA�C���V���^�C���̂���Ă������Ƃ��ÂɌ��߂Ăق����Ǝv���܂��B ���� / �����Ŗ��ɂ����́A�A�C���V���^�C���̍l���o�������ꑊ�ΐ������ƈ�ʑ��ΐ������ł��B�K�����I�̑��ΐ������͌���ł����������̂ł��̂ŁA���̓_�͊Ԉ��Ȃ��ł��������B ���NjL ��ł͗��j�̏펯�ɏ]���ēd���C���_(�}�N�X�E�F��������)�̓��[�����c�ϊ��ɑ��ĕs�ςł���Ƃ��Ęb�������߂܂������A���͏]���ؖ��͌���Ă���A�}�N�X�E�F���������̓��[�����c�ϊ��s�ςł͂���܂���B���̏Ռ��̎�����<�}�N�X�E�F���������ɂ����郍�[�����c�ϊ��s�ϐ��ؖ��̌��̔���>�Ŏ����Ă��܂��̂ł������������B�@ |
|
| ���A�C���V���^�C���͕����w�̕����������S�ɊԈႦ�Ă��� | |
|
��Ɋ֘A���Ă���ɏq�ׂ������Ƃ�����܂��B
�ǂ̖{�ɂ��w�E����Ă��Ȃ��̂ŁA�����ŏq�ׂ����Ă��炢�܂��B����́u�A�C���V���^�C�������ΐ����_�Ƃ����������_���\�z����ۂɁA���̕��������ԈႦ�Ă��܂����v�Ƃ������Ƃł��B ��ł��q�ׂ܂������A���ꑊ�Θ_�����\���ꂽ�����̕����w�ɂ������{�I�ȕ����@���́A�O�����ł����B 1 �j���[�g���̉^���@���A2 �j���[�g���̖��L���̖͂@��(�d�͗��_)�A3 �}�N�X�E�F���̓d���C���_ ���̎O�ł��B ���Ă܂��b�̑O��Ƃ��Ēm���Ă����Ăق����̂́A�����w�̊�b�@���́A�傫����ɕ�������Ƃ������Ƃł��B �m1�n�^���̖@��(�u�͊w�v�Ƃ��Ă�A�͂�����������q���ǂ̂悤�ɉ^�����邩��T������w��) �m2�n�̖͂@��(�͂̐������̂��̂��������镪��) ��G�c�Ɍ����āA�����w�̊�b�@���͂��̓�ɕ����邱�Ƃ��ł���B ���āA�����ŏ��1�`3���A�ǂ���ɑ����̂������Ă݂܂��ƁA1�̓j���[�g���͊w�Ƃ��\�������悤�ɁA���R�m1�n�ɑ����܂��B 2 �́A���L����(�d��)���ǂ̂悤�Ȑ����̗͂���\���������̂ł�����A����͂������m2�n�ł��B 3 �̓d���C�w�ł����A����̓}�N�X�E�F������������b�Ƃ��闝�_�ł��B���̕������́A�d�C�̗́A���C�̗͂��ǂ̂悤�Ȃ��̂���\���������̂ł�����A�m2�n�ɑ����܂��B�A�C���V���^�C���́A���[�����c�͂��������čl�@�����Ă��܂����A���������ł����S�̓}�N�X�E�F���������ł����āA���̕������̒��̈�������c(���A��)����(���A��)���ϕ��`�N�[�����̖@���e��k�������^��^2�Ɗ��S���l�ł��邱�Ƃ�����킩��ʂ�A�}�N�X�E�F���d���C���_�́A�͂̐������̂��̂��������镪��m2�n�ƂȂ�܂��B �܂Ƃ߂܂��ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B 1 �́m1�n�ɑ����� 2 �́m2�n�ɑ����� 3 �́m2�n�ɑ����� ��������āA�s���l�́A���łɋC�t����Ă��邩������܂���B ���ꑊ�Θ_��������Ƃ��A�A�C���V���^�C���͓��ꑊ�ΐ������Ƃ���������p���āA1�̃j���[�g���͊w��3�̃}�N�X�E�F���d���C�w���A�܂����[�����c�ϊ��ɑ��ċ���(�s��)�Ƃ����`(���[�����c�ϊ��ŗ��_�̌`���ς��Ȃ��悤�ɂ��邱��)�ɓ���I�ɕ\�����悤�Ƃ����̂ł��B �������A����́A�������_�̍\�z�̕������Ƃ��āA���炩�ɊԈ���Ă��܂��B �Ȃ��Ȃ�A1�͉^���̖@���ł���A3�̖͗͂@���ł��̂ŁA�������_�Ƃ��ẮA�S���قȂ�������̂��̂ł��B ������A���ꑊ�ΐ������ł�����1��3���A���[�����c�ϊ����ς̌`�ɁA�킴�킴����K�v���A�K�R���ȂǂȂ��̂ł��B �������A�A�C���V���^�C���́A�Ȃɂ����Ⴂ�����̂��A�܂����̓����ꑊ�ΐ������œ��ꂵ�ĕ\�������B���ꂪ�A��ɑ傫�ȉ߂��ƌ��������R�ł��B���̌��ʁA�j���[�g���͊w�́A���ꑊ�Θ_�Ƃ����͊w�Ɋ܂܂�闝�_�ƂȂ�܂����B ���ꂵ�悤�Ǝv���̂Ȃ�A�܂����ꂷ�ׂ��́A2��3�A���Ȃ킿�d���C�w�Ɩ��L���̖͂@��(�d�͗��_)�̂͂��ł��B�d���C�͂͋ߐڍ�p�́A�d�͓͂������u��p�͂ƈقȂ����`���ŕ\������Ă��܂����̂ŁA�u������A�Ȃ�Ƃ�����I�E���ʓI�Ȍ`���ŕ\���ł��Ȃ����H�v�ƍl����̂������w�҂Ƃ��Ă͎��R�ȑԓx(���ꂪ�{���ɐ��������ǂ����͕ʂƂ���)�Ƃ������̂ł��B �Ƃ��낪�A�͊w�̕������ƃ}�N�X�E�F�����������A���ꑊ�ΐ������ł����ă��[�����c�ϊ��s�ς̌`�Ƃ��Ă��܂����B ���̕������̉߂����A���Θ_�a���ւƌq����d��ȃ~�X�ƂȂ����킯�ł��B ����ɁA�ւ������Ĉ������ƂɁA�����w�҂Ȃ炱���ŏq�ׂ����Ƃ��炢�����C�t���͂��̂��ƂȂ̂ɁA����ɂ��̓_����ɂ��Ȃ��̂́A�Ȃ��Ȃ̂ł��傤���H�����܂ŁA�A�C���V���^�C���ɉ�������̂͂Ȃ�Ȃ̂��B ���낻��A�C���V���^�C���ւ̉��������̕ӂɂ��Ă����Ȃ��ƁA�����ɑ傫�ȉЍ����c�����ƂɂȂ�܂��B ���ΐ����_�Ƃ����R�œh��ł߂�ꂽ���_���A�u�l�ލō��̕�v�ȂǂƏ̂��āA����̎q�������Ɉ����n���킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B�@ |
|
| ���������A���ʗ��A�^�L�I���A�^�C���}�V���A�o�q�p���h�b�N�X�̖��� �@���S���������� |
|
|
���ΐ����_�Ɋւ���b�ł́A�������A�^�L�I���A�o�q�̃p���h�b�N�X�Ȃǂ̖�肪���낢��Ƌc�_����Ă��܂��B
����͂r�e�I�ɂ��̂����v�f�������Ă��A�悭��ʏ��Ȃǂł��̉\�����_�����Ă��܂��B �������A���̂��ނ����Ȃ炢���̂ł����A�^�����ȕ����w�҂܂ł��^���ɋc�_���Ă���l�q�́u���Θ_���Ԉ���Ă���v���Ƃ����炩�ɂȂ������ƂȂ��ẮA����ɑς����������̂�����܂��B ���łɑ��Θ_�̎��Ԃ̓f�^�����ł��������Ƃ��������Ă��܂��̂ŁA����͂����̖��Ɍ���������ׂ��������܂��B �m�����n �܂��͂��߂ɁA���ԂɊւ���A�C���V���^�C���̎��s����������Ă����܂��B ���Θ_�ł́A���Ԃ������g���ē��ꑊ�ΐ������ƌ����x�s�ς̌����̂��ƂŒ�`���܂����A����ɂ���āA���Ԃ́A���Ƃ������̂̐����ɔ�������̂ɂȂ�܂����B ���ԂƂ́A�{������Ȑ����̂��̂ł͂Ȃ��̂ł����A�A�C���V���^�C���������ɂ���Ă��܂��A���̍I���Ȏ���ɂ݂�Ȃ��x����Ă��܂������Ƃ͂���܂ōĎO�q�ׂĂ��܂����B �����܂łŃA�C���V���^�C���͂��łɓ�̃~�X��Ƃ��Ă��܂��B �܂��A���ԂƂ͌����g���Ē�`����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��̂ɂȂ�������p���Ă��̂悤�ɒ�`���Ă��܂���(����ɂ͂��͗��R������܂��A��q)���Ƃ�1�Ԗڂ̃~�X�B ��ڂ́A���̒�`�Ɂu���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�Ƃ��������������������̗p�������ƁA���ꂪ2�Ԗڂ̃~�X�ł���܂��B ���āA�A�C���V���^�C���́A�Ȃ��A����ȋ����Ȃ��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������Ƃ����܂��ƁA�d���C�w�Ɨ͊w���_���A���ꑊ�ΐ������œ���I�ɕ\������Ƃ�����������j(�����ł��A�C���V���^�C���͊Ԉ����)�������ɐ��������邽�߂ɂ͎��Ԃ������邵���Ȃ��Ȃ�A��������炵�����������āA���Ԃ������g���Ē�`����Ƃ������Ƃ����������ł��B �u�G�[�e�����݂���Ȃ��͓̂��R���B���[�����c�̂悤�Ȑl�H�I�ȉ����ȂLj�؍l���Ȃ��ł悢�̂��I�Ƃɂ����A���ꑊ�ΐ������ƌ����x�s�ς̌����������l�����낵���I�v�Ƃ����𐬗������邽�߂ɁA�A�C���V���^�C����1905�N�̘_���̖`���ł킴�킴�u�͂āA�悭�l����ƁA���ԂƂ͂���ȂɎ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��v�ȂǂƐ�o���A�_���̍ŏ��Ɏ��Ԃ̒�`�������Ă���Ƃ����I���ȓW�J���l���܂����B ���ꑊ�Θ_�Ƃ����͊w���_�Ɠd���C���_��\���`���œ��ꂷ��ɂ́A���[�����c�ϊ������Ȃ��B�A�C���V���^�C���͓������łɔ��\����Ă������[�����c�ϊ��̌����ɁA���[�����c��Ƃ͑S���Ⴄ���[�g���炽�ǂ蒅�����������̂ł��B �G�[�e���Ƃ������̂ɒ��ڐG��Ȃ��`�ŁA��������ł������G�[�e���������܂�����������@�͂Ȃ����Ɩ͍����܂����B �����ē��ꑊ�ΐ������Ƃ�������ɍ��o�����R�̌�����p���Ă��̏�Łu���ԁv�����Œ�`�����������g���b�N��������Ƃ��܂��������ƂɋC�Â����̂ł��B�Ȃ����Ԃ�����p���Ē�`�������ƌ����܂��ƁA���[�����c�ϊ��̌����̒��Ɍ����x�����܂܂�Ă���̂ŁA�����ւ����Ă������߂ɂ́A����p���Ē�`����ق��Ȃ������킯�ł��B ���܁A�u�R�̌����v�Ƃ����Ђǂ��\����p���܂������A�Ȃ����̂悤�ɕ\������̂�(���ׂ��Ȃ̂�)�� ���u���ΐ������v�ɂ܂�����̏�Ȃ����j�̌o�܂𖾂炩�ɂ��� ��ǂ�ł��炦�킩��܂��B ���Ȃ킿�A�A�C���V���^�C���́A�G�[�e���Ƃ������̂ɒ��ڐG��邱�ƂȂ��A�Ȍ��ɂ�������ƃ��[�����c�ϊ��̌����ɁA�ǂ����Ă����ǂ蒅�����������B ���̂��߂ɂ́A�l�ނ����Ƃ��Ɩ��ӎ��̂����Ɏ������킹�Ă����u���ԂƂ͉F���ɋ��ʂɈ�l�ɗ���Ă�����́v�Ƃ����f�p�Ŏ��R�Ȗ��A�P���Ȃ��Ă����Ԃ����̂悤�ɒ�`��������������Ȃ������킯�ł��B �������A���̃A�C���V���^�C���̎��Ԃ��A����̉�X�̎��ԂƑS�����т��Ȃ����̂ł��������Ƃ́A�l�ގj��ɂ����錈��I�ȃ~�X�ƂȂ�܂����B���̂��ƂɊւ��ẮA���̕łł��ڂ����q�ׂĂ��܂��B �������v�̍l�@���瑊�Θ_�ɂ����鎞�Ԙ_�̊ԈႢ�������� ���Ē��X�Əq�ׂĂ��܂������A���ΐ����_�ł̎��Ԃ͎��̂悤�ɕ\���������̂ƂȂ�܂����B ���������^��(1�|v^2/c^2) ���銵���n(����l)����A���̊����n(�ʂ̉^�����Ă���l)������ƁA�u����̎��Ԃ�������肷����ł���悤�ɂ݂���A����������͂��݂��l�ł���A�ǂ�����^���v�Ƃ������Ɋ�Ȑ��E�ւƓ˓����Ă��܂����B ���ԂƂ����̂́A���ɂ킩��ɂ������̂ɂȂ����̂ł�(����p���āu���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�Œ�`����Γ��R�ł���)�B ��̎�����A���͌����x�����ɒ������Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ��āA�u����������Έ��ʗ����j���̂��H�^�C���}�V���͉\���H�^�L�I���͂ǂ����H�v�ȂǂƂ����l���łĂ���̂ł����A����ȐS�z�͖��p�ł��B���Ԃ�����p���āA�݂��ɖ��������u���ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�Œ�`����A���̂悤�ȋc�_��������Ȃ��Ȃ�͓̂�����O������ł��B ���������̖�� ���̂̑��x�͌����x�������Ȃ��ƂȂ����̂́A�A�C���V���^�C�������Ǝ��Ԃ�����Ɍ��ѕt���A���Ԃ��㎮�̂悤�ɕ\�����Ă��܂�������ł���A�������ꂾ���̈Ӗ���������܂���B�����x�������̐��̏�����x�ł��闝�R�Ȃǂ܂������Ȃ��̂ł��B�������������`��錻�ۂ͍��ア����ł��݂���ł��傤�B���̂��Ƃ͂��łɎw�E����͂��߂Ă��܂����B �����ʗ��̖�� �܂��A�����x������ƈ��ʗ����j��邩�H�Ƃ��������A�A�C���V���^�C��������ɏ㎮�̂悤�Ɏ��Ԃ�\���������炻���v�������ł����āA���ȏ�̃X�s�[�h�ɂȂ��Ă����ۂɈ��ʗ����j�ꂽ�肷�邱�Ƃ͂���܂���B�㎮�́A������v�l�ɂ��Y���ł���A�Ԉ���Ă���̂ł�����A�����S���������B ���^�C���}�V���̖�� ���Ԃ����R�ɂ����̂ڂ��^�C���}�V���͍��邩�H�Ƃ����×�����̖����A�������킷�悤�ň����ł����A���̓����́u�s�\�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����l�́A���Ԃ����̂̂悤�ɕ߂炦�����ł��B���Ԃ̗�����t�]�����邱�Ƃɐ�������Ή�X�͉ߋ��ւƖ߂��̂ł͂Ȃ����H�Ƃ����l����̂ł����A���̍l���͌��ł��B���Ԃ͕����I���̂ł͂���܂���B�l�Ԃ�����ɍl���o�����T�O�ł��B���ԂƂ́u�F���S�̂��ߋ����疢���ֈ�l�ɗ������́v�Ƃ����×�����̐l�ދ��ʂ̖��ɂ����Ȃ��̂ł��B���Θ_�ŁA���Ƃ������̂Ǝ��Ԃ����т������߂ɁA���Ԃ͕K�R�I�Ɏ��̂Ƃ��Ă̐��������тĂ��܂��܂����B����l�����Ԃ������̂̂悤�ɍl���Ă��܂��K��������̂��A���Θ_���e�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ԂƂ������t���o�����ɁA�u�Ȃ������̐i�s�͋t�]���Ȃ��̂��H���ڂꂽ���͂ǂ����Ď��R�ɃR�b�v�ɖ߂�Ȃ��̂��H���̂悤�Ȍ��ۂ͂Ȃ��N����Ȃ����H�v�Ɩ₤�̂Ȃ�A����͕����I�Ȗ₢�Ƃ����܂����B���ԂƂ́A�l�ނ����Â̐̂��u�ߋ����疢���ֈ�l�ɗ���Ă������́v�Ƌ��ʂ̃��[���Ƃ��Ė��Ă������̂Ȃ̂ł�����A�u�Ȃ��t�]���Ȃ��̂��H�v�ȂǂƖ₤�͈̂Ӗ��̂Ȃ����Ƃł���Ƃ킩��ł��傤�B ���o�q�̃p���h�b�N�X�̖�� ����͂܂��ɁA���ΐ����_�ł̎��Ԃ̒�`���̂��̂��甭���������ł��B�A�C���V���^�C�������Ԃ�����p���Ċ�����������̌������g���Ē�`�������Ƃ���A�K�R�I�ɐ�����p���h�b�N�X�ł��̂ŁA���ꂪ���菊�Ƃ������Ԃ̒�`���̂��Ԉ���Ă������Ƃ������������ƂȂ��ẮA�u�o�q�̃p���h�b�N�X�́A�p���h�b�N�X���̂��ԈႢ�ł������B���ۂ͂���Ȃ��Ƃ͋N����Ȃ��B�c�_���邱�Ǝ��̂����Ӗ��Ȗ��ł���B�v�Ƃ������_�ɂȂ�܂��B���̖��Ӗ��Ș_�����A20���I�̐l�X�͉��X�Ƒ����Ă����킯�ł��B�Ȃ�Ƃ������Ԃ̖��ʌ����ł��傤�I �� �ȏ�̋c�_���܂Ƃ߂܂��ƁA�A�C���V���^�C���̍l�������ԂƂ����͉̂R�ł������A�Ƃ������Ƃł��B���̎�������Ȏv�l�ɁA20���I�̐l�ނ͐U��ꑱ�����킯�ł��B�@ |
|
| �����Ԃ̒x��̃J���N���𖾂炩�ɂ��� | |
|
���Θ_�̎��Ԃ͉R�ł���A��X�͂�����x����Ă������Ƃ���ŏq�ׂ܂������A���Θ_�ł͂ǂ̂悤�ɂ��āu���Ԃ��x���v�Ɛ�������Ă���̂��A���̋\�Ԃɖ������J���N���������Ő������܂��B
�m�����n ���}�́A�u���ΐ����_�v(���쓟�v��)�ɂ�������v�̐}�ł��B �����n�r���ɌŒ肳�ꂽ�C���������Ɍ������������鑕�u���l���A�r���͊����n�r�ɑ��Ă������ɑ��x�u�œ����Ă���Ƃ��A���̌��ۂ��r����ϑ����Ă��܂��B ���܁A��̍��}���r���n�}�A�E�}���r�n�}�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��B �n�r�����n�r�ɑ��Ăǂ�ȑ��x�ő����Ă��銵���n�ł������Ƃ��Ă��A�^��ɔ��˂��ꂽ���͂҂����苾�l�ɓ��B����A�Ƃ��������ׂ����Ƃ������Ă���̂���}�ł��B ���ꑊ�ΐ����_�̖{���́A���̐}�őS�ĕ\������Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��قǏd�v�Ȑ}�ł��B ��̓I�Ɍ����A���͕��̂Ɠ����悤�Ȑi�s�����A��������Ȃ��ƂɁA���̂̏ꍇ�Ƃ͈���āu�x�N�g����������āA�r�n�}�łr���n�}���x�N�g���̒����������Ȃ��Ă���̂ɁA���̃x�N�g���̑傫���́A�ˑR���l���ł���v�ƌ����Ă���̂��A��}�ł��B ���̐}�ł́A�����w�A���w�̋K������������Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��Ă��������B��̂悤�ɁA�������̂Ɠ����悤�ɐi�s����Ȃ�AS�n�}�̍������ꂽ�x�N�g���́AS���n�}�̃x�N�g�����������`����Ă���̂ł�����AS�n�}�̃x�N�g���̑傫���͂��ł���͂�������܂���B���R��(���O2�{v^2)�ƂȂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �S���������Ȑ}�ł��B �Ȃ����Θ_�ł́A����Ȃ������Ȑ}��`���̂��H����A�`����������Ȃ��̂��H ����́A�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�𗼗������邽�߂ɂ́A��̂悤�ɕ`����������Ȃ�����ł��B ���ꑊ�ΐ������́A�j���[�g���͊w�ɂ�����K�����C�̑��ΐ��������A�d���C�w�ɂ��K�p�ł���Ƃ������̂ł�����A���͓��R���̂̂悤�ɐi�s����Ǝ咣����������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�ł�����A�����w�҂͏�}�̂悤�ɕ`���̂ł��B �܂��A�����x�s�ς̌����́A�u�ǂ�Ȋ����n���猩�Ă������x�͈��l���ł���v�Ǝ咣������̂ł�����A��͂�A���̌����𐬗������邽�߂ɂ́A�r�n�}�Ńx�N�g�����r���n�}��蒷���`���Ă����Ȃ���A�ˑR�r�n�}�ł��̑傫�������Ƃ���Ƃ�������ȕ`���������邱�ƂɂȂ�܂��B �A�C���V���^�C���́A�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�̗Z�����͂������킯�ł����A���͂��̓�͂��݂��ɐ����̂��Ƃ��咣���Ă���(�������Ă���)�A�Z�������邱�Ƃ́A�_���I�ɕs�\�Ȃ̂ł��B �s�\���\�Ƃ��邽�߂ɂ́A��Ȍ�����T�O�����ĉ������͂���(�떂����)���肪����܂���B�A�C���V���^�C���́A���ԂƋ�ԂƂ����A�l�ނ��×���莝�����킹�Ă������R�ȊT�O���A���Ȃ��Ȃɂ��Ă��������Ă��܂����B �u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v���A�݂��ɖ������Ă���A���e��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A �������x�s�ς̌����́A���Ԃ�O��ɂ������̂ł��� �ŏؖ����Ă��܂��B ���āA��}�ŁA���Ԃ��ǂ̂悤�Ɋ�Ȃ��̂ɂȂ邩�����Ă݂܂��傤�B �������狾�܂ł̋������k�Ƃ��܂��B �r���n�ł́A��������o��������̋��l�ɓ��B����܂ł̎��Ԃ�1�́A���R ��1���k�^���@�E�E�E�E1 �ƂȂ�܂��B �r�n����r���n���݂�ƁA��̉E���̐}�̂悤�ɂȂ�̂ŁA��̋��l�ɓ��B����܂ł̎��Ԃ�2�́A�s�^�S���X�̒藝���A(���E��2)^2��(���E��2)^2�@+�@�k^2�@�ł�����A t2���k�^��(��^2�@-�@��^2)��(�k�^��)�^��(1�@-�@��^2/��^2)����1�^��(1�@-�@��^2/��^2) �ƂȂ�A1�������Ԃ͒x��܂�(^2��2��̈Ӗ��ł�)�B ���ꂪ�A�����Ă���n���猩��ƁA����̎��v���������i�ނƂ������Ƃ̃J���N���ł��B �݂��ɖ��������u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�𗼗������邽�߂ɁA���Ԃ̒�`��ύX���A��Ȏ��ԊT�O������グ�A����ŃG�[�e���������������̂ł����B �����āA���[�����c��̐l�H�I�ȉ�����������@���A���Ȍ��ɂ�������ƃG�[�e����肪�����ł���Ƃ��Đ��� �����w�҂Ɏ����ꂽ�̂ł��B �������A�A�C���V���^�C���̔���������Ȏ��Ԃ��A�����̎��ԂƑS�����e��Ȃ����̂ł��邱�Ƃɓ����̊w�҂͋C�t�����A�u����T�O�̑�ϊv�I�v�ȂǂƊ��Ⴂ�������Ƃ�(���܂��Ɋ��Ⴂ�͑����Ă���E�E)�A�����w�j��ɂ����錈��I�ȃ~�X�ƂȂ�܂����B���̕ӂ̎���ɂ��ẮA �������v�̍l�@���瑊�Θ_�ɂ����鎞�Ԙ_�̊ԈႢ�������� �ɏڂ����L���Ă��܂��B ���ǁA����������̌����������ɗZ�������邽�߂ɂ́A�ǂ����ɖ����������邱�ƂɂȂ�̂ł����A���Ԃɂ��̂�����������̂ł��B�߂��ނׂ����Ƃł��B ���̊�Ȏ��ԊT�O��p���āA��Ԃ̕�����`�����������̂�����A��Ԃ܂ł��������Ȃ��ƂɂȂ����̂ł����B�������́A��������ԁE��ԊT�O��������ꑱ���Ă���̂ł��B ���lj� �u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v���A�݂��ɖ������Ă��邱�Ƃ́A �������x�s�ς̌����́A���Ԃ�O��ɂ������̂ł��� �ŏؖ��ς݂ł����A�ʎ��_������ؖ��ł��܂��B ���u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�����������Ă��邱�Ƃ̕ʏؖ� �m�ؖ��n ��̌����v�̐}��p���ďؖ����܂��B ��L�ł����łɌ��y�������Ƃł����A�u���ꑊ�ΐ������v���咣����A�������̂̉^���Ɠ����悤�ɂȂ�A���̐i�s�o�H�͏�}�̖��(�x�N�g��)�̂悤�ɂȂ�܂��B ���ɁA�u�����x�s�ς̌����v���咣����A�u�ǂ�Ȋ����n����������Ă����̑傫���͂��v�Ȃ̂ŁAS���n�}�ł��Ȃ��S�n�}�ł���͂�x�N�g���̒����͂��Ƃ���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B S���n�}�ł����AS�n�}�ł����ƂȂ��Ă���̂ł����A�����Ő��w��̉߂���Ƃ��Ă��܂��B �x�N�g���̒���������ĕ`����Ă���̂ł�����A���̑傫���͓��R����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B ���x�x�N�g���̕����͑��x�̕������A���̒����͑��x�̑傫����\���Ƃ����̂́A���w�E�����w�̊�{�K���ł��B �Ƃ��낪�A���̋K�������A��}�ł́A�x�N�g���̒������Ⴄ�̂ɂǂ�������Ƃ��Ă���̂ł��B ����́A�P���Ȑ��w�̃~�X�Ȃ̂ł��B �ł́AS�n�ł��x�N�g���̒����������Z������悢�̂ł͂Ȃ����H�Ƃ��āA(�����͂��̂܂܂Ƃ���)�Z�����ĕ`���ƁA���x�́A���̃x�N�g���}�ł́A���ꑊ�ΐ����������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B �u���ꑊ�ΐ������v���܂����Ă�A�K�R�I�ɏ�}�ƂȂ邪�A���̏̂��ƂŁu�����x�s�ς̌����v�𗧂Ă悤�Ƃ���ƁA���w�̋K���Ɉᔽ���Ă��܂��B ����ł͂ƁA�u�����x�s�ς̌����v���ɗ��āA�x�N�g���̒�����S�n�}��S���n�}�œ������`���ƁA���x�́u���ꑊ�ΐ������v���ǂ����Ă����藧���Ȃ��}�ƂȂ��Ă��܂��B ���ǁA����ɖ����Ȃ�����������͕̂s�\�Ƃ킩��܂����B ����āA�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�́A���������Ă��邱�Ƃ��ؖ�����܂����B �ؖ��I���B �������E�E�E����ɂ��Ă��A���w�Ƃ͋��낵�����̂ł��B����������}�ɂ��A�s�^�S���X�̒藝��K�p����ƁA��Ɏ������悤�Ɍv�Z�͂ł��Ă��܂��A���Ԃ��Z�o����Ă��܂��̂ł�����I�����������̂�匳�ɂ����ƁA���̐�̌��ʂ͂ǂ��܂ł����������A�������Ȃ��̂��o�Ă��܂��B���ΐ����_�̎��Ԃ�����ł���̂́A���͂���ȂƂ���Ɍ������������̂ł��B�@ |
|
| �������x�s�ϑ��Ƒ��ΐ������̖��������ؖ��ł̃A�C���V���^�C���̃g���b�N | |
|
1905�N�̘_���u�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v�ŁA�A�C���V���^�C���́u�����x�s�ς̌����v�Ɓu���ꑊ�ΐ������v�������Ȃ�����������ؖ���^���Ă��܂��B�������A���̖��������̏ؖ��ɂ́A�����g���b�N(���܂���)���g���Ă���A���̏ؖ��̓f�^�����ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��ȉ��Ŗ��炩�ɂ��܂��B
�m�����n �܂��A�͂��߂Ɂu���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�̒�`���L���܂��B �����x�s�ς̌��� �T�D�u�^�̌��̑����́A�����̉^����Ԃɖ��W�Ȉ��l���ł���B�v ���ꑊ�ΐ����� �U�D�u�������ɓ����x�^�������Ă��邷�ׂĂ̊����n�ɂ����āA���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�܂����������`�ŕ\����A�����̊����n�̂Ȃ�������ʂȂ��̂�I�яo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�v �A�C���V���^�C���́A���̇T�ƇU����{�I�Ȍ����Ƃ��č̗p�����ꑊ�ΐ����_�����グ�܂����B �Ƃ���ŁA�U���l���ɓ����ƁA�T�̌����x�s�ς̌����͂��̇V�̂悤�ɂ��\������܂��B �����x�s�ς̌����̕ʕ\�� �V�D�u�����Ȃ銵���n(�ϑ���)���猩�Ă��A���̑����͈��l���ł���B�v �A�C���V���^�C���̓��ꑊ�Θ_�́A��̇T�ƇU����b�ɂ�������Ă��܂��B�{�ɂ���ẮA�u�����x�s�ς̌����v���V�Ƃ��A�U�ƇV������ꑊ�Θ_���ł��Ă���Ə����Ă�����̂�����܂��B ���ӂ��Ăق����̂́A�V�͇U�́u���ꑊ�ΐ������v�̐������܂�ł���Ƃ������Ƃł��B ���[�����c�ϊ��̓��o�́A���낢��ȋ��ȏ��Ŏ�����Ă��܂����A�u�Ȃ��Ƃ����鑊�ΐ����_�v���Q�l�ɂ��A�܂����̓��o����ʂɍs���Ă���ʂ�ɍs���Ă݂܂��B �m�܂����[�����c�ϊ��̓��o����n �����n�ł���r�n���l���A���̂��A���A���������W�n���l���܂��B ����0�Ō�����u�p�b�ƕ��o���ꂽ�Ƃ��܂��B�o�_�Ɋϑ��҂����āA���̐l�̂r�n�ł̍��W��(���A���A��)�Ƃ���ƁA�g�ʂ��o�ɓ��B���鎞�������Ƃ���A���͌��_�𒆐S�Ƃ��锼�a���������̋��ʂɒB���܂�����A���̋��ʂ̕������́A ��^2����^2�{��^2�{��^2��(����)^2�@�@�E�E�E�E�E1 �ƂȂ�܂�(^2��2��)�B�ȒP�̂��߁A������݂̂��l����ƁA ��^2��(����)^2�@�@�E�E�E�E�E�E2 �ƂȂ�܂��B ���܂r���n�Ƃ���������̊����n���A�r�n�ɑ����������ɑ������Ői��ł���Ƃ��܂��B��������������0�łr�n�� �r���n�̌��_����v�����Ɖ��肵�܂��B �o�_�̊ϑ��҂̂r���n�ł̍��W��(�����A�����A����)�Ƃ��܂��B �����x�s�ς̌������A�r���n�ɂ���ϑ��҂ɂƂ��Ă������͂��ł�����A���̊ϑ��҂o�Ɍ������B���鎞���������Ƃ���ƁA�g�ʂ͂r���n�̌��_�𒆐S�Ƃ������a�������̋��ʏ�ɂ���܂��B��Ɠ��l�ɂ�������ōl����ƁA ����^2��(������)^2�@�E�E�E�E�E3 �����ŁA���ꑊ�ΐ��������A���߂�ϊ��́A�ꎟ���ɂȂ�͂��ł��B�Ȃ��Ȃ�A�r�n���猩�ĕ��̂̉^�������������^�������Ă���A�r���n���猩�Ă��A���������^�������Ă���悤�Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł��B ���̂��߂ɂ́A���߂�ϊ��͈ꎟ���ŕ\������Ă���悢���ƂɂȂ�܂�����A ��������(���|����)�@�E�E�E�E�E4 �ƁA�Ƃ肠�������肵�Ă݂܂��B�܂��A��Ԃ̓���������(��Ԃ̉E�����ƍ������ō��ʂ͂Ȃ����Ƃ���)�A4�̋t�ϊ����A���̂����ϐ��Ƃ��Ă��Ȃ��ϐ�����肩���āA������-���ɒu�������A ������(�����{����) �Ƃł��邱�Ƃ������킩��܂��B �܂��A�����x�s�ς̌������A����������0�Ɍ��_�˂��ꂽ���́A������ōl����ƁA ���@�������@�E�E�E�E�E�E5 �������������E�E�E�E�E6 �ƂȂ��Ă���͂��ł��B ���āA3�`6��4�̎�����A���A�����A���A��������������ƁA ����1�^��(1�|��^2�^��^2)�@�E�E�E�E7 �ƂȂ�A�L���ȃ��[�����c���q�����܂�܂����B ����ɁA3�`7��5�����A ��������(���|����)�@�E�E�E�E8 ��������(���|���E���^��^2)�@�E�E�E�E�E9 �ƁA���[�����c�ϊ��̎����ȒP�ɓ����o����܂��B���A���Ɋւ��Ă͗����܂��B �m���[�����c�ϊ����o�I���n ���āA��̓��o���@������킩��ʂ�A���[�����c�ϊ��́A�����x�s�ς̌����Ɠ��ꑊ�ΐ�������p���ē����ꂽ���Ƃɒ��ڂ��Ă��������B���[�����c���A���̕ϊ������̂Ƃ͈Ⴄ���@�ŁA�A�C���V���^�C���́A���̑S�������ϊ����ɂ��ǂ�����̂ł��B��������̊Ȍ��Ȍ����������瓱�����Ƃɐ��������킯�ł��B �A�C���V���^�C�����_�����Ŏ����Ă��铱�o���@�́A������������G�ł����A��͂��̌������瓱���Ă���{���I�ɂ͓����ł��B ��̓��o�ߒ����������U��Ԃ�܂��ƁA5�A6��2�A3�Ȃǂ́A�T�̌����x�s�ς̌����̕\����������͏o�Ă��Ȃ����ŁA����͓��ꑊ�ΐ������̐������܂V�̕\������o�Ă��鎮�Ƃ킩��܂��B �܂��A��̌��̐i�s�����ɂ������Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�A�r�n�ł����͂��̂r�n�̌��_�𒆐S�Ƃ������ʏ�ɂ���A���܂��r���n�ł����̂r���n�̌��_�𒆐S�Ƃ������ʏ�ɂ���E�E�ƂȂ��Ă���A����ł͑S�������I�ȃC���[�W���`���܂���B��ȕ����I�C���[�W�Ƃ������̂�������A�n���ƂɈႤ���Ԃ�����Ƃ�����ȕ��@�Ō떂�����������ď�̂悤�ɒW�X�Ɛ��w�I�E�L���_�I�Ɍv�Z��i�߂�ƁA�������[�����c�ϊ��܂ł��ǂ���܂��B ���̂悤�Ƀ��[�����c�ϊ��́A�����x�s�ς̌����Ɠ��ꑊ�ΐ������Ƃ�������瓱���ꂽ�킯�ł����A���̓�̌����́A���� �������x�s�ς̌����́A���Ԃ�O��ɂ������̂ł��� ���u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�����������Ă��邱�Ƃ̕ʏؖ� �Ŏ������ʂ�A�݂��ɖ������Ă���A�����𗼗������邱��(��������b�ɂ��ė��_���\�z���邱��)�͕s�\�Ȃ̂ł��B�s�\�ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���́A�V�������ԊT�O������Ƃ������@�ŁA����炪�������Ă��Ȃ��悤�Ɍ��������邱�Ƃɐ������܂����B �A�C���V���^�C���́A1905�N�̘_���u�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v�ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �u���āA�Î~�n���璭�߂��Ƃ��A�ǂ�Ȍ��ł��A���ɉ��肵���悤�ɁA���ꂪ�������œ`�d����Ȃ�A�^���n(���n)���炻��߂��Ƃ����A�����悤�ɑ������œ`�d����Ƃ������Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����x�s�ς̌����𑊑ΐ������Ɩ����Ȃ������ł���Ƃ������Ƃ��A�����ؖ����Ă��Ȃ�����ł���B�v ���̂悤�ɏq�ׂ�������ŁA�u�����x�s�ς̌����v�Ɓu���ꑊ�ΐ������v�������Ȃ������ł��邱�Ƃ��A���[�����c�ϊ��̎�(�_�����ł͌W�����|�����Ă��܂����{���I�ɓ���)��p���āA�ؖ����Ă���̂ł��I �����Ƀg���b�N������܂��B���C�Â��ł��傤���H �A�C���V���^�C���́A�u�����x�s�ς̌����v�Ɓu���ꑊ�ΐ������v���������ł��邱�Ƃ̏ؖ��ɁA���̓�̌������瓱���o�������[�����c�ϊ�����p���āA���̖����������ؖ����Ă���̂ł��B �����������ؖ�����̂ɁA�͂��߂ɓ�̌�������������(�������ł���)�Ɖ��肵�������瓱���������p���āA�����������ؖ����Ă���B ����́A���w�I�ȏؖ��ɂȂ��Ă��܂���B �[�I�Ɍ����A���̏ؖ��̍\���́A���̖����������ؖ�����̂ɁA�u��̌����͖������ł���v�Ƃ����ؖ����ׂ����_����������p���ďؖ����Ă���A�Ƃ����`�ƂȂ��Ă���̂ł��B �܂�A�u�����x�s�ς̌����Ɠ��ꑊ�ΐ��������A�������ł��邱�Ƃ��ؖ����悤�B�܂����̓�̌����͖������ł���Ɖ��肷��(1�Ƃ���)�B���āA��̌����͖������ł���B�Ȃ��Ȃ�A1�ʼn��肵�Ă��邩��ł���B����āA�ؖ����ꂽ�B�v�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ��\���ƂȂ��Ă���̂ł��B �ؖ��Ƃ�����A�f�^�����ł��B 1905�N�̗��j�I�_���́A�����ȃf�^�����ł��邱�Ƃ��͂����肵�܂����B �܂��A���[�����c�ϊ��Ƃ����T�O���́A�������瓱����Ă���ȏ�A���Ӗ��ȋ��\�̎Y���ƒf��ł��܂��B �A�C���V���^�C���̘_���́A����̋��ȏ��ɂ���悤�Ȃ�������Ƃ������������Ȃ���Ă��炸�A���Ȃ蕡�G�Ȍ`�ŏ�����Ă���A���̂��ߖ��_�̏œ_���ڂ₯�A��L�̖��������̏ؖ����A��قǒ��ӂ��Ă��Ȃ��ƁA���Ȃ��ؖ����Ȃ���Ă���悤�ȋC�ɂ������܂��B �������A�A�C���V���^�C���̏ؖ��̎��Ԃ́A��̂悤�Ȃ��̂ł���A����́u�ƂĂ��ؖ��Ƃ͌ĂׂȂ��v���̂ł������̂ł��B�떂�����A�B���͐����̐��E�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��悤�ł��B�@ |
|
|
���lj�
�A�C���V���^�C����1905�N�_���u�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v�̘_���W�J�́A���܂�ɂ���ł��B�����ł͏�ŏq�ׂ��ϓ_�����A���������傫�Ȏ��_���炨�����ȓ_���w�E�������킯�ł����A���̘_���̖`���ŃA�C���V���^�C���́A���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B �E�E�E���Ȃ킿�A�ǂ�ȍ��W�n�ł��A�������ɂƂ����Ƃ��A�j���[�g���̗͊w�̕����������藧�ꍇ(���̂悤�ȍ��W�n�́A���݂ł͊����n�ƌĂ�Ă���)�A���̂悤�ȍ��W�n�̂ǂꂩ�璭�߂Ă��A�d�C�͊w�̖@������ь��w�̖@���͂܂����������ł���Ƃ������_�ł���B���̐��_��1���̒��x�̐��m���ŁA���Ɏ����I�ɂ��ؖ�����Ă���B�����ł��̐��_(���̓��e�����ꂩ��h���ΐ������h�ƌĂԂ��Ƃɂ���)������Ɉ�������i�߁A�����w�̑O��Ƃ��ĂƂ肠���悤�B�܂��A����ƈꌩ�A�������Ă���悤�Ɍ����鎟�̑O����������悤�B���Ȃ킿�A���͐^���A�����̉^����Ԃɖ��W�ȁA�ЂƂ̒�܂����������������ē`�d����Ƃ����咣�ł���B�Î~���Ă��镨�̂ɑ���}�b�N�X�E�F���̓d�C�͊w�̗��_���o���_�Ƃ��āA�^�����Ă��镨�̂ɑ���A�ȒP�Ŗ����̂Ȃ��d�C�͊w�ɓ��B���邽�߂ɂ́A�����̓�̑O���ŏ\���ł���B�E�E�E ���̂悤�ɂ܂��_���`���ŁA�u���ꑊ�ΐ������v�Ɓu�����x�s�ς̌����v�𑁁X�ɓ������Ă��܂��B�u�ꌩ�A�������Ă���悤�Ɍ�����E�E�v�ȂǂƂڂ����������������Ă��܂����A�ꌩ�ǂ��납�A���̓�̌����́A���炩�ɖ������Ă��܂��B �������A�A�C���V���^�C������͂�u�ꌩ�E�E�v���C�ɂȂ�̂ł��傤�A�Ȃ�ƁA�����_���̇T���u�^���w�̕��v�̌㔼�ɂȂ��Ă悤�₭���[�����c�ϊ����o���Ă���A���̂悤�ɏq�ׂāA��̌������������ĂȂ����Ƃ������ؖ��ɂƂ肩����܂��B �E�E�E���āA�Î~�n���璭�߂��Ƃ��A�ǂ�Ȍ��ł��A���ɉ��肵���悤�ɁA���ꂪ�������œ`�d����Ȃ�A�^���n(���n) ���炻��߂��Ƃ����A�����悤�ɑ������œ`�d����Ƃ������Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����x�s�ς̌����𑊑ΐ������Ɩ����Ȃ������ł���Ƃ������Ƃ��A�����ؖ����Ă��Ȃ�����ł���B�E�E�E�E ��̕��͂̂��ƂŁA��̌������������邱�Ƃ������Ă���̂ł����A���ꂪ�A��R�̏ؖ��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͈��Ŏ������ʂ�ł��B �u�������Ă���悤�Ɍ����邪�A�������f�łƂ��Ė������Ă��Ȃ��I�v�Ǝ咣����Ȃ�A�{���́A�_���̖`���ł��ꂪ�������Ă��Ȃ����Ƃ��܂��^����Ɏ����Ȃ���Ȃ�܂���B�ɂ�������炸�A�A�C���V���^�C���́A�_�����ł��̂��₵���ȓ�̌������A���̖��������̏ؖ������Ă��Ȃ���ԂŎ��ԂƋ�Ԃ̒�`�ɓ��X�Ǝg���Â���̂ł��B���̊���A���������͂����������Ȃ̂ł��傤�H �����āA�_���T���̌㔼�ɂȂ��āA�������v�������悤�ɏ�̂悤�ɏq�ׂāA�悤�₭�ؖ��ɂƂ肩����B �ǂ����āA�㔼�ŏؖ����邱�ƂɂȂ����̂ł��傤���H(���₻�̂悤�ɂ�����Ȃ������̂��H) ���̗��R�́A�Ƃɂ������ɂ����[�����c�ϊ��̌����ɒH����Ȃ�����̏ؖ����ł��Ȃ����Ƃ��A�A�C���V���^�C�����g�悭�킩���Ă�������ł��B�����āA���̏ؖ����A��̌������������ĂȂ��Ə���ɉ��肵�ē����o�������[�����c�ϊ���p���Ė��������������Ƃ����f�^�����̏ؖ��ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͐��Ɏc�O�Ȃ��Ƃł��B �܂��A���̌����A�����̘_���̐R�������������Ȃ��������Ƃ��A���܂��炱��Ȃ��Ƃ������Ă��x���Ƃ͂����A�����w�̗��j�ɂƂ��Ă͒ɍ��̏o�����ƂȂ�܂����B ���ΐ����_�̓A�C���V���^�C�������Ȃ��Ă��a�����Ă������̂悤�Ȍ��������Ȃ���邱�Ƃ�����܂����A����Ȃ��Ƃ͐�ɂ���܂���B�l�ޑS�̂��A�C���V���^�C�����x����Ă��܂����B�_������o���ꂽ���_�ŁA�f�ŕs�̗p�ɂ��ׂ����x���̂��̂������̂ł��B �A�C���V���^�C���́A�ꌾ�ł͌����Ȃ��قǑ����̃~�X��Ƃ��Ă��܂����A�����Ŏw�E�������������̏ؖ����ӂɂ����Ă������ɋ����ȉ߂���Ƃ��Ă��邩���A�킩���Ă���������Ǝv���܂��B 21���I�������݁A���܂��ɂ���ȋ��\�ɂ����Ȃ����_��M�Ă��錻�㕨���w�Ƃ́A��̂ǂ�Ȋw��Ȃ̂��B�����āA�l�Ԃ̗ǎ����\���Ȃ���A���̐�A�l�ނ͂ǂ��܂ő��ΐ����_�Ɗ��Y���Ă�������Ȃ̂ł��傤���H�@ |
|
| �����ꑊ�ΐ������ւ̏d��^�f | |
|
�����ł́A�ēx�A���ꑊ�ΐ��h�����h���Ƃ肠���Ă݂܂��B���̌����̑��݂��A���ΐ����_�Ɏ~�܂炸�A�����w�S�̂�S���������Ȍ`�ɘc�߂Ă��܂��B���̑�R�̌������Ȃ��������w�̍��{�����ɐ������A���㕨���̕���������点�Ă��܂��B���̏d�傳�͂����狭�����Ă��������邱�Ƃ͂���܂���B
���āA�܂������������̂́A���ꑊ�ΐ������͂���܂ł����̈�x������(����)���ꂽ���Ƃ��Ȃ��Ƃ��������ׂ������ł��B���̂��Ƃ́A���Ŏ����Ă��܂��̂ŁA�������������B ���u���ΐ������v�ɂ܂�����̏�Ȃ����j�̌o�܂𖾂炩�ɂ��� �����ǂ�ł��炦�A���㕨���w�������ɂ���������Ȍ`�Ō`������Ă������ɐS�������邱�Ƃł��傤�B �A�C���V���^�C�����͂��߂Ă��̓��ꑊ�ΐ������Ƃ�����Ȍ����𐢂ɏo�����̂ł����A���̂悤�ȓ��e�ł��B ���ꑊ�ΐ����� �u�������ɓ����x�^�������Ă��邷�ׂĂ̊����n�ɂ����āA���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�܂����������`�ŕ\����A�����̊����n�̂Ȃ�������ʂȂ��̂�I�яo�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�v ��͂��ɂ����ւ�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ��܂��B �K�����I�̑��ΐ������ƍ��{�I�ɈႤ�̂͗͊w�ɏœ_�����Ă�̂ł͂Ȃ��A�u���ׂĂ̊�{�I�����@���́E�E�v�ƑS�����@���ɏœ_�ĂĂ���_�ł��B����Ȋ�Ȏ咣�́A���ΐ������Ƃ����u�K�����I�̑��ΐ������v�����m��Ȃ����������̊w�҂ɂ��Ă݂�A�܂��ɋ��V���n�̎咣�������̂ł��B ������O�̂��Ƃł����A�V������������o���ꂽ�Ƃ��A�����w������������Ƃ��č̗p���邩��ɂ͂܂���ɂ��̐������������I�Ɍ�����Ƃ���������ׂ��o�܂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͂����܂ł�����܂���B���w���ł��킩�闝���ł��B �Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���Ɠ��ꑊ�ΐ������Ɋւ������A�����Ȃ���Ȃ��܂܂�����ł����A�Ȃ������̊Ԃɂ������w�ɂ����ĔƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ������̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ČN�Ղ���悤�ɂȂ��Ă������̂ł�(�����w�̍��������̂��Ƃł��邱�Ƃ��悭�l���Ă݂Ă�������)�B �A�C���V���^�C������̌������o�������_(1905�N)�ł͂܂��h�����h�̏�Ԃł����Ȃ������B ��������̕����w�҂��A���̂��Ƃɂ͋C�t���Ă��āA����ȏd��Ȍ���(�����ł���)�͑��}�Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��I�I�ƌx�����Ă��܂��B �u���Θ_�v(�����w�j�������s��ҁA���C��w�o�ʼn�)�ɂ́A�����̗l�q��`����_�����������^����Ă��苻�����Ђ��܂����A���̒��ŁA�����̕����w��A�DH�D�aucherer(�u�[�w���[)�́A�u���̌����ڎ����I�Ɍ����邱�Ƃ͎��㖽�ߓI�ȗv���ł���B�v�Əq�ׂĂ��܂����A�܂������������咣�ł��B �܂��A�ʎq�_�̒a���Ɍ���I�ȉe����^���������̑�䏊�o��������(�v�����N)���u�E�E���̏��F�̖��͂��̗̈�̂��ׂĂ̗��_�I�T���ɂ����čŏd�v�Ȃ��̂Ƃ݂Ȃ���鉿�l������v�Ƃ��̊v���I�Ȃ̌����ɑ��u�����}���v�Ǝ咣���Ă���B �A�C���V���^�C����1905�N�ɒ����i�K�ł͂܂������A�\�z�̒i�K�ɂ����Ȃ������Ƃ������Ƃł��B �����āA�������炪�S���s���Ȃ̂ł����A�C���V���^�C�����������̌������������́A�����I������x���Ȃ���Ȃ��܂܁A���ꑊ�ΐ������Ƃ���(���������N���Ă͂Ȃ�Ȃ������Ƃ���)�A��ΓI�n�ʂ��m�ۂ��Ă������̂ł��B ������100�N�����Ă��A���܂��ɂ��̌����̐��������������l�͂��Ȃ��Ƃ����Ռ��̎����B ���ꑊ�ΐ��������A�����w�̍����̌����Ƃ��č̗p�������Ƃ�20���I�����w�ɂ�����ő�̎��s�ł����B �㐢�̐l�X����́u1���I�ɂ��킽���ĕ����E�ɌN�Ղ������ɂ���ȁh�������h�v�Ə��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B ���lj� ���ꑊ�ΐ����_�́A���̓�������w�������Ƃ��Đ��藧���Ă��܂��B 1 ���ꑊ�ΐ����� 2 �����x�s�ς̌��� 1 �̓��ꑊ�ΐ��������Ԉ���Ă��邱�Ƃ́A����܂ŗl�X�ȂƂ���(�E�E����1�`3)�Ő������Ă��܂����B 2 �̌����x�s�ς̌����Ɋւ��ẮA����������G�ł��B ���́u�����x�s�ς̌����v�ւ̉��߂̂����܂������A���ΐ����_�Ƃ�����_���c�点�錴���Ƃ��Ȃ��Ă���킯�ł��B�����ł����ꑊ�ΐ�����������I�ɂ���݂����Ă���̂ł����A����̕��G�ȓ_�����L�Ŗ����ɐ������Ă��܂��B���Ђ������������B �u�����x�s�ς̌����v�ł͂Ȃ��u���ꑊ�ΐ������v�ɒ��ڂ��ׂ��@ |
|
| �����𒆐S�ɐ����Ă��܂������ΐ����_ | |
|
�A�C���V���^�C�����g������킵������Ɂu���Θ_�̈Ӗ��v�Ƃ����̂�����܂��B���̒��ŁA���ԂɊւ��ĉ�����Ă���ӏ�������̂ł����A�A�C���V���^�C���̎��ԂƂ������̂ɑ���߂������Ăɕ������߂�����܂��̂ŁA����͂��������グ�܂��B
�m�ڍׁn �u���Θ_�̈Ӗ��v(�A�C���V���^�C����)�@�E�E�E���ΐ����_�́A���̓`�d�@���̏�Ɏ��Ԃ̊T�O���������A�Ȃ��̍����Ȃ��Ɍ��̓`�d�ɒ��S�I���_�I������^����Ƃ����āA�����Δ����B�������Ȃ��玖��͂��̒ʂ�ł���B���Ԃ̊T�O�ɑ��ĕ����I�ȈӋ`��^���邽�߂ɂ́A��X�̏ꏊ�ɂ�����W���������Ă邱�Ƃ��\�ɂ���悤�ȁA�����̑��삪�v�������B���Ԃ̂��̂悤�Ȓ�`�ɑ��āA�ǂ�Ȏ�ނ̑����I�ڂ��Ƃ�����͖��ł͂Ȃ��B�������Ȃ��痝�_�ɂƂ��ēs���̂悢�̂́A����Ɋւ��Ă���ꂪ�����m���Ȃ��Ƃ�m���Ă��鑀��݂̂�I�Ԃ��Ƃł���B�}�b�N�X�E�F���ƃ��[�����c�̌����̂������ŁA���̂��Ƃ́A�^�̌��̓`�d�ɑ��Ă����A���̍l�����邢���Ȃ錻�ۂ�������ɍ��x�ɐ��藧�̂ł���B �E�E�E �� / ���̏����̉p��ŏ��ł͂����炭1940�N�`50�N������ł͂Ɛ�������܂��B���{��ŏ��ł�1958�N�B �����ǂ�ŁA���̕��͒��̒v���I���������Ɏw�E�ł���l�͂����Ȃ��ł��傤�B ���������̐l�́A�u���[��A�������̓A�C���V���^�C���I�v�ȂǂƎv���Ă��܂��Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B �l�ԂɂƂ��Ă����Ƃ��킩��Â炢�h���ԁh�Ƃ������̂ɖڂ����A1���I�̂��̊ԁA�l�ނ��x���Â����A�C���V���^�C���́A�����Ȃ�ʍ��\�t�ł������ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B �㕶�ɁA�A�C���V���^�C���̍l�����h���ԁh�̈Ӗ������ĂɋL����Ă��܂��B �u���̓`�d�@���̏�Ɏ��Ԃ̊T�O���������E�E�v�Ƃ����Ӗ��́A�ȒP�ɂ����u�^�̌����x����p���Ď��Ԃ��`����v�Ƃ����Ӗ��ł��B�v���I�Ɍ���Ă���̂͂����ł��B �h���h�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���H ���Ƃ́A���́h�����h�ł���A�u1�b�ԂɌ����^��i�ދ����v�Ƃ��Ē�`�������̂ł��B �܂�A ����299863381m/s�E�E�E�E�E�E�E1 �ł��ˁB �̂���h���x�h�Ƃ����̂́A ���x=�m�����n�^�m���ԁn �ŕ\����Ă��܂����B�@ ������A�A�C���V���^�C���́A�h���ԁh�x����p���Ē�`�����̂ł��B(�����Łu�͂��v�ƋC�Â����l������ł��傤)���������Ǝv���܂��H ���Ԃ������x����p���Ē�`����ɂ́A���̑O�Ɏ��ԂƂ������̂��������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Ȃ��Ȃ炃�Ƃ�1�̋����^���Ԃŋ��߂�����̂�����ł��B �A�C���V���^�C���o���ȑO�̑f�p�Ȏ��ԊT�O�ŔF������Ă��������x����p���Ď��Ԃ��`����Ƃ�������I�_���~�X������Ă���̂ł��I ���̔n���n�������A������������������Ɩڂ����J���Ă݂Ă�������(�����Đ^�����Ȏ��Ԃ��A��Ȏ��Ԃɕς�����I) �A�C���V���^�C���̂�������Ƃ́A�܂������̃C���`�L�������Ƃ킩��ł��傤�B ����A�w�E�������Ƃ́A�N�w�҂̐�㓇�뎁��������Ɏ咣����Ă�����e�Ɠ����Ǝv���܂��B�u�A�C���V���^�C���̎��Ԃ̒�`�͏z�_�ňӖ����Ȃ��v�Ƃ������̂ł��ˁB�����N�w�҂����猩����ꂽ�Ƃ����قǂ̂��̂ł��Ȃ��āA���܌������悤�ɂ�����Ƃ̎w�E�ŒN�ɂł������ł�����̂ł��B�u�Ӗ����Ȃ��v�ǂ��납�A��ɂ���Ă͂Ȃ�Ȃ��~�X���A�C���V���^�C���͔Ƃ��Ă��܂����̂ł��B ����ɂ��Ă��A�Ȃ�����ȊȒP�Ȃ��ƂɁA�������͂�������x����Ă��܂����̂ł��傤���H ����͂��Ԃ�A�����x������ɂ��Ƃ��������Ă������߁A�Ǝ��͎v���Ă��܂��B ���ȂǂƂ����L���ɂȂ�̈Ӗ�������܂���B���Ƃ́h299863381m/s�h�ł���A����������A�˂Ɂh299863381m/s�h�ɒu�������ēǂ܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł��B �������A�֗��Ȃ��̂�����A�������A���A���A�E�E�E�Ƃ�����ŏ����Ă��邤���ɁA��������ɂȂ�h���^���h�Ƃ����P�ʂ̈ӎ�������Ă��܂��āA�A�C���V���^�C���������ȃ~�X��Ƃ��Ă�����ɋC�Â��Ȃ������킯�ł��B ���ł͂Ȃ��A�h299863381m/s�h�Ƙ_������������Ă�����A���ΐ����_�͂����炭�a�������A1���I�ʂɂ����ɍς̂ɂƉ���܂�ĂȂ�܂���B ���Ƃ����L����P�ɂ��Ă��������������̂����ΐ����_�ł������Ƃ����܂��B ���N�Ƃ����悻�҂��A�������̉��l�ł��������ԁE��Ԃ��A���̃N�[�f�^�[�Œǂ����A���������������f���ƕ������̒��S�ɋ������Ă��܂������̂�����A���Ԃ����Ԃ���͓z��ɐ��艺����A�Ȃ����c�߂��Ă�������������A�ǂ��܂ł������Ȃ�ɂȂ��Ă������̂ł����B ���ꂪ�A20���I�̑��ΐ����_�̕��ꂾ�����̂ł��B�^���ł���Ƃ��낪�߂����ł��ˁE�E�E �Ƃ���ŁA��Łu�E�E�E�����Δ����B�v�ƃA�C���V���^�C���������Ă��܂����A�����͑��Θ_��ᔻ����E�C����^�����Ȋw�҂����������̂ł��ˁI ���Ƃ͑�Ⴂ�E�E�E ���NjL ��ł́A���Ԃ̂��Ƃ��q�ׂ܂������A���ΐ����_�́A���ԁE��ԊT�O�����{�I�ɕϊv�������_�ł��B���Ԃ݂̂Ȃ炸�A��ԊT�O�܂ł��ς��Ă��܂��܂����B�A�C���V���^�C���́A���Ƃ������̂�p����(��Ύ�����)�A���ԁE��Ԃ��Ē�`���Ă������̂ł����A����͂ł��Ȃ����k�������̂ł��B ��ԂɊւ���A�A�C���V���^�C���̌���I�ȃ~�X�������܂��傤�B ���x=�m�����n�^�m���ԁn�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E2 2 �̂悤�ɏ����A�����C�t���ł��傤�B ��Ԃ������x����p���Ē�`���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A���(�����̊T�O�A���̑����)�x����p���Ē�`����ɂ́A���̑O�ɋ�ԊT�O�����m�ɕ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł�(2�����Ă��������I)�B�ɂ�����炸�A�A�C���V���^�C���o���ȑO�̑f�p�ȋ�ԊT�O�ŔF������Ă��������x����p���Ă܂���Ԃ��`����Ƃ�������I�~�X��������̂ł��I(�����āA��Ԃ̕��܂Ŋ�Ȃ��̂ɂȂ�܂���) �ǂ��ł����H ���ΐ����_���A�Ȋw���_�Ƃ��Ă̎��i�̂Ȃ����_�ł���Ƃ킩�����ł��傤�B����ɂ��Ă��E�E�E�l�ԂƂ����̂́A���Â���ł��B���Θ_�̂��Ƃ�S���m��Ȃ��l���A��̐�����ǂ߂A�����Ɂu���������ȁv�Ƃ킩��܂��B�������A�u20���I�ő�̈̋ƁI����T�O��ϊv�����V�˂̗��_�I�v�Ƃ����W��ƂƂ��ɑ��Θ_���w�l����̐�������ƁA�Ƃ���ɖ�̂킩��Ȃ����Ƃ������o���E�E�E�E������āA�Ȃ��Ȃ̂ł��傤�H�S���w�̊i�D�̃e�[�}�ł́H�@ |
|
| ���H�w�ҁA�Z�p�҂͊����ɒm���Ă��� | |
|
�u���[�U�[(Laser)�v(����V��)�Ƃ����{�����Ă�����A����d��ȋL�q�������܂����B���[�U�[�W���C���̌�����������镶���̋L�q�Ȃ̂ł����A���̂��̂ł��B
�E�E�E���Ƃ��A������50Hz�܂Ŋϑ��\�Ƃ���ƁA��=50cm�Ƃ��ă���10^-5 rad/s�̌��܂ő��肪�ł���B���̕��@��p����ƁA�n���̎��]���x������ł���݂̂Ȃ炸�A�F���̒��ł̒n���̉�]���������肷�邱�Ƃ����\�ƂȂ��Ă����B �ʏ�ł͌��߂����Ă��܂������Ȃ��̂킸���ȋL�q�̒��ɁA���Θ_�̉R��\�����e�����荞�܂�Ă���̂ł�����A�����܂��B �Ԏ��̉ӏ��A�u�F���̒��ł̒n���̉�]���������肷�邱�Ƃ����\�ƂȂ��Ă����B�v�Ƃ����L�q�ł��B ����́A�F���ɐ�Όn�Ƃ������̂����݂��邱�Ƃ��Ӗ����Ă��܂��B ���[�U�[�W���C���̓��[�U(��)���g���ĉ�]�p���x�����o���A�q��@�̈ʒu������̌��ƂȂ����^���鑕�u�ł�(�ڂ����́A�������������������)�B���̑��u���g����(�܂�����g����)�u�F���̒��ł̒n���̉�]���������肷�邱�Ƃ��\�v�Ƃ������Ƃ́A������Όn����ɐi�s���Ă��邱�ƈӖ����A����́A�t�ɂ����Ό��Ƃ�����i���g���ΐ�Όn�����߂���Ƃ������Ƃł���܂��B ������u��Όn�ȂǂȂ��B�ǂ�ȂɎ�i�������Ă�������Ȃ��B�S�Ă̊����n�͓����Ȃ̂��I�v�Ǝ咣���Ă�܂Ȃ����ꑊ�ΐ��������A����Z�p�̑O�ɂ������Ȃ��ے肳��Ă���B (�������ɁA�������̂̂悤�Ɋ����̖@���ɏ]���悤�ȉ^����������̂��Ƃ�����A���̏ꍇ�́A�������A��Όn�����߂邱�ƂȂǂł��Ȃ����k�ł��B) �H�w�҂�Z�p�҂́A���Θ_�Ȃǂ͂��߂���ᒆ�ɂȂ��A�}�N�X�E�F�����d���C�w�������������Ƃ����炷�łɊF���M���Ă������Ɓu��Όn�𑫏�ɓd���g(��)�͐i�s����v�Ƃ������̍l�������̂܂ܗp���ă��[�U�[�W���C�������听�����݂܂����B�����āA��L�̌��_�ł��B���͂⑊�Θ_�������c���]�n�ȂǂȂ��̂ł��B ����ɂ��Ă��A�Ȃ�����ȑ�R�̗��_��21���I�����ɐ����c���Ă���̂ł��傤���B���ɂ͕s�v�c�łȂ�܂���B ���ׂĂ̎����������ɃN���A�[���Ă���ʎq�͊w�ƑΔ䂵�Ă݂Ă��������B�R��떂�������炯�̑��Θ_�̑��݂ɕ��ꂩ�������ł��B ���[�U�[�W���C�������ł͂���܂���B���̐��X�̎����ɂ����Ă����ΐ����_�����S�ɔے肳��Ă��邱�Ƃ𑼂ŋL���Ă��܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������B �܂�����̌��ƂƂ��ɑ��Θ_�̍��{������������ꑊ�ΐ������������ɂ���������Ȍ`�Ō`������Ă������A���̋\�Ԃ̗��j���`���ɏ����Ă��܂��̂ŁA���Ђ��ǂ݂��������B��ÂɌ���A���ׂĂ����炩�ɂȂ�܂��E�E�E�@ |
|
| �������{�̂���������ȋL�q | |
|
�J�̖{�ł́A���Θ_�̍��������̐����ɂ����ĉߋ�����������ȋL�q�����X�ƍs���Ă��܂����B�����āA���ꂪ���u���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă��āA���܂ł�����̋L�q���������܂��B�u�����w�҂͂ǂ��܂Ői���v���ɂƂ�w�E���܂��B
�E�E�E���͑O�̏͂ŁA�A�C���V���^�C���́A�����w�̂��ׂĂ̖@������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃɐ��������Əq�ׂ��B�������A����ɂ́A�ЂƂ�����O���������B���́A�d�́A�܂�A���L���͂Ɋւ���@�������́A�������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B����́A���ꑊ�Θ_�̂ЂƂ̌��ׂƂ�����ł��낤�B�E�E�E�E ��̕��͂́A�A�C���V���^�C���ɐ��]���ꂽ�Ƃ��납��́A����Ȃɂ�����������Ȑ������o�ĂĂ��Ă��܂��D��Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B ���炩�Ȗ���������ɂ�������炸�A�Ƃɂ������ɂ��ǎ҂������Ɂu���Θ_�͂������I�v�̐��E�ɂЂ��Â肱�����Ƃ����Ӑ}�����ĂƂ�܂��B��̐����������ɂ���������ŁA�f�^��������������܂��B �܂��A�u�ЂƂ�����O���������B�v�Ƃ������t�ɒ��ڂ��܂��傤�B �ʏ�u�ЂƂ�����O���������B�v�ȂǂƂ������t�́A�u100������̂�����1������������I�v�Ƃ����ꍇ�ɂ̂ݎg���܂��B���邢�͏��������āu10������̂�����1������������I�v�Ƃ����ꍇ�ɂ�������邩������܂���B ���������ł����g���Ȃ����Ƃ��炢�N�ł��킩��܂��B �u3�������2�͂��������A1�͈Ⴄ�v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Ɏg���܂���B �Ƃ��낪�E�E�E�E�A�Ȃ�Ə�ł́A�u3�������2�͂��������A1�͈Ⴄ�v�Ƃ����ꍇ�Ɏg���Ă���̂ł��I �����A�����w�̊�{�@���Ƃ����A�j���[�g���͊w�A�d���C�w�A���L���̖͂@���̂���3�����ł����B �����āA�A�C���V���^�C���́A�j���[�g���͊w�Ɠd���C�w��2����ꑊ�ΐ������Ƃ��������̂��ƂɁA����I�ɋL�q���邱�Ƃɐ�����(���͂����ł��d��ȋ^�f������܂�-->*)�A���L���̖͂@���ł͎��s�����̂ł����A���̏Ŏg���Ă���̂ł��B ���炩�ɂ��������ł��ˁH ��ŁA�u�E�E�����w�̂��ׂĂ̖@������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃɐ��������Əq�ׂ��B�v�Ə����Ă��܂����A�����ł��������ȕ\�����g���Ă��܂��B������2�����̐����Łu���ׂĂ̖@������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃɐ��������E�E�v�ȂǂƓ��R���͂Ȃ������̂ł��傤���B ���Ɏw�E����悤�Ɂu2���ŁA1�~�v�̏Ō�����킯���Ȃ��̂ł��B ����ɓ��R���́A�u���́A�d�́A�܂�A���L���͂Ɋւ���@�������́A�������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�v�ȂǂƏq�ׂ܂��B �����ŁA����I�Ȃ��ƂɋC�t���ł��傤�B ���ꑊ�ΐ������Ƃ����̂́A�u���ׂĕ����@���́A���ׂĂ̊����n�ł��̖@���������`�Ő��藧�v���Ƃ��咣������̂ł��B�ɂ�������炸�A���L���͂Ɋւ���@�������́A�������ꑊ�Θ_�I�ɏ����ւ��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�̂ł��B�����ŕ��ʂȂ�u���ꑊ�ΐ������͊Ԉ���Ă���̂ł͂Ȃ����H�v�Ƌ^�⎋����̂����R�ł͂Ȃ��ł��傤���B�u3�̂����A2�͐������Ă��A1���ǂ����Ă��������Ȃ��v�Ƃ����ꍇ�A���ꑊ�ΐ������������������炾�I�Ƃ���̂��ł����R������ł��B�������A�����ɂ͏�L�{�̂悤�ɂ��̓_������ނ�ɂ���āA�����c���Ă��܂����̂ł��B �u�ЂƂ�����O���������B�v�Ȃǂƌ����āA�����Ă͂����Ȃ��̂ł��I ���R���������炭����Ȃ��Ƃ��炢���X�C�t���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����A�A�C���V���^�C�����_�l�ƂȂ��Ă��錻��ł�(��L�{�̏o�ł�1983�N)�A����Ȗ{���̂��Ƃ͐�ɏ����Ȃ��B �Ƃɂ����u����́A���ꑊ�Θ_�̂ЂƂ̌��ׂƂ�����ł��낤�B�E�E�E�E�v�ȂǂƂ���������ɂ��Ȃ�Ȃ�������������āA���ւ������Ɛi��ł��܂������Ȃ��悤�ł��B �������Ɂu100�̗��_�������āA���̓�99�͓��ꑊ�ΐ����������A������1�������ꑊ�ΐ����������Ȃ��v�Ƃ����ł���Ȃ�A���̏ꍇ�͖��������邩������܂��A��͂��������łȂ����Ƃɒ��ڂ��Ă��������B �ǂ��ł����H���������ł��傤�B �u�ق�Ƃ��ɁA�����������j�����ǂ��Ă�����̂��E�E�v�Ǝv����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �����ł͊����ɔے肳��Ă��邵�A��L�̂��Ƃ��`���j�͂ނ��Ⴍ���Ⴞ���ŁA���Θ_���C���L�`�ł��邱�Ƃ��炢����ł��킩��܂��B�C�t����������A���X�ɑ��Θ_���̂ĂĂ��������B ����ɑʖډ����ɂ�����B ��ŁA�u����́A���ꑊ�Θ_�̂ЂƂ̌��ׂƂ�����ł��낤�B�E�E�E�E�v�ƌ�������A���R���́A�ǂ̋��ȏ��ł������Ă���悤�ɁA���Ɉ�ʑ��ΐ������ɂ̂��Ƃ����d�͗��_�A��ʑ��ΐ����_���A�C���V���^�C���͊�������Ƃ������������܂��B �����ŁA�ǂ̋��ȏ��ł��u�߂ł����I�������͓V�˃A�C���V���^�C���I�v�ŏI���܂��B ���Ĉ�ʑ��ΐ������Ƃ͂Ȃ�ł��傤���H ��ʑ��ΐ����� �u���ׂĂ̊�{�I�����@���́A�C�ӂ̍��W�n�œ����`�ŕ\�����B�v�Ƃ������̂ł��B �悭�l���Ă��������B�u���ׂĂ̊�{�I�����@���́E�E�v�ƌ����Ă��܂��ˁH�A�C���V���^�C���͏d�͗��_��������ʑ��ΐ������ɑ����č���������Ȃ̂Ɋw�҂͂Ȃ�����ł悵�Ƃ���̂��H���܂��ɏd�͗��_�����������Ă��Ȃ��̂ł���B�A�C���V���^�C����������ʑ��ΐ������Ƃ������܂�ɂ���Ȍ����͂��܂��Ɏ�����Ă��Ȃ��B����ĉ����ɂ����Ȃ��B ���������ꑊ�ΐ��������܂��ɂ��̐������͎�����Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A���ꑊ�ΐ������Ɍ����Ă͏�̂��Ƃ��ŁA�{���͌���ɂ܂Ő����c���Ă��邱�Ǝ��̂��������������Ȃ̂ł��B ���̃y�[�W�̖`���ŁA�v�����N�������q�ׂĂ���悤�ɃA�C���V���^�C������o���������̉����͂܂��^����Ɏ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ȃ̂ł��B �ɂ�������炸�A���㕨���w�ɂ�(�������Ƃ�)�����悤�Ƃ����C�z���猩���Ȃ��B�����u�����v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���E�E �����āA�s�v�c�Ȃ��ƂɁA����̊w�҂͂Ȃ������ꑊ�ΐ�����(��ʁE�E�ł͂Ȃ��I)�ɑ������`��(���[�����c�ϊ����ϐ��̌`��)�A�������Ǝ��������̗��_�����킹�悤�Ƃ��Ă���B���ꑊ�ΐ������ƈ�ʑ��ΐ������͌��㕨���̍��������ł��B����ŁA��̏ł��B���㕨���͂����ނ��Ⴍ����ƌ����Ă����Ǝv���܂��B �� �A�C���V���^�C���́A�d���C�w�����ꑊ�Θ_�I�ɔc�����悤�Ƃ����̂ł����A���̏ؖ��͊ԈႢ�ł��邱�Ƃ������A�}�N�X�E�F���������ɂ����郍�[�����c�ϊ��s�ϐ��ؖ��̌��̔����Ŏ����܂����B)�@ |
|
| ���ŋ߁A�}�ɏo�Ă����u���Θ_�͌����x�ȏ�̑������֎~���Ă��Ȃ��I�v | |
|
�ŋ߁A�Ƃ݂ɁA�u���́A���Θ_�͌����x�ȏ�̑������֎~���Ă��Ȃ��I�v�Ƃ������t�����ɂ���悤�ɂȂ�܂����B�Ȃ��A�}�ɂ���Ȃ���������Ȍ��t���Ђ�ς�ɕ������悤�ɂȂ��Ă����̂ł��傤���H(��̑O�ɂ͂܂�������Ȃ��������Ƃł��B)
���݁A���Θ_�̃C���`�L���L���F�m�������A���͂⌤���҂ł��������ʉ��ł͂Ђ����ɋC�t���Ă��錻��ɂ�����(�����x�ȏ�̌��ۂ��������o����Ă���)�A���Θ_�M��҂͑����Ȃ�����������͂��߂Ă��܂��B ��̌��t�͂��̗��Ԃ��Ȃ̂ł��B ���́A���Θ_�ł́A�����x�ȏ�̑������֎~���Ă���̂ł��B����́A�A�C���V���^�C���̌��_��(1905�N�u�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�v)����������ɂ킩��܂��B�@�A�C���V���^�C���́A���̘_���́u�T�D�^���w�̕��v�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B A�@�E�E�E�����������ƂȂ�ꍇ�́A�����̍l�@�͖��Ӗ��Ȃ��̂ƂȂ�B�Ȃ��A�����̗��_�ɂ����ẮA���� �� ���A �����w�I�ɂ݂āA������̑����Ɠ�����ڂ��ɂȂ����Ƃ��A����Ȍ�̋c�_������A��������悤�B�E�E�E(�u���ΐ����_�v) ���̂悤�ɁA���Θ_����������l�A�C���V���^�C���� �� �������I�ȍő�̑��x���I�Əq�ׂĂ���̂ł��B �����������������ɑ��Θ_�M��҂́u����A���́A���Θ_�͌����x�ȏ�̑������֎~���Ă��Ȃ��I�v�ȂǂƂ����̂ł��傤���H �����A���Θ_��M���邻�̐l�����́A���������̂�������܂���B B�@�u���X�ɑ��x���グ�Ă��Ă����z����悤�ȏ��֎~���Ă��邾���ł����āA�͂��߂��炃���傫�����x�Ȃ��OK�Ȃ̂��I�v�ƁB ����Ȃ��������Ȑ������x����Ă͂����܂���B 1905�N�ɍ�����Ƃ��Ă��������B�����āA�A�C���V���^�C����A�̘_���̕��͂����Ȃ��������Ƃ��Ă��������B ���̂Ƃ��A���Ȃ���A�̕��͂��AB�̈Ӗ��ȂǂƂƂ�ł��傤���H �Ƃ�킯������܂���B ����ł��A�f���ɁA�������̐��̒��̍ō��X�s�[�h�͂��ȂȂ��E�E�Ǝv���̂ł��B �����āA�ߔN�ɂȂ�܂ŁA�����w�҂͑��Θ_�ł͂����Ȃ̂��ƌ����Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�ߔN�A�}�Ɂu���Θ_�ł͌����ȏ�̑������֎~���Ă��Ȃ��v�ȂǂƑS���������Ȃ��Ƃ������͂��߂��B180���̑�]���I(���������Ƃ��́A�u�Ȃɂ�����ȁE�E�v�Ǝv�����ق�������) �����A����ɃA�C���V���^�C�����uA�̕��͂́A����B�̈Ӗ��Ȃv�Ƃ��ď����Ă����Ƃ�����A�킴�킴���A�̂悤�ɏ����킯������܂���B(�펯�ōl���Ă��������B)�܂��A����B�̈Ӗ��ł������Ƃ�����A���̍ۂ́AA�̌�ɑ�����B�̈Ӗ������ł��邱�Ƃ𒍎߂Ƃ��ĕK�������͂��ł�(������펯)�B�Ƃ��낪�A�_���ɂ͂���Ȓ��߂͈�Ȃ��B ���̂悤�ɊȒP�ȍl�@����A���Θ_�ł́A�����x�ȏ�̑������֎~���Ă��邱�Ƃ������ɂ킩��̂ł��B�@ �@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_�̌��̏ؖ� | |
| ��ʑ��Θ_�̊ԈႢ�ƁA�r�b�O�o���F���_�̖��_��`���܂��B�@ | |
| ����ʑ��ΐ����_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ̏ؖ� | |
|
��ʑ��ΐ����_�̊�b�ɂȂ��Ă��錴���ɓ�������������܂��B
����͐^�̏d�͂ƌ������̗�(������)���������̂ł��邱�Ƃ��咣������̂ł���A��ʑ��Θ_�̉��䍜�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ͂����m�̒ʂ�ł��B���쓟�v���u���ΐ����_�v�ɂ́A���̌��������̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B �u�������ʂƏd�͎��ʂ͖{������̂��̂ŁA�����x�ɂ���Đ����錩�����̗͂Əd�͂Ƃ͌����I�ɋ�ʂł��Ȃ����̂ł���B�v����������Ƃ����B ���̐����ɂ́A2��ނ̓����������܂Ƃ߂ĕ\������Ă��܂��B �͂��߂́u�������ʂƏd�͎��ʂ͖{������̂��̂ŁE�E�v�́A�������ʂƏd�͎��ʂ̓��������咣����ÓT�I�ȓ��������ł��B���Ƃ́u�����x�ɂ���Đ����錩�����̗͂Əd�͂Ƃ͌����I�ɋ�ʂł��Ȃ����̂ł���B�v�̓A�C���V���^�C�����l���o�������̂ŁA��̂��̂Ƌ�ʂ��邽�߂ɂ�����h�A�C���V���^�C���̓��������h�ƌĂԂ��Ƃɂ��܂��傤�B �ÓT�I�ȓ��������̕��͐������̂ł����A�A�C���V���^�C���̓��������̕��͊Ԉ���Ă���̂ł��B ��҂̓��������ɑ���A�C���V���^�C���̍l�@�~�X����A��ʑ��Θ_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ��ȒP�ɏؖ����邱�Ƃ��ł��܂��B�ڂ����������܂��B �m��ʑ��Θ_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ̏ؖ��n �v�l�������s���čl���܂��B�{�Ȃǂł��悭������v�l�����̕ό`�ł������Ȃ��Ă݂܂��B���ܖ��d�͂̉F����Ԃ̒��ɁA��ӂ�50���قǂ̑傫�ȃG���x�[�^��������ł��āA���̃G���x�[�^�̐^��(�㉺���E�̕ǂ��痣��Ă���ꏊ)�ɉF����s�m�̂l������l�����Ă���Ƃ��܂��B���̃G���x�[�^�ɂ͑����Ȃ��O�͌����Ȃ��Ƃ��A�G���x�[�^�͂͂邩���ɂ���_�l�������[�v�ł艺������Ă���Ɖ��肵�܂��B���[�v�͂܂������ɐL�тĂ��܂��B �l���ɂ͓��R�Ȃ��犵�����ʂ�����A�͂������u���̗͂ɒ�R���āA���̏�ɂӂ��v�������A�l���͂����Ă��܂��B���́h�����h�Ƃ�������������̍l�@�̃|�C���g�ł��B ���āA���ܓV��(��)���G���x�[�^�̐^���ɓˑR�o�������Ƃ��܂��B ���̏u�ԁA�l���͊������ʂ����̂ŁA�m���Ɋ����ϓ��̔���������܂��B����܂łӂ�ӂ�ƕ����Ă����Ƃ���ɏd�͂Ƃ����͂���������̂ł�����A���̏�ɂӂ�낤�Ƃ��鐫�������������킯�ł��B ���̕��̌ŗL�́h�������h������܂��B�����āA���܃G���x�[�^�͐_�l�ɂ���ă��[�v�ł艺�����Ă���̂ł�����A�G���x�[�^���͓̂V�̂̕��ւ͗������Ă������A�l���݂̂����ֈ����悹���邱�ƂɂȂ��āA�₪�Ăl���̓G���x�[�^�̉��̏��ɂԂ��鎖�ԂɂȂ�܂��B �l���͗��������d�͂��Â��Ă���킯�ł�����A�������Ă���Ԃ�(���ɂԂ���܂�)�����ϓ��̔������Ȃ���Â��邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B���̏ꍇ���`�Ƃ��܂��傤�B ������̕ʂ̏��l���Ă݂܂��B ���ܐ_�l���җ�ȃX�s�[�h�Ń��[�v��������͂���(������̃X�s�[�h���������Ă���)�A�G���x�[�^��ˑR����ɂЂ��グ�͂��߂��Ƃ��܂��傤�B���̏ꍇ�A�����ϓ��̔����͂���ł��傤���H����܂���ˁB ���̏ꍇ�́A�����G���x�[�^���オ���Ă��������Ȃ̂ł�����A���R�̂��ƂȂ��犵���ϓ��̔����͂���܂���B��̓V�̏o���̂Ƃ��ƁA���͎̂��Ă��Ă������I���e���܂�ň���Ă��܂��B���̏����X�s�[�h���������Ȃ��炽�������ɔ����Ă��邾���ł�����A�h�������h�����悤�ɂ��ł��Ȃ��킯�ł��B���̏ꍇ���a�Ƃ��܂��B �����w�҂͂���܂ŏ`�̏ꍇ�Əa�̏ꍇ���܂������������Ƃ��Ĉ����Ă��܂����B�������̗͂ȂǂƂ�������̗͂��g���ΐ��w�I�ɂ͂������Ɉ�v����ł��傤���A�����I���e���ᖡ����A��ł݂��悤�ɂ܂�ňႤ���̂ł���A�����I�ɈقȂ���́A��ʂł�����̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �]������悭�s���Ă����l�@�́A�l�����������ɂ��Ă�����l����Ƃ������̂ł����B�������ɂ��̏ꍇ�͏`�ł��a�ł������ϓ��̔���������A��̗͂̋�ʂ͂ł��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B ���̂��ƂɋC���悭���̂��A�A�C���V���^�C���͈Ӗ����g������ʉ��������āA��L�̏d�͌n(�`)�Ɖ����n(�a)�����S�ɓ����ł���(�����I�ɋ�ʕs�\)�Ƃ��Ĉ�ʑ��ΐ����_������Ă��܂��܂����B ���㕨���ł́A��̎v�l�����̂悤�ȏꍇ�ł������u�������̗́v���u�d�́v�Ƃ��Ă��܂����A�A�C���V���^�C�������������v�l�����������Ƃ������ƂɋC�Â��A���̃C�R�|���͐��藧���Ȃ��Ƃ킩��ł��傤�B �`�Əa�̍l�@����A���̓�̏����{�I�ɈقȂ���̂ł��邱�Ƃ͖��炩������ł��B �`(�d�͌n)�ł͊����ϓ��̔���������B �a(�����x�n)�ł͊����ϓ��̔������Ȃ��B ���ĂɈقȂ���̂ł���A�����I�ɋ�ʉ\�ł��B �A�C���V���^�C���́A�������̗͂�^�̏d�͂ɏ��i�������킯�ł���(�^�̏d�͂Ɗ��S�ɓ����Ƃ���)�A����܂ł̍l�@����A��ɂ���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��Ƃ킩��ł��傤�B�`�Əa�́A���͕����I�ɈقȂ���̂������̂ł��B �ȏ���A�h�A�C���V���^�C���̓��������h�͌���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B ����āA��ʑ��ΐ����_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ��ؖ�����܂����B �ؖ��I���B ���������A�C���V���^�C������̎v�l�����ɋC�Â��Ă���A�d�͌n�Ɖ����x�n�������ȂǂƎv�������Ƃ͐�ɂȂ������Ƃ킩��܂��B �A�C���V���^�C���́A�P���Ȏv�l�������瓙���������l����ʑ��Θ_���݂ւƂ����̂ł����A��L�̂悤�Ȃ��Ƃ܂łӂ��߂������Ƒ��l�ȏꍇ��T�d�Ɍ������ׂ��������Ǝv���܂��B ��L�ؖ������ʑ��Θ_��ے肷�邱�Ƃ��ł����킯�ł����A�ʂ̃A�v���[�`�Ƃ��āA�u���ꑊ�Θ_���Ԉ���Ă��邱�Ƃ��A���Lj�ʑ��Θ_���ے肳���v�Ƃ��������Ƃ��Ă����܂��܂���B ��ʑ��Θ_�́A���������ƈ�ʑ��ΐ������Ƃ�����̎w���������琬�藧���Ă��܂��B ���ꑊ�ΐ��������Ԉ���Ă���Ȃ�A����������x�n�ɂ܂Ŋg��������ʑ��ΐ����������R�Ԉ���Ă��邱�Ƃ������A�������b�Ƃ����ʑ��ΐ����_���Ԉ�������_�ł���ƒf�肷�邱�Ƃ��ł��邩��ł��B�@ |
|
| �����Θ_�̋��ȏ��ɂ�����u���������v�̍l�@�́A��͂肨������ | |
|
���������ł̃A�C���V���^�C���̌�����Ŏw�E���܂������A�����ł͂��ꂪ���ȏ��łǂ̂悤�ɋL�q����Ă��邩�����Ă݂܂��傤�B���Θ_�̌��Ђł�����R���Y���̒����u�����w�͂ǂ��܂Ői���v(��g����I��)�̒��̈�߂��Ƃ肠���܂��B
���R���́A�G���x�[�^�̎v�l�����̐�����������A���̂悤�ɓ���������������Ă��܂��B �u�����w�͂ǂ��܂Ői���v �E�E�E�����łЂƂ�Ȃ��Ƃ�����B�E�ɏq�ׂ��悤�ɁA�j���[�g���͊w�ł́A�������̗͂ƍl�����Ă������̂��A�A�C���V���^�C���̗��_�ł͖{���̗͂ɏ��i���ꂽ�B�������A����́A�P�ɗ͊w�I�\���ɂ����炸�A���ׂĂ̕������ۂɂ����āA���̌��ʂ��A�{���̏d�͂̌��ʂƓ��l�Ɉ����邱�ƂɂȂ����B���̍Ō�ɏq�ׂ����Ƃ́A���ɏd�v�Ȃ��ƂŁA����̓j���[�g���͊w�ɂ͂Ȃ��������Ƃł���B���ꂪ�����ɏd�v�ł��邩�́A���߂ł킩��Ǝv���B����͂Ƃ������A��ʑ��Θ_�ł́A��n�̉����x�^���ɂ�萶����͂́A�����Ƃ��ɁA�{���̏d�͂Ɠ����̌��ʂ����͂Ƃ��Ĉ����邱�ƂɂȂ����킯�ł���B�����ŁA���̎咣�������Ƃ����B ���������ƁA���R�������{�I�Ɋ��Ⴂ�����Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B �ǂ����Ԉ���Ă��邩�́A��̐Ԑ��̋L�q���悭�����Ă��܂��B��Ŏ����ؖ������悤�ɁA�����x�^���ɂ�錩�����̗͂́A�����܂Ō������̗͂ł����āA�����ϓ��̔����������Ȃ��̂�����A�{���̏d�͂Ƃ͂܂������Ⴄ���̂ł���܂��B�ɂ�������炸�A��L�����ł͊��S�ɓ����Ƃ��Ĉ����Ă���A���ꂪ���Ȃ킯�ł��B �������́A�͂₭���̌��ɋC�t���A��ʑ��Θ_���̂Ă��錈�S�����Ȃ���A���̏�ɗ���������F���_�͂ق�Ƃ��ɂ������Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B ���lj� ����ɁA�{���I�ɂ͓����ł����A�����ʂ̊ϓ_(�ϓ_2�Ƃ��܂�)����A��̏`�Ƃa�̈Ⴂ��������Ă݂܂��傤�B �m�ϓ_2�̐����n �`�ł́A�V�̂��o������킯�ł�����A���̏u�Ԃ���d�͏ꂪ���͂ɔ������A�l���������ɂ��̏d�͏�̉e�����ɓ���܂��B�����ł͂l���́A�V�̏o�����ォ��m���ɏd�͂��Â��Ă���Ƃ�����킯�ł��B�Ƃ��낪�A�a�ł͂ǂ��ł��傤���H�_�l�������G���x�[�^����Ɉ��������Ă��邾���Ȃ̂ł�����A�ǂ��ɂ��d�͏�Ȃǐ����Ă��炸�A���̏��ɂԂ���܂łl���͂ǂ�ȗ͂��Ă��Ȃ��킯�ł��B���̂悤�ɍl����ƁA�`�Ƃa�����{�I�ɈႤ�Ȃ͖̂��炩�ł��B �����I��� �m���L�n �Ƃ���ŁA�����Œ��ӂ��Ăق������Ƃ�����܂��B��L�̂悤�ɐ�������ƁA�����w�҂���u�����ʑ��Θ_��K�p����ƁA�a�̉����x�n�̋�Ԃɂ��d�͏ꂪ�����Ă��邱�Ƃ��������Ƃ��ł���I�I�v�Ƃ������_���K�����܂��B�������A�����͊��Ⴂ���Ȃ��Œ��������̂ł����A�A�C���V���^�C���́A���̎�̎v�l�������s������Ɉ�ʑ��Θ_�����݂����̂ł���A�����A�C���V���^�C�����{�T�C�g�̎v�l�����ɋC�Â��Ă���Έ�ʑ��Θ_�Ȃǒa�����Ȃ������ƒf�����邱�Ƃ��ł��邩��ł��B���j�̏������܂�����Ȃ��Œ����������̂ł��B �u����v�l�������ԈႦ�ĉ��߂������߂ɁA�Ԉ�������_������ꂽ�B���̊Ԉ�������_��ʂ̎v�l�����ɓK�p�����������߂��������ƂȂǂł��Ȃ��B�v�Ƃ����_�����\���������Ă��������B���̂��Ƃ���A�ϓ_2�ɂ����āA��ʑ��ΐ����_��p������(���̒a���O�̗���ɂ�����)�A�`�Əa�̊��S�ȓ��������ؖ����邱�Ƃ��ł��Ȃ���Έ�ʑ��Θ_�͊Ԉ���Ă���Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A���̓��������ؖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���܂��B����܂ł̐������A�`�Ƃa�͍��{�I�ɈقȂ����ł��邱�Ƃ͒N�̖ڂɂ����炩������ł��B�@ |
|
| ����Ԃ�3��ނɕ��ނł��� | |
|
�����ł́A��Ԃ̕��ނƂ��̒�`�Â����s���܂��B
��ԂɊւ��Ă̓g�b�v�y�[�W�ł��_���܂������A��ԂƂ������t�́A���ԂƓ����ŁA�ǂ����̂���͂�����Ƃ�����`�Â����Ȃ���Ȃ��܂g�p����Ă������������āA���̂��Ƃ�20���I�����w������������֓����Ă��܂����Ƃ����C�����Ă��܂��B �ȉ��ł́A��Ԃ̕��ނ����݂܂��B ��Ԃ́A�h�L����h�A�h���W�h�A�h�^��h�̎O�ɕ��ނł���ƍl���܂����A���̎O�𖾗Ăɋ�ʂ��Ȃ��܂g���Ă������߂ɁA���㕨���w�͍����̓x���ӂ��߂Ă���C�����܂��B���킵�����Ă����܂��傤�B ��Ԃƕ����āA�܂��Ȃɂ�A�z���邩�Ƃ����ƁA������L����Ƃ������Ƃł��傤�B�����͂Ă��Ȃ��L�����Ă��邻�̍L���肻�̂��̂������Ă���킯�ł��B ���̈Ӗ��ŋ�Ԃ��l����A�u�������Ȃ��Ƌ�Ԃ͑��݂��Ȃ��v�Ƃ��u���������邩���Ԃ����݂���v�Ƃ������c�_�͂��܂�Ӗ��̂Ȃ����Ƃł���Ƃ킩��ł��傤�B���������낤���Ȃ��낤���L���肻�̂��̂͂���̂ł���"�L���聁���"�̓A�v���I���ɑ��݂�����̂ƍl����̂����R�ł��B �Ƃ��낪�A��ԍ��W�ƂȂ�Ə����Ӗ�����������Ă��܂��B ��ԍ��W(���邢�͍��W���)�́A��������ɃA�v���I���ɑ��݂�����̂ł͂Ȃ��A���w�I�ȊT�O�ł����āA���̂̈ʒu���L�q���邽�߂ɐ��݂����ꂽ���̂ł���Ƃ������ƂɋC�Â����Ƃ���ł��B���̈ʒu���L�q����̂ɕK�v�ł���Ƃ����K�v�����琶�ݏo����܂����B ���̈ʒu���L�q����̂ɍ��W�Ƃ������̂�ݒ肹����Ȃ�����ݒ肷��̂ł���A�����Ȃ��̂ɍ��W���l�������ꂽ�肷�邱�Ƃ͂���܂���B���̈Ӗ��ł́A�u���̂��Ȃ�����(��ԍ��W)�͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����܂��B ��ԍ��W�́A����ݏo���ƕ֗�������Ƃ������R�Ől�Ԃɂ���čl�������ꂽ���̂ł����āA���́u�l�������ꂽ���́v�Ƃ����̂́u�T�O�v�ł���A�A�v���I���ɑ��݂�����̂Ƃ͂܂������Ⴄ���̂ł��邱�Ƃ��\���ɔF�����Ȃ���Ȃ�܂���B�T�O�Ǝ��ݕ��͈Ⴄ�̂ł��B �u���ԁv�Ɋւ��Ă������ł����A�����̂Ƃ�����×�����N�w�҂������w�҂������܂��ɂ����l���Ă��Ȃ������悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B �A�C���V���^�C���̒���(��)�̒��Ɂu�f�J���g�́A��ԂI�ΏۂƂ͖��W�ɕ����Ȃ��ő��݂�������̂Ƃ݂Ȃ����Ƃɒ�R���Ă����v�Ƃ������t������܂����A���́u��ԁv�͂܂��Ɂu��ԍ��W�v���w���Ă���Ƃ����܂��B ���ɐ^��ł��B �����w���T�ɂ́u�����̑��݂��Ȃ��ȋ�Ԃ̂��Ɓv�Ƃ���܂��B�������A�f�B���b�N�̋�E���_�ɂ�����悤�ɁA�u�^��Ƃ͂��͕��̓d�q���т�����Ƃ܂�����ԁv�Ƃ����悤�ɂ��q�ׂ��邱�Ƃ���A�h�L����h��h���W�h�Ƃ����Ӗ��́u��ԁv�ƈقȂ�A��Ԃ̒��g�̕����I�������s���₤�����t���Ƃ킩��܂��B����͋�Ԃ��̂��̂̕����Ƃ���Ԃׂ����̂ł��B �ȏ�̂悤�ɍl���Ă��܂��ƁA�h�L����h�A�h��ԍ��W�h�A�����āh�^��h�̎O�͂܂�����������Ӗ��̌��t���Ƃ킩��ł��傤�B��ԂɊւ��ẮA���q�ׂ�3��ނ̕��ނ��͂�����ƔF�����邱�Ƃ��d�v�ł��B ��Ԃ�3��ނɕ��ނł���A�Ǝ��͍l���܂��B ���㕨���w�ł́A�u��ԁv�Ƃ������ƂɊւ��ĈӖ��̍����������܂��B ��������Ƃ��������Ύ��ԂƓ������A���Ƃ��Ɣ��R�Ƃ����A�����܂��Ȓ�`�̂܂܂Ɂu��ԁv�Ƃ������t���g�p���Ă������Ƃ��������Ă���Ƃ�����ł��傤�B ����F���_���������ȕ����ɂ�����ł��܂����̂��A�u��ԂƂ͂Ȃɂ��H�v�Ƃ������{�I�Ȗ₢���Ȃ�������ɂ��Ă������ʂƂ�����̂ł��B ����̕����w�҂́A�u��ԁv�Ƃ������t���A��Ԗڂɏq�ׂ��{���I�ȁh�L����h�̈Ӗ������łȂ��A�u�^��v��u��ԍ��W�v�̈Ӗ��Ƃ��Ă��g���Ă��܂��Ă��܂��B ���̒ł����A����̕����w�ł́A�u��ԁv�Ƃ����ꍇ�͂����܂Łh������L����h�̈Ӗ��ł����p���Ȃ��B���w�I�ȋ�ԍ��W�������Ƃ��͕K���u���W�v�Ƃ��u��ԍ��W�v�Ƃ������t��p����B�w�̓��[�N���b�h�w��p����B�܂��A�u�^��v���A����܂Łu��ԁv�Ƃقړ��`�Ŏg�p����Ă������A���ꂩ��͐^��(�܂��Ԏ��g�̕���)�������ꍇ�͂��ł��u�^��v�Ƃ������t���g�p����B �ȏ������̕����w�̊m�ł���K���Ƃ��Ă����A���㕨���̂悤�Ȑ��w�V�Y�Ɖ������s�т̋c�_�͏�������ƐM���܂��B �u���(�L����)�v�A�u��ԍ��W�v�A�����āu�^��v�A���̎O�͌��t�̏�Ō����ɋ�ʂ��ׂ��ł��B���̎O�����i�ɋ�ʂ��Ȃ���g�p���Ă����A���ʂ��̂悢�����w���\�z�ł���Ǝv���܂��B ��ԕ��������Ƃ̃R���m�E�P���C�`���͂��̒����ŁA�u���(�^��)�͋����ł͂Ȃ��A�����������߂��̕����Ȃ̂ł���v�Əq�ׂĂ����܂��B�����[���l���ł����A�\���Ƃ��āh��ԁh�Ƃ������t�͗p�����Ɂh�^��h�Ƃ������t�ň�{����������������Ȃ����K�ł���Ǝv���܂��B ��ʑ��ΐ����_�ł́A�u��Ԃ��Ȃ���v�ȂǂƎ咣���܂����A�܂������I�O��Ȏ咣�ł��B���3��ނ̈Ӗ����l���Ă��A�u��Ԃ��Ȃ���v�ȂǂƂ����l�����o�Ă���]�n�͂���܂���B���Θ_�ł́A���ԂƓ��l�A��Ԃɂ�����N�w�I�l�@������Ȃ��Ǝv���܂��B�@ |
|
| ������F���_�͊��S�ɂ������� | |
|
��L�ؖ��ɂ��A��ʑ��ΐ����_����������_�ł��邱�Ƃ͒N�̖ڂɂ����炩�ɂȂ�܂������A�F�l�������m�̂悤�ɁA����̉F���_�͂��̈�ʑ��Θ_����b�Ƃ��Ă��܂��B
�����w�Ƃ����w��́A��b�ƂȂ�����������ɑS�Ă�W�J���܂��̂ŁA���̍��{�̕������������Ԉ���Ă�����A�����炻������s��Ȍ��������\�z���悤�Ƃ��A�c�_�S������R�ƂȂ��Ă��܂��܂��B���ݓV�˂Ə̂����z�[�L���O��y�����[�Y����ʑ��Θ_����g���F����u���b�N�z�[���ɂ��Ę_���Ă��܂����A����炪�����ɐ��w�I�ɗ��h�ł��낤�ƁA�S�����ł���ƒf�肷�邱�Ƃ��ł��܂�(���{�̈�ʑ��Θ_���Ԉ���Ă���̂ł�����I)�B ���āA����u���[�o�b�N�X�u���E�̘_���E�r�b�O�o���͂��������H�v(�ߓ��z����)��ǂ�ł��āA�����[���L�q�������܂����̂ŁA���L�ɏЉ�܂��B �w�E�����A�����Ƃ��Ȃ��ƂȂ̂ł����A�V�˂Ə̂����l�����ɂ�����ƁA�ǂ������킯���l�Ԃ͈Î��ɂ������Ă����M������ł��܂��X��������܂��B���̓_���ߓ����͓˂��Ă��܂��B �u���E�̘_���E�r�b�O�o���͂��������H�v�@�F���ɂ������͂̕��z�͋ψꐫ�������̂ŁA�����������邽�߂ɁA�C���t���[�V�����E�r�b�O�o���_�����܂ꂽ�킯�����A���̂��߂ɂ͏����̉F���͔��ɍ����x�Ŗc�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �قƂ�Ǘ�ɋ߂��傫��(�v�����N����)����1�Z���`�̑傫���ɂȂ�̂ɁA10�̃}�C�i�X33��b����������Ȃ��B ���̖c�����x�́A���̑��x��10��22��{�ȏ�ɂȂ�B����́A�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�̑��x���E ���A�͂邩�ɒ��������̂ɂȂ�B �C���t���[�V�����E�r�b�O�o���_�̎x���҂́A�ʏ�A���̂悤�ɓ����āA���̊Ԃ̎����������Ă���B �F�����A�C���t���[�V�����E�r�b�O�o���_�ł����悤�ɁA���̑��x��10��22��{(1����100���{)�ȏ�̍����x�Ŗc������ꍇ�A���̉F���́A���Ԃ���Ԃ��܂����݂��Ȃ��Ƃ���ɖc�����Ă����̂�����A���ꑊ�ΐ����_�ɂ��A���̂̑��x�����̑��x�̌��E���邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ����������K�p����Ȃ��B ����ɁA�c������̂͋�Ԃ��̂��̂ŁA���̋�Ԃ̒��̕��������݂������ї���Ă����̂ł͂Ȃ�����A������ɂ��Ă��A���̌��ۂɂ͌����̌��E�͓K�p����Ȃ��B �����A����͂�����������Ȃ��ƈ���������Ƃ��Ă��A�E�L�̃C���t���[�V�����E�r�b�O�o���_�ŁA�����Ǝ��Ԃ��c�_����ɂ́A����𑪂��ɂȂ鎞�ԂƋ�Ԃ̑��݂��A�O��Ƃ��ĕK�v�ł͂Ȃ����Ǝv����B�����ŁA�C���t���[�V�����E�r�b�O�o���_�́A�܂��܂������e�X�g���ꂽ���Ƃ̂Ȃ��A���m�̎��R�Ȋw�́h�@���h��p���Ă��邱�ƂɂȂ�B�E�E�E�E �����Ă݂�A���̂Ƃ���Ǝv���܂��B �ߓ����͉F���_�w�҂̖��������咣�������Ǝw�E����Ă���B �u�F���a�������Ɏ��ԁE��Ԃ͑��݂��Ă��Ȃ��I�v�Ƃ����Ȃ���A���̂Ƃ��̏����ԁE��Ԃ�p���ċc�_���Ă��邱�Ƃ̂����������F���_�w�҂͂͂����ĔF�����Ă���̂ł��傤���B �l�ԂƂ����̂́A��U�������ƐM�����߂A�����ڂ������Ȃ��Ȃ��āA�����̐M�������_�ɗL���ȉ��߂ӎ��̂����ɂ��Ă��܂����̂̂悤�ł��B�����Č��㕨���w�͂Ȃ����A�C���V���^�C����D�悵�Ă��܂��X��������܂��B �Ƃ���ŁA����Љ���ߓ��z�����́u���E�̘_���E�r�b�O�o���͂��������H�v�́A�����ւ�Ȗ����ł��B ���Θ_�����Ƃɂ���C���t���[�V�����E�r�b�O�o���F���_��D�悷��{���������ŁA�������鑼�̑����̉F���_(���Θ_��p���Ȃ��F���_)�������Ɉ����Ă��Ă��̒��҂̉Ȋw�҂Ƃ��Ă̑ԓx�ɂ͌h�����܂�(�ߓ����͒����ȓV�̕����w��)�B ���̖{��ǂ߂A�r�b�O�o���F���_�ɗL���Ȍ���I�ȏ؋��Ȃǂ��͂ȂɈ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��A�����ɉ�X���}�X�R�~�̏��ɗx�炳��Ă��邩���킩��܂��B���Ј�x�ǂ�ł݂Ă��������B�@ |
|
| ���r�b�O�o���F���_�ɑ���t�����_�[���̎w�E | |
|
�u�Ȋw���_���ɂ���7�̋\�ԁv�����ł���ƁA�V�̕����w�҃g���E���@���E�t�����_�[�����A�u�W�����_�͂������Ȃ��Ƃ��炯�v�Ƒ肵�āA����F���_�����̂悤�ɏq�ׂĂ���ӏ����݂��܂����B
����̃r�b�O�o���F���_�̊�Ȏp���f���o����Ă���Ǝv���܂��̂ŁA�Љ�Ă����܂��B �u�Ȋw���_��������7�̋\�ԁv �W�����_�͂������Ȏ����炯 ���݂̎��R�Ȋw�̑̌n�ɂ͑傫�ȊԈႢ������B��Ȑ��w���_���肪�܂���Ƃ���A�����̂���ӂ�ȗ��_�����Ă͂₳���B ���̐��ł���V���w���ɂƂ��Ă��A���߂���Ō�܂ŁA�������Ȏ����炯�ł���B �܂��A�W�����_�Ƃ��đ����̊w�҂̎x���Ă���u�r�b�O�o�����_�v�ɂ��čl���Ă݂Ăق����B���̗��_�ł́A�ȉ��̂悤�Ȏ����^��Ȃ��Ɏ����K�v������B ����́A���ԂƋ�Ԃ͑��݂��Ă��Ȃ������B �����鎞�A�����ɂ���Ď��ԂƋ�Ԃ����R�Əo�������B �������̌����͕s���ł���B ���F���͌������������c�����Ă����B ���F���͋ψ�ł���B ���F���ɂ͋ψ�łȂ���\��������B ���F���̖c���ɂ���ċ�͓��m�̋����͑��傷�邪�A��͓��̑��z�ƒn���̋����͕ς��Ȃ��B ���̂悤�Ȗ������炯�̗��_�����C�Ŏ�����Ă���̂ł���B����͖��炩�ɉ��������������B�E�E�E �t�����_�[���̂��̎w�E�ƁA��L���̓��������Ɋւ���w�E�A����ɑ��̃y�[�W�ŏq�ׂ����Θ_�ɂ�����l�X�ȋ\�Ԃ̎w�E�����킹�ēǂ�ł��������A����F���_�������Ɍ����������݂Â��Ă��邩���킩���Ē�����Ǝv���܂��B�@ |
|
| ���F���w�i���˂̓r�b�O�o�����_�̌���I�ȏ؋��ł͂Ȃ� | |
|
��ɏЉ���u���E�̘_���E�r�b�O�o���͂��������H�v(�ߓ��z����)�ɂ́A���낢��Əd��Ȏ������w�E����Ă��܂��B1965�N�Ƀy���W�A�X�ƃE�B���\�������������F���w�i���˂́A����܂Ńr�b�O�o�������ۂɂ����������ʏ؋��Ƃ���A�}�X�R�~��[�֏��Ȃǂɂ���Đ���Ɍ��`����Ă����̂͂����m�̂Ƃ���ł��B
�������A�����͂������Ă���A���j�̉A�ɉB��Ă��������ׂ��������������̂ł��B �r�b�O�o�����_�����\�������͂邩�ȑO�Ɍ��݂̔w�i���˂̉��x2�D73�j�ɋɂ߂ċ߂��l���A���F���_�̊ϓ_���瑽���̓V���w�҂��Z�o���Ă����̂ł��B �����g�͂��߂Ēm�����̂ł����A���ԂɂقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������Ǝv���܂��̂ŁA�����ɖ{�����p���A�Љ�܂��B �u���E�̘_���E�r�b�O�o���͂��������H�v �F���w�i���˂͕K�������r�b�O�o���_�������\�������킯�ł͂Ȃ� �r�b�O�o���_�A���F���_�Ƃ�����̉F���_�ɂ�������X�̘_���ɂ́A�d�v�Ȗ�肪����������Ă���B ���̒��ň�Ԃ悭�m���Ă���̂́A�F���w�i���˂ł��낤�B �F���w�i���˂Ƃ����̂́A�����͌n�Ȃǂ̔������̂��炭������������A�F����Ԃ��̂��̂������Ă�����̂��Ƃł���B���ʁA���̌����A��Ή��x�ɂ��ĉ��j(���Ȃ݂ɗ�j<�P���r��>���}�C�i�X273�D16��)�̍��̕��˂ɑ������邩�ŕ\�����B ���̕��˂Ƃ́A���z�I�ɐ^�����ȕ��̂�����˂������̂��ƂŁA���̔g�����Ƃ̖��邳(�G�l���M�[)�̕��z(�v�����N���z�Ƃ����B�}5�|1)������ƁA���x�ɂ݈̂ˑ����ĕ��z�̃s�[�N�����܂��Ă���B����āA�ϑ����ꂽ���̃v�����N���z������A���̕��ˉ��x�����߂���B �܂��A���̂����鉷�x�̔M���t��Ԃɂ���Ƃ��A���̕��̂��̂��̂���o�Ă�����̃v�����N���z�́A�������x�̍��̂�����˂������̃v�����N���z�Ɨގ����Ă���B���Ȃ킿�A�ϑ����ꂽ���̍��̕��ˉ��x�́A���̌����Ă��镨�̂̉��x�������Ă���Ƃ�����B �r�b�O�o���_�ɂ��A�r�b�O�o������͊e�f���q���o���o���ɔ�ь����Ă����Ԃ��������A���̎��Ԃ��o�Ɠd�q�����q�j�ɂƂ炦����(�܂茴�q���ł���)�B����ƁA���R�d�q�����Ȃ��Ȃ������߂Ɍ��͎��R�ɔ�щ���悤�ɂȂ�A�F���́A��Ή��x�ɂ���4000K�̌����[�������M���t��ԂɂȂ���(������F���̐���オ��Ƃ���)�B���̂Ƃ��̌����F���w�i���˂Ƃ��Č��݊ϑ��ł���Ƃ����킯���B �������A��͂���̌����ԕ��Έڂ���悤�ɁA���̉F���̐���オ��̂Ƃ��̌����ԕ��Έڂ��āA���x�Ɋ��Z�����4000K��肾���ԒႭ�Ȃ��Ă���͂����Ɨ\�����ꂽ�B �Ƃ���ŁA�����̐l������(���_�A�V���w�҂��܂߂Ă���)�A�F���w�i���˂̓r�b�O�o���_�݂̂��\���������̂ŁA�r�b�O�o���_�ł��������ł��Ȃ��ƐM���Ă���悤�����A����͕K���������m�Ƃ͌����Ȃ��B �O�q�̃A�[�T�[�E�G�f�B���g���́A1926�N�ɏo�����V�̕����w�̋��ȏ��̐�发�ɁA�P���ԋ�Ԃ̉��x����͌n���̐��̌��̋��x����v�Z���āA��Ή��x��3�D2K�ƎZ�o���Ă���B ���̐��N��A����͌n�̑��݂��m������Ă���A�h�C�c�̓V���w�҃G�����X�g�E���Q�i�[�́A�F����Ԃł̃C�I�������ۂ��������āA������̌����قƂ�ǖ����ł���悤�ȏ�Ԃ̋�͌n�Ԃ̋�Ԃ̉��x���v�Z���A��Ή��x��2�D8K �Ƃ����B ����ɁA1941�N�A�`�E�}�b�P���[�́A�J�i�_�̃r�N�g���A�V����̑��ɁA�P���ԕ����̃X�y�N�g���ϑ�����P���ԋ�Ԃ̉��x��2�D3K�ƎZ�o�����A�ƕ��Ă���B �����̐��l�́A�ǂ���A�ŋ߂̉F���w�i���˂̑���l�ł���2�D73K�ɋ����قNj߂��B �܂��A���̎O�̐��l�́A1965�N�ɏ��߂Ċϑ����ꂽ�Ƃ��ɏo���ꂽ�w�i���ˉ��x��3�D5K�Ɣ�ׂ�ƁA�ŋ߂̑���l�ɂ��߂��B �������A�G�f�B���g�������Q�i�[���A���̉��x�ڑ�����@�����邩�ǂ����́A�_�q���Ă��Ȃ��B �F���w�i���˂̉��x���߂����� ���āA�r�b�O�o���_�ƒ��F���_�Ɨ��҂����ꂽ1940�N��̏I��育��́A�r�b�O�o���̍ł����͂Ȑ��i�҂́A�R�[�l����w�ɂ������V�A���܂�̕����w�҃W���[�W�E�K���t(�}5-2)�Ɣނ̓��������������t�E�A���t�@�[����у��o�[�g�E�n�[�}���������B 1946�N�ɃK���t�����\�����_���ł̃r�b�O�o���_�ւ̍ł��d�v�ȍv���́A�j�Z�����_�̓����ł������B �E�E�E �A���t�@�[�ƃn�[�}���́A1948�N�ɁA���n�̉̋ʂ��番�������w�i���˂̉��x���v�Z���āA��Ή��x��5K�Ɠ������o�����B�ނ�͂���ɁA���̔w�i���˂́A������̌�����藣���Ċϑ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������ꂸ�A���̖����肪�ϑ����ʂɍ������邩������Ȃ��ƌx�������B ���̓�l�́A1949�N�ɂ́A�V�����ϑ����ꂽ�������琄�肳�ꂽ�F���S�̂̕����̖��x���g���Ă��̌v�Z����蒼���A28K�Ƃ����V�������l���o�����B �K���t���g�A����Ƃ͈قȂ��������������l�����āA�����3K�ƌv�Z�����B�����A�̂��قǏo�ł��ꂽ�ނ̒����u�F���̑n���v�ɂ́A�F���̔N�30���N�Ƃ̑z��̂��ƂɁA�����50K�Ƃ����B���̌�A�K���t�͂���ɁA�����1953�N�ɂ�7K�A1956�N�ɂ�6K�ƕς��Ă���B �v����ɁA�r�b�O�o���̎x���҂̌v�Z�����w�i���˂̉��x���A���̌���ۂɊϑ����ꂽ���l�ɁA��ɋ߂������킯�ł͂Ȃ��B���݂̊ϑ����ʂ�2�D73K�Ɉ�ԋ߂������̂́A�r�b�O�o���x���҂��v�Z�����w�i���˂̉��x�ł͂Ȃ��A�ނ��냌�Q�i�[�̌v�Z������͌n�ԋ�Ԃ̉��x(2�D8K)�������B �F���w�i���˂̔����Ƃ��̉��߂ɂ��� �Ƃ���ŁA1950�N�ォ��1960�N�㏉���ɂ����ċ������鉼���A��Ƃ��ăK���t�����̎x������r�b�O�o���_�ƁA�z�C�������̐������F���_���h��Ș_�����J��Ԃ��A�����傰���ɂ����A�F�����_�Ƃ����̐퍑����̂悤�ȗl����ттĂ����B�������A���������́A�Ȋw�̔��W�̂��߂ɂ́A�K�v�ł������]�܂������Ƃł�����B 1965�N�ɁA�E�B���\���ƃy���W�A�X���F���w�i���˂��������_�ŁA���̏͋}�ς����B���̊ϑ����ʂ́A�����v�����X�g����w�̃��o�[�g�E�f�B�b�P�Ƃ��̓����������v�Z���āA��Ή��x3�D5K�̉F���w�i���˂ł���ƌ��_�����B���R�Ȃ���A�f�B�b�P�����́A���傤�ǂ��̂���ނ玩�g�A�F���̔w�i���˂��ϑ�����v��𗧂Ă悤�Ƃ��Ă����Ƃ��낾�����B �������A�E�B���\���ƃy���W�A�X�̒n��ϑ��ł́A3�D5K�̍��̕��˂̃s�[�N�͊ϑ��ł��Ȃ���������A���̉��x�̐���ɂ͊O�}�@(����ψ���̂������̕ϐ��ɑ��Ċ������m���Ă���Ƃ��A���̕ψ�O�Ŋ��l�𐄒肷����@)���p�����Ă��āA���̉��x�̐���l�ɏ��X�s�m���ȂƂ��낪�������̂͂�ނȂ��Ƃ��낾�낤�B �����œǎҏ����ɂ�����x�v���o���Ă��������������A�r�b�O�o���̎x���҂̑��ɂ��A��͌n�ԋ�Ԃ�P���ԋ�Ԃ̉��x���v�Z�����V���w�҂�30�`40�N�O���炷�łɂ��āA�������̉��x�ƔM���t��Ԃɂ�����ח��q�����݂��Ă��ꂪ�ϑ��\�Ȃ�A��Ή��x�ɂ���3K�t�߂̔w�i���˂��ϑ����ꂤ��\������Ă����̂��B �������A�r�b�O�o���̎x���҂������E�B���\���ƃy���W�A�X�̊ϑ��ȑO�ɗ\���������x�́A�ϑ����ꂽ���l��3�D5K�������Ȃ荂�����̂����������B �ɂ�������炸�A�V���w�҂݂̂Ȃ炸�A�Ȋw�҈�ʂ̑命���́A���̔w�i���˂̊ϑ����r�b�O�o�����̐�ΓI�ȏ����ƌ��Ȃ����B����Ȏ����͂Ȃ������ɂ�������炸�A�z�C�����g���ނ̐��̔s�k��F�߂��Ƃ����悤�ȉ\��U��܂��l�����܂ŏo�Ă����B ���̌��ʁA���F���_�͑命���̐l�����ɖ��������悤�ɂȂ�A��ʓI�Ɉْ[�_�Ƃ܂ōl������悤�ɂȂ��Ă��܂����B �@ |
|
| ���F���̑�K�͍\��(�O���[�g��E�H�[��)�ƃr�b�O�o�����_�̖��� | |
|
�R���m�E�P���C�`���̒����u����̐��E��˂��Ƃ߂��ʎq�͊w�v�ɂ́A���Ăł͒m���Ă��Ă����{�ł͂قƂ�ǏЉ��Ȃ�(�Ӑ}�I�ɕ������Ă���H)�悤�ȏd�v�Ȏ������������w�E����Ă��܂��B
�r�b�O�o�����_�ƃO���[�g�E�E�H�[��(�F���̑�K�͍\��)�̊W�����̈�ŁA�R���m���́A���̂悤�ɏq�׃r�b�O�o�����_�̊�ȓ_���s���˂��Ă��܂��B �u����̐��E��˂��Ƃ߂��ʎq�͊w�v �E�E�E ���Ƃ��u�n�̂��Ă��݂�����ɂȂт��Ă���v�ʐ^�����āu�n�������Ă���v�Ɖ��肵�Ă��A��ɂȂ��ĕʂ̃��[�r�[������Ɓu�O�����畗�������Ă��������v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃł���B�u�r�b�O�o�����_�v��u�A�C���V���^�C�����ΐ����_�v���A����Ƃ܂�������������Ƃ��Ă���̂ł���B�u�r�b�O�o�����_�v�̊�{�ƂȂ����̂́A�G�h�E�B���E�n�b�u�����ϑ��Ō��o�����u�F���̐ԕ��Έځv�Ƃ������ۂ��u��͂����ꉓ�������Ă���v(�n�������Ă���)�Ƃ����^����ԂƉ��߂��A�������u�F�����c�����Ă���v�Ƃ������藝�_�𐔊w�I�ɔ��W���������Ƃ���n�܂����B �c���Ƃ����^���ɂ͕K���u�n�܂�v������B�n�b�u���̖c���萔���t�Z����ƁA�u�F��(���ԂƋ��)�͕S�\���N�O�ɒa�������v�ƂȂ����̂ł���B �������A�u�r�b�O�o�����_�v�̌��_�ƂȂ����u�F���̐ԕ��Έځv�Ƃ������ۂ́A��͓��m�����ꉓ�������Ă���Ƃ����^����Ԃ��W�J�Ɋm�F�����킯�ł͂Ȃ��B�u�n�̂��Ă��݂�����ɂȂт��Ă���v�Ƃ����ꖇ�̐Î~�ʐ^(���܂�ɂ��X�̋�͉͂����ɂ���̂ŁA�^���̒��ڊm�F�͂ł��Ȃ�)�����āu�n�������Ă���v�^����ԂƉ��߂��A�u�ǂ�����X�^�[�g�����̂��A���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��H�v�Ƃ������_�𐔊w�I�ϓ_����ςݏd�˂����̂ł���B ���������x�̍����ʂ̎ʐ^�⃀�[�r�[�Łu�n�������Ă��Ȃ������v���Ƃ�������A�r�b�O�o���F���_�͒����ɕ��Ă��܂��B�u�r�b�O�o�����_�v������̓r��Ƃ����̂́A�n�b�u���F���]�����̂悤�Ȑ��x�̍����V�̊ϑ��@�킪�ł��グ���āA�r�b�O�o�����_�Ƒ傫���������錻�ۂ����X�Ɣ�������Ă��邩��ł���B ���̍ő�̂��̂ɁA�F���̑�K�͍\��(�O���[�g�E�E�H�[��)�̔���������B �r�b�O�o�����_�ł́A�F�����a�������͕̂S�\���N�O�Ƃ���Ă������A�n�b�u���]���������������O���[�g�E�E�H�[�����`�������ɂ́A���ƈ�牭�N��������̂ł���B���̔N���e������킯���Ȃ����A�n���̎R��C���n���̒a�����Â��킯���Ȃ��B ���ꂾ���ł͂Ȃ��B�n�b�u���F���]�����̐V���Ȋϑ����ʂɂ���(�����A�r�b�O�o�����_�̊�{�Ƃ���Ă����ԕ��Έڂł����݂��̋�͓��m�����ꉓ�������Ă���Ƃ������߂����������)�A�F���̔N��̓r�b�O�o���������S�\���N�O���甼����70�`80���N�O�ɏC������Ă��܂��̂ł���B�O���[�g�E�E�H�[�������������A�F���ɂ͔N��S���N�p���T�[�̂悤�ȓV�̂��U���ɑ��݂���̂ł���B���\�`���\���N�����o�Ă��Ȃ��F���̒��ɁA�S�����牭�̃p���T�[��O���[�g�E�E�H�[�������݂���̂́A�ǂ��l���Ă��I�J�V�C�B ���ꂾ���ł��r�b�O�o�����_�̔j�]�͏[���Ƃ����邪�A���������r�b�O�o���̊�{�u�n�b�u���萔�v(�F���c��)�������������Ȃ�A�O���[�g�E�E�H�[���Ɍ������͏W�c�̃{�C�h(�o�X�^�u�̖A�̂悤�ȕ\�ʂɋ�͂��W�����A�A�̒��͉���������)�Ȃnj`�������킯���Ȃ��̂ł���B �������A�u�F���̐ԕ��Έځv�͌����Ɋϑ�����镨�����ۂł���B�ƂȂ�ƉF���̐ԕ��ΈڂƂ������ۂ́A�r�b�O�o�����_��������͂����ꉓ������(�n�������Ă���)�^����Ԃ��������̂ł͂Ȃ��������ƂɂȂ�B�E�E�E �R���m���ɂ��Ă��A�ߓ����ɂ��Ă��A�E�C�������Ă����̎������@�肨�����Ă��邻�̎p���ɂ͐S��h�����܂��B ���{�ł́A�ǂ̊w�҂��u�r�b�O�o�����_�͊��S�ɐ������v�Ƃ����O��Ř_��i�߂Ă����܂����A���Ă��ď�Ȃ��Ȃ�܂��B �����̂悤�ȁu�����������߂����邪�A������������������̂�����A���̂悤�ɂ����߂ł���v�Ƃ������l�ȉ��߂������ɕ��ׂČ�������Ƃ����A����Ȑ^���Ȏp�������{�l�w�҂ɂ͌����Ă��܂��B �ᔻ���_��Y��A���������u�A�C���V���^�C�����I�C���t���[�V�����r�b�O�o�����_���I�v�Ɨ��s�ɏ�������Ă����ގp�́A����͊w�҂̂���ł͂���܂���B �Ȋw�҂́A�͂₭�C�Â��Ȃ���Ȃ�܂���B�C�Â����҂̏����ł��B�@ |
|
|
������M�����m�̌��t
�����ȓV�̕����w�ҁE����M�����m(�_�ސ��w����)�́A�u�F���ɂ͈ӎu������v�̒��ŁA���㕨���w�̌��ׂƂ������ׂ��A���w�Ώd�̊댯���ɂ��Ă��̂悤�ɏq�ׂĂ����܂��B ����́A���㕨���ւ̌x���Ƃ��Ƃ�܂��傤�B �u�E�E�E�����w�҂̒��ɂ́A������p�����\�����ł���������A����ł悵�ƍl����l�����������B���������������Ƃ������w���Ǝv���A���̐����̕����w�I�Ӗ����l���悤�Ƃ��Ȃ��l���A���X�ɂ��Ă���B�������A����Ȃ����ł͖{���ɕ����w�̌������ł���̂��A���ɂ͋^��ł���B������A�u(��)���ŏ����A�����Ȃ邩��E�E�E�v�Ƃ�������������l�ɑ��āA���́u���̎��̕����I�ȈӖ�����悤�ɐ������Ăق����v�Ɛq�˂邱�Ƃɂ��Ă���B����ƁA�����Ă��̐l�́u���ăo�J�ȓz���v�Ƃ����������B�����A����ł��˂�����ŕ����Ă݂�ƁA�����Ƃ��������Ȑ������ł���l�͈ĊO���Ȃ��B����͐����̎��Ӗ���B���ɂ����l���Ă��Ȃ�����ł���B�����w�҂ł���A�����Ȃ̂�����A�w�Z���炪�����Ώd�ɂȂ�̂����R�Ȃ̂�������Ȃ����A����͂Ȃ�Ƃ��c�O�Ȃ��Ƃł���B���̎Ⴂ�l�ɂ͕����w�����������A�Ƃ����b���悭�������A����͐����Ώd�̂����ł͂Ȃ����ƁA���ɂ͎v���ĂȂ�Ȃ��B�E�E�E�v �����ǂƂ��A�S�������I�ƐS�ŋ��т܂����B(�����������������Ă����̂�) ����́A���㕨�����̂��̂ւ̌x�J�Ƃ����Ă悢�B �C���t���[�V�����r�b�O�o�����_�Ȃǂ��A�܂��ɍ��x�Ȑ����̗V�тɂ������A���Ӗ����̂��̂ƒf���ł��܂���(��ʑ��Θ_���R�ł������)�A�㕶����A����F���_�̐Ƃ��A�낤�����ǂ����Ă��v�킴������܂���B �����F���_�����ł͂Ȃ��̂�������܂���B �u10�����̐��E��\�����]����6�����͔����Ȑ��E�Ɋ������܂�Ă��邩��ϑ��ł��Ȃ��̂��I�v�Ǝ咣����C���`�L���������v���v�����钴�����_���ǂ����u���͉R�ł����v�ȂǂƂȂ�Ȃ��悤�ɋF�����ł��E�E�E�@ �@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_�̌��ɂ��� | |
|
��ʑ��ΐ����_�ɂ�������_(���)���w�E���܂��B����̗��_�����w����ʑ��ΐ����_����{�̈�Ƃ��č\�z����Ă���̂��Ƃ���A����́A�����̖��(���)���܂�Ō���Ɏ����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B
��� 1. �d�͐ԕ��Έڂ����ȏ��ɂ���āA�c�h�b�v���[���ʂŐ�������Ă�����̂ƁA���h�b�v���[���ʂŐ�������Ă������(�Ȃ�)�Ƃ���܂����A��̃h�b�v���[���ʂ͕����I�Ӗ����܂������قȂ���̂ł��B�]���āA��Ƃ���(�ȏ�)�ɐ�������Ă��邱�Ƃ͂��������B 2. ��ʑ��ΐ����_�ŁA�V�������c�V���g����(�Ⴆ�Α��z�n)�ɉ��āA��Ԕ��a������(�l�Ԃ̖ڂ̑O�̒Z�������ł���)��{�̕��w�̒�������ȏ゠�邱�Ƃ͖����ł���B 3. �V�������c�V���g�\�ʂ��A�����w���_���"����"�ł��鎖�ۂ̒n���ʂł���A�����������(�l�Ԃ̊���̎��v�Z�ł���)��ʍ��W�ϊ��Ő���������ł����肷��݂����̓��ٓ_(��)�ł����邱�Ƃ͖����ł���B�@ �@ |
|
| ���r�b�O�o���F����u���b�N�z�[���𐳂����Ƃ܂��M���Ă���̂ł����H | |
|
1)�@�u���b�N�z�[���̊T�O�̌��ƂȂ����V���o���c�V���g�̉��͂��鎿�_�����z���A���̉��̏d�͏�����Ώ̂̌`�Ƃ��d�͏ꂪ�ω����Ȃ��Ƃ��ɁA�A�C���V���^�C���̕������ɏ]���ĉ��������̂ł���B��ʑ��ΐ����_����������Ɖ��肵�Ȃ���A��ʑ��ΐ����_�̐������Ȃ����ٓ_�Ƃ��Ă̎��_�������Е��ʼn��肷��Ƃ�������������@���������Ă���B����͖��炩�ɐ��w�I�ɊԈႢ�ł��茈���ău���b�N�z�[���͑��݂��Ȃ��B�܂����_�̌`����ʎq�͊w�Ő������悤�Ƃ��Ă��邪����͖��̂���ւ��ɉ߂��Ȃ��B
2)�@�F���͗B�ꂱ�̉F�������Ȃ��B�����I�Ɋϑ��s�\�ȉF���������ɂ����X�̏Z�މF�����A���̒���1�ɂ����߂��Ȃ��Ƃ����l���͖��炩�ɘ_���I�ɂ��蓾���A�ԈႢ�ł���B����䂦��150���N�O�ɉF�����ˑR�o�������Ƃ������Ƃɑ���A�_���I�ȕK�R��������ł��Ȃ�����̓r�b�O�o���F���̗��_�Ƃ��Ă̐������͂Ȃ��B 3)�@�A�C���V���^�C���͎���̘c�݂̐����Ƃ��ė͂������Ă��Ȃ�������L�т���k�肵�Ȃ����̂̑��ʖ_���l������A���̑��ʖ_�̊T�O�͂܂������ł��������C���[�W���Ă��顁@���̕��������ɋ߂������ʼn~�^��������Ɠ��ꑊ�ΐ����_�̌��ʂɂ���āA�����ĕό`���邱�Ƃ��Ȃ��Ɖ��肵���ɂ��ւ�炸�A�������ό`�������̂悤�Ȍ��_�������炳���B����͎��͋�Ԃ̘c�݂Ƃ����T�O�ɂ����������ƍl�����̂���ʑ��ΐ����_�ł���B��ʑ��ΐ����_�ł͕����Ƌ�Ԃ�ʕ��Ƃ��Ď�舵�����R�Ȃǂ܂�łȂ��B��ʑ��ΐ����_�ŋ�Ԃ݂̂����k��c�������A���̕��������̂܂܂̑傫���Ƃ������͂��蓾�Ȃ��B��ʑ��ΐ����_�̗��O�ɏ]���A��ɋ�Ԃƕ����͓��l�̘c�݁E�c���E���k�����邽�߉F�����c������k������悤�Ɋϑ�����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��B 4)�@�F����Ԃł́A�d�͂��d�v�Ȗ������ʂ����M�͊w��2�@���͂��̂܂܂ł͐��藧���Ȃ��B�d�͂��l���ɓ���M�͊w��2�@�����l����ƁA�F���ł͕������M�I���t�ɂ��镔���ƁA�d�͓I�ɕ������ÏW���Ă��镔�������݂��Ȃ���A�Ⴂ�Ɏp��ς����̂悤�ȏ�Ԃ̕ω����P�v�I�Ȃ��̂Ƃ��đ��݂�������B 5)�@�y���W�A�X�ƃE�B���\���̔��������F����2.7�j�w�i���˂��`������n�͉F���S�̂ɍL�����ΐÎ~�n�ł��肻��͐^�̊����n�ł���B����ȊO�̏]�������n�ƍl�����Ă����n�́A�����ɂ͉����x�n�Ƃ������ƂɂȂ�B�F����Ԃɑ��݂��镨����2.7�j�ŔM�I���t��Ԃɂ��肱���̕�������2.7�j�̔w�i���˂��s�Ȃ���B �@ |
|
|
6)�@�F�����L���ł���A���̋�Ԃ͋Ȃ����Ă���A���̒���i�ތ��͓��R�̎��Ȃ���A�Ȃ����Đi�ށB�F���̋ȗ����������ȂǏ]�������n�Ƃ��ꂽ�^���n�̉����x�̌��ł���B�w�i���˂��`������n����ΐÎ~�n�ł��邩��A���̂悤�ɑ����X�s�[�h�ʼn^�����镨���ɑ��Ă��̉����x�Ɗ������ʂ��������킹���͂Ő�ΐÎ~�n�ɂƂǂ܂点�悤�Ƃ�������ɗ͂������B���ꂪ�܂������ԕ��ΈڂƂȂ��Ċϑ������B
7)�@�F�����L���ŕ��Ă���A���q�͂��̑傫�����R���v�g���g���Ƃ���Î~���ʂ������ƂɂȂ�B���������̐Î~���ʂ͉F���̑傫�����ɂ߂đ傫���ׂɔ��ɏ������B���q�����̎��ʂ����o�ł���قǂ̑����ɂȂ����Ƃ��ɂ͋Ɍ��̑����Ƃ��Ă̌����xC�Ƌ�ʂł��Ȃ����A���m�ɂ͌��͑��x�[������Ɍ��l�Ƃ��Ă̌����xC�����܂ł̂����鑬�x�ʼn^���\�ł���B 8)�@�N�F�[�T�[�̓r�b�O�o�����f���ɂ��ΉF���̏����ɂ̂ݑ��݂����Ƃ����V�̂ł���B����������͖{�����낤���B���݃N�F�[�T�[�͋�͂Ƌ�͂̑��ݍ�p�ɂ���Č`�������Ƃ�������L�͂ł��邪�A���ꂪ��������N�F�[�T�[���O�ɒʏ�̋�͂��K�v�ɂȂ邵�A���݂ɂ����Ă����̗l�ȑ��ݍ�p�͂����ėǂ��͂��ł���B�܂���͂ƃN�F�[�T�[�����ݍ�p������炪�قȂ����ԕ��Έڂ������Ƃ������ۂ��z�[���g���E�A�[�v���������A���̂��Ƃ͓V���w��疳������Ă���B 9)�@�w�i���˂����邱�Ƃ��F���ɂ͐�ΐÎ~�n�����݂��邱�Ƃ��킩�邪�A���̎��͉F���ɂ͐Î~�n��������ł�����Ƃ������ꑊ�ΐ����_����ł̉��������ے肷�邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ�����ꑊ�ΐ����_�͏C�����K�v�ł��邱�ƂɂȂ�̂����A�����̓I�ɏC���Ă��������B����ɂ�茻�݊ϑ�����Ă���ԕ��Έڂ�����������̂����A�ɂ߂ĉ����ł͌��݂̈�ʓI�ȗ\���Ƃ͈قȂ��Ă���B�V�����l�����ɂ��A�]���F���̒n�����܂ł̋����ƍl���Ă����������F���̋ȗ����a�ƂȂ�B�܂���ʑ��ΐ����_�̗��O����́A�F���͖c�������k���ł��Ȃ��͂��Ȃ̂ɁA��ʑ��ΐ����_�������ƉF���͒���Ԃɂ���Ȃ��ƌ����������������邽�߂Ɉ�ʑ��ΐ����_�Ɍ����x�b�ȊO�ɉF���̋ȗ����a�q��萔�Ƃ��Ċ܂܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��������B 10)�@�Ñ�M���V���ł͓V���������ł͂Ȃ��n�������������Ă���n���̐��m�ȑ傫�������߂��Ă����B�������V�����̓v�g���}�C�I�X�ɂ���Ċ������ꏟ���������߂��B���̓V�����ɂ͊ϑ����ʂƐ��������邽�ߑ��݈Ӗ��̕s���Ȏ��]�~�Ƃ������̂�79���̗p���Ă���B����ɂ����ẮA�r�b�O�o���F�����嗬���߂Ă��邪�A���̉F���̒a�����Ƃ���鎞���̐��������܂����Ȃ����߁A���̎����ɂ����ʗp���Ȃ��]���̕����w�펯�Ƃ͔�����C���t���[�V�������_���̗p���Ă���A������������ق���т������n�߁A�X�ɗ��_�����������悤�Ƃ��Ă���B����͐��Ɍ���̎��]�~�ł���B �@ |
|
|
11)�@�G�l���M�[�ɂ͐F�X�Ȏ�ނ����邪�A�^���G�l���M�[����ƂȂ�B�����ăG�l���M�[�̕ۑ������d�v�Ȋ�Ƃ��ĉF�����`������Ă���B�G�l���M�[�ۑ�������v�l�������s���Ɓu���ʁ��G�l���M�[�v�ł��邱�Ƃ��킩��A����ɕK�R�I�ɑ��ΐ����_���������B�܂��G�l���M�[�͓�������ɂ����Ƃ����������ʂɂ��̌�������A����ɂ��̊������ʂ͉F���S�̂ɑ��݂��镨������̏d�͍�p�ɂ���Ă�����ƍl������B
12)�@�ĉȊw���́u�T�C�G���X�v1998.2.27���s�ɉF���̖c������������Ă��肻�̌����͔��d�͂Ƃ��Ắu�F�����v�����݂��邽�߂ł��낤�Ƃ����L��������܂����B�F�������Ō������̃G�l���M�[�ɔ�Ⴕ���͂Ő�ΐÎ~�n(�w�i���˂��Ȃ��n)�ɂƂǂ߂��悤�Ƃ���ƁA�������ケ�̂悤�Ɋϑ�����邱�Ƃz�[���y�[�W�ɂ����ė\�����Ă��܂����B���������F���͏��������ƍl���ėǂ��͂��ł��B 13)�@��ʑ��ΐ����_�̐��ƂƎ��̂������Ƃ̃u���b�N�z�[���ɂ��Ă̋c�_���f�ڂ���Ƌ��ɁA�Ȃ����Ƃ̓u���b�N�z�[�������݂���Ƃ����Ԉ�������_���o���Ă��܂����������̘_���ߒ����������邱�Ƃɂ�薾�炩�ɂ��܂����B���w�I�ɂ͂��ׂĂ̗��_���K�p�s�\�ȓ��ٓ_�Ƃ������̂���Ɋ��ɑ��݂�����̂Ƃ��Ď�舵���Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B 14)�@�F���͌����c����������c���ɕω����Ă������Ƃ��������嗬�ƂȂ����悤���B���̒���L���ŕ��Ă��Ėc�������k�����Ȃ����F���ł́A���܂łɎ������ȒP�ȉ����݂̂ŁA���̂悤�ɉ��߂����悤�Ȋϑ��f�[�^�������邱�Ƃ��������B�@�ȗ����a�q�̉F�����^��������̉����x�Ɗ������ʂ��������킹���͂Ō����ΐÎ~�n�ɂƂǂ܂点�悤�Ƃ�������ɗ͂������A���ꂪ�ԕ��ΈڂƂȂ��Ċϑ������B���̐ԕ��Έڂ̓r�b�O�o���I�ɂ͉����c�����Ă���悤�ɉ��߂����B�����ɉF����1/4�����邱��ɂ͉F���͂قƂ�ǍL�����Ă������t�ɂ��ڂ܂��Ă����Ƃ������ʂ�����ɉ����A�r�b�O�o���I�l����K�p����ƁA�����ߋ��ɂ͌����c�����A�ŋ߂ɂȂ�����c������悤�ɂȂ����Ɖ��߂���邱�ƂɂȂ�B 15)�@�z�[���y�[�W�J�݈ȗ��̐����ƌ��݉F���_�W�̐��Ԃ̏ɂ��ď������B�����̓V���w�҂��r�b�O�o�����^�⎋���Ă���A�z�[�L���O�͓��ٓ_������������ȈӖ��ł̃u���b�N�z�[���̑��݂�ے肵���B���̃r�b�O�o����u���b�N�z�[���ɑ���ے�̏ؖ��̓p���h�b�N�X�ł���A���������_������Ȃ������ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@ |
|
|
16)�@�c���F���ȊO�ł́A�����̒��V���̈�A�̌��q�̕��o�̌o�߂�����ł��Ȃ��ƌ����Ă����B�����Œ��Ă�����F�����f���ł͂��ꂪ�����ł���B�����������Ă�����͏d�͂̍�p�ɂ���ΐÎ~�n�ɂƂǂ߂��悤�Ƃ����ׂ̈ɐԕ��Έڂ������ƍl�����B����͏d�͐ԕ��Έڂł���A���̎���艓���̓V�̂ł͂������痈����̐ԕ��Έڂ���1���������l�������Ԃ��������i�ނ��Ƃ��킩��B�܂����ꂩ��ߋ��ɂ����Ă͎��Ԃ̐i�ݕ����x���������Ƃ��킩��B�����ɂ�蒴�V���̌��q�̕��o�������Ȃ邱�Ƃ����m�ɐ����\�ł���B
17)�@���V���̊ϑ��f�[�^���瓾����ԕ��ΈڂƋ����̊W�ƒ��F�����f������\�z�����ԕ��ΈڂƋ����̊W�̃��C�������ۂɌ����܂����B���V���̃f�[�^��2004�N�ɔ��\���ꂽ�����̃f�[�^��p���܂����B���̂܂܂ł͑S����v���܂���ł������A���F�����f�����瓾���郉�C���̋�����z+1�{�ɕ����Ɗϑ��f�[�^�ɂقڈ�v���܂����B����͖{���ϑ��f�[�^�̌��x�� (z+1)^2 �{�ɕ���ׂ��ł���̂����Ă��Ȃ������ł͂Ȃ����ƍl�����܂����B�܂���r�I�߂��̒��V���̃f�[�^����F���̋ȗ����a��150�����N���x�Ɨ\�z����܂����B 18)�@�N�F�[�T�[���ŗL�̐ԕ��Έڂ����\���ɂ��Č������܂����B�ŋ߂̕����Ɋ��N�F�[�T�[�Ȃǂ͒��S�̔��ɏd�͂̋��������ɕ��˕��ʂ�����Ɨ\�z����Ă���悤�ł��B�������̕��˕��ʂڊϑ�����ΌŗL�̐ԕ��Έڂ����\���͂���ƍl�����܂����B�܂����I�@�ւ��ԕ��Έڂ̈قȂ������(NGC 7603�@�Ƃ��̋߂��̋��)�����ݍ�p�����Ă���ƋL�ڂ��Ă��邱�Ƃ₻��炪���ۂɑ��ݍ�p���Ă���\�����������Ƃ̊ϑ����ʂ������܂����B�ŋ߂̐[���F���̊ϑ��ł͔��ɉ����̉F�����߂��̉F�����قƂ�Ǖς�肪�Ȃ��Ƃ������ʂ������Ă��邱�Ƃ������N�����ďЉ�܂����B 19)�@�F���}�C�N���g�w�i���˂��r�b�O�o���h��葁�������ɁA��萳�m�ɉF����Ԃ���̍��̕��˂Ƃ���Eddington��ɂ���ė\������Ă��܂����B�w�i���˂�10������1�̂�炬�̓r�b�O�o���ɂƂ��Ă��F���̏����ɑ�K�͍\������邱�Ƃ�����ł���Ƃ�����_������A���F�������̍���ł͂���܂���B�r�b�O�o���h�ɂ���čl����ꂽ�o�C�A�X���f���͒��F���ɂ��K�p�\�Ŗ��������ł��܂��B�ŋ߂̌����Ŕw�i���˂ɂ͑��z�n�⒴��͕��ʂɊW�����炬������A����͔w�i���˂���X�̋ߖT�̉F����ԗR���ł��邱�Ƃ���������������̂ł��B 20)�@���F����ے肷�闝�R�Ƃ��ĉF���}�C�N���g�w�i���˂�10������1�̉��x��炬�����Ȃ����ƁA�����Ă��̕��˂�2.725K�̐��m�ȍ��̕��˂��������Ƃ����̍����Ƃ���Ă��܂��B�@���F�����f���ɂ����ăV�~�����[�V���������Ƃ���A�w�i���˂̂قƂ�ǂ́A�͂邩��10�����N���̉����������Ă������̂ł���A�ߖT�̉F����Ԃ̕����R���̑e����炬�͑S�̂̒��ɖ����ꕽ�ω�����Ċ��炩�Ȃ�炬���`�����邱�Ƃ��킩��܂����B�@�܂�2.725K�̐��m�ȍ��̕��˂́A�F����Ԃ̕�������͂Ȃǂ̔M���˂���G�l���M�[��2.725K�������ۂ͂�⍂�����x�ƂȂ�@�ԕ��Έڂ���2.725K�̔w�i���˂���2.725K�Ɉێ����邱�Ƃ��\�Ȃ��Ƃ������܂����B�@����\�ȏ����Ƃ���150�����N�̋�������˂��i�ފԂɏ��Ȃ��Ƃ��F����Ԃ̕����ɂ���60%���z������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��킩��܂����B�@���̌��E�̏����ł͉F����Ԃ̕����̉��x��3.59K�ł��邱�Ƃ��킩��܂����B�嗬�h�̎咣�ł́ATired�@Light ���f���ł͍��ԕ��Έڂ̏ꏊ�ł̔w�i���˂�2.725K�����������x�����X�����Ă��Ȃ�������Ȃ��ƍl���Ă��܂��B����������͒��F�����f���ł͂Ȃ��A����F�����f���ł��B����������āATired�@Light ���f������ђ��F�����f����ے肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B 21)�@Case Western Reserve University �@��Lawrence M. Krauss ���������w�҃O���[�v���]���̕����w�҂̒�����A�u���b�N�z�[���̌`���̉ߒ��̓u���b�N�z�[���֗������Ă����ϑ��҂̎��_�ł͂Ȃ��A�O���̊ϑ��҂̗��ꂩ��l����ׂ��ł���A���ۂ̒n�������`������ɂ͖����̒����̎��Ԃ�K�v�Ƃ��邽�߁A�u���b�N�z�[���͑��݂��Ȃ��Ɣ��\���܂����B�@����͎��⑽���̑f�l�̕����咣���Ă������ƈ�v������̂ł��B�@Lawrence M. Krauss ���͕����w��̒��ł͔��ɏd�v�Ȑl���Ƃ��Ēm���Ă���A���㑽���̕����w�҂��Ǐ]����Ɨ\�z����܂��B�@�܂������ʑ��ΐ����_���瓯���������o���ꂽ�ƌ�����r�b�O�o���c���F�����l�����������̂ƍl�����܂��B �@ |
|
| ���A�C���V���^�C���͖c������F���ɔ����� | |
|
1917�N�A�A�C���V���^�C���͔ނ̓�������ʑ��ΐ����_���A�F���_�ɓK�p���悤�Ƃ��܂����B�����ɂ���ċ�Ԃ͘c�݂�����͂�������2�����̕��ʂ��ȖʂɂȂ�悤�Ȃ��̂ł���ƍl�����̂ł��B�����ĉF���ɑ��݂��镨�����ǂ��ł������悤�ɕ��z���Ă���̂ł���A�ǂ��ł������ȖʂƂȂ肻���2�����ōl����Ȃ���̕\�ʂ̂悤�ɂȂ�ł��낤�Ɨ\�z�����̂ł����B���̗ސ����A�C���V���^�C���͉F���Ɉ�ʑ��ΐ����_��K�p����ΉF���͗L���ŕ������E�ƂȂ�ł��낤�ƍl���܂����B����ɁA�ނ͉F�������ԓI�ɕω����čs�����Ƃ̂Ȃ��ÓI�Ȃ��̂ł���Ƃ�������������킦�܂����B�ނ̐M�O�ɂ��A�F�������ԂƂƂ��ɂ��̑傫����ς��čs���Ƃ������Ƃ͋�����Ȃ����Ƃł������̂ł��B
�������A1920�N��ɂȂ��āA�t���[�h�}������ʑ��ΐ����_����͌����ĐÓI�ȉF�����f���������o�����Ƃ͂ł����A�F���͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɖc�����邩�������͏k�����邩�̂ǂ��炩�ł��鎖���ؖ������A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B���̏ؖ��͂ނ����������̂ł��傤���A���̂����悻�̗����͈�ʑ��ΐ����_�̊T�O���g��Ȃ��Ƃ��j���[�g���͊w�����ŏ\���ł��B�n���̕\�ʂ��瓊�����{�[���͒n���ƃ{�[���Ƃ̊Ԃ̏d�͍�p�ɂ��A�������Ȃ���㏸���Ă��������͗������邩�̂ǂ��炩�����ł��B�Î~����̂͏㏸���痎���Ɉڂ��u�݂̂ŁA���ԓI�ɂ�0�ɂȂ�܂��B�Ƃ���ŁA�F���ɂ��邷�ׂĂ̕����͏d�͂ɂ���Č݂��Ɉ��������܂��B��̒n���ƃ{�[���Ƃ̊W���F���ɓ��Ă͂߂�ƁA�㏸����͖̂c���ɓ�����A��������͎̂��k�ɓ�����܂��B�����ĐÎ~�͂ł��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�܂�Î~���āA���ԓI�ɑ傫���̕ω����Ȃ��F���̓j���[�g���͊w�������ʑ��ΐ����_������������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ�̂ł��B �A�C���V���^�C���͂��̌��ʂ�m���ė��_���܂����B�����Ĕނ̐Î~�F�����f���𐬗������邽�߂ɁA�F�����ƌĂ�鍀���A�ނ̗��_�̂��Ƃ��Ƃ̕������ɕt�������܂����B�d�͂����͂����ł��邽�߂ɐÎ~���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ŁA���̂��߂ɂ��̈��͂ƒނ荇�킹�邽�߂ɁA�˗͂̍����F�����Ƃ��ĕt���������̂ł��B���̐˗͎͂����I�ɂ͑S����������Ă��Ȃ��ˋ�̗͂ł���A�ނ̐M�O�����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�͂ł��B�@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_�ɂ��F���̖c���Ƃ͂ǂ�Ȏ����Ӗ�����̂� | |
|
1929�N�n�b�u���ɂ���Ĕ������ꂽ�A�����ɑ��݂����͌n�قǐԕ��Έڂ������Ƃ��������ɂ��A�c���F�����L���M������悤�ɂȂ�܂����B��ɃA�C���V���^�C���́A���̐M�O���Ȃ��A�F���͖c������Ƃ����l�����������ƐM����悤�ɂȂ�ƂƂ��ɁA�F�����̓������w���́u�ő�̎��s�v�������ƌ����Ă��܂��B
�n�b�u���̔������{���ɖc���F�����x�����邩�ǂ����ɂ��ẮA���̏͂ł���ɏڂ����������܂��B�����ł͖{���Ɉ�ʑ��ΐ����_���Î~�F����ے肷��̂��ǂ����ɂ��Č������Ă݂܂��傤�B �����ŁA���̖��ɂ��Ďv�l�������s�����Ƃɂ��悤�B�c������F���̎��Ԃ��t�ɂ����ꍇ�A�܂��͎��k����F�����l���Ă݂悤�B�F���������ɂ��āA1/��(����1)�̐ςɂ���1/��3�Ɏ��k�����ƍl���Ă݂܂��傤�B���̂Ƃ��F���͂ǂ̂悤�Ɏ��k����̂ł��傤���B�F���̑�K�͍\���͂��̊����Ŏ��k���Ă����̂ł��傤���B��͂̑傫���͂ǂ��ł��傤���B�f���n�̑傫���͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�P���̑傫���͂ǂ��ł��傤���B���߂čl����Αf���q�̑傫���͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B���������ǂ̃��x���Ŏ��k��������̂ł��傤���B�ǂ����]���̖c���F�����f���ł́A���Ԃ��t�ɂ������A��艺�̃��x���ł̑傫���͂��̂܂܂ŁA��ԏ�̃��x�����A�܂�F���̑�K�͍\���A��́A�f�n�E�E�E�E�Ƃ������ԂɊԊu�������Ȃ���k���i��ł����ƍl���Ă���悤�ł�(���̕����𖾗Ăɉ���������̂����͒m��܂���)�B���������̎��k�̕����̍����������ł���Ƃ͎v���܂���B ������1�̎��k�̃��f���Ƃ��Ē����q���̎��k���l���Ă݂܂��傤�B���̂悤�ȓV�͎̂��k�ɂ�蕨�����x�����܂�A���͂⌴�q�̍\���͏��������S�̂������q��������Ȃ錴�q�j�ƂȂ�܂��B�ʏ�̌��q�̍\���͉�Ă��܂����A��艺�ʂ̃��x���̒����q�͂��̑傫�������ێ����Ă���̂ł��B���̐����̉ߒ��ł͒��V���������N�����A���̔����ɂ�肻�̐��̈ꕔ�𐁂�����܂����A���������Ȃ������������l�������A���̐��̎��ʂ͎��k�O�����k����قƂ�Ǖω��͂��܂���B ���̂悤�Ȏ��k�Ƃ͑S���قȂ���������̎��k�̕����ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B����͓��ꑊ�ΐ����_�ɂ�郍�[�����c���k�ł��B���P�b�g�Ō����x�ɋ߂��悤�ȑ����Ŕ�s�����Ƃ��܂��B���̂Ƃ��^���̕�����1/���Ɏ��k�����ƍl���܂��B���������ւ�傫�Ȑ��Ƃ����Ƃ��A���̃��P�b�g�͈��k�̂��߂ɔj��A���̒��̏斱���͎���ł��܂��ł��傤���B���ꑊ�ΐ����_�ł͂��̂悤�ɂ͍l���܂���B�O�̌n���猩��Ǝ��k���Ă���悤�ł��A���̃��P�b�g�̒��̏斱���͎��k���Ă���Ƃ������Ƃ��犴���Ȃ��ʼn߂������Ƃ��ł��܂��B�܂胍�[�����c���k�ł͕����̍ŏ����x���ɂ����Ă��������ɓ��������k���Ă��邽�߂ɁA�����̊�����k�����ǂ͂��̎��k�����n�̒��ɂ����ẮA���k�̂��ׂĂ̌��ʂ��L�����Z�����āA�܂��������k���Ă��Ȃ��̂Ɠ�����Ԃɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B���ɁA���P�b�g����s���Ă���Ƃ��Ƀ��P�b�g�̒��̏斱�����O�̉F���������ꍇ���l���Ă݂܂��傤�B���̂Ƃ��O���烍�P�b�g�������Ƃ��Ƃ͋t�ɁA�F���S�̂����P�b�g�̉^�������ɑ��ă��[�����c���k���܂��B�����ă��P�b�g���猩��ƁA�F���S�̂̎��ʂ������������������悤�ɂ݂��邱�ƂɂȂ�܂��B�F���̂ǂ����̘f���̏Z����1�̃��P�b�g�������Ŕ����Ƃ����Ĉ��k����Ď���͂��܂���B���P�b�g���猩��Ǝ��k�����ʂ��������Ă���悤�Ɍ����Ă��A���P�b�g�̊O�̎҂ɂƂ��ẮA��قǂƓ��l�̗��R�ɂ�肻���̎��k�̌��ʂ��ׂĂ��L�����Z���������Ă킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B�@�F���̎��k�������q���ƃ��P�b�g�̂ǂ���̗l�����Ƃ邩���l���Ă݂܂��傤�B����͎��͊ȒP�Ȃ��Ƃł��B�����q���̎��k�͂��̍l���ɑ��ΐ����_����������ł��炸�A����ɔ䂵�ă��P�b�g�̕��͑��ΐ����_�ɂ����k�ł��B�F�����f�������ΐ����_��蓾����̂ł����烍�P�b�g�̂ق��̎��k�������̗p����͓̂�����O�ł͂Ȃ��ł��傤���B�����œǎ҂̕��͉F�����f���͈�ʑ��ΐ����_�ł���A���P�b�g�͓��ꑊ�ΐ����_�ł͂Ȃ����Ǝv���邩������܂��A��ʑ��ΐ����_�����͓����������Ɠ��ꑊ�ΐ����_��蓱����邱�Ƃ��l������̎��k�̗l�������ꑊ�ΐ����_�ɂ���Đ����ł��Ȃ���Ȃ�܂���B �����āA���P�b�g����݂��F���̂��̂悤�Ȏ��k��������łȂ��A��Ԃ�3�̕������ׂĂɑ��ċN�������Ƃ��Ă��F���ɂ���l�ɂ͂�͂�킩��Ȃ��ł��傤�B�����Ă���͂܂������A��ʑ��ΐ����_�ɂ��F���S�̂����k�����̂Ɠ������ۂƍl���Ă悢�̂ł��B�@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_�̌��_�ɂ��ǂ� | |
|
��ʑ��ΐ����_�ɂ��Ẳ�����͂�������܂��B�����������̂��ׂĂ��^�ɁA��ʑ��ΐ����_�����S�ɗ��������l�ɂ���ď�����Ă���Ƃ͌���܂���B���̒��Ҏ��g�͊��S�ɗ������Ă���ƐM���Ă��āA���ۂɂ��̐����I��舵���ɂ��Ă�����Ă����Ƃ��Ă��A���̐^�̗��O�ɂ��ă}�X�^�[���Ă���ꍇ�͏��Ȃ��̂ł��B����������ƃA�C���V���^�C�����g���A���낢��ȌX�̏ꍇ�ɂ����āA��ʑ��ΐ����_��K�p����Ƃ��Ɍ��̗��O��Y��Ă��܂��Ă��邩������܂���B
��ʑ��ΐ����_���A���炵���A�����ăA�C���V���^�C�����V�˂ł���ƌ�����̂́A���̗��_���A�����ɂ�炸�ɏ����ɓ��̒��Ř_���ɂ���Ċ������ꂽ����ł��B�����āA�����̕����w�̂��낢��ȗ��_���A�����̐l�X�ɂ���Đςݏd�˂��`�����ꂽ���̂��قƂ�ǂł���̂ɑ��āA���ΐ����_�́A�A�C���V���^�C��������l�̗͂ɂ���Đ��ݏo����A�����Ă��̌�C�����s���Ă��Ȃ��Ƃ��낪���قȂ̂ł��B ���̂悤�ȗ��_�̐���◝�O�ɂ��čl����Ƃ��ɁA���̐l�ɂ���ď����ꂽ�����͂قƂ�ǐM�p����ɑ���܂���B���̗��_�̉��p�̐���ɂ��Ă͌��_�ɗ����Ԃ��Č������ׂ��ł��B ���Ĉ�ʑ��ΐ����_�̏o���_�͏d�͎��ʂƊ������ʂ̓������ɂ���܂��B���̂��Ƃ́A�d�͂Ɖ����x�̓����������Ӗ����Ă��܂��B�����Ă����蓾���鎞�ԓI��ԓI�Ȓl�̕����I���߂̋��ߕ����A�ނ̒���������p���邱�Ƃɂ��܂��傤�B (���ꂨ��ш�ʁu���ΐ����_�v�ɂ��ā@�`�D�A�C���V���^�C����)�@�K���ɑI�^����Ԃ̊�̂j�ɑ��đ��ΓI�ɏd�͏ꂪ���݂��Ȃ��悤�ȁA1�̎���̈悪����Ƃ���B���̂����A���ڂ��Ă��邱�̗̈�Ɋւ��Ăj���K�����C��̂ł���A���ꑊ�ΐ����_�̏����ʂ͂j�ɑ��đ��ΓI�ɓK������B���̓����̈���A�j�ɑ��đ��ΓI�ɉ�]���Ă����2�̊�̂j�f�ɏ��������čl���邱�Ƃɂ���B��X���l���Ă��鑜���m�肷�邽�߂ɁA������1�̕���ȉ~�Ղ������āA���̒��S�̂܂������ʓ��ň�l�ɉ�]���Ă���p�j�f���l����B�~�Ղj�f��̂ւ�ɍ������Ă���ϑ��҂́A���a�����ɊO���������͂�������B�d�d�d�d�d�d�d�d�~�ՂƂƂ��ɉ^������ϑ��҂��A1�P�ʂ̑��ʖ_���~�Ղ̂ւ�ɂ���Ɛڐ����Ȃ��悤�ɒu���Ȃ�A�K�����C�n���画�f���āA�����1���Z���Ȃ�B�Ƃ����̂́A�^���̂͂��̉^�������ɒZ�k���邩��ł���B����ɑ��đ��ʖ_���~�Ղ̒��a�����ɒu���A�j���画�f���āA����ǂ͂����Ƃ��Z�k���Ȃ��B �����ŏЉ���A�A�C���V���^�C���̍l�������킩��₷��������Ă݂܂��傤�B�����x�ʼn�]����~�Ղ��l�����ꍇ�A���S���͓����Ă��Ȃ����~�Ղ̉��͂��̂����������ʼn^�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���̉^���̑����������x�ɔ䂵�ď\���ȑ��������Ƃ����̒����͓��ꑊ�ΐ����_�̌��ʂ��܂��B�͂������Ă��Ȃ�������L�т���k�肵�Ȃ����̂̑��ʖ_���~�Ղ̉��ł��̐ڐ������ɒu���܂��ƁA���̌����ɂ��ւ�炸���ꑊ�ΐ����_�̌��ʂɂ�蒷�����k��ł��܂��܂��B�Ƃ��낪�~�Ղ̒��a�����ł͒����͏k�݂܂���B���Ԃɂ����Ă����̌��ʂ��āA�~�Ղ̉��ł͐i�ݕ����x��܂��B�܂����̉~�Ղ̔��a�Ɖ�]�X�s�[�h���炱�̉~�Ղ̉��̊O����������(���S��)�͌��肳��܂��B���̗͂́A�~�Ղ̊O�̊�ƂȂ�n�̐l���猩��Ί����̍�p(���S��)�Ɖ��߂���܂����A�~�Ղ̉��ɍ��|���Ă���l����͏d�͂̍�p�Ƌ�ʂ��邱�Ƃ͂ł��܂���B��ʑ��ΐ����_�ł́A���̏d�͂Ɗ����̗͂��ƍl���Ă��܂��B�܂��]�ɂ���ē���ꂽ�͂́A�d�͂Ɠ����ƍl���A��]�ɂ���č��̂̑��ʖ_���k�ނ��Ƃ���A�d�͂ɂ���Ă����̑��ʖ_�͓��l�ɏk�ނƍl����킯�ł��B�~�Ղ̉����璆�S�܂ł̋����̊Ԃɓ��ꑊ�ΐ����_�œ����邾���̎���̘c�݂��������A�����Ă��̎���̘c�݂́A���̎��ɉ~�Ղ̉��ɂ���ϑ��҂��������鉓�S�͂Ɠ������d�͍�p�ɂ���Ă������炳���ƍl����̂ł��B�܂�́A��ʑ��ΐ����_�œ����鎞��̘c�݂͓��������Ɠ��ꑊ�ΐ����_�ɂ���Ă���Ƃ����킯�ł��B ���Ă����ŋC�����Ă������������̂ͤ�A�C���V���^�C���͎���̘c�݂̐����Ƃ��ė͂������Ă��Ȃ�������L�т���k�肵�Ȃ����̂̑��ʖ_���l���Ă��邱�Ƃł�����̑��ʖ_�̊T�O�͂܂������ł��������C���[�W���Ă��܂�����̕����ɑ�����ꑊ�ΐ����_�̌��ʂɂ���āA�����ĕό`���邱�Ƃ��Ȃ��Ɖ��肵���ɂ��ւ�炸�A�������ό`�������̂悤�Ȍ��_�������炳���̂́A���͋�Ԃ̘c�݂Ƃ����T�O�ɂ����������ƍl�����̂���ʑ��ΐ����_�Ȃ̂ł��B�����ł́A���͂╨���Ƌ�Ԃ̋�ʂ͂܂���������܂���B��Ԃ̘c�݂͂܂��ɕ����̃C���[�W�ɂ���Đ�������Ă���̂ł��B�����̐l�X�ɂ���ĊԈ���ĉ��߂���Ă���̂́A��ʑ��ΐ����_�ł͋�Ԃƕ������ʕ��Ƃ��Ď�舵���悤�ɍl�����Ă���_�ł��B����������ꏊ�ɂ����Ă���傫�����߂Ă���ȏ�́A�����ɂ����Ă͂��̕������̂��̂���ԂȂ̂ł��B���܂ł̉F�����f���ɂ����ẮA�F�����c������k������Ƃ��ɁA�������`�����錴�q�Ȃǂ̑傫���͕ς�炸�A���������ċ�͂Ȃǂ̓V�̍\���̑傫�������̂܂܂ŁA���̊Ԃ̉F����Ԃ����������Ȃ�����L���Ȃ����肷��悤�ɍl���Ă��܂��B��������ʑ��ΐ����_�ł͕����Ƌ�Ԃ�ʕ��Ƃ��Ď�舵�����R�Ȃǂ܂�łȂ��̂ł��B�A�C���V���^�C�����������悤�ɁA���ԂƋ�Ԃƕ������݂��ɓƗ��������̂ł͂Ȃ��A���݂��ɊW�������ĉF���Ɏ����݂���̂ł��B��Ԃƕ�����ʕ��Ƃ��Ĉ��������̑傫�������̂܂܂ŕ����Ԃ̋������ω����F�������k��c�������Ă����悤�ɍl����̂́A�j���[�g���͊w�̍l�����ł��B�Ȃ���ʑ��ΐ����_��p�������ʂ��A�j���[�g���͊w�Ɠ������ʂɂȂ�ł��傤���B���̂����������Ȃ��F�����Ȃ��̂����ɕs�v�c�ł��B�@ |
|
| ���Ȃ���ʑ��ΐ����_�̉��߂��Ԉ�����̂� | |
|
����܂łɏq�ׂ����R�ɂ��A�F���S�̖̂c������k�͕s�\�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B�������Ȃ��S�Ă̐l�X���ɕ����w�҂��Ԉ�������߂����Ă���̂ł��傤���B���̗��R�������ōl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B
�܂���ʑ��ΐ����_�ɂ���Ԃ����k�܂��͖c������Ƃ������Ƃ�����Ƃ��܂��B���̂悤�ȋ�Ԃ̖c���܂��͎��k���ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��Ӗ�����̂��͕��G�Ȗ��ł��莄�ɂ͂ƂĂ������ł��܂��A�傫�ȏd�͂�L���鐯�̎��ӂł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ��N���ċ�Ԃ̘c�݂ƂȂ�킯�ł��B�������F���S�̖̂c�����k�͂ǂ��ł��傤���B�S�̓I�ɖc�����邩���k���邩�͂����܂ł��O���猩���Ƃ��̃C���[�W�ł�������܂���B�F���ɊO�Ƃ����T�O�͑��݂��Ȃ��̂ł����炠���܂ł��F���̒��őS�Ă��l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł��B�����F�������k���悤�Ƃ��Ă���ʑ��ΐ����_�̗��O�ɏ]���A���̒��Ɋ܂܂��S�Ă̕��������l�Ɏ��k����̂ł�����A�F���̑傫���𑪒肷�镨�������̂��k���ǂ͂��̎��k�̌��ʂ��L�����Z�����Ă��܂��܂��B���̂悤�ɍl�����ꍇ�F���̊�Ƃ��Ă̑傫���݂̂��c�����āA���̒��ɑ��݂��镨���͂��̑傫����ς����Ɏ���ɊɂȂ��Ă����Ƃ����l���͑S���̃i���Z���X�ł��B�F���̊T�O���͂�����Ɛg�ɂ��Ă��炸�A�F�����X�ɑ傫�Ȃ��̂̑��݂����肵�����̕��������g���ĉF���̑傫���𑪂낤�Ƃ��Ă��邩��Ԉ���Ă��܂��̂ł��B ��ʑ��ΐ����_���̂͌����Ė��\�̗��_�ł͂���܂���B�j���[�g���͊w�͌����ɋ߂������ł͖��͂ł������A���ꑊ�ΐ����_�ł͂��̂悤�ȏꍇ�ł��K�p���鎖���ł��܂��B���������ꑊ�ΐ����_�ł��Ȃ������x���z�����Ȃ����x�ł��̂悤�Ȓl���Ƃ��Ă���̂��͕�����܂���B�܂���ʑ��ΐ����_�ł��F���S�̂��ǂ��Ȃ��Ă���̂����l����ꍇ�܂��܂���͂Ȃ̂ł��B�Ⴆ�ΉF���̑傫�����v�Z����ꍇ�A��ʑ��ΐ����_�����ł͉���������܂���B�F���̒��ɂǂꂾ���̎��ʂ��ǂ̂悤�Ȗ��x�ő��݂��Ă���̂��Ƃ�����O�����Ė�����Ή��̌v�Z���ł��Ȃ��̂ł��B���Ȃ킿��ʑ��ΐ����_���̂ɂ͉F���̑傫�������肷�邾���̗͂��Ȃ����ƂɂȂ�̂ł��B�F���̑傫�������肷��͂��Ȃ����_�ɉF���̑傫�����ω�����Ƃ������������҂��邱�Ǝ��̂����������̂ł��B�F���̑傫�������肷�邱�Ƃ��ł��闝�_�Ƃ́A�����ƑS�Ă̂��ƗႦ�ΉF���ɂ͂ǂꂾ���̕��������݂���̂��Ƃ������Ƃ����̗��_���̂��瓱���o����悤�ȗ��_�łȂ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B���������̏�����������_������̂��ǂ�������s���ł��B�@ |
|
| ����ʑ��ΐ����_����͒��F����������� | |
| �r�b�O�o�����f���ł͉F�����L���ł��邩�ǂ����͉F���̖c���̑����ƉF���̖��x�̊W�Ō��܂�܂������A�����ł̎��̎咣�ɏ]���A�F���̖c���͕K�R�I�Ƀ[���ɂȂ�̂ł����瓖�R�F���͗L���ŕ��Ă�����F���łȂ���Ȃ�܂���B�������낢���ƂɁA���̉F�����f���͂܂������A�C���V���^�C�����n�߂ɗ\�z�������̂Ȃ̂ł��B���̃��f����������ʑ��ΐ����_�̗��O�ɗB�ꉈ�����̂ł���A�A�C���V���^�C���̈̑傳���������܂��B���̂��Ƃ��Ƃ̗��O�ɗ����Ԃ肻��Ɩ�������悤�ȓ�������������ŏo���ꍇ�A���̐����Ɍ��ׂ����邩�A�܂��͂��̓K���ɊԈႢ������ƍl����ׂ��łȂ̂ł��B��ʑ��ΐ����_�̐�������r�b�O�o�����f���������o���ꂽ�Ƃ����Ă��܂����A��ʑ��ΐ����_�̗��O�ɗ����Ԃ��Ԃ̖c���͕����̖c���ł���ŏ�����������l�܂�����ԂȂ�A���Ԃ��o�߂��Ă������ċȋ�Ԃ͏o�����܂���B�܂��t�Ɍ��݂̉F���̎p���ȋ�Ԃ��啔�����߂�Ȃ�A���Ԃ��t�߂��ɂ��ĉߋ��ɋt����Ă������Ă������蕨�����l�܂�����ԂɂȂ�͂��܂���B���̗��O�Ɛ����̃M���b�v�́A�����̓K������߂ɉ����ԈႢ���Ȃ����ǂ����ׂȂ���Ȃ�܂���B�����̒P���ȕό`���d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�����ݏo�������O����ԏd�v�ł��邱�Ƃ�F�����Ȃ�������܂���B�@ | |
| �����F�����f���̂܂Ƃ� | |
|
�r�b�O�o���̏����Ō����������Ƃ̌��z����ʂ̐l�ɗ^����悤�ȁA�嗬�̐l�X�̎v���̐Ό��ɖ����������́A�����炷��ΐM�����������̂ł��B�@�����r�b�O�o�����ے肳���Ύ��������̒n�ʂ▼�����D���Ă��܂��Ƃ������|�ɂ����̂Ȃ̂ł��傤���B�@���������ׂċ]���ɂ��Ă��^�����͂����肳����̂��A�Ȋw�҂ɗ^����ꂽ�g���ł��B�@�����h�ɍ��ɂ��Ђ˂�ׂ��ꂻ���ȗ���ł��̂ŁA��⋭�߂̔������������������������Ǝv���܂��B�@�u�ᔻ�����Ȃ炾��ł��ł���v�A�Ƃ����͎̂嗬�̐l�������悭�������Ƃł����A�m���ɂ��������m��܂���B�@���̃z�[���y�[�W�����̑����̔��r�b�O�o���T�C�g�ƈႤ�Ƃ���́A�V�������F�����f���𐔎��Ŏ��������Ƃł��傤�B�@���܂Ńo���o���ɏ����Ă����̂ŁA���̒��F�����f���̑S�̂��悭�킩���Ă��Ȃ��������邩������܂���̂ŁA�܂Ƃ߂Ď��ɏ������Ƃɂ��܂��B�@�@�����ɏ������F�����f���́A�����܂ł������l������̈Ăł���A���̈Ăɒv���I���ׂ��������Ƃ��Ă��A���F�����������ɔے肳���킯�ł͂���܂���B�@�������嗬�̃r�b�O�o����M����X�́A���̈Ă��p�ĂɂȂ�悤�A�܂����܂łɎ����w�E�����r�b�O�o���̖��_����������悤�A����w�͂��Ă��������B�@
���͉F���͗L���ŏd�͂ɂ���ĕ��Ă��āA�傫�������������Ȃ炸���ł���ƍl���Ă��܂��B�@�L���ŕ����F���ɂ͉^���ʂ̕��ϒl�����݂��A���̌n�͉F���w�i���˂������ΐÎ~�n�ł���A���̑��̏]�������n�ƍl�����Ă����n�͉����x�������܂�(���̍l���͂ǂ̊����n���猩�Ă����̑��x�͓����Ƃ������ΐ�������ے肷����̂ł͂���܂���)�B�@���̉����x�͔w�i���˂ɑ��鑬�xv�ƉF���̋ȗ����aR�ɂ�苁�߂邱�Ƃ��ł��A���̒l�́@a=v^2/R �ƂȂ�܂��B�@�F���_�I�ԕ��Έڂ͂��̏d�͂ɂ���ċȂ���������Ԃ������x�^�����邱�Ƃɂ���ΐÎ~�n�ɂƂǂ߂悤�Ƃ���F������̔���p���Đ�����A�ƍl���Ă��܂��B�@���̎��ۂ̐�����(��9�͑��ΐ����_�̏C��)�Ɏ������悤�ɉF���S�̂���̏d�͍�p�Ƃ��Č��ł́AF=E/R�@(E�͌��̎��G�l���M�[�AR�͉F���̋ȗ����a)�̗͂��Ă��̃G�l���M�[�������A���̔g���́A��=��0e^(x/R)�@�@(��0�͕��ˎ��̔g���Ae�͎��R�ΐ��̒�Ax�͒n���܂ł̋����AR�͉F���̋ȗ����a)�@�ɕω����܂��B�@����͐ԕ��Έځ@�� = e^(x/R) -1 �Ƃ�����킹�܂��B�@���̐��������ۂ̊ϑ��f�[�^�ɓK�p����ƁA�@���V���̊ϑ��f�[�^����F���̋ȗ����a�͖�150�����N�A�����F���̈���̑傫����2��*150�����N�ƂȂ�A��940�����N�ɂȂ�ƍl���Ă��܂��B�@�����炭�F���̎��ʖ��x�͂��̑傫���ɉF�����������ՊE���x�ɂȂ邱�Ƃ��\�z����܂��B�@��16�͂ɏ������悤�ɁA�����̋�͂��痈����͉F���S�̂���̏d�͍�p�ɂ��ԕ��Έڂ���̂ł�����A�d�͂̋����V�̂���E�o������Ɠ����ł���A���˂�����͂ł�z+1�������������Ԃ̌o�߂��x���Ȃ�܂��B�@����͂��̕��o���������̉F���ł͎��Ԃ̌o�߂��x�������Ƃ��l���邱�Ƃ��ł��܂��B�@����ɂ�艓���̒��V���̎��Ԍo�߂̐������ł��܂��B �F���w�i���˂͍��܂Ńr�b�O�o���ɂ���ė\������r�b�O�o���̍����Ƃ���Ă��܂����B�@����������͉F���̏����̎c���ł͂Ȃ��F����Ԃɑ��݂��镨�����M�I���t�ɂ��邽�ߕ��˂��Ă���ƍl���Ă��܂��B�@�F����Ԃɑ��݂��镨���̕��˂ɂ��ǂ����ĉF���w�i���˂�10������1�ƌ������炩�������̂��A2.725K�̍��̕��˂ɂǂ����Č���Ȃ���v���邩�ɂ��Ă͑�20�͂ɂĐ������Ă��܂��B ���q�͗L���ȉF���ɂ����Ă͍ő�ł����̉F���̑傫���ȏ�̔g���������Ƃ͂ł����A�Î~���ɂ͐��1000�����N���x�̔g�����������̔g���́@�������^��C(���̓v�����N�萔�A���͗��q�̐Î~���ʁAC�͌����x)�ŕ\����܂��B�@���̂����悻�̐Î~���ʁ@m=(6.63�~10^-34)�^(3�~10^8�~1�~10^27)��2�~10^(-69)�����ƂȂ�܂��B�@�������q�̋ɂ킸���ȐÎ~���ʂ��v�������A���̃��f���̐��ۂ��킩��ł��傤�B �F���͖{���I�ɂǂ��������Ă��ł������p�����Ă���ƍl���܂�(���S�F������)�B�@�N�G�[�T�[�ɂ��ẮA�嗬�̕��X�͂���炪�������ԕ��Έڂ��A10�����N�ȏ�̉���(10���N�ȏ�O)�ɂ������݂������ԓI�ȕ肪����ƍl���Ă��܂��B�@�������A���̓N�G�[�T�[�̐ԕ��Έڂ͂����炭�X�̃N�G�[�T�[�����ŗL�̐ԕ��ΈڂƂ���Ɛ�Ɏ������F���̘p�Ȃɂ��F���_�I�ԕ��Έڂ𑫂������̂ŁA���̉F���ɋ�ԓI�ɂ����ԓI�ɂ���Ȃ����݂��Ă���ƍl���Ă��܂��B�@�F�������ԓI�ɂ͒���ۂ��ω����Ȃ����R�Ƃ��āA4��(�M�͊w��2�@���ɂ���)�ŏ������悤�ɉF���ł͕������M�I���t�ɂ��镔���ƁA�d�͓I�ɕ������ÏW���Ă��镔���Ƃ����݂��Ȃ���A�Ⴂ�Ɏp��ς��A���̂悤�ȏ�Ԃ̕ω����P�v�I�Ȃ��̂Ƃ����݂�������ƍl���Ă��܂��B�@�Ǐ��I�ɂ͐i�����Ă��܂����A����͈���I�Ȑi���ł͂Ȃ��܂��Ҍ�������i���ł���A��ǓI�ɂ͒���Ԃ�ۂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�@���ۓI�ɂ͉F���͏d�͂ɂ���ĖڂɌ�����悤�ȋ�͂��`�������͂Ɍ�����˂��A���̒��S�j�͏d�͓I�ɕ����������x�ƂȂ��Ă��܂��B�@�����������̏d�͂ŕ������钆�S�j��V�̂͌����āA�u�ǂ��܂ł����k�������Č����E�o�ł��Ȃ��u���b�N�z�[�����`������x�ƌ��ɂ͖߂�Ȃ��v�A�ƍl����ׂ��ł͂���܂���B�@��͂̒��S�j�͔��ɍ����x�Ɏ��k���܂����A�����Ď��ۂ̒n�����͌`�����ꂸ�A����ǂ��납���̉�]�ʂƐ��������ɃW�F�b�g������A��͊ԋ�Ԃɕ����o���ŏI�I�ɏ������邩�A�������͐V���ɕʂ̋�͂ƗZ�������ʂ�⋋����ēx����������A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B�@�F���u���b�N�z�[���ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă��܂��قǂ̏d�͂̍�p�ɂ���āA�d�����f�̓o���o���ɂ���A�W�F�b�g���畬�o����镨���͗z�q��d�q�ɊҌ�����Ă���ł��傤�B�@�܂芈����͊j�Ȃǂ̍����x�ȏ�Ԃɕ������Ă����V�̂́A�d�͂𗘗p�����F���̃��T�C�N���Z���^�[�ł���A��͊ԉF����Ԃɕ������Ҍ����Ă���̂ł��B�@�܂肱���u���b�N�z�[�����h�L�͒��F���ɂƂ��ĂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂Ȃ̂ł��B�@���ۂ̒n�������`���������ɓ��������̂͌��ł����E�o�ł��Ȃ��Ƃ����l������͂������ꂽ���̂ł��B�@��ʑ��ΐ����_���瓱�����Ƃ��ł���Ƃ����̂͊ԈႢ�ł���A�Ƃ����̂����̃u���b�N�z�[���ے�̒��ړI���R�ł����A�ԐړI�ȗ��R�������ɂ���̂ł��B�@�z�[�L���O���ŋ߂ɂȂ藝�R�͏����Ⴂ�܂����A�����ĕ�������������E�o���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����u���b�N�z�[����ے肵�Ă��܂��B���̍l���ɕ��݂���Ă����悤�Ɏv���܂��B�@ �@ |
|
| ���u���Θ_�v�͂�͂�Ԉ���Ă��� | |
| ���̕��͂́A�w�u���Θ_�v�͂�͂�Ԉ���Ă����x(���҂�8�l���܂��̂ŁA�ʂɏ����܂�)�̊ԈႢ���w�E���邱�Ƃ�ړI�ɏ�����Ă���B�����^�C�g���Ȃ̂ŁA�ȉ��w����ԁx�Ɨ������đՂ��B���̖{�́w�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�͊Ԉ���Ă����x(�ȉ��A�w�A���_�x)�Ƃ������Ȋw�{�̑��҂��B����ǂ́w����ԁx�͑O��́w�A���_�x�̒��҂��܂�8�l�ɂ��A8�т̘_���̘_���W�ɂȂ��Ă���B�@ | |
|
��1�@�X�쐳�t�E�w�펯�������đ��Θ_���l�������x
�X�쎁�́u�펯���瑊�Θ_���l�����v�Ƃ����̂�ݗ����ĉ��s���Ă���A�ƒ��ҏЉ�ɂ͂���B���̕��͂����̉��̓]�ڂł���B �O�����͂��̉�̐ݗ���ӏ����]�ڂ���Ă���B���̎�|�́u�������͕����w�҂ɁA������𗝉��ł���悤�ɏ����ė~�����Ɨv�����Ă��悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�Ƃ����A���ɂ����Ƃ��Ȏ����B���Θ_���킩��ɂ����Ƃ��������q�ׁA���͂��Ă��邾���ŁA������Ԉ���Ă���A�ȂǂƂ͌����Ă��Ȃ��B �Ƃ��낪�A���̌㔼���ɂȂ�ƓˑR�A���Θ_�͊ԈႢ���A�ƌ����n�߂�̂ł���B�X�쎁�́A������E���V�}���ʁA�u���v�̂�����v���Ƃ肠���āA���������B �w��ꐢ�I�̐l�X�́A�Ȃ���Z���I�̐l�X��������ċ��������v�𐳏�Ȏ��v�Ƃ��ĔF�߂��̂��s�v�c�Ɏv���ł��낤�B������ċ��������v�́A���Ԃ������ꂽ����w�j�������ꂽ�̂ł͂Ȃ��āA���v�������Ďw�j�̉�]���x�������ꂽ���̂ɉ߂��Ȃ�����ł���B�x�@�Ƃ����悤�Ȓ��q�B �ᔻ����̂͂�������ǁA�Ȃ��E���V�}����(�X�쎁�͂��̌��t���g���Ă��Ȃ���)���A�P�Ȃ鎞�v��(�@�B�I�H)�������ƍl������̂��A�ƌ����_��S��(���Ȃ��Ƃ����̕��͂̒��ł�)���炩�ɂ��Ă��Ȃ��̂͂ǂ������H ���v���������̂͏펯�ɔ����邩��A�Ƃɂ����ԈႢ�ŁA��ꐢ�I�ɂȂ�����킩�邾�낤�A�̈�_����ł́A�ɂ�����\���҂̓T�^�I�p�^�[���ƕς���ł͂Ȃ����B*1 ����ɐX�쎁�͓��R���Y���́w���ΐ����_�x�Ƃ����{(���������Ă��܂�)�̏����̏I���ɁA�w�{���͗͊w(�ϕ��������܂�)�Ɠd���C�w�̊�b�m����������A�K�������ł���B�����{����ǂ�ł��A���ꂪ�����ł��Ȃ��悤�Ȃ�A���͂⑊�ΐ����_���w�Ԃ��Ƃ�������߂�ׂ��ł��낤�x�Ə����Ă��鎖�������A�w���̋L�q�́A�����w���̈ꕔ�͂��̖{��ǂ�ł��������邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ��A���������đ��Θ_�𗝉��ł��Ȃ��ƁA�͂��߂��猈�߂Ă������Ă���x�ƌ����B ������Ƒ҂��Ă��傤�����ȁB ���R���́u�����ǂ߂ΐ�Η����ł���v�ƌ��������̂ł����āA�u�ł��Ȃ��z�͂�����߂�v�Ƃ����̂͏C���ł��낤�ɁB����������āA���Θ_�͗����ł��Ȃ����̂Ƃ���Ă���A�ƍl����̂͂���܂�ł͂Ȃ����B�X�쎁�́w�����A���̂悤�Ȉٗ�̋L�q�����̖{�̏����ɏ����ꂽ�Ȃ�A���̖{�̒��҂̐��_��Ԃ���Ԃ܂�A�l�i���^����̂ł͂Ȃ����x�Ƃ܂ŏ����Ă��邪�A���̒��x�̂����蕶��́A�Q�l���Ȃǂł͂��Ȃ��݂Ȃ��c�B �ǂ����A�X�쎁�͑��Θ_�͗����ł��Ȃ��ē�����O�A�Ǝv���Ă���悤���B����Ȏ��������Ă���B�w���̌�����ŁA���͂܂����ΐ����_�𗝉����Ă���l�ɉ�������Ƃ��Ȃ��B(����)���̌��������łȂ��A���͂܂����ΐ����_���悭���������Ƃ܂��߂Ɍ������l�ɉ�������Ƃ͂Ȃ����A�܂����낢��Ȗ{��G���ŗ��������Ƃ����l�̋L�q�����������Ȃ��̂ł���B�x�Ƃ܂ŏ����Ă���̂ł���B*2 �܂��߂Ɍ������B���͑��Θ_�𗝉����Ă���B�����āA���Θ_�𗝉����Ă���l�ɂ��������������B�������Ă���Ə����Ă���{��G�����������Ƃ�����I ����Ɍ����A���Z�����x�̐��w�Ɨ��Ȃ̑f�{�������āA�����w�ԋC�̂���l�ɂȂ�A���ꑊ�Θ_�̏����̕����Ȃ炿���Ɨ����ł���悤�������鎩�M������B*3 ���߁[����̌�����ɂ����Ƃ����āA���Ԃɑ��Θ_�𗝉����Ă���l�������ƁA�v������ł����A�����A��������B �������A�X�쎁�ɂƂ��ẮA���R���̂悤�Ȕ����́A���Θ_�Ɋւ��鎿����^�u�[�ɂ��悤�Ƃ��Ă��邩�炾�A�Ƃ������ɂȂ�炵���A����ł͏펯�l�͋^��������Ă����₷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł͂Ȃ����A�ƌ����̂��B �Ђ˂��ꂽ�������ƁA���₵���������玿�₵���炦����B �������A�g�w�ԋC�̂���l�ɂȂ�h�ƕt�я������������A�u���₷�邱�Ƃ̓^�u�[�Ȃ낤�v�Ǝv���Ă���l�͂�͂�A�g�w�ԋC�̂���l�h�Ƃ͌����������B ���̌�A����ɔ��Ȏ���X�쎁�͏����Ă���B �w��Z���I�����Ǝc���Ƃ���\�]�N�A���͓�Z���I�̏펯�l�̒��Ɂu������ċ��������v�v�̐��̂����j�����҂�����A���̂悤�Ȕ�펯��f�ŋ��ۂ������Ƃ̏؋����L�q���Ă������ł���B�x �X�쎁�́g�ߑs�h�ȑz���͂Ƃǂ܂�Ƃ����m��Ȃ��B���Θ_�₻�̋A���ł���u���v�̂�����v���M�����Ă���͓̂�Z���I�ő�̊쌀�ł���A�w���̊쌀�̊��m���A�������������O��đ傫�����̂ł��邽�߂ɁA���̑��̖ʔ����������b�͂�������e���������Ȃ��āA�l�X�Ɍ�����������Ȃ��Ȃ�ł��낤�x�Ƃ܂Ō����Ă���B ����ȂƂ���œ�ꐢ�I�̂����|�l�̐S�z���Ăǁ[���B�@ |
|
|
��2�@�E�c�o�i�E�w���Θ_�͕���x
���̐l�́w�A���_�x�̒��҂ł���B���̂��߁A�ŏ��ɑO���ɑ��锽����������Ă���B ���ʂ́|�Ȃ�ƁI�^��7���A����3���B���������̂قƂ�ǂ��u�V�˃A�C���V���^�C�����Ԉ���Ă���͂����Ȃ��v�Ƃ����荇���������A�Ƃ������Ƃ��B���`�ށB���ꂪ�ق�Ƃ�������J���ׂ����Ƃł���B*4 ��ɂ���āA�u�����w��̔��Ȃ܂ł̕ێ�I�Ȕh�������ɂ���āA�L�v�Ș_�����ׂ��������s���Ă���Ƃ��������v������A�Ȃ�Ęb���o�Ă��邪�c�ق�ƂɗL�v�Ș_���Ȃ炫�ꂢ�����ς�������鎖�Ȃ�ĂȂ��Ǝv�����B ���āA��҂̈ӌ��͑O�̖{�Ɠ��l�ŁA���ς�炸�A�����͌���l�̗���ɂ���ĕω�����͓̂��R���A�Ƃ��������Ƃ��Ă���B ���낢��A�ʔ������W�b�N���g���Ęb�����Ă��镔��������܂��̂ŏЉ�悤�B ���u��������v �A�C���V���^�C���̎v�l�����̈�ɁA�w���ƈꏏ�Ɍ��̑��x�ʼn^��������A�����~�܂��Č����邩�x�Ƃ����₢������B����ɂ������A�E�c���͂����ᔻ����B�w���͂����Ȃ�Ӗ��ł������܂���B�������l�Ԃ͌���������悤�ɂł��Ă��܂���B��̖�������̂悤�Ɍ��������Ώ����͍l�@�ł��郌�x���ɂȂ�܂��B ���Ƃ��A���܂����ɉs���w�����������[�U�[�������ˑ��u������Ƃ��܂��B1�i�m�Z�R���h�����d���𗬂��Č��Ɍ����ă��[�U�[�����������Ƃ���ƁA��O�Z�Z���`�̒����̌����������Ŕ��ł����܂��B���̃��[�U�[�����n�ォ�猩���܂����H�@�X�y�[�X�V���g���̑����猩���܂����H�@�܂��āA�����Ō��Ɍ������Ă��郍�P�b�g�̒�����A���̌����������܂����H�@������̏ꍇ����Ɍ����܂���B�x ����͊m���ɁA�l�Ԃ̖ڂ͔��ł�����������猩�邱�Ƃ͂ł��c�v�l�����Ƃ����̂͂���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �A�C���V���^�C���̋^����A�C���V���^�C�����g�̈Ӑ}�����`�Ō����ւ���Ȃ�A �w�d��⎥��̑���@�������āA�����ő���Ȃ�������\�����Ă���d����𑪒肷��ƁA����͓����Ă��Ȃ��悤�Ɍ�����̂��H�x �ƂȂ�B�A�C���V���^�C���́u�g�̌`�����āA�Î~�����Ód��ƐÎ��ꂪ����Ƃ͍l���������v�Ǝv���āA���Θ_��������̂ł���B �m���ɁA�d���C�̖{�Ȃɏ����Ă���d���g�̊G�̌`�̓d��Ǝ��ꂪ�~�܂��Ă�����C���������B�}�b�N�X�E�F���������������Ȃ����B ���u�������A�����_�̑��ΐ��H�v �����̑��ΐ�(����l���猩��Ɠ����Ɍ����錻�ۂ��A���̐l�Ƃ͑��ΓI�ɉ^�����Ă���l���猩��ƁA�����ł͂Ȃ��Ȃ�)�Ƃ����̂́A���Θ_�̏d�v�Ȍ��ʂł��邪�A����͂����܂ŁA�u�Ⴄ�ꏊ�̓������v���ʂ̗��ꂩ�猩��ƁA�u�Ⴄ�ꏊ�̈Ⴄ�����v�ɂȂ�A�Ƃ������ۂł���B�E�c���͂�����u�����ꏊ�̓��������v���u�����ꏊ�̈Ⴄ�����v�ɂȂ�A�Ƃ������ۂ��ƌ��������ŁA���Ă��܂��B�Ȃ�ڑ��Θ_�ł��A�u�����ꏊ�̓��������v���u�����ꏊ�̈Ⴄ�����v�ɕς��͂����Ȃ��B*5 ���́A����Ɠ����ԈႢ���m�g�j�́u�A�C���V���^�C���E���}���v�ł���Ă����B���낵�����ł���B ���u���s���ł͐��Ԃ͂킩�邩�H�v �r�e�t�@���ɂ͐���(�X�^�[�{�[)�̌����Ƃ��ėL���Ȍ��s���ł��邪�A�E�c���͂��ꂪ����Ƃ������Ƃ͌��̑��x���^����Ԃɂ���ĕς���Č����鎖�̏؋����A�ƌ����Ă���B�������A���s���̎����ő��肵�Ă���̂͊p�x����������A�u���̂���Ă���p�x���^����Ԃɂ���ĕς��v���Ƃ������Ă��邾���ł���B�����āA�����ő���ꂽ�p�x�͑��Θ_�̗\���Ɩ������Ȃ��B ���u���z�̋߂��Ō��͋Ȃ��邩�H�v ��ʑ��Θ_�̏؋��Ƃ��āA���z�̋߂���ʂ�����Ȃ�����A�Ƃ����ϑ����������邪�A�E�c���͂��ꂪ�d�͂̂����łȂ��A���z�̕t�߂ɂ��闱�q�Ȃǂɂ����܂̂������A�ƌ����Ă���B ������A���܂��A�v�Z�����̂���[�B���z�̕t�߂ɂǂ�Ȃӂ��ȗ��q������̂��A�������������ׂĂ��猾���Ă�[�B �Ƃ���Ŗʔ����̂́A�����ŌE�c�����w���͋�Ԃ́u���v�ŁA�����Ȃ����̂��Ǝv���Ă��܂��B�Ȃ������肷��u�����v�ł��ƁA����͉��H�Ƃ������ƂɂȂ邩��ł��x�ƌ����Ă��邱�Ƃł���B�Ȃ��ʔ������Ƃ����ƁA����̓R���m�P���C�`���̗��_�Ƃ܂���������Η�����̂ł���B�������R���m���͌E�c�����ŋ߂̒����w�r�b�N�o�����_�͊Ԉ���Ă����x�Ŏ����グ�Ă���c�B ���u�������Ă������ɂȂ�Ȃ��H�v �d�q��������������Ă��������͑����͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�d�q���j���[�g���͊w�ɏ]���Ƃ����ꍇ�A�d�q�������܂ʼn�������̂ɕK�v�ȓd���͂�������(�g�������́h�ƌ����Ă����H)25���{���g�قǂł���B�������A���ۂɂ͂���Ō����ɂȂ�����͂��Ȃ��B ���̎����ɑ��A�E�c���͂������_����B �w��������͓̂d����ɂ��܂��B�d����̓`�d���x�͒n����ł͂قڏ���͌����ł��B�����������̂ʼn�������̂ł���������ȏ�ɂȂ�Ȃ��͓̂��R�Ȃ̂ł��B�x �d�q���������邽�߂̓d����́A�d�q�ƈꏏ�ɑ����Ƃ�����̂��H ���R�A����Ȏ��͂Ȃ��B�����Ƃ��P���ȃ��J�j�Y���Ƃ��ẮA�d�q�̒ʂ蓹�ɉ����āA�Ód��������Ă����悢�B�����d�q�������o���Ă���u������v�Ƃ���ɓd��������K�v�Ȃ�ĂȂ��̂ł���B ���ɂ����̐l�̌����Ă鎖�Ɋւ��āA�����������Ƃ͎R�ق�(�{���������ȁB���������{����������Ă���瓖�R��)����܂����A�����ł͂��̒��x�ɂ��Ă������B�@ |
|
|
��3�@����G�Y�E�w�G�[�e���ƐV������Ώ̏d�͗��_�x
3�A4�N�O�ɁA�E��]�̃R�}�̏d�����y���Ȃ�A�Ƃ����_�����o�āA���Ԃ𑛂������B�������s��ꂽ�ǎ��́A�c�O�Ȃ���ے�I���ʂɏI������B*6 �܂��ŏ��ɁA���⎁�ɂ��^��ɑ���l�������q�ׂ��Ă���B���⎁�͐^����u���v�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��B��̗ʎq�_�Ȃǂł͐^��́w�_�[�N�}�^�[���w�i�t�˂�����������Ȃ����A������^��̃G�l���M�[�x�ŏ[�����Ă���A�ƌ����Ă���̂ł��邪�c�B �����\������������(����ȂƂ���łȂ��_�[�N�}�^�[���o�Ă���̂ł��낤��)�̂͊�������čl�����Ƃ��Ă��A���̐^��̃G�l���M�[�Ƃ��������ɃG�[�e���Ɍ��ѕt���čl���Ă���̂́A������ƍ���B*7 �^��ɃG�l���M�[���[�����Ă��鎖�ƁA��ΐÎ~��Ԃ����鎖�͑S���ʂ̖��肾�Ǝv���̂����B ���⎁�́w�f���q�_�ւ̓��ꑊ�Θ_�̉��p�ɂ͓�̓�_������B��͑f���q�̕�������́A�G�[�e���̑��݂ɂ���Ă��̉e�����邩������Ȃ����Ƃł���B(����)�������(���͑f���q�����w�҂ł͂Ȃ��̂őf���q�̎������ǂ�����đ��������ڂ������Ƃ͒m��Ȃ���)�A�f���q���E�͕������ՓˁA����A����̐��E�ł��邩��A���������^���̊����n�̕ϊ����ł��郍�[�����c�ϊ��Ȃ����A���ꑊ�Θ_�������o���̂͊Ԉ���Ă���Ǝv���邱�Ƃł���B�x�Əq�ׂĂ���B ��̌E�c���������悤�Ȏ��������Ă��āA�悭����p�^�[���̊ԈႢ�Ȃ̂����A�f���q�Ȃ艽�Ȃ肪�������Ă����Ƃ��Ă��A���̕��̂ɏ���Ă���l(�f���q�ɂ͐l�͏��Ȃ��A�Ƃ��������݂͂Ȃ�)�����������Ԃ����[�����c�ϊ��̎����炵�Ă��A�ʂɈ������Ƃ͉����Ȃ��B�������A���x���ς���Ă���̂ł��邩��A�u�ԏu�Ԃŕʂ̃��[�����c�ϊ������鎖�ɂȂ�̂����B ���̌�A����܂��u�܂����v�̘_�|���o�Ă��܂��B�A�X�y�̎���(���⎁�̓A�X�y�N�g�̎����Ɠǂ݊ԈႦ�Ă���B����ȂƂ���܂ŃR���m�P���C�`�Ɠ����ł���)���ɂ����āA�ʎq�_�ł͒������͓�����O�̌��ۂ��A�ƌ����Ă���̂ł���B �A�X�y�̎����͂�����d�o�q���ւ̎����ŁA�ʎq�͊w�Ō����u�g���̎��k�v���������ŋN���鎖�����������̂ł��邪�A���̒������͏����^�Ȃ��̂ŁA���Θ_������Ŕj���킯�ł͂Ȃ��B���[��[���́A���̃A�X�y�̎����Ɋւ���{��ǂ߂A�����Ă������Ă�����ǂȂ��B ���āA���̌�A���⎁���g�̏d�͂̎����ɂ��Ă̘b���o�Ă���B�܂���̎����ɂ��āA�w���͘_���ɂ����d�͂Ƃ������t�͈�x���g�p�������Ƃ��Ȃ��x�ƌ����Ă���B����͊m���ɂ������B�R�}������Čy���Ȃ���(���m�Ɍ����R�}�����ɋy�ڂ��͂��キ�Ȃ���)����ƌ����āA���d�͂Ƃ͌��炸�A�����ʂ̗͂������Ă��邾���̎���������Ȃ��̂ł��邩��B ���⎁�͎����̎����̌��ʂ͑Ώ̏���g����ʑ��Θ_�ł͏o�Ă��Ȃ��A�ƌ����A�J���^���̔�Ώ̏���g���A�o�Ă��邩���A�ƌ����Ă��܂����A�J���^���̔�Ώ̏�͖��O�͔�Ώ̂����A�p���e�B�͕ۑ�����锤���Ǝv���̂ł��邪�B�����Ƃ��A���⎁���g���A�����ɗ��_���瓱���o�����Ƃ͂ł��Ȃ��A�ƌ����Ă���(�����ł킩�锤���A�Ƃ����킯���B���������̎������ǎ��Ŕے肳��Ă��Ắc)�B �ے�I���ʂɏI������ǎ������ɂ��ĉ����R�����g�����邩�A�Ɗ��҂����̂ł����A����͂Ȃ������B���x�͗��������Ŕ�Ώ̂𑪒肷��A�Ƃ��������Ō�ɏq�ׂĂ���܂��B�������鎖���̂͂ǂ�ǂ����Ăق����A�Ǝ����v���܂����c�������葊�Θ_�͔ے肳���A�ƌ����̂͊��ي肢�����Ƃ��낾�B ���������A��Ǐ��ꎁ���E���ɉ���Ă��猖�܂���Ə��Ă�A�Ƃ������Ă����̂́A���̎����ƊW������̂��낤���B�@ |
|
|
��4�@����E�w���Θ_��ł��ӂ��V���o�[�n���}�[�x
���҂̓������́A���Θ_�̐��w�����������A�ƕ�������Ă���B�w�Ȃ������w�҂܂ł������w���ł��킩�鐔�w�g���b�N���x����Ă��܂��̂ł��傤���x�Ƃ�������B ���̐��w�g���b�N�́A�u���ł��镨�����ł��鎖��Y��Ă���v�Ƃ������炵���̂ł���B�����āA���́g�{�����ł�����́h�𑊑Θ_��ł��ӂ����A�Ƃ����Ӗ��Łu�V���o�[�n���}�[�v�ƌĂ�ł���B(�Ȃ��V���o�[�Ȃ�ł��傤�H�A�C���V���^�C����T�j���ȂƊԈႦ�Ă���c�Ȃ�Ă����Ƃ͂Ȃ���ȁB) �ł́A�������̎咣�����Ă������B �܂���ڂ� E=MC2 �ɂ��āA�w��ʂɒm���Ă���悤�ȏd�v�ȈӖ��������Ă��Ȃ��x�Ǝ咣���Ă��܂��B �܂��A�C���V���^�C���̘_���w���ʂƃG�l���M�[�̓������̏����I�ؖ��x�Ƃ����_���Ɋւ��A�w�����f�[�^����ؗp�����ɁA���z���������� E=MC2 ���o���Ă��܂��B�펯�I�ɍl���ăf�[�^�����Ȃ��ŊW�����o����͂�������܂���x�Ǝ咣���Ă��܂��B �Ƃ��낪�A���̃A�C���V���^�C���̘_��(��������1905�N�̘_���Ə����Ă��܂���)�́A1945�N�̘_���Ȃ̂ł���B1945�N�ƌ����A�������Θ_���ł���40�N�B�܂�A���Θ_�Ɋւ�������f�[�^�Ȃǂ������ɑ�������Łu E=MC2�����ǁA����ȊȒP�ȏؖ��������v�ƕ⑫���邽�߂ɏ����ꂽ�_���Ȃ̂ł���B�u�����f�[�^���Ȃ��Ɂv�Ƃ����ᔻ�͂܂����̓_�œI�O�ꂾ�B �܂��A���_�������玮����鎖���̂́A�ʂɕs�v�c�ł��Ȃ�����[���ᔽ�ł��Ȃ��B�������́u�������Ƃ���Ƃ��Ȃ�B���ۂɂ����Ȃ邩�ǂ����͎����Ŋm���߂悤�v�Ƃ����_���ɂ͑��݉��l���Ȃ��A�Ƃł������̂ł��낤���B �v�Z�ɂ��ẴR�����g�̌�A�������͂���Ȏ��������Ă���B �uE=MC2 �͉��肵�������I�Ӗ����L�q���������̗��_���ɂ����܂���B�ʓI�v�f���܂������܂�ł��Ȃ��̂ŁA�P�ʂ␔�l�����Ďg�����͂ł��Ȃ��̂ł��B(����)�_���̂ǂ��ɂ��P�ʂ�ʂ�ݒ肵�Ă���ӏ��͂���܂���B(����)���̓_�ɋC������ E=MC2 �̈Ӗ����������A�w���ʂ̒P�ʂ� C2 �{�傫���G�l���M�[�̒P�� E �ŃG�l���M�[�Ǝ��ʂ̓����������肷��� E=MC2 �ƂȂ�x�Ȃ�Ƃ�����܂��Ȃ�ł��傤���B�v ����A������܂��ł��傤����ǁB �����̘_���ŒP�ʂ��ȗ�����Ă���̂́A�g�ݗ��ĒP�ʂ��g���Ă���Ǝv���Ă���A�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł���B �Ⴆ�AM��[kg]�AC��[m/s]���g�����̂Ȃ�G�l���M�[�̒P�ʂ�[Kg�Em2/s2](�����MKS�P�ʂȂ̂ŁA�W���[���ɓ�����)�ɂȂ邵�AM��[�і�]�AC��[���[�h/��]���g�����̂Ȃ�G�l���M�[�̒P�ʂ�[�іځE���[�h2/��2](����ȕςȒP�ʂ͂������Ȃ����A��낤�Ǝv������)���g���A�Ƃ��������̂��Ƃ��B�ǂ̒P�ʂ��g���Ă� E=MC2 �͐�������B ���������A E=MC2 ���́A�j����̍ۂ̃G�l���M�[�ȂǂŎ��Ă���A�Ƃ������������̐l�͂ǂ��l���Ă���̂ł��낤�H ���ɓ�����������������Ă���̂��A�A�C���V���^�C���́u�^�����Ă��镨�̂̓d�C�͊w�ɂ��āv�Ƃ����_���ɂ��āB �������́A�A�C���V���^�C���̘_���̐����̒��ŁA�E�E�E�ƕό`����Ă���̂�����(���ӂ�x'�Ŕ������āAx'��0�ƒu���������Ȃ̂�)�A��̎��ł̓т�()�̂����g���h�������̂ɁA���̎��ł́g���h�łȂ��Ȃ��Ă���I�Ɣᔻ���Ă���̂��B �w�����ʼn����s��ꂽ���Ƃ����ƁA�u���̊��ʂƔ{���ɕt���銇�ʂƂ��Ԉ���Ē��g���v�Z���Ă��܂����v�܂��́u���m���т��ꎟ���̋��ߕ��ŏo���Ă��܂����v�̂ł��B�x �ق�ƂɃA�C���V���^�C��������Ȏ���������̂Ȃ�A���w���ɂ����邾�낤�B�������A�����ł͒P�ɏȗ����������ŁA�т����ł��邱�Ƃ��A�C���V���^�C�����Y�ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B����Ȃ��Ƃ͕��ʂ̐l�Ȃ疾�炩���Ǝv���B �������͉��̎��̃тɔ����L�������Ă��邱�Ƃ��ǂ��l���Ă���̂��낤�H�A�C���V���^�C���͊��łȂ������������قǐ��w���ł��Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł��낤��(�v���Ă��邩������Ȃ��Ȃ�)�B ���āA���̌�A��ɂ���āu�����x�s�ς̖@���v�ɕ���������n�߂�B���킭�A �u������ʂȃJ���̕������x���N���猩�Ă����Ɖ��肵�܂��B�w�J�����x���̖@���ł��B�����ł��Ȃ��͐��̒��̕����@�������̃J���Ɉ���������悤�ɏK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌ��_����ł��傤���x�v �����x�͎����ň��Ƃ킩���Ă��邪�A����ȕςȃJ���͒N�������ĂȂ������`�B�����ɂ���đ��x���ς���Č�����J���Ȃ炢����ł����邯��ǁB ���Θ_�̖{�͂����Ă��A�����x���̘b�������̂ŁA�����x��肾�������Θ_�̑O�Ǝv���Ă���l�͂�������������������Ȃ����c���ۂɂ́A�d���C�̊�{�@���ł���}�b�N�X�E�F���������������Ȃ���ϑ�����l�ɂƂ��Ă�(���Θ_�Ȃ��ɂ�)�������Ȃ��A�Ƃ��������傫���̂ł���B�܂�A�d���C�w�̏����ۂ͂��ׂāA���Θ_�̏؋��Ȃ̂����c�B ���̌�A�}�C�P���\���E���[���[�̎����ɂ��āA�u�����Ȃ���������Ă���̂Ȃ�A�����X���Ȃ��Ă͂����Ȃ������v�Ƃ����悭�킩��Ȃ��_���̌�ŁA���̌v�Z�����S�Ɍ�����Ă��܂����A�����Ȃ��Ă����̂ł��̍��͂����܂ŁB�@ |
|
|
��5�@�|���O�E�w��ʑ��Θ_�Ɨʎq�͊w�̊T�O�I�����x
�͂����茾���܂��āA���̘_���͂܂Ƃ����I(�т����肵���Ȃ��A����) ���e�́A�A�C���V���^�C���̈�ʑ��Θ_���ʎq�͊w�Ƃ��܂����v���Ȃ��A�Ƃ����A�ŋ߂̑f���q��������Y�܂��Ă���b��ɂ��Ẵ��r���[�ɂȂ��Ă��܂��B �u����̗ʎq���Ɛԕ��ψʂ̗ʎq���ɊW������̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����\�z���E�ݑ��ɂ�����A�Ƃ����_�������A������ƃG�L�Z���g���b�N����(�����̊w��݂̍���ɕ��匾���Ƃ�����������肠�����肷��)�A���x�̕��͂ŁA���̐l�̂����炳�܂Ɂu����`�v�Ȃ̂ƑS�R�Ⴂ�܂��B �Ƃ����킯�ŁA���̕����̂ɂ͂���ȏ㌾�����Ƃ͓��ɂȂ��B �u���̕����̂ɂ́v�ƒ��߂�t�����̂́A���ҏЉ�̂Ƃ���łԂ����܃Q�[�V�������Ă��܂�������ł���B �Ȃ�ƁA�Ō�̏��ɂ��������Ă���̂��B �u���݁A�r�b�N�o�����z���関���̈���������w�F���t���N�^���\���̓�x(����)�⃔�F���R�t�X�L�[�u�Փ˂���F���v�̍ĕ]������}�����{�̏o�ł��������v ���F���R�t�X�L�[�`�`�`�B�u�Փ˂���F���v�ƌ����A�V���ɖ�������u����`�v�Ȗ{�ł͂Ȃ����B���e�́A�����̎���ɖؐ�����a�����Ȃ�����т����A���ꂪ�n���̂���ʂ�A�����ɂȂ����A�Ƃ������́B�������n���̂���ʂ鎞�ɂ͒n���̎��]����U�~�܂��A�܂������o����(�����̒��Œn���̎��]���~�܂�b������)�A���̎��ɋ����̏d�͂̉e���ŊC�͊�����(���[�[����)�A��������H�����͍~���Ă����(�����́g�}�i�h)�A�ƃG�h�����h�E�n�~���g�����i�D�o�D�z�[�K�����^���A�Ȗ{�ł���B ���������ƁA�u�����A�܂�łr�e�݂����B�ʔ������Ȗ{���ȁv�Ǝv���l�����邩������Ȃ��B����A���������v���Ă��B�ǂނ܂ł́B �ǂ�ł݂�ƁA���̖{�A���܂�ɘ_�����ނ��Ⴍ����ŁA�ǂ�ł���ƕ��̗����ƕ��̗����ƁB�n�~���g����z�[�K���̂悤�ȁA���s���Ȃ߂��Ⴍ���Ⴓ�Ȃ玄������Ȏ��͌���Ȃ��̂����c�B ���Ƃ����̖{�A�s���̈�����(���j�̋L�q�ƍ���Ȃ����Ȃ�)���o�Ă���Ƃ����A�u���̎����͏W�c���Y�ǂ̂��ߖY���ꂽ�̂��v�ŕЕt���Ă��܂��B�����̎���ɂ͏W�c���Y�ǂ����s�����̂ł��傤���B �Ƃɂ����A����Ȗ{���ĕ]�����Ă��܂����A�Ƃ����̂�����A�Ȃ܂Ȃ��Ȏ��ł͂��݂܂��܂��B�ǂ��Ȃ���A�y���݂��B�|�������g���u����`�v�Ȃ̂��ǂ����́A���̎��܂Ŕ��f��҂ƒv���܂��傤�B �������҂��w�F���t���N�^���\���̓�x�Ƃ����{�ԏ��X����o���Ă��܂���(��ɂ���āA���̖{���̂͂܂Ƃ��ł���B�������A�g�r�b�N�o�����z���関���̈�h�֑͌�L���ł��낤)�A����ɂ����F���R�t�X�L�[��i�삷�镔��������܂��āc���[�ށB���̌オ�y���݂��B�@ |
|
|
��6�@�Έ�ρE�w���ԂƎ������������Ă��鑊�Θ_�x
�u���ԂƂ͂��鎞���Ƃ��鎞���̍��̑傫���ł���A�����͍��W�n�̎����ŕω�������̂ł͂Ȃ��B���鎞��t1�Ƃ����̂́A�n����ł��낤�ƁA�����E�ł��낤�ƕς����̂ł͂Ȃ��B�܂��A���鎞��t2�Ƃ����̂����W�n�̎����ŕς����̂ł͂Ȃ��B�Ƃ������Ƃ́A���̍��ł��鎞�� t=t1-t2 �Ƃ����傫�����ω�����͂��Ȃ��B�v�Ƃ����̂��Έ䎁�̎咣�����A�����Ȃɂ������g�͂����Ȃ��h�ōς܂��Ă��܂��Ă͋c�_�ɂ��Ȃ�ɂ��Ȃ�Ⴙ�ȁB �\�肩�炷��ƁA�g���Ԃ͏k�ނ������͏k�܂Ȃ��h�݂����Șb�Ȃ̂��Ǝv�������A���̘_�����炷��ƁA���Ԃ��������k�܂Ȃ��悤�ł�ȁB �d�Ԃ̒��Ń{�[���𓊂������̋O���̒����̈Ⴂ�͌����ɂ�鑬�x�̈Ⴂ�Ő����ł���A������������Ă����Ȃ̂��A�Ƃ����������Ō����x�s�ς̌�����ے肵�܂��B �������ɁA�{�[���̏ꍇ�͂����Ȃ̂����c���̏ꍇ�͑��x���ς��Ȃ��Ƃ�����������������Ƃ����̂ɁA�Ȃ�ł킩���̂��Ⴀ�B ���̐l�̕��͂͂ǂ����_����ʂ�z���āu����Ȃ͂����Ȃ����炻��Ȃ͂����Ȃ��v�Ƃ��������ɂȂ��Ă���̂ŁA�͂����茾���ēǂ�ł��g���Ȃ��B ��ʑ��Θ_�ɂ��Ă��A���Ɂu��Ԃ��Ȃ���v�Ƃ������t�ɋ����������Ă���悤�ł���B�Ⴆ����ȋ�B �u�I���S���B�Ɉُ�ɋ����d�͂�������ꏊ������B�ό��n������Ă���L���ȏꏊ�ł��邪�A����͐}6�̂悤�ɁA�n���ɔ��Ɏ��ʖ��x�̍������������邩��f���傫���Ȃ��Ă���̂��ƍl������B��ʑ��Θ_�ɂ��A�����̋�Ԃ��ُ�ɋȂ����Ă���Ƃ���Ă��邪�A��Ԃ��Ȃ����Ă���̂ł͂Ȃ��n���̈��͂̋����̈Ⴂ�ƌ�����v ��ʑ��Θ_�́A�u�����̋�Ԃ��ُ�ɋȂ����Ă��邩��A���͂������v�ƍl���Ă���B������A�u�����ł͂Ȃ��Ĉ��͂������v�ł͔��_�ɂȂ����ĂB�@ |
|
|
��7�@�n��x㸁E�w���E���̋��܂ƌ����x�s�ς̌����̌������x
���̐l����ɂ���ă��[�����c�Z�k�ɕ��������Ƃ��납��b���n�߂Ă���(���낻�날�������A���̃p�^�[��)�B �܂��A�u�p�E���̂悤�Ȉꕔ�̊w�҂̓��[�����c�Z�k�͌����I�Ɋϑ��\�Ȍ��ۂł���Ƃ��������������咣���v�u����ŁA���[�����c�Z�k�͐��w��̌������ɉ߂��Ȃ��Ƃ����ӌ�������B�v�Ƃ����ɂ��A�����w�҂̊Ԃł�������������Ă���Ǝv�킹��悤�ȏ����������Ă���B����͂���`�Ȑl�̏퓅��i�ł���B�x����Ă͂����Ȃ��B ��҂̎咣�̗�Ƃ��ăW���[�R�t�ƃ����_�E�́u�^�����Ă��镨�̂̒������k�ނ̂́A���̂��̂��̂ɋN���鉽�炩�̕ω��ł͂Ȃ��A�P�ɕ��̂�����𑪒肷����ɑ��ĉ^�����Ă��邩��Ȃ̂ł���v�Əq�ׂĂ���Ƃ��������o���ė��Ă���̂ł��邪�A�Ȃ�قǁA�ڂ�[�[�[���Ɠǂ�ł���ƃp�E���̈ӌ��ƃW���[�R�t�������_�E�̈ӌ����Η����Ă���悤�Ɍ����邩������Ȃ��B �������A�p�E���́g�ϑ��\�h�ƌ����Ă��āA�W���[�R�t�������_�E�́g���肷����ɑ��ĉ^�����Ă���ƒZ�k������ł���h�Ƃ����Ӗ��̎��������Ă���̂�����A�����Η����Ă��Ȃ�(�ǂ������ϑ��ł���ƌ����Ă���ł͂Ȃ���)�B �X�R�x���c�C���Ƃ����l���u���������R�[�X����ł����̉F���D���l���A���̗��҂��������x�Ŕ��ł���ꍇ�ɁA��{�̃��[�v�łȂ���Ă���Ƃ���ƁA�������̗��҂��Ƃ��ɑ��x�𑝂��Ă����ƁA���҂̋����͏k�܂Ȃ����A���[�v�ɂ̓��[�����c�Z�k���N����̂Ń��[�v�͐��A�Ɛ������Ă���v�Əq�ׁA�u�v�l�̎Y���Ƃ͂����A��_�ȍl���\������̂��Ǝv���v�ƁA�܂�ŃX�R�x���c�C�����Ԉ���Ă��邩�̂悤�Ɍ����B �������A���[�v�����A�Ƃ������͊Ԉ���Ă��Ȃ��B���Ԃ�A�X�R�x���c�C���́u���[�v�ɂ̓��[�����c�Z�k���N����v�Ƃ͌���Ȃ������Ǝv�����B���̃p���h�b�N�X�̓u���[�o�b�N�X�u��͗��s�Ɠ��ꑊ�Θ_�v(�Â��͂r�e�}�K�W���̘A��)�ŐΌ����v�����Љ�Ă����A�g�A�i���O�̃p���h�b�N�X�h�Ƃقړ������̂Ȃ̂ŁA�����̂���l�͎Q�Ƃ��ė~�����B ���ɂ�����o�q�̃p���h�b�N�X(�E���V�}����)�ɂ��ďq�ׂĂ��邪�A�n�ꎁ�́u��ʑ��Θ_�͈͓̔�������p���h�b�N�X�ł͂Ȃ��v�ƌ����Ă���悤���B��ʑ��Θ_��F�߂Ă���킯�ł��Ȃ������Ȃ̂ɂ�������������������̂͂Ȃ��s�v�c���B �����ɑ��ΐ��̘b�ɂ��āA���Ƃ��ƃ��[�����c�����[�����c�ϊ�����������ɁA�u���̎��Ԃ͌������̎��Ԃł���v�ƌ��������Ƃ��Ƃ肠���A�A�C���V���^�C���͂�������Ă���̂ł悭�Ȃ��A�Ƃ����Ӗ��̎��������Ă���B���[�����c���g���A�C���V���^�C���̍l�����ɂ͌�Ɏ^�������A�Ƃ������͓s���悭�Y��Ă���������悤�ŁB �����x�s�ς̌����ɑ��Ă����A�n�ꎁ�́u���x v �œ����Ă����������o����̑��x�͎����ϑ����Ȃ���� c+v �ő����Ă���̂����A�����ϑ������ c �Ȃ鑬�x�Ƃ��đ��肳���x�ł���������Ȃ����A�ƌ����o���܂��B�n�ꎁ�͂��̍l�����Ō����x�s�ς̌��������������{�������Ă���炵�����A�w����ԁx�̒��ł͂ǂ̂悤�ȗ��_���A��̓I�ɂ͐G��Ă��Ȃ��̂Ř_�]�͔����܂��B �������A���̐l�͂��������A�w�����x�̑���x���ǂ̂悤�ɍs���Ǝv���Ă���̂ł��傤���H�@��ł���B�@ |
|
|
��8�@�㓡�w�E�w���ΐ����_�̂ǂ��������������x
�㓡�����ŏ��Ɏw�E����̂́A��ɂ���āw�����x�s�ς̌����x�B �㓡���̔ᔻ�̘_�_�͂���������܂��B�܂���1�̓_�́A (1)���Θ_���A�����x�s�ς���A�l�����I�����̕s�ϐ��������o���Ă��邱�Ƃ��������Ȃ��B ������Əڂ����������܂��B ���W(x,y,z)�ŕ\�����ꏊ�ƍ��W(x',y',z')�ŕ\�����ꏊ�̊Ԃ̎O�����I�ȋ�����l�Ƃ���ƁA�E�E�E�ƕ\����܂��B���̋���l�́A���W������]�����Ă��ς��Ȃ��B ���Θ_�ɂ����ẮA���ꂪ�l�����I�Ɋg������܂��B�܂�A�E�E�E�̂悤�ɂȂ�܂��B �㓡���́A�����x�s�ϐ����瓱�����̂́A�E�E�E�Ƃ������ł��锤���A�Ǝw�E���܂�(����́Al�Ƃ��������xc�̌���t-t'�̎��Ԃ������Đi�ށA�Ƃ������ł���B ����������l*���s�ς��Ƃ���̂͊ԈႢ���A�ƌ㓡���͌����Ă���킯�ł���B �m���ɁA�u������0�ɂȂ�v�Ƃ����������āA�u0�ɂȂ�Ȃ��ꍇ�ł����́g�����h�͕s�ςł���v�ƌ��_����̂͘_���̔��̂悤�Ɍ����邩������Ȃ��B �������A���̓_�Ɋւ��ẮA�A�C���V���^�C���̘_���Ȃ�A�ڂ��������Ă��鑊�Θ_�̖{�Ȃ��ǂ߂Η��R�������Ə����Ă���B ���́A���[�����c�ϊ����ꎟ���ł��邱�Ƃ���Al*���s�ςɂȂ��Ă���Ȃ���ΐ������Ȃ�����������B�㓡���͑��Θ_�̕������鎞�A���̓_��ǂݗ��Ƃ����̂ł��낤�B �Ȃ��A����l*�̕s�ϐ���F�߂�ƁA���Θ_�̌��ʂ��S�ē����o����܂��B�㓡�������̓_�͂킩���Ă���炵���A�w�����F�߂�ƁA�u�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�͏펯�ł͗����ł��Ȃ��l�X�Ȋ�Ȃ��邢�͐_��I�Ȍ��ۂݏo���v���Ƃ��K�R�̋A���ƂȂ�̂ł��B�x�Əq�ׂĂ��܂��B���̐l�́A���̓_�͂悭�킩���Ă���̂ŁA���̑O���������Ƃ����̂ł��낤���c�B ���āA���̌�A�㓡���̓}�b�N�X�E�F���������̕s�ϐ��ɂ��ċc�_���Ă��܂��B�㓡���̓��[�����c�ϊ��̂悤�Ɏ��Ԃ⋗����L�яk�݂�������A�����̑��ΐ����ǂ������A�Ƃ���������������Ȃ��Ă��A�������ω�����A�Ǝv����������}�b�N�X�E�F���������͕s�ςɂȂ�A�ƌ����B�܂�A���[�����c�ϊ��ł͂Ȃ��K�����I�ϊ�����悢�A�ƌ����Ă���B �Ƃ��낪�A���̌v�Z���Ԉ���Ă���̂ł���B �㓡���� 1�@�Î~��Ԃł̃}�b�N�X�E�F���������̉��̈�Ƃ��āA��������ɐi��ł������\�����������B 2�@���̉����K�����C�ϊ����Č�����(���R�A�����͕ς���Ă��܂�)�B 3�@���̃K�����C�ϊ����������o���悤�ȕ��������o���A���ꂪ�������ω������ꍇ�̃}�b�N�X�E�F���������ɂȂ邱�Ƃ������B �Ƃ������Ōv�Z���Ă���̂����A����ł́A���l�������Ȃ炤�܂������Ă��A�ǂ�ȏꍇ�ł����v�A�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B ���ہA�u�}�b�N�X�E�F�������������̂܂܃K�����C�ϊ�����v�Ƃ������(1)�`(3)���P���ȕ��@�Ōv�Z����ƁA�}�b�N�X�E�F���������͌��̎��Ƃ͈�����`(�����������ւ������炢�ł͒���Ȃ��قLjႤ��)�ɂȂ��Ă��܂��B �����ł��㓡���́A�����̌v�Z���@((1)�`(3))���Ԉ���Ă��邽�߂ɁA�����Ă���v�Z���ԈႢ���ƒf���Ă��܂��Ă��܂��B����`�{�ɂ͂悭����b�ł��B �㓡���͎��Ɂu�Î~���W�n�͐ݒ�ł��Ȃ����v�Ƃ����^�C�g���̏͂ŁA�w�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�͊Ԉ���Ă����x�̍�҂ł���E�c���̈ӌ��ƃA�C���V���^�C���̈ӌ��̔�r�����Ă���B �A�C���V���^�C���F �Î~���W�n�̐ݒ�͂ł��Ȃ��B �E�c�F �������˂��ꂽ�A���̈ʒu���̂��̂���ΓI�Î~�_�A�܂��ΓI�Ȍ������𑪂��_�ɂȂ�B �����Ō㓡���́A�w�������A���̍l��(������̒��F�E�c���̍l��)�ɂ���_������Ǝv���܂��B�Ƃ����̂́A���̎�̊�_�́A���ۂɑ��肵�悤�Ƃ��Ă��A��̓I�ɒ�߂悤���Ȃ��̂ł��B�n����ő��肵�悤�Ǝv���Ă��A�n���͓����Ă��邵�A�傫������Α��z�n���̂������Ă��邵�A����ɋ�͌n�����ē����Ă���̂�,��_�͂܂��Ɏv�l��̎Y���Ƃ��Ă����Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ǝv����̂ł��x�ƌE�c���̈ӌ��𐳂����ᔻ���Ă���(�����A�㓡����I)�B �ł́A�㓡���͂ǂ��l���Ă���̂��Ƃ����ƁA�u���������̐�ΓI�Ȓl c �Ɠ������l�ő��肳���悤�ȍ��W�n����ΐÎ~�n�ł���v�Ƃ����l���������Ă��܂��B ����͂������������ɍ����̂Ȃ�A�����͂������l�����ł���B�������A�c�O�Ȃ�������ɍ���Ȃ��B �܂��A�㓡���͖���ԓ��ʼn����𑪂����ꍇ�Ɠ��l�A�����ꂽ��ԓ��Ō����𑪂��Ă����܂������Ȃ��A�Ƃ����l���������A�n���͓d���w�ȂǂʼnF������d���g�I�ɎՒf����Ă���̂ŁA����n�ł͂Ȃ��̂ŁA�n����̌������ǂ���ނ��ɂ����ł���悤�Ɏv����̂ł́A�ƌ����Ă���B �������A���Ƃ���ƁA�d���w�̏㉺�ŁA������(�Î~�n���H)�ω����鎖�ɂȂ�܂��B�ƂȂ�ƁA���ׂ̈Ɂg�����������h�Ƃ����悤�Ȍ��ۂ��N���肻���ł��B���Ƃ���ƖڂɌ����鐯��͘c��Ō����锤�B����ς�A�����ɂ����܂���B ���āA���̏͂̑薼�́u�A�C���V���^�C���̑��ΐ����_�������_��I�Ŋ���Ȍ��ہv�Ƃ������́B����܂ł̒��ғ��l�A�E���V�}���ʂ�[�����c�Z�k�Ȃǂɑ��u����Ȏ��͂��肦�Ȃ��v�Ɣ��_���Ă��܂��B ����܂ł̒��҂ɔ�ׂ�ƁA�u���肦�Ȃ����炠�肦�Ȃ��v���̏z�_�@�͏��Ȃ����A����ł���͂�A�l����������Ă���_�A���Θ_���̂�������Ă���_�Ȃǂ��悭�����܂��B �܂����ΓI�ȑ����ɂ��ďq�ׂĂ��܂��B�����Ɨv��Ƃ���ȋ�ł��B ���̍��W�n�ɑ��A���x v1�Av2 �œ�����̍��W�n���l����B����ƁA���W�n1�̌��_�̈ʒu�͌��̍��W�n�ł݂�� x1=v1t ���W�n2�̌��_�� x2=v2t �ƂȂ�B ����ƁA���̓�̌��_�̋����� (v1-v2)t �ƂȂ�B�܂�A����2�_�̗���鑬�x�͒P���Ȉ����Z�ł������ƂɂȂ�B ����A�A�C���V���^�C���̑��Θ_�ł͑��x�̍��́@�E�E�E�ɂȂ��Ă���̂ŁA����͂��������ł͂Ȃ����B �������A���͌㓡�����g���q�ׂĂ��邪�A���Θ_�ł̑��Α��x�Ƃ����̂́A�u���x v2 �œ������猩���A���x v1 �œ����l�̑��x�v�ł��B����Av1-v2 �ɂȂ�̂́u�Î~���Ă���l���猩���A���x v1 �̐l�Ƒ��x v2 �̐l�̋����̕ω����銄���v�ł��B ���̓�͌��闧�ꂪ�Ⴂ�܂��B���Θ_�I�Ȍ���(�E���V�}���ʂȂ胍�[�����c�Z�k�Ȃ�)������ǂ���������ɂȂ�܂����A���Θ_�I�ȏꍇ�ɂ͂����ł͂Ȃ��B ������A����Ă���͓̂�����O�B�㓡�����u�����������m�Ȍ`�ł̎w�E�́A���j����{�������߂Ăł��v�ƌ����Ă���悤�ȁg�唭���h�ł͑S���Ȃ��B �����������ƁA�g�N�����̂悤�ȊԈႢ��{�ɏ����Ȃ������h�Ƃ������ƁB ���Ɍ㓡�����w�E���Ă���̂��A�u���̂ɂ����̂Ђ�����v���ۂł��B����́A����Ă��鐅�̒��ł́A���̑��x�����̗���ɂЂ�������A�Ƃ������ۂŁA���Θ_���g���Ɣ��ɂ킩��₷���������ł��܂��B �܂��A�A�C���V���^�C���ɂ��������Ȍ��ɐ������܂��B 1�@�܂��A�~�܂��Ă��鐅�̒��ł́A���̑��x��(c)�ł͂Ȃ��A(c�����ܗ�)�ɂȂ�B 2�@�����ŁA���̐������x���ŗ���Ă���悤�ȍ��W�n�Ɉڂ�B�ʂ̌������������(1)�̌��ۂ��Ȃ��猩��A�Ƃ������ƁB���Θ_�ɂ��������A�������������ϑ��҂����������A�ǂ����̗�����Ƃ��Ă��\��Ȃ��B 3�@���̍��W�n���猩���(1)�ŏo����(c�����ܗ�)�Ƃ������x���ǂ̂悤�Ɍ����邩���v�Z����(�����ł͑��Θ_�I�ȑ��x�̑����Z�̕��@���g��)�B���̓������u���ɂЂ�����ꂽ���̑��x�v�ƂȂ�B �~�܂������̒��Ō����x���Ȃ邱�ƁA����т��̋��ܗ��������炩�A�͂킩���Ă��܂�����A�����Ă��鐅�̒��łǂ��Ȃ邩�́A�������̂ł͂Ȃ��A�ϑ��҂����킩��A�Ƃ������ɂȂ�܂��B ����ɔ�����㓡���̔��_�͂����ł��B �u(���E��) �̍��͓����̂ɂ����́g�Ђ�����h�̌��ʂ̂͂��Ȃ̂ɁA�A�C���V���^�C���͂��̌��ʂ̂��Ƃ͑S���l�����A�P�ɑ��Α����̍l�����玮���Ă��܂��B���������̂ɂ���Č�������鎖�͎����ł���A������ς���A�����̂ɂ����́g�Ђ�����h���ʂ͑��݂���A�ƍl����͎̂��R�ł��傤�v ���R�ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�C���V���^�C���͏��(1)�̂悤�ɂ��āA���������~�܂��Ă���ƍl���āA���ꂩ�瑊�Α��x�̎����g���Ă��邩��ł���B�~�܂��Ă��鐅�Ɂg�Ђ�����h���Ȃ��͓̂��R�ł͂Ȃ����B �㓡���̓A�C���V���^�C�����ǂ��������������Ă���̂����悭�����������ɔ��_����A�Ƃ����g�܂����h�Ȏ�������Ă���̂ł���B ���āA���̌�A�k�ޖ_�̘b�Ƒo�q�̃p���h�b�N�X�̘b�������Ă��邪�A����܂����Θ_���悭�킩���Ă��Ȃ��l��������A�ȉ��̋^�₪�q�ׂ��Ă��邾���ł���B �^��(�`)�u���f����̖_�����n�ő���Ǝ��k����Ȃ�A������̖_�����f�n�ő���ΐL�т�͂��Ȃ̂ɁA��͂���k���鎖�ɂȂ��Ă���̂ł��B�v �^��(�a)�u�`�͂`�f�������ɑ��đ������œ����̂Ŏ������E�E�E�{�������Ƃ�̂��x���Ǝ咣(�܂��͐���)����ł��傤�B�Ƃ��낪�A�`�f�͂`�������ɑ��Ă��œ����Ă���̂ŁA�������E�E�E�{���������̂��x���Ǝ咣(�܂��͐���)���܂��B���̓�̎咣�͖��炩�ɖ������Ă��܂��ˁv �ǂ�����A�g���n�̓����Ƃ��f�n�̓������Ⴄ�Ӗ��ɂȂ��Ă���h�Ƃ������Ő����ł���B�^��(�`)�Ɋւ��Č����ƁA�g���n�̎��Ԃœ����ɁA���f�n�̖_�̗��[�𑪂�h�Ƃ�������Ɓg���f�n�̎��Ԃœ����ɁA���n�̖_�̗��[�𑪂�h�Ƃł͈Ӗ����Ⴄ�A�Ƃ��������̎��Ȃ̂ł���B �����������ƁA������ƋC�̂��������Θ_�̖{�Ȃ�ڂ��Ă���(�c�O�Ȃ��ƂɁA�C�̂����Ă��Ȃ��{�ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ����A����͂��������Ȃ��B�Ȋw������ɂ��X�^�[�W�����̖@���͗L���Ȃ̂ł���)�B ���������A�������茩��킩��͂��̊ԈႢ�X�ƔƂ��āA�����C�Ŗ{�ɂ܂ŏ�����Ƃ����̂́A�㓡�����u���Θ_�͊Ԉ���Ă���v�Ƃ����O���u���A���̑O��ɂ������v�Z���ʂ�(���܂��܉����̊ԈႢ��)�o�����ɂ͌��Z���Ȃ�(���Ȃ��Ƃ��A�܂��߂ɂ��Ȃ�)�����ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B ������đ��l������Ȃ��āc�B���������̘_���Ɂu2��ԈႦ�Č��ǂ͐����������ɂȂ��Ă���v�Ƃ��������ڂ�����������B���������A�g�C�Â��Ȃ������L�����h�������́g�C�����Ȃ��������_�̌��N�ɂ������h�ɂ͋C�����Ȃ��A�Ƃ����l�ԐS����㩂ɂ͗����Ȃ��悤�ɋC�����Ȃ��Ă�(���₱��̓}�W���Șb)�B ���āA���̘b�̓}�C�P���\���E���[���[�̎����Ȃ̂����A�����ł��㓡���͋ꂵ�����������Ă��܂��B�܂��㓡���́A�E�c���̌v�Z(�}�C�P���\���E���[���[�̎����ɉ�̓~�X������A�Ƃ������)�̕s�������܂�(�����A�㓡����!!)�B �������A�E�c���̌v�Z�ɊԈႢ�����邩��ƌ����ă}�C�P���\���E���[���[�̎������������Ǝv���Ă���킯�ł͂������A�Ȃ��B �Ȃ�ƁA�㓡���͎������u���̂����������A�Əq�ׂĂ���̂��B �}�C�P���\���E���[���[�̎����ł́A���̐}�̂悤�ȑ��u���g���܂��B �������� M1 �ɔ��˂��Ă���n�[�t�~���[�ɔ��˂�����ƁA�n�[�t�~���[�ɔ��˂��Ă��� M2�Ŕ��˂������������A�Ƃ����̂��}�C�P���\���E���[���[�̎������u�ł���B �Ƃ��낪�A�㓡���� P2 �̕����ɂ��n�[�t�~���[���Ȃ��Ɗ����N���Ȃ��A�Ƃ����B����͑S�������ł��Ȃ��B���̊���2�̈ʑ���(�s�H��)�̂�������Ԃ���N���蓾��̂ł����āA�n�[�t�~���[��u���Ȃ��Ă����͂����ƋN���܂��B ���ۂɂ��̃n�[�t�~���[�@P2 ���K�v�ȗ��R�́A�������̒���ʂ蔲���鋗����o���œ����ɂ��邽�߂ł���B�Ƃ��낪�c�}�����Ă������������B����ł́A����̌����肪�A����ʂ�}�ɂȂ��Ă���̂ł���I �}�̊ԈႢ���̂͏����Ȃ��ƂƂ��Ă��B�㓡���́u�ŐV�̃I�v�g�Z�p���g���čĎ�������K�v������܂��B�v�Əq�ׂĂ���B���̑厖�Ȏ������}�C�P���\���E���[���[�ȗ���x���Ď�������Ă��Ȃ��A�Ǝv���Ă���̂ł��낤��(���̎v���Ⴂ�́A��������̂���`�Ȋw�҂ɋ��ʂ̂��̂ł��邪)�B �㓡�������Ɏ��グ��͉̂��h�b�v���[���ʂɂ��āB���h�b�v���[���ʂƂ����̂́A���̐i�s�����ɑ��Đ^���ɐi�ތ����̋N�����h�b�v���[���ʂŁA���Θ_�I�łȂ��h�b�v���[���ʂ̏ꍇ�A�g�̐i�s�����Ɣg���̐i�s���������p�ł���h�b�v���[���ʂ͋N����Ȃ��B�������A���Θ_�I�ȏꍇ�A�E���V�}���ʂɂ�鎞�Ԃ̒x��̕��A�^���̏ꍇ�ł��ԕ��Έڂ��N����B��������h�b�v���[���ʂƌĂ�ł���B �㓡���͂��̉��h�b�v���[���ʂ̎��������Əo���Ă��Ȃ���A�������ϑ��҂ɋ߂Â��ꍇ�ł��ԕ��ΈڂɂȂ�A�Ƃ������������Ă݂�����A�u����͐M�����Ȃ����ł��B���Θ_���Ԉ���Ă���Ƃ��������悤���Ȃ��ł��傤�B���̎w�E���{�������j��͂��߂Ăł��v�ƁA�킴�킴�S�`�b�N�̂Ō����Ă��܂��B �ǂ������̐l�́u�������߂Â��Ă��鎞�͐�ɐԕ��Έڂł͂Ȃ��̂��v�Ƃ����g�펯�h������A���Θ_�͂��́g�펯�h�ɂ���Ȃ�����ԈႢ���A�ƌ����Ă���悤�Ȃ̂ł���B���Θ_�͌������߂Â��Ă��鎞�ł��ԕ��Έڂ���\��������A�Ǝ咣���Ă���ɂ�������炸�A�ł���B ���́g�펯�h�������ɗ��ł����ꂽ���̂Ȃ�A�㓡���̎p���ɂ͉��̖����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�㓡���͎���u�ǂ��炪���������i�D�̎����ޗ��ɂȂ�ł��傤�v�Əq�ׂĂ���̂ł���B�܂�A����Ȏ�����ϑ��͂܂��Ȃ��̂��A�Ǝv���Ă���̂��B �Ƃ��낪�A���h�b�v���[���ʂ͊ϑ��Ŋm�F����Ă���̂ł���B���Ƃ��ΓV�̂��畬���o���K�X�ł���F���W�F�b�g�̐ԕ��Έڂ���A�^���ɕ����o���K�X���痈������ԕ��Έڂ���(�������A���Θ_�̗\���ǂ����)���Ƃ��킩���Ă���̂ł���B �㓡���́g�펯�h�͂��͂�펯���肦�Ȃ��B ���̌�A�d����ɂ������œd�q�̑��������������Ȃ��͓̂d���g�������Ői�ނ��炾�A�ƁA�E�c���Ɠ������������Ă�����A���[�����c�Z�k�Ǝ��ۂ̌������ɂ��Ă��낢��Ə����Ă��܂����A����Ɋւ��Ă͏ȗ������Ă��������܂��B �㓡���̕��͂��́u����ԁv�̒��ł͎��ł����ƌv�Z���Ă��镔���������A�܂�����̂��b��̂�����̂ł������A�Ō�̕��ɂȂ�ƁA�����قƂ�ǂ����̃C�`�������Ɖ����Ă���B ����莩���́g�펯�h���㐶�厖�ɕۂ��A����ɔ����鎖�͈ꗶ���Ȃ��u�M�����Ȃ��v�ƕЕt���Ă���̂͘b�ɂ��Ȃ�ɂ��Ȃ�Ⴕ�Ȃ��A�Ƃ������x���ł���B ���̖{�̑тɂ́u���J�I���ق�j��A�v�l�̉ƒ{���Ɏ��~�߂�����������v�Ƃ���܂��B�������J�I���ق����A�v�l�̉ƒ{�������m��A�g�����h�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B �����̏���ɍ�肠�����g�펯�h���������o�悤�Ƃ��Ȃ����̖{�̍�҂����̈�̉����A�v�l�̉ƒ{���Ƃ��Ɏ��~�߂������Ă����ƌ����̂��B �������A����`�Ȋw�͍����܂��A�����玟�ւƏo�ł���Ă���̂ł���E�E�E�B�@ �� *1 �m�X�g���_���X�̑�\����M���Ă���l�����́A�ʂ�����2000�N�ɂȂ����牽�ƌ������낤���H *2 �Ȃ�ł��A���̌�����A�����w�҂̒��������Y�����o�Ȃ�����������̂��������B�������A�ꌾ���������Ȃ������Ƃ��B����ς�A������Ă��܂�����ł��傤���˂��B *3 ���̑O�͒��w���ɂȂ����Ԃ�������邩�����������A���l���͂킩���Ă��ꂽ(�S���ɁA�͖��������ǂ�)�B *4 ���ۂɂ͒ɂ������������J�Ȕᔻ���������̂ɁA�������Ă���A�Ƃ����\���������B *5 �Ȃ�ł����킴�킴���������Ŕᔻ���Ă����ē��ӂ��ɂȂ��Ă���A���������c�B *6 �u�E�l���C�Z���X�E��v�Ƃ�������̒��ŁA��l���ƈ��l���Ό����鎞�A��l���͉E���ɃW�����v�����̂ŁA���l��荂����Ԃ��Ƃ��ł��ď��Ă�A�Ƃ����V�[�����������B���⎁�̎������ʂ�F�߂��Ƃ��Ă��A�W�����v�̍������ς��قǂ̏d�͌����͂����Ȃ��������B *7 ��̗ʎq�_�Ȃǂɏ����Ă���^��̐�����A�d�q�Ɨz�d�q�������őΔ�������A�Ȃǂ̘b�����āA�u����A�^��ɂ̓G�l���M�[���[�����Ă���B���̃G�l���M�[�����ݏo���G�l���M�[���͉��������v�Ƌ���ł���g����`�h�̐l����������(���⎁�͂������ɂ����܂ł͌����Ă��Ȃ���)�B�����������������l�ɐ����Ă݂����̂��u�^��͒�`�ɂ��G�l���M�[�Œ�̏�Ԃł����A��������G�l���M�[�����ݏo���ƁA���̌�ɂ͉����c���ł����H�v�Ƃ������ł���B���ꂪ�w�}�b�J���h���[�q���L�x�݂����ɂr�e�Ȃ�A�u�����낢���I�v�ł��ނ��ǁB �@ |
|
| �����ΐ����_�Ǝ��p�� | |
|
���ꑊ�ΐ����_���[���Ȋw�ҒB�̉a�H�ƂȂ��Ă���̂͑O�q�����ʂ�ł��B �������܂��A�K���������ꑊ�ΐ����_����ΓI�ɐ������A�Ƃ�������܂���B
������m�F����؋��͑�������܂����A�ے肷��؋����������t�����Ă��܂��A�Ⴆ�j���[�g���͊w���܂������ł������̂ł��B �w�ǂ̃P�[�X�ɂ����āA�j���[�g���͊w�͏\���Ɍ�����Ă���A19���I�̉Ȋw�ҒB�́A����Ŗw�ǐ��̒��̑S�Ă̌��ۂ��Ȋw�I�Ɍ�������Ǝv������ł����̂ł��B �������Ȃ���A���ꑊ�ΐ����_�̔��\�ɔ����A���Ɣ�r�������Α��x�������ł��Ȃ��̈�ł́A�j���[�g���͊w�����鎖��m�����̂ł��B ����Ɠ��l�ɁA���ΐ����_���܂��A�������ȏ������ł͕��鎖�����肦�܂��B v/c��0 �̋Ɍ��Ƃ��ē��ꑊ�Θ_���j���[�g���͊w���܂ނ悤�ɁA�Ɍ��Ƃ��ē��ꑊ�Θ_���܂`�ł̐V���ȗ��_�����܂�鎖���\���ɂ��肦��ł��傤�B �A���A���̎��ƁA�[���Ȋw�҂������Ώ�����A���ꑊ�Θ_�����́A�S���ʂ̎����̘b�ł��B ����͐����ɂ��Č����܂��B�͂����藼�҂͋�ʂ��ĉ������B �Ⴆ�A�[���Ȋw�҂����Θ_�̔��Ƃ��Ďw�E����_���ɁA�f�B�b�P/�u�����X�̘_��������܂��B ����́A��ʑ��Θ_�ɑR���ďo���ꂽ���ł����A���̋Ɍ��Ƃ��ē��ꑊ�Θ_���܂�ł��܂��B��ʑ��Θ_�����ꑊ�Θ_���܂ނ̂Ɠ��l�ɁB �ł�����A���ꂪ�������ē��ꑊ�Θ_�����ł���\���͖����̂ł��B ����Ɍ����Ȃ�A�ɒ[�Șb�A���ɃA�C���V���^�C���̌��_���̌����������Ƃ��Ă��A���ꑊ�Θ_���̂͗h�邪�Ȃ��ł��傤�ˁB ���̉���ł�������x���̎����͖ܘ_�̂��ƁA���ꑊ�Θ_�������I�������_�I�Ȍ��A���W�����낢��Ȑl�ɂ���ĂȂ���Ă��Ă���̂ł�����B �����A���݂̑��Θ_�̋L�q�̓A�C���V���^�C���̎���������Ƃ͕\�����قȂ�܂��B ���̎����w�҂͗ǂ��m���Ă��邩��A���� �u���ꑊ�Θ_�̌����������v�ƌ����đ������Ă�l�B�̖{�ȂA�܂Ƃ��ɑ���ɂ͂��Ȃ��̂ł��B �[���Ȋw�ҘA���ɂ͎c�O�ł��傤���A���ꑊ�ΐ����_�����{�I�ɕ������\���́A�����ꂽ�؋����猾���Ă��A����Ȃ��[���ɋ߂��ƌ�����ł��傤�B ������A���Θ_�̔��Ƃ��ċ^���Ȋw�{�ɏo�Ă�����̂ɃA�X�y�̎����_��������܂��B����͏�̗�Ƃ͏����Ӗ����Ⴂ�܂����A��͂葊�Θ_�̔��Ƃ͂Ȃ蓾�܂���B (���������A���̘_����EPR�_���Ƃ�����A�C���V���^�C���̗ʎq�_�ɑ���l���Ɋ�Â��Ă��܂��B�ڂ����͂���܂������ɏ��������B) ���ΐ����_�����Ɏ��p�̈�Ƃ��Ă�����̂ɂ͉��L�̗Ⴊ�������܂��B�@ |
|
|
��1�D
���ɃJ�[�i�r�͑����̎Ԃɓ��ڂ���Ă��܂����A���ꂪ�ǂ�Ȍ����œ��삵�Ă���̂������m�ł��傤���H GPS�l�H�q�����痈��d�g���L���b�`���Ă���E�E�E�����ł͏\���ł͂���܂���B �ʒu�m�ɒm�邽�߂ɂ́A������O�p���ʂɋ���K�v������܂��B�����āA���ׂ̈ɂ͏��Ȃ��Ƃ��O�ȏ�̉q������̓d�g����M����K�v������܂��B �����Œ��ӂ��ׂ��͐l�H�q���͈ړ����Ă���A�ԂƉq���̋����͎�M�����d�g�Ƒ����Ă������ԂƂ���v�Z���邵���Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B �f�o�r�q���̎��v�͌��q���v�Ȃ̂ŋ����܂��A�J�[�i�r���̂̎��v�͐������U�q�Ȃ̂ŁA������Ă�50�`100ppm���炢�ł��B���̕���K�v�ł��邽�߁A������ʂ̉q���d�g����M����K�v������܂��B�܂�s���l���K�v�ł��B �܂�A�l�H�q���͎��v��ς�ł���K�v������A�e�q���̎��v�͓������Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B ���̓������ꂽ���v�Ńi�r���̂̎��v���C������̂ł��B ���R�Ȃ���A���X�x�������x�ňړ�����q���̎��v�͑��Θ_�I�ȕ��K�v�Ƃ��܂��B �����āA�����������Ă���̂ł��B �܂��A�����܂ł�����܂���GPS�q���ƃi�r�̑��x������������܂����A�n���͎��]���Ă��܂��B�����炱��͌����x���łȂ���Θb�ɂȂ�܂���B(GPS�q���͈ړ��q���ŁA�n����ɂ�24�@����܂��B���]����0.5�P���B) ���A��قǏq�ׂ��悤�Ɉړ����Ă�����̂���̋����̑��ʂɓd�g���g�����߁A�����x(�d�g������)�����łȂ���A�����Ȃ����킯������܂���B �܂�A���X�}�C�P���\���^���[���[�̎����������o���K�v�Ȃǖ����A�ԈႢ�Ȃ������x(�d���g)�͈��Ȃ̂ł��B �قȂ銵���n�A�قȂ鎞��ł̑��Θ_�I�Ȏ��Ԃ̕ω��́A���͂�Ȋw�҂̍l���闝�_�����̘b�ł͂Ȃ��A���H�I�ȋZ�p�Ƃ��ĉ��p����Ă�����ł��B (���������A�l�H�q���͒n��������d�͂��������̂ŁA��ʑ��Θ_���g���Ă��܂��B������A�l�H�q���̎��v�͈�ʑ��Θ_�̐i�ݕ��Ɠ��ꑊ�Θ_�̒x�ꕪ�ƂŁA������������ăg�[�^���ł͐i�݂܂��B) ���͎��̈ȑO������Ђł̓J�[�i�r������Ă���A�ׂɍ����Ă��}�j�A�b�N�Ȃ���������Ă܂����B�@ |
|
|
��2�D
�V���N���g���� /�@����́A��X�̎������Ƃ̌W��肪�[����ł͂���܂��A���p����Ă��镨�ł���ɂ͈Ⴂ����܂���B �V���N���g�����͗z�q�Ȃǂ��������邽�߂̑��u�ł��B ����́A�z�q��76GeV(�M�K�E�G���N�g�����E�{���g�F�M�K��109)�Ƃ��ɂ܂ʼn������܂�����A���R�Ȃ���j���[�g���͊w�ł͍���Ȃ��Ȃ�܂��B ����A�u����Ȃ��Ȃ�v�Ȃ�ă������Ⴀ��܂���B���ʂ�80�{���炢�ɂȂ�܂��B ����͓��R�A���Θ_�Ōv�Z���邵������܂���B ���ꂪ�ԈႢ�Ȃ����삷��̂́A���ꑊ�Θ_�ł̌v�Z���ʂ��A���ۂ̌��ʂƖ������Ȃ��ƌ������ł��B������A�ɂ߂Đ��m�ɁA�ł��B ���ۂ̉�����ւ̎���̓}�C�N���g(�������g)��p���A���̎��g�����������闱�q�̑��x�ɓ���(�V���N��)���ĕω������܂�����A���ꂪ�ԈႢ�Ȃ��V���N������ƌ������Ƃ́A���̎��g���̔��g���ȉ��̐��x�Ő������A�Ƃ������Ƃł��B (���݂ɁA���̉�����̍����g���U�ɂ̓}�O�l�g�����Ƃ����^��ǂ��g���Ă��܂��B���̃p���T�[�d���ɂ̓N���C�X�g�����Ƃ����^��ǂ��g���܂��B������A�����Ŏ���Ȃ������I^^;) �V���N���g�����͉~�`�ł�����A����͓����ō����ړ����闱�q�ɑ��Č��S�͂������Ă��܂��B �����炱��͉����x�^���ł���A���ꑊ�Θ_�ł͋L�q�ł��Ȃ��ȂǂƏ������[���Ȋw�{������܂��B ����͖��炩�Ȍ���A�Ƃ������A�����x�^���ł��鎖�͐������̂ł����A���ꑊ�Θ_�ł��ꂪ�L�q�ł��Ȃ��Ƃ����̂͌���Ă��܂��B ���ꑊ�Θ_���Ɍ��Ƃ��ăj���[�g���͊w���܂ނ̂͑O�q�̂Ƃ���ł�����A���ꑊ�Θ_�������x�^�����L�q�ł��Ȃ��Ƃ����Ȃ�A�j���[�g���͊w�����Ăł��Ȃ����ɂȂ��Ă��܂��܂��B����ȃA�z�Ȏ��͖����ł��傤�H�@ |
|
|
��3�D
����̕����w�ł́A�u��̗ʎq�_�v�Ƃ������̂����W���Ă��Ă��܂��B(���͂ƌ����A���̗L���ȃf�B���b�N�ł��B) ����́A�ʎq�_�Ɠ��ꑊ�Θ_�����̂��Ă��Ăł������ł��B ���_�A�������������܂߂Ă��܂������ł��鎖����嗬�ƂȂ�����ŁA������������Ƃ͔ے�ł�����̂ł͂���܂���B �Ƃ���ŁAQED�F�ʎq�d���C�w���m�肵�ē��ꑊ�Θ_��ے肷�����������Ƃ�����܂��B �Ƃ��낪�A����QED�́A�����������Θ_�I�ȗʎq�͊w�ł���A�������̗ʎq�_�̗���ł��B ���������A�����l���Ă����ł��傤�˂��H ���Θ_�I�ʎq�_���m�肵�āA���Θ_��ے肷��̂̓M���O�Ƃ����v���܂���(�� ����ɁA�m���Ă����ė~�����̂́A���ݗ������ɂ߂锼���̍H�w�������ė����_�͗ʎq�_�ł���Ƃ������ł��B �܂����p���܂ł����Ă܂��A�ߔN�ł́u�ʎq�f�B�o�C�X�v�ƌĂ�钴�� LSI �̃A�C�f�A������܂��B ���ꑊ�Θ_��F�߂��ɂ� LSI �����Â炭�Ȃ��Ă��Ă���A�������̍��B �@ |
|
|
��4�D
���͂▾�炩���Ǝv���܂����A�ꕔ�̉Ȋw�҂��������������Ă���b����Ȃ��āA���ɐ��E���̋Z�p�҂����Θ_(���ɓ��ꑊ�Θ_�ł���)���ΓI�Ȋ�ɂ��Ă��܂��B �����āA���ɓd�g�n(�u�d�g�����v����˂��]�A�H�w�̓d�g (^^;;/)�ł́A���ꖳ���ł͍I���s���Ȃ����܂ŗ��Ă��܂��B ���͎����ŋߒm�����̂ł����A���̈�Ԍ���I�ȗ���Ō�ɂ����܂��B����͓d�g�n���肶��Ȃ��A�@�B�n���W���܂��B �q���̍��ǂ{�ɂ́A�p���Ɂu���[�g������v�������āA���ꂪ�����̊���A�Ə����Ă���܂����B ���̊�́A�w1[m] �́A�����^��1/299792458[s] �̊Ԃɐi�ދ����ł���(1983�N)�x�ƒ�`����Ă��܂��B �܂�A���Θ_�̑O��ł���u�����x���̌����v�́A���₠���钷���̊�ł��B�@ �@ |
|
| �����ΐ����_�͊Ԉ���Ă��� | |
| ���� ���ΐ����_�͌���Ă���@ | |
| ��(��)�@�n�߂� | |
|
�u���ΐ����_�͊Ԉ���Ă���v�Ƃ��u���������v�Ƃ��F��ȕ����٘_�������Ă��܂����A�����ɐ��Ƃ̐搶���̓r�N�Ƃ����Ă��܂���B����͉��̂Ȃ̂��B�{����˂��Ă��Ȃ�����ł��B
�v������r�e�܂����̋�z�I�F���_���Ԃ��グ�Č��Ă��A�v���̐搶���̓r�N�Ƃ����܂���B ���Θ_�̂������ȏ��̌����͎��ɂ���̂ł��B �����ɓ�(��)�ݍ��܂Ȃ�����A�搶���̓n�i���Ђ��|���Ȃ��ł��傤�B ���̌��_����o�ė��鏊�̕s�v�c�ȗ������A������������� �u�����Ȃ��Ă�̂�����d�����Ȃ��B�N��}�l�ɂ͉�(��)����Ȃ����낤���ǁv�Ƃ����̂������ł��B ������(����) ���ɂ́A�ǂ����Ă����̖��ɓ��ݍ��܂Ȃ���Ȃ�܂���B �����ŁA�����ł́A���Θ_�̎����g���đ��Θ_�̖��_��������鎖�ɂ��܂��B �Ƃ͐\���܂��Ă��A�ŏ�������������ׂ��ĂẮA�N�������������Ȃ��Ȃ�ł��傤����A�悸�͂₳����������n�߁A�{�`�{�`�ƍ��x�ȏ��Ɉڂ��čs�����ɂ��܂��B �� �ŏ��́A�₳�����b����ł� �悭���Θ_�ł́g ���P�b�g�ȂǂʼnF�����s�����ė���ƉY�����Y�ɂȂ� �h�Ɛ\���܂��B ���P�b�g�̒��ł͐��N�����o(��)���Ă��Ȃ��̂ɁA�n���̕��ł͉��S�N���o���Ă���ƌ����b�ł��B ����ɑ��A���Θ_�ɋ^��������Ă���l�́@�u�ǂ����������Ă��邩�͑��ΓI�Ȗ�肾�B �g ���P�b�g�̕����Î~���Ă��āA�n���̕��������Ă��� �h�ƍl���Ă����������͂Ȃ��B ���̏ꍇ�A�n���̕������N�����o���Ă��Ȃ��̂ɁA���P�b�g�̒��ł͉��S�N���o���Ă��鎖�ɂȂ�B ������ǂ����� ?�v�Ɣ��_���܂��B ����ɑ��ẮA���Θ_������L���ȉ͏o�Ă��܂���B �����A���̕ӂ���b��i�߂Ă݂悤�Ǝv���܂��B �������ɁA�n�������ї�����ȉF���D������Ƃ��܂��B���̉F���D�́A�b��29�������̑����Œn�����牓�������Ă��܂��B ���̉F���D�͋���ł��̂ŁA���ɂ���l�ɂƂ��ẮA�قƂ�ǐÎ~���Ă���̂ƕς�肠��܂���B �B��̈Ⴂ�́A�n���̐l���l�ΔN���Ƃ�ԂɁA�F���D�̒��̐l��������N���Ƃ�Ȃ��Ƃ����������ł��B���̉F���D�́A�b��29�������̑����Ŕ��ł��܂��̂ŁA���Θ_�̌v�Z���ɂ�肻���Ȃ�̂ł��B �n�����т����Ă�����N�A�n���͂��������܂���B�F���D�̓G���W�����~�߁A������s�𑱂��Ă��܂��B������s�ł�����A���ɂ���l�ɂƂ��ĉF���D�͒�~���Ă���̂ƑS��������Ԃł��B ���鎞�A���̉F���D����n���̕����Ɍ����āA���P�b�g��b��29�������̑��x�Ŕ��˂����Ƃ��܂��傤�B ���̃��P�b�g�͐Î~���Ă���F���D�ɑ��āA�b��29�������̑����œ����Ă��܂�����A���P�b�g�̒��̎��Ԃ͉F���D�̒������x���1�^4�����i�݂܂���B ����́A�n�����猩��1�^16�̑����ł������Ԃ��i�܂Ȃ������Ӗ����܂��B �Ƃ��낪�A�����Ŗ�肪�������܂��B ���̃��P�b�g�́A�F���D���猩��Ίm���ɓ����Ă���̂ł����A�n�����猩��A���́A��~���Ă���̂ł��B �F���D�́A�n������b��29�������̑����ʼn��������Ă��܂����A���P�b�g�͂��̉F���D�ɑ��Ĕ��Ε����ɕb��29�������̑����Ŕ��ł��܂��̂ŁA��������0�ŁA���P�b�g�͒n�����猩��ƒ�~���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B �n�����猩��A���P�b�g�̕������˂��ꂽ�n�_�ɒ�~���A�F���D�̕������̂܂ܔ�s�𑱂��Ă��鎖�ɂȂ�̂ł��B ��������ƁA���̃��P�b�g�̒��̎��Ԃ̐i��͒n���Ɠ����łȂ���Ȃ�܂���B ����Ȃ̂ɁA���P�b�g�̒��̎��Ԃ��n����1�^16�����i�܂Ȃ��ł͖������܂��B �u�����@�ǂ�����I�v ���̔��Θ_�́A�����ŏI����Ă��܂��B�����Ŏ~�߂Ă͑ʖڂȂ̂ł��B�{���̖��͎��ɂ���̂ł�����B�����ɓ��ݍ��܂Ȃ�������Ƃ̐搶���̓r�N�Ƃ����܂���B�����āA���Ȃ�s���ȏ�Ԃł��K�����I����Ɂu����ł����Θ_�͐������v�Ǝ咣���鎖�ł��傤�B ������A���ׂ̈ɂ����̖��𖾂炩�ɂ���K�v������̂ł��B �� �Ƃ���ŁA���̐ݒ�ɑ��āu�F���D�͎~�܂��Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����Ă���ł͂Ȃ����B������~�܂��Ă���Ƃ���̂̓C���`�L���B�v�Ƌ������������邩���m��܂���B �����Ƃ��Șb�ł��B�������A����������Ă��܂��ƁA�n���̕��������Ă��܂��̂ŁA�n�����Î~���Ă���Ɖ��肵�Ă̋c�_�����藧���Ȃ��Ȃ�܂��B ���ɁA�n���̐i�s�����Ƌt�̕����ɁA�n���Ɠ������x�Ń��P�b�g�˂����Ƃ��Ă݂܂��傤�B ���̏ꍇ�A���P�b�g�̕����Î~���Ă��āA�n���̕��������Ă��鎖�ɂȂ�܂��B ��������ƁA�n���ɂ���l�͔N���Ƃ炸�ɁA���P�b�g�̒��̐l���N���Ƃ�Ƃ������ɂȂ�̂ł��B �������Ȃ��瑊�Θ_�ł́A�����������������Ă��܂���B �����܂ł��n�����Î~���Ă���Ƃ����O��Řb�����Ă��܂��B ���Ƃ�����A��́A�F���D���Î~���Ă���Ƃ�����������Ȃ��Ƃ��ׂ��ł��傤�B ���ꂪ�ʖڂ��ƌ����̂Ȃ�A�n���͓����Ă���Ƃ����O��ŁA���_�𗧂ĂȂ���Ȃ�܂���B �t�ɁA�����Ă���n����Î~���Ă���A�Ɖ���ł���̂Ȃ�A�G���W�����~�߂Ċ�����s�����Ă���F���D���A�Î~���Ă���Ɖ���ł��锤�ł��B �܂�A�����������Ȃ̂ł��B �ǂ����ɂ��Ă��������Ȃ̂ł��B����ɓ����Ă���̂͒n�������ł͂���܂���B���z�n�A�P���n�A��͌n�A�݂�ȓ����Ă��܂�����A��́A�ǂ����Ȃ��āg�Î~���Ă���h�Ƃ�����ǂ��̂�������Ȃ��Ȃ�܂��B �������́A���ӎ��Ɂg�����Ă���n���h��Î~���Ă���Ɖ��肵�ċc�_��i�߂Ă��܂��B ���Ƃ�����g�F����ԂŃG���W�����߂Ă���F���D�h�͉F���D�̗��ꂩ�猩�āg��~���Ă���h�Ƃ��Ă����͂Ȃ��ł��傤�B �S�Ă͑��ΓI�Ȗ��ł�����B ���������킯�ł������̐ݒ���������肢�܂��B ����ł́A���͕�����Ԃ̒��Ɉڂ��A���w�Z���x�̂₳�������ňȂāA���̖��ɂ��čl���Ă݂܂��傤�B�@ |
|
| ��(��)�@��Ԃ̒��̎��Ԃ̖��� | |
|
��(a) �����Ă����Ԃ̒��ł͎��Ԃ��x���(���)
�E�}�́A��Ԃ̒��̗l�q�����������ł��B�`�C�a�͍��Ȃ̈ʒu�ł��B��Ԃ͑��x �ʼnE�����ɓ����Ă��镨�Ƃ��܂��B�����ŁA�`�̍��Ȃ̐l���������z���ׂɁA���C�^�[�ʼn�_�����Ƃ��܂��傤�B��������ƁA���̌��͂a�̐l�ɂ́A�܂������`���a�̕����֗����l�Ɍ����܂��B�Ƃ��낪�A������O���猩�Ă����l�ɂ́A���͂`���a���̕����֗����l�Ɍ����܂��B���������瑬���Ƃ͌����A�`����a�ɓ͂��Ԃɗ�Ԃ������͑O�ɓ����Ă��邩��ł��B��������ƁA��Ԃ̊O���猩�����̑��s�����́A��Ԃ̒��Ō������̑��s�������������Ȃ�܂��B ����́A���Θ_�ȑO�̍l�����ł����Ȃ�A�u��Ԃ������Ă���̂����瓖����O�ł͂Ȃ����A��Ԃ̊O���猩�����̑��x�́A��Ԃ̒��Ō������̑��x�ɗ�Ԃ̑��x�����Z����Ă���B�����炻�̕��A�������L�тē��R�v�ƂȂ�̂ł����A���Θ_�ł́A�s���̑��x�͗�Ԃ̒����猩�Ă��A�O���猩�Ă������t�ƂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����͍s���܂���B ���Θ_�ł́A�]��������O�����������A������O�ł͒ʂ�Ȃ��̂ł��B �ł́A�ǂ�������悢�̂ł��傤���B���̏ꍇ�ɂ́A���Ԃ̕���ς���̂ł��B �܂��́A���x�̎����@�E�E�E�@�Ƃ��āA�����Ǝ��Ԃ̊W�����Ă݂܂��傤�B ��ԓ��Ō������̑��s���Ԃ��@t / ��ԊO���猩�����̑��s���Ԃ��@t��/ ��ԓ��Ō������̑��s�������@�`�a / ��ԊO���猩�����̑��s�������@�`�a���Ƃ���� ��ԓ��ł̌��̑��x�́@�E�E�E�@��ԊO���猩�����̑��x�́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�����ŁA���̓�̎������킹�܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂����A�} �ł́@�@�`�a�@���@�`�a���ł�����A����� ���ɓ��Ă͂߂Ă݂܂��� t�@���@t���@�ƂȂ�܂��B ���̌��ʂ́s�������̓`��錻�ۂł��A��ԓ��ł̕����A�O���猩��������̓`�d���Ԃ��Z���t�Ƃ�������\�킵�Ă��܂��B����́A��Ԃ̒��̕����O�������v�̐i�ݕ������Ȃ��A�Ƃ������Łs�����Ă����Ԃ̒��ł́A�O�ɔ�ׂĎ��Ԃ��x���t�Ƃ������ɂȂ�킯�ł��B ���ꂪ�A���Θ_�ŗǂ������鏊�́u�����Ă���n�ł͐Î~�n�������Ԃ��x���v�Ƃ������_�̂₳���������̈�ł��B�����܂ł͒���ʂ�ł��B(�� �F ����͎��Ǝ��̍l���ł͂Ȃ��A�w���㕨���̐��E�]�T ���ΐ����_�Ɨʎq�͊w�̒a���x�掵�́u���v�̃p���h�b�N�X�v�̂�����^�������̂ł��B) ���Ď����炪���ł��B�@ |
|
|
��(b) �����Ă����Ԃ̒��ł͎��Ԃ��i�ށH
�E�̐}����������B�������ԓ��̗l�q�ł����A�`�Ƃa�̐l�͑Ίp����Ɍ����������č����Ă��܂��B ���A�����ŁA�`�̍��Ȃ̐l���������z���ׂɁA���C�^�[�ʼn�_�����Ƃ��܂��傤�B��������ƁA���̌��͂a�̐l�ɂ́A�܂������`���a�̕����֗����l�Ɍ����܂��B�Ƃ��낪�A���̌��i���O���猩�Ă����l�ɂ́A���͂`���a���̕����֗����l�Ɍ����܂��B���������瑬���Ƃ͌����A�`����a�ɓ͂��Ԃɗ�Ԃ������͑O�ɓ����Ă��邩��ł��B �} �ł͂`�a�����`�a���̕����������Z���̂ŁA��Ԃ̊O���猩�����̑��s�����̕����A��Ԃ̒��Ō������̑��s���������Z���Ȃ�܂��B����͑O�Ɣ��̌��ʂł��B �O�Ɠ��l�ɂ��ċ����Ǝ��Ԃ̊W�����߂Ă݂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�@�} �ł́@�`�a�@���@�`�a���ł�����@t�@���@t���ƂȂ�܂��B ��������ƁA���x�͌��̑��s���Ԃ́A��Ԃ̒��̕����O�����]���Ɋ|���鎖�ɂȂ�܂ł��B����́A����������A��Ԃ̒��̕����O�������v�������i�ށA�܂莞�Ԃ��i�ނƂ������ɂȂ�킯�ł��B �O�Ɠ��������ł�����̂ɁA���x�́A��Ԃ̒��̕����O�������Ԃ��i�ގ��ɂȂ�܂����B �} �̏�Ԃł́A��ԓ��̎��Ԃ͊O���x�ꂽ�̂ł����A�} �̏�Ԃł͋t�ɐi�ގ��ɂȂ�̂ł��B����͈�̂ǂ��������ł��傤���B������ԓ��ł̌��̎����Ȃ̂ɁA�������錋�ʂ��o�ė��܂����B ���̓�̏�Ԃ͈�̂ǂ����Ⴄ�̂ł��傤���B����́A���́A���̐i�ޕ����Ȃ̂ł��B�����ŁA���̕������A����������ʉ����Ē��ׂČ��܂��傤�B�@ |
|
|
��(c) ���̐i�ޕ����ɂ���Ď��Ԃ̒x��i����قȂ�H
�}�����ĉ������B�~����`���Ă���A�E���̉~�ɂ͖�`���Ă���܂��B�܂��A�����̉~�ł����A����́A��ԓ��̈�_0���������A���̎��Ԃɓ��B����ʒu(��ԓ����猩��)�ł��B�����āA�E���̉~�́A���̈ʒu���Ԃ̊O���猩���ꍇ�̈ʒu�ł��B ��Ԃ͓����Ă��܂��̂ŁA�~�͉E���Ɉړ����܂��B�]���āA�����̉~�̒��S0�������́A�E���̉~�ɓ��B���鎖�ɂȂ�܂��B��Ԃ̒��ł́A���͈��̎��ԂɈ��̋�����i�ނ̂ł����A������O���猩�Ă���ƁA���̋����́A�i�ޕ����ɂ���ă}�`�}�`�ɂȂ�܂��B�@����ɑ��Θ_�̗����Ă͂߁A�����ɉ��߂��悤�Ƃ���A���Ԃ̒x��i��݂͂ȈقȂ��ė��܂��B �O�̂����ł́A�O���猩�����̌��̋����̒��������A��ԓ��̎��Ԃ��x��Ă��܂����̂ŁA��������p���܂��ƁA�~�̔��a�����̒����� (��{�I�ɑO���ɔ���) �����Ԃ��x��A�Z���� (��{�I�Ɍ���ɔ���) �����Ԃ��i�ގ��ɂȂ�܂��B ������ӏ����������Ƃ����������̂ݎ��Ԃ͒x����i�݂����܂��B ���̑��̕����ł́A���̒������F�Ⴂ�܂��̂ŁA���Ԃ̒x��i��͑S���قȂ��ė��܂��B �����������甭�������Ȃ̂ɁA�ǂ̕����Ɍ�����������ɍ̂邩�ŁA�����̎��Ԃ̐i�ݒx�ꂮ�������قȂ��ė���̂ł��B �S���n���������ł����A���́A�S�̂͂����Ȃ��Ă����̂ł��B���Θ_�ŁA�悭�g���鏊�̗�́A���̖����ɂ�����̕����̂ق�̈�������̂����ɉ߂��܂���B�@ |
|
|
��(d)�@���Ԃ͒x������Ȃ���ΐi�݂����Ȃ�
���ɑ��������痈����ōl���Ă݂܂��傤�B ���܂ł̂́A�P������ł̘b�ł������A���ۂ̏ꍇ�A�����͑�R����܂��B���͑O�������납��������ɗ��܂��B���������ꍇ�ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�Î~���Ă��鎞�́A�Ƃ������A�����Ă����Ԃɏ���Ă���ꍇ�A�i�s�����ɑ��đO���痈�������ɂ��āg�����x�s�ς̌����h�ōl����Ύ��Ԃ͐i�݁A��납�痈����ōl����Ύ��Ԃ͒x��鎖�ɂȂ�܂��B����́A�S���A�Œ��ꒃ�Șb�ł� �����A�ǂ������痈�悤�ƁA���̏u�Ԃ̂��̏ꏊ�̎��Ԃ͓����ł��傤�B���������ꍇ�A�s���Ԃ͒x������Ȃ���ΐi�݂����Ȃ��t�ƍl����̂��Ó�(���Ƃ�)�ł��B�����ŁA���Θ_�ɏڂ������́A�u�A�C���V���^�C���́w���Ԃ��x���x�Ƃ͌��������A�w�i�ށx�Ƃ͌����Ă��Ȃ��A������A���O�̗����͐��藧���Ȃ��v�Ƃ�������邩���m��܂���B�Ƃ��낪�A���ׂĂ����ƁA���̖������o�Ă���̂ł��B����́A���������A�Љ�Ă����܂��B ���̑O�ɁA�ȒP�ȏ����瓖�����Ă����܂��傤�B �܂��A���̔n���������ʂɂȂ�����������ł��B�Ȃ��A�����Ȃ����̂��H����́A�A�C���V���^�C�����s���̑��x�͐���t�Ƃ�������ł��B�s�����Ă���n���猩�Ă��A�Î~���Ă���n���猩�Ă������͓����t�Ƃ��Ă��܂�������A�������������������Ă��܂����̂ł��B���͂����ɂ���܂��B�@ |
|
| ��(�O)�@�����x�s�ς̌����ɍ����͖��� | |
| ��(1)�@�����x��͖{���ɐ������̂��H�@ | |
|
�A�C���V���^�C���͌����x�͐�ŁA�����Ȃ���̂����������Ȃ��Ƃ��܂����B����͖{���ɐ������̂ł��傤���B����ׂ邽�߂ɁA�F����ԂɁ@A�AB�AC�@�Ƃ����O�̒n�_��ݒ肵�܂��傤�B
A �� B �̋����� 29��km ����AB �� C �̋����� 29��km ����Ƃ��܂��BA�AB�AC �̎O�̒n�_�͒�����ɕ���ł��܂��BA ���烍�P�b�g��b�� 29��km �̑����ŁAB �̕����Ɍ����Ĕ��˂��A�������� C ��������P�b�g��b�� 29��km �̑����ŁAB �̕����Ɍ����Ĕ��˂����Ƃ��܂��傤�B���̓�̃��P�b�g�͈�b��ɂ� B �n�_�ŏo��܂��B ���ʂ̊��o�Ō����A���̓�̃��P�b�g�̑��Α��x�� �b�� 58���j�� �̂͂��ł��B�Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C���́A��̃��P�b�g�̑��Α��x�� �b�� 30���j�� ���Ȃ��Ƃ��܂����B�@�����A�����Ȃ邩��ł��B�ł��A���̎��̌��ʂ́A�����ɍ����܂���B���Θ_�ł́A�ǂ��炪�����Ă��邩�́A���ΓI�Ȃ͂��ł��B A �̃��P�b�g����܂��Ă��āAB �n�_�� C ���P�b�g���AA ���P�b�g�̏��ɁA����ė����Ɖ��߂��Ă������킯�ł��B�����ŁA�������߂�����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���B B �n�_�́A1�b�Ԃ� 29��km �̋������ړ����āAA ���P�b�g�̂Ƃ���ɂ���Ă��܂��B�܂�b�� 29��km �̑����ňړ����ė������ƂɂȂ�킯�ł��B����͖�肠��܂���B ���ɁAC �̃��P�b�g�́@29 �{ 29 �� 58��km�@�̋����� 1�b�Ԃ� A ���P�b�g�̂Ƃ���܂ł���Ă������ɂȂ�܂��B���ꂪ�A�b�� 58��km �łȂ��ĉ��ł��傤���B1�b�Ł@58��km �̍����k�߂���A����͕b�� 58��km �ł��傤�B���Θ_�̗����͓��������Ă��܂��B �����ŁA���ꂩ�炱�̖��̌����ɂ��ĉ𖾂��Ă������ɂ��܂��B���A���̑O�ɁA�����������A��{�I�Ȃ��Ƃ��炠�����Ă����܂��傤�B�@ |
|
| ��(2)�@�A�C���V���^�C���̑����_ | |
|
��(a) �}�C�P���\���E���[���[�̎���
�A�C���V���^�C���̏o�������ΐ����_�̍����́g�����x�s�ς̌����h�ɂ���܂��B �ł́A���́g�����x�s�ς̌����h�͈�̂ǂ����琶�܂ꂽ�̂ł��傤���B����́A�}�C�P���\���E���[���[�̎�������ł��B�}�C�P���\���ƃ��[���[�̓�l�́A����`����}�̂Ƃ��ẴG�[�e�������݂���̂��ǂ����ׂ�ׂɎ��������܂����B�F���ɃG�[�e�����[�����Ă���̂Ȃ�A�n���̓G�[�e���̊C�̒����j������Ă���悤�Ȃ��̂ł��B�����A�����ł���Ȃ�A�G�[�e���͒n���̓����Ɣ��̕����ɗ���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B �����ŁA�ނ�͍l���܂����B�G�[�e���̗���ƕ��s�Ɍ��������������ꍇ�ƁA���p�ɉ����������ꍇ�Ƃł́A���̑��s���Ԃ��Ⴄ�̂ł͂Ȃ����A�ƁB ����́A�M���ɓn���ꍇ�̗�������ސ�����܂��B�M���̑Ί݂ɓn���ꍇ�A�M�͗���ɗ�����܂��̂ŁA���炩���ߏ㗬�Ɍ����Ď߂ɐi�܂Ȃ���Ȃ�܂���B��������ƁA���̏ꍇ�A�M�͎��ۂ̒����������������q�s���鎖�ɂȂ�܂��B�����Ƃ��A�ڊ݂̂��߂ɑD���݂ɕ��s�ɕt����ꍇ�́A�q�s���@�������قȂ�܂����A����́A�P���������c�_�ł�����A�ׂ������͖��Ȃ��ł��������B�܂��A��ɕ��s�ɐi�ޏꍇ�ł��A�㗬�Ɍ����ꍇ�Ɖ����Ɍ����ꍇ�Ƃł͏��v���Ԃ�����ė��܂��B�㗬�Ɍ����ꍇ�A�M�͗���ɂ���Č�������܂��̂ŁA�������Ԃ͒x��܂����A�A��͉�������ĒZ�����ԂŒ����Ă��܂��܂��B ���̗l�ɗ���ɕ��s�ɐi�ޏꍇ�ł��A���Ɖ���Ƃł͍q�s���Ԃ��Ⴄ�̂ł��B���l�̎������ɂ��Ă������锤�ł��B �����A�G�[�e�������݂���̂Ȃ�A��̌����A�G�[�e���̗���ƒ��p�ȕ����ƕ��s�ȕ����Ƃɕ����ē������������������ꍇ�A���͓����ɂ͖߂��ė��Ȃ��ƍl�����܂��B �����Ŕނ�́A�}�̗l�Ȏ������u���l�Ă��܂����B ���̑��u�Ɍ���ʂ��A�G�[�e���̗���ɕ��s�ȕ����ƒ��p�ȕ����Ƃɕ����ē������������������Ȃ�A�����A���̌��́A�����ɂ͖߂��ė��Ȃ��ł��傤����A�����ɂ́A�����Ɗ��Ȃ��o�邾�낤�ƁB�G�[�e���̗���̐��m�ȕ����͔�(�킩)��Ȃ��Ă��A���̑��u����]��̏�ɏ悹�ĉA�K�Ȉʒu�ɗ������A���Ȃ��o�锤���ƁB�����l���Ď��������̂ł����A���ǁA���Ȃ͏o�܂���ł����B ���̎������ʂ����āA�A�C���V���^�C���́s �����Ă���n���猩�Ă��A�Î~���Ă���n���猩�Ă����̑��x�͓��� �t�Ə���Ɍ��߂����̂ł��B�������A����́A�]��ɂ����v�ł����B ���̎����Ŕ�(�킩)�������́A�u����܂ōl�����Ă����l�ȃ^�C�v�́A���̔}�̂Ƃ��ẴG�[�e���͑��݂��Ȃ��v�Ƃ����������������̂ł��B����ȏ�ł��Ȃ���A����ȉ��ł�����܂���B ���̓������A���̔������̌n�̉^���ɕt�����Ă���ƍl����A���̎������ʂ͉��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B ���ꊵ���n�ŁA�������Î~�n�������ł̎����ł�����B �n���ゾ���Ŋώ@�������A�������k�Ɍ��˂����Ă����ʂł��傤�B����́A����A��Ԃ̒��Ői�s�����ƁA���̐i�s�����ƒ��p�ȕ����ƂɌ��˂����Ē��ׂĂ݂�l�ȕ�������ł��B ����ł͈Ӗ�����܂���B �{���ɒ��ׂ�����Βn���̊O����ώ@���Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ���g��Ԃ̊O���猩��Ɓh�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B �ނ�͒n���̊O����ώ@���܂������H�@����Ă��Ȃ��ł��傤�B �ɂ��ւ�炸�g��Ԃ̊O���猩��Ɓh�ƁA����Ă���̂����Θ_�Ȃ̂ł��B �g�����x�s�ς̌����h�ɍ����ȂǗL��܂���B�N���������Ă��Ȃ��̂ł�����B ����́A�A�C���V���^�C���̑����_���琶�܂ꂽ���ł��B�@ |
|
|
��(b)�@�}�C�P���\���E���[���[�̎����͉ʂ����Đ������Ă���̂��H
���Ɂg���̎������{���ɐ������Ă���̂��ǂ����h�Ƃ����������ɂȂ�܂��B�ƌ����̂́A�}�C�P���\���ƃ��[���[�̓�l�͒n���̉^�������]�ōl���Ă�������ł��B �u���]�ʼn��������I�v�ƌ���ꂻ���ł����A���́A���]�ɂ͖�肪�L��̂ł��B����͎��]�Ƃ̂���݂���ł��B���]�ōl����A�G�[�e���͓����琼�֗���邾���ł����A���]�ł͂����͍s���܂���B���]�̏ꍇ�G�[�e���̗���́A���E���E�[�E��ŕς���ė��܂��B ��͓����琼�ւƗ���A���͐����瓌�ւƗ���Ă����܂��B�����āA�����ɂ͓��ォ��~�蒍���A�[���ɂ͓V��ւƏ����čs���܂��B ���̗l�ɗ��ꂪ�ϓ]���Ē�܂�Ȃ��̂ł��B��]����g���Ă���̂�����A�����A�������ς���Ă��Ή��o�������ȋC�����Ȃ��ł�����܂��A���͂����ȒP�ł͗L��܂���B �w���㕨���̐��E�]�T ���ΐ����_�Ɨʎq�͊w�̒a���x �ɂ��܂��ƁA���_���o�����u�Ō�̎�����1887�N��8����8,9,10,11���y��12���̒��Ɨ[���ɍs��ꂽ�v�Ƃ���܂��B �����Ŗ��Ȃ̂́A���Ɨ[���ł��B���]�ł́A�G�[�e���͒����ɂ͓��ォ��~�蒍���A�[���ɂ͎l������W�܂��ēV��ɏ����čs���܂��B����ł́A��]����ǂ����ɉĂ����ʂł��傤�B�B��̉\���́A���]�ɂ��G�[�e���̗��ꂾ���ł��B�u�����̌��ʂ́A���]�ɂ��G�[�e���̗�������ے肵�����ɂȂ�̂�����A�ʂɖ�薳���ł͂Ȃ����B�v�ƌ���ꂻ���ł����A�������s���܂���B �n���̓����͎��]�ƌ��]�����ł͂Ȃ�����ł��B���z�n���̕����A�����Ă���̂ł�����A���̉e���ɂ��G�[�e���̗�������������Ȃ���Ȃ�܂���B���z�n�͕b�� 20�����ŋ߂��̍P���n������Ă��܂��B�����āA���̍P���n���b�� 320�����ŋ�͌n�̒����Ă��܂��B���̎��ɁA���̋�͌n���܂��b�� 160�����ő��̋�͌n�ɑ��ē����Ă���̂ł��B ��������ƁA�G�[�e���̗���ƌ����Ă��A�{���̏��A�ǂ����̕������痬��Ă���̂��A�����������������Ȃ��Ȃ�܂��B���G����ȗ���ƂȂ锤�ł��B�n���̎��]�ɂ��G�[�e���̗�����A���̉^���̗���ɂ���đ��E(��������)����Ă��Ȃ��Ƃ�������܂���B �Î~���Ă���G�[�e���̒���n�����j������Ă���Ɖ��肷��̂Ȃ�A�F���̂ǂ����ɐ�ΓI�ɐÎ~���Ă���_�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����āA��������_�Ƃ��āA�n���̉^���̕���������o���Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ȃ���A�G�[�e���̖{���̗���͂��߂Ȃ��ł��傤�B����������͕s�\�Ȏ��ł��B ��ꂻ��́A��ΐÎ~�_��F�߂鎖�ɂȂ�A���ΐ��̌��������ے肷�鎖�ɂȂ�܂��B ����́A���A���Θ_�����ے肷�鎖�ɂȂ���̂ł��B����Ȏ��͑��Θ_�M��҂ɂ͐�ɔF�߂��Ȃ����ł��傤�B �]���āA���̎������ʂ����Đ������Ă���̂��ǂ����A���Ƃ������Ȃ��Ȃ�܂��B�����������ł�����A���̎������ʂ���u�����x�s�ς̌����v�f����ȂǁA�����Ă̊O�Ȃ̂ł��B �u�����x�s�ς̌����v�ɍ����ȂǗL��܂���B����̓A�C���V���^�C���̋�z��萶�܂ꂽ���ł�����B�@ |
|
| ��(�l)�@�����̖�� | |
|
���߂́u��Ԃ̒��̎��Ԃ̖����v�̏��ł́A���̕����ɂ���Ď��Ԃ��x�ꂽ��i�肷�鎖���w�E���܂������A���̒��x�̎��ł͑��Θ_�̐搶���̓r�N�Ƃ����Ȃ��ł��傤�B
�u���́g���Ԃ̎��h�́A���O������Ƀf�b�`�グ�����ł͂Ȃ����B�{���̑��Θ_�ł́A����ȗc�t�Ȏ��͂��Ă��Ȃ��B�����ƍ��x�Ȏ����g���Ă���̂��B����ȕ��łǂ�Ȍ��ʂ��o�������ŁA�������̒m�������ł͂Ȃ��B���Θ_�Ƃ͊W�Ȃ��B�v�Ƃ����̂������ł��傤�B �����Ƃ��A���̂����͎��̓Ǝ��̈Ăł͂Ȃ��A�u�k�Д��s�u���㕨���̐��E�|�T�@���ΐ����_�Ɨʎq�͊w�̒a���v�̒��ɂ���掵�́u���v�̃p���h�b�N�X�v�̂������A�������肻�̂܂ܐ^���āA���̌��ʂ��o���������Ȃ̂ł����ǁB ����͂܂��A�Ƃ������A�����Ȃ�\������ł��̂ŁA���Θ_�̌����w�E����ɂ́A�{���̎��͌������܂���B ���Θ_�̌��́A�����̈Ӗ��̊��Ⴂ���痈�Ă���̂ł��B�@���A�����ǂ̗l�Ɋ��Ⴂ�����̂��A�������(�킩)���Ă��炤�ɂ́A�����̈Ӗ���m���Ă��������K�v������܂��B �����ɂ����A�^�̌��������邩��ł��B �����ŁA�����ł́A���Θ_�̎����ߒ���ʂ��āA�������ł���̂���������čs�����ɂ��܂��B ��芸�����́A������w�ŏK�������̎��̌��ĕ��ɏ]���A�����P���Ȏ�������p���Đ������鎖�ɂ��܂��傤�B�@ |
|
|
��(a)�@���[�����c�ϊ��̗U��
�܂��A�}�̗l�Ȓ������W�n���l���܂��B���̍��W�n�̂���_ �o( ) �Ɍ��_ O�������������Ƃ��܂��傤�B ���̋��� �q �͌����� �A���v���Ԃ� �Ƃ��ā@�E�E�E�@�ŋ��܂�܂��B ���ɁAO P �Ԃ̋��� �q �̓����s�^�S���X�̒藝��苁�߂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B (���F���ł����Ȃ�̂��́A���́A�l���Ȃ��ʼn������B�u��A���̌��̑����v�̏��ŏo�Ă��܂�����)�B �����Ł@(1-4-1)�C(1-4-2) �̓��q���������ā@�E�E�E�@�ƒu���܂��B���A�����������ƍH���ā@�E�E�E�@�Ƃ��Ēu���܂��傤�B ���ɁA�����ɐV�������W�n (�^��undou�̓�����)���l���܂��B �O�̌n�́A�Î~���Ă����̂� �r�n(�Î~seishi�̓�����)�Ƃ��܂��B ���G�r�n�E�t�n�͎�������ɕt�������ŁA���Θ_�{���̌Ăі��ł͂���܂���B �{����K�n�EK�L�n�ƂȂ��Ă����̂ł��������������ɂ����̂ŁA����ɕς��܂����n �� �r�n �ɑ��āA���x �� ���������E�ɓ����Ă��镨�Ƃ��܂��B ���̏�ŁA �n �ł� �r�n �Ɠ��l�ɂ��Č��̑��������̋����Ǝ��Ԃ̊W�������߂Ă݂܂��傤�A��������ƁA����́@�E�E�E�@�ƂȂ�͂��ł��B �Ƃ���ŁA �n�̌��_ O���������� �n�̂o���_�܂ő���l�q���A�r�n��茩����ǂ�������ł��傤���B ����́A�}�̗l�ɂȂ�A���̎��́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B ��������ƁA�ꌩ�A���W�̗l�Ɍ����Ă������A���́A�������̓����� �r�n�E �n�Ƃ����قȂ闧��Ō��������Ƃ������������ė��܂��B ���Ƃ�����A���̓�̎�����ׂĘA���������@�E�E�E�@�ɂ��A����������Ă��N�ɂ�����͌����Ȃ��ł��傤�B �����ŁA����������킯�ł����A���̂܂܂ł͉����܂���̂ŏ����Ɂ@�E�E�E�@�����ĉ������ɂ��܂��B �Ȃ��A������������������̂��Ƃ������́A���Ȃ��ʼn������B���ȏ��ɂ���̂����̂܂ʂ��Ă��邾���ł�����B���ʁ@�E�E�E�@�������܂��B ���ꂪ���Ɍ������[�����c�ϊ��ł��B �Ƃ���ŁA�����ŁA�悭���Ƃ����̂��A���̃��[�����c�ϊ��̕���� ��P�P�@�̒��ł��B�n�̑��x ������ �Ɠ����ɂȂ�ƕ��ꂪ 0 �ɂȂ� �� ��������ɂȂ�܂��B������ �� ����Ɓ@��P�P�@�̒����}�C�i�X�ɂȂ� �� �������ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����Łu����͍���A�����ɑ��݂��鋗���⎞�Ԃ�������ɂȂ����苕���ɂȂ����肵�Ă͍���B����́A�����Ȃ镨�����������Ȃ��Ƃ������Ȃ̂��v�Ƃ������߂����܂�ė����킯�ł��B�������A������Ƒ҂��ĉ������B�����ɂ͏d��Ȍ����Ƃ����L��̂ł��B�@ |
|
|
��(b)�@�t�n�̈ړ����x����������Ƒ��Θ_������
�n �̑��x����������Ƃǂ��Ȃ�̂��A�}���悭���ĉ������B�n �̑��x �@������ ����ƁA �n�̌��_ �������� �n �̂o���_�ɓ͂����Ƃ��Ă��A������r�n���猩�鎖�͂ł��܂���B�Ȃ��Ȃ� �n ���̂��̂������ȏ�̑����ʼn��������Ă��邩��ł��B������ς���A����́A�r�n �̊ϑ��҂� �n ��������ȏ�̑����ʼn��������Ă���̂Ɠ������ɂȂ�܂��B ���̏�Ԃł� �n ��蔭���������Ȃ���� �r�n �ɂ͓͂��܂���B�]���āA�r�n �̊ϑ��҂ɂ� �n �͌����܂���B�@�܂�A���̏�Ԃł� �n �͑��݂��Ȃ������R�ƂȂ�̂ł��B ���̏�Ԃł́A���Θ_���ׂ̑O�Ȃ��Ȃ�܂��B ���Ɍ�����ς��āA�r�n �̌��_ O ���������A �n �Ɍ������Ă���Ƃ����ōl���Ă݂܂��傤�B �n �̑��x���������Ă����Ȃ�A�r�n �̌��_ O �������� �n �� �o���_�ɂ͉i�v�ɓ͂��܂���B�ǂ����Ȃ�����ł��B�ǂ����Ȃ����(1-4-7) �̘A���������͐������܂���B�A�����������������Ȃ���A���Θ_�����藧���Ȃ��Ȃ�܂��B�܂�A�������ł͑��Θ_�͖����ƂȂ�̂ł��B�v����ɑ��Θ_�����藧�ׂɂ́A�n�̑��x�������ȉ��ł��鎖���g��ΕK�v�����h�������킯�ł��B �u�����Ȃ镨�����������Ȃ��v�̂ł͂Ȃ��u��������A�A�������������藧���Ȃ��Ȃ�A���Θ_������v�Ƃ����̂��^�̈Ӗ��������̂ł��B �r�n �� O �_�������� �n �� �o���_�ɉi���ɓ͂��Ȃ���A������ �⎞�Ԃ́@�E�E�E�@��������ɂȂ�Ƃ����͓̂��R�ł��傤�B�i���ɓ͂��Ȃ�(�܂薳���̉����ɂ���)�̂ł�����B�܂��A���x �@�������������_�� �@�� �������ɂȂ�Ƃ����̂����R�ł��傤�B���̘A����������������������������̂ł�����B ����͍��Z��N���x�̐��w�̒m��������킩�鎖�ł��B�������@�@�̃O���t�������Ă݂�A�����ɂ킩��܂��B�O���t�͉i�v�� ���ɂ͓��B���܂���B�]���� �̎��̎������ȂǑ��݂��܂���B����𐔊w�Ŗ����ɉ����Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�@��P�@�̒����}�C�i�X�ɂȂ�A�������o�ė��܂��B�����������ɂȂ�Ƃ́A�����������ł��傤�B���Θ_�̋����̖��Ƃ́A���́A�����������x�̎��������̂ł��B �Ȃ��A�����ŁA�}1�]4�]6���猩�� �� �������△����ɂȂ��Ă��A �� �������△����ɂȂ�Ȃ���A�W�Ȃ��ł͂Ȃ����ƁA�v����������邩���m��܂���̂ŁA�������Ă����܂��B ���[�����c�ϊ��ɂ́A�t�ϊ��Ƃ������̂�����܂��B����́@�E�E�E�@�Ƃ������̂ł��āA����Ɋւ��ẮA���ϊ��ƑS�������`�ł��B ���������āA�^���n�̑��x �@������ �Ɠ����ɂȂ�A����͖�����ɂȂ�A������ �⎞�Ԃ� ��������ɂȂ�܂��B�����āA���x ������ ����A����͋����ɂȂ�܂��B�䂦�ɁA �� �������△����ɂȂ�܂��B�@ |
|
|
��(c)�@�����x�s�ς̌������g�����Ȃ镨�����������Ȃ��h���K�肵�Ă����B
��̕��Łg�����Ă���n�̑��x����������ƘA�������������藧���Ȃ��Ȃ�A���Θ_������h�Əq�ׂ܂����B�����āg���Θ_�����藧�ɂ́A�n�̑��x�������ȉ��ł��鎖����ΕK�v�����ł���h�Ƃ��q�ׂ܂����B �����̐l�́A�������������ʁu�����Ȃ镨�����������Ȃ��̂��v�Ɣ��f�����̂ł����A���́A�����ł͂Ȃ������̂ł��B ����́A����ݒ肵���i�K�ŁA�����Ȃ鎖���`���Â����Ă����̂ł��B �A�C���V���^�C���́g�����x�s�ς̌����h�Ƃ����������Ă܂����B ����́g�����Ă���n���猩�Ă��A�Î~���Ă���n���猩�Ă��A���̑��x�͓����h�Ƃ������ł��B �]���̍l�����Ȃ�A�����Ă��镨���甭���ꂽ���̑��x�́u���̑��x�v�{�u���̑��x�v�� �G�@�����Ă��镨���甭���ꂽ�����O���猩�����̌����̃x�N�g���\�� �G�@�����Ă��镨���猩�����̑��x�̃x�N�g���\�� �G�@�����Ă��镨�̑��x�̃x�N�g���\�� �������̂ł����A�A�C���V���^�C���́A������@�b�b���b�b �Ƃ��܂����B ���̌��ʁ@ �̍������x�̑傫���� �ƂȂ�A����������ɗ}�����Ă��܂����̂ł��B���ƕ��̍������x�ł�������~�܂�Ȃ̂ł�����A����⑼�̕��̑��x����A�P�Ƃ̑��x�����������Ȃ��͓̂��R�ł��傤�B �����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�ŏ�����A�����Ȃ�l�ɏ��������Ď������ĂĂ���̂ł�����B���ʂ������Ȃ��ē��R�������̂ł��B�����Ď������������ʁA�����Ȃ����킯�ł͂���܂���B �܂��A�������x�̎��ɂ��Ă��A����������˂܂킵�ā@�E�E�E�@�ȂǂƂ�����������o���K�v�͗L��܂���ł����B�ŏ�����A�u�����x�s�ς̌����v�ō������x�̏���������ɗ}���Ă����̂ł�����B�܂�g�P�Ƃ̑��x���������x���������Ă͂Ȃ�Ȃ��h�Ƃ����̂́A�ŏ����炻�����߂��Ă�������Ȃ̂ł��B �����āA������`���Â����̂��u�����x�s�ς̌����v�ł����B�������āu�����x�s�ς̌����v�ɂ͉��̍������L��܂���B�N���������Ă��Ȃ��̂ł�����B�@ �@ |
|
| ����@���̌��̑��� | |
| ��(��)�@���̐����@ | |
|
�O�͂ł́A���Θ_�̌��ɂ��āu�����x�s�ς̌����v�ɂ͍������������ƁA�u�����x��v�͎������������ʂ����Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�ŏ�����A���������O��Ŏ������Ă��Ă����̂��Ƃ�������������܂����B�������A���̒��x�̎��ł͑��Θ_�̐��Ƃ͔[�����Ȃ��ł��傤�B�����ŁA�����̎��͗ǂ��Ƃ��Ă��A�Ȃ����A���ɁA�����̖���ԈႢ�̗L�鎖���Љ�܂��B
���Θ_�̒��ɂ͊e�_�Ƃ��� ���u�Î~�n�̓�J���œ����ɋN�������o�����ł��A������Ă���n���猩��ƁA�����Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ� ���u�����Ă��镨�̂̐��@�́A�����Î~�n���猩��Ək��Ō�����v�Ƃ� ���u�����Ă���n�̎��Ԃ͐Î~�n�ɔ�ׂĒx���v���Ƃ��������Ȑ�����R����܂��B �Ƃ��낪�A�����͑S�ĊԈ���Ă���̂ł��B ���̌����́A�A�C���V���^�C�������̈Ӗ����Ԉ���ĉ��߂������ɂ���܂����B�ނ͎�������������̈Ӗ��𐳂����������Ă��܂���B���ׁ̈A�b���g���`���J���Ȏ��ɂȂ��z�V�O�E���d�s�v�c�ȕ����ւƍs���Ă��܂����̂ł��B ��́A�����Ԉ���Ă���̂��A�ǂ������������̂��A�������(��)�����Ă��炤�ɂ́A���̑O�ɁA���̈Ӗ���m���Ă��炤�K�v������܂��B�����ŁA�����ł́A���[�����c�ϊ��̗U���ߒ��K���Ȃ���A�O�͂����������ڂ����������čs�����ɂ��܂��B�@ |
|
|
��(a)�@���[�����c�ϊ��U���̕��K
�܂��A�}�Ȓ������W�n���l���܂��B���̍��W�n�̂���_ �o( ) �Ɍ��_ �������i�Ƃ��܂��傤�B��������ƁA���̋��� �q �͌����� �A���s���Ԃ� �Ƃ��ā@�E�E�E�@�ŋ��܂�܂��B�����ŁA���� ���C�ӂ̎����ł͂Ȃ��A���̑��s���Ԃł��鎖���A�͂����肵�ė��܂��B ���Ɍ������������� �o �Ԃ̋��� �q ���A�o�_ �̍��W��苁�߂Č��܂��傤�B �s�^�S���X�̒藝��� �q �̓��́@�E�E�E�@�ł��̂ŁA������J�����܂��Ɓ@�E�E�E�@�ɂȂ�܂��B���̕����͌v�Z��K�v�Ȃ������̂őO�͂ł͏Ȃ��܂����B�����Łu �͂Ƃ������A���� �q �� �o�_�̍��W��苁�߂��̂Ȃ�@�@�͍��W�ł͂Ȃ����v�ƌ�����������邩���m��܂���̂Ő������܂��B �܂��́A�s�^�S���X�̒藝����ł��B �}�̗l�ȏꍇ�A�s�^�S���X�̒藝�́@�E�E�E�@�ł��B�����ł́@�E�E�E�@���@�E�E�E�@���@�E�E�E�@���ӂ̒����ł����狗���ł��B���W�łȂ����͌����܂ł�����܂���B�ł͎O�����̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�} �̗l�ȏꍇ�AO�o �Ԃ̋����� R �Ƃ��܂��ƁA�s�^�S���X�̒藝�́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�����ā@�E�E�E�@�ł�����@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B ���̏ꍇ �@�͕ӂ̒����ł�����S�ċ����ł��B�@���͍��W�������Ƃ��Ă� ���̒��ł͋����ƂȂ�̂ł��B���͖{���́@�E�E�E�@�Ə����ׂ����ł����A�ʓ|�Ȃ̂� 0 ���Ȃ���Ă��邾���ł��B���W�́A�J�b�R�̒��́@ �� 0,�@ �� 0,�@ ��0�@�ɓ�����܂��B �����0 ���Ȃ��@�E�E�E�@�ƂȂ�܂����A����͂����܂ł������̎��ł��B ���Ɂ@�E�E�E�@���܂������̊W���ł��B�@�E�E�E�@�ł�����B���������킯�ŁA���̓��������ďo�������@�E�E�E�@�́A���R�̂��ƂȂ���A�����̊W���ƂȂ�܂��B�̂Ɂ@�E�E�E�@���܂��A�����̊W���ƂȂ�̂ł��B ���ɁA���̎��͋����Ǝ��Ԃ̊W���ł�����܂�����A�����̎���蓱���ꂽ�Ƃ���̃��[�����c�ϊ��@�E�E�E�@�́A���R�̂��ƂȂ���A�����Ǝ��Ԃ̊W���Ƃ������ɂȂ�܂��B �]���āA���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@,�@�E�E�E�@�͋����ł��� ,�@�E�E�E�@�͎��ԂȂ̂ł��B�@ |
|
|
��(b)�@���[�����c�ϊ��̈Ӗ�
���[�����c�ϊ��� �} 2�]1�]4 �̒��̊W���ł���A�����Ǝ��Ԃ̊W���ł��鎖�͊��ɐ������܂����B�����ŁA�����łׂ͍�������������čs���܂��傤�B ���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�Ƃ� �}�̒��̋����́@�E�E�E�@�̎��ł��B����͌��� �n�̌��_ O������o���_�܂ő��������̋����� �������̃x�N�g�������ł��B���o���_�� ���W�ł�����܂��B ���� �ł����A����� �} 2�]1�]4 �̒��̋����� �̎��ł��B����͌��� �r�n�̌��_ O���U�n �̂o��(�r�n�̂o)�_�܂ő��������̋����� �������̃x�N�g�������ł��B���o�_�� ���W�ł�����܂��B���̎��ɁA �Ƃ� �n�ɂ����āA����O���_���o���_�܂Ői�ނ̂Ɋ|���鎞�Ԃł����A�Ƃ͂r�n�ɂ����āA����O�_����o�_�܂Ői�ނ̂Ɋ|���鎞�Ԃł��B �����������₷������ׂɈꗗ�\�̗l�Ȍ`�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂��傤�B�@�E�E�E�@�������A���̈Ӗ���������܂��Ɓ@�E�E�E�@�Ƃ́A �n�ł̌��̑��s������ �������������r�n�ł̌��̑��s������ �����������Ƃr�n�ł̌��̑��s���ԁ@�ƂňȂ��ĕ\�킵�����ŁA�@�E�E�E�@�Ƃ́A �n�ł̌��̑��s���� ���r�n�ł̌��̑��s���� �Ƃr�n�ł̌��̑��s������ �����������ƂňȂ��ĕ\�킵�����Ƃ������ɂȂ�܂��B �܂胍�[�����c�ϊ��Ƃ́A�r�n�́@�E�E�E�@��@�E�E�E�@��ϐ��Ɏg���āA �n�́@�E�E�E�@��@�E�E�E�@��\�킵�����Ƃ������ɂȂ�̂ł��B�Ȃ��A���[�����c�ϊ��@�E�E�E�@�́A���̂܂܂ł͔ɎG�ł��̂Ł@�E�E�E�@���@���@�ɁA �@�� ���@�ɒu�������ā@�E�E�E�@�Ƃ����`�ŗp�����Ă��܂��B ���ɁA���[�����c�ϊ��ɂ͋t�ϊ��Ƃ��ā@�E�E�E�@�Ƃ����̂�����܂��B����́A�����Ă���n�� �� ��ϐ��Ɏg���āA�Î~�n�� �� ��\�킵�����ł��B���̎��́A�e�_�̏ؖ��̎��ɕp�ɂɏo�ė��܂��B�@ |
|
| ��(��)�@�e�_�̌��̏ؖ� | |
| �����i�K���I���܂����̂ŁA�����͊e�_�̖��_�ɓ���܂��B�e�_�̃e�[�}�́u�������̑��ΐ��v�A�u���[�����c���k�v�A�u���Ԃ̒x��v�ɂ��Ăł��B�����ɂ��ẮA�������Ȃ̂����͂����肳����ׂɁA���ȏ��̋L�q�����̂܂Љ�܂��B�������Ȃ���A�w�Z�̋��ȏ��Ƃ����̂́A���Ă��āA������ɂ��������Ă��镨�ł��āA���̂܂܂ł́A���������Ă�̂��悭������܂���B�����ŁA�����̌�ɉ���������͂����A���̌�ŁA����_�]���鎖�ɂ��܂��B�Ȃ��A���ȏ��ł͐Î~�n�� �j�n�A�����Ă���n�͂j���n�ƂȂ��Ă����̂ł����A����͎��̕��͂̓s����A�r�n�E �n �ƕς��A���̔ԍ������̕��͂̔ԍ��ɂ��낦�鎖�ɂ��܂��B����ȊO�͎�������܂���B�@ | |
| ��(1)�@������(�������̑��ΐ�)�@ | |
| ����́u�Î~�n�̓�J���œ����ɉ������N�������Ƃ��Ă��A������Ă���n���猩��ƁA�����Ƃ͌����Ȃ��v�Ƃ����b�ł��B�@ | |
| ��(a)�@���ȏ��ł͂r�n�� �� �Ƃ�����̓_�œ������ɋN�����o�����́A�n �ł͈�ʂɓ����ł͂Ȃ��Ȃ�@�E�E�E�@�Ŏ����@�E�E�E�@�Ɂ@�E�E�E�@�Ŏ����@�E�E�E�@�ɋN�����Ɗϑ������B �ϊ�����@�E�E�E�@�ƂȂ邩��@�E�E�E�@�ƂȂ��� �� �łȂ����� �� �@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿 �r�n �Ł@�E�E�E�@�̈قȂ��̏ꏊ�œ����ɋN�������Ɗϑ�����錻�ۂ��A �n �ł͓����Ƃ͊ϑ�����Ȃ��̂ł���B�@(����)�@�E�E�E�@���̕��͂ł́A�͂����茾���āA���������Ă�̂��ǂ�������܂���̂ʼn�����܂��B�@ | |
|
��(b)�@���
�܂��A�Î~�n�̒��� P1 �_ �� �o2 �_�Ƃ�����̏ꏊ��u���܂��B�����āA���̓�̏ꏊ�œ����ɉ������N�������Ɖ��肵�܂��B���̎��̎����� �Ƃ��܂��傤�B���ɁA���̌��ۂ��Ă���n����ڌ������Ƃ��܂��B���̎��� �n �ł̎����� �o1 �_ �ɂ��Ắ@�E�E�E�@�o2 �_ �ɂ��Ă� �@�E�E�E�@�Ɖ��ɒu���Ă݂܂��B �������Ă����āA�����ɁA���[�����c�ϊ��@�E�E�E�@�������ė��A����� �r�n �ł̎��� �Ƃr�n�ł̓�J���̍��W�@�@�Ɓ@ �@�Ƃ������� �n �ł̎����@�E�E�E�@�Ɓ@�E�E�E�@�Ƃ����߂Č��܂��傤�B�@��������ƁA����́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B �����ł����A �n �̓�J���̎����������ł���Ȃ�@ �| �@��0 �ɂȂ锤�ł��B �����ŁA ��� �������Ă݂܂��B�@�Ƃ��낪�A���ʂ́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA�K������ �@ �| �@�� 0 �Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B���̎��Ł@ �| �@�� 0 �ƂȂ�̂́@ �� �@�̎������ł��B �������u �� �łȂ����� �� �Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�ƂȂ�A�u�����ꏊ�łȂ�����A �n �ł͓��������Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����l���������܂�ė����킯�ł��B����͌���������u�Î~�n�� �̈قȂ��J���œ����ɉ������N�������Ƃ��Ă��A������Ă���n���猩��Γ����Ƃ͊ϑ�����Ȃ��v�Ƃ������ɂȂ�킯�ł��B���ꂪ�u�������v�̗����ł��B �����Ă݂�A�u�m���Ɂv�A�u�Ȃ�قǁv�A�Ǝv���ė��܂��B�������Ȃ���A����͊Ԉ���Ă��܂��B�@ |
|
|
��(c)�@���̏ؖ�
�܂����ɁA�����ł̓��[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�ɂr�n�ł̎��� �Ƃr�n�ł̓�J���̍��W �� �Ƃ������āA �n �ł̎����@�E�E�E�@�Ɓ@�E�E�E�@�Ƃ����߂Ă��܂����A�N���A���̎�������ȕ��Ɏg����ƌ��߂��̂ł��傤���B���̎��́A����Ȏ��ׂ̈̎��ł͂���܂���B���[�����c�ϊ��͌������������̋����Ǝ��Ԃ̊W���Ȃ̂ł��B���ꂩ��A���̊ԈႢ����̓I�ɐ������Ă����܂��B ���ȏ��̐ݒ�ł� ,�@,�@ �͔C�ӂ̎����ƂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���A����������鏊�̃��[�����c�ϊ��� , �͔C�ӂ̎����ł͂���܂���B����́A���̑��s���Ԃł��B�@�E�E�E�@�� �r�n �ɂ����āA���� O�_���� �o�_ �܂ő���̂Ɋ|���鎞�Ԃł����@�E�E�E�@�� �n �ɂ����āA���� O���_���� �o���_�܂ő���̂Ɋ|���鎞�Ԃł��B ���� �C �C �C �ł����A��������ȏ��̐ݒ�ł͔C�ӂ̓_�̍��W�ƂȂ��Ă��܂����A����Ă͂߂鏊�̃��[�����c�ϊ��� �͔C�ӂ̓_�̍��W�ł͂���܂���B����́A�}�̒��̋����́@�E�E�E�@�ł��B����́A�r�n�ɂ����Č������������̋��� �n�o�� �����������ł��B���W�Ɖ��߂��Ă� �o�_�� ���W�Ɍ����܂��B�����ĔC�ӂ̓_�̍��W�Ȃǂł͂���܂���B �]���āA���[�����c�ϊ������ȏ��̗l�Ȑݒ�Ŏg�����͏o���܂���B����͊ԈႢ�ł��B �Ƃ����\���܂��ƁA���������٘_�ɑ��܂��Ă� �u �g�����A������0�̏u�ԂɌ��_�n���A���� �̎��ɂo�_�ɓ͂����h�Ɖ��߂���� �������Ƃ݂Ȃ��Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����H�}�̒��ł́A�o�_�͎��R�ɂƂ��̂�����A�����Őݒ肵�Ă��鏊�̓_��}�̒��ɂo�_�Ƃ��Ēu���Ζ��͖����낤�v�Ƃ��������������邩���m��܂���̂ŁA�����������A�ǂ��Ȃ�̂�������Ă݂܂��傤�B �܂��ݒ�ł́A��̓_ �� �Ƃ�����܂��̂ŁA����� P1, P2 �_�Ƃ��� �} 2-2-2 �̒��ɔC�ӂɒu���܂��B��������ƁA����́A�} 2-2-3 �̗l�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A�����Ŗ�肪�����܂��B�ݒ�ł� �@�͐Î~�n�S�̂̎����̔��ł��B�]���� P1 �_ �ł� P2 �_ �ł������͓����łȂ���Ȃ�܂���B�Ƃ��낪�A�}�Ŗ��炩�ȗl�Ɂ@�E�E�E�@�Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B ���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�́A���X�A���̑��s���Ԃł�����A��������̓��B�����ƒu�������Ă��A�n�S�̂̎����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��BP1 �_ �� P2 �_ �̈ʒu���Ⴆ�A���̑��s�������Ⴂ�܂�����A���B����������ė��܂��B�]���ā@�E�E�E�@�Ƃ͂Ȃ�܂���B���[�����c�ϊ��� �������Ƃ݂Ȃ��A�Î~�n�̒��ł���قȂ�ʒu�̎����͈قȂ鎖�ɂȂ��č��������ɂȂ�܂��B ���������킯�ŁA���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�������Ɂ@�E�E�E�@�����W�Ƃ݂Ȃ��Ă��A���܂��s���Ȃ��̂ł��B�ł͑S���ʖڂȂ̂��ƌ����Ƃ����ł�����܂���B�@ |
|
|
��(d)�@���̈Ӗ��̊��Ⴂ
���́A���̂����ł��g�������̑��ΐ��h�̗����𐬂藧��������@������̂ł��B ����ɂ́A�ǂ�����Ηǂ��̂��B����ɂ́A�܂��A�Î~�n�̎�������v���鏊�A�܂�@�E�E�E�@�ƂȂ鏊��T���o���A������ P1�_ �� P2�_�Ƃ�u�����ł��B���̈ʒu�͐Î~�n�̌��_O���瓯�ꔼ�a�̋��ʏ�ł��B������P1�_��P2�_�Ƃ�u���A�Î~�n�ł̌��̓��B�����͊F�����ɂȂ�܂��B�����������ł�����B���A�����Ă���n�ł̌��̓��B�����͈�v���܂���B �]���āA�����łȂ玮�́@�E�E�E�@�͐��藧���܂��B�����āA�����łȂ�u�Î~�n�� �̈قȂ��J���œ����ɉ������N�������Ƃ��Ă��A������Ă���n���猩��Γ����Ƃ͊ϑ�����Ȃ��v�Ƃ��������͂��������܂��B�u������(�������̑��ΐ�)�v�Ƃ́A���́A������������ȏ������Ő��藧���̈Ӗ����Ԉ���ĉ��߂������������̂ł��B �m���ɁA������������������łȂ�A�����������������藧�ł��傤�B�������Ȃ���A����́A���̋��ʏ�ł̂ݐ��藧�����ł����琳�����͂���܂���B���ʂ�����ł��O�ɏo����Ō�A�Î~�n�ł��瓯�ꎞ���͑��݂��܂���B�����Ȃ�ƁA�C�ӂ̏ꏊ�Ɏ��R�ɍ��W��ݒ肷�鎖���o���Ȃ��Ȃ�܂��B �܂�A���̗l�ɖ������Ă��܂��̂ł��B����ł́A��ʐ��������܂���B�]���āA�������̗��_�͌��ƂȂ�܂��B�@ |
|
| ��(2)�@���[�����c���k(�����Ă���n�̐��@�͏k��) | |
| ����́u�����Ă��镨�̂̐��@�́A�Î~�n���猩��Ǝ��ۂ��k��Ō�����v�Ƃ������ł��B�@ | |
|
��(a)�@���ȏ��ł͂r�n�@�E�E�E�@�ŐÎ~���Ă��钷���@�E�E�E�@�̖_���l����B�_�� ���ɕ��s�ɒu����Ă��镨�Ƃ���B
�_�̗��[�̂r�n �̍��W���@�E�E�E�@�C�@�E�E�E�@�Ƃ���Ɓ@�E�E�E�@�ł����āA����� �ɖ��W�ł���B���̖_�x �œ����Ă��� �n ���猩���炻�̒����͂ǂ��Ȃ�ł��낤���B�n ���猩��Ɩ_�͑��x�@�|�@�œ����Ă���A���̒����� �n �œ����� �Ɋϑ������_�� ���W�̍��ɂ��^�����锤�ł���B �n �ł̒����� �Ƃ���Ɓ@�E�E�E�@�ł��邪�A�ϊ��ɂ��@�E�E�E�@�ł��鎖����@�E�E�E�@�Ƃ����W�������@�E�E�E�@�ƂȂ�B�]���� �n ���猩���_�̒����� �̊������Ŏ��k���Č�����B���l�� �n �ŐÎ~���Ă��� ���ɕ��s�Ȗ_�̒����́A�r�n ���猩��� �̊������������k���Č�����B�ƂȂ��Ă��܂��B ������A�ǂ�������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŕ⑫���Đ������܂��B�@ |
|
|
��(b)�@�⑫����
�܂��A�r�n �ɒu���Ă��钷�� �̖_���l���܂��B���̖_�� ���ɕ��s�ɒu����Ă��镨�Ƃ��܂��B �_�̗��[�̍��W���@�E�E�E�@,�@�E�E�E�@�Ƃ���A���̒����́@�E�E�E�@�ŕ\�킳��܂��B�Ƃ���ŁA���̖_�x �œ����Ă��� �n ���猩����A�ǂ�������ł��傤���B�@�E�E�E�@�n ���猩��ƁA�_�̕������x �| �@�ŁA�܂蔽�Ε����ɓ����Ă��鎖�ɂȂ�܂��B�����āA���̒����� �n �œ����� �Ɋϑ��������̖_�� �@���W�̍��ɂ��^�����锤�ł��B�����ŁA�_�̗��[�̍��W�� , �@�ƒu���Ă݂܂��傤�B��������ƁA���̒����́@�E�E�E�@�ŗ^�����鎖�ɂȂ�܂��B ���ɁA�����ɁA���[�����c�t�ϊ��́@�E�E�E�@�������ė��āA����� �n ���ϑ��������̖_�̗��[�̍��W�@�E�E�E�@,�@�E�E�E�@�Ǝ����́@�E�E�E�@�Ƃ����@�E�E�E�@���āA�r�n�ł̖_�̗��[�̍��W �� �����߂Ă݂܂��傤�B ��������Ɓ@�E�E�E�@�������܂��B�����ŁA���̓���ꂽ���W�@ , �@ ���r�n �ɉ�����_�̒��������߂Ă݂܂��B �_�̒��� �� �| �ł�����A�@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�Ƃ���ŁA���̎��̍Ō��ǂ����ĉ������B�Ō�́@�@�� �n ��茩�����̖_�̒����@�E�E�E�@�ł��B�]���āA���̌��ʂ��s �r�n �ł̖_�̒����t�Ɓs �n ��茩�����̖_�̒����t�Ƃ̊Ԃɂ́@�E�E�E�@�Ƃ����W�̂��鎖���킩��܂��B �����ŁA���̎���f�l�ɂ�������l�Ɍ��t�ɒu�������Ă݂܂��傤�B��������ƁA����́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B �Ƃ���ő��Θ_�ł́@�E�E�E�@�͏��1��菬�ł��̂ŁA���̌��ʂ́@�E�E�E�@�Ƃ������ɂȂ�̂ł��B�@��������ƁA����́s �Î~���Ă���_���A�����Ă���n���璭�߂��ꍇ�A���̒����́A�Î~�n�Ō���̂ɔ�ׂā@�E�E�E�@�̊����ŏk��Ō����� �t�Ƃ������ɂȂ�A����͂܂��t�̌����Ƃ��ās�����Ă���_��Î~�n���璭�߂Ă��A���l�ɏk��Ō�����t�Ƃ��������ɂ��Ȃ�킯�ł��B�����āA�������s�����Ă��镨�̂̐��@�́A�����Î~�n���璭�߂�ƁA�{���̐��@���k��Ō�����t�Ƃ������_��������̂ł��B ���ꂪ�A���[�����c���k�̗����ł��B ������A���̋C�Ȃ��ɓǂނƁA�����̉���l�Ȃ�u�Ȃ�قǁI�v�Ǝv�킹���܂��B�������A������Ԉ���Ă��܂��B�@ |
|
|
��(c)�@���̏ؖ�
�܂����̊ԈႢ�̓��[�����c�t�ϊ��́@�E�E�E�@�� �n �ł̖_�̗��[�̍��W�@ , �Ǝ����� �Ƃ�������A�r�n �ł̖_�̗��[�̍��W�@�E�E�E�@,�@�E�E�E�@�����܂�Ɗ��Ⴂ���Ă��鎖�ł��B���̎��́A����Ȏ��̂��߂̎��ł͂���܂���B����́A���̑����������Ǝ��Ԃ̊W���ł�����B ���ɋ��ȏ����ݒ肵�Ă��鏊�� , , , �@�͖_�̗��[�̍��W�ł����A����������鏊�̃��[�����c�t�ϊ��� �C �͖_�̗��[�̍��W�ł͂���܂���B ����́A���̓��B�_�� �C ���W�ł��B�������āA���̎��̂͌��̑��s������ �C�@�����������Ȃ̂ł��B ��̓I�ɐ\���܂��ƁA �͐Î~�n�ɉ����Č������������̋��� OP �� �����������ł����A �͓����Ă���n�ɉ����Č������������̋��� O�� P���� �@�����������ł��B��������W�Ɖ��߂��Ă��}�̒��� �o,�o���_�� �C ���W�Ɍ����܂��B�������āA�_�̗��[�̍��W�Ȃǂł͂���܂���B ���ɁA���[�����c�t�ϊ��� �C ���܂����̑��s���Ԃł��āA�C�ӂ̎����ł͂���܂���B���������킯�ł�����A���[�����c�t�ϊ������̂悤�Ȑݒ�ɗp���鎖�͏o���܂���B����́A�Ԉ���Ă��܂��B �����͌����܂��Ă��A���������ӌ��ɑ��܂��Ắu�_�̗��[�̈ʒu��} 2-3-4 �̒��� P1�_,�@P2�_�Ƃ��Ēu���Ζ�薳���̂ł́v�Ƃ��������������邩���m��܂���̂ŁA��������ǂ��Ȃ邩���A����Ă݂܂��傤�B �_�̗��[�̈ʒu��Î~�n�� P1 �_ �A�o2 �_�̈ʒu�ɒu���܂��B �����āA�_�� ���ɕ��s�ł�����@�E�E�E�@�Ƃ��܂��B�������Đ}�����܂��ƁA����́A�}�̗l�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪���������ɁA�����ł��@�E�E�E�@�Ƃ͂Ȃ�܂���B����͑O���Ɠ������ł��B �ݒ�ł́u����� �ɖ��W�Łv�Ƃ���܂������A���[�����c�ϊ���p������薳�W�Ƃ͂Ȃ�܂���B �ݒ�� �͌n�S�̂̎����ł����A���[�����c�ϊ��� �͌��̑��s���Ԃł��B �ꏊ���Ⴆ�Ό��̓��B����������Ă��܂��B���R�A�����͈�v���܂���B �̂ɁA�@1 �� 2�C �� �@�Ƃ͂Ȃ�܂���B ��������ƃ� ���̍��������܂���A���́@�E�E�E�@�ł͂Ȃ��@�E�E�E�@�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��B �Ƃ��낪�A��������ƁA���_�� ���o�ė��܂���A���[�����c���k�̗��_�����܂�ė��Ȃ��Ȃ�܂��B ����ł͕s�s���ł��̂� �� ���̍���������l�� �n�ł̎�������v���鏊�A �n �̌��_ O����蓯�ꔼ�a�̋��ʏ�� P1�_ �� P2�_ �Ƃ�u���Č��܂��傤�B �}�̂悤�ɂ���� �n �ł̌��̑��s�����͈��ł�����A���̓��B������ P1�_�ł� P2�_�ł������ɂȂ�܂��B�]���āA�����Ă���n�ł̎�������v���܂��B�Ƃ��낪���x�́A�_�̕��� ���ɕ��s�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B���̏�A�r�n �̎�������v���܂���B�܂�A���̗l�ɖ������Ă��܂��̂ł��B���A�����̖��͑O���́g�������h�̗����ɒ�G���ė��܂��B�@ |
|
| ��(3)�@���[�����c���k�̖��� | |
|
��(a)�@���[�����c���k�̗��_�̗U���͓������̗����Ɩ�������
�O���́g�������h�ł́s�Î~�n�� �̈قȂ��̏ꏊ�Ł@�����ɋN�������Ɗϑ�����錻�ۂ́A�����Ă���n�ł́@�����Ƃ͊ϑ�����Ȃ��t�Ƃ��������ł��B �Ƃ��낪�A�����g���[�����c���k�h�̂Ƃ���ł́A�_�̗��[�̈ʒu�𑪒肵�����̎������A�Î~�n�����łȂ������Ă���n�ł܂œ����ɂ��Ă��܂��B����͓������̗����ɔ����鎖�ł��B �������̗����ɏƂ炷�Ȃ�s�Î~�n�ɒu���Ă���_�̗��[�̈ʒu���A�����Ă���n����@�����Ɋϑ������Ƃ��Ă��A���̈ʒu�͐Î~�n���Ԃł́@�������̎��̈ʒu�ł͂Ȃ��t�ƂȂ锤�ł��B �u���ꂪ�ǂ������A����������Ă��_�̈ʒu�������Ȃ�W�����ł͂Ȃ����I�v�ƌ���ꂻ���ł����A�����͍s���܂���B�Ȃ��Ȃ�ϑ��҂������Ă��邩��ł��B����͗���������J��Ԃ��A�_�������Ă���̂Ɠ������ɂȂ�܂��B���ꂪ�����Ă��Ȃ���Ζ�薳���̂ł����A�@�����Ă��邩����ɂȂ�̂ł��B �ʒu�������܂�����B �����Ă���_�̗��[�̍��W��ʁX�̎����ɑ������Ȃ�A���������@�͏o�Ȃ��ł��傤�B�@�������̗����ɏƂ炷�Ȃ�s�����Ă���_�̗��[�̈ʒu���A�Î~�n���瓯���Ɋϑ������Ƃ��Ă��A���̎������Ă���ʒu�́A�_�̌n�̎����ō��[�� �̎��̈ʒu�E�E�[�� �̎��̈ʒu�t�ƂȂ锤�ł��B���ꂪ�����Ɍ����Ă��邾���ł��B ���̏�Ԃ�}������ΐ}�̗l�ɂȂ�ł��傤�B�@�E�E�E�@ ���̐}�ł����āA�Î~�n�ł̈ʒu�ɑΉ�����ʒu���A�����Ă���n��茩�悤�Ƃ���Ȃ�A���[�� ( ) �E�[�� ( ) �@�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B��������ƁA�_�̒����͌n�̐i�s�����ɂ���ẮA������������Z���������肷�邩���m��܂���B���̏ꍇ�A�����͏d�v�ȗv�f�ƂȂ�܂��B�@�W�����ȂǂƏ���ɊO���܂���B�܂葊�Θ_�Ƃ́A���̗l�ɁA�����̒��ɂ��疵�����܂�ł��镨�������̂ł��B�ƌ����Ă��A���Θ_�M�҂̕������̒��x�̎��Ŕ[������锤���Ȃ��ł��傤���A���[�����c�ϊ��������̐}����z�����āA�u����ł������͏k�ށv�ƃK�����I����̎咣�������ł��傤����A���̎��ɂ��Ă��G��Ă����܂��傤�B�@ |
|
|
��(b)�@�����O�ɐi�߂ΐ��@�͏k�݁A�������ɐi�߂ΐ��@�͐L�т�
�}�����ĉ������B����������钼�O�ɂ� �r�n �� O �_�� �n �� O���_�͏d�Ȃ��Ă��܂��B������ O�CO���_�������� �n �̂o���_�ɓ͂������A �n �͋����ɂ��� �����E�Ɉړ����Ă��܂��̂ŁA�r�n�̋��� �� �n �̋��� �@�ɔ�ׂ� �@���������Ȃ�܂��B����́A������ς���� �n �̐��@�� �r �n �ɔ�ׁA�k�Ƃ������ɂ��Ȃ�킯�ł��B��������l���āg�����Ă��镨�̂̐��@�͏k�ށh�Ƃ������������藧�������ȋC�����Ȃ��ł�����܂��A���͂����P���ł͂���܂���B�����ɂ͗��\������̂ł��B�t�������܂��B �������n�̐i�s�����Ƌt�����ɔ�������ǂ��Ȃ�ł��傤���B �}�����ĉ������B����������钼�O O�_�� O���_�͏d�Ȃ��Ă��܂��B�����āA����������Ăr�n �̂o�_�ɓ͂������A �n �� �����E�Ɉړ����Ă��܂��̂� �n�̋��� �� �r�n�̋��� �ɔ�ׂ� ���������Ȃ�܂��B��������ƍ��x�́A�����Ă���n�̐��@�̕����Î~�n���L�т����ɂȂ�̂ł��B����O�ɔ��������̐}�ł́A�����Ă���n�̐��@�͏k��Ō������̂ł����A���Ɍ��������̐}�ł́A�t�ɐL�тČ�����̂ł��B ����́A�������́E���߂́u��Ԃ̒��̎��Ԃ̖����v�̏��ŏq�ׂ��̂Ǝ������ۂł��傤�B�O�ɐi�ތ�����ɂ��čl����ΐ��@�͏k�݁A���ɐi�ތ�����ɂ��čl����ΐ��@�͐L�т�B�������āA��_��蔭���ꂽ���͓����ɑO�ɂ����ɂ��i�ނ��́B���������ꍇ�A���@�͏k�݂����Ȃ���ΐL�т����Ȃ��ƍl����̂��Ó��ł��傤�B ����̓A�C���V���^�C�����ςȑ���(�����x�s�ς̌����̓���)����������A�g�����O�ɐi�ޕ����h�Ő��@���k�݁A���̔����Ƃ��āg�������ɐi�ޕ����h�Ő��@���L�тāA�������Ȏ��ɂȂ��Ă��܂����̂ł��B ���[�����c���k�́A���̌��������ɂ�萶�������̂���́g�����O�ɐi�ޕ����h������߂炦�����ł����琳�����͂���܂���B�S���i���Z���X�ȕ��ƂȂ�܂��B �Ƃ���ŁA���́u��������ɔ��������̐}�v�́u���[�����c�t�ϊ��v�Ƃ��֘A������܂��̂ŁA���̎��ɂ��Ă��G��Ă����܂��傤�B�@ |
|
|
��(c)�@����O���ɔ��������ƁA����ɔ��������Ƃł�
�Î~�n�Ɠ����Ă���n�̗��ꂪ�t�]����B �}�̗l�Ɍ������Ɍ�����ƁA�o�_�A�o���_�́@�E�E�E�@,�@�E�E�E�@���W�� (�| ),�@(�| ) �ƂȂ�܂��̂ŁA��������[�����c�ϊ��@�E�E�E�@�ɑ�����Ă݂܂��傤�B�@��������Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA���[�����c�t�ϊ��@�E�E�E�@�Ƃ悭�����`���o�ė��܂��B���� �� �A �� ������ւ���Ă��邾���ł����ǁB �����Ă܂��A����́A���̕����͌��̂܂܂ŁA�n�̐i�s�������t�ɂ��Ă����l�̌��ʂ������܂��B�i�s�������t�ɂ���Ƃ������́A���x �@�� (�| ) �ɂ���Ƃ������ł�����A��������[�����c�ϊ��ɑ�����Ă݂܂��B ����Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA�������͂蓯�����ʂ������܂��B�����ł�����ƁA�t�ϊ��̎��Ɛ��ϊ��Ō��̕����ƌn�̕����Ƃ��t�ɂ������̎�����ׂĂ݂܂��傤�B �@�E�E�E�@ ���̗l�ɓ͎��Ă��܂��B�Ⴄ�̂� �� �A �� ������ւ���Ă��鎖�����ł��B����͈�̉����Ӗ����Ă���̂ł��傤���B��1�́A����O���ɔ��������̂r�n�� �� ��\���Ă���A��2�͌�������ɔ��������� �n �� �� ��\���Ă��܂��̂ŁA�����}�ɂ��ĕ��ׂĂ݂܂��傤�B��������Ɓ@�E�E�E�@�} �̗l�ɂȂ�܂��āA�����Ƃ����̌o�H�̒��������w���Ă��鎖������܂��B�܂�@�E�E�E�@�Ȃǂ̗l�ɁA(�@)�̒��̋L�����v���X�ɂȂ��Ă鎮�́A�}�ł͌��̌o�H�̒������������A�t�Ɂ@�E�E�E�@�Ȃǂ̗l�ɁA(�@)�̒��̋L�����}�C�i�X�ɂȂ��Ă鎮�́A�}�ł͌��̌o�H�̒Z�����������Ă����̂ł��B �������A�����O���ɔ�����ꂽ���ƁA����ɔ�����ꂽ���Ƃł́A�r�n�� �n �̗��ꂪ�t�]���鎖������܂��B�}�Ŗ��炩�ȗl�ɁA ���@��������ɔ�����ꂽ���� �n �̌��̌o�H�́A�����O���ɔ�����ꂽ���� �r�n �̌��̌o�H�Ƒ������Ă���A ���@��������ɔ�����ꂽ���� �r�n �̌��̌o�H�́A�����O���ɔ�����ꂽ���� �n �̌��̌o�H�ɑ������Ă��܂��B ���@��������ɔ��������� �n �́A��ʂɑ��Θ_�Ō������́g�Î~�n�h�Ɠ�����Ԃɂ���A ���@��������ɔ��������� �r�n �́A��ʂɑ��Θ_�Ō������́g�����Ă���n�h�Ɠ�����Ԃɂ���܂��B �{���͂r�n���g�Î~�n�h�ŁA �n���g�����Ă���n�h�ł�����A�����ł͂r�n�� �n�̂���ׂ���Ԃ��t�]�������ɂȂ�܂��B�܂�A�n�̐i�s�����Ƌt�����Ɍ�����ƁA�Î~�n�Ɠ����Ă���n�̗��ꂪ����ւ���Ă��܂��̂ł��B���������킯�ł�����g�Î~�n�h���́g�����Ă���n�h���̂ƌ����Ă��Ӗ�����܂���B���̕�����ň����J��Ԃ�܂�����B ���A���ȏ��̗��_�̗U���̎d���́A������������肻�̂܂g���āA�S���t�̌��ʂ��������o�������o���܂��̂ŁA������Љ�Ă����܂��傤�B�@ |
|
|
��(d)�@�����Ă���_�̐��@�͐Î~�n�ɔ�ׂĐL�т�B
�����ł́A �n �ɒu���Ă���_���r�n���ώ@����Ƃ����`�ŁA���ȏ��ɏ����Ă���菇���������肻�̂܂g���āA�t�̌��ʂ��o���Ă݂܂��傤�B�u �n �ŐÎ~���Ă��钷�� �̖_���l����B�_�� ���ɕ��s�ɒu����Ă�����̂Ƃ���B �_�̗��[�� �n �ł̍��W�� , �Ƃ���Ɓ@�E�E�E�@�ł����āA����� �ɖ��W�ł���B���̖_���r�n ���猩����A���̒����͂ǂ��Ȃ�ł��낤���B�r�n ���猩��Ɩ_�͑��x �@�œ����Ă���A���̒����́A�r�n �œ����� �Ɋϑ������_�̗��[�̍��W�̍��ɂ��^�����锤�ł���B�r�n�ł̒����� �Ƃ���Ɓ@�E�E�E�@�ł��邪�ϊ����@�E�E�E�@�ł��鎖����@�E�E�E�@�Ƃ����W�������@�E�E�E�@�ƂȂ�B�Ƃ���Ł@�E�E�E�@�ł��邩��@�E�E�E�@�ƂȂ�sU�n�ɂ���_�̒����͂r�n��茩��ƐL�тČ�����t���ɂȂ�v�ƂȂ�܂��B ���܂����Ă���Ǝv���Ă͂����܂���̂ŁA�����\�̗l�Ȍ`�ɂ��A���ȏ��̂����ƕ��L���Ĕ�ׂĂ݂܂��傤�B���̒ʂ艽�̂��܂���������܂���B���̗l�Ȃ����ł͂ǂ����ł����藧�̂ł��B �ȏ�̘_�ɂ��u���[�����c���k�v�͌��ƂȂ�܂��B �����Ă܂��A�������A���͂́u��Ԃ̒��̎��Ԃ̖����v�ŏq�ׂ������A���̒P�Ȃ�v�����ł͂Ȃ��A���Θ_�̖{���ɗR�����镨�ł��鎖��������ɂȂ�Ǝv���܂��B�@ |
|
| ��(4)�@�������v�̒x��(���Ԃ̒x��) | |
|
���̍��Ɋւ��܂��ẮA�O�̓�̍��Ƃ͕ʂ̖{���̗p���Ă��܂��B ���̗��R�́A���̗U���̎d���ɔ[��������������A��������Â炩��������ł��B ���͎R���������̂ł����A������������ŏ��F�́A���M�҂̃~�X�Ƃ���邾���ő��Θ_�̃~�X�ł͖����Ƃ����̂������������̂ŊO���܂����B
�����ł́A�ʂ̖{(�����N���w�͊w�x�։ؖ[)�ɍ݂��������̗p���Ă��܂��B�����A���̖{�̌����́A��发���L�̔��ɉ���Â炢�����������Ă���܂���(���e�͑債�����Ȃ��̂ł���)�������ƕs�K�v�ɂ�₱�����Ȃ�܂��̂ŁA�ŏ�����|�ďЉ�鎖�ɂ��܂����B�Ȃ������́A�Î~�n�� �n�A�����Ă���n�� �n�ƂȂ��Ă����̂ł����A������A���̕��͂ƍ��킹��ׂ� �r �n�E �n �Ƃ��܂��B�@ |
|
|
��(a)�@���ȏ��̓��e
���ȏ��ł́u �n �� ����̂���_�@�@�Ƃ������Ɏ��v���u���Ă���Ƃ���B ���̎��v�� �n ���猩��ƐÎ~���Ă���̂ł��邪�A�r �n���猩��Ƒ��x �œ����Ă��鎖�ɂȂ�B���āA���́@�@�Ƃ������œ�̎������N�������Ƃ��悤�B�����āA���̓�̎����̋N�������������@ �C�@�E�E�E�@�Ƃ������B ���ɁA�����ɁA���[�����c�t�ϊ��@�E�E�E�@�������ė��āA����� �n �ł̎����@ �C�@�ƍ��W�� �Ƃ������āA���̎��� �r �n �ł̎��� 1 �� 2 �Ƃ����߂Ă݂悤�B��������Ɓ@�E�E�E�@��������B ���̓���ꂽ 1�C2 ���r�n ���猩�����̗������̊Ԃ̎��ԊԊu�����߂Ă݂悤�B����́@�E�E�E�@�ƂȂ�B �Ƃ���ŁA���̎��̉E�ӂ� �@�� �n �Ō������̗������̊Ԃ̎��ԊԊu�ł��邩��A�n �����C���ɂ���ׂɁA����������ɏo���ā@�E�E�E�@�Ƃ����A���̎������t�ŕ\�킵�Č���@�E�E�E�@�ƂȂ�B�����ā@�@�͏��1��菬�ł���������A��������l���ɓ����Ƃ��̎��́@�E�E�E�@�Ƃ������ɂȂ�̂ł���B ����́w�����o�����̌o�ߎ��Ԃł��AU�n �ő������ �r�n �ő���������Ԃ��Z���x�����b���w�����Ă���n�ł̕����Î~�n�ł������Ԃ̐i�ݕ������Ȃ��B�܂�A���Ԃ��x���x�v�ƌ����Ă�킯�ł��B �m���ɁA��������̗͂��ꂾ�������̋C�Ȃ��ɓǂނƁA�����v�킹���܂��B�������A������Ԉ���Ă��܂��B�@ |
|
|
��(b)�@���̏ؖ�
�܂����ɁA������O���Ɠ������ł����A���[�����c�t�ϊ��@�E�E�E�@�� �n �ł̓�̎����@ �C�@�Ǝ��v�̈ʒu�̍��W�� �Ƃ�������A�r �n �ł̎���( �n �ł́@ �C�@�ɑΉ�����)�����܂�Ɗ��Ⴂ���Ă��鎖�ł��B���̎��́A����Ȏ��ł͂���܂���B����́A���̑��������̋����Ǝ��Ԃ̊W���ł�����B�����̌��ɂ��Ă��ڂ����������Ă����܂��B���ȏ��ł� 1 �C 2 �C �C �������Ƃ��Đݒ肵�Ă��܂����A����������鏊�̃��[�����c�t�ϊ��́@ �C�@�͎����ł͂���܂���B����͌��̑��s���Ԃł��B ���[�����c�t�ϊ��� �� �}�� �r �n �ɉ����Č��� O�_ ���� P�_ �܂ő���̂Ɋ|���鎞�Ԃł����A �@�� �n �ɉ����Č��� O���_���� �o���_�܂ő���̂Ɋ|���鎞�Ԃł��B�������ĔC�ӂ̎����ł͂���܂���B ���ɁA���ȏ��ł� �����v�̒u���Ă���ʒu�Ƃ��āA ����̔C�ӂ̓_�̍��W�ɐݒ肵�Ă��܂����A���[�����c�t�ϊ��� �@�͔C�ӂ̓_�̍��W�ł͂���܂���B����� �} 2�]4�]2 �̒��̋����� �ł��B����� �n �ɉ����Č��� O���_���� P���_�܂ő��������̋����� �����������ł��B���W�ƌ��Ȃ��Ă� P���_�� ���W�Ɍ����܂��B�������ĔC�ӂ̓_�̍��W�Ȃǂł͂���܂���B ���̎��ɁA�A�C���V���^�C���⑊�Θ_�̐��Ƃ������Ƃ��Ă��鎖�� �s���[�����c�ϊ��� �͎��ԂƋ��ɕϓ�����t �Ƃ�����������܂��B ���[�����c�ϊ��� �@�́A �@�� 0 �̎��� 0 �ł������ԂƋ��ɑ傫���Ȃ� �� ��(������)�ł͖�����ɂȂ�܂��B���ł͂���܂���B ����� ����̋������낤�ƁA�o���_�� ���W���낤�Ɠ������ł��B ����A�ݒ�� �͎��v�̈ʒu�ł����瓮���܂���B����͕s�ςł��B���������_������A���v�̈ʒu�� �����[�����c�ϊ��� �ɑ�����鎖�͊ԈႢ�Ȃ̂ł��B �� �Ƃ͌����܂��Ă��A�����Ă鎖�̈Ӗ����킩��Ȃ��Ƃ����܂���̂ŁA�����}�ł����Đ������鎖�ɂ��܂��B ������(�Q�Ɛ})�@�E�E�E�@�ŏ� 0���̎��ɂ́A�r�n �̌��_ O �� �n �̌��_ O���͏d�Ȃ��Ă��܂��B���̎��́A�܂����͔�����Ă��܂���B �]���� �o�_�E�o���_�͌��_�̒��ɂ���܂��B �̂Ɂ@�@���@0�ł��B ���Ɍ��� 0 ���ɔ��˂���1���Ԍo����(�܂�1����)���� �}�� �}1�Ƃ��܂��B���Ԃ����ɂ���̑��s�����͐L�тčs���A2���̎��ł�1���̎��̂��傤�ǔ{�ɂȂ�܂��B���ꂪ �}2�ł��B�}�ł킩��܂��l�ɁA1���̎��̂o1,�o1���_��2���̎��̂o2,�o2���_�Ƃł͈ʒu���Ⴂ�܂��B���R1���̎��� ��2���̎��� ���ʒu���Ⴂ�܂��B���ꂪ���[�����c�ϊ��� �ł��B ����ɑ��Ď��v�̈ʒu�Ƃ����͓̂����܂���A1���ł��낤��2���ł��낤�Ɠ����ꏊ�ł��B���̗l�Ɏ��v�̈ʒu�� �ƃ��[�����c�ϊ��� �Ƃł͈Ӗ����Ⴄ�̂ł��B ���[�A���ꂩ��A�u�����ꎞ�ԑ�������A�Ƃ�ł��Ȃ������ŁA����Ȕ�r�Ȃ��o���Ȃ����v�Ƃ����A�����ȋc�_�͂�߂ĉ������ˁB����͂����܂ł��A�P���������b�ł�����B �Ƃ����킯�ŁA�����ʒu�ł̎��Ԍo�߂��]�X������Ƀ��[�����c�ϊ����g�����͏o���܂���B���[�����c�ϊ��͌��̑����������Ǝ��Ԃ̊W���ł�����B���̓��B�������ς��Γ��B�ʒu���قȂ��ė��܂��B�����͐i��ł���̂ɁA�ʒu�����̂܂܂Ƃ����킯�ɂ͍s���܂���B �����̏��̈Ⴂ�ɋC�Â����������Ďg���Ƃ������Ȏ��ɂȂ�܂��B�����Ƃ��A�����͌����܂��Ă��A���̃��[�����c�ϊ��� �Ǝ��v�̈ʒu�� �Ƃ���v��������@�������킯�ł�����܂���B �����ŁA���͂��������Ă݂āA���Θ_�̎����{���͉��������Ă���̂��ׂĂ݂܂��傤�B�@ |
|
|
��(c)�@���̈Ӗ����鏊
����ɂ́A�܂� U �n �̌��_ O����� ���ɐ����Ɍ����A����� �r�n����ϑ����鎖�ł��B��������ƁA���̐}�� �}�̗l�ɂȂ�܂��B���̏ꍇ�A���̓��B�_�� ���W �́A�����Ȃ鎞�ł� O���ł�������ƂȂ�A���ȏ��̐ݒ�ƍ��v���鎖�ɂȂ�܂��B �܂肱�������ꍇ�łȂ� �@�����v�̈ʒu�ƌ��Ȃ��Ă������x���Ȃ��Ȃ�̂ł��B�����Ă���������ԂłȂ�g���Ԃ̒x��_�h�̌��ƂȂ��� ���@�E�E�E�@�͐��藧���܂��B�����ŁA���́A���̎��̈Ӗ��ɂ��čl���Č��܂��傤�B �܂��� �}�ɒ��ڂ��ĉ������B���̔�����鎞��0���A1 ��1���A2 ��2���Ƃ���@�E�E�E�@�Ƃ������Ƃ� (2�]4�]3) �̎��́@�E�E�E�@�Œu�������Ă������Ƃ������ł��B����� �}�ōl���Ă������Ƃ������ɂȂ�܂��B ���́@�E�E�E�@������������Ɓ@�E�E�E�@�ɂȂ�܂��̂� ����� �}�ɓ��Ă͂߂čl���Ă݂܂��傤�B �܂Âo,�o���_�̏��̊p�x���ƁA�r�n�ɉ���������� �AU�n�̈ړ����x�� �Ƃ���� U �n ���ł̌��̑��x�͕X��(���w��)�@�ɂȂ�܂��B��������Ɓ@�E�E�E�@�́@cos�Ɓ@�Ƃ��Ȃ�̂ł��@�E�E�E�@�����ŁA������� �ɖ߂��@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B��������A����́A�}�̒��̎O�p����\�킵�Ă���̂��Ƃ������������Ă��܂��B�@�܂�@�E�E�E�@�Ƃ́A�}�̒��̎O�p���̎��������̂ł��B���R�@�E�E�E�@�̌��̎��ł���@�E�E�E�@���܂� �} �̎O�p���̎��Ƃ������ɂȂ�܂��B �܂�u���Ԃ̒x��v�_�̌��ƂȂ������́A�{���́A�} 2�]4�]11 �̒��̎O�p����\�킵�Ă����킯�ł��B �� �u������Ƒ҂āA����Ȃ�w�����Ă���n�̎��Ԃ͐Î~�n�ɔ�ׂĒx���x�Ƃ������������藧�ł͂Ȃ����v�ƌ���ꂻ���ł����A�����͍s���܂���B�Ȃ��Ȃ�A���̎��� ���ɐ����ɔ����ꂽ���݂̂ōl�����Ă��邩��ł��B���̕����̌��͈�؍l������Ă��܂���B���̕����̌��ōl�����Ȃ�A���̎��͐��藧���܂���B ���ɗ����ς��āA�r�n�̌��_ O��� ���ɐ����ɔ����ꂽ������ɂ��čl���Č��܂��傤�B ��������ƁA�}��莮�́@�E�E�E�@�ƂȂ�A�S�������̌��ʂ������Ă��܂��܂��B���̏ꍇ�AU �n �̕��� �r�n ��莞�Ԃ��i�ގ��ɂȂ�̂ł��B�����āA��O�Ɍn�̐i�s�����Ƌt�����Ɍ�����ΐ}�̗l�Ɂ@ �� �@�ƂȂ�܂��āAU �n �̎��Ԃ̕����m���� �r�n ���i�ގ��ɂȂ�܂��B �Ƃ����킯�Łu���Ԃ̒x��v�_�̗����͐��藧���܂���B ���A�}�����̐����ł͏��������˂�Ƃ������ׂ̈ɁA���ȏ��Ɠ��������ŁA�����̌��ʂ��o���A���̗��_�����ł��鎖���ؖ����Ă����܂��傤�B�@ |
|
|
��(d)�@�t�����藧��
�@�E�E�E�@�ƁA���̗l�ɂȂ�܂��B���������������ł́A��������ŁA�ǂ����̌��ʂł�������̂ł��B�]���āu�����Ă���n�̎��Ԃ͒x���v�Ƃ������_�����ƂȂ�܂��B���A�����s�����Ă���n�ł̌��̑��x�t��X��@ �Ƃ������́A�����ł͐[���l���Ȃ��ʼn������B����͎��͂́u�A�C���V���^�C���̘_���ᔻ�v���l�͂́u�l��������v�̏��ł��o�ė��܂�����B�����āA���̎��A�Ӗ����͂����肵�ė��܂��B�@ |
|
| ��(�O)�@�e�_�̌��̂܂Ƃ� | |
|
���܂ł̘_�Ŗ��炩�ȗl�Ɂu�������v�u���[�����c���k�v�u���Ԃ̒x��v���̐��͑S�ĊԈ���Ă��܂��B�����̐��ɂ͉��̍������L��܂���B�����āA���̊ԈႢ�̌��̓��[�����c�ϊ��̎g�p�ɗL�����̂ł��B�A�C���V���^�C���́A���[�����c�ϊ���C�ӂ̍��W��C�ӂ̎����̕ϊ������Ǝv������Ŏg�p���܂����B���ꂪ���������̊ԈႢ�̌��ł����B���[�����c�ϊ��� �}�ɉ�������̑��s�����Ƒ��s���Ԃ̊W���������̂ł��B�����ĔC�ӂ̍��W��C�ӂ̎����Ȃǂ̕ϊ����ł͗L��܂���B
�ł́A�ǂ����āA���̗l�ȊԈႢ�����̂ł��傤���B����̓A�C���V���^�C�����u�����v�Ɓu���W�v�C�u���ԁv�Ɓu�����v�Ƃ��������Ă�������ł��B �����ŁA�u�����v�Ɓu���W�v�̈Ⴂ�ɂ��Đ������Ă����܂��傤�B �u���W�v�Ƃ́@�@����̓_�̈ʒu�ł���A�u�����v�Ƃ́@�@������W����ʂ̍��W�܂ł̊Ԃ̒����ł��B�����āA�u�����v�Ƃ́@�@���Ԏ���̓���̈ʒu�ł���A�u���ԁv�Ƃ́@�@���鎞������ʂ̎����܂ł̊Ԃ̒����ł��B�A�C���V���C���͂����ɋ�ʂ������������Ă��܂����B ���ׁ̈A�ォ��ǐ������搶�����C�Â����������ꂽ�̂ł��傤�B �ł͂Ȃ��������Ă��܂����̂��Ƃ����ƁA����͕����Ɨp�@�Ɍ������L��܂��B�����ŏ����A���������W������ �̕����ŕ\����܂��B������0����_�ɂ���A�����͍��W�̐��l�ő�p����܂��B�����獬�������Ă��܂��킯�ł��B ���ɁA�����Ǝ��Ԃ������@�E�E�E�@�̕����ŕ\�킳��܂��B������ 0 ���n�_�Ƃ���A���Ԃ͎����̐��l�ő�p����܂��B�]���č����͂���܂��B���̏�A�����Ǝn���̈������Ɂu���ԁv�Ƃ������t�́u�����v�Ɓu�o�ߎ��ԁv�̗����̈Ӗ������˔����Ă��܂��B����͓��{�ꂾ���łȂ��p��� time �ł��h�C�c��� Stunde �ł������悤�ł��B�{���A�l�́A���̎��X�ɉ����Ďg���ʂ��Ă���̂ł����A�ǂ����A�C���V���^�C���͘_�����������A�C�Â����������Ă��܂����l�ł��B ���̌��ʁA�{���A���̑��s���Ԃł��� �����̓��B�����ɒu���������(�����܂ł͗ǂ��̂ł���)�A���ꂪ��Ԃ̔C�ӂ̎����ɂ܂Ŋg����߂���Ă��܂����̂ł��B ���ɁA���̑��������� OP�� �����������ł��� ���A���̓��B�_(�o�_)�� ���W�Ɖ��߂���鏊�܂ł͗ǂ��̂ł����A���ꂪ�A�C�ӂ̓_�� ���W�Ɗg����߂���Ă��܂����ɖ�肪����킯�ł��B �{���́@�E�E�E�@�������̂ł��B ���ꂼ��̍��ڂ́A�F�A�ʂ̕��ł����אڂ��鍀�ڂɓ���̏���������� �� ���������܂��B������ƌ����ė��ꂽ���ڂ܂� �� �ɂȂ�킯�ł͂���܂���B �����̏��̋�ʁE���ĕʂ��ɋC�Â����O�i�_�@�ł��Ɓ@�E�E�E�@�Ƃ���Ă��܂��A�ԈႢ���Ă��܂��܂��B���������������āA���ՂɁA�����Ƃ��Ă��܂��͖̂��ł��傤�B�Ƃ����킯�ŁA���[�����c�ϊ��Ƌ��ȏ��̐ݒ�Ƃ͉��̊W������܂���B�ݒ�Ǝ��Ƃ����W�ł�����B ���̗l�Ȑݒ�Ƀ��[�����c�ϊ����g�����Ƃ����̂́A�o�X�̔R����v�Z���鎮�ł����ċT�̎������v�Z������A�̎��b���v�Z���鎮�ł����Đ��k�̕��l���v�Z����l�Ȃ��̂ł��B���̗l�Ȏ�������ΖŒ��ꒃ�ɂȂ�܂��B �������āA���̖Œ��ꒃ������Ă���̂����Θ_�Ƃ����킯�ł��B�]���āA���Θ_�͑S���̌��Ȃ̂ł��B �ƁA�����܂Ő\���܂��Ɛ��Ƃ̐搶���́A���Ԃ�u���O���w�E���Ă���̂͋��ȏ��̎��M�҂̃~�X�ł����āA�A�C���V���^�C���̃~�X�ł͂Ȃ��B�A�C���V���^�C���͂��̗l�ȓ������͂��Ă��Ȃ��B������A���Θ_���Ԉ���Ă�Ƃ͌����Ȃ��B�v�Ƌ���ł��傤�B �����ŁA���́A�A�C���V���^�C���̘_���ɂ��Ę_�]���邱�Ƃɂ��܂��B�@ �@ |
|
| ���O�@�A�C���V���^�C���̘_���ւ̔ᔻ | |
|
����܂ł̘_�́A������w�ŏK�������̋��ȏ��ɉ����Ă̕��ł����B�Ƃ��낪�A�C���V���^�C���̌���(�|��)�́A�����͂Ȃ��Ă��܂���ł����B�������S������Ă����̂ł��B�]��ɂ��������Ȃ��A�قƂ�ǂ��u�d�d�Ɖ��肵�悤�v�u�d�d�ƂȂ锤���v�Ƃ������t�̗���ŁA����Ɛ������邢�͌��߂��Ő��藧���Ă���l�Ɍ����܂����B�����]��ɂ����Ȃ��ׁA���Ǝ��Ƃ̑����肪�悭�������A�����ɋꂵ�ޖʂ����������̂ł����A���̕⒍�������Q�l�ɂ��Ȃ���ǂ�ł������ɁA���̘_���ɂ����̂��鎖�������ė��܂����B
����͑O�ɁA���ȏ��̊ԈႢ�ɋC�Â��Ă��Ȃ������画��Ȃ��������ł��B ���̘_����|�ꂽ�搶�� �u���w���ł��킩�鏉�����w���g���āA���ΐ����_�̍����Ƃ�������d�v�Ȍ������Ă���B���̐����́A�o���_�ƂȂ�O��ڎw�����_�Ɏ���܂ŁA���҂����ԍŒZ�R�[�X�����ǂ��āA���ɕ����ȁA�����������͂��ӂ��_�|�ŁA�ǎ҂��S�[���܂ň��������Ă����B���̘_���͕����w�̖͔͂Ƃ��āA������u���҂͕K����ǂ��ׂ��ł���B�v�Ƃق߂������Ă����܂��B ���������ɂ́A�����͌����܂���B���ɓm��Ș_���Ɍ����܂��B���́u�ŒZ�R�[�X�����ǂ��āA�����Ȑ����v�����Ă��鏊�ł��B���̎��A�v�����⎗�����Ƃ̍����œǎ҂����Ⴂ�̐��E�Ɉ������荞��ł��܂��B�܂����̘_���ł́A���[�����c�ϊ��̗U���̏��ŁA�����ȗ����ꂷ���Ă��āA�Ȃ��A���ꂪ�����Ȃ�̂�������Ȃ���������܂����B ���̓��������ƌ����Ă��܂�����܂łł����A���̐搶���g�u����ȏ�������v�ƒf���āA���ɕ⒍���������Ă����邭�炢�ł��B�Ƃ��낪�A���̉���ł���{���̎��̗���Ƃ͑S�����W�ɏ�����Ă���A���̐搶�Ǝ��̂����Ō㔼���o���Ă�����̂ł��B �����Ȃ�Ɓu�Ȃ�ŁA���ꂪ�A�����Ȃ�̂��H�v�Ƃ������̋^��͉����܂���B ���̐搶���A������������A���̓r�����Ȃ������o���Ȃ������̂ŁA��ނ��A�������̂����Ō��_���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƌ^���Ă��܂��܂��B �����Ƃ�����́A�Q�X�̊��J��Ƃ������ŁA�搶���g�͉������Ă���ꂽ�̂����A��X���X�̎҂ɉ�����l�ȃ��x���̎��ł͕\���Ȃ��̂ŁA��ނ��ʂ̕��@���Ƃ�ꂽ�̂����m��܂���B ���̗l�ȕs�\���Ș_���𑽂��̐搶��������Ă������āA������₷����(��)�_���I�Ő������̂���L�`���Ƃ����`�Ɏd�グ�����Ă������̂ł��傤�B �������A���̉��ǂ̑啔���́A�A�C���V���^�C���̐����Ă�����ɍs��ꂽ�ł��傤����A�A�C���V���^�C���̏��F�̉��ōs��ꂽ���́A�ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B ������w�ŏK�������̑��Θ_�́A���̗l�ɂ��ĉ��ǂ���̌n���Ă�ꂽ���̂������̂ł��傤�B�����猴���Ƃ͈Ⴄ�̂��Ǝv���܂��B�A�C���V���^�C���̘_���́A�͂����茾���ĉ�����ɂ����A�����Ř_�������̂܂Љ��̂̓����ɂ��āA���̉�����͈͂Ŗ��̂��鏊�����A�����������Ă���_�]���鎖�ɂ��܂��B�@ |
|
| ��(��)�@�_���̐����Ɩ�� | |
| ��(1)�@�������̒�`�@ | |
|
�A�C���V���^�C���́A�ŏ��Ɂs�������ɂ��Ă̒�`�t���߂܂����B����́g��ӏ��̎������������ł��邩�ǂ������ǂ�����Ĕ��肷�邩�h�Ƃ������̂ł��B��ʂɎ����͎��v�Ōv���܂��B�������������ꂽ�ꏊ�ł́A���̎��v���m�������Ă���Ƃ����ۏ͗L��܂���B�����ŃA�C���V���^�C���́A���̗l�ȕ��@�Ŏ��v�������Ă��邩�ǂ����肷�鎖�ɂ��܂����B
�܂� �`�_ �� �a�_ �ƂɈ�Â��v��u���A�`�_ ��� �a�_ �Ɍ����Č��˂��A�a�_ �Ŕ��˂����� �`�_�ɖ߂��܂��B �}�@�E�E�E�@ ���̎��� �`�_ �ł̔��ˎ��� A �� �a�_ �ł̔��ˎ��� B �� �`�_ �Ɍ����߂��ė������̎��� �Ƃ𑪒肵�Ă����܂��B�������Ă����āA�����̃f�[�^���A���̉����̑��s���� �Ɗ҂�̑��s���� �Ƃ��Z�o���܂��B ��������ƁA����́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B����͓������������������������ł�����A�{�� �� �͓����l�̔��ł��B �]���āA�`�C�a�̎��v�������Ă���@�E�E�E�@�ƂȂ�Ȃ���Ȃ�܂���B�����Ȃ�Ȃ������玞�v�������Ă��Ȃ��Ƃ������ł��B��������������A�C���V���^�C���́@�E�E�E�@���ȂāA��̎��v�������Ă��鎖�̍����Ƃ��܂����B�@�����܂ł́A��肠��܂���B�@ |
|
| ��(2)�@�����Ǝ��Ԃ̑��ΐ� | |
|
��(a)�@�����̑��ΐ�
���ɃA�C���V���^�C���́A�����Ă���_�̏�ł����l�̎v�l���������܂����B ��(�)�@�{�̌����ł� �u���� A B �̖_������A���̗��[�� �`�C�a �Ƃ���B�����Ė_�̗��[�ɁA���ꂼ���̎��v���Ƃ����B���̎��v�͐Î~�n�ŃL�`���ƍ��킹�Ă��镨�Ƃ���B�����@A�@�� �` ������������˂���A�����@B�@�� �_�a �Ŕ��˂���A���� �@�ɂ��̌��͂` �ɗ����߂����Ƃ���B����Ɍ����x�s�ς̌�����p����Ύ��̊W����������B (����͐Î~�n���猩���ꍇ�̊W���ł���)�@�E�E�E�@��̊W��������ƁA�_�ƈꏏ�ɑ����Ă���ϑ��҂��猩��Ƃ��`�C�a��̎��v�͍����Ă��Ȃ��B�@ �����ŁA������W�n���猩���Ƃ��A��̎������������ł������Ƃ��Ă��A�����Ă��鑼�̍��W�n���炻�������A�������ɋN�������ƌ��Ȃ��킯�ɂ͍s���Ȃ��B�v �Ƃ���Ă��܂��B���̕����́u�������̑��ΐ��v�̍ŏ��̘_���ł����A�K�v�����������Ă��ĉ�����ɂ����̂ŁA����Đ������܂��B ��(�)�@�_���̉�� ���� A B �̖_������A���̗��[���`�C�a�Ƃ��܂��B���̖_�͑��x �� ���������`����a�̕����֓����Ă��镨�Ƃ��܂��B���ɁA�_�̗��[�ɂ��ꂼ���̎��v�����t���܂��B���̎��v�͐Î~�n�ŃL�`���ƍ��킹�Ă��镨�Ƃ��܂� �`�[�ł̎��� A �̎��� �`�[���������˂���A �a�[�ł̎��� B �̎��� �a�[�Ŕ��˂���āA �`�[�ł̎��� �̎��Ɍ��� �`�[�ɖ߂��ė����Ƃ��܂��B ���̗l�q��Î~�n���猩��Ɛ}�̗l�ɂȂ�܂��B����́A�_�̓����ƌ��Ǝ����Ƃ̊W�����������ł��B ���̐}���A�Î~�n���猩���ꍇ�̌��̑��s���������߂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ł����@�E�E�E�@���̉����̑��s���ԁ@�E�E�E�@���̊҂�̑��s���ԁ@�E�E�E�@�ł�����A������l���ɓ���܂��ƁA�́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B ���̎����A���H�E���H�̌��̑��s���Ԃ����߂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�킯�ł��B���ꂪ�A�C���V���^�C���̎��ł��B �Ƃ��낪�A�����Ŗ�肪�����܂��B���̌��ʂ́@�E�E�E�@�Ƃ͂Ȃ��Ă��܂���B�����ŁA�A�C���V���^�C���͎����̍�����s�������̒�`�t�ɏƂ炵���킹�āu�Î~�n�œ������������Ă�����ӏ��̎��v�ł��A�����Ă���n�ɂ���Γ��������������Ȃ��v �����s�Î~�n�̓�ӏ��œ����ɋN�������o�����ł��A������Ă���n���猩��Ɠ����Ƃ͌����Ȃ��t�ƒf�����킯�ł��B�������A����͊Ԉ���Ă��܂��B ��(�)�@�u�����̑��ΐ��v�̌��̏ؖ� �A�C���V���^�C���͂Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�����Ă��܂��B�@�O���ɉ����ās�Î~�n�t�Ł@�E�E�E�@�����藧�����̂́A�����������҂�����������𑖂�������ł��B�������������x�ő���Ώ��v���Ԃ������ɂȂ�͓̂��R�ł��傤�B�Ƃ��낪�A����́s�����Ă���n�t�ł́A���̉����Ɗ҂�̑��s�����͓����ł͂���܂���B�������Ⴆ�Α��s���Ԃ�����Ă��Ă��d�����Ȃ��ł��傤�B�@�E�E�E�@�����藧���Ȃ��̂͂��̂����ł��B�@�@���v�̂����ł͂���܂���B�}�ł킩��l�ɁA���͉��H�͖_�̒���������������A���H�͖_�̒��������Z�������Ă��܂��B����ł��Č��̑��x���������҂�������Ƃ�����A�����Ɗ҂�̑��s���Ԃ�����ė��Ă��d�����Ȃ��ł��傤�B �����́A�a�_��������̂Ō����ǂ����̂Ɏ��Ԃ��|����A�҂�͂`�_���ߊ���ė����̂Ō��ʂƂ��ĒZ�����ԂŖ߂��Ă��܂����B�������ꂾ���̎��ł��B����̓A�C���V���^�C���̂������Ԉ���Ă���̂ł��B�A�C���V���^�C���́u�Î~�n�ł������Ă���n�ł����̑��x�͓����v�Ƃ��܂����B���̌��ʁu�����Ă���_��Ŕ����ꂽ���v�ł��u�����Ɗ҂�̑��x���v�Ƃ�����Ȃ��Ȃ����̂ł��B �Ƃ��낪�A��������ƁA�_�̏�ł͌��͉������҂���������Ԃʼn������Ă���̂ɁA������O���猩��ƁA���͉����͖_�̏�����������Ԃ��|���đ���A�҂�͖_�̏�����Z�����ԂŖ߂鎖�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�E�E�E�@ ����͔��ɕs���R�Ȏ��ł��B����ł͕s�s���ł��̂ŁA������ς��āA�_�̊O�̎��� ���Ƃ� �_�̏�̎��� ���ω�����l�ɂ��Č��܂��傤�B��������ƍ��x�́A�_�̏�̎��Ԃ́A���������̎��͊O�����x��A�߂�̎��͊O�����i�ގ��ɂȂ��Ă��܂��܂��B ������s�s���ł����A����͎������͂́u��Ԃ̒��̎��Ԃ̖����v�̏��Ŏ������u����O���ɔ�����Γ����Ă���n�̎��Ԃ͒x��A����ɔ�����ΐi�ށv�Ƃ����̂Ǝ������ۂł��傤�B ���������͂̏��Ŏ������������́A�P�Ȃ鎄�̃f�b�`�グ�ł͂Ȃ��A���̍����A�C���V���^�C���ɗL�������������ė��܂��B����́A�Ƃ������A�������������Ō��̉����̑��s���ԂƊ҂�̑��s���ԂƂ��قȂ��Ă��܂��@�E�E�E�@�Ƃ́A�Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł��B�����āA���v�̂����ł͂���܂���B����́A�P�ɁA�A�C���V���^�C���̂������Ԉ���Ă��邾���̘b�ł��B�����ŁA�A�C���V���^�C���̂����̊ԈႢ�𗝉����Ē����ׂɁA���̗l�ȗ�Ő������čs�����ɂ��܂��傤�B �`�n�_�Ƀ��C�g��ݒu���A������蓌�Ɍ��˂����a�n�_�Ŕ��˂����Ė߂��ė�������Ƃ��܂��B���̊ԁA�ϑ���(�{���A�Î~�n�̊ϑ��҂ł�����)�����̕��ֈ��̑��x�ňړ����Ă�����̂Ƃ��܂��B����͐Î~�n�Ɠ����Ă���n�̗�������ւ��������̘b�ł��B �����`�n�_�������� A �ɁA���܂��܊ϑ��҂������ɂ��āA���̌��i��ڌ������Ƃ��܂��B�����Č����a�n�_�ɓ͂������� B �ɂ͊ϑ��҂� tB�@�n�_�̏��Ɉړ����Ă��܂��B���̎��ɁA�����`�n�_�ɖ߂��ė������ϑ��҂͍X�Ɉړ����� �n�_�̏��ɂ��܂� �@�E�E�E�@ ���āA���̏ꍇ�A�����Ă���ϑ��҂́A���� tB �n�_�� �n�_��蔭���ꂽ�ƌ����ł��傤���B��Ɍ���Ȃ��ł��傤�B���̐l�́A�����܂ł��A���͂`�n�_��蔭���ꂽ�ƌ������ł��B������ɁA�ϑ��҂ɁA���� tB �@�n�_�� �n�_���甭���ꂽ�ƌ��킹�Ă���̂����Θ_�Ȃ̂ł��B ���Θ_�ł́A���̔������_�͊ϑ��҂Ƌ��ɓ����Ă��邩�̂悤�ł��B���ꂪ���̖ڈ���Ȃ��F����Ԃł����Ȃ�A�����������o�����邩���m��܂���B���A�������A�ڈ�̑����n��ł͂����͍s���܂���B ���ɁA�ϑ��҂��Î~���Ă��āA�_�̕��������Ă���ōl���Č��܂��傤�B�`�n�_�Ɋϑ��҂������Ă��āA�����Ă���_�̂`�[���`�n�_�ɍ����|���������A���܂��܁A�_�̂`�[������������ꂽ�Ȃ�A�ϑ��҂͂`�n�_�Ō���������ꂽ�Ǝv�����ނł��傤�B �������A����͊��Ⴂ�Ƃ������̂ł��B �{���́A���͖_�̂`�[���甭����ꂽ�̂ł����āA�`�n�_���甭����ꂽ�킯�ł͂���܂���B�_�̕����Î~���Ă��āA��n�̕��������Ă���ƍl�����Ȃ�A�_�̂`�[�����������A���܂��܂`�n�_���A������ʂ�|�����������Ƃ������ɂȂ�܂��B ���̏u�Ԃɂ́A�`�n�_�͕ʂ̏��Ɉړ����Ă���킯�ł��B�]���āu�`�n�_��������āv�ƌ����킯�ɂ͍s���܂���B ���āA�����Łs���̉��H�ƕ��H�Ƃő��s�����Ƒ��s���ԂƂ��قȂ�t�Ƃ��������g�_���������A�ϑ��҂������Ă���h�Ƃ����ɒu�������čl���Ă݂܂��傤�B �_���Î~���Ă���ƍl����̂Ȃ���̈ړ��͒P�ɂ`�a�Ԃ̉��������ł��B���͓����Ă���ϑ��҂̕��ɂ���܂��B�L���F����Ԃɖ_�Ɗϑ��҂���������A�ϑ��҂͎����������Ă���Ƃ͒m�炸�A�_�������Ă���Ɗ��Ⴂ���Ă�����̂Ƃ��܂��B �_�̂`�[�������������ꂽ���A�ϑ��҂́A���܂��܁A�`�n�_�ɂ��Ă����ڌ����܂��B(���G���̎��A�_�̂`�[�͂`�n�_�ɍ݂����Ƃ���)�B �����Č����_�̂a�[�ɓ͂������A�ϑ��҂́@�E�E�E�@�����ړ����� tB �n�_�̏��ɂ���̂ł����A���̐l�́A�����������Ă���Ƃ͂�����m��܂���A���� tB �n�_���甭�����āA�a�n�_�Ŗ_�̂a�[�ɓ͂����ƍ��o���Ă��܂��B �����Ō��̐i�����́@�E�E�E�@�ƌv�Z���܂��B ���ɁA�����`�[�ɖ߂��ė������A�ϑ��҂́A�X�ɁA�@�������Ɉړ����Ă���̂ł����A���̐l�́A�����������Ă���Ƃ͑S���m��܂���A�_�̕����A�X�Ɂ@�E�E�E�@�����E�Ɉړ������Ɗ��Ⴂ�����܂��B�����ŁA�������˂��ꂽ���A�_�̂a�[�͂a���n�_�̏��ɍ݂��āA���͂��̈ʒu��蔽�˂���Ă`�[�ɖ߂��ė����Ǝv���Ⴂ������킯�ł��B��������ƁA���̕��H�̑��s�����́@�E�E�E�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �����Ŋϑ��҂́A���H�͌��̑��s�������L�сA���H�͒Z�k����Ă��܂����ƍl�����ނ킯�ł��B�������Ȃ���A����́A�ϑ��҂��A�����������Ă���Ƃ͒m�炸�A�_�������Ă���ƍ��o���Ă��邩�炱���Ȃ邾���ł��B ���ۂɂ́A���͖_�̗��[�����̎��Ԃʼn��������ɉ߂��܂���B���� tB �n�_�Ŕ�����ꂽ�킯�ł��Ȃ���A�a���n�_�Ŕ��˂��ꂽ�킯�ł��Ȃ��̂ł��B����͊ϑ��҂̊��Ⴂ���痈�镨�ł��B ���������ł͊ϑ��҂́A�����̓����������������A���̑��s�����ɉ����Ă��܂��܂��B���̌��ʁA���̑��s�������L�т���k�肵�Č�����킯�ł��B �����̏��̊��Ⴂ��������s �ϑ��҂��Î~���Ă��āA�_�̕��������Ă��� �t�Ƃ����ł��s �_���Î~���Ă��āA�ϑ��҂������Ă��� �t�Ƃ����ɒu�������Ă݂鎖�ɂ��A�����Ȃ��������鎖���o���܂��B �Ⴆ�A�}�̗l�Ɂs ���x �ʼnE�����ɓ����Ă���_�̂`�[��蔭���ꂽ�����a�[�ɓ͂��� �t�ꍇ�ł��A�`�n�_�ɐÎ~���Ă���ϑ��҂̌����A���́g�݂����̑��s�����h�́s �_���������A�ϑ��҂����x �Ŕ��Ε����ɓ����Ă��� �t�ƒu�������Ă݂鎖�ɂ��u�_�̏���������������� �v�Ɓu�ϑ��҂����������� �v�Ƃ̍��v�ŕ\�킷�����o���܂��B��������ŕ\�킹�@�E�E�E�@�ł��B���A����͂܂��@�E�E�E�@�ł�����܂�����A���̎��́@�E�E�E�@ (�_�̊O���猩�����̑��x)��(����)�{(�_�̑��x) �����\�킵�Ă��鎖�ɂȂ�܂��B ����́A�����̍l�����ɂ�鑬�x�̍����ƈ�v���܂��B���ꂪ������������Ȃ̂ł��B �A�C���V���^�C���́s�Î~�n���猩�����݂̂����̈ړ������t���s�_��ł̌��̈ړ������t�Ɂs�_�̈ړ������t�����������Ƃ��܂����B���ׁ̈A���́s�����̑��s�����t���L�сs�҂�̑��s�����t���k��ł��܂����킯�ł����A����Ŕނ́s�Î~�n��茩�����̌��݂̂����̑��x�t���s�����t���s�҂�t�������ɂ��Ă��܂��B����͕s���R�Ȏ��ł��B����Ȏ���������A�s�Î~�n��茩�����̌��̉����̑��s���ԁt�́s�_��ł̎��ԁt���������Ȃ�A�s�҂�̎��ԁt�́s�_��ł̎��ԁt�����Z���Ȃ��āA�����𗈂��܂��B����͖����ꒃ�Ȃ����ł��B �Î~�n��茩���u���݂̂����̈ړ������v���u�_��ł̌��̈ړ������v�{�u�_�̈ړ������v�Ƃ����̂Ȃ�A�u���݂̂����̑��x�v���u�_�̏�ł̌����v�{�u�_�̈ړ����x�v�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B �ł�����B�������Ȃ���A�����I�ɒ��낪����Ȃ��ł��傤�B�������Ȃ�����s�Î~�n��茩�����̌��̉����̑��s���ԁt���s�_��ł̎��ԁt���������Ȃ�A�Ђ邪�����ās�҂�̑��s���ԁt���s�_��ł̎��ԁt�����Z���Ȃ��āA�s���R�ȏ�ԂɂȂ��Ă��܂����̂ł��B �����Ɗ҂�̎��Ԃ���v���Ȃ��͎̂��v�̂����ł͂���܂���B�P�ɁA�A�C���V���^�C���̂������Ԉ���Ă��邾���̘b�ł��B�A�C���V���^�C���́u�������̒�`�v�͐Î~�n�ł͐��藧���܂����A�����Ă���n�ł͐��藧���܂���B���������킯�ŁA������蓱���ꂽ���́@�s�Î~�n�̓�ӏ��œ����ɉ������N�������Ƃ��Ă��A������Ă���n���猩��Ɠ������Ƃ͌����Ȃ��t�Ƃ����u�����̑��ΐ��v�̗������ԈႢ�ƂȂ�܂��B�@ |
|
|
��(b)�@���[�����c�ϊ��̗U��
���ɃA�C���V���^�C���� �g��������������v�l�����h �� �g�������W����h �Ɉڂ��čs���A���[�����c�ϊ���U�����鎖�ɂ��܂����B ���̎����́A�O���ł��w�E���܂����ʂ�Ԉ���Ă��܂��̂Łu��������̗��_�͑S�Č���Ă���v�Ɛ��Ď̂Ă鎖���o����̂ł����A���ɂ���肪�L��܂��̂ŁA���̂܂܍s�����ɂ��܂��B �Ƃ͌����܂��Ă��A�����̕����Ɋւ��܂��Ă͔��ɍ��x�Ȑ��w (����������) ���g���Ă��܂��āA��ʌ����ɉ������ɂ́A������ƍ���Ȃ��̂�����܂��B �����ŁA���̗U���ߒ��S�����Љ��͎̂~�߂ɂ��āA���������ςɗ����Ȃ���A���̂��鏊������_�]���Ă������ɂ��܂��B�ł�����A��������o�Ă��Ă��A�����ɍl���������ĉ������B ��(�)�@���W�ƍ��W�n�̒�` �܂��ŏ��ɃA�C���V���^�C���́A���W�n�ɂ��Ē�`�����܂����B�Î~���Ă���n��Î~�n�Ƃ��A����� �j �n�ŕ\�킵�A�����Ă�����W�n���^���n�Ƃ��āA����� k �n�ŕ\�킵�܂����B�����Ƃ��A����ł́A�ǂ������Ƃ�����������Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�����ł́A���� �r�n�E �n �ɓ��ꂷ�鎖�ɂ��܂��B ���ɃA�C���V���^�C���́A�e���W�n�̍��W����}�̗l�ɒ�߂܂����B �@�E�E�E�@ �����Ă���n�� ���� ��(�N�T�C)���ɁA ���� ��(�C�[�^)���ɁA ���� ��(�c�F�[�^)���ɂ��Ă��܂��B �����āA���̍��W�n�ɉ�����A����_�̈ʒu�Ǝ��������W�`���Ł@�Î~�n�ɂ��Ă� �Ƃ��@�^���n�ɂ��Ă� ( , , , ) �Ƃ��܂����B���̏�ŁA�ނ́A�s������g�̐��l�����ѕt����W��������̂��A�����̉ۑ肾�t�ƌ����Ă��܂��B�m���ɁA���̒ʂ�ɍs���A�o���オ�����W��(���[�����c�ϊ�)�́A���W�Ǝ����̊W���ɂȂ��Ă��锤�ł��B�@���ۂɂ� �����Ǝ��Ԃ̊W���ɂȂ��Ă���̂ł����ǁB �����犨�Ⴂ�������킯�ł��B���̌�A�ނ́s �@�� �Ə������ɂ���A �n �ɐÎ~���Ă���C�ӂ̓_ ( , , ) �́@�@�@�@�@�Ƃ���3�̐��l�̑g�ɂ���Ĉʒu���K�肳���B�t�Ƃ��܂����B �������������̂��ƌ����ƁA�v����ɁA �n �̍��W���r�n �̐��l�ł����ĕ\�킵�����Ƃ������̂悤�ł��B�����Ă���̂́A �����������ł����� �������E �������̍��W�ɕω��͂���܂���B �]���āA �ƒu�������Ă������x���Ȃ��Ȃ�܂��B���� �����������ł��B���̕����͓����Ă��܂��̂ŊW�����K�v�ƂȂ�܂��B����� �}���^�����܂��B���̐}���A�@�E�E�E�@�����藧���܂��̂ŁA������g�����Ƃ����킯�ł��B������ �n�̃� ���W�� �ɑ������镔�������� �ł����đ�p����A�s �n�̔C�ӂ̓_�̍��W ( , , ) �� �Ƃ���3�̐��l�ɒu����������t�ƌ����Ă�킯�ł��B ������ �� �ł�����A����͎�����g �n �̐��l�� �r�n �̐��l�ł����ĕ\�킵���h���ɂȂ�܂��B �������Ă����ăA�C���V���^�C���́A�s�������W����Ō�������������v�l�����t�Ɉڂ�܂����B ��(�)�@���̉������� (���[�����c�ϊ��̗U��) �n �̎����� �̎��ɁA �n �̌��_ O������ �������Ɍ����Ĕ�����A�Œ�_�Ŏ��� �ɔ��˂���āA���� �ɖ߂����Ƃ���B�@��������� �n �ł́@�E�E�E�@�����藧�B �����Î~�n�Ō��A�Ɨ��ϐ� ��p���āA �� () �̌`�ŏ����Ώ㎮�́@�E�E�E�@�ƂȂ邪�A �����ʂƂ�����̊W���́@�E�E�E�@�Ƃ��������������ŕ\�킹��B�����āA����́@�E�E�E�@�Ƃ�������������B �Ƃ���Ă��܂��B���̕ӂ͓���̂ʼn���͂��܂���B�����ăA�C���V���^�C���́A�@���܂ŏq�ׂ��c�_�Ɠ������� ���� �y�� ���� �����ɓK�p����� �Ɋւ��ā@�E�E�E�@��������B���̎����ɓ����蒍�ӂ��ׂ��_�́A�r�n ���璭�߂��� �� ������ �� �������ւ̌��̓`�d���x�� �ł���Ƃ������ł���B�@�E�E�E�@�ƌ����Ă��܂��B ������͖������ĉ��������@(���̓`�d���x�� �ł���)�@�ɒ��ڂ��ĉ������B����͔ނ̌����u�����x�s�ς̌����v�ɔ����Ȃ��̂ł��傤���B���ꂪ�ʂ�̂Ȃ�A�����Ă��镨�̂�蔭���ꂽ���̑��x�́A�����Î~�n��茩���ꍇ �łȂ��Ă��ǂ����ɂȂ�܂��B �ƌ����Ă��u���̎����ǂ�������Ȃ��v�Ǝv������������ł��傤����������܂��B �O�̘b�́A��(�N�T�C)��(�܂� ��)�����Ɍ��𑖂点�Ă̘b�ł������A���x�� ��(�C�[�^)��(�܂� ��)�y�� ��(�c�F�[�^)�� �����Ɍ��𑖂点�Ă̘b�ł��B����� �n �� ���� �܂��� ���� �����Ɍ��𑖂点���ꍇ�A����� �r�n ���猩��Ƃǂ������邩�Ƃ����b�ł��B���������ƁA����Â炢�̂� ���� ���������Řb��i�߂Ă݂܂��傤�B ���� �Ɍ���������A���� �Ƀ����̍��W �̏��Ŕ��˂���āA���� �Ɍ������_O���ɖ߂��ė����Ƃ��܂��B ����� �n �Ō���ΐ}�̗l�ɂȂ�܂����A�r�n ���猩��ΐ}�̗l�ɂȂ�܂��B�@�E�E�E�@ �t�n �͓����Ă��܂��̂ŁA�r�n ��茩�����̊e�����ł̌��̈ʒu�͐} 3�]3�]8�̗l�ɂȂ�A���̋O�Ղ͎O�p�`�ɂȂ�܂��B���̏�ԂŁA�r�n ��茩�����̌����� �Ƃ����Ȃ�A �n �ɉ���������͎O�p���ɂ��@�E�E�E�@�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B �������A����������������ʂȂ�A �n �ł̌����� �̂܂܂ɂ��Ă����āA�r�n ��茩�����̌����� �ɂ��������A��قlj�����₷���̂ł́A�Ǝv���̂ł����A�A�C���V���^�C���́A�����͂��܂���B�ނ́A���� ���Ƃ��A������鑬�x�͖����Ƃ��Ă��܂��̂ŁA�r�n ��茩�����̌��������傫���o���Ȃ��̂ł��B�������A����Ȃ�A�r�n ��茩�����̃��������̌����� �Ƃ���̂��ςł��傤�B����ł͌����� ��菬�����Ȃ��Ă��܂��܂��B����͌����x�s�ς̌����ɔ����Ȃ��̂ł��傤���B ���Ƃ��E�T���L���C�����܂��B�����������́A�ǂ�������(����)�I�Ƃ������A���������ɍs���Ă���l�ł��B ����́A�Ƃ������A����͎����A�O�͂̑�O�߁u���Ԃ̒x��v�̏��Łs �n���Ō��_ O����� ���ɐ����Ɍ����A������r�n���ϑ������ꍇ�̌����� �Ƃ���A �n���ł̌����͎O�p���ɂ��A�X��@ �@�ɂȂ�t�Ƃ����̂Ɠ������ł��傤�B ���́u�����Ă���n�ł̌����v�Ɓu�����Î~�n���猩���ꍇ�̌����v�Ƃ͈Ⴄ�Ƃ����O��ł���Ă����̂ł����A���������A�C���V���^�C���ł������Ă����̂Ȃ�A���������؍����͂Ȃ��Ǝv���܂��B �܂��A�C���V���^�C���́A�ʂ̏��ł́s����A�r(�j)�n���猩��A(k)�n�̌��_�ɑ�����̐�[�̑��Α��x�� �| �ł���t�Ƃ����Ă��܂��B �ނ́A����ł͌����͐�Εs�ςƂ��Ȃ���A�����ł͂��̗l�ɍD������ɕω������Ă���̂ł��B ���Ȃ�̌�s����`�ł��傤�B ���̎��ɃA�C���V���^�C���́s�ȏ�O�̕���������@�E�E�E�@���������t�Ƃ��Ă��܂��B�����A���������������������Ȃ�Ƃ������ł��傤�@�E�E�E�@���̌�s ��0�̏u�ԂɁA �̑�����������Ɍ����Č��� �n�̌��_���甭�˂��ꂽ�Ƃ��悤�B ���̌��ɑ��Ắ@�E�E�E�@����������t�Ƃ��Ă��܂��B�������A��������ł��B�@�E�E�E�@�͊m���A �n �̔C�ӂ̓_�̃� ���W���������ł��B( , , , )�ł�������B����ɑ��� �@�͌��̑��s�����ł��B����Ȏ�������� �͌��̑��s�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���W�ƌ��Ȃ��Ă��A���� ���Ԋ|���ē��B�������̃� ����̈ʒu�ɂ����Ȃ�܂���B�������� �́A�C�ӂ̍��W�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��B ���� �ł����A��������̑��s���Ԃł��B�����Ƃ��s ��0�̏u�ԂɌ������˂���t�Ƃ���܂����̂ŁA��������̓��B�����ƌ��Ȃ����͏o���܂��B���������A�C�ӂ̎����Ƃ܂ł͌��Ȃ��܂���B �͂����茾���鎖�� �͌��̑��s�����Ƒ��s���Ԃ̊W�����Ƃ������ł��B��������̓��B�ʒu�Ɠ��B�����̊W���ƌ��Ȃ����͏o���܂����A���̑��� �� �́A�C�ӂ̍��W��C�ӂ̎����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B ����Ȍ�� �� �́s�������������̋����Ǝ��ԁt�܂��́s���B�ʒu�Ɠ��B�����t�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��B ���ɃA�C���V���^�C���́A�@�Ɏ��������ā@�E�E�E�@�Ƃ��܂����B�����ĕ��G�Ȍv�Z��������Ń��[�����c�ϊ����o���Ă��܂��B�����ł̃��[�����c�ϊ��̗U���́A������ƌ��ɂ́A�����w�Z�ŏK���������ƑS������Ă���l�Ɍ������̂ł����A�{���I�ɂ͓������������̂ł��B�s���̑����������Ǝ��ԁt�Ƃ���W�����o���Ă��܂�����B �� ���̎��̗U���ߒ��ł́A�ꌩ�A���Ⴂ�������l�Ȃ��������Ă���܂��B�Ⴆ�A���̐߂̍ŏ��̌��̉����̏��ɂƌ����̂�����܂����B�����ł� �� �� �������ł��B�]���Ă��̎��͒N�����Ă������̎��ł��B�Ƃ��낪���̎��́A�{���͎��Ԃ̎��ƌ����ׂ����Ȃ̂ł��B�Ȃ��Ȃ��ŁA�����������ɂ��Ă��邩��ł��B�@���̎��͎��Ɂ@�E�E�E�@�Ƃ�₱�����W�J����Ă��܂��B �������ŁA�����Ȃ�̂��ɂ��ẮA���͐����o���܂���B�����������w�ł͗ǂ��g�����@���Ƃ����������͌����܂��B ���̎��̍ו��͎��̗l�ɂȂ��Ă��܂��B�@�E�E�E�@ ��̓I�ɂ́@�E�E�E�@�ł��B�@������ ( 0,0,0,t )�@�����܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�]���Ă����� �͒N�����Ă������ł��B�Ƃ��낪���� �̏��ł́@�E�E�E�@�ƂȂ��Ă��āA�����̏��� ��@ �@�������Ă��܂��B���́@�@ �́A�O�߂́u�����̑��ΐ��v�̏��ŏo�ė����l�Ɂs���̉����̑��s���ԁt�ł��B������ �́s���̊҂�̑��s���ԁt�ł��B�������@���� �{ ���� �� �����@�ɂȂ�܂����ǁB�ł́A���͂ǂ��ł��傤�B ���̎��� �ł́@�E�E�E�@�ƂȂ��Ă��āA ���W�̏��ɋ����� �����X�Ɠ����Ă��܂��B �́s���̑��s�����t�ł��B�����ł́s���W�t�̈ʒu�Ɂs���̑��s�����t�����X�Ɠ����Ă�����A�s�����t�̈ʒu�Ɂs���̑��s���ԁt�������Ă����肵�Ă���̂ł��B ���̎��ɃA�C���V���^�C���́A �����ʂƂ���A���̊W���́@�E�E�E�@�Ƃ��������������ɂȂ� �Ƃ��܂����B ��������́@�����炱���Ȃ�̂������ł��܂���B���A���̗l�ɏے��I�ɏ����������̍��W�`���̎����A���̂܂ܔ����������ɂ��ėǂ��̂��ǂ������A�ǂ�������܂���B�����A�������ʂƂ������t���̒����������Ă��鎖�̏؋����ƌ������͏o���܂��B���Ԃɂ��닗���ɂ���A�����������Ă��邩������o����̂ł��B�����������Ȃ��u�����v��u���W�v�ł͔����o���܂���B ���������Ɓu���ۂ̕����ł́A��������W��������Ă���ł͂Ȃ����v�ƌ���ꂻ���ł����A����͊��Ⴂ�Ƃ������ł��B���́u�����v��u���W�v�̋ߖT�ɂ�0�ƌ��Ȃ��Ă��ǂ����̔����ȕ����L��Ƃ��Ĕ������Ă���̂ł��B�]���Ė{���́u�����v��u���W�v�Ŕ������Ă���̂ł͂Ȃ��A�u���ԁv��u�����v�Ŕ������Ă���̂ł��B �����������̑O�܂ł͎�������W�̊W���ƌ��Ȃ��Ă��\���܂��A��������������ł́A���̑��s���ԂƑ��s�����̊W���ɂȂ��Ă��܂��܂��B �]���āA����������ďo�ė������@�E�E�E�@�́A���R�A���̑��s�����Ƒ��s���Ԃ̊W���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̏�A �����̑��s�����Ǝ��Ԃ̊W���ł�����A����� (3-3-6)�� �ɑ�����ďo�������@�E�E�E�@���܂��A���R�̎��Ȃ���A���̑��s�����Ǝ��Ԃ̊W���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̌�A��₱�����v�Z�����ā@�E�E�E�@���o���A�i�X�ƃ��[�����c�ϊ��ɋ߂Â��čs���A�ŏI�I�Ɂ@�E�E�E�@�Ƃ����`(���[�����c�ϊ�)�Ɏd�グ�čs���܂����A�@�����̉ߒ������čs���܂��ƁA����ȏ���E�T���L�����͖������Ă��A���[�����c�ϊ������̑��s�����Ƒ��s���Ԃ̊W���ł��鎖�͖����ƂȂ�܂��B �]���āA���[�����c�ϊ��͌��̑��s�����Ƒ��s���Ԃ̊W���Ȃ̂ł��B����́A�C�ӂ̍��W��C�ӂ̎��������߂鎮���ł͂���܂���B�@���̊�{�ɗ����Ԃ�A�����w�Z�ŏK�������[�����c�ϊ��̋��ߕ�����{�I�ɓ������������������Ă��܂��B �A�C���V���^�C���́A�����A�g���A�����@�o���o���Ɍ��𑖂点�܂������A���ȏ��͍ŏ�����߂Ɍ��𑖂点�ā@�E�E�E�@�Ƃ��܂����B�����ŁA�O�����͓����Ɍv�Z�o���܂��B�����ăA�C���V���^�C���́A�����ł͏Љ�܂���ł������A���ʔg�Ƃ��ā@�E�E�E�@�Ƃ������������Ă��܂��B�����A���������ɗp����A�ꋓ�Ƀ��[�����c�ϊ������܂��B �����w�Z�ŏK���������́A�ꌩ�A�A�C���V���^�C���̂����ƈ���Ă���l�Ɍ������̂ł����A�{���I�ɂ͓������������̂ł��B�����A�A�C���V���^�C���̎����A�X�}�[�g�ŁA�����I�ŁA�ȒP�Ȃ����ɐi�����Ă��������ł��B�A�C���V���^�C���̂����́A�m��ȏ��������ĉ�����ɂ����̂ŁA�����̐搶��������Ă������ĉ��ǂ��A���̂悤�Ȍ`�Ɏd�グ�����Ă������̂ł��傤�B�@ |
|
|
��(c)�@�����Ă��镨�̂͒������k��
���ɃA�C���V���^�C���́A�g�����Ă��镨�̂̒������k�ށh�Ƃ����������̗l�ɂ��ē����o���܂����B ��(�)�@�����ł� �u���a�q�̍��̂̋����l���悤�B���̋��́g�^�����Ă���n�h�ɑ��Ă͐Î~���Ă���A���̒��S�́g�^�����Ă���n�h�̍��W���_�ɌŒ肳��Ă���B����͐Î~�n�ɑ��ẮA���x �œ����Ă���B���̕\�ʂ�\���������́@�E�E�E�@�Î~�n�̎����@�@�� 0 �̏u�ԂɁA���̕�������Î~�n���猩��@�E�E�E�@���̎�������Ε�����l�ɁA�Î~��Ԃł͋��̌`�����Ă��鍄�̂ł��A�����Ă����Ԃł́@�|(�Î~�n���璭�߂��)�|�@3���̒������@�E�E�E�@�Ƃ�����]�ȉ~�̂̌`�ɂȂ�B�]���� �������̒����� 1�F �@�̊����ŏk��Ō�����B�v�@�E�E�E�@�ƂȂ��Ă��܂��B ������A���������Ă���̂��A�����ς������Ȃ��Ǝv���܂��̂ŕ⑫���Đ������܂��B ��(�)�@���� ����́A���̂̋��������Ă��鎞�A�����Î~�n���猩��ǂ������邩�ƌ����b�ł��@�E�E�E�@���a�q�̍��̂̋��̕\�ʂ�\�킷���́@�E�E�E�@�ł����A���ꂪ�@�E�E�E�@�ƃM���V�������ɂȂ��Ă��闝�R�́A�A�C���V���^�C�����^���n�̍��W���M���V�������ŕ\�킵������ł��B����͓������̕\�ʂ̎��ł��A�^���n�ɂ��鋅�̕\�ʂ̎����Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ł��B �������ȏ����̑��Θ_�̎��ŏ��������@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B���̎��� �Ƀ��[�����c�ϊ��@�E�E�E�@��������A���́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂����A����� t ��0��������@�E�E�E�@�ƂȂ�A�{���̎� ���o�ė���Ƃ����킯�ł��B ���́A���̎���� �������A �������A �������́A���̒��S����\�ʂ܂ł̒��������߂Č��܂��傤�B �܂��A �������ł����A���ׂ̈ɂ� �� (3-4-2) �� ��0, ��0�������܂��B�o ���R�G���_ O �𒆐S�Ƃ��鋅�� x�@�������鏊�̍��W�� (x, 0�C0) ������ �p �@�E�E�E�@��������ƁA���́@�E�E�E�@�ɂȂ�܂��̂ŁA�������@�E�E�E�@�������܂��B���l�ɂ��� �������A �������͋��ɔ��a �q �������܂��B���̌��ʁA�O���̒����́@�E�E�E�@�ƂȂ�u�����Ă��鋅�͐Î~�n���猩��� �������̒����� 1�F �̊���ŏk��Ō����A��]�ȉ~�̂̌`�ɂȂ�B�v�ƌ����Ă�킯�ł��B ����́u�����Ă��镨�̂́A���̐i�s�����̒������k��Ō�����v�Ƃ������̌��̘_���ł��B��������̋C�����ɓǂނƁA��������M���������܂��B�������A������Ԉ���Ă��܂��B ��(�)�@�������k�ސ��̌��̏ؖ� �܂����̌��́A�����Ă��鋅�̕\�ʂ̎����@�E�E�E�@�Ɖ^���n�̍��W�ŕ\������A����Ƀ��[�����c�ϊ������������ł��B���[�����c�ϊ��́@�@�͍��̂̋��̕\�ʂ̍��W�Ȃǂł͂���܂���B����́A���̋��ʔg�̓��B�_�̍��W�ł��B�������́A���̑��s������ �����������A �����������A �����������Ȃ̂ł��B���[�����c�ϊ��́A���̓��B�����ⓞ�B�_�̍��W�̊W���ł͂����Ă��A�C�ӂ̎�����C�ӂ̍��W�̊W�����ł͂���܂���B�]���āA���̗l�ȉ��p�͏o���܂���B�ԈႢ�ł��B ���ɁA�����ł� ���@�E�E�E�@�� ��0�������ā@�E�E�E�@�Ƃ��Ă��܂����A�Ȃ� ��0�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��傤���B�{���ɂ� �Î~�n�̎��� ��0 �̏u�ԂɁA���̕�������Î~�n���猩��� �Ƃ��邾���ŁA���̗��R��K�R����������Ă��܂���B�ł͕ʂ̎�����������ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B�@������A�������O�̃��[�����c�ϊ��ōl���Ă݂܂��傤�B ���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�ł����B����ɁA �@�����Ă݂܂��傤�B��������� ��0�ɂȂ�܂��B���ɁA �@��������� �̓}�C�i�X�ɂȂ�܂��B���̎��ł� �̒l����� ���ϓ����Ă��܂��̂ł��B����ł́A���̂̋��̔��a( �����̂�)�͎��Ԃɂ���Ă��ϓ����鎖�ɂȂ��Ă��܂��܂��B����͕s�s���ł��傤�B�s���̂̋��� �������̒��������Ԃɂ���ĕϓ�����t�Ȃ�Ęb�͕�������������܂���B ���ꂪ�������̂Ȃ� ��0 ������ɑ������ȂǏo���܂���B�������ɂ́A���m�ȏ������K�v�ƂȂ�܂��B����������0�����ł���̂́A ���ǂ�Ȓl�ł��낤�ƌa�̒������e�����Ȃ��������ł��傤�B �������������ł́u�����Ă��鋅�� �������̐��@���k�ށv�Ƃ������_��n��o���O�Ɂu �������̐��@�����Ԃɂ���ĕϓ�����v�Ƃ����ʂ̗��_���Ă��܂��܂��B����ł͕s�s���ł��̂ŁA ��0�������� �̍��������A���������Ă��܂����ƍl�����̂ł��傤���A���ɁA���ӔC�ł��B���̑O�Ɂu �̕����̓��������v�������������̂ɖ�肪����ƋC�Â��ׂ��ł����B �{���̖��͑���������[�����c�ϊ��ɂ���̂ł�����B�} �Ŗ��炩�ȗl�ɁA���[�����c�ϊ��� �@�͎��ԂƋ��ɑ傫���Ȃ�܂��B�@�E�E�E�@�u�������̂̋��� �������̐��@���k�ށv�Ƃ������_���A���̗l�ȃ��[�����c�ϊ����g���������琶������ł��鎖�͖����ł��傤�B ���́A���̖������ʔg�Ƃ����ϓ_���猩�����Č��܂��傤�B�A�C���V���^�C���͋��ʔg�ƍ��̂̋��Ƃ��������Ă��܂��B���̋��ʔg�̎��Ƃ́@�E�E�E�@�Ƃ������Ń��[�����c�ϊ�����鎞�̓y��ƂȂ鎮�ł��B�������ʔg�œ`��鎞�A���̔g�ʂ̔C�ӂ̓_���o( ) �Ƃ���A�㎮�����藧�Ƃ������̂ł��B�����č��̂̋��̕\�ʂ̎��́@�E�E�E�@�ł��B����͋��ʔg�̎��̈����O�̎��ŁA�������鏊�̂n�_����o�_�܂ł̋����̎��@�E�E�E�@�ƑS�������`�����Ă��܂��B�]���č����͂��܂��B���̂̋��̕\�ʂ�\�킷�����A���̋��ʔg�̎����ǂ�������ʂ̎��ł��B���̏�A���[�����c�ϊ��� �@�͌��̋��ʔg�� �ł��B�����獬�����Ă��܂��܂��B�������Ȃ���A���҂͊�{�I�ɕʕ��ł��B ���ʔg�͎��ԂƋ��ɑ傫���Ȃ�Ō�͖�����ɂȂ�܂��B����ɔ�ׂč��̂̋��͍��̂ł�����A���Ԃł͌a�͕ϓ����܂���B�����������ł�����A���̂̋��̎��Ƀ��[�����c�ϊ��������鎖�͊ԈႢ�Ȃ̂ł��B����Ȏ������ās���a���k�ށt�ȂǂƂ������_�Ă������ɂ͂Ȃ�܂���B�P�ɁA�Ԉ���Ă��邾���ł�����B �����Řb�����ɖ߂��A ��0����������ɖ߂�܂��傤�B�A�C���V���^�C���́A ��0 ��������Εs�s���� ����������Ƃ��āA���Ղ�0 �������܂����B����������́A�ނ������̑n�������̈Ӗ��𗝉����Ă��Ȃ�����\�I���Ă��܂��B�@��0�@�Ƃ������́A���[�����c�ϊ��ł́A�܂�����������Ă��Ȃ���Ԃ��Ӗ����Ă���̂ł��B�@���̎��A���͂܂����_�̒��ɂ���܂��B�]���ċ��ʔg (���̓��B�_) �̊e���W�� ��0,�@ ��0,�@ ��0,�@ ��0,�@ ��0,�@�@��0�ł��B��������ƁA�{���̗l�Ɂu�Î~�n�̎����@ ��0�@�̏u�ԂɁA���̕�������Î~�n���猩��v���Ƃ���Ă��Ӗ��Ȃ��Ȃ�܂��B ��0�@�̏u�ԂɎ��@�E�E�E�@���r�n��茩��@�E�E�E�@�ƂȂ��āA�S�Ă̍��W��0�ɂȂ�v�Z�s�\�ɂȂ��Ă��܂��܂��B ���̏�Ԃł�3���̒��������߂鎮���o�ė��܂���B���R�̎��Ȃ���r�n��U�n�Ƃ̒����̔���o�ė��܂���B�@�u����ł́A�܂����v�� ��0 �ɂ���A���x�́@�@�����ԂƋ��ɕϓ����Ă��܂��A���̂̋��̔��a�����ԂƋ��ɖc�����č��������ɂȂ�܂��B�ǂ����ɂ��Ă��A�C���V���^�C���̌v�Z�͐��藧���܂���B�����������ł�����u�Î~�n���猩��A�����Ă��鍄�̂̋��� �������̒������k�ށv�Ƃ������_�����ɂȂ�܂��B�@ |
|
|
��(d)�@���Ԃ̒x��
��(�)�@�����ɂ� �u���ɐÎ~�n�ł͎��� �������A�^���n�ł͎��� ��^���鎞�v���l���悤�B�Î~�n�̎����� �̎��A�^���n�̌��_�ɌŒ肳��Ă��鎞�v������ �������A���̏ꏊ�� �Ƃ���A�ϊ������ɂ��@�E�E�E�@�܂��A �� �Ƃ̊Ԃɂ́@�E�E�E�@�Ƃ����W������B�@�E�E�E�@�ƂȂ�B����̂ɐÎ~�n�ōl����ƁA�Î~�n�̎��Ԃ̈�b���ɁA�����Ă��鎞�v�́@�E�E�E�@�Ƃ���܂��B��������t���ȗ����ꂷ���ĉ�����ɂ����̂ŁA���t�����Đ������܂��B ��(�)�@�⑫���� �u�^���n�̌��_ O���Ɏ��v���Œ肳��Ă���Ƃ��܂��B�����ĐÎ~�n�̎����� �̎��ɁA�^���n�̎��v������ �������Ă���Ƃ��܂��傤�B���̎��^���n�̌��_ O���́A�Î~�n�� ����̈���_ �̏��ɍ݂����Ƃ��܂��B���[�����c�ϊ���� �� �̊Ԃɂ́@�E�E�E�@�Ƃ����W�̂��鎖���������Ă��܂��B������ �� �Ƃ̊Ԃɂ́A�Î~�n�Ɖ^���n�̈ʒu������ �} ���@�E�E�E�@�Ƃ����W�̂��鎖���������Ă��܂��B �����ŁA���� �@�� �����ɑ�����Ă݂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��B�����ł��̌��ʂ������H���ā@�E�E�E�@�Ƃ����Č��܂��傤�B��������ƁA���̌��ʂ��^���n�ɂ��鎞�v�́A�Î~�n���Ԃ̈�b���Ɂ@�E�E�E�@�b�Âx��鎖�ɂȂ�B�v�ƌ����Ă�킯�ł��B ���̘_���������̗��ꂾ�������Ă���ƁA�������肻�̋C�ɂ������܂��B�������A������Ԉ���Ă��܂��B ��(�)�@���̏ؖ� �܂����̕s���R�Ȏ��́@�E�E�E�@�Ƃ������_�̎����o���Ă���A��������H���ā@�E�E�E�@�Ƃ��A���̌��ʂňȂāA�^���n�̎��Ԃ͐Î~�n�̎��Ԃ̈�b���Ɂ@ �b�Âx���Ƃ������ł��B �������Ȃ���A�C���V���^�C���́A�ŏ� �� ��C�ӂ̎����Ƃ��Ă������ł��B�@�E�E�E�@��������@�@�͎����̊W���ł��傤�B�Ƃ��낪�A���ɂ́A������H���Ĉ�b���� �b�Âx���Ƃ��܂����B�ł��A��������� �@�͌o�ߎ��Ԃ������ɂȂ��Ă��܂��܂��B�܂�A�����ł� �� ���o�ߎ��ԂƂ��Ď�舵���Ă���̂ł��B�������A���A�o�ߎ��Ԃɂ���ւ�����̂ł��傤���B ���̎��ł����Čo�ߎ��Ԃ����߂����̂Ȃ�@ �| �@�Ƃ����`�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�����ł͂Ȃ��A�������H���������̎��Ȃ�A�܂������̊W���̂܂܂ł��傤�B�@�E�E�E�@�� �������Ƃ��Đݒ肵���̂Ȃ�@�E�E�E�@�́A�����܂ł������̊W���łȂ���Ȃ�܂���B��������ƁA�����ł� �� �̈Ⴂ��U�n�̎����Ƃr�n�̎����̈Ⴂ�Ƃ������ɂȂ�܂��B����́A�����̎����� �̎��Ƀ����h���̎����� �ł���Ƃ������x�̈Ⴂ�ɂ����Ȃ�܂���B���{��12���̎��A�C�M���X��3���ł�����A�A�C���V���^�C�����̂����ōs���A�C�M���X�̎��Ԃ͓��{�ɔ�ׂ�1����9���Ԃ̊����Œx��Ă��鎖�ɂȂ�܂��B �ʂɊԈႢ�ł͂���܂���B�����A����́A���Ԃ̒x��ƌ�����莞���ł����ǁB�C�M���X�̎��v�����{�ɔ�ׂ�9���Ԓx��Ŏ�������ł���̂͊m���ł��B�������A�ʂɃC�M���X�̎��v�̎������ޑ��x���A���{�ɔ�ׂ�1����9���Ԃ̊����Œx��Ă���킯�ł͂���܂���B �A�C���V���^�C���̂���Ă���ԈႢ�Ƃ́A���́A���������ԈႢ�Ȃ̂ł��B�A�C���V���^�C���͎����̂���ƁA���Ԃ̐i�s���x�̈Ⴂ�Ƃ��������Ă��܂��B�A�C���V���^�C���͎����Ǝ��Ԃ��������Ă��邩��A���������ԈႢ��Ƃ��̂ł��B�@�E�E�E�@�����[�����c�ϊ��{���̈Ӗ��ŗp����A �� �͌��̑��s���Ԃł�����A���̎��͖��Ȃ��s���Ԃ̒x��t�̎��ɂȂ�܂��B �������Ȃ��̂́A�A�C���V���^�C���� �� �������Ǝv������ł�������ł��傤�B ���ɁA�{���ł́u �� �Ƃ̊Ԃɂ́A�@�Ƃ����W������v�Ƃ��������肪����܂������A��������ł��B�O�ɂ��\���܂����l�ɁA���̐߂ōŏ��ɐݒ肳�ꂽ �́A�r�n��Ԃɉ�����C�ӂ̎����ł��B����ɑ��� �� �Ƃ� U�n�̌��_ O�����r �n�̌��_ O �̏����� ������ړ����č��W �̏��܂ōs���̂Ɋ|���鎞�Ԃł��B �ŏ��̐ݒ�� �́A�r�n��Ԃ̔C�ӂ̎����ł����A�@�@�� �� U�n�̈ړ����ԂȂ̂ł��B���̓�� �͉��̊W������܂���B�S���̕ʕ��ł��B����Ȃ̂ɃA�C���V���^�C���́A���҂��܂�œ���̕��ł��邩�̂悤�Ɉ����Ă��܂��B������A�ނ������Ǝ��ԂƂ��������Ă��鎖����N���鎖�ł��傤�B�{���Ȃ�A���̓�� �͕ʁX�̋L���ŕ\�킳�Ȃ���Ȃ�܂���B�r�n��Ԃ̎����� �ŕ\�킷�̂Ȃ�AU �n�̈ړ����Ԃ� �s �ŕ\�킷�Ƃ��B�������Ȃ�����A��ʂ������������Ă��܂��킯�ł��B �����Ƃ��A�u�r�n�̎����� ��0 �̎��� U�n �̌��_�� �r�n �̌��_�Ƃ��d�Ȃ��Ă����v�Ƃ��������ł��t����Θb�͕ʂł����B�@�E�E�E�@���̎��́AU �n�̈ړ����� �s ���r�n�̎��� �ł����đ�p���鎖���o���܂��̂� �s �� �����ƌ��Ȃ������o���܂��B �������Ȃ���A�����ɂ́A���̗l�ȏ����͉������Ă��܂���B�]���āA �� �ƃ��[�����c�ϊ��� �Ƃ��������ł���Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��L��܂���B�����Ƃ��A����������Ă��܂��Ƙb�������ŏI����Ă��܂��A���̖���Nj��ł��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA�A�C���V���^�C�����Y�ꂽ�Ƃ������ɂ��Ęb��i�߂܂��B ���ɃA�C���V���^�C���́@�E�E�E�@�� �� �� �������悤�Ƃ��Ă��܂����A�Ȃ��A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��悤���B���̕K�R���ƍ�����������Ă��܂���B�{���A���̓�� �͕ʕ��ő���ł���l�Ȃ��땨�ł͂���܂���B���[�����c�ϊ��@�E�E�E�@ �� �Ƃ� �}�̒��̋����� �̎��ł��B����́A�����Î~�n�̌��_ O ����o�_�܂ő��������̋����� �����������ł��B���W�ƌ��Ȃ��Ă��o�_�� ���W�Ɍ����܂��B�@�E�E�E�@����ɑ��āA�@�� �Ƃ� �} 3�]5�]5 �̒��̋����� �ł��B����́AU �n�̌��_ O���� �r�n�� ����� ���Ԋ|���Ĉړ��������̋����ł��B���W�ƌ��Ȃ��Ă� U �n���_�� �r�n ����ɉ�����ʒu�ɂ����Ȃ�܂���B���̓�� �͉��̊W������܂���B�ǂ����đ���o����̂ł��傤���B����Ƃ��A�C���V���^�C���� �@�� �����v�̈ʒu�ƌ��A������@�E�E�E�@�ɑ������AU�n�ł̎������o�ė���Ƃł��l���Ă����̂ł��傤���B�����������Ƃ�����A����́A�Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�ł��B���̎��́A�����������ł͂���܂���B ���[�����c�ϊ��́A���̓��B�ʒu�Ɠ��B�����̊W���Ȃ̂ł��B���v�̈ʒu���Ԃ̎��������߂鎮�Ȃǂł͂���܂���B�܂��A���ɁA�S�������Ă����������Ƃ��Ă��A�����ɐV���Ȗ�肪�����ė��܂��B����́u�������v�Ƃ̗��݂���ł��B �������̗����ł́u�Î~�n�̓�ӏ��œ����ɉ������N�������Ƃ��Ă��A������Ă���n���猩��Ɠ����Ƃ͌����Ȃ��v�ƂȂ��Ă������ł��B�Î~�n�ł͓������ł����Ă��A�����Ă���n���猩��ƌ��_�Ƃ��̑��̏ꏊ�Ƃł͎������قȂ��Ă��鎖�ɂȂ��Ă��܂��B �����āA���̎��͍ŏ��̐ݒ�ɂ��^���n�̌��_����ɂ��č���Ă��܂��B��������ƁA���_����ɂ��āu���Ԃ̒x��v�̎���������Ƃ��Ă��A������A���_�ȊO�̏ꏊ�ɂ͓K�p�ł��܂���B����Ƃ�����ꏊ�Ŏ����̌n���قȂ��Ă��܂�����A��Ƃ��ċ��ʂ̎��͑n��Ȃ��Ȃ�܂��B ���̗l�ɖ������ė���̂ł��B �����Ƃ��A�����͌����Ă��A�A�C���V���^�C���̂����ŗ����̐��藧���������킯�ł�����܂���̂ŁA���́A�����̏����������Ă݂܂��傤�B�܂��͑O�ɖ߂��ā@�E�E�E�@�� �� �@�� �������錏�����W�ƌ����ϓ_���猩�����Ă݂܂��傤�B�@�E�E�E�@�� �Ƃ͐Î~�n�Ō������B�������̓_�o�� ���W�ł��B�@�E�E�E�@�����āA �� �Ƃ́AU �n ���_�̂r�n ����ɉ�����ʒu�ł��B�@�E�E�E�@�� �Ɂ@�@�� ��������Ƃ������́A���̓�� ����v������Ƃ������ł��B ����ɂ́A�ǂ�����悢�̂��B����ɂ́A���̓��B�_�ł���o�_���AU �n ���_ O����莲�ɐ����Ɉ���������Ɏ����ė��鎖�ł��B��������Ηv�����ꂽ��ԂɂȂ�܂��B�����Ă����}�ŕ\�킹�� �} 3-5-8 �̗l�ɂȂ�܂��B����́A�O��(���ȏ�)�́g���v�̒x��h�̏��Ŏ������uU �n �ɉ����āA���_O����� ���ɐ����Ɍ����A������r�n���璭�߂����� �} �Ɠ����ł��傤�BU �n �̌��_�@O�������� ���ɐ����ɔ����A������r�n��蒭�߂�A���̓��B�_�� ���W�͏�� U �n ���_�݂̍�ꏊ�Ɠ����ɂȂ�܂��B �]���āA���̎��Ɍ���A�A�C���V���^�C���̐ݒ�͐��藧���A���_�̎��@�E�E�E�@�����藧���܂��B���R�A�C���V���^�C���̗��_�����藧���܂��B�������Ȃ���A����́A ���ɐ����ɔ����ꂽ���݂̂ōl�����Ă��鎖�ł����āA���̕����̌��͈�؍l������Ă��܂���A�������͗L��܂���B���̕����̌��ōl�����Ȃ�A���̎��͐��藧���Ȃ��Ȃ�܂��B����ǂ��납�A�����n�̐i�s�����Ƌt�����ɂł�������@�E�E�E�@�ƂȂ��āA�^���n�̎��Ԃ��Î~�n���i��ł��܂��܂��B���A�������́A�O�͂́u���Ԃ̒x��v�Ɠ����ɂȂ�܂��̂ŁA�_�͏ȗ����܂��B �Ƃ������A���������킯�ŁA�u�����Ă��鎞�v�̒x��v�����ԈႢ�ƂȂ�̂ł��B ���̍��Ɋւ������A���ȏ��̂����ƃA�C���V���^�C���̂����́A������A����Ă��܂���B���͂̕\�ʂ��������Ă���ƁA�S���A����Ă���l�Ɍ������̂ł����A�{���I�ɂ͓������������̂ł��B �����܂ł̘_�Ŗ��炩�ȗl�ɁA�ꌩ�A���ȏ��̎��M�҂̊ԈႢ�Ɍ�����l�Ȏ��ł��A�˂��߂čs���A���̍����A�C���V���^�C���ɂ��������������Ă��܂��B�A�C���V���^�C�������������ԈႢ�����Ă�������A���̐搶�����A�C�Â����ǐ����Ă��܂����ƌ����ׂ��ł��B�@ |
|
| ��(��)�@�A�C���V���^�C���_�����̂܂Ƃ� | |
|
�A�C���V���^�C���́A�F��ȊԈႢ�����Ă��܂��B
(2)(a)�́g�����̑��ΐ��h�̏��ł́A�����Ă���_�̂`�[�ƐÎ~�n�̂`�n�_�Ƃ��������Ă��܂����B�����Ɍ����A�ނ̘_���ɂ́u�Î~�n�̂`�n�_�v�Ƃ������t����L��܂���B�����P�Ɂu�`������������˂���A�_�a�Ŕ��˂���āA�`�ɖ߂��ė����v�Ƃ��邾���ł��B�ŏ������ʂ����Ă��Ȃ��̂ł�����A�����ɋC�Â��l�̂��锤���L��܂���B���ۂɁA�ނ̐����̈Ӗ��𗝉����悤�Ƃ���A�Î~�n�ɂ`�n�_�Ƃ����ꏊ��ݒ肵�A�����Ɋϑ��҂�u���Ȃ���Ȃ�܂���B�������Ďn�߂ĈӖ����ʂ�̂ł����A���̎��ɂ́A�����ɁA���ɂ��C�Â����ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪���̗ǂ��搶���́A����Ȏ������Ȃ��Ă����𗝉�����܂��̂ŁA�����ɋC�Â��`�����X�������܂��B �����������́A���̗l�ɓ��̈����҂��A�����̓��ł�������l�ɂƁA�������ݍӂ��ĕ��ג��������ɁA���߂Ĕ��鎖�ł��B�|�ꂽ�搶�́A�g�Ȍ��ɂ��Ė��āh�Ƃق߂������Ă����܂����A���̊Ȍ����������Ȏ҂������̂ł��B ���ꂾ���ȗ�������Ă���ƁA�_�̂`�[�ƐÎ~�n�̂`�n�_�Ƃ��������Ă��Ă��A�N���C�Â��܂���B�V�h������ŗ�Ԃ�����������ꂽ�����A��Ԃ̒��̐l���ڌ������Ƃ��āA���̐l�́A��Ԃ��r�܂ɒ��������u���͒r�܂�蔭���ꂽ�v�ƌ����ł��傤���H ��Ɍ���Ȃ��ł��傤�B �ɂ��ւ�炸�A��������킹�Ă���̂����Θ_�Ȃ̂ł��B �_�̂`�[�ƐÎ~�n�̂`�n�_�Ƃ���������Ƃ����̂́A�V�h�Ɨ�Ԃƒr�܂Ƃ��ƌ��Ȃ��ɓ������s�ׂł��B ����(2)(b)�́u���[�����c�ϊ��̗U���v�̏��ł́A�A�C���V���^�C���̓��[�����c�ϊ������̑��s�����Ƒ��s���ԂƂ��瓱���o���Ă��Ȃ���A�o���オ�������[�����c�ϊ��� �� ��C�ӂ̍��W��C�ӂ̎����Ɗ��Ⴂ���Ă��܂����B ���̎������Θ_����z�V�O�ȕ����ւƓ����čs���������ł��B ����́A�ނ��u�����ƍ��W�v�A�u���ԂƎ����v���������Ă������炻���Ȃ����Ǝv���܂��B ����(2)(c)�u�����Ă��镨�̂͒������k�ށv�̏��ł́A���̋��ʔg�ƍ��̂̋��̎��Ƃ��������Ă��܂����B �ǂ�������̎��ł�����A���̌`�͎��Ă��܂��B�����獬���͂��܂��B �������Ȃ���A���҂͊�{�I�ɕʕ��Ȃ̂ł��B ���ʔg�͎��ԂƋ��Ɋg�債�܂����A���̂̋��̌a�͎��Ԃł͕ϓ����܂���B �����̏��̈Ⴂ�ɋC�Â����������Ă��܂��ƁA���鎞�͍��̂̋��̗����ōl���A���鎞�͋��ʔg�̗����ōl���A���҂̗������r���œ���ւ���Ă��C�����Ȃ��Ȃ�܂��B���̌��ʂƂ��āu �������̐��@���k�ށv�Ƃ̌��_�ł�����A�V�����ł��������̗l�ȋC���ɂȂ�L���V�ɂȂ�܂��B�{���͒P�ɊԈ���Ă��邾���̘b�ł����B ����ł� �̍�������ƍ��̂̋��������Ɋg�債�Ă��܂��̂ŁA����ł͕s�s���� ��0�����Ă̍����������悤�Ƃ��܂��B�Ƃ��낪�A����Ȏ�������ƁA�g�������_�̂Ȃ��Ɏ���( �� 0 �ł͌��͂܂�������Ă��Ȃ�����)���@ �� 0, �@ �� 0, �@�@�� 0,�@�@�@�� 0, �@�@�� 0 , �@ �� 0 �ƂȂ��Čv�Z�s�\�ɂȂ�h���ɋC�Â��Ă��܂���B �A�C���V���^�C���́A����Ȏ��ɂ͖��ڒ��������̂ł��B (2)(d)�́u���Ԃ̒x��v�̏��ł́u�r�n�ł̎����v�Ɓu �n �̈ړ����ԁv�̍�����u�r�n�ɉ�������̓��B�_�� ���W�v�Ɓu�r�n ����ɉ����� �n ���_�̈ʒu�v�Ƃ̍��������Ă��܂����B �u�����ł͂Ȃ��B���ꂪ�������鏊�����߂Ă���̂��v�Ƃ����ꍇ�A����́g �n �̌��_��� ���ɐ����ɔ����ꂽ���h�ɂ��Ă̂ݍl���鎖�ƂȂ�A���̕����̌��͈�؍l������Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA������萶�܂��Ƃ���̗��_�͕��Ր��������Ȃ��Ȃ�܂��B ���̗l�ɑ��Θ_�Ƃ́A�����鏊�ɖ������܂�ł��镨�������̂ł��B����̓A�C���V���^�C�����A�v�����݂⊨�Ⴂ�E�������Ƃ̍����Ŏ���n��������A�����Ȃ����̂ł��傤�B�A�C���V���^�C���̂���Ă鎖�́A�������������Ă���ƃX�S���̂ł����A�ǂ��悭���Ă݂�Əo����߂Ȃ̂ł��B�����̐搶�����A���̊ԈႢ�ɋC�Â��Ȃ������̂́A�]��ɂ������Ȍ��ɂ܂Ƃ߂��Ă�������ł��傤�B �����܂ŗ���Δ��������̗l�ł����A���́A�܂��s�\���Ȃ̂ł��B�Ƃ����̂́A���X�ɕ���ł��鑊�Θ_�̖{�ł́u�������v��u���[�����c���k�v�E�u���Ԃ̒x��v�Ȃǂ��������̂Ɂu�l��������v���g���Ă��邩��ł��B����ł́A�����A������Ԉ���Ă���ƌ����Ă��u���O�̗����͎O�����̗������A����͎l�����Ȃ̂�����b�ɂȂ��v�ƈ�R���ꂩ�˂܂���B ���̎l�����̗������{���͊Ԉ���Ă���̂ł����A�����������Ȃ����ɂ͘b�͏I���܂���B�@ �@ |
|
| ���l�@�l��������_�̌�� | |
|
���ΐ����_�ł́A���̐��E���O������Ԃ̑��Ɏ��Ԃ������Ďl�����Ƃ��Ă��܂��B�����̐l�́A����ɂ��Ắu�����ς��ȁ[�v�Ƃ͎v���Ȃ�����A�̂��l�������̂����炻�������m��Ȃ��A�Ǝv���Ă����邩���m��܂���B
�Ƃ���ŁA���Θ_�ł́A���̑��x���������鎖�͌�@�x�ƂȂ��Ă��܂��B�Ƃ��낪�A�������Θ_�ł��@�u���b�N�z�[���_�ł́u�u���b�N�z�[���̓�����ŕ��̗������x�͌����A�����艜�ł͌������Ă��܂��A��������O�ɏo���Ȃ��v�Ƃ���Ă��܂��B����͖������闝���ł��B ���ׁ̈A���Θ_�ł́u�u���b�N�z�[���ɓ���ƁA���ԂƋ�ԂƂ�����ւ���Ă��܂��v���ƌ����A�Ƃ�ł��Ȃ�������n��o���āA���������܂����܂����B����͖Œ��ꒃ�ȗ����ł��B �C���[�W���Č��ĉ������B���P�b�g�̐i��ł���������ˑR���Ԃɕς��A���܂Ŏ�������ł������Ԃ���Ԃɕς��Ƃ��������B�C���[�W�o���܂����B�����ł��傤�B���Ԃ��ǂ�����ċ�Ԃɕς���̂ł��H �����ŁA�C���[�W���₷���悤�ɉ��̘b�����Ă݂܂��傤�B�i�s�����̋�Ԃ��ˑR�A���Ԃɕς����Ƃ��܂��B���āA��������ƁA���܂ŁA�O���ɂ��������͉����ɕς�̂ł��傤���H�i�s�����̋�Ԃ����Ԃɕς��ƌ����܂����A���E�㉺�����̋�Ԃ͌��̂܂܂Ȃ̂ł��B�Ȃ��Ȃ�A���E�㉺�����͑��x�� 0 ������ł��B�@���x 0 �ł͎��ԂƋ�Ԃ̌��͂ł��܂���B���ԂƋ�Ԃ���シ��ɂ͑��x����������K�v������̂ł��B���Θ_�̎��ł��A���ԂƓ���ւ��̂� ���W �܂�i�s�����̋�Ԃ����ƂȂ��Ă��܂��B ���āA��������ƁA�ǂ��������ɂȂ�̂ł��傤���H ���P�b�g�̍��E�㉺�̑����猩��i�F�͘A�����Ă��܂��B�����˔j�ȑO�ɎߑO�Ɍ����Ă������́A�����˔j��ɂ����̊O������܂��B���Ԃɕς������̋�� (��) ���A���E�㉺���猩��ƌ��̂܂܂Ȃ̂ł��B������ǂ����܂����H��������ƁA�i�s�����̋�ԂƁA���E�㉺�����̋�ԂƂ̐������͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���H���̂悤�ɁA�������Ȏ��ɂȂ�̂ł��B ���Θ_�ł́A��ԂƎ��ԂƂ͓���ւ��\�̕��Ƃ��Ă��܂��B �������Ȃ���A����͌�������������ꂽ�����ł����āA�������͂���܂���B ���������A��ԂƎ��ԂƂ͑S���َ��̕��ŁA����ɘ_��������̂ł͂���܂���B��Ԃ̎����́A�c�E���E�����@���R�Ɉړ��o���܂��B�i�ގ����A�߂鎖���o���܂��B�܂��A���̏�ɗ��܂鎖���o���܂��B����ɑ��āA���Ԃ͖߂鎖���~�܂鎖���o���܂���B���A����I�ɑO�ɗ���邾���ł��B������A������̎��R�ɂ͂Ȃ�܂���B��X�Ɏ��R�x�͂Ȃ��̂ł��B��X�����Ԏ��̒���i��ł���̂ł͂Ȃ��A���Ԃƌ����x���g�R���x�A�[�̏�ɏ�������Ă���l�ȕ��ł�����B ��Ԃ̎����Ǝ��Ԃ̎����Ƃł͎����Ⴂ�܂��B�����������ł������Ԃ̎����Ǝ��Ԃ̎����Ƃ�Ɉ������͏o���܂���B ����́A���ꂱ���ʎ����̘b�ł��B�����ŁA�����ł́A���̌��ɂ��Đ������܂��B�܂��́A���̗l�ȗ��_���A�ǂ̗l�ɂ��ďo�����̂�����������čs���܂��傤�B�@ |
|
| ��(��)�@�l��������̗��_�̗U�� | |
| ��(1)�@�l�������W�̗U�� �@ | |
|
(����͓r���܂ł̓��[�����c�ϊ��̗U���Ɠ����ł�)�@�܂��́A�}�̗l�Ȓ������W���l���܂��B�����āA���̍��W�n�̂���_ �o( ) �Ɍ��_ O �������������Ƃ��܂��傤�B��������ƁA���̋����͌����� �A���s���Ԃ� �Ƃ��ā@�E�E�E�@�ŋ��܂�܂��B���Ƀs�^�S���X�̒藝���A���̋����̓��́@�E�E�E�@�ŋ��܂�܂��B���̓��q���������ā@�E�E�E�@�ƒu���܂��傤�B�����Ď��ɁA�E�ӂ����ӂɈڍ����ā@�E�E�E�@�Ƃ����܂��B�����܂ł́A���[�����c�ϊ��̗U���Ɠ����ł��B�����炪�Ⴂ�܂��B
���̌�A�����@�E�E�E�@�ƌ������ɏ���������̂ł��B�������Ă����āA���W�̌`�Ԃ����܂ł́@�@�Ƃ�����������@�@�E�E�E�E�@�Ƃ����`�ɂ�芷���܂��B�@�E�E�E�@�ƌ����l�ɂł��B���ꂩ�� (4-1-5) ����4�Ԗڂ̍��@�@�������W�ɑg�ݓ���� �Ƃ��܂��B��������ƁA�V�������W�́@�E�E�E�@�Ƃ����`�ɒu���������܂��B���ꂪ���Θ_�̎l�������W�ł��B�����p���܂��� ���́@�E�E�E�@�Ƃ����`�ɒu�������܂��B���ɁA���W�̉�]�Ƃ������̂��l���܂��傤�B �@ |
|
| ��(2)�@���W�̉�] �@ | |
|
�O������Ԃł́A���_ O ���� P �_�܂ł̋������q�Ƃ��܂��Ɓ@�@�͍��W�̉�]�ɑ��āA���̒l�͕ς��܂���B���� �y�� �̂܂��� �� ������]�������W�n ���l���܂��B��������ƁA�����o�_�̍��W�͐V�������W�n�ł� �ŕ\����܂��B������������̂� �} �ł��B�}���A�O�̍��W�ƐV�������W�Ƃ̊Ԃɂ́@�E�E�E�@�Ƃ����W���������܂��B����́A�����w�Z�̐��w�̋��ȏ��ɍڂ��Ă��鎖�Ȃ̂ŏؖ��͂��܂���B
���̏ꍇ�AP�_�̍��W�͕ς��܂����AOP �Ԃ̋����͕ς��܂���B �@ |
|
| ��(3)�@���[�����c�ϊ��͎l������Ԃɉ�������W�̉�]�̗l�ȕ� �@ | |
|
�l�������W�@�E�E�E�@�͊��ɋ��܂��Ă��܂��̂ŁA���͂����ɁA���[�����c�ϊ��@�E�E�E�@�������ė��āA����Ɏl�������W�Ă͂߂Ă݂܂��傤�B��������� (2-1-8-1)�́@�E�E�E�@�Ƃ����`�ɒu�������܂��B
���ꂪ�l�������W��p�������[�����c�ϊ��ł��B�Ƃ���ŁA������� �̍��� �̍����ׂĂ݂ĉ������B�������Ă��鎖�ɋC�Â���܂��B�����ŁA�����Ƃ͂����蔻��悤�ɔ����o���ĕ��ׂČ��܂��傤�B��������� �@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA�����A�ΏƓI�Ȍ`�ł��鎖��������܂��B���́A����͍��W�̉�]�̎��Ɏ��Ă���̂ł��B �����ŁA���ɁA �@�ƒu���Č��܂��傤�B��������Ǝ��́@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��č��W�̉�]�̎��@�E�E�E�@�Ƃ�������ɂȂ�܂��B��������s���[�����c�ϊ��́A�l������Ԃɉ�������W�̉�]�̗l�ȕ����t�ƌ��Ȃ����l�ɂȂ����̂ł��B�܂��A���̎�����s �̍��W�� �̍��W�Ƃ��A�����ȕ��Ƃ��Č����\�t�Ƃ̉��߂��o�ė��܂��B �Ƃ���Ŏl�Ԗڂ̍��W�� �� �Ŏ����I�ϐ������Ԃ� �݂̂ł�����A�l�Ԗڂ̍��W�������Ԏ��ƌ��Ȃ��܂��B�����Ă܂� �̍��W�� �@���ŁA�n�̐i�s�����̍��W�ł��B��������A�n�̐i�s�����̋�Ԏ����Ǝ��Ԃ̎����Ƃ�����Ɉ����A�����ȕ��Ƃ��Č����\�Ƃ������߂��o�ė����킯�ł��B �����āA�������A�l��������Ƃ����T�O�����܂�A�u���b�N�z�[���ɓ˓�����ƁA���ԂƋ�ԂƂ�����ւ���Ă��܂����Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ����z�ւƔ��W���čs�����̂ł��B�@�������Ȃ���A���̗��_�͊Ԉ���Ă��܂��B �@ |
|
| ��(��)�@�l��������_�̌��̏ؖ� | |
| ��(1)�@���W�̉�]�E����̓]���͖����B�O�p���̌�� �@ | |
|
���[�����c�ϊ��Ɏl�������W��g�ݍ���ŏo�������@�E�E�E�@�� �� ���@cos�Ɓ@�Ɂ@i�����@���@sin�Ɓ@�ɒu�������Ă݂���@�E�E�E�@�ƂȂ��āA���W�̉�]�̎��Ƃ�������ɂȂ����B�u������A���[�����c�ϊ��͎l������Ԃɉ�������W�̉�]�̗l�ȕ����B�v�Ƃ������ł����A�ʂ����āA�����Ȃ̂ł��傤���B
���ɒu�����@�� �� cos��,�@i���� �� sin�Ɓ@�ɖ��͖����̂ł��傤���B���́A����̂ł��B �� �� cos�� �@�́A�܂��悢�Ƃ��܂��傤�B�������@i���� �� sin�Ɓ@�ɂ͖�肪����܂��B�@i�����@ �̒��ɂ� �� �������Ă���̂ł��B�Ƃ������́@sin�Ɓ@�̒��ɂ́@cos�� �������Ă���Ƃ������ɂȂ�܂��B ����� sin�� �� i���� �� i��cos�Ɓ@�Ƃ������Ł@sin�Ɓ@�́@cos�Ɓ@�ɔ�Ⴗ��Ƃ������ɂȂ�̂ł����A����ł��ǂ��̂ł��傤���B ���������@ sin�� �Ɓ@cos�Ɓ@�Ƃ͋t�̊W�ɂ���܂��Bcos�Ɓ@���傫���Ȃ�@ sin�Ɓ@�͏������Ȃ�A cos�Ɓ@���������Ȃ�@sin�Ɓ@�͑傫���Ȃ�܂��B cos�� �� 1�@�̂Ƃ��@�@ sin�Ɓ� 0 cos�� �� 0�@�̂Ƃ��@�@�@sin�Ɓ� 1 �ł��B �ǂ����āA sin�Ɓ@���@cos�Ɓ@ �ɔ��o����̂ł��傤���B���̂������ɂ͖���������܂��B���ꂾ���ł͂���܂���B���̎O�p���̊ԈႢ�ɂ́A�܂���������̂ł��B�����ŁA���̎O�p���̖��ɂ��āA�����Əڂ������ׂĂ݂܂��傤�B �܂��́A �� �� cos�Ɓ@����ł��B �� �̌��̎��́@�@�ł����B��������ĒP�������Ă݂܂��傤�B�@�E�E�E�@��������� �@�ɂȂ�܂��B�]���āAcos�� ���@ �@�ł��B�Ƃ���ŁA���̎����悭���ĉ������B���q��蕪��̕����������̂ł��B���q��蕪��̏������@cos�Ɓ@������ł��傤���B����ł́@cos�Ɓ�1�@�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �{���@cos�Ɓ@ �́@0 ���bcos�Ɓb�� 1�@�Ȃ̂ł��B ���Ɂ@sin�Ɓ@�̎������l�ɒP�������Ă݂܂��傤�B ��������� sin �Ɓ@���@ �@ �ɂȂ�܂��B�@�E�E�E�@�P�������ꂽ�@cos�Ɓ@ �Ɓ@sin�Ɓ@ �����܂�܂����̂ŁA�������ׂĂ݂܂��Bcos�� ���@�@, �@�@sin �Ɓ@���@ �@ �����āA��������ɂ��ĎO�p�`��`���Ă݂܂��傤�B��������ƁA����́A�}�̗l�ɂȂ�܂��B�}���悭���Ă��������B�����ςł͂���܂��B�Ε�(�C�[�n)�̐��@�@�@ �̕�����(�C�[��)�̐��@ c ���Z���̂ł��B����͘_���I�ɖ������܂��B���p�O�p�`�ł́A�Εӂ͑��̓�ӂ�蒷���Ȃ���Ȃ�܂���B����ł͒��p�O�p�`�͐��藧���܂���B(�� �F �����̋L�� i �@�͎����ƕ����� 90���Ⴄ�����������������Ȃ̂ŁA�������Đ��l�݂̂ň����Ă���܂��B) �����Ƃ��A��(�C�[�n)�̐��@�ƕ�(�C�[��)�̐��@�Ƃ����ւ���A���p�O�p�`�͐��藧���܂��B���A����������ł́A���Θ_���]�ޕ����ւ̗��_�U���͂ł��܂���B�]���āA���̎O�p���̂������͑S���̌��ƂȂ�܂��B����ȕ������������āA�u���W�̉�]�̎��Ƃ�������ɂȂ����v�ƌ����Ă��A�������܂���B ���p�O�p�`�̐��藧���Ȃ��O�p���ł́A���W�̉�]�ɓK�p�̂��悤������܂���B ���W�̉�]�̊p�x �� �͒��p�O�p�`�̊p�x �� �Ȃ̂ł��B �{��������Ă���l�̒��ɂ́A������w�E�����̂��x������Ă��A cos�ƁA sin�Ɓ@�Ƃ����A�n�C�p�[ cos�ƁA�n�C�p�[ sin�Ɓ@ �Ƃ���Ă�����������܂��B�������A�ǂ����܂������Ƃ��A���W�̉�]�͒��p�O�p�`�Ő��藧�b�ł�����A���p�O�p�`�̗��������藧���Ȃ���A���̗��_�����藧���悤������܂���B �]���āA���ȏ��̌����g���[�����c�ϊ��͎l������Ԃɉ�������W�̉�]�̗l�ȕ����h�Ƃ����g�l���h�͑S���̌��ƂȂ�܂��B ������������ɂ��Ă��A���������A���܂����킹�Ă��炱�����ė~�������ł��B �O�p�����ł���߂Ȃ̂ł�����A���W�̉�]������̓]��������܂���B �l��������Ȃǂ܂������̊G�ƂȂ�܂��B �Ƃ���ŁA�}��ǂ����ĉ������B���̐}�́A�����Ă���n�̑��x�ƌ����Ƃ̊W��\���Ă���l�ɂ��A�����܂��H�@���́A���̎O�p���́A�����ɂ����{���̈Ӗ����L�����̂ł��B���W�̉�]�Ȃǂł͂���܂���B�@���́A���̐����ł��B �@ |
|
| ��(2)�@�O�p���̖{���̈Ӗ� �@ | |
|
��(a)�@��ԓ��Ō������ƊO���猩�����Ƃ̊W
�����ł́A�܂��A���͂Ŏg�����u��Ԃ̒��̎��Ԃ̖����v�̘b�����p���܂��B �E�}�́A��Ԃ̒��̗l�q�����������ł��B�`�C�a�͍��Ȃ̈ʒu�ł��B��Ԃ͑��x �ʼnE�����ɓ����Ă��镨�Ƃ��܂��B�����ŁA�`�̍��Ȃ̐l���������z���ׂɁA���C�^�[�ʼn�_�����Ƃ��܂��傤�A��������ƁA���̌��͂a�̐l�ɂ́A�܂������`���a�̕����֗����l�Ɍ����܂��B�Ƃ��낪�A���̌��i���O���猩�Ă����l�ɂ́A���͂`���a���̕����֗����l�Ɍ����܂��B ���������瑬���Ƃ͌����A�`����a�ɓ͂��Ԃɗ�Ԃ������͑O�ɓ����Ă��邩��ł��B���̗l�q�́A�}�̎O�p�`�ŕ\����܂��B����͗�Ԃ̒��Ō������̍s�ՂƁA������Ԃ̊O���猩���ꍇ�̌��̍s�ՂƁA��Ԃ̈ړ��Ƃ̊W��\�������ł��B�@���̎O�p�`�x�̊W�Ō������Ă݂܂��傤�B ��������ƁA����́A�} �̗l�ɂȂ�܂��B���Θ_�ł́A��Ԃ̒��̌��̑��x�� �Ȃ̂ł�����������ĎO�p�`�����ōl���Ă݂܂��Ɓ@�@�ɂȂ�܂��B���̐}�͉��ƂȂ� �} 4�]2�]2 �Ɏ��Ă���ł��傤�B������̕��́A�Ԉ���Ă����̂�����A�������̕����{���Ƃ������ɂȂ�܂��B �@ |
|
|
��(b)�@���������@ cos�Ɓ@�͖{���́@ �@�Ł@sin�Ɓ@�͖{���� i ������
�����ŁA�} ��� , �����߂Ă݂܂��傤�B��������Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA���W�ϊ��̎��ɂ����������ƁA�������玗�������o�ė��܂��B�����ł͂���܂��B���ɁA����� ���@�@�E�E�E�@�ɑ�����Ă݂܂��傤�B�@��������Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA���������������W�̉�]�̎��Ǝ����`�ɂȂ�܂��B�����������ł͂���܂���B �����ŁA���̎��� �� �b�n�r�� �Ɂ@i �@ �� �r�h�m�� �ɒu�������Ă݂܂��傤�B��������Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��č��W�̉�]�̎���(4-1-11) ���Ƃ�������ɂȂ�܂��B�������Ȃ���A����� �� �b�n�r�� �� i �� �r�h�m�� �ɒu�����������ł�����A�������͂���܂���B���́A���̂b�n�r�ƂƂr�h�m�Ƃ��A (4-2-2) ����������̂Ɠ��������ŁA�ȒP�Ȏ��ɒ����Ă݂܂��傤�B��������Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂���(4-2-2)���ƑS���������ʂɂȂ�܂��B �܂�A���W�̉�]�̏��ł������� cos�ƁE sin�� �Ƃ́A���� ���� �b�n�r�ƁE�r�h�m�� �̎��������̂ł��Bcos�� �ɂ������� (4-1-10) ���� �� �Ƃ́A���͐}4�]2�]4 �̒��́@�@�̎��ł���Asin�� �ɂ������� i���� �Ƃ́A���͐}4�]2�]4�̒��� i �@�̎��������̂ł��B ���W�̉�]�̏��ŁA�� �� i�������O�p���Ƃ��Ă��������Ƃ��Ă��A�Ȃ���Ȃ�ɂ����藧���Ă����̂́A�������������t�����L��������ł��B ������A�A�C���V���^�C�����~���R�t�X�L�[���͒m��܂��A���Ƃ��肵�č��W�̉�]���Ƃ��E����̓]���ȂǂƁA�Ƃ�ł��Ȃ������ւƔ��W�����čs�����̂ł��B����́A����ȑ�w�ȕ��ł͂���܂���B�P�ɁA�u�s�����Ă���n�̑��x�t�Ɓs�����Ă���n���Ō������̑��x�t�ƁA�s������O���猩���ꍇ�̌��̑��x�t�Ƃ̊W�v��\���Ă��邾���ł�����B �@ |
|
|
��(c)�@�� �͑��Θ_�̖���������W��
�}�ł́A��Ԃ̊O���猩�����̑��x�� �C��Ԃ̑��x�� �Ƃ��Ă���ׁA���p�O�p�`�����X��A��Ԃ̒��ł̌��̑��x�� �Ƃ��܂������A����́A���͑���(4)�́u�������v�̒x��v���O�͑���(2)��(��)�́u�A�C���V���^�C���̃��[�����c�ϊ��̗U���v�̏��ł����ĂƂ��Ďc���Ă��������ł��B�����ŁA�����ł́A����ɂ��āA�l���Ă݂鎖�ɂ��܂��傤�B �܂��́A��Ԃ̒��Ō������̑��x�ƁA������O���猩���ꍇ�̌��̑��x�̔������Ă݂܂��B��������Ɓ@�E�E�E�@�ɂȂ�܂��B����͉����ƌ����ƁA���킸�ƒm�ꂽ���[�����c�ϊ��̕���ł��B�����āA������Ђ�����Ԃ��܂��Ɓ@�E�E�E�@�ƂȂ�܂��āA���[�����c�ϊ��́@���@�ɂȂ�܂��B���āA�����ł������ �} �����ĉ������B����̓��[�����c�ϊ������߂鎞�Ɏg���}�ŁA�����Ă���n�ƐÎ~���Ă���n�̊W��\���Ă��镨�ł��B �n �� �r�n �ɑ��đ��x �� ���������E�ɓ����Ă��镨�Ƃ��܂��B(���G t �� t���� 0 �̂Ƃ��AO �� O���͏d�Ȃ��Ă��镨�Ƃ���) ���̐}����P���� �̋��������߂܂��Ɓ@�E�E�E�@�ɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���[�����c�ϊ��ł́@�E�E�E�@�ƂȂ��Ă��܂��āA�����ɂ́@�E�E�E�@�Ƃ����A�킯�̕�����Ȃ��W�������Ă��܂����B�ŏ��́A���ꂪ�����Ӗ�����̂��ǂ�����܂���ł����B�@�������A���ꂪ�@�E�E�E�@�������ł����Ȃ�A���ƂȂ��A���̈Ӗ����鏊������l�ȋC�����܂��B �܂�A����́A���Θ_�̖���������W��������ł��B���Θ_�ȑO�̍l�����ł����Ȃ�A��Ԃ̒��Ŕ��������̑��x�� �A��Ԃ̑��x�� �Ƃ��܂��ƁA�O���猩�����̑��x�� �@�ƂȂ�܂��B�@(���G�@ �A�@ �̓x�N�g��) �Ƃ��낪�A���Θ_�ł͗�Ԃ̒��Ō����������O���猩�������������ł�����@�E�E�E�@�Ƃ��Ȃ���Ȃ�܂���B�������A����́A�_���I�ɖ������܂��B������������������ׂɁA���͂ǂ�������i���̂������A�@����́@�E�E�E�@�ƂȂ�悤�ɂ������ł��傤�B��������Ζ��͏����܂��Ƃ���Ł@�E�E�E�@�ł�����@�E�E�E�@�ƂȂ�@�@�� �� �Ɠ����Ӗ��ɂȂ�܂��B�@ ��������������A���[�����c�ϊ��́@�E�E�E�@�́A���Θ_�̖����E����������W���Ƃ݂Ȃ���킯�ł��B���͑������������W�����|���鎖�ɂ���Ė��������Ă����̂ł��傤�B���̎�����A�t�Ɂg��Ԃ̒��Ō�����̑��x�ƁA������A�O���猩���ꍇ�̌��̑��x�Ƃ́A�{���A�Ⴄ�̂��h�Ƃ������������ė��܂��B �A�C�V���^�C���́A�����I�Ɂu�Î~�n���猩�Ă��A�^���n���猩�Ă������͓����v�Ƃ��Ȃ���A���_�U���̏��ł́u�^���n�� ���ɐ����ɔ���������Î~�n���猩��ƁA���̑��x�́@�@�ɂȂ�v���Ƃ���Ă��܂����B ��X�A�f�l���猩��u������A����Ȃ̗L��I�H�v�ł����A�{�l�́A���ڒ��Ƃ������A�Z�ʖ��V�Ƃ������A�������鎖�C�ł���Ă��܂����B����Ȏ�������A�ǂ�Ȋ�z�V�O�ȗ��_�ł��n���ł��傤�B�@ |
|
| ��(3)�@�l�������W�͑��݂��Ȃ� | |
| ����̓]���̊ԈႢ�́A�͂����肵�܂������A���́A����ȑO�̖��Ƃ��āA�l�������W�̊ԈႢ������܂��B�@�b�̗����A��]���W�̕����ɂ��܂������A���́A�������̕����A����{�I�Ȗ�肾�����̂ł��B �@ | |
|
��(a)�@�@,�@ �͋����ł����č��W�ł͂Ȃ��B
���Θ_�ł� ���@�E�E�E�@�́@, �@������ɍ��W�ƌ��Ȃ��A�@�E�E�E�@�ƒu�������Ďl�������W�ɂ��Ă��܂����A����͊Ԉ���Ă��܂��B�@�E�E�E�@�̌��̎��́@�E�E�E�@�ł����B����́A���[�����c�ϊ��̐����̏��ł��ڂ����q�ׂ܂����l�ɁA�����̎��ł��B�@�E�E�E�@�ł�����B���̎��́@, �@�͑S�ċ����Ȃ̂ł��B���W�Ȃǂł͂���܂���B�������A�@�ɂ��Ă͍��W�ƌ��Ȃ������o���܂����A�́A�����͍s���܂���B����͖����ɋ����ł�����B�@�E�E�E�@ �} �̒��Ō������������� O P�@�Ԃ̋����ł��B ���̎��̖{���̈Ӗ��́A���� O�o�� �����������̓��Ɓ@���� O�o�� �����������̓��Ɓ@���� O�o�� �����������̓��Ƃ����������́A�������x �� ���Ԋ|���đ��������̋��� O�o �̓��ɓ������Ƃ����������ł��B ����́A�P�Ȃ鋗���̊W���ł��B���̎��́A�u�E�ӂ����ӂ������Ƃ����_�œ������v�ƌ����Ă邾���ł��āA�������āu���ӂ����W�ʼnE�ӂ������A�����ė��҂������v���ƁA���킯�����������Ă���킯�ł͂���܂���B ������A�������Ⴂ�����̂��@�@�����W�A �������Ǝv������Ł@�E�E�E�@�ƒu���@�E�E�E�@�ƕω������āA�������l�������W�Ɏ����čs���܂����B���̌��ʁA�s��Ԏ����Ǝ��Ԏ����Ƃ������Ō����\�t�Ƃ����A�Ƃ�ł��Ȃ����Ⴂ�̐��E�ւƁA�����ς��čs�����̂ł��B�{���́A�P�Ɂs�E�ӂ����ӂ������Ƃ����_�œ����t�Ƃ����������������̂ł����B ���̎��́@�E�E�E�@�܂łɗ��߂�ׂ��ł��B������@�E�E�E�@�Ƃ���ΊԈႢ�ɂȂ�܂��B�@���̏ꍇ�́@�E�E�E�@�Ƃ����̂��������̂ł��B���́@�@�̑O�̃}�C�i�X�L���܂Ł@�@�͈̔͂ɓ���ā@�@�Ƃ���̂́A���w��̃e�N�j�b�N�ł͉\�ł��A����ȏ��Ŏg���Ă悢�킯�͂���܂���B����́A�����������Œ��ꒃ�Ȃ����ł��B����Ȏ�������ƁA�����̖{��������鎖�ɂȂ�܂��B ���������̕��͖��ɗႦ��Ȃ�u�l�́A�m��Ȃ��v�Ƃ��鏊���A��Ǔ_������炵�āA�u�l�A�@����Ȃ��v�Ƃ���l�ȕ��ł��B�@�܂��u�@�@���@�@�����v�Ƃ��鎖���o���܂��B�@�����āA������u�@ ���@ �����v�Ɠǂ݊����鎖���o���܂��傤�B���t�V�тȂ�Ƃ������A�厖�ȕ��͂ł���Ȏ��͋�����܂���B�O���Ȃ�A�푈�ɂȂ肩�˂܂���B ������ɑ��Θ_�ł́A���������Œ��ꒃ�𐏏��ł���Ă���̂ł��B�u�������v��u���[�����c���k�v�E�u���Ԃ̒x��v�E�u����̓]���v�����A���F�̓p�\�R���̕ϊ��~�X�݂����ȕ��ł��傤�B�l�X�́A�ϊ��~�X�̌��ʏo���オ�������͂��A�u��z�V�O���I�v�A�u�s�����v�A�u�f���炵���v�A�u�n�����Ă���v���Ƌc�_�������Ă���悤�Ȃ��̂ł��B�@ |
|
|
��(b)�@�l�Ԗڂ̍��W�͑��݂��Ȃ�
���@�E�E�E�@�̒��� �@�͍��W�ł͂Ȃ������ł��鎖�́A�͂����肵�܂����B�������A����ɂ��ւ�炸�@�@�� �O������Ԃ̊�{���W�ł������{�����ł����鎖�ɕς��͂���܂���B�܂�����ō��W�͌��_����̋����ŕ\�킳��܂��B���̎����� �u���W�v���u�����v�Ǝv������ł�������������ł��傤�B���ׁ̈A���� ���܂����W�ɏo����̂ł͂ƁA���v���̕������邩���m��܂���B ���Θ_�͂��̎v�������̂܂��ɂ��܂����B�������A���̎v�����͗]��ɂ����Ղł����B�@�E�E�E�@�����W�ɂ��悤�Ǝv���Ώo���Ȃ����Ƃ͂���܂���B���A�������A����͎O������ԓ��̍��W�ɂȂ邾���ł��� �@���� ���E ������Ɨ�������l�̍��W���������W�⎟���ɂȂ�킯�ł͂���܂���B��������́@���̐����ł� ���ׂ̈ɂ́A�܂��A ���́@�E�E�E�@�Ɛ} ��p���鎖�ɂ��܂��B�@�����Ď��ɂ́A������x�N�g���ɒu�������܂��B ��������ƁA�� �́@�E�E�E�@�ƂȂ�A�} �͐}2 �̗l�Ȍ`�ɒu���������܂��B �l�Ԗڂ̍��W�ɑ������� �̓x�N�g���ł� �ł��B�}�Ǝ����疾�炩�ȗl�� �́@�@�̍����ł��B�@�E�E�E�@�́A���ꂼ��Ǝ��̍��W���������A�Ǝ��̕��������������Ă��܂��B�]���āA���̍��W��������Ɨ����Ă��܂��B �Ƃ��낪 �́A�����@�@�̍����ł�����A ���E ���E ������Ɨ����Ă��܂���B�̂ɁA��l�̍��W�E�������蓾�܂���B ���������A�Ɨ��������W�E�����Ƃ������̂́A���̍��W�E�����ɊW�Ȃ��Ǝ��̒l���Ƃ����̂ł��B�Ⴆ�A�@�� �@�� ���ǂ�Ȓl�ł��낤�ƊW�Ȃ��A ����Ɏ��R�ɒl���Ƃ�܂��B , �����l�ł��B �Ƃ��낪�A�@�͂����͍s���܂���B �@�� �@�̒l�ɍS������܂��B�@�E�E�E�@�̒l�����܂�A�@�̒l�͈�ɌŒ肳��܂��B������ �@�̂ǂꂩ �������A�A������ ����������܂��B�]���āA�@�Ɏ��R�x�͗L��܂���B �u�����͌������A �@�̕���ς��鎖�����ďo����ł͂Ȃ����B��������� �Ɏ��R�x�͂��鎖�ɂȂ�v�Ƃ��������������邩���m��܂���B�Ƃ��낪�A �@��ς���� O�o �Ԃ̋����������܂��̂ŁA�@���A�����ē�������܂��B �]���āA �Ɏ��R�x�͂���܂���B�@�� ����Ɨ����Ă��Ȃ��̂ł��B �̂ɁA��l�̍��W�E�������蓾�܂���B���������킯�ŁA�l�Ԗڂ̍��W�E�����͑��݂��܂���B �����Ȃ玞�Ԏ����Ƃ��ċ�Ԏ����Ƃ͕ʌɎ������l�����܂����A �ƂȂ�����ł�����b�͕ʂł��B ����͎��Ԃ̎����ł͂���܂���B�����̎����Ȃ̂ł��B ����ł��A�܂��A��s���̕������낤���Ǝv���܂��̂ŁA���x�� �����W�ɂ��Ċ��Ⴂ�̐��E����ڂ����܂��Ē������Ǝv���܂��B �@�E�E�E�@�� �@�����W�ɂ���ꍇ�A����܂ł̐�[�̍��W�����W�ɂ��Ă��܂����B�]���āA���̂����ōs���� �̍��W�� �̐�[�̍��W�A�܂�o�_�̍��W�Ƃ������ɂȂ�܂��B��������ƁA�@�̍��W�� () �Ƃ������ɂȂ�̂ł��B �����Ƃ��A����ł́A���̍��W�Ƃ̂肠�������܂���̂ŁA���̍��W���C�����ā@�E�E�E�@�Ƃ��Ēu���܂��傤�B��������ƁA�o�����X���Ƃ�ā@�E�E�E�@�Ƃ��Ă��A�������������Ȃ�܂��B�ł����� ���̎��A�n�߂āA�����̎���x�N�g���̎��Ƃ̊Ԃɐ����������ė��܂��B�@�E�E�E�@�Ƃ����l�� �����āA���ꂼ��̎����֘A���������A���̊ԂɈ�ѐ����o�ė��܂��B�@�E�E�E�@ �����W�ɂ���Ƃ́A���́A�����������������̂ł��B �ʂɁg�l������ԂɂȂ�h���ƌ����A�傻�ꂽ���ł͂���܂���ł����B�Ƃ����킯�ŁA�@�@���Ƃ� ���E ���E ������Ɨ�������4�̍��W�E�����Ƃ͂Ȃ�܂���B �@ |
|
|
��(c)�@�l�������W��z�肵�Ă��s�s������
�l�������W�ł� �� ���Ƃ��āA������p���鎖�ɂ��A���������A ��,�@ ��,�@ ���ɒ��������l�̍��W���ł����݂��邩�̔@�����o�����Ă��܂����A����͊ԈႢ�ł��B �ǂݕ��I���Θ_�̖{�ł́A�l��������͐} 4�]2�]9 �̗l�Ȍ`�ŕ\�킳��A�����w�̖{�ł͐} �̗l�Ȍ`�ŕ\�킳��܂��B�ǂ������Ԏ��ɒ�������`�Ŏ��Ԏ���������Ă��܂��B�} �ł͋�Ԏ��� �����������Ă���܂��A����́A�l�����S����}�ŕ\�킷�����o���Ȃ��̂ŁA ���ő�\���Ă��邾���ł��B ���Ȃ݂ɁA������w�ōu�`�������̐}�͐}�]�]�ł����B�����ł́A�����܂ł��A ���� ��,�@�@��,�@ ���ɒ������鎲�Ƃ��čl�����Ă��܂��B�������Ȃ���A���̐����ߒ��ɗ����߂�A�����łȂ����͖����ƂȂ�ł��傤�B����ɂ����A���ɁA��Ԃ��}4�]2�]11�̗l�ȍ��W��Ԃł����Ȃ�AO�o�Ԃ̋��� �@�����߂�ꍇ�A�s�s�����܂��B�@�E�E�E�@�ƂȂ邩��ł��B����ł͋��� �� 0 �ɂȂ��Ă��܂��܂��B�����l��������̏��ł́A���Θ_��n�������̌��̎����@�E�E�E�@����������Y��Ă��邩�̗l�ł��B ����ǂ��납�A���Θ_ (���ȏ��w�����w�ւ̓��@���x)181�łł́A��L�̓��������ā@�E�E�E�@���Ƃ��A�����W�J���āA�u�ŗL���v��A�u�l�����x�v�A�u�l�������x�v�A�u���Θ_�I�^���ʁv�A�u�Î~���ʁv�A�u�d������2�v �A�u��ʑ��Θ_�v���A�n���������_�𑱁X�Ƒn��o���Ă��܂��B �ԈႢ�ɊԈႢ���d�˂����_�̑n�o�́A���̌�����X�����Ă���̂ł����A�������́A������̗���E�W�J�ƂȂ�܂��āA��ʌ�������ɂ͂�����Ɩ���������܂��̂ŁA��߂܂��B �����A������������������̓W�J���S�Ắ@�@�� 0 �ł��鎖�����悤�Ƃ��鎖���痈����̂ł��B �����āA�����Ǝn���̈������ɂ́A���́@�@�����Θ_�̈�ԍŏ��ɏo�ė��āA���ɂ��\���m���̖����w���Ɍ��������ς�A���t���Ă��鎖�ł��B ���ȏ�( �w�͊w�x �����N�� ) �ł́u�����x�s�ς̌����@�E�E�E�@�Ƃ������B�@ �C�@�͊����n�łǂ��炩�猩�Ă������͈��̑��x�œ�������A�@�ɑ��Ĉ�l�Ȓ����^���́A �ɑ��Ă���l�Ȓ����^���łȂ���Ȃ�Ȃ��B �����x�s�ς̌����ɂ��A�@�E�E�E�@�Ȃ�@�@ �ł��̋t�����藧�B�]���ā@�@�Ɓ@�@�Ƃ̊W�́@�E�E�E�@�̌`�łȂ���Ȃ�Ȃ��B ���ΐ������ɂ��� �ɑ��Đ��藧���� �ɑ��Ă����藧���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����@�E�E�E�@�łȂ���Ȃ�Ȃ��B����@�E�E�E�@�܂�Ak �́E�E�E�E�萔�� �{1���Ƃ邩�A�|1���Ƃ邩�ł��鎖���킩��B v ��0 �̏ꍇ���l����@�@���@ �ł��邩�� k ��1�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�E�E�E�v���Ƃ���Ă��܂��B �u��������Ă���̂��A�ǂ�������Ȃ��v�Ǝv������������ł��傤���A���Ȃ��Ƃ��u �� ���K������ 0 �Ƃ͌���Ȃ��v�Ƃ����O��Řb��i�߂Ă��鎖�����͂�������ɂȂ�Ǝv���܂��B �@�� �� 0 �Ȃ�A���̗l�ȏ�����A�����ɂ����������Ș_�́A�ŏ�����K�v����܂���B���� �� �� 0 �Ȃ̂ł����炱�̗l�Ș_�͈Ӗ�����܂���B�������Ȃ���A�������鎖�ɂ���ĉ����m��Ȃ��w���B�́A�ŏ��Ɂ@�E�E�E�@�� 0 �Ƃ͌���Ȃ��A�Ƃ�������ς�^�����A��ɁA�l��������̏��ɗ������A�� 0 �ł��鎖�ӎ��ɔے肵�u����͎l�����Ȃ̂��A�O�����Ƃ͈Ⴄ�v�ȂǂƂ����g���`���J���Ȏ�������Ă��܂��܂��B ���ہA���ȏ���s�̖̂{�ł��A���̎�̋^������������ȏ��ł́u����͎O�����Ƃ͈Ⴄ�̂��v�ƓB���h���A����ȏ�^����������܂Ȃ��l�ɂ��Ă��镨�𑽁X�������܂��B �����Ȃ�ƁA���Θ_�̌��͉i�v�ɐ����܂���B�u�����A���������H�v�Ǝv���Ă��A�u����A�������Ԉ���Ă���ɈႢ�Ȃ��v�ƋO���C�����Ă��܂��܂��B ���Θ_�̌��́A��x���̎����Ō������Ȃ���Δ���܂���B��{�ɗ����A��A�f�l�ɂ�������l�ɂƎ������ݍӂ��Č����������A�n�߂Ĕ��鎖�ł��B���Θ_�Ƃ́A���́A�������A���������Ȃ��̂������̂ł��B�w�ǂ��A�A�C���V���^�C���̑��Ƃ���Ɗ��Ⴂ�A�������Ƃ̍����A�����͎v�����݂��琬�藧���Ă��܂��B ���x�Ȑ��w���g���Ă���ׁA�����̐l�́A����ɘf�킳��A���������f���炵�����_�ł��邩�̔@�����o�������Ă��܂����A���́A�Ƃ�ł��Ȃ��㕨�������̂ł��B ���܂��ɃA�C���V���^�C���́A�o���オ�������̈Ӗ��𐳂����������Ă��܂���B�Ԉ���ĉ��߂��Ă��܂�����A�������瓱����鏊�̗��_�́A���Ƃ��Ƃ��A�Ƃ�ł��Ȃ������ւƍs���Ă��܂��܂��B ���Θ_�Ƃ́A����A�r�e�f��̗l�ȕ��ł��B�f���̒��ł͐l�͎��R�ɋ���ׂ܂����A�ߋ��̐��E�ւ��s���܂��B�f���̒��ł́A�n��̕����@���⎞�Ԃ̏������������ł�����̐��E���n���̂ł��B ����Ɠ����ŁA������Ǝ��Ă��邾���Ŗ��W�̎���p���A���[�������ł��Ή��ł��o����ł��傤�B �������A����͌����̐��E�Ƃ͊W����܂���B���@�[�`�����E���A���e�B�[�̐��E�̘b�ł��B���Θ_�Ƃ́A���́A���z�����̐��E�̘b�������̂ł��B �Ȃ��A���������Ă鎖�́g���Θ_�̐����̉��߂��Ԉ���Ă���h�Ƃ����������ł��āA�ʂɁg���Θ_���\�z���Ă���悤�Ȍ��ہh�܂ő��݂��Ȃ��A�ƒf�����Ă���킯�ł͂���܂���B�F���͍L���ł�����A�������邩����܂���B�����A���ɁA���Θ_�̗\�z����l�Ȍ��ۂ����݂����Ƃ��Ă��A���Θ_�������������Ƃ͎v��Ȃ������ǂ��ł��傤�B����́A�Ԉ���Ă��܂�����B���̎��͂��̎��ŁA���̌��ۂ��ϑ������͂��āA��������@���������o���悢�����ł��B���ꂪ�Ȋw�Ƃ������ł��傤�B�@ �@ |
|
| ���܁@�g�������ؖ��������Θ_�̐������h�ւ̈٘_ | |
| ��(��)�@�d�q��������������Ă����������Ȃ��@ | |
|
�u�����Ȃ镨�����������Ȃ��v�Ƃ������̐��������ؖ������Ƃ��āA�悭�A�d�q�̉��������̘b���������܂��B����́A�g�d�q�����d���ʼn������Ă��A�����ɋ߂Â��ɂ�A���x�͉����ƂȂ�A������d�����グ�Ă���������(��)���Ȃ��Ȃ�h�Ƃ����b�ł��B���̎����ɂ��g���ΐ����_�̐��������ؖ����ꂽ�h�Ƃ悭�����Ă��܂��B
�������A����ɂ��ẮA���͈٘_������܂��B�d�q�������u�̎d�g�݂��ǂ��Ȃ��Ă���̂��́A�m��܂��A�d���ʼn���������藘���Ȃ��ē��R�Ǝv���܂��B���Θ_�͊W�Ȃ��ł��傤�B ���b�g�͕���葬������܂���(���͂ۗ̕L�⒪�̗��ꓙ�͖������܂�)�d�q�͓d���ɂ���ĉ�������܂��B�������āA�d���͂̓`�d���x�͌����ł��B�d�ɂ���o��d���̔g�������œ`���܂��B�����A�d�q�������ő����Ă����Ȃ�A���̓d�q�ɂƂ��ēd���̔g(��)�͑��݂��Ȃ������R�ƂȂ�܂��B ���Ɠ������x�ő����Ă���҂ɂ́A�������݂��Ȃ��̂Ɠ��������ł��B�]���āA�d���̔g�͓d�q�ɂ͉��̉e�����^�����܂���B���x�ɗ����������āA�n�߂ė͓͂`���̂ł��B�������傫����Α傫���قǁA�傫�ȗ͂��`���܂��B�Ƃ����킯�ŁA�d�q�������ɋ߂Â��ɂ�ĉ����������Ȃ��Ȃ�͓̂��R�ł��B ���������Ɓu�d���̔g�Ƃ͉������B�d��(�d��)�̏ꂾ�B�g�Ȃǖ����v�ƌ���ꂻ���ł��̂Ő������܂��B �g�Ƃ����\�����s�K�Ȃ�s��̗���t�̗l�ȕ��ƍl���ĉ������B�d�ɂɓd�C������O�ɂ́A�d�ɂ̎��͂ɓd��(�d��)�̏�͑��݂��Ă��܂���B�d�ɂɓd�C������ƁA�d�ɂ̎���ɓd��(�d��)�̏ꂪ�������A�`���a���b���c�̏��Ŋg�����čs���܂��B����͌����Ŗ����̔ޕ��ւƊg�����čs���܂��B���̌�A�d�C���ƁA�d�ɂ���d���������A�d�ʂ̖�����Ԃ��`���a���b���c�̏��Ŋg�����čs���܂��B ���̎��ɁA�܂��d�C������ƁA���͂ɓd�ʂ̗L���Ԃ��g�����čs���A��Ɠd�ʂ̖�����Ԃ��g�����čs���܂��B ���ꂪ�g�ł��B�d�C�������ςȂ��̏�Ԃł́A�d�ʂ̗L�閳���̕ϓ��͗L��܂���B���������A�����d�ʂ̗���́A��̗l�ɁA���X�Ɠd�ɂ���Ԃɗ���o���Ă���̂ł��B�����d���̔g�Ɛ\���グ���̂ł��B �d�ʂ̏�(�d��)�Ȃǂƌ����ƁA��Ԃ��̕����d�C��ттĂ��āA���ꂪ�Œ肳��Ă��邩�̔@�����������ł����A�����ł͂���܂���B��̓d�ʂ��K�肵�Ă���g�͏�Ɉړ����Ă���̂ł��B��ɐV�����g���d�ɂ��痬��o�āA�����̔ޕ��ւƈړ����Ă��܂��B���x�A��̗���̗l�ɁB�����u�s���̗͂���͐₦�����āA���������̐��ɔv�ƌ����A����ł��B�����āA���̔g���̓`�d���x�������Ȃ̂ł��B ���ɁA�����ŁA�d���̔g�̗�����A���q�̗���Ɍ����ĂĂ݂܂��傤�B���ۂɂ́A�d��͕����ł͂���܂���̂ŁA�������������Ă͖��ł����A�ڂ��Ԃ��ĉ������B�d�q���Î~���Ă��鎞�ɁA�d�ɂ��痬��o�ēd�q�ɓ����闱�q�̗ʂ́A��b�Ԃ� 30������ �̕��̗ʂ�����܂��B�Ƃ���ŁA�����A�d�q���b�� 29������ �̑��x�ő����Ă�����ǂ��Ȃ�ł��傤���B���̏ꍇ�A�d�q�Ɠd���̔g�Ƃ̑��Α��x�͕b�� 1������ �ł�����A�d�q�ɓ����闱�q�̗ʂ́A��b�Ԃ� 1������ �̕��̗ʂ�������܂���B����́A�Î~���Ă��鎞�� 30 ����1�ł��B �܂�A�d�q���b�� 29������ �ő���A������G�l���M�[�́A�Î~���Ă��鎞�� 30 ����1�Ɍ���킯�ł��B�d�q�������ɋ߂Â��߂Â����A�d�q�ɓ����闱�q�̗ʂ͌���A�����ł�0�ɂȂ�܂��B���̗��q�Ƃ����T�O���A�G�l���M�[�Ƃ����T�O�ɒu��������A�����Ƃ��鎖�͂�������ɂȂ�Ǝv���܂��B�v����ɁA�d�q�������ɋ߂Â��߂Â����A�d�q���猩�����̓d���̔g�͊ԉ��т��Ă��܂��A���̎����Ă���G�l���M�[�����܂��ė���̂ł��B �]���āA�d�q��������G�l���M�[�������Ă��܂��A�����ł�0�ɂȂ�܂��B������A�d�q�͌����ɋ߂Â��ɂ�����������Ȃ��Ȃ�킯�ł��B������d�����グ�悤�Ɩ��ʂȎ��ł��B �����ł�����x�A�d�q�̉����̘b�ɖ߂�܂��傤�B �����A�d�q�������Ŕ��ł����Ȃ�A�d���͓͂d�q�ɍ�p���鎖�͏o���܂���B�d�q���猩��ƁA��ɂ́A�d���̔g�ȂǑ��݂��Ȃ�����ł��B���Ɠ������x�ő����Ă���҂ɂ́A�������݂��Ȃ��̂Ɠ��������ł��B���Ɠ������x�Ń��b�g���������Ȃ�A���̓��b�g�ɗ͂�^�����܂���B���x�ɗ����������Ă����A�͓͂`���̂ł��B�d�q�͑��x�������ɋ߂Â��ɂ�A�d���̔g������G�l���M�[������A�����ł�0�ɂȂ�܂��B �]���āA�d�q�͌����ȏ�ɂ͐�ɉ����o���܂���B������d�����グ�悤�Ɩ��ʂȎ��ł��B�܂��t�ɁA�d���̔g�̒��ɁA�d�q�������ȏ�̑����œ˂�����ōs�����Ȃ�A�d���̔g�̗���́A�t��(�u���[�L)�ƂȂ�܂��̂ŁA�d�q�͗���Ɠ��������A�܂�A�����܂Ō�����������ł��傤�B �]���āA�d�q�́A�d���ɂ��������u���g������A��Ɍ��������܂���B�����Ƃ��A�d�ɂ��d�q�������Œǂ�������l�ȑ��u�ł��o����Θb�͕ʂł����B �Ƃ������A���������킯�ŁA���̘b�͑��Θ_�̐��������ؖ�����̂ɂ͖𗧂��܂���B�@ |
|
| ��(��)�@���͏d�͂ŋȂ���̂��H | |
| ��(1)�@���͏d�͂ŋȂ���Ƃ������ɑ���٘_�@ | |
|
���Ɂg���Θ_�̐��������ؖ�����ޗ��h�Ƃ��āg�d�̓����Y�h�Ƃ������̂�����܂��B����́A���̌��ɍ݂�ʂ̐��̌����A�O�̐��̏d�͂ɂ���ċȂ����A�����O��Ɍ�����Ƃ����b�ł��B�V�̎ʐ^�̖{�ɂ́A���X�A���������̂��ڂ��Ă��܂��B���̎ʐ^�̉��߂��������̂��ǂ����A���ɂ͔�(�킩)��܂��A�g�����d�͂ɂ���ċȂ���h�Ƃ����l���ɂ͎^���ł����˂܂��B
�d�͂Ƃ����͕̂����Ԃɓ����͂ł��B���m�ɂ́A���ʂƎ��ʂ̊Ԃɓ����͂ł��B���͎��ʂ������Ă��܂���B�ǂ�����āA�d�͂̉e��������̂ł��傤���B�ƌ����Ă��A�s���Ɨ����Ȃ����������ł��傤�B�܂��͓d�C�͂⎥�C�͂��Q�l�ɂ��čl���Č��܂��傤�B�d�C�ɂ� �{ �� �| ������܂��B�d�C�͂Ƃ� �{ ��| �Ȃǂ̓d�C��тт����̓��m�̊Ԃœ����͂ł��B���m�ɂ͓d�Ԃɓ����͂ł��B �{ �� �{ ������ �| �� �| �ȂǓ��ɂ̓d�C��тт����q�͔������A�{ �� �| �Ȃǔ��̓d�C��тт����q�͈��������܂��B ���Ɏ��͂ł����A��������C��ттĂ�����̓��m�̊Ԃœ����͂ł��B���C���Ȃ���Η͓͂����܂���B �d�C�͓͂d�Ԃɓ����͂ł����A���͎͂��Ԃɓ����͂ł��B�����̗͂́A���̂��̂ɂ͍�p���܂���B ���l�ɂ��čl����ƁA�d�͎͂��ʊԂɓ����͂ł�����A���̗͎͂��ʈȊO�̂��̂ɂ͓����܂���B ���āA�����Ŗ{��ɖ߂�܂��B�s�����d�͂ŋȂ���t�Ƃ������ł����A���������Ɍ��͎��ʂ������Ă��܂���B�����ł͂Ȃ�����ł��B ���͏d�͂Ɍĉ����鐬���������Ă��܂���B�ǂ�����āA�d�͂̉e��������̂ł��傤���B �d�͂̎��́@�E�E�E�@�Ƃ������ł��B������M�̎��ʂƂ��Am�̈��͂ɂЂ���鏬���̂̎��ʂƂ��čl���Ă݂܂��傤�B���͎��ʂ������Ă��܂��� m = 0 �ł��B��������ƌv�Z����� F �� 0 �ƂȂ�A���҂̊Ԃɂ͉��̗͂������Ȃ��Ȃ�܂��B�܂�d�͂̉e���Ȃǎl�������Ȃ�̂ł��B �����Ƃ��u���̎��͌Â�����ɍ��ꂽ���ŁA���S�Ƃ͌���Ȃ��B�����厖�Ȏ��������Ƃ��Ă��邩���m��Ȃ��v�ƍl�������������ł��傤�B�@�����A���ɂ����������Ƃ��Ă��A���A�ʂɖ�肪���݂��܂��B ����́A��p�̕����ł��B �d�͂͏�ɕ����̒��S�Ɍ������ē����A���͔����������ɊO�Ɍ������Ĕ��U���čs���܂��B����͏d�͂Ƃ͐����̕����ł��B�@�E�E�E�@���̗l�ɍ�p�̕��������Ȃ̂ɁA�ǂ����ās�����d�͂ɂ���ċȂ���t���ƌ�����̂ł��傤���B���ɂ����A�d�͂Ɍĉ����鐬�����L��̂Ȃ�A���̐����ǂ�������p���āA�����Ïk���ʼn����Ă��悳�����ȕ��ł����A���́A�܂��A���̗l�Ȍ���������������܂���B�܂��A�����n�ʂɍ~��ς����Ă��悳�����ȕ��ł����A������������͂���܂���B���̒m���Ă�����́A��ɊO�Ɍ������Ĕ��U���Ă��������ł��B�����Ƃ��A�����Ɍ������ė��������A���̕����Ɏ�荞�܂�G�l���M�[�ɕϊ�����邱�Ƃ͂���܂����A����͏d�͂Ƃ͕ʂ̘b�ł��B �Ƃ���ŁA�s�����d�͂ɂ���ċȂ���t���Ƃ����l�����́A��̂ǂ����琶�܂ꂽ�̂ł��傤���B���Θ_�ł́s�����d�͂ɂ���ċȂ���t�Ƃ����l�����̐����Ƃ��āA�悭�G���x�[�^�[�̘b���g���Ă��܂��B������A���Ԃ�A�G���x�[�^�[����Ȃ̂ł��傤�B�����ŁA�����ł́A���̘b�𗘗p���Ȃ���A����ɂ��Ă̈٘_���q�ׂĂ݂鎖�ɂ��܂��B �G���x�[�^�[�����������痎������ƁA���ɂ���l�͖��d�͂̉F����Ԃɂ���l�ȍ��o���܂��B�y���⌮�����O�ɏo���Ă����ɗ����܂���B�Ȃ��Ȃ�G���x�[�^�[���l���y�����������������x�ŗ������Ă��邩��ł��B�t�ɁA���d�͂̉F����Ԃɕ����Ă���G���x�[�^�[�������x�ňȂĈ����g����ꂽ�Ȃ�A���ɂ���l�́A���͂�������Ə��Ɉ��������A�܂�ő�n�̏�ɂł������Ă��邩�̗l�ȍ��o���鎖�ł��傤�B �����珰�������Ĕ�яオ���Ă��A������������鑬�x�Œǂ������ė��đ���ߑ�����̂ŁA���ɂ���l�͈��͂ɂ���Ĉ����߂��ꂽ���̗l�ȍ��o���܂��B���̎��A�G���x�[�^�[�̕Е��̕ǂ̌������u������������ŁA���Α��̕ǂɓ��������Ƃ��܂��悤�B ���͂��̐��������̂ł����A����ł��G���x�[�^�[���A�ق�̏����͏㏸���Ă��܂�����A���͂ق�̏����ł������������ʒu�ɓ�����܂��B���̎��A���ɂ����l�ɂ́A��u�A�����d�͂ŋȂ������l�Ɍ�����ł��傤�B�G���x�[�^�[�̒��ɂ���l�ɂ́A�d�͂Ɖ����x�̋�ʂ͂��܂���B �ꉞ�A��T�̖{�́A���������������Ȃ���Ă��܂��B�m���ɁA���̏ꍇ�A�d�͂Ɖ����x�̋�ʂ͂��܂���B�ł��A������ƌ����āA�d�͂Ɖ����x���S�p�[�Z���g�������ƁA�ǂ����Č�����̂ł��傤���B�����������Ă��邾���ňႤ���͑�R����܂��B�����x�ł����ď㏸����G���x�[�^�[�̒��ɍ����������A���ɂ���l���猩�āA�Ȃ������l�Ɍ������Ƃ��Ă��A���ꂾ���Łs�����d�͂ŋȂ���t�Ƃ͒f���ł��܂���B �����Ŏ��́A�����Ƃ͌���Ȃ��Ƃ�����������܂��B�@ |
|
| ��(2)�@�ʂȗ� | |
|
��(a)�@�F���X�e�[�V�����ɍ������ތ�
�����ɁA�F����Ԃɕ����сA���]�ɂ���ďd�͂���肾���Ă���F���X�e�[�V����������Ƃ��܂��B�F���X�e�[�V�����͎��]���Ă��܂��̂ŁA���ɂ���l�͉��S�͂ɂ���ĊO�ǂɉ��������A�d�͂������Ă��܂��B���鎞�A�F���X�e�[�V�����̓V��̌������u�A������������ŗ����Ƃ��܂��傤�B���͂��̂����������̂ł����A����ł��A�F���X�e�[�V�����������͓����Ă��܂�����A���́A�ق�̏����ł����A��]�����Ɣ��̕����ɂ��ꂽ�ʒu�ɓ�����܂��B ���̎��A���ɂ���l�ɂ́A������u�Ȃ������l�Ɍ�����ł��傤�B�������Ȃ���A���̋Ȃ����������͏d�͂̕����Ƃ͉��̊W������܂���B��]�����Ɣ��̕����ɂ��ꂽ�����ł��B�ƌ����Ă��A�} �ł́g�����Ȃ���̂��߂ɍs�������Ȃ̂��A�悭����Ȃ��h�ł��傤�B������ �} �ŋ�̓I�Ɏ����܂��B �@�E�E�E�@���̗l�ɋȂ���܂��B�@ |
|
|
��(b)�@�l�H�q���̏ꍇ
���ɁA�l�H�q���̒��ɍ������ތ��ōl���Ă݂܂��傤�B�l�H�q���̒��͖��d�͂ł��B���鎞�A�l�H�q���̑�����A��u�A������������ŁA���Α��̕ǂɓ��������Ƃ��܂��傤�B���́A���̂����������̂ł����A����ł��A�q���������͓����Ă��܂��̂ŁA���͐}5�]12�̗l�ɁA�i�s�����Ɣ��̕����ɂ��ꂽ�ʒu�ɓ�����܂��B���̎��A���ɂ���l�ɂ́A������u�Ȃ������l�Ɍ����܂��B�������A�q���̒��͖��d�͂ł��B ���̏ꍇ�A���͖��d�͂ł��Ȃ��鎖�ɂȂ�܂��B�@ |
|
| ��(3)�@�d�͂Ɖ����x�͓������H�@ | |
|
���ɁA�����ŁA������x�G���x�[�^�[�̘b�ɖ߂�܂��傤�B�u�d�͂Ɖ����x�Ƃ͋�ʂ����Ȃ��v�Ƃ̎��ł����A�ʂ��āA�����Ȃ̂ł��傤���B�����ŁA���̃G���x�[�^�[�̘b���Č������Ă݂܂��傤�B
�s�����x�ňȂĈ����g������G���x�[�^�[�̒��ł́A�l�͔�яオ���Ă��A������������鑬�x�Œǂ������ė���̂ŁA���͂������ɕ߂܂�A���͂ň����߂��ꂽ�l�ȍ��o����t�Ƃ̎��ł����A�ʂ��Ă��̎��A�{���ɏd�͂ɂ�闎���̗l�Ȋ��o���Ă���̂ł��傤���B��яオ�����l�Ԃ́A�����̖@���ł܂��������ł��܂��B�������G���x�[�^�[�̏����A�����Ƒ������x�Œǂ��������ł��B������������A�P�ɁA�Ǔ˂���Ă��邾���̊��o�ł͂Ȃ��ł��傤���B �����Ŏ��́A���������v�l���������Ă݂܂��傤�B�����Ƀh�[��������̋���ȃG���x�[�^�[������Ƃ��܂��B���̃G���x�[�^�[�͖��d�͂̉F����Ԃɕ�����ł��܂��B�����āA���̃G���x�[�^�[�������x�ňȂĈ����g�����Ƃ��܂��傤�B���ł͏d�͂������Ă���Ɖ��肵�܂��B���ɁA���̃G���x�[�^�[�̒��Ŗ���˂���������Ă݂܂��傤�B�G���x�[�^�[�͓V��͍������ǂ������̂ŁA��͓V��ɂ��ǂɂ������炸�ɗ����ė��܂��B�Ƃ���ŁA���̖�́A�n��Ŏ˂����Ɠ����悤�ȗ�����������ł��傤���B���Ԃ�@���Ȃ��ł��傤�B �n��̏ꍇ�A�˂���͓r����������]�������āA��̐�[�����Ɍ����ė����ė��܂��B�Ƃ��낪�A�G���x�[�^�[�̒��Ŏ˂���͕����]�������鎖�Ȃ��A�H�������̂܂ܗ����ė��锤�ł��B�Ȃ��Ȃ�A��͂܂��������ł��邾���ŁA�ʂɗ����Ă���킯�ł͂Ȃ�����ł��B��܂��������ł���Ƃ�����A�G���x�[�^�[�̏���������鑬�x�Œǂ������ė��āA��̉H���ɒǂ��������ł��B�]���Ė�̐�[�����ɂȂ��ė����ė��鎖�͂���܂���B���̃G���x�[�^�[�̒��ł̖�́A�d�͂ɂ���ė����Ă���̂ł͂Ȃ��A�P�ɁA���ɒǂ�����Ă��邾���ł�����B�d�͂̂��钆�Ŏ˂�ꂽ��́A�r���ŕ����]�������Đ�[�����Ɍ����ė����ė��܂����A�d�͂̂Ȃ��G���x�[�^�[�̒��ł́A��͕����]�����鎖�Ȃ��H�������̂܂܁A���ɕߑ�����܂��B �s�n��Ŏ˂�ꂽ��d�͂ɂ�藎�����鎖�t�Ɓs�����x�ňȂĈ����g������G���x�[�^�[�̒��Ŏ˂�ꂽ��A�G���x�[�^�[�̏��ɕߑ�����鎖�t�Ƃ̊Ԃɂ́A���̗l�ȈႢ������̂ł��B�n�ォ��ˏo���ꂽ��́A���͂ɂ���Ĉ����߂���܂��B���̎��A��̏d�S�ɋ߂���[�����ɂȂ��ė����ė��܂��B�d�͂̏ꍇ�A�ˏo�͂ƈ��͂Ƃ̗͊W�ł����������ۂ��N���܂����A�͊W�̂Ȃ��G���x�[�^�[�̒��ł́A���̗l�Ȍ��ۂ͋N���Ȃ��ł��傤�B�P�ɁA�G���x�[�^�[�̏��ɁA��ǂ�����邾���ł�����B�]���āA�������A�d�͂Ɖ����x�Ƃ͎��Ă���悤�ňႤ�̂��Ƃ������������ė��܂��B �����������Ă��邩��ƌ����āA�����Ƃ͌���܂���B�@ |
|
| ��(4)�@�܂Ƃ߁@ | |
|
�����̗�ł͂����肷�鎖�́A���̋Ȃ���́g�������̏d�́h�̕����Ƃ͉��̊W�������Ƃ������ł��B
�����܂������i��ł��鏊���A���̂������x�܂��͉~�^���ł����ĉ������A���ׁ̈A���̂̒��ɂ���l�ɂ́A�����Ȃ������l�Ɍ������A�����A���ꂾ���̎��ł��B�ʂɁA�d�͂ŋȂ������킯�ł͂���܂���B�@�G���x�[�^�[�̏ꍇ�A�g�������̏d�́h�Ɓg���̋Ȃ���h�̕�������v���Ă��܂�����A�����������Ȃ������ł��B�����獬������̂ł��B ���������킯�ŁA�s�����d�͂ŋȂ���t�Ƃ��������؋��s�\���ƂȂ�܂��B�@ |
|
| ���Z�@�I���Ɂ@ | |
|
���̗l�ɁA���Θ_�Ƃ́A���Ɍ��̑������Ȃ̂ł��A���Ɍ����d�˂����_��n���Ă��܂��B�قƂ�ǂ́A�A�C���V���^�C���̎v�����݂ƍ����E�����_���琬�藧���Ă��܂��B�@ �@ |
|
| �����ꑊ�ΐ����_�̃~�X | |
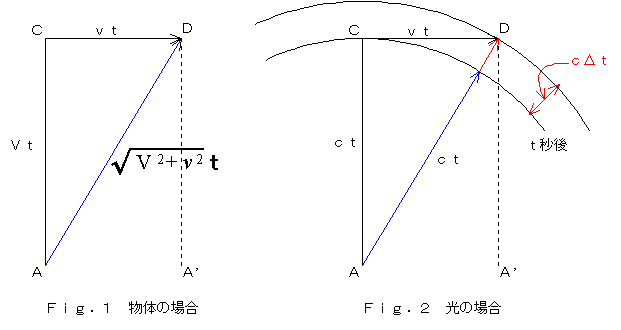 |
|
|
�����ꑊ�ΐ����_�̃~�X�̏o���_
�A�C���V���^�C���̍l�������Ƃ�}�Ŏ����āA���ꑊ�ΐ����_�̃~�X���w�E���܂��傤�B ��}�̂e�����D1�͕��̂̏ꍇ�ŁA�e�����D2�͌��̏ꍇ�ł��B ����������ʂ̎��ۂƂ��āA�ˑ�`�b�͐}�ʼnE�����ɑ��x���œ��������^�����Ă��܂��B���b��ɂ`�f�c�̈ʒu�ɂ��܂��B ���܁A���̂��`����b�ɓ�����ƁA�ˑ�̏�ɋ���ϑ��҂́u�`����b�ɕ��͔̂��ł������v�ƕ��܂��B���ꂪ20���I�����w����ё��Θ_�̌����u���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʏo���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B ����A��������ʏォ��ϑ�����ƁA���̂͂`����c�ɔ��ōs���܂��B���ꂪ�K�����I�̑��ΐ������ł��B�� �b��̈ʒu�������Ă���̂ŁA���̎O�p�`�͂ǂ̒������� �b��ƂȂ��Ă��āA���̖���������܂���B ���͂e�����D2�ł��B 1�@�`����b�Ɍ����ă��[�U�[�p���X�˂���ƁA�b�ɂ͓��B���܂���B�Ȃ��Ȃ�ˑ�`�b�͓����Ă��邩��ł��B�������A�A�C���V���^�C���́u���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʂł��Ȃ��v�Ƃ��Ă���̂ŁA�u�b�ɍs���v�Ƃ��Ă��܂��B�����ł��łɃA�C���V���^�C���͊Ԉ���Ă��܂��B 2�@�������A���ʏォ��ϑ�����ƁA�u�`����c�ɍs���v�Ƃ��Ă��܂��B�A�C���V���^�C���́u���ׂĂ̕����@���͓����ł���v�ƍl��������ł��B������u�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ������v�ƌ����܂��B�K�����I�̑��ΐ����������ɂ܂Ŋg���������̂ł��B�������A���[�U�[���͂`����c�ɂ͔��ōs���܂���B 3�@�}�C�P���\���E���[���[�̎����Ŏg�������͋��ʔg�ł��B���������āA���̌��͂c�ɓ͂��܂��B�������A�b�ɓ͂����ƁA�c�ɓ͂����͈قȂ���������̂ł��B���R���ԓI�ɂ��قȂ���̂ł��B �Ƃ��낪�A�C���V���^�C���́A�u���b��Ɍ��͂c�ɓ͂��v�Ƃ��܂����B���ꂪ�L���ȁu�����x�s�ς̌����v�ƌĂ����̂ł��B���������Ȃ�傫���ł��낤�Ƃ��W�Ȃ��A�`�c������ �� �Ƃ��Ă��܂��B �ȏ�ł�������̂悤�ɁA�e�����D1�Ƃe�����D2�͈قȂ镨�����ۂł���ɂ��ւ�炸�A������u�����v�Ƃ��Đ����W�J���āA���܂��܂̖��������ׂāu���ԁv��ς�����A�u�����v��ς����肵�Ē�������킹�Ă������̂����ꑊ�ΐ����_�Ȃ̂ł��B ���ꑊ�ΐ����_�̓��e�͋ߎ��I�ɂ̓j���[�g���͊w�ł��̂ŁA�������悤�ȍ��o�����Ă��܂����A���̂��{���͊Ԉ�������_�ł��B �������ɂ���āu���ԁv��ς�����A�u�����v��ς����肷��͕̂����w�ł͂Ȃ����Ƃ�21���I�̐l�X�ɓ`���܂��B �� �u���̃A�C���V���^�C�����܂����Ԉ���Ă������Ȃ�ĐM�����Ȃ��B�@�E�E�E�@�v�@��������Ɣq�ǂ��܂��ƁA��͂荪�{�I�ȕ����A���Ȃ킿�u���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʂł��Ȃ��v�Ƃ���20���I�����w�̍������Ȃ��l���ɌŎ����Ă��邱�Ƃ��悭������܂����B20���I�G���N�g���j�N�X�ł́u��ʂł���v�ƂȂ��Ă���̂ŁA���̕ӂ�������x�ڂ��������������܂��B �� �܂���}�e�����D1���̂̏ꍇ����������l���Ă��������B �`����b�Ɍ����ĕ��̂𓊂����ꍇ�A�������ꏊ�͂`�ł��ˁB ���b��Ɏ�����ꏊ�͂ǂ��ł����H �ˑ��̊ϑ��҂́u�b���v�Ɠ����܂��B��n(�����ł͎���)���`�����ϑ��҂́u�c���v�Ɠ����܂��B ���Ȃ킿�A�`�b�Ƃ����ˑ��̊ϑ��҂͎��������������Ă��邩�����ĂȂ����͖��W�Ɂu���̂͂`����b�ɔ��ł������v�ƕ��܂��B ���̂��Ƃ�(�������d�v�ł�)�A�`�f����c�ɍs�������ƂƓ����I�ɓ����ł��B �Ȃ��Ȃ�g�`�Ƃ����ꏊ�h�͂��b��͂`�f�ɂ���̂�����B�܂��g�b�Ƃ����ꏊ�h�͂��b��ɂ͂c�ɂ���̂�����B ���ꂪ20���I�����w�́u���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʏo���Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B �`�ŕ��̂𓊂������Ƃ͎����Ȃ̂ł����A�`�f�œ����Ăc�Ŏ�������ƂƉ���ς��Ȃ����ۂł��B���ꂪ���x���q�ׂĂ���u���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʏo���Ȃ��v�Ƃ������ƂȂ̂ł��B �g���́h�̏ꍇ�́g���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʏo���Ȃ��h�ł�����A����͐������ł��B20���I�����w�͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ�K�����I�̑��ΐ������ł��B ���������������ɂ܂Ŋg�������̂��u�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�v�ł��B ���̂e�����D3���̏ꍇ�U�������ɂȂ�ƁA���ꑊ�ΐ����_�̊ԈႢ����ڗđR���Ǝv���܂��B �`�|�C���g�ŋ��ʔg�˂��āA���b���(������x�����܂��傤�A�g���b��́h)�g�ʂ͂ǂ��ł����H �g��1�ł����H�g��3�ł����H ���b��Ɂg�����Ƃ������́h���`�f�ɂ��邩��ƌ����Ĕg�ʂ́u�g��3�v�ɂȂ�̂ł����H�u�������B�g��3���v�Ƃ��Ă���̂��A�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ������ƌĂ�鉼�݂ł��B�Ȃ��A�C���V���^�C���������l�������́A���x���q�ׂĂ���悤�Ɂu���������^���͐�ΐÎ~�Ƌ�ʏo���Ȃ��v�Ƃ��Ă��邩��ł��B�g���́h�Ɓg���h���悤�Ɉ����Ă���̂ł��B ����Ɂu�ˑ�`�b�n�������x�͂��v�A�u��`������n(�����ł͎���)�ł������x�͂��v�Ƃ��Ă��܂��B���ꂪ�L���Ȍ����x�s�ς̌����ƌĂ�鉼�݂ł��B ������A(������x�����܂��傤�A�g������h)�A�`�b���`�f�c�������ł���Ɠ����ɁA�����x���ŋ��ʔg���`����g�c�h�ɂ��b��ɓ͂��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��킯�ł�(�g�b�v�y�[�W�̗L���Ȃe�����D1�u�k�A�����A�����A���̒��p�O�p�`�v�Q��)�B�g�͂������Ȃ����̂��͂��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���h�̂ł��B ���̖�����邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��u���ԁv��ς��Ȃ���Ȃ�܂���B�u�ˑ�`�b�n�ƒ�`������n�ł͎��Ԃ��Ⴄ�v�ƁB����� �� �Ƃ��f�Ɏ��Ԃ̗����ς��āg�͂������Ȃ�����͂��Ă��邱�Ƃɂ����h�̂ł��B �܂��́u�^���n�̋�Ԃ͏k�ނ̂��v�ƁB ���ꂪ�u�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�v�ł��B 20���I�G���N�g���j�N�X�ł́A�g��1�C�g��2�C�g��3�̋�ʂ��o���܂��B�u��ʏo���Ȃ��v�Ȃǂƌ����ƁA�G���N�g���j�N�X�Z�p�҂ɓ{���܂��B ���{�I�ɊԈ�������z�𐳂������Ƃɂ��āA�g���ԁh��ς�����g�����h��ς����肵�Ē�������킹�ăj���[�g���͊w�����������Ă����̂����ꑊ�ΐ����_�ł��B �@ �u���ԁv�͂ǂ̌n�������ŁA�u���Ό����x�v������n�̓����ŕς��Ƃ����̂��A�����������w�ł��傤�B�@ |
|
|
���n���X�E���C�w���o�b�n
��L�����ŁA�g���ۂɂ͓͂��ĂȂ����̂��͂��Ă��邱�ƂɂȂ��Ă���h���Ƃ���������ɂȂ����ł��傤���B ���������~�X��������x�����̒��ň�ԑ������x�ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B1�i�m�b�ł�������30���������i�܂Ȃ��X�s�[�h�����̒��̍ō����x���ƋK�肷�邱�ƂɂȂ�̂ł��B �����ŁA�w���ΐ����_�̒a���x(�n���X�E���C�w���o�b�n��)�̒�����A��������L�q�����Љ�Ă����܂��傤�B���̃n���X�E���C�w���o�b�n�̓A�C���V���^�C���ɋ��������u��5�l�̂�����1�l�����������ł��B�����������m��܂��A�������ł������A�C���V���^�C���͊w�Z�̐搶�ɂȂ肽����S�ŁA��̈�ʑ��ΐ����_������������ł��ˁB �w��̈قȂ����n�_�`�A�a������Ƃ���B���M����12�F00�ɂ`���甭�˂����Ƃ���B���̐M���͂a�Ŕ��˂���āA�`��12�F10�ɖ߂��Ă���Ƃ���B���̏ꍇ�A���a�Ɍ��M���͓͂����̂��B�A�C���V���^�C���ɂ��A����͎����ł͌��߂��Ȃ��B��`�ɂ���Ă������߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�A�C���V���^�C���ɂ��A�a�Ɍ������B����̂�12�F00����12�F10�܂ł̎����ł���A�ǂ̐�����I��ł��ǂ��̂ł���B �����ŁA�����a�ɓ͂���������12�F02���Ƃ��悤�B���܁A�����`�a��i�ނ̂ɁA�����3�����Ȃ��Ă悢�M�� �w ������Ɖ��肵�悤�B��������ƁA�����a��12�F02�ɓ�������Ƃ��A������̐M�� �w �́A������3����������11�F59�ɓ͂����ƂɂȂ�B�����̐M���͂��傤��12�F00�ɂ`�n�_���瑗��o���ꂽ�̂ɁA����͊�ł���B�M�� �w �͂`���o��O�ɂa�ɓ͂��Ă��邱�ƂɂȂ�B���������K�肷��Ɩ����Ɋׂ�B�������A����́u����葁���M�� �w �����݂���v�Ƃ��������݂�������ł���B�A�C���V���^�C���ɂ��A�������Č���葁���M���͑��݂��Ȃ��̂ł���B�x ��������������ǂ�ŁA�u���������v�Ǝv�����̂͐��E���Ŏ������������悤�ł��B�����u���������v���ƌ����ƁA�O���͕����w�ł͂Ȃ��̂ł��b�ɂȂ�܂��A�㔼�́u���� �w �����12�F02�ɂa�ɓ��B���Ă��邱�Ƃ��Ɍ��߂Ă���g�_���I�h�v�ɘb��i�߂Ă���̂ł��B������܂����H���̌����Ă��邱�ƁB �A�C���V���^�C���Ƃ����l�́A���������_���W�J�܂�A��Ɂu�����Ȃ�v�ƒf�肵�Ă���A�I�݂ɘb�������Ă����A���邢�͍I�݂ɐ����W�J�����邱�Ƃ̏��Ȑl�������悤�ł��B�l�X���n�}���Ղ��_�@�ł��B ���ΐ����_�̋��ȏ��ɂ́A���������_�@���悭�����܂��B���Ƃ��A�L���� �d������2�@�o���镔���ł����A�ł��|�s�����[�Ȃ����̓��[�����c�ϊ����g���ăj���[�g���͊w�����������āA�ߎ�������K���ɍ����̂ĂāA�u���ꂪ�Î~�G�l���M�[���B�v�Ƃ�����̂ł����A�����ł͂Ȃ��v�Z�ł́A�d�^�����^���ʂƂ����̂�����܂��B ���鑊�Θ_�̋��ȏ��̈ꕔ�����Љ�܂��ƁA �w�d�^�����l�� �����ŁA�E�E�E�E�r�����E�E�E�l����(�k�|��)�^���A�E�E�E�r�����E�E�E�����������k�|�����������āA �d������2�@�@��B�x �Ƃ����̂�����܂��B �܂��́A�ʂ̑��Θ_�̋��ȏ��ł� �w�d�^�������� �䂦�ɂd������2�@�ł���B�x �Ƃ����̂�����܂��B ����30�N�ȏ�A�����������v�Z�𐳂����ƐM���Ă��܂������A���Ӑ[���l����Ɓu���������v���ƂɋC���t���܂��B ����́u���̃G�l���M�[���d�Ƃ���B���ɂ͉^���ʂ�����B�䂦�ɂd�^���͉^���ʂł���B�v�Ƃ���_�@�ł��B �u���ɂ͉^���ʂ�����v�Ƃ���������͎�������m���߂��Ă���̂Ő������ł��B�������A�u�d�^���͉^���ʂł���v�͐������ł����H ���̃G�l���M�[�ɂ͔M�G�l���M�[��^���G�l���M�[�A�Ԗ����h������ʎq�G�l���M�[�d������(�n�[�E�j���[)�Ȃǂ�����܂��B������������Ŋ�������A�Ȃ��^���ʂȂ́H �b�����āA���������̍����̂Ȃ�����������u�������v�ƌ��ߍ���Ōv�Z������A�ړI�̎��ɗe�ՂɎ����Ă�����͓̂��R�ł��B��q�����u�n���X�E���C�w���o�b�n�̘_�@�v�ƂȂ��ς��Ȃ��ł��B ���ΐ����_�̋��낵���́A�������������Ȃ����_�@���u�������v�Ɛl�X�ɐA���t���閂�͂ɂ���悤�Ɏv���ĂȂ�܂���B�@ |
|
|
���Ǒz
���͏��N�̍��A�A�C���V���^�C���ɓ���A�،h�̔O�������ăA�C���V���^�C���h���Ă��܂����B15�C16�̍��ł��B���̍��A���̓A�C���V���^�C���̌����悤�Ɂu���̃X�s�[�h�ȏ�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�ƍl���܂����B�Ȃ����̂悤�ɍl�������́A���N�Ȃ��玟�̂悤�Ȃ��Ƃł����B �����A2�@�̃��P�b�g�`�A�a������A�݂��ɔ��Ε����Ɍ����ɋ߂����x�Ŕ��ł������ꍇ�A���P�b�g�`�Ƃa�͌����ȏ�̃X�s�[�h�ŗ���邽�߁A�݂��ɒʐM�͏o���Ȃ����炾�A�Ǝv�����̂ł��B ���̃X�s�[�h�܂�d�g�̃X�s�[�h�ȏ�̑����ŗ���čs���̂�����ʐM�͕s�\���Ǝv�����킯�ł��ˁB�ʐM���s�\�Ƃ������Ƃ́A�����������͖̂����Ƃ������ƂƓ����ł��B�݂��ɑ���̃��P�b�g�̑��݂��m�F���邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă������ȉ��̃X�s�[�h�łȂ���Εs�\�ł��ˁB���̂悤�ɁA���������N�͍l�����킯�ł��B �������ăA�C���V���^�C���̑��x�̉��@���܂�����ȏ�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����𐳂����Ƃ��āA���N�̊ԁA���ΐ����_��M���Ă����̂ł��B ������1993�N��(���|�ucos��)�������Ƃ��A�u����͂�����Ƃ��������v�Ƃ������ƂɋC���t���܂����B���P�b�g�`�A�a�����Ƃ������ȏ�̑����ŗ���čs���Ă��A���Ƃ���1�D5���̃X�s�[�h�ŗ���čs���Ă��A�u�ʐM�͏o����v�ƋC���t�����̂ł��B�Ȃ����ƌ����Ɓu�����͈��v������ł��B�Е��̃��P�b�g�̃X�s�[�h�������ȉ��ł���A�M��(���^�d�g)�͓͂��܂��B�����Е��̃��P�b�g�����l�ł��B�����ȉ��̃X�s�[�h�ł���ΐM���͓͂��܂��B�܂�`�Ƃa�̑��Α��x�����Ƃ�1�D5���ł����Ă��ʐM�͉\�ł��B �������������P�b�g�̉^���Ɉˑ�����̂ł�����A���������N�̍l�������Ƃ͐������ł��傤�B�ł��A�}�C�P���\���E���[���[�̎������������茤������ƁA�����͈��ł��邱�Ƃ������������A�����20���I�G���N�g���j�N�X�Łg�����͌����̉^���ɂ͈ˑ����Ȃ��h(�܂�x�N�g�����������ׂ������̂��̂ł͂Ȃ�)���Ƃ��͂�����Əؖ�����Ă���̂ŁA���͂� ���������N�̍l���͒ʂ�Ȃ��ł��B ����͌����܂ł��Ȃ��A�A�C���V���^�C���̑��x�̉��@���͔j�]���Ă��邱�Ƃł���A���Θ_�̕�����Ӗ����܂��B �������P�b�g�`��(�܂��̓��P�b�g�a��)�A�����ȏ�Ŕ�ԂƁA����(�d�g��)�g�����ʐM�͕s�\�ł��B�Ȃ��Ȃ��(�d�g)�͓͂��Ȃ�����ł��B�������A�����������Ԃ��o������͍̂���Ǝv���܂��B�Ƃ����̂̓��P�b�g�͌����ɂȂ����u�Ԃɑ唚������\�������邩��ł��B���̌��͏����̃z�[���y�[�W�ʍ��ŏq�ׂ܂����B ��������500�N��A1000�N��ɐl�ނ����炩�̕��@�ŁA�������z����u�Ԃ������ł���A�����ȏ�̃X�s�[�h�ʼnF�����s�ł���悤�ɂȂ����m��܂��A����͖��Ƃ���21���I�̎������Ƃ��Ă͐S�̉��ɂƂǂ߂Ă������Ƃɂ��܂��傤�B ������ɂ���A���P�b�g�`�Ƃa�̑��Α��x���������Ă�����s�s���͂Ȃ����Ƃ�(���|�ucos��)�ɂ���Ė��炩�ɂȂ����Ǝv���܂��B�������ł��傤���B�@ |
|
|
���u�k�A�����A�����A���̒��p�O�p�`�������v
��ʂ̐l�X�ɂ͓�������ł����A���ɑ��Θ_����������ɂ́A�������ł�����ꑊ�ΐ����_�̏o���_�ɂȂ��������A�����ł��Љ�Ă����܂��B ���x���q�ׂĂ��܂��g�b�v�y�[�W�e�����D1�u�k�A�����A�����A���̒��p�O�p�`�v�ɂ��ẮA���������O�p�`�͐��w�I�ɂ������I�ɂ����݂��Ȃ��킯�ŁA���̐}�`�ؖ�����L�e�����D2��e�����D3�Ŏ����܂����B ���̑��݂����Ȃ��O�p�`(�����ł����ƁA�k2�{��2��2�|��2��2�@��0�@�͕s�ςł���Ƃ����A�C���V���^�C���̍l��)����A���ꑊ�ΐ����_�̊�b�ɂȂ������̕��������l���o����܂����B ����2������2�{����2�{����2�|��2����2 ��s�ςƂ���B�����ŁA4�������W(���A���A���A������)���̂����A������0�A������0�Ƃ���A �@�E�E�E�@��s�ςƂ���B (�������A���̎����̂��̂̓A�C���V���^�C�����l���o�������̂ł͂Ȃ��A�G�f�B���g�����̒����uTHE MATHEMATICAL THEORY OF RELATIVITY�v(CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 1923)������p�������̂ł��B) �������ă��[�c��T��A���p�O�p�`�̎O�����̒藝���烍�[�����c�ϊ��������o����A�O��I�Ƀj���[�g���͊w�����������čs�����ƂɂȂ����̂ł����A�����w�Ƃ��Đ��������Ƃ�����Ă����̂��A�^���ɍl�������Ă��������B ������_�A�d�v�Ȏ��́A1905�N�̃A�C���V���^�C���̘_��������x��������ƒ��Ӑ[���ǂݒ������Ƃł��B����̃n�C�e�N���ォ�猩��ƁA�u����͊Ԉ���Ă����v�Ǝw�E�ł��镔�������鏊�Ɍ����܂��B ���Ɍ������Ȃ��œǂ݂����̂́A����25�̃A�C���V���^�C�������w�╨���w�ɂ��Ƃ����������ł��B���Ƃ��u�d���ߒ��̋N����^��̈�_��1�̑��x�x�N�g�������肵�Ȃ��Ă��悢�v�Ƃ����L�q�����邱�Ƃł��B����͐��w�ƕ����w�̔j�����Ӗ����܂��B�j�[���X�E�{�[�A�����Θ_�ɔ����Ă������R�����ɂ͂悭������܂��B�@ |
|
|
�������@���̕s�ϐ�
�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�̂��ƂɂȂ��Ă���u���ꑊ�ΐ������v�Ƃ������݂́A�������̂Ɠ��l�̉^���@���ɏ]���ׂ����Ƃ����v���ł����A����͂�����̑�������v���u�����x�s�ς̌����v�Ƃ������݂ƂƂ��ɁA���w�I�ɂ́u�����镨���@���́A�����銵���n�ɑ��ĕs�ό`���ɕۂ����ׂ��ł���B���̂��߂ɂ̓K�����[�ϊ��͔j�����ă��[�����c�ϊ����̗p����B�v�Ƃ�����̂ł��B �����������t�̐����Ȃ����v���́A�ꌩ�Ó����̂���悤�ɕ������܂����A���Ӑ[��������ƁA�u�����x�����͐�ɑ��ΓI�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���s�ϒl���ł��邱�Ƃ�O��ɐ��w�W�J����B�v�Ƃ����v���ɑ��Ȃ�܂���B �Ⴆ�A1�����\�����ꂽ2�̍��W(�����n)������ꍇ�A �������� �@�@�@���f�������f �ł��邱�Ƃ��ΓI�ȑO��Ƃ��A�u��Ɍ����x�͂����v�ł���A�u���Ԃ��ς��̂��v�Ƃ��Đ��w�W�J����Ƃ��Ă���킯�ł��B �������u�����镨���@���́A�����銵���n�ɑ��ĕs�ό`���ɕۂ����ׂ��ł���B�v�Ƃ����v���̓K�����[�ϊ��Ő��藧���Ă��邱�Ƃ𗝉�����K�v������܂��B �Ⴆ�Ώ�̗�ŁA���Ό����x���ω����鎮 �������� �@�@�@���f�����f�� �ł��A�������ƕ����@���Ƃ��ĕs�ό`���ɕۂ���Ă��܂��B���Ό����x�� ���f�����|�� �ɂȂ�����A�����@���ł͂Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��̂ł��B 1��������܂��ƁA�}�b�N�X�E�F���d���������������ƁA�g�����̈�A �d���`sin�o(2�^��)�E(���|����)�p �������܂����A��������f���ɃK�����[�ϊ����āA �������f�{�����f �@�@�@�������f ��������ƁA �d�f���`sin�o(2�^��)�E�m���f�|(���|��)���f�n�p �ł�����A(���|��)�����f�@�Ƃ����A �d�f���`sin�o(2�^��)�E(���f�|���f���f)�p �ƂȂ�A�����@���͕s�ό`���ɕۂ���Ă���̂ł��B�����g�����Ɏ��������́A �@�E�E�E�@�ł���A�������ƕ����@���̕s�ϐ���ۂ��Ă��܂��B ���������āA�u�����x�͂����Ȃ���W�n����ɂ��łȂ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ������R�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B �悭�m���Ă���悤�Ƀj���[�g���͊w�̓K�����[�ϊ��ɑ��ĕs�ό`���ł��B�����Ƀ}�b�N�X�E�F���d���͊w���܂� ���Ό����x(���|�ucos��)�ɂ���ăK�����[�ϊ��ɑ��ĕs�ό`����ۂ��Ƃ����������������B�@ |
|
|
���]�v�ȒǐL
�g���ΐ����_�h�Ƃ����ƁA�g���ΐ��h�Ƃ������t�̖��͂ɂ���āA�ǂ������\�����������_�Ȃ̂���S���m��Ȃ��Ă��A�u���������_���v�Ɛl�X�̔]���ɊȒP�ɓ��荞�݂܂��B �Ȃ����Ƃ����ƁA�g���ΐ��h�Ƃ����̂͐l�X�ɂƂ��Ĕ��ɔ����������������t������ł��B�������͏�Ɂg���ΓI�h�ɐ����Ă��܂��B�g���ΓI�h�ɐ����Ă����Ȃ���ƂĂ�����Ă��Ȃ�����ł��B �u���͕n�R���B�ł����̒��ɂ͂����ƕn�R�Ȑl������B�䖝���悤�B�v����A���Ȃ킿�g���ΓI�h�ł��B �u���̉Ƃ͏������B�ł����̒��ɂ͂����Ə����ȉƂɏZ��ł���l������B����ōK�����ƍl���悤�B�v����A���Ȃ킿�g���ΓI�h�ł��B ��������āA�������͏�Ɂg���ΓI�h�ɐ����Ă��܂��B�������Ȃ��Ɓu�ƂĂ�����Ă��Ȃ��v����ł��B �X�̒ʍs�l�Ɂu����ȂɌg�ѓd�b�����y���邱�Ƃ́A���ł�100�N���O�ɃA�C���V���^�C���́g���ΐ����_�h�ɂ���ė\������Ă�����B�v�ƌ����Ă����B�قڑS�����u���[�A�����ˁB�A�C���V���^�C���́B�v�Ɠ����܂��B ���������������� �g���ΐ����_�h�B���t�ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�@ �@ |
|
| ��GPS�͓��ꑊ�ΐ����_���ʑ��ΐ����_�̕挊���@�����̂� | |
|
GPS�����ΐ����_�̐����������������ɂȂ��Ă���炵���Ƃ������Ƃ́A���T�E�����h�[���̖{��ǂ�Œm�����B�u���[�v����F���v�Ƃ����{�ł���B���̒��ɁA�u��5�� ���ΐ����_�\�\�A�C���V���^�C�������W�������d�͗��_�v�Ƃ�������������B
���̖��́A�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�̘_�|�ɁA�{���I�Ȍ������o�����҂ɂƂ��ẮA�ڂ̏�̂��Ԃ̂悤�Ȃ��̂������B���_�I�Ɂu�������A�������v�Ɣ��_���Ă��A���̗��_���������Ƃ����؋��̂悤�Ȃ��̂���������ꂽ��A���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�Ƃ���ŁA���̖��ɂ́A��ӓ_�����邩������Ȃ��B����܂ŒN���������Ƃ��Ă������_�Ƃ����悤�Ȃ��̂��B���́A����ׂĂ݂悤�ƍl�����B ���T�E�����h�[���̖{�̑�5�͂́A�u�Ō�Ɂv�Ƃ����߂ł́A�u��ʑ��ΐ����_�v�Ƃ������t�̂ق��ɂ́A�u���̂ق��̈�ʑ��Θ_���ʂɂ�邸��v�Ƃ������t��A�u���ΐ����_�v�Ƃ������t�����\��Ă��Ȃ��B����ł́A�͂����肵�Ȃ��B ���͐}���قɍs���āAGPS�̂��Ƃ����グ�Ă���A���ΐ����_�̖{��T���āA����������o�����B�������A�����̖{�̒��ɂ́A�����m�肽���Ǝv���Ă������Ƃ̏��͏�����Ă��Ȃ������B�����m�肽���Ǝv���Ă���̂́AGPS�̎��v�̕�ɁA��ʑ��ΐ����_�ł͂Ȃ��A���ꑊ�ΐ����_���ǂ̂悤�ɗ��p����Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�ǂ����ŁA����炪���ɗ��p����Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�ǂC������̂����A���̏o�T���v���o�����Ƃ��ł��Ȃ��̂������B �ӂƁA�u�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂�A�����o�Ă��邩������Ȃ��v�Ƃ����l�����v�������B�����̂��߂̃L�[���[�h�́uGPS�v�ƁuSpecial Relativity�v�ł悢�͂����B�������āA�������̉p���ɂ�鎑���y�[�W�������o�����B�����̒��ŁA�����Ƃ��e���͂̂��肻���Ȏ����ɂ��āA�����ȓ��e�𗝉����邽�߂ɁA���{��ւƖ|�邱�Ƃɂ����B����́A���̃z�[���y�[�W�ɂ���A�u�������E�̑��ΐ����_ GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�Ƃ������̂ł���B�����ɂ́A���̒m�肽��������A�͂�����Əq�ׂ��Ă���B �܂��́A�u�������E�̑��ΐ����_ GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�̒��́A�v�_���܂Ƃ߂悤�B����́A���ꑊ�ΐ����_�̗\���ɂ��A�u1���ɂ�7�}�C�N���b�x��v�A��ʑ��ΐ����_�̗\���ɂ��A�u�����45�}�C�N���b������ɐi�ށv����A�u����������̑��Θ_�I���ʂ̑g�ݍ��킹�v�ɂ���āA����ɂ��u���悻38�}�C�N���b���� (45�|7��38)�A��葬���������ށv�Ƃ������Ƃł���B ���̂��Ƃɂ��ĉ����m��Ȃ��ŕ����Ă���ƁA�Ȃ�قǁA�Ɣ[�����Ă��܂������Ȑ����ł���B�������A����͂��������B�������������̂��Ƃ����ƁA��ʑ��ΐ����_�̗\���l�ƁA���ꑊ�ΐ����_�̗\���l�Ƃ��A���ꂼ��ʁX�̕������Ōv�Z����āA���̌��ʂƂ��Ă̐��l���A�P���ɉ��Z���ĕ�l�����߂Ă���Ƃ����_���B �A�C���V���^�C���͓��ꑊ�ΐ����_�ƈ�ʑ��ΐ����_�̃l�[�~���O���̗p����Ƃ��A��ʂ���v���Ƃ��āA�l���悤�Ƃ���Ώۂ���W�n�́A�^����Ԃ��l���Ă���B���ꑊ�ΐ����_�ł́A�݂��Ɂu���鑬�x�v�������Ă���Ώۂ���W�n�̂��Ƃ������l���Ă���A��ʑ��ΐ����_�ł́A�݂��Ɂu��������x�v�������Ă���Ώۂ���W�n�̂��Ƃ��l���Ă���B�����āA���ꑊ�ΐ����_�ɑg�ݍ��܂�Ă���u���x�̍��v�Ƀ[��������ƁA���̗��_���j���[�g���͊w�ւƎ�������悤�ɁA�A�C���V���^�C���́A��ʑ��ΐ����_�ɑg�ݍ��܂�Ă���u�����x�̍��v�Ƀ[��������ƁA���ꑊ�ΐ����_�ւƎ�������Ƃ����������l���Ă���B�͂����āA���̂悤�ɂȂ��Ă���̂��ǂ����Ƃ������Ƃ́A���ɂ́A�悭������Ȃ����A�����̃v�����j���O�}���͘_���I�ł���A������₷���B �j���[�g���͊w (NM)�Ɠ��ꑊ�ΐ����_ (SR)�̊W���l����ƕ�����₷���B���ꑊ�ΐ����_�Ɍ���郍�[�����c�ϊ��̎��ɂ́A�� (�������́A�A�C���V���^�C���̌��_���ł̓�) �̋L���ł���킳��鍀�ɁA�݂��̈ړ����xv ���܂܂�Ă���B������v = 0 �Ƃ����ƁA��=1 �ƂȂ��āA���ꂪ�|�����Ă��鐔�����A�j���[�g���͊w�̂��̂ƂȂ�B���̂悤�ȊW�ɂ��鎮�𗘗p���āA�Ӗ������߂���Ƃ��́Av ��0 �̒l���A0 �łȂ��l���Ƃ������Ƃɒ��ӂ��āA�ꍇ����������K�v������B���ΐ����_�̎��Ƃ��āAv ��0 �ł͂Ȃ����炩�̒l�����Čv�Z�����Ƃ��́A�����K�p�����Ώۂ̌��ۂɑ��āA������x�Av ��0 ����ꂽ�j���[�g���͊w�̎���p���āA�����̌��ʂ��A�P���ɉ��Z����ȂǂƂ������Ƃ́A�����Ăł��Ȃ��͂��ł���B �j���[�g���͊w (NM)�Ɠ��ꑊ�ΐ����_ (SR)�ɂ��čl�����A���̊W���A���ꑊ�ΐ����_ (SR)�ƈ�ʑ��ΐ����_ (GR)�̊W�ɂ��čl���邱�Ƃ��ł���B���̂Ƃ��A���̂悤�Ș_���W�������Â���̂́A���xv �ł͂Ȃ��A�����xa �ł���B��ʑ��ΐ����_�ł́A�d�͉����xg �̂��Ƃ���ɍl�����Ă䂭�B���炩�̉����x�������Ă�����W�n�ǂ����̂��Ƃ��A���ꑊ�ΐ����_�ł͎�舵�����Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ������O���A�A�C���V���^�C���͉��N���v���Â��āA��ʑ��ΐ����_�ݏo�����Ƃ����B��ʑ��ΐ����_�ɂ��Ę_����ꂽ���͂�ǂ�ł��ƁA�A�C���V���^�C���͈�ʑ��ΐ����_ (GR)�̉����x��0 �ɂȂ����Ƃ����ꑊ�ΐ����_ (SR)�Ɏ�������ƁA�����Â��Ă���Ƃ��낪���邪�A���̏������A�ǂ̂悤�ɑg�ݍ��܂�Ă���̂��A���ɂ́A�悭������Ȃ��B�A�C���V���^�C���́A�����̕\���Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ŁA�u���܂�ɕ��G�ɂȂ�̂ŁA���炭���ꑊ�ΐ����_�����悤�v�Əq�ׂĂ���B��ʑ��ΐ����_�̌��_���ɂ́u���ꑊ�ΐ����_�́v�Ƃ������t�����x�������̂����A����ɂ��Ắu���v�����p����Ă��鍭�Ղ��Ȃ��B�A���C�V���^�C���́A�u�j���[�g���͊w�̐��E�v�̂��Ƃ��A�u���ꑊ�ΐ����_�̐��E�v�ƌĂѕς��ē��ꎋ���Ă���悤�Ɏv����B����ƁA��ʑ��ΐ����_�� a = 0 �̂Ƃ��ɓ��ꑊ�ΐ����_���܂�ł���̂ł͂Ȃ�(SR �܂ށ�— GR)�A���ڃj���[�g���͊w���܂�ł��� (NM �܂�— GR) �Ƃ������ƂɂȂ�B�m���A��ʑ��ΐ����_�̎����Ƃ��ɁA���炩�̖���W�������߂邽�߁A�j���[�g���͊w�ɏ������鎮 (�|�A�b�\���̎���������) �𗘗p���Ă����悤���B��ʑ��ΐ����_�Ƃ������_���̏W���́A�����Ƀj���[�g���͊w�n�̎����܂�ł���̂ł���B�������A���ꑊ�ΐ����_�̎����܂�ł���̂��ǂ����́A�悭������Ȃ��B ��ʑ��ΐ����_���A���S�Ȑ������������Ă���̂��ǂ����Ƃ������Ƃ́A�����ł͐[���Nj����Ȃ��ł������B��ʑ��ΐ����_ (GR)�����ꑊ�ΐ����_ (SR)���܂݁A���̓��ꑊ�ΐ����_ (SR)���j���[�g���͊w (NM)���܂�ł��� (NM �܂�—- SR �܂�—GR)�A�Ƃ��邩�A��ʑ��ΐ����_ (GR)�͓��ꑊ�ΐ����_ (SR)���܂�ł��Ȃ����A�j���[�g���͊w (NM)���܂�ł���A���ꑊ�ΐ����_ (SR)���j���[�g���͊w (NM)���܂�ł��� (GR—-�܂� NM �܂�— SR) �Ƃ��邩�A������ɂ��Ă��A�����̗͊w�n�́A�ЂƂ̏W���̂ƂȂ��Ă���̂ł���B ����ƁA���̂Ƃ��A��̊O���Ώ� x �ɂ��āA���̗͊w�n�̏W���̂̒��́A�ǂ����̗v�f�_�ɑΉ����鎮 g ��K�p�� g(x) ���Ƃ���ƁA���̓����O���Ώ� x �ɂ��āA���̗͊w�n�̏W���̂ɂ���A���̎� s ��K�p���� s(x) �Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��͂��ł���B���z�̏ꍇ���������āA�Ō�ɂǂꂩ���������̂�I�Ԃ��߂ɁAg(x) �� s(x) ��ʁX�Ɍv�Z���邱�Ƃ͂ł��邾�낤�B�قȂ�O���Ώ� y ���������Ƃ��āAg(x) �� s(y) �����߂邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�������A��������̊O���Ώ� x �ɑ��āA�قȂ鎮 g�� s ��z�肵�āA�����̌v�Z���s���� g(x) �� s(x) �����߁A�����āA�����̒l��g(x) + s(x) �̂悤�ɉ������킹�ė��p����Ƃ����̂́A�ǂ��l���Ă��A�_���I�ł͂Ȃ��B����͐��w�I�ɂ͐������Ȃ����Ȃ̂ł���B GPS�̌��q���v�ɂ����āA��ʑ��ΐ����_ (GR)�̗\���l�Ɠ��ꑊ�ΐ����_ (SR)�̗\���l�����߂āA�����̘a���v�Z���ė��p���Ă���Ƃ����́A��L�̐��w�I�Ȑ����́Ag(x)+ s(x) �ɑΉ����Ă���B���̂Ƃ��� x �Ƃ́A�O����ɂ���GPS�q���̌��q���v�ł���B����́A���w�I�Ȗ����ł���B�o�q�̃p���h�b�N�X�Ƃ��̂悤�ȁA�����̂��Ƃɐ��܂ꂽ�����Ƃ������̂ł͂Ȃ��A���ɃV���v���ȁA��b�I�Ș_���ɂ����閵���Ȃ̂ł���B GPS�l�H�q���ɑ������ꂽ���q���v���A�n��ǂ̓������q���v�ɑ��āA���炩�̕���K�v���Ƃ������Ƃ́A�����Ƃ��đ��݂���̂��낤�B�������A���̂悤�Ȃ킯�ł��邩��AGPS�̎��v�̕�Ɋւ��āA��ʑ��ΐ����_�Ɠ��ꑊ�ΐ����_�́A���ꂼ��̗\���l�����Z���ė��p����Ƃ������Ƃ́A�����̑��ΐ����_�̌��ɂȂ�ǂ��납�A�t�ɁA�����̑��ΐ����_�̂ǂ����ɁA�Е����A����Ƃ��o���ɁA���炩�́A�����Ę_���I�ł͂Ȃ��A��̃��J�j�Y��������ł���Ƃ������ƂȂ̂��B����́A�Ђ���Ƃ���Ɓu�挊 (grave)�v�ɂȂ邩������Ȃ��B�����炭�A���ꑊ�ΐ����_�̂ق��͊m���ɁB �NjL�B�}���قŎ肽�{���w�K���āA��ʑ��ΐ����_�̃A�C���V���^�C���������̉��̈�ł���A�V�����@���g�V���g�v�ʂ��g���āAGPS�q���̌��q���v�̕�l���v�Z������@���w�B����ɂȂ���āA����v�Z���s�����Ƃɂ��A���ɑ��ΐ����_�̗\���l�ɂ�����s��Ȃ������ꍇ�ɂ��Ē��ׂ��B�����āAGPS�q���̎��v������ɂ����l�����߂āA����������Ɋ��Z�����B�u�������E�̑��ΐ����_ GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�ł́A���̒l��10km������Ə����Ă���B�������A��������i�K��Ōv�Z����ƁA���̒l�́A�킸��3cm�ɉ߂��Ȃ����Ƃ����������B�ǂ����A����̕b���ł���86400�Ƃ����������A���������x�|���Ă��܂��āA10km����l�ɂȂ��Ă��܂����悤���B���T�E�����h�[�����A�����̒��ŁA����10km�l�����p���Ă���B�͂����āA���̒l��10km�Ȃ̂�3cm�Ȃ̂��A�ł���A�����h�[�������ɂ��njv�Z���Ăق������̂ł���B �@ |
|
| ��GPS�̌��q���v�͓��ꑊ�ΐ����_�ƈ�ʑ��ΐ����_�ŕ�ł��邩�H | |
|
���̃y�[�W�̃^�C�g���́A�������T���ڂȂ��̂ł��邪�A�p���ŋL�����^�C�g���̂ق��́A���Ȃ�ߌ��Ȃ��̂ł���B���Ă݂�ƁA�uGPS�͓��ꑊ�ΐ����_����ʑ��ΐ����_�́A���邢�͗����́A�挊���@������������Ȃ��v�Ƃ������ƂɂȂ�B���́A��ɁA������̃^�C�g�����ł��āA������ӖāA��L�̓��{��̃^�C�g���Ƃ����B
GPS�����ΐ����_�̐����������������ɂȂ��Ă��� (�炵��) �Ƃ������Ƃ́A���T�E�����h�[���̖{��ǂ�Œm�����B�u���[�v����F���v�Ƃ����{�ł���B���T�E�����h�[���́A���̂悤�Ȓm���̖{�ł���ɂ�������炸�A�����Ƃ������̂��A�܂������g���Ă��Ȃ��B���S�Ȏ��R���ꕶ���B���̂悤�Șb�p�̓��e�ŁA��w�̍u�`�ɂ����铱������������A���ꂩ���̓I�Ȑ����Ȃǂ��o����Đ��������A�����Ɗw�������͋����������Ċw��ł䂭���Ƃ��낤�B���̂悤�ȁA���R���ꂾ���ŗ��_�����w�̍Ő�[�̒m�������ꂽ�A600�y�[�W�ȏ������{�̒��ɁA�u��5�́@���ΐ����_�\�\�A�C���V���^�C�������W�������d�͗��_�v�Ƃ�������������B ���́u���ꑊ�ΐ����_�v�̐߂ł́A���̍����ȉȊw�҂����Ɠ����悤�ɁA�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�ɂ�����u��̉��� (���邢�͗v���������͉���)�v�̂��Ƃ��A�Ԉ���āA������Ă���B�����ł���B�u�����@���͂����銵���n�ɂ����ē������v�Ɓu���̑��� (c) �͂ǂ̊����n�ɂ����Ă��������B�v�܂��A�悭�����܂Ŋȗ����������̂��B����ł́u����v�Ă͂Ȃ��u���ʁv�ł���B�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�ɂ�����u��̉���v�́A�A�C���V���^�C���ȑO�́A���[�����c��|�A���J���ɑ�\�����Ȋw�҂����̌����ƁA�A�C���V���^�C���̌����Ƃ���ʂ���A�d�v�ȗv���ł���̂�����ǁA���㕨���w�̍Ő�[�ɂ���Ȋw�҂������A���̂悤�ȕ\����M���Ă��܂��̂��B����ł́A�����w�ɂ�����_�������^���Ă����������Ȃ��B ���Ɍ����x�s�ς̉���̂ق��́A�{�������Ɣ����ȕ\���ɂȂ��Ă��āA�����ł́A�����x���v�������Q�ƌn�Ƃ��Ắu���n�v�Ƃ������t���g�ݍ��܂�āA�����o��Ƃ��̔����̂��A���̒��n�ŐÎ~���Ă��Ă��A�^�����Ă��Ă��A����炩��o�����̑��x�́A�����l�ƂȂ�Ƃ������肪����Ă���B���s�̂�����������W�n���A���n (�Î~�n) �Ɖ^���n�ƍl���āA�������܂Ƃ߂Ċ����n�ƌĂт����̂��낤���A���̂悤�Ȋȗ����ɂ���āA���̖{���I�ȕ��� (�����x�𑪒肷��Q�ƌn���ǂ��ɂƂ邩�Ƃ�������) �������Ă��܂��Ƃ������ƂɁA�N���C�Â��Ă��Ȃ��炵���B ����́A�A�C���V���^�C���ɂ������邱�Ƃł���B�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_���A����Đ��E���̉Ȋw�҂Ɏ�����Ă��܂����̂́A���̉���̗������s�\���ł������Ƃ������ƂɁA�ЂƂ̌���������B�A�C���V���^�C���������ō��������Ă䂭�̂����A���ݏo�����̂��������Ă�����W�n�Ƃ������̂ƁA���̑��x�𑪒肷��Q�ƌn�Ƃ��Ă̍��W�n���A���̂܂ɂ��A�N�ɂ���Ă�������Ȃ��ԂɁA�܂�������ʂ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���B�A�C���V���^�C���́A���ꑊ�ΐ������̌��_���ŋL�����A��2�ɂ���u�����x�s�ς̗v���v�̒�`�ɁA������Ə����Ă��邪�A�����ł́A�����x�́u���n�v�ő��肳���Ɖ��肳��Ă���̂ł���B�����Ԃ�A���̃y�[�W�̘_�|���A�ʂ̂Ƃ���ւƗ����Ă��܂����B���̖��ɂ��ẮA�����Ǝ��������Ă���A�ڂ�����邱�Ƃɂ������B������A���Ȃ�d�v�Ȗ��ł���B �u�����@���͂����銵���n�ɂ����ē������v�Ƃ����A�u���ΐ������̗v���v�̕\���ɂ��A�����炩��肪����B�����炭�A�܂��m���Ș_�̍��q���܂Ƃ߂Ă��Ȃ����A�����ɂ��u���̕����@�����L�q����ϑ��҂̎��_�������͍��\�n�v�Ƃ����v�f�������Ă��܂��Ă���B����ɂ��Ă��A�����������̂��߂̃A�C�f�B�A�����邪�A�ڂ����������悤�Ƃ���ƁA���̃y�[�W�̘_�|���痣��Ă��܂��̂ŁA���̂�����Ő�グ�Ă������Ƃɂ��悤�B ���T�E�����h�[���̖{�́u��5�́@���ΐ����_�\�\�A�C���V���^�C�������W�������d�͗��_�v�ւƖ߂�B���̏͂̍Ō�̐߁u�Ō�Ɂv�̂Ƃ���ɁAGPS�̃G�s�\�[�h������Ă���B�����̃G�s�\�[�h�́A���̏͂̓��������ł��g���Ă���A�Ō�̂Ƃ���ł��G��邱�Ƃɂ���āA�C���I�Ȓ��a��}�낤�Ƃ��Ă���悤���B�{�_�ւƖ߂낤�B ���T�E�����h�[���̍l�����ȒP�ɗv��ƁAGPS�Ŏg���Ă��鎞�v���A���ΐ����_�̗\���Ɋ�Â��ĕ���Ȃ��ƁAGPS�̐��x���A����̃��x���ɂ܂ň����グ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������Ƃ������Ƃł��낤�B���̖��́A�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�̘_�|�ɁA�{���I�Ȍ������o�����҂ɂƂ��ẮA�ڂ̏�̂��Ԃ̂悤�Ȃ��̂������B���_�I�Ɂu�������A�������v�Ɣ��_���Ă��A���̗��_���������Ƃ����؋��̂悤�Ȃ��̂���������ꂽ��A���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �ŋ߁A���������G�l���M�[���Ƃ��đ���Ԃ��J������āA����ɑ��āA���镨���w�҂������A���̂悤�Ȃ��Ƃ͗��_�゠�肦�Ȃ��Ɣ��_���Ă������A���ۂɁA���̂悤�ȎԂ��ł��Ă��āA���ۂɐ������ő����Ă���̂�����A�Ԉ���Ă���̂́A���炩�ɕ����w�҂����̂ق��ł���B���̂悤�ȎԂ̃G���W���ɂ��郁�J�j�Y���ɂ́A�i�v�����p�����Ă���Ƃ����Ƃ��낪�ӓ_�̈�ɂȂ��Ă���B�ڂ������Ƃ͊�Ɣ閧�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���̉i�v���ɂ��A�킸���ȃG�l���M�[���𗘗p���āA���炩�̐G�}�̍�p���g�ݍ���ŁA�����_�f�Ɛ��f�ɕ������āA���̐��f�𗘗p����Ƃ����̂�����A����͂���܂ł̈Ӗ��ɂ��u�i�v�@�ցv�ł͂Ȃ��B�Ƃ��Ƃ��A���̂悤�ȋZ�p���J������āA���̒��ɏo�Ă���悤�ɂȂ����̂��B���̐��E�͑傫���ς���Ă䂭�ɈႢ�Ȃ��B ���̂��Ƃ́A�t�̂��� (���邢�͓�������) ���A�u���ꑊ�ΐ����_���ʑ��ΐ����_�v�ƁuGPS�̎��ԕ�v�Ő��藧��������Ȃ��B���_�̗\���ƁA����̌��؎����Ƃ��A���܂�����������A���̗��_�͊m���Ȃ��̂ɂȂ��Ă䂭�B �Ƃ���ŁA���̖��ɂ́A��ӓ_�����邩������Ȃ��B����܂ŒN���������Ƃ��Ă������_�Ƃ����悤�Ȃ��̂��B�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�̘_�|�ɂ́A���̂悤�Ȗӓ_�����������B�܂������ɔF�߂��Ă��Ȃ����A����͊m���ȁu���v�̂悤�Ɍ����Ă���B����́A������_���̂Ƃ���ɂ���̂ł͂Ȃ��āA��������������܂��̂悤�ȁA�����I�Ȏ��̗p�����Ƃ����A�ꌩ����Ɓu�Ղ���������Ƃ���v�ɂ������B����GPS�ɂ��Ă̖ӓ_���A�悭�����̂Ƃ���ɉB��Ă���悤���B ���T�E�����h�[���̖{�̑�5�͂́A�u�Ō�Ɂv�Ƃ����߂ł́A�u��ʑ��ΐ����_�v�Ƃ������t�̂ق��ɂ́A�u���̂ق��̈�ʑ��Θ_���ʂɂ�邸��v�Ƃ������t��A�u���ΐ����_�v�Ƃ������t�����\��Ă��Ȃ��B�����ł��A���t�̒��ۉ����g�ݍ��܂�Ă��āA���̂��肩���B����Ă��܂��Ă���B�����炭�Ӑ}�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���̖��ɂ��Ēm��Ȃ����C�Â��Ă��Ȃ��̂ŁA�������Ă���̂��낤�B ���͐}���قɍs���āAGPS�̂��Ƃ����グ�Ă���A���ΐ����_�̖{��T���āA����������o�����B���̈�́u����̗͊w�v (�גJ�ŕv���^��g���X���^2002.04.15) �Ƃ����{�ł���A���Ɂu��ʑ��ΐ����_����@�u���b�N�z�[���T���v(Edwin F. Taylor�EJohn Archibald Wheeler ���^�q��L�`��^������Ѓs�A�\���E�G�f���P�[�V�������^2004.12.25) ���肽�B�����̖{����A�A�C���V���^�C���̈�ʑ��ΐ����_�̌��_�ł�����A�A�C���V���^�C���������Ƃ����e���\���`���̔����������̉��̈�ł���A�V�����@���c�V���g (Schwarzschild) ���Ƃ��������AGPS�̎��v�̕�ɗ��p����Ă��邱�Ƃ�m�����B�����̖{��ǂނƁA���̂悤�Ȏ����g���Ă̌v�Z�Ƃ������̂���̓I�ɕ�����悤�ɂȂ�B�Ȃ��Ȃ��ǂ��{���B���R����ł̐��������ł́A���̂��Ƃ̖{�������������Ă��Ȃ����Ƃ�����B�������g���Ĕ��W���Ă�������̂��Ƃ𗝉����悤�Ƃ�����A��͂�A�����̐����ɂ��Ă��m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B �������A�����̖{�̒��ɂ́A�����m�肽���Ǝv���Ă������Ƃ̏��͏�����Ă��Ȃ������B�����m�肽���Ǝv���Ă���̂́AGPS�̎��v�̕�ɁA��ʑ��ΐ����_�ł͂Ȃ��A���ꑊ�ΐ����_���ǂ̂悤�ɗ��p����Ă��邩�Ƃ������Ƃł���B�ǂ����ŁA����炪���ɗ��p����Ă���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ�ǂC������̂����A���̏o�T���v���o�����Ƃ��ł��Ȃ��B����ŁA���̏o�T��T���Ă���̂ł��邪�A�����̖{�ɂ́A�̐S�ȂƂ��낪�L����Ă��Ȃ��̂��B �}�N�X�E�F���̓d�����������A���ꑊ�ΐ����_�ւƋy�ڂ����e���̂��Ƃ��A���낢��Ȗ{��T���o���āA�x�N�g���L���Ȃǂ��g���āA�����𗝉����Ȃ���m�[�g�ɂ܂Ƃ߂Ă����Ƃ��ɁA�ӂƁA�u�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă݂�A�����o�Ă��邩������Ȃ��v�Ƃ����l�����v�������B�����̂��߂̃L�[���[�h�́uGPS�v�ƁuSpecial Relativity�v�ł悢�͂����B�������āA�������̉p���ɂ�鎑���y�[�W�������o���A�v�����g�A�E�g���āA������ǂނ��Ƃɂ����B�����āA�����̒��ł��A�����Ƃ��e���͂̂��肻���Ȏ����ɂ��āA�����̂��Ƃ����A�����ȓ��e�𗝉����邽�߂ɁA���{��ւƖ|�邱�Ƃɂ����B ���ꂪ�A���̃z�[���y�[�W�ɂ���A�u�������E�̑��ΐ����_�@GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�Ƃ������̂ł���B���̂悤�ȃy�[�W����������ƁA�����A�C���V���^�C���̑��ΐ����_��M��l�Ԃ̂悤�Ɏv���邩������Ȃ����A�����ł͂Ȃ��B����͂���ŁA�����I�Ȏ����Ƃ��āA���{�������J���邱�Ƃɂ��Ă���̂ł���B�����̏����A����ɐ�\�肷��̂ł͂Ȃ��A�I���W�i���̏��̑S�̑���������ŁA�_�|�ɕK�v�ȕ��������o���Ă��邾�����Ƃ������Ƃ��A�͂�����Ǝ����Ă����������炾�B ���́u�������E�̑��ΐ����_�@GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�ɂ́A���̒m�肽��������A�͂�����Əq�ׂ��Ă���B���̃E�F�u�T�C�g�̃y�[�W�ɏ�����Ă��邱�Ƃ��{���̂��Ƃ��Ƃ�����A�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_����ʑ��ΐ����_�̂ǂ��炩�A���邢�́A���̗������A�܂Ă�A���������T���Ɍ����ƁA���ꑊ�ΐ����_�̎��ƁA�V�����@���c�V���g���̎��́A�ǂ��炩�A���邢�́A�������Ԉ���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł���B���̂��Ƃ��ے������̂��A���̃y�[�W�̃^�C�g���́A�uGPS�̌��q���v�͓��ꑊ�ΐ����_�ƈ�ʑ��ΐ����_�ŕ�ł��邩�H�v(GPS might dig a grave of Special Relativity or of General Relativity perhaps of both) �Ƃ������ƂɂȂ�B�����Əڂ����A����ɋ�̓I�ɐ������邱�Ƃɂ��悤�B �܂��́A�u�������E�̑��ΐ����_�@GPS�i�r�Q�[�V�����V�X�e���v�̒��́A���̃y�[�W�̘_���I�ȓW�J�̂��߂ɕK�v�ȕ����ɂ��Đ������悤�B�킸���ȗʂł���̂ŁA�܂��A���̕������A�����Ɉ��p���悤 (���L�̐F�Ⴂ�����̕���)�B�������A�����ɂ����� ( ) �̒��߂͍�������B �n��ɂ����l�̊ϑ��҂́A�l�H�q���Q���A�����ɑ��鑊�ΓI�ȓ����̏�Ԃɂ���̂����邱�ƂɂȂ�̂ŁA���ꑊ�ΐ����_�́A�����̎��v�Q�����x���������ނƌ���ׂ����ƁA�\�����Ă���B���ꑊ�ΐ����_�́A�l�H�q���ɏ���Ă��錴�q���v���A�n��̎��v�Q���A�����̑��ΓI�ȓ����́A���Ԓx�����ʂ̂��߂ɁA���x���������ފ����Ƃ������̂�����̂ŁA1���ɂ�7�}�C�N���b�x��邾�낤�Ɨ\�����Ă���B ����ɁA�l�H�q���Q�͒n���̏�̋O�����x�ɂ���A�����ł́A�n���̎��ʂɗR�����鎞��̋ȗ��́A�n���\�ʂł̋ȗ����A�������B��ʑ��ΐ����_�́A���ʂ̂��镨�̂ɁA���߂����v���A��艓���̈ʒu�ɗ���Ă��鎞�v�ɑ��āA���x���������ނ悤�ɂ݂��邾�낤�Ɨ\�����Ă���B���̂悤�Ȃ��ƂȂ̂ŁA�n���̕\�ʂ��猩���Ƃ��A�l�H�q���ɂ��鎞�v�Q�́A�n��ɂ��铯�����v�Q�ɑ��āA��葬���������ނ悤�Ɍ����B��ʑ��ΐ����_���g�����v�Z�́A���ꂼ���GPS�q���̒��ɂ��鎞�v�Q���A�n��ɒu����Ă��鎞�v�Q���A�����45�}�C�N���b������ɐi�ނ��낤�ƁA�\�����Ă���B ����������̑��Θ_�I���ʂ̑g�ݍ��킹�́A���ꂼ��̐l�H�q���Ɏ��t����ꂽ���v�Q���A�n��ɂ��铯�����v�Q�ɑ��āA���悻38�}�C�N���b���� (45�|7��38)�A��葬���������ނ��낤�Ƃ������Ƃ��A�Ӗ����Ă���B �v�_�������܂Ƃ߂�ƁA���ꑊ�ΐ����_�̗\���ɂ��A�u1���ɂ�7�}�C�N���b�x��v�A��ʑ��ΐ����_�̗\���ɂ��A�u�����45�}�C�N���b������ɐi�ށv����A�u����������̑��Θ_�I���ʂ̑g�ݍ��킹�v�ɂ���āA����ɂ��u���悻38�}�C�N���b���� (45�|7��38)�A��葬���������ށv�Ƃ������Ƃł���B ���ꂪ�u�挊 (grave)�v�̕����ł���B���ꂪ���ΐ����_�́u���v�ł͂Ȃ��u�����v�ł���ƁA�����咣����̂́A�����̐����̂��Ƃł͂Ȃ��B���̂悤�Ȑ������`�F�b�N�ł���悤�ȏɁA��������킯���Ȃ��B���́A�����̐����̒l�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�u���ΐ����_�̗\���l�v�Ɓu��ʑ��ΐ����_�̗\���l�v�Ƃ��A���Z����āA��̕�l�Ƃ������̂����߂��āA���ꂪ���ۂɖ𗧂��Ă���Ƃ����_�ɂ���B���Ƃ�����A���̂悤�ȑ���́A���S�ɐ������Ȃ��B�ǂ����ɉ��炩�̌�������邩�A���炩�̃g���b�N������ł���B�Ȃ��Ȃ�A�u��ʑ��ΐ����_�v�Ɓu���ꑊ�ΐ����_�v�́A�����Ɉ�̑Ώ� (�����ł�GPS�q���̌��q���v�Q) �ɓK�p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂����炾�B �����ƊȒP�Ɍ����ƁA��ʑ��ΐ����_�́A�����x�������ĉ^��������W�n�̊Ԃł̗��_�ł���A���ꑊ�ΐ����_�́A�����x�������Ȃ������n�Ƒ��̂������W�n�̊Ԃł̗��_�Ȃ̂ł���B���Ɉ�ʑ��ΐ����_���A�����x�������Ȃ����W�n�Ԃ̖@�����܂�ł����Ƃ��Ă��A���ꂪ�K�p�ł���̂́A�������Ȃ̂ł���BGPS�ɑ�������Ă��錴�q���v�̏��A��ʑ��ΐ����_�̓K�p����Ƃ�����A����́A���ꑊ�ΐ����_�̓K�p�O�̂��ƂɂȂ�B�t�ɁA����ɓ��ꑊ�ΐ����_���K�p���ꂽ��A��ʑ��ΐ����_�̓K�p�͂ł��Ȃ��͂����B�Ђ���Ƃ���ƁA�d�͉����x�Ɋւ��Ă�����ʑ��ΐ����_�̃V�����@���c�V���g����K�p���āA�O�����ړ����鑬�x�ɑ��Ă͓��ꑊ�ΐ����_��K�p�����Ƃ����̂��낤���B����Ȃ��Ƃ��ł���Ƃ������_���ǂ����ɂ����āA���ꂪ�ۏႵ�Ă���Ƃ����̂��낤���B���Ƃ��A�����܂ŏ������Ă��A�O�������l�H�q���́A�~�^���������͑ȉ~�^�����s���Ă���̂ŁA�����n�ł͂Ȃ��A���炩�ɉ����x�n�ł��邩��A���ꑊ�ΐ����_�́A���S�ɓK�p�ł��Ȃ��B���̎��_�Ɋւ��Ă��A��L�E�F�u�T�C�g�̋L�q���e�͊Ԉ���Ă���B GPS�l�H�q���ɑ������ꂽ���q���v���A�n��ǂ̓������q���v�ɑ��āA���炩�̕���K�v���Ƃ������Ƃ́A�����Ƃ��đ��݂���̂��낤�B�������A���̌������A��ʑ��ΐ����_�����Ő������邱�Ƃ��ł��Ȃ��āA���ꑊ�ΐ����_�������Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A���Ȃ��Ƃ����ꑊ�ΐ����_�͐������Ȃ����A��ʑ��ΐ����_���������Ȃ��Ƃ����\����������B���邢�́A���Ɉ�ʑ��ΐ����_���������Ƃ��Ă��A���̃V�����@���c�V���g���ł͕s�\���ł���Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B ���̂悤�Ȃ킯�ł��邩��AGPS�̎��v�̕�Ɋւ��āA��ʑ��ΐ����_�Ɠ��ꑊ�ΐ����_�́A���ꂼ��̗\���l�����Z���ė��p����Ƃ������Ƃ́A�����̑��ΐ����_�̌��ɂȂ�ǂ��납�A�t�ɁA�����̑��ΐ����_�̂ǂ����ɁA�Е����A����Ƃ��o���ɁA���炩�́A�����Ę_���I�ł͂Ȃ��A��̃��J�j�Y��������ł���Ƃ������Ƃ������Ă���B �͂����āAGPS�̌��q���v�́A�{���ɓ��ꑊ�ΐ����_�̗\���ƈ�ʑ��ΐ����_�̗\���ŁA��ł���̂��낤���H�@ �@ |
|
| ���d�͏� | |
|
����I�Ȍo���Ɍ���A�͂�`�B������̂����������̂ɍ�p���y�ԂƂ������́A������蓾�܂���B�������A���z��f���Ȃǂ̓V�̂́A�����Ƃ��뉽�����݂��Ă��Ȃ��Ǝv����ȋ�Ԃ̒��ŁA�݂��ɉ�������đ��݂��Ă���ɂ�������炸�A���炩�Ɍ݂��ɉe�����y�ڂ������Ă��܂��B�V�˃j���[�g���ɂ�������Ȃ������A���̈��͍�p�̃��J�j�Y���́A���I���E�ɑ��݂��镨���w�ő�̓�ƌ����Ă��ǂ��ł��傤�B
���ꑊ�ΐ����_�̈�ʉ��Ƃ��Ắw��ʑ��ΐ����_�x�ɂ��ẮA�O�w���������x�̐߂ŁA���_���������Ȃ����Ƃ��w�E���܂����B�����ł͏d�͗��_�Ƃ��Ắw�A�C���V���^�C���̈�ʑ��ΐ����_�x�ɂ��ĊȒP�ɐG��Ă����܂��傤�B�@ |
|
|
��1 ���ꗝ�_
���ݕ����w�̕���ɂ́A�����I�Ȑ��E(�d��)���������g��ʑ��ΐ����_�h�Ƌɔ��̐��E(�d���͂ƁA��̊j��)���������ʎq�_�Ƃ����A���ꂼ��Ɨ�������̗L�͂ȗ��_�����݂���Ƃ���Ă��܂��B���ꗝ�_�Ƃ����̂́A�ȒP�Ɍ������̓�̗��_����ɓ��ꂷ�邱�ƂŁA����������g�l�̗́h�̂��ׂĂ��A��̗��_�Ő������悤�Ƃ������݂ł��B �����I�ɈقȂ��Ă���A�ʂ̕\��������A���e��Ȃ���������������̗��_�����݂���̂͂��������킯�ł�����A���҂͓��ꂳ��邩������ے肠�邢�͑傫���C������Ȃ���Ȃ�܂���B ���ꗝ�_�ւ̒���́A���R�A�C���V���^�C�������݂Ă����悤�ł����A���ʂ��グ�邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B���̌���l�X�Ȍ������Ȃ���Ă��܂����A������������̌��ʂ��͂����Ă��܂���B �ő�̌����́A�����I�Ȑ��E(�d��)���������g��ʑ��ΐ����_�h�Ɍ�肪���邩��ł��B�ƌ������A�����������_�̍\�z(���_���q�ׂ郁�J�j�Y���̃C���[�W)���ǂ�����܂���B�@ |
|
|
��2 �ߐڍ�p�Ə�
�t�@���f�[�́A���̉��u��p�I�ȓ����������d�����ݍ�p���ߐڍ�p�ɒu����������r�Ƃ��āA��ԓ��ɉ������g��N�h���ꂽ��ԂƂ��Ắg�d����h�Ƃ����T�O�����܂����B �A�C���V���^�C���������d�͍�p�̐����́A��{�I�ɂ͂��̃t�@���f�B�̃A�C�f�A�ɂ��̂܂ܕ�������̂ł��B���Ȃ킿�A���͍�p�̍�p�����ɂ��āA�A�C���V���^�C���́A�s���ʂ̑��݂��A���͂̋�Ԃɉ��������I�Ȏ��ݕ����N������Ԃ��g�d�͏�h�Ɩ��t����A���̏d�͏ꂪ��̒��ɂ��鎿�ʑ̂ɓ���������t��p���g�d�͍�p(������)�h�ł���Ɛ������܂����B �s���ʂ̑��݂����ڎ��͂̋�Ԃ�c�܂���t�Ƃ����\���ɕς��Đ������Ă���ꍇ������܂����A������ɂ��Ă��A������������Ԃ̑��݂����ڊm�F�ł��Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł́A�G�[�e�������Ƒ卷����܂���B �s���ʂ̑��݂��A���͂̋�Ԃɕ����I�Ȏ��ݕ����N�����t���邢�́s���ʂ̑��݂��A���͂̋�Ԃ�c�܂����t��Ԃ��g�d�͏�h�ł���Ƃ����C���[�W�́A�t�Ɍ����A����(�d�͏�)���玿�ʂ���菜�����Ƃ��A��ɂ�����g������ԁh���c��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A���ʂ̑��݂�����̋�Ԃɉ������N����A���邢�͋�Ԃ�c�܂���Ƃ������z�́A���������[������e��Ƃ��Ă̋@�\�������������g������ԁh�Ƃ������̂��A���ʑ̂⎞�ԂƂ͓Ɨ����đ��݂��邱�Ƃ�O��ɂ����T�O���ƌ�����ł��傤�B �g������ԁh�́A���������Â��犵��e����ԃC���[�W���̂��̂ł��B�����Ɂq��N���ꂽ�����I�ȉ����r�����݂���Əq�ׂ邱�Ƃ́A���̂̂悭�킩��Ȃ����ݕ�(�G�[�e��)�̑��݂�F�߂邱�ƂƖ{���I�ɂ͓����ł��B�@ |
|
|
��3 ���L���̖͂@�����Ƃ̖���
�d�͂̍�p�Ƃ����̂́A�Γ��ȓ�̎��ʂ̊ԂŋN����̂ł�����A���ɃA�C���V���^�C���̐����̂悤�Ɂs���ʂ̑��݂�����ɕ����I�ȉ������N���A���ꂪ���̎��ʑ̂ɓ���������t�̂��Ƃ����ꍇ�A���̍�p�͓�d�ɋN���邱�ƂɂȂ�܂��B ���Ȃ킿�A�n��(����m1)�ɂ���Đ������d�͏ꂪ�A����m2 �̕��̂ɓ���������Ȃ�A�n�����A����m2 �̕��̂�����������d�͏�̓�������͂��ł��B���̂��Ƃ� F = G(m1/r)�~(m2/r)�@(G �����L���͒萔) �Ƃ������L���̖͂@�������l�����킹��A�e���ʂ���N����d�͏�̋����́A���ꂼ��m1/r�Am2/r�ŗ^������ƌ������ƂɂȂ�܂��B ����͎��́g��h�̊T�O�Ƃ̑������]��ǂ��Ȃ��̂ł��B�܂�A�ώ��ɍL����O������ԓ��ɁA��_����g�U����g�e���́h(����ԓ��̂����_�ɑ��݂�����̂ɂ���Đ�������͂̋�Ԃ̊e�ʒu�ɂ������p�̋���(���ʑ̂���N���镨���I�ȉ����̓���)���A���ݕ�����̋����̓��ɂł͂Ȃ��A�����ɔ���Ⴗ�邱�ƂɂȂ�Ƃ����}���A�Ƃ������d�g�݂͂����ɂ��s���R�ł��B ��_���N���ɂ���3 ������ԂɊg�U����A���邢�͗�N���鉽��������A���̉����̔Z�x�́A���Ƃ��Γ_�������甭�������̊g�U�̏ꍇ�̂悤�ɁA�N������̋����̓��ɔ���Ⴕ�Ĕ��܂��Ă����ƍl����̂����R�ł��傤�B�@ |
|
|
��4 �G�l���M�[�ۑ����̊ϓ_����
�n���\�ʂ̋߂��ł́A���R�������镨�̂́A���Ԃ̌o�߂Ƌ��ɗ����̑��x�𑝂��Ă����܂��B�܂肻�̕��̂����^���G�l���M�[�͎��Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɑ������܂��B ���̎��́A���̗����^�����L�q�����@�����ł��B E =1/2(mv2)+mgh (1) [ �A���Ag �͏d�͉����x�Ah �́A���x0 �̏�Ԃ��痎�����n�߂����̂̑��x�� �ɒB�������_�܂łɗ������������A��\���܂��B] �ʏ�A���̂̉����ɂ́A������g�O�́h�������K�v������܂����A�d�͂ɂ�闎���^���́A���̎��g�ƒn���̊Ԃ̈��͂̓����ɂ���ċN���Ă��āA�n���y�ѕ��̎��g�ȊO����̗�(�O��)�͊֗^���Ă��܂���B���������̌��ۂɂ́A�G�l���M�[�̈�`�Ԃł��鎿��(���̏ꍇ�A�n���y�ѕ��̎��g�̎���)�́A�ω��͔���Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B�]���āA���̂��l������^���G�l���M�[���ǂ�����A�ǂ̂悤�ɋ�������Ă��邩�𖾂炩�ɂ���K�v������܂��B ���݂̕����w�ł́A���̖��ɂ��Ă�(1)���̑�2 ���ɁAmgh �Ƃ����`�ŋL�q���ꂽ�A������g�|�e���V����(�ʒu�̃G�l���M�[)�h�Ƃ����T�O��p���Đ������Ă��܂��B �m���ɒn��ɂ�����̂����̍����܂Ŏ����グ�邽�߂ɂ́A�͂������Ďd��������K�v������A�����ŏ���ꂽ�G�l���M�[�́A�Ώە��ɑ��č��x��^���邽�߂����ɏ���ꂽ�悤�Ɍ����܂��B���̂��Ƃ��A��̕��̊Ԃɓ������͂̍�p���A��̕��̂̊Ԃɑ��݂����ԓI�Ȋu��������̃G�l���M�[�ł���ƍl����A�X���[�Y�ɔ[���ł��܂��B ���̉��߂��s��t�̗��_���l�A���J�j�Y���ږ��炩�ɂ�����̂ł͂���܂��A�A�C���V���^�C���̃A�v���[�`���L�������m��Ȃ��̂ŐG��Ă����܂����B���͂ł���Ɍ�����i�߂܂��B�@ �@ |
|
| �����ΐ��������ʊ� / ���c�ЕF | |
|
����
���Ԃł͂������A���̊w���̊Ԃł��܂��ǂ�������Ɨ��w�҂̊Ԃł���u���ΐ������͗������ɂ������̂��v�Ƃ������ɑ��ꂪ���܂��Ă���悤�ł���B�������ɂ����ƕ����Ă��̂��߂ɂ������ċ������h�������l�����Ƃ�肽�����邾�낤���A�܂������s����t�Ȃ����͕����������Ă����ċߊ��Ȃ��l�����邾�낤���A�����̎d���ɖZ�����Ď��ۉɂ̂Ȃ��l�����邾�낤���A�܂��O��I����`�̖�˂ɕ��������ď�����ۂl�����邾�낤���A���͂��܂��܂ł���B�A�C���V���^�C�����g���u�����̈�ʌ����𗝉�������l�͐��E�Ɉ�_�[�X�Ƃ͂��Ȃ����낤�v�Ƃ����悤�ȈӖ��̎������������Ɠ`�����Ă���B�����Ă��̌��t���܂��l���܂��܂ɂ��낢��ɉ��߂�����Ă͂₳��Ă���B ���������́u�����v�Ƃ��������̈Ӗ����͂����肵�Ȃ��ȏ�́u�������ɂ����v�Ƃ��������̈Ӗ�������߂Ĕ��R�s������t�Ƃ������̂ł���B�Ƃ�悤�ɂ���ẮA�ǂ��ɂł������B �����Ƃ��Ȋw��̗��_�Ɍ��炸�����Ƃ������͂��ł��e�ՂȂ��ƂłȂ��B���Ƃ������̎q���������Ɍ������Č������ł��A���ꂩ�炻�̎q���̂ق�Ƃ��̐S���������ݎ����x�܂ŗ�������͕̂K�������e�ՂȎ��ł͂Ȃ��B������[���ɗ������邽�߂ɂ́A���̎q�������Ă����������������킵�ނ�悤�ɂȂ����K�R�ȉ��v�����^����m���s�����t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����m��Ȃ���ΕL��s�Ђ����傤�t�������b�v���Łs�ڂԂ傤�t�̐e��s���₶�t���鎖��Ƃ���������Ȃ��B�܂��Ă���������̑a�u�������l�͂Ȃ�����̎��ł���B �Ȋw��́A�ꌩ�ȒP�b���ās�߂���傤�t�Ȃ悤�Ɍ����閽��ł���͂�ق�Ƃ��̗����͑��O����ł���B���Ƃ��j���[�g���̉^���̕����Ƃ������̂�����B����͒��w�Z�̋��ȏ��ɂł��ڂ����Ă��āA�N�̂䂩�Ȃ����w���͂Ƃ����������łɂ�����u�����v���鎖��v������Ă���B�����w�Z�ł͂���ɏڂ����J��Ԃ��đ��i�́u�����v����������B��w�ɂ͂����ĕ����w���U����l�͂���ɐ[����O�i��l�i�́u�����v�ɐi�ނׂ���͂��ɂȂ��Ă���B�}�b�n�́u�͊w�s���q���j�[�N�t�v�ꊪ�ł��ǔj���đ��������̔�]�I�Ȗڂ����Ă݂Ďn�߂Ă����炩�u�����v�炵����������𐁂��ė���B�������悭�悭�l���Ă݂�Ƃ���ł͂܂��[�����낤�Ƃ͎v���Ȃ��B �Ȋw��̒m���̐^����m��ɂ͉Ȋw������m�����̂ł͕s�[���ł��鎖�͂������ł���B�O���֏o�Ă݂Ȃ���Αc���̎����킩��Ȃ��悤�ɁA�������Ȋw���ƂɌ`����w�s���������傤�����t�̂悤�Ȃ��̂ƑΏƂ��A�܂��F���_�Ƃ����悤�ȋ��ɏƂ炵�Ĕ�]�I�Ɍ�����łȂ���ΉȊw�͂ق�Ƃ��ɂ́u�����v�����͂����Ȃ��B����������������ʓI�Ȗ��͕ʂƂ��āA�����ŗ�ɂƂ����j���[�g���̕����̏ꍇ�ɂ��ĕ����w�͈͓̔������ōl���Ă݂Ă��A���ǃj���[�g�����g���ގ��g�̕����𗝉����Ă��Ȃ������Ƃ����p���h�b�N�X�Ɉ����s�ق����Ⴍ�t����B�Ȃ�ƂȂ�Δނ̕����������Ȃ���̂��𗹉����鎖�́A���ΐ����_�Ƃ������̂̏o���ɂ���Ďn�߂ĉ\�ɂȂ�������ł���B���������Ӗ��Ō����A�j���[�g���ȗ��ނ̕����𗝉��������Ǝ��M���Ă����l�͂��Ƃ��Ƃ��u�������Ă��Ȃ������v�l�ł����āA�������Ă��̕����ɕs�������������̍���ɔY��ł�������߂ď����̐l���������͔�r�I�悭�������Ă���ق��̑��ɑ����Ă����̂�������Ȃ��B�A�C���V���^�C���Ɏ����Ďn�߂Ă��̓�_�����炩�ɂ��ꂽ�Ƃ���A�ނ͏��Ȃ����j���[�g���̕����𗝉����鎖�ɂ����đ��l�҂ł���ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����Ɠ����_�@�ʼn����čs���ƌ��ǃA�C���V���^�C�����g���܂��O��I�ɂ͑��ΐ������𗝉������Ȃ��̂�������Ȃ��Ƃ������ɂȂ�B ���������ӂ��ɍl���ė���Ǝ��ɂ͖`���Ɍf�����A�C���V���^�C���̌������Ȃ�ƂȂ���핗�h�I�ȈӖ��̃j���A���X��ттĎ��ɋ����B �v���Ɉ�ʑ��ΐ������̒����Ɠ����ɂ܂������炩�̒Z��������Ƃ���A������ɐɂ���������Ă���̂̓A�C���V���^�C�����g�ł͂���܂����B�����炭�����s�����߂��t�Ȕނ̖ڂɂ́A�Ȃ��O������Ȃ��_�A��[��v����_�������������͂��Ȃ����Ƃ������͐�w�Ȍ�y�̂����ɂ��z������Ȃ����͂Ȃ��B ���Ȕ�]�̉s�����̐l���g�ɕs�����Ɗ�������_������Ɖ��肷��B�����Ă����̓_�܂ł��Ȃ��̔�]�Ȃ��Ɉ�ʑ����ɏ��F����^������鎖������Ɖ��肵�����ɁA����ɂ��Ƃ��Ƃ��������ď������������������������Ȃ��قǂɗ�Â��������l�Ƃ͂ǂ����Ă����ɂ͎v���Ȃ��B ����䂦�Ɏ��͔ނ̌��t������̕��h�I�ȈӖ��̃j���A���X��������B���ɂ͂��ꂪ�����̌��t���Ƃ͂ǂ����Ă��v���Ȃ��āA�������Ă������������ɔY�ޗ]��̋�s�̂悤�ɂ������Ȃ����B����͂��܂�̋ȉ���������Ȃ��B�����������������߂��\�ł͂���B�@ |
|
|
����
�Ȋw��̊w���A���ƂɈ�l�̐����Ă���A�_���ƃC���̌���s���������t����w�҂̎d���Ƃ��Ă̊w���ɁA��ΓI�u���S�v�Ƃ������������ȈӖ��Ŗ]�܂ꂤ�鎖�ł��邩�ǂ����B������قƂ�ǖ��ɂȂ�Ȃ��قǖ����ɕs�\�Ȏ��ł���B�����w�Ҏ��g�̎��Ȕ�]�\�͂̒��x�ɉ����āA����F�߂Ċ��S�Ɓu�v���v���͂������\�ŁA�����Đq���ʂɍs�Ȃ��Ă��鎖�ł���B�����v������K�^�Ȋw�҂́A���̎d���������Ō��Ċ��S�ɂȂ�̂�҂��Ĉ��S���Ă���\���鎖���ł���B�����������ȈӖ��̊��S���s�\���ł��鎖��ɐɃ��A���C�Y�������s�K�Ȃ�w�҂͑��ΓI���S�ȏ�̊��S�����}���鎖�̕s�\�Ŗ��Ӌ`�Ȏ���m���Ă���Ɠ����ɁA�����̎d���́u���S�̒��x�v�ɑ��Ă�┻�R���鎩�o���������\�ł���B���̌���Ƃ���Ńj���[�g����A�C���V���^�C���͖��炩�ɂ��̌�̕��ނɑ�����w�҂ł���B ���́A�{���c�}����h���[�f�̎��E�̌��������ł��邩��m��Ȃ��B�������ނ�̎����v�����тɐ^���s���t�Ȋw�҂̔ϖ�s�͂����t�Ƃ��������l���Ȃ����͂Ȃ��B �w�����w�Ԃ��̂ɂƂ��Ă�����̊��S�̒��x��ᔻ���s���S�ȓ_��F������́A���̊w���𗝉����邽�߂ɂ܂��ɓw�ނׂ��K�v�����̈�ł���B �����������Ɍ�����ĂȂ�Ȃ����ŁA�����Ă�������Ό������₷����������B���Ȃ킿���������u�s���S�v������Ƃ������́A���ׂĂ̐l�Ԃ̍\�������w���ɋ��ʂȂقƂ�ǖ{���I�Ȏ��ł����āA���������ꂪ���邽�߂ɒ����ɂ��̊w�����S�ł���Ƃ����悤�ȊȒP�Ȃ��̂Ƃ͌���Ȃ����A�ނ��낻�������_��F�߂鎖�����̊w���̕�U�s�قĂ�t�ɑ���K�i�ƌ��Ȃ��ׂ��ꍇ�̑������ł���B���������ꍇ�ɁA��̌��_���w�E���Ďc��啔���̒����܂ł����苎���Ƃ��邪���Ƃ��ԓx�����l���Ȃ����͂Ȃ��B�A�C���V���^�C���̏ꍇ�ɂ����������l���Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��悤�ł���B����������͂�����u�g�������v�̑ԓx�ł����āA�܂��߂Ȋw�҂̑ԓx�Ƃ͎���Ȃ��B �u���S�v�łȂ����������Ċw���̑n�ݎ҂�ӂ߂�̂́A���S�łȂ����������Đl�Ԃɐ��܂ꂽ����l�Ԃɐӂ߂�ɓ������B �l�Ԃ𗝉����l�Ԃ����コ���邽�߂ɂ́A�ӖړI�ɒQ�����Ă͂Ȃ�Ȃ����A�v���łɔ��Ă��Ȃ�Ȃ��Ɠ��l�ɁA��̊w���𗝉����邽�߂ɂ́A���̒Z����F�߂鎖���K�v�ł���Ɠ����ɁA���̂��߂ɂ��������̒��������̂����Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͂��܂�Ɏ����I�Ȏ��ł���ɂ�����炸�A�ł���ÂȂ�ׂ��Ȋw�Ҏ��g���牝�X�ɂ��ĖY�ꂪ���Ȏ��ł���B ���Ȃ������ΐ������͂��Ƃ������Ȃ�s���̓_�����㔭������A�܂����Ƃ������Ȃ�����I���������̐��ɕs���Ȃ悤�Ɍ����Ă��A���ꂪ���߂ɍ��{�I�ɔے肳�ꂤ�ׂ������̂��̂ł͂Ȃ��Ǝ��͐M���Ă���B�@ |
|
|
���O
���ΐ������̔�r�I�ɐ[�������邽�߂ɂ͂��̐��w�I�n���𗝉����鎖�͂����炭�K�v�ł���B����������͕K�v�ł��邪�A���ꂾ���ł͂܂��u�K�v���[���ȏ����v�ɂȂ�Ȃ����������ł���B���w�����͗������Ă��A���Ȃ����A�C���V���^�C���̔c���s�͂����t���Ă��邲�Ƃ����̌������u���ށv���͕K�������\�łȂ��B �܂�����ɂ����āA���w�̕��G�Ȏ��̊J�W���[���ɗ������Ȃ��ł������A�A�C���V���^�C�������̗��_���\������ۂɕ���ŗ����v�l��̓������A���Ȃ�Ɍ�炸�ɒʗ����鎖���K�������s�\�ł͂Ȃ��̂ł���B�s�\�łȂ��݂̂Ȃ炸������x�܂ł̂���Ӗ��ł̗����͂������Ă���߂ėe�ՂȎ���������Ȃ��B���Ȃ����A�C���V���^�C���ȑO�̗͊w��d�C�w�ɂ������b�I�T�O�̔��W���v�̍��q����j�I�ɒǐՂ��ߖ��s����݁t������ɂ܂����ʑ��ΐ����_�Ɏ����X����Ȃ�A���̐l�̓����͂Ȃ͂�����������łɂ������Ă��Ȃ�����A���̌����̍��{����̗]�V�Ȃ����邢�͂ނ��떳���Ȃ������������Ȃ��킯�ɂ͍s���܂��Ǝv���B����l�̓R�����o�X�̗���z�N����ł��낤�B����������ɂ͊k�s����t��j��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�C���V���^�C���͂����ŗ]�V�Ȃ����ԂƃG�[�e���̊k���ӂ����܂łł���B �k���ӂ��ĐV���ɗ��Ă����{���肩��o�����āA���ꂩ�琄�_����錋�ʂ܂ł̘_���I���s���͐��w�҂ɐM���������ł悢�B�����Č��ʂƂ��ďo���������R����n���̔������𑽏��ł��F�ߖ��키�����ł��āA�������ċq�ϓI���݂̈�̑��������ɔF�߂鎖���ł����Ƃ���A���̐l�͏��Ȃ��Ƃ�����ƂƂ��Ă��łɂ��̌���������x�܂Łu�����v�������̂ƌ����Ă������ĕs�ςł͂Ȃ��B ���ʘ_�̈�ʂ�m������ɂ��ꂪ�����^���݂̂Ɋւ���Ƃ����_�Ɉ��̕�����Ȃ����邢�͕s����������l�́A���łɗ��h�Ɉ�ʘ_�̖�˂ɓ������ׂ����i������Ă���B�����Ă����ɍĂё��̃R�����o�X�̗��Ɉ����s�ق����Ⴍ�t���邾�낤�B �{�_�ɂ͂����Ă���̂�╡�G��Ƃ�Ȃ����ł����ƈȊO�ɂ͖�����Ȃ��悤�Ȃ��̂���ł���Ƃ͎v���Ȃ��B�����ǂ����Ă��킩��Ȃ����̂ł�������A�A�C���V���^�C�����g�����̒ʑ��u�`�������悤�Ȏ��͂����炭�Ȃ������ɑ���Ȃ��B���͂ǂ�Ȃނ��������_�ł����ꂪ�u�����w�v�Ɋւ������̂ł������A�f�l�s���낤�Ɓt�ɂǂ����Ă��Ȃ��̐����������鎖���ł��Ȃ��قǂɂނ��������̂�����Ƃ͐M�����Ȃ��B�����������炻��͏��Ȃ��������łȂ��Ƃ������悤�ȐS����������B ���Ȃ��������f�l���x�[�g�[���F���̋Ȃ𖡂키�Ɨނ������x�ɁA���ΐ������𖡂키���͂���ɂ��s�\�ł͂Ȃ��A�܂������������x�ɖ��키��������قLj������ł��Ȃ��Ǝv���B�@ |
|
|
���l
���̌������w��̈ꌴ���Ƃ��Č������́u����v���邢�́u���l�v����Ƃ��Ăǂ��ɂ��邩�B���ꂪ�����ɂ��邩�A�l���̉^�ѕ��ɂ��邩�B������قƂ�ǖ��ɂȂ�Ȃ��قǖ��炩�ł���悤�Ɏ��͎v���B�����͔ނ̍l����i�߂���̂Ɏg��ꂽ�K�v�ȓ���ł������B���̓����ނ͉����Ȃ��̂̐��w�҂�F�l�̂Ƃ��납���ė����B����͂܂��ɐl�̒m��Ƃ���ł���B���̓���̎g�������ǂ��܂Ő������Ă��邩�͂����炭�����̖��ł͂���܂����B��������肷��̂͐��Ƃ̎d���ł���A�����Ă���͕K���������̃A�C���V���^�C����v���Ȃ��d���ł���B��������l�̃A�C���V���^�C����K�v�Ƃ����d���̒��j�^���́A���̓����K�v�Ƃ���悤�ȉH�ڂɊׂ�悤�Ȏv�l�̓��ɒT�肠�Ă����A���ꂩ��ǂ����Ă����̓����K�v�Ƃ���Ƃ��������Ŕj�������ł���B���ꂾ���̌��т͂ǂ��l���Ă��ۂގ��͂ł��Ȃ��Ǝv���B���Ƃ��ނ̗��_�̉^��������ǂ����낤�Ƃ��A���ꂾ���͊m���Ȏ��ł���B�����ɔނ̓��]�̈̑傳��F�߂ʂ킯�ɂ͍s���܂��Ǝv���B �i�|���I�����^���̗[�ׂɓ�吼�m�̌Ǔ��ɂ��т����I����Ă����̈̑傳�ɕς��͂Ȃ������B�������A�C���V���^�C���̂悤�Ȏd���ɂ��̂悤�ȗ[�ׂ����낤�Ƃ͑z������Ȃ��B�Ȋw��̎d���͍���̉Ƃ̂悤�Ȑ����҂̉h�̖��Ƃ͔�r���ł��Ȃ��B �������܂��l���Ă݂�ƈ�ʑ��ΐ����_�̎����I�؍��Ƃ������͌����Ɍ����Ύ���Ȏ��Ƃł���B���Ƃ��V���^���̐����Ɋւ���]���̍�����Ȃ�܂ŏ��p����A���I�s�ɂ����傭�t�ϑ��̌��ʂ����Ȃ�܂Ŕނ̐��ɗL���ł����Ă��A����͂��̗��_�̊m�����𑝂���������A�����ȈӖ��ł��̐�ΗB�ꐫ�����肷��ɏ[���Ȃ��̂ł���Ƃ͂ɂ킩�ɂ͐M�����Ȃ��B�X�y�N�g�����̕ψʂ̂��Ƃ��͂Ȃ����猈��I�؍��Ƃ��Ẳ��l�ɂ��Ȃ�̋^�₪����悤�Ɍ�����B ���͉Ȋw�̐i���ɋ��ɂ�����A�w���ɐ�ΗB��̂��̂��L���ȏ����ɐݒ肳��悤�Ƃ͐M�����Ȃ����̂̈�l�ł���B����Ŗ��I�����̓��������ǂ�s�����l�Ƃ��Č������Ƀv�g���~�[���R�y���j�N�X���K�����[���j���[�g�������̃A�C���V���^�C�������ǂ͂����������l�̈قȂ鎞�̎p�Ƃ��Ėڂɉf��B���̉ʂĂȂ������闷�H�����R�ɂ������̌���ɏI�����āA����ł��悢��ފ݂ɓ��B�����̂��ƐM�����邾���̍��������������͎̂��ɂ͍���ł���B ����Ŏ��͌��݂��邪�܂܂̑��ΐ����_���ǂ��܂ŕۑ�����邩�Ƃ������͈�̋^��ɂȂ肤��Ǝv���B����������ɔ����āA�ǂ����Ă��^��ɂȂ�Ȃ��B��̊m���Ȏ����́A�A�C���V���^�C���̑��ΐ������Ƃ������̂������A��������A���Ȃ����啔���̓���̊w�E�ɖ����ȑ��݂�F�߂�ꂽ�Ƃ��������ł���B���ꂾ���̎����͂����Ȃ�^���[���l�ł��F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ����낤�Ǝv���B ����͂������傫�Ȏ����ł͂���܂����B�Ȋw�̊w���Ƃ��Ă���ȏ��]�ގ����͂����ĉ\�ł��邩�ǂ����A���Ȃ����]���̗��j�͖��炩�ɂ����������҂�ے肵�Ă���B ���������킯�Ŏ��̓A�C���V���^�C���̏o�����������j���[�g���̎d���̈̑傳�������Ȃ��Ɠ��l�ɁA�A�C���V���^�C���̌�ɂ�����ׂ��w��x�̂��߂ɔނ̎d���̗��h���������Ȃ���ׂ����̂łȂ��Ǝv���Ă���B �������������w�����꒩�ɂ��Ă���������A�܂����̂��߂ɑn�ݎ҂̈̂����ꎞ�ɏ��ł���悤�Ȏ����\���Ǝv���l������A����͂����炭�Ȋw�Ƃ������̖̂{���ɑ��鍪�{�I�̌�����琶�������ł��낤�B �����Ȃ�ꍇ�ɂ��A�C���V���^�C���̑��ΐ������́A�g�ł�����Ɏq���̒z�������̏�s�̂悤�ȕ��ł͂Ȃ��B�����Ȋw�ƌ��炸��ʕ����j��ɂЂƂ���ڗ����Č����錘�łȐΑ��̈ꗢ�ˁs������Â��t�ł���B�@ |
|
|
����
���ΐ������ɑ��锽�Θ_�Ƃ������̂����X�Ɍ�����B���������̒m�蓾������͈̔͂ł́A���̌����̑��݂��낤������قǂɗL�͂Ȃ��̂͂Ȃ��悤�Ɏv����B ���Θ_�҂̔��̂����Ȃ�u���@�v�́A���߂�ƌ��ǂ��̌����̊�b�I�ȉ����T�O�����܂�͂Ȃ͂�������l�̏펯�ɂ��ނ��Ƃ����ꎖ�ɋA������悤�Ɍ�����B �Ȋw�Ə펯�Ƃ̌��́A����͉Ȋw�̖��ł͂Ȃ��Ăނ���F���_��̖��ł���B�]���ĉȊw��̖��ɔ�ׂĂނ������̒��x����i��ɂ���B ���������Ȃ������j�I�Ɍ������ɏ]���̕����I�Ȋw�ł͂�����펯�Ȃ���̂́A�_���I�n���̐����̂��߂ɂ́A�ɂ����Ȃ��Ƃ͌����Ȃ��܂ł��A���Ȃ�����ނ��]���Ƃ��Ċ��p���ꂠ�邢�͉�������ė����B ���z�������Ȃ��Œn�����^�s���Ă���Ƃ������A�n�������`�ő��G�_�s���������Ă�t�̏Z�����t�s�����t���ɂԂ牺�����Ă���Ƃ������A�����������������ɓ����̏펯�ɔ����Ă������͑z������ɓ�Ȃ��B �[�N���b�h�w�̏o���_�������ɏ펯�I�ɂ��������v���Ă��A�����ے肷�ׂ��_���͌�����Ȃ��B���������ꍇ�ɂ����̂Ƃ�ׂ����͓����B���Ȃ킿�펯���̂Ă邩�A�_�����̂Ă邩�ł���B���w�҂͂Ȃ���S�O�s���イ����t���Ȃ��펯�𓊂��o���Ę_�������B�����w�҂͂��Ƃ����₢��Ȃ���ł����̗�ɂȂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �����w�̑Ώۂ͋q�ϓI���݂ł���B�����������̂̑��݂͂������ł��낤���A������o���_�Ƃ��Đ������������w�̊w���͕L��s�Ђ����傤�t��r�I�����̉��肩��_���I�b��㈁s�����t�ɂ���āu�ϑ����ꂤ�鎖�ہv���u�����v����n���ł���B���̖ړI���B����ꂤ����x�ɂ���Ċw���̑��ΓI���l����܂�B���̖ړI�����Ȃ藧�h�ɒB�����āA���������{���肪��펯���Ƃ����ꍇ�ɏ펯���̂Ă邩�w�����̂Ă邩�����ł���B���݂���Ƃ���̕����w�͌�҂�I��Ői��ŗ�����̌n���ł���B ���͏펯�ɏd����u���ʎ�̌n���̐����s�\���m���ɏؖ����邾���̍����������Ȃ��B�������������ꂪ���������Ɖ��肵����ǂ����낤�B����͏��Ȃ��������̂����镨���w�Ƃ͑S�R�ʎ�̂��̂ł���B�������Ă��ꂪ���������Ƃ��Ă��A���ꂪ���ݕ����w�̑��݂�ے肷�鎖�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��Ǝv���B�����čŌ�ɓ�҂̗D���ᔻ������̂�����A����͉Ȋw�ȊO�̐��E�ɋ��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ |
|
|
���Z
���R�̐X�����ہs�����傤�t�������l�̍��W�̊w�ɂ��߂���Ƃ������͂��܂�Ɋ�������т����ł���ƒQ���鎍�l�����邩������Ȃ��B����������͖��炩�Ɍ���ł���B���ΐ����_���ǂ��܂œO�ꂵ�Ă��A����ς�Ԃ͏��A���͉̂�������߂Ȃ��B�������̐l�Ɠ����悤�ɍl����Ȃ�A������l�̑S�\�̐_���F�����x�z���Ă���Ƃ����l���������ɂ��т����r���Ȃ��̂ł��낤�B ���̂Ƃ��뎄�́A���ׂĂ̐��l���Ȋw�n���̐^���𗝉����āA�����ɐl�����ɂ̋A���F�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ƐM����قǂɓO�ꂵ���Ȋw�҂ɂȂ蓾�Ȃ��s�K�ȉ��^�҂ł���B����Ŏ��ɂ͐l���݂ɉԂ����Ċ�ь��ɑ��Ă͉̂��B�������������Ă���Ԃɂǂ�������ƓˑR�ȕs����������B����͉Ԃ⌎���̑����������̋�ې��E�̂��܂�Ɏ��~�߂ǂ���̂Ȃ������Ȃ��ł���B�ǂ������܂���悤���Ȃ��A���s�ق��܂t�̊C�ɂ��ڂ��Ƃ��鎞�Ɏ��̎�ɐG�����̂����w�̘_���I�n���ł���B��ΓI���Z�̐��E�������Ȃ��܂ł��A���߂đ��ΓI�̊m�������Ȋw�̐��E�ɋ��߂����B ���������Ӗ��Ŏ��́A�����悤�ȕs���Ɨv���������Ă��鑽���̐l�ɁA���w�̌n���̒��ł����ƂɃA�C���V���^�C���̗��_�̂��Ƃ������ꂽ���̂̌����������߂����B�����̐l�͈ꌩ�����Ȃ悤�Ɍ����钊�ۓI�n���̒��ɉԒ������̔������Ƃ́A������ނ̂��������A�����������������̂�����������A�c���s�͂����t���Ȃ��܂ł����Ȃ����ˌ��s�ׂ�����t���鎖���ł��邾�낤�Ǝv���B(�吳�\��N�\��)�@ �@ |
|
| �����ꑊ�ΐ����_�ɐ��ޘ_���I�Ȍ��ɂ��� | |
|
On Logical Errors Underlying the Special Theory of Relativity
�e���[�� Z. �J���m�t (Temur Z. Kalanov) ���ꑊ�ΐ����_�̗͊w�I�Ȋ�Ղ��ᔻ�I�ɉ�͂����B���̊�Ղ��{���I�Ș_���G���[���܂�ł��邱�Ƃ��������B�����́A��ʓI�Ɏ�����闝�_���������Ȃ����Ƃ̔����ł��Ȃ��ؖ��ł���B �Ȋw�͐��E�̒m���̋A�[�I�ȕ��@�ł���B�������傭�A(���������Ɨ��_�̃V�X�e���Ƃ��Ă�) �Ȋw�I�Ȑ^���́A�ُؖ@�I�Ȕ��W�̌����ɏ]���B�^���ُؖ̕@�I�Ȕ��W (���Ȃ킿�A�ȒP�Ȍ`�����畡�G�Ȍ`���ւ̏㏸�����ł̗ʂƎ��̕ω�) �́A���闝�_�Q�́u�a���Ɛ�Łv�A���_�̕ϊ��Ɠ������܂ށB���_�Q�̑I���́A�Ó����Ƃ��������b�Ƃ��ĂȂ����B�A�C���V���^�C���ɂ��A�����ɂ͓�̊�����݂���B���Ȃ킿�A�u�O�I�Ȑ������́v� (���Ȃ킿�A�����f�[�^�Ƃ̈�v) �ƁA�u���I�Ȑ������́v� (���Ȃ킿�A���a�Ɣ������̊��o�����A�_���@���ɏ]������) �ł���B�����̊�����Ȃ����_�́A���炩�ɐ������Ȃ��B�������A�����͖��ʂȗ��_�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�������Ȃ����_�́A�l�Ԃ̈ӎ��̋��E�����z����Ƃ����A�S���I�ȈӖ��������Ă���B���̍l���ł́A20 ���I�ɂ�����A���̂悤�Ȑ������Ȃ����_�̈���A���[�}�[-���[�����c-�|�A���J��-�A�C���V���^�C���ɂ��A���ꑊ�ΐ����_�ł���B�����A���ׂĂ̕����w�҂������A���̗��_��m���Ă���A������p�����Ĕᔻ�I�ɉ�͂�����̂��������A���̗��_�̊�b�̕s���肳�ɋC�����Ă�����̂́A�킸���ł���B ���́A���ꑊ�ΐ����_�̗͊w�I�Ȋ�b��ᔻ�I�ɉ�͂��Ă���[1-9]�B�܂�A�}�C�P���\��-���[���[�̊������ƁA���̌v�Z��A���k�����ƃ��[�����c�ϊ����ł���B���̉�͂̌��ʂ́A���̂悤�ɂȂ��Ă���B�@ |
|
| ��(1) �}�C�P���\��-���[���[�̎����f�[�^�ƌv�Z�f�[�^�̊Ԃɖ��������݂���Ƃ����l�����A���[�}�[-���[�����c-�|�A���J��-�A�C���V���^�C���̓��ꑊ�ΐ����_�ɂ�����J�n�_�ł���B��ɂ���f�[�^�̊�b�Ɋւ���A���̖����̌����ɋC�Â����Ƃ��ł���B�n���Ƒ��z�͑��ΓI�ȓ����̏�Ԃɂ��� (V�����ΓI�ȓ����̑��x�ł���)�B����́A�n�����A���z�̎Q�ƌnS�̒��́A�n���^���nE�ł���A���z���A�n���Q�ƌnE�̒��́A���z�^���nS�ł���Ƃ������Ƃł���B�}�C�P���\��-���[���[�̊��v�� (����ƌv�Z���s��) �ϑ��҂́A�n���Q�ƌn�̒��ɂ���B�������傭�A���v�Ɗϑ��҂͐Î~�nE�̒��ɂ���B�_���I�Ȗ@���ɂ��A�����f�[�^�ƌv�Z�f�[�^���݂��ɔ�r���邱�Ƃ́A�Î~�nE�ɂ����čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@ | |
| ��(2) �}�C�P���\��-���[���[�́A�����f�[�^�ƌv�Z�f�[�^�̖����́A�����̊�b�I�Ȕ�r���Ԉ���ĂȂ��ꂽ���ƂɊ�Â��Ă���B�����A�����f�[�^�ƌv�Z�f�[�^�́A�قȂ�Q�ƌn�ɑ����Ă���B���Ȃ킿�A�����f�[�^�́A�n���ɌŒ肳�ꂽ�Q�ƌnE �ɏ������Ă���A�n���̉^�����xV ���܂ތv�Z�f�[�^�́A���z�ɌŒ肳�ꂽ�Q�ƌnS �ɏ������Ă���B����āA�����̃f�[�^���݂��ɔ�r���邱�Ƃ́A�ŏ��Ŏ�v�Ș_���G���[�ł���B���̃G���[�͕K�R�I�ɁA���k�����Ƃ��̐��w�I�ȕ\���ł��郍�[�����c�ϊ������B�@ | |
| ��(3) �}�C�P���\��-���[���[�̎����f�[�^�ƌv�Z�f�[�^�́A�����A�n���ɌŒ肳�ꂽ�A��̓����Q�ƌnE �ɑ�������̂ł���A���S�Ɉ�v�������̂ƂȂ�B�_���̊ϓ_����́A���̂��Ƃ́A���k�����ƃ��[�����c�ϊ������}�C�P���\��-���[���[�̎����Ǝ��Ƃ͈�v���Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă��� (���Ȃ킿�A���k�����ƃ��[�����c�ϊ������������Ȃ����Ƃ��A�����f�[�^�ɂ���ďؖ������)�B�@ | |
|
��(4) ���[�����c�ϊ����̕����I�ȈӖ��́A���_�I�ȉ�͂̊J�n�_���A���̂悤�ɕ\�����Ƃ��A���炩�ɂȂ�B
(i) ���[�����c�̎��̐��_�̕W���I�ȕ��@�A���Ȃ킿�A���̔g�ʂ̕������ւ́A�K�����C�ϊ��̓��� (�}��) �Ƃ������@�B (ii) ���W�́A���݂ƕϊ��̌����B�܂�A��ʂɁA���W�̕ϊ��Ƃ����W�����݂����A���݂̂̂̍��W�́A�ϊ��ƍ��W�����݂���B���ۂɁA���̂��Ƃ́A���̂悤�ɂ��Ė��炩�ɂ����B (a) (�Ⴆ�A�}�C�P���\��-���[���[�̊��v�ɂ�����) �����̔g�� (���Ȃ킿�A���̓_) �́A�����I�ȑΏە�L �ł���B���W�nS (���Ȃ킿���z) �ɂ���������̔g�ʂɑ���������́A���̕\���ŗ^������B �@�@�@xL=ct ������c �͐^��ł̌����x (����Ox ���̐��̕����ւƓ`�d�����) �ł���At �͎��Ԃł���B (b) �����I�ȓ_ (�Ⴆ�A�}�C�P���\�����[���[�̊��v�̋��ł���A����͒n�����Ӗ�����E �́A���W�nE �ɂ���) �́A����M �ł���B�K�����C�ϊ��́AS �n��E �n�ɂ�����A�_M �̍��W�ɊW���Ă���B �@�@�@xM = Vt + x��M �����ŁAV �́AOx ���̐��̕����ɂ�����AS �n�ɑ���AE �n�̉^�����x�ł���(V��c)�B (c) �����̔g�ʂɂ�������������ւ́A�K�����C�ϊ��̓��� (�}��) �́A���W�Ԃ̓��������Ӗ�����B �@�@�@xM(t) = xL(t) ����M ��L �̍��W�Ԃ̓������Ƃ́A����M ��L �́A�݂��̌��� (��v) ���Ӗ����Ă���B�������āA���̂悤�ȓ��� (�}��) �̕����I�ȈӖ��́A����M ��L �́A�݂��̌��� (��v) ���Ӗ����Ă���B (d) ���ɁAxM(t) = xL(t)��t �ɂ������鎮�ł���A�}�C�P���\��-���[���[�̎����ɂ���āA�����^������B �@�@�@t = D/(c�|V) (S�n�ɂ�����) �@�@�@t = D/c (E�n�ɂ�����) ������D�́A���v�̌��̒����ł���B (e) xM = xL (S�n�ɂ�����) �� x��M = x��L (E�n�ɂ�����)�̓��������A�C�ӂ̎��Ԃ̏u�Ԃɂ����āA�ς��Ƃ������Ƃ́A���[�����c�ϊ� (��) �ɂ�����A���̂悤�Ȍ��ʂƂȂ�B �@�@�@xM = ��(x��M + ��x��L), xL = ��(x��L + ��x��M) �@�@�@xL = ct, x��L = ct��, �� �� V/c �@�@�@�� �� (1 – ��2)1/2 (���k���q) (f) ���[�����c�ϊ����ɂ��A�C�ӂ̏u�Ԃɂ����āAxM = xL �� x��M = x��L�̓��������ς��Ƃ������Ƃ��]���B�������āA���[�����c�ϊ��̕����I�ȈӖ��́A����M��L���A�C�ӂ̏u�ԂɁA�݂��Ɍ��� (��v) ���邱�Ƃ��A���[�����c�ϊ������Ӗ�����Ƃ������ƂɂȂ�B�@ |
|
| ��(5) �}�C�P���\��-���[���[�̎��́A�X�̌��̓_L���A����u�ԂɁA���v�̋�M�Ɠ����Ƃ���ɂ���Ƃ���������\�킵�Ă���B����āA��v (����) �_�̋�ԍ��W�ƁA��v�̎��Ԃ́A�����̎��ɂ����Ē萔�l�ƂȂ�B�@ | |
| ��(6) ��ڂ̘_���G���[�́A��v (����) �_�̋�ԓI�ȍ��W�ƈ�v���Ԃ��A���[�����c�ϊ����ɂ�����ϐ��ł��邱�Ƃł���B�}�C�P���\��-���[���[�����̊ϓ_�ɂ��A���̃G���[�́A�X�̌��_L���A�C�ӂ̏u�Ԃɂ����āA��M�Ɠ����Ƃ���ɂ���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B���̌��ʂƂ��āA��ԍ��W�ƁA���̎��Ԃ̊W�������B�������A���̂悤�ȊW�̑��݂́A���̂��ƂƁA�Η�����B(i) �����x�s�ς̌��� (�Ȃ��Ȃ�A���͏�ɁA���̌����邢�͎�Ƃ��čl�����邩��ł���)�B(ii) ���Ԃ̖{��[4,8]�B�@ | |
| ��(7) �O�ڂ̘_���G���[�́A���[�����c�ώ������k���q�����܂�ł���Ƃ������Ƃł���B���k���q���́A���z�ɑ��Ă̋�M (���Ȃ킿�A���̌��Ǝ�Ƃ���) �̓����ƁA��L�̓����Ƃ����A���݂̓Ɨ��ȓ������A�ˑ����������ւƕς���B���̂��Ƃɂ��A���̑��xc�̏�ŁA���̑��xV�̈ˑ���������AV/c <1�̌`���ƂȂ�B����ɁA��ԂƎ��Ԃ̊Ԋu�́AV�Ɉˑ�����悤�ɂȂ�B���ʓI�ɁA���k���q�͌����x�s�ς̌����ƑΗ�����B�@ | |
| ��(8) �����x�s�ς̌����́A�C�ӂ̎Q�ƌn�ŕς��B���ہA�^��ł̌����x�����̌����̑��x�ƓƗ����Ă���Ƃ���ƁA����͂܂��A���̌����̑��x�̕ω��ƓƗ����Ă��邱�ƂɂȂ�B�@ | |
| ��(9) �����x�̕s�ϐ��́A�����ÓT�͊w�̕����_�ł͂Ȃ��A�ʎq�̑����̈�ł�����q�ł���Ƃ��������ɂ���Đ��������B����Q�ƌn�ɑ���A�C�ӂ̗ʎq (���ɁA���q) �̓����́A��ΓI�ȓ����ł���[6,9]�B��ΓI�ȓ����́A�Q�ƌn�̑I���ɂ͂��Ȃ� (���̂��Ƃ́A���x���Z���_���ς����Ȃ����Ƃ��Ӗ����Ă���)�B�@ | |
| ��(10) �A�C���V���^�C���̎�E = mc2 (������m�͕����_�̎���) �͐������Ȃ����A�Ȃ����Ƃ����ƁA1�ƁA���̓��� (1�P��) �Ώۂł͂Ȃ��A�قȂ� (���݂ɓƗ���) �ΏیQ���A�����Â���ʂ̏�@���_���I�Ȍ��ł��邩��ł���[6,9]�B����āA����͎l�ڂ̘_���G���[�ł���B�@ | |
|
��L�̂��Ƃ���A���̂��Ƃ�������B
(a) ���ꑊ�ΐ����_�͐�ɐ������Ȃ��B (b) �����x�s�ς̌����́A�V�����ʎq�_�̎Q�Ɠ_�ł���[6,9]�B�@ |
|
|
���Q�ƕ���
[1] T.Z. Kalanov. �}�C�P���\��-���[���[�����Q�̐��������_��� (Correct theoretical analysis of the Michelson-Morley experiments). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 11-12 (1995) p. 22. [2] T.Z. Kalanov. ���[�����c�ϊ��̔����̏ؖ� (Proof of non-correctness of the Lorentz transformation). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 1-2 (1996) p. 32. [3] T.Z. Kalanov. ���Ή^���̗��_�̂��߂� (For the theory of relative motion). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 12 (1997) p. 15. [4] T.Z. Kalanov. ���Ԃ̗��_�̂��߂� (For the theory of time). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 5 (1998) p. 24. [5] T.Z. Kalanov. �����_�̗͊w�F������ (Kinematics of material point: modern analysis). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 7 (1999) p. 9. [6] T.Z. Kalanov. E �� mc2 : �������̎��Ԃ̍ł�������������� (E �� mc2 : The most urgent problem of our time). Doklady Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan, No. 5 (1999) p. 9. [7] T.Z. Kalanov. ���ΐ����_�̊�b�ɉ������_���I�Ȑ��X�̌��ɂ��� (On logical errors lying in the base of special theory of relativity). Bull. Am. Phys. Soc., V. 46, No. 2 (2001) p. 99. [8] T.Z. Kalanov. ���Ԃ̖{���ɂ��� (On the essence of time). Bull. Am. Phys. Soc., V. 47, No. 2 (2002) p. 164. [9] T.Z. Kalanov. �ʎq�_�̐V������b�ɂ��� (On a new basis of quantum theory). Bull. Am. Phys. Soc., V. 47, No. 2 (2002) p. 164. �@ |
|
| �@ | |
|
���߂��@�@���߂�(�ڍ�)�@�@�@�� Keyword�@�@�@�@ |
|