 �@ �@
��15���I�@���l�T���X / ���ň���p�̔��� |
  
|
|
���l�T���X�Ő����B���l�T���X�̎O�唭���̈���ň���p���h�C�c�̃O�[�e���x���N�ɂ���Ĕ������ꂽ�B���̋Z�p�́A15���I���܂łɃ��[���b�p�e�n�ɓ`���A��v�ȓs�s�Ŋ��ň���p�ɂ�������n�܂����B����15���I�������琢�I���܂ł̖�50�N�ԂɈ�����ꂽ���{�́A���ɃC���L���i�u��(Incunabula)�ƌĂ�Ă���B�C���L���i�u���Ƃ������t�́A���e����Łu�h��(��肩��)�v���Ӗ����Ă������A�]���āu���̔��B�̂͂��߁v�Ƃ����Ӗ���15���I�̈���p��\�����A�₪��15���I���{���̂��Ӗ����閼���Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B�����w��A1501�N�ȍ~�Ɉ�����ꂽ���̂Ƌ�ʂ���Ă���B���̔����́A�����̐�����]���̎ʖ{�����v���E�����ɂ��A�V�����m����v�z�̕��y�ɑ傫�Ȗ������͂������ƂƂȂ�B |
��1�D���l�T���X�Ƃ�
�@
15�`16���I�̉��B�̓��l�T���X���ł���B���l�T���X�́A�Đ��E�����̈ӂł���A����͂ƌ��т��Ă��������I�ȑ̐�����l�Ԑ����d�����邱�Ƃ����߁A�v�z�╶�w��|�p�ɌÑ�M���V����[�}�����̕��������߂镶���I�ȉ^�����W�J���ꂽ�B���|�����Ƃ��w�|�����ƌ����Ă���B���l�T���X�́A�k���C�^���A�̓s�s�������f�Ղŗ������A�x�����H�Ǝғ����x�z�����l���������Ƃ�w�i�ɃC�^���A�Ŏn�܂�A����ɉ��B�e���Ɏs���̉^�������łȂ��{�앶���Ƃ��Ă��L�܂����B
�@
���l�T���X���˂̒n�ł���C�^���A�͒n���C�ɓ˂��o�������̒n�̗�����A11���I����7���I�Ȍ㑱�����C�X�����̒n���C�x�z��������ƊC����Ճ��[�g���m�ۂ����B�C�^���A�͒n���C���Ղ̒��S�Ƃ��ă����@���g�f��(�����f��)�Ŋ�����悵���B�����@���g�f�ՂƂ́A�A���r�A���l�Ȃǂɂ���ăG�[�Q�C���݂���G�W�v�g�Ɏ���n���C�������ݏ����ɂ����炳�ꂽ�Ӟ����͂��߂Ƃ��鍁�h���⌦�Ȑ��i�E��E������Ȃǂ̕��Y��������Ɛ����n���C���݁E�k�C���݂̍��X�֓]�����A�����ւ͋�⓺�E�ѐD���E�I���[�u�����������炷����f�Ղ̂��Ƃ������B�W�F�m�o�⃔�F�l�c�F�A�͊C�m�f�Փs�s�Ƃ��ăt�B�����c�F��~���m�͎�H�Ƃ◬�ʂ̒��S�Ƃ��ď��H�Ɠs�s�Ƃ��Ĕɉh�����B�x���古�l�B�͕����M���Ƃ̐킢�ɏ������s�s�̎x�z�����l�����A�s�s���a�������グ���B�C�^���A�́A�������̉����A�����A���a���ɍו�������A�����e���Ƃ������̐₦�Ȃ�����ł��������B�k�C�^���A�̋��a���ł́A����̌��Ђ���M�ƒm�������A�V�������������o�����߂ɌÑ�M���V���ƃ��[�}�̕��������A�����I�ȑ�������l�Ԓ��S�̍l���������Ƃɂ������R�Ɗv�V��l�X�ȕ���œW�J�����B�Â�����̗��j�I�������⒤���̌���������ɍs����l�ɂȂ�A�G��⌚�z�Z�p�Ɋw�������ꂽ���ߖ@�⒲�a�̔���Nj�����悤�ɂȂ����B���l�T���X�����́A�e�n�ő����̑�������ł����������A�}�j���t�@�N�`���A�̊���������ɔ��������Ղ̊g��A��q�C����̖��J���A����p�A�z�R����Z�p�A�������ǁE�^�͂⋴�����̐v���z�Z�p�A�U���E�h��p�̌R���Z�p�ȂǗl�X�ȋZ�p�̖ʂŊ��C������������ł������B�܂��A�l�X�Ȓm���̋z���ɔ����m�I��������悤�Ȋw�������ɐ���ƂȂ��Ă����B�@ |
��2�D���l�T���X���̌R���Z�p�ƃ_���B���`�̋@�B�Z�p
�@
15���I�̉��B�́A���ʌp����ُ@���Ԃ̗��Q�W�ȂǂŐ푈���J��Ԃ��ꂽ����ł��������B��C���푈�ɗp������悤�ɂȂ�A�����̋R�m���ɂ��`�Ԃ̐푈�ƈقȂ�V���Ȑ푈�̌`�����悤�ɂȂ����B
�@
�����Ɏ�H�Ǝ҂����͐E�ƕʂɃM���h(���Ǝґg��)����葊�ݕ}���ƋZ�p�̈ێ��E�`���ɓw�߂Ă����B�M���h�����ł͐e���A�E�l�A�k��̊K�w���ł��A�Z�p�����̈ێ����}��ꂽ�B�M���h�͎���ɁA���v�ی�̂��ߐV���Ȑe���𐧌����M���h���x����낤�Ƃ��A���R�������r�����ꎟ��ɐV�Z�p�̊J���ɏ��o�����Z�p�̌Œ艻���������炵���B���l�T���X���ɂȂ�ƁA�����s�s�x�z�҂͎x�z���m���̂��ߌR���Z�p�����߂Ƃ���n�ӍH�v�ɕx�Z�p�҂����߂��B�|�p��g�ɕt���Z�p�̊v�V�����݂�V�����`�̍H�w��(�R���Z�p��)�����܂�A���l�T���X���̋Z�p�ƌ|�p�̋�ʂ͂Ȃ��A�Z�p�҂͖@����M����x�z�҂ƂȂ����x���B�̌o�ϓI�����̂��ƂŊ����B��������ɂ͒P�Ȃ�G��⒤���̌|�p�ƂƂ��Ă����łȂ��A���z�E�y�E�@�B���̋Z�p�҂ł���Ȋw�ɂ����������\�ɏG�ł��H�w�҂����߂�ꂽ�B
�@
���l�T���X���Ɋ�����l�Ƃ��ă��I�i���h�E�_�E���B���`�����グ�Ă݂�B���I�i���h�́A�|�p�Ƃł���Z�p�҂ł���Ȋw�҂ł�����A�����ʂō˔\���������u���\�̓V�ˁv�Ƃ������Ă���B���̎���́A������z��Ȃǂ̌R���ɋZ�p�̏d�_���u����Ă����B���I�i���h���R���ږ��������l�ł�����A�u���i�E���U�v�E�u�Ō�̔ӎ`�v���̊G��`������ƂƂ��Ė���m���Ă���B�G��͏��Ȃ������̂����A���I�i���h��������e��5,000�]���������Ă���B�����ɂ́A�|�p�E�Ȋw�E�Z�p�̑���ɂ킽�镪��̃X�P�b�`�Ɛ������L����Ă���B���̒��ł��@�B�Ɋւ��邱�Ƃ������c����Ă���B�R���Z�p�Ƃ��āA�U��@�B�E��ԁE���e�g�C���̍\�z��������B���R�n���̐���Ɏ��g���́A�n�̂�����p�����ώ@���A�\�ʓI�����łȂ���U�ɂ������̊ώ@���s���Ă���B�l�̂����l�ʼn�U�ɂ��ڍׂȊώ@���c���Ă���B�����̋L����Ă����e�͓������łɎg���Ă����ł��낤���u�ނ��X�P�b�`�������́A����̍\�z��`�������̂����背�I�i���h�̌����m�[�g�ł��낤�B�����̂��Ƃ��猩����悤�ɁA���I�i���h�́A���R��[���ώ@���A�|�p�ł��Ȋw���Z�p���d�ˍ��킹�����̂̍l���������Ă������Ƃ�����B�������A���ۂɃ��I�i���h�̒��z�������̋@�B�Z�p�ɂǂ̂悤�ȉe����^�������͒肩�łȂ��B�@ |
��3�D�}�j���t�@�N�`���A�Ɗ��������鐶�Y����
�@
�����̏I��荠�ɏ��i���ʂ����������n�߁A�C�M���X���͂��߂Ƃ������������ł͖ѐD���Ƃ�����ƂȂ�A�K�͂��g�債�ѐD���̃}�j���t�@�N�`���A(�H�ꐧ��H��)���ł����B�����B����܂ł̎�H�Ƃ́A�Ɠ��H�Ƃ����S�Ő��i�ɂȂ�܂ő啔���̐��Y�H���������Ă����B���i���ʂ�����������Ǝs��g��Ƌ��Ɍo�c�K�͂��傫���Ȃ�A�}�j���t�@�N�`���A���Y�̐����Ƃ�悤�ɂȂ����B�ŏ��͑����̎�H�Ǝ҂��ق�����A�X������I�ɐ��Y����̐��ł��������A����ɍH����ōH���Ɖ����鐶�Y�̐��ɂ��A���Y���̌�����͂���悤�ɂȂ����B�l�X�Ȑ�������Ń}�j���t�@�N�`���A���Y�̌n������ƂȂ�A���Y�H���͍ו������ꂻ��Ɍg���J���҂̎g�p���铹��́A���ړI�Ɏg�������A���Ɖ������d���ɓK�����������������悤�ɂȂ����B��H�Ƃ̍H��Z�p�̒~�ςƂ��Ă̋@�B�����v�̐����Z�p�͏d�v�Ȃ��̂ł���B�@�B���v�͂��ǂ��ŒN���ŏ��ɍ��o�������͒f��ł��Ȃ����A14���I�����ɂ͉��B�e�n�ŏC���@�̒��ŋK���������������ێ����邽�߂ɓo�ꂵ���B14���I������ɂ͎���Ɏs�������Ɍ����̌����ɓ����v�Ƃ��ďo�������B14���I������ɂ̓C�^���A�Œ莞�@���������ꋤ�ʂ̎��Ԃ邱�Ƃɂ�蒁���̂���̐����Ƃ���悤�ɂȂ�A�莞�@�͎���Ɋe���ɍL�����Ă������B14���I���ɂ͐��쓮�̎��v�ɕς��Q�����[���}�C�œ��������v���ł����x�����サ�����p���^���v�������悤�ɂȂ����B16���I�����ɂȂ�ƁA�̍z�Ƌ������H�̗D��Ă�����h�C�c�𒆐S�Ƃ��ăM���h����������A���v�͑g�D�I�ɗʎY�����悤�ɂȂ����B���v�t�����̎����Ă������v�̐����Z�p�͑��̍H�ƕ���ɂ��L����A�H��@�B�����ǁE�l�Ă�����Ă����B�@ |
��4�D����p�̔���
�@
����ɕK�{�Ȃ��͎̂��ł���B���ƈ���p�̓��l�T���X�ɂ�����ȉe����^�����B���͒����㊿����ς�105�N�ɏ��ʍޗ��̌��z�̑�p�i�Ƃ��ĐA�����@�ۂ̎���������B���̐����Z�p�̓V���N���[�h��ʂ�A13���I�ɂȂ�ƃ��[���b�p�ɂ��`���A�����H�ꂪ�ł��A15���I�����ɂ̓��[���b�p�e���ɐ����H�ꂪ�ݗ����ꂽ�B�����̌����͓����͈����∟���z�̂ڂ�������Ƃ��č���Ă����B�������Y���ꃋ�l�T���X���͏��̓`�B��i�Ƃ��Ė{�������o�ł����悤�ɂȂ����B���̕��y�ɂ��A�G�W�v�g���Y�̃p�s���X��10���I�Ɏ��̎g�p���n�܂�Ƌ��Ɏp�������A�������ʂɎg�p����Ă��������ȗr�玆(parchment)�����ƒu����������B���ɕ������L�^���邱�Ƃ́A�L���ꂽ���𑁂��L���n��ɍL���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A����ꂽ�ʖ{�ł͂����Ɍ��E������B�����ő�ʈ�����l���o���ꂽ�B�h�C�c�E�}�C���c�̃O�[�e���x���O(Johannes Gutenberg�F1400���`1468)�́A���������Â���ɒ��킵�A�����p���������������������B��������p�C���N���J�������B����@�͍L���p�����Ă����������i�鈳�k�@�����p���v���X���̈���@���J�������B1454�N���ɍŏ��̈���u42�s�����v�������B���̌�A1500�N�܂łɈ���H��̓��[���b�p�e�n�ɐ��S�̍H�ꂪ�ł����B
�@
���̎���́A�����E�v�z�̍��g�����}���郋�l�T���X���ɓ���A�@�����v���}���悤�Ƃ���Ƃ��A��������������L�����O�ɔЕz���ꂽ�B��������̔����́A������ʂ��ēǂݏ����̔\�͂�V�m�����A��ʑ�O�ɍL�܂��Ă������B�l�X�ȕ���ő����̖{������o�ł���A�����ǂl�X�̍l�����ɉe����^�����Ȋw�̑䓪�ƋZ�p�̍L����ɉe����^���邱�ƂɂȂ����B�@ |
��5�D�z�R����Z�p�ƍH��Z�p�̐i�W
�@
�C�^���A�͓����f�ՂŔɉh���A15���I���߂���ƃh�C�c�͍z�Ƃ�����ƂȂ�H�Ƃ𒆐S�Ƃ��Ĕ��W�����B�f�ՂőΉ��Ƃ��Ďx������̎��v���������A��h�C�c�̋�z�R�̍̌@������ƂȂ����B�܂��A��C���̕���̐������H�Ǝ҂ɂ��������v�̊g��ȂǂƋ��ɍz�R�J����������悵���B�}�j���t�@�N�`���A�ŋ������̓��������ł��A�������H�Z�p�̔��B������ƂȂ�A�@�B���v�̐����S�C���Y�̂��߂̍H��p�@�B���o�������B�H��@�B�̔��B���@�B�Z�p�̔��W�̍�����x�����B�������v�̍��܂�͍z�R�����Z�p�ɊS���W�܂�A�����Ɋւ��钘���@�B�Ɋւ��钘�삪16���I���ɑ������ŏo�ł��ꂽ�B
�@
���l�T���X���̍H�w����̎�Ȓ��҂ƒ���������Ă݂�B
�@
�� V.�r�����O�b�`���́A�C�^���A�̖���w�҂ŋ����̐�发�Ƃ��Ē���u�s���e�N�j�A(�H�p)�v���o�ł���A�����z�R�Ƃɉe����^�����B�z�Ώ���������̗n�Z�@�Ȃǖ���̕��@���̌n�I�ɏ�����Ă���B���悤�ɂȂ����B
�@
�� G.�A�O���R���́A�h�C�c�̍z�R�w�ҁA��҂ōz���w��n���w�����������B�u�f�E���E���^���J(�����ɂ���)�v�S12���̒��삪���㔭�����ꂽ�B
�@
�� A.���b�����́A�C�^���A�̌R���Z�p�҂ŁA���w�A�R���Z�p�A�y�؋Z�p���w�сA�u��X�̍I���ȋ@�B�v�����B������l�T���X���\����@�B�}�W�ł���B�����̋Z�p��m��d�v�ȕ����ł���B
�@
�� J.�x�b�\���́A���I�i���h�̌�p�҂Ƃ����t�����X�{��̋Z�p�҂ł��邪�ڂ������Ƃ͕s���ł���B�u�@�B�Ɗ��̌���v���Ă���B�@ |
��6�D ���Ղ̔��B�Ƒ�q�C����̓����ƋZ�p�I�m���̑̌n��
�@
���l�T���X����15���I�͐��E�̍L�����V������������n���I�c���̎���ł��������B�C�^���A�𒆐S�Ƃ��Ēn���C���Ղ͐���ł��������A�n���C���݂Ɩk�C���݂Ɍ����A�����E�C���h�Ɏ�����Ղ͒��p����A���r�A���l�ɂ䂾�˂��Ă����B�A���r�A�̒���l������ɒ��ڂ̎���͉��B�ɂƂ��Ĕ��ȊS���ł������B���B�ɐ�삯�Ē����̓A�a�́A1405�N����1433�N�̊�7��ɂ킽��A����A�W�A�C��A�C���h�m���݁A�A���r�A�A�A�t���J���݂Ɖ������s���A�V���̊ϑ�����ܓx��m�蒆���Ŕ������ꂽ���C�R���p�X��p���C���h�m�̑�m���f���s�����B���B�ł��A����܂ł̒n�}�̋��m�肽���~���ƁA�C���h�Ƃ̒��ڎ���̉\����T�鎖������A�吼�m�ɖڂ�������ꂽ�B�C�^���A�ł͌��Ղ�����ɂȂ�A���������x�ꂽ�����C�R���p�X������A�C�}�̔��B������A�V���ϑ��ɂ��ܓx�q�@�̊m���A���l�T���X�����T���S�͉��B�l�̖ڂ�n���C����吼�m�ւƌ����������B
�@
15���I�ȑO�̉��B�C��Ŏg���Ă����D�ɂ́A�����D�̌`���Ƃ��Ėk���D�Ɠ���D���������B�k���D�͖k�C�E�o���g�C���݂̌��ՂŎg�p����A��{�}�X�g�Œ����`�̔��������͂��Ői�ޑD�Œǂ����̍q�C�ɓs���̂悢�D�ł���B�ǂ͑D�������Ɏ��t�����Ă����B����D�́A�n���C�ŗ��p���ꂽ�O�p��������ꂽ�D�ł������B15���I�ɂ͂���Ƃ����̑D�̓��������W�����D���o�ꂵ���m�q�C�ɑς�����悤�ɂȂ�A��m��������q�C����̖��J���ƂȂ����B����܂ł̉��ݍq�@�ɕς���m�q�C������ɂ́A���ʂ�m�邱�Ƃ͕K�v�s���ł������B���ʂ��������C�R���p�X�́A������12���I�����Ɏg�p����n�߂Ă����B���B����́A�S��V�R���ł����莥���������j���g�p���A�w�싛��w��j�Ƃ���ꐅ�ɕ����ׂĎg�p������̂ł������B13���I�����ɂ͒n���C��ł��g���n�߁A�C�^���A�ł͊C�}�����B���A�q�C�p��Ȃǂ삷��E�l���o�����A�������C�R���p�X�ւ̉��ǂ��s���A���݂̕����̉t�̎��R���p�X���o��19���I�܂ŁA�q�C���x����q�C�p��Ƃ��Ă����Ƃ��d�v�Ȃ��̂ƂȂ����B
�@
��q�C����̐�삯�Ƃ��čq�C�Z�p�̔��W�ɍv�������̂́A�|���g�K���̃G�����P�q�C���q(Henrique o Navegador:1304�`1460)�ł���B�w�҂⏑�����W�ߍq�C�p��n���w���������鋒�_�����A�q�C�p��D�̂┿���Z�p�̉��P���s�����B�����ŁA�D�����琬���D���O�m�p�ɉ��ǂ��T���q�C�Ɍ����킹�A�A�t���J���C�݂�쉺����q�H���J���B�o�[�\���~���[�E�f�B�A�X�́A1488�N�ɃA�t���J�嗤��[�̊�]��ɓ��B�����B���̌�A���@�X�R�E�_�E�K�}�́A1497�`1499�N�Ɋ�]������C���h�܂ł̍q�C�ɐ��������B�|���g�K���̓C���h�q�H���J�f�Ղ�Ɛ肵�A��s���X�{���͔ɉh�����B����܂Ō��Ղʼnh���Ă����W�F�m�o��׃l�c�F�A�͐������邱�ƂɂȂ����B�C�^���A�E�W�F�m�o���܂�̃N���X�g�t�@�E�R�����u�X�́A�C�^���A�̓V���w�҃g�X�J�l�����吼�m�q�H�ɂ��C���h���B�̉\���������������Ƃ�(���̍��̐��E�n�}�ɂ͓�k�A�����J�嗤�͂Ȃ�����)�A�X�y�C�������C�T�x��1���̉������A���ɍq�H�����A���C���h�����ɓ��B�����B���̌��k�A�����J�嗤�̔����Ƒ����m�̔����Ɍ��т����B�}�[�����̎w������5�ǂ̑D�c�͑���ȋ��̂���1�ǂ��������E������ʂ����A�n�������̂ł��邱�Ƃ��n�߂Ď������B���̌���T���q�C�ȂǑ����A�q�H���J���Ղ�A���n�̊m�ۂɏ��o�����ƂƂȂ����B
�@
���C�R���p�X�̎w����������͖k�ɐ��̕����Ɍ����ƐM�����Ă������A�q�C���Ɏ��j�̎w��������ʂ̖k���̕�(�Ίp)�⎥�j�̌X������(���p)�����邱�Ƃ������悤�ɂȂ����B���̂悤�Ȏ��n�ɋN���������ۂ�������邽�߂ɁA�����I���@�̏d�v����������̂��E�B���A���E�M���o�[�g(William Gilbert�F1544�`1603)�ł���B�M���o�[�g�́A�n�������ł���ƍl���A���`����(���n��)�����������s�����B���̎������玥�̎w�ɐ��A�Ίp�╚�p�̌��ہA���̋z�������́A����ɐÓd�C�̐��������������u���C�ɂ��āv(De agnete:1600)�삵�A��̓d���C�w�̊�b��z���d���C�w�̑c�Ƃ����Ă���B
�@
���B����Z�p�̂��ƂŁA�l�X�Ȗ��_�����������K�v�ƂȂ����B�Ⴆ�z�R�ł́A�B���̍\�z�A�B���̊��C�E�r���E���o�A���̂��߂̐��Ԍ����Ȃǂ̂ق��ɒn���w�I�E�n���w�I�E�z���w�I�m�����v�����ꂽ�B�l�X�Ȓm���̏W�ς��K�v�ƂȂ�A�����ɂł������{�I�Ȋw����������w�ɑ��A���H�I�ȋZ�p�w��������w��������邱�Ƃ��K�v�Ƃ����悤�ɂȂ����B�Z�p�Ɋ֘A�����m�����w�⊈���ɑ̌n���������Ƃ��A�Ȋw��Z�p�̐i���ɖ��������Ƃ�����B �@�@
�@ |
 �@ �@
���u42�s�����v��t 1455�N�� |
   �@
�@
|
Gutenberg, Johannes.(1397?-1468)
�@
A Noble Fragment Being a Leaf of the Gutenberg Bible,ca.1455.
�@
�{���́A����p�̑n�n�҃O�[�e���x���N�������������ň���p�ɂ��A���߂Ĉ�����ꂽ���e���ꐹ���Ƃ��Ēm���Ă���B���s������160����180���ƌ����A���̂�����4����1���r�玆�ɁA�c��4����3�����Ɉ�����ꂽ�B����������̂�48���ŁA���̂������{��21���Ƃ���Ă���B��ʓI�ɂ́u�O�[�e���x���N�����v�Ƃ��ėL���ł��邪�A1�ł��T��42�s�ň������Ă��邽�߁u42�s�����v�Ƃ��Ă�Ă���B���̗�t�́A1921�N�ɃA�����J�ɂ������s���S�{���o���o���ɂ���j���[���[�N�Ŕ���ɏo���ꂽ���̂̈�ł���A�������r�L�̈ꕔ���ő�23�͂̓r�������25�͂̓r���܂łł���B��24�͂ł́A�u�E�E�E�ڂɂ͖ڂ��A���ɂ͎��������āE�E�E�v�Ƃ����L���Ȃ�����̕������܂܂�Ă���B |
���O�[�e���x���N����
�@
(Gutenberg Bible)�@15���I�Ƀh�C�c�̃��n�l�X�E�O�[�e���x���N�����ň���Z�p��p���Ĉ���������E���̈�������B�O�[�e���x���N�����͓��������Ƃ��L�����ʂ��Ă������e���ꐹ���u�����K�[�^�v���e�L�X�g�Ƃ��Ă���B�قƂ�ǂ̃y�[�W��42�s�̍s�g�݂ł��邱�Ƃ���u�l�\��s����(42-line Bible�A42B)�v�Ƃ��Ă�A���@���W���[���E�}�U�����̃R���N�V�������甭�����ꂽ���j�I�o�܂���u�}�U��������(the Mazarin Bible)�v�Ƃ��Ă��B�r�玆�Ɉ�����ꂽ���̂Ǝ��Ɉ�����ꂽ���̂�����A180����������ꂽ�ƍl�����Ă��邪�A�����_�ő��݂��m�F����Ă���͕̂s���S�Ȃ��̂��܂߂�48���ł���B���{�ł�1987�N�ɊۑP���w���������̂��c��`�m��w���ۑ����Ă���B���̈���ɗp����ꂽ�����́u�l�\��s�����v�̖��̂���uB42�v�ƌĂ�Ă���B
�@
�M���̎q�Řr�����̋��H�E�l�ł������O�[�e���x���N�͊��ň���̋Z�p�����p���ɐ����A�}�C���c�̎��Ɖƃ��n���E�t�X�g���玑���Đ����̈���Ɏ�肩�������B�O�[�e���x���N�͓��������Ƃ��悭�ǂ܂�Ă������e���ꐹ���u�����K�[�^�v���e�L�X�g�Ƃ��đI���A�����K�[�^�����܂��܂Ȉٖ{�����݂������߁A13���I�Ƀp����w�ōZ�����ꂽ�u�p���{�v�����C���e�L�X�g�Ƃ��A���̂ق��̃e�L�X�g���K�X�Q�Ƃ����B�O�[�e���x���N�����͌��ݗ��ʂ��Ă��鐹���Ƃ͈قȂ��Ă���A�J�g���b�N����̗��j�̒��Ő��T����͂����ꂽ�u�G�Y�����O�v����сu�G�Y�����l�v����сu�}�i�Z�̋F��v���܂݁A�e���̖`���ɂ̓q�G���j���X�̌��t���t����Ă���B�����ɂ̓q�G���j���X���m���̃p�E���k�X�ɂ��Ă��莆�������߂��Ă��邪�A����͒����̐����̓`���ł������B�O�[�e���x���N�����͈ꌩ�J���[�Ɍ����邪�A�{�����̂��͍̂��F�ŒP�F�������A���Ƃ�����蕶���Ə���r����ŏ����������Ă���B
�@
�O�[�e���x���N�����̈���́A1455�N2��23���ɊJ�n���ꂽ�B���ߗr�玆��45��������ꂽ�Ƃ�����B�r�玆�ł̂����A����������̂͊��S�Ȃ��̂�4���ƕs���S�Ȃ��̂�8���̍��v12���ł���B���Ɏ���135��������ꂽ�ƍl�����Ă��邪�A���ł͊��S�Ȃ��̂�17���A�s���S�Ȃ��̂�19���������Ă���B
�@
�O�[�e���x���N�����͒��炭�Y�ꋎ���Ă������A1763�N�Ƀt�����X�̃t�����\���E�M���[���E�h�E�r���[��(Francois Guillaume de Bure)���}�U�������@���̃R���N�V��������u�l�\��s�����v���B���̏d��ȉ��l�ɋC�Â������ƂŁA���̑��݂��L�����ڂ��ꂽ�B���̂��Ƃ���u�}�U���������v�ƌĂ�邱�Ƃ�����B
�@
���O�\�Z�s����
�@
�s������u�O�\�Z�s�����v�ƌĂ�鐹�������ăO�[�e���x���N�̎�ɂ���Ĉ�����ꂽ�A���邢�́u�l�\��s�����v��葁��������ꂽ�ƍl����ꂽ���Ƃ����������A����̌����҂����̓O�[�e���x���N����uDK�v(�h�i�g�D�X��J�g���R���̈Ӗ�)�ƌĂ�銈���Z�b�g��������A���x���g�E�v�t�B�X�^�[(Albert Pfister)��1460�N���������s�������̂ƍl���Ă���B�u�O�\�Z�s�����v���u�l�\��s�����v����̂��̂ł���Ƃ������Ƃ����߂Ď������̂�19���I�̌����҃J�[���E�f�B�A�b�R(Karl Dziatzco)�ł���B�u�O�\�Z�s�����v�͂킸��15�������������Ă��Ȃ��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���v���j�E�X�u�������v��3�� 1472�N |
   �@
�@
|
Plinius Secundus, Gaius.(23-79)
�@
Historia Naturalis.
�@
�v���j�E�X�́A���[�}�̐����ƁA���q�ƁB�w��A���ɔ����w�ɊS���[���A�ނ̌�������B��̒��삪���́u�������v�ł���B���̌��{�́A�Ñ�M���V����胍�[�}�ɂ�����2,000�_�̏�������2�����̎������o���Ă܂Ƃ߂����̕S�Ȏ��T�ŁA�S37������Ȃ���ɖc��ȁA�������悭���ڂ��ꂽ�����ȑS�����̂悤�Ȃ��̂ł���B�{���́A���[�}���̊����̊����҂ł���t�����X�l�j�R���E�W�����Z���̎�ɂ���āA���F�j�X�ň�����ꂽ���̂ł���B19���I���ɃC�M���X�Ŏ��Ɣň�������J�݂����v�E�����X�ɉe����^�����B �@ |
���v���j�E�X�̔�����
�@
(Naturalis Historiæ)�@���[�}�̑�v���j�E�X�����������B�S37���B�n���w�A�V���w�A���A����z���Ȃǂ�����m���Ɋւ��ċL�q���Ă���B�������̐�s�����Q�Ƃ��Ă���A�K�������{�l�������A���������������ł͂Ȃ��B���b�A���l�A�T�l�ԂȂǂ̔�Ȋw�I�ȓ��e�������܂܂�A�w��I�ȑ̌n�����S�ɐ����Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@
�Â�����m���Ă������A���Ƀ��l�T���X����15���I�Ɋ��ň���Ŋ��s����Ĉȗ��A���[���b�p�̒m���l�����Ɉ��ǂ���A���p����Ă����B�Ȋw�j�E�Z�p�j��̋M�d�ȋL�q���܂ނق��A�|�p��i�ɂ��Ă̋L�q�͌Ñネ�[�}�|�p�ɂ��Ă̎����Ƃ��Ĕ��p�j������d���ꂽ�B�܂��A���z���w�ɂ��e����^�����B
�@
���������ɋL���ꂽ����
�@
�v���j�E�X���L�����w�������x�ɂ́A���݂��鐶���ɍ������āA�y�K�T�X�A���j�R�[���A�X�t�B���N�X�A�}���e�B�R�A�A�T���}���_�[�Ƃ������L���Ȃ��̂���A�R���R�b�^�A�A���t�B�X�o�G�i�A�J�g�u���p�X�ȂǁA���܂�m���Ă��Ȃ����̂܂ŁA�����̉������L����Ă���B
�@
���A�s�X(Apis) �E���ɎO�����^�̔���������Y���B�G�W�v�g�̐_���B
�@
���A���t�B�X�o�G�i(Amphisbaena) �G�`�I�s�A�ɐ��ޑo���̓ŎցB
�@
���G�A���[(Eale) �J�o���炢�̑傫���ŁA�]�E�̔��������A�ѐF�͍����邢�͉����F�ŁA�C�m�V�V�̊{�������A�ǂ̊p�x�ɂ����������Ƃ̏o�����{�̒����p���������B
�@
���J�g�u���p�X(Catoblepas) ���������n�ʂɐ��ꉺ���Ă��āA���̖ڂ������҂͒N�ł������ɐ▽����B
�@
���R���R�b�^(Crocota, Corocotta) �n�C�G�i�Ǝ����C�I���Ƃ̌�z�ɂ���Đ��܂������B�l�Ԃ⋍�̐���^����B
�@
���T���}���_�[(Salamandra) �g�J�Q�̂悤�Ȍ`�������A�S�g����_�ɕ����Ă��铮���B
�@
���X�t�B���N�X(Sphinx) �т����F�ŋ��Ɉ�̓��[������b�B
�@
���h���S��(Draco) �C���h�ɐ��ރh���S���͏ۂƐ키�ۂɁA�̂��������A�����Ȃ��悤�ɂ���B
�@
���g���g��(Triton) ���l�����̎p�������C�_�B
�@
���i�E�v���E�X(Nauplius) �D�̌`�������L�B
�@
���l���C�X(Nereis) ���l�����̎p�������C�̐���B
�@
���o�V���X�N(Basiliscus) �L�����i�C�J(���r�A��������)�ɐ�������ғł̃g�J�Q�̈��B���̖ڂŌ���ꂽ�҂͑����A�������͐Ή�����Ƃ�����B
�@
���t�F�j�b�N�X(Phoenix) �A���r�A�ɐ������A�傫���͘h���炢�ŁA��܂��͋��F�A���͐��A�K�N�F�̖т��_�X�ƍ�����A�͎̂��B
�@
���y�K�T�X(Pegasus) �G�`�I�s�A�ɐ������闃�̐������p�����n�B
�@
���}���e�B�R�A(Mantichora) �G�`�I�s�A�ɐ������A��͐l�ԁA�͎̂��q�A�K���̓T�\���̂悤�ŁA�l�Ԃ̐���^����Ƃ����B
�@
�����j�R�[��(Monoceros) �C���h�ɐ������A�n�̑́A���̓��A�ۂ̎��A���̔��������A�z�̒����ɍ����A������{�̊p�������Ă����֖҂ȏb�B
�@
�����E�N���R�^(Leucrocota) �n�C�G�i�َ̈�B���o�قǂ̑傫���ŁA���̎��A���q�̎�A���A���A���F�̓��A���ꂽ���A���܂ŗ����������A���̂����Ɉ�{�̘A��������������B�l�Ԃ̐���^����B�@�@
�@ |
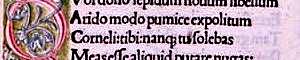 �@ �@
���g�}�X�E�A�E�P���s�X�u�L���X�g�ɕ킢�āv���� 1473�N |
   �@
�@
|
Thomas A Kempis.(1380?-1471)
�@
De Imitatione Christi.
�@
�{���́A�C���m���L���X�g�̋����ɏ]���Đ������ׂ����Ƃ������߂����ŁA�L���X�g���̌ÓT�Ƃ��Đ������̂����A�����炭�{���قǍL���ǂ܂ꂽ�{�͂Ȃ��ł��낤�B���e����̌����͉������o�ł���A���E�e����ɖꂽ�B�{���̒��҂ɂ��ẮA���S�N�̊ԁA�����̊w�҂����ɂ���ċc�_���������킳��Ă������A���݂ł̓h�C�c�̐_��v�z�ƂŐ��E�҂ł���g�}�X�E�A�E�P���s�X�Ƃ����A�E�O�X�e�B�k�X��̏C���m�Ƃ���Ă���B�{���ɂ́u�N����������������ƑF�����Ȃ��ŁA���������Ă��邩�ɒ��ӂ���v�Ƃ���A���҂��s���ł��邱�Ƃ́A�܂����҂̖{�]�Ƃ���Ƃ���ł���B�]���āA�����̒���N���s���ł���B�W���̏��́A�A�E�O�X�u���N�̈���ҁA�M�����^�[�E�c�@�C�i�[�ɂ���čŏ��Ɉ�����ꂽ���̂ł���B�@ |
���u�L���X�g�ɕ킢�āv
�@
(�L���X�g�ɂȂ炢�āADe imitatione Christi)�@�g�}�X�E�A�E�P���s�X�ɂ���ď����ꂽ�{�ŁA�J�g���b�N�̃N���X�`�����̗쐫�̖{�Ƃ��Ď����K���ɍL���ǂ܂ꂽ�B���e�����͓�����1418�N����ɏo���ꂽ�B���̒��Ґ������������A����ł̓P���s�X�̒����Ƃ݂Ȃ���Ă���B�u�L���X�g�ɕ킢�āv�́A14���I����15���I�̐_��I�h�C�c�E�I�����_�w�Z�̕����ł���A�@�����v�O�̃J�g���b�N�E�L���X�g���̂����Ƃ��̑�ȃf�B���H�[�V�����̎�����̈�ƔF�߂��Ă���B�C�G�Y�X��͌����ɌP���Ŏg�p����B���[�}���c�𒆐S�Ƃ���J�g���b�N������łȂ��A�����̃v���e�X�^���g�����̖{�ɍ����]����^���Ă���A���[�f�B�o�ł��o���Ă���B
�@
�W�����E�E�F�X���[�ƃW�����E�j���[�g���́A��S�ɉe����^���������Ƃ��Ă����Ă���B�S�[�h�����R�͂��̏��������Đ��ɕ������B
�@
���]1
�@
�u�L���X�g�̖͕�v�u�L���X�g�ɕ킢�āv�Ɩ��B�L���X�g���M���Ƃ��čL���ǂ܂���z���B�g�}�X�E�A�E�P���s�X�̒��Ƃ����B
�@
(Thomas a KEMPIS, 1379-1471)�́A�h�C�c�̃P�����i����ɑ����钬�P���y���Ő��܂ꂽ�_���`�҂ł���A�Z��c�Ƃ���C����ɓ���A�����������c��ł����B�h�i�ȏC���m�Ƃ��Đ��U��_�ɕ������l�ł���B���e����̎�ʖ{��300��ȏ�A������{�́A2000��ȏ������A�����I���ɁA�ƁA���o�ł���A19���I�ɂ͋ߑ��o���B1596�N�ɂɃ��[�}���a��{���o�Ă���B�w�R���e���c�X�����a�x�Ȃ郉�e���ꌴ��(Contemptvs Mvndi)�̃��[�}���|��ł���B
�@
�����ȍ~�́A�����̘a��(�R�ؖ�A�r�J��A���E�i���)���o�ł���e���܂ꂽ�B�M�k�ɂ�������Ղ����͂ɉ����A�쐫�̐[�����e���܂ꂽ���R�ł���B���T�̓I�����_���4���ł���B�e���ʁX�ɏ�����ė��z�����B��1-2���́A�ّz���B��3-4���́A��(Dominus)�Ƃ�����(Servius)�܂��͒�q (Discipulus)�Ƃ̑Θb�̌`�ŁA�u�S�Ă��̂Ă�A��������A���O�͑S�Ă����o����B�~����̂Ă�A��������A���O�͕����������o���B�v(3�F32)�Ƌ����Ă���B
�@
�u���Ƃ��A����ׂ����Ő����̑S�Ă�m��A������N�w�҂̐���m���Ă��A�_�̈��ƌb���Ȃ������Ȃ�A���̑S�Ăɉ��̉v�����낤���v(1�F1)�Ɛ����B���Ƃ��ƏC���҂�Ώۂɏ����ꂽ���̂ł���B��������ʐM�k�ɂ����ǂ���A�ÓT�I�����̈�Ƃ���Ă���B���e�́u��I�����̗L�v�Ȃ銩�߁v�A�u���I�����̊��߁v�A�u���I�Ԉ��ɂ��āv�A�u���̂Ɋւ���h�i�Ȋ����v��4������Ȃ��Ă���B�쐫��[�߂�u�M�v�Ƃ������u�M�S�v�̏��A�Ƃ����ق����悢��������Ȃ��B���j�I�ɂ��M�d�Ȗ{�B
�@
���]2
�@
15���I�h�C�c�C���@�ňꐶ���������ّz�ƋF���̏C���������P���s�X�̂��̖{��ǂނƁA���͒p���������Ȃ�B�ƂĂ��L���X�g�ɂȂ炦�Ȃ��Ǝv���B�Ⴆ�Ίw�₪���葏���Ǝv���悤�Ǝ��̌��t��ǂނȂƂ����u�����ԓI�Ȓm���ɂ���������߁v�Ƃ��A�u�Ǐ����ނ���܂����F��ɂ���ē����鎩�R�ȐS�̑�z���v�Ƃ��A�u���l�̐������D��S�Őu�˂�����͔̂����邪�悢���Ɓv�u�₽��Ȕᔻ�������̂�����邱�Ɓv�Ȃǂ́A�S�ɓ˂��h����B
�@
�傢�Ȃ���炬�����߂�4�����́A1�����̈Ӑ}��葼�l�̈Ӑ}�������Ȃ�2�����̏��L������葽����菭�Ȃ��ق���I��3�������l���Ⴂ�n�ʂ�I��4�_�̌�S�����������A����悤�F�邾���A�ƂĂ��o�������������B�P���s�X�����߂�͔̂푢������l�Ԃ̎����E�����E���h�E�����ȗ~�]�ł���A�푢���̋�����i���̐_�ւ̈��ƕ��]�ł���A�Ȃ�Ⴍ���錪�����ł���B���Ȕے�(����)�Ƃ�����~�]�̗̎��ł���B
�@
�P���s�X�̎v�z�ɂ́A���R(�l�Ԃ̎���)�Ɛ_�̌b�݂Ƃ͑���������̂Ƃ����F��������B���R�͍��������̂�~�����A�������ꎩ���I�ɐ��䂳���̂��D�̂܂Ȃ��B�Ƃ��낪�_�̌b�݂͎��Ȃ̗}���ɓw�߁A���o�I�Ȃ��̂ɍR���A������]�ݎ��g�̎��R����s�g���Ȃ��B���R�͎����̗��v�̂��ߍ���܂�B�Ƃ��낪�_�̌b�݂͎��ȗ��v���A�����̐l�̖𗧂��Ƃ�����B���R�͋��J��y�̂�����邪�A�_�̌b�݂̓C�G�X�̌䖼�̂��ߍ����d�ł�����тƂ��đς���B���R�͗~�[�ŁA�^������Ⴄ���Ƃ���сA���L���D�ށB�_�̌b�݂͏�[���l�Ƃ킩�������Ⴄ���^����B���R�͎����̓��̂�C���U�炷���������߁A�_�̌b�݂͓��̗~���݁A������܂�邱�Ƃ������B
�@
�P���s�X�̎v�z�̓L���X�g�ɂȂ炢�A���Ǝ��̒��A���Ȕ��ȂƉ��P�̌��ӂŁu�E���R�v�̓����s�����Ƃ���B���R�x�z�E���R�̍���(�l�Ԗ{���̎��R�̍���)������B����͋ߑ�̐l�Ԓ��S��`�A���R�~�]��`�Ƃ͑������邾�낤�B���ꂪ�ߑ�̉Ȋw�Z�p�̎��R�x�z�E�����Ɨ��\�̊W�ɂ��邱�Ƃł���B�l�Ԃ��_�ɂȂ莩�R�x�z�E�����ɏ��o��������̘������������Ƃ��P���s�X�͂Ȃ�Ƃ������낤�B
�@
���]3
�@
�g�}�X�E�A�E�P���s�X�́A�����̎v�z�Ƃł���A�J�g���b�N�̎i�ՁB���̖{�́A�\���̏Љ�ɂ��ƁA�u�����ɂ��ōł��悭�ǂ܂ꂽ�����v�ł���Ƃ��������Ă��邻���ł��B��֒��������Ă���C�����Ȃ�������܂��B
�@
���̖{�ɂ́A����_�w�p��Ȃǂ͏o�ė��܂���B�u��̐����ɖ𗧂��܂��߁v�u���Ȃ邱�ƂɊւ��邷���߁v�u���ʓI�ȈԂ߂ɂ��āv�u�Ւd�̔�ւɂ��āv�̑S4�͂���Ȃ�A�O��I�Ɍh�i�ȐM�̉����邩�A�����ł��A�����Ƃ̊ւ���f���A�L���X�g�ɂȂ炤���̂ƂȂ鎖�̑��������Ă��܂��B
�@
�{������т��Ă���̂́A�u�_�Ƃ̊ւ��̂Ȃ��l���A�P�Ȃ�푢���Ɉ˂藊�ސl�����A�����ɋ����v�Ƃ������ł��B���̈Ӗ��ł́A�L���X�g�҂̊�{�p�����L���������ł���Ƃ������܂����A�ނ���L���X�g�҂łȂ����ɂ��A�傢�Ȃ�S�̕�����^���Ă����{���Ǝv���܂��B���ԂƂ̊ւ��ɔ��Ă��܂������Ȃǂ́A�{���̑�3�͂Ȃǂ́A���ɑ傫�ȈԂ߂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@
���A�u�푢���Ƃ͈�؊ւ��ȁv�u��s�����߂Ȃ����v�I�Ș_�����A�ǂ������ɂ͈���������܂��B���̖{�́A���������̃J�g���b�N�̏C���m�����ɏ����ꂽ�����Ȃ̂ŁA�����(�������v���e�X�^���g�M�k��)���o�Ōy�X�������z���������̂ł͂Ȃ����͏��m���Ă���̂ł����A����ɂ��Ă��u�푢���Ƃ͈�؊ւ��ȁv�Ƃ����̂́A���������˂܂��B
�@
�������������́u�_�ɂ̂ݐS�������A�푢���Ƃ͊ւ��ȁv�ȂǂƂ͋����Ă��܂���B�_�͐l�Ԃɑ��u��������S�Ďx�z����v(�n���L1:28)�ƌ����܂����B����Ɂu�ɂ߂ėǂ������v(��1:31)�푢���E�ɂ����āA�B��u�ǂ��Ȃ��v�ƌ���ꂽ�̂́A�u�l���Ƃ�ł��邱�Ɓv(��2:18)�ł���A�����炱���l��j���Ə����ɑn�����ꂽ�̂ł��B�_�͕ʂɁu�_�����q�݁A����������A�R�ɂ������Đ�l�̂悤�ɋ�s��ς߁v�ȂǂƂ͌����Ă��炸�A�l�ԂɁu�푢���Ƃ̊ւ��̒��Ő�����v�ƌ����Ă��鎖�́A���������Ă���Ǝv���̂ł��B
�@
���̎��ɂ��āA�R���R���́u�����̕����v�̒��ŁA������₷�����Ƃ��Ő������Ă��܂��B�H���u�l�Ԃ̐��n��́A���Ԃ̂悤�Ȃ��̂ł���B���Ԃ��S�Đ��̒��ɂ���Η���ėp���Ȃ���A����ƂĂ܂��������萅����͂ˏo���ẮA��鎖�������Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ������ŁA���̐g�͂��̐��ɂ���āA�S�ɂ͐_�����A���̐��̍ߙ������ĎR�ɓ����悤�Ȑ^���������A���̐��̍ߙ���łڂ����߂ɐ키�̂ł���v�B������̕����A���̊��o�ɂ͂҂����藈��悤�Ɏv����̂ł�(�Ƃ͌����ʂȓ_�ł́A�R���̘_��������͂���ʼnߌ��Ȃ�ł���(��))�B
�@
�܁A�����Ƃ����̖{���o�����ɂ́A�v���e�X�^���g�͑��݂��܂���ł������A���ɏ������ʂ�A���̖{�͏C���m�����ɏ����ꂽ�����Ȃ̂ŁA�d���̂Ȃ��������m��܂��B���ہA�g�}�X�E�A�E�P���s�X�̌�100�N���炢�ɂ́A�@�����v���N�����Ă��܂���ŁB
�@
������������p����Ă��܂����A�v���e�X�^���g�ł͊O�T��������Ă��鏑����������\���p����Ă܂��B���{��͌Â߂������̂ł����A���������̂��Ǝv���܂��B���Ղ���̃L���X�g�ƐM�k�A��q�Ƃ̑Θb�`���̓W�J�́A�����������������ɓǂ܂��Ă����H�v�ł��B
�@
���̖{�ɏ�����Ă���ʂ�ɐ����悤�Ǝv������A����Ȏ��͐�Εs�\�Ȃ̂ł���(�u�L���X�g�ɂȂ���Đ�����v�ƌ����A����Ȑ��������l�ԂɊȒP�ɂł���̂Ȃ�A�L���X�g���\���˂ɂ�����K�v�ȂǂȂ������̂ł͂���܂���)�A���̖{��ʂ��ĐS�̕����悤�Ƃ����ǂݕ��ł���A���̖{�͑����̐S�̗Ƃ�^���Ă����Ǝv���܂��B�����A�u�_�ɐS�������Ă��Ȃ��l���������ɋ����v���A�悭���킦��{���ƌ����܂��傤�B�@�@
�@ |
 �@ �@
���u���e���ꐹ���v 1478�N |
   �@
�@
|
Biblia Latina.(with additions by Mewnardus Monachus)
�@
�h�C�c�̈���ƎҁA�A���g���E�R�[�x���K�[�ɂ���Ĉ�����ꂽ���e���ꐹ���B�R�[�x���K�[�́A��������p�ɂ����čł����������j�������x���N�̈���҂ł���B�Ő�����1485�N���ɂ́A100�l�̐A���H�ƈ���H���g���A24��̈���@�𑀂���200��ȏ�̏��Ђ���������B�ނ́A1475�N�ɍŏ��̐�����������A�S����15�_�̐���������o�ł��Ă��邪�A�{���͂��̑�3�Ԗڂ́u���e���ꐹ���v�ł���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���A���X�g�e���X�u���R�w����W�v 1482�N |
   �@
�@
|
Aristoteles.(B.C.384-22)
�@
Opera de naturali philosophia.(with additions by Petrus Antonius Sforzantes)
�@
�A���X�g�e���X�́A�M���V���̓N�w�ҁB�Ñ�M���V���ɂ����鎩�R�w�͊��Ƀ\�N���e�X�ȑO�̓N�w�҂����ɂ����ė��_�I�Ȕ��W���݂Ă������A�A���X�g�e���X�́A���̎v�ٓI�ȌX���ɏڍׂȎ��R�ώ@�ɂ��Ȋw�I�A�v���[�`���Ƃ肢��A�ߑ㎩�R�Ȋw�̕��@�_�I��Ղ�z�����B���e����ŃA���X�g�e���X����W�Ƃ��ẮA1479�N�ɃA�E�O�X�u���N�Ŋ��s���ꂽ4���{������A�u�I���K�m���v�Ɓu���R�w�v�����^���Ă���B�{����2�Ԗڂ̈���{�ł��邪�A�A���X�g�e���X�̎��R�w�Ɋւ���_�����W�߂����̂Ƃ��Ă͍ŏ��̒���W�ł���B����҂̃t�B���b�|�E�f�B�E�s�G�g���́A���m�ÓT�𒆐S��1474�N���烔�F�j�X�ň�����n��1482�N���ɂ͊������I���Ă���A�{���͔ӔN�̍�ł���B�@ |
���A���X�g�e���X1�@
(�A���X�g�e���[�X�A�Ê�: Ἀ�σǃЃу̓�έ�Ƀ�ς - Aristotélēs�A��: Aristotelēs�A�O384�N - �O322�N3��7��)�́A�Ñ�M���V�A�̓N�w�҂ł���B�v���g���̒�q�ł���A�\�N���e�X�A�v���g���ƂƂ��ɁA�����u���m�v�ő�̓N�w�҂̈�l�ƌ��Ȃ����B�܂��A���̑���ɘj�鎩�R�����̋Ɛт���u���w�̑c�v�Ƃ��Ă��B�C�X���[���N�w�⒆���X�R���w�ɑ���ȉe����^�����B�܂��A�}�P�h�j�A���A���N�T���h���X3��(�ʏ̃A���N�T���h���X�剤)�̉ƒ닳�t�ł��������Ƃł��m����B���O�̗R���̓M���V�A��� aristos (�ō���)�� telos (�ړI)����B
�@
���@
�I���O384�N�A�g���L�A�n���̃X�^�Q�C���X(��̃X�^�Q�C��)�ɂďo���B�X�^�Q�C���X�̓J���L�f�B�P�����̏����ȃM���V�A�l�A�����ŁA�����}�P�h�j�A�����̎x�z���ɂ������B���̓j�R�}�R�X�Ƃ����A�}�P�h�j�A���A�~�����^�X3���̑҈�ł������Ƃ����B�c���ɂ��ė��e��S�����A�`�Z�v���N�Z�m�X���㌩�l�Ƃ��ď��N�����߂����B���̂��߁A�}�P�h�j�A�̎�s�y��������㌩�l�̋��Z�n�ł��鏬�A�W�A�̃A�^���l�E�X�ɈڏZ�����Ƃ���������Ă��邪�A���m�Ȃ��Ƃ͓`����Ă��Ȃ��B�����Ă���̂́A�O367�N�A��17��18�ɂ��āA�u�M���V�A�̊w�Z�v�ƃy���N���X��搂����A�e�i�C�ɏ��A�����Ńv���g����Â̊w���A�A�J�f���C�A�ɓ��債���Ƃ������Ƃł���B�C�Ǝ���̃A���X�g�e���X�ɂ��Ă͐^�U�̒肩�Ȃ�ʂ��܂��܂Șb���`�����Ă��邪�A����ɂ́A�e�̈�Y��H���ׂ�������A�H���}���̂��߂ɌR���ɓ�������܂��A������Ɉ�t(������)�Ƃ��Đg�𗧂Ă悤�Ƃ��������܂��s�����A����Ō��ǃv���g���̖��@�����̂��ƌ����҂������B������ɂ���A����͂����ŕw�ɗ�݁A�v���g������������܂ł�20�N�߂��N���A�w�k�Ƃ��ăA�J�f���C�A�̖�ɗ��܂邱�ƂɂȂ�B�A���X�g�e���X�͎t�v���g������u�w�Z�̐��_�v�ƕ]���ꂽ�Ƃ��`�����A���ɂ͋��t�Ƃ��Č�i���w�����邱�Ƃ��������Ƒz������Ă���B�I���O347�N�Ƀv���g�����S���Ȃ�ƁA���̉��ɓ�����X�y�E�V�b�|�X���w���ɑI���B���̎����A�A���X�g�e���X�͊w���������ăA�e�i�C������B�A���X�g�e���X���w�������������R�ɂ͏������邪�A�f���X�e�l�X��̔��}�P�h�j�A�h�������Â��Ă��������̃A�e�i�C�́A�}�P�h�j�A�Ɖ��̐[���ݗ��O���l�ɂƂ��č���ȏ�ɂ��������Ƃ����R�̂ЂƂƌ����Ă���B���̌�A�J�f���C�A�́A6���I�ɓ����[�}�鍑�c�郆�X�e�B�j�A�k�X1��(�݈� 527�N - 565�N)�ɂ���ĕ������܂ő������B
�@
�I���O347�N�A�}�P�h�j�A���t�B���b�|�X2���̏��قɂ��A����13�ł��������q�A���N�T���h���X(��̃A���N�T���h���X�剤)�̎t���ƂȂ����B�A���X�g�e���X�͕٘_�p�A���w�A�Ȋw�A��w�A�����ēN�w���������B
�@
�����q�A���N�T���h���X�����ɑ���(�I���O336�N)�������N�̋I���O335�N�A�A�e�i�C�ɖ߂�A���g�̎w���ɂ��A�e�i�C�x�O�Ɋw���u�����P�C�I���v���J�݂���(�����P�C�I���Ƃ́A�A�e�i�C�̓��k�́A�A�|�����E�����P�C�I�X�̐_�悽��y�n���w��)�B��q�����Ƃ͊w���̕��L(�y���p�g�X)��疗y���Ȃ���c�_�����킵�����߁A����̊w�h��疗y�w�h(�y���p�g�X�w�h)�ƌĂꂽ�B
�@
�A���N�T���h���X�剤�̎���A�A�e�i�C�ł̓}�P�h�j�A�l�ɑ��锗�Q���N���������߁A�I���O323�N�A����̌̋��ł���J���L�X�ɐg�����B�������A�����ŕa�ɓ|��(���邢�͓Ől�Q�����������Ƃ�)�A�I���O322�N�Ɏ������Ă���B
�@
���v�z
�@
�A���X�g�e���X�̒���͌��X550���قǂ������Ƃ�����邪�A���̂����������Ă���͖̂�3����1�ł���B�قƂ�ǂ��u�`�̂��߂̃m�[�g�A���邢�͎����p�ɔF�߂������m�[�g�ł���A���J��z�肵�Ă��Ȃ��������ߊȌ��ȕ��̂ŏ�����Ă���B���܂��܂Ȍo�܂��o�āA���h�X���̃A���h���j�R�X�̎�ɓn��A�I���O30�N���ɐ����E�ҏW���ꂽ�B���ꂪ���݁A�w�A���X�g�e���X�S�W�x�ƌď̂���Ă��镶���ł���B���������āA�����Ɏc����Ă���L�q�̓A���X�g�e���X���Ӑ}�������̂ƈقȂ��Ă���\���������B
�@
�L�P����̏،��ɂ��A�t�v���g�����l�A�A���X�g�e���X���������Θb�т��������悤�ł��邪�A�܂Ƃ܂����`�œ`�����Ă�����̂͂Ȃ��B
�@
�A���X�e���X�́A�u�_���w�v��������w��ʂ���ɓ���邽�߂́u����v(�I���K�m��)�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ�����ŁA�w��̌n���u���_�v(�e�I���A)�A�u���H�v(�v���N�V�X)�A�u����v(�|�C�G�[�V�X)�ɎO�����A���_�w���u���R�w�v�A�u�`����w�v�A���H�w���u�����w�v�A�u�ϗ��w�v�A����w���u���w�v�ɕ��ނ����B
�@
���_���w
�@
�A���X�g�e���X�̎t�v���g���́A�Θb�ɂ���Đ^����Nj����Ă����ؘُ_��N�w�̗B��̕��@�_�Ƃ������A�A���X�g�e���X�͌o���I���ۂ����ɉ�㈓I�ɐ^�����o�����͘_���d�������B���̂悤�Ȏ�@�͘_���w�Ƃ��ĎO�i�_�@�Ȃǂ̌`�ő̌n�����ꂽ�B
�@
�A���X�g�e���X�̎���������A����̘_���w�̐��ʂ́w�I���K�m���x (Organon) 6���Ƃ��ďW�听����A��������ɒ����̊w�k���_���w�̌������s�����B
�@
�����R�w(���N�w)
�@
�A���X�g�e���X�ɂ�鎩�R�w�Ɋւ���_�q�́A�����w�A�V���w�A�C�ۊw�A�����w�A�A���w������ɘj��B
�@
�v���g���̓C�f�A�������^�̎��݂ł���Ƃ���(���`����)���A�A���X�g�e���X�́A���I���`���������ƕs���Ɍ�������������{�I���݂ł���Ƃ���(���`����)�B���܂��܂ȕ��̂̓���������Â��Ă���̂́A�u���v�Ɓu��v�A�u���v�Ɓu���v�̑Η����鐫���̑g�ݍ��킹�ł���A�����̊�b�ɂ͉E��C�E���E�y�̎l�匳�f���z�肳��Ă���B����̓G���y�h�N���X��4���f�_����b�Ƃ��Ă��邪�A��茻���⊴�o�ɍ����������̂ƂȂ��Ă���B
�@
�A���X�g�e���X�̉F���_�͓��S�~��̊K�w�\���Ƃ��Ę_�����Ă���B���E�̒��S�ɒn��������A���̊O���Ɍ��A�����A�����A���z�A���̑��̘f�������A���ꂼ��e�w���\�����Ă���B�����̓V�̂́A�O�q��4���f�Ƃ͈قȂ銮�S���f�ł����5���f�u�A�C�e�[��(�G�[�e��)�v����\�������B�����āA�u�A�C�e�[���v���琬�邪�䂦�ɁA�����̓V�͓̂V������i���ɉ~�^�����Ă���Ƃ����B����ɁA�ŊO�w�ɂ́u�s���̓��ҁv�ł��鐢�E�S�̂́u��ꓮ�ҁv�����݂��A���ׂẲ^���̋��ɂ̌����ł���Ƃ����B�C�u���E�X�B�[�i�[�璆���̃C�X�����N�w�ҁE�_�w�҂�A�g�}�X�E�A�N�B�i�X���̒����̃L���X�g���_�w�҂́A���́u��ꓮ�ҁv�������u�_�v�ł���Ƃ����B
�@
�A���X�g�e���X�̎��R�w�����̒��ōł������Ȑ��ʂ��グ�Ă���̂͐����w�A���ɓ����w�̌����ł���B ���̌����̓����͌n���I���ԗ��I�Ȍo�������̎��W�ł���B���S��ɘj�鐶�����ڍׂɊώ@���A���Ȃ葽���̎�̉�U�ɂ����肵�Ă���B���ɁA�C�m�ɐ������鐶���̋L�q�͏ڍׂȂ��̂ł���B�܂��A�{�̎��Ɍ����A�����̉ߒ����ڂ����ώ@���Ă���B ��̐����̓v�V���[�P�[(��: �Ճ҃ԃŁA�a��ł͗썰�Ƃ���)��L���Ă���A������ȂĖ������Ƌ�ʂ����Ƃ����B���̏ꍇ�̃v�V���[�P�[�͐����̌`���ł���(�w�y���E�v�V���[�P�[�X�x��2����1��)�A�h�{�ێ�\�́A���o�\�́A�^���\�́A�v�l�\�͂ɂ���ċK�肳���(�w�y���E�v�V���[�P�[�X�x��2����2��)�B�܂��A���o�Ɖ^���\�͂����������A�����Ȃ�������A���ɓ��鐶���̕��ޖ@����Ă���(�������A�w�������x��6����1�͂ł́A�A���Ɠ����̒��Ԃɂ���悤�Ȑ����̑��݂��������Ă���)�B
�@
����ɁA�l�Ԃ͗���(��p���闝���k�k�[�X�E�|�C�G�[�e�B�R���l�A�����k�k�[�X�E�p�e�[�e�B�R���l)�ɂ���Č��ۂ�F������̂ŁA���̓����Ƃ͋�ʂ����A�Ƃ��Ă���B
�@
���`����w(���N�w)
�@
�����ɂ��� / �A���X�g�e���X�́A����̎t�v���g���̃C�f�A�_���p�����Ȃ�����A�C�f�A��������V�����Ď��݂���Ƃ����l����ᔻ���A�t�̃C�f�A�Ƌ�ʂ��āA�G�C�h�X(�`��)�ƃq�����[(����)�̊T�O������B�A���X�g�e���X�́A���E�ɐ��N���錻�ۂɂ́u�������v�Ɓu�`�����v������Ƃ��āA�������҂ɕ����A��҂�����Ɂu���͈�(��p��)�v�A�u�`�����v�A�u�ړI���v��3�ɕ����A�s��4�̌���(�A�C�e�B�A aitia)������Ƃ���(�l������)(�w�`����w�xA���w���R�w�x��2����3�͓�)�B���������łł��Ă��邩���u�������v�A���̂��̂̎��̂ł���{���ł���̂��u�`�����v�A�^����ω��������N�����n��(�A���P�[�E�L�l�[�Z�I�[�X)�́u���͈��v(�g�E�f�B�A�E�e�B)�A�����āA���ꂪ�ڎw���Ă���I��(�g�E�e���X)���u�ړI���v(�g�E�t�[�E�w�l�J)�ł���B���ݎ҂ԓI�Ɍ����Ƃ��A���ݓI�ɂ͉\�ł�����̂��A�f�ނƂ��Ẳ\��(�f���i�~�X)�ł���A����ƁA���łɐ����������̂Ŏv�l����̉�����������(�G�l���Q�C�A)�Ƃ���ʂ����B�������\�Ԃ��猻���Ԃւ̐����̂����ɂ���A�����������Ȃ������`���Ƃ��čō��̌���������������̂́A�u�_�v(�s���̓���)�ƌĂ��B
�@
���e�_ / �A���X�g�e���X�́A�q��(A��B�ł���Ƃ����Ƃ���B�ɂ�����)�̎�ނ��A���e�Ƃ��ĉ��L�̂悤�ɋ敪����B���Ȃ킿�u���́v�u�����v�u�ʁv�u�W�v�u�\���v�u�v�u�ꏊ�v�u���ԁv�u�p���v�u���L�v(�w�J�e�S���[�_�x��4��)�B�����ł����u���́v�͕��Վ҂ł����āA���ނ�����킵�A�q��Ƃ��Ă��p������(������)�B����ɑ��āA�q��Ƃ��Ă͗p�����Ȃ���̂Ƃ��Ă̑����̂�����A�`���Ǝ����̗��҂���Ȃ��������ɑΉ�����B
�@
�ϗ��w / �A���X�g�e���X�ɂ��ƁA�l�Ԃ̉c�ׂɂ͂��ׂĖړI������A�����̖ړI�̍ŏ�ʂɂ́A���ꎩ�g���ړI�ł���u�ō��P�v������Ƃ����B�l�ԂɂƂ��čō��P�Ƃ́A�K���A�������z��(�A���e�[)�ɂ����銈���̂����炷�����̂��Ƃł���B�K���Ƃ́A����ɉ��y�邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A���������H���A�܂��́A�l�Ԃ̗썰���A�ŗL�̌`���ł��闝���W�����邱�Ƃ��l�Ԃ̍K���ł���Ɛ�����(�K����`)�B�܂��A�����I�ɐ����邽�߂ɂ́A���f����邱�Ƃ��d�v�ł���Ƃ��������B���f�ɓ�����̂́A���|�ƕ��R�Ɋւ��Ă͗E���A���y�Ƌ�ɂɊւ��Ă͐ߐ��A���݂Ɋւ��Ă͊����ƍ���(���C)�A���_�Ɋւ��Ă������A�{��Ɋւ��Ă͉��a�A���ۂɊւ��Ă͐e���Ɛ^���Ƌ@�m�ł���B�������A㵒p�͏�O�ł����Ă����ł͂Ȃ��A㵒p�͉����I�ɂ����悫���̂ł���A���ɂ����Ă͏X���s�ׂ��̂��̂�������Ȃ��Ƃ����B�܂��A�e�X�ɂӂ��킵�������O��z������z���I���`(�w�I���)�ƁA���Ȃ�ꂽ�ύt�����邽�߂̍ٔ����I�ȋ����I���`(�Z�p�I���)�A����ɉ����āq�����r�����I���`�Ƃ���ʂ����B�A���X�g�e���X�̗ϗ��w�́A�_���e�E�A���M�G�[���ɂ��傫�ȉe����^�����B�_���e�́w�鐭�_�x�ɂ����āw�j�R�}�R�X�ϗ��w�x���p�����Ă���A�w�_�ȁx�n���тɂ�����n���̊K�w�\�����A���́w�ϗ��w�x�̕��ނɋ����Ă���B �Ȃ��A����̒���ł���w�j�R�}�R�X�ϗ��w�x�́u�j�R�}�R�X�v�Ƃ́A�A���X�g�e���X�̕��̖��O�ł���A�q�̖��O�ł�����j�R�}�X���疽�����ꂽ�B
�@
�����w / �A���X�g�e���X�́w�����w�x�������A�����w��ϗ��w�̉�������ɍl�����B�u�l�Ԃ͐����I�����ł���v�Ƃ���͒�`����B�������āA�����̕K�v�̂Ȃ����̂͐_�ł���A�����ł��Ȃ����͖̂�b�ł���B���҂Ƃ͈قȂ��āA�l�Ԃ͂����܂ł��Љ�I���݂ł���B���Ƃ̂�����͉����A�M�����A�|���e�B�A�A���̈�E�Ƃ��Ă̙G�吧�A�Ǔ����A���吧�ɋ敪�����B�����́A���Ƒ��q�A�M�����͕v�ƍȁA�|���e�B�A�͌Z�ƒ�̊W�ɂ��̌��^�����ƌ�����(�j�R�}�R�X�ϗ��w)�B�A���X�g�e���X���g�́A�ЂƖڂŌ��n���鏬�K�͂̃|���X�𗝑z�Ƃ������A�A���N�T���h���X�剤�̓o��Ƒޏ�̕���ƂȂ������̎���A��͐��E���Ƃ̌`���������Ă���A�Ñ�M���V�A�̓`���I�s�s���Ƒ̐��͉ߋ��̂��̂ƂȂ�������B
�@
���w / �A���X�g�e���X�ɂ��A�|�p�n�슈���̊�{�I�����͖͕�(�~���[�V�X)�ł���B���w�͌�����g�p���Ă̖͕�ł���A���z���̖͕킪�ߌ��̐����ɂ͕K�v�s���ł���B��i��e�̖ړI�͐S��̏Ƃ��ẴJ�^���V�X�ł���A�ߌ��̌��ʂ͋}�](�y���y�e�C�A)�ƁA�l���ĔF(�A�i�O�m�[���V�X)�Ƃ̍I�قɂ��Ƃ����B�ÓT�I�쌀�p�̎O��v�̖@���́A����́w���w�x�ɂ��̍��������߂Ă���B
�@
���㐢�ւ̉e��
�@
�㐢�u���w�̑c�v�Ə̂����悤�ɁA�A���X�g�e���X�̂����炵���m���̌n�͖ԗ��I�ł���A�����Ƃ��Ă͊����x�������A�̑�Ȃ��̂ł������B����̑���ɘj��w���́A13���I�̃g�}�X�E�A�N�B�i�X�ɂ��_�w�ւ̓������o�āA�������[���b�p�̊w�҂�������x������邱�ƂɂȂ�B�������A�A���X�g�e���X�̏����̑Ó��ȕ��������łȂ��A����������T�܂ł������ᔻ�Ɏx������邱�ƂɂȂ����B
�@
�Ⴆ�A����̕����w�A�����w�Ɋւ���ł́A�f���N���g�X�́u���q�_�v�u�]���m�I�����̒��S�v���ɑ���A�A���X�g�e���X�́u4���f�_�v�u�]�͌��t���₷�@�ցv�������M�ꑱ���邱�ƂɂȂ�A�����Ɏ���܂ł��̊w���Ɉ٘_��������҂͏o�Ă��Ȃ������B
�@
����ɁA�K�����I�E�K�����C�͑��z���S��(�n����)�������Đ��U�A���X�g�e���X�w�h�ƑΗ����A���ʂƂ��čٔ��ɂ܂Ŋ������܂�邱�ƂɂȂ����B�����̃A���X�g�e���X�w�h�́A�]�������u�A���X�g�e���X�J���鈫���̓���v�ƌ��Ȃ��A�`�����Ƃ��狑�Ƃ�������B�Ñ�M���V�A�ɂ����đ傢�ɉȊw��i���������A���X�g�e���X�̐����A��̎���ɂ͋t�ɂ����x�点�Ă��܂����Ƃ�������Ȏ��Ԃ����������ƂɂȂ�B
�@
�����A���̌�̓N�w�ɂ�����A���X�g�e���X�̉e�����Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ⴆ�A�G�h�����g�E�t�b�T�[���̎t�ł������N�w�҃t�����c�E�u�����^�[�m�́A�u�����Ƃ����T�O�͎����������������̂ł͂Ȃ��A�A���X�g�e���X��X�R���N�w�����łɒm���Ă������̂ł��邱�Ƃ��������Ă���B
�@
������
�@
�A���X�g�e���X�́A�I���O4���I�ɁA�A�e�i�C�ɑn�����ꂽ�w���u�����P�C�I���v�ł̋���p�̃e�L�X�g�ƁA���ƌ����̘_���̓��ނ̒�������Ƃ���Ă��邪�A�O�҂͂�������U�킵�����߁A�����`������Ă���A���X�g�e���X�̒���͂��������҂̐��ƌ����ɒ��q�����_���ł���B�@ |
���A���X�g�e���X2�@
(B.C.384-322) ���Ԉ�ʂōł��L���ȓN�w�҂Ƃ����Ƃ��Ԃ�\�N���e�X���Ǝv����ł����A����ɕ�������炸�L���Ȃ̂��A���̃A���X�g�e���X�ł��B
�@
����ς�A���́`�A����ł���B�t�W�e���r�n��ŕ��������w�g���r�A�̐�x�̉e���������Ǝv����ł���B���Ƃ��ƁA�u�A���X�g�e���X�v�Ƃ������t�̋����ɃC���p�N�g�������ɁA�S���ɔ��M�����e���r�ԑg�̃I�[�v�j���O�Łu�l�Ԃ͖{���I�ɒm�邱�Ƃ�~����v�Ȃ�Ă������t���K���K���������ꂽ���ɂ́A�����A�ۂ����ɂ��m���x�͏オ��܂���ˁB
�@
���̃A���X�g�e���X�̒m���x�͍����̓��{�Ɍ��������Ƃł͂Ȃ��A�Ñ�̃M���V�A���E�A����сA���̌�̐��m���E�ɂ����Ă��A���X�g�e���X�Ƃ������O�͓N�w�j��̑僁�W���[�Ƃ��Ēm���Ă��܂����B
�@
�Ă������A������ƑO�̐��m���E�ł̓v���g����\�N���e�X�̖��O�������̃A���X�g�e���X�̖��O�̂ق����m���Ă����悤�ł��B
�@
���ہA�g�}�X�E�A�N�B�i�X�̎咘�w�_�w��S�x�̒��Ŏg����u�N�w�ҁv�Ƃ������t�́A�N�w�҈�ʂ̂��Ƃł͂Ȃ��u�A���X�g�e���X�v�l�̂��Ƃ������Ă��܂��B
�@
�܂�A�g�}�X�̐����Ă������゠����ł́A�u�N�w�ҁ��A���X�g�e���X�v�Ƃ����}�����������邮�炢���W���[�ȑ��݂�������ł��ˁB
�@
����ȓN�w�j��̑僁�W���[�ł���A���X�g�e���X�ł����A���W���[�Ƃ������������āA���̒���ʂ��v���g���ƌ�����ׂ܂��B
�@
�����܂Ŏc�����Ă���A���X�g�e���X�̒���́A�v���g���̑Θb�т̂悤�Ɋ������ꂽ��i�ł͂Ȃ��A���Ƃ��ƃA���X�g�e���X���A�J�f���C�A�Ȃǂōs�����u�`�̍ۂɗp���郁���Ƃ��Ďc����Ă������̂��A��X�A�A���h���j�R�X�Ƃ����l���e�[�}���ƂɕҏW�������̂ł��B
�@
����ł͐}���قŌ�������Ɓw�A���X�g�e���X�S�W�x�Ɩ��ł��ꂽ���삪�Ђ�������܂����A���̈�ʂɁw�A���X�g�e���X�S�W�x�ƌĂ�Ă����A�̒���Q�́A�A���h���j�R�X���ҏW�������̂Ȃ�ł��ˁB
�@
���{�ŏo�ł���Ă���w�A���X�g�e���X�S�W�x�̐Ԓ��F�̒���Q����ڂł��ς����Ƃ̂���l�͂킩��Ǝv���܂����A���̕��ʂ���z�肳���悤�ɁA���R�A���̃R���e���c�̋L�q�ʂ����Ȃ�̂��̂ɂȂ�ł��낤�Ƃ������Ƃ͑z���ł��܂���ˁc�c�B
�@
���A���X�g�e���X�̐��U
�@
�A���X�g�e���X���āA�w���̕����͂������傫�����グ�����ł����ǁA����Ɋr�ׂĂ��́u���U�v�Ɋւ��镔���͈ӊO�Ǝ�肴������Ȃ��N�w�҂ł���ˁB
�@
�v���g����\�N���e�X�A����ɃJ���g�����肾�ƃG�s�\�[�h���������Ă������Ƃ�����܂����ǁA���������u���U�v�̕������N���[�Y�A�b�v����邶��Ȃ��ł����B
�@
�A���X�g�e���X���A�A���N�T���_�[�剤�̉ƒ닳�t�ɂȂ����肵���l�ł�����A�F�X�ƃG�s�\�[�h�͂����ł��傤���ǁA�Ȃ����A����܂�A���X�g�e���X�̐��U�͒��ڂ���Ȃ��X���ɂ���܂���ˁB
�@
���Ԃ�A�������c����Ă��Ȃ��Ƃ��A�����������R�������ł��傤���ǁA����ł��A����Ƃ��т��������͂��܂���ˁB
�@
����ȁA�u���U�v�Ɍ������Ă��Ă��Ȃ������A���X�g�e���X�ł����A���̃R���e���c�ł̓A���X�g�e���X�̐l����傫���l�̎����ɕ����ďЉ�������Ǝv���܂��B
�@
��1�A�c�N���`�N��
�@
�A���X�g�e���X��B.C.384�N�ɃA�e�i�C�̂͂邩�k���ɂ���X�^�Q�C���Ƃ����h�c�ɂŐ��܂�܂����B
�@
�v���g����\�N���e�X���������̃M���V�A���E�ɂ����镶���I�Ȓ��S�n�ł������A�e�i�C������̓����Ƃ���A���̃X�^�Q�C���͂ǂ��ł��傤�ˁB
�@
���Ƃ��D�y�Ƃ����Ƃ�����Ɠs�s�̋K�͂��傫�����銴�������܂��B
�@
�Ă������A�H�c�A�X�A�����Ƃ������������ݒn�ɂ��Ă�������ƋK�͂��f�J����������܂���B
�@
�ǂ̂ւ�ł��傤�ˁB����s�Ƃ��A��֎s�Ƃ��A�O�O�s�Ƃ�(��H�O�O�͋K�͓I�ɂ͐X���f�J�����c?)�A����Ȋ����̒n���s�s���Ⴆ�Ƃ��Ă͂��傤�ǂ��������m��܂���ˁB
�@
���̃A���X�g�e���X�A���܂�̓h�c�ɂł����ljƒ���͂����Ԃ�ǍD�������悤�ł��B
�@
�܂��A�������ɂˁA�v���g���قǂ̖��ƂƂ����킯�ɂ͂����܂���(�Ă������A���������h�c�ɂȂ̂ŗljƂƂ�����قǗR���������ƕ����Ȃ������̂�������܂���)�A���e�̃j�R�}�R�X�̓}�P�h�j�A�̉��ł���A�~�����^�X�Ƃ����l�ƒ��N�̗F�l�ł���A���A���̐l���̎厡��ł�����܂����B�܂��A���e�����łȂ��A��e�ł���p�C�X�e�B�X�Ƃ����l������҂̉ƌn�̖��������炵���A�A���X�g�e���X�̉ƒ�͕��������ǂ��Ă��A��������ǂ��Ă��o�ϓI�ɂ͐̂��炩�Ȃ�b�܂�Ă����ƕ��������悤�ł��B
�@
�����ŁA���e�́u�j�R�}�R�X�v�Ƃ������O�Ɂu��H�v�ƂЂ��������������������Ǝv���܂����A����͂�����ƌ�ɒu���Ă����āA�����̓A���X�g�e���X�̐��U�Ɋւ���b��𑱂��܂��B
�@
����ȁA������u�����Ƃ��v�̉ƒ�ɐ��܂������A���X�g�e���X�ł����A�q���̍��̃A���X�g�e���X�͕��e�̂ĂŃ}�P�h�j�A�̋{��Ȃǂɂ��o���肵�Ȃ���A�w�̂��闼�e�̂��ƂŁA���ꑊ���ɍ��x�ȋ�����Ă����ƍl�����܂��B
�@
�A���X�g�e���X�̗c�N����Ɋւ��Ă͂���܂莑�����Ȃ��̂ŁA�u�ނ����e���獂�x�ȋ�������v�Ƃ������ƂɊւ��ẮA����܂�͂����肵�����Ƃ͌����Ȃ���ł����A�ނ��c��������̒��ɖ��炩�ɉ�U�w�I�Ȓm�����������ł��낤�Ǝv����ӏ�������̂ŁA�����������m�����ǂ��Őg�ɂ������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���炭�A�Ⴂ���Ɉ�҂ł��鎩���̕��e���瓾���̂ł��낤�ƍl����̂���ԑÓ����Ǝv����ł��ˁB
�@
�m���ɁA�A���X�g�e���X�͌�X�A�J�f���C�A�ł����̎������߂����Ă��܂����A�A�J�f���C�A�Ɖ�U���Ă���܂茋�т��Ȃ���ł���ˁB
�@
�ł�����A�����́A�A���X�g�e���X�́A�c�N������N���ɂ����āA������ȏ�̈�w�I�Ȓm�����l�����Ă����ƍl���Ă����̂��悢�ł��傤�B
�@
���̂悤�ɁA��r�I�b�܂ꂽ�q��������߂������A���X�g�e���X�ł����A�A���X�g�e���X�̗��e�͔ނ��܂��Ⴂ���Ɏ���ł��܂��܂��B
�@
���e��l�̎����͂킩��܂��A���e�̎���A�A���X�g�e���X�̓A���X�g�e���X�̎o�v�w�̂Ƃ���ɗa�����܂��B
�@
NHK�̒��h���Ȃ��Ƃ�����ӂ����l�����h���h���s�K�ɂȂ��Ă����܂����ǁA�K���Ȃ��ƂɁA�A���X�g�e���X��a���邱�ƂɂȂ����`���̌Z�ł���v���N�Z�m�X�͂Ȃ��Ȃ��̍D�l���ł������炵���A�A���X�g�e���X�ɂ����Ƃ���������{���A�ނ���l�O�̐N�Ɉ�ďグ�܂��B
�@
���̂悤�ɁA�A���X�g�e���X�̗c�N���ォ��N����܂ł��U�b�ƊT�ς��Ă݂�ƁA�m���ɁA���e�Ƃ̎��ʂƂ����s�K�͂���܂������A�S�̓I�ɊςāA�����ނˍK���������ƍl���Ă����ł��傤�B
�@
�ʂɁA�����߂�ꂽ�Ƃ����������Â����Ƃ��Ȃ��A�}�P�h�j�A�̉��{�ɏo���肵�Ȃ����炵�Ă������炢�ł�����ˁB
�@
�������A���̌�A���e�̎d����̊W�������Ď��R�ƍ\�z���ꂽ�}�P�h�j�A���{�Ƃ̐e���ȊW���A�A���X�g�e���X�̎c��̐l���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă������ƂɂȂ�܂��B
�@
��2�A�A�J�f���C�A�ł̐���
�@
���e�Ƌ`�Z�v�w���獂�x�Ȋw��I������{���ꂽ�A���X�g�e���X�́A17�ɂȂ����Ƃ��A���܂�̋��̃h�c�ɃX�^�Q�C���𗣂�A�Ԃ̓s�A�e�i�C�Ɍ������܂��B
�@
�������ł��������A�̂̒��Ɂɂ������炢�ɓ��ꂽ�A�Ԃ̓s�哌������Ă����̎�������܂���ˁB
�@
�A���X�g�e���X���A�e�i�C�Ƃ����s�s�ɓ��������Ă����̂��ǂ����͒肩�ł͂���܂��A�Ƃɂ����A�A���X�g�e���X�͉ƋƂł����҂��p�����ɃA�e�i�C�ɍs���A�v���g���̊J�����A�J�f���C�A�̖��@���܂��B
�@
�����ň���Ȃ̂́A�Ȃ��A���X�g�e���X���A�J�f���C�A�ɓ��w(�H)�����̂��Ƃ����_�ł��B
�@
�m���ɁA�A�J�f���C�A�͓����Ƃ��Ă�������x�̖������l�����Ă����悤�ł����A���̍��̃A�e�i�C�ɂ̓A�J�f���C�A�ȊO�ɂ��w�Z�����݂��A�����̊w�Z�Ƃ̕]�����r�ׂ�ƁA�A�J�f���C�A�͂���قǗL�͂ȋ���@�ւł͂Ȃ������悤�ł��B
�@
���ہA���������炭�ł��傫�Ȑ��͂������Ă����ł��낤�Ǝv����w�Z�́A�C�\�N���e�X�Ƃ����l�����J�����C���w�Z�ł����B
�@
�ł�����A���ʂɍl����ƁA�A�J�f���C�A�ȊO�̊w�Z�ɓ��w���Ă��Ă����������Ȃ��͂��Ȃ�ł����A�Ȃ����A�A���X�g�e���X�̓A�J�f���C�A��I�т܂����B
�@
���̑I���̗��R�͂������l�����܂����A�A���X�g�e���X�̓A�e�i�C�ɏo�����O�ɁA�O�����ăv���g���̋L�����Θb�тɐG��Ă����̂�������܂���B
�@
�N��I�Ɍ����A�A���X�g�e���X���Y�܂ꂽ�i�K�ł��łɃv���g����40��ł����炢�����̑Θb�т͐��ɏo�Ă����ł��傤���A�N�w�҂Ƃ��Ă̔\�͂��ăV�P���A�ɏ�����邮�炢�ł�����A���̖����������ɂ܂ō����Ă����̂ł��傤�B
�@
�ł�����A���ɁA�A���X�g�e���X���v���g���̒���ɐG��ĉ��炩�̒m�I�e�����A���̂��Ƃ̂䂦�ɃA�J�f���C�A�̖��@�����̂��Ƃ��Ă������ĕs�v�c�͂���܂���B
�@
���āA�A�J�f���C�A�ɓ��������A���X�g�e���X�ł����A�����Ɋw���ł���v���g���̎p�͂���܂���ł����B
�@
�v���g���̐��U�ɂ��ĊT�ς����ӏ������Ă���������Ƃ킩���ł����A�A���X�g�e���X���A�J�f���C�A�ɂ���Ă������傤�ǂ��̎��A�v���g���̓V�P���A�̃f�B�I���ƃf�B�I�j���V�I�X�̋��߂ɉ����āA���ڂƂȂ�V�P���A���s�ɗ����������ゾ������ł��ˁB
�@
����ȃv���g���s�ݏ̃A�J�f���C�A��������ł����A�A���X�g�e���X�͂���Ȃ��Ƃ������܂��Ȃ��ɃA�J�f���C�A�ɓ��w���܂��B
�@
�����āA��B.C.366�N�A�V�P���A���玸�ӂ̂ǂ��ŋA�������v���g���ƃA���X�g�e���X�͎n�߂Ċ�����킹�邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�A�J�f���C�A�ł̃A���X�g�e���X�̐����́A�v���g���̎O�x�ڂ̃V�P���A���s�Ȃǂ������ăA�J�f���C�A���̂̂�����Ƃ��������͂��������̂́A��{�I�ɂ͕����Ȃ��̂������ƍl�����܂��B
�@
���āA�t���ł���v���g�����A�҂������Ƃł悤�₭�A���X�g�e���X�̊w���������O���ɏ���Ă����킯�ł����A�v���g���̋A����A�A���X�g�e���X�͂��̃A�J�f���C�A�Ń��L���L�Ɠ��p�������A�ŏI�I�ɂ͎t���ł���v���g������u�m��(�k�[�X)�v�Ƃ����ٖ��ŌĂ��قǂ̐l���ɂȂ�܂��B�܂��A�A�J�f���C�A�ɓ��w���Ă�����x�̔N���������A�A���X�g�e���X����r�I�u��y�v�I�ȃ|�W�V�����ɗ��悤�ɂȂ�ƁA�ނ͌�y����������M�����W�߁A�w���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���t�Ƃ��ċ����鑤�̗���ɂ������Ă��������ł��B
�@
�A���X�g�e���X���g���[�������w�������𑗂邱�Ƃ��ł���A�J�f���C�A�̐����ɖ������Ă����ƍl�����܂����AB.C.347�N�A�A���X�g�e���X37�̔N�ɁA�v���g��������80�̐��U����܂��B
�@
�����āA���̃v���g���̎��Ɍĉ����邩�̂悤�ɃA���X�g�e���X���܂������N�ɃA�J�f���C�A�������Ă����܂��B
�@
�����A�����ň���Ȃ̂́A�A���X�g�e���X���A�J�f���C�A�������������ł��B
�@
��̓I�Ɍ����ƁA�A���X�g�e���X������B.C.347�N�Ƃ����N�ɃA�J�f���C�A���������̂͊ԈႢ�Ȃ���ł����A�A���X�g�e���X���v���g���̐��O�ɃA�J�f���C�A���������̂��A�v���g���̎���ɃA�J�f���C�A���������̂��Ƃ����_�ɂ��Ĉӌ���������Ă����ł��B
�@
���m�ÓT�p���́w�j�R�}�R�X�ϗ��w�x��|���p����́A�A���X�g�e���X�̓v���g�������ʑO�ɃA�J�f���C�A���������Ƃ��Ă��܂����A�u�k�Њw�p���ɂɎ��^����Ă���w�A���X�g�e���X�x�������������F�M�́A�v���g��������Ŏ��̊w���I���ŃX�y�E�V�b�|�X���I�ꂽ���Ƃ��ăA���X�g�e���X�̓A�J�f���C�A���������Ƃ��Ă��܂��B
�@
�Ȃ�ƂȂ��A�A���X�g�e���X���A�J�f���C�A�����������Ƃ̗��R�t���������݂Ă݂�ƁA�����F�M���咣����悤�ɁA�v���g������̊w���I���Ȃǂ�����ł��������킩��₷���ł����ǁA�p������咣����u�v���g�������ʑO�v���ɂ�����Ȃ�̍����������ł��B
�@
�A���X�g�e���X�̗c�N������T�ς����Ƃ��ɁA�A���X�g�e���X�����e�̐E�Ə�̊W�Ń}�P�h�j�A���{�Ɛ[���W�������Ă����Ƃ������Ƃ������܂�����ˁB
�@
�p����̑��̐l�����́A���̃}�P�h�j�A�Ƃ̐[���W���A���X�g�e���X���A�J�f���C�A����������Ȍ����ł���ƍl�����ł��B
�@
���̓����A�}�P�h�j�A�̓M���V�A�n���̖k���Ɉʒu����e�b�T���A���U�ߗ��Ƃ��A�A�e�i�C�ɂƂ��đ傫�ȋ��ЂƂȂ��Ă��܂����B
�@
�������A����ɗւ�������悤�ɁA�v���g���̎��̑O�N�ɂ�����B.C.384�N�Ƀ}�P�h�j�A�̓J���L�f�B�P�����̒��S�s�s�I�������g�X���U�ߗ��Ƃ��A�A�e�i�C�Ɏ���Ă͂܂��Ɂu�������ɂ����@�v�ɂȂ��Ă�����ł��B
�@
���R�A����ȎЉ��ł̓A�e�i�C�����̔��}�P�h�j�A�̋C�^�͍��܂�܂��B
�@
�u�����āA�A���X�g�e���X�͎������}�P�h�j�A���ƂƐ[���W�������Ă��邱�Ƃ����o�����Q����O�ɑ��X�ɃA�e�i�C��E�o�����̂��B�v
�@
�A���X�g�e���X���A�e�i�C�������������ɂ��Ėp����̑��ɗ��l�́A���̂悤�ȓ����̐����I�A�������́A�R���I�������ɂ��āA�A���X�g�e���X�̓v���g�������ʑO�ɃA�e�i�C��E�o�����Ǝ咣�����ł��ˁB
�@
�ł�����A����痼�w�c�̑����Ɏ��˂����ނ��ƂȂ��A�Ƃɂ����AB.C.347�N�A�v���g�������N�ɃA���X�g�e���X�̓A�J�f���C�A���������Ƃ������Ă����܂��傤�B
�@
��3�A���Q�̎���(�A�b�\�X����~���e�B���l��)
�@
�v���g���̎��A�A�J�f���C�A�̊w���I���A�}�P�h�j�A�̃M���V�A�N�U�A�A�e�i�C�����ɂ����锽�}�P�h�j�A�@�^�̍��܂�ȂǁA���R�͐F�X�l�����܂����A�Ƃɂ������ɂ�B.C.347�N�ɁA�A���X�g�e���X�͓����A�J�f���C�A�̊w�F�N�Z�m�N���e�X�ƂƂ��ɃA�e�i�C�̒n������܂����B
�@
�����āA��������A���X�g�e���X�̕��Q�������n�܂�܂��B
�@
�A���X�g�e���X�̓A�e�i�C����������A���A�W�A�̃A�^���l�E�X�Ɍ������܂��B
�@
�����A���̃A�^���l�E�X�̓w���~�A�X(�w�����C�A�X)�Ƃ����l�����G��Ƃ��Ď��d���Ă�����ł����A���̃w���~�A�X�͓z�ꂩ��g���N��������A�J�f���C�A�Ŋw��ł����l���ŁA�A���X�g�e���X�Ƃ̓A�J�f���C�A����ɐe�����������炵����ł��ˁB
�@
���R�A�A�J�f���C�A�Ŋw��ł������炢�ł�����A�w���~�A�X�͓N�w�ɂ�����������A�A�^���l�E�X�ɂ���Ă����A���X�g�e���X���A�����̎x�z���ɂ���A�b�\�X�Ƃ������ɏZ�܂킹�A�����œN�w������̂ɏ\���Ȋ��𐮂��Ă��ꂽ�����ł��B
�@
����ȃw���~�A�X�̍D�ҋ��������āA�A���X�g�e���X�͂��̒n�ɎO�N�̒����ɂ킽���đ؍݂��܂��B
�@
�A�J�f���C�A����������A�w�������Ƃ����ʂł͕s����ȗ���ɂ������ł��낤�Ǝv����A���X�g�e���X�ɂƂ��āA�A�b�\�X�ɂ�����O�N�ԂƂ������Ԃ͔��ɗL�Ӌ`�Ȃ��̂������ł��傤�B
�@
�������A����ȍK���ȏɂ������A���X�g�e���X�́AB.C.345�N�ɃA�b�\�X���烌�X�{�X���̃~���e�B���l�ւ̈ڏZ��]�V�Ȃ�����܂��B
�@
��ɂ��������悤�ɁA�A�b�\�X���ʒu���Ă���̂͏��A�W�A�Ƃ����n���Ȃ�ł����A�����A���̏��A�W�A�͓����ɂ���y���V�A�Ƃ������卑�̋��Ђɂ��炳��Ă��܂����B
�@
���Z�̐��E�j�̎��Ƃ��v���o���Ă��炢������ł����A�����̃y���V�A�Ƃ����Β��h���̑卑�ł�����ˁB
�@
�������A�w���~�A�X�͂���Ȓ��卑�̈��͂ɂ��������A�����O�̐����͂ŁA���̑卑�}�P�h�j�A�Ƃ̊W���������A�Ȃ�Ƃ��A�^���l�E�X�̓Ɨ����ێ����Ă�����ł��B
�@
�ł��A����ς�A�y���V�A�̑����猩����A����ȏ����̙G��Ȃ�Ďז��Ȃ�������Ȃ��ł����B
�@
�����A�y���V�A���������A���^�N�Z���N�Z�X�́A�ڂ̏�̂��Ԃł���w���~�A�X��r�����ׂ��A�A�^���l�E�X�̒n�Ɏh�q�𑗂�A�w���~�A�X��ߗ��ɂ��Ă��܂��܂��B
�@
�y���V�A�����w���~�A�X��ߗ��ɂ������R�Ƃ��ẮA���R�A�ڂ̏�̂��ԓI�ȑ��݂�r������Ƃ����Ӗ�����������ł����A������A���̗��R�Ƃ��āA�w���~�A�X���W���������悤�Ƃ��Ă����}�P�h�j�A�̏���T��Ƃ����ړI���������悤�ł��B
�@
�Ă������A�l�I�ɂ́A���炭��҂̗��R�̕������C���������Ǝv����ł���ˁB
�@
�����̃y���V�A�̐��͂��l����A������ƋC��������Ώ��A�W�A�̏����Ȃ�Ĉ�|�ł����Ǝv����ł���B
�@
�ނ���A���͓I�Ȃ��Ƃ��l����ƁA�y���V�A�ɂƂ��Ė{���̋��ЂƂȂ蓾��̂́A���A�W�A�̔w��ɂ���}�P�h�j�A�ł��傤�B
�@
���āA�ߗ��ɂ���Ă��܂����w���~�A�X�́A�ŏI�I�ɍi��Y�ɂ���Ă��܂��܂��B
�@
���̎������āA�ی�҂ł���w���~�A�X���������A���X�g�e���X�͎d���Ȃ����X�{�X���ɈڏZ������ł��ˁB
�@
���X�{�X���̃~���e�B���l�ɈڏZ�����Ƃ��A�A���X�g�e���X�͂��ł�40�ɂȂ��Ă��܂������A���̔N�A�A���X�g�e���X�̓w���~�A�X�̖Âɂ�����s���e�B�A�X�Ƃ��������ƌ������A��l�̎q�����������܂��B
�@
�܂��A���̒n�ɂ͌�ɃA���X�g�e���X�ő�̒�q�ƂȂ�e�I�v���X�g�X�����܂����B
�@
�g�����Ƒ��ƗD�G�Ȓ�q�Ɉ͂܂�āA�~���e�B���l�ł̊w�������́A�A�b�\�X�ɂ����Ƃ��قǂ̏[�����͂Ȃ��������̂́A�A���X�g�e���X�ɂƂ��Ă�����x�����̂������̂������ƍl�����܂��B
�@
�A�b�\�X�ƃ~���e�B���l�ŁA�A���X�g�e���X�͎�ɐ����w�I�ȒT�����s���A���̂Ƃ��̒T�����ʂ́w���������_�x�Ȃǂ̒���ɂ܂Ƃ߂��A�����ɓ`�����Ă��܂��B
�@
���āA�~���e�B���l�̒n�Ŋw�������𑗂��Ă����A���X�g�e���X�ł����AB.C.342�N�A����ȃA���X�g�e���X�̂��ƂɁA���̃}�P�h�j�A���t�B���b�|�X����A�u���q�ł���A���N�T���h���X�̋���W�ɂȂ��Ăق����v�Ƃ����v�����͂��܂��B
�@
�A���X�g�e���X�ƃ}�P�h�j�A�Ƃ̊Ԃɂ͗c�������疧�ڂȊW���������̂ŁA�A���X�g�e���X�͂��̗v�����đ����}�P�h�j�A�̒n�Ɍ������܂��B
�@
�A���X�g�e���X���}�P�h�j�A�ɒ������Ƃ��A�A���N�T���h���X��14�ł����B��ɃA���N�T���h���X�剤�Ƃ��đS���E�ɂ��̖����Ƃǂ납���l���ƁA�㐢�A���w�̑c�Ƃ��Ēm����V�˂������Ŏn�߂Ċ�����킹�邱�ƂɂȂ�܂��B
�@
�}�P�h�j�A�ł̃A���X�g�e���X�̐����Ԃ�͂��܂����悭�킩���Ă��܂��A�A���X�g�e���X�͎������}�P�h�j�A�ɏ��W�����t�B���b�|�X���ÎE����A�A���N�T���h���X��20�̎Ⴓ�ɂ��ĉ��ʂ��p������B.C.336�N�܂Ń}�P�h�j�A�ɑ؍݂��܂��B
�@
���ʂ����N���B.C.334�N�A�A���N�T���h���X�̓M���V�A�Ɠ����W�����сA�}�P�h�j�A�ƃM���V�A�̘A���R�𗦂��ď��A�W�A�ɍU�ߍ���ŁA�L���ȓ����������J�n���܂��B
�@
�������A���̂Ƃ��A�A���X�g�e���X�͂��łɃ}�P�h�j�A�̒n����ɂ��Ă��܂����B
�@
�A���N�T���h���X�̓����������n�܂��N�O��B.C.335�N�A�A���X�g�e���X�͍ĂуA�e�i�C�̒n�ɖ߂�܂��B
�@
�A���X�g�e���X���Ȃ������ōĂуA�e�i�C�ɖ߂����̂��͒肩�ł͂���܂��A�����̃A�e�i�C�́A�A���N�T���h���X�̑㗝�Ƃ��Ď����I�ɃM���V�A�n����x�z���Ă����A���e�B�p�g���X�̓������ɂ�����Ă��܂����B
�@
�܂�A�A���X�g�e���X���A�e�i�C���������Ƃ��ɃA�e�i�C�̐l�X���u�������ɂ����@�v�Ƃ��Ď������Ă������Ԃ�����Ӗ��ł͌��������Ă����킯�ł��B
�@
�������A���̂Ƃ��̃}�P�h�j�A�ɂ������I�Ȏx�z�́A����I�Ȑ�̂Ƃ����`���̂��̂ł͂Ȃ��A�ꉞ�A�����W�Ɋ�Â����̂������̂ŁA�A�e�i�C�ɂ��A���X�g�e���X�����ꂽ�Ƃ��قǁu���}�P�h�j�A�v�̕��͋C�͂Ȃ������悤�ł��B
�@
�A�e�i�C�ɓ��������Ƃ��A�A���X�g�e���X��49�B
�@
���̌�A�A���X�g�e���X�͂��̃A�e�i�C�̒n�ŁA���������w���Ƃ���V���Ȋw�������A���̊w���ł����Ђ����猤�������ɑł����ނ��ƂɂȂ�܂��B
�@
��4�A�����P�C�I���̑n�݂Ǝ��@�`��x�ڂ̃A�e�i�C�����`
�@
12�N�Ԃ�ɃA�e�i�C�ɖ߂����A���X�g�e���X�ł����A���������Ċw�A�J�f���C�A�ɍĂі߂邱�Ƃ͂���܂���ł����B
�@
���̗��R�Ƃ��ẮA�����̃A�J�f���C�A(���̂Ƃ��̊w���̓A���X�g�e���X���A�e�i�C���������Ƃ��Ɉꏏ�������N�Z�m�N���e�X)�������̕�������N�w�ł͂Ȃ����w�I�ȕ����Ɍ����đ傫���V�t�g���Ă������炾�Ƃ����邱�Ƃ�����܂����A�{���̂Ƃ���͂킩��܂���B
�@
�A���X�g�e���X�́A�A�e�i�C�ɖ߂�����A�x�O�ɂ������̌�������A�����ɃA�J�f���C�A�Ƃ͕ʂɁu�����P�C�I���v�ƌĂ�鎩��̊w�������܂��B
�@
�A���X�g�e���X�͂��̊w���̕��L���v���v�������Ȃ���A�w���ɏW������q�B�Ƌ��ɓN�w�k�`���J��L���Ă��������ł��B
�@
�Ñ�M���V�A���(����M���V�A�ꂾ�Ƃǂ��Ȃ낤�H)�u���L�v�̂��Ƃ��u�y���p�g�X�v�Ƃ����܂����A�����P�C�I���̐l�X�����́u���L�v�œN�w�����Ă������Ƃ���A��X�A�A���X�g�e���X�w�h�̐l�X�́u�y���p�g�X�h�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B
�@
�Ăш��Z�̒n���A���X�g�e���X�́A���ăA�J�f���C�A�ōs���Ă����悤�ɁA�V�����w���ōu�`�����Ȃ���[�������w�������𑗂�܂��B
�@
�����P�C�I���ŃA���X�g�e���X���s�����u�`�̓��e�͂悭�킩���Ă��܂��A12�N�̕��Q�����̍Œ��ɂ��w��I�Ȍ��r��ς�ł����A���X�g�e���X�̍u�`�́A�A�J�f���C�A����ɍs���Ă����u�`�����L���ɂ����Ă��[���ɂ����Ă�����ɂ��������[���������̂ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B
�@
�������A����ȃA���X�g�e���X�̊w�������������͑����܂���B
�@
�A���X�g�e���X���A�e�i�C�ɂ���Ă���B.C.335�N����12�N���B.C.323�N�A�A�e�i�C�̒n�Ƀ}�P�h�j�A�̃A���N�T���h���X�剤�������̓r���ɕa�������Ƃ����m�点���͂��܂��B
�@
��ɂ��������悤�ɓ����̃A�e�i�C�́A�}�P�h�j�A�̃A���e�B�p�g���X���A�g�b�v�ł���A���N�T���h���X�剤�ɑ����đ㗝�������Ă���ł����B
�@
����ȏ��ɂ����āA��������Ă��鍑�ɓ������Ă��鍑�̃g�b�v�����Ƃ������͂�����ǂ��Ȃ�ł��傤��?
�@
���R�A��������Ă���A�e�i�C�����̑����炵����A�u������`!!!!!!�v�I�ȏɂȂ�܂���ˁB
�@
�����āA�u������`!!!!!!�v�̎��ɗ���s���́u�������ǂ��o��!!!!!!!!!�v�ł���ˁB
�@
�����̃A�e�i�C�ł�����Ɠ������Ƃ��N�����Ă��܂��܂��B
�@
�A���N�T���h���X�剤�����̕���āA�A�e�i�C�̖��O�̊ԂɁA���ăA���X�g�e���X���A�e�i�C����ɂ����Ƃ��Ɠ����悤�Ȕ��}�P�h�j�A�̋@�^���Ăэ��܂�܂��B
�@
����Ȓ��ɂ����āA�A���N�T���h���X�剤�̉ƒ닳�t�߂Ă����A���X�g�e���X�̓A�e�i�C�̖��O����i�D�̃^�[�Q�b�g�ɂ���Ă��܂��܂��B
�@
�܂��A�����Ɍ����ƁA�u�^�[�Q�b�g�ɂ����v�Ƃ����Ƃ���܂ł͂����Ȃ������݂����Ȃ�ł����A�A���X�g�e���X�̎���(�������A�����P�C�I���̊w���Ƃ��͕ʂł���c)�ł͖��炩�Ɂu�������Ă����c�v�݂����ȕ��͋C���Y���悤�ɂȂ��Ă����炵���ł��B
�@
�����āA���ɁA�A���X�g�e���X�̓G�E�������h���Ƃ����_���ɂ���āA�u�s�h�_�v�̍߂ői�����Ă��܂��܂��B
�@
���̍����́A�A���X�g�e���X�����ăw���~�A�X���]����̂�������Ƃ������Ƃ𗝗R�ɂȂ��ꂽ���̂�������ł����A�܂��A�͂����肢���āA����������ł��B
�@
���ǁA�\�N���e�X���ٔ��ɂ�����ꂽ�Ƃ��Ɠ����悤�ɁA�����ƓI�ȍs�������ۂɂ͎���Ă��Ȃ�����ǂ����炩���ߏ������Ă������ق����������낤�Ǝv����l���ɑ��āA�\�����Ȃ�ƂȂ������Ƃ��炵���߂��ł��������č������A�ŏI�I�ɂ͎��Y�ɂ��Ă��܂����Ƃ������Ƃł��ˁB
�@
���̍������āA�A���X�g�e���X�͎����̐g�ɔ���댯�����������Ă������Ƃ�[���Ɏ~�߂āA�A���N�T���h���X�̔ߕ͂����̂Ɠ���B.C.323�N���ɁA�����P�C�I���̂��ׂĂ�����q�ł���e�I�v���X�g�X�ɑ����A�A�e�i�C����G�E�{�C�A�̃J���L�X�ɗ������܂��B
�@
���̃J���L�X�Ƃ����y�n�̓A���X�g�e���X�̕�e�ł���p�C�X�e�B�X�̌̋��ł��B
�@
�J���L�X�ɈڏZ�����Ƃ��A�A���X�g�e���X��61�ɂȂ��Ă��܂������A���̈ڏZ�̗��N�AB.C.322�N�ɃA���X�g�e���X��62�̐��U����܂��B
�@
�A���X�g�e���X�̎����́u�a���v�Ƃ���Ă��܂��B�ڏZ���Ă����Ɏ����Ƃ��l����ƁA���炭�A�A�e�i�C���o��Ƃ��ɂ͂������łɃA���X�g�e���X�͕̑̂a���ɐI�܂�Ă����Ǝv���܂��B
�@
�A�e�i�C������Ƃ��A�A���X�g�e���X�́A����̐g�ɂ��������������������ă\�N���e�X�̐g�ɋN�����������ɂȂ��炦�āA�������A�e�i�C�����闝�R���u�A�e�i�C�l�������A�N�w�ɑ��čĂѓ����߂���Ƃ����Ƃ��Ȃ��悤�Ɂv�Ɛ��������Ɠ`�����Ă��܂��B
�@
���̓`�����^�����ǂ����͒肩�ł͂���܂��A��������ăA���X�g�e���X�̐��U��ǂ������Ă݂�ƁA�A���X�g�e���X�̓\�N���e�X��v���g���Ɠ����悤�ɃA�e�i�C�Ƃ����y�n�œN�w�ɐ�S���Ȃ�����A�Ō�܂ł��̃A�e�i�C�Ƃ����y�n�ɍ������낷���Ƃ��ł��Ȃ������N�w�҂��Ƃ�����ł��傤�B
�@
�X�^�Q�C�����A�e�i�C���A�b�\�X���~���e�B���l���}�P�h�j�A���A�e�i�C���J���L�X�A�l�X�ȓy�n��]�X�Ƃ��Ȃ��玩��̊w�������������Ă����A���X�g�e���X�̐��U�́A����Ӗ��A�v���g����\�N���e�X�ȏ�ɓ����̎Љ�ɖ|�M���ꂽ�l���������ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B�������A����Ȃӂ��ɐ��̒��ɖ|�M����Ȃ�����A�A���X�g�e���X�̍��グ���w���́A����Ȍ�̐��m���E�Ɉ��|�I�ȕ��Ր��������Đ��ȉe���͂�^���Ă������ƂɂȂ�܂��B�@ |
�����w�̑c�^�A���X�g�e���X3
�@
�v���g�����\�N���e�X�̒�q�������悤�ɁA�A���X�g�e���X�̓v���g���̒�q�ł���B�����t�v���g���ƈقȂ��Ă����̂́A�t�v���g�����\�N���e�X�̖₢�ɓ����������悤�Ƃ����̂ɑ��A�A���X�g�e���X�͂₪�Ďt�v���g���̃C�f�A���ƑΗ�����l�������B�N�w�E���w�E���R�w�E�_���w�E�����w�Ȃǂ̕��L���������s���A��X�w���̌n�Â���B�Ñ�M���V���N�w�S�̂��A�A���X�g�e���X�̋���ȉe�ɕ����Ă���A�ƌ����Ă��ǂ���������Ȃ��B���̃A���X�g�e���X�̓N�w�Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȃ��̂������̂��낤���H
�@
�܂��́A�A���X�g�e���X�̐l�����Ȍ��ɐU��Ԃ��Ă݂悤�B�A���X�g�e���X�́A�\�N���e�X�̎���15�N�قnjo�����I���O384�N�ɁA�k���}�P�h�j�A�n���̃J���L�f�B�A�����̃X�^�Q�C���X�ƌ������ɐ��܂ꂽ�B���j�R�}�X�̓}�P�h�j�A�{��Ɏd�����҂��������A�����������̓A���X�g�e���X�ɉe����^���Ă���ƍl������B17�ŃA�e�i�C�ɏ㋞���A�v���g���̊J�����A�J�f���C�A�ɓ��w�����B���̎��A�v���g���͊���60�B�A���X�g�e���X�́A������20�N�قlj߂����B�A���X�g�e���X��37�̎��ɁA�v���g����80�ŖS���Ȃ�B�A�J�f���C�A�́A�v���g���̉��ł���X�y�E�V�b�|�X������w���Ƃ��Č�p�҂ƂȂ����B�A���X�g�e���X�́A(���3��w���ƂȂ�)�F�l����q�̃e�I�t���X�g�X�̌̋����X�{�X���ɈڏZ���A�����w�̌����Ɏ��g�ށB
�@
���̌�A�̋��}�P�h�j�A�̃t�B���b�|�X���ɏ������13�̍c���q(��̃A���N�T���h���X�剤�I)�̉ƒ닳�t�ɏA�C���A3�N�ԋ��������B�J�C���l�C�A�̐킢�ɏ��������}�P�h�j�A�͑S�M���V���̔e�����m���������A�t�B���b�|�X�����ÎE�����ƃA���N�T���h���X��20�ő��ʂ����B���̃A���N�T���h���X�剤���A�I���G���g���E�S�̂��܂ސ��E�鍑�����݂��A�M���V�������E��Ȋ�����V�����w���j�Y������̖����J����̂ł���B�A���X�g�e���X�̓A�e�i�C�ɖ߂�A�}�P�h�j�A�{��̎x���̉��A�I���O335�N�A���̓��x�O�Ɋw�������P�C�I����n�݂����B�A���X�g�e���X���g�͂��܂�b������肭�Ȃ��A���̂��߂ɖȖ��ȍu�`���e�����������B���ꂪ�A�����̃A���X�g�e���X�̒���̑啔���Ƃ��č����ɓ`�����邱�ƂɂȂ�B
�@
�A���N�T���h���X�剤�������������ɋ}������ƁA�A�e�i�C�̒��ł͌��������}�P�h�j�A�\�����N�������B�g�̊댯���@�m�����A���X�g�e���X�́A�w�����q��(�O�q��)�e�I�t���X�g�X�Ɉς˂āA����̓G�E�{�C�A���̃J���L�X�ɖS������B�I���O322�N�v�B
�@
���̂悤�ɁA�A���X�g�e���X�̐��U�́A�A�J�f���C�A�ł�20�N�ɋy�ԏC�s����A�A���N�T���h���X�̉ƒ닳�t������܂ރM���V���e�n�̕�����A�����P�C�I���ł̊w���Ƃ��Ă̋��灕���������3�ɕ�������B����āA�A���X�g�e���X�̓N�w���ꖇ��̂悤�ɍl����̂ł͂Ȃ��A�Ⴋ���̏C�s���ォ��ӔN����̋��n�Ɏ���܂ł́A���̐������̐Ղ�H��悤�ȃA���X�g�e���X�l�@���������̂�������Ȃ��B
�@
�c�O�Ȃ���A���a�����[�}����ɐe���܂�Ă����D��ȕ��̂̃A���X�g�e���X�̒���̑����͎����Ă��āA�w���̊w�k�����ɏ����ꂽ�u�`���e����ɂ�������Ȓ���W�̕������݂ɓ`�����Ă���B����Ȗ�ŁA�A���X�g�e���X�̓N�w�͓�����Ǝv���Ă���B�A���X�g�e���X�̒���Ƃ��̊w��̌n�͑���ɂ킽��A�N�w�҂ł��Ȃ��l�̂悤�Ȗ}�l�ɂ͂Ƃ��Ă��ǂݓ��Ȃ����A���������Ȃ��B
�@
�_���w�ɂ́A�u�J�e�S���[�_�v�u����_�v�u���͘_�O���v�u���͘_�㏑�v�u�g�s�J�v�u�\�t�B�X�g�I�_���v�A���_�w�̎��R�w�ɂ́A�u���R�w�v�u�V��_�v�u�C�ۘ_�v�u�������Ř_�v�u�썰�_�v�u���R�w���_�W�v�u�������v�u���������_�v�u���������_�v�u�����^���_�v�u�������s�_�v�u���i�W�v�u���W�v�A���������_�w�̐��w(����������͌������Ȃ�)�A�_�w�́u�`����w�v�B�܂����H�w�Ƃ��Ă̍s�w�Ɂu�j�R�}�R�X�ϗ��w�v�u�G�E�f���X�ϗ��w�v�u�哹���w�v�u�����w�v�u�Ɛ��w�v�A�����H�w�̐���w�Ɂu�٘_�p�v�u���w�E���|�n��_�v�c�ƌ������ɁA���L���L���肪����(�������������̍����̋U������݂���)�B���Ɂu���w�̑c�v�ƌ�����ɑ��������̌n�\���ł���B�܂��A��������⼌����̕��̂ł͂Ȃ��A�_���ɋ߂��̍ق̒���͌Ñ�M���V���̓N�w�j��A�A���X�g�e���X�ɂ���ď��߂Ė{�i�I�Ȍ`���Ƃ���(���Ⴆ�A�^���X��\�N���e�X�͂�������������c���Ȃ��������A�v���g���͑Θb�тƌ������قȋY�Ȍ`�����g�������A�s�^�S���X�h�̉��`�͋��c�����̔閧������)�B
�@
�����ꂾ�������̊w�������邪�A����̊w��I�������炷��ƁA��T���炯�ł���B���ɁA���R�w���_�ɂ����ẮA�ނ̊w���͂܂������ߋ��̂��̂ł���(�Ⴆ�A�V�����Ɋ�Â����V���w����̎��R�������́A���̓T�^�I�Ȃ��̂ł���B)�B�������A�A���X�g�e���X���������D�ꂽ�w�҂Ƃ��ĔF�m����Ă���̂́A���̎���̌���ꂽ�ϑ��Z�p�E���@��p���ė��_��g�ݗ��ĂĂ������A����_�⓴�@�̂��̎v�l�̓����D��Ă��邩��ł���B���������]��������������ɁA���R���ώ@���āA�Ⴆ�����̐��ɍ���Ȃ����ۂł����Ă��A�ώ@���ʂ̕���D�悵���B�����̎v�ٓI�ƑP�ł͂Ȃ��A�ނ͂����܂ł��ώ@�����ɒ����Ȍo����`���т����B
�@
�A���X�g�e���X�́A�l�Ԃ̎v�l��������ʂ��u���v�u�s���v�u����v��3�ɋ敪���A�w���3�ɕ��ނ����B�ނ́A�u���_�w�v�Ɛl�Ԃ̍s�ׂɊւ��u���H�w�v����ʂ��A���_�w�́u���R�w�v�u���w�v�u�_�w�v�ɕ��ނ��A���H�w�ɂ́u�ϗ��w�v�u�����w�v������B�A���X�g�e���X�́A�����̊w�╪�ނɐ旧����Ƃ��āu�_���w�v���A�����̊w��ɋ��ʂ��铹��(�I���K�m��)�ƈʒu�Â����B
�@
���H�w�́A�l�Ԃ̍s�ׂ�Љ�ۂ������̂ŁA���w�̂悤�Ȍ������͓���ꂸ�A�o���I�Ȃ��̂��d�����������G�c�ȔF����������Ώ\���Ƃ����B�A���X�g�e���X�̊w�╪�ނ́A�Ώۂ̓����ɉ����ĔF���̌�������ς��Ă���B�A���X�g�e���X�̂��̊w��ς́A���̌�����ȕό^��ւ�Ȃ�����X�g�A�h��G�s�N���X�h�ɂ��p�������(������̉�X�̎Љ�����n�E���n�̋�ʂ�����Ă��邪�A���̂悤�ȕ��ނ̓A���X�g�e���X�ɂ܂ők��̂ł���)�B
�@
�A���X�g�e���X�̓N�w�̒��ŁA�ł������G�Ȃ͓̂O�ꂵ��"���@�_"�̈ӎ��ł���B�ώ@�����A�펯�A�w�����E���グ�A���͂��Ȃ���A�₦���_�q�̏�����l�@�̌��E�ɗ��ӂ���B�ꍇ�ɂ���ẮA�Ǝ��̑�������o���̂��B�����������q�́A�w��I�ȒT�������܂���ׂ��葱����������Ǝ����Ă���B
�@
�ȏ�̂悤�ɁA�A���X�g�e���X�̊w���S�Ăɂ킽���Ă����Ř_����͖̂����Ȃ̂ŁA��v(�Ǝv����)�Ș_�_�����������グ��B�܂��́u���̓N�w�v�ƌĂ����(���`����w�ɂĎ�舵���_�l)�B���o�̑ΏۂƂȂ�A�^���ω��̑��ɂ���u���R�v��ΏۂƂ�����̘_�y�́u���̓N�w�v�ƌĂсA������������ƕ��ՓI�Ȋw����u���̓N�w�v�Ƃ��č\�z���āA�u���̓N�w�v�Ƌ�ʂ��Ă���B
�@
"���ׂĂ�"�l�Ԃ��A"�m"�����߂�B������"���o"(���܊��̒��̐G�o)����������̂Ƃ��Đ��܂�A�A����"�h�{"�@�\(���V��ӂƕ�����ւɂ�莩�Ȃ��ێ�����)��"���B"�@�\(��������Y����)��{���Ƃ���B�l�Ԃ̏ꍇ�́A�����̎����o����L�������܂�A�L������ɂ��Čo�����l������B�X�ɁA�Z�p��m��������g���Đ�������ω������Ȃ��琶���Ă����B���ꂪ�l�Ԃł���B�Z�p�͌o�����甭����(�Ⴆ�Ίy��̉��t�̗��K�A�O����̏K��etc.)�A�o���������Z�p�͖��ɗ����Ȃ���������Ȃ��B�������A�o�����L�x�Ȑl�����A�Z�p�m��S���Ă���҂̕����A��X�́u�m�b����ҁv�ƍl����B�Ȃ��Ȃ�A"�Z�p"�͎����̍��{�������邪�A"�o��"�����̗��R�������Ȃ�����ł���B�u��(�������⌴��)��������v���Ƃɂ���āA���l�̎���̒m����`�B���鎖���ł���̂ł���B�A���X�g�e���X�́A���̂悤�ɂ��āA�w��E�m���E�Z�p�����藧��ʂ��������m�ɂƂ炦�悤�Ƃ��Ă���B
�@
���������m���ςɂ́A�d�v�Ȗ��_������B���ɁA�w���Z�p��"��"�ł͂Ȃ�"����(�J�g���[)"�Ɋւ��Đ�������B�u���̖�͂��̐l�ɂ͌��������A���̐l�ɂ͌����Ȃ������v�ƌ����o���ł͂Ȃ��A�u���̂悤�ȑ̎��ɂ́A���̖����v�ƌ������ՓI�Ȗ@����c�����邱�Ƃ��A�w���Z�p�Ȃ̂ł���B�����āA���̕��Ղ�c�����邽�߂ɁA���v��m���̎�@�����������̂ł���(���Ⴆ�ΓV�C�\��Ȃ����̈��)�B���N1���l����ʎ��̂ŖS���Ȃ����Ƃ���A���N�����̂��炢�̐l���S���Ȃ�ƑS�̓I�ȌX���̐����͂ł��邪�A�������A�u�����A������ʎ��̂ɑ������ǂ����v�ƌ���������̌ʂ̏o�����̐����͗��Ă��Ȃ��B����́A�ӎU�L���肢�̗̈�̘b�ł���B���ɁA���t�ɂł��Ȃ����̂͒m���Ă���Ƃ͌����Ȃ��ƌ��������B���̂Ȃ�A�w���Z�p�͂��ׂĘ_�Ɛ����̑̌n�������Ă��邩��ł���B����ŁA���]�Ԃ̏����Ȃǂ́A�m���ł͂Ȃ��o����ʂ��ē������̂ł���A�{�l���̂������Ƃł����̓��ł��Ȃ���������Ă��邪�����ł��Ȃ��m����ł���(���K����芵���)�B�ނ́A���̂悤��"�Z�p�E�w��"��"�o��"����ʂ����B
�@
�m�̒Nj�����ׂ�"�Z�p�A�w��"�����A���Ƃ��Ƃ͐�����֗��ɂ��邽�߂̎��p�ړI������(���Ⴆ�ΐ����ɕK�v�ȋZ�p�����w�A������͌�y�̋Z�p)���A�����𗣂�Ď��ȖړI�I���i�����������ۓI�Ȋw��ւƐ�������(���Ⴆ�ΐ��w)�B�A���X�g�e���X�́A������O�̒m���Ƃ���B���������w�₪���܂��ɂ́A�u�����̗]�T(�X�R���[)��������Ȃ�Ȃ��v(�X�R���[�́A�X�R��(�w�Z�A�N�w)�A�X�N�[���Ȃǂ̌ꌹ)�ƍl�����B���퐶���̎��Ԃ��A�N�̂��߂ł��Ȃ��������g�̂��߂ɗp���A�����̖ڕW���������Ă������߂̎��ԁA���ꂪ�A���X�g�e���X�̃X�R���[�ł��A���R�l�̏ł���B�܂�A�ނ����������̂́A�l�Ԃ͎�������芪�����E�̏����ۂ������ɐ������Ă���̂��A���̍����E������q�˂��ɂ͂����Ȃ����݂ł��邱�ƁA���������l�Ԋρ��m���ς������Ă����̂ł���B
�@
�A���X�g�e���X���l����A�w��{���̌����T�����ڎw���ׂ����ɂ̍����͉����B����́A�����4�̗ތ^�Ɏ���������B���́u���ʈ��v�����łł��Ă���̂��A���́u�`�����v������͈�̉��ł��邩���{���A��O�́u�n�����v�����ꂪ���ɂ���Đ��܂�Ă��邩�A��l�́u�ړI���v������ڎw���Đ��ݏo���ꂽ�̂��B�������u�l�����_�v�ƌĂԁB�Ⴆ�A���F�̊�������A���ʈ���"�؍�"�ł���A�`������"���F��"�ł͂Ȃ�"��"���{���ł���A�n������"�E�l"�ł���A�ړI���͉Ƌ�Ƃ��Ă̗p�r�c�ƌ������ƂɂȂ�B�B�@���āA�u���ꂪ�����������ł��邩�v�͂��̕��̖{���ł���B�R�b�v�̖{���́A�ؐ��Ƃ��������Ƃ��v���X�`�b�N���Ƃ��A�����Ƃ������Ƃ��ɂ͉��̊W�������B���݂ɉt�̂����Ă����邱�Ƃ��R�b�v�̖{���ł���B�^�C���͊ۂ��Ȃ���Γ]����Ȃ��B���̂悤�ɕ��̖{���́A�`�E�`�Ԃ�}��ɂ��ďd�Ȃ��Ă���̂ł���B���̂悤�ɁA�A���X�g�e���X�͎�������ʂ�"�`��(�G�C�h�X)"��"����(�q�����[)"�̗��ʂ���I�ɔc�����悤�Ƃ��鎋�_�������Ă����B�ނɂ��A�`���Ǝ��ʂ���Ȃ�����u����(�E�[�V�A)�v�ł���(�E�[�V�A�ɂ��Č�ŏڏq)�B
�@
����R�b�v�͐l�H�������A�A���X�g�e���X�́u���R�Ƃ͉����v��_����B���R�́A�l�H��s���R�Ƒ��Ȃ����A���R�̎��݂��킴�킴�ؖ�����͈̂Ӗ��������B���R�Ɛl�H�̋�ʂ́A�l�Ԃ̐��E�F���őO��ƂȂ���̂ŁA����ł��łɗ�������Ă���ł���{�I�Șg�g�ł���B�A���X�g�e���X�ɂ��A���R�͌��ۂ�������邽�߂̍����ł���B���R�́A"�����T�O"�ł���A"���@�T�O"�ł�����B
�@
�u���R�ɂ���đ��݂�����́v�́A���A����y�A�A���A��C�Ȃǂ̌��f���Ӗ����A�u�����̂����ɉ^���ω��ƐÎ~�̏o���_�E����(�A���P�[)�������Ă���v�_�Ől�H�i�Ƃ͈قȂ�B�Ⴆ�A���͐E�l�̎肪�����ď��߂Ċ������邪�A�a�l�͈�҂������������ɂ��Ă��a�C������̂͑̂ɔ�����Ă��鎡���͂ł���B�l�H���Ƃ������āA�n���������߂��������Ă���̂ł���B�Ԃ̎�����ɂ��Ă����l�ł���B�����āA�����Ԃ̎�����̌������ׂ��ڕW(�I���_)���A���߂����߂��Ă���B����́A���Ȏ������������_�ŐÎ~����B�܂��A���ׂĂ̐����͓���̎q�������Č�Ɏc���B�|���āA�l�H���͎��Ԃ̌o�߂Ƌ��ɒ����͉�̂��āA����Đ����邱�Ƃ͂Ȃ��B���R�͉^���ω����Ȃ�����A�S�̂Ƃ��Č���ΐ₦������̒������Đ�����~�A�T�[�N�����Ȃ��Ă���B
�@
�A���X�g�e���X�̑��̓N�w�ɂ��Ă����ƌ������A���ɑ��̓N�w�ɂ��āB��q�����悤�ɁA����Ƃ�����u���݂�����́v�𐳂ɂ��̑��݂�����̂Ƃ��Ă̌���ɍl�@���镁�ՓI�w����A�A���X�g�e���X�͍\�z���Ă���B���ɓI�ɂ�"�_"��ΏۂƂ���u�_�w�v�Ƃ�������(����`����w(���^�t�B�V�J)��́A���̍���Ȏ��݂ł�����̓N�w�Ɋւ���_�l)�B�u���݁v�̖�����舵���ɂ�����A�A���X�g�e���X����N�����d�v�ȊT�O��"�J�e�S���[(���e)"�ƌ����l�����ł���B�Ⴆ�A�u�l�̕�1���[�g���̔����y�����v������Ƃ���B�����́A����ʣ��u���L��A����́v�Ȃǂ������̃J�e�S���[�ɕ�������B�J�e�S���[�͕���(��10�Ƃ�������)���邪�A�d�v�Ȃ̂�"����"�Ƃ���ȊO�̃J�e�S���[�Ƃ̋�ʂł���B���̂Ƃ́A����ɂ��Č��̂ɑ��̑O���K�v�Ƃ��Ȃ��u���ꎩ�̂Ƃ��đ��݂���v�ƌ�������̂ł���(���q���|�P�C���m�������Ƃɒu����Ă��镨�̈Ӗ�)�B�Ԃ������S��5�~�����Ƃ���B���S���Łu�Ԃ��̂��������v�ł͉��̎���������Ȃ��B�g�}�g�����ĐԂ��B�u5���������v�ł́A����5�~������������Ȃ��B�펯�ōl����A�u�����S���v�ƌ����������S���w�����āu�Ԃ���5���������v�ƌ��������łȂ���Δ������͂ł��Ȃ��B���Ԃ́A���̋t�ł͂Ȃ��B�����S���A����"�q���|�P�C���m��"�ł���B���̂悤�Ȉ��肵�����̐��E�Ƃ��Đ��������Ă���\�����A"����(�E�[�V�A)"�ł���B�A���X�g�e���X�́A�����"���̂Ƃ͉���"�ƌ����T�����s���B���̂��K�肷�����4��(�{���A���ՁA�ށA���)�����A����ɂ��Ă̕��͂������Ă������̂ł���B
�@
���ɁA�A���X�g�e���X�̎��H�N�w�̕��@�_�Ƃ��Ă̗ϗ��w(�G�[�g�X�^�G�V�b�N�X(�ϗ�)�̌ꌹ)��_�l����B���ɁA�l�Ԃ̍s�ׂ͂��ׂČʓI�ł���B�ʐ��ɔ����h�炬�E�s�m�萫�̈Ӗ�����������K�v������B�Ȃ̂ŁA���ɐl�ԓI�Ȏ����̌����ɓ������Ă͉ߏ�Ȍ������͊��҂ł��Ȃ��B��G�c�ȌX����@���������������A�ǂ��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���p�����߂�d���́A���w�҂ƉƋ�E�l�ł͓����ł͂Ȃ��B���̗��҂���������̂́A���������u���{�v�������Ă���̂ł���B�����đ�O�ɁA���H�́u�P���l�͉��ł��邩�v��m��݂̂Ȃ炸�A�P���l��"�Ȃ�"���Ƃ�ڎw���̂ł���B
�@
�������Ȃ̂́A�ނ̗ϗ��w�́A�����w�Ɩ��ڕs���ȊW�̓_�ł���B�l�X�͐_�X�⓮���ƈ���ĒP�Ƃł͐��������Ȃ��̂ŁA�����̕K�v�ɉ����ėl�X�ȋK�͂̎Љ���̂����ݏo����Ă���(�Ɓ������|���X���s�s����)�B��ϗ��w��ɂ����ẮA�l�ԂɂƂ��Ă̑P�A�܂�K���Ƃ͉����Ȃǂ̏���肪��������邪�A����炪�𖾂���邾���ł͏\���ł͂Ȃ��A���������l�Ԃ̑P��K���������\�ɂ���|���X�̏���������Ȃ��Ȃ�Ȃ��̂ł���B�P�����ƁA�������ƂƂ͉����w���̂��A�����̏����Ƃ͉����A�|���X�ł̋���͂����ɂ����ׂ����A�ȂǂȂ�(������炪������w��Ŗ����B���̗ϗ��w���A��ɑ����X�g�A�h�A�G�s�N���X�h�A���^��`�Ȃǂ̃w���j�Y�����w�h�ƈႤ�̂́A����炪�����w�������Ă���_�ł���)�B
�@
���āA�l�Ԃ̍s�ׁA�����̋��ɖړI(�ō��P)�͉����H�����Ă��̐l�́A"�K��"�ň�v����B�������A�K���̒��g�܂ňꏏ�Ƃ͌���Ȃ��B�u���N��A����Y��A����_�etc.�c�B�A���X�g�e���X�́A���߂Đl�Ԃ̎��R�{���ɑ������l�@��W�J����B�l�Ԃ̌ŗL�̋@�\�Ƃ��ẮA���S�X(���ʁA����)���������̂���������ɂȂ�B�������������̗L�����z���������A�l�Ԃ̑P���Ɋւ��Č���I�ȈӖ������B���ꂪ���ۂɊ������Ă���ꍇ�ɁA�l�ԌŗL�̑P�����܂�A���ꂪ�K�����Ӗ�����ƃA���X�g�e���X�͍l�����B���̓�̗v�f���A�K������ɂ���ۂ̎w�j�Ƃ����B�ނ́A�l�ԂɂƂ��Ă̍K�������������ϑz�̐����Ɍ��o�����B�l�Ԃɂ́A�m�I�Ȋ����̌X�������R�{���I�ɔ�����Ă���̂ł���A�l�ԓI�ȍK���͓˂��l�߂��_�̐�����邱�ƂŁA���߂Ċ����Ɏ���B�e�����D�ލs�ׂ⊈���Ɏ��Ԃ�Y��Ėv�����邱�ƂŁA�[���[���Ɗ�тɖ�������A���̂��ƂŗL���̐�����l�Ԃ́A�P�Ȃ鎩�R�I�Ȑ�����Đ_�X�̐��Ɏ��铹���J���Ă���B���̂悤�ɃA���X�g�e���X�̑��̓N�w�Ɨϗ��w�͂Ȃ����Ă���̂ł���B
�@
�A���X�g�e���X�ɂƂ��Ă̍K���͐_�̐����ɋ߂Â��������A�ނɂƂ��Đ_�͓V�̂̉^�s�̌����ł���B�_�͎����ȊO�̉��҂ɂ��ς킳��邱�Ƃ��Ȃ��A�Ђ�����v���ɂӂ��銮�S�ȗ����I���݂ł���B�V�̂͐_�ɓ���ē������́B�]���Đ_�͎��瓮�����ƂȂ����������́A��s���̓��ң�ł���Ƃ����B�l�Ԃ̍K���ɂ́A�~�]�̖�������y��Nj����颋��y�I������▼�_�Ɛ��`��Njy���颐����I����������邪�A�A���X�g�e���X�́A���̐^����T�����_�̐����ɋ߂Â���ϑz�I��������ł��K���Ȑ����ł���ƍl�����̂ł���B
�@
���āA�A���X�g�e���X�̓N�w�̂ق�̈ꕔ��`�������������A�ނ̓N�w�̈�[�ɂ͑��ݓ��ꂽ�Ǝv���B
|
������ɐ������X�ƃA���X�g�e���X�̓N�w�̓K�p�ɂ���
�@
�A���X�g�e���X�̊w��́A���݂Ɏ���܂ŐF��ȉe����^���Ă���B�O�q�̂悤�ɁA�A���X�g�e���X�͕���"�{��"��"����"�Ƃ͉����ɂ��ĉ�X�̑O�Ɏ������Ƃ������A���̂��߂ɔނ��p�����T�O�E���@�_��"�J�e�S���["�ƌ����l�����ł���B����ɐ������X���A�ӎ������ɐF��Ȏ��ۂ��J�e�S���C�Y���Ă���B�Ⴆ�A���̂g�o�̃��j���[�͕���ʂɃJ�e�S���C�Y���Ă��邵�A�e���ځA�Ⴆ�ΎԂ̃R�[�i�[�ł�"�X�|�[�c�J�["��"���^��O��"���敪�����Ă�̂��J�e�S���C�Y�̈�ł���B�܂��O�q���Ă���悤�ɁA���̊w��𗝌n�ƕ��n�ɕ����Ă���̂��A���̃A���X�g�e���X�̊w��I���@�_�Ƀ��[�c������B
�@
�܂��A���t�ł͓`�����Ȃ�"�o��"�ƁA�w��I��"�m��"�̈Ⴂ�m�ɋ�ʂ����̂��A���X�g�e���X�ł���B�Ⴆ�A�싅�̃o�b�e�B���O�̗��_�͎��ׂ��ɂ���B�R�[�`�����҂́A��������t�Ŗ��m�ɓ`�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�I�肪���ۂɃ{�[����ł��ăz�[�������ɂ���ɂ͓��ŗ������������ł͑ʖڂŁA���x���������K���̂Ŋo�����܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɁA���t�œ`����"�m��(�w���Z�p)"�Ƒ̂ő̓�����"�o��"�͈قȂ邱�Ƃ��������̂ł���B
�@
�A���X�g�e���X�̓N�w�͓���ƍl�����Ă��邪�A��X�̈ӎu�Ƃ͊W�Ȃ��A���ɃA���X�g�e���X(�̊w��)�̉e����F��ȂƂ���ŎĂ���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@
���N���X�`�����ł��鎄�ƃA���X�g�e���X�N�w�̊֘A�ɂ���
�@
�A���X�g�e���X�̓N�w��w��ς͂��̌�̃X�g�A�h��G�s�N���X�h�Ɉ����p����邪�A�����ɂ������N�w�Ƃ̊ւ�肪�`����Ă���B�V���̎g�k���s�^�ɂ��̋L�q������B���㋳��̃p�E�����A2��ڂ̐鋳(�`��)���s�ŃA�e�l�ɍs�����Ƃ��̂��Ƃł���B�p�E���́A�A�e�l�̒����̎��鏊�ɋ���������̂����ĕ��S�����B����ʼn�ł̓��_���l�����Ƙ_�������A�����ł͋����킹���l�X�Ƙ_���������B���̒��ɃG�s�N���X�h��X�g�A�h�̓N�w�҂��������l�����āA�p�E���ɂ���������"�u���Ȃ��������Ă��邱�̐V�����������ǂ�Ȃ��̂��A�m�点�Ă��炦�Ȃ����B��Ȃ��Ƃ��킽�������ɕ������Ă��邪�A���ꂪ�ǂ�ȈӖ����m�肽���̂��v�B���ׂẴA�e�l�l�₻���ōݗ�����O���l�́A�����V�������Ƃ�b�����蕷�����肷�邱�Ƃ����ŁA�����߂����Ă����̂ł���"(���V���������)�A�Ə�����Ă���B�����Ɠǂݔ���Ă��܂����������A����̓A���X�g�e���X���ϑz�̐���"����Ƃ��Ă������ƂɈ�v����B"�����̗]�T(�X�R���[)"�������A������"�m�I����"����Ƃ���A���X�g�e���X�I�����́A�u�����V�������Ƃ�b�����蕷�����肷�邱�Ƃ����ŁA�����߂����Ă����̂ł���v�ƌ��������̋L�q�ƈ�v����B
�@
����̃p�E���͐S�ł͋����ɕ��S���Ă������A���Ƃ��A�e�l�̐l�X�ɕ�����`�������ƌ����v������A�Ȃ�ׂ��ނ�̓N�w��@���̘_���𗘗p���Ȃ�����A�������q�ד`���悤�Ɠw�͂���B���ʂ́A"����҂͂������A����҂́A�u����ɂ��ẮA������܂��������Ă��炤���Ƃɂ��悤�v�ƌ�����"�c�ł���B���̌��t�́A���{�̐����Ƃ̢�O�����Ɍ������܂���ƈꏏ�ŁA���߂����x�ƕ����C�̂Ȃ��ƌ����ӎu�̔����ł���B�M���V���l�����́A�ނ炩�猩��ΊO���l�ł���ٖM�l�ł���p�E�����A���߂��犮�S�ɏォ��ڐ��Ō��Ă��āA����������������Ɍy���ނ���������Ă���̂ł���B�܂�A�����œo�ꂵ�Ă���A�e�l�̓N�w�ҒB�́A�����B�̕��������w��I�ɏ㋉�ŁA�M�Ɋւ��Ă����[���v�������Ă���ƍl���Ă���B�M���V���̓N�w���\�N���e�X�ȗ��̒����`���������Ă���ƌ������j�w�i�A�M���V���̕����̕������ً̈��̕��������G�łĂ���ƌ����M���V���l�̈ӎ��������ł��Ȃ����낤(�����̎v�l��ԓx�́A���ɃL���X�g���k�𔗊Q���Ă������̃p�E���̎p�ł���)�B
�@
�����ɏd��Ȗ�肪����ł���B�m�I�Ȋ��������ے肷��l�́A�����͂��Ȃ����낤�B�l���ے肵�Ȃ����A�ނ���m�I�����͍D����(�������"�߂�ǂ�"���͂������Ă��邭�炢������)�B�������A�����ł̘_�_�͂����ł͂Ȃ��̂ł���B"�l�Ԃ̗�"��"�_�̗�"�A�ǂ����l���̒��S�ɒu�����ƌ����_�_�Ȃ̂ł���B�A���X�g�e���X�̍ŏ�̍K����"�l�Ԃ̒m"�̒Nj��ł���A�_�ɋ߂Â��A�_�̐^�������A�_�̐����𑗂邱�Ƃł���B����A�����͂��������Ȃ��B�l�Ԃ̗͂ł́A�����Đ_�ɂȂ�Ȃ����_�ɋ߂Â����Ƃ��ł��Ȃ��B�l�Ԃɂ͍߂�����A�_�ɋ߂Â��ɂ͐_�̓Ƃ�q�ł���C�G�X�E�L���X�g�̋~���������ȊO�̓��͖����B�A���X�g�e���X�ɂ����Ă͐l�Ԃ̗͂Ɠw�͂̉�����ɐ_������A�����ɂ����Ă͐l�ԂƐ_�̊Ԃɂ͎���̗͂œn�鎖�̂ł��Ȃ��傫�Ȓf�₪����̂ł���B"�X�g�A�h��G�s�N���X�h��̓N�w"��"�p�E���̓`��������"�́A����I�ȏՓ˂�Ƃ꓾�Ȃ��ł���B�M���V���N�w�ɂƂ��āA�����̌��"���̂������"�́A����I��"�T���̐�"�ƂȂ�B�u�ǂ������ԓ_�őË����܂��傤�v�ƌ����悤�ɁA����ӂ�ɂł�����ł͂Ȃ��̂ł���B����̓A���X�g�e���X�̊w��I���@�_���A����̉�X�ɉv�ł���̂Ƃ͕ʖ��ł���A����"�l�Ԃ����ɂ���čK����̂�""���������̍K���Ƃ���̂�"�ƌ���"���ɂ̖₢"�Ȃ̂ł���B�V���̃R�����g�̐M�k�ւ̎莆(���)�ɂ́A�l�Ԃ̒m�b�E�͂��Ύ���������������̂悤�Ɍ��y���Ă���B
�@
�u�\���˂̌��t�́A�ł�ł����҂ɂƂ��Ă͋����Ȃ��̂ł����A�킽�������~����҂ɂ͐_�̗͂ł��B����́A���������Ă��邩��ł��B�u�킽���͒m�b����҂̒m�b��łڂ��A�����҂̌������Ӗ��̂Ȃ����̂ɂ���B�v�m�b�̂���l�͂ǂ��ɂ���B�w�҂͂ǂ��ɂ���B���̐��̘_�q�͂ǂ��ɂ���B�_�͐��̒m�b�������Ȃ��̂ɂ��ꂽ�ł͂Ȃ����B���͎����̒m�b�Ő_��m�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B����͐_�̒m�b�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�����Ő_�́A�鋳�ƌ��������Ȏ�i�ɂ���ĐM����҂��~�����ƁA���l���ɂȂ����̂ł��B���_���l�͂��邵�����߁A�M���V�A�l�͒m�b��T���܂����A�킽�������́A�\���˂ɂ���ꂽ�L���X�g���q�ד`���Ă��܂��B���Ȃ킿�A���_���l�ɂ͂܂���������́A�ٖM�l�ɂ͋����Ȃ��̂ł����A���_���ł��낤���M���V�A�l�ł��낤���A�����ꂽ�҂ɂ́A�_�̗́A�_�̒m�b�ł���L���X�g���q�ד`���Ă���̂ł��B�_�̋������͐l���������A�_�̎コ�͐l������������ł��v�B
�@
�܂��A�����������̃��[�}�̐M�k�ւ̎莆�ɂ́A�m�b������ƌւ�Ȃ�����͋����Ȑl�Ԃ̐^����W����s�M�S�ƕs�`�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ���Ă���B
�@
�u�s�`�ɂ���Đ^���̓�����W����l�Ԃ̂�����s�M�S�ƕs�`�ɑ��āA�_�͓V����{���������܂��B�Ȃ��Ȃ�A�_�ɂ��Ēm�肤�鎖���́A�ނ�ɂ����炩������ł��B�_������������ꂽ�̂ł��B���E������ꂽ�Ƃ�����A�ڂɌ����Ȃ��_�̐����A�܂�_�̉i���̗͂Ɛ_���͔푢���Ɍ���Ă���A�����ʂ��Đ_��m�邱�Ƃ��ł��܂��B�]���āA�ނ�ɂ͕ى��̗]�n������܂���B(����)�����ł͒m�b������Ɛ������Ȃ�������ɂȂ�A�łт邱�Ƃ̂Ȃ��_�̉h�����A�łы���l�ԂⒹ��b�┇�����̂ȂǂɎ��������Ǝ��ւ����̂ł��B�v
�@
�A�e�l�̓N�w�ҒB�̓p�E���̕�������ɕ��������A"�������A�ނɂ��čs���ĐM�ɓ������҂��A���l������"(����)�c�Ə�����Ă���B���{�́A�������̓N�w��@�����×�����A����"�v�z�̌��{�s"�̂悤�ȍ��ł���B���̂悤�ȍ��Ő�����1���ɂ������Ȃ��N���X�`�����́A�p�E���̎p�����ƂĂ��Q�l�ɂȂ�Ǝv���B�@�@
�@ |
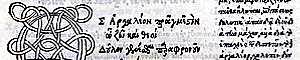 �@ �@
�����[�N���b�h�u�w���_�v���� 1482�N |
   �@
�@
|
Euclides.(B.C.330��-275)
�@
Elementa geometriae.
�@
���[�N���b�h(�G�E�N���C�f�X)�́A�I���O300�N���̃A���L�T���h���A�̐��w�ҁB�M���V���w�A���������[�N���b�h�w���̑听�ҁB�u�w���_�́A�s�^�S���X�ȗ��̂����鏉���M���V���̐��w�I�m�����W�听���A��т����̌n�ɑg�D���ĕҏW�������̂ŁA�����ł��Ȃ����E���Ŏg���Ă���ŌÂ̐��w�e�L�X�g�ł���B�����������A���E�ɖ{���قǍL�����z���A�����o�ł��ꂽ���͖̂����ł��낤�B�{���ͤ1482�N�ɃA���r�A�ꂩ��̃��e�����Ƃ��ă��F�j�X�Ŋ��s���ꂽ�ŏ��̈���{�ł���A�w�I�}�`���Ĉ�����ꂽ�ŏ��̖{�i�I�Ȗ{�ł���B�����Ė{���ɓY����ꂽ�}�̍אS���Ƃ킩��₷���́A�Ȍ�̐��w���̃��f���ƂȂ����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���q�O�f���u�|���N���j�R���v���� 1482�N |
   �@
�@
|
Higden, Ranulphus.(?-1364)�@
�@
Polycronycon.
�@
�u�|���N���j�R���v�́A14���I�����̃C�M���X�̃x�l�f�B�N�g��C���m�ł������q�O�f���������̒m�����W���������̂ŁA�V�n�n�����瓖���܂ł̐��E�j(������N��L)�𐧍삷�ׂ��A40�قǂ̏���琢�E�n���̐�����6�ɕ��������E�̗��j��ҏW�����B1340�N��ɔނ͂��̎d�����~�肽���A��p�҂ɂ���ă��`���[�h2���̎���܂ő�����ꂽ�B���̒���͑����̊�Ղƒ����R���ۂ̋L�ڂ��܂ނ��A14���I�̗��j�A�n���A�Ȋw�̒m�������ڂ��A2���I�ȏセ�̐l�C��ۂ����B1387�N�g�����B�T�̃W���������e���ꂩ��p��֖|�A�p���ōŏ��̊��ň���҂Ƃ��Ēm����v�D�J�N�X�g���ɂ���āA�E�F�X�g�~���X�^�[��1482�N�ɏ��߂Ċ��{�ƂȂ����B�@ |
�V�n�n������14���I���t�ɓ���܂ł̐l�ނ̗��j��N�㏇�ɏ��q�����s��ȗ��j���B���҃q�O�f���̓C�M���X�̃x�l�f�B�N�g��C���m�ł��邪�A�ꍑ�̗��j�ɂƂǂ܂�Ȃ����E�j�ςͤ�A�E�O�X�e�B�k�X�́w�_�̍��x�̂Ȃ��̃L���X�g���I���j�ς����̍���ɂ���Ƃ������Ă���B�l�ނ̗��j��6�̎���ɋ敪���A���ꂼ��̎���̂Ȃ��ŋ���ȗ͂��ւ����鍑�̋��S��`���o�����ƂŁA���̔w��ɂ���_�̐ۗ��������������A���ɐ�����҂ւ̓����I���P���o�����Ƃ��Ă���B�{���ɂ͒����R���ۂ̋L�q���܂ނ��̂́A14���I�����̗��j�A�n���A�Ȋw�Z�p�Ȃǂɂ��Ă̒m����������q�O�f���̐��E�j��ɂ����鎩���̗��j�I�Ӌ`��ʒu�t���̎��݂��A�����̒m���K�w���炨�����ȋ��������ł���B���̌�C�M���X����o���ꂽ���j���̑������{���́u�p���v��搂��p���ɂ������قǁA�{���̍��{�̐��_��2���I�ȏ�ɂ킽�荪�����x������Ă����B�q�O�f����1364�N�ɖS���Ȃ邪�A���̌���g�����B�T��1387�N���A���e���ꂩ�璆�p��ɖ|�Ċ������݂��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���g�}�X�E�A�N�B�i�X�u�_�w��S�v���� 1485�N |
   �@
�@
|
Thomas Aquinas.(1225-74) �@
�@
Summa theologicae.
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X�́A�C�^���A�̐_�w�ҁA�N�w�Ҥ���l�Œ����̃X�R���N�w�̑听�ҁB�u�_�w��S�v�́A���҂̔ӔN�ɏ����ꂽ�ނ̐_�w�I�A�N�w�I�̌n�̏��ł����\�I����ł���B�ʏ́u�_�w�I�X���}�v�ƌĂ�A������1266�N�����M���͂��߂��A1273�N�ɒ��Ҏ��S�̂��ߖ����̂܂I�������B���̒���͑S��3������Ȃ�A�ŏ��̈���{�Ƃ��Ă�1471�N�ɑ�2�����A1473�N�ɑ�1�����A1474�N���ɂ͑�3�������ꂼ��ʂȈ���҂ɂ���Ċ��s����Ă���B���̖c��Ȓ����]���Ƃ���Ȃ��o�ł�����́A1485�N�ɂȂ��Ė{���ɂ���Ď������ꂽ�B�o�[�[�����̈���ҁA�~�q���G���E���F���X���[�ɂ���đ�1���A��2����1���A��2����2���A��3���ƁA�S4�������s����A������̐��{��1���ɍ��Ԃ���Ă���B�@ |
���_�w��S
�@
�_�w��S(������������A���e����FSumma Theologica)�́u�_�w�̏W�听�v�Ƃ����Ӗ��̑�����������[���b�p�̐_�w���B13���I�ɒ����I�ȃL���X�g���_�w���̌n�������Ƌ��ɏo�������B��ʓI�ɂ̓g�}�X�E�A�N�B�i�X�́w�_�w��S�x���ł��悭�m���Ă��邪�A���ɂ��w�[���Y�̃A���N�T���f����A���x���g�D�X�E�}�O�k�X�̎�ɂ��w�_�w��S�x�����݂���B
�@
�w�_�w��S�x�̓����́A�����̐_�w�ɂ����ėp�����Ă����w����W�x(�Z���e���e�B�G)��w�����x(�R�����^���E��)�ɂ��ɋL����Ă������e��L�@�I�ɕ��ނ��A�̌n�I�ɐ������Ă���Ƃ���ɂ���B�܂�A�����̌��t�⋳���E�_�w�҂̌��t������������Ă������̂��킩��₷���܂Ƃ߂Ȃ����Ă���̂ł���B����ɒ����̎i���������t���w�Z���w�ɂ����Đ���ɂ����Ȃ�ꂽ���_����߂̐��ʂ����荞�܂�Ă���B
�@
������
�@
�w�_�w��S�x�̓g�}�X�E�A�N�B�i�X�̐����钘��̒��ł��ł��L���Ȃ��̂ł��邪�A�����̌��t�ɂ��ΐ_�w�̏��w�Ҍ����̋��ȏ��Ƃ��ď����ꂽ���̂ł���Ƃ����B�����ăL���X�g���k�łȂ��l�X��z�肵�ď�����Ă���킯�ł͂Ȃ����A����ł�����߂Ė����ɗ����ƌ[��(�M��)�̗Z�����͂����A�ǎ҂��L���X�g���M�Ɋւ��鎖���ł������Ŕ[���ł���悤�ɏ�����Ă���B�����āu��S�v�𖼏��ȏ�A����܂ł̐_�w�ɂ����Ĉ���ꂽ������e�[�}�ɂ��Ę_���悤�Ƃ����ӗ~��ł������B
�@
�w�_�w��S�x�̓g�}�X�E�A�N�B�i�X�̃��C�t���[�N�ł���A�ނ̐��U�̌����̏W�听�ł������B�ނ͂���܂łɁw�Έً��k��S(Summa Contra Gentiles)�x�Ƃ������������グ�Ă��邪�A�w�_�w��S�x�͂��̐��ʂ����܂��āA���������ꂽ���̂ɂȂ��Ă���B
�@
�g�}�X��1265�N���납��w�_�w��S�x�̒��q�ɂƂ肩�����Ă��邪�A��O���̊�����ڎw���Ē��q�𑱂��Ă���1273�N12��6���A�~�T������Ă����g�}�X�ɓˑR�̐S���̕ω����N�������B�_�̈��|�I�Ȓ��ړI�̌��������Ɠ`�����Ă���B�w�_�w��S�x����Ղ̕��̓r���܂Ŋ������Ă������A�ނ͈Ȍ��̒��q����߂Ă��܂��B
�@
1274�N3��7���Ƀg�}�X����������ƁA�c���ꂽ��q�������t�̍\�z�������p���ő�O���̎c��̕���(��ՂƏI��)�������������B
�@
��
�@
�w�_�w��S�x�͈ȉ��̂悤�ȎO���\������Ȃ��Ă���B
�@
��ꕔ�@�_�Ɛ_�w(���Ȃ鋳��)�ɂ��� ���Ȃ鋳���A�B��̐_�A�_�̖{���A�_�̑��ݏؖ��A�������ρA�O�ʈ�́A�푢���Ƒn��
�@
��@�ϗ��Ɛl�Ԃɂ��� �l�Ԃ̐����A�l�Ԃ̂͂��炫�A�s�ׁA�ΐ_���Ɛ��v���A�߂Ɖ��b�A�C���҂ƏC������
�@
��O���@�L���X�g�ɂ��� ������ꂽ���t�ł���L���X�g�A�L���X�g�̐��U�A���̔�ՁA�I���ƐR��
�@
�S�̂̍\���Ƃ��ẮA��ꕔ�ŁA�_�ɂ��n����`�����Ő_�ւƌ����������I�푢���ł���l�Ԃ̉^���ɂ��ĕ`���A��O���ŁA�_�ւƌ������ۂ̓�����ׂł���L���X�g�ɂ��ĕ`���Ƃ����\�z�Ɋ�Â����̂ŁA�l�I�v���g�j�Y���I�Ȕ��o�ƊҋA�̌������āA�����ɋL���ꂽ�o�����𗝉����邽�߂̃L���X�g���S�I�A�~�ώj�I�Ȑ��E�ς��������B
�@
�X�̕����̍\��������ƁA��{�I�ɂ͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B�܂��A�`���ɖ��(�e�[�[)�������B���Ƃ��A�u�C�G�X�͕n���������Ƃ������Ƃ͔ނɂӂ��킵�����Ƃł��邩�H�v�Ƃ���������Ƃ��悤�B���Ɏ���ɑ��邢�����̈٘_����������B�٘_�͐�����ߋ��̑�w�҂̈��p�ɂ���Ă����Ȃ���B���Ƃ��Η�ɑ��Ắu�A���X�g�e���X�͒��f���d�A�������ł��n�R�ł��Ȃ����f��I�Ԃ̂��ō��̐������ł���Ƃ��Ă���v�ȂǂƂ�����ł���B���ɑΘ_�������B����͈٘_�ɔ����錩���ł���B���Ƃ��u�����ɂ��ΐ_�͐��������Ƃ��������ł���Ƃ����B�C�G�X���n���������������A�C�G�X���_�ł���Ȃ�A�n�����������͐������������ł������ɂ������Ȃ��v�Ȃǂł���B�Ō�ɂ����̗���܂������������B�͈٘_���邢�͑Θ_�����̂܂܍̗p�������̂ł͂Ȃ��A�S�̂������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������B�܂�P���Ɉ٘_��ے肵�Ă��Ȃ��Ƃ���Ɂw�_�w��S�x�̖ʔ���������B���Ƃ��Η�ɑ���ł́u���f�ɐ����邱�Ƃ��ō��̐������ł���Ƃ����̂͐������B�����A���̗��R�́A�ґ�ɐS�D����A���邢�͖����̕�炵�ɋ��X�Ƃ��邱�ƂŐl���̖ړI��������Ȃ����߂ł���B�C�G�X�ɂƂ��Đl���̖ړI�͐_�̂��Ƃ����L�߂邱�Ƃł������B���̂��߂ɂ͕n������炵�̂ق��������₷�������Ƃ�����B�v�Ƃ�������ɂ܂Ƃ߂���B�@ |
���g�}�X�E�A�N�B�i�X(1225��-1274)
�@
�X�R���N�w�̑听�ҁ@
���g�}�X�E�A�N�B�i�X�ƃA���X�g�e���X�N�w�Ƃ̏o�
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X(1225��-1274)�́A��C�^���A(�i�|������)�̃A�N�B�m�̗̎僉���h���t���݂̎q�Ƃ��Đ��܂�܂������A��e�̃e�I�h�����_�����[�}�鍑�̃z�[�G���V���^�E�t�F���Ƃ̖���Ƃ�������̌����ł����B�g�}�X�E�A�N�B�i�X��5�̍��ɁA�C���@�v�z�̑c�ł���x�l�f�B�N�g�D�X���z���������e�E�J�b�V�m�C���@�ɓ�����܂����A����͉@���߂锌���̃V�j�o���h�̌���p�����߂ł����B�����e�E�J�b�V�m�C���@����i�|����w�ɐi�w���Đ_�w���w�g�}�X�E�A�N�B�i�X�͗��e�̊��߂ɋt����āA�����̃��[�}�E�J�g���b�N����̐��E�҂ł͂Ȃ��A�_�̖{����T������N�w�I�Ȑ_�w����������ł������h�~�j�R��̏C���m�Ƃ��Ă̓�����݂܂��B
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X�́A�_���`�I�ȃL���X�g���_�w�Ɨ����I�ȃA���X�g�e���X�N�w���w�p�I�ɓ������āA�X�R���N�w(�X�R���w)��_�̑��݁E�{�����ؖ�����N�w�Ƃ��Ċ����������l���Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�A�N�B�i�X�����߂ăA���X�g�e���X�N�w�ɐG�ꂽ�̂́A20�Ńh�~�j�R�C����̉���ɂȂ�O�̂��Ƃł���A15���ɃC�X���������̓N�w��(�_�w��)���o�R�����A���X�g�e���X�̓N�w��ǂƂ���Ă��܂��B�h�~�j�R�C����Ŋw�p���r��ςA�N�B�i�X�́A1244�N���ɃP�����Ŋw���E�M��̎t�ƂȂ�A���x���g�D�X�E�}�O�k�X(1193���]1280)�Əo��܂��B���Ք��m�ƌĂꂽ�h�~�j�R��̃A���x���g�D�X�E�}�O�k�X�́A�_�w�E�N�w�E���R�w�E�B���p�Ȃǖ��w�ɐ��ʂ����G�˂ł���A�A���X�g�e���X�N�w�̏ڍׂȒ��ߏ��������Ē�q�̃g�}�X�E�A�N�B�i�X�ɓN�w�I�ȉe����^���܂����B1245�N������A�p����w�Ő_�w�E�N�w�������鋳���ƂȂ����A���x���g�D�X�E�}�O�k�X���g�}�X�E�A�N�B�i�X�͒����Ȓ�q(����)�Ƃ��ĎO�N�ԂقǕ⍲���܂������A�A�N�B�i�X�̎���ɃA�N�B�i�X�̎v�z���ْ[�̌��^���|����ꂽ���ɂ́A�A���x���g�D�X�͘V�̂ɕڑł��ĖS����q��_�w�I�ɕٌ삵���Ƃ����܂��B
�@
�A���x���g�D�X���A�N�B�i�X���A���X�g�e���X�N�w���C�X�����o�R�Őێ悵���̂ŁA�A���F���G�X(�C�u���E���V���h)�̃A���X�g�e���X�N�w�̒��߁E����̉e�����Ă���A�v���g���̊ϔO�_�I�ȃC�f�A��`�Ɛ_�̎��݂��Z�����Ă��镔��������܂��B�D�G�Ȋw�Ɛ��т��C�߂��A�N�B�i�X�́A�p����w�Ŋw�ʂ��擾���Đ_�w�̋��ڂ����悤�ɂȂ�܂����A���c�E���o�k�X4����������M�C����ꂽ���߂ɁA1259�N������C�^���A�ɖ߂��ă��[�}��i�|���ŕ�炷���ƂɂȂ�܂��B1272�N�̃t�B�����c�F�̋����c�ł́A����̋��`�E�v�z�Ɋւ��Ĕ������L�ȃg�}�X�E�A�N�B�i�X�̎v�z���W�听���邱�Ƃ��v������A�A�N�B�i�X�́w�_�w��S�x�̒��q�Ɏ��|����܂����B���{��`�I�ȃh�~�j�R����\����_�w�҂ƂȂ����g�}�X�E�A�N�B�i�X�́A�w�V�g�I���m(Doctor Angelicus)�x�ƌĂ�Đ��p�E����A�E�O�X�e�B�k�X�ƑΓ��ȗ���ɗ��ƌ���ꂽ�p�˂ł������A1274�N�ɑ�2��������c�Ɍ������r���Ŏ��v���܂����B1323�N7��18���ɂ́A�A���B�j�����̋��c���n�l22���ɂ���ăg�}�X�E�A�N�B�i�X�͐��l�ɗ��A�A�N�B�i�X�̏������w�_�w��S(�X���}�E�e�I���W�J)�x�͒����L���X�g����̒��S�I�ȋ��`�̌n�ƂȂ��Ă����܂����B
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X�̍ő�̌��т́A������`�I�ȃA���X�g�e���X�N�w����g���āw�����L���X�g����̐������x��ۏ���s�傩�Ȗ��Ȑ_�w�̌n���\�z�������Ƃł���A�X�R���w�I�Ș_�l�̕��@�_�ɂ���Đ_�̑��݂Ɩ{�����ؖ��������Ƃł������B�X�R���w�Ƃ͊Ȍ��Ɍ����A�w�ڍׂȌÓT�lj�(�e�L�X�g�lj�)�x�Ɓw�_���I�Ȏv�l�v���Z�X�x�ɂ���Ė����_�E���_��ُؖ@�I�ɉ������悤�Ƃ���w��̋Z�@�̂��Ƃł��B�g�}�X�E�A�N�B�i�X�͂��̃X�R���w�I�Ȏv�l�v���Z�X�̃p���_�C��(���_�I�g�g��)�̒��ŁA���Ȃ芮���x�̍����w���^�����̎���W���_�w��S�x�������ƂŃL���X�g���j�ɕs���̖��O�����̂ł��B
|
���g�}�X�E�A�N�B�i�X�ɂ��X�R���N�w�̊����Ɓw�_�w��S�x�̎v�z
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X�́w�X�R���N�w�̊�����(�听��)�x�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂����A����̓A�N�B�i�X���X�R���N�w(�X�R���w)�̕��@�_�����p���āA�������[���b�p�̃L���X�g�����E���x����w���ՓI�Ȑ_�w�̌n�����ݘ_(���O�_)�x���\�z��������ł��B�X�R���w�́A�_�w�I�Ȏ��^�����ɑ���^�ۗ��_���W�߂��w�N�G�X�e�B�I�l�X(���^)�x�Ɛ_�w�I�ȋ^��ɑ���W���I(�����I)�ȉ��W�߂��w�X���}(��S)�x�Ƃ�����̕���W�����܂����B�A���X�g�e���X�N�w���L���X�g���_�w�ɉ��p�����A�N�B�i�X�́A���Ɂw�X���}�x�̕���ő傫�ȍv�������āA�w�_�w��S�x�Ƃ�����\��������������܂����B�w�N�w�͐_�w�̛X��(�͂�����)�x�ł���Ƃ����O��ɗ��w�_�w��S�x�́A�w�_�Ɛ_�w�ɂ��āE�l�ԂƗϗ��ɂ��āE�L���X�g�ɂ��āx�Ƃ���3������\������Ă��܂����A���ݘ_(���O�_)�ƗB���_(���ژ_)���Η����镁�_��(���Ր푈)�ł́w�_�w��S�x�͎��ݘ_���ؖ����鍪���Ƃ���܂����B
�@
���[�}�E�J�g���b�N����f�������ݘ_(���O�_)�Ƃ����̂́A���[�}�E�J�g���b�N������w�L���X�g(�_)�̕��Ր��̌���x�ƌ���v�z�ł���A����g�D(���E��)�̌��Ђ͖ڂɌ����Ȃ����ՓI�ȑ���(����)������Ƃ������ݘ_�Ɏx�����Ă��܂����B�w���ՓI�ȊϔO(�T�O)�x�Ɓw�ʓI�Ȏ���(����)�x�Ƃ�����ꍇ�ɁA�m�o�ł��Ȃ����ՓI�ȊϔO�̂ق�����ɑ��݂��āA���̕��ՓI�ȊϔO(�C�f�A�I�Ȍ��^)�ɂ���āA�ʓI�E��̓I�Ȏ��������o�����Ƃ����l�����̂��Ƃ����ݘ_�Ƃ����܂��B���ɁA�l�Ԃ����ՓI�Ȏ��݂ƐM���Ă���w�ϔO�x�͌ʓI�Ȏ������w�����邽�߂́w�L��(�T�O)�x�ɉ߂����A���ՓI�Ȏ��݂Ƃ͐l�Ԃ̒m�������o�����I�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��Ƃ���l������B���_(���ژ_)�Ƃ����܂��B�L���X�g�����x�z�I�ł������������[���b�p���E�ł́A�g�}�X�E�A�N�B�i�X���_�������ݘ_�������ȋ��`�ł������A���R�ӎu���w�E����h�D���X�E�X�R�g�D�X��B���_(���ژ_)�Ŏ��ݘ_��_�������E�B���A���E�I�b�J���̓o��ɂ���āA����Ɏ��ݘ_�͔��I(��Ȋw�I)�Ȏv�z�Ƃ��đނ����Ă������ƂɂȂ�܂����B
�@
�A���X�g�e���X�́A�������E�̎��ہE�������w�`��(�G�C�h�X)�x�Ɓw����(�q�����[)�x�̗v�f�ɂ���ė������܂������A���E�Ő��N���錻�ۂ̌����Ƃ��āw���͈�(��p��)�E�`�����E�ړI���E�������x�̎l���グ�܂����B���̃A���X�g�e���X�̎l�����_�̉e�������g�}�X�E�A�N�B�i�X�́A�����̉^���̌����Ƃ��āw��p���x�����肵�܂��B�A�N�B�i�X�͉^���̌��X�̌���(��p��)���ǂ�ǂ�k���Ă����A�Ō�ɑ��̉����̂ɂ��e������Ȃ��w���̓���(���̍�p��)�x�ɍs�������Ǝ咣���܂����B���̑��̓��҈ȊO�ɂ��A���E�ōŏ��̑��݂ł���w�K�R�I���ݎҁx�A���S�Ȑ^�E�P�E���̌��^�ł���w�C�f�A�I�ϔO�x�A�ړI�I�ȍs�����\�ɂ���w�m�I���݁x���グ�āA�w�_�̑��݁x��i�K�I�ɘ_���܂����B�w���݁E�^���E�P�s�E��p�x�ɊW�����ԏ��߂̌�����k���Ă����A�Ō�ɂ͑��̉����̂ɂ��e�����Ȃ��w��ΓI�E���ՓI�ȑ��ݎҁ��_�x�ɍs���������ƂɂȂ�A�w�����L�ݏo���Ȃ��x�Ƃ����K�R�I�Ș_���ɏ]���Ȃ�w�_�̑��݁x�͊��S�ɏؖ�����邱�ƂɂȂ�Ƃ����̂��A�N�B�i�X�̎v�z�ł����B
�@
�����Ɗȗ������Č����Ȃ�A�������E�ɂ���S�Ắw�s���S�Ȏ����E���ہE�s���x�̔w��Ɂw���S�����̌��^�E���`(�C�f�A�I�Ȃ���)�x������Ƃ����v�z�ł���A�F���̒����ƍō��̗ϗ�(�P�E�^��)�̍����Ƃ��āw�_�̎��݁x���K�R�I�ɗv�������Ƃ������̂ł��B����́A���ۊE�̔w��ɉi�����Ղ̌��^�Ƃ��ẴC�f�A�E��z�肷��v���g���̃C�f�A��`(�C�f�A���X��)�̏Ă������ł���A�g�}�X�E�A�N�B�i�X�̐_�w�v�z�̓A���X�g�e���X�N�w�ƃL���X�g���_�w�����������łȂ��A�w�����̑n����(������̑n����)�x�Ƃ��Ă̐_��_�w�I�ɕ⋭���邽�߂Ƀv���g���̃C�f�A��`�ӎ��I�ɗp���Ă���̂ł��B���_���ɂ�����w���ݘ_�ΗB���_�x�̍\�}�́w�C�f�A�_�ΗB���_�x�̐}���ɒu�������邱�Ƃ��\�ł����A�A�N�B�i�X�͐��E�ɂ���S�Ă̎����́w���݂��̂��́��_�x��������푢���ł���ƒ�`���܂����B
�@
�l�Ԃ����m���푢���ł����A�A�N�B�i�X�͔푢���̓A���X�g�e���X�I�Ȍ`���Ǝ�������Ȃ���̂ł���Ƃ��āA�l�Ԃ�l�Ԃ��炵�߂Ă���`��(�{��)�́w�����I�ȍ��x���Əq�ׂ܂����B�S�m�S�\�̐_�̖{���L����w�l�Ԃ̍��x�́A�l�ԂɁw�m���x�Ɓw�ӎu�x�Ƃ����ɂ߂ďd�v�Ȕ\�͂�^���܂��B�h�D���X�E�X�R�g�D�X�͐l�ԂɂƂ��čł��{���I�ȗ͂��w�ӎu�x�ƍl�����̂ɑ��āA�g�}�X�E�A�N�B�i�X�͐_�̎��݂ς��邽�߂́w�m���x�������ł����l�̂���͂��Ƃ��܂����B�g�}�X�E�A�N�B�i�X�́A�l�Ԃ̒m���������o���w���`�E�ߐ��E�E�C�E�v���x��4�̓��̎�����ړI�Ƃ��Đ����邱�Ƃ��w�P�Ȃ鐶�����x�ł���Ƃ��āA�Œ�I�ȃC�f�A(�P��)��ڎw���Đ�����w��m��`(������`)�x�̐��E�ς���܂����B
�@
�g�}�X�E�A�N�B�i�X�ȍ~�̓N�w�ł́A�ߑ�I�Ȍ[�֎�`�_�Ƃ��āA�����̐l���̉��l�K�͂������̎��R�ӎu�ɂ���đI���ł���A�ꍇ�ɂ���Ă̓C�f�A�I�ȑP���ς����E���邱�Ƃ��ł���Ƃ����w��ӎ�`�x�̐��E�ς��D���ɂȂ��Ă����܂��B�g�}�X�E�A�N�B�i�X�́w���`�E�ߐ��E�E�C�E�v���x��4�̓��́w�����ɂ�閽��(�����P���u������茾���@)�x�ɍs�������Ƃ��܂������A���̗����ɂ�閽�߂̋��ɂ̍����́A�S�m�S�\�̐_����߂��i�����Ղ́w���R�@�x�ł���Ǝ咣���܂����B�l�Ԃ����R�@�ς��ė����Ɋ�Â�����(�@��)�𐧒�ł���̂́A�l�Ԃ��w�_�̊��S�ȗ����x�̈ꕔ���^�����Ă��鑶�݂ł��邩��ł��B�����āA�l�Ԃ̒m���́w�`���ł��鍰�x�ɂ���ĕۏ���Ă���Ƃ����̂��A�N�B�i�X�̐_���S�̐l�Ԋςł���A�L���X�g���Ō����w�i���s�ł̍��x�Ƃ����̂́w�_(�C�f�A)�̈ꕔ�x���l�Ԃ̎���(�g��)�ɏh�������̂ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B����ɂ́A���͍Ăъ��S�Ȑ_�̌��ւƋA�҂��邱�ƂɂȂ�܂����A���̍l�������v���g���́w���ׂĂ̎����E�T�O�̓C�f�A�E���N���Ƃ��Ă���x�Ƃ����v�z���炫�Ă���Ɛ�������܂��B
�@
�J���^�x���[�̃A���Z�����X��s�G�[���E�A�x���[������n�܂����X�R���w�̗��j�́A���W���[�E�x�[�R����A���x���g�D�X�E�}�O�k�X���o�āA�g�}�X�E�A�N�B�i�X�̎���Ɏ��ݘ_�Ƃ��Ă̊����x�����ߍŐ����ɓ��B���܂����A�X�R���w�͎���Ɍ��Ў�`�I�ȕ����w�E���`�w�Ƃ��čd���I�ȌX�������߂܂��B�Љ�����P����V���Ȓm���≿�l��ł��Ȃ��Ȃ�A�L���X�g���̐��������ؖ����邾���̖����ɗ������X�R���w�́A�h�D���X�E�X�R�g�D�X��E�B���A���E�I�b�J���̎v�z�ɂ���Ĕᔻ�I�ɏ��z�����邱�ƂɂȂ�A�G���X���X����e�[�j���̐l����`�A�C�^���A�E���l�b�T���X�̗������o�āA�[�֓I�E�Ȋw�I�ȋߑ�N�w�̓o��ŗ��j�̕Ћ��ւƒǂ�����܂����B�@�@
�@ |
 �@ �@
�����N���e�B�E�X�u���̖{���ɂ��āv��2�� 1486�N |
   �@
�@
|
Lucretius, Titus Carus.(B.C.94-55��)
�@
De rerum natura.
�@
���N���e�B�E�X�́A�I���O94-55�N���̃��[�}�̎��l�ŁA�N�w�҂ł��邪�A���̐��U�ɂ��Ă͂قƂ�lj����m���Ă��Ȃ��B�ނ̗B��̒���Ƃ���Ă���̂����́u���̖{���ɂ��āv�Ƃ����N�w�I���P���ł���B���N���e�B�E�X�̎��͕��G�ŁA���M�̍S�����痣��Đ��_�����R�ɂ���Ƃ����ނ̐Ȃ��]�́A���R�̖@���̐����̒��ɕ\������Ă���B����̓A�g���̎��R�̉^���Ɉˑ����Ă��邱�Ƃ��������̂ŁA���ׂĂ̕����̓A�g���łł��Ă���ƌ����B���N���e�B�E�X�̍ŏ��̈���{�́A1473�N���u���b�Z�ŏo�ł���Ă���A�W���̏���1486�N�Ƀ��F���[�i�ŏo�ł��ꂽ���̂ł���B�@ |
�����N���e�B�E�X�w���̖{���ɂ��āx / ���]
�@
�{���́A���[�}�̎��l���N���e�B�E�X(Titus Lucretius Carus�Ac.94-c.55B.C.)�̌�������B��̍�i�ł���B�F�l�����~�E�X��ɁA�G�s�N���X�̎��R�ɂ�������������̓��߂ɂ�ł�������Ƃ����X�^�C���ŏ����ꂽ�{���́A�G�s�N���X�̎v�z�����݂ɂ܂œ`����M�d�Ȏ����ł�����(��1)�B
�@
�{���ɂ͑�1�����疢���Ƃ�����6���܂ł��Ƃ���邱�ƂȂ�������̒ʑt�ቹ������B�ЂƂ͈�т������q�_�ł���A�����ЂƂ͔��@���I�ԓx�ł���B���N���e�B�E�X�ɂ���(��2)�A�ЂƂтƂ����R�⎀��������A�����̌�����_�X�ɋA���A�@���ɉe������Ă���̂́A�ЂƂ��Ɏ��R�⎀�ɂ���m���������Ă��邩�炾�B���̌�����m��A���⎩�R�������Ȃ���̂��𗝉�����A���ꂪ����ɐ_�X�Ƃ͊W�Ȃ��A�܂��ނ�݂ɋ����ׂ����̂ł��Ȃ����Ƃ����������ł��낤�A�Ƃ����킯�ł���B�����Ń��N���e�B�E�X��������ނ��邽�߂ɉ��p����̂��A�G�s�N���X�̌��q�_�ł���B
�@
�G�s�N���X�̌��q�_�́A�f���N���g�X��̂���Ɠ��l��(���邢�͂���ɏ]����)���R���ۂ�s���̕��������q�̉^���ɂ���Đ������悤�Ƃ�����̂ł���B�������^�����邽�߂ɂ́A�����̂ق��ɕ����ɂ���Đ�߂��Ă��Ȃ���ԁ�������͂��ł���A�������疜���̖{���͕���(���q)�Ƌł���Ƃ����B�����ŁA�u�ł́A����u�Ԃ̂��ׂĂ̌��q�̈ʒu�Ɖ^���ʂ��킩������͂��̌�N����ł��낤���Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��邾�낤�v�ƍl����Ύ��R�͕K�R�I�ł���B���N���e�B�E�X�ɂ��A�G�s�N���X�́u�ΌX�^���v(clinamen[���e����])���l���邱�Ƃɂ��A�K�R�ł͂Ȃ����R�̓���I�B�܂�A���q�͒ʏ��Ԃ����ɂނ����Đi�ނƂ���邪�A�u�S���s��Ȏ��ɁA���s��Ȉʒu�ŁA�i�H����������A�^���ɕω��𗈂炷�ƌ�����ʂȂ����������v�̂��ƌ����B����͕K�R��^���Ƃ����u�ނ�݂ɋ������v�l����ނ��A�����̎��R�ӎu���m�ۂ��邽�߂̐����ł�����B
�@
�{���Ń��N���e�B�E�X���Ƃ肠���鎩�R���ۂ́A��X�̔F����_�̓�������A�F�����n�̐����A���A��`�A�C�ہA�n�k�A���A�a�C�Ȃǂɋy��ł���B�����Ăǂ̏ꍇ�ɂ��Ă����ꂪ�咣����̂́A�����͂��ׂĐ_�ɂ��̂ł͂Ȃ��A���q�̉^���ɂ��̂��Ƃ������Ƃł���B���̈�т����ԓx�ɂ���ꂪ����ׂ��́A����x��̒m���ł͂Ȃ��A�u���̒��Ɋї�����Ȋw�I���_�v(���c�ЕF)�ł���(��3)�B
�@
�܂��{����ǂ߂Ζ��炩�Ȃ��Ƃł��邪�A���N���e�B�E�X(���邢�̓G�s�N���X)�̔��@���I�ԓx�����Ղɔ��_�_�△�_�_�ɓǂݑւ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B����͎��R���ۂ̌�����_�ɂ��Ƃ߂邱�Ƃ�@����ے肵�͂������A�_�̑��݂�ے肵�����Ȃ߂���͂��Ă��Ȃ��B�ނ���w�C���A�X�x��w�I�f���b�Z�C�A�x�Ɍ�����悤�ȋC�܂���Ȑ_�X��ے肵�Ă���Ƃ��������邾�낤�B������A���N���e�B�E�X�́u�Ȃ��킽�����������̂悤��(�ߎS��)�����ɒu����A�Y�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��I�����A�_�͑��݂���̂��I�v�Ƃ������₢�����ɂ͖����ł���B�Ȃ��Ȃ�A�_�X�͐l�ԂƂ͂������������ł���A�Ƃ����̂����N���e�B�E�X�̎咣�Ȃ̂�����B
�@
(��1)���Ƃ��Aclinamen �Ƃ����T�O�́A���N���e�B�E�X�̖{���ɂ���ē`����ꂽ���̂ł���A�f�B�I�Q�l�X�E���G���e�B�I�X�ɂ���ĕۑ����ꂽ�G�s�N���X�̂��̂Ƃ���鏔��i�ɂ͌����Ȃ��B
�@
(��2)�u�G�s�N���X�ɂ��v�ƕ\�L���ׂ����Ƃ����ӌ������邩������Ȃ����A�����ł́u���N���e�B�E�X�ɂ��v�ƋL���B�ǎ҂ɂ́u���N���e�B�E�X(���邢�͂���ɂ��G�s�N���X)�ɂ��v�Ɠǂݑւ��Ă������������B
�@
(��3)���c�ЕF�́u���N���`�E�X�ƉȊw�v�́A�Ȃ������܁����N���`�E�X��ǂނ̂�������������Ɓw���̖{���ɂ��āx�̉������Ȃ�l�Z�łɂ���60���łقǂ̕��́B���̒��Ŏ��c�ЕF�́u���N���`�E�X�͈�̈̑�ȉȊw�I�َ̖��^�ł���v�Ɠ������������A���̈Ӌ`������Ă���B���e�ɂ��Ă͕ʂ̋@��ɂ䂸�邪�A���N���e�B�E�X�Ȍ�̕����w���������ʂƂ̑Δ�̂Ȃ��ɂ����ꗧ���N���e�B�E�X���܂��������ɖ��͓I�ł���A��������N���e�B�E�X�̐H�O�����邢�̓f�U�[�g�Ƃ��ēǏ��q�ɐ��E���鎟��B�܂��A���̌���(�����^����)�Ɏ��g�Ȋw�҂ł����������c�ЕF�̉Ȋw�ςⓖ���̉Ȋw�E�ɂ�������v�����͂��Ȃ����f����A�Ƃ����ʂ̈Ӗ��ł������̂��Ȃ���i�ł���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���A�E�O�X�e�B�k�X�u�_�̍��v 1490�N |
   �@
�@
|
Augustinus, Aurelius.(354-430)
�@
De civitate dei.(bound with: De trinitate.)
�@
�A�E�O�X�e�B�k�X�́A�Ñ�L���X�g���̍ő�̋����ł���B�{���́A41�N�����[�}�ɋN��������ЊQ���Â����[�}�̐_�X��Y��ăL���X�g����M�������߂ł���Ƃ̔��ɔ������āA�u�_�̍��v�Ɓu���̍��v��Η������邱�Ƃɂ���āA��K�͂̃L���X�g���싳�_��W�J�������B�����́A413�N�����M�ɂƂ肩����426�N���܂ł�14�N�ԂɑS22���������グ��ꂽ�B�L���X�g���̒n�Ղ̏�ɐ��܂ꂽ���m�ŏ��̗��j�̓N�w�Ȃ����A���j�̐_�w�ł���Ƃ�����B�W���̏��́A�����̈���Ǝ҂̈�l���n�l�X�E�A�[�����o�b�n�ɂ��o�[�[���ň�����ꂽ���̂ŁA�A�E�O�X�e�B�k�X�̑��̒��삪1�_���{����Ă���B�@ |
���w�_�̍��x
�@
(���e����FDe Civitate Dei contra Paganos�A�t���^�C�g���A�_�̍�:�ً��Ƃ̑Ό�)�@5���I�����ɏ����ꂽ�A�E�O�X�e�B�k�X����̎�v����B
�@
���E�̑n���ȗ��̗��j��n�̍��Ƃ���ɕ����B����Ă���_�̍��̓�̗��j�Ƃ��ď��q����B�S22����萬��A�O��10���Œn�̍����A�㔼12���Ő_�̍���_����B�A�E�O�X�e�B�k�X��410�N�̃S�[�g���ɂ�郍�[�}�ח����@�ɕ��o�����L���X�g���ւ̔��ɁA���̒���ɂ���ĉ������B
�@
���̌�͐����̌��ł���A�A�E�O�X�e�B�k�X�̒����݂̂Ȃ炸�A���ׂẴL���X�g���Ŏg����B
�@
��ꊪ / �}���Z���k�X�̋��߂ɉ����A�_�̍���n���҂ł���^�̐_���掂���ً��k�����ɑ��ĕٌ삷��Əq�ׂ�B�_�̍��̍ō��̖@�́A�u�_�͂�������̂ɍR���A�ւ肭����҂ɉ����������v�Ƃ���ɂ���B�������͓������x������ǂ��납�A�w�����s���@���I�s���ɂ����Đ��F�������Ă���B�܂��A�ً��k�ɂ��N���X�`�����ւ̔��Q�A�N���X�`�����w���ւ̖\�s�ɂ��čl�@����B
�@
��� / ���[�}�̗��j���l�@���A�L���X�g���̍L�܂�O�A�������̐_�X�����q����Ă������A���[�}�ɑ����̍ЊQ���������Ǝw�E����B���̍ЊQ�̑��́A�����I���ł���B�����̐_�X�́A���܂����ă��[�}�l�ɓ�����^���Ȃ���������łȂ��A���ȍՓT����v�������B�A�E�O�X�e�B�k�X�͔ނ�̏��_�̍�ɂ��ĕ`�ʂ��A���̂悤�ȏX���ȍՓT���D�ސ_�X�́A�s��̉��S�ɈႢ�Ȃ��ƒf������B�A�E�O�X�e�B�k�X�̑i���́A�ً����̂ĂāA�L���X�g���ɉ�S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_�X�͈��삾�Ƃ������̂ł���B
�@
��O�� / ���[�}�̗��j�ɂ��āB
�@
��l�� / ���[�}�̔��W�͐^�̈Ӗ��ɂ����ẮA�_�X�ł͂Ȃ��A�B��^�̐_�̌�|�ɂ��Əq�ׂ�B���_���l�����E�ɎU�炳�ꂽ�̂́A����ɂ���āA���U�̐_�X�̋����A�Ւd�_�a�����A�ʂ���邽�߂ł���B
�@
��܊� / �A�E�O�X�e�B�k�X�͈̑�ȃ��[�}�̍����A�L���X�g���̐M�̂��߂Ɏ����������Ȃ������}���҂̌Q��̂����ɔ�������B
�@
��\�O�� / ���߂̖��B�l�Ԃ̍߂ƁA���̌Y���Ƃ��Đl�Ԃɗ^�����鎀�ɂ��āB
�@
���\�ꊪ / �����̍��̏I���A���Ȃ킿�i���̌Y���ɂ��āB
�@
���\�� / ���k�ɑ���i���̏j���Ƒ��̎҂ɂ�������i���̌Y���̖ɂ��āB�V�ɂ����Đ��k�͍߂�Ƃ����Ƃ̂ł��Ȃ����R�ӎu����B�j�����ꂽ�҂͎������g�ɂ��Ēm��ƂƂ��ɁA�łڂ��ꂽ�҂����̉i���̋ꂵ�݂�m��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���V�F�[�f���u�j�������x���N�N��L�v���e���ꏉ�� 1493�N |
   �@
�@
|
Schedel, Hartmann.(1440-1514)�@
�@
Liber chronicarum.
�@
�{���́A�h�C�c�̈�҂Ől���w�҂̃n���g�}���E�V�F�[�f�����A���E�̗��j�E�n���Ɋւ����A�ٕ������^�����u���E�N��L�v�ł���B�j�������x���N�ő�̈���ƎҁA�A���g���E�R�[�x���K�[�ɂ���āA��2,000�̖ؔő}���Y���Ĉ������A��ʂɁu�j�������x���N�N��L�v�ƌĂ�Ă���B���̏����́A��̏o�ŕ��ɂ���ė��j���Ƃ��Ă̎����I���l�͎���ꂽ���A���̑}���G�A����܂����̖ؔʼn�⏔�s�s�ɂ��Ă̋L�q�͍����]������Ă���B�O�[�e���x���N�́u42�s�����v�ɂ���15���I�̂����Ƃ��L���ȏo�ŕ��ł���B�����N�ɓ�������Ǝ҂ɂ���āA�h�C�c��ł�������ꂽ�B�@ |
���j�������x���N�N��L
�@
�h�C�c�̈�ҁE�l���w�҂̃n���g�}���E�V�F�[�f�� (Hartmann Schedel) �����e����ŏ������N��L�B�Q�I���O�E�A���g(Georg Alt)�̃h�C�c���ƍ��킹�āA�C���L���i�u��(�ŏ����̊����{)�Ƃ���1493�N�ɏo�ł��ꂽ�B���̓����̊���ǂ���A���̖{�ɂ͕\�����Ȃ��B�`���̋L�q�������āA���e���w�҂͂��̖{�������́w�N��L�x(Liber Chronicarum)�ƌĂԁB�p�ꌗ�ł͏o�ł��ꂽ�s�s�ɂ��Ȃ�Łw�j�������x���N�N��L�x(the Nuremberg Chronicle)�A�h�C�c�ꌗ�ł͒��Җ���t���āw�V���[�f���̐��E�j�x(Die Schedelsche Weltchronik)�ƌĂ�邱�Ƃ������B��������{�̑}�G�͒��F����Ă��邱�Ƃ��������A����͈����Ɏ�œh��ꂽ���̂ł���B
�@
���̔N��L�ł́A���E�j��7�̎���ɋ敪���ĉ�����Ă���B
�@
��1���F���E�̑n�������^���܂ŁB
�@
��2���F�A�u���n���̒a���܂ŁB
�@
��3���F�Ñ�C�X���G���̃_�r�f���܂ŁB
�@
��4���F�o�r�����ߎ��܂ŁB
�@
��5���F�C�G�X�E�L���X�g�̒a���܂ŁB
�@
��6���F���݂܂ŁB���̕������ł������B
�@
��7���F���E�̏I���ƍŌ�̐R���̊T�v�B
�@
�w�N��L�x��1493�N7��12���A�j�������x���N�Ń��e����ŏo�ł��ꂽ�B�����N��12��23���Ƀh�C�c��o�ł��ꂽ�B���e�����1400�`1500���A�h�C�c���700�`1000�����o�ł��ꂽ�B1509�N�̖{�̉��t�ɂ́A���̎��܂łɃ��e����Ƃ���539���A�h�C�c��Ƃ���60�����o�ł��ꂽ���Ƃ�������Ă���B���݁A���e����{����400���A�h�C�c���{����300�����c���Ă���B�}�G�����F���ꂽ�{�������A���̒��F���̋Ǝ҂��������قǂ������B���̑}�G�������I�[���h�E�}�X�^�[�E�v�����g (Old master print) �Ƃ��Đ��ʂŒ��F����Ĕ���ꂽ���Ƃ������B�܂��A�}�G�����������Ĕ����邱�Ƃ��������B����E�o�ł́A��ƃA���u���q�g�E�f���[���[�̑㕃��(�㌩�l)�A�A���g���E�R�[�x���K�[ (Anton Koberger) ���s�����B�R�[�x���K�[�̓f���[���[�̐��܂ꂽ1471�N�A���H�E�l����߂Ĉ���ƁE�o�ʼnƂɂȂ�A�h�C�c�̏����̏o�ʼnƂƂ��čł�����������l�ƂȂ����B�ŏI�I�ɂ͈���@24������L���A��������u�_�y�X�g�Ȃǃh�C�c�̏��s�s�ɑ����̎x�X���o�����B�@ |
���R�[�x���K�[�Ɓw�j�������x���N�N��L�x
�@
���N1993�N�̓C���L���i�u�����\���鏑���̈�w�j�������x���N�N��L�x�����s����Ă��炿�傤��500�N�ڂɂ�����B���́w�N��L�x�̓��e����ƃh�C�c��̗��ł����삳��A�O�҂�1493�N7��12���A��҂����N12��23���Ɋ������ꂽ�B
�@
���̏������a�����������̃��[���b�p�ł̓O�[�e���x���N���l�Ă������ň���p�ɂ�郁�f�B�A�v�����i�W���A�����ȗ��̎ʖ{�̖���������ɏ������Ȃ�A����{���D�ʂɂȂ�������B
�@
����p�̓}�C���c�Ŏn�܂�A�V���g���X�u���N�A�o���x���N�A�P�����A�C�^���A�̃X�r�A�R�A�A�E�N�X�u���N�A���[�}�A�o�[�[���A���@�l�c�B�A�Ɠ`�d���A1470�N�ɂ̓��n�l�X�E�[���[���V���~�b�g���j�������x���N�ɍŏ��̈���H�[��ݗ����Ċ������n�߂��B��2�̍H�[���J�݂����̂��A���g���E�R�[�x���K�[�ł���B3�Ԗڂ��t���[�h���q�E�N���C�X�i�[�A�����V���w�҃��n�l�X�E���M�I�����^�k�X�ł���B�������ăj�������x���N�ł�1500�N�܂łɓs��19�l�̈���Ǝ҂����������B15���I�A�j�������x���N�̈�����̔����ȏ�͏@���W���ł���A���̂�����3����1�ȏオ�������A�_�w���ł������B
�@
�w�j�������x���N�N��L�x����������A���g���E�R�[�x���K�[�͑�X�p�������c�ޗT���ȏ��l�̉Ƃ�1440�N��ɐ��ꂽ�B�����j�������x���N�̓h�C�c�ōł��ɉh�������H�Ɠs�s�ƂȂ�A�x�T���l�w���s�Q����̉���ɑI�o����s�s�̐����o�ςɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����B�R�[�x���K�[�Ƃ����̈�ł������B�A���g���͎Ⴂ�����H�t�̏C�Ƃ������Ƃ�����B�������Ǝ҂ɂ͉�ƃA���u���q�g�E�f���[���[�̕��������B���̔ނ������A�ǂ��ŁA�N�̋��ň���p���K�������̂��͂悭�킩���Ă��Ȃ��B�[���[���V���~�b�g���炱�̐V�����Z�p���w�Ƃ��l�����悤�B������ɂ���1470�N���Ɉ���H�[���J�����悤���B
�@
1470�N�ɃE���X���E�C���O�����ƌ������A�܂����N���ꂽ�f���[���[�̑��q�ɃA���u���q�g�Ƃ������������Č�̋����̖��e�ɂ��Ȃ����B�A���g���̓E���X���Ƃ̊Ԃ�8�l�̎q�������������B1491�N�ɃE���X�������E����ƁA���N�Ƀ}���K���[�e�E�z���c�V���[�n�[�ƍč������B�ޏ��Ƃ̊Ԃɂ�17�l�̎q�������������B�����̃��[���b�p�ł͗c�����S���������A�܂��ĎO�̃y�X�g�̑嗬�s�Ŏq�����c�����Ƃ͑�ςȂ��Ƃł������B����ɂ��Ă��A���[���b�p�ő�Ƃ���ꂽ��������o�c���A�L���̔��Ԃ����グ���A���g���̃o�C�^���e�B�[�ɂ͋��Q����B
�@
����Ǝ҂Ƃ��ẴA���g���E�R�[�x���K�[�̍ŏ��̍�i��1471�N���s�̃��n���E�j�_�[�w�����̎�����x�Ƃ����B�ߔN�A�����ł͂Ȃ��Ƃ�������������B������ɔނ̖��O���ŏ��ɍ��܂��̂�1473�N7��24�����s�̃{�G�e�B�E�X�w�N�w�̈Ԃ߁x�ł���B�ȗ��������������ނ���1504�N�܂Ŗ�240���𐢂ɑ���A�g�p����������27���(���邢��25���)�ɏ��B���ތ�͂����ς�o�Ŕ̔����s�������A1513�N��70�ŖS���Ȃ����B
�@
�R�[�x���K�[�̈���_����N��ʂɂ݂Ă݂�ƁA1470�N�オ35�_�A1480�]85�N��59�_�A1486�|89�N��39�_(1490�N�͈�����̋L�^�Ȃ�)�A1491�]95�N��50�_�A1496�]1500�N��46�_�A1501�|04�N��11�_�ȂǂƂȂ��Ă���B�R�[�x���K�[�����̃j�������x���N�̈���Ǝ҂Ɠ��l�ɏ@��������і@�����𒆐S�Ɏd���������B�ނ̑�\��Ƃ��ẮA���e���ꐹ��(1475�N����)�A�h�C�c�ꐹ��(1483�N����)�A�A���g�j�k�X�w�_�w��S�x(1477�|79�N����)�A�{�G�e�B�E�X�w�N�w�̈Ԃ߁x
�@
(1473�N����)�A���H���M�[�l�w�����`���x(1478�N����)�A�j�R���E�X�E�f�E�����w���������x(1481�N����)�ȂNJ����ł��d�˂����̂�A�}�G�{�Ƃ��Ē����ȃt���h�����w��Δ��x(1491�N)�A��q�̃n���g�}���E�V�F�[�f���w�j�������x���N�N��L�x
�@
(1493�N)�A�f�����[��w�َ��^�x(1498�N)�A�w���r���C�b�^�̓V�[�x(1500�N)�Ȃǂ�����B�Ƃ�킯���s500�N���}�����w�j�������x���N�N��L�x�͑}�G�̖L�x���Ɛ���ɊW�����l�X�̏d�v���A�����ĊW�������ɂ߂Ă悭�ۑ�����Ă��邱�ƂŗL���ł���B
�@
���̏����̏o�łɊW�����l�X�͓����̃h�C�c���\���镶���l����ł������B�j�������x���N�̗L�͎҃[�o���g�E�V�����C���[�����o���҂ƂȂ�A��ƃ~�q���G���E���H�[���Q���[�g�ƃ��B���w�����E�v���C�f�������t���A�[�g�E�f�B���N�^�[(�����ނ�̍H�[�Ńf�����[���C�Ƃ��Ă���A�{���̑}�G����ɎQ�������ƍl�����Ă���)�A�l���w�҃n���g�}���E�V�F�[�f�����{�����������낵�A�j�������x���N�s�̎������Ŕ\���Ƃł������Q�I���N�E�A���g���e�{�̐���ƃ��e���ꂩ��h�C�c��ւ̖|���S���A�R�[�x���K�[��������茜�����B
�@
�w�N��L�x�o�ł̌_�ɂ��R�[�x���K�[�͒P�Ȃ�ق�����Ǝ҂ł���A���E�ҏW�ɂ͐[���ւ���Ă��Ȃ��悤�����A��擖�����������R�[�x���K�[�Ɉς˂邱�Ƃ͎����ł������Ǝv����B�Ƃ����̂́A�ؔʼn�̂�1809�_�A600�ł��z��������������A���������̃h�C�c��ł��ɏo�łł���͓̂����̃j�������x���N�ł͔ނ������đ��ɂȂ��A����ɁA�o�ŕ����̋L�^�͂Ȃ������ݕ������琄�肵�ă��e�����1500���A�h�C�c���1000���Ƃ��������Ƃ��Ă͔j�i�̑啔��������グ����傫�Ȉ�����͂�͂葼�̂ǂ��ɂ��Ȃ���������ł���B�����āA�w�j�������x���N���v�@�T�x(1484�N)�Ɓw��Δ��x�̖ؔʼn��S�������̂����H�[���Q���[�g�ł���A�ނ�̐e�����W���ȑO���炠�����B�܂��A
�@
�w�N��L�x�o�ł̂����������w��Δ��x�p�ɐ��삳�ꂽ���G���V�����C���[���������Ƃł������Ɛ�������Ă���B����A�_�ł̓R�[�x���K�[�͏o���҂Ɖ�ƂƂ̊Ԃ��y���̒��ٖ��Ƃ��Ė��L����Ă���A�ނ��M�]�����l���ł������Ƃ������Ƃ��ł���B�܂�A�R�[�x���K�[���{���̏o�łɉʂ����������͌����Čق�����ƎҒ��̏����Ȃ��̂ł͂Ȃ������̂ł���B�@�@
�@ |
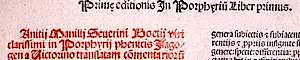 �@ �@
�����M�I�����^�k�X�u�v�g���}�C�I�X�̓V���w��S�̔����v���� 1496�N |
   �@
�@
|
Regiomontanus.(Johannes Muller)(1436-76)
�@
Epytoma in Almagestum Ptolemaei.
�@
�{���́A�M���V���̓V���w�҃v�g���}�C�I�X���A�M���V���V���w���W�听�����u�A���}�Q�X�g�v�̍ŏ��̈���{�ŁA���F�j�X�ň�����ꂽ�B�R�y���j�N�X�́u�V�̂̋O���ɂ��āv�A�j���[�g���́u�v�����L�s�A�v�ƕ��ѓV���w���3��ÓT�ɐ������Ă���B�u�A���}�Q�X�g�v�́A�M���V�A�ő�̓V���w���ł���������łȂ��A������ʂ��čł����Ђ��������V���w���ł���B���������āA�琔�S�N�ɂ킽���ēV���w�E���x�z���A���̓V������ʂ��āA�����̐l�X�̉F���ς̒��S�ƂȂ����B���[���b�p�̓V���w�́A�u�A���}�Q�X�g�v�̌����ɂ���ď��߂ăM���V�A�V���w�̐����ɓ��B���邱�Ƃ��o�����Ƃ����邪�A���̏\���ȗ����́A���n���E�~���[���[�ɂ���ď��߂ĉ\�ƂȂ����B�~���[���[�́A���M�I�����^�k�X�̖��ł悭�m��ꂽ�h�C�c�̓V���w�ҁA���w�҂ł���B�@ |
���N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X
�@
(���Ƀ�ύ�ǃ�ς ���у̓ɃÃʃ�ῖ��ς, ���e����: Claudius Ptolemaeus, 83�N�� - 168�N��)�́A�w�A���}�Q�X�g�x�̒��҂Ƃ��Ēm����Ñネ�[�}�̓V���w�ҁA���w�ҁA�n���w�ҁA�萯�p�t�B�G�W�v�g�̃A���N�T���h���A�Ŋ����B�p�̂̓g���~�[ (Ptolemy)�B
�@
�N���E�f�B�I�X(�N���E�f�B�E�X�AClaudius)�̓��[�}�l�̈�ʓI�ȃm�[����(���O)�̈�ł���A�v�g���}�C�I�X(���у̓ɃÃʃ�ῖ��ς)�̓M���V���l�̖��ł���B���̂��߁A�N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�́A���[�}�s�������^����ꂽ�M���V���l�ƍl������B�܂�A�N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�Ƃ������́A�M���V���l�Ƃ��Ă̖{���̖��ł���v�g���}�C�I�X���R�O�m�[�����Ƃ��āA�s�����ƂƂ��ɃN���E�f�B�I�X�Ƃ����m�[������^����ꂽ���[�}�l�Ƃ��Ă̖��ł���B���������āA�M���V�A�l�Ƃ��ẮA�A���N�T���h���A�̃v�g���}�C�I�X(���у̓ɃÃʃ�ῖ��ς ὁ Ἀ�ɃÃ̃��˃σ�ύς)�ƌĂԂׂ��ł��邪�A��ʓI�ł͂Ȃ��B����A���[�}�l�Ƃ��ẮA�ق��Ƀv���G�m�[�����������Ă����͂��ł��邪�A����͕s���ł���B�����A�N���E�f�B�I�X�Ƃ����m�[�����̓��[�}�c��N���E�f�B�E�X�ɂ���ė^����ꂽ�\���������A�e�B�x���E�X(Tiberius)�Ƃ����v���G�m�[�������Ƃ��ɗ^�����Ă����Ǝv����B���Ȃ킿�A�ނ̃��[�}�l�Ƃ��Ă̖{���̓e�B�x���E�X�E�N���E�f�B�E�X�E�v�g���}�G�E�X(Tiberius Claudius Ptolemaeus)�ł������\�����w�E����Ă���B
�@
���Ɛ�
�@
�咘�w�A���}�Q�X�g�x�ŁA�n�����F���̒��S�ɂ���A���z�₻�̑��̘f�����n���̎�������Ƃ����V�������������B�������A�V�����Ȃǂ̓v�g���}�C�I�X�����߂ď������킯�ł͂Ȃ��A�w�A���}�Q�X�g�x�̓��e�́A�A���X�g�e���X��q�b�p���R�X�ȂǁA����ȑO�̌Ñ�M���V�A�̓V���w�̏W�听�ł���B�w�ɂ�����G�E�N���C�f�X�́w���_�x�̂悤�ɁA�w�A���}�Q�X�g�x�͂���܂ł̓V���w�𐔊w�I�ɑ̌n�t���A���p�I�Ȍv�Z�@���������ƂŁA�����I���̊ԓV���w�̕W���I�ȋ��ȏ��Ƃ��Ă̒n�ʂ��B���̒��œ����ΐ��̉^�s�ȂǂŌ���ꂽ�t�s��f�����u���]�~�v�Ƃ��������ȉ~��`���Ȃ���n���̎������]���邱�Ƃɂ���ċN����Ɛ������A����ɂ���ēV�����̒n�ʂ�������B�V�̊ϑ��̕��@��V�̂̋O���v�Z�A���z�܂ł̋����₻�̑傫���Ƃ�����������m�����ЂƂɂ܂Ƃ߂����Ƃ��V���w�ɂ�����v�g���}�C�I�X�̋Ɛтł���B
�@
�Ȃ��A�w�A���}�Q�X�g�x�̖{���̏����̓M���V����Łw�����ƃŃʃ��уǃ�ὴ ��ύ�˃у��̃�ς�x(Mathematike Syntaxis�AMathematical Treatise�A���w�S��)�ł���B�ʏ̂Ƃ��āwἩ ���Ã�ά�Ƀ� ��ύ�˃у��̃�ς�x(He Megale Syntaxis�AThe Great Treatise�A��S��)���p�����Ă���A�A���r�A��ɖ|�ꂽ�ۂɕt�����芥��Al���A���e����ɍĖ|�ꂽ�Ƃ��ɂ����̂܂c��ASyntaxis(Treatise)���ȗ�����āwAlmagest�x(The-greatest�A�ő�)�ɂȂ����B���̂��Ƃ�����킩��悤�ɁA�w�A���}�Q�X�g�x�͓����͐��w���Ƃ��Ĉ����Ă���A���ʊw�ȂǍŐ�[�̐��w�I�ȓ��e���܂�ł����B
�@
�����w�Q�I�O���t�B�A(�p���)�x(Geographia�A�n���w)�Ɏ��߂��Ă���n�}�́A���E�ŏ��߂Čo�ܐ���p�������ł���A�Ñ�̐l�X�̒n���Ɋւ���m�����W���������̂ł���B�������Ȃ���V���ϑ����̃f�[�^�����܂萳�m�ȕ��ł͂Ȃ��A�n���̎��������ۂ�7���قǂ̑傫���ƌv�Z���Ă���B���̒n�}�́A��1,000�N��̑�q�C����ɂ��e�����y�ڂ��A�N���X�g�t�@�[�E�R�����u�X�́u�����������ɍq�C�����ق����A�W�A�ւ͋ߓ��ł���v�ƍl���ăA�����J�嗤�����鎖�ɂȂ�B
�@
�܂��A�����w�e�g���r�u���X�x(Tetrabiblos�A�l�̏�)�́A�萯�p�̌ÓT�Ƃ��Ēm���Ă���B
�@
�ق��ɁA���s���̌����Ɋւ��钘���≹�y�Ɋւ��钘�����������B
�@
���y�ɂ��ẮA�������̉��̐���ŕ\���s���^�S���X�h�̕��@�_��ᔻ�I�Ɍp�������B�萫�I�ȕ��@���������ÓT���̃A���X�g�N�Z�m�X�́w�n�����j�A���_�x��V�s���^�S���X�h(�s���^�S���X�h�̓`���͋I���O4���I�̖��Ɉ�x�r��Ă���)�̗��ꂩ��ɗ�ɔᔻ���A�Ǝ��̌������N�����n�����j�A�_(�S�O��)�����B
�@
19���I�ɂȂ�A�v�g���}�C�I�X�̊ϑ����ʂ��Ē��������V���w�҂�́A���ʂ̒��ɂ���덷���B�Ñ�V���w�Ɣ�ׂĂ��ϑ��n�_��ϑ����Ԃ��Ԉ���Ă���Ȃǃ~�X�̑������̂������B�J���t�H���j�A��w�T���f�B�G�S�Z�̓V���w�҃f�j�X�E���E�����X�́A�v�g���}�C�I�X���s�����Ƃ����V�̊ϑ��́A�v�g���}�C�I�X�ϑ��ȑO�̃��[�h�X���A�q�b�p���R�X�̊ϑ����ۂ��Ɠ��p�������̂ł���Ǝw�E���Ă���B�@ |
���A���}�Q�X�g
�@
(��: Almagest)�̓��[�}�鍑����ɃG�W�v�g�E�A���N�T���h���A�̃N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�ɂ���ď����ꂽ���w�ƓV���w�̐�发�ł���B���T�� �ÓT�M���V�A��: �ʃ��ƃŃʃ��уǃ�ἠ ��ύ�˃у��̃�ς (�M���V�A��: Mathematike Syntaxis (�w���w�S���x)�A��� He Megale Syntaxis(�w��S���x)�Ƃ��Ă��)�Ƃ��������ł������B���ꂪ��ɃA���r�A��ɖ|�ꂽ�ۂ� al-kitabu-l-mijisti("The Great Book") �Ƃ��������ɂȂ�A���ꂪ����Ƀ��e����ɖ|��� ���e����: Almagest �Ƃ������O�ɕς�����B
�@
�w�A���}�Q�X�g�x�ɏ�����Ă����V�����͘f���̉^����������郂�f���Ƃ���1000�N�ȏ�ɂ킽���ăA���u�y�у��[���b�p���E�Ɏ����ꂽ�B�w�A���}�Q�X�g�x�͌���̉�X�ɂƂ��āA�Ñ�M���V�A�̓V���w�ɂ��Ēm���ł̍ł��d�v�ȏ�ƂȂ��Ă���B�܂��w�A���}�Q�X�g�x�́A���{������ꂽ�Ñ�M���V�A�̐��w�҃q�b�p���R�X�̕����ɂ��Ă̈��p�𑽂��܂ނ��߁A���w���w�Ԏ҂ɂƂ��Ă����l�̂���{�Ƃ���Ă����B�q�b�p���R�X�͎O�p�@�ɂ��Ă̖{�������A�ނ̌����͎����Ă��邽�߁A���w�ҒB�̓q�b�p���R�X�̌������ʂ�Ñ�M���V�A�̎O�p�@��ʂɂ��Ă̏�Ƃ��āw�A���}�Q�X�g�x���Q�l�ɂ��Ă���B
�@
���w�A���}�Q�X�g�x�̉e��
�@
���̃v�g���}�C�I�X�ɂ�鐔���V���w�̕�I�Ȑ�发�͂���ȑO�̃M���V�A�V���w�̎Q�l���̂قƂ�ǂɎ���đ�����̂ƂȂ����B����{�͂����I�ȓ��e�ł��������߂ɐl�X�̋������������ƂƂȂ�A�ʂ̖{�͒P�Ɂw�A���}�Q�X�g�x�������e������x��ɂȂ����B���ʂƂ��āA�����̌Â��{�͎ʖ{����Ȃ��Ȃ�A����Ɏ����Ă������B�����ł́A�q�b�p���R�X�̂悤�ȓV���w�҂̌������ʂɂ��ĉ�X���m��m���̂قƂ�ǂ́w�A���}�Q�X�g�x�ł̈��p�ɗR������B
�@
�������y�у��l�T���X����́w�A���}�Q�X�g�x
�@
�w�A���}�Q�X�g�x�̍ŏ��̃A���r�A����9���I�ɓ�̕ʁX�̎d���ɂ���čs�Ȃ�ꂽ�B���̂����̈���̓A�b�o�[�X���̃J���t�E�}�A���[���̉����ɂ���čs�Ȃ�ꂽ�B���̍��ɂ̓��[���b�p�ł́w�A���}�Q�X�g�x�̑��݂͖Y����A�킸���ɐ萯�p�̋����̒��Ɏc��݂̂ƂȂ��Ă����B���̂��߁A�����[���b�p�̐l�X�̓v�g���}�C�I�X���A���r�A��ł̖|��{�ɂ���čĔ������邱�ƂƂȂ����B12���I�ɂ̓X�y�C����ł�����A��ɐ_�����[�}�c��t���[�h���q2���̎x���ɂ���ă��e����ɂ��|�ꂽ�B�܂����̍��A�N�����i�̃W�F�����h�ɂ���ăX�y�C���̃g���h�ŃA���r�A��ł��璼�ږ|�ꂽ�ʂ̃��e����ł����ꂽ�B�W�F�����h�͐��p��̑�����|�邱�Ƃ��ł����A�q�b�p���R�X��\���A���r�A��� Abrachir �Ȃǂ����̂܂c���Ă���B
�@
15���I�ɂȂ�Ɛ����[���b�p�ŃM���V�A��ł�����A���M�I�����^�k�X�Ƃ��Ēm����h�C�c�̃��n���E�~���[���[���M���V�A�̍˔\���鐕�@�����n���l�X�E�x�b�T���I���̊��߂ɂ���ă��e����̏���ł��o�ł����B���������Ƀ��e����̊���ł��g���r�]���h�̃Q�I���M�E�X�ɂ���č��ꂽ�B���̔łɂ͖{���Ƃقړ������ʂ̒��߂��t���Ă����B���̖|��̓��[�}���c�j�R���E�X5���̎x���ɂ���čs�Ȃ��A����܂łɏo����Ă�����{��u�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă����B���̐V��{�͔��ɗǂ����P���ꂽ���̂����������߂͂��܂�o�����ǂ��Ȃ��A�傫�Ȕᔻ�������N�������B���c�͂��̖{�̌�������ۂ��A���M�I�����^�k�X�̖�{�̕������̌㐔���I�ɂ킽���čD��ŗp����ꂽ�B
�@
�w�A���}�Q�X�g�x�̒��߂͂���܂łɁA�A���N�T���h���A�̃e�I���ɂ�����(����)�A�p�b�v�X�ɂ�����(�f�Ђ̂ݎc��)�A�A���j�E�X�ɂ�����(�r��)�Ȃǂ�����B�@ |
| �@ |
 �@ �@
��16���I�@�V�������E�� / �V��������n������ |
   �@
�@
|
|
���l�T���X�����B�Ñネ�[�}����ɁA�n�����S�̉F���̌n��������v�g���}�C�I�X�́u�V�����v���������[���b�p�Љ���x�z���Ă����B�|�[�����h�̓V���w�҃R�y���j�N�X�ɂ���Ēn���͑��z�𒆐S�ɉ���̘f���ɉ߂��Ȃ��Ƃ���u�n�����v�����\����A�����̃L���X�g���I���E�ς��ς����ƂƂȂ����B�R�y���j�N�X�̐����ʐ��ƂȂ�ɂ͌�S�N���܂��v���邪�A���̎���́A�@�����v�A��q�C����ȂǁA�ߑ�ւ̏o�����Ȃ��o�������������B�܂��A���[���b�p�l�ɂ��g�n����̔����h�ɂ���ă��[���b�p�����̂��߂̍L��ȊC�O�s�ꂪ�J����A���H�Ƃ��}���ɔ��W���A���[���b�p�ɋߑ㍑�Ƃ����܂ꂽ�B�R�y���j�N�X�ɂ���ăA���X�g�e���X�ȗ��̐��E�ς�������A�Ȋw���_���萶���A�ɉh�̐��I�ƂȂ����̂ł���B�@ |
���V���v��
�@
16���I�A�|�[�����h�̓V���w�ҁA�R�y���j�N�X(1473-1543)���v���钼�O�A�����w�V����]�_(�V���̉�]�ɂ���)�x�����s���ꂽ�B�ނ̋����ӌ�������A�ՏI�̍ۂɏo�ł��ꂽ�̂ł���B�������ނ̎茳�ɓ͂����A���̐����Ԍ�ɔނ͖v�����B
�@
�R�y���j�N�X�������̏o�ł�ՏI���O�Ɋ��s���悤�Ƃ������R�́A�ނ�1530�N���ɑł����Ă��F���ςł���n����(�n���̎��]�ƌ��]��F�߂��)�Ɍ������������B���̎����́A���ăA���X�g�e���X(�M���V���̓N�w�ҁBB.C.384-B.C.322)��v�g���}�C�I�X(2C���̃M���V�A�l�B�Ñネ�[�}����Ɋ���B�咘�w�V���w��S(�A���}�Q�X�g)�x)�炪���N�ɓn���ď������A����Ƃ���Ă����n�����S�ɉF���������Ă���Ƃ����V����(�n�����S��)��ے肷����̂ł������B
�@
���ɃL���X�g���̒��_�ɗ����[�}���c�͓V�������^���A�v�g���}�C�I�X�̓V�����N�ɓn���āA������F�̒���Ƃ���Ă������߁A�V������ے肵�Ēn�������咣����Ƃ������Ƃ́A�J�g���b�N�����G�ɉ��ƂƓ��l�ł������B���ă����E�X���O���S����(�O���S���E�X��)���V�����Ɋ�Â��Ē��肳��A�����L���X�g�����E�Ő����E�����E�Љ�E�@���̂�����ʂŒ蒅���Ă������݂āA�R�y���j�N�X�́A�n�����͒P���ɔF�m�������̂ł͂Ȃ��Ǝ������A�����钼�O�܂ŋ��̓��ɔ�߂Ă����Ƃ���Ă���B
�@
�R�y���j�N�X�v��A�����w�V���̉�]�ɂ��āx�͗\�z�ʂ�Ɍ������������B�����āA�J�g���b�N�̔��@�����v(�R�@�����v)�ɂ�����֏��ژ^(Index�B���J�g���b�N�Ώۂ̒��앨�ƒ��҃��X�g)�ɍڂ���ꂽ(1616)�B�܂������̃h�C�c�@�����v�̒��S�������}���e�B�������^�[(1483-1546)���A�����̋���Ɋւ��Ĕᔻ�I�ł������ɂ�������炸�A�R�y���j�N�X�̎咣�͐����L�ڂ���̈�E�s�ׂł���Ɣ����قǂł������B
�@
�R�y���j�N�X���v���Ė�20�N��A���"�V���w�̕�"�Ə̂����l�����C�^���A�ɒa�������B�K�����I���K�����C(1564-1642)�ł���B�K�����C�́A�C�^���A�̃g�X�J�i������̗̂ł���s�T�x�O�ŁA���y�Ƃ̉Ƃɐ��܂ꂽ�B1581�N�A�s�T��w�ɓ��w���Ĉ�w���w�Ԃ��A���w�E�����w�ɊS���A��w��f�O�A�G�E�N���C�f�X(���[�N���b�h�BB.C.300���̃M���V�A�l�w��)��A���L���f�X(�V�`���A���V���N�T�̐��w�E�����w�ҁBB.C.287?-B.C.212)�̒����Ɋ�Â��A�U��q�̓�����(�U��q�̗h���K�͂�����Ă��A�������Ԃ�������)�����ēV�������ǁA"���V��"�Ƃ��Ĕ��\����^����(�s�T�吹���ŗh���V�����f���A���������Ƃ���q���g���Ƃ�����������)�A1589�N�A25�ɂ��ăs�T��w�̋����ƂȂ����B
�@
�����̕����w����ł́A�A���X�g�e���X�̎��R�N�w��n���ō����ЂƂ��ėp�����Ă����B�Ⴆ�A���̂Ɋւ��āA�d�����̂قǑ�����������̂�����ł������B�K�����C�̓A���X�g�e���X�̒����ǂ��A���̐��͐����ł͂Ȃ��Ɣᔻ�����B�������F�߂�ꂸ�A�ނ̓s�T��w�𗣂�āA�������F�l�c�B�A���a���̃p�h���@��w�����Ƃ��āA���F�l�c�B�A�ɈڏZ�A���̂̌����ɖv��(�L���Ȍ̎��ł���s�T�̎Γ�����傫���̈Ⴄ2�̕��̂��ɗ��Ƃ��A�����ɒ��n�������Ƃ��������͎����ł͂Ȃ��A�K�����C�̒�q�ɂ��n��Ƃ���Ă���)�A���̌�A���̗̂������Ԃ͎��ʂɂ͈ˑ������A���������͗������Ԃ�2��ɔ�Ⴗ��Ƃ������̖̂@��������B
�@
���F�l�c�B�A�ɈڏZ�����Ƃ��A�C�^���A�ł͈̑�ȓN�w�҂��@���ٔ���(�ْ[�R�⏊)�ɍ�������Ă���(1592)�B�W�����_�[�m���u���[�m(1548-1600)�Ƃ����N�w�҂ł���B���F�l�c�B�A�ɂ����u���[�m�́A�Đ_�_(�͂���)�������Ă����B�Đ_�_�͕��̂����_���_�̂����Ă��鐫���̂�����ł���A�_�Ɩ����͓���ł���Ƃ����l�����ł��邽�߁A�_�͒��z�I���݂ł���Ƃ��ĐM��L���X�g�����ْ[������Ă����B�܂��R�y���j�N�X��A�R�y���j�N�X�ȑO�ɒn���̎��]�����F�����Ƃ����h�C�c�w�҃j�R���E�X���N�U�[�k�X(1401-64)��M�Ă����u���[�m�́A�w�����ȉF���Ə����E�ɂ��āx�Ȃǂ��A�����̉F���̒��ɂ́A�₦�������Ǝ��ł��J��Ԃ������̐��E(���z�n�̂���)������Ǝ咣���A�n���������F���̒��ŗB�ꐶ�������鐯�ł���Ƃ��������̃L���X�g����̐��E�ςƂ͑S���ΏƓI�ł������B�u���[�m�̐��E�ς͔Đ_�_�ƒn�����������Ƃ��Ă��邱�ƂŁA���J�g���b�N�̊댯�l���Ƃ��Čx�����ꂽ�B
�@
�K�����C�̓A���X�g�e���X�̐��������w�����ł͂Ȃ��A�V���w�ɂ����Ă��ᔻ�I�ł������B�K�����C�̓R�y���j�N�X��u���[�m�Ɠ������A�n������M���Ă����̂ł���B�K�����C��7�ΔN���ł���h�C�c�̓V���w�҃��n�l�X���P�v���[(1571-1630)�́A�R�y���j�N�X�̒n�����Ɋ������A���҂Ƃ��ăK�����C�Ɛe����[�߁A1597�N�A�K�����C�̓P�v���[�Ɉ��Ă��莆�ɒn������M���Ă���ƋL�����B�������n�����ْ͈[�ґΏۂƂȂ邽�߁A�����͏�ɔ������Ă����B����Ȓ��A�ނ�ɏՌ����������B1600�N�A�u���[�m�����Y�ɏ����ꂽ�̂ł���B
�@
�u���[�m�͑ߕߌネ�[�}�Ɍ쑗����A7�N�ԁA�q��ƍ�����Ă����B�����ĕ��Y��ڑO�ɂ��āA�u���[�m�́u�������鎄�����A�����������n�������Ȃ�����(�R�⊯)�̕����^���̑O�ɕ|�ꂨ�̂̂��Ă���ł͂Ȃ����v�Ɣ����A��ɂ̐��ЂƂ������Β��ɏ����Ă������B�u���[�m�ƃK�����C�Ƃ̊Ԃɂ͒��ړI�ȐڐG�͂Ȃ��������A�K�����C�ɂƂ��āA�u���[�m�̕��Y�͑��l���ł͂Ȃ��A�@���ٔ��̋��낵�������߂ĒɊ������B�������A�n�����̍l�����Ȃ��邱�Ƃ͂Ȃ��A����Ɍ�����i�߂��B
�@
1608�N�A�I�����_�Ŗ]�������������ꂽ�̂����������ɁA�K�����C���g���]�������A1610�N3���A�ؐ��̉q����4��������(�K�����C�q���B��1�q�����C�I�A��2���G�E���p�A��3���K�j���f�A��4���J���X�g�Ƃ���)�B�K�����C�͂��̊ϑ����ʂ��w���E�̕x�Ƃ��Ę_�����\�����B������@�ɁA�K�����C�̒n���������������Ȃ�A�P�v���[���K�����C��i�삷��ړI�Œn�������咣�����B���̌�A�K�����C�͋����̖��������ƌ��]�A���z�̍��_�A���ʂ̉��ʁA�V�̐삪�P���̏W���ł��邱�ƂȂǁA�s�ς̉F�����咣����n�����S�̓V������傫���������������X�ƍs�����B�n�������]�E���]���Ȃ���A�����͔����ł��Ȃ��������̂Ƃ��āA�R�y���j�N�X�̒n�����𗠕t����m�ł���؋��ƂȂ����̂ł���B���̂��߃A���X�g�e���X�h�̊w�҂�A�V�������咣����h�~�j�R�C�����ƌ������_���ƂȂ��Ă������B
�@
�h�~�j�R�C����m�́A�ْ[�R�⏊�ɃK�����C�̒n�����ْ̈[����i���A1616�N�A�K�����C�̓��[�}�ɏ������ꂽ�B1��ڂ̏@���ٔ��ł������B�����ł́A�n�������咣�����A�啝�Ȍ������T����Ƃ̒����ɗ��܂�A���߂ƂȂ������A���N�A�R�y���j�N�X�́w�V���̉�]�ɂ��āx���ꎞ�I�ɉ{���֎~�����ɂ��Ă���B
�@
�t�B�����c�F�x�O�ɏZ�����ڂ��A���炭���������l���Ă����K�����C���������A1632�N�A�ނ́w�V���Θb�x���t�B�����c�F�Ŕ��������B�n�����ƓV���������ꂼ��咣����ғ��m�̑Θb���L�������̂ŁA�n����������I�Ɏ咣����`�ł͏�����Ă͂��Ȃ��B�������A��̉e�����l�����̂��A1633�N�A�ēx���[�}���c���ْ̈[�R�⏊����o���𖽂����A2��ڂ̏@���ٔ��ɂ������Ă��܂����B
�@
�w�V���Θb�x���T�d�Ɏ��M���ꂽ�ɂ�������炸�A�n������i�삵�Ă���ʂ�����A1��ڂ̍ٔ��ł̒��������Ă���Ƃ������Ƃł������B1��ڂ̖��ߔ������e���咣�����K�����C��2��ڂ̍ٔ��ł����߂��咣���邪�A�ْ[�R�⏊�������1��ڂ̍ٔ��̓P��ƁA�K�����C�̗L�ߔ����������n���A�K�����C�͏I�g�Y�̐g�ƂȂ��Ă��܂����B�܂����c����J�g���b�N�ɂ�����j�傪�鍐�A���ׂĂ̖�E�D����A�w�V���Θb�x�̋֏��ژ^���������A�����Ēn���������𖽂���ꂽ(�n���������̐鐾��������ꂽ�K�����C���A�鐾�����"����ł��n���͓���"�ƂԂ₢���Ƃ���Ă��邪�A�ނ̍���ɂ����錤���̔M�ӂƁA���߂������Y�̌��f�𔗂�ꂽ�����̍ٔ�����l���āA���̔����͂��肦�Ȃ��Ƃ���A��ɑn�삳�ꂽ�Ƃ�������L�͂ł���)�B
�@
��1633�N�̔����������ꂽ�K�����C�́A��������ɓ�ւɌ��Y����A�t�B�����c�F�x�O�ɗH����A�Ď��t���̐����̐g�ƂȂ������A�t�B�����c�F�ɂ���Z���ւ̋A��͋�����Ȃ������B��1634�N�ɂ́A�K�����C���x�����������v���A1637�N�ɂ̓K�����C�̕ЊႪ�����A��1638�N�ɂ́A�Ƃ��Ƃ����Ⴊ��������(�]�����ɂ�鑾�z�ϑ��������Ƃ����������)�B
�@
����ł��K�����C�͎��M�s��ӂ炸�A�ނ̌������q�Ƒ��q�Ɏ��M�����A1638�N�Ɂw�V�Ȋw�Θb�x���A�J�g���b�N�̑���������Ȃ��A�v���e�X�^���g���I�����_�̃��C�f���Ŕ��������B
�@
1642�N�A�K�����C�͗H���78�N�̐��U���I�����B�������v����g���͐��炸�A�Ƒ��̕�n�ɑ���ꂸ�A������ǂނ��Ƃ��A�������Ă邱�Ƃ������ꂸ�A�����Ȗ�����1737�N�܂ʼn����ꂽ�B
�@
�㐢�ɂȂ�A���[�}���c���n�l�X���p�E���X2��(��1920-2005)�͏��߂āA�ٔ��̌������\(1980)�A���c���g���ٔ��̌���F��(1983)�A���N�����ψ���̓K�����C�̗L�ߔ�����P���B������1992�N�A2��ڂ̍ٔ�����359�N�Ԃ�ɁA�K�����C�͋��c�ɂ���Ĕj��������ꂽ�̂ł������B
�@
��
�@
��l���́A�ߑ㎩�R�Ȋw�̊�b��z�����C�^���A�̓V���w�ҁE�����w�ҁA�K�����I���K�����C�ł��B���l�T���X���̌㔼�`�����Ɋ����K�����C�ł����A�J�g���b�N����̌��Ђ���ΓI���������ƂŁA������������̗��z�E���d�Ă������ŁA�����ɂ�����o��������A���o�ȂǂŊm���߂��錻���̐��E���d���̂��A�ߑ�Ȋw�҂������̂ł��B���̑�\���A�R�y���j�N�X�E�K�����C�E�P�v���[��V���w�҂ł���Ƃ����܂��B�����āA�ނ�̊���ɂ��A�Ȋw�E�Z�p�̊v�V���N�X��Ă����A��̃j���[�g��(�C�M���X�B1642-1727)����͂��߂Ƃ���A17�E18���I���x����̑�ȉȊw�ҒB�ƌ����Ă��ߌ��ł͂���܂���(�j���[�g���̐��N�̓K�����C�̖v�N�Ɠ����Ƃ����̂������[���ł�)�B
�@
���āA����̊w�K�|�C���g�ł��B�R�y���j�N�X�E�K�����C�E�P�v���[��3�l�͒n�������咣���A����̓V������ے肵�܂����B�R�y���j�N�X���������n�������A�K�����C�͖]�����Ȃǂ��g�p���Ď��A�܂��P�v���[���f���^���̖@�����m�F����Ȃǐ����I�Ɏ����܂����B�R�y���j�N�X�́w�V����]�_(�V���̉�]�ɂ���)�x�͐V�����ے��̗p��W�ɓo�ꂵ�܂����A�K�����C�́w�V���Θb�x�́A���ے��̗p��W�̂ݓo�ꂵ�Ă��܂��B�����Œ��������������邱�Ƃ͂��܂肠��܂��A�]�T������Βm���Ă��炢�����ł��B
�@
�{�҈ȊO�̓V���w�҂��o����Ƃ���Ȃ�A���X���オ����܂����A�n�����̐����咣�����C�^���A�̃g�X�J�l��(1397-1482)�����܂��B�R�����u�X(1446/51-1506)�̍q�C�ɉe����^�����l���ł��B
�@
�܂��W�����_�[�m���u���[�m���o�ꂵ�܂����B�ނ͓V���w�҂ł͂���܂���ł������A�Đ_�_�ƒn������Z�������Ĕ��\�����̂ŁA���c�̓{��ɐG�ꏈ�Y����܂����B�Đ_�_�͂̂��ɃI�����_�̓N�w�҃X�s�m�U(1632-77)�ɂ���Ď��グ���܂����B
�@
�]�k�ł������l�T���X���͉Ζ�(�ΖC)�E���j�ՁE���ň���̎O��Z�p�v�V������܂����B�Ƃ��Ɋ��ň����1450�N���A�}�C���c�o�g�̃O�[�e���x���N(1400?-68)�̉��ǂɂ���ĐV���ȕ������J���܂����B��ʈ���ɂ���āA�v�z�̕��y���i�W����Ă����̂ł��ˁB���̃O�[�e���x���N�̖��O���m���Ă����܂��傤�B�@ |
| �@ |
 �@ �@
�����B�g�����B�E�X�u���z�ɂ��āv�G���菉�� 1511�N |
   �@
�@
|
Vitruvius Pollio, Marc.(B.C.1���I)�@
�@
M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior factus cum figuris et tabula ut iam lrgi et intelligipos sit.
�@
���B�g�����B�E�X�͋I���O�̃��[�}�̌��z�ƁA���z���_�ƂƐ��肳��邪�A���v�N�A�o���͕s���B�{���́A���[�}�̒鐭���m�����Č��ݎ��Ƃ������ɂȂ��������ɍv�����悤�Ƃ��āA�����̌��z�m�����W�听�������z�Z�p�̕S�ȑS���ł���B���z�͓����̊T�O�ł́A�P�Ɍ��z�݂̂Ȃ炸�A�y�A�R���A�@�B�Ȃǂ̋Z�p�����܂�ł���B�{���������ꂽ�̂́A�I���O25�N���Ɛ��肳��Ă���A���z�Ɋւ���c���Õ����̒��ōł��Â����̂ł���B�ʖ{�̍ł��Â����̂́A8���I�ɐ��삳�ꂽ�Ɛ��肳����p�����ق̃n�[���[���ɂ̎ʖ{�ŁA��r�I���S�Ȃ̂Ō㐢�̍Z���{�̒�{�ƂȂ��Ă���B����{�̍ŌÂ̂��̂�1486�N�����[�}�Ŋ��s���ꂽ���̂ł���B �@ |
���}���N�X�E�E�B�g���E�B�E�X�E�|�b���I
�@
(���e����: Marcus Vitruvius Pollio, �I���O80�N/70�N�� - �I���O15�N�ȍ~)�@���a�����[�}���Ɋ����������z�ƁE���z���_�Ƃł���B�w���z�ɂ��āx(De Architectura�A���z�\��)�����B���̏����͌�������ŌÂ̌��z���_���ł���A�����炭�̓��[���b�p�ɂ�����ŏ��̌��z���_���ł�����B
�@
�E�B�g���E�B�E�X�ɂ��ẮA�w���z�ɂ��āx�̒��҂ł��邱�ƈȊO�ɂ͒m��ꂸ�A���̏o���N�A�v�N�A�ƌn�͕s�ڂł���B���������삩��͔ނ����z�Ƃł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A�܂��A�t���J�푈���ɃK�C�E�X�E�����E�X�E�J�G�T���̉��ŋΖ����A�A�E�O�X�g�D�X�Ɏd�������Ƃ��m�F�ł���B����ɂ���Ė����悤�Ƃ����悤�ł��邪�A�ނ́w���z�ɂ��āx�����[�}���z�ɂǂ̂悤�ȉe����^�������͒肩�ł͂Ȃ��B
�@
�w���z�ɂ��āx�͂����炭�I���O30�N����I���O23�N�̊Ԃɏ����ꂽ�Ɛ��������B���̏��ɂ����čł��m��ꂽ���_�́A���錚�z���������邩�ǂ����́A�E�l�̋Z��`���ł͂Ȃ��A���z�Ƃ̎d�����Љ�Ƃ������Ɉˑ�����Ƃ������̂ł���B�܂��A�u�悢���z�́A���ł��A���K���A���Ƃ���3�̏����ɂ���Đ��藧�v�Ƃ���莮�͑����E�B�g���E�B�E�X�ɋA�����邪�A���ꂪ���ڔނ̗��_�ł��邩�A����Ƃ��|��҂ɂ��~���ł��邩�ǂ����ɂ��Ă͋c�_������B
�@
�w���z�ɂ��āx�����݂ɓ`���̂́A�J�[�����ɂ��J�������O�����l�T���X�̎����ł���B���̃��e���꒘��Ɠ��l�A���̂Ƃ����ꂽ�����̕M�k�{�ɂ���āA���̖{�͓`����ꂽ�B���ݎc��ʖ{�́A���̑��������̂Ƃ��ɐ��삳�ꂽ�ʖ{�̂ЂƂA��p�����ِ}���������n�[���C�ʖ{2767�Ԃ��{�Ƃ��Ă���B�E�B�g���E�B�E�X�̗��_�͒����ɂ����Ă��m���Ă������A���l�T���X���̌��z�Ƃɓ��ɒ��ڂ���A�V�ÓT��`���z�ɓ���܂ŌÓT�I���z�̊�Ƃ��ĉe����^�����B
�@
�E�B�g���E�B�E�X�́w���z�ɂ��āx�̒��Ő��Ԃɂ��Ę_���Ă���B�Ñ�M���V�A�ɂ����āA���ԂƂ͐����ɗ���鏬��̗���𗘗p���č쓮�����鉡�����̎ԗւ��Ӗ����A��̂悤�ɗ������鐅�̗͂𗘗p���č쓮�����錻��I�Ȑ��Ԃ͒m���Ă��Ȃ������B�E�B�g���E�B�E�X�́w���z�ɂ��āx�ɂ����Č�҂̐��Ԃ��Љ�A�������p���邱�Ƃł�苭�͂Ȑ��͂����p�ł��邱�Ƃ��A���[���b�p�ŏ��߂Ē����B�����āA���m�ł͌���Ɏ���܂ł�����̐��Ԃ���ʓI�Ȃ��̂Ƃ��Ďp����Ă���B���̂��Ƃ���A�����c�ɗ��Ƃ��č쓮������`���̐��Ԃ́A�������̃M���V�A�^�E�m���E�F�[�^�ƑΔ䂵�āA�E�B�g���E�B�E�X�^�ƌĂ�Ă���B�@ |
���E�B�g���[�E�B�E�X / ���z��
�@
������Â����z�͂��邪�A������Â����z���͂Ȃ��B�킸���Ɋ��㒆���ɒf�Ђ�K��(����)�p����邭�炢�ł���B
�@
������{���͐��E���z�w�j��ɂ����āA����߂ċM�d�Ȉ�����Ƃ������ƂɂȂ�B���z���Ƃ��Ă����ł͂Ȃ��A���[�N���b�h�́w���_�x�A�v�g���}�C�I�X�́w�A���}�Q�X�g�x�ƕ��ԁg���E�͌^�̌����h��ł����Ă�����I�ȋL�O��ł��������B����Ȍ��z���͂��̌��1452�N�ɃA���x���e�B���w���z�\���x�킷�܂ŁA�܂������o�����Ȃ������B���������A���x���e�B�̏����ɂ��āA���́w���z���x���\���ō\������Ă��邱�Ƃ̓��P�������B
�@
�����c�O�Ȃ��ƂɁA���҂̃E�B�g���[�E�B�E�X(�\�L�̓��B�g�����B�E�X�Ƃ�)�ɂ��Ă͂��܂̂Ƃ���o�����o���������킩���Ă��Ȃ��B�I���O�ォ�I���O1���I����̐l���������Ƃ������Ƃ�����ł�����x�Ȃ̂��B�����ƃ����E�X���J�G�T����A�E�O�X�g�D�X�̈˗��ŁA��K�͂Ȍ��z��Z�p�J���ɂ�������Ă������낤�B���������u���l�b���X�L��~�P�����W�F���قǂ̑劈��������̂��낤���Ǝv����B
�@
���������Ă����ŏd�v�Ȃ̂̓E�B�g���[�E�B�E�X�l�̂��Ƃł͂Ȃ��āA�����̏I�ȏW���l���Ƃ��ẴE�B�g���[�E�B�E�X�Ƃ������ƂɂȂ�B�Ƃ��ɂ��̂���u���z�varchitectura�Ƃ́A����Ȃ錚�z�p�����ł͂Ȃ��āA�u���Z�p�̌����I�m����i�����E�l�����̐���𑣂��w��������H���̏p�̑S�ʂɂ�����邱�Ɓv�������Ă����Ƃ������ƁA���Ȃ킿�s�s�����̑S�m�S�\���߂��邽�߂̋Z�@�����u���z���v�������Ƃ������Ƃ�m���Ă����K�v������B
�@
�ڂ����{���ɏo������̂�1969�N�������B���̔N�A���C��w�o�ʼn��{���̑O�g�ɂ�����w�E�B�g���[�E�B�E�X���z���x�����C��w�ÓT�p���̈���Ƃ��Ė|�s���ꂽ�B
�@
�O�h�̎O�����ŕn�R��炵�����Ă����g�ɂ͂Ƃ��Ă���̏o�Ȃ����̂��������A���N�O���瓌�C��w�̎d�������Ă������ŁA��w�̍L������ɖ�����B�u�ӂ���A�N����Ȃ���ɊS������̂��A���z���߂����Ă�́H�v�ƌ���ꂽ�B������̕��������h�Ȉ���͑Ζ�ɂȂ��Ă��āA�܂��ɌÑネ�[�}�̂���Ƃ�����m���Ƃ����ׂ����n���������ĂĂ����B
�@
�����ɓǂ킯�ł͂Ȃ��������A�t�����V�X�E�C�G�C�c�ɂ��ە�����A�������ʓǂ��Ă��������ɁA�����悤�̂Ȃ������������Ă����B����͔����w�ł����ĕS�ȑS���ł���A���z�Z�@���ł����ČR�����ł���A���V���w�ɂ����R�w�ɂ��l�Ԋw�ɂ��|�p�_�ɂ��Ȃ��Ă���B
�@
�ŏ��ɃK�[���Ƃ��ꂽ�̂́A�E�B�g���[�E�B�E�X�̌������z�p���A�^�N�V�X�A�f�B�A�e�V�X�A�I�C�R�m�~�A��3�ɂ���Đ������Ă����Ƃ������Ƃ������悤�ɉ����B�^�N�V�X�́u���z�\�����ꂽ���̂��x�ɓK�����Ɓv���A�f�B�A�e�V�X�́u�z�u�Ƒg���Ă��ꗂ��Ȃ����Ɓv���A�I�C�R�m�~�A�́u���z���̂̊O�e���V�����g���[���ǂ̂悤�Ɋ܂ނ��Ƃ������Ɓv������킵�Ă���B����͂ǂ����Ă������Ȏ��g�݂ł���B
�@
���ꂾ���ł��ڂ��Ƃ��Ă͖����Ȃ̂����A�E�B�g���[�E�B�E�X�͂��̌����ɂ��ƂÂ��āA����Ȃӂ��ȕ��ނƒ�`�����Ă݂���B
�@
�܂��͌��z�Ƃ��g���ׂ������(1)����������A(2)�����v������A(3)��B������A�ɕ�����B�����v�Ɗ�B�����[�`���ɂȂ��Ă���Ƃ��낪���̎��������Â��Ă���B
�@
(1)�̌����́A����Ɂu���p�n�̌����������v�Ɓu���l�̉Ɓv�ɕ������āA�������z���̌��ĕ��ɂ́A1�h��I�A2�@���I�A3���p�I��3��̈Ӑ}��p�ӂ���B������������B
�@
���̂����ł����ɕt�^�����ׂ��f�U�C�����Ƃ��āA�E�B�g���[�E�B�E�X�́u�����v(�t�B���~�^�X)�Ɓu�p�v(�E�e�B���^�X)�̏d�v���������A���ꂱ�����u���̗��v(�E�F�k�X�^�X)�̒Nj����ׂ����̂��Ǝ咣�����B���́u���v�u�����v�u�p�v�́A�̂��Ƀw�����[�E�E�H�b�g���ɂ���ăf�B���C�g(���)�A�t�@�[���l�X(����)�A�R���f�B�e�B(����)�Ɩ��t���Ȃ����ꂽ���̂ł����邪�A�������Ȃ���ڂ��Ȃ�A�E�H�b�g���̌������������E�B�g���[�E�B�E�X�̒��B�ɌR�z��������B
�@
����ǂ������܂ł́A�܂��ɃM���V�A�I�Ƃ������w���j�Y���I�Ƃ������A�����̌��z�ƂȂ�l�������Ȃ��Ƃ������B�w���j�Y���Ƃ����̂͂��̂��炢�̓x�ʂ���ʂ��͗ʂ������Ă����B�ڂ����������������̂͂��̐�̂Ƃ�ł��Ȃ���쐫�Ȃ̂ł���B
�@
�Ȃ�ƃE�B�g���[�E�B�E�X�͂����u���Ă邱�Ɓv�̍s�ׂƌ����ɂ́A���������u�Ӗ����^������ӏ��v�Ɓu�Ӗ���^����ӏ��v�Ƃ�����̎��o�Ɠ������K�v���Ƃ݂Ȃ����̂��I�@
�@
�f�U�C���ɂ́u�Ӗ��̏��^�v�Ɓu�Ӗ��̕t�^�v�Ƃ��߂�����Ȃ�������Ȃ��ƌ������̂��B�܂�ŃV�j�t�B�A���ƃV�j�t�B�G���B���������A����̓\�V���[�����烁�������|���e�B���ւč����Ɏ���������v�z���̂��̂ł͂Ȃ����B
�@
�E�B�g���[�E�B�E�X�́u�����錚����Ԃ͌��n�I�ȏ�������o������v�ƍl���Ă����B����䂦�l�Ԃ��ǂ̂悤�ɍŏ��̒�Z���������Ƃ������Ƃ@�������Ă����B
�@
���̓��@���u�Ӗ����^������f�U�C���v�Ɓu�Ӗ���^����f�U�C���v�̓��@�ɂȂ����Ă����B�ڂ��́w���z���x��̎��̂悤�Ȃ������ǂ�ŁA�����������̂������B
�@
�v��ƁA�����Ȃ̂��B�u�l�Ԃ͑O�����݂ł͂Ȃ��������ĕ������悤�ɂȂ��āA�肪���ݏo�����邩�ɋC�������̂ł���v�u���Ől�Ԃ͉̔����ɂ���āA���߂đ��݂̉���������悤�ɂȂ����̂��v�u���̉������l�X�ɉ�������炵�A�W�Z�������炵���v�u�������čŏ��͖̗t�ʼn������A���A��T���Ă��������Ɍ@��A�������Ɍ��n�I�ȏ����Â�����n�߂�悤�ɂȂ����̂ł���v�B
�@
�u���������l�Ԃ͖͕�I�ł����Ċw�K�I�ł���v�u����䂦�ǂ�ȏZ�܂��̍H�v�ɂ��Ă��A���݂Ɍ������͂��͂Ȃ��A��҂̎}�ɗ���n�����ƁA�D��h�肱�߂ĕǂ����邱�ƁA�J���𗬂����߂̉����ɌX�����邱�ƂȂǂ́A�����Ƃ����܂ɗ��s�����͂��ł���v�u���͂��������Z�܂��̎d�g�݂��m�����Ă��A���ꂪ�O���ɗ���Đ^�������Ƃ��A���̒n�ɍޗ����s�����Ă��邱�Ƃɂ���v�u�������āA���̒n�̌��z�Ƃ͐V���ȍH�v�ɓ��B������̂Ȃ̂ł���v�u�Ӗ����^��������́A�Ӗ���^������̂�l�X����������̂́A���̂Ƃ��ł���v�I
�@
����͂����A�l�Ԃ̌����̎��݂̈Ӗ��̂قƂ�ǂ̂��Ƃ��E�B�g���[�E�B�E�X�͏����Ă��܂����Ƃ����ׂ����B
�@
�E�B�g���[�E�B�E�X�̎���̓w���j�Y���̎���ɂ�����B���łɃM���V�A���z�͑S�����������Ă���B
�@
�����Ńw���j�Y�����������C�͂Ȃ����A�I���O322�N�̃A���L�T���h���X�̎�����I���O30�N�̃A�E�O�X�g�D�X�ɂ�郍�[�}�鍑�ݗ��܂ł̖�300�N���A�ӂ��̓w���j�b�N���ɂ�����B���̃w���j�Y���̓��F�͂��낢�날�邪�A�ꌾ�ł����u�l�Ԃ��Z�ސ��E�v�ɂ�����u�m�̕ω��Ɗg���v���ӎ��I�ɒNj����������Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�B����ł��������͓������Ă���B
�@
�A���N�T���h���A�́u���Z�C�I���v(�}����)�ɖ����̏�������������̂��͂��߁A�n���𑪂����q�b�p���R�X��|�Z�C�h�j�I�X��A���X�^���R�X�A�w�̃��[�N���b�h��A���L���f�X��A�|���j�E�X�A�嗷�s����Ă��s���[�e�A�[�X�A�f���N���g�X��G�s�N���X�̌��q�N�w�҂�̎������_��A�~���̃��B�[�i�X����K���_�[���ɉ萶���������܂ŁA����炢��������u�l�Ԃ̔��e�v�Ɓu�m�̕ω��̔��e�v��S���Ă����B
�@
�Ƃ��Ƀw���j�Y��������Â���͓̂s�s���z�Q�A�Ȃ��ł��_�a�ƌ���ł���B
�@
�R�X�̃A�X�N���s�I�X�_��̕����}��y���K�����̈�ՌQ�����Ă���ƁA�w���j�Y���Ƃ͂��̐��E�ς��̂��̂��@���I���䑕�u�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B�G�t�F�\�X�̌���Ȃ��25000�l�̎��e�͂Ȃ̂��B
�@
�f�[���g���A�X�̂悤�ɓs�s����d�������Ƃ��Ƃ��āA�����Ԃ铮�I�ł��������Ƃ����ڂ����B����͂�����u�V�F�m�C�L�X���X�v�Ƃ��Ă���\�����o�ŁA�s�s����ȏ�̋����̂��q���ň�̓��I�g����}�����̂ł���B�w���j�b�N�E�o���b�N�Ƃł����������Ȃ�قǂ��B
�@
�Ƃ��������w���j�Y���̓s�s���z�́A�_�a�ł��ꌀ��ł���s�s���̂��̂ł���A��1�ɂ͐��E����I�ł���A��2�ɓ��I�ŁA����ł��đ�3�ɐ��k�ȍ\�����D�̂ł���B�E�B�g���[�E�B�E�X�����̐��_�̉����ɂ������Ƃ͂܂��������Ȃ��B
�@
���E����I�œ��I�ŁA����ł��Đ��k����܂�Ȃ��\���Ƃ������́\�\�B������āA�Ђ���Ƃ��č����̓��{���߂����ׂ��\�����o�ł͂Ȃ��������B
�@�@
�@ |
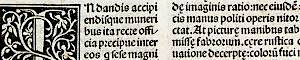 �@ �@
���v���g���u�S�W�v���� 1513�N |
   �@
�@
|
Platon.(B.C.427-347)
�@
Omnia Platonis opera.
�@
�v���g���́A�M���V�A�̓N�w�ҁB������ʓI�Ɍ����Ă���u�v���g���S�W�v�́A���[�}�c��`�x���E�X(14-37�N)�̎t�F�ł������Ƃ�������g���V�����X�̕ҏW�ɂ����̂���{�ƂȂ��Ă���B����́A�M���V���ߌ��̏㉉�`�����܂˂�4�����P�ʂƂ������̂ŁA���ꂪ��W�܂��đS�W���`�����Ă���B�v���g���̒���Ō�������ŌÂ̂��̂́A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̃{�[�h���A���}���قɏ�������Ă���ʖ{�ŁA895�N�ɐ��삳�ꂽ�Ƃ݂��Ă���B�v���g���S�W�����߂Ĉ���{�Ƃ��ēo�ꂷ��̂́A1484�N�Ƀt�B�����c�F�ň�����ꂽ���e�����ł���B��������M���V���ꌴ�T�Ƃ��Ă�1513�N�Ƀ��F�j�X�̃A���_�C���E�v���X�Ŋ��s���ꂽ�W���̂��̂��ŏ��ł���B �@ |
���v���g��
�@
(�v���g�[���A��F����ά�уփˁA���FPlato/Platon�ABC427-BC347)�́A�Ñ�M���V�A�̓N�w�҂ł���B�\�N���e�X�̒�q�ɂ��āA�A���X�g�e���X�̎t�ɓ�����B�v���g���̎v�z�͐��m�N�w�̎�v�Ȍ����ł���A�N�w�҃z���C�g�w�b�h�́u���m�N�w�̗��j�Ƃ̓v���g���ւ̖c��Ȓ��߂ł���v�Ƃ�����|�̂��Ƃ��q�ׂ��B�w�\�N���e�X�ٖ̕��x��w���Ɓx���̒���Œm����B�������钘��̑唼�͑Θb�тƂ����`��������Ă���A�ꕔ�̗�O�������A�v���g���̎t�ł���\�N���e�X����v�Ȍ���Ƃ���B
�@
�����̃v���g���́A�u�h�i�v��u�E�C�v�Ƃ������Ñ�M���V�A�̓`���I�ȓ��Ƃ͉����A����͋���������̂��ǂ����A�Ƃ��������Ƃ�T���������A�����̒��ł͒��ړ����͗^����ꂸ�A�Ō�ɂ͍s���l�܂�(�A�|���A)�Ɏ���B�����ɂ́A���E��ڂɌ����錻���̐��E�u�����E�v�Ƃ��̌��ɂȂ銮�S�ɂ��Đ^���̐��E�u�C�f�A�E�v�Ƃɕ�����C�f�A�_��W�J�����B
�@
�s���^�S���X�w�h�̎v�z���w�сA�Ƃ�킯�A�w���d��v�z��I���y�E�X���I�ȗ։��]�����̉e�������B�����ȍ~�A���̉e���������Ɍ�����B�܂��A�p�����j�f�X���̃G���A�h�ɂ��S���A����Θb�тł̓G���A�h�̐l���������Γo�ꂳ���Ă���B
�@
�v���g���͏��߂ė��_�I�ɐl�Ԃ̂�����ɂ��čl���悤�Ƃ����l���ł���A���̎O�敪��(�w���Ɓx436A�A580C-583A�A�w�e�B�}�C�I�X�x69C)���Ȃ��āA�l�Ԃ̂�����̓�����������悤�Ƃ����B�C�f�A�_�ɏ]���ė썰(�v�V���[�P�[)�̕s�����̘_������(�w�p�C�h���x)�A��ʓI�ȗ����ł́A���̎v�z�͐l�Ԃ̗썰�Ɛg��(����)��ʁX�̎��̂Ƃ��ė��Ă����_�A�Ђ��Ă̓f�J���g��̕��S�_�̌����̂ЂƂƌ��Ȃ���Ă���B
�@
�v���g���̓A�e�i�C�x�O�ɃA�J�f���C�A�Ƃ������Ŋw�Z���J�݂����B�v���g���̌�p�҂���ׂ��A�A�J�f���C�A�����_�Ɋ��������l�X�̓A�J�f���C�A�h�ƌď̂����B
�@
�Ȃ��A��q����悤�Ƀ��X�����O�����ӂł������炵���B�܂��A�p���N���`�I�����u�s���S�ȃ��X�����O�ƕs���S�ȃ{�N�V���O����ƂȂ������Z�ł���v�ƕ]�������Ƃ��m���Ă���B
�@
�����U
�@
���t�@�G����u�A�e�i�C�̊w���v�@�t���X�R��B�Ȃ��A����̓��I�i���h�E�_�E���B���`���摜�����f���Ƃ����B
�@
�I���O427�N�A�A�e�i�C�Ō�̉��R�h���X(�p���)�̌��������M���̑��q�Ƃ��āA�A�e�i�C�ɂďo���B
�@
�c���̖��ɂ��Ȃ�Łu�A���X�g�N���X�v�Ɩ������ꂽ���A�̊i�����h�Ō������L������ (�Ê�: �Ƀ���ύς) ���߁A���X�����O�̎t���ł���A���S�X�̃A���X�g���Ɂu�v���g���v�ƌĂ�A�ȍ~���̂��������蒅�����B
�@
�Ⴂ���͐����Ƃ��u���Ă������A�₪�Đ����Ɍ��ł��o���A�\�N���e�X�̖�l�Ƃ��ēN�w�ƑΘb�p���w�B�I���O399�N�A�A�e�i�C�̎��l�����g�X(�p���)�̋N�i�ɂ���āA�\�N���e�X�́u�_�X�ɑ���s�h�ƁA�N�����ɊQ�ł�^�����߁v�𗝗R�ɍٔ��ɂ�������B�@��ł̓��[�ɂ�莀�Y�Ɍ�����ꂽ�\�N���e�X�͓Ŕt�����ŌY������B
�@
���̌�A�v���g���̓A�e�i�C�𗣂�A�C�^���A�A�V�`���A��(1��ڂ̃V�`���A�s)�A�G�W�v�g��������B���̎��A�C�^���A�Ńs���^�S���X�h����уG���A�h�ƌ𗬂��������ƍl�����Ă���B
�@
�I���O387�N�A�A�e�i�C�x�O�̖k���A�A�J�f���C�A�̒n�̋ߖT�Ɋw����ݗ������B�����̓A�e�i�C��O�̐X�̒��A�����̑̈�ꂪ�݂���ꂽ�p�Y�A�J�f���X(�p���)�̐_��ł���A�v���g���͂��̓y�n�ɏ����������Ă����B�ꏊ�̖��ł���A�J�f���C�A�����̂܂܊w���̖��Ƃ��Ē蒅�����B�A�J�f���C�A�ł͓V���w�A�����w�A���w�A�����w�A�N�w����������ꂽ�B�����ł͑Θb���d���A���t�Ɛ��k�̖ⓚ�ɂ���ċ��炪�s��ꂽ�B�v���g���̒�q�ɓ�����A���X�g�e���X��17�̎��ɃA�J�f���C�A�ɓ��債�A�Ȍ�A�v���g�����S���Ȃ�܂ł�20�N�Ԋw�Ɛ����𑗂����B�v���g���v��A���̉��̃X�y�E�V�b�|�X���Ղ��p���Ŋw���ƂȂ�A�A���X�g�e���X�̓A�J�f���C�A���������B
�@
�I���O367�N�A���l(�t��)�ł������f�B�I����̍�����A�V�`���A���̃V�����N�T�C�֗��s����(2�x�ڂ̃V�`���A�s)�B�V�����N�T�C�̎Ⴋ�G��f�B�I�j���V�I�X2��(�p���)���w�����ēN�l�����̎�����ڎw�������A�����������ɂ̓f�B�I���͒Ǖ�����Ă���A�s����ɏI���B
�@
�I���O361�N�A�f�B�I�j���V�I�X2�����g�̋�����]���A3�x�ڂ̃V�����N�T�C���s���s�����A�܂����Ă������Ɋ������܂�A���x�̓v���g�����g����ւ���Ă��܂��B���̎��v���g���́A�F�l�ł���s���^�S���X�w�h�̐����ƃA���L���^�X�̏��͂āA�h�����A�e�i�C�ɋA�邱�Ƃ��ł����B�N�l�����̖��͋I���O353�N�Ƀf�B�I���������ɂ��ÎE���ꂽ���Ƃɂ���ēr�₦���B
�@
�v���g���͔ӔN�A���q�ƃA�J�f���C�A�ł̋���ɗ͂𒍂��A�I���O347�N(�I���O348�N�Ƃ�)�A80�Ŗv�����B�@ |
���N�w
�@
���C�f�A�_
�@
��ʂɁA�v���g���̓N�w�̓C�f�A�_�𒆐S�ɓW�J�����ƌ�����B�����ω����镨���E�̔w��ɂ́A�i���s�ς̃C�f�A�Ƃ������z�I�Ȕ͌^������A�C�f�A�������^�̎��݂ł���A���̐��E�͕s���S�ȉ��ۂ̐��E�ɂ����Ȃ��B�s���S�Ȑl�Ԃ̊��o�ł̓C�f�A�𑨂��邱�Ƃ��ł����A�C�f�A�̔F���́u���_�̖ځv�ŖY�p����Ă������̂��u�z�N�v (anamnêsis�A�A�i���l�|�V�X)���邱�Ƃɂ���ē��邱�Ƃ��ł�����̂ł���A���̑z�N���炩�đ����Ă����C�f�A�̐��E�ꋁ�߂�Ƃ���̈�(erôs�A�G���[�X)��������Ƃ����B
�@
�N�w�҂͒m�������邪�A���̈��̑Ώۂ́u������́v�ł���B������ɁA�h�N�T(�v���Ȃ��A�v������)������ɂ����Ȃ��҂̈��̑Ώۂ́u����A���A����ʂ��́v�ł���B���̂悤�ɘ_���ăv���g���́A���ݘ_�ƒm�������т��Ă���B����ɂ��A���̉F���͐_������(�q�����[)����C�f�A��͌^�Ƃ��Đ��삵�����̂ł����āA������n��ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�v���g���́A�ō��̃C�f�A�͑P�̃C�f�A�ł���A���݂ƒm������ō������ł���Ƃ����B
�@
�����Ƃ��A�v���g���̒���̒��ŃC�f�A�_�����m�ɓW�J�����̂̓p�C�h���Ȃǒ����̈�A�̑Θb�тɌ�����B����̃v���g�����C�f�A�_���Ȃ����ێ����Ă������ɂ��Ă͌����҂̊ԂŌ�����������Ă���A�u�G�C�h�X�v�Ȃǂ̃C�f�A�̗ދ`����������ɃC�f�A�_�ƌ��т��邱�Ƃ��\���ǂ����A�u����v(����)�̔c���̍��فA�Ƃ������_�_���߂����ċc�_������B
�@
�������_�E�|�p�_
�@
�v���g���͌o����`�̂悤�ȁA�l�Ԃ̊��o��o������Ղɐ������v�z��ے肵���B���o�͕s���S�ł��邽�߁A�������F���Ɏ��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƍl�������߂ł���B
�@
�܂��A�w���Ɓx�ɂ����ẮA�|�p�ɂ��Ă��ے�I�ȑԓx��\���Ă���(�w���Ɓx��10��)�B���o�ő����邱�Ƃ��ł�����͕s���S�Ȃ��̂ł���A���S�ȎO�p�`�⊮�S�ȉ~�⋅���̂��̂͏�Z�s�ς̃C�f�A�ł���B�|�p�̓C�f�A�̖͕�ɂ����Ȃ������̎���������ɖ͕킷����́A����ɂ͎����̖͕�ɂ����Ȃ����̂ɐl�̊S��������������̂ł���A�Ƃ��Č|�p�ɉ��l�����o���Ȃ������B
�@
���ϗ��w
�@
�v���g���̗ϗ��w�̓��F�́u���͒m�ł���v�Ƃ����\�N���e�X����p������m��`(�p���)�I�ȋL�q�ɏW���B����������͓����`�B�\�ȋZ�p�m�ł���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B���Ƃ́A���܂��O�͒m���Ă��������܂ꂽ��Y��Ă��܂����z�N(�A�i���l�[�V�X)�����ׂ��m�ł���A�C�f�A�Ɏv���I�Ɏ���`����w�I�m�ł���B���Ȃ킿�A�v���g���͌`����w�ƂЂƂɂȂ����ϗ��w�����߂Ċm�������B
�@
������ɁA�Z�p�I�ɋ������Ȃ��m�����������[�߁A�l�Ɋ�������ɂ́u���̋C�Â����v(�G�s�����C�A�E�e�[�X�E�v�V���P�[�X)���K�v�ł��邪�A���̈Ӗ��͗��O�I�ȓ��̓��I�����Ɍ����Ă̐��_�̋���Ƃ������Ƃł���A���̖ړI�́A��Ɍ����ʗ��O�̗�����ʂ��đP�̃C�f�A�Ƃ����ō����݂ɂ܂Ő��_�̎˒����y�Ԃ��Ƃł���B
�@
���̗ϗ��w�͍��Ɗw�A�����w�Ƃ����Љ�I���x�������̋A���Ƃ���B�ЂƂ̗썰�������A�ӎu�A��~�ɕ������悤�ɁA���ƍ\���K�w���x�z�K�w�A�h�q�K�w�A�E�\�K�w�ɕ�����A���ꂼ��ɊY�����铿�͒m�b�A�E�C�A�ߐ��ł���B�����ɂ͌Ñ�M���V�A�̃}�N���R�X���X(��F��)�ƃ~�N���R�X���X(���F�����Ȃ킿�X�̐l��)�Ƃ̗ޔ�̌�����������B �����O�̓��̒��a���������`�ł���B���Ƃ̍ŏd�厖�Ƃ͋���ł���A���Ȃ킿�v���g���̗ϗ��w�́A�l�ϗ��A������ɑ���Љ�ϗ��Ƃ��Ă̐����w�A�����ɑ���ϗ��w�Ƃ��Ă̋���w�A�ɎO�������̂ł���B�@ |
�������^����
�@
�v���g���̒���Ƃ��ē`�����ꂽ�����̒��ɂ́A�^�U�̋^�킵�����̂�A�����̊w�҂ɂ���ċU��Ƃ���Ă�����̂��܂܂�Ă���B
�@
�v���g���̒����̐^��͂��łɋI���O�̃A���N�T���h���A�̕����w�҂ɂ���ċc�_����Ă���B���ݓ`���ŏ��̑S�W�Ҏ[�͋I���O2���I�ɍs��ꂽ�B�Ñネ�[�}�̃g���V�����X�́A�����`����Ă����v���g���̒�������̓��e���玷�M���ɕ��ׁA�����ɉ�����4����W�ɕҎ[�����B���݂̃v���g���S�W�͊��s�ɂ�肱�̃g���V�����X�̑S�W�ɏ������Ă���A���^���ꂽ��i�����ׂĊ܂ށB�������g���V�����X�͂��łɂ��̎��A�������̍�i�̓v���g���̂��̂ł��邩�ǂ����^�킵���A�Ƃ��Ă���B
�@
�v���g���̐^�M�ł���ƌ����҂̊Ԃō��ӂĂ��钘��̂����A�ł��ӔN�̂��̂́w�@���x�ł���B�����ł́w���Ɓx�Ɠ������A�����Ƃ͉����Ƃ������Ƃ�����A���z�I�ȋ���ɂ��Ă̘_���ĂѓW�J����邪�A�N�l���̎v�z�͓o�ꂵ�Ȃ��B�܂��A���M���ׂ����ƂɁw�@���x�ł̓\�N���e�X�ł͂Ȃ������́u�A�e�i�C���痈���l�v������߂�B�����̌����҂́A���́u�A�e�i�C����̐l�v���v���g�����g�Ƃ݂Ȃ��A���̌���̕ω��́A�v���g�����\�N���e�X�Ǝ����Ƃ̎v�z�̈Ⴂ���������o����Ɏ��������Ƃ��������Ă���A���̂䂦�Ƀ\�N���e�X��o�ꂳ���Ȃ������̂��ƍl���Ă���B
�@
�w�@���x�̑��҂Ƃ��ď����ꂽ�ł��낤�w�G�s�m�~�X�x(�w�@����сx)�ł͓N�l���̎v�z���Ăѓo�ꂷ�邪�A�w�e�B�}�C�I�X�x�̉F���ςƁw�G�s�m�~�X�x�̉F���ς��قȂ邱�ƁA���̗̂���Ȃǂ���A�قƂ�ǂ̊w�҂́w�G�s�m�~�X�x���q���邢�͌��̋U��Ƃ��Ă���B�������w�G�s�m�~�X�x�͍ŔӔN�̃v���g�������̎v�z�����k���ď����c�������̂��ƍl���Ă���w�҂������Ȃ��瑶�݂���B
�@
�v���g���̓C�\�N���e�X�̉e�����A������蕶�̂�ς��Ă��邱�Ƃ��������Ă���B���͂Ɏg�����b��ꉹ�̘A���Ȃǂׂ镶�̓��v�w�ɂ��A����ł͂��Ȃ�̍�i�̎��M�����ɂ��Ċw�ҊԂ̈ӌ��͈�v���Ă���B���Ƃ��g���V�����X���w�N���g���x�̌�ɂ������w�p�C�h���x(�\�N���e�X�̎��̒��O�A�s���^�S���X�w�h�̓�l�ƃ\�N���e�X���Θb����)�́A�����̍�i�ɑ����邱�Ƃ��������Ă���B���������̓��e����A�������̍�i�ɂ��Ă͎��M�N��ɂ��Ă̘_��������B�@ |
���㐢�ւ̉e��
�@
�v���g���̐��m�N�w�ɑ���e���͒�q�̃A���X�g�e���X�ƕ���Ő��ł���B
�@
�v���g���̉e���̈��Ƃ��ẮA�l�I�v���g�j�Y���ƌĂ��Ñネ�[�}�����A���l�T���X���̎v�z�Ƃ����������邱�Ƃ��ł���B�u��ҁv����̖����̗��o������l�I�v���g�j�Y���̎v�z�́A�������̃L���X�g����l�T���X���N�w�A����Ƀ��}����`�Ȃǂɉe����^����(�������A�O�m�[�V�X��`��A���X�g�e���X�N�w�̉e�����傫���A�v���g�����g�̎v�z�Ƃ͗l�����قȂ��Ă��܂��Ă���)�B
�@
�v���g���́w�e�B�}�C�I�X�x�̒��̕���ŁA����ҁu�f�[�~�E���S�X�v���C�f�A�E�Ɏ����Č����E�����Ƃ����B���́u�f�[�~�E���S�X�v�̑��݂��u�_�v�ɒu�������邱�Ƃɂ��A1���I�̃��_���l�v�z�ƃA���N�T���h���A�̃t�B�����̓��_�����ƃv���g���Ƃ����т��A�v���g���̓M���V�A�̃��[�Z�ł���Ƃ������B�w�e�B�}�C�I�X�x�͐����[���b�p�����ɗB��`������v���g���̒���ł���A�v���g���̎v�z�̓l�I�v���g�j�Y���̎v�z���o�R���Ē����̃X�R���N�w�Ɏp�����B
�@
�Ȃ��A�A�g�����e�B�X�̓`���́w�e�B�}�C�I�X�x����сw�N���e�B�A�X�x�ɗR������B
�@
�J�[���E�|�p�[�́A�v���g���́w�|���e�B�A�x�ȂǂɌ�����v��`�I�ȎЉ���v���_���Љ��`�⍑�Ǝ�`�̋N���ƂȂ����Ƃ��āA�v���g���v�z�ɐ��ޑS�̎�`��ᔻ�����B�@
�@ |
 �@ �@
���^���^�[�����u�V�Ȋw�v���� 1537�N |
   �@
�@
|
Tartaglia, Niccolo.(1500-77)
�@
Nova Scientia inventa da Nicolo Tartalea ...
�@
�^���^�[�����́A�C�^���A�̐��w�ҁB�ނ́A�Ɗw�̋Z�t�ł���A���ʎm�ł���A���w�҂ł������B�^���^�[������3�����������������@���J������Ƃ����A�ނ̎���ɂ�����ł��d�v�Ȑ��w�I������1���Ȃ��Ƃ����B�{���̒��Ŕނ́A�e���w�A���ʊw�A�H�w�Ȃǂ������Ă���A���̒���́A�͊w�̗��j�ɂ�����V��������̏o���_�Ɉʒu������̂ł���B�ނ́A���˕��̋O�Ղ͂��̏d���̂��߂ɂ�����_�Œn�ʂ̕��ɋȂ�����ƍl���A���̋O�Ղ��������w�I���_�����߂������������Ȃ������B�ނ́A�C�肩��Œ����e������45�x�̋p�œ�����Ƃ������Ƃ��w���A���m�ȗ͊w�I�����ɂ�������A���̌������琔�w�I�ɒe������㈂��邱�Ƃ́A�K�����I�܂ő҂��˂Ȃ�Ȃ������B���F�j�X���B�@ |
���j�R���E�t�H���^�i�E�^���^���A
�@
(Niccolò Fontana Tartaglia�A1499/1500-1557)�@�u���V�A���܂�̃C�^���A�̐��w�ҁA�H�w�ҁA���ʎm�ŁA���F�l�c�B�A���a���̕�L�W�������B�ނ́A�A���L���f�X��[�N���b�h�̏��߂ẴC�^���A�����܂ޑ����̒������A���w�W�̕ҏW�̕���ō����]�����ꂽ�B�^���^���A�́A���߂Đ��w��p���đ�C�̒e���̌v�Z���s�����B�ނ̌����́A��ɃK�����I�E�K�����C�ɂ�闎�̂̎����ɂ�茟���ꂽ�B
�@
�j�R���͔z�B�l�ł������~�V�F���E�t�H���^�i�̑��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B1505�N�A�~�V�F�����E����A�j�R����2�l�̌Z��A�ꂪ�n���̒��c���ꂽ�B1512�N�ɂ̓J���u���[�����푈�Ńt�����X�R���u���V�A�ɐN�U���A����Ȃ�ߌ����o�������B�u���V�A�R��7���Ԃɓn���ĊX����������A�t�����X�R�����ɐN�U�ɐ�������ƁA�X�̐l�B�͋s�E���ꂽ�B�푈�̏I���ɂ́A45000�l����Z�����E����Ă����B�j�R���̊{�ƌ��W���t�����X�R�ɂ���Đ藎�Ƃ��ꂽ�B����ɂ���āA�j�R���͕��ʂɂ͘b���Ȃ��Ȃ�A�u�^���^���A(�ǂ���)�v�Ƃ����j�b�N�l�[�����t����ꂽ�B
�@
�^���^���A�́A�������s����O�ɉƒ닳�t����A���t�@�x�b�g�̔������K���������ł���A�c��̔����͓Ɗw�Ŋw�Ƃ����b������B������ɂ��Ă��A�ނ͖{���I�ɓƊw�������B
�@
�ނ�1543�N�ɕҏW�������[�N���b�h���_�̏��߂Ă̋ߑト�[���b�p���ƂȂ����{�͂ƂĂ��d��Ȃ��̂ł������B2���I�̊ԁA���[���b�p�ł̓G�E�h�N�\�X�̗��_�̋L�ڂɌ��̂���A���r�A��ł�������e����ł��g���ă��[�N���b�h�w���������Ă����B�^���^���A�ҏW�̂��̂̓M���V�A��ł����ɂ������̂ł������B�ނ͂܂����̗��_�ɏ��߂ċߑ�I�ȃR�����g��t�����B��ɁA���̗��_�̓K�����I�ɂƂ��ĕs���̓���ƂȂ����B
�@
�^���^���A�́A�����ł̓W�F�������E�J���_�[�m�Ƃ̑Η��ōł��L����������Ȃ��B�J���_�[�m�́A�^���^���A�̎O���������̉�@���o�ł��Ȃ��Ɩ��āA������ꂽ�B���N��A�J���_�[�m�́A�Ɨ͂Ń^���^���A�Ɠ�����@�ɒH�蒅�����V�s�I�[�l�E�f���E�t�F�b���̖����\�̘_�������܂��ܖڂɂ����B���̖����\�_���̓^���^���A�̂��̂��O�ɏ�����Ă������߁A�J���_�[�m�͖͖����Ɣ��f���āA���̒����Ƀ^���^���A�̉�@���ڂ����B�J���_�[�m�������̖��O�ʼn�@�\�������Ƃ�m��A�^���^���A�͌��{�����B�ނ͌��O�̑O�ŃJ���_�[�m�J�����B
�@
�^���^���A�́A4�̒��_�̊Ԃ̋�����p���ĎO�p���̑̐ς�\���^���^���A�̌������l�Ă������Ƃł��m����B����͎O�p�`�ɂ�����w�����̌�������ʉ��������̂ł���B�W����p�X�J���̎O�p�`�́A�ʖ����^���^���A�̎O�p�`�Ƃ������B�@ |
�����@�̒e���w
�@
�����̃��[���b�p�̐푈�ł͍U��킪�ő�̎R��B��ǂ������j�邽�߂ɊJ�����ꂽ�̂��u���@�v�ł����B�ȗ��u�e�����ɂ߂�v���Ƃւ̂�����肪���w�W�����A�R���s���[�^�[�݂܂����B
�@
���@�ƌ����Ă��A���ł����Α�^�N���[���Ԃقǂ̋���Ȃ��́B�U��q�ƃS��(�̂悤�Ȃ���)�̒e�͂𗘗p���āA�d�����\�L��������𐔕S���[�g��������Ƃ��o���܂����B������ǂ������ӂ����Ƃ��͔��芅�т𗁂т���ł��傤�ˁB
�@
Ballista �Ƃ����|�̂������̂悤�ȓ��@�͂��łɃM���V���E���[�}���ォ��g���Ă����悤�ł��B�����w�҃A���L���f�X�͂���̐��ƂŁA��|�G�j�푈�ł͑劈�����Ƃ��B�����̓��@�� Trebuchet �ƌ����āA�U��q�̔����𗘗p�������́B����HP�̐}������Ƃ��������̌����͂킩��܂��ˁBCatapults �͂����̑��̂̂悤�ł��B
�@
�Ζ���g������C�����߂Ď���ɓo�ꂵ���̂́A�P�S���I�̕S�N�푈�B�����̑�C�͎l�p���S�_��ɕ��ׁA�O�����^�K�Œ��߂��ȒP�Ȃ��́B���łɊ����̈�ɂ��������@�Ɣ�ׂ�Ɩ������x�͂��܂ЂƂł������A���S���̂��̂����y����ɂ�A���@�Ɏ���đ���܂����B
�@
��C�͂������Ζ�̎�ށA�C�e�̏d���A���ˊp�x�A�������A�����Ȃǂɂ���Ēe�������X�ƕω����鈵���ɂ�������B�C����̌o���Ɗ������ł͂Ȃ��Ȃ����x���オ��Ȃ������悤�ł��B�����œo�ꂵ���̂��A�e���̐��Ƃ��Ȃ킿�C�p�Ƃł����B
�@
�C�^���A�l�^���^�[�����͂R�����������̉�@�̔����҂Ƃ��ėL���ł����A�{�E�͒e���̐��ƁB�S�T�x�Ŕ��˂��邱�Ƃ������Ƃ��˒����҂����ƂɋC�Â��܂����B�K�����C�͂���𐔊w�I�ɏؖ��B�u������(�p���{���Ȑ�)�v��u�����̖@���v�͂��̕��Y���ƌ����Ă��܂��B���������A���I�i���h���_�����B���`����C�̌����Œm���Ă܂����A�~�P�����W�F���͒z��̐��ƂŁA�t�B�����c�F�x�O�ɂ͔ނ̐v������ǂ����܂��Ɏc����Ă���Ƃ��B
�@
����͕ς���āA��Q����햖���B�A�t���J����Ńh�C�c�R�Ɛ���Ă����p�ČR�͍��˖C�̖����������������ƂɋC�Â��܂����B�}篁A�����A�C���A���x�A�n���̎��]�܂ł��g�ݍ��e���\�̍�蒼���ɒ���B���������̍�Ƃ͐l�Ԃ̌v�Z�͂̌��E���Ă��܂����B�G�b�J�[�g�ƃ��[�N���[�́A�P������{�̐^��ǂ��g�����u�����v�Z�@�v�ɂ��̌v�Z�������邱�ƂɁB�j�㏉�̃R���s���[�^�[ �uENIAC�v���Y�����グ���u�Ԃł��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���R�y���j�N�X�u�V�̂̋O���ɂ��āv���� 1543�N |
   �@
�@
|
Copernicus, Nicolaus.(1473-1543)
�@
De revolutionibus orbium coelestium.
�@
�R�y���j�N�X�́A�|�[�����h�̓V���w�ҁB��w���w��A�_�w�A�V���w���C�߁A��҂̎d���̂������A�V���w���������A�n�����̌����ɂ��̐��U��������B1543�N�A���̒��O�Ƀj�������x���N�Ŗ{�������s���A�n���������\�����B�{���̊��s�ɂ������ẮA����̔����ڗ����Ĕ��ɗp�S�[���ԓx���Ƃ������A�����̑����̓V���w�҂�@���Ƃ��猃���������A1616�N�ɂ̓J�g���b�N����̋֏��ژ^�ɍڂ���ꂽ�B1757�N����эēx�̋֎~���1822�N�ɂ悤�₭��������A�K�����C�����߂Ƃ��A�P�v���[��j���[�g����̌��������ɂ���Ďx�����ꂽ�B18���I���̍P�������̑���̐����ɂ��A�ނ̊w���́A���S�Ɏ������Ƃ���ƂȂ����B�@ |
���j�R���E�X�E�R�y���j�N�X
�@
(���e���ꖼ: Nicolaus Copernicus�A�|�[�����h�ꖼ: �~�R���C�E�R�y���j�N Mikołaj Kopernik�A1473-1543 )�@�|�[�����h�o�g�̓V���w�ҁA�J�g���b�N�i�Ղł���B�����嗬�������n�����S��(�V����)�����z���S��(�n����)���������B����͓V���w�j��ł��d�v�ȍĔ����Ƃ����B�R�y���j�N�X�͂܂��A����ł͎i���������Q�����(�J�m��)�ł���A�m���A�����A�@�w�ҁA�萯�p�t�ł���A��҂ł��������B�b��I�ɗ̎�i�Ղ߂����Ƃ�����B
�@
�R�y���j�N�X�́A1473�N�Ƀg�����Ő��܂ꂽ�B���Ƃ͋��s�X�L��̈�p�ɂ���B�g������1772�N�̃|�[�����h�����ɂ���ăv���C�Z�������̂ƂȂ�A���݂̓|�[�����h�̈ꕔ�ɕ��A���Ă���B�����I�ɂ̓h�C�c�l�������Ƃ�����B�������A�����͖����̊T�O�����m�ł͂Ȃ��A�s�s(Thornisch�]�g�����s��)�⍑��(Polnisch�]�|�[�����h����)�����̐l���̑����Ƃ��ďd�v������鎞��ł������B�|�[�����h�E���g�A�j�A���a���͒P�ꖯ���ɂ�鍑�����Ƃł͂Ȃ��A�|�[�����h���ɏ]�����������Ƃł��������߁A�|�[�����h�l�A���g�A�j�A�l�A�h�C�c�l�A�`�F�R�l�A�X���o�L�A�l�A���_���l�A�E�N���C�i�l�A�x�����[�V�l�A���g�r�A�l�A�G�X�g�j�A�l�A�^�^�[���l�Ȃǂ������ɊW�Ȃ���炵�Ă���A�|�[�����h�̎s�����������Ă���l�͊F�u�|�[�����h�l�v�ł������B�������̋��ʌ���̓��e����ƃ|�[�����h��ł���A�N���N�t��w�ő�w������Ă����邱�Ƃ���A�R�y���j�N�X�����퐶���ɍ���Ȃ����x�̃|�[�����h���b�����Ƃ��ł������Ƃ͐��肳��Ă��邪�A�{�l���|�[�����h��ŏ��������̂͌��ݔ�������Ă��炸�A�ނ����ۂɓ����b�ȏ�̃|�[�����h����ǂ̒��x�g�������͒肩�ł͂Ȃ��B
�@
�ނ̐��́u�R�y���j�N�X�v�̓��e����\�L�� Copernicus ����{��œǂ݉��������̂ŁA�|�[�����h��ł́u�R�y���j�N (Kopernik) �v�ƂȂ�B�|�[�����h��Łu�����v�̈Ӗ��B���Ȃ킿�ނ́u�����̃~�R���C(�j�R���E�X)�v�ł���B�����̈ꑰ�̃R�y���j�N�Ƃ̓|�[�����h�̃V���W�A�n���I�|�[�����ɂ���Â����R�̊X�R�y���j�L (Koperniki) �̏o�g�B�V���W�A�n����13���I�̃����S���ɂ��|�[�����h�N�U�ŏZ�������ĎU��U��ƂȂ邩�����x��ĎE����邩���Đl�����傫�������������߁A�|�[�����h�̓��n�̏���͕����̂��߂ɐ������瑽���̃h�C�c�l�ږ��������Ă���(�h�C�c�l�̓����B��)�B���̂Ȃ��ŃR�y���j�N�X�̕����̐�c(�̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ)���h�C�c�̊e�n�������Ă��āA���̂��߈ꑰ���h�C�c�����Ƃ��Ă������̂Ɛ��������B
�@
10�̎��A���������T���ȏ����l���������e���S���Ȃ�A��e�̃o���o���E���@�b�c�F�����[�f (Barbara Watzenrode) �͊��ɖS���Ȃ��Ă����B���̂��߁A����̏f���ł��郋�[�J�X�E���@�b�c�F�����[�f (Lucas Watzenrode) �����̎���A�R�y���j�N�X�ƌZ�����Ă��B���[�J�X�͓�������̗��C�i��(�J�m��)�ł���A��Ƀ��@���~�A (Warmia) �̗̎�i���ƂȂ����B�R�y���j�N�X�̌Z��A���h���[�A�X (Andreas) �̓|�[�����h���̃v���C�Z���̃t�����{���N(�h�C�c��: �t���E�G���u���N Frauenburg)�̃J�m���ƂȂ�A���o���o�� (Barbara) �̓x�l�f�B�N�g�C���@�̏C�����ƂȂ����B���̖��J�^���[�i (Katharina) �͎s�̕]�c�ψ��������o���e���E�Q���g�i�[ (Barthel Gertner) �ƌ��������B
�@
1491�N�ɃR�y���j�N�X�̓N���N�t��w�ɓ��w���A���̐����ȋO���v�Z���j��͂��߂čs���������ȓV���w�҂ŏ]��������Ƃ���Ă����V�����ɉ��^�I�Ȍ����������Ă����A���x���g�E�u���[�t�X�L�����ɂ���Ă͂��߂ēV���w�ɐG�ꂽ�B����Ƀj�R���E�X�����w�Ɉ������܂�Ă������Ƃ��A�E�v�T���̐}���قɎ�������Ă��铖���̔ނ̖{������M�����Ƃ��ł���B���ƌ�A�f���̌v�炢�Ő����̐E�ɂ������̕ۏ�A4�N�Ə����̊ԃg�����ɂ������ƁA1496�N����1503�N�ɂ����ė��w���A�C�^���A�̃{���[�j����w��p�h���@��w�Ŗ@��(���[�}�@)�ɂ��Ċw�є��m�����擾�����B����ɉ��������Ă����f���͔ނ��i�ՂɂȂ邱�Ƃ�]��ł������A�J�m���ƃ��[�}�@�ɂ��Ċw��ł���ԂɁA�ނ̉��t�ł��蒘���ȓV���w�҂ł���h���[�j�R�E�}���[�A�E�m���@�[���E�_�E�t�F�b���[���Əo��A���̒�q�ƂȂ����B
�@
�₪�ăm���@�[���̉e���ɂ��{�i�I�ɒn�����ɌX�|���A�V�����ł͎��]�~�ɂ���������Ă����V�̂̋t�s�^�����A�n���Ƃ̌��]���x�̍��ɂ�錩������̕��ł���Ɛ�������Ȃǂ̗��_�I���t�����s���Ă������B�������R�y���j�N�X�͘f���͊��S�ȉ~�O����`���ƍl���Ă���A���̓_�ɂ��Ă͏]���̓V�����Ɠ��l�ł���P�Ƀv�g���}�C�I�X�̓V�����������]�~�̐������炵���ɉ߂��Ȃ��B���ۂɂ͘f���͑ȉ~�O����`���Ă��邱�Ƃ́A���n�l�X�E�P�v���[�ɂ�蔭�����ꂽ(�����Ƃ��V�̂��~�^����`���Ă���Ƃ�������ɂ��A�V���w�҂͓V�̂̋t�s�^���̐����𔗂�ꂽ�̂ł���A���������v�����݂����݂��Ȃ������̂Ȃ炻�������V�̉^����T�����铮�@���瑶�݂��Ȃ������̂ł���A�R�y���j�N�X���~�^���ɂ�����������E�͂�ނȂ������Ƃ���]������)�B
�@
1526�N�ɂ̓N���N�t��w����̃u���[�t�X�L�����̓V���w�̍u���̓����̐e�F�Ő��w�҂̃x���i���h�E���@�|�t�X�L (Bernard Wapowski) ���|�[�����h�����ƃ��g�A�j�A������̔Ő}�S�̂̒n�}���쐬�����ہA�R�y���j�N�X�͂��̎��Ƃ���`�����B�����̎d�����������A�t�����{���N�̐����t�߂̓��œV�̂̊ϑ��E�����𑱂��A�V�������_�̑n���Ɍ������Ă����B�����1535�N�A�u�n���̓������v�Ɋւ���R�y���j�N�X�̏d�v�Ș_���̏o�łɌ����Ă̓��@�|�t�X�L�͗͂�݂��A�o�ł𐿂������Ă����E�B�[���̊W�҂֎莆�������ďo�ł̍Ñ�������Ȃǂ��Ă���B���@�|�t�X�L�͂��̎莆���o����2�T�Ԍ�ɑ��E�������߁A�_���̏o�ł����͂��邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@
���Ȃ̒n�����̔��\�ɂ��e�������ꂽ�R�y���j�N�X�́A�咘�w�V�̂̉�]�ɂ��āx�̔̔���1543�N�Ɏ������}����܂ŋ����Ȃ�����(�ގ��g�͊����������������鎖�����������ƌ����Ă���)�B����̓|�[�����h�̃t�����{���N�̑吹���ɖ������ꂽ�Ƃ݂��Ă������A�⍜�͊m�F����Ă��Ȃ������B�V���`�F�`����w�Ȃǂ̃`�[����2004�N���甭�@��i�߁A�吹���̐[����2���[�g���̏ꏊ����2005�N�āA�⍜�������B
�@
���̈⍜�͏ё���Ɠ��W�����݂��ɔ��Ɏ��Ă��āA����ƔN����قڈ�v���Ă����̂ŁA�⍜���R�y���j�N�X�̂��̂ł���\�������܂����B2008�N11���A�V���`�F�`����w�ƃX�E�F�[�f���̃E�v�T����w�Ƃ̋����ŁA���̈⍜�ƁA���̏ꏊ��4���I�ȏ���ۊǂ���Ă����R�y���j�N�X�̂��̂Ƃ����є��Ƃ�DNA�Ӓ���s���A���҂�DNA�̈�v�ɂ�肱�̈⍜���R�y���j�N�X�̂��̂ƍŏI�I�ɔF�肳�ꂽ�B�@ |
���u�V���̉�]�ɂ��āv�@
(���e����: Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI�A�p���: On the Revolutions of the Heavenly Spheres by Nicolaus Copernicus of Torin 6 Books)�@1543�N�ɏo�ł��ꂽ�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�̒n�������咣���������ł���B1512�N����s��ꂽ��5���e��������c�ɂ����ẮA�����̉��ǂɂ��Ă��c�_���ꂽ�B���̂Ƃ��ӌ������߂�ꂽ���̂́A1�N�̒����ƌ��̉^���̒m�����s�\���ł��������ߖ��̉������ł��Ȃ��������Ƃ�F�������R�y���j�N�X���A���z�n�̍\�������{����l���Ȃ��������̂ł���B1539�N�ɃQ�I���N�E���e�B�N�X���R�y���j�N�X�̒�q�ƂȂ�R�y���j�N�X�̎�e��ǂ݁A���N�e�B�X�̓V���w�̎t�̃��n�l�X�E�V�F�[�i�[�ɊT�v�𑗂�A1540�N�� Narratio�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�BNarratio�̕]���ƃ��N�e�B�X�̋������߂ɂ��w�V���̉�]�ɂ��āx�̏o�łɃR�y���j�N�X�͓��ӂ��A�ނ̎��̒��O�ɏo�ł��ꂽ�B
�@
���R�y���j�N�X�̉F��
�@
�R�y���j�N�X�I�]��ƌ������t������悤�ɁA�R�y���j�N�X (1473-1543) �̒n�������Ȋw�̔��W�ɋy�ڂ����e���ɂ͑傫�Ȃ��̂��������B�����R�y���j�N�X�͂�����ЂƂ̉����Ƃ��Ē�o���������ŁA���������Ď��ׂ��M�O�Ƃ͍l���Ă��Ȃ������炵���B�ނ͂��̐������[�}������h�����邱�Ƃ�����āA���O�ɂ͑�X�I�ɐ������邱�Ƃ����Ȃ��������A�n�������L�q���������u�V�̂̉�]�ɂ��āv���o�ł��ꂽ�̂́A���̎��̒��ゾ�����̂ł���B
�@
�R�y���j�N�X�͂����ɂ��Ēn�����ɓ��B�����̂��낤���B�n�������������w�҂̓R�y���j�N�X�����߂Ăł͂Ȃ��B���łɃM���V������ɃA���X�^���R�X���R�y���j�N�X�Ɠ����悤�Ȏ咣�������Ă������A14���I�ɂ̓p����w�̃I�b�J���h�̊w�҃j�R���X���n���̎��]���������Ă����B�R�y���j�N�X�����������Ɛт����邱�Ƃ͒m���Ă����炵���B
�@
�R�y���j�N�X������I�������̂́A�v�g���}�C�I�X�̉F���ςł͐����ł��Ȃ����������ؓI�ȃf�[�^�Ɋ�Â��Đ����������Ƃɂ������B�ނ́A��������͂邩�ɊȒP�A�P���ɐ����ł��鎖���ł��A�`���I�Ȑ����̂�����ɖ��������ɁA���������łȎ��ؓI�f�[�^�Ɋ�Â��ďؖ����悤�Ƃ���ԓx���т����B
�@
�Ƃ����Ă��A�R�y���j�N�X���K�����I�Ɠ����悤�ȈӖ������ɂ����ċߑ�I�ȉȊw���_�̑̌��҂ł������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�ނ̓s�^�S���X�I�A�V�v���g����`�I�ȋC�������L���Ă���A���̓_�ł͉ߋ��������������v�z�Ƃł��������B
�@
�R�y���j�N�X�̎���܂Ŏx�z�I�ł������v�g���}�C�I�X�̉F�����Ƃ͎��̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@
�܂��F���͍P���V�Ō���ꂽ�L���ȋ��̂ł���A��܌��f����G�[�e���ɂ���č\������Ă���A�����ɏ��X�̍P�����Ƃߍ��܂�Ă���B���ɁA���̗L���ȉF���̒��S�ɒn���������āA�P���V�͂��̒n���̎��������Ɉ�x��]���Ă���B����ɁA�n���ƍP���V�Ƃ̊Ԃɂ͗V���V����݂��Ă���B����͒n�����猩��ƁA���A�����A�����A���z�A�ΐ��A�ؐ��A�y���̏��ɁA�n���̎�����~��`���ĉ�]���Ă���B���̉�]�ɂ͈���Ɉ��̎����̂ق��ɁA���̂��̈��̎����������ĉ���������]������̂�����B
�@
���������̌n������悭�������邽�߂ɁA�v�g���}�C�I�X�̗��_�ł͐������̉~���������ꂽ�B���Ƃ��Ήΐ����n���ɋ߂Â����艓���������肷�錻�ۂ�������邽�߂ɁA�ΐ��̋O���̒��S���n���̒��S�ƊO�ꂽ�Ƃ���ɂ���A�ΐ��͂��̋O�������ɉ^�����邽�߂ɕ��G�ȓ���������̂��Ɛ��������B����𗣐S�~�Ƃ����B
�@
���ɁA�V���������ܗ����~�܂�����t�s�����肷�錻�ۂ�������邽�߂ɁA�V���̋O���̒��S���~����`���Ă���A�V���͂��̋O���ɂ����ĉ�]���邽�߂ɕ��G�ȓ���������̂��Ɛ��������B��������V�~�Ƃ����B
�@
�������ăv�g���}�C�I�X�����������~�̐���80�ɂ��Ȃ�A�F���̓�����������邽�߂ɂ́A���ɕ��G�Ȏ葱�����K�v�ł������B
�@
����ɑ��ăR�y���j�N�X�́A�P���V�̉�]��n���̎��]�ɂ���Đ��������B�����������Ɉ�x�P���V����]����̂́A�n�������]���Ă��邱�Ƃ̔��ʂ��Ǝ咣�����̂ł���B���ɗV���͑��z�𒆐S�Ɍ��]���Ă���A�n�������̗V���̂ЂƂ��Ǝ咣�����B
�@
�������ăR�y���j�N�X�̐��ł́A�v�g���}�C�I�X�̐����͂邩�ɒP���ɉF���̓���������ł��邱�ƂɂȂ����B�v�g���}�C�I�X���K�v�Ƃ����~�̐���30�Ɍ��炷���Ƃ��ł����B
�@
�����R�y���j�N�X�͈ˑR�Ƃ��āA�V�̂��L���ł����Đ_�ɂ���č��ꂽ�̂��ƍl���Ă����B�ނ͓V�̊w�҂ł���ȏ�ɁA�h�i�Ȑ_�w�҂ł��������̂��B
�@
�R�y���j�N�X�̐��ɂ́A���������̓�_���w�E����Ă����B�ЂƂ́A�n�������]����̂ł���A���̈ʒu�ɂ���čP���ɂ͎����Ƃ����ׂ����ۂ�������͂��ł���̂ɁA���ꂪ�F�߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ������B�R�y���j�N�X�͍P�����n���������܂�ɂ�����Ă��邽�߂ɁA�l�Ԃ̖ڂɂ͎������f��Ȃ��̂��Ǝ咣�������A����͂���Ӗ��Ő������l�����ł�������������Ȃ��B�����ł͊ϑ��@�킪����I�ɔ��W�����������ŁA���̍P���������ϑ������悤�ɂȂ��Ă���B
�@
��ڂ͕��̗̂������߂����Ă̖�肾�����B�����n�������]���Ă���̂Ȃ�A�����������̂͂܂��������ɂł͂Ȃ��A�������ꂽ�Ƃ���ɗ�����͂��Ȃ̂ɁA���ۂ͂����ł͂Ȃ��B���^�[�͂��̂��Ƃ����炩���āA�u�R�y���j�N�X�́A�n�Ԃ𑖂点�Ȃ����n�̂ق��������Ă���̂��ƐM����悤�Ȃ��҂ł���B�v�Ƃ̂̂������B���̓��͌�ɃK�����I�ɂ���āA�����̖@���̒��Ŏn�߂ė��H���R�Ɛ��������B
�@
�R�y���j�N�X�̐��͂��炭�̊ԁA�܂��߂ɂƂ肠�����邱�Ƃ��Ȃ���������ɁA�e���̑ΏۂƂ���邱�Ƃ��Ȃ������B���ꂪ�傫�Ȗ��������N�����̂́A�K�����I�̎���ɂȂ��Ă���ł���B�@�@
�@ |
 �@ �@
�����F�T���E�X�u�l�̂̍\���ɂ��āv���� 1543�N |
   �@
�@
|
Vesalius, Andreas.(1514-64)
�@
De humani corporis fabrica.
�@
���F�T���E�X�́A�x���M�[�̉�U�w�ҁA�O�Ȉ�ŁA���l�T���X�ő�̉�U�w�ҁB���F�T���E�X�́A23�ŃC�^���A�̃p�h���@��w�̋����ƂȂ�A�Ñォ�璆���ɂ����Đ�N�ȏ�����Ђ�ۂ��Ă����K���m�X�̊w�������ɂ���Č����w�E���A�ߑ��U�w�̊�b��z�����B���F�T���E�X�̂��̒����́A�����̌��Ђ���łȂ������̎��R���̂��̂̒����玖�������ݎ��A������ڍׂȐ}���ɂ����炷���Ƃɂ���āA�ߑ��U�w�̋��łȊ�b���m�����������łȂ�����������N�ɏo�ł��ꂽ�R�y���j�N�X�́u�V�̂̋O���ɂ��āv�ƕ���ŁA�ߑ�Ȋw�̐���������Â���L�O��I����Ƃ��Ȃ����B |
���A���h���A�X�E���F�T���E�X
�@
(Andreas Vesalius�A1514-1564 )�@��U�w�҂ň�t�A����ɐl�̉�U�ōł��e���͂̂���{�A�t�@�u���J���ƁgDe humani corporis fabrica�h(�l�̂̍\��)�̒��ҁB���F�T���E�X�͌���l�̉�U�̑n�n�҂ƌ�����B���F�T���E�X�̖��́A�o�T�ɂ���ăA���h���A�X�E���F�T�� (Andreas Vesal) ��A���h���A�X�E�t�@���E���F�Z�� (Andreas van Wesel) �Ƃ�������B
�@
���l���̏����Ƌ���
�@
���F�T���E�X�͓����_�����[�}�鍑�̎x�z���ɂ������A�u�����b�Z���̈�t�̉Ƃɐ��܂ꂽ�B���A�A���h���G�X�E�t�@���E���F�Z���́A�c��}�N�V�~���A��1���̎���G���@�����h�E�t�@���E���F�Z�� (Everard Van Wesel) �̎������ł���B�A���h���G�X�̓}�N�V�~���A���̖�t�Ƃ��Ďd���A��͂��̌�p�҃J�[��5���̏]�� (Valet de Chambre) �Ƃ��Ďd�����B�ނ͑��q���Ɠ`�ɏ]�킹�A�����̋K�͂ł������M���V����ƃ��e������w���邽�߂Ƀu�����b�Z���́u���L�������F��v(Brethren of the Common Life) �ɓ�������B
�@
1528�N�Ƀ��F�T���E�X�̓��[���@����w�ɋZ�|�擾�ׂ̈ɓ��w�������A1532�N�ɔނ̕���(�J�[��5����)�]�҂Ƃ��ĔC������A���F�T���E�X�̓p����w�ň�w����I�ɒNj����悤�ƌ��S��1533�N�Ɉڂ��Ă���B�����Ŕނ̓W���b�N�E�f���{��(���R�u�X�E�V���r�E�X�AJacques Dubois)�ƃW�����E�t�F���l��(�t�����X��ŁA�p���) (Jean Fernel) �̌��ŃK���m�X�̊w�����w�B���̎���ɉ�U�w�ւ̋�����傫�����A�܂��A�Z���g�E�C�m�Z���g��n�ō��������Ό������Ă����B
�@
�_�����[�}�鍑�ƃt�����X���퓬���n�߂��ׁA1536�N�Ƀp��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ胋�[���@���ɖ߂����B�����Ń��n�l�X�E���B���^�[�E�t�H���E�A���f���i�n (Johannes Winter von Andernach) �̌��Ō������C�����A���̔N�ɑ��Ƃ����B���F�T���E�X�̘_���gParaphrasis in nonum librum Rhazae medici arabis clariss ad regem Almansorum de affectum singularum corporis partium curatione�h�́A���W (Rhazes) �̑�9�̏��ɂ��Ẳ���ł���B�ނ͋����Ƃ̘_���̌�Ƀ��[���@��������܂łق�̂��炭�؍݂����B1536�N�Ƀ��F�l�c�B�A�ɂ��炭�ڏZ������A���m���擾�̌����̂��߂Ƀp�h���@��w�Ɉڂ�A1537�N�Ɏ擾�����B
�@
���ƌ�A���F�T���E�X�͂����Ƀp�h���@�ŊO�Ȋw�Ɖ�U�w�̋����ɔC�����ꂽ�B�s�T�ƃ{���[�j���ɂċq�����s�����B����܂ŁA�����̎��͎�ɁA�u�t�Ɏd�����������O�Ȃɂ�铮���̉�U�ɏ]���āA�K���m�X�̌ÓT�I�ȋ��ȏ���ǂނ��Ƃ���Ƃ��ċ������Ă����B�K���m�X�̎咣�����ۂɌ������悤�Ȏ��݂͂Ȃ������B����͘_���̗]�n�ȂǂȂ����̂������B���̈���ŁA���F�T���E�X�͋���̎�v�ȓ���Ƃ��ĉ�U���s�Ȃ��A���k�����̌Q�ꂪ�e�[�u�������͂ޒ��A�������g�Ŏ��ۂ̉�U������s�����B���n�̒��ڂ̊ώ@���B��̐M���ł����Ƃ����l���́A�����I�ȏK���Ƒ傫����������Ă����B
�@
���F�T���E�X�́A6�̑傫���`���ꂽ��U�}���Ƃ��āA���k�̂��߂ɔނ̎d�����ɕ`�������̂������Ă����B�����̊������������L���o����Ă���̂�m��ƁA1538�N�ɁgTabulae Anatomicae Sex�h�Ƃ����薼�ł��̑S�Ă��o�ł����B����ɑ����āA1539�N�ɃK���m�X�̉�U�w�Q�l���̍ŐV�ŁgInstitutiones Anatomicae�h���o�ŁA���ꂪ�p���ɓ͂��Ɣނ̈ȑO�̋����̈�l�͂��̔ł��U��������e���o�ł����B
�@
�܂�1538�N�ɂ́A�������������b���Ɋւ��鏑�Ȃ��o�ł����B����͂قƂ�ǂǂ�ȕa�C�ł��s�����ʓI�Ȏ��Âł��������A�ǂ����猌�����̂��Ƃ������ƂŊ���̈٘_�������킳��Ă����B�K���m�X��i�삷��Ñ�M���V�����ł́A�����ɋ߂����ʂ��猌����邪�A�C�X�����ƒ����̕����ł͏��ʂ̌����������ʂ��甲���Ă����B���F�T���E�X�̎�����̓K���m�X���x�����A��U�}��ʂ��Ă��̘_���𗠕t�����B
�@
1539�N�A�p�h���@�̍ٔ��������F�T���E�X�̎d���ɊS�������A���Y���ꂽ�ƍߎ҂̎��̂̉�U���\�ɂȂ����B�ނ͊Ԃ��Ȃ��ɍו��ɕx��U�}�������A����ׂ����m�ȍŏ��̃Z�b�g�����ꂽ�B�����̑����͈ϔC���ꂽ��Ƃɂ���č��ꂽ�̂ŁA����ȑO�ɍ��ꂽ���̂�肸���Ɨǂ��i���ł������B
�@
�{���[�j���؍ݒ���1541�N�ɁA�x�T���E�X�̓K���m�X�̌����̂��ׂĂ��l�ԂƂ������ނ��듮����U�w�Ɋ�Â��Ă����Ƃ��������𖾂炩�ɂ���(��U���Ñ�̃��[�}�ŋ֎~����Ĉȗ��A�K���m�X�́A����Ƀo�[�o���[�}�J�N������U���āA�ނ炪�l�ԂƉ�U�w�I�ɓ��l�ł���Ǝ咣���Ă���)�B�������Ĕނ̓K���m�X�́gOpera omnia�h�̒����ł��o�ł��A���g�̉�U�w���ȏ��������n�߂��B���F�T���E�X��������w�E����܂ŁA�����͎w�E���ꂸ�A�����ԁA�l�̉�U�w�����������b�Ƃ���Ă����B�������Ȃ���A����ł�����l�X�̓K���m�X���x�����A���炩�ȊԈႢ���Ƃ��ă��F�T���E�X�ɕ��S�����B
�@
���F�T���E�X�́A�X�ɘ_���������N�������B���x�̓K���m�X�����ł͂Ȃ������f�B�[�m�E�f�E���b�c�B (Mondino de Liuzzi) �����ăA���X�g�e���X (Aristotle) �����_�������B�����3�l���S���̋@�\�ƍ\���ɂ��Ď������ƍl���Ă������Ƃ͖��炩�ȊԈႢ�������B���Ƃ��A���F�T���E�X�͐S����4�̎�����Ȃ�A�̑���2�t�A�����Č��ǂ̎n�܂�͊̑��ł͂Ȃ��S���ł��邱�ƂɋC�t�����B���̃��F�T���E�X���K���m�X�̌����w�E�����L���ȗ�́A���{���͂�������̍�����o���Ă��āA2�ł͂Ȃ�(�K���m�X�͓�����U���炻���v���Ă���)���Ƃ̔����ƁA���t�͐S�[�Ԓ��u��ʉ߂��Ȃ����Ƃ̏ؖ��ł���B
�@
1543�N�Ƀ��F�T���E�X�́A�X�C�X�̃o�[�[���ɂ����Ė��̒m�ꂽ�����ƃ��[�R�v�E�J���[�E�t�H���E�Q�[�v���@�C���[ (Jakob Karrer von Gebweiler) �̎��̂̌��J��U���w�������B�O�Ȉ�t�����c�E�C�F�b�P���}�� (Franz Jeckelmann) �̋��͂̂��ƁA���F�T���E�X�͍��i��g�ݗ��čŏI�I�ɂ͂��̌�A���i���o�[�[����w�Ɋ�t�����B���̕W�{(�u�o�[�[���X�P���g���vThe Basel Skeleton)�͍��Ɏc��B��̃��F�T���E�X�̗ǂ���Ԃ̍��i�W�{�ł���A�܂����E�ōł��Â���U�w�W�{�ł�����B����̓o�[�[����w�̉�U�w�����قɌ��݂��W������Ă���B
�@
���t�@�u���J
�@
1543�N�Ƀ��F�T���E�X���o�ł���������悤���n�l�X�E�I�|���k�X (Johannes Oporinus) �ɗv�������A7�����琬��t�@�u���J�gDe humani corporis fabrica�h (�l�̂̍\��)�́A�l�̉�U�̊v�V�I�Ȏd���ŃJ�[��5���ɕ������A���̐}�ł̓e�B�e�B�A�� (Titian) �̒�q�ł���W�����E�X�e�t�@���E���@���E�J���J�� (Jan Stephen van Calcar) �ɂ���ĕ`���ꂽ�ƐM�����Ă���B���T�Ԍ�ɂ͊w���ׂ̈ɗv��ł̃G�s�g���gAndrea Vesalii suorum de humani corporis fabrica librorum epitome�h���o�ł��A����͍c��̑��q�̃X�y�C���̃t�F���y2���ɕ�����ꂽ�B
�@
���̎d���͂܂���U���肫�Ƃ������ƁA��ɑ̂́u��U�w�I�ȁv���_�ƌĂ��悤�ɂȂ������̂����������B���Ȃ킿�A���̓I�Ɋ튯��z�u���āA�{���I�ɕ����I�\���Ƃ��Ă̐l�Ԃ̓����\�����������B����́A�ȑO�ɗp����ꂽ�A�萯�p�̌����Ɠ��l�A�����K���m�X�A�A���X�g�e���X�I�����Ɋ�Â���U�w�̃��f���ƒ������ΏƓI�������B����I�ȉ�U�w���ȏ��������f�B�[�m (Mondino) �Ƃ׃����K�[ (Berenger) �ɂ���ďo�ł��ꂽ���A�ނ�̎d���͂����ƃK���m�X�ƃA���r�A�w���Ɋ�������̂������B
�@
���`���̏��̗ǂ��L�ڂ����łȂ��A3�̕��ʂ��琬�鋹����5��6�̐�ł��琬��卜�������A�܂��������̓����̑O��𐳊m�ɋL�ڂ����B�̑��̌��ǂ̕قɂ��ẴG�e�B�G���k (Etienne) �̊ώ@���ؖ������݂̂łȂ��A��Ö����L�ڂ��A�����đَ��̒����`�Ö��Ƒ�Ö��̊Ԃɒʉ߂���A����ȍ~�Ö��ǂƖ������ꂽ�ǂ������B�Ԃ͈݁A�B�������Č����ƌq�����Ă���̂��L�ڂ��A�H��̍\���̐��������_���n�߂ė^���A�q�g�̖Ӓ��̒����̏������ɋC�t���A���̏c�u�Ƌ����̗ǂ������A�����č��ł����F�̖����]�̉�U�̖L�x�ȋL�ڂ������B�ނ͉����͗������Ȃ������B�܂��A�]�_�o�̐������͎��_�o����̑Ƃ��A��O���܂ƁA��܂�掵�_�o�Ƃ݂Ȃ����Ƃŕ�����ɂ������̂ƂȂ��Ă���B
�@
���̎d���̒��ŁA���F�T���E�X�͂܂��l�H�ċz���L�ڂ������߂Ă̐l���ƂȂ����B
�@
���F�T���E�X�̎d���͎��ۂ̌����Ɋ�Â������߂Ă̂��̂ł͂Ȃ��A���̎���̏��߂Ă̎d���ł��Ȃ��������A�����ׂō��ݓ������}�ł̍�i���l�A�����Ă����������|�p�Ƃ��ނ玩�g�̉�U�ł͂�����ƒ���Ƃ��������������Ƃ����Ԃɖ����Ƃ��č�肩�����̂ł���B�C���ł��܂��Ȃ��o�ł���A���̎��������F�T���E�X�͈���҂̋L�^����m�����B�t�@�u���J�̏��ł��o�ł����Ƃ����F�T���E�X�͂܂�30�ł������B
�@
���c�鎘��Ǝ�
�@
�o�Ō�܂��Ȃ��A���F�T���E�X�͍c�鎘��Ƃ��čc��J�[��5���̋{��ɏ��҂��ꂽ�B�ނ́A�p�h���@�ŗ��C����\��ł���̂����F�l�c�B�A�̏�@�ɒm�点���B���f�B�`�Ƃ̌��݃R�W��1�����A�s�T�̊g����w�Ɉڂ�悤���������A���F�T���E�X�͂�������ۂ����B ���F�T���E�X�͋{���I�B�����ł́A�ނ������Ƃ��Ĕn���ɂ��鑼�̈�t�ƑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����(�����̈�p�͓��ȓI�����݂̂��w���A�O�ȓI�ȏ����͏������s���Ă���)�B
�@
���̌�12�N�ɓn���ă��F�T���E�X�͋{��Ƌ��ɗ������A�킢��n�㑄�����ł̉���̎��Â⌟����U��O�Ȏ�p�����A�����ē���̈�w�I�Ȏ�����������I�Ȏ莆���������B���̐��N�̊Ԃ�Radicis Chynae�Ƃ����̓����ɂ��Ă̒Z�������������A����͔ނ��g�p����̂�i�삷��̂͂�������̉�U�w�I�Ȕ�����i�삷����̂ł���B����́A���F�T���E�X�̎d���ɑ��āA�c��ɂ���Ĕނ���������悤�ɋ��߂�U���̋@��������o�����B1551�N�A�J�[��5���̓T���}���J�Ń��F�T���E�X�̎�@�̏@���I�܈ӂ�����R�����ϔC�����B���F�T���E�X�̎d���͕]�c��ɂ���ċ����ꂽ���A�U���͑������B4�N��ɔނ𒆏�����҂̈�l���A�l�Ԃ̑̂��̂��̂��K���m�X����������������ω������Ǝ咣����_�����o�ł����B
�@
�J�[��5�����ވʂ�������A���̑��q�̃t�F���y2���̌����Ń��F�T���E�X�͋{�쐶���𑱂����B����͐��U�ɓn��N���Ƌ{���̔���count palatine�ƂȂ�Ƃ������̂������B1555�N�ɁgDe Corporis�h�̉����ł��o�ł����B
�@
1559�N6��30���A�A����2���̖��G���U�x�[�g�E�h�E���@�����ƃX�y�C�����t�F���y2���̌����Ń����S�������K�u���G���E�h�E�����W���Ƃ̔n�㑄�����ŃA����2���͑��ɉE�ڂ��т��ꂽ�B���̎��ÂɃT���H�����́A�t�F���y2���Ƀ��F�T���E�X�̔h�����˗��A7��3���ɓ��������ÂɎQ��������A����2����7��10���Ɏ��S�����B
�@
1564�N�Ƀ��F�T���E�X�͍ȂƖ���3�l�Ńu�����b�Z���Ɍ��������A�Ƒ��ƕʂ�1�l�Ő��n����̗��ɏo���B�W�F�[���X�E�}���e�X�^ (James Malatesta) �w�����̃��F�l�c�B�A�͑��Ƌ��ɃL�v���X���o�čq�s�����B�G���T�����ɒ������Ƃ��A���F�T���E�X�̓��F�l�c�B�A�̋c���A�ނ̗F�Œ�q�̃t�@���s�E�X�̎��ɂ���ĐȂ����p�h���@�̋����̍��ɍĂђ������Ƃ�v�����鏑�M��������B
�@
�����Ԃ̃C�I�j�A�C�ł̋t���ŋꂵ�߂�ꂽ�̂��A���F�T���E�X�̓U�L���g�X���ō��ʂ����B�����Ŕނ͊Ԃ��Ȃ��a�C�Ŏ����A�P�ӂ̐l�����V���Ȃ���Έ�̂͑ł��̂Ă���Ƃ���ł������B���S������49�ł������B
�@
���F�T���E�X�̏���̗��͏@���ٔ��̃v���b�V���[�̂��߂��ƌ����Ă����B�����ł͂���͍������Ȃ��A����̓`�L��҂ɂ���ċp������Ă���B���̃X�g�[���[��de Saxe �Ƃ��ăJ�[��5���ƃv�����X�I�u�I�����W�̌��Ŏd���Ă����q���[�o�[�g�E�����Q (Hubert Languet) �ɂ���čL����ꂽ�B�ނ́A���F�T���E�X��������ꂽ�Ƃ��ɂ́A�܂��S���������Ă����X�y�C���̋M���̌������s�������Ƃ��A�ނɎ��Y�鍐�����@���ٔ��ɓ������A��1565�N�Ɏ咣�����B�����āA�t�F���y2���ɂ���Ă��̔��������n����ւƕς���ꂽ�A�Ƃ������ɂȂ��Ă����B���̘b�͉��N���o���āA���x���ĕ��サ�čŋ߂܂ŐM�����Ă����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���A���L���f�X�u�N�w�y�ъw�̑�z����S�W�v���� 1544�N |
   �@
�@
|
Archimedes.(B.C.287��-212)
�@
Opera, quae quidem extant omnia, multis iam seculis desiderata, ...
�@
�A���L���f�X�́A�I���O�̃M���V���̓V���w�ҁA���w�ҁA�����w�ҁB�Ñ�̂����Ƃ��V�˓I�Ȑ����Ȋw�҂ł���A���L���f�X�́A�V�`���A���̓s�s���ƃV�����N�T�C�ɐ��܂�A�I���O212�N�A���|�G�j�푈���Ƀ��[�}���ɎE���ꂽ�B�M���V������̏����̓p�s���X�ɏ����ꂽ���A���̃p�s���X�͎��C�Ɏキ�����͕ۑ����o���Ȃ��B�����ŌÑ㖖���璆���͂��߂ɂ����ăp�s���X�ɏ�����Ă���M���V���̒�����A��r�I�ۑ��̂����r�玆(�p�[�`�����g)�ɏ����ւ����Ƃ��s��ꂽ�B�������ď����ʂ��ꂽ�ʖ{�����Ƃɂ��Ċ����ň�����ꂽ�A���L���f�X�S�W�����s���ꂽ�̂�16���I�ɂȂ��Ă���ł���B�{���́A�g�}�X�E�Q�n�E�t�E���F�i�g���E�X�ɂ���Ċ����ň�����ꂽ���߂ẴA���L���f�X�S�W�ł���A�o�[�[���Ŋ��s���ꂽ�B |
�A���L���f�X�́A�Ñ�ő�̐��w�ҁA�����w�҂����āA�H�w�҂ƌ����ėǂ��ł��傤�B�ނ̓`�L�̓v���^�[�N�A�|���r�E�X���̑��̐l�̒���ɂ���Ēf�Ђ�m�鎖���o���܂����A����ɂ��Ɣނ̓C�^���A�̃V�`���A���Ő��܂�A�����̊w��̒��S�n�A�G�W�v�g�̃A���N�T���h���A�ɍs���A�����Ń��[�N���b�h�̒�q�B�ɋ������Đ��w���������A���[�N���b�h���w�̔��W�Ɋ�^���܂����B���̌�V�`���A�ɋA��A�����q�G����II��(�ނ͋��炭���̐e�ʂ������Ǝv���܂�)�Ɏd���A�����𑱂��A�قƂ�ǑS����������ŏ����܂������A�I���O 212�N�A�V�`���A�������[�}�鍑�ɍU�߂��Ċח������ہA���[�}�R�̕��m�ɎE����Đ��U���I���܂����B
�@
�ނ́u�A���L���f�X�点��v�̖��Œm����g���@���̑���X�̋@�B�����܂������A���ɁA�����ƃV�`���A�h�q�ׂ̈ɗl�X�ȍL��@�B�A���@�Ȃǂ̕�����l�Ă����ƌ����Ă��܂��B���̑����͂Ă��̉��p�ɂ��@�B�ŁA�Ⴆ�A�����̖��Ō������ꂽ���D���d���Đi���o���Ȃ������ہA���Ԃƃ��[�v��p���ĂĂ��̌��������p���đD��i�������A�u���Ɏx�_��^���Ă����A�n�������������Č�����v�Ƃ����L���ȃZ���t���������ƃv���^�[�N�͕��Ă��܂��B�܂��E�B�g���E�B�E�X�͂��́u���z�\���v�̒��ŁA�����̊����������ۂ����A�������Ɋm���߂���@�́A���̒��ł̏d�ʂ��v�邱�Ƃɂ��Ηǂ��Ƃ�������������ɔ������A�A���L���f�X�̕��̂̌������u�G�E���[�J(������)�I�v�Ƌ��Ƃ����G�s�\�[�h���q�ׂĂ��܂��B���̎��ɗp����ꂽ�͂�������͂Ă��̉��p�������̂ł��B�X�ɑ傫�ȉ��ʋ��ő��z�����W�߁A���[�}�̌R�D�ɂ��ĂĂ�������コ�����ƌ����A�A���n�[���́u���w��T�v�̔��G�ɂ͂��̗l�q���`����Ă��܂��B
�@
�ނ͂��̗l�Ȏ�X�̍H�w�Z�p�ɂ��ẮA���������c���܂���ł������A���ꓙ�̋Z�p�̗��_�I�����ƂȂ�͊w�A���w�ɂ��đ����̒�����c�����̂ł��B�܂�A�ނ͎��H������ɂ���ē���ꂽ���ʂ��A���x�͊w��p���Č����ɐ��w�I�ɏؖ����鎖�ɂ���āA�͊w�A���w�������W�������̂ł����B�ނ̂��̗l�Ȋw��I���@�͌㐢�ɍL���e����^���A�Ⴆ�K�����I���ނ̒���� 100��ȏ���A���L���f�X�����p���Ă��鎖�ʼn���l�ɑ傫�ȉe�����A�A���L���f�X�I�����Ŕނ̗��_�̏ؖ���^���Ă��܂��B�A���L���f�X�̑��ʂȋƐт̂����A���ɏd�v�Ȃ��̂́u�Ă��̔����̖@���v���m�����A�d�S�Ƃ����T�O��n�����A�×͊w�̊�b��z�������ƁA�~��������ň͂܂ꂽ�Ȑ��}�`�̖ʐς��u���s���@�v�Ƃ����}�`�ɓ��ڂ��鑽�p�`��ӂ��ׂ����čs�����Ƃɂ���āA�}�`�̖ʐς�~�����A���p�`�̖ʐρA���ɋߎ���������@���m���������ƂȂǂł��B�u���s���@�v�͌�Ƀj���[�g�����m��������ϕ��@�̊�b��^�������̂ł��B�������u���̂̌����v�̔����������ł��B
�@
�ނ̒���͈ꕔ����ꂽ���̂�����܂����A��Ƃ��ăr�U���`���鍑�̃R���X�^���`�m�[�v��(�C�X�^���u�[��)�ɁA�M���V����̃e�L�X�g���A�܂��A���r�A�ꌗ�ɁA�A���r�A��̃e�L�X�g���c��A����炪�����Ƀ��e����ɖ�ēǂ܂�Ă����̂ł��B���ꓙ�̘_���̏o�ł̍ŏ��̂��̂�1501�N�Ƀ��F�j�X�ŏo�ł���܂������A����͂ق�̒f�ЂŁA1503�N�ɓ��������F�j�X�Ń}�[�x�J�̖�́u�l�ӌ`�A�~�̋��ϖ@�v ���o�ł���܂����B�܂�1543�N�Ƀ^���^�[���A���}�[�x�J�̖��p���āu���ʂ̒ލ��ɂ��āv�Ɓu���̂ɂ��āA��ꕔ�v���o�ł��Ă��܂��B �������A�A���L���f�X�̋Ɛт��L�����[���b�p�ɕ��y���邫��������^�����̂�1544�N�̖{���̏o�łŁA�{���́u���̂ɂ��āv���܂�4�̒�����������S����̃M���V���ꌴ���ƃ��e���������߂Ă��܂��B�{���Ȍ�A�{���Ɋ܂܂�Ȃ��������̂��܂߁A�܂��l�X�̊w�҂������������āA�A���L���f�X�̒���̏o�ł����X�ƍs���A�L�����������l�ɂȂ����̂ł��B�ނ̗͊w�A���w�A���w�̉e�������l�́A�ꐡ�����Č��邾���ŁA�x�l�f�b�e�C�A�X�e���B���A�K�����I�A�P�v���[�A�g���`�F���A���C�v�j�b�c�A�j���[�g����������A�A���L���f�X�̈̑傳������܂��B�@ |
���A���L���f�X
�@
(Archimedes�A��: Ἀ�σԃǃ�ή��ς�ABC287-BC212 )�@�Ñ�M���V�A�̐��w�ҁA�����w�ҁA�Z�p�ҁA�����ƁA�V���w�ҁB�ނ̐��U�͑S�e��͂߂Ă��Ȃ����A�ÓT�Ñ�ɂ������ꋉ�̉Ȋw�҂Ƃ����h�������]���Ă���B�ނ������w�ɂ����炵���v�V�͗��̐×͊w�̊�b�ƂȂ�A�×͊w�̍l�@�͂Ă��̖{������������B�ނ͊v�V�I�ȋ@�B�v�ɂ��G�ŁA�V�[�W�E�G���W����ނ̖����������A���L���f�B�A���E�X�N�����[�Ȃǂł��m����B�܂��A���X�̕�����l�Ă������Ƃł��m����B
�@
��ʂɂ́A�A���L���f�X�͎j��܂�Ȉ̑�Ȃ�Ñ�̐��w�҂Ƃ����]�����Ă���B������p���ĕ������̖ʐς����߂���s�����@�A�~�����̋ߎ��l�v�Z�A�ނ̖��Łu�A���L���f�X�̗����v�Ƃ��Ă��㐔�����̒�`�A��]��(en)�̑̐ς̋��ߕ���A�吔�̋L���@���l�Ă��Ă���B
�@
�A���L���f�X�̓V���N�T�̐킢(en)�ɂ����āA�ނɂ͊�Q�������Ȃ��悤���߂�������Ă����ɂ��ւ�炸�A���a�����[�}�̕��m�ɎE�Q���ꂽ�B�}���N�X�E�g�D�b���E�X�E�L�P�����A���L���f�X�̕���Q���������`���ɂ��ƁA�ނ̕�͋��ʂɊO��(en)����~�����ۂ��Ă����B�A���L���f�X�́A���Ƃ���ɊO�ڂ���~���́A�̐ς̔�ƕ\�ʐς̔䂪�ǂ���� 2:3 �ł��邱�Ƃ𗧏��Ă���A�ގ��g���̏ؖ����ł����ʂ�������̂ƌ��Ȃ��Ă����B
�@
���������i�X�Ƃ͈قȂ�A�A���L���f�X�̐��w�Ɋւ���L�q�͌Ñ�ɂ����ĂقƂ�ǒm���Ă��Ȃ������B�A���N�T���h���A����`��������w�͑����A���L���f�X�����p���Ă����ɂ��ւ�炸��I�ɓZ�߂��Ȃ��������A530�N�Ƀ~���g�X�̃C�V�h���X���ҏW���A6���I�ɂ̓A�X�J�����̃G�E�g�L�I�X(en)�̒��삪�L���ǂ܂�A���߂Ĉ�ʂɒm����悤�ɂȂ����B�������܂������܂łɔp�ꂽ���A���l�T���X���ɂ͑����̉Ȋw�҂ɔ��z�̌�������ڂ������A1906�N�ɔ������ꂽ�A���L���f�X�E�p�����v�Z�v�g(en)����́A�ނ��������w�I�A���Ɏ���A�m���Ă��Ȃ��������@�̉ߒ��ɂ��Ă̏��邱�Ƃ��ł����B
�@
��
�@
�A���L���f�X�͋I���O287�N�A�}�O�i�E�O���G�L�A�̎����A���s�s�ł���V�V���[���̃V���N�T�Ő��܂ꂽ�B���̐��N�́A�r�T���`������̃M���V�A(en)�̗��j�ƃc�F�c�F�[�X(en)���咣�����A�A���L���f�X�͖�75�Ŗv�����Ƃ����ӌ����瓱����Ă���B�w���̌v�Z�x�̒��ŃA���L���f�X�́A���e���̓V���w�ҁu�y�C�f�B�A�X (Phidias)�v�ƍ����Ă���B�v���^���R�X�͒����w�Δ��`�x�ɂāA�V���N�T�����Ă����q�G����2���̉��҂������ƋL���Ă���B�A���L���f�X�̓`�L�͗F�l�ł�����w���N���C�f�X�������c���Ă��邪�A����͎����Ă��܂��ו��͓`����Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A�ނ͌��������̂��A�q���͂����̂��ȂǑS���킩��Ȃ��B�Ⴂ���A���L���f�X�́A�T���X�̃R�m����G���g�X�e�l�X�������G�W�v�g�̃A���N�T���h���A�Ŋw����C�߂��\��������B�A���L���f�X�̓T���X�̃R�m����F�l�ƌĂсA�w�w���_�x(�A���L���f�X�̖�����)(en)��w���̖��x�ɂ̓G���g�X�e�l�X�Ɉ��Ă�����������B
�@
�A���L���f�X�͋I���O212�N�A��|�G�j�푈�̂����Ƀ��[�}�̏��R�}���N�X�E�N���E�f�B�E�X�E�}���P�b���X��������R����2�N�Ԃ̍U�����o�ăV���N�T���̂����N�Ɏ��B�v���^���R�X���L���������ɂ��ƁA�܂��ɊX���苒���ꂽ���A���L���f�X�͍��̏�ɕ`�������w�}�`(en)�ɂ��ďn�l���Ă����B���[�}�̕��m�̓A���L���f�X���}���P�b���X�̌��֘A�s����悤���߂��Ă������A�A���L���f�X�͎v�Ē����Ƃ�������₵���B����ɕ��m�͌������A���������Ĕނ��E�����B�v���^���R�X�́A���̎E�Q�͘A�s�����O�̏o�����������\�����������Ă���A���̈�b�ɂ��ƁA�A���L���f�X�͐��}��B���^��ł����Ƃ���A��������ڂ̂��̂ƌ������m�ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ����B�}���P�b���X���R�̓A���L���f�X��L�\�ȉȊw�҂ƒm���Ă������ߊ�Q�������Ȃ��悤�w�߂��o���Ă����ɂ��ւ�炸�A�E�Q���ꂽ�Ƃ����m�点�Ɍ��{�����Ɠ`���B
�@
�A���L���f�X�Ŋ��̌��t�́u���̐}�`�����킳�Ȃ��ł���(���̉~�ނ�)�v(��: ��ή �ʃ̓� �у�ύς ��ύ�ȃɃ̓�ς ��ά�σ��ууÁA��: Noli turbare circulos meos�A�p: Do not disturb my circles)�Ɠ`������B����́A���m�����ݍ��ۂɃA���L���f�X�͉~�̐}��`���Đ��w�I�v�������炵�Ă���Œ����������߂ł���B�������A���̌����`���ɂ͏؋��͖����A�v���^���R�X�̋L�q�̒��ɂ����o���Ȃ��B
�@
�A���L���f�X�̕�͔ގ��g���D���w�I�ؖ����ނɑI��A�����a�ƍ����������Ɖ~���̃f�U�C�����Ȃ��ꂽ�Ɠ`����Ă����B�ނ��S���Ȃ��Ă���137�N��̋I���O75�N�A���[�}�̗Y�ى�(en)�}���N�X�E�g�D�b���E�X�E�L�P�����N�@�G�X�g���Ƃ��ăV�`���A�ɋ߂Ă������A�A���L���f�X�̕�ɂ��ĕ������B�ꏊ�͓`����Ă��Ȃ��������A�ނ͒T�������ɃV���N�T��Agrigentine��̋߂��A����ɂ�Ȃ݂��Ȃ��ꏊ�ɕ�������o�����B�L�P������𐴑|�������Ƃ���A�������͂����蕪����悤�ɂȂ�A�����܂ޔ蕶�����o����悤�ɂȂ����B
�@
�]������܂����A���L���f�X�̐l���̋L�^�́A�ނ��v���Ă��璷�����Ԃ��߂�����ɌÑネ�[�}�̗��j�Ƃ����ɂ���ċL�^���ꂽ�B�V���N�T�U�͂��L�����|�����r�I�X�́wUniversal History �x(���Վj)�ɂ�70�N�O�̃A���L���f�X�̎����L����Ă���A����̓v���^���R�X��e�B�g�D�X�E���E�B�E�X���o�T�ɗ��p���Ă���B���̏��ł̓A���L���f�X�l�ɂ���G��A�܂��X��h�q���邽�߂ɔނ�����삵�����Ƃ����y���Ă���B�@ |
�������Ɣ���
�@
�������̉���
�@
�ł��l�����Y�t�����A���L���f�X�̈�b�́A�`��̕��G�ȕ����̑̐ςׂ���@���v�������ꌏ�ł���B�E�B�g���E�B�E�X�ɂ��ƁA�q�G����2�����_�a�ɕ�[���邽�߂ɉ����ō�点�������̉���(en)�ɂ��āA�A���L���f�X�͋��H�E�l����̍����������Ă��܂����Ă��Ȃ����ǂ����m�F���˗����ꂽ�B���x�ׂ�Έ�ڗđR�����A����ɂ͉�����n�����đ̐ς��v�Z���₷���`�ɐ��`���˂Ȃ炸�A���ɂ������������ɂ͉�������ʂ̎�@���l����K�v�ɔ���ꂽ�B���̖�����������q���g���A���L���f�X�͓������ɓ����B�����ɓ���ƁA���ʂ������Ȃ邱�ƂɋC�Â����A���L���f�X�́A���͈��k�ł͗e�ՂɌ��e���Ȃ��������牤���𐅑��ɒ��߂�Γ����̐ϕ����ʂ��㏸���A�e�Ղɑ̐ς𑪂邱�Ƃ��ł���ƍl�����B�����ĉ����̏d�ʂ����̑̐ςŏ�����Ζ��x�����߂���B������d���y�������̋����������Ă���A�����̖��x�͓����̐ς̏������Ⴂ�B�A���L���f�X�́uEureka�v(��: ��ὕ�σŃȃ�!�A�u���[���J�I�v�u�����������I�v�̈�)�Ƌ��тȂ���A�����̂��܂蕞�𒅂�̂��Y��ė��Œʂ�ɔ�яo�����Ƃ����B�m�F��Ƃ͏�肭�s���A�����ɂ͋₪�������Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B
�@
���̉����̊��̘b�́A�`����Ă���A���L���f�X�̒���ɂ͌���ꂸ�A���L���f�X���v���Ă����200�N��E�B�g���E�B���X�������������ɋL�q����Ă���G�s�\�[�h�ł���B����ɁA��d���傫�����̑̐ς����̕��@�Œ��ׂ悤�Ƃ��Ă��A���ʕϓ������������ߑ���덷���ł��Ȃ��Ƃ����^�������Ă���B���ۂɂ́A�A���L���f�X�͘_�q�w���̂̌����x�Ŏ咣����A���L���f�X�̌����ł��闬�̐×͊w�̌����ʼn��������̂ł͂ƍl������B���̌����ł́A�����𗬑̂ɐZ�����ہA����͒u�������闬�̂̎��ʂƓ������͂�B����𗘗p���A�V���̈�[�ɒ݂邵�����ƃo�����X����铯�����ʂ̋���������[�ɉ����āA���Ƌ��𐅒��ɐZ����B�������ɍ������������Ĕ�d���Ⴂ�Ƒ̐ς͑傫���Ȃ�A�u�������鐅�̗ʂ������Ȃ邽�ߊ��͋��������͂����܂�B�����āA�V���͊���������ɌX�����ƂɂȂ�B�K�����I�E�K�����C���A���L���f�X�͂��̕��͂�p������@���l���t���Ă����Ɛ������Ă���B
�@
���A���L���f�B�A���E�X�N�����[
�@
�H�w����ɂ�����A���L���f�X�̋Ɛтɂ́A�ނ̐��a�n�ł���V���N�T�Ɋ֘A����B�M���V�A�l���q�Ƃ̃A�e�i�C�I�X���c�����L�^�ɂ��ƁA�q�G����2���̓A���L���f�X�Ɋό��A�^�A�A�����ĊC��p�̋���ȑD�u�V�����R�V�A���v (en)�̐v���˗������Ƃ����B�V�����R�V�A���͌Ñ�M���V�A�E���[�}�����ʂ��Č������ꂽ�ő�̑D�ŁA�A�e�i�C�I�X�ɂ��Γ������600�A�D���ɒ뉀��M�����i�V�I���A����ɂ͏��_�A�v���f�B�[�e�[�̐_�a�܂Ŕ����Ă����B���̋K�͂̑D�ɂȂ�ƐZ���������ł��Ȃ��Ȃ邽�߁A�A���L���f�X�̓A���L���f�B�A���E�X�N�����[�Ɩ��Â���ꂽ���u���l�Ă��A���܂�������~���o���H�v���{�����B����́A�~���̓����ɂ点���̔�݂����\���ŁA�������]������ƒႢ�ʒu�ɂ��鐅�����ݏグ�A��Ɏ����グ�邱�Ƃ��ł���B�E�B�g���E�B�E�X�́A���̋@�\�̓o�r�����̋뉀���邽�߂ɂ��g��ꂽ�Ɠ`����B����ł́A���̃X�N�����[�͉t�̂����łȂ��ΒY�̗��Ȃnjő̂���������i�ɂ����p����Ă���B
�@
�A���L���f�B�A���E�X�N�����[�́A�˂��\�������߂ċ@�B�Ɏg�p������Ƃ��Ēm���Ă���B�˂��\���̓A���L���f�X�̂悤�ȓV�˂ɂ����v�����Ȃ��Ƃ����l������A���ۂɒ����ł˂��\����Ǝ��ɋ@�B�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�u�˂��͒����œƎ��ɐ��ݏo����Ȃ������A�B��̏d�v�ȋ@�B���u�ł���v�Ƃ�������B
�@
���A���L���f�X�����
�@
�A���L���f�X�����(en)�Ƃ́A�V���N�T�h�q�̂��߂ɐv���ꂽ����̈��ł���B�u�V�b�v�E�V�F�C�J�[�v(the ship shaker) �Ƃ��Ă�邱�̑��u�́A�N���[����̘r���̐�ɒ݂邳�ꂽ����������܂����\���ŁA������܂��߂Â����G�D�Ɉ����|���Ęr���������グ�邱�ƂőD���X���ē]����������̂ł���B2005�N�A�h�L�������g�ԑg�uSuperweapons of the Ancient World�v�ł��ꂪ���삳��A���ۂɖ��ɗ��������Ă݂��Ƃ���A�N���[���͌����ɋ@�\�����B
�@
���u�A���L���f�X�̔M�����v�͉R���^����
�@
2���I�̒��q�ƃ��L�A�m�X�́A�I���O214�N-�I���O212�N�̃V���N�T���(en)�̍ۂɃA���L���f�X���G�D�ɉЂ��N�����Č��ނ����Ƃ������b���L���Ă���B�����I��A�g�����X�̃A���e�~�I�X�̓A���L���f�X�̕���Ƃ͑��z�M��背���Y(en)�������Ə��q�����B����͑��z�����������Y�ŏW�߁A�œ_��G�͂ɍ��킹�ĉЂ��N�����Ă������̂Łu�A���L���f�X�̔M�����v�ƌĂꂽ�Ƃ����B
�@
���̂悤�ȃA���L���f�X�̕���ɂ��Ă̌��y�́A���̎����W�����l�T���X�ȍ~�ɋc�_���ꂽ�B���l�E�f�J���g�͔ے�I�������������A�����̉Ȋw�҂����̓A���L���f�X�̎���Ɏ����\�Ȏ�@�Ō������݂��B���̌��ʁA�O����ɖ����ꂽ���⓺�̏������̑�p�Ƃ���Ƒ��z������W�I�̑D�ɏW�߂邱�Ƃ��ł����B����́A���z�F�Ɠ��l�ɕ����ʔ��ˊ�(en)�̌����𗘗p�������̂ƍl����ꂽ�B1973�N�ɃM���V�A�̉Ȋw�҃C�I�A�j�X�E�T�b�J�X���A�e�l�x�O�̃X�J���K�}�X(en)�C�R��n�Ŏ������s�����B�c5�t�B�[�g(��1.5��)��3�t�B�[�g(��1���[�g��)�̓��Ŕ疌���ꂽ��70����p�ӂ��A��160�t�B�[�g(��50m)��̃��[�}�R�͂Ɍ����Ă��x�j�����̎�����͌^�ɑ��z�����W�߂��Ƃ���A���b�őD�͉��サ���B�������A�͌^�ɂ̓^�[�����h���Ă������߁A���ۂ����R���₷�������\���͔ے�ł��Ȃ��B
�@
2005�N10���A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w (MIT) �̊w���O���[�v�͈��1�t�B�[�g(��30cm)�̎l�p����127����p�ӂ��A�ؐ��̖͌^�D��100�t�B�[�g(��30m)�悩�瑾�z�����W��������������s�����B�₪�Ĕ��_��̔�������ꂽ���A�܂�o�������߂�10���Ԃ̏Ǝ˂𑱂������D�͔R���Ȃ������B�������A���̌��ʂ���C��������������̎�i�͕���Ƃ��Đ��藧�ƌ��_�Â���ꂽ�BMIT�͓��l�Ȏ������e���r�ԑg�u�������`���v�Ƌ������T���t�����V�X�R�Ŗؐ��̋��D��W�I�ɍs���A���X�̍������Ƃ킸���ȉ����������B�������A�V���N�T�͓��݂ŊC�ɖʂ��Ă��邽�߁A���ʓI�ɑ��z���˂����鎞�Ԃ͒����Ɍ����Ă��܂��_�A�����Ђ��N�����ړI�Ȃ�Ύ������s�������x�̋����ł͉Ζ��J�^�p���g�Ŏˏo���鑾��̕������ʓI�Ƃ����_���w�E���ꂽ�B
�@
�����̑�
�@
�Ă��ɂ��ċL�q�����Â���́A�A���X�g�e���X�̗���������ꡊw�h��A���L�^�X�Ɍ����邪�A�A���L���f�X�́w���ʂ̒ލ��ɂ��āx�ɂ����āA�Ă��̌�����������Ă���B4���I�̃G�W�v�g�̐��w�҃p�b�v�X�́A�A���L���f�X�̌��t�u���Ɏx�_��^����B��������Βn�������Ă݂��悤�B(��: ��ῶς �ʃ̓� ��ᾶ �Ѓ�ῶ �ȃ�ὶ ��ὰ�� ��ᾶ�� �ȃǃ�ά�Ѓ�)�v�����p���ē`�����B�v���^���R�X�́A�D�������ɏd���ו����^�ׂ�悤�ɂ��邽�߂ɃA���L���f�X���u���b�N�Ɗ���(en)�@�\���ǂ̂悤�ɐv���������q�ׂ��B�܂��A�A���L���f�X�͑�ꎟ�|�G�j�푈�̍ۂɃJ�^�p���g�̏o�͂�x�����߂�H�v��A�I�h���[�^�[(�����v)�����������B�I�h���[�^�[�͎��ԋ@�\�����ԂŁA���܂��������𑖂閈�ɋ��ɗ��Ƃ��Ēm�点��\���������Ă����B
�@
�}���N�X�E�g�D�b���E�X�E�L�P���͖ⓚ�@�̒���w���Ƙ_�x(De re publica)�ɂċI���O129�N�ɂ�������b���̘^���Ă���B�I���O212�N�ɃV���N�T���̂������R�}���N�X�E�N���E�f�B�E�X�E�}���P�b���X�́A2��̋@������[�}�Ɏ����A�����B����́A���z�ƌ�������5�f���̉^�s��͕킷��V���w�p�@��ł���A�L�P���̓^���X��G�E�h�N�\�X���v�������l�̋@��ɂ��G��Ă���B�ⓚ�ł́A�}���P�b���X�͓Ǝ��̃��[�g���o�R���V���N�T���玝���A����1����茳�ɗ��߁A����1��̓��[�}�̔����̐_�a (���B���g�D�[�X�̐_�a�ATemple of Virtue) �Ɋ����B�L�P���́A�}���P�b���X�̋@��ɂ��ăK�C�E�X�E�X���s�L�E�X�E�K���X(en)�����L�E�X�E�t���E�X�E�t�C���X(en)�ɐ������鉺����c���Ă���B
�@
Hanc sphaeram Gallus cum moveret, fiebat ut soli luna totidem conversionibus in aere illo quot diebus in ipso caelo succederet, ex quo et in caelo sphaera solis fieret eadem illa defectio, et incideret luna tum in eam metam quae esset umbra terrae, cum sol e regione.
�@
��F�K���X���������ƁA�V��Ɍ����Ă������̑��u��ʼn��x����]���N��A�������z��ǂ����B�����Č��Ƒ��z���꒼���ɕ��ԂƂ���ł͌��̉e���n���ɗ����A���H���Č����ꂽ�B
�@
����͂܂��Ƀv���l�^���E�������z�n�V�̐����ł���B�A���N�T���h���A�̃p�b�v�X�́A����ł͎���ꂽ�A���L���f�X�̌��e�wOn Sphere-Making�x�ł����@��̐v�ɂ��ĐG��Ă���Əq�ׂ��B�ߔN�A�A���e�B�L�e�B�����̋@�B��M���V�A�E���[�}�̌ÓT����ɓ����ړI�Ő��삳�ꂽ�@�B�ނ̌������s���Ă���B�����́A�ȑO�̓I�[�p�[�c������Ă������A1902�N�ɔ������ꂽ�A���e�B�L�e�B�����̋@�B��ʂ��āA�Ñ�M���V�A����ɂ͋@�\�̏d�v�����ɓ����鍷�����u�̋Z�p�͏[���Ɏ��p�\�Ȉ�ɒB���Ă����Ɗm�F���ꂽ�B
�@
�����w
�@
�@�B��u�̐v�Œ����ł��邪�A�A���L���f�X�͂܂����w�̕���ɂ��傫�ȍv�����c�����B�v���^���R�X�́w�Δ��`�x(�u�p�Y�`�v)�ɂāA�u��(�A���L���f�X)�͏����Ȃ�v���ɂ��ׂĂ̈���Ƒ�]�𒍂��A���Ȏ��p�I���p��_�y�������Ƃ͊F�����ƌ������v�ƋL�����B
�@
�A���L���f�X�́A����Ō����ϕ��@�Ɠ�����@�Ŗ������𗘗p���Ă����B�w���@��p����ނ̏ؖ��ł́A�������݂��邠��͈͂����肷�邱�ƂŔC�ӂ̐��x�ʼn��邱�Ƃ��ł����B����͎��s�����@�̖��Œm���A�~������(�p�C)�̋ߎ��l�����߂�ۂɗp����ꂽ�B�A���L���f�X�́A�ЂƂ̉~�ɑ��ӂ��ڂ��Ȃ��炻�������ݓ����傫�ȑ��p�`�ƁA�~�̒��Œ��_���G��Ȃ��炷���ۂ���܂鏬���ȑ��p�`��z�肵���B����2�̑��p�`�͕ӂ̐��𑝂₹�Α��₷���A�~���̂��̂ɋߎ����Ă䂭�B�A���L���f�X��96�p�`��p���ĉ~���������Z���A�ӂ��̑��p�`���炱���31⁄7(��3.1429)��310⁄71(��3.1408)�̊Ԃɂ���Ƃ������ʂ��B�܂��ނ́A�~�̖ʐς͔��a�ł��鐳���`�ɉ~�������悶���l�ɓ��������Ƃ��ؖ������B�w���Ɖ~���ɂ��āx�ł́A�C�ӂ�2�̎����ɂ��āA����̎��������x���������킹��(���鎩�R�����|����)�ƁA�K�������ЂƂ̎��������邱�Ƃ������A����͎����ɂ�����A���L���f�X�̐����ƌĂ��B
�@
�w�~���̑���x�ɂăA���L���f�X��3�̕�������265⁄153(��1.7320261)��1351⁄780(��1.7320512)�̊ԂƓ������B���ۂ�3�̕������͖�1.7320508�ł���A����͔��ɐ��m�Ȍ��ς��肾�������A�A���L���f�X�͂��̌��ʂ����@���L���Ă��Ȃ��B�W�����E�E�H���X�́A�A���L���f�X�͌��_�����������A�㐢�ɑ��ĕ��@��������������o�����悤�Ƃ����̂ł͂ƍl�@���Ă���B
�@
�w�������̋��ϖ@�x�ŃA���L���f�X�́A�������������Ő�ꂽ�����̖ʐς��A�������ƒ����̌�_�ƒ����ƕ��s�Ȑڐ����ڐG����3�_�_�Ƃ���O�p�`�̖ʐς�4⁄3�{�ɂȂ邱�Ƃ��ؖ������B����́A���������ƌ���(en)��p����B�ŏ��̎O�p�`�̖ʐς�1�Ƃ��A���̎O�p�`��2�ӂ�����(en)�Ƃ��A�������̌��Ԃɓ��l�Ȏ�i��2�̐V�����O�p�`��z�肷��ƁA���̖ʐς̘a��1/4�ƂȂ�B������ɌJ��Ԃ��ĕ������̐ؕЂ����s�����ƁA�ʐς́A�E�E�E�E�ƂȂ�B
�@
�w���̌v�Z�x�ł́A�A���L���f�X�͉F����Ԃ����ł��ׂď[�U����Ƃ������A�ʂ����ĉ������K�v���Ƃ������Z�ɒ��B�W�F�[����(en)(�q�G����2���̑��q)���n�߂��̂悤�Ȑ��͖����ƌ�����c��Ȃ��̂Ƃ����������Ȃ����A�A���L���f�X�̓~���A�h(en)(��: �ʃ҃σ�άς)�Ƃ����Ñ�M���V�A��10,000��\���P�ʂ����ɑ吔�P�ʂ�ݒ肵�A�ŏI�I�ɉF���߂鍻�̐���8�r�M���e�B���I�� (vigintillion) = 8�~1063(1000�ߗR��)�ƌ��_�Â����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���A�O���R���u�����ɂ��āv���� 1556�N |
   �@
�@
|
Agricola, Georgius(1494-1555)
�@
De re metallica.
�@
�A�O���R���́A�h�C�c�̍z�R�w�Ҥ�n���E�z���w�ҁA�l���w�ҁA��ҁB���C�v�`�q��w�œN�w�A�_�w�A����w���w�сA�ꎞ�c���B�J�E�̃��e����w�Z�ŋ��������A�Ăу��C�v�`�q��w�ɋA��A�l���w�҂Ƃ��ėL���ɂȂ����B��Ɉ�w�ɓ]���C�^���A�ŏC�Ƃ��A�x�[����(�{�w�~�A)�̍z�R�����A�q���X�^�[���ɋA��A��҂��ƂƂ���T��A�U�N�Z����x�[�����̏��z�R�A�n���A�z���̌������n�߂��B���̌�A�P���j�b�c�Ɉڂ��Ă���������𑱂��A����珔�w�̊�b��z���A�����̏��������B�{���͔ނ̎���o�ł���A�����̍z�R�A����A�z���A��A�n�����Ɋւ���m���̏W�听�ŁA�L�x�ȑ}���G�Ƒ��ւ��āA18���I�ɂ�����܂ŋߑ�I�Y�Ƃ̖u���ɑ傫�ȉe����^�����B�S12��(���{1��)��273���̖ؔʼn悪����B |
���Q�I���N�E�A�O���R��
�@
(Georg Agricola�A�Q�I���M�E�X�E�A�O���R���AGeorgius Agricola�A�{�� �Q�I���N�E�o�E�G���AGeorg Bauer�A1494-1555)�@�h�C�c�̍z�R�w�ҁA�z���w�ҁA�l���w�ҁA���[1]�B�u�z�R�w�̕��v�Ƃ��Ēm����B�ނ̖{���ł���o�E�G�� Bauer �́u�_�v�v�̈Ӗ��ł���AAgricola �͂��̃��e���ꖼ�B�咘�Ɂw�z�R���x(De re metallica)������A�T�z�p�����p�A�z���A�z���A�f�w�ȂǂɊւ���L�q������[1]�B�����̍z���ɂ��Ă̋L�q������B�z�R�����o�ł���O�ނ́w���̖{���ɂ��āx�A�Ƃ����{�������Ă���A�����̈╨�Ƃ��Ă�����A�z���̓���Ӓ�ō������s���Ă��鏔�������L�ڂ��Č㐢�Ɋ��^���Ă���B��\���1533�N������ҏW����1550�N�Ɋ��������S12�����烉�e����ō\�������w�f�E���E���^���J�x(en:De re metallica)�ł���B�܂��A���{�ł͎O�}�������|�A���s����Ă���B���ۂɍz�R�œ����l�X�̌o���┭���A�������Ȋw�̌��t�Ɏ����Ă����A�ЂƂ̐V�����̌n��n�o�����A�O���R���́A���̂悤�Ɏ��R����Ƃɖ������Ă������߁A�B���p�ȂǓ�����ے肵�A�y�̂��Ă����B
�@
��
�@
1494�N3��24���A�h�C�c�̃U�N�Z���O���E�J�E(en:Glauchau)�ɐ��܂ꂽ���̂́A�c�����ɂ��Ă͂悭�������Ă��Ȃ��B�c���B�b�J�E�̃��e����w�Z�Ŋw�сA20�Ń��C�v�c�B�q��w�ɓ���A�M���V������w�B
�@
1518�N�A�c���B�b�J�E�ŃM���V���ꋳ�t�ɂȂ邪�A��Ƀ��C�v�c�B�q��w�̍u�t�ƂȂ�B�A�O���R����30�̎��ɃC�^���A�֗��w���p�h���@�A�x�l�c�B�A�A�{���[�j���̑�w�ň�w�A���w�A����w���w�B�܂��A�x�l�c�B�A�ň���Ƃ̕��Ə̂����A���h�D�X�E�}�k�e�B�E�X��m��B����Z�p���w�Ԃ��߂Ƀ~���m�ɂ���K���X�H��ɂ��K�ꂽ�B
�@
1527�N����1531�N�ɂ����ăC�^���A���A���r���A�{�w�~�A�̃��A�q���X�^�[���̈�҂ƂȂ�A���A�q���X�^�[���ōz�R�w�����������B1530�N�ɍz�R�w�Ɋւ���w�x���}�k�X�x�����B
�@
1531�N����1535�N���A�P���j�b�c�ɈڏZ���A�����𑱂���B1533�N���A�O���R���̑�\��ł���w�f�E���E���^���J�x���͂��߂�B1546�N�ɂ̓P���j�b�c�̎s���ɔC�����ꂽ�B
�@
�������A 1555�N11��21���Ƀh�C�c�_���푈��@�����v�ɉ�����A���k�Ƃ̌��_�̍Œ��ɔ]�����œ|��A���S�����Ƃ����B�@ |
���ŏ��̒n�w�� / �A�O���R���́w�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āx(1546�N)
�@
����̐��ł������u�_�v�v(Bauer) �����e���ꉻ�������u�A�O���R���v (Agricola) �ōL�����ɒm����Q�I���O�E�o�E�A�[ (Georg Bauer, 1494-1555) �́A���̍z�R�Z�p�Ɋւ���S�Ȏ��T�I�ȑ咘�w�f�E���E���^���J�xDe re metallica (�o�[�[���A1558�N) ��z���w���w���@���̖{���ɂ��āxDe natura fossilium (�o�[�[���A1546�N) �ɂ���Ēn�w�̋ߑ�I�Ȋ�b��z�����l���Ƃ��č����]������Ă���B���̓�̋L�O��I�Ȓ���̉A�ɉB��ė��j�ƒB�ɕs���ɉߏ��]������Ă���̂��A1544�N�ɏ�����A�ނ̑��̒n�w�I�Ȓ���Ƌ��ɏo�ł��ꂽ�w�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āxDe ortu et causis subterraneorum (�o�[�[���A1546�N) �ł���[2]�B�w�f�E���E���^���J�x����ɍz�R�Z�p�������A�w���@���̖{���ɂ��āx���z���̑̌n�������L�q�E���ނ𒆐S�ۑ�Ƃ��Ă����̂ɑ��A�w�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āx�͑��R�����A�ΎR�A�n�k�A����A�n�����A�z��������̌`���̌����𒆐S�ɘ_�q���Ă���A�����ɂ�����ŏ��̐^�̈Ӗ��ł̑����I�Ȑ��n�w���ƈʒu�t���邱�Ƃ��ł���B
�@
�n�����E�Ɋւ���A�O���R���̍ŏ��̒���w�x���}�k�X�A���邢�͍z���E�ɂ��āxBermannus sive de re metallica (�o�[�[���A1530�N) �͑�l����`�҃��b�e���_���̃G���X���X�̏^����Ȃǂ��ĕ��w��i�Ƃ��Ẳ��l���������A�Θb�҂䂦�ɑ̌n�I�Ȑ�发�Ƃ͌������A�����ɂ��z���E�����ւ̗U���̏��Ƃ��������ۂ߂Ȃ��B����ɑ��āA�w�x���}�k�X�x�ȍ~�̖�15�N�Ԃɂ킽��z�R�n�т̒���t�Ƃ��Ă̊�����ʂ��čz���E�Ɋւ���m���ƌo����~�ς����������ʂł�����n�w���Q�̕M��������̂��A�w�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āx�Ȃ̂ł���B�{���́A�w�f�������^���J�x�Ɏ���A�O���R���̈�A�̍�i�̊�b��z���Ă���A�܂��ɔނ̒n�����E�ς��č\������ۂ̌��ƂȂ钘��ł���B�����m�蓾����n��n�����E���������Ñ�E�����̒���Ƃ̋c�_���E���͂������w�҂Ƃ��Ă����łȂ��A�z�R��҂Ƃ��čz�v�B�̎��a�ƑΛ����A�z�R�o�c�ɓ����܂ł������n�̌o���E�ώ@���瓾���L�x�Ȓm���������ۉƂƂ����A�O���R������{����ʂ��ē����Ɋώ@���邱�Ƃ��ł���B�܂��A���C�v�j�b�c�́w�v���g�K�C�A�xProtogaea (1691�N�����M) �ɂ܂ŋy�� (�����ߑ�ƌĂԂ̂������ł��낤) ���l�T���X�E�o���b�N���̒n���̗��_�ɂ�����c�_�E�����Ώۂ̎����Ƃ������w��Ƃ��Ă̘g�g�݂��o�����̂��{���Ȃ̂ł���B�@
�@
�z�Y�����L���ŌÂ�����̍z����������ł������{�w�~�A�R�n�n���̏o�g�ł���A�O���R���͈�t�Ƃ��Ă̋�����A���ɌÑ�M���V�A�E���[�}�̌ÓT�I�Ȓ�����w�I�E���@�w�I�Ɍ������郋�l�T���X���ɃC�^���A�𒆐S�ɗ��s����������u�l����`��w�v�̉e���������Ă����B�]���āA�ނ͓����̐l����`�I�Ȏ�@�Ɋ�Â��ČÑ㌠�Ђ̃e�N�X�g���d�_�I�ɋᖡ����c�_�W�J������Ă���B�T���ƂȂ�������́A�Ñ�ł̓A���X�g�e���X�́w�C�ۘ_�x�A�e�I�t���X�g�X�́w�Ηޘ_�x�A��v���j�E�X�́w�������x�A�Z�l�J�́w���R�����x�A�f�B�I�X�R���f�X�́w�}�e���A�E���f�B�J�x���ł���A�����ł̓A���B�Z���i�́w�Ηނ̋ÌłƋÌ��ɂ��āx�ƃA���x���g�D�X�E�}�O�k�X�́w�z���_�x���ł���B�w�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āx�́A�܂̏�����Ȃ��Ă���B�n�����≷��A�z��A��A�͐�◤�C�̌`���̌����ƃ��J�j�Y������������ꏑ�A���R������n���M�A�ΎR�A�n�k�����Ƃ�����A�z���̍z���Ɠy�ށE�ÌŊ�ނ̌`������������O���A�Ηނ̌`������������l���A�����Ƃ��̍z���̌`��������������ł���B���ɁA�z���ނ̌`���Ɋւ���㔼���ł́A�����z���w�̋��l�A���x���g�D�X�E�}�O�k�X�����̋c�_�Ώۂ̒��S�ɐ����āA�O�ꂵ���ᔻ�������Ă���B�ȉ��A���̌㔼���Ɋւ��ď����Љ�悤�B
�@
�A�O���R���������l���@�ɂ��z������ (�y�ށA�Ì��`�ށA�ΗށA������) �́A18���I�̍z���w�ɂ܂ő傫�ȉe����^���邪�A���ł����ނ◰���ނ���Ɋ܂ދÌ��`�� succi concreti �Ƃ����V�����T�O�̒�o�����ڂ����[3]�B���̕��ޖ@�̍������x���Ă���̂́A�z���̐����_�ł���B�A�O���R���́A�S�Ă̍z�������Ƃ��ƍz�����́u�`�vsuccus ���Ì��������̂ƍl���Ă���B�Ì��`�ނ����ł͂Ȃ��A������Ηނ���{�I�ɂ́A���ꂼ��̎�ɌŗL�̏`���Ìł��ďo�����Ƃ�����ł���B�����̋c�_�̓��ɖڋʂƂȂ�̂��A�u�Ή��`�vsuccus lapidescens �Ƃ����T�O�ł���B�u�Ή��`�v�͎��炪�Ìł��čz���ɂȂ邾���ł͂Ȃ��A���̓��A�����܂ނ�������̂����̐ڐG�ɂ��z��������Ƃ������̂ł������B�܂�A�A�O���R���́A���́u�Ή��`�v�̗��_�ɂ���ĉ��̌`���̎d�g�݂�������悤�Ƃ����̂ł���B���̗��_�̖{���Ƃ��̌���ɂ��Ă͑��̏ꏊ�Ŗ��炩�ɂ����̂ł����ł͏ڏq���Ȃ����A16���I�ɂ̓A�O���R���ɋ����e�������h�C�c�̍z���w�ҒB�����ł͂Ȃ��A�J���_�[�m (Girolamo Cardano) ��t�@���s�I (Gabriele Falloppio)�A�`�F�U���s�[�m (Andrea Cesalpino) �Ƃ������C�^���A�̑厩�R�w�ҒB�����̗��_������Ă������Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ�����[4]�B
�@
���̂悤�ȍz���`���_�Ɍ��炸�A�ΎR��n�k�A�n�����A���Ɋւ���A�O���R���̋c�_�́A�����ߑ�̒n�w�j��ɂ����Ĕ��ɏd�v�ł��邱�Ƃ��������A�����ŏ��̑����I�Ȑ��n�w���Ƃ��Ắw�n���̎����̋N���ƌ����ɂ��āx�̑��̌����҂ɂ�邳��Ȃ錤�����ە����Ė{�e����鎖�ɂ�����[5]�B
�@
��
�@
[1] ���F�[�W����w(�x���M�[)�Ȋw�j������ �q���������BEmail : jzt07164@nifty.ne.jp
�@
[2] �{���������������͔��ɏ��Ȃ��B�h�C�c���ɂ͖�Ҏ҂ɂ�镶���w�E�n���w�I�l�@���t�^����Ă��邪�A�܂Ƃ܂��������Ƃ͂����Ȃ��BG. Agricola, Schriften zur Geologie und Mineralogie I : Epistula ad Meurerum ; De ortu et causis subtennaneorum libri V ; De natura eorum quae effluunt ex terra libri IV, eds. Georg Fraustadt & Hans Prescher (Georg Agricola-Ausgewählte Werke, 3), Berlin, VEB, 1956, pp.188-211. ���ɋ����`���_�Ɋւ������̕��͂ɂ��ẮA�ȉ��Q�� : R. Halleux, �g La nature et la formation des métaux selon Agricola et ses contemporains �h, Revue d�fhistoire des sciences, 27 (1974), pp. 211-222.
�@
[3] �A�O���R���̍z�����ނ̉e���ɂ��Ă͈ȉ��Q�� : J. Schroeter, �g Georg Agricolas Mineralsystem und sein Nachleben bis ins 18. Jahrhundert �h, Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen, 37 (1957), pp. 198-216; C. P. St Clair, The Classification of Minerals: Some Representative Systems from Agricola to Werner, Ph. D. diss., University of Oklahoma, 1966; D. R. Oldroyd, From Paracelsus to Haüy : The Development of Mineralogy in its Relation to Chemistry, Ph. D. diss., University of New South Wales, 1974; R. Laudan, From Mineralogy to Geology, Chicago, Chicago University Press, 1987.
�@
[4] �ْ� : Le concept de semence dans les théories de la matière à la Renaissance de Marsile Ficin à Pierre Gassendi, Turnhout (Belgium), Brepols, �ߊ�, �̃A�O���R���ɂ��Ă̑�5�͂��Q�ƁB���̏͂�����ρE�M���_���u�T���S�`���̌Ñ�_�b�ƃA�O���R���̐Ή��`���_�̒a���v���������ł���B
�@
[5] ����h�C�c�����Q�l�ɂ����M���n���w�j���b��L�O���ƂƂ��ĕ����̌����҂ɂ�鋤���v���W�F�N�g�̌`�Ŏ��������邱�Ƃ��{���ɂ͑��������Ǝv����B�@ |
�����C�v�j�b�c�ȑO�̒n�w�j�����̉ۑ�
�@
�M�҂́A���������ߑ�̕���(���ɍz��)�̉Ȋw�ɂ�����u��q�v�̗��_�Ɋւ��錤���Œn�w�Ɋւ��镶���𑽂����͂���@��Ă���(3)�B����̔��\�ł́A���Ƀ��l�T���X������1691�N���Ɏ��M���ꂽ�ƍl�����郉�C�v�j�b�c�̒n�w���w�v���g�K�C�A�x�̐����܂ł́A�ߑ�Ȋw�̌`�����Ƃ����鎞��̒n������ - �u�n�����E�v - �ɂ��Ă̎v�z�������ɓW��J����Ă����������l�����čs����ŁA���コ��Ɍ������Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����̉ۑ�_�ɂ��ĊT�������B���̍ہA����Ȋw�̔��W�ɂƂ��Ē��ړI�ɏd�v�ł��������̂łȂ��A���̓����̐l�ԂɂƂ��ďd�v�ł���������Q�Ɍ������Ă鎖�ɏd�_��u�����B
�@
���l�T���X���ƈ�ʂɏ̂����14-15���I�̃C�^���A�Ɂu�l����`�v�ƌĂ��Ñ�M���V�A�E���[�}�̒���Ƃ̌ÓT�ɑ��镶���w�I�����@�w�I�Ȏu�����������������������B�l����`�ҒB�̊�����ʂ��āA�Ñ�̕����ɑ���m�������債�A���I���W�i���ɋ߂��e�N�X�g����ɓ���悤�ɂȂ����B�Ƃ�킯�A�f�B�I�X�R���f�X(Dioscorides)�̈��p�{�����w�}�e���A�E���f�B�J�x(Materia medica)�Ɉ�t�B�̊S�͏W�܂����B�A�������ɗ��܂炸�A���R���̈��I���p�̊ϓ_����Ñ�l�̋L�����z���Ǝ��ۂ�(���ɃA���v�X�Ȗk�ōz�v�B�̊ԂŒm���Ă���)�z���E�̕����Ƃ̑Ή���m��K�v����������悤�ɂȂ����B���̗v���ɂ��������������̂��A�{�w�~�A�R�n�̍z�R�n�т̈�҂ł������Q�I���O�E�A�O���R��(Georg Agricola)�ł������B
�@
�ނ́A�����̑�w����ŕW���I�������A���X�g�e���X��`�̎��R�w���w��A��w���w�Ԃ��߂ɃC�^���A�ɗ��w���A�������ɂ߂Ă����l����`�I�Ȏ�@���w�сA���F�l�c�B�A�ł̓q�|�N���e�X�̒���W�̕ҏW�Ȃǂɂ�������������B�ނ̒��쒆�œ��ɗL���Ȃ̂́A�z�R�Z�p�ɂ��Ă̕S�ȑS���I�ȏ��w�f�E���E���^���J�x(De re metallica. Froben, Basel, 1550)�ƁA�����̃A���x���g�D�X�E�}�O�k�X(Albertus Magnus)�́w�z���ɂ��Ă�5���x(De mineralibus libri V)�ȍ~�ōł��d�v�ȑ̌n�I�z���w���Ƃ�����w���@���̖{���ɂ��āx(De natura fossilium. Froben, Basel, 1546)��2���ł��낤�B�������A�ނ́A�n�������Ɋւ��邱�Ƃ�A�R�A��A��A�z���E�����̌`���ɂ��Ă܂Ƃ߂����l�T���X���ōł��d�v�Ȓn�w���w�n���̎����̌����ƋN���ɂ��āx(De ortu et causis subterraneorum. Froben, Basel, 1546)��������(4)�B����́A���������ߑ�̍ŏ��̖{�i�I�Ȓn�w���Ƃ��ĔF������˂Ȃ�Ȃ��B�����Ɍ�����n�����E�̋L�q�ł́A��w����J���L�������ō̗p����Ă����A���X�g�e���X�́w�C�ۘ_�x��A�A���X�g�e���X�̒���ɂ����Ă����z���Ɋւ���L�q��₤���߂ɗp����ꂽ�A���x���g�D�X�̏�q���ȊO�ɂ��A�Ñネ�[�}�̃X�g�A��`�N�w�҃Z�l�J�́w���R�����x(Quaestiones naturales)�����p����(5)�A�X�|���W��̒n���𗬂����C�␅�ɂ��Ă̐������Ȃ��ꂽ�B�]���āA�A�O���R���ɂ́A����܂ł̓`���I�ȃA���X�g�e���X��`�̗���Ƀ��l�T���X�l����`�Ȃ�ł͂̃A�C�f�A�̍�����������̂ł���B�ނ̒���́A���l�T���X���̒n�����E�̋c�_�ɂ����ď�ɏd�p����A�c�_�̘g�g�݂ɑ傫�ȉe����^�����B
�@
�f�B�I�X�R���f�X�̖{�����w�}�e���A�E���f�B�J�x�̒��߂��s�����ɊS���W�������Ă���16���I�㔼�̃i�`�������X�g�B�́A�z���ɂ��Ă̋c�_�ɂ��Ă��Ă����5���̗����̂��߂ɃA�O���R���̒�����Q�l�ɂ����B�����ɁA�n�����E����эz���`�����_���w�n���̎����̌����ƋN���ɂ��āx������ꂽ�B���Ɍ����Ȃ̂́A�C�^���A�̃s�G�g���E�}�b�e�B�I��(Pietro Mattioli)�ł���B�ނ̃f�B�I�X�R���f�X���������听����[�߂����Ƃɂ��A�A�O���R���̒n�����E�̎����Ɋւ���L�q�́A�Ȗ��Ȍ�M�Ԃ����グ�ď��̌�����ϋɓI�ɍs���Ă����f�B�I�X�R���f�X�����ҊԂōł��M�������錠�ЂƂȂ����B���̃l�b�g���[�N�̒��S�ɂ����l�����A�s�T�A�����̏��㉀�����J�E�M�j(Luca Ghini)�ł������B���̌���p�����A���h���A�X�E�`�F�U���s�[�m(Andreas Cesalpino)�̍z���w���w�z���ɂ��āx(De metallicis. Roma, 1596)���A�A�O���R���̉e����F�Z�����f���Ă���B�啔�̃A�O���R���̒���W�ɔ�g�т��Ղ������ނ̍z���w�����A���Ȃ�̉e����17���I�O���ɋy�ڂ���(6)�B
�@
�c�O�Ȃ���A���ɑ�������������j�ƒB�̊S���W�ߐ���Ɍ������ꂽ�w�f�E���E���^���J�x�Ȃǂɔ�ׂ�ƁA���̂悤�ɏd�v�ł������A�O���R���́w�n���̎����̌����ƋN���ɂ��āx�́A�̌n�I�Ȍ������w�ǂȂ���Ă��炸�A���̏��̗����Ɛ������ʒu�t���������ߑ�̒n�w�j���������悤�Ƃ�����j�Ƃ̋}���Ƃ��Ďc����Ă���B
�@
�A�O���R���̒���Ɍ�����悤�ȁA�A���X�g�e���X�̐��E�ςɃ��l�T���X�̐l����`�Ȃ�ł͂̃Z�l�J���̌Ñ�X�g�A�h�N�w�҂̒���̍Đ����瓾��ꂽ�A�C�f�A������������`���Ƃ͕ʂɁA�n�����E�ɂ��Ă̎v�l�ւ̂��������I�Ȑl����`�̉e���́A�v�����g����`�̕����ł������B�F���_���w�e�B�}�C�I�X�x�ȊO�͂���܂Ő����Ŗw�ǒm���Ă��Ȃ������v�����g���̒���̖|����s�����t�B�����c�F�̃v���g���E�A�J�f�~�[�̎�v�l�����A�}���V���I�E�t�B�b�`�[�m(Marsilio Ficino)�ł���B����܂ł̃A���X�g�e���X��`���R�w�̍������v���g����`�`����w�Œu�������邱�Ƃ�ނ͈Ӑ}���Ă���A��X�̃v���g���ւ̒�����i�̒��ŁA���̌�̃��l�T���X���̉F���_�ɑ傫�ȉe����^����Ǝ��̃A�C�f�A��W�J���čs�����B�Ⴆ�A�R�y���j�N�X�����z���S���Ɏ������o�܂����݂ł�����ɋc�_����Ă��邪�A���炩�ɔނ̓t�B�b�`�[�m�̑��z�ƉF���̐��藧���̗��_��ǂ�ł����B�t�B�b�`�[�m�̉e���������l�T���X���̃v�����g����`��(�Ƃ������́A�ނ���t�B�b�`�[�m��`��)�́A���E�Ƃ�����F��(�}�N���N�X���X)�Ɛl�ԂƂ������F��(�~�N���R�X���X)�̑Ή��Ƃ����Ñォ�炠��A�C�f�A���D�݁A���W�������B�܂��A�S�Ă̎����������A�������A���ł��čs���Ƃ������C�t�T�C�N�����z���E��n�����E�ɔF�߂����Ƃ����M���ׂ��_�ł���B�����ł́A��n��F�����̂��̂����̗썰�������A�����Ă���Ɨ������ꂽ(7)�B
�@
�t�B�b�`�[�m�̃v���g����`�I�ȉF���_�ɑ傫���e�����āA17���I�̒n�����E�ɂ��Ă̎v�l�`���̍\�z�Ɋ�^����������̑傫�Ȑ��͂��u���w�N�w�ҁv(�P�~�J���E�t�B���\�t�@�[)�B������(8)�B�ޓ��́A���l�T���X���̈�w�j��ł��d�v�ȃX�C�X�l��t�p���P���X�X(Paracelsus)�̎v�z�ɑ傫���e������Ă����B17���I�ɉ��w�N�w�ҒB�̒��쒆�Ŕ��B����n�����E�ς́A�A���X�g�e���X��`�����܂�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������́w�n���L�x�Ɍ�����V�n�n���̕�����I�݂Ɏ�����邱�Ƃɐ��������B�ޓ��̕`���n�����E���̑�\�I�ȗႪ�A�p���̃p���P���X�X��`�҃��o�[�g�E�t���b�h(Robert Fludd)�ƃG�h���[�h�E�W���[�_��(Edward Jorden)�̂��̂��낤�B���Ƀt���b�h�̉F���ς̉e������17���I���t�̒���ƒB�́A�F���Ƃ����}�N���R�X���X�Ɛl�̂Ƃ����~�N���R�X���X�̑Ή������łȂ��A�n���̓����ɐl�̂̌��t�z�̗ޔ��ǂݎ��Ȃǂ̐l�̂ƒn�����E�̗ޔ�A���͑�F���Ƒ�n�����̗ޔ���݂�u�W�I�E�R�X���X�v(�n���̉F���E�n�̐��E)�I�ȃA�C�f�A�W������(9)�B���̂悤�ȉ��w�N�w�̓`���ɂ�����u�W�I�E�R�X���X�v�T�O�̌`���E���W�̗��j�́A�̌n�I�Ɍ��������ׂ��ۑ�ł���B
�@
�ȏ�̂悤�ȃ��l�T���X������̉��w�N�w�I�ȓ`�����ň炿17���I���Ɏp�������n�����E������Ɏ�舵���w��W�������u�n�����E�̎��R�w�v(Physica subterranea)�̊T�O���A�����̐}���Ƌ��ɓǎ҂ɔ��ɃC���p�N�g��^����`�ői���邱�Ƃɐ��������̂��A�L���ȃ��[�}�̃C�G�Y�X��m�A�^�i�V�E�X�E�L���q���[(Athanasius Kircher)�̋L�O��I����w�n�����E�x(Mundus subterraneum. Amsterdam, 1655-1656)�Ȃ̂ł���B���̏���������ȍ~�̒n���_�ɗ^�����e���͌v��m��Ȃ����̂����邪�A���̖{�i�I�Ȍ����͂܂��w�Ǎs���Ă��Ȃ�(10)�B�L���q���[�̒n�����E������艻�w�N�w�̓`���ɓY���`�ł���ɓW�J���������̂��A�h�C�c�l���n���E���A�q���E�x�b�q���[(Johann Joachim Becher)�ɂ��w�n�����E�̎��R�w�x(Physica subterranea. Leipzig, 1669)�Ɍ�������̂Ȃ̂ł���(11)�B�{���́A18���I�̉��w�ɂ�����ȉe����^��������ł���A���̑S�e���ڍׂɋᖡ���������҂��]�܂��B
�@
����܂ŁA�f�J���g�ȍ~�̊w�I�ȉ��߂�O�ʂɉ����o�����@�B�_�I�Ȓn�������̃��J�j�Y���̐������肪�n�w�j�̒ʎj��Ȋ����Ă����B�������A�@�B�_�I�`���݂̂����łȂ����w�N�w���̃W�I�E�R�X���X�I�Ȓn�����E�̗������Ɍ������A��̒���ɂ܂Ƃ߂�����ꂽ���̂��A�̑�Ȃ�h�C�c�l�N�w�� G.W.���C�v�j�b�c�̑����I�n�w���w�v���g�K�C�A�x(Protogaea. Goettingen, 1749)�Ȃ̂ł���(12)�B���̏����ߑ㐼���̒n���_�̋L�O��𗝉����邽�߂ɂ́A�n�����E�̎��R�w�̓`���𐳂����w�ђ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł���B
�@
��
�@
(1)�@�{���\�́A���N�Ԃɂ킽���Ď����R�c�r�O���ƌ��킵�� e-���[����ł̋c�_�Ɋ�Â��Ă���A�����ɒ��X�Ƌc�_�ɂ������Ē��������ւ̊��ӂ̔O��\�������B
�@
(2)�@�x���M�[�E���F�[�W����w �Ȋw�j������ �q��������(E-mail : jzt07164@nifty.ne.jp)
�@
(3)�@���m�_���́AH. Hirai, Le concept de semences dans les theories de la matiere a la Renaissance : de Marsile Ficin a Pierre Gassendi. (Ph. D. diss. ) University of Lille 3 (France), 1999�B�M�҂����W����͂ł����n�w�j�W�̕����́A�gSelect Bibliography for Early Earth Sciences.�h JAHIGEO Newsletter, 2, (2000), pp. 4-10 �Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B
�@
(4)�@���݂ł́A�ƖS�W�ő�3��(G.Fraustadt & H.Prescher (eds.),�@Schriften zur Geologie und Mineralogie I. Georg Agricola-Ausgewaehlte Werke, vol. III, VEB, Berlin, 1956)�ɔ[�߂��Ă���B
�@
(5)�@�Z�l�J�́w���R�����x(���C��w�o�ʼn�A1993�N)�́A�����n�w�j�ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�ł���A���̒n���_�I�j�I�Ȍ��n����̕��͂��҂����B
�@
(6)�@17���I��ʂ��čł��d�v�ł���Ƃ����z���w�� Gemmarum et lapidum historia (Hanau, 1609)���� Anselmus Boetius de Boodt �́A�A�O���R���ƃ`�F�U���s�[�m�ɑ������Ă���B
�@
(7)�@�Ⴆ�A�t�B�b�`�[�m�̑听����[�߂��咘�w���ɂ��āx(De Amore)(�M��w���̌`����w�x�A�����ЁA1985�N)�ł́A���̃^�C�g������͑z������ɂ������A�F���S�̂ɐ������s���n�点��`����w�I�ȑ��z�����E�̒��S�ɂ���S�Ă����̎�������Ƃ����A�ޓƎ��̉F���_���W�J����Ă���A���l�T���X�l�ɉe����^�������Ƃ͔ۂ߂Ȃ����낤�B
�@
(8)�@���l�T���X���̃p���P���X�X��`����щ��w�N�w�ɂ��ẮAA.G.�f�B�[�o�X�w�ߑ�B���p�̗��j�x(���}�ЁA1999�N)���Q�ƁB�����ɂ́A�W�I�E�R�X���X�Ɋւ���L�q�����ɑ����B
�@
(9)�@�t���b�h�ْ̈[���肬��̐_�q�w�I�ȉ��w�N�w�ɂ��w�n���L�x�����̍�Ƃ��������f�J���g�́A�t���b�h�̕`�����n�������̕����ނ̐M����Ƃ���̊w�I���߂ɂ���ď���������B���ꂪ�A�ނ́w�N�w�����x�̑�4���Ɍ�����悤�Ȓn�������̊w�I���J�j�Y���Ȃ̂ł���B�ނ̉��߂́A�����̓_�Ō�̋@�B�_�I�Ȓn���`�����_�̓`���ɉe����^�����B���̈�[���A�L���ȃX�e�m�́w�v���h�����X�x�ɂ����f����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�t���b�h�̒���ɂ��ẮAJ.�S�h�E�B���w��������C�R���F�t���b�h�̐_���F�����x(���}�ЁA1987�N)�Q�ƁB
�@
(10) �w�n�����E�x�Ɏ��^����Ă���}�ŌQ�́AJ.�S�h�E�B���w�L���q���[�̐��E�}�ӁF��݂����镁�Ղ̖��x(�H��ɁA1986�N)����ʂ��Č��邱�Ƃ��ł���B
�@
(11) �{����17���I�h�C�c���̕����ł��A�߁X�h�C�c�� G.Olms ���X����o�ł����\��ł���B
�@
(12) �w���C�v�j�b�c����W�x��10���A(�H��ɁA1991�N)�A121-202�ŁB�@ |
��Physica Subterranea �w�n�����E�̎��R�w�x
�@
�܂��A���l�T���X���ɐl����`�̗����ŁA�V���ɃM���V�A�E���e���̌Ñ�̕����ɑ���m�������傷��ƁA�Ƃ�킯�A��w�I���p�̊ϓ_����̊S�ŁA�Ñ�l�̋L�����z���Ǝ��ۂ́A���ɃA���v�X�Ȗk�ōz�v�B�̊ԂŒm���Ă���A�z���E�̕����Ƃ̑Ή���m��K�v����������悤�ɂȂ�܂��B������A���������s���Ɉڂ����̂��A�h�C�c�̃{�w�~�A�R�n�ߍx�̍z�R�n�т̊X��҂ł������Q�I���O�E�A�O���R��(Georg Agricola) �ł��B�ނ́A�����̑�w����ŃX�^���_�[�h�������A���X�g�e���X��`�̎��R�w���w��A�C�^���A�ɗ��w���A���l�T���X���C�^���A�ŗ������ɂ߂��l����`�I�ȕ��@�w�I�E�����w�I��w�̎�@���w�сA���F�l�c�B�A�ł́A�q�|�N���e�X�̕ҏW��ƂȂǂɂ����������܂��B
�@
�ނ̒��쒆�Ŕ��ɗL���Ȃ̂́A�z�R�Z�p�ɂ��ċL���ꂽ�S�ȑS���I�� �w�f�E���E���^���J�x(De re metallica. Froben, Basel, 1650)�ƁA�����̃A���x���g�D�X�E�}�O�k�X�́w�z���ɂ��Ă�5�̏��x (De mineralibus et lapidibus libri V.) �ȍ~�A�ł��d�v�ȑ̌n�I�z���w���ł���w�z���ɂ��āx (De mineralibus. Froben, Basel, 1546�N) ��2���ł����A�����Ƃ͕ʂɁA�n���̓����Ɋւ��邱�Ƃ�A�R�A��A��A�z���E�����̌`���ɂ��ċL���ꂽ���l�T���X���̍ł��d�v�Ȓn�w�I�ȏ��w�n���̎����̌����ƋN���ɂ��āx(De ortu et causis subterraneorum. Froben, Basel, 1546)���A�ނ͋L���܂��B
�@
���̏��Ɍ�����A�O���R���̒n�����E�̋L�q�́A��w����J���L�������ō̗p����Ă����A���X�g�e���X�́w�C�ۘ_�x��A�A���X�g�e���X�̕s����₤���߂ɗp����ꂽ���ɉe���͂̂������A���x���g�D�X�́w�z���ɂ��Ă�5�̏��x �ȊO�ɂ��A�Ñネ�[�}�̃X�g�A��`�N�w�҃Z�l�J�́w���R�ⓚ�x (Quaestiones naturales) �𑽗p���A�X�|���W��̒n���𗬂����C�␅�ɂ��Ă̐������Ȃ���Ă��܂��B�]���āA�A�O���R���̒n�����E�̋L�q�́A����܂ł̓`���I�ȃA���X�g�e���X��`�̗���Ƀ��l�T���X�l����`�҂Ȃ�ł͂̃A�C�f�A�̍����������܂��B
�@
�A�O���R���� �w�n���̎����̌����ƋN���ɂ��āx �́A���̌�A�������l�T���X���̒n�����E�̋c�_�ɂ����ď�ɏd�p����A�c�_�̋c��̎����Ȃǂ̘g�g�݂ɑ傫�ȉe����^���܂��B
�@
���ɁA���̑�5�����z���ɂ��Ă̋c�_�ɔ�₳��Ă���Ñネ�[�}�̃f�B�I�X�R���f�X(Dioscorides) �̈�w�{���� �w�}�e���A�E���f�B�J�x (Materia medica)�̒��߂��s�����ƂɊS���W�������Ă������l�T���X����̃i�`�������X�g�B�́A�A�O���R���̒n�����E����эz���`�����_������܂��B���Ɍ����Ȃ̂́A�C�^���A�̃s�G�g���E�}�b�e�B�I��(Pietro Mattioli)�ŁA�ނ̃f�B�I�X�R���f�X���������听����[�߂����Ƃɂ��A�A�O���R���̒n�����E�̎����Ɋւ�����ƃA�C�f�A�́A�f�B�I�X�R���f�X�̌����ҒB�̃T�[�N���ōł��M�������錠�ЂƂȂ��Ă����܂��B�f�B�I�X�R���f�X�����҂����́A�Ȗ��Ȍ�M�Ԃ����グ�Ă��āA�T���v������̌�����ϋɓI�ɍs���Ă��܂����B���̃l�b�g���[�N�̒��S�ɂ����l�����A�C�^���A�̃s�T�A������n�n�������㉀���̃��J�E�M�[�j(Luca Ghini)�ł��B
�@
�M�[�j�̌���p���ŁA�����ɂȂ����̂��A���h���A�E�`�F�U���s�[�m (Andreas Cesalpino) �ŁA�ނ̍z���w�� �w�z���ɂ��āx (De metallicis, Roma, 1596)���A�A�O���R���̉e����F�Z�����f���Ă��܂��B�啔�̃A�O���R���̒���W�ɔ�ׁA�g�т��Ղ������`�F�U���s�[�m�̍z���w�����A���Ȃ�̉e����17���I�O���͕ۂ��Â��܂��B
�@
�A���X�g�e���X�̐��E�ςɐl����`�Ȃ�ł͂̃Z�l�J���̑��̌Ñ�̓N�w���̍Đ����瓾��ꂽ�A�C�f�A�̍����̓`���Ƃ͕ʂɁA���������I�Ȑl����`�̉e���́A�v�����g����`�̕����ł��B���ɁA�w�e�B�}�C�I�X�x�ȊO�́A����܂Ő����Ŗw�ǒm���Ă��Ȃ������v�����g���̒���̖|����s�����t�B�����c�F�̃v���g���E�A�J�f�~�[�̎�v�l���}���V���I�E�t�B�b�`�[�m�́A���炩�ɃA���X�g�e���X��`�̎��R�w�̍��{���v���g����`�Œu�������邱�Ƃ��Ӑ}���Ă����l���ŁA�ނ̎�X�̃v���g��������i�̒��ŁA���̌�̃��l�T���X���̉F���_�ɑ傫�ȉe����^����Ǝ��̃A�C�f�A��W�J���čs���܂��B�R�y���j�N�X�����z���S���Ɏ������o�܂����݂ł�����ɋc�_����ċ��܂����A���炩�ɔނ́A�t�B�b�`�[�m�̑��z�ƉF���̐��藧���̗��_��ǂ�ł����̂ł��B
�@
�t�B�b�`�[�m�̉e���������l�T���X���̃v�����g����`��(�Ƃ������́A�ނ���t�B�b�`�[�m��`��)�B�́A���ɐ��E�Ƃ�����F��(�}�N���N�X���X)�Ɛl�ԂƂ������F��(�~�N���R�X���X)�̑Ή��E�ĉ��Ƃ����Ñォ�炠��A�C�f�A���D�݁A���W�����܂��B�@
�@
���̃t�B�b�`�[�m�̃v���g����`�I�ȉF���_�ɑ傫���e�����A17���I�̒n�����E�̎��R�w�̓`���̍\�z�ɉe����������������̑傫�Ȑ��͂��A���l�T���X���̃p���P���X�X��`���w�N�w��(�P�~�J���E�t�B���\�t�@�[)�B�ł��B16���I�㔼����17���I�O���ɔ��B����W�I�E�R�X���X(�n���̉F�����邢�͒n�I���E)�I�Ȓn�����E�ς́A����܂ł̃A���X�g�e���X��`�҂����܂�������邱�Ƃ̂ł��Ȃ����������́w�n���L�x�Ɍ�����V�n�n���̕�����I�݂Ɏ�����邱�Ƃɐ������܂��B�����������A���w�N�w�ҒB�̕`���W�I�E�R�X���X���̑�\�I�ȗႪ�A�p���̃p���P���X�X��`�҃��o�[�g�E�t���b�h�ƃG�h���[�h�E�W���[�_���ł��B�ޓ��̉F���ς̉e������17���I���t�̒���ƒB�̒��ɂ́A�F���ƌ����}�N���R�X���X�Ɛl�̂Ƃ����~�N���R�X���X�����łȂ��A�n���̓����ɐl�̂̌��t�z�̗ޔ��ǂݎ��Ȃǂ̐l�̂ƒn�����E�̗ޔ�A���͑�F���Ƒ�n�����̗ޔ���݂�W�I�E�R�X���X�Ƃ����A�C�f�A�����W�������܂��B
�@
�t���b�h�ْ̈[���肬��̐_�q�w�I�ȉ��w�N�w�ɂ��w�n���L�x�����̍�Ƃ��������f�J���g�́A�t���b�h�̕`�����n�������̃X�g�[���[��ނ̐M����Ƃ���̊w�I���߂ɂ���ď���������_�l�\���܂��B���ꂪ�A�w�N�w�����x�̑�4���Ɍ�����n�������̊w�I���J�j�Y���Ȃ̂ł��B���̃f�J���g�̉��߂́A�����̓_�Ō�̋@�B�_�I�Ȓn���`�����_�̓`���ɑ傫���e����^���܂��B���̈�[���A�L���ȃj�R���X�E�X�e�m�̎d���w�v���h�����X�x���ɂ����f����邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�@
��q�����悤�ȉ��w�N�w�I�ȓ`���̓����ň�����A17���I�O���́u�n�����E�̎��R�w�v(Physica subterranea) �̊T�O���A�����̐}���Ƌ��ɔ��ɃC���p�N�g��^����`�ői���邱�Ƃɐ��������̂��A���[�}�̃C�G�Y�X��m�A�^�i�V�E�X�E�L���q���[�̃}�X�^�[�E�s�[�X�w�n�����E�x (Mundus subterraneum. Amsterdam, 1655-1656) �ł����B
�@
����ɁA�L���q���[�̒n�����E�������A�L�~�A(�������w���B���p)�I�Ȓm�̓`���ɓY���`�œW�J���ꂽ���̂��A�h�C�c�l���n���E���A�q���E�x�b�q���[�ɂ��w�n�����E�̎��R�w�x (Physica subterranea. 1669)�B
�@
�f�J���g�ȍ~�̊w�I�ȉ��߂�O�ʂɉ����o�����@�B�_�I�Ȓn�������̃��J�j�Y���̐����ƁA��q�̉��w�N�w�̓`���ň�܂ꂽ�W�I�E�R�X���X�I�Ȓn�����E�̗������A�����Ɍ�������̒���ɂ܂Ƃ߂�����ꂽ���̂��A���̈̑�Ȃ�h�C�c�l�N�w�ҁE���R�w�҃��C�v�j�b�c�́w�v���g�K�C�A�x (Protogaea. 1691�N���������)�Ȃ̂ł��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���I���e���E�X�u���E�n�}���v���� 1570�N |
   �@
�@
|
Ortelius, Abraham.(1527-98)
�@
Theatrum Orbis Terrarum.
�@
�I�����_�̒n���w�ҁA���w�ҁB���ߒn�}�̍쐻�Ɣ̔��ɏ]�����Ă������A�e�n�ɗ��s���Ēn�}�̏N�W�ɓw�߁A�t�����h���̈ꏤ�l�̒����@�Ƃ���53�t�̒n�}���܂ށu���E�n�}���v��ҏW�����B�}���R�E�|�[���́u���������^�v�̉e�����A�W�A�n����`����Ă��邪�A��������s�\���ł���A���̎���̃��[���b�p�ɂ�����A�W�A�̔F��������������B���̒���ɂ�������{�n�}�́A���[���b�p�Ő��삳�ꂽ���ŋɂ߂ď����̂��̂ł���B�@ |
���A�u���n���E�I���e���E�X
�@
(Abraham Ortelius�A1527-1598)�@�t�����h���l�̒n�}����ҁE�n���w�ҁB�ߑ�I�n�}����̑n�n�҂Ƃ��Ēm���Ă���B���x���M�[�̃A���g�E�F���y�����܂�B�A�E�N�X�u���N�̗L�͎҂ł���I���e���E�X�t�@�~���[�̈���ŁA���[���b�p�̍L�͈͂𗷍s�����B���ɁA17�J�������܂Ȃ����s�������ƂŒm���A��y�ѐ��h�C�c(1560�N�A1575�N�H�A1576�N)�A�t�����X(1559�N-1560�N)�A�C���O�����h�y�уA�C�������h(1576�N)�A�C�^���A(1578�N�A1550�N����1558�N�̊Ԃɋ��炭2�x��3�x)��K��Ă���B
�@
1547�N�ɒn�}�̍���t�Ƃ��āA�A���g�E�F���y����"afsetter van Karten"��St Luke�̃M���h�ɓ������B�ނ̏����̌o���̓r�W�l�X�}���ł���A1560�N�ȑO�̑����̗��s�͏��ƖړI�̂��̂ł������B�Ⴆ�t�����N�t���g�ւ̖{�ƈ���̌��{�s�ւ̖��N�̖K��ł���B
�@
�������Ȃ���A1560�N�Ɍ�Ƀ����J�g���}�@�ŗL���ƂȂ�Q�����h�D�X�E�����J�g���Ƃ̃g���[�A(Trier)�A�����[�k�A�|���`�G(Poitiers)�ւ̗��s�̍ۂɂ́A�����J�g���̉e���ɂ���āA�Ȋw�I�Ȓn���w�҂Ƃ��Ă̌o�����n�܂����B�I���e���E�X�͗F�l�̏����ɂ���āA��ɗL���ɂȂ����n�}(�uTheatrum Orbis Terrarum�v(���E�̕���))�̕ҏW�ɐ�O�����B
�@
1564�N�ɂ́Amappemonde�Ƃ���8���g�̐��E�n�}�����������B����͌��Theatrum Orbis Terrarum�̒��ɏk�����ꂽ�`�ŕ\��Ă���B���̑傫�Ȓn�}�̗B�ꌻ������R�s�[�́A�o�[�[����w�̐}���قɂ���B
�@
1565�N�ɂ́A�G�W�v�g��2���̒n�}���o�ł����B�����1568�N�ɃI�����_�̊C�݂�Brittenburg��̌v��}�A1567�N�ɃA�W�A��8���g�̒n�}�A6���g�̃X�y�C���̒n�}���o�ł����B
�@
1570�N5��20���ɁA���E���̋ߑ�I�n�}�ł���uTheatrum Orbis Terrarum�v���A���g�E�F���y����Gilles Coppens de Diest�ɂ���ďo�ł��ꂽ�B53���g�Œn�}70�}�ł������B6�N��Ɂw�n���w�̕�Ɂx���o�ŁA���������嗤�̕�������Ă���B
�@
���̒n�}�̓I�����_��A�t�����X��A�h�C�c���3�̔ł�1572�N�܂łɏo�ł��ꂽ�B(�I���e���E�X���S���Ȃ�1598�N�܂ł�25��ނ̔ł��o�ł���Ă���B)�܂��A�������̔ł͂����1612�N�܂ő����ďo�ł���Ă����B
�@
1595�N�̔łɂ͓��{�n�}���lj�����A���̒n�}�����[���b�p�ɂ�����ŏ��̓��{�n�}�ł���Ƃ���Ă���B
�@
�قƂ�ǂ̒n�}�͖��炩�ɍĕҏW����Ă���B(�ŏ��̔ł�87�l�̒��҂̃��X�g��1601�N�̃��e����̔łł�183�l�ɑ������Ă����B)�܂��A�`�ʖ��͖����@�̑����ɕs��v�������Ă���B�P���Ȍ��͂�������ʓI�ȊT�O����ڍׂȕ����Ɏ���܂ő����̕����ł���B�Ⴆ�A�ŏ��̔łł͓�A�����J�͊O�`�����ɕs���S��1587�N�̃t�����X��̔łŏC������Ă���B�܂��A�X�R�b�g�����h�̐}�ł̓O�����s�A���Y(Grampians)�̓t�H�[�X�ƃN���C�h�̊ԂɈʒu���Ă���B
�@
�������A�S�̂Ƃ��ẮA���̃e�L�X�g��������n�}�́A�ނ���Ȃ锎�w�y�юY�Ƃ̕s���̋Ɛтł���B
�@
�����̒n�}�̓y��Ǝ���i�́A�I���e���E�X�̃G�[�W�F���g�ƃp�g�����ł���Gilles Hooftman�Alord of Cleydael�AAertselaer�̕x�Ɗ�Ɗ����ɂ���ďW�߂�ꂽ38���̃��[���b�p�A�A�W�A�A�A�t���J�A�^�^�[���A�G�W�v�g�̒n�}�ł������B�����̒n�}�͂قƂ�ǂ̓��[�}�ň�����ꂽ���̂ŁA8����9���̂݃x���M�[�ň�����ꂽ���̂ł���B
�@
1573�N�ɂ́AAdditamentum Theatri Orbis Terrarum�Ƃ����^�C�g����17���̕⑫�̒n�}���o�ł����B�����4��Additamentum�������ďo�ł���Ō�̂��̂�1597�N�ɏo�ł��ꂽ�B
�@
�I���e���E�X�̓R�C���A���_���A�A���e�B�[�N�ɋ����������Ă���A�f���炵���R���N�V������z�����B������1573�N�ɏ��Ёu Deorum dearumque capita ...ex Museo Ortelii�v�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B
�@
1575�N�ɂ́AArias Montanus�̐��E�ɂ��X�y�C����(�t�F���y2��)�������̒n���w�҂ƂȂ����B
�@
�I���e���E�X�̌��т��F�߂�ꂽ�̂́A1994�N�ɃC�M���X�̉Ȋw���w�l�C�`���[�x�ɁA�A�����J�̉Ȋw�j�ƃW�F�[���Y�E�����̘_�����f�ڂ���Ă���ł���B�@ |
���ߑ�n�}���̒a�� / �A�u���n���E�I���e���E�X�Ɓu���E�̕���v�̗��j�@
�A�u���n���E�I���e���E�X(1527-1598)�@���炭���܂ꂪ�����x�߂Ȃ̂ƁA�����J�g��(1512-1594)�����邩�獷�ʉ�������̂ł��傤���A�q�C�҂ɂƂ��Ă͐������Ƃ������ׂ��n�}�̐���E�ҏW�҂Ƃ��Ă͊ԈႢ�Ȃ�������w�̑��݂ł����B�Ɛт��F�߂��Č�ɒn���w�҂ɗ���̂����R�ƌ����ׂ��ŁA���̐l�̑��݂��������16���I���`17���I���E�̒T���͂����ƒx���Ȃ��Ă��������m�ꂸ�A��q�C����̌㔼�ȍ~�𑤖ʂ���x�������l�̈�l�ƌ��ėǂ��Ǝv���܂��B
�@
���̖{�A�ނ̐��삵���n�}�� �w���E�̕���x �̉������̂ɁA�w�i�E���U�E���ӏ�E�����҂��L�q�����Љ�j�I�ȓ��e�ƂȂ��Ă��܂��B�ǂ����Ă�����{�ł�����y�[�W�ƌ���̑Δ�\�݂����ȕ�����X�g�݂̂Ƀy�[�W�����₵�Ă��镔��������̂ł����A���������������Ă��ӊO�ɓǂ܂�����̂�����܂��ˁB
�@
���āA���Ƃ��Ƃ͒n�}����̑����E�l�Ƃ��Đg�𗧂ĂĂ����I���e���E�X�ł����A���鎞�����J�g���Ɠ�l�ꏏ�Ƀt�����X�֗��s�ɏo�������_�@�Ƃ��āA���Ȃ�����n�}����̎��ƂɎ��g�ގ��ɂȂ�܂��B��l���ǂ�����ďo��������͂悭����܂��A�Ђ�n�������܂Ƃ߂Ēn�}�����w�ҁE����҂ƁA�Ђ�o���オ�����ł����Ɉ���E����������E�l�ł�����ړ_�͑������ŁA������ӂ̂���肩��m�荇�����̂�������܂���ˁB
�@
���̎���̒n���w�ɂ����Ă͐��҂ł���A��}�Z�@�ł��m���郁���J�g���ɑ��āA�I���e���E�X�͏�L�́w���E�̕���x���n�߂Ƃ��Ď��ۂɂ������̏ڍגn�}�̔��s���s���A�ߑ�I�Ȓn�}����E�ҏW�҂Ƃ��Ă͑n�n�҂ƌ����Ă��܂��B
�@
����́A�����J�g����̒n�} �w�A�g���X�x ���A���s���͏��Ȃ����̂̒n�}���̂��̂̑㖼���I�ȑ��݂ƂȂ��čs�����̂ɑ��āA�I���e���E�X�́w���E�̕���x�́A���E�e�n�̒n�}�������������肷�邱�ƂōŐV�̒n���������ɂ܂Ƃ߂Ĕ��s����Ƃ����A�قڎ��ƂƂ����ׂ����앨�ŁA�X�ɘA�N���肵�Ă������Ő��x�����߂Ă����A�������S�̐}�E�n��ڍא}�Ƃ������݂ł��̗p����Ă���n�}���̌`�����̂������ƂŁA�ŐV�̎��������Ƃ��Ĕ��ɍ����]�����l�����Ă������̂͑ΏƓI�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@
�Ƃ���ŁA�ނ� �w���E�̕���x��i�悵���҂̒��ɂ́A�����J�g���ق�������������͎ҁE�p�g���������Ȃǂ̎��Ӑl���̂ق��ɑ啨�����܂����B
�@
�X�y�C�����t�F���y�Q���B
�@
�����Ŏ��O�ɑ��߂̃G�X�s�m�[�T���@�����ڂ�ʂ��̂ł����A���@���͒n�}������⎩���̌̋����ڂ��Ă��Ȃ������c�O�Ɏv�����炵���A�{��̃����������ɃI���e���E�X�̌��ɑ����A�I���e���E�X�̓X�y�C���̏ڍא}��lj����������ł��ɍ��A���������ɂ������̂��ēx�������Ƃ����܂��B�|�p��i�ł����̎���͌��͎҂̈ӌ����傫���e�������̂ł�����A���肪�����Ƃ��Ȃ�I���e���E�X���ߕq�ȑΉ��������̂�������C�����܂��ˁB
�@
���ɒn��}�Ƃ��Ă͂�����B1595�N�łł͓��{�n�}�̎������s���Ă���A���{�l���Â��n�}�Ƃ��Ď����ȂǂŌ��邠�̌`�̒n�}�̑����́A���̓I���e���E�X�̐��앨(���{�}�̍�}�҂̓e�B�Z���Ƃ����l)�����������肵�܂��B1570�N�̔łł͂��������ȋL�q�������̂��A20���N�ł����܂Ő��m�ɂȂ��Ă��Ă�̂͂�����Ɗ��S���܂��B
�@
�Ō�ɁA�����J�g�����I���e���E�X�ɑ������莆�̈�߂��B
�@
�w���ꂼ��̍쐬�҂̒n�}�𒉎��ɍČ����ꂽ���Ƃɑ��A�h�ӂ�\�������Ǝv���܂��B�����������Ƃ͒n���w�I�Ȑ^���\���邽�߂ɕs���ȓ_�ł����A�n�}�쐬�҂ɂ���Ė�������Ă��Ă���̂ł��B�@(����)�@�e�n��̍ŗǂ̒n�}��I�������_�A���z�Ŕ�����悤�A�܂������ȃX�y�[�X�Ɏ��[�ł��A�]�ޏ��֎����čs����l�Ɉ���֗̕��ɂ܂Ƃ߂��_�ŁA���Ȃ��͑傢�Ȃ�^����̂����R�ł��x �����J�g���ɂ����܂Ō��킹��̂ł�����A�ނ����̕ҏW�҂ƍl���Ă͌��ł��傤�B�@�@
�@ |
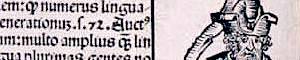 �@ �@
�������e�[�j���u���z�^�v���� 2�� 1580�N |
   �@
�@
|
Montaigne, Michel de.(1533-92)
�@
Essais de Messire Michael Seigneur de Montaigne.
�@
�����e�[�j����1570�N�Ƀ{���h�[�ō��@�@�]�芯�̐E��ނ��A�Ȍ�͓Ǐ��Ɩّz�̐����ɓ������B�c������胉�e���ꋳ����Ă����ނ́A���̎����̂Ђ�����ȓǏ��⓯����̌��������j�����ɂ��Ă̌����A���Ȃ�L�x�Ȓm����ӌ����܂����Ǐ��]�^�A���z�^�̌`�ŏ����Ƃ߂����̂����́����z�^���ł���B�����e�[�j���̕��͂͒��ۓI�Ȏv�z����̓I�A���o�I�Ɍ����̂ł���A���t�͕����ł���Ȃ���\���ɈӖ������߂��Ă���B�{���́u�䉽����m��H(�N�E�Z�E�W��)�v�Ƃ����L���ȋ�́A�����e�[�j���̐����̎v�l�@�ł���A�t�����X�̃y�[�p�[�o�b�N�E�V���[�Y�̖���(�N�Z�W������)�ɂ��Ȃ��Ă���B�@ |
�����z�^
�@
(���������낭)�������́w�G�Z�[�x(��: Les Essais)�́A�t�����X�̃������X�g�A�~�V�F���E�h�E�����e�[�j����107�̐��M���W�߂�1580�N�Ɋ��s���������ł���B�����e�[�j���͐��M(�G�b�Z�C�A�G�Z�[)�Ƃ����A����̘b��Ɋւ����ϓI�ȒZ�����͂̌`���������̂ł���A���̏����͂��̃G�Z�[�����߂Ă���B�l�Ԃ̂�����c�ׂ�f���I�ȕ��͂ŏȎ@���邱�Ƃɂ�胂���e�[�j���͐l�Ԃ��̂��̂𗦒��ɋL�q���悤�Ƃ��A�������X�g���w�̓`�����J�����B�t�����X���essai�́u���݁v��u��āv�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@
��
�@
�����e�[�j���͓ǎ҂̋�����������A�������ނ悤�ɈӐ}���ꂽ�I���ȃ��g���b�N��p���ď����Ă���A���鎞�ɂ͘b�肩��b��ւƈӎ��̗���ɉ����ē����悤�Ɍ����A�܂����鎞�ɂ͍�i�̂�苳��I�Ȑ�������������\���I�ȕ��̂�p���Ă�����B�Ñ�M���V�A�A���e�����w�A�C�^���A���w����̈��p�������Ε⋭�Ƃ��ėp������B
�@
��
�@
�����e�[�j���̖ړI�͐l�ԁA���ɔގ��g���A���S�ɗ����ɋL�q���邱�Ƃł���Ɓw���z�^�x�̒��ŏq�ׂĂ���B�����e�[�j���͐l�Ԑ��̑傫�ȑ��l���ƈڂ�ς��₷�����������̍ő�̓����ł���ƔF�����Ă����B�u�����g�Ƃ������̂����傫�ȉ�������ق͌������Ƃ��Ȃ��B�v�Ƃ����̂��T�^�I�Ȉ��p��ł���B
�@
�����e�[�j���͎��g�̕n��ȋL���͂�A�{���Ɋ���I�ɂ͂Ȃ炸�ɖ��������������𒇍ق���\�͂�A�㐢�ɂ܂Ŏc�閼����~������l�Ԃւ̌�������A���ɔ����������痣��悤�Ƃ��鎎�݂̂��ƂȂǂ������Ă���B
�@
�����̃J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̊Ԃ̖\�͓I��(�����e�[�j���̈ӌ��ɂ���)��ȕ����������e�[�j���͌������Ă���A���̏������ɂ̓��l�T���X�炵����ʔߊώ�`�Ɖ��^��`���`���Ă���B
�@
�����āA�����e�[�j���̓��}�j�X���̋��͂Ȏx���҂ł������B�����e�[�j���͐_��M���A�J�g���b�N���������Ă������A�_�̐ۗ����ǂ̂悤�ȈӖ��ŌX�̗��j��̏o�����ɉe�����Ă��������q�ׂ邱�Ƃ͋��ۂ��Ă����B
�@
�V���E�̐����ɔ����Ă���A���ꂪ���Z���ɂ����炵���ꂵ�݂�Q���Ă����B
�@
�}���^���E�Q�[���������Ɉ����Ȃ���A�����e�[�j���͐l�Ԃ��m�������l���ł��Ȃ��ƍl���Ă���B���̉��^��`�́w���C�����E�Y�{��(�p���)�ٌ̕�x�Ƃ��������G�Z�[�ɍł��ǂ�����Ă���A���̏͂͂����ΒP�Ƃł��o�ł���Ă����B��X�͎��g�̐��_��M�p�ł��Ȃ��A�Ȃ��Ȃ�v�l�͉�X�ɋN������̂ł��邩��B��X�͖{���̈Ӗ��ł͂������R���g���[���ł��Ȃ��B��X�����������D��Ă���ƍl���鑊���̗��R�͂Ȃ��B�����e�[�j���͍���ɂ���ē���ꂽ�����ɂ͋ɂ߂ĉ��^�I�ŁA���̂悤�Ȏ����͍��₩�瓦��邽�߂ɗe�^�҂��ł������������̂�������Ȃ��Ǝw�E���Ă���B�ʏ�u�m���͐l��P�ǂɂ͂ł��Ȃ��v�Ƒ肳��Ă���߂ɂ����āA�����e�[�j���͎��g�̃��b�g�[���u���͉���m���Ă���̂��H�v(Que sçay-je?)�ł���Ə����Ă���B�Y�{���ٌ�̃G�Z�[�͕\�ʓI�ɂ̓L���X�g����ٌ삵�Ă���B�������Ȃ���A�����e�[�j���̓L���X�g���k�ł͂Ȃ��Ñ�M���V�A�E���[�}�̒��q�Ƃ����Ɍ��y�����p���Ă���A���Ɍ��q�_�҃��N���e�B�E�X�ɑ������y���Ă���B
�@
�����e�[�j���͌������q������Ă邽�߂ɂ͕K�v���ƍl���Ă������A�����ɂ�錃��������͎��R�ɂƂ��ėL�Q�Ȃ��̂Ƃ��Č������B�u�����͒��Ă̂悤�Ȃ��̂ł���B���̊O�ɂ��钹�͕K���ɂȂ��ē��낤�Ƃ��邪�A���ɂ��钹�͕K���ɂȂ��ďo�悤�Ƃ���B�v�Ƃ������t������B
�@
����Ɋւ��ẮA���ۓI�Ȓm���ᔻ�Ŏ��ꂳ���邱�Ƃ�����̓I�ȗ��o���̕����D��ł����B�u�q���̋���ɂ��āv�Ƃ����G�Z�[�̓f�B�A�k�E�h�E�t�H��(�t�����X���)�ɕ������Ă���B
�@
�����e�[�j���̃G�Z�[�ɖ����Ɍ���Ă���v�l�̌��㐫�́A�����ł��l�C��ۂ��Ă���A�[�֎���܂ł̃t�����X�N�w�ōł����o������i�ƂȂ��Ă���B�t�����X�̋���ƕ����ɋy�ڂ��e���͈ˑR�Ƃ��đ傫���B�t�����X�̌��哝�̃t�����\���E�~�b�e�����̌����ȏё��ʐ^�ł́w���z�^�x����Ɏ����ĊJ���Ă���B�@ |
�������Ƃ����������_�Ƃ́A�����Ƃ������̑��l���Ə_������������_�ł���B
�@
(���̕��̑O�ɂ��镶�͈ȉ��̒ʂ�)�@�����̎����A���i�ɂ��܂�Ŏ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����̑��̍˔\�͂��܂��܂ȏK���ɏ����ł���Ƃ������Ƃł���B��ނ�������������̐������ɂւ���A�����Ă���̂́A�������Ă���Ƃ��������ŁA������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����Ƃ����������_�Ƃ́A�����Ƃ������̑��l���Ə_������������_�ł���B
�@
���^���͉�X���K���ɂ��s�K�ɂ����Ȃ��B�������̍ޗ��Ǝ�q�Ƃ���X�ɒ��邾���ł���B�������A�����������͂ȉ�X�̐S���A�����̂����Ȃ悤�ɁA���˂������̂ł���B���ꂪ��X�̐S�̏�Ԃ��K���ɂ�����s�K�ɂ����肷��E�B��́E�����ȁE�����Ȃ̂ł���B
�@
���킽���͐l�Ԃ��A�l�Ԃ̂��ƂŁA���ЂƂ킽���ɖ��W�Ȃ��̂͂Ȃ��B(�e�����`�E�X/�����e�[�j���̓��̏��ւ̓V��̗��ɍ��܂ꂽ��)
�@
���l�Ԃ͎��ɋ����Ă���B�������C��������Ȃ������ɁA�_�X�����_�[�X�Ƃł����グ��B
�@
���ЂƂ́A�����Ƃ悢����ɂ��Ȃ����Ƃ��c�O�Ɏv�����Ƃ͂ł��Ă��A����̎�����̂����킯�ɂ͂����Ȃ��B
�@
���������A�_��ł����͂ł��Ȃ�����ɐ�����悤�ɂ����Ă��ꂽ�����Ɋ��ӂ��悤�ł͂Ȃ����B
�@
�������L�ƋY��Ă���Ƃ��A�Ђ���Ƃ���ƔL�̂ق����A����ɗV��ł���̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
�������A�s���ƃ����e�[�j���Ƃ͏�ɓ�ł����āA�B�R�Ƌ�ʂ���Ă����B�m���F�����e�[�j���͈ꎞ�{���h�[�s�����Ƃ߂��B�����̂��߂Ƃ����ǂ��A���Ȃ̗ǐS�̎��R����������������܂��Ƃ����ӎ��B�n
�@
�����͂���Ȃɐ[���A���S�ɁA�������ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�킽���̈ӎu���킽���������h�ɗ^����Ƃ����A����͖����ȍS���ɂ���Ăł͂Ȃ�����A���̔��f���������̂��߂ɊQ����邱�Ƃ͂Ȃ��B
�@
�������̐E�Ƃ̑啔���͂��ŋ��݂����Ȃ��̂��B�s���̒��͑S�̂��ŋ������Ă���t�����͗��h�Ɏ����̖����������Ȃ���Ȃ�ʁB������������̐l���̖����Ƃ��ĉ����Ȃ���Ȃ�ʁB���ʂ�O�������݂Ƃ܂���������A���l�̕��������̕��Ƃ܂��������肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����͔畆�ƃV���c�Ƃ���ʂł��Ȃ��B��ɂ�������h��Ώ\���Ȃ̂ŁA�S�܂œh��K�v�͂Ȃ��B
�@
�������ꂽ�L���͎ア���f�͂ƌ��т₷���B
�@
�������̏ꍇ�A������҂̌��Ђ��w�ڂ��Ƃ���҂̎ז�������B
�@
���V�N�͂����̊�����S�ɑ�����ᰂ����ށB
�@
�������͎��R�̍앨�̔������ƖL�����̏�ɁA���܂�ɂ������̍�ׂ����������āA������������蒂�������Ă��܂����̂��B����ǂ����R�͂��̏������̋P��������Ƃ���ŁA�����̂͂��Ȃ��܂�Ȃ����݂ɐԒp���������Ă���B
�@
���ɒ[�͂킽���̎�`�̓G�Ȃ̂ł���B
�@
���N�w�҂̑F�����ґz(�߂�����)�́A�����̍D��S�̗�(����)�ƂȂ邾���ł���B�N�w�҂��������������R�̋K���ɉ����Ԃ��̂͂͂Ȃ͂������Ƃ��Ȃ��Ƃł��邪�A���̎��R�̋K���͉������̂悤�Ȑ����Ȓm����K�v�Ƃ͂��Ȃ��̂ł���B�ނ�͂������U�����A�ޏ��k���R�l�̊�����܂�ɂ��������A���܂�ɐl�דI�ɓh(��)�藧�ĂĂ����Ɏ����̂ŁA����ȂɈ�l�Ȉ�̂��̂ɑ��āA����Ȃɂ����낢��ȏё������܂�邱�ƂɂȂ�B�ޏ��͂����ɕ����������Ă��ꂽ�悤�ɁA�����Ă䂭���߂̒m�b�����Ă��ꂽ�B����͓N�w�҂�������������̂悤�ɁE�I���ȁE�������肵���E���̂��̂����E�m�b�ł͂Ȃ����A�����ɂ��ޏ��ɂӂ��킵���y�Ō��N�Ȓm�b�ł���B����͍K���ɂ��đf�p�ɓK���ɁE��������Ύ��R�I�ɁE�����邱�Ƃ�m���Ă���҂ɂ����ẮA�N�w�҂̒m�b������ȏ�̂��Ƃ𗧔h�ɂ��Ă̂��Ă���B�����Ƃ��P���ɂ��̐g�����R�Ɉς���Ƃ������Ƃ́A����ɍł������ɐg���ς��邱�Ƃł���B�������m�Ɩ��D����͂悭���ꂽ���]���x�߂�̂ɂȂ�Ɗy�ȁE�_�炩���E�����Č��N�I�Ȗ��ł��낤�I�@(�����炭���̋�́A�����e�[�j���̒��ōł������Έ��p�����ł��l�����Y�t(��������)������̂̈�ł����āA�ނ̑ӑĂƉ��^��`�Ƃ̍����ɂ���ꂪ���ł��邪�A�ނ��냂���e�[�j���̌��N�ȏ펯�������A�����Ɍ���ׂ��ł���B����͊w��m���̔ے�ł͂Ȃ����āA�P�ɑ�ꌴ�����������˂����ʓN�w�҂̎v���オ��ƁA������N�w�̔N���Ƃ��A�����Ȃ߂Ă���ɂ����Ȃ��B)�@ |
���w�G�Z�[�x�~�V�F���E�h�E�����e�[�j��
�@
237�E177�E34�E9�E6�E4�E13�B����̏O�c�@���I���̌��ʂ������������B����Ƃ����قnj�����ꂽ�B�����E����E�����E���Y�E�Ж��E�ێ�E���������̑��̏��ɂȂ�B���͔�����ʕ��ׂ̊P�����Ȃ���I���J�[�ԑg�����Ă����B���x�̂��ƂȂ���́A���҂Ɣs�҂̉��G�̂悤�ȋ���ƍ��܁B�u�o���U�C�A�o���U�C�v�w�c�Ɓu�s���̎���v���҂̉�ʂ����݂ɗ��āA�ڂ��͂����̂��ƂȂ��炷�������������Ă����B�A�i�E���T�[�́u����͓�吭�}�̎���̖��J���ł��v�ƌ����Ă����B
�@
�I���J�[������O�́A���q�o���[�̐��E�������Ă����B�����ł���Ȃ��Ƃ������Ă����B���̎��������Ă����ǂł́A�r������L���X�^�[���o�Ă��ĊJ�[���n�܂�A���ꂪ��������I���Ƒ����ă��C����ʂł̓o���[���p������A�����Ɖ��̃T�u��ʂɂ͊e���}�́g���m�X�R�A�h���o��悤�ɂȂ��āA�����ɂ͓�̃Q�[���E�X�R�A�������i�s���Ă����̂ł���B
�@
��A�A�ڂ��͋v�X�Ƀ����e�[�j���́w�G�Z�[�x��ǂ݂����Ȃ��Ă����B�I���ɂ����o�Ȃ��������̂́A�����e�[�j���͂���g�c���h�������B���e���l�Ɏs���ƂȂ�A����������A�����̎Љ�ɐi�s���鐔���̏o�������牓������ē��X�𑗂�ɂ͂ǂ������炢�������A���炭�v�������B
�@
��
�@
�����e�[�j���͂���l�Ɋ��߂��A35�̂��납��5�A6�N�������ēǂB�u�ǂ݂Ȃ����v�Ƃ͌���Ȃ���������ǁA�܂��Ƃɏ_�a�ȕ\��ŁA�������f�łƂ��ă����e�[�j�������߂��̂̓��C�X�E�g�}�X�������B�u���͈�l�I�ׂƂ���������e�[�j���ł��ˁv�A���������ăg�}�X�͂ڂ��̖ڂ�`�����݃j�b�R�������B70�N��㔼�A�j���[���[�N�ł̂��Ƃ��B
�@
���{�ɋA���Ă��炭���āw�G�Z�[�x���d����A���ꂪ���ɖ{��6�����������̂ɂ�����Ƃт����肵�����A�R��ׂ�����(�ڂ��������ɖ{��ǂނ̂͂߂��炵��)�A�g�}�g�W���[�X����t���݂ق����Ƃ���ő�1�y�[�W���J�������Ƃ��悭�����Ă���B
�@
�`���A�u���Ԃŕ]���ɂȂ肽���̂Ȃ�A�������Ă����ƋZ�I���Â炵�Đg�����������낤����ǁA����͎������������Ă���̂����炻��Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��A�����g�����̖{�̑�ނȂ̂��v�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ������Ă���B�ӂ���A�����������ƂȂ̂��Ǝv�����B�u�����g�����̖{�̑�ނ��v���A�����B
�@
�w�G�Z�[�x�͒��X�Ƃ�������L�ł���B�܂�Łg����L�h���B38�ʼnB�ق��������e�[�j�����u���w�̏��_�̉��v�ɓ����āA�]���������������đ��낤�Ƃ������k�J�ǂ̕���L�ł���B
�@
������16���I�̒����̕���L������A���{�ł����ΐ퍑����̉Q���Ō�����������������Ƃ����̂ɋ߂��A���������o�傪����B
�@
���V�A���E�t�F�[������16���I�́u���������炵�̐l�Ԃ̐��I�v���ƌ������悤�ɁA���̎���͍������M�����m�����E�l���悭�������B�@���푈�̎���ł����āA�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g���݂��Ɍ����Ƃ��Ă����B�����̓��{�ɑ����Ă����A��������ƐV���̓�吭�}�̂ǂ����I�Ԃ��Ƃ����A�t�����X�����߂đ̌�����I���̎��ゾ�����B
�@
����Ȉړ��ƑI���̎���̂Ȃ��ŁA������孋����ĉ����������ĉ߂������Ƃ����̂́A�����̎���炷��Ƃ����Ƃ��ɓ˔�Ȃ��Ƃł���B�����������e�[�j���́A�����Č�����ނ����B�x�T�ȉƂɈ���Ă������Ƃ��A���̌��f���y�ɂ����B�����͒ǂ��߂��Ă����������Ƃ͂������Ă���B����ł��A�����e�[�j���́u���͂��ꂩ��͂�������Ȃ��v�ƌ��S���āA�����Љ��ނ����B
�@
�w�G�Z�[�x�͂����ւ�ɂ�����肵�Ă���B���͂����s�̑��x�ŒԂ��Ă���B
�@
����̓����e�[�j�����g�ɂƂ��Ă��A�V���Ɍo�����邱�ƂɂȂ����u�v���̑��x�v�ł������낤��(�����������Ƃ������̂̓����e�[�j�������߂Ăł���������A���́u�v���̑��x�v�����̌�̃��[���b�p�ɂ�����G�b�Z�C�̕�^�ɂȂ����̂���)�A�����ǂނ����ɂƂ��Ă��A����͊܂݂̑������x�ł���B�ڂ��́w�G�Z�[�x��ǂ݂͂��߂�1���Ԃقǂ������Ƃ��A���̊ɂ₩�Ȏv�l���x�����w�G�Z�[�x�����j���ĉ��x�����x���ǂp����Ă������͂Ȃ̂ł��낤���ƂɋC�������B
�@
�����łӂƁg�v���h�Ƃ������t���v�������B�g�v���h�́A�ڂ��������e�[�j���ɕ����������̂悤�Ȃ��̂ł���B���̏O�c�@���I�����߂��邢�������̏o�����̂ǂ������肷�邩�Ƃ����ƁA���́g�v���h���Ȃ����炾�����B
�@
�~�V�F���E�h�E�����e�[�j���̓}���[�m�̌����e��������Ă���B�X�s�m�U�Ɠ����ł���(��842��Q��)�B�����e�[�j�������E�s�����������Ă���ƌ����Ă����̂́A���̌��Ɩ��W�ł͂Ȃ��B�}���[�m�ł͂��邪�A�T���ȏ�قŐ��܂������B���܂��ɕ��e��1554�N�Ƀ{���h�[�̎s���ɂȂ����B
�@
���̕��e�ɂ���ă����e�[�j���͉p�ˋ�����������B2����̃��e����̉ƒ닳�t�Ɏn�܂�A6����̃R���[�W���E�h�E�M���C�G���k�A�Ñネ�[�}�̎����Ƃ̏o��A�{���h�[��w�ł̓��X�A�@�w���w�g�D�[���[�Y��w�Ȃǂ������ɒʉ߂��āA�㊥24�Ń{���h�[�����@�@�̍ٔ���(�]�芯)�ɂȂ����B����͗ljƂ̎q�����G���[�g�ɂȂ��������̂��ƁA���̂܂܂Ȃ烂���e�[�j���͂����̓c���ɂȂ��Ă������낤�B
�@
���A�����@�@�̓����ɃG�`�G���k�E�h�E���E�{�G�V�[�������B�����ŁA�Ⴍ���Đ[���������������B���̃{�G�V�[�Ƃ̏o��������e�[�j�����������B����A�ς����B���̐e�F�͂킸��30���������ʼnu�a�ɓ|��Ď��̂ł���B
�@
�����e�[�j�������̗F�l��������̂͊i�ʂ������B�u���E�{�G�V�[�ƕt��������4�N�Ԃɂ���ׂ���A����ȍ~�̐l���Ȃ�ĈÂ��đދ��Ȗ�ɂ����Ȃ��v�Ƃ��������Ă���B�l�͂Ƃ��Ɂu�l���v�����u�r���v�@�Ɏv����s�������f������̂Ȃ̂��B
�@
�w�G�Z�[�x�͈ꋓ�ɏ��������̂ł͂Ȃ�����A���낢��̎����̃G�b�Z�C�������Ă���B���������͎��M���ɕ���ł��邪�A���Ƃʼn��x�����M���������Ă���̂�(��������Â���̂������e�[�j���̊y���݂ł��萶�����ł��������B��879��̈�_����̂悤��)�A�ǂ��̕����������̃����e�[�j���̕��͂ŁA�ǂ����~�n���̃����e�[�j���Ȃ̂��͋�ʂ����ɂ����B
�@
�������ŏ��̂���̃G�b�Z�C�́A�����炩�Ƀ��E�{�G�V�[���������߂��݂��̂肱����悤�ɂ��ĕ��͂��Ԃ��Ă���B�G�s�N���X��Z�l�J��L�P���̓N�w����āA�Ȃ�Ƃ��r���⓮�h��߈����������悤�Ƃ��Ă���̂��`����Ă���B�����炱�̎����̃����e�[�j���͒Ԃ邱�Ƃ�ʂ��āA�Ñ�M���V�A�̓N�l���������u�A�^���N�V�A�v(�S�̕���)���߂Â��悤�Ƃ��Ă����ƌ�����B
�@
�����e�[�j���̓��E�{�G�V�[�Ǝ��ʂ���2�N��Ɍ������A�Â��ĕ��������āA�̎�ƂȂ����B���ւɗ����������Ƃ��͂��߂�̂͂�������ŁA�Ƃ�킯1569�N�Ƀ��C�����E�X�{���́w���R�_�w�x�����e���ꂩ��|���̂����������ɁA�������ɓǏ��O���E���M�O���ɌX���Ă������B
�@
����ǂ��A���̎����̃����e�[�j���͂܂��u�A�^���N�V�A�v�ɂ͉��������B�v���������قǁA���M�������قǁA�ϑz�̂��Ƃ����^��������B�����������e�[�j���͂��̓�������N���オ���Ă�����^�������Ɉ���Ȃ������B�d�������B���ꂱ�����̂��Ƀf�J���g�ɉe����^�������^�̐��_�ł���B
�@
�����e�[�j����ǂނƂ́A���̗N���オ����^�̑O�ŗ����~�܂郂���e�[�j�����A�������ɂ��̉��^�̏�ʂ��玩�g����Ă����A���������I�g���܂�ʎ����Ől�Ԃ̐��߂�悤�ɂȂ��Ă����Ƃ����ǂނ��ƂȂ̂ł���B
�@
�Ȃ�قǃ��C�X�E�g�}�X�����߂��̂͂����������̂ł���B���^����ڂ����炳���A�����̉��^�𗣂�Ă������ƁA�����Ƀ����e�[�j���̐^�������������B
�@
�����ЂɁu�N�Z�W�����Ɂv������B�t�����X�̓����̕��ɂ̖|��V���[�Y�ŁA�ڂ������ł��̂������\���������b�ɂȂ��Ă����B���̃N�Z�W���́gQue Sais Je ?�h�ł���B�u�����������͉�����m���Ă���̂��낤���v�Ƃ����Ӗ��ŁA���ꂱ���̓����e�[�j�����L���ɂ����u�₢�v�������B���^�̂��߂́u�₢�v�������B
�@
�����e�[�j���̉��^���Ȃ킿�N�Z�W���́A�f�J���g��q���[���Ƀq���g��^�����قǂ̐V�����N�w�̉萶���ł������B���^��^�O�����Ƃ������Ƃ́A���ꂪ�����܂ł̎��Ԃ����ׂĈ�����Ƃ������Ƃł���B�����e�[�j���̕��͂ɂ͂��̂悤�ȃN�Z�W����������鎞�Ԃ��̂��̂��Ԃ��Ă���B�Ƃ��낪�A���̈������̃v���Z�X�ŁA�����e�[�j���͂ӂ��ɔ��B�܂��A�e������B���Ȃ킿�A�N�Z�W���Ɏn�܂�v�����̂Ƃ��Ȃ�����A�������琶����v���̕��@�Ɋւ������߂��������ɔ�������B���̏������́A��C�ɂ��m�ւɂ����Ă���B��C���m�ւ����^�������ď����͂��߁A�r���łЂ�߂��A�e�������Ȃ�����B
�@
���̏������A���̎v���̕��@�́A�����e�[�j�����g�̌������ɂ��Ɓu��F�̐��n�̌���f����ɂ́A������̂ق����炿��肿���ƁA�����������王���𑖂点��v�Ƃ������@�ł���B�S����6���ɂ킽��g�v���h�́w�G�Z�[�x��ǂނ̂��Ȃ��������낢���Ƃ����ƁA���̕��@�ɏo��邩�炾�����B
�@
�Ƃ���ŁA�w�G�Z�[�x��2�������������Ƃ���ŁA�����e�[�j���͂ӂ����ь����Љ�ɌĂі߂���A���e�Ɠ��l�̃{���h�[�s����2���Ƃ߂��B����͂܂��ɓc���ł���B
�@
�����������e�[�j���̓J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�̒��������̂ɔ��A�u�V���c�𒅂��ȏ�̓V���c�𒅂��l�ԂƂ��ĐU�镑�����A�V���c�Ɣ畆�Ƃ͈قȂ���̂��v�ƌ����āA�܂��܂��V���c��E���ł��܂��̂��B�������炪�w�G�Z�[�x3���ȍ~�ɂ�����B�����烂���e�[�j���̐^�����ɏo���̂́A3�������ɂȂ�B
�@
���̂悤�ȁw�G�Z�[�x�����ǂڂ��Ɏ����������Ƃ́A�u���������ɓ���Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������B
�@
���������l�ԂƂ������̂́A�w���ɂȂ�Ίw���ɂȂ����ŁA�d���ɂ��Ύd���ɂ����ŁA��������Ό��������ŁA���e�ɂȂ�Ε��e�ɂȂ����ŁA�����Ƃ�ٌ�m�ɂȂ�Ƃ܂����̕��ۂŁA���̎Љ�̑S�̂�������Ɍ���������̂ł���B�Ƃ��ɑI���ɏo�鐭���Ƃ͎�����������ɂ��邾���ł͂Ȃ��A�Љ�����傾�Ǝv�����ށB�܂�u���������ɓ���悤�v�Ƃ���B�����āA�ǂ����A���ɓ��ꂽ���A�s�ޓ]�̌��ӂ����Ƃ���B
�@
�����A����Ȃ��Ƃ͂߂����ɐ��藧�͂��͂Ȃ��A�����Ă��͂��̎�����ꂽ�����点�邾���Ȃ̂��B
�@
�����e�[�j���͂��̂��Ƃ��悭�������Ă��āA�ǂ�Ȃ��̂ɂ����������ɓ���Ĉ̂��邱�Ƃ����߂��B�����āA�������炸��鎩���̂ق������߂邱�Ƃ����߂��B���́u����v�����̂܂ܒԂ邱�Ƃ��A�܂��A�G�Z�[(�G�b�Z�C)�Ƃ����V�����v���L�q�̕��@���������������킯�Ȃ̂ł���B
�@
�����炱���A�s�����Ƃ߂������e�[�j���͎����̂��Ƃ��A������`���Ă͂��邱�Ƃ��Ȃ������̂ł���B�u�����͋`���E�ΕׁE���E�s���̌��R����G�ł���v�B
�@
���Ȃ݂Ƀs�G�[���E�O���[�h�́w�G�b�Z�C�Ƃ͉����x�Œm�����̂����A�G�b�Z�C�Ƃ����̂̓��e����́u���v����h���������t�ŁA���ł̌v���̂悤�ȈӖ��������Ă����B
�@
�Ƃ������Ƃ́A�����A�����A�T�����݂�ȃG�Z�[�ł���A�����⌟����T�������A���Ȃ����Ƃ��܂��A�G�Z�[�Ȃ̂ł���B�ڂ��Ƃ��ẮA���ꂩ����ڐ��̂Ȃ����Ƃ��ẴG�Z�[�̌������������B�����Ɏ����Ȃ����������G�Z�[�Ƃ��Ă��������B���������A���������ɓ���Ȃ���������I�������B�@ |
���u�����e�[�j�����z�^���v
�@
�����I�E�@���I�����̉Q���Ɏ����ƂƂ��Đ������o���ƁA�Ⴂ�Ƃ�����e���ÓT�̖L�x�Ȓm�������ƂɎ��M���ꂽ�u���z�^�v�́A��������[���l�ԓ��@�Œm����B�e����ɖ|��čL�͂ȉe�����������A���ꎩ�g�����[���b�p���\����ÓT�ƂȂ����B�{���͂��̍_�j�ȌÓT��S����҂��A�Ǝ��ɗ��Ă��e�[�}�ʂɁA���{�̍��q������I��ŕҎ[�������̂ŁA�ǂ�����ǂ�ł��悢�i�D�́u�����e�[�j������v�ƂȂ��Ă���B
�@
�����e�[�j��(1533�`92)��t�����X�E�y���S�[�����܂�̓N�w�ҁA�������X�g�B��15�N�ԃ{���h�[�s�̕]�c���߂����ƁA���E��ނ��A���܂�̋��̃����^�[�j���̋���ɂ������āu���z�^�v�̎��M�ɐ�O�����B�ꎞ�͍Ăу{���h�[�ɏo�Ďs���߂����A�ēx�B�������ɂ��ǂ��āu���z�^�v�̉��M�E�����ɐ����o�����B�t�����X�@���푈�̎���ɂ����āA�����e�[�j�����g�̓��[�}�E�J�g���b�N�̗���ł��������A�v���e�X�^���g�ɂ��l���������A�����h�Ƃ��ė��h�̗Z�a�ɓw�߂��B
�@
�m���n�M�a��]����(�낭�܂�����)�͂��炭�����B�u���^�[�j�����Ƃ����邨�������A�킽���̗אl�@���N�������g�̃��I��������̍ۂɁA�Q�O�ɂ����Ԃ���Ď��Ȃ�悤�ȂǂƂ́A���������N���\�z�������B���܂��͂����̉��l�̈�l����V�Y�Œ��Ɏ��Ȃꂽ�̂����Ȃ��������B�܂����̂���c�̈�l�͓ɓ˂����Ă��Ď��ɂȂ��ꂽ�ł͂Ȃ����B�G�X�L���X�͉Ƃ̉��~���ɂȂ��Ď��ʂ��Ƌ�������Ă���A�����イ��V�ɕ�炵�������߂������B�Ƃ��Ƃ����������h(�킵)�̒ܐ悩�痎���Ă����T�̍b�̉��ɂԂ���Ď��B����҂͂Ԃǂ��̎�q�̂��߂ɁA����c��͔�������������Ȃ��瓾�����̂��߂ɁA�G�~���E�X�E���s�h�D�X�͓������(������)�ɑ����Ԃ������߂ɁA���ꂩ��A�E�t�B�f�B�E�X�͉�c���ɂ͂��낤�Ƃ��Ĕ��ɂԂ��������߂ɁA���B����A���̂܂��̊ԂŁA��s�R���l���E�X�E�K���X�A���[�}�x�@�R�̏��e�B�M���k�X�A�c�c���ꂩ��Ȃ����������Ƃɂ̓v���g���w�҂̃X�y�E�V�b�|�X�A���ꂩ��킪�@���l�̂���l�́A�����ɂȂ��ꂽ�B���킢�����ɍٔ����̃x�r�E�X�͑���ɔ����Ԃ̎��s�P�\��^�����Ƃ���A���̊ԂɎ����̖��̕�����������Ď���ł��܂����B�܂���҂̃J�C�E�X�E�����E�X�͕a�l�̊�̎��Â����Ă���ԂɁA�}�Ɏ��ɏP���Ď����̕�������Ԃ炳�ꂽ�B�����������Ă���ɉ�����Ȃ�A�킽���̒�̈�l�J�s�e�[�k�E�T���E�}���^��(��\�O��)�́A�Ƃɂ��̗E�C��F�߂��Ă������A���鎞�|�[���̗V�Y���ɉE�̎��̏�����̂Ƃ�������ɑł��ꂽ�B�\�ʂɂ͂����菝���ł����������Ȃ��������A���̂��߂ɂ��������Ȃ���x�݂����Ȃ��������A���ꂩ��܁A�Z���Ԃ����đ����Ŏ��B��͂苅�ɓ������������ł���B����Ȏ���́A����Ȃɂ����A����Ȃɏ�X�A�����̊�O�Ɍ�����̂����́A�ǂ����Đl�́A���Ƃ����l������������邱�Ƃ��ł��悤���B�ǂ����Ď����I�n�����̍A���Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��v��Ȃ��ł����悤���B
�@
�N�����͌����邩������Ȃ��B�u����͂ǂ�Ȃӂ��ɂ��悤�Ƃ��܂����̂��B��ɂ��Ȃ��������v�ƁB�킽���������v���B�����āA�ǂ�ȕ��@�łȂ�Ǝ��̏P��������������̂Ȃ�A�(������)�̔�����Ԃ邱�Ƃ����Ă����B�킽���͂�������݂Ȃǂ��Ȃ��B�܂������킽���́A���y�ɉ߂��������������ł悢�̂��B����킽���́A�������Ƃ肤��ŏ�̕��@���Ƃ�B���ꂪ�ǂ�Ȃɕs���_�Ȏ����ɂȂ�Ȃ����@�ł��낤�ƁB
�@
�킽���͌����ċꂵ�ނ��́A�ނ�����҂�Ƃ�������ꂽ���B
�@
�ǂ�����T(���тイ)���킽�����K���ɂ��A�킽���̊������܂��Ă���܂��悤�ɁI(�z���e�B�E�X)
�@
�����������A����Ŏ������ނƍl����̂͂��납�ł���B�l�X�͉������藈����A���͂˂���A������͉��̕ւ���Ȃ��B���͏t���B�����ЂƂ��ю����A���邢�͔ނ�݂�����̏�ɁA���邢�͂��̍Ȃ�q��F�ɁA�˔@�Ƃ��āA�s�ӂɁA����ė��Ă݂��܂��B�ǂ�Ȃɔނ�͋��(������)����������������]���邩�B����ȂɋC�𗎂Ƃ��A����Ȃɕς��ʂāA����ȂɋC���������҂��A���Č������Ƃ����邩�B�ǂ����Ă��������炻��ɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̒{���̂悤�Ȗ��ڒ��́A����Ɍ含�̂���l�̔]���ɏh�邱�Ƃ�����ɂ��Ă��A(����͑S�R�s�\���Ƃ킽���͎v���̂���)���̏��i�����܂�ɍ��������ɔ������B�������ꂪ��������G�ł���Ȃ�A�ڋ�(�Ђ��傤)�Ƃ����������邱�Ƃ��A�킽���͂����߂邾�낤�B���������͂䂩�Ȃ��̂�����A�m���n����͌N���A�������̉��a��(�����т傤����)�ł����Ă��A�܂����h�ȗE�m�ł����Ă��A�����悤�ɕ߂炦��̂�����A�c�c�ǂ�ȂɌ��łȓS�̊Z(��낢)���N���܂���Ȃ��̂�����A�c�c�m���n��������Ƒ����ӂ܂��Ă�����Ƃ߂邱�Ƃ��A���₱���ł��|�����Ƃ��A�w�ڂ��ł͂Ȃ����B�����āA�܂��ނ��炻�̂����ɑ���ő�̋��݂���菜�����߂ɁA�S�R���ʂ̂Ƃ͂��ׂ��ׂ̓�����낤�ł͂Ȃ����B�ނ�����ق���菜���āA�ނƊ���e�������ł͂Ȃ����B�����������Ύ���]���ɂ��Ƃ��ł͂Ȃ����B��ɂ��������A���������̂��ׂĂ̌`���ɂ����āA�S�̒��Ɏv���݂悤�ł͂Ȃ����B�n���܂����Ă��A��(�����)�������Ă��Ă��A�s����������ƈ�������Ă��A�����������(�͂�)���悤�ł͂Ȃ����B�u�ǂ����낤�B���������ꂪ���ł�������H�v�ƁB�����āA�����Ŏ��Ȃ�b�B���悤�ł͂Ȃ����B�j�����ƁA�y���݂��Ƃ̍Œ��ɂ��A��ɂ����̋������v���o�����邠�̂���Ԃ����̂����ł͂Ȃ����B���܂�Ɋ��y�ɖ����ɂȂ��āA�������������̊��삪�ǂ�Ȃӂ��Ɏ��̑O�ɂ��炳��Ă��邩�A�ǂ�Ȃɂ��т��ю������̊��y�ɂ��݂����낤�Ƃ��邩��Y��Ȃ��悤�ɂ��悤�ł͂Ȃ����B���̂悤�ɃG�W�v�g�̐l�����͂������̂ł���B�ނ�͂��̉���̍Œ��ɁA��������(����݂�����)�̊ԂɁA���҂̃~�C���������ė������āA��H�҂����ւ̌x���Ƃ����̂ł���B
�@
�����͂������܂��̍Ō�̓����ƍl����B
�@
��������Ύv��ʍ������(����)�����Ċ�Ԃ��Ƃ��ł��悤�B(�z���e�B�E�X)
�@
�ǂ��Ŏ���������҂��Ă��邩�킩��Ȃ��B�����炢����Ƃ���ł����҂Ƃ��ł͂Ȃ����B���̏����͎��R�̏����ł���B�����w�т����҂͋��]��Y�ꂽ�B�����Ɏ����ׂ�����m��A�����͂������]�ƍS���Ƃ����������B�m���n�����̔��D(�͂�����)���s�K�łȂ��킯����肦���҂ɂƂ��ẮA���̐��ɉ��̕s�K���Ȃ��B
�u���ɂ��āv���@ |
���u�����e�[�j�����z�^�v�ݓc���m
�@
���͖{�N�x���|���b��܌���i�Ƃ��āA�֍��G�Y��u�����e�[�j�����z�^�v�𐄑E�������̂̈�l�ł���B
�@
�������{���𐄑E�������̉�������́A��������ꂼ��̗��R�����Ă�锤�����A���͓��Ɉψ���̎w���ɏ]�āA������̐��E���R�����\���邱�Ƃɂ���B
�@
��A���|���b��܂͖|��ɂ��^�֓���K�肪����ȏ�A���N�Ƃ��ӂ킯�ɂ͍s���܂����A���ɖ|�w�j��c���I�Ȏ��n�ƌ���ׂ����̂ɂ́A�����K�p���ׂ��ł���Ƃ��ӂ̂����̈ӌ��ł����B�K�Ѝ�N�x�ɉ��āA�֍��G�Y���́u�����e�[�j�����z�^�v�O���̖��������A���Ƃ̊Ԃ͖ܘ_�A���������l�X�̖����v�I�]�������Ƃ��猩�āA�{���̔@���͍ł��K���Ȍ���i�ł���Ǝ��͐M�����B
�@
��A�|��̉��l�͉��ɂ�Č����邩�Ƃ��Ӗ��́A�r���f���P�G�g�ł���B����A�n��Ƃ̔�r�]���̔@���́A�܂������Ӗ��ɋ߂��B���A�������A�|��̂�����������ԂƂ��ӏꍇ�ɁA���炻�̔��f�ɂ͊��������Ǝv�ӁB���w�ӏ܂̑ԓx�ɁA������̕��������ӂ̂Ɠ��l�ł���B���͎��̏��_����A�֍��N�̖�Ƃ���N�x����ƒf�肷��B
�@
�C�@�����̌ÓT�I�A�����I���l�B
�@
�u�����e�[�j�����z�^�v�͕��������w�̗L����A�ł��M�d�ȌÓT�̈�ł���݂̂Ȃ炸�A�ߑ�v���̈�匹��Ƃ��āA���E���|�j��A���̉e�����r���[���A�L���A������I�ł���B�]�ӂ܂ł��Ȃ��A�ߑ㕶�����t�����ɉ��āA�������������̗ǐS�Ɖb�q�̏����A����̓��{���炳��Ĕ@���Ȃ�Ӌ`�����邩�Ƃ��ӂ��Ƃ́A�N������Â���ꕶ�w�҂��l�Ȃ��Ă͂Ȃ�ʂ��Ƃł���A�Ǐ��̖��x�̊�����m�炵�߂邱�ƁA�����A���̏��ɔ@�����̂͂Ȃ��Ǝ��͍l�ւ�B
�@
���@���̖|��͒N�ɂł��o����Ƃ��ӂ₤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���ۗD�G�Ȗ�Ƃ��͂��₤�Ȃ��̂̂����ɂ��A�N����Ă���������ł́A���̒��x�̂��̂ɂȂ�Ƃ��ӎ�ނ̂��̂��������A���́u�����e�[�j���v�́A�H�L�ȋ��{�ƍ˔\�Ɠw�͂Ƃ�ւāA�͂��߂Ă悭�����̐^�ʖڂ�`�֓�����̂ł���A��ɂ��̕��̗̂����ƖM��\���ɂ́A��Ҏ��g�́u�����e�[�j���v�I�Ƃ��v�͂�镗�i��K�v�Ƃ���̂ł���B�֍��N�́u�����e�[�j���v�́A���ɁA�����܂ł̓��{�ɉ��āA���l����ċy�Ȃ����₤�ȁA�����ƖƂ̔����ȏƉ��������A���炭���S�ȈӖ��ɉ�����u�����e�[�j���v���{�ꌈ���Ƃ��āA���E�Ɍ֎�����ɑ�����̂ł���B
�@
�n�@�u�����e�[�j�����z�^�v�̖|�����̓��{�ɉ��āA���w�܂��l������Ƃ��ӎ���I�Ȍ��ۂɂ��āA���́A������ʂ̒��ӂ����N���A���ɁA���O���̎��҂ɂ��̃j���E�X��`�ւ����v�ӁB����͉������Y�قɁA�䂪���̕��d(�Ⴕ���d�������F�߂�Ȃ�)���A�������͊K���̔������Ɩ֖��ɍS�͂炸�A��ɐi���Ǝ��R�̖����ł��邱�Ƃ���蓾����̂��ƐM���ċ^�͂Ȃ��B���̖|�����\�N�������ɏo�ŁA���{�̑�w���̑啔���������ǂ�ł�Ȃ�A�����͂����������̒������邭�ȂĂ�炤�Ǝv�ӂ����ł���B(���O�Z�E��)�@
�@ |
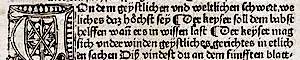 �@ �@
���}���R�E�|�[���u���E�̕s�v�c�����������^���v 1590�N |
   �@
�@
|
Polo, Marco.(1254-1324)
�@
Delle meraviglie del mondo per lui vedute;
�@
�u���������^�v�̓}���R�E�|�[�����A1270�|95�N�ɂ킽�铌�����s�œ����m�����L���ƃ����ɂ���ăt�����X��Ō��q���A������s�T�̕����ƃ��X�e�B�`�A�[�m���L�^�������̂ł���B���̓��e�͏��͂ł��̗��s�����s���ꂽ�o�܁A�����Ɏ����Č����Ɏd�����͗l����уC���E�n�[�����̎g�b�ɓ������ċA������ɂ�����������𗪏q���A�����{���ł͐��E�����A�W�A�����f����s���̎q�ׁA�����S������̏�����A�����������s�œ��������A�A�H�̍q�C�Ōo�߂�����C�����̎�������Ă���B�{���́A���l�T���X���ɂ����郈�[���b�p�́A�����Ɋւ���B��̒m���̌���ƂȂ����B�܂��{���ɂ���ē��{���u�����̍��W�p���O�v�Ƃ��Ă͂��߂Đ��m�ɏЉ��A�R�����u�X�̐V�嗤�����̂��������ƂȂ����Ƃ������Ă���B���X�e�B�`�A�[�m�̋L�^�����c�{�͂��Ԃ�C�^���A��ŏ����ꂽ�̂ł��낤���A���łɎU�킵�A��������̂͂���Ɋ�Â����l�̌Îʖ{�A�ÔŖ{�ł���B�@ |
�����������^
�@
�}���R�E�|�[�����A�W�A�����Ō����������e���q���A���X�e�B�P���E�_�E�s�T���̘^�Ҏ[�������s�L�ł���B���{�ɂ����Ă͈�ʓI�Ɂw���������^�x�Ƃ������Œm���Ă���A�w���E�̋L�q�x("La Description du Monde")�Ƃ��Ă��B�܂��A�ʖ{���ł́A�w�C���E�~���I�[�l�x("Il Milione"�A100��)�Ƃ����^�C�g�����L���ł���B����́A�}���R�E�|�[�����A�W�A�Ō������𐔂���Ƃ������u100���v�ƌ��������ƂɗR������B
�@
1271�N�Ƀ}���R�́A���j�R���Əf���}�b�t�F�I�ɓ�������`�ŗ��s�֏o�������B1295�N�Ɏn�܂����s�T�ƃW�F�m���@���a���Ƃ̐킢�̂����A1298�N�̃������A�̐킢�ŕߗ��ƂȂ������X�e�B�P���Ɠ����S���ɂ������Œm�荇���A���̏������q�����Ƃ����B
�@
���������^��4���̖{����Ȃ�A�ȉ��̂悤�ȓ��e���L�q����Ă���B1���� / �����֓�������܂ł́A��ɒ������璆���A�W�A�ő����������Ƃɂ��āB2���� / �����ƃN�r���C�̋{��ɂ��āB3���� / �W�p���O(���{)�E�C���h�E�X�������J�A����A�W�A�ƃA�t���J�̓��C�ݑ����̒n��ɂ��āB4���� / �����S���ɂ�����푈�ƁA���V�A�Ȃǂ̋ɖk�n��ɂ��āB
�@
�������̍��W�p���O
�@
���{�ł́A���[���b�p�ɓ��{�̂��Ƃ��u�����̍��W�p���O�v(Chipangu)�Ƃ��ďЉ���Ƃ����_�œ��ɂ悭�m���Ă���B�������A���ۂ̓}���R�E�|�[���͓��{�ɂ͖K��Ă��炸�A�����ŕ������\�b�Ƃ��Ď��^����Ă���B�Ȃ��A�u�W�p���O�v�͓��{�̉p���ł���u�W���p���v(Japan)�̌ꌹ�ł���B���{��(������ŃW�[�x���O�H)�ɗR������B
�@
���������^�ɂ��ƁA�u�W�p���O�́A�J�^�C(�����嗤)(���Ђɂ���ẮA�}���W(�����̒�����)�Ə�����Ă�����̂�����)�̓��̊C��1500�}�C���ɕ����ԓƗ����������ŁA����ȋ����Y�o���A�{�a�▯�Ƃ͉����łł��Ă���ȂǁA����Ɉ��Ă���B�@�܂��A�W�p���O�̐l�X�͋������q�҂ł���A�O�����悭�A��V���������A�l�H���̏K��������B�v�Ƃ̋L�q������B�u����ȋ����Y�o���v�Ƃ����͉̂��B�̋��Y�n���w���A�u�{�a�▯�Ƃ͉����łł��Ă���v�Ƃ����̂͒��������F���ɂ��Ă̘b�������̂ł���Ƃ̐�������B
�@
�����z
�@
�����̃��[���b�p�̐l�X���炷��ƁA�}���R�E�|�[���̌����Ă������e�͂ɂ킩�ɐM����A�ނ͉R���Ă�肳�ꂽ�̂ł��邪�A���̌㑽���̌���ɖ|��A��ʖ{�Ƃ��Đ��ɍL�܂��Ă����B��̑�q�C����ɑ傫�ȉe����^���A�܂��A�W�A�Ɋւ���M�d�Ȏ����Ƃ��ďd�ꂽ�B�T���Ƃ̃N���X�g�t�@�[�E�R�����u�X���A1438�N����1485�N���ɏo�ł��ꂽ1���������Ă���A�������݂͌v366�ӏ��ɂ��j���Ă���A���̂��Ƃ���A�W�A�̕x�ɑ���ȋ������������ƍl������B�c�{�ƂȂ�n���{�͑�������U�킵�A�e�n�ɒf�ГI�ʖ{�Ƃ��ė��z���Ă���A���S�Ȍ`�Ŏc���Ă��Ȃ��B���������ʖ{�́A����138�킪�m�F����Ă���B
�@
���e��
�@
1300�N���}���R�E�|�[�����{���Łu�����S���鍑�v���Љ���悤�ɁA�C�u���E�o�b�g�D�[�^��C�E�S���T���X�E�f�E�N�����B�z(�p���)�������̏���`�����B
�@
1355�N�ɂ̓C�u���E�o�b�g�D�[�^�̌��q���C�u���E�W���U�C�[(�p���)���M�L�����u���s�s�̐V��Ɨ��̋��قɊւ���ώ@�҂����ւ̑��蕨�v�Ń}���[�����ɁA�W���`�E�E���X[1]�E�g�D�O���N��(�C���h)�E�T���h���E�p�T�C����(�X�}�g��)�E�V�����[���B�W��������(�}���b�J)�E�}�W���p�q�g����(�W����)�E��[2](��s�̑�s�A�������E�ő�̖f�Ս`�̈��B)���Љ���B�C�u���E�o�b�g�D�[�^�̖|���[���b�p�ɂ����炳�ꂽ�̂�19���I�ɂȂ��Ă���ł���B
�@
1406�N�ɂ̓��C�E�S���T���X�E�f�E�N�����B�z(�p���)���u�e�B���[���I�s(�X�y�C�����)�v�ŁA�����S���鍑�̌�p���Ƃ̂ЂƂu�e�B���[�����v���Љ���B�������A1396�N�ɏ\���R�ƃI�X�}���鍑�̊Ԃōs��ꂽ�j�R�|���X�̐킢�̉e������A�����C�X�������Ƃł���e�B���[���ɑ��郈�[���b�p�Љ�̔����͗�߂����̂ŁA���������^�ɑ���悤�ȔM���͋N����Ȃ������B
�@
���̌�����������^��������q�C����̒T���ƂɂƂ��āA�A�W�A��ڎw�������͂Ƃ��ċ@�\���A�R�����u�X�E�R���e�X�A�}�[�����炪���[���b�p�̔��l���E�ɕx�������炷���ƂɂȂ����B
�@
16���I�����ɂ́A�|���g�K���l�g���E�s���X(�p���)���A�}���b�J�ɑ؍݂��Ă������Ɍ������������܂Ƃ߂��w���������L(�|���g�K�����)�x�����B�@�@
�@ |
 �@ �@
��17���I�@�ߑ�Ȋw�ւ̑D�o / ���L���͂̔��� |
   �@
�@
|
���̎���́A�u��@��17���I�v�ƌĂ��B�ُ�Ȋ��C�ɂ���ċ��삪�����A�y�X�g���͂��߂Ƃ��邳�܂��܂ȉu�a�����s������A�@����̑Η��ɋN������푈����������������B���یo�ς͕s�U�Ɋׂ�A�o�ϓI�g��̏I�����}���A�l����������B�t�����X�ł̓��C14���ɂ���Ύ�`���m�����u��Ύ�`�̎���v�Ƃ�������B���̔��ʁA�R�y���j�N�X�̒n�����́A�C�^���A�̃K�����C��h�C�c�̃P�v���[��̎�ʼnȊw�I�ɏؖ�����A�܂��C�M���X�̃j���[�g���ɂ���Ĕ������ꂽ���L���̖͂@�������w�I�ɏؖ������ȂǁA���R���ۂ𐳂��������I�Ɍ��ɂ߂悤�Ƃ���g�Ȋw�v���h���N�����B���̑��ɂ����܂��܂ȉȊw�I�����┭�����Ȃ���A�܂��Ɂu�Ȋw�̐��I�v�ƌĂԂɂӂ��킵������ƂȂ����B�@�@
�@ |
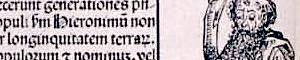 �@ �@
���o�C�A�[�u���}�v���� 1603�N |
   �@
�@
|
Bayer, Johann.(1572-1625)
�@
Uranometria...
�@
�o�C�A�[�̓h�C�c�̓V���w�ҁB�ٌ�m���ƂƂ����B�Ñ�̐��}�́A�V���V�Ɠ��l�ɓV�����F���̊O���璭�߂��悤�ɁA���Ȃ킿����𗠕Ԃ��ɕ`�������̂������������A�{���́A���Ԃ��łȂ��ŏ��̐��}�ł���B�܂��A�ߐ��ɂȂ�Ƒ�q�C����ɓ���A�����̍q�C�҂��씼���̊C�ɏ������悤�ɂȂ�A�V�����������������ꂽ�B�o�C�A�[�͂���������V��12���������߂Ė������A�{���Ŕ��S�V��51���ɕ`�������}��\�����B���̒��Ńo�C�A�[�́A���̈ʒu���L�q���A�M���V�������Ƃ��ꂪ�������鐯���ɂ���Đ��𖽖�������@�������B���̐��}�̐��ɗ^����ꂽ�M���V�A���������́A���ł��L���g���Ă���B�{���́A���S�Ȑ��}����邽�߂̍ŏ��̎��݂ł���A������ꂽ�ŏ��̐��}�ł���B�@ |
�����n���E�o�C�G��
�@
(Johann Bayer, 1572-1625) �h�C�c�̖@���ƁB���̓��[�n���Ƃ��A���̓o�C�A�[�Ƃ��o�C���[�Ƃ��\�L���邱�Ƃ�����B�o�C�G���́A1572�N�Ƀo�C�G�����n���̃��C���Ƃ������ɐ��܂ꂽ�B1592�N���C���S���V���^�b�g�Ŋw�сA��ɃA�E�N�X�u���N�Ɉڂ�Z�݁A���U�̂قƂ�ǂ������ʼn߂������B�A�E�N�X�u���N�ł́A1625�N�ɖS���Ȃ�܂Ŏs�c��t�̖@���ږ�߂��B1603�N�A31�̂Ƃ��ɑS�V���}�w�E���m���g���A�xUranometria �������B�o�C�G���̐E�Ƃ́A�����ΓV���w�҂Ƃ��ďЉ��Ă���B�������Ȃ���A���������V���w�҂Ƃ̓e�B�R�E�u���[�G��K�����I�E�K�����C�̂悤�ɓV�̊ϑ����s�����A�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X��n�l�X�E�P�v���[�̂悤�ɓV�̗��_���\�z����l���̂��Ƃł��邪�A�o�C�G���͐��}��1�҂����݂̂ŁA����ȊO�̓V�̊ϑ��L�^��V�̗��_�͉���m���Ă��Ȃ��B
�@
����Ƃ̃o�C�G�����V���w�E�ɂ����Ă��̖���m����悤�ɂȂ����̂́A��q�́w�E���m���g���A�x�ɂ����̂ł���B���̐��}���ɂ͂������̓���������A���̓V���w����̋L�q�ɑ���ȉe�����y�ڂ����B
�@
���o�C�G������
�@
�w�E���m���g���A�x������ȑO�̐��}�ƈقȂ��Ă����̂́A�k�����̒��ܓx�n���Ō��邱�Ƃ̂ł��Ȃ��V�̓�ɕt�߂̐��X����Ȃ鐯�������^�������Ƃł���B�����̓o�C�G�������ƌĂ��B�o�C�G�������͎��̂Ƃ���/ �C���f�B�A�����A�J�����I�����A���債���傤���A�����Ⴍ���A��������A����A�Ƃт������A�ӂ����傤���A�ق��������A�݂��ւэ��A�݂����A�݂Ȃ݂̂����� (12����) / �Ȃ��A�u��������v�͓��{�ł́u���������v�ƌĂ�Ă���A�u�݂����v�͌�Ɂu�͂����v�ɉ������ꂽ�B
�@
���o�C�G������
�@
�w�E���m���g���A�x�ł͂܂��A�}�ŏ�Ŋe���ɃM���V�A������[�}������Y�����B����͌�̓V���w�҂ɂ���čP���̕\���@�Ƃ��ē]�p����o�C�G�������ƌĂ��B�o�C�G��������p�����P���̖����@�́A���݂ł������Ɏg���Ă���B
�@
���o�C�G�� - �V���[����l����
�@
�w�E���m���g���A�x���قڎl�����I���1627�N�ɁA�����A�E�N�X�u���N�� �w�L���X�g�����}�x�ƌĂ�鐯�}�������s���ꂽ�B���̐��}�̕Ғ��҂̃����E�X�E�V���[���A�o�C�G���Ɠ���l���ł͂Ȃ����ƍl����ꂽ���Ƃ��������B�V���[���o�C�G���Ɠ����A�E�N�X�u���N�Ŋ��������̎m�ł���A�V���[���܂��o�C�G���Ɠ����@���ł���A�Ƃ��ɐ��}�������s����Ȃǂ̋��ʓ_������ꂽ����ł���B�������Ȃ���A�w�L���X�g�����}�x���J�g���b�N����̋��`�ɑ����č쐬����Ă���̂ɑ��āA�o�C�G���́u�v���e�X�^���g�̌��v(Os Protestantium) �ƃA�_�������قǔM�S�ȃv���e�X�^���g�M�k�ł��������Ƃ���A�݂��ɑR���͂̑��ɂ��������҂�����l���ł������Ƃ͍l���ɂ����A���̐��͌��݂ł͔ے肳��Ă���B�@ |
���w�E���m���g���A�x
�@
(VRANO=METRIA )�@1603�N�Ƀh�C�c�̃��n���E�o�C�G���ɂ���ďo�ł��ꂽ���}���ł���B�w�o�C�G�����}�x �Ƃ������B�����́A�����ɂ� Uranometria: Omnium Asterismorum Continens Schemata, Nova Methodo Delineata, Aereis Laminis Expressa �Ƃ����A�w�E���m���g���A - �V�������@�ŕ`����A���ň�����ꂽ���ׂĂ̐����̐}���W�߂��x �Ƃ����Ӗ��ł���B
�@
�w�E���m���g���A�x Uranometria �̓M���V�A�ꌹ�̃��e����ŁA�u�V��v ���Ӗ����� urano- �� �u����v ���Ӗ����� -metr- ����Ȃ�Burano- �̓M���V�A�_�b�ɓo�ꂷ��V��_�ŋ��_���̃E�[���m�X (��ὐ�σ���ός) �⃀�[�T�C�̈ꒌ�E�[���j�A�[ (��ὐ�σ���ί��) �Ɍ����Ă���(��f���G�̒����㕔�̏������E�[���j�A�[)�Burano- �� geo- �ɓ��ꊷ����ƁA�w�ɂ����� geometry �ɂȂ�B
�@
�w�E���m���g���A�x �́A1603�N�Ƀo�C�G���ɂ���ď���N���X�g�t�H���X�E�}�O�k�X (Christophorus Mangus) ����o�ł��ꂽ�A�S�V�������ŏ��̐��}�� (star atlas) �ł���B(�V�̓�Ɏ��ӂ����^�����V���V��ꖇ���̂̓V���}�Ȃ�A����ȑO�ɂ����݂���)�����G���܂ސ��̕`��Ȃ�тɒ����́A�A���N�T���_�[�E�}�C���[ (Alexander Mair�A1562�N��-1617�N) ���S�������B�������W�ɂ���Ă���A���̔z�u�͒n�ォ�猩�グ�����(����̒ʏ�̐��}�Ɠ���)�ł���B
�@
�}�ł͑S52�t����Ȃ��Ă���B����1�t�́A���Ɏ��߂�ꂽ���G�Ȃ̂ŁA���}��51�t�ɂȂ�B���}�́A�܂��v�g���}�C�I�X��48������1�t�������āA49�Ԗڂɂ̓v�g���}�C�I�X���m�邱�Ƃ̂ł��Ȃ������V�̓�Ɏ��ӂ̐V�����������ꊇ���ĕ`���Ă���B������2�t�́A�k�����Ɠ씼���̓V���}�ł���B
�@
���w�E���m���g���A�x�̏o�T
�@
�ȏ�̂悤�ȓ��������������I�� �w�E���m���g���A�x �ł͂��邪�A�o�C�G���̓Ƒn�ł͂Ȃ��A�l�^��������݂���B
�@
�܂��A�P���̃f�[�^�́A��Ƃ��� �u�e�B�R�̐��\�v �̊��S�łɋ����Ă���B�u�e�B�R�̐��\�v ���������ꂽ�̂́A�s���S�łł���1602�N�̂��Ƃł���A���S�ł́A1627�N�ɂ悤�₭�P�v���[�� �w���h���t�\�x �Ɏ��^���ꂽ�B�������A���\���̂��̂�16���I���ɓ��l��(�菑���R�s�[�{)�Ƃ��ė��z����Ă���A�v�����V�E�X��z���f�B�E�X�A�u���E�炪�V���V���쐻����ۂɈˋ����Ă����B�܂��A�u�e�B�R�̐��\�v �Ɏ��^����Ă��Ȃ��암�� �u�v�g���}�C�I�X�̐��\�v �ɂ���ĕ���Ă���A�V�̓�ɕt�߂́A�o�C�G���ɂ��A�����S�E���F�X�v�b�`�A�A���h���A�X�E�R���T�[���A�y�h���E�f�E���f�B�i�A�y�g���X�E�e�I�h���X�̊ϑ��Ɋ�Â��Ă��邳��Ă���B���ۂ̃f�[�^�̓e�I�h���X�ɋ����Ă�����̂ƍl�����Ă���B
�@
���}���`����ɎQ�ƕ�����Y���Ă���̂́A�����I�قǑO�ɃC�^���A�̃s�b�R���~�j���o�ł������}�ŗp���Ă����@�ł���B
�@
�܂��A�����G�}�̒��ɁA�O���e�B�E�X�� �w�A���e�A�W���x �ɑ}�܂ꂽ���R�u�E�f�E�w�C���̐����}�̃R�s�[�����������B
�@
���@
�����̗��j�͂ƂĂ��Â��̂ł����A���}�ƂȂ�ƁA���̗��j�͋ߐ��E���l�T���X�̈���Z�p�̔�������ł��B
�@
1�D�p���f�B�[�V���}�@17���I�㔼
�@
�p���̃E�C��E��O������w�̐��w�����ł���C�O�i�X��K�X�g����p���f�B�[������B��V�A�k�V�A�ԓ�4���̐}����Ȃ�A�������W��a���̋O�����`����Ă��܂��B�`���[���Y�̊~�̖؍���S���̉ԍ����ڂ�A��\������2�d�Ȃǂ̌��݂Ƃ̈Ⴂ�������܂��B
�@
2�D�s�A�k�X���u�V���w���ȏ��v�@1540�N
�@
���҂͐��w�ҁA�V���w�ҁA�n���w�ҁA�n�w�p�@��̔����҂ł��B�������W�ŕ`����Ȍ`�����Ă��邪�A���̑����ł̂悤�ɂ͎g�����Ƃ��ł��܂���B���������ׁ̗A�����͂܂��Ɨ����Ă��炸�A�܂�3�C�ɂȂ��Ă��܂��B
�@
3�D�O���`�E�X�̐����}���@1600�N
�@
�O���̓O���`�E�X�ɂ�鐯�������Љ��A�㔼�͔��p�ƃ��R�u��f��Q�C���ɂ�鐯���G���ڂ����Ă��܂��B���̔z�u�A�z��͕s���m�ł���A�܂��v���A�f�X���Ɨ����������ƂȂ��Ă��܂��B
�@
4�D�o�C���[���}�@1603�N����
�@
���[�n����o�C���[�͖@���ƂŃA�}�`���A�V���Ƃł����B51���̐��}��1709�̐����܂ސ��\���ڂ����A���E�ŏ��̐������}�ł��B����͑�4��1655�N�̂��̂��g���Ă��܂��B
�@
5�D�Z�����E�X�V���}�@17���I�㔼
�@
�k�V�A��V�ň�̓V���}�ŁA�������W�ɂ��킹�Ēn���̌o����������Ă��܂��B�������Ȃ�����ǂ��(�A���S�D��)�A�����ɍ�(���ɍ���)��[�t���e�X�삪�`����Ă��܂��B���͂ɂ͓V���ϑ������ڂ��Ă��܂��B
�@
6�D�L���X�g���V���}�@1708�N
�@
�Z�����E�X��17���I�O���V���[�̍�����L���X�g�����}�̊�Â��쐬�������́B�y�K�T�X������V�g���K�u���G���ȂǁA�]��������u�������Ă��܂��B
�@
7�D�o�b�J�[�V���}�@1684�N
�@
�I�����_�̒n�}����҃����b�g��s��o�b�J�[���쐬�������́B�����J�g�����Ɏ������e�@��p���Ă���A���ܓx�ɂ��鐯���قNJԉ��т��ĕ`����Ă��܂��B
�@
8�D�{�[�f���}�@1782�N
�@
�x�������V����̑䒷�{�[�f���t�����X�`�[�h���}����ɍ쐬�������́B�����≤┍����`����A�����̋��E����_���Ŏ����Ă��܂��B
�@
9�D�V���V
�@
�����p����ƓV�̂̏o�v�̕��ʊp��쒆���x�A�C�ӂ̎����̐����\�����Ƃ��ł��܂��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���x�[�R���u����v�v���� 1620�N |
   �@
�@
|
Bacon, Francis.(1561-1626)
�@
Instauratio Magna.
�@
�x�[�R���̓C�M���X�̓N�w�ҁA�����ƁB�]���A���X�g�e���X�̓N�w�͒��������̃J�g���b�N����̋����Ɏ�������āA�w��̐��E�ɐ�ΓI���Ђ������̂ƂȂ��Ă����B�������A16�`17���I�ɂȂ�ƃ��[���b�p���ɐV���Ȓm�I�T���̋@�^�������N����A�Â����ГI�����̊�b���h���Ԃ���悤�ɂȂ����B�x�[�R���͂��̋@�^�̒��ŁA�v�����A���X�g�e���X�I�X�R���N�w�̂��Ƃɉ��������ĕs�U�̏�Ԃɂ������w��̐��E�����v���ׂ��A�u����v�v�Ə̂���6������Ȃ�s��ȑ̌n�I���q���\�z�����B�{���́A���̑�2���ɓ�����u�V�@��(�m�[�E���E�I���K�k��)�v�Ƃ��Ă�A1608�N�ɒ��z�������܂ł�12�N�ԁA���Ȃɐ��Ȃ��d�˂��ƌ����Ă���B�u����v�v�Ƃ����̂́A�x�[�R�����g�������̎d���S�̂ɑ��Ă����薼�ł��������A���ǂ͖������ŏI������B |
���e�D�x�C�R��(Francis Bacon 1561-1626)
�@
�C�M���X�̖���ɐ��܂�A��@���A�j�݂ɂ܂łȂ������A���d���E��Njy����Č��E�������A�ӔN�������ς猤���ƒ���ɔ�₵���B�ނ́A�X�R���I���`�ɑ���S�m���̉��v��ڎw���āw��v�V�x�Ƃ����咘���v�悵�A�܂��A����炪��������A���p�����ꂽ��̃��[�g�s�A���w�j���[�E�A�g�����e�B�X�x�ɋL�����B�����ɂ����āA�ނ́A���̒��ł̈͂����݂ɂ��x�z�g�������A�܂��A�l�ނ̒��ł̐A���n���ɂ��x�z�g�������A���R�̒��ł̉Ȋw�Z�p�ɂ��x�z�g���������d�v�ł���ƒ����B�܂�A�L���̃p�C�̎�蕪��D�������̂ł͂Ȃ��A�p�C���̂��̂�傫�����悤�Ƃ����̂ł���B�ނ́A�L���̍��̒D�����������邾���̒P�Ȃ鐭���Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�܂������A�l�ނ̐V���Ȏ���̕������J�����Ƃ���N�w�҂������̂ł���B
�@
�������A�ނ́A�����̉���I�Ȏ��R�Ȋw�̏�����(�R�y���j�N�X�A�P�v���[�A�n�[���B�[�A�M���o�[�g��ɂ��)�ɂ͖��m�ł��������A�܂��A�ނ̒���ɂ͂����Β����I���R�ς����܂Ƃ��Ă���B�����A�ނ̋Ɛт͂��̂悤�ȌʓI�����̒m���ɂł͂Ȃ��A�e��������A��悳���ׂ����R�f�Ƃ����ނ̑ŏo�����ߑ�Ɠ��̐��E�ςɂ����Ӌ`������̂��B
�@
���̎��R����̍��̔��z�́A�n���K�͂̐A���n�̒D�������Ƃ���2�̐��E�����o����\���I�ɂȂ��Ă悤�₭��������ĉߌ��Ȃ܂łɐZ�����A�l�Ԏ��g�̐�������Ԃ܂��قǂЂǂ����Q�⎩�R�j��A�����͊��̏����ݏo���܂Ŏ������B�����ŁA����ɍ����ł́A�l�Ԓ��x�̐�͂��Ȏ҂����̂悤�ȑ厩�R���x�z�������̂��A���r���[�Ɏ��R�𑀍삷������A�ނ���A���R�͂��ׂĎ��R�ɂ܂����Ă��������������ʓI�ł͂Ȃ��̂��A�Ȃǂ̔��_����������Ƃ��낾�낤�B
�@
���w��v�V�x (Instauratio Maguna) 1620
�@
�X�R���w�ɂƂ��Ă����A��������b�Ɋ�Â����A�m���ƋZ�p�Ƃ��ׂĂ̐l�Ԃ̒m���̑S�̓I�v�V���߂����č\�z���ꂽ�e�E�x�[�R���̑̌n�I����̑��́B����́A1�@�w��̕��� / 2�@�V�@��(�m�����E�I���K�k��) / 3�@�F���̏����� / 4�@�m���̊K�i / 5�@���N�w(�s�w)�\�_ / 6�@���N�w ��6����������̂Ƃ��Čv�悳�ꂽ�������ł���A���ۂɒ����ꂽ�̂́A1�ɑ�������w�w��̐i���x��2�́w�V�@�ցx�����ł������B�@ |
���w�V�@�ցx
�@
�w�I���K�m���x�Ƃ́A�@�ւƂ����Ӗ��̃M���V�A��ł���A�w��I�ɂ́A�����̓���ƂȂ���́A���Ȃ킿�A�_���w�̂��Ƃ��w���B�����āA�Ƃ��ɓN�w�ł̓A���X�g�e���X�̘_���w�W�̒���6���̑��̂ł���B�e�D�x�[�R���́A���̃A���X�g�e���X�̘_���w�̌n�ɂ����V���Ȋw�⌤���̓����ׂ��_�������̒��ɂ���킻���Ƃ����̂ł���B���̓����́A�ꌾ�Ō����A�A���X�g�e���X�̘_���w�̌n���`���I�ŋȁs��㈖@�t�ɏI�n���Ă����̂ɑ��āA�e�D�x�[�R���́A�����̊ώ@�E��������W�߂������Ɋ�Â��s�A�[�@�t���d���������Ƃɂ���B
�@
��3�̖�S
�@
�l�Ԃ̖�S�ɂ́A3�̂��̂�����B��1�́A���Ȃ̑c���̒��Ŏ��Ȃ̗͂�L�����悤�Ƃ�����̂ł���A�ʑ��I�ő����Ă���B��2�́A�c���̐��͂Ǝx�z�Ƃ�l�ނ̊ԂɐL�����悤�Ƃ�����̂ł���A��1�̂��̂��i�i�͂��邪�A���������̂��̂Ɠ������~�]�ɓ�������Ă���B��3�́A�l�ނ��̂��̂̎��S���R���E�ւ̗͂Ǝx�z�Ƃ��v�V���A�L�����悤�Ƃ�����̂ł���A���̂�茒�S�ł�荂�M�ł���B�Ƃ���ŁA�l�Ԃ̎����ւ̎x�z�́A�����m���ƋZ�p�̂����ɂ���B���R�͂���ɏ]���Ă������߂��ꂤ�邩��ł���B����䂦�A��3�̖�S�͗L���ȋZ�p�ƒm�������߂�B�m�������l�Ԃ̎��S���R���E�ւ̗͂Ȃ̂ł���B
�@
���m�͗͂Ȃ� (scientia est potentia)
�@
�����̊w��A���ɃX�R���̒m���͌�T����ŁA���������ɂ����Ȃ����A�����ƋA�[�@�Ƃ������������@�ɂ���ē�����^�̒m���́A���R���x�z���A�l�ނɕ����������炷�͂ƂȂ���̂ł���A�Ƃ���ߐ��m���ς̃e�[�[�B
�@
�����R�͕��]�ɂ���Đ�������� (Natura parendo vicitur)
�@
�l�Ԃ����R�𐪕����悤�Ƃ��Ă��A���R�͎��R�@���ɂ����]��Ȃ��B�܂�A����𐪕�����ɂ́A�A�l�Ԃ̌��Ђ�v�����������Ă��Ă͂�����Ƃ����������̂ł���A�܂��l�Ԃ����R�ɕ��]���āA���R�@�������������A������t��ɂƂ��ė��p���Ă����A���R�͂��̎��R�@���ɏ]�����䂦�ɁA�l�Ԃɏ]�����ƂƂȂ�̂ł���B����䂦�A���R���x�z����ɂ́A�܂����R�ɕ��]����A���݂��Ȋώ@��������s���Ȃ̂ł���B
�@
���C�h�� (idola)
�@
�l�Ԃ̐��_�ɐ[���������낵�A�������m���̊l����W���錶�e�B����ɂ�4��ނ���B���Ȃ킿�A
�@
�q�푰�̃C�h�� idola tribus �r���l�ԂƂ����푰�ɍ����������o�̍��o�A�[�l���A����̉e���Ȃǂɂ�鋕�� / �q���A�̃C�h�� idola specus �r���v���g���́q���A�̔�g�r�̂悤�ɁA�l�̐��i��S�A�K���A���R�Ȃǂ��琶���鎋��̋����ɂ�鋕�� / �q�s��̃C�h�� idola fori �r���𗬂����錾��̌��t�����ݓI�Ȃ��̂Ƃ��邱�Ƃɂ���Đ����鋕�� / �q����̃C�h�� idola theatri�r������̎�i�̂悤�ɂ������킵���_�̌��Ђɂ���邱�Ƃɂ���Đ����鋕��
�@
��4�ł���B�����������ɂ́A�u���������炷�����v���d�����A�^�̋A�[�@�ɂ���āA�������A���Ղɋ߂Â��Ă����ׂ��ł���B
�@
���w� / �a / ���I
�@
�X�R���̂悤�Ȓm���h�́A�q�w偁r�̂悤�ɂЂ����玩���̓����玅���o���ĖԂ�����Ă���B�܂��A�����p�̂悤�Ȍo���h�́A�q�a�r�̂悤�ɂЂ�������̂��W�߂Ďg�������ł���B�������A�q���I�r������̉Ԃ���ޗ����z���W�߁A����ɂ���������̗͂ŕό`���������Ė������o���悤�ɁA�m���ƌo���Ƃ͐��������т����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���́A�o�����炳�܂��܂Ȏ������W�߂āA�m���ŏ������m�������o�����@�������s�A�[�@�t�ł���B
�@
�������\ tabula praesentiae / �s���\ tabula absentiae / ���x��r�\ tabula gradum sive comparativae
�@
�������s�A�[�@�t�̂��߂ɕK�v�Ȏ葱���B�܂��A���̐��������Ƃ������Ƃł͋��ʂ̎�����W�߂�B���̂悤�Ȏ���́A�q�m��I����r�ƌĂ�A�����������̂��q�����\�r�ł���B���ɁA�m��I����Ɏ��Ă��Ȃ�����̐����������Ȃ�������W�߂�B���̂悤�Ȏ���́A�q�ے�I����r�ƌĂ�A�����������̂��q�s���\�r�ł���B����ɁA���̐��������܂��܂Ȓ��x�ő��݂��鎖����W�߂�B���̂悤�Ȏ���́A�q��r�I����r�ƌĂ�A�����������̂��q���x��r�\�r�ł���B���̌�A�P�������ɂ�������s�A�[�@�t�ł͂Ȃ��A�^�̋A�[�@�Ƃ��āA���̐����Ɩ������鐫��������3�̕\�Ɋ�Â��ď��O���Ă����Ƃ����s�ے�I���@�t���̂��A���̂悤�ɂ��Ďc�������̂���A�^�ɐ��������肳�ꂽ�q�m��I�`���r��������B�������A���̂悤�ɂ��ē���ꂽ���̂́A�b��I�ȍŏ��̒m���̎��n�ɂ������A��萳�����m���邽�߂ɂ́A���������ɂ��낢��Ƒg�����ČJ��Ԃ��Ă����K�v������̂��B�@ |
���Ƃ͒��ɁA�Z�ނ��߂Ɍ��Ă�̂ł����āA�O���猩�邽�߂ł͂Ȃ��B
�@
���Ǐ��͏[�������l�Ԃ�����A�������Ƃ͐��m�Ȑl�Ԃ����B
�@
�����ɂ���ŏ�̏ؖ��Ƃ͌o���ł���B
�@
�����҂́A�`�����X�����o���̂ł͂Ȃ��A���o���B
�@
���ȓN�w�͐l�̐S�_�_�ɌX���A�[���ȓN�w�͐l�̐S���@���֓����B
�@
�����҂͎����ɗ^�������葽���̋@������B
�@
�������̉^���ǂ����W�����Ă������̖��́A���̐l�̎蒆�ɂ����Ȃ��B
�@
�����҂͌��݂Ɩ����ɂ��čl���邾���Ŏ��t�ł��邩��A�߂����������������悭��l���Ă���ɂ��Ȃ��B
�@
�����i�͂˂ɑ��l�Ƃ̔�r�ɂ����Ăł���A��r�̖����Ƃ���ɂ͎��i�͖����B
�@
����В��肷��l�Ԃ͌��҂Ɍy�̂���A���҂Ɋ��Q����A�I�l�Ԃɂ��Ă܂��A�ނ玩�g�̍����S�̓z��ƂȂ�B
�@
�������̔����͎����ł���A�t���̔����͕s���s���ł���B
�@
�����Ԃ��������Ȃ���A�N�ɂ����ĎႭ�Ƃ��A���Ԃɂ����Ă͘V���Ă��邱�Ƃ����肦��B
�@
���E�ςƂ����̂͏I�����ꂽ���C�ł���B
�@
�����҂͌��o�����������̋@�������B
�@
���@���͐����̕��s��h���ׂ������ł���B
�@
�����M�͖̎��O�ł���B���ׂĖ��M�ɂ����ẮA���҂��������҂ǂ��ɒǐ�����B�����Đ���̏ꍇ�Ƃ͔��ɁA�܂����s�������āA�ォ�痝�_������ɓ��Ă͂߂���B
�@
�������Ȃ�@�����@�h���w�����A�L���X�g���̋����قǑP���d���������̂͂Ȃ������B
�@
���ȓN�w�́A�l�̐S�_�_�X���邪�A�[���̓N�w�͐l�̐S���@���ւƓ����B
�@
���^���Ƃ����D�ꂽ�n�Ղ̏�ɗ����Ƃɔ䂷�ׂ������݂͂Ȃ��B
�@
�����h�I�ȌX����L����l�Ԃ́A���l�����Ď����̋@�m�������ꂳ����Ɠ����ɁA���������l���L����|���K�v������B
�@
���w��ɂ��܂葽���̎��Ԃ�������̂͑ӑĂł���B�w������܂�ɑ�������ɗp����̂͋C��艮�ł���B
�@
���������l�͕����y�̂��A�P���Ȑl�͕����̎^���A�����l�͕��𗘗p����B
�@
�����j�͐l�Ԃ������ɂ��A���͑��˂�����̂ɁA���w�͉s�q�ɂ��A���R�N�w�͐[���ɂ��A�ϗ��w�͏d���Ȃ炵�߁A�_���w�ƏC���w�͋c�_�ɏG�ł�����B
�@
���܂��Ƃɉh�_�͐�̂悤�Ȃ��̂ŁA�y���āA�ӂ�����͎̂x���Ď����グ�邪�A�d���ď[���������̉��ɒ���ł��܂��B
�@
�����ɔc���̂��߂Ɉ����Ȃ��҂͂��Ȃ��B�݂�Ȉ��ɂ���ė��v�E���y�E���_�悤�Ǝv���Ĉ����Ȃ��B
�@
������l���R���͂��Ƃ������Ƃ��l���Ă݂�A����͂��̂��̂��_�ɑ��Ă͑�_�ł���A�l�Ԃɑ��Ă͔ڋ��ł���B�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@
�����U���������邱�Ƃ́A����̍������̂悤�ɁA���������p�ɖ𗧂����邩���m��Ȃ����A���̎���ቺ������B
�@
���ٔ����Ƃ��Ă̐E���́A�@�����𖾂��邱�Ƃɑ����A�@���Ƃ𐧒肷�邱�Ƃł͂Ȃ��B
�@
������҂̋��s�͂ق��̎҂̍��Y�ł���B
�@
�������̎��ɑ���Ȃ���懎҂Ɏ�芪���ꂽ�ő�̈�懎҂͌Ȏ��g�ł���B
�@
�����h�ȉƂ������~�n�Ɍ��Ă�҂́A�݂������S���ɂ䂾�˂�҂ł���B
�@
�����������ő�̉��v�҂ł���B
�@
���V�g�͗͂ɂ����Đ_�Ɠ������낤�Ɨ~���Ė@��j���đ��A�l�Ԃ͒m���ɂ����Đ_�Ɠ������낤�Ɨ~���Ė@��j���đ����B
�@
���s�v�c�[����͒m���̎�q�ł���B
�@
���Ȃ͎Ⴂ�j�ɂƂ��Ă͏���l�ł���A���N�̒j�ɂƂ��Ă͗F�ł���A�V�N�̒j�ɂƂ��Ă͊Ō�w�ł���B
�@
�����ׂĂ̂��̂��ω�����͖̂��炩�����A���ۂɂ͏���������̂ł͂Ȃ��B�����̑��ʂ͂˂ɓ������B
�@
���Ȏq�����҂́A�^���ɐl������ꂽ���̂ł���B�Ƃ����̂́A�Ȏq�͑P�ł���A���ł���A�厖�Ƃ̑��ł܂Ƃ��ƂȂ邩��ł���B
�@
���P���Ȃ���A�l�Ԃ͂����̒�����ɂ����Ȃ����A���邳���L�Q�ȗȓ����ɂƂǂ܂낤�B
�@
���l�̓V���͗Ǒ����邩�A�G�����邩�A���̂����ꂩ�ł���B������A�܂����ėǑ��ɐ������A�G�����˂Ȃ�Ȃ��B
�@
�������̍˔\�͎��R���̂悤�Ȃ��̂ŁA�w��ɂ���ę��肷�邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B
�@
���ň��̌ǓƂ͐^�̗F��������Ȃ����Ƃł���B
�@
���N�����͔��f��������������邱�ƁA�]�c����������s���邱�ƁA���܂����d�������V������ĂɓK���Ă���B
�@
�����ʂɂ���l�Ԃ́A�O�d�̖l�ł���B�N�傠�邢�͍��Ƃ̖l�A�����̖l�A�d���̖l���B
�@
����_�Ȑl�Ԃ̓K�ȗp�����́A����ڂƂ��Ďw���������B�����Ƃ��đ��̎w�}�������邱�Ƃɂ���B
�@
���x�͔�����邽�߂ɂ���B�������ړI�́A���_�ƑP�s�ł���B
�@
�����͗ǂ����g�����A�ꍇ�ɂ���Ă͈�����l�ł�����B
�@
�����͂��₵�̂悤�Ȃ��̂ŁA�T�z���Ȃ��ꍇ�͖��ɗ����Ȃ��B
�@
����������j�͎��N���N�V�����Ǝv���ł��낤�B
�@
����O�ɖ𗧂ŏ�̎d������т́A�ƍَ҂��A���邢�͎q���̂Ȃ��j�ɂ���ĂȂ����B
�@
���Ȏ��g��M������l�Ԃ͎��͌����̓G�ł���B
�@
�������邱�ƂƁA�����Ȃ邱�Ƃ͕s�\���B
�@
���^�̗F�����ĂȂ��̂́A�܂������S�߂ȌǓƂł���B�F�l���Ȃ���ΐ��E�͍r��ɂ����Ȃ��B
�@
���킪�S��ł�������F�������Ȃ��l�X�́A�ȂƌȂ̐S�Ƃ�H���l�S�ł���B
�@
�������̂��߂Ɉ���͐l�Ԃ����邪�A�F���͐l�Ԃ���������B
�@
�����l�͖������M���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���O���`�E�X�u�푈�ƕ��a�̖@�v���� 1625�N |
   �@
�@
|
Grotius, Hugo.(1583-1645)
�@
De Jure Belli ac Pacis.
�@
���ۖ@��������`�I���R�@�ɂ���Ċ�b�������I�����_�̖@���w�҃O���`�E�X�̒����B�O���`�E�X�́A30�̂���I�����_�ɋN�������_�w�_���ɉ����A���[�t�F�X�^�C���̌Ï�ɗH�����g�ƂȂ����B��������E����t�����X�ɖS�����A���̑؍ݒ��ɖ{�������B�{���́A���݂̂悤�ɖ@������������Ă��Ȃ�����Ɉ�̉ۑ����舵���Ă���A�_�w�Ɩ@�w�Ƃ̕������͂��߁A���ƌ�������[�}���c�������Ȃ�x�z�҂����l�Ɠ��l���R�@�ɏ]���ׂ����̂Ƃ��A�l�Ԃ̒n�ʂ̊m���ɍv�������B�܂����E���a�@�\�̌`���╽�a��c�̗��O�A�C�m���R�_�A�Y���v�z�A���Y�̓N�w�I��b�Â��A���Y�擾�̖@���A�_���̖@���Ȃnj㐢�ɋy�ڂ����e���͑傫���A�ߑ㍑�ۖ@�A�ߑ㎩�R�@�Ɋւ���s���̖����Ƃ���Ă���B�@ |
���w�푈�ƕ��a�̖@�x�t�[�S�[�E�O���e�B�E�X(1625�N)
�@
�ߐ�����ߑ�ւƎ��オ�ڍs���钆�A�l�ނ̕����ɂƂ��čł��K�v�Ȃ��Ƃ������Ƃ̊W�𗥂���@�����������邱�Ƃł������B���ۊW�ɂ����Ė@����`�����݂��Ȃ��Ƃ�������͊댯�Ȍ�T�ł���A�J��ƌ��ɂ����āA���a�Ɠ��l�Ɏ����ׂ��@������ƃO���e�B�E�X�͂��̒���Ŗ��炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă���B�u���R����߁A�����Ƃ̍��ӂ��藧�����v���K�@�����ێЉ�̒��ŗL���ł���̂ł��邽�߂ɂ́A�푈���܂��@�̎��s�̈�̎�i�Ƃ��čs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��O���e�B�E�X�̎咣�ł���A�ÓT�I�Ȑ���̗��_����Ă���B
�@
���ێЉ���x�z����@�Ƃ��Ă͎��R�@�A�����@�A�_�Ӗ@�̎O�����邪�A�O���e�B�E�X�̕��ނɂ��Ύ��R�@�ƈӎu�@�̓������Ƃ���Ă���B���R�@�͐l�Ԃ̎Љ�I�{�����瓱�����@�ł���A����͑��l�̌�����N�Q�����A���l�̂��̂�̗L���Ă��鎞�͂��ꂩ�瓾�������ƂƂ��ɕԊ҂��邱�ƁA�𗚍s����`���A���ȉߎ��ɂ�鑼�l�̑��Q�����邱�ƁA�ƍ߂ɏ]���ČY�����������邱�ƂȂǂ��܂܂��B
�@
�u�_�����݂��Ȃ��Ƃ��l�Ԃ̎����͐_�ɂ������Ȃ��Ƃ������Ƃ͋Ɉ��̍߂�Ƃ����ƂȂ��ɂ͗e�F�����Ȃ��Ƃ���ł��邪�A����ɉ�X�������e�F�����Ƃ��Ă��A��X������܂ŏq�ׂĂ������Ƃ́A������x�A���͂�L����ł��낤�v�Ƃ��āA���R�@�̗��_�Ɛ_�w�̗��_�����Ă���B
�@
�����ăO���e�B�E�X�͎��R�@�ƑΔ䂳���ӎv�@�ɂ��Đ_�̎��R�ӎv�Ɋ�Â����_�̖@�Ɓu�͏��炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������R�@�ɊY������l�̖@����B���̐l�̖@���獑�ۖ@�͐��܂ꂽ�̂ł���A�O���e�B�E�X�͖@�̋N���ɂ��Ă͎Љ�_����̗���ɗ����Ă��邽�߂ɖA���ӁA�_��Ɋ�Â����̂Ƃ���Ă���B
�@
�u���R�@�Ƃ́A����s�ׂ��A�����I�{���ɍ��v���Ă��邩�ۂ��ɂ���āA���̓����Ƃ��ē����I�ɒ��Ȃ��̂ł��邩�A����Ƃ������I�ɕK�v�Ȃ��̂ł��邩���w�����鐳���������̖��߂ł���v���̂悤�Ȏ��R�@�͐������E�ɂ����čł��x�z�I�Ȗ@�ł���A�_�ł����������ς��邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƍl���Ă���B�����Đ푈�Ƃ́u�͂ɂ���đ����l�X�̏�ԁv�ł���A�u�����������ƎЉ�̐����͂��ׂĂ̗͂̎g�p���ւ��Ă��炸�A�����Љ�ɔ�����͂��Ȃ킿���l�̌�����D�����Ƃ���͂̎g�p���ւ��Ă���v�Ƃ��Ă��̐푈�����`�ɓK������ɂ����Đ������ł���Ƙ_�l���Ă���B
�@
�푈�͎匠�҂ɂ����I�푈�Ǝ��l�ɂ�鎄�I�푈������B���I�푈�ɂ͎��I�푈�ɂ͂Ȃ����ʂȌ��ʂ�����A����͎匠�Ƃ������̎҂̖@�I�x�z�ɕ��]���Ȃ��ō��ʂ̌��͂̓����ɂ����̂ł���A�匠�҂͍��Ƃɋ��ʂ̎�̂Ɗe���ɌŗL�̎�̂Ƃɋ敪�����B�����ċ��ʓI�{���͊��S�Ȃ�c�̂Ƃ��Ă̍��Ƃł���A�ŗL�I��̂Ƃ͊e���̖@���ɏ]�������A�M���A�l���ł���B
�@
�������푈�̌����Ƃ͎��g�̐����ƍ��Y�̊�Q����̖h�q�A���Y�̉A�����ČY���̎O�̌����Ɍ��肳���B�푈�Ƃ͌����I�Ɏi�@�I�������s�\�ȏꍇ�ɂ����Č�����ی삵�A���Q�����邽�߂̍s�ׂł���B���������āA�N�����������ꍇ�ɐ푈�ɑi���邱�Ƃ������Ȍ����ɂ��ė��Ă���A�����ɂ͋��L���A���啨�A���L���A��L���A���A�_��A���@�A�O���g�߂̕s�N���A�Y���Ȃǂ��������Ă���B�@ |
���t�[�S�[�E�O���e�B�E�X1
�@
�I�����_�̖@�w�ҁB�ÓT�I�Ȏ��R�@�̗��_���������A�ߑ㍑�ۖ@�̗��_���m�������B���ɊC�m�@�Ɛ푈�@�̌����ƐтŒm���Ă���B
�@
�I�����_�̃f���t�g�s�Ƀ����E�O���e�B�E�X�̑��q�Ƃ��Đ��܂�A11�Ń��C�e����w�ɓ��w�����B�����ŃX�J���W�F�[���Ɏt�����A14�ő��Ƃ����B���̗��N�Ƀt�����X�ւ̊O���g�ߒc�ɐ��s���A�A����4���ɉy�������B�I�����A����w���疼�_�@�w���m�̊w�ʂ�^�����A�A����16�ŕٌ�m�Ƃ��Ďd�����͂��߂�B1603�N�ɃI�����_�ƃ|���g�K���̕��͏Փ˂ŃI�����_�̓��C���h��Ђ������������̂̈ꕔ�̊��傪���̕ߊl���̕��z�Ɏv�z�I�ȗ��R���甽���Ď�]����e�N���悤�Ƃ����B��Ђ̓O���e�B�E�X�ɂ��̕ߊl�s�ׂ̐�������ۏႷ�邽�߂ٌ̕���˗������B�O���e�B�E�X��1606�N�Ɂw�ߊl�@�_�x�������グ�āA�X�R���w�̎��R�@�ƍ��Ɩ@�̊T�O���g���ĕߊl�̖���̌n�I�ɘ_���A���̐��������ؖ������B(���������̘_���͉��炩�̗��R�Ō��J����Ȃ�����)�O���e�B�E�X��1607�N�Ɍ��������ɔC�������B24�ɃO���e�B�E�X�̓X�y�C���ƃI�����_�̋x������n�܂������ɂ́w���R�C�_�x���Ŕ��\���A�f�Ղ̓Ɛ茠���咣���Ă����X�y�C���̎咣���U�����ăI�����_�̓��C���h�ɂ�����f�Ռ���i�삵���B�O���e�B�E�X�͎��R�@�Ɋ�Â��Ȃ���C�m�ɂ����鎩�R���m�������B1613�N�ɃI�����_�̃��b�e���_���s��\�ƂȂ����O���e�B�E�X��1618�N�̃}�E���b�c�ɂ��N�[�f�^�ŏI�g�ŌY��鍐���ꂽ�B�����ŃO���e�B�E�X�́w�^�̏@���̏ؖ��x��w�I�����_�@�w����x�Ȃǂ̊�b�I������i�߂Ă���A�E�����ăp���ɖS�������B�w�푈�ƕ��a�̖@�x�͂��̖S�������ŏ����ꂽ����ł���A�O���e�B�E�X�̒���̒��ōł���\�I�Ȃ��̂ł���B���̒���ł͎��R�@�Ɋ�Â����Ƃ����@�����̑��݂𗝘_�����邱�Ƃ�_���Ă���A�r�g���A��X�A���X�̖@���_�W�����Ă���B�O���e�B�E�X�͌�ɃX�E�F�[�f���̃p�����q�Ƃ��Đ����̊����ɖ߂邪�A1635�N�Ɏ��E�����B���̋A�H�Ńo���g�C�ŊC��̂ɂ����A�㗤���邱�Ƃ͂ł��������X�g�b�N�Ŏ��������B���̈�̂͐��n�̃f���t�g�ɉ^��A�e���̕�n�ɖ������ꂽ�B�@ |
���t�[�S�[�E�O���[�e�B�E�X2
�@
�O���e�B�E�X Hugo Grotius �mHuig de Groot�n(1583�N�|1645�N)�B�u���ۖ@�̕��v�ƌĂ��l�[�f�������g(�I�����_)���܂�̖@�w�ҁB�I�����_�ꖼ�q���[�z�[(�n�C�t)�E�f�E�t���[�g�B�O���e�B�E�X�̓t���[�g�̃��e����ǂ݁B
�@
�f���t�g�s����4�x�A����ɂ̓��C�f����w�̗��������w�߂����m�A�����E�f�E�t���[�g�̑��q�Ƃ��āA�n�v�X�u���N�Ɨ̃l�[�f�������g�̃f���t�g�ɐ��܂��B�O���e�B�E�X�̗c�N��1588�N�Ƀl�[�f�������g���X�y�C�����玖����Ɨ��A�����̂Ȃ��ŏ��N������߂����B�c������_���̗_�ꍂ���A1594�N�A11�Ń��C�f����w���w�B�ÓT�����w�҃X�J���Q����Ɋw�ԁB98�N�t�����X�g�ߒc���ƂȂ�n���A�A����4���ɖʉ��B�A����A99�N�ɕٌ�m���J�ƁB
�@
1601�N�A�z�����g�B�c���l�[�f�������g�j�̕Ҏ[���ϑ������B���̗��j����1604�N�܂łɍŏ��̑��e���������邪�A�O���e�B�E�X�̐��O�ɂ͏o�ł��ꂸ�A�v���1657�N�Ɂu�l�[�f�������g���@�N��L�vAnnales et historiae de rebus Blegicis�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B
�@
1603�N�ɋN�������l�[�f�������g���D�ɂ��|���g�K���D�ߊl�������A���̎����𐳓�������_������A1604�`6�N�̊Ԃɍq�s�E���Ղ̎��R���咣�����u�ߊl�@�_�vDe iure praedae commentarius�����M�B���̒�����O���e�B�E�X�̐��O�Ɋ��s����邱�Ƃ͂Ȃ��������A1609�N�A���̂Ȃ��̑�O����12�͂��C���������������Ŕ����o���A�u���R�C�_�vMare liberum�Ƃ��ē����ŏo�ł��č��ۓI�ȑ�_���������N�������B
�@
1607�N�Ɍ��@���ƂȂ�A�����̓�����ݎn�߂�B1613�N�ɂ̓��b�e���_���̖@���ږ�ɔC�������B
�@
�����̃O���e�B�E�X�́A�J�����B�j�Y���̂Ȃ��ł���ΓI�ȗ\�����ے肷��A���~�j�E�X�h�ɑ����Ă������A��茵�i�ȃz�}���X�h�Ƃ̏@���_������������Ȃ��ŁA1618�N�ߕ߂����B���N�s��ꂽ�h���h���q�g�@����c�ŃA���~�j�E�X�h���ْ[�ƒf�肳�ꂽ���߁A�I�g�ł�鍐�����B�������S���͂��قnj��������̂ł͂Ȃ��A�S�֒��Ɂu�^�̐M�̏ؖ��v���I�����_��Ŏ��M�����B���̏��͌�ɉ����������ă��e����Ɉڂ���A�u�L���X�g���̐^���ɂ��āvDe veritate religionis Christianae�Ƃ���1627�N�Ƀt�����X�ŏo�ł����B
�@
���āA1621�Ɍ��I�ȒE�o�����s���A�t�����X�ɖS���B �t�����X�ł́A���C13���̔�̂��Ǝ咘�u�푈�ƕ��a�̖@�vDe iure belli ac pacis(1625�N)�����B
�@
���̌�A1631�N�Ƀl�[�f�������g�ɋA�����邪�A�c���ł͎����ꂸ�A�n���u���N�ɑދ��B�X�E�F�[�f���A�t�����X�Ȃǂ�]�X�Ƃ��A�C��̂Ŏ��S�����B
�@
�O���e�B�E�X�̖@�v�z�͏����́u�ߊl�@�_�v�Ɓu�푈�ƕ��a�̖@�v�̊ԂŎ�ω����Ă��邱�Ƃ�����A�莮����������A�����l�[�f�������g�ɐ��܂�A���ۊW�̂��������Ƃ���Ȃ��ŁA�ꍑ�@���z�����������Ƃ̋��ʖ@�Ƃ��Ă̖����@(ius gentium)�̎v�z�ɂ��ǂ���A������x���镁�ՓI�Ȍ����Ƃ��Ď��R�@�������킹�l�������Ƃ����悤�B�_�@�ł͂Ȃ����R�@���@�̌����ƍ��肵�����͑傫�����A���R�@�����ꎩ�̂Ƃ��Ă͌����ΏۂƂ͂��Ă��Ȃ����Ƃ�����A�O���e�B�E�X�̎��R�@�T�O�ɂ́A�_�@�Ƃ̊֘A���炢���Ă��A�����@�Ƃ̊֘A���炢���Ă��A�B�����������͎̂����ł���B
�@
�܂�����ł́A�O���e�B�E�X�̖@�v�z�̂��V�����A������ɂ��Ă̋^�����N����Ă��邪�A���ƊT�O���B���ȂȂ��ł̍��ۖ@�v�z�ɁA����̍��ۖ@�Ɠ����x���̖��ӎ������߂�͍̂���Ƃ�������B���ƊT�O�̐����ƂƂ��ɍ��ۖ@�T�O�����������̂��Ƃ���A�O���e�B�E�X�́A��͂�u���ۖ@�̕��v�ł������ƕ]�����邱�Ƃ��ł��悤�B�@ |
���t�[�S�[�E�O���[�e�B�E�X3
�@
(�I�����_��FHugo de Groot, �p��FHugo Grotius, 1583-1645)�@�I�����_�̖@�w�ҁB�t�����V�X�R�E�f�E���B�g�[���A�A�A���x���R�E�W�F���g��(en)�ƂƂ��ɁA���R�@�Ɋ�Â����ۖ@�̊�b����������Ƃ���A�u���ۖ@�̕��v�Ə̂����B�N�w�ҁA����ƁA���l�ł�����A�����Ƃ��āw���R�C�_�x�A�w�푈�ƕ��a�̖@�x�Ȃǂ�����B���ăI�����_�Ŕ��s����Ă���10�M���_�[�����ɏё����g�p����Ă����B�܂��A�O���e�B�E�X(Grotius)�Ƃ̓��e���ꖼ�ł���A�I�����_��t���l�[�� Hugo de Groot �̓ǂ݂̓q���z�[=�f=�t���[�g�ɋ߂��B
�@
���\�N�푈���W�J����Ă����I�����_�̃f���t�g�ɐ��܂ꂽ�B���ł��郄���̓��C�f����w�ŃW���X�g�D�X�E���v�V�E�X(en)�ƂƂ��ɕ��������Ƃ��������B�c�N���̃O���[�e�B�E�X�̓q���[�}�j�Y���ƃA���X�g�e���X�I�ȋ�����{����A�_���ł������ނ�11�̎��Ƀ��C�f����w�ɓ��w�����B�O���[�e�B�E�X�����w���������̃��C�f����w�͖k���[���b�p�ł����Ƃ��A�J�f�~�b�N�ȋ�����s����w�Ƃ��Ēm���Ă���A�t�����V�E�X�E�W���j�E�X(en)�A�W���Z�t�E�W���X�g�t�E�X�J���Q�[��(en)�A���h���t�E�X�l���E�X(en)�����C�f����w�Ŋ��Ă�������ł�����[1]�B
�@
1599�N�A�O���[�e�B�E�X�̓f���E�n�[�O�Ŋ��E�āA1601�N�ɂ́A�z�����g�B�̎j�w�j�������ƂȂ����B1604�N�ɏ��߂č��ۖ@�Ɍg��邱�ƂƂȂ�A�̌n�I�ȍ��ۖ@�̎�e�����B�����āA�I�����_���l�ɂ��V���K�|�[���C���ɂ�����|���g�K���̃L�����b�N�D�Ƃ��̑D�̉ݕ��̍����������̑i�葱���ɏ]�����邱�ƂƂȂ����B
�@
���w���R�C�_�x
�@
1603�N�A�I�����_�̑D���E�T���Ƃł����郄�R�u�E���@���E�w�[���X�P���N(en)���|���g�K���D�T���^�E�J�^���[�i����\�߂�������Ƃ́A�X�y�C���E�|���g�K�����N�A�����I�����_�ƌ�킵�Ă�������(���\�N�푈)�ł������B�w�[���X�P���N�̓I�����_���C���h��Ђ̎q��Ђł���A���X�e���_���Ɨ���Ђ̎Ј��Ƃ��ē����Ă������A�ގ��g�ɂ́A�I�����_���{�Ⓦ�C���h��Ђ��猠�͂��s�g���錠����t�^���Ă����킯�ł͂Ȃ��������A�I�����_���C���h��Ђ̊���́A�w�[���X�P���N�������炵���x����邱�Ƃ�]��ł����B�Ƃ͂����A�I�����_�����ł̓w�[���X�P���N�ɂ�����\�߂̑Ó���������Ă��������ł͂Ȃ��A�ϗ��ʂ�����I�����_���C���h��Ђ̈ꕔ�̊��傩��\�߂ɂ�镨�i�̊l�������ۂ��铮�����������B�������A�|���g�K�����ݕ��̕Ԋ҂�]��ł����B�I�����_���C���h��Ђ̑�\�́A�O���[�e�B�E�X�ɂ��̝\�߂ɂ�����_���˗����邱�ƂƂȂ���[2]�B
�@
1604�N����1605�N�ɂ����ẴO���[�e�B�E�X�̊����́A�wDe Indis�x�Ƒ肳�ꂽ���Ȃɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�O���[�e�B�E�X�́A���C���h��Ђɂ��\�߂̑Ó��������R�@�ɋ��߂悤�Ƃ����B
�@
1609�N�A�O���[�e�B�E�X�́A�w���R�C�_�x(����:Mare Liberum�Aen)�����B�O���[�e�B�E�X�͂��̖{�ɂ��A�C�͍��ۓI�ȗ̈�ł���A�S�Ă̍��Ƃ́A�C��œW�J�����f�Ղ̂��߂Ɏ��R�Ɏg�����Ƃ��ł���Ǝ咣�����B
�@
�����̃C�M���X�́A�f�Ղɂ����ăI�����_�Ƌ����W�ɂ��������߁A�O���[�e�B�E�X�̎咣�ɐ^�������甽�����B�X�R�b�g�����h�l�̖@�w�҂ł���E�B���A���E�E�G���E�H�b�h(en)���p��ŏ��߂āA�C���@�ɂ��Ē������l���ł���A1613�N�ɂ̓O���[�e�B�E�X�ɑR����`�ŁA�wMare Liberum in An Abridgement of All Sea-Lawes�x�����M�����B�O���[�e�B�E�X�͂���ɔ��_����`��1615�N�ADefensio capitis quinti Maris Liberi oppugnati a Gulielmo Welwodo�����B1635�N�A�W�����E�Z���f���́A�w�����C�_�x(����:Mare clausum)�ɂ����āA�C�͌����Ƃ��āA���n�̗̈�Ɠ����K�p������̂Ǝ咣�����B
�@
�C���@���߂���_�c�����n����ɂ�āA�C�m���Ƃ͊C���@�̐����𐄐i���邱�ƂƂȂ����B�I�����_�l�̖@�w�҂ł���Cornelius van Bynkershoek�������wDe dominio maris�x(1702�N)�ɂ����āA���n����邽�߂ɑ�C���͂��͈͓��̊C�̎x�z��(�̊C)�͂��̉��݂̍����ۗL����Ǝ咣�����B���̎咣�͊e���Ŏx������A�̊C��3�}�C���Ƃ���Ƃ��ꂽ�B
�@
���̘_���͍ŏI�I�ɂ́A�o�Ϙ_���ɂ܂Ŕ��W�����B���Ƃ��A�����b�J�����Ńi�c���O�ƃN���[�u��Ɛ肵�Ă����Ƃ��Ă��A�I�����_�́A���R�f�Ղ��咣���Ă�������ŁA�C�M���X�́A1651�N�ɍq�C���𐧒肷�邱�ƂŃC�M���X�̍`�p�ɃC�M���X�D�ЈȊO�̓��`���ւ����B�q�C���̐���ɂ���āA��ꎟ�p���푈���u�������B
�@
���_�w�_���ƃO���[�e�B�E�X
�@
�O���[�e�B�E�X�́A�z�����g�B�̖@���ږ�ł��郈�[�n���E�t�@���E�I���f���o���l�t�F���g(en)�̂��ƂŐ����I�L�����A��ςނ悤�ɂȂ�A1605�N�ɃI���f���o���l�t�F���g�̃A�h�o�C�U�[�ƂȂ�����A1607�N�ɁA�z�����g�B�A�[�[�����g�B�A�t���[�X�����g�B�̍����̊Ǘ��҂ƂȂ�A1613�N�ɂ̓��b�e���_���̃y���V���i���[(en)�ƂȂ����B�������ł̓}���A�E�t�@���E���C�Q�X�x���Q���ƌ������A8�l�̎q����������(�A���A���̂���4�l�͚��)�B
�@
�O���[�e�B�E�X���I���f���o���l�t�F���g�̂��Ƃœ����Ă�������Ƃ́A�X�y�C���Ƃ̐푈��Ԃ�12�N�ԋx���ԂɂȂ�������ł������B1609�N�A�I�����_�̓X�y�C���ƃA���g�E�F���y���ɂ����āA12�N�x�������������B���̌��ʁA�I�����_���Ă����O���͎�菜����A���ۓI�n�ʂ͌��シ�邱�ƂƂȂ����B����A�I�����_�����ł͉��v�h�́u�\����v�̉��߂��߂���_�w�_�����N����[3]�B
�@
���̐_�w�_���̏œ_�́A�A���~�j�E�X�h(���S�̓��C�f����w�̐_�w�������[�R�u�X�E�A���~�j�E�X)���\����̉��߂ɑ��Ċ��e�ł��邱�Ƃ���������Ƃɑ��āA���i�ɉ��߂��邱�Ƃ��z�}���X�h(���S�͓��������C�f����w�̃t�����V�X�N�X�E�z�}���X)���咣�����_�ɂ������B�O���[�e�B�E�X��I���f���o���l�t�F���g���͂��߂Ƃ���I�����_�̏㗬�K�w�̓A���~�j�E�X�h���x������p���������Ă���[3]�B����ŁA�z�}���X�h�̎x���w�͓암���B���瓦��Ă������v�h�̖S���҂��A�s�s�̉��w���Ȃǂł�����[3]�B���ʁA�_�w�_���̓I�����_�Ɨ��̉ߒ��ł̊K�������A����ɍ��ƂƋ���̊Ԃłǂ��炪��ʂɗ��ׂ����Ƃ������Ƙ_�ɔ��W����[3]�B
�@
1618�N�A�h���g���q�g�ɂ����ăh���g��c���J�Â��ꂽ���ʁA�z�}���X�h�̑S�ʓI�����ɏI���A�I���f���o���l�t�F���g��1619�N5���ɍ��Ɣ��t�߂ŏ��Y����A�O���[�e�B�E�X�͑ߕ߂��ꃌ�[���F�V���^�C����(en)�Ɏ��e���ꂽ�B
�@
1621�N�A�Ȃ̋��͂ăO���[�e�B�E�X�͒E���ɐ������A�{1�������Ɍg���A��H�p���ւƖS�������B���̖{�Ɋւ��ẮA�A���X�e���_����en:Rijksmuseum�ƃf���t�g��en:Prinsenhof�����ꂼ�ꎩ�炪���L����{���A�E���̍ۂɎ����o�����{���������Ă���Ǝ咣���Ă���B
�@
�p���ɓ��������O���[�e�B�E�X�ɑ��t�����X�����C13���͔N����^���A���̐�����d�����B�O���[�e�B�E�X�̓t�����X�ɂ����āA�ގ��g�̒���̒��ōł��L���ƂȂ�N�w�̍�i�W�����������邱�ƂƂȂ����̂ł���B
�@
���w�L���X�g���̐^���x�Ɓw�푈�ƕ��a�̖@�x
�@
�p���؍ݒ��A�O���[�e�B�E�X�͗l�X�ȕ���Ŏ��M��Ƃ��s���Ă���B�O���[�e�B�E�X�͐_�w�ɊS����������Ă���A�w�y���M���E�X�h�ɂ��Ă̒T���x(1622�N)�A�w�X�g�o�G�E�X�x(1623�N)�A�w�L���X�g���̐^���x(1627�N)�A�w�A���`�N���X�g�_�x(1640�N)�A�w�����������x(1641�N)�A�w���������x(1644�N)�ƒ���������[4]�B���̒��ł��w�L���X�g���̐^���x("De veritate religionis Christianae")��6�����ɂ���č\������A�싳�_�̕���ɂ�����ŏ��̃v���e�X�^���g�̃e�L�X�g�u�b�N�ł������B�O���[�e�B�E�X�́w�L���X�g���̐^���x�ɂ����āA�_�����݂��邱�ƁA�_�̗B�ꐫ�A���S���A�������A�i���E���\�E�S�m�E�܂������P�ł��邱�ƁA�����̌����ł��邱�Ƃ�_���Ă�����[5]�B
�@
��������w�푈�ƕ��a�̖@�x("De jure belli ac pacis")�ł���B�w�푈�ƕ��a�̖@�x�ɂ���āA�u�푈���@�ɂ��K��������̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���Ƃ����u���H�I�ړI�̂��߂̗��_�I����v�Ƃ��Ắu���R�@�_�v��W�J����[6]�v�i�D�ƂȂ����B
�@
���X�E�F�[�f����g
�@
�������X�g�����g�h�̑������I���j�G���}�E���b�c�����S����1625�N�ȍ~�ɃI�����_�ւ̋A�����ʂ������ŁA�I�����_����̉��͂�f���Ă����B1631�N�Ɉ�x���b�e���_���֖߂������Ƃ����邪�A����Ƀn���u���N�֑������B
�@
1634�N�A�����X�E�F�[�f����g�Ƃ��ē����@��邱�Ƃ��ł����B�����̃X�E�F�[�f�������O�X�^�t2���A�h���t�́A���ŌR�����w������ۂɂ́A�������Ƃ̒��ɁA�O���[�e�B�E�X�́w�푈�ƕ��a�̖@�x���g�s���Ă����Ƃ����[7]�B�O�X�^�t2���A�h���t�̌���p�����A�N�Z���E�I�N�Z���V�F���i���܂��A�O���[�e�B�E�X�𒓕��X�E�F�[�f����g�Ƃ��Čٗp�����B�O���[�e�B�E�X��1645�N�ɂ��̐E���������܂ŁA�S�����Ԓ��ɗ��p���Ă����p���̎���𗘗p�����B
�@
�O���[�e�B�E�X�̍Ŋ��͓ˑR�ł������B�t�����X����X�E�F�[�f���ւ̗��̓r��A�O���[�e�B�E�X�����D����j���A�O���[�e�B�E�X�́A���X�g�b�N�ɕY�������B���サ�Ă����O���[�e�B�E�X�́A���X�g�b�N��1645�N8��28���ɕa�v�����B�ނ̈�̂́A�t��������������f���t�g�̃f���t�g�̐V����Ŗ����Ă���B�@�@
�@ |
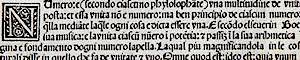 �@ �@
���P�v���[�u���h���t�\�v���� 1627�N |
   �@
�@
|
Kepler, Johannes.(1571-1630)
�@
Tabulae Rudolphinae,quibus astronomicae,temporum loginquitate collapsae resturatio continetur...
�@
�P�v���[�̓h�C�c�̓V���w�ҁB�{���́A�R�y���j�N�X�A�K�����C�A�j���[�g����Ƌ��ɋߑ�V���w�ƉF���Ɋւ���V�����T�O�̐��҂Ƃ��Ēm����P�v���[���A�ނ̗��_�Ɋ�Â��Ē������ŏ��̘f���ʒu�\�ł���B16���I�ő�̓V���ϑ��ƂƂ�����f���}�[�N�̃e�B�R�E�u���[�G�̒�q�ƂȂ����P�v���[�́A�t�̊ϑ��Ɋ�Â��Ęf���̈ʒu�\�̍쐬�ɏ]�����A�u���[�G�̖v��͍c�郋�h���t2���t���̐��w�҂ƂȂ����B�u���[�G�����N�ϑ������f���̈ʒu�Ɋ�Â��āA���߂Ċϑ���������f���̋O���Ƃ��̉^���@���A������P�v���[��3�@���������B���̖@�����A�j���[�g���̖��L���͔����̊�b�ƂȂ������Ƃ͗L���ł���B���h���t2���̉��b���L�O���Ė������ꂽ���̕\�́A���\��100�N�̂������W���I�ȓV�̕\�Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B�@ |
�����h���t�\
�@
�_�����[�}�鍑�c�郋�h���t2���̒����ɂ���āA1627�N�Ƀh�C�c�̓V���w�҃��n�l�X�E�P�v���[���쐬�����V���\�ł���B���e����ɂ�錴��� Tabulae Rudolphinae Astronomicae�A�p��ł� the Rudolphine Tables�A�h�C�c��ł� Rudolphinischen Tafeln �Ƃ����B �V���\�Ƃ́A���N���́w���ȔN�\�x�́u��v�Ɓu�V�����v�����킹���悤�ȓV���f�[�^�E�u�b�N�ŁA�����ɏ��f���̈ʒu���Z�\����Ȃ�A��Ƃ��Đ萯�p�ɂ�����o���V�{�}�̍쐬�̂��߂ɗ��p���ꂽ�B�q���݂ł��A�萯�p�̋��{�ɂ͓V�̗�t�����Ă���)�܂��A�ΐ��\��f���̈ʒu���Z�̎菇�����߂��Ă����B
�@
�f���̈ʒu���Z�\�́A�v�g���}�C�I�X�̑̌n�Ɋ�Â��w�A���t�H���\�\�x(13���I�㔼)��M�I�����^�k�X�̓V�̗�A�R�y���j�N�X�̑̌n�Ɋ�Â��w�v���C�Z���\�x(1551�N)�ɑւ����̂ł���B�P�v���[�̖@���Ɋ�Â��Čv�Z���ꂽ���̐��l�͏]���̐��\��30�{�̐��x�������A�n�����̗D�ʐ�������I�ȕ��Ƃ����B
�@
�܂��A�P���̃J�^���O�����^����Ă���B16���I������R�s�[���o����Ă��ău���E�̓V���V��o�C�G���̐��}�w�E���m���g���A�x�̌��f�[�^���܂ށu�e�B�R�E�u���[�G�̐��\�v�̊��S��(1,006�������^)�̑��A����ɘR�ꂽ�P�����v�g���}�C�I�X��o�C�G������̂������A����ɓ씼���ŃI�����_�̍q�C�҃y�[�e���E�P�C�Z�����ϑ������P���̃J�^���O�����^����Ă���(�����Љ�)�B�e�B�R�̊ϑ����x�́A�ϑ��@������剻���邱�Ƃɂ����1���p�ȓ��ɒB���Ă���A��C���̕���s���Ă����B�@ |
�����n�l�X�E�P�v���[1
�@
(Johannes Kepler�A1571-1630)�@�h�C�c�̓V���w�ҁB�V�̂̉^�s�@���Ɋւ���u�P�v���[�̖@���v�����������Ƃł悭�m���Ă���B���_�I�ɓV�̂̉^�����𖾂����Ƃ����_�ɂ����āA�V�̕����w�҂̐��I���݂��Ƃ�����B���w�ҁA���R�N�w�ҁA�萯�p�t�Ƃ���������B���B�⋋�@(ATV)2���@�̖��O�ɔނ̖����̗p����Ă���B
�@
�P�v���[��1571�N12��27���A�h�C�c�̃V�����[�x���n���ɂ��鎩�R�s�s���@�C���E�f�A�E�V���^�b�g�ɂāA�n�C�����q�E�P�v���[�ƃJ�^���[�i�E�P�v���[�̊Ԃɐ��܂ꂽ�B�v���e�X�^���g�ł���A����͏@���I�Η��̍��܂��Ă��������̐_�����[�}�鍑�ɂ����āA�P�v���[�ɋ��������錴���̈�ƂȂ����B�_�w�Z�ɐi�w�����̂��A1587�N�A�e���[�r���Q����w�ɓ��w�����w���w�B1594�N�ɂ̓O���[�c�̊w�Z(���݂̃O���[�c��w)�Ő��w�ƓV���w��������悤�ɂȂ����B1597�N�ɂ̓o�[�o���E�~���[���[�ƌ����B��������1598�N�ɂ̓O���[�c�����߂Ă����I�[�X�g���A����t�F���f�B�i���g2�����O���[�c����̃v���e�X�^���g�̐��E�҂Ƌ��t�ɒ�����̑ދ��𖽂��A�P�v���[�͎��E����B
�@
����Ȑ܁A1599�N�A�e�B�R�E�u���[�G (1546-1601) �ɏ���Ƃ���(�P�v���[���g�̎咣�ɂ��A�P�v���[�̓u���[�G�ɋ��������҂Ƃ��ď����ꂽ�̂ł����āA����ł͂Ȃ�)�v���n�ɏ�����A�P�v���[�͂����������v���n�ւƈڂ���[1]�B�e�B�R�͑�ϑ��Ƃł���A1576�N����1597�N��21�N�ԁA�f���}�[�N(���X�E�F�[�f����)�̃��F�����ɃE���j�{���V��������݂��ēV��̊ϑ��𑱂��A����Ƀv���n�ł��ϑ��𑱂��Ă����B���̊ϑ��f�[�^�͖]�����̂Ȃ����������A����Ŋώ@���ꂽ���̂Ƃ��Ă͍ō��̐��x�������Ă���A���m�Ŗc��Ȋϑ��f�[�^�͂̂������]�Ȑ܂̂̂��P�v���[�̎�ɓ���A�P�v���[�̖@�������̊�b�ƂȂ����B����Ńe�B�R�͎���̃f�[�^����n�������x������؋��������邱�Ƃ��ł����A�������������V��������Ă����B
�@
1601�N�Ƀe�B�R���S���Ȃ�ƁA�P�v���[�̓u���[�G�̌�C�̃��h���t2���{��t�萯�p�t�Ƃ��Ĉ��������d���A�e�B�R�̎c�����ϑ��f�[�^�����ƂɌ����𑱂����B�������A�e�B�R�̈⑰�Ƀ��h���t2�����x�����͂��������ϑ��f�[�^�̑���͂قƂ�ǎx����ꂸ�A�P�v���[�ƃe�B�R�̈⑰�̂������ɂ͑������N�����B1609�N�A��\��Ƃ����u�V�V���w�v�����M����[2]�B�u�P�v���[�̖@���v�̑�1�Ƒ�2�@�������̘_���ɂ����߂��Ă���B1611�N�ɂ�3�l�̎q�̂����̈�l�ƍȂ̃o���o�����������A1612�N�Ƀp�g�����ł��������h���t2�����S���Ȃ�ƁA�P�v���[�̓v���n�𗣂�A�I�[�X�g���A�̃����c�ɏB���w���̐E���B1613�N�ɂ̓Y�U�i�E���C�e�B���K�[�ƍč����A1618�N�ɂ̓P�v���[�̑�O�@���\�������A1620�N����1621�N�ɂ͌̋��������e���x���O�ɂ����ĕ�J�^���[�i�������ٔ��Ɋ|����ꂽ���߁A���̒n�ɂƂǂ܂��čٔ��ƕٌ�ɖz�������B1621�N�ɖ��ߔ������������ƃ����c�ɖ߂������A1626�N�ɂ͔����R�ɂ���ă����c����Q�������߃E�����ւƈڂ�A������1627�N�ɂ̓��h���t�\�������������B1630�N�A���[�Q���X�u���N�ŕa�������B
�@
�����R�N�w
�@
�P�v���[�̎��R�N�w�̒��S�͘f���_�ɂ���B�P�v���[�͐����F���̒����̒��S�Ƃ���_��V�̉��y�_��������_�Ŏ��R�N�w�ɂ�����s���^�S���X�I�`���̒����ȗi��҂ł������B���̔��ʁA�R�y���j�N�X��e�B�R�E�u���[�G�A�K�����I�E�K�����C���E�p�ł��Ȃ������~�^���Ɋ�Â��V�̘_����A�ȉ~�^������{�Ƃ���V�̘_�������A�ߐ����R�N�w�����V�����B
�@
�P�v���[�̐^�̌��т́A���w�I�ȗ��t�����������������f�����o����Ƃ������@�̐��҂��������ɂ���B�ނ̃��f�����̂��̂͌���Ă������A���ʓI�ɂ���̓K�����I�E�K�����C�A�A�C�U�b�N�E�j���[�g�����o�ČÓT�����w�̐����ւƂȂ����Ă����B
�@
�������P�v���[�́u���w�I���t���v�́A�܂��������ɂ����ĕs�\���Ȃ��̂ł������B�Ⴆ�Δނ������ɒ������ʑ̑��z�n���f���́A�u�f����6���݂��邱�Ƃ́A�����ʑ̂�5��ނ������݂��Ȃ����Ɗ֘A������ɈႢ�Ȃ��v�Ƃ����v�����݂ɂ����̂ł���B�܂��P�v���[�͉ΐ��̉q����2�ł��鎖��\���������A����́u�n���A�ΐ��A�ؐ��̉q���̐������䐔����Ȃ��Ă���v�Ƃ����v�����݂ɂ����̂ł���B���ʂƂ��ĉΐ��̉q���̐���2�ł��������A���̉����̑O��ł���ؐ��̉q���̐��́A�����m���Ă���4�����y���ɑ��������̂ł���B
�@
���P�v���[�̖@��
�@
�P�v���[�ȑO�̓V���w�ł́A�f���͒��S�̐��̎��͂����S�ȉ~�O���ʼn^�s����ƍl�����Ă����B�H���A���S�Ȃ�_�͊��S�Ȃ�^������A�Ƃ������̂������B�f���͋t�s�^�������鎖���m���Ă������A���̖��͎��]�~�̍l�������鎖�ʼn�������A�ŏI�I�ɂ̓N���E�f�B�I�X�E�v�g���}�C�I�X�ɂ���ēV�����͂قڊ������A�����ɂ킽���Ęf���͉~�O���ʼn^�s����ƐM����ꂽ�B
�@
�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�͒n����������B���݁A����́u�R�y���j�N�X�I�]��v�Ƃ��āA���z�̑�]����\������ۂɔ�g�Ƃ��ėp�����邪�A���̃R�y���j�N�X���܂��A�f���͉~�O���ʼn^�s����Ƃ����l���ɔ����Ă���A�R�y���j�N�X�̒n�����͏]���̓V�����ɑ��A���Ȃ����]�~�œ����x�̐��x���o���邾���ɉ߂��Ȃ��B���ۂɂ́A���]�~�Ȃ��ł�����Ȃ�̐��x�������邽�߁A���_�̒P�����̂��߂ɐ��x���]���ɂ���n�����_�҂����������B�t�ɁA����������p���Łw�v���C�Z�����\�x���쐬�����G���X���X�E���C���z���g�Ɏ����ẮA�t�Ɏ��]�~�̐����v�g���}�C�I�X�̓V�����������₵�Ă��܂��A�������ĔώG���𑝂��Ƃ������ʂƂȂ����B
�@
����ɑ��ăP�v���[�́A�f���̉^����c�~�A�������͑ȉ~�ł���Ƃ����B�f���̋O����ȉ~�Ɖ��肷��ƃe�B�R�E�u���[�G�̊ϑ��������ʂ�����ł��邱�Ƃ�������A��ɃP�v���[�̖@���Ƃ��ꂽ�B����ɂ���Ă悤�₭�n�����́A�]���̓V���������P�������m�Ȃ��̂ƂȂ����̂ł���B
�@
�P�v���[�̖@���ɂ���ē�����錋�_�́A�����̓��ɔ���Ⴗ��͂ɂ���āA�f�������z�Ɉ�����Ă���Ƃ��������ł���B�P�v���[�́u���z�Ƙf���̊ԂɁA���͂̂悤�ȗ͂����݂���v�Ƃ��āA���̎��ɋC�t���Ă������A���̗͂̐��̂��𖾂���Ɏ���Ȃ������B��ɃA�C�U�b�N�E�j���[�g���ɂ���āA���̗͂����L���͂ł���Ƃ��ꂽ�B
�@
���P�v���[�\�z
�@
�P�v���[�͂܂��A����~���l�߂��Ƃ��ɁA�ʐS�����i�q���Ŗ��ɂȂ�Ɨ\�z�����B ���̗\�z�̓P�v���[�\�z�ƌĂ�A�K���������~���l�߂�ꍇ�Ɋւ��Ă̓K�E�X�ɂ���đ��X�ɏؖ����ꂽ���A �s�K���ȕ~���l�ߕ��Ɋւ��ẮA400�N���̊Ԗ������̖��ł������B�P�v���[�\�z��1998�N�ɁA�g�[�}�X�EC�E�w�C���Y�ɂ���āA�R���s���[�^����g���ĉ������ꂽ�B�@ |
�����n�l�X�E�P�v���[2
�@
(Johannes Kepler 1571-1630) �v���[�͗��V�Ȑl�ł������B�����Ă��ׂĂɒ��a�����߂����A�P�v���[�̐���������͂���������Ȃ������B�܂��߂����āA�ǂ����������P�v���[�̈ꐶ�ł������B
�@
�P�v���[�͓V���w�E���w��̋��l�ł���B�����A����̏ꏊ�������炩�ł͂Ȃ��B�`�L���{�ɂ���Ă��Ȃ�Ⴄ�B�悤����ɂ��̐��U�͂��܂�悭�킩���Ă��Ȃ��B���̐���ł́A�J�[���E�Z�[�K����TV�ԑg�u�R�X���X�v(1980�N�H)�̒��́u�F���̒��a�v�ŕ`���ꂽ�P�v���[�̐��U���L���ɋ����c���Ă��邾�낤(�u�R�X���X�v�͒P�s�{�ɂ��Ȃ��Ă���)�B
�@
�P�v���[��1571�N12��27���ɓ�h�C�c�̃��@�C���E�f�A�E�V���^�b�g�Ő��܂ꂽ�B���n���������Ƃ����B�����A���[���b�p�ł͏@�����v�̗��������r��Ă����B���@�C���E�f�A�E�V���^�b�g�̏Z���̑����̓J�g���b�N�ł��������A�P�v���[�Ƃ̓v���e�X�^���g�ł������B�ł����Ƀv���e�X�^���g�̋���Ȃ��������߁A�P�v���[�̓J�g���b�N����Ő�������Ƃ����B����[�ɁA�ނ̈ꐶ�͏@���ɐU��ꂽ���̂ƂȂ����B
�@
�c���͂��̒��̎s���܂ł����Ƃ������傾�����P�v���[�Ƃ��������A���͐g�����������b���Ƃ��ĕ�炵�Ă����B��͋�����������Ă����B��l���ĉƂ��邱�Ƃ�����A����������܂�ނ�M�S�Ɉ�ĂȂ������Ƃ����B����1588�N(�P�v���[17��)�̂Ƃ����Ō�ɉƂ��o���܂܂ɂȂ����B�܂��A�P�v���[�͎q���̂���̕a�C�����ƂŁA�ڂ����������Ƃ���(�����̓V���w�҂Ƃ��Ă͒v���I)�B
�@
�P�v���[�̏��N����̎v���o�́A��ɘA����Ĝa������������(6�̂���)�A���ɘA����Č��H����������(9�̂���)���Ƃ����B���ꂪ�ނ̓V���w�ɑ��鋻����ڊo�߂������炵���B
�@
�P�v���[�̍˔\�ƐM�S��F�߂������w�Z�̐搶�̑E�߂�����A�P�v���[�̓��^�[�h�̖q�t�ɂȂ邽�߂̏㋉�w�Z�ɐi�ށB�w����̑S�����̊w�Z�ł̐����͐����̕������C���ŁA�ނɂƂ��Ă͂��܂肨�����낢���̂ł͂Ȃ������炵���B�����A���[�N���b�h�w�ɂ͔��ȋ������������悤���B
�@
���̌コ��ɁA�`���[�r���Q����w�_�w���ɐi�w����B�����ŁA�R�y���j�N�X�̒n������m�����B
�@
��w�𑲋Ƃ����P�v���[�͖q�t�ɂ͂Ȃ炸�A�O���[�c�̃M�i�W�E��(���w���獂�Z���x�H)�̐��w���V���w�̋����ɂȂ�B�������A���Ƃ͐��k�̗����������̂������炵���B�Ȃɂ�����ƒ��ɂ�������炸�A�t�c�t�c�ƕ����Ă��鎩���̃A�C�f�A�̌������n�߂Ă��܂��L�l�Ȃ̂��B���������A���w�𗝉��ł��Ȃ����k������ȂǂƂ������Ǝ��́A�P�v���[�ɗ����ł��Ȃ��������낤�B�����ł��A���̂����l���K���������������łȂ�������邱�Ƃ��ł���B
�@
�P�v���[�����C�����O���[�c�̒��͏@���I�ȋْ���Ԃɂ������B�P�v���[�������1595�N�̐萯��́A���g�̏P���ƃE�B�[���암�ւ̃g���R�R�̏P���Ă��̂ŕ]���ƂȂ����B�����u�F���̐_��v�ł́A�f����5�����Ȃ��̂�(�����͐����A�����A�ΐ��A�ؐ��A�y���̂�5�݂̂��m���Ă����A�n���͂������f���Ƃ͔F������Ă��Ȃ�����)�A�����ʑ̂�5�����Ȃ�(���l�ʑ́A���Z�ʑ�(������)�A�����ʑ́A���\��ʑ́A����\�ʑ�)���炾�Ƃ����A�C�f�A���q�ׂ��Ă���B�܂�A�e�f���̋O���͂��ꂼ����ڂ��邻���̐����ʑ̂Ɏx�����Ă���Ƃ������̂ł���B�ނ͈ꐶ���̃A�C�f�A�̂��������(���A��������ʑ̂Ƙf���̋O���͖��W�ł���)�B
�@
1597�N4���A�P�v���[�͌�����������7�̘A��q(���M�[�i)������A�x�T�ȕ��Ђ��H���̖��o�[�o���ƌ�������B�o�[�o���Ƃ̊Ԃ̓�l�̎q�́A��l�Ƃ�����܂��Ȃ����Ƃ����B�P�v���[�̓��M�[�i�����������B�������A�Ȃ͕a�C�����ŁA���܂��ɋ����̈����P�v���[���������Ƃ����B
�@
���̂���A�O���[�c�̃v���e�X�^���g�͒e������B�P�v���[���ꎞ����������肵�Ă���B�������������ɁA�P�v���[�̓`�R�E�u���[�G�̏�������B�P�v���[�͂��̏��҂��邱�Ƃɂ���(1600�N�A���{�ł͊փ����̍��킪�N�����N)�B
�@
�`�R�͎����̐����Ŗc��Ȋϑ����������ƂɁA�V�������z�n�̗��_�̍\�z�����݂Ă��āA�D�G�ȏ��肪�~���������̂��B�����A�Ă�ł݂��P�v���[�͗\�z�ȏ�̓��̗ǂ��ł������B�����̎������P�v���[�ɑS��������ƁA���̐��ʂ�S���Ƃ��Ă��܂��Ƌ���A�`�R�͊ϑ��������Ȃ��Ȃ������Ȃ������B
�@
�P�v���[�͗F�l�ɑ��A�u�`�R�́A���܂��ܐH���ł̌�炢�̂Ƃ��ɁA�����͂���f���̉����_�ɂ��āA���̓��͕ʂ̘f���̌�_�ɂ��ĂƂ�����Ɏ����ܘR�炵�Ă����ȊO�ɂ́A�ނ̎��o���������@���^���Ă���܂���B�v�u�`�R�� ����߂ăP�`�ŁA�ϑ����ʂ������Ă���Ȃ��B�v�Ƌ�s�����ڂ��Ă���B
�@
���̂ق��A��l�̐��i�̈Ⴂ������B�ތ������ŕn�R�ȃP�v���[�ɑ��A����D���ȑ�������`�R�A��l�͂�������イ�P���J�Ƙa�����J��Ԃ��Ă����Ƃ����B�`�R�͓������\����ϑ��ƁA�P�v���[�͓������\���闝�_�ƁA���̑Η��Ƃ����������ł���B
�@
�������A�`�R�͂₪�Ď���ł��܂�(1601�N)�B�`�R�̐����Ŗc��Ȋϑ������̓P�v���[�̂��̂ɂȂ����B
�@
�P�v���[�͂Ƃ��ɉΐ������������B�`�R���ΐ��̋O���͉~�ɓ��Ă͂߂ɂ������ƂɋC�����Ă����B���N�̌����̌��ʁA�P�v���[�͂�����u�����v���o�����Ǝv�����B�����A���̋O���͍ő�Ŋp�x��8'(���A��1'����1����1/60�̑傫��)�̈Ⴂ�����B�P�v���[�ɂ͂��̈Ⴂ���ł��Ȃ������B�������đȉ~�Ă͂߂Ă݂��Ƃ���҂�����Ȃ��ƂɋC�������B�P�v���[�̑�1�@��(�ȉ~�O���̖@��)�̔����ł���B1605�N�̂��Ƃł������B�P�v���[�͓����ɑ�2�@��(�ʐϑ��x���̖@��)���������Ă���B�����Ƃ��A�����̏������u�V�V���w�v�����ۂɏo�ł��ꂽ�̂́A�������`�R�̈⑰�̖W�Q�̂���1609�N�ɂȂ��Ă����B
�@
�������A�P�v���[�ɕs�K���������B����s���ɂȂ����v���n�ɓV�R�����͂��A�Ȃƒ��j������(1610�N)�B���܂��ɍc�邪�ς���Ă��܂������߁A�Ȍ�c��t���w�҂Ƃ��Ă̋����͖����Ɏx�����Ȃ��Ȃ�B
�@
�P�v���[�̓����c�̏B���w�ĂƂ��ă����c�ɕ��C����(1612�N)�B���̒��ł��A�܂��@���̖ʂŃP�v���[�͋�J����B�P�v���[�͐V���k�ł͂��邪�A�����Ƀ��^�[�h�̋��`���ׂĂ�[�����Ă����킯�ł͂Ȃ��炵���B�P�v���[�͂��̒��ŃX�U���i�E���C�e�B���K�[�Ƃ��������ƍč�����B�Œ�_�̏����ƌ��������Ƃ����̂͂��̂Ƃ��������Ă���Ƃ�����������B�P�v���[�͂��̏����Ƃ̊Ԃ�6�l�̎q������������(8�l�Ƃ�����������A3�l�͗c�����Ď���)�B���̂���A���Ń��C�������Ƃ��āA��M�̒��̃��C���̗ʂ̂��܂�ɂ��������ȗʂ����m��A�u���C����M�̗e�ρv(1615�N)�Ƃ����{�������Ă���B����͍��̐ϕ��ɂȂ�����e�ł�����B
�@
���̂���P�v���[�͕ʂȋ�J�����邱�ƂɂȂ�B�ނ̕ꂪ�A���������Ɋ������܂�Ė����Ƃ��č�������Ă��܂����̂��B�������Ă������A�P���J�D���ł��������̂ŁA�܂��̐l�����Ɍ����Ă��܂����悤���B1615�N�A70�̔ޏ��͑ߕ߂���Ă��܂��B�P�v���[�͗l�X�ȉ^�����s���āA��̋~�o�����݂�B���̂������ǂ����͂킩��Ȃ����A1621�N��͎ߕ������B�Ō�̍���������������Ȃ���̐q��ł��A�����ł���Ǝ������Ȃ������Ƃ����B�����A�����Ƃ��đߕ߂���āA�����Ŏߕ������͈̂ٗᒆ�̈ٗ�̂��Ƃł������B�����Ƃ��ߕ�����Ĕ��N�ŕ�͎���ł��܂��B���܂��ɂ��̊ԁA�p�����M�[�i�►��l��a�C�Ŏ����Ă���B
�@
���������Ԃ��P�v���[�͌����𑱂��A1618�N�P�v���[�̑�O�@��(���a�̖@��)�����Ă���(���ꂪ�����ꂽ�u���E�̘a���_�v��1619�Nor1620�N�̏o��)�B�f���̌��]���x�����z���牓���Ȃ�قǒx���A���������̃P�v���[�̑�O�@���ɏ]���Ēx���Ȃ�Ƃ������Ƃ���A�P�v���[�͘f���̉^���͑��z���f���ɗ͂��y�ڂ��A���ꂪ�f�������Ă���ƍl�����B�P�v���[�́A�K�����I(�C�^���A�A1564�N�`1642�N)�����������ؐ��̉q�����A���̖@���ɏ]�������邱�Ƃ��m���߂��B�����Ď��ۂɁA���̑�O�@������̑傫�Ȏ肪����Ƃ��āA�j���[�g���͖��L���̖͂@��������B1627�N�ɂ͌��Ắu�f���^�s�\�v(���h���t�\)����������B
�@
�����������c�ł��@���I���Q�������Ȃ�A�P�v���[��Ƃ͍c��R���i�ߊ����@�����V���^�C���̏����ŁA�E����(1627�N)���o�ăT�K���ɈڏZ����(1628�N�A�P�v���[57��)�B���@�����V���^�C���̓P�v���[��萯�p�҂Ƃ��Ċ��҂����悤�ł���B�����Ƃ��A���̂���͐萯�p�ƓV���w�͕s���̂��̂ł������B���̎����A�P�v���[�͓V�̂̈ʒu�̑����I�f�[�^�W�u(1621�N����1639�N�܂ł�)�V�̈ʒu��v(1630�N)���������Ă���B�܂������ɏI��������A���E�ŏ��̂r�e�����Ƃ������ׂ��u���v�������Ă���B�����ɂ͌��ɗ��s���āA�����猩���낵��(���グ��)�n���̎p���`����Ă���B�A�C�f�A�͑�w����̂��̂�(�w�������ɘb�������������Ă��炦�Ȃ�����)�B�P�v���[�̂��̂��߂ɁA�ނ̕ꂪ�����̌��^��������ꂽ�Ǝv������ł��܂��B
�@
���̂���A�V�̗�쐬�̂��߂̌v�Z����Ƃ��Čق����o�[�`�F�Ɩ��X�U���i������������A��l�Ɏq�����ł�����(�P�v���[�̑�)�ƁA��r�I���a�Ȑ������߂����B�������A����������͑����Ȃ��B���@�����V���^�C�������r���Ă��܂����̂��B
�@
�P�v���[�͎x�����Ȃ��c��t���w�҂Ƃ��Ă̋��������߂ăv���n�Ɍ��������B���肢�Ŏ�����������P�v���[�͑�ςɗ�������ł����Ƃ����B���ہA�r���̏h�ŃP�v���[�͎���ł��܂��̂�(1630�N�A�P�v���[59��)�B
�@
����ł́A�����c�ł̖������̍������߂ă����c�Ɍ��������B�M�a�Ŏ��Ƃ����B����ȑ������c�܂ꂽ�炵���B��������ł́A�����̂Ȃ��P�v���[�͗��̓r���ɖ����ȐH�����Ƃꂸ�A���㎀�����Ƃ����B�悤�₭�����Ă����{�ŃP�v���[�ƒm�ꂽ�Ƃ����B������̕����A�ތ������A�܂��߈�A�����̋�J���˕t���܂��Ƃ����P�v���[�炵�����ɕ���������������Ȃ��B
�@
�P�v���[�̂���͐헐�̒��Ŕj��A���݂�����ꂽ�܂܂ɂȂ��č����Ɏ����Ă���B
�@
�P�v���[�̋����͕��L���A��ɏグ���V���w�A���w�A�����Ăr�e�������肩�A���w�A���y(�f���̉^���̔w��ɂ͊w�I�E���y�I���a������Ƃ����P�v���[�̐M�O������B�ނ͈ꐶ���̌��e��ǂ����߂�)�A���Ԃ̌`�̍l�@�Ȃǂ��s���Ă���B
�@
�P�v���[�ɂ͋^���[���A�܂��{����ۂ��Ƃ�����������悤���B�܂������̍˔\�ɑ��鎩�M�ƁA���ׂȂ��Ƃł��悭�悷��Ƃ������ʂ��������Ƃ����B�����I�Ȑ����A�Ƒ��Ƃ̕��a�ȕ�炵�������Ȃ��������Ƃ͊m���Ȃ悤���B�@ |
�����n�l�X�E�P�v���[3
�@
���n�l�X�E�P�v���[�́A�\�����ʏo�����̘A���ɖ|�M���ꂽ�l���𑗂����B���܂ꂽ�͓̂쐼�h�C�c�̏��s�s�A���@�C���E�f�A�E�V���^�b�g�ŁA�c���������̎s���߂Ă����B���X�͂悢�ƕ��������̂����A���e�͉Ƃ�s�݂ɂ��ėb���Ƃ��Ċe�n����Q���A���Ԃ�P�v���[��20�ɂȂ�O�Ɏ���ł��܂����B���n�l�X�͎��l���傤�����̒��j�Ƃ��āA��ɕ�e�Ɉ�Ă�ꂽ�B
�@
12�̂Ƃ��A�_�w�Z�ɓ��w�B17�Ńe���[�r���Q����w�ɐi�݁A���{�ے����o�Ă���ɐ_�w�̕���i�߂��B�v���e�X�^���g�̐��E�҂ɂȂ�̂��ނ̖ڕW�������B�Ƃ��낪1594�N(22��)�A���������Ő_�w�̉ے����C������Ƃ���ŁA�P�v���[�͓ˑR�A�I�[�X�g���A�̃O���[�c�ɂ���_�w�Z�̐��w���t�ɐ��E�����B�ނ͑�w�ŁA�_�w�̂ق��Ƀ~�q���G���E���X�g�������琔�w�ƓV���w���w��ł���A���̕��M�S��������̐��E�ɂȂ������̂��B�s���s���Ȃ���A�P�v���[�͂��̐l�����e�ꂽ�B
�@
�O���[�c�ł̃P�v���[�́A�w�Z���t�Ƃ��Ă̎d���̂ق��ɁA�n��̐��w���Ƃ����E�������˂Ă����B���̎�Ȏd���͓V���w�Ɋ�Â���̍쐬�ƁA���N�̏o�����ɂ��Đ萯�p���g�����\�������邱�Ƃ������B�萯�p�͎������Ƃ��Ă��d�v�ŁA�P�v���[�̗\���͕s�v�c�Ƃ悭���������B�萯�p�����܂�ǂ����̂Ƃ͎v���Ă��Ȃ������P�v���[�����A���ǂ͐��U��ʂ��A�l�̋��߂ɉ����Ă��܂��܂ȗ\�����s���Ă����B
�@
1597�N(27��)�A������ƂȂ�w�F�����̐_��x���o�ł����B�P�v���[�͂��łɑ�w����A���X�g��������R�y���j�N�X�̒n�����̂��Ƃ�m��A����Ɏ䂩��Ă����B�����������ɂ͂܂������̓䂪�����āA�P�v���[�͉F���̔閧��Ǝ��ɉ������������Ƃ����̂������B���z�n�̘f���̐��Ɣz�u���܂̑��ʑ̂ɂ���Đ��������Ƃ����ނ̗L���ȃA�C�f�B�A�͂��̖{�ɓo�ꂷ��B�P�v���[�͏I���A�F���͐��w�I�ɍ��グ���Ă���ƐM���ċ^��Ȃ������B�ނɂƂ��āA�F���ɔ�߂�ꂽ���w���𖾂��邱�Ƃ́A�����n�������_���������邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������̂��B
�@
���̖{�̈�����I����ăP�v���[�̂Ƃ���ɓ͂������O�ɁA�P�v���[�͎��ƉƂ̖��o���o���E�~�����[�ƌ��������B23�̃o���o���͂��ꂪ�O�x�ڂ̌����ŁA�q�ǂ�����l�����B�P�v���[�͌�ɐ��܂�鎩���̎q�ǂ������Ɠ��l�A���̎q�����������B�Ƃ��낪���̗��N�A���@�����v���N����A�O���[�c�ł̓v���e�X�^���g�ɑ���Ǖ��߂��o�����B�P�v���[�͏�����ɖ߂邱�Ƃ������ꂽ���A���̓s�s�͂��͂���S�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B
�@
����Ȓ��A�P�v���[�͓��カ���Ă̓V���ϑ��ƃe�B�R�E�u���[�G����A�����̂Ƃ���ɗ��Ȃ����Ƃ����U�������B�e�B�R�͂��̏����O�A�v���n�ɂ���_�����[�}�c�郋�h���t2���̉��Ɉڂ��Ă��Ă����B�P�v���[��1600�N(28��)�ɔ��N�قǒP�g�Ńv���n��K�ˁA�e�B�R������炳���f�ГI�ȃf�[�^�����ƂɁA�ΐ��̉^���ɂ��Č��������B�����Ĉꎞ�A����A���̔N�̂����ɉƑ���A��ăv���n�Ɉڂ����B
�@
�\�z�O�������̂́A���̗��N�A�e�B�R������ł��܂������Ƃ������B�e�B�R�̏���Ƃ��čc��ɂ��Љ��Ă����P�v���[�͓ˑR�A�c��t���̐��w���ɔC������A�e�B�R�̎d���������p�����ƂɂȂ���(29��)�B�ő�̋Ɩ��́A�e�B�R�̊ϑ��Ɋ�Â��ēV�̂̉^�s���܂Ƃ߂��\�A�w���h���t�\�x�������E�o�ł��邱�Ƃ������B
�@
���ۂɂ́A�܂��o�ł��ꂽ�̂́w�V���w�̌��w�I�����x(1604�N)�Ɓw�V�V���w�x(1609�N)�Ƃ�����̖{�ł���B�O�҂ł́A���̂�������͖̂ڂ������Y�ɂȂ��Ă��邩�炾�Ƃ������Ƃ����߂Ė��炩�ɂ����B�����Č�҂ł́A�ΐ��̉^���ɂ��Ă̏ڂ����������s���A���̋O�����ȉ~�ł��邱�Ƃ�A��莞�Ԃɘf���Ƒ��z�����Ԑ����`���ʐς͈��ł��邱�ƂȂǂ����(������P�v���[�̑��@���Ƒ��@��)�B�܂����̖{�ł́A�V���w�ł͕����I�����̒T�����d�v���Ƃ����M�O�̂��ƁA���z����́u�́v�ɂ���Ęf������������Ă���Ƃ����l�����q�ׂ��Ă���B
�@
������1610�N�ɂ́A�C�^���A�l�K�����I���]�����œV���ϑ����s�����Ƃ����j���[�X����э���ł����B�P�v���[�͂���ɂ������ܔ������A�K�����I�́w���E�̕x���x������w���E�̕҂Ƃ̑Θb�x(1610�N)���o�ŁA����Ƀ����Y�ɂ�鑜�̌`���ɂ��Ę_�����w���܌��w�x(1611�N)���������B
�@
�������������̏�ł́A1611�N�͔ߎS�ȔN�������B�c�郋�h���t2������̃}�e�B�A�X�ɂ���đވʂ������A���N�ɖv�����B�����Ă��̊ԂɋN�����������̒��A�q�ǂ���l�ƍȂ̃o���o�����a�C�ŖS���Ȃ����B���N�A�P�v���[�̓I�[�X�g���A�̃����c�Ɉڂ�A�����ňȑO�Ɠ����悤�ȁA�w�Z���t���c��w���Ƃ����d���ɏA�����ƂɂȂ�B�w���h���t�\�x�̊��������������A�P�v���[�̎d���Ɋ܂܂�Ă����B
�@
�����c�ŃP�v���[�́A��l�ڂ̍ȁA�Y�U�i�E���C�e�B���K�[���}����(1613�N)�B���̂Ƃ�41�������P�v���[�́A����11�l���̉ԉŌ���T�d�ɋᖡ���A�ŏI�I��24�̃Y�U�i�ɋ��������̂������B���������̎����̃P�v���[��������ōK���������Ƃ͌����Ȃ����낤�B�Ȃ��Ȃ�P�v���[�́A�L���X�g���̏��h(�J�g���b�N�A���^�[�h�A�J�����@���h)�ɂ͂��ꂼ�ꌩ��ׂ��Ƃ��낪����ƍl���Ă���A���ʂƂ��Ăǂ̏@�h��������ԂƔF�߂Ă��炦�Ȃ���������ł���B
�@
����ɂ�����A���̎����ɂ͑�ςȏo�����Ɍ�����ꂽ�B��e�J�^���[�i�̖����ٔ��ł���B����͌����|����̂悤�Ȃ��̂ł͂���������ǂ��A���ۂɑ����́u�،��v���W�߂��ăJ�^���[�i�͑ߕ߂���Ă��܂��A�ٔ��ɂ�����ꂽ�B�P�v���[��1620�N����21�N�ɂ����ă������e���x���N�ɋA��A��ٌ̕�͓I�Ɏ菕�������B�K���A�����͍ŏI�I�ɑނ����A�J�^���[�i�͎ߕ����ꂽ���A���̔��N��ɖS���Ȃ����B
�@
���̂悤�ȓ��X�̒��ŁA�P�v���[�͎����̌������������i�߂Ă����B�w���C���M�̐V�����̐ϑ���x(1615�N)�A�w�R�y���j�N�X�V���w�̊T�v�x�S3��(1617-21�N)�A�w�F���̒��a�x(1619�N)�Ƃ������{�����̎����ɏ�����A����Ɂw�F�����̐_��x�̑��ł��o�ł��ꂽ(1621�N)�B���̂����w�F���̒��a�x�ł́A�f���̂������̋������a��(�n�[���j�[)�Ƃǂ̂悤�ȊW�ɂ��邩���c�_����A���f���̑t�ł�u���K�v���_����ꂽ�B������P�v���[�̑�O�@���A�f���̎�����2�悪���z����̋�����3��ɔ�Ⴗ��Ƃ����W�́A���̒��Ŏ����ꂽ�ő�̔����������B
�@
�����܂�����A�@�����v�̐헐�������Ă����B�P�v���[�Ɏc���ꂽ�Ō�̎d���A�����Ɗ������ꂸ�ɂ����w���h���t�\�x�̏o�ŏ����͐������������A�����c�ł͂��̎d���͑�����ꂻ�����Ȃ������B1626�N(54��)�A�P�v���[�͉Ƒ���A��ă����c����ɂ��A���[�Q���X�u���N�ɉƑ��𗎂���������ƁA���e�Ɗ������g���ĒP�g�E�����Ɍ��������B�����Ă����ŁA���Ɂw���h���t�\�x(1627�N)�͗z�̖ڂ������B
�@
���̌�A�P�v���[�͒鍑�̏��R���@�����V���^�C���ɏ����������邱�ƂɂȂ�A���x�ڂɂȂ邩�킩��Ȃ������z�������ăU�[�K���Ɉڂ����B�����Ă����ŁA�܂�����R�@�����v�Ɋ������܂ꂽ�B����ǂ��납�A1630�N�ɂ́A���@�����V���^�C���̐����I�n�ʂ��낤���Ȃ����B�P�v���[�͎��Ԃ̐��ڂ�����낤�ƁA���̔N�̏H�A���[�Q���X�u���N�Ɍ��������B���ʂƂ��Ă��ꂪ�����ɂȂ����B���̓r���ŕa�C�ɂ��������P�v���[�́A���n��11��15���ɑ�������������B58�������B
�@
�P�v���[�̐��U�́A�Ƃ�킯�@�����v�̂��߂ɁA�g���ɖ����Ă����B���ꂾ������ɖ|�M����Ȃ��玩���̌����ɏW�����A����قǑ����̖{���o�����̂͋��ٓI�Ǝv���B�S���Ȃ��������A�P�v���[�͎����̖{����������A��������Ă���r���������B���q�̎��1634�N�ɏo�ł��ꂽ���̈��́A�����猩����ł��낤�V�����ۂɂ��ĕ��ꕗ�ɏ����ꂽ���̂ŁA�ߑ�I�Ȃr�e�̐�삯�Ƃ�������B�w���̍��̒��z�Ɋ�Â����̍�i�ɂ́A�w���x�Ƃ����\�肪�t�����Ă����B�@ |
���e�B�R�E�u���[�G�ƃP�v���[
�@
�萯�p�A���̐肢���@�ɂ��������Ȃ�̍���������̂��Ƃ����^����������萯�p�t�����܂����B�h�C�c�̊w�҃��n�l�X�E�P�v���[�A��ɂ��̎t�ƂȂ�e�B�R�E�u���[�G�ł��B�V�̂̉^�s����l�ԂɊւ�錻�ۂ�\���ł���Ƃ���Ȃ�A�ςȌ`������̐肢������̂ł͂Ȃ��A�����ƓV�̂̉^����[���݂߂Ă��̉��ɂ���@����m��K�v������̂ł͂Ȃ����ƍl�����̂ł��B
�@
�ނ�̌����ȑO�ɂ��A�ꉞ�V�̂̉^�s�\�͂���܂����B���������ꂪ�������������̂ŁA�f���}�[�N�̐萯�ƃe�B�R�͂����Ɛ��x�̍����^�s�\�����낤�Ƃ��Ă��܂����B�傪����ȓV������f���}�[�N���ɂ����Ă��炢�A���ĂȂ����x�Ŋϑ��𑱂��܂����B�����A�]�����̂Ȃ�����ōō����x�̊ϑ����ʂł���A�e�B�R�͋�C�̋��܂ɂ�萯�̈ʒu���킸���ɂ���邱�Ƃ��m���Ă����ƌ����܂��B
�@
���������ɂ��萯�p�t�͂����킯�ŁA�킴�킴�c��ȗ\�Z���Ă��̂悤�Ȍ���������Ӗ�������̂��A�Ƃ������R�Ńe�B�R�͉��������Ă��܂����B�e�B�R�̓e�B�R�Ŋ�łȐ��i�����������ŁA�ӌ����Փ˂��A���ǔނ̓f���}�[�N�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����Ĉڂ����悪�A�_�����[�}�鍑�̂��̂�����ƕςȍc��A���h���t2���̌������ł����B
�@
�e�B�R�̖����̉\�ŕ������P�v���[�́A��q���肷�邽�ߌ̋�����e�B�R�̂��Ƃ֍s���Ă��܂��B�v�f�ʂ�e�B�R�ɒ�q���肵���P�v���[�͂������Ɏt���e�B�R����傫�ȐM���A�e�B�R�̎���ɔނ�16�N�ɓn���Ċϑ������M�d�ȃf�[�^���p�����ƂɂȂ�܂��B���̓�l�̂߂��荇�킹�ɂ���ăP�v���[��3�@���̔����A����ɂ̓j���[�g���͊w�ւƔ��W�����̂ł�����A���̂��Ƃɓ����ꂽ�o��������A�ƌ����Ă�������������܂���ˁB
�@
�P�v���[���e�B�R���������f�[�^�́A������������Ă��Ȃ����̊ϑ��l�ł����B�e�B�R�͊ϑ��Z�p�ɂ͗D��Ă������̂́A���w�̘r�͂��܂�Ȃ����������ł��B����A������p�����P�v���[�́A�f�[�^����N���v�Z�����鏈�������ӂł����B�������킯�ŁA�P�v���[�͂܂������Șf���O�������߂邱�Ƃ���͂��߂܂����B�v�g���}�C�I�X�̓V�����A�R�y���j�N�X�̒n�����Řf���̉^���͈�ʂ�����ł��Ă����͂��ł������A�e�B�R�̐����Ȋϑ��f�[�^����Z�o���ꂽ�O�����Ƃ�����̐��͍���Ȃ����Ƃ�������܂����B���ɉΐ��̋O���͎����l�Ƃ̈Ⴂ���傫���A����܂ł̐����C�������Ƃ��K�v�ɂȂ����̂ł��B
�@
�V�����Ɣ�ׂāA�R�y���j�N�X�̒n�����͒P�Ɂu���ȒP�ɐ����ł���v�Ƃ����Ӗ��݂̂������Ă��܂����B��������ɃP�v���[���ΐ��O���̌v�Z���甭������O�̖@���A�����ăj���[�g���̔������閜�L���̖͂@���Ɖ^���̖@���ɂ���āA�n�����͒P�Ɏ��_��ς��Ă݂₷�����邾���̂��̂ł͂Ȃ��A�u�n���͓����Ă���v�ƒf���ł��闝�_�ւƔF����ς��܂����B�@ |
���e�B�R�E�u���[�G
�@
���ꂽ���̖�ɋ�����グ��Ɛ������̐��������܂��B�F���ɂ͉�X�l�ނ���炷�n�����܂��F���ɑ�R���鐯�̈�ŁA���z�n�̑�3�f���ł��邱�Ƃ͊F�m���Ă��邱�Ƃł��B�n���Ƒ��z����ё��̘f�����ǂ̂悤�Ȉʒu�W�ɂ���̂��ƌ������ƂɊւ��Ă����ł͒n���͑��z�̎��������Ă���ƌ������Ƃ��펯�ɂȂ��Ă��܂����A���ꂪ�펯�Ƃ��Ē蒅����܂łɂ͐l�ނ�������z�������Ă��炩�Ȃ�̔N����v���܂����B�Ñ㐢�E�ł͒n���Ƒ��z����ё��̘f���̊W�ɂ��Ă̓A���X�^���R�X�̂悤�ɒn���������Ă���Ƃ����n�����͏o���ꂽ���̎x����ꂸ�v�g���}�C�I�X�������V�������蒅���A�ȍ~16���I�܂Ŏ��X�^�`�͎��������̂̓V�����������ɂ킽���ĐM�����Ă��܂����B���ꂪ�R�y���j�N�X�A�K�����I�A�P�v���[�Ƃ������V���w�҂�16���I�㔼����17 ���I�O���ɋ삯�Ċ��A���ꂩ��悤�₭�n�������F�߂���悤�ɂȂ����킯�ł��B�����������̐l���Ɣ�ׂ�Ɩڗ����܂��A�k���Ȋώ@�N�ɂ킽�葱���ēV�����ƒn�����Ɋւ��Ă��Ȃ�ς�����A�C�f�A���o�����l�����e�B�R�E�u���[�G�ł��B�ނ��W�߂��f�[�^���Ȃ���P�v���[�̌����͂ł��Ȃ������ƌ����_�ł��V���w�̔��W�ɂ��Ȃ��^�����l���ł��B
�@
���V���w�҂ւ̓�
�@
�e�B�R�E�u���[�G(1546�`1601)�͓����f���}�[�N�̂������w���V���O�{��(���̓X�E�F�[�f���암)�̋M���̉Ƃɐ��܂�܂������A���܂�Ă܂��Ȃ��f���̉Ƃɗ{�q�ɏo����Ă��܂��B���������̏f�������Ȃ肨�������������悤�ŁA���̂��Ƃ��ނ���Ɋe�n�̑�w��V�w���邤�ő傢�ɖ𗧂��ƂɂȂ�܂��B�u���[�G�͎n�߂���V���w�҂��u���Ă����킯�ł͂Ȃ������悤�Ő����ƂɂȂ邱�Ƃ�]��ł����Ƃ��f�������̂悤�Ȋ��҂����߂Ă����Ƃ������Ă��܂��B������ɂ��悻�̂��߂�13�����w�ɒʂ��A�Ȍ�e�n�̑�w�Ŋw�Ԃ��ƂɂȂ�܂����A�܂��̓f���}�[�N�̃R�y���n�[�Q����w�œN�w�ƏC���w�̕������n�߂܂��B��������w�ŕ����n�߂ĊԂ��Ȃ��u���[�G14�̎��ɔނ͓��H��ڌ����܂��B����萯�Ƃ����H��\�����A���ꂪ�����ɓI���������Ƃɋ������������u���[�G�͂��̌�V���w�ɋ����������v�g���}�C�I�X�̓V���w��ǂ݂ӂ���܂��B�ނ̓V���w�ւ̋����͂��̌㋭�܂肱�������܂邱�Ƃ͂Ȃ� 1562�N�Ƀ��C�v�`�q��w�̖@�w���ɓ]�w�����ɂ�������炸���w�ƓV���w�ɔM�����Ă��������m���Ă��܂��B
�@
���̂���ɂȂ�ƃu���[�G�͎���ϑ����s���A�����̈ʒu�ɂ��ꂪ���邱�Ƃ�m��悤�ɂȂ��Ă��܂��B�������Ƀ��[���b�p�ɂ͐��}�\�����݂��A�u���[�G�̍��ɂ̓A���t�H���\�\(13���I�㔼�ɍ��ꂽ��)�ɂ��킦��1551�N�ɂ̓v���C�Z���\�ƌĂ�鐯�}�\������Ă��܂������A�������Q�Ƃ��Ȃ���ϑ����A�\�ɕ`���ꂽ���ƌ��݂̐����̈ʒu�ɂ��ꂪ���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B�܂� 1563�N�ɂ͖ؐ��Ɠy�����ώ@������܂ŗp�����Ă����f���^�s�\�ɑ傫�Ȍ덷�����邱�Ƃ��������Ƃ��`�����Ă��܂��B�u���[�G�͂��̌ピ�B�b�e���x���O��w�A���X�g�b�N��w�Ŋw�сA����Ƀo�[�[���A�A�E�O�X�u���O���܂��A1571�N(1573�N����)�ɂ͌̋��̃f���}�[�N�ɋA�������Ƃ����Ă��܂��B�������u���[�G�����w�̒m�����Ђ��炩�������Ƃ������ő��̗��w���ƌ������邱�ƂɂȂ�A���̌��ʕ@���������Ƃ���Ă��܂����̂����B�b�e���x���O��X�g�b�N�ŗV�w���Ă������̂��Ƃł����B�@���������Ƃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ̓u���[�G�ɂƂ肢���������S����������s�ׂ������悤�ŁA���Ƌ���������p�e��^�J���̖͑��@��p�ӂ��A�t���@�����ꂽ�Ƃ��ɂ͂����C���ł���悤�ɂ̂�̂悤�ȕ����펞�g�т��Ă��������ł��B�u���[�G�ɂ��Ă͉����Ȏ��M�ƂƂ����]��������邱�Ƃ��������悤�ł����A����͕@���ꂽ���Ƃɂ����̗��Ԃ��ł͂Ȃ����Ƃ����w�E���ׂ���Ă��܂��B������t���@��p�ӂ�����A������g��������т₩�ȃp�e�ł�����悤�ɂ��Ă��A���F����͑�֕��ɉ߂��Ȃ��킯�ŁA�����B�����߂ɘ����E�����ɂȂ�Ƃ����̂�������悤�ȋC�����܂�(������ꂾ���Ńu���[�G�̍s�����������̂͊댯���Ǝv���܂���)�B
�@
���l�X�Ȕ���
�@
1570�N��ɂ̓e�B�R�E�u���[�G�͓V���w�҂Ƃ��Ċ���悤�ɂȂ��Ă���A���̊ԂɐF�X�Ȃ��Ƃ����܂��B���̋Ɛт�1572�N�̐V�������A1577�N�̑�a������(���̌�u���[�G��20�N�Ԃ�5�̜a�������܂�)�Ƃ������̂ł������A����͓����̉F���ς�h�邪���傫�Ȕ����ł����B���܂ł̓V���w�ł̓A���X�g�e���X�̊w���ɏ]���A����艓���ł͉����ω��͋N���炸�i���s�ς̓V���ł���ƐM�����Ă��܂����B�������u���[�G�͐V�������Ƒ�a�������������������艓���ŋN�������Ƃ����ۂɎ����A�A���X�g�e���X�ȗ��̉F���ς̌����������ƂɂȂ����킯�ł��B���ꎩ�g�͌Ñ�̓V���w�҂����̐����x�����悤�Ƃ����l���Ȃ̂ł����A�ނ̐����Ȋϑ��͂���������Ђ�����Ԃ��悤�Ȍ��ʂ������������ƌ������Ƃ͉��Ƃ�����Șb�ł��B
�@
���X�g�b�N������o�[�[�����ւăA�E�O�X�u���O�ւƂ���ė���1568�N����1570�N��O���̃u���[�G�̍s���ɂ��Ă̓A�E�O�X�u���O�ɂ����ċ������̗v�����Ĕ��a6���[�g���̑�ی��V��1�����ԐE�l���ق��č�点����̍s���ŏ��Ƃɂ���ĈႢ������悤�ł��B�u���[�G�̓V���w��̋Ɛт̈��1572�N�ɐV���������Ƃ����o�������������܂����A�V�������̏ꏊ�ɂ��Ă̓A�E�O�X�u���O�؍ݒ��Ɍ������Ƃ�����ƁA�̋��f���}�[�N�ɋA�������Ƃ��Ɍ���������O�ɏo�ċ�����グ���Ƃ��Ɍ������Ƃ����������܂��B 1573�N�ɃR�y���n�[�Q���Łu�V���ɂ��āv�Ƃ����_���������Ă���̂ŁA���̂���ɂ͊��ɋA�����Ă��邱�Ƃ͊m���ł������̊Ԃ̎��͂��܂�킩���Ă��Ȃ��悤�ł��B
�@
����������̖ʂł�27�̎�(1573�N)�ɔ_�Ƃ̖��ƌ�����(���̌�9�l�̎q�����������邱�ƂɂȂ�܂�)�A���ꂪ�����ňꑰ���ł̃g���u�����������A�u���[�G�͌̋��𗣂�ă��[���b�p�e�n��f�r���܂��B���s�̖ړI�͓V���w�̌����ƂƂ��ɏZ�ޏꏊ��T�����Ƃ������悤�ł����A���̗��s���Ƀ��B�b�e���x���O�Ńv���C�Z���\�쐬�҂̑��q����S���̌��e�������Ă���������ƁA�w�b�Z���ł͗̎僔�B���w����4���ɓV���ϑ����������Ă���������Ƃ��m���Ă��܂��B�������Ȃɂ������̌�̃u���[�G�ɂƂ�傫�ȓ]�@�ƂȂ�̂̓��B���w����4���ƒm�荇�������ƂŁA�ނƒm�荇�����Ƃ��Ȃ�����̌�̌��������͂ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�̋��f���}�[�N�ɋA���Ă����u���[�G�̂��ƂɃf���}�[�N���t���f���N2������V���䌚�݂̐\���o����������ł��܂����A�t���f���b�N�ɂ�������悤�i�������̂̓��B���w����4���ł����B
�@
���E���j�{���V����ɂ�
�@
�f���}�[�N���t���f���N2�����u���[�G�̂��߂ɓV���䌚�݂�\���o�A����ɂ��f���}�[�N�̃t���F�����ɋ���ȓV���䂪����邱�ƂɂȂ�܂��B�t���F�����͌��݂̓X�E�F�[�f���̂ɂȂ��Ă��܂��������̓f���}�[�N�̂ŁA���͂��悻10�L���̏����ȓ��ł����B��������ɍ��ꂽ�V����͔��ɑ�K�͂ȕ��œV���ϑ����ɂ��킦�ď��ɁA�������A������A�H��(�V���@������邽��)������Ă��������łȂ������������܂邽�߂̐ݔ����p�ӂ���Ă��܂����B���̓V����͒n������F�����ϑ��������ɂȂ��Ă��܂����A����͓����̓V�̊ϑ��͖]�������Ȃ��������߂ɓ���ōs���Ă���A�����x�Ő��̈ʒu�����߂悤�Ƃ���Ƃǂ����Ă���K�͂Ȑݔ����K�v�ɂȂ�܂��B�n���̊ϑ����̓g���l���łȂ����Ă���A�~�`�̊ϑ����̒����ɂ͎�����K��Z���V�Ȃǂ̊ϑ��@�킪�u����A�ǂɂ����č��x�ɉ����ϑ��҂��ʒu��ς��邽�߂̊K�i������ł���܂��B�ϑ��҂̓h�[����̓V����ʂ��Đ��̈ʒu�𑪒肵�Ă��܂����B�����̊ϑ����u�͖ؐ��ŕ��Ɏキ�A�u���[�G�͊ϑ����x�����߂����ʒn���Ɋϑ�������邱�Ƃ�I�Ƃ����킯�ł��B
�@
�V����͂��̌����ڂ͂���������s�̂悤�ł���A�E���j�{��(�V�̏�)�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂��B����������ł���ɂ͎苷�ɂȂ�(������ƈ��̐�������������)�A�ʓ�������ɂ����ăX�e�����{��(���̏�)�ƌĂ�Ă��܂����B���̓V�����1576�N 8���Ɋ�������12���ɂ͊ϑ����J�n���A���̓V����Ńu���[�G�͐����ȓV�̊ϑ���20�N�ɂ킽���čs���đ�ʂ̃f�[�^�����W���邱�ƂɂȂ�܂�(��q�̜a�����������̓V���䂪�ł��Ă����̂��Ƃł�)�B�V���䌚�݂͍��ɂ��甜��ȏo��(2���|���h)�������Ȃ��Ƌ��Ƀu���[�G���g���f�����瑊��������Y2���|���h�Ǝ��g������������������̔̔����v��������ł悤�₭�������A���̈ێ��̂��߂ɂ���n�����炠������v�����Ă���ꂽ�ƌ����Ă��܂��B�Ȃ��u���[�G�{�l�ɑ��Ă��N��(400�|���h)���x������Ă��܂��B
�@
������1588�N�Ƀt���f���N2�����������A�N���X�e�B�A��4�������ɂȂ�Ə��X�Ƀu���[�G����芪����͕ω��������n�߂܂��B�����Ă��Ƀt���F�����̓V����͕�����A�u���[�G��1597�N�ɓ�������A1599�N�Ƀv���n�ɒ����Ƃ�����ςȑ̌������邱�ƂɂȂ�܂��B�N���X�e�B�A��4�������ʂ��Ă��炵�炭�͉�������̎x�����������̂ł������ꂪ����ɓr�₦�Ă����܂��B����ɂ̓u���[�G�������̔����Ă����������t�����̔������ĂԂ��ƂɂȂ�A�������炳��ɓV����̗L�p�����^�⎋����鎖�ԂɎ����Ė��p�Ɣ��f���ꂽ���߂ɉ������ł����ēV���䂪�����ꂽ�ƌ����Ă��܂��B����Ńu���[�G�̉����Ȑl�����l�X�̔������Ă���A�ނ̃p�g�����ł������t���f���N2���̎��ƂƂ��ɕ\�ɕ��o�����Ƃ������Ă��܂��B�u���[�G�̓V����ł̑ԓx�̓E���j�{���̕ǂɗ��̈̑�ȓV���w�҂̏ё�����ׂ��Ƃ��Ɏ����̏ё���u���A����ɔނ̌�p�҂̏ё���`�����Ă����Ƃ�����b���`�����Ă��܂����A�ގ��g�͎����ɂ��Ȃ������ȓ`�B�@����g���ď�����ƈ��Ɏw�߂������Ă������߂Ɏd�����ǂ�ǂ�i�Ƃ������Ă��܂�(���̕ӂ͂���̉����Ȑl�����傢�ɖ𗧂����H�̂�������܂���)�B
�@
1599�N�Ƀv���n�ɓ������u���[�G�͓����̐_�����[�}�c�郋�h���t2��(���̐l�����Ȃ�������l���Ƃ��Ēm���Ă��܂�)�̂��ƂœV���w�ҁE�B���p�t�E�萯�p�t�Ƃ��Čق��܂��B�v���n�x�O�̃y�e�i�N��ɓV������\���܂���1601�N�ɔނ͎���ł��܂����ߐV���Ȕ����Ȃǂ͂Ȃ��A�V���w�҂Ƃ��Ẵu���[�G��1597�N�Ƀt���F�������o�����_�ŏI����Ă����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ł��B���������̃v���n�؍݂����ʂ������̂��Ƃ����ƌ�̓V���w���W�̓_����͏d�v�ȏo�����ł����B�����1600�N����u���[�G�̂��ƂŃP�v���[�������n�߁A�P�v���[�̓u���[�G�̎���A�ނ��~���Ă��������f�[�^��L�����p���Ȃ���P�v���[�̏��@�����m�����邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�@
���u���[�G�̉F����
�@
���N�ɂ킽��V�̊ϑ����s���c��Ȏ����f�[�^���c������(������P�v���[���L�����p���Ă����܂�)�A�a����V�������ď]���̉F���ςɋ^�`��悵���u���[�G�ł����A�ގ��g�̉F���ς͏]���̓V�����ł����B�u���[�G�����܂ꂽ�N�̓R�y���j�N�X������ł���3�N��ł����A�ނ͒��N�̊ϑ��̌��ʃR�y���j�N�X�̒n�����ł͂Ȃ��V������������Ɏ���܂��B�������P���ȓV�����ł͂Ȃ��A�n���ȊO�̘f���͑��z�̎��������Ă��邪���z�͂����̘f���ƂƂ��ɒn���̎��������Ă���Ƃ����̂��u���[�G�̍l�����ł����B
�@
�u���[�G�����̂悤�ȍl�����Ɏ������͔̂ނ��n�����ɋ^��������Ă������߂ł����A����ɂ��Ă͔ނ����N�ɂ킽���Ď������J��Ԃ��Ȃ�����N���������Ȃ����Ƃ���^���������Ƃ����̂���ʓI�ł����A����Ŕނ����M�Ƃł��肻��̂ɒn������������Ȃ������Ƃ������������܂��B��������҂̐�����17���I�̉Ȋw�҂̂Ȃ��ɖ��M�ƂȐl�����邱�Ƃ��v���Ə��X�ꂵ���Ǝv���܂��B��͂肱���̓u���[�G������߂Ď��ؓI�ȓV���w�҂ł��������Ƃ��������Ēn��������̏�Q�ɂȂ����̂��낤�Ƃ������܂��B�Ȃɂ��u���[�G�̓V����ł͖]�����͗p�����Ă��炸�A�ނ��]�����̂Ȃ�����̓V���w�҂ł��������Ƃ��l������K�v������Ǝv���܂��B���݂̊ϑ��Z�p���g���P���ɂ��Ă̔N�����������肳��܂�������͔��ɏ����ȕ��ŁA��X�����ԋ߂��P���ŔN�������͍ő�0.76�b�Ƃ̂��Ƃł��B 1�b��100�L�����50�Z���`�Ƃ����p�����ɂ�����A����͏œ_����10���[�g���̓V�̖]�����Ŏʐ^���B���Ă�����ł�0.05�~����������Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�悤�ŁA��������Ŋm�F���邱�Ƃ͖����������킯�ł��B����䂦�Ƀu���[�G�͓V�������x�����邱�ƂɂȂ����̂ł��B����������Ĕނ̑��݂̓R�y���j�N�X��P�v���[�ɔ�ׂ�Ɨ]��ڗ����܂��A����̎����f�[�^���Ȃ�����̌�̓V���w�̔��W�����������킯�ŁA�Â�����ƐV��������̋��n�������ʂ������ƌ������Ƃ͂ł���Ǝv���܂��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���K�����C�u���E2��̌n�ɂ��Ă̑Θb�v���� 1632�N |
   �@
�@
|
Galilei, Galileo.(1564-1642)
�@
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.
�@
�K�����C�́A�C�^���A�̕����w�ҁA�V���w�ҁB1583�N�Ƀs�T�̐����̒ݓ������āA�U��q�̓����������A�s�T�̎Γ��ŗ��̂̎������s���A�A���X�g�e���X�̎��R�w�̌��𐳂��ȂǁA�ߑ�͊w�����̊�b��z�����B1609�N�ɂ͖]���������āA�V�̊ϑ��ɉ��p����X�̔����������B���ɖؐ��̉q���̔����́A�R�y���j�N�X�̒n�����Ɉ��^�����B�������A�ނ̌������ʂɑ��锽�����������̂ŁA���[�}�ɕ����ى��������A1616�N�@���ٔ��ɂ������A�n�����̕����𖽂���ꂽ�B�t�B�����b�c�ɋA�����K�����C�́A1632�N�ɖ{�����A���{���ďo�ł������A�ًc���o�ă��[�}�ɗH���ꂽ�B�悤�₭�͂��ꂽ���A�u����ł��n���͓����v�ƂԂ₢���Ƃ����Ă���B�@ |
���K�����I�E�K�����C
�@
(Galileo Galilei�A�����E�X��1564-�O���S���I��1642)�@�C�^���A�̕����w�ҁA�V���w�ҁA�N�w�҂ł���B�p�h���@��w�����B���̋Ɛт���V���w�̕��Ə̂���A���W���[�E�x�[�R���ƂƂ��ɉȊw�I��@�̊J��҂̈�l�Ƃ��Ă��m����B1973�N����1983�N�܂Ŕ��s����Ă���2000�C�^���A�E����(�����̕����`)�����ɃK�����I�̏ё����̗p����Ă����B
�@
�g�X�J�[�i�n���ł́A���j�̖��O�ɂ́u���v��P���`�ɂ��Ă��̖��O�Ƃ��邱�Ƃ�����B���B���`�F���c�H�E�K�����C�̑��q���u�K�����I�E�K�����C�v�Ɩ��t����ꂽ�̂����j�䂦�ƍl������B�C�^���A�ł͓��Ɉ̑�Ȑl���𐩂ł͂Ȃ����ŌĂԏK��������(���ɂ��A�_���e�A���I�i���h�A�~�P�����W�F���A���t�@�G���A��)���߁A���ł���u�K�����I�v�ƌď̂���邱�Ƃ������B���Ȃ݂ɁA�K�����I�E�K�����C�̉ƌn�ɂ͓����u�K�����I�E�K�����C�v�Ƃ������̈�t�������B
�@
��
�@
�K�����I��1564�N�Ƀg�X�J�[�i������̃s�T�Œa�������B���̃��B���`�F���c�H�E�K�����C (Vincenzo Galilei) ��1520�N�t�B�����c�F���܂�̉��y�Ƃł�����(���������c��ł���)�B��̓y�[�V�����܂�̃W�����A�E�A���}���i�[�e�B (Giulia Ammannati)�B��l��1563�N�Ɍ������A���̗��N�ɃC�^���A�̃g�X�J�[�i������̃s�T�Œ��q�̃K�����I�����܂ꂽ�̂ł������B���̌�A�K�����I�ɂ͒�4�l�A��2�l���o�����B
�@
1591�N�ɕ�������ł���́A�Ƒ��̕}�{�▅�̎��Q���̎x�����̓K�����I�̌��ɂ̂��|���邱�ƂɂȂ����B
�@
�����B���`�F���c�H�͉����w�̌����Ő��I�ȋL�q�E���͂��d�������@��p�����B���ꂪ��ɑ��q�K�����I���^�������ō̂������I�Ȏ�@�ɉe����^���邱�ƂɂȂ����Ǝw�E����Ă���B
�@
1581�N�K�����I�̓s�T��w�ɓ��w���邪�A1585�N�ɑފw�B1582�N������g�X�J�[�i�{��t���̐��w�� �I�X�e�B���I�E���b�`�Ƀ��[�N���b�h��A���L���f�X���w�сA1586�N�ɂ̓A���L���f�X�̒���Ɋ�Â��ēV�������ǂ��ŏ��̉Ȋw�_���w���V���x�\����B
�@
1589�N�Ƀs�T��w�̋����̒n�ʂāA���w���������B1592�N�p�h���@��w�ŋ����̐E�A1610�N�܂Ŋw�A���w�A�V���w���������B���̎����A�ނ͑����̉���I��������ǂ𐬂������Ă���B
�@
�K�����I�́A���̂̉^���̌���������Ƃ��Ɏ������ʂ𐔓I(���w�I)�ɋL�q�����͂���Ƃ�����@���̗p�����B���̂��Ƃ�����̎��R�Ȋw�̗̈�ō����]������Ă���B�ވȑO�ɂ͂��̂悤�Ȏ�@�̓��[���b�p�ɂ͂Ȃ������A�ƍl�����Ă���B����ɃK�����I�́A�V���̖��╨���̖��ɂ��čl���鎞�ɃA���X�g�e���X�̐��⋳��x��������ȂǁA�����̗��_�̌n�⑽���h���M���Ă�����ɖӖړI�ɏ]���̂ł͂Ȃ��A�������g�Ŏ������s���Ď��ۂɋN���錻�ۂ������̊�Ŋm���߂�Ƃ������@���̂����B����ɂ�茻��ł́u�Ȋw�̕��v�ƌĂ�Ă���B
�@
�K�����I�͂������F�l�c�B�A��K��Ă������A���̃��F�l�c�B�A��(6�قǔN����)�}���i�E�K���o(Marina Gamba�A1570�N���܂�)�Əo��A���ۂ��n�܂�A�����p�h���@�ɂ������K�����I�̉Ƃœ�l�͈ꏏ�ɕ�炵�n�߂��B��l��2��1�j�����������B�K�����I�͌h�i�ȃ��[�}�E�J�g���b�N�̋��k�ł������B����F�߂�`�̌��������Ȃ������̂́A����ɓG�ӂ������Ă�������ł͂Ȃ��A�����̒햅�̖ʓ|�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������߁A�o�ϓI���S���d����������ł���B
�@
�M�̓Ă��K�����I�́A��l�̖��A���B���W�j�A�E�K�����C(Virginia Galilei, 1600�N8��12�� - 1634�N4��2��)�ƃ����B�A(Livia, 1601�N - 1659�N)��c�������ɃA���`�F�g��(�p���)�̐��}�b�e�I�C���@�ɓ��ꂽ�B���B���W�j�A��1616�N�C�����ɂȂ�}���A�E�`�F���X�e (Maria Celeste) �Ɖ�������(���̖��͐���}���A�̖��ƁA���K�����C�̈�����V���w�ɂ��Ȃތ��t��g�ݍ��킹�����̂ł���BCeleste�Ƃ͓V�̂��ƁB)�B�}���A�E�`�F���X�e��ƕ��K�����I�͐e�q�̏�ɖ�����ꂽ�莆�̂��Ƃ�����Ă����悤�ŁA�}���A�E�`�F���X�e���畃�K�����I�Ɉ��Ă��莆124�ʂ��K�����I�̎���ނ̕����̒����甭�����ꌻ�����Ă���B�����B�A��1617�N�C�����ɂȂ�A���J���W�F���Ɖ��������B���q�̃��B���c�F���c�B�I(Vincenzio, 1606�N - 1649�N)��1619�N�ɕ��ɔF�m����A�Z�X�e�B���A�E�{�b�L�l�[�� (Sestilia Bocchineri) �ƌ��������B
�@
����(�����C�^���A)�̌��͎҂����̌��͑����̉Q�Ɋ������܂�钆�ŁA(������V���̌����Ɋւ��Ă͓V�˓I�ł͂��������̂�)������l�ԊW�Ɋւ��Ă͕s����őf�p�ȍl���������Ă����K�����C��(���̐��n����Ȋw�҂����ɔ�ׂ��)���܂肤�܂�������ꂸ�A����ɓG�𑝂₷�`�ɂȂ��Ă��܂��A���ɂ͔ނ̂��Ƃ������v��Ȃ��҂ɂ���āA�ނ̎x�������n�����������ɂ��Ĉْ[�R��ŒNjy�����悤�ɒǂ����܂ꂽ��A�E����������A��֏�Ԃł̐����𑗂邱�ƂɂȂ����B�E�������o�ϓI�ɋꋫ�ɗ����������d�˂��K�����I�͕a�C�����ɂȂ����B����ɁA����ȃK�����I���ŕa���Ă���Ă����ň��̒������B���W�j�A(�}���A�E�`�F���X�e)��1634�N�ɕa�C�Ŏ������B������1637�`1638�N����ɂ͎����B�����A������������ȏɂ����Ă��K�����I�͌��q�M�L�Ő��ʂ��c���A1642�N�ɖv�����B
�@
���N��
�@
1564�N �C�^���A�̃s�T�x�O�ʼn��y�ƂŌ������̃��B���`�F���c�H�E�K�����C�̒��j�Ƃ��Đ��܂��(�����A���̒n�̓g�X�J�[�i������̂�����)�B
�@
1581�N �s�T��w�ɓ��w(��w��U)�B
�@
1585�N �s�T��w�ފw�B�Ƒ��Ńt�B�����c�F�ɈڏZ�B
�@
1586�N �ŏ��̘_���w���V���x�\�B
�@
1587�N ���߂ă��[�}��K��B�����̐w�N���X�g�t�@�[�E�N�����B�E�X��q�ˁA�����E�̈������肤�B
�@
1589�N �s�T��w���w�u�t(����ł͋���)�ɏA�C(3�N�_��)�B
�@
1591�N �����B���`�F���c�H�����B
�@
1592�N �s�T��w�̐E���C����ɂȂ�B/(�W�����_�[�m�E�u���[�m�A�ߔ������B)/ ���F�l�c�B�A���a��(���݂̃C�^���A�̈ꕔ)�̃p�h���@��w����(6�N�_��)�ƂȂ�ڏZ�B���̍��A���̂̌������s�����Ƃ����B
�@
1597�N �P�v���[���̎莆�ŁA�n������M���Ă���ƋL���B
�@
1599�N �p�h���@��w�����ɍĔC�B���̍��A�}���i�E�K���o�ƌ����B2��1�j����������B
�@
(1600�N �W�����_�m�E�u���[�m�A���[�}���c���ɂ����Ԃ�̌Y�ɂȂ�B)
�@
1601�N����g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1���̑��q�R�W��2���̉ƒ닳�t�����C(��w�̋x�Ɏ����̂�)�B
�@
(1608�N �l�[�f�������h���a��(�I�����_)�Ŗ]�����̔������������B)
�@
1608�N �g�X�J�[�i����t�F���f�B�i���h1�������B�K�����I�̋����q�̃R�W��2�����g�X�J�[�i����ƂȂ�B
�@
1609�N 5���I�����_�̖]�����̉\���A�����Ő���B�Ȍ�V�̊ϑ����s���B
�@
1610�N �ؐ��̉q�����A�u���f�B�`��(�g�X�J�[�i����Ƃ̂���)�̐��v�Ɩ��Â���B������w���E�̕x�Ƃ��Č�������B���̍�����A�n�������y���邱�Ƃ������Ȃ�B/ (�P�v���[���w���E�̕҂Ƃ̑Θb�x���A�K�����I��i�삷��B)/ �s�T��w�������g�X�J�[�i����t�N�w�҂ɔC������A�����݂̂�A��t�B�����c�F�ɖ߂�B
�@
1611�N �����`�F�C�E�A�J�f�~�[����B
�@
1613�N �w���z���_�_�x�����s�B
�@
1613�N���H �}���i�ƕʂ�A�ޏ��̐V��������������������Ƃ���邪�A�`�L�̋L�ڂ݂̂ō������Ȃ��Ƃ�������B
�@
1613�N�� 2�l�̖����C���@�ɓ����B
�@
1615�N �n�������߂���h�~�j�R��C���m�����[�j�Ƙ_���ƂȂ�B
�@
1616�N ��1��ْ[�R�⏊�R���ŁA���[�}���c�����א��Ȃ���A�Ȍ�A�n�����������Ȃ��悤�A���ӂ���B �R�y���j�N�X�́w�V�̂̉�]�ɂ��āx�A���[�}���c�����{���ꎞ��~�ƂȂ�B
�@
1623�N �w����ӎ����x�A���[�}���c�E���o�k�X8���ւ̌��������Ċ��s�����B
�@
1631�N �������̂���t�B�����c�F�x�O�A���`�F�g���̏C���@�̘e�̕ʑ��ɏZ�ށB
�@
1632�N �w�V���Θb�x���t�B�����c�F�Ŋ��s�B���[�}�ւ̏o���𖽂����A���[�}�ɒ����B
�@
1633�N ��2��ْ[�R�⏊�R���ŁA���[�}���c�����א��Ȃ���L�߂̔������A�I�g�Y�������n�����(����Ƀg�X�J�[�i��������[�}��g�قł̓�ւɌ��Y)�B�V�G�i�̃s�b�R���~�[�j��i����ɐg�����ڂ����B�A���`�F�g���̕ʑ��֖߂邱�Ƃ��������(�������A�t�B�����c�F�ɍs�����Ƃ͋ւ���ꂽ)�B
�@
1634�N �K�����I���ŕa���Ă��������}���A�E�`�F���X�e����(���܂ꂽ�Ƃ��̖��̓��B���W�j�A)�B
�@
1637�N �Жڂ������B���N�A����������B�Ȍ�A���M�͒�q�Ƒ��q���B���c�F���c�B�I�ɂ������M�L�ɂȂ�B
�@
1638�N �I�����_�Łw�V�Ȋw�Θb�x���B�����M�L�ɂ͒�q�̃G���@���W�F���X�^�E�g���`�F�����s�����B
�@
�ӔN �U��q���v���B�}�ʂ𑧎q�ƃ��B���B�A�[�j�ɏ�����点��B
�@
1642�N �A���`�F�g���ɂĖv�B�@ |
���V���w
�@
�K�����I�͖]�������ł�������������ꂽ��l�ł���B�l�[�f�������g�A�M���a��(�I�����_)��1608�N�ɖ]�����̔��������ɂ��Ēm��ƁA1609�N5���Ɉ����10�{�̖]�������쐬���A�����20�{�̂��̂ɍ��ς����B
�@
�����p����1609�N���ɖ]�����������Č����K�����I�́A���ʂɉ��ʁA�����č�������(�K�����I�͂������C�ƍl����)�����邱�Ƃ������B����ł͂��̂悤�Ȋ�Ό^�̓V�̂̕\�ʂ̉��ʂ̓N���[�^�[�ƌĂ�Ă���B���͊����ɋ��`�ł���Ƃ���Â��A���X�g�e���X�I�ȍl���ł͐��������Ȃ����̂ł������B
�@
�܂��A���N��1610�N1��7���A�ؐ��̉q����3�����B���̌㌩��������1�̉q���ƕ����A�����̉q���̓K�����I�q���ƌĂ�Ă���B�����̊ϑ����ʂ�1610�N3���Ɂw���E�̎g�ҁx(Sidereus Nuncius) �Ƃ��Ę_�����\���ꂽ(���̘_���ɂ́A3���܂ł̊ϑ����ʂ��f�ڂ���Ă��邽�߁A�_�����\��4���ȍ~�ƍl����ꂽ���Ƃ����邪�A���Ȃ��Ƃ��A�h�C�c�̃��n�l�X�E�P�v���[��4��1���ɂ��̘_����ǂ��Ƃ��������Ă���)�B���̖ؐ��̉q���̔����́A�����M�����Ă����V�����ɂ��Ă͕s���Ȃ��̂ł�����(�ڍׂȗ��R�͓V�������Q��)�B���̂��ߘ_���Ɋ������܂�͂������A���E�I�Ȗ��������B�ӔN�ɁA�����̉q���̌��]�������q�C�p�̎��v�Ƃ��Ďg�����Ƃ���Ă��Ă��邪�A���x�̂悢�\�ł��Ȃ��������Ƃ�A�ܓV���Ɏg���Ȃ����ɂ́A�D���ɑ傫�Ȑݔ���ςޕK�v�����������Ƃ���A���ۂɂ͎g���Ȃ������B
�@
�����̊ϑ��ł́A�������������������ɁA�傫����ς��邱�Ƃ����������B�����M�����Ă����V�����ɏ]���Ȃ�A�����͂�����x�������������邱�Ƃ͂����Ă��A�O�����̂悤�ɍׂ��͂Ȃ炸�A�܂��A�n������̋����͈��̂��߁A�傫���͌����ĕω����Ȃ��͂��ł������B
�@
����ɁA�]�����ł̊ϑ��ő��z���_���ϑ������ŏ��̐��m�l�ƂȂ����B�������A�����̓V���w�҂��������ɑ��z���_���ϑ����Ă����\��������B�`��ʒu��ς��鍕�_�́A�V�͕s�ςŁA����艓���ꏊ�ł͉i���ɕω��͖K��Ȃ��Ƃ���V�����ɂ͕s���ȏ؋��ɂȂ����B����́A�A���X�g�e���X�h�̌����҂ƌ������c�_�ƂȂ����B
�@
�Ȃ��A�K�����I�͔ӔN�Ɏ������Ă��邪�A����͖]�����̌��߂��ł���ƍl�����Ă���B
�@
�K�����I��1597�N�ɃP�v���[�Ɉ��Ă��莆�̒��ł��łɒn������M���Ă���ƋL���Ă��邪�A17���I�����܂ł͂�����������邱�Ƃ͂Ȃ������B��ɂ����3�_(�ؐ��̉q���A�����̖��������A���z���_)�̏؋�����A�n�������������Ɗm�M�����K�����I�́A���̌�A�n�����Ɍ��y���邱�Ƃ������Ȃ����B
�@
���̑��ɂ́A�V�̐삪�����̍P���̏W���ł��邱�ƂȂǂ����������B�@ |
�������w
�@
�s�T�̑吹���ŗh���V�����f���A(����ɂ͍��F�̗h��)�����āA�U��q�̓�����(���������̏ꍇ�A�傫���h��Ă���Ƃ����A�������h��Ă���Ƃ����A�����ɂ����鎞�Ԃ͓���)�������Ƃ����Ă���B����������͌㐢�ɓ`����b�ŁA���ۂɂǂ̂悤�ȏł��̖@�����������̂��͕s���ł���B���̖@����p���ĔӔN�A�U��q���v���l�Ă������A���ۂɂ͐���͂��Ȃ������B
�@
�K�����I�͂܂��A���̖̂@���������B���̖@���͎��2����Ȃ�B1�́A���̂����R��������Ƃ��̎��Ԃ́A�������镨�̂̎��ʂɂ͈ˑ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B2�߂́A���̂���������Ƃ��ɗ����鋗���́A�������Ԃ�2��ɔ�Ⴗ��Ƃ������̂ł���B
�@
���̖@�����ؖ����邽�߂ɁA�s�T�̎Γ��̒��ォ��召2��ނ̋����ɗ��Ƃ��A���҂������ɒ��n����̂��������A�Ƃ������Ă���B ���̗L���Ȍ̎��̓K�����I�̒�q���B���`�F���c�H�E���B���B�A�[�j (Viviani) �̑n��ŁA���ۂɂ͍s���Ă��Ȃ��A�Ƃ��錤���҂������B���̃G�s�\�[�h�ɐ旧���Ċ��Ɂu�����̖@���v�����Ă����I�����_�l�̃V�����E�X�e���B���̎����ƍ������Č㐢�ɓ`�����鎖�ɂȂ�B����Č�q�̃A���X�g�e���X�̗��_�������������̂̓K�����I�ł͂Ȃ��X�e���B���̌��тƂȂ�B
�@
���ۂɃK�����I���s���������́A�߂ɒu�������[���̏���A�d�����قȂ�傫������������]���������ł���B�߂ɓ]���镨�̂ł���������Ɨ����Ă����̂ŁA����ŏd���ɂ���ė������x���ς��Ȃ����Ƃ��������̂ł���B���̎����́A���ۂɂ����̗l�q��`�����G�悪�c���Ă���B
�@
�A���X�g�e���X�̎��R�N�w�̌n�ł́A�d�����̂قǑ����������邱�ƂɂȂ��Ă������߁A�����ł��A���X�g�e���X�h�̌����҂Ƙ_���ɂȂ����B�K�����I���g�́A���Ƃ��A1�̕��̂𗎉��������Ƃ��ƁA2�̕��̂��Ђ��łȂ������̂𗎉��������Ƃ��ŁA�������Ԃɍ���������̂��A�Ƃ����悤�Ȕ��_���s���Ă���B
�@
���Ȋw�v��
�@
�K�����I�́A�j�R���E�X�E�R�y���j�N�X�A���n�l�X�E�P�v���[�A�A�C�U�b�N�E�j���[�g���ƕ��сA�Ȋw�v���̒��S�l���Ƃ���Ă���B
�@
�ǎ҂ɓ���̎����𑣂��Č������邱�Ƃɂ���āA�����̐��������ؖ�����Ƃ�����i���Ƃ����A�ŏ����̉Ȋw�҂ł���B�������A���̂悤�Ȏ�i���Ƃ����Ȋw�҂̓K�����I�ȑO�ɂ��C�u���E�A���E�n�C�T��(���e�����A���n�[��)�A�E�C���A���E�n�[�x�[�A�E�B���A���E�M���o�[�g�Ȃǂ�����(�n�[�x�[��M���o�[�g���Ȋw�v���𐄂��i�߂��l���Ƃ���Ă���B�܂��A�K�����I�͎����̒��ł��т��уM���o�[�g�Ɍ��y���Ă���)�B
�@
���L���Ȏ��s
�@
�ނ����\�������ɂ͑傫�ȉ߂��̂�����������������A�ߑ�Ȋw�̔��������̐l���̂��߁A���̂悤�ȉ߂��͂����ē��R���Ƃ����w�E������B������̃P�v���[����̃j���[�g���Ȃǂ������悤�Ȏ��s���������B�����ł͎�Ȃ��̂�������B
�@
�P�v���[�̖@�������\����Ă��u���ׂĂ̓V�̂͊��S�ȉ~��`���ĉ^������v�Ǝ咣�������A�u�ȉ~�^���Ȃǂ�����킯���Ȃ��v�Ƃ����悤�ȃP�v���[���Âɔᔻ���镶�������Ă���B���̈Ӗ��ł́A�K�����I�̓A���X�g�e���X�I�ȍl���ɂ܂������Ă�������̐l���ł������B�P�v���[�̃��h���t���\�����\����A�ȉ~�O���Ɋ�Â��Ęf���̈ʒu�\����鎞��ɂȂ��Ă��P�Ȃ������B
�@
�n�����̏؋��Ƃ��Ē������������B���ۂɂ́A���Ƒ��z�̏d�͂������ł���A�K�����I�̎���̉Ȋw�ł͂܂��������ł��Ȃ����ۂł������B�K�����I���g�͒����������n�����̍ł��d�v�ȏ؋����ƍl���Ă����ӂ������邪�A���̎咣�͓����������Ă����Ȋw�I�����ɂ����������A�ŏ��������Ă������̂ł������B�����K�����I�̐�����������A�����͓���1�x�����N���Ȃ��͂��ł��邪�A���ۂɂ͒ʏ��2��N����B�K�����I��2�x����悤�Ɍ�����̂́A�n�`�Ȃǂ������炷���̂ŗ�O�I�Ȃ��̂��Ǝ咣�����B�@ |
���K�����I�ٔ�
�@
�K�����I���n�����������A����𗝗R�ɗL�ߔ����������Ƃ͂��Ȃ�L���ł���B���̂��Ƃ���A�����n��������������̂͂��ׂĈْ[�Ƃ���A����ɂ���ĉȊw�̔��W���j�Q���ꂽ�A�Ƃ����l��������Ă����B���������݂ł́A�K�����I���_�����������L���X�g���̖{�����悭�������A�Ȋw�I�Ȍ��t�ł��������Ă������߂ɉ����v��ꂸ�A�ł��������̋U�ٔ��ŗL�ߔ��������̂ł͂Ȃ����A�Ǝw�E����Ă���B
�@
����1��̍ٔ�
�@
�K�����I���n�����ɂ��Č��y���n�߂�ƁA�h�~�j�R�C����m�����[�j�Ƙ_���ɂȂ�A�����[�j�̓��[�}���c�����א���(�ȑO�ْ̈[�R�⏊������ς�������)�ɃK�����I�������Ă���n�����ْ͈[�ł���Ƒi�����B���̍ٔ��̒S�������̓C�G�Y�X������x���g�E�x�����~�[�m���@�� (Francesco Romulo Roberto Bellarmino) �������B���̂Ƃ��̔������̓o�`�J���̔閧�������ɕۊǂ���Ă��邪�A��2��̍ٔ��܂ł̓r���ŋU�����ꂽ�^�����Z���ł���B ���̓��e�́A���̂悤�Ȃ��̂ł������B
�@
�u���z�����E�̒��S�ɂ����ē������A��n�������Ƃ�����L�ӌ���S�ʓI�ɕ������A�����Ă��̈ӌ����ӂ����јb���Ăł������Ăł��A�ǂ̂悤�Ȏd���ɂ����Ă��������A�������A�ٌ�m���Ȃ��悤�悤�������A�\������ꂽ�B�����Ȃ���ΐ��Ȃ͂�����ٔ��ɂ�����ł��낤�ƁB���̋֎~�߂ɃK�����I�͓��ӂ��A�]�����Ƃ���B�v�B
�@
�������A���̔������ɃK�����I�̏����͂Ȃ��A��2��̍ٔ��ɂ����Ă��K�����I�͌������Ƃ��Ȃ��Ǝ咣���Ă���B
�@
��1��ٔ��̔�����������鏭���O�A�S�������̃x�����~�[�m���K�����I�̗F�l�֑������莆�ɂ́A�u���́A���Ȃ��ƃK�����I���A�������������̈ӌ���1�̉����Ƃ��āA������1�̐�ΓI�^���Ƃ��Ăł͂Ȃ����\����̂ł���A����܂ňȏ�ɐT�d�ɍs�����Ă悢�Ǝv���v�ƒԂ�A�K�������K�����I�̌�����ے肵�Ă��Ȃ��B���̎莆�̓��e�Ɩ������邽�߁A��1��ٔ��̔������͑�2��ٔ��̂��߂ɋU�����ꂽ�ƍl�����Ă���B
�@
��1��ٔ��̒���A1616�N�A���[�}���c���̓R�y���j�N�X�̒n�������ւ���z�����o���A�R�y���j�N�X�́w�V���̉�]�ɂ��āx�͈ꎞ�{���֎~�̑[�u���Ƃ�ꂽ�B
�@
���̌�R�y���j�N�X�̒����́A�P�ɐ��w�I�ȉ����ł���A�Ƃ����A�������A
�@
�u�V�̂��g���ۂɁh�����ɓ������͌`����w�̗̈�ł����ċ���̋����ɕ����邪�A�V�̗̂\�������e�Ղ���萳�m�ɂ��鉼�ݓI��i�ł���A���̎咣�͌`����w�ł��_�w�ł��Ȃ��̂ŁA����̋����ɕ�����K�v�͂Ȃ��A�Ƃ�����������A�n��������҂ɑ�����w���ł��邱�Ƃɂ��A������̔ᔻ�ł͂Ȃ��A�Ƃ�������𖾂炩�ɂ���s�ׁv
�@
��t���āA���c������{�����ċ����ꂽ�B�K�����I�́A�x�����~�[�m�̒���������A���炭�͊������T�����B
�@
����2��̍ٔ�
�@
1630�N�K�����I�́A�n�����̉�����w�V���Θb�x�����M�����B���̏��́A�V�����ƒn�����̗����������܂ʼn�����̘b�Ƃ��āA���ꂼ���M����2�l�Ƃ��̊Ԃ��Ƃ�������҂̌v3�l�̑Θb�Ƃ����`������āA�n�����݂̂������ċ֗߂ɂӂ�邱�Ƃ��Ȃ��悤�A���Ӑ[�������Ă������B�K�����I�́A�x�����~�[�m�̔������̓��e����A�n�������Љ�Ă��A���̐��ɑS�ʓI�Ɏ^������Ə����Ȃ���Ζ��͂Ȃ��ƍl���ďo�ŋ����Ƃ�A���[�}���c������̏C���������邱�Ƃ������ɏo�ŋ���^�����B�w�V���Θb�x�́A1632�N2��22���A�t�B�����c�F�ň���A���s���ꂽ�B
�@
��1633�N�A�K�����I�͍ēx���[�}���c���̌��א��Ȃɏo������悤������ꂽ�B��^�́A1616�N�̍ٔ��ŗL�߂̔������A��x�ƒn�����������Ȃ��Ɛ����ɂ�������炸�A�����j���āw�V���Θb�x�������Ƃ������̂������B�K�����I���A�����Ă��̏������[�}�ł͂Ȃ��t�B�����c�F�ŋ����Ƃ������ƁA���[�}���̒S���҂ɁA�����Ə��̖��������������炸�ɋ����Ƃ������ƁA�K�����I������ɏڂ����Ȃ��t�B�����c�F�̏C���m��R�����Ɏw���������ƂȂǂ����ɖ��Ƃ��ꂽ�B�������A�S�������S�y�[�W����Ƃ������R�ŏ����Ɩ����̑��t�ōς܂��邱�Ƃɂ͎��O�Ƀ��[�}���S���҂����ӂ��Ă���A�K�����I���w�������t�B�����c�F�̐R�����͐��K�̃t�B�����c�F�ْ̈[�R�⊯�ł������B����ɁA���̕\����3���̃C���J���������Ă��邱�Ƃ����A���ꂪ���c�Ɏ艺������Ƃ����Ӗ����Ƃ����˂��Ȃ������߂�����҂����[�}�ɂ���A���Ƃ��ꂽ�B����������3���̃C���J�́A�t�B�����c�F�̏o�ŋƎ҂̃}�[�N�ŁA���̏��Ђɂ��������Ă������ߎ��ۂɂ͖��ɂ͂Ȃ�Ȃ������B
�@
�ٔ��ŃK�����I�́A�x�����~�[�m���@�����L�����u�K�����I�͑�1��̍ٔ��Œn�����̕����𐾂��Ă��Ȃ����A�������߂����v���ꂽ���Ƃ��Ȃ��v�Ƃ����ؖ������o���Ĕ��_�����B���������א��Ȃ́A�K�����I��L�߂Ƃ���Ƃ����ٔ��L�^�������o���čĔ��_�����B���̍ٔ��L�^�ɂ͍ٔ����̏������Ȃ��A����͌��א��Ȏ��炪��߂��K���ɉ���Ȃ����̂ł������B�������A�ٔ��ł͗L�߂̍ٔ��L�^��L���Ƃ��A�K�����I�̏������Ă����ؖ����͖����Ƃ��ꂽ�B��1��̍ٔ��̒S�������x�����~�[�m��1621�N�Ɏ������Ă���A�����̍��������Ƃ͂ł��Ȃ������B���̌��ʁA�K�����I�͗L�߂ƂȂ����B���א��ȑ��̋L�^�ɂ́A�n�������u�����Ă͂����Ȃ��v�Ə����Ă��������A�K�����I����o�����u�x�����~�[�m���@���̏ؖ����v�ɂ́A�����邱�Ƃ̐���ɂ��Ă̋L�ڂ͂Ȃ������B�ٔ��ł͂��̖��߂����ۂɂ������Ƃ����O��Ői�߂�ꂽ�B�K�����I���g�͂�������ꂽ���ǂ����L���ɂȂ����Ȃ������Ƃ͌�����Ȃ��Ɠ����Ă���B1616�N�ɃK�����I�ƃx�����~�[�m�ȊO�̐l�����������ƂɂȂ��Ă���A����ɂ��Ă̓K�����I���F�߂Ă��邪�A���̐l�����N�ʼn��l�����̂��ɂ��Ă͕s���̂܂܂ł������B
�@
1616�N�����̍ٔ��ɂ��Q�����A�K�����I�̐e�F�ł��������o���x���[�j���@�� (Maffeo Vincenzo Barberini) �����[�}���c�E���o�k�X8���ƂȂ��Ă������A���c�̕ی�͂Ȃ������B����ɂ��A�w�V���Θb�x�ɓo�ꂷ��V���v���`�I(�u���̒P���Ȑl�v�Ƃ����Ӗ�)�͋���̈ӌ��������Ă���A�V���v���`�I�͋��c���g���Ƌ��c�{�l�ɐ������҂�����A���{�������c���ٔ��𖽂����Ƃ������̂�����B���̐��ɂ͕����Ȃ����A��������L���M�����Ă���B����ɃK�����I���g�A�h�i�ȃJ�g���b�N���k�ł������ɂ�������炸�A�Ȋw�ɂ��Ă͋���̌��ЂɖӖړI�ɏ]�����Ƃ����₵�A�N�w��@������Ȋw�����邱�Ƃ�������Ƃ��A�����K�����I���x�����Ă����E���o�k�X8��������Ԃ����悤�ɃK�����I�����悤�ɂȂ����v���Ƃ����B�����Č��ʓI�ɂ̓K�����I�ٔ��ɂ����āA�K�����I���ْ[�̓k�Ƃ��čق����錋�ʂɌq�����Ă���B
�@
1633�N�̍ٔ��̒S��������10���������A�L�߂̔������ɂ�7���̏��������Ȃ��B�c���3���̂���1���̓E���o�k�X8���̐e���ł������B����1���͂��̍ٔ��ɂ͂��Ƃ���ᔻ�I�Ȕ����������Ƃ���Ă���B�������A��������7���̏��������Ȃ��̂́A�P�Ɏc��̔����͔��������A�ʂ̌��p�ōٔ��ɏo�Ȃł��Ȃ����������ł͂Ȃ����Ƃ�������������Ă���B�Ȃ��A�S���̏������Ȃ��Ă��A�L�߂̔����͗L���ł������B
�@
�L�߂�������ꂽ�K�����I�́A�n���������Ƃ��������������|�������ꂽ�ْ[���╶��ǂݏグ���B���̌�ɂԂ₢���Ƃ���� "E pur si muove"(����ł��n���͓���)�Ƃ������t�͗L���ł��邪�A����l���Ĕ��������͎̂����łȂ��ƍl�����A�K�����I�̐���M���q�炪��t���ʼn����������L�͂ł���B�܂��A�u����ł��n���͓����v�̓C�^���A��ł͂Ȃ��M���V�A��Ō������Ƃ�����������B
�@
���ٔ��Ȍ�
�@
�K�����I�ւ̌Y�͖����Y�ł��������A����ɓ�ւɌ��Y�ɂȂ����B�������A�t�B�����c�F�̎���ւ̋A��͔F�߂�ꂸ�A���̌�ꐶ�A�Ď��t���̓@��ɏZ�܂킳��A�U���̂ق��͊O�ɏo�邱�Ƃ��ւ���ꂽ�B���ׂĂ̖�E�͔����Ɠ����ɔ��D���ꂽ�B�w�V���Θb�x�͋֏��ژ^�ɍڂ����A1822�N�܂œP��Ȃ������B
�@
��������_�͉��ꂸ�A�J�g���b�N���k�Ƃ��đ��邱�Ƃ�������Ȃ������B�K�����I�̔�҂̃g�X�J�[�i����́A�K�����I���ْ[�҂Ƃ��đ���͔̂E�тȂ��ƍl���A���[�}���c�̋��������܂ŃK�����I�̑��V�����������B���������͂��̎���ɂ͏o���A�����ȋ��Ɋ�Â�������1737�N3��12���Ƀt�B�����c�F�̃T���^�E�N���[�`�F�����ōs��ꂽ�B
�@
���ٔ��̉e��
�@
���̌�A�K�����I�̒����̓C�^���A�ł͎����㔭�s�ł��Ȃ��Ȃ������߁A�w�V�Ȋw�Θb�x�́A�K�����I�̌��e�����҂��ɂ���Ď����o����A�v���e�X�^���g�����̃I�����_�ŏ���Ɉ�����ꂽ�Ƃ����ݒ�Ŕ��s���ꂽ�B
�@
�t�����X�̃��l�E�f�J���g�́A�K�����I�ٔ��̕A���R�Ȋw�Ɋւ��鎩���̏o�ł����߂�킹�����Ƃ��w���@�����x(1637�N��)�ɋL���Ă���B
�@
�����̃��[�}���c���̓C�^���A�O�ł̌��͂͂Ȃ������̂ŁA�C�^���A�O�ł͉e���͂��܂�Ȃ������B�������A�Ȋw�I���ɏ@�������o�������鈫�������s�̑O��ƂȂ����Ƃ����ᔻ������B
�@
���ٔ��̌���
�@
���̍ٔ��ɂ͋^�₪�������Ƃ���A19���I�㔼���猟���s��ꂽ�B��1�̑傫�ȋ^��́A1616�N�̔�����2��ނ���A���e���܂������t�ł��邱�ƁB��2�ɂ́A�w�V���Θb�x�̔����ɂ̓��[�}���c�����琳���̋����������ɂ�������炸�A�����������Ĉْ[�̗��R�Ƃ��ꂽ���Ƃł���B
�@
Giorgio di Santillana ��ɂ��A�L�߂̍ٔ��L�^���̂��̂��A���א��Ȏ��g���U���������̂ł������B���������ɐM����킯�ɂ͂����Ȃ����A���߂̔������������Ƃ����؋������܂�������Ȃ����ƂƁA��2�̗��R������ɂ������������Ƃ���A�����̂Ȃ��L�߂̔������͋U���ł���Ƃ����l���������Ȃ��Ă���B�������A����1616�N�̗L�߂̔��������U���ł���Ƃ������ɂ��ẮA�U�������҂��N�Ȃ̂������ɂ킩���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����A�������ɂ����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����咣������B
�@
���̂ق��A���̂悤�Ȑ�������B
�@
1.�@���������A1616�N�̍ٔ��͑��݂��Ȃ��B����́A�����K�����I�͍������N�i������Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ������ɂ��Ă���B���̐��Ɋ�Â��ƁA�x�����~�[�m���K�����I���Ăяo�����̂́A���x�A�n�������֎~����z�����o��A�Ƃ������Ƃ��K�����I�ɓ`���邽�߂ł������B���̌�A�x�����~�[�m���K�����I���Ăяo���A���炩�̗L�ߔ������������A�Ƃ����\���L�܂������߁A�������K�����I���x�����~�[�m�ɖ��߂̔�����(���m�ɂ́A�K�����I�͉��̗L�߂̔������Ă��Ȃ��Ƃ����ؖ���)������Ă�������A�Ƃ����B
�@
2.�@1616�N�̍ٔ��̏����̂Ȃ��L�߂̔�����(�炵������)�́A�x�����~�[�m�������������n�����Ƃ��ɁA���Ȃ����҂��x�����~�[�m�̌����ł̔������L�q�������̂ł���(���Ȏ҂��������Ƃ̓K�����I���F�߂Ă���)�B���������̐��ł��A�L�q�����҂̖������炩�łȂ��B�܂��A�S�������̏������Ȃ��ȏ�A�L���ȕ����łȂ��Ƃ��������ɂ����͂Ȃ��B
�@
3.�@1616�N�̍ٔ��̏����̂Ȃ��L�߂̔�����(�炵������)�́A�ٔ��̐���s���ɍ��킹�Ă��炩���ߗp�ӂ��ꂽ���̂ŁA���Ƃ̓x�����~�[�m�̏������������������ŗL���ɂȂ�悤�A��ɍ���Ă������̂������B�������A���ǁA�K�����I�͗L�߂ƂȂ�Ȃ��������߁A���̕����Ƀx�����~�[�m�̏����͂���Ȃ������B�����������̓��[�}���c���Ɏc����A��2��̍ٔ��ŏ؋��Ƃ��ꂽ�B
�@
�����[�}���c���̑Ή�
�@
1965�N�Ƀ��[�}���c�p�E��6�������̍ٔ��Ɍ��y�������Ƃ[�ɁA�ٔ��̌��������n�܂����B�ŏI�I�ɁA1992�N�A���[�}���c���n�l�E�p�E��2���́A�K�����I�ٔ������ł��������Ƃ�F�߁A�K�����I�ɎӍ߂����B�K�����I�̎����������350�N��̂��Ƃł���B
�@
2003�N9���A���[�}���c����������(�ȑO�ْ̈[�R�⏊)�̃A���W�F���E�A�}�[�g��i�� (Angelo Amato) �́A�E���o�k�X8���̓K�����I�𔗊Q���Ȃ������Ƃ����咣���s�����B
�@
2008�N1��16���́w�����V���x�ɂ��ƁA���[�}���c�x�l�f�B�N�g16����17���ɃC�^���A�������[�}�E���E�T�s�G���c�@��w�ł̋L�O�u����\�肵�Ă������A1990�N�̐��@������ɃI�[�X�g���A�l�N�w�҂̌��t�����p���āA�K�����I��L�߂ɂ����ٔ����u�����������v�Ɣ����������ƂɊw���Ŕᔻ�����܂�A�u�������~�ɂȂ����B���̌�x�l�f�B�N�g16����2008�N12��21���ɍs��ꂽ�A���A��l�X�R����߂��u���E�V���N2009�v�Ɋ֘A���������ŁA�K�����I��̋Ɛт��̂��A�n���������߂Č����ɔF�߂Ă���B�@�@
�@ |
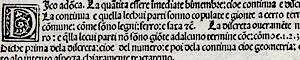 �@ �@
���f�J���g�u���@�����v���� 1637�N |
   �@
�@
|
Descartes, Rene.(1596-1650)
�@
Discours de la methode pour bien conduiresa raison, & chercher la verite dans les sciences.
�@
�{���́A�f�J���g�����߂ďo�����_���W�u���@��������ю��_�v�ɂ��������ł���A�ڂ����W��́u�������A�������̊w��ɂ����Đ^�������߂�����@�ɂ��Ă̏����v�ł���B�f�J���g�́A1628�N�Ƀt�����X�������ăI�����_�ɈڏZ���A�قǂȂ��u���R�w�v�̑̌n���l���͂��߂āA1633�N���Ɂu�F���_�v�Ƃ����_���������グ�����A���̎��C�^���A�ŃK�����C���n�����䂦�ɏ@���ٔ��ŗL�߂Ƃ��ꂽ���Ƃ��āu�F���_�v�̏o�ł������킹���B�������A�l�X�̋��߂������āA���R�w�S�̂ł͂Ȃ��A���̈ꕔ�����A����Ό��{�̌`�Łu�C�ۊw�v�u���܌��w�v�Ƃ�����̘_���ɏ����A����ɔނ̐V���ȁ��w�����Ȃ킿��͊w�̘_�������Ĕ��\���邱�Ƃɂ����B���̑����Ƃ��āA�����`�̂ŁA����̎v�z�̌�����l�X�ɓ`���悤�Ƃ��ď������̂��{���ł���B�@ |
�����@����
�@
(���@�����Ƃ�)�@1637�N�Ɍ������ꂽ�t�����X�̓N�w�ҁA���l�E�f�J���g�̒����ł���B����́sDiscours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences�t�ŁA�u�����𐳂��������A�������̒m��[1]�̒��ɐ^����T�����邽�߂̕��@�����v�ł���B�����Ɩ��Discours�́ATraité�����ȏ��̂悤�ɑ̌n�I�ɏ����ꂽ�_���ł���̂ɑ��āA�l�p��ʘ_�l�̈ӂł���A�f�J���g���g�������Z���k�ւ̏��ȂŁu���@�̎��݁v�ł���ƌĂ�ł���B�N�w�I�ȓ��e�͂��̌�ɏo�ł��ꂽ�w�Ȏ@�@Meditationes de prima philosophia�x�Ƃقڏd�Ȃ��Ă��邪�A�w���@�����x�͎��`�̋L�q���ӂ��݁A�v���̏�����ǂ��Ă킩��₷��������Ă��邽�߁A���̈���Ńf�J���g�N�w�̊j�S��m�邱�Ƃ��ł���B�����A�����̖{�����e����ŏ�����邱�Ƃ��������A���e����̋������\�����Ⴉ���������̏�����q�������ł��ǂ߂�悤�ɁA�t�����X��ŏ�����A6�̕����ɕ�����Ă���B�Ȃ����ł́A�@���ٔ��ɂ���Ĉْ[�Ƃ���邱�Ƃ�����āA�U���Ŕ��s���ꂽ�B
�@
����1��
�@
�u�ǎ�(bon sens)�͂��̐��ł����Ƃ������ɔz������Ă�����̂ł���v�Ƃ��������o���Ŏn�܂�B�����ł̗ǎ��͗����Ɠ��ꎋ�ł�����̂Ƃ����B���S�Ȑ��_�������Ă��邾���ł͏\���ł͂Ȃ��B���̏����̖ړI�́A�����𐳂����������߂ɂ��������ׂ����@��������Ƃ������A�f�J���g���g����X�̐S����l�@�Ɏ���܂łɂǂ̂悤�ȓ������ǂ��������������Ƃł���A�Ɛ錾����B�w�Z�ł̑S�ے����C�����u����Ȋw��@Sciences occulte�v�܂ŏ��������ɂ�������炸�A�����̋^�f�ɂƂ���Ă��鎩���������f�J���g�́A��w�E���j�E�Y�فE���́E���w�E�_�w�E�X�R���w�E�@�w�E��w�́A�L�v�Ȋw��ł͂��邪�ǂ���s�m���Ō��łȊ�Ղ������Ă��Ȃ����Ƃ�������A�����̊w����������蝱���Ƃɂ����A�ƌ��B
�@
����2��
�@
�O�\�N�푈�ɏ]�R���ăh�C�c�ɂ����Ƃ��̎v���ɂ��ďq�ׂ�B�L���ȁu�g�F�v�Ɉ�����������āA�ŏ��ɍl�������Ƃ͈�l�̎҂��d�グ���d���͂�������̐l�̎���o���d���ɔ�ׂĊ��S�ł���A��l�̏펯����l�Ԃ������̖ڂ̑O�̎����ɒP���ɉ������_�͑����̈قȂ����l�X�ɂ���Č`�����ꂽ�w����D��Ă���A�Ƃ������Ƃ������B�^���҂������Ƃ������Ƃ́A�������������^���ɑ��Ă͉��̉��l���Ȃ��ؖ��ł���B���������ăf�J���g�͂��̎��܂ŐM�����Ďe��Ă����ӌ�����E�p���邱�Ƃ��u�����B���̍ۂɐ��_��4�̏����Ƃ���
�@
1. �������ؓI�ɐ^���ł���ƔF�߂���̂łȂ���A�����Ȃ鎖���ł������^�Ȃ�Ƃ��ĔF�߂Ȃ�����
�@
2. �������悤�Ƃ���������悭�������邽�߂ɁA�����̏������ɕ������邱��
�@
3. �����Ƃ��P���Ȃ��̂�������Ƃ����G�Ȃ��̂̔F���ւƎ���A���̂Ȃ������̊Ԃɒ��������肷�邱��
�@
4. �Ō�Ɋ��S�ȗƁA�L�͂ȍČ��������邱��
�@
���߂��B����ɂ��f�J���g�͑㐔�w�⑼�̏��Ȋw���������āA������L���Ɋ��p�������Ɗ��������A�����̏��Ȋw�̊�{�ƂȂ�ׂ��N�w�̌��������������Ă��Ȃ����ƂɋC�Â��B���̂Ƃ��ނ�23�ł��������A�����ƌo����ς݉~�n�����N��ɂȂ�܂ŁA�����������T���������獪�₷�邽�߂ɑ����̎��Ԃ��₷���Ƃ����ӂ���B
�@
����3��
�@
�������s���f�ł���Ԃł������̍s�ׂ𗥂��K���Ȑ����𑗂邽�߂Ƀf�J���g���݂���3�̓��������Љ��B
�@
1. �����̍��̖@���ƏK���ɏ]�����ƁB
�@
2. ��x���S�������Ƃ͒f�ł��B�R�Ƃ��čs�����ƁB
�@
3. �˂ɉ^�����������ɍ����ƂɂƂ߁A���E�̒������������̗~�]��ς���悤�ɓw�͂��邱�ƁB
�@
�f�J���g�͗����������������������Ō��߂����@�ɏ]���Đ^���̔F���ɋ߂Â����Ƃ��A�����ɂƂ��čőP�̐E�Ƃƍl�����B�g�F�������o�āA9�N�Ԃ͐��Ԃ����ĕ����A�^�킵�����́E��T���ώ@���Ȃ��A1628�N���悢��N�w�̊�b���߂邽�߁A�I�����_�ɉB�ق��邱�Ƃɂ����B
�@
����4��
�@
�f�J���g�́A�����ł��^����������ޗ]�n������̂͋^���A���o�E�_�E���_�ɓ��肱��ł����S�Ă�^���łȂ��Ɖ��肵�Ă��A������U�ƍl���悤�Ƃ���u���v�͂ǂ����Ă����҂��łȂ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â��B�t�����X��ŏ����ꂽ�w���@�����x�́uJe pense, donc je suis�v���͍l����̂Ŏ��͂�����A�f�J���g�Ɛe���̂����������Z���k�����e����uCogito ergo sum�v�u��v���A�䂦�ɉ䂠��v�R�M�g�E�G���S�E�X���Ƃ����B���̖���́A��X�����Ă����R�Ɨ���������̂͂��ׂĐ^���ł��邱�Ƃ���ʋK���Ƃ��ē����B���̋K������f�J���g�́A����ɐ_�̑��݂Ɩ{���E�썰�ɂ��ĉ�㈂��Ă���B
�@
����5��
�@
���\���T���Ă����_���w���E�_�x(�w�F���_�x)�̓��e�𗪏q����B
�@
����6��
�@
�K�����C�̐R��ƒn�����̔۔F�Ƃ����������A�f�J���g�Ɏ����̕����w��̈ӌ��̌��\���S�O�������Əq�ׂ�B�l�Ԃ����R�̎�l�Ƃ��邽�߂̐����ɂƂ��ėL�p�Ȓm���ɓ��B���邱�Ƃ͉\�ł���A������B�����Ƃ̓f�J���g�ɂ���߂Ǝv��ꂽ�B������ώ@�͏d�v�ł���A���O�����ꂩ�瓾�闘�v���݂��Ɍ��J���邱�Ƃ������ɂȂ�͂����ƁB�������A�K�����I�����ŋ��P���f�J���g�́A�܂���������Ă��Ȃ���̐^����T�����鎞�Ԃ�����Ȃ����߂ɁA������_�c�������悤�Ȏ����̒����͐��O�ɏo�ł��邱�Ƃ�f�O���邱�Ƃɂ����B�����������������p�ӂ��Ă������Ƃ�m��l�X�ɈӐ}���������Ȃ��悤�A1634�N�ɂȂ��ď����ꂽ�_�l����T�d�ɑI�ꂽ�w���܌��w�x�w�C�ۊw�x�w�w�x�Ɂw���@�����x���Č��\���邱�Ƃɓ��ӂ����A�Əq�ׂ�B�@�@
�@ |
 �@ �@
���n�[���B�u���������_�v���� 1651�N |
   �@
�@
|
Harvey, William.(1578-1657)
�@
Exercitationes de generatione animalium.
�@
�n�[���B�́A�C�M���X�̈�ҁA�����w�҂Ō��t�z�̔����ҁB�����I���@���ċ����āA�����̈ō����ォ��ߐ��̐����w���J�����w�ҁB�P���u���b�W�A�p�h���A(�C�^���A)�̗���w�Ŋw�у����h���ŊJ�Ƃ����B�L�͂ȉ�U�w�I�T���Ɛ����Ȏ����ɂ���āA���t�͑S�̂Ƃ��ĕ���ꂽ�njn�������Ă��邱�Ƃ��m�F���A�̏z�𖾂炩�ɂ����B�n�[���B�̌��t�z���̓K���m�X�̊w�������S�ɕ����A�ߑ㐶���w�̊�ՂƂȂ����B�܂��ӔN�͔����w�̌����ɖv�����A�{���ɂ���āu���ׂĂ̔����͗�����(Exovo ommia)�v�Ƃ��������̐��B�Ɋւ���ߑ�̂����錩�����x�z���閽��̔��[��������B�@ |
���E�C���A���E�n�[�x�[
�@
(�n�[���B�[�A�n�[���F�[�AWilliam Harvey�A1578-1657)�@�C�M���X�̉�U�w�ҁA��t�B���t�z�����������B�P���u���b�W��w�Ɋw�̂��A�C�^���A�̃p�h���@��w�ʼn�U�w�҃t�@�u���L�E�X�Ɏt�����Ĉ�w�̊w�ʂ��擾����B�C�M���X�ɋA����A����Ƃ��Ă̕]�����m�����A1618�N�A�����̃X�e���A�[�g���̍����ł������W�F�[���Y1���̎���ƂȂ�B�W�F�[���Y1���̎���́A�̂��Ƀs���[���^���v���ŏ��Y�����`���[���Y1���Ɏd�����B1645�N����I�b�N�X�t�H�[�h��w�}�[�g���E�J���b�W�̊w��(Warden)�߂�(-1648�N)�B1628�N�A���t�z���\�B����́A���������_���ĂB���ɁA�A���X�g�e���X�̐���M����w�҂���̔ے�ӌ������������B1642�N�ɖu�����������k�v���ɍۂ��A�n�[���F�[�̓X�e���A�[�g��(���}�h�̑�)���x�������B���̂��߁A���}�h�̔s�k������I�ɂȂ�ƃ����h���x�O�ɑނ����B
�@
���_�ւ̍Ĕ��_�́A1649�N�ɍ��q�̌`�ōs�Ȃ����B�܂��A�ނ͔����w�ł��傫�ȑ��Ղ��c�����B�ނ̓V�J�̌���O�ォ��̔����̒i�K���ώ@���A�A���X�g�e���X�́w�َ��͌��o�����琶����x�Ƃ�������ے肵���B�ނ͂ٓ��ނ̗������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A���̓����Ƃ̔�r���炻�̑��݂��m�M���A�u���ׂĂ͗�����v�Ƃ̌��t���c�����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���z�b�u�X�u�����@�C�A�T���v���ŏ��� 1651�N |
   �@
�@
|
Hobbes, Thomas.(1588-1679)
�@
Leviathan, or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill.
�@
�z�b�u�X�́A�s���v�����C�M���X�̑�\�I�����v�z�ƁB�I�b�N�X�t�H�[�h��w�𑲋ƌ�A�M���̉ƒ닳�t��A�t�����X�ɖS�����̃`���[���Y�c���q�̐��w���t���Ƃ߂��肵�Ȃ���A���슈���ɐ�O�����B����́u�����@�C�A�T���A���Ȃ킿����I����юs���I���Ɓv�ł���A�S�����Ƀt�����X�Ŏ��M����A�v���������̃C�M���X�ŏo�ł��ꂽ�B�ނ́A������_�ɂ���Ăł͂Ȃ��A�_��Ƃ��������I�ȊϔO�ɂ���Ċ�b�Â����B�{���́A�ߑ㖯���`�v�z�̊�{�I�g�g�݂ł���Љ�_��������߂č\�z�������B�@ |
�������@�C�A�T��
�@
(Leviathan)�@�g�}�X�E�z�b�u�Y�������������N�w���B1651�N�ɔ��s���ꂽ�B�薼�͋����ɓo�ꂷ��C�̉��������B�A�^���̖��O������ꂽ�B�����ȑ薼��"Leviathan or the matter, forme and power of a common-wealth ecclesiasticall and civil"�B
�@
�{���̓z�b�u�Y�ɂ���Ē����ꂽ���Ƃɂ��Ă̐����N�w�̒���ł���B���m�ɂ����鍑�Ƃ̊T�O�͐l�Ԃ̐����I���i�ɂ���Đ������Ă���|���X�ł��邪�A���l�T���X�Ȍ�ɂ͋ߑ�I�ȍ��Ƃ̊T�O�͌������ꂽ�B�j�b�R���E�}�L�����F�b�������͊W���獑�Ƃ̐������l�@���Ă���A����ɏ@���푈�����Ȃǂ�ʂ��č��Ƃ̐V���ȓN�w�I�Ȋ�b�t�������߂���悤�ɂȂ����B�z�b�u�Y�̓C�M���X�ł̓�����ʂ��Ă��̖��ӎ������悤�ɂȂ�A�V�������Ɨ��_�̊�b�t���A�V���Ȑ����������m�����邱�Ƃ�ڎw�����B
�@
�z�b�u�Y�͐l�Ԃ̎��R��Ԃl�̖��l�ɑ��铬��(���e����: bellum omnium contra omnes, �p��: the war of all against all)�ł���Ƃ��A���̍���������邽�߂ɂ́A�u�l�Ԃ��V���̌����Ƃ��Ď������鎩�R���𐭕{(���̏ꍇ�͎c���c��ł���A���̐��{���w���āw�����@�C�A�T���x�ƌ����Ă���B�E�̌��G�ɕ`����Ă��鉤���������w�����@�C�A�T���x�͐��{�ɑ��Ď���̎��R�������n�����l�X�ɂ���č\������Ă���)�ɑ��đS�����n(�ƌ����Љ�_���)����ׂ��ł���B�v�Əq�ׁA�Љ�_��_��p���ď]���̉����_�����ɑ����Ή��������������闝�_���\�z�����B���̗��_�͐b��(�����Ō����b���́A���ƌ��͂̍s�g����q�̂Ƃ��Ă̐l��)�̎��R���匠�҂̖��߂ł���@�̒��ق���̈�Ɍ��肳��Ă��܂��A�匠�҂ɑ���b���̒�R�����F�߂��Ȃ��B
�@
�z�b�u�Y�̍��Ɨ��_�́A�g�D�L�f�B�f�X�́w��j�x�̖|���l�Ԃ̗~�]����b�ɂ��Ȃ��獇���I�Ȍv�Z���s�����ƂŐ����������\�z���邱�Ƃ�_�����w�@�w�v�j�x�\���Ă��邱�Ƃ��番����悤�ɁA������`�I�ȍl�����������Ă������Ƃ�������B���̋c�_�͌�ɃW�����E���b�N���w������_�x�Ńz�b�u�Y�Ƃ͈قȂ鎩�R��Ԙ_����Љ�_��̘g�g�݂ō��Ƃ̋K�͗��_�̍Č������s���A�܂��W�����E�W���b�N�E���\�[���w�Љ�_��_�x�Ŏ��R�ӎu�����e�l�̎Љ�_��Ɋ�Â������Ƃ݂̍����_���A�������̔ᔻ���Ȃ���邱�ƂɂȂ�B����Ń}�C�P���E�I�[�N�V���b�g���{����l�Ԗ{���̕��͂��獑�Ƃ̐������\�z�����݂������N�w�̒���Ƃ��č����]�����Ă���B�����ɂ����Ă��{���͍��������w�⍑�ې����w�ɂ����鍑�Ƃ̐l�i�̓��ꐫ��\���̐l�H���A�匠�̐�ΐ�������c�_���N���Ă���B
�@
�������j
�@
�X�y�C���̖��G�͑����C���O�����h�ɔ���1588�N4��5���Ƀz�b�u�Y�͐��܂ꂽ�B�c���̍�����p�ˋ�����A14�ŃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w���Ę_���w��X�R���N�w���w��19�ő��Ƃ��ċM���̉ƒ닳�t�ƂȂ����B1610�N�Ƀ��[���b�p�։ƒ닳�t�Ƃ��Ă̈����̎d���œn�������ɁA�ߑ�̓N�w�⎩�R�Ȋw�̒m���ɐG��A1629�N�̃��[���b�p�n�q�ł̓��[�N���b�h�w�̂悤�ȉ�㈓I���@�_���K�����A1630�N��3�x�ڂ̓n�q�ł͗��j�ƎЉ�ɂ��Ă̊w��I�̌n�̊�b���\�z���Ă���B���̂悤�Ȓm�I�w�i�������Ȃ��琶�U�ɂ킽���Đ����ɂ��Ă̌������s���A�g�D�L�f�B�f�X�́w��j�x�̖|��A�w�@�w�����x�A�w�s���_�x�A�{���w�����@�C�A�T���x�A�w�x�q�[���X�x�Ȃǂ̒���\�����B
�@
�z�b�u�Y���v�z���`�����鎞���̓C���O�����h�ɂƂ��ė�����������������ߓn���ł������B1603�N�ɃX�`���A�[�g�����������A�����ɂ���č�����̔ᔻ�Ɖ����_�������咣�����Ƌc��ɂ���R�c���s���A�����Ƌc��̑Η����[���������B������1628�N�Ɍ����̐��肪�N�b�N�ɂ���ċN������A��1629�N�ɂ͋c����U���ꂽ�B�������X�R�b�g�����h�Ŕ�������������ƍ����͐��B�̂��߂ɋc������W�������A�����Ƌc��̑Η��͂���ɐi�s���A1642�N�ɓ���ɓ˓������B���̓���̓s���[���^���v���ƌĂ�A�N�����E�F�������c��h�����a�����������邱�ƂɂȂ����B�������N�����E�F���̌��i�ȃs���[���^�j�Y���͖��O�̔������A���ꂪ�������Â̌����ƂȂ����B���̌�Ƀ`���[���Y2���������Ƃ��ČĂі߂���A�X�`���A�[�g�����������邪�A����̃W�F�[���Y2�����ꐧ�������s�������߂ɋc��̓I�����_���ł������E�B���A��3���������Ƃ��A�����͓T�����F�����č����̐�ΓI�����𐧌����邱�Ƃŗ������������������B���̊v���͖��_�v���ƌ����A��̃s���[���^���v���ƍ��킹�Ďs���v���ƌĂ��B�{���w�����@�C�A�T���x�����M���ꂽ�̂̓N�����E�F�����������������č����̃`���[���Y2�����t�����X�֖S�����������ł���A���̃C�M���X�s���v���ɂ����鍬���̎���ł������B
�@
�����e
�@
�{���͐l�Ԃ������Ă��銴�o��C�}�W�l�[�V�����A����A�܂��^���A�m���Ȃǂɂ��ďq�ׂ���ɐl�Ԃ̎��R��Ԃ̐����₻������z���邽�߂̋K�͂ł��鎩�R�@��_������1���u�l�Ԃɂ��āv�Ɏn�܂�B�܂���2���u���Ƃɂ��āv�ł͍��Ƃ��n�݂���闝�R�⍑�Ƃɂ�����匠�҂Ɛb���̊W��_�����B��3���u�L���X�g�����Ƃɂ��āv�ł̓L���X�g���̐��������Ɏn�܂�A�����ł̋���⋳��͂̈Ӌ`���l�@����B��4���u�Í��̉����ɂ��āv�ł͈Í��̎x�z�҂ɂ��ďq�ׂĂ���A�Ō�̌��_�ł͐l�Ԃ̖{���I�Ȕ\�͂��炻��܂ł̋c�_���T�����Ă���B
�@
���l�Ԗ{��
�@
�z�b�u�Y�͐l�Ԃ��{���I�Ɏ����Ă��鐫������_�l���n�߂�B���������l�Ԃ̔F���ߒ��͊��o�Ɋ�Â��Ă���B���o�͊O�E�̕��̉^���ɑ��Ĕ������A���p�ɂ�蓾��ꂽ���̂̉^���͉f���Ƃ����l�Ԃɓ���������B����͑��A�܂��̓C�}�W�l�[�V�����ƌĂ�A�L����v�l���̂��̂ł�����B�v�l�͖ړI�I�ɋK�����ꂽ���̂Ƃ����łȂ����̂�����B���̎v�l�̓r��ŔF���Ώۂɖ��̂�^���邱�Ƃ��\�ł���B���̂��^����ꂽ���͂��Ƃ����ڊm�F���Ȃ��Ƃ��A���̂��v���o�����ƂŋL�����Ăі߂��B���̂��̂��̂��番�����Ďg�p����閼�̂͌���ƂȂ�A�l�Ԃ̗����ɂƂ��čł��d��Ȃ��̂ł���B
�@
���t�͐l�ԂɊw����\�Ƃ����B�w��̏o���_�͒�`�ƌĂ��K�Ȗ��̂�p���Ė�����\�z���邱�Ƃł���B���̖��肩��_���I�v�l�Ɋ�Â��Đ��_��i�߂�B���̈�A�̉ߒ����瓾�����A�̋A���̒m�����w��ł���A���̌����Ώۂɂ���Ď��R�N�w�ƎЉ�N�w�ɑ�ʂ����B�l�Ԃ͂��̂悤�ȔF���Ɋ�Â��Ď���̍s�������肵�Ă�����̂́A���ۂɍs�����쓮���Ă���̂͏F���ł͂Ȃ��l�Ԃ̈ӎu�̓������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�l�Ԃ̈ӎu�̓����͏�O�ł���A���|�A���Q�A�D��S�Ȃǂ̂������O�����݂��Ă���B
�@
�����R���
�@
�X�l������̈ӎu��B�����悤�Ƃ����i�����͂ł���A���ƈȑO�̏�Ԃł��鎩�R��Ԃ𗝘_�I�ɑz�肵���ꍇ�ɂ͑傫�Ȍ��͂̊i���͔F�߂��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�e�l�͌��͂̌���ƂȂ�g�́A�m���A���i�A�i�ʂȂǂɂ���đ����̌��͂�����̂́A�����I�Ȋϓ_�ɗ��Ăΐl�Ԃ̔\�͂͑Γ��ɗ^�����Ă��邩��ł���B
�@
���������͂������ł������Ƃ��Ă�����Ă���Ώە��������ŕ����ł��Ȃ����߂ɕ����҂̈ӎu���B���ł��Ȃ��Ȃ�Δނ�͓G�ΊW�ɂȂ�B�l�Ԃ̖{���ɂ͋����A�s�M�A�����S�̏�O������A�����͕s��I�ɓG�ΊW��n�o����B���������Đl�Ԃ͂��̓G�Ύ҂ɑ��Đ搧�U���������邱�ƂŎE�Q�܂��͕��]�����邩��I�����邱�ƂɂȂ�B����͐l�Ԃ̎��ȕۑ����ŏd�v�̉��l�ƌ��Ȃ���鎩�R���ł���A���̎��R����Nj����邱�Ƃ͎��R�łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@
���������R�Ɏ��R�����s�g����ΐl�X�͏�ɍU�������댯�ɎN����邱�ƂɂȂ�A���ʓI�Ɏ��R��Ԃ͖��l�̖��l�ɑ���푈�ɔ��W����B���R��Ԃł̐푈�ł͐퓬�����s����Ă��邩�ǂ��������ł͂Ȃ��A����͊�Q��������Ӑ}�������ꂽ��Ԃƍl������B���̂悤�ȏ�Ԃł͐l�Ԃ͉i���I�ɋ��|�Ɗ댯�ɔ��������Ȃ���Ȃ炸�A����ɂ���Čo�ςW�����邱�Ƃ͕s�\�ł���A�l�Ԃ̐����͌ǓƂ��c�E�Ȃ��̂ƂȂ�B
�@
���Љ�_��
�@
���R��Ԃł̏������������邽�߂ɂ͐푈�������炷��O�ɒ��ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͎��R���̍s�g��}�����A�܂����ʌ��͂ɂ���đ��݂̖��Ď����邱�Ƃ��K�v�ł���B���̂��߂Ɏ��R��ԂŐ��܂ꂽ�������~�����邽�߂Ɏ��R�@�͎��̂悤�Ȋ�{�I�ȋK�͂������B���̎��R�@�́u���a����ɂ���]�݂��������A���a�ւƐi�߁B���̖]�݂��Ȃ���ΐ푈���s�̂��߂������i���g�p����v�Ƃ������̂ł���A���̎��R�@�́u���l�Ƌ��ɕ��a�Ǝ��Ȗh�q�̂��߂ɕK�v�Ȍ������������v�Ƃ������̂ł���B
�@
���̎��R�@�ɍ��ӂ��邽�߂ɂ͑��݂ɐM���������A���R��������A���n���邱�Ƃŋ��ʌ��͂��\������B�_��ɎQ������l�X�͑㗝�l�𗧂ĂĂ��̑㗝�l�ɋ��ʌ��͂�^���Č_��̗��s���Ď�������̂ł���B���̊W�͑㗝�l�ƌ_��ɎQ������l�X�̓��ꐫ���ێ�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B���̓��ꐫ�ɂ���Ă����炳���Љ�����R�����E�F���X�A���ƂƌĂ��B
�@
������
�@
�z�b�u�Y�ɂ����Ƃ̓����@�C�A�T���ƌĂ��B�����̍s�҂���\������Ă��Ȃ�����l�i�̒P�ꐫ�������A���̐l�i���\����̂��匠�҂ł���A����ȊO�͐b���ƂȂ�B�匠�҂��ۗL����匠�͐�ΓI�Ȃ��̂ł���A��l�Ŏ匠�҂ƂȂ鐭���̐��͌N�吧�A�����S�̂��匠�҂ł���Ȃ�Ζ��吧�A�ꕔ�̐l�тƂȂ�M�����ƂȂ�B
�@
�匠�͐b���̂��߂̎����ێ��⍑�h�A���@�A�i�@�A�ݕ������Ȃǂ̌������܂܂�Ă���A���Ƃ͐b���̎��ȕۑ���ۏႷ����̂ł���B�������匠�҂��S�Ă̐b���̍s�����ł���킯�ł͂Ȃ��A�@�����ق���̈�ł͐b���͎��R�ł���B�匠�҂͎Љ�_��Ɋ�Â��Ă���A�S�Ă̍s���𐧌��ł���킯�ł͂Ȃ�����ł���B����ɐb���͎匠�҂̖��߂ɏ]�����ƂŎ��ȕۑ������Ȃ���ꍇ�ɂ͓��S�ɂ���R���F�߂���B�@ |
���g�}�X�E�z�b�u�X�@(Thomas Hobbes,1588-1679)
�@
���R�@�N�w�҂̃g�}�X�E�z�b�u�X�́A���[���b�p�̗��j�ōő�̌������̈�ɕ�炵�Ă����\�\���ʂƂ��āA����̗��_���l�Ԃ̖{���ɂ��ēO��I�ɔߊϓI�Ȃ̂��A�܂����傤���Ȃ����B
�@
�}�[���Y�x���[�̋߂��ɐ��܂�A�n��������������q�t�̕��e�������ɖS���Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�Ⴋ�g�}�X�E�z�b�u�X�͗T���ȏf������Ɉ�Ă�ꂽ�B14 �̎��ɃI�b�N�X�t�H�[�h�̃��[�h�����E�J���b�W�ɓ��w���āA5 �N��Ɋw�m��������Ă���B1608 �N�ɂ́A�f���H���V���[���݂ł���E�B���A���E�L�����F���f�C�b�V���̑��q�̉ƒ닳�t�ɂȂ����B�������ŌÓT�ɖv�����鎞�Ԃ��ł����B�A���X�g�e���X�w�h�́A���t�̋Ȍ|�݂����Ȏv�z�Ɍ��C���������z�b�u�X�́A���j�ƃc�L�W�f�X�̔M�S�ȐM�]�҂ɂȂ��Ă�����(�z�b�u�X�́A�ނ̖{�� 1628 �N�ɖ�o����)�B1610 �N�ɍŏ��̃��[���b�p�V�w���I������ŁA�t�����V�X�E�x�[�R���ƒm�荇���ɂȂ�B�ł��Ȋw�I�Ȑ��E�ςɓS�|����̂́A����� 1630 �N�ɂȂ��Ă���A���[�N���b�h�́w�w�x�Ɏ䂩�ꂽ�̂ƁA���[���b�p�嗤�̗��s���ɁA���[���b�p�̉Ȋw��(���Ƀ����Z���k�_���̒���)�����Ƃ��̂��Ƃ������B
�@
�z�b�u�X�͓��ɁA�K�����I���͊w�̎��_���t�]���������Ƃɖ������ꂽ�B�r�����_���Ƃ͋t�ɁA�K�����I�͕��̂̎��R��Ԃ͉^�����Ă��邱�Ƃł���A�Î~���Ă��邱�Ƃł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă����B���̂́A�~�߂��Ȃ����肸���Ɠ���������A�Ɣނ͘_�����B1636 �N�ɃK�����I�ɉ������A�z�b�u�X�͂��̍l���𑍍��I�ȎЉ�N�w�ɂ��Ă͂߂悤�Ƃ����B�ނ͂����3�̕����ɕ����č\�z���邱�Ƃɂ����B1 �ڂ́u���̘_�v�ł���A�ނ͂�����̌����Ɗ֘A�Â��悤�Ǝv�����B2 �ڂ́u�l�Ԙ_�v�ŁA�l�͂ǂ�����(���o��~�]��H�~�ȂǂɎh������)�����Ă��镨�̂Ƃ��Č��Ȃ����̂��A�܂��l�Ԃ͊O���̉^���ɂǂ��e�������̂����������Ƃ����B3 �ڂ́u�s���_�v�ŁA���������_�C�i�~�b�N�Ȑl�Ԃ̑��ݍ�p���A���̂̐����͊w�ɗ^���錋�ʂ���悤�Ǝv�����B
�@
�C�M���X�̍����Ƌc��̑Η����[���ɂȂ��Ă����̂ŁA�z�b�u�X�͒���̔��\�������Ђ�����Ԃ����Ƃɂ����B1640 �N�� �u�@�w�v�_�v���o�ł������A����ɂ́u�l�Ԙ_�v�Ɓu�s���_�v�̊T�����܂܂�Ă������B����̒���͋c��h�̗v���ɔ����ĉ��}�h���x�����Ă���悤�Ɏv��ꂽ���߁A�z�b�u�X�͊�Q���y�Ԃ̂�����āA���̔N�̏I��荠�Ƀp���ɖS�����A11 �N�Ԃ��B��Đ������Ă����B�z�b�u�X�͍Ăу����Z���k�_���̒��Ԃɓ����āA���炭�͎Ⴋ�S�����q�̐��w�ƒ닳�t���߂����A���̉��q�͌�Ƀ`���[���Y2���ƂȂ����l�����B
�@
1642�N�ɂ́A�z�b�u�X�́u�s���_�v�����s���ꂽ���A���̖{�ł́A�ނ̗��_�̌n�̑�O���ɂ��āA����ɏڂ������R�Ƃ������͂ɂ��W�J����Ă���B�ł����ꂪ�C�M���X�ł͂����Ƃ��]���ɂȂ�Ȃ������̂ŁA�z�b�u�X�͐V���Ș_���������n�߂����A���x�͂����ƒn�ɑ��̒������`�ŗ��_��������悤�Ƃ����B�����ďo�����{���u�����@�C�A�T���v(1651) ���B
�@
�u�����@�C�A�T���v(1651) �͂܂������Ȃ��z�b�u�Y�̌��삾�B�z�b�u�X�̎咣�ł́A�l�Ԃ͐��܂���P�ǂȂ̂ł͂Ȃ��A���܂�����Ȓ��S�I�ȉ��y��`�҂��\�\�u������l�Ԃ̎����I�ȍs���̖ړI�́A�����ɉ��炩�̂������Ƃ�����A�Ƃ������Ƃ��v�B�l�̍s�������߂铮�@�́A���R�̏�Ԃ̂܂܂ł́A�Ȏ������~�ɓ������̂�����A�������Ă����Ȃ��Ǝ��ɔj��I�Ȍ����������炵���˂Ȃ��B��������}�����Ȃ��ƁA�l�͓��I�ȓ��@�ɓ�������āA���݂��Ɍ��˂��������낤�B�z�b�u�X�͐l�ԎЉ�u���R��ԁv�\�\�s�����Ƃ�@�̋K��������������ԁ\�\�ɂ�������ǂ��Ȃ邩��`�����Ƃ���B���̌��_�͔߂������̂��B����Ȑl���́u�ǓƂŁA�n�����A�ڗ�ŁA�c���ŁA�Z�����̂ɂȂ�v�A�u���l�����݂��ɐ푈��ԂƂȂ�v
�@
����ł��A�F��������(�����I�ȈӖ��ł͂Ȃ��A���̓I�ȏ����ɂ�����)�A�������т邱�Ƃɑ��ď�M�I�Ȉ���(���R��)�������A�����Ă�����x�̍�����(���R�̖@��)�����Ȃ�A����������������͂̊Ԃ̋ύt��ԂƂ��ẮA�܂Ƃ��ɋ@�\����Љ����ė��邾�낤�A�ƃz�b�u�X�͌��_�����B�����͊ȒP���B���l�̎��R���́A�����ȊO�̂�����l�ɑ���\�͂𐳓�������B�����玩�����������т邽�߂ɁA�l�X�͖\�͂��ӂ邤������������邱�Ƃɓ��ӂ���悤�ɂȂ邾�낤�B�ł��A�����Ȃ�Ƃ��݂��̊Ԃɋٔ������s����ȋύt��Ԃ������Ă���B�ǂꂩ��̏W�c���A�\�͂͂ӂ��Ȃ��Ƃ��������̖�j�����Ƃ���A�ق��݂̂�Ȃ������j���āA�܂��푈��Ԃɋt�߂肵�Ă��܂����낤����B
�@
����Ȃ�A�l�ԎЉ���a�Ɉ��肵�đ������߂ɂ́A�Љ�_��ɒ��ɂ����蕨�\�\�u�����@�C�A�T���v�\�\��D�荞�ޕK�v������B���̃����@�C�A�T���Ƃ����͍̂��Ƃ��\�\��ΌN�吧�ł�����I�ȋc��ł��\��Ȃ��B��ȓ_�́A���Ƃ͖\�͂Ɛ�ΓI���Ђ�Ɛ�I�ɗ^������Ƃ������Ƃ��B����ƈ����ւ��ɍ��Ƃ́A���̐�ΓI�Ȍ��͂��s�g���ĕ��a�ȏ�Ԃ�ۏ���(����ȍs�ׂ����E�����҂���Ƃ�����)�B���͎����̐�ΓI�Ȍ��͂��A�s�������������I�ɂ����������Ă���邱�ƂɊ��S�Ɉˑ����Ă���Ƃ������Ƃ�m���Ă��邩��A���Ƃ̑��Ƃ��Ă����̌��͂𗔗p���Ȃ��C���Z���e�B�u������B�������A���p���Ȃ��ۏ͂Ȃ��B�ł����p����A���ƂƂ��Ă͂��ꂪ�ǂ�Ȍ��ʂ������炷���o�債�Ȃ��Ⴂ���Ȃ��킯���B
�@
�z�b�u�X�̐��̖ʔ����Ƃ���́A�������Ƃ��A���R�A���`�A���L���Ƃ������T�O�ɂ́A���R�ȈӖ��Ƃ��A�{���I�ȈӖ��Ƃ��A�i���I�ȈӖ��Ȃ܂������Ȃ��A�Ƃ����_���B�����͂Ђ�����Љ���グ�����̂ł����Ȃ��B�푈�ƎЉ�I�������������Ƃǂ߂邽�߂ɁA�����@�C�A�T�����@��x��ʂ��č�肾���A����������̂��B���j�������悤�ɁA�ǂ�ȉ��l�ς��i���ł͂Ȃ��A���͂̏��ς��Ώ������ω�����̂��B
�@
�Ƃ�킯�z�b�u�X�́A�@���̂��̂͊��S�ɗ͂ɂ���Ďx�����Ă���A�Ƌ����w�E����B���͂��鋭�����Ђ���돂�Ɏ����Ȃ��@�Ȃ�āA�܂Ƃ��ȈӖ��ł̖@�Ƃ͌ĂׂȂ��B������z�b�u�X�́u�@���؎�` (Legal positivism)�v�̑n�n�҂̈�l�Ƃ���Ă���B�܂�A�@���������ƌ������̂͂Ȃ�ł��������A�Ƃ������ꂾ�B�u�s���Ȗ@���v�Ȃ�Ă̂͂����̖��������ł����Ȃ��B
�@
���̋c�_���̏ɂ��Ă͂߂Ă݂�ƁA�c��h�̔����́A�`���[���Y�����l���������ɂ͈�@�ɂȂ�B�ł��`���[���Y�ꐢ�����Y���ꂽ�Ƃ���A���x�͋c��h�ւ̔��R�����ׂĈ�@�ɂȂ�B�z�b�u�X�ɂ����ẮA�͂������������߁A�͂��������`���B���Ƃ́\�\�ǂ�ȑ̐��ł����Ă��\�\�s���̕��a���ێ��ł������A��ɒ�`���炵�Đ������Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�t�����X�S�����̉��}�h�ɗ���ҌĂ�肳�ꂽ�z�b�u�X�́A�u�����@�C�A�T���v���s����ɃC�M���X�ɋA��A������c�̑O�ɏo�������B���̌�܂��Ȃ��A����͓N�w�O����̎c��\�\�w���̘_�x(1655) �Ɓw�l�Ԙ_�x(1657) �����s�B
�@
�z�b�u�X�͂����ނˁA�����h���łЂ�����ƕ�炻���Ƃ�������ǁA�����ɉ��X�Ƒ����_���Ɏ��X�Ɗ������܂�邱�ƂƂȂ����B�܂��̓f���[�̎i���W�����E�u�����[���Ƃ̎��R�ӎu�Ɋւ���_��(1654, 1658, 1682 ���Q��)�B1655 �N�Ƀz�b�u�X�́A�~�̖ʐς͐ϕ��œ�����Ǝ咣�B����ɂ͐��w�҂̃W�����E�E�H�[���X�����_���Ă����̂ŁA�z�b�u�X�͂���ɔ����A��A�̘_�� (1656, 1657) �����s���A�E�H�[���X�Ɣނ́u�V��ȁv���w���͂�����B1661 �N�ɁA�U���͈͂��L���ă��o�[�g�E�{�C���Ƃł����Ẳ�������ɂ܂ōL�����B�u�z�b�u�X���̍l���v(1662) �ł���͋x���錾�����B
�@
1660�N�̉������Â̌�ŁA�`���[���Y�̓z�b�u�X�𑊒k���ɂ��ĔN����^�����B1666 �N�̃����h����̌�A�p���̉��@�̓z�b�u�X�́u�����@�C�A�T���v�փ��X�g�ɉ�����c�Ă��o���Ă����B���̋c�ẮA���l�̉���ŋM���@��ʉ߂��Ȃ��������ǁA���㒘����o���Ƃ��ɂ͂܂������ɐ���������Ɖ��̓z�b�u�X�Ɍ������B�z�b�u�X�͂���ɏ]�����̂ŁA�ނ̂��̑��̐����I�Ȓ��앨�́A����o�łƂȂ����B���̂�������͓��M�ɒl����B1681 �N�́u�C���O�����h�ɂ�����N�w�҂Ɩ@�w�k�Ƃ̑Θb�v�ł̓R�����E���[�ɍU���������A�����匠��i�삵���B1682 �N�́u�r�q���X�v�́A�����c��(1640 �N�Ƀ`���[���Y�ꐢ�����W���A1660 �N�܂ő����������k�v�����̋c��)�Ɛ����k�v���ɂ��ẮA�����I�ȗ��j�L�q���B�ӔN�ɂ́A���`�̎��M�ƃz�����X�́u�C���A�X�v�u�I�f���b�Z�C�A�v�̖|������Ă����B
�@
�z�b�u�X�͈�ʂɁA17 ���I�́u���R�@�v�N�w�҂ōł��L�͂Ȑl���Ƃ���Ă��āA���̌�̃C�M���X�̐����E�Љ�E�o�ϗ��_�ɂ����܂����e�����y�ڂ����B�x���T�� �� ���p��`�ɂ̓z�b�u�X���̉��y��`�̗v�f������B���R�Ȃ���A�Η����鎩�ȗ��v�̊Ԃ̎Љ�I�ߍx�Ƃ������z�́A�A�_���E�X�~�X�̒��Ɏ��ɘI���ɏo�Ă���(�ł��X�~�X�́A���̉��y��`�I�ȓ��@�Â��̕����͂��܂�F�߂�����Ȃ����������)���A���̌�̌��݂ɂ�����o�ϊw�̒��ɂ������Ă���B������Љ�K�͂̓��I�ȑn���Ɛi���Ɋւ���Ō�̕����́A�q���[�� �� �n�C�G�N �̗����Ƀp�N���Ă���B
�@
�z�b�u�X�̑ɂɂ����̂��W�����E���b�N�Ƃ����Ɗy�ϓI�� �t�����X�v�z�Ƃ����̌n���A���ɃW�������W���b�N�E���\�[�Ƃ���̃C�M���X�̕��g�Ƃ������ׂ��E�B���A���E�S�h�E�B�����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���{�C���u��C�Ɋւ��镨���͊w�I�V�����v��2�� 1662�N |
   �@
�@
|
Boyle, Robert.(1627-91)
�@
New experiments physico-mechanical, touching the air.
�@
�{�C���́A�C�M���X�̉��w�ҁA�����w�ҁB�A�C�������h�ɐ��܂�A�C�[�g���Z�𑲋Ƃ��đ嗤�ɕ����A�A����A�����V�����w���T�����Ă����w��O���[�v�ɉ�������B���̊w��O���[�v�́A�̂��ɉ�������(Royal Society)�ɔ��W���A�ނ͂��̊����̈�l�Ƃ��Ċ����B�ނɂ͕����w����щ��w�ɂ킽�鑽���ʂ̋Ɛт�����A1657�N���Q�[���P�̐^�������m��A����̃t�b�N�Ƃ��܂��܂Ȏ������s���A1660�N�ɖ{���̏��ł����B��C�̑̐ς����̈��͂ɔ���Ⴗ��Ƃ������{�C���̖@�����́A�W���̑�2�łɂ���Ė��炩�ɂ��ꂽ�B |
����C�̒e���Ƃ��̌��ʂƂɊւ��镨���|�͊w�I�ȐV����
�@
���o�[�g�E�{�C�� (1627-1691)
�@
1640�N��������1650�N��̏����܂ł̊ԂɁA�h�C�c�̉Ȋw�҂Ń}�O�f�u���O�̎s���ł��������I�b�g�[�E�t�H���E�Q�[���P�́A�e�풆�ɍ��^������o�����Ƃ��ł���r�C�|���v���J�����܂����B���̃|���v�œ�����^���p���āA�ނ͗L���ȁu�}�O�f�u���O�̔����v�̎������s�����̂ł��B���̎����ɂ���āA�Q�[���P�͗e��̒������C��r�o����ƁA��C���ꎩ�g�̏d���ɂ���đ傫�ȗ͂�������ė��邱�Ƃ��ؖ������̂ł��B�Q�[���P��1672�N�ɂ��̃|���v�̔����Ǝ����̌��ʂ����g�̎�ŏ����ɂ���̂ɐ旧���āA1657�N�ɃW�F�Y�C�b�g�̏C���m�J�X�p�[�E�V���b�g���A���̒����u�����ƋC���̗͊w�v�ɃQ�[���P�̐^��|���v�̂��Ƃ��������̂ł����B
�@
�{�C���͂��̃V���b�g�̏������Q�[���P�̔����Ǝ����ɂ��Ă̕��͂�ǂ�Ŏh������A�������܃Q�[���P�̃|���v�̉��ǂɒ��肵�A����ł��������o�[�g�E�t�b�N�̑傫�ȏ���������Ċ����ɂ������܂����B
�@
���̐V�����|���v��p���āA�{�C���͐^��̐����A���Ƃ��A�^�ł͕����R���Ȃ����Ƃ≹���`���Ȃ����ƂȂǃQ�[���P�̎�����ǎ����A�Â��ăg���`�F���̋C���v�̎�����^�Ŏ��݁A��C�̏d���͍���29�C���`�̋⒌�ɑ������鎖���m���܂����B�܂��A�^�ł͂ǂ�Ȍ`��̂��̂ł���A�����ɗ������邱�Ƃ��m���߂��̂ł��B
�@
�^��|���v�̎g�p�ɂ���ėl�X�Ȍ��ۂ��o���������ʁA�{�C���͂���ɋ�C�̕����I�����̌����ւƐi��ł����܂����B�ނ͋�C�̒e���ɂ��ďq�ׁA����Ɂu��C�̂ˁv�Ƃ�����`��^���A����ɋ�C�̗e�ςƈ��͂Ƃ̑��݊W���������܂����B�{�C���͋�C�̒e���́A��C�̗��q�Ɨ��q�Ƃ̊Ԃ̋������ӂ�����A�������肷�邱�Ƃɂ���Đ�������̂ƍl���܂����B
�@
���̂悤�ȕ����𗱎q�Ƃ̊Ԃ̋����ƍl����Ƃ����A�Ñ�̌��q�_������Ӗ��ŕ������邱�Ƃɂ���ċߑ�Ȋw�̊�{���O���ł�������̂ł��B
�@
�{���̓{�C���̉Ȋw�Ɋւ��鏈����ł����āA��ɋL�����������ׂɋL�q���Ă��āA�o�łƓ����ɑ傫�Ȕ������Ăт܂����B��N��ɑ��ł��o�ł���܂������A����ɂ͏��łɑ��Ă悹��ꂽ�t�����V�X�E���C�i�X��g�[�}�X�E�z�b�u�X�̔��_�ɑ��āA�{�C���͎���̊w���̐��������咣���镶�͂������Ă��܂��B���̉��M�����ŋ�C�̒e�������߂Ē�ʓI�ɘ_���A���n�ɂ����Ă͋�C�̑̐ςƈ��͂Ƃ͔���Ⴗ�鎖�������Ă��܂��B���݁u�{�C���̖@���v�Ƃ��Ēm���Ă��邱�̌����́A�^���̖@���Ɏ����Œ莮�����ꂽ���R�@���ł������̂ł��B�@ |
�����o�[�g�E�{�C��
�@
(Robert Boyle�A1627-1691)�@�A�C�������h�E���Y���A(�p���)�o�g�̋M���A���R�N�w�ҁA���w�ҁA�����w�ҁA�����ƁB�_�w�Ɋւ��钘��������B�����h����������t�F���[�B�{�C���̖@���Œm���Ă���B�ނ̌����͘B���p�̓`���������Ƃ��Ă��邪�A�ߑ㉻�w�̑c�Ƃ���邱�Ƃ������B���ɒ����w���^�I���w�ҁx ( The Sceptical Chymist) �͉��w�Ƃ�������̊�b��z�����Ƃ���Ă���B
�@
�A�C�������h�A�E�H�[�^�[�t�H�[�h�B���Y���A�ɐ��܂��B���͏���R�[�N�����`���[�h�E�{�C���ŁA����7�Ԗڂ̑��q�A14�Ԗڂ̎q�ł���B���`���[�h�E�{�C����1588�N�ɃA�C�������h�ɕ����A���A�n���Ǘ����ƂȂ�A���o�[�g�����܂ꂽ����ɂ͑�n��ɂȂ��Ă����B
�@
�Z�����Ɠ��l�A�c������Ɍ��n�̈�Ƃɗ��q�ɏo���ꂽ�B���̌��ʃ{�C���Ƃ̎q���4�N�قǂŏ\���ɃA�C�������h��𗝉����A�ʖł���悤�ɂȂ����B���o�[�g�̓��e����A�M���V����A�t�����X����w�сA8�̂Ƃ��ɕꂪ�S���Ȃ�ƁA�C���O�����h�̃C�[�g���E�J���b�W�ɑ���ꂽ�B�����A���̗F�l Henry Wotton ���Z���߂Ă����B
�@
�C�[�g���E�J���b�W�ł́A�����ƒ닳�t Robert Carew ���ق��A���q�����̋����C�����B�������A���o�[�g�͂��܂�ƒ닳�t�̌������Ƃ��Ȃ������B�C�[�g����3�N�Ԃ��߂�������A���o�[�g�̓t�����X�l�ƒ닳�t�Ƌ��ɊC�O���s�ɏo���B1641�N�ɂ̓C�^���A��K��A���̔N�̓~�̓t�B�����c�F�ʼn߂����A�K�����I�E�K�����C�Ɏt������(�K�����I��1642�N�v)�B
�@
��
�@
1644�N�A�嗤���[���b�p����C���O�����h�ɖ߂����{�C���́A�Ȋw�I�����ɋ����S�����悤�ɂȂ��Ă����B���͂��̑O�N�ɖS���Ȃ�A�C���O�����h�̓h�[�Z�b�g�̃X�^���u���b�W�ɂ��鑑���ƃA�C�������h�̓������b�N�B�̍L��Ȓn���𑊑������B��҂͕����N�����E�F���̃A�C�������h�N���ɏ悶�Ď擾�����y�n�ł���B����ȍ~�{�C���͉Ȋw�I�����ɐ��U�������悤�ɂȂ�A��̉�������̕�̂ƂȂ����Ȋw�ҏW�c "Invisible College" �̈���ƂȂ����B�ނ�̓����h���̃O���V�����E�J���b�W�ŕp�ɂɉ���J���A�ꕔ�̓I�b�N�X�t�H�[�h�ł�����J�����B
�@
1647�N�ɏ��߂ăA�C�������h�ɏ��L����y�n��K��A1652�N�ɃA�C�������h�ɈڏZ�������A�c�ɂł͂Ȃ��Ȃ��������i�܂��C���C������悤�ɂȂ����B����莆�ŃA�C�������h�ɂ��āu��ȍ��ŁA���w�ɂ��Č������Ă��邵�A���w�p�̊����Ȃ��Ȃ�����ł��Ȃ��B�B���p�ɂ͕s�����ȓy�n���v�ƋL���Ă���B1654�N�A�A�C�������h����ɂ��ăI�b�N�X�t�H�[�h�Ɉڂ�Z�ނ��Ƃɂ����B
�@
1657�N�A�I�b�g�[�E�t�H���E�Q�[���P�̋�C�|���v�ɂ��Ėڂɂ��A���o�[�g�E�t�b�N������Ƃ��Ď����C�|���v�̐�����n�߂��B1659�N�� "machina Boyleana" �Ɩ��t������C�|���v�����������A��A�̋�C�ɂ��Ă̎������n�߂��B�I�b�N�X�t�H�[�h��w���j�o�[�V�e�B�E�J���b�W�ɂ�19���I���߂܂� Cross Hall �������Ă������Ƃ������蕶������B�����{�C���͂��̃z�[���̈�p����Ă����B
�@
��C�|���v���g�����������ʂ� New Experiments Physico-Mechanicall, Touching the Spring of the Air, and its Effects... �Ƒ肵��1660�N�ɏo�ŁB���̖{�ɑ��Ĕᔻ�I�Ȏ҂̒��ɃC�G�Y�X��m�� Francis Line (1595–1675) ������ALine �̔ᔻ�ɔ��_����`�Łu�C�̂̑̐ς͈��͂Ɣ���Ⴗ��v�Ƃ����{�C���̖@���ɏ��߂Č��y���邱�ƂɂȂ����B
�@
�������A���̖@��(����)���ŏ��ɒ莮�������̂� Henry Power ��1661�N�̂��Ƃł���B�{�C���� Power �̏������_�������p���Ă��邪�A����Ă��̍�҂� Richard Towneley ���Ƃ��Ă����B���[���b�p�嗤�ł͂��̖@����莮�������̂̓G�h���E�}���I�b�g���Ƃ���邱�Ƃ����邪�A�ނ�����\�����̂�1676�N�̂��ƂŁA���̎��_�܂łɂ̓{�C���̋Ɛт�m���Ă����ƌ����Ă���B1663�N�A�`���[���Y2���̋��� "Invisible College" ���牤��������������B�{�C�����ݗ����c��̈���������B1680�N�A�{�C���͉��������ɑI�ꂽ���A�A�C�̍ۂ̐����̓��e�ɂ��߂炢���o���A��E�����ނ��Ă���B
�@
�{�C���́A�u�����@�v�A�u��s�Z�@�v�A�u�i�v�Ɩ��v�A�u�Z���ɂ߂Čy���d������Z�@�v�A�u�ǂ�ȕ��ł����܂Ȃ����D�v�A�u�o�x���m�F����m���ȕ��@�v�A�u�z���͂�L���Ȃǂ̔\�͂����߂����ɂ�a�炰���∫�������Ȃ����炩�Ȗ���������炷��v�Ƃ�����24�́u�������������̂̈ꗗ�v��������B���̈ꗗ�ɋ�����ꂽ�����͌�ɂ��̂قƂ�ǂ��������Ă���Ƃ����_�Œ��ڂɒl����B
�@
�{�C���̓I�b�N�X�t�H�[�h����Ƀi�C�g (Chevalier) �ƂȂ��Ă����BChevalier �͂��̐��N�O�ɉ������߂ɂ���Đ��肳�ꂽ�ƌ����Ă���B�{�C�����I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ�������͐����k�v���̌㔼�ɂ����邪�AChevalier �ƂȂ����{�C�����ǂ������������ʂ������̂��͂悭�킩���Ă��Ȃ��B
�@
1668�N�A�{�C���̓I�b�N�X�t�H�[�h���烍���h���Ɉڂ�A�o���� Lady Ranelagh �̉Ƃɐg�����B
�@
1689�N�A���Ƃ��Ɛg�̂���v�ł͂Ȃ������{�C���̌��N�͂߂����萊���A��������ł̊������T����悤�ɂȂ�A�}�̗p�����Ȃ����藈�q�͉Ηj�Ƌ��j�̌ߑO�Ɛ��j�Ɠy�j�̌ߌゾ���Ɍ���Ƃ����B�����āA1691�N12��31���A���炩�̎��a�ɂ�閃Ⴢ������Ŏ����BSt Martin in the Fields �ɖ������ꂽ�B
�@
���Ȋw�I�T��
�@
�Ȋw�҂Ƃ��Ẵ{�C���́A�t�����V�X�E�x�[�R�����w�m�����E�I���K�k���x�ō̗p���������ɒ����������B�������{�C�����g�̓x�[�R�����܂߂Đ�l�̉e����F�߂Ă��Ȃ������B����ς��������Ɏ������ʂf���邽�߂ɓ�����̓N�w���_�ɉe������Ȃ��悤�ɂ����Ɖ��x������Ă���A���q�_��l�E�f�J���g�̌��q�_�ւ̔��_�ɂ��Ă��������T���A�w�m�����E�I���K�k���x���̂ɂ��Ă���Ɉꎞ�I�ɎQ�Ƃ���ɗ��߂��B�ނ̋C���ɂƂ��ĉ����̍\�z�قǑ��e��Ȃ����̂͂Ȃ������B�ނ͒m���̊l�����ŏI�ړI�ƌ��Ȃ��Ă��āA���ʂƂ��ĉ����I���̊Ԃ̐�l�����������L���Ȋw�I�T���̖ړI�ɂ��Ă̓W�]���B�������A����͔ނ��Ȋw�̎��p���ɑS�����ӂ�Ȃ������Ƃ��A���p���̂��߂̒m�����y���Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B
�@
�{�C���͘B���p�t�������B������ώ�������\����M���Ă���A���̂��߂̎������s���Ă���B�܂��A�w�����[4�������肵���B���p�ɂ���ċ����𑝂₻���Ƃ���s�ׂ��ւ����@����1689�N�ɔp�~����ɂ������āA�d�v�Ȗ������������B�ނ̕����w�ɂ�����d�v�ȋƐтƂ��āA�{�C���̖@���̔��\�A���̓`�d�ɋ�C���ʂ����Ă�������̉𖾁A������������ۂ̖c���͂̌����A��d�Ƌ��܂̌����A�����̌����A�d�C�̌����A�F�̌����A���̐×͊w�̌���������B���w���D��Ō��������B�ŏ��̒���̑薼�� The Sceptical Chymist(���^�I���w�ҁA1661�N)�����A���̒��ʼn��◰���␅�₪�^�̓������Ǝ������߂̎���B���p�t�̍s��������ᔻ���Ă���B�ނɂƂ��ĉ��w�͘B���p�t���t�̋Z�@�ւ̒P�Ȃ�t�����ł͂Ȃ��A�����̍\����T������Ȋw�������B�ނ͕����̊�{�\���v�f�Ƃ��Č��f�̑��݂�F�߁A�������Ɖ���������ʂ����B�����̐��������o����Z�@�ɂ��ėl�X�Ȑi���������炵�A�����������v���Z�X�� "analysis"(����)�Ɩ��t�����B����ɔނ͌��f���l�X�Ȕ����q�ō\������Ă���ƍl�������A������m�F����Z�p�͓������݂��Ȃ������B�܂��A�R�Ă�ċz�����w�I�Ɍ������A�����w�I�������s�������A�D�������i���������߉�U�ɂ܂ł͓��ݍ��߂Ȃ������B
�@
���_�w�ւ̊S
�@
���R�N�w�҂Ƃ��Ă̈�ʂƂ͕ʂɁA�{�C���͐_�w�ɂ��Ă����Ԃ��������B�������_���ɂ͖��S�������B1660�N�̉������ÂŔނ͋{��ɍD�ӓI�Ɍ}�����A1665�N�ɂ͍�����̐��E�҂ɂȂ�Ƃ��������ŃC�[�g���E�J���b�W�̍Z���E����ꂽ�B�������A�ނ̏@���I����͋���Ɍق�ꂽ���E�҂ł���������l�ł��邩�炱���Ӗ�������Ƃ��āA���̐\���o��f������B
�@
�C�M���X���C���h��Ђ̏d���Ƃ��āA�ނ͓��m�ւ̃L���X�g���z���ɐs�͂��A�鋳�t�ւ̊�t����̊e�팾��ւ̖|��Ɏ���������B�����̃J�g���b�N����͐����̓��e���ꂾ���Ƃ������j���������A�{�C���͊e���̎�����Ő������ǂ߂�悤�ɂ��ׂ����Ƃ������j���x�����Ă����B�V���̃A�C�������h��ł�1602�N�ɏo�ł��ꂽ���A�{�C���̑������͂قƂ�Ǖ��y���Ă��Ȃ��B1680�N����1685�N�ɂ́A����ѐV���̃A�C�������h��ł̈���Ɏ����𓊂��Ă���B���̓_�ł́A�����A�C�������h���x�z���Ă����C���O�����h�l�̓A�C�������h�l�ɉp��̎g�p�����v���Ă���A�{�C���̑ԓx�Ƃ͈قȂ�B
�@
�{�C���͈⌾�ň�Y�̈ꕔ�_�_�A���_�_�A�ً��Ȃǂ̕s�M�S�҂���L���X�g������邽�߂̈�A�̃��N�`���[ (Boyle Lectures) ���J�Â��邱�ƂɈ②�����B���̂Ƃ����L���X�g�����̘_���ɂ͌��y���Ă��Ȃ��B
�@
���Ɛ�
�@
���x�����̏ꍇ�A�C�̂̑̐ς͈��͂ɔ���Ⴗ�邱�Ƃ��B���̖@���̓{�C���̖@���ƌĂ��B�̂��ɃW���b�N�E�V�����������̖@�������x�ω����������ꍇ�ɂ��Ĉ�ʉ������{�C�����V�������̖@���������B
�@
�Q�[���P�����������^��|���v�����ǁB�̂��Ƀ��J�[���������̐^��|���v�̔����Ɖ��ǂ��L�O���ă|���v����ݒ肵���B
�@
1661�N�A���܂��܂ȉ��w�����������ȗ��q�̉^���ɂ���ċN����Ƃ��������A�A���X�g�e���X��4���f��(��C�A���A�y�A��)�����Ó��ł���ƒ����B�@ |
���M�͊w
�@
(thermodynamics)�@�����w�̈ꕪ��ŁA�M���ۂ��̋����I�������爵���w��B�A�{�K�h���萔���x�̕��q���琬�镨���̋����I�Ȑ����������I�ȕ�����(�G�l���M�[�A���x�A�G���g���s�[�A���́A�̐ρA�����ʂ܂��͕��q���A���w�|�e���V�����Ȃ�)��p���ċL�q����B�Ȃ��A�M�͊w�ɂ͑傫�������āu���t�n�̔M�͊w�v�Ɓu�t�n�̔M�͊w�v������B�u�t�n�̔M�͊w�v�͂܂��A����ꂽ�ł������藧���Ȃ��悤�ȗ��_�����ł��Ă��Ȃ��̂ŁA�P�Ɂu�M�͊w�v�ƌ����A���ʂ́u���t�n�̔M�͊w�v�̂��Ƃ��w���B
�@
��
�@
18���I�㔼����19���I�ɂ����ď��C�@�ւ������E���ǂ��ꂽ���A�����͊w��I���ʂ����p�������̂łȂ����o���I�ɐi�߂�ꂽ���̂ł������B������̍��C�̂̐�������������A19���I���߂ɂ̓{�C�����V�������̖@��(���z�C�̂̐���)�Ƃ��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���A�܂��M���ƍl����M�f�����L�͂ł������B
�@
1820�N��ɂȂ�ƁA�J���m�[���M�@�ւ̉Ȋw�I������ړI�Ƃ��ĉ��z�M�@��(�J���m�[�T�C�N��)�ɂ�錤�����s���A�����ɖ{�i�I�ȔM�͊w�̌������n�܂����B���̌������ʂ͔M�͊w���@���ƃG���g���s�[�T�O�̏d�v��������������̂ł��������A�J���m�[�͔M�f���ɑ���ꂽ�܂ܑ������A�d�v�����F�������ɂ͂���Ɏ��Ԃ����������B
�@
�Ȃ��������t�[���G���M�`���̌����\�������A����͔M�͊w�Ƃ͒��ڊW�Ȃ��A�ނ��땨�����w�Ɍ����Ȑ���(�t�[���G�ϊ��ɂȂ���)���c�����ƂƂȂ����B
�@
�M���G�l���M�[�̈�`�Ԃƍl���G�l���M�[�ۑ��̖@��(�܂�M�͊w���@��)���͂��߂Ē����̂̓}�C���[�ł���B�ނ�1842�N�ɂ���\�������S�����ڂ���Ȃ������B�������قړ������ɃW���[�����s�������l�̌����̓g���\��(�P�����B����)�̒m��Ƃ���ƂȂ�A�ނ�̋�������������@�������炩�ɂ��ꂽ�B
�@
����Ƀg���\���̓J���m�[�̌�����m��A��Ή��x�̊T�O����єM�͊w���@���ɓ��B�����B�N���E�W�E�X���Ɨ��ɑ�ꂨ��ё��@���ɓ��B���A�J���m�[�T�C�N���̐��w�I��͂���G���g���s�[�T�O�̏d�v���𖾂炩�ɂ���(�G���g���s�[�̖������N���E�W�E�X�ɂ��)�B��������1850�N��ɂ͗��@�����m�����ꂽ�B
�@
19���I�㔼�ɂȂ�ƁA�w�����z���c�ɂ���Ď��R�G�l���M�[���A�܂��M�u�Y�ɂ���ĉ��w�|�e���V��������������A���w���t�Ȃǂ��܂ލL���͈͂̌��ۂ�M�͊w�Ř_���邱�Ƃ��\�ɂȂ����B
�@
����A�{���c�}����}�N�X�E�F���ɂ���đn�n���ꂽ���v�͊w�����W���A�M�͊w�I���T�O�q�_�����̓I�ɉ��߂ł���悤�ɂȂ��āA�M�͊w�Ɠ��v�͊w�͎Ԃ̗��ւ̂悤�ɂ��Ĕ��W���Ă������B
�@
1999�N�ɃG���I�b�g�E���[�u�ƃ��R�u�E�C���O���@�\���́A�u�f�M�I���B�\���v�Ƃ����T�O�����ĔM�͊w���č\�z�����B�u���Y�����X����f�M����œ��B�\�ł���v���Ƃ��ƕ\�L���A���́u�v�̐�������G���g���s�[�̑��݂ƈ�Ӑ����������B ���̌����I�Ɋ�b�t�����ꂽ�M�͊w�ɂ���āA�N���E�W�E�X�̕��@�ŗp�����Ă����u�M���E�₽���v�u�M�v�̂悤�Ȓ����I�Ŗ���`�ȊT�O����b����r�������B���x�͖���`�ȗʂł͂Ȃ��G���g���s�[���瓱�o�����B ���̃��[�u�ƃC���O���@�\���ɂ��č\�z�ȗ��A���ɂ��M�͊w���č\�z���鎎�݂��������s���Ă���B
�@
���M�͊w�̗l�X�ȕ��@
�@
�M�͊w�ɂ͗l�X�ȃX�^�C��������D�������e�̔M�͊w��̂ɁA���_�̏o���n�_�ƂȂ錴��(�v��)�ɂ͗l�X�ȑI�ѕ�������A�Ⴆ�Α����̔M�͊w�ł́C�M�͊w�̖@�����ł���{�I�Ȍ����Ƃ��č̗p���Ă���A���������̗v����I��ŔM�͊w��W�J���Ă����X�^�C��������B
�@
����ɔM�͊w�ŗp����}�N���ϐ��ɂ͎��ʐ��Ǝ�������2��ނ�����A�o���_�ł̃}�N���ϐ��̑I�ѕ����l�X�ł���A�ȉ��ł͔M�͊w�̗l�X�ȃX�^�C���ނ��Ă݂�B
�@
�����̃~�N���ȕ����w�Ƃ̊W
�@
�ÓT�͊w�Ȃǂ̃~�N���n�̕����w�̒m����p������@
�@
�~�N���n�̕����w�̒m����p�����A�M�͊w�����ŕ������_�̌n�Ƃ��Ę_������@
�@
����{�I�ȕϐ��̑I�ѕ�
�@
���ʐ���ԗʂ�������{�I�ȕϐ��ɑI��Ř_���W�J���Ă������@
�@
��{�I�ȕϐ��̈ꕔ���A���x�Ȃǂ̎������ɂ��������ĔM�͊w��W�J���Ă������@
�@
�����̔M�͊w�ł͉��x�A���́A�̐ρA�����ʂ���{�I�ȕϐ��Ƃ��ďo���_�ɗp���Ă���B���������ɂ��G���g���s�[�Ȃǂ��o���_�ɗp���āA���x�∳�͂͗p���Ȃ��X�^�C��������B
�@
���M�͊w�̖@��
�@
1. �M�͊w���@�� / ����A��B�AB��C�����ꂼ��M���t�Ȃ�AA��C���M���t�ɂ���B
�@
2. �M�͊w���@��(�G�l���M�[�ۑ���) / �n(���n)�̓����G�l���M�[U�̕ω�dU�́A�O�E����n�ɓ������M�ƊO�E����n�ɑ��čs��ꂽ�d���̘a�ɓ������B����Ɉ�ʂɁA�O�E�ƕ���������������n(�J���n)�ł́A�O�E����n�ɕ������������邱�Ƃɂ��n�̃G�l���M�[�̑����ʂ�����邱�ƂɂȂ�B
�@
3. �M�͊w���@�� / 1. �M��ቷ�̕��̂��獂���̕��̂ֈړ������A����ȊO�ɉ��̕ω����N�����Ȃ��悤�ȉߒ��͎����s�\�ł���B(�N���E�W�E�X�̌���) / 2. ���x�̈�l�Ȉ�̕��̂��������M��S�Ďd���ɕϊ����A����ȊO�ɉ��̕ω����N�����Ȃ��悤�ȉߒ��͎����s�\�ł���B(�g���\��(�P�����B��)�̌���) / 3.�@����i�v�@�ւ͎����s�\�ł���B(�I�X�g���@���g�̌���) 1.�����ɂ͑�O�@��(��Η�x�̓��B�s�\)���K�v�B���@���͑���i�v�@�ւ��������邽�߂ɂ͒ቷ�M������Η�x�ł���K�v������Əq�ׂĂ��邾���ŁA����i�v�@�ւ������s�\�Ƃ܂ł͌����Ă��Ȃ��B / 4. �f�M�n�ŕs�t�ω����N����Ƃ��A�G���g���s�[�͕K����������B�t�I�ȕω��ł̓G���g���s�[�̑����̓[���ƂȂ�B(�G���g���s�[����̌����E�N���E�W�E�X�̕s����)
�@
4. �M�͊w��O�@�� / ��Η�x�ŃG���g���s�[�̓[���ɂȂ�B(�l�����X�g�E�v�����N�̌���)
�@
���@���y�ё��@���́A���h���t�E�N���E�W�E�X�ɂ���Ē莮�����ꂽ�B�@ |
���{�C���E�V�������̖@��
�@
����ԕ�����
�@
�܂��́u��ԕ������v����b���n�߂悤�B
�@
���Z�Ŋw�Ԃ��ƂȂ̂ŕ��K�����˂Ă��̕ӂ肩��n�߂�̂��������낤�B�@���̎��̓{�C���̖@���ƃV�������̖@����g�ݍ��킹�邱�Ƃœ�����B�@�ǂ��܂ł��{�C���̖@���ŁA�V�������̖@���������������Ȃ�Ă͎̂��͂���܂ŋC�ɂ������Ƃ��Ȃ��B�@�Ȋw�j�ɂ͋������Ȃ���������B�@���ʂ������S�Ăł����āA���������l�̌l�I�Ȏ����Ȃǂ͂ǂ��ł������Ǝv���Ă����B
�@
�������^�̗����̂��߂ɂ́A���������̔w�i�ɂǂ�Ȃ��Ƃ��������̂���m��Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ�����B�@�����Ƃ͐ςݏd�˂ł����āA���������ɂ��Ă��̌��ʂ��o�����Ƃɐ��������̂��A�Ƃ�������������ł��邱�Ƃ��厖�Ȃ̂��B
�@
���̎��̒��� �̓�������\���B�@�����̗ʂ������قǑ̐ς�������͓̂��R���B�@����A�{�����H�@����ꏏ�ɂ����班���k�ނ����m��Ȃ�����Ȃ����B�@���ہA����ȉ��w�ω�������B�@���������w�ω��ɂ��Ă͍l���Ȃ����Ƃɂ��悤�B�@����ɗʂ𑝂₵�Ă��k�܂Ȃ����Ƃ͎����Ŋm���߂��Ƃ������ƂŔ[�����Ă��炨���B
�@
����A�ʂ̌����������Ă��������������ȁB�@���ꂩ��͂��̎��ɏ]���悤�ȋC�̂ɂ��Ă̂ݍl���邱�Ƃɂ���̂��B�@���̂悤�ȋC�̂��u���z�C�́v�ƌĂԁB�@��������ɂ͂���Ȃ��̂͑��݂��Ȃ��B�@�����̋C�̂͂��̎��ɂ����悻�]���̂����A�F�X�Ȍ����������Ă��̎�����͂ق�̏������������̂��B�@���������������炢������Ȃ����B�@�ׂ������Ƃ��C�ɂ��Ă��肢��Ɛ�i�߂Ȃ��B����錴���Ȃ͖{���ɑ�Ȃ��Ƃ�����������ōl��������̂��B
�@
�N���H�@�u�Ȋw�Ȃ�ď��F���z����ŁA�����ɂ͉��̖��ɂ������Ȃ��v�Ȃ�Ďq�����݂�����������Ă�̂́H�@���܂Ɉ̂����ɂ����������Ƃ������l�ɏo���킷�̂����A�����Ȃ艽�������o����ȂǂƊ��҂�������ǂ������Ă���B�@���w�⍂�Z�ŏK���͈͂ł͂܂���b�����w��łȂ��̂����瓖�R���낤�B�@������������炢�Ȃ�����ƉȊw�������̖��ɗ����̂ƂȂ�悤�ɉ��ǂɋ��͂��ė~�������̂��B
�@
��ԕ������̐����ɖ߂낤�B�@���̎��̒��� �́u�C�̒萔�v�ƌĂ����̂��B�@���������̐ς�牷�x���A�l�Ԃ̍D������Ɍ��߂��P�ʂŕ\�����ʂ̊Ԃ̊W�����т��Ď������̂�����A���R���덇�킹�̂��߂̐������K�v�ɂȂ�B�@���l���̂��̂ɏd�v�ȈӖ����B����Ă���킯�ł͂Ȃ��������̖��ɗ������m��Ȃ��̂ňꉞ�����Ă����B
�@
���x �́u��Ή��x�v���g���B�@�V�����������C�̂̉��x�Ƒ̐ς̊W�ׂĂ����Ƃ���A���x���Ⴍ�Ȃ�قǑ̐ς����邱�Ƃ����������B�@���̊W���O���t�ɂ���ƒ����ɂȂ��Ă���A���̂܂܂��[���Ɨ�₵�Ă����ƂЂ���Ƃ��đ̐ς� 0 �ɂȂ��Ă��܂��Ƃ��낪����̂ł͂Ȃ����ƍl������B�@���̉��x���u��Η�x�v�ƌĂԁB�@�������� -273 �� �t�߂��B�@1787 �N�̂��ƂȂ̂ł܂�����ȒႢ���x�����o���Z�p�͂Ȃ����A���̉��x����ɂ������x���g���A�̐ςƉ��x����Ⴗ��Ƃ����@�����o���オ�邾�낤�B�@���ꂪ�u��Ή��x�v�ł���P�ʂ� K(�P���r��)���g���B�@�܂�A0 �� ���� 273 K�A100 �� ���� 373 K ���B
�@
�u��Η�x�v�̑��݂͔ނ�萔�\�N���O�ɂƂ����ɗ\�z�͂���Ă����킯�ŁA�V���������̎d���Ƃ��ẮA���W�����o�������ƁA�ǂ�ȋC�̂ɑ��Ă������W�����悻���藧���Ƃ��������Ƃ��V���������킯���B�@�����A�����܂ł̘b�Łu�V�������̖@���v����ەt�������낤�B
�@
�����q�^���_�ɂ���
�@
�Ƃ���ł��̎�����A���͈��̎��ɉ��x�� 2 �{�ɂȂ�Ƒ̐ς� 2 �{�ɂȂ�Ƃ��A���x�����̎��Ɉ��͂� 2 �{�ɂ���Ƒ̐ς������ɂȂ�Ƃ���������������̂����A�Ȃ������Ȃ�̂��A�Ȃ�Ď��������Ɛ����ł��邾�낤���H
�@
��������k�ނ͓̂�����O���Ɗ����邩���m��Ȃ����A����͂���قǓ�����O�̂��Ƃł͂Ȃ��B�@���͂Ƒ̐ς͔���Ⴗ��B�@�Ȃ��P�Ȃ锽���ł����āA2 ��ɔ����Ƃ��ł͂Ȃ��̂��낤�B�@�b���x�ꂽ���A���ꂪ�u�{�C���̖@���v�ł���B
�@
�����͌��q�╪�q�ȂǂƂ����l���͈�ʓI�ł͂Ȃ������̂ł��̂��Ƃ��������͓̂���������낤���A���ł͂����Ɛ��������Ă���B�@�����������ł͂����������Ƃɂ��Ă̐����͂��Ȃ��B�@�Ȃ��Ȃ�A ����Ȃ��Ƃ͒m��Ȃ��Ă��M�͊w�̊�b���w�ԏ�ʼn���x�Ⴊ�Ȃ����炾�B
�@
�M�͊w�ł͋C�̂������̕��q����o���Ă���Ƃ����O�Ȃ��Ă��_�����i�߂���̂ł���B�@���̂��Ƃ��ǂ������ł���悤�ɁA�����ĕ��q�^���ɂ��Ă͐G��Ȃ��܂܂Ő����𑱂��悤�B�@�܂��A�킴�킴�Â��T�O�ɌŎ�����K�v���Ȃ��̂ŁA�����������̂��߂ɏ������炢�͐G��邱�Ƃ����邾�낤���A�_���ɂ͏悹�Ȃ����肾�B
�@
�u�C�̕��q�^���_�v�Ɋ�Â������́A�{������͓��v�͊w�̍l�����ł���̂ŁA�u���v�͊w�v�̃y�[�W�ł�邱�Ƃɂ��悤�B�@�ŋ߂́u�M�͊w�v�Ɓu���v�͊w�v�̋��ڂ��ڂ₯�Ă��Ă���A�M�͊w�̋��ȏ��ɂ������Ȃ�u�C�̕��q�^���_�v����������Ă�����A���߂���u�M���v�͊w�v���邢�́u���v�M�͊w�v�Ȃ�ċ�ɓ���܂Ƃ߂Đ��������肷�邱�Ƃ������Ă���B�@������������������x�ɋl�ߍ��ނƁA���������ɂǂ̊T�O���ǂ����������œ����ꂽ�̂��Ƃ����_���̗��ꂪ�����ɂ����Ȃ��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƐS�z���Ă���B
�@
�����ŏ��X�ÏL���̂����A���̉���ł͂���ȋ�ɂ��āu�M�͊w�v�Ɓu���v�͊w�v�̎v�z�̈Ⴂ�m�ɋ�ʂ��邱�Ƃɂ��悤�B�@���̕������p�ȍ����������Ȃ��čςނƎv���B
�@
�����x�Ƃ͉���
�@
�Ƃ���ŁA�����������x���ĉ����낤�H�@�������₽���͎�̊��o�ŕ����邪�A����𐔒l�����ēǂނ��߂ɂ͉��x�v���g�����킯���B�@���x�v�Ƃ����̂͋C�̂�t�̂̉��x�ɂ��̐ϖc���𗘗p���Ă���̂ł���B�@�̐ς̕ω������x�Ƃ��ēǂ�ł���̂�����A���x�Ƒ̐ς����W�ɂ���̂͂���Ӗ�������O���ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
���F�@�����̎���ɂ͋�C���x�v�Ȃ���̂��g���Ă����B�@��C�̔M�c���𗘗p���ăK���X�ǂ̒��̐��ʂ�ǂނ��̂ł���B�@�܂��C�̂قǑ傫�ȕω��ł͂Ȃ����A�t�̂ɂ����x�ɔ�Ⴕ���̐ϕω�������̂ŃA���R�[�����x�v�A���≷�x�v�Ȃǂ������̖ڐ���œ����悤�Ɏg�����킯���B�@�ނ���t�̉��x�v�̕������^���ł���̂ŕ֗��ł���B�@�܂������̉t�̂͐l�Ԃ̐������ł͓���Ȃ��Ƃ������_������B�@�ł��g�߂ȉt�̂ł��鐅�ɂ��Ă͗�O�ł���A4���ő̐ς��ŏ��ƂȂ�Ƃ������ʂȐ��������邽�߂ɁA�̐ςƉ��x�̃O���t�������Ɣ��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B
�@
�Ђ���Ƃ���Ɖ��x�̖{���ɊW��������ƕʂ̉����������āA���̗ʂƋC�̂̑̐ς̊Ԃɂ͔��W�����藧���Ă��Ȃ������m��Ȃ��B�@����ǂ��납�A���X�ŕω������ς��悤�ȂЂǂ����G�ȊW�ɂȂ��Ă��邩���m��Ȃ��B�@����ł����̂悤�ɂ��ċC�̂̑̐ς���ɂ��ĉ��x�𑪂��Ă������́A����Ȃ��Ƃɂ͌����ċC�t���Ȃ����ƂɂȂ�B
�@
����ƃV���������̂�������Ƃ͏����l����Ε�����悤�Ȕn���������������̂��낤���H�@���₢�␔�S�N�O�̐l���������č��̖}�l���͗y���Ɍ����B�@���ꂭ�炢�̂��Ƃ͓����̐l�����ē��R�C�t���Ă������낤�B�@����ăV���������̋Ɛт��]�����ꂽ�̂́u���W�v�����o�������Ƃɂ��̂ł͂Ȃ��āA�ǂ�ȋC�̂��g���Ă������W�����藧���Ă��邱�Ƃ����o�����Ƃ����Ƃ���ɂ�������̂��낤�B
�@
�C�̂̎�ނɂ���đ̐ϕω����o���o����������A�ǂ̋C�̂̑̐ϕω������x�̊�Ɏg�����炢�����낤���Ƃ����s�����N����Ƃ��낾���A�ǂ�ȋC�̂ɂ��Ă���������������Ƃ����̂ł��̕s���͂��Ȃ�y�������ɈႢ�Ȃ��B�@�܂��A�C�̂̑̐ςƁA���x�̖{����\���ʂƂ̊ԂɁA���Ȃ�P���ȊW�����邱�Ƃ����҂ł��������B
�@
�ł́A���x�̖{���Ƃ͉��Ȃ̂��B�@���̂܂ܕ����̑̐ςɗ���悤�ȉ��x�̒�`���g���Ă��Ė�肪�N���邱�Ƃ͂Ȃ��̂��낤���H�@�ʂ̐M���ł����`�����o���Ȃ�����A����ς�s���Ŏd���Ȃ��B�@���������炭�͂��̕s����w�������܂܂ʼn䖝���ė~�����B�@���ꂪ�M�͊w�Ƃ������̂��B�@ |
�������ς̕ϑJ
�@
���l�������ƌ��q�_
�@
�u�����Ƃ͉����v�Ƃ����₢�ɑ��āA�M���V�A����ɓ�̈قȂ�����������o���ꂽ�B��̓A���X�g�e���X(�O�O���l�|�O���)�ɂ���ďW�听����A�M���V�A�̎��R�N�w�ɂ����Ďx�z�I�ƂȂ����u�l�������v�ł���B������̓M���V�A����ɂْ͈[�I�ȍl�����Ƃ��ꂽ���\�����I�ɕ������A����̕����ςɂ��ʂ��Ă���u���q�_�v�ł���B
�@
�u�����̍����͐��ł���v�Ƙ_�����̂̓^�[���X(�O�ܔ��������N)�ł��邪�A�������A�i�N�V���l�X(�H�|�O�ܓ�Z��)�͋�C�A�w���N���C�g�X(�O�l�����|�H)�͉����ꂼ��n�������ł���Ƃ����B�����������_�c���ăG���y�h�N���X(�O�l��O�|�l�O�O��)�́u�y�A���A��C�A�v�̎l���n�������ł���Ƙ_�����B���Ȃ킿�A�����͂��̎l�̕��������܂��܂Ȋ������ō�������Đ����Ă���Ƃ����̂ł���B����ɃA���X�g�e���X�́A�����Ƃ��Ắu��́v�Ɂu���|��v�A�u���|���v�Ƃ������Η�����l�̐������t�^����邱�Ƃɂ���Ďl�̌��������o����Ƃ����B���������āA�����ɂ����A���X�g�e���X�̍l���́u�ꌴ���A�l�������v�ƌĂԂׂ���������Ȃ�(����z��Y�w�����ߑ�Ȋw�|�|���̎��R�ς̗��j�ƍ\���x�V�j�ЁA��㎵��N�B���ɑ�5�́u�����ς̓]���v�Q��)�B
�@
���āA�A���X�g�e���X�ɂ��A�l�����Ǝl�����Ƃ͐}�|1�Ɏ������悤�ȊW�ɂ���B���Ȃ킿�A�y�́u���|��v�A���́u��|���v�A��C�́u���|���v�A�́u���|���v�̐��������ꂼ������Ă���B�܂��A�y�Ɛ��́u�d���v�̐���������(�y�͐����d��)�A��C�Ɖ́u�y���v�̐���������(�͋�C�����y��)�Ƃ��ꂽ�B���̂��߁A�y�Ɛ��͎���̐����ɉ����ĉ��~�^�����A�t�ɁA��C�Ɖ͏㏸�^������̂ł���B
�@
����̍��x�ɐ������ꂽ�����ς����L���Ă���ł��낤�ǎ҂ɂ́A��L�̂悤�ȃM���V�A�̕����ς́A�����ɂ��e�G�ȁA����ɂ����r�����m�ȕ����ς̂悤�ɉf�邩������Ȃ��B�������A�����Ă����ł͂Ȃ��B�A���X�g�e���X�̕����ς́A����ꂪ����I�Ɋώ@���邱�Ƃ̂ł��镨���̕ω���^�������ɍI�݂ɐ������Ă����̂ł���B
�@
���Ƃ��A�y�͎�𗣂��Ɨ������邵�A���͒Ⴂ���ւƗ����B����A�����̍ۂɊώ@�����悤�ɁA��C���(��)�͐����悭�㏸����B�܂��A�u��|���v�̐��������������߂Ă݂悤�B�}�|1�ɂ��A���́u���|���v�̐���������C�ɂȂ�B����͐���M�����C(�����̌������ł́A�����C)�ɂȂ�Ƃ����g�߂Ȍo���������ɐ������Ă����B���l�̂��Ƃ����̌����A�����ɂ��Ă�������킯�ŁA�l�����́A�l������ω������邱�Ƃɂ���đ��݂ɓ]���\�Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA���̗��_�ɂ���āA���R�E�ɐ����Ă��鑽�ʂȕ����ω����̌n�I�ɐ����\�ƂȂ����̂ł���B
�@
����ǂ��납�A���������ݓ]���\���Ƃ������Ƃ́A�H�v����ł́A�l�ԂɂƂ��ėL�p�ŋM�d�ȕ����A���Ƃ�����s�V�s���̖�����o�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B�Ñ�G�W�v�g�ȗ��̗��j�����B���p(Alchemy)���A���X�g�e���X�̕����ςɂ��̂��ǂ���������o�����̂����R�Ƃ����悤�B
�@
����A���A��A���A���ȂǂƂ������l�Ԃ̊��o�m�o�͑��ΓI�ł���ӂ�Ȃ��̂ƍl���A���̂悤�Ȃ��̂Ɋ�b�����������ςɖO������Ȃ��l�X�������B���Ƃ��A�f���N���g�X(�O�l�Z�����|�O������)�������ŁA�ނ͑��l�ȕ����̍���ɂ́A����ȏ㕪���ł��Ȃ����ɂ̗��q�����q( atom �Ƃ́A�����s�\�Ƃ����Ӗ�)�������āA���̌��q�̑g�ݍ��킹�̌��ʂƂ��āA�O�q�̎l�����͂��Ƃ��A�ł��A�_�炩���A�����A�����A�Â��A�h�����̎�X�̐��������������������݂��Ă���ƍl�����B�������A���q�͗����ɂ���Ă̂ݑz�肷�邱�Ƃ��ł��A���o�ɂ���ĂƂ炦�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
���q�_�ɂ��A���q�͋�(�^��)�̒����щ���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A���q�ƌ��q�̊Ԃɂ͉����Ȃ���Ԃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ł���(�����A���q�ƌ��q�̊Ԃɕ��������݂���A����ɕ����\�ƂȂ邩��)�B���̂��߁A���q�_�͘_���I�ɐ^��̑��݂�O��Ƃ��Ă���B���̓_�ł����q�_�́A��(����)�̑��݂͔F�߂�Ȃ��Ƃ������ꂩ��A�u���R�͐^�����������v�Ƃ����A���X�g�e���X�ƍD�ΏƂ��Ȃ��Ă���B
�@
�^�����ɗ��q�Ƃ��Ă̌��q����щ���Ă���A�X�����ۂ͂��̌���ɂ����Ȃ��Ƃ��錴�q�_�̍l�����́A����߂ėB���_�I�����_�_�I�ł���A���̂��߃M���V�A�̎��R�N�w�łْ͈[�ɂƂǂ܂炴������Ȃ������B
�@
���B���p
�@
�×��̘B���p�́A�A���X�g�e���X�̕����ςɂ���ė��_�I�E�N�w�I��b��^�����A�A���r�A���E�ł���ɔ��W������ꂽ�B����ɁA�\��|�I�ɂ����ẴA���r�A���E�ƃ��e�����E�Ƃ̐ڐG��ʂ��Ē������[���b�p�ł�����������߂��B�����Ƃ��A�Ñ�E�����ɂ�����B���p�́A�����ϊ���ʂ��ċ�����鑀��ɂƂǂ܂炸�A���_�ϊ��̗��_�Ƃ��Ă̐��i�����킹�����Ă������Ƃɒ��ӂ��˂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�Ñ�E�����ɂ����Ă͕����Ɛ��_(��)�͏ے��I�Ȍ��т��������Ă���A���ւ̓]���͍��̏����ł��������̂ł���B
�@
���āA�B���p�ŏd�����ꂽ�����́A�����A����A����ɉ��ł������B�����O��̕����́A�Ɠ��̐F�������A���̕����Ɖ������₷���Ƃ��������������Ă���B���̌��ʁA���܂��܂ȑ���̉ߒ��ŁA�ꌩ�A���Ɏ����������������ꂽ���Ƃ��O��̕������B���p�ŏd�p���ꂽ���R�ł��낤�B�������A�����O��̕����ɁA���邢�͑��̕����ɁA�����Ȃ鑀��������悤�ƁA��(��s�V�s���̖�)���ł���킯���Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A�B���p�͋ߑ�Ȋw�ȑO�̂�����̂ɈႢ�Ȃ��B�������A���w(Chemistry)���B���p�ƌꌹ�������Ă��邱�Ƃɂ݂���悤�ɁA�����̐����Ɋւ���c��Ȍo���I�m���̒~�ρA�������̉���(�}2�Q��)�A�܂������������̏d���Ƃ������_�ŁA�B���p�͋ߑ�Ȋw�̌���̈�������̂ł���B
�@
���Ȋw�v���̎���
�@
�\�����I�́u�Ȋw�v���v�̎���Ƃ�����B�R�y���j�N�X(��l���O�|��l�O)�A�P�v���[(�����|��Z�O��)�A�K�����I(��ܘZ�l�|��Z�l��)�A�f�J���g(��܋�Z�|��Z�܁�)��̌����܂��āA�ŏI�I�ɂ̓j���[�g��(��Z�l��|�ꎵ��)���V��̗͊w(�f���^��)�ƒn��̗͊w(�����S�̗���)��I�ɐ������邱�Ƃɐ�����������ł���B���̎���A�����ςɂ����Ă��傫�ȓ]�����������B
�@
�K�b�T���f�B(��܋��|��Z�܌�)�̓f���N���g�X���̌��q�_�������A�g���`�F��(��Z�����|��Z�l��)�͐^��̑��݂������I�ɖ��炩�ɂ����B���̂悤�ȋc�_��O��ɂ��āA�{�C��(��Z�|��Z���)�́A��Z�Z��N�́w���^�I���w�ҁx�ɂ���āA�ߑ�Ȋw�̈ꕔ�Ƃ��Ẳ��w�̊�b��z�����B
�@
�{�C���ɂ��A�����͊��m�ł��Ȃ��قǏ������A���ۏ㕪�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������q(�M�S�ȃL���X�g���k�ł������{�C���́A���\�̐_�̗͂ɂ�镪���\���̗]�n���c���Ă���)���琬���Ă���A�����̗��q(���q)�A����ї��q�̌�����������(���q)�̔z���^���̌��ʂ������̐����Ƃ��̕ω��ɑ��Ȃ�Ȃ��B����ɁA�{�C���͋���(���Ƃ���)���������ł͂Ȃ��A�P��̌��q���琬�鏃���ȕ����A���Ȃ킿�P��(���f)�ł���Ƙ_���āA�B���p�������I�ɕs�\�ł��邱�Ƃ��������B�����āA�{�C���̕������_�́A�j���[�g���̗͊w�̌n�ƂƂ��ɁA���R�E������Ő����ȋ@�B�d�|���Ƃ݂Ȃ��@�B�_�I���E���̈ꗃ��S�����̂ł������B
�@
���̎����A���[���b�p�ł́A���{��`�̔��B�ɔ����āA�o�ϓI�E�����I��̂Ƃ��Ắu�l(individual)�v(�����s�\�Ƃ����Ӗ�)���o�ꂵ���������Ƃ�z�N����̂́A���R�ρE�����ςƎЉ�ρE�l�Ԋς̑��ւƂ����_�ŋ����[��(�e�E�{���P�i�E�A���c�m����w�����I���E������s���I���E���ցx�݂������[�A���Z�ܔN�A�Q��)�B
�@
���t���M�X�g���A�J�����b�N�A�G�[�e��
�@
�\�����I�Ɋm�����ꂽ�ߑ�I�����ς��猻��̕����ςɎ���ߒ��ɂ́A�t���M�X�g���A�J�����b�N(�M�f)����уG�[�e���Ƃ����O�̉��z�������߂��_�c��������(���J�O�j�u����̕����ρv�A�w����̗��_�I�����x��g���X�A���Z���N�����A�Q��)�B
�@
�V���^�[��(��Z�Z���|�ꎵ�O�l)�́A�R���̕����̓t���M�X�g��(�R�f)�Ƃ������f���܂�ł���Ƃ̉���������B�R�Ă̍ہA���̕�������t���M�X�g���������o���Ƃ����̂ł���B���̗��_�́A�R�Č��ۂ�I�ɐ������Ă����Ƃ����_�ʼn���I�Ȃ��̂ł������B�������A��������C���ŔM�����ꍇ�A�����D�����Ƃ̋������d���Ȃ�Ƃ���������������邽�߂ɂ́A�t���M�X�g���͕��̎���(�y��)�����Ƃ��˂Ȃ�Ȃ������B���̖��������������̂������H�A�W�F(�ꎵ�l�O�|�ꎵ��l)�̎_�f���_�ł���B�ނ́A��C����5����1�̐������A�R�Ă̍ۂɕ����ɌŒ肳��邱�ƁA�܂����̐����������̌ċz�ɕs���Ȃ��Ƃ𖾂炩�ɂ��A������_�f�Ɩ��������̂ł���(�}�|3�Q��)�B
�@
�\�����I������\�㐢�I�ɂ����āA�����H�A�W�F���܂ޑ����̉Ȋw�҂́A�M���ۂ͓��ʂ̕����I���̂Ƃ��ẴJ�����b�N(�M�f)�ɂ��ƍl���Ă���(�M������)�B���ہA�����H�A�W�F�͌��f�\�ɃJ�����b�N���f���Ă���B����A�����t�H�[�h(�ꎵ�O�|�ꔪ��l)��́A�C�g�̐���̍ہA��ʂ̔M���������邱�ƂȂǂ������ɔM�^�������������B�M����������M�^�����ւ̓]���͕K�������e�Ղł͂Ȃ��������A�M�ʂł͂Ȃ��A�G�l���M�[���ۑ������Ƃ����G�l���M�[�ۑ���(�M�͊w���@��)�̊m���Ƃ��ɁA�J�����b�N�͂悤�₭���̗��j�I�������I�����B
�@
�×��A�y�A���A��C�A�̎l�����Ƃ͕ʂɁA�V��E(�������̐��E)���\�������܌��f�Ƃ��āu�G�[�e���v�Ȃ���̂��z�肳��Ă����B�G�[�e���T�O�́A�ߑ�Ȋw�̊m���ȍ~���������сA�\�㐢�I�ɂ͌�(�d���g)�̔}�̂Ƃ��ĐV���Ȗ�����^����ꂽ�B�������A�G�[�e���ɑ���n���̑��Ή^�������o���悤�Ƃ����}�C�P���\���|���[���̎���(�ꔪ����)�̔ے�I���ʂ��߂���_�c�̖��A�G�[�e���̑��݂�s�v�Ƃ���A�C���V���^�C��(�ꔪ����|���܌�)�̑��ΐ����_�̒�o(��せ��)�ɂ���āA�G�[�e�������̒������j�ɖ�������B
�@
���̂悤�ɁA�t���M�X�g���A�J�����b�N�A�G�[�e���Ƃ��������z�����́A�����Ƃ͉������߂���_�c�̒��ł��ꂼ��d�v�Ȗ������ʂ����Ă����̂����A����̕����ςɎ���ߒ��Ŕp�����ꂽ�̂ł������B
�@
������̕�����
�@
���I�����܂łɌ×��̕����ς����S�ɕ��@�������R�Ȋw�́A���q�����w��ʎq�͊w�̔��W�̒��ŁA���������̋��ɂ̃��x���܂Ŏ����I�E���_�I�ɉ𖾂��邱�Ƃɐ��������B(���̋�̓I�Ȑ��ʂɂ��ẮA���Ƃ��A�D�����m�E���쐳�`�E������O���Ғ��w�����͐����Ă���|�|����̕����ρx�����o�ŁA����ܔN�A�Q�ƁB)
�@
���āA��������݂�Ί�ȕ����ςɈˋ����A�B���p�ɂ���������Ñ�E�����̐l�X�Ƃ���ꌻ��l�́A�S���قȂ��������ς������Ă���Ƃ����邾�낤���B�ނ���A���ʂ��镔�����傫���̂ł͂���܂����B�Ȃ��Ȃ�A�����̍\����������q�E���q���x���ʼn𖾂�������Ȋw�́A�B���p�҂������]���Ȃ����Ȃ��������Ƃ��\�ɂ����Ƃ������邩��ł���B��������A�������v���̂܂܂ɕ����E�������邱�Ƃɂ���ėL�p�ȕ�������肾���Ă��錻��̉Ȋw�Z�p�҂����́A�u�m�͗͂Ȃ�v�u���R�͕��]����x�z�����v�Ƙ_���ċߑ�I�w��ς̑n�n�҂ɂ��čŌ�̘B���p�t�Ƃ��̂����x�[�R��(��ܘZ��|��Z��Z)�̎q���B�Ƃ����邩��ł���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���}���u�O���f�Ղɂ��C���O�����h�̍���v���� 1664�N |
   �@
�@
|
Mun, Thomas.(1571-1641)
�@
England's Treasure by forraign trade. or the ballance of our forraign trade is the rule of our treasure.
�@
�g�[�}�X�E�}���́A�C�M���X�̏d����`�ҁB���ߖf�Ղɏ]�����A���C���h��Ђ̗����ƂȂ�A�f�ՂɊւ����u�ψ���ψ��ƂȂ�B���C���h��Ђ́A�����ѐD�����̃C�M���X�̍H�Ɛ��i��A�o���A����ƈ����ւ��ɍ������̓��m�̕��Y��A������ړI�Őݗ����ꂽ���̂ł��邪�A���C���h�ɂ̓C�M���X�H�Ɛ��i�ɑ���w���͂��Ȃ������B���������Ėf�ՐԎ��ɂ��C�M���X�̋��E��E�M���������o�����B���̏��́A�����̓��C���h�f�Ղɑ��鐢�_�̔ᔻ�ɑ��A���C���h��Ђ̗�����ق��邽�߂ɏ����ꂽ���̂ł���A�u�킪���̖f�Ս��z���A�킪���̍���̊�ł���v�Ƃ��A�f�Ս��z����W�J�����B�{���́A�}���̖v��⎙�ɂ���ďo�ł���A�d����`�̑�\�҂Ƃ��Ă̔ނ̖���s���Ȃ��̂Ƃ����B�@ |
�}���w�O���f�Ղɂ��C���O�����h�̍���A���Ȃ킿�킪���̊O���f�Ղ̍��z���킪���̍���Ɋւ���@���ł���x
�@
MUN, T., England's Treasure by Forraign Trade. or, The Ballance of our Forraign Trade is the Rule of our Treasure. , London, Printed by F. G. for Thomas Clark, and are to be sold at his shop at the south entrance of Royal Exchange, 1664, ppiv+220+ads., 16mo
�@
����(1571-1642)�́A�����h���̌��D���f�Տ��̂R�j�Ƃ��Đ��܂��B��N�n���C�f�Ղɏ]�����A�����C�^���A�ɒ��݁B���̌ネ���h���ɗ����������x��ςށA���C���h��Ђ̗����ɂ��A�����B�d����`�̏����̒��҂ɂ́A�`���C���h�A�f�b�J�[�����C���h��ЊW�҂��������A�u�}�������ɉ�����_�q�̘_�c�́A���̌l�I�n�ʂɗR��ē�������鏊�����B�v�ł���B
�@
���̂��݁A�嗤�̉ݕ����l�؉������̌����ɂ��ѐD���𒆐S�Ƃ���A�o����N��A�����Y�Ƃ̕s���A�ݕ��s�����������B�c��ł��A�����̌�������荹�����ꂽ���A�ݕ��s���̌����̈�Ƃ��ꂽ�̂��A���C���h��Ђɂ��ݕ��A�o�ł������B�}����1621�N�Ɂw���C���h�f�_�x���o�ł����̂́A���C���h�f�Ղ̂��߂̋�(���ۂ́A���A�����̊O���ʉ�)�A�o��i�삷�邽�߂ł������B���́w�f�_�x�㈲����_�@�ƂȂ�A�}���[���ƃ~�b�Z���f���Ƃ̊Ԃɘ_�����N��B���҂́A�ݕ��s���̌�������n�܂�O���בւ̋@�\�ɂ܂łɓ��e���g��A�������Œ��������s(1622-3)���邱�Ƃɂ��A���V���d�˂��B�{���w����x�́A���̘_���܂��Ē�����Ă���B���s�́A���q�̃W�����E�}���ɂ���Ē��Ҏ����1664�N�ɂȂ��ꂽ�B�������A�{���̎�v������1622-5�N�ɏ����ꂽ�ƌ����Ă���B�O�N(1663)�̒n����A�o���������F�������{�s���o�ł̌_�@�ƂȂ����̂ł��낤�B�d����`���\���鏑���ł���B
�@
���҂͖f�Տ��l�ł��邱�ƂɌւ�������A���l�́u�q�͕x���̂�����Ȃ��畃�̐E�Ƃ��������݁A(�������ɂ����Ȃ��̂�)�W�F���g���}���ɂȂ��āA���̍��Y���Ë��ƕ��c�̂����ɔ�����邱�Ƃ𖼗_�Ɏv���A�ΕׂȖf�Տ��l�Ƃ��Đe�̂��Ƃ��p���ŁA���̎��Y����葝�傷�邱�Ƃ��l���Ȃ��v���Ƃ���X�����v���Ă���B���l������x�܂����Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ��A�{�����M�̈ꓮ�@�ł������悤�Ɏv����B�{���́A�q�ɗ^���鋳�P�̕��̂ŋL����Ă���B
�@
�}�����w�f�_�x�ŁA���C���h�f�i��̂��߂ɓW�J�����̂��A�u�f�Ս��z�_�v�ł���B�w����x�ł͂��̗��_���X�ɑ̌n�I�ɓW�J�����B
�@
�u�킪�����É������̓��C���h��Ђɂ�������ꂽ������ɂ����ẮA��Ђ̎Ј��́A�C���O�����h���瓌�C���h�ɔN�X�A�o����O�����݂��ǂ�قǂ̋��z�ł��낤�ƁA�����o�����Ɠ����z�̋�݂�N�X�������܂˂Ȃ�Ȃ��A�Ɠ��ʂ̒��ӂ������ċK������Ă��邱�Ƃł���B��Ђ͂˂Ɋm���ɂ���𗚍s���A��]�������Ƃ��Ȃ��Ă킪�����̍���̑���������炵�Ă����̂ł���B�v(�w�f�_�x)�ƋL���B
�@
�}������������(��)�̑���Ƃ͉����B�܂��́A���C���h��Ђ����t�̂��ߎ����o�����x(���i�E�M����)�Ǝ����A�������������x�������{general�@stocke�Ƃ̍��z����M����B�}���̗�ł́A���[���b�p�ŏ����鍁���E���E�y���V���������V���A�̃A���b�|�Ńg���R�l����w������̂ɔ�ׂāA���C���h���璼�ڍw����������O���̈�̋��z�Ŕ�����B�Ƃ����Ă��A���̍��z�����l�̗����ƂȂ�̂ł͂Ȃ��B������������̂�ʂƂ��Ă��A������ԁE�댯�̑���ɉ����ė��q�E�ی����E�^���E�㗝�l���ɔ�p����������B�������A�����u(�����̂�����)�킪�����̕����Ɛb���̘J��employment�Ƃ��A���܂������C���h���i�̂��߂Ɏx������㉿����p�̔��ɑ傫�ȕ��������߂邱�Ƃ́A�����̂�낱�тƂ���Ƃ���ł���B�v(�w�f�_�x)���邢�́A���{���啪�́u�łƕ��ۋ��Ƃ��č����É��ɁA�܂����^�Ƃ��đ㗝����E���␅�v�Ɏx�����邵�A�����ɍq�C�̂��߂̐H�Ƃ═���ی������̑��Ɏx������̂ł��邪�A�����������́c�킪���̌��{���x�́m�����ł́n�ړ]�ɂ����Ȃ��̂ł���A�������Ă��̔���ł͂Ȃ��v(�w�f�_�x)�Ƃ������B�\�\��������A���v�̑傫���A�����ĕx�̑����̑傫�����u�n�f�Ղ̏��オ���R�������B
�@
����ł��A�f�Ղɂ���ĕx����������ɂ��Ă��A�A�����i�����������邩�ėA�o����đ�O���̏��i�ƌ��������ꍇ�́A������������̂ł͂Ȃ����Ƃ̋^�₪�o�Ă���B�}���͓�����B���荑�ɂ���ẮA�������i��K�v�Ƃ��Ȃ��ꍇ������A���̏ꍇ�͉ݕ���A�o������Ȃ��B�������A�A���i�����܂ňȏ�ɍ�������Ȃ���A�A���i�͌��ǍėA�o����邱�ƂɂȂ�A�����ɂł͂Ȃ���������ݕ��Ƃ��Ċҗ�����B�u����ꂪ���i�A�o�̎蔤���ƂƂ̂��A�Ȃ�ׂ��ߖāA�C�O�֔������͉̂��Ȃ�Ƒ���o�������A���̂Ƃ��ɉݕ�������ɉ����ėA�o���ׂ����Ƃ����̂́A��w�����̂��A�����Ɋl�����邽�߂��Ƃ����̂ł͂Ȃ��B�����ł͂Ȃ��āA�ŏ��͈�w�����̊O�����i�̗A�����\�ɂ��A�����Ă킪���̖f�Ղ��g������B�������āA������ėA�o����A���̂����ɂ킪���̍�������Ȃ����炸�������邱�ƂɂȂ�̂ł���B�v�A�o�ƗA���̍��z�ł���u���̒��ߍ��z�Ȃ����]��́A���ׂĉݕ��Ƃ��Ă��A�܂��͍ėA�o����������Ȃ��悤�ȏ��i�Ƃ��Ă��A�����ꂩ�ɂ���Ė߂��Ă���ق��͂Ȃ��B���̍ėA�o�́A���łɖ��炩�ɂ����悤�ɁA�킪���̍�������邽�߂ɂ͈�w�����ꂽ���@�Ȃ̂ł���B�v
�@
�C�^���A�ł́A����̏�����ł͍��؏����g���ĉݕ���ߖA�M�d�ȋ���͏��i�Ƃ��ĊO���f�ՂɎg�p���Ă���B�ꌩ�A���C���h�f�ՂŋM������A�o����͍̂���̗����̂悤�ł��邪�A���͂���ȏ�̍���������炷�̂ł���B�A�_���E�X�~�X���w���x�_�x�ň������L���ȉӏ����A�����ł����p����B�u�ЂƂтƂ́A���̎d���̒[�����������ᖡ���悤�Ƃ��Ȃ��̂ŁA���̔��f��������ɂ�������̂ł���B���Ȃ킿�A��������ꂪ�A�_�v�̍s�����A��܂��ǂ��ɑ�n�̒��֗Ǎ����ǂ�ǂ�܂��̂Ă邳�܂ł������Ȃ��Ȃ�A�����́A�����_�vhusbandman�Ƃ͌����ɂނ��닶�lmad man���Ǝv���ł��낤�B�������A����̓w�͂̌����ł���n����ǂ��ɂȂ��Ă��̘J�����l����Ȃ�A�����́A����̍s���̒l�ł��ƁA���̍s���ɂ��L���ȑ��������o���̂ł���B�v������A�ʓI�f�Ս��z���ɑ��鑍���I�f�Ս��z���̎咣�ł���B
�@
�}���͖f�Ս��z�_�Ɋ�Â��āA�ݕ��_�A�ב֘_�A�����_��W�J���A�����I�ȍ��x�̈�ʗ��_�����݂��Ə����ꂽ�{�����邪�A�����̘_�͂���قǏڍׂƂ�(���ɂ�)�v���Ȃ��̂ŁA�����ł͋������Ђ��ꂽ��_�_�ɂ��Ă̂��Ă����B
�@
�܂��́A�x�ɂ��Ă̍l�@�ł���B�ނɂ����ẮA�x�Ƃ͎s�������ɕK�v�Ȃ��̂����L���邱�Ƃł���A�x�ɂ͎��R�I�Ȃ��̂Ɛl�דI�Ȃ��̂�����Ƃ���B�O�҂͓V�R�����ł���A��҂͏Z���̋ΘJ�Ɉˑ�����B�C�O�f�Ղ�_���āA�u���̏������̍��݂����ƂƂ��āc�x�T�ɂȂ邱�Ƃ́A�����݂�����̎��Y�������Ƒ���������@�ɔ�ׁA���_��v���̓_���猩�Ă��Ƃ���̂ł͂Ȃ��B�v�Ƃ���}���́A�u�C�O�ł͖f�ՋƂ債�w������݂̂Ȃ炸�����ɂ����Ă͎�H�Ƃ��ێ������i�����߂˂Ȃ�ʁB�v(�w�f�_�x)�Ƃ����B�f�ՋƂƎ�H�Ƃ���邪���ɂ�����Ƃ��́A���Ɓ`�Љ���p���A�n���ɂȂ邩��ł���B���H�Y�Ƃ̐��Y�������R�̕��Y���A���v���������͓S�z�ƓS���i�A���тƖѐD�����ׂĉ���Ƃ���ł���B�x�̑���́u�^�̌������������������Ƃ����A���܂���ꂪ�Nj����邱�̘_�l�̎��Ȃ̂ł���B�v(�w�f�_�x)�Ƃ܂ʼn]���A���ƂƐ����ƁA���Ɍ�҂Ɋւ��ċΘJ�����サ���B�����ƂƘJ��(�ΘJ�E�w�͂Ƃ�)�����������}���ł��邪�A�c�O�Ȃ��獡������ݍ���ŁA�����ɐ��Y�͂傷�邩�ɂ��ẮA�G��邱�Ƃ��Ȃ��B
�@
���ɉݕ����ʐ��B�u�N�����F�߂�悤�ɁA�ꍑ���ɉݕ�����������̍��ɎY���鏤�i����w�����ɂ���B����́A����ꕔ�̂ЂƂтƂɂƂ��Ă͂��̎�������݂ė����ɂȂ邪�A���ƂɂƂ��Ă͂��̖f�ʂ��猩�ė��v�ɂ܂��ɔ�����B���Ȃ킿�A�ݕ���������Ώ��i�͈�w�����ɂȂ�A���l�ɂ܂��A���i�������ɂȂ���̎g�p�Ə����������v�B�ݕ��̑�������������������(�ݕ����ʐ�)�A�A�o���i���i�̍������A�A�o�����������邱�Ƃ͔F�����Ă���̂ł���B����䂦�A�f�Ղɂ���ĉݕ����A�������߂悤�Ƃ��邱�Ƃ́A�f�Ղ������ɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ���B�}���́A�P�Ȃ�u���I�j�X�g(�d����`��)�ł͂Ȃ��B�������A�ނɂ͌�̃q���[�����ݕ����ʐ��ƕ����āA�d����`�ᔻ�̓���Ƃ����A���{�ʐ��̉ݕ��ʎ��������@�\�̔F���͂Ȃ��B
�@
(��)�u�d����`�҂͉ݕ������������d�����A�u����v(treasure)�|�d����`�҂��悭�g�����t�\�Ɠ��ꎋ�����B�u����v�Ƃ́A�x�z�҂����z�̍ٔ���p�ɏ[�Ă邽�߁A�܂��b�����ق��o��̂��߂ɁA�K���ɂ��ߍ������Ƃ�����̒�������Ɏw�����t�������B�v�}�����g�́A����͐푈���F�ł���Ƃ��A����͕K�v������A�l�̗́E�H�ƂȂ�тɕ�����A���B���E�������E���������̂�����ł���Ə����Ă���B�@�@
�@ |
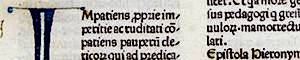 �@ �@
���X�s�m�U�u�_�w�����_�v���� 1670�N |
   �@
�@
|
Spinoza, Baruch de.(1632-77)
�@
Tractatus Theologico-Politicus.
�@
�X�s�m�U�́A�I�����_�̓N�w�ҁB�����I�����_�ł́A���ƌ��͂������̂��Ƃɂ������A�_�w���N�w�̗̈��Ƃ��A���_�̎��R���낤������Ă����B�ނ͖{�����ŏo�ł��A���R�Ɛ����̔ᔻ���s���A�_�w�ƓN�w�͂��̂��̂��̖ړI�Ɗ�b���قɂ��A���݂��ɓƗ��������̂ł���Ƃ����B�������A�{���̏o�łƓ����ɐ��E�ҁA�_�w�҂����͌��������_���A1774�N�ɃI�����_�@�@�́u�_�������A���_��ł���v�Ƃ��Ė{����������A�̔����邱�Ƃ��֎~�����B�ނ̎v�z�͖��_�_�A�B���_�Ƃ��Ė�100�N�̊ԑ����Ă������A�]���̌Œ�T�O����������A�V���Ȗڂœǂݏo�����悤�ɂȂ�Ɛl�X�Ɋ�����^�����B���ƂɎv�l�ƌ��_�̎��R�Ɋւ��Ă̋��͂Ȏ咣�́A�ߑ�v�z�j�㒍�ڂ��ׂ����̂�����A�h�C�c�N�w���ɉe����^�����B�@ |
���o�[���[�t�E�f�E�X�s�m�U
�@
(Baruch De Spinoza, 1632-1677)�@�I�����_�̓N�w�ҁA�_�w�ҁB��ʂɂ́A���̃��e���ꖼ�x�l�f�B�N�g�D�X�E�f�E�X�s�m�U(Benedictus De Spinoza)�Œm����B�f�J���g�A���C�v�j�b�c�ƕ��ԍ�����`�N�w�҂Ƃ��Ēm���A���̓N�w�̌n�͑�\�I�ȔĐ_�_�ƍl�����Ă����B�܂��A�h�C�c�ϔO�_��t�����X����v�z����ȉe����^�����B
�@
�A���X�e���_���̕x�T�ȃ��_���l�̖f�Տ��̉ƒ�ɐ��܂��B���e�̓|���g�K���ł̃��_���l���Q���瓦��I�����_�ֈڏZ���Ă����Z�t�@���f�B���B�c���̍����w��̍˔\�������A���r�ƂȂ�P���������A�ƋƂ���`�����߂ɍ�������͎Ȃ������B
�@
�`�����玩�R�ȏ@���ς������A�_�����R�̓����E���肩���S�̂Ɠ��ꎋ���闧�ꂩ��A�����̃��_�����̐M�̂��肩����T�̈����ɑ��Ĕᔻ�I�ȑԓx���Ƃ����B���炭���̂���1656�N7��27���ɃA���X�e���_���̃��_���l�����̂���w�[����(�j��E�Ǖ�)�ɂ����B���M�I�ȃ��_���l����ÎE���ꂻ���ɂȂ����B �Ǖ���̓n�[�O�ɈڏZ���A�]�����J��Ԃ��Ȃ��玷�M�������s���B1662�N�ɂ̓{�C���ƏɐɊւ��Ę_�������B
�@
1664�N�ɃI�����_���a�h�̗L�͎ҁA�����E�f�E�E�B�b�g�Ɛe�������ԁB���̌��ۂ̓X�s�m�U�̐����W�̒��쎷�M�Ɍq�����Ă����B���̑O�ォ���\��w�G�`�J�x�̎��M�͐i�߂��Ă������A�I�����_�̐�����̕ω��ȂǂɑΉ����āw�_�w�E�����_�x�̎��M��D�悳���邱�ƂƂȂ����B1670�N�ɓ����ŔŌ����U���āw�_�w�E�����_�x���o�ł����B���̖{�́A�����̉�ǂƉ��߂�ړI�Ƃ��Ă����B�������A1672�N�ɃE�B�b�g���s�E����A���̐܂�ɂ́A�X�s�m�U�͐��U�ő�̓��h���������Ƃ���(�u��̋ɒv(ultimi barbarorum)�v�ƃX�s�m�U�͌`�e����)�B
�@
1673�N�Ƀv�t�@���c�I���n�C�f���x���N��w�����ɏ��ق���邪�A�v���̎��R���p���ċ�������邱�Ƃ����ꂽ�X�s�m�U�́A��������ނ����B�������������]���̈���ŁA1674�N�ɂ́w�_�w�E�����_�x���֏��ƂȂ�B���̉e���ŗ�1675�N�Ɂw�G�`�J�|�w�I�����ɂ���ďؖ����ꂽ�x���������������A�o�ł�f�O�����B�X�s�m�U�̎v�z�̑����ł������B���M�ɂ�15�N�̍Ό��������Ă���B�������A�X�s�m�U�v��F�l�ɂ��1677�N�Ɋ��s����Ă���B�܂��A���̗�1676�N�ɂ̓��C�v�j�b�c�̖K��������A���̓�l�̑�N�w�҂݂͌��̎v�z�𗝉��������ɂ͎���Ȃ������B�x�̕a(�x���j��]�x�ǂȂǂ̐�������)�������Ă������߁A���̗��N�X�w�[�t�F�j���w��(�n�[�O�߂�)��44��(1677�N)�̒Z�����U���I�����B�⍜�͂��̌�p�������͎����Ă��܂����B
�@
�n�[�O�ڏZ��A�X�s�m�U�̓����Y�����ɂ���Đ��v�𗧂Ă��Ƃ����`���͗L���ł���B
�@
�Ȃ��A�X�s�m�U�͋M���̗F�l�炩����ꂽ�N�����\���ɂ������Ƃ������邪�A����̓X�s�m�U�̐M���ɍ���Ȃ��B�X�s�m�U�̃����Y�����͐��v�̂��߂ł͂Ȃ��w�p�I�ȒT���S�ɂ����̂��Ƃ����̂������ɂ����Ȃ��B
�@
���O�ɏo�ł��ꂽ����́A1663�N�́w�f�J���g�̓N�w�����x�Ɠ����ŏo�ł��ꂽ1670�N�́w�_�w�E�����_�x(Tractus Theologico-Politicus)�����ł���B�w�l�Ԓm�����P�_�x(Tractatus de intellectu emendatione)�A�w���Ƙ_�x�A�w�G�`�J�x���̑��́w�w�u���C�ꕶ�@�j�v�x(Compendium gramatices linguae Hebraeae)�ȂǂƂƂ��ɁA�v��Ɉ�e�W�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B����͕����I�ɃX�s�m�U���g���o�ł������킹�����߂ł���B�ȏ�̒���͑S�ă��e����ŏ�����Ă���B��e�W�̒��́w���_�_�x(Korte Verhandeling van god)�̓I�����_��ŏ�����Ă��邪����͗F�l�����e����̌������I�����_��ɖ����̂ł���B(�X�s�m�U�͓����b�ɂ̓|���g�K������g���I�����_��ɂ͊��\�ł͂Ȃ������B)�@ |
���N�w�j��̈Ӌ`
�@
�X�s�m�U�̓N�w�j��̐��҂́A���^�̉ʂĂɁu��v���̂ɉ䂠��(cogito ergo sum)�v�ƌ�����f�J���g�ł���B����͐��_�̌`���Ƃ��Ă͂��邪�A���̎����Ƃ���́A�v�҂��鎄�����݂���Ƃ������Ȉӎ��̒��o�ł���B���^�ɂ����ċ��߂�ꂽ�m�����́A���̒��o�ɂ����Č��o�����B������X�s�m�U�́u��͎v�҂����݂���(Ego sum cogitans.)�v�Ɖ��߂��Ă���(�u�f�J���g�̓N�w�����v)�B
�@
���̎v�z�͏����̘_�l����ӔN�̑��w�G�`�J�x�܂łقڈ�т��A�_�����R (deus sive natura) �̊T�O(���̎��R�Ƃ́A�A���̂��Ƃł͂Ȃ��A�l�╨���܂߂����ׂĂ̂���)�ɑ�\������l�i�I�Ȑ_�T�O�ƁA�`���I�Ȏ��R�ӎu�̊T�O��ނ���O�ꂵ������_�ł���B���̍l���̓L���X�g���_�w�҂��������A�X�s�m�U�͖��_�_�҂Ƃ��čU�����ꂽ�B
�@
�ꌳ�I�Đ_�_��\�Y�I���R�Ƃ����v�z�͌�̓N�w�҂ɋ����e����^�����B�ߑ�ł̓w�[�Q�����ᔻ�I�Ȃ�����X�s�m�U�Ɏv������Ă���(�B��̎��̂Ƃ����v�z�������̐�ΓI�Ȏ�̂֔��W������)�A�X�s�m�U�̎v�z�́A���_�_�ł͂Ȃ��A�ނ���_�݂̂����݂���Ǝ咣���閳���E�_(Akosmismus)�ł���ƕ]���Ă���B�t�����X����v�z�̃h�D���[�Y���A���̑��ݘ_�I�Ȋϓ_�̌��㐫���������A�w�X�s�m�U�x�Ƃ����薼�̘_�����o���Ă���B
�@
��\��w�G�`�J�x�́A����́u�w�I�����ɂ���Ę_���ꂽ�v�Ƃ����`�e���\���Ă���悤�ɁA�Ȃɂ�肻�̒��g���@���Ɏ����Ă���悤�ɁA���[�N���b�h�́w���_�x���霂Ƃ������`�E�����E�藝�E�ؖ��̈��̌n�ł���B����͂܂���Q.E.D(�u���ꂪ�ؖ������ׂ������ł������v���������e����̗�)�̑s��ȗ���ł���A�N�w���Ƃ��Ă���ȏ�Ȃ��قǓO�ꂵ����㈂����݂����̂ł������B
�@
���̒���ɂ����ăX�s�m�U�́A����ꂽ��������ђ�`����o�����A�܂��ꌳ�I�Đ_�_�A�����Ő��_�Ɛg�̖̂������グ�A�㔼�͌�����`�I�Ƃ�������ϗ��w���c�_���Ă���B
|
�����ݘ_�E�F���_
�@
�����ł́A�`����w�I�ȑ�1���Ƒ�2���̊T�v����ɋL�q����B
�@
�f�J���g�͐_���Ȏ��̂Ƃ��Đ��E�̍���ɐݒ肵�A���̂��Ƃɐ��_�Ɛg��(���́�����)�Ƃ�����̗L�����̂𗧂Ă��B�������A�X�s�m�U�ɂ��A���̖{���ɑ��݂���������̂́A�����_�݂̂ł���B�X�s�m�U�ɂ����ẮA���������̊��S��������̒��Ɋ܂ސ_�́A���Ȃ̊��S���̗͂ɂ���Ă̂ݍ�p���ł�����̂ł���(���Ȍ���)�B����������A�_�͒��z�I�Ȍ����ł͂Ȃ��A�����̓��ݓI�Ȍ����Ȃ̂ł���B�_�Ƃ͂��Ȃ킿���R(���̎��R�Ƃ́A�A���̂��Ƃł͂Ȃ��A�l�╨���܂߂����ׂĂ̂���)�ł���B������ꌳ�_�E�Đ_�_�ƌĂԁB�_���B��̎��̂ł���ȏ�A���_���g�̂��A�B��̎��̂ł���_�ɂ������̈قȂ鑮��(�_�̖{�����\������Ɖ�X����l������ꑤ��)�Ƃ��Ă̎v�҂Ɖ����Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B�܂��A�_�̖{���͐�ɖ����ł��邽�߁A�����ɑ����̑����������B���̏ꍇ�A���Y�I���R�Ƃ��Ă̏��X�̂���(�L���ҁA���邢�͌�)�͑S�āA�\�Y�I���R�Ƃ��Ă̐_�Ȃ����Ă͍݂肩�l�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ����̂ł���A�_�̕Ϗ�Ȃ����_�̂��鑮���ɂ�����l�Ԃł���Ƃ������ƂɂȂ�B
�@
�X�s�m�U�́A�u�l�Ԑ��_���\������ϔO�̑Ώۂ�(������)���݂���g�̂ł���v�Ɛ錾����B�Ȃ��Ȃ�A�u�������镨����юv�҂��镨�͐_�̑����̕Ϗ�ł���v�ȏ�A��͓������̂̓�̑��ʂɑ��Ȃ�Ȃ�����ł���B����ɂ���ĐS�g�̍���Ƃ�����X�̌����I�Ȃ��肩��������ł���A�ƃX�s�m�U�͍l�����B���_�̕ω��͐g�̂̕ω��ɑΉ����Ă���A���_�͐g�̂���Ɨ��ɂ���킯�ł͂Ȃ��A�g�̂����_����Ɨ��ƂȂ肦�Ȃ��B�g�̂ɐ悾���Đ��_������(�B�S�_)�̂ł��Ȃ����_�ɐ悾���Đg�̂�����(�B���_)�̂ł��Ȃ��B�����铯�ꑶ�݂ɂ�����S�g���s�_�ł���B���̏�A�l�Ԃ̐g�̂�ΏۂƂ���ϔO���瓱���ꂤ����̂�����F��������l�Ԃ̗L���Ȑ��_�́A�S���R��F�����鈽�閳���̒m���̈ꕔ���ł���Ƃ��Ă���A���̑S���R���u�z�O�Iobjective�v�Ɏ��Ȃ̂����Ɋ܂ނƂ���̎v�҂��閳���̗�(potentia infinita cogitandi)�ɂ���Č`�������X�̎v�z�ƁA���̗͂ɂ���ĊϔO���ꂽ���R�̒��̌X�̎����Ƃ́A�����d���Ői�s����Ƃ��Ă���B���Ȃ킿�v�҂Ƃ������ʂ��猩��Ύ��R�͐��_�ł���A�����Ƃ������ʂ��猩��Ύ��R�͐g�̂ł���B���҂̒���(���_���\������Ƃ���̊ϔO�Ƃ��̑Ώۂ̒���)�́A�������̂̓�̑��ʂ���������A��v����Ƃ��Ă���B |
���ϗ��w
�@
�X�s�m�U�́A�f�J���g�Ƃ͈قȂ�A���R�Ȉӎu�ɂ���Ċ���𐧌䂷��v�z��F�߂Ȃ��B�ނ���A�X�s�m�U�̐S�g����_�̒��ڂ̋A���Ƃ��āA�Ɨ��I�Ȑ��_�ɏh�鎩�R�Ȉӎu����̓I�ɎI�Ȑg�̂��x�z����A�Ƃ����\�}�͊��p�����B�X�s�m�U�́A�X�̈ӎu�͕K�R�I�ł����Ď��R�łȂ��Ƃ�����A�ӎu�Ƃ�������(�����̗L)���X�̈ӎu�����̌����Ƃ��čl����̂́A�l�ԂƂ������̂��X�̐l�Ԃ̌����Ƃ��čl����Ɠ��l�ɕs�\�ł���Ƃ��Ă���B�܂��ϔO�͊ϔO�ł��邩����ɂ����čm��Ȃ����ے���܂�����̂Ƃ��Ă���A���R�ӎu�Ɖ������\�ۑ��E����͂��͒P�Ȃ�g�̂̉^���ł���Ƃ��Ă���B
�@
�X�s�m�U�ɂ����ẮA�\�ۓI�ȔF���Ɉˑ���������(���h�����O)��j��������̂́A�K�R����c�����闝���I�ȔF���ł���Ƃ���Ă���B�����̊O���ɂ��鎖���̔\�͂Œ�`�����悤�ȕs�\�S�ȊϔO(�L���͂ɂ݈̂ˑ�����ϔO)�������āA�����ŗL�̔\�͂ɂ݈̂ˑ����閾�Ĕ��R����\�S�ȏ��ϔO���`�����邱�Ƃ��\�ɂ�����̂́A�X�s�m�U�ɂ����Ă͗����I�ȔF���ł���B���̏�A�u�����̐��_�́A���ꎩ�炨��ѐg�̂��A�i���̑��̉���(sub specie aeternitatis)�F�����邩����A�K�R�I�ɐ_�̔F����L���A�݂����炪 �_�̒��ɂ���(in Deo esse)�A�_��ʂ��čl������(per Deum concipi)���Ƃ�m��v���Ƃ���A�l�Ԃ͐_�ւ̒m�I���ɒB���A�_�����Ȏ��g��F�����Ė������閳���Ȉ��ɎQ�^���邱�Ƃōō��̖����邱�Ƃ��ł���ƃX�s�m�U�͑z�肷��B
�@
��̋c�_�́A�̎��ȕۑ��Փ���ے肵�Ă���킯�ł͂Ȃ��B�e�X�����݂ɌŎ�����͂́A�_�̐����̉i���Ȃ�K�R���ɗR������B�~���̌��͐_�݂̍肩�������Ȃ��͂ɗR������̎��ȕۑ��̃R�i�g�D�X(�Փ�)�ł��邱�Ƃ��A�X�s�m�U�͔F�߂��B�������A���̊e�X�������ł͂Ȃ��S�̂ƌ��Ȃ���邩���菔���͑��݂ɒ��a�����A���l�̖��l�ɑ��铬���ɂȂ肩�˂Ȃ����̕s�\�S�ȃR�i�g�D�X�̃J�I�X���\�S�ȕ����֓������߁A�S�̂Ƃ��Ă̎��R(�_)�̕K�R���𗝐��ɂ���ĔF�����邱�ƂɎ��Ȃ̖{����F�߁A�܂����̔F���𑼎҂ƕ������������Ƃ��v�������B
|
�����Ƙ_
�@
��q�̃G�`�J�̋c�_�ɂ��A�����͂������Ɋ����ł���B�Ƃ͂����u���ׂč��M�Ȃ��̂͋H�ł���ƂƂ��ɍ���ł���v�B����ɏ]�����錻���̐l�Ԃ́A�����ɂ����Ă͒��Ԃ����|���邱�Ƃɓw�߁A�����ŏ��������҂͎��Ȃ��v������葼�l���Q�������Ƃ��ւ�Ɏ���B���l�̌��������Ȃ̌����Ɠ��l�Ɏ��˂Ȃ�Ȃ����Ƃ�������@���́A����ɑ��Ă͖��͂Ȃ̂ł���B�u�����Ȃ銴������������������̊���ɐ��~�����̂łȂ���ΐ��~�������̂łȂ��v�Ƃ��闧�ꂩ��́A�X�s�m�U�͍��Ƃ̌��\�ɂ���Đl�����ی삳��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ���B�����Ă��̂��߂ɂ͐b����̊�]�Ȃ����͌Y���ւ̋��|�ɂ���ď]�������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ��Ă���B�������ɐ��_�̎��R�͌l�̓��ł͂��邪�A���Ƃ̓��͈��S�̒��ɂ݂̂��邩��ł���B
�@
�������̑������c�̂��S���O����Ȃ�Ƃ����吭���A��̑I������Ȃ�Ƃ��M�������A��l�̐l�Ԃ̎蒆�ɂ���Ƃ��N�吭���ƌĂ��B���̓������A���邢�͋����̕s�K��r�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ė��Ă�ꂽ���Ƃ̖@���ɂ݂�����]���悤�ȗ����ɓ������҂���ł͂Ȃ������ɂ����ẮA�������������l�X�ɑ��Ă͊O���玩�R��^���邱�Ƃ��@�̖ړI�ł���Ƃ��Ă���B�܂����_�̎��R�ɂ��ẮA�����F�߂Ȃ����Ƃ́A���@���_�����킵�߁A���̂�s����ɂ���Ƃ��Ă���B
�@
�܂��X�s�m�U�̐����v�z�̓����́A���̌�����`�ɂ���B�����ւ̗��z��ێ��������̒�����Y��Ȃ����̎p���͊��l���̃I�����_���a���̐����ƂƂ̌𗬂��瓾��ꂽ���̂ƍl������B
|
���@���Ƃ̊W
�@
�X�s�m�U�̔Đ_�_�́A�_�̐l�i��O��I�Ɋ��p���A�����̌��ɑς����鍇���I�Ȏ��R�_�Ƃ��ė^�����Ă���B�X�s�m�U�͖��_�_�҂ł͌����ĂȂ��A�ނ��뗝�_�_�҂Ƃ��Đ_����藝���I�ɘ_���A�l�i�_�ɂ��ẮA����O�̗���͂ɓK�������l�ԓI�b�@�̏��Y�ł���Ƃ��Ă���B
�@
�L���X�g���ɂ��ẮA�X�s�m�U�Ƃ��ẮA�L���X�g�̕����́A�M�ҒB�ɑ��Ă݂̂��̔c���͂ɉ����Ď����ꂽ�o���ɑ��Ȃ�Ȃ��Ƃ��A�܂��L���X�g���������g��_�̋{�Ƃ��Č�������Ƃ́A�u���t�͓��ƂȂ����v(���n�l)�Ƃ������ƂƂ��ɁA�_�������Ƃ������L���X�g�̒��Ɍ����������Ƃ�\���������̂Ɖ����Ă���B�܂����̕�V�͓����̂��̂ł���Ƃ��闧�ꂩ��́A�������͗��@�Ƃ��Ă̌`����_���g����Ă��邩�ۂ��ɂ�����炸�_�����L�v�ł���Ƃ��Ă���A�_�̖��߂ɑ���s�{�ӂȗꑮ�Ƃ͑Βu�����Ƃ���́A�l�Ԃ����R�ɂ�����̂Ƃ��Ă̐_�ɑ��鈤�𐄏����Ă���B�܂��_�����̐��`�̍s�g�Ɨאl���ɂ���đ��h����Ƃ����Ӗ��ł̃L���X�g�̐��_����������A���l�ł����Ă��~����Ǝ咣���Ă���B
|
���ᔻ
�@
�J�[���E�|�p�[�̓X�s�m�U�̓N�w��{����`�Ƃ��Ĕᔻ���Ă���B�|�p�[�́A�X�s�m�U�̒���u�G�`�J�v��u�f�J���g�̓N�w�����v�́A��������{����`�I�Ȓ�`�ɂ݂����ӂ�A�u�����������̒�`�͎�O����œI�O��́A����ɂȂ�炩�̖�肪����������������ł͖����I�Ȃ��̂��v�Ɣᔻ�����B�܂��A�X�s�m�U�̊w�I���@(�����E�Q�I���g���R)�ƁA�w�̕��@�Ƃ̗ގ����́A�u�܂���������ׂ����̂��́v�Ƃ��Ă���B�|�p�[�̓X�s�m�U�ƈقȂ�A�J���g�͖{���̖��Ǝ��g��ł���ƕ]�����Ă���B�@
�@ |
 �@ �@
���Q�[���b�P�u�^��Ɋւ���}�O�f�u���N�̐V�����v���� 1672�N |
   �@
�@
|
Guericke, Otto von.(1602-86)
�@
Experimenta nova(ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio, ...
�@
�h�C�c�̕����w�ҁB�ߑ㎩�R�Ȋw�̊�b��z�����w�҂̈�l�ŁA�K�����C���Ɠ������@�\�I�����I���@���Ȋw�̒��ɓ��������B�^��|���v�����Đ^�ۂ��������A��C�̏d���A�M�c���������o�����B�^��̎����ł́A�ŏ��Ԃǂ����̒M���g�������A�M�����Ď��s���A�^��ɂ���e��������̋��ɂ��Đ��������B�}�O�f�u���N�̎s���������Q�[���b�P�́A1654�N�ɍ����t�F���f�B�i���g�O���̑O�ŁA�^��Ɋւ���������s�����B�ނ́A�����������̔��������킹�Ĉ�̋��ɂ��A�r�C�|���v�Ő^��ɂ�����A4�̔n���g���đS�͂Ŕ��Ε����Ɉ������点���B�����͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��������A���ɑ剹���𗧂Ăē�ɗ��ꂽ�B�{���́A�����^��̎������܂Ƃ߁A���s�������̂ł���B�@ |
���I�b�g�[�E�t�H���E�Q�[���P
�@
(Otto von Guericke�@1602-1686)�@�h�C�c�̉Ȋw�ҁA�����ƁA�����ƁB���ɐ^��̌����Œm���Ă���B�h�C�c�̃}�N�f�u���N�̋M���̉Ƃɐ��܂ꂽ�B1646�N����1676�N�܂Ńh�C�c�̃}�N�f�u���N�s���߁A�O�\�N�푈�̃}�N�f�u���N�̐킢�ʼn�ŏ�ԂɊׂ����}�N�f�u���N�̕����ɗ͂�s�������B
�@
����C���Ɛ^��
�@
1650�N�A�C�ӂ̗e��ɐڑ��ł��A�V�����_�[�ƃs�X�g���ł��̗e����̋�C��r�C����^��|���v�����A�^��̓����̌����Ɏg�����B�Q�[���P�͋C���̗͂ɂ��Ă̎��������J���Ă���B���a51cm�̓����̔�����e��(�}�N�f�u���N�̔���)��2�g�ݍ��킹�A���̓����̋�C��^��|���v�Ŕr�C����B2�̔������ꂼ���8���̔n���Ȃ��A��������������点�A����ł�2�̔���������Ȃ��Ƃ��������ł���B���ɍĂы�C������ƁA�����͊ȒP�ɗ��ꂽ�B1663�N�ɂ̓x�������̃u�����f���u���N�I���t���[�h���q�E���B���w�����̑O�ŁA24���̔n���g���������������I���Ă���B
�@
���̂悤�Ȏ����́A�A���X�g�e���X���u���R�͐^��������v�Əq�ׂ����Ƃɂ��u�^���v��(�܂�A�^��Ƃ�����Ԃ͍��Ȃ��Ƃ��鉼��)�ւ̔��ƂȂ�A���N�̓N�w�҂���щȊw�҂̋c�_�ɏI�~�����ł��ꂽ�B�Q�[���P�͂܂��A�^���̂��Ђ�����̂ł͂Ȃ��A���ӂ̗��̂����̂ɑ��Ĉ��͂������Ă��邱�Ƃ��ؖ������B
�@
�Q�[���P�͂܂��C���v��p�����V�C�̗\�z���s���A���ꂪ�C�ۊw�̐�삯�ƂȂ����B�ӔN�͓d�C�̌����ɒ��͂������A���̐��ʂ͂قƂ�nj������Ă��Ȃ��B���E���̐Ód���d�@(���C�N�d�@) "Elektrisiermaschine" �������B�@ |
�����x
�@
���̂��������A�܂��͗₽���Ƃ������Ƃ𐔒l�ŕ\�������̂����x�ł��B
�@
�Ɏ���������ƁA�������͉������Ɗ����܂��B�܂��A���Ɏ������Ɨ₽���Ɗ����܂��B�Ƃ��낪�A���̉������A�₽���Ƃ������o�͐l�ɂ������ɂ������܂��B�������������x�̐��ł��A�������Ɗ������ł́A�܂�ł�����������������̂ł��B�����ŁA�ǂ̂悤�ȏ������ł����Ă��A�N�������ʂ̂��Ƃʼn������A�₽����`���������߂ɁA���l�ŕ\�����Ƃ��l�����܂����B�������A�₽���Ƃ������o�I�ȕ\���̂����ɁA���l�ŕ\�������̂����x�Ȃ̂ł��B���ݎg���Ă��鉷�x�̒P�ʂōł��Â��̂͂�(�؎����x)�ł��B�P�V�Q�O�N���A�t�@�[�����t�@�C�g(�h�C�c)�̐ݒ肵�����̒P�ʂ́A�����A�����J�A�J�i�_�Ȃǂ̍��Ŏg���Ă��܂��B�Â��ĂP�V�Q�S�N���A�X�E�F�[�f���̓V���w�҃Z���V�E�X���t�@�[�����n�C�g�Ƃ͈قȂ�P�ʂ������x�v������܂����B���ꂪ�A��(�ێ����x)�ł��B���ݓ��{���͂��ߑ����̍��X�ł͂��̒P�ʂ��g���Ă��܂��B���̂ق��A�����w�̕���ł̓C�M���X�̕����w�҃P���r���̒�߂�K(��Ή��x*)�����x�̒P�ʂƂ��Ďg���Ă��܂��B
�@
���x�ƔM�G�l���M�[�B
�@
���ׂĂ̕��̂́A���q�╪�q�ɂ���č\������Ă��܂��B���̂��M���Ȃ�̂́A���̌��n�╪�q�̉^���������ɂȂ邩��ł�(�}�P)�B����A�₽���Ȃ�̂͌��n�╪�q�̉^�����s�����ɂȂ邩��ł�(�}�Q)�B���̉^�����w�ł͔M�G�l���M�[�ƌĂ�ł��܂��B�܂�A���̂̉��x�́A�M�G�l���M�[�̏�Ԃɂ���č����Ȃ�����A�Ⴍ�Ȃ����肵�Ă���̂ł��B�����āA���ׂĂ̕���(��Ή��x�O�x�ȏ�̕���)�́A�M�G�l���M�[�ɉ�������������ԊO������˂��Ă��邱�Ƃ��m���Ă��܂��B���x�͔M�G�l���M�[�̏�Ԃ𐔒l���������̂ł��B�@ |
�����x�v�̗��j
�@
���镨�̂��A�M���E�₽���Ƃ������Ƃ��A���̒N���ɐ������`�������Ƃ����v���͌Â����炠��܂����B���ݗp�����Ă��鑽���̉��x�v�̌����́A���̂̂��M������ɐڂ��鑼�̕��̂ɓ`��鐫��(�M�`��)�𗘗p�������̂ŁA��ʂ̉ƒ�Ŏg���Ă���̉��v�⊦�g�v�ɑ�\����܂��B�����́A�ڐG�^���x�v�ƌĂ�Ă��܂��B���x�v�̗��j������Ƃ��̔M�`���̌����𗘗p�������x�v�́A���l�b�T���X�ȍ~����قǕς���Ă��܂���B�Ƃ��낪�A�����I�ɓ����ĖڂɌ������(������)�𗘗p�����A�Ⴆ�u�������v�v�Ȃǂ̉��x�v������܂����B����͓S��K���X�Ȃǂ̍������̂�ڎ����Ȃ���A�{�̂ɓ������ꂽ�t�B�������g�̋P�x�Ɣ�r���ĉ��x�𑪂�܂��B���̌�A�ڂɌ����Ȃ���(�ԊO��)�𗘗p�������x�v�ւƔ��W���čs���܂��B���肽������(���蕨��)�ɒ��ڐG��Ȃ��Ă��A���ꂽ�ʒu���牷�x������邱�ꂩ��̉��x�v�́A��ڐG�^���x�v�ƌĂ�Ă��܂��B
�@
���t�B�����̉��x����
�@
�A���L�T���h���A�m�w�҃t�B�����͉��ŏo�����e����̋�C�����x�ω��ɂ���Ėc���A���k���錴���𗘗p�B�M���𑪂鑕�u��������B
�@
���K�����I�̉��x�v
�@
�K���X���ƃK���X�ǂ��g���ĉ��x�𑪂鑕�u��������B�K���X���g���Ă��邽�߉��x�ω������Ŋm���߂邱�Ƃ��ł����B���������̑��u�͋C���̉e���������邽�ߒZ���Ԃ̊Ԃ̉��x�ω��������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B
�@
���T�O���h�̑̉��v
�@
�K�����I�̗F�l�ň�t�̃T�O���h�̓K�����I�̂��������u�����ǁA�K���X�ǂ𐅕��ɂ������ɉt�H����ꂽ�B�����p���ėF�l�̈�w�҃T���g���I�͊��҂̉��𑪂����Ƃ�����B
�@
���t�B�����c�G(�C�^���A)�ł���ꂽ�A���R�[�����x�v
�@
�C�̂̂����ɁA�C���ɂ���đ̐ς��قƂ�Ǖω����Ȃ��A���R�[����p�����B���̉��x�v�́A���݂̂��̂Ƃ���قǕς�肪�Ȃ����A���ꂵ���ڐ���͂܂��Ȃ������B
�@
���Q�[���b�P�̉��x�v
�@
��C�|���v�ŏ��߂Đ^������������ƂŒm����Q�[���b�P���C�̖̂c���𗘗p�������x�v������Ă���B���̒���u�^��ɂ��Ẵ}�O�f�u���O�̐V�����v�ɂ͖ڐ����z�������x�v���c����Ă���B
�@
���t�@�[�����n�C�g�̐��≷�x�v
�@
1720�N�A���p�I�Ȑ��≷�x�v���B����̓A���R�[���␅�Ƃ͈���āA�K���X�ǂ̕ǂ��ʂ炳���A�t�����邱�Ƃ��Ȃ����߁A�����M���̎��ɂ͂��������ڐ�����w���B�����āA���̉��x�v�ɂ���āu�X�̗Z��_�R�Q�x�v�u���̕����_�Q�P�Q�x�v���B���̖ڐ���́A���݂ł��A�����J�A�J�i�_�ȂǂŎg���Ă���B
�@
���Z���V�E�X�̐��≷�x�v
�@
�X�E�F�[�f���̓V���w�ҁE�����w�҃Z���V�E�X�́A�C���v�̖ڐ��肪���̎��A���� �������鉷�x���˂Ɉ��ł��邱�ƂɋC�Â��A��C���̂Ƃ��̐��̕����_�ƁA�X�� �Z��_�Ƃ̊Ԃ��P�O�O���������ڐ��������B���̖ڐ���́A���ݓ��{�ȂǑ��� �̍��X�Ŏg���Ă���B
�@
���M�d�C�̔���
�@
�X�����ꂽ�e��ƁA������ꂽ�e��Ƀr�X�}�X�_��n���A����łӂ��̓��̗e��� ���������Ō��єM����Ɠd�C�������(�M�d�C)���Ƃ��h�C�c�̕����w�҃[�[�x�b�N �������B���̌����͌�̔M�d���x�v�Ȃǂɗ��p����Ă���B
�@
���ԊO���̔���
�@
1800�N�A�C�M���X�̓V���w�҃n�[�V�F���͑��z���������Ƃ��A�ԐF���̊O�ɕ��� �̉��x����������̈�(�ԊO��)�����邱�Ƃ��B��̉��x�v�̗����ς���d�v �Ȗ������ʂ������B
�@
���v�����N�̕��˖@��
�@
�h�C�c�̕����w�҃v�����N�͔M���˂̃G�l���M�[�ʎq���ԊO���̐U�����ɔ�Ⴗ��� ���A6.625*10-27�G���O�E�b�̃v�����N�萔���B����܂ŘA���I�ƍl�����Ă� ���G�l���M�[���A�L���Ȓl�����G�l���M�[�ʂ���ł��Ă���ƋK�肵�A�X�y�N�g�� ���z�̕��˖@���������B�@ |
�����x�v�̎��
�@
���M����(�ԊO��)�𗘗p�������x�v
�@
���蕨�̂�����˂���Ă���ԊO���̗ʂʼn��x���肪�ł��邽�ߔ�ڐG���肪�\�B�M���˂𗘗p����̂ŁA����ł���̈悪�L�͈͂ɂ킽���Ă���B
�@
���M�d�C�𗘗p�������x�v
�@
��������ނ̋�����d�C�I�ɐڐG�����[�ɉ��x����^����ƔM�N�d�͂ɂ���ēd���������B���̔M�d�C����(�[�[�x�b�N����)�𗘗p�B�S�|�A�����A���q�͔��d�A�Ζ������Ȃǂ̕���Ŏg�p����Ă���B
�@
���d�C��R�𗘗p�������x�v
�@
���x�ω��ɂقڔ�Ⴕ�ċ����̓d�C��R���ω����鐫���𗘗p�B���������\�������R�̂̒�R�l�𑪒肵�ĉ��x��m��B�ق��ɁA�T�[�~�X�^���x�v������B
�@
���t�̖̂c���𗘗p�������x�v
�@
�t�̂����x�ω��ɂ��c���A���k���鐫���𗘗p�B���j�I�ɍł��Â�����m���Ă��鉷�x�v�ŁA�\�����ȒP�Ȃ��������Ȃ��Ƃ��猻�݂ł����g�v�A�̉��v�ȂǂɍL�����p����Ă���B
�@
�����͂𗘗p�������x�v
�@
���x�v�����̈��͕ω��ɂ����̃u���h���ǂ��ω����錻�ۂ𗘗p�B�ȒP�ȍ\���ł�������v�ł���A�d�C���g��Ȃ��̂ň��S���������A�v���Z�X�v���p�ɑ����g�p����Ă���B�@�@
�@ |
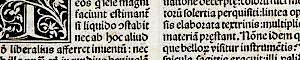 �@ �@
���z�C�w���X�u�U��q���v�v���� 1673�N |
   �@
�@
|
Huygens, Cristian.(1629-95)
�@
Horologium Oscillatorium sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae.
�@
�I�����_�̕����w�ҁB�n�[�O�ɐ��܂�A�͂��߂͖@�����w���A�₪�Đ��w�ɓ]�����B�����Y�̐V���������@�����A�܂����͂Ȗ]�����𐧍삵�Ă��̐ڊ���Y���H�v���A���߂ēy���̊������B�U��q�̉^�����������A�K�����C�̍l�ĂW�����ĐU�q���v�������B�܂��d�́A���S�͂̌������s���A�e���̂̏Փ˂ɍۂ��ē����@���𖾂炩�ɂ����B����ɏ��߂Č��̔g�����𗧂ā��z�C�w���X�̌������\���āA���̔��ˋ��܁A�����ܓ��̏����ۂ�������g�����̊�b���m�������B�@ |
���N���X�e�B�A�[���E�z�C�w���X
�@
(Christiaan Huygens �A1629-1695)�@�I�����_�̐��w�ҁA�����w�ҁA�V���w�ҁB
�@
1629�N �n�[�O�ɐ��܂ꂽ�B�Ƃ͑c����������b�߂�����ł���A�N���X�e�B�A�[���̎����ł���R���X�^���e�B���E�z�C�w���X(Constantijn Huygens)�́A�I�����_�̎��l�ō�ȉƂł��������B
�@
1655�N ���w�Ɩ@�����w��Ń��C�f����w�𑲋Ƃ����B��ɕ����w���������A��������Ȑ��̋��ςȂǂŐ��w�̍˔\�������B
�@
1655�N ���삵��50�{�̔��˖]�����œy���̉q���^�C�^���������B
�@
1656�N �u�y���̊v����ł��邱�Ƃ������B�܂��I���I���启�_��Ɨ��������ăX�P�b�`���c���A���ꂪ�ŏ��̃I���I���启�_�̃X�P�b�`�ƂȂ����B
�@
1656�N �U��q���v�����߂Ď��ۂɐ��삵���B
�@
1658�N �u���v�v(Horologium )�����B
�@
1666�N �t�����X�������W�������o�e�B�X�g�E�R���x�[���̏����Ńp���ɈڏZ���A�A�J�f�~�[�E�����C�����E�f�E�V�A���X�̉���ƂȂ����B
�@
1673�N �u�U��q���v�v(Horologium Oscillatorium )���B
�@
1675�N �q�Q�[���}�C�̂����e���v���v��A���ꂪ��ʂɁu���E���̎��p�I�ȋ@�B�����v�v�ƌ����Ă���B
�@
1675�N �u(������)����ꂽ�]�����v(Astroscopia Compendiaria )�����B���̒��ŋ�C�]����������B
�@
1675�N ���E�ŏ��߂ĉΖ���g���������^�̃G���W�����B
�@
1685�N �i���g�̒��ߔp�~�ɔ����n�[�O�ɖ߂����B
�@
1690�N �u���ɂ��Ă̘_�l�v���A���̒��Ō��̔g����������B
�@
�U��q���v�̔����@�Ƃ��ẮA�ނ��w�I�ɃT�C�N���C�h�ł��邱�Ƃ��ؖ����Ă����A����Ȑ��ɂ����ĕ��̂��d�͂̉e�����ō~������Ƃ��A�Ȑ���̂ǂ̓_����~�����n�߂Ă��Œ�_�ɓ�������܂łɕK�v�Ȏ��Ԃ͓���ł���Ƃ��������𗘗p�����ƍl������B���̐v�̓C�\�N�����A�g�[�g�N�����ƌĂ��B��q���Ă��邪�A�K�����I�͐U��q�����v�ɗp����Ƃ����A�C�f�A�����łɎ����Ă���A�܂��S�b�g�t���[�g�E���C�v�j�b�c�͂���Ɋւ��Đ��w��őO�i�K�I�Ȍ��ʂ��o���Ă����B
���̑��z�C�w���X���܂��̓n�C�Q���X���ڊ���Y���B�z�C�w���X�̌����B���̔}��Ƃ��ẴG�[�e���̒��̋Ɛт�����B�@ |
���U��q���v (Pendulum clock)
�@
�U��q�͒ʏ�̈Ӗ��ł́u�d�͐U��q�v�̂��Ƃł����A�����ł́u�˂���U�q�v���o�ꂵ�܂��B�u�˂���U�q�v��1793�N�� Robert Leslie �ɂ�蔭������A�܂��Ȃ��u�˂���U�q���v�v�����삳��܂��B�u�d�͐U��q���v�v�͔M���������@���F�X����A�������琳�m�ł������A�u�˂���U�q���v�v�̕��͔M�������@��1951�N�Ɏ���܂łȂ��A�v�����u�Ƃ��Ă͐��m�ł͂���܂���ł����B�������A�悭���ꂽ�悤�ł��B�u�˂���U�q���v�v�͓��{�ł͂قƂ�ǔ̔�����Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂���(�ґ�i)�A���ݎ��v�X�Ō���u�����v�̂��Ȃ�̕������A���́u�˂���U�q���v�v�̐^����������������Ă��܂��B
�@
�U��q���v�͌v���v�f�Ƃ��āA�U��q�A���Ȃ킿�h���d����g�p���鎞�v�ł���B�v���̂��߂ɐU��q���g�p���闘�_�́A���ꂪ�����u������ł���B�܂�A�U��q�͂��̒����Ɉˑ����Đ��m�Ȏ��ԊԊu�ŐU�����邪�A����ȊO�̎��ԊԊu�ł͐U�����Ȃ��̂ł���B1656�N�̃N���X�e�B�A�[���E�z�C�w���X�̔�������1930�N��Ɏ���܂ŁA�U��q���v�͐��E�ōł����m�Ȍv�����u�ł���A����ɂ��L�͈͂Ŏg�p����邱�ƂɂȂ����B�U��q���v�����삷�邽�߂ɂ́A�ړ����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�ǂ̂悤�ȓ������A���邢�͉����x���U��q�̓����ɉe����^���A�s���m�ƂȂ�B�]���āA�����^�щ\�Ȍv�����u�ɂ͑��̎d�g�݂��g�p����K�v������B�U��q���v�͍����ł́A�����I�ŁA�A���`�[�N�̉��l�̗��R���珊�L����Ă���B
�@
�����j
�@
�U��q���v�̓h�C�c�̉Ȋw�҂ł���N���X�e�B�A�[���E�z�C�w���X�ɂ��1656�N�ɔ�������A���N�ɓ��������ꂽ�B�z�C�w���X�͔ނ��f�U�C���������v�����邽�߂Ɏ��v�E�l�̃T�������E�R�X�^�[(Salomon Coster)�ƌ_������сA�R�X�^�[�����ۂ̎��v�������̂ł���B�z�C�w���X��1602�N�Ɏn�܂�K�����I�E�K�����[�̐U��q�̌����ɐG�����ꂽ�B�K�����I�͐U��q���v���@�\�ɗL�v�ƂȂ鐫���A���Ȃ킿�������������B����͐U��q�̐U���̎������ߎ��I�ɂ͐U���̑傫���Ɉˑ����Ȃ��Ƃ������Ƃł���B�K�����I��1637�N�ɐU��q���v�̃A�C�f�A�������Ă���A�ނ̎q����1649�N�ɕ����I�ɍ\�z�������A�ǂ���������ɂ͎���Ȃ������B�U��q�͌v���@�\�Ɏg�p���ꂽ�ŏ��̒��a�U���q�ł���A����̓����͎��v�̐��x�����I�ɑ��債�A1��15���ł��������̂�15�b�ƂȂ�A����ɂ��A�����́u�o�[�W�ƃt�H���I�b�g�ɂ�鎞�v�v����蒼����A�U��q�Œu����������ɂ�A�}���ɍL�܂邱�ƂɂȂ����B
�@
�����̏����̎��v�̓o�[�W�E�G�X�P�[�v�����g�ɂ��A�U��q�̐U�����傫���A100���ɂ��Ȃ����B1673�N�̐U��q�̕��͂������{�u�U��q���v�v(Horologium Oscillatorium)�̒��ŁA�z�C�w���X�����������Ƃ́A�傫�ȐU���͐U��q��s���m�ɂ��A���̌��ʁA���u�Œ����쓮�͂ɂ������Ǝ��v�̑��x�ɔ�������Ȃ��ϓ��������邱�Ƃł������B
�@
���v�����Ǝ҂͐U���p�x�����x�ł���U��q�݂̂��������������ƂɋC�����A����ɂ��1670�N���A�A���J�[�E�G�X�P�[�v�����g���������ꂽ�B�A���J�[�E�G�X�P�[�v�����g�͐U��q�̐U����4��-6���ɐ��������B���̃A���J�[�͐U��q���v�̕W���I�ȃG�X�P�[�v�����g�ƂȂ����B���債�����x�ɉ����A�A���J�[�̋����U���ɂ��A���v�̔��́A��蒷���A���x���U��q�����[���邱�ƂɂȂ�A����ɂ��A�K�v�Ƃ���铮�͂͏������Ȃ�A���͋@�\�̖��Ղ����������B�b�U��q(����̓��C�����U��q�Ƃ��̂���)�ł�1��̐U����1�b�ŁA���悻1���[�g��(39.37�C���`)�̒���������A�L���g�p����邱�ƂɂȂ����B���̎���̒����ċ������v�́A�ŏ��̓E�B���A���E�N�������g(William Clement)�ɂ���Đ�������A�u���c������̎��v�v(grandfather clock)�Ƃ��Ēm���邱�ƂɂȂ����B���̂悤�Ȑi�W�̌��ʁA���v�̐��x�����債�A����ȑO�͂܂�ł��������j��1690�N���Ɏ��v�̔Ֆʂɕt���������邱�ƂɂȂ����B
�@
�U��q���v�̔����Ȍ�A18���I��19���I�̎��v�̊v�V�̔g�͐U��q���v�ɑ����̉��ǂ������炵���B���i��(deadbeat)�G�X�P�[�v�����g��1675�N�Ƀ��`���[�h�E�^�E�����[(Richard Towneley)���������A1715�N�ɂ̓W���[�W�E�O���n��(George Graham)���ނ̐����W�����v(precision regulator clock)�Ɏg�p�������Ƃ����ʂɍL�܂�A����唼�̌���̐U��q���v�Ɏg�p����Ă���B�U��q���v���Ăɒx���Ȃ邱�Ƃ���A���x�̕ω��ɂ��A�U��q�̖_���L�т���k�肷�邱�Ƃ��G���[�̌����ł��邱�Ƃ��킩�����B����͉��x������U��q�̔����ʼn�������A1721�N�ɂ̓W���[�W�E�O���n���ɂ�鐅��U��q�A1726�N�ɂ̓W�����E�n���\��(John Harrison)�ɂ��u���̂��^�U��q�v(���邢�́u�i�q���U��q�v,grid-iron pendulum�U��q���������ꂽ�B�����̉��ǂɂ��18���I�����ɂ͐����U��q���v��1�T�ԂŐ��b�̐��x�����������B
�@
19���I�Ɏ���܂ŁA���v�͌l�̐E�l�ɂ�����ł���A�ƂĂ������ł������B���̎���̐U��q���v�̖L���ȏ���͂��̉��l���x�T�Ȑl�̐g���̏ے��ł��邱�Ƃ������Ă����B���[���b�p�̂ǂ̍��́A�ǂ̏ꏊ�̎��v�E�l���A�ނ玩�g�̓��L�ȗl���W�������B19���I�܂łɁA���v�̕��i���H��Ő��Y�����悤�ɂȂ�ƁA����ɒ����K���͐U��q���v����ɓ���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B
�@
�Y�Ɗv���̊ԁA���X�̐����͉ƒ�̐U��q���v�ɂ���ĕҐ�����Ă����B�����Ɛ��m�ȐU��q���v�́A�W�����v(regulator)�ƌĂ�A�d����ɐݒu����A�d���̊Ǘ��⑼�̎��v�����킹��̂Ɏg�p���ꂽ�B�ł������ȕ��͓V���W�����v(astronomical regulator)�ƌĂ�A�V�̊ϑ����œV�̊ϑ��Ɏg�p���ꂽ��A���ʂɎg�p���ꂽ��A�V���q�@�Ɏg�p���ꂽ�B19���I�̎n�߂ɊC�R�V����̓V���W�����v�͍����ɂ����鎞���z�M�T�[�r�X�̂��߂̎�v�ȕW���̖�ڂ��ʂ������B1909�N����́A�����W����(National Bureau of Standards)(���݂�NIST)�͕č��̎����̕W�������[�t���[(Riefler)�U��q���v�Ɋ�b��u�����B���̎��v��1���ɂ��悻10�~���b�̐��x���������B1929�N�ɂ́A�V���[�g�E�V���N���m�[��(Shortt-Synchronome)���R�U��q���v�Ɉڍs���A1930�N�ɂ̓N�H�[�c���v�Ɉڍs�����B�V���[�g(Shortt)��1�N��1�b�قǂ̐��x������A���p�Ő��Y���ꂽ�U��q���v�ł͍ł����x���������̂ł������B
�@
�U��q���v��1927�N�ɃN�H�[�c���v�����������܂ł�270�N�ԁA���m�Ȍv���̂��߂̐��E�W���ł���A����E���̊Ԃ��W���Ƃ��Ďg�p���ꂽ�B�t�����X��1954�N�Ɏ���܂ŁA�W�����v�Q�̈�Ƃ��āA�U��q���v���g�p�����B����(2007�N)�Ɏ���܂łŁA�ł����m�Ȏ����I�ȐU��q���v�ł�1990�N���Edward T.Hall�ɂ���č��ꂽLittlemore���v�ł��낤�B�@ |
���d�g��
�@
�@�B���̐U��q���v�͂��ׂĎ���5�̕��i�������Ă���B
�@
�����͌��A���Ԃ����߂̕R�ɕt�����d��A�������̓[���}�C
�@
�����Ԃ̗�(�z�C�[���̗�)�A����͓��͌��̑��x�������グ�A�U��q���g�p�ł���悤�ɂ���
�@
���G�X�P�[�v�����g�A����͐��m�Ȏ��ԂŏՌ���U��q�ɗ^���A�U��q��h�ꑱ�������A�����Ď��Ԃ̗���J�����A1��̗h�ꂲ�Ƃɒ�߂�ꂽ�ʂ����O�i������B���ꂪ�����Ă���U��q���v�́u�`�N�^�N�v���̌���
�@
���U��q�A�R�ɕt�����d��
�@
���w����A���邢�͔ՖʁA����͂ǂꂾ���G�X�P�[�v�����g����]�������A�]���Ăǂ�قǂ̎��Ԃ��o�߂����̂����L�^����B�ʏ�A�`���I�Ȏ��v�̖ʂɂ͉�]����j���t���Ă���B
�@
�����Ɛ��I�ȐU��q���v�͈ȉ��̕��G�ȕ����܂�ł��邱�Ƃ�����B
�@
���ŏ����Ԃ̗�(Striking train) -- 1���Ԃ��ƂɎ��Ԃ̐������`���C����炷�A�����Ɛ��I�Ȃ��̂ł�15�����Ƃɖ炵�A�� -- �ʏ�̓E�F�X�g�~���X�^�[�E�`���C�� -- ��炷���Ƃ�����B
�@
���J�����_�[�ՁA�j���Ɠ��t��\���A���ɂ͌����\������
�@
�����̑��̔ՁA���̑�(��������)��\������A��]����~�̏�Ɍ��̊G���`���Ă���B
�@
���ώ����ՁA����͏����̂��̂Œ������A���߂ɑ��z������ɗ������Ɏ������킹�邽�߂ɂ���B����͎��v�ŕ\������鎞�ԂƁA���z�̈ʒu�ɂ�鎞�Ԃ̈Ⴂ��\������B���̈Ⴂ�͔N�ԂŁ}16�����x�B
�@
���J��Ԃ����u(Repeater attachment)�A����̓m�u�������Ǝ����̃`���C�����J��Ԃ��B���̒��������u�́A��ԂɎ�����m�肽�����ɁA�l�H�̏Ɩ����ł���ȑO�Ɏg�p���ꂽ�B
�@
�@�B���̃}�X�^�[���v�Ƃ��Ďg�p�����d�C�@�B���U��q���v�́A���͌����d�C���͂̃\���m�C�h(solenoid, ���^�R�C��)�Œu���������A����͎��C�ɂ��U��q�ɏՌ���^����B�܂��G�X�P�[�v�����g���A�X�C�b�`���邢�͌����o��Œu���������A����ɂ��U��q���Ռ���^���鐳�����ꏊ�ɂ��邱�Ƃ����m����B�������A�����ƍŋ߂̃N�H�[�c�U��q���v�ƍ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�N�H�[�c�U��q���v�͓d�q�N�H�[�c���v�̃��W���[�����U��q��h�炵�Ă���̂ł���A�{���̐U��q���v�ł͂Ȃ��A���̂Ȃ�A�v���̓��W���[�����̃N�H�[�c�E�N���X�^���ɂ���Đ��䂳��A�h��Ă���U��q�͒P�ɏ���̃V�~�����[�V�����ł����Ȃ�����ł���B
�@
���d�͐U��q���v(Gravity-swing pendulum)
�@
�U��q�̎����͗L�����̕������ɔ�Ⴗ��B�U��q���v�̑����͐U��q�̏d���_�̏�ŏグ���艺�����肷�邱�Ƃɂ���Ē��߂���B�����Ώd��̉��ɒ��ߗp�̃i�b�g������B�����̐U��q���v�ł́A�������ɂ͕⏕���߂��g�p����A�����ȏd���U��q�̖_�ɉ����ď㉺������B�����̓��̎��v�ł́A���߂͖_�̏�ɓ��ڂ��������ȎM�Ŏ������Ă���A�����ɏ����ȏd����t�����������菜�����肵��(�U��q��)�L������ω������A����ɂ��(���v��)���������v���~�߂��ɒ��߂ł����B
�@
�����x�
�@
�����𐳊m�ɕۂ��߂ɁA�U��q�͒ʏ�͔M�ω��Œ������ϓ����Ȃ��悤�ɍ���Ă���B�������c�����邱�Ƃɂ��A�U��q�̒��������x�Ƌ��ɕϓ����A���x���オ��Ƌ��Ɏ��v�͒x���Ȃ�B�����̍����x���v�͉t�̂̐����U��q�̏d��̈ꕔ���̏d�S���グ�邽�߂Ɏg�p���A����ɂ��U��q�̗L�����������B�W�����E�n���\��(John Harrison)�͂��̂��^�U��q(gridiron pendulum)�����A���قȂ�M�c���������������牡���肷��o���W���[��������B���̂悤�ȋ����ɂ͐^�J�A�����A�|�Ȃǂ�����A����ɂ��L�łȐ���̎g�p���T���A�L����0�̐U��q�����������B19���I�̏I���ɂ͔M�ɂ��ϓ������ɏ��������������p�\�ƂȂ�A���ꂪ�P���ȐU��q�̖_�Ɏg�p���ꂽ�B���̂悤�ȕ����ɂ̓C���o�[�A�j�b�P���^�S�����A�n�Z�V���J�A�܂�K���X���܂܂�Ă����B��҂͂��܂��ɏd�͌v(gravimeter)�̐U��q�Ƃ��Ďg�p����Ă���
�@
����C��R
�@
�U��q���h����C�ɂ͔S�x������A����͋C���A���x�A���x�ɂ��ω�����B���̒�R��������͂��K�v�Ƃ���A���͂͂���ȊO�Ɋ����߂��̎��Ԃ��g�傷��̂Ɏg�p�����B�U��q�͐��x���グ�邽�߂ɁA��C��R--���ꂪ���͂��ł��K�v�Ƃ��鏊--�����炷���߂ɖ����ꂽ�藬���^�ɂ��邱�Ƃ�����B19���I��20���I�n�߂̓V����̎��v�̐U��q�͊i�[�e����œ��삳���A��C��R�����炷���߂ɋC���������āA�U��q�̐U������荂���x�ƂȂ�悤�ɂ����B
�@
�����������ƃ`�N�^�N��(Leveling and 'beat')
�@
���𐳊m�ɍ��ނ��߂ɂ́A�U��q���v�͐�ɐ����łȂ��Ƃ����Ȃ��B�����łȂ��ƁA�U��q�͈���ɌX���A�G�X�P�[�v�����g�̑Ώ̓��������Ă��܂��B���̏�Ԃ́A���v�̃`�N�^�N�����畷����邱�Ƃ��ł���B�`�N�^�N���͐��m�ɓ����Ԋu�Łu�`�N...�^�N...�`�N...�^�N�v�̂悤�ɕ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���������łȂ��A�����u�`�N.�^�N...�`�N.�^�N�v�̂悤�ɕ�������A���v�̓`�N�^�N�ُ�(out of beat)�ɂȂ��Ă���A�����ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���̖��ɂ�莞�v�͊ȒP�ɒ�~���A���ꂪ�C���˗��̍ł����ʂ̗��R�ł���B������⎞���������(watch timing machine)������`�N�^�N���Ɉˑ�������@���͍����x�ɔ��f�ł���B�Â������u�����̎��v�ɂ͂����A�r�ɐ����ɂ��邽�߂̒����p�̃l�W���������A���V�������̂ł͋@�B���u�̒��ɐ������ߑ��u���t���Ă����B����I�ȐU��q���v�ł́A�`�N�^�N���̎������ߑ��u���t���Ă��āA���̒����͂���K�v���Ȃ��B
�@
���Ǐ��d��(Local gravity)
�@
�U��q�͏d�͂̑����ɂ�葬���Ȃ�A�Ǐ��d�͈͂ܓx�⍂�x�ɂ���ĕω����邽�߁A�U��q���v���ړ��������Ƃ͒������Ȃ����K�v������B�Ⴆ�A�U��q���v���C��4000�t�B�[�g�̒n�_�Ɉړ�����A1��������16�b�x��邱�ƂɂȂ�B���v�����������̒���Ɉړ�����A�d�͂��Ⴍ�Ȃ邽�߁A����\�ƂȂ邭�炢�ɒx���Ȃ�B
�@
���˂���U��q���v(Torsion pendulum)
�@
�u�˂���U��q�v�́u�˂���o�l�U��q�v�Ƃ��Ă�A�ւ̂悤�ȉ�(�唼�͌�������X�|�[�N��4�̋������Ă���)�ŁA���ꂪ�o�l�|�̐�����(���{��)����݂艺�����Ă���A�˂���U��q���v�̓������u�ƂȂ��Ă���B��(��������)��]���āA�T�X�y���V�����E�X�v�����O�������グ����A�����߂����肷��B�C���p���X���X�v�����O�̏㕔�ɉ�������B�d�͐U��q���������ƂĂ��x���A30�����邢��1�N���l�W�������K�v���Ȃ��B1�N�ԁA�l�W�������K�v���Ȃ����v�́u400�����v�v�A�u�i�v���v�v���邢�́u�L�O�����v�v�Ƃ��Ăꂽ�B�u�L�O�����v�v�ƌĂꂽ�͎̂��X�����L�O���̑��蕨�Ƃ��ꂽ����ł���B�h�C�c�̉�Ђł���Schatz��Kundo�͂��̌`���̎��v�̎�Ȑ����Ǝ҂ł������B���̌^���̎��v�͋Ǐ��d�͂̉e�����Ȃ����A����Ă��Ȃ��U��q���v���͉��x�ɉe�������B
�@
�O��������Ǝ��Ă���u�����v���ŋ߂悭�������܂��B�A���A����͊O��������(�d�r��2�g�K�v)�A���炭�u�˂���U��q���v�v�̊O����^���������̂��Ǝv���܂��B
�@
���G�X�P�[�v�����g(Escapement)
�@
�G�X�P�[�v�����g�́A�ʏ�͎��ԑ��u����U��q���쓮���A���������ޕ����ł���B�唼�̃G�X�P�[�v�����g�ɂ͌Œ��ԂƋ쓮��Ԃ�����A�Œ��Ԃł͉��������Ȃ��B�U��q�̓������G�X�P�[�v�����g���쓮��Ԃɐ�ւ��A�G�X�P�[�v�����g�͎��ɐU��q�̎����̂��镔���ŐU��q�������B���ڂ��ׂ��A��������������O���n���\���̃O���X�z�b�p�[�E�G�X�P�[�v�����g�ł���B�������v�ɂ����ẮA�G�X�P�[�v�����g�͏����ȏd���o�l�ɂ���Ă����Β��ڋ쓮����A��������ȏd���o�l�̓������g���[���ƌĂ��Ɨ��̎d�g�݂ɂ���ĕp�ɂɃ��Z�b�g�����B����ɂ��A�G�X�P�[�v�����g�����ԑ��u�̕ϓ��̉e�������������B19���I����ɂ����ẮA�d�C�@�B���̃G�X�P�[�v�����g�����W�����B����ɂ����ẮA�@�B�I�X�C�b�`��d�q���d�ǂ��U��q�̗h��̂����Z�����Ԃɓd���ɒʓd����B�����́A�m���Ă�����ɐ����Ȏ��v�̊���Ŏg�p���ꂽ�B�ʏ�͓V�����v�Ő^��U��q�Ƌ��Ɏg�p���ꂽ�B�U��q���쓮����d�C�̃p���X�͎��ԑ��u�����s�X�g�����쓮�����B
�@
20���I�ɁAW.H.�V���[�g(W.H. Shortt)�͎��R�U��q���v�^�V���[�g�E�V���N���m�[�����v�������B���̎��v�̐��x��1����1�b��100����1�ł������B���̎��v�ɂ����ẮA�v���U��q�͉��������ɁA�d����t�����A�[��(�d�̓A�[��)�ɉ�����ē��������Ă���B�d����t�����A�[���͕K�v�ƂȂ钼�O�ɁA�ʂ�(�]������)���v�ɂ���āA�U��q�ɉ��낳���B���ɏd�̓A�[���͎��R�U��q�ɉ��������A���S�Ɏ��R�U��q�ɂ���Č��肳�ꂽ���ԂɊJ�������̂ł���B��U�A�d�̓A�[�����J�������ƁA�d�̓A�[���͑��u���J�����A�]�����v�ɂ��A�������邱�Ƃɔ����Ď������g�����Z�b�g����B�S�̂̎����͏]�����v�̐U��q�̏�̏����ȃu���[�h�E�X�v�����O�ɂ���ē���������Ă���B�]�����v�́A�����x�������悤�ɐݒ肳��A�d�̓A�[���̃��Z�b�g�E�T�[�L�b�g�͐���A�[�����N�����A�u���[�h�E�X�v�����O�̐�ɐڐG����B�������]�����v���]��x���悤�Ȃ��Ƃ�����A�u���[�h�E�X�v�����O�̓A�[���������A����ɂ��U��q�����������B����ɂ�鎞�Ԃ̐i�ݕ��̓u���[�h�E�X�v�����O�͎���̎����ɂ͏]�������A���̎��ɏ]������B���̌`���̎��v��1920�N��̒����납��V����̎g�p�̕W���ƂȂ������A�N�H�[�c���v������Ɏ���đ������B
�@
�������\��(Time Indication)
�@
�����\���́A�قƂ�Ǐ�ɓ`���I�ȔՖʂŁA�����Ɏ��j�ƕ��j���t���Ă���B�����̎��v�ł́A��O�̏����Ȑj���⏕�Ֆʂ̏�ŕb��\������B�U��q���v�́A�ʏ�̓K���X�̃J�o�[���J���ĕ��j��Ֆʂ̏�ł܂킵�Đ����������ɍ��킹��悤�Ƀf�U�C������Ă���B���j�͊���₷���t���N�V�����E�X���[�u�̏�ɓ��ڂ���A����ɂ��X���[�u�̏�ʼn�]���邱�Ƃ��ł���B���j�͎��Ԃ̗�ŋ쓮����Ă���̂ł͂Ȃ��A���j�̎��ɐڑ����ꂽ�����Ȉ�A�̎��Ԃɂ���ċ쓮����Ă���B�]���āA���j����]����Ύ��j�������I�ɉ�]����B
�@
���X�^�C��(Style)
�@
�U��q���v�͒P�Ɏ��p�I�Ȍv�����u�ȏ�̂��̂ł������B�U��q���v�͏��L�҂̕x�ƕ�����\�����邽�߂̍����g���̏ے��ł������B�U��q���v�͈Ӑ}���ꂽ�p�r�͂��Ƃ��̂��ƁA�قȂ鍑�Ǝ���ɌŗL�ȓ`���I�X�^�C���Ŕ��W�������B���̃X�^�C���͂��̎���ɐl�C�̂������Ƌ�̃X�^�C�������������f���Ă���B���Ƃ́A�A���e�B�[�N���v�̔��ƕ����Ղ̔����ȈႢ����A���\�N�ȓ��̐��x�ŁA�������ꂽ���������肷�邱�Ƃ��ł���B�ȉ����A�U��q���v�̊���̌`���ł���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���j���[�g���u���R�N�w�̐��w�I����(�v�����L�s�A)�v���� 1687�N |
   �@
�@
|
Newton, Sir Isaac.(1643-1727)
�@
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
�@
�j���[�g���̓C�M���X�̕����w�ҁA�V���w�ҁA���w�ҁB17���I������ɂ�����V���w����ї͊w�̎�v���́A�K�����C�̗��̂Ɋւ��錤������ʉ����ė͊w�̍��{�������m�����邱�ƂƁA�V�̊Ԃɍ�p����͂̐��������߂Ęf���̉^���Ɋւ���P�v���[��3�@����������邱�Ƃł������B����2�̖������������̂��{��(�P�Ɂ��v�����L�s�A���Ƃ�����)�ł���B���̒��Ńj���[�g���́A�������g�����������^���̖@���▜�L���̖͂@�����܂Ƃ߁A����ɂ����̖@���Ɋ�Â��Ęf���⌎�̉^���ɂ��Ę_���Ă���B�{�������ɏo�Ă���200�N�̊Ԥ���̏����̑�v�͂قƂ�Ǖϊv����邱�ƂȂ��A�㐢�̗͊w�͂��ׂĖ{�����ʊ�b�Ƃ��Ēz���グ��ꂽ�B�₪�đ��ΐ����_��ʎq�͊w�ɂ���ăj���[�g���͊w�͉��ς�]�V�Ȃ����ꂽ���A������̏ꍇ�ɂ��Ɍ��̋ߎ��l�Ƃ��Ă͍����ł��\���̐������������Đ��藧�̂ł���B�@ |
�����R�N�w�̐��w�I������
�@
(Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica)�@�A�C�U�b�N�E�j���[�g���̒����̂ЂƂŁA�j���[�g���̗͊w�̌n������������B1687�N���A�S3���B�ÓT�͊w�̊�b��z��������I�Ȓ���ŁA�ߑ�Ȋw�ɂ�����ł��d�v�Ȓ����1�B�^���̖@���𐔊w�I�ɘ_���A�V�̂̉^���▜�L���̖͂@���������Ă���BPrincipia �Ƃ������̂ł��悭�m���Ă���B���{��ł́u�v�����L�s�A�v�u�v�����V�s�A�v�ƕ\�L�����B
�@
���̖{���o�ł��ꂽ���������E���@�Ƃ��Ă̓G�h�����h�E�n���[�Ƃ̂��Ƃ肪����Ƃ����B�G�h�����h�E�n���[��1684�N�̉ĂɃP���u���b�W��w��K�₵���̂����A�����Łu�f���������̕����ɔ���Ⴗ��͂ő��z�Ɉ�������Ɖ��肵���ꍇ�A�f�����`���Ȑ��͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��낤���H�v�ƃj���[�g���Ɏ��₵�����Ƃ��Ƃ����B���̎���ɑ��ăj���[�g���́u�ȉ~���낤�v�Ƒ��������B�j���[�g���͂���ȑO�Ɏ������g�ł��������v�Z�����݂����Ƃ�����A���łɓ����Ă����̂��Ƃ����B
�@
�����ăj���[�g����1684�N11�����A�n���[�Ɂu��]���Ă��镨�̂̉^���ɂ��āv�Ƃ����_���𑗕t�����B�����ǂn���[���j���[�g���ɂ��̘_�����܂߂ăj���[�g���̗͊w�����̐��ʂ��o�ł��邱�Ƃ�E�߁A���_���̓v�����L�s�A��ꊪ�̍��q�ƂȂ�A1687�N�̉č��A500�y�[�W�]��̃v�����L�s�A���ł��o�ł���邱�ƂƂȂ����B�܂��j���[�g���̓��ɂ̓L���X�g���I�Ő_�ɂ�钁�����Ă�ꂽ���E�ς��������Ƃ���_�w�I�ȓ��@�����������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B������ɂ���n���[�ɑE�߂��Ă��珉�ň���Ɏ���܂ŁA���̏��ɌX�����j���[�g���̏�M�A���i�Ԃ�͐��܂������̂ł������ƌ����Ă���B
�@
1687�N�łɏ��ł��o�ł���A1713�N�ɂ͑��ł��A1726�N�Ƀw�����[�E�y���o�[�g�����ҏW������O�ł��o�ł��ꂽ�B
�@
�����̓��e����ŏ�����Ă���B �S3���ł���A���ꂼ��̊��̃^�C�g������їv�_�͈ȉ��̂Ƃ���B
�@
��1�� ���̂̉^���ɂ��� �^�̕��̂̉^���@��
�@
��2�� ���̂̉^���ɂ��� ��R�̂���}���̒��ł̕��̂̉^���@��
�@
��3�� ���E�̑̌n�ɂ��� �����̉F���̐��w�I�Ȃ����݂������Ă���A�n����̕��̂ł���A���z�̂܂����܂��f���ł���A�a���ł���A���̈ʒu���A���L���͂̐��w�I�@���ɂ���ē���I�ɐ����ł���A�Ƃ������Ƃ������Ă���B
�@
�S����ʂ��Đ��w�I�ȓ���Ƃ��Ă͌����I�Ƀ��[�N���b�h�́w���_�x��p���Ă���B����ɓW�J�̌`�����w���_�x�P���Ă���A�����_�I�Ȍ`�����̗p���Ă���B�ŏ��Ɍ����������A���̌������g���ďؖ�����Ƃ��������Ői��ł��������ł���B
�@
�����A�������i�ݎn�߂Ă��������E�ϕ��͗p�����A�ł��邾�����[�N���b�h�w������p���ĉ�����悤�Ƃ������߁A���ɑ啔�̒���ɂȂ��Ă���B����́A������ϕ��ȂǂŃv���C�Z���̃S�b�g�t���[�g�E���B���w�����E���C�v�j�b�c��Ƃ��̓��e(��Ύ���)��\�L�@�Ȃǂő����Ă������߂Ɛ�������Ă���B�j���[�g���ƃ��C�v�j�b�c�͎��Ԃ̑������ł���Ԃ̑������ł������Ό��������{�I�ɑ��Ⴕ�A�������Փ˂��Ă���(��Ԃ̋L�����Q�Ƃ̂���)�B�������A�ꕔ�ł͂��邪�㐔��͂�p���Ă���ӏ��������킯�ł͂Ȃ��B
�@
�o�œ����A���ɓ�����ƌ���ꂽ�B��q�̂��Ƃ�������ɂ��̗p���ꂽ���w�I��@�����G�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����ł������B�v�����L�s�A�̏o�łɂ��ÓT�͊w�̊�b���z���ꂽ�̂ł��邪�A���̔��ʁA�j���[�g������g�������w�I�Z�@�����G�ł��������ߎ��R�N�w����ʂ̑f�l�ɂ͋߂Â��ɂ������̂ɂ��Ȃ����B
�@
��O���Ŏ����ꂽ���E�ς̓L���X�g���i��̂��߂Ɋ��p���ꂽ�B�j���[�g���̗F�l�̃{�C���̈�Y�����Ƃɍs����悤�ɂȂ����{�C���E���N�`���[�Y(en:Boyle Lectures)�Ƃ�����A�̍u�`�ɂ����āA���R(�F��)�����w�I�ɒ��������Ă��邱�Ƃ��v�����L�s�A��p���Đ������A����ɂ��_�����݂��Ă��邱�Ƃ������ꂽ�B
�@
��́u��R�̂���}�����ɂ����镨�̂̉^���v�́A���e�����e�ł������ɂ�������炸�p����ꂽ���w�I������[�N���b�h�w�����ł��������Ƃɂ������s���ƂȂ��Ă����ʂ��������B�嗤���ł̓��C�v�j�b�c�̐��w�I��@���p�����鎩�R�N�w�҂���������A�j���[�g�����v�����L�s�A�ŗp�������w�I��@�����C�v�j�b�c���̔����ϕ��w�ŏ����������Ƃ��s�����B����ɂ��A��́u��R�̂���}�����ɂ����镨�̂̉^���v�͓����j���[�g���ɂ���ď�����Ă��������A���Ȃ茵���ɐ��������悤�ɂȂ����B
�@
18���I�ɂ̓��O�����W�����j���[�g���͊w�̌�̗͊w�̔��W�𑍍����w��͗͊w�x(1788)�ɂ܂Ƃ߂邱�ƂɂȂ���(��͗͊w�B���O�����W���͊w)�B�@ |
���A�C�U�b�N�E�j���[�g��
�@
(Isaac Newton, 1643-1727)�@�C���O�����h�̓N�w�ҁA���R�N�w�ҁA���w�ҁB�_�w�ҁB�j���[�g���͊w���m�����A�ÓT�͊w��ߑ㕨���w�̑c�ƂȂ����B�ÓT�͊w�͎��R�Ȋw�E�H�w�E�Z�p�̕���̊�b�ƂȂ���̂ł���A�ߑ�Ȋw�����̐����ɉe����^�����B
�@
�A�C�U�b�N�E�j���[�g����1642�N�̃N���X�}�X�� �C���O�����h�̓��C�݂Ɉʒu���郊���J�[���V���[�B�̏��s�s�O�����T��(�p���)��������10km�قǗ��ꂽ�ꊦ���E�[���X�\�[�v���o�C���J�[���X�^�[���[�X(�p���)(Woolsthorpe-by-Colsterworth)�ɂ����āA�����̃A�C�U�b�N�E�j���[�g���Ƃ��āA�n�i�E�A�X�L���[���Ƃ��Đ��܂ꂽ���A���܂ꂽ�����e�͂��łɑ��E���Ă����B���n���Ƃ��Đ��܂ꂽ�Ƃ����Y�k�͂��̎q�͒��������܂��A�ƌ������Ƃ����B�Ȃ��A�A�C�U�b�N�Ƃ������́A ���� �́w�n���L�x�ɓo�ꂷ�鑾�c�̈�l�C�T�N�ɗR������B
�@
���e�́A�g���Ƃ��Ă̓��[�}��(�Ɨ����R�_��)�ƋM���Ƃ̒��ԓI�Ȉʒu�Â��̐g��(���̋��m�̂悤�Ȃ���)�Ŕ_�����c�݁A37�̎��ɋߍx�̔_�Ƃ̖�(�A�C�U�b�N�̕�n�i�E�A�X�L���[)�ƌ����������A�A�C�U�b�N�����܂��3�����O�Ɏ�������(��Ƀj���[�g���̋`���ƂȂ�l���́A���̕����e��ȕϐl�ł������A�Əq�ׂ��Ƃ����B�����̈�Ƃ͓����̃C���O�����h�Ŗu�����������m���K���ɑ�����҂������A��t�A��t�A�q�t�Ȃǂ�y�o���Ă���)�B
�@
����̓A�C�U�b�N��3�̎��ɋߗׂ̖q�t�̃o�[�i�o�X�E�X�~�X�ƍč����ăA�C�U�b�N�̌��𗣂�A�A�C�U�b�N�͑c��ɗ{�炳��邱�ƂɂȂ����B�A�C�U�b�N�͕�������̂��Ȃ��N��ŗ��e�̈���m��Ȃ��q�ƂȂ����B��e���č��������R�̂ЂƂ͑��q�̗{���邱�Ƃ��������B��e�̓X�~�X�Ƃ̊Ԃ�3�l�̎q���Y�ނ��ƂɂȂ�B���q�A�C�U�b�N�͕�̂��̑I���ɔ����u�����ĉƂ��ƏĂ��E���v�ȂǂƎE�Q����|�𖾂����Ĝ����B���̈ꎞ�̌���ɋ��ꂽ�����������āA��N�͎���ƕt�������ꂸ�̊W��ۂ��ʓ|�������B
�@
��e�̓j���[�g���̍˔\�ɋC�t���Ă��Ȃ��������A�e�ނ�����ɋC�����Ă��ꂽ���Ƃ�����A1655�N�ɔނ̓O�����T���̃O���}�[�X�N�[���ɓ��w���邱�ƂɂȂ����B�w�Z�͎����7�}�C��������Ă����̂ŁA��̒m���̖�t�̃N���[�N�Ƃɉ��h�����B�j���[�g���͂��̉ƒ�ŁA��w�W�̑����ɏo��A����ɋ��������悤�ɂȂ����B�܂��A�N���[�N�Ƃ̗{���X�g�[���[�Ƃ͐e�F�ƂȂ���(�j���[�g���͂��̃X�g�[���[��18�ō��邱�ƂɂȂ�A��Ɏ���܂Őe���Ȍ��ۂƋ��K�I�ȉ����𑱂��邱�ƂɂȂ�B�����A�j���[�g���͖@�I�ɂ͌����͂����A�I���Ɛg�̂܂܂ł�����)�B�O���}�[�X�N�[��������A�j���[�g���͎��ȓI�Ȑ����𑗂�A�̎��W�A���ԁA�����v�A�����v�̐���Ȃǂ��s���Ă����B�܂��A�̂������������I�Ŗڗ����ʎq���������߁A�F�l�����̂��炩���̓I�ł��������A����Ƃ������������߂����N�ƌ��܂����ď��������Ƃ����������ɁA�����ɑ��鎩�M�����悤�ɂȂ����Ƃ����B���̏o�����Ƃ����������Ɋw�N�Ŏ�Ȃ̐��т��Ƃ�悤�ɂȂ����Ƃ�������B
�@
�w�Z�ɒʂ��悤�ɂȂ���2�N������14�ɂȂ������ɁA��̍č����肪�������A��͍č�����Ƃ̊Ԃɂł���3�l�̎q���ƂƂ��ɃE�[���X�\�[�v�̉ƂւƖ߂��Ă����B��́A(�S���Ȃ������̕v���₵��)�_�����c�ނ��Ƃ��l���A���e�̂悤�Ƀj���[�g�����_��(�S��)���s�����Ƃ����҂��A���̎d������`���Ă��炨���ƃO�����T���E�X�N�[����ފw�������B��e�͕w���͔_�Ƃ̂ق�����ƍl���Ă����炵���Ƃ����B�Ƃ��낪�j���[�g���͔_��Ƃ��ق����炩�����܂܁A(�O�̉��h���)�N���[�N�Ƃɍs���Ă͉��w����ǂ萅�ԂÂ���ɔM�������B���̂��߁A��͔ނ��S�������ł͂Ȃ��Ǝv���A�����̂��Ƃ�e�ނ�F�l���ɑ��k���A�P���u���b�W�̃g���j�e�B�J���b�W�Ŋw����ق����悢�Ƃ������������ꂽ�B�����āA�j���[�g����2�N��ɂ͊w�Z�ւƕ��w���邱�ƂɂȂ�A�����Ńg���j�e�B�J���b�W�̎̏��������邱�ƂɂȂ����B���Ƃŋ���������e�́A�����A�Z�p�A���e����A�Ñ�j�A�����ł������B
�@
1661�N�ɏf���ł���E�B���A���E�A�X�L���[���w��ł����P���u���b�W��w�g���j�e�B�E�J���b�W�ɓ��w�����B���w�����́u�T�u�T�C�U�[�v�Ƃ��ĉ��ɁA1������Ɂu�T�C�U�[ sizar�v�Ƃ��Đ����Ɏ����ꂽ�B����͍u�t�̏��Ԏg���Ƃ��ĐH�����^��g����������邩���Ɏ��Ɨ���H���Ə������A�Ƃ������̂ł������B�命���̊w���́u�R���i�[�v�Ƃ�������Ŋw����҂����������̂ŁA�j���[�g���͌��g�������v���������Ɛ��@����A���������g���ł��������Ƃ�A�����̉ƕ��̂��Ƃ�����A�������Ƒł������Ȃ������Ƃ����B
�@
�����A��w�ł̍u�`�̃J���L�������Ґ��́A�X�R���N�w�Ɋ�Â��čs���Ă���A�܂��Ƃ��ăA���X�g�e���X�̊w���Ɋ�Â��Ă������A�j���[�g���͓����Ƃ��Ă͔�r�I�V�������w���E���R�N�w���̂ق����D�݁A�f�J���g��K�����I�A�R�y���j�N�X�A�P�v���[�Ƃ��������R�N�w�҂̒������D��Ŋw�B�Ⴆ�A���w����ł́A�G�E�N���C�f�X�́w���_�x�A�f�J���g�́w�w�x���e����ő��ŁA�E�B���A���E�I�[�g���b�h��Clavis Mathematicae(�w���w�̌��x)�A�W�����E�E�H���X�́w�����Z�p�x�Ȃǂł���A���R�N�w����ł̓P�v���[�́w���܌��w�x�A�`���[���g���̌��q�_�N�w�̓��发�Ȃǂ�ǂ̂ł���B
�@
�����Ńj���[�g���͗ǂ��t�ɏ������ƂɂȂ����B�A�C�U�b�N�E�o���[�ł���B �P���u���b�W�ɂ�����1663�N�ɊJ�݂��ꂽ���[�J�X���w�u���̏��㋳���ɏA�C�����o���[�̓j���[�g���̍˔\�������]�����A����Ȕ��^�����B�o���[�͎��ԁA��Ԃ̐�ΐ����d�v������v���g����`������w�҂ł���A�j���[�g���̎v�z�ɂ��傫�ȉe����^�����B�o���[�̂�����������1664�N�Ƀj���[�g���́u�X�J���[�v(���w�����x�������w��)�ɂ��Ă��炤���Ƃ��ł��A����ɗ��N�ɂ͊w�ʂ����^����邱�ƂɂȂ�B�ނƂ̏o��ɂ���ăj���[�g���̍˔\�͊J�Ԃ��A1665�N�ɖ��L���́A�藝���A����ɔ�������є����ϕ��w�ւƔ��W���邱�ƂɂȂ����B�j���[�g���̎O��Ɛт͑S��25����܂łɂȂ��ꂽ���̂ł���B
�@
�܂��A�j���[�g���������������ʂ�̂ɗL���ɓ������ƂɂȂ�A�����ЂƂ̏o�������������B��l�ł�������Ǝv�����߂��炷���Ԃ��̂ł���B�w�ʂ��擾�������A�����h���ł̓y�X�g���嗬�s���Ă���(�y�X�g�͈ȑO14���I�Ƀ��[���b�p�̐l����1/3(�ȏ�)�����S�������قǂ̋��낵���a�C�������B�j���[�g�����w���̎��̂���͐��x�ڂ̏P���ł�����)�A���̉e���ŃP���u���b�W��w��������邱�ƂɂȂ�A1665�N����1666�N�ɂ�����2�x�A�j���[�g���̓J���b�W�Ŕނ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������G������������A�̋��̃E�[���X�\�[�v�ւƖ߂�A�J���b�W�ł��łɓ��Ă������z�ɂ��Ď��R�Ɏv�l���鎞�Ԃ��B�܂�1664�N�A�܂�y�X�g�őa�J����O�ɏ��w���̎����ɍ��i���ď��w���Ă������Ƃ��A�̋��ŗ��������Ă�������Ǝv������̂ɖ𗧂����B�������ăj���[�g���́u�����@�v�Ɣނ��ĂԂ���(=�����u�����ϕ��w�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ镪��)��A�v���Y���ł̕����̎���(���w)�A���L���͂̒��z�Ȃǂɖv�����邱�Ƃ��ł����̂ł���B���ǁA���̂킸��1�N���قǂ̊��ԂɃj���[�g���̎�v�ȋƐт�����яؖ����Ȃ���Ă���̂ŁA���̊��Ԃ̂��Ƃ́u���ق̏��N�v�Ƃ��A�u�n���I�x�Ɂv�Ƃ��Ă�Ă���B
�@
���L���̖͂@���Ɋւ��āA�Â��`�L�Ȃǂł́u�����S�̖��烊���S��������̂����Ė��L���͂��v�������v�Ƃ�����̂������������A��{�I�ɃE�[���X�\�[�v�؍ݓ����̕����L�^�╨������킯�ł͂Ȃ��A�͂邩���(���o�[�g�E�t�b�N�ƁA���L���͂Ɋւ��Đ�挠�����̂������������������)�����������A�ƃj���[�g�����m�l��e�ނȂǂɌ�����b�Ȃǂ����ƂɂȂ��ė��z�����b�ɂ����Ȃ��B�܂藘�Q�W�ғ��l�����b�₻�̓`���̗ނɂ������A���e�Ɋւ��Ă͐^�U���s���ł���B �`�L��Ƃ����p���鎑���Ƃ��āA������̍�ƃE�B���A���E�X�g�D�[�N���̏����� Memoirs of Sir Isaac Newton's Life ��1726�N4��15���Ƀj���[�g���Ɖ�b�����A�Ƃ���ȉ��̂悤�Ȃ����肪����B
�@
�gwhen formerly, the notion of gravitation came into his mind. It was occasioned by the fall of an apple, as he sat in contemplative mood. Why should that apple always descend perpendicularly to the ground, thought he to himself. Why should it not go sideways or upwards, but constantly to the earth's centre.�h
�@
���̕��͂��ނ��@���ɓ���ɋN���邱�ƂɊS�������A�������痝�_�ւ̒��z�Ă������Ƃ����ނ̌�����\�����邽�߂ɍ��ꂽ�b�A�Ƃ������Ă���A�^�U�͒肩�ł͂Ȃ��B�܂��A�j���[�g�������������N�ɁA���H���e�[���͔ނ̃G�b�Z�C Essay on Epic Poetry (1727)�̂Ȃ��Ŕނ��j���[�g���̖Âɕ������b�Ƃ��āu�A�C�U�b�N�E�j���[�g���͒�d�������Ă���ۂɁA�����S�̖��烊���S��������̂����āA�ނ̏d�͂Ɋւ���ŏ��̔��z���v�Ƃ����b���Љ�Ă���B
�@
�j���[�g�������L���̖͂@�����v���������������̓��@�́A�P�v���[�̖@���ł���B�P�Ȃ镨�������錻�ہA�n����ɂ��镨�̂�n������������͂Ƃ��Ắu�d�́v�ł���A�j���[�g���ȑO������ɒm���Ă���A�u���z���n���ɂȂ�炩�́w�쓮����́x���y�ڂ��Ă���v�ƃC���[�W�����̂̓P�v���[�ł���A���̗��҂����т����̂��j���[�g���̔����ł������B
�@
1665�N�ɃJ���b�W�𑲋Ƃ��A�o�`�F���[(Bachelor of Arts; �w�m)�̊w�ʂ��B
�@
1667�N�Ƀy�X�g�������܂�ƁA�P���u���b�W��w�ɖ߂�A���̔N��10���A����w�Ńt�F���[�E�߂Ă���2�����K�i���痎���������ɑ���1�����������A�������v3���������߁A�j���[�g���̓t�F���[�ɂȂ邱�Ƃ��ł��A��������x�������悤�ɂȂ����B(��Ȋw�҂ł́A���̂悤�ɏ��������ŁA�^�Ɍb�܂ꂽ�l�͋H���ƍ������F�͎w�E���Ă���B) ���̔N�Ɂw���������̉�� (De Analysi per Aequationes Numeri Terminorum Infinitas) �x��������(���s1671�N)�B�܂��_���w�����̋����ɂ���(De methodis serierum et fluxionum) �x�\�����B
�@
���̐��w�I�����ɂ��ĉ������ƁA�j���[�g���ƃ��C�v�j�b�c�͂��ꂼ��Ɨ��ɁA�قȂ������_��������ϕ��@�������B��X�A�D�挠���߂���������ȑ������W�J����邱�ƂɂȂ�B�j���[�g���̔��\�̓��C�v�j�b�c���x���̂����A���C�v�j�b�c��葁���������Ă����A�Ǝ咣�����B�j���[�g���͕a�I���ȋ^�S���������i�ŁA���C�v�j�b�c�����Ƃ̎咣�𑱂��āA����25�N�̒����ɂ킽��@�쓬�����s�����ƂɂȂ�B
�@
1669�N�ɃP���u���b�W��w�̃��[�J�X�����E�ɏA�����B����͎t�o���[���j���[�g���̍˔\��F�߂Ă��āA�����̃|�X�g���q�ɏ���Ƃ����`�Ŏ��������̂ł���B���t�̐\���o�ɑ��A�j���[�g���͈�x�f�������A���ǂ��̐\���o������邱�Ƃɂ����B���[�J�X�����Ƃ��Ă̋`���́A�w�A�Z�p�A�V���w�A���w�A�n���w�̂����ꂩ�̍u�`�w���킸��10��قǎ����ƂƁA�T��2��w���Ƃ̉�ɏo�邾���ł悢�Ƃ������̂ł������B�j���[�g���͎������J�����w�ɂ��ču�`�������A���e���a�V���������������������炵���A�w�����ЂƂ���u�`�Ɍ��ꂸ�o�Ȏ҂������Ƃ������Ƃ������������B
�@
���[�J�X��������ɁA�ނ̓�咘���ƂȂ�w���w(Opticks)�x�̎��M(���s��1704�N)����сw���R�N�w�̐��w�I�������x�̎��M�E���s(1687�N��)�A����ѐ���������B���p�̎����Ȃǂɖv�������B�j���[�g���͓N�w�҂ł������̂ŁA���R�w�ɑ����M�Ɠ������炢�̏�M�A���邢�͂���ȏ�̏�M��_�w�ɒ������B�j���[�g���̎���c���ꂽ����1624���̂����A���w�E���R�w�E�V���w�֘A�̖{��259����16%�ł���̂ɑ��āA�_�w�E�N�w�֘A��518����32%�ł���B
�@
�j���[�g�����N�w�҂Ƃ��āA����������B���p�������d�����A�M�S�Ɍ������s���w�͂��Ă����Ƃ��������ɂ��ẮA��̎���ɓo�ꂷ�邱�ƂɂȂ�Ȋw�҂������A���������̋C�ɓ���p�Y������邽�߂ɁA�������䂪�߂ď�������A���������ɓs���̈������������邩�����ʼnȊw�j�������Ƃ������Ƃ��J��Ԃ��ꂽ�̂ŁA�₪�ĖY����Ă��܂����ƂɂȂ����B20���I�ɂȂ�A�P�C���Y�Ȃǂ����j�I�����̎��W�E�Č����s���A�悤�₭���������Ȋw�j�̉R�A�Ȋw�҂�ɂ��R�����炩�ɂȂ������̂ł���B
�@
�w���R�N�w�̐��w�I�������x�����s(1687�N)���Ă܂��Ȃ��̂��ƁA���ʂɏA�����W�F�[���Y2�����P���u���b�W��w�ɑ��Ċ����Ă���Ƃ����o���������������A���̍ۍs��ꂽ1686�N�̖@��R���ɑ�w���̑S����\�O���[�v�̈���Ƃ��ĎQ�����A�B�R�Ɗ����͂˂̂��锭���������B���ꂩ��2�N���1688�N�ɂ́A��w����I�o���ꂽ�����@�c��(���@�c��)�ɂȂ邱�ƂɂȂ����B�����A�c���Ƃ��Ă͖w�ǔ��������Ȃ������Ƃ���A�c��ł̗B��̔����́u�c���A����߂ĉ������v�������Ƃ����B
�@
�j���[�g���͑咘�̎��M�̌�Ŕ��Ă���(�w���R�N�w�̐��w�I�������x�̎��M���犧�s�ɂ�����܂łɁA���o�[�g�E�t�b�N�Ɛ�挠���߂���m���������A����O���j�W�V���䒷�̃W�����E�t�����X�e�B�[�h�Ƃ�����I�Ȃ���������������)�A��w�ł̊w���I�����ɂ��肵�Ă����Ƃ���A��L�̂悤�Ȑ����I�Ȃ��Ƃւ̊ւ�肪�A��w���痣�ꂽ�����I�Ȑ��E�Œn�ʂ����Ƃ����~�]�ɉ������B�����ŋ����q�ŁA19�ΔN���Ȃ���Ќ𐫂ɕx�݁A�����܂�肪���܂��A���łɒ������E�Ől���������Ă����`���[���Y�E�����^�M���[�ɑ��Đ����֘A�̃|�X�g�𐢘b���Ă����悤�Ɉ˗������B�܂��v�����L�s�A�̊��s�ɂ��j���[�g���̒m���x���オ��A�L���ȓN�w�҃W�����E���b�N�Ƃ��m�������Ă����̂ŁA�ނɂ��|�X�g�̏Љ���˗������B�����A�����ɐF�ǂ��Ԏ������炦���킯�ł͂Ȃ������B
�@
���_�I�ɔ��Ă��������ɁA���Ă��O�ꂽ�`�ɂȂ����B�₪�ăj���[�g���͐��_��Ԃɕϒ����������悤�ɂȂ����B�s����H�~���ނɋꂵ�݁A��Q�ϑz�ɂ��Y�܂��ꂽ�B�W�����E���b�N�ւ̏��Ȃ̒��ɂ́A(�����q��)�`���[���Y�E�����^�M���[�͎����\���悤�ɂȂ����Ƃ��������e���������肵�����̂��c���Ă���B2�N�قǎ���Ɉ�������悤�ȏ�ԂɂȂ����Ƃ�������B������g�����h�ƕ\������l�����邪�A���a���x�ł͂Ȃ��������Ƃ����w�E�A�ň��̕ꂪ��������Ɏ��������Ƃ̉e�����������Ƃ̎w�E������(���1697�N6���Ɏ�������)�B�B���p�ɂ����Ă����Ώd�����𖡌�����Ƃ����s�ׂ����������߂Ɉꎞ�I�Ȑ��_�s���Ɋׂ����\������������Ă���B���̑s�N���ɂ�����X�����v�ɂ����Ă����]�͖����ŁA���[���b�p���ɓ���Ȑ��w����V���ɏo�肵�Ă������n���E�x���k�[�C�́u���������2�̓_������Ƃ���B��̕��̂���̓_���牺�̓_�܂ň��݂͂̂ŗ������鎞�ɗv���鎞�Ԃ������ƒZ������ɂ́A�ǂ̂悤�ȓ��ɉ����č~������Ηǂ����H�v�Ƃ����ő��~���_�ƌĂ�����1696�N�ɏo��A���N1���[���j���[�g���̉��Ɍf�ڎ��������A�o��ɖڂ�ʂ����j���[�g���͍����ϕ��@�ƌĂ��V�������w�̕�������őg�ݗ��āA�����̏o�ΑO�܂łɉ��I�������Ńx���k�[�C�ɓ��e�����B
�@
����ȋꂵ������ł͂��������A�₪�ċ����q�̃����^�M���[�����n��̂��܂������č�����b�ɂȂ�A1696�N4���ɂ̓j���[�g���ɉ��������NJĎ��̃|�X�g���Љ�Ă���A1699�N�ɂ͉��������ǒ����ɏ��i���邱�ƂɂȂ����B�����^�M���[�Ƃ��Ă͓����Â߂ł������t�ɏ������茤�����痣��Ď��ԓI�A�̗͓I�ɗ]�T�̂���n�ʂƐE�ɏA���������肾�������A�A�C���X�ʉU���l�̑ߕ߂���ɕЂ��[���牘�E��o���A����������j��ł��o�����B����w�����ɂ��Ă͑N�₩�Ȏ���݂ŁA�����̑{�����ɕϑ��p�̕���^����Ȃǂ��A�U�������V���W�P�[�g�̐e���V�����[�i�[��߂炦�čٔ��ɂ����A��t�߂�K�p���Ď��Y�ɂ����B �ݐE���͋U�����肪���������B����A��݂̋��݂ɑ��鑊�ΓI���l�̐ݒ�ɂ����Ďs��̋�̋��ɑ��鑊�Ή��l�������A���ʂ̋�����Ⴍ�ݒ肵�����ߋ�݂��n��������݂ƌ��������Ƃ������ۂ������N�����Ă���A����͐}�炸���C�M���X��������̋��{�ʐ��Ɉڍs���錴���ƂȂ����B�j���[�g���͑����NjΖ�����ɂ͋����Ɠ��ʎ蓖��2000�|���h����N���āA���Ȃ�T���ɂȂ����B�����āA�l��1720�N�܂łɓ�C��Њ���1���|���h�̓������s�����B�܂�C�M���X�j������Ƃ������������@�u�[��(South Sea Bubble ��C�A������)�Ƀj���[�g������낤�Ƃ��A�u�[���̊��Ԓ������������������Ɍ��ǃj���[�g���͑呹�������Ƃ����(��C��ЂƂ����̂̓C�M���X�̉�ЂŁA�X�y�C���̒���ĂƂ̖f�ՂœƐ茠�āA�z��f�ՂŖ\�����ނ��ڂ��Ă�����Ђł���A��C�A�������Ƃ͓��Ђ����`�����Ċ����\���������A���Ƃ̕s�U������݂ɏo��Ɗ��͖\������1720�N�ɓ|�Y���A�����̓����Ƃ��j�Y����Ɏ����������ł���)�B
�@
�����Ƃ��ẮA�����ǂɋ߂Ă���͘B���p�ɖv�������B(����̉Ȋw�҂��g�Ȋw�I�h�ƌĂԗނ̌����͍s���Ă��Ȃ��B���������ނ̋Ɛт����\���ꂽ�̂�1696�N�̓��ǂ܂ł�53�N�Ԃł���B)�ӔN�A�w��̐���̒������ϑ��Ɋւ�����j�I�L�q�x�����ƂɂȂ���̂́A�C�M���X������̋��`�Ƃ͈قȂ邽�߁A�e��������A���O�ɂ͔��\���Ȃ�����(1754�N��)�B�j���[�g���̍l���̊T���́u�O�ʈ�̂̋��`�̓A�^�i�V�E�X�������ɂ������̂������肾�v�Ƃ������̂ł���B�����������ƂȂǂ���A�ނ͂����炭�A���E�X�h�ً̈��k�A�܂胆�j�e���A���������̂��낤�A�Ƃ���w�E������Ƃ����B
�@
1705�N�ɁA�A����������i�C�g�̏̍���������ꂽ�B���^�̉��̓g���j�e�B�E�J���b�W�ŁA���R�N�w�̋Ɛтɑ�����̂ł������B���R�N�w(���R�Ȋw)�̋ƐтŃi�C�g�̏̍�������ꂽ�̂́A�j���[�g�����ŏ��ł���B
�@
���^����20�N�قnj��1727�N�Ɏ������A�E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɑ���ꂽ�B�⌾��͎c���Ă��炸�A��i�͉���Âɕ��z����A���L���Ă����_���͂���̖@�葊���l�̔_�v�Ɏp����A�j���[�g���̎���̓E�F�X�g�~���X�^�[�����}���قɂȂ����B�@
�@ |
 �@ �@
��18���I�@���[���b�p�s���Љ�̐��� / �o�ϊw�̐��� |
   �@
�@
|
18���I�̃��[���b�p�́A�ꐧ�N��̌Â������Љ�玟��ɐl�����匠�҂ƂȂ�ߑ�Љ�ւƈڍs����ߒ��ɂ���A�[�֎�`�^���A�Y�Ɗv���A�t�����X�v�����N����A�}���ɎЉ�ω����Ă�������ł������B���̎���ɂ́A���_�_�A���_�_�A�o����`�A������`�A�l��`�A���R��`�A���R�@�A�Љ�_��@�Ȃǂ̎v�z���W�J����u�����̐��I�v�ƌ�����B�[�֎�`�^���́A�]���̐�Ύ�`�Љ�ɂȂ��Ă�����̌��Ђ�j�悤�Ƃ���s���Љ�̎��Ȏ咣�ł���A�����I�A�����I���E������āA���邢�����I�Ȑ��E�ɉ��v���悤�Ƃ��镗��������������B�܂����̎���ɂ́A�o�ϊ����̔��B�ɂ���ėl�X�Ȍo�ϗ��_�����܂ꂽ�B���̒��ł��A�_���E�X�~�X�́A�ߑ�s���Љ�̌o�ϊ����𑍍��I�ɉ𖾂��A�o�ϊw���͂��߂Ċw��I�ɑ̌n�Â����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���x�[�R���u�咘��v���� 1733�N |
   �@
�@
|
Bacon, Roger.(1214?-94)
�@
Opus Majus ad Clementem quartum, pontificem Romanum.
�@
���W���[�E�x�[�R���́A�C�M���X���������̃X�R���N�w�҂ŁA���̔����ɂ�聃���ٔ��m Doctor mirabilis���Ə̂��ꂽ�B���́u�咘��v�́A���c�N�������X4���̕ی���Ē�����13���I�́u�m�v�̕S�ȑS���Ƃ�������B�{���́A�����B�ꊮ�S�Ȏʖ{�Ƃ��čl�����Ă����g���j�e�B�E�J���b�W�̂��̂���T�~���G���E�W�F�u���ҏW���ďo�ł��ꂽ���̂ł��邪�A��7���͌�ɂȂ��Ĕ�������Ă���A���̕����������Ă���B�@ |
�����W���[�E�x�[�R���u�咘��v
�@
�q�D�x�[�R���̓C�M���X���܂�̃t�����V�X�R�h�̏C���m�ŁA�I�N�X�t�H�[�h��w�ŃA���X�g�e���X�̎��R�w�y�ѐ��w���w�сA�X�Ƀp����w�ɂ��w�т܂����B1240�N��ɂ́A�p����w�ōu�`�����Ă��܂��B���炭���̎��Ƀy�g���X�E�y���O���k�X�ɁA�y���O���k�X�̎��Ό����⎩�R�w�����ɉ���������̏d�v���ɂ��ċ�������Ǝv���܂��B1247�N�ɔނ̓I�N�X�t�H�[�h��w�ɖ߂�A�����ŃO���[�X�e�X�g�Ɏt�����A���w�ɋ��������Ɏ���܂����B1251�N�ɂ̓I�N�t�H�[�h��w�����ƂȂ�A1257�N�Ƀt�����V�X�R�h�ɓ���܂��B�C���m�Ƃ��āA�N�w��_�w�A�܂��@�w���������A�X�Ɉ�w���������A�����ăA���X�g�e���X�A���[�N���b�h�A�A���L���f�X���̋Ɛтڌ��T�Ō�������ׁA�M���V�A��A�w�u���C�ꓙ���w�сA����w�҂Ƃ��Ă̌������s���A���[���b�p�ŏ��̃w�u���C�ꕶ�T�A�M���V�A�ꕶ�T������Ă��܂��B�ނ��܂��A�����j��ɂ������u���\�̐l�A�z���E�E�j���F���U���X�v�̈�l�ŁA���̔����ɓ����̐l�͔ނ��u���ٔ��m�A�h�N�g���E�~�����B���X�v�ƌĂ��ł����B
�@
�ނ́A�����I���@�����R�w�����ɂ͕s���ŁA�{���I�ł��邱�Ƃ��m�M���Ă���A�����̌��ʂƏ]���̓`���I�A�A���X�g�e���X�I�l�����Ƃ�����Ȃ��ꍇ�́A�e�͂Ȃ��`���I�l������ᔻ���A�U�������̂ŁA���X�Ƀt�����V�X�R�h�����ɑ����̓G������čs�����ɂȂ�܂����B�Ⴆ�A�h�~���S�h�̏C���m�Łu�S�Ȕ��m�A�h�N�g���E�E�j���F���U���X�v�ƌĂꂽ�A�����X�R���N�w�̋��l�A�A���x���g�E�X�E�}�O�k�X�������x�[�R���ɂ���āA�ȒP�Ɂu���m�Ȓj�v�ƂЂƂ��ƂŕЕt�����Ă��܂��B���̈׃t�����V�X�R�h�̎��͎҂ŁA��͂�D�ꂽ�Ȋw�ҁA�N�w�҂ł������{�i���F���g�D���|�ނ̓x�[�R���̍s������łȂ��A�x�[�R���̐M���Ă����B���p�Ɛ萯�p�������Ă����̂Ł|�̔����A�܂��ނ̕��ł������̏@���E�����z�Ȓ��q�Ŕ����u�N�w�����̓K�p�v�Ƃ����_���������Ĕ��ɉ������̂ŁA���� 1277-79�N���p���œ�������(���ڂ̌��^�͂͂����肵�܂���)���̒��O�܂ŗH����Ă��܂����̂ł��B
�@
�ނ̕]�������c�����ň������Ă��鍠�A�ނƐe�����������@�����@���N�������X�l���ƂȂ�A1266�N�ɔނ̌�������𑗂��Ă����l�Ɉ˗����悱���܂����B�ނ͓���4�����琬��咘���v�悵�Ă���A����͊w��̑S����������\��ł������A�}���\���ύX���āA1267�N�{�����܂Ƃ߁A����������c�傷����ƍl���āA���̗v��u������AOpus minus�v������A���҂�1268�N�ɑ���A�X�ɒǂ������āu��O����AOpus tertium�v�𑗂�܂����B�ނƂ��Ă͖@���̌㉇�āA�����Ǝ��R�ɋ��͂Ɍ�����i�߂��������̂ł����A�s�^�Ȏ��ɃN�������X�l���͂��̔N��11���ɖS���Ȃ�A���̌�͂Ȃ��̂ԂĂɂȂ��Ă��܂����̂ł����B
�@
���́u�咘��v�͌����������琬���Ă����̂ł����A�{���͑�Z���܂ł����߂��Ă��܂��B�掵���܂œ��ꂽ�ł́A�I�b�N�X�t�H�[�h��1897�N�ɏo����܂����B�{���́A��ꕔ�ł́A�^���̒Nj�����炷�l�̌����������A�A���X�g�e���X���̊����̌��Ђɂ�肩���邱�ƁA�K�����炭�����ςɌŎ����邱�ƁA��O�̈ӌ��ɂ����˂邱�ƁA���������̒m�����ӂ肩�����Ď����̖��m�����������Ɠ��������Ă��܂��B�m���ɂ��̒ʂ�Ȃ̂ł����A�����̃X�R���N�w�҂ւ̂��Ă����肪�܂܂�Ă��鎖�͖����ł��B��́A�_�w�ƓN�w�ɂ��āA��O���͐��m�Ɍ��T��ǂ݁A���߂̌��ꌤ���A��l���͐��w�ŁA���R�w�����̖���𐔊w�I�`��(�ނ̏ꍇ�͊w�ł���)�ŕ\���o���Ȃ���Ί��S�ł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă��܂��B��ܕ��͌��w�ł����Ŕނ̓O���[�X�e�X�g�A�A���n�[���A�v�g���}�C�I�X�ƃ��[�N���b�h�̋Ɛт����ƂɁA�����Y�̌��w�A���ɂ��̑��̊g���p�|�߂��ˁ|���̋��܂Ɋ�Â��Č������Ă��܂��B�܂��ނ͉��ʋ��ɂ��Ă��q�ׁA��������]�����̔�����\������l�ȕ��͂������Ă��܂��B��Z���ł́A�Ȋw�����ɉ���������̏d�v���ɂ��ďq�ׁA���̗l�ȕ��@��p���邱�Ƃɂ���ā|���݂̔�s�@�A�����ԁA�D�D�A�����̗͂l�ȋ@�B����邱�Ƃ��ł���ł��낤�Əq�ׂĂ��܂��B�ܘ_�A����͔ނ̔�}�ȑz���͂��������̂Ɏ~�܂�܂����A�������A�Ȋw�����͎����ɂ���čs���A���w�I�ɉ��������ׂ��A�Ƃ����l�����͋����ׂ��ߑ㐫�ŁA���̈Ӗ��ł͔ނ͗D��5���I�͐i��ł����ƌ�����ł��傤�B�������A�c�O�Ȃ��ƂɁA�ނ̒���͈���p�����Ȍ���A�����I�ɏo�ł��ꂽ�݂̂ŁA�ނ̎咘�͖{�����ŏ��̏o�łł��B�]���āA�����ɂ킽���Ĕނ̐^���͖�������ė����̂ł����B�@ |
�����W���[�E�x�[�R��
�@
(Roger Bacon�A1214-1294)�@�u���Q�I���m�v(Doctor Mirabilis)�Ƃ�ꂽ13���I�C�M���X�̓N�w�ҁB�J�g���b�N�i�ՂŁA�����Ƃ��Ă͒��������_�����łȂ��o���m������ώ@���d�������̂ŋߑ�Ȋw�̐��҂Ƃ�����B
�@
�C�M���X�̃T�}�Z�b�g�B�C���`�F�X�^�[���܂�B���Ƃ͂��Ƃ��ƗT�����������A�w�����[3������̐����Ɋ������܂�Ď��Y��v������A�Ƒ��͒Ǖ��̗J���ڂɂ������B
�@
�x�[�R���̓I�b�N�X�t�H�[�h��w�Ŋw�сA�A���X�g�e���X�̒���ɂ��ču�`����悤�ɂȂ����B�₪�āA�t�����V�X�R��ɓ���A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�̋����ƂȂ����B1233�N����A�����̃��[���b�p�̍ō��w�{�ł������p����w�֕����Ċw�B�����A�t�����V�X�R��ƃh�~�j�R��͐V�i�C����ł��������A�w��̐��E�ʼnX��������������Ē��ڂ���Ă����B�t�����V�X�R��̗Y�̓w�C���Y�̃A���N�T���f���ł���A����̃h�~�j�R��̓A���x���g�D�X�E�}�O�k�X�A�g�}�X�E�A�N�B�i�X�Ƃ����t��R���r�����̖���y���Ă����B���̂悤�ȉ₩�Ȋw��̐��E�ɂ����ăx�[�R���̗D�G���͒��ڂ���A�}���X�R�̃A�_������J���i�����o�[�g�E�O���X�e�X�g�Ƃ���������̗L���w�҂����Ɛe����[�߂��B�x�[�R���̎��Ƃł́A������ώ@�������Ȃ����Ƃɓ������������B
�@
�x�[�R���̊w��̓C�X�������̉Ȋw�҂����̒���(������C�X�����Ȋw)�ɗR��������̂����������B���̂��Ƃ��x�[�R���ɓ����̃��[���b�p�̊w��ɂ�������_���C�Â����邱�ƂɂȂ����B�����A�A���X�g�e���X�͌����Ă��炵���Ƃ͂����������킸���Ȗ|��ł����m���Ă��炸�A�w�҂����̓M���V�A����w�ԂƂ������z���Ȃ������B����͐����̌����Ɋւ��Ă������ł������B�����̌����̓A���X�g�e���X�I�Ȏ�@�łȂ��A�C�X�������̉Ȋw�҂ł���C�u���E�A���E�n�C�T���I�Ȍo���ɂ��ƂÂ�����@�ɂ���čs���Ă����B�x�[�R�����t�Ƌ����̂̓}�n���N���A�E�s�J���h�D�X�̃y�g���X�Ȃ�l���ł������B�����炭����́w���C����(�f�[�E�}�O�l�[�e�[)�x�Ƃ�������Œm���鐔�w�҃y�g���X�E�y���O���k�X�̂��Ƃł���ƍl�����Ă���B�x�[�R���͑��̊w�҂����̂悤�ɂȂ��Ȃ��������Ȃ����Ƃɂ��炾���A�����w������x�w��O����x�ɂ����ăw�C���Y�̃A���N�T���f������U�����Ă���B
�@
�₪�ăx�[�R���͔얞���M�[�E�t�[���N(�������̓t�[�R�A�A�t�[�R�[)�Ȃ鐕�@���ƒm�荇���A���̊w���ɋ�������������@�����璘����܂Ƃ߂�悤���߂�ꂽ�B�����A�x�[�R���̓t�����V�X�R��̒��ŋ��Ȃ����q���������邱�Ƃ��֎~����Ă������߁A�͂��߂͏��C�łȂ������B���������̐��@�������c�N�������X4���ɂȂ�A�x�[�R���ɑ��֗߂����Ăł��閧���ɒ��q������悤���߂��B�x�[�R���͂�����Ē�����܂Ƃ߁A1267�N�ɋ��c�ɑ������B���ꂪ�w�咘��x�ł���B���Ɂw�咘��x���܂Ƃ߂��w������x�������ď����ꂽ�B1268�N�ɂ͑��������������w��O����x�����c�ɑ���ꂽ���A���c�͓��N���������B���c�̕ی���������x�[�R����1278�N�Ƀt�����V�X�R��̓����Œf�߂���A�A���u�v�z���L�߂��^���œ������ꂽ�B�H��10�N�ɂ�����A�����̃C�M���X�M���������x�[�R���̉�������߂����߁A�ߕ����ꂽ�B
�@
������Ǝv�z
�@
����̒��ŁA�x�[�R���͐_�w�����̉��v����Ă���B�X�R���w�̂悤�ȊT�O�̏ڍׂȋ敪�ɏW�����邱�Ƃ���߂Ă����Ɛ������̂��̂���������ׂ����ƍl�����̂ł���B�x�[�R���͓����Ƃ��Ă͐��I�Ȏv�z�ł��������A�����҂����ɐ����̌��T�̌��t�A�M���V�A��A�w�u���C����w�Ԃ��Ƃ����߂��B�x�[�R�����g�͐�������ɐ��ʂ��A�����̐�����M���V�A�N�w�̏�����A�ƌ��ɂ���ăI���W�i�����炩���͂Ȃ�Ă��邱�Ƃ�Q���Ă����B�����Đ_�w�w�K�҂����ɑ��āA�����ƍL�����w����w�Ԃ��Ƃ����߁A��w�̃J���L�������̉��v���K�v�ł���ƍl�����B
�@
�x�[�R���͐_�w��w��ɂ����Ă���������l�ɒǐ����邱�Ƃ�ے肵���B�ނ́w�咘��x�ł͐��w�A���w�A���w�Ɋւ���L�q���܂܂�A�F���̋K�͂ɂ��Ă܂Ō��y����Ă���B����ɋ����ׂ����ƂɃx�[�R���͌㐢�ɂ����Č������A�]�����A��s�@����C�D����������邱�Ƃ܂ŗ\�z���Ă���B�܂��A�F���̉^�s���l�Ԃ̉^���ƐS�g�ɉe������ƍl���Ă����B�ǂ�����Ă����̐挩���ɂ͋������ւ����Ȃ����A�x�[�R���͑��ɂ������E�X��̖��_���w�E���A�A�C�U�b�N�E�j���[�g�����400�N���������̓������O���X�ɂ����Č��̃X�y�N�g�����ϑ����Ă����B
�@
�ނ͓������E�̍Ő�[�ɂ������A���r�A�Ȋw�ƓN�w�ɐe����ł���A�ߑ�Ȋw����肵�Čo���Ɗώ@�̏d�v�������������B�x�[�R���ɂ͕S�Ȏ��T�����\�z���������悤�����A�����ɏI������̂��f�Ђ����c����Ă��Ȃ��B�@�@
�@ |
 �@ �@
�������e�X�L���[�u�@�̐��_�v���� 2�� 1748�N |
   �@
�@
|
Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de.(1689-1755)
�@
De l'Esprit des Loix.
�@
�����e�X�L���[�́A�ߑ㏉���ɂ�����t�����X�̑�\�I�v�z�Ƃł���B�{���͔ނ̑�\�I����ł���A���ł����s�����Ɠ����ɑ傫�Ȕ������ĂB�����̖@�����x�̌�����Nj����A�@�ƕ����I���_�I���v�f�Ƃ̑��݊W���𖾂��A�@�����x�ɑ��Ă͒n���I�A�Љ�I�������d�����āA��̎Љ�w�I�����Ɏh����^�����B�܂��{���̗��j�I�Ӗ��́A�C�M���X�����̏Љ�A���Ɍ��͋ύt�_�Ƃ��Ă̎O�������_�̎咣�ɂ���A����̓A�����J���O�����@�̐�����n�߁A�̂��̐����y�юЉ�v�z�ɑ����̉e����^�����B�@ |
���@�̐��_ 1
�@
(De l'Esprit des lois)�@1748�N�ɃW���l�[���ŏo�ł��ꂽ�[�֎v�z�ƃ����e�X�L���[�j�݃V�����������C�E�h�E�X�S���_�̐������_���B���{�ł͌��͕�����莮�����������Ƃ��ėL�������A���̘_�_�͐����w�A�@�w�A�Љ�w�A�l�ފw�ȂǑ���ɂ킽���Ă���B�Ȃ��A������������A�{�����ł͌��͂��O��(���@���E�i�@���E�s����)�݂̂Ȃ炸�A�l���Ȃ����܌��ɂ܂ŕ������ׂ��ł���|��������Ă���B
�@
�����e�X�L���[��3000�ȏ�̈��p����܂ނ��̒���Ș_�l�̂��߂̒����Ǝ��M�ɁA�ق�20�N���₵���B���̂Ȃ��ŁA�ނ͗�����`�A���͕����A�z�ꐧ�p�~�A�s���I���R�̕ێ��A�@�̋K�͂Ȃǂ��咣���A����ɂ͐����I�E�@�I�����x�͂��ꂼ��̋����̌ŗL�̎Љ�I�E�n���I�����f�������̂ł���ׂ����Ƃ������Ƃ��咣�����B
�@
�w�@�̐��_�x�́A�w�@�̐��_�ɂ��āA���邢�͖@�����ꂼ��̐��́A�K���A�C��A�@���A���ƂȂǂƎ�茋�Ԃׂ��W�ɂ��āx(De l'esprit des lois, ou, Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c.) �Ƃ���������1748�N�ɏo�ł��ꂽ�B���{���ł̏o�ł��������ߓ����͓����ŏo����Ă����B
�@
�o�ł����ƈȍ~2�N�Ԃ�����20�ȏ�̔ł��d�ˁA�傫�Ȕ����������N�������B�������ܕێ琨�͂⋳��͂���̔ᔻ���ĂсA1751�N�ɂ͋֏��ژ^�ɉ�����ꂽ����ŁA�_�����x�[�����^�������悤�ɁA�S�ȑS���h����͏^���ꂽ�B�Ƃ͂����A���h���ɂ��A�����e�X�L���[���M�������ɍD�ӓI���������߂ɔ���҂͂����B�܂��A�ނ̕��y����_(��q)�Ƃ����ׂ����_�ɂ��ᔻ����ꂽ�B�����Ŕނ͂��������ᔻ�ɓ�����ׂ��A1750�N�Ɂw�@�̐��_�̗i��x�\�����B
�@
������ւ̐v���Ȗ|��ɂ���Ă���������`�ŁA�t�����X�ȊO�ɂ��e�����y�ڂ��Ă������B�Ⴆ�Ήp��ł́A���ł�2�N��ɂ�����1750�N�Ƀg�}�X�E�i�W�F���g�ɂ���ď㈲����Ă���B
�@
�ނ̌��͕����_�́A�M���̖������d��������̂ł��������A���̍��i�͖����`�����ɂ����Ă��K�p�\�Ȃ��̂ł������B����䂦�ɁA�A�����J���O�����@�̘g�g�݂�A�t�����X�v������1791�N���@�̐���ɂ�����ȉe�����y�ڂ����̂ł���B
�@
�������_
�@
�����e�X�L���[��3�̐����V�X�e�����̂�グ�A�L�͂ɘ_�����B����3�Ƃ́A���a���A�N�吭�A�ꐧ���ł���B���a���I�V�X�e���́A�ނ炪�ǂ̂悤�Ɏs���I���������g�����Ă䂭�̂��Ɉˑ����āA�ڂ܂��邵���ς��B���ΓI�ɍL���������g�����Ă����ꍇ�ɂ͖����`�I���a���ƂȂ邵�A��苷���������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ͋M�������I���a���ƂȂ�B�N�吭�Ɛꐧ���̋�ʂ́A�����҂̌��͂��S�������钆�Ԑ���(�M���A���E�҂Ȃ�)�����݂��邩�ۂ��Ɉˑ����A���݂���ꍇ�ɂ͌N�吭�A���Ȃ���ΐꐧ���ƂȂ�B
�@
�����e�X�L���[�ɋ���A���ꂼ��̐����V�X�e���̒ꗬ�ɂ́A�ނ���{�����ƌĂ��̂����݂��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�̐����x������A���̋@�\���~���ɉ^�p����_�ŁA�s���̍s���̓��@�t���ƂȂ���̂ł���B
�@
���a���ɂƂ��ẮA�����I�Ɏ����������v��D�悵�悤�Ƃ���u���v������ɂ�����B�N�吭�ɂ����ẮA��荂���n�ʂ���������߂�~���A���Ȃ킿�u���_�v������ł���B�ꐧ���ł́A�x�z�҂������炷�u���|�v���w���B�����āA�C�ӂ̐����̐��́A���ɂ��̓K�Ȋ�{�����������Ă���A�����ł��Ȃ��̂ł���B�����e�X�L���[�͂��̗�Ƃ��āA�C���O�����h�̗�������Ă���B�s���[���^���v���̌�A���̍������a����ł����Ă邱�Ƃ��o���Ȃ������̂́A���̂��߂ɕK�{�������͂��́u���v�������Ă������炾�Ƃ����̂ł���B
�@
�����R�ƌ��͕���
�@
�w�@�̐��_�x�̓�ڂ̑傫�ȃe�[�}�́A�����I���R�Ƃ����ێ����邽�߂̍ŗǂ̎�i�Ɋւ�����̂ł���B�u�����I���R�v�ƃ����e�X�L���[�������Ƃ��A����͑�v�u�l�̈��S�v�������́u�e�l�����̈��S�̓��Ɏ��������琶����S�̕��Áv���Ӗ����Ă���B
�@
�ނ͂��̎��_�𐭎��I���R�Ɋւ����̕T���Ƌ�ʂ��Ă���B���̈�ڂ́A���R���W�c�I�����̂Ȃ��ɑ�����A�܂莩�R�Ɩ��吭���Ƃ��錩���ł���B��ڂ́A���R�Ƃ͈�̑��������ɗ~���邱�Ƃ����ł��ł���̂Ȃ��ɑ�����Ƃ����l���ł���B�����e�X�L���[�́A�����̕T���͂Ƃ��ɐ^���łȂ����肩�A���R�̓G�ɂȂ肤��ƍl���Ă����B
�@
�����I���R�͐ꐧ���̂��Ƃł͎����ł��Ȃ����̂ł���A�ۏ��ꂽ���̂łȂ��Ƃ͂����A���a����N�吭�ł͉\�ɂȂ�̂ł���B��ʂɁA�m�ł���y��̏�ɐ����I���R���m������ɂ́A���̓�̂��̂��K�v�ɂȂ�B
�@
�܂���ڂ��������͂̕����ł���B�����e�X�L���[�́A�W�����E���b�N�́w������_�x����b�ɂ����ďC���������A���@���A�i�@���A�s�����͂��ꂼ�ꕪ�L�����ׂ��ł��邱�Ƃ�_�����B�C�ӂ̌��͂������I���R��N�����Ƃ���A�ʂ̌��͂��y�I�ł��邩��ł���B�ނ̓C���O�����h�̐������x���L���_�����Ȃ��ŁA�ǂ̂悤�ɂ���ΌN�吧�̂Ȃ��ɂ����Ă��������ꂪ�B������A���R���ۏ����̂����������Ƃ����B�����ɔނ́A���͂��������Ă��Ȃ���A���a���ɂ����Ă��������R�͕ۏ��ꂦ�Ȃ����Ƃ��q�ׂ��B
�@
��ڂ́A�l�̈��S�̂��߂ɖ��@�ƌY�@���K�ɐ��肳��邱�Ƃł���B�����Ŕނ��v���`���Ă����̂́A���݂̉�X�������Ƃ���̃f���[�E�v���Z�X�Ɋւ��鏔�����A���Ȃ킿�����ȍٔ����錠���A�L�߂��m�肷��܂ł͖��߂ł��錠���A�߉ȂƌY���̋ύt�Ȃǂł���B����Ƃ̊֘A�ɂ����āA�����e�X�L���[�͓z�ꐧ�̔p�~�⌾�_�E���Ђ̎��R�ɂ��Ă��_���Ă���B
�@
���C�y�ƎЉ�
�@
�w�@�̐��_�x�̎O�Ԗڂ̑傫�ȃe�[�}�́A�@�Љ�w�̗̈�Ɋւ����̂ł���A�����ꏭ�Ȃ���ނ����̑n�n�҂ƈʒu�Â����邱�Ƃ�����B�����A�_�l�̑啔���́A�n����C�ǂ̂悤�ɐl�X�́u���_�v�ݏo�����L�̕����ƍ�p�������Ă��邩�A�Ƃ������ƂɊւ���Ă���B�����ł����u���_�v�Ƃ́A����y�n�̐l�X���A�ق��̓y�n�Ƃ͈قȂ邻�̓y�n���L�̎Љ�x������x�ւƌ����킹����̂��w���Ă���B���̓_�ɂ��Č��̘_�҂����́A���������e�X�L���[�̋c�_���u�ԓ�����̋����ł����Ė@�̈Ⴂ��P���ɐ���������̂��v�Ɲ��������B
�@
�������A�w�@�̐��_�x�œW�J����Ă���c�_�́A���������}�������y���ɉs�����͂������܂܂�Ă���B�������A�ނ̎咣���鎖��ɂ͌���̎��_����͊�قɌ�������̂������̂͊m���ł���B�������A�ɂ�������炸�A���R�Ȋw�I���_���琭���w�ւ̃A�v���[�`���s���Ƃ����ނ̎�@�́A���ځE�Ԑڂ��킸�A�����w�A�Љ�w�A�l�ފw�Ȃǂ̕���ɑ���ȉe�����y�ڂ����B�Ȃ��ł��A�A���N�V�X�E�h�E�g�N���B���́A�����e�X�L���[���狭���e�������l���ł���B�ނ́w�A�����J�̖��吭���x����́A�����e�X�L���[�̗��_���A�����J���������ɓK�p���悤�Ƃ������Ƃ��M����B
�@
���{���ɂ�������{
�@
�{���ɂ����Ă͍]�˖��{���A�ꐧ���̓T�^�I�ȗ�Ƃ��ċ������Ă���(��1����6�ґ�13�͂Ȃ�)�B�����e�X�L���[�́A�u���{�ł͋��U�̐\�����Ă���K�q���ł��玀�߂ƂȂ邪�A���܂�������y�����A�ӂƂ����C���ꂩ��ł������悤�Ȑl�X�́A�c�s�ȌY���ł����Ă�����Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B�܂��p���ׂ����y(�O��)�ɂӂ����Ă����c��(���R)���A���鏎���̖����C�ɓ����Ďq�ǂ������A���̎q�͑剜�̏������̎��i����i�E����Ă��܂����B���̔ƍ߂͌��ɂȂ�Ό��̉J���~�邱�ƂɂȂ邽�ߍc��ɂ͉B���ꂽ�B�@���̎c�s���͂��̎��s��W����v�ƁA���{�ɂ�����Y���̎c�s���Ɩ��͂��ɂ��ďq�ׂĂ���B�@ |
���@�̐��_ 2
�@
�����߁@�������x
�@
�����e�X�L���[�́w�@�̐��_�x�ł́A���̂ɂ��āA�q�O��̐��̂�����B����́A�u���a���v�u�N�吧�v�u�ꐧ�v�ł���r�Ƃ���܂��B��̓I�ɂ́A�q���ɁA���a���̂Ƃ́A�l���S�́A���邢�͂���ɐl���̈ꕔ���匠�������̂ł���A���ɁA�N�吭�̂Ƃ́A�B��l���A��������܂�������@�ɑ����ē������鐭�̂ł���A��O�ɁA����ɔ����āA�ꐧ���̂ɂ����ẮA�B��l���A�@���������Ȃ��A���̂�̈ӎu�ƋC�܂���ɂ��A���ׂĂ��Ђ��܂킷�r�ƌ���Ă��܂��B
�@
���a���ɂ��ẮA�q���a���ɂ����āA�l���S�̂��匠�����Ȃ�A����͖��吧�ł���A�匠���l���̈ꕔ�̎蒆�ɂ���Ȃ�A����͋M�����ƌĂ��r�Ƃ���A����ɓ�ɕ�������Ă��܂��B���吧�ɂ��ẮA�q�l�����㗝�҂��Ȃ킿��������C�����邱�Ƃ��A���̐��̂̍��{�����ł���r�Ƃ���A�M�����ɂ��ẮA�q�M�����ɂ����ẮA�匠�͈�萔�̐l�X�̏����ɂ���r�ƌ���Ă��܂��B
�@
�N�吭�̂ɂ��ẮA�q�]���I�A�ˑ��I�Ȓ��Ԍ��͂��A�N�吭�́A���Ȃ킿�A�B��l����{�@�ɑ����Ďx�z���鐭�̖̂{�����Ȃ��r�Ƃ���A�q�N��Ȃ����ċM���Ȃ��A�M���Ȃ����ČN��Ȃ��A���N�吧�̊�{�I�Ȋi���ł���r�ƌ���Ă��܂��B
�@
�ꐧ���Ƃɂ��ẮA�q�ꐧ���̖͂{�����炵�āA������s�g����B��̐l�Ԃ́A������������ЂƂ�̎҂ɍs�g������r�Ƃ���܂��B
�@
�����߁@���̂̌���
�@
���ꂼ��̐��̂̌����ɂ��ẮA�q���a���̖̂{���́A�l���S�̂��A���邢�́A���鐔�Ƒ����匠�������Ă��邱�Ƃł���A�N�吭�̖̂{���́A�N�傪�匠������������܂����@�ɂ��s�g���邱�Ƃł���A�ꐧ���̖̂{���́A�����ЂƂ肪�����̈ӎu�ƋC�܂���ɂ��x�z���邱�Ƃł���B�����̐��̂̎O�̌��������������ɂ́A���̂��Ƃ����ŏ\���ł���r�ƌ���Ă��܂��B
�@
���吧�̌����ɂ��ẮA�q���O���Ƃɂ́A���܈�̔������K�v�ł���A����́u�����v�ł���r�Ƃ���A�q���̓��������ނƂ��ɂ́A��S�͂����e�ꂤ��S�ɂ��̂т��݁A�×~�͂�����S�ɂ͂��肱�ށB�~�]�͂��̑Ώۂ�ς��A�l�͈����Ă������̂������Ȃ��Ȃ�B�@�ɂ���Ď��R�ł������҂��A�@�ɂ������Ď��R���邱�Ƃ�]�ށr�Ƃ���܂��B
�@
�M�����̌����ɂ��ẮA�q�M���͈�̒c�̂��`�����A���̒c�̂͂��̓����ɂ���āA���ȌŗL�̗��v�̂��߂ɖ��O��}������B���̓_���炵�āA�@�����s�����ɂ͖@�����݂��邾���ŏ\���ł���r�Ƃ���A�q�ߓx���A���������āA����琭�̂̍��ł���r�Ƃ���܂��B
�@
�N�吧�̌����ɂ��ẮA�q�N�吭�̂́A�g���I���ЁA�n�ʁA�����āA���܂�ɂ��M����������O��Ƃ��Ă���B���_�̖{���́A�Έ��ƒ��������߂邱�Ƃɂ���B���_�́A���������āA���̂��Ƃ��炵�Ď��R�ɂ��̐��̂Ɉʒu�Â����Ă���r�Ƃ���܂��B
�@
�ꐧ���̂̌����ɂ��ẮA�q���a���ɂ����Ă͓������A�N�吧�ɂ����Ă͖��_���K�v�ł���悤�ɁA�ꐧ���̂ɂ����Ắu���|�v���K�v�ł���r�Ƃ���܂��B���a�Ȑ��̂ɂ��ẮA�q���a���̂́A�]�ނ��܂܂Ɋ댯�Ȃ��A���̔��������߂邱�Ƃ��ł���B����́A���̖@�Ƃ��̗͎��̂ɂ���Ĉێ������r�Ƃ���܂��B
�@
�N��Ɛꐧ�̑Δ�ł́A�q�N�吭�̂́A�ꐧ�ɂ������đ傫�ȗ��_�������Ă���B�N��̉��ɂ��̍����ɍ������������̐g��������̂����̖{���ł��邩��A���Ƃ͂����肵�Ă���A�����͂���邪���������A�����҂̈�g�͂����������S�ł���r�Ƃ���܂��B
�@
����O�߁@���̂̕��s
�@
���ꂼ��̐��̂̕��s�ɂ��Ă�����Ă��܂��B
�@
���吧�̕��s�ɂ��ẮA�q���吧�̌����́A�l�X�������̐��_�������Ƃ��݂̂Ȃ炸�A�ɓx�̕����̐��_�������A�e�l���������x�z���邽�߂ɑI�҂ƕ������낤�Ɨ~����Ƃ��ɂ����s����r�Ƃ���܂��B
�@
�M�����̕��s�ɂ��ẮA�q�M�����́A�M���̌��͂����ӓI�ƂȂ�Ƃ��ɕ��s����B�x�z����҂ɂ��A�x�z�����҂ɂ��A�����͑��݂����Ȃ��Ȃ�r�Ƃ���܂��B
�@
�N�吧�̕��s�ɂ��ẮA�q�N�吧�́A�������������ɏ��c�̂̓�����s�s�̓�����D���Ƃ����s����r�Ƃ���܂��B�܂��A�q�N�吧�̌����́A�ō��̊��ʂ��ō��̗�]�̂��邵�ł���Ƃ��A�����Č����҂���l���̑��h��D���A�ނ�ӓI�Ȍ��͂̂��₵������Ƃ���Ƃ��A���s����r�Ƃ�����܂��B
�@
�ꐧ���̂̕��s�ɂ��ẮA�q�ꐧ���̂̌����́A���̖{�����炵�ĕ��s���Ă��邩��A���������s����r�Ƃ���܂��B
�@
�e���̂̕��s���q�ׂ���ŁA�q���̂̌������ЂƂ��ѕ��s����ƁA�ŗǂ̖@�����@�ƂȂ荑�Ƃɔ�������̂ƂȂ�B���̌��������S�ł���A���@���悢�@�̌��ʂ����B�����̗͂����ׂĂ��r�ƌ���Ă��܂��B
�@
����l�߁@�O�������_
�@
�L���ȎO�������_�ɂ��ẮA�q�e���Ƃɂ͎O��ނ̌��͂�����B���@���A�����@�ɑ����邱�Ƃ���̎��s���A����юs���@�ɑ����邱�Ƃ���̎��s���ł���r�Ƃ���܂��B
�@
�����āA�q���̌��͂ɂ��A�N��܂��͎������́A�ꎞ�I�܂��͍P�v�I�ɖ@�����߁A�܂��A���łɒ�߂�ꂽ�@�����C���܂��͔p�~����B���̌��͂ɂ��A�ނ͍u�a�A�����s�Ȃ��A��g���������A���S��ۏ��A�N����\�h����B��O�̌��͂ɂ��A�ނ͍߂��A���l�Ԃ̌W�����ق��B�����͍Ō�̂��̂��ٔ����ƌĂсA���̈������ɍ��Ƃ̎��s���ƌĂԂł��낤�r�ƌ���Ă��܂��B
�@
�����e�X�L���[�́A�q����O�̌��͂́A�Î~���s�������o���͂��ł���B�����A�����̕K�R�I�ȉ^���ɂ���Đi�ނׂ����������̂ŁA�������Đi�܂�������Ȃ������r�Əq�ׂĂ��܂��B
�@
����ܐ߁@�����l�@
�@
�����e�X�L���[�́w�@�̐��_�x�ɕ`����Ă��鐭�����x�_�ɂ��čl���Ă݂܂��B
�@
�e���̂̕��͂ɂ́A�Q�l�ɂ��ׂ��ӌ�����������܂��B���ɁA���吧�����s����Ƃ��̗�Ƃ��āA������������Ƃ��݂̂Ȃ炸�A�ɓx�ɕ����ɂȂ����Ƃ��������Ă���̂͌d��ł��B
�@
�������A�e���̂̌����ɂ��Ă̍l�@�͕s�K�ł��B�����E�ߓx�E���_�́A�ǂ̐��̂ɂƂ��Ă��K�v�Ȃ��̂ł��B�ǂꂩ��𐭑̂̌����Ƃ��Čf����̂́A�������l�����ŕs�\�����ƌ��킴��܂���B
�@
�܂��A�����e�X�L���[�́A���@���E���s���E�ٔ����ɂ��O�������������Ă��܂��B�ٔ����́A�i�@���Əd�Ȃ��Ă��܂��B���Ƃ̌��͋@�\�U�����A���͑��݊Ԃ̗}���ɂ���ċύt��ۂ��Ƃ͏d�v�ł���Q�l�ɒl���܂��B
�@ |
���@�̐��_ 3 �`���吭�����łт�܂Ł@
�����吧�̌�����������Ƃ�
�@
���吭�̌����́A�l�������̐��_���������݂̂Ȃ炸�A�ɒ[�ȕ����̐��_�������A�e�l�������ɖ��߂�����̂Ƃ��đI�l�����ƕ����ł��肽���Ɨ~���鎞�ɕ��s����B
�@
�l���͎��炪�ϑ��������͂ɂ���䖝���o�����A�S�Ă��������g�ōs���A���V�@�ɕς���ĐR�c���A��E�҂ɑ����Ď��s���A���ׂĂ̍ٔ����ɂƂ��đ��낤�Ɨ~����B
�@
�����Ė��吭�ɂ����Ă͓������͂⑶�݂����Ȃ��Ȃ�B�l������E�҂̐E�����s�����Ƃ�~����B������A�l�͖�E�҂����͂⑸�h���Ȃ��B���V�@�̐R�c�͂��͂�d�����Ȃ��Ȃ��B
�@
�N�Z�m�t�H���́u�����v�ɂ́A�l���������𗔗p�������鋤�a���̐��ɂ���̂܂܂̕`�ʂ�������B�`�J���~�f�X�͎��̂悤�Ɍ����B
�@
�u�����������̎��A���͏�Ɏ��ɂȂɂ�����V�����o���v�����܂����B�`�n�R�ɂȂ��Ă���͎��͌��Ђ܂����B�������������̂͒N���Ȃ��A�������l���������Ă��܂��B�`���ł͋����������͂��̐Ȃ𗧂��Ď��Ɉ��������܂��B���͉��l�ł��B
�@
���͎����̕n�R�̌̂Ɏ����ɖ������Ă��܂��B�������������������ɂ́A����槑i�҂����̂��@������]�V�Ȃ�����Ă��܂����B�ނ�ɊQ����������A�ނ炩��Q���闧��ɂ��邱�Ƃ��悭�m���Ă�������ł��B
�@
���͍��ɐł����߂Ă��܂������A�����ł͍�������{���Ă���܂��B���͂��͂⎸���S�z�͂���܂���A����]�݂�����܂��B�v
�@
�����吭�点�鐭���Ƃɂ���
�@
�`�l�������̂悤�ȕs�K�Ɋׂ�̂́A�l�������̐g��������҂����������������g�̕��s���B�����Ƃ��āA�l���s�����悤�Ɩ��߂�Ƃ��ł���B
�@
�l���ɔނ�̖�S����������Ȃ��悤�ɁA�ނ�͐l���ɐl���̈̑傳�ɂ��Ă������Ȃ��B�l�����ނ���×~�ɋC�����Ȃ��悤�ɁA�ނ�͐₦���l�����×~�ɂ����˂�B
�@
�l���ɑ����̂��̂�^���邽�߂ɂ́A����ȏ�ɑ����̂��̂�l��������グ�˂Ȃ�Ȃ��B�`�l�������̎��R���痘�v�������o���悤�Ɍ�����Ό�����قǁA�l���͂��̎��R�����킴��Ȃ��u�Ԃɋ߂Â��ł��낤�B
�@
�l���͖\�N�̎������鈫����g�ɕt�������\�N�����ƂȂ�B�₪�Ďc���ꂽ�킸���Ȏ��R���䖝�ł��Ȃ����̂ɂȂ�B�����Ă�����l�̖\�N���䓪����B�����Đl���͂��ׂĂ������B���̕��s�ɂ���ē������v�܂ł��B
�@
�����吭��ۂ��߂̋��P
�@
�`����̂ɖ��吭�ɂ͔�����ׂ����ɒ[������B���吭���M�����܂��͈�l�����ւƓ����s�����̐��_�A�����āA���吧��ꐧ�����ւƓ����ɒ[�ȕ������_�ł���B
�@
�V���n���牓���u�����Ă���̂Ɠ������炢�A�^�̕����̐��_�͋ɒ[�ȕ����̐��_���牓���u�����Ă���B
�@
�^�̕������_�́A�S�Ă̎҂����߂���悤�ɂ�����A�N�����߂���Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��A�S�Ă̎҂������Ɠ����ɐl�X�ɕ��]�����߂��邱�Ƃɂ���
�@
���R��Ԃɂ����ẮA�l�Ԃ͊m���ɕ����̒��ɐ��܂�邪�A�����ɂƂǂ܂邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�Љ�ނ�ɕ��������킹�A�ނ�͖@���ɂ���Ă����Ăѕ����ɂȂ邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@
���̖{���̏��݂͎��R�̂��Ƃɂ���̂ł����āA����͗ꑮ�̂��Ƃɂł��A�ɒ[�ȕ��C�ȕ��C�̂��Ƃɂ���킯�ł��Ȃ��B
�@
�̑�Ȃ鐬���A���ɐl�����傢�ɍv�����鐬���́A�l���Ɏ��瓱�����Ƃ����͂�s�\�ƂȂ�Ȃ�قǂ̘������������炷�B �`�y���V�A�l�ɑ���T���~�X�̏����̓A�e�i���a���s�����A�A�e�i�l�̔s�k�̓V�����N�T�C���a����ŖS�������B
�@
�������̕��s�̉e��
�@
���̂̌���(���吭�ɂ����Ă͐l���̓�)���ЂƂ��ѕ��s����Ƃ��́A�ŗǂ̖@�����������@���ƂȂ�A���ƂɓG����B���̌��������S�ł���Ƃ��́A�������@�����悫�@���̌��ʂ����B�����̗͂��S�Ă��̂ł���B
�@
���鋤�a�������s����Ƃ��́A���̕��s���������A���̌������Ăі߂����Ƃɂ���Ă����A���ꂩ�琶���邢���Ȃ�Q���������ł��Ȃ��B����ȊO�̐�����͂ǂ�����v���A�����Ȃ���ΐV���ȊQ���ƂȂ�B
�@
�����a���̐�������͈�
�@
���a���͏����ȗ̓y�����������Ȃ��B�����łȂ���A����͂قƂ�Ǒ��������Ȃ��B�傫�ȋ��a���ɂ͑傫�ȍ��Y�����݂��A�l�S�ɐߓx���Ȃ��Ȃ�B�`���v�͌l������l�͑c�����Ȃ��Ă��K���ň̑�Ō��h�ł��肤��Ɗ�����B�����Ă܂��Ȃ��A�c���̔p�Ђ̏�ł�����l�̑�ł��肤��Ɗ�����B
�@
���a���́A��������ΊO���̗͂ɂ���ĖłсA�傫����Γ����̌��ׂɂ���Ėłт�B�@ |
���V�����������C�E�h�E�����e�X�L���[
�@
(Charles-Louis de Montesquieu, 1689-1755)�@�t�����X�̓N�w�҂ł���B�{���́A�V�����������C�E�h�E�X�S���_(Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu)�ŁA���E�u���[�h(La Brède)�ƃ����e�X�L���[(Montesquieu)��̒n�Ƃ���j��(baron)�ł��������B
�@
1689�N1��18���A�t�����X�쐼���ɂ���{���h�[�ߍx�Ő��܂ꂽ�B�ނ�7�̎��A�ꂪ�����B��̈�Y���p�����A���E�u���[�h�j�݂ƂȂ�B�{���h�[��w�@�w�����ƌ�A1709�N����p���ɗV�w�B1713�N���A�����]��ɂ��A������B���N�A25�Ń{���h�[�����@�@�̎Q�����ƂȂ�B1716�N�A�����̎��ɂ��A�����e�X�L���[�j�݂݈̎ʂƃ{���h�[�����@�@���@���̊��E���p������B�������A�����ʂɂ͖��S�ŁA1721�N�ɂ́A�����Łw�y���V�A�l�̎莆�x���o�ŁB1726�N�A37�ŁA�{���h�[�����@�w�@���@���̊��E�����E�B�Ȍ�A�w�������ɓ���B1728�N1���A�A�J�f�~�[�E�t�����Z�[�Y�̉���ɑI�o���ꂽ����A4�����珔�����̗��ɏo��B1731�N�ɑc���ł���t�����X�ɋA���B1734�N�A�w���[�}�l���������_�x�A1748�N�A�w�@�̐��_�x���o�ŁB
�@
�C�M���X�̐����ɉe�����A�t�����X��Ή�����ᔻ���A�ύt�Ɨ}���ɂ�錠�͕������̊�b��z�����B
�@
�@�Ƃ́A�u�����̖{���ɗR������K�R�I�ȊW�v�ł���ƒ�`���A���͂����Ȃ������`�Ԃɂ��@����́A�����I���R���ۏႳ��Ȃ��ƍl���A���M��20�N�������ƌ����鎩�g�̒���w�@�̐��_�x�̒��ŁA�������͂𗧖@�E�s���E�i�@�ɎO��������O�������_������B
�@
�ӔN�́A���͂̌��ނɔY�܂��ꂽ�B����Ȓ��A����w�S�ȑS���x�ׂ̈Ɂu��_�v�̎��M�Ɏ��g���A�������邱�Ƃ͖���1755�N2��10���Ƀp���Ő��������B
�@
�Љ�w�̕� (pères de la sociologie) �ƍl�����Ă���B
�@
�w�y���V�A�l�̎莆�x�̈�߂ł́A��L���X�g�����̏o�����̍����𗣍������e���Ă���ׂƂ��A�܂��A�u�v�w���݂̈���ɉ�������^����̂͗����̉\���ł���v�Ƙ_�q�����ӏ�������(�����̗������݂̂��咣)�B�@�@
�@ |
 �@ �@
�����\�[�u�G�~�[���v���� 4�� 1762�N |
   �@
�@
|
Rousseau, Jean-Jaques.(1712-78)
�@
Emile, ou de l'Education.
�@
���\�[�́A�t�����X�[�֎�`���\����v�z�ƁA���w�ҁB�u�G�~�[���v�́A���{�����I�ȍ\����������_�ŁA����ɂ�����l�Ԃ̎��R���̎咣�̂��Ƃɕ����I�ȌÂ��Љ�I�Ό��Ə@���I�s���e��Y�قɔᔻ�����B�܂������N�ɏo�ł����u�Љ�_��_�v�͒��ږ��吧�𗝑z�Ƃ���ߑ㖯���`�̌ÓT�Ƃ��āA�Ȍ�̐����v�z�ɑ傫�ȉe�����y�ڂ����B�{���̏��ł̊��s�ɍۂ��ă��\�[�͍��O(�I�����_)�ň�����邱�Ƃ��咣�������A����3�l�̏o�ŎҊԂ̕��G�ȏ�����̌��ʁA�قړ����Ƀp���ƃI�����_��8�܂�ł�12�܂�ł��o�ł��ꂽ���A���ł̌���ɂ͂��܂��ɖ�肪����B�u�G�~�[���v�͏o�ł����Ƃ����A�p���̍����@�@�ɂ���ēE������A���\�[�����ߕ߂̖��߂��o���ꂽ�̂Ń��\�[�̓p���ꂽ�B�W�����̓I�����_�ł�12�܂�łł���B |
�����ł̓�
�@
���\�[(Rousseau, Jean-Jacques 1712-1778)�w�G�~�[���x (mile, 1762)�́A����_�̌ÓT�ł������łȂ��A�[�֎v�z�̏��Ƃ��Ă��łɃt�����X�v�����v�z�I�ɏ������Ă����ƌ����Ă���B�_�q�Ƃ������́A�G�~�[���Ƃ������N�����R�ɑ����Ă��̂��ƂɊS���Â��悤�ȋ���@�ɂ���Đ������Ă����X�g�[���[���W�J�����B�����܂ł��Ȃ��_���W�J���X�g�[���[�̒��Ř_�����Ă���̂ł��邪�A���̌����́u�l�͐��܂�Ȃ���ɂ��đP�ł����āA�Љ��^�����鋳��͈��ł���v�Ƃ�����̂ł������B���̎v�z�̓J���g�ɉe�����Ă��邱�Ƃ͂悭�m���Ă��邱�Ƃł��邪�A���w�̏�ł̓Q�[�e�ɂ��e�����y�ڂ��Ă���̂ł���B
�@
���̂悤�Ɏv�z�j��d�v�Ȉʒu���߂Ă���w�G�~�[���x�̏��ŏ����ɂ��āA���̐^��_�����ꐢ�I�ȏ���p�����Ă������Ƃ́A��Ƃ������A����������邽�߂̍ޗ��������Ȃ������킪���ł́A�R���N�^�[��Y�܂����̈ȊO�̉����ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B���\�[�����Ƃł������f���t�[��(Dufour, Thophile 1844-1922)���A�ڍL�q�ɂ�郋�\�[����ژ^�𑐍e�̌`�ň₵�Ă����B���ꂪ1925�N�ɒ���̑���Ȃǂ̃t�@�N�V�~���}�ł�t���Ċ��s���ꂽ*�̂ł��邪�A�w�G�~�[���x���ł̔��肪����Ă����B���̂��Ƃ����[�ƂȂ��Č�̘_�c��U�������̂ł���A�Ƃ��ɂ͌Ï��ژ^�L�q�̓T���\���ɂ��f���t�[���̔ԍ����t�L����邱�Ƃ��������B�������������Ɍ��������A�ؖ��Ə������������\���ꂽ�̂��A1952�N��Book Collector���̋L��**�ł������B�����ɂ͎��̂悤�ȏ��Ő����̑}�b���L�q����Ă���B
�@
1761�N����A�w�G�~�[���x�́u����_�v�Ƒ肷�鑐�e�̂܂ܗF�l�����̊Ԃʼn�ǂ���Ă����B�����āu���炵���v�Ƃ����]���������āA������o�ł��悤�Ƃ������ƂɂȂ����B���\�[�̓p���ŏo�ł��邱�Ƃ���]���Ă����̂ŁADuchesne�Ɉ���o�ł��˗������B�������A���\�[�̒���̓t�����X���ǂ̌��{�Ɉ����|���邱�Ƃ͏\���ɗ\�z����邱�Ƃł��������B�F�l�����͏o�Ő헪�����Ă��BDuchesne�����ۂ̈���o�ł�����̂ł��邪�A�\���ɕ\�������o�ŎҖ��̓I�����_��Naulme�Ƃ����B8�ܔ���12�ܔ���2��̔ł���������̂ł��邪�A�{���͂������12�ܔ��̓����g�ł��g�p����Ă����B����Duchesne��Naulme�̖��ō�����8�ܔ������łƂ������ƂɂȂ�̂ł��邪�A�����������Ȃ��A���̂قƂ�ǂ��o�ł��Ƃ�����Ă��ꂽ�F�l�����ւ̑���{�ɓ��Ă�ꂽ�̂ł������B���̂��߂ɂ��̌��ł̌����R�s�[�͂���߂ď��Ȃ��̂ł���B�܂��A���́u�p���Łv�̈���ɂ��x��āA�p���ň�����ꂽ�V�[�g��������I�����_��Naulme���A������������e�Ƃ��āA������u�^�́v�I�����_�łN�Ɋ��s���Ă���B
�@
�W�莆��ɃZ�l�J�́w�{��ɂ��āx����̈��p������Ƃ��Ĉ������Ă���B�������傪��3���̕W�莆�ɂ��������Ă��āA����2�s�ڂ̐擪2��unatura genitos�v�́A�Z�l�J�̌����ł́ugenitos natura�v�ł���B���e����ł͌ꏇ���]�|���Ă��Ă��Ӗ��ɕς�肪�Ȃ��Ƃ͂����A����̈Ӗ�����Ƃ��낪���\�[�̎v�z�̌������ق��Ă��邾���ɂ�����ƋC�ɂȂ�Ƃ���ł���B���̖���̌�L�́A���łɂ̂ݑ��݂��Ă��邽�߁A����l���ꌩ���Č��ł��m�F�ł���ڈ��ɂȂ��Ă���͔̂���ł���B���̗v�̂ɂ���āA��g���ɔŁw�G�~�[���x�̊����Ɍf�����Ă���W�莆�ʐ^������ƁA����͌���8�ܔ��ł͂Ȃ��A���ł̈���~�X�����ׂĒ�������Ă����2��8�ܔ��Ǝv����BFleuron(���E�����Ȃǂɓ����Ԗ͗l�̃J�b�g)���X�V���ꂽ���̂ł���B��g���ɔŃZ�l�J�w�{��ɂ��āx(�Ύ�،�����)������啔���̖��o���ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B
�@
�u�����͕a�ɔY��ł��Ă����邱�Ƃ��ł��邵�A�܂��������������̂Ɍ������Ă�������ł��邩��A�����炪�߂������߂悤�Ǝv���Ȃ�A���R���炪�A�����������Ă����v�@ |
���W�������W���b�N�E���\�[
�@
(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)�@�X�C�X�̃W���l�[���ɐ��܂�A��Ƀt�����X�Ŋ����N�w�ҁA�����N�w�ҁA����N�w�ҁA����N�w�ҁA��ƁA��ȉƂł���B�[�֎v�z�̎���ɂ�����18���I�t�����X�Ŋ����B�h�D�j�E�f�B�h���A�W�����E���E�����E�_�����x�[���A���H���e�[�����A������̑����̃t�����X�̒m���l�ƂƂ��ɕS�ȑS���h�̈�l�ɐ�������B
�@
1712�N�A�X�C�X�̃t�����X�ꌗ�̓s�s�W���l�[���ɂāA���v�E�l�̑��q�Ƃ��ďo���B����8���ɂ��ĕ��r���B
�@
7�����畃�ƂƂ��ɏ�������j�̏�����ǂށB���̎��̑̌�����A��������������d��v�z�̑f�n���|��ꂽ�B1725�N�A���͑ޖ��R�l�Ƃ̌��܂����ƂŃW���l�[�����瓦�S���˂Ȃ�ʎd�V�ƂȂ�B�Z���Əo���Ă��܂��ǎ����R�ƂȂ����W�������W���b�N�́A����̏f���ɂ���Ėq�t�ɗa�����A���̌�A���ؐl�̋��ɐg������A�����H�ɒ�q���肷��ȂNjꂵ���̌�������B3�N��A�o�z���ĕ��Q�����ɓ���B���̌�����܂��܂ȐE�Ƃ����������A�ǂ̐E�ɂ������������Ƃ��ł��Ȃ������B���Ƃ��������Ă����Q�͎~�ނ��ƂȂ��A�����̐i�ނׂ�����T�������B
�@
1732�N�A�W���l�[���𗣂�A���B�����j�ݕv�l�̈��l�ƂȂ�A���̔�̉��ł��܂��܂ȋ�������B����͈�l�Ŗc��ȗʂ̏�����ǂ݁A���{��g�ɂ����B�܂��A�ǓƂ��D�B���̎����ɂ��Ă͔ӔN�A���U�ōł��K���Ȏ����Ƃ��ĉ�z���Ă���B
�@
���v�z
�@
���\�[���^�����v�z�I�e���͑���ɘj�邪�A�����ł͎�ɐ����v�z�ƂƂ��Ẵ��\�[�ɂ��ċL�q����B
�@
�t�����X�ɂ����ẮA��������{�_����ɂ��A�N��Ɂu�匠�v(�����ɂ��Ă̌��茠)��������Ƃ̎v�z���\������Ă����B���̌N��匠�̊ϔO�́A�t�����X�Ȃǂ𒆐S�ɁA�����̐�Ή������x���鋭�͂ȍ����ƂȂ��Ă����B�������A���\�[�͂��̊ϔO��]�p���A�l���ɂ����匠��������Ƃ����u�l���匠�v�̊T�O��ł����Ă��B�l���匠�̊T�O�́A���̌�A�����`�̐i�W�╁�ʑI�����̊m���ɑ傫����^���邱�ƂɂȂ����B
�@
����A���\�[��̃t�����X�[�֎v�z�ɐG������Ďn�܂����t�����X�v���ɂ����ẮA�u���v���h�v�Ɩ��w�����ꂽ�҂ւ̔��Q�A�s�E�A�ٔ����o�Ȃ����Y���Ƃ��������|�������s��ꂽ�B���x�X�s�G�[����i�|���I���Ƃ������w���҂����́A�l���̑�\�҂ɂ��Č��@���茠�͂�L����҂Ƃ��ēƍِ������s�����B
�@
���\�[�̐����v�z�̓����́A���ɂ��u�Љ�_����v�ɂ�������悤�ɁA�]���̉��l�ς�`�����̊��K���������ꂽ�l�𗝑z�Ƃ���Ƃ���ɂ���ƌ�����B
�@
�܂��A�u�_�����x�[�����ւ̎莆�F�����ɂ��āv�ɂ����ẮA�����̎��J�^���V�X�̋@�\��ᔻ�����B
�@
�f�B�h����_�����x�[�����A������S�ȑS���h�Ɛ[���𗬂������A���g���S�ȑS���̂������̍��ڂ����M�������A��Ɏ�`�咣�̈Ⴂ��\�[�{�l�̔�Q�ϑz�̈�������A���邱�ƂɂȂ�B
�@
���]���E�e��
�@
���\�[����e�������҂Ƃ��ẮA�N�w�҂̃C�}�k�G���E�J���g���L���ł���B ������A�����̎��ԂɃJ���g���U���ɏo�Ă��Ȃ��̂ŁA���͂̐l�X�͉����������̂��Ƒ����ɂȂ����B���͂��̓��A�J���g�́A���\�[�̒���w�G�~�[���x��ǂݒ^���Ă��܂��A�����̎U����Y��Ă��܂����̂ł������B�J���g�́A���\�[�Ɋւ��A�w���Ɛ����̊���Ɋւ���ώ@�x�ւ̊o���ɂĎ��̂悤�ɏ����c���Ă��� - �u�킽���̌������\�[���������Ă��ꂽ�B�ڂ�����܂��D�z���͏��������A�킽���͐l�Ԃh���邱�Ƃ��w�ԁv�B
�@
���\�[�Ɠ������J���g�ɉe����^�����N�w�҂̈�l�Ƃ��Ēm����C�M���X�̃f�C���B�b�h�E�q���[���́A���\�[�ƌ�F�W���������B�������A�q���[���ƃ��\�[�͌�ɐ������B
�@
�܂��A���l�t���[�h���q�E�w���_�[���������\�[�̉e����[�����B�w���_�[�����̎��҂��ڍׂɕ��͂����}���e�B���E�n�C�f�K�[���Ȃ������\�[�Ɍ��y���Ȃ����Ƃɒ��ڂ����t�B���b�v�E���N�[�����o���g�́A�n�C�f�K�[�ɂ����郋�\�[�I�Ȗ��ݒ�̋t���I�Ȕ��f���w���j�̎��w�x(���{��� �������X,2007)�ɂ����Ę_�����B
�@
�鐭���V�A�̍�ƃ��t�E�g���X�g�C�͐N���Ƀ��\�[�����ǂ��A���U���̉e�������B�n��ł��������g���X�g�C�̐����ƍ�i�ɂ́u���R�ɋA��I�v�̎v�z�����f���Ă���B
�@
�Ȃ��A���\�[�̎v�z�����ۂɁu���R�ɋA��I�v�Ƃ����t���[�Y���悭���������ɏo����邪�A���\�[�̒���ɂ́u���R�ɋA��I�v�Ƃ�����̓I�ȕ���͈�x���o�ꂵ�Ȃ��B���\�[�̒���̂ЂƂ̉��߂Ƃ��āA���\�[�͂��̂悤�Ɍ����Ă���悤�Ȃ��̂ł���Ƃ���栂��ł���A���̂悤�ȕ]�̓��\�[�̍ݐ����ɂ����������A����ł���ƌ�����B
�@
�N�w�҂Ƃ��Ă͌[�֎v�z��(�t�B���]�[�t)�Ɉʒu�Â����郋�\�[�����A��ƂƂ��Ă��傫�Ȑ��������߂Ă���A���́u���v������ɉ����o�����앗�́A��̃��}����`�̐�삯�ƂȂ����Ƃ����A���̒��傩�ڍׂȎ��`�ł���w�����x�́w�����^�x�̖��ŖM�ꑾ�Ɏ��Ȃǂ̃G�b�Z�C�ɂ����̌��y���݂���B �܂��{�l���u��z�̂܂܂Ƀy���𑖂点���v�Ƃ����w�V�G���C�[�Y�x��18���I�t�����X�ɂ�����ő勉�̃x�X�g�Z���[�ƂȂ�A���H���e�[���́w�J���f�B�[�h�x�ƕ��я̂��ꂽ�B�@ |
���G�~�[�� / ���\�[�̋���_
�@
���\�[�́u�G�~�[���v������_�Ƃ��ĉ���I�������͓̂�d�̈Ӗ��ɂ����Ăł���B��͋���̖ڕW�Ƃ��Đl�Ԃ̎��R���Ƃ����T�O�����������ƁA������͋���̑ΏۂƂ��Ắu�q�ǂ��v���������Ƃł���B
�@
�l�Ԃ̎��R���Ƃ́A�l�Ԃ̖{���̂�����A���邢�͐l�Ԃ̖{���ƌ��������Ă��悢�B����Ƃ́A�l�Ԃɐl�Ԗ{���̂������g�ɒ��������A�l�ԂƂ��Ăӂ��킵�����������ł���悤�ɓ������Ƃ��A���\�[�͂����咣�����B�����ċ��� Education �Ƃ����t�����X��́A���e����́u�����o���v���邢�́u�����o���v�Ƃ����Ӗ��̌��t���ꌹ�Ƃ��Ă���Ƃ������B�܂�l�ԂƂ��Ė{���N�ɂ����Ȃ���Ă�����́A����������o���̂�����Ƃ����킯�ł���B
�@
�����Ŏ咣����Ă���l�Ԃ̂�����Ƃ́A�u�w��E�|�p�_�v��u�l�ԕs�����N���_�v�œW�J���ꂽ���R��Ԃɂ�����l�ԁA���Ȃ킿�u���R�l�v�ƃp�������Ȃ��̂ƍl���Ă悢�B
�@
���\�[�́A�l�Ԃ͎��R�̏�Ԃł͎��R�ł������ł��������A�Љ�����A������i�������邱�ƂŁA�������ƍl����B���̑�������������痧������A�l�Ԗ{���̐����������߂����߂ɂ͂ǂ�������悢���B
�@
�u�Љ�_��_�v�́A�����̂ɂ��āA�l�Ԃ����������̂����߂��Ď������g�̎�l�ƂȂ�A�������݂��ɕ����ł����R�Ȑ��������ۏႳ���悤�Ȑ��x���ǂ̂悤�ɂ��ĉ\����_�������̂ł������B���́u�G�~�[���v�́A���̎Љ�����������R�l�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̂�������A�X�̐l�Ԃɂ����Ăǂ̂悤�ɂ���Ƃ���ǂ��邩��_�������̂��B���҂͂��ꂼ��A�����Ƌ���Ɖ]���ʂ̐،�����A�l�Ԗ{���̂�����A�܂�l�Ԑ����l�������̂��ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@
���̂悤�ɐ�������A�u�G�~�[���v�̖`��������A���̂悤�Ȓ����I�ȕ��͂��悭�����ł��悤�B
�@
�u����������҂̎�𗣂��Ƃ����ׂĂ͂悢���̂ł��邪�A�l�Ԃ̎�Ɉڂ�Ƃ��ׂĂ������Ȃ�E�E�E����ɂ��̂悤�ȏ�Ԃɂ����ẮA���܂ꂽ�Ƃ����瑼�̐l�X�̂Ȃ��ɂق��肾����Ă���l�Ԃ́A��������䂪�l�ԂɂȂ邾�낤�B�Ό��A���ЁA�K�R�A����A�킽�����������������Ă��邢�������̎Љ�x�����̐l�̎��R�����߂��낵�A���̂����ɁA�Ȃ�ɂ������炳�Ȃ����ƂɂȂ邾�낤�v(�����Y��A�ȉ�����)
�@
�l�Ԃ��l�Ԃ��������Ǝ咣���邱�̕��͂́A�������l�Ԃ��������Ǝ咣����u�w��E�|�p�_�v��A�u�l�Ԃ͐��܂�Ȃ���ɂ��Ď��R�ł��邪�A������������Ƃ���œS���ɂȂ���Ă���v�Ǝ咣����u�Љ�_��_�v�̕��͂Ƌ��������Ă���B
�@
���̐l�Ԃ͑������̂��B�l�Ԃ��Љ�x�̂Ȃ��ɖ��v���A��l�̎����������݁A�܂��ΓI�ȒP�ʂł��邱�Ƃ���߁A�Љ�̒P�Ȃ����A�܂�S�̂̒��ł̂ЂƂ̑��ΓI�ȑ��݂ɐ���ʂĂ�����ł���B
�@
�u���R�l�͎��������ׂĂł���B�ނ͒P�ʂƂȂ鐔�ł���A��ΓI�Ȑ����ł����āA�����ɑ��āA���邢�͎����Ɠ����̎҂ɑ��ĊW���������ł���B�Љ�l�͕���ɂ���ĉ��l�����܂镪�q�ɂ����Ȃ��B���̉��l�͎Љ�Ƃ����S�̂Ƃ̊֘A�ɂ����Č��܂�B���h�ȎЉ�x�Ƃ́A�l�Ԃ����̂����Ȃ��s���R�Ȃ��̂ɂ��A���̐�ΓI���݂������āA���ΓI�ȑ��݂�^���A��������ʂ̓���̂̒��Ɉڂ��悤�Ȑ��x�ł���B�����ł́A�l�̂ЂƂ�ЂƂ�͎�������̐l�ԂƂ͍l�����A���̓���̂̈ꕔ���ƍl���A�Ȃɂ��Ƃ��S�̂ɂ����Ă����l���Ȃ��v
�@
�Љ�̂Ȃ��ɂ�����l�Ԃ́A���R�l�Ƃ͈قȂ��āA�˂ɑ��҂Ƃ̊W���̒��Ő����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̊W���́A�Ό�����]�Ƃ��������̂ōʂ��Ă���B
�@
�u�킽�������̒m�b�Ə̂�����̂͂��ׂĔڋ��ȕΌ��ɂ����Ȃ��B�킽�������̏K���Ƃ������̂͂��ׂċ��]�ƍS���ɂ����Ȃ��B�Љ�l�͓z���Ԃ̒��ɐ��܂�A�����A����ł����v
�@
�Љ�l���z���ԂɊׂ�̂́A�Љ�̒��ɕs�������������A��l�Ɠz��̑Η��������Ă���Ƃ������ԂƂƂ��ɁA�Љ�l�����R�l�Ƃ��Ď����Ă����������⑸���̊���������A��������̖ڂ��C�ɂ��Ȃ��琶���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�����Ԃ������Ă���B
�@
���Ԃ̋���Ƃ�������̂��A���������z���Ԃ�����������肾�B����́u�������l�̂��Ƃ��l���Ă���悤�Ɍ��������Ȃ���A�����̂��Ƃ̂ق��ɂ͂������čl���Ȃ���d�̐l�Ԃ�����ق��\���Ȃ��v
�@
�������l�Ԃɂ́A�l�ԂƂ��Ăӂ��킵������������߂����Ƃ��ł��Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�l�ԂɎ��R�ɂ��Ȃ���Ă���{���̂�������A�B����Ă����ꏊ���瓱���o���A�l�ɂ����g�ɒ���������A���ꂪ����̖������A�ƃ��\�[�͂����B����́A���R�ȏ�Ԃɂ�����l�ԁA�܂莩�R�l�Ƃ͂��������ǂ̗l�Ȃ��̂��A������悭�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�u���R�̒����̂��Ƃł́A�l�Ԃ݂͂ȕ����ł����āA���̋��ʂ̓V�E�͐l�Ԃł��邱�Ƃ��B������A���̂��߂ɏ\���ɋ��炳�ꂽ�l�́A�l�ԂɊW�̂��鎖�Ȃ�ł��Ȃ��͂����Ȃ��E�E�E�킽���������{���Ɍ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂͐l�Ԃ̏����ł���v
�@
�������ă��\�[�́A���R�̒����̂��Ƃɂ�����l�Ԃ̂�����₻�̏����ɂ��Ă̎����̃C���[�W�������A����ɉ����ē���̌l�����炵�Ă����l�q���A�ǎ҂Ɍ����悤�Ƃ���B�u�G�~�[���v�́A���\�[���`�������R�l�̃C���[�W���A����̌l���g�ɒ����Ă����ߒ��Ȃ̂ł���B���������Ă���́A�Љ�_��_�ɂ����Ă̂悤�ɁA���������̂���肩�����Ƃ������́A�{��������Ă������������Ȃ����߂ɂ͂ǂ�������悢���A�ɂ߂Ď��H�I�ȉۑ��Njy���Ă���킯�ł���B
�@
�Ƃ���ŁA���\�[���݂����狳�炵�悤�Ƃ��Ă���l�Ƃ́A�����������Ă͎q�ǂ��ł���B���\�[�͐��܂ꂽ����̃G�~�[���������A�ނ��N���ɂȂ��Ĉ�l�̎��R�l�Ƃ��Ď�������܂ł̊ԁA�G�~�[���ɕt���Y���āA����𑱂���B�����炱�̖{�́A�q�ǂ��͂����ɂ��đ�l�ɂȂ邩�A�Ƃ����e�[�}�����݂����Ă���Ƃ�����B
�@
���́u�q�ǂ��v�ɏœ_�������āA�����_����Ƃ������@�́A����l�̉�X�ɂƂ��Ă͒������A�v���[�`�ł͂Ȃ����A���\�[�̎���ɂ����ẮA���Ȃ�Z���Z�[�V���i���ł������͂����B�Ȃ��Ȃ�A�q�ǂ����q�ǂ��Ƃ��Ĉӎ�����n�߂��̂́A����ƃ��\�[������������ł̂��Ƃɉ߂��Ȃ��������A�܂��Ă��̎q�ǂ���Ώۂɋ����_����Ȃǂ́A����܂ōl���������Ȃ��������Ƃ����炾�B
�@
�A���G�X�ɂ��A�����̃��[���b�p�ɂ́u�q�ǂ��v�Ƃ����T�O�͂Ȃ��ɓ����������B�q�ǂ��͐l�Ԃ��������ɂ����ĂƂ�ꎞ�I�ŁA��X������������Ƃ����ӎ��͑��݂��Ȃ������B�q���́A��l�Ƃ͎����̈Ⴄ���݂Ȃ̂ł͂Ȃ��A��l�Ƃ͒��x�̍��Ō��т��Ă��鑶�݂Ƃ��Ĉӎ����ꂽ�B�q���͂���������l�Ƃ��Ă̐l�Ԃ̖��n�ȏ�ԁA���邢�͂ł������Ȃ��̐l�ԁ���l�Ƃ��Ĉӎ�����Ă����B
�@
�����炻���ɂ́u�q�ǂ��炵���v�Ƃ����T�O�͐������悤���Ȃ��A���������č����̑�l�������q�ǂ��炵���ƌ��т��Ă��邠���邱�Ɓ`�q�ǂ��炵�������A�q�ǂ��炵���������A�q�ǂ��炵���V�с`�Ƃ��������̂��Ȃ������B�q�ǂ��̕����͑�l�̂�����k�����������̂��̂��������A�q�ǂ��̗V�т͑�l�̗V�т̉����������B�q���͑�l�ƈꏏ�Ɏ���ɓ����ăr�[���������̂����A���ǂ�������Ƃ����āA��������邱�Ƃ��Ȃ������B
�@
���������q�ǂ����ɕω���������̂́A�A���G�X�ɂ��A16���I����17���I�ɂ����Ăł���B����͂܂�������V�т̕���ł����ꂽ�悤�ŁA�l�X�Ȑ}�����������Ă���B
�@
����������̕���Ɏq�ǂ��̊T�O���������܂�邱�Ƃ́A���\�[�̎���܂łȂ������͂����B���\�[�̎���̌�����Ƃ����A�_�w��̋��`�ⓚ��C���w�̃e�[�}���Ï����邱�ƂŁA�{����l�̂��߂ɍ��ꂽ�J���L�����������̂܂q�ǂ��ɓK�p���������̂��̂Ƃ����Ă��悩�����B
�@
�����Ƀ��\�[�́A�q�ǂ��̔��B��̌��E���悭�l���A�q�ǂ��̔\�͂ɉ����āA����ɂӂ��킵����������ׂ����Ƃ����e�[�[���������B����́A�ނ̋���_�́A����̗��j���悷����̂������ƕ]�����Ă��悢�B�@ |
�����\�[�̌��t
�@
�����R������B�����Ď��R�������铹�����ǂ��Ă����B���R�͐₦���q������������B
�@
�������Ȃ���̂ł��A���R�Ƃ���������̎肩��o��Ƃ��͑P�ł���B�l�Ԃ̎�ɓn���Ĉ��ƂȂ�B
�@
���ǂ�Ȃ��̂ł��A���R�Ƃ���������̎肩��o��Ƃ��͑P�ł���A�l�Ԃ̎�ɓn���Ă���͈��ƂȂ�B
�@
���R�ɂ͓��ނ���B�ߋ��Ɋւ��鎖����̉R�Ɩ����Ɋւ��錠����̉R�ł���B
�@
���Ȋw��|�p�͈����ґ�ɂ����Ȃ��A���U�̑����ɂ����Ȃ��B
�@
������Ƃ͎��R�̐��A���Ȃ킿�V���ɏ]�����ƂłȂ���Ȃ�Ȃ��B�c���Ƃ��邢�͎Љ�̂��߂�ڕW�Ƃ��A�����Ƃ������ɂȂ�����́A�l�̖{������������̂ł���B
�@
���q�����������e�Ɍ��т����Ă���̂́A����������ۑ�����̂ɕ��e��K�v�Ƃ�����Ԃ����ł���B
�@
���q����s�K�ɂ��邢����m���ȕ��@�́A���ł��A�Ȃ�ł���ɓ������悤�ɂ��Ă�邱�Ƃł���B
�@
���x�z���ꎩ�̂́A���ꂪ���_�ɕ�����Ƃ����Ȃ��ꑮ�I�Ȃ��̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A��x�z�҂̈ӌ��ɂ���Ďx�z���Ă���̂ł���A���̐l�����̈ӌ��Ɉˑ����Ă��邩��ł���B
�@
�����ɑ���p�S�����������낵�����̂ɂ��A���̐ڋ߂𑣐i����B
�@
�����R�Ɣ����́A�Љ����Y�̎Y���ł���w��ƌ|�p�ɂ���ĊQ�����B
�@
�����R�͂������Ă������\���Ȃ��B����ꎩ�g���\���̂́A�˂ɂ����ł���B
�@
�����ɂƂ��đ����͖Ƃꂦ�Ȃ��^���ŁA�������̑������痣��悤�Ƃ���A���������͂������ꂵ�݂ɏo��B
�@
���������j�������R�ɂ���Ƃ������Ƃ́A���ꎩ�̂͊Q���ł͂Ȃ��B����͏������l�ނ̍K���̂��߂ɁA���R���炤���������ł���B
�@
���l�ɂ͓��̒a��������B��́A���Ɍ��ꂽ�a���A��͐����ɓ���a���ł���B
�@
���l�Ԃ͎��R�Ȃ��̂Ƃ��Đ��܂ꂽ���A������Ƃ���ō��ɂȂ���Ă���B�Ȃꂪ���l�̎�l�ł���Ǝv���Ă���悤�Ȑl�Ԃ����͂���ȏ�̓z��ł���B
�@
���l���̎��R�͍��Ƃ̋����ɔ�Ⴗ��B
�@
�������Ƃ́A�x�z�҂Ɩ��O�Ƃ̊ԂɌ����P���Ȍ_��ł���B
�@
���j�͒m���Ă��邱�Ƃ�����ׂ�A���͐l�ɉx��邱�Ƃ�����ׂ�B
�@
���s�^�͊m���Ɉ̑�ȋ��t�����A���̎��Ɨ��͍����A���ꂩ�炦�����v�́A��������ɔ�₵����p�ɕC�G���Ȃ��B
�@
�����ւ̉R�Ƃ́A���^�����̉R�ł���B�Ƃ����̂́A���l�Ƃ��A���邢�͎����̗��v�̂��߂ɂЂƂ�V�����Ƃ́A�����̗��v���]���ɂ��Ă܂ŒV���̂Ɠ������A�s��������ł���B
�@
�����m�͂������Ĉ��܂Ȃ��B�댯�ȍ߈��ނ̂͂�����T�̊ϔO�ł���B
�@
�����j�͐l���̕��ʂ������̕��ʂ��������������`���o���B�@�@
�@ |
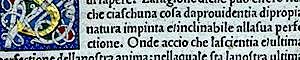 �@ �@
���P�l�[�u�t�B�W�I�N���V�[�v���C�f���ŏ��� 2��(���{1��) 1767�N |
   �@
�@
|
Quesnay, Francois.(1694-1774)
�@
Physiocratie, ou constitution naturelle du Gouvernement le plus avantageux au genre humain. Recueil publie par Dupont de Nemours, Pierre Samuel.
�@
�P�l�[�́A�t�����X�d�_��`�̑n�n�ҁB�_���̗���ɊS�������A�����̃t�����X�Љ�ŁA�_���̑d�Ō��ە��S���ߏd�ɂȂ��Ă��鎖��A�d����`�̋��s�ɂ��J���̒ቺ��ړI�Ƃ��č����̗A�o�֎~���s���A���̌��ʔ_�Y�����i�̉�������������l�ȑ[�u�Ȃǂɑ��ċ��������A�t�����X�_�ƍČ��̂��߂ɁA�Ő��̉��v�ƁA�����A�o���R�̕K�v����������B�P�l�[�̖����ł��s���̂��̂ɂ����̂́A1758�N�ɒ������u�o�ϕ\�v�ɂ����Ăł���B�{���́A�ނ̒�q�f���|���E�h�E�k���[�����P�l�[�̎�v�_����Ҏ[���Ċ��s�������̂ŁA�P�l�[�́u���R���_�v�ɂ��ču�߂����f���|����101�łɂ킽�钷���̏��������Ă���B�^�C�g���łɂ�1768�N�̊��N���݂��邪�A�{����1767�N11���Ɍ�������Ă���A����Ĉ�����ꂽ���̂ł���B |
���P�l�[�u�o�ϕ\�v
�@
�u�d�_��`�v(�t�B�W�I�N���V�[)�Ƃ́A�����ɂ�����ݕ��̒~�ς��Ȃč��x�Ƃ���d����`(�}�[�J���e�B���Y���A���邢�͐��i�҂̖�������ăR���x���e�B�Y��)�ɑ��A�x�̌���͎��R(�t���V�X)���琶�Y�I�J���ɂ���Ă����炳��鏊���ɂ���Ƃ���o�ώv�z�ł���B�u�o�ϕ\�v�̐����G�b�Z���X�́A���̏���������Ǝx�o�ɉ��A���̈ꕔ�͐��Y�I�K��(�_�ƎҊK��)�̎��̐��Y�̌����Ƃ��Ċ�����������A���̃v���Z�X�����䋉���I�ɒ~�ς��āA�������č����o�ς��g��Đ��Y�Əz�ߒ��ɂ��^�s����邱�Ƃ����������Ƃ������̂ł���B�P�l�[�́A�n��K��(�������A������K��)�A�_�ƎҊK��(���Y�I�K��)�A���H�K��(�Y�I�K���Ƃ����)�̎O�K�������ԍ��E�ݕ��̗���̃W�O�U�O����p���āA�����o�Ϗz�̃��J�j�Y���������A���̎v�z���ꖇ�̕\�Ƃ��̉���ɕ\�������B�{��O�Ȉ�ł������P�l�[�̕��͓I�������I�ȉȊw���_�̂�����Ƃ����悤�B�Ȋw�j�I�Ɍ��Ă��A�����l�̂̃C���[�W�͐����N�w�҃z�b�u�Y�ɓT�^�I�Ɍ��邲�Ƃ��A�����̎Љ�Ȋw�̐V�������z�ݏo���Ă���B
�@
�u�o�ϕ\�v�̔��z�́A�����̌`���Ƃ��Č���̌o�ϊw�̊�{�I�g�g�ɂȂ��Ă���A�}���N�X�́u�Đ��Y�\���v�u��]���l�w���v�A�������X�́u��ʋύt���_�v�A���I���`�F�t�́u�Y�ƘA�֕��́v(�u�����Y�o���́v)�A�T�~���G���\���̏搔���_�A�u�����o�όv�Z�v(SNA)�Ȃǂ̌o�ϓ��v�A�o�σT�C�o�l�e�B�N�X�́A�݂Ȃ��̕������u�o�ϕ\�v�Ɍ��o�����Ƃ��ł���B���̈Ӗ��ŁA�Ȋw�Ƃ��Ă̌o�ϊw�̗��j�I�n�܂����������̂ł���Ƃ��Ă������߂��ł͂Ȃ��B���j�I�ɂ́A�p���҃f���|�����P�l�[�̒�����L�����ɏЉ�Ă��邪�A�]����蕡���̈قȂ����e�L�X�g�����o����Ă���B���݂ł́A�~�[�N�A�N�`���X�L�[�v�l�ɂ�镧�p�Ζ�e�L�X�g���L�����p�\�ƂȂ��Ă���B�@ |
���d�_��`
�@
18���I�̌㔼�A�t�����X��Ή����́A�����I�Ɛ菤�l����ʕi(���₵�Ђ�)�H�Ƃ̕ی�琬�𒆐S�Ƃ���t�����X�^�d����`����(�R���x���e�B�X�� colbertisme)��A���Z����𒆐S�Ƃ��鏤�Ǝ�`(�W��������[�̑̐�)�ɂ���āA�o�ϓI�ɂ������I�ɂ��j�](�͂���)�ɍ�(�Ђ�)���A�̐��I��@�ɒ��ʂ����B���̍Č���Ƃ��đ�_�o�c�̔��W����� F. �P�l�[��n�n�҂Ƃ��A���̎��R�@�v�z����I�咣��o�ϊw����c�q�����W������ V.R. �~���{�[(�~���{�[��)�AP. S. �f���|����h��k���[���A�����V�G��h�������r�G�[���AA. N. �{�[�h�[(�{�[�h�[�t)�AG. F. ����g���[�k�AA. R. �`�����S�Ȃǂ��\�҂Ƃ����c�̌o�ϊw�҂ɋ��ʂ���o�ώv�z������I�咣����_�̌n���ꊇ���Ď������́B�d�_�v�z�̐��҂Ƃ��Ă̓P�l�[�����O�ɁA17���I����18���I���߂ɂ����Ċ��� P.Le P. �{�A�M���x�[���AJ. �{�[�_���AR. �J���e�B�����Ȃǂ������邱�Ƃ��ł��邪�A�P�l�[�͒P�Ȃ�_�Əd���ł͂Ȃ��A���{���I��_�o�c���d�������_�Ō���I�ɈقȂ��Ă���B
�@
�d�_��`�͖{���t�B�W�I�N���V�[�ƌĂ��B���̖��̂̓f���|����h��k���[�����P�l�[�̒���W��ҏW���Ă���ɁsPhysiocratie�t(1767)�̖��̂���������ł���A���ꂪ��ʉ������̂́A�����炭19���I���t�� L. F. E. �f�[�����d�_�w�h�̎�v�����2���{�ɕҏW���A���̖��̂����Ă���Ȍ�ł���B�d�_��`��(�t�B�W�I�N���b�gphysiocrates)�����́A�����������G�R�m�~�X�g��conomistes �ƌĂ�ł����B���ꂪ�d�_��`agricultural system �ƌĂ��悤�ɂȂ����̂́AA. �X�~�X���s���x�_�t�ł����Ă��Ƃɂ����̂Ǝv����B
�@
���d�_�w�h�̐����I�咣
�@
�t�B�W�I�N���V�[�Ƃ́A���Ƃ��Ɓq���R�̓����r���Ӗ������ŁA�d�_�w�h�͉��������@�I�ɐ������鍇�@�I�ꐧ��`���ŗǂ̐��̂ƍl���A�����̃��C�����F���Ȃ��玩�R�I�����ɂ��J���I�Љ���������悤�Ƃ����B���̂��ߐ����I�ɂ́A�Ƃ�킯�o�Ϗ�̎��R���C��`�ƒn��ɑ���P��ېłƂ�����B���R���C��`�̒́A�d����`�I�ȍ��ƓI����Ɛ�̔r���ɂ���Ă͂��߂āq��������x�r�A�Ƃ��ɔ_�Y���ɂ͂��̐���ȍĐ��Y���\�ɂ���q�lj� bon prix�r���ۏ���A���̌��ʁA��ʂł͒n��K���̎�������n�オ�������A���ʂł͔_�Ǝ��{�̑����ɂ��_�Ɛ��Y���̏㏸���\�ɂȂ�A�Ƃ�����������b�Ƃ��Ă����B�܂��n��ɑ���P��ېŘ_�́A����(����)�I�ȑd�ŕ��S��p�~���āA�ېőΏۂ�_�Ƃł������݂�������]���l�܂�q�����Y�� produit net�r�Ɍ��肷�ׂ����Ǝ咣���A�_�Ǝ��{�Ђ��Ă͎Љ�I�����{�̍Đ��Y�̏k����������邱�Ƃ��Ӑ}�������̂ł���B���̗��_�I�����́A�n��̒n������ƂȂ鏃���Y���������A�Đ��Y�ɂƂ��Ē��ڕK�v�̂Ȃ����R�����̉\�������Ƃ��������ɂ������B�����̐����I�咣��O��ɂ��A�d�_�w�h�Ƃ�킯�P�l�[�́A���{���I��_�o�c����b�Ƃ���Љ�\���𐭎��Z�p�I���@�ɂ���Ď��ؓI�ɕ��͂��A��������R�I�����Ƃ��ĕ`���o�����Ƃ����B���̌o�ϊw�̌n�́A�Љ�̍\����n��K���A���Y�K���ł���_�ƎҊK���A�s���Y�K���ł��鏤�H�ƎҊK���ɎO�����A�_�Ƃ�������]���l�܂�q�����Y���r�݂����A���ꂪ�n��K���ɒn��Ƃ��Ďx������Ƃ����\�z�̂��ƂɁA�q�o�ϕ\�r(1758)�Ƃ��đ����I�Ɏ����ꂽ�B
�@
���Ɛтƌ��E
�@
�����������͂́A�܂���1�ɃA���V��������W�[�����̃t�����X�̎Љ�\����ΏۂɁA���̌o�Ϗz��Ǝ��ȋK���I���������������̂Ƃ��āA�S�̂Ƃ��Ĕc���������̂ł���B����͌o�ϊw�̗��j��A�Љ�I�����{�̍Đ��Y�Ɨ��ʂƂ����i���{�̏z�Ƃ��ĉ𖾂��邽�߂̋N�_�Ƃ��āA�s���̋Ɛт��Ȃ��q�V�˓I�Ȓ��z�r(K. �}���N�X)�ł������B��2�ɂ���́A��]���l�𗬒ʕ��ʂɂ�����q���n�Ɋ�Â������r�ɋ��߂�d����`�I������ނ��A���̑n�o�̏�Y���ʂɋ��߂��̂ł����āA���̓_�ł͌o�ϊw�̌����𗬒ʕ��ʂ��琶�Y���ʂ֓]�������邱�ƂɂȂ�A���{��`�I���Y�͂��邽�߂̊�b���m�������Ƃ�����B�������̔��ʁA�d�_��`�҂��y�n��x�̗B��̌���ƍl���A�q�����Y���r���q���R�̑�����́r�ƍl���錩���ɌŎ����邩����ł́A�ނ�͏�]���l�܂�q�����Y���r�����{�ƘJ���Ƃ̎Љ�I�W����ł͂Ȃ��A�����I�ɓy�n(���R)�Ƃ̊W��������o�����ƂɂȂ�A���������ď�]�̒n��ւ̋A���͂��̕����I�ȓy�n���L�W�ɗR��������̂ƍl�����B�܂��A���̗����Ƃ͈���ďd�_��`�҂��q�����Y���r�Y�K���̔N�O����(���{)�Ƃ̊W�łƂ炦�A�����I�ɂ͍k��҂̏�]�Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�y�n��x�̗B��̌���Ƃ���d�_��`�I�ȕ����I�O�ς�����������Ƃ��Ă��A�d�_�w�h�́A�܂����i�̌������l��J�����Ԃ��̂��̂Ƃ��Ĕc�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���̂��߁A���ǂ��̏�]���A�k��҂��ނ�̔N�X�����g�p���l�Ƃ��Ă̐�����i�ʂ̍Œ��(�J������)���ēy�n���L�҂̂��߂ɐ��݂����g�p���l�̒��ߕ��Ƃ��ĂƂ炦�邱�Ƃ����ł��Ȃ������B����䂦�A���̒��ߕ��܂�q�����Y���r��n��Ƃ��Ď�������n��K�����A�N�X�̍Đ��Y�̎w�����������̂悤�ȕ����I�O�ς́A�ˑR�Ƃ��Ďc�邱�ƂɂȂ����B�������ďd�_��`�̏��w���́A�����ꏭ�Ȃ��ꕕ���I�y�n���L�x�z�̂��Ƃł̃u���W���A�I���Y�Ƃ����A��ʓI�Ȗ����������i�������̂ł������B
�@
���d�_�w�h�̌p������W
�@
�P�l�[�̌�p�҂����́A���̓_���߂����Ă̗��������ɑ��l�ł������B�Ȃ��ł��~���{�[�́A���̕����I�O�ςɌŎ����ێ�I���i�����������_�œ����I�ł���B����Ƃ͑ΏƓI�Ƀ`�����S�́A�P�l�[�̏����P���Ȃ�����A�K���W�⎑�{�̕��͂̓_�ŁA�ߑ�I�ȁq�u���W���A�I�{���r�̖ʂ𐄂��i�߂��B�ނ͐�����(��������)�Ƃ��Ă��A�y�n�P��ł⎩�R���C�����O�ꂳ���悤�Ƃ����B�������A�t�����X�v���O�̓����Ƃ��Ă͋}�i�I�ł��肷���A���� A. �X�~�X�́s���x�_�t���s��1776�N�Ɏ��r���A�����ɏd�_�w�h�̎��ۓI�������������̂����B�d�_�w�h�̗��_�I�v���̑����́A�ނ���C�M���X�ÓT�h�o�ϊw�̓`���I���n�̂Ȃ��ŁA���ڂɂ� A. �X�~�X�ɂ���Čp�����ꔭ�W������ꂽ�B�܂��Љ�I�Đ��Y�̑��̓I�֘A�������\���I�c���́A��N�� K. �}���N�X�̍Đ��Y�\���_�̐����Ɏ�����^������̂ł��������Ƃ����ڂ����B�@ |
���t�����\���E�P�l�[
�@
(François Quesnay�A1694-1774)�@�t�����X�̈�t�E�d�_��`�̌o�ϊw�ҁB1758�N�ɁA�d�_��`�̍l�����̊�b�����"Tableau economique"(�w�o�ϕ\�x)���o�ł������ƂŒm����B����́A���͓I��@�Ōo�ϊ����ɂ��Ă̐��������݂�A���炭�͍ŏ��̊����ł���A�o�ώv�z�ւ̍ŏ��̏d�v�ȍv����1�ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@
1718�N�O�Ȉ�ƂȂ�A1749�N����͋{���t�Ƃ��ă��F���T�C���{�a�ŕ�炵���B1752�N�M���ɗ��邪�A50�Α�Ōo�ϊw�̌������u���A�_�Ƃ̐��Y�͂����߂邱�Ƃ��d�v�ł���Ɛ������o�ϕ\�\���A�d�_��`�o�ϊw�̑c�Ƌ��ꂽ�B�P�l�[�̌o�ϕ\�̃A�v���[�`�́A�}���N�X�̍Đ��Y�\���A�������X�̈�ʋύt���_�A�P�C���Y�̗L�����v�̌����A���I���`�F�t�̎Y�ƘA�֕\�A�~���g���E�t���[�h�}���ƃA���i�E�V�������c�̉ݕ��������_�Ɏp���ꂽ�B
�@
�P�l�[�̓p���ߍx�A�����̃E�[�����ɂ��郁���[�ŁA�ٌ�m�ł��鏬�n��̑��q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B16�ŊO�Ȉ�ɒ�q���肷��ƊԂ��Ȃ��p���֍s���A�����œ��ȂƊO�Ȃ��w��ŊO�Ȉ㒷�̎��i��ƁA�}���g�ŊJ�Ƃ����B1737�N�Ƀt�����\���E�W�S�E�f�E���E�y�C���j�[�ɂ��ݗ����ꂽ�O�ȃA�J�f�~�[�̏I�g�����ǒ��ɔC������A�����̏�ΊO�Ȉ�ƂȂ����B1744�N�ɖ�w���m�̖Ə���B�ނ͍����̏�Γ��Ȉ�ƂȂ�A���̌㍑���̑��ږ���Ȉ�ƂȂ��āA���F���T�C���{�a�ŕ�炵���B�ނ̕����͒���K�ɂ���A�u����K�̉�v(Reunions de l'entresol)�͂��̖�����������̂ł���B���C15���̓P�l�[���ƂĂ����h���A�P�l�[�������̎v�z�ƂƌĂ�ł������̂ł���B�P�l�[���M���ɏ������Ƃ��A�����̓P�l�[�̘r��3�{�̃p���W�[(�t�����X��Ŏv�z���Ӗ�����p���Z(pensée)����̔h��)���A���e����̕W��ł���"Propter ex cogitationem mentis"��Y���ė^�����B
�@
�P�l�[�́A�ނ̎���Ő₦���s���Ă����{��̉A�d�ɉ��S���邱�ƂȂ��A��Ɍo�ϊw�̌����ɐ�O�����B1750�N���A�P�l�[�̓W�[���EC�EM�E�h�E�O�[���l�[(1712-1759)�ƒm�荇�����B�O�[���l�[���܂��A�o�ϕ���̔M�S�ȒT���҂������B�����āA����2�l�̒����l�̎���ɁA����Ɍo�ϊw�ҒB�́A�܂��͋�ʂ̂��߂̌�̌Ăѕ��ł͏d�_��`�ҒB�́A�w�h���`������Ă������B���̃O���[�v�̒��ōł������Ȑl���́A��~���{�[(�w�l�Ԃ̗F�x(1756-60�N)�A�����āw�_�ƓN�w�x(1763�N)�̍��)�A�j�R���E�{�[�h�[(�w�o�ϓN�w����x(1771�N))�A�M���[�����t�����\���E���E�g���[�k(�w�Љ���x(1777�N))�A�A���h���E������(�������푈�̊ԁA��������̎��R�ɂ��ăt�F���f�B�i���h�E�K���A�[�j�ƌ��킵���_���Œm����B)�A�����V�F�E�������B�G�[���A����Ƀf���|���E�h�E�k���[���ł���B1764�N����1766�N�ɃA�_���E�X�~�X�����o�N���[���f���[�N�Ƒ嗤�ɑ؍݂���ԂɃp���ʼn߂��������Ƃ�����A�����ŃP�l�[�₻�̐M��ҒB�Ɩʎ����������B�X�~�X�͔ނ́w�������̕x�x�Ɋւ���P�l�[��̉Ȋw�I���ɍ����h�ӂ����B
�@
�P�l�[��1774�N12��16���Ɏ����������A�����Ȕނ͈̑�Ȑ��k�������Ƃ��ł����B�������ĂƂȂ����W���b�N�E�e�����S�[�ł���B�P�l�[��1718�N�Ɍ������āA���q�Ɩ��������B�O�҂ɂ�鑷���q�͍ŏ��̗��@�c��̃����o�[�ƂȂ����B
�@
���o�ϕ\
�@
1758�N�ɃP�l�[�́A�d�_��`�̍l�����̊�b�����"Tableau economique"(�w�o�ϕ\�x)���o�ł����B����́A���͓I��@�Ōo�ϊ����ɂ��Ă̐��������݂�A���炭�͍ŏ��̊����ł���A�o�ώv�z�ւ̍ŏ��̏d�v�ȍv����1�ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@
�P�l�[���ނ̑̌n�ɂ��Ē��q��������͎��̒ʂ�ł���B�f�B�h���ƃ_�����x�[���́w�S�ȑS���x(1756�N�A1757�N)�́A�u�_�Ɓv�Ɓu�����v�Ɋւ���2�̋L���B�f���|���E�h�E�k���[���́w�d�_��`�x�́A���R�@���Ɋւ����b�B�w�_�Ɖ����̌o�ϓI���{�̈�ʓI���j�x(1758�N)�A�����ē����ɏo�ł��ꂽ�w�o�ϕ\�Ƃ��̐����A�܂��̓V�����ɂ�鍑���̌o�ς̗v��x(�L���ȕW��A�u�n�����_���͕n���������B�n���������͕n���������B�v�ƂƂ���)�A�w���ƂƐE�l�̘J���Ɋւ���Θb�x�A�����Ă��̑��̂�菬���Ȓf�ЁB
�@
�w�o�ϕ\�x�͂��̖����������ƒ��ۓI�`�Ԃ̂��߁A���Ԉ�ʂ̎x���͂قƂ�Ǔ����Ȃ��������A�w�h�̎�v�Ȑ錾���Ƃ݂Ȃ��邩������Ȃ��B����̓P�l�[�̐M��҂ɂ���āA�l�ނ̒m�b�ɂ���v�Ȑ��Y���ɗ���ƍl����ꂽ�B�A�_���E�X�~�X�Ɉ��p���ꂽ�Ƃ���ł́A�����Ɖݕ��ƕ��ԁA���ƎЉ�̈���ɍł���^����3�̈̑�Ȕ����i��1�ł���Ƒ�~���{�[���q�ׂĂ���B
�@
���̖ړI�́A���S�Ɏ��R�ȏ�Ԃɂ����āA�B��̕x�̌���ł���_�Ɛ��Y���������̂̐��̊K��(�y�n���L�҂̏��L�K���A�_���̐��Y�K���A�����ĐE�l�Ə��l���܂ޕs�Y�K��)�̒��ɕ��z�������@������莮�ɂ���Ď������ƁA�����Đ��{�̗}���ƋK���̃V�X�e���̉��ł̑��̔z�����f���̒莮���A���R�̒�������̈ᔽ�̈قȂ�����A�Љ�S�̂ɗǂ��Ȃ����ʂ������炷���Ƃ�`�����Ƃł���B�P�l�[�̗��_�I�Ȏ��_���画�f����ƁA�����I�Ȍo�ϊw�҂Ɛ����Ƃ��z�����Ă�����ׂ����Ƃ́A�����Y���̑����Ƃ������ƂɂȂ�B�����Ĕނ͂܂��A��ɃX�~�X���f�����悤�ɁA�S�������y�n�ł͂Ȃ��Ă��A�n��̗����͌��������łɎЉ�̈�ʓI�����Ɋ֘A���Ă��邱�Ƃ𐄘_����B
�@
���̍�i�Ƒ��̏��Ђ������������Ȕł́A1758�N�ɍ������ڂ̊ē��ɂ��������F���T�C���{�a�ň�����ꂽ���A���̐����͍����̎�Ŏ���肳�ꂽ�ƌ����Ă���B���̖{�͊���1767�N�ɂ͗��ʂ�������A���݂͂��̕����i������s�\�ł���B���������̓��e�̓~���{�[�́w�l�Ԃ̗F�x�A�����ăf���|���E�h�E�k���[���́w�d�_��`�x�ɕۑ����ꂽ�B
�@
�ނ̌o�ϊw��̒���́A���W�F�[�k�E�f�[���ɂ�鏘���ƒ��߂����āA�p���̃M���[�}���Ђ��甭�s���ꂽ�w��v�o�ϊw�ҁx�̑�2���ɏW�߂��Ă���B�܂��ނ́w�o�ϊw�ƓN�w�̒���W�x�́A�I�[�M���X�g�E�I���P���̏��_�ƒ��߂����ďW�߂�ꂽ(�t�����N�t�H�[�g�A1888)�B�w�o�ϕ\�x�̌��̌��e����̃t�@�N�V�~�������́A�C�M���X�o�ϋ���甭�s���ꂽ(�����h���A1895)�B�ނ̑��̒���́A�w�S�ȑS���x�́u�؋��v�Ƃ����L���ƁA1773�N�́w�w�̐V�����v�f�̑��āx�����w�w�I�^���̏؋��̒T���x�ł������B�P�l�[�̉����́A�O�����W�����E�h�E�t�[�V���ɂ��Ȋw�A�J�f�~�[�ŕ��������ꂽ�B(�A�J�f�~�[�̑I�W�A1774�N�A134�ŎQ�ƁB)�܂�F.J.�}�������e���́w��z�^�A�f���E�I�Z�v�l�̉�z�^�x�AH.�q�b�O�Y�́w�d�_��`�x(�����h���A1897)���Q�Ƃ̂��ƁB�@ |
�����j��
�@
�P�l�[�̌o�ϗ��_�̋L�q�͒ʏ�A�����̎嗬�ł���V�ÓT�h���_�̊ϓ_����ǂ܂��e�L�X�g�Ɋ�Â��Ă���B������̌ÓT�h�o�ϗ��_�̗��j�I�w�i�Ɗϓ_�̒��ŗ�������ƁA�����̃e�L�X�g�͈قȂ������e�𖾂炩�ɂ���B�P�l�[�̍l����1628�N�ɃE�B���A���E�n�[���F�C�ɂ���čĔ������ꂽ���t�̑̌n�I�z�Ō`������Ă���B�P�l�[�͉�U�w�̓������ނ��Ƃŕw�̎����B���Ă������߁A�ނ͓��Ȉオ���ɂ��Ęb���Ă��邩�𗝉����Ă����B�������Ȉ�̓K���m�X�ɏ]�����b������������B�����́A�������痣�ꂽ�K�ȏꏊ�̌����������邱�Ƃɂ����邱�Ƃ��ł���B�P�l�[�̓`���[�u�̃V�X�e����p���āA���͂����������邽�߂ɂ͏ꏊ�����W�ł��邱�Ƃ����������B�O�Ȉ�ɂ���o���ꂽ���̏؋��́A���Ȉ�̎Љ�I�n�ʂ�S���ቺ�����A���Ȉソ�������炾�������B�������A�����1749�N�Ƀ|���p�h�D�[���v�l�̂�������̓��Ȉ�ɂȂ������ƊO�Ȉ�̃P�l�[�ɖ�����^�����B
�@
���̘_���͍��ׂȂ��̂ł͂Ȃ������B����͈�w�̃p���_�C���̏Փ˂������B�b���́A�K���m�X(�I���O129�N - �I���O200�N)�ɂ���Đ������ꂽ�B�ނ̗��_�͐�N�ȏ�ɂ킽���Đ��m��w���x�z�������A������t�B���G��邱�Ƃ��ł���ނ̖{���̃e�L�X�g�́A�B�ꃋ�l�T���X�����̃M���V�A�ꂩ�烉�e����ւ̖|��݂̂ƂȂ����B�K���m�X�ɂ��A���t�ɂ͐S�����猌�t��������튯�܂ł̈���I�ȗ��ꂪ����B�P�l�[�̎咣�̓E�B���A���E�n�[���F�C(1578-1657)�ɂ����1628�N�ɍĔ������ꂽ���t�̑̌n�I�z�Ɋ�Â��Ă������A���̐���1661�N�Ƀ}���s�[�M���э��ǂ������Ƃ��ɗB�ꌈ��I�Ȃ��̂ɂȂ����B���̂��߃P�l�[�̎咣�ł́A�K���m�X�̑̌n�ł͗����ł��Ȃ����A���t���Đ����ꂽ�Ɛ��������B����͎����������Ȃ��ғ��m�̋c�_�������B�������A�o�ϗ��_�ɂ͋����[���ސ�������B�K���m�X�ɂ��A�S������o�铮�����Ɗ̑�����o��Ö����͂��ׂĂ̊튯�ɂ���ď����邪�A�n�[���F�C�ɂ��A���t�͍Đ������B���l�ɐV�ÓT�h�o�ϊw�ɂ��A���i�ɂ͌l�̌��p�Y���邱�ƂŔj��邽�߂̈���I�ȗ��ꂪ���邪�A�ÓT�h�o�ϊw�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��u���Y�I�v�ȘJ���̏o�͎͂��̌o�Ϗz�̓��͂ƂȂ�B
�@
�P�l�[�̌o�ϊw�ւ̋����́A�ނ�60��O���ɂ́A�ނ̋{��ł̒n�ʂɂ��t�����X�����̓|�Y�ɒ��ʂ������Ƃ�˂�����ꂽ1750�N���ɋN�����B�x�̖������܂���������Ȃ������Ƃ��A�ނ͏��i�̌o�Ϗz���x�z���Ȃ������t�z�Ɠ��l�ł���ƍl�����B�����H�A�W�G�̎_�f�Ɋւ�������́A������Ŏn�܂����B�P�l�[�͐S�����튯�̂��߂ɓ��ʂȏd�v���������Ă���̂Ɠ��l�ɁA�_�Ƃ��Љ�ƌo�ς̐��x�ɓ��ʂȏd�v���������Ă���ƍl�����B
�@
���j�I�ɁA�t�����X�����͋M���B�ɑ��Ďア�ʒu�ɂ������B�ނ̓Ɨ��������߂邽�߁A�����͋M���B���{��ɂ����ґ��݂��ɋ������Ƃ��������A�ޓ��̎��Y���y�����邱�ƂŁA�M���B��敾�������B���F���T�C���{�a�͂��̓`���ő���ꂽ�B�l����0.5%(�Q���}�������҂ƃL���X�g�����`��鍂���Ќ����ւ�A�M���ƕ�炷)�����̏������̂قƂ�ǂ���̂��Ă����B���̂��߁A�E�l�ƍH�ƓI�T�[�r�X�ւ̎��v�̂قƂ�ǑS�����A�z�I�Ȍo�ς̗���ɑS�����͂��Ȃ��Љ�I���傩�痈�Ă����B�����āA�����M���Ɛ��E�҂��o�ς̍Đ��Y�Ɩ��W�ł������Ƃ���A���̂��߂ɓ����Ă���҂́A�E�l�������B
�@
�A�_���E�X�~�X����W�����E�X�`���A�[�g�E�~���܂ł̌ÓT�h�o�ϊw�́A�u�Y�I�J���v�Ɋւ���P�l�[�̋c�_���A���̒��S�I�咣�Ƒ������B�ނ́w�o�ϕ\�x�̒��ŃP�l�[�́A�n��K��(�M���Ƒm�E)�͔_�ƂƍH�Ƃ̃T�[�r�X�邪�A�y�n��_���ɒ��݂��邱�Ƃ͕ʂƂ��ĉ������Y���邱�ƂȂ��A�E�l�͎��������Y�������̂Ɠ��������̂��̂�_�ƂƑ��̐E�l�Ɏx�����A�B��_���������A���Y����[���A�n��K���ƐE�l�B�ɋ���������ŏ����v��ۗL�������Ƃ������Ă���B
�@
���_�P�l�[�́A�n��K���Ƃ����̂��߂ɓ������ׂĂ��̂ł������ƌ��R�ƕ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ނ́A�ނ���낤�Ƃ����̐���ᔻ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�������Ƃ����������I�ɐ��������@�́A�E�l�Ɛ����Ǝ҂��u�s�Y�K���v�ƕ\�����邱�Ƃ������B���̂��߃P�l�[�́A�E�l�Ɣ_���̎d���̊Ԃɂ͈Ⴂ������ƒf������B�H�Ɛ��i�̉��i�́A�Đ��Y�̔�p�Ō��肷��B�����͍��ڂ̉��i�����́u���R�ȁv��ɕ��������邾�낤�B�_�Y�����i�͍Đ��Y�̉��i���Ă���̂ŁA���̕��傪�P�ɍĐ��Y�I�ł���̂ɑ��A�B��_�Ƃ������x�Y����B��������_�Y�����������i�������Ȃ����R��1�́A�������ɋ߂����v�ł���B
�@
�u���ޗ��̌������o�����������1����ł̂��̎�̑����̑O���瑶�݂������ւ̏���̊g��ƁA�Đ����ꂽ�x�̍X�V�Ɛ^�̐����ɂ���Č`�����x�̑n���Ƃ́A��ʂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�@
�P�l�[�ɂ��_�ƂƍH�Ƃ̉��i�̋�ʂ́A�����̕���̃C�M���X�̔��ɈقȂ�����ʂɂ�藝���ł���B�f���B�b�h�E���J�[�h�́A��菭�Ȃ����Y���̍����y�n���k����邽�߁A�_�Ɛ��Y�̑����͕������㏸������Ɛ������Ă���B�������H�Ɛ��i�̑��Y�́A1������̐��Y��������A����ɂ�艿�i�����������邾�낤�B�P�l�[�ɂƂ��āA����͂�����̏z�H�ƁA���j�I�ɑS���������B
�@
�s��̊g�傪���Y�̑����ƒP���̌����������N�����Ƃ����A�_���E�X�~�X�̗L���Ȏ咣�́A�J���͂̕����̐[���ƗU������锭���ɂ��A��ʐ��Y�ɂ̂��y���Ă���B�������A�t�����X�̐E�l�ɂ́A�I�[�_�[���C�h�̐��Y���������B�ʏ�A�����i�̐��Y�͋K�͂̌o�ς�S�����Ȃ��B�P�l�[�͌o�Ϗz�ɂ��ċc�_���邽�߁A�A�_���E�X�~�X���p���Ŏw�����A�X�~�X�̓P�l�[���S���Ȃ�O�Ɂw�������̕x�x���P�l�[�ɕ����悤�Ƃ����B�������x�̕��z�ɖ��炩�ɉe������A�C�M���X�Ɣ��ɈقȂ����t�����X�̏ɑ���ނ�̓��ʂȊW�̂��߁A�X�~�X�ł������������̏d�_��`�̍l���͗����ł��Ȃ������B
�@
�����̔����i���̗p�����_�Ɗv���ɂ���āA�C�M���X�̎Y�Ɗv���͐�s�����B--���_������Ă����ł͂Ȃ����B�C�M���X�̌n��ɑ����āA�t�����X�k���Ŋ��Ɏ��{��`�I�_�Ƃ̗Ⴊ����ꂽ�B�t�����X�S�̂ɑ��ăC�M���X���f�����̗p���邱�Ƃ́A�����̍H�ƊJ���̑O������Ƃ��āA���Y���̍��܂������B�t�����X�̖����͔_�ƊJ���̒��ɂ���A���݂̎Y�ƍ\���̊g��̒��ɂ͖����Ƃ����P�l�[�̎咣�́A�������Ȃ����͓I�ȃ}�X�^�[�s�[�X�ł���B
�@
�H�Ɛ��i�̂��߂̂��̏����̎��{��`�I�_�Ƃɑ�����v�́A�t�����X�H�ƂɐV�����s������B���̎s�ꂪ���������ƁA�o�͂����̌o�Ϗz�̓��͂ƂȂ邽�߁A�t�����X�̍H�ƂƖf�Ղ́u���Y�I�Ɂv�Ȃ邾�낤�B�����Ă��̍H�Ɛ��Y�́u��p�����v���������낤�B����䂦�H�ƂƍH�|���u�s�Y�K���v�ƌĂԂ��Ƃ͈�ʓI�ɂ͌�肾���A���̗��j�I�ɂ����Ă̂ݐ������ƌ����悤�B
�@
�u�������āv�̃e�����S�[�ƂƂ��ɁA1774�N�ɏd�_��`�v���O�����̑��������{���ꂽ�B�����������̖��m��O���[�v����̍����I�������玩���B�̗��v���グ�����ƂŁA�e�����S�[�̉��v�ɑ����R�����o�����B�t�����X�ɂ����鍒���̊ł�p�~���邱�ƂŁA�Œ�z�������Ɏx�����Ă���3�{�ȏ���W�߂Ă��������̋M���̐Ŏ��ҒB�ɑŌ���^�����B1774�N�̕s��͏������i���㏸�������B�����ĐŎ��ҒB�́A���R�f�Ղō��⍑���܂ł������������@�ŗ��v�Ă���Ƃ����\���L�߂��B�l�X�̓��F���T�C���̋{��֍s�i�����B1776�N�Ƀe�����S�[���A���ׂĂ̓�����p�~���邽�߂̑����Ƃ��Ĕ_���̕����Ɠs�s�̃M���h��P�p����悤��Ă����Ƃ��A�����͔ނ̓G�ɓ������A�e�����S�[�̎��E�����߂��B�ނ̓G�̃W���b�N�E�l�b�P�������������ɂȂ�A�l�b�P���v�l����ɂ��Ă����p���s���̃T�����ł͂����ɁA�d�_��`�I�l���͂��ׂĂ̏d�v�����������B�t�����X�̕��ƃA�����J�Ɨ��v���ւ̃t�����X�̊֗^�Ɏ������������邽�߂ɑ��ł��邱�Ƃ��ނ���A����ɑ����̎؋����t�����X�v���ւ̓����J�����B�@
�@ |
 �@ �@
���X�~�X�u���x�_(�������̕x)�v���� 2�� 1776�N |
   �@
�@
|
Smith, Adam.(1723-90)
�@
An Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations.
�@
�A�_���E�X�~�X�́A�C�M���X�̌o�ϊw�ҁB�G�W���o���ߍx�ɐ��܂�O���X�S�[��w�Ŋw�B�A�_���E�X�~�X�́u���x�_�v�́A�o�ϊw�ɂ�����ÓT���̌ÓT�ł���A�ߑ�s���Љ�����߂đ����I���̌n�I�ɉ𖾂��������ł���B���̋Ɛтɂ���ăA�_���E�X�~�X�́A�g�o�ϊw�̕��h�ƌĂ�Ă���B�u���x�_�v�͌o�ϊw�j��A19���I�ȍ~�ɕ�������������w�h�̌����ƂȂ��Ă���A���ׂĂ̊w���͑����ꏭ�Ȃ���X�~�X��f�ނƂ��Ĕ��W���Ă����̂ł���B |
�����x�_
�@
( An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations / �A�_���E�X�~�X���B1776�N���B���{��`�Љ�����߂đ̌n�I�ɂƂ炦�A���ƂƘJ�����l���ƂɊ�Â��Ď��R���C��`�̌o�ς���������ÓT�w�h�̑�\�o�ϊw���B)
�@
���w���x�_�x(�������̕x)�ݏo�����w�i
�@
�A�_���E�X�~�X�̎咘�w���x�_�x���o�ł��ꂽ�̂�1776�N�̂��Ƃł���A�ނ̐��U�̌㔼���͎Y�Ɗv���̖u�����Əd�Ȃ��Ă���A���{��`�̊m���Ɍ����Ď��オ�傫���ς���Ă����]�����ɂ�����B�����A�C�M���X�Y�Ɗv���̐i�W�������o���������ł́A�X�~�X�̑̌n�Ƃ��̎���Ƃ̑Ή��W�͂킩�����Ƃ��Ă��A�����ɂ��ăX�~�X�̑̌n�����܂ꂽ�̂��͂킩��Ȃ��B
�@
�X�~�X�́w���x�_�x�͏d����`�̊�@�Ƃ��������Ő������B����܂ł̏d����`�̏펯�ɂ��A�ꍑ�͑������]���ɂ��Ă̂o�ϗ͂�ł��A�A���n�ۗ̕L�Ƃ��̋����_�Ƃ��鍑�Ƃ̋��s�I����ɂ���Ă̂݁A�ꍑ�o�ς̔��W���\�ł���A�Ƃ����̂ł���B
�@
�d����`�ɑR���A�����̃C�M���X�ɏ���ⳂƂ��āA�X�~�X�́w���x�_�x������̂ł���B
�@
�����e
�@
���x�Ƃ́H
�@
�]���̏d����`�ɂ��A�u�x���ݕ��v�ƋK�肳��A�����ɂ��ė�������ݕ��𑝂₵���o����ݕ������炷���Ƃ����ϓ_���琭���肳���B�����A�X�~�X�́A�x�Ƃ͍������N�X�ɏ���邢�������̐����K���i��։v�i�A�Ƃ��ĂƂ炦���B
�@
�����Ƃɂ���
�@
�����Љ�ł͕n�����҂ł��A���J�Љ�̍��������L���ł���B�X�~�X�͕����Љ������Â��鐶�Y�͂̊�b���A�����ɂ���Ĕ}���镪�ƁA���Ȃ킿�Ǘ��I�J���̎Љ�J���ւ̌����ɒu�����B�X�~�X�́C���Ƃ��J�����Y�͂����P���闝�R���C�L���ȃs���H��̗�������Ȃ���������Ă���B�����E�l��1�l�����Ńs��������Ȃ��1����1�{�̃s�������邱�Ƃ��e�Ղł͂Ȃ��B�Ƃ��낪�X�~�X���K�ꂽ�s���H��ł́C10�l�̘J���҂���ƂS���ē����C1�l������1����4800�{���̃s�������Ă����B���Ƃ����̂悤�ɘJ���̐��Y�͂����߂�̂́C1�J���҂̏n����Z�\�����P���C2����d������ʂ̎d���ֈړ����鎞�Ԃ�ߖC3�J����P�������ċ@�B�̔�����e�Ղɂ���C�Ƃ���3�̌����ɗR�����Ă���B���Ƃ́A���̂悤�ȍH����̕��Ƃ����łȂ��C�Љ�S�̘̂J������̋���Ȍ����J���ƂȂ�A�Љ�I���Ƃɂ����čs���Ă���B�����Љ�̕x�T�͎Љ�I���Ƃ̌��ʂȂ̂ł���B
�@
�����ƂƏ��ƎЉ�
�@
�X�~�X�́C�L�͂ȕ��Ƃݏo���u�����v�Ƃ����l�Ԃ̍s�ׂ��A����◘���S�ł͂Ȃ��A�l�Ԗ{���ɂ��Ȃ�������������Ɨ��ȐS�̌��ʂł���ƍl�����B���Ƃ��C�p����K�v�Ƃ���Ȃ�A�p�����ɋ�i����̂ł͂Ȃ��A�p�������~���Ă��镨��^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ЂƂ��юЉ�I���Ƃ��m������Ă��܂��ƁA�e�l�݂͂�����̘J���ɂ���č�肾���ꂽ���Y���̂����A�������g������镪�����������A���̐l�X�̘J�����Y���ƌ������邱�Ƃɂ���āA����̘J�����Y�������ł͖�������Ȃ��~�]���[�����悤�Ƃ���B���̂悤�ɂ��āA���������S�ƂȂ�悤�ȏ��ƎЉ�ɐ�������B�����ŃX�~�X���������ƎЉ�Ƃ́A�_�Ƃ��H�Ƃ��܂߂��L���Ӗ��ł���A�s���Љ�̌o�ϓI���ʂ�\��������̂ł��������B���ƎЉ�ł́A�ݕ����d�v�Ȗ������ʂ����B�p�����Ɠ����̕��X�������������邽�߂ɂ́C�p����������~������Ɠ����ɓ������p������������Ƃ����~�]�̓�d�̈�v���K�v�ł��邪�C����͕K����������킯�ł͂Ȃ��B�l�X�́C�����������X�����̕s�ւ�����邽�߂ɁC�قƂ�ǂ��������鏤�i���u���Ƃ̋��ʂ̗p��v(�����蓊)�Ƃ��ėp����悤�ɂȂ����B�p�����́C�����̃p��������ł����ݕ��ƌ������C���ɂ��̉ݕ�����Ȃǂ̎������K�v�Ƃ�����̂ƌ�������Ȃ�C���X�����̕s�ւ͉��������B
�@
�����R���i�ƌ��������
�@
�X�~�X�́A���ׂĂ̂��̂ɂ��āA���̌������l�́A��������L���邱�Ƃɂ���ē�����x�z�͂ɓ������Ȃ�ƍl�����B��������A�s��ŋ��߂���A�J���܂��͘J���̐��Y�����ǂꂾ���x�z���邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ������Ƃɂ���Č��߂���ƍl�����B�ݕ��o�ς̂��Ƃł́A����Ɍ����䗦�����łȂ��A���ډ��i�����܂��Ă���B���̂悤�ȑ��݈ˑ��W������I�Ɉێ�����Ă䂭���߂ɂ́A�����̏������l�X�̎��R�Ȉӎu�ɉ����āA�e�l�̗��v�ƒ��a���ꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�Ȍ����̏������A�X�~�X�́u���R���i�v�Ƃ����T�O�ŕ\�������B���R���i�̂��Ƃł́A�e�l�����R�ɍs�����A�I���������ʁA���Y�v�f�̔z�������܂�A���܂��܂ȍ��E�T�[�r�X�̎Y�o�ʂ���܂�B�����Ő��Y���ꂽ���̂́A�l�X���K�v�Ƃ���ʂƈ�v����悤�ɂȂ�B�X�̐l�X�́A����ɂƂ��Ă����Ƃ��]�܂����Ǝv�����������悤�Ƃ����Ƃ��ɁA�Љ�S�̂Ƃ��Ē��a�̂Ƃꂽ��ԁA�܂肷�ׂĂ̍��E�T�[�r�X�ɂ��āA���v�Ƌ����Ƃ���v����悤�ȏ�Ԃ��������A�����������Ԃɂ킽���Ĉێ������B�e�l�����ꂼ�ꎩ���̗��v���l���čs�����Ă���ɂ�������炸�A�Љ�S�̂Ƃ��Ė]�܂�����Ԃ���������̂́A�܂��Ɂu���������v�ɂ����̂ł���ƃX�~�X�͍l�����̂ł���B�J���҂��݂�����̘J���̐��Y�������ׂĎ��Ƃ����{���I�ȏ�Ԃ́A�����̒~�ςƓy�n�̏��L���i�s����ɂ�āA�ێ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���R���i�́A�J�������̑��ɁA�����A�n�ォ��\������邱�ƂɂȂ�B�����āA���̔w��ɂ́A�J���ҁA���{�ƁA�n��Ƃ����O��K�������݂��A���̎O��K������s���Љ�\������A���ꂼ������I�ȓ��@�ɂ��ƂÂ��čs�����Ȃ���A���R���i�̂��ƂőS�̂Ƃ��Ē��a�̂Ƃꂽ��Ԃ��ێ����Ȃ���A�Љ�S�̂̕x�̒~�ς������Ȃ��Ă䂭�Ƃ����̂��X�~�X�̐��E�ς������B
�@
���w��������_�x�Ƃ̊֘A
�@
�w���x�_�x�ɂ�����X�~�X�̍l���́A����ɐ旧��17�N�O�ɏ����ꂽ�ނ́w��������_�x(1759�N)�ɂ�������Ɩ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����^��͑��������o����Ă����B�܂�A�X�~�X�́w���x�_�x�ɂ����闘�ȐS�Ɋ�Â��s��s���̕]���ƁA�w��������_�x�ɂ����闘���I�Ȋ���̕]���Ƃ̊W���ǂ̂悤�ɉ������Ƃ����A������u�A�_���E�X�~�X���v�ł���B
�@
�����A����́w��������_�x�ɂ�����u�����v������������̂ɉ߂��Ȃ��B�X�~�X�́u�����v�́A���ʂȗ��Q�E����W�̂Ȃ��l�ǂ����̊ԂŐ��藧�����鐥�F�̊�����w�����̂ł���A���ȓI�o�ύs�ׂ�ے肷����̂ł͂Ȃ��B
�@
�w��������_�x�ŒNj������̂́A�l�X���Γ������R�ɐU�镑���A�N���������̗��v��Nj����Ă���݂Ȃ����悤�ȎЉ�ł̒����`���̉\���ł���B
�@
�X�~�X�ɂ��A���������Љ�ɂ����钁�����x����̂́A��I�Ȉ�̊��ł͂Ȃ��A�s�҂��ꂼ��̗���ɉ��ɉ䂪�g�������čl���邱�Ƃɂ���Đ�����u�����v�ł���B�䂦�ɁA�ΏۂƂȂ�s�ׂ́A���ׂ��̂��߂̍s���ł����Ă����܂�Ȃ��B���ȐS�ƁA�ЂƂ������ȐS�����������l�ɑ��铯������{�����ɂ�����Ă���̂ł���B
�@
�������A���l����������A�������ɔ������i�����悤�ȍs�ׂɑ��ẮA�l�X�́u�����v���Ȃ��ł��낤�B���������āA�Љ���̂Ȃ��ŁA�l�X�͎���ɁA�����̗��ȓI�s�ׂ��A�����ȑ��l�̖ڂ���݂Đ��F���ꂤ��͈͓��ɗ}����Ƃ����̂ł���B
�@
���@
�X�~�X�������̊�b�ɗ����ł͂Ȃ������u�����̂��A���邢�͎s��Љ�̍\�������Ƃ��ė��ȐS�⎩���S���l�����̂��A�˂��l�߂�A�l�Ԃ͑S�m�S�\�ł͂Ȃ��Ƃ�����{�I�F��������������ł���B������19���I�ȍ~�̐V�ÓT�h�o�ϊw���l�Ԃ�S�m�S�\�̌o�ϐl�ƋK�肷��Ƃ���ƁA�܂�������������_������B�X�~�X�́A�X�̐l�Ԃ�������x�̑���Ƃ����ړI�̂��߂����ɍs������悤�ȁu�����I�v�ȑ��݂��Ƃ͍l���Ă��Ȃ������B�����āA�ނ͋ɒ[�ȃ��b�Z�E�t�F�[���������鐭���I�A�i�[�L�Y���Ƃ͖����Ȏv�z�Ƃł���B���ȗ��v�̒Nj��́A�ʼn_�ɂȂ���Ă��悢�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��āA�u���`�̃��[����N���Ȃ��͈͂Łv�Ƃ����O��ƂȂ����������̂ł���B�@ |
���������̕x�̐����ƌ����̌���
�@
( An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations )�@1776�N�ɏo�ł��ꂽ�A�_���E�X�~�X�̒���ł���B�w���x�_�x�A�܂��́w�������̕x�x�̖��ł��m����B���ɑO�҂���ʓI�ł��邽�߁A�Ȍ�{���ł��O�҂�p���邱�ƂƂ���B�{���͎Y�Ɗv���Ȍ�ɂ�����o�ϊw�ɂ��Ė��m�ɋL�q����Ă���B�{���͑S�A�ܕ҂ō\������Ă���B
�@
�����v
�@
���x�_��1776�N�ɏo�ł���Ĉȍ~�A�A�_���E�X�~�X�̑������A�ގ���̎�ɂ����4�x�̉������s���Ă���(1778�N�A 1784�N�A1786�N�A1789�N)�B����ē��{��ւ̖|���1789�N�ɏo�ł��ꂽ��ܔł����ɍs���邱�Ƃ������B�������A1791�N�ɏo�ł��ꂽ�掵�ł��A�_���E�X�~�X���������Ƃ��s�����Ō�̔łł͂Ȃ����Ƃ�����������A��������l���Ȃ�����b�ɂ������|�������B
�@
5��̉�����o��Ԃɂ͑����ׂ̍��ȈႢ�����݂���B1778�N ���� - ���łƂ̍��ق͏d�v�łȂ����̂ł��������A�r���̒lj����s���Ă���B1784�N ��O�� - �d����`�ᔻ�����̎�ȓ��e�Ƃ���ʍ��̒Ǖ₨��ђ�����g�ݍ��݁A�ڎ���t�����B�O�����琬��B1786�N ��l�� - ��O�ł���킸���ɉ������{���ꂽ�B�A�_���E�X�~�X�͖{�̏��߂̓ǎ҂ɑ��鍐���ɂ����āu(��l�łł�)���͂����Ȃ��ނ̕ύX�������Ȃ������B�v�ƌ����Ă���B1789�N ��ܔ� - ��A����蕥���Ă���B
�@
���̌�̔ł̓A�_���E�X�~�X����������1790�N�ȍ~�ɏo�ł���Ă���B�G�h�E�B���E�L���i�� (Edwin Cannan) �w���̉��A���߂�5�̔ł����L����Ĕ�r����Ă���Z���ł�1904�N�ɏo�ł���Ă���B
�@
�����e
�@
�Y�Ɗv�� / �{���̑��ґ��͂����O�͕͂���(division of labor)�̔��W���������Ă���B��\�͑��߂ł́A �������̏I���Ɋւ��闝���𑣂��Ă���B
�@
�o�ϊw�̓��发�Ƃ��� / �A�_���E�X�~�X�̒���́A�d����`�̔�]����єނ̎���ɍl�����Ă����V���̌o�ϊw�̑����̂Ƃ��ċL�q����Ă���B�{���͒ʏ�A�ߑ�o�ϊw�̒[���ł���ƍl�����Ă���B�{���͑��̌o�ϊw�҂Ɍ����ĂƂ��������A�ނ���18���I�����ɂ����镽�ϓI�ȋ�������l�X�Ɍ����ď����ꂽ���̂ł���B���������āA�{���͌���̓ǎ҂ɂƂ��ČÓT�h�o�ϊw(classical economics)�̔�r�I�������₷������Ƃ��Ă̌ÓT�Ƃ��ēǂp����Ă���B�w���x�_�x�͑S�ܕт��o�ϊw�̗��_���ł���A���̈ꕔ�݂̂��o�ϊw�̗��_�Ƃ��Ĉʒu�Â��邱�Ƃ͌��ł���B���̏��͗��j���ł͂Ȃ��A���Ր������������_���ł���̂ŁA���̓��e�̈ꕔ�̐V���������Ĕ��f���鏑���ł͂Ȃ��B���̏؋��Ƃ��āA�㐢�A�P�C���Y�́w���x�_�x��B��u�l��Łv�̌o�ϊw�Ƃ��āA���Ȃ킿�A�B�ꊮ�����ꂽ�o�ϊw���Ƃ��A����ȍ~�̌o�ϊw�����ׂĂ��̉���ɂ����Ȃ��Ƃ��č����]�����Ă���B
�@
�u���������v / (invisible hand)�͖{���̊T�O�Ƃ��Ă����Ό��y�������̂ł���B���́u���������v�̔w��ɂ���v�z�́A�l�X�����̗~���Ƌ��R�̒Nj���ʂ��Ė��ӎ��I�Ɏ���̍��W������ł��낤�Ƃ����咣�ł���B
�@
�Ɛю�` / �Ɛю�`(Meritocracy�A�����g�N���V�[)�͖{���ɂ����ċ��������e�[�}�ł���B
�@
���d����`�ᔻ
�@
�X�~�X�̏d����`����ւ̔ᔻ�́A�ݕ�����E�Ő���E�d�ʼn��v�ƍ��̔��s���ɂ��ēW�J����Ă���B�d����`�́A��Ή����̂��ƁA�f�Ղɂ���č��݂邱�Ƃňꍑ�̕x�傳���悤�Ƃ������A���̐���̌��ʂƂ��āA�t�ɋ��ݕ�����ʂɍ��O�ɗ��o���A�R���x�o�̑���ƂƂ��ɃC�M���X�o�ς�敾�����錴���ƂȂ��Ă����B�X�~�X�̔ᔻ�́A�g�[�}�X�E�O���V�����ɑ���ᔻ�Ƃ��Ẳݕ��̉����ł���A���R��`�̗��ꂩ��̊ł̓P�p�A�����āA�d�ʼn��v�Ɛ��̒��B�̂��߂̍��̔��s�̒�~�ł���B
�@
���{�ł͂��܂�m���Ă��Ȃ������̔w�i�Ƃ��āA�C�M���X�ł͕������̏���ʂ��}���ɑ������Ă���A�������Y���Ȃ��C�M���X�ł̓t�����X����̗A���ɂ��ׂĂ��ˑ����Ă����B���̂��߁A�t�����X�Ƃ̖f�ՐԎ����}���ɑ��債�Ă����̂ł���B�f�ՐԎ������Ƃ̑����Ƃ݂Ȃ��d����`�ɂ����������ł͎��R�̖@�����䂪�߂邾���ł���A�o�ς����������Ă��܂��ƃX�~�X�͍l�����B �X�~�X�́A�x�̊T�O���]���̖f�Ղɂ����݂̊l������J���̐��Y�͂̑���ւƓ]�邱�ƂŁA�o�ϊw�𐬌��������̂ł���B
�@
���e��
�@
���x�_�͌[�֎v�z�̎���ɏo�ł���A���҂���ьo�ϊw�҂݂̂Ȃ炸���{����ђc�̂ɉe����^�����B�Ⴆ�A�A���L�T���_�[�E�n�~���g�������x�_�ɂ���Ċ����Ɖe�����Ă���B�{�����f�C���B�b�h�E�q���[����V�������E�h�E�����e�X�L���[�A�����ďd�_��`�҃W���b�N�E�e�����S�[�Ƃ������v�z�ƁE�o�ϊw�҂����ɂ���Ċm���ς݂ł��������_�̏Ă������ł���Ƃ����Ă��邱�Ƃ́A�ꕔ�ɂ����Ă͐^���ł���B�������Ȃ���A�{���͌o�ϊw�ɂ�������i�ł���A�����w����ь��㐔�w�A�Ȃ�тɎ��R�Ȋw�ɂƂ��Ắw�v�����L�s�A�x�̈ʒu�Â��Ɨގ�������̂ł���B
�@
�㐢�A�����̒��q�Ƃ����x�_�ɉe������A����̒���̏o���_�Ƃ��Ă����p�����B�W�������o�e�B�X�g�E�Z�C��f���B�b�h�E���J�[�h�A����сA����Ɍ�̎���ɑ�����J�[���E�}���N�X�����x�_���o���_�Ƃ������q�ƂɊ܂܂��B�@ |
���A�_���E�X�~�X
�@
(Adam Smith�A1723-1790)�@�X�R�b�g�����h���܂�̃C�M���X(�O���[�g�u���e������)�̌o�ϊw�ҁE�_�w�ҁE�N�w�҂ł���B�咘�́w���x�_�x(�܂��́w�������̕x�x�Ƃ��B����w�������̕x�̐����ƌ����̌����xAn Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)�B�u�o�ϊw�̕��v�ƌĂ��B
�@
2007�N���C���O�����h��s�����s����20�|���h�����ɏё����g�p����Ă���B�ߋ��ɂ̓X�R�b�g�����h�ł̎������s��������s�̈�A�N���C�Y�f�[����s�����s����50�|���h�����ɂ��ё����g�p����Ă����B
�@
�A�_���E�X�~�X�͐Ŋ֗��Ƃ��ăX�R�b�g�����h�̊C�����̒��J�R�[�f�B�[�ɐ��܂ꂽ���A���͐��܂�锼�N�O�Ɏ��S�����B���N�����͕s�ڂł��邪�A1723�N6��5���ɐ���������Ƃ͖��炩�ɂȂ��Ă���B���S�l�ƂȂ�����́A�S�v�Ɠ����A�_���Ƃ������O����l���q�ɂ��A���U����𒍂����B�X�~�X��4�̎��ɃX���Ɏd���ďグ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ����U���ɑ������̂́A�U���Ƃ���X���ɂ͌����Ȃ��Ƃ��������������A�������Ă��܂��قǓ����I���i�������A�h�肪�������B
�@
�O���X�S�[��w�œN�w�҃t�����V�X�E�n�`�\���̉��œ����N�w���w�сA1740�N�ɃI�b�N�X�t�H�[�h��w�ɓ��w���邪�A1746�N�ɑފw�B1748�N����G�f�B���o���ŏC���w�⏃���w�������n�߁A1750�N���A��ɗF�l�ƂȂ�N�w�҃q���[���Əo��B���̌�A1751�N�ɃO���X�S�[��w�Ř_���w�����A��1752�N�ɓ���w�̓����N�w�����ɏA�C����B1757�N�A�G���W�j�A�̃W�F�[���Y�E���b�g������w�\���Ŏ��������E�C���X���J�Ƃ��邱�Ƃ��菕�������B1759�N�ɂ̓O���X�S�[��w�ł̍u�`�^�w������_�x(�܂��́w��������_�xThe Theory of Moral Sentiments)�\���A�������m���B�����̗��_�͉�X�ɂ͓����������銴�o(Moral Sence)������Ƃ����������E�Z���X�w�h�Ɋ܂܂��B
�@
1763�N�ɂ͋����E�������A��3��o�N���[���݃w�����[�E�X�R�b�g�̃O�����h�c�A�[�ɉƒ닳�t�Ƃ��ē��s���t�����X�ɓn��B���̍��p���̃C�M���X��g�ٔ鏑�߂Ă����q���[���̏Љ�ŃW���b�N�E�e�����S�[��W�����E���E�����E�_�����x�[���A�t�����\���E�P�l�[���͂��߂Ƃ���t�����X�m���l�Ɛe�������B�������A�o�N���[�̒킪�p���ŕa�v�������Ƃ�����������(�ÎE�������Ǝv���Ă������A�X�~�X���g�̎莆�ɂ��a�v�Ɣ���)�C�M���X�ɖ߂����B�X�~�X��1766�N�ɃX�R�b�g�����h�ɖ߂�A1776�N3��9���ɏo�ł���邱�ƂɂȂ�w���x�_�x�̎��M�ɂƂ肩����B
�@
�A�����J�Ɨ��A�e�����S�[���r�̔N�ɔ��\���ꂽ�w���x�_�x�̓A�_���E�X�~�X�ɐ��Ȗ��_�������炵�A�C�M���X���{�̓X�~�X�̖��_�E�A�C��Őf�������A�X�~�X�͕��Ɠ����Ŋ֗��̐E��]�݁A1778�N�ɃG�f�B���o���̊ňψ��ɔC�����ꂽ�B�����͑O�L��2���݂̂ŁA���ʂ܂ł��̉��葝��ɏW�������B1782�N�̕�̎���͊�s���ڗ����A�ŊE���̐����ɐg���݁A�X��p�j����悤�ɂȂ�B1787�N�ɂ̓O���X�S�[��w���_�w���ɏA�C���A1790�N�ɃG�f�B���o����67�Ŏ��S�����B�����̑������������P���Ƃɕ����A���̒��O�A���e�ނ����ׂďċp�������Ƃ�����B
�@
����������_
�@
�w������_�x�ɂ��A�l�Ԃ͑��҂̎������ӎ����A���҂Ɂu����(sympathy)�v����������A���҂���u�����v����悤�ɍs������B���́u�����v�Ƃ����������ɂ��A�l�͋�̓I�ȒN���̎����ł͂Ȃ��A�u�����Ȋώ@��(impartial spectator)�v�̎������ӎ�����悤�ɂȂ�B�u�����Ȋώ@�ҁv�̎������猩�Ė�肪�Ȃ��悤�l�X�͍s�����A���҂̍s���̓K�X���f���邱�Ƃɂ��A�Љ�����̒����Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă��邱�Ƃ��q�ׂ���B���̂悤�ɎЉ�́u�����v����ɂ��Đ��藧���Ă��邽�߁A�Љ�́u���P(beneficence)�v���͂��߂Ƃ������݂̈���Ȃ��Ƃ����藧������Ƙ_�����B�܂��A�x�T�Ȑl�X�́A��n���S�Z���ɕ����ɕ��z����Ă����ꍇ�Ƃقړ���̐����K���i�̕��z���A�u���������v�ɓ�����čs�Ȃ��Ƃ������Ƃ��q�ׂĂ���B�@ |
���A�_���E�X�~�X�w���x�_�x
�@
�����̐H���͖≮��p�����̎����S�ɂ���Ă���
�@
�u���������v�ɓ�����ĎЉ�̗��v�����i����Ă���
�@
�����Ƃ́A�l�Ԃ̖{���ɂЂ��ތ����Ƃ����������琶����
�@
(����)�@�ق��̂����Ă��̓����͂ǂ���A�ЂƂ��ѐ��n����ƁA���S�ɓƗ����Ă��܂��A�ق�炢�A���̐������̏�����K�v�Ƃ��Ȃ��B�Ƃ��낪�l�Ԃ́A���Ԃ̏������قƂ�ǂ����K�v�Ƃ��Ă���B�����A���̏����𒇊Ԃ̔����S�ɂ̂݊��҂��Ă݂Ă��ނ��ł���B�ނ��낻������A�������ꂪ�A�����ɗL���ƂȂ�悤�ɒ��Ԃ̎����S���h�����邱�Ƃ��ł��A�����Ă��ꂪ���Ԃɋ��߂Ă��邱�Ƃ𒇊Ԃ�����̂��߂ɂ��邱�Ƃ��A�������g�̗��v�ɂ��Ȃ�̂��Ƃ������Ƃ��A���ԂɎ������Ƃ��ł���Ȃ�A���̂ق��������ƖړI��B���₷���̂ł���B���l�ɂ����̎������\���o����̂͂���ł��A���̂悤�ɒ�Ă���̂ł���B���̂ق������̂����������A����������Ȃ��̖]�ނ���������܂��傤�A�Ƃ����̂��A���ׂĂ̂��������\���o�̈Ӗ��Ȃ̂ł����āA���������ӂ��ɂ��āA�����́A���������̕K�v�Ƃ��Ă��鑼�l�̍D�ӂ̑啔�����������Ɏ�肠���̂ł���B
�@
����ꂪ�H�����Ƃ��̂��A�����������p�����̔����S�ɂ��̂ł͂Ȃ��āA�������g�̗��v�ɂ������邩���̊S�ɂ��̂ł���B����ꂪ�Ăт�����̂́A�����̔����I�Ȋ���ɂ������Ăł͂Ȃ��A�����S�ɂ������Ăł���A����ꂪ�����Ɍ��̂́A����ꎩ�g�̕K�v�ɂ��Ăł͂Ȃ��A�����̗��v�ɂ��ĂȂ̂ł���B
�@
���l�̎������߂����������A���������ɓ�����āA�Љ�̗��v�𑣐i����
�@
�Ƃ��낪�A���ׂĂǂ̎Љ���A�N�X�̎����́A���̎Љ�̋ΘJ�����̔N�X�̑S���Y���̌������l�Ƃ˂ɐ��m�ɓ������A����ނ���A���̌������l�Ƃ܂��ɓ��ꕨ�Ȃ̂ł���B����䂦�A�e�l�́A����̎��{���������̋ΘJ�����̈ێ��ɗp���A�����̋ΘJ�������A���Y�����ő�̉��l�����悤�ȕ����ɂ����Ă䂱���ƁA�ł��邾���w�͂��邩��A��������K�R�I�ɁA�Љ�̔N�X�̎������ł��邾���傫�����悤�ƍ���܂邱�ƂɂȂ�킯�Ȃ̂ł���B
�@
�������A����͂ӂ��A�Љ��ʂ̗��v�i���悤�ȂǂƈӐ}���Ă���킯�ł͂Ȃ����A�܂��������Љ�̗��v���ǂꂾ�����i���Ă���̂����m��Ȃ��B�O���Y�Ƃ��������̎Y�Ɗ������ێ�����̂́A�����������g�̈��S���v���Ă̂��Ƃł���B�����āA���Y�����ő�̉��l�����悤�ɎY�Ƃ��^�c����̂́A�������g�̗����̂��߂Ȃ̂ł���B
�@
�����A�������邱�Ƃɂ���āA����́A���̑����̏ꍇ�Ɠ������A���̏ꍇ�ɂ��A���������ɓ�����āA�݂�����͈Ӑ}���Ă����Ȃ�������ړI�𑣐i���邱�ƂɂȂ�B���ꂪ���̖ړI���܂������Ӑ}���Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ́A���̎Љ�ɂƂ��āA������Ӑ}���Ă����ꍇ�ɂ���ׂāA���Ȃ炸�����������Ƃł͂Ȃ��B�����̗��v��Nj����邱�Ƃɂ���āA�Љ�̗��v�i���悤�Ɛ^�ɈӐ}����ꍇ�����A�����ƗL���ɎЉ�̗��v�i���邱�Ƃ���������̂ł���B
�@
�Љ�̂��߂ɂƏ̂��ď��������Ă���k�y[�Ƃ͂��|�₩��A�Ƃ�����]���A�Љ�̂��߂ɂ����������������Ƃ����悤�Șb�́A���܂����ĕ��������Ƃ��Ȃ��B�����Ƃ��A�����������������Ԃ����ԓx�́A���l�̂������ł͒ʗႠ�܂茩���Ȃ�����A������������Ă������߂�����̂́A�ׂɍ��̐܂�邱�Ƃł͂Ȃ��B
�@
�����̎��{���ǂ�������ނ̍����Y�Ƃɗp����悢���A�����āA���Y�����ő�̉��l�����������Ȃ̂͂ǂ����������Y�Ƃł��邩���A�X�l���ꂵ���A�������g�̗���ɂ������āA�ǂ�Ȑ����Ƃ◧�@�҂��������A�͂邩�ɓI�m�ɔ��f���邱�Ƃ��ł���A�Ƃ������Ƃ͖��炩�ł���B�X�l�Ɍ������āA�����̎��{���ǂ��g������悢�����w�����悤�Ƃ���悤�Ȑ����Ƃ�����Ƃ���A����́A���悻�s�K�v�Ȑ��b���݂�����w�������ނ���łȂ��A��l�͂��납�����@��c��ɂ������Ă������Ĉϑ��͂ł��Ȃ��悤�Ȍ������A�܂��A��ꂱ��������s�g����K�C�҂��Ǝv���Ă���悤�Ȑl���̎蒆�ɂ���ꍇ�ɍł��댯�Ȍ������A�����ɂ��A�����ęG�z�ɂ��A�����ň����邱�ƂɂȂ�̂ł���B�@�@ |
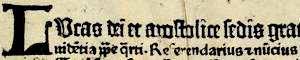 �@ �@
���t�����N�����u�����E�N�w�_�W�v���� 1779�N |
   �@
�@
|
Franklin, Benjamin.(1706-90)
�@
Political, miscellaneous, and philosophical pieces...
�@
�t�����N�����́A�A�����J�̐����ƁA�o�ŋƎҁA�Ȋw�ҁA���q�ƁB����}���ق����A�A�����J�N�w�����ݗ����A�����̌������Ƃɍv�������B�T��O����A�N�w����щȊw�̌����ɖ��߁A��d�œ_�����Y��n�[���j�J�̔����������B�܂��d�C�ɋ����������A���J���ɑ��������ė��d�Ɠd�C���������̂ł��鎖�𗧏����B1776�N�ɂ̓A�����J�Ɨ��錾�N���ψ��̈�l�ɂȂ����B�{���́A�t�����N�����̐����w����ѓƗ��푈�O��̃A�����J�̐����Ɋւ���_���ƁA�ނ̓N�w�I�_�����W�߂����̂ŁA�����h���ŏo�ł���Ă���B �@�@
�@ |
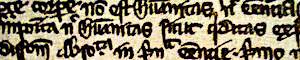 �@ �@
���J���g�u���������ᔻ�v���� 1781�N |
   �@
�@
|
Kant, Immanuel.(1724-1804)
�@
Critik der reinen Vernunft.
�@
�J���g�́A�h�C�c�̓N�w�҂Ŕᔻ�N�w�̑n�n�ҁB�{���͂��̎咘�ŁA����V�I���Ɓ��o���I������A�����͓I���Ɓ������I������Ƃ̋�ʂ𗝘_�I�ɖ��炩�ɂ�����ŁA����V�I�������f���͂����ɂ��ĉ\�ɂȂ邩����ɂ��A�挱�I�ϔO�_��ł����Ă����B�{�����������Ɏ��������@�ɂ��Ĕގ��g���A�u�c�D�q���[���̌x���ɂ����̂ł���v�ƍ������A�q���[���̉��^�I�o����`�Ƃ̐ڐG�ɂ�邱�Ƃ��������Ă���B�h�C�c�ϔO�_����ь���N�w�̊�b���Ȃ�����ł���B �@ |
�����������ᔻ 1
�@
(Kritik der reinen Vernunft)�@�h�C�c�̓N�w�҃C�}�k�G���E�J���g�̎咘�ŁA����(A�Ɨ��̂����)��1781�N�ɁA����(B�Ɨ��̂����)��1787�N�ɏo�ł��ꂽ�B�J���g�̎O��ᔻ�̈�ŁA1788�N���́w���H�����ᔻ�x(���ᔻ)�A1790�N���́w���f�͔ᔻ�x(��O�ᔻ)�ɑ��āA���ᔻ�Ƃ��Ă��B�l�Ԃ̗������S�������ɂ��Ă̌ÓT�I�����B���C�v�j�b�c�Ȃǂ̑��ݘ_�I�`����w�ƁA�q���[���̔F���_�I���^�_�̗������p�����A���ᔻ�I�ɏ��z�������m�N�w�j��A�����Ƃ��d�v�Ȓ���̂ЂƂł���B
�@
���T�_
�@
�w���������ᔻ�x�́A�����F���̔\�͂Ƃ��̓K�p�̑Ó������u�����̖@��v�ɂ����ė������g���R�����ᔻ����\���������Ă���B�䂦�ɂ���͓N�w(�`����w)�ɐ旧���A�����̑Ó��Ȏg�p�͈̔͂��߂�N�w�̗\���w�ł���ƃJ���g�͂����B
�@
�J���g�͗���������Ǝ��̌����ɏ]���Ď�����F������ƍl���邪�A���̌����͌o���ɐ旧���ė����ɗ^��������ݓI�Ȃ��̂ł���A�������g�͂��̋N�����������Ƃ��o�����A�܂����̌�������E���Ď���̔\�͂��s�g���邱�Ƃ��o���Ȃ��B��������A�o���͌o���ȏ��m�蓾�鎖���ł����A�����͌����Ɋ܂܂�鎖�ȏ��m�蓾�Ȃ��̂ł���B�J���g�͗������֘A���錴���̋N�����A�o���ɐ旧�A�v���I���ȔF���Ƃ��āA�o������b�Ƃ������������o���̃A�v���I���Ȑ���ł��钴�z�_�I�ȔF���`���ɂ��Ƃ߁A����ɂ���ĔF�������̌����𖾂炩�ɂ��邱�ƂɂƂ߂�B
�@
���w�Ҍ����̉���F ���Ȃ킿�u�F������v�Ƃ���闝�����̂��̂́A��������͔F���ł���͈͊O�ɂ��邱�Ƃ����_�Ƃ����B�u�R�y���j�N�X�I�]��v���������̂ł���B
�@
���l�ԓI�F���\�͂Ƃ��̐���
�@
�`���I�ȉ��^�_�́A�F���̓��e���l�Ԃ̐��_�ɗR�����邱�Ƃ���A�O�E�Ƃ̑Ή����^���A�����ĔF�����̂��̂̐����̑Ó�����ے肵���̂����A�J���g�͂��������F���̔���ݐ��Ɣ�Ó����ւ̋^��ɑ��āA���̂悤�ɓ�����B���Ȃ킿�A�o���̉\�̏����ł��钴�z�_�I����͂��ׂĂ̐l�ԗ����ɋ��ʂȂ��̂ł����āA�䂦�ɂ��̐���̂��Ƃɂ���F���́A���ׂĂ̐l�ԂɂƂ��đÓ��Ȃ��̂ł���A�ƁB
�@
�����ŃJ���g�͔F���̐���ȑO�ɂ���u�����́v�ƌo���̑Ώۂł���u���v����ʂ���B�u�����́v�͗�����G�����A�����ƌ含�ɓ��������A����ɂ���Đl�ԗ����͒��ςƊT�O�ɂ���āA�����z�_�I����ł���ӂ��̏������ρE��ԂƎ��ԁA�܂�12�̔��e���Ȃ킿�����含�T�O�̂��ƂɁA�݂�����̌o���̑ΏۂƂ��ĕ���^����B
�@
�������A����͈���ŁA�l�ԗ������A��X�̔F���\�͂z������̂ɁA�F���\�͂�K�p���邱�Ƃ��s�\���ƌ��������Ӗ�����B�S�Ă̐l�ԓI�F���͒��z�_�I����̂��Ƃɂ�����Ă���A�̂ɁA�`���I�ɍl�����Ă������ڒm�A�m�I���ς̉\���͔ے肳���B�_��C�f�A(���O)�ƌ��������z���A�l�ԗ����ɂƂ��ĔF���\�ł���Ƃ����`���I�Ȍ`����w�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�J���g�́A�F���̑Ώۂ��A���o�ɗ^����꓾����̂ɂ̂��肷��B���Ȃ킿�A�l�ԗ����́A���������ɗ^��������̂ς��A����ɏ����含�T�O��K�p����ɗ��܂�̂ł���B
�@
�����ƌ含�͈قȂ�\�͂ł����āA������}�����̂́A�\�z�͂̎Y�o����}���ł���B�܂������̑��l�͓��o�A���Ȃ킿�u��v���v(�܂�f�J���g�̃R�M�g)�ɂ���ē��ꂳ��Ă���B�������A�����ɂ͎��ȔF�����g�債�A�����̂Ȃ������݂�c�����悤�Ƃ���`����w�ւ̖{���I�f��������B���̂��߁A�F�������́A�{���含�T�O�̓K�p���ꂦ�Ȃ��������I�T�O�E�����T�O�����m�낤�Ɨ~���A�����ɂ����e��K�p���悤�Ƃ���B�������A�J���g�͔F���̊g��ւ̂��̗~���𗝐��̙G�z�Ƃ��Ĕᔻ���A�F�����ꂦ�Ȃ����̂͂����v�҂��邱�Ƃ݂̂��\�ł���Ƃ���B���̂悤�ȗ����T�O�Ƃ��āA�_�E���̕s�ŁE���R����������B
�@
���A���`�m�~�[(�w���EAntinomie)
�@
�����T�O�E���O (Idee) �́A�l�Ԃ̔F���\�͂z���Ă���̂ŁA���O��F�����A�q��t�����悤�Ƃ��鎎�s�́A���s�ɏI��炴��Ȃ��B�J���g�́A���̂悤�Ȍ含�̌��E��4�̓w�������̑g�ݍ��킹�ɂ���Ď����B
�@
������������́A���̓��e�������Ȃ���A�含�T�O�̎g�p�̎d���Ƃ��ēK�ł͂Ȃ����߁A�ǂ�����^�ł���A�����́A�ǂ�����U�ł���Ƃ������ʂɂ����B�J���g�͂��̂悤�ȓ�Ԃ̖������A�_���I�w���Ƃ��Ăł͂Ȃ��A�P�Ɍ含�T�O�̓K�p����������藧���Ȃ����̂ɂ��Ă̌��q�ł��邱�ƂɋA������B���������w������Ƃ��Ă͎����̕K�R���Ǝ��R�Ɋւ��Ă̔w������(��O�A���`�m�~�[)����������B����́A�L���X�g���ɂ����ė\��Ƃ̊֘A�œ`���I�ɂ����Ζ��ɂ��ꂽ�₢�ł��邪�A�J���g�ɂ����Ă͈��ʐ��E�K�R���Ƃ��������含�T�O�𗝐��T�O�ł��鎩�R�ɓK�p���鎖����A�����𗈂����l�Ɍ�����̂ł���A�o���ɂ����Ă͕K�R�����A������o�Ă���l�ԗ����ɂ����Ă͎��R�����藧���́A�J���g�̔ᔻ�̑̌n���ł͑o�����ɐ^�Ȃ̂ł���B
�@
�������A�F���͍����I�Ȃ��̂����߂邩��A�F�������ɂ��邱�Ƃ���@���ɂ��č����I�Ȃ��̂Ɏ���̂��Ƃ������Ƃ��ۑ�ɂȂ����B���ۂ̍��������߂�Ɖ\�I�Ȑ��E�ɋ��߂���A�������A�\�I�Ȑ��E���猻�ۂ��^�����Ă���Ƃ���ƌ��ۂ̍����͉\���ł����Ȃ��B����̂ɁA�F�������ۂ��甲���o���Ȃ����̂ł���̂ŁA�w���H�����ᔻ�x�œW�J����邱�ƂɂȂ�B�F�������ۂł����Ȃ����̂ɁA�\�����o�����̂ł���B�������������T�O�Ɛl�ԗ����̖��́w���������ᔻ�x�̒��ł́A�K�������\���ɓW�J���ꂸ�A�����݂̍����l�X�ɕ`���Ă���B�����āA�w���������ᔻ�x�Ɓw���H�����ᔻ�x�́w���f�͔ᔻ�x����������Ƃ���Ă���B�@ |
�����������ᔻ 2
�@
�w���������ᔻ�x�́A�Ȋw�̐���������₤�Ƌ��ɁA�o���Ɋ�Â��Ȃ��u�`����w�v��ᔻ���鎎�݂ł���B
�@
1)�@�J���g�̌������Ƃ𗝉����邽�߂ɂ́A�܂��A�����ƌ含�Ɨ����Ƃ����O�̔\�͂���ʂ���K�v������B
�@
�u�����v�́u���ρv�̔\�͂ł���A���ԂƋ�ԂƂ����`�������B(�u���ρv�Ƃ́A�J���g�̏ꍇ�A������A�������肷�銴���I(�����o�I)�Ȓ��ڒm���Ӗ�����B)��X�������������蕷�����肷��ۂɂ͏�ɁA���̏����Ƃ��āA���ԂƋ�ԂƂ����`������s���Ă���͂��ł���B��X�͕�(���邢�͉����̃C���[�W)�����(����ю���)�Ȃ��ɍl���邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂�����B
�@
�u�含�v�Ɩ��u�t�F�A�V���^���g(Verstand)�v�Ƃ����h�C�c��́A�u����v�u��������v�Ƃ����Ӗ��̓���(verstehen)���痈�Ă��āA�u��������́v�u�펯�v(�p��́A"understanding")���Ӗ�����B���̏����Ȍ`�����A�J���g���u�J�e�S���[�v�ƌĂԁA���f�̘_���I�`���ł���B(����ɂ́A�m���ے�Ƃ������f�́u���v�A���݂�S�̂Ƃ������f�́u�ʁv�A���̂���ʐ��Ƃ������f�́u�W�v�A�K�R��\�Ƃ������f�́u�l���v������B)
�@
����ɑ��āA�����Ŗ��ɂȂ��Ă���u�����v�́A��荂���́A�含�̔��f�𑍍��I�ɊW�Â���A�����̔\�͂ł���B�Ⴆ�A�u�l�Ԃ͎��ʁv�Ƃ�������́A�u�����v�Ƃ����}�T�O����āA�u�l�Ԃ͐����ł���v�u�����͎��ʁv�Ƃ�����̔��f�𑍍��������̂ł���B(�J���g�̏ꍇ�A�����Ƃ����A�w��ǎO�i�_�@���w���B�Ƃ���ŁA�J���g�́A���R�m��܂���ł������A�u�c���F���v�Ƃ��u�r�b�O�o���v�Ƃ����������_�ݏo���̂́A�含�̔��f(�o���I�f�[�^)�𑍍����闝���̓������Ǝv���̂ł����A�J���g�ɏڂ����l�A�ǂ��ł��傤���H)
�@
2)�@���ɁA���͓I���f�Ƒ����I���f�̋�ʁA�A�v���I��(a priori)�ȔF���ƃA�|�X�e���I��(a posteriori)�ȔF���̋�ʂ���������K�v������B
�@
�A�|�X�e���I����(a posteriori���u����̂��̂���́v)�F���Ƃ́A�o���Ɉˑ�����F���ł���B�Ⴆ�u�S�ẴJ���X�������v���ǂ����́A���ۂɒ��ׂĂ݂Ȃ���Ε�����Ȃ��B�]���āA���̒m���́A�����Ă��A���R�I�ł���B
�@
����ɑ��A�A�v���I����(a priori���u����̂��̂���́v)�F���Ƃ́A��X�́u�o���v�Ɉˑ����Ȃ�(�]���ĕ��ՓI��)�m�����Ӗ�����B�Ⴆ�A�u�O�p�`�̓��p�̘a���p�ł���v���Ƃ͎O�p�`�̖{�����瓱�����m���ł���B�܂����p�O�p�`�Ɋւ��郆�[�N���b�h�̒藝�́A�ǂ�Ȏ��̏��(���邢�͓��̒���)�}�������ďؖ����Ă���������A�����I�Ɂu�o���v�Ɉˑ����Ă��Ȃ��B����Ɉꕔ(�S���H)�̘_���I�m�����A���ۂɒ��ׂ�K�v�̂Ȃ��A���ՓI�ɑÓ�����m���ł���B����炪�A�v���I���ȔF���̑�\�B
�@
3)�@�X�ɁA�q��̓��e�����Ɋ܂܂��悤�Ȕ��f���A���͔��f�Ƃ����B�Ⴆ�u�Ԃ��o���͐Ԃ��v�Ƃ�������́uA��A�ł���v�Ƃ������ꗥ�̌`�����Ă��邩��A���͔��f�ł���A����䂦�A�v���I���ɐ��������f�ł���B(���݂ł́A�_���w�␔�w�̖���́A�S�ĕ��͔��f���A�ƍl����l�����Ȃ肢�邪�A�u1�{1�v�Ƃ������͂��Ă��A�u��2�v�Ƃ����q��͌��o���Ȃ��̂ŁA�J���g�͑����I���f���ƍl���Ă���B)
�@
�������f�Ƃ́A���ɐV�����q���t�^���锻�f�ł���B�Ⴆ�u�J���g�͐��U�Ɛg�������v�Ƃ������f�́A�u�J���g�v�Ƃ������Ɂu��x���������Ă��Ȃ��v�Ƃ����V�����q���t�^���Ă���B(���݂Ɂu�Ɛg�҂͖����ł���v�Ƃ������́A�悭��Ɉ�����镪�͔��f�̓T�^�B)
�@
���āA�w�₪�V�����m���ނȂ�A����͑����I���f�ł���B�����Ă��ꂪ���ՓI�ɐ������F���ł���Ȃ�A�A�v���I���Ȕ��f�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�]���āA���R�Ȋw�Ȃǂ̌o���Ȋw�͉\���A�Ƃ����₢�́A�u�A�v���I���ȑ����I���f�͂ǂ̂悤�ɂ��ĉ\���v�Ƃ����₢�ɂȂ�B
�@
�J���g���g���������w���������ᔻ�x�̗v��ł���w�v�����S���[�i(����)�x����A�v�_���������o���ƁA
�@
1�@��X�̔F���̌���́A�����ƌ含(�Ɨ���)�ł���B
�@
2�@���w�̒m���́A�����̔\�͂ł��钼��(��������)�ɂ����Đ�������A�A�v���I���ȔF��(�������f)�ł���B
�@
3�@���R�̔F��(�����w)�́A�o���I�Ȑ��E��ΏۂƂ����A�A�v���I���ȑ������f�ł���A����́A���ςɂ���ė^�����鑽�l�ȑf�ނ��A�含���_���I�ȃJ�e�S���[�̓���ւ����炷���Ƃɂ���Đ�������B
�@
4�@�����͂��������F���𑍍����铭��������B�������������A���ςƂ����n�Ղ𗣂�P�ƂŁA�����R�I�ȑΏ�(�_�A���E�S�́A��)�̔F��(���u�`����w�v)�ݏo�����Ƃ���ƁA�K�R�I�Ɍ�T�Ɋׂ�B
�@
(�Ⴆ�A�u���E�͖����ł���v�Ƃ�������́A������ؖ�����c�_���g���āA���̂܂܁u���E�͗L���ł���v�Ƃ����A���̖�������ؖ�������B������A�A���`�m�~�[(�w��)�Ƃ����B)
�@
�]���āA��X���F��������̂́A�����Ƃ����`������ė^������u���ہv�������A�Ƃ������ƂɂȂ�B���̔w��ɂ��邩������Ȃ��u�����́v�͔F���o���Ȃ��B(�u���v�Ƃ�����ς��A�u���ہv�܂蒼�ς̑ΏۂƂ��ė^�����Ȃ�����A�u�����́v�͈̔͂ɑ�����B)
�@
�����ŃJ���g�́A�f�J���g�̂悤�ɁA�m�����������邽�߂̏�����o���Ă䂭�Ƃ������@(�u���z�_�I�v���@)���Ƃ��Ă���B(���ꂪ�v���g���ȗ��́A�N�w�̈�ԃI�[�\�h�b�N�X�ȕ��@�ł��낤�B)
�@
�J���g�̎���ꐢ�I���o�ď����ꂽ�A�E�B�g�Q���V���^�C���́w�_���N�w�_�l�x�́A�_���w�̒m���͑S���ʕ������A���@�����e���A�w��ǃJ���g�ł���B�@ |
�����H�����ᔻ 3
�@
�u�����v���{���̓���������̂́A���H(�s��)�̏�ʂł���B�u�s�ׂ���v�Ƃ������߂́A�l�Ԃ̓��Ȃ闝�����痈��B�u�F�l��������̂͋`���ł���v�Ƃ�����ʓI��������A�u�c���N�͑�c�N�̗F�l�ł���v�A�䂦�ɁA�u��c�N�͓c���N��������ׂ��ł���v�Ƃ����s�ׂ��w�������B�����ł͌o������m�����������̂ł͂Ȃ��A�m�����A�v���I���Ɍo�������肷��B
�@
�����`����w�̊�b�Â� / �J���g���ڎw���̂́A�����ϗ��w�ł���B
�@
�u�P�Ɍo���I�ł����Đl�Ԋw�ɑ�����S�Ă̎�������A���S�ɐ��߂�ꂽ�����ȓ����N�w����x�n��o�����Ƃ��A���̏�Ȃ��K�v�ł���B�v�u��̖@�����A�����I�Ȃ��̂���ׂ��ł���A�K����ΓI�ȕK�R����ттȂ���Ȃ�Ȃ��B�v�u�w�R�����Ă͂Ȃ�Ȃ��x�Ƃ������߂́A�l�Ԃ����ɓ��Ă͂܂�A���̗����I���ݎ҂ɂ͖��W�ł���Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�v�u����䂦�A�`���̍����́A�l�Ԑ��Ƃ��A�l�Ԃ��u����Ă��鐢�E�̏Ƃ��̂����ɋ��߂���ׂ��ł͂Ȃ��A�A�v���I���ɏ��������̊T�O�̂����ɂ̂݁A���߂���ׂ��ł���B�v�u�����I�ɑP�ł���Ƃ�������̂́A�@���ɍ��v���Ă��邾���ł͏\���ł͂Ȃ��A����ɂ���͓����@���̂��߂ɍs������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�v
�@
������(Autonomie) [��̐��ƕ��Ր�]
�@
���Ȍ���(���ȗ��@) / ���R�Ȉӎu�͑��݂���B�l�Ԃ́A�S�����R�ł���B(�u�������Ƃ��Ȃ��ƎE����v�ƌ����Ă��A�u�������Ƃ��Ȃ��v���Ƃ��o����B�Ƃ������A�o���邩��u�E����v�ƌ����ċ����̂ł���B)���҂̖��߂ɏ]���čs�ׂ���Ȃ�A�z��ł���B��������������ׂ����A��������߂�͍̂ŏI�I�ɂ͎����ȊO�ɂ͂��Ȃ��B
�@
�i���Ɠ����@���̈�v / �i��(�i��)�Ƃ͎�ϓI(���l�I)�s���̕��j�B�����@���Ƃ͕��ՓI�@���u�S�Ă̐l�́c���ׂ��ł���B�v�B(�Ⴆ�A���J���ꂽ��K�����Q����Ƃ������Ƃ��A�N�ł��i���Ƃ��邱�Ƃ͏o����B����������͌����Ď��H�I�@���ł͂Ȃ��A���������̊i���ɂ����Ȃ����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���������ꂪ�����闝���I���ݎ҂̈ӎu�ɑ���K���Ƃ����Ȃ�A����̊i���ɂ����Ď��Ȗ������邩��ł���B)
�@
���H�����̒茾���@ / �u���̈ӎu�̊i�����A��ɓ����ɁA���ՓI���@�̌����Ƃ��đÓ�������悤�ɁA�s�ׂ���B�v(�����̃|���V�[�ɏ]���čs�����Ȃ����A�������N���̗p����|���V�[�́A���ł��A(�S�Ă̐l���]���ׂ�)��ʓI�Ȗ@���𗧂Ă�ۂ̌����Ƃ��Ă��ʗp����悤�Ȃ��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B)
�@
(�����Ɍ����\����Ă���̂́A�u�����͖@���ɏ]���čs�Ȃ���ׂ����Ɓv�u�����Ō��߂��@���ɏ]���čs�ׂ���Ƃ����A�l�̎���������̐��v�u���̖@�������ׂ��`���Ƃ��ẮA���Չ��\���v�Ƃ����A�O�_�ł���B�O�_�ڂ��ǂ��l���邩�ɂ��Ă͓���_������B)
�@
�����ȖړI
�@
�����I�s�ׂ̓��@�́A(�u�D���v�u�����v�Ƃ��u�����̗��v�v�Ƃ�)�����I�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���������Ȃ�A(����͎��Ȉ��Ɋ�Â����ȓI�ȍs�ׂɂ�����)�s�ׂ͂��̐������̍����������Ă��܂����낤�B�u�P����������A��������������A���ׂ����v�A�Ƃ����̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@
1�@�����@���́A�A�v���I���Ȃ��̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B���������@�����o���I(�������I)�������瓱�����Ȃ�A���ՑÓ��ł͂��肦�Ȃ��B
�@
2�@�ӎu�̌��茴�����A�~���̑Ώۂɋ��߂�Ȃ�A����͑S�Čo���I(�����R�I)�ł���A�Ώۂɂ���Ĉ����N���������s���̊���A�܂莩�Ȉ������Ȃ̍K���A�Ɋ�b���������ƂɂȂ�B
�@
3�@�]���āA�����@���́A���e�ɂł͂Ȃ��A�ӎu�̌`���ɂ����W������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@
4�@���̖ړI�̎�i�ł͂Ȃ��A�����@�����̂��̂�ړI�Ƃ���ӎu�������A�����̂ł���ӎu�A���Ȃɂ�莩�Ȏ��g�����肷��ӎu�ł���B(�ӎu�̎���)
�@
5�@�����I�s�ׂ̓��@�́A�����@���ɑ���(�]���āA�܂����Ȃɑ���)���h�ł���B
�@
�l�Ԃ́A�����E�ɑ�����Ɠ����ɁA�b�q�E(�����̐��E)�ɂ������Ă���B�����Ɋ�Â��s�ׂ́A�l�Ԃ݂̂Ȃ炸�A�_��V�g�ł������A�S�Ă̗����I���ݎ҂��A������������悤�ȍs�ׂł���B�����ɐl�Ԃ̍ō��̑���������B
�@
(�����͊����E�̏Z�l�ł����āA�����������Ȃ��B������A�����{�\���~�]�ɏ]���āA�s������B�����ɖ����͖����B����A�_��V�g�́A�m���E�̏Z�l�ł����āA���̂������Ȃ��B������A��ɂ��������ɏ]���āA�s�ׂ���B�����ɂ������͖����B����ɑ��āA�l�Ԃ́A�m���E�̏Z�l�ł���Ɠ����ɁA�����E�̏Z�l�ł�����B������l�Ԃ������A���ȓ��ɖ�����������B���������Ƃ����邽�߂ɁA�����̗~�]�Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ɐl�Ԃ̐^�̈̑傳������B)
�@
�ړI�̍�
�@
�u���Ƃ́A���قȂ闝���I���ݎ҂����ʂ̖@���ɂ��̌n�I�Ɍ������ꂽ���̂ł���ƁA���͉�����B�����I���ݎ҂͑S�āA���̊e�X�����Ȏ��g�Ƒ��̑S�Ă̎҂��A�����ĒP�Ɏ�i�Ƃ��Ď�舵�킸�A��ɓ����ɖړI���ꎩ�̂Ƃ��Ĉ����ׂ��A�Ƃ����@���ɂ��������Ă���B�ꗝ���I���ݎ҂��ړI�̍��ɂ����āA���ՓI�ɗ��@������̂ł���Ȃ���A�ގ��g�����̖@���ɕ��]���Ă�����ꍇ�A���̗����I���ݎ҂́A�ړI�̍��ɐ����Ƃ��ď�������B���ꂪ���@�҂ł���A���������̂ǂ̑��ݎ҂̈ӎu�ɂ����]���Ă��Ȃ��ꍇ�A����͖ړI�̍��Ɍ���Ƃ��ď�������B�v
�@
�������@�ƒ茾���@
�@
�u�P�ʂ���肽���Ȃ�A���Ƃɏo�Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ��u���Ƃ��ʔ�����A�o�Ă���Ă�������v�Ƃ������悤�ȁu�����c�Ȃ�v�Ƃ������������u�����v���@�ƌĂԁB�����I�s�ׂ͖{�������������i�̂��̂ł͂Ȃ��B��̏��������ɁA�u�������ׂ�������A�������ׂ����v�Ƃ�����ΓI�u�茾���@�v�ł���B����ł�����X�͗����̍��̈�����肦��̂ł���B
�@
�����E�Ɖp�m�E
�@
�������Ȃ��痝���̍��ƁA��X�̓��̂����ɏZ��ł��邱�̊����̍��͈�v���Ȃ��B�Ƃ�����葊������ꍇ�������B��X�͂����Ύ��Ȉ��⊴��̗U�f�ɕ����āA���������Ƃ������Ȃ��Ă��܂��B�܂��A���̌����̐��E�́A�s���S�Ȃ��̂�����A�������s�ׂ��K���Ȍ��ʂ������炷�Ƃ͌���Ȃ��B�u�搶�̖�͊Ԉ���Ă��܂��v�Ǝ��ƒ��Ɍ����w�E�����肷��ƁA�搶���牅�܂�Č�łЂǂ��ڂɂ������肷��(��)�B
�@
���̕s���Ɛ_�̑��݂̗v��
�@
�����ŃJ���g�́A���_�����̗��ꂩ��͏ؖ��ł��Ȃ������A���̕s���Ɛ_�̑��݂��u�v���v����B�����łȂ���A�l�̓��̊������A�܂��L���Ȑl�̂��̐��ł̍K�����ۏ��ꂦ�Ȃ�����A�ł���B��X�����邱�Ƃ��o����̂́A�����̐��E�����ł���B�����̐��E�́A���ς̑Ώۂɂ͂Ȃ炸�A�ڂɌ����Ȃ��B�������e�l�������Ɋ�Â��čs�ׂ��邱�Ƃɂ���āA���̑��݂��u�������v�̂ł���B
�@
���R�Ȉӎu�ɂ�鎩�Ȍ���(������)�̑��d�A�y�сA���̎��R�Ȑl�i��P�Ȃ��i�Ƃ��Ă��������Ă͂Ȃ�Ȃ��\�Ƃ������J���g�ϗ��w�̍��{����́A��{�I�ɂ́A����̗ϗ��w�ł����{�����Ƃ��ĔF�߂��Ă���B
�@
�܂��A�ꌩ�������u�茾���@�v�Ƃ��������ς��A�����@���͂��̌��ʂł͂Ȃ��A���ꎩ�̂ɂ����ĉ��l������(�܂�A���ꎩ�̂ɂ����Ď���˂Ȃ�Ȃ�)�Ƃ����A��̍l�������\���Ă���B
�@
�X�ɂ܂��A�u�����@���ւ̑��h�v���̓��@�Ƃ݂闧��́A�l�Ԃ̎����S(�v���C�h)�d�����l�����ł���A���ׂĂ������̗��v�ɊҌ����čl���邱�Ƃ��펯����������ɂ����Ă͕���������ł͂����Ă��A�悭�l���Ă݂�ƁA�l�Ԃ̐M�O�̂�����Ƃ��Đ���������������Ă���(�Ǝv��)�B
�@
���`���ϗ�
�@
�u����(���ׂ�)�v����������J���g�̗ϗ��w���́A�u�`���ϗ�(deontic ethics = deontische Ethik)�v�ƌĂ��B�l�̍s�ׂ̓��e�́A�����܂ł����������߂�ׂ����̂ł͂��邪�A���߂��ȏ�́A�������]��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A�`���Ȃ̂ł���B�J���g�́A��ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��u���S�`���v�ƁA�����͂���Ȃ��u�s���S�`���v�Ƃ���ʂ���B�����́A����ɁA�������g�ɑ���`���ƁA���l�ɑ���`���Ƃɕ������B
�@
�Ⴆ�A�u���ȕۑ��v�͎������g�ɑ��銮�S�`���ł���B���E�͋�����Ȃ��B���E�����Ȃǂ����R�_���B
�@
��q�́u�R�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂����S�`�������A����͑��l�ɑ��銮�S�`���ł���B�u�؋���Ԃ��v�Ƃ����̂�����(�T�����̋Ǝ҂����������т���)�B
�@
����A�u���Ȃ̌���(���聁�琬)�v�͎������g�ɑ���s���S�`���ł���B���Ԃʂɂ����A�̂�b���A�悭�����A���{�����߂�A�Ƃ������Ƃ��B
�@
�u���l��������v�Ƃ����̂́A���l�ɑ���s���S�`���B�������u���v�Ƃ͊���ł͂Ȃ�(����͖��߂��꓾�Ȃ�)�B���l�������e�ɂ���Ƃ������Ƃ��A�ƃJ���g�͌����B
�@
�����̋`���͗����I�ȑ��ݎ҂ł���l�Ԃ̖{�����瓱�����`���ł��邩��A���̖ړI�◘�v���]�X����̂ł͂Ȃ��A�������u�ׂ��v�ł��邩��A�������ׂ����Ƃ������i�����B�Ⴆ�Α��l�ɐe�ɂ��ׂ��ł���Ƃ������R�́A���ǂ͎������������邩��Ƃ������Ȉ��Ɋ�Â����Ă͂Ȃ炸�A�[�I�ɁA���ꂪ���������Ƃ�����A���ȐS�𗣂�čl�����������������Ȃ�����A�Ƃ������Ƃ��B
�@
���w���H�����ᔻ�x�̖��_
�@
1 �u�F�l���E�l�S�ɒǂ��Ă��āA�����Ă���Ɨ��܂ꂽ�̂ɁA�w�R�����Ă͂Ȃ�Ȃ��x�Ƃ��������@���ɏ]���āA�ǂ��Ă����E�l�S�ɗF�l�̋��ꏊ��������v�̂́A���������낤���H
�@
(�J���g�͐������ƌ����B�u�R�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����̂́A���S�`���ł���A��Ɏ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������@���ł���B�m���Ɂw�����x���u�U����ȁv�Ɩ����Ă���B�������A����͂���Ȃɂ܂ł��Ď��Ȃ���Ȃ�Ȃ��u��ΓI�v�ȋK���Ȃ̂��낤���H�܂��A�w�����x�́u�E����(���E���ɂ����)�v�Ƃ������߂ɔ����Ȃ��̂��낤���H)
�@
�����́A�܂��A�u�����S�Ɋ�Â��āA�Z���E�����h�C�c�ւ̐푈�ɍs�����A����Ƃ��אl���̐��_�Ɋ�Â��āA�N�V���Đg���̂Ȃ���̋��ɗ��܂邩�v(�T���g��)�Ƃ������A���������̖��߂��ۂ��ꂽ�ŁA�����I�ԗ��R���A�J���g�͗^���Ă���̂��낤���H
�@
2 �u�F�l�������Ă��邩�珕�������v�Ǝ����v�����Ƃ��A���͂��̗F�l���D�������珕�������Ǝv���̂��낤���A�J���g�Ɍ��킹��A�u�D��������v������Ƃ����s�ׂ́A�s�����ł���B�u�D���v�u�����v�Ƃ���������́A�����I�s�ׂ̌����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂�����B
�@
���̓_�Ɋւ��āA�J���g�̍ΎႢ�F�l�ł����������l�V���[�́A����������������ĕ��h�����B
�@
�u�l�͐i��ŗF�l�ɐs�����Ă���̂����A�߂������ƂɍD���ł������Ă���̂��B�����Ŗl�͂����Ύv���Y�ށA�����͗L���Ȑl�Ԃł͂Ȃ��̂��ƁB�v�u�������B���ɕ��@�͂Ȃ��B�N�͓w�߂ėF�l���y�̂��A�������ɋ`���̖����邱�Ƃ����X�Ȃ���s�����Ƃ��B�v
�@
����͂��瑊�Ȕᔻ�����m��Ȃ����A����⎩�Ȉ��͂�����u���v�I�Ȃ��̂Ȃ̂��낤���H�����������(�����Ɨ����̖����Ƃ��A�����I���߂̑Η��Ƃ��A�u��v�Ƃ�)���A�����Ɛ��ʂ���l�����̂��A�w�[�Q���ł���B�@ |
���C�}�k�G���E�J���g
�@
(Immanuel Kant, 1724-1804) �h�C�c�̓N�w�ҁA�v�z�ƁB�v���C�Z�������o�g�̑�w�����ł���B�w���������ᔻ�x�A�w���H�����ᔻ�x�A�w���f�͔ᔻ�x�̎O�ᔻ���\���A�ᔻ�N�w����āA�F���_�ɂ�����A������u�R�y���j�N�X�I�]��v�������炷�B�h�C�c�ϔO�_�N�w�̑c�Ƃ������B
�@
�C�}�k�G���E�J���g��1724�N�A���v���C�Z���̎�s�P�[�j�q�X�x���N(�����V�A�̃J���[�j���O���[�h)�Ŕn��E�l�̎l�j�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���U�̂قƂ�ǂ����̒n�ʼn߂��������Ŗv�����B���e�̓��^�[�h�̌h�i��`��Ă������߁A�J���g�͂��̔Z���ȉe���̂��ƂɈ�����B
�@
1732�N�A���e����w�Z�ł���t���[�h���q�Z�ɐi�B1740�N�ɂ̓P�[�j�q�X�x���N��w�ɓ��w����B�����A�_�w�������내�������A�j���[�g���̊���ȂǂŔ��W�𐋂����������R�w�ɊS���������A�N�w�����N�k�b�c�F���̉e���̂��ƁA���C�v�j�b�c��j���[�g���̎��R�w�����������B
�@
1746�N�A���̎����ɂƂ��Ȃ���w������B�w���������Ȃ��Ȃ����̂ɉ����āA�ŋ߂̌����ł̓N�k�b�c�F���ɂ��̓Ƒn����F�߂��Ȃ��������Ƃ���w�����铮�@�ɂȂ����Ɛ��肳��Ă���B���̎���w�ɘ_��(������w���͑���l�x)���o���Ă��邪�A���e����łȂ��h�C�c��ł��������ƁA�܂��A�w���̕����Ɋw�ʎ���ɂ��Ă̋L�^���c���Ă��Ȃ����ƂȂǂ���A�����ȑ��Ƃł͂Ȃ����r�ފw�ɋ߂����̂ł������Ǝv����B���ƌ��7�N�Ԃ̓J���g�ɂƂ��Ă͂��邵�������ŁA�P�[�j�q�X�x���N�x�O��2�A3�̏ꏊ�ʼnƒ닳�t�����Đ��v�����ĂĂ����B
�@
1755�N�A(���K�ɏo�ł��ꂽ���̂Ƃ��Ă�)�ŏ��̘_���wAllgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels(�V�E�̈�ʓI���R�j�Ɨ��_)�x�ő��z�n�͐��_���琶�����ꂽ�Ƙ_�����B���̘_���͈�����ɏo�ŎЂ��|�Y�������ߋɏ����݂̂��������ꂽ�B4���A�P�[�j�q�X�x���N��w�N�w���Ɋw�ʘ_���w�ɂ��āx���o���A6��12���A����ɂ��}�M�X�^�[�̊w�ʂ��擾�B9��27���A�A�E���i�_���w�`����w�I�F���̑�ꌴ���̐V�������߁x�Ō��J���c�������Ȃ��A�~�w����蓯��w�̎��u�t�Ƃ��ĐE�ƓI�N�w�҂̐����ɓ���B
�@
1756�N�A���t�N�k�b�c�F���̐����ɂ�茇�����o�����O�����̒n�ʂ邽�߁A����ɕK�v��2��̌��J���c�̑�1��ڂ̑f�ނƂ��āw�����I�P�q�_�x������킷�B4��12���ɑ�1��ڂ̌��J���c�������Ȃ��邪�A�v���C�Z�����{���I�[�X�g���A�Ƃ̎��N�푈�O�ɂЂ����A������[�����Ȃ����j��ł��o�������߁A���O�����A�C�̘b�͔����ƂȂ�B1764�N�A�P�[�j�q�X�x���N��w���w�����̐Ȃ�Őf���ꂽ���J���g�͂�����Ŏ��B�܂��A1769�N�ɃG�������Q���A�C�F�[�i����������A�C�̗v�������������A���u�n�̑�w����������������Ƃ��n���̃P�[�j�q�X�x���N��w������ɔ�����̏��ق����Ă���������(��q����悤�ɗ��N��1770�N�ɋ����A�C)�A�������f���Ă���B
�@
1764�N�A�w���Ɛ����Ȃ���̂̊���ɂ���ώ@�x�o�ŁB
�@
1766�N�A�w����҂̖��x���o�ŁB�J���g�̓G�}�k�G���E�X���F�[�f���{���ɂ��Ă����q�ׂĂ���B
�@
�u�ʂ̐��E�Ƃ͕ʂ̏ꏊ�ł͂Ȃ��A�ʎ�̒����ɂ����Ȃ��̂ł���B-(����)-�ʂ̐��E�ɂ��Ă̈ȏ�̌����͘_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�����̕K�R�I�ȉ����ł���B�X�G�[�f���{���O�̍l�����͂��̓_�ɂ����Ĕ��ɐ����Ȃ��̂ł���B-(����)-�X�G�[�f���{���O���咣�����悤�ɁA���́A�k�g�̂���l���������S�ƁA���̐S�̋����̂��A���łɂ��̐��E�ŁA������x�͒������邱�Ƃ͂ł���̂ł��낤���B-(����)-�B���͂��̐��E�ƕʂ̐��E���ɉ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B-(����)-�B�����ɂ��Ă̗\���͂����ɍ�����Ă���B�v
�@
���ɂ������̏�������o�ł��N�w���t�𑱂��Ă������A1770�N�A�J���g46�̂Ƃ��ɓ]�@���K���B�P�[�j�q�X�x���N��w����N�w�����Ƃ��Ă̏��ق�����A�Ȍ�A�J���g�͈��ނ܂ł��̐E�ɂƂǂ܂�B�A�E�_���Ƃ��āw���E�Ɖz�E�̌`���ƌ����x(�����F���e����)������킷�B�O�ᔻ���̂����Ƃ��d�v�Ȓ���̈�ŁA��́w���������ᔻ�x�ɂȂ���d�v�ȍ\�z���q�ׂ��Ă���B
�@
��w�����Ƃ��ẴJ���g�́A�N�w�݂̂Ȃ炸�A�n���w�A���R�w�A�l�Ԋw�Ȃǂ��܂��܂ȍu�`��S�������B�b��͑��l�ł����Ă��A���₩�ȃJ���g�̊w�Ґ����̓��X�́w���������ᔻ�x�̏o�łŌ��I�ɕω������B�ނ͈�C�Ƀh�C�c�N�w�E�̌����ɂ݂����_���̉Q���ɓ��荞�B�w���������ᔻ�x�͂��̓�����Ǝa�V�Ȏv�z�̂��߂ɓ�����̓ǎ҂ɐ������������ꂸ�A���܂��܂ȋc�_���N�������̂ł���B���ɃW���[�W�E�o�[�N���[�̊ϔO�_�Ɠ��ꎋ���Ĕᔻ����҂������A�J���g�͏����w�v�����S�[���i�x���o�ł��Ď��g�̓N�w�I����𖾂炩�ɂ��A�܂��A�w���������ᔻ�x�̑O�����A���z�_�I��㈘_�����e������2��(�����ł�B�łƌĂ�)���o�ł��Č�����������Ɠw�߂��B
�@
�J���g�̓����̍\�z�ł́A�w���������ᔻ�x�͒P�Ƃł��̔ᔻ�̑S�e���������̂ɂȂ�͂��ł������B�������A�\�z�̑傫���Ǝ��Ԃ̐���ɂ�藝�_�N�w�̕����݂̂��ŏ��ɏo�ł����B�c����H�N�w����сu���Ǝ�̔ᔻ�v�͌�Ɂw���H�����ᔻ�x����сw���f�͔ᔻ�x�Ƃ��ďo�ł���邱�ƂɂȂ����B�����̂��u�O�ᔻ���v�ƌĂԁB
�@
�J���g�͓N�w�I�_���̉Q���ɂ��������̊w�Ґl���͏����ł������B�ӔN�ɂ̓P�[�j�q�X�x���N��w�����߂��B�������A�v���C�Z�������x�������E�A�J�f�~�[�ɃJ���g�͏��ق���Ȃ������B
�@
�J���g�̍\�z�ł͔ᔻ�͌`����w�̂��߂̊�b�t���ł���A����ȍ~�̊S�͌`����w���������B�܂��J���g�̓N�w�ɂ͓����ւ̊S���Z���A���łɔᔻ�̂����ɕ\������Ă��������Ə@������ѐ_�T�O�ւ̊S�͏@���N�w�����Ƃ��邢�����̒���ւƌ��������B
�@
�J���g�͎O�ᔻ�ŕ\�����ꂽ�����@���ւ̓N�w�I�l�@�������߁A�w�P�Ȃ闝���̌��E���ɂ�����@���x������킵�����A����͓����ێ牻�̌X�������߂Ă����v���C�Z���̏@������ɂ��킸�������֎~���ꂽ�B�J���g�͎����̐��������^�킸�A�܂��A�w�ғ��m�̘_���ɐ��{��������邱�Ƃɂ͔��ł��������A��ʐl�����R�Ȍ��_�ɂ���Ĉ�E�ɑ���댯�����l�����Ă��̔��֏��������ꂽ�B
�@
1804�N2��12���ɐ����B�ӔN�͘V���ɂ��g�̐���ɉ����ĘV�l���F�m�ǂ��i�s�A�c��ȃ�����e���c�������̂́A����Ƃ��Ă܂Ƃ߂��邱�Ƃ͐��ɂȂ������B�ނ͍Ŋ��ɖ����̐������ɍ������Ŕ��߂����C�������ɂ��A�u����ł悢�v(Es ist gut.) �ƌ����đ�������������Ƃ����B�����̃h�C�c�̓N�w�҂͘_�G�����܂߂ăJ���g�̎��ɒ��ӂ�\�����B�������甼���ȏ�o�߂���2��28���ɂȂ��đ�w���������Ȃ��A�s�̕�n�ɑ���ꂽ�B���̕�͌��݂��J���[�j���O���[�h�ɏ��݂��A�����ɂ́u�䂪��Ȃ鐯��ƁA�䂪���Ȃ铹���@���A��͂��̓�Ɉ،h�̔O������Ă�܂Ȃ��v(�w���H�����ᔻ�x�̌��т��)�ƍ��܂�Ă���B�@ |
���J���g�̎v�z
�@
���T��
�@
��ʂɃJ���g�̎v�z�͂���3�̔ᔻ�̏��ɂ��Ȃ�Ŕᔻ�N�w�ƌĂ��B�������A�J���g���g�݂͂�����̔ᔻ����N�w�ƌĂ��̂��D�܂Ȃ������B�J���g�ɂ��A�ᔻ�͓N�w�̂��߂̏����E�\���w�ł���A�ᔻ�̏�ɐ^�̌`����w�Ƃ��Ă̓N�w���z�����ׂ��Ȃ̂ł���B�h�C�c�ϔO�_�̓J���g�̂��̗v���ɂ������悤�Ƃ������݂ł��邪�A�J���g�͂�������܂�D�ӓI�ɂ͕]�����Ȃ������B�܂��A�h�C�c�ϔO�_�̑��ł��J���g�������]�����Ȃ���A�����̂ƌo�����������Ƃɂ��ăJ���g��s�O��Ƃ��]�����A����A�J���g���������悤�Ƃ����̂ł���B�J���g�̎v�z�͈ȉ���3�̎����ɋ敪�����B
�@
�O�ᔻ�� / �w���������ᔻ�x���s�O�A�����̎��R�N�w�_�l����A�E�_���w���E�ƒm���E�ɂ��āx�܂�
�@
�ᔻ�� / 1768�N-1790�N�B�w���������ᔻ�x�ȍ~�̎O�ᔻ�����܂ޏ�����B����ȍ~�A��ᔻ�����܂߂Ĕᔻ�N�w�ƌĂ�
�@
��ᔻ�� / 1790�N-1804�N�B��O�ᔻ�w���f�͔ᔻ�x�Ȍ�Ɋ��s���ꂽ���삨��ш�e�w�i�����a�̂��߂Ɂx��������
�@
���O�ᔻ��
�@
�����̃J���g�̊S�͎��R�N�w�ɂނ������B���Ƀj���[�g���̎��R�N�w�ɔނ͊S�������A�w���͐˗͘_�x�Ȃǃj���[�g���̗͊w��V���w����e������ł�������z���悤�Ƃ���_�����������B���R�N�w�ɂ����Ă͂��Ƃɐ��_�ɂ�鑾�z�n�����ɂ��ĊS���������B�܂����X�{����n�k������Ռ�����A��̒n���Ɋւ���_�����������B
�@
����ŁA�J���g�̓C�M���X�o���_����e���A���ƂɃq���[���̉��^��`�ɋ����Ռ������B�J���g�͎���u�ƒf�_�̂܂ǂ�݁v�ƌĂ��C�v�j�b�c�����H���t�w�h�̌`����w�̉e����E���A������o���ɂ��ƂÂ��Ȃ��u�`����w�҂̖��v�Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ�(�w����҂̖��x)�B���R�Ȋw�Ɗw�̌����Ɏx����ꂽ�o���̏d���ƁA���̂悤�Ȍo�����m���̉c�݂Ƃ��ĉ\�ɂȂ�\�����̂��̂̒T�����Ȃ���Ă����B
�@
�܂��A�J���g�̓��\�[�̒����ǂ݁A���̍m��I�Ȑl�Ԋςɉe�������B����͔ނ̓����N�w��l�Ԙ_�ɓ��ɉe����^�����B
�@
�������āA�m���ɂƂ��đΏۂ��^������ӂ��̗̈�Ƃ����ł̐l�ԗ����̓������������w���E�ƒm���E�ɂ��āx���������B���̎��_�Ō�N�́w���������ᔻ�x�̊�{�I�ȍ\�z�͂��łɌ���Ă������A���ꂪ����̖{�ɂ܂Ƃ܂�܂łɂ͒����N����v���邱�ƂɂȂ�B
�@
���ᔻ�N�w
�@
�]���A�l�ԊO���̎��ہA���̂ɂ��ĕ��͂���������̂ł������N�w��l�Ԃ��ꎩ�g�̒T���̂��߂ɍĒ�`�����u�R�y���j�N�X�I�]��v�͗L���B�ނ́A�l�Ԃ̂����������A���H�����A���f�͂Ƃ��ɔ��ȓI���f�͂̐����Ƃ��̌��E���l�@���A�w���������ᔻ�x�ȉ��̎O���̔ᔻ���ɂ܂Ƃ߂��B�u��X�͉���m�肤�邩�v�A�u��X�͉����Ȃ����邩�v�A�u��X�͉���~�����邩�v�Ƃ����l�Ԋw�̍��{�I�Ȗ₢�����ꂼ��w���������ᔻ�x�A�w���H�����ᔻ�x�A�w���f�͔ᔻ�x�ɑΉ����Ă���B�J���g�̔ᔻ�Ƃ͔ے�ł͂Ȃ��ᖡ�������B
�@
���F���_
�@
�J���g�ɂ��A�l�Ԃ̔F���\�͂ɂ͊����ƌ含�̓��̔F���`�����A�v���I���ɂ��Ȃ���Ă���B�����ɂ͏������ςł����ԂƎ��Ԃ��A�含�ɂ͈��ʐ��Ȃǂ� 12 ��̏����含�T�O(�J�e�S���[�A���Ȃ킿���e�Ƃ��̂���)���܂܂��B�����含�T�O�͎��Ԍ��肽��}��(schema)�ɂ���Ă̂݊����ƊW����B
�@
�ӎ��͂��̓��̌`��(�����ƌ含)�ɂ��������Ă̂ݕ�����F������B���̔F�������̌o���ł���B�����A���̌`���ɓK�����Ȃ��������O�͌����I�ɐl�Ԃɂ͔F���ł��Ȃ����A���Ȃ��Ƃ��ۑ�Ƃ��ĕK�v�Ƃ����T�O�Ƃ����B���������ɂ�闝�O�͂���ΐ�Ύ҂ɂ܂Ŋg�����ꂽ�����含�T�O�ł���B�_���邢�͒��z�҂����̑�\��ł���A������J���g�͕����̂ƌĂԁB
�@
������w���ɂ����Ă͒藧�̑��ł͊��S�Ȍn��ɂ͖�����҂��܂܂��Ǝ咣�����B����ɑ��A���藧�̑��ł͐����Ԃɂ����ė^����ꂽ�n��ɂ͔퐧��҂݂̂��܂܂��Ǝ咣�����B���̂悤�ȑΗ��̉����͓����I�ł͂����Ă��\���I�ł͂Ȃ����O�ɋq�ϓI���ݐ���t�^����挱�I���肩��������邱�Ƃ�K�v�Ƃ���B���O�͗^����ꂽ���ۂ̐���n��ɂ����Ė�����҂ɓ��B���邱�Ƃ����߂邪�A�������A���B���Ē���邱�Ƃ͋����Ȃ��K���ł���(�w���������ᔻ�x)�B
�@
�Ȃ��A�w�v�����S���i�x�ɂ��A�����含�T�O�͂���Ό��ۂ��o���Ƃ��ēǂݓ���悤�ɕ����ɂ���킷���Ƃɖ𗧂��̂ŁA�������A�����̂ɊW��������ׂ����̂Ȃ�Ζ��Ӌ`�ƂȂ�B�܂��A�o���ɐ�s��������\�ɂ��钴�z�_�I�Ƃ����T�O�͂���ɏ�L�̊T�O�̎g�p���o������Ȃ�Β��z�I�ƌĂ�A���ݓI���Ȃ킿�o�����Ɍ���ꂽ�g�p�����ʂ����B
�@
���ϗ��w
�@
�����T�O��(���ς��������߂�)���_�I�ɂ͔F�����ꂦ���A�P�Ɏv�҂̑Ώۂɂ����Ȃ����Ƃ��w���������ᔻ�x�ɂ����Ďw�E���ꂽ���A����痝�����O�Ɨ������������ʂ̕��@���w���H�����ᔻ�x�ɂ����čl�@����Ă���B�w���H�����ᔻ�x�́A�������H���������݂��邱�ƁA�܂菃�����������ꂾ���Ŏ��H�I�ł��邱�ƁA���Ȃ킿�������������̂����Ȃ�K�荪��������Ɨ��ɂ��ꂾ���ŏ[���Ɉӎu���K�肵���邱�Ƃ��������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���B
�@
�J���g�����_�̊�b�ł��邱�̏��ɂ����āA�l�Ԃ͌��ۊE�ɑ����邾���łȂ��b�q�E�ɂ�������l�i�Ƃ��Ă��l�����A���ۊE���x�z���鎩�R�̈��ʐ������łȂ��A�����̂̒����ł���b�q�E�ɂ�������ʐ��̖@���ɂ��]���ׂ����Ƃ��_������B�J���g�́A���̕����̂̉b�q�I�������x�z����@�����A�l�i�Ƃ��Ă̐l�Ԃ��]���ׂ������@���Ƃ��Ē�o����B
�@
�����@���́u�Ȃ̈ӎu�̊i�����˂ɓ����ɕ��ՓI���@�̌����Ƃ��đÓ�����悤�ɍs�ׂ���v�Ƃ����茾���@�Ƃ��Ē莮�������B
�@
�J���g�͏��������ɂ���Č��o����邱�̖@���Ɏ���]������(�ӎu�̎���)�ɂ����ď������������H�I�ɋq�ϓI�Ɏ��ݓI�ł��邱�Ƃ��咣���A�������玩�R�̗��O���܂����H�I�ɋq�ϓI���ݐ�����������Ƙ_�����B�����@���ɐl�Ԃ��]�����Ƃ��ł���Ƃ������Ƃ��A�b�q�E�ɂ������鑶�ݎ҂Ƃ��Ă̐l�Ԃ����R�I�����ȊO�̕ʂ̌�������������A���Ȃ킿���R�ł���Ƃ������Ƃ���������ł���B
�@
�܂��A�_�E�s���̗��O�́A�L�����ɔ�Ⴕ���K��(���Ȃ킿�ō��P)�̎����̏����Ƃ��ėv�������B
�@
�����w�E�ړI�_
�@
�Ō�ɃJ���g�͋��`�̗����ł͂Ȃ����A�l�Ԃ̔F���\�͂̂ЂƂ��f�͂ɂ��čl�@�������A���̈��ł��锽�ȓI���f�͂��u����������J�e�S���[�̉��ɕ�ۂ���\�́v�ƒ莮�����A�������I(�����I)���f�͂ƖړI�_�I���f�͂̓��ɕ����čl�@���������B���ꂪ�w���f�͔ᔻ�x�ł���B���̏��́A���̌�W�J�������H�_�A���w�Ȃǂ̊�b�Ƃ��ĕ]������Ă���B�܂��n���i�E�A�����g�ȍ~�A�w���f�͔ᔻ�x�𐭎��N�w�Ƃ��ēǂޓǂݕ�������A����N�w�ɂ����ăJ���g�̐�߂�ʒu�͋ɂ߂ďd�v�ł���Ƃ����悤�B�ᔻ���ȍ~�̃J���g(��ᔻ��)�́A�ӂ����я@���E�ϗ��w�ւ̊S�𑝂����B�Ƃ��Ƀt�����X�v���ɃJ���g�͏d��ȏՌ����A�S�������Ă��̐��ڂ�������Ă����B�������̓����_��l�Ԙ_�ɂ͂��̒m�������e����Ă���B���̓����_�͋`���_�ϗ��Ƃ��Č��݂̓��K�͗ϗ��w�̈�����Ȃ��Ă���B
�@
�����j�N�w
�@
�J���g�͐l�ނ̗��j���A�l�Ԃ��Ȃ̎��R�I�f������������v���Z�X�Ƃ��đ�����B�l�ԂɂƂ��Ă̎��R�I�f���Ƃ́A�{�\�ł͂Ȃ������ɂ���čK���⊮������ڎw�����Ƃł���B
�@
�������N�w
�@
�w�l�ς̌`����w�x�́w�@�_�x�ɂ�����J���g�́A���R�@���x�z���l�X������l�ɑ��Ă̎b��I�Ȏ��R�������Ƃ������R��Ԃ�z�肵�A���̎b��I�Ȍ������m��I�Ȃ��̂ւƂ��邽�߂Ɋe�l�͎��R��Ԃ��甲���o�����ʂ̍ٔ�����������Ƃ��`�����ĎЉ��Ԃւƈڍs����ׂ��ł���(�J���g�ɂ����Ă���͋`���ł���)�Ƃ��郍�b�N�I�ȎЉ�_�����W�J���Ă���B�������A���Ƃ͑��̍��ƂƂ̊Ԃɂ���ʂ̋��ʂȌ��͂������Ȃ����߂Ɍ������������������J��L���邱�ƂɂȂ�A���݂��ɑ��Ă͂Ȃ����R��Ԃɂ���B���ƂɂƂ��Ă̎��R���(�푈���)��E���čP�v�I�ȕ��a�������炷���Ƃ͐l�ނɂƂ��Ă͌����ɂ͓��B�����Ȃ������B���ׂ��ł���悤�ȗ��O�ł���B�J���g�́A���̍P�v�I�ȕ��a��ԂւƋ߂Â����߂ɁA���E�s���@�Ǝ��R�ȍ��Ƃ̘A�����\�z���Ă���B�w�@�_�x��w�i�����a�̂��߂Ɂx�ŏq�ׂ��Ă��邱�̍\�z�́A���ۘA�������̎v�z�I��Ղ�p�ӂ����B�u�i�����a�̂��߂Ɂv�̒��ł͓����̒�����]�˓��{�̑ΊO�����]�����Ă���B
�@
���@���N�w
�@
�J���g�͏@�����A�����̊�b�̏�ɐ��藧�ׂ����̂ł���Ƃ��Ă���B�_�́A�K���Ɠ��̈�v�ł���u�ō��P�v���\�ɂ��邽�߂ɗv�������B���̎v�z�͗����@���̗���ł��邪�A�[���@����r�����悤�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�@
���l�Ԋw
�@
�J���g�́A�N�w�ɂ́A�u�킽���͉���m�邱�Ƃ��ł���̂��낤���v(Was kann ich wissen�H)�A�u�킽���͉������ׂ��Ȃ̂ł��낤���v�A�u�킽���͉���]�ނ̂��悢�̂��낤���v�A�u�l�ԂƂ͉����낤���v�Ƃ���4�̖��ɑΉ�����4�̕��삪����Ƃ�����ŁA�Ō�̖��ɂ��Č�������w���u�l�Ԋw�v�ł���Ƃ����B������́A�J���g�N�w�̑S�̂�l�Ԋw�̑�n�ł���Ƃ��Ă���B
�@
���n���w
�@
�J���g�̓P�[�j�q�X�x���N��w��1765�N���玩�R�n���w�̍u�`��S�����A�n���w�ɉȊw�I�n�ʂ�^�����B�J���g�͒n���w�Ɨ��j�w�̈Ⴂ���ꏊ�I�L�q���s���̂��n���w�ŁA���ԓI�L�q���s���̂����j�w�ł���Ƃ����B���̌����͌㐢�̒n���w�҂̏펯�ƂȂ����B�܂��A�u�����n���w�v�̍u�`�ł́A���{�ƃ��b�v�����h�Őe�E���������q�ɑ���Y�����قȂ�A��̓I�ɂ͓��{�ł͎q�̉Ƒ�����Ƃ��ɌY�ɏ�����邪�A���b�v�����h�ł͓����Ȃ��Ȃ��������E�����Ƃ͕ꂪ�q��}�{����Ȃ�������A�Ƃ��������p���āA�n���I�����قȂ�Ηϗ��⓹�����قȂ�Ɛ������B�@ |
���_�̑��ݏؖ�
�@
�����ݘ_�I�ؖ� / �A���Z�����X�̏ؖ�(�w�v���X���M�I���x)
�@
�u�����Ȏ҂͐S�̂����Ő_�͂Ȃ��ƌ������v(����)
�@
�������A��������傢�Ȃ���͉̂����l�����Ȃ����́��ƌ�����A�ނ������m������ł��낤�B���ꂪ���݂��邱�Ƃ�ނ��m�����Ȃ��Ƃ��Ă��A�ނ̒m���̒��ɂ͑��݂��Ă���B�Ƃ���ŁA��������傢�Ȃ���͉̂����l�����Ȃ����́����A�m���̂����ɂ������݂��Ȃ��ƍl���邱�Ƃ́A�s�\�ł���B�Ȃ��Ȃ�A�m���̂����ɂ������݂���Ƃ���A����͂܂����ۂ̂����ɂ����݂���ƍl�����邩�炾�B���̕������傢�Ȃ���̂Ȃ̂�����B
�@
���`����w�I�ؖ��E���R�_�w�I�ؖ�(�ړI�_�I�ؖ�) / �A���X�g�e���X�ɂ��ؖ�
�@
���̐��E�ɂ́A������ړI������B����������̂����E�n���҂ł���_�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@
���`����w�I�ؖ��E�F���_�I�ؖ� / ���E�̋��R���ɂ��ؖ�(���C�v�j�b�c)
�@
��������������̂����݂���Ȃ�A��ΓI�ɕK�R�I�ȑ��ݎ҂��܂����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A���Ȃ��Ƃ������g�͎��݂���B�䂦�ɐ�ΓI�ȑ��ݎ҂��܂����݂���B
�@
���A���X�g�e���X����уg�}�X=�A�N�B�i�X�ɂ��ؖ�
�@
���̐��E�̒��ʼn����������Ă���Ƃ������Ƃ́A�m���Ȏ����ł���B�����Ă�����̂͂��ׂāA���҂ɂ���ē�������Ă���B��������Ă�����̂́A�ŏI�I�ɂ́A����͓���������������(�s���̓���)���Ȃ킿�_�ɂ���ē�������Ă���B
�@
(��)������v�Ƃ����̂́A�ʏ��X����������A�ꏊ�̈ړ��ł͂Ȃ��A�ނ���A�ꗱ�̎킪��Ԃ���ɂȂ�悤�ȁA�����ω��̓���(�\�Ԃ��猻���Ԃւ̉^��)���Ӗ�����B�]���āA�_�͑S�Ắu�^���v�̖ړI(������)�ł�����B
�@
���J���g�̔ᔻ
�@
�J���g�������Ŏ咣���Ă���̂́A�_�͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�_�̑��݂��ؖ�����͕̂s�\���Ƃ������Ƃł���B(����͋t�Ɍ����A�_�����݂��Ȃ����Ƃ��ؖ�����̂��s�\���A�Ƃ������Ƃ��B)�J���g�́A��ɁA�w���H�����ᔻ�x�̂Ȃ��ŁA���H�̗��ꂩ��A�_�̑��݂�v�����A����Ɂw���f�͔ᔻ�x�̂Ȃ��ŁA���R�̍��ړI���ɂ��āA�m��I�ɘ_���Ă���B�܂�A�w��I�ɂ͐_�̑��݂��ؖ����邱�Ƃ͕s�\�����A�����_�����݂��Ȃ���A��X�̐������s�����A�����������F���������������A������_�͑��݂���͂����A�Ƃ������������Ă���B(����́A�E�B�g�Q���V���^�C���̗L���ȁA�u��肤�邱�Ƃ͖����Ɍ�肤��B��肦�Ȃ����̂ɂ��ẮA���ق��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�Ƃ�������ƁA���ɂ悭���Ă���A�ƌ������A�������B)�@ |
���w��(�A���`�m�~�[)
�@
�J���g�������Ă���A���`�m�~�[�ɂ́A�l������B
�@
1 ���E�͗L��(���ԓI�A��ԓI��)�ł��� / ���E�͖����ł���B
�@
2 ���E�ɂ�����ǂ�Ȏ��̂��P���ȕ�������o���Ă��� / �P���Ȃ��̂ȂǑ��݂��Ȃ��B
�@
3 ���E�ɂ͎��R�Ȍ��������݂��� / ���R�͑��݂����A���E�ɂ������͎��R�@���ɏ]���Đ��N����B
�@
4 ���E�̓����O�ɕK�R�I�ȑ��ݎ҂����̌����Ƃ��đ��݂��� / �K�R�I�ȑ��ݎ҂ȂǑ��݂��Ȃ��B
�@
�u���E�͎��Ԃɂ����Ďn�܂�������A��Ԃ���݂Ă����E�Ɉ͂܂�Ă���B�v�Ƃ����e�[�[(�̑O��)�̏ؖ��́A���̂悤�ɂ���(�w���@��p����)�s����B�u�Ȃ��Ȃ�A���E�����Ԃɂ����Ďn�܂�������Ȃ��Ɖ��肹��A��������A�^����ꂽ�ǂ̎��_�܂łɂ��i�����o�߂��A�]���Đ��E�ɂ����鏔�����̎��X�Ɍp�N���鏔��Ԃ̖����̌n���ꋎ�������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A�n��̖������Ƃ����̂́A�p���I�ȑ����ɂ���Ă͌����Ċ������ꂦ�Ȃ��Ƃ����_�ɂ��̖{��������B����䂦�A�����̗��ꋎ�������E�n��Ƃ����͕̂s�\�ł���A����āA���E�̎n�܂�͐��E�����ɑ��݂��邽�߂̕K�R�I�ȏ����ł���B���ꂪ�ŏ��ɏؖ������ׂ����Ƃł������B�v(��)
�@
�t�ɁA�u���E�͎n�܂���������A��Ԃɂ����Ă����E�������Ȃ��B���ԂƂ����_����݂Ă��A��ԂƂ����_����݂Ă��A�����ł���B�v�Ƃ����A���`�e�[�[(�̑O��)�̏ؖ����A���̂悤�ɂ��čs����B
�@
�u�Ȃ��Ȃ�A���E���n�܂�����Ƃ��Ă݂�A���̂Ƃ��ɂ́A�n�܂�Ƃ����͈̂�̌����݂Ȃ̂�����A����ȑO�ɁA�������݂��Ă��Ȃ����Ԃ��旧���Ă������ƂɂȂ邪�A��������A���E�����݂��Ă��Ȃ����Ԃ��A�܂�Ȏ��Ԃ���s���Ă������ƂɂȂ�B�������Ȃ���A�Ȏ��Ԃɂ����Ă͉��炩�̕�����������͕̂s�\�ł���B�c�c����䂦�A���E�ɂ����Ă͏����̑����̌n�n�܂肤�邪�A���E���̂��̂͂����Ȃ�n�܂���������Ȃ��B����䂦�A���E�͉ߋ��̎��ԂƂ����_����݂Ė����ł���B�v
�@
�]���āA�J���g�ɂ��A�����̌��_���A�ǂ�����ؖ�����A�ǂ�����ے肳��邱�ƂɂȂ�B����������A�u���E�͖������v�Ɖ��肵����A���̋t�́u���E�͗L���ł���v�Ƃ������肪�ؖ�����A�u���E�͗L�����v�Ɖ��肵����A���̋t�́u���E�͖������v�Ƃ������肪�ؖ�����邱�ƂɂȂ�B
�@
���̖����̌����͂Ȃɂ��H
�@
�ȒP�Ɍ����Ă��܂��A���ԂƋ�ԂƂ����̂́A�������đΏۂ���X�ɗ^�����銴���̌`���ɂ����Ȃ��̂ɁA��������݂���Ώۂ̌`���Ǝv������Ă��܂��_�ɁA�������������������鏊�Ȃ�����̂ł���B�܂�u�����v���u�������v�Ƃ��ė���������_�����Ƃ������Ƃł���B�������āA�J���g�́A����̗�����A�u���z�_�I�ϔO�_�v�ƌĂԂ��ƂɂȂ�B
�@
(��)�u�����v�Ƃ������t�̈Ӗ����A����̗p�@�Ƃ͈Ⴄ����ł��B�J���g(���邢�̓J���g���ᔻ���Ă���`����w�҂���)�́A�u�����v�Ƃ������t���A�����ʂ�A�u�I���̂Ȃ��v���u�ǂ�Ȍ��E(����)�������Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��Ŏg���Ă��܂��B���������Ӗ��ł́A���鎞�_��(���̎��_�ŏI����Ă��܂�����)�u�����̐��E�n���ꋎ�����v�Ƃ����̂́A�������Ă���킯�ł��B�@�@ |
 �@ �@
�������H�A�W�F�u���w�v�_�v���� 2�� 1789�N |
   �@
�@
|
Lavoisier, Antoine Laurent.(1743-94)
�@
Traite elementaire de Chimie, presente dans un ordre nouveau et d'apres les decouvertes modernes.
�@
�����H�A�W�F�́A�t�����X�̉��w�ҁB�p���ɐ��܂�}�U������w�𑲋ƌ�A�@�����w���A����ɉȊw�ɋ������o���A�V���w�A�A���w�A�z���w�����C�߁A���w�̓G���Ɏt�������B�����A�ӂ��R�Ăɂ��d�ʂ̑������Ƃ��m�F���Ĉȗ��A�C�̂ƔR�Ă̌����ɐ�S���A�����D�������Ƒ�C���̌ċz�����镔���Ƃ̌����ɂ�邱�Ƃ��ؖ������B�܂��L�@�������̌��f���͖@�̌��^�𗧂Ă��B�����̌����ɂ��A�V���������I�ȉ��w�̑̌n���m������A����܂ő����ߑ㉻�w�̏o���_�ƂȂ����B�@ |
���A���g���[�k�����[�����E�h�E�����H�A�W�G
�@
(Antoine-Laurent de Lavoisier�A1743-1794)�@�t�����X�����p���o�g�̉��w�ҁB���ʕۑ��̖@�����A�_�f�̖����A�t���M�X�g������Ŕj�������Ƃ���u�ߑ㉻�w�̕��v�Ə̂����B
�@
1774�N�ɑ̐ςƏd�ʂ��ɂ͂����ʎ������s���A���w�����̑O��ł͎��ʂ��ω����Ȃ��Ƃ������ʕۑ��̖@�����B�܂��A�h�C�c�̉��w�ҁA��t�̃Q�I���N�E�V���^�[�������������x�z�I�ł������t���M�X�g������ނ��A1774�N�ɔR�Ă��_�f�Ƃ̌����Ƃ��Đ��������ŏ��̐l���ŁA1779�N�Ɏ_�f(���ۂ͐��f�C�I��)���uoxygène�v�Ɩ��������B
�@
�����Ύ_�f�̔����҂ƌ��y����邪�����Ƃ��Ă̎_�f���̂̔����҂�1775�N3���ɃC�M���X�̎��R�N�w�ҁA����ҁA�_�w�҂̃W���[�t�E�v���[�X�g���[�ɗD�挠�����邽�߁A�����ȕ\���ł͂Ȃ��B�Ȃ��A���w�j�I�Ɏ_�f�̔����҂̓v���[�X�g���[�ł���B�@ |
���o������w������
�@
1743�N8��26���A�t�����X�����p���ɗT���ȕٌ�m�ł��镃�̌��ɐ��܂�邪�A�����H�A�W�G��5�̍��ɕ�������f��̌��ň�Ă�ꂽ�B
�@
1754�N���1761�N�܂Ń}�U�����w�Z�ʼn��w�A�A���w�A�V���w�A���w���w�ԁB�C���w��N�w�ɉ����Ă��̌�͕��̐E���p���ׂ��@���Ƃ�ڎw�����B
�@
1761�N����̓p����w�@�w���ɐi�w����1763�N(���邢��1764�N)�ɕٌ�m�����ɍ��i���č����@�@�@�w�m�ƂȂ邪�݊w���ɓ����o�g�̓V���w�҂ł���j�R���E���C�E�h�E���J�[���A�����w�҂̃x���i�[���E�h�E�W���V���[����͐A���w���w�сA�ȑO���烉���H�A�W�G�ƂƐe���������������w�ҁA�z���w�҂̃W�������G�e�B�G���k�E�Q�^�[��(�t�����X���)����͒n���w�ƍz���w���A���w�҂̃M���[�����t�����\���E���G��(�t�����X���)����͉��w���w��Ŏ��R�Ȋw�ɋ��������悤�ɂȂ�B�܂��A�@�w���ɍݐЂ��Ă���ɂ��ւ�炸���w�̍u�`�u������A�Q�^�[���Ƌ��Ƀt�����X�̒n���}�쐬�ɋ��͂����B
�@
���̌���Q�^�[���ƃA���U�X�������[�k�ȂǗ��s���Ċe�n��������ہA�e�n���̐p�ɊS�������Ĕ�r�������������Ƃ������H�A�W�G���ŏ��̌����ł������B���̐p�Ɋւ��錤���͌�Ƀ����H�A�W�G�̓��L���ׂ���ʎ����̒����ł��鐄���ł͂Ȃ��m���Ȏ������d������Ă���B�@ |
���t�����X�Ȋw�A�J�f�~�[����猋��
�@
1766�N�Ƀt�����X�Ȋw�A�J�f�~�[���w�s�s�̊X�H�ɍŗǂȖ�ԏƖ��@�x�ɂ��Ă̘_�������ܕ�W���A�����H�A�W�G�͍ŏ��ɒ������_���ɂ��ւ�炸1766�N4��9����1���܂��B���̌�A�Q�^�[���ƒn���}�쐬�̗��s�ŏW�߂��������̕��͂������ʂ\����1768�N5��18���Ƀt�����X�Ȋw�A�J�f�~�[�̉���ƂȂ����B���̍����C�M���X�̉��w�ҁA�����w�҂̃w�����[�E�L�����F���f�B�b�V�������f�����A����R�Ăɋ����������ē��N�����痂�N1769�N�ɂ����čs��ꂽ�����K���X�e��ɓ����101���Ԃ�������u�y���J���̎����v�Ő����y�ɕς��Ƃ����l�匳�f�������S�ɕ������B
�@
1768�N����胉���H�A�W�G�T���Ȑ��܂ꂾ�����ɂ��ւ�炸�A����������p���K�v���������Ƃ���A�s������ŋ�����藧�Ăč����Ɉ����n�����Ő����l�̐E�ƂɏA���A���Y��L���ɉ^�p���悤�Ƃ����B
�@
1771�N12��6���A���Ő����l�����̃W���b�N�E�|�[���Y(Jacques Paulze)�̖��ł���}���[���A���k�E�s�G���b�g�E�|�[���Y(�t�����X���)�ƃp���ɂ���T�����b�N����(�t�����X���)�Ō�������B��l�̊ԂɎq���͂ł��Ȃ��������̂̍ȃ}���[���A���k�͕v�����H�A�W�G�̖��ɗ��Ƃ��Ɖp��A���e����A�C�^���A����w�сA�n���w�I�ȉ��w��G��̕`�����Ȃǂ��K���B�����ăA�C�������h�̉Ȋw�҂ł��郊�`���[�h�E�J�[������v���[�X�g���[�̘_����莆�������H�A�W�G�̂��߂Ƀt�����X��ɖ|�A�����̍ۂɂ͔��ɍׂ����_�܂ŃX�P�b�`���A�L�^�Ɏc�����B�@ |
���l�X�Ȏ�������w���w�����@�x�o�ł܂�
�@
1772�N���ɂ͋M���̒n�ʂ��B1775�N���͉Ζ�Ǘ��̊ē��ƂȂ�A1776�N�ȗ��A�C���H���ő�C�p�̉Ζ�����ǂ��A�ɐ̐��Y�ʂ�啝�ɑ��₵�ĉΖ�̐����͂傳�����B�����ĉΖ�ɒY�_�J���E��������ƉΗ͂��オ�邱�Ƃ����Ĕ_�Ƃɕ�V�����x�������Ƃŏɐ���点���B���̂悤�Ƀ����H�A�W�G�͔_�Ƃɂ��S�������A��ɉ����_�Ɗw��A�t�����X���{�̔_�ƈψ���ɉ���邱�ƂƂȂ����B
�@
1774�N1���ɏ�L�́u�y���J���̎����v��艻�w�����̑O��ł͎��ʂ��ω����Ȃ����Ƃ����o�����ʕۑ��̖@�����B���N�ɔR�Ă��_�f�Ƃ̌����Ƃ��Đ��������B�Ȃ��A�����H�A�W�G��1773�N2��20���t���̎����m�[�g�Ɂu���w�ɉ�����v���ɂȂ�v�Ə������B
�@
1774�N4���ɂ̓��g���g�Ɏ������ĉ��M���A�R�Ăɂ��ł������D�̏d�����r����u���g���g�̎����v���s���A�A�C�������h�̋M���A���w�҂̃��o�[�g�E�{�C���������u�̗��q(�t���M�X�g��)�v�����݂��Ȃ����Ƃ��𖾁B���N��11��12���Ƀt�����X�Ȋw�A�J�f�~�[�Ŕ��\�����B�Ȃ��A���N��10���Ƀv���[�X�g���[���t�����X��K��A����D�����M����ƋC�̂��o�Ă���b�����B���̌ド���H�A�W�G�͐����12���ԉ��M���A�R�Ă͎_�f�ƕ������������邱�Ƃ��������A�X�E�F�[�f���̉��w�ҁA��w�҂̃J�[���E���B���w�����E�V�F�[����1773�N���ɖ����\�ł͂��������̂́u�ɂ�C�v�����Ă����B
�@
1777�N�ɔR�Ă������Ǝ_�f���������邱�Ƃł���Ɛ������A1779�N�Ɏ_�f(���ۂ͐��f�C�I��)���uoxygène�v�Ɩ��t�����B
�@
1781�N�ɃL�����F���f�B�b�V�������f�Ǝ_�f�������Đ����ł��������ɊS�������������H�A�W�G��1783�N�ɃL�����F���f�B�b�V�����s�����������ʎ�����p���Ēǎ����A�������f�łȂ����Ƃ��ؖ������f���uhydrogène�v�Ɩ��t�����B�ŏ��̓t���M�X�g�����ɍm��I�ł����������H�A�W�G��1783�N���@�ɂ��ăt���M�X�g���Ɋւ���_�����A�t���M�X�g���������R�Ɋ��S�ے肷��悤�ɂȂ����B 1782�N���痂�N��1783�N�ɂ����ē����o�g�̎��R�Ȋw�ҁA���w�ҁA�����w�ҁA�V���w�҂ł���s�G�[�����V�����E���v���X�Ƌ��ɕX�M�ʌv�����A1777�N�Ɏ������Ă��������̌ċz�͈�̔R�Ăł��邱�Ƃ��𗠕t�����B
�@
1787�N�A�����H�A�W�G�͓����o�g�̉��w�ҁA��t�̃N���[�h�E���C�E�x���g���[�A���C���x���i�[���E�M�g���E�h�E�����{�[�A�A���g���[�k�E�h�E�t���N����(�t�����X���)�Ƌ��ɐV�������w�p�ꂪ�����ꂽ�w���w�����@�x���B�����̖����@���m�����A���f���`�t���A�܂��A���̐������_�f�Ɛ��f�ł��邱�Ƃ\�����B�����A����̓����H�A�W�G�ɐ旧���āE�L�����F���f�B�b�V�������ɔ������Ă������A���Ȃ�̕ϐl�Ől�Ԍ����������L�����F���f�B�b�V���̓����H�A�W�G�̔��\�ɉ��̊S���D�挠���咣���Ȃ��������߁A�����H�A�W�G�ɗD�挠���������邱�ƂƂȂ����B
�@
���N��1787�N�̓����H�A�W�G�̏��L�n�ł���I�����A���̒n���c��ő�O�K����c���Ƃ��Ė��߂Ă����B�@ |
���w���w���_�x�o�ł��珈�Y�܂�
�@
1789�N�A�w���w���_(Traité élémentaire de chimie)�x���o�ł��A33�̌��f�\�������A�ߑ㉻�w�̊v���𐬂��������B13�̐}�ł̓}���[���A���k���肪���A��ꕔ�ɂ͋C�̂̐��������A��͉����_�A���Ɋւ���L�q�A��O���ɂ͉��w�̎������Ƃ��̑���ɂ��ď�����A���ʕۑ��̖@���ɂ��Ă̖��m�ȋL�q��������Ă���B���݂Ɂw���w���_�x�͏o�ł��炻�̌��10�N�ԁA���[���b�p�S�y�ŕW���I�ȋ��ȏ��Ƃ��ꂽ�B�Ȃ����N�A�����H�A�W�G�͐V���ɒ��f���M���V�A��̐������Ȃ��ƌ����ӂł���uazotikos'�v�Ɉ���Łuazote�v�Ɩ��t�����B
�@
���N��1789�N�Ƀt�����X�v�����u���B���������H�A�W�G�̓p���ŋM���K���̕⑫��c���߂Ă����B1790�N�ɂ͊e���x�𑪂�A�̐ς̏������̎��ʂ𑪒肵�ĐV�������ʂ̒P�ʂ����c���邽�ߐV�x�ʍt�@�ݗ��ψ���̈ψ��߂��B���̍��̎����͌ċz�ƔR�Ă̊W���ׂ鉻�w�ł͂Ȃ������w�I�Ȏ����Ɉڂ��Ă������B
�@
1791�N�ɒ��Ő������x���p�~���ꂽ���A�����H�A�W�G�̎��͂������t�����X�̍����ł��������C16���ɐM������č��ƍ����ψ��ɔC�����ꂽ�B���̌�t�����X�̋��Z�⒥�Ő��x�����v���悤�Ƃ����B
�@
1792�N�A�����H�A�W�G�͎����ɐ�O���邽�߂ɐ��{�̐E�Ƃ�S�Ď��C���ďZ���������z�����B�������t�����X�v���ɉ�����ăt�����X�Ȋw�A�J�f�~�[�����ƂȂ�A�����H�A�W�G�̌ċz�ƔR�ĂɊւ��鐶���w�I�Ȏ����͓r���ŏI����Ă��܂����B
�@
�t�����X�v���u�����1793�N11��24���Ɋv�����{�����Ő����l���s�����琳�K�̐łɉ����A���z�Ȏ萔�����Ƃ������ߓG�����A�S�Ă̒��Ő����l���w����z���ꂽ�B���̌ド���H�A�W�G�͎��A���Ő����l�̖��ƌ������Ă������ƂȂǂ����R�ɓ������ꂽ�B���������H�A�W�G���g�͂����܂ō������ł͂����A�ނ���ł̕��S�����炻���Ɠw�͂��Ă����B
�@
1794�N5��8���̊v���ٔ����̐R���Łu���ƗL�Q�������^�o�R�ɍ��������v�Ƃ̉ˋ�̍߂Ŏ��Y�̔������������B�����������H�A�W�G�ٌ̕�l�̓����H�A�W�G�̉Ȋw��̎��т�٘_�������u���a���ɉȊw�҂͕s�v�ł���v�ƍٔ����Ɏw�E����A���̓��̓��ɃR���R���h�L��ɂ���M���`���ŏ��Y���ꂽ�B
�@
�����H�A�W�G�������A���Y���ꂽ���R�ɂ��ẮA�v���w���҂̈�l�ʼn��w�҂ł��������W�������|�[���E�}���[���A���Ċw��ɒ�o�����_�����R����S�����������H�A�W�G�ɂ����(��ʎ��������b�g�[�Ƃ��郉���H�A�W�G�ɂ��u���������������̓��e�ł��������߁v)�p�����ꂽ���Ƃ̋t���݂ɂ����̂ł���Ƃ��`�����Ă���B
�@
�����o�g�̓V���w�҂ł���W���[�t�����C�E���O�����W���́A�����H�A�W�G�̎��ɐڂ��āu�ނ̓���藎�Ƃ��͈̂�u�����A�ނƓ������]�������̂������ɂ�100�N�����邾�낤�v�ƃ����H�A�W�G�̍˔\��ɂ��B
�@
�Ȃ��A���Y��̐l�Ɉӎ�������̂����������邽�߁A���͂̐l�ԂɁu�a���A�\�Ȍ���u���𑱂���v�Ɛ錾���Ď��ۂɏu�����s�Ȃ����Ƃ����b�����邪�A�����H�A�W�F�̏��Y��35���Ԃ�28�l�����Y���闬���Ƃ̓r���ōs���A�������ۂɎ��Y�ɗ���������l�̋L�q�ɂ��̂悤�Șb�͂Ȃ��A�{�[�����[��t��1905�N�̘_�������Ƃ�1990�N��ȍ~�n��ꂽ�s�s�`���ƍl������B�@�@
�@ |
 �@ �@
���W�F���i�[�u�����̌�������ь��\�Ɋւ��錤���v���� 1798�N |
   �@
�@
|
Jenner, Edward.(1749-1823)
�@
An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae.
�@
�W�F���i�[�́A�C�M���X�̈�҂Ŏ퓗�@�̔����ҁB18���I�̃��[���b�p�ł́A�V�R���͂����Ƃ����낵���a�C�̈�Ƃ���A1�N�Ԃ�60���l�ɂ��̂ڂ鎀�҂��o���Ă����B�����ɂ��������l�͓V�R���ɂ�����Ȃ��Ƃ������_�w�̑̌��ɒ��ڂ��A�V�R���\�h�̂��߂̋����ڎ�@�����A�ߑ�Ɖu�w�A�\�h��w�̊�b��z�����B�ނ́A8�̃t�B���b�v�X�Ƃ����j���ɍŏ��̗\�h�ڎ�����݁A�X�ɂ��̏��N�ɐ^���̓�ጓł�ڎ킵�Ċ��S�ɗ\�h�ł��邱�Ƃ��ؖ������B�W�F���i�[�͂��̌��ʂ�{���ɂ܂Ƃ߂ĉ�������ɒ�o�������A�L�Q�_�҂���������Ȃ��������߁A����ŏo�ł����B��ʐF�̓��Ő}��4������B�@�@
�@ |
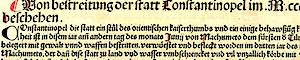 �@ �@
���}���T�X�u�l���_�v���� 1798�N |
   �@
�@
|
Malthus, Thomas Robert.(1766-1834)
�@
An Essay on the Principles of Population.
�@
�}���T�X�́A�C�M���X�̌ÓT�h�o�ϊw�ҁB�u�l���_�v�͓����v�z�E�ɌN�Ղ��Ă������\�[�A�S�h�E�B���A�R���h���Z��̌�����ے肷�邽�߁A�����ŏo�ł��ꂽ���̂ł���B����́u�l���̌����Ɋւ���1���_�A���̌����������̎Љ�̉��P�ɋy�ڂ��e���A�Ȃ�тɃS�h�E�B�����A�R���h���Z������т��̑��̒��q�Ƃ����̎v���ɑ����]�v�ł���B�}���T�X�̐l�����_�́A���̓����̂�����o�ϊw�҂����ӂ��������������(�������͐l���������h������̂ŁA�����Ƃ������̂͏�ɘJ���҂̐����ɕK�v�Ȑ����։�������X��������)�������I�ɐ��������B�������A�ނ��ᔻ�����_�q�Ƃ����̍U���͌������A���̂��߃}���T�X�͐��U�ɂ킽���Ė{���������������Ȃ���Ȃ�Ȃ������B�@ |
���w�l���_�x1
�@
(An Essay on the Principle of Population)�@�g�}�X�E���o�[�g�E�}���T�X�ɂ��l���w�̌ÓT�I����ł���B���̒���̐��m�ȑ薼�́A���łƑ��ňȍ~�ňȉ��̂悤�ɈقȂ�B
�@
���ŁF�w�l���̌����Ɋւ����_�@�S�h�E�B�����A�R���h���Z�[���A���̑��̏����̌����ɐG��ĎЉ�̏����̉��P�ɑ���e����_��(An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of society, with remarks on the speculations of Mr. Godwin, M. Condorcet and other writers.)�x
�@
��ňȍ~�F�w�l���̌����Ɋւ����_�A�܂��͐l�ނ̍K���ɑ���ߋ�����ь��݂̉e���ɂ��Ă̌����F�l�ނ̍K���ɑ���e���������N���������̏����̏�����ɘa�ɂ��Ă̌��ʂ��̌����ɂ��(An Essay on the Principle of Population, or, a View of its past and present effects on human happiness : with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions.)�x
�@
���҂̃g�}�X�E���o�[�g�E�}���T�X�͌ÓT�o�ϊw�̔��W�Ɋ�^�����o�ϊw�҂ł������B1766�N2��13���ɖq�t�̉ƒ�ɐ��܂�A�P���u���b�W��w�Ŋw�B1798�N�Ƀ}���T�X�́w�l���_�x�����M���������A�C�M���X�ł̓t�����X�Ƃ̐푈�╨���̍����Ȃǂ̌o�ϖ�肪�o�����Ă���A��Ƃ��ċ~�n�@�����̐��c�_����Ă��������ł������B�܂��t�����X�v���̉e���ŁA�E�B���A���E�S�h�E�B����̌[�֎v�z�Ƃɂ��A�Љ���ǂɂ��n���⓹���I�ޔp�̉��P�̎������咣����Ă����B���̂悤�ȏ�̒��Ń}���T�X�͐l���̌������������Ƃŗ��z�I�Ȋv�V�h��ᔻ���悤�Ƃ����B
�@
���ł͓����ŏo�ł���傫�Ȕ������ĂB1803�N�ɂ͑啝�Ȓ������������āA���Җ���t���đ��ł��o�ł����B�Ȍ�A�ł��d�˂邲�Ƃɑ����������1826�N�ɏo�����Ō�̑�Z�łł͏��ł̖�ܔ{�̌ꐔ�ɒB���Ă���B
�@
�P�C���Y�́A�}���T�X�̕]�`�̒��ŁA���ł��u���@�ɂ����Đ挱�I���N�w�I�A���̂͑�_�ɂ��ďC���I�A�ؗ�Ȍ����Ə�ɕx��ł���v�ƕ]�������A���ňȍ~�́u�����N�w�͌o�ϊw�ɂ��̐Ȃ��䂸��A��ʌ����͎Љ�w�I���j�̐��҂ɂ��A�[�I���Ɉ��|����A�N�̍��̋P�������ˋC�Ɛ���ȈӋC�͏��������Ă���v�ƋL�q�����B
�@
���l���̌���
�@
�܂��}���T�X�͊�{�I�ȓ�̎����ł���O���u�����Ƃ���n�߂�B
�@
���ɐH��(��������)���l�ނ̐����ɕK�v�ł���B
�@
���Ɉِ��Ԃ̏�~�͕K�����݂���B
�@
���̓�̑O�瓱���o�����l�@�Ƃ��āA�}���T�X�͐l���̑��������������Y����y�n�̔\�͂����s���ɑ傫���Ǝ咣���A�l���͐�������Ȃ���Ί����I�ɑ������邪���������͎Z�p�����I�ɂ����������Ȃ��A�Ƃ�������������B
�@
�l���͐�������Ȃ���Ί����I�ɑ�������Ƃ��������͗��_��ɂ����錴���ł���B�����������ł���A�����������L�x�ł���A�Љ�̊e�K�w�ɂ�����Ƒ��̐����\�͂Ȃǂɂ���Đl���̑��B�͂����S�ɖ������ł��邱�Ƃ��O��ɂȂ��Ă���B���̗��_�I����ɂ����ĔɐB�̋������@�Â����Љ�x��H�������ɂ���Ĉ�ؗ}������Ȃ��Ȃ�A�l�����͌����̐l�����傫�����̂ɂȂ�ƍl������B�����Ń}���T�X�͕č��ɂ����āA��萶�������╗���������ł���A�����������������߂ɁA�l����25�N�ԂŔ{����������������A���̑������͌����ė��_��ɂ�������E�ł͂Ȃ����A�������j�I�Ȍo���Ɋ�Â�����Ƃ���B�����Ől��������Ȃ����25�N���ɔ{��������̂ł���A����͊����I�ɑ������邱�ƂƓ��`�ł���B
�@
���������͎Z�p�����I�ɂ����������Ȃ��Ƃ��������͎��̂悤�ȋ�̓I�Ȏ���ŗe�Ղɍl�@�ł���B���铇���ɂ����Đ����������ǂ̂悤�ȑ������ő�������̂����l�@����ƁA�܂����݂̍k��ɂ��Č�������K�v������B�����őP�̔_�Ɛ���ɂ���ĊJ���i�߁A�_�Ƃ�U�����A���Y����25�N��2�{�ɑ��������Ƃ�����z�肷��B���̂悤�ȏŎ���25�N�̊Ԃɐ��Y����{�������邱�Ƃ́A�y�n�̐��Y������l���ċZ�p�I�ɍ���ł���ƍl������B�܂肱�̂悤�Ȕ{�������w���ĎZ�p�����I�ȑ����Əq�ׂ邱�Ƃ��ł���B���̎Z�p�����I�Ȑ��������̑����͐l���̑����ƕs�ύt�Ȃ��̂ł���ƍl������B
�@
���n���̏o��
�@
���Ƀ}���T�X�͂��̂悤�Ȑl���̔���I�ȑ����ɑ��鐧�����A�ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������炷�����l�@���Ă���B���A���ɂ��Ă͖{�\�ɏ]���ĔɐB���A���������߂���]���Ȍ̂͏ꏊ��{���̕s�����玀�ł��Ă����B�l�Ԃ̏ꍇ�ɂ͓��A���̂悤�Ȗ{�\�ɂ�铮�@�Â��ɉ����āA�����ɂ��s���̐�����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂�o�Ϗɉ����Đl�Ԃ͂��܂��܂Ȏ�ނ̍����\�����Ă���ƍl����B���̂悤�ȍl���͏�ɐl�����𐧌����邪�A����ł���ɐl�����̓w�͂͌p������邽�߂ɐl���Ɛ��������̕s�ύt���܂��p������邱�ƂɂȂ�B�l�����̐����͐l���̌���ێ��ł���A�l���̒��ߕ��̒����ł͂Ȃ��B
�@
���̂悤�Ȏ�������l�����̌p�����A���������̌p���I�ȕs���������炵�A���������ďd��ȕn�����ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�l�����������߂ɘJ���҂͉ߏ苟���ƂȂ�A�܂��H���i�͉ߏ������ƂȂ邩��ł���B���̂悤�ȏŌ������邱�Ƃ�A�Ƒ���{�����Ƃ͍���ł��邽�߂ɐl�����͂����Œ���邱�ƂɂȂ�B�����J���͂ŊJ�����ƂȂǂ�i�߂��邱�ƂŁA���߂ĐH���i�̋����ʂ����X�ɑ������邱�Ƃ��\�ƂȂ�A�ŏ��̐l���Ɛ��������̋ύt������Ă����B�Љ�ł͂��̂悤�Ȑl���̌����ɏ]������������������Ă��邱�Ƃ́A���Ӑ[����������^���悤���Ȃ����Ƃ�������ƃ}���T�X�͏q�ׂĂ���B
�@
���̂悤�ȕϓ�������قnj����Ȃ��̂Ƃ��Ē��ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ̗��R�͗��j�I�m�����Љ�̏㗬�K���̓����ɓ������Ă��邱�Ƃ���������B�Љ�̑S�̑��������A�����̐��l���ɑ�������Ґ��̊����A�������x�ɂ��s�����Ȋ��K�A�Љ�̕n���w�ƕx�T�w�ɂ���������̎��S���A�J���̕ω��Ȃǂ��������ׂ��ΏۂƂ��ėł���B���̂悤�ȗ��j�͐l���̐������ǂ̂悤�ɋ@�\���Ă����̂��𖾂炩�ɂł��邪�A�����̐l�������ł͂��܂��܂ȉ�ݓI���������邽�߂ɕs�K���ɂȂ炴������Ȃ��B�@ |
���w�l���_�x2
�@
�l�Ԃ͕K�����ʁB�����鎞�Ԃ��L���ł���A���̏I���_�Ɋ�]���Ȃ����Ƃ��A�������Đl�Ԃ̐������K���ɂ�������̂��B�}���T�X�̐l�ԊςƂ����͈̂ꌾ�ł��������v�邱�Ƃ��ł���B�����A�l���@���̖��̂ŗL���ȃ}���T�X�́A�����ň��ՂȌ[�֎v�z�A�l�Ԃ̊����\���ɗ␅�𗁂т������ƂŁA�o�ώv�z�̗��j�̒��Ōǐ�Ƃł������Ă����n�ʂ��߂Ă���B
�@
�}���T�X�̔��[�֓I�ȗ��ꂪ�ۗ����Ă���̂��A���̓V�˓I�ȏ�����w�l���_�x�ł���̂͌����܂ł��Ȃ��B�}���T�X�͌X�̐l�Ԃ̏����̐�]�䂦�̍K���Ƃł������u�t���v���A�l�ޑS�̂ɓK�p�����B�ނ͐l�ނ̓����̂�����_�ɂ܂����ڂ���B�ЂƂ͐l�Ԃ̐����ɐH���̐ێ悪�K�v�ł��邱�ƁA������͒j���̐��I�ȗ~�]�����ɋ������Ƃł���B���̌�����O��ɂ���ƁA�}���T�X�͐l�Ԑ��̉��P����̖L�������������Ƃ͑z��ł��Ȃ��Ǝw�E�����B
�@
�܂����I�̗~�]�̋����́A�l����������B���̑����͓��䐔��I�ȃX�s�[�h�ł���A���E�l����10���Ƃ���A�����25�N���Ƃɔ{�����A���̔䗦��1�C2�C4�C8�A�d�d�ƂȂ邾�낤�B����ɑ��ēy�n����̔_�Y���̎��n�͎���ɒ������Ă����A���̎��n�ʂ͓�������I�ȃX�s�[�h(1�C2�C3�C4�A�d�d)�ł����������Ȃ����낤�B�����Ȃ�ƁA�l���̑��������H�Ƃ̐��Y������������A�₪�Đl����{�������̐H�Ƃ����A�l�����̂��̂̕��������Ă��܂����낤�A�ƃ}���T�X�͎w�E�����B
�@
�}���T�X�̗\���͔��ɔߊϓI�Ȃ��̂ł���A���̐l����{���邾���̐H�Ɛ��Y�̕ǂɁA�l�����˂������邽�тɁA�l�ނ́u�ϋɓI�����v���̗p���Ă����Ƃ����B����͎��S���̑����Ɍ����Ɏ������B���Ƀ}���T�X�͎Љ�̉��w�K���̏ɒ��ڂ��Ă���B�}���T�X�̂����l���́u�ϋɓI�����v�Ƃ́A���w�K���̎q���������h�{�s�ǁA���N��Ԃ̕s�ǂȂǂ̍������瑁���Ɏ��S���Ă��܂����Ƃɓ��ɒ��ڂ������̂ł���B���āu�\�h�I�����v�ɂ��ẮA�w�l���_�x�̓x�d�Ȃ�Ĕł̉ߒ��ŁA�L�q���ڍׂɂ͂Ȃ��Ă������A���̏��łł͂قƂ�nj��y����Ă��Ȃ��ɓ������B�Ȃ��}���T�X�́u�\�h�I�����v�ɂƂ��ẮA���s�ׂ̎����A��D�A������x�点�邱�ƂȂǂ�����Ă���B�����������͂����܂ł��Ώ��Ö@�ł���A�}���T�X�͐l���@�����炭��u�A���ȗ\���v����{�I�ɏC�����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@
���ă}���T�X�̐l���@���́A�����̃��[�L���O�v�A�����l����Ƃ��ɂ��ЂƂ̘_�_���N���Ă���Ƃ�����B�}���T�X�͓����̃C���O�����h�̋~�n�@�̏�����A����ɂ͕x�T�ȊK������n���K���ւ̏����ĕ��z�ɂ��A���ꂪ�n�������̂̏�Ԃ�����Ɉ���������Ɠ����ɁA����ɂ͍����S�̂̐����܂ŋ��ЂɂȂ�Ɛ������B
�@
�Ⴆ�Εn���K���ւ̐H�Ɖ������l���Ă݂�B��葽���H�Ƃ����Ƃŕn���K���̐l�����������邾�낤�B��������ƈȑO���������S������菭�Ȃ��H�Ƃ�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邾�낤�B�܂�n���̐��������P���邱�Ƃ��A���ǂ͕n�����g�͂������̂��ƍ����S�̂̐����̐��������������Ă��܂��B���̓_�́w�l���_�x�̏��ł���A�ނ̌o�ϊw�I������ł���u�H�������_�v(1800�N)�ŁA�~�n��ڎw�����H���������A�H�i�̍����i�������炷�Ƃ����c�_�ɔ��W���邱�ƂɂȂ�B
�@
�܂��}���T�X�͕x�T�Ȏ҂���n�����҂֍ĕ��z�ɂ���āA����͋ΘJ���瑼�҂ւ̈ˑ��ւ̍ĕ��z�ł�����Ƃ��w�E���Ă���B�n�����҂ɏ������ړ]���Ă��ނ�͋������ŏ���Ă��܂��A�����S�̂̒��~�Ȃ����낤�A�Ƃ����̂��}���T�X�̏������z�_�̊j�S�ł��낤�B���̕n�҂ւ̏����ĕ��z���A�ΘJ�Ȃ��A���~�����������邱�ƂŁA�o�ϐ�����}������Ƃ����c�_�͍����܂łȂ�炩�̌`�Ōp�����Ă���c�_�̂�����ł���B
�@
���̃}���T�X�́w�l���_�x�̓A�_���E�X�~�X�̌o�ϐ����_�ւ̔��_���Ӑ}���Ă������B�}���T�X�ɂ��X�~�X�͈��́u�g���b�N���_�E���v���_��������Ƃ݂Ȃ��Ă���B�܂�Љ�̕x�̑��傪�n���K���̐��������P���邾�낤�A�Ƃ������Ƃł���B���������̂悤�ȉ��P�̉\���͂Ȃ����Ƃ̓}���T�X�̐l���@���̓K�p���炷��Ύ������낤�B�H�����Y�����Ȃ�A�x�̑���́A�n���K���̐l�X�̐����K���i��Ԉ��i�ɑ���w���͂��߂Ă��܂��A�ƃ}���T�X�͏����Ă���B�܂��H�Ɖ��⏤�Ɖ��ɑ��Ă��}���T�X�͔ߊϓI�ł���B�H�Ɖ��⏤�Ɖ����邱�Ƃ��A�J�����ێ����邽�߂̊��(�}���T�X�ɂ�����͔_�Ɛ��Y�����̂��̂��낤)�͒���邩�������Ă��܂����낤�B�_�Ƃɓ������鍑�͐l���̑����������A���Ƃ�H�Ƃɓ����������͐l������ؓI�ł��邾�낤�B�������ǂ̓����̃p�^�[���ł����Ă��₪�ă}���T�X�̐l���@�����K�p����邩����A���̌��ʂ͐l�ނɁu�A�T�ȗ\���v�������̂ɂ��������Ȃ��̂ł���B
�@
�ł͖`���ɖ߂��āA���̂悤�Ȉ��̃f�B�X�g�s�A�I���E�ς̒��ŁA�}���T�X�͂ǂ�ȍK���ς���肦���̂��낤���B�}���T�X�͔ߎS�ȏ��h���ɂȂ邱�ƂŎЉ�I�ȋ�����A�������I�ȊQ�����팸���悤�Ƃ������@���萶����Ɛ����Ă�悤���B����ߎS�����Ă����̑P�ƍK���Ƃł������ׂ��Ȃ̂��낤�B�����A�}���T�X�̐l���@���͂��̂܂܂̌`�ł͈ێ��ł��Ȃ��B�܂��ނ̏����ĕ��z�_�₻�̐l�Ԋςɂ��Ă��c�_�S�o�̂܂܂��Ƃ�������B�}���T�X�͑��ɂ��w�o�ϊw�����v�ŋ��Q�̗��_��W�J���Ă���B����͍����̒�����ؘ_�̋N���Ƃ��ĕԂ茩��K�v�����邾�낤�B����ɂ��Ă͂܂��@������߂����B�@ |
���܂��������a���҃}���T�X
�@
���ߊϓI�Ȏi�Ղɂ��ď����̐����o�ϊw�҂́A���܂��̂��܂������Ă���@
�H�����i�̋����قǂ̍����́A�����̍��Ŗ\����s���ݏo���A�A�����J��[���b�p�̔�r�I�T���Ȑl�X�ł��炻�̉e����g�������Ċ�����悤�ɂȂ��Ă���B�������ŁA�O���[�o���s�ꂪ���E 70 ���l�̕�������Ƃ����M���͗h�炬�n�߂Ă���B�����I�ȕs���̎��オ�n�܂����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ꂪ���������ʂƂ��āA�g�}�X�E�}���T�X�̖��O���Ăяo���悤�ɂȂ��Ă����B�ł�����̌��������܂ɂȂ��ē��Ă͂܂�悤�ɂȂ����Ƃ�����A����͉ߋ��I�̌o���Ƃ܂�ő��e��Ȃ����̂ƂȂ�B
�@
�}���T�X�����߂Ă��̔��z�����ɂ����̂́A1789 �N�́w�l���_�x�ł̂��Ƃ������B����͐l�Ԃ̐l�������ƁA�H�Ƌ����̑����Ƃ����ߌ��I�ȓ�̋O�Ղ������ɂ��Ă����B�l���͂��̂܂܂��Ɩ����ɑ�����X���ɂ��邪�A�H�Ƌ����͗L���ȓy�n�Ƃ�������ɒ��ʂ��Ă��܂��B���ʂƂ��āA�Q���a�C�A�푈�ɂ�鍂�����S���Ƃ����u���̐���v���A�H�������\�͂Ɍ������������ɐl�X��ۂ��߂ɕK�v�ƂȂ�̂��A�Ƃ����̂�����̋c�_�������B
�@
1803 �N�̑��łł́A�}���T�X�͌��X�̌��������b�Z�[�W�������a�炰�āA�����I�Ȑߐ��̊T�O���������B���������u�\�h�I�Ȑ���v�́A���S�����o������ʂ��āA��������l�������Ȃ�����H����ǂ����߂�Ƃ�������悤�̂Ȃ��_���ɑR�ł��邩������Ȃ��B�Ӎ����Ə��q���ɂ���āA�l�������͏\���ɗ}�����Ĕ_�Ƃ��Ή��ł���悤�ɂȂ�B
�@
�}���T�X�ɂƂ��ĕs�^�Ȃ��ƂɁ\�\�����㑱����ɂƂ��Ă͂��肪�������ƂɁ\�\�}���T�X��������������̂͗��j�̓]���_�������B����̔��z�A���ɑ��ł̂��̂́A�H�Ɖ��ȑO�̎Љ�̋L�q�Ƃ��Ă͐��m�ƌ����邩���m��Ȃ��B�O�ߑ�Љ�͊m���ɁA�Ɩ����̊ԂŊ낤���o�����X���ێ����Ă����B�ł��������łɃC�M���X�Ŏn�܂��Ă����Y�Ɗv���́A�o�ϐ����̒������ʂ�����ς����������B�o�ς͐l���������}���Ɋg�債�͂��߁A���������������\�Ȍ`�Ō��コ���Ă������̂������B
�@
�H���̓}���T�X�����ꂽ�悤�ɕs������ǂ��납�A�f�Ղ̊g��ƁA�A���[���`����I�[�X�g�����A�̂悤�Ȓ�R�X�g�̔_�Ɛ��Y�������E�o�ςɉ����ɂ�āA�ނ���L�x�ɂȂ��Ă������B������Ƃ��������o�ςɊ�Â����v���d�v�Ȗ������ʂ������B���ɁA1846 �N�̍����@�p�~�́A�C�M���X�J���҂����������A���H���̉��b�ɂ������铹���J�����B
�@
�}���T�X�́A�o�ϓI�ȗ\�������邱�ƂȂ���l���\�����܂��������B�L�`�̎���ɂ��l����������������Ƃ�������̑z��͂܂������Ă����B���[���b�p����ɁA�ꍑ�A�܂��ꍑ�ƁA���������Ōo�ϔ��W�ɂƂ��Ȃ��ɉh�ɂ�āu�l���]���v���N�������B�o�����Ǝ��S���͂ǂ����������A�l���������₪�Ēx���Ȃ��Ă������B
�@
�}���T�X�ْ̈[�̐����Ăт������������̂� 1970 �N�㏉���A�Ō�ɐH�����i�������������������B���Ȃ��Ƃ������́A�l���I�Ȍx���͂���Ȃ�̍���������悤�Ɍ������B�����ɐl���������͋}���ɏ㏸�����B���W�r�㍑�̍����o�������A�c�����S���̌����ɒǂ����قlj�����̂Ɏ��Ԃ������������炾�B�ł����̂Ƃ����A�l���ߏ�ɑ���S�z�͞X�J�������B�u�̊v���v�₻�̌�̔_�ƌ����̉��P���H�����Y��啝�ɑ��₵�����炾�B
�@
���E�̐l�������́A40 �N�O�� 2�� �Ńs�[�N���}�����B���̍��ɂ��炻�ꂪ�S�z���ׂ����ł͂Ȃ������̂Ȃ�A���݂��ꂪ 1.2% �ɒቺ���Ă���ȏ�A�Ȃ�����S�z�ɂ͒l���Ȃ��B�ł��l�����̂��̂��S�z�̎�ɂ͂Ȃ�Ȃ��ɂ�����A���ɃA�W�A�Ȃǂ̋}���Ȍo�ϐ����ɔ������C�t�X�^�C���̕ω��͌��O�̃^�l���B�����l�͖L���ɂȂ�ɂ�ē��̏���ʂ������Ă����B�E�V�͐l������������̍�����K�v�Ƃ���̂ŁA��{�H���̎��v�͑����Ă����B�l�I�}���T�X�h�́A���E�����m���̐H���������� 67 ���l�̐l��(2050 �N�ɂ� 92 ���l)��{������邾�낤���ƐS�z����B
�@
�����ł��A���O�͂��܂�ɔߊϓI���B�ő� 19 ���I�̂悤�ɓ��A���ĊJ�����ׂ������n�͂Ȃ���������Ȃ��B�ł��_�Ɛ��Y�������ł��ɂȂ����ƍl����ׂ����R�͂Ȃ��B���́u�̊v���v�ɑ���傫�ȏ�Q�̈�́A��`�q�g�݊����앨�ɑ��閳�����Ȑl�X�̕s���ł���A���ꂪ���[���b�p�����łȂ��A�����A�o���Ɏg���锭�W�r�㍑�̐��Y���牟��������ł��܂��Ă���̂��B
�@
�������I�ɑ����Ă���̂͐����I���s��
�@
���肪���Ȃ��Ƃ����A���{�����������Ɉ��������Ă���B�H�Ƌ֗A���ǂ�ǂ�g�債�Ă���̂��B����������͈ꎞ�I�ɂ͂��̍��ɋ~�ς������炷��������Ȃ��B�ł����ꂪ�L�܂�ɂ�Đ��E�s��͌������Ȃ�B����������Ⴂ�Ȑ���Ƃ��ẮA�A�����J�������̃G�^�m�[�����Y�ɕ⏕�����o���āA�A�������ւ̈ˑ������炻���Ƃ��邱�Ƃ��B���v�ɑΉ���������R���𑝂₻���Ƃ������̋؈Ⴂ�Ȑ���́A���N�̃g�E�����R�V���Y�̎O���̈���z���グ�Ă��܂��Ɨ\�z����Ă���B
�@
�l�I�}���T�X�h�͂������H���s���ɂ��Ă��ꂱ�ꌾ�����͂��邾�낤�B�ł����̋��`�́A������G�l���M�[�̐�ΓI�Ȑ����Ƃ������z�Ƃ��Ă�����邱�Ƃ������B���Ƃ��u�s�[�N�I�C���v�̔��z�Ȃǂ��B1970 �N�㏉���̋����̌�ŁA�Ζ���Ђ͒lj��̖��c�������ĔߊϘ_�҂����̗����������B����́A�������i�������V�������c�T�������Ȃ���������Ƃ������R���傫���B�ł����c�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�o�ς͐V�����G�l���M�[���������Ċ��p���邱�ƂœK���ł���B
�@
�����ƐV�����}���T�X�̌��E�_�́A�n�����g���ɑR���ׂ������K�X�r�o��}����ׂ����Ƃ����c�_�Ƃ��ēo�ꂵ�Ă���B�ł�����܂���Y�f�o�ς̈ڍs�őΉ��\���B�_�ƂƓ������A����ɕK�v�Ȓ���������ɂ��Ă���̂́A���{���Y�f�ł���������Ȃ��Ƃ����������I�Ȍ��ׂ��B�]���^�̐����ɂ͐������Ă��A�l�X�̑n�ӍH�v�ɂ͐���ȂǂȂ��B�����炱���}���T�X�͓I�O���܂������Ă������A���܂Ȃ��܂������Ă���B�@ |
���}���T�X�l���_�Ɋւ���l���g���_�I���߂ւ̔ᔻ�I����
�@
�}���T�X�w�l���_�x���ł́A�`���Ŗ������Ă���悤�ɃS�h�E�B���̕����Љ�_�ւ̔ᔻ�����̖ړI�Ƃ��Ă���B���́u�l���͂˂ɐ��������̐����ɉ����Ƃǂ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ɓv�Ɩ�������Ă���B
�@
�����Ń}���T�X�͐l���ƐH�Ƃ̑����I�䗦�̍��ق��咣���A�l���E�H�Ƃ̑����䗦���ق������}���T�X�u�l�������v�ł���\�ƃ}���T�X�Ɠ�����̎��҂����͍l�����B�ނ炪�l��������l���E�H�Ƃ̑����䗦���قƂ��đ������̂ɂ͖������Ȃ������B�Ȃ��Ȃ�A�}���T�X�́u�l��(������)�Ɠy�n�̐��Y(��)�Ƃ́A��̗͂̂��̎��R�I�s�����v�ɔ�ׂ�A���̑��̘_�_�́u���ׂȕ����I�Ȗ��ł���v�Ƃ���������ł���B
�@
�}���T�X�͐l���Ɋւ���u������v�u�O����v���o�����B�ȉ��A���łɎ����ꂽ�u�����v����݂Ă݂悤�B�u���A�H�Ƃ͐l�Ԃ̐����ɕK�v�ł��邱�Ɓv�u���A�����Ԃ̏�O�͕K�R�ł���A�قڌ��݂̏�Ԃ̂܂܂ł��葱����Ǝv���邱�Ɓv�}���T�X�͏�L���������u�O����v�������o�����B�ȉ��͘Z�ŁB
�@
1�u�l���͕K�����������ɂ���Đ��������v
�@
2�u�l���́A���邫��߂ċ��͂������ȖW���ɂ���đj�~����Ȃ���ΐ�������������Ƃ���ł͂˂ɑ�������v
�@
3�u�����̖W���A����їD���Ȑl�������̗͂�}�����A���̌��ʂ������Ɠ��������ɕۂW���́A���ׂē����I�}���A�߈�����ы��R�ɕ������邱�Ƃ��ł���v(���m�̂悤�� �u�����I�}���v�Ɋւ��Ă͑�2�ł�����M���ꂽ)�B
�@
�}���T�X�́u�l�����B�����v�Ɓu���������ɂ���ċK�������l���v(�K������)�͋ύt������ƍl�����B�u�K�������v�͓�̑���ł���B
�@
�����}���T�X���l������_����ɂ�����A�u�K�������v�̔����ɊS���Ă������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��l���ɑ���u�W���v�_�Ɍ��т��Ă���B���ہA�}���T�X�́u�K�v�Ƃ����ً}�́A�L���s���n�������R�̖@����(���A���̐�)�����̌��x���ɗ}������B�A���̗ނ������̗ނ����̈̑�Ȑ����@���̑O�ňޏk����(���A���̐�) �͕M�ҁv�B)�Əq�ׂĂ���B
�@
�l�Ԃ��A���̐����@�����瓦��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��\�Ƃ��Ă���B�]���āA�삪�����悤�ɁA�}���T�X�u�K�������v�́u�l���͐H�Ƃ̐����Ɉ����߂����v�����ł���Ƃ���̂͑Ó��ł���Ƃ����悤�B���̋�̓I�u��p�v�Ƃ��ē������̂Ƃ��āA���S���Ɋւ���ϋɓI�}���Ɨ\�h�I�}�����}���T�X�͋������B
�@
�}���T�X�ɂ��u���B�����v�A�u�K�������v�̑��ݍ�p�������邱�ƂŁu�K���ƔߎS�Ƃ����݂Ɍ�����ЂƂ̔g���^���v�����܂�邱�ƂɂȂ�B
�@
���ꂪ�A�쎁�̘_����Ƃ���́A�}���T�X�l���g���_�Ə̂������̂ł���B
�@
�o�ϓI�ȖL�����E�n���Ɛl���̑����E�����W�Ƃ��Đ�����^���A�l���́u���B�v�A�u�K���v�Ƃ������̌��ݍ�p����l���͕s�f�̐U���̒��Ɏ��Ȃ��������̂ƂȂ炴����A�����E���ށA�i�]�E�t�]�̔g��������}���T�X�͍l�����B
�@
��́A���̔g���^�����u�l�������̗��_�v�ƌĂсA�}���T�X�l���_�̖{�̂ł���Ƃ����B
�@
�����āu���ԓI�E���W�j�I�Ȑl�������̎������v���}���T�X���_�̒��_�ł���Ƒ������B
�@
��̃}���T�X�l���������߂ɁA�X�����͋^�����������ł���B�}���T�X�̏ꍇ�A�u���B�����v�Ƃ������̗p�@�͎��ɑ��l�ł���A�K��������̌����Ӗ��ł́u���B�����v�ƃ}���T�X�̂��ꂪ��v���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��X���̓�ᔻ�̘_���ł������B�܂��A�������͓�����̂悤�ɔᔻ����B
�@
���Ȃ킿�A��́u�g���^���v���u���B�����v�Ɓu�K�������v�́u���ݍ�p�̌��ʂƂ��Ă����l�����Ȃ������v�ƁB�l�������ƌo�ϓI�l�@�����т���_�@�������Ƃ����Ɣᔻ����B�X��������̔ᔻ�͑Ó��ł���Ɩ{�e�����ӂ���B
�@
��X�́A�������������������ƂɁA�}���T�X�l�������E�l�����_�͖{���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł����������Č�������K�v������B�����ŁA���̐l�������������o�����ƂɂȂ����}���T�X�̐l�����肪�ǂ̗l�Ȃ��̂ł������̂���m��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�Ƃ��낪�A�}���T�X�u�l���̌����v�Ƃ͉��ł��邩�\�Ƃ����₢�ɂ��āA�͂�����ƒ�܂��������͖����ɂȂ��悤�ł���B�Ƃ����̂��}���T�X���l�������Ƃ������t��l�X�ȈӖ��ŗp��������ł���B�]���ă}���T�X�̎v�z�̊j�ł���u�l������ principle of population�v�����������Ă��邩�������Ă͗l�X�ȉ��߂�����Ă����B�����A�s�v�c�Ȃ��Ƃ�1798 �N�w�l�������Ɋւ����_ An essay on the principle of population�x���o�ł��ꂽ�����̃C�M���X�ł́A�}���T�X�Ɍ����Đ������̔ᔻ��������͂������u�l�������v���ߎ��̂�����c�_�͂قƂ�ǐ����Ă��Ȃ��B���ہA�}���T�X�w�l���_�x���ł̖ړI�̂ЂƂ̓S�h�E�B���ᔻ�ɂ������ɂ��ւ�炸�S�h�E�B��[1801,71-3]�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�u�킪���ҁk�}���T�X�̂��Ɓl�̘J��̘_������l���ƐH�Ƃ̔䗦�͘_���̗]�n�̂Ȃ����̂ł���A�܂��o�ϊw�Ƃ����Ȋw�ɂƂ��ĉ��l������n�����Ȃ����̂Ǝ��͍l����v
�@
�S�h�E�B���̓}���T�X�̎������l���̌�����l���ƐH�Ƃ̔䗦�̍��قƑ��������Ƃɂ��Ĉ٘_����Ă͂��Ȃ��B�S�h�E�B���u�l�������v�ᔻ�́A�Ⴆ�ΐl�������̗���}���T�X���A�����J�̎���ɋ��߂��̂ɑ��A�S�h�E�B���̓X�E�F�[�f���̎����p���Ĕᔻ�������Ƃł��낤�B
�@
�l���͐�����i����������������X��������\�Ƃ����}���T�X�̌����ɑ��āA�V�[�j�A�́A����͓��ʂȎ���̂��Ƃł����邱�Ƃł���A�}���T�X�l�������͈�ʓI����ɂ͂Ȃ肦�Ȃ��Ɣᔻ�����B�V�[�j�A�̌����́A�H�Ƃ͐l������������������X��������\�Ƃ����_�ɂ�����3�B�V�[�j�A�̃}���T�X�ᔻ�́A�}���T�X�u�l�������v���̂��̂ƁA�l���������߂ɓ��ݍ��_�ő��̃}���T�X�ᔻ�҂Ƃ͈�����悷���̂ł��������A�}���T�X�u�l�������v���̂�Nj����Ă͂��Ȃ��B
�@
�}���T�X�Ɛ������̘_�����J��Ԃ������J�[�h�E�ɂ����Ă̓}���T�X�u�l�������v��ϋɓI�Ɏ���̌o�ϊw�I�̌n�Ɏ����ꂽ�B�}���T�X�l�������́A������̐l�X�ɂ����Ă͂قڋ��ʂ��l���ƐH�Ƃ̔䗦�̍��قƂ��ĔF������Ă����B���������펯�I�����Ƃ�������}���T�X�u�l�������v���߂Ɉق��������̂��A�엺�O�Y�ł������B�{�ł���������悤�ɓ�͓Ǝ��̃}���T�X�u�l�������v���߂���A���{�l���_�j�̑b���������B
�@
�ߔN�A�����͓엺�O�Y�Ƌg�c�G�v�̃}���T�X�w�l���_�x���߂�Δ䂵�ڍׂȌ������s���Ă���B���̏�Ń}���T�X�w�l���_�x���߂Ƃ��ē엝�_�̕s�����𒆐��͎w�E���Ă���B
�@
�M�҂͈ȑO�A�w�l���_�x�Ɓw�o�ϊw�����x�ɂ�����u���l�_�v�̈�̐ړ_�Ɋւ��Ď�̍l�@���s�����B�����ŕM�҂̓}���T�X�̐l���w�I�l�@�ƌo�ϊw�I�l�@�͕��f����������̂ł͂Ȃ��}���T�X�̌n�Ƃ��ē���I�ɑ�����ׂ��ł���ƍl���Ă���B�]���ă}���T�X�o�ϑ̌n�𗝉�����ɓ�����A�}���T�X�l���������ǂ̂悤�Ɏ~�߁E�ǂ̂悤�ɒ莮������ׂ����\�͔��ɏd�v�ȉۑ�ł���B
�@
�w�l���_�x�Ɓw�o�ϊw�����x�̐ړ_��_�������̂ł́A�Ⴆ�ΐl�������v�A�H�Ɓ������Ƃ����}��������B�����A�l�������Ɋւ��ď\���ȑk�y���Ȃ���Ă��Ȃ��B
�@
�{�̑_���̓}���T�X�u�l�������v�Č��������邱�Ƃɂ���B
�@
�엝�_�E�����_��ʂ��čl�@���邱�Ƃɂ���B��͐l��������l���g���_�֏������A�l���������l���g���_�Ƃ����B�����A�M�҂͐l���������l���g���_�ƍl���Ă���B
�@
���̓_�́A�����_�ɓ��ӂ��Ă���B���Ȃ킿�A�l�������͐l���g���_�̂��Ƃ������Ă͂��Ȃ��B
�@
�������Ȃ���A�����_�Ɍ�����l���g���_����}���T�X�u�H�Ɛ�s�_�v�����ݎ�錩���ɂ͓��ӂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�u�H�Ɛ�s�_�v�͐l������������̉��߂ł���A�l���g���_�ł͂ނ���l����s�_��������Ă���Ɩ{�͍l���Ă���B
�@
�}���T�X���H�Ɛ�s�_�E�l����s�_�̂ǂ�����̂��Ă������\�́w�l���_�x�Ɓw�o�ϊw�����x�����т����ŏd�v�Ȏ��_�ł���B�����A�����_�ł́A�}���T�X�H�Ɛ�s�_����}���T�X�̗L�����v��s���������B
�@
�����́A�}���T�X�H�Ɛ�s�_������z�����_�[�ɂ��A�}���T�X�l������Ƃ͐H�Ƒ��Y�݂̂��l���K�͑�����ۏႵ�A�H�Ƃ��Z�p�I�ł����Ă������ɑ��傷��Ȃ�A�l���ɂ��܂����E���Ȃ��\�Ƃ��Ă���B
�@
�������A����́A���ɐl�������̌�ǂł���A���ɁA�l���g���_�Ƃ̋�ʂ����Ă��Ȃ��Ƃ����_�ŕ]���ł��Ȃ��B
�@
�{�ł́A�l�����������W�X�e�B�b�N�E���f���Ƃ��đ����Ă���B�l�������͐H�Ɛ�s�_�ł���A�l���g���_�͐l����s�_�Ƃ��Ĉʒu�Â��Ă���B�܂��A���������Ȃ���w�l���_�x�ɂ�����}���T�X�̈Ӑ}�ƁA�o�ϊw�I�l�@�ւ̐ړ_�𐳊m�ɋ��ݎ�邱�Ƃ��ł��Ȃ����낤�B
�@
�����������c�_�̐����Ɖ𖾂̂��߁A�{�ł͐l���g���_�ɂ�������_�A�H�Ɛ�s�_�̖��_�ƃ}���T�X�z�胂�f���A�l�������Ɛl���g���_�̑���A�����Đl�������Ɛl���g���_�̐ړ_��_���A�ŏI�I�ɐl�������E�l���g���_�ƌo�ϊw�I�l�@�̐ړ_��_����B�@ |
���g�}�X�E���o�[�g�E�}���T�X
�@
(Thomas Robert Malthus�A1766-1834)�@�C�M���X�T���[�B�E�b�g���o�g�̌o�ϊw�ҁB�ÓT�h�o�ϊw���\����o�ϊw�҂ŁA�ߏ�������A�L�����v�����������l���Ƃ��Ēm����B
�@
���ٌ͕�m�ŐA���w�҂̃_�j�G���E�}���T�X�ŁA�[�֎�`�҂ł���B�ނ̓W�������W���b�N�E���\�[�Ɛe��������A�}���T�X�̐��N1766�N�Ɏ���Ƀ��\�[�����҂��Ă���B���̑�2�q�Ƃ��Đ��܂�A�ƒ닳�t����w�����A�܂�����������ߍׂ��ȋ�������B18�ŃP���u���b�W��w�W�[�U�X�E�J���b�W�ɓ��w���A���w�ƕ��w���w�сA1788�N�ɑ��Ƃ�����A�L���X�g��������ڎw���ĕw�ɗ�B���̊Ԃ�1796�N�Ɂw��@�x�����B�o�ł͂��Ȃ��������A���ꂪ�ŏ��̒����ƂȂ����B 1793�N���ʌ������ƂȂ�A1805�N�ɂ̓w�C���x���[���J���b�W�̋����ƂȂ����B
�@
1798�N�Ɏ咘�w�l���_�x���A���̒��Łu�����I�ɑ�������l���ƎZ�p�����I�ɑ�������H�Ƃ̍��ɂ��l���ߏ�A���Ȃ킿�n������������B����͕K�R�ł���A�Љ�x�̉��ǂł͉�����꓾�Ȃ��v�Ƃ��錩��(�u�}���T�X��㩁v)������B�܂�A�l�ނ̍K����Nj�������@���Ă����̂ł���B
�@
�}���T�X�̓h�C�c�A�X�E�F�[�f���A�t�B�������h�A���V�A�ɑ؍݂��A���̍��̐l�����ϑ����A�����̕⋭�ɗ͂𒍂����B�����āA���Ȋw�I�ȁw�l���_�x��2�ł�1803�N�ɏo�����B���̔łɂ͐����o�ςɊւ���d�v�_�����lj�����Ă���B���̂悤�ȃ}���T�X�̍l�������掂�����̂������������A����������傫�Ȃ��̂ɂȂ�A�Y�������ōŕn���w���~�����Ƃ���l�����u�}���T�X��`�v�Ƃ�������悤�ɂȂ����B�o�ϊw�҂Ƃ��ĔF�m�����悤�ɂȂ�A1803�N�ɂ͐V�����ݗ����ꂽ���C���h��Еt���w�Z�̐����o�ϊw�����̐E�ɕt���A�����̈琬�ɓ������Ă���B
�@
�}���T�X�́A���̕t���w�Z�̋����Ƃ��ďI�����߁A�v�����̂�1834�N12��29���ł���B���̊ԁA�w�l���_�x�����肷��Ȃǎ��M�����������ɍs�����B�l���v�w�I�ɍl�@�������ʁA�u�\�h�I�}���v�Ɓu�}���I�}���v�̓�̐��䑕�u�̍l�����ɓ��������A���̎v�z�͌�̃`���[���Y�E�_�[�E�B���̐i���_�����͂Ɏx����v�z�ƂȂ����B���Ɏ��R�����Ɋւ���l�@�ɏ��Ȃ��炸�e����^���Ă���B���Ȃ킿�A�l�ނ͉b�q������A���݂ǂ�̐���������������悤�Ƃ��邪�A���A���̐��E�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B����ă}���T�X�̐l���_�̂Ƃ���̎��R���������A���̐��E�ɂ͋N����B���̂��߁A���������ɂ����ėL���Ȍ̍������������̂������c��A�q���͗L���ȕψق��p�����ƃ_�[�E�B���͌��_�����̂ł���B
�@
�}���T�X�̎v�z�́A�o�ϊw�̂����ł́A�l�ԗ����̌[�ւɂ�闝�z�Љ�̎������咣����E�B���A���E�S�h�E�B����R���h���Z�ւ̔ᔻ�Ƃ��ʒu�Â�����B1820�N�ɂ̓f���B�b�h�E���J�[�h�̌o�ϐ��ɔ��_�����w�o�ϊw�����x(���ю��O�Y�A��g���ɏ㉺)�����B
�@
���ɂ�1810�N�Ɂw�s�������Ɋւ���_�l�x���A1814�N�ɂ́w�����@�̌��ʂɂ��Ă̍l�@�x�A1815�N�Ɂw�n��̐����Ƒ����ɂ��Ă̒����x�Ȃǂ��Ă���B�@�@
�@ |
 �@ �@
��19���I�`�@����ւ̉˂��� / ���ΐ����_�̊m���� |
   �@
�@
|
19���I�́A�Y�Ɗv���̐i�W�ƁA�s���Љ�̐����ɂ���ă��[���b�p�����̑̐����傫���ς��������ł���B�Y�Ɗv���́A�Y�Ƃ̋Z�p�I��b����ς����A����͑�ʐ��Y�̎���ւƓ˓������B�܂����{��`�I�A���R��`�I�̐������������邱�ƂɂȂ�A�����ɁA�J���^���ƎЉ��`�v�z���������������B���Ђ̏o�ł���ʐ��Y�̎���ƂȂ�A�o�ŕ����̔��W�͏��̑����������炵���B����ɂ��Ȋw�Z�p�̒m���͂Ђ낭���y���A�����̐l�B�̊S�ƍD��S�������N�������Ƃɂ���āA�܂��܂��i���̓x������[�߂Ă������B���̂悤�ɂ���19���I�̌㔼�𒆐S�Ƃ����Ȋw�Z�p�́A�ϖe���Ȃ�������̐i���̖{����ς��邱�ƂȂ��A20���I�Ɏp����Ă������B�@�@
�@ |
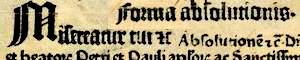 �@ �@
�����J�[�h�u�o�ϊw�y�щېł̌����v���� 1817�N |
   �@
�@
|
Ricardo, David.(1772-1823)
�@
On the Principles of Political Economy, and Taxation.
�@
���J�[�h�́A�C�M���X�̌o�ϊw�ҁB���_���n�̏،�����Ǝ҂̎q�Ƃ��Đ��܂�A���Ƃɂ���č����Ȃ����B�A�_���E�X�~�X�̒����ɐڂ��Čo�ϊw�ւ̊S�������A���ƊE�������Čo�ϊw�̑̌n���ɓw�߂��B�o�ϊw�̉ۑ�����x�̐����ƌ������̒T���ɂ���Ƃ������́A�n��E�����E�����̕��z���K�肷��@�����߂鎖�ł���Ƃ��A���̂��߂ɌÓT�h�̉��l�_�������������B�X�~�X�ɂ���đn�݂��ꂽ�ÓT�h�o�ϊw�ɂ�����ނ̒n�ʂ͋ɂ߂đ傫���B�{���͒P�Ƀ��J�[�h�̎咘�ł��邾���łȂ��ÓT�h�o�ϊw�̊������L�O����������Ƃ��ĕs���̖����ƂȂ��Ă���B�@ |
���o�ϊw����щېł̌����@
(On the Principles of Political Economy, and Taxation)�@1817�N�ɔ��\�����C�M���X�̌o�ϊw�҃f�C���B�b�h�E���J�[�h�ɂ�錤���ł���B1772�N�ɐ��܂ꂽ���J�[�h�̓C�M���X�̌o�ϊw�҃A�_���E�X�~�X�́w���x�_�x�̌����܂��Ȃ�����A�i�|���I���푈�ɂ�����嗤�����߂ň����N�����ꂽ�C�M���X�̍������i�̍��������ɑ�\���������Ƃ��āA1815�N�ɋc��͒n�����邽�߂ɍ������i���ێ����鍒���������肵���B���J�[�h�͂��̌o�Ϗɂ����č������i��ی삵�Ă��܂��ƕ������{�̒~�ς������炵�A���{�ƁA�n��A�J���҂̏������z�ɖ�肪������Ƙ_���āA������̃C�M���X�̌o�ϊw�҃g�}�X�E���o�[�g�E�}���T�X�Ƙ_����W�J���Ă����B
�@
���̒���ł͉��l�A�n��A�z�R�n��A���R���i�A�����A�����A�O���f�Ղ̌o�ϊw�I�ȓ����𖾂炩�ɂ�����ŁA���{�̉ېł��ǂ̂悤�ȉe����^���邩��_���Ă���B����܂ł̌o�ϊw�̗��j�ɂ����ďd����`�͖f�Ղ��瓾����x�����l�ƌ��Ȃ��Ă������A�X�~�X�͎g�p���l�̊T�O��p���Ėf�Վ��x�ł͂Ȃ������̗]�����A�o���A���O�̊���A�����邱�Ƃŕx�傳���邱�Ƃ��\���Ɣ��_�����B���J�[�h�͂��̎g�p���l�̊T�O����ʓI�łȂ����߂Ɍ������l�̊T�O����Ă���B�������l�Ƃ͂��̕��i�̉��l�������������K���牿�l�f������̂ł���A���̒l�͂��̕��i�Y�����p�Ɠ������ƃ��J�[�h�͍l�����B���������ă��J�[�h�͓����J�����������l�ݏo���Ƃ��������J�����l�����m�������B
�@
�����ɂ��Ă̓}���T�X���w�l���_�x�Ř_�����悤�ɁA�����������̂��߂ɕK�v�Ȕ�p�߂���Ɛl���̒��߂��������錩�����Q�Ƃ��A���������Ē����͐����ێ��ɏ��v�̍����w���ł�����x�Ɉێ������Ƃ����������������_�����B����ɒn��Ɋւ��Ă͓y�n���Y���̒n��Ԃ̍��z�͎x������Ƃ������z�n��_��_���A����n��̒n��͑��̒n��Ƃ̊W���獶�E�����ƍl�����B�Ⴆ�Ύ��{�Ƃ�10�̗��v��������y�n������ɂ������炸�A8�̗��v���������Ȃ��y�n���g���A�n��ɒn����x�����ꍇ���z�肷��B���̏ɂ����Ď��{�Ƃ͒n��͗��v�̂���1������n��Ƃ��Ďx�������Ƃ��\�ł���B�Ȃ��Ȃ�A���{�Ƃ͓y�n���ړ����邱�Ƃɂ����10�|1��9�̗��v�邽�߂ɏ]����8�̗��v���������̗��v���m�ۂ��邱�Ƃ��\�ł��邽�߂ł���B�����Ń��J�[�h���w�E���邱�Ƃ͎��{��~�ς��Đ��Y���̍����y�n�����łȂ��Ⴂ�y�n����Ă��܂��ƁA�n�オ���債�ė��������ቺ���Ă��܂����Ԃ��N����B���������āA���J�[�h�͈����ȍ��������O����A�����A�n���D�����Ȃ��o�ϐ�����咣�����B�@ |
���f���B�b�h�E���J�[�h
�@
(David Ricardo�A1772-1823)�@���R�f�Ղ�i�삷�闝�_���������C�M���X�̌o�ϊw�ҁB�e������r�D�ʂɗ��Y�i���d�_�I�ɗA�o���鎖�Ōo�ό����͍��܂�A�Ƃ���u��r���Y����v���咣�����B�J�����l���̗���ɗ������B�o�ϊw�����f��������A�v���[�`�����߂ĂƂ������Ƃő̌n�����邱�Ƃɍv�����A�ÓT�h�o�ϊw�̌o�ϊw�҂̒��ōł��e���͂̂�������l�ł���A�o�ϊw�̂Ȃ��ł̓A�_���E�X�~�X�ƕ���ŕ]�����B�ނ͎��ƉƂƂ��Ă��������A�����̍���z�����B
�@
���J�[�h��17�l�Z���3�ԖڂƂ��ă����h���Ő��܂ꂽ�B�ނ̉Ƃ̓X�y�C���n����у|���g�K���n�̃��_���l�ŁA�ނ����܂��ق�̏����O�ɁA�I�����_����p���ֈڏZ���ė����B14�̂Ƃ��A���J�[�h�̓����h���،�������ŕ��e�G�C�u���n���E���J�[�h�̎d���ɉ�������B21�̂Ƃ��A���J�[�h�͉Ƒ��̐����h���_�����̐M�����₵�A�N�G�[�J�[���k�̃v���V���E�A���E�E�B���L���\���Ƌ삯��������B����ɂ���ĕ��e���犨������邱�ƂɂȂ�A���犔�������l�Ƃ��ēƗ����邱�ƂɂȂ����B���̌ナ�J�[�h�̓��j�e���A���h�̋��k�ƂȂ��Ă���B
�@
���J�[�h�̏،�������ł̐����͔ނ�T���ɂ��A������42�ƂȂ���1814�N�Ɏd�������ށB�O���X�^�[�B�̃M���g�R���E�p�[�N(Gatcombe Park)�ɓ@����w�����A���U�̏Z���Ƃ����B1819�N�ɂ̓A�C�������h�̓s�s�I����ł���|�[�^�[�����O�g�����珎���@(���@)�ɏo�n�A���I���đ�c�m�Ƃ��Ď��R�f�Ղ��咣���A�܂��A�����@�̔p�~���咣�����B1821�N�ɂ̓g�[�}�X�E�g�D�b�N��W�F�[���Y�E�~���A�}���T�X��x���T���Ȃǒ����Ȍo�ϊw�҂ƂƂ��ɁA�����o�σN���u(Political Economy Club)�̐ݗ��ɐs�͂����B
�@
���J�[�h�́A�W�F�[���Y�E�~���̐e�F�ł���A�~���͔ނɐ����ւ̑�u��o�ϊw�̒��q�����߂��B���̒����ȗF�l�̒��Ƀg�}�X�E���o�[�g�E�}���T�X��W�F���~�E�x���T��������B
�@
��
�@
���J�[�h�́A1799�N�ɏo�ł��ꂽ�A�_���E�X�~�X�́w���x�_�x��ǂ݁A�o�ϊw�ɋ��������悤�ɂȂ����B���̏����O��1797�N�ɃC���O�����h��s�����{�ʐ����~���s�������̑�������C���t���[�V�������������邱�ƂɂȂ������A����ɂ���1810�N�Ƀ��J�[�h�́w�n���̉��i�����ɂ��Ą��������\���̏ؖ��x(The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes)�Ƃ������_�\�A�ݕ����ʐ��ɗ����ċ��{�ʐ��ւ̕��A���咣�����B
�@
���J�[�h�œ��ɗL���Ȃ̂��A�����@���߂���}���T�X�Ƃ̘_�����琶�܂ꂽ���R�f�Ղ̎咣�ƒn��_�ł���A���R�f�Ղɂ�闘���~�ς̑���ˍ��x�̑��i�ƘJ�����l���ɋ��������n�����ɂ�錋�ʂƂ��Ă̒n��̌`�����w�o�ϊw����щېł̌����x�Ŏ咣�����B�����A�_������_�����������}���T�X�̎咣�ɂ��Ă��A�ނ��w�l���_�x�Ō��y�����l���ɑ��錩���ɂ��Ă͓��ӂ��A�w�o�ϊw����щېł̌����x�̋c�_�őO��Ƃ��Ă���B�@�@
�@ |
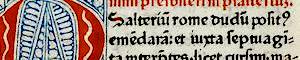 �@ �@
���V���[�y���n�E�A�u�ӎu�ƕ\�ۂƂ��Ă̐��E�v���� 1819�N |
   �@
�@
|
Schopenhauer, Arthur(1788-1860)
�@
Die Welt als Wille und Vorstellung.
�@
�V���[�y���n�E�A�́A�h�C�c�̓N�w�ҁB�ނ̓N�w�̓J���g�̔F���_�ɏo�����A�t�B�q�e��w�[�Q���̊ϔO�_�I�N�w�҂��U�����Ă͂��邪�A���̍��{�I�v�z��̌n�̍\���́A�������h�C�c�ϔO�_�ɑ�����B�{���́A�V���[�y���n�E�A��30�̎���4�N�̍Ό��������Ċ��������I���̑咘�ł���B���̌�̔ނ̒��q�̈�́A�{���̒P�Ȃ钍���ɉ߂��Ȃ��ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B�������o�œ����́A���Ԃ̒��ڂ�S���Ђ����A�V���[�y���n�E�A�����߂Đ��]���̂́A�{���ɂ���Ăł͂Ȃ��A����Ζ{���̒����Ƃ���1851�N�Ɋ��s�����N�w���_���W�̌�ł���B�@ |
���ӎu�ƕ\�ۂƂ��Ă̐��E�@
(Die Welt als Wille und Vorstellung)�@1819�N�Ɍ������ꂽ�h�C�c�̓N�w�҃A���g�D���E�V���[�y���n�E�A�[�̒����B
�@
����ꕔ�u�\�ۂƂ��Ă̐��E�̑��l�@�v
�@
�V���[�y���n�E�A�[�́A���E�͂킽���̕\�ۂł���Ƃ����B���̂��Ƃ́A�����Ȃ�q�ςł����Ă���ςɂ�鐧����Ă��邱�Ƃ������Ă���B
�@
�V���[�y���n�E�A�[���{���̏��_�Ƃ݂Ȃ��Ă��锎�m�_���u�������̎l�̍��ɂ��āv�ɂ����Ă͈ȉ���4�ނɕ�������Ă���B
�@
1. ��V�I�Ȏ��ԋ�ԁA�Ȃ����́u���� (essendi) �̍���(�[�����R��)�v
�@
2. �����ƌ��ʂ̖@���A���邢�́u���� (fiendi) �̍����v
�@
3. �T�O�_���I���f�A�Ȃ����́u�F�� (cognoscendi) �̍����v
�@
4. �s�ׂ̓��@�Â��̖@���A�Ȃ����́u�s�� (agendi) �̍����v
�@
����u�ӎu�Ƃ��Ă̐��E�̑��l�@�v
�@
���E�́A��ςɂ���Đ��ꂽ�q�ςƂ��Ă͂킽���̕\�ۂł���B�������������łȂ��A�V���[�y���n�E�A�[�́A���E�͂킽���̈ӎu�ł���Ƃ������B����ꎩ�g�́A�\�ۂɂ����Ă͐g�̂̓���Ƃ��Ēm���Ă��邪�A���̂��̂����Ȉӎ��ɂ����Ă͐�����Ƃ���ӎu (Wille zum Leben) �Ƃ��Ēm����B����ΐg�͕̂\�ۂɂ����ĕ\�����ꂽ�Ƃ���̈ӎu�ł���B�����œƉ�_�������ɂ́A���Ȃ���ސ� (analogie) ���āA���E�̑��̖{�����ӎu�Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł���Ƃ��āA�u������\�ہA���Ȃ킿������q�ς͌��ۂł���B�������ЂƂ�ӎu�݂͕̂����̂ł���v�ƃV���[�y���n�E�A�[�͐����B�������Ĕc�����ꂽ�ӎu�͖Ӗڂł����āA�ŏI�̖ڕW��L���Ă͂��炸�A���̓w�͂ɂ͊����͂Ȃ����̂Ƃ����B���̂悤�Ȉӎu�ɂ����ẮA��Q���������ē���ꂽ�����͈ꎞ�I�ł����āA���������ׂ͑ދ��ɂ����Ȃ��̂ł���A�����܂ł��ϋɓI�Ȃ̂͌��R�ł���Ƃ�����B
�@
����O���u�\�ۂƂ��Ă̐��E�̑��l�@�v
�@
�V���[�y���n�E�A�[�́A�C�f�A (Idee) �ɂ��āA�\�ۂɂ����Ĕ͌^�Ƃ��ĕ\�����ꂽ�ӎu�ł���ƈʒu�Â��Ă���B�C�f�A�͖͕�̑ΏۂƂ��ē�����Ăъo�܂��������͂�ނ��̂ł��邱�Ƃ���A�T�O�͎���ł���̂ɑ��ăC�f�A�͐����Ă���Ƃ�����B���̃C�f�A�͒i�K�I�ɕ\���������̂ł���A����ɂ�����̂́A���@�E�ł͎��R�́A�L�@�E�ł͓��A���̎푰�A�����I�ɂ͐l�Ԃ̌��ł���Ƃ�����B���݂����߂铬���ɂ����Ă͏��������C�f�A�́A���̐苒�����������ʂ̃C�f�A�ɒD�悳���܂ł́A�Ȏ��g���̂Ƃ��ĕ\��������̂Ƃ����B�����ł͕͌̂ϑJ������̂ł��邪�A�C�f�A�͂����܂ł��s�ςł���Ƃ����B�������x�z���Ă��関�����Ȍ����̐��E�ɑ��ẮA���������C�f�A�̐��E�ɂ͒��a������B�����ŃC�f�A�̐��E�ɂ����Č|�p�ɒ��������l�́A�ӎu�Ȃ��A��ɂȂ���т����Ȃ��Ƃ��ꎞ�I�ɂ͓���ł��낤�Ƃ�����B
�@
����l���u�ӎu�Ƃ��Ă̐��E�̑��l�@�v
�@
�����悤�Ƃ���ӎu�́A���̂�����R�ɍm�肵����A���邢�͎��R�ɔے肷��ƌ�����B��O���܂łɍl�@����Ă����悤�ȁA�ӎu���m�肳�ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���̐��E�Łu����v���̂�������B����ɑ��A�ӎu���ے肳�ꂽ�ꍇ�ɂ�����A���̐��E�Łu�Ȃ��v���̂ɂ��ẮA�ŏI�I�ɂ͓N�w�҂͒��ق��鑼�Ȃ����̂Ƃ����Ă���B
�@
���ۓI�m���͊i����^���邱�Ƃɂ���āA���̐l�Ԃ̍s�ׂ������т�������̂ł͂����Ă��A�����т������l�����݂�����̂ł���A�����܂ł��ӎu�̓]���𐬂�������̂́A�u���͂���Ȃ�v�Ƃ������o�I�Ȓm�݂̂ł���Ƃ�����B���̒m�ɒB���āA�}�[���[�̃��F�[����ؒf���āA�����̋��(�̉��̌���)���̂Ă��҂́A���� (Mitleid) �Ȃ�������(Mitleid)�̒i�K�ɒB����B���̂Ƃ����R�Ȃ���(������)�Ƃ��Ă̈ӎu�͎����I�ɍĐ����̂ł���A�V���[�y���n�E�A�[�̐��҂́A���ȐS�E�푰�ɐB�̔ے�ɓO���A���n�E�����E�e�H�ɊÂA�̂̎��ƂƂ��ɉ�E����Ƃ���Ă���B�@ |
���A���g�D���E�V���[�y���n�E�A�[
�@
( Arthur Schopenhauer�A�V���[�y���n�E�G���E�V���E�y���n�E�G���Ƃ� 1788-1860 )�@�h�C�c�̓N�w�ҁA�咘�́w�ӎu�ƕ\�ۂƂ��Ă̐��E�x(Die Welt als Wille und Vorstellung 1819�N)�B�������_���̂��̂Ƃ�����v�z�ƁA�C���h�N�w�̐����𖾝��Ɍ��s�������v�z�Ƃł���A���̓N�w�͑����̓N�w�ҁA�|�p�ƁA��Ƃɏd�v�ȉe����^���A���̓N�w�A������`�̐��ƌ��邱�Ƃ��ł���B
�@
1788�N�A�x�T�ȏ��l�̕��̂��ƃ_���c�B�q�ɐ��܂��B��(���n���i�E�V���[�y���n�E�A�[)�͏�����ƂŁA���Ȍ����I�Ȑ��i�ł������B���ɔ����ėc�������烈�[���b�p�e���𗷍s����B17�̂Ƃ��A���������B���̈�u�ɏ]���ď��l�̌��K�����n�߂����A�w��ւ̏�M���̂Ă��ꂸ1809�N�A�Q�b�e�B���Q����w��w���ɐi�w����B�S�b�g���[�v�E�G�����X�g�E�V�����c�F�̂��ƂœN�w���w�сA�̂��N�w���֓]������B�V�����c�F���J���g�ƃv���g����ǂނ悤�ɂ�����B�]����A�x��������w�Ɉڂ�A�t�B�q�e�̍u�`����B
�@
1819�N�A�w�ӎu�ƕ\�ۂƂ��Ă̐��E�x�������A�x��������w�u�t�̒n�ʂ邪�A�����x��������w�������ł������w�[�Q���̐l�C�ɍR���邱�Ƃ��ł����A�t�����N�t���g�ɉB���B���n�ŗ]�����߂����B
�@
�{�l�́u���ɁA�G�b�N�n���g�A�����Ă��̎��́A�{���I�ɂ͓������Ƃ������Ă���v�Əq�ׂĂ���B
�@
�V���[�y���n�E�A�[�͌|�p�_�E���E�_���L���ł��邪�A�ނ��딎�w�ŁA�@���w���玩�R�w�܂ł�����W��������ԗ����������N�w�҂Ƃ��Ă̑��ʂ������B
�@
�n���g�}���A���@�[�O�i�[�A�q�g���[�A�g���X�g�C�A�n�[�f�B�A�t���C�g�A�v���[�X�g�A�g�[�}�X�E�}���A�w�b�Z�A�����K�[�A�x���N�\���A�����O�A�W�b�h�A�z���N�n�C�}�[�A���[�g���B�q�E�E�B�g�Q���V���^�C���A�A�C���V���^�C���A�x�P�b�g�A�t�[�R�[�Ƃ������A19���I�㔼����20���I�ɂ����Ċ��������̓N�w�ҁA�|�p�ƁA��Ƃɑ傫�ȉe����^�����B���{�ł��X���O���͂��߁A�x�C�Y�A�����Y�A����N���ȂǑ����̍�Ƃɉe�����y�ڂ����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���w�[�Q���u�@�̓N�w�v���� 1821�N |
   �@
�@
|
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich.(1770-1831)
�@
Grundlinien der Philosophie des Rechts.
�@
�w�[�Q���́A�h�C�c�̓N�w�ҁB1818�N�Ƀx��������w�ɏ�����A�h�C�c(�v���C�Z��)���Ƃ̓N�w�I�w���҂ƂȂ����B�N�w�̉ۑ�͌����̍����I�c���ł���Ƃ��A��������ނ͂܂��A���������ċ�z�I�����ɂ͂���[�֎�`�̐����I�v�V�̌�����r���āA�����ɂ��Ȃ������v��]�B�u�����I�Ȃ��̂͌����I�ł���A�����I�Ȃ��̂͗����I�ł���v�Ƃ����L���Ȍ��t�́A����(�N�w)�ƌ����Ƃ̘a���Ƃ����w�[�Q���N�w�̍��q�������̂ł��邪�A���ꂪ�{���̏����Ɍf�����Ă���B�{���́A�w�[�Q���̍ł��P�������~�n��������̒���ł���B�@ |
���u�@�̓N�w�v1
�@
(Grundlinien der Philosophie des Rechts)�@1821�N�ɃQ�I���N�E���B���w�����E�t���[�h���q�E�w�[�Q���ɂ�鍑�Ƃ����Ƃ��������w�E�@�N�w�̒���ł���B�w�@�N�w�x�w�@�N�w�j�v�x�w�@�N�w�v�j�x�w�@�N�w�T�v�x�ȂǂƂ��Ă��B
�@
1770�N�Ƀh�C�c�Ő��܂ꂽ�w�[�Q����1801�N����C�F�[�i��w�ŋΖ����Ă���A���̎����Ɉׂ��ꂽ�@�N�w�̘_�l�w���R�@�̖@�w�I��舵�����x�A�w�l�ς̑̌n�x�Ȃǂ��{���w�@�̓N�w�x�̊�b�ɂȂ��Ă���B�ȑO�̓C�F�i��w�̍u�t�A�j�����x���N�E�M�i�W�E���̋������o��1818�N�Ƀx��������w�Ɉڂ�A�����Ŗ{���͏o�ł��ꂽ�B1831�N�Ɏ�������܂łɐ��O�ɏo�ł��ꂽ�Ō�̃w�[�Q���̒���ł���B���ݓǂ܂�Ă�����e�ł͎���Ƀw�[�Q���̍u�`�̎�u�����ҏW����������₪�������Ă���A�w�[�Q�������ڎ��M�������͂ł͂Ȃ����Ƃɒ��ӂ�v����B���e�Ƃ��Ă͏��L��_��A�s�@�ɂ��Ę_�����1�����ۖ@�A�ӔC�A�����A�ǐS�ɂ��Ę_�����2�������A�Ƒ��A�s���Љ�A���Ƃɂ��Ę_�����3���ϗ����琬�藧���Ă���B
�@
�w�[�Q���ɂ��A�q�ϓI���_�Ƃ͉Ƒ���s���Љ�A���ƂȂǂ̎��R�Ȑl�Ԃ̍s�ׂɂ�萶�ݏo����鐸�_�̋q�ϑԂł���B����͒��ۖ@�A�������A�l�ς̎O�̒i�K�ɋ敪����A���̒i�K��ʂ��Čʐ��ƕ��Ր�������B�w�[�Q���͐l�ς��܂��O�i�K�ɋ敪���A�Ƒ��A�s���Љ�A���Ƃ��琬����̂Ƒ�����B�Ƒ��Ƃ͈���⊴�o�Ƃ����`���ɂ������̂Ƌq�̂̓���̒i�K�ł���A�s���Љ�͎s��ɂ����Ă����炳���~�]�Ɋ�Â��J���̑̌n�ł���A���Ƃ͎s���Љ�̗~�]�̑̌n���ۂ��Ȃ��痧�@���⎷�s���A�N�匠��p���ĕ��Ր��������������邽�߂Ɏs���Љ�̗��Ȑ����Ď�����B�܂����Ƃ͑ΊO�I�ɂ͕��Ր��ł͂Ȃ����ێЉ�ɂ�������ꐫ����������Ӌ`������B�@ |
���u�@�̓N�w�v2
�@
�u�����I�Ȃ��̂͌����I�ł���A�����I�Ȃ��̂͗����I�ł���B�v(�w�@�̓N�w�x����)
�@
���̕���͈ȑO�A�Œ��ꒃ�ɕ]���������������A�u�����͂��ׂĐ������v�ƌ����Ă����ł͂Ȃ��B�ނ���A�����ɂ����Ď��Ȃ���������^�����u���R�v�̖{�����A�ƌ����Ă���̂ɋ߂��B
�@
�������G���R�Ȉӎu�̊T�O
�@
�u�v�l�ƈӎu�̋�ʂ́A���_�I�ȑԓx�Ǝ��H�I�ȑԓx�̋�ʂɑ��Ȃ�Ȃ����A�����͓�̕ʂȔ\�͂��Ƃ�����ł͂Ȃ��B�ӎu�͓���Ȏd���ł̎v�l�Ȃ̂ł���B�܂�A���Ȃ������݂ւƈڂ��u���Ƃ����d���ł̎v�l�A���ȂɌ����݂�^����Փ��Ƃ��Ă̎v�l�A�Ȃ̂ł���B�������H�I�ł���Ƃ��A���͊����I�ł���A�܂�A���͎��Ȃ��K��(������)����B���Ȃ��K�肷��Ƃ����̂́A��̋�ʂ𗧂Ă邱�Ƃł���B�������A�������Ă邱�̋�ʂ́A�܂����̂��̂ł�����B���K��͎��ɑ����Ă���A������藧�Ă���ړI�����ɑ����Ă���B���Ƃ��������K��Ƌ�ʂ�������Ă�(�܂�A������u�O�E�v�ɗ��ĂĂ�)�A�����͂�͂莄�̂��̂ł��葱���Ă���B�����́A�����ׂ������́A�������������̂ł���A���̐��_�̍��Ղ�ттĂ���B�v�@
��1) ���R�Ȉӎu(���Ր�)
�@
�u�ӎu�́A1)�����Ȗ��K�萫�A�܂莩��̎��ȓ��ւ̏����Ȕ���(������)�Ƃ����v�f���܂ށB�����ł́A�ǂ�Ȑ������A���R��~����~�]��Փ��ɂ���Ē��ڂɌ������Ă�����e���A���邢�͉��ɂ���Ăł��낤�ƁA�^�����K�肳��Ă�����e���A�������Ă���B���ꂪ�A��ΓI���ۂ��邢�͕��Ր��Ƃ����������Ȗ������A���Ȏ��g�̏����Ȏv�҂ł���B�v
�@
��2) ���Ȍ���(���ꉻ)
�@
�u2)���l�ɁA����́A��ʂ̂Ȃ����K�萫����A��ʂ��邱�Ƃւ́A���e����ёΏۂƂ��ċK�萫���K�肵�[�肷�邱�Ƃւ̈ڍs�ł���B�\���̓��e�́A���R�ɂ���ė^����ꂽ���̂ł��A���_�̊T�O�ɂ���Đ��ݏo���ꂽ���̂ł��\��Ȃ��B���Ȏ��g���K�肳�ꂽ���̂Ƃ��đ[�肷�邱�Ƃɂ���āA����͌����݈�ʂւƕ��ݏo���̂ł���B�\���ꂪ�ʐ��A���邢�͎���̓��ꉻ�Ƃ����v�f�ł���B�v�@
��3) ���Ȏ���(���ȕ��A)
�@
�u3)�ӎu�́A������̌_�@(���\���v�f)�̓���ł���B�\�܂�A���ȓ��֔��Ȃ�����ɂ���ĕ��Ր��ւƘA��߂��ꂽ���ꐫ�A�\�ʐ��ł���B
�@
����́A���Ȏ��g�֊W����ے萫�ł������A���Ȃ��K�肷��B�����������Ȏ��g�ւ̊W�Ƃ��āA����͎��Ȃ̋K��Ԃɑ��Ė��S�ł���A���̋K��Ԃ����Ȃ̂��̂ł���A�u�ϔO�I�Ȃ��́v�Ƃ��Ēm��B�܂�A����ɂ���Ĕ����Ă��炸�A�����Ɏ��Ȃ�[�肵�����瑶�݂��Ă���ɉ߂��Ȃ��A�P�Ȃ�\���Ƃ��āA�m��B
���ꂪ�ӎu�̎��R�ł���B�v�@
�\�����͗��_�I�ɏd�v�Ȍ��Ȃ̂ň��p�������A���������ǂ�ʼn��������Ă���̂�����Ȃ��Ă��A�W�����R�ł���B
�@
��̓I�ɍl����ƁA��̂��ꂼ��́A
�@
1) ���͎��R�ł���B���ꂩ��w�Z�ɍs���̂��A�}���K�i���ɍs���̂��A�ƂŐQ�Ă���̂��A���̎��R�ł���B(�������������A�Ƃ����̂Ȃ�A���̐��Ɂu��(�m��)�v�������A���E����̂��A���̋��ɂ̎��R���B)
�@
2) ���́A�������A���܂��܋��t������A����A�����͉J�����ǁA�Ƃ������w�Z�ɍs���Ď��Ƃ����悤�B
�@
3) �������t�Ȃ̂́A�����Ō��߂����Ƃ����A���Ȃ�~�߂Ă��������A�D���ł���Ă������A���͖{���͎��R���B�����獡���͊撣�낤�B
�@
�����Ɨϗ�
�@
�J���g�I�����̗���ɂ����ẮA�l�̈ӎu�̎��R�Ȍ��f���d�������B�������A����͌`���I�ŁA��̓I���e�������Ă����ɁA�����̒��ŗL���Ȍ��ʂ������炷���ǂ����A�^�킵���v�f������B�w�[�Q���́A�J���g�I������(Moralität)�̗������A�ϗ�(Sittlichkeit)�Ƃ���������\�z����B����́A��̓I�ɂ́A
�@
(a) �O�I�ɂ́A�u�Ƒ��A�s���Љ�A���Ɓv�Ƃ��������̂̒��ŁA����������A
�@
(b) ���I�ɂ́A�l�̓��ʂ��`���u�S�p(Gesinnung)�v�Ƃ��Ē��ړI�Ȃ��̂ƂȂ����A�������ł���B
�@
1) �Ƒ��G���Ɋ�Â�������
�@
2) �s���Љ�G�~�]�̃V�X�e���Ɛl�Ԍ`���@
3) ���ƁG�m�ɂ�鎩�ȔF��
�@
���̓��A�Ƒ��ɂ��ā\
�@
�w�[�Q���́u�ߑ�I�v�����̗��O����Ă���B����́u���R�Ȍl�̈��ɂ�錋�т��v�ƒ�`�ł���B����������͐��ݓI�ɖ������܂ފT�O�ł���B
�@
1) �l�̎��R(�G�S�C�Y��)�Ƌ�����
�@
�l�������I�ȑ��݂ł��邱�ƂƋ����̂̈���ł��邱�Ƃ͕K�������������Ȃ��B����͌���(�Ƒ�)�̏ꍇ�������ł���B�w�[�Q���͉Ƒ����u���́v�ƍl����B����́A�l���A�u���҂ɂ����Ď��Ȃ��ӎ�����v���̑��ݏ��F�̒��ŁA���Ȃ̌ʐ���������A����ɂ���Ă��g�傳�ꂽ���ȂƂ��ĉƑ�����������Ƃ������ƁA�����Ă��̎��Ȃł���݂��ւ̌��g�I�s�ׂ̒��ŁA��荂�����Ȃ̖{��������������A�Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B(���������l�̎��Ȓ��S�I�W���Ƒ��Ȃ�A�����ɂ͎��Ȃ����荂�����O�͑��݂��Ȃ��B�����̎����́A����(�Z�b�N�X)�Ɋ�Â��������S(�W�F���_�[)��O��ɂ���u�ߑ�I�v�Ƒ��̗��O����̂��邾�낤�B)
�@
2) ���Ƃ�������ƌ����Ƃ������x
�@
�������R�I�Ȋ���ł���ȏ�A�����Ƃ��������I���x�Ƃ��܂���v����Ƃ͌���Ȃ��B�����̊�b�ł��鈤�́u�ϗ��v�I�Ȃ��̂ł���B�w�[�Q���I�Ӗ��ł́u�ϗ��v�Ƃ́A���Ƌ��Ɍ`�������A�l�̐S�p�ł���A�K����x�ł���B�]���āu�ϗ��I�v���Ƃ́A���ɂ��s�ׁA�܂莩�Ȃ̈ꕔ�Ƃ��Ă݂̌��ւ̔z���A�̒��Ō`�����肳���A���_�I�Ȉ��ł���B
�@
�����Ƃ����Ӗ��ł̃G�S�C�X�e�B�b�N�Ȋ���I�Ȉ��ƁA(��)��Ƃ����Ӗ��ł̓��肳�ꂽ�ϗ��I�Ȉ��́A�K�������������̂ł͂Ȃ��B�������L���P�S�[���Ƃ͈Ⴂ�A�w�[�Q���͊����Ă������ʂ��Ȃ��B����͈�ɂ́A�l�ԓI�����A����ƃG�S�C�Y������藣�����Ȃ�A���͐������������Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂�����ł���B�������܂���ɂ́A�G�S�C�X�e�B�b�N�Ȉ�����M�ɂ���āA�l�������Ƃ����V�X�e���̒��ɋ�藧�Ă�B���ꂪ���x�͂��̒��ŁA�G�S�C�X�e�B�b�N�Ȉ���ϗ��I�Ȉ��ւƍ��߂铭��������A����ł���B�����������̘B�����u�Ƃ��ăw�[�Q���͌����Ƃ������x���l���Ă���B
�@
�\�������Ɍ��_�����ǂނƁA�����悤�ȋC�����邪�A�ǂ����B�u�Փ��̏����v�Ƃ������Ƃ������Ă���̂����B�܂�A�l�̗~�]�́A�u�ϗ��v�̋������̒��Ő��_�I�Ȃ��̂ւƏ����A�Ƃ������Ƃ��B
�@
����́A���́u�Љ�v�ł��������B�Ⴆ�A��Ј��́A���ʂ͉�ЂŁA�`�[���̈���Ƃ��Ċ�������B�����̈ӎv�̓`�[���̒��Ō��������A�`�[���̈ӎu���������B�������������̒��ŁA���͒b������B���̐��̒��͗��v�Љ�����Љ����A���т����B���������̉�ԂɌŎ�����A���̋��ꏊ�͂Ȃ��Ȃ�B�ł����������̂��������̂Ă���A����ȏ�̉�Ђ̔��W���Ȃ���������Ȃ��B
�@
�Љ�͐킢���B�Љ�͉Ƒ��Ƃ͐��������A�����ɂ͂�荂���̋�����������B
�@
���̋��������X�Ɏ��������̂́A���Ƃɂ����Ăł���B�\����͌���l�ɂ́A�����l�������B�\����������ʓI�Ȃ��̂قǁA���^���Ȃ��̂��A�Ƃ����l�����͂���B���������̗��v�ɂȂ邱�Ƃ��A���̐l�̗��v�ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ̕����A�q�ϓI�ɂ͐������B�܂荑��l�ނƂ������x���̕����A���l�⎄�̉Ƒ����Ђ��A��蕁�ՓI�ŁA�厖���A�Ƃ����l�����͂���B���̕��ՓI�Ȃ��̂Ƃ́A�w�[�Q���̍l���ł́A���E�̗��j�ł���A�|�p��@����w�Ƃ������u��ΓI���_�v�ł���B�@ |
���u���_���ۊw�v1
�@
G.W.F.�w�[�Q��(1770�`1831)��1807�N�ɏo�ł�������B���ӂ͐��_�̌��ۊw�B�{���́A�ϔO�_�̗���ɂ����Ĉӎ�����o�����A�ُؖ@�ɂ���Ď��X�Ɣ��W�𑱂��邱�Ƃɂ���Č��ۂ̔w��ɂ��镨���̂�F�����A��ςƋq�ς��������ꂽ��ΓI���_�ɂȂ�܂ł̉ߒ���i�K�I�ɋL�q�������́B�J���g�̔F���ƕ����̂Ƃ̕s��v�Ƃ����v�z�����A�h�C�c�ϔO�_�̐�s�҂ł���t�B�q�e�A�V�F�����O���ᔻ������ŁA�w�[�Q���Ǝ��̗��_��ł����Ă����߂Ă̒����ł���B����������Ēm���A�����̓N�w�҂ɉe����^�����B
�@
�w�[�Q���̓N�w��n�̒��ł́A�u���_���ۊw�v�Ƃ́u�ӎ��v����Ƃ���N�w�̕���ł���B�u���_���ۊw�v�̗̈�ɂ�����u�ӎ��v�̔��W���A�w�[�Q���ُؖ̕@�Ɋ�Â��Ď����A
�@
1. �ӎ����̂���
�@
2. ���Ȉӎ�
�@
3. ����
�@
��3�i�K�������B�u�ӎ����̂��́v�̒i�K�ł́A�u�����I�ӎ��v����u�m�o�v�ցA�����āu�含�v�ւƔF�����[�߂���B���ɂ��̂悤�ȔF���̎�̂Ƃ��Ắu���ȁv�����o����A�u���Ȉӎ��v��������B���́u���Ȉӎ��v�Ɠ����Ȉӎ��𑼎҂ɂ��F�߂邱�Ƃɂ���āA���l�́u���Ȉӎ��v�����F�����A�P�Ȃ鎩��������ՓI�ȁA���҂Ƃ̋��ʐ������u���ȁv�A�u�����v�̌���Ƃ��Ắu���ȁv��F���ɂ���Ɏ���B���̉ߒ����u���_���ۊw�v�ł���B
�@
����Łw���_���ۊw�x�ł͂��قȂ�L���Ӗ��ł́u���_���ۊw�v���L�q����Ă���A�O�q�́u�����v�i�K�Ɏ���܂ł́u���_���ۊw�v�ɑ����āA�u�q�ϓI���_�v�u��ΓI���_�v�����l�@�̑ΏۂɊ܂߂�B�܂�u�ӎ��v���邢�́u��ϓI���_�v�݂̂Ȃ炸�L���u���_�v��ʂ����̑ΏۂɊ܂ށB
�@
�{���̌���́u�w�̑̌n �v(System der Wissenschaft)�ł����āA�w�[�Q���N�w�̌n�̑��_�Ȃ��������Ƃ��Ď��M���ꂽ���̂ł��邪�A��ɏo�ł��ꂽ�G���`�N���y�f�B�[�ł́A���_���ۊw�ɑΉ�����͂͂Ȃ��B�@ |
���u���_���ۊw�v2
�@
�u���_���ۊw�v�́A�ł��f�p�Ȓm�̂��������n�߂āA���X�ɁA����ʓI�Ȓm�ւƍ��܂��Ă䂭�A�m�̌`�Ԃ���㈂��鎎�݂ł���B�ŏ��Ɉӎ��̑ΏۂƂ��Č���Ă���m(�Ⴆ�A�u���݁v�u���v�u�@���v�Ȃ�)�́A��̓I�ɒ��ׂĂ݂�ƁA���ׂĊW���ƍ�p�̂����Ő��藧���Ă�����̂ł��邱�Ƃ�����B���̊W���Ƃ́A�ł���ʓI�Ɍ����A�u���҂Ɏ��ȂƂ��ĊW����v�Ƃ�����p�ł���B���ꂪ�u�ӎ��v��u���Ȉӎ��v�����āu���_�v�̊�{�\���Ȃ̂ł���B
�@
��A) �ӎ��\�u�T�O�v�̍\��
�@
�u�ӎ���[����]�ɂ��Ă̈ӎ��ł���v�Ƃ����\�������B������u�u�����v�Ƃ����B
�@
���o�I�m�M / �u���v�u�����v�Łu���̂��́v���u���̎��v���ӎ����Ă���Ƃ������ړI�m
�@
���������ׂĂ݂�ƁA�u���̍��v�Ƃ͈�ʓI�ȁu���v�ł���A�u���̎��v�Ƃ͈�ʓI�ȁu���v�ł���B�u���̍��v�ł������ʓI�ȁu���v�ł�����悤�ȋ�̓I���݂́A�u���v�ł���B
�@
�m�o / ��
�@
��������������ׂĂ݂�ƁA�u���v�Ƃ͏������̏W���́A�����Ă͏��@���̏W���̂ł���B
�@
�含 / �@���@�@
(�J���g�������悤��)���R�̖@���Ƃ́A�ΏۂƂ��Č���鎩��(�ӎ�)�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@
��B) ���Ȉӎ��\��l�Ɠz��ُؖ̕@
�@
�����G�~�]
�@
a) �~�]�͊O�I�Ώۂւƌ������B�Ⴆ�ΐH�~�́A���̑Ώۂ�H�炢�s�����B����ɂ���đΏۂ͏��ł���B����������Ɠ����ɁA�~�]�����ł���B���R�̗~�](�����I�~�])�́A�u�Ώۂ�ے肷�邱�Ƃɂ���Ď��Ȃ�ے肷��v�Ƃ������Ƃ̌J��Ԃ��ł���B(����͊O����(���u���v�̒m��Ȃ�������)����ė���B���͗~�]�Ɂu�P����v�B�~�]������ƁA���͎��ȂɋA��B����͗~�]�������I�~�]������ł���B)
�@
b) ����ɑ��āA�l�ԓI�~�]�́A��������~�]�ł���B�u���������肩��F�߂��邱�Ƃ�F�߂�v�Ƃ�����d�̍\�������B(�u���v�Ƃ��u�����S�v�����A���̓T�^�ł���B���҂���̏��F��K�v�Ƃ���B���̂悤�ɁA�w�[�Q���̌����u���Ȉӎ��v�Ƃ́A�{���́A���́u���v�ɂ����āu���ȁv���ӎ�����u���v�̈ӎ��������B)
�@
���ݏ��F / ���R�̓���
�@
���̍ł������I�ȗ~�]�́A���̗͂��������邱�ƁA���̎��R�������邱�Ƃł���B���͍ł���Ȏ��̐������������R�Ɏx�z�ł��邱�Ƃ��A���̎��Ȉӎ��ɑ��ďؖ��������B(�����̐M�O�◝�z�̂��߂ɑS�Ă��̂Ă�o��̂���l�́A�F�����ڒu�����B�u�N�̂��߂ɂȂ玀��ł������v�ƌ����j�́A�����̐S���x�z���邱�Ƃ��o����B�\�{�����H�Ⴄ�悤�ȋC�����邪�B)
�@
�������A���́A���̑��݂̐�ΓI�ے�ł���B
�@
�����Ł@
�@
1)���R�̂��߂ɂ͎������}��Ȃ�������(����m�E�M���̃^�C�v)�ƁA
�@
2)�����̐��̂��߂ɂ͎��R�����̂Ăĉ}��Ȃ�����(���z��̃^�C�v)�A�Ƃ����A
�@
��̐l�Ԃ̃^�C�v�������B
�@
��Ɠz�\�J��
�@
a) ��l�́A�z��̘J����ʂ��āA�S�Ă��x�z���鎩�R������B�z��́A��l�̖��߂ɗꑮ���A�������̂ĂāA�����J������B
�@
b)�@�������z��́A�J���ɂ����āA������������B�J���͑S�Ă̑Ώې���ے肷��͂ł���B�z�ꂪ�J���ɂ���đn��o�����́A�����̐��_�̑Ώۉ��ł��肻�̍�i�ł���B�z��́A�J���Ƃ����ے�̊����ɖv�����邱�Ƃɂ���āA�S�Ă̑��Ґ���ے肷��͂ł��邱�Ƃ������Ă���B(�����܂����̑��Ґ�(��ΓI����)�ł���B) ����ɑ��āA��l�́A���̐�����z��̘J���Ɉˑ����Ă���B�܂�A���������ł͉����o�����A�ނ���z��ɗꑮ���Ă���B�����ɖ{���̎��R�͂Ȃ��B
�@
(�������čŏ��̎v�����݂́A���̔��̐^���ւƋt�]����B������u�ُؖ@�v�ƌ����B���̌��̒��S�T�O�́u�J���v�ł���B�J���͑���(�Ώ�)�ɊW����ے萫�ł���B����ɂ���đΏۂ́u���ȁv�̂��̂ƂȂ�B�w�[�Q���ɂ��A���҂Ɏ��ȂƂ��ĊW����A���̔ے萫���l�Ԃ̖{���Ȃ̂ł���B�ے聁������荞�ނ��Ƃŏ��߂āA���̎��R�͌���������B)
�@
�w�[�Q���́A�֗~�I�ȃJ���g�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�X�����ۂ�������̂�N�w�������A���̖{�̂́A�ے�Ƃ����W���̕��͂ɂ������B��(�����_)�́A�܂��g��(������)�Ƃ������̔��̂��̂ƈ�̂��̂Ƃ��ē����Ă��銈���ł���B���ɁA��(�����_)�́A���l(�����̎�)�ƑΗ����Ȃ���J���ɂ���Đ��E�����Ă���͂ł���B�J���͍����鐢�E��ے肷��͂ł��邪�A���͢����̖{���Ƃ́A�w�[�Q���Ɍ��킹��A���̑S�Ă�ے肷���p���̂��̂Ȃ̂ł���B
�@
���́A���̂��̂�����Ƃ����_�C�i�~�b�N�ȍ\���́u�ُؖ@�v�ƌĂ��B���̣�Ƃ��w�[�Q���͌����B�u�Ⴆ�A�p�\�R������A����͖��炩�ɑf�l�����ۂ��Ă�ˁB��ɉ������������Ƃ���点�Ă���Ȃ���B�����~�܂����Ⴄ�B����������Ŏg�����Ǝv���A�u���v���̂Ă�B�z��̂悤�ɁA�p�\�R������̌������܂܁A��J���邵���Ȃ���B�h����B�v�Ƃ��낪�A���N��̍��A�`������(����)�́A�u���[��˂����v�ƋC���͌�����Ȃ̂ł���B���̂悤�ɁA�G���m�������p�\�R������Ɗ`���ے�����́A���݂����ے肵�������Ƃɂ���āA�V�����u�p�\�R���ے��v�ݏo�����̂ł���B�������̐Ȃ̎R������ɂ��u�������������v��E���[���������͍̂�����̂����A���ꂪ�J���Ƃ������̂��B
�@
���łɁA���́A���̎��ł����鎄(����X)�́A���̐�ΓI�ȑ���(���_)�Ƃ��A�����ł͂Ȃ����Ⴄ���̂ł��Ȃ��B���́u�����v�Ɓu�Ⴄ�v�̂ǂ���ɗ͓_��u�����ɂ���āA�w�[�Q���w�h�̓w�[�Q���S����A�E�h�ƍ��h�Ƃɕ��Ă��܂��̂ł���B
�@
(�Ō�́u���ł����X�A��X�ł��鎄�v(������X)���A�w�[�Q���́u���_�v�ƌĂԁB���̐�ΓI�Ȃ�����A�܂�u��ΓI���_�v���A�u�|�p�A�@���A�w�v�ł���B�u���_�v�̋�̓I�Ȍ`�Ԃ́A�w�@�̓N�w�x�ɏ���B)
�@
��C) ���_
�@
1. ����
�@
2. ���_
�@
3. �@��(�|�p)
�@
4. ��Βm(�w)
�@
�@ |
 �@ �@
���L�F���P�S�[���u���ꂩ���ꂩ�v���� �S2�� 1843�N |
   �@
�@
|
Kierkegaard, Soren Aabye.(1813-55)
�@
Enten-Eller. Et Livs-Fragment udgivet af Victor Eremita.
�@
�{���́A�f���}�[�N�̎��l�A�N�w�҂ŁA������`�̕��ƌ�����L�F���P�S�[���̏�����ł���A�����ŏo�ł��ꂽ�B����Ɂu���B�N�g���E�G���~�^�ɂ�芧�s���ꂽ�l���̈�f�Ёv�Ƃ���A���B�N�g�����Ó���Ŕ��������̈����o������o�Ă������ނ��A���̏����̓��e���Ȃ��Ƃ����ݒ�ƂȂ��Ă���B���̏��́A���I�����҂Ɨϗ��I�����҂Ƃ������ꂩ�A���ꂩ���Ƃ��đΗ������A���̓�ґ����ǎ҂ɑi����`�����Ƃ��Ă��邪�A���͂���ȒP���Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����͎v�ٓN�w�ւ̒���̐��z���ł���A���Ȕᔻ�̏��ł�����B�w�[�Q����`�́�������A��������ƌ�������ł͉A������Ă��܂��l�Ԃ̎����I�����������ꂩ�A���ꂩ���Ƃ������f�ɂ���ĘI�悳���悤�Ƃ����̂��L�F���P�S�[���̈Ӑ}�ł���B |
���u���ꂩ���ꂩ�v
�@
(Enten-Eller: Et Livs Fragment�A udgivet af Victor Eremita)�@1843�N�ɓN�w�҃L���P�S�[���ɂ�蔭�\���ꂽ�N�w���ł���B�L���P�S�[����1813�N�Ƀf���}�[�N�Ő��܂ꂽ�N�w�҂ł���A������`�̎v�z�Ɋ�^�������ƂŒm���Ă���B�{���w���ꂩ�A���ꂩ�x�̓L���P�S�[����30�ɂȂ������Ƀf���}�[�N�̎v�z�E�ɉ����_�@�ƂȂ�������ł������B�{���̓��B�N�g���E�G���~�^���Ƃ�����̈����o�������̎�L����肵�A������o�ł���Ɏ������o�܂��q�ׂ�Ƃ��납�珘�����n�܂��Ă���B���I�Ȑl���𑗂����`�̎�L�Ɨϗ��I�Ȑl����I�a�̎�L�ɂ͂��ꂼ��S���قȂ�v�z���Δ�I�Ɏ�����Ă���B
�@
�`�̎�L�ŏq�ׂ��Ă�����I�����͎��̂悤�ȓ��e���܂�ł���B����̔ߌ��ƌÓT�̔ߌ��̓��e�ɂ͔ߌ��ɂ�����߂̊T�O�̑��Ⴊ����A�M���V�A�ߌ��͊O���I�Ȋ����ɂ��߂ł��邪�A�A���e�B�S�l�[�̂悤�ȋߑ�ɂ�����ߌ��͓����I�ȍ߂̈ӎ��ł���ƌ��Ȃ��B�l�Ԃ̔߈��ɂ��Ă��|�p�ł͊O���ɕ\���ł��Ȃ��悤�Ȕ��ȓI�߈������グ�Ă���B�����čł��s�K�Ȑl�Ԃɂ��Ēlj��ɖW�����邽�߂Ɋ�]�̒��Ɍ��݂��邱�Ƃ��ł��Ȃ��l�A�������͊�]�ɖW�����邱�ƂŒlj��̒��Ɍ��݂��Ă���Ƙ_����B�L���P�S�[���͖��������̒j���̂Ăĕʂ̒j�ƌ������A�ނ����{���ł���Ɗm�M���閺�̐�͂�����`���A�܂��앨�̎��n�𑝂₷���߂ɓy�n��ς��Ȃ������܂��_�v��`���B���y��Njy������I�����͏�Ɏh�������߂邱�ƂőΏۂ�ω������A�ω����Ȃ��Ȃ�Ƒދ��ɂȂ�B�ދ��͋��Ɋ�Â��Ĕ������A����͐l�ԂɁu῝�v���N�������̂ł���B���������邽�߂ɐl�Ԃ͎��X�ƐV�����C���炵�����߂ċC�܂���ɐ�����B�L���P�S�[���̌����ɂ��Ȃ�A���I�����̍s��������͐�]�ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@
�a�̎�L�ł͂`�̒��ҁA�܂���I�����ɂ�������Ă���F�l�ɑ��鏑�ȂƂ��ď�����Ă���B�܂������̔��I���l�ɂ��āA�����̖{���̉ۑ�Ƃ͈��~�̗v�f�ƌ����ȓ��ʐ������������邱�Ƃł���A�������Ɛ������Ƃ������̏����ł���Əq�ׂ���B�閧���������܂܌������邱�Ƃ͂����Ă͂Ȃ炸�A�������ɂ����ē��ʓI�Ȑ����������d�v�ł���A�ǂ̂悤�Ȍo�N�ɑ��Ă��i������ۂ�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��ƍl����B�܂�l���ɂ����Đl�Ԃ́u���ꂩ�A���ꂩ�v�̈��I�ԕK�v������̂ł���A���I�����ɑ��Ă���ɖ�������ϗ��I������I�Ԃ��Ƃ��咣�����B���̑I���͎��R�ɍs�����Ƃ��\�ł���A���R�Ȍ��f�ɂ���ėϗ��I�����̋`���Ǝ���̎g����B������B���Րl�ԓI�Ȃ��̂����������Ȃ��l�Ԃ͎������g�����̌��E�ɒB���Ă����O�҂ł��邱�Ƃ����o���A����ɑ���������ʐ����l�����邱�Ƃ��������B�@ |
���Z�[�����E�I�[�r�G�E�L�F���P�S�[��
�@
(�f���}�[�N��: Søren Aabye Kierkegaard�A1813-1855)�@�f���}�[�N�̎v�z�ƁB�N�w�҂ł���A�����ł͈�ʂɎ�����`�̑n�n�ҁA�܂��͂��̐�삯�ƕ]������Ă���B�L�F���P�S�[���͓����ƂĂ��e���͂����������w�[�Q���N�w���邢�͐N�w�[�Q���h�A�܂�(�ނ��猩��)���e�킸�`������ɂ�����铖���̃f���}�[�N����ɑ���ɗ�Ȕᔻ�҂ł������B
�@
���{��ł́A�u�Z�[�����E�I�[�r�G�E�L���P�S�[��(�L�F���P�S�[��)�v�Ƃ̕\�L���ʗp���Ă��邪�A�f���}�[�N��̌����ɋ߂��J�^�J�i�\�L�́u�Z�A���E�I�[�r�C�E�L�A�P�S�[�v�ł���B�Z�[�����Ƃ����\�L���L�F���P�S�[��(�L���P�S�[��)�Ƃ����\�L���A���{�̃L���P�S�[����e���A��Ƀh�C�c�ꕶ�����o�R���Ă������Ƃɂ��Ƃ��낪�傫���ƍl������B
�@
�L�F���P�S�[���̏����̒���̑����͂��܂��܂ȉ������g���ď�����Ă���B�܂��A���鉼���̒��҂��A����ȑO�ɏ����ꂽ��i��(����܂�)�����̒��҂ɑ��ăR�����g���邱�Ƃ�����������(�ł������Ȃ̂́w�N�w�I�f�Ђւ̌��тƂ��Ă̌㏑���x���낤)�B������ׂĂ̒���̓L�F���P�S�[���ɂ���ď����ꂽ�킯�����A���̂��܂��܂ȉ����g�p�̂��߂ɔނ̒���͈�т������߂�������Ƃ�����B�L�F���P�S�[���͂��̂������Ŗ{���ł̒�������\���Ă���A�ގ��g�͍ĎO�A�U���̒��҂����Ǝ��������Ⴆ�Ȃ��łق����A�Ǝ咣���Ă����B������͌��݂܂ł��܂�ǂ܂�Ă��Ȃ��B
�@
�܂��A�ނ̖����ł���u�L���P�S�[���^�L�F���P�S�[���v(Kierkegaard)�́A����f���}�[�N��ł�kirkegård�ƂÂ��A�u��n(�p��@churchyard�Ccemetery)�v���Ӗ�����B�������Ȃ���A���̌��t�͂��L������ɗאڂ���~�n�u����̒�(�p��@church garden)�v�A����ɗאڂ̓y�n���Ӗ�����B�u����̒�v�Ƃ��������ɂȂ������R�͈ȉ��́u���U�v�ɐ[���W���Ă���B���Ȃ݂ɁAkierkegaard �̖����u��n�v(kirke-gaard)���Ӗ�����̂ŁA�� �̂��Ƃɖ��Ӗ��� �� ��}�������Ȃǂ̐������݂����邪�A�����̂Ȃ������ł���B�����Ƃ���i�ɑΉ�����̂͂܂��� �� �ł����āA���� �� �������ΝX�������邽�߂ɔ����ɑ����� je / ie �ƒԂ���P�[�X�ƍl����ׂ��ł���B(���Ƃ��Ό��݂� kærlighed ���L���P�S�[���́AKjerlighed �ƒԂ�悤��)�L���P�S�[���̕��~�J�G���̏o�g�n�ł��郆�����n��̕����ł͕ꉹ�̝X�����������݂���B�����炭�̋��̔�����z�N���Ȃ��炱�̂悤�ɂÂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
�����U
�@
�Z�[�����E�L�F���P�S�[���̓R�y���n�[�Q���̕x�T�ȏ��l�̉ƒ�ɁA���~�J�G���E�y�U�[�Z���E�L�F���P�S�[���A��A�[�l�E�Z�F�[�����X�_�b�^�[�E�����̎��l�̎q���̖����q�Ƃ��Đ��܂ꂽ�B���e�̃~�J�G���͔M�S�ȃN���X�`�����ł������B�~�J�G���͐_�̓{������Ǝv�����݁A�ނ̂ǂ̎q�����L���X�g�����Y�ɏ�����ꂽ34�܂ł����������Ȃ��ƐM������ł������A����͎��̗��R�ɂ��B
�@
���X�A�L�F���P�S�[���Ƃ̓��������������̃Z�f�B���O�Ƃ������ŋ���̈ꕔ����ďZ��ł����n�����_���ł���A���̃~�J�G���͗c������A���̋�����J���A�_��������B���̌�A�~�J�G���͎�s�R�y���n�[�Q���ɂ����āA�r�W�l�X�Ő��������߂��B�~�J�G���͂��̐����������_��������㏞�ł���ƐM���Ă����B�܂�A�_��������������̎����̐����E�ł̐����ł���ƁB������̗��R�Ƃ��āA�~�J�G�����A�[�l�ƌ�������O�ɔޏ���D�P���������Ƃł���ƍl�����Ă���B�~�J�G���͈�x�N���X�e�B�[�l�E�j�[���X�_�b�^�[�E���C�G���Ƃ��������ƌ������Ă��邪�A�ޏ��͎q�����ł��Ȃ������ɔx���Ŏ���ł��܂��B���̒���ɁA�~�J�G�����A�[�l�Ɩ\�͓I�Ȑ��I�����������ƍl�����Ă���B
�@
�~�J�G���͂���炪����K�v�Ƃ���(�@���I�ȈӖ������ł�)�߂ƍl���A�q�������͎Ⴍ���Ď��ʂƎv�����̂����A���ۂɎ��l�̎q���̂����A�����q�̃Z�[�����ƒ��j���������ܐl�܂ł�34�܂łɖS���Ȃ��Ă���B���������āA������34�܂łɎ��ʂ��낤�Ɗm�M���Ă���(�Z�[�����E)�L���P�S�[����34�̒a�������}�����Ƃ��A�����M���邱�Ƃ��ł����A����Ɏ����̐��N�������m�F���ɍs�����قǂł���B
�@
1835�N�ɕ��~�J�G���̍߂�m�����Ƃ��̂��Ƃ��L���P�S�[������u��n�k�v�ƌĂ�ł���B���̎����̂̂��ނ͕��������𑗂邱�ƂɂȂ����B(�u��n�k�v��1838�N�Ƃ����������A���̐��ł͂��Ƃ��ƕ������������Ă����L���P�S�[�����A���̎������������点���Ƃ��Ă���B)���̂悤�ɁA���~�J�G���̃L���X�g���ւ̐M�S�Ɣގ��g�̍߂ւ̋���́A���q�Z�[�����ɂ������p����A�ނ̍�i�ɑ���ȉe����^���Ă���(���ɁA�w������Ƃ��̂̂��x�ɂ����Ă͌����ł���)�B
�@
������́A�L�F���P�S�[���̐l���ƍ�i�ɑ���ȉe���͂��y�ڂ������̂Ƃ��ẮA�ގ���̃��M�[�l�E�I���Z��(1823�N - 1904�N)�Ƃ̍���̔j�����������邾�낤�B�L�F���P�S�[����1840�N��17�̃��M�[�l�ɋ������A�ޏ��͂�����������̂����A���̖��N��A�ނ͈���I�ɍ����j�����Ă���B���̍���j���̗��R�ɂ��ẮA�����̑����i�K����d�v�Ȗ��̈�[��S���Ă���(�L�F���P�S�[�����g�A�u���̔閧��m����̂́A���̑S�v�z�̌�����̂ł���v�Ƃ����䎌�����g�̓��L�ɒԂ��Ă���)�A�����̑��w���ꂩ�\���ꂩ�x�Ɏ��^����Ă�����w�U�f�҂̓��L�x�⒆���́w�l���s�H�̏��i�K�x�Ɏ��^����Ă���w�ӂ߂����\�ӂ߂Ȃ���H�x�Ȃǂ́A���M�[�l�ɂ܂���A�̎����Ƃ̖��ڂȊ֘A���w�E����Ă���B����j���̌����ɂ��āA�^���͒肩�łȂ��B�����̕�������́A�L�F���P�S�[���{�l�����ꂽ�������o���Ă������ƁA����炩�ȉ����ł��������M�[�l���u�J�D�v�̎����Ɉ������荞�ނ܂��Ƃ������ƂȂǂ�ǂݎ�邱�Ƃ��ł��邪�A���I�g�̓I���R�������ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝw�E���錤���҂�����A�^���͂��܂���ɕ�܂�Ă���B���M�[�l���L�F���P�S�[���ɍ���j���̓P������߂�o���������������߂���Ȃǂ������߁A�ނ͏�L�̒����ȂǂňӐ}���ă��M�[�l����������˂��������Ǝ��݂��肵�Ă���B
�@
��l�́A�����炭���M�[�l��1847�N�Ƀt���[���N�E�X���[�Q��(1817�N�`1896�N)�ƌ����������Ƃ����������Ă����ƍl�����Ă���B���M�[�l�͕v�ɃL�F���P�S�[���̒���̍w�����˗�������A�ꏏ�ɂ��̒����ǂ�����Ă���B��N�A1849�N�Ƀ��M�[�l�̕����S���Ȃ�ƁA�L�F���P�S�[���̓��M�[�l�Ƃ̘a���ƗF��̉����߂��莆���A�v�t���[���N���Ă̎莆�ɓ������ē������邪�A���̎莆�͕��������܂ܑ���Ԃ���Ă���B���̌シ���ɁA�V�����[�Q���v�w�̓t���[���N�������̃f���}�[�N�̐��C���h�����̑��ɔC�����ꂽ���߁A�f���}�[�N�𗷗����Ă���B���M�[�l���߂邱��ɂ́A�L�F���P�S�[���͂��łɖS���Ȃ��Ă����B�L�F���P�S�[���̓f���}�[�N����̉��v�����߂�������Œ��ɓ����œ|��A���̌�a�@�ŖS���Ȃ����B
�@
�L�F���P�S�[���͌Z���̎莆�̌`�ɂ��⌾���̒��ŁA���M�[�l���u���̂��̂��ׂĂ̑����l�v�Ɏw�肵�Ă����B���M�[�l�͈�Y�̑����͒f��������e�̈������ɂ͉����A���ĕ��������܂ܑ���Ԃ��ꂽ�莆�����̂Ƃ��ޏ��̎�ɓn���Ă���B���M�[�l�y�єޏ��̐e�F�ŃL�F���P�S�[���̖Âɓ�����w�����G�b�e�E������̓w�͂ɂ���āA�����̈�e�͌㐢�ɓ`�����邱�ƂɂȂ�B
�@ |
���L�F���P�S�[���̓N�w
�@
�L�F���P�S�[���̓N�w������܂ł̓N�w�҂����߂Ă������̂ƈႢ�A�܂��ނ�������`�̐�삯�Ȃ����n�n�҂ƈ�ʓI�ɕ]������Ă���̂��A�ނ���ʁE���ۓI�ȊT�O�Ƃ��Ă̐l�Ԃł͂Ȃ��A�ގ��g���͂��߂Ƃ���ʁE��̓I�Ȏ������݂Ƃ��Ă̐l�Ԃ�N�w�̑ΏۂƂ��Ă��邱�Ƃ�����ɂ���B
�@
�u���Ɏ���a�Ƃ͐�]�̂��Ƃł���v�Ƃ����A�������E�łǂ̂悤�ȉ\���◝�z��Nj����悤�Ɓ������ɂ���Ă����炳����]������ł��Ȃ��ƍl���A�����Đ_�ɂ��~�ς̉\���݂̂��M������Ƃ����B����͏]���̃L���X�g���́A�M���邱�Ƃɂ���ċ~����Ƃ����M�Ƃَ͈��ł���A�܂����E����j�S�̂��L�q���悤�Ƃ����w�[�Q���N�w�ɑ��A�l�Ԃ̐��ɂ͂��ꂼ�ꐢ�E����j�ɂ͊Ҍ��ł��Ȃ��ŗL�̖{��������Ƃ������������������Ƃ�����I�ł������B
�@
���w�[�Q���ɍR����
�@
�N�w�j�I�ɂ́A�L�F���P�S�[���̓N�w������Â��Ă���̂́A�����̃f���}�[�N�ɂ����Ă����ȉe���͂��ւ��Ă����w�[�Q���N�w�Ƃ̑Η��ł���B
�@
�w�[�Q���̊w���ɂ����ẮA�C�}�k�G���E�J���g�ȗ��̏d�v���ƂȂ��Ă����A���������Ǝ��H�����A�����҂ƗL���ҁA�X�̐l�ԂƐ�ΐ^���̊Ԃ̊W�͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��A�Ƃ����₢�����グ����B�w�[�Q���ɂ��A�L���I���݂́A�܂��ɂ��ꂪ�L���ł��邪�䂦�ɁA�����̐��E�ɂ����Ă˂Ɏ���̔ے萫�̌_�@�ɒ��ʂ��邪�A���̂Ƃ��L���҂͂��̔ے萫��ُؖ@�I�_���ɂ����Ď~�g����Ƃ������@�ŁA���̔ے萫���������A���^���ɋ߂����݂Ƃ��Ď�������߂Ă������Ƃ��ł���Ƃ����B
�@
����ɑ��āA�L�F���P�S�[���ɂƂ��ẮA�X�̗L���I�Ȑl�ԑ��݂����ʂ��邳�܂��܂Ȕے萫�A�����A�����́A�w�[�Q���I�Ȓ��ۘ_�ɂ����ĉ����������̂ł͂Ȃ��B���̂悤�Ȓ��ۓI�ȋc�_�́A���j�A�����ɂ�����l�Ԃ̊����̊O���ɗ����Ă�����L�q����Ƃ��ɂ̂ݗL���Ȃ̂ł����āA���j�̓����ɂ����Ď���̍s������I�������f���Ȃ���Ȃ�Ȃ������I�Ȏ�̂ɂƂ��ẮA����͈Ӗ����Ȃ��Ȃ����̂Ȃ̂ł���B���̂悤�Ȋϓ_����L�F���P�S�[���́A�w�[�Q���ُؖ̕@�ɑ��āA�ނ��t���ُؖ@�ƌĂԂƂ���̂��̂����B�t���ُؖ@�Ƃ́A�L���I��̂�����̔ے萫�ɒ��ʂ����Ƃ��ɁA����𒊏ۓI�ϓ_����~�g����̂ł͂Ȃ��A���̔ے萫�A�����ƌ��������A���������̎����I���ɂ����Đ^���Ɏ~�߁A�Λ����邽�߂̘_���ł���B
�@
�L�F���P�S�[���͎���̎v�z�̓�������̓I�v�l�ƌĂсA������w�[�Q���I�Ȓ��ۓI�v�l�ɑΒu����B���ۓI�v�l�Ƃ́A�����ɂ����ČX�̎�̂���������Ă���悤�Ȏv�l�ł���̂ɑ��A��̓I�v�l�Ƃ́A��̂�����I�ł���悤�Ȏv�l���Ƃ����B
�@
���̉����ɂ����āA�L�F���P�S�[���́u��̐��͐^���ł���v�ƒ莮�����邪�A�t���I�Ȃ��ƂɁA�ނ́u��̐��͔�^���ł���v�Ƃ������B�����ɂ����ăL�F���P�S�[�����Ӑ}���Ă���̂́A���̂悤�Ȃ��Ƃł���B���Ȃ킿�A���j�I�A�����I�ȑI���̏�ʂɂ����Ă͎�̐��ȊO�ɐ^���̌���͂��肦�Ȃ�(��̐��͐^���ł���)���A���̂��Ƃ͎�̐����w�[�Q���I�ȈӖ��ł̐�ΓI�^���̌���ł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���ۂɂ́A��̂͂˂ɐ�ΓI�^������u�Ă��Ă���(��̐��͔�^���ł���)�̂ł���B
�@
�����q�X�^�C���Ɠ��L
�@
�L�F���P�S�[���͒��q�ƂƂ��Đ��U���삯�A�}������܂łɑ��ʂ̒�����c�������A���̒���͑傫���u���I����v�Ɓu�@���I����v�Ƃɕ��ނ��邱�Ƃ��ł���B���邢�́u���I����v���u���I����v�Ɓu�N�w�I����v�ɍĕ��ނ���3�̋敪�𗧂Ă邱�Ƃ��ł���B�u���I����v�͂����ς�U���ɂ���ď�����A�u�@���I����v�͎����ŏ�����Ă���Ƃ������Ƃ͒��ڂ��Ă悢�����ł���B
�@
���{�ɂ����Ắw�U�f�҂̓��L�x�̂悤�ȁu���I����v��A�w���ɂ�����a�x�w�N�w�I�f�Ёx�Ȃǂ́u�N�w�I����v���肪�Љ���X���ɂ���A�w��̕S���Ƌ�̒��x�Ȃǂ́u�@���I����v(�@���ƃL�F���P�S�[���Ƃ��Ă̒���)�͌ڂ݂��Ȃ����Ƃ������B�������L�F���P�S�[���̖{�ӂ́u�@���I����v�Ɍ������Ă����͖̂����Ȏ����ł���B
�@
�����̎v�z�ɉe����^�����A������u�L�F���P�S�[���v�̎v�z���A�u���I����v�Ɉ���Ƃ��낪�������߁A�u�@���I����v�̑��݂��y�����ꂪ���ł���A���A�L�F���P�S�[���̂��ׂĂ̒��슈���͍��{�I�Ɂu�@���I����v�̂��߂ɏ����ꂽ���̂ł���Ƃ������Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����Ȃ�A�ނ̒���͓������狳���̂��߂ɏ����ꂽ���̂ł���A�u���I����v�̈�͋����̂��߂̏��t�Ƒ������Ă�����ׂ����̂ł���(�w�s���̊T�O�x��w������Ƃ��̂̂��x�Ȃǂ́A�N�w�I�ɏd�v�Ȓ�����A�����܂ʼn����̉��ŏ����ꂽ���ʂ̒���ł���Ƃ������Ƃɒ��ӂ��ꂽ��)�B
�@
�܂��A�L�F���P�S�[���͗c���̍������L��Ԃ�K���������Ă���A�}������܂ł̐��U�ɂ킽���ē��L���������ߑ������B���́w���L�x���ŋ߂̌����ɂ����Ă͒��앨�Ɠ���(���A�����������炻��ȏ�)�̉��l�������̂Ƃ��Ĉ����邱�Ƃ������B�w���L�x�ɂ́A���앨�ɑ���Ӑ}�̕\����M�[�l�ւ̑z�����Ԃ��Ă���B�������A�L�F���P�S�[���{�l�͂����ꂱ�́w���L�x�������̉��ɎN����邾�낤�Ɨ\�����Ă��ʑ̂�U���悤�ȏC���E������Ƃ��{���Ă���B�@�@
�@ |
 �@ �@
���_�[�E�B���u��̋N���v���� 1859�N |
   �@
�@
|
Darwin, Charles.(1809-82)
�@
On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of favoured races in the struggle for life.
�@
�_�[�E�B���́A�C�M���X�̔����w�ҁA�i���_�ҁB�C�M���X�C�R�̑��ʑD�r�[�O�����ɔ����w�҂Ƃ��ď�D���āA�K���o�S�X�����Ȃǂ̓씼�����A�q���A�e�n�̔����w�I�ώ@���琶���i���̐M�O�ċA�������B1844�N�Ɏ�̋N���̖��ɂ��Ă̊T�v���L������A1856�N���玷�M�Ɏ�肩����A3�N������Ŗ{�������s�����B�{���̐��m�Ȗ́u���R�I���̕��r�ɂ���̋N���A�܂��͐��������ɂ�����L���Ȏ푰�̕ۑ��ɂ��āv�ł���A�{���ɂ�萶���i���̎�������A���R�����������������B�W���̏��ɂ́A��From author���̃T�C��������A���҂̌���{�ł���B�@ |
����̋N��
�@
("On the Origin of Species")�@�`���[���Y�E�_�[�E�B���ɂ��1859�N11��24���ɏo�ł��ꂽ�i���_�ɂ��Ă̒���ł���B�薼�͊�g���ɔł̂悤�Ɂw��̋N���x�ƕ\�L����ꍇ�ƁA�����ЌÓT�V�ɔł̂悤�Ɂw��̋N���x�ƕ\�L����ꍇ������B
�@
�_�[�E�B���́A�w��̋N���x�̒��ŁAevolution �ł͂Ȃ��ADescent with modification �Ƃ����P����g���Ă���B����� Evolution �Ƃ����ꂪ�i����O�i���Ӗ����Ă���A�_�[�E�B���͐i���ɂ��̂悤�ȈӖ������߂Ă��Ȃ���������ł���B
�@
�ނ͎��R�I���ɂ���āA�����͏�Ɋ��ɓK������悤�ɕω����A�킪���đ��l�Ȏ킪������Ǝ咣�����B�����Ă��̉ߒ��������A�K�Ґ����Ȃǂ̃t���[�Y��p���Đ��������B
�@
���R�I���Ƃ́A�u(1)�������������͌̊ԂɈႢ������A(2)���̈ꕔ�͐e����q�ɓ`�����A(3)�����e�͂��ɐB�͂������������ߐ��܂ꂽ�q�̈ꕔ���������E�ɐB�ł��Ȃ��B�����̈Ⴂ�ɉ����Ď�����Ɏq���c�����ϓI�\�͂ɍ���������̂ŁA�L���Ȍ̂����������ێ��E�g�U����Ƃ������J�j�Y���v�ł���B
�@
�ނ͑S�Ă̐����͈�킠�邢�͂ق�̐���̑c��I�Ȑ������番�Ēa�������̂��Əq�ׂ����A���ۂɂ̓^�C�g���ɔ����āA�ǂ̂悤�ɌX�̎킪�a�����邩(�핪��)�͂قƂ�ǐ������Ȃ������B�����̒n���I���z������ɂ��Ă��킸���Ɍ��y���Ă���B������ DNA ���`�̎d�g�݂ɂ��Ă͒m���Ă��Ȃ������̂ŁA�ψق��`�̎d�g�݂ɂ��Ă͂��܂������ł��Ȃ������B�܂��i����i���Ƃ͈Ⴄ���̂��ƔF�����A����̕��������Ȃ����R�̕ψقɂ��@�B�_�I�Ȃ��̂��Ƃ����B�_�[�E�B���͐i���̊T�O�𑽂��̊ώ@�������ɂ��T�Ȃǂ̎��ؓI���ʂɂ���āA�i���_�������̒i�K���痝�_�ɂ܂ō��߂��̂ł���B
�@
�{���͔���ƌ����ɓǂ݂₷��������Ă���A���L���S���W�߂��B�����̐����w�̍��{���Ȃ��@���I�M�O��ے肵�����߂ɁA�Ȋw�I�����łȂ��A�@���I�A�N�w�I�_���������N�������B�_�[�E�B���̍v���ȗ��A�����i�����̊m���Ȃǐi�����_�͋}���ɔ��W�����B���������R�I����͓K���i���̗v���Ƃ��Č��݂��Ȋw�I�ɔF�߂�ꂽ���f���ł���B
�@
�����ۂ��A21���I�ɂȂ��Ă��A�����J���O���ł͐i���_��ے肷��n���Ȋw��C���e���W�F���g�E�f�U�C���Ȃǂ̐������i���_�c�̂ɂ���Ď咣����Ă���B
�@
��
�@
�{���̊��S�ȑ薼�́w���R�I���̕��r�ɂ��A���Ȃ킿���������ɂ����ėL���ȃ��[�X�̑������邱�Ƃɂ��A��̋N���x"On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life"�ł���B
�@
���ł́A��2��(1859�N��1860�N��2��̋L�^����)�ȍ~�A13�N�Ԃɓn����M�E�C���������āA1872�N�̑�6�ł܂Ōp�����ꂽ�B���ɁA��6�łł́A�u���R�I����ɂނ���ꂽ��X�̈٘_�v�̏͂�V���ɒlj����A����܂łɊ�ꂽ�٘_�ɂ��ĉ��q�ׂĂ���(�}���ꏊ�́A��5�ł̑�7�́u�{�\�v�̑O�B���������āA��7�͈ȍ~�̏͂́A��6�łł�1���ԍ����J�艺����)�B�܂��A��6�łł́A�^�C�g���̐擪�� "On" ����菜���ꂽ�B�Ȃ��A��6�łɂ��Ă��C�����������A�_�[�E�B���ɂ��ŏI�I�ȕҏW��1876�N�ł������Ƃ����B�ł��d�˂�ɂ�Ĕᔻ�ɉ����Ď��R�I���ȊO�̗v�����F�߂�悤�ɂȂ��Ă������B
�@
���R�I����ɂȂ���L�^��l�@�́A�r�[�O�����̍q�C��(1831�N-1836�N)����т��̒��ォ�瑱�����Ă����B�{���ɂȂ��钼�ړI�Ȍ����́A�q�C����6�N���1842�N6���Ƀm�[�g35���ɓZ�߂�ꂽ�u�X�P�b�`�v(���_���̂���)�A�����1844�N6-7����231�y�[�W�ɓZ�߂��u�G�b�Z�[�v�ł������B�����́A�_�[�E�B�����g�ŕۊǂ��Ă���A���M�����͌��\����Ă��Ȃ������B1856�N����A�_�[�E�B���́u��̋N���v�Ɋւ���{�̎��M���n�߂����A1858�N�ɃE�H���X����̎莆�ɂ���āA���̖{�̎��M�𒆒f���邱�ƂɂȂ����B���̒��f���ꂽ����̗v���(���{�E�A�u�X�g���N�g)�Ƃ��Ē����ꂽ���̂��{���w��̋N���x�ł���B�@ |
���`���[���Y�E���o�[�g�E�_�[�E�B��
�@
(Charles Robert Darwin, 1809-1882)�@�C�M���X�̎��R�Ȋw�ҁB��z�����n���w�ҁE�����w�҂ŁA��̌`�����_���\�z�B�S�Ă̐����킪���ʂ̑c�悩�璷�����Ԃ������āA�ނ����R�I���ƌĂv���Z�X��ʂ��Đi���������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�i���̎����͑������ɉȊw�E�ƈ�ʑ�O�Ɏ����ꂽ����ŁA���R�I���̗��_���i���̎�v�Ȍ����͂ƌ��Ȃ����悤�ɂȂ����̂�1930�N��ł���A���R�I����͌��݂ł��i�������w�̊�Ղ̈�ł���B�܂��ނ̉Ȋw�I�Ȕ����͏C�����{����Ȃ��琶�����l���Ɉ�т������_�I������^���A���㐶���w�̊�Ղ��Ȃ��Ă���B�i���_�̒̌��т��獡���ł͐����w�҂ƈ�ʓI�Ɍ��Ȃ����X���ɂ��邪�A���g�͑������ɒn���w�҂𖼏���Ă���A����̊w��ł��n���w�҂ł���Ƃ����F�����m�����Ă���B
�@
�G�f�B���o����w�ň�w�A�P���u���b�W��w�ŃL���X�g���_�w���w��ł���Ƃ��Ɏ��R�j�ւ̋�������B5�N�ɂ킽��r�[�O�����ł̍q�C�͔ނ��`���[���Y�E���C�G���̐Ĉ���𗝘_�Ɗώ@�ɂ���Ďx�����������Ȓn���w�҂Ƃ��Ċm�������B�܂����̍q�C�L�͐l�C��ƂƂ��Ă̒n�ʂ��ł߂��B�r�[�O�����q�C�ŏW�߂��쐶�����Ɖ��̒n���I���z�͔ނ�Y�܂��A��̕ω��̒����ւƓ������B������1838�N�Ɏ��R�I������v�������B���̃A�C�f�B�A�͐e�������l�̔����w�҂Ƌc�_���ꂽ���A���L�͂Ȍ����Ɏ��Ԃ�������K�v������ƍl�����B
�@
���_�������グ�悤�Ƃ��Ă���1858�N�ɃA���t���b�h�E���b�Z���E�E�H���X���瓯���A�C�f�B�A���q�ׂ����_��������B��l�̏��_�͑����ɋ������\���ꂽ�B1859�N�̒����w��̋N���x�͎��R�̑��l���̂����Ƃ��L�͂ȉȊw�I�����Ƃ��Đi���̗��_���m�������B�w�l�Ԃ̗R���Ɛ��Ɋ֘A�����I���x�A�����w�l�y�ѓ����̕\��ɂ��āx�ł͐l�ނ̐i���Ɛ��I���ɂ��Ę_�����B�A���Ɋւ��錤���͈�A�̏��ЂƂ��ďo�ł���A�Ō�̌����̓~�~�Y���y��ɗ^����e���ɂ��Ę_���Ă���B
�@
�_�[�E�B���̑�z���݂͂Ƃ߂��A19���I�ɂ����ĉ����ȊO�ō���������s��ꂽ�ܐl�̂����̈�l�ƂȂ����B�E�F�X�g�~���X�^�[���@�ŃW�����E�n�[�V�F���ƃA�C�U�b�N�E�j���[�g���ׂ̗ɖ�������Ă���B2002�NBBC���s�����u100���̍ł��̑�ȉp���l�v���[�ő�4�ʂƂȂ����B�@ |
����������
�@
7�̃`���[���Y�E�_�[�E�B���B�ꂪ���������N�O�B
�@
�`���[���Y�E�_�[�E�B���́A�T���Ȉ�t�œ����Ƃ����������o�[�g�E�_�[�E�B���ƕ�X�U���i�̊ԂɁA6�l�Z���5�Ԗڂ̎q��(���j)�Ƃ��āA1809�N2��12���ɃC���O�����h�A�V�����b�v�V���[�B�V�����[�Y�x���[�Ő��܂ꂽ�B�����̑c���͍����Ȉ�t�E�����w�҂ł���G���Y�}�X�E�_�[�E�B���ł���A����̑c���͓��|�ƁE��ƉƂł���W���T�C�A�E�E�F�b�W�E�b�h�ł���B
�@
�c�����m�͔����w�҂Ƃ��āA�����o�[�g�Əf���W���T�C�A2��(��X�U���i�̒�)�͎��ƉƂƂ��ă_�[�E�B���ƂƃE�F�b�W�E�b�h�Ƃ͐e���ł���A���e�Ȃǐ��g�̍���������A�߂������ʊW�ɂ������B��X�U���i�̓_�[�E�B����8�̎��ɖv���A�L�������C����3�l�̎o����e������Ƃ߂��B���o�[�g�͎v�����[���������A�Ȃ̎��ɂ���Č��i���𑝂��A�q�������ɂ͌������ڂ��邱�Ƃ��������B
�@
�E�F�b�W�E�b�h�Ƃ̓_�[�E�B���̒a�������͊��ɉp�������������Ă������A���ƂƂ����X�͎�Ƀ��j�e���A������̐M�k�������B�_�[�E�B���Ƃ̓z�C�b�O�}�̋}�i�I�Ń��x�����ȍl�����ɓ������Ă����B�ꑰ�̒j���͖����Ȏ��R�v�z�ƂŔ�@���I���������A�����o�[�g�͂�������ɏ]���Ďq�ǂ������ɉp��������Ő�����������B�������_�[�E�B���͌Z�����Ƌ��Ƀ��j�e���A���̋���֒ʂ����B�@ |
���c����
�@
�q���̂��납�甎���w�I����D�݁A8�̎��ɂ͐A���E�L�k�E�z���̎��W���s���Ă����B�����o�[�g�͑c���Ƃ͈قȂ蔎���w�ɋ����͂Ȃ��������A���|������������ߗc���̃_�[�E�B���͎����̏����Ȓ��^�����Ă����B�܂��c���Ɠ����̌Z�G���Y�}�X�͉��w�����ɖv�����Ă���_�[�E�B���Ɏ�`�킹���B�_�[�E�B���͌Z�����Y�ƌĂ�ŕ�����B
�@
1818�N����V�����[�Y�x���[�̊�h�ɍZ�Ŋw��A16��(1825�N)�̎��ɕ��̈�Ƃ������邽�ߐe���𗣂�G�f�B���o����w�ň�w���w�ԁB�������A�l�Ԃ̗������������ŁA�܂������̏W�Ȃǂ�ʂ��Ď��̌��ɑ��������R�E�̑��l���ɖ������Ă������Ƃ���A�������܂���������Ă��Ȃ�����̊O�Ȏ�p��A�A�J�f�~�b�N�ȓ��e�̑ދ��ȍu�`�ɂȂ��߂��A1827�N�ɑ�w�����邱�ƂɂȂ�B���̍��A��Ă̒T�����s�ɓ��s�����o�������鍕�l�̉���z��W�����E�G�h�����X�g�[�����瓮���̔�������p���w�B�_�[�E�B���͔ނ��u���Ɋ������ǂ��Ēm�I�Ȑl�v�ƕ�����B����͌�Ƀr�[�O�����̍q�C�ɎQ���������W�{�����ۂɖ𗧂����B2�w�N�ڂɂ̓v���j�[����(�}�i�I�ȗB���_�ɖ�����ꂽ�����w�̊w�������̃N���u�B�Ñネ�[�}�̔����w�ґ�v���j�E�X�ɂ��Ȃ�)�ɏ������A�C�������̊ώ@�Ȃǂɏ]�������B�_�[�E�B���̓��o�[�g�E�O�����g�̊C�m���Ғœ����̐����Ɖ�U�w�̌�������`�����B������A�O�����g�̓W�������o�e�B�X�g�E���}���N�̐i���v�z���̎^�����B�_�[�E�B���͋��������A���̍��c���̒����ǂݗގ������T�O���A�����Ă��̍l�����_���I�ł��邱�Ƃ�m���Ă����B��w�̔����w�̎��Ƃ͒n���w�̉ΐ����Ɛ������_���Ȃǂ��܂�ł������ދ��������B�܂��A���̕��ނ��w�сA�������[���b�p�ōő�̃R���N�V�������ւ����G�f�B���o����w�����قŌ�������`�����B
�@
�G�f�B���o����w�ŗǂ����ʂ��c�����A���̓_�[�E�B����q�t�Ƃ��邽�߂�1827�N�ɃP���u���b�W��w�N���C�X�g�E�J���b�W�ɓ���A�_�w��ÓT�A���w���w�����B�_�[�E�B���͖q�t�Ȃ�����Ԃ̑������w�ɔ�₷���Ƃ��o����ƍl�����̒�Ă����Ŏ��ꂽ�B�������P���u���b�W��w�ł��͂Ƃ��E�B���A���E�_�[�E�B���E�t�H�b�N�X�ƂƂ��ɕK�C�ł͂Ȃ����������w�⍩���̏W�ɌX�|�����B�t�H�b�N�X�̏Љ�Ő��E�ҁE�����w�҃W�����E�X�e�B�[�u���X�E�w���Y���[�Əo��e�����F�l�A��q�ƂȂ����B�_�[�E�B���͊w���ł́A�w���Y���[���J�݂����뉀���l�ł悭�U�����Ă������ƂŒm���Ă����B��Ƀw���Y���[�Ƃ̏o��ɂ��āA�����̌����ɂ����Ƃ������e����^�����ƐU��Ԃ��Ă���B�܂����������E�҂Œn�w�w�҂������A�_���E�Z�W�E�B�b�O�Ɋw�сA�w���w�ɕ��X�Ȃ�ʍ˔\�������B�����ɓ����̃_�[�E�B���͐_�w�̌��ЃE�B���A���E�y�C���[�́w���R�_�w�x��ǂ݁A�f�U�C���_(�S�Ă̐����͐_���V�n�n���̎��_�Ŋ����Ȍ`�Ńf�U�C�������Ƃ����)�ɔ[�����M�����B���R�N�w�̖ړI�͊ώ@����ՂƂ����A�[�I���_�ɂ���Ė@���𗝉����邱�Ƃ��ƋL�q�����W�����E�n�[�V�F���̐V�����{��A�A���L�T���_�[�E�t���{���g�̉Ȋw�I�T�����s�̖{��ǂB�ނ�́u�R����M�Ӂv�Ɏh������A�M�тŔ����w���w�Ԃ��߂ɑ��Ƃ̂��Ɠ��y�����ƃe�l���t�F�֗��s����v��𗧂āA���̏����Ƃ��ăZ�W�E�B�b�O�̃E�F�[���Y�ł̒n�w�����ɉ�������B
�@
���̎���ɂ͉��y��A��Ɏc��������Ƃ�߂邱�ƂɂȂ�����Ƃ��Ă����B�܂���N�ڂ�1827�N�Ăɂ̓W���T�C�A2���₻�̖��ŏ����̍ȂɂȂ�G�}�E�E�F�b�W�E�b�h�ƃ��[���b�p�嗤�ɗ��s���A�p���ɐ��T�ԑ؍݂��Ă���B����͍ŏ��ōŌ�̃��[���b�p�嗤�؍݂������B
�@
1831�N�ɒ��̏�̐��тŃP���u���b�W��w�𑲋Ƃ����B�����̉Ȋw�j�Ƃ͂��̗���w������_�[�E�B���̐l���̒��ł����ɏd�v�Ȏ����������ƌ��Ă��邪�A�{�l�͂̂��̉�z�^�Łu�w��I�ɂ̓P���u���b�W��w��(�G�f�B���o����w��)���镨�͉����Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B�@ |
���r�[�O�����q�C
�@
1831�N�ɃP���u���b�W��w�𑲋Ƃ���ƁA���t�w���Y���[�̏Љ�ŁA���N���ɃC�M���X�C�R�̑��ʑD�r�[�O�����ɏ�D���邱�ƂɂȂ����B�����o�[�g�͊C�R�ł̐��������E�҂Ƃ��Ă̌o���ɕs���ɂȂ�Ȃ����A�܂��r�[�O�����̂悤�ȏ��^�̃u���b�O�D�͎��̂������������ƂŐS�z���A���̍q�C�ɔ��������A�f���W���T�C�A2���̎��Ȃ��ŎQ����F�߂��B��C�̔����w�҂͑��ɂ���A���o�[�g�E�t�B�b�c���C�͒��̉�b����̂��߂̋q�l�Ƃ��Ă̎Q�����������߁A�C�R�̋K���ɂ���قǔ����邱�Ƃ͂Ȃ������B���������x���͒��ƈӌ��̑Η�������A�̂��Ɂu�R�͂̒��ł́A�͒��ɒʏ�͈̔͂ňӌ��\������̂������ƌ��Ȃ��ꂩ�˂Ȃ������v�Əq�ׂĂ���B
�@
�r�[�O������1831�N12��27���Ƀv���}�X���o�q�����B��ĂɌ������r���ɃJ�[�{���F���f�Ɋ�`�����B�_�[�E�B���͂����ʼnΎR�Ȃǂ��ώ@���A�q�C�L�^�̎��M���n�߂Ă���B���̂��Ɠ�ē��݂�쉺���o�C�[�A���o�ă��I�f�W���l�C���ɗ������ƁA�����Ȋ͂̔����w�҂������͈�}�R�[�~�b�N�����D�������߁A������Ȃ���_�[�E�B�������̌�C�߂邱�ƂɂȂ����B�r�[�O�������C�݂̑��ʂ��s���Ă���ԂɁA�����֒����̒������s�����т��эs���Ă���B�����e�r�f�I���o�ďo�q���炨�悻1�N���1832�N12��1���ɂ̓e�B�G���E�f���E�t�G�S���ɂ����B�r�[�O�����͂��̓�����Ⴂ�j����A��A��A�鋳�t�Ƃ��ċ��炵�A��A���Ă��Ă������A�_�[�E�B���̓t�G�S�����Ɛ鋳�t�ƂȂ����������̈Ⴂ�ɃV���b�N�����B�t�G�S�����͒n�ʂɌ����@�����悤�ȂƂ���ɏZ�݁A�܂�ŏb�̂悤���Ə����L���Ă���B���݂̒����𑱂��Ȃ���1834�N3���Ƀt�H�[�N�����h�����ɗ���������Ƃ��A�w���Y���[���猃��ƕW�{�̎���m�点��莆��������B
�@
1834�N6���Ƀ}�[�����C����ʉ߂��A7���ɓ�Đ��݂̃o���p���C�\�Ɋ�`�����B�����Ń_�[�E�B���͕a�ɓ|��A1���قǗ×{�����B�K���p�S�X�����̃`���^����(�T���E�N���X�g�o����)�ɓ��������̂�1835�N9��15���ł���A10��20���܂ő؍݂����B�����̃K���p�S�X�����͎��l���Y�n�������B�_�[�E�B���͏������n���w�I�ɂ����Â����̂Ƃ͎v���Ȃ���������(���݂ł͂��悻500���N�ƍl�����Ă���)�A�ŏ��]�E�K���͊C���������H������ɘA��Ă������̂��ƍl���Ă������A�K���p�S�X������]�E�K���͏����̂��������ɗl�X�ȕώ킪����A�ڂ����҂Ȃ�Ⴂ�������ɕ�����قǂ��Ƌ������A���߂ăK���p�S�X�����̕ώ�̕��z�ɋC�Â����B�Ȃ��A���̎��A�_�[�E�B�����K���p�S�X�������玝���A�����Ƃ����K���p�S�X�]�E�K���A�n���G�b�g��175�܂Ő����A2006�N6��22���ɐS������̂��ߑ��E���Ă���B
�@
��ʂɂ̓K���p�S�X�����Ń_�[�E�B���t�B���`�̑��l������i���_�̃q���g���ƌ����Ă��邪�A�_�[�E�B���̑��Ղ����������t�����N�E�T���E�F�C�ɂ��A�_�[�E�B���̓K���p�S�X�����؍ݎ��ɂ̓]�E�K����C�O�A�i(�K���p�S�X���N�C�O�A�i����уE�~�C�O�A�i)�A�}�l�V�c�O�~�ɂ�苭���������������B�������܂���̐i���╪���ɋC�����Ă��Ȃ������̂ŁA����͐����̑��l�������̂܂܋L�ڂ��锎���w�I�ȋ����������B���ނ̕W�{�͕s�\���ɂ������W���Ă��炸�A����炪�߉��Ȏ�ł���Ƃ��l���Ă��炸(���V�N�C�ȂǕʂ̒��̈��킾�ƍl���Ă���)�A�ǂ��ō̎悵�����̋L�^���c���Ă��Ȃ������B�K���p�S�X�����珔���̐����̑��l���ɂ��Ď��������Ƃ��ɂ͊��ɏ����̒����\�肪�I������A�_�[�E�B���͂Ђǂ�������Ă���B���ޕW�{�ɂ��Ă͌�Ɍ����ɍۂ��ē��D���Ԃ̃R���N�V�������Q�l�ɂ�����Ȃ������B�܂��W�{���̃t�B���`�ނ�}�l�V�c�O�~�ނ����ꂼ��߉��Ȏ�ł���Ə��߂Ĕ��������̂́A�A����ɕW�{�̐����𐿂����������ފw�҂̃W�����E�O�[���h�������B
�@
1835�N12��30���Ƀj���[�W�[�����h�֊�`���A1836�N1���ɂ̓I�[�X�g�����A�̃V�h�j�[�֓��������B���̌�A�C���h�m�����f���A���[���V���X���Ɋ�`������6���ɃP�[�v�^�E���֓��������B�����ł͓����P�[�v�^�E���ɏZ��ł����V���w�҂̃W�����E�n�[�V�F����K�˂Ă���B�܂��w���Y���[����̎莆�ɂ���āA�C�M���X�Ń_�[�E�B���̔��w�I���������܂��Ă��邱�Ƃ�m�炳�ꂽ�B�Z���g�w���i���ł̓i�|���I���̕揊���U�Ă���B8���ɓ�ăo�C�[�A�ɍĂї�����������V��̕s�ǂ̂��ߓ������ւ̍Ē����͂��Ȃ�Ȃ������B�J�[�{���F���f�A�A�]���X�������o��1836�N10��2���Ƀt�@���}�X�`�ɋA�������B�q�C�͓���3�N�̗\�肾�������A�ق�5�N���o�߂��Ă����B
�@
��Ƀ_�[�E�B���͎��`�ŁA���̍q�C�ň�ۂɎc�������Ƃ��O�����c���Ă���B��͓�ĉ��݂��ړ�����ƁA�������������߉��Ǝv�����ɒu���������Ă����l�q�ɋC�Â������ƁA��߂͓�Ăō��͐����c���Ă��Ȃ���^�̚M���މ����������ƁA�O�ڂ̓K���p�S�X�����̐����̑�������ėR���ƍl������Ȃ��قǓ�Ă̂��̂Ɏ��Ă��邱�Ƃ������B�܂�_�[�E�B���͂��̍q�C��ʂ��āA�씼���e�n�̓�������A�����̈Ⴂ����A�킪�Ɨ����đn���A����ȗ��s�ς̑��݂��Ƃ͍l�����Ȃ��Ɗ�����悤�ɂȂ����B�܂��_�[�E�B���́A�q�C���Ƀ��C�G���́w�n���w�����x��ǂ݁A�n�w���킸���ȍ�p�����ԗݐς����ĕω�����悤�ɁA���A���ɂ��킸���ȕω�������A�������Ԃɂ���Ē~�ς��ꂤ��̂ł͂Ȃ����A�܂��嗤�̕ω��ɂ���āA�V���������n���ł��āA���������̕ω��ɓK��������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�z������Ɏ������B
�@
�_�[�E�B���͂��̍q�C�̂͂��߂ɂ͎������w�̑f�l�ƍl���Ă���A�����̖��ɗ��Ă�Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B�������q�C�̓r���Ŏ�����w���Y���[�̎莆����A�����h���̔����w�҂͎����̕W�{�̏W�Ɋ��҂��Ă���ƒm�莩�M���������B�T���E�F�C�́A�_�[�E�B�������̍q�C�œ������́u�i���̏؋��v�ł͂Ȃ��A�u�Ȋw�I�T���̕��@�v�������Əq�ׂĂ���B�@ |
���A����
�@
�_�[�E�B�����A�������Ƃ��A�w���Y���[���莆���p���t���b�g�Ƃ��Ĕ����w�҂����Ɍ����Ă����̂ʼnȊw�E�ł��łɗL���l�������B�_�[�E�B���̓V���[���Y�x���[�̉ƂɋA��Ƒ��ƍĉ��Ƌ}���ŃP���u���b�W�֍s���w���Y���[�Ɖ�����B�w���Y���[�͔����w�҂��R���N�V�����𗘗p�ł���悤�J�^���O�����A�h�o�C�X���A�A���̕��ނ��������B���q���Ȋw�҂ɂȂ��ƒm�������͑��q�̂��߂ɓ����̏������n�߂��B�_�[�E�B���͋������R���N�V�������ł�����Ƃ�T���ă����h�������삯������B���ɕۊǂ��ꂽ�܂܂̕W�{����u���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@
12�����{�ɃR���N�V���������q�C�L�������������߂ɃP���u���b�W�Ɉڂ����B�ŏ��̘_���͓�A�����J�嗤���������Ɨ��N�����Əq�ׂĂ���A���C�G���̋����x���̂���1837�N1���Ƀ����h���n���w��œǂݏグ���B�����A�M���ނƒ��ނ̕W�{�������h�������w��Ɋ����B���ފw�҃W�����E�O�[���h�͂����ɁA�_�[�E�B�����N���c�O�~�A�A�g���A�t�B���`�̍������킹���ƍl���Ă����K���p�S�X�̒�������12��̃t�B���`�ނ��Ɣ��\�����B2���ɂ̓����h���n���w��̉���ɑI�ꂽ�B���C�G���͉�����Ń_�[�E�B���̉��Ɋւ��郊�`���[�h�E�I�[�E�F���̔����\���A�Ĉ�����x�������̒n���I�A���������������B
�@
1837�N3���ɂ��d�������₷�������h���ɈڏZ���A�Ȋw�҂�`���[���Y�E�o�x�b�W�̂悤�Ȋw�҂̗ւɉ�������B�o�x�b�W�̂悤�Ȋw�҂͂��̓s�x�̊�ՂŐ������n�����ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�ނ��됶������鎩�R�@����_���p�ӂ����ƍl���Ă����B�����h���Ń_�[�E�B���͎��R�v�z�ƂƂȂ��Ă����Z�G���Y�}�X�Ƌ��ɕ�炵���B�G���Y�}�X�̓z�C�b�O�}���ŁA��ƃn���G�b�g�E�}�e�B�m�[�Ɛe�����F�l�������B�}�e�B�m�[�͕n�����l�X���H�Ƌ������z���đ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��悤�ɍs��ꂽ�A�z�C�b�O�}�̋~�n�@�����̊�b�ƂȂ����g�}�X�E�}���T�X�̃A�C�f�B�A�𐄐i�����B�܂��_�[�E�B���̗F�l�������s���m�ŎЉ���ɂƂ��Ċ댯���ƌ����đނ����O�����g�̈ӌ��ɂ������X�����B
�@
�_�[�E�B���̒������ʂ��c�_���邽�߂ɍs��ꂽ�ŏ��̉�ŁA�O�[���h�͈قȂ铇����W�߂�ꂽ�K���p�S�X�}�l�V�c�O�~������ł͂Ȃ��ʂ̎킾�������ƁA�t�B���`�̃O���[�v�Ƀ~�\�T�U�C���܂܂�Ă������Ƃ��������B�_�[�E�B���͂ǂ̕W�{���ǂ̓�����̏W�������L�^��t���Ă��Ȃ��������A�t�B�b�c���C���܂ޑ��̏�g���̃��������ʂ��鎖���ł����B�����w�҃g�[�}�X�E�x���̓K���p�S�X�]�E�K�������̌��Y�ł���Əq�ׂ��B3�����{�܂łɃ_�[�E�B���͐�Ŏ�ƌ�����̒n���I���z�̐����̂��߂ɁA�u�킪���̎�ɕς��v�\�����l���n�߂��B7�����{�Ɏn�܂�uB�v�m�[�g�ł͕ω��ɂ��ĐV�����l�����L���Ă���B�ނ̓��}���N�́u��̌n������荂���Ȍ`�ԂւƑO�i����v�Ƃ����l�����̂Ă��B�����Đ�������̐i�������番��n�����ƌ��Ȃ��n�߂��B�u��̓��������̓��������������ƌ����͕̂s�����ł���v�B
�@
��̕ω��Ɋւ��錤���W������Ɠ����ɁA�����̓D���ɓ��荞��ł������B�܂��q�C�L�����������Ă���A�R���N�V�����Ɋւ�����Ƃ̃��|�[�g�̕ҏW���s���Ă����B�w���Y���[�̋��͂Ńr�[�O�����q�C�̓����L�^�̑咘�����������邽�߂�1000�|���h�̎��������𐭕{��������o�����B�_�[�E�B���͓�A�����J�̒n���Ɋւ���{��ʂ��ă��C�G���̐Ĉ�����x������A�C�̉����Ȃ�悤�Ȓ������Ԃ����݂������Ƃ�F�߂��B���B�N�g���A���������ʂ������傤�ǂ��̓��A1837�N6��20���ɍq�C�L�������I�������C���̂��߂ɂ܂��o�łł��Ȃ������B���̍��_�[�E�B���͑̂̕s���ɋꂵ��ł����B9��20���Ɂu�S���ɕs���ȓ����v���o�����B��҂͑S�Ă̎d�����グ��2�A3�T�Ԃ͓c�ɂŗ×{����悤���߂��B�E�F�b�W�E�b�h�Ƃ̐e�ʂ�K�˂邽�߂ɃV���[���Y�x���[��q�˂����A�E�F�b�W�E�b�h�Ƃ̐l�X�͍q�C�̓y�Y�b��������x�މɂ�^���Ȃ������B9�����N��̂��Ƃ��G�}�E�E�F�b�W�E�b�h�͕a���̏f����Ō삵�Ă����B�W���X����(�W���T�C�A�E�E�F�b�W�E�b�h2��)�͒n�ʂɒ��ݍ��R��������w���āA�~�~�Y�̓����ł��邱�Ƃ����������B11���Ƀ����h���n���w��ł��̘b�\�������A����̓~�~�Y���y��̐����ɉʂ������������ؓI�Ɏw�E�����ŏ��̃P�[�X�������B
�@
�E�B���A���E�q���[�E�F���͒n���w��̎����ǒ��Ƀ_�[�E�B���𐄑E�����B��x�͎��ނ������A1838�N3���Ɉ������B�r�[�O�����̕��̎��M�ƕҏW�ɋꂵ��ł����ɂ�������炸�A��̕ω��Ɋւ��Ē��ڂɒl����O�i�������B�v���̔����w�҂���͂������A�K���ɂƂ��ꂸ�ɔ_����n�g�̈��ƂȂǂ�������ۂ̌o���k���@����Ȃ������B�e�ʂ�g�p�l�A�אl�A���A�ҁA���D�����ԂȂǂ�������������o�����B�ŏ�����l�ނ𐄘_�̒��Ɋ܂߂Ă���A1838�N3���ɓ������ŃI�����E�[�^�������߂Č��J���ꂽ�Ƃ��A���̎q�ǂ��Ɏ����U�镑���ɒ��ڂ����B6���܂ʼn������݉��A���ɁA�S���̕s���ŋꂵ�B�c��̐l���̊ԁA�ݒɁA�q�f�A�����������o���A�����A�k���Ȃǂ̏Ǐ�ł����Ή������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B���̕a�C�̌����͓��������m���Ă��炸�A�����̎��݂͐������Ȃ������B���݁A�V���[�K�X�a���������̐S�̕a����������Ă��邪���炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B6�����ɂ̓X�R�b�g�����h�ɒn�������̂��߂ɏo�������B���s�ȁu���v���R�̒����ɎO�{�����Ă��邱�ƂŗL���ȃO�����E���C���ώ@�����B��ɂ���͊C�ݐ��̍����Ɣ��\�������A�X�͊��ɂ����~�߂��Ăł����̍����Ǝw�E���ꎩ����P�邱�ƂɂȂ����B���̏o�����͐��}�Ɍ��_�ɑ��邱�Ƃւ̉��߂ƂȂ����B�̒������S�ɉ����7���ɃV���[���Y�x���[�ɖ߂����B�@ |
������
�@
�o�L�������C���ƃG�}�̌Z�W���T�C�A3����1838�N�Ɍ�������ƃ_�[�E�B�����������ӎ����n�߂��B1838�N7���ɁA�����̔ɐB���������߂��m�[�g�ɏ����̌��ʂ��ɂ��ē�̑��菑���������B�g�����h�Ɓg�������Ȃ��h�B���_�ɂ͎��̂悤�ɏ������B�u�i���̔����A�N���Ƃ��Ă���̗F�l�c�c������ɂ��挢���܂��v�B���_�ɂ��Ă͎��̂悤�ɏ������B�u�{�̂��߂̂���������A�����낵�����Ԃ̖��ʁv�B
�@
���ǃ_�[�E�B����11���Ƀv���|�[�Y���A1839�N1���Ɍ��������B��������߂��Ă����ɂ�������炸�_�[�E�B���͎����̔�@���I�ȍl����b�����B�G�}�͎��ꂽ���A�����`�������莆�̂��Ƃ�ŁA��l�̍��ق����L���������������ق߂�Ɠ����Ɏ����̃��j�e���A���̋����M�ƕv�̗����ȋ^�O�������œ�l�𗣂�Ȃ�ɂ��邩���m��Ȃ��ƌ��O��ł��������B�G�}�͐M�S���Ă��u������Nj����Ă������������Ȃ����ƁA�l���m��K�v�̂Ȃ����Ƃɂ܂ŕK�v�ȏ�ɉȊw�I�T�����������܂Ȃ��łق����v�Ƃ������Ă���B�_�[�E�B���������h���ʼnƂ�T���Ă���Ԃɂ��a�C�͑������B�G�}�́u��������ȏ㈫���Ȃ�Ȃ��ň����̃`���[���[�A������������ɂ��Ă��Ȃ����ŕa�ł���悤�ɂȂ�܂Łv�Ǝ莆�������A�x�݂����悤�i�����B���ǃK�E�A�[�ʂ�ɉƂ������A�N���X�}�X�ɂ͂��́u�����فv�ֈ����z�����B1839�N1��24���Ƀ_�[�E�B���̓����h����������̉���ɑI�o����A5�����29���Ƀ��A�̉p��������Ń��j�e���A�����ɃA�����W���ꂽ���������s��ꂽ�B�����I���Ɠ�l�͂����ɓS���Ń����h�����������B12���ɂ͒��j�E�B���A�����a�������B
�@
1839�N�ɂ̓r�[�O�����q�C�̋L�^���t�B�b�c���C�͒��̒���ƍ��킹���O���{�̈���Ƃ��ďo�ł���D�]�����B�����1843�N�܂łɑS�܊��́w�r�[�O�����q�C�̓����w�x�Ƃ��ēƗ����ďo�ł���A���̌������Ɖ������J��Ԃ����B������1842�N����w�r�[�O�����q�C�̒n���w�x�S�O�����o�ł��ꂽ�B�@ |
�����R�I����ւ̓��B
�@
�����h���Ō����𑱂��Ă���Ƃ��ɁA�g�}�X�E�}���T�X�́w�l���_�x��Z�ł�ǂ�Ŏ��̂悤�ɏq�ׂ��B
�@
1838�N11���A�܂莄���̌n�I�Ɍ������n�߂�15������ɁA���͂��܂��ܐl���Ɋւ���}���T�X���C���炵�ɓǂ�ł����B���A���̒����p���I�Ȋώ@���玊�鏊�ő��������̂��߂̓w�͂𗝉��ł����B�����Ă��̏��ł͍D�܂����ψق͕ۑ�����A�D�܂�����ʂ��͔̂j���X�������邱�Ƃ������Ɏ��̐S�ɕ����B���̌��ʁA�V�����킪�`������邾�낤�B�����ŁA�����Ď��͋@�\���闝�_�����ɓ���...C.R.�_�[�E�B�� �w���`�x
�@
�}���T�X�͐l�Ԃ̐l���͗}������Ȃ���Γ��䐔��I�ɑ������A�����ɐH�Ƌ������z���j�ǂ��N����Ǝ咣�����B�_�[�E�B���͂����ɂ�����h�E�J���h���̐A���́u��̌��v��쐶�����̊Ԃ̐����̂��߂̓w�͂ɉ��p���Č������A��̐����ǂ̂悤�ɂ��đ�܂��ɂ͈��肷�邩��������鏀�����ł��Ă����B�������ɐB�̂��߂ɗ��p�ł��鎑���ɂ͌��肪����̂ŁA�D�܂����ψق��������̂͂�萶�����єނ�̎q���ɂ��̕ψق�`����B�����ɍD�܂����Ȃ��ψق͎����邾�낤�B���̌��ʁA�V��͒a�����邾�낤�B1838�N9��28�ɂ��̓��@�������t���A�����т̂悤�Ȃ��̂ƋL�q�����B�ア�\���͉����o����A�K���I�ȍ\���͎��R�̌o�ς̌��Ԃɉ������߂���B������t�������āA�_���������Ƃ������ꂽ�̂�ɐB�֗p����̂Ɣ�r���A�}���T�X�I���R���u�\���v�ɂ���ĕψق����グ�A���̌��ʁu�V���Ɋl�������\���̂����镔���͊��S�ɏn�����Ă��芮�����v�Əq�ׂ��B�����Ă��̃A�i���W�[�������̗��_�ł����Ƃ������������ƍl�����B
�@
�_�[�E�B���͍��⎩�R�I���̗��_�̃t���[�����[�N�������Ă����B�ނ̌����͒{�Y�w����A���̍L�͂Ȍ����܂Ŋ܂B�킪�Œ肳��Ă��Ȃ��Ƃ����؋��̔����A�A�C�f�B�A�̍ו���������邽�߂̒������s�����B10�N�ȏ�A���̌����̓r�[�O�����q�C�̉Ȋw�I�ȃ��|�[�g���o�ł���Ƃ�����v�Ȏd���̉A�ōs���Ă����B
�@
1842�N�̂͂��߂Ƀ��C�G���Ɉ��ĂĎ����̍l����`���A���C�G���͖��F���u�e�X�̎�̎n�܂�����鎖�����ۂ���v�ƋL�����B5���ɂ�3�N�̌������o�ĎX��ʂɊւ��錤���\�����B���ꂩ��u�y���V���X�P�b�`�v�Ƒ肵�ė��_�������n�߂��B9���ɂ̓����h���̕s�q���ƌ���������ă����h���ߍx�̃_�E�����Ɉ����z�����B1844�N1��11���ɃW���Z�t�E�_���g���E�t�b�J�[�Ɏ����̗��_���u�E�l����������悤�Ȃ��̂ł����v�ƓY���đł��������B�t�b�J�[�͎��̂悤�ɓ������B�u���̍l���ł́A��A�̈قȂ�_�̐����ƁA�Q�i�I�Ȏ�̕ω����������̂����m��Ȃ��B���͂ǂ̂悤�ɕω����N�������̂����Ȃ��̍l�����Ċ������B����Ȃɑ������̖��ň��S�ł���Ƃ͎v��Ȃ������B�v
�@
7���܂łɂ͑������Ƃ��ɔ����āu�X�P�b�`�v��230�y�[�W�́u�G�b�Z�C�v�Ɋg�����A�������̎��ɂ͑���ɏo�ł���悤�Ȃɗ��B11���ɂ͓����ŏo�ł��ꂽ�i���Ɋւ��钘���w�n���̎��R�j�̍��Ձx�����L���_���������N�������B���̖{�͈�ʐl�̎�̕ω��ɑ���S�������N�����A�x�X�g�Z���[�ƂȂ����B�_�[�E�B���͂��̑f�l�̂悤�Ȓn���w�Ɠ����w�̋c�_����R�������A�����Ɏ��g�̋c�_��T�d�Ɍ��������B1846�N�ɂ͒n���w�Ɋւ���O�Ԗڂ̖{�������������B���ꂩ��C�����Ғœ����̌������n�߂��B�w������Ƀ��o�[�g�E�O�����g�ƂƂ��ɍs�����悤�ɁA�r�[�O�����q�C�Ŏ��W�����t�W�c�{����U�����ނ����B�������\���̊ώ@���y���݁A�߉���ƍ\�����r���Ďv�������B
�@
1847�N�Ƀt�b�J�[�̓G�b�Z�C��ǂ݁A�_�[�E�B�����]�d�v�Ȋ��z���������������A�p���I�ȑn���s�ׂւ̃_�[�E�B���̔��ɋ^���悵�A�܂��^�����Ȃ������B1851�N�ɂ͂����Ƃ����킢�����Ă������̃A�j�[��10�Ŏ��������B8�N�ɂ킽��t�W�c�{�̌����͗��_�̔��W���������B�ނ͑���������A�킸���ɈقȂ����̂̊튯���V�������ŕK�v�����悤�ɏ\���@�\���邱�Ƃ������B�܂��������̑��ŃI�X�����Y���̌̂Ɋ��Ă��邱�Ƃ����A�̐i���̒��ԓI�Ȓi�K�������Ă��邱�ƂɋC�t�����B
�@
1848�N�ɂ͕����o�[�g���v�����B��҂Ƃ��Đ������������_�[�E�B���͐��U�h�����Ă����B���̍��̃_�[�E�B���Ƃ͕���f���̎c�������Y�̉^�p�Ő��v�𗧂ĂĂ����B100�|���h�Œ����̕�炵���ł��������ɁA�v�Ȃ͕��Əf������900�|���h�̎x�����Ă��āA�ӔN�ɂ͔N8000�|���h�̉^�p�v���������ƌ�����B�_�[�E�B���Ɠ����悤�Ɉ�҂�ڎw�����܂����Z�G���Y�}�X���̂��Ƀ_�E���ɈڏZ���A���̍��Y�ŗD��ȉB�ِ����𑗂��Ă����B1850�N�ɂ͐��E�q�C����A�������g�}�X�E�n�N�X���[�ƒm�荇���Ă���B
�@
1853�N�ɉ�������烍�C�����E���_������܂��A�����w�҂Ƃ��Ă̖��������߂��B1854�N�ɍĂю�̗��_�̌������n�߁A11���ɂ͎q���̓����̍��ق��u���l�����ꂽ���R�̌o�ς̈ʒu�v�ɓK�����Ă��邱�Ƃŏ�肭�����ł���ƋC�t�����B�@ |
���_�[�E�B���̐i���_
�@
�����R�I���
�@
�����̐i���́A���ׂĂ̐����͕ψق������A�ψق̂����̈ꕔ�͐e����q�֓`�����A���̕ψق̒��ɂ͐����ƔɐB�ɗL�����������炷��������ƍl�����B�����Č���ꂽ�������̓��m�������A���݂������邽�߂̓w�͂��J��Ԃ����Ƃɂ���ċN���鎩�R�I���ɂ���Ĉ����N�������ƍl�����B
�@
���l���`����`�̎x���ƃp���Q�����̒�
�@
��`�ɂ��Ă̓p���Q����(�p���Q�l�V�X)�Ƃ������������Đ��������B����́u�W�F�~���[���v(en:Gemmules)�Ƃ��������ȗ��q���̓�������A�e�튯�Ŋl����������~���A���B�זE�ɏW�܂�A�����E�`�����q�Ɏp����A�q�̑̂ɂ����Ċe�튯�ɕ��U���邱�ƂŐe�̓�����`����A�Ƃ������ł���B�_�[�E�B���́A���}���N�Ɠ����悤�Ɋl���`���̈�`���x�����Ă����̂ł���B
�@
�����f���̈�`�̖@���͓����܂��m���Ă��Ȃ������B�����͈�`�����̗Z����(��`��`���镨�����������Ƃ��Ă��A����͎q���ł���ߒ��Ŋ��S�ɗZ������)���L���m���Ă������A�_�[�E�B���̓����f�����s���������Ɠ����悤�ɁA�X�C�[�g�s�[�̌��G�����Ō`�����K�������Z������킯�ł͂Ȃ��Ƃ��~�߂Ă����B�������t���~���O�E�W�F���L�����s�����ψق͗Z�����邩��W�c���Ɉێ�����Ȃ��Ƃ����ᔻ�ɏ�肭�����邱�Ƃ��ł������U�_�[�E�B����Y�܂����B�܂��ψق��ǂ̂悤�ɒa������̂���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�_�[�E�B���͓����̑����̉Ȋw�҂Ɠ������i���Ɣ�������ʂ��Ă��炸�A�H���┭�����̎h���ɂ���ĐV���ȕψق����܂��ƍl�����B���̖��͌�ɓˑR�ψق����������܂ʼn�������Ȃ������B
�@
�����f���̈�`�Ɋւ���_�����_�[�E�B���̏��ɂ��疢�J���̂܂܌��������Ƃ����邪�A����͌㐢�̍��b�Ń����f���̎������_�[�E�B�����m�邱�Ƃ͂Ȃ�����(�����f�����g�́w��̋N���x�������Ă������A�قƂ�ǖڂ�ʂ��Ă��Ȃ�����)�B
�@
�����I���ɑ��錩��
�@
���R�I���\�ȕ��ƌ��Ȃ����E�H���X�̓N�W���N�̉H��S�N���N�`���E�̒������H�ȂǁA�ꌩ�����̖��ɗ����������Ȃ������ɂ��K���I�ȈӖ�������̂��낤�ƍl�����B�_�[�E�B���͂��̉\����ے�����Ȃ��������A�����̐����Ŏ����p�[�g�i�[�I�т̎哱���������Ă��邱�ƂɋC�Â��Ă���A�����ɗL���łȂ����������̐R����̂悤�Ȃ��̂Ŕ��B���邱�Ƃ�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����B�����Ď��R�I����Ƃ͕ʂɐ��I������������B����ɐ���(�����̐����ŗY�Ǝ��̔䗦��1��1�ɂȂ邪�A�ꕔ�̐����ł͕肪���邱��)��I��^�̖������߂ĉȊw�I�ɍl�@���鉿�l������ƍl�����B���ɐ���Ɋւ��Ă͐����i���̎��_��������ł���ƍl���A��ɕp�x�ˑ��I��(�p�x�ˑ������A�����ƔɐB�\�������R���ɍ��E�����̂ł͂Ȃ��A�O���[�v���̂��̐����̑��ǂɈˑ�����A�܂肠�鐫�����u�����h�ł���v���Ƃ����Ő����ƔɐB�ɗL���ɓ�������)�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�T�O����肵�Ă����B�������A�����̖��͕��G�Ȃ̂Ō㐢�Ɏc�����������S���낤�Ƃׁ̂A���m�ȓ������c���Ȃ������B
�@
�V���Ȏ킪�`������郁�J�j�Y�����핪���ƌĂ��A�ǂ̂悤�ȃ��J�j�Y���ł��ꂪ�N����̂��͐[���Nj����Ȃ������B���̂��ߔނ̎���A���R�I�������Ŏ핪�����N���邩�ǂ����ŋc�_���N�������B�@ |
�����R�I����̌��\
�@
1856�N�̂͂��߂ɗ��Ɛ��q������C���z���Ċg�U���邽�߂ɊC���̒��Ő����c��邩�ǂ����ׂĂ����B�t�b�J�[�͂܂��܂��킪�Œ肳��Ă���Ƃ����`���I�Ȍ������^���悤�ɂȂ����B�������ނ�̎Ⴂ�F�l�g�}�X�E�n�N�X���[�͂͂�����Ɛi���ɔ����Ă����B���C�G���͔ނ�̖��ӎ��Ƃ͕ʂɃ_�[�E�B���̌����ɋ�����������Ă����B���C�G������̎n�܂�Ɋւ���A���t���b�h�E�E�H���X�̘_����ǂƂ��A�_�[�E�B���̗��_�Ƃ̗ގ��ɋC�t���A��挠���m�ۂ��邽�߂ɂ����ɔ��\����悤�������B�_�[�E�B���͋��ЂƊ����Ȃ��������A������ĒZ���_���̎��M���J�n�����B����ȋ^��ւ̉��݂��邽�тɘ_���͊g������A�v��́w���R�I���x�Ɩ��t����ꂽ�u����Ȗ{�v�ւƊg�債���B�_�[�E�B���̓{���l�I�ɂ����E�H���X���n�ߐ��E���̔����w�҂�����ƕW�{����ɓ���Ă����B�A�����J�̐A���w�҃G�C�T�E�O���C�͗ގ������S������A�_�[�E�B���̓O���C��1857�N9���Ɂw���R�I���x�̗v����܂ރA�C�f�B�A�̏ڍׂ������������B12���Ƀ_�[�E�B���͖{���l�Ԃ̋N���ɂ��ĐG��Ă��邩�ǂ����q�˂�E�H���X����̎莆��������B�_�[�E�B���́u�Ό��Ɉ͂܂�Ă��܂��v�ƃE�H���X�����_����Ă邱�Ƃ��܂��A�u���͂��Ȃ������y���ɐ�ɐi��ł��܂��v�ƕt���������B
�@
1858�N6��18���Ɂu�ψق����Ƃ̌^���疳���ɗ���Ă����X���ɂ��āv�Ƒ肵�Ď��R�I�����������E�H���X����̏��_��������Ƃ��A�܂��w���R�I���x�͔��������i��ł��Ȃ������B�u�o�@���������ꂽ�v�ƏՌ������_�[�E�B���́A���߂�ꂽ�Ƃ��菬�_�����C�G���ɑ���A���C�G���ɂ͏o�ł���悤���܂�Ă͂��Ȃ����E�H���X���]�ނǂ�ȎG���ɂł����\����Ɠ��������ł��ƌ����Y�����B���̎��_�[�E�B���̉Ƒ����͍g�M�œ|��Ă�����ɑΏ�����]�T�͂Ȃ������B���Ǘc���q�ǂ��`���[���Y�E�E�H�[�����O�͎��ɁA�_�[�E�B���͎�藐���Ă����B���̖��̓��C�G���ƃt�b�J�[�̎�Ɉς˂�ꂽ�B��l�̓_�[�E�B���̋L�q���ꕔ(1844�N�́u�G�b�Z�[�v����̔���)�Ƒ��(1857�N9���̐A���w�҃O���C�ւ̎莆)�Ƃ��A�E�H���X�̘_�����O���Ƃ����O���\���̋����_���Ƃ���1858�N7��1���̃����h�������l�w��ő�ǂ����B
�@
�_�[�E�B���͑��q�����S�������ߌ��Ȃ�����������A�E�H���X�͋�����ł͂Ȃ����}���[�����ւ̍̏W���s���������B���̋������\�́A�E�H���X�̗��������̂ł͂Ȃ��������A�E�H���X�������҂Ƃ��ďd��Ɠ����ɁA�E�H���X�̘_�����Â��_�[�E�B���̋L�q�\���邱�Ƃɂ���āA�_�[�E�B���̐�挠���m�ۂ��邱�ƂƂȂ����B�@ |
���w��̋N���x�ւ̔���
�@
���̔��\�ɑ���S�͓����قƂ�ǖ��������B8���Ɋw��Ƃ��Ĉ������A���̎G���ł����x�����グ��ꂽ���ߎ莆�ƃ��r���[�����������������A�w��͗��N�̉����Ŋv���I�Ȕ����������Ȃ������Əq�ׂ��B�_�u������w�̃T�~���G���E�z�[�g�[�������́u�ނ炪�V�����ƍl�����S�Ă͌�肾�����B�������̂͌Â��l�����������v�Əq�ׂ��B�_�[�E�B����13�����ԁA�u����Ȗ{�v�̗v��Ɏ��g�B�s���N�ɋꂵ���Ȋw��̗F�l�����͔ނ��܂����B���C�G���̓W�����E�}���[�Ђ���o�łł���悤��z�����B1859�N11��22���ɔ������ꂽ�w��̋N���x�͗\�z�O�̐l�C�����B����1250���ȏ�̐\�����݂��������B
�@
�����Ƃ�����͎��R�I����������Ɏ����ꂽ����ł͂Ȃ��B�����A���łɐ����̐i���Ɋւ��钘��͂��������\����Ă���A�������f�n�͂������B���̖{�́w�n���̎��R�j�̍��Ձx�������Ȃ��_���Ƒ傫�Ȋ��}�ƂƂ��ɍ��ۓI�ȊS���������B�a�C�̂��߂Ɉ�ʓI�Ș_���ɂ͉����Ȃ��������A�_�[�E�B���ƉƑ��͔M�S�ɉȊw�I�Ȕ����A�̃R�����g�A���r���[�A�L���A���h������`�F�b�N���A���E���̓����ƈӌ������������B�_�[�E�B���͐l�Ԃɂ��Ắu�l�ނ̋N���ɂ�����������������v�Ƃ�������Ȃ��������A�ŏ��̔�]�́w���Ձx�́u�T���ɗR������l�ԁv�̐M����^�����ď����ꂽ�Ǝ咣�����B�����̍D�܂��������̂ЂƂł���n�N�X���[�̏��]�̓��`���[�h�E�I�[�E�F����ɑł��A�Ȍ�I�[�E�F���̓_�[�E�B�����U�����鑤�ɉ�������B�I�[�E�F���̔����͊w��I�Ȏ��i�����@�������Ƃ������A���I�Ȍ𗬂��r�₦�邱�ƂɂȂ����B�P���u���b�W��w�̉��t�Z�W�E�B�b�O��������j�镨���Ƃ��Ĕᔻ����(���A�Z�W�E�B�b�O�Ƃ͐��U�F�D�I�ȊW��ۂ���)�B�w���Y���[�����₩�ɂ����ނ����B�i���_�̍\�z�ɋ��͂��Ă������C�G���͂����ɂ͑ԓx�𖾂炩�ɂ����A�ŏI�I�ɂ͗��_�Ƃ��Ă͂��炵���ƕ]���������A��͂蓹���I�A�ϗ��I�Ɏ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ����ă_�[�E�B���𗎒_�������B�w�����L�x�Œm����t�@�[�u�������Ύ҂̈�l�ŁA�_�[�E�B���Ƃ͎莆�ňӌ��̌����������������ӌ��̍��v�ɂ͎���Ȃ������B
�@
�_�[�E�B���͂��܂�̔����̌������Ɂu���̗��_���������̂ɂ͎�̐i���Ɠ��������̎��Ԃ������肻�����v�Əq�ׂ��B�������t�b�J�[�A�g�}�X�E�w�����[�E�n�N�X���[�Ȃǂ̎x���҂̎x�����Ă��̊w���͎���ɎЉ�ɂ�����F�m�Ɖe���͂��g�債���B
�@
�����w�҂̃x�C�c��~�����[���x���҂ɖ���A�ˁA�i���_��⋭����l�X�Ȏ���������B�A�����J�ł̓n�[�o�[�h��w�̒����ȐA���w�҂������G�C�T�E�O���C���A�h�C�c�ł̓G�����X�g�E�w�b�P�����i���_�̕��y�ɓw�߂��B
�@
�p��������̔����͗l�X�������B���t�Z�W�E�B�b�O�ƃw���Y���[�͂��̍l����ނ������A���R��`�I�Ȑ��E�҂͎��R�I����_�̃f�U�C���̓���Ɖ��߂����B�q�t�A�����w�҃`���[���Y�E�L���O�Y���[�́u�܂��������h�ȗL�_�_�̊T�O�v�ƌ��Ȃ����B1860�N�ɏo�ł��ꂽ7�l�̉p��������̎��R��`�_�w�҂ɂ��w�G�b�Z�C�E�A���h�E���r���[�x�͑n������ɗ�ɔᔻ���Ă������A�p��������̎w�����ɂ���Ĉْ[�ƍU�����ꂽ�B���̖{�̓_�[�E�B�����璍�ӂ����炷���ƂɂȂ����B���̒��Ńx�[�f���E�p�E�G���͊�Ղ��_�̖@����j��A�ނ�̐M�O�͖��_�_�I���Ǝ咣���A�����Ɂu�_�[�E�B�����̂��炵������͎��R�̎��Ȑi���̗͂̑s��Ȍ���[���x������]�v�Ə̎^�����B�G�C�T�E�O���C�͖ړI�_�ɂ��ă_�[�E�B���Ƌc�_���A�ނ̗L�_�_�I�i���Ǝ��R�I���͎��R�_�w�Ƒ������Ȃ��Ƃ����p���t���b�g�͗A������Ĕz�z���ꂽ�B
�@
1860�N�ɂ̓I�b�N�X�t�H�[�h��w�ŁA�n�N�X���[�A�t�b�J�[��x���҂ƃE�B���o�[�t�H�[�X��i���甽�Ύ҂ɂ�铢�_��s��ꂽ�B��ʂɒm����悤�ɁA��i��������I�ɘ_�j���ꂽ�킯�ł͂Ȃ�(�E�B���o�[�t�H�[�X�́u��̕ω��ɔ��͂��Ȃ����A�_�[�E�B���̐����ɂ͔��ł���v�Əq�ׂ��B�܂������w�̒m�����Ȃ��������ߐ����Ɗ���ɂ̂݊�Â��Ę_���A�c�_�͂��ݍ���Ȃ�����)�o�������������Ǝ咣�����B���O�͗��h�ɕق������҂ɐ���Ȕ���𑗂����B���������̓��_�͐i���_�̒m���x�������グ�邱�ƂɂȂ����B1877�N�A�P���u���b�W��w�̓_�[�E�B���ɖ��_���m�������B
�@
�E�H���X��1858�N�ɑ������ŏ��̎莆�ł�(���߂ăE�H���X���_�[�E�B���Ɏ莆�𑗂����̂�1856�N���ƌ�����)�A��͕ώ�Ɠ��������Ő��܂��̂ł͂Ȃ����A�����Ēn����C��̗v�����傫���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�����������(�����̑n���_�ł͎�͐_��������s�ςȂ��̂����A�����ώ�͕i����ǂȂǂŒa��������Ƃ���������������)�B���������N�ɍĂё����Ă������̎莆�ł̓}���T�X�́w�l���_�x�����f����Ă���_�[�E�B���̎��R�I����ɋ߂����̂ɂȂ��Ă����B���������̍��_�[�E�B���͐��ԓI�n�ʂ�K�����U�ɂ܂ōl�@���y��ł����B���N�o�ł��ꂽ�w��̋N���x��ǂE�H���X�́u�����Ȏd���Ŏ����͉����y�Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B
�@
�_�[�E�B���̐e�����F�l�O���C�A�t�b�J�[�A�n�N�X���[�A���C�G���ł����l�X�ȗ��ۂ�\���������A����ł��Ⴂ������̔����w�҂����Ƌ��ɏ�Ƀ_�[�E�B�����x�����������B�n�N�X���[���@���ƉȊw�̕������咣�������ŁA�O���C�ƃ��C�G���͘a����]�B�n�N�X���[�͋���ɂ����鐹�E�҂̌��Ђɑ��čD��I�ɘ_�w��A�Ȋw���x�z���鐹�E�҂ƋM���I�ȃA�}�`���A�̗D�ʂ�]�����悤�Ǝ��݂��B���̎��݂ł̓I�[�E�F�����n�N�X���[�Ɠ������ɂ������A�I�[�E�F���͌�����q�g�Ɨސl���̔]�̉�U�w�I���قɊ�Â��A�n�N�X���[���u�q�g�̗ސl���N���v���咣�����ƍ��������B�����Ƃ��n�N�X���[�͂��傤�ǂ�����咣���Ă����B2�N�ɂ킽��n�N�X���[�̃L�����y�[���̓I�[�E�F���Ɓu�ێ�h�v��Ǖ����邱�ƂɌ��I�ɐ��������B
�@
�_�[�E�B���͎��R�I���̔������E�H���X�ɒf��Ȃ��������\�Ƃ������Ƃ��A�蕿�̉����Ǝ~�߂��邱�Ƃ��ꂽ�B�������E�H���X�͂ނ��낻�̍s�ׂɖ������A�_�[�E�B�������S�������B���R�I���ȊO�͑����̓_�ňӌ����قɂ��Ă����ɂ�������炸�A�E�H���X�ƃ_�[�E�B���̗F�D�I�ȊW�͐��U�������B�����������҈ȊO�ł��̍s�ׂ���������҂�����A�蕿������肵���Ƃ����ᔻ������邱�Ƃ͂ł����A���̌`�̔ᔻ�͌��݂ł��c�����Ă���B�_�[�E�B���͌�N�A�����ɍ������Ă����E�H���X�������邽�߁A�O���b�h�X�g���ɔN�����t��������Ȃǎx�����s���Ă���B
�@
�w��̋N���x�͑����̌���ɖ|�ꂽ�B�����ăn�N�X���[�̍u�`�ɌQ�������l�X�ȕ���̎�����̌����҂̊S���������A�ނ�̎�v�ȉȊw�̃e�L�X�g�ƂȂ����B�_�[�E�B���̗��_�͓����̗l�X�ȉ^���Ɏ�������A��O�����̃J�M�ƂȂ����B�_�[�E�B�j�Y���Ƃ�����͔��ɍL�͂Ȑi���v�z���܂ޗp��ƂȂ����B1863�N�̃��C�G���́wGeological Evidences of the Antiquity of Man�x�͐i���ɔᔻ�I�Ń_�[�E�B���𗎒_���������A��j����ւ̑�O�̊S���������B���T�Ԍ�A�n�N�X���[�́w���R�ɂ�����l�Ԃ̈ʒu�x�͉�U�w�I�ɐl�ނ͗ސl���ł��邱�Ƃ��������B�w�����[�E�x�C�c�́w�A�}�]���͂̔����w�ҁx�Ŏ��R�I���̌o���I�ȏ؋�������B�F�l�����̊�����1864�N11��3���̃_�[�E�B���̃R�v���E���_����܂������炵���B���̓��A�n�N�X���[�́u�Ȋw�̏������Ǝ��R�A�@���I�h�O�}����̉���v��ڎw��X�N���u�̍ŏ��̉���J�����B�@ |
���l�Ԃ̗R���Ɛ��I��
�@
�l���̍Ō��22�N�Ԃ��a�C�̓x�d�Ȃ锭��ɔY�܂��ꂽ���������p�������B���_�̗v��Ƃ��āw��̋N���x���o�ł������A�������u����Ȗ{�v�̘_���I�Ȗʂɂ��Ă͏\���ɏq�ׂĂ��Ȃ������B�_���I�ȖʂƂ͑��̓�������̐l�ނ̒a���ƁA�q�g�̐��_�\�́E�����Љ�̌����ɂ��Ăł���B����ɂ܂��L�p�ł͂Ȃ��������I�Ȕ��������������̊튯�ɂ��Đ������Ă��Ȃ������B�����a�C�ɂ��������Ƃ��ɂ͎������������A����ƒ{�������Ĉꏏ�ɊC�����ۗ̕{�n�֍s���A�����Ŗ쐶�̃����ɋ����������ꂽ�B����͔������Ԃ��ǂ̂悤�ɍ������R���g���[�������Ǝ��m���ɂ���̂��ɂ��Ċv�V�I�Ȍ����ւƌq�������B�t�W�c�{�Ɠ��l�ɑ����튯�͈قȂ��ňقȂ�@�\�����B�ƂɋA��ƃc�^�A���ň�t�̕����ŕa�ɕ������B���̍��_�[�E�B����K�ꂽ�q�̓h�C�c�Ń_�[���B�j�X���X���L�����G�����X�g�E�w�b�P�����܂܂ꂽ�B�E�H���X�͂܂��܂��S���`�̕����ɂ̂߂荞��ł��������A����ł����͂Ȏx���҂̂܂܂������B�_�[�E�B���́u����Ȗ{�v�̍ŏ��̕����͑傫�ȓ{�A�w�A���̕ψفx�ɑ��債���B���̂��ߐl�ނ̐i���Ɛ��I���Ɋւ��ċL�q���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����B�ނ͎��R�I���Ɋւ�����̃Z�N�V���������������������ɂ͖����\�̂܂܂������B
�@
���C�G���͐l�ނ̐�j����ɂ��Ę_���A�n�N�X���[�͉�U�w�I�Ƀq�g���ސl���ł��邱�Ƃ��������B1871�N�Ƀ_�[�E�B���́w�l�̗R���Ɛ��Ɋ֘A�����I���x�ő����̏؋�����Đl�ԂƓ����̐��_�I�A���̓I�A�����������A�q�g�͓����ł���Ƙ_�����B�����ăN�W���N�̉H�̂悤�Ȕ���p�I�ȓ����̓�����������鐫�I�����Ă��A�q�g�̕����i���A�����A�g�̓I�E�����I�Ȑl��Ԃ̓����𐫑I���ɂ���Đ������A�����Ƀq�g�͈�̎�ł���Ƌ��������B�G��}�𑽗p���������͊g������A��1872�N�ɂ́w�l�Ɠ����̊���̕\���x���o�ł����B����͎ʐ^�𗘗p���������̖{�̈���ŁA�l�Ԃ̐S���̐i���Ɠ����s���Ƃ̘A������_�����B�ǂ���̖{���l�C������A�_�[�E�B���͎����̈ӌ�����ʂɎ����ꂽ���ƂɊ������u�N�ł��Ռ����邱�ƂȂ�����ɂ��Ęb���Ă���v�Əq�ׂ��B
�@
�����ă_�[�E�B���͂������_�����B�u�l�ނƂ��̍��M�ȓ����A�������Ă���l�ւ̓���A�l�ԂɂƂǂ܂炸�����₩�Ȑ��������������ސS�A�_�̂悤�Ȓm���A���z�n�̉^���Ɩ@���ւ̗����A���邢�͂��̂悤�ȑS�Ă̍����ȗ́A[�ƂƂ���]�l�Ԃ͂��̑̂̒��ɖ����܂����c��̍��Ղ��c���Ă���v�@ |
�����̑��̌���
�@
�t�W�c�{�̕��ށA�X��ʂ̌`���ƕ����A�n�g�̎���i��̉��ǁA�~�~�Y�ɂ��y��`���̌����Ȃǂł��Ɛт��c���Ă���B�����̌������ꂼ��P�Ƃł������w�j��ɖ������c�������̐��ʂ������Ă��邽�߁A�i���_�̗��_�I�\�z���Ȃ��Ă������w�j��ɖ����c�������Ȑ����w�҂ƂȂ����ł��낤�Ƃ���]��������B
�@
�w�r�[�O�����q�C�̒n���w�x�̍ŏ��̊��u�T���S�ʂ̍\���ƕ��z�v(1842�N)�ł́A���l�ȗl���̎X��ʂ̐����v�����l�@�������~�����������B����̓_�[�E�B���̎��ソ�т��ь@�펎�����s��ꂽ���A1952�N�Ɋj�����ɔ�����K�͂Ȍ@�풲���œ���ꂽ�f�[�^�ɂ��A�悤�₭�������������������Ƃ��m�F���ꂽ�B�t�W�c�{�̕��ފw�����ɂ�郂�m�O���t(1851�N)�́A�����ł��t�W�c�{�̕��ފw�����̊�{�����ƂȂ��Ă���B
�@
�}�_�K�X�J���̃����ȐA�� Angraecum sesquipedale �̉Ԃɓ��قɔ��B��������ȋ��̌`��ɒ��ڂ��A���̋��̉����疨���z�����钷��������������������͂����Ɨ\�z����(�u�����ɂ�郉���̎ɂ��Ă̘_�l�v1862�N)�B�_�[�E�B���̎���A���̋��̒����Ɠ�����27cm�̒����̌��������X�Y���K(�L�T���g�p���X�Y���K)���������ꂽ�B�����������ۂ������N�����i���̗l���́A���ł͋��i���ƌĂ�Ă���B�q�g�̗R���ɂ��Ă��A�ސl���Ńq�g�Ƌ߉��̎킪�A�t���J�ɂ����������Ȃ����Ƃ���A�A�t���J�Œa�������Ɨ\�z�����B������_�[�E�B���̎���ɂ��̗\�z���������������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�@
���q�̃t�����V�X�E�_�[�E�B���Ƌ��ɁA��ɃC�l�ȐA���̃N�T���V�̗c�t���p���A�������Ɋւ��錤�����s�����B�c�t��̐�[�Ō������m���A���̎h���������ɓ`�B����ċ��Ȃ������N�����ƌ��_���A1880�N�ɁwThe Power of movement in plants(�A���̉^����)�x�Ƒ肵���������L���Ă���B���̌�A���̌����҂�ɂ��A�h����`�B���镨���̌������s���A�A���z�������̈�ł���I�[�L�V���̔����ւƂȂ������B
�@
�r�[�O�����q�C����A�����Ă����ɔ��\���ꂽ�~�~�Y�̓����Ɋւ��鏬�_�́A�����̓~�~�Y�ɂ���قǂ̗͂͂Ȃ��ƍl�����Ă������߁A�ᔻ�������A�Ō�̒���w�~�~�Y�Ɠy(�~�~�Y�̍�p�ɂ��엀�y�̌`���y�у~�~�Y�̏K���̊ώ@)�x(1881�N)�ł�40�N�ɂ킽�錤�����ʂ��܂Ƃ߂��Ă���B����͂��~�~�Y�̓������֒����Ă���ƌ�������̂́A�~�~�Y�Ɠy��Ɋւ��閾���Ș_���ƌ����ʂƁA���݂��������邱�Ƃɂ���Ă����ɂ��ĉߋ���m�肤�邩�ɂ��ẲB���ꂽ�_�c�Ƃ����ʂ������Ă���B�@ |
���ӔN
�@
1880�N�ɌZ�G���Y�}�X�����a�����̂����v����ƁA�ނ����Ă����_�[�E�B����Ƃ͔߂��݁A�u�����ǂ��A�����ɖ������Z�������v�Əq�ׂ��B
�@
�N���Ƃ����_�[�E�B���͎���ɔ��₷���Ȃ������A�������~�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B���ɉƂɎc���Ă����t�����V�X�Ɩ������A�g�p�l����������`�����B�ӔN�̊y���݂̓G�}�̃s�A�m�Ə����̘N�ǂŁA���ɌÓT�������s�̏������D�B�ނ̐i���Ɋւ�������Ɗώ@�́A�c�^�A���̉^���A�H���A���A�A���̎��ƎƑ��Ǝ̉e���A����̉Ԃ̑��^�A�A���̉^���\�͂ɂ܂ŋy�B1881�N�̍Ō�̖{�ł͎Ⴂ���̊S�ɗ����߂�A�~�~�Y���y��`���ɉʂ���������_�����B
�@
1882�N��������S���ɒɂ݂��o����悤�ɂȂ�̂����������s���R�ɂȂ����B1882�N4��19���Ƀ_�E�����̎���Ŏ��������B�ނ̓_�E�����̃Z���g���A���[����ɑ�����ƍl���Ă������A���������͉Ȋw�̗D�ʐ�����ʂ̐l�X�Ɉ�ۂÂ���D�@�ƌ��Ȃ����B�t�b�J�[�A�n�N�X���[�A���{�b�N�Ƃ������F�l�����A���������E�B���A���E�X�|�e�B�X�E�b�h�A�t�����V�X�E�S���g����͉Ƒ���������A�@�ւɋL���������A����Ɖ����A�c��ɓ����������B�_�[�E�B���͓��N4��26���ɍ����ɕt����E�F�X�g�~���X�^�[���@�ɖ������ꂽ�B
�@
�ȃG�}��1896�N�Ƀ_�E���Ŗv���A��ɖS���Ȃ����Z�G���Y�}�X�Ɠ������_�E���̕�n�ɑ����Ă���B�j���[���[�N�^�C���Y���̓_�[�E�B���̎����̓��W�L���Łu�i���_�������̂ł͂Ȃ��A�A���X�g�e���X�̎��ォ�炠���������̋^����Ȋw�I�ɉ��������̂��v�Əq�ׂ��B�@ |
���Љ�v�z
�@
�_�[�E�B���͓����̑����̐l�Ɠ����悤�ɐl�핽����`�҂ł͂Ȃ��A�܂������͔\�͂����Ƃ��l���Ă����B��������ʓI�ȍ��ʎ�`�����L���Ă͂��Ȃ������B�l��Ԃ̐����w�I�ȍ��ق͔��ɏ������̂ŁA�l����قȂ鐶����ƍl����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ咣���Ă����B�z�ꐧ�x�ɔ����A�r�[�O�����͒��̃t�B�b�c���C�ƏՓ˂����̂��z�ꐧ�x�ɑ���ӌ��̑��Ⴞ�����B�t�B�b�c���C���u(�z�ꂽ����)���݂̏�Ԃɖ������Ă���Ɠ������B������ނ�͓z��ł��čK���Ȃ̂��v�ƌ������̂ɑ��A�u��l�̑O�ł����������̂�����A�{�S���ǂ���������Ȃ��v�Ɠ����t�B�b�c���C�̓{������B�u���W���ł͎�l�ɂ��z��s�҂̏�ʂɑ������Ă���A�u���W�����o�q����Ƃ��ɁA�z��s�҂��x�ƌ��邱�Ƃ��Ȃ��̂����ꂵ���A���̍��͓�x�ƖK��Ȃ����낤�Ə����c���Ă���B�A����ɂ͓z�����^�����x�������B
�@
�܂��u������l����قȂ��Ƃ��ă����N�t������v���Ƃɔ����A��x�z���̐l�X���s�҂��邱�Ƃɔ������B�����̍�Ƃ͎��R�I�������R���C��`�̎�����H�̎��{��`�A�l�퍷�ʁA�푈�A�A���n��`�ƒ鍑��`�ȂǗl�X�ȃC�f�I���M�[�ɗp�����B�������_�[�E�B���̎��R�ɑ���S�̘_�I�Ȏ��_�́u��̑��݂̏�ɑ����ˑ����đ��݂���v�ł����āA�s���[�g���E�N���|�g�L���̂悤�ȕ��a��`�A�Љ��`�A���R��`�I�ȎЉ���v�A�����{��`�Ƌ��͂̉��l�����������B�_�[�E�B�����g�͎Љ�P���Ɏ��R�̒��̑I���Ɠ����̊T�O���瓱����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝ咣�����B�u�Љ�_�[�E�B�j�Y���v�ƌ����p���1890�N������g���o�������A1940�N��Ƀ��`���[�h�E�z�t�X�^�b�^�[���E�B���A���E�T���i�[�̂悤�ȉ��v��Љ��`�ɔ��������R���C�̕ێ��`���U�����邽�߂Ɏg���o���ƌy�̓I�ȈӖ����������悤�ɂȂ����B����ȗ��A�ނ炪�i�����瓱���o����铹���I���_�ƍl���邱�Ƃɑ��ėp������l�|��ƂȂ����B
�@
���D���w
�@
�_�[�E�B���͂��Ƃ��̃t�����V�X�E�S���g����1865�N�̋c�_�ɋ������o�����B�S���g���͈�`�̓��v���͂�������_�I�\�͈͂�`���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�����̕i����ǂ̌����͐l�Ԃɉ��p�ł���Ǝ咣�����B�w�l�Ԃ̗R���x�Ń_�[�E�B���͎ア�҂������ĉƑ��������Ƃ͎��R�I���̗��v���������ƂɂȂ�Ǝw�E�������A��҂ւ̉������T���邱�Ƃ͂����̓���̖{�\���댯�ɂ��炷�ƌx�������B�ނ͐l�̋����\�͂⓹���S�����R�I���ɂ���Č`���ꂽ�ƍl���A����ł������S�������l�Ԃ͐����ł��Ȃ��ł͂Ȃ����Əq�ׂ��B�܂��_�[�E�B���ɂƂ��ċ���͂��d�v�������B
�@
�S���g�����������o�ł��A�u���܂���\�͂�����l�v�̒��ŋߐe���𐄏������Ƃ��A�_�[�E�B���͎��ۓI�ȍ����\�z���āu�B������\�Ȑl��̉��P�v�悾���A�܂����z�I���Ƌ����v�Əq�ׁA�P�Ɉ�`�̏d�v�������\���Čl�Ɍ����C��������D�B�_�[�E�B���̎���1883�N�ɃS���g���͂��̍l����D���w�Ɩ��t���A�����ɐ�������w�W�������B���R�I����������f����`�w�ɂ���Ĉꎞ�I�Ɏ��Ă��Ă����Ƃ��D���w�^���͍L�͈͂ɂЂ낪�����B�x���M�[�A�u���W���A�J�i�_�A�X�E�F�[�f���A�A�����J���O�����܂ނ������̍��Œf��@�̋����ƂȂ����B���Ƀi�`�̗D���w�̓_�[�E�B���̃A�C�f�B�A�̐M�p���������B
�@
���Љ�_�[�E�B�j�Y��
�@
������Љ�`�Ɋւ���T�O���L�q�I�ɂׂ̂邱�Ƃ͗ϗ��I�ȁu�ł���|�ׂ��ł���v�̖��������N�����B�g�}�X�E�}���T�X�͎������������l���������j�]�������炷�Ǝ咣�����B�����1830�N��Ɏ��e���⎩�R���C�o�ς������������̂ɗp����ꂽ�B�i���͎Љ�I�܂݂�����ƌ��Ȃ���Ă����B�n�[�o�[�g�E�X�y���T�[��1851�N�̖{�w�Љ�Êw�x�͐l�Ԃ̎��R�ƌl�̉���̃A�C�f�B�A�̊�ՂɃ��}���N�I�i���̊T�O��p�����B�_�[�E�B���̐i�����_�́u�����v�̖�肾�����B�_�[�E�B���́u���铮�������̓��������������ƌ����͕̂s�������v�ƍl���A�i���͐i���ł͂Ȃ��ړI���Ȃ��ƌ��Ȃ������A�w��̋N���x�̏o�ł̂������Ƃ���ᔻ�҂́u�����̂��߂̓w�́v�Ƃ����_�[�E�B���̐������C�M���X�Y�Ƃ̎��{��`���}���T�X��`�I�ɐ�����������肾�ƌ����Ă����������B�_�[�E�B�j�Y���Ƃ����p��͎��R�s��̔��W�Ɋւ���u�K�Ґ����v�ƌ����T�O�A�G�����X�g�E�w�b�P���̐l�퍷�ʓI�Ȑi���ςȂǑ��̑����̐i���Ɋւ���v�z�Ɏg��ꂽ�B�@ |
���@����
�@
�T�^�I�Ȏ莆���������_�[�E�B���͐��U��2000�l�Ǝ莆�ɂ��ӌ����������A���̂�����200�l�����E�҂������B�����Đ����ɑ���_�w�I�Ȍ�����ے肵���킯�ł͂Ȃ��������A�����������Ƃ������������A���E�G���U�x�X(�A�j�[)�����g�I�ȉ��̍b�㖳�����ʂƁA�����M�S�����������_�[�E�B���́u���͐_��߂Ƃ͊W�Ȃ��A���R���ۂ̈�ł���v�Ɗm�M�����B
�@
�_�[�E�B���̉ƒ�͉p�������������Ă��炸�A���̂����c���A���A�Z�͎��R�v�z�Ƃ��������A�_�[�E�B�����g�͐����̖��됫���^��Ȃ������B�p��������n�̊w�Z�ɒʂ��A���E�҂ɂȂ邽�߂ɃP���u���b�W�Ő_�w���w�B�E�B���A���E�y�C���[�̎��R�̃f�U�C���͐_�̑��݂̏ؖ��ł���Ƃ������R�_�w���m�M���Ă����B�������r�[�O�����q�C�̊Ԃɋ^���������n�߂��B�Ⴆ�Ȃ��[�C�v�����N�g���͒N��������ڂɂ��邱�Ƃ��Ȃ��̂ɑn�����ꂽ�̂��H�C�����V���}�q�����A�������܂q�ǂ��ɐH�ׂ�����o�`�̂悤�ȑ��݂��y�C���[�̎����ݐ[���f�U�C���_�Ƃ��������ǂ̂悤�ɒ��a����̂��H
�@
�ނ͂��炭�����ȐM�������Â��A�����̍����Ƃ��Đ��������p�������A�������q�ׂ���j�ɂ͔ᔻ�I�������B��̕ω������Ă���Ƃ������w�̗F�l���������̂悤�ȍl�����A�_���I�ȎЉ�����ނ��ދ���ׂ��ً��ŁA�p��������̓����I�Ȓn�ʂ�ᔻ���邽�߂̔��������`�҂����_�_�҂ɂ��}�i�I�Ȏ咣�̈�킾�A�ƍl���Ă��邱�Ƃ�m���Ă����B�_�[�E�B���͏@�����̐����c��헪�ł���Ə��������A�܂��_�����ɓI�Ȗ@���̌���҂ł���Ǝv���Ă����B������1851�N�̃A�j�[�̎��͎����������L���X�g���M�ւ̏I�����Ӗ������B�n���̋���̐l�X�ƂƂ��ɋ���̎d������`�����������A�Ƒ������j���ɋ���ɒʂ��Ԃ͎U���ɏo�������B���̂���ɂ͒ɂ݂�ꂵ�݂�_�̒��ړI�Ȋ��ƍl��������A��ʓI�Ȏ��R�@���̌��ʂƍl��������悢�Ǝv���Ă����B1870�N��ɐe���Ɍ����ď����ꂽ�w���`�x�ł͏@���ƐM��ɗ�ɔᔻ���Ă���B���̃Z�N�V�����́w���`�x���o�ł����Ƃ��ɃG�}�Ƒ��q�̃t�����V�X�ɂ���č폜���ꂽ�B1958�N�ɑ����m���E�o�[���E�ɂ���ďo�ł��ꂽ�V�����łł͍폜���ꂽ�S�ẴZ�N�V���������ʂ肨���߂��Ă���B1879�N�ɏ����ꂽ���Ȃł́A�����͂����Ƃ��ɒ[�ȍl���ɐG�ꂽ���ł����Ă��_�̑��݂�ے肷��ƌ����Ӗ��ɂ����閳�_�_�ł͂Ȃ��A�u�s�m�_�����̐S�������Ƃ��悭�\���v�Əq�ׂĂ���B�ӔN�̃_�[�E�B���̗F�́A�G�Ύ҂���̔ᔻ�ɔ��A�M�ƉȊw�̊Ԃŗh���_�[�E�B���̒x�^畏�����z���Ă���B
�@
1915�N�ɏo�ł��ꂽ�w�z�[�v�v�l����x�̓_�[�E�B�������̏��ŐM�����߂����Ǝ咣�����B�_�[�E�B���̍Ŋ��̓��X���Ƃ��ɑ��������w�����G�b�^�́A���̂悤�Ȑl�͌������ɗ��Ă��Ȃ�����������Ƃ��Ȃ��Əq�ׂ��B�ނ̍Ŋ��̌��t�͍ȂɌ�����ꂽ�B�u���O�������Ƃ悢�Ȃ������Ɗo���Ă��Ȃ����v�@
�@ |
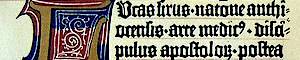 �@ �@
���}���N�X�u���{�_�v���� 3�� 1867�|94�N |
   �@
�@
|
Marx, Karl Heinrich.(1818-83)
�@
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie.
�@
�}���N�X�́A�h�C�c�̎Љ��`�ҁB�Ȋw�I�Љ��`(���Y��`)�̑n�n�ҁA���ۘJ���҉^���A�v���^���̎w���ҁB�ނ́A�{���A�x����������w�Ŗ@�w�A���j�A�N�w���w�сA���ƌ�C�G�i��w����w�ʂ��B1844�N�Ƀp���ŃG���Q���X�Ɛe�������сA���u���W�����I�Љ��`�̔ᔻ��ʂ��ĉȊw�I�Љ��`�̊m���̂��߂̐��U�ɂ킽���l�̋��͂����܂ꂽ�B1847�N�Ƀ����h���ŊJ�Â��ꂽ���Y��`�ғ����̑�2����ɏo�Ȃ��A�G���Q���X�Ƌ����ŗL���ȁu���Y�}�錾�v�������A���Y��`�̗��_�Ɛ�p�����k�����`�ő̌n�I�Ɏ������B�h�C�c��ǂ�ꂽ��A�����h���Ɉڂ�A�u�o�ϊw�ᔻ�v�A�u���{�_�v�A�u��]���l�w���j�v�̊����ɓw�͂������A�u���{�_�v�͖����̂܂܌��e�Ƃ��ăG���Q���X�Ɉς˂�ꂽ�B��1���̓}���N�X�������Ō��e���o�ŎЂɎ������ݏo�ł������A2�E3���̓}���N�X�̎���A��e�������G���Q���X�̎�ɂ���ďo�ł��ꂽ�B�@ |
�����{�_ 1
�@
(Das Kapital �ACapital : a critique of political economy)�@�J�[���E�}���N�X�̒���B�h�C�c�ÓT�N�w�̏W�听�Ƃ����w�[�Q���ُؖ̕@��ᔻ�I�Ɍp�����������ŁA����܂ł̌o�ϊw�̔ᔻ�I�č\����ʂ��āA���{��`�I���Y�l���A��]���l�̐����ߒ��A���{�̉^�����@���𖾂炩�ɂ����B�S3��(�S3��)���琬��B�T�u�^�C�g���́u�o�ϊw�ᔻ(a critique of political economy)�v�B�`���ɁA�u�Y�ꂪ�����킪�F �E���A�����A�����ȃv�����^���A�[�g�O�q��m ���B���w�����E���H���t�ɂ������v�Ƃ̌������L����Ă���B
�@
1867�N�ɑ�1�������߂Ċ��s����A1885�N�ɑ�2�����A1894�N�ɑ�3�����������ꂽ�B��1���́A�}���N�X���g�ɂ���Ĕ��s���ꂽ���A��2���Ƒ�3���́A�}���N�X�̎���A�}���N�X�̈�e�����ƂɁA�t���[�h���q�E�G���Q���X�̌��g�I�Ȑs�͂ɂ���ĕҏW�E���s���ꂽ�B
�@
�u��4���v�ƂȂ�\�肾�����ÓT�h�o�ϊw�̊w���ᔻ�Ɋւ��镔���́A�G���Q���X�̎���A�J�[���E�J�E�c�L�[�ɂ���Č������ꂽ���A�w���{�_�x�Ƃ����\��Ɋւ���Ō��̖��A�J�E�c�L�[�́u�Ǝ��̌����v�Ȃǂɂ��A�w���{�_�x��4���Ƃ��Ăł͂Ȃ��w��]���l�w���j�x(3��4����)�̕\��Ŋ��s���ꂽ�B���̌�A�\�r�G�g�̃}���N�X�����[�j����`�������ɂ���ĐV���ȕҏW�ɂ��ł����s���ꂽ�B(�A�J�f�~�[��)����͂���ɏC�������Marks-Engels Werke�̑�26���T�`�V�Ƃ��Ċ��s���ꂽ�B(���F���P�ł܂��͑S�W��)
�@
��
�@
�}���N�X�́A�u�V���C���V���v�̕ҏW�҂Ƃ��āA�����I�ȗ��Q�W�������ߒ��ŁA����ɁA�Љ�ϊv�̂��߂ɂ͕����I���Q�W�̊�b���Ȃ��o�ςւ̗����̕K�v����F�����A�o�ϊw�����ɖv�����Ă������B
�@
1843�N�ȗ��A�}���N�X�͌o�ϊw�̌������J�n����B�S����̃p���ł̌�������n�܂�A9���́w�p���E�m�[�g�x�A6���́w�u�����b�Z���E�m�[�g�x�A5���́w�}���`�F�X�^�[�E�m�[�g�x�ȂǂƂ��Ă��̐��ʂ��c���Ă���B�Ȃ��A�����̃m�[�g�́A��������w���{�_�x���e�ł͂Ȃ��B
�@
1849�N�A�}���N�X�̓����h���S����A��p�}���قɒʂ��Č����𑱂��A1850�N - 1853�N�܂ł̐��ʂƂ��āw�����h���E�m�[�g�x24���������グ���B����̓}���N�X�̃m�[�g���A�ő啪�ʂ��߂�o�ϊw�m�[�g�ł��邪�A���̎����̃m�[�g�̓��e�ɂ͍��Ɗw�A�����j�A�����j�A�C���h�j�A�����j�A�܂��������ȂǁA���e�̈قȂ鑽���̘_���������Ă���A���̎����Ƀ}���N�X�̌������o�ϊw�ᔻ�ɓ��������Ƃ͂����Ȃ��B
�@
�}���N�X���o�ϊw�ᔻ�Ɋւ��鎷�M�ɂƂ肩�������̂�1857�N����ł���B����͏��i�E�ݕ���_���邲���ꕔ�̂��̂ɂƂǂ܂�A�w�o�ϊw�ᔻ�A��ꕪ���x�Ƃ���1859�N�Ɋ��s���ꂽ�B�܂��A���̎����̌��e�́w�o�ϊw�ᔻ�v�j�x�w��]���l�w���j�x�Ƃ��āA�}���N�X�̎���ɏo�ł��ꂽ�B
�@
�w���{�_�x���̂��̂̑��e�ōł����S�I�ƂȂ������̂́A1863�N����1865�N���܂łɎ��M���ꂽ���e�Q�ł���B�����Ń}���N�X�͂����܂��ȑS3���̑��e�̂������������I�����B�������A����͖��ӎ��Ɋ�Â��������I������Ƃ����Ӗ��ɂƂǂ܂�A������ċᖡ�E�č\�����A���͂Ƃ��ď��q�������A��������Ƃ�����Ƃ͂܂�܂�c���ꂽ�B���́u1863�N����1865�N�܂ł̑��e�v�̂��Ƃ�VMEGA�ҏW�ψ��͂܂Ƃ߂āu��3�̎��{�_���āv�ƌĂ�ł���B���������̑��e���������̂��̂ł���A�}���N�X�͂��̂��ƂɎ��o�I�ł������B���̑�2���Ƒ�3���̑��e�ɂ��ă}���N�X��1866�N�̒i�K�ŃG���Q���X�Ɉ��ĂāA�u�ł��オ�����Ƃ͂����A���e�́A���̌��݂̌`�ł͓r�����Ȃ����̂ŁA�l�ȊO�̂���ɂƂ��Ă��A�N�ɂƂ��Ă������o�łł�����̂ł͂Ȃ��v�Ǝ莆�ɏ������قǂł������B
�@
1867�N�ɑ�1�������s���ꂽ���A���̌���}���N�X�͏��q�̉��P������Ԃ��A�u�܂������ʌ̉Ȋw�I���l�����v�Ǝ����ŏ̂���قǂɔ[���ł���łƂȂ����u�t�����X��Łv���o�ł��ꂽ�̂͂悤�₭1872�N - 1875�N�ł������B���̂悤�ɁA�}���N�X�͑�1�����s��������ɉ������d�ˁA��2���Ƒ�3���̍�Ƃ͑啝�ɒx��A�n���ƕa��̒��Ŗc��Ȗ��������e���c�����܂܁A1883�N�ɐ����������B�}���N�X�͑�ςȈ��M�ł������̂ŁA��e�̓G���Q���X�����ǂ߂��A�ҏW��Ƃ͔ނɂ����s�����Ƃ��ł��Ȃ�����(��Ƀ}���N�X�̕����̓ǂݕ����J�E�c�L�[�ƃx�����V���^�C���ɓ`��)�B�G���Q���X�́A�}���N�X���₵���c��ȑ��e�ƈ��M�̑O�ɁA��Ԃׂ̍�����Ƃ�]�V�Ȃ�����A�ڂ����������Ƃ����B�Ȃ�2004�N�ɂ́A�w���{�_�x��2���̕ҏW�ɍۂ��Ă̓G���Q���X�ƂƂ��ɁA���܂Łu�G���Q���X���e�ҏW�̌��q�M�L�ҁv�Ƃ��Ĉ����Ă����I�X�J���E�A�C�[���K���e�����������x���̕ҏW��ƂɊ֗^���Ă������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���B
�@
�w�o�ϊw�ᔻ�x�Ƃ�����Ń}���N�X���ŏ��ɍ\�z���Ă����̂͑S6�҂ł��������A����͌�Ɂw���{�_�x�S4���\���ɕύX���ꂽ�B�}���N�X�́w���{�_�x�\�z�͗��_�I�W�J���琬���1�� - ��3���ƁA�w���j���琬���4���ł������B�������}���N�X�̐��O�Ɋ��s���ꂽ�̂͑�1��(���ł�����A�ƌꏉ�ŁA������2�ŁA�}���N�X�Z�{����ŁA���V�A���)�݂̂ŁA���ƂɎc�����͖̂c��Ȍo�ϊw�ᔻ�Ɋւ���m�[�g�ނł���B���݂����̑��e�̑����̓A���X�e���_���Љ�j���ی������A���邢�̓��X�N���̌���j�����ۊǁE�������V�A�Z���^�[�ɕۊǂ���Ă���B�@ |
�����{�_ 2
�@
����1�� / ���{�̐��Y�ߒ��̌���
�@
�����i�Ɖݕ�
�@
�}���N�X�́A����Ȏ��{��`�o�ς��\������A�ł��P���ł���ӂꂽ�v�f�ł��鏤�i�̕��͂���o������B
�@
���i�́A�l�Ԃ̗~�]���݂����g�p���l(�ߑ�o�ϊw�Ō����Ƃ���̌��p�̑ΏۂƂȂ����)�ƁA���̂��̂Ƃ̌����䗦�ł���킳���������l(���W�����ݕ��\���Ƃ��Ă͉��i)�����B�����W�ɂ����ꂽ�i�́A�Ȃ����l���������ƌ�����̂��B�g�p���l������������ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�g�p���l���قȂ邩�炱�������̈Ӗ������邩��ł���B�ł͏��i����g�p���l����苎��Ɖ����c�邩�B����́A���i�Ƃ́A���R���ɂȂ�炩�̐l�Ԃ̘J�����t����������J�����Y���ł���A�Ƃ������Ƃ����ł���B��̏��i�������ł���Ƃ����Ƃ��A���̏��i�̐��Y�ɔ�₳�ꂽ�J���̗ʂ��������B���������̘J���́A�V���c��ȕz�Ƃ�������̓I�Ȏg�p���l���`������悤�ȁA�ٖD�J����D�z�J���Ƃ�������̐��̂���J��(��̓I�L�p�J��)�ł͂Ȃ��B�J���̋�̐����͂��Ƃ�ꂽ���ۓI�ȘJ���A�P�Ȃ�l�Ԃ̔\�͂̎x�o�Ƃ��Ă̒��ۓI�l�ԘJ���A���̂悤�ȘJ���̐��Y���Ƃ��ē�̏��i�͓������Ƃ����B���ۓI�l�ԘJ���̋Ìŕ��A���ꂪ���l�̎��̂ł���B���l�̗ʂ��Ȃ킿���ۓI�l�ԘJ���̗ʂ́A��{�I�ɂ͘J�����Ԃɂ���Ă͂����A���̍ۂɘJ���̋��x��J���̕��G�����l�������B
�@
����ɁA���l�ʂ��K�肷��J�����Ԃ́A���̏��i�Y����̂ɕK�v�ȌʓI�A���R�I�ȘJ�����Ԃł͂Ȃ��A�Љ�I�ɕK�v�Ƃ���镽�ϓI�J�����Ԃł���B���Ƃ��A����Љ�ɁA1��8���ԘJ����1���̃V���c�����鏤�i���Y��A�ƁA1��8���ԘJ����7���̃V���c�����鏤�i���Y��B������Ƃ���A�Љ�S�̂Ƃ��Ă�16���ԘJ����8���̃V���c�����Y����A���ς���A1���������2���ԘJ������₳��Ă��邱�ƂɂȂ�B���i���Y��A����ɂ���̂�2���ԘJ�����̉��l�A���i���Y��B����ɂ���̂�14���ԘJ�����̉��l�ł���B���������Ă悭��������悤�ɁA�ӂ��҂���������킯�ł͂Ȃ��B
�@
���i�̉��l�́A���̏��i�̐��Y�ɔ�₳���Љ�I�ɕ��ϓI�ȘJ���ʂɂ���Č��܂�B���ꂪ�}���N�X���A�A�_���E�X�~�X��J�[�h����p�����W�������J�����l�_�̂���܂��ł���B
�@
�������A���i�͎���̉��l�����������ŕ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���鏤�i�̉��l�ʂ́A���̏��i�̎g�p���l�ʂɂ���ĕ\�������B���ꂪ�ݕ��̋N���ł���B���i�Љ�ŁA�����̏��i�̎g�p���l�ʂɂ���đ��̂��ׂĂ̏��i�̉��l�ʂ�\�����邱�Ƃ��Љ�I���ӂƂȂ����ꍇ�A���̓���ȏ��i���ݕ��ƂȂ�̂ł���B�ݕ����i�̑�\����(gold)�ł���A���̎g�p���l�ʁA���Ȃ킿�d�ʂ��ݕ��̒P�ʂƂȂ����B
�@
�܂��A���i�̉��l���ݕ��ŕ\���������̂����i�ł���B���鏤�i�̉��i�͎��v�����̕ϓ��ɂ��A���l�Ɨ���ĕϓ����邪�A���l�͂��̉��i�ϓ��̏d�S�ɑ��݂��A�����I���ϓI�ɂ́A���i���܂ޘJ���ʂɂ���āA���l�ɂ���ĉ��i�͋K�肳���B
�@
���i��ݕ��́A���{��������邽�߂̘_���I�O��ł���B��ʂ̏��i���ʂ́A�����̏��L���鏤�i�Ƒ���̂����i�Ƃ̊Ԃ́A�ݕ���}��Ƃ��������̉ߒ��ł���A���i�|�ݕ��|���i�ł���B���̗��ʂ́u�������߂ɔ���v�A�܂�~�������i����ɓ���A���̎g�p���l������邱�Ƃɂ���ďI���B����ɑ��āA���{�Ƃ��Ẳݕ��̗��ʂ́u���邽�߂ɔ����v�A�c�ݕ��|���i�|�ݕ��c �ł���B���̗��ʂ̖ړI�͉��l�A�������A��葽���̉��l�邱�Ƃł���A���{�Ƃ��Ẳݕ��̗��ʂ͏I��邱�Ƃ̂Ȃ������̉ߒ��ł���B���{�Ƃ́u���ȑ��B���鉿�l�v�ł���A���ꂪ�ŏ��̎��{�T�O�ł���B���{�𗝉����邽�߂ɂ́A���l�Ƃ͉����A�ݕ��Ƃ͂Ȃɂ��A���i�Ƃ͂Ȃɂ������_�I�ɖ��炩�ɂ���Ă���K�v�����������߂ɁA���{�T�O�̑O�ɏ��i�A�ݕ��A���l�Ȃǂ̊T�O����������Ă����킯�ł���B
|
���ݕ��̎��{�ւ̓]���A��]���l�̐��Y
�@
�ł́A���{�͂ǂ̂悤�ɂ��ĉ��l���B���A�ׂ���̂��B���̓����́A���牿�l�Y�������ȏ��i���Ȃ킿�J���͏��i�����L����A�����J���҂���̍��ɂ���Ăł���B
�@
�@�B�Ȃǂ̐��Y��i��ݕ������̂܂��{�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��B������j�I�����̉��Łu���{�v�ɓ]������B���̌���I�ȏ����Ƃ́A���Y��i�����L����u���W���A�W�[(���{�ƊK�������Y��i�̏��L��)�ƁA�����I�g����������Y��i�̏��L��������R�ƂȂ����A�J���͏��i�ȊO�ɔ���ׂ����i�����������Ȃ������J���҂̑��݂ł���B
�@
���{(���̐l�i���Ƃ��Ă̎��{��)�́A�J���҂���J���͏��i���w������B�J���҂͂��̑Ή��Ƃ��āA���������B�����͘J���͏��i�̉��i�ł���B�J���͏��i�̉��l�͂��̍Đ��Y�̂��߂ɕK�v�Ȕ�p�A���Ȃ킿�J���҂ƉƑ��̐�����ɂ���Č��܂�B�J���͏��i�̎g�p���l�́A�J�����ĉ��l�ݏo�����ƁA���������{�ƂɂƂ��Ă̎g�p���l�́A����̉��l���鉿�l�ݏo�����Ƃł���B�J�����ĘJ���҂����ݏo�������l���u��]���l�v�ł���A���{�Ƃ�������擾����B——���ꂪ�}���N�X�����炩�ɂ������(�J���҂����ݏo�������l�|�J������]���l)�̔閧�ł���A���{�ׂ̖��̔閧�ł���B���Ƃ��Γ���1���~�̘J���҂�2���~���̉��l�ݏo���Ȃ�A��������1���~���̏�]���l�����{�Ƃ̂��̂ƂȂ�B�t�Ɍ����A��]���l�����܂Ȃ��J���ҁA�����̒����ȏ�̉��l�ݏo���Ȃ��悤�ȘJ���҂́A���{�ɂƂ��Ă͍w������K�v�����@���Ȃ��B
�@
���{�͎g�p���l�������ړI�̂��߂ɐ��Y���s���̂ł͂Ȃ��A�����̏�]���l(�Ώۉ����ꂽ�s���J��)�̒Nj��A���Ȃ킿�u�������v�̂��߂ɐ��Y���s���B���������āA�Ⴆ������Q�삪�����A�H�Ƃ̐��Y���K�v�ł����Ă��A�������������Ȃ���Ύ��{�͐��Y�͂��Ȃ��B�t�ɕ���ȂǎЉ�ɂƂ��ėL�Q�Ȃ��̂ł��A���������o��Ύ��{�͐��Y����B�}���N�X�͂��̂��Ƃ��w���{�_�x�̒��ŁA�u�܂����Ɏ��{��`�I���Y�ߒ��̐��i�I�ȓ��@�ł���K��I�ȖړI�ł���̂́A���{�̂ł��邾���傫�Ȏ��ȑ��B�A���Ȃ킿�ł��邾���傫����]���l���Y�A���������Ď��{�Ƃɂ��J���͂̂ł��邾���傫�ȍ��ł���v�Ə������B
|
����]���l���Y�̓�̕��@ ��ΓI��]���l���Y�Ƒ��ΓI��]���l���Y
�@
���{���擾�����]���l��������ɂ͓�̕��@������B���ɁA�J���͂̉��l(�܂��͂��̉��i�\���ł������)�����ł���Ȃ�A�J�����Ԃ����������邱�Ƃł���B����1���~�̘J���҂�8���ԘJ����2���~���̉��l�ݏo���Ƃ��A12���ԘJ���ɉ��������3���~���̉��l�ݏo���A��]���l��1���~����������B������ΓI��]���l���Y�Ƃ����B�������A���̕��@�ɂ͌��E������B�܂�1����24���Ԃ����Ȃ��B����ɒ����J���҂͘J�����Ԃ̒Z�k�����߂ĘJ���g����g�D���Ď��{�Ƃɒ�R����B
�@
�����ŁA�Ƃ�����̕��@�́A�J�����Ԃ����Ȃ�ΘJ���͂̉��l�܂��͒��������炷���Ƃł���B��قǂ̘J���҂̓�����������1���~����5��~�ɔ���������A��]���l��2���~����2��5��~�ɑ��傷��B����𑊑ΓI��]���l���Y�Ƃ����B�������A���O��ɘJ���͂̉��l�����炷���Ƃ͂ł��Ȃ��B�J���͂̉��l�܂��͒����́A�J���͏��i�̍Đ��Y��A�܂�J���҂Ƃ��̉Ƒ��̐�����ɂ���Č��܂��Ă���B���{�̑��������I�ɒ��������炷���Ƃ́A�J���҂��s�\�ɂ��A�J���͏��i�̍Đ��Y��s�\�ɂ�����B�����J���҂Ȃ����Ď��{�͏�]���l���Y�ł��Ȃ�����A�Z���I�ɂ͂Ƃ����������I�ɂ͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͕s�\�ł���B�ł͂ǂ����邩�B����͐��Y�͂̏㏸�ɂ���ĉ\�ƂȂ�B���Y�͂��㏸�����A�J���҂̐�����i���\�����鏤�i�̉��l�������Ȃ�A�J���҂̐�����������Ȃ�A�J���͏��i�̉��l���ቺ���A���������������Ă��J���͂̍Đ��Y���\�ƂȂ�B�����������邽�߂ɂ́A���Y�͂���{�ƂȂ�悢�̂ł���B�X�̎��{�͂������ȏ��i��ڎw���Đ��Y�͂��㏸�����邽�߂ɁA���݂ɋ������Ă���B���̋����������{���������A�X�̏��i�����������A����������������A����������������O��ݏo���Ă���B
�@
���Y�͂��㏸�������i�ɂ́A���ƁA���Ƃɂ��ƂÂ����ƁA�@�B����H�Ƃ�����A�}���N�X�͂��ꂼ��ɂ��ĕ��͂��Ă���B
�@
���{���{��`�ɂ����鐳�Ј��̒����ԉߖ��J���͐�ΓI��]���l���Y�̊T�O�ɂ���āA�Ј��̒�����͑��ΓI��]���l���Y�̊T�O�ɂ���āA�悭�������邱�Ƃ��ł���B
|
�����{�̒~��
�@
�����J���҂���悵�Ď��{��������]���l�́A���{�Ƃ̏��L����Ƃ���ƂȂ�B���{�Ƃ͂����S�ď���邱�Ƃ��\�����A�u���{�̐l�i���v�Ƃ��Ă̎��{�Ƃ͌l�I�����ߖāA��]���l���Ăю��{�ɓ]�����A���{�~�ς������Ȃ���(��]���l�̎��{�ւ̓]��)�B�������玑�{�Ƃ́u�֗~�v�̌��ʁA�x���~�ς����Ƃ����Љ�I�ӎ��������A�֗~��P�Ƃ���v���e�X�^���e�B�Y�������{��`�̐��_�ƂȂ�(�}�b�N�X�E���F�[�o�[�w�v���e�X�^���e�B�Y���̗ϗ��Ǝ��{��`�̐��_�x)�B
�@
���{�̒~�ς̉ߒ��́A�܂��܂������̒����J���҂����{�ɕ�ۂ���邱�Ƃł���A���{�|���J���W�̊g��Đ��Y�ł���B���j�I�Ƀ��[���b�p�ł́A�r�ѐ��Y�̂��߂ɕ����̎傪�_����y�n����ǂ��o���͂����݂ɂ���āA�_������쒀���ꂽ�_�����A�Y�Ɠs�s�ɈڏZ���v�����^���A�[�g�ɓ]�������B���{��`�̏����Ɍ����A���Ƃ̖\�͂𗘗p�����v�����^���A�[�g�̑n�o��{���I�~�ςƂ����B
�@
�܂��A���ΓI��]���l���Y�ɔ������Y�͂̑���́A��]���l����]������鎑�{�ɂ��āA�s�ώ��{(���Y��i�w���ɓ�����ꂽ���{)�ɑ���ώ��{(�J���͍w���ɓ�����ꂽ���{)�̔䗦�𑊑ΓI�ɏ��������Ă���(���{�̗L�@�I�\���̍��x��)�B�������Ē����J���҂̂܂��܂������̈�蕔�����A���ΓI�ߏ�l��(���Ǝ҂┼���Ǝ�)�ɓ]������B���{��`�I���Y�̂��Ƃł́A����Ŏ��{�Ƃ̑��ɂ͕x���~�ς���A�����Œ����J���҂̑��ɂ͕n�����~�ς���Ă����B
�@
���{�~�ς̔��W�ɔ����āA���Y�͎���ɏW�ς��A���R�����͓Ɛ�ւƓ]������B�����J���҂ɂ���ĒS���鐶�Y�̎Љ���i�ވ���ŁA�ˑR�Ƃ��ĕx�̎擾�͎��{�ƂɈς˂��Ď��I�Ȃ܂܂ł���A���{�ƒ��J���̊Ԃ̖����͂܂��܂��傫���Ȃ�B���̖��������{��`�́u�����̏��v�ƂȂ�A�ƃ}���N�X�͑�1�������ԁB
�@
��1���ł́A��]���l�����Y�ߒ��ɂ����Ē����J���҂���̍��ɂ���Đ��ݏo����Ă��邱�Ƃ��������B��]���l�͗����A���q�A�n��̖{���A���̂ł���A�����A���q�A�n��͏�]���l�̌��ی`�Ԃł���B�����ɂ��ẮA��3���ŕ��͂����B
|
����2��
�@
��2���͎��{�̗��ʉߒ��̌����A���Ȃ킿�A���{���I���Y�l���̍Đ��Y�Ɋւ��錤���ł���B��1�����}���N�X���g���\���⏖�q�̎d�グ�A���s�܂Ŋւ�����̂ɑ��A��2���́A�}���N�X�̎���A�c����Ă����������̑��e(��2���̃G���Q���X�ɂ�鏘�����Q��)���G���Q���X���ҏW�A���s�������̂ł���B
�@
��1�тƑ�2�т͎��{�̏z���]�Ȃǂ������Ă���A�ʎ��{�̗��ʉߒ��ł̉^�����l�@�����B����Ύ��{�Ƃ��o�c�̏�Ŏ��{�̓��������鎞�Ɠ������_�ł���B���ہA�}���N�X�́A�H��o�c�҂ł������G���Q���X�ɂ����Ύ��{�̉�]���Ȃǂɂ��ďƉ�̎莆�𑗂�A�o�c�̃��A���Ȍ����ɂ�����������w�сA���̑��e�ɔ��f�����Ă���B
�@
��3�т͎Љ�S�̂ɂ����鎑�{�̗��ʉߒ��̌����ł���B�u�Đ��Y�_�v�ƌĂ�闝�_����ŁA�Љ�I�����{�̊ϓ_����A���{���I���Y�l�����ێ��E�������邽�߂ɁA���{�̐��Y�E���ʁE�ē������A�ǂ̂悤�Ȑ���E�����̉��ł����Ȃ��Ă��邩���l�@�������̂ł���B�}���N�X�̓t�����\���E�P�l�[�̌o�ϕ\�Ɏh�����Ȃ���u�Đ��Y�\���v�Ƃ��郂�f�������肠���A�}�N���I���_���玑�{�̗��ʁE�z��_�����B
�@
����3��
�@
��3���́A���{��`�I���Y�̑��ߒ��̌����ł���B��3������2���Ɠ��l�ɁA�}���N�X���g�̎�Ŋ��s���ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�}���N�X�̑��e���G���Q���X���ҏW(��3���̃G���Q���X�ɂ�鏘�����Q��)�������̂ł���B
�@
��3���͑�1���Ƒ�2���̌������ӂ܂��A���{��`�o�ς̈�ʓI�E���ՓI�ȏ����ۂł��鉿�i�A�����A���ϗ������A���q�A�n��Ȃǂ������A���{��`�o�ς̑S�̑��̍č\�������݂��B�@ |
���w���{�_�x�̕��@
�@
�}���N�X���w���{�_�x�ŗp�������@�́A���{��`�Љ�S�̂̍��ׂƂ����\�ۂ�O���ɂ����A���͂Ƒ����ɂ���Ď��{�T�O���m�肵�A�L���ȕ\�ۂ͂��Ȃ�����������{�T�O��L���ɂ��Ă������Ƃ�ʂ��āA���{��`�Љ�̑S�̑����T�O�I�ɍč\������Ƃ����A���͂Ƒ�������b�Ƃ���ُؖ@�I���@�ł���B
�@
�u�\�ۂ��ꂽ��̓I�Ȃ��̂���A�܂��܂����Ȓ��ۓI�Ȃ��̂ɂ����݁A���ɂ́A�����Ƃ��P���ȏ��K��ɂ܂œ��B����ł��낤�B�������炱��ǂ́A�ӂ����т��Ƃ��ǂ�̗����n�܂�͂��ł����āA�Ō�ɍĂѐl���ɂ܂œ��B����ł��낤�B��������Ǔ��B����̂́A�S�̂̍��ׂƂ����\�ۂƂ��Ă̐l���ł͂Ȃ��A�����̏��K��Ə��֘A���Ƃ��Ȃ����L���ȑ��̂Ƃ��Ă̐l���ł���v(�}���N�X�w�o�ϊw�ᔻ�����x)�B
�@
���ꂪ�}���N�X���w���{�_�x�ŗp�����u�㏸�E���~�v�ƌ�������@�A�w�[�Q���ُؖ@�̔ᔻ�I�p���Ƃ���Ă�����̂̊j�S�̈�ŁA���̕��@�̊j�S�́A�B���_����b�Ƃ��镪�͂Ƒ����ɂ��Ώۂ̊T�O�I�č\���ł���B�w���{�_�x�̃T�u�^�C�g�����u�o�ϊw�ᔻ�v�ł���̂́A�����̎嗬�ł������ÓT�h�o�ϊw�Ƃ�����p�����o�ϊw(�}���N�X�̈����ɂ��u�����o�ϊw�v)�ւ̔ᔻ��ʂ��Ď�����ł����Ă�����ł���B
�@
�}���N�X���w���{�_�x�ɂ����āA�ÓT�h��ᔻ�������̒��S�_�́A�ÓT�h�����{��`�Љ���j�I���i�������Ƃ������ɁA�u���R�Љ�v�ƌĂ�ŁA������������ՓI�ȎЉ�̐��ł��邩�̂悤�Ɍ��Ȃ����Ƃ����_�ɂ���B���Ȃ킿���{��`�Љ�͗��j�̂��鎞�_�ŕK�R�I�ɐ������A���W���A�₪�Ď��̎Љ�x�ւƔ��W�I�ɉ�������Ă����A�Ƃ����u���j���v�����Ă��Ȃ��Ƃ����̂��B
�@
�}���N�X�́w���{�_�x��1���́u���Ƃ����v�ɂ����āA���̂��Ƃ��w�[�Q���ُؖ@�Ɍ��y���Ȃ���A�����q�ׂ��B�u���̍����I�Ȏp�Ԃł́A�ُؖ@�́A�u���W���A�W�[�₻�̋�_�I��َ҂����ɂƂ��ẮA���킵�����̂ł���A���낵�����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A���ُؖ̕@�́A����������̂̍m��I�����̂����ɁA�����ɂ܂��A���̔ے�A�K�R�I�v���̗������܂݁A�ǂ̐��������`�Ԃ����^���̗���̂Ȃ��ŁA���������Ă܂����̌o�ߓI�ȑ��ʂ���Ƃ炦�A�Ȃɂ��̂ɂ���Ă��Ј�����邱�ƂȂ��A���̖{����ᔻ�I�ł���v���I�ł��邩��ł���v�B�@ |
���w���{�_�x�̒��̋��Y��`�_
�@
�w���{�_�x�́A���{��`�I���Y�l���Ƃ���ɏƉ����鐶�Y�E���Տ��W��������������ł���A���Y��`�̖������f����`��������ł͂Ȃ��B�������A�}���N�X�͎��{��`�̏��������A���{��`�ȑO�̐��Y�l��(�������A�z�ꐧ�Ȃ�)�̏ꍇ��A�����̋����Љ�(���Y��`�Љ�)�̏ꍇ�Ƃ����ΑΔ䂵�Ă���B
�@
�w���{�_�x�S3���̒��Łu���Y��`�Љ�v�ƋL�ڂ���Ă���ӏ��͑�ꕔ�́u���Y��`�Љ�łͤ�@�B�ͤ�u���W�����Љ�Ƃ͂܂������قȂ��������͈͂����v�Ƒ�́u���Y��`�Љ�ł͎Љ�I�Đ��Y�Ɏx�Ⴊ�o�Ȃ��悤���炩���߂�����Ƃ����v�Z���Ȃ���邾�낤�v�̂킸��2�ӏ��ł���B�}���N�X�͎��{��`�Ƃ͈قȂ鋦���I�Ȑ��Y�l�����A�u�����I���Y�l���v�A�u���������J���̗l���v�A�u�����I���Y�v�A�u�Љ���ꂽ���Y�v�Ȃǂƕ\�����Ă���B���ڍׂȋK��Ƃ��ẮA�u�����I���Y��i�ŘJ�������������̑����̌l�I�J���͂����o�I�Ɉ�̎Љ�I�J���͂Ƃ��Ďx�o���鎩�R�Ȑl�X�̘A���́v(��1����1��)�A�u�J���҂������������g�̌v�Z�ŘJ������Љ�v(��3����1��)�A�u�Љ�ӎ��I���v��I�Ȍ����̂Ƃ��đg�D�v(��3����6��)�Ȃǂ�����B
�@
�܂��A�w���{�_�x�ɂ����č��Ƃ͏d�v�ł͂Ȃ��A�u�ӎ��I�v��I�Ǘ��v(��1��)�u�ӎ��I�ȎЉ�I�Ǘ�����ыK���v(��3��)�Ƃ������`�ŗ����ɂ���ċK������Ƃ�����ʘ_���q�ׂ��Ă��邾���ł���B
�@
�}���N�X�́w���{�_�x��3���ŁA�u���R�̍��v�Ɓu�K�R�̍��v�̖��ɐG��A���Y��`�v���̖ړI���q�ׂĂ���B���Ȃ킿�A�o�ς����{��`����]���l(������)�̒Nj�����������A�Љ�̍����I�ȋK���̉��ɕ����ĎЉ�̕K�v�ɑ��鐶�Y�Ƃ����o�ϖ{���̂���������邪�A����ł����Y�͐l�Ԃ��������Ă�����ŕK�v�ȕx�����肾�����߂̍S���I�ȘJ��(�K�R�̍�)���v��B�������A���̎��Ԃ͎��ԒZ�k�ɂ���Ď���ɒZ���Ȃ�A�]�Ɏ���(���R�̍�)���g�傷��B�w���{�_�x��3���ł́A���̎��Ԃ̊g��ɂ���Đl�Ԃ̑S�ʔ��B�������Ȃ��A�l�Ԃ���������ƃ}���N�X�͎咣�����B�@ |
���w���{�_�x����
�@
���X�̃}���N�X�̃v�����Ɋ�Â��w���{�_�x�̕����ɂ��Ă͗l�X�ȋc�_�������Ă���B���݁A�}���N�X�ƃG���Q���X�̑S�Ă̒��앨�����s����VMEGA�̎��݂����ۓI�ȋ�����Ƃōs���A���̒��Łw���{�_�x�̍\���ɂ��Ă��ᖡ����Ă���B���̐VMEGA�ɂ������II���u�w���{�_�x����я����J��v�S15��24�����̕ҏW��L�E�~�V�P�[���B�`�AL�E���@�V�[�i�AE�E���@�V�`�F���R�A��J���V��AC�EE�E�t�H���O���[�g�AR�E���[�g�AE�E�R�b�v�t�A�呺��AM�E�~�����[�ȂNJe���̌����҂ɂ��A�i�߂��Ă���B
�@
�����̓��{���͍����f�V��ɂ����̂ŁA���������������̗��w�����Љ��`�E���Y��`�𒆍��Ɏ����A�����ƌ�����(�Ȃ��A�����ւ̔����ł��銿�w�҂̒����[(�[��)���A���{���ɐ�Ċ�������s�������̂́A���e�͖ʔ��������͂������ł���Əq�ׂāA���̂܂ܕ������Ă��܂����ƌ����Ă���)�B���{�_�̓ǂݒ����́A�t�����X�̃��C�E�A���`���Z�[������{�̜A���A�����m�i�A���J�s�l��ɂ���čs���Ă���B
�@
���ᔻ
�@
�}���N�X��`��ʂ�ᔻ���������w�h�͑������邪�A�w���{�_�x���̂��̂�ᔻ������\�I�Ș_�҂̈�l�ɃI�[�X�g���A�̌o�ϊw�҂ŃE�B�[���w�h�̃I�C�Q���E�t�H���E�x�[�����o���F���N������B�x�[�����o���F���N�́A�w�}���N�X�̌n�̏I���x�̂Ȃ��ŁA�}���N�X����1���ł͉��l�͓����J���ʂɂ���Č��܂�Ƃ����Ă���̂ɁA��3���ł͂���Ƃ͕ʂ́A�����ϓ��ɂ��ƂÂ����Y���i�ƕ��ϗ������̗��_�������o���Ă���Ƃ��āA������w���{�_�x�̑�1���Ƒ�3���̖����Ɣᔻ�����B
�@
�܂��A���̖��Ɋւ���āA���l�����i�ɓ]������ۂɁA�����l�������Y���i���т����Ƃ���}���N�X�̗����ᔻ�����h�~�g���E�G�t�E�{���g�P���B�b�`�Ȃǂ�����B�����̂��āu�]�`���_���v�Ƃ����B�@ |
���J�[���E�n�C�����q�E�}���N�X
�@
(Karl Heinrich Marx, 1818-1883)�@�h�C�c�̓N�w�ҁA�v�z�ƁB�����v�z�j�A�o�ώv�z�j�̏�ł́A19���I�ȍ~�̋��Y��`�^���E�J���^���̗��_�I�w���ҁA�o�ϊw�҂Ƃ��Ēm����B20���I�ɂ����čł��e���͂��������v�z�Ƃ̈�l�Ƃ����B�e�F�ɂ��ē��u�̃t���[�h���q�E�G���Q���X�ƂƂ��ɁA��I�Ȑ��E�ς���ъv���v�z�Ƃ��ĉȊw�I�Љ��`��ł����āA���{��`�̍��x�Ȕ��W�ɂ�苤�Y��`�Љ��������K�R����������B�}���N�X�̌o�ϊw�ᔻ�ɂ�鎑�{��`���͎͂咘�w���{�_�x�Ɍ������A�w���{�_�x�Ɉˋ������o�ϊw�̌n�̓}���N�X�o�ϊw�ƌĂ��B
�@
�J�[���E�}���N�X(�ȉ��A�}���N�X)�́A1818�N5���A�v���C�Z�����������̃��[�[���͔Ȃɂ���g���[�A�ɂāA���n�C�����q�E�}���N�X�ƕ�A�����G�b�g�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�B���n�C�����q�̉ƌn�́A��X���_�����̃��r(���E�҂Ő_�w��)�߂�ƕ��ł��������A���n�C�����q���g�́A���R��`�I�Ȍ[�֎v�z�������A1812�N����t���[���[�\���̉���ł��������ٌ�m�ł���A�}���N�X�����܂��O�ɁA���_��������L���X�g���̃v���e�X�^���g�ɉ��@�����B��A�����G�b�g�����_�����̃��r�̉ƌn�Ȃ̂ŁA�}���N�X�̏o���̓��_���n�h�C�c�l�Ƃ����邪�A�}���N�X���g��6�̍��ɕ��e�Ɠ������v���e�X�^���g(�L���X�g��)�̐�����Ă���̂ŁA���_�����k�ł͂Ȃ��B
�@
1830�N�A�}���N�X12�̂Ƃ��A�g���[�A�̖���M���i�W�E���ɓ��w�B�}���N�X�̓��w�����M���i�W�E���͊J���I�ȍZ���ŁA�Z�����M��ȃ��\�[�̎x���҂ł������B�}���N�X�̍��Z���Ƙ_��(�N�w)�̎��́A�u�E�Ƃ̑I���ɂ������Ă̈�N�̍l�@�v�ł������B
�@
1836�N�A�}���N�X18�̂Ƃ��A�o�̗F�l�Ō��������̖��������C�G�j�[�E�t�H���E���F�X�g�t�@�[����(22��)�ƍ����B���̌�{����w�Ɋw�сA��Ƀx��������w�ɓ��w���A�w�[�Q�����h�̉e������B����ɁA1841�N�ɂ̓C�G�i��w�֓��w�B�w�ʐ����_���́w�f���N���g�X�ƃG�s�N���X�Ƃ̎��R�N�w�̍��فx�ł������B���̊w�ʐ����_���ɂ��A�}���N�X�͓N�w���m�ƂȂ����B
�@
1842�N�A�}���N�X24�̂Ƃ��A�P�����őn�����ꂽ�u���W�����}�i��`�́u���C���V���v��M�߂�B���̍��ɐ��U�̗F�l�ɂ��ă}���N�X�ő�̎x���҂ƂȂ�t���[�h���q�E�G���Q���X�Ƃ̏o����ʂ����Ă��邪�A���̎��̏o��͂��݂��ɂقƂ�lje���������炳�Ȃ������B�}���N�X�́u���C���V���v�̕ҏW�������Ă������A�قǂȂ����V�A���{�ᔻ�̂��߂Ɏ����V���Ђւ̒e���ɂ��A1843�N3���Ɏ��E�����B
|
�����[���b�p�������Ƌ��Y��`�錾
�@
1843�N6���A�}���N�X25�̂Ƃ��ɃC�G�j�[�E�t�H���E���F�X�g�t�@�[�����ƌ����B11���Ƀp���֏o���A�}���N�X�͗F�l�ł���A�[�m���g�E���[�Q�A�Q�I���N�E�w�����F�[�N�ƂƂ��ɁA�p���Łw�ƕ��N���x���o�ł����B�������Ȃ���A�w�ƕ��N���x��2���Ŕp���ƂȂ�A�}���N�X�̓h�C�c����̖S�����Y��`�҂��u�T���s���Ă����u�t�H�A���F���c�v���Ɋ�e����悤�ɂȂ����B1844�N8���A�t���[�h���q�E�G���Q���X���p���Ƀ}���N�X��K��A10���ԑ؍݂��A���̎�����{�i�I�ȓ�l�̌�F���͂��܂����B�܂��A���̎����}���N�X�́A�n�C�����b�q�E�n�C�l�Ƃ̒m���Č�F���n�߂邱�ƂƂȂ�B�������u�t�H�A���F���c�v���Ɋ�e���ꂽ�v���C�Z�������t���[�h���q�E���B���w����4���̔ᔻ�L���ɕ��S�����v���C�Z�����������ږ⊯�̃t�����X���{�ւ̓��������ɂ��A1845�N1���ɂ̓p������x���M�[�̃u�����b�Z���֒Ǖ���]�V�Ȃ����ꂽ�B���̎��̃x���M�[���{�̎���ɂ́u���݂̐������ɂ��Ă̒���\���Ȃ��v�Ƃ����������t���Ă���A�}���N�X�͂�����Ŋm���B�������A�}���N�X�͂��̊m��͐����ɎQ�����Ȃ����Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��Ɖ��߂��A�Ȍ�������I�Ȋ����𑱂����B
�@
1846�N�A�}���N�X28�̂Ƃ��A�ݏZ�n�̃u�����b�Z���ɂăG���Q���X�ƂƂ��Ɂu���Y��`���ےʐM�ψ���v��ݗ��A����ɋ��Y��`�g�D�̕��h�����̉ߒ��ŐV���Ɂu���Y��`�ғ����v�̌����ɎQ�悷�邱�ƂɂȂ�A�w���Y�}�錾�x���N�������B�w�g���[�A�V���x���@�֎��Ƃ��Ă����u�^���Љ��`�ҁv�J�[���E�O�����[���Ƙ_��������̂����̍��ł���B�������Ȃ���A�u���Y��`�ғ����v�����ꗂɋN��������������ɂ��A�}���N�X��͑g�D�����̏����h�ɓ]���A����ɂ�1848�N2���̃t�����X�v���̂���3��3���Ƀx���M�[�x�@�ɕv�w�Ƃ��}������A24���Ԉȓ��̍��O�ދ��𖽂���ꂽ���߁A�����t�����X�Վ����{�̏����ɉ����ăp���ɂ��ǂ�B�����ɂ̓v���C�Z�������̂̃P�����ւƈړ����w�V���C���V���x��n���������̂́A���{�ɒe������ė�1849�N�ɂ͔p���ƂȂ�A5���ɂ͍��O�Ǖ��ƂȂ�B��������̓p���ւƖ߂���̂̃t�����X���{�̎����͔����h�������Ă���A�}���N�X�̓G���Q���X�̏����ɉ����āA1849�N8�����A�����h���ɖS�������B�Ȍ�A�}���N�X�͖S���Ȃ�܂ŃC�M���X�ɂƂǂ܂葱�����B
|
���S���惍���h���ł̑؍ݐ���
�@
�}���N�X�̐e�F�ł���x���҂ł������G���Q���X�́A�����h���Ŏ��������L�����Ђɋ߂Ă���A�����ʂɂ����ă����h���ɑ؍݂���}���N�X���x�����B�����������h���S���㐔�N�Ԃ̃}���N�X�͕n���ɂ������ł���A��j�O�C�h��1850�N11���ɁA�O���t�����c�B�X�J��1852�N�ɁA���j�G�h�K�[��1855�N3���ɁA���ꂼ��S���Ȃ��Ă���B1851�N����}���N�X�́u�j���[���[�N�E�g���r���[���v���̓��h���ɂȂ�A1862�N�܂�500��ȏ��e�����B1851�N12���Ƀt�����X�ɂ����đ哝�̂̃��C�E�i�|���I�����N�[�f�^�[���N�����Ď��������邪�A����ɑ��ă}���N�X��2�������1852�N2���ɂ́w���C�E�{�i�p���g�̃u�������[��18���x�\���A�����������B1864�N�Ƀ����h���Ō������ꂽ���C���^�[�i�V���i���ɎQ���A�哱��������A�o�N�[�j���ƌ������_�������B
�@
�����h���S���ȍ~�A�}���N�X��1850�N����S���Ȃ�1883�N�܂ł�30�N�ԁA��p�}���قɒ�10������قƂȂ�[����6���܂Ŗ����ʂ������A�o�ό����Ɩc��ȗʂ̎������W���s�����B�}���N�X�́w���{�_�x�́A���̒��N�ɂ킽��o�ό������琶�܂ꂽ�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B1859�N�ɂ́w�o�ϊw�ᔻ�x���o�ł����B
�@
1867�N4��12���A�w���{�_�x��ꊪ�����s�B���{�̐��Y�ߒ��Ɋւ��錤�����ʂ̏W�听�ł������B
�@
1871�N3��26���A�}���N�X53�̂Ƃ��Ƀp���E�R�~���[���������B�킸��72���Ԃ̒Z���ԂȂ�����A�p���ɂ����Ė��O�I�N�ɂ�鐢�E���̘J���ҊK���̎����ɂ��v���������a�������B���̂Ƃ��}���N�X�́w�t�����X�̓����x�Ƒ肷�鎷�M�������Ȃ��A���̐������x�������B�����ɁA�u�Ȃ����F���T�C���ɓ��������{�R��ǂ�Ȃ��̂��v�ƃp���E�R�~���[����ᔻ�������B
�@
�����h���ł̃}���N�X�Ƃ̐����͗T���ŁA���C�h�����������B�ЂƂ�̃��C�h�̓}���N�X�̎q�����Y���A�Ȃ̓{�������邽�߂ɁA�G���Q���X�������̎q���Ƃ��ĔF�m�����B
|
���ӔN
�@
1871�N�̃p���E�R�~���[���̖I�N�����ȍ~�́w���{�_�x�̎��M�����ɐ�O���A���S�ɂ��y�ԃ��|�[�g�������Â����B�}���N�X�́A�S���n�����h���ɂ��Ȃ���A����̗��_�̌n�̍\�z���s���ƂƂ��ɁA�h�C�c�A�t�����X�̋��Y��`�^���ւ̏����������Ȃ��A���_�I�x���ł��葱�����B1875�N�ɂ̓h�C�c�Љ���`�^���̃A�C�[�i�n�h�ɂ��Ăĕ����𑗂�A����͂̂��Ɂw�S�[�^�j�̔ᔻ�x�Ƃ��ďo�ł��ꂽ�B1881�N12��2���ɍȃC�G�j�[�����S�����B
�@
1883�N3��14���A�S���n�����h���̎���ɂāA�I�|���֎q�ɍ������܂ܐ�������(65��)�B1883�N3��17���ɂ͖������s��ꂽ�B�}���N�X�̑��V�́A�Ƒ��ƃG���Q���X��̂����e�����F�l�ɂ��v11�l(�܂���9�l)�Ŏ���s�Ȃ�ꂽ�B���̂Ƃ��̃G���Q���X�̒����́u�J�[���E�}���N�X�̑��V�v�Ƃ��Ĉ₳��Ă���B�ނ̕�̓C�M���X�̃A�[�`�E�F�C�w�̋߂��ɂ���n�C�Q�C�g��n�ɂ���A1956�N�ɂ͗L�u�̎�ŐV���ɃX�E�F�[�f���Y�̍���e�̋�����������ꂽ�B�����Č��݂Ɏ���܂ŁA�ނ̐��O�̖ʉe���ÂԂ��Ƃ��ł���B
�@
�}���N�X�́A�ނ��S���Ȃ钼�O�܂Ő��͓I�Ɏ��M�������s���Ă���A�ނ̌��ɂ͖c��ȑ��e���₳��Ă����B�����Ĕނ̖v��A�₳�ꂽ���e�Ɋ�Â��A�ނ̈ӎv���p�����G���Q���X��1889�N�Ɂw���{�_�x���ҏW�E�o�ŁA�����1894�N�ɂ́A��O���̕ҏW�E�o�ł��s��ꂽ�B�@ |
���}���N�X�̗��j��
�@
���B���j��
�@
�}���N�X�̗��j�ςɂ��A���̎���ɂ����镨���I�����̐��Y�l�����Љ�̌o�ϓI�@�\(�Љ�I����)���`�����A������̎Љ�I�A�����I�A���_�I�������ߒ����(�ӎ�)���K�肷��Ƃ��Ă���B���������āA�l�Ԃ̈ӎ��ƎЉ�I���݂Ƃ̊W�́A�l�Ԃ̈ӎ������̎���ɂ�����Љ�I����(�����I�����̐��Y�l��)���K�肷��̂ł͂Ȃ��A�t�ɂ��̎���ɂ�����Љ�I���݂��A�����o�ς�|�p�E�����E�@���Ƃ������A������̈ӎ����̂��̂��K�肷��Ƃ����W���������邱�ƂɂȂ�B �l�Ԃ̎Љ�I���݂�y��ɂ��āA���̎���ɂ�����ӎ����K�肷��Ƃ����W����A�l�Ԃ̎Љ�I���݂������\���A�l�Ԃ̈ӎ����㕔�\���Ƃ�сA�˂Ɏ���ƂƂ��ɕω����鉺���\���̂���悤���A���̎���ɂ�����㕔�\���̕ω���K�R�I�ɂ����炷���̂Ƃ��ꂽ�B���̂悤�ȃ}���N�X�̗��j�ς�B���j��(�B���_�I���j��)�Ƃ����B�}���N�X�̌��t�ł͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@
�w�o�ϊw�ᔻ�@�����x�@/�@�l�Ԃ́A���̐����̎Љ�I���Y�ɂ����āA���́A�K�R�I�ȁA�����̈ӎv����Ɨ��������W���A�܂肩���̕����I���Y���͂̈��̔����i�K�ɑΉ����鐶�Y���W���A�Ƃ�ނ��ԁB���̐��Y���W�̑��͎̂Љ�̌o�ϓI�@�\���`�Â����Ă���A���ꂪ�����̓y��ƂȂ��āA���̂����ɁA�@���I�A�����I�㕔�\�������т������A�܂��A���̎Љ�I�ӎ����`�Ԃ́A���̌����̓y��ɑΉ����Ă���B�����I�����̐��Y�l���́A�Љ�I�A�����I�A���_�I�������ߒ���ʂ𐧖�B�l�Ԃ̈ӎ������̑��݂��K�肷��̂ł͂Ȃ��āA�t�ɁA�l�Ԃ̎Љ�I���݂����̈ӎ����K�肷��̂ł���B
�@
���l�ԎЉ�̔��W�Ƒa�O
�@
�Ⴂ����A�}���N�X�́A�l�Ԃ̍��o�����V�X�e����Y���W���l�Ԃ̎�𗣂�A�t�ɐl�Ԃ�G�ΓI�ɗ}�������ԁA���Ȃ킿�a�O���������邱�Ƃ��w�E�����B(�u�a�O�v�Ƃ������t�̓w�[�Q���N�w�ł悭�p������B)�a�O�̌`�Ԃ͂��܂��܂ł���A���i��ݕ����l�Ԃ��x�z���J���{���̂�낱�т�������J���̑a�O�A���Y�ɂ�����l�ԂƋ@�B�̒n�ʂ��t�]���A�l�Ԃ̎�̐����ے肳��A�܂�Ŏ��Ԃ̈ꕔ�̂悤�ɂ����@�B�Z�p�ɂ��a�O�Ȃǂł���B�������A�B���_�I�ȗ��j��(�B���j��)���m��������A�}���N�X�A�G���Q���X�́u�a�O�v�Ƃ����p����قƂ�ǎg���Ă��Ȃ��B
�@
�����{��`�̔��W�Ɗv��
�@
�}���N�X�́w���{�_�x�̒��ŁA���{��`�ɓ��݂��邳�܂��܂Ȗ����_����_���l�@�������A���{��`���̂��͎̂Љ�̐��Y�������߂邽�߂ɕK�v�Ȓi�K�Ƒ����Ă���A���{��`�o�ς̔��W�E���n�Ƃ���ɔ������Q�A�K�������̌����Ȃǂ��_�@�Ƃ��āA�v�����N���苤�Y��`�ւƈڍs����ƍl���Ă����B�}���N�X�����Y��`�v���̑O��Ƃ��Ă����̂́A�����̃C�M���X�A�h�C�c�A�t�����X�Ȃǂɑ�\����鐼���̐��n�������{��`�I���Y�l���ł������B�������A���ۂɎЉ��`�v�������������̂̓��V�A�A�����A�L���[�o�Ȃǎ��{��`�̔��W�̒x�ꂽ���X�ł������B�@ |
���}���N�X�̏@����
�@
�}���N�X�́A�w������Ƀw�[�Q���N�w���������邩�����A��������݂��������������B���������������������B1837�N(19��)�̂Ƃ��Ƀm�[�g�ɏ������u��]�҂̋F��v�Ƃ������́A�u�^���̎��b�������c���ĉ����牽�܂Ŏ�グ���v�_�ւ̕��Q�Ƃ����t���[�Y�Ŏn�܂��Ă���B
�@
�}���N�X��26�̂Ƃ��A�_���w�w�[�Q���@�N�w�ᔻ���_�x�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@
�u�@���I�ߎS�͌����I�ߎS�̕\���ł�����Ό����I�ߎS�ɂ�������R�c�ł�����B�@���͒ǂ��߂�ꂽ�҂̗����ł���A���Ȑ��E�̏�ł���ƂƂ��ɁA��Ȃ���Ԃ̗�ł�����B����͐l���̈���(�A�w��)�ł���B�l���̌��z�I�K���Ƃ��Ă̏@����p�����邱�Ƃ͐l���̌����I�K����v�����邱�Ƃł���B�ނ�̏�Ԃɂ���������̌��z�̔p����v�����邱�Ƃ́A�����̌��z��K�v�Ƃ���悤�ȏ�Ԃ̔p����v�����邱�Ƃł���B�����ď@���̔ᔻ�́A�@��������ɂ��J�����̔ᔻ�̖G���ł���B�v
�@
����"����"�ɂ��Ắw�w�[�Q���@�N�w�ᔻ���_�x�ɁA�ɂݎ~�߂ł���|�̋L�q������B���Ђ͒��ł������N��������ł���ƂƂ��ɁA�����A�ɘa��Âł��u�ɂȂǂ̒ɂݎ~�߂Ƃ��Ă��g�p����Ă����B
�@
�u���[�m�E�o�E�A�[�����_���l���������ɂ͔ނ�����_��������L���X�g���ɉ��@������悢�Ǝ咣�����̂ɑ��A26�̃}���N�X�́A���L���̃G�S�C�Y�������K���q�Ə��l���������_���l�ɋ�����̂ł���A���@�͖��Ӗ��ł���B�K�v�Ȃ̂͐l�Ԃ��G�S�C�Y�����������邱�Ƃł���A�Ɣ��_���Ă���(�w���_���l���ɂ悹�āx)�B
�@
�}���N�X���g�̓t�H�C�G���o�b�n����e�����Ė��_�_�I�ɂȂ�A�Љ����j���`�����錴���͏@���I���O�ł͂Ȃ��A���ɓI�ɂ͌o�ςɋ��߂�ׂ��ƍl�����B�@ |
���}���N�X�̕��w�E�|�p��
�@
�M���V���ߌ��A�V�F�C�N�X�s�A�Ȃǂ̌����w�����D�����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���t���C�g�u�����f�v���� 1900�N |
   �@
�@
|
Freud, Sigmund.(1856-1939)
�@
Die Traumdeutung.
�@
�t���C�g�́A�I�[�X�g���A�̐_�o�a�w�ҁA���_���͊w�ҁB�p���Ŋw�сA�i�D�u���C�A�[�ƍÖ��p�ɂ��q�X�e���[���Â����݂����A��ɍÖ��p�̑���Ɏ��R�A�z�@���l�Ă��A���_���͊w��a���������B���_���͂́A�ꌩ���Ӗ��Ɍ����閲�̓��e�ɂ��Ӗ�������A���̉��ߖ@�ɂ���Ēf�ГI�ł܂Ƃ܂�̂Ȃ����̌��ݓ��e�����߂���̂ł���B�{���́A���_���̗͂��_�I��b���Ƃ炦�����̂ŁA���_���͂��w�Ԃ��߂̕s���ȓ��发�Ƃ���Ă���B�u�����f�v��1900�N�܂ŏo�ł���Ȃ��������A�����シ�ׂĂ̎�v�ȓ_��1896�N���߂Ɋ������Ă����B�W�����́A�Z�ΐF�̊v���ɍĐ��{����Ă���B�@ |
�������f�@
(Die Traumdeutung, The Interpretation of Dream)�@1900�N�ɔ��\���ꂽ�A�I�[�X�g���A�̐��_�Ȉ�W�[�N�����g�E�t���C�g�ɂ�閲�Ɋւ��鐸�_���͊w�̌����ł���B
�@
�t���C�g��1856�N�ɐ��܂�A�E�B�[����w�ň�w���w�ԁB�]��U�̐���Ƃ��ăE�B�[�������a�@�ɋΖ����A�t�����X�̃T���y�g���G�[���a�@�ł��w�ԁB1893�N�ɗF�l�̈�t���[�[�t�E�u���C�A�[�Ƌ����Łw�q�X�e���[�����x�\����B�{���͈�t�Ƃ��ĒS����������Ɋւ��錤���̐��ʂł��������A�o�œ����͕]������Ȃ��������߂ɏ���600�����������邽�߂�8�N�Ԃ��������B
�@
���ɂ��Ă̍l�@�͌Ñォ��s���Ă������A�S���w�I�Ȋϓ_����̌����͑����Ȃ��B���������Ė��̌����ɂ��Ă��_�w�I�Ȑ������Ȃ���Ă����B�₪�ĐS���w�I�Ȑ��������݂��A�������̊��o�̎h���ɂ���Ė��ɂ��̎h�������f�����Ƃ����������Ȃ����悤�ɂȂ����B�������t���C�g�́A���̊��o�h�������ł͂Ȃ����Ƃ��w�E���A���̓��e�_��ԂƊ֘A�t����c�_�����܂��܂Ȏ��ጤ���Ɋ�Â��ēW�J�����B
�@
�����̍\��
�@
�t���C�g�ɂ��Ζ��̑f�ނ͋L����������o����Ă���A���̑I����@�͈ӎ��I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ӎ��I�ł���B���������Ĉꌩ����Ɨ��G�Ȗ��̓��e�ɂ����Ă����ӎ��Ɋ�Â�����������������Ă���A���܂��܂ȏo��������̕���Ƃ��ĘA����������̂ł���B����ɂ͂��܂��܂ȑ_�������邪�A��ʓI�ɂ͖��Ƃ͐��ݓI�Ȋ�]���[����������̂ł���B�܂薲�͖��ӎ��ɂ�鎩�ȕ\���ł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@
�����Âւ̉��p
�@
�t���C�g�͖��ɂ����ď[�������悤�Ƃ����]���C���[�W�ɂ��B���ɕ\������Ă��邩�ɂ��Ē��ӂ��Ă���B���̗��R�Ƃ��Ă͊�]�m�����邱�Ƃ�W���悤�Ƃ���ӎ��ɂ���Ė����c�Ȃ���邱�Ƃ������Ă���B�ӎ��ɂ�閲�̌��{��������邽�߂ɖ��ӎ��͊�]���ԐړI�ȕ\�������p����̂ł���B�Ȃ��Ȃ�A�ʏ�ł͈ӎ��I�ɗ}�������ׂ��ƌ��Ȃ���Ă��鐫�~�����̒��ł͊�]�Ƃ��Ĕ������邽�߂ł���B�t���C�g�͕����Љ�̐����ɂ��l�Ԃ̖{�\����������Ă�����̂́A����͏��ł����킯�ł͂Ȃ��A���̐��~�͈Úg�I�ȕ\���ɂ���Ė�����������̂Ƒ����邱�Ƃ��ł���Ƙ_����B�@�@
�@ |
 �@ �@
���L�����[�u���ː��̌����v���� 2�� 1910�N |
   �@
�@
|
Curie, Marie.(1867-1934)
�@
Traite de radioactivite.
�@
�t�����X�̏��������w�ҁA���w�ҁB�x�N�����̌����Ɏh������āA�v�s�G�[���Ƌ��Ɍ����ɑł����݁A�V�R�E�����z���烉�W�E������у|���j�E�������A���˔\���f�̑��݂ƌ��q�̎��R�����Ƃ����āA�����̌��q�j�����w�̐����Ȃ����B1903�N�x�N������v�Ƌ����Ńm�[�x�������w�܂����B�v�̎��セ�̌�C�Ƃ��ăp����w�\���{���k�̋����ɏA�C���A1910�N�ɋ������W�E���̕����ɐ��������B���̋Ɛтɑ��ė��N�m�[�x�����w�܂����B��1�����E��풆�́A�w�����u�ɂ���Ê�����g�D�A���͍��ۘA���̒m�I���͍��ۈψ���̈ψ��Ƃ��āA�Ȋw�̍��ۋ��͂ɐs�͂����B�@ |
���}���[�E�L�����[�@(1863�`1934)
�@
1863�N�@11��7���|�[�����h�̃����V�����ŁA�W���[�u���w�̋��t�̕��X�N���f�t�X�J���ƁA�v�������c�ɋM���̖��ł�͂苳�t�ł����Ƃ̊Ԃɂł����A5�l�q�ǂ������̖����q�Ƃ��Đ��܂��B��́A�ޏ��̒a�����ォ�猋�j�ɂ�����B������A�q�ǂ������́A�������ĕ�ɃL�X�����邱�Ƃ��A������Ȃ������B
�@
�}���[�́A�q���̂��납��A�L���͂ƏW���͂ƌ��w�S�ɂЂ��ł����B
�@
�����ɂȂ��Ė{��ǂ�ł���ޏ��̂܂��ŁA�o�������A�������炵�Ĉ֎q���s���~�b�h�̂悤�ɂ݂��������A�ޏ��͂܂������C�t���Ȃ������Ƃ����G�s�\�[�h������B
�@
1873�N�@����܂ŁA���w�̕����w�������������A���J������ꂽ���߂ɁA�������ꂵ���Ȃ�B���̂��߁A��h���������ɂ����A���e�́A���������邱�Ƃɂ���B
�@
1876�N�@�a�����Ă�����h���̂ЂƂ肪�A�`�t�X�ɂ�����A���ꂪ�A�o�̃]�[�V���ƁA�u���[�j���ɂ���A�]�[�V���́A�S���Ȃ�B
�@
1878�N5���@��A�x���j�łȂ��Ȃ�B
�@
��͖S���Ȃ�A�����킦���A���܂����@�b�ɁA���̂��Ă��܂������̂��߂ɁA�����Ă��܂����A���T�y�j���ɂ́A���Ȃ炸�A�Ƒ��ŃT�����[���������݁A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A�����ă|�[�����h�Ȃǂ̊e���̕��w��ǂݏグ�镃�̘N�ǂƊ��z�Ɏ��������ނ��A�������肽�����߂������B
�@
1883�N�@6���A�����V�����̍������w�Z�𑲋ƁB���їD�G�̋����_�������炤�B���̂���1�N�Ԃ͂��Ȃ��ł̂�т肭�炷�B
�@
1884�N�@�����V�����ɋA��A�ƒ닳�t���n�߂�B
�@
��ړ���w��ɎQ�����ă|�[�����h�̕�������B
�@
1885�N�@�o�̃u���[�j���́A�ƒ닳�t�����Ȃ���A�p���܂ł́A�ؕ���1�N�ԕ��̊w������߁A��w���w�Ԃ��߂Ƀp���ɍs���A�\���{���k��w�ɂ͂���B
�@
1886�N�@�}���[�́A���݂��݂̉ƒ닳�t�����āA�u���[�j���ɑ�������B����́A�ޏ������o���̂Ƃ肫�߂̂��߂ɂł������B
�@
���āA�ޏ��́A���̉ƒ닳�t��̃]���t�X�L�[�Ƃ̒��j�J�W�~�[���Ɨ��ɂ����邪�A�ނ̗��e�ɉƒ닳�t�ӂ����ƌ����āA���������B
�@
���J�Ɣ߂��݂̂Ȃ��A�ޏ��́A�u���[�j���̂��߂ɂ��A�ƒ닳�t�����̂܂ܑ�����B
�@
1890�N�@�p���ŁA�u���[�j���́A�w�F�̃J�W�~�[���E�h���X�L�[�ƍ���B�����āA�}���[�ɍ��x�͂��Ȃ����A�p���ɂ��ĕ��ł�������ł����ƁA�莆��������B
�@
1891�N�@�Ă̏I���A�}���[�́A�J�W�~�[���E�]���t�X�L�[�ƃJ���p�`�A�̎R���ɂ���R�����ō������A�ӂ���̌����ɂ��Ęb���������A���ɁA�D�_�s�f�Ȕނ̑ԓx�ɁA���̏I�������S����B
�@
�ޏ��́A�p���ɂłāA�\���{���k��w�ɓ��w�B
�@
�����w�Ɛ��w���w�ԁB���O���}���A����A�t�����X���Ƀ}���[�ƂȂ̂�B
�@
�ŏ��́A�u���[�j���v�Ȃ̉Ƃɉ��h���邪�A�������y���ޕv�ȂƋ����������ĕw�ɗ�݂����Ǝv���ޏ��́A�ЂƂ肮�炵���n�߂�B
�@
���̓`���ƂȂ��Ă���A�H�ׂ���̂��A�\���ɐH�ׂ��A�����ĕX�̂悤�ȕ����ł́A�ҕ��̓��X��������B
�@
1893�N�@�����w�̊w�m�����Ɏ�Ȃō��i����B�w�m�����Ƃ�B
�@
1894�N�@�s�G�[���E�L�����[������B���w�̊w�m������2�Ԃō��i����B
�@
�ċx�݂Ƀ|�[�����h�ɋA��A���Ƃ��������̂��p���ɂ��ǂ�B
�@
1895�N�@�s�G�[��(36��)�ƌ�������B�}���[�E�L�����[�ƂȂ�A�t�����X�̍��Ђ��Ƃ�B
�@
���̌������ɂ́A�w�ւ��@���V�����Ȃ��������A�ӂ���́A���̂��Ƃ����ɁA���Ƃ��̑��蕨�̏��؎�Ŕ������A���]�Ԃɂ̂�A�V�����s�ɍs���B
�@
1896�N�@�����������i�����Ɉ�Ԃō��i����B
�@
1897�N�@�����C���[�k�����܂��B���m�_���̃e�[�}�Ƃ��ăt�����X�̕����w�҃x�N�����̌����ɖڂ��Ƃ߁A�E�����������̕��ː��̌����ɂƂ肭�ށB
�@
�����A�}���[�E�L�����[�̎��������ׂ�ꍇ�A���Ȃ炸�A����˔\�̋����I�Ȏ��̂ɑ��飍����}���ق̐ӔC��������邽�߂̏��ނɏ��������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@
���̓����̉��琶����댯�͂킸���Ȃ��̂ł͂��邪�A���̓����͌��݂ł��A���⍡�㐔��N�́A���˔\�����т��܂܂ł���Ƃ������Ƃł���B
�@
1898�N�@�s�b�`�u�����h(�_���E�����̂��ƁB�E���j�E���ƃg���E�����ܗL���Ă���B)�ɁA�V����2�̕��ˌ��f�����邱�Ƃ��A��������B�����ɁA��|���j�E�������W�E����Ɩ��O������B
�@
���Ȃ݂ɁA�|���j�E���́A�ޏ��̌̍��|�[�����h���疼�O���Ƃ������̂ł���B
�@
���̂��납��A�ӂ���́A�����������Ƃ肭��ł�����˔\�����̉e����̓��Ɏn�߁A���₷���Ȃ�B
�@
1900�N���납��A�����𑱂���ӂ���̂܂��ɁA�ނ�ɑ����Ⴂ�����҂������W�܂�悤�ɂȂ�B���̒��ɂ́A�A���h���E�h�r�G���k��A�|�[���E�����W�����@���������B
�@
�A���h���E�h�r�G���k�́A�}���[�̂��Ƃ��A�[�������Ă����Ƃ����B�����āA�ޏ��̍Ō�̏u�Ԃ܂ŁA������Ƃ���ŁA�₦���ޏ��ɉe�̂��Ƃ��t���]�����Ƃ������Ƃł���B
�@
1902�N�@�������W�E�����Ƃ肾�����Ƃɐ�������B
�@
�}���[�̕��A�_�X�̎�p������������Ɏ��S����B�}���[�́A�ň��̕��̎��ɖڂɂ������Ƃ��ł��Ȃ������B
�@
�D�P���Ă����ޏ��́A���㐔���ԂŎ��S���関�n�����o�Y����B���̌����́A���˔\�̂����ł͂Ȃ����ƌ����Ă���B
�@
1903�N�@�_������ː������ɂ��錤����ŁA���w���m�ɂȂ�B
�@
�s�G�[���E�L�����[�ƂƂ��ɁA����˔\�̔�����ŁA�m�[�x�������w�܂�������B
�@
���Ȃ݂ɁA����́A�m�[�x�������w�ܑ�3��ڂł���A��1��ڎ�҂́A�����g�Q���ł������B
�@
1904�N�@�s�G�[�����\���{���k��w�̕����w�����ɂȂ�A�}���[�̓s�G�[���̌������̎�����C�ɂȂ�B�����̃G�[�u�����܂��B
�@
1906�N�@�s�G�[�����הn�ԂɂЂ���Ď��ʁB�s�G�[���̂��Ƃ����ŁA�\���{���k��w�̍u�t�ɂȂ�B11��5���A�ޏ��́A�O�C�̔ޏ��̕v���I�����Ƃ��납��A�u�`���ĊJ�����B
�@
1908�N�@�\���{���k��w�̋����ƂȂ�B
�@
1910�N�@�����ȋ������W�E���̕����ɐ�������B�s�G�[���̕��A�x���̂��߂ɁA���̐�������B�B
�@
1911�N�@�ޏ��́A�t�����X�w�m�@��5�̃A�J�f�~�[�̂����́A�Ȋw�A�J�f�~�[����ɁA�����Ƃ��ď��߂ė���₷�邪�A�킸���̍��ŁA���I����B
�@
����W�E���̔�����ŁA�m�[�x�����w�܂���܂���B
�@
���̔N�A�ޏ��ɂƂ��āA��X�L�����_����������B
�@
�ޏ��ƒ��N�e�����Ă��Ă����|�[���E�����W�����@���ƁA�ޏ��̊W���V���ɖ\�I�����B
�@
�ނ̍ȂƁA�Ȃ̕�e���A�V���̃C���^�[�r���[�ɓ�������A�ٔ����ɑi�ׂ܂ł������B�ޏ����A�ނɑ��ď��������ʂ��̎莆���A�����W�����@���̋`�Z�ɂ���ē��܂�āA���J�����B�����W�����@���́A���������܂ŁA�܂����܂�A�}���[�̃\���{���k��w�̋����̒n�ʂ��낤���Ȃ�B
�@
�t�����������Ă��炭���@����B�������A�ޏ��́A���A���̂܂܂̒n�ʂɂƂǂ܂�B�������A���̃X�L�����_���̘b�́A�l�X�̐S�����������܂ł́A��1�����E�����܂��Ȃ���A�Ȃ�Ȃ������B
�@
�Ȏq�ƕʋ����Ă������W�����@���́A2�N����Ƃɂ��ǂ邪�A�ޏ��Ƃ̗F��͂��̂܂ܑ����B�������A�ނ́A���̉��N�����Ƌ����q�̏����k�Ɨ��ɂ����A�q���܂łȂ��Č�������B
�@
1913�N�@�����V�����̕��˔\�������̗������ɏo�����āA�|�[�����h��Ō�������B
�@
1914�N�@�\���{���k��w�Ƀ��W�E���������E�L�����[�ق��������A�����ɂȂ�B�����g�Q���ԂŁA��ꎟ���E���̐���������܂��A�������̎��Âɂ����B
�@
1918�N�@�푈���I���A�}���[�����́A�����̃f�p�[�g�ŁA�A�ԁA���̏�������������A����ŁA����������A�L�����[�ق�����ŁA�������B
�@
�����ԁA��������������Ă����|�[�����h�́A�Ɨ��������Ƃ�A�}���[���悭�m���Ă���s�A�j�X�g�̃p�f���t�X�L�[�������V�������{�̎��O���ƂȂ����B
�@
1920�N�@���W�E�����������������颃L�����[���c����ł���B
�@
1921�N�@��t���ɂ��1�O�����̃��W�E���������Ƃ邽�߂ɃA�����J�ɂ킽��A�劽�}��������B�Ȃ��Ȃ�A�ޏ��̓��W�E�����������A�����Ȃ�������g�p�����\�����Ȃ������B���̌��ʁA�吨�̃K�����҂����W�E�����Â������Ă��邪�A�ޏ��͂Ȃɂ����v��������Ă��炸�A���̂��߁A�����ɂ��A�l���ɂ��߂��܂ꂸ�A�����s����̂��A�s�\�ȏ�Ԃł��������炾�B
�@
���̂��Ƃ��A�������A�����J�̃W���[�i���X�g�̃~�V�C���ƁA�E�B���A���E�v���E���E�����j�[�v�l�́A�}���[�̗͂ƂȂ邱�Ƃ��A���ӂ��A�ޏ��̂��߂ɁA���������߁A���W�E����ޏ��ɂ킽���v������ĂāA��������s�����̂������B
�@
1922�N�@��m�I���͍��ۈψ��̈ψ��ɂȂ�A�������͂��߂�B
�@
�Ȋw�w�m�@����ɂȂ�B
�@
1923�N�@�L�����[���c�A���W�E��������\���N�L�O�Ղ��Ђ炭�B
�@
1929�N�@�����V�����ɂ��Ă��郉�W�E���������̂��߂̃��W�E�������ɃA�����J�ɍs���B
�@
1932�N�@�����V�����̃��W�E���������̊J�����ɏo�Ȃ���B���ꂪ�A�|�[�����h�������˂��Ō�ɂȂ�B
�@
1934�N�@7��4���@�����Ԃ̕��˔\���������Ƃ́A�Đ��s�ǐ������n���ǂŁA�S���Ȃ�B�Z�\�Z�������B
�@
1935�N�A�ޏ��̖��̃C���[�k�ƁA���̕v�t���f���b�N�E�W�����I���m�[�x�����w�܂���܂���B
�@
�������A�ӂ���Ƃ����N�̕��˔\�̉e���ƌ����錴���ŁA���ꂼ��A50��̎Ⴓ�Ŏ������Ă���B
�@
�L�����[�v�l��2�Ԗڂ̖��G�[���̓s�A�j�X�g�ɂȂ������A�펞���A����R�t�����X�R��ɎQ�����A�A�����J�e���̐펞���h������Ѣ�p���E�v���X��̋����ҏW�����Ƃ߂��B
�@
�A�����J�̃M���V�����ݑ�g�A�w�����[�E���u�C�X�ƌ������邪�A�w�����[�́A���̌テ�j�Z�t�̎����ǒ��ƂȂ�A1965�N�Ƀm�[�x�����a�܂���܂���B
�@
�q���̂���A���߂ēǂL�����[�v�l�̓`�L�́A�q���p�̊G�{�ł����B
�@
���̎��̂��ƂŁA�S�Ɏc���Ă��邱�Ƃ́A���̖��O�ƁA(�ǂ����Ă��A���{�l�̏ꍇ�A�������v���o���Ă��܂��܂����̂ˁB)�A�|�[�����h�Ƃ������̂��ƁA�m�[�x���܂ƁA�s�G�[���E�L�����[�̃V���b�L���O�ȖS���Ȃ���ł����B
�@
���̌�A�����A�L�����[�v�l��2�Ԃ̖��G�[�����������L�����[�v�l�`���܂��āA������݂��Ă�����āA���̂����܂����w�̗l�q�ɁA�����ꂢ��܂����B
�@
�}���ق��Ђ炢�Ă���Ԃ́A�����Ɛ}���قŕ����E�E
�@
�Z�܂��ɋA���Ă���́A�����ɂ����āA�H�ׂ���̂��H�ׂȂ��ŁA�����E�E
�@
���ʓ|��Ă��܂��āA�`�Z�̃J�V�~�[���̂����ɂ�Ă�����āA���A�̃X�e�[�L��H�ׂ�������Ƃ��E�E�E
�@
���ƁA�O���A�E�K�[�X�����ł��A�f��Ƃ��݂āA�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�����݂����ȃC���[�W���������̂ł����E�E�E
�@
�W���[�̏������{��ǂ�ŁA�ޏ��̐l�ԂƂ��ẮA���͂Ƃ��A�������n�߂āA�w��̐��E�ɂ����Ēj���ƑΓ��ɂ���Ă������Ƃ́A��ς��݂������̂�m�邱�Ƃ��ł��܂����B
�@
�m���ɂ��ӂ�A�������Ă����ޏ��́A�ƂĂ����͓I�Ȑl�������Ǝv���܂��B
�@
�ޏ��̃X�L�����_�������ɂ��ẮA���ꂱ���A�W���[�̖{��ǂނ܂ł́A���܂������m��Ȃ������̂ł����A
�@
����������ʂ�m�������Ƃ́A���ɂƂ��ẮA�}�C�i�X�ɂ͊������܂���ł����B
�@
�ޏ����A������s�G�[���̖S�����Ƃ��A�������Đl�������邱�Ƃ��A��߂Ȃ��������Ƃ��A�������Ċ������ł��B�@�@
�@ |
 �@ �@
���A�C���V���^�C���u��ʑ��ΐ������̊�b�v���� 1916�N |
   �@
�@
|
Einstein, Albert.(1879-1955)
�@
Die Grundlage der allgemeinen Relativitatstheorie.
�@
�A�����J�̗��_�����w�ҁB�h�C�c���܂�ł��邪�A1901�N�ɃX�C�X�Ŏs�����A��Ƀx��������w�̕����w�����ɂȂ������A1933�N�i�`�ɒǂ��ăA�����J�ɓn��s�����������B���ł�1901�N����M�͊w�y�ѓ��v�͊w�Ɋւ���_���\���Ă������A1905�N�Ɍ��ʎq�����A�u���E���^���̗��_�A���ꑊ�ΐ����_�Ƃ������{�I���v���I���_�𗧂đ����ɔ��\�����B���̂��߂��̔N�́���Ղ̔N���ƌ�����B1915�N�Ɉ�ʑ��ΐ����_���������A���̗��_����ꎟ���E����܂��Ȃ��C�M���X�̓��H�ϑ����ɂ���Ċm���߂�ꂽ���Ƃɂ���āA�A�C���V���^�C���Ƒ��ΐ����_�̖��͐��E���Ŕ����I�ɒm����悤�ɂȂ����B���ΐ����_�́A�]���̗͊w�̘g�g�݂����{�I�ɕϊv���A20���I�����w�̊�b��z�����B1921�N�ɂ́A���������w�ւ̌��тɂ��m�[�x�������w�܂���܂����B�@ |



 �@
�@


 �@
�@ �@
�@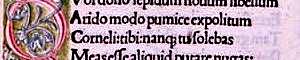 �@
�@ �@
�@ �@
�@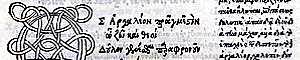 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@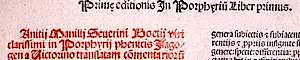 �@
�@ �@
�@ �@
�@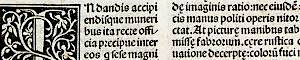 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@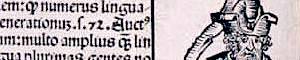 �@
�@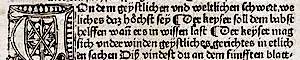 �@
�@ �@
�@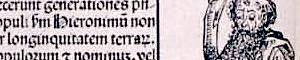 �@
�@ �@
�@ �@
�@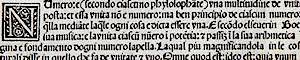 �@
�@ �@
�@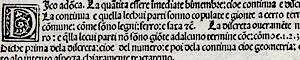 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@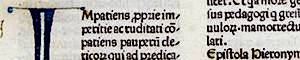 �@
�@ �@
�@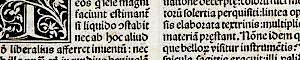 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@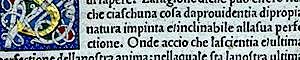 �@
�@ �@
�@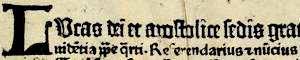 �@
�@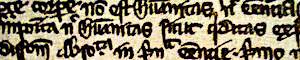 �@
�@ �@
�@ �@
�@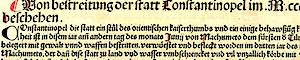 �@
�@ �@
�@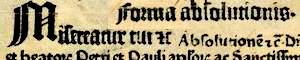 �@
�@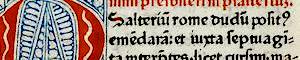 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@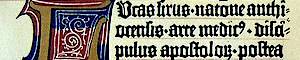 �@
�@ �@
�@ �@
�@ �@
�@